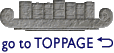知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
技術的範囲
技術的範囲 ┃ 2025年 ┃ 2024年 ┃ 2023年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2018年 ┃ 2017年 ┃ 2016年 ┃ 2015年 ┃ 2014年 ┃ 2013年 ┃ 2012年 ┃ 2011年 ┃ 2010年 ┃ 2009年 ┃ 2008年 ┃ 2007年 ┃ 2006年 ┃ 2005年 ┃ 2004年 ┃ 2003年 ┃ 2002年┃
最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、裁判所がおもしろそうな(?)意見を述べている判例を集めてみました。
内容的には詳細に検討していませんので、詳細に検討してみると、検討に値しない案件の可能性があります。
日付はアップロードした日です。
2025.01.23
令和6(ネ)10038 不当利得返還等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和7年1月15日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人は、原判決が「構成要件1F及び1Hの「横G(Ghosei)」は、 従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、車両の傾 斜走行状態での正確な横Gであると認められる。」と判断しているが、むしろ、本件 明細書において、「正確な横G」は、本件課題との関係で、タイヤでの荷重接地点変 化から生じる戻り角(ρ)を加味した正確な傾斜角及び加速度センサーと角速度セ ンサーの関連付けにより明らかになったロールによる速度変化の影響を加味して導 かれる、加速度センサーにおいて安定走行時に検出される横G(Gken)のこと を指すものとして説明されており、他方、「横G(Ghosei)」は、本件課題と の関係で、正確な横Gの検出が可能となったことを踏まえた、車両を安定化に導く ブレーキシステムの構成要素の一つとして説明されていると主張する。 そこで、控訴人が主張する「戻り角(ρ)」に着目すると、発明の詳細な説明には 「ハイブリットセンサー20 には、進行方向の加速度を検出する加速度センサー 21、 進行方向ロール速度を検出する傾斜角速度センサー22 及び ロール方 向の加速度を検出する加速度センサー23 が小型に内蔵されおり、ライダーの体 重を含めた合成重心に近いところにレイアウトされる。 ハイブリットセンサー2 0 には、傾斜時に生じる理論バンク角(Φ)及び傾斜によってタイヤでの荷重接 地点変化から生じる戻り角(ρ)が同時に存在している。 (図8も同時参照)セ ンサー20 に生じる力(ベクトルA)と 実際に生じる力(ベクトルA ’)とは ずれが生じている。 このずれ角(戻り角(ρ))によって、正確な横Gを検出する ことが解析された。」(【0060】)、「Gken = g・cosΦ・tanρ- Ψ・Rhenと変形でき、シンプルな式になる。ここで、表されるΦは 車両の理 論バンク角度であり理論傾斜角でもある、 傾斜角速度センサー22 から検出さ れる角速度Ψ(rad/sec) を時間積分して得られた角度であり、ρは傾斜 戻り角であり、RはGセンサー#23の実車取付けの高さ(図8b hsen ) をそれぞれ示している。」(【0063】)との記載が認められるが、この記載は、「横 加速度(Gken)」を解析した結果として、傾斜角Φ、傾斜戻り角ρ、傾斜角速度 Ψ等を用いた式で表すことができることを示すに尽きるのであり、他方で、特許請 求の範囲の記載において、本件発明1の「横加速度(Gken)」は「横加速度を検 出する加速度センサー」により検出されたものとの特定がされているものの、傾斜 角Φ、傾斜戻り角ρ、傾斜角速度Ψ及びRhenに基づき、Gken=g・cos Φ・tanρ−Ψ・Rhenという演算から導き出されたことは特定されていない から、控訴人の主張はその前提を欠く。
また、仮に「横加速度を検出する加速度センサー」により検出された「横加速度 (Gken)」を正確な横Gであるとするならば、正確な横Gの検出は「横加速度を 検出する加速度センサー」が本来的に備えている機能であり、正確な傾斜角の検出 とは無関係である。そうすると、控訴人が主張する「1)「走行時の横Gセンサーと 角速度センサーを関連付けること」及び「正確な傾斜角の検出」によって、走行状 態での「正確な横G」の検出を可能とすること」という課題とは矛盾することにも なるから、控訴人の主張は本件明細書の記載とは整合しない独自の見解であって採 用することはできない。
イ 「Ψ」を角加速度を表す記号「Ψ.」への訂正について (ア) 特許がされた特許請求の範囲、明細書又は図面における訂正について、特許 法126条1項ただし書2号は、「誤記又は誤訳の訂正」を目的とする場合には、願 書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが、 ここで「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいこと が、当該明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載全体から客観的に明らかで、 当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという 場合でなければならないものと解され、特許法134条の2第1項ただし書2号の 「誤記又は誤訳の訂正」も同様に解される。
したがって、明細書等の記載について、物理学上意味をなさないことが客観的に 明らかであることが認識できたとしても、物理学上意味をなさないことの一事をも って、ただちに同号の「誤記」と認められるわけではなく、当該物理学上意味をな さない記載について訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければ、 同号の「誤記」とは認められないと解するのが相当である。この点、控訴人は、請 求項に記載された計算式に係る誤記の訂正に関して、それを字義通り解すると、次 元の異なる物理量同士の減算となり、その技術的意味が理解困難となること等を理 由として、誤記の訂正が認められることを主張するが、技術的意味が理解困難とな ることの一事をもって誤記の訂正が認められるものとはいえないから、控訴人の上 記主張は採用できない。
(イ) 以上を踏まえ、本件明細書等の記載について検討する。
控訴人は「Ψ」を角加速度を表す記号「Ψ.」に訂正することを主張する。本件特 許権に係る特許請求の範囲及び本件明細書には、「傾斜角速度(Ψ)」、「角速度検出 値(Ψ)」、「角速度Ψ(rad/sec)」、「角速度(Ψ)」「車両のロールによる角速度」、「ロール方向の角速度」、「角速度出力(Ψ)」、「ロール角速度Ψ」、「ロール速度Ψ」、「傾斜角速度Ψ」及び「ロール角速度(Ψ)」(請求項1〜4、【0055】、【0061】、【0063】、【0066】、【0073】、【0084】、【0085】、【0090】、【0127】、【0130】、【0131】)との記載が認められ、他方で、「該傾斜角速度(Ψ)の時間微分で得られる傾斜角加速度(dΨ/dt)」(請求項2)、「傾斜し始めの傾斜速度(ロール速度Ψ)を時間微分 dΨ/dt した角加速度を検知(図中ΔΨの部位)することにより」(【0131】)との記載も認められるから、本件明細書においては、傾斜角速度を「Ψ」、傾斜角加速度を「dΨ/dt」又は「ΔΨ」と表しているものと認められる。
そして、本件発明1では「横加速度を検出する加速度センサーのロールによる影 響を取り除く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法」と特定され、 本件発明2では「加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正 後の横G(Ghosei)の導出方法として、前記横加速度から前記加速度センサ ーの車両取り付け高さと前記傾斜角速度(A)または傾斜角速度(B)のいずれか の積、との差分を求め、」と特定されているところ、請求項1を引用して記載された 請求項4には「前記信号演算として、加速度センサーのロールによる影響を取り除 く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法として、前記検出された 横加速度(Gken)から加速度センサーの車両取り付け高さ(hsen)と前記 検出された傾斜角速度(Ψ)の積、との差分を求めること、の導出方法を有する事」 と記載され、本件明細書には「実際の走行傾斜時に検出される検出横G(Gken) は、傾斜角の時間的変化である傾斜角速度(Ψ)を用いた補正が必要であることか ら 補正後の横G(Ghosei)はGhosei = Gken−(Ψ・Rhse n)として表される。」(【0073】)、「2)、 走行時に変化する実際の検出横G(Gken)を少なくとも傾斜角の時間微分(dΦ/dt)値である傾斜角速度(Ψ) を用いた補正を行い、補正後の横G(Ghosei)をGhosei= Gken −(Ψ・Rhsen)の式を用いて補正した値の算出G値」(【0085】)、「項目2)は、走行時の傾斜により検出された検出G(Gken)は車両のロールによる誤差 が重畳されるため ロール成分を取り除くために角速度の補正を行うことが必要と なる。 すなわち、センサーからの検出G(Gken)から規範G成分の部位を実 際の検出される横G(Gken)に置換え、角速度による補正を行えば 規範同様 にロールによる影響を排除した 補正後の制御で使用できるG(hosei)が導 け、Ghosei=Gken−(Ψ・Rhsen) の様に表される。ここで補正項 として傾斜角速度を加味している理由は、前記したように制御上無視できない要素 になっているためである。」(【0087】)などと記載されている。
以上によると、本件特許権に係る特許請求の範囲及び本件明細書の記載は、傾斜 角加速度は傾斜角速度の時間微分で得られるという認識の下、両者を明確に区別し た上で、「加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 G(Ghosei)の導出方法」について、加速度の次元の物理量である実際の走 行傾斜時に検出される検出横G(Gken)から、速度の次元の物理量である傾斜 角速度(Ψ)にセンサー取付け高さRhsenを乗じた値を減算することで終始一 貫していると認められる。 そうすると、本件明細書等に記載された「加速度センサーのロールによる影響を 取り除く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法」について、当業 者は本件明細書に物理学上意味をなさない導出方法が記載されていることを理解す るにとどまり、角速度Ψを角加速度Ψ.の趣旨に理解するのが当然であるとまでは認 められない。
・・・
(エ) 以上のことから、控訴人が主張する「Ψ」を角加速度を表す記号「Ψ.」への 訂正は認められず、本件各発明のいずれについても、特許請求の範囲に記載された 発明が本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 104条の3
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2025.01.15
令和6(ラ)10001 保全異議申立却下決定に対する保全抗告事件 特許権 令和6年10月22日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
当裁判所も、基本事件における相手方の申立ては、原々決定が認容した限度\nで認容するのが相当であると判断する。その理由は、後記1のとおり補正し、 後記2のとおり当審における抗告人の補充主張に対する判断を、後記3のとお り当審における抗告人の追加主張に対する判断を、それぞれ付加するほか、原 決定「理由」第4の1から7まで(6頁18行目から33頁7行目まで)に記 載のとおりであるから、これを引用する。当裁判所は、後記1の補正及び後記 2(1)の判断のとおり、乙1発明に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点2 −3、2−5)について、原決定とは異なり、当業者が、相違点1−1に係る 本件発明1の構成を容易に想到するとは認められないことから、本件発明の進\n歩性が欠如するとは認められないと判断するものである。
・・・
乙1公報の発明の詳細な説明には、「さらに、容器2およびその中味 は必ず薬用でなければならないというわけではない。衛生的あるいは 非酸化性の移送あるいは保管の状態を必要とする液体状あるいは固体 状の化学物質を充填した他のタイプの容器も本発明の方法によって処 理できる。」との記載がある。このうち「さらに、容器2およびその中 味は必ず薬用でなければならないというわけではない。」という第1文 は、その記載に基づいて、容器2及びその中味について、薬用でもよ いが、薬用であることが必須であるわけではなく、薬用以外でもよい という意味と解され、薬用とそうでない場合の双方を含むものと解さ れる。そのため、これに引き続く第2文の「衛生的あるいは非酸化性 の移送あるいは保管の状態を必要とする液体状あるいは固体状の化学 物質」についても、薬用とそうでない場合の双方を含むものと解され、 第1文によって、第2文にいう上記「化学物質」から薬用の物質が排 除されており、薬用以外の化学物質のみが含まれると解すべき根拠は 認められない。そうすると、乙1発明が、薬用の化学物質についての 非酸化性の移送を排除しているとは認められない。
しかしながら、乙1公報の発明の詳細な説明には、PTHペプチド 含有製剤の製造については何も記載されておらず、PTH類縁物質の 含量が低い高純度のPTHペプチド含有凍結乾燥製剤を得るとの課題 も開示されていないから、乙1発明に接した当業者が、乙1発明を、 「当該製剤中のPTHペプチド量と全PTH類縁物質量の和に対する いずれのPTH類縁物質量も1.0%以下であり、及びPTHペプチ ド量と全PTH類縁物質量の和に対する全PTH類縁物質量が5. 0%以下」であるPTHペプチド含有凍結乾燥製剤の製造方法に適用 することを想起するとは認められない。
抗告人は、PTHが酸化しやすい物質であることは本件特許の優先 日前の技術常識であり、当業者は、PTHペプチドを有効成分とする 凍結乾燥注射剤を製造するに当たり、「製剤開発に関するガイドライン」 (乙20)に基づき、酸化を防止して、高純度の医薬品を製造するこ とができるよう製造工程を確立することを検討するから、乙1発明を PTHペプチド含有凍結乾燥製剤の製造のために使用することを当然 検討すると主張する。
しかし、乙1に、抗告人の主張する上記技術常識を組み合わせ、更 に乙20の文献の記載を組み合わせたとしても、当業者が、典型的製 造過程によりPTHペプチド含有凍結乾燥製剤を工業的に製造しよう とするとPTH類縁物質を含んだ製剤が製造されてしまうという課題 を認識するとはいえず、乙1発明を「当該製剤中のPTHペプチド量 と全PTH類縁物質量の和に対するいずれのPTH類縁物質量も1. 0%以下であり、及びPTHペプチド量と全PTH類縁物質量の和に 対する全PTH類縁物質量が5.0%以下」の無菌注射剤であるPT Hペプチド含有凍結乾燥製剤の製造方法に適用することを想起すると も認められない。 その他、抗告人が主張する事情を考慮しても、乙1発明に本件特許の優先日前の技術常識を組み合わせることによって、当業者が、相違点1−1に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和5(ワ)70607 特許権 民事訴訟 令和6年10月22日 東京地方裁判所
ア 本件発明に係る特許請求の範囲の記載によれば、「第 1 制御装置」(構成要\n件 J)は、自動回帰発動条件1)(「前記第 1 送受信アンテナにより一定時間以 上前記遠隔操縦装置からの信号を受信しなかったと判断された場合」)、又は、 同2)(「前記電源の残量が半分以下になったと判断された場合」)のうち、「少 なくともいずれか一方の判断が行われた場合」に、本件発明の遠隔操縦無人 ボートを、「前記初期位置に自動回帰させるため、前記現在位置および前記 初期位置に基づいて、前記推進動力源と前記操舵装置との動作を制御する」 ものである(いずれも構成要件 J)。
もっとも、この記載によっても、本件発明の「第 1 制御装置」は、自動回 帰発動条件1)及び2)の各場合に自動回帰のための動作制御を行い得る構成\nをいずれも備えたものである必要があるか、いずれか一方の構成を備えた装\n置であれば足りるかについては、必ずしも明らかでない。
イ そこで、本件明細書の記載を参酌すると、本件発明は、「ボートが波に乗っ て、リモコン(遠隔操縦装置)の電波が届かないような遠くまで流されてし まった場合」、「波により船体が激しく揺れて、遠隔操縦装置からの電波を受 信するアンテナが岩等に当たり破壊されてしまった場合」及び「ボートに搭 載されている電源の残量が少なくなって、駆動電力が供給され難くなった場 合」、すなわち、遠隔操縦装置との通信途絶(前 2 者)及び電源残量の不足 (後者)という事態を具体例として示しつつ、そのような事態においてもな お紛失することなく、必ず回収できる遠隔操縦無人ボートを提供することを 解決すべき課題とし(【0004】〜【0007】)、本件発明の構成を備えることに\nよって、「一定時間以上遠隔操縦装置地の間の通信が途絶えた場合、または、 電源の残量が半分以下になった場合」に、「自動的にボートを初期位置に回 帰させることができ」、「ボートを紛失してしまうことがない」として、この 課題を解決する作用効果が得られるとするものである(【0008】、【0009】)。
ここで、自動回帰発動条件1)の場合に初期位置に自動回帰させること及び 同2)の場合に初期位置に自動回帰させることは、前者が遠隔操縦装置との通 信途絶、後者が電源残量の不足という相互に原因の異なる危機的状況への対 処を想定したものである。このため、本件発明は、その作用効果を奏するた めに、いずれの危機的状況にも対処できるようにすることを要するものと理 解される。そうすると、本件発明における「第 1 制御装置」(構成要件 J) は、自動回帰発動条件1)に係る判断と同2)に係る判断のいずれもが行われ得 る機構を備えることを前提として、そのいずれかの条件が満たされた場合に\n自動回帰のための動作制御を行う装置を意味するものと解される。本件発明 の実施例としてはこのような装置のみが開示され、いずれか一方の機構のみ\nを備えるものが本件発明の技術的範囲に含まれることの明示的な記載も示 唆もない。これに加え、このように解することは、本件発明に係るボートが 電源の残量を検出する残量検出装置(構成要件 I)を備えることを発明特定 事項としていることによっても裏付けられる。仮に、自動回帰発動条件2)に 係る判断を行い得る機構がなく、同1)が満たされた場合に自動回帰のための 動作制御を行う機構のみを備えた装置も本件発明の技術的範囲に含まれる\nものと解した場合、本件発明の発明特定事項として電源の残量を検出する残 量検出装置を備える構成を採用したことの技術的意義が理解し難いものと\nなるからである。
ウ 小括
以上のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲及び本件明細書の記載によ れば、本件発明の「第 1 制御装置」(構成要件 J)は、自動回帰発動条件1)に 係る判断と同2)に係る判断のいずれもが行われ得る機構を備えることを前\n提として、そのいずれかの条件が満たされた場合に自動回帰のための動作制 御を行う装置を意味するものと解される。これに反する原告の主張は採用で きない。
3 争点 1-5(均等侵害の成否)について
原告は、仮に被告製品が本件発明の構成要件 J を充足しないとしても、電源の 残量に着目した自動回帰のための動作制御の条件として、電源の残量が半分以下 となった場合とするか他の所定量以下となった場合とするかの相違は、本件発明 の本質的部分の相違ではなく、本件特許の出願経過において意識的に除外された ものでもないことなどから、被告製品につき本件発明の均等侵害が成立する旨を 主張する。
しかし、前記認定事実(前記 2(1))によれば、本件特許の出願経過において、 特許庁審査官から、拒絶理由として、補正前請求項 1 発明の「所定の条件」につ き明確性要件違反及びサポート要件違反を指摘され、また、補正前請求項 6 発明 の「所定値」につき明確性要件違反を指摘されたことを受け、原告は、本件補正 により、自動回帰のための動作制御の条件につき、本件発明の構成要件 J のとお り補正したものである。原告によれば、本件補正は出願当初の明細書の記載内容 の範囲内で行ったものであるところ(乙 4)、本件明細書には、自動回帰発動条件 につき、本件発明の実施形態の 1 つとして、「上記実施形態では、自動回帰の際 に、障害物に衝突しないように、通ってきた経路を戻っている。しかし、通って きた経路を戻らなくてもよい。この場合、ボート に障害物を検知するセンサ を設け、自動的に障害物を回避できるようにすることが好ましい。電源 12 の残 量が少ない場合にボート を自動回帰させる場合、通ってきた経路を戻るので は、少なくとも電源 12 の残量が半分以上あることを条件に戻す必要がある。障 害物センサを設けることにより、電源 12 の残量が半分以下になって、自動回帰 させても操作者の下までボート が戻って来ることができる。」との記載があり (【0061】)、他に自動回帰発動条件としての電源の残量の数値に言及する記載は 見当たらない。この点を踏まえると、本件補正は本件明細書【0061】の記載に基 づいて行われたものと理解される。
そうすると、原告は、本件補正により、電源の残量に着目した自動回帰のため の動作制御の条件につき、ボート が通ってきた経路を戻るケースにも対応し 得るものとする趣旨で、「前記電源の残量が半分以下になったと判断された場合」 (自動回帰発動条件2))とする数値限定を行ったものとみるのが相当であり、「半 分以下」とするもの以外は特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべ きである。
したがって、本件発明の構成要件 J の文言非充足との関係における均等侵害の 主張については、少なくとも均等の第 要件を欠き、自動回帰発動条件2)に係る 「半分以下」の構成を備えない被告製品について、均等侵害が成立するとは認め\nられない。この点に関する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和5(ワ)70346 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月10日 東京地方裁判所
前記前提事実に加え、証拠(乙9)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品は、ユーザーが自動車のドアを開けることで磁気センサーモジュールがド アに設置された磁石の磁気を感知しなくなると、バックライトモジュールが オン状態(点灯状態)になる一方で、ユーザーが自動車のドアを閉じること で磁気センサーモジュールが磁気を感知すると、バックライトモジュールが オン状態からオフ状態(消灯状態)になること、そして、バックライトモジ ュールがオン状態(点灯状態)のまま放置されると、徐々に減光しながら消 灯するが、これは、バックライトモジュールが、接続されているコンデンサ の充電又は放電による影響を受けるからであり、発光持続時間を正確に調整 するための制御回路や制御プログラムを用いることによって消灯までの時間 が制御されているものではないこと、点灯状態と消灯状態の時間間隔は、コ ンデンサの性能(静電容量)やその劣化(静電容量の低下)の程度によって\n左右されるため、製品の使用期間が長くなりコンデンサのエイジングが進む と点灯開始から消灯までの時間間隔が短くなり、所望の時間間隔で消灯させ ることはできないこと、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、被告各製品の発光持続時間は、コンデンサの性能\nやその劣化の程度によって左右されることになるのであるから、被告各製品 は、発光持続時間を正確に調整することができるものとはいえない。 これに対し、原告の主張は、構成要件Fにいう「調整可能\」の文言解釈に つき、前記判断とは異なる文言解釈に立つものであり、上記文言解釈に係る 前記説示に照らし、いずれも採用の限りではない。
・・・
前記3のとおり、被告各製品は、本件発明の構成要件Fを充足しないから、\n本件発明の技術的範囲に属するとはいえず、その余の争点を判断するまでもな く、原告の請求は理由がないことになる。もっとも、本件の事案に鑑み、本件 の中核的争点の一つである争点2−1に限り、念のため、以下判断を示してお くこととする。
・・・
前記(1)の乙8公報の記載によれば、乙8発明は、外部電源が完全に不要な 自動車スカッフプレートに適用される発光モジュールを提供することを課題 とするものであり(【0004】)、この課題を解決するための発光モジュ ールは、発光素子及びリードスイッチが設けられた「ランプ板」、及び電線 を介してランプ板に接続される「電池」が、いずれも「導光板」に埋設され る構成を有し(【0005】、【0015】ないし【0017】)、この構\ 成により「導光板10の内部に発光素子20に必要な電力を供給することが できる電池40を設置するため、完全に外部電源が不要となる」(【001 9】)ことによって、上記の課題を解決するものと認められる。その他に、 乙8公報には、上記課題の解決の手段として、上記以外の構成は記載されて\nいない。
そして、前記(1)及び前記(2)イのとおり、乙8発明の構成は、外部電源が完\n全に不要な発光モジュールである導光板10に、これに埋設されたランプ板 50、電池40等を密封するための収容溝カバー70を設け、スカッフプレ ート80の上面には凹部を設け、この凹部に発光モジュールである上記導光 板10を収容するものである。 そうすると、乙8発明においては、導光板10に係る上記構成(電池40\nを導光板10の内部に埋設して、導光板10の底面に電池40を密封する収 容溝カバー70を設け、この導光板10をスカッフプレート80の内部に収 容しているものをいう。)は、乙8発明の課題解決に直結した構成であるか\nら、乙8発明に接した当業者がこれを変更する動機付けを認めることはでき ない。
のみならず、乙8公報には、電池の交換についての記載はなく、乙8発明 に接した当業者が仮に電池の交換という課題を着想したとしても、相違点8 −1に係る構成とするためには、(a)収納溝カバー70を除いた上で、(b)\n導光板10に代えてスカッフプレート80に電池40を収容する収容孔を設 け、当該電池収容孔を底面側から開口するものとし、(c)当該収容孔を覆 うカバーを設け、当該カバーを取り外すことで電池40を交換可能とし、(d)\nスカッフプレート80に収容することになった電池と、導光板10内に埋設 されているランプ板50等との電気接続を行うという、複数回の変更が必要 になり、しかも、上記の変更内容には、乙8発明の課題解決に直結した構成\nの変更も含まれていることが認められる。 これらの事情の下においては、乙8発明に接した当業者において上記のよ うに変更する動機付けはないといわざるを得ず、当業者が本件発明を容易に 想到し得たものと認めることはできない。
これに対し、被告は、乙10文献には、無線車両発光ペダルの下表面から\n電池を交換可能にするために背面に取り外し可能\な電池カバーを設けること が開示されており、乙10文献及び乙11文献によれば、電池を内蔵する機 器一般において、電池を交換可能にするために、取り外し可能\な方式で電池 の収容孔を覆うカバーを設けることは周知技術であるから、乙8発明に乙1 0文献の技術事項や周知技術を組み合わせることにより、乙8発明の収容溝 カバー70を取り外し可能とすることは、当業者にとって容易想到であると\n主張する。
しかしながら、乙8発明に接した当業者において、スカッフプレート80 には、底板が設けられるものと理解するのが相当であることは、前記(2)イに おいて説示したとおりある。そうすると、底板が設けられるため、収容溝カ バー70は、スカッフプレート80の下表面に対して露出していないのであ\nるから、被告の主張は、乙10発明や周知技術を組み合わせるための前提を 欠く。
のみならず、乙11公報によれば、表示部を有し電池を電源とする電子機\n器において、表示部とは反対の裏側に電池交換のための取り外し可能\なカバ ーを設けることは技術常識であるといえるものの、当該技術常識を超えて、 乙8発明のように独立したモジュールが設けられ、底板(スカッフプレート 80)の凹部にモジュールを収容する電子機器において、底板の裏側から底 板に収容されているモジュール内部の電池を交換することまでが技術常識で あったものと認めるに足りない。 しかも、乙10文献については、乙8発明のスカッフプレート80に相当 する底板に相当する部材がないのであるから、下側から電池カバーを設ける という単純な技術常識によっては、乙8発明の電池の収容に係る構成と置換\nするなどして相違点8−1に係る構成に容易に想到することはできない。\nそうすると、被告の主張を考慮しても、乙8発明から出発して相違点8− 1の構成に至るための動機付けを認めることはできず、被告の主張は、前記\n判断を左右するものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和5(ワ)70272 特許権侵害排除等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月23日 東京地方裁判所
ア 本質的部分の認定について
第1要件にいう特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分であると解すべきであり、上記本質的部分は、特許請求の 範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効 果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に 見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定す\nることによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値 は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定めら れることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細 書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、 そして、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される 場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化した ものとして認定され、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程 大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のも のとして認定されるものと解される。 ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されてい るところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、\n明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術 に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきで\nある。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及 び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記 載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると 解される。
・・・
ウ 本件発明の本質的部分
(ア) 本件発明に係る特許請求の範囲及び本件明細書の各記載によれば、本 件発明は、フランジ幅の狭い形鋼の梁に親綱支柱を設置するのに手間が かからない、親綱支柱取付治具を提供するという課題を解決することを 目的として(【0006】及び【0007】)、矩形状の板の端部で上下 方向に間隔を開けてU字状に折り曲げられた折り曲げ部を含み(構成要\n件C)、かつ、矩形状の板の第1の方向端部より逆方向の端部までの長 さが、治具が取付けられる形鋼のフランジの幅より長い(構成要件E)\nという構成を採用したものであり、このような構\成を採用することによ り、U字状の折り曲げ部を幅の狭いフランジ部に係合した状態で、親綱 支柱の取付具を位置決めして固定でき、その結果、フランジ幅の狭い形 鋼の梁に親綱支柱を設置するのに手間がかからない、親綱支柱取付治具 を提供できるとの効果を奏する(【0013】及び【0014】)もので あると認められる。そして、上記の「U字状に折り曲げられた折り曲げ 部」は、これを幅の狭いフランジ部に係合した状態で親綱支柱の取付具 を位置決めして固定できることから、フランジ幅の狭い形鋼の梁に親綱 支柱を設置するのに手間がかからないようにするという課題解決に寄与 する構成であるということができる。\n
他方、本件明細書には、乙17発明の存在を明示ないし示唆する記載 は存在しないが、前記イのとおり、本件出願までに公知となっていた乙 17発明は、命綱取付装置を梁に簡単に取り付けるために、本体下部の U字形フック部を梁の下部と垂直方向で係合させるとともに、略L字状 本体の横片先端を下方に折り返して形成させたコ字形フック部を梁の上 部と水平方向で係合させるという構成を採用しており、このうちコ字形\nフック部(乙17文献図面目録の【第3図】2b)は、命綱支持具を梁 の長手方向に沿った任意位置に配置して命綱を建物外周壁上部に沿った 任意位置へ簡単に取付けることができるという、構成要件Cの「U字状\nに折り曲げられた折り曲げ部」と同様の効果を奏するものと認められる。 そうすると、乙17発明は、本件発明との関係で従来技術に相当する ものであり、かつ、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題とし て記載されている部分は、本件出願時の従来技術に照らして客観的に見 て不十分であったと認められるから、本件発明の従来技術に見られない\n特有の技術的思想を構成する特徴的部分の認定に当たっては、乙17発\n明の内容も参酌して認定されるべきである。
そして、上記のとおり、設置するのに手間がかからないようにすると の課題解決に寄与する構成要件Cの「U字状に折り曲げられた折り曲げ\n部」と同様の構成については、乙17発明が既に備えていたものである\nから、本件発明と従来技術である乙17発明との主な差異は、本件発明 では、折り曲げ部の存在する端部から逆方向の端部までの長さが治具を 取り付ける形鋼のフランジ幅より長いのに対し、乙17発明では、コ字 形フック部の存在する端部から逆方向の端部までの長さが同フック部と 係合させる梁の上部の幅(フランジ幅)と同一であるという点にすぎな い。
したがって、本件発明は、従来技術と比較してその貢献の程度が大き いとはいえないから、その特許請求の範囲の記載の一部について、これ を上位概念化したものとして認定することはできず、本件発明の本質的 部分は、特許請求の範囲に近接したものとなるというべきである。 (イ) 以上によれば、本件発明における従来技術に見られない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分については、原告が主張するように「1)U字 状に折り曲げられた折り曲げ部を有し、2)その反対方向における長さを フランジ幅よりも長くしている」という構成であると認めることはでき\nず、矩形状の板の端部で上下方向に間隔を開けてU字状に折り曲げられ た折り曲げ部を設けた上で、この折り曲げ部の存在する端部から矩形状 の板の逆方向の端部までの長さを治具が取付けられる形鋼のフランジ幅 よりも長くするという構成、すなわち、構\成要件C及びEにより近接し た構成であると認定されるべきである。\n
エ 被告製品の第1要件の充足性
前記2で説示したとおり、被告製品は構成要件C及びEをいずれも充足\nするとは認められず、本件発明の「治具」は、「上下方向に間隔を開けて U字状に折り曲げられた折り曲げ部」が「前記矩形状の板の前記第1の方 向の端部」と連続する(構成要件C)のに対し、被告製品は、本件発明の\n「折り曲げ部」に相当するフック部が、同「矩形状の板」に相当する底板 ではなく、側板の端部と連続しており、また、本件発明の「治具」は、 「前記矩形状の板の前記第1の方向端部より逆方向の端部までの長さは、 前記治具が取付けられる形鋼のフランジ幅より長い」(構成要件E)のに\n対し、被告製品は、「矩形状の板」の「第1の方向端部より逆方向の端部 までの長さ」に相当する、形鋼に取り付けられた際に形鋼のフランジの二 辺と平行になる二辺に係る底板の端部間の長さが、形鋼のフランジの幅よ り長いとはいえない。
したがって、本件発明と被告製品とは本件発明の本質的部分において異 なっているというべきであり、両者の異なる部分が本件発明の本質的部分 ではないといえないから、均等の第1要件を満たすとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2025.01.13
令和5(ワ)8403 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月22日 大阪地方裁判所
事案に鑑み、まず第2要件及び第3要件について検討する。
イ 第2要件について
前記(1)で判示したとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体においては、\n傾斜部5)が、「笠木下部材」内に配置されたものに当たり得るとしても、少なくと もそれ自体が通気性能を有する「換気部材」ではないという点で、本件特許の特許\n請求の範囲に記載された構成とは異なる。\n原告は、本件発明の作用効果は、笠木下部分への取り付けが容易で、外壁下地材 の上端部の外方側に対して第1垂直部を当接させることにより笠木下部材の位置決 めが容易になることにあり、「換気部材」を傾斜部5)へと置き換えても、被告製品 が本件発明と同一の目的を達成し同一の作用効果を奏することを妨げるものではな い旨主張する。
しかし、本件発明が解決しようとする課題は、迅速な設置が困難であることに限 られるものではなく(前記(1)ア(ア)c)、本件明細書の記載からすると、本件発明 の目的ないし作用効果は、雨水や虫等の浸(侵)入を防止し、通気機能及び防水機\n能の信頼性の高い笠木下換気構\造体を提供することにもあると認められる(前記 (1)ア(ア)b(a)〜(c))。そして、別紙「図面」記載1及び2の各図面のとおり、被 告製品を部材とする笠木下換気構造体は、開口6)及び傾斜部5)と第1水平部2)との 隙間から建物内に雨水や虫等が浸(侵)入し得る構造となっているから、構\成要件 Cにおける「換気部材」を傾斜部5)に置き換えた場合、迅速な設置を可能にし、換\n気量を確保するという本件発明の目的は達成し得るとしても、雨水や虫等の浸(侵) 入を防止し、通気機能及び防水機能\の信頼性の高い笠木下換気構造体を提供すると\nいう本件発明の目的を達成することができないし、本件発明と同一の作用効果を奏 するともいえない。したがって、均等侵害の第2要件を認めることはできない。
ウ 第3要件について
本件発明は、従来技術である蛇行経路タイプの換気部材を用いた場合の課題(迅 速な設置が困難で換気量も少ないこと、蛇行経路を介して雨水や虫等が浸(侵)入 するおそれがあること等)を解決する換気部材を採用したものといえるところ(前記(1)ア(ア)b(a)、(b))、「換気部材」を従来技術である蛇行経路タイプに近い傾 斜部5)に置き換えることについては阻害要因があるものと認められる。原告は、通 気性能と防水性能\を生じさせるために、笠木下部材内に浸入する雨水を遮断する遮 蔽板を笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成することで同様の目的を達し得る\nことは広く知られており、当業者であれば、被告製品のように雨水を遮断する遮蔽 板と笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成する方法を用いることは容易に想到\nし得る旨主張する。しかし、そもそも本件発明の「換気部材」を被告製品の「傾斜 部」に置き換えると、第2垂直部に形成される「複数の開口」(その上下方向の位 置関係に特段の限定はない。)の「傾斜部」より上方部分において、笠木下部材内 に直通経路の通気路が形成され、防水性能を保持できなくなる可能\性がある。その ため、防水性能を保持するには「複数の開口」と「傾斜部」の位置関係や高さに創\n意工夫を要することとなるから、当業者が、被告製品の製造等の時点において上記 置換えを容易に想到することができたものとは認められない。したがって、均等侵 害の第3要件を認めることはできない。
エ 以上のことからすると、被告製品に関して、本件発明に対する均等侵害(間 接侵害)の成立を認めることはできない。
(3) 小括
以上のとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体は、本件発明の技術的範\n囲に属しないから、被告製品に関する間接侵害は認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和5(ワ)10237 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年11月14日 大阪地方裁判所
前記2(2)ア認定のとおり、本件発明は、非力な者であっても、危険な野生動物が 生息している場所において、簡単かつ確実に屠殺できるようにすることを解決すべ き課題とし「(【0008】ないし「【0012】)、このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで、対象動物との距離を調整できるようにし、例え\nば、猛禽類に対しては距離を長く取ったり、安全性を確保できる場合には距離を短 く取って確実に電極を動物の体に接触させたりすることができるという効果が得ら れるというものである。
一方、証拠(甲2、乙18)によれば、本件特許の出願時点で、野生動物を殺処 分する手段として、麻酔ガス等を用いることや電気スタナーを用いることなどが知 られていたことが認められる。これらの手段は、動物を殺害することはできるが、 即効性に欠けたり、即効性があっても動物に近づく必要があることから危険を伴っ たりするものであった。 そうすると、本件発明は、従来技術である電流を用いた屠殺手段を踏まえ、簡単 かつ安全確実な屠殺手段を提供するものであり、本件発明の構成中の本質的部分は、\nこのような屠殺手段を提供する竿体の伸縮構造(構\成要件Aの「伸縮自在の所定長 さの竿体」)、バッテリ部、電源昇圧部及びインバーター部の背負い構造(構\成要 件F)、双方の手でそれぞれ電源スイッチと竿体を把持できる通電コードの並列構\n造(構成要件G)に認められるものというべきである。\n
イ 前記2で検討したとおり、被告製品は、少なくとも、構成要件Aの「伸縮自\n在の所定長さの竿体」の部分、構成要件F及びGを充足しないのであるから、本件\n発明の構成中、被告製品と異なる部分が本件発明の本質的部分ではないとの均等侵\n害の第1要件は認められない。
(2) 第5要件について
ア 証拠(乙8ないし17)によれば、本件特許の出願経緯について、以下の事 実が認められる。
・・・
イ 以上の審査経緯に鑑みれば、原告は、当初、竿体の伸縮構造については固定\n長の竿体も含むものとし、バッテリ部、電源昇圧部及びインバーター部の背負い状 態の構成については携行可能\であるとするのみで背負い構造に限られないものと\nし、双方の手でそれぞれ電源スイッチと竿体を把持できる並列構造については双方\nの手でそれぞれ把持することが明示的に記載されていないものとし、土中の接地電 極と同電位とする回路構造については土中を閉回路に含まない回路構\造も含むもの として、特許請求の範囲を記載していたが、進歩性欠如及び明確性要件違反を指摘 されたことから、拒絶査定を回避するため、現在の特許請求の範囲の請求項1の記 載のとおりに限定したのであり、限定により除外された部分は、いずれも本件特許 の特許請求の範囲から意識的に除外したものであることが認められる。 そうすると、被告製品と本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載との相違点 は、いずれも原告が意識的に除外した部分に該当するから、均等侵害に関するその 余の原告の主張を前提としても、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特 許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときと の第5要件を満たさないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(ネ)10023 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年11月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 当審における控訴人の補充主張について
ア 控訴人は、被告方法において、一つの辺でも最大粒径より小さなバリがあれ ば、磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなっ ていることは原理・論理的に明らかであると主張する。 しかしながら、モールド樹脂内の磁性体粉末の具体的な粒子径の形状・分布、樹 脂の性質、隙間の形状・構造、加えられる圧力等により、隙間を通過する磁性体の\n量は変化するものと推測されるところ、被告方法においては、様々な粒子径、形状 の磁性体が使用されている(乙3,4)から、モールド樹脂内の磁性体粉末の具体 的な粒子径の形状・分布、樹脂の性質、隙間の形状・構造等がどのようなものであ\nる場合に隙間を通過する磁性体がどの程度あるのかについて、必ずしも一義的に明 らかではないといわざるを得ない。したがって、控訴人が主張する、磁性体粉末の 最大粒子径よりも小さなバリがあることをもって、当然に磁性体粉末容積比(バリ) の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなっているものとはいえない。
また、仮に被告方法における磁性体粉末の粒子径分布とバリの大きさとの関係性 から一定の事実を推認することができる余地があり、例えば、磁性体モールド樹脂 内の全磁性体粒子のうちの最小粒子径が隙間よりも大きい場合には、磁性体は隙間 を通過することができないため、樹脂のみが隙間から流出することが推測される一 方、逆に、全磁性体の粒子径が隙間よりも十分に小さい場合には、樹脂と共に磁性\n体も隙間を通過することから磁性体粉末容積比(コア)及び磁性体粉末容積比(バ リ)に変化がないものと推測される余地があるといえるとしても、被告方法におい て磁性体粒子のうちの最小粒子径が被告方法で使用されている●●及びパンチで形 成される隙間よりも大きいことを示すなど、被告方法における粒子径分布とバリの 大きさとの関係性を示す証拠はないから、控訴人の上記主張は裏付けを欠き、採用 することができない。
イ 控訴人は、原判決は、控訴人の主張を誤解し、かつ、控訴人提出の証拠評価 を誤ったものと考えられると主張し、樹脂の流出が止まる原因については、パンチ による加圧と樹脂からの抗力(硬化や樹脂と隙間との摩擦等による抗力)が均衡す ることと主張しており、原判決のように「被告方法の加圧・加熱過程で加圧を続け ても樹脂の流出が止まるのは、磁性体粉末が隙間を埋めることが理由であるから、 被告方法においては、樹脂が隙間から優先的に排出されるといった事象が生じたこ とが示されている」という主張はしていない旨を主張する。 しかしながら、樹脂の流出が控訴人の主張する機序によるものであるとしても、 前記アのとおり、被告方法において磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容 積比(コア)よりも小さくなっていることを認めることはできず、上記(1)の判断を 左右するものとはいえない。 したがって、控訴人の上記主張は採用できない。
ウ 控訴人は、甲27の実験結果によると、被控訴人主張の製造方法は、バリに おける磁性体粉末の容積比がキャビティ内の磁性体粉末の容積比より低くなること が明らかとなっているから、原判決の判断は妥当ではない旨主張する。 この点、甲27の第4(10頁〜)に記載されている実験方法で利用・設定され ている磁性体粉末の組成、樹脂の組成、磁性体粉末と樹脂の配合割合、予備成形し\nたコアの製造方法、加圧温度及び溶融粘度という条件が、実際の被告方法で用いら れているものと同一であると認めるに足りる証拠はなく、それらが実際の被告方法 と同じ条件であると客観的に裏付ける証拠もない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和5(ネ)10042 特許権 民事訴訟 令和6年12月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 乙9発明と乙10発明は、ともに制動保持装置(乙10においては坂道 発進補助装置)を備え、それらはブレーキがかかった状態を保持する機 能を有するものであることに照らすと、乙9発明及び乙10発明は、そ\nのような機能を用いる車両である点で共通する技術分野に属するといえ\nる。また、乙10発明と同様に、乙9発明においても、制動保持装置の 故障発生が想定され、それに対処する課題が存在することは当業者には 明らかである。
そうすると、乙9発明に触れた当業者は、上記の制動保持装置の故障 発生という課題を認識し、その課題を解決する点において、乙10発明 を乙9発明に適用する動機があるということができる。
イ これに対し、控訴人は、乙9発明は、制動保持装置26が故障している か否かを検出する技術思想を有しておらず、故障を検知する乙10発明 を適用する動機付けに欠ける旨主張する。 しかし、上記2(1)エのとおり、乙9発明は、エンジンおよび車両各部 の状態を検出するセンサ群を備えるものであり、車速零信号が出力され ているときに制動保持信号を出力し、エンジン始動後に制動解除信号を 出力する制動保持解除信号発生手段と、制動保持信号に応動して制動装 置を作動状態に保持し、制動解除信号に応動して作動状態にある制動装 置の作動を解除する制動保持手段とを具備している。そして、乙9発明 において制動保持装置の異常が検知された場合には、上記の乙9発明に おいて求められている状態、すなわち、制動保持装置の作動によりブ レーキ液圧が作用し、もってブレーキがかかった状態を保持できなくな ることは明らかである。そうすると、乙9発明に触れた当業者は、上記 の制動保持装置の故障発生という課題を認識し、その課題を解決するた め、乙10発明における制動保持装置の異常を検出する信号を付加する 動機付けがあるといえる。
ウ 以上によれば、乙9発明に乙10発明の制動保持装置の故障を検知して 運転手へ警報を発する技術を適用することは当業者が容易に想到し得る といえる。 そして、上記2(1)イ〜エのとおり、乙9発明が、エンジン自動停止に より発生する問題を、センサ群からの検出信号に基づいて制動保持装置 を作動させることにより解消する技術思想を有することに照らせば、制 動保持装置の故障を検知し、制動保持装置を作動させることができない 故障が生じた場合には、その検知結果をエンジン自動停止条件の一つと して用い、相違点1に係る「前記故障検出装置によって前記ブレーキ液 圧保持装置の故障を検出した時に前記原動機停止装置の作動を禁止する」 構成とすることは、当業者が容易になし得た事項といえる。\nよって、乙9発明に乙10発明を適用した際に、本件発明の相違点1 に係る構成を得ることは、当業者が容易に想到し得たものといえる。\n
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和3年(ワ)28206
対応する審決取消訴訟はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和5(ワ)70425 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年12月12日 東京地方裁判所
前記前提事実に加え、証拠(甲5ないし10、14)及び弁論の全趣旨に よれば、被告プログラムは、GoPayというタクシー料金の決済機能を備\nえており、GoPayは、d払いと連携することによって初めてd払いを利 用することができるようになること、他方、d払いは、訴外ドコモが提供す る決済機能であり、タクシーを利用した際にその利用したタクシー料金に限\nり利用することができるにとどまり、これ以外の場面では決済手段として使 用することができないこと、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、被告プログラムにおけるd払いは、タクシー料金 の個別の支払ごとにその都度利用されるにとどまるものであるから、被告プ ログラム自体がd払いという決済機能そのものを提供するものとはいえない。\nしたがって、被告プログラムは、本件発明の構成要件Bにいう「前記アプ\nリケーションで提供されるサービス」を充足するものとはいえない。
(3) 原告の主張に対する判断
原告は、本件発明の特許請求の範囲の文言上「提供するサービス」という 記載にはなっていないから、「サービス」の提供主体と「アプリケーション」 の提供主体とが法的に同一主体でなければならないという限定はなく、本件 明細書等【0030】の記載によれば、各サービスが様々な主体によって提 供されるものであることは、当業者のみならず一般人にとっても技術常識に 属する事項であるから、アプリケーションと各サービスが異なる法的主体に よって提供される場合も当然に含まれるものである旨主張する。 しかしながら、本件発明の構成要件は、「アプリケーション」と「サービ\nス」の内容及び関係を一義的に規定するものではないから、本件明細書等を 参酌しない限り、その関係等が明らかにならないことは、上記において説示 したとおりである。そして、本件明細書等のうち、「アプリケーション」と 「サービス」の内容及び関係につき記載した部分(【0012】、【001 4】、【0030】)を参酌すれば、「アプリケーション」は、総合サービ スを提供するものであり、構成要件Bにいう「前記アプリケーションで提供\nされるサービス」は、アプリケーション自体がクレジット機能、クーポン機\n能その他の機能\そのものを提供するものに限られると解するのが相当である から、タクシー料金の個別の支払ごとにその都度利用されるd払いを含むも のではないと解するのが相当である。 したがって、サービスの提供主体の同一性についていう原告の上記主張は、 充足性の判断を左右するものとはいえず、採用することができない。
・・・
4 争点2−1−3(乙1−3発明に基づく新規性、進歩性の有無)について 前記2及び3のとおり、被告プログラムは、本件発明の構成要件を充足しな\nいから、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえず、その余の争点を判断 するまでもなく、原告の請求は理由がないことになる。もっとも、本件の事案 に鑑み、本件の中核的争点の一つである争点2−1−3に限り、念のため、以 下簡潔に判断を示しておくこととする。
・・・
前記(1)に加え、証拠(乙1、5)及び弁論の全趣旨によれば、乙1−3発 明におけるクーポンを選択・設定するという画面の表示について、「コマン\nドが処理されることで生成される」旨の開示はないものの、乙1−3発明に よれば、かざすクーポンで選択・設定された「クーポン」は、携帯電話の画 面に表示されるのであるから、当該表\示データは、アプリの利用者がクーポ ンを選択する操作に基づき生成されていると認めるのが相当である。 そうすると、乙1−3発明に接した当業者は、乙1−3発明に「コマンド が処理されることで生成される」という記載がないとしても、上記操作をコ マンドに置き換えて上記画面を表示させる構\成を容易に想到することができ るといえる。
したがって、乙1−3発明に接した当業者が乙1−3発明から出発して相 違点1−3−1の構成に至ることは、容易であるといえる。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2024.12.11
令和6(ネ)10033 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月29日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
以上によれば、本件発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見 られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、従来技術の上記課題\nを解決するために、本件発明の構成要件A3ないしC3で特定される前縁\n板を備え、かつ、前縁板の一部である縦板部が構成要件B2及びC1ない\nしC3の構成を備えていることにあると認められるから、構\成要件B2は本件発明の本質的部分であると認められる。 そして、被控訴人製品が本件発明の構成要件B2を充足しないことは、\n補正の上で引用した原判決「事実及び理由」第4の1(2)の説示及び前記2 のとおりであるところ、この相違点は本件発明の本質的部分であることに なる。
したがって、被控訴人製品は、本件発明の本質的部分を備えておらず、 均等の第1要件を満たさない。 控訴人は、庇板の内外の雨水をともに縦板部の下端まで導いて落下させ る構成が本件発明の本質的部分であり、構\成要件B2の被控訴人製品と異 なる部分は本件発明に特有の作用効果を生じさせるための部分でなく、本 件発明の本質的部分ではないと主張するが、前記説示に照らし採用するこ とができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
2024.12.11
令和6(ネ)10033 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月29日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
これを本件についてみるに、本件発明において、従来技術の庇は、前記 2(2)のとおり、樋板9の幅wの分だけ庇板2の前方へ余分に突き出るため 庇の全長が必要以上に長くなる、樋板9が樋溝95a、95bを備えてい るので構造が複雑化して庇がコスト高となるとの課題のほか、樋溝95a、\n95bは上面が開放されているため塵芥が堆積しやすく、頻繁な保守、点 検が必要となること、樋溝95bに塵芥が堆積して雨水の通路が塞がれる と、突出部93と庇板2の下面との隙間98より雨水が外部へ浸出し、決 められた箇所以外の随所から雨水が漏れ出て流れ落ちるという課題があ り(段落【0006】)、本件発明は上記課題を発明が解決しようとする課 題とした。そして、本件発明は、この課題を解決するための手段として、 本件発明の構成要件A3ないしC3で特定される「前縁板」が、「庇板の開\n放された前端面を塞ぐように全幅にわたって取り付けられ」(構成要件A\n3)、「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド 面となっている縦板部」(構成要件B2)を備えることで、庇板の前方への\n突出部分をなくすことができ、庇の全長が短くなり小型化が図られ、構造\nの複雑化を招かないものとした(段落【0014】)。さらに、前縁板の一 部である縦板部について、上記構成要件B2のほか、「縦板部の下部内面に\nは、全幅にわたる凹部が形成され」(構成要件C1)、「凹部は開口部分の上\n部が庇板の中空部と連通するように庇板の開放された前端面と対向し」 (構成要件C2)、「開口部分の下部が外部と連通するように庇板の下方へ\n突出して」(構成要件C3)いることで、縦板部の凹部が縦板部の内面の側\nに開口することとなり、塵芥が堆積するおそれがなく、仮に凹部に塵芥が 付着しても雨水により外部へ洗い流される構造が実現されるものであっ\nて(段落【0014】)、このことは当業者であれば容易に理解し得るとい える。
以上によれば、本件発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見 られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、従来技術の上記課題\nを解決するために、本件発明の構成要件A3ないしC3で特定される前縁\n板を備え、かつ、前縁板の一部である縦板部が構成要件B2及びC1ない\nしC3の構成を備えていることにあると認められるから、構\成要件B2は本件発明の本質的部分であると認められる。 そして、被控訴人製品が本件発明の構成要件B2を充足しないことは、\n補正の上で引用した原判決「事実及び理由」第4の1(2)の説示及び前記2 のとおりであるところ、この相違点は本件発明の本質的部分であることに なる。
したがって、被控訴人製品は、本件発明の本質的部分を備えておらず、 均等の第1要件を満たさない。 控訴人は、庇板の内外の雨水をともに縦板部の下端まで導いて落下させ る構成が本件発明の本質的部分であり、構\成要件B2の被控訴人製品と異 なる部分は本件発明に特有の作用効果を生じさせるための部分でなく、本 件発明の本質的部分ではないと主張するが、前記説示に照らし採用するこ とができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> ピックアップ対象
2024.11.19
令和5(ワ)70393 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年9月26日 東京地方裁判所
原告は、上記認定に係る本件明細書【0050】につき、「一般的に用 いられる円管又は角筒管の支柱に比べ、必要に応じて、短手方向の幅を薄 くすることができる」との一文は、「支柱」を主語とする記載であるから、 本件各発明は、短手方向の幅を薄くする必要がない場合には、円管又は角 筒管の支柱を排除するものではなく、「回動板状部材」には、角筒管も含 まれる旨主張する。
そこで検討するに、本件明細書【0050】には、「以上説明した仮設 防護柵1の効果を説明する。回動板4は板であり、短手方向に厚さを有し、 回動板4が定着板3,3の間に配置され、2つの回動軸により回動可能な\n構成であるので、ガードレール6と回動板4を倒した状態で、基礎架台2\nの上方に形成されたウェブ部22の短手方向の幅に収容することができ る。ガードレール6と回動板4を起立した状態で、ボルト、ナットにより、 定着板3により回動板4を固定できる。一般的に用いられる円管又は角筒 管の支柱に比べ、必要に応じて、短手方向の幅を薄くすることができる。 仮設防護柵1を小型化、軽量化、コンパクト化を達成でき、設置・撤去作 業の効率化を図ることができる。道路路肩、歩車道境界のみならず、上り 車線・下り車線を分離するためにも使用することができる。」と記載され ている。
上記記載によれば、「一般的に用いられる円管又は角筒管の支柱に比べ、 必要に応じて、短手方向の幅を薄くすることができる。」との一文は、板 である「回動板4」について説明する文脈に続くものであり、その直後に、 「仮設防護柵1を小型化、軽量化、コンパクト化を達成でき、設置・撤去 作業の効率化を図ることができる。」という本件各発明の効果が記載され ていることを踏まえても、上記一文の主語は、「回動板4」であると解するのが相当である。 仮に、原告の主張のように、「(円管又は角筒管を含む)支柱」を主語 にした場合には、本件各発明の効果を奏し得ない構成をも含むことになる\nから、本件明細書【0050】の効果に係る上記記載に矛盾する上、本件 各発明の課題を解決できない構成を含むことになるため、本件各発明の課\n題解決手段に照らし、相当であるとはいえない。そうすると、原告の主張 は、本件各発明の課題解決手段を正解するものといえない。
原告は、本件明細書【0032】に「回動板4の形状は矩形に限定され ず、楕円、小判等の縦長形状等、適宜の形状を取り得る。」との記載があ るほか、【0060】に「回動板4は中実板に限らず、中空板等、板から 構成される部材であれば、他の形態でもよい。」との記載があることから\nすると、中空の四角形に構成された角筒状の回動部材107も、上記「回\n動板状部材」に含まれる旨主張する。
しかしながら、原告引用に係る本件明細書【0032】には、かえって、 「回動板4は正面形状が矩形状で所定の厚さの存する薄板であり」と記載されていることからすると、上記明細書の記載は、「薄板」とはいえない 角筒状の回動部材107を含む趣旨ではないことは、明らかであるから、 原告主張は、その前提を欠く。また、【0060】についても、「中実板 に限らず、中空板等、板から構成される部材」という記載であるから、文\n字どおり、「中実板」、「中空板」その他の「板」の形状からなる部材を 意味するものと解するのが相当であり、前記認定に係る課題解決手段に照 らしても、上記記載は、「板」とはいえない角筒管を含む趣旨ではないこ とは、明らかである。そうすると、原告の主張は、本件各発明の課題解決 手段を正解するものといえない。
その他に、原告は、技術説明会においても、本件各発明の課題は、基礎 架台の短手方向の厚みを薄くするというものではなく、基礎架台に起伏す る部材が基礎架台に収納できるようにして設置・撤去の作業効率を上げる ものである旨主張するものの、本件各発明の課題は、本件明細書【000 7】等の記載を参酌すれば、文字どおり、仮設用防護柵の起伏する部材の 幅を小さくすることであって、基礎架台の短手方向の厚みを薄くすること にある。そうすると、その他の原告の主張を含め、原告の主張は、本件各発明の課題解決手段を正解するものといえない。したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
ウ 以上によれば、被告製品は、本件各発明にいう「回動板状部材」(構成\n要件1Dないし1G及び2Dないし2H)を充足するものとはいえない。
(2) 争点1−2(均等侵害の成否)について
原告は、仮に被告製品の角筒状の回動部材107が、本件各発明の「回動板 状部材」を充足しないとしても、被告製品の角筒状の回動部材107は、本件 各発明の「回動板状部材」と均等なものとして、その技術的範囲に属すると主 張する。
しかしながら、本件各発明の課題解決手段は、回動部材を板状にすることに よって、基礎架台(H形鋼)の短手方向の厚みを薄くするものであることは、 上記において繰り返し説示したとおりである。そうすると、本件各発明の「回 動板状部材」は、本件各発明の課題解決手段そのものであるから、本件各発明 の本質的な部分ではないということはできず、また、これを、被告製品の角筒 状の回動部材107に置き換えると、本件各発明の課題を解決することはでき ず、本件各発明と同一の作用効果を奏するものとはいえないことは、前記説示 に照らし、明らかである。 そうすると、被告製品は、本件各発明の特許請求の範囲に記載された構成と\n均等なものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> ピックアップ対象
2024.11.18
令和4(ワ)11025等 特許権侵害差止等請求本訴事件、不当利得返還請求反訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月21日 大阪地方裁判所
上記本件明細書の記載によると、本件発明は、大きなダニ捕獲能力を発揮\nすることを目的として、その手段は、ダニ誘引物質を含浸させた織物シート からダニ誘引物質を拡散させることで広い範囲のダニを誘引した上で、マッ トの内部にダニ捕獲用の粘着テープと、これに対して千鳥状に被着させたダ ニ用食餌を入れた多孔質通気性袋を配することで、ダニ誘引物質で誘引され たダニを、マットの表裏両面からさらに内部に侵入させ、粘着テープに触れ\nさせ、そこで捕捉するようにするというものである。 そして、ダニを誘引させる物質として、「香料」を織物シートに含侵させた 上、「食餌」入りの多孔質通気性袋を配置させる位置を両面粘着テープの表\n裏両面に配置させることにより、多孔質通気性カバーの内側に誘い込み、混 ぜ物のない粘着層に触れさせて補足させる構成をとるものであるから、本件\n発明において「多孔質通気性袋」は、食餌が同位置にとどまり、粘着層の粘着 力を低減させない機能を備えるべきことが想定されているといえる。加えて、\n多孔質通気性袋の構造上、一袋でこれらが実現でき、構\成材料の数も減らす ことができるようになっている。
以上を踏まえると、構成要件A−3にいう「多孔質通気性袋」とは、辞書\n的にも、本件明細書の記載からも、少なくとも内包物を内部で保持し、拡散 を防止することができる構造を有することが必要であると解することが相当\nである。一方、販売被告製品では、ダニ誘引物質が2枚の不織布シートやガ ーゼ等で重ねて挟み込まれているのみであり、その周囲からダニ誘引物質が 零れ落ちるようなものであるから、誘引物質を内部で保持することができる 構造であるとは認められない。\n
この点、原告は、本件発明における「袋」の意義について、ダニ食餌を入れ ることができ、かつ、一つの袋のみで粘着テープの表裏両面に配置すること\nができればよく、口を閉塞している必要はないから、被告製品も、多孔質通 気性袋を有すると主張するが、上記説示に照らし、採用できない。
(5) よって、販売被告製品は、構成要件A−3を充足せず、同構\成要件を充足 することを前提とする構成要件C、D、F及びGも充足しない。\n
3 争点A3(均等侵害が成立するか)について
上記2のとおり、本件発明は、ダニ食餌を零れ落ちさせることなく保持する ことができる「多孔質通気性袋」に収納することで、粘着テープの高い粘着力 を実現するとともに、構成材料の数を減らすことを実現しており、そのために\n袋構造を有することが本質的要素となっているものと認められる。\nそうすると、多孔質通気性袋に代わり、挟み込んだ物が零れ落ち得る2枚の 不織布やガーゼでダニ誘引物質を挟み込む構造を有している販売被告製品は、\n本件発明の非本質的部分で相違点があるに過ぎないとはいえないし、これらを 置換したときの作用効果が同一であるともいえない。
よって、第1要件(非本質的部分)及び第2要件(置換可能性)がいずれも\n認められないことから、均等侵害は成立しない。
4 小括(特許権侵害について)
(1) 以上の次第であり、被告製品は、本件特許の技術的範囲に属しないので、 原告の本件特許権侵害に関する主張(争点A1ないしA6)は、その余の争 点について判断するまでもなく理由がない。
(2) なお、被告は、原告の均等侵害の主張について、時機に後れた攻撃防御方 法として却下することを求めているが、その審理のために訴訟が遅延するも のとは認められないから、採用しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.11.13
令和5(ヨ)30402 特許権に基づく差止及び廃棄仮処分命令申立事件 特許権 民事仮処分 令和6年9月20日 東京地方裁判所
(1) 疎明資料(疎甲7)によれば、本件債務者製品は、「前記落とし口部の上方 に対向して配置され、水平方向に延びるフランジ状の平板部と、この平板部の 内周側から下方に向かって縮径するように延びるテーパー部と、このテーパー 部の下端から下方に向かって延びる円筒部とを有する落とし口対向部」を備え ていることが認められ、これらの構成を有すること自体は、当事者間に争いは\nない。
(2) そして、本件発明2−2の構成要件2−2−Dの「蓋部材」は、特許請求の\n範囲の記載上、「落し口部の上方に配置される」ものとされており、その余の 限定はされていない。また、本件明細書2の記載によれば、「鉛直方向の上方 から見て落し口部の開口を塞ぐように配置される形状であれば良い。」(段落 【0081】)との記載があるものの、第1実施例における【表1】のケース\n1及び【表2】のケース11によれば、落とし口部の開口を完全に塞ぐように\n配置されていない形状についても、これを完全に塞ぐように配置された形状と 同様に、サイフォン現象が生じていることが確認されている(段落【0068】)。 上記構成要件及び本件明細書2の各記載によれば、本件構\成要件にいう「蓋部材」は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていない形状も含む ものであり、落とし口部の上方に配置されれば足りるというべきである。 これを本件債務者製品についてみると、上記認定事実によれば、本件債務者 製品の落とし口対向部は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されてい ないものの、落とし口部の上方に配置されているものと認められる。そうする と、本件債務者製品の落とし口対向部は、構成要件2−2−Dの「蓋部材」を\n充足するものと認めるのが相当である。
(3) これに対し、債務者らは、「蓋部材」とはその直径が落とし口部外径の直径 より大きく、落とし口部の開口を覆い塞ぐものに限られると主張するものの、 上記において説示したところを踏まえると、採用することができない。
また、債務者らは、「蓋部材」は単なる開口よりも優れたサイフォン効能を\n発揮させる部材でなければならず、本件債務者製品はこれに該当しないと主張 する。しかしながら、本件発明2−2の特許請求の範囲及び本件明細書2の各 記載には、債務者ら主張に係る限定がされているものと認めることはできず、 債務者らの主張は、採用の限りではない。 さらに、債務者らは、本件債務者製品のテーパー部は「誘導ガイド」(本件 特許2の請求項5)に当たるから、「蓋部材」には該当しないと主張する。し かしながら、上記にいう「誘導ガイド」は、本件発明2−2ではなく、本件特 許2の請求項5で特定される構成にすぎず、仮に、同請求項5の記載をみても\n「前記蓋部材の下面には、誘導ガイドが形成され」と記載されるにとどまるこ とからすると(疎甲4)、「誘導ガイド」は、「蓋部材」の一部として構成さ\nれ得るものと認めるのが相当である。そうすると、債務者らの主張は、「誘導 ガイド」の構成を正解するものとはいえない。\n したがって、債務者らの主張は、いずれも採用することができない。 その他に、債務者らの主張を改めて検討しても、債務者らの主張は、本件発 明2−2の構成要件及び本件明細書2の各記載に基づかないものに帰し、いず\nれも採用の限りではない。
(4) 以上によれば、本件債務者製品は、構成要件2−2−Dを充足するものと認めるのが相当である。\n
3 争点2(本件債務者製品の縦リブの「前記鍔部の上面と前記蓋部材の下面の外 周部とを連結する」該当性(構成要件2−2−E))\n
(1) 疎明資料(疎甲7、14)によれば、本件債務者製品の整流板(債権者が同 製品における「縦リブ」と呼称する部分をいう。以下同じ。)は、落とし口対 向部のうち平板部の下面に接続しており、当該下面の接続部分は、上記落とし 口対向部の下面の外周部に位置するものと認められる。そして、疎明資料(疎 甲7、14)によれば、整流板は、同製品の鍔部の上面と接続しているものと 認められる。
そうすると、本件債務者製品の構成のうち、構\成要件2−2−Eの「縦リブ」 に相当する整流板は、「鍔部の上面」と、「蓋部材」に相当する落とし口対向部の「下面の外周部」とを連結していることが認められる。 したがって、本件債務者製品は、構成要件2−2−Eを充足するものと認め\nるのが相当である。
(2) これに対し、債務者らは、本件債務者製品の整流板が3つの部材(分割板、 流入促進部、渦流防止部材)に分かれることを前提として、分割板のうち鍔部 上にある部分は落とし口対向部と連結しておらず、渦流防止部材は鍔部に連結 していないから、いずれも構成要件2−2−Eを充足しない旨主張する。しか\nしながら、本件発明2−2の構成要件及び本件明細書2の各記載を踏まえても、\n債務者ら主張に係る「分割板」、「流入促進部」、「渦流防止部材」という概 念が使用されていないことからすると、少なくとも構成要件充足性を検討する\nに当たっては、本件債務者製品の整流板を上記にいう3つの概念で区分するの は相当ではない。のみならず、債務者パナソニックの販促資料(疎甲14)に\nよっても、債務者パナソニックは、本件債務者製品の整流板を上記3つの概念\nで区別していないのであるから、取引の実情等を踏まえても、債務者らの主張 は、独自の見解というほかない。
また、債務者らは、「縦リブ」は「鍔部上にのみ」配置されるものであると 解した上で、本件債務者製品の整流板は、落とし口部の開口に重なり「鍔部上 のみ」に配置されていないため、「縦リブ」に該当しない旨主張する。しかし ながら、特許請求の範囲の記載上、債務者主張に係る限定はされていない。そ して、本件明細書2(段落【0034】)には「上面視で落し口部20に重な らない位置で周方向に間隔をあけて配置された複数の縦リブ23」という記載 が認められるものの、他方、本件明細書2(段落【0083】)には「縦リブ 23の形状、数量についても本実施の形態に限定されることはなく」と記載さ れていることからすれば、本件発明2の上記認定に係る技術的特徴に鑑みても、 「縦リブ」は、蓋部材を下方から支持し、雨水を整流する機能を有しているも\nのであれば足り、必ずしも鍔部の真上にある構成に限定されるものとはいえな\nい。そうすると、債務者らの主張は、前記判断を左右するものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 104条の3
2024.11.13
令和5(ワ)70178 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年9月26日 東京地方裁判所
(1) 「乾燥して造粒物を得る工程」の終期
本件の争点整理の経過に鑑み、主たる争点である争点1−2のうち、中核 的争点である「乾燥して造粒物を得る工程」の終期がいつであるかという点 につき、まず判断する。この点につき、原告は、「乾燥して造粒物を得る工程」 の終期とは、「打錠用粉体に適した造粒物を得るために必要な状態まで溶媒が 除去された時点」(原告はこの時点までの乾燥を「必要な乾燥」といい、これ 以降の乾燥を「余分な乾燥」として区分している。)である旨主張する(第4 回弁論準備手続(技術説明会)調書参照)。
そこで検討するに、本件明細書に係る前記認定事実によれば、本件明細書 の記載(【0010】、【0033】等)を踏まえると、本件発明の課題は、酢 酸亜鉛水和物中の結晶水が消失して無水物に転移することを防ぐことにあり、 その課題の解決手段としては、乾燥工程における品温を40゜C)未満とするも のであると認めるのが相当である。そして、「乾燥」とは、一般的に熱を与え るなどして不要の液体分を取り除くことを意味するものであり(甲9、10)、 本件明細書においても、上記と異なる意味で使用されているところはない。 そうすると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を 意味するものであり、その終期とは、文字どおり、全ての乾燥が終了した時 点であると解するのが相当である。 これを原告の上記主張についてみると、原告は、乾燥には「必要な乾燥」 と「余分な乾燥」に区分され、「余分な乾燥」では40゜C)を超えることが許容 される趣旨をいうものである。
しかしながら、本件発明の構成要件及び本件明細書を精査しても、原告が\n自認するように、「必要な乾燥」と「余分な乾燥」に区分されるという原告の 解釈を裏付ける記載や示唆は一切なく、上記の間にある「打錠用粉体に適し た造粒物を得るために必要な状態まで溶媒が除去された時点」という原告主 張に係る概念も、本件発明の構成要件及び本件明細書に一切記載されておら\nず、それ自体明確性を欠くことに鑑みても、原告の主張は、その根拠を欠く ものというほかない。
かえって、原告の主張によれば、「余分な乾燥」では40゜C)を超えることが 許容されることになるから、乾燥工程における品温を40゜C)未満とする本件 発明の課題解決手段に明らかに抵触するものとなり、本件明細書によれば本 件発明の課題を解決できないことになる。そうすると、原告の主張は、本件 発明の課題解決手段を正解しないものといえる。 したがって、原告の主張は、採用することができない。
(2) 被告方法への当てはめ
前記認定事実によれば、被告医薬品の医薬品製造販売承認書には「乾燥終 点における製品温度は《50゜C)》以下とする」と記載されており、被告医薬 品に係る製造指図記録書においては、いずれも、品温41.0゜C)以上で乾燥 終了との指示がされていることからすると、被告方法における「乾燥して造 粒物を得る工程」では、品温が41゜C)以上になることが認められる。そうす ると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を意味する ものであるから、被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温 が40゜C)未満」という構成要件を充足するものとはいえない。\nしたがって、被告方法は、構成要件1−1A及びC、1−3D、2−1A\n及びC、2−3Dを充足するものと認めることはできない。
・・・
3 争点1−1(特許法104条による推定の可否)
(1) 被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温が40゜C)未満」 という構成要件(構\成要件1−1A及びC、1−3D、2−1A及びC、2 −3D)を充足しないことは、前記2において説示したとおりである。 そうすると、仮に、被告医薬品が特許法104条に基づき本件発明に係る 製造方法により生産したものと推定された場合であっても、前記2において 説示したところによれば、当該推定は、覆されるものと認めるのが相当であ るから、争点1−1は、本件において結論を左右するものとはならない。 もっとも、当事者双方の主張の経過に鑑み、念のため判断するに、前提事 実及び前記認定事実によれば、本件発明の優先日前に出された本件ニュース リリースには、「NPC−02(酢酸亜鉛)ウイルソン病治療剤ノベルジン® 錠25mg及び50mgの製造販売承認(剤形追加)を取得」という記載が あるところ、本件ニュースリリース前から原告によって販売されているノベ ルジンカプセル25mg及び50mgは、ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害\n剤)であり、酢酸亜鉛水和物を有効成分とするカプセル剤である。そして、 前記認定事実によれば、剤形追加に係る医薬品とは、既承認医薬品等と有効 成分、投与経路、効能・効果及び用法・用量は同一であるが、剤形又は含量\nが異なる医薬品をいうことからすると、本件ニュースリリースに係る医薬品は、ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)であり、酢酸亜鉛水和物を有効成\n分とする酢酸亜鉛錠であるものと認められる。 これらの事情の下においては、本件ニュースリリースに係る医薬品は、本 件発明により生産される物と同一のものといえるから、本件ニュースリリー スの掲載により同医薬品の存在が対外的に公表されているといえる。そうす\nると、本件発明により生産される「物」は、本件発明の優先日前の時点にお いて、当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られたもので あったと認めるのが相当である。 したがって、被告医薬品は、特許法104条に基づき、本件発明に係る製 造方法により生産したものと推定することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2024.10.28
令和4(ワ)70058 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月18日 東京地方裁判所
(ウ) 前記(イ)によれば、本件特許の出願時において、グラップルバケット装 置において、グラップルした木材が長尺である場合、所定以上の長さを 有する木材をチェーンソー等の切断装置を用いて作業員が所定の長さに\n切断しなければならないとの課題については、甲27文献において開示 された従来技術によって解決することが可能であったから、本件明細書\nにおいて従来技術が解決できなかった課題として記載されているところ は、出願時の従来技術に照らして客観的に不十分であると認められる。\nそうすると、本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分を認定するに当たり、甲27文献に記載されている技術 的事項も参酌することが許されるというべきである。
(エ) 前記(ウ)において検討したところによれば、本件特許の出願前に、甲2 7文献において、一方の側部に把持部、他方の側部に切断装置が装着さ れているバケットを備えた枝切り走行装置が開示されていたと認められ るから、本件発明と従来技術との相違は、当該切断装置の構成に係る部\n分にすぎず、グラップルした被グラップル材を切断できるようにしたグ ラップルバケット装置であること自体ではないと認められる。そうする と、従来技術と比較して本件発明の貢献の程度が大きいと評価すること はできないから、本件発明の本質的部分については、これを上位概念化 したものとして認定することはできず、特許請求の範囲の記載とほぼ同 義のものとして認定されるというべきである。
したがって、前記(ア)及び(イ)に照らし、本件発明における従来技術に 見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、グラップル装置\nに設けられた切断装置について、バケットの側壁の外側あるいは内側の 一方側に位置してバケットの開口縁から離れた位置からバケットの側壁 に沿う位置にわたって側壁に沿う方向に回動し、かつバケットの開口縁 側に対向する側の側縁に切刃を有してバケットの側壁に沿う位置にわたって側壁に沿う方向に回動し、かつバケットの開口縁側に対向する側の側縁に切刃を有してバケットの開口基端部に枢支された切断刃と、上記切断刃の回動基部に連結して上記切断刃を回動させる油圧シリンダとからなり、切断刃の切刃を、切断刃の回動中心と油圧シ リンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃の切断方向側にずれた位置に設 けるとともに、この切刃の切断方向への回動方向に対して後方へ円弧状 に反らせたとの構成、すなわち構\成要件C及びDに係る構成を採用する\nことによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾き 角度θの値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効 果を発揮できるようにしたことと認めるのが相当である。
イ 前記2のとおり、被告製品は構成要件D2を充足するとは認められない\nところ、前記アのとおり、本件発明の構成要件C及びDに係る構\成を採用 することによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾 き角度θの値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効 果を発揮できるようにしたことが本件発明の本質的部分であるから、被告 製品が本件発明の本質的部分を備えているとは認められず、本件発明と被 告製品とが異なる部分が本件発明の本質的部分ではないとはいえない。 したがって、被告製品は第1要件を充足しない。
◆判決本文
以下に、イ号図面などがあります。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和4(ワ)9112等 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年8月22日 大阪地方裁判所
ア 上記本件明細書の記載からは、経糸、緯糸、パイル糸の「径」を認識する 方法は見当たらず、また、経糸又は緯糸の径がパイル糸の径よりも細くされ ることについての技術的意義に関する記述はない以上、そこから上記の「径」 を認識する方法を推測することもできない(原告は【0043】の記載を指 摘するが、パイル糸に「多数の微細長繊維を含ませる」ことと、基布の経糸 又は緯糸の繊度(太さ・細さ)との関係は不明というほかない。)から、これ らは当業者の理解する技術常識によって決すべきこととなる。 イ この点、繊維の形態的な太さは、一般的にその断面が不規則な形状を示し ているので、正確な計測は困難であり、したがって、一定の長さ当たりの重 量で繊維の太さが示されているとされ、また断面の形状にあっては、天然繊 維の形状は、それぞれ特有の形をしており、化学繊維は、その形状も人為的 に自由につくることができ、断面は主として紡績方法によって決まり、円形・ だ円形その他複雑なものもある、とされている(乙4。三訂版「繊維」(昭和 61年刊行))。
また、繊維における細さ(繊度)にはいろいろの表し方があり、メートル\n法の番手(1グラムの糸が何メートルの長さを持つかを示すもの。番手が大 きいほど糸は細い。)や、デニール、テックス(いずれも一定長の糸の重量) が用いられ、デニールと繊維ごとの比重を用いて断面積を算出する方法もあ る(乙5。「繊維の科学」(昭和53年刊行))。撚りの強さによっても見た目 の太さが変わる(乙6。令和2年当時のウェブサイト。)。本件明細書におい ても、パイル糸の繊度に関し、デニールが用いられている部分がある。
ウ ところで、「径」の字義は、「1)さしわたし。直径。2)みち。小道。近道。」 というものである(乙7(広辞林第六版))。また、広辞苑第七版においては、 「まっすぐ結ぶ道。さしわたし。」とされており、「差渡し(さしわたし)」の 字義は、「1)さしわたすこと。一方から他方へかけ渡すこと。また、その長さ。 2)直径。わたり。けい。」とされている。これらを踏まえると、「径」とは「直 径」を意味するものと解される。「直径」の字義は、「円または球の中心を通っ て円周または球面上に両端をもつ線分。また、その長さ。さしわたし。」とい うものであるから(広辞苑第七版)、「直径」が認識されるためには、平面に おいては円又はそれに近い形状のものが想定されていると解される。 他方、前記のとおり、糸は繊維の集合体であって、繊維の断面は一般的に 不規則な形状を示すものであるから、少なくとも、「径」の大小の比較に、「断 面積」(空隙を除外するかどうかを問わない)を用いることはできないものと 解される。この点、原告は、糸の太さを断面積で表すことが当業者にとって\n一般的な手法となっていたとしてその旨の証拠(甲25から27まで)を提 出するが、それらは口輪筋線維、等方性黒鉛材料の気孔、血管について画像解析により断面積を測定した例にすぎず、技術分野が全く異なるもので、原告主張の事実は認めるに足りない。
(3) 構成要件1Cの充足の検討\n
ア 原告は、各糸の径は糸の断面積を測定することにより比較判断することが 可能であり、かつこれを製品状態で測定すべきものとした上で、かかる測定\n方法を採用した測定結果を証拠(甲19の1・2)として提出する。 この測定は、被告製品のシール材に対し、接着剤を滴下して浸み込ませ、 乾燥後、養生テープで固定し、パイル糸の配列方向に対し垂直となるように、 シール材に金尺を当てて、カット治具である剃刀刃を沿わせて一回のスライ スにより切断し、断面画像を撮像した上、該画像を解析して、緯糸とパイル 糸の断面積を求めるというものである。 イ しかし、本件訂正発明1の構成要件1Cは、糸の「径」の大小をその要素\nとしており、糸の太さの比較に断面積を用いることは文言の一義的な意味に 反し、また前述の当業者の技術常識にも合致しないものである。
また、具体的な測定手段をみても、上記測定は、被告製品を加工、破壊し た上で測定するものであって、原告が自らいう「製品状態での測定」とも前 提を異にするものである(そもそも、製品状態では糸に様々な方向から様々 な力が作用し、一定の「断面積」を得ることは困難であると考えられ、「製品 状態での測定」という前提自体、本件明細書や当業者の技術常識から導き得 るのかについて疑問なしとしない。)。加えて、上記切断方法は、繊維の方向 に垂直に正確に切断されることが保証されるものともいえず、切断角度、切 断箇所の違いによる断面積の変化が何ら考慮されていないと見受けられ、測 定の条件統制にも疑義がある。画像解析についても、糸(及びこれを構成す\nる繊維)の外郭のとらえ方や、空隙の有無等によって「断面積」が異なり得 ることが見て取れる。
これらのことからすると、甲19号証の1・2に示された測定手段は、画 像の作成過程、画像解析の双方において、測定の正確性、合理性が担保され たものとはいえないというべきである。 また、画像解析の結果報告される糸の断面(空隙を含む外郭)は、不定形 で円又はそれに近い形状を備えておらず、かかる画像から、「径」(といえる もの)を認識することも困難である。
ウ そうすると、甲19号証の1・2によって、被告製品について構成要件1\nCの充足が立証されたということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠 はない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和5(ネ)10101 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年6月18日 知的財産高等裁判所 (原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)24476
オ 上記ウ及びエによれば、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題 として記載されている従来技術(特許文献1)は、出願時の従来技術に照 らして客観的に不十分であるから、乙3に記載されている技術的事項を参\n酌することが許されるというべきである。 そうすると、本件発明は、上記課題を解決するために「覚醒度合生体情 報取得部で取得した人の覚醒度合に関する生体情報に応じて前記三つの 発光手段の発光量の総和を略一定にしたままそれぞれの発光手段の発光 量比を変化させるための調節部」との構成を採用したものであるが、他方、\n乙3には、上記エのとおり、「覚醒度合生体情報取得部で取得した人の覚醒 度合に関する生体情報に応じて複数(二つ)の発光手段の発光量の総和を 一定としたままそれぞれの発光手段の発光量比を変化させるための調節 部」が開示されており、その相違は「三つの発光手段の発光量の総和」か 「複数(二つ)の発光手段の発光量の総和」かの差でしかない。 したがって、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいとはい えず、本件発明の本質的部分は、特許請求の範囲に近接したものとなると いうべきであり、具体的には、本件特許の課題を解決するために採用され た構成が構\成要件C/Dであることから、「覚醒度合生体情報取得部で取 得した人の覚醒度合に関する生体情報に応じて、赤色、青色及び緑色の三つの発光手段の発光量の総和を略一定としたままそれぞれの発光手段の 発光量比を変化させるための調節部」を有していることが本件発明の本質 的部分であると解するのが相当である。
これに対し、本件各照明装置は、「覚醒度合生体情報取得部で取得した人 の覚醒度合に関する生体情報に応じて、赤色、青色及び緑色の三つの発光 手段の発光量の総和を略一定としたままそれぞれの発光手段の発光量比 を変化させるための調節部」を有していないから、本件発明と本件各照明 装置とは本質的な部分において異なっているというべきである。
カ 上記アないしオによれば、本件各照明装置が本件発明の本質的部分を備 えているとはいえず、均等の第1要件を満たさない。
キ 控訴人は、前記第2の5(1)アのとおり、本件発明は、ヒト(人)の覚醒度 合に応じて照度を略一定にしつつ色温度を変化させる点がその本質的部 分であると主張する。 しかし、上記オに説示したとおり、特許発明の貢献の程度は従来技術と 比較して大きいとはいえないから、控訴人が主張するようにこれを上位概 念化することはできないというべきであり、控訴人の上記主張を採用することはできない。また、仮に、控訴人の主張するとおり、人の覚醒度合に応じて照度を略 一定にしつつ色温度を変化させる点が本件発明の本質的部分であると解 したとしても、本件各照明装置は、人の覚醒度合に応じて照度を略一定に しつつ色温度を変化させる構成を有していないから、均等の第1要件を満\nたさないとの結論を左右しない。
すなわち、本件マットレス(1)は、当該マットレスを使用する人の睡眠の 状態を計測する機能を備えており、本件発明の構\成要件B(「人の覚醒度合 に関する生体情報を取得する覚醒度合生体情報取得部と、」)を充足するも のであり、本件マットレス連携アプリは、本件マットレス(1)を使用した人 の睡眠深度、睡眠スコア、睡眠効率、寝つき時間、中途覚醒回数、目覚め の状態及び深い睡眠を表示する機能\を備えているが(原判決第2の2(6)ア 及びウ、同(7))、本件各照明装置は、本件マットレス(1)等により取得された 人の覚醒度合に関する生体情報に応じて照度を略一定にしつつ発光手段 の発光量比又は色・温度を変化させる機能を有していない。\n
本件各照明装置の使用者が、任意に本件各照明装置の発光手段の色・温 度を変化させる操作をすることが可能であるとしても、そのことをもって、\n本件各照明装置が人の覚醒度合に応じて照度を略一定にしつつ発光手段 の発光量比又は色・温度を変化させる構成を有していることにはならない。\nしたがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
ク 以上によれば、本件各照明装置は、均等の第1要件を充足しないから、 その余の要件について判断するまでもなく、本件発明と均等なものとして、 その技術的範囲に属するということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2024.08.27
令和4(ワ)22517 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年8月21日 東京地方裁判所
被告は、トイレットペーパーの表面、裏面の各シートをそれぞれ表\面に凹凸 をつけるエンボス処理した後、それぞれのシートの凸部同士を内側にして2プ ライにするようなダブルエンボスでは、表面と裏面のシートのエンボスが干渉\nし、これらを常に干渉しないようにすることはほぼ不可能であり、付与された\n後のエンボスの形状、深さを明確に測定することができないので、本件発明1 は、シングルエンボスのトイレットロールのみに限定されると主張する。 しかしながら、本件明細書1記載の方法でエンボス深さDを測定することが でき、そこで測定されたエンボス深さDに本件発明1の技術的意味があるもの であれば、本件発明1のトイレットロールが、シングルエンボスのトイレット ロールに限定されるとは認められない。また、トイレットロールにおけるエン ボスであるという性質上、各エンボスの形状については一定のばらつきがある ことが想定されているといえる。
もっとも、本件発明1のエンボス深さDは、X−Y平面上のエンボスの高さ プロファイルを得ることができ(【図5】(a))、エンボスの周縁frやその最 長部aがどこに位置するのかを特定できるトイレットロールについて、【図5】 (b)、【図6】のような断面曲線を得た上で、測定されたものであり、そのよう にして測定されたものであるエンボス深さDが一定の数値のトイレットロール について本件発明1の効果を奏するとしているものといえる。各被告製品は、 各シートのエンボスの凹凸の位置関係を特に調整しないまま、プライボンディ ングした通常の2プライのダブルエンボスである(弁論の全趣旨)。このような ダブルエンボスのトイレットロールにおいては、表面と裏面にそれぞれ付され\nたエンボスが重なるとは限らず、エンボスの周縁が一致することが保証されて いないことから、エンボスの周縁が明確にならず、また、エンボスの凹凸の位 置がずれることにより干渉し、その形状が明瞭でないエンボスが生じ得る。そ して、甲51報告書によれば、各被告製品については、原告がエンボスとして 特定した部分の中央に、断面曲線で上に凸の曲率極大点が認められるなど、そ のエンボスが本件発明1のエンボス深さDを測定する際に想定されていた凹部 形状のものであるかが必ずしも明らかではないほか、X−Y平面上のエンボス の高さプロファイルによって、エンボスの周縁frやその最長部aがどこに位 置するのかを確定できるものとは必ずしもいえない。そうすると、そのような エンボスが付された各被告製品のトイレットロールについてエンボスを10個 選んで測定を行い、それらの平均値として一定の深さDを求めたとしても、本 発明1におけるエンボス深さDが測定できたということはできない。
(7) 以上によれば、原告測定方法は、本件明細書1に記載されたエンボス深さの 測定方法とはいえず、原告測定方法に基づいた甲10報告書によって、各被告 製品が構成要件1Bを充足するとは認めることはできない。甲51報告書その\n他の証拠によっても、各被告製品について、本件発明1におけるエンボス深さ Dが明らかであってその数値が構成要件1Bを充足するということを認めるに\n足りない。したがって、各被告製品はいずれも構成要件1Bを充足するとはいえない。\n
・・・・
構成要件2Eは、「前記把持部には、ほぼ中央に上向きに非切抜部を有するほ\nぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴、又は上向きに非切抜部を有して横方向 に沿って並ぶ二個の指掛け穴が形成されており、」というものであり、特許請求 の範囲の「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴」 との文言は、その「指掛け穴」が既に「形成」されているものであることから も、その「形成」されている「指掛け穴」が「ほぼ長円の一つのスリット状」で あり、また、そのほぼ長円の上部輪郭が非切抜部であると理解することができ るものであるところ、本件明細書2の上記部分には、そのような理解に沿う構\n成が記載されているということができ、そのような理解を前提として、その「ス リット状のほぼ長円」の上部輪郭の非切抜部を固定端とする片部がスリットの 切り抜きにより上方に折り返されるものであることが記載されているといえる。 また、【図1】に記載された指掛け穴も上記の理解に沿ったものである。そうす ると、構成要件2Eの「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット\n状の指掛け穴」とは、同構成について本件明細書2において記載されている、\n上記に述べたとおりの構成のものであると認められる。\n
(2) 被告製品1の包装袋のスリットは、写真2の左側の写真の赤破線で示された とおりのものであり、被告製品3の包装袋のスリットは、写真2の右側の写真 の赤破線で示されたとおりのものである。 前記(1)のとおり、構成要件2Eについては、その「指掛け穴」が「ほぼ長円の\n一つのスリット状」であって、その「スリット状」の「ほぼ長円」の上部輪郭の 非切抜部を固定端とする片部がスリットの切り抜きにより上方に折り返される ものであり、その非切抜部は、「スリット状」の「ほぼ長円」の一部を構成する\nものである。そして、非切抜部を固定端とする片部が上方に折り返されるため には、その非切抜部の固定端が、「スリット状」の「ほぼ長円」の上部輪郭にあ る必要がある。
被告製品1及び被告製品3の包装袋のスリットをみると、その両端部はそれ ぞれ外側に湾曲して下方に向かい、終端が内側に位置しているから、このよう なスリットの両端部の終端の位置を考慮すると、被告製品1及び被告製品3に おいては、形成されている「スリット状」の「指掛け穴」の下部輪郭が「非切抜 部」であるともいえ、その非切抜部を固定端とする片部がスリットの切り抜き により上方に折り返されるものではない。また、原告主張の熱融着部(写真3 参照)とスリットとを見ると、スリットは、その中央が、その上方に対しては、 弧状であるとしても、その左右には、上方への折り返しとなる頂点が存在せず、 それ自体「ほぼ長円」を形成しているとはいえず、「スリット状」の「ほぼ長円」 が形成されていないから、原告主張の上記熱融着部の円弧が「スリット状」の 「ほぼ長円」の上部輪郭にあるとはいえず、そこを構成要件2Eの「非切抜部」\nであるということはできない。そうすると、被告製品1及び被告製品3には、 「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴」に相当 する構成があるとはいえない。\n
(3) 原告は、被告製品1及び被告製品3のスリットが切り抜かれることで把持部 に下に凸の円弧が生じ、スリットと熱融着部などによって形成される非切抜部 によって、ほぼ長円の形状の指掛け穴が形成されると主張する。 しかし、前記(1)のとおり、構成要件2Eにおいては、形成されている「指掛\nけ穴」が「ほぼ長円の一つのスリット状」であって、その「スリット状」の「ほ ぼ長円」の上部輪郭の非切抜部を固定端とする片部がスリットの切り抜きによ り上方に折り返されるのであり、その非切抜部は、「スリット状」の「ほぼ長円」 の一部を構成するものである。被告製品1及び被告製品3においては、「スリッ\nト状」の「ほぼ長円」が形成されているとはいえず、被告製品1及び被告製品 3において、スリットの上方の熱融着部などによって形成される部分が構成要\n件2Eの非切抜部であるとする原告の主張は採用できない。
原告は、本件発明2では指掛け穴の有するスリットが内側に回り込んでいるの に対し、被告製品1及び被告製品3ではスリットが内側に回り込んでいない点で、 被告製品1及び被告製品3が本件発明2と文言上相違するとした上で、この点に ついて均等侵害が成立する旨主張する。
しかしながら、被告製品1及び被告製品3においては、スリットは、その中央 部分のみが上方に対して弧状であり、本件発明2の構成とは基本的な形状が異な\nるといえるものなのであって、これが直ちに被告製品1及び被告製品3の製造時 において本件発明2から容易に想到することができたとは認めるに足りず、また、 原告は、本件異議申立事件の決定の予\告後に、指掛け穴を構成要件2Eの構\成に 限定したと述べて構成要件2Eの構\成を加えて、他の構成の指掛け穴の形状を意\n識的に除外したといえる。したがって、均等侵害をいう原告の主張には理由がな い。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第3要件(置換容易性)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2024.07.21
令和3(ワ)2873 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年5月30日 大阪地方裁判所
原告は、被告が、本件書類提出命令にもかかわらず、正当な理由なく、本件提出 対象書類を提出しなかったなどとして、民訴法224条3項により、本件証明事実 を真実であると認めるべきであって、前記被告製品10台に係る限界利益を157 3万8528円と認定すべきである旨主張する。 この点、確かに、被告が本件書類提出命令に応じて本件提出対象書類を提出した とは認められないものの、本件証明事実に係る原告の主張によると、被告製品10 台の利益率は6割を超えるものとなって、合理的とは言い難いことから、被告の限 界利益の額を前記のとおり認定するのが相当である。
(3) 損害の不存在ないし推定覆滅について
ア 被告は、佐賀県畜産公社においては、被告製品の購入に当たって競争入札が 行われたところ、原告と被告が入札して被告が落札したのであって、落札により販 売業者は1社に決定されるから、原告と被告が競合するような市場は存在せず、侵 害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情は存在しないとした上 で、ミヤチク、いわちく及びフードパッカー津軽についても同様であって、原告に 損害はなく、特許法102条2項は適用されない旨主張する。 しかしながら、そもそも、被告が主張する競争入札の存在や具体的内容が明らか ではないところ、佐賀県畜産公社においては、競争入札自体は行われたとしても、 原告も同じ競争入札に参加していたというのであるし、その他の入札についても原 告に参加資格があり、落札したとされる被告が参加していなければ(本件特許権の 侵害品である被告製品がなければ被告は参加できなかったと考えられる。)、原告 が落札した可能性もあることを考慮すると、原告において被告の侵害行為がなかっ\nたならば利益が得られたであろうという事情は存在しない旨の被告の主張は採用で きない。
イ 被告は、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」が本件発明の 唯一の特徴的部分であるといえるところ、仮に被告製品がこの構成要件を充足する\nとしても、利益に対して貢献しているのはその余の侵害品の性能(機能\、デザイン 等特許発明以外の特徴)であって、損害の推定覆滅事情に当たる旨主張する。しか しながら、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」部分以外で顧客誘 引力のある被告製品の具体的性能や、その性能\の顧客に対する訴求の程度は明らか でないから、被告の主張は採用できない。
ウ さらに、被告は、本件発明では旋回流を利用するのに対して(甲5)、被告 製品(乙15)では、突部9(別紙「被告製品写真・図面」の図2参照)が邪魔 板(バッフル)となって旋回流を阻害することで、上下循環流発生を発生させ、豚 足をランダムな動きとするものであり、また軸流においては豚足が下方へ潜り込ん でいくこと、邪魔板(バッフル)に衝突することによる脱毛、豚足同士の水平方向 及び上下方向の衝突による脱毛の効果が甚だ大きく、性能において本件発明と比較\nして顕著な相違があるから、特許法102条2項の推定は覆滅される旨主張する。 この点、原告製品の動画(甲5)と被告製品の動画(乙15)とを比較すると、 豚足の動きに一定の差があり、被告製品では豚足が下に潜り込むような動きをして いるように見え、被告が主張する上下方向の動きがあることがうかがわれる。かか る動きによる豚足の脱毛効果への影響の程度や、その性能の被告製品の売上げへの\n貢献の程度は必ずしも明らかでなく、前記の性能を理由とする推定覆滅が認められ\nるとしても、その割合は、5%を超えるものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2024.06.16
令和4(ワ)2058 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年5月30日 大阪地方裁判所
(1) 特許法102条2項に基づく主張について
ア 限界利益額 被告は、少なくとも令和2年6月1日から令和5年6月末までの間、被告各製品 を販売し、この間の限界利益額(被告各製品の全体)は合計8557万2953円 (税込)である。(争いなし) 被告は、被告各製品における本件訂正発明2−1、同2−3及び本件発明3の実 施部分は一部であるから、損害額算定における限界利益額は、上記一部に相当する 限界利益額を基準とすべきであると主張するが、被告の指摘する事情は、推定覆滅 事由として考慮すべきであるから、上記主張は採用できない。
イ 推定覆滅事由
特許法102条2項は損害額の推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得 た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠ける ことを主張立証した場合には、その限度で前記の推定は覆滅される。
(ア) 部分実施(本件特許2及び同3の寄与の程度等)
被告各製品は、外枠(床開口用枠体及び取付部材)、蓋セット、ビスセット、梱 包ケース、断熱材により構成されるところ、本件訂正発明2−1、同2−3及び本\n件発明3の実施部分は上記外枠のみである。(争いなし) 原告は、原告製品(高気密型床下点検口・収納庫)における本件訂正発明2−1、 同2−3及び本件発明3の実施部分の構成である「スライドコア」は、原告製品の\n使用において不可欠であり、容易かつ精度のよい施工を実現するといった重要かつ 優れた効果を有し、顧客誘引力の源泉となっているところ、「スライドコア」と強 い類似性を有する被告各製品の「外枠」も顧客誘引力の源泉となるから、上記部分 実施による推定覆滅は大きいものではない旨主張する。 確かに、原告製品のパンフレットには「スライドコア方式が簡単施工で高い気密 性を実現する」ことが記載されているが、他にも顧客を誘引するための特徴(例え ば、耐荷重性に優れていること、蓋枠パッキンによる気密性の確保、肌に優しい樹 脂一体成形品であること、バリアフリープラン対応であることなど)を有すること が記載されている(甲11の19)。また、被告各製品にも、外枠以外の構成にお\nいて、薄型化・軽量化設計であることやバリアフリー設計であること、抗菌仕様で あることといった顧客の誘引に影響する特徴がある(甲4)。外枠に関する施工の 容易性や高い気密性は需要者が注目する特徴であると考えられるものの、他の特徴 と比較して特に重視される事項であるとまでは認めるに足りず、原告製品の「スラ イドコア」ないしこれに相当する部材といえる被告各製品の外枠が、各々の製品に おいて強い顧客誘引力を有していると評価することはできない。 そうすると、被告各製品における発明の実施部分が外枠のみであるとの点は、相 当程度の推定覆滅事由になると解するのが相当である。
(イ) 市場の同一性及び市場における競合品
被告各製品及び原告製品は、樹脂枠を備えた床下点検口・収納庫である。本件訂 正発明2−1、同2−3及び本件発明3の効果は、施工の容易性や気密性及び断熱 性の確保、ガタ付きの防止であるところ、被告各製品のカタログ(甲4)によれば、 被告各製品は、床開口寸法が606×606mm(外形寸法622×622。高さ は67.5mm、182.5mm、463mmのものなど複数の型がある。)であ り、施工が容易でバリアフリー設計であり、気密性及び断熱性等を訴求している。 また、原告製品のカタログ(甲11、12〔枝番を含む。〕)によれば、原告製品 は、床開口寸法が606×606mmのものなどであり(幅広サイズなど複数の型 がある。)、防腐高気密型、高耐久、高断熱、バリアフリー等を訴求している。 これらによれば、被告各製品及び原告製品の需要者は、各製品において、床下点 検口・収納庫の形状、性能や操作の容易性を重視するものと解されるから、被告各\n製品と同程度の形状、性能、機能\及び操作性を実現し、同種の用途に用いられる製 品は競合品に該当するというべきである。
被告が競合品であると主張する製品(甲14ないし18〔各枝番を含む。以下同 じ〕、乙32、33)のうち、少なくとも、Panasonic製の床下収納ユニ ットの「高気密・高断熱住宅用」(甲14)と、DAIKEN製の「ホーム床点検 口」(甲15)は、被告各製品の寸法と同程度の型であるものがあり、性能や機能\、 操作性において同程度であるといえるから、被告各製品及び原告製品と性能、用途\n等において共通する競合品であると認められる(その余の製品については、形状や 訴求されている性能や機能\、操作性が一部被告各製品と合致するものの、同程度と までは認められない。)。他方で、床下収納点検口・収納庫の市場における被告各 製品や原告製品の市場占有率が明らかではなく、また、上記競合品の販売価格と乙 第35号証から推知される被告各製品の販売価格との間には一定の差があることは 否定できない。
以上によれば、市場において上記競合品が存在することは推定覆滅事由となるが、 これをもって大幅な推定覆滅を認めることは相当ではない。
(ウ) 被告の営業努力
特許法102条2項の推定を覆滅する事由として認められる被告の営業努力とは、 通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をいう。被告は、被告各製品の売上につ いて被告の営業努力によるところが大きいと主張するが、これを認めるに足りる証 拠はないから、この点は覆滅事由として認めることはできない。
(エ) 推定覆滅の程度
被告は、上記のほかにも被告製品の機能や工夫をもって推定覆滅事由に該当する\nなどと主張するが、証拠がなく、当該主張を採用することはできない。 以上の検討した諸事情を総合考慮すると、部分実施であること及び一定数の競合 品が存在することによる推定覆滅が認められるところ、本件においては8割の限度 で損害額の推定が覆滅されると解するのが相当である。これに反する原告及び被告 の主張はいずれも採用できない。
(2) 特許法102条3項に基づく主張について
原告は、同条2項の推定覆滅が一部でも認められたとしても、推定覆滅の理由が 「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている」という推定覆滅事由でない限り は、当該推定覆滅部分については、同条3項を適用することができると主張する。 この点、同条2項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者 が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の 売上げの減少による逸失利益に相当するものであるのに対し、同項による推定の推 定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、 特許権者は、売上げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による 実施料相当額の損害を受けたものと評価できるから、同条3項の適用が否定される ことにはならないと解される(知的財産高等裁判所令和2年 第10024号・令 和4年10月20日特別部判決参照)。 本件においては、上記競合品が存在することは同条2項による推定覆滅事由の一 つとなるが、当該推定覆滅部分について原告に実施許諾の機会があったと認めるに 足りる証拠はない。したがって、当該推定覆滅部分について、同条3項を適用する ことはできないというべきである。
(3) 以上によれば、上記(1)アの限界利益額8557万2953円から8割の推 定覆滅がされた1711万4590円(税込)が、被告の被告各製品の販売による 原告の損害であると認められる。 また、本件の事案の内容、経過等にかんがみ、原告の弁護士費用及び弁理士費用 171万円は、被告の特許権侵害行為と相当因果関係がある原告の損害と認める。 したがって、原告の損害額は1882万4590円となる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2024.06.11
令和3(ワ)22564等 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 知的財産裁判例 令和6年3月22日 東京地方裁判所
原告はかかる行為は、不正競争行為(不競法2条1項21号)に該当すると提訴しました。被告も反訴しています。 裁判所は、特許は無効だが、不正競争行為には該当しないと判断しました。
なお、サブコンピネーション発明の「〜のための」という文言も発明を限定するのかが問題となっています。
ウ 甲32発明の各構成が本件発明の構\成要件JないしNの構成にそれぞれ\n相当するかを検討する前提として、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電\n話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 被告らは、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信す\nるための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能\を特定して いるから、請求項1ないし4の解釈を踏まえて請求項5に係る本件発明 の構成を認定すべきであると主張するものと解される。\n
そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記 載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するた めのRFIDインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の 発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信 し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報 であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ 以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わ される受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本 件発明に係る特許請求の範囲の請求項5には、受信装置とは別の他の装 置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記 載されているものと理解できる。
そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求 項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構\成要素、組成、 作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に\n係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲 を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能\等を何ら特 定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を 特定するために意味を有しないことになるから,これを除外して当該請求 項に係る発明の要旨を認定することが相当であるといえる。
本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Jの「RFIDインター\nフェースを有し、」との記載は、受信装置が「RFIDインターフェース を有し」ていることを、構成要件Kの記載は、受信装置が「個別情報の発\n信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要\n件Lの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求し た個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成\n要件Mの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記 要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理 を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件\nJの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は 上記の構造、機能\等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機\n能等を請求項4記載の構\成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機\n能等自体を何ら特定していないから、「請求項4記載の携帯電話」との記\n載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認 めることはできない。
以上によれば、上記の「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するた めの」を除外して請求項5に係る本件発明の要旨を認定することが相当で あるというべきであって、被告らの上記主張を採用することはできない。
・・・
(2) 小括
以上によれば、本件発明は、甲32発明と同一の構成を有しているから、\n新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの と認められ、被告モビリティは原告に対してその権利を行使することができ ない(特許法104条の3第1項、123条1項2号、29条1項3号)。
3 争点1−3(被告らによる虚偽告知の内容)について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記2のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和3年6月23日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上(前提事実(5)エ)、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。 なお、被告らは、原告の前訴訟代理人であった弁護士Ci作成に係る令和3 年7月26日付け意見書について、文書提出命令を申し立てているところ(東\n京地方裁判所令和4年(モ)第264号)、本訴のいずれの争点との関係でも 取調べの必要性が認められるとはいえないから、上記申立てを却下する。\n4 争点2(被告らと原告との間の競争関係の有無)について 事業者間の公正な競争を確保するという不正競争防止法の目的(不正競争防 止法1条)に照らすと、同法2条1項21号の「競争関係」は、現実の市場に おける競合が存在しなくとも、市場における競合が生じるおそれがあれば認め られると解するのが相当である。
そして、前提事実(2)及び(3)並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、決済 に利用される通信端末及びインターネットを利用した決済システムを開発して 販売していること、被告モビリティは、決済システムに利用され得る本件発明 に係る特許権を有し、同特許権について実施権を許諾してライセンス収入を得 ることを業としていることが認められ、被告モビリティ自身が決済端末の開発、 販売をしておらず、現実の市場における競合が存在しないとしても、市場にお ける競合が生じるおそれはあるといえる。
3 争点1−3(被告らによる虚偽告知の内容)について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記2のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和3年6月23日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上(前提事実(5)エ)、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。
(2) 不正競争行為に係る過失について
本件全証拠によっても、被告らにおいて本件通知行為時までに本件特許が 無効となることを具体的に認識し得たことを基礎付ける事情は認められない。 他方で、前提事実(5)のとおり、被告モビリティは、原告がマザーズ市場に 上場する約2週間前に、岡三証券に対して本件通知行為をしたものであると ころ、同時点においては、原告から本件特許が無効である旨の主張は一切さ れておらず、原告が初めて具体的な引用例を示した上で本件特許の新規性又 は進歩性欠如の主張をするに至ったのは、本件訴訟係属中に前訴訟代理人弁 護士らを解任して現在の訴訟代理人弁護士に本件を委任した後であった。以 上の事情に加え、一般に、特許権は特許庁においていったん特許要件ありと して特許査定を受けた権利であることを考慮すると、本件通知行為時点にお いて、被告らに本件特許の無効理由を調査する義務まで負わせることが相当 であるとはいい難い。したがって、被告らに不正競争行為につき過失があるとの原告の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> 営業誹謗
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和3(ワ)15964 特許権 民事訴訟 知的財産裁判例 令和6年3月22日 東京地方裁判所
3 被告ダンパは、「入力」を受けるものであるか(構成要件G)(争点1−1)\nについて ア 本件発明1の構成要件G、Hは、「前記剪断部は、入力により荷重を受けた\nときに、変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とする弾塑性履歴型ダン パ」というものであり、本件発明1の対象となる「弾塑性履歴ダンパ」につ いて「剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収 を行うことを特徴とする」ものであるとされている。したがって、本件発明 1のダンパは、上記に記載された特徴を有するダンパであるところ、その「入 力」がどのようなものであるかについて、本件発明1の特許請求の範囲では 何ら定められていない。
イ ここで、前記1 で説示したとおり、本件各発明は、上部構造物、下部構\ 造物に分離できる橋梁等の建築物において、地震のときに、その接続部にお いて橋軸方向に限らず、複数方向の水平力がかかってしまうところ、同接続 部においては、I字形ダンパでは単一方向の入力にしか対応できないという 課題について、同課題を解決するために、複数の剪断面を持ち、かつ、その 向きが異なるダンパを適用するというものであり、本件各発明は、そのよう なダンパが本件各発明の構成をとることによって、剪断部が、入力により荷\n重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うというものである。 本件明細書に記載された本件各発明の課題は、上記のとおりであり、従来 から知られていた剪断パネル型ダンパである単純なI字形ダンパに対して 単一方向からの入力しか想定されない場面においては、本件各発明における 解決すべき課題は存在しない。単一方向からの入力でなく複数方向からの入 力が想定される場合に、本件各発明が解決すべき課題が存在することとなる。 そして、本件明細書には、前記1 に記載のとおりの本件各発明の意義が記 載されているほか、本件明細書に記載された実施例は、全て、複数方向から の入力が問題となり、そのような複数方向からの入力に対し、本件発明1の 構成をとることによって対応することができるものであると認められる。本\n件明細書のその他の部分にも、単一方向からの入力に対応することに関する 記載はない。これらの本件明細書の記載及び構成要件G、Hの記載から、本\n件発明1に係るダンパは、ダンパに対して複数方向からの入力が想定される 構造物等の部位に用いられ、ダンパの剪断部に対して複数方向からの入力が\nあり、これに対して対応することができるダンパであると解するのが相当で ある。
ウ 以上によれば、本件各発明におけるダンパは、その剪断部に複数方向から の入力があり、その剪断部がそれに対する入力により荷重を受けたときに、 変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするもの(構成要件G、H)で\nあると解するのが相当であり、構成要件Gに係る「入力」は、「複数方向か\nらの入力」を意味し、本件各発明のダンパは、ダンパに対して複数方向から の入力があることを前提として、その剪断部が複数方向からの入力により荷 重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするダンパ であると認められる。 被告ダンパについて検討すると、本件において、原告は、被告ダンパ単体の 譲渡等を問題にするのではなく、被告ダンパが住宅である被告製品に用いられ て、そのような被告製品が販売されていることを特許発明の実施として、被告 製品の販売額を基礎として実施料率相当額の損害を請求する。
被告は、6種の被告ダンパを4種の耐力パネルのいずれかに組み込み、これ を住宅である被告製品の部材として用いている(前提事実 )。被告ダンパは各 平行板部及び各ウェブ部の一端又は両端が耐力パネルに溶接されているので あって、耐力パネルから取り外して使用されることはおよそ想定されておらず、 各耐力パネルも、建物の水平方向に延びる梁や土台等にはさまれるように固定 されて設置されており、住宅販売後に耐力パネルのみを取り外して別の用途に 使用するということはおよそ想定されていない(前提事実 )。すなわち、被告 ダンパは、耐力パネルに物理的にも溶接され、取り外されることはおよそ想定 されず、耐力パネルと不可分一体となっているものといえる。 そうすると、本件において問題となる被告の行為は、被告ダンパが不可分一 体の一部となった被告製品の製造、販売等であって、被告ダンパが組み込まれ た被告製品が本件発明1の技術的範囲に属するか否かが問題になるというべ きである。
なお、被告は、Σ型の形状の鋼材である被告ダンパを作成し、これを他の部 材に組み込むことで耐力パネルを製造していることがうかがえる。もっとも被 告ダンパ単体には「一対のプレート」は接続されておらず、耐力パネルに組み 込まれることによって初めて、「一対のプレート」の具備が問題になるのである から、耐力パネルに組み込まれる前の被告ダンパ自体が本件発明1の技術的範 囲に入ることはないと解される。 被告製品に組み込まれ、被告製品と不可分一体となった被告ダンパに対して 加わる力について検討する。
ア 被告ダンパはいずれも4種類の耐力パネルのいずれかに組み込まれてい るところ、耐力パネルは、その構造上、耐力パネルが接続している梁の方向\nの力(耐力パネルが平行四辺形に変更する方向の力)が加わると、いずれの 耐力パネルについても、被告ダンパに鉛直方向の力が加わり、所定レベル以 上の力が加わると剪断変形によって地震力を吸収する。このとき、被告ダン パに対しては、鉛直方向の力以外の力は加わらない。他方で、耐力パネルに 梁と垂直方向の力が加わっても、被告ダンパには力が加わらず、地震力を吸 収することができない。地震力のうち、これらの力の合力については、いず れも上記二つの力に分解できるから、結局、被告ダンパには鉛直方向の力の みが加わるということになる(乙33)。被告製品においては、建物の特定 の方向に複数の耐力パネルを設置するとともに、これと直交する方向にも複 数の耐力パネルを設置しており、このように複数の耐力パネルを直交方向に 設置することによって、個々のパネルの被告ダンパには鉛直方向の力のみが 加わり、その方向の力のみしか吸収できないとしても、各方向に沿って設置 された耐力パネルが、両方向に対応する地震力の分力を吸収することで建物 全体では任意の方向の地震力を吸収できるように設計されているといえる (乙3)。
イ 被告ダンパに対しては、一応、前記アのとおりの力のみが加わるといえる が、耐力パネルが設置されている上下の梁がねじれる(回転する)力が加わ った場合には、耐力パネルの構造上、被告ダンパに対し鉛直方向とは異なる\n方向の力が加わる可能性がないわけではない。そこで、被告製品において鉛\n直方向からどの程度ずれる力が加わり得るのかについて検討する。
被告は、被告ダンパを搭載した実物大の住宅サンプルに対して、過去最大 級の地震の一つである兵庫県南部地震の際にJR鷹取駅で観測された地震 波(以下「鷹取地震波」という。)を適用して地震時挙動を測定する実験を行 ったところ、その結果によれば、1階に対する2階床の最大回転角は、0. 14°(乙40)、これにより耐力壁に設置されたダンパに対して加わる力 の鉛直方向からのずれは、0.022°であったこと(乙41)が認められ る。
ウ 以上を前提に、被告ダンパの剪断部に本件発明1における複数方向から の入力があり、その剪断部が複数方向からの入力により荷重を受けたとき に変形してエネルギー吸収を行うものといえるか否かについて検討する。 特許請求の範囲にも本件明細書にも、前記の複数方向のうち1つの方 向といえる角度範囲をどの程度のものと想定しているかについての直 接的な記載はない。しかし、そもそも、本件発明1のダンパは、建築物 や橋梁等の建物、建造物で用いられるものであるところ、従来のI字型 ダンパは、想定する角度からわずかでもずれれば機能しなくなるという\nものではない。I字形ダンパは、入力方向のずれが生じている場合でも、 パネルと平行し、面内を通る方向の分力については、入力がパネルと面 内を通る方向と平行だった場合と同様に作用することになるから、実際 の入力と面内を通る方向とのずれがごくわずかであれば、実際の入力と ほとんど変わらない力が面内を通る分力として剪断パネルに作用する。 例えば、入力方向が0.1°ずれた場合には、
Cos0.1°=約0.9999985
により、約99.99985%の力が面内を通る分力として剪断パネル に作用することになり、この程度の入力方向のずれでは、I字型ダンパ に生じる効果に観測できるほどの差は生じないことは明らかである。ま た、建築の分野において橋梁や住居などの一定の大きさの建造物を建築 するに当たって、施工誤差が生じることは当然であり(原告は、後記の とおり耐力パネル設置に当たって少なくとも±0.82°の据え付け誤 差が生じると主張している。)、I字型ダンパもそのことを前提に用いら れるものとして想定されており、施工の限界を超えた小さい角度差は、 単一方向の入力として想定されているというべきである。さらに、I字 型ダンパはパネルと平行し、面内を通る方向から力が加わることによっ て、平行四辺形に剪断変形することによってその力を吸収するというも のである(前記2 )が、I字型ダンパの剪断パネルにも一定の厚さが あり、少なくとも厚さの中に納まるような入力方向の小さなズレであれ ば、パネルの面内を通る方向からの力と評価し得、少なくともこの程度 の入力方向のずれは、同一方向からの入力として想定されているともい える。
本件明細細書においても、本件各発明のダンパは、図面上、いずれも一 見して複数の剪断部の方向が異なることが明らかなもののみであり、そ の入力方向のズレが相当に小さいことを想定した場合の記載、図面はな い。そのずれが相当に小さく、例えば、0.1°程度の差を複数方向か らの入力と想定した場合、複数のパネルを連結しながらどのように配置 すれば効率的に入力を吸収できるかは、本件明細書によっても明らかで はない。上記のような差の入力の場合、厚みのある鋼板を用いて、2枚 の剪断パネルを0.1°程度の角度をつけて接合し、ダンパを作成する ことを実現することが現実的であるとはいえない。 以上に述べたところに、前記 で記載した本件発明1の意義を考慮す ると、本件発明1で対象としている複数方向からの入力は異なる方向か らの入力であるというべきところ、その異なる方向からの入力には、少 なくとも、従来のI字型ダンパにおいて同一方向からの入力として想定 されていたといえる入力を含まないものと認められる。
前記イで認定したとおり、被告製品は、少なくとも鷹取地震波を前提 にすると、これによって剪断パネルに一定のねじれが生じ、被告ダンパ に鉛直方向からずれた方向からの力も加わることが認められる。しかし、 そのずれは0.022°(なお、cos0.02°=約0.9999999 26)と極めて小さいものである。この程度のずれは、その小ささから もこれによって被告ダンパに生じる効果に観測できるほどの差が生じ るとは認めるに足りないし、このずれは、被告製品が用いられる分野の 施工の限界を超える程度であるといえる。また、そのずれは、被告ダン パのウェブ部を形成する鋼板の厚みの中に収まるような小さなもので あることがうかがえる。 これらによれば、上記実験結果によれば、本件においてねじれによっ て加わり得る入力方向の違いは、従来のI字型ダンパにおいて同一方向 からの入力として想定されていたといえる範囲のものであり、前記 で 説示した本件発明1が異なる入力方向として想定しているものではな いというべきである。 また、被告製品が鷹取地震波を超える地震波に遭遇することは想定さ れ得る。しかし、上記実験で用いられたのが過去最大級の地震の一つで ある鷹取地震波であり、その場合であっても上記のとおり入力方向の違 いが極めて小さいことからすると、現実に想定し得る鷹取地震波を超え る地震においても、被告ダンパに対して本件発明1が想定する程度の鉛 直方向からのずれが生じる剪断パネルのねじれが生じるとも認められ ない。
以上によれば、被告製品で用いられている被告ダンパの剪断パネルに 対してねじれの影響によって生じる入力方向の違いは、その小ささから、 本件発明1が想定する程度に達するような、異なる方向からの入力であ ると評価できるものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和5(ネ)10037 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 特許法102条2項の適用について
ア 特許権者が特許権侵害を理由に民法709条の不法行為に基づく損害賠償を 請求する場合には、特許権者において、侵害者の故意又は過失、自己の損害の発生、 侵害行為と損害との間の因果関係及び損害額を立証する必要があるところ、特許法 102条2項は、特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵 害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害 の額と推定すると規定している。
イ この規定の趣旨は、特許権者による損害額の立証等には困難が伴い、その結 果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者 が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と 推定し、これにより立証の困難性の軽減を図ったものであり、特許権者に、侵害者 による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在 する場合には、特許権者がその侵害行為により損害を受けたものとして、特許法1 02条2項の適用が認められると解すべきである(知的財産高等裁判所平成25年 2月1日特別部判決(同裁判所平成24年(ネ)第10015号)、同裁判所令和元 年6月7日特別部判決(同裁判所平成30年(ネ)第10063号)、令和4年特別 部判決参照)。
ウ これを本件について、前記(1)の認定事実を前提として検討すると、本件では、 原告のSDエンジンは、SD装置が本件各発明を含むステルスダイシング技術を用 いたレーザ加工機能を実現するために必須となる部品であって枢要な機能\を担うも のであり、被告による被告旧製品(侵害品)の製造及び輸出・販売行為がなかった ならば、原告は自らのSDエンジンを被告又は他のSD装置の製造者に販売するこ ならば、原告は自らのSDエンジンを被告又は他のSD装置の製造者に販売するこ とにより、輸出・販売された被告旧製品に対応する利益が得られたであろうという ことはできる。しかしながら、原告はSDエンジンを販売していたものであって、 侵害品と同種の製品であるSD装置を製造・販売していたものではない。また、原 告において自らSD装置を製造する能力があり、具体的にSD装置を製造・販売す\nる予定があったことを認めるに足りる証拠もない。原告の逸失利益はあくまでもS\nDエンジンの売上喪失によるものであって、SD装置の売上喪失によるものではな い。そして、SD装置とSDエンジンとは需要者及び市場を異にし、同一市場にお いて競合しているわけではない。したがって、SD装置の売上げに係る被告の利益 全体をもって、原告の喪失したSDエンジンの売上利益(原告の損害)と推定する 合理的事情はない。
エ この点、原告は、被告旧製品の限界利益のうち、SDエンジン相当部分の限 界利益が原告の損害と推定されるべきであるとも主張する。しかし、SDエンジン は、SD装置の一部を構成する部品であって、その対価は製造原価を構\成する多数 の項目の一つにすぎない。そして、本件において、SD装置の限界利益のうちのど の程度の部分が、それぞれの部品に由来するものであるかを特定するに足りる事情 はなく、「SDエンジン」に由来する部分を特定することは困難というほかないので あって、「SDエンジン相当部分」の限界利益を一義的に特定することはできない。
仮にこれを算出する場合にも、確立した算出方法があるわけではなく、どのような 要素を考慮し、どのような論理操作を行うかによって様々な結論を導くことが可能\nであるから、このように算出された限界利益の「SDエンジン相当部分」をもって 本件における原告の損害を推定し、覆滅事由の主張立証責任を転換するための合理 的な基礎とすることはできないというべきである。したがって、原告の前記主張は 採用することができない。
オ 以上によれば、本件において、侵害者による特許権侵害行為がなかったなら ば利益が得られたであろうという事情があるとして特許法102条2項の規定の適 用が認められるとはいえるものの、SDエンジン相当部分の限界利益を特定するこ とができないから、同項の推定規定により本件における原告の損害を認定すること はできない。前記各知的財産高等裁判所特別部の判決は、いずれも特許権者等にお いて特許実施品又は侵害品と市場及び需要者を共通にする製品を販売等していたと いう事情が存在する事案について判断したものであるから、本件について、上記の ように解することと矛盾するものではない。原告は、知的財産高等裁判所令和4年 8月8日判決(同裁判所平成31年(ネ)第10007号)も引用するが、同判決 の事案は、特許権者が完成品を販売し、侵害者が間接侵害品である部品を販売して いた事案であって、本件のような完成品の限界利益中の当該部品に相当する部分の 特定が問題になった事案ではないから、同項の適用に関する前記結論を左右するに 足りるものではない。
そうすると、本件における原告の損害の認定は、特許法102条2項の推定規定 の適用以外の方法で行うのが相当である。
(3) 別件訴訟2(965特許)の考慮について
被告は、別件訴訟2の対象特許である965特許による侵害を考慮し、本件と別 件訴訟2において損害額を2分の1とするのが相当であると主張するが、各対象製 品の製造・販売等が965特許を侵害するものであるか否かという点は、本件訴訟 の審理対象となっているものではなく、仮に本件において原告に生じた損害のうち、 965特許の侵害による損害と重なる部分があるとしても、本件において965特 許の侵害が成立することを前提として損害額を算定することは相当ではないから、 損害の算定方法にかかわらず、被告の上記主張は採用することができない。
(4) 特許法102条1項(令和元年法律第3号による改正後のもの。本件は改正 法の施行日(令和2年4月1日)前の事案であるが、経過規定は設けられていない から、以下においては、改正後の条文を適用する。)による損害額の算定 ア 特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益 の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害者の譲 渡した物の数量(譲渡数量)に特許権者がその侵害行為がなければ販売することが できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者の実施の能力の限度で\n損害額とするが、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売するこ とができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応 じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の 立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規 定である(知的財産高等裁判所令和2年2月28日特別部判決(同裁判所平成31 年(ネ)第10003号)参照)。
特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者が「侵害の行為が なければ販売することができた物」(同項1号)とは、侵害行為によってその販売数 量に影響を受ける特許権者の製品であれば足り、特許権者が特許実施品又は専ら特 許実施品の生産のために用いる物(部品)を販売しており、侵害行為がなければ、 特許権者は自らの製品を販売することができたという関係にある場合には、特許権 者は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品を販売していたというこ とができるから、同項の適用が是認される。
そして、本件では、前記(2)のとおり、被告の侵害行為がなければ、原告はその製 造する原告エンジンを販売することができ、これにより利益を得ることができたも のと推認され、原告は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品である 原告エンジンを販売していたということができるから、同項を適用することができ る。
イ 限界利益
原告は、原告エンジンの限界利益について●●●●●●●●●円であると主張す るが、前記認定事実のとおり、原告は被告に対し、●●●●●円で原告エンジンを 販売していたのであるから、上記の限界利益額をそのまま採用することはできない。 そして、原告従業員の陳述書(甲73)によると、被告旧製品(対象製品1(2)B) のSDエンジンの競合品である原告エンジン(800DS一式)の原価は●●●● ●円(1万円未満切り捨て)であり、これを前提とすると、原告エンジンの一台当 たりの限界利益は●●●●●円(=●●●●●円−●●●●●円)、●●台分の限界 利益は4億1280万円となる。 なお、LDモジュールは侵害行為がなければ特許権者である原告が販売できた物 であると認めるに足りないから、LDモジュールに係る部分は考慮しない。
ウ 推定の覆滅
本件各発明は、ステルスダイシング機能そのものに係るものではなく、同機能\を 用いて加工対象物をレーザ加工する際の端部の処理に関するものであること、本件 各発明に係る技術については、AF低追従を用いるという代替技術や、端部におい てはレーザ加工をしないという手法(エッジオフ)が存在し、現に、被告がAF低 追従を用い、エッジオフ機能を有する被告新製品を販売していることからすると、\n本件各発明自体の顧客吸引力が高いとは認められないこと、原告エンジンを組み込 んだ被告又はディスコ社のSD装置が被告旧製品と全く同じ性能や機能\を有するも のではないこと、被告が個々のユーザの製造プロセスや加工対象物の形状に応じて
SD装置の仕様を変更し、モジュールを開発して提供するなどして被告製品を販売 していたこと等、本件に表われた事情を総合すると、特許法102条1項1号の「特\n許権者が販売することができないとする事情」に相当する数量は、7割であると認 めるのが相当である。
エ 損害額
以上によると、特許法102条1項により算定される損害額は、1億2384万 円(=4億1280万円×(1−0.7))であり、同条3項により算定される損害 額(後記(5)イ)を上回る。
なお、原告は、同条1項による損害額の算定においては、原告エンジン一台当た りの限界利益額に侵害品の販売台数を乗じた金額に、1台当たり300万円の実施 料相当額を加算すべきであると主張し、同項2号の規定は、同項1号の実施相応数 量を超える数量又は特定数量がある場合において、一定の条件で実施料相当額の損 害を加算することを認めている。しかし、前記ウで認定した「特許権者が販売する ことができないとする事情」に相当する数量は、その性質上、特許権者が実施許諾 をし得たものとは認められないから、本件では、同項2号の規定を適用して、実施 料相当額を加算することはできない。したがって、原告の主張は採用することがで きない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和5(ネ)10078 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これを本件において検討するに、前記(1)イのとおり、本件発明1は、「底部 に取り付けられた安定補助板により支えられてテーブルなどの上に立たせら れる」「折畳式コップ型容器」(段落【0003】)であって「安定補助板が例 えば紙や合成樹脂などから形成され、後から容器本体に取り付けられる構成」\n(段落【0005】)を採用した従来技術を前提とし、「成形が簡便な自立型 の包装容器の提供を目的とする」(段落【0006】)ことを発明が解決しよ うとする課題とし、当該課題を解決する手段として「前記包装容器を容器と して形成した状態において、前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自 立片が載置面に沿って前記奥行の方向に突出し、前記自立片によって前記載 置面に自立させられる」(本件発明1の構成要件B)という構\成を採用するこ とにより、「包装容器を自立させる自立片が底面片に連なっているため、一体 的な成形が簡便である」(段落【0013】)という効果を奏するものである。 そうすると、本件発明1において従来技術に見られない特有の技術的思想 を構成する特徴的部分は、従来技術における安定補助板が、底部に一体的に\n成形された構成である、「前記包装容器を容器として形成した状態において、\n前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片が載置面に沿って前記奥 行の方向に突出し、前記自立片によって前記載置面に自立させられる」こと にあると考えられる。
そして、本件発明1と被控訴人製品とは、包装容器を容器として形成した 状態において、本件発明1の「底面片」が筒状の底部を形成するのに対し、 被控訴人製品は、包装容器を自立させる舌状片が、包装容器の底部を形成す る六角片と同一面に連なっておらず別に構成されている点において相違する\nものと認められるところ、この相違に係る本件発明1の構成、すなわち「底\n部を形成する底面片」が「自立片」と同一面に連ねられていることは、これ までの検討によれば、本件発明1の本質的部分に当たるものということがで きる。
そうすると、上記相違点に係る本件発明1の構成については、本件発明1\nの本質的部分ではないということはできない。そして、前記(1)ウのとおり、 上記の点については、本件各発明について共通するものということができる。 したがって、被控訴人製品は均等侵害の第1要件を充足しないから、その 要件について検討するまでもなく、均等侵害は成立しない。
イ 控訴人は、前記第2の3(4)ウのとおり、本件各発明の本質的部分は、「自立 片」によって載置面に自立させられる構成を採用した点にあり、当該「自立\n片」が内容物に直接接触してこれを支える片という意味における「底面片」 と、同一面に連なることにあるのではないと主張する。 しかし、本件各発明の本質的部分については上記アのとおりと認められる から、本件各発明と被控訴人製品とは、その本質的部分において異なるもの というべきである。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和5(ネ)10084 特許権侵害損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は、第1審原告の請求のうち、1755万3642円及びうち12 69万1831円に対する平成21年9月27日から、うち25万3585円 に対する平成22年9月26日から、うち170万7608円に対する平成2 4年9月30日から、うち290万0618円に対する平成25年9月29日 から、各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理 由があるからこの限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきで あると判断する。その理由は、当審における当事者の主張も踏まえて原判決を 後記1のとおり補正し、後記2のとおり当審における第1審原告の補充主張に 対する判断を付加し、後記3のとおり当審における第1審被告の補充主張に対 する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」第4(原判決45頁2行目 から94頁12行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
・・・
原判決92頁1行目の・・・、同頁5行目の「0.5%」を「0.2%」に、それぞれ改める。
◆判決本文
原審はこちら。
◆令和2(ワ)13317
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和3(ワ)15964 特許権 民事訴訟 令和6年3月22日 東京地方裁判所
3 被告ダンパは、「入力」を受けるものであるか(構成要件G)(争点1−1)\nについて
ア 本件発明1の構成要件G、Hは、「前記剪断部は、入力により荷重を受けた\nときに、変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とする弾塑性履歴型ダン パ」というものであり、本件発明1の対象となる「弾塑性履歴ダンパ」につ いて「剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収 を行うことを特徴とする」ものであるとされている。したがって、本件発明 1のダンパは、上記に記載された特徴を有するダンパであるところ、その「入 力」がどのようなものであるかについて、本件発明1の特許請求の範囲では 何ら定められていない。
イ ここで、前記1 で説示したとおり、本件各発明は、上部構造物、下部構\ 造物に分離できる橋梁等の建築物において、地震のときに、その接続部にお いて橋軸方向に限らず、複数方向の水平力がかかってしまうところ、同接続 部においては、I字形ダンパでは単一方向の入力にしか対応できないという 課題について、同課題を解決するために、複数の剪断面を持ち、かつ、その 向きが異なるダンパを適用するというものであり、本件各発明は、そのよう なダンパが本件各発明の構成をとることによって、剪断部が、入力により荷\n重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うというものである。
本件明細書に記載された本件各発明の課題は、上記のとおりであり、従来 から知られていた剪断パネル型ダンパである単純なI字形ダンパに対して 単一方向からの入力しか想定されない場面においては、本件各発明における 解決すべき課題は存在しない。単一方向からの入力でなく複数方向からの入 力が想定される場合に、本件各発明が解決すべき課題が存在することとなる。 そして、本件明細書には、前記1 に記載のとおりの本件各発明の意義が記 載されているほか、本件明細書に記載された実施例は、全て、複数方向から の入力が問題となり、そのような複数方向からの入力に対し、本件発明1の 構成をとることによって対応することができるものであると認められる。本\n件明細書のその他の部分にも、単一方向からの入力に対応することに関する 記載はない。これらの本件明細書の記載及び構成要件G、Hの記載から、本\n件発明1に係るダンパは、ダンパに対して複数方向からの入力が想定される 構造物等の部位に用いられ、ダンパの剪断部に対して複数方向からの入力が\nあり、これに対して対応することができるダンパであると解するのが相当で ある。
ウ 以上によれば、本件各発明におけるダンパは、その剪断部に複数方向から の入力があり、その剪断部がそれに対する入力により荷重を受けたときに、 変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするもの(構成要件G、H)で\nあると解するのが相当であり、構成要件Gに係る「入力」は、「複数方向か\nらの入力」を意味し、本件各発明のダンパは、ダンパに対して複数方向から の入力があることを前提として、その剪断部が複数方向からの入力により荷 重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするダンパ であると認められる。
被告ダンパについて検討すると、本件において、原告は、被告ダンパ単体の 譲渡等を問題にするのではなく、被告ダンパが住宅である被告製品に用いられ て、そのような被告製品が販売されていることを特許発明の実施として、被告 製品の販売額を基礎として実施料率相当額の損害を請求する。 被告は、6種の被告ダンパを4種の耐力パネルのいずれかに組み込み、これ を住宅である被告製品の部材として用いている(前提事実 )。被告ダンパは各 平行板部及び各ウェブ部の一端又は両端が耐力パネルに溶接されているので あって、耐力パネルから取り外して使用されることはおよそ想定されておらず、 各耐力パネルも、建物の水平方向に延びる梁や土台等にはさまれるように固定 されて設置されており、住宅販売後に耐力パネルのみを取り外して別の用途に 使用するということはおよそ想定されていない(前提事実 )。すなわち、被告 ダンパは、耐力パネルに物理的にも溶接され、取り外されることはおよそ想定 されず、耐力パネルと不可分一体となっているものといえる。
そうすると、本件において問題となる被告の行為は、被告ダンパが不可分一 体の一部となった被告製品の製造、販売等であって、被告ダンパが組み込まれ た被告製品が本件発明1の技術的範囲に属するか否かが問題になるというべ きである。
なお、被告は、Σ型の形状の鋼材である被告ダンパを作成し、これを他の部 材に組み込むことで耐力パネルを製造していることがうかがえる。もっとも被 告ダンパ単体には「一対のプレート」は接続されておらず、耐力パネルに組み 込まれることによって初めて、「一対のプレート」の具備が問題になるのである から、耐力パネルに組み込まれる前の被告ダンパ自体が本件発明1の技術的範 囲に入ることはないと解される。 被告製品に組み込まれ、被告製品と不可分一体となった被告ダンパに対して 加わる力について検討する。
ア 被告ダンパはいずれも4種類の耐力パネルのいずれかに組み込まれてい るところ、耐力パネルは、その構造上、耐力パネルが接続している梁の方向\nの力(耐力パネルが平行四辺形に変更する方向の力)が加わると、いずれの 耐力パネルについても、被告ダンパに鉛直方向の力が加わり、所定レベル以 上の力が加わると剪断変形によって地震力を吸収する。このとき、被告ダン パに対しては、鉛直方向の力以外の力は加わらない。他方で、耐力パネルに 梁と垂直方向の力が加わっても、被告ダンパには力が加わらず、地震力を吸 収することができない。地震力のうち、これらの力の合力については、いず れも上記二つの力に分解できるから、結局、被告ダンパには鉛直方向の力の みが加わるということになる(乙33)。被告製品においては、建物の特定 の方向に複数の耐力パネルを設置するとともに、これと直交する方向にも複 数の耐力パネルを設置しており、このように複数の耐力パネルを直交方向に 設置することによって、個々のパネルの被告ダンパには鉛直方向の力のみが 加わり、その方向の力のみしか吸収できないとしても、各方向に沿って設置 された耐力パネルが、両方向に対応する地震力の分力を吸収することで建物 全体では任意の方向の地震力を吸収できるように設計されているといえる (乙3)。
イ 被告ダンパに対しては、一応、前記アのとおりの力のみが加わるといえる が、耐力パネルが設置されている上下の梁がねじれる(回転する)力が加わ った場合には、耐力パネルの構造上、被告ダンパに対し鉛直方向とは異なる\n方向の力が加わる可能性がないわけではない。そこで、被告製品において鉛\n直方向からどの程度ずれる力が加わり得るのかについて検討する。 被告は、被告ダンパを搭載した実物大の住宅サンプルに対して、過去最大 級の地震の一つである兵庫県南部地震の際にJR鷹取駅で観測された地震 波(以下「鷹取地震波」という。)を適用して地震時挙動を測定する実験を行 ったところ、その結果によれば、1階に対する2階床の最大回転角は、0. 14°(乙40)、これにより耐力壁に設置されたダンパに対して加わる力 の鉛直方向からのずれは、0.022°であったこと(乙41)が認められ る。
以上を前提に、被告ダンパの剪断部に本件発明1における複数方向から の入力があり、その剪断部が複数方向からの入力により荷重を受けたとき に変形してエネルギー吸収を行うものといえるか否かについて検討する。
・・・
前記イで認定したとおり、被告製品は、少なくとも鷹取地震波を前提 にすると、これによって剪断パネルに一定のねじれが生じ、被告ダンパ に鉛直方向からずれた方向からの力も加わることが認められる。しかし、 そのずれは0.022°(なお、cos0.02°=約0.9999999 26)と極めて小さいものである。この程度のずれは、その小ささから もこれによって被告ダンパに生じる効果に観測できるほどの差が生じ るとは認めるに足りないし、このずれは、被告製品が用いられる分野の 施工の限界を超える程度であるといえる。また、そのずれは、被告ダン パのウェブ部を形成する鋼板の厚みの中に収まるような小さなもので あることがうかがえる。
これらによれば、上記実験結果によれば、本件においてねじれによっ て加わり得る入力方向の違いは、従来のI字型ダンパにおいて同一方向 からの入力として想定されていたといえる範囲のものであり、前記(ア)で 説示した本件発明1が異なる入力方向として想定しているものではな いというべきである。
また、被告製品が鷹取地震波を超える地震波に遭遇することは想定さ れ得る。しかし、上記実験で用いられたのが過去最大級の地震の一つで ある鷹取地震波であり、その場合であっても上記のとおり入力方向の違 いが極めて小さいことからすると、現実に想定し得る鷹取地震波を超え る地震においても、被告ダンパに対して本件発明1が想定する程度の鉛 直方向からのずれが生じる剪断パネルのねじれが生じるとも認められ ない。
以上によれば、被告製品で用いられている被告ダンパの剪断パネルに 対してねじれの影響によって生じる入力方向の違いは、その小ささから、 本件発明1が想定する程度に達するような、異なる方向からの入力であ ると評価できるものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2024.05. 1
令和5(ネ)10078 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(4) 当審における控訴人による均等侵害の主張に対する判断
ア 控訴人は、仮に被控訴人製品が、本件各発明に文言上はその技術的範囲に 属しないものとしても、これと均等なものとして、特許権侵害に当たる旨を 主張する。
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用い\nる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、 1)同部分が特許発明の本質的部分ではなく、2)同部分を対象製品等における ものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果 を奏するものであって、3)上記のように置き換えることに、当該発明の属す る技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製 造等の時点において容易に想到することができたものであり、4)対象製品等 が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同 出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、5)対象製品等が特許発明の 特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる などの特段の事情もないときは、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解する\nのが相当である。
そして、上記1)の要件(第1要件)における特許発明における本質的部分 とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない 特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求\nの範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効 果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見 られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定するこ\nとによって認定されるべきである(最高裁平成6年(オ)第1083号同1 0年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁、最高裁平成28 年(受)第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号 359頁参照)。
これを本件において検討するに、前記(1)イのとおり、本件発明1は、「底部 に取り付けられた安定補助板により支えられてテーブルなどの上に立たせら れる」「折畳式コップ型容器」(段落【0003】)であって「安定補助板が例 えば紙や合成樹脂などから形成され、後から容器本体に取り付けられる構成」\n(段落【0005】)を採用した従来技術を前提とし、「成形が簡便な自立型 の包装容器の提供を目的とする」(段落【0006】)ことを発明が解決しよ うとする課題とし、当該課題を解決する手段として「前記包装容器を容器と して形成した状態において、前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自 立片が載置面に沿って前記奥行の方向に突出し、前記自立片によって前記載 置面に自立させられる」(本件発明1の構成要件B)という構\成を採用するこ とにより、「包装容器を自立させる自立片が底面片に連なっているため、一体 的な成形が簡便である」(段落【0013】)という効果を奏するものである。
そうすると、本件発明1において従来技術に見られない特有の技術的思想 を構成する特徴的部分は、従来技術における安定補助板が、底部に一体的に\n成形された構成である、「前記包装容器を容器として形成した状態において、\n前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片が載置面に沿って前記奥 行の方向に突出し、前記自立片によって前記載置面に自立させられる」こと にあると考えられる。
そして、本件発明1と被控訴人製品とは、包装容器を容器として形成した 状態において、本件発明1の「底面片」が筒状の底部を形成するのに対し、 被控訴人製品は、包装容器を自立させる舌状片が、包装容器の底部を形成す る六角片と同一面に連なっておらず別に構成されている点において相違する\nものと認められるところ、この相違に係る本件発明1の構成、すなわち「底\n部を形成する底面片」が「自立片」と同一面に連ねられていることは、これ までの検討によれば、本件発明1の本質的部分に当たるものということがで きる。
そうすると、上記相違点に係る本件発明1の構成については、本件発明1\nの本質的部分ではないということはできない。そして、前記(1)ウのとおり、 上記の点については、本件各発明について共通するものということができる。 したがって、被控訴人製品は均等侵害の第1要件を充足しないから、その 要件について検討するまでもなく、均等侵害は成立しない。 イ 控訴人は、前記第2の3(4)ウのとおり、本件各発明の本質的部分は、「自立 片」によって載置面に自立させられる構成を採用した点にあり、当該「自立\n片」が内容物に直接接触してこれを支える片という意味における「底面片」 と、同一面に連なることにあるのではないと主張する。 しかし、本件各発明の本質的部分については上記アのとおりと認められる から、本件各発明と被控訴人製品とは、その本質的部分において異なるもの というべきである。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2024.04.30
令和5(ワ)70001 特許専用実施権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年4月17日 東京地方裁判所
以上のような本件明細書等から認められる本件各発明の目的、課題の解決手 段からすれば、本件各発明は、オゾンによる殺菌等を行った処理後の被処理水 に含まれる残オゾンの低減と、被処理水の生物処理の促進とを両立させること ができる廃水処理装置及び廃水処理方法を提供することを目的としており、そ の解決手段としては、第1の収容槽内にオゾンを含むマイクロナノバブルを供 給するオゾン供給手段を有するとともに、第1の収容槽とは別に、被処理水の 生物処理を行う第2の収容槽を設けることとした上で、そこに第1の収容槽に おいてオゾンによって処理された被処理水を残オゾンとともに収容し、生物処 理能力を低減させる原因となる残オゾンを積極的に酸素分子に化学変化させる\nために、第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給 手段と、所定の担体を有するというものである。
したがって、本件各発明においては、オゾンによる殺菌等を行った後の被処 理水に含まれる残オゾンの低減をも目的として第2の収容槽とそれに関する構\n成を設けているのであり、残オゾンを低減させるための構成ともいえる第2の\n収容槽内に、少なくとも積極的にオゾンを供給することは、課題の解決に至ら ず、本件各発明において第2の収容槽とそれに関する構成を有することとした\nことと相容れないものといえる。
そして、オゾン発生装置で製造されるオゾンは、純度100%のオゾンガス が製造されるものでないことは技術常識である上、本件明細書【0031】に おいて、オゾン発生装置29によって発生し、このオゾン発生装置29に接続 され吸気管を介し吸気されたオゾンは、複数分岐した枝管24を通って圧縮部 22内に噴出されるようになっていて、この圧縮部22内に噴出された気泡が オゾンを含むマイクロナノバブルとされていることからしても、第1収容槽内 に供給される「オゾンを含むマイクロナノバブル」については、当然に酸素(空 気)を含むものも想定されていたといえる。
以上に照らせば、本件各発明の特許請求の範囲の「第1の収容槽内にオゾン を含むマイクロナノバブルを供給するオゾン供給手段」と、「第2の収容槽内に 酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段」の記載は、特にオゾ ン供給の有無という点において上記課題の解決のための対照的なマイクロナノ バブルの供給手段として記載されているものと解するのが相当であり、「第2の 収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段」は、第1 の収容槽への供給手段と異なり、そのマイクロナノバブルにはオゾンが積極的 に加えられているものではなく、その供給手段には、オゾンが積極的に加えら れたマイクロナノバブルを供給する供給手段を含まないというべきである。し たがって、第2の収容槽内にオゾンが積極的に加えられたマイクロナノバブル を供給する酸素供給手段を有する装置は、構成要件Dを充足しないと解される。\n
(3) 被告システムは、前記第2の1(6)のとおり、構成要件Dの第2の収容槽に当\nたる曝気槽内に、酸素及びオゾンを含むマイクロナノバブルを供給する被告装 置を有しており、そのマイクロナノバブルには、オゾン発生装置から得られた オゾンガス、すなわちオゾンと酸素の混合ガスが用いられていて、オゾンが意 図的、積極的に加えられていると認められるから(甲16、18、21、弁論の 全趣旨)、構成要件Dを充足しない。\n
(4) 原告は、被告装置は、オゾンよりも多くの酸素が残存して含まれている上、 当該オゾン自体も活性炭により化学変化させて酸素となることにより、好気性 微生物及び通性嫌気性微生物を活性化させており、十分効果的である旨主張す\nる。
しかし、本件明細書に記載された本件各発明の目的、課題の解決手段等から すれば、本件各発明における「酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素 供給手段」は、前記(2)のとおり解するのが相当である。 また、原告は、オゾンは微量であるが、大気中に存在するし、「オゾン発生装 置」で生成されたオゾンは自然に消滅して酸素に置き換わるものなので、「第2 収容槽内においてはオゾンの量を早期に低減」させることは、2次的な効果に すぎない旨主張するが、前記(1)及び(2)で述べたところによれば、残オゾンを早 期に低減させることが本件各発明の2次的な効果にすぎないといえない。
(5) 以上によれば、被告システムは構成要件Dを充足せず、本件発明1の技術的\n範囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.04.22
令和5(ネ)10010 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(イ) 乙18分析及び乙24分析における分析対象物である公然実施発明
(引用発明)に基づく進歩性欠如の主張について a 公然実施発明は、公然実施品の具体的な構成又は組成等に基づいて認\n定されるため、通常、その公然実施品自体に課題が記載されていること はなく、何らかの課題があることを認識することは困難であるから、公 然実施発明に基づく容易想到性の有無を判断するにあたっては、公然実 施品から出願日(優先日)当時の技術常識を前提にして技術的思想や課 題を認識できるかどうか、その構成又は組成を変更する動機付けがある\nか否かを検討すべきである。
・・・
c 被控訴人の主張について
(a) 被控訴人は、前記第2の3(3)〔被控訴人の主張〕イ・ウのとおり、 本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人製品「無限七星FIS H」の重量平均分子量4.5×104との比較において、「1500 0」という上限値が技術的にいかなる意義を有するのかが不明であ り、本件優先日において、ポリアリルアミンの重量平均分子量上限値 の「15000」と、公然実施発明に係る同「45000」は、いず れもポリアリルアミンの重量平均分子量として広く知られ、一般的に 利用されている範囲内のものであるから、本件発明は、公然実施発明 に基づいて当業者が当然に予測することができたもので、進歩性を有\nしない旨を主張する。
この点につき、乙13(特開昭58−201811号公報)は、モ ノアリルアミンの重合体の製造方法について記載されたものである ところ、アリル化合物が通常のラジカル系開始剤によっては重合し難 いという問題があったことから、ラジカル系開始剤を用いて、モノア リルアミンの高重合度の重合体を製造する方法を提供することを目 的とするものであり、請求項1に記載の特定のラジカル系開始剤(分 子中にアゾ基とカチオン性の窒素原子を持つ基とを含む。)を用いれ ば、モノアリルアミンの無機酸塩が、極性溶媒中で極めて容易に重合 し、高収率で高重合度の重合体が得られることを見出したものであっ て(特許請求の範囲の記載、2頁左上欄及び3頁左下欄)、実施例に は、乙13記載の製造方法によって製造された数平均分子量(Mn) が「6500〜45000」のポリアリルアミンが記載されている。 しかし、乙13は、ポリアリルアミンを水に含有した際の機能につい\nて、また、数平均分子量の違いによる機能の差異について記載ないし\n示唆するものではないから、乙13の記載から、公然実施発明(引用 発明)の「無限七星FISH」について、含有成分であるポリアリル アミンの重量平均分子量等の物性を変更することが動機付けられる ものとはいえない。
また、乙12の1(メディカル社のウェブサイト)には、「PAA 🄬(ポリアリルアミン)」の製品紹介が記載されており、「日東紡が 世界で初めて工業的製法を確立したポリアリルアミン(PAA🄬)は、 一級アミンを主成分とする機能性カチオンポリマー」であり、「様々\nな素材のカチオン化や高機能化に最適」であることや、「お客様の使\n用目的・用途に応じてのご提案も可能」であることが記載され、「ア\nリルアミン塩酸塩重合体[1級アミン単独、水溶液]」として、重量 平均分子量(M.W.)が「1,600」(PAA−HCL−01)、 「15,000」(PAA−HCL−3L)、「100,000」(P AA−HCL−10L)等の製品が、また、「アリルアミン(フリー) 重合体[1級アミン単独、水溶液]」として、重量平均分子量(M. W.)が「1,600」(PAA−01)、「15,000」(PA A−15C)、「25,000」(PAA−25)等の製品が、それ ぞれ記載されている(1/3−2/3頁)。 また、乙12の2には、メディカル社の研究・開発の歴史について 記載され、「PAA🄬」に関して、「1984(昭和59)年 PA A🄬の(ポリアリルアミン)の重合方法発明および販売開始」、「1 991年(平成3)年 低分子PAA🄬を直接染料用固着剤として用 途開発・販売開始」等の記載がある。 しかし、乙12の1及び乙12の2も、ポリアリルアミンを水に含 有した際の機能や、重量平均分子量の違いによる機能\の差異について 記載ないし示唆するものではないから、乙12の1の記載から、公然 実施発明(引用発明)の「無限七星FISH」について、含有成分で あるポリアリルアミンの重量平均分子量等の物性を変更することを 動機付けられるものとはいえない。
そうすると、乙13、乙12の1及び乙12の2の各記載を考慮し ても、前記公然実施発明(公然実施品)の構成又は組成について、技\n術的思想や課題を認識できるような、本件優先日当時の技術常識があ ったとはいえないから、たとえ、重量平均分子量が「15000」又 は「45000」であるポリアリルアミンが市販されたものであり、 当業者に広く知られ、一般的に利用されているものであったとして も、そのことを根拠に、当業者が公然実施発明のポリアリルアミンの 重量平均分子量等の物性を変更することを当然に予測できるとはい\nえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(b) 被控訴人は、前記第2の3(3)〔被控訴人の主張〕エのとおり、本件 明細書にはポリアリルアミンの重量平均分子量につき本件訂正に係 る数値範囲は記載されていないから、当該数値範囲に特別な技術的意 義は認められず、本件明細書には重量平均分子量と発明の効果との間 に因果関係があることも記載されていないから、市販品として容易に 入手可能な重量平均分子量のポリアリルアミンを採用することに困\n難性はなく本件発明は進歩性を有しないと主張する。
そこで本件発明の技術的意義について検討すると、前記アのとお り、本件明細書には、簡便に調製でき、且つ優れた機能を有する機能\ 水を提供することを課題とし(段落【0002】ないし【0010】)、 当該課題を解決するために、機能水に、式(3)(式(3’)を包含\nする。)で表される不飽和アミンに由来する構\造単位を含むポリマー 等の多価アミン及び/又はその塩を機能成分として含有することを\n特徴とし、当該機能成分の機能\として、魚介類又は精肉の鮮度保持を 含む種々の機能を有することが開示されている(段落【0012】、\n【0013】、【0015】及び【0026】)。
また、式(3)で表される不飽和アミンに由来する構\造単位を含む ポリマーとして、本件発明のポリアリルアミン又はジアリルアミン重 合体に該当するポリマーBが例示されており、その重量平均分子量が 「例えば100〜200,000、好ましくは300〜100,00 0、さらに好ましくは500〜50,000である」こと(段落【0 052】ないし【0055】)、ポリマーBの市販品として、重量平 均分子量が「1600」であるポリアリルアミン(PAA−01)、 「15,000」であるポリアリルアミン(PAA−15C)及び「5, 000」であるジアリルアミン重合体(PAS−21)が開示されて いる(段落【0065】)。
そして、実施例において、具体的に、重量平均分子量が「1600」 若しくは「15,000」であるポリアリルアミン又は重量平均分子 量が「5,000」であるジアリルアミン重合体及び精製水を配合し た試験液を用いて、魚介類又は精肉の鮮度保持を含む種々の機能を確\n認したことが開示されている(段落【0108】ないし【0237】)。 そうすると、本件明細書の記載から、「重量平均分子量500〜1 5000」のポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体を含有する 機能水である本件発明には、前記のとおりの機能\を有する点で技術的 意義があることが認められる。
そして、前記(a)のとおり、公然実施発明(引用発明)に基づいて、 その含有成分であるポリアリルアミンの組成に着目し、重量平均分子 量等の物性をあえて変更することについて動機付けがあるとはいえ ないから、前記本件発明との相違に係る重量平均分子量の数値範囲の ものに置換することが容易に想到できたものとはいえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.04.14
令和5(ワ)3375 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月21日 大阪地方裁判所
前記(ア)のとおり、構成要件B2は、「縦板部」について、「庇板の開放された\n前端面に当接され」ていることと「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」 こととをいずれも備える旨規定している。当該当接部分と、「前面が雨水を下方へ 導くガイド面となっている」部分との位置関係については、構成要件B2の文言か\nらは一義的には明らかでないものの、本件明細書において、前記(イ)のように、本 件発明が、庇の全長が必要以上に長くなるなどの従来の庇の問題に着目して小型化 と構造の簡易化を実現し、保守、点検に手数を要さない庇を提供することを目的と\nしていること、その問題を解決するための手段として、前縁板は、「庇板の開放さ れた前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている縦板部」と、 「庇板の上面に当接され上面が雨水を縦板部のガイド面へ導くガイド面となってい る横板部」とが一体に形成されて成り、前記縦板部の下部内面には凹部が形成され るとの構成が示されていること、当該構\成において、庇板の上面に溜まった雨水は、 庇板の上面を伝って前縁板まで導かれ、横板部のガイド面を経て縦板部のガイド面 を伝って縦板部の下端より落下し、庇板と横板部との隙間より浸入した雨水は、縦 板部の内面を伝って下方へ流下して凹部内に流れ込み、凹部から溢れ出て縦板部の 下端より落下する旨が記載されていることからすれば、構成要件B2の「縦板部」\nは、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面が雨水を下方へ導くガ イド面となっている」ことを要するものと解するのが、当業者にとって合理的であ る。
そして、「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」部分と、「庇板の開 放された前端面に当接され」た部分とがいずれも備わっているが、両部分が離間し て存在し、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面が雨水を下方へ 導くガイド面」となっていない構成が「縦板部」に含まれるとの解釈は、本件明細\n書に示される本件発明の目的(庇の小型化や構造の簡易化)や作用に整合しないし、\n本件明細書上、これを許容するような記載や示唆も見当たらない。したがって、少 なくとも、かかる構成は構\成要件B2の「縦板部」を充足しないものというべきで ある。
イ 被告製品についてみると、被告製品の構造(形状)の概要は、別紙「イ号製\n品」及び「ロ号製品」の各図面記載のとおりであるところ(前提事実(4)ア)、両 別紙の各【図7】のとおり、庇板102の開放された前端面129に、先端見切1 04(「前縁板」に相当する。)の当接部145の板部が当たって接している、す なわち当接しているものと認められる。 しかしながら、雨水を下方へ導くガイド面140aは、中間に横方向へ延びる張 出部142を介して当接部145の板部とは離間して存在しており、当接部145 の板部の「前面」が雨水を下方へ導くガイド面となっているとは到底いえない。そ うすると、被告製品には、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面 が雨水を下方へ導くガイド面となっている」構成が備わっておらず、被告製品は、\n構成要件B2の「縦板部」を充足しない。\n
ウ これに対し、原告は、被告製品の折れ板部140(別紙「図面」の【原告主 張図1】及び【原告主張図2】の橙色部分)は、前端面129に当接する当接部1 45及び前面が雨水を下方へ導くガイド面140aを備えるから、構成要件B2の\n「縦板部」に該当する、構成要件B2の「縦板部」は、雨水を縦方向に導くガイド\n面を備えているから「縦板部」との語が用いられたにすぎず、被告製品が前方へ張 り出す張出部142を有するからといって、非充足になるとはいえない旨主張する。
しかし、前記アに述べたとおり、本件特許の特許請求の範囲の請求項及び本件明 細書の各記載からすると、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面 が雨水を下方へ導くガイド面」となっていない構成を、構\成要件B2の「縦板部」 に含めることはできないというべきであるから、被告製品の折れ板部140が当接 部145及びガイド面140aを備えるとしても、当接部145の板部の前面が、 ガイド面140aとは離間し、雨水を下方へ導くガイド面となっていない以上、折 れ板部140が構成要件B2の「縦板部」に該当するとは認められない。\nしたがって、被告製品が構成要件B2を充足する旨の原告の主張は採用できない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.04.11
令和5(ネ)10086 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、化合物自体が公知文献に明記されており、当該化合物を初めて 製造できたことに技術的意義が認められる物質特許の発明については、化合 物自体は公知であるから、その発明は新規性を欠くと解すべきであり、仮に 新規性を有するのであれば、その発明の技術的意義は当該化合物を製造でき たことについて認められるものであるから、その技術的範囲は、発明者が現 実に発明した製造方法によって製造された物か、単離された高純度の化合物 に限定されるべきであると主張するが、以下に述べるとおり採用できない。
ア 発明が技術的思想の創作であること(特許法2条1項参照)にかんがみ れば、特許出願前に頒布された刊行物(同法29条1項3号)に物の発 明が記載されているというためには、同刊行物に発明の構成が開示され\nているだけでなく、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の 創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその\n技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されてい ることを要する。
特に当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造 方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、 刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当 該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理解\nし得る程度の記載があることを要するというべきであり、刊行物に製造 方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業 者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時\nの技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことがで きることが必要であるというべきである。
そして、本件において、公知文献である本件引用例に5−アミノレブ リン酸リン酸塩の製造方法に関する記載は見当たらず、乙16〜18の 各論文によっても、特許出願時の技術常識に基づいて当業者がその製造 方法その他の入手方法を見出すことができたとは認められない(以上は 原判決「事実及び理由」第3の3(1)イ〔14頁〜〕に同じ。)。
イ 他方、本件明細書には、5−アミノレブリン酸リン酸塩の物質の構成が\n開示されている(【0009】、【0014】〜【0016】)にとど まらず、当業者がその製造方法を理解し得る程度の記載があるところ (【0007】、【0019】〜【0028】、【0034】〜【00 36】)、これは、新規の化学物質の発明である本件発明について、当 業者が実施し得る程度の発明の技術的思想を開示するものであって、単 なる製造方法としての技術的意義にとどまるものではない。
そして、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の 効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法\nにかかわらず及ぶこととなる(最高裁平成24年(受)第1204号同 27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照)。
ウ なお、控訴人が指摘するような、本件特許の出願の際に製造等していた 者については先使用による通常実施権(特許法79条)により、本件特 許の出願後に製造方法等の発明をした者については通常実施権の設定の 裁定(同法92条)により、特許権者との利益の調整が図られることに なる。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和4(ワ)9716
本件特許の無効審判に関する審決取消訴訟です。
結論は本件と同じです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2024.04.10
令和5(ワ)70114 不当利得返還等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月27日 東京地方裁判所
2 サポート要件違反があるか(争点4−1)について
本件発明1について
ア 本件発明1の構成要件1Fは、「前記信号演算として、横加速度を検出す\nる加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 G(Ghosei)の導出方法を少なくとも有し、」というものであり、構\n成要件1Hは、「当該車両において、前記傾斜角速度(Ψ)と前記補正後の 横G(Ghosei)の組合せにより、車両挙動が判断され、・・・」とい うものであり、本件発明1は、算出された補正後の横G(Ghosei)を 利用するECUによって車輪を適切に制動し、これによってロール方向の挙 動の抑制を図る車両ブレーキ制御装置(構成要件1I)であるとされている。\nそして、本件発明1は、前記1のとおり、自動二輪車等の制御装置につ いて、従来は、正確な傾斜角の検出ができなかったという課題を解決して、 車両の走行状態での正確な横Gを検出できるようにしたというものである。 これらからすると、構成要件1F及び1Hの「横G(Ghosei)」は、\n従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、 車両の傾斜走行状態での正確な横Gであると認められる。 ここで、制動指令の前提となる「横G(Ghosei)」は、「横加速度を 検出する加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った」(構\n成要件1F)ものであるとされていることから、「横G(Ghosei)」 は、横加速度を検出する加速度センサーの検出値を基に、これに補正をか けて得られる値であると理解できる。もっとも、本件発明1の特許請求の 範囲には、「横G(Ghosei)」について、単に加速度センサーの値か ら「ロールによる影響を取り除く演算を行った」(構成要件1F)と記載す\nるのみで、どのような演算をするかは明示されていない。そうすると、特 許請求の範囲には、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載さ れ、その解決のための構成は記載されていないといえる。\n
イ 本件明細書には本件発明の意義として前記1のとおりの記載があり、車両 の正確な傾斜角の検出ができず、正確な横Gを検出できなかったという課題 を解決して、車両の走行状態での正確な横Gを検出できるようにしたという ものであるとされている。
もっとも、本件明細書には、従前は検出できなかった正確な傾斜角の検出 をどのようにするかや、その傾斜角が判明した場合に正確な横Gを算出する ためにどのような補正を行うかについての記載はない。
他方、本件明細書には、センサーによる検出結果を補正して横Gを算出す る方法として、Ghosei = Gken − (Ψ・Rhsen) (式A) との記載がある(【0073】)。本件明細書の【0073】では、「Gken」 は、実際の走行傾斜時に検出される検出横Gであるとされ、「Ψ」は傾斜角 速度、「Ghosei」はΨを用いたGkenの補正後の横Gであるとされ ていて(なお、「Rhsen」について、本件明細書には定義がないものの、 「hsen」について路面とセンサとの距離であることを示唆する記載があ ったり(【0050】【0058】【0061】、図8、9)、「RはGセンサー #23の実車取付けの高さ(図8b hsen)」(【0063】)との記載、 Ψ・Rhsenについて、Rhsenに1を代入した上で「但し、センサー 取り付け高さ Rを1mとする。」との記載(【0074】)があったりする ことから、「Rhsen」車体を垂直にしたときのセンサ取り付け位置の高 さであることを一応推測できる。)、その「Ghosei」は、本件発明の課 題として言及されている「正確な横G」であると理解することができる。そ して、式Aは、その体裁から、本件発明の意義(前記1参照)として記載さ れている、「横Gセンサー」で検出されたGkenと「角速度センサー」で 検出されたΨを用いて「正確な横G」を算出する方法を記載した式であると 理解できる。
しかしながら、「Ψ・Rhsen」からは、傾斜角は算出されないし、式 Aから、傾斜角を算出することなく「正確な傾斜角の検出ができなかった諸 問題」が解決されていると理解することもできない。さらに、Ghosei 及びGkenは、加速度の次元(長さ/時間2)を有し、Ψ・Rhsenは 速度の次元(長さ/時間)の次元を有していることから、式Aは物理学上、 明らかに意味を持たない式である(弁論の全趣旨)。 そして、本件明細書には、式Aの他に、センサーによる測定値を基に「正 確な横G」を算出する方法についての記載はない。
ウ 本件明細書によれば、本件発明は、車両制御のためには「正確な横G」の 取得が必要であるところ、横加速度を検出する加速度センサーの値をその まま用いることができないこと、当該値から正確な横Gを算出するために は傾斜角度を取得することが必要だがそれができないことが課題として記 載され、本件発明はその課題に対して、車両の傾斜走行状態での正確な横 Gを算出したものであるとされており、「横加速度を検出する加速度セン サーのロールによる影響を取り除く演算を行った」という「横G(Ghos ei)」についての、当該演算が、本件発明の課題解決の根幹に当たる部分 であるといえるといえる。 しかしながら、特許請求の範囲には、その演算について、従来の課題を 解決するに足りる構成は記載されていない。また、本件明細書の発明の詳\n細な説明をみても、関係する記載は前記イのとおりである。本件明細書の 式A(【0073】)が、一応、上記の演算であると理解することはできる が、他に、関係する記載はない。そして、前記イのとおり、式Aは本件発明 の課題とされている傾斜角を算出しない上、そもそも物理学上意味をなさな い式であり、当業者はおよそ式Aを用いて車両制御に利用可能な横G(Gh\nosei)が算出できると理解できるものではない。
エ 原告は、本件明細書の記載は、別紙対比表のとおり誤記があり、正しく\nは同表の「訂正後」欄記載のとおりであると主張する。構\成要件1Fの「演 算」については、式Aのみが当たり得るところ、式Aは前記イで認定した とおり、次元の異なる物理量の差し引きをしていることから物理学上意 味をなさない式であり、当業者は、式Aに何らかの誤りがあると理解する ことができるといえる。この点について式Aについて、原告が主張すると おりGhosei=Gken−(Ψ.・Rhsen) (式A´)(ただし、「Ψ .」は傾斜角加速度)の誤記であると理解すれば、減算される物理量の次元が異なるという問題については解消される。しかし、次元を整える目的のみであれば、その訂 正の方法は式A´とすることに限られるものではないのであり、他に解消 方法を考え得るのであり、その考え得る解消方法が物理法則やそれを踏ま えた技術常識等に照らして不合理であることを認めるに足りる証拠はな い。そうすると、式Aの記載のみから、どのような誤記であるかのかが一 義的に定まるものであるとはいえない。 さらに、原告は、式Aについて「Ψ」を「Ψ.」に訂正するに当たって、 そのままでは式Aに関する説明が記載されている【0073】のその他の 記載と矛盾が生じるため、式Aのみならず、同段落における他の「Ψ」の 記載も「Ψ.」に訂正し、1か所の「傾斜角速度」との記載も「傾斜角加速 度」に訂正するものとしている。
しかし、原告が主張する訂正により、訂正後の【0073】は、「この補 正後の横G(Ghosei)は、(0063)式のGkenから傾斜角加速 度(Ψ.)を用いた補正であり、(0067)の式に対して、傾斜角が変化しない状況である。すなわち、式の「Ψ.・Rhsen」の項については、ゼロとなることから二つの式を整理し記述すると、・・・」との記載を含むことになるが、傾斜角加速度(Ψ.)がゼロであっても、傾斜角速度(Ψ)がゼロでないとき(定速傾斜時)は傾斜角が変化する状況なのだから、傾斜角加速度(Ψ.)に関する項「Ψ.・Rhsen」がゼロであることは直ちに「傾斜角が変化しない状況」を意味するものではないから、原告が主張する訂正をすると同記載部分の趣旨が理解できなくなってしまう。他方で、当該箇所について、「Ψ」を「Ψ.」に訂正しなければ、その内容は理解可能である。\n
同様に、原告が主張する訂正後の【0073】の「・・・この様に、式 の「Ψ.・Rhsen」の項について、ゼロにしたデーターは、定常円旋回 時に得られたデーターと呼ばれることがある。・・・」との記載についても、 定常円旋回時には、傾斜角が一定になるため、「傾斜角速度」が0になると ころ、「傾斜角加速度」に関する項が0になっても、「傾斜角」が変化しな いとは限らない(傾斜角加速度が0の場合には、定速傾斜の場合も含まれ る。)のであるから、訂正すると同記載部分の趣旨が理解できなくなって しまう。この点についても、当該箇所について訂正しなければその内容は 理解可能である。\n
さらに、式Aは、測定された加速度(Gken)を角速度(Ψ)の値に よって補正する式であるといえるが、これは、「走行時の横Gセンサーと 角速度センサーを関連付けることによって、従来は、正確な傾斜角の検出 ができなかった諸問題を解決」(前記1)という本件明細書に記載されて いる課題解決の基本的な方法として明示されている手法に文言上最も沿 うものである。他方、式Aを式A´に訂正すると少なくとも直接的にはこ れに文言上最も沿うものとはいえない内容になってしまう。 また、原告は、誤記を訂正した後の【0063】の記載によれば、傾斜 走行時に検出される検出横G(Gken)には、ロール速度の変化の影響 である加速度成分(Ψ.・Rhsen)が重畳されていること、重畳された 当該加速度成分は、傾斜角速度センサーの速度変化である傾斜角加速度 (Ψ.)を減算することで取り除くことができることが分かるなどと主張す る。
しかし、前記イで説示したとおり、本件明細書においてセンサーで取得 した加速度の値を修正して得られる制御に用いる加速度として言及され ているのは【0073】の横G(Ghosei)のみであり、【0063】 には、本件発明1の「横G(Ghosei)」の算出方法は記載されてい ない。仮に、【0063】に本件発明1に係る「加速度センサーのロール による影響を取り除く演算」が「Ψ.・Rhsen」を減算する趣旨であることを示唆する記載があると評価できるとしても、【0073】の方がより直接的な制御に用いる修正後の加速度を算出する方法に関する記載であると評価できるにもかかわらず、式Aについては、前記イで説示した問題がある。
また、【0063】には、Gken=g・cosΦ・tanρ−Ψ・Rhen (訂正後は「Gken=g・cosΦ・tanρ+Ψ.・Rhsen」)という式が記載されており、訂正後の式には「Ψ.・Rhsen」という項が含まれているものの、これを減算(訂正後は加算)した「g・cosΦ・tanρ」が物理学上、本件発明で算出することが課題とされている「正確な横G」に当たり、同物理量が判明すれば「正確な傾斜角の検出ができなかった諸問題」を解決できるものと理解できると認めるに足りる証拠はない。そうすると、仮に【0063】の記載が原告の主張するとおりの誤記であると認定できるとしても、当該式のみからでは、センサーによる検出値である「Gken」から「Ψ.・Rhsen」を減算することが課題解決につながり、構成要件1Fの「ロールによる影響を取り除く演算」に当たるものであると理解できるとはいえない。\n
また、原告の主張中には、【0063】より前の【0061】、【0062】の記載から【0063】の記載が誤記であることが理解できると主張する部分があるが、【0061】、【0062】にも多数の誤記があり、「Ψ」と「Ψ.」に関する誤記のみならず「−」と「+」に関する誤記まであり、どの部分が誤記であるのか容易に理解できるとは認め難い。もともと、本件明細書では、その全体にわたって、その説明の当初から基本的に一貫して加速度の次元の物理量から角速度(周速度)の次元の物理量を加算ないし減算するという式を前提とする内容で説明が記載されていて、前記エで説示したとおり、当該式に直接関連しない部分についてもこれと矛盾しない内容になっていた。そのような本件明細書について、当該式を訂正すると別の部分と矛盾が生じる内容になっている。これらからすると、当業者は、本件明細書に記載の誤りがあることを理解するとしても、本件明細 書において、本来どのようなことが記載されようとしていたのかや、どの部分がどのような誤記であるかを理解することができるとは認められない。
以上のとおり、当業者は、式Aに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Aの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式A´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Aの訂正と整合するように、本件明細書の式Aに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。
これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Aが式A´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Aについて式A´の誤記であると理解できることを前提とする原告の主張はその前提を欠く。
オ 本件発明1の意義は前記1のとおりである。そして、本件発明1の構成\n要件1Fには、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載され、 その解決のための構成は記載されていないといえるところ、前記ウのと\nおり、その課題の解決のための構成について、本件明細書に記載がある\nとはいえない。また、その記載がないにも関わらず、当該課題について、 当業者がそれを解決できると認識できることを認めるに足りない。そう すると、本件発明1は、本件明細書に記載された説明で、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるとはいえないし、当業者が技術常識に照らし発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。よって、本 件発明1は、本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
本件発明2について
ア 本件発明2は、算出された補正後の横G(Ghosei)を利用する、自 動二輪車の車両解析装置であるとされており、横G(Ghosei)の算出 方法については、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと傾斜 角速度の積との差分を求めるものとされている。 本件明細書においてこれに関する記載としては式Aに関する記載がある が、当該記載は本件明細書に記載された課題を解決する発明であると理解で きないものであることについては、前記 で説示したとおりである。他に本 件明細書には当該部分に係る記載があるとはいえない。よって、本件発明2 は本件明細書に記載されている発明であるとはいえない。
イ この点について、原告は、構成要件2Eの補正後の横G(Ghosei)\nの算出方法について、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと 「傾斜角速度」の積との差分との記載は、横加速度から加速度センサーの 車両取り付け高さと「傾斜角加速度」の積との差分の誤記であると主張す る。 しかし、本件明細書には、補正後の横Gに関する記載は式Aに関する記 載しかなく、ここには、「傾斜角加速度」の積との記載はない。原告は、式 Aが式A´の誤記であると主張するが、これが誤記であると理解できない ことについては前記 エで説示したとおりである。そうすると、仮に構成\n要件2Eが2E´の誤記であると理解できるとしても、本件発明2が本件 明細書に記載された発明であるとは認められない。 よって、本件発明のいずれについても、本件明細書に記載された発明であ るとはいえず、サポート要件を欠くものであると認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.03.24
令和5(ネ)10071 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月21日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
当裁判所は、本件請求原因の追加は攻撃方法の提出であって、民事訴訟法 143条ではなく同法157条の規律に服するものではあるが、結論的には 時機に後れたものとして却下を免れないと判断する。その理由は、以下のと おりである。
(1) 控訴人の本件請求は、特許法100条1項、3項に基づく差止請求、廃 棄請求及び不法行為に基づく損害賠償請求である。そのいずれも、被控訴人 による被控訴人製品の譲渡等が控訴人の有する「本件特許権」を侵害すると の請求原因に基づくものである。
そして、特許法は、一つの特許出願に対し一つの行政処分としての特許査 定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許 権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が\n付与されるものではない。そうすると、ある特許権の侵害を理由とする請求 を法的に構成するに当たり、いずれの請求項を選択して請求原因とするかと\nいうことは、特定の請求(訴訟物)に係る攻撃方法の選択の問題と理解する のが相当である。請求項ごとに別の請求(訴訟物)を観念した場合、請求項 ごとに次々と別訴を提起される応訴負担を相手方に負わせることになりかね ず不合理である。当裁判所の上記解釈は、特許権の侵害を巡る紛争の一回的 解決に資するものであり、このように解しても、特許権者としては、最初か ら全ての請求項を攻撃方法とする選択肢を与えられているのだから、その権 利行使が不当に制約されることにはならない。
(2) 以上によれば、控訴人による本件請求原因の追加は、訴えの追加的変更に 当たるものではなく、新たな攻撃方法としての請求原因を追加するものにと どまるから、本件請求原因の追加が民事訴訟法143条1項ただし書により 許されないとした原審の判断は誤りというべきである。
(3) もっとも、被控訴人は、本件請求原因の追加が攻撃方法に該当する場合に は民事訴訟法157条1項に基づく却下を求める旨の申立てをしている(引\n用に係る原判決の第3の2「被告の主張」欄(2))から、以下この点につい て判断する。
ア まず、本件請求原因の追加に至るまでの原審における手続等の経緯とし て、別紙「本件請求原因の追加に至る経緯」記載の事実が認められる (本件記録から明らかである。)。
すなわち、被控訴人は、答弁書(令和4年2月28日付け)の段階で、 乙1公報及び乙3公報等の公知文献を具体的に示して、均等論の第4要 件の充足を争う詳細な主張を提出した。その後、控訴人と被控訴人は、 同年11月までに、当該争点に関する議論を含む主張書面を2往復させ 主張立証を尽くしてきた。この間の書面準備手続調書には、被控訴人の 「均等論の第4要件を中心に反論書面を提出する」との進行意見が記載 されるなど、均等論の第4要件の充足性は、少なくとも本件の中心的な 争点の一つと認識されていた。そうして、侵害論に関する主張立証が一 応の区切りとなった同月28日のウェブ会議による協議(書面による弁 論準備手続に係るもの。以下同じ。)において、裁判所から双方当事者 に被控訴人製品は本件発明1の技術的範囲に属さないとの心証開示があ り、双方は和解を検討することとなった。その後間もなく和解交渉は不 調に終わったところ、令和5年1月27日の協議において、控訴人は、 消弧作用についての再反論(注・均等論の第2要件関係)及びこれまで の主張の補充等を記載した準備書面を提出すると述べた。ところが、控 訴人は、同年2月27日付け準備書面をもって、本件請求原因の追加の 主張をするに至った。これに対し、被控訴人は、同年4月13日付け準 備書面をもって、時機に後れた攻撃方法としての却下又は著しく訴訟手 続を遅延させる訴えの変更としての不許決定を求める申立てをした。\n
イ 以上に基づいて、まず、本件請求原因の追加が「時機に後れた」ものと いえるかどうかを検討するに、本件において、控訴人が本件請求原因の 追加を求めた理由は、請求項1に係る本件発明1の技術的範囲の属否を 問題とする限り、被控訴人が提出した公知文献(特に乙1公報及び乙3 公報)との関係で均等論の第4要件(公知技術等の非該当)は満たさな いと判断される可能性が高いことを踏まえ、本件付加構\成を備える請求 項3に係る本件発明2を議論の俎上に載せることで、均等論の第4要件 をクリアしようとしたものと理解される。
しかし、上記アのとおり、均等論の第4要件を争う被控訴人の主張は、 既に答弁書の段階で詳細かつ具体的に提出されており、これに対する対 抗手段として、本件請求原因の追加を検討することは可能であったもの\nである。その後、約9か月にわたり双方が主張書面を2往復させてこの 点の主張立証を尽くしていたところ、その後に裁判所からの心証開示を 受けた後に、しかも、控訴人自ら、補充的な書面提出のみを予定する旨\nの進行意見を述べていたにもかかわらず、突然、本件請求原因の追加を 行ったものであって、これが時機に後れた攻撃方法の提出に当たること は明らかである。
ウ 次に、故意又は重過失の要件についてみるに、本件請求原因の追加は、 当初から本件特許の内容となっていた請求項3を攻撃方法に加えるとい う内容であるから、その提出を適時にできなかった事情があるとは考え 難い。外国文献等をサーチする必要があったケースとか、権利範囲の減 縮を甘受せざるを得なくなる訂正の再抗弁を提出する場合などとは異な る。控訴人からも、やむをえない事情等につき具体的な主張(弁解)は されていない。そうすると、時機に後れた攻撃方法の提出に至ったこと につき、控訴人には少なくとも重過失が認められるというべきである。
エ そして、本件請求原因の追加により、訴訟の完結を遅延させることとな るとの要件も優に認められる。すなわち、本件発明2の本件付加構成を\n充足するか否かについては、従前全く審理されていないから、本件請求 原因の追加を許した場合、この点について改めて審理を行う必要が生ず ることは当然である。そして、被控訴人は、仮に本件請求原因の追加が 許された場合の予備的主張として、本件発明2の本件付加構\成のクレー ム解釈及び被控訴人製品の特定に関する詳細な求釈明の申立てをする\n(控訴答弁書19頁〜)などしていることを踏まえると、この点の審理 には相当な期間を要し、訴訟の完結を遅延させることとなることは明ら かである。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.03.23
令和4(ワ)9521 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月26日 大阪地方裁判所
ア 本件各発明は、耐熱性透明材料として好適な熱可塑性樹脂組成物と、当該 組成物からなる樹脂成形品ならびに樹脂成形品の具体的な一例である偏光 子保護フィルム、樹脂成形品の製造方法に関する発明である(【0001】)。 アクリル樹脂の透明度の低下を防止するためにUVAを添加する方法が 公知であったが、成形時の発泡やUVAのブリードアウト、UVAの蒸散に よる紫外線吸収能の低下との問題につき、従来技術として、アクリル樹脂に組み合わせるUVAとして、トリアジン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物およびベンゾフェノン系化合物が用いられていた(【0003】、【00\n05】、【0006】)。しかし、これらの従来技術として例示されたアクリル 樹脂(【0006】記載の特許文献)には、いずれも分子量が700以上のU VAは開示されていなかった。
イ 本件各発明は、従来技術の化合物には、主鎖に環構造を有するアクリル樹脂との相溶性に課題があり、高温成形時の発泡やブリードアウトの発生の抑制が不十\分であったことから、これらの課題を克服するため(【0007】、【0008】)、樹脂組成物を構成要件1B記載の構\成とし、その製造方法を構成要件6B記載の構\成とし(【0009】、【0010】)、これにより11 0゜C)以上という高いTgに基づく優れた耐熱性や高温成形時における発泡 及びブリードアウトの抑制、UVAの蒸散による問題発生の減少との効果を 奏することとなった(【0015】)。
ウ したがって、本件各発明の本質的部分は、ヒドロキシフェニルトリアジン 骨格を有する、分子量が700以上のUVAが、主鎖に環構造を有する熱可塑性アクリル樹脂と相溶性を有することを見出したことにより、110゜C)以 上という高い優れた耐熱性や高温成形時における発泡及びブリードアウト の抑制、UVAの蒸散による問題発生の減少という効果を有する樹脂組成物 を提供することを可能にした点にあると認められる。
エ 数値をもって技術的範囲を限定し(数値限定発明)、その数値に設定する ことに意義がある発明は、その数値の範囲内の技術に限定することで、その 発明に対して特許が付与されたと考えられるから、特段の事情のない限り、 その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分に当たると解す べきである。
上記検討によれば、分子量を「700以上」とすることには技術的意義が あるといえるうえ、本件において、上記特段の事情は何らうかがえない。 オ そうすると、被告UVAの分子量が「700以上」ではないとの相違点は、 本件各発明の本質的部分に係る差異であるというべきであるから、被告製品 及び被告方法について、均等の第1要件が成立すると認めることはできず、 均等侵害は成立しない。
カ 原告は、本件各発明におけるUVAの分子量である「700」に厳格な技 術的意義はなく、本件各発明の本質的部分は、分子量が十分に大きいという上位概念であると主張する。 しかし、このような上位概念化は、前述の数値限定発明の技術的意義に関 する考え方と相容れず権利範囲を不当に拡大するものである。また、本件証 拠上、本件各発明におけるUVAの分子量が十分に大きいということが当業者にとって自明であるとも認められないし、分子量が十\分に大きいことと、被告UVAの分子量との比較における本件各発明の数値の臨界的意義との 関係は何ら明らかにされていない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 数値限定
>> ピックアップ対象
2024.03.23
令和4(ワ)9100 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月21日 東京地方裁判所
被告方法では、磁性体モールド樹脂で成形されているEコア及びIコア並び にコイルを合体させたコアを、●(省略)●に形成されたキャビティに配置し、 加圧しつつ加熱して樹脂を硬化させてモールドコイルを作成する(以下「加圧・ 加熱過程」という。)ところ、加圧・加熱過程で●(省略)●から磁性体モール ド樹脂が漏れ出し、これが硬化してバリが形成される(第2の2前提事実 )。 原告は、上記の被告方法において、キャビティに配置されるEコア、Iコア を形成する磁性体モールド樹脂(以下「磁性体モールド樹脂(コア)」という。) が構成要件Fの「該キャビティ内に充填した磁性体モールド樹脂」に該当し、\n加圧によって漏れ出してバリを形成する磁性体モールド樹脂(以下「磁性体モ ールド樹脂(バリ)」という。)が「該排出した磁性体モールド樹脂」に該当 し、磁性体モールド樹脂(バリ)を構成する磁性体粉末の容積比(以下「磁性\n体粉末容積比(バリ)」という。)が磁性体モールド樹脂(コア)を構成する\n磁性体粉末の容積比(以下「磁性体粉末容積比(コア)」という。)よりも小 さいと主張するものと解される。
もっとも、被告方法を用いて被告製品を製造する過程において、磁性体粉末 容積比(コア)と磁性体粉末容積比(バリ)について、これらを直接測定して 比較し、後者の容積比の方が小さいものであったことを示す証拠はない。他方、 被告からは、被告方法で作成されたモールドコイルにおいて、磁性体粉末容積 比(バリ)と磁性体粉末容積比(コア)がほぼ同じである旨の電子顕微鏡で撮 影された画像の分析結果(乙4)が提出されている。
ア 原告は、磁性体粉末容積比(コア)と磁性体粉末容積比(バリ)について、 磁性体粉末の粒子径が、磁性体モールド樹脂が漏れ出す隙間よりも大きけれ ば、樹脂が隙間から優先的に排出されるために磁性体粉末容積比(バリ)の 方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなるところ、被告方法の加圧・ 加熱過程で加圧を続けても樹脂の流出が止まるのは、磁性体粉末が隙間を埋 めることが理由であるから、被告方法においては、樹脂が隙間から優先的に 排出されるといった事象が生じたことが示されていると主張する。これに対 して、被告は、被告方法において加圧・加熱過程で加圧を続けているにもか かわらず樹脂の流出が止まる理由について、磁性体によって隙間が埋められ たためではなく、触媒等を利用した上で加熱により樹脂が硬化したためであ ると主張している。
原告は、被告が主張するような短時間で硬化は生じない旨主張するが、被 告方法における樹脂の硬化につき、この原告主張を裏付けるに足りる証拠は ない。また、樹脂の流出が止まったのが磁性体粉末が隙間を埋めたものであ ることを裏付ける証拠はない。被告が実際に使用している被告方法において、 原告が主張するのとは異なる理由により樹脂の流出が止まったことを否定 できず、被告方法において、原告が主張する事象が生じたことによって樹脂 の流出が止まると認めるには足りない。そうすると、原告の主張はその前提 を欠く。
イ(ア)原告は、加圧・加熱過程において磁性体モールド樹脂が漏れ出す隙間が 磁性体粉末の粒子径よりも小さければ、樹脂が優先的に流出するために 磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さく なるという原理を前提に、被告方法で生じている隙間は十分に小さいも\nのであると主張する。
(イ)しかし、被告方法において隙間に相当するものの幅、形状・構造等は不\n明である。原告は、バレル研磨跡に生じている被告製品の角に生じた研磨 跡に着目し、バリの幅は研磨跡を超えることはないなどとして、研磨跡か らバリの幅を推計し、バリの厚さは●(省略)●を超えるものではないな どとも主張する(甲8)。しかし、研磨跡によりバリの幅を正しく把握で きるかは明らかでなく、原告指摘の事実によっても、隙間に相当するもの の幅、形状・構造等は不明である。\n
(ウ)被告方法で用いられる磁性体粉末の大きさについても、被告が用いた磁 性体のD99は、●(省略)●D90は、●(省略)●であることは認め られる(乙3)が、被告方法においては、様々な粒子径、形状の磁性体が 使用され、具体的な粒子径の分布は不明である。そして、被告方法で作成 されたモールドコイル及びバリの電子顕微鏡で撮影された画像(乙4)に よれば、被告方法で隙間に相当するものの幅に比べて格段に小さな磁性体 粒子が多数含まれていることが認められる。
(エ)原告が前記(ア)で主張する原理について、全磁性体粒子のうちの最小粒子 径が隙間よりも大きい場合には、磁性体は隙間を通過することができない ため、樹脂のみが隙間から流出することは推測できる。逆に、全磁性体の 粒子径が隙間よりも十分に小さければ、樹脂と共に磁性体も隙間を通過す\nることから磁性体粉末容積比(コア)及び磁性体粉末容積比(バリ)に変 化がないものと推測でき、隙間より大きな磁性体粒子の割合が極めて小さ い場合にも同様である。他方で、これら以外の場合には、磁性体粉末の具 体的な粒子径の形状・分布、樹脂の性質、隙間の形状・構造、加えられる\n圧力等により、隙間を通過する磁性体の量は変化するものと推測される。 そして、それらについて、どのようなものであった場合に隙間を通過する 磁性体がどの程度あるかについて、これを認めるに足りる証拠はない。
(オ)以上によれば、被告方法においては、様々な粒子径、形状の磁性体が使 用されているところ、その全磁性体粒子のうちの最小粒子径が被告方法 で使用されている●(省略)●よりも大きいことを認めるに足りない。ま た、そのように全磁性体粒子のうちの最小粒子径が被告方法で使用され ている●(省略)●よりも大きいことが認められない場合、被告方法にお いて、どのような割合で磁性体と樹脂が被告方法における隙間に相当す る部分を通過するかは明らかではなく、特に本件のように隙間よりも小 さな粒子径を有する磁性体粒子が多数含まれる場合には、原告が主張す る原理によって、被告方法において磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性 体粉末容積比(コア)よりも小さくなっているという事実を認めるに足り ない。
ウ 以上によれば、被告方法において磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体 粉末容積比(コア)よりも小さくなっていることを認めるに足りる証拠はな い。かえって、前記 のとおり、被告からは、被告方法で作成されたモール ドコイルにおいて、粉末容積比(バリ)と粉末容積比(コア)が変わらない 旨の電子顕微鏡で撮影された画像の分析結果(乙4)が提出されている。
(3)よって、被告方法において粉末容積比(バリ)の方が粉末容積比(コア)よ りも小さくなっていることを認めることはできず、被告方法が構成要件Fを充\n足するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.02.24
令和5(ワ)70454 特許権侵害等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月9日 東京地方裁判所
(1) 「検査分析装置」及び「検査分析」の意義について
本件発明に係る特許請求の範囲においては、構成要件A、D、F及びGに\n「検査分析装置」との記載があり、構成要件A、B、C、E及びHに「検査\n分析」との記載があるものの、それらの意義は、当該特許請求の範囲の記載 からは明らかではない。
そして、本件明細書には、技術分野に関し、「半導体集積回路装置…の開 発、製造などの検査分析工程で用いられる走査型電子顕微鏡(SEM)、共 焦点レーザ顕微鏡などの検査分析装置の利用方法に関」する(【0001】) との記載が、背景技術に関し、「半導体ウェハ、半導体チップなどの検査分 析においては、検査分析対象となる試料と検査分析装置の性能が合致しない\nと全く有効な検査分析とならない。」(【0004】)及び「半導体ウェハ、半 導体チップの検査分析においては、そのコスト増が著しく、半導体集積回路 装置の開発、製造コストの増大の要因になっている。」(【0005】)との記 載が、課題に関し、「本発明の目的は、半導体集積回路装置などの開発、製 造を効率的に行うために用いられる検査分析工程において、低コストで効率 的に検査分析が行える技術を提供することである。」(【0015】)との記載 が、課題を解決するための手段に関し、本件発明は、検査分析装置の管理者 側と検査分析を希望するユーザ側のそれぞれにセキュリティ確保手段を講じ た上、ユーザが、離れた場所にある検査分析装置を、リアルタイムでリモー ト操作する、又は、ユーザが事前に作成した操作レシピーデータに基づいて 検査分析を行う旨(【0016】ないし【0019】)の記載に加え、「本件 発明の検査分析は、細く絞ったレーザビームを試料面へ照射してその反射光、 散乱光、透過光の少なくとも一つを検出すること、または電子ビームを照射 して二次電子、散乱電子、透過電子の内の少なくとも一つを検出することに より、試料上の所望の箇所を分析するものである。」(【0024】)との記載 が、発明の効果に関し、「本件発明により、検査分析を所望する複数ユーザ に対し、ユーザは個別に検査分析装置の導入のための投資することなく、ユ ーザ試料の検査分析が効率よく行うことが可能となった。」(【0026】)と\nの記載が、それぞれある。これらの記載に照らすと、「検査分析装置」とは、 試料を装填等して、ユーザのリモート操作によりその試料を分析し、検査す る検査分析ユニットを有する装置を意味し、「検査分析」とは、試料を装填 等して、ユーザのリモート操作によりその試料を分析し、検査する工程を意 味すると理解することができる。
これに対し、原告は、「検査分析装置」について、「インターネットを介し たリモート操作が検査分析の対象となるコンピュータ装置であり、当該検査 分析に異常がないことを条件とし、リモート操作した情報を提供するコンピ ュータ装置」と、「検査分析」について、「インターネットを介した検査分析 装置に対するリモート操作に異常がないかの検査分析」と、それぞれ解すべ きである旨主張し、検査の対象が「リモート操作」であることを前提として いるものと解されるが、本件明細書には、原告が主張する解釈の根拠となる 記載はないから、同主張は理由がない。
(2) 被告方法の構成要件充足性について\n
原告の主張は明確ではないものの、被告の動画配信サービスを提供するサ ーバが、「検査分析装置」に該当し、同サービスにおいて、視聴者が動画配 信の内容についてコメントを付したり、高評価ボタンを押下したりすること が、「検査分析」であると主張するものと理解することができる。 しかし、被告の動画配信サービスを提供するサーバは、検査分析の対象と なる試料の装填等を想定したものではなく、ユーザからリモート操作される ことによりその情報等を分析し、検査する検査分析ユニットを備えているも のと認めることはできないから(弁論の全趣旨)、同サーバは、構成要件A、\nD、F及びGの「検査分析装置」に該当しない。 同様に、被告の動画配信サービスにおいて、視聴者が、動画配信の内容に ついてコメントを付したり、高評価ボタンを押下したりすることは、試料を 装填等することを前提とするものではなく、ユーザが同試料について情報等 を分析し、検査するものでもないから、構成要件A、B、C、E及びHの\n「検査分析」に該当しない。 その他、原告の主張する被告方法の内容に照らし、被告方法が「検査分析 装置」又は「検査分析」に該当する装置又は工程を備えるものとは認められ ない。以上のとおり、被告方法が構成要件AないしHを充足すると認めることは\nできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.02.23
令和5(ネ)10026 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年1月31日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ア 控訴人は、構成要件2Bを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表\面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で2.0μm以下であることを要する」と解する根拠は、特許請求の範囲の文言にも本件発明2の課題にも なく、当業者の技術常識等からみても非現実的である旨主張する。
イ しかし、構成要件2Bは「前記排水溝の壁面の表\面粗さが、算術平均粗 さ(Ra)で、2.0μm以下であることを特徴とする」と規定してお り、本件発明2の特許請求の範囲の文言全体をみても、排水溝壁面の表面粗さについて、一部は2.0μmを超えるが製品の一定範囲や所定の\n測定箇所が2.0μm以下であるものを含む、あるいは全体の算術平均 粗さ(Ra)の平均値が2.0μm以下であるものを含むと解すべき文 言はない。
この点は、本件明細書2の記載をみても同様である。控訴人が指摘す る本件明細書2の記載や図面は、従来技術や実施例に係る排水溝の性状 等を特に留保なく説明するものであり、控訴人が主張するように、作業 過程で異常(イレギュラー)が発生した箇所があることを前提とし、こ れを除いた「任意の箇所」を示すものであることを窺わせる記載はない。 控訴人は、1)製紙用弾性ベルトの排水溝は、作業前に設定した加工条 件に基づいて均一的に連続加工されるものであること、2)作業時の諸要 因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないこと、3)排 水溝の壁面を全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって製品の性状を把握\nするという、当業者の技術常識を考慮すべき旨主張する。
しかし、上記のとおり明確な構成要件2Bの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な\n拡張解釈というべきであって、特許請求の範囲の解釈に当たって当業者 の技術常識を考慮するという枠組みを超えるものといわざるを得ない。 控訴人の主張は、当業者が定める自社製品の品質基準としてはともかく、 独占権が付与される特許請求の範囲の解釈としては採り得ない。 なお、控訴人が指摘する大阪地方裁判所平成15年(ワ)第10959号 同17年2月28日判決は、控訴人の主張を裏付けるものではない。
ウ したがって、原判決判示のとおり、構成要件2Bは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表\面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で2.0μm以下であること」を要すると解するのが相当である。
そうすると、控訴人が主張する<ステップ1>から<ステップ2の2 B>まで、すなわち「各測定結果に係る9溝ないし18溝のデータ数値 を参照し、特定の溝壁面の表面粗さ数値が他の溝の同一壁面に比して突出して高くなっている」ものを「当業者からみて明らかに溝加工作業時\nに生じた異常(イレギュラー)」として除外すること、及び「測定結果 に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ(Ra)で2.0μm以下である結果が得られているか否か」(控訴人の他の主張と併せると、\n任意の測定箇所の算術平均粗さの「平均値」が2.0μm以下であるこ とを意味すると解される。)により充足性を判断する判断手法は、構成要件2Bを逸脱する独自の解釈に基づくものといわざるを得ず、採用で\nきない。
・・・
(2) 公然実施発明Bに基づく本件発明1の新規性欠如の有無について
イ 公然実施をされた発明に当たるかについて
(ア) 控訴人は、本件特許1の出願当時、当業者は、ベルトBの外周面にD MTDA(エタキュアー300)が使用されていることを通常利用可能な分析方法によって知ることができなかった旨主張する。\n
(イ) しかし、まず、証拠(乙37、124、128、129)によれば、 エタキュアー300は、本件特許1の出願前から実用化され、ウレタン 用の硬化剤として注目されていたことが認められる(原判決44頁〜)。 控訴人は、上記文献等はシュープレス用ベルトに使用される硬化剤に ついて言及するものでないと主張するが、上記文献等はポリウレタン全 般向けの硬化剤としてエタキュアー300を説明するものであるところ、 シュープレス用ベルトに利用される硬化剤が他の一般的なポリウレタン の硬化剤と異なるとみるべき根拠はない(上記文献等には、代表的な従来品が本件明細書1【0003】に従来のシュープレス用ベルトの硬化\n剤として記載されているMOCAである旨の記載も複数ある。)。
また、被控訴人は、遅くとも平成9年7月時点ではエタキュアー30 0を使用していたところ(原判決45頁)、上記ア(イ)の認定事実によ れば、被控訴人は硬化剤としてDMTDAを使用することを独自に見出 したのではなく、エタキュアー300を製造販売するアルベマール社の 国内関連会社との取引を契機として知ったと認められる。この事情は、 他の当業者が硬化剤の候補としてエタキュアー300に着目する蓋然性 を裏付ける事情となることは明らかである。 控訴人は、さらに、ポリウレタンの硬化剤はDMTDAの他にも約8 0種類存在し(甲43)、その全てについて標準品を準備して分析依頼 を行うことは非現実的であると主張する。
しかし、「ポリウレタン樹脂ハンドブック」(乙128)に「実用化 されている熱硬化PUエラストマー用芳香族ジアミン架橋剤」として記 載された5種類、あるいは特開2000−248040号公報(乙12 7)にポリウレタンプレポリマーと反応させるアミン硬化剤組成物とし て記載された芳香族ポリアミンの15種類、その中でも好ましいと記載 された4種類には、いずれもエタキュアー300又はDMTDAが含ま れており、当業者は、従来用いられているMOCA(本件明細書1【0 003】)と同類であるこれらの硬化剤を想定するとみるのが自然であ る。
(ウ) 控訴人は、ベルトの外周面に着目し、外周面のみを切り出して分析を 依頼することは、当業者が通常に利用可能な分析技術とはいえない旨主張する。\nしかし、本件特許1の出願日前において、外周層、内周層等の複数の 層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリマーと硬化剤と を混合してベルトの弾性材料とすることは技術常識であり(原判決44 頁)、自由に解析等をなし得る状態に置かれたベルトを解析して構造等を特定することは可能\であったと認められる(このことは甲25に記載された断面写真から明らかであり、原判決の認定に問題はない。)。 したがって、ベルトBの外周層を切り出して分析を依頼することは、 本件訴訟において控訴人(甲10の1〜4)及び被控訴人(乙1〜3) が行ったのと同様、本件特許1出願前の当業者にも可能であったと認められる。\n
なお、当業者が仮に外周層と内周層に異なる硬化剤を用いる製造方法 を認識せず、これらを区別せずに分析を依頼した場合、全体について硬 化剤としてDMTDAが使用されているという分析結果を知ることにな り、この結果はベルトBの正しい構成なのであるから(乙32)、「外周面を構\成するポリウレタンは、」「ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている」との構成を含め、本件発明1の内容を知り得たといえることに変わりはない。\n
(エ) したがって、本件特許1の出願当時、当業者は、ベルトBの外周面に DMTDA(エタキュアー300)が使用されていることを通常利用可 能な分析方法によって知ることができたと認められる。ベルトBが公然実施された発明とはいえない旨をいう控訴人の主張は採用できない。\n
◆判決本文
原審はこちら。
◆大阪地裁平成29(ワ)4178
原審では、被告は、一旦、損害論に入ってから、2.0μm以下である」との構成要件を充足しないとして、非侵害の主張を行いましたが、これは「時機に後れた」とは認定されませんでした。
原告は、第15回弁論準備手続期日から損害論の審理が開始されたにもかかわ
らず、被告は、被告製品1〜3及び5と同じシリーズの製品等における排水溝壁
面の表面粗さの測定結果(乙152〜159)を新たに証拠提出するとともに、非侵害の主張を行ったことが時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張する。\nしかし、被告が前記証拠等を提出したのは、原告が、訴状においてはイ号製品
が本件発明2の技術的範囲に属する旨を主張しつつも、被告製品1〜3及び5の
排水溝壁面の表面粗さに限定して立証活動をしていたが、裁判所が本件発明2については損害論に入る旨の心証開示を行ったことを受けて、被告製品1〜3及び\n5の各製品と同じシリーズの製品等についても本件発明2の技術的範囲に属する
旨を改めて主張したことに対応するものであって、必ずしも時機に後れたものと
は認められない。したがって、原告の前記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.02.16
令和5(ワ)70102 特許権侵害差止及び特許権侵害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年12月4日 東京地方裁判所
ア 本件発明の構成要件BないしDは、ポリフェノールの重量、EGCGとE\nCGの合計重量又は総カテキンの重量につき、各構成要件記載の重量%以下\nに限定するものであるが、上記構成要件にいう「茎が取り除かれた」とは、\n本件発明の半発酵茶葉が茎を含まないことを意味するのか、あるいは、茎を 含む半発酵茶葉のポリフェノール等の重量%を測定するための条件を示す ものか、文言上必ずしも明らかではない。そのため、本件明細書の記載を考 慮して、その用語の意味を解釈すると、本件明細書の記載【0079】には、 「サンプリング方法:できた各号のお茶の茎を取り除き、篩い分けて12メ ッシュパス20メッシュオンの砕茶を各800g採取する。」として、本件 発明の半発酵茶葉は、その茎が取り除かれることが明確に記載されている。 そして、本件明細書の他の実施例をみても、官能試験によって本件発明の効\n果が確認されている茶葉は、いずれもサンプリングの段階で茎が取り除かれ たものであり、本件明細書全体の記載によっても、茎が含まれた茶葉につい ては、本件発明の効果を確認するような記載が一切存在せず、本件発明の茶 葉に茎が含まれることを示唆する記載も一切認められない。 上記各構成要件及び本件明細書の記載を踏まえると、上記各構\成要件にい う「茎が取り除かれた」とは、本件発明の半発酵茶葉が茎を含まないことを 意味するものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、前記認定事実及び弁論の全趣旨(被告各製品 (双方当事者持参に係るもの)に係る茎の有無の確認結果〔第3回弁論準備 手続期日及び第4回弁論準備手続期日〕を含む。)によれば、被告各製品の 茶葉には、いずれも多くの茎が含まれていることが認められる。 したがって、被告各製品は、本件発明の構成要件BないしDを充足するも\nのと認めることはできない。
のみならず、原告による本件各試験は、被告各製品において茎を除いてポ リフェノール等の重量%を測定していることまで立証するものではなく、上 記構成要件BないしDを立証する前提を欠くものといえる。しかも、原告に\nよる本件各試験は、被告らが釈明したとおり(第1回弁論準備手続調書参照)、 本件各試験に係る具体的な実施条件等が明らかにされていないため、上記構\n成要件BないしDにいう成分重量を的確に立証するものとはいえない。その 上、原告が採用した測定方法は、本件明細書【0082】に記載された測定 方法(カテキンにあってはISO14502、ポリフェノールがGB/T8 313をいう。)とは異なるものであるから、上記構成要件BないしDに各\n規定する成分重量を立証するに適切なものとはいえない。 この理は、原告が時機に後れて提出した本件試験その2(甲19、20) についても、測定に当たり茎が除かれていない点、具体的な実施条件等を欠 く点において同様に当てはまるものであり、同試験も上記認定判断を左右す るに至らない。
したがって、原告の立証は、上記各構成要件の充足性を裏付けるに的確な\nものとはいえず、このような観点からしても、被告各製品は、本件発明の構\n成要件BないしDを充足するものと認めることはできない。 イ これに対して、原告は、1)仮に茎を取り除かなければ、被告各製品には全 体の13重量%から18重量%の茎が含まれているはずであり、見た目も悪 くなるはずであるが、実際にはそうではないこと、2)仮に茎が完全には取り 除かれていなかったとしても、少々の茎は、この業界では茎が取り除かれた ものとみなされていること、3)仮に茎が取り除かれていないとしても、被告 各製品の半発酵茶という性質に何ら変わりはないことを主張する。 しかしながら、本件特許に係る茶葉は、茎が取り除かれているものである ことは、上記において説示したとおりであり、原告の主張は、本件特許の構\n成要件の用語の意義を正解しないものである。また、被告各製品には、少々 とはいえない茎が含まれていることも、上記において認定したとおりであり、 原告の主張は、その前提を欠くというほかない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.02. 7
令和3(ワ)18262 損害賠償請求事件(特許権侵害) 特許権 民事訴訟 令和5年12月6日 東京地方裁判所
ア 証拠(乙18、29、30)及び弁論の全趣旨によれば、令和2年1月 22日から令和4年2月22日までの間の被告製品の売上高は、1億17 57万6451円であったと認められる。
イ(ア) 原告は、被告が、令和2年1月1日から同月21日までの間も被告製 品を販売したと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
(イ) また、原告は、被告の公式ホームページにおいて、被告製品の販売数 量について「27万着突破!」、「30万着突破!」と記載されていたこ とを指摘して、被告製品の販売数量は少なくとも27万着であり、これ に1着当たりの単価5980円を乗じると、被告製品の売上高は16億 1460万円を下らないと主張する。 そこで検討すると、確かに、証拠(甲4、14)によれば、被告の公 式ホームページにおいて上記の記載がされていたことが認められるもの の、同ホームページに記載されていた販売価格(5980円。弁論の全 趣旨によれば、この価格はブラジャーの一般的な販売価格として相当な ものと認められる。)を前提とすると、前記アにおいて認定した被告製品 の売上高は、請求書記載の被告製品の輸入数量(乙17)、被告製品に係 る販売管理データ記載の販売数量(乙18)、被告の損益計算書記載の売 上高(乙20、21)、被告における被告製品以外の売上高(乙22ない し24)と整合的であるといえる。これに対し、被告製品の販売数量が 27万着以上であることを示す資料は、被告の公式ホームページの記載 以外に存在しない。
これらの事情に照らせば、令和2年1月22日から令和4年2月22 日までの間の被告製品の売上高は前記アにおいて認定したとおりであっ て、被告の公式ホームページにおける販売数量の記載は虚偽のものであ ったと認めるのが相当である。
(ウ) したがって、原告の前記各主張を採用することはできない。
(2) 相当な実施料率について
ア 本件発明の実施に対し受けるべき料率については、1)本件発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界にお ける実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)本件発明自体の価値すなわち本 件発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)本件発明を被 告製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者 である原告と侵害者である被告との競業関係や特許権者である原告の営業 方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきで ある。
イ 本件についてみると、本件発明の実際の実施許諾契約における実施料率 は、5パーセントであることが認められる(甲15ないし18)。 また、本件発明は、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、 個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の 補正機能等に対応することが可能\な女性用衣料を低コストで提供すること を可能とするものであるところ(前記1(2)イ)、被告製品も、女性のバス トの補正を主たる機能としたものであるから(甲3、4、14)、本件発明\nを被告製品に用いることが被告の売上げ及び利益に大きく貢献していると 認めるのが相当であって、他のものによる代替可能性はうかがわれない。\nさらに、原告と被告は、いずれも女性用衣料を販売しているから(前提 事実(1)、(5)及び(6))、その市場において競業関係にある。 これらの事情に照らすと、特許権侵害をした者に対して事後的に定められ る本件発明の実施に対し受けるべき料率については、6パーセントと認め るのが相当である。
(3) 特許法102条3項により算定される額について
以上によれば、特許法102条3項により算定される本件発明の実施に対 し受けるべき金銭の額に相当する額は、705万4587円(1円未満四捨 五入)と認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.02. 5
令和3(ネ)10084 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年11月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
【当審における双方の補充的主張に対する判断】
(1) 第1審原告の補充的主張について
ア 第1審原告は、計算鑑定書の別表において、1)対象期間における原反ロー ルの購入面積が第1審被告製品(1)の販売面積よりも大きかったり、2)原 反ロールの購入面積と第1審被告製品(1)の販売面積が一致するデータが 多かったりするなどといった不自然な結果が記載されていると指摘する。 しかし、1)については、加工する際の歩留まりやロス、仕損じがあること を考えれば、原反ロールの購入面積よりも販売面積が小さくなることは何 ら不自然ではない。2)についても、計算鑑定書は、第1審被告製品(1)の品 番毎の原反ロールの月毎の面積について、●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のであ り(計算鑑定書19頁)、基準量が1であるとき(例えば、原反ロールを特 段加工することなく転売する場合)、原反ロールの購入面積と第1審被告 製品(1)の販売面積が一致したとしても何ら不自然ではない。第1審原告 は、計算鑑定の結果が、第1審被告らが提出する調査報告書(乙58)や 製品説明書(乙1)の売上高等のデータと異なることも指摘するが、計算 鑑定人が中立的な立場からその職責において計算を行ったものであり、第 1審被告らの提出する資料と一部データが異なるとしても、そのことから 信用性が失われるものでもない。 また、第1審原告は、信用調査会社による競合会社の動向調査の結果で ある甲88を提出して第1審被告らの売上高等について独自の主張をす るが、外部の調査会社による調査結果にすぎず、その調査結果の信用性が 高いことを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ 第1審原告は、第1審原告製品の販売価格には第1審被告製品(1)の●● ●●のものがあることを指摘して、原判決の判断の前提には誤りがあり、 推定覆滅事由が認められないと主張する。しかし、そのような販売価格の 製品があることは、仮に第1審被告製品(1)が販売されなかった場合に、か えって第1審原告製品の販売の可能性を減少させるにすぎず、むしろ推定\n覆滅を肯定する事情であるにすぎない。
(2) 第1審被告らの補充的主張について
ア 第1審被告らは、限界利益の算定上、原判決別紙「売上高・経費一覧表」\nの番号6〜8、11〜14は第1審被告製品(1)の製造販売に直接関連し て追加的に必要になった経費であるから控除されるべきであると主張す る。しかし、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造 販売に直接関連して追加的に必要になった経費には当たらないというべ きであり、上記各経費を控除の対象とすることは相当でない。
イ 第1審被告らは、第1審被告らの利益額の90%又は少なくとも77% の推定覆滅を認めるべきであると主張する。しかし、その指摘する根拠と する理由(第1審被告製品(1)に耐候性等の本件発明の作用効果が確認で きないこと、設計変更が容易であること、第1審被告らの営業努力・ブラ ンド力・売上シェア等)については、本件証拠上、その事実が認められな いか、仮に認められたとしても、原判決が認定した限度を超えて特許法1 02条2項の推定を覆すに足りるものではない。
◆判決本文
1審における推定覆滅の事情は以下です
◆平成30(ワ)1130
b そこで,被告らが特許法102条1項ただし書の推定覆滅事由として主張
する点について検討するに,次のとおり,2割の推定覆滅を認めるのが相当
である。
(a) 被告らは,本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の
印刷領域の面積の限定は,顧客吸引には全く寄与しておらず,被告旧製品
と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり,被告旧製品のカ
タログでも,印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし,
原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり,本件発明
は,被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。
しかし,前記1(9)で説示したとおり,本件発明の従来技術とは異なる技
術的特徴は,再帰反射シートの印刷層について,「印刷領域が独立した領域
をなして繰り返しのパターンで設置されており,連続層を形成せず」,「独
立印刷領域の面積が0.15mm2〜30mm2」,かつ,「白色の有機顔料…着色
剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより,印刷層周辺の密着\n性を向上させ,耐水性・耐候性を向上させるとともに,色相の改善を図る
ことにあるのであるから,その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措
定する被告らの上記主張は,その前提を欠くものである。また,被告旧製
品と被告新製品の耐候性の実験結果(乙45〜49)についても,その実
験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから,これをもって
直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな
い。そして,証拠(甲3,4,9,10,23,67〜70)及び弁論の
全趣旨によれば,被告旧製品のカタログやウェブサイトには,本件発明の
技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記\n載が多数存在することも認められる。
したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当
ではないというべきである。
(b) 次に,被告は,本件発明は,被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら
ず,むしろ,3Mブランドに裏付けられた被告らの信用,実績及び知名度
等こそが,被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで
あり,現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き
く変化していないと主張する。
しかし,仮に被告らが3Mグループとしてのブランド力を有するとして
も,これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な
証拠は提出されていない。また,仮に被告旧製品から被告新製品に切り替
えた前後で売上高が大きく変化していないとしても,顧客において被告旧
製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上,従
前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた
可能性が否定できないから,これをもって直ちに本件発明が顧客への販売\nに貢献していないということはできない。
したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの
は相当ではない。
(c) また,被告らは,主要国道および高速道路等における道路標識に用いら
れる被告製品を含む長尺ロール製品については,再帰反射シートのパイオ
ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく,原告は被告旧製品
の販売数量分の実施能力を有していないのであり,実際に,被告らの販売\nする被告製品並びにその他の製品(Diamondグレード及びEngi
neeringグレードの再帰反射シート)の売上比がそれぞれ●(省略)
●であり,原告製品の売上比が10%であるから,仮に被告製品(1)が販売
できなくなったとすれば,そのうちの●(省略)●(=10/(10+●
(省略)●))のみが原告製品に向かうことになると主張する。
しかし,そもそも,競合品といえるためには,市場において侵害品と競
合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは,被告ら
が販売するDiamondグレード及びEngineeringグレード
の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが,弁論の全趣旨
によれば,前者の価格は被告旧製品の●(省略)●以上であり,後者の性
能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから,これらの製品の\n価格や性能等を捨象して,同様の用途に用いられる再帰反射シートである\nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると,被告
らが主張するDiamondグレード及びEngineeringグレー
ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認
めることはできず,それゆえに被告旧製品の需要がDiamondグレー
ド及びEngineeringグレードの再帰反射シートと原告製品の売
上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。
したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの
は相当ではない。
(d)さらに,被告らは,仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと
しても,原告の逸失利益は,被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益
率を乗じた額にとどまるところ,原告製品の販売単価は被告旧製品の●(省
略)●程度の価格帯であり,原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ
く●(省略)●程度であるはずであり,原告製品の限界利益率は被告製品
のそれの●(省略)●程度にすぎないことが推認されるから,特許法10
2条2項によって推定される損害額は,原告の逸失利益を大幅に超えるこ
ととなると主張する。
この点,弁論の全趣旨によれば,原告製品の販売単価は,被告旧製品の
●(省略)●程度の価格帯であることが認められるところ,仮に被告旧製
品が販売されなかったとしても,原告において,被告旧製品の限界利益と
同額の限界利益を得ることができたとは認め難く,この点については,一
定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが,他方で,原告製品の販売単
価が低価格であることにより,その販売数量が,被告製品の販売数量より
も大きくなる可能性もあるのであるから,大幅な推定覆滅を認めるのが相\n当であるともいえない。
(e)以上の事情を総合考慮すると,被告らが主張する推定覆滅事由のうち,
原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ,推定覆滅事由とし
て考慮するのが相当であり,その覆滅割合は2割と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.01.30
令和1(ワ)17622 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月14日 東京地方裁判所
被告は、本件発明1、5は、被告製品1、2の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品1、2は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明1、5を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は1対1として計算すべきであると主張する。
しかし、被告が販売する被告製品1、2は、本件発明1、5を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品1、2に対する一連の ものといえ、本件発明1、5を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法1、2によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品1、2を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2024.01.24
令和1(ワ)17622 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月14日 東京地方裁判所
本件発明6は、電鋳管についての物の発明であるところ、特許請求の範囲に おいて、当該電鋳管について、細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物 を形成する工程(メッキ工程)、細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させる工程(引っ張り工程)、変形させた細線材を除去する工 程(分離工程)を経て製造されることが記載されている。 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、\n特性等が同一である物として認定される。そして、物の発明についての特許に 係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、 当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表\しているのか、又は 物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限 定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当 該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占 権を有するのかについて予測可能\性を奪うことになる。したがって、出願時に おいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか、 又はおよそ実際的でないという事情が存在するなどの第三者の利益を不当に 害しない事情が存在するのでない限り、物の発明についての特許に係る特許請 求の範囲にその物の製造方法が記載されている特許請求の範囲の記載は、特許 法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するとは いえない(最高裁平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷 判決・民集69巻4号700頁参照)。本件発明6の特許請求の範囲において は、物の製造方法が記載されているところ、出願時において製造された物をそ の構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか、又はおよそ実際的 でないという事情についての主張はなく、また、同事情を認めるに足りる証拠 もない。
・・・
本件明細書には、本件発明6の電鋳管と同様の形状等を有する電鋳管につい て本件発明6の方法以外の複数の方法で製造できると記載されている【004 1】、【0042】)。そして、本件発明6の引っ張り工程及び分離工程の方法に よった場合の電鋳管の内面精度について、特許請求の範囲、本件明細書、図面 には記載はない。また、原告が主張する本件発明6の技術的範囲に属するとい う場合の電鋳管の客観的な内面精度自体が必ずしも明確ではなく、また、本件 特許の出願当時、引っ張り工程及び分離工程により製造された電鋳管の内面精 度を含む構造又は特性が、技術常識により明らかであったことを認めるに足り\nる証拠はない。
そうすると、電鋳管の発明である本件発明6について、少なくとも引っ張り 工程及び分離工程に関して電鋳管のどのような構造又は特性を表\しているの かが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明らかであるとは いえない。原告の主張は採用することができない。
・・・
被告は、本件発明1、5は、被告製品1、2の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品1、2は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明1、5を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は1対1として計算すべきであると主張する。 しかし、被告が販売する被告製品1、2は、本件発明1、5を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品1、2に対する一連の ものといえ、本件発明1、5を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法1、2によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品1、2を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。
◆判決本文
なお、本件については、控訴審判決はなさそうですが、対応する審決取消訴訟にて、請求項6は不可能・非実際的理由がなくても、PBPクレームだから自動的に明確性違反だとはならないと判断されてします(内面精度との技術的関係が不明として明確性違反と判断されています)。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載
されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に
いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時
において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\である
か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる(最高裁
判所平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集
69巻4号700頁)。
もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許
請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合(プロダクト・バイ・
プロセス・クレーム)、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され
た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ(前掲最高裁判\n決)、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表\して
いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に
より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を
読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が
その範囲において独占権を有するのかについて予測可能\性を奪う結果となり、
第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。
そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製
造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願
時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表\
しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義
的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不
可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ\nれる。
・・・
そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を
加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着
物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける
ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、
3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細
線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す
るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱
又は溶剤で溶かす方法が記載されている(【0041】、【0116】)が、
これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても
一切記載がなく、ましてや、本件発明6及び訂正発明9の製造方法(上記
3)の方法に含まれる。)が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の
内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上
記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し
たとも認められない。
そうすると、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電
鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.12.14
令和2(ワ)25892 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年11月29日 東京地方裁判所
イ 本件明細書には、「本発明の物品は、カートリッジの嵌合端部と嵌合す る受容端部を有する制御ハウジングも含むことができる。したがって、制 御ハウジングとカートリッジ本体は、機能可能\に連結されるものとして特 徴づけることができる。このような受容端部は特に、カートリッジの嵌合 端部を受容する開口端部を有するチャンバーを含んでよい。・・・特有の 実施形態では、カートリッジの嵌合端部を制御ハウジングの受容端部と嵌 合させると(カートリッジの嵌合端部を制御ハウジングのチャンバーの中 まで所定の距離だけスライドさせるなどすると)、吸引可能な物質媒体と\n電気加熱部材が整列して、吸引可能な物質媒体の少なくとも一部分を加熱\nできるようになる。」(【0008】)、「カートリッジ本体305は、 制御ハウジング200の受容チャンバー210と嵌合する嵌合端部310 と、」(【0040】)との記載がある。また、図4、図7、図9等には、 吸引可能な物質を消費者の方に運ぶように構\成された反対側の吸い口端と、 外面および内面を有する壁とを有する実質的に筒状のカートリッジの嵌合 端部310が示されるとともに、電気加熱部材に電力を供給する電気エネ ルギー源を含む制御ハウジングの端部として、中央部の円筒状の突出部を 取り囲むように、円筒形のカートリッジの外壁の外径よりやや大きい内径 を有する円筒形の受容チャンバー壁があり、カートリッジを受容チャンバ ーに挿入することで、カートリッジの外壁であり嵌合端部の外側が、受容 チャンバーの外壁の内側に、ほとんど隙間なく接する状態が示されている。 すなわち、本件明細書には、カートリッジの嵌合端部と制御ハウジング の嵌合端部(受容端部)が嵌合すると記載され、その実施形態として、カ ートリッジが制御ハウジングの受容チャンバーに挿入されることで、相補 形状を有するといえる、円筒形の外壁という形状を有するカートリッジの 嵌合端部と、円筒形の受容チャンバー壁という形状を有する制御ハウジン グの嵌合端部(受容端部)とが、カートリッジの外壁の外側の嵌合端部が 受容チャンバーの外壁の内側に接することで、ほとんど隙間なく配置され るという状態ではまり合っていることが示されているといえる。これは、 上記の「嵌合」についての一般的な意義に沿ったものである。他方、本件 明細書には、制御ハウジングの「受容端部」あるいは「受容チャンバー」 については、【0008】、【0040】以外に、本件明細書の【001 2】、【0018】、【0027】、【0059】、【0061】、【0 102】等にも記載があるが、カートリッジの嵌合端部の端面に接触又は 近接するのみで、それを制御ハウジングの「受容端部」とする記載はない し、上記アの一般的な意義と異なる意味で「嵌合」が使われていることを 示唆する記載もない。
ウ 本件発明は、前記1 のような技術的意義を有するところ、制御ハウジ ングとカートリッジの関係として、想定し得る様々な構成のうち、構\成要 件Dにおいて「前記制御ハウジングは、前記カートリッジに機能可能\に連 結されている嵌合端部を有する」として、それぞれの嵌合端部が「嵌合」 するものであることを明確に定めている。そして、そのような構成の下で、\n制御ハウジングとカートリッジが「機能可能\に連結され」、また、「吸引 可能な物質媒体と電気加熱部材が整列して、吸引可能\な物質媒体の少なく とも一部分を加熱できるように」なることがあるとしている。 本件発明においては、制御ハウジングとカートリッジの関係が上記のと おり定められているところ、「嵌合」の語句の一般的な意義(前記ア) や本件明細書の記載(前記イ)もその一般的な意義を前提としていると 解されることからも、「前記カートリッジに機能可能\に連結されている 嵌合端部」とは、その嵌合端部自体が一定の形状を有するとともに、ハ ウジングの嵌合端部も一定の形状を有し、それら両嵌合端部の形状が、 相補形状であり、それぞれの形状によって、互いにほとんど隙間なくは まり合うものをいうと解される。
(3) 被告製品の構成dについて\n
ア 被告製品の構成dは、「加熱式デバイスは、加熱式タバコスティックを\n受け入れるエンドキャップと、エンドキャップの底面に形成されたスリッ トを貫通してエンドキャップ内まで延びるヒータブレードのベース部上に 形成された導電トラックに電力を供給するバッテリーを含むメインボディ と、を有する加熱式喫煙デバイスであって、使用者はエンドキャップの底 面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入可能であり、該挿入によっ\nてヒータブレードのベース部が加熱式タバコスティックに挿入され、加熱 式喫煙デバイスのスイッチが入れられると、タバコロッドを加熱するため に、ヒータブレードの導電トラックがバッテリーと通電し、」である。 そして、構成要件Dの「カートリッジ」に当たり得るのは加熱式タバコ\nスティックであり、当該加熱式タバコスティックの篏合端部に当たり得る のは、加熱式タバコスティックの吸い口とは反対の先端部である。
イ 原告らは、エンドキャップに加熱式タバコスティックがぴったりとはま るから、エンドキャップの底面と、加熱式タバコスティックの先端面は、 ほぼ同径の円形であり、「形状が合った物」であり、「エンドキャップの 底面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入可能であ」ることは「は\nめ合わせる」ことである旨主張する。 しかしながら、加熱式タバコスティックの先端面の形状とエンドキャッ プの底面の形状自体はほぼ同径の円形であるとしても、エンドキャップ の底面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入した状態は、加熱式 タバコスティックの先端面がエンドキャップの底面に突き当たって接し た状態になっているのみである。加熱式タバコスティックの先端面とエ ンドキャップの底面のそれぞれの形状は、相補形状ではなく、それぞれ の形状によって、互いにほとんど隙間なくはまり合うものであるとはい えない。
なお、制御ハウジングは、構成要件Dの文言上、「前記電技加熱部材に\n電力を供給する電気エネルギー源を含(む)」(構成要件D)ものであ\nるところ、被告製品における制御ハウジングはメインボディであるから、 エンドキャップそれ単独では、制御ハウジングに当たることはない。 ウ 原告らは、ヒータブレードのベース部が「篏合端部」に当たるとも主張 する。
しかしながら、前記のとおり、構成要件Dの「カートリッジ」に当たり\n得るのは加熱式タバコスティックであり、当該加熱式タバコスティックの 篏合端部に当たり得るのは、円筒状の形状を有する加熱式タバコスティッ クの吸い口とは反対の先端部であるが、当該先端部は、原告らが「篏合端 部」と主張するヒータブレードのベース部の形状と、相補形状ではなく、 それぞれの形状によって、互いにほとんど隙間なくはまり合うものである とはいえない、なお、このことは、ヒータブレードのベース部とエンドキャップ底面と を合わせた構成を考えても同様である。\n
エ 以上によれば、被告製品の構成dのヒータブレードのベース部とエンド\nキャップ底面は、いずれも構成要件Dの「篏合端部」に当たらず、その他、\nこれに該当する部分はないといえる。 そうすると、被告製品は、構成要件Dを充足する部分を有せず、その余\nを判断するまでもなく本件発明の技術的範囲に属さない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.10.25
平成25(ワ)7478 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟__全文__ 平成28年10月14日 東京地方裁判所
また,本件明細書等には,「第二の割り溝」を形成する方法について, 手法は特に問わないとしており,エッチング,ダイシング,スクライブ 等の手法を用いることが可能であるとされ,このうち,線幅を狭くする\nことが可能であるなどの理由から,スクライブが特に好ましいとするに\nとどまっており(段落【0009】),「第二の割り溝」に関して,そ の形成の方法は特に限定されていない。 そして,本件においては,本件明細書等に従来技術が解決できなかっ た課題として記載されているところが,出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分であるという事情は認められない。\n
以上のような,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明 細書記載の従来技術との比較から導かれる本件発明の課題,解決方法, その効果に照らすと,本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分は,サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物\n半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当たり,半導体層 側にエッチングにより第一の割り溝,すなわち,切断に資する線状の部 分を形成し,サファイア基板側にも何らかの方法により第二の割り溝, すなわち,切断に資する線状の部分を形成するとともに,それらの位置 関係を一致させ,サファイア基板側の線幅を狭くした点にあると認める のが相当であり,サファイア基板側に形成される第二の割り溝,すなわ ち,切断に資する線状の部分が,空洞として溝になっているかどうか, また,線状の部分の形成方法としていかなる方法を採用するかは上記特 徴的部分に当たらないというべきである。
ウ 被告方法は,前記2で認定したように,サファイア基板上に窒化ガリ ウム系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当た り,半導体層側にエッチングにより切断に資する線状の部分を形成し, サファイア基板側にもLMA法のレーザースクライブによって切断に資 する線状の変質部を形成するとともに,それらの位置関係を一致させ, サファイア基板側の線幅を狭くしているのである。 そして,前記2(1)イで説示したとおり,LMA法でサファイア基板 を加工した場合,溶融領域が発生し急激な冷却で多結晶化し,この多結 晶領域は多数のブロックに分かれるが,加工領域中央に実質の幅が極端 に狭い境界が発生し,この表面に垂直な境界線の先端に応力集中するの\nで割れやすくなることが認められる。 そうすると,被告方法は本件発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分を共通に備えているものと認められる。\nしたがって,本件発明と被告方法との相違部分は本質的部分ではない というべきである。
エ 被告らの主張に対する判断
この点に関して被告らは,LMA法のレーザースクライブについて, 対象と「非接触」であるため,クラック等が発生せず,かつ,ほぼ垂直 に分割されることから,本件発明の課題自体が存在しないことになり, そのような方法を用いたとしても,本件発明の本質的部分に当たらない 旨主張する。
そして,乙14(再公表特許第2006/062017号。以下「乙\n14文献」という。)の段落【0039】には,【図9】,【図10】 に関して,LMA法により形成された変質領域に隣接する正常領域のブ レイク面が略垂直である旨の記載がある。 しかしながら,他方で,乙14文献の段落【0043】等には,同じ 【図9】,【図10】に関して,デフォーカス値によっては,正常領域 のブレイク面の垂直方向につき多少の傾斜や段差が存在する旨の記載も あるのであって,LMA法のレーザースクライブであるからといって, 切断面が斜めになることで不良品が生じるという本件発明の課題が発生 しないと認めることはできない。 したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
オ 以上のとおりで,被告方法は,均等の第1要件を充足すると認められ る。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.10.25
平成28(ワ)25436 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年9月24日 東京地方裁判所
前記(2)ウのとおり,本件明細書2記載の従来技術と比較して,本件発明2 における従来技術に見られない特有の技術的思想(課題解決原理)とは,従来,グ ルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のyggB 遺伝子に着目し,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子 を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変する ことによって,グルタミン酸の生産能力を上げるための,新規な技術を提供するこ\nとにあったというべきである。また,前記(2)エで検討したとおり,本件明細書2に おける従来技術の記載が客観的に見て不十分であるとは認められない。\n
(ウ) 前記(3)アのとおり,19型変異使用構成は,本件発明2−5に含まれる,\n本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)の変異型yggB遺 伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する構成であり,前記(イ)の本件発明2にお ける特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば,19型変異使用構成の本質\n的部分は,「コリネ型細菌由来のyggB遺伝子に,コリネバクテリウム・グルタ ミカム由来のyggB遺伝子におけるA100T変異に相当する変異を導入し,当 該変異型yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し,ビオチンが過剰量存在す る条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。\n
(エ) 被告は,出願経過,本件優先日2当時の技術水準,19型変異使用構成の効\n果から,19型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては,特許請求の範囲の\n記載の上位概念化をすべきでなく,特許請求の範囲に記載された「変異後のygg B遺伝子の配列である配列番号22という特定のアミノ酸配列におけるA100T 変異」に限定して認定されるべきであると主張する。
しかしながら,前記(2)ア及びイの本件明細書2の記載内容によれば,本件発明2 は,特定の配列のyggB遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象 とするものではなく,また,その解決原理としても,グルタミン酸生産能力を上げ\nるために,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用い てメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変するという 新規な技術を導入するというものであったから,本件発明2の請求項1や請求項4 において変異を導入する前のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙され,請求項6 において変異後のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮して も,本件発明2及びそれに含まれる19型変異使用構成の本質的部分を認定するに\n当たっては,yggB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体 の変異前の具体的配列,あるいは,A100T変異に相当する変異を導入した後の yggB遺伝子の具体的配列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当で ある。これは,被告が指摘するように,本件特許2の出願当初の請求項1にはyg gB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種や変異前後のyggB遺伝子のアミノ酸 配列が特定されていなかったところ,補正によって,現在の請求項1のようにyg gB遺伝子のアミノ酸配列の配列番号が,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブ レビバクテリウム・フラバムを含む。)又はコリネバクテリウム・メラセコーラに 由来する配列番号6,62,68,84及び85に特定されるようになったこと(【0 033】,乙80〜84),請求項1に記載された配列番号6,62,68,84 及び85のアミノ酸配列が相互に相同性が高いこと(乙85)を考慮しても同様で ある。また,被告は,出願経過に関連して,本件特許2の再訂正後の請求項の記載 も考慮すべきとも主張するが,当該訂正の内容は,少なくとも訂正前の本件発明2 の本質的部分の認定には影響しないというべきである。 そのほか,本件優先日2当時の技術水準や19型変異使用構成の効果についての\n被告の主張が採用できないことは,前記(2)エ及び(3)イのとおりであり,これらを 理由として,19型変異使用構成の本質的部分を特許請求の範囲に記載された変異\n前後のyggB遺伝子の具体的配列に限定すべきともいえないから,この点の被告 の主張も,前記(ウ)の判断を左右するものではない。
イ 相違点1について
前記ア(エ)のとおり,19型変異使用構成の本質的部分については,yggB遺伝\n子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体の変異前の具体的配列,あ るいは,A100T変異に相当する変異を導入した後のyggB遺伝子の具体的配 列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当であることに加え,以下の(ア) 及び(イ)の点を考慮すれば,相違点1に係る違い,すなわち,導入されている変異型 yggB遺伝子が由来する細菌の種類の違い及びそれによるyggB遺伝子の具体 的な配列の違いは,19型変異使用構成の本質的部分とはいえない。\n
・・・
(エ) これらの点からすれば,相違点3に係る違い,すなわち相違点2に係るA9 8T変異に加えて,被告製法4の菌株ではV241I変異が導入されているという 点は,本件明細書2で開示された本件発明2の課題解決原理である膜貫通領域の変 異ないしC末端側変異と関連しない部位の1つのアミノ酸に保存的置換を加えるも のであり,A98T変異に加えることで課題解決に影響するものではないから,1 9型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。\nオ したがって,19型変異使用構成と被告製法4との相違点1ないし3は,い\nずれも,特許発明の本質的部分ではないから,(12)及び(13)の菌株を使用する被告製法 4は均等の第1要件を充足すると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 賠償額認定
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.09.25
令和3(ワ)33996 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年7月7日 東京地方裁判所
(1) 均等の第1要件にいう特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の 特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を 構成する特徴的部分であると解すべきである。\nそして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、 特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきであ る。 また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には、上記のとおり確定される特許発明の本 質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備え ていると認められる場合には,相違部分は本質的部分ではないと判断すべ きである。
・・・
これらの記載に照らすと、本件発明は、把持部を水平方向に軸回転させ て負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢する負荷を 軽くすることを可能にする構\成を採用することにより、使用者が、「弛緩」 と「伸張」の動作を加えながら適切な「短縮」のタイミングを出現させる ことができ、各筋肉群が「弛緩−伸張−短縮」のタイミングを得て、連動 性よく動作を行うことができることを可能にするとともに、両腕を屈曲さ\nせて把持部を引き下げることに伴い、両腕を外側に広げることに対する抗 力が減少する構成を採用することにより、筋の「共縮」を防ぐことを可能\ にし、もって、筋肉の硬化を伴うことなく、筋肉痛や疲労など身体への負 担が少なく、柔軟で弾力性の富んだ肩部や背部の筋肉等を得ることができ るトレーニング器具を提供し、従来技術の課題を解決するものといえる。 そうすると、これらの各構成については、従来技術に見られない特有の技\n術的思想を構成する特徴的部分であると認めることができる。\n
そして、本件明細書においては、上記の各構成のうち、上記把持部を軸\n回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢す る負荷を軽くすることを可能にする構\成について、「把持部60を昇降揺動 部材50に対して軸回転することにより、回転伝達部91及びクランク機 構部92を介して摺動軸57が上下動することに伴い、クランプにより連\n結されたウェイト31が上下動する。」(【0026】)、「把持部60を昇降 揺動部材50に対して初期状態である略正面方向から外側水平方向へ回転 付勢力に抗して軸回転することにより、摺動軸57が昇降揺動部材50に 対して下方向に摺動し、前記クランプにより連結されたウェイト31が引 き上げられる。」(【0027】)との記載がある。
これらの記載に照らすと、本件発明の特許請求の範囲において、上記把 持部を軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向 に付勢する負荷を軽くすることを可能にする構\成に対応する構成は、把持\n部の回転運動を伝達し、同伝達された回転運動を摺動軸の上下動に変換す るクランク機構部を具備する負荷伝達部であり、構\成要件Gの構成である\nと認められる。 本件においては、被告製品が構成要件Gに相当する構\成を備えていない こと(相違点B)に争いがなく、本件発明の本質的部分を被告製品が共通 に備えているとは認められないから、本件発明と被告製品の相違点Bが本 質的部分ではないということはできず、被告製品は、均等の第1要件を満 たさない。
その他にも原告はるる主張するが、いずれも上記結論を左右しない。 以上によれば、被告製品は、その余の要件を検討するまでもなく、本件 発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえないから、\n本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.09.22
令和4(ワ)15678 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年8月30日 東京地方裁判所
(1) 「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く」の意義について
構成要件Bの「4枚の略矩形状壁面の内、相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁が相互に折畳み可能\に順次連続して連結されるとともに、」との記載から、本件発明の折り畳み式テントには、「4枚 の略矩形状壁面」が設けられていること、その内の「相隣る2枚の略矩形状 壁面」において「互いに対応する側縁」が存在すること、この「互いに対応 する側縁」を「除く」「他の側縁」が存在し、この「他の側縁」が「相互に 折り畳み可能に順次連続して連結され」ていることが理解できる。
また、構成要件Cの「前記相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁は、着脱可能\な接合手段を介して接合されることにより、前記4枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成され、」との記載からは、構\成要件B の「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「着脱可能な接合手段」を備えていること、この「接合手段を介して接合されることによ\nり」、「前記4枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成される」ことが理解できる。また、このような解釈は、本件明細書の、「また、この筒状周壁\n部1における正壁面2の右側縁2aと右壁面3の左側縁3bには、接合・分 離が可能な面ファスナーのような接合手段23が設けられている。図7に図示されるように、正壁面2の右側縁2aと右壁面3の左側縁3bとは前記接\n合手段23により、一体に接合され、または分離される。前記分離された接 合手段23によって、図8に示されるように、両壁面開口部24が構成される。」(【0022】)との記載及び「筒状周壁部1では、図7に図示されるよ\nうに、4枚の壁面2、3、4、5の各両側縁2a、2b、3a、3b、4a、 4b、5a、5bの内、側縁3aと4b、4aと5b、5aと2bとを相互 に折畳み可能に連結し、側縁2aと3bとを後述する接合手段23で接合することで筒状周壁部1が構\成されている」(【0021】)との記載とも整合する。 そして、構成要件Bの「除く」の通常の語義は、「加えない。除外する。別にする。」(広辞苑第七版)であると認められる。\n加えて、上記「除く」は、その直前の「他の側縁」に限定を付す趣旨で あると理解するのが自然であることを踏まえると、構成要件Bは、「4枚の略矩形状壁面」が有する「側縁」から、「着脱可能\な接合手段を介して接合される」ことになる「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」を 除外又は別にした「他の側縁」が、「相互に折り畳み可能に順次連続して連結される」ことを規定するものであると解するのが相当である。\n
(2) 被告各製品が構成要件Bを充足するか否かについて
前記(1)のとおり、構成要件Bの、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」とは、構\成要件Cにおいて規定された、「着脱可能な接合手段\nを介して接合される」「側縁」であると解するのが相当である。 前提事実(3)イのとおり、被告各製品には、第1板状体10ないし第4板 状体40の4枚の板状体が形成されているところ、本件において、各板状体 が構成要件Bの「略矩形状壁面」に該当する。 また、前提事実(3)イのとおり、被告各製品の第1板状体10と第4板状 体40は、その対向部15a及び45bが、着脱可能な接合部60を介して接合されるから、対向部15a及び45bは、構\成要件Bにおいて除外又は別にするとされ、かつ、構成要件Cにおいて「着脱可能\な接合手段を介して 接合され」ると規定される、「前記相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応 する側縁」に該当する。 そうすると、構成要件Bにおいて、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁」は、被告製品の第1板状体10と第4板状体\n40の対向部15a及び45bを除外した他の側縁、すなわち、第1板状体 10の左右の側縁を構成する対向部15b、第2板状体20の左右の側縁を構\成する対向部25a及び25b、第3板状体30の左右の側縁を構成する\n対向部35a及び35b、第4板状体40の左右の側縁を構成する45aがこれに該当するものと解される。\n そして、証拠(甲6、乙1)によれば、これらの側縁は、相互に折り畳み 可能に順次連続して連結される構\成を有していると認められ、構成要件Bの「他の側縁が相互に折り畳み可能\に順次連続して連結される」に該当する。
(3) 被告の主張について
被告は、「除く」の「別にする」との語義に着目して、「別にする」もの と「別にされない」ものとでは、異なる性質・構成を有していることに照らすと、構\成要件Bは、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「相互に折り畳み可能」ではなく、「順次連続して」おらず、「連結され」てもいないことを規定するものと解すべきであり、被告各製品は、互いに対\n応する側縁が相互に折り畳み可能に順次連続して連結されるから、構\成要件 Bを充足しない旨主張する。
しかし、仮に、「除く」を「別にする」との意味であると解釈したとして も、「別」とは、「1)わけること。…2)異なること。そのものではないこと」 (広辞苑第七版)の意味を有するにすぎないから、別にされた「相隣る2枚 の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」とが、一部でも同じ 性質・構成を有していてはならないということにはならない。そして、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の構\成は、構成要件Cによ\nり要件が付加されているのであるから、これにより、「相隣る2枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」は、異なる構成を有しているといえる。\n
・・・
(ア) 構成要件Bについて
a 前記2(1)で説示したとおり、構成要件Bは、「着脱可能\な接合手 段を介して接合される」ことにより、「前記4枚の略矩形状壁面でも って筒状周壁部」を構成する「側縁」を除外した「他の側縁」が、「相互に折畳み可能\に」「順次連続して」「連結」されることを規定している。 そして、乙2発明においては、エンドパネルとサイドパネルの着脱 部となる側縁は、ジッパーや紐等の取付手段を介して取り付けられ (乙2c)ていることから、構成要件Bの「他の側縁」に相当する側縁は、上記「エンドパネルとサイドパネルの着脱部となる側縁」を除\n外した側縁(乙2c)であるところ、乙2発明においては、この側縁 が、相互に折畳み可能に順次連続して連結されている(乙2b)。したがって、乙2発明と本件発明は、構\成要件Bの構成の点におい\nて一致するものと認められる。
b これに対し、原告は、本件発明の「着脱可能な接合手段を介して接合される」「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が一\n組のみであるのに対し、乙2発明では、テントを容易に折り畳めたり することができるよう、対向する2枚のエンドパネルが2枚とも取外 し可能な構\成又は2枚とも一端がサイドパネルにヒンジ結合された構成のみが開示されているから、本件発明と乙2発明は、構\成要件Bの点で一致しないと主張する。しかし、本件特許の特許請求の範囲において、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の組数を限定する記載はない上、本 件明細書において、【0022】及び図8には「相隣る2枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」が一組である構成についての記載があるものの、これは一実施例にすぎず、そのような構\成に限定する旨の記載は存在しないから、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応す る側縁」が、一組に限定されると解釈することはできない。 また、原告は、本件発明に係る折り畳み式テントは、災害時に体育 館等の避難所に設置されて利用されることを想定していることなどか ら、設置の利便性や強度を考慮し、あえて一組のみを分離可能としたと主張する。しかし、本件明細書には、原告の主張する課題や作用効果について\nの記載はない。以上によれば、原告の主張はいずれも採用することができない。
(イ) 構成要件Eについて
a 本件発明は、「前記接合手段を介して接合される側縁を有する2枚 の略矩形状壁面により開閉自在な両壁面開口部が設けられたことを特 徴とする」との構成(構\成要件E)を有しており、乙2発明は、「前 記手段を介して取り付けられる側縁を有する2枚の略矩形状のサイド パネル及びエンドパネルにより開閉自在な両壁面開口部が設けられた ことを特徴とする」との構成(乙2e)を有している。そして、本件特許の特許請求の範囲の記載において、「接合手段」\nにつき特段の限定は付されていないことから、壁面と壁面を接合する 手段であれば足りると解されるところ、前記(1)ア(オ)のとおり、乙2 文献においては、乙2発明の「取付手段」は、ジッパーが好ましい手 段であるが、単純な紐や布などの他の取付手段を使用してもよいとさ れており、それらはいずれも壁面と壁面を接合する手段であるといえ る。したがって、本件発明と乙2発明は、構成要件Eの構\成の点で一致 するものと認められる。
b 原告は、本件明細書の【0014】や【0028】には、壁面の開 放部分にテントのフレーム等が存在しないために、車椅子等がテント 内外に出入する際にフレームやファスナー等の変形・破れ・土砂の付 着等を阻止できる旨が記載されており、これらの記載に照らすと、構成要件Eの「開閉自在な両壁面開口部」は、壁面の開放部分にフレー\nムやファスナー等が存在しない構成であると解されると主張する。
しかし、本件特許の特許請求の範囲の記載において、4枚の略矩形 状壁面と床面との間の連結手段の有無を含め、「開閉自在な両壁面開 口部」が、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成に限定される旨の記載はない。\n また、本件明細書の【0014】は、本件発明の効果に関する記載 であり、同【0028】は、本件発明の実施例の効果に関する記載で あって、本件発明の両壁面開口部の構成を限定するものとは認められないから、構\成要件Eの文言を原告主張のとおり限定解釈する根拠とはならない。
また、仮に、構成要件Eが、底面にフレームやファスナー等が存在しない構\成に限定されるとしても、乙2文献には、ファスナーを紐に変更することも可能である旨が記載されているから(前記(1)ア(オ))、 乙2発明は、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成を含むものであるといえる。よって、原告の主張は理由がない。\n
c 原告は、本件明細書の【0022】及び図8の記載を考慮すると、 構成要件Eは、壁面開口部に設けられている接合手段を外すことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外方に向か\nって開放することができるという構成を示したものであると主張する。 しかし、本件明細書には、本件発明の実施例について「壁面2、3、 4、5の側縁上下端部は、…三角形に近い形状の上閉塞面20、下閉 塞面19でもってこの上下の空隙部は閉塞されるようになっている。 なお、正壁面2の右側縁2aと右壁面3の左側縁3bとの上下端部を 塞ぐ二等辺三角形状の分割上閉塞面20a、分割下閉塞面19aは、 三角形の頂角を通る中心線を境に2分割される。左右に分割された分 割上閉塞面20a、分割下閉塞面19aは、前記接合手段23と同様 な上閉塞面接合手段22、下閉塞面接合手段21によって、接合また は分離可能に接合される。」(【0023】)との記載があるところ、この記載に照らすと、同実施例は、正壁面2の右側縁2aと右壁面3の\n左側縁3bに設けられた接合手段に加え、上閉塞面接合手段22、下 閉塞面接合手段21を外すことによって初めて、壁面を外方に向かっ て解放することができる構成を有しているといえる。したがって、上記【0022】及び図8の実施例の記載を根拠として、構\成要件Eが、両壁面開口部について、壁面開口部に設けられている接合手段を外す ことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外 方に向かって開放することができるという構成を規定していると解釈することはできない。\n また、上記【0023】の記載によれば、「壁面2、3、4、5」 と、「三角形に近い形状の上閉塞面20、下閉塞面19」は別部材で あることは明らかであるから、構成要件Eが、接合手段について、「2枚の略矩形状壁面」のみに設けられていることにより、「両壁面\n開口部」が「開閉自在」となることを規定したと解釈することもでき ない。 以上によれば、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 小括
その他、原告が種々主張するところを検討しても、前記(1)の結論を左右 するものとはいえず、本件発明は、乙2発明と同一の構成を有しているから、新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの\nと認められ、原告は被告に対してその権利を行使することができない(特許 法104条の3第1項、123条1項2項、29条1項)。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.08. 9
令和4(ワ)9716 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年7月28日 東京地方裁判所
(ア) 特許法29条1項は、同項3号の「特許出願前に」「頒布された刊 行物」については特許を受けることができない旨規定する。当該規定の 「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発 明の構成が開示されているだけでなく、発明が技術的思想の創作である\nこと(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者 が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の\n技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技 術的思想が開示されていることを要するというべきである。 特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製 造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないか ら、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、 当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理\n解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊 行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に 接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、\n特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出 すことができることが必要であるというべきである。
ここで、5−ALAホスフェートは、新規の化合物であり、上記アの とおり、本件引用例には、列挙された化合物の中に5−ALAホスフェ ートが含まれているものの、本件引用例にその製造方法に関する記載は 見当たらない(乙2)。 したがって、5−ALAホスフェートを引用発明として認定するため には、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤 等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づ\nいて、5−ALAホスフェートの製造方法その他の入手方法を見出すこ とができたといえることが必要である。
(イ) 被告は、乙16文献から乙18文献の記載からすれば、本件優先日 当時、5−アミノレブリン酸単体の製造方法は周知であった上、5−ア ミノレブリン酸をリン酸溶液に溶解すれば、弱塩基と強酸の組合せとな り、5−アミノレブリン酸リン酸塩を得ることができることは技術常識 であり、このことからすれば、本件優先日当時の当業者は、5−ALA ホスフェートの製造を容易になし得た旨主張する。 確かに、上記第2の1(5)イ及びエのとおり、乙16文献及び乙18文 献には、甲13の1文献を引用しつつ、「ALA生産が確立されてい る」、「ALAの産生に成功した」、「発酵の下流では、イオン交換樹 脂を使用するALA精製プロセスも確立されて」いるなどと記載されて いる。しかしながら、甲13の1文献には、同オのとおり、「発酵液か らのALAの精製」の項において、ALAが塩基性水溶液中では非常に 不安定であり、種々の検討の結果、5−アミノレブリン酸塩酸塩結晶を 得るプロセスを確立することに成功した旨が記載されているにすぎない。 そうすると、乙16文献及び乙18文献においては、細菌を培養して発 酵液中にALA(5−アミノレブリン酸)を産生させる技術は開示され ているものの、5−アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていな いといえる。 また、上記第2の1(5)ウのとおり、乙17文献には、発酵液中に培地 成分と混合した状態で存在するALAの濃度が開示されているにすぎな い。そうすると、乙17文献においても、5−アミノレブリン酸単体を 得る技術は開示されていないといえる。 以上のとおり、乙16文献から乙18文献までにおいて、5−アミノ レブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえない。これに加え、 上記第2の1(5)アのとおり、本件引用例においても「5−ALAは・・ ・化学的にきわめて不安定な物質である」、「5−ALAHClの酸性 水溶液のみが充分に安定であると示される」と記載されていて(【00 07】)、これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認めら れることも考慮すると、本件優先日当時において、5−アミノレブリン 酸単体を得る技術が周知であったとは認められない。
この点に関し、原告は、5−アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上 で、5−ALAが物質として取り出されている必要はなく、発酵液中に 培地成分等と混合した状態であってもよい旨主張する。 しかしながら、本件優先日当時、種々の成分を含む混合液に酸又は塩 基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識 であったとは認められないことからすれば、本件引用例に接した本件優 先日当時の当業者が、化合物である5−アミノレブリン酸リン酸塩を製 造する方法として、培地成分等と混合した状態で5−アミノレブリン酸 が存在する発酵液にリン酸を添加する方法(又はこの発酵液をリン酸溶 液に添加する方法)を、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮することな\nく見出すことができたとはいえない。 また、上記第2の1(5)ウのとおり、乙17文献において、培地に酵母 抽出物やトリプトン等が含まれることが記載されていることからも明ら かなように、培地成分等と混合した状態にある発酵液には種々のイオン が夾雑物として含まれているのであるから、このような発酵液にリン酸 を添加したとしても、等しい物質量の酸及び塩基の中和反応によって5 −アミノレブリン酸リン酸塩という化合物が製造されたと評価すること はできないというべきである。したがって、原告の上記各主張はいずれも採用することができない。そして、このほか、本件優先日当時の当業者が、5−ALAホスフェー トの製造方法その他の入手方法を見出すことができたというべき事情は 存しない。
(ウ) 以上によれば、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思 考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技\n術常識に基づいて、5−ALAホスフェートの製造方法その他の入手方 法を見出すことができたとはいえない。したがって、本件引用例から5−ALAホスフェートを引用発明として認定することはできない。
◆判決本文
本件特許についての審決取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.08. 3
令和4(ワ)2049 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年7月6日 東京地方裁判所
(ウ) 小括
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件発明 1 の「底部」 は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、「容器」として機能\nする筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでい\nる部分を指すものと理解される。また、「底面片」は、このような「底部」を形成す るものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下 側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。さらに、「自立片」は、このような「底 面片」と同一面に連なるものであり、かつ、載置面に沿って前記奥行の方向に突出 し、包装容器を前記載置面に自立させる機能を有するものということになる。\n
イ 被告製品の構成要件充足性\n
(ア) 被告製品においては、背面片が片(A)側に折られて筒状に形成される(構成 e1、e’-1)。その際、背面片の下端に連ねられた六角片(構成 d-3、d’-3)は、筒状部 分下端から内側に折り込まれ、この折り込まれた六角片は、筒状部分内部に収めら れる内容物の下部に位置し、筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止してい る(構成 e-2、e’-2)。このため、被告製品の六角片は、本件発明 1 の「底部を形成 する底面片」に相当するものといえる。
(イ) 被告製品の舌状片は、片(A)の下端に連ねられた部材であり(構成 d-4、d’-4)、 筒状部分の下端(六角片の接続箇所の反対側)から内側に折り込まれ(構成 e-3、e’- 3)、容器として形成した状態において、六角片と共に、略弧状に湾曲した状態とな り、片(A)に連なって、載置面に沿って背面側に突出し、載置面に置くと、舌状片に よって、被告製品は、載置面に背面方向に斜めに自立する(同 b、b’)。このため、 被告製品の舌状片は、本件発明 1 の「自立片」に相当するものといえる。 他方、筒状部分の下端から内側に折り込まれた六角片と舌状片とは接触しておら ず、両者の間には隙間がある(同 e-4、e’-4)。このことと、被告製品の筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止する機能を果たしているのは六角片であることを\n併せ考えると、舌状片は、筒状部分の下側を塞いでいるとはいえず、「底部を形成す る底面片」に相当するものとはいえない。
(ウ) 六角片と舌状片とは、六角片は背面片の下端に連ねられているのに対し、舌 状片は片(A)の下端に連ねられており、同一面に連なるものとはいえない。 したがって、被告製品は、「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片」(構\n成要件 B)を充足しないから、本件発明 1 の技術的範囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.06.29
令和4(ネ)10046 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年5月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
損害額については、ほぼ伏せ字になっています。102条3項の侵害は料率2%で計算し、それよりも2項侵害の額の方が大きくて最終的に約1100万円の損害賠償が認定さられています。
なお、1審では、特許の技術的範囲には属するが、一部の構成要件が日本国外に存在するので、非侵害と認定されてました。概要だけはすぐにアップされていましたが、全文アップは約1ヶ月かかりました。
ア 被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行為が本件発 明1の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に該当するか否 かについて
(ア) はじめに
本件発明1は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末 装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の 発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」(特許法2条3 項1号)とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をい うものと解される。 そして、本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介 して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(以下「ネットワーク型システム」という。)の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構\成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能\を有す るようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいう ものと解される。 そこで、被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行 為が本件発明1の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に 該当するか否かを判断するに当たり、まず、被告サービス1のFLAS H版において、被告システム1を新たに作り出す行為が何かを検討し、 その上で、当該行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当するか及び 当該行為の主体について順次検討することとする。
(イ) 被告サービス1のFLASH版における被告システム1を新たに 作り出す行為について
a 被告サービス1のFLASH版においては、訂正して引用した原判 決の第4の5(1)ウ(ア)のとおり、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指定する(2))と、それに伴い、被控訴人FC2のウェブ サーバが上記ウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを ユーザ端末に送信し(3))、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、ユーザ端末のFLASHが、 ブラウザのキャッシュにあるSWFファイルを読み込み(4))、その 後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押す(5))と、上記SWFフ ァイルに格納された命令に従って、FLASHが、ブラウザに対し動 画ファイル及びコメントファイルを取得するよう指示し、ブラウザが、 その指示に従って、被控訴人FC2の動画配信用サーバに対し動画フ ァイルのリクエストを行うとともに、被控訴人FC2のコメント配信 用サーバに対しコメントファイルのリクエストを行い(6))、上記リ クエストに応じて、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイ ルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、 それぞれユーザ端末に送信し(7))、ユーザ端末が、上記動画ファイ ル及びコメントファイルを受信する(8))ことにより、ユーザ端末が、 受信した上記動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウ ザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能\と なる。このように、ユーザ端末が上記動画ファイル及びコメントファ イルを受信した時点(8))において、被控訴人FC2の動画配信用サ ーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末はインターネットを利用 したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザに おいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能\となる から、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明1の 全ての構成要件を充足する機能\を備えた被告システム1が新たに作り 出されたものということができる(以下、被告システム1を新たに作 り出す上記行為を「本件生産1の1」という。)。
b これに対し、被控訴人らは、1)被告各システムの「生産」に関連す る被控訴人FC2の行為は、被告各システムに対応するプログラムを 製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることに 尽き、いずれも米国内で完結しており、その後、ユーザ端末にコメン トや動画が表示されるまでは、ユーザらによるコメントや動画のアップロードを含む利用行為が存在するが、ユーザ端末の表\示装置は汎用ブラウザであって、当該利用行為は、本件各発明の特徴部分とは関係 がない、2)被告システム1において、ユーザ端末は、被控訴人FC2 がサーバにアップロードしたプログラムの記述並びに第三者が被控訴 人FC2のサーバにアップロードしたコメント及び被控訴人FC2の サーバにアップロードした動画(被告システム2及び3においては第 三者のサーバにアップロードした動画)の内容に従って、動画及びコ メントを受動的に表示するだけものにすぎず、ユーザ端末に動画やコメントが表\示されるのは、既に生産された装置(被告各システム)をユーザがユーザ端末の汎用ブラウザを用いて利用した結果にすぎず、 そこに「物」を「新たに」「作り出す行為」は存在しない、3)乙31 1記載の「一般に、通信に係るシステムはデータの送受を伴うもので あるため、データの送受のタイミングで毎回、通信に係るシステムの 生産、廃棄が一台目、二台目、三台目、n台目と繰り返されることま で「生産」に含める解釈は、当該システムの中でのデータの授受の各 タイミングで当該システムが再生産されることになり、採用しがたい」 との指摘によれば、被控訴人FC2の行為は本件発明1の「生産」に 該当しないというべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、被控訴人FC2が被告システム1に 対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをア ップロードすることのみでは、前記aのとおり、本件発明1の全ての 構成要件を充足する機能\を備えた被告システム1が完成していないと いうべきである。
2)については、前記aのとおり、被控訴人FC2の動画配信用サー バ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用し たネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受 信することによって、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能\を 備えた被告システム1が新たに作り出されるのであって、ユーザ端末 が上記ファイルを受信しなければ、被告システム1は、その機能を果たすことができないものである。
3)については、上記のとおり、被告システム1は、被控訴人FC2 の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインタ ーネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必 要なファイルを受信することによって新たに作り出されるものであり、 ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存されたファイルが廃棄され るまでは存在するものである。また、上記ファイルを受信するごとに 被告システム1が作り出されることが繰り返されるとしても、そのこ とを理由に「生産」に該当しないということはできない。 よって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(ウ) 本件生産1の1が特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否か について
a 特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、 移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が 当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであると ころ(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷 判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年(受)第580 号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参 照)、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解され る。 前記(イ)aのとおり、本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブ サーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人FC2の動画配\n信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サー バがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末 がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサ ーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国 に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。す なわち、本件生産1の1において、上記各ファイルが米国に存在する サーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信 することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、 新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在 するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、 我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題とな る。
b ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(以下、単に 「国外」という。)に設置されることは、現在、一般的に行われてお り、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システム の利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であ るネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構\成する端末が日本国内(以下「国内」という。)に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用するこ とは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義\nの原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえす\nれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る 特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。他方で、当該システムを構\成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を 生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。 これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許 権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り 出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについ ては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構\成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考\n慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができる ときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当 である。
これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的 態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが 送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、 国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム 1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観 念することができる。 次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサー バと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能\である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表\示されるように するために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能\と構成要件1Gの表\示位置制御部の機能を果たしている。
さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利 用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケー ションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現し ており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係る システムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るもので ある。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内 で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特 許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。
c これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の 効力が当該国の領域においてのみ認められる」のであるから、海外 (国外)で作り出された行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当 しないのは当然の帰結であること、権利一体の原則によれば、特許発 明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施することをいうことからすると、一部であっても海外で作り出されたものがある場合には、特許法2条3項1号の「生産」に該当しないというべきであ\nる、2)特許回避が可能であることが問題であるからといって、構\成要 件を満たす物の一部さえ、国内において作り出されていれば、「生産」 に該当するというのは論理の飛躍があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判例においては、 カードリーダー事件の最高裁判決(前掲平成14年9月26日第一小 法廷判決)等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、そ の例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきである旨主張する。\n
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に 関し、被疑侵害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法 2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システム を構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、前記bに説示した事情を総合考慮して、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生\n産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することがで きない。
2)については、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否か の上記判断は、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすというものではないから、2) の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特 許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定めら れ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意 味することに照らすと、上記のとおり当該行為が我が国の領域内で行 われたものとみることができるときに特許法2条3項1号の「生産」 に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しないというべ きである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たる ためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内において完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、また、我が国が締結した条約及び特\n許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」 に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用する ことができない。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(エ) 被告システム1(被告サービス1のFLASH版に係るもの)を 「生産」した主体について
a 被告システム1(被告サービス1のFLASH版に係るもの)は、 前記(イ)aのとおり、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画 を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存された上記SWF\nファイルによる命令に従ったブラウザからのリクエストに応じて、被 控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2 のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末 に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって、新たに作り 出されたものである。そして、被控訴人FC2が、上記ウェブサーバ、 動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、 これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファ イル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末によ る各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、 被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、 自動的に行われるものであることからすれば、被告システム1を「生 産」した主体は、被控訴人FC2であるというべきである。
この点に関し、被告システム1が「生産」されるに当たっては、 前記(イ)aのとおり、ユーザが、ユーザ端末のブラウザにおいて、所 望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指定すること(2))と、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すこと(5))が必要とされるところ、上記のユ ーザの各行為は、被控訴人FC2が設置及び管理するウェブサーバに 格納されたHTMLファイルに基づいて表示されるウェブページにおいて、ユーザが当該ページを閲覧し、動画を視聴するに伴って行われる行為にとどまるものである。すなわち、当該ページがブラウザに表\示されるに当たっては、前記のとおり、被控訴人FC2のウェブサーバが当該ページのHTMLファイル及びSWFファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が受信したこれらのファイルがブラウザのキャ ッシュに保存されること(4))、また、動画ファイル及びコメントフ ァイルのリクエストについては、上記SWFファイルによる命令に従 って行われており(6))、上記動画ファイル及びコメントファイルの 取得に当たってユーザによる別段の行為は必要とされないことからす れば、上記のユーザの各行為は、被控訴人FC2の管理するウェブペ ージの閲覧を通じて行われるものにとどまり、ユーザ自身が被告シス テム1を「生産」する行為を主体的に行っていると評価することはで きない。
b これに対し、被控訴人らは、1)米国に存在するサーバが、ウェブペ ージのデータ、JSファイル(FLASH版においてはSWFファイ ル)、動画ファイル及びコメントファイルを送信することは、被控訴 人FC2が行っているのではなく、インターネットに接続されたサー バにプログラムを蔵置したことから、リクエストに応じて自動的に行 われるものであり、因果の流れにすぎない、2)日本(国内)に存在す るユーザ端末が、上記ウェブページのデータ、JSファイル(SWF ファイル)、動画ファイル及びコメントファイルを受信することは、 ユーザによるウェブページの指定やウェブページに表示された再生ボタンをユーザがクリックすることにより行われ、ユーザの操作が介在しており、また、仮に被控訴人FC2が1)の送信行為を行っていると しても、特許法は、「譲渡」と「譲受」、「輸入」と「輸出」、「提供」 と「受領」を明確に区分して規定している以上、被控訴人FC2が上 記受信行為を行っていると解すべきではない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記aのとおり、被控訴人FC2 が、ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設 置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSW Fファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操 作を介することなく、被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプ ログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、 被告システム1を「生産」した主体は、被控訴人FC2であるという べきである。
また、2)については、前記aのとおり、ウェブページの指定やウ ェブページに表示された再生ボタンをクリックするといったユーザの各行為は、被控訴人FC2の管理するウェブページの閲覧を通じて行われるにとどまるものであり、ユーザ端末による上記各ファイルの受\n信は、上記のとおりユーザによる別途の操作を介することなく自動的 に行われるものであることからすれば、上記各ファイルをユーザ端末 に受信させた主体は被控訴人FC2であるというべきである。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(オ) 小括
以上によれば、被控訴人FC2は、本件生産1の1により、被告シス テム1を「生産」(特許法2条3項1号)したものと認められる。
・・・
8 争点8(控訴人の損害額)について
(1) 特許法102条2項に基づく損害額について
ア 主位的請求関係について 控訴人は、被控訴人らが、本件特許権の設定登録がされた令和元年5月 17日から令和4年8月31日までの間、被告各システムを生産し、被 告各サービスを提供することによって、●●●●●●●●●●円を売り 上げ、これにより被控訴人らが得た利益(限界利益)の額は、●●●● ●●●●●●円を下らず、このうち令和元年5月17日から同月31日 までの分(5月分)の売上高は●●●●●●●●円、限界利益額は●● ●●●●●●円を下らないと主張する。 しかしながら、控訴人が上記主張の根拠として提出する甲24によって、 上記の売上高及び限界利益額を認めることはできず、他にこれを認める に足りる証拠はない。 したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 予備的請求関係について
(ア) 本件生産1ないし3により「生産」された被告システム1ないし3 で提供された被告各サービスの割合 前記4のとおり、被控訴人FC2は、本件生産1により被告システム 1を、本件生産2により被告システム2を、本件生産3により被告シス テム3を「生産」し、本件特許権を侵害したものであり、本件生産1な いし3は、いずれも、サーバがユーザ端末に動画ファイル及びコメント ファイルを送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものである。 しかるところ、被告各サービスで配信される動画でコメントが付され ているものの数は限られており、令和3年1月11日の時点において、 被告サービス1で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、コメン トが付された動画は●●●●●●●個であり(乙85)、その割合は● ●●●パーセントであったこと、被告各サービスは、日本語以外の言語 でもサービスが提供されているものの、そのユーザの大部分は国内に存 在すること(甲9、弁論の全趣旨)からすれば、被告各サービスのうち、 本件生産1ないし3で「生産」された被告システム1ないし3によって 提供されたものの割合は、本件特許権が侵害された全期間にわたって● ●●パーセントと認めるのが相当である。
(イ) 被控訴人FC2の利益額(限界利益額)
a 被告サービス1関係
乙84によれば、令和元年5月17日から令和4年8月31日まで の期間の被告サービス1の売上高は、別紙6売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス1」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙7−1限界利益額等\n一覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス1」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産1により「生産」\nされた被告システム1によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産1による売上高は、 ●●●●●●●●●●●円(●●●●●●●●●●●●円×●●●● ●)と認められ、被控訴人FC2が本件生産1により得た限界利益額 は、別紙7−2限界利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産1」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。
b 被告サービス2関係
乙84によれば、令和元年5月17日から令和2年10月31日 までの期間の被告サービス2の売上高は、別紙6売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス2」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙7−1限界利益額等一\n覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス2」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産2により「生産」\nされた被告システム2によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産2による売上高は、 ●●●●●●円(●●●●●●●●円×●●●●●)と認められ、被 控訴人FC2が本件生産2により得た限界利益額は、別紙7−2限界 利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産2」欄記載のとおり、合計●●●●●●円と認められる。
c 被告サービス3関係
乙84によれば、令和元年5月17日から令和2年10月31日 までの期間の被告サービス3の売上高は、別紙6売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス3」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙7−1限界利益額等一覧表\の「限界利益額」欄の「被告サービス3」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であることが認められる。 このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産3により「生産」 された被告システム3によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産3による売上高は、 ●●●●円(●●●●●●円×●●●●●)と認められ、被控訴人F C2が本件生産3により得た限界利益額は、別紙7−2限界利益額算 定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産3」欄記載のとおり、合計●●●●円と認められる。
d まとめ
(a) 前記aないしcによれば、被控訴人FC2が本件生産1ないし 3により得た限界利益額は、別紙7−2限界利益額算定表の「限界利益額(消費税相当分(10%)を含む)」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●円と認められる。\n なお、被控訴人FC2は、仮に、本件において被控訴人FC2に 対する損害賠償の支払が命ぜられるとしても、消費税上輸出免税 の対象になる旨主張するが、被控訴人FC2による被告各サービ スの提供が輸出取引に当たることを認めるに足りる証拠はないか ら、被控訴人FC2の上記主張は理由がない。
(b) 以上のとおり、被控訴人FC2が本件生産1ないし3により得 た限界利益額は、合計●●●●●●●●●●●円であり、この限 界利益額は、特許法102条2項により、控訴人が受けた損害額 と推定される(以下、この推定を「本件推定」という。)。
(ウ) 推定の覆滅について
被控訴人らは、被告各サービスにおいて、本件各発明のコメント表示機能\が、システム全体の機能の一部であり、顧客誘引力を有していないことは、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張する。\n そこで検討するに、被告各サービスで配信されている動画で、その売 上高に貢献しているものの多くはアダルト動画であり(甲4の1及び2、 9、11、弁論の全趣旨)、動画上にコメントが表示されることが視聴の妨げになることは否定できないこと、令和3年1月11日の時点において、被告サービス1で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、\nコメントが付された動画は●●●●●●●個であり(乙85)、その割 合は●●●●パーセントにとどまっていることに照らすと、被告各サー ビスにおいて、コメント表示機能\が果たす役割は限定的なものであって、 被告各サービスの多くのユーザは、コメント表示機能\よりも動画それ自 体を視聴する目的で利用していたものと認められる。そして、本件各発 明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信システムにおいて、動 画上にオーバーレイ表示される複数のコメントが重なって表\示されるこ とを防ぐというものであり(前記1(2)イ)、その技術的意義自体も、上 記システムにおいて限られたものであると認められる。
以上の事情を総合考慮すると、被告各サービスの利用に対する本件各 発明の寄与割合は●●と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える 部分については、前記(イ)d(b)の限界利益額と控訴人の受けた損害額 との間に相当因果関係がないものと認められる。 したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるか ら、特許法102条2項に基づく控訴人の損害額は、上記限界利益額の ●割に相当するものであり、別紙4−2認容額内訳表の「特許法102条2項に基づく損害額」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。\n
(2) 特許法102条3項に基づく損害額について(予備的請求関係)
ア 特許法102条3項に基づく控訴人の損害額については、1)株式会社帝 国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の 在り方に関する調査研究報告書〜知的財産(資産)価値及びロイヤルテ ィ料率に関する実態把握〜」(本件報告書)の「II).我が国のロイヤルテ ィ料率」の「1.技術分類別ロイヤルティ料率(国内アンケート調査)」 の「(2) アンケート調査結果」には、「特許権のロイヤルティ料率の平均 値」について、「全体」が「3.7%」、「電気」が「2.9%」、「コンピ ュータテクノロジー」が「3.1%」であり、「III).各国のロイヤルティ 料率」の「1.ロイヤルティ料率の動向」には、国内企業のロイヤルテ ィ料率アンケート調査の結果として、産業分野のうち「ソフトウェア」については「6.3%」であり、「2.司法決定によるロイヤルティ料率調査結果」の「(i)日本」の「産業別司法決定ロイヤルティ料率(20 04〜2008年)」には、「電気」の産業についての司法決定によるロ イヤルティ料率は、平均値「3.0%」、最大値「7.0%」、最小値 「1.0%」(件数「6」)であるとの記載があること、2)前記(1)イ(ウ) のとおり、本件各発明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信シ ステムにおいて、動画上に複数のコメントが重なって表示されることを防ぐというものであり、その技術的意義は高いとはいえず、被告各サービスの購買動機の形成に対する本件各発明の寄与は限定的であること、\nその他本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると、本件生産1ないし3 による売上高に実施料率2パーセントを乗じた額と認めるのが相当であ る。
そして、本件生産1ないし3による売上高(消費税相当分(10パー セント)を含む。)の合計額は、●●●●●●●●●●●円(●●●●● ●●●●●●円+●●●●●●円+●●●●円(前記(1)イ(イ)aないし c記載の本件生産1ないし3の各売上高に消費税相当分(10パーセン ト)を加えた額の合計額))と認められるから、●●●●●●●●円(● ●●●●●●●●●●円×0.02)となる。 これに反する控訴人及び被控訴人らの主張はいずれも採用することが できない。
イ そして、控訴人の特許法102条2項に基づく損害額の主張と同条3項 に基づく損害額の主張は、選択的なものと認められるから、より高額な 前記(1)イ(ウ)の同条2項に基づく損害額合計●●●●●●●●●円が本 件の控訴人の損害額と認められる。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和元年(ワ)25152
関連事件はこちら
◆平成30(ネ)10077
1審です。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
>> その他
>> ピックアップ対象
2023.06.28
令和3(ワ)10032 特許権 民事訴訟 令和5年6月15日 大阪地方裁判所
そして、対象製品等が特許発明の構成要件の一部を欠く場合であっても、当該\n一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ前記均等の他の要件を充足するとき は、均等侵害が成立し得るものと解される。 これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用\nすることは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、 構成要件の一部を他の構\成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区\n別すべき合理的理由はないし、本件において、原告は、被告製品には構成要件 C の「消弧材部」に対応する消弧作用を有する部分が存在し、置換構成を有する旨\n主張していると解されるから、被告の前記主張を採用することはできない。
イ 第1要件ないし第3要件
原告は、別紙「均等侵害の成否等」の「原告の主張」欄記載のとおり、本件発 明の本質的な構成部分は構\成要件のうち A-1 ないし A-3、B-3 及び B-4 であり、 構成要件 C は本件発明の課題解決方法に資するものではないとして、第1要件は 満たす旨主張するところ、被告もこれを積極的に争っていない。
一方、第2要件及び第3要件に関し、原告は、被告製品の構成 c の「接着剤で 接着することにより形成された密閉された空間26」が本件発明の構成要件 C の 「消弧材部」と同一の作用効果(消弧作用)を有することを示す実験報告書等(甲 13、14、32)を証拠提出する。これらは、被告製品と同じ構造を有する製\n品につき、ヒューズエレメント部が密閉構造である場合と、非密閉構\造である場 合又は端子一体型ヒューズ素子を取り出して遮断試験用基板に実装して遮断試 験を行った場合の、各アーク放電の持続時間を対比した結果、密閉構造のものは、\n非密閉構造等のものに比べ、同持続時間が2分の1ないし3分の1になったとい\nうものである。しかし、これらは、被告製品の「密閉された空間」と本件発明の 「消弧材部」の各作用効果の対比自体を行うものではないことに加え、被告が証 拠提出する試験報告書(乙16)によれば、被告製品、被告製品に消弧材部を設 けたヒューズ及び被告製品のヒューズ素子のみを対象として、アーク放電の持続 時間を記録したところ、被告製品が最も同時間が長かったという結果であったこ とが認められ、被告製品とヒューズ素子の各アーク放電の持続時間について、原 告が提出する実験報告書(甲14)と相反する結果となっている。そうすると、 原告が提出する前記証拠その他の事情等から、被告製品の構成 c が本件発明の構\n成要件 C と同様の作用効果を有するとまでは認め難いから、少なくとも第2要件 が満たされるとはいえない。
ウ 第4要件
前記イの点は措くとしても、以下のとおり、第4要件も満たさない。 被告は、被告製品の構成は、本件発明の特許出願時における公知技術(乙1発\n明)と同一又は当業者が乙1発明から出願時に容易に推考可能であった旨を主張\nする。
(ア) 乙1公報は、発明の名称を「表面実装超小型電流ヒューズ」とする公開特\n許公報であり、発明の詳細な説明には次の記載がある(乙1)。
・・・・
(イ) 乙1発明の構成\n
乙1発明がα-1、β-1 ないしβ-4 及びδの構成を有することは当事者間に争\nいがなく(別紙「均等侵害の成否等」の「第4要件」欄)、乙1公報の段落【0008】 【0016】【0018】【0020】及び【図2】(A)の記載内容に照らすと、α-2 及び γの構成を有するものと認められる。\nまた、被告主張のα-3 の構成(金属電極2の可溶線挟持部22に挟み込まれる\nことにより一体形成されている電極一体型ヒューズ)に関し、原告は、電極とヒ ューズが同一の金属によって一体的に形成されているとの趣旨であれば否認す ると述べるところ、乙1公報には、可溶線5は、両端部を金属電極2に挟持され 本体1の空間6に架張された可溶線を示す旨(同【0016】)、可溶線5の端部は 第1板部221と第2板部222とにより挟み込まれ、金属電極2に固定される 旨(同【0018】)の記載があることから、可溶線5と金属電極2は異なる部材で 構成され、可溶線5は、可溶線挟持部22において挟持されることによって金属\n電極2に接続されているものと認められる(α-3’)。 以上から、乙1発明の構成は、別紙「裁判所の認定」の「乙1発明の構\成」欄 記載のとおりとなる。
(ウ) 被告製品の構成\n
被告製品が a-1 ないし b-4 及び d の構成を有することは当事者間に争いがな\nく、構成 c を有することも実質的に争いがないから、被告製品の構成は、別紙「裁\n判所の認定」の「被告製品の構成」欄記載のとおりとなる。\n
(エ) 被告製品と乙1発明の対比
被告製品の a-1、a-2 及び b-1 ないし d の各構成は、それぞれ、乙1発明のα1、α-2 及びβ-1 ないしδの各構成と同一であるものと認められる。\nそこで、被告製品の構成 a-3 と乙1発明の構成α-3'が一致するかを検討する。 「一体」の字義は、「一つになって分けられない関係にあること」であるところ (広辞苑第七版)、被告製品は、別紙「被告製品写真」の3及び4に示されるよ うに、ヒューズ本体4と2つの平板状部10の部材が連続し、一つになって分け られないように形成されていることが明らかである。一方、乙1発明の可溶線5 と金属電極2は、異なる部材で構成され、また、可溶線5は、可溶線挟持部22\nにおいて挟持されることによって金属電極2に接続されていることから、可溶線 5と金属電極2は、同一材料で形成されておらず、一つになって分けられないよ うに形成されてもいない。 したがって、可溶線5と可溶線挟持部22は一体に形成されているとは認めら れず、乙1発明は構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しており、被告製 品は、公知技術と同一であるとはいえない。
(オ) 乙1発明と乙3発明に基づく容易推考性
被告は、乙1発明が構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しても、被告 製品の構成 a-3 は、乙1発明の構成α-3’を乙3発明の構成に置換することによ\nり、当業者にとって容易に推考可能である旨を主張する。\n
a 乙3公報は、発明の名称を「面実装型電流ヒューズ」とする公開特許公報で あり、発明の詳細な説明には次の記載がある(乙3)。
(a) 技術分野
「本発明は、過電流が流れると溶断して各種電子機器を保護する面実装型電流 ヒューズに関するものである。」
・・・・
(b) 背景技術
「従来のこの種の面実装型電流ヒューズは、図7に示すように、セラミックか らなるケース1と、このケース1の内部に形成された空間部2と、前記ケース1 の両端部に形成された外部電極3と、この外部電極3と電気的に接続された断面 が円形のヒューズエレメント部4とを備え、前記ヒューズエレメント部4の溶断 部5を前記ケース1の内部に形成された空間部2内に配設した構成としていた。」\n(【0002】)
(c) 発明が解決しようとする課題
「上記した従来の面実装型電流ヒューズにおいては、ヒューズエレメント部3 として同じ線径のものや同じ材料のものを使用しているため、線径や材料によっ て決まる溶断電流等の溶断特性を調整することができないという課題を有して いた。」(【0004】) 「本発明は上記従来の課題を解決するもので、溶断特性の調整ができる面実装 型電流ヒューズを提供することを目的とするものである。」(【0005】)
(d) 課題を解決するための手段
「本発明の請求項1に記載の発明は、絶縁性を有するケースと、このケースの 内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部電極と、この 外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設したヒューズエ レメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一部を切削する ことによって設けたもので、この構成によれば、ヒューズエレメント部の切削に\nよって溶断部の線径を調整できるため、溶断特性を調整することができるという 作用効果が得られるものである。」(【0007】) 「本発明の請求項3に記載の発明は、特に、ヒューズエレメント部と外部電極 とを一体の金属で構成したもので、この構\成によれば、ヒューズエレメント部と 外部電極とを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができると いう作用効果が得られるものである。」(【0009】)
(e) 発明の効果
「以上のように本発明の面実装型電流ヒューズは、絶縁性を有するケースと、 このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部 電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設し たヒューズエレメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一 部を切削することによって設けているため、この切削によって溶断部の線径を調 整でき、これにより、溶断特性を調整することができるという優れた効果を奏す るものである。」(【0016】)
(f) 発明を実施するための最良の形態
「図4、図5において、本発明の実施の形態2が上記した本発明の実施の形態 1と相違する点は、ヒューズエレメント部15と外部電極13とを一体の金属で 構成した点である。この場合、外部電極13はケース11の底部11aの端面お\nよび裏面に沿うように折り曲げている。」(【0035】) 「上記構成においては、ヒューズエレメント部15と外部電極13とを一体の\n金属で構成しているため、ヒューズエレメント部15と外部電極13とを接続す\nる必要はなくなり、これにより、生産性を向上させることができるという効果が 得られるものである。」(【0036】) 【図4】 【図5】
b 容易推考性
(a) 乙3公報の発明の詳細な説明によれば、乙3発明は面実装型電流ヒュー ズに関する発明であり(段落【0001】)、従来の面実装型電流ヒューズにおいて は、ヒューズエレメント部4として同じ線径のものや同じ材料のものを使用して いるため、線径や材料によって決まる溶断電流等の溶断特性を調整することがで きないという課題を有していたこと(同【0004】)に対し、絶縁性を有するケー スと、このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成され た外部電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を 配設したヒューズエレメント部とを備え、ヒューズエレメント部の切削によって 溶断部の線径を調整でき、溶断特性を調整することを可能としたものである(同\n【0007】【0016】)。そして、特に、ヒューズエレメント部と外部電極とを一体 の金属で形成する構成をとることによって、ヒューズエレメント部と外部電極と\nを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができるという効果を 奏すること(同【0009】【0036】)や、発明の実施の形態として、外部電極13 がケース11の底部11a の端面及び裏面に沿うように折り曲げられた形態が記 載されている(同【0035】【図4】【図5】)。 以上によれば、乙3公報には、面実装可能な小型ヒューズにおいて、生産性の\n向上を目的として、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外部電極を一体の 金属で形成するという乙3発明が開示されているといえる。
一方、乙1公報の発明の詳細な説明によれば、乙1発明は表面実装超小型電流\nヒューズに関する発明であり(段落【0001】)、従来の表面実装小型電流ヒュー\nズは、可溶部あるいは可溶線が合成樹脂や低融点ガラス等の絶縁物に直接接触し た構造である場合、可溶部等が熱的中立性を保てず本来のヒューズとしての溶断\n性能がおろそかにされている問題(同【0002】〜【0004】)や、電極をケース内 に配置固定した後、電極間に可溶線を架張して半田付けする方式は、半田が固ま る際に生じる盛り上がりの差により電極間の長さ、すなわち、可溶線の長さにば らつきが生じるという問題があったこと(同【0005】)に加え、従来の小型ある いは超小型電流ヒューズは、各部品を一つ一つバッチ工程で加工組立てを行う必 要があり、部品が小さいためその作業は困難を極め、製造し難く、その結果、低 コスト化にも限界があるという問題があった(同【0006】)。これに対し、乙1 発明は、可溶線5を挟持した一対の金属電極2が箱型形状を有する本体1の両端 に取り付けられ、蓋部3を本体1の上面より僅かに沈む位置まで押し込み接着剤 を塗布して蓋部3を本体1に固定して内部を密閉し、可溶線は本体1の内部空間 に浮いた状態で架張されている構成をとることで(同【0008】)、溶断特性のば らつきを最小限に抑えることや従来型と比べて2倍以上大きい遮断能力を有す\nることを可能としたこと(同【0028】〜【0030】)に加え、連続工程で製作組立 を行うこと、特に、可溶線5を挟持した一対の金属電極2を組み立てた後に鞍部 21を本体1の双方の短側壁11に嵌合させて固定することにより、製造が容易 になって、大幅なコスト削減が可能となるという効果を奏するものである(同\n【0020】【0027】)。 そうすると、乙1発明と乙3発明は、いずれも表面実装型ヒューズに関する発\n明であり、その技術分野は同一である。また、乙1発明と乙3発明は、いずれも 生産性の向上という同一の課題に対し、予めヒューズと電極とを組み合わせた後\nに本体に固定するという技術思想に基づく課題解決手段を提供する発明である ことに加え、乙1発明の溶断時間のばらつきを抑えるという課題と乙3発明の溶 断特性を調整するという課題は、所望の溶断特性を実現するという点で関連して いるといえる。 したがって、乙1発明と乙3発明は、技術分野、課題及び解決手段を共通にす るから、乙1発明に乙3発明を適用する動機付けが存在するものと認められる。
(b) 原告の主張
原告は、乙1発明と乙3発明とは、その課題等が相違することのほか、乙3発 明において、ヒューズエレメント部の切削を容易にするためには、乙1発明のケ ース11は上下方向の中央で分割される必要があること、乙1発明の本体1の空 間部6内に乙3発明のヒューズエレメント部15を配置する場合、ヒューズエレ メント部15を切削する必要があるが、所望の抵抗値が得られるように切削する ことは実質的に不可能であることから、乙1発明に乙3発明を組み合わせること\nはその構成上不可能\であることなどの阻害要因があるとして、被告製品と乙1発 明の相違部分は、乙3発明から容易に推考できたとはいえない旨を主張する。 しかし、前記(a)のとおり、乙1発明と乙3発明の課題は同一又は関連してい る。また、乙3公報の発明の詳細な説明によれば、ヒューズエレメント部の切削 は、スクライブやパンチング等の機械的方法によって行うが、予めヒューズエレ\nメント部の切削をした後にケースに固定をしてもよい旨が記載されていること から(段落【0022】【0027】【0028】)、ヒューズエレメント部を切削するため に、ケースを上下方向の中央で分割する必要があることにはならない。また、乙 3発明を乙1発明に適用するに当たり、乙1発明の空間部6内に、外部電極と一 体の金属で形成され、溶断部を配設したヒューズエレメント部を配置することと なるが、空間部6内にヒューズエレメント部を配置する場合に、当該ヒューズエ レメント部を切削する必要が必ずしもあるともいえない(ヒューズエレメント部 の一部の切削は本体への配置前に行うことができる。)。その他、乙1発明に乙 3発明を組み合わせることについて阻害要因があることをうかがわせる事情は ない。 したがって、原告の前記主張は採用することができない。
(c) 以上から、乙1発明に乙3発明を適用する動機付けが存在し、これを阻害 する要因は認められないから、乙1発明の可溶線と金属電極は異なる部材で構成\nされる構成に代えて、乙3発明の、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外\n部電極部を一体の金属で形成する構成を採用して被告製品の構\成とすることは、 当業者が本件特許の出願時に容易に推考し得たものと認められ、被告製品は、均 等の第4要件を満たさない。
・・・
2 争点2(本件追加の可否)について
本件追加は、被告製品が、本件発明に係る請求項とは別の請求項記載の本件発 明2の技術的範囲に属するとして請求原因を主張し、本件特許権の侵害に基づく 各請求を追加するものであるから、訴えの追加的変更に当たると解するのが相当 であるところ、当裁判所は、本件追加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させ ることとなると認め、これを許さないこととする(民訴法143条1項ただし書、 同条4項)。
すなわち、本件追加に係る請求原因は、原告において、審理の当初から主張す ることが可能であったところ、令和4年11月28日の書面による準備手続中の\n協議において、当裁判所は、当事者双方に対し、被告製品は本件発明の技術的範 囲に属さないとの心証を開示して、話合いによる解決を検討するよう促し、その 後、和解協議を行ったものの、令和5年1月27日の同協議において、これ以上 の和解協議は行わないこととなり、口頭弁論の終結に向けて、原告は、これまで の主張の補充及び反論を記載した書面を提出する旨述べたが、同年2月27日付 けの準備書面5において、本件追加を行ったものである(当裁判所に顕著な事実)。 このように、本件追加が行われた時点で、本件訴訟は、被告製品が本件発明の技 術的範囲に属さないとの当裁判所の心証開示を踏まえた和解協議を終え、審理を 終結する直前の段階に至っていた。仮に、本件追加を許した場合、被告製品が本 件発明2の技術的範囲に属するか否かや、本件特許に係る無効理由の有無につい ても改めて審理を行う必要があり、そのために相当な期間を要することになるこ とは明らかである。そうすると、本件発明2が本件発明1の従属項であり、構成\n要件の一部が同一であること、その他原告が指摘する事情を考慮しても、本件追 加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることになると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.06. 7
令和4(ネ)10107 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年6月1日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 前記(2)のとおり、被控訴人製品は「摺動導通部」を有しない点において、 本件発明と異なる。
ところで、訂正の上引用した原判決の第3の1(2)のとおり、本件発明は、一対 のプランジャをコイルばねの密巻き部分に接触させて導通を確保するという本件先 行発明における、2つの摺動導通部が形成されることによる抵抗の分散が検査の精 度を狭めるという課題を解決するために、摺動導通部の数を減らし、検査精度を向 上可能とするというものであり、プランジャと接触して導通を確保する摺動導通部\nを有することは、本件発明の本質的部分である。 そうすると、被控訴人製品と本件発明の構成中の異なる部分(摺動導通部の存否)\nは、本件発明の本質的部分に当たる。
イ 控訴人は、「密巻き部」に関する本件発明と被控訴人製品の相違点は、「本件 発明では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているところ、被 控訴人製品では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているかが 定かではなく、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」が導通経路とな っている可能性がある点」であり、被控訴人製品について均等侵害が成立すると主\n張する。しかしながら、訂正の上引用した原判決の第3の2(4)のとおり、被控訴 人製品において、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分が導通経路となっ ていることを認めるに足りる証拠がなく、このことは、当審において提出された動 画(甲86)を踏まえても変わらない。そうすると、控訴人の「密巻き部」に関す る均等の主張はその前提を欠く。
ウ したがって、その余の点につき検討するまでもなく、被控訴人製品について、 本件発明の均等侵害は成立しない。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和2(ワ)12013
添付文書はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.05.30
平成29(ネ)10043 特許権侵害差止等請求承継参加申立控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年1月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
問題の請求項は以下です。
A ユーザテレビ機器(22)上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって,
B 該システムは,複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して,デジタル格納デバイス(31)に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と,
C 双方向テレビ番組ガイドを用いて,該ユーザテレビ機器(22)に含まれる該デジタル格納デバイス(31)に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と,
D 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して,該双方向テレビ番組ガイドを用いて,該デジタル格納デバイス(31)に複数の番組データをデジタル的に格納する手段であって,該複数の番組データのそれぞれは,該複数の番組のうちの1つに関連付けられている,手段と,
E 該双方向テレビ番組ガイドを用いて,該デジタル格納デバイス(31)に格納された該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と,
F 該デジタル格納デバイス(31)に格納された該複数の番組のリストから,該デジタル格納デバイス(31)に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と,
・・・
J 該双方向テレビ番組ガイドを用いて,現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの該選択された番組に対して,選択された番組リスト項目情報画面を該ユーザテレビ機器(22)に表示する手段であって,該選択された番組リスト項目情報画面は,該選択された番組に関連付けられた番組データの1つ以上のフィールドと,1つ以上のユーザフィールドとを含む,手段と,
K 該1つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する手段と
L を備えた,システム。
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は,構成要件Cは,「双方向テレビ番組ガイド」を用いて,「デジタ\nル格納デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば, 充足することになるものであって,「デジタル格納デバイス」自体を必須の構成要素\nとして規定するものではないと主張するが,本件発明は,デジタル格納部を含むユ ーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから, 被告物件(液晶テレビ製品)が本件発明の技術的範囲に属するというためには,被 告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要であることは,\n
前記1のとおり補正して引用する原判決が認定説示するとおりである。 すなわち,本件発明に係る特許請求の範囲は,「ユーザテレビ機器(22)上で動 作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって」(構成要件A),・・・「双方向テ\nレビ番組ガイドを用いて,該ユーザテレビ機器(22)に含まれる該デジタル格納 デバイス(31)に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と,」(構成要件C)・・・「を備えた,システム」(構\成要件L)と記載されているから,本件発明の双方向テ レビ番組ガイドシステムは,ユーザテレビ機器に含まれるデジタル格納デバイスに 番組をデジタル的に格納(録画)する手段という構成を含むものである。\nそして,本件明細書には,「本発明は・・・番組および番組に関連する情報用のデ ジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに関する。」(【0001】) として,双方向テレビ番組ガイドシステムが「デジタル格納部を備えた」ものであ る旨が記載されている。また,従来技術として,「番組ガイド内で選択された番組を 独立型の格納デバイス(典型的にはビデオカセットレコーダ)に格納することを可 能にする双方向番組ガイド」(【0004】)が指摘され,その操作に関し,「ビデオ\nカセットレコーダの操作には通常は,ビデオカセットレコーダ内の赤外線受信器に 結合される赤外線送信器を含む操作経路が用いられる。」(【0004】)と記載され ており,「独立型の格納デバイス」を用いる従来技術について記載されている。その 上で,従来技術の課題として「独立型のアナログ格納デバイスを用いると,デジタ ル格納デバイスが番組ガイドと関連付けられる場合に実施され得るようなより高度 な機能が不可能\になる。」(【0004】)と記載され,これを受けて,本発明の目的 を「デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供すること」(【0005】)と記載している。以上に加え,「番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイス の使用は,独立型のアナログ格納デバイスを用いて行われ得る機能よりも,より高\n度な機能をユーザに提供する。」(【0009】)という記載を併せ考慮すると,本件\n発明は,独立型のアナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能\をユーザに 提供するために,双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備え ることを目的としたものと認められる。
以上によると,被告物件が構成要件Cを充足するというためには,「番組をデジタ\nル的に格納可能な部分」を含むこと(内蔵すること)が必要というべきである。\nこれに対し,控訴人は,本件明細書の【図2】及び【0016】によると,本件 発明には,「デジタル格納デバイス」が「ユーザテレビ機器」に外部インターフェー スを介して接続されるような構成も当然に含むように説明されていると主張するが,\n控訴人指摘の「デジタル格納デバイス31は,セットトップボックス28内に内蔵 されるか,または出力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップ ボックス28に接続された外部デバイスであり得る。」(【0016】)との記載は, 「ユーザテレビ機器22の例示的構成を示す」【図2】からも明らかなとおり,「ユ\nーザテレビ機器」の一部を構成する「セットトップボックス」内に内蔵するか,「セ\nットトップボックス」に外付けするかを記載するにとどまり,「ユーザテレビ機器」 に外付けする構成を当然に含むものということはできない。かえって,「ユーザテレ\nビ機器22の例示的構成」において,「オプション」とされている「第2の格納デバ\nイス32」(【0014】)については,「第2の格納デバイス32がユーザテレビ機 器22に内蔵されていない場合」(【0017】)との記載が認められるところ,「デ ジタル格納デバイス」については,これと同旨の記載は見当たらない。
また,控訴人は,本件明細書の【図3】及び【0080】には,デジタル格納デ バイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フロッピーディスク又は録画可能な\n光ディスク)である場合が説明されていると主張するところ,控訴人指摘の【00 80】には,「デジタル格納デバイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フロッ ピーディスクまたは録画可能な光ディスク)である場合」との記載がある。しかし,\n本件明細書には,「デジタル格納デバイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フ ロッピーディスクまたは録画可能な光ディスク)を用いる場合」(【0085】)との\n記載もあるほか,「デジタル格納デバイスは,光格納デバイスまたは磁気格納デバイ ス(例えば,書き込み可能なデジタル映像ディスク,磁気ディスク,もしくはハー\nドドライブまたはランダムアクセスメモリ(RAM)等を用いたデバイス)であり 得る。」(【0008】),「第2の格納デバイス32は,任意の適切な種類のアナログまたはデジタル番組格納デバイス(例えば,ビデオカセットレコーダ,DVDディ スクに録画する能力を有するデジタル映像ディスク(DVD)プレーヤ等)であり\n得る。」(【0014】),「デジタル格納デバイス31は,書き込み可能な光格納デバイス(例えば,記録可能\なDVDディスクの処理が可能なDVDプレーヤ),磁気格\n納デバイス(例えば,ディスクドライブまたはデジタルテープ),または他の任意の デジタル格納デバイスであり得る。」(【0015】),「デジタル格納デバイス49において用いられるリムーバブル格納媒体」(【0082】),「例えばデジタル格納デバイス49がフロッピーディスクドライブであり,選択された番組を有するディスク がドライブ内に無い場合」(【0084】),「デジタル格納デバイス49内のリムーバブルデジタル格納媒体上に格納する」(【0104】)との記載もあり,これらの記載 によると,本件明細書においては,「デジタル格納デバイス」は,「リムーバブル格 納媒体」(フロッピーディスク,DVDディスク等)と区別されるものであり,「リ ムーバブル格納媒体」を処理することが可能な機器(フロッピーディスクドライブ,\nDVDプレーヤ等)を指すことが多いものと認められる。そうすると,控訴人指摘 の【0080】の上記記載から,直ちに本件発明にはデジタル格納デバイスがリム ーバブル録画媒体である場合が含まれるということはできない。
(2) 控訴人は,間接侵害を主張するところ,被告物件である液晶テレビ製品は, 単に放送を受信するだけで,いずれもそれ自体に録画できるメモリー部分(デジタ ル格納部)を備えておらず,録画先としては,外付けのUSBハードディスクやレ グザリンク対応の東芝レコーダーとされており,これらを被告物件に接続すること によって初めて,被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画すること が可能であるから,デジタル格納部を被告物件に内蔵させる余地はない。そうする\nと,被告物件は,デジタル格納デバイスを含むユーザテレビ機器を備えた双方向テ レビガイドシステムの「生産に用いる物」ということができない。
また,前記(1)のとおり,本件発明は,独立型のアナログ格納デバイスでは不可能\nであった高度な機能をユーザに提供するために,双方向テレビ番組ガイドシステム\nがデジタル格納デバイスを備えることを目的としたものであり,従来技術に見られ ない特徴的技術手段は,双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイス を備えること,すなわち,これを内蔵することにあるというべきである。そうする と,被告物件は,デジタル格納デバイスを内蔵するものではないから,本件発明に よる「課題の解決に不可欠なもの」であるとはいえない。
したがって,被控訴人による被告物件の製造,輸入,販売及び販売の申出は特許\n法101条2号所定の間接侵害に当たらない。これに対する控訴人の主張が理由のないものであることは,既に説示したところ から明らかである。
なお,被控訴人は,控訴人の間接侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当た る旨を主張するが,控訴理由書において,既に提出済みの証拠に基づき判断可能な\n主張をしたものであるから,訴訟の完結を遅延させるものとまではいえず,上記主 張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.05.29
令和5年5月26日 知財高裁特別部判決 令和4(ネ)10046号
ア ネットワーク型システムの「生産」の意義
本件発明1は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備え るコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、そ の実施行為としての物の「生産」(特許法2条3項1号)とは、発明の技術的範囲に 属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。 そして、本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介して、サー バと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(ネットワー\nク型システム)の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件\nを充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有 機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能\を有する ようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解され る。
イ 被告サービス1に係るシステム(被告システム1)を「新たに作り出す行為」 被告サービス1のFLASH版においては、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指\n定すると、被控訴人Y1のウェブサーバが上記ウェブページのHTMLファイル及 びSWFファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、その後、ユーザが、ユーザ端末において、 ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すと、上\n記SWFファイルに格納された命令に従い、ブラウザが、被控訴人Y1の動画配信 用サーバ及びコメント配信用サーバに対しリクエストを行い、上記リクエストに応 じて、上記各サーバが、それぞれ動画ファイル及びコメントファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が、上記各ファイルを受信することにより、ブラウザにおい て動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能\となる。このように、ユ ーザ端末が上記各ファイルを受信した時点において、被控訴人Y1の上記各サーバ とユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、 ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが\n可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明1の全\nての構成要件を充足する機能\を備えた被告システム1が新たに作り出されたものと いうことができる(以下、被告システム1を新たに作り出す上記行為を「本件生産 1の1」という。)。
ウ 被告システム1を「新たに作り出す行為」(本件生産1の1)の特許法2条3項 1 号所定の「生産」該当性
特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効 力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内にお いてのみ認められることを意味するものであるところ、我が国の特許法において も、上記原則が妥当するものと解される。 本件生産1の1において、各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユー ザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまた がって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国 と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生 産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題と なる。 ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(国外)に設置されるこ とは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネ ットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵 害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたと\nしても、当該システムを構成する端末が日本国内(国内)に存在すれば、これを\n用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者\nが当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るも のである。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格 に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在するこ\nとを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解するこ とは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該 システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととな\nって、妥当ではない。他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、\nこれも妥当ではない。
これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保 護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条 3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素\nの一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果\nたす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、\nその利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3 項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。 これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国 に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ 端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信 (送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信すること によって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われ たものと観念することができる。
次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人Y1のサーバと国内に存在 するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ\n端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表\示されるコメント同士が重な らない位置に表示されるようにするために必要とされる構\成要件1Fの判定部の 機能と構\成要件1Gの表示位置制御部の機能\を果たしている。 さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することが できるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の 向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利 用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影 響を及ぼし得るものである。 以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われた ものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生 産」に該当するものと認められる。
これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の効力が当該国 の領域においてのみ認められる」のであるから、国外で作り出された行為が特許 法2条3項1号の「生産」に該当しないのは当然の帰結であること、権利一体の 原則によれば、特許発明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施す\nることをいうことからすると、一部であっても国外で作り出されたものがある場 合には、特許法2条3項1号の「生産」に該当しないというべきである、2)特許 回避が可能であることが問題であるからといって、構\成要件を満たす物の一部さ え、国内において作り出されていれば、「生産」に該当するというのは論理の飛躍 があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、\n我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判 例においては、カードリーダー事件の最高裁判決(最高裁平成12年(受)第5 80号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁)等によ り属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、その例外を設けることの悪影響 が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは\n立法によってされるべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に関し、被疑侵 害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」 に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバ\nが国外に存在する場合であっても、前記 に説示した事情を総合考慮して、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3 項1号の「生産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することが できない。
2)については、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かの上記判断は、 構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の\n効力を及ぼすというものではないから、2)の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その 成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該 国の領域内においてのみ認められることを意味することに照らすと、上記のとお り当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときに特許法2 条3項1号の「生産」に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しな いというべきである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たるためには、特 許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内に\nおいて完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、ま た、我が国が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則 の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物\nを新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要である ことを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用することができ ない。したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
エ 被告システム1の「生産」の主体
被告システム1は、前記イのプロセスを経て新たに作り出されたものであるとこ ろ、被控訴人Y1が、被告システム1に係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及び コメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファ イル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介するこ となく、被控訴人Y1がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動 的に行われるものであることからすれば、被告システム1を「生産」した主体は、 被控訴人Y1であるというべきである。
オ まとめ
以上によれば、被控訴人Y1は、本件生産1の1により、被告システム1を「生 産」(特許法2条3項1号)し、本件特許権を侵害したものと認められる。
◆判決要旨
1審はこちら。
◆令和元年(ワ)25152
関連事件はこちら
◆平成30(ネ)10077
1審です。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判管轄
>> その他
>> ピックアップ対象
2023.05.25
令和5(ネ)10009 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年5月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1 本件訴えの適法性(本案前の抗弁)について
(1) 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合に は、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解す るのが相当である(最高裁昭和49年(オ)第331号同51年9月30日第一小 法廷判決・民集30巻8号799頁、最高裁昭49年(オ)第163号、164号 同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁参照)。
(2) 令和2年事件について(乙1、2)
ア 令和2年事件は、控訴人が、スマートフォン(型番SHV39、SHV40、 SHV41、SHV42及びSHV43。以下併せて「前訴被告製品」という。) の被控訴人シャープによる製造、被控訴人KDDIによる販売が、本件特許権を侵 害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請 求をした事案である。 令和2年事件においては、前訴被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1、 3及び4の各発明の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には前訴被告製 品にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーション (以下「前訴アプリ」という。)における「操作メニュー情報」の有無が争点とな った(令和2年事件における争点1−3)。 この争点について、控訴人は、「・・・できるように」という言葉は、目標・目 的・基準等を示すものであるから、「操作メニュー情報」は実行される命令の内容 の全部を利用者において理解することができるものである必要はなく、実行される 命令の内容を利用者が理解できることを目標・目的としている程度の表現があれば\n足りるなどとして、前訴被告製品における前訴アプリによるページ一部表示(本件\nにおける「一部表示画像」に相当する。)が「操作メニュー情報」に当たると主張\nした。
イ 令和2年事件の第一審である東京地方裁判所は、前訴被告製品における前訴 アプリの動作について、「1)利用者が前訴アプリの画面上に表示されたアイコン画\n面に指で触れて一定時間待つ操作(ロングタッチ)をすると、当該アイコンを移動 できる状態に遷移し、2)当該アイコンが指に追随して移動し、アイコンが指に追随 して右又は左に移動した距離が一定距離を超えると、縮小モードとなって、表示中\nの当該ページの画面が90%の大きさに縮小され、画面の左端又は右端に隣接する ページの画面の一部(ページ一部表示)が表\示され、3)更に当該アイコンをその方 向に移動させると、移動方向に隣接するページの画面がスクロールされて表示され\nる」ものであると認定し、ページ一部表示である直方形部分を見た利用者は、それ\nがどのような命令を実行する表示であるのかを理解することができないから、前訴\n被告製品のページ一部表示の画像は、本件発明1及び3の構\成要件Bの「操作メニ ュー情報」を有するとは認められないと判断した(乙2。東京地裁令和2年(ワ) 第15464号同3年7月14日判決)。そして、上記判断は、控訴審である知財 高裁令和4年2月8日判決(乙1)においても維持され、同判決は、上訴されるこ となく確定している(弁論の全趣旨)。
(3) 本件について
ア 本件は、控訴人が、スマートフォン(型番SHV44、SHV45及びSH V46。被告製品)の被控訴人シャープによる製造、被控訴人KDDIによる販売 が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為 に基づく損害賠償請求をした事案である。 本件においては、被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の各発 明(本件発明)の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には被告製品にイ ンストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーション(本件ホ ームアプリ)における「操作メニュー情報」の有無が争点となった。 本件における争点1(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)についての 控訴人の主張は、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び前記第2の 3に記載するとおりである。
イ 被告製品における本件ホームアプリの動作は、概要次のとおりである(前提 事実(6)ウ)。
「1)利用者が本件ホームアプリの画面上に表示されたショートカットアイコンを\n長押しすると、当該ショートカットアイコンはタッチパネル上の指等の動きに追随 して移動できる状態になり、2)当該ショートカットアイコンの移動距離が一定距離 になった場合に、縮小モードとなって、表示中の中央ページ画面が縮小表\示され、 画面の左端又は右端に隣接するページの画面の一部(一部表示画像)が表\示され、 3)更に当該ショートカットアイコンを一部表示画像の範囲に入れると、隣のページ\nの画面が表示される。」\nなお、原判決は、一部表示画像を見た利用者は、それが左右のページの一部を表\ 示していることを理解できるとはいえず、仮に理解できたとしても、当該画像の領 域までショートカットアイコンをドラッグすることによって対応するページにスク ロールするという命令が表示されていると理解できるように構\成されているとはい えないから、被告製品の一部表示画像は「操作メニュー情報」に当たらず、被告製\n品が本件発明の構成要件B、E、F、Gの「操作メニュー情報」を有するとは認め\nられないと判断した。
(4) 令和2年事件と本件の比較
令和2年事件と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一で あり、その特許請求の範囲の請求項1及び3の各発明の技術的範囲への被疑侵害品 の属否が問題となっている点も共通する。 本件の対象製品である被告製品は、令和2年事件の対象製品である前訴被告製品 と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認さ れるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことはうかがえず、特に、 問題とされているアプリケーションは同一(いずれもAQUOS Home)であ って、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたこ\nともうかがえず、また、問題となる動作(前記(2)イ及び(3)イ)は同一又は少なく とも実質的に同一である。 そして、令和2年事件と本件における争点は、対象製品(前訴被告製品又は被告 製品)にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーショ ン(前訴アプリ又は本件ホームアプリ)における「操作メニュー情報」の有無であ るから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点 についての控訴人の主張も実質的に同一である。 そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が 存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法 行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和2年事件における 控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和2年事件判決 が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成\n(前訴アプリの動作)と、被告製品の構成(本件ホームアプリの動作)が実質的に\n同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由に より、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提\n起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、 被控訴人らの令和2年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著し く損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。
(5) 控訴人の主張に対する判断
この点、控訴人は、令和2年事件における対象製品である前訴被告製品の構成\na1 と、本件訴訟における被告製品の構成 a1、a1’、a1”が異なり、また、構成 a3、 a3’、a3”、p1〜p3 が追加されているから、新たな判断が必要であると主張する。 しかしながら、控訴人の主張する被告製品の構成 a1、a1’、a1”及び p1〜p3 は 「一部表示画像」に関するものではなく、構\成 a3、a3’、a3”は、「一部表示画像」\nの画面上の領域(座標)をより具体的に特定したにすぎないものであって、前記 (2)イの前訴アプリの動作を変更するものではないから、控訴人の主張する構成は、\nいずれも、「一部表示画像」が構\成要件B、E、F、Gの「操作メニュー情報」に 該当するかを検討するに当たり、その判断に影響を与え得るものとはいえない。 また、上記控訴人の主張する構成の差異が、前訴被告製品の前訴アプリと被告製\n品の本件ホームアプリにおける実質的な差異であると認めるに足りる証拠はない上、 仮に、当該構成部分において、前訴被告製品の前訴アプリと被告製品の本件ホーム\nアプリに差異があるものと認められたとしても、その差異は、被告製品の本件ホー ムアプリにおける「操作メニュー情報」の有無に係る判断を左右するものとはいえ ず、さらに、控訴人が、控訴審において追加した構成も、上記判断を左右するもの\nではない。 したがって、上記控訴人の主張は採用できない。
(6) 小括
したがって、控訴人が本件において本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償 請求をし、これに係る主張をすることは、令和2年事件における紛争の蒸し返しに すぎないというべきであり、同事件の当事者である控訴人と被控訴人らとの間で、 控訴人の請求について審理をすることは、訴訟上の信義則に反し、許されない。
◆判決本文
原審は令和4年(ワ)第11889号ですが、アップされていません。
上記別事件はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.05.19
令和2(ワ)4913 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年4月20日 大阪地方裁判所
(c) 原告は、前記の各製品について、アウタロータ型電動モータを採用しておら ず、被告製品及び原告製品と構造が根本的に異なること、被告製品及び原告製品は、\n主として車輌工場において重要保安部位向けに使用されるのに対し、瓜生製作のU BX−AFシリーズ以外は主にそれよりも重要度の低い部位に用いられること、デ ソータやエスティックの製品は電動式衝撃締め付け工具ではなくナットランナーと\n思われること等を理由に、いずれも競合品に該当しないと主張する。 しかし、被告カタログ及び前記競合品の各カタログ(乙52の4、54の3、5 6の1・2、58、73、74)には、工具に採用されているモータの型がアウタ ロータかインナロータかといった点に関する記載がないことや、モータの構造は製\n品の外部から確認できるものではないこと等を踏まえると、モータの構造それ自体\nが需要者の購入動機の形成に寄与する場合が多いとは認められず、アウタロータ型 電動モータを採用していないことをもって直ちに競合品から排除されるとするのは 相当でない。また、被告製品及び原告製品の各カタログを見ても、締め付け工具で あること以上に各製品の用途を限定する旨の記載はなく(甲35、36、乙58)、 これらの製品が主に車輌工場において重要保安部位向けに使用される一方、他の製 品が異なることについて的確に裏付ける証拠はない。また、証拠(乙1、4、34) によれば、一般に、ナットランナーは、インパクトレンチやパルスツールとはモー タの回転を締付力に変換する方式が異なることから、高精度である一方でトルクが 低く抑えられ、反力受けが必要であるという特徴を有し、パルスツールとは性能・\n用途が異なる場合があるといえるが、デソータ及びエスティックの前記各製品は、\n低反力で反力受けを要さず、作業者が直接手に持って締め付け操作を行うことが可 能な製品であり、かつトルク範囲も被告製品のものと重複するものであることから、\n被告製品及び原告製品と性能・用途等において共通する競合品であると認められる。\nしたがってこの点の原告の主張は採用できない。
(d) 以上によれば、被告製品及び原告製品と共通する電動式締め付け工具の市 場において競合品が一定数存在することが認められる。もっとも、当該市場におけ る被告製品や原告製品の市場占有率等が明らかではないことや、競合品と認められ る製品の中には、被告製品との価格差が比較的大きいものもあると考えられること 等を踏まえると、競合品の存在を理由とする大幅な覆滅を認めることはできないと いうべきである。
c 侵害品の性能\n
(a) 被告カタログ(乙58)によれば、被告製品は、その「主な特徴」として、 「バッテリーツール、高い生産性、高トルク、高精度、低反力、メンテナンス軽減、 多様な使用環境に対応」と記載されている。また、より具体的な特徴として、被告 製品は、バッテリー残量等を作業者から容易に確認できるLEDインジケータが表\n示されること、作業者の手になじむバランスのとれたツールであること、オイル漏 れの影響を軽減してメンテナンス周期を延ばす新型のパルスユニットを採用してい ること、効率的な冷却システムを搭載していること、予備バッテリーを内蔵し通信\nを維持したままバッテリー交換が可能であること、回転速度が6000rpmまで\n設定可能であること、独自のコントローラ「Power Focus 6000」及びソフトウェア\nにより容易に作業内容等を設定可能であること、内蔵されたブザーからの音でも締\nめ付けが可能であること、デュアルアンテナにより無線環境に対応しツールの接続\n性を向上していること、高速バックアップユニット機能を搭載していること等が記\n載されている。一方で、モータの構造や、被告製品がアウタロータ型電動モータを\n採用していることについての記載はない。 また、被告カタログでは、前記のメンテナンス軽減・周期の改善に関して、新し い特許技術と設計により、従来品よりもメンテナンス周期が長くなっていること、 オイル漏れ対策やエアセパレータの採用及び優れた冷却性能がパフォーマンスと稼\n働時間の向上に寄与していることの記載があるほか、「高いトルク性能」として、\n「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、「高度なモーター制御」により締付け 時間が早くなり生産性が向上する旨が記載されている。 そして、証拠(乙58、59)及び弁論の全趣旨によれば、ABは、次のとおり の技術(発明)について、特許を出願し、その多くが日本国内を含めて登録されて おり、これらの技術が被告製品に採用されていると認められる。
1) オイルパルスユニット内のオイルと空気を分離する機構を備え、オイルチャ\nンバから分離された空気が再びオイルチャンバに戻ることを防止する技術(乙 59の1)
2) 遠心作用によりオイルから空気を取り出すための分離手段を備え、パルスユ ニット内の空気の割合を低くすることにより、高いパルス発生効率を実現する 技術(乙59の10)
3) 作動流体を利用したヒートパイプにより、電動モータの熱を効率的に放散し て冷却する技術(乙59の2)
4) ステータ要素とロータ要素との間の相対変位を感知するセンサーに係る技術 でありモータ制御の精度に資する技術(乙59の3)
5) モータとパルスユニットとの接続を改良し、高い生産性、低反力、高トルク 及びメンテナンス周期を改善させる技術(乙59の4)
6) 電圧供給源の遮断時に、動作制御ユニット及び無線通信装置への電圧供給を 連続して維持することによりバッテリーユニットの交換立ち上げにおける遅 れを実質的に減少する技術(乙59の5)
7) 油圧パルスユニット内のオイルレベルが低すぎる場合に、警告信号を出す方 法及びシステムに関する技術(乙59の6)
8) トルク限度及び角度回転限度を超えて締結具が更に締め付けられることを防 止するため、締付具が事前に締め付けられていたか否かを検出する方法に係る 技術(乙59の7)
9) オイルパルスユニットについて機構及び各種部材の形状を工夫し、トルク衝\n撃が与えられた直後に高圧室の圧力を迅速に除去し、次のトルク発生のための 迅速な加速を可能とし、トルクの増大及びトルクの間隔の短縮を実現し、衝撃\n率の増加を実現する技術(乙59の8)
10) パルスユニットの部品の摩耗により生じた粒子を除去するための磁石を備え、 さらなる摩耗等を防ぎ、メンテナンス軽減を実現する技術(乙59の9) そのほか、コントローラである Power Focus 6000 及びソフトウェアにより多種\n類のツールを接続し、作業内容に合わせたコントロールが容易であるという特徴は、 被告カタログ等において、前記記載以外にもページを費やして強く訴求されている (乙58、85)。
(b) 衝撃発生部が油圧パルス発生部である電動式衝撃締め付け工具において、 アウタロータ型電動モータを採用するという本件訂正発明は、電動式衝撃締め付け 工具の基幹部分であるモータに関する発明であり、インナロータ型電動モータが採 用される場合と比較して、小型、軽量、低反力、耐久性実現の作用効果を有する点 で、相当の技術的価値があるといえる。実際に、被告製品のモータを本件訂正発明 の技術に属しない構造に変更するにはモータの構\造等を変更する必要があり、その 場合には製品全体の構造や技術を見直す必要があり、この点からの代替技術が採用\nされる可能性が高いとはいえない。\nもっとも、本件訂正発明の作用効果である「小型、軽量、低反力、耐久性」を実 現する技術及び被告製品で訴求される各特徴を実現する技術は、アウタロータ型電 動モータ以外にも存在する。被告製品においてアウタロータ型電動モータを採用し たことによる作用効果は、被告カタログにおいて訴求されている「高トルク」、「低 反力」及び「メンテナンス軽減」に関連し得るが、前記(a)のとおり、被告カタログ では、「高トルク」を実現する技術として「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、 「高度なモーター制御」が記載されており、実際に、被告が保有し被告製品で採用 されている技術においても実現されていると認められる。 そのほか、前記(a)のとおり、被告製品には、本件訂正発明以外にも多数の技術が 使用され、当該技術による作用効果が被告カタログにおいて被告製品の特徴として 記載されており、需要者に強く訴求されていることが認められる。
(c) したがって、被告製品は、本件訂正発明及びその作用効果以外にも、種々の 技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が、需要者の購入動機\nの形成に相当程度寄与していると認められる。被告製品が多彩な機能を有し、これ\nが顧客誘引力に寄与していることは、被告製品が、対応する原告製品よりも総じて ●(省略)●であるという価格差にも裏付けられているといえる。 (d) 以上より、被告製品の性能に係るこれらの事情は、特許法102条2項に基\nづく推定を、相当程度覆滅する事由であると認められる。
d 本件訂正発明は被告製品の一部のみに使用されていること
前記1(2)のとおり、本件訂正発明は、インナロータ型電動モータを搭載した従来 の電動式衝撃締め付け工具の有する課題を解決するため、出力トルクが大きいアウ タロータ型電動モータを採用し、小型及び軽量で、低反力かつ耐久性を有する電動 式衝撃締め付け工具を提供するというものであり、被告製品の特徴とされる「高ト ルク、低反力、メンテナンス軽減」(前記c(a))の作用効果の実現に使用されてい るといえるが、前記cで検討した諸事情からすれば、それらの作用効果は、本件訂 正発明のみによって実現されているとはいえない上、被告製品が備える種々の性能\nの一部にすぎないことが認められる。したがって、本件訂正発明が被告製品の一部 のみに使用されていることは覆滅事由に該当する。ただし、覆滅の基礎となる事情 は前記cの事情と重複することから、推定覆滅の程度の検討に当たっては被告製品 の性能を理由とする推定覆滅と実質的に重なるものとして評価するのが相当と解さ\nれる。
e 本件訂正について
本件訂正は、衝撃発生部について、油圧パルス発生部に限定するものであり、被 告製品における発明の作用効果やその実施に影響を与えるものではないこと等を踏 まえると、本件訂正の事実を覆滅事由として認めることは相当でない。
(ウ) 推定覆滅の程度
以上のとおり、本件においては、一定数の競合品の存在、被告製品の性能及び本\n件訂正発明が被告製品の一部のみに使用されていることを理由とする推定覆滅が認 められ、前記(イ)のとおりの事情を総合的に考慮すると、6割の限度で損害額の推定 が覆滅されるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はい ずれも採用できない。
(エ) 以上から、特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額は、被告製 品ごとに、別紙損害一覧表(裁判所認定)の表\1及び表2の各「2項損害額」欄記\n載のとおりとなる。
イ 特許法102条3項の重畳適用について
(ア) 特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第 三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、 侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為が なければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸 失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解され る。 そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該 推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき は、同条3項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆 滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超える\nこと以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情がある ことを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下におい て、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと 解される(知的財産高等裁判所令和4年10月20日特別部判決参照)。
(イ) これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは 競合品の存在、被告製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明が被告製品の\n一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力\nを超えること以外の理由により特許権者が販売等をすることができないとする事情 があることを理由とするものである。
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵 害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された 蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実 施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることが できたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明 の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用している\nと認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構\を有していると認め られるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪 失したとはいえない。
また、被告製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明は被告\n製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、被告製品 の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるもので あり、このような特許発明が寄与していない部分について、原告が実施許諾をする ことができたとは認められない。 したがって、本件においては、特許法102条2項による推定の覆滅部分につい て、同条3項の適用は認められない。
ウ 特許法102条3項に基づく損害額
(ア) 実施料率
本件訂正発明について実施許諾契約がされた事実はない(弁論の全趣旨)。 また、証拠(甲32、33)及び弁論の全趣旨によれば、平成15年9月20日 に社団法人発明協会が発行した「実施料率〔第5版〕」において、「金属加工機械」 の技術分野における平成4年度〜平成10年度の実施料率の平均値についてイニシ ャル有りが4.4%、イニシャル無しが3.3%であること、同様の最頻値が5%、 3%、中央値が4%、3%であること、平成22年8月31日に発行された経済産 業調査会が発行した「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プ ログラム著作権・技術ノウハウ〜」において、「成形」の技術分野における実施料 率の平均値が3.4%であることが認められる。これらに、原告と被告とが競業関 係にあること、本件訂正発明の内容、重要性、代替可能性、被告製品の売上に対す\nる貢献の程度のほか、本件訂正により特許請求の範囲が減縮されていること等本件 に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件における実施に対して受けるべき料率 としては、4%が相当であると認める。これに反する原告及び被告の主張はいずれ も採用できない。
(イ) 以上から、特許法102条3項に基づき推定される損害額は、被告製品ごと に、別紙損害一覧表(裁判所認定)の表\1及び表2の各「3項損害額」欄記載のと\nおりである。
エ 原告の損害額
(ア) 原告は、被告製品の型番ごとに、平成29年7月から令和3年10月の期間 につき、特許法102条2項に基づく損害額と、同条3項に基づく損害額のうち高 い方を選択的に請求していることから、被告製品の型番ごとに認められる損害額は、 別紙損害一覧表(裁判所認定)の表\1の「損害額」欄記載のとおりであり、合計す ると4078万9003円(平成29年7月から令和2年3月31日分までが28 12万1254円、同年4月1日から令和3年10月31日分までが1266万7 749円)となる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2023.05.10
令和4(ネ)10111 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和5年4月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人らは、本件通知書に記載されたキャタピラン+等が本件特許権を侵 害していると考えている旨の見解に関し、仮にこれが不正競争防止法2条1項21 号にいう「虚偽の事実」に該当するのであれば、特許権者としては、特許権の被疑 侵害者を発見した場合であっても、後日裁判所により特許権の侵害はない旨の判断 がされ、損害賠償を命じられるとのリスクを回避するため、被疑侵害者に対し訴訟 提起前に警告書を送付することがおよそできなくなるから、上記の見解が同号にい う「虚偽の事実」に該当するとの判断は誤りであると主張する。
しかしながら、特許権者が特許権の被疑侵害者を発見し、訴訟提起に先立って当 該被疑侵害者に対し警告書を送付したが、後日裁判所により特許権の侵害がない旨 の判断がされた場合であっても、当該警告書の送付が特許権者の正当な権利行使の 範囲内の行為であると評価されるときは、同送付は違法性を欠き、当該特許権者が 同送付を理由として損害賠償責任を負うことはないのであるから、特許権者が被疑 侵害者に対し訴訟提起前に警告書を送付することがおよそできなくなることを前提 とする控訴人らの上記主張は、前提を誤るものとして採用することができない。
(5) 控訴人らは、本件告知行為の違法性の有無に関し、1)控訴人らと被控訴人 との間の紛争の発端は、被控訴人が控訴人Xらとの間で締結した共同出願契約(乙 30の1及び2)における約定(事前の協議・承諾なく本件特許権に関わる製品を 販売した場合には、本件特許権を剥奪できるとするもの)に違反し、単独でキャタ ピラン等の製造・販売を開始したことであること、2)控訴人Xは、本件通知書にお いて、キャタピラン等とキャタピラン+等が別の商品であり、これらが異なる状況 にあることを分かりやすく明記していること、3)本件通知書の記載は、キャタピラ ン+等がキャタピラン等と同様に本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を与えるものではないことを根拠に、本件告知行為の目的は被控訴人の取引先が過 去に販売したキャタピラン等について損害賠償請求をすることであり、同目的が 「裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定したキャタピラン等の存在 を奇貨として、本件特許権を侵害しないように改良されたキャタピラン+等につい ても、裁判所による判断がされる前に、本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控 訴人の取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン+等を早期に「結 ばない靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優 位に立つこと」であるとの認定は誤りであると主張する。
しかしながら、控訴人Xは、本件告知行為をした時点において、被控訴人がその 製造・販売する商品をキャタピラン等からキャタピラン+等に入れ替え、「結ばな い靴紐」の市場においてキャタピラン等の販売が縮小していることを十分に認識し\nていたこと(補正して引用する原判決第4の4(2)イ)、被控訴人は、令和2年1 2月22日、前訴の控訴審判決において命じられたキャタピラン等に係る損害賠償 金(平成28年4月1日から平成30年8月31日までに生じたもの)を支払った ものと認められること(乙7の3、弁論の全趣旨)、キャタピラン等に係る損害賠 償金(平成30年9月1日から令和3年4月30日までに生じたもの)についても、 遅くとも本件告知行為の前までには、その額の確定等の手続が終了し、被控訴人か らその支払がされるのを待つ状況となっていたものと認められること(甲60、7 7、弁論の全趣旨)、控訴人Xは、本件包括協議において、直接又は間接に、被控 訴人が「結ばない靴紐」の市場から撤退することを一貫して求めていたと認められ ること(甲59ないし67、70ないし74)、本件通知書の送付を受けた被控訴 人の取引先は、キャタピラン等と同様にキャタピラン+等についても本件特許権を 侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたこと(補正して引用する原判決第4の 4(2)イ及びウ)、その他、補正して引用する原判決第4の4(1)において認定した 各事実に照らすと、控訴人らが主張する上記1)の事情や本件通知書の記載内容を考 慮してもなお、本件通知書においてされたキャタピラン等に係る本件特許権の行使 等についての言及は、あくまで名目的なものであったといわざるを得ず、本件告知 行為の真の目的は、補正して引用する原判決第4の4(2)イのとおり、キャタピラ ン等と同様にキャタピラン+等も本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控訴人の 取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン+等を早期に「結ばない 靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優位に立 つことであったと認めるのが相当である。
この点に関し、控訴人らは、キャタピラン+等の取扱いを停止した4社のうち2 社(株式会社シューマート及び株式会社チヨダ)は当初本件通知書に対して反論を したのであるから、両社は本件告知行為によりキャタピラン+等が本件特許権を侵 害するおそれがあるとの強い印象を受けたものではないと主張する。確かに、本件 通知書の送付を受けた株式会社シューマートは、「キャタピラン+等が本件発明の 技術的範囲に属するというのであれば、その説明をしていただきたい」旨の回答 (乙A2)をし、本件通知書の送付を受けた株式会社チヨダも、「株式会社チヨダ は、入手済みの弁理士の見解書を踏まえ、キャタピラン+等については本件発明の 技術的範囲に属しないと判断している」旨の回答(乙A6)をしたものと認められ るが、結局、両社は、本件告知行為の約4か月後に、それぞれ本件通知書において 求められたとおりにキャタピラン+等の取扱いを停止したものと認められるのであ り(弁論の全趣旨)、加えて、本件通知書の記載内容も併せ考慮すると、両社が本 件通知書の送付を受けた際に上記のような回答をしたことは、両社において本件告 知行為によりキャタピラン+等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を受けたとの認定を左右するものではない。
また、控訴人らは、キャタピラン+等の取扱いを停止した4社のうちその余の2 社(朝日ゴルフ株式会社及び株式会社Olympicグループ)は控訴人らと被控 訴人との間に紛争が生じていることを理由に、紛争が解決するまでキャタピラン+ 等の取扱いを一時的に停止したにすぎず、キャタピラン+等が本件特許権を侵害す ると認識してその取扱いを中止したものではないと主張するが、本件通知書の記載 内容及び両社が本件通知書の送付を受けた後速やかにキャタピラン+等の取扱いを 停止したものと認められること(弁論の全趣旨)に照らすと、株式会社Olymp icグループの回答書(乙A12)に「キャタピラン等及びキャタピラン+等に関 する控訴人Xと被控訴人との間の紛争が解決するまで、これらの商品の販売をしな い方針である」旨の記載があることを考慮しても、両社は、本件告知行為によりキ ャタピラン+等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたものと 認めるのが相当である。 以上のとおりであるから、控訴人らの主張を採用することはできない。
(6) 控訴人らは、本件告知行為に係る過失の有無に関し、被控訴人の第1主張 書面(本件仮処分の手続において提出されたもの)に記載された本件発明の構成要\n件B1)の「非伸縮性素材からなり」に係るクレーム解釈は特許請求の範囲及び本件 明細書等の記載から大きく外れた荒唐無稽なものであり、同主張書面を見てもキャ タピラン+等が本件特許権を侵害していないと判断することはできなかったから、 本件告知行為について控訴人らに過失はない旨の主張をする。
しかしながら、補正して引用する原判決第4の2及び前記(1)ないし(3)において 説示したところに照らすと、被控訴人が上記第1主張書面においてした主張(本件 発明の「非伸縮性素材からな(る)中心ひも」は「伸縮性素材からなるひも本体と 比較して伸縮性が乏しいもの」をいうところ、キャタピラン+等のひも本体(外層) と中心ひも(芯材)の伸縮性を比較した試験結果によると、キャタピラン+等は本 件特許権を侵害しない旨の主張(補正して引用する原判決第4の4(2)イ))は、 十分な説得性を有する相当なものであるといえ、加えて、補正して引用する原判決\n第4の4(2)イにおいて指摘した各事情も併せ考慮すると、控訴人らは、遅くとも 同主張書面を受領した時点で、キャタピラン+等の製造・販売が本件特許権を侵害 しない可能性が相当程度にあることを容易に認識し得たと認められるから、そのよ\nうな認識可能性があったにもかかわらず本件告知行為に及んだ控訴人らには、過失\nがあると認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2023.05. 2
令和3(ワ)6908 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月30日 大阪地方裁判所
前記本件明細書の記載によれば、本件特許発明は、落下物受取装置の基端部 の縁と足場構築体の作業空間の外側面の間に隙間が生じ小さい物品が落下し\n人体を負傷する危険があり、当該隙間を単純な板材で塞いだ場合には落下物受 取装置を格納する際に板材を取外す必要がある等姿勢変更の作業が困難であ るといった課題に対し(【0008】【0009】)、当該隙間を覆うことができ、 かつ落下物受取装置の姿勢変更等によって隙間が変化する場合でもそれに追 従し確実に隙間を塞ぐことができる隙間遮蔽装置を提供するものである(【0 014】【0038】)。本件明細書には、本件特許発明の実施例として、隙間遮 蔽装置は、固定部材を落下物受取装置の基端部に取付一体化した構成とする場\n合と、落下物受取装置に後付けされるユニットを構成する場合とを挙げており\n(【0016】)、後付け可能かつ着脱自在の隙間遮蔽装置の実施例の一つ(ユ\nニット20a)として、固定部材に枢結手段を介して遮蔽部材を回動自在に連 結するものが記載されている(【0039】【0040】【0043】)。 このような固定部材に枢結手段22を用いて遮蔽部材を回動可能に枢結す\nる方法は、本件明細書上、「図4に示す1実施形態において」(【0039】)、 「図示のようにユニット20aを構成する場合は」(【0043】)と記載され\nているとおり、後付けユニットタイプの隙間遮蔽装置の一実施例という位置付 けで記載されているに過ぎない。また、本件明細書には、固定部材の大きさ及 び形状並びに落下物受取装置への固定方法については適宜の方法を採用する ことができることが示唆されており(【0040】)、その余の本件明細書の記 載を見ても、「固定部材(21)」が、特定の構成を備えるべきものであるとか、\n枢結手段が、固定部材(21)と別途独立のもの(部材)であることが前提で あることをうかがわせるとかの旨の記載はない。 したがって、本件特許発明における「固定部材(22)」とは、実施例のよう に固定部材とは別の枢結手段が存在する場合に限らず、固定部材が枢結手段と 一体のもの、一つの部材が固定部材と枢結手段を兼ねるものなどもこれに当た ると解される。
むしろ、枢結手段が固定部材から独立して存在すること(独立した部材であ ること)等が要求されていないとの解釈は、上記のとおり実施例の一つとして 挙げられた固定部材に遮蔽部材を枢結する「蝶番」について、「枢結部材」では なく「枢結手段」と記載されていることと整合するといえる(【0039】【0 043】)。 なお、構成要件Cないし同Fには「固定部材(21)」として符号が記載され\nているものの、これは請求項の記載内容を理解するために補助的に付されたも のであると解され(特許法施行規則24条の4及び様式29の2の〔備考〕1 4のロ)、それ以上に本件特許発明における固定部材の構成を符号により特定\nされる実施形態に限定するものであると解すべき事情も見当たらない。 したがって、本件明細書の記載を参酌しても、本件特許発明において、上記 (1)のとおり、1)落下物受取装置の基端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成す\nる部材であること(構成要件C)、2)(隙間遮蔽装置使用時に)固定部材から足 場構築体に向けて遮蔽部材が延びていること(構\成要件D)、3)遮蔽部材が回 動自在に枢結されていること(構成要件E)、4)(隙間遮蔽装置不使用時に)遮 蔽部材が固定部材に向けて回動することにより固定部材の上に重ねられるこ と(構成要件F)という要素を充たせば「固定部材」(構\成要件C〜F)に相当 する部材であるといえ、これに加え、枢結手段とは独立して存在することを要 するものではないと解すべきである。
(4) 被告製品における「蝶番(の第1翼片)」が本件特許発明の「固定部材」に 相当するか(あてはめ)
別紙被告製品説明書のとおり、被告製品における蝶番は、第1翼片、第2翼 片及び回転軸から成り、第1翼片(図3右側のもの)が落下物受取装置の基端 部にリベット等で固着され、第2翼片(図3左側のもの)が遮蔽部材に固着さ れている。これにより、被告製品の蝶番の第1翼片は、1)落下物受取装置の基 端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成する部材であること(構\成要件C)、2) (隙間遮蔽装置使用時に)固定部材(第1翼片)から足場構築体に向けて遮蔽\n部材が延びていること(構成要件D)、3)遮蔽部材が回動自在に枢結されてい ること(構成要件E)、4)(隙間遮蔽装置不使用時に)遮蔽部材が固定部材に向 けて回動することにより固定部材の上に重ねられること(構成要件F)という\n要素を全て充たしているといえ、本件特許発明の「固定部材」に相当する部材 であるということができる。
被告は、このように解すると構成要件Fの構\成及びその構成の作用効果の説\n明と矛盾する旨主張するが、保管・運搬に便利となるとの作用効果は、遮蔽部 材を回動自在に枢結することによりもたらさせるものであって、固定部材の構\n成に由来するものではないから、その主張は失当である。 したがって、被告製品は、構成要件Cないし同Fを充足しており、構\成要件 A、同B、同Gを充足することは争いがないから、本件特許発明の技術的範囲 に属する。
・・・
(2) 推定覆滅事情
被告は、本件特許発明は、製品の一部のみに実施されるものであること、被 告製品には他の顧客誘引力がある一方、本件特許発明に顧客誘引力が乏しいこ と、本件特許発明以外の特許発明の実施や被告商品に付された商標が顧客誘引 力を持つことから、上記損害額の8割は推定が及ばないものと主張する。
ア 本件特許発明の意義
前判示のとおり、本件特許発明は、建設現場等で高所からの工具等の落下 による負傷等を防止するために設置される落下物防止装置(朝顔)において、 「落下物受取装置は、…該落下物受取装置の基端部の縁と、足場構築体の作\n業空間の外側面の間には、狭小な隙間を生じることが不可避である。このた め、…小さい物品が落下すると、前記隙間を通過することにより地上に向け て落下するおそれがあり、金属製等の落下物の場合、微小な物品であっても 人体を負傷する危険がある。」等の課題に対して、隙間(S)を覆う隙間遮蔽装 置を設け、前記隙間遮蔽装置は、前記落下物受取装置の基端部に固定される 固定部材と、該固定部材から足場構築体に向けて延びる遮蔽部材を備え、前\n記固定部材に対して前記遮蔽部材を回動自在に枢結しており、前記遮蔽部材 は、不使用時に前記固定部材に向けて回動することにより、該固定部材の上 に重ねられるように構成することにより該課題を解決するものである。\n この点、証拠(甲3、4(枝番を含む))及び弁論の全趣旨によると、被告 製品における遮断板によって遮蔽される隙間は、足場の設置態様によっては 相応に幅が広いものも想定され(少なくとも被告主張のような傷害結果が生 じることが極めて稀な小さなもののみが通過する隙間に限られないと認め られる。)、被告製品においても、朝顔において隙間を塞ぐことが重要な意義 を有するものと扱われていることが認められるのであって、本件特許発明は、 これを効果的に行うものとしての技術的意義を有し、実施品の顧客誘引力を 高めるものであると認められる。
イ 他方、朝顔の性能としては、被告主張のとおり、上部から外方への落下物\nを直接受け止める部分であるパネル部分(本件特許発明でいう落下物受取装 置)の性能が重要であろうことは商品の性質上当然であり、被告が、本件特\n許発明以外の特許を実施している点を指摘するのも、この趣旨をいうものと 理解することができる。また、作業効率性、美観性といった被告製品の他の 要素も顧客誘引力に相応に寄与することも理解できるところである。もっと も、被告商品2に付された被告商標については、これについて特段の顧客誘 引力があることをうかがわせる証拠はないため、本件において考慮すること は困難である。また、本件特許発明が製品の一部に実施されているという主 張は、落下物受取装置が遮断板に向かって傾斜を持った態様で運用されるこ とからすると、同装置で受け取られた落下物は遮断板に至り、遮断板によっ て更に下方への落下が阻止されることになるのであって、このように、遮断 板と一体となって落下物の下方への落下が防止されるという被告製品の構\n成からすると、本来的な意味で特許技術が製品の一部にのみ実施されたもの であるということはできない。なお、被告は、本件特許発明は、遮蔽部材を落下物受取装置の基底部に回動可能に固定することのみを特徴としている旨主張するが、抽象的には遮蔽部材を設置して隙間を塞ぐ構\成は他に考え得る趣旨をいうものと解したとしても、その具体的な競合品等に関する主張立証はされていないから、これを推定の覆滅に当たって考慮することは困難である。
ウ 本件において、イに述べた事情はあるものの、被告が指摘する事情はなお 同種の商品一般の顧客誘引力の重点の置き方を指摘するものにとどまって おり、これらの事情を特許法102条2項による推定を覆滅させる事情とし て重く見るのは相当でなく、総合的にみると、(1)で推定される原告の損害 のうち、3割の限度ではその推定の覆滅の立証があったものというべきであ る。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2023.04.15
令和4(ネ)10073等 特許権侵害損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエ アロゾルを発生させる方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が、被控 訴人らに対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイスである原判決別紙物件 目録記載の被告製品(被告製品1〜3)の販売、輸出、輸入及び販売の申出をする\nことが本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為(民法709条)に基づき、 選択的に、1)特許法102条2項の損害額●●●●●●●●●円(同項の推定の覆 滅が認められた場合に当該覆滅部分について予備的に同条3項に基づく売上額の2\n0%相当の損害額)又は2)同条3項の損害額●●●●●●●●●円を請求するとと もに、3)弁護士・弁理士費用相当額●●●●●●●●円(上記1)の同条2項の損害 額の1割に相当する額)を請求するものとして、●●●●●●●●●円及びこれに 対する不法行為の後であり被控訴人らへの各訴状送達の日の翌日である令和2年3 月10日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5 分の割合による遅延損害金の連帯支払を原審で求めた事案である。
(2) 原審は、1)特許法102条2項による被控訴人らが受けている利益の額は3 706万0935円と推定されるが、被告製品の売上げにはそれらが別件発明の実 施品であることも貢献しているため5割の推定覆滅を認めるのが相当であり、同項 の損害額は1853万0467円となる(また、上記の覆滅の理由からして上記覆 滅部分についての同条3項の適用は認められない。)とする一方で、2)実施料率は 10%を下らないものと認めるのが相当であり、同条3項の損害額は1975万2 707円となるところ、より高額である上記2)の損害額をもって控訴人の損害額と 認め、これに弁護士・弁理士費用としてその1割である197万5270円を加え た2172万7977円及びこれに対する前記遅延損害金の連帯支払を被控訴人ら に求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却 した。
・・・・
(c) 同じくAmazon seller centralに係る手数料等について、控訴人は、令和元 年7月のFBA運搬費は異常に高額であり、少なくとも本件FBA配送代行手数料 ●●●●●●●●円は控除されるべきものではないなどと主張する。
そこで検討するに、証拠(甲10、甲A38、44、甲46、47、51、52、 53の1〜4、54の1〜5、甲55、62、乙25、26)及び弁論の全趣旨に よると、1)令和元年7月分のAmazonのFBA手数料(Amazon FBA/handling charge) は●●●●●●●円、FBA運搬手数料(Amazon FBA/haulage express)は●●● ●●●●●円であったこと、2)平成30年7月から令和元年12月までの期間中、 FBA運搬手数料又はこれに相当し得るとみられる費用は、平成30年11月から 令和元年9月までの間において計上されているところ(ただし、平成30年11月 及び12月においては「Amazon /FBA haulage handling charge」である。)、同年 11月分及び12月分は●●●●円程度、平成31年1月分は●●●●円余りであ ったものの、同年2月分から同年(令和元年)6月分まではいずれも●●●●円に 満たない額となっていたにもかかわらず、同年7月分として上記のとおり急激にそ の額が増大し、その後、同年8月分として●●●円余り、同年9月分として●●● 円余りが計上された後、同年10月分以降は、FBA手数料とともにゼロ円となっ たこと、3)同年4月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少し、同年5月において、「商品評価損」●●●●●●●円の計上と 「期末商品棚卸高」●●●●●●●●円の計上により、「商品」が●●●●●●● ●円増加し、同年6月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少したこと、4)同年7月30日及び同月31日の2日間に、「Fjp20190724PATENT-14」などの符号(末尾の数字のみ、3〜17の範囲で異なっている。) のある一律●●●円のFBA配送代行手数料(FBA Per Unit Fulfillment Fee)が ●●●●件計上され、その合計額は●●●●●●●●円に上ったこと(本件FBA 配送代行手数料)、5)同月におけるFBA配送代行手数料の支出において、そのよ うに同一の符号をもって一律の金額で同時期に多数のものが計上されている例は、 他に認め難いこと、6)控訴人は、別件仮処分決定に係る特許権侵害差止仮処分申立\n事件(東京地裁民事第29部にて審理)において、令和元年7月11日付けで、被 控訴人アンカーに対する申立てを取り下げ、その後、同月25日、別件仮処分決定\nがされたこと、7)控訴人は、別途、被控訴人らを債務者として、特許権侵害差止仮 処分命令の申立て(東京地裁平成30年(ヨ)第22123号(東京地裁民事第4\n0部にて審理))をしていたところ、当該事件で、被控訴人らは、令和元年9月3 0日付けの準備書面をもって、被控訴人ジョウズにおいては同月末までに被告製品 全ての在庫がなくなる予定であることから、保全の必要性がない旨を主張し、その\n後、それを疎明する資料として、被控訴人ジョウズが同月にAmazonに対し被告製品 の所有権放棄の依頼をしたことを示す書面を提出した上、同年11月5日付けの準 備書面をもって、保全の必要性がない旨を改めて主張したことが認められる。
前記1)〜7)の事情(なお、前記4)について、「20190724PATENT」の符号は、令和 元年7月24日付けのもので、特許に関連するものであることを強くうかがわせる ものである。)のほか、AmazonのFBAサービスに係る証拠(甲53の1〜4。余 剰在庫の管理等のために、Amazonフルフィルメントセンターに保管されている在庫 について、出品者、出品者の倉庫、仕入れ先又は販売業者に返送したり、その所有 権を放棄したりする旨を依頼するサービスがあることなどが記載されている。)や、 配送手数料等についてはその対象となる行為が行われた後に請求がされるのも合理 的であると解され、本件FBA配送代行手数料が平成31年(令和元年)4月ない し6月の在庫に係る会計上の処理と関連している可能性があることなども考慮する\nと、本件FBA配送代行手数料●●●●●●●●円については、別件仮処分決定の 発令に関連して、また、前記7)の仮処分命令申立事件に対する対応やその準備等の\nために、大量の被告製品について一律に、通常の販売とは異なる特別の取扱いがさ れたことから発生したものであることが強く推認され、この推認を覆すに足りる事 情は見当たらない。
したがって、Amazon seller centralに係る手数料等のうち、本件FBA配送代行 手数料●●●●●●●●円については、被告製品の販売に直接必要となった経費と して控除すべきものではなく、控除が認められる支払手数料額は●●●●●●●● ●円となる。
上記に反する被控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。なお、被 控訴人らは、当審で追加された特許法102条3項の損害に係る控訴人の主張に対 し、前記3)の商品評価損については、令和元年の期末の商品評価損調整でゼロとす る仕訳を行ったなどと主張するところ、そのような事実を認めるに足りる証拠はな いものの、仮に、そのような事後的な調整の事実があったとすれば、そのことは、 本件FBA配送代行手数料の支出が被告製品の販売とは直接関係なくされたもので あるとの前記推認を裏付けるものであるとみることができる。
◆判決本文
原審はこちら
◆令和2(ワ)4332
関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求
◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円
◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2023.04.11
令和2(ワ)27972 特許権侵害損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月22日 東京地方裁判所
本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」(構成要件1D、1E\n等)について
本件各発明の特許請求の範囲には、「前記拡散レンズを複数のレンズ部か ら形成し、各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並 設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、 光の経路と交差する所定の面上に並ぶように配置し、前記各レンズ部を、互 いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異 なるように形成したことを特徴とする」(構成要件1D〜F)と記載されて\nいる。
これらによれば、本件各発明の照明装置の拡散レンズは、複数のレンズ部 から形成されていて、各レンズ部の各LEDの並設方向への曲率半径と、各 LEDの並設方向と直行する方向への曲率半径を比較することができるので あり、また、各レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なると いうというのであるから、本件発明のレンズ部は、拡散レンズにおいて、そ こに形成されているという複数のレンズ部のそれぞれのレンズ部について、 その位置、形状が特定された上で、それぞれのレンズ部(各レンズ部)につ いてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向 への曲率半径を把握することができるものであると理解するのが自然なもの である。
・・・
これら本件明細書の記載をみても、本件各発明の実施形態として記載され ているものは、本件発明の拡散レンズにあるという複数のレンズ部(各レン ズ部)のそれぞれのレンズ部について、その位置、形状を特定した上で、そ れらのレンズ部についてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設 方向と直交する方向への曲率半径を把握することができるものであるといえ る。それぞれのレンズ部については、一方向に異なる曲率を有する複合曲面 を有するものも含まれるものの、その場合でも、そのレンズ部が特定された 上で、そのレンズ部に求められる機能を考慮し、そのレンズ部についてある\n方向において曲率半径(RY)を有するものとしている。そして、本件明細 書において、それぞれのレンズ部の位置、形状等が特定されないことを前提 とする記載はない。
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件各発明の 拡散レンズは、それぞれについてその位置、形状が特定される複数のレンズ 部を有するものであり、そのそれぞれのレンズ部についてのLEDの並設方 向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握す ることができるものであるといえる。そして、特許請求の範囲及び本件明細 書の記載からも、本件各発明は、拡散レンズにおいてそのような各レンズ部 を有する発明について、前記1(2)のような効果を奏するという技術的意義を 有するものと認められる。
(2) 各被告製品において使用されているLSD(もっとも、各被告製品に実際 に使用されている各LSDの種類や具体的構成は明らかではない(前記2(2)、 (4))。)について検討する。各被告製品におけるLSDは、拡散レンズの機能を有するフィルム表\面の 構造体である数十\μm程度の微細な凹凸が、シームレスかつランダムに、す なわち継ぎ目なく不規則に配置されたものであり、かつ、凹凸の部分の個々 の大きさや形状を規定して作成されているものではなく、統計的に評価して フィルム全体として入射光を所定の角度で拡散する性能を有するように設計\nされているものである(同(1)〜(3))。
すなわち、各被告製品におけるLSDは、フィルムの表面に微細な凹凸の\n構造体を有し、それらが凸レンズと凹レンズがシームレスかつランダムに配\n置されたマイクロレンズアレイとして機能し、それぞれの微細な凹凸の構\造 体によって光がランダムに広げられるが、それらが重なり合うことによって、 統計的に評価して、フィルム表面全体が所定の性能\を有する拡散レンズとし ての機能を有するものである。そして、各被告製品におけるLSDがこのよ\nうなものであるところ、そこにおいて、前記(1)のとおりの本件各発明におけ るそれぞれの「レンズ部」を把握することは困難なものといえる。そして、 原告は、各被告製品について、その断面図の例を示すところ、その各例にお いても、別紙原告の示す例のとおり、LSDの表面は境目なく不規則に様々\nな形状の凹凸が連続しており、本件各発明におけるそれぞれの「レンズ部」 を把握することができない。 原告は、原告の示す各例において、LSDの表面の部分的に突出した複数\nの部分等はそれぞれレンズとして作用するから、それぞれが1つの「レンズ 部」であり、「複数のレンズ部」を備えることを主張する。しかし、前記(1) のとおり、本件各発明の「レンズ部」は、それぞれのレンズ部の位置、形状 が特定されるものであって、本件各発明は拡散レンズにそのような「レンズ 部」を有するものにより前記1(2)のような効果を奏するといえるものである ところ、原告の示す各例においても、上記のようなそれぞれのレンズ部(各 レンズ部)について、その位置、形状を具体的に特定するものではない(前 記第2の2(1)(原告の主張)イ、別紙原告の主張する凸部の例)。
以上によれば、各被告製品に使用されているLSDの形状によれば、各被 告製品において、本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」(構成\n要件1D、1E等)にいうそれぞれの「レンズ部」の範囲を特定することが できないものであって、各被告製品は本件各発明にいう「各レンズ部」を有 するということはできず、それぞれのレンズ部についてのLEDの並設方向 への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握する ことができず、各被告製品は、本件各発明の曲率半径についての構成(構\成 要件1E、1F)を充足するともいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.04.11
平成30(ワ)10590 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月20日 大阪地方裁判所
◆本件特許
(7) 原告が販売することができないとする事情
ア 競合品の存在
被告が競合品であると主張する製品のうち、アツギが販売する「大人のス
ポパン」(乙60の2の1)、イーゲートが販売するショーツ(乙60の4の
1)、ワコールが販売する「すそピタショーツ」(乙61の1)、千趣会が販売
するショーツ(乙61の2、61の3)及びグンゼが発売する「超立体ぴっ
たりフィットショーツ」(乙61の5)は、脚口(裾口)ないし臀部部分が立\n体的な構造であり、脚口(裾口)部分のずりあがりが防止されることなど本\n件各特徴に相当する作用効果を有することを特徴とする商品であるといえ、
価格帯も、ワコールが販売する製品を除き、概ね同一であり、競合品である
と認められる。ワコールが販売する製品は、3000円前後と原告製品より
も高額であるものの、同社が女性用下着メーカーとして有名でありその商品
に高いブランド力があると認められること等を踏まえると、なお競合品に含
まれるといえる。
したがって、原告製品と被告製品とが販売される市場において、原告製品
と競合する製品が複数存在することが認められ、かかる競合品の存在は、原
告が販売することができない事情に該当するといえる。
もっとも、原告製品のうち、220番製品及び420番製品は、楽天市場
内の「ボックスショーツ」で区分される製品のランキングにおいて、平成2
5年5月15日から令和元年7月7日までの長期間にわたり連続1位を獲
得している(甲50、73)等、原告のブランドは需要者に相応に知られて
おり、かつ需要があると認められることを踏まえると、競合品の存在を理由
とする覆滅の程度が大きいとまではいえない。
イ 被告製品固有の特徴
証拠(甲3〜8、23、24、)によれば、被告製品は、本件各特徴に加え
て被告各特徴(1)ウエスト・脚口にはゴムを使用せず、2)綿の中でも、繊維
長が長く、吸湿性が高く、やわらかい風合い等の特徴を持つスーピマコット
ンを使用し、3)各パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たらない仕様であり、
4)品質表示を記載するタグをタグから製品本体に転写してプリントする方\n法に変更していること)を備えており、かつ当該被告特徴について、本件各
特徴に次いで、需要者に訴求されていることが認められる。
また、証拠(甲48〜50)及び弁論の全趣旨によれば、原告製品は、1)
少なくともウエスト部分にゴムを使用し、2)スーピマコットンは使用されて
おらず、3)パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たる仕様であり、4)品質表示\nを記載するタグが付けられていることが認められる。
原告商品及び被告商品は、余多ある女性用ショーツの中で、装飾的な意味
でのデザイン性よりも、履き心地、肌触り等の機能面、実質面を重視した商\n品を購入しようとする需要者を販売対象とした商品であると認められ、その
ような需要者にとって、被告各特徴は、購入動機の形成にそれなりに寄与す
るものであるといえる(乙67)。よって、被告製品が原告製品とは異なる被告各特徴を備えることは、原告
が販売することができない事情に該当すると言い得る。
ただし、被告各特徴に基づく顧客誘引力は、商品の形状・機能に直接かか\nわる本件各特徴と比較すると限定的であると考えられること、被告特徴2)に
ついて、素材それ自体で見れば、被告製品と原告製品のうち220番製品及
び420番製品は綿95%、ポリウレタン5%と同一であり、その余の原告
製品も綿92%、ポリウレタン8%と大差がないこと、被告特徴4)について、
本件対象期間中に販売された被告製品の一部はタグ付きである可能性があ\nること(甲40)等をふまえると、その覆滅の程度は限定的に解すべきであ
る。
ウ ハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品にない、ウエスト丈がハイウエストのもの(被告
製品3−1及び3−2。ハイウエストタイプ)が存在し、当該ハイウエスト
タイプの存在が、原告が販売することができないとする事情に該当すること
は争いがない。被告製品のうちハイウエストタイプは、被告製品の販売数量合計●(省略)
●のうち、●(省略)●であり、約26.8%である(計算鑑定の結果)。
被告製品においてハイウエストタイプを好む需要者が一定程度存在する
と認められることを踏まえると、被告製品にのみハイウエストタイプが存在
するという事情は、特許法102条1項1号に基づく推定を一定程度覆滅す
るものと認められる。
エ 販売価格
証拠(甲3〜8、48〜50、75)によれば、原告のウェブサイトで販
売される107番製品(ローライズ丈)及び407番製品(普通丈)の販売
価格は2500円(税込)、楽天市場で販売される220番製品(セミ丈)及
び420番製品(普通丈)の販売価格は1500円〜1520円(税込)で
あるのに対し、被告製品の一般向けの販売価格はレギュラー丈(被告製品1
−1及び1−2)が1080円(税抜)、ショート丈(被告製品2−1及び2
−2)が平均980円(税抜)、ハイウエストタイプ(被告製品3−1及び3
−2)が平均1280円(税抜)であると認められる。なお、原告製品のロ
ーライズ丈及びセミ丈と被告製品のショート丈、原告製品の普通丈と被告製
品のレギュラー丈が、それぞれ対応関係にある。
同種かつ同程度の機能等の製品相互間で価格が顧客誘引力に影響を与え\nること、これが女性用下着一般及びその中でも原告商品及び被告商品の想定
需要者層に妥当することは明らかである(乙67)。原告商品の販売数量を
見ても、価格以外の要素があり得るといえるものの、高額(2500円)の
407番製品及び107番製品の販売数量が●(省略)●枚、●(省略)●
枚であるのに対し、低価格(約1500円)の220番製品及び420番製
品が●(省略)●枚、●(省略)●枚と非常に高い比率を占める(計算鑑定
の結果)。
もっとも、販売量の多い220番製品及び420番製品と、被告製品(ハ
イウエストタイプを除く)の価格差は、420円〜540円であり、両製品
の価格帯自体が1000円〜1500円程度の範囲であること等を踏まえ
ても、その差が大きいとはいえず、顧客誘引力に大きな影響を及ぼすとまで
はいえない。したがって、被告製品が原告製品よりも低価格であることは、原告が販売
することができないとする事情に該当するといえるものの、当該事情を理由
として推定された損害が覆滅される程度は高いとは言えない。
オ 被告の営業努力
特許権者等が販売することができない事情として認められる侵害者の営
業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力を行い、製品の購買
動機の形成に寄与したと認められるものをいうところ、被告指摘の事情を勘
案しても、このような事情には該当しない。
カ 本件発明の技術的意義が被告製品の利益に貢献する程度
被告は、構成要件Dの「腸骨棘点付近」について、上前腸骨棘を中心とし\nつつ下前腸骨棘付近を含むものと解釈した場合、仮に被告製品が構成要件D\nを充足するとしても、本件発明の作用効果を奏さないため、被告製品に対す
る本件発明の寄与度が零であると主張する。
しかし、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近を含む場合でも本件発明の作
用効果を奏するものであることは前記2(1)のとおりであるから、被告の主
張は採用できない。
キ 実際の着用状態からみた本件発明の貢献度
被告は、一定以上の割合の被告製品については、需要者が着用した場合に
身体的個体差等の影響により着用状態において本件発明の技術的範囲に属
しない場合があり得、当該事情をもって原告が販売することができないとす
る事情に該当と主張する。
しかし、被告製品は、その設計時に想定された着用状態において、本件発
明の技術的範囲に属するものであり、実際の個別具体的な着用状況において、
被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置しない場合
があることをもって販売することができない事情が存すると解することは
相当でない。
ク 推定覆滅の割合(まとめ)
以上によれば、本件においては、競合品の存在、被告製品が被告各特徴を
有すること、ハイウエストタイプが存在すること及び原告製品よりも低価格
であることについて原告が販売することができない事情に該当すると認め
られ、前記イで認定した事情を踏まえると、当該事情に相当する数量は、全
体の15パーセントであると認めるのが相当である。
・・・
証拠(甲11、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の実施に対し
受けるべき実施料率は6パーセントと認めるのが相当である。
なお、被告は、原告がそのウェブサイトにおいて本件特許権侵害に基づく
訴訟を被告に提起し、徹底的に争う旨の意思表明をしていることから、ライ\nセンスの機会を自ら放棄したとして、特許法102条1項2号が規定する
「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しく
は通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」に該当し、同号
に基づく実施料相当額の損害は認められない旨主張する。
しかし、被告が主張する事情は、原告の被告に対するライセンスの機会の
喪失を否定する事情に該当するとはいえず、同号の括弧書に該当する場合で
あるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 102条1項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.03.24
令和4(ネ)10087 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 業界における実施料等の相場について
ア 一審原告は、前記第2の4(4)ア aのとおり、原判決が、甲55報告書 の例外的事象における実施料率を理由に、電気等の分野の実施料率の平均 値を採用しなかったのは不当である旨主張する。 しかし、原判決は、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となると いう甲55報告書の指摘に着目して、電気等の分野の実施料率の平均値を 採用しないとしたのであり、その判断は首肯できるものである。 イ 一審原告は、前記第2の4(4)ア bのとおり、乙13陳述書における実 施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙13陳述書は、具体 的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示したものと 理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を吟味する必要 があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や分割出願制度等を 利用した出願を全てまとめて1パテントファミリーとして、パテントファ ミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、1件当たりのライセンス 料率が過少にならない工夫をしていること等に鑑みると、その信用性が否 定されるべきものとはいえない上、そもそも原判決は、乙13陳述書にお ける料率をそのまま採用しているのではなく、その他の各種事情を総合勘 案した上で、料率を決定しているのであるから、一審原告の主張は採用で きない。
(2) 代替品の不存在について
一審原告は、前記第2の4(4)ア のとおり、本件訂正発明によらずに、 本件訂正発明の効果を奏することは経済的に現実的ではなかった旨主張す る。 しかし、これを的確に裏付けるに足りる証拠はないし、その他の各種事 情を総合考慮すると、そもそもこの点のみをもって本件結論が左右すると はいい難いから、一審原告の上記主張は採用できない。
・・・
一審被告は、「本来解像度」の用語の意義について、本件明細書等【00 32】に「「本来解像度」とは「本来画像」の解像度をする。」と定義され ているので、「本来画像」の意義が問題となるところ、「本来画像」の用語 の意義、内容は不明確であるから、本件特許明細書には、構成要件G’にお\nける「本来解像度」の意義を理解するための記載がなく、サポート要件に反 する旨、当審において新たに主張するが、本件明細書等の「本来画像」及び 「本来解像度」に関する関係記載(【0006】、【0032】、【007 9】、【0115】、【0118】、【0119】、【0124】ないし 【0126】、【0128】ないし【0130】等)を総合すれば、当業者 は、「本来画像」及び「本来解像度」が何を意味するかにつき十分に理解で\nきるというべきであるから、本件訂正発明は本件明細書等の発明の詳細な説 明に記載したものといえる。 その他にも、両当事者はるる主張するが、いずれも本件結論を左右し得な い。
第4 結論
以上によれば、一審原告の請求は、主位的請求である不法行為に基づく損害 賠償請求権に基づき819万9458円及びこれに対する令和元年12月13 日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を 求める限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由\nがないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及 び一審被告の控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとお り判決する。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和1(ワ)32239
関連審決取消訴訟事件です。
◆平成28(行ケ)10257
同一特許についての別侵害訴訟の控訴審と1審です
◆令和2(ワ)29604
この事件では、知財高裁は、損害額の算定について以下のように言及されています。
一審原告は、前記第2の3(4)ア aのとおり、甲26報告書の79頁
は、デバイスに関して、クロスライセンスの方式による場合において、
実施料率の相場が1%未満すなわち0.数%であることを示すにすぎ
ないから、原判決のこの点に係る認定には誤りがある旨主張する。
しかし、甲26報告書の79頁によれば、デバイス等においては、製
品が数百ないし数千の要素技術で成り立っていること、互いの代表特\n許をライセンスし合い、実施料率の相場は1%未満であることといっ
た一般的な事情が認められところ、これに加えて、引用に係る原判決
第4の11(3)イ 及び のとおり、一審被告が被告製品の製造販売の
ためにした複数のライセンス契約におけるアプリ特許(標準必須特許
以外の特許)に係るパテントファミリー1件当たりのライセンス料率
は平均●●●●●●●%であり、これを画像処理に関連する発明に限
定すると1件当たりのライセンス料率は、平均●●●●●●●●%と
なること等、本件特有の事情も考慮すれば、原判決の相当実施料率の
認定に誤りがあるとはいえない。
一審原告は、前記第2の3(4)ア bのとおり、ライセンス料は、主
として「代表特許」の価値によって決まるので、乙14陳述書の計算\nにおける標準必須特許を除く「全ての特許の件数で除した1件当たり
のライセンス料率」は不当にディスカウントされたものである旨主張
する。
しかし、乙14陳述書は、代表特許(甲26の79頁にいう「相互\nの代表的な特許」)ではなく、標準必須特許(携帯電話事業分野の標\n準規格の実施に不可欠な特許)と、アプリ特許(通信規格に適合する
ために不可欠とはいえない特許)を分けて扱っているのであり、それ
自体は合理的なことであって、このような方式を採ることが不当なデ
ィスカウントに当たるともいえないから、一審原告の主張は採用でき
ない。
一審原告は、前記第2の3(4)ア cのとおり、乙14陳述書におけ
る実施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。
しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙14陳述書は、
具体的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示し
たものと理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を
吟味する必要があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や
分割出願制度等を利用した出願を全てまとめて1パテントファミリー
として、パテントファミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、
1件当たりのライセンス料率が過少にならない工夫をしていること等
に鑑みると、その信用性が否定されるべきものとはいえない上、そも
そも原判決は、乙14陳述書における料率をそのまま採用しているの
ではなく、その他の各種事情を総合勘案した上で、料率を決定してい
るのであるから、一審原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.03.22
令和2(ワ)19221 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月28日 東京地方裁判所
以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して 製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。
ウ 「その物の生産に用いる物」について 前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属 マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的 範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物 であるといえる。
(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残 存する汚れ自体を、金属マグネシウム(Mg)単体の作用により減少させる ことによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり(【000 6】)、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム(Mg)単体と水と の反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進さ せることを見出し(【0007】)、構成要件1Aの「金属マグネシウム(M\ng)単体を50重量%以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用い る構成を採用したものであると認められる。\n
そして、被告製品は、前記(1)イ(ア)のとおり、構成要件1Aを充足するも\nのであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マ グネシウム(Mg)単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体 を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されている から、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の 課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について ア 特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通している もの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本 国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではな く、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状\n態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。 本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネ ットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をす る旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄 補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグ ネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものがより好ま しく(【0020】)、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウ ムの粒子の平均粒径は、4.0〜6.0mmであることが最も好ましい (【0022】)と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品 は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯 ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗\n濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の 実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規 格品や普及品であるということはできない。 以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通してい るもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構\n成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くと も口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通している ものになったといえると主張する。 しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、 市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡\n等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ま しくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立 法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、 これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に 該当するということはできない。 したがって、被告の主張は採用することができない。
(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請 求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。 そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和2年1月頃までに は、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被 告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和2年4月から 同年7月にかけてレビューを記載した購入者45人のうち、20人の購入者 が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、7人の 購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃ ん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解され る記載をしていることを認めるに足る証拠(甲111)が提出されているこ とからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る 金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品 が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる(当裁判所に顕 著な事実)。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件1Aの「網体」に\nは含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯 を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件 各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。 しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをと るために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編ん で造ったもの。」(広辞苑第7版)の意味もあると認められること、本件明 細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品 は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したもので あるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出 しやすいものとなっている。」(【0023】)、「この網体の素材は、耐水性 があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、 強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエス テル繊維を用いることが好ましい。」(【0024】)、「この網体自体の織り 方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」(【0 025】)と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されてい ないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する 態様による使用方法であることに変わりはないといえる。 したがって、被告が、購入者が構成要件1Aの「網体」には含まれない、\n布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法 が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に 用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> 汎用品
>> 不可欠性
>> ピックアップ対象
2023.03.21
令和2(ワ)3473 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月23日 大阪地方裁判所
ア 本件各発明の技術的意義
本件明細書上、本件発明1には、ブラケットを放熱部に取り付けることに より外装部の変形及び破損を防止すること(本件意義1)及び放熱部製造時 の不良率の低減(本件意義3)があるものと読み取れる。原告はこれに加え、 外装部が放熱部におけるブラケットの接続部分よりも後方に延びている構\n造により、ユーザーが、ブラケットが取り付けられている位置よりも後方の 外装部を掴み、自らの手が照明器具の照射する光を遮らずに、照射範囲を正 確に把握しながら照射方向を変更することを可能とする技術的意義(本件意\n義2)がある旨主張するが、本件明細書に記載はなく、構成要件Hとして追\n加された経緯等をふまえると(甲11の1、14の1)、後付けの感をぬぐえ ず、本件各発明の直接の作用効果としての意義は乏しい。
イ 本件各発明の技術的意義が被告製品の売り上げに貢献する程度等
(ア) 本件意義1について
スポットライト製品一般は、本件特許発明より相当前から市場に存在 し、既に成熟した市場が形成されており(乙5、弁論の全趣旨)、市場動向 調査によれば、スポットライト製品は、演色性や色温度などにおいて高い 付加価値を有する製品の開発が期待されている状況にあり(乙30、3 1)、原告、被告、競合他社のカタログ等において、配光制御・特性、光色、 レンズ設計、省エネ、製品の大きさ、軽さ、デザイン等が訴求されている こともうかがえる(甲5、6、乙15、16、25ないし29) これに対し、外装部の変形及び破損防止という本件意義1は、いわば製 品として当然に担保されるべき機能及び要素であるといえ、また、材質、\nブラケットの取付方法及び取付部分の構造の工夫等、本件各発明以外の技\n術によっても実現可能であり、現に各照明器具メーカーにおいて一般に実\n現している効果であると考えられる。 また、原告は、平成26年以降、原告実施品と同じシリーズ名・製品名 で、ブラケットを放熱部ではなく外装部に取り付け、外装部を厚肉とする ことで外装部の変形及び破損の防止を実現した原告後継品を販売してい る(弁論の全趣旨)。すなわち、本件意義1は、これを欠いても、同一シリ ーズ・製品として顧客に販売することが可能な程度の顧客誘引力しか有し\nないと評価し得る。このことは、カタログに文言上本件意義1が明示され てないとしても、商品の写真から本件意義1に係る特徴を看取できること を考慮しても同様である。
(イ) 本件意義3
本件意義3は、不良率低減という製造コスト削減に寄与するものである といえるが、本件意義3によるコスト削減(製品価格への反映)の程度が 不明であること等を踏まえると、被告製品の利益に対する寄与度が大きい とは認められない。
(ウ) 以上のような事情を踏まえると、本件意義1及び3の顧客誘引力は限 定的であり、本件意義1及び3が被告製品の売り上げに貢献する程度は低 いと言わざるを得ない。
ウ 原告実施品の販売実績等
原告は、本件期間前に原告実施品の販売を開始した後、本件登録日(平成 28年8月5日)以降は在庫品限りとして原告実施品を販売するにとどまっ ており、平成28年以降の原告実施品の販売数は16個である(甲17、1 8)。 このように、原告が本件登録日以降原告実施品を製造しておらず、その販 売方法(販路)等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、原 告が原告後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技 術により本件各発明と同様の作用効果を奏していることは、前記(1)で説示 した特許法102条2項の推定の前提事実を欠くとまでいうことはできな いものの、本件推定を大きな割合で覆滅させる事情というべきである。
エ 競合品の存在
本件期間中、ブラケットが外装部ではなく、放熱部を含む別の部分に取り 付けられているという特徴を有する製品は、パナソニックのTOLSOシリ\nーズ(乙25)、オーデリックのC1000シリーズ(乙27の2ないし27 の4)、三菱電機のAKシリーズ、彩明シリーズ、鮮明シリーズ及びLEDス ポットライトシリーズ(乙29)をはじめ、複数存在する。これらの製品は、 原告実施品及び被告製品と価格帯も概ね同程度である。 以上の事情に鑑みると、被告製品には、競合品が存すると認められ、かか る競合品の存在も推定を覆滅させる事情に当たる。
オ 原告の市場占有率
被告は、スポットライト市場又は店舗用照明市場における原告の市場占有 率が低いとして、被告製品が存在しない場合、その需要の多くが競合他社の 製品へ流れ、原告実施品を販売できたはずであるとはいえない旨主張する。 しかし、被告が主張する原告を含む照明器具メーカーの市場占有率は、ス ポットライトを含む店舗用照明器具市場における機器全般ついてのもので あって、スポットライト以外の幅広い商品群を含むものと解されるから、原 告実施品等との関連が乏しく、推定を覆滅させる事情に当たるとはいえな い。
カ 覆滅の程度
以上の事情、とりわけ本件特許発明の技術的意義や実施品の販売状況を重 視した上総合的に考慮すると、本件においては、被告製品の販売がなかった 場合に、これに対応する需要が原告実施品ないし原告後継品に向かう蓋然性 はむしろ低いとみるべきであって、特許法102条2項により推定された損 害の8割について覆滅されるというべきである。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2023.03. 1
令和2(ワ)13626 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月17日 東京地方裁判所
原告は、1) 本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には、浄化され たスクラバー流体を更に処理することなく、海に放出することを要する との記載はない、2) 本件訂正により、本件特許の【請求項1】の従属項 である【請求項10】を訂正するに当たり、浄化されたスクラバー流体 の品質が所定レベルより低い場合、浄化されたスクラバー流体を分離機 入口に戻す構成を維持しているから、本件発明は、分離機での浄化処理\n後、環境への放出前に、更に浄化処理を行う態様を予定している、3) 本 件明細書の「ディスクスタック遠心分離機をスクラバー流体に適用する ことによって、汚染物質相の大部分が濃縮形態で取り除かれ得る」 (【0014】)との記載によれば、ディスクスタック遠心分離機によ っても分離し得ない汚染物質相が残存し得る以上、補助的にフィルタ等 による分離を行うことは排除されないと主張する。
しかし、上記1)については、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細 書において、浄化されたスクラバー流体を更に処理することなく、海に 放出することを要することを明示した記載は見当たらないものの、前記 (ア)のとおり、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の各記載並びに 原告の本件異議申立事件における主張、さらには、本件明細書には、\n「ディスクスタック遠心分離機」により「浄化されたスクラバー流体」 を更に浄化するための装置を設けることを示唆する記載が見当たらない ことは、いずれも、「浄化されたスクラバー流体を前記第一の分離機出 口から環境に放出するための手段」(構成要件F)とは、「分離機」に\nより「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられた 浄化設備により浄化処理されることなく、船の外側に放出されるなどす るものをいうとの理解をもたらすものであるから、その点を明示する記 載が存在しないからといって、前記(ア)の解釈が左右されるものではない。
上記2)については、前記(ア)bのとおり、本件明細書の記載(【000 8】、【0009】及び【0014】)によれば、本件発明に係る浄化 設備について、「スクラバー流体」の浄化能力を向上させ、また、点検\n修理の必要性を最小とするために、「ディスクスタック遠心分離機」を 使用し、この「分離機」の動作により、「浄化されたスクラバー流体」 が規制を満たすことになり、環境への影響を最小にして環境に解放する ことができ、他の処理をするための設備を設ける必要がなく、機器の点 検修理や交換の必要性を最小にすることができるものであると理解する ことができる。そうすると、本件発明は、「分離機」の動作によって上 記の作用効果を実現するものであるから、「浄化されたスクラバー流体」 を再び「分離機」入口に戻すことを排除するものではないが、「分離機」 により「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられ た浄化設備により浄化処理されて、船の外側に放出されるなどすること を予定したものではないというべきである。したがって、本件訂正後の\n【請求項10】の記載をもって、本件発明が、「分離機」での浄化処理 後、環境への放出前に、別に設けられた浄化設備により更に浄化処理を 行う態様を予定しているということはできない。\n
上記3)については、本件明細書の記載からは、「ディスクスタック遠 心分離機をスクラバー流体に適用することによって、汚染物質相の大部 分が濃縮形態で取り除かれ」(【0014】)た「浄化されたスクラバ ー流体」について、「汚染物質相」が残存するため規制を満たさず、環 境に放出することができないとは直ちには読み取れない。そうすると、 本件明細書の【0014】の記載をもって、「分離機」により「浄化さ れたスクラバー流体」を補助的にフィルタ等により浄化処理することが 示唆されているということはできない。 したがって、原告の上記各主張は、いずれも採用することができない。
イ 小括
以上のとおり、被告製品1(主位的主張)及び被告製品2は、構成要件\nFを充足しないから、その余の点を判断するまでもなく、本件発明の技術 的範囲に属するとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(ネ)10071 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、仮に本件発明7の構成要件Aの「圧力風の作用のみによって」\nの構成は、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移\n送が「圧力風」の「作用」だけで実現されることをいい、「圧力風」の「作 用」以外の作用が加わって上記移送が実現されるものは、「圧力風の作用の みによって」を備えるとは認められないと解した場合には、被告各製品にお いては、「圧力風」の「作用」にブラシの回転作用が加わることによって茶 枝葉が移送ダクト内に送り込まれている点で、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるとはいえず、本件発明7と相違することとなるとしても、被\n告各製品は、均等の第1要件ないし第5要件を充足するから、本件発明7の 特許請求の範囲(請求項7)に記載された構成と均等なものとして、本件発\n明7の技術的範囲に属する旨主張する。
そこで、まず、均等論の第1要件について検討するに、本件発明7の特 許請求の範囲(請求項7)の記載及び前記1(2)認定の本件明細書の開示事 項を総合すれば、従来の茶葉の摘採を行う摘採機は、「刈刃前方側に茶葉移 送のための分岐ノズル付き送風管を配し、分岐ノズルからの送風によって、 刈刃から収容部まで茶葉を移送するのが一般的であり、その移送路は、刈刃 のほぼ後方に延びる水平移送部と、その後に収容部の上部に臨むように接続 された上昇移送部を具えていたが、このような移送形態(送風形態)では、 水平移送部を要する分、移送装置、ひいては摘採機の前後長が長くなり、摘 採機の取り回し性を低下させてしまうという問題があったことから、本件発 明7は、上記問題を解決し、水平移送部を設けることなく、刈取直後、即、 茶葉を上昇移送できるようにし、摘採機の前後寸法の短縮化を図り、摘採機 をコンパクトに構成できるようにした茶枝葉の移送装置を開発することを課\n題とし、この課題を解決するための手段として、水平移送部を設けることな く、刈刃の後方から移送ダクト内に背面風を送り込む吹出口が設けられ、こ の吹出口から移送ダクト内に背面風を送り込むことによって、刈取後の茶枝 葉を刈刃から所定の位置まで移送する構成を採用し、具体的には、刈刃後方\nからの背面風によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この移送ダクト 内に流す圧力風の作用のみにより、負圧吸引作用によって刈り取り直後の茶 枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部な ど適宜の部位に移送する構成とし、これにより刈り取り直後、水平移送部を\n設けることなく、そのまま茶枝葉を上昇移送することができ、前後長の短縮 化が図れ、コンパクトな茶刈機が実現できるという効果を奏することに技術 的意義があり、水平移送部を設けることなく、刈刃の後方側から送風される 「圧力風の作用のみ」によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この負 圧吸引作用によって刈り取り直後の茶枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後 は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部4など適宜の部位に移送するようにした ことが、本件発明7の本質的部分であるものと認められる。
しかるところ、前記2(2)で説示したとおり、被告各製品においては、 「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が「圧力風」の作用に 「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が加わることによって実 現されているといえるから、被告各製品は、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるものとは認められない。\nしたがって、被告各製品は、本件発明7の本質的部分を備えているもの と認めることはできず、本件相違部分は、本件発明7の本質的部分でないと いうことはできないから、均等論の第1要件を充足しない。
◆判決本文
1審は、こちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.01.28
令和3(ネ)10099 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年12月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被告製品1は第3要件を充足するか(争点1−2−3)
ア 被告製品1の製造開始時において、本件訂正発明6における「前記電解 室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構成を、被告製品1\nにおける「1)内タンク6の側壁の一部、2)流出孔3を有する内タンク6の 底部、3)4つの高分子膜10」との構成に置換することは、当業者が容易\nに想到し得たかについて検討する。
イ 前記2のとおり、本件訂正発明6においては、構成要件11Aの隔膜に\nよる区画は、隔膜によって電解室の内部と外部とが完全に区画されるもの であり、電解室の内部と外部とは、水が連通することがない独立した構造\nとなっている。また、本件明細書1においては、電解室の内部と外部を分 ける隔膜は、縦に設置されたもののみが開示され、陽極で発生する水素と 陰極で発生する水素は、別空間に排出されると理解される。 これに対し、被告製品1は、内タンク空間と外タンク空間の間を水が連 通する構成の下で高分子膜10を水平に配置し、高分子膜10の上側に保\n持された陰極電極板11で発生する水素ガスと、高分子膜10の下側に保 持された陽極電極板12で発生する酸素ガスの混合が起こり得る状態を 許容した上で、陽極電極板12で発生した酸素ガスは、枠体5内に集めて 大きな気泡を形成し、流出孔3から内タンク6内に進入するのを防止した 上、内タンク6と外タンク2の隙間内の水内を通って外部に排出するとい うものである(乙29の1・2)。そうすると、本件訂正発明6と被告製品 1は、その基本的発想を異にするものというべきであって、被告製品1に おける「1)内タンク6の側壁の一部、2)流出孔3を有する内タンク6の底 部、3)4つの高分子膜10」との構成への置換が本件訂正発明6の単なる\n設計変更とはいえない。
また、本件明細書1においては、「前記電解室の内部と外部とを区画する 一つ以上の隔膜」との構成を、被告製品1のような「1)内タンク6の側壁 の一部、2)流出孔3を有する内タンク6の底部、3)4つの高分子膜10」 との構成に置換した場合に生じ得る事項についての示唆もないから、本件\n明細書1において、上記のような置換をする動機付けとなるものも認めら れない。
ウ 控訴人は、前記第2の3(7)アのとおり、陽イオン交換膜を用いた固体高 分子水電解において、陰極室と陽極室を貫通孔により水を連通する構成は、\n被控訴人が製造販売を開始した平成29年11月以前から周知の技術で あるとして、甲36文献、甲37文献、甲40文献を提示するので、以下、 検討する。 甲37文献は、オゾン水製造装置、オゾン水製造方法、殺菌方法及び 廃水・廃液処理方法に関するものであり(【0001】)、電解反応を利用 した化学物質の製造において、多くの電解セルでは、陽極側と陰極側に 存在する溶液あるいはガスが物理的に互いに分離された構造を採るが、\n一部の電解プロセスにおいては、陽極液と陰極液が互いに混じり合うこ とを必要とするか、あるいは、混じり合うことが許容されることを前提 として(【0002】)、陽極側と陰極側が固体高分子電解質隔膜により物 理的に隔離され、陽極液と陰極液は互いに隔てられ、混合することなく 電解が行われる従来のオゾン水電解(【0005】)では、電解反応の進 行に伴い液組成が変化し、入側と出側で反応条件が異なるなどの問題点 があったことを踏まえ(【0006】)、電解セルの流入口より流入した原 料水がその流れの方向を変えることなく、直ちに電解反応サイトである 両電極面に到達し、オゾン水を高効率で製造できる等の作用を有するオ ゾン水製造装置等を提供することを目的としたものである(【001 6】)。
その技術分野(オゾン水製造装置)及び目的(オゾン水を高効率で製 造すること等)のいずれも本件訂正発明6と異なるし、その具体的構成\nも、貫通孔11が設けられた電解セル8(陽極1、陰極2及び固体高分 子電解質隔膜3)に直交して原料水(オゾン水)の流路が設けられると いうものであって(【0034】及び【0035】)、電極室の内部に被電 解原水が貯留され、電気分解が行われる本件訂正発明6とは異なる。し たがって、甲37文献に開示された事項を本件訂正発明6に適用する動 機付けは見い出せない。
甲40文献は、電源のない場所に持ち運び、水素の吸入や水素水の飲 用に使用することのできるポータブル型電解装置に係る技術分野に属す るものであり(【0001】)、電解ユニット3は、ケーシング31、高分 子膜32、電極板33、34、スプリング35からなること(【0028】)、 ケーシング31は、内部に反応室311となる容積が確保されており、 側部に外部と反応室311とを連通するように穿孔された連通孔314 が設けられていること(【0029】)、電解ユニット3の高分子膜32は、 イオンの通過を規制するイオン交換機能を有する薄膜からなるもの(例\nえば、ナフィオン)で、ケーシング31の窓孔311を閉塞する大きさ の方形に形成されていること(【0030】)が記載され、使用形態とし て、内部に原水Wが収容されたタンク1にキャップ2、ガイド筒4、水 素吐出管5を一体的に取付けられること(【0034】)、スイッチ9が入 れられると、原水Wが電気分解され、ケーシング31の反応室311の 内部にあるプラス極の電極板34で水素イオンと電子とが生成されて高 分子膜32を通過し、ケーシング31の窓孔312に露出しているマイ ナス極の電極板33で水素(ガス)が生成され、水素は、微細な気泡H を形成してタンク1の内部で水素水からなる電解水を生成すること、プ ラス極の電極板34で生成されたオゾン(ガス)は、高分子膜32を通 過することなくケーシング31の反応室311の内部に滞留され、ケー シング31の反応室311の内部の滞留圧力が大きくなると連通孔31 4から吐出されること(【0041】)が記載されている。 しかし、甲40文献には、陰極室及び陽極室についての記載はないか ら、これを見ても、陰極室と陽極室とを貫通孔により水を連通する構成\nが記載されているとはいえない。別紙2の図2において、マイナス極の 電極板33より上側部分を陰極室と、プラス極の電極板34より下側の 反応室を陽極室であると解釈すると、連通孔314は、陽極室とその外 部を貫通するものであって、陽極室と陰極室を貫通するものではない。 マイナス極の電極板33より上側部分と、ケーシング31側面の外側部 分はつながった空間であることから、ケーシング31側面の外側部分も 陰極室であるとみた場合には、連通孔314は、陽極室(反応室)と陰 極室(ケーシング31側面の外側部分)を貫通するものであるといえる が、酸素と水素が同じ陰極室内に排出されることになり、被告製品1の 構成に至らない。\n甲36文献に係る発明の公開日は平成30年11月22日であり、甲 36文献自体の発行日は令和2年3月11日であるから、その内容や位 置付けについて検討するまでもなく、甲36文献は、被控訴人が被告製 品1の製造販売を開始した平成29年11月時点における周知文献とは いえない。
エ 以上によれば、控訴人主張の周知技術は、いずれも、本件訂正発明6に おける「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構\n成を、被告製品1における「1)内タンク6の側壁の一部、2)流出孔3を有 する内タンク6の底部、3)4つの高分子膜10」との構成に置換する動機\n付けになるものとはいえない。
これらの事実関係によれば、このような置換が容易であったとはいえな いから、被告製品1は、均等の第3要件を充足しない。 前記(1)ないし(3)によれば、被告製品1は、均等の第1要件及び第2要件を 充足するものの、第3要件を充足しないから、第5要件について判断するま でもなく、本件訂正発明6の技術的範囲に属しない。
◆判決本文
1審はこちら。
1審では、構成要件を具備せず、また実施可能\要件違反の無効理由有りと判断されていました。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.01.13
令和1(ワ)14320 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月7日 東京地方裁判所
前記(1)で検討したところによると、本件発明1の技術的意義は、固定プレ ートの孔自体が、橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側 面側という2箇所で支持する方向に突起を向かせて固定することができる構\n成となっているため、高度な医学的判断を要せずに、確実に軟骨下骨を背側 面側及び手掌側面側という2箇所で支持することを可能にすることにあると\n認められる。
そうすると、本件発明1の構成のうち、本質的部分であるといえるのは、\n橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という2箇所 で支持する方向に突起を向かせて固定することができる孔が設置されている ことを定めた構成要件1E、1J及び1Kであると解するのが相当である。\nそして、これまで検討したところによると、被告製品4は構成要件1J及\nび1Kを充足せず、これらの本件発明1の構成と異なる部分は、本件発明1\nの本質的部分ではないとはいえないから、第1要件を充足せず、均等侵害は 成立しない。
(3)原告の主張の検討
原告は、本件報告書(甲26)によれば、被告製品4は、ガイドブロック を用いて被告製品4の孔にロッキングスクリューを固定すれば、一組の平行 ピンを用いた従来の平板固定によっては達成できなかった遠位橈骨の軟骨下 骨及びその遠位側の関節表面の位置の安定化という課題を解決することがで\nきるから、本件発明1と技術的思想を共通にしているといえ、孔の軸線が遠 位橈骨内で交差するか遠位橈骨外で交差するかは本件発明の本質的部分では ないと主張する。
しかし、本件報告書の検証結果の信用性を肯定することができないことは 前記4(2)のとおりであるし、その信用性を肯定できたとしても、前記(1)の とおり、遠位橈骨の骨折を固定するための骨プレートであり、ネジを固定す るための固定プレートを貫通する複数のネジ孔が、固定プレート頭部の遠位 側と近位側の2列に概ね平行に並んで設置されている固定プレートは、先行 技術として存在していたのであるから、従来プレートが一組の貫通孔のみを 設けていたことを前提に、二組の貫通孔を設けていることが本質的特徴であ ると評価することはできない。 また、本件発明1は固定プレートの発明であるから、固定プレート自体の 構成、すなわち、固定プレートに設置された孔の構\成を比較すべきであり、 被告製品4にガイドブロックを用いることを前提に、被告製品4が軟骨下骨 を背側面側及び手掌側面側という2箇所で支持する方向にロッキングスクリ ューを向かせることができるかどうかという観点から比較することは相当で はない。
さらに、孔の軸線が遠位橈骨内で交差しないのであれば、孔に突起を挿入 しても、突起が当然に軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という2箇所で支 持することはなく、遠位橈骨の軟骨下骨及びその遠位側の関節表面の位置の\n安定化という課題を解決することはできないから、孔の軸線が遠位橈骨内で 交差する方向に突起を向かせる構成となっていることは、本件発明1の本質\n的特徴であるといえ、そのような孔の構成を有していない被告製品4に均等\n侵害が成立することはない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.01.11
令和3(ワ)4920 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年12月22日 大阪地方裁判所
ア 前記(1)アによれば、リベラル社は、平成30年7月5日時点において、別 件特許(「活量調質水溶液及び活量調質媒体の製造方法」)により、水酸化物イ オン活量調質水溶液を製造し、これを希釈して、旧ATWのほか「ATW−1、 ATW−001」を製造していたことが認められるところ、前記(1)イのとおり、 被告は、当初、リベラル社から購入した旧ATWをそのままボトルに詰め、又は、 ラベルを貼り替える方法により、旧被告製品や無限七星FISHを製造し、販売\nしていたのであるから、これらの製品は、前記水溶液を希釈したものであると認 められる。一方、前記(1)エ及びオのとおり、被告は、原告の本件特許出願の後か らは、リベラル社から購入した本件特許に規定される組成を有する現ATWを1 0倍希釈して被告製品や無限七星FISHを製造、販売するようになったところ、 本件代理店契約においては、現ATWを含めたATW水溶液は、別件特許の製造 方法による旨の合意がなされている。 また、原告が代表取締役を務めるATW社は、別件訴訟において、旧ATWと\n現ATWは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ATWを10 倍薄めたものが旧ATWである旨を記載した準備書面を提出しているところ、リ ベラル社が発行した請求書では、現ATWの1リットル当たりの単価は旧ATW の同単価の10倍になっていること、本件代理店契約においてATW水溶液の品 質として標準仕様と10倍濃縮仕様がある旨の記載があることのほか、原告も、 本件訴訟において、現ATWは旧ATWの10倍の濃度である旨を主張している (原告準備書面(4)第2の2(3)イ)。これらの事実関係に照らすと、旧ATW及び現ATWは、一貫して、同様の製造方法により製造された、アミノ基を含む成分が水溶、濃縮された水酸化物イオン活量調質水溶液を希釈したものであり、本件特許に規定される組成を有する現ATWを10倍希釈したものが旧ATWであると認められる。
イ また、証拠(乙2、18、24、25、33、36、37)及び弁論の全 趣旨によれば、次の事実が認められる。 すなわち、被告が平成30年11月10日にリベラル社に対して発注し同月1 2日に納品された旧ATWのボトル20本のうち、開封せずに保管していたもの (以下「保管ボトル」という。)について、被告がそのうち1本を開封し、10 0ml分(以下「分析対象物」という。)を小分けにして、愛媛大学のP2名誉 教授に提供した。同教授は、令和3年9月30日、分析対象物について、乙18 分析をした結果、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであることが判明し た。また、被告は、保管ボトルのうち1本(被告が「無限七星FISH」のラベ ルを貼付したもの)を、株式会社東ソ\ー分析センターに提供し、前記センターは、 同年10月19日、保管ボトルの内容物について乙24分析をした結果、その重 量平均分子量は、4.5×10⁴であった。
ウ 前記(1)イ及びウのとおり、無限七星FISHは、鮮魚の鮮度を保持する機 能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており、また、証拠(乙19)\n及び弁論の全趣旨によれば、リベラル社が被告に販売した旧ATWの成分表記に\nは「重合アミン、水」との記載があったことが認められる。
エ 前記ア〜ウの事実関係に照らすと、現ATWが10倍に希釈化された旧A TWと同一成分である無限七星FISHに係る引用発明は、ポリアリルアミン又 はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が95重量%\n以上である水であって(a’)、ポリアリルアミンの重量平均分子量が500〜 50000であって(b’)、魚介類の鮮度保持の機能を有する(c’)、機能\ 水(d’)という構成を有するものと認められるから、被告製品のみならず、旧\n被告製品や無限七星FISHも本件発明の各構成要件を充足するものと認められ\nる。したがって、引用発明は、本件発明の各構成要件を充足する。\n
(3) 公然実施について
特許法29条1項2号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者 が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)イのとおり、 被告は、本件特許の優先日前の平成30年10月から、無限七星FISHを製造 及び販売して、引用発明を実施した。
(4) 原告の主張について
ア 原告は、旧ATWは、別件特許に基づく方法により製造されているのに対 し、現ATWは、ポリアリルアミンを使用して製造されているから、両者の成分 は異なる旨を主張する。 しかし、両者の成分の違いを明らかにする証拠はなく、前記(1)オ及びキのとお り、被告は、本件代理店契約において、リベラル社及びATW社との間で、AT W水溶液の仕様は、別件特許の製造方法によることを合意したことや、ATW社 が、別件訴訟において、旧ATWと現ATWは、いずれもアミノ基という原子団 を含んだ水溶液で、現ATWを10倍薄めたものが旧ATWである旨を記載した 準備書面を提出したのであるから、旧ATWと現ATWの製造方法が異なる旨や 両者の成分が異なる旨の原告の主張は直ちに採用することはできず、その他、原 告の主張事実を裏付ける証拠はない。
イ また、原告は、乙18分析及び乙24分析は、いずれも、測定対象の水溶 液がどの時期に製造、販売され、どういう形で試験に供されたのか全く不明であ ることを指摘し、さらに、乙18分析の内容については、1)乙18のFig.1の スペクトルの面積比を理由に高分子化合物の繰り返し構造をCH₂−CH−CH₂ と推定することが困難なこと、2)3ppm付近のシグナルの変化を理由に当該シ グナルがアミン(CH₂−NH₂)であると推定できる根拠が不明であること、3) Fig.1とFig.4a)のスペクトルが異なることといった疑問点があるから、 いずれも信用性がない旨を主張する。
しかし、前記(1)認定の事実からすれば、乙18にいう「2018年10月に販 売が始まった初代無限七星」とは、旧ATWと成分を同じくする旧被告製品又は 無限七星FISHであると理解できるし、乙24は保管ボトルのうち1本を分析 した結果であることが明らかであり、これに反する証拠はない。そして、乙18 分析は、核磁気共鳴分光法及び質量分析法により、分析対象物の含有成分がポリ アリルアミンであることを推定した上で、それを踏まえて、分析対象物と市販の ポリアリルアミンの水溶液について核磁気共鳴分光法のスペクトルを比較して、 分析対象物の含有成分がポリアリルアミンであると結論づけているところ、原告 の主張1)について、原告主張のように、ポリマーのNMRはピーク(スペクトル) がブロードになりやすく、面積比を算出する切断箇所の設定によって面積比の値 が異なり得ることから、Fig.1のスペクトルの面積比「1.00:0.55: 0.80」が完全に「2:1:2」に一致しなくとも、同一環境の水素の数の比 を「2:1:2」とみなし、CH₂−CH−CH₂の部分構造が考えられるとする\nことは不合理ではない。また、原告の主張2)について、3ppm近辺のCH₂に対 応するシグナルの位置は、隣に窒素原子が繋がっていることを示唆するところ、 トリフルオロ酢酸を加えると、2.7〜3.3ppmのシグナルが3.0ppm のシグナルに変化したというのであるから、分析対象物にトリフルオロ酢酸によ り塩を形成するアミン(CH₂−NH₂)が存在すると考えて矛盾はないというべ きである。さらに、原告の主張3)については、確かに、Fig.1とFig.4a) のスペクトルは一致していないが、一方で、トリフルオロ酢酸塩のスペクトルで あるFig.2a)とFig.4b)は、ほぼ一致している(乙18、25)。こ の点について、証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば、ポリアリルアミンは、 共存物の影響でアミン部位が塩の状態になっている場合、スペクトルのピーク位 置の出現がシフトする可能性があり、ポリアリルアミンの塩の形成状況によって\nスペクトルの形状が変化し、複雑になるものと認められ、一方で、強い酸である トリフルオロ酢酸を加えて、全てのアミノ基をアンモニウムに変換し、均一な状 況にすることにより、一定の分析結果を得ることができたものと認められるから、 Fig.1とFig.4a)のスペクトルが異なるからといって、乙18分析の信 用性に疑義を生じさせることにはならない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.01. 3
平成29(ワ)7384 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月15日 大阪地方裁判所
ウ 覆滅割合
(ア) 市場の同一性
原告と被告は、マッサージチェアの分野でシェアを競い合う企業でマッサージチ ェアという需要者を共通にする同種製品を取り扱う同一の市場で競業している。 被告の主張は、具体的な被告の製品と原告の製品とを比較し、個別の販売相手先 や販売ルートを細かく分断して、これらが異なるから「市場の非同一性」があるな どと主張している。しかし、このような立論が成り立つのであれば、個別の販売相 手先や販売ルートが共通の場合でない限り、市場は無意味に細分化されてしまう。 同種製品で共通する需要者層を対象にして潜在的に影響を受ける競争の場が想定で きるのであれば、市場が同一性を有しているといえる。 また、本件特許II)及びIII)の実施品である原告の製品(以下「原告製品」という。) には対象被告製品と同じような価格帯の製品も複数存在するから、この点からも市 場の同一性は否定されない。
(イ) 市場における競合品の不存在
侵害訴訟の損害論においては、特許権を侵害する製品が販売されることによって、 特許権者の特許実施製品の販売が減少するという関係があるか否かを問題とすべき であるから、侵害関係のない製品についての適法な同種製品のシェア自体は、推定 覆滅事由としては関係がない。 また、競合品の範囲は、本件特許II)及びIII)の特許権の技術的構成を踏えて、その\n目的・作用効果を把握した上で、当該目的・作用効果が同じで原告製品の販売数量 に影響を与える製品という前提に立脚して考察されるべきであって、「背メカで被 施療者の首元から背中、腰にかけてマッサージを行うマッサージチェア」であるか 否かによって範囲を画し、これを前提とすると、殊更に本件特許II)及びIII)の具体的 な構成や解決手段をその考慮対象から一切捨象することになる。\n
(ウ) 侵害者の努力(ブランド力、宣伝広告)
原告は、古くから一貫してマッサージチェアを製造販売している老舗であり、被 告ともシェアを常に争う信用力のある会社である。また、原告は、世界で各種の受 賞実績のある国際的にも認知された会社であり、被告に劣らずグッドデザイン賞を 受賞するデザイン性を備える複数の原告製品を販売している。 したがって、原告企業より被告企業の方が格別に信用力を有し、原告のブランド 力に比して侵害品が利用者にとって購買動機となるなどということはない。 また、開発段階において開発に携わる従業員を配することは、ごく通常のことで あり、原告においても日々機械によるマッサージを人間の揉み心地に近づけるべく 開発努力を重ねている。営業段階において、マッサージチェアの魅力を伝える為の 営業活動は、原告においても常時行っており、被告だけに特別の活動ではない。
(エ) 侵害品の性能\n
対象被告製品のカタログ等には、対象被告製品の仕様(発明の構成)が明記され\nており、本件発明II)及びIII)の作用の発現が示唆されていることから、需要者に一切 訴求されていない本件特許II)及びIII)の作用効果に関連する仕様、機能は、対象被告\n製品の購入動機になり得ない旨の被告の主張は失当である。 被疑侵害品である対象被告製品の具体的な実施態様に関するパンフレット等には、 利用者へ訴求する記載が多数ある。本件特許II)及びIII)の技術的構成を採用するから\nこそ、各種コースのマッサージや腕を含む人体全体のマッサージ効果を高めるマッ サージチェアを提供できるのであり、これらの技術的構成を回避してマッサージチ\nェアを提供することは製品の性能に大きな影響を及ぼし、仮に回避し得たと考えて\nも、その代替的構成を採用するには無視できない費用がかかる。\n
(オ) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されているものではないこと
本件特許II)及びIII)は、椅子式のマッサージチェアにあって身体のマッサージに関 する構成、構\造に係る基本的な技術である。被疑侵害品である対象被告製品の一部 に本件特許II)又は本件特許III)の発明が実施されていたとしても、対象被告製品は、 この実施部分を除いてしまえば、全体としての製品構成が成り立たない。すなわち、\n本件特許II)は、椅子式マッサージ機にあって肩を側方からマッサージする「肩また は上腕の側部」の技術的構成に関する重要な特許であり、本件特許III)は、「腕部」 をマッサージする技術的構成に関する重要な特許であって、この実施部分があるか\nらこそ利用者の需要が喚起されているといえる。 本件特許II)に関し、被疑侵害品である被告製品II)を利用する利用者は、様々な自 動コースを自由に判断して設定するのであり、その際に、「肩または上腕の側部」 に効果的なマッサージを行うことができる構成を有している製品か否かが製品選択\nには重要である。本件特許II)の構成の内容は、取扱説明書の中でもこれを織り込ん\nでしばしば説明されており、それが被疑侵害品である被告製品II)の全般に亘ること も明らかで、本件特許II)の構成を抜きにしては、被告製品II)の多くの自動コースも 成り立たないことも一見して明らかである。 本件特許III)に関して、開口の向きを考慮しつつ、腕のエアマッサージを行う本件 特許III)の技術的構成の具体的な実施態様は、これを採用する製品の外観にもマッサ\nージ効果にも大きな影響を及ぼす。
(カ) まとめ
以上を総合的に考慮すると、推定覆滅される割合は、少なくとも55%以上には ならない。
エ 損害額
(ア) 特許法102条2項に基づく損害額の算出ができる対象被告製品について 不当利得期間及び損害賠償期間を通じた限界利益の額(前記イ(ウ))について、前 記ウのとおり、推定覆滅される割合は、55%以上にはならないから、被告が開示 した限界利益率を前提とした場合は、●(省略)●を下らず、原告が主張する限界 利益額を前提とした場合は、●(省略)●を下らない。
(イ) 特許法102条2項に基づく算出ができない対象被告製品について 被告の開示によれば、被告製品12、30及び32の限界利益はマイナスであっ て、赤字が計上される製品であるので、これには特許法102条2項に基づく算出 ができない。前記3製品について、●(省略)●そして、前記3製品について、こ の限度で特許法102条3項の主張を行う。
・・・
(ウ) まとめ
前記(ア)及び(イ)を総合すると、被告の開示した限界利益額による場合、特許法102条3項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●(省略)●となり、原告が主張する修正限界利益額による場合、同条3項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●(省略)●となり、少なく見積もっても50億円を下らない。
(3) 特許法102条2項及び3項に基づく主張
ア 特許法102条1項と同条3項の関係と同条2項 特許法102条1項と3項の併用に関する令和元年法律第3号による改正(以下 「令和元年改正」という。)後の特許法に関する考え方として、産業構造審議会知\n的財産分科会特許制度小委員会の報告書(「実効的な権利保護に向けた知財紛争処 理システムの在り方」)において、わざわざ2項との関係でも「同様の扱いが認め られることと解釈されることが考えられる」と記載されており、その解釈可能性が\nあることへの言及があるから、2項と3項の併用については、条文に明示されなか ったとはいえ、全面的に併用適用が否定されたわけではなく、解釈に任されること を明らかにしている。 したがって、特許法102条2項に基づき主張された損害のうち推定が覆滅され た部分について、同条3項の重畳適用が認められるべきである。
◆判決本文(侵害論)
関連事件1です。
同じく富士医療器による特許権侵害を認定ししてるとして、約4800万円の損害を認めました。
◆平成30(ワ)1391
原告・被告が逆の侵害訴訟はこちら。
◆令和2年(ネ)10024
この1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.12.17
令和3(ワ)9530 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年11月28日 大阪地方裁判所
(2) 「中央部が突出する概略円錐状」の意義について
ア 構成要件Dは、「該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」と規定しているところ、「該複数のコニカルビット群」とは、3条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに取り付けられたコニカルビットを指す(構\成要件C)から、構成要件Dは、3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットのみにより、中央部が突出した概略円錐状に形成されていることを要すると解される。その他、本件発明に係る請求項において、「中央部が突出する概略円錐状」に関する記載はない。\n
イ 本件明細書には以下の内容が示される。
従来の掘削ヘッドは、複数の小形ビットが台金に固着されていたので、掘削中 に岩石等に当たった際、刃先が逃げることができず、損傷を受けやすいという問 題点や掘削によって生じた繰粉が穴底からうまく排出されにくいという問題点 があった(【0003】)。このような問題点を解決するものとして、直径方向に対 向するように設けられた2条の螺旋翼を有する掘削刃の螺旋翼の周縁部及び下 端に多数の小形ビットを取り付けたスクリューオーガ用掘削刃がある。これには、 軸回りに回転自在な小形のビット(コーン刃)が設けられていて、岩石等に当た った時に当該コーン刃が回転して逃げることができるため、損傷しにくいという 利点があるが、2条の螺旋翼が直径方向に対向するように設けられ、これら2条 の螺旋翼にそれぞれ設けた小型ビットで掘削を行うものであるから、掘削中に岩 石等に遭遇したときは、2条の螺旋翼に設けたビットが当該岩石に当たるたびに 断続的な衝撃を受け、スクリューオーガ装置全体が上下に振動して、円滑な掘削 ができなくなるおそれがあるほか、螺旋翼自体が先端側の外径が小さくなるよう に全体として円錐状の尖った形状となっているので、芯ぶれにより、掘削される 穴が曲がりやすいというおそれもある(【0004】)。本件発明は、掘削中に岩石 等に当たってもビットの刃先が損傷しにくく、断続的な衝撃をうけにくく、しか も穴曲がりが生じにくい掘削ヘッドを提供することを目的とし、基部がスクリュ ーオーガロッドに取り付けられる基軸の外周部に、外径の等しい3条の螺旋翼が 設けられ、これら3条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに、円錐状の 尖った刃先部を有する複数のコニカルビットが軸回りに回転自在にそれぞれ取 り付けられ、該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に 形成されていることを特徴とする構成をとるものである(【0005】【0006】)。 3条の螺旋翼が並列に設けられていることにより、掘削中に岩石等の掘削しにく い物体に当たっても、断続的な衝撃が比較的小さくてすむようになるとともに、 胴部における3条の螺旋翼の外径をほぼ一定にしておくことにより芯ぶれが生 じにくくなる結果、穴曲がりが少なくなるという効果を奏するものである(【0006】 【0007】【0020】)。これらの本件明細書の記載内容に加え、図面(【図1】〜 【図4】)に照らすと、外径の等しい3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複 数のコニカルビット群により、「中央部が突出する概略円錐状に形成されている こと」の技術的意義は、胴部における3条の螺旋翼の外径を変えることなく、該 複数のコニカルビット群により、基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状 の形状にすることで、穴曲がりが生じることを防ぎつつ、掘削効率を高めること にあるものと認められる。 また、本件明細書には、発明の実施形態に関して、「小型ビット20,…は、 それぞれが取り付けられている螺旋翼10の傾斜方向にほぼ沿うように傾けて 設けられている。また、前記ヘッド15には複数(図示例では3個)の小型ビッ ト20,…が設けられていて、掘削ビットの先端部は、これら小型ビット群によ って側面視概略円錐状を呈している。」(【0011】)、「掘削ヘッド1の先端部 には、全体形状が概略円錐状となるように多数のコニカルビット20,…が設け られているので、これらビットにより効率よく掘削が行われる。」(【0016】) との記載もある。
ウ 証拠(乙1、2)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成19年7月3 日付けの拒絶理由通知書(乙1)により、特許庁から、本件発明は、引用発明1 及び2に基づき進歩性を欠くとの拒絶理由を通知されたことに対し、構成要件D\nに該当する部分を付加して補正した上で、意見書(乙2)において、引用発明1 は、螺旋翼が2条で、円周方向における螺旋翼同士の間隔が大きく、ヘッド先端 部のビットの密度が低くなり、しかもヘッド先端部のビットの先端はほぼ同一平 面状に位置していて、仮想先端面が平板状を呈しているのに対し、本件発明は、 3条の螺旋翼の先端部に複数のコニカルビットが取り付けられ、ヘッド先端部が、 全体として中央部が突出する概略円錐状の外形に形成されているから、引用発明 1と本件発明とは構成が大きく相違している旨を主張したことが認められる。\nこのような出願経過に照らすと、原告は、構成要件Dに該当する部分を付加し\nて補正することで、3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビッ トにより、ヘッド先端部が全体として中央部が突出する概略円錐状の外形である ことを特定したものと解される。
エ 前記アないしウのとおり、構成要件C及びDの文言、本件明細書の内容、\n「中央部が突出する概略円錐状に形成されていること」の技術的意義、出願経過 に照らすと、「中央部が突出する概略円錐状」とは、3条の螺旋翼の先端部に取 り付けられたコニカルビットのみにより、側面視を含む全体形状において基軸先 端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしていることを意味しているものと 解するのが相当である。本件明細書には、発明の実施形態として、3条の螺旋翼 の先端側に、概略円錐状のヘッド15が、基部を基軸2に固定されており、ヘッ ド15に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を 呈しているものが示される(【0011】)ことから、発明の実施形態には、3条の 螺旋翼の先端部に取り付けられたコニカルビットが側面視を含む全体形状にお いて基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしており、かつ、ヘッド1 5に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を呈す る形態を含むものと解する余地があるが、前記アの構成要件C及びDの文言に照\nらすと、「中央部が突出する概略円錐状」の上記解釈は左右されない。
(3) 被告各製品について
ア 被告製品1
争いのない事実、証拠(甲5、乙10の1〜3)及び弁論の全趣旨によれば、 被告製品1は、その3条の螺旋翼20の先端部に設けられた3〜4基のコニカル ビット30により、側面視(基軸10先端方向を上に向けた場合。以下同じ。) において、中央部が平坦又は間隙のある、浅いハ字状に線が描かれていること、 全体形状として、基軸10から放射状に3本の緩やかな曲線(ほぼ直線)が描か れていることが認められる。
・・・
カ 以上のとおり、被告各製品の3条の螺旋翼の先端部に取り付けられたコニ カルビットは、いずれも、側面視を含む全体形状において、直線、緩やかな曲線 又は点を形成するにすぎず、同コニカルビットのみにより、基軸先端方向に向か って径が小さくなる円錐状を形成しているとはいえず、構成要件Dを充足すると\nは認められない。
(4) 原告の主張について
原告は、「中央部が突出する概略円錐状」とは、効率よく安定した掘削を行う という本件発明の技術的意義を有するか、これと同一の作用効果を奏するもの、 すなわち、3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットが「概 略錐面状」に並んで配置されることを意味し、当業者は、本件明細書の記載から そのように理解する旨を主張し、当業者の認識や技術常識を裏付ける証拠として、 公開特許公報(甲23の1〜12)、パンフレット等(甲24の1〜3)、アン ケート結果(甲25の1〜8)、大学教授の意見書(甲28の1、29の1)を 提出する。
しかし、前記(2)のとおり、構成要件Dは「該複数のコニカルビット群により、\n中央部が突出する概略円錐状を形成」と規定しており、本件明細書や出願経過等 をみても、コニカルビットが概略錐面状に並んで配置していることと解すべき記 載等はないから、同構成要件を充足するには、コニカルビット群のみにより、(中\n央部が突出する)概略円錐状を形成する必要がある。 原告は、前記各証拠は、回転式の土木用掘削ヘッドにおいて、コニカルビット、 掘削刃などの掘削ビット類の配列、又は複数の掘削ビット類の全体形状を、当業 者は「概略円錐状」と表現することを示すものである旨述べる。しかし、原告が\n提出する公開特許公報(甲23の1〜12)に係る特許の中には、本件特許の出 願後に出願又は公開されたものが含まれており、それらは本件特許出願時の当業 者の認識を裏付けることにはならない。この点は措くとしても、これらの公報の 内容は、掘削爪等の配置、スクリュー刃全体、ヘッドの先端やヘッド部分全体、 掘削面や地盤改良体等の形状が、それぞれ円錐状であるなどと個別に特定するも のであり、これらの公報全体をみても、回転式の掘削ヘッドにおいて掘削ビット 類の配列や全体形状が一般的に「概略円錐状」と表現されているとは認められな\nい。そして、少なくとも、これらの公報の中に、被告各製品のようにコニカルビ ット(3条の螺旋翼の先端部に取り付けられたもの)が並んでいる形状を指して (中央部が突出する)概略円錐状と表現することを示すものはない。また、パン\nフレット等(甲24の1〜3)には、「円錐ヘッド」や「円錐型ヘッド」として、 螺旋翼の外周部から中心軸に近づくにつれてビットが先端に向かって高い位置 に取り付けられている掘削ヘッドの写真が掲載されているものの、どの部分を指 して円錐形状と表現しているかについては明らかでないし、被告各製品のように\nコニカルビットが並んでいる形状そのものを指して概略円錐状と表現するもの\nとも認められない。さらに、アンケート結果(甲25の1〜8)については、8 名の回答者の中に本件特許の発明者や同発明者の出身会社の代表者、原告と何ら\nかの取引関係があると考えられる者が含まれている(甲25の1、2、8、弁論 の全趣旨)など、アンケート対象者の中立性等に疑義があることに加え、質問の 形式も、被告各製品の螺旋翼先端部のコニカルビット群の形状をどう表現するか\nと問うのではなく、「「螺旋翼先端部のコニカルビット群」を見て「(概略)円 錐状」と認識できますか?」と一定の結論を示唆するものであって、適切とは言 い難い。回答者は、当該質問に対して、いずれも「できる」と回答しているもの の、その理由として、「ビットの高さが違う」「外側より先端部の方が飛び出し ている」「掘削後円錐に断面がなる」「写真より(中略)円錐形状を推定・想像 が行える」「日本テクノ製のコニカルヘッドと認識した」などとコメントしてお り、コニカルビットが並んでいる形状を概略円錐状と表現した趣旨か否かが不明\nである回答が含まれているほか、理由の説明内容が区々であり、このアンケート 結果から、当業者が一般的に被告各製品のようにコニカルビットが並んでいる形 状を(中央部が突出する)概略円錐状と認識するものと理解することは困難であ る。そして、大学教授の意見書のうち、甲第28号証の1には、ヘッドが回転し たときにどのような軌跡を描いているかを立体的にイメージすれば、ビットの軌 跡でトレースされる立体的形状が円錐状に近い形になることが指摘されている が、「複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成され ている」(構成要件D)ことに、「回転する複数のコニカルビット群の軌跡によ\nり、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」ことを含むと解釈すること は文理に沿わないし、当業者が一般的に、掘削ヘッドの「複数のコニカルビット 群」との文言から、その形状(配置)をヘッドが回転したときの軌跡でイメージ することを裏付ける資料もない。甲第29号証の1には、「概略円錐状」とは、 数学的(幾何学)な意味での円錐ではなく、中央が尖った錐状立体に近い概形を 意味していることが指摘されているが、その根拠は不明である。
以上から、原告が提出する証拠は、いずれも回転式の土木用掘削ヘッドにおい て、掘削ビット類の配列又は全体形状を、当業者が「概略円錐状」と表現するこ\nとを示すものとはいえず、被告各製品のようにコニカルビット(3条の螺旋翼の 先端部に取り付けられたもの)が並んでいる形状を、当業者が一般的に(中央部 が突出する)概略円錐状と理解することを裏付けるものでもないから、原告の前 記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.11.25
令和2(ネ)10024 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
原判決は、本件発明C−1の特許請求の範囲(請求項1)の記載 に基づく解釈として、1)構成要件Cの記載によれば、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」の3要素により形成された部分をもって成るものが「空洞部」であり、「空洞部」に「外側立上り\n壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在しない部分が許容され ると解されず、「空洞部」全体にわたって「内側立上り壁」が存在す ることを要する、2)構成要件Dの記載によれば、「空洞部の先端部」に「内側立上り壁の…前端部」が存在することは明らかであるところ、「内側立上り壁の…前端部」という記載は、更に「空洞部の先端\n部」以外にその後方部分にも「内側立上り壁」が存在することを示 唆するものと理解される、3)構成要件Bの記載によれば、「前腕挿入開口部」は、「空洞部」の一部ではなく、「空洞部」とは別の「肘掛部」の構\成部分でありつつ、「空洞部」に連続して設けられた部分であると解され、また、「前腕挿入開口部」と「空洞部」から成る「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の相対的な位置 関係は、「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する と解され、さらに、「前腕部を挿入保持する」ように「空洞部」が構成される、4)構成要件E、E−1、E−2の記載によれば、「前腕挿入開口部」が「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための」部分であるところ、そこに位置する施療部は「底面部」と「外側立上\nり壁」によりL型に形成されていることから、当該施療部には「内 側立上り壁」が存在しないと解されること、「前腕挿入開口部から延 設して…設けられ」ている「空洞部」が、「肘掛部」中の別の構成部分であることに鑑みると、「内側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画するものであるとの示唆を看取することもで\nき、そもそも、「前腕挿入開口部」につき、「内側後方から施療者の 前腕部を挿入するための」ものと特定されていること自体、「前腕挿 入開口部から延設して…設けられ」た「空洞部」の内側側方からは、 「空洞部」に「施療者の前腕部を挿入する」ことができないことを 示唆するものと解される、5)他方、請求項1の記載から、「空洞部」 中に「内側立上り壁」が存在しない部分があるとの示唆を読み取る ことはできないとして、本件発明C−1の「空洞部」(構成要件B、C)とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解される旨判断した。\n
しかしながら、1)及び5)については、構成要件B及びCから読み取れる事項は、「該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部」が「外側立\n上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」という3要素から形成さ れていることであり、他方で、「空洞部」のどの部分に、「外側立上 り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」を設けるべきかについては、 請求項1には何ら記載がない。「空洞部」が上記3要素から成ること と、上記3要素をどのように形成するかは別問題であるから、「空洞 部」に「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在し ない部分が許容されると解されないとの原判決の判断には、論理の 飛躍がある。
2)については、構成要件Dには、「空洞部の先端部」以外の後方部分における「内側立上り壁」の範囲については記載も示唆もなく、また、構\成要件Dの記載は、「空洞部の先端部」とその後方部分の一部に形成されている構成も、本件発明C−1の「空洞部」に該当すると解釈することと矛盾しないから、構\成要件Dから「内側立上り壁」が「空洞部」全体に及ぶべきことを読み取ることはできない。
3)については、構成要件Bの記載によれば、「前腕挿入開口部」は「肘掛部」の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」の部材であり、「空洞部」は「肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部\nを挿入保持するため」の部材であると定義されるところ、いずれも 「前腕」を「挿入」する機能を実現する部材であることで共通することからすると、「前腕挿入開口部」と「空洞部」は、「前腕部を挿入する部分」において重なることが示唆されているから、両者に厳\n密な線引きをすべき理由はない。また、仮に構成要件Bの記載について原判決の解釈を前提としても、「内側立上り壁」が「空洞部」の一部に形成されている構\成であっても、「肘掛部」に「空洞部」と「前腕挿入開口部」とが別構成として設けられ、「肘掛部」において「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する構\成とすることもできるから、本件発明C−1の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものでなければならないという結論 が論理必然的に導き出されるわけではない。
4)については、構成要件E、E−1、E−2は、「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の位置関係等を直接規定したものではなく、また、構\成要件E−2から読み取れる事項は、「前腕挿入開口部」に位置する施療部が底面部と外側立上り壁によりL型に形成されているということだけであり、そのことから直ちに、「内 側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画する ことを看取できるものではない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし5)は、本件発明C−1の「空 洞部」(構成要件B、C)は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することの根拠となるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。\n
(b) 次に、原判決は、本件発明C−1の「空洞部」(構成要件B、C)とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解されることは、本件明細書Cの記載及び本件特許Cの出願経過か\nらも裏付けられると述べ、具体的には、1)本件明細書C記載の本件 発明C−1の技術的意義に鑑みると、本件発明C−1は、肘掛部の 長さ方向全域に「外側立上り壁」と「内側立上り壁」が形成された 椅子式マッサージ機を前提として、肘掛部の内側後方から施療者の 前腕部を挿入可能となるように「内側立上り壁」を廃した「前腕挿入開口部」を設けたと認められるから、そのような肘掛部の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部」と、そ\nこから「延設して肘掛部の内部に…設けられ」ている「空洞部」と は、「内側立上り壁」の有無により画されるものと理解されるし、「手 掛け部」を設けたのは手部及び前腕部の広範を同時にマッサージす るために肘掛部の前端部にまで「内側立上り壁」が形成されている ことを踏まえたものである以上、本件発明C−1における「肘掛部 の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面 部とから形成され」た「空洞部」の「内側立上り壁」は、手部及び 前腕部の広範を同時にマッサージすることができるように、「空洞 部」全体にわたって存在することが想定されているといえる、2)本 件親出願の明細書(乙C8)の【0046】、【0047】及び図1 4は、本件明細書Cの【0046】、【0047】及び図14と同様 に、前腕部施療機構の中部に「内側立上り壁」が形成されていない実施例に関する記載であるところ、これらは、本件出願Cの出願に当たり、本件親出願の請求項からの変更の根拠として挙げられてい\nない、本件補正時に提出された平成23年5月9日付け意見書(以 下「本件意見書」という。乙C12)において、控訴人は、本件各 発明Cが、「肘掛部の長さ方向全域に前腕部施療機構として左右一対の立上り壁を設けた椅子式マッサージ機」に関する発明であり、「施療者の肘関節付近にまで左右一対の立上り壁が存在すること\nによる施療者の肘関節付近の圧迫による不快感を解消し、更に前腕 部施療機構を有していても施療者が起立及び着座を快適に行う事ができるようにした施療機を提供するもので」あるとした上で、「空洞部の先端部」に設けた「手掛け部」に関しては、そこに「内側立\n上り壁」が存在することを前提とした説明をしつつ、「前腕挿入開口 部」に関しては、そこには「内側立上り壁」がない形状にしたとす る説明をしている、他方、請求項2、すなわち肘掛部の中部に「前 記底面部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された 施療部」を設けることについても説明しているが、そこで言及され ている本件明細書Cの記載のうち、関係するのは【0046】のみ である、本件拒絶理由通知に示された「引用文献2」(乙C19)と 本件補正後の発明(本件発明C−1及びC−2)との相違について、 「引用文献2」に開示された前腕部施療部は「肘挿入用凹溝」であ り、その断面形状は略横向き「凹」字状であるのに対し、本件補正 後の発明においては、前腕挿入開口部に位置する施療部は「底面部」 及び「外側立上り壁」により形成された断面略「L型」であり、ま た、手掛け部が形成される空洞部に位置する施療部は、「底面部」、 「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「手掛け部」に囲われた形 状(実施の形態では「ロ型」)であるため、その構成が相違する旨説明している、断面が略「コ」字状の前腕部施療部の問題点として、前腕挿入開口部においては、上面に位置する部分が腕部の載脱をス\nムーズに行う上で障害となり、手掛け部においては「内側立上り壁」 が存在しないため、施療者の体重を掛ける上で不安が残ることを指 摘している、こうした説明内容に加え、本件補正により「前記底面 部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された施療部 を備え」る請求項2(本件発明C−2)を請求項1の従属項として 追加したにもかかわらず、当該発明における上記略「コ」字状の前 腕部施療部の問題点の有無等に関する説明が見当たらないことに 鑑みると、本件補正における控訴人の説明は、請求項2の追加にか かわらず、本件発明C−1の「空洞部」につき、その全体にわたっ て「内側立上り壁」が存在する構成を前提としていたと理解される、3)本件明細書Cの【0046】及び図14の記載が本件親出願から の分割出願(本件出願C)や補正(本件補正)にもかかわらず一貫 して存在する点については、本件発明C−1に係る特許請求の範囲 の請求項1の記載自体から「空洞部」につき、その全体にわたって 「内側立上り壁」が存在する構成と理解されることに鑑みると、分割出願や補正による本件特許Cの発明の内容の変化に応じてこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないと見るべきである\n旨判断した。
しかしながら、1)については、本件明細書Cには、本件発明C− 1の一実施形態(本件発明C−2の実施例)として、肘掛部の中部 に外側立上り壁、手掛け部、底面部よりコ型に形成された施療部を 設けたマッサージ機の記載があり(【0046】、図14)、図14で は、コ型に形成された施療部、すなわち、内側立上り壁が存在しな い部分が空洞部(62a)と図示されており、また、別の実施形態 を示す図8においても、内側立上り壁が存在しない部分が空洞部 (62a)と図示されている。これらの記載を参酌すれば、本件発 明C−1の「空洞部」は、肘掛部中の内側立上り壁が存在する部分 に限られるわけではなく、その全体にわたって「内側立上り壁」を 備えることを要しないことは明らかである。 また、本件発明C−1は、肘掛部の長さ方向全域に立上り壁を設 けることによる不都合(ア)上腕部内側の肘関節付近を圧迫し不快感 を与える、 腕部の載脱行為を妨げる、 快適な起立及び着座を妨 げるという不都合)を解決することを課題とし(【0005】ないし 【0008】)、(ア)及び の課題は、前腕挿入開口部の内側立上り壁 を廃したことにより、 の課題は、肘掛部に手掛け部を設けたこと により解決したものであり、それを超えて、「内側立上り壁」の有無 が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画し、空洞部はその全体に わたって内側立上り壁を備えるものであるという「空洞部」が備え るべき構成を導くことはできない。さらに、本件明細書Cの【0016】には、底面部及び外側立上り壁の二面において膨縮袋を備えることで前腕部に対するマッサ\nージを実施することができる旨が記載されていることに照らすと、 手部及び前腕部の広範を同時にマッサージするためには、「底面部」 及び「外側立上り壁」の二面が存在すれば足り、「内側立上り壁」が 「空洞部」の全体にわたって存在することは想定されていない。 次に、2)及び3)については、本件親出願の分割出願として本件出 願Cを出願するに際し、本件親出願の明細書(乙C8)の【004 6】、【0047】及び図14を分割要件を満たすことの根拠として 挙げられていないからといって、本件特許Cの出願経過において、 本件発明C−1の「空洞部」をその全体にわたって「内側立上り壁」 が存在する構成に限定したという控訴人の意思が客観的に表\され ているとはいえない。むしろ、控訴人は、本件意見書において、請 求項1及び2に係る本件補正の根拠として、本件出願Cの願書に最 初に添付した明細書(以下「本件出願Cの当初明細書」という。乙 C9)の【0046】を明確に挙げていること、当該段落は本件明 細書Cの【0046】と同じであり、「内側立上り壁」が備えられて いない部分を「空洞部(62a)」として指し示した「図14」の構成を説明していることからすると、「空洞部」についてその全体にわたって「内側立上り壁」が存在することを要しないことを前提とし\nていたことは明らかであり、本件明細書Cの【0046】及び図1 4の記載が存在することは本件特許Cの発明の内容の変化に応じ てこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないとの原判決 の3)の判断は誤りである。
また、被控訴人が2)で指摘する本件意見書における説明は、「空洞 部」と「内側立上り壁」の関係については何ら言及されておらず、 控訴人が、空洞部をその全体にわたって「内側立上り壁」が存在す る構成に限定する意思を客観的に表\明しているということはでき ない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし3)は、本件発明C−1の「空 洞部」(構成要件B、C)は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することを裏付けとなるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。\n
・・・
これを本件についてみるに、前記ウ認定の本件推定の覆滅事由は、特 許発明が被告製品1の部分のみに実施されていること及び市場の非同 一性であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。\nしかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅 部分については、被控訴人による被告製品1の各仕向国への輸出があっ た時期において、控訴人製品1は当該仕向国への輸出があったものと認 められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製 品1は、被告製品1の輸出がなければ輸出することができたという競合 関係があるとは認められないことによるものであり(前記ウ c)、控訴 人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすること ができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたも のと認められる。 一方で、本件各発明Cが侵害品の部分のみに実施されていることを理 由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に 係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品1に対し本件各発明Cが寄 与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このよう な本件各発明Cが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をす ることができたものと認められない。 そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由 に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法102条3項の適用を認める のが相当である。
(ウ)a これに対し、控訴人は、特許発明が侵害品の一部のみに実施されて いることを理由とする覆滅事由は、需要を形成する一要因にすぎず、 侵害品に向かっていた事情が全て特許権者の製品に向かうかどうかを 判断する一要素であるから、市場の非同一性等を理由とする覆滅事由 と区別する理由はないこと、覆滅事由ごとに特許法102条3項の適 用の有無を区別することは、実施料率の算定が煩雑になり妥当でなく、 そもそも製品の需要形成には様々な要因が複合的に絡み合っており、 覆滅事由ごとに覆滅割合を認定して当該覆滅部分にライセンス機会の 喪失による逸失利益が認められるか否かを認定判断することは実際上 困難であることからすると、本件各発明Cが侵害品の部分のみに実施 されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、 特許法102条3項の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、前記 で説示したとおり、上記推定覆滅部分は、個々 の被告製品1に対し本件各発明Cが寄与していないことを理由に本件 推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Cが寄与してい ない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものとは認 められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。 b また、被控訴人は、1)特許法102条1項において、特許権者が自 己実施できたと推定される部分(1号)とは別にライセンスをし得た 部分(2号)とを区別し観念できるのは、同項が、侵害者の販売する 「数量」に基づいて、権利者の逸失利益に係る損害額を算定する方法 を採用しているからであり、他方で、同条2項は、侵害者の「利益」 を権利者の逸失利益と推定する損害額算定方法をとっており、同項の 推定が覆滅されるのは、最終計算の結果としての損害額であり、計算 過程の途中数値である侵害品の数量の一部が計算の基礎から除かれる わけではなく、同項の推定を覆滅する過程において、権利者のライセ ンスの機会の喪失による逸失利益をも含む全ての逸失利益が評価し尽 されているというべきであるから、推定覆滅部分に対して同条3項を 適用することは、権利者の損害の二重評価となり、許されない、2)同 条1項2号が新設された令和元年改正特許法において、同条2項につ いて実施料相当額の損害が明文において規定されなかったのは、この ような趣旨によるものと解される、3)仮に推定覆滅部分について同条 3項の重畳適用が認められる場合が理論的にあり得るとしても、被告 製品1について、「市場の非同一性」を理由とする覆滅事由に係る推定 覆滅部分につき、輸出に際して海外市場の事業者から受け取る対価は、 あくまで海外市場に基づく利益であり、このような海外市場における 利益まで特許法102条2項の推定が及ぶものと解し、日本国内の特 許権に基づいて独占することは、特許権の保護範囲を逸脱しており、 法が予定していないものであり、また、日本国の特許権に基づいて仕向国への輸出行為のみを切り取り、ライセンスする場合は現実に考え\n難く、ライセンスによる実施料相当額の得べかりし利益を得られなか ったとは言い難いとして、本件推定の推定覆滅部分については、同条 3項を適用することはできない旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、前記 で説示したとおり、特 許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができるこ とに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特 許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた 実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の 喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解されるところ、特 許法102条2項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、 特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができ た実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するもので あるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が 実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上 げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施 料相当額の損害を受けたものと評価できるから、特許権者の損害を二 重に評価することにはならない。また、同条1項2号が新設された令 和元年改正特許法において、同条2項について、同条1項2号と同様 の法改正がされなかったからといって直ちに同条2項による推定の推 定覆滅部分について同条3項の適用を否定すべき理由にはならないと いうべきである。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.08.18
令和3(ネ)10079 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 控訴人は、前記第2の5(1)アのとおり、本件発明の「係止片」は、1)所定 位置において、それ自体として針先の再露出を直接防止し、2)片状の部材で あり、3)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、4)大径部に円筒状部と一 体形成され、5)小径部側には設けられていないものをいうから、上記構成要\n素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられていても構成\n要件1E4)の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの主張もこのよ うな理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第3の2(1)(補正後のもの)のとおり、 本件発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機能\nを有する係止片は小径部側には設けられてはならず(係止片が小径部側に設 けられていないことに特有の技術的意義がある。)、したがって、小径部に設 けられることで構成要件1E4)の充足が妨げられる係止片は、その形状を問 われないものであるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小\n径部側に存することは、対象製品が構成要件1E4)を充足することを妨げる ものである。
また、控訴人は、係止片は針先の再露出を「それ自体」として、かつ、「直 接」に防止しなければならない旨主張するところであるが、特許請求の範囲 及び本件明細書の記載上、根拠を見いだし難い(いずれにせよ、大径部係止 手段と小径部側壁部から構成される「係止片」は、それ自体により直接に針\n先の再露出を防止していると認められる。)。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」(へん)状の部材であるから、「係止片」とは「片 状(へんじょう)の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判断 に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片 状のものに限定する意義は見いだせない。また、いずれにしても、被告製品 は、小径部側壁部の突端面により縦リブの側面を挟持するものであるところ (引用に係る原判決第2の1(3)イd(補正後のもの))、小径部側壁部の突端 面を「片」と理解することに支障があるとは思えない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2022.08.12
令和2(ワ)4331 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月13日 東京地方裁判所
同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠(乙A80)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法102条2項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、5割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法102条2項により算定される損害額は、1853万0467円(3706万0935円×0.5(1円未満切り捨てとする。以下同じ。))となる。
エ 覆滅部分についての特許法102条3項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法102条2項の推定の覆滅部分について同条3項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条3項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−3には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は3.8%(最大値5.5%、最小値1.5%)(4件)、「健康;人命救助;娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は5.3%(最大値14.5%、最小値0.5%)(54件)と記載されている(乙A73)。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和4年1月27日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の10%と判断した(乙A80)。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能\にする代替技術 が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、10%を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法102条3項により算定される損害額は、1975万2707円(1億9752万7078円×10%)となる。
◆判決本文
関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求
◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円
◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.07.24
令和2(ワ)17423 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
これらの記載から、送風機によって生起された圧力風が刈刃後方の吹出 口から背面風として移送ダクト内に送り込まれること、この背面風は、刈 刃の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉を移送ダ クトの吐出口まで搬送する移送作用を有すること、刈刃の後方から背面風 を吹き出すことにより、吹出口近傍に負圧が形成されて、茶葉が、負圧吸 引作用により、刈刃部分から吹出口側に引き寄せられ、その後、上昇流を 形成する背面風に乗って、移送ダクト内を上昇し、吐出口から収容部に設 けられた茶袋内に収容されること、刈刃から背面風の吹出口までの距離が 比較的長いものに本発明を適用する場合、背面風による負圧吸引作用は幾 らか低下することが考えられるため、圧力風を振り分けて生じさせた正面 風により、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましいことを理解 できる。
ウ 以上の各記載によれば、本件発明1の「圧力風」とは、移送ダクトの内 部に流される空気流であって、背面風及び刈刃前方からの補助的な送風で ある正面風を含むものであり、「圧力風の作用のみによって」とは、刈り 取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が上記のよ うな「圧力風」の「作用」だけで実現されることと解するのが相当であり、 「圧力風」の「作用」以外の作用が加わって上記移送が実現される場合に は、「圧力風の作用のみによって」を備えるとは認められないというべき である。
(2) 被告各製品が「圧力風の作用のみによって」(構成要件A)を備えるか\n
ア 証拠(甲4ないし6、乙6、8)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の回転ブラシはブラシシャフト及びこれに取り付けられたブラシから成 り、ブラシシャフトが回転することに伴ってブラシが回転する構造をして\nいること、被告各製品の回転ブラシR、刈刃(22')、移送ダクト(6')、吹出 口(38')及び収容部(4')の構造の概要は、別紙概要断面図記載のとおりであ\nり、被告各製品による摘採作業中、回転ブラシRは、160ないし300 rpmの回転数(1秒当たり2.6ないし5回転)で、茶枝葉を移送ダク ト(6')にかき込む向き(別紙概要断面図でいえば、時計回り)に回転し、 刈刃(22')後方の吹出口(38')から上方(W')に向かって吹き出した圧力風は、 移送ダクト(6')内を収容部(4')に向かって流れること、回転ブラシの高さ は、被告各製品のうち3段階調整方式のものは上下に約50mmずつ3段 階で、5段階調整方式のものは上下に約40ないし60mmずつ5段階で、 それぞれ調整することができることが認められる。これによれば、被告各 製品は、その摘採作業中、摘採する長さに合わせて高さを設定した回転ブ ラシが高速で回転して刈刃により刈り取られた茶枝葉を移送ダクト内にか き込み、移送ダクト内を流れる圧力風が茶枝葉を収容部まで移送する構造\nを有するということができる。
そして、証拠(乙9、10)によれば、被告各製品の取扱説明書には、 茶枝葉を長く刈り取る場合は回転ブラシを高く調整し、短く刈り取る場合 はこれを低く調整し、ブラシシャフトと芽の高さが同じくらいになるよう に設定する必要があり、回転ブラシの高さが適切に設定されなければ、茶 枝葉をスムーズに刈り取ることができない旨が記載されていたことが認め られ、これによれば、被告各製品は、刈り取る茶枝葉の長さに合わせて回 転ブラシを設定することが予定されていたということができる。さらに、被告各製品による摘採作業中、操縦者が回転ブラシを任意に回転させたり、回転させなかったりすることができることを認めるに足りる証拠はない。\n
以上によれば、被告各製品においては、回転ブラシを摘採する茶枝葉の 長さに応じて適切な高さに設定することを前提とし、刈刃により刈り取ら れた茶枝葉は、摘採作業中、常時回転するブラシに当たって移送ダクト内 に送り込まれ、その後、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風 により、移送ダクト内を通り、収容部に到達すると認めるのが相当である。 したがって、被告各製品においては、「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の 位置」までの移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることによって実現されているといえるから、被告各製品は「圧力風 の作用のみによって」を備えるものとは認められないというべきである。
イ これに対して、原告は、原告各実験結果によれば、回転ブラシを備える 被告各製品と回転ブラシを取り外した被告各製品とで摘採量に有意な差は なく、むしろ回転ブラシを取り外した被告各製品の方が摘採量が多いこと もあり、被告各製品は回転ブラシがなくても背面風(圧力風)の作用のみ によって茶枝葉を移送することができるので、「圧力風の作用のみによっ て」を備えると主張する。
しかし、前記(1)のとおり、「圧力風」以外の作用が加わって上記移送が 実現されている場合は、「圧力風の作用のみによって」を備えないという べきであるところ、被告各製品については、前記アのとおり、回転ブラシ を摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定した上で摘採すること が予定されており、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、常時回転する回転\nブラシに当たって移送ダクトに送り込まれた上で、上向きに吹き出し、移 送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達す ることからすると、「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることなく、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」 までの移送が実現されているということはできない。
また、前記(1)の「圧力風の作用のみによって」(構成要件A)の解釈に\nよれば、被告各製品が「圧力風の作用のみによって」を備えるというため には、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わっていない必要があるから、 回転ブラシを備える被告各製品における茶枝葉の移送態様自体が検討され るべきであり、回転ブラシを備える被告各製品による摘採量とこれを取り 外した被告各製品による摘採量とを比較することによっては、「圧力風の 作用のみによって」を備えるか否かを明らかにすることはできないという べきである。
以上によれば、被告各製品においては、刈り取られた茶枝葉、回転ブラ シ、移送ダクト等の位置関係等からして、回転ブラシの回転作用が加わっ て茶枝葉の移送が実現されているといえ、原告各実験結果については、直 ちにこれらを採用することは困難であるといわざるを得ない。したがって、 原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.07.19
令和4(ネ)10021 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明2の特許請求の範囲の請求項2(「化合物が、式IにおいてR3およびR2はいずれも水素であり、R1は−(CH2)0−2−iC4H9である化合物の(R),(S),または(R,S)異性体である請求項1記載の鎮痛剤」)の記載に照らすと、本件発明2の化合物は、本件発明1の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明2の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが(前記1(2)及び(4))、一方で、本件発明2の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明2の化合物に該当するCI−1008及び3−アミノメチル−5−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、CI−1008を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明2の化合物に該当するS−(+)−3−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある(前記1(3)、(6)、(7)及び(9))。
しかし、前記(1)オ(ア)dの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明2の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明2の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明1の化合物の範囲に含まれる本件発明2の化合物が、本件発明1及び2の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明1及び2の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明1及び2は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明3は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するGABA類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第1要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載(前記1(4))によれば、本件発明3は、本件発明3の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の3つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと(前記2(1)オ(ア)a)に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明3において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明3の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明3に係る特許請求の範囲(本件訂正後の請求項3)に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明3の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第1要件を満たさない。\n
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19925等
特許権は同じで、被告(被控訴人)が異なる事件(1)です。
令和4(ネ)10009
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19927
被告(被控訴人)が異なる事件(2)です。
令和4(ネ)10002
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22283
被告(被控訴人)が異なる事件(3)です。
令和4(ネ)10012
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19924
被告(被控訴人)が異なる事件(4)です。
令和4(ネ)10020
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19929
被告(被控訴人)が異なる事件(5)です。
令和4(ネ)10013
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19917
被告(被控訴人)が異なる事件(6)です。
令和4(ネ)10016
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19918等
被告(被控訴人)が異なる事件(7)です。
令和4(ネ)10039
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19919
被告(被控訴人)が異なる事件(8)です。
令和4(ネ)10028
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19920等
被告(被控訴人)が異なる事件(9)です。
令和4(ネ)10015
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19922等
被告(被控訴人)が異なる事件(10)です。
令和4(ネ)10036
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19923等
被告(被控訴人)が異なる事件(11)です。
令和4(ネ)10017
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19926
被告(被控訴人)が異なる事件(12)です。
令和4(ネ)10003
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19928
被告(被控訴人)が異なる事件(13)です。
令和4(ネ)10037
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19931等
被告(被控訴人)が異なる事件(14)です。
令和4(ネ)10025
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19932
被告(被控訴人)が異なる事件(15)です。
令和4(ネ)10026
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22290等
本件特許の無効審判事件の審取です。
令和2(行ケ)10135
審決は、「訂正後の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効、請求項3,4に係る発明についての本件審判の請求は,成り立たない。」と判断していました。
知財高裁は、審決維持です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.07. 4
令和2(ワ)29604 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月27日 東京地方裁判所
ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は1%以下であるとも記載されている。(甲26)
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 3.5% 9.5% 0.5%
コンピュータテクノロジー3.1% 7.5% 0.5%
電気 2.9% 9.5% 0.5%
司法決定 電気 3.0% 7.0% 1.0%
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、11社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある1社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー1件当たりのライセンス料率は、 平均●(省略)●%であると計算された。(乙14) また、前記 の10社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●(省略)●%から逓減する特殊な規定となっていた1社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、1件当たりのライセ ンス料率は、平均●(省略)●%と計算された。(乙16) 平成20年5月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「HDTV対応によって、大画面 テレビなど周囲のAV機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が\n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。(甲29・43頁) 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな4〜5型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精\n細化してHDTV対応にできる」」との記載もある。(甲29・59頁) 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。(弁論の全趣旨)
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を0.5%ないし9.5%程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許1件当たりで計算した実施料率が、0.01%を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品\nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、\nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、0.01%の限度で認めるのが相当である。\nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、24 00円程度の部品(甲31)を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その\n2400円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.06.30
令和4(ワ)3374 特許権侵害行為差止等請求事件(承継参加) 特許権 民事訴訟 令和4年6月20日 大阪地方裁判所
このように、甲6食品実験等と乙12実験等の結果は異なっているところ、 前記2(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるLED5)が青色 発光するのは、パーシャル室を(チルドではなく)微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−3度 から約−1度に保たれることになるから、乙12ないし乙15の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙12、13実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は5〜47.8度(至適増殖温度は30〜37度)であり、枯\n草菌の一般的な増殖可能温度域は5〜55度(最適発育温度帯は20〜4\n5度)であること(乙12、13に添付の参考資料)と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲6実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲15食品実験及び甲15培\n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙12実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲6食品実験等を採用 することはできず、乙12実験等によるべきである。 そして、乙12、13実験等によると、そもそも本件製品において青色L EDが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙15実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が6つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき(本件測定器具の精度については議論があるものの)精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色\n光の照射を受けなかった豚肉の方が3日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度(光量子束密度)は、白色光等他の波長域の光も含めて最大7μE/m2/s 程度であって(乙8)、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、LED4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと(光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと)を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」(構成要件B)を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。\n争点1についての原告の主張(請求原因)は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記2のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点3−7(乙36公報記載の乙36発明に基づく新規性欠如の有無) を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙36公報に記載された「FL-40SB(東芝電気(株))」 は、混在する光を発することを指摘して、乙36公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ400nm から490nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと(構成要件B)\nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す\nる。 しかし、前記(2)によれば、乙36公報の特許請求の範囲第2項は「500 nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙36公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも500nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、(中略)更に好ましくは、360nm か ら400nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、400nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−2についてはおよそ400nm〜500nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−11にあっては、枯草菌に前記光源−2を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙36公報に接した当業者は、波長が400 nm〜500nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙36発明が開示されていると容易に理解し得るものである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.06.21
令和3(ネ)10102 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月8日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
当裁判所も、被告各製品は本件各発明の構成要件1E4)等をいずれも充足し ないものであるから、本件各発明の技術的範囲に属せず、したがって、その余 の点について判断するまでもなく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと 判断する。
その理由は、後記1のとおり原判決を補正し、後記2に当審における当事者 の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第4の 1及び2に記載されたとおりであるから、これを引用する。
・・・
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は、前記第2の5(1)アのとおり、本件各発明の「係止片」は、1)片 状の部材であり、2)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、3)大径部に円 筒状部と一体形成され、4)小径部側には設けられていないものをいうから、 上記構成要素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられて\nいても構成要件1E4)等の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの 主張もこのような理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第4の1(1)エ(補正後のもの)のとおり、 本件各発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機 能を有する係止片は小径部側には設けられていないこととされている(係止\n片が小径部側に設けられていないことに特有の技術的意義がある。)と理解 するのが相当であり、したがって、小径部に設けられることで構成要件1E\n4)等の充足が妨げられる係止片は、その形状を問われないものというべきで あるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小径部側に存する\nことは、対象製品が構成要件1E4)等を充足することを妨げるものである。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」(へん)状の部材であるから、「係止片」とは「片 状(へんじょう)の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件各発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判 断に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を 片状のものに限定する意義は見いだせない。以上によれば、控訴人の上記主張は、いずれも採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.06. 6
令和3(ネ)10022 特許権侵害に基づく不当利得返還等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審原告は,本件各発明は「ユーザの発信地域ごとに異なるWebデー タの送信が可能なWebページ閲覧システムを提供することを目的とす\nる」(本件明細書等の段落【0013】)ことから,この目的を達成する ための地域判別の原理は,回線網の敷設地域とISPのサーバが保有する 一群のIPアドレスとの一定の対応関係の存在を利用したものであるとし て(原判決「事実及び理由」第3の1(原告の主張)(2)〔原判決12 頁〕),「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈として,第一義的 には,「ユーザ端末に割り当てたIPアドレスを所持しているアクセスポ イントに通常アクセスするユーザの地域」と解釈すべきであり,「IPア ドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷 設範囲に相当する地域」も同義であると主張し,また,本件各発明は,設 置場所に対応する地域がユーザ端末の存在する地域と対応することに基づ いて,その地域に関連する情報を提供するというエリアターゲティングを 目的とする発明であるから,そもそも,アクセスポイントの「設置場所」 といった地点を判別する意味はなく,「アクセスポイントの設置場所」 (アクセスポイントが属する地域)を判別するステップを介するかどうか を問題とすること自体が誤りであると主張する(原判決「事実及び理由」 第3の1(原告の主張)(5)ア(ア)〔原判決16頁〕)。
しかしながら,特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づい て定めなければならず,特許請求の範囲に記載された用語の意義は,明細 書及び図面を考慮して解釈すべきであるところ(特許法70条1項・2 項),構成要件1B2等において「判別」の対象となっているのは文言上\nあくまで「アクセスポイントが属する地域」であるから,本件特許請求の 範囲の用語の意義としてアクセスポイントの設置場所を無視することはで きない。また,本件明細書等の記載を考慮すると,本件各発明は,ダイヤ ルアップ接続を前提として,ユーザ端末がアクセスポイントの設置された 地点の近傍に所在する蓋然性が高いという経験則を利用して,そのアクセ スポイントの設置場所の近傍をユーザが所在する地域と想定することによ って,ユーザの所在する地域に対応した地域情報をある程度の確率で提供 することができるという技術的思想に基づくものであること,したがって, 「アクセスポイントに対応する地域」等は「アクセスポイントの設置され ている地点とその近傍の一定の地域」と解釈されるべきことは前記⑴のと おりであるから,まさにアクセスポイントの設置場所を判別することに意 味があるのであって,一審原告の上記主張は採用することができない。 そして,このことは,本件特許の出願経過からも明らかである。すなわ ち,本件特許の出願経過は原判決「事実及び理由」第2の2(2)イ記載のと おりであるが,一審原告は,出願経過中の本件補正により,「IPアドレ スと地域とが対応したIPアドレス対地域データベース」を「IPアドレ スとアクセスポイントに対応する地域とが対応したIPアドレス対地域デ ータベース」とし,さらに「IPアドレスが属する地域」を「IPアドレ スを所有するアクセスポイントが属する地域」(甲12の13)として, 自ら「アクセスポイントが対応する」及び「アクセスポイントが属する」 をあえて付加している。そして,一審原告は,意見書(甲12の14)に おいて,「アクセスポイントが属する地域を判別することについて は,・・・ユーザの発信地域は,ユーザ端末101aがアクセスポイント 109aに接続しているため,正確にはアクセスポイント109aに対応 する地域である」と説明し,さらに,本件拒絶査定不服審判における審判 請求書(甲12の16)において,「・・・,IPアドレス対地域データ ベースにおいてはIPアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域, 例えば県や市,さらには市よりも狭い地域を対応付けておくことによって, ユーザ端末が接続しているアクセスポイントの属する地域から,ユーザ端 末の地域を県単位,市単位または市よりも狭い地域単位で判別することが できるという顕著な効果を奏します」と述べている。このように,一審原 告自らが「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈につき,IPアド レス毎にアクセスポイントが設置された地域を対応付けることを意味する ものと主張していたものである。
さらに,一審原告が主張するところの「アクセスポイントに通常アクセ スするユーザの地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線 網等の敷設範囲に相当する地域」は,そもそもどのような範囲を意味する のか必ずしも明らかではないが(特に「物理的回線網の敷設範囲」という 用語は本件明細書等にはない用語であり,ダイヤルアップ接続を前提とす ると,ダイヤルアップ接続においてユーザは世界中のどのアクセスポイン トへも接続が可能であるから,「物理的回線網の敷設範囲」という限定の\n仕方はアクセスポイントの地域を限定する意味を持たないと解される。), 一審原告の主張から推測するに,NTT東西が構築した地域IP網を念頭\nに置いて,地域IP網を経由する接続においては,ダイヤルアップ接続と は異なり,アクセスポイントは各地域IP網エリア単位で固定されていて, ユーザがアクセスポイントを選択することができないことから,アクセス ポイントが設置されている場所がどこであるかにかかわらず,「アクセス ポイントの属する地域」を「アクセスポイントに通常アクセスするユーザ の地域」又は「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範 囲に相当する地域」と解釈しているものと推認される。しかしながら,前 記1(2)イのとおり,そもそも「地域IP網」が現れたのは,平成11年以 降のことであり,本件特許出願時(平成10年6月26日)には存在しな い仕組みであって,出願当時に存在した技術常識ともいえず,当然,本件 明細書等には記載も示唆もされていない。したがって,特許請求の範囲に 記載された用語の意義を解釈するに当たり,上記事実を参酌することはで きないというべきである。 この点に関して一審原告は,本件各発明は,実施例にあるダイヤルアッ プ接続に限定されるものではなく,地域IP網経由の接続も含むものであ る旨主張する。
しかしながら,本件明細書等には,「・・・もちろん,ユーザの発信地 域以外の地域の情報を閲覧したい場合には,ユーザが発信地域以外の地域 のアクセスポイントに接続するか,従来と同じ方法を用いて従来と同じ方 法を用いて選択すればよいことはいうまでもない。」(段落【003 8】)と記載されているところ,この記載は,ユーザが任意の地域のアク セスポイントを選択して接続することを意味するものであって,このよう なアクセスポイントのユーザによる選択はダイヤルアップ接続では可能で\nあるもの,地域IP網経由の接続では通常は想定されていないものである。 そうすると,本件特許の技術的範囲を,地域IP網経由の接続を前提とす る事項まで拡大することは,本件明細書等に開示された技術的範囲を逸脱 することになるというべきである。本件各発明がダイヤルアップ接続を前 提としているという解釈は実施例に限定した解釈ではない。 いずれにしても,上記「アクセスポイントに通常アクセスするユーザの 地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲 に相当する地域」との解釈は,本件特許請求の範囲の記載からかけ離れた 解釈であり,採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.05.13
令和2(ワ)3297 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月22日 大阪地方裁判所
前記(ア)及び(イ)の「収納」の字義、本件訂正後発明1に係る請求項の記載 内容に照らすと、ケーシングに「収納」するとは、長尺部材の全部がケーシング 内に完全に収まることを要するものではなく、ケーシングと長尺部材の位置関係 として、ケーシングにしまわれている状態(整然と入れられた状態)を意味し、 少なくとも、ケーシングの開口部を含めたケーシングの内部に長尺部材の大部分 が入れられている状態はこれに当たると解するのが相当である。
(エ) 前記(1)のとおり、被告製品の押さえローラーは、マグネットスクリーン シートの巻き出し及び巻き取りのための開口部付近に、同シートと接するように 配置されている。また、別紙「写真目録」の写真に示されるように、被告製品の 押さえローラーは、本体ケースの内側にその全部が収まっているものではないが、 キャップ(側板)に支持されており、その大部分が本体ケースに覆われているこ とから、構成要件 1D-1 のケーシングに相当する、本体ケース及びキャップにし まわれている状態であるといえる。 したがって、被告製品の押さえローラーは、本体ケース及びキャップに収納さ れていることから、被告製品は、構成要件 1D-1 を充足する。
イ 被告の主張について
(ア) 被告は、本件訂正後発明1において、長尺部材がケーシングの開口部の内 側に位置付けられるのは、スクリーンシートが長尺部材によって局所的に抑え込 まれ、シート全体に張力を与えて端部(特に長手端部)までピンと張った状態で スクリーンシートを設置面に展張保持できるようにすることを実現するための ものであるところ、長尺部材がケーシングの縁どりから外側に突出していると、 その作用効果が阻害される旨を主張する。
そこで、長尺部材の技術的意義について検討する。本件訂正後発明1は、マグ ネットスクリーン装置に関する発明であるところ、従来のマグネットスクリーン 装置には、使用に際して巻き出されたスクリーンシートを設置面に展張保持した 際に“カール”と呼ばれる現象、すなわち、非使用時のスクリーンシートの巻回 形態が“くせ”として残り、巻き出し後も依然として反映される現象が生じ、か かるカールによってプロジェクターから投影される像を所望に映し出すことが できない技術的課題があった(【0005】〜【0007】)。これに対し、本件訂正後 発明1は、非使用時ではマグネット面が投影面に対して相対的に内側となるよう にスクリーンシートがロール部材に巻き取られている構成にすることによって\n(【0009】)、スクリーンシートを巻き出した際、そのシート長手端部では局所 的に湾曲しようとする力が働くものの、その湾曲方向は設置面側となっており、 スクリーンシートが設置面にむしろ貼り付くように作用し、ロール部材に巻かれ\nていた時の“くせ”をスクリーンシートが有する場合であったとしても、それは 設置面に貼り付くように好適に作用するので、スクリーンシートを“カール”の\n発生なく展張保持することを可能とした(【0019】)。一方、かかる構成にする\nことによって、スクリーンシートの巻出し又は巻取りがロール部材の“設置面遠 位側”からなされることになるから(【0036、図6】)、スクリーンシートが設 置面から浮き上がる方向に作用する。すなわち、ロール部材におけるスクリーン シート巻き出しポイント又はスクリーンシート巻き取りポイント(図7。長尺部 材を設けない場合において、スクリーンシートを巻き出し又は巻き取った際のス クリーンシートとロール部材の離別箇所又は接触箇所)がロール部材の上側半分 に位置付けられることとなる(【0037】、【0038】)。そこで、長尺部材は、使 用に際して「巻き出される又は巻き取られるスクリーンシートと接するように」、 「開口部に位置付けられ」、「設置面に対して相対的に近い側に位置付けられる ロール部材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」(構成要件 1D-4)ることに より、スクリーンシートを投影面側から設置面側に向かって局所的に抑え込む機 能を有するものである(【0030】、【0048】)。長尺部材が前記機能を発揮する\nためには、長尺部材がない場合にスクリーンシートが自重や磁着力等により設置 面に自然に接する地点よりもロール部材側でスクリーンシートに接する地点に 存すれば足りるといえる。そうすると、長尺部材の技術的意義からみた場合、必 ずしも、長尺部材はケーシングの内側に完全に位置する必要まではないと解する のが相当である。加えて、本件明細書1において、「展張保持」は、スクリーン シートを広げた状態の維持という意で使用されており(【0003】、【0005】、【0019】等)、シート全体に張力を与えながらスクリーンシートを張る作業自体を指すも のではないし、同作業を経て張られた状態を指すものでもない。したがって、長 尺部材の技術的意義から、「収納」の意義について長尺部材が必然的にケーシン グの完全な内側に位置づけられることを示すものと解することはできない。 また、被告は、本件明細書1には、「本発明のマグネットスクリーン装置10 0では、スクリーンシート10、ロール部材20および長尺部材30がケーシン グ40内に収納されている。より具体的には、ロール部材20に対して巻回保持 されたスクリーンシート1がケーシング40の内部に収められており、かかる巻 回状態のスクリーンシート10に隣接して長尺部材30も同様にケーシング4 0内に収められている。」(【0044】)との記載がある旨も指摘する。しかし、 これは、本件特許1に係る発明のスクリーン装置の具体化態様に関するものであ るから(【0042】)、当該記載があるからといって、「収納」の意義が「内部に 収められていること」に限定されることにはならない。
(イ) 被告は、被告製品において、キャップは「ケーシング」を構成しないこと、\n仮にキャップが「ケーシング」を構成するとしても、被告製品は、キャップの縁\nどりとケーシングの縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラ\nーの半分以上がはみ出した構造であるから、いずれにしても押さえローラーはこ\nれらに「収納」されていない旨を主張する。 確かに、本件明細書1では、「ケーシング40が「第1サブ・ケーシング40 A」と「第2サブ・ケーシング40B」とから構成されている」(【0044】)と 記載されており、ケーシング40の側面を覆う部材がケーシングに含まれること は明記されていない。しかし、一方で、本件明細書1において、「ロール部材2 0は、その端部がケーシングの内壁に取り付けられており」(【0046】)、「ケ ーシングに取り付けられた突起具48」(【0058】)などとされており、ケーシ ング40の側面を覆う部材がケーシングを構成することを前提とした記載がな\nされている。また、本件訂正後発明1に係る請求項1は、ケーシングに関し、「ス クリーンシート、ロール部材及び長尺部材を収納するケーシングを更に有して成 り、」、「ケーシングはスクリーンシートの巻き出しおよび巻き取りのための開 口部を有し、」と記載されているに留まり、開口部を有することを除いて、ケー シングの意義について特段の限定を加えるものではない。そうすると、本件訂正 後発明1において、ケーシングとは、スクリーンシート等の部材を外側から覆う 部材であると解するのが相当であり、このうち側面部分についてのみケーシング から除外するべき理由はない。
また、被告は、被告製品を設置面側から観察することを前提として(別紙「写 真目録」の写真4参照)、被告製品について、キャップの縁どりとケーシングの 縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラーの半分以上がはみ\n出した構造である旨を主張するものと解されるが、同目録の写真1ないし3から\nすると、被告製品の押さえローラーはケーシング(本体ケース及びキャップを含 む。)の開口部を含めたケーシングの内部に大部分が入れられているものと認め られ、ケーシングにしまわれている状態にあるといえる。押さえローラーがケー シングにしまわれている状態か否かは、投影面側又は設置状態における側面側を 含む被告製品の全体を観察して判断すべきであって、使用状態において視認され ない設置面側からの観察に限定すれば押さえローラーがケーシングから多くは み出しているように見えるからといって、ケーシングにしまわれている状態にな いと判断する合理的理由はない。
・・・
(3)ア 本件訂正後発明1と引用発明1−1とを比較すると、引用発明1−1 の 1a〜1e の各構成は、本件訂正後発明1の各構\成要件とそれぞれ一致するもの と認められる。
イ これに対し、原告は、引用発明1−1においては、開口部からスクリーン 本体4を巻き出す又は巻き取る際には、スムーズな巻き出し又は巻き取りを可能\nにし、スクリーンシートを傷付けることを防止するために押さえ部5を、敢えて、 被磁着体90から離した態様(第1配置態様)で行うものであって、押さえ部5 を被磁着体90に近接させた態様でスクリーン本体4を巻き出す又は巻き取る という技術的思想はないことを指摘し、1)本件訂正後発明1では、長尺部材が「非 使用時並びに巻き出し時及び巻き取り時において、ケーシングに収納されて」(構\n成要件 1D-1)いるのに対し、引用発明1−1においては、押さえ部5が収納ケー ス2に「収納」されていない、2)本件訂正後発明1では、長尺部材が「ロール部 材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」(構成要件 1D-4)ているのに対し、 引用発明1−1においては、押さえ部5は巻取りロール3の下側ロール胴部分に 隣接した位置から離れないよう設置されているものではないとして、引用発明1 −1は、本件訂正後発明1の構成要件 1D-1 及び 1D-4 において相違する旨を主張 する。
しかし、乙10公報記載の特許請求の範囲請求項2において、「押さえ部」は、 「前記張設されたスクリーン本体における前記巻取りロールに近接した部位を ・・・被磁着体側に向けて押さえ付け得るものとなされている」ところ、同請求項2 では、「前記収納ケースに取り付けられた押さえ部と、を備え」と特定されてい るに留まり、収納ケースに対し押さえ部が可動か否かについては記載されていな い。一方、同請求項2に従属する乙10公報記載の特許請求の範囲請求項3では、 「前記押さえ部は、前記収納ケースに対し移動可能に取り付けられ」と押さえ部\nが可動であることが明記されている。また、乙10公報には、請求項2の発明の 効果として、押さえ部によって、巻取りロールに近接した部位をも被磁着体に磁 着させた状態でスクリーン本体を張設することができ、張設されたスクリーン本 体のスクリーン層の略全面を有効面として使用することができる旨が記載され ている(【0019】)一方、請求項3の発明の効果として、収納ケースに対し移動 可能に取り付けられた押さえ部を移動させ、被磁着体から離れた第1配置態様に\nすることで、スクリーン本体の引き出し操作、巻き取り操作をスムーズに行うこ とができ、被磁着体に近接した第2配置態様にすることで、スクリーン本体にお ける巻取りロールに近接した部位を幅全体にわたって被磁着体側に向けて押さ え付けることができる旨が記載されている(【0020】)。これらの乙10公報の 記載内容に照らすと、引用発明1−1において、押さえ部は、スクリーン本体の 巻取りロールに近接した部位をも被磁着体側に向けて押さえ付けるとの機能を\n有し、被磁着体に磁着させた状態で張設されたスクリーン本体の略全面を有効面 として使用することができるとの効果を奏するものとされるのであるから、引用 発明1−1には、押さえ部5を被磁着体90に近接させた態様でスクリーン本体 4を巻き出す又は巻き取るという技術思想が表れているといえるし、また、乙1\n0公報記載の特許請求の範囲請求項2には、押さえ部が移動可能でないものが含\nまれると解するのが相当である。そして、乙10公報の図1、2からすると、押 さえ部5を移動可能でないものとした場合において、押さえ部は収納ケース2に\n収納されているものと認められる。なお、乙10公報上、実施形態や他の実施形 態では、収納ケース又はケース本体に対して押さえ部又は可動体の先端部が可動 なもののみが記載されているが(【0029】)、請求項2との関係においては、付 加的な効果を奏する実施例の一つにすぎず、前記認定を左右するものではない。 以上によれば、引用発明1−1において、押さえ部5が収納ケース2に収納さ れる構成、及び、押さえ部5が巻取ロール3の下側ロール胴部分に隣接した位置\nに固定して設置された構成を有するものと認められ、本件訂正後発明1の構\成要 件 1D-1 及び 1D-4 と一致する。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
2022.05. 5
平成30(ネ)10034 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記の各種実験結果によると、被告製品は、長時間の塩水噴霧試験(乙 14実験)、試験紙を用いた湿気の流入実験(乙19実験、乙20実験) の結果からすると、端部部材だけで外部雰囲気(湿気や水等の流体物) の流入を遮断するものとはいえないが、同じ場所に10数滴の液体を滴 下したり(乙15実験の第2実験)、連続して液体を注入したり(甲4 9実験の実験2)、液体を滴下後に強い衝撃を加える(乙15実験の第 3実験、甲49実験の実験3)といった条件がない限り、少量の水滴を 滴下した実験では、端部部材だけでも液体の流入は抑制されており(甲 33実験、甲49実験の実験1)、また、湿気の流入も短時間であれば 抑制されている(甲58実験の試験1及び試験2)ことからすると、被 告製品の端部部材は外部雰囲気(湿気や水等)の進入を抑制するものと いえる(なお、乙15実験の第1実験は、被告製品の端部部材及びOリ ングのみならず弁本体側のOリングも外しており、甲50実験の試験結 果からすると、上記認定を左右するものではなく、また、乙16実験は、 圧縮機の取付孔側面に穴を穿設しており、実験条件の前提が異なるため、 上記認定を左右するものではない。)。
また、乙1実験、乙14実験、甲49実験、甲58実験、乙19実験 及び乙20実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材(Oリング) を備えた被告製品においては、外部雰囲気(湿気や水等)の流入が完全 に抑制されていることが認められる。 そうすると、被告製品は、端部部材(H)をボディ の上部側の開口部 に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材 の構\n成を備えることにより、ボディ と取付孔の間を密封して外部雰囲気の 流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は、構成要\n件B6の「『密封』嵌合」の文言も充足する。 したがって、被告製品は、構成要件B6を充足する。\n
・・・
引用に係る原判決第3の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 のと おり、被告製品の構成につき、控訴人は、原判決別紙被告製品目録(原告)\n(以下「原告作成目録」という。)記載のとおりであると、被控訴人は、 同被告製品目録(被告)(以下「被告作成目録」という。)記載のとおり であるとそれぞれ主張する。原告作成目録の写真2と被告作成目録の写真 1がそれぞれ被告製品の外観形状を、原告作成目録の図1と被告作成目録 の写真2がそれぞれ同内部構造を明らかにするものであるところ、これら\nを対比すると、被告製品の構成部材の名称や配置についてはほぼ争いがな\nく、争いがあるのは、ソレノイドと弁本体の境界をどの部分と位置付ける\nかに関してのみであり、この点に関する当事者双方の主張は、上記原判決 第3の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 及び のとおりである。 そこで、原告作成目録の図1と被告作成目録の写真2を見ると、いずれ においても構成要件B8の「プランジャ」は「プランジャ 」、「バルブ」 は「弁本体(V)」、「ロッド」は「作動ロッド 」にそれぞれ当たり、「作 動ロッド 」は電磁コイル を含むボディ やシール部材 より下部まで 上下に可動する構成となっている。そして、前記アにおいて説示したとお\nり、ロッドは、本件発明におけるソレノイドの一部を構\成するものといえ るから、本件発明における「ソレノイド」部は、控訴人が主張するとおり、\n原告作成目録の図1の「ソレノイド 」の矢印で示される範囲までを指す ものと理解するのが相当である。そうすると、同図1のとおり、被告製品 におけるシール部材 は、本件発明との対比におけるソレノイド の部分 (ソレノイド の下端側である弁本体(V)側)の外周に設けられたもので あり、弁本体(V)からの流体の進入を防止するものであるといえる。
・・・
被告製品は、構成要件B6及びCを充足するものであり、その他の構\成要 件の充足性については引用に係る原判決の第2の2 のとおりであるから、 争点2(均等論)について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属 するものである。
・・・
被告製品の実施料率について判断する。 甲79報告書によれば、日本国内で特許出願を行った国内企業・団体 のうち上位となっている企業・団体(対象2031件)及び株式会社帝 国データバンク保有データ信用調査報告書ファイル(約143万社収録) の中からライセンス契約を実施していると判断できる企業(対象975 件)につき、重複データを削除した合計3006件を調査対象とし、平 成21年11月5日から平成22年2月15日までを調査対象期間とし て、技術分類別ロイヤルティ率のアンケート調査を実施した結果(有効 回答は563件)によると、本件発明に最も近い技術分野である「精密 機械」のロイヤルティ率は、最大値9.5%、最小値0.5%、平均値 3.5%であった(同報告書52頁)ことが認められる。また、同報告 書によると、実施料の決定要因の重要度としては、1)当事者におけるラ イセンスの必要性、2)ライセンス対象(特許権の評価)の重要度が高い ことが挙げられている。
なお、控訴人は、前記第2の4 ウ【控訴人の主張】 のとおり、平 成4年度から平成10年までのデータによる実施料率〔第5版〕データ や平成10年3月30日言渡しの別件判決の説示を基にした主張もする が、平成27年から平成30年までの間の実施料率を問題とする本件で は参考とならず、採用の限りではない。
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合すると、本件 発明は、「ソレノイド」を備えた制御弁の発明であるが、その特徴的部\n分は、1)アッパーブレードの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を 塞ぐ端部部材と、2)取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材の 2つの構成を採用したことにあり、これらの構\成によって、外部雰囲気 (湿気や水等の流体)の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上\nさせるとともに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決め ができ、ボルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向 上するという効果を奏するものである。 これに対し、相手方ハウジング部材に取付孔を設けてこの部分に容量 制御弁を挿入するという技術は、本件発明の出願時には公知の技術であ る(乙8、9)。また、シール部材の配置については、原告製品2のよ うに、取付孔と端部部材の間のシール部材を設けることなく、腐食防止 のために鉄系材料にメッキを施して可変容量制御弁の耐久性を保つ代替 技術(従来技術。本件明細書の【0011】)があることから、ソレノ\nイドの耐食性の向上という観点からいえば、当事者のライセンスの必要 性の程度が高いとはいえず、特許としての重要度も高いとはいえない。 そして、被控訴人が●●●社向けに作成した、原告製品2との比較を 含む被告製品のプレゼンテーション資料(乙25)には、重要設計項目 として、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が 挙げられているように、弁本体の機能や動作性等が重視され、本件発明\nの上記特徴的部分については何ら言及されていないから、被告製品にお ける本件発明の実施の程度及びその価値は相対的に低いと言わざるを得 ない。
以上のような本件各事情を総合すると、前記 のとおり、控訴人と被 控訴人は、可変容量制御弁の分野では国際的にシェアを分かち合う競業 関係にあるといった事情を考慮しても、被告製品における本件特許の実 施料率は2%程度であると認めるのが相当である。 ウ ところで、前記 アのとおり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の共 有関係にあり、その持分割合について両社で特段の合意がされたと認める に足りないから、民法250条により共有持分は相等しい割合に推定され る。 そうすると、特許法102条3項による損害は、以下の計算式のとおり、 ●●●●●円であると認定するのが相当である。
[計算式] ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
特許法102条1項による損害について
・・・
c 原告製品2の限界利益額に関する覆滅事由について
前記3 イ のとおり、本件発明は、「ソレノイド」を備えた制御\n弁の発明であるが、その特徴的部分は、1)アッパープレートの外側で 取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材と、 2)取付孔と端部部材の間に配置されるシール部材の2つの構成を採用\nしたことにあり、これらの構成によって、外部雰囲気(湿気や水等の\n流体)の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上させるととも\nに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決めができ、ボ ルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向上すると いう効果を奏するものである。
前記 ウ のとおり、原告製品2は、取付性の向上及び端部部材に よる外部雰囲気(湿気や水等の流体)の進入の抑制といった本件発明 の作用効果を備えているといえるが、アッパープレードの外側で取付 孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備え ている(上記1)を備える。)ものの、端部部材と取付孔との間のシー ル部材(Oリング)を備えておらず(上記2)を備えておらず)、腐食 防止のために鉄系材料にメッキを施している。また、原告製品2は、 自動車に搭載するソレノイドを有する可変容量コンプレッサ制御弁で\nある以上、自動車メーカーとしては、外部雰囲気の進入の抑制という よりは、原告製品2の制御弁としての機能及び動作性に最も着目する\nものといえる。 このように、原告製品2は、本件発明の従来技術の課題とされてい る、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであるこ\nとや、原告製品2は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御 弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、\n原告製品2の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利 益と認めるのは相当ではないところ、原告製品2が備える機能等や顧\n客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利 益の全額から95%の覆滅を認めるのが相当である。
・・・
エ 控訴人が販売することができないとする事情
特許法102条1項1号に規定するところの侵害品の譲渡数量の全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少と相当因果関係を阻害する 事情であり、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存 在すること(市場の非同一性)、2)市場における競合品の存在、3)侵害者 の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、4)侵害品及び特許権者の製品の機 能(機能\、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在すること等の事 情がこれに該当するというべきである(前掲知財高裁大合議判決)。 以下これを前提として検討する。
前記第2の4 ア【被控訴人の主張】 aのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社の前身である●●●社及 び同社が買収した●社と被控訴人との間では、長年の取引関係があり、 被控訴人は、こうした取引関係を通じて構築された信頼関係に基づいて、\n●●●社との間で年間●●●●個に及ぶ被告製品の取引を行ってきたが、 控訴人は、●●●社の事業領域については何らの商圏を有していなかっ たのであるから、容量制御弁を年間●●●●個生産する能力があるとし\nても、せいぜい従前●●●社に納入していた程度の数量である●●万個 程度の数量しか販売することができなかったというべきである旨主張す る。
確かに、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社及び●社、●● ●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等の点で表彰を受\nけるなど、一定の信頼関係を築いてきたこと(乙36ないし40)は認 められるものの、前記 カ及びキのとおり、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●、こうした事情に照らせば、原告製品2 について本件侵害期間より前の期間に納入していた数量の限度でしか 販売することができなかったとはいえないから、被控訴人の上記主張は 理由がない。
前記第2の4 ア【被控訴人の主張】 bのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社は、防水手段についてメ ッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては 全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控 訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換する ことは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人が原告製品\n2を納入することができるというものではない旨主張する。 しかし、「販売することができない事情」で考慮されるべき事情は、 本件侵害期間中に原告製品2を被告製品の販売個数では販売することが できなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記の ような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由 がない。
前記第2の4 ア【被控訴人の主張】 cないしeのとおり、被控訴 人は、「販売することができない事情」として、●●●社の購入動機や 信頼関係の存否等につき主張する。 そこで、検討するに、前記 キによれば、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●被告製品を選択した理由の1つとして価格面を挙げている ことが認められる。実際、控訴人の担当部長が作成した報告書(甲67) の添付資料によると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●ことが認められる。被告製品が原告製品2と比 較して価格面で有利であったという点は、本件侵害期間中における原告 製品2の販売個数に少なからず影響する事情であるということができる。 また、前記 のとおり、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社 及び●社、●●●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等 の点で表彰を受けるなど、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係\nを築いてきており、実際のところ、●●●社が原告製品2から被告製品 に切り替えた理由の1つとして、被控訴人のサポート態勢等を挙げてい る。被控訴人が被告製品の販売個数を順調に維持することができた背景 には、こうした事情が影響しているものと認められるから、被控訴人と ●●●社との信頼関係の構築は、本件侵害期間中における原告製品2の\n販売個数に影響する事情であるといえる。 さらに、証拠(乙25、32、48)によれば、被控訴人は、原告製 品2と被告製品の起動性に関する対比実験を提示し(乙25)、●●● 社の仕様等に関する要望を受けて改良し、●●●社は、被告製品の制御 弁としての性能面を評価して被告製品を採用したことが認められるから、\nこうした事情は、本件侵害期間中において、被告製品の販売実績に相当 する原告製品2を販売し得たことを阻害する事情であるといえる。 以上で指摘した事情を総合考慮すると、侵害品である被告製品の譲渡 数量を控訴人が販売することができない事情に相当する数量は、譲渡数 量全体の2割であると認めるのが相当である。
・・・
なお、共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めを した場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をす ることができる(特許法73条2項。なお、本件では、控訴人が●●●● ●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠 はない。)ところ、特許法102条1項により算定される損害については、 侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなけ れば販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出さ れる額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲 渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情にも当たらないから、後記の同条2項による損害の推定における場合と 異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。
・・・
キ 特許法102条1項2号による実施料相当額ついて
前記エ のとおり、特許法102条1項1号の「その全部又は一部に相 当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができない とする事情」としては、侵害品である被告製品と原告製品2の価格差、被 控訴人によるサポート面や協力態勢の面で●●●社との間との一定の信 頼関係の構築、被告製品と原告製品2の性能\面の差異といった事情がある と認められる。
ところで、特許法102条1項2号は、括弧書で「特許権者・・・が、当該 特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許 諾・・・をし得たと認められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧 書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認めら れないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないこと を規定するものであると解される。 これを前提として本件についてみると、特許法102条1項1号に規定 する特定数量に該当するとされた事情は、上記のとおりであるところ、被 告製品と原告製品2の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被\n控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められな いが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前 提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセン スをし得たのに、その機会を失ったものといえる。 これらの事情を総合考慮すると、特定数量2割のうちライセンスの機会 を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の1割とするのが 相当である。
また、前記 アのとおり、本件侵害期間中の被告製品の1個当たりの販 売価格は●●●●●●●円(本件侵害期間の総販売金額●●●●●●●● ●●●●●●●円を、同期間における総製造数●●●●●●●●個で割っ た額(乙23参照)。)であり、前記 イのとおり、被告製品の実施料率 は2%程度とするのが相当であり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の 共有関係にあることも前記認定事実のとおりである。 以上を前提とすると、特許法102条1項2号により算定される控訴人 の損害額は268万円と認められる。
・・・
特許法102条2項による損害について
ア 覆滅事由について
本件侵害期間中における月別の被告製品の生産個数及び売上高は当事者 間に争いがないが、控除すべき経費の範囲及びその額について争いがある。 ところで、特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵 害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事 情がこれに当たると解され、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様等に 相違があること(市場の非同一性)、2)市場における競合品の存在、3)侵 害者の営業努力、4)侵害品の性能(機能\、デザイン等特許発明以外の特徴) 等の事情がこれに当たり、また、特許発明が侵害品の一部分のみに実施さ れている場合には、この点も、推定覆滅の事情として考慮することができ るが、特許発明が侵害品の一部分のみに実施されていることから直ちに上 記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の 侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的 に考慮して決するのが相当である(知財高裁令和元年6月7日大合議判 決・判例時報2430号34頁以下参照)。 控訴人は、特許法102条2項による損害の算定に当たり、覆滅事由は ないと主張しているところ、被控訴人は、1項ただし書と同様の事由、す なわち、1)●●●社における事情、2)代替品の納入が可能であること、3) 原告製品2と被告製品の性能に本件発明以外に相違があること、4)被告製 品が原告製品2と比較して低価格であること、5)被控訴人の市場開発努力、 営業努力、販売力の事情を指摘して、覆滅事由を主張するので、この点に つき、まず検討を加える。
前記 エで説示したのと同様に、●●●社が原告製品2の供給を打ち切 って被告製品を採用したのは、被告製品が原告製品2と比較して価格面で 有利であったこと、被控訴人は、●●●社及びその前身の●●●社(●● ●社が買収した●社を含む。)と長年取引関係にあって信頼関係を醸成し ており、被告製品の販売個数を順調に伸ばしてきたのはこうした事情が背 景にあるものと推認されること、被控訴人は、原告製品2と被告製品の起 動性に関する対比実験を提示し、●●●社の仕様等の要望を受けて改良し たことにより、被告製品の採用に至ったものと認められる。
こうした被告製品の価格面での優位性、被控訴人の企業努力等の事情に 加えて、被告製品における本件発明が実施されている部分の位置付け、本 件発明の顧客吸引力等の事情についてみると、被告製品は容量制御弁であ り、ソレノイドの耐食性や取付容易性といった本件発明の特徴的部分もさ\nることながら、弁本体の機能がむしろ重要であり(被控訴人が●●●社向\nけに作成した被告製品のプレゼンテーション資料(乙25)には、本件発 明の特徴的部分については何ら触れるところはないことは既に説示したと おりである。)、また、前記 イ のとおり、相手側ハウジング部材に取 付孔を設けてこの部分に容量制御弁を挿入するという技術は、本件発明の 出願時には公知の技術であり、密封構造に関しても、容量制御弁の高耐食\n性については、鉄製材料をメッキ処理するといった従来技術(代替技術) が存在していたことからすると、被告製品における本件発明の位置付けは 重要なものとはいえず、顧客吸引力も低いものと言わざるを得ない。 被控訴人の主張する覆滅事情は上記の限度で理由があり、これらの事情 を総合考慮すると、覆滅割合は9割とするのが相当である。
イ 本件特許が共有であることについて
本件特許権は、控訴人及び●●●●●●の共有に係るものであり、前 記 オで説示したとおり、●●●●●●は、少なくとも本件侵害期間中 において本件特許権を実施していない。 ところで、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定 めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施 をすることができる(特許法73条2項)。本件では、控訴人が●●● ●●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証 拠はないから、本件特許権の共有者である控訴人は、共有持分割合に応 じて特許法102条2項により推定される損害の按分割合に応じた損害 賠償を請求することができるにすぎない旨の被控訴人の主張は理由がな い。
他方で、実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず 請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施してい ない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法102 条3項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があ るところ、仮に、同条2項により推定される全額を共有に係る特許権を 実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利 益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る 特許権を実施する共有者が同条2項に基づいて侵害者が得た利益を損害 として請求するときは、同条3項に基づいて推定される共有に係る特許 権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、 侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条2項に より推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその 立証責任を負うというべきである。
次に、前記第2の4 イ【控訴人の主張】 のとおり、控訴人は、● ●●●●●が特許法102条3項に基づく損害賠償請求権について控訴 人が消滅時効を援用することにより、被控訴人は、控訴人に対して●● ●●●●の被控訴人に対する実施相当額を控除すべき旨を主張すること ができない旨主張する。 しかし、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、●●●●●● の被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分 であり、可分債権である●●●●●●の損害賠償請求権が時効により消 滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰 属したかのように控訴人がこれを行使することができるわけではないか ら、控訴人が●●●●●●の被控訴人に対して有する損害賠償請求権を 援用することができる正当な利益を有する者ではなく、控訴人の上記主 張は明らかに失当である。 もっとも、●●●●●●の特許法102条3項に基づく損害賠償請求 権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用するこ とにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重 払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリ スクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害 により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当 とはいえないというべきである。
ウ 損害額の算定
前記アのとおり、特許法102条2項に基づき、被控訴人が特許権侵害 により受けた利益の額を算定するに当たり、控除すべき経費については前 記第2の4 イ のとおり当事者間に争いがあり、仮に、被控訴人が主張 するところの覆滅事由を考慮せずに控訴人が請求する●●●●●●●● ●●●円を前提としたとしても、前記アの覆滅割合(約90%)分を控除 すると、●●●●●円である。そうすると、前記イ のとおり、●●●● ●●の特許法102条3項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅し ている場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する 余地があるものの、このような場合を仮定しても、特許法102条2項に より算定される損害額は、上記●●●●●円を上回ることはない。
小括
以上によれば、特許法102条1項による損害額は●●●●●円であり、 同条2項による損害額は●●●●●円を上回ることはなく、同条3項による 損害額は●●●●●円であるから、特許法102条により算定される損害額 は●●●●●円をもって相当と認める。 また、控訴人は、本件において弁護士及び弁理士に委任して訴訟を遂行し ているところ、被控訴人による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用及び弁理士費用は、本件事案の性質及び内容、認容額、本件事案の難易 度等を考慮すると、●●●●●円とするのが相当である。 そうすると、本件特許権侵害による損害額は8920万円となる。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成29年(ワ)3569号
「密封嵌合」とは,「ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもた\nらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度に,端部材が取付孔に対してぴっちり
と封をするように機械部品がはまり合う関係」を意味すると解されるところ,Oリン
グ(シール部材(13))を外した被告製品が,取付孔内部への水分の進入を抑制する効果
があるとは認められないのであるから,被告製品の端部材(H)が取付孔に「密封嵌合」
しているとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告製品は,構成要件B6の「該アッパープレートの外側で前記取付\n孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材」に係る構成を\n有しない。そうすると,被告製品は,その余の構成要件を検討するまでもなく,本件\n発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.05. 5
令和1(ワ)25152 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月24日 東京地方裁判所
2 争点1(準拠法)について
(1) 差止め及び除却等の請求について
特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された 国の法律であると解すべきであるから(最高裁平成12年(受)第580同 14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁)、本件の差止 め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日 本法が準拠法となる。
(2) 損害賠償請求について
特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題では なく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律 関係の性質は不法行為である(前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷 判決)。したがって、その準拠法については、通則法17条によるべきである から、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。 原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末 に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権 を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、 権利侵害という結果は日本で発生したということができるから、上記損害賠 償請求に係る準拠法は日本法である。
・・・
前記(1)のとおり、被告システム1は、構成要件1Bないし1F及び1Hを\n充足し、前記前提事実(6)アのとおり、被告システム1が構成要件1A、1G\n及び1Iを充足することは、当事者間に争いがない。 そして、前記(2)のとおり、被告システム2及び3は、構成要件1Aないし\n1F及び1Hを充足し、前記前提事実(6)イのとおり、被告システム2及び3 が構成要件1G及び1Iを充足することは、当事者間に争いがない。\nしたがって、被告システムは本件発明1の技術的範囲に属するものと認め られる。
(2) 被告FC2による被告システムの「生産」の有無について
ア 本件発明1の関係での被告システム1(被告サービス1のFLASH版) の「生産」について
本件発明1の「実施」として被告FC2による被告システム1の「生産」 があるといえるかを、まず、被告サービス1のFLASH版について検討 する。
(ア) 物の発明の「実施」としての「生産」(特許法2条3項1号)とは、 発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解され る。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること を意味する属地主義の原則(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年 7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12 年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7 号1551頁参照)からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに 限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当 たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内にお\nいて新たに作り出されることが必要であると解すべきである。
(イ) 前記3(1)のとおり、被告システム1は、本件発明1の構成要件を全\nて充足し、その技術的範囲に属するものであって、被告システム1にお ける構成1aないし1iは、本件発明1の構\成要件1Aないし1Iにそ れぞれ相当する。 また、被告サービス1のFLASH版においてコメント付き動画を日 本国内のユーザ端末に表示させる手順は、前記(1)ウ(ア)のとおりであっ て、被告サービス1がその手順どおりに機能することによって、上記の\nとおり本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムであ\nる被告システム1が新たに作り出されるということができる。 そして、本件発明1のコメント配信システムは、「サーバ」と「これと ネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とす\nる物であるところ(構成要件1A)、被告システム1においては、日本国\n内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これ\nとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存 在しているものといえる。
他方で、前記3(2)アによれば、本件発明1における「サーバ」(構成\n要件1A等)とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有\nするとともに(構成要件1B)、端末装置に「動画」及び「コメント情報」\nを送信する機能(構\成要件1C)を有するものであるところ、これに該 当する被告FC2が管理する前記(1)ウ(ア)の動画配信用サーバ及びコメ ント配信用サーバは、前記(1)イ(ア)のとおり、令和元年5月17日以降 の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在して いるものとは認められない。
そうすると、被告サービス1により日本国内のユーザ端末へのコメン ト付き動画を表示させる場合、被告サービス1が前記(1)ウ(ア)の手順ど おりに機能することによって、本件発明1の構\成要件を全て充足するコ メント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に 存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在 するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム(被告システ\nム1)が作り出されるものである。
したがって、完成した被告システム1のうち日本国内の構成要素であ\nるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことに\nなるから、直ちには、本件発明1の対象となる「物」である「コメント 配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることが できない。
(ウ) 原告は、被告システム1では、多数のユーザ端末は日本国内に存在し ているから、被告システム1の大部分は日本国内に存在している、被告 FC2が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外 の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大 部分は日本国内で行われている、本件発明1において重要な構成要件1\nHに対応する被告システム1の構成1hは国内で実現されている、被告\nシステム1については「生産」という実施行為が全体として見て日本国 内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバ を国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論とな るのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム1は、量的に見て も、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、 被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価すること ができると主張する。
しかしながら、前記(ア)のとおり、特許法2条3項1号の「生産」に該 当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内におい\nて作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止 権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、 明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出され\nるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲 を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム1の構成要\n素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム1 が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。 また、前記(1)ウ(ア)の2)−2及び5)からすれば、被告システム1にお いては、被告FC2のウェブサーバがユーザ端末に配信するSWFファ イルによって規定される条件に基づいて、2つのコメントが重複するか 否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示\n位置の指定が行われており、構成要件1Fの「判定部」及び構\成要件1 Gの「表示位置制御部」に相当する構\成1f及び1gの動作の実現は、 日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということ ができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成\n要件1Hに対応する構成1hのうち「前記ユーザ端末のディスプレイに\nは、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間におい て、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント1及び前記コ メント2とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に\n相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるも のということができるものの、構成要件1Hに対応する構\成1hのうち 「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記 ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国 内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現 されるものであり、構成1hが日本国内に存在するユーザ端末のみによ\nって実現されているとはいえない。前記1(2)イで検討したところからす れば、本件発明1の目的は、単に、構成要件1Fの「判定部」及び構\成 要件1Gの「表示位置制御部」に相当する構\成等を備える端末装置を提 供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメン トを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システ ムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信(構成要件\n1C及び1H)並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメ ント情報の送信(構成要件1B、1C及び1H)を行う「サーバ」は、\nこの目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。\nこの点からしても、本件発明1に関しては、ユーザ端末のみが日本に存 在することをもって、「生産」の対象となる被告システム1の構成要素の\n大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきで ある。 さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用 可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考\nえられ、同オのとおり、平成26年当時、日本法人である被告HPSが、 被告FC2の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサー ビスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全 証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年5月17日以 降の時期において、米国法人である被告FC2が本件特許権の侵害の責 任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本 国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論と して著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められな い。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(エ) 以上によれば、被告サービス1のFLASH版については、本件発明 1の関係で、被告FC2による被告システム1の日本国内での「生産」 を認めることができないというべきである。
・・・
オ 小活
以上のとおり、本件発明1の関係でも、本件発明2の関係でも、被告サ ービス(FLASH版及びHTML5版)において、被告FC2による被 告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2022.04.23
令和2(ワ)19920等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月19日 東京地方裁判所
医薬の用途発明においては,一般に,物質名,化学構造等が示されるこ\nとのみによっては,当該用途の有用性を予測することは困難であり,当該\n医薬を当該用途に使用することができないから,医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには,明細書の発明の詳細な説明にその医薬の\n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が,前記判示のとおり,本件明細書等には,本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には,本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば,神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること\nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また,侵害受容性疼痛, 神経障害性疼痛,心因性疼痛などの種類を問わず,痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり,いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば,他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は,本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり,その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ,上記 に摘示した各記載によれば,侵害受容性疼痛,神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は,その発症原因,痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり,痛みの種類を問わず,痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり,いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば,他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば,本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく, 本件明細書等の記載に接した当業者が,本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって,本件明細書等の記載は訂正前発明1及び2を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず,実施可\n能要件を充足しない。\n
(5) 原告の主張について
これに対し,原告は,本件特許出願当時,慢性疼痛は,それが侵害受容性 疼痛,神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても,末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛\nの痛みであるとの技術常識が存在したので,当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から,本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(オ) 以上によれば,上記(ア)ないし(ウ)の各記載から,侵害受容性疼痛,神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と,脊髄のNMDA受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても,本件特許 出願当時,本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛(炎症性疼痛,術 後疼痛,転移癌に伴う骨関節炎の痛み,痛風,火傷痛等)や神経障害性 疼痛(三叉神経痛,急性疱疹性神経痛,糖尿病性神経障害,カウザルギ ー等)により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難\nく,まして,これらの記載から,当業者が,薬理試験結果の記載もなく, 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は,被告医薬品が構成要件3B及び4Bの文言を充足しない場合であっ\nても,均等侵害が成立すると主張する。 しかし,相手方が製造等をする製品(対象製品)が,特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属すると認められる\nためには,当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特\n許発明の本質的部分ではないことを要する(第1要件)。 本件発明3及び4と被告医薬品との相違部分は,その用途にあるところ,同 各発明は,既知の薬物である本件化合物が,侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので,その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。\nしたがって,被告医薬品は,第1要件を充足しないので,均等侵害は成立し ない。
7 まとめ
以上によれば,訂正前発明1及び2に係る特許は,実施可能要件及びサポー\nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり,本 件訂正は訂正要件を具備せず,同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また,被告医薬品は,本件発明3及び4の技術的範囲に属しない。
◆判決本文
特許権は同じく、被告が異なる事件です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.04.13
令和2(ワ)5616 特許権 令和4年1月25日 東京地方裁判所
2 争点1(被告各製品の20ライン分のラインバッファは,「単一のVRAM」 を充足するか(構成要件D及びHの充足性))について\n
(1) 「単一のVRAM」の意義
ア 本件特許の特許請求の範囲における構成要件Dにおいては,「グラフィ\nックコントローラ」が,「該中央演算回路の処理結果に基づき,単一のVR AMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い,「該読み 出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すると\n規定されている。 また,構成要件Hにおいては,「グラフィックコントローラ」が,「前記\n単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度 を有する画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出したビットマ ップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び「前記単\n一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出したビット マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」することが規定され\nている(なお,構成要件Hにおける「前記単一のVRAM」との文言から,\n構成要件Dと構\成要件Hの「単一のVRAM」は同一の意義を持つものと 解される。)。
さらに,構成要件F,H,Jによると,「ディスプレイパネルの画面解像\n度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」は,「外部ディス プレイ手段」に表示するためのものであるといる。\nこれらの記載によれば,構成要件D及びHの「単一のVRAM」は,「グ\nラフィックコントローラ」により,「ビットマップデータの書き込み/読み 出し」がされるものであって,外部ディスプレイ手段に表示するための「デ\nィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット マップデータ」の書き込み/読み出しがされるものであり,前記「ディス プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマッ プデータ」の全体を記憶することが可能なものと解するのが相当である。\nそして,前記1に認定した本件明細書の記載(特に段落【0115】,【0 117】,【0127】)も,その記載内容に照らせば,構成要件D及びHの\n「単一のVRAM」が,「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なも\nのであるとの上記クレーム解釈に整合しており,同解釈を裏付けるものと 評価することができる。
イ 原告は,構成要件Hは,ビットマップデータの読み出しの具体的な方法\nについて何らの特定もしておらず,ディスプレイパネルの画面解像度と同 じ解像度を有する画像のビットマップデータを一挙に読み出すことを規 定したものとは解されない旨を主張する。しかし,特許請求の範囲の記載, 明細書の記載を検討すると,上記アに説示したとおり,「単一のVRAM」 は,「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の ビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なものと認めるのが相\n当である。原告の上記主張は採用することができない。
(2) 「単一のVRAM」の充足性
以上のクレーム解釈を前提に,被告各製品が,構成要件D,Hの「単一の\nVRAM」を充足するかについて検討する。 前記前提事実のとおり,被告各製品は,データ処理手段としてのCPU(中 央演算回路)及び液晶コントローラ(グラフィックコントローラ)を備える ものであるところ,このCPU(中央演算回路)は,無線通信手段から受信 した信号(圧縮した通信信号)をデコードして画像データを展開し,拡大/ 縮小(補間/間引き)を適宜行って内蔵用表示データ及び外部用表\示データ を生成し,生成した表示データを同CPU(中央演算回路)に接続されたS\nDRAMに書き込み/読み出しを行い,その内蔵用表示データ及び外部用表\ 示データを液晶コントローラ(グラフィックコントローラ)に送信する構成\nを有している。しかして,この液晶コントローラ(グラフィックコントロー ラ)には,6個の2Mビット(256kバイト)DRAMが内蔵されている ところ,これは,外部表示用のラインバッファ(20ライン分)であり,画\n像全体を書き込み/読み出しするためのものではないというのである(被告 各製品の構成d)。\n
しかして,このような,被告各製品の液晶コントローラ(グラフィックコ ントローラ)が内蔵するDRAMは,少なくとも外部表示用にはラインバッ\nファ(外部表示手段に表\示するための画像全体を書き込み/読み出しするた めのものではない)として用いられるものであるから外部表示手段に表\示す るための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像 のビットマップデータ」の全体を記憶するものではないことは明らかである というほかない。 そうすると,被告各製品における上記DRAM(20ライン分のラインバ ッファ)は,「単一のVRAM」との文言を充足するものとは認められず,被 告各製品が,構成要件D及びHを充足するものとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.04.10
平成30(ワ)4329等 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月18日 東京地方裁判所
争点は、技術的範囲の属否、無効(104条の3)、損害額の認定、覆滅の程度などです。
被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに270万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成3 0年3月又は同年11月以降であり、前記(1)イ(ア)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠(甲82)によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠(乙75)及び弁論の全趣旨によれば、令和3年1月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数270万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ア)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ア)a及びdのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており(ただし、 商品ごとに、これを1個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。)、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法102条2項により推定される損害額の10%について\n推定の覆滅を認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.04. 4
令和3(ネ)10049等 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
3 争点1−1(被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)\nである先端部を有しているか)について
(1) 「楕円形」の一般的な意味について
ア 「楕円形」とは,「楕円状をなした形」をいい,「楕円」とは,「円錐曲線 (二次曲線)の一つ。幾何学的には,一平面上で二定点(F,F’)からの距離の和 (FP+F’P)が一定であるような点Pの軌跡。」を意味する(「広辞苑 第六版」 (平成20年1月11日発行,株式会社岩波書店)1705頁,乙2参照)。この点, 被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠(甲 2。令和元年5月30日印刷)では,「楕円形」について,「楕円状をなす形,ある いは,それに近い形。」(デジタル大辞典の解説),「楕円のような形。また,そのよ うな形のさま。小判がた。長円形。側円形。」(精選版日本国語大辞典の解説)とさ れている。 上記を踏まえると,一般に,「楕円形」とは,「楕円状をなした形」をいい,幾何 学上の楕円の形状がそれに含まれることはもとより,同形状とは異なるがそれに近 い形についても用いられる語であると解される。 もっとも,幾何学上の楕円の形状とは異なるがそれに近い形として,どのような 形が「楕円形」に含まれるか,「楕円形」の意味の外延は,上記の辞書的な意味から は明確とはいえない。
イ 上記に関し,「卵形(たまごがた)」は,「鶏卵に似た楕円形。」を意味する語 である(上記「広辞苑 第六版」1756頁,甲78参照)。なお,被控訴人が提出 するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠(甲77。令和3年 7月29日印刷)では,「卵形(たまごがた)」について,「鶏卵のような楕円形。ま た,そのような形のもの。たまごなり。」(精選版日本国語大辞典の解説),「鶏卵に 似た楕円形。たまごなり。らんけい。」(デジタル大辞典の解説)とされている。 また,「卵形(らんけい)」は,「たまごのような形。たまごがた。」を意味する語 である(上記「広辞苑 第六版」2933頁)。なお,上記証拠(甲77)では,「卵 形(らんけい)」について,「卵のような形。楕円の一方が少し細くなっている形。 たまごがた。」(精選版日本国語大辞典の解説),「卵のような形。たまごがた。」(デジタル大辞典の解説)とされている。 そうすると,「楕円形」の語は,「卵形」を含むものとして用いられることもある ものの,他方で,前記アの「楕円形」の意味において,「卵形」と同義である旨の説 明はもちろん例示としても「卵形」という説明がみられないことや,上記のとおり, 「卵形」の意味においても,限定なしで「楕円形」と同義であることは何ら示され ず,「鶏卵に似た」,「鶏卵のような」といった限定を付して「楕円形」という語が用 いられたり,「楕円の一方が少し細くなっている形」との説明がされていることも踏 まえると,「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられる ところである。
ウ 以上によると,「楕円形」の語は,幾何学上の楕円の形状及びそれに近い形を いうものであるが,当該楕円の両端(当該楕円とその長軸が交わる2点をいう。)付 近の曲線を比較した場合に,その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状(「卵形」 など。当事者の主張における「長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状」。 以下「曲率に差のある形状」という。)を含むものとして「楕円形」の語が用いられ ているか否かは,明細書(図面を含む。)における当該「楕円形」の語が用いられて いる文脈等を踏まえて判断する必要があるというべきである。
エ これに対し,被控訴人は,「楕円形」の語が卵形等を含むものであると主張し て,インターネットでの画像検索の結果(甲10の1〜6)やウェブサイト等にお ける語の使用例(甲79〜84)を指摘するが,それらは一般に「楕円形」の語が どのような形を説明する際に用いられているかといった事情を示すものにすぎず, 「楕円形」の語が上記各証拠で示される各種の形をその意味として当然に含むこと を示すものとは解されない。
(2) 本件明細書における「楕円形」の語について
ア 本件明細書に,「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。 ただし,請求項1の発明においては先端部が「球形」とされ,本件明細書でも「球 形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると,少なくとも,本件発明 の「楕円形」は,円形(球形の断面)を含むものではなく,円形を含み得るような 広い意味の語ではないことは理解されるといえる。
イ(ア) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」 の1(2)を踏まえると,本件発明が解決しようとする課題は,従来技術について,矢 の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた,1)矢を的から外すときに 丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と,2)ダブ ル突入の場合に後ろの矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け,後ろの 矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題(以下,併せて「ピン抜 けの課題」という。)のほか,矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルム の重なりにより生じていた,3)上下方向の重心に偏りがあるという課題(以下「重 心の課題」という。)であると解される。
(イ) 本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は,ピン抜けの課 題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると,ピ ン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ,「かえ し」の存在をなくすという観点からは,先端部の形状は,幾何学上の楕円の形状で 足り,曲率に差のある形状である必要はない。したがって,ピン抜けの課題の解決 手段の一つであるという事情は,本件発明における「楕円形」の語が,曲率に差の ある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ,曲率に差のある 形状とした場合,具体的な形状次第では,的やダブル突入の場合の前の矢のフィル ムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ,ピン抜\nけの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点,本件明細書に は,先端部の形状について,「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン 抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は,何ら記載さ れていない。
他方,本件明細書上,重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端 部の形状との関係は明確ではないが,重心の課題の原因の一つとして,矢の先端部 の頭部と円柱部との位置のずれが挙げられていることのほか,本件発明の効果等に 関し,請求項1の発明に係る実施例についてのものではあるものの,「ピンを従来 の丸釘から先端球形に変更することによって矢の長手方向の重心位置を矢の先端方 向に寄せることができた」ことが記載され,その変形例が本件発明に係るもので, 上記実施例と同様に従来の矢の丸釘と比較した丸ピンの重量等について具体的な記 載がされていることも考慮すると,「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状 は,円柱部との位置のずれを解消しやすく,また,上下方向の重心に偏りがなく, かつ,従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重 くなるといった観点から,重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理 解することもあり得る。しかし,そのような観点からも,先端部の形状は,幾何学 上の楕円の形状で足り,曲率に差のある形状である必要はない。むしろ,曲率に差 のある形状とした場合,具体的な形状次第では,円柱部との位置の調整が困難にな ったり,上下方向の重心に偏りがなく,かつ,先端部が相対的に重くなるといった 特徴が十分に発揮できなくなり,重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえると\nころである。この点,本件明細書には,先端部の形状について,「楕円形」としてど のような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料とな り得るデータ等は,何ら記載されていない。
ウ 本件発明の実施例は,本件明細書の【0065】〜【0069】及び【図3】 のとおりであり,先端部の長手方向の断面は,請求項1の発明の実施例(同【図2】) の先端部の形状である「球形」の長手方向の断面である円を左右(矢の進行方向か らすると前後)に二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形(換言する と,「円」を左右に引き伸ばしたような形)であって,「小判型」や「俵型の断面」 などというべきものであり,幾何学上の楕円の形状とは異なるものの,長手方向の 両端の曲率を同じくするものである。上記の形については,本件明細書に実験結果 が記載されており,また,前記イ(イ)で指摘したような,ピン抜けの課題の解決や重 心の課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いものといえる。
(3) 構成要件B及びDの「楕円形」の意味及び文言侵害の成否について\n
ア 前記(1)及び(2)の点を踏まえると,構成要件B及びDの「楕円形」は,幾何\n学上の楕円の形状や,本件発明の実施例の形のような,楕円に近い形状であって長 手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で,曲率に差のあ る形状は含まないものと解するのが相当である。なお,これと異なる技術常識を認 めるべき証拠もない。
イ 被告製品のピンの先端部は,「長手方向断面が,前部が曲率の緩い曲線形状, 後部が略円錐形となるように円弧を描き,後部の円柱部との接合面が上下に角を有 し,前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」(構成要件b)であり,\n曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものである から,構成要件B及びDの「楕円形」には含まれない。\nしたがって,被告製品が,文言上,本件発明の技術的範囲に属するとは認められ ない。
ウ 被控訴人は,曲率に差のある形状のピンの先端についても,1)「かえし」が ないため矢が抜きやすいこと,2)上下方向の重心が均等であり,また,3)従来技術 の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり,矢全体の長手方向の重心を前寄りに 寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件B及びD\nの「楕円形」に含まれると主張するが,前記(1)及び(2)で認定説示した点に照らし, 上記1)〜3)を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできな い(なお,被控訴人の上記主張によると,請求項1の発明に係る「球形」が,同時 に本件発明に係る「楕円形」に含まれることとなり得,この観点からも上記主張は 相当といい難い。)。 また,被控訴人は,本件で問題になっているのは,一般的に楕円形といえばどの ような形を最初に思い浮かべるかではなく,卵形や涙滴型のような,長手方向の端 の一方が他方よりも緩い曲率の形状を「楕円形」と表現するのか否かであると主張\nするが,被告製品の先端部の形状が本件発明の構成要件B及びDの「楕円形」に含\nまれるかという判断に先立って,まず,本件発明の構成要件の解釈として構\成要件 B及びDの「楕円形」の意味が問題となるのであるから,被控訴人の上記主張は, その前提を誤るものといえ,前記ア及びイの判断を左右するものではない。
4 争点1−2(均等侵害の成否)について
・・・・
(エ) 本件発明の構成要件A〜Eに加え,前記(ア)ないし(ウ)を踏まえると,本件発 明について,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは,\nピンと巻いたフィルムによって構成される吹矢において,構\成要件B〜Dのうち, 特に「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とか らなるピン」,「先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ・・・たフィルム」 及び「前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続さ れた」という構成を採用することにより,ピン抜けの課題と重心の課題をともに解\n決するという点にあると解される。
(オ) 前記3で認定判断した構成要件B及びDの「楕円形」の意味及び弁論の全趣\n旨によると,本件発明の先端部の形状と被告製品の先端部の形状について,1)本件 発明では「楕円形」であるのに対し,被告製品では,曲率に差のある形状を基礎と して,「長手方向断面が,前部が曲率の緩い曲線形状,後部が略円錐形となるよう に円弧を描」く形状となっていること(なお,別紙乙第1号証のとおり,後部の略 円錐形となるような円弧について,一定の曲率が選択されているものである。乙3 の1・2,乙15参照)と,2)根元段差部分があることとにおいて,異なっている ということができる。 上記のうち1)について,前記3(2)イで指摘したところからすると,本件発明は, 少なくともピン抜けの課題の解決方法として,「長手方向断面が楕円形である先端 部」という構成を採用したものと解される。そして,同イ(イ)で指摘したとおり,「長 手方向断面が楕円形」という形状を曲率に差のある形状に変更した場合,ピン抜け の課題の解決や重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところ,「楕円形」と してどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断 の資料となり得るデータ等は本件明細書に記載されていない。 そうすると,本件発明における前記3(3)で認定判断した意味での「長手方向断面 が楕円形」という先端部の形状の特定は,本件発明の本質的部分に含まれるものと いうべきであり,それを被告製品の先端部の形状に置き換えることは,本件発明の 本質的部分を変更するものというべきである。 ウ したがって,本件発明の構成中に,被告製品と異なる部分が存在するところ,\n異なる部分は本件発明の本質部分であるから,第1要件を満たさない。
(2) 第3要件について
また,本件全証拠をもってしても,本件発明の「長手方向断面が楕円形」という 形状を被告製品の先端部の形状に置き換えることについて,前記3(2)イ(イ)で指摘 したとおり,曲率に差のある形状への変更によりピン抜けの課題の解決や重心の課 題の解決に支障を生じ得るともいえる一方で,どのような範囲内の変更であればそ れらの課題がなお適切に解決されるかの判断の資料となり得る記載が本件明細書に ないにもかかわらず,当業者が被告製品の製造等の時点において上記置換えを容易 に想到することができたというべき技術常識等は認められない。 したがって,第3要件も満たさない。
(3) まとめ
したがって,その余の点について判断するまでもなく,均等侵害は成立しない。
(4) 被控訴人の主張について
ア(ア) 被控訴人は,第1要件について,「かえし」部分が存在せず,矢が的や前の 矢から引き抜きやすい滑らかな曲線状の長手方向断面形状を有する先端部と,当該 先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンを備えているという点が本件発明の本 質的部分であると主張するが,前記(1)ア及びイで認定説示したとおりであって,被 控訴人の上記主張は採用できない。それゆえ,上記主張を前提とする本件発明と被 告製品との一致点・相違点に係る被控訴人の主張も採用できない。 (イ) 被控訴人は,第1要件について,ピンの先端部の後方部の形状に着目したと いう点で本件発明は技術的思想として新しいなどとも主張するが,そのような着眼 点に本件発明の一つの特徴があるとしても,その上で,本件発明においては,課題 解決の方法として,「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたとい う事情を均等侵害の成否の検討においても無視することはできず,また,ピンの先 端部の後方部の形状に係る構成は,本件発明による複数の課題の解決のうちのいま\nだ一つにとどまるというべきものであるから,被控訴人の上記主張は,前記(1)イ及 びウの認定判断を左右するものではない。
イ 被控訴人は,第3要件について,本件発明は,矢が的や前の矢から引き抜き やすいピンの先端部を提供するものであり,そのためにはピンの先端部の形状は球 形や楕円形に限られず,「かえし」部分が存在せず,かつ,引き抜く際の抵抗がよ り小さくなるような滑らかな曲線状で形成されていればよいことは,当業者におい て容易に想到できるなどと主張するが,前記ア(ア)のとおり,本件発明の本質的部分 についての被控訴人の主張は採用できないから,当業者において容易に想到できる という被控訴人の上記主張は,その前提を欠くものであり,第3要件を満たさない というべきことは,前記(2)のとおりである。その余の被控訴人の主張も,本件発明 の本質的部分についての被控訴人の主張を前提とするものか,本件発明において課 題解決の方法として「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたと いう事情を無視するもので相当でないものであって,いずれも採用できない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.03.30
令和2(ワ)19931等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月16日 東京地方裁判所
いわゆる医薬用途発明においては,一般に,当業者にとって,物質名, 化学構造等が示されることのみによっては,当該用途の有用性及びそのた\nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり,当該発明に係る医薬\nを当該用途に使用することができないから,そのような発明において実施 可能要件を満たすためには,明細書の発明の詳細な説明に,薬理データの\n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより,当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明1及び2の特許請求の範囲においては,本件化合物が「痛みの 処置における」(構成要件1B)「鎮痛剤」(構\成要件1C)及び「鎮痛 剤」(構成要件2C)として作用することが記載されているところ,いず\nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし, 本件明細書には,本件化合物について,「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛,術後疼痛,転移癌に伴う骨関節炎の痛み, 三叉神経痛,急性疱疹性および治療後神経痛,糖尿病性神経障害,カウザ ルギー,上腕神経叢捻除,後頭部神経痛,反射交感神経ジストロフィー, 線維筋痛症,痛風,幻想肢痛,火傷痛ならびに他の形態の神経痛,神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」(前記1(1)イ)と記載されて いることに照らすと,本件発明1及び2は,本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって,本件発明1及び2について実施可能要件を満たすというた\nめには,本件明細書の発明の詳細な説明に,薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより,上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ア)の各文献の記載によれば,本件出願当時,術後疼痛試験は,ラ ットの皮膚,筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより,痛 覚過敏を引き起こし,これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが,技術常識であったと認められる。 そして,本件明細書には,「S−(+)−3−イソブチルギャバ」\n(弁論の全趣旨によれば,構成要件3Aを充足する本件化合物の一種で\nあると認められる。)が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており,さらに,「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後1時間以内にピークに達 し,3日間維持された。実験期間中,動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」(前記1(1)キ(キ)),「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも3時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は,ギャバペンチンおよびS− (+)−3−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して\nも等しく有効なことである。」(同(コ))との記載がある。 以上によれば,本件出願当時,本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は,本件化合物について,侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し,その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明3の構成と均等なものであるかについて\n
(ア) 原告は,本件発明3は,慢性疼痛に対する画期的処方薬として,抗て んかん作用を有するGABA類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり,その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから,対象となる痛みが侵害受容性疼痛か,神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく,効能・効果を神経障害性疼痛や\n線維筋痛症に伴う疼痛とし,慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は,均等侵害の第1要件を満たすと主張する。
しかし,前記1(1)アのとおり,本件特許に係る発明は,てんかん,ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が,痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し,反復使用により耐性を生じず,モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ,前記2(1)イのとおり,本件 出願当時,痛みには種々のものがあり,その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると,いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは,本件発明 3において本質的部分というべきであり,その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は,本件発明3の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって,本件発明3に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明3の本質的部分でない\nということはできないから,被告医薬品は均等の第1要件を満たさない。
(イ) また,前記(1)アによれば,原告は,本件訂正前発明3においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ,本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると,本件発明3との関係においては,被告医薬品の効能・効果\nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって,被告医薬品は均等の第5要件も満たさない。
(ウ) 以上によれば,被告医薬品は,本件発明3の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。\n
イ 被告医薬品が本件発明4の構成と均等なものであるかについて\n
前記アと同様に,いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは,本件発 明4の本質的部分というべきであり,被告医薬品は均等の第1要件を満た さず,また,本件発明4との関係においては,被告医薬品の効能・効果で\nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から,均等の第5要件も満たさない。 したがって,被告医薬品は,本件発明4の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。\n
◆判決本文
関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和2(ネ)10059 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟__全文__ 令和4年2月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上によると,基礎出願A,Bの上記記載に接した当業者は,上記本件優先日当 時の技術常識とを考え併せ,「大豆胚軸」以外の「ダイゼイン類を含む原料」を発酵 原料とした場合でも,ラクトコッカス20-92株のようなエクオール及びオルニ チンの産生能力を有する微生物によって,発酵原料中の「ダイゼイン類」がアルギ\nニンと共に代謝されるようにすることにより,発酵物の乾燥重量1g当たり,8m g以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールを含有する,食品素材として用い られる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたという\nべきであるから,本件訂正発明を基礎出願A,Bから読み取ることができるものと 認められる。 したがって,本件訂正発明は,少なくとも基礎出願A,Bに記載されていたか, 記載されていたに等しい発明であると認められ,本件訂正発明は,基礎出願A,B に基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。 そうすると,本件特許は,特許法104条の規定の適用については,本件優先日 である平成19年6月13日に出願されたものとみなされるから,本件訂正発明生 産物が同条の特許出願前に日本国内において「公然知られた物でない」か否かを検 討するに当たり,本件優先日以降に公開された乙B3(国際公開第2007/06 6655号。国際公開日2007(平成19)年6月14日)を考慮することはで きない。
ウ 「公然知られた物でない」に当たるか
その物が特許法104条の「公然知られた」物に当たるといえるには,基準時に おいて,少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた 事実が存することを有するというべきところ,本件訂正発明生産物が,本件優先日 当時に公知であった乙B16,乙B24に記載されていたとはいえず,また,乙B 16又は乙B24から本件訂正発明を容易に想到することができないことは後記3 (4),(6)のとおりである。そうすると,本件優先日時点において,乙B16又は乙 B24に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたという ことはできない。 また,被控訴人らは,本件訂正発明生産物は,乙B16の「実施例1」の「乾燥 重量1g当たり,1mg−3mgのエクオールが生成」している発酵物「992m g」に栄養強化添加物である「97.48%」の純度のオルニチン(乙B67の国 際公開公報(WO2006/051940))を「8mg」加えたものであるにすぎ ないから,「公然知られた物」であると主張するが,前記アのとおり,本件訂正発明 生産物は,「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって,前記発 酵物の乾燥重量1g当たり,8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオール が生成され,食品素材として用いられる物」であるから,乙B16に乙B67を組 み合わせたとしても,「発酵物の乾燥重量1g当たり,8mg以上のオルニチン及び 1mg以上のエクオールが生成された」物に当たらないから,上記被控訴人らの主 張は採用できない。
なお,被控訴人らは,本件発明による生産物について,乙B4により公然知られ た物に当たる旨の主張をしていたので念のため検討するに,乙B4に本件訂正発明 が記載されていたとはいえず,また,乙B4から本件訂正発明を容易に想到できた ものではないことは後記3(3)のとおりであり,乙B4によっても当業者が本件訂 正発明生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。 したがって,本件訂正発明生産物は,本件優先日当時,「公然知られた物でない」 といえる。
エ 被控訴人方法の構成について\n
被控訴人らは,被控訴人原料の生産方法が原判決別紙「被告方法目録」記載の被 控訴人方法であることについて自白が成立しているから,特許法104条の推定は 働かないと主張する。そして,令和元年6月7日の原審第4回弁論準備手続期日に おいて,当事者双方が,被控訴人方法の構成について原判決別紙「被告方法目録」\n記載のとおりである旨陳述している(当裁判所に顕著)。 原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴人方法と,当審で控訴人 が主張する被控訴人方法とでは,前者における「α3 前記酵素処理工程を経て得 られたダイゼインを含む処理液と,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●をアルギニンを含む培養液と共に混合して発酵処理をし,」との構成部\n分を,後者では「α3−1 前記酵素処理工程を経て得られたダイゼインを,アル ギニンを含むその他の成分と混合して培地とした上,これを滅菌処理して滅菌済培 地とし,」と「α3−2 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●を同滅菌済培地に植菌して発酵処理をし,」との構成に変更するというものであ\nるところ,同α3−1及びα3−2の内容は,α3の内容を更に具体化・詳細化し ようとするものであり,また,控訴人は,原判決における本件訂正発明に係るクレ ーム解釈に基づく場合の構成としてα3−1及びα3−2とすべきと主張している\nものであるから,まずは,原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴 人方法(α1〜6によるものであって,α3をα3−1及びα3−2に変更しない もの)の構成について検討を進めることとする。\n
オ 推定の覆滅について
被控訴人らは,被控訴人原料の生産方法が被控訴人方法であり,これが本件訂正 発明の方法とは異なるから,本件訂正発明の方法を使用していないとの主張立証を しているものと解されるから,以下,被控訴人方法(まずは,α1〜6によるもの であって,α3をα3−1及びα3−2に変更しないもの)が本件訂正発明の方法 とは異なるものであるか検討する。
・・・
c 原判決は,構成α3の「アルギニンを含む培養液」は,本件発明の構\成要件 A−2,A−3の「アルギニンを含む発酵原料」に当たらず,被控訴人方法は本件 発明のA−2,A−3を充足しないと判断したが,本件訂正発明においても,構成\n要件B’−1に「アルギニンを含む発酵原料」とあるので,α3の「アルギニンを 含む培養液」が構成要件B’−1の「アルギニンを含む発酵原料」に当たるか検討\nする。 構成要件B’−1は,「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を」と\nいうものであるが,これは,構成要件A’においてダイゼイン類にアルギニンを添\n加したものを指すと解するのが自然である。そして,上記bのとおり,被控訴人方 法の構成α3においては,「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養\n液を,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と共に混合して発 酵処理をしているところ,「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養 液の混合物を,「オルニチン産生能力及びエクオール産生能\力を有する微生物」であ る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●で「発酵処理」してい るから,上記混合物は発酵原料に当たるというべきである。そうすると,同混合物 は,「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料」に当たるから,被控訴人 らの主張する被控訴人方法を前提としても,被控訴人原料の生産方法は,本件訂正 発明の構成要件B’−1を充足し,構\成要件B’−1の発酵原料を微生物で発酵処 理することを内容とする構成要件B’−2も充足する。\n
この点,原判決は,本件発明について,アルギニンは,発酵処理をする前の発酵 原料の調製をする段階において発酵原料に含まれているものであり,構成α3の「ダ\nイゼインを含む処理液」が発酵原料に当たり,「アルギニンを含む培養液」は発酵原 料ではなく,発酵効率の促進等を目的とする栄養成分に当たるものと解した上で, 被控訴人方法は発酵処理段階においてアルギニンが初めて現れるから本件発明の構\n成要件を充足しないと判断した。
しかしながら,本件特許請求の範囲及び本件明細書をみても,ダイゼイン類にア ルギニンを添加した後に微生物を加えることと,ダイゼイン類とアルギニンと微生 物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はな い。また,本件明細書をみると,【0091】に「発酵原料(発酵に供される原料)」 との記載があるものの,【0093】には「ダイゼイン類を含む発酵原料としては, ダイゼイン類を含む限り,特に制限されるものではない」と発酵原料に特段の制限 がないものとされており,そのほかには発酵原料を定義付ける記載はない。前記1 (2)のとおり,本件訂正発明においてオルニチン産生能力及びエクオール産生能\力 を有する微生物による発酵に供されるのは,「ダイゼイン類」と「アルギニン」であ り,ダイゼイン類にアルギニンが添加されたのちに微生物が添加されたとしても, ダイゼイン類に,アルギニンと微生物が同時に添加されたとしても,アルギニンが 発酵に供されることに変わりがない。そうすると,被控訴人方法におけるアルギニ ンが,発酵原料ではないというべき理由がない。
原判決は,本件明細書の【0033】の「当該エクオール含有大豆胚軸発酵物は, 発酵原料として大豆胚軸を用いて製造される」との記載及び【0036】の「大豆 胚軸の発酵において,発酵原料となる大豆胚軸には,必要に応じて,発酵効率の促 進や発酵物の風味向上等を目的として,酵母エキス,ポリペプトン,肉エキス等の 窒素源;グルコース,シュクロース等の炭素源;リン酸塩,炭酸塩,硫酸塩等の無 機塩;ビタミン類;アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に,エクオール産 生微生物として,アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの(中略)を\n使用する場合には,大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって,得 られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合,アルギニンの 添加量については,例えば,大豆胚軸(乾燥重量換算)100重量部に対して,ア ルギニンが0.5〜3重量部程度が例示される。」と発酵原料となる大豆胚軸には, 必要に応じて,発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を添加してもよいと記載さ れていることから,発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は,発酵原料とは別の 成分として扱われていると認定したが,ダイゼイン類を含む「大豆胚軸」が発酵原 料に当たることと,ダイゼイン類を含む処理液とアルギニンを含む培養液のいずれ もが発酵原料に当たると考えることは何ら矛盾するものではない。また,【0036】 の記載も,大豆胚軸にアルギニンを添加したものを発酵原料とみなすことと矛盾す るものではない。したがって,原判決の判断には誤りがあるというほかない。 そうすると,α3の「アルギニンを含む培養液」は,構成要件B’−1の「アル\nギニンを含む発酵原料」に当たると認めるのが相当であるから,被控訴人方法が構\n成要件A’,B’−1,B’−2を充足しないことが立証されているとはいえない。
・・・
(ウ) 以上のとおり,被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していない ことが立証されているとはいえないから,特許法104条の推定が覆滅されたと認 めることはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2022.03. 8
平成29(ワ)24942 特許権侵害に基づく不当利得返還等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月20日 東京地方裁判所
本件特許の請求項1は下記です。 通信ネットワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において、 ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセスポイントのIPアドレス、およびIPアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したIPアドレス対地域データベースを用いて、前記ユーザ端末に割り当てられたIPアドレスを所有するアクセスポイントが属する地域を判別する第1の判別ステップと、 前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第1の選択ステップと、 前記選択されたウェブ情報を、前記IPアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信する送信ステップと、 を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。
被告方法等は,本件各発明の技術的範囲に属するものであるから,被告が被 告方法等を用いて行う地域ターゲティング広告等のサービスを提供する行為 は,本件特許権を侵害するものである。そして,被告はその侵害行為について 過失があったものと推定されるから(特許法103条),原告は,被告に対し, その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が 受けた損害の額としてその賠償を請求することができる(同法102条3項) ところ,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準とし,そこに, 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 また,不当利得返還請求については,同項の「受けるべき金銭の額に相当す る額」は,本来,侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払 うべきであった実施料相当額であるから,侵害者がこれを支払うことなく特許 発明を実施した場合は,その実施により,侵害者は同額の利得を得,特許権者 は同額の損失を受けたものと評価することができるから,同項の「受けるべき 金銭の額に相当する額」が不当利得(民法703条)における受益者の利得の 額に相当し,かつ,権利者の損失の額に相当すると認めるのが相当である(知 財高裁平成27年(ネ)第10488号,同第10088号同年11月12日 判決・判時2287号91頁参照)。 そこで,被告が被告方法等を使用して上げた売上高及び実施に対し受けるべ き料率(相当実施料率)につき,以下検討する。
(2) YDN及びプレミアム広告について
ア YDN及びプレミアム広告の売上高
YDN及びプレミアム広告の売上高は,以下のとおりであると認められる。
(ア) YDNの売上高
証拠(乙25)によれば,原告主張の損害算定期間(平成19年7月2 5日〜平成30年6月26日)の売上高(消費税抜き。以下,売上高につ き,特記なき限り同じ。)は,別紙売上高・損害額一覧表のとおりであり,\nYDNのエリアターゲティングを行っている部分の売上高総額は,●省略 ●であると認められる(●省略●なお,端数処理の関係で1円の誤差が生 じている。)。
(イ) プレミアム広告の売上高
同様に,同期間のプレミアム広告のエリアターゲティングを行っている 部分の売上高総額は,●省略●であると認められる(●省略●)。
イ 相当実施料算定の基礎となる売上高の範囲
被告は,YDN及びプレミアム広告の売上高のうち,下記(ア)ないし(エ)に 係る各部分については,相当実施料算定の基礎となる売上高から除外すべき であると主張するので,この点について検討する。
(ア) ●省略●について
被告は,本件各発明の技術的範囲には●省略●から,被告方法等におい て,本件各発明の技術的範囲に含まれる部分があるとしてもそれは●省略 ●であると主張する。 しかし,本件各発明にいう「アクセスポイントに対応する地域」等は, 特に●省略●ものではないので,相当実施料算定の基礎となる売上高を● 省略●理由はないというべきである。
(イ) スマートフォンを利用した売上部分について
被告は,スマートフォンの利用による売上げは相当実施料算定の基礎と なる売上高から控除すべきであると主張する。 しかし,証拠(甲73・3頁)及び弁論の全趣旨によれば,スマートフ ォンからインターネットのウェブサイトを閲覧する場合には,モバイル接 続(4G接続ないし3G接続)又はWi−Fi接続の2通りの方法があり, 自宅等のWi−Fi環境がある場所では,通信容量制限のあるモバイル接 続ではなく,Wi−Fi経由の接続を行うのが一般的であるところ,スマ ートフォンによりWi−Fi接続を行う場合には,接続に用いられるIP アドレスは自宅のWi−Fiに用いられるIPアドレスであり,この場合 には,本件各発明に基づくIPアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別しているものと認められる。 他方で,モバイル端末からのインターネット接続(いわゆる4G接続な いし3G接続)の場合に,IPアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別することができないことは,原告が自認するところであるから, 相当実施料算定の基礎となる売上高は,かかる接続を利用しない場合(W i−Fi経由での接続の場合)に限定することが必要であるというべきで ある。
(ウ) ●省略●について
被告は,●省略●を控除したものとされるべきであると主張する。
a そこで検討するに,証拠(乙27)及び弁論の全趣旨を総合すると, 以下の事実を認めることができる。
●省略●
b 上記aで認定した事実によれば,被告方法等において,●省略●を控 除することが相当であるというべきである。
c これに対して,原告は,●省略●と考えられると主張するが,これを 認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
(エ) 他のターゲティング機能に対応する部分について\n
被告は,「年齢」,「性別」,「行動履歴」など「地域」以外のターゲ ティング機能に対する部分の売上げは,本件における相当実施料額の算定\nの基礎とならないと主張する。 この点,証拠(甲22,26)によれば,被告のYDNやプレミアム広 告においては,地域ターゲティングに加え,「時間帯」,「性別」,「年 代」,「行動履歴」等に基づくターゲティングも行われていることがうか がわれるが,他方で,プレミアム広告の商品紹介(甲26)においては, 「エリアターゲティング」が最初に紹介され,また,被告の広告本部本部 長が,平成19年11月5日付けの日経マーケティングのウェブ上の記事 (甲27)において,1)被告は地域ターゲティングに力を入れており,I Pアドレスなどの情報で地域ターゲティング広告ができるようになり,地 域限定のプロモーションや地域限定で企業活動をしている広告主もター ゲットに入ってきたこと,2)地域ターゲティング広告に性別や年齢別など によるデモグラフィックターゲティングも組み合わせればより効果的で あること,3)地域ターゲティング広告は,中小企業,インフラを手がける 大手企業などの需要もあることなどを述べていることが認められる。 そうすると,地域ターゲティングは中心的な機能であり,他のターゲテ\nィング機能に比べてその重要性は高いというべきであり,また,これらの\n機能は重複して利用されることも多く,その寄与の度合いを個別に算定す\nることが困難であることにも照らすと,地域ターゲティング機能と関連の\nある売上高については,その全額を対象とするのが相当である。
ウ 相当実施料算定の基礎とすべき売上高
上記アのYDN及びプレミアム広告の売上高から,上記イに従って控除す べき分を控除した額は,以下のとおりである。
(ア) YDNについて
証拠(乙25)によれば,YDNについて,●省略●となる。
(イ) プレミアム広告について
同様に,プレミアム広告については,●省略●となる。
(ウ) 以上によれば,本件特許権侵害による損害額の算定に用いるべき売上高 は,YDNにつき●省略●,プレミアム広告につき●省略●となる(それ ぞれの各年度の内訳は別紙売上高・損害額一覧表の該当欄記載のとおり。)。\n
(3) スポンサードサーチについて
原告は,被告が提供するターゲティング広告に係るサービスのうち,スポン サードサーチに係る売上高も相当実施料の算定の対象とすべきであると主張 するのに対し,被告は,スポンサードサーチにおいては本件各発明を実施して いないから,その売上高は相当実施料の算定の対象外であると主張する。
ア そこで検討するに,●省略●ことが認められる。
しかし,他方で,●省略●本件各発明を実施して行われているとは認めら れないので,スポンサードサーチに係る売上高も損害額算定の対象とすべき であるとの原告主張を採用することはできない。
イ なお,原告は,スポンサードサーチが本件各発明の実施に当たらないとの 主張は時機に後れた攻撃防御方法に当たると主張するが,被告は,当初から, 原告主張のターゲティング広告の提供サービスが本件各発明の技術的範囲 に属することを否認していたこと,侵害論の審理においては●省略●が中心 的な争点であったこと,損害論の審理に入り,スポンサードサーチが実施料 算定の基礎となるかが争点となり,これを契機としてスポンサードサーチが 本件各発明の実施に当たるかどうかが問題となったことなどの本訴の経緯 に照らすと,被告の上記主張が時機に後れたものということはできない。
(4) 相当実施料率について
ア 相当実施料率の算定基準
特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」の算定に当たり,実施に対し受けるべき料率は,1)当該特 許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合 には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の 価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,3) 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様,4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れ た諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである(知財高裁平成 30年(ネ)第10063号令和元年6月7日特別部判決・判時2430号 34頁参照)。
イ 実施料率等について
(ア) 証拠(甲30,79,100)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実 を認めることができる。
a 原告は,あどえりあ社を通じて,本件特許に係るライセンス(通常実 施権の許諾。以下「本件ライセンス」という。)を行っている。
b 本件ライセンスの料金体系は,1)多数のウェブサイトやアプリ等に一 括で広告を配信するアドネットワーク事業を行う企業を対象とするア ドネットワーク事業社用(甲30・2枚目),2)クライアントに対しシ ステム等を使ってサービスを提供する企業を対象とするサービス提供 事業社用(同3枚目),3)自社でウェブサイトを運営する企業を対象と するウェブサイト運営社用(同4枚目)の3種類がある。
c 上記1)(アドネットワーク事業社用)の料金は,登録料1万円(初年 度のみ)と,アドネットワーク事業社のクライアントに対する広告請求 金額に対する1.5%(親会社の業務を子会社が行う場合は3%)の割 合によるライセンス利用料である。
上記2)(サービス提供事業社用)の料金は,クライアントの特許利用 も含めたライセンスを受ける場合は,登録料1万円(毎年)と,サービ ス提供事業社と各クライアントの間の月額契約料金の3%の割合によ るライセンス利用料である。
上記3)(ウェブサイト運営社用)の料金は,当該ウェブサイトが50 00万PV以上で,かつ,自社サイト内の広告の地域ターゲティングを 行う場合は,登録料1万円(初年度のみ)及び基本利用料10万円(年 額)に加え,広告売上げの3%の割合によるライセンス利用料となる。 なお,ウェブサイト運営社が,当該ウェブサイト内で物品などの販売を 補助するサービスを行う場合は,更にビジネス利用料5000円〜(年 額)を要するとされている。
d 本件ライセンスの実績としては,アドネットワーク事業社用のライセ ンス利用料につき1.5%で契約した例,サービス提供事業社用のライ センス利用料につき3%で契約した例,ウェブサイト運営社用のライセ ンス利用料につき1.5%で契約した例や,0.75%で契約した例が ある。
(イ) 甲30のライセンス料金表の各類型の適用に関し,原告は,広告を掲載\nするサイトを基準とするもの,すなわち,自らのウェブサイトにおいて広 告を掲載する場合は3%であるが,他社のウェブサイトに広告を掲載する 場合は1.5%とするものであると主張するのに対し,被告は,広告の主 体を基準とするもの,すなわち,第三者の広告を請け負って掲載する場合 はアドネットワーク事業社用の条件に従って1.5%の料率が適用され, 自社の広告を掲載する場合は3%の料率が適用されると主張する。
甲30のライセンス料金表の各類型が適用される広告掲載サービスに\nついては,本件ライセンスに係る特許権者である原告が当然知悉している と考えられるところ,アドネットワーク事業社用について他の場合より安 い料率が設定されることについての原告の説明,すなわち,他社のウェブ サイトに広告を掲載する場合には別途広告枠を媒体社などから購入する 必要がありその費用が掛かるためにアドネットワーク事業社用では料率 を下げているとの説明や,それにもかかわらず親会社の業務を子会社が行 う場合は3%としたのは,アドネットワーク事業社である親会社が広告掲 載を自らの子会社の広告枠で行う場合には広告枠の購入費用は子会社に 支払われるために親子会社全体としてみれば費用支出がないからである との説明は合理的であるといえる。 被告は,ウェブサイト運営者用のライセンス料金表に「EC(電子商取\n引)を含む,ウェブサイト内で物品などの販売を補助するサービス」が対 象となることが記載されていることをもって,ウェブサイト運営者用の実 施料率が3%であるのは,自社商品の広告表示を切り替えるといったサー\nビスを提供することを念頭に置いたものであると主張する。しかし,同サ ービスを行う場合に発生するのはビジネス利用料であって,広告利用料で はないので,上記の記載から,ウェブサイト運営者用のライセンス料金表\nが適用されるのは自社の広告を掲載する場合であると認めることはでき ない。
むしろ,甲30・4枚目においては,ウェブサイト運営者用の「広告利 用料」は「広告売上の3%」と規定されているところ,ここに「広告売上」 と記載されているのは,他社の広告を自らのサイトで行うことにより広告 売上げを得る場合を想定としているからであると推認するのが自然かつ 合理的である。 そうすると,原告が主張するとおり,本件ライセンスにおけるライセン ス料率は,自らのウェブサイトにおいて広告を掲載する場合は3%である が,他社のウェブサイトに広告を掲載するなどして,広告枠を媒体社など から購入する費用を生ずる場合には1.5%とするものであると認めるの が相当である。
(ウ) 上記(イ)の説示を踏まえ,被告の地域ターゲティング広告が本件ライセ ンスのいずれの類型に属するかにつきみるに,YDNのうち被告ウェブサ イトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告はウェブサイト運営社用 に当たるから,ライセンス料率は3%となり,YDNのうち他の提携ウェ ブサイトに広告を掲載する部分はアドネットワーク事業社用に当たるか ら,ライセンス料率は1.5%となるものと認められる。 この点につき,被告は,過去にウェブサイト運営社用に当たるにもかか わらず0.75%や1.5%のライセンス料率が適用されたことがあるこ とを指摘し,本件においてもこれらの料率を参考とすべきであると主張す るが,証拠(甲100)及び弁論の全趣旨によれば,これらは原告とライ センシーとの関係に基づき特別に減額されたものであることがうかがわ れ,他にサービス提供事業社用の類型ではあるものの,原則どおりライセ ンス料率を3%として契約した実績もあることからすれば,上記のとおり 認定するのが相当である。
ウ 実施料率を下げるべき他の事情について
●省略●
(イ) 被告は,被告自身の多数の特許を実施することによりウェブ広告の分野 において大きなシェアを獲得することができているのであるから,本件各 発明の相当実施料率の算定に当たってもこの点を考慮すべきであると主 張するが,被告がウェブ広告の分野において多数の特許を実施しているこ とやそれが売上げに寄与していることは,本件特許の相当実施料率を算定 すべき上で考慮すべき事情ということはできない。 また,被告は,本件特許の相当実施料率の算定に当たり,被告が自身の 努力により●省略●を作成したことを考慮すべきであると主張するが,上 記と同様,この点も本件特許の相当実施料率を算定すべき上で考慮すべき 事情ということはできない。
(ウ) 被告は,甲20公報を引用し,本件各発明の「IPアドレス対地域デー タベース」は「アクセスポイント側」の情報を用いるものであり,●省略 ●含まないとした上で,原告の主張を前提とするのであれば,本件各発明 の価値・技術的意義は低いなどと主張する。 しかし,被告の上記主張は,データベースの構成と●省略●を誤解・混\n同するものであり,その前提において失当であり,また,本件各発明が公 知技術との関係で新たな技術的意義が存在しないということはできない。 むしろ,本件各発明は,IPアドレスを所有するアクセスポイントが属 する地域を判別し,判別した地域に対応したウェブ情報を選択して前記ユ ーザ端末に送信する方法によって,同一URLにおいてもユーザの発信地 域ごとに異なるウェブ情報を送信することができるという効果を得る発 明であって,他にGPS等のシステムを用いることなく,ユーザ端末に割 り当てられたIPアドレスとIPアドレス対地域データベースを照合す るという比較的簡易な方法によりユーザの発信地域の判別をすることが できるものであるから,従来技術にはない新たな技術的意義を有するとい うことができる。
(エ) 被告は,本件特許の相当実施料率の算定に当たり,地域ターゲティング 以外のターゲティング機能の効用を考慮すべきであると主張する。\nしかし,地域ターゲティングは中心的な機能であり,他のターゲティン\nグ機能に比べてその重要性は高いというべきであり,また,これらの機能\ は重複して利用されることも多く,その寄与の度合いを個別に算定するこ とが困難であることは,前記(2)イ(エ)のとおりである。このため,YDN 及びプレミアム広告が地域ターゲティング以外のターゲティング機能を\n備えていることを考慮しても,適用すべき実施料率を下げることが相当と いうことはできない。
(オ) 被告は,YDNのクリック数や売上げは,被告が長年にわたり多大な労 力を積み上げてきたサービスの圧倒的な利用者数及びアクセス数を前提 とするものであり,これらは本件各発明と無関係であるから,本件特許の 相当実施料率の算定に当たってはこの点を考慮すべきであると主張する。 しかし,YDNの売上げにおいて,被告の提供するサービスの利用者数 や被告のウェブサイトへのアクセス数が影響を与えたとしても,本件各発 明の売上げ及び利益への貢献の程度という観点からみると,本件各発明は, IPアドレス対地域データベースを使用して,アクセスポイントの属する 地域を判別することを通じて,地域によって異なるウェブ情報をユーザ端 末に送信することを可能にするものであるから,エリアターゲティング広\n告に必要不可欠なものであり,本件各発明と同程度に簡易かつ効果的に地 域判別をし得る代替技術の存在を示す証拠のないことに照らすと,本件各 発明を利用することができない場合には,被告のYDNやプレミアム広告 の利用者に対する訴求力は大幅に減殺されたものというべきである。 このような本件各発明のYDN及びプレミアム広告の提供サービスに おける必要不可欠性や売上げや利益に対する貢献度に照らすと,YDNの 売上げにおいて,被告の提供するサービスの利用者数や被告のウェブサイ トへのアクセス数が影響を与えたとしても,これをもって,適用すべき実 施料率を下げることが相当であるということはできない。 また,被告は,プレミアム広告においては,被告ウェブサイトへのアク セス数のみが売上げに貢献するので,本件各発明は売上げに寄与,貢献し ていないと主張するが,上記と同様の理由から,そのような事情をもって 適用すべき実施料率を下げることが相当であるということはできない。
エ 小括
以上によれば,本件各発明の実施についての相当な実施料率は,YDNの うち被告ウェブサイトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告につき 3%,YDNのうち他の提携ウェブサイトに広告を掲載する部分は1.5% と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
2022.02.22
令和3(ネ)10066 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 前記のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり(原判決46頁 23行目ないし49頁1行目),本件各発明の特許請求の範囲の記載内容 に加え,本件明細書の段落【0012】の記載内容及び【図7】に記載さ れた本件各発明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容か\nらすれば,本件各発明の「操作メニュー情報」とは,「ポインタの座標位置 によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段 に表示するため」の「画像データ」であり,出力手段に表\示され,利用者 がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構\ 成されていることを要するものというべきである。
イ そして,被告製品のページ一部表示が,縮小された中央ページの右端又\nは左端あるいは両端に,幅が細く縦長の白みがかった長方形として表示さ\nれること,そこには何の文字,図形,記号,アイコン等は表示されないこ\nとからすれば,当該長方形部分のみを見た利用者は,それがどのような命 令を実行する表示であるのかを理解することはできないというべきであ\nり,したがって,被告製品のページ一部表示の画像は本件各発明の「操作\nメニュー情報」には当たらず,本件ホームアプリが構成要件Bの「操作メ\nニュー情報」を有するとは認められないことは,前記のとおり補正して引 用する原判決が説示するとおりである(原判決49頁2行目ないし50頁 6行目)。
控訴人は,1)被告製品においては構成e又は構\成e’によってそれまで 表示されていなかったページ一部表\示の画像が液晶画面に表示されるよ\nうになること,2)ページ一部表示の画像と壁紙画像との境界が明確である\nことを指摘するが,これらの点は,いずれも利用者がページ一部表示の画\n像自体から「実行される命令結果」の内容を理解することができるか否か に関わるものではないから,上記の判断を左右するものではないというべ きである。また,控訴人は,3)被告製品のページ一部表示の画像が表\現し ている表示内容は,実行されるスクロール命令の結果を小さな絵で表\現し た画像であるとも指摘するが,上記のとおり,ページ一部表示の画像は,\nその表示内容等からすれば,利用者がその表\示自体から「実行される命令 結果」の内容を理解できるように構成された画像データであるということ\nはできない。 なお,上記の判断に照らすと,控訴人が上記第2の3(1)アにおいて主張 する判断基準によったとしても,被告製品のページ一部表示の画像は,少\nなくとも同主張における3)の要件を満たすものとはいえないから,本件ホ ームアプリが構成要件Bの「操作メニュー情報」を有するとは認められな\nい。
ウ したがって,控訴人の主張(1)アは採用することができない。
(2) 控訴人の主張(1)イについて
ア 控訴人が主張(1)イにおいて指摘する各点は,いずれも上記(1)で検討し たところと同様の事情であるといえるから,いずれも前記の判断を左右す るものではないというべきである。そして,このことは,本件ホームアプ リに係るソースコードの記載内容を基に検討した場合であっても同様で\nある。
イ したがって,控訴人の主張(1)イは採用することができない。
(3) 小括
ア 控訴人は,上記のほかにも,争点1−3について縷々主張するが,いず れも前記の判断を左右するものではないというべきである。 イ 以上によれば,本件ホームアプリは,構成要件Bにいう「操作メニュー\n情報」を有するとは認められず,被告製品が構成要件Bを充足するものと\nは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,被告製品 が本件各発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.02.14
令和2(ワ)19927 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年12月24日 東京地方裁判所
原告は,本件発明3は,慢性疼痛に対する画期的処方薬として,抗て んかん作用を有するGABA類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり,その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから,対象となる痛みが侵害受容性疼痛か,神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく,効能・効果を神経障害性疼痛や\n線維筋痛症に伴う疼痛とし,慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は,均等侵害の第1要件を満たすと主張する。 しかし,前記1(1)アのとおり,本件特許に係る発明は,てんかん,ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が,痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し,反復使用により耐性を生じず,モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ,前記2(1)イのとおり,本件 出願当時,痛みには種々のものがあり,その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。 そうすると,いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは,本件発明 3において本質的部分というべきであり,その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は,本件発明3の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって,本件発明3に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明3の本質的部分でない\nということはできないから,被告医薬品は均等の第1要件を満たさない。
(イ) また,前記(1)アによれば,原告は,本件訂正前発明3においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ,本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると,本件発明3との関係においては,被告医薬品の効能・効果\nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって,被告医薬品は均等の第5要件も満たさない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2022.02.13
令和1(ワ)25121 特許権 令和3年12月9日 東京地方裁判所
このように,乙8発明は,ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し,そのリンク情報を取得して記憶し, ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして,かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は,ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ,当該リンクを出力することは,ユーザに対する提案を行うも のということができ,また,当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから, ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると,乙8発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は,構成要件1Eの「前記第1又は第2受付手段によって受け\n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し, また,乙8発明の,アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は,構\成要件5Eの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに,乙8発明における,ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は,構成要件1Fの「前記個人情報に基づいてウェブサ\nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し,上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は,構\成要件5Fの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他,構成要件E及びFと乙8発明の間に,相違する点は認められない。\n以上によれば,構成要件E及びFは,乙8発明の構\成と同一のものといえる。
エ 構成要件G(「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と,を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと,を更に有する」)につき,\n乙8発明と対比する。 構成要件Gに関し,本件明細書の記載をみると,「飲みすぎないように!」などの\nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり(【0119】),かかる記載内容 からすると,構成要件Gにおける「注意を促す」とは,気を付けるように仕向ける,\n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして,乙8発明は,スケジュールが未完了であることが確認すると,アバタ ーから,「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な,スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する(【0\n043】)。そして,乙8発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている(【0024】等)ところ,上記機能は,ユ\nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け,又は, スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると,乙8発明の,アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は, 構成要件1Gの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し,ま\nた,乙8発明の,ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は,構\成要件5Gの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他,構成要件Gと乙8発明の間に,相違する点は認められない。\n以上によれば,構成要件Gは,乙8発明の構\成と同一のものといえる。
オ 構成要件H(「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ\nグラム。」につき,乙8発明と対比する。 乙8発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は,情報の提供に当た るため,この点をもって既に,アバター管理部を有する乙8発明の学習・生活支援 サーバは,情報を提供する装置(「情報提供装置」)であるということができる。 また,上記サーバは,アバター管理部のほかに,ユーザ情報管理部,テキスト分 析部,情報収集部,コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており,制御部は,\n少なくとも一つのCPU等を備え,ROM等に予め記憶されたプログラムを読み込\nんで実行することにより,上記各部の機能を事項することが可能\となるものである (【0021】等)ことから,乙8発明の学習・生活支援サーバは,情報提供装置で あって,各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ,乙8発明\nは,構成要件1Hの「情報提供装置」,構\成要件5Hの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他,構成要件Hと乙8発明の間に,実質的に相違する点は認められない。\n以上によれば,構成要件Hは,乙8発明の構\成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって,本件各発明は,その全ての構成要件が,乙8発明の構\成と実質 的に同一のものであるから,本件各発明は,乙8発明との関係で,新規性を欠くも のといわざるを得ず,いずれも,特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる(特許法29条1項3号,123条1項2号)。
(5) 原告らの主張について
原告らは,1)乙8公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは, 構成要件Eにおける,議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す\nる,2)乙8公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは,ウェブサイトの 所在を示す情報であって,この所在を示す情報が,「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく,乙8発明は構成要件Eと相違し,また,ウェブサイトのリ\nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Fの「情報」とも相\n違する,3)乙8発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは,構成要件Gの,気を付けるよう仕\n向けることとは相違する,4)乙8発明のユーザ端末は,情報提供をするものではな いから,構成要件Hと相違する,などとして,本件各発明が乙8発明の構\成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら,原告らの上記各主張は,次のとおり,いずれも理由がないという べきである。 まず,上記1)及び3)の点については,乙8発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは,スケジュールが完了していないことを知り,新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって,「スケジュールの 修正の依頼」も,ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから,構成要件Eの「提案を行う」と実質的に同一の構\ 成であるといえる。また,乙8発明の上記のような働きは,まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け,又は,気を配るよう に仕向けることであるといえるから,乙8発明は,構成要件Gの「注意を促す手段」\nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。\nまた,上記2)の点については,構成要件Eの「提案を行う」との文言について,\n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に,ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく,ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上,前記説示のとおり,キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは,当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し,まさに,この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると,乙8発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは, 構成要件Eが規定するユーザに対する「提案を行う」との構\成と,同一であるとい わなければならない。また,構成要件Fの「情報」との相違を指摘する原告の主張\nも,結局,リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず,これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが,前記のと おり,ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは,ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において,ユーザに提案すべき情報を表示するものであり,乙8発明\nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは,構成要件Fの「情報」と異なるもので\nはないというべきである。 さらに,上記4)の点は,前記説示のとおり,乙8発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは,構成要件1Hの「情報提供装置」,構\成要件5Hの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば,原告らの主張はいずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.01.26
令和3(ネ)10031 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 控訴人の主張ア(イ)(本件発明の課題解決原理に基づく検討について)に つき
本件発明の技術的意義(前記1(2))に鑑みれば,本件明細書に開示され た発明は,半導体チップ上の領域ごとのゲート電極周縁長の合計が異なる 半導体集積回路装置(具体的にはシステムLSI)において,このような 領域ごとのゲート電極周縁長の合計のばらつきが,従来知られていたマイ クロローディング効果による局所的なパターン寸法の変動などとは異な り,半導体チップ全体にわたるCDロスに許容できないほどの変動をもた らすという,本件特許の出願時においては新規な課題を見い出し,これを, ダミーパターンを挿入してゲート電極周縁長のばらつきを抑えることに より解決したものである。したがって,本件発明の課題とその解決原理に 照らすと,本件発明の「半導体集積回路装置」は,システムLSIを意味 するものと解される。
本件特許の出願時に既に慣用されていたDRAMにおいて,メモリセル アレイを構成するビットラインやワードラインが,DRAMにおける他の\n回路と比較して周縁長が密な回路パターンであり,メモリセルアレイ領域 とそれ以外の回路領域とではゲート電極周縁長の合計がばらつくという 技術常識があったとしても,それが,DRAMを構成する半導体チップ全\n体にわたるCDロスに許容できないほどの変動をもたらすものであるこ とは,本件明細書に何ら言及されておらず,また,上記の新規な課題が, システムLSI中の一部の領域にすぎないDRAM単体においても同様 に生じるものであると認めるに足りる証拠はない。 そうすると,本件発明の課題とその解決原理に照らして,本件発明の「半 導体集積回路装置」は,システムLSIを意味するものと解され,DRA Mを含むと解することはできない。
ウ 控訴人の主張ア(ウ)(審査経過に基づく検討について)につき
控訴人は,審査経過に関し,第1回目及び第2回目の拒絶理由通知につ いて,審査官は,本件特許の発明がシステムLSIの発明であるとは認識 しておらず,また,出願人の意見書においても,本願発明と引用発明の相 違点について,本願発明はシステムLSIであるのに対して引用発明はシ ステムLSIではないという説明はしていないと主張する。 しかし,そもそも特許発明の技術的範囲の画定は,特許請求の範囲の記 載に基づいて定められるが,特許請求の範囲に記載された用語の意義の解 釈は明細書及び図面を考慮して行われるのであって(特許法70条1項及 び2項参照),特許出願の審査過程において,審査官がその特許発明をどの ように理解していたかということは,裁判所の特許発明の技術的範囲の画 定の判断を拘束するものではない。
また,出願人は,第1回目の拒絶理由通知に対する意見書(平成15年 11月28日提出,乙2)において,特許法29条1項3号及び同条2項 の規定に該当しない理由として,「言い換えると,ダミーパターンを挿入す ることによって,異なるマスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の 程度を小さくします。このため,ライン状パターンに品種に依存した寸法 変動が生じることを防止できるので,DRAM等の搭載率が用途又は仕様 により異なるシステムLSIにおいても,ゲート電極又はメタル配線等の 加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に一定にできます。従って, 請求項4の発明によると,動作マージンのバラツキが解消された半導体集 積回路装置を実現できるという格別の効果が得られます。」(乙2〔2〜3 頁〕)と記載し,第2回目の拒絶理由通知に対する意見書(平成16年3月 25日提出,乙4)において,特許法29条2項の規定に該当しない理由 として,「言い換えると,ダミーパターンを挿入することによって,異なる マスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の程度を小さくします。こ のため,本願明細書の段落番号[0132]に記載されておりますように, 『半導体集積回路装置の品種によりマスクパターンレイアウトが大きく 異なる場合にも,マスクパターンレイアウトの違いに起因してライン状パ ターンに寸法ばらつきが生じることを防止できる。従って,DRAM等の 搭載率が用途又は仕様により異なるシステムLSIにおいても,ゲート電 極又はメタル配線等の加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に 一定にできるので,動作マージンのバラツキが解消された半導体集積回路 装置を実現できる』という格別の効果・・・が得られます。」(乙4〔4頁〕) と記載し,いずれの意見書においても,本願発明がシステムLSIに用い られて効果を生ずることを明確に述べており,このような段階を踏まえて 本件特許が登録されたものである。 したがって,仮に,審査官が,拒絶理由通知を発出する際に,特許請求 の範囲に記載された発明の要旨認定において,「半導体集積回路装置」を, その一般的な字義どおりに,DRAMを含む半導体集積回路装置全般と解 釈しており,また,出願人の意見書において,本願発明と引用発明の相違 点として,本願発明はシステムLSIであるのに対して引用発明はシステ ムLSIではないことが明示されていなかったとしても,それに基づいて, 本件発明の「半導体集積回路装置」にシステムLSIではないDRAM自 体が含まれるということはできない。
(3) そうすると,本件発明における「半導体集積回路装置」(構成要件1A,1\nE,5B,5E等)という語は,システムLSIを意味するものとして用い られており,DRAMはこれに含まれないというべきであり,DRAMであ ることに争いのない被控訴人製品(前記第2,2による引用のうちの原判決 「事実及び理由」第2,2⑽(原判決8頁20〜23行目))は,本件発明1 の構成要件1A,1E,本件発明5の構\成要件5B,5Eをいずれも充足せ ず,本件発明1及び本件発明5の技術的範囲のいずれにも属さないものと認 められる。 控訴人は種々主張するが,その主張は,いずれも採用することができない。
◆判決本文
原審はアップされていません。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.01.11
平成31(ワ)647 債務不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月26日 東京地方裁判所
ウ そこで,以上の説示を前提として,以下,公然実施発明1への甲5−1発 明の組合せの可否について検討する。 まず,公然実施発明1は,スリープ状態とスリープ解除状態とを有し,スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス\nマートフォンというものであり,他方,甲5−1発明の技術分野は,生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると,両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また,公然実施発明1は,スリープ状態において,ホームボタンを押すことによ り,デバイス機能を有効にするときに,起動して認証を行うというものであるか\nら,ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに,パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。\nこの点,公然実施発明1においては,ホームボタンの押下の後,パスコード認証の 前に,ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ\nるが,この構成については,タッチパネル入力による誤作動防止(パスコードによ\nる認証の設定がされている場合は,パスコードやホーム画面の誤作動防止であり, パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても,ホーム画面の誤作動 防止)という,ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ,パスコード 認証という構成は,これとは別の,ユーザ識別のための構\成として把握することが できるものであって,上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構\ 成であるというべきである。そして,甲5−1発明における「ユーザがデバイスを オンにする,ロックを解除する,または,起動する」ことは,デバイスの機能を有\n効にすることであるといえ,また,デバイス機能を有効にする前に,生体情報の提\n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると,公然\n実施発明1と甲5−1発明とは,デバイスの機能を有効にするときに,ユーザ識別\nのための認証動作を行う点に関して,その作用機能が共通するものと認められる。\n以上によれば,公然実施発明1と甲5−1発明においては,技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって,当業者(その発明の属する技術の\n分野における通常の知識を有する者)において,両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり,その他,本件全証拠をみても,両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると,公然実施発明1のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として,甲5−1発明におけるデバイス\nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため\nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構\n成を組み合わせることは,当業者が容易に想到できたことである。また,公然実施 発明1はパスコードの入力による認証に関して,誤ったパスコードが入力されると, ロック状態が維持され,ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ\nれる構成を有するし,甲5−1発明も,特定されたユーザが許可されていないと判\n断した場合,認証を行うようユーザに指示する構成を有し(甲5文献【0080】),\nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること,及びユーザ認\n証のための操作が行われると,認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは,当該技術の性質・内容に照らし,周知慣用技術といえる。そして,公然実 施発明1は,使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な使用者と認証され\nなければロック状態を維持するものであるところ,公然実施発明1に甲5−1発明 を組み合わせる際に,かかる構成をあえて排除又は変更する理由は,本件全証拠を\nみても見当たらない。 以上からすると,当業者は,相違点1に係る構成を容易に想到することができた\nものといえ,本件発明1−1を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ア) 被告は,公然実施発明1は,パスコードの入力という使用者識別機能を有\nするものの,指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく,こ れを有する甲5発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし,前記認定のとおり,両発明においては,いずれも,デバイスの機能を有\n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって, パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの,両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると,被告の上記主張は,採用することができない。
(イ) また,被告は,公然実施発明1は,ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ,これ\nは,デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ\ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲5発明の課題と共通しないから,公然実施発明1に甲5発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら,前記説示のとおり,公然実施発明1に係るパスコード認証という 構成については,ユーザ識別のための構\成として,上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構\成として把握することができるというべきである。 そうすると,公然実施発明1におけるパスコードによる認証という構成と,甲5−\n1発明におけるシームレスな認証処理という構成とは,ユーザにおいて許可されて\nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり,両発明において,デバイス機能を有効に\nするときのユーザ認証の動作に関して,その作用機能が共通するものと認められる\nことに変わりはない。すなわち,ユーザによる誤作動の防止と,スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは,その性質内容に 照らし,互いに別個のものということができ,公然実施発明1がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって,これに甲5−1発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると,被告の上記主張は,採用することができない。
(ウ) さらに,被告は,本件発明1−1は,1) 指紋認証による使用者識別機能が,\n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により,かつ,使用者による 追加操作なしに行われる,2) 使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な\n使用者と認証されなければ,移動通信端末機のロック状態を維持するとともに,デ ィスプレイ部にメッセージを表示する,3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると,使用者識別機能による認証の結果にかかわらず,\nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが,公然実\n施発明1にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ,甲5発明 には,上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため,両者を組み合わせても,\n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし,被告主張の上記1)については,上記ウで説示したとおり,公然実施発明 1のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として,甲5−1発明における\nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証\nするための構成を,公然実施発明1のスライダを備えたロック画面を残したまま組\nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また,公然実施発明1は,パスコードを入力することによる使用者識別機能によ\nる認証の結果,認証されなければロックを維持するものといえるところ,公然実施 発明1に甲5−1発明を組み合わせる際に,かかる構成をあえて排除又は変更する\n理由が認められないこと,ユーザ認証がされなかった場合には,ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること,及びユーザ認証のための操\n作が行われると,認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは,前記説示のとおりである。そうすると,被告主張の上記2)及 び3)について,実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば,本件発明1―1は,当業者が公然実施発明1に甲5−1発明を組\nみ合わせることにより,容易に想到することができたものといえ(特許法29条2 項),本件発明1−1は,特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある(同法123条1項2号)。
・・・
7 争点3−3(無効理由2の解消の有無)
(1) 本件訂正事項2−1,2−2に係る訂正による無効理由2の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項2−1は,本件発明2−1の構成要件2−1Cの活性状態をロック\n画面が表示されたものに限定するものであり,本件訂正事項2−2は,本件発明2\n−2の構成要件2−2Aに,「前記ロック画面には,現在の時間を表\示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項2−1,2−2に係る訂正による無効理由2の解消の有無 しかしながら,本件訂正発明2−1及び本件訂正発明2−2と公然実施発明2と を対比してみたとしても,前記5(2)で認定した公然実施発明2の構成からすれば,\nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点,同画面に\n現在の時間を表示することができる点について,相違するものではない。\n以上によれば,本件訂正事項2−1,2−2に係る訂正によっても,無効理由2 を解消することはできないといわなければならない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.01.11
令和1(ワ)27053 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月31日 東京地方裁判所
争点1−1(被告製品の小径部側壁部は,係止片は大径部側に一体形成される一方 小径部側には設けられていないという文言を充足するか−構成要件1E4),2E4), 3E5)充足性)について
構成要件1E4),2E4),3E5)によれば,「係止片は」「大径部側に」「一体形成 される一方」「小径部側には設けられておらず」というのであり,上記のとおり,本 件発明は,従来よりも安全性などの向上を図るというその目的をより良く達成する という上記の技術的見地から,針先再露出防止を担う係止片の構成を工夫して,拡\n開部の大径部側に一体形成し小径部側には設けないという構成を採用したものとい\nうことができる。これによれば,本件発明において,拡開部に設ける「係止片」に ついては,大径部側に一体形成されている必要があるとともに,小径部側には設け られていない構成である必要があるものであって,「係止片」が小径部側に設けられ\nている構成は排除されているものといわなければならない。\n
そして,この「係止片」は,使用後の針先再露出を防止する部材であるといえる が,当該部材が針先の先端側への移動を阻止して針先再露出を防止する態様につい ては,構成要件1Dに「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた\n所定位置において,該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止 される」とある以上には何ら具体的な限定がなされていない。また,本件明細書の 発明の詳細な説明を見ても,当該部材が,針先の先端側への移動を阻止する具体的 態様を限定する根拠となり得るような記載は見当たらない。加えて,本件特許の出 願経過を見ると,証拠(乙14,15)によれば,原告は,令和元年5月15日頃, 特許庁から進歩性欠如等を理由とする拒絶理由通知を受け,その際,構成要件1D\nに関し,「針先プロテクタの断面形状を,周知の形状である小径部と大径部とを備え た楕円形とし,大径部の周壁に針ハブ係合部を設け,大径部の周壁で覆われた内部 に係止部を設けた構成とすることは,当業者が容易になし得たことである。」などと\n指摘されたことを踏まえて,同年6月19日,従前の請求項で「前記拡開部の前記 大径部に対応する位置に,前記筒状の周壁に一体形成された前記係止部が設けられ て」と記載していた部分を,「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方, 前記小径部側には設けられておらず,」と補正したものであることが認められる。そ の上で原告は,同日特許庁に提出した意見書において,本件発明の進歩性を基礎付 ける事情として,拒絶理由通知書で審査官が指摘した引用文献(乙27,29)に ついては,いずれも針先プロテクタの小径部側に係止部が設けられており本件発明 とは異なる旨主張し,その際,当該係止部が針先の先端側への移動を阻止する具体 的態様には言及していなかったことが認められる。そして,本件特許は,その上で 登録されている。
そうすると,本件特許請求の範囲の記載文言をみても,本件明細書の発明の詳細 な説明をみても,小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」が針先 の先端側への移動を阻止する具体的態様を限定する根拠となり得るような記載がな く,加えて,原告自身,本件特許の出願手続においては,その特許請求の範囲を前 記のように「前記小径部側には設けられておらず,」と補正した上で,意見書におい て,具体的態様については何ら限定しないまま,小径部側に「係止片」が設けられ ていない点を本件発明の進歩性を基礎付ける事情として主張し,その上で本件特許 が登録されたものである。 以上によれば,本件発明において小径部側に設けられてはならない「係止片」は, 針先の先端側への移動を阻止する具体的態様が限定されているものではなく,他の 部材と協働して針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものであるといわなけ\nればならない。
そこで,被告製品をみるに,前記前提事実によれば,被告製品においては,針基 に設けられた針リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが,小径部側壁部の 突端面により縦リブの側面を挟持することで互いに係合することにより,針基が針 先保護部に対して回動することを防止する構成になっており,仮にこのような回動\nが発生して針基の受部が大径部係止手段のない小径部側まで移動した場合には,針 基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前進することになる。すなわ ち,小径部側壁部がなければ,大径部係止手段が無効化されて,針基が前進し,留 置針の針先が針先保護部の先端側から再露出することになるのであるから,被告製 品においては,小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段による針基の 受け部の係止が協働して機能することによって,針先の再露出を防止していると認\nめられる。
そうすると,被告製品の小径部側壁部は,他の部材と協働して,針先の先端側へ の移動を阻止する構成であるといえ,当該小径部側壁部は,本件発明において小径\n部側に設けられることが排除されている「係止片」に当たるといわなければならな い。これによれば,「係止片」が針先抜出防止機構を含むものであるか否かに関わら\nず,被告製品は,小径部側に「係止片」が設けられているものとして,本件発明に おいて排除されている構成を有しているから,本件発明の構\成要件1E4),2E4), 3E5)をいずれも充足しないといわなければならない。 したがって,被告製品は,本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,本件発明の構成要件1Dの「係止片」が,針ハブ(に設けられた受部)\nと「係止」されることによって「再露出を防止する(つまり,留置針が前進しな いように止める)」ものであるのに対し,被告製品の小径部側壁部は,針基の縦リ ブの側面を挟持して針基の回動を防止しているだけで,針基の前進を防止してい るわけではないから,「係止片」に該当しないなどと主張する。 しかし,前記説示のとおり,本件発明にいう「係止片」は,他の部材と協働し て針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものといわなければならない。そ\nして,被告製品において,小径部側壁部がそれ単体として針先の再露出を防止す るものでないとしても,小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段に よる針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再露出を防止し\nているものである以上,本件発明にいう「係止片」に該当しないということはで きない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ また,原告は,被告製品の小径部側壁部が針基の縦リブの側面を挟持する場所 は,針基と針先保護部の位置関係にかかわらないのであって,留置針の針先側へ 針先プロテクタが移動せしめられた「所定位置」において係止するものでないた め,被告製品の小径部側壁部は「係止片」に当たらないとも主張する。 しかしながら,前記のとおり,被告製品は,小径部側壁部がそれ単体として針 先の再露出を防止するものではなく,小径部側壁部による針基の回動防止と大径 部係止手段による針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再\n露出を防止するものであり,その機能が発揮される場所は,前記前提事実のとお\nり,針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる位置に限定されている。 このことからすれば,被告製品の小径部側壁部は,「留置針の針先側へ針先プロテ クタが移動せしめられた所定位置において」,大径部係止手段と協働して針先の再 露出を防止しているといえる。被告製品の小径部側壁部が,針先と針先保護部の 位置関係にかかわらず針基の縦リブの側面を挟持しているという事情は,この説 示を左右するものではない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ さらに,原告は,本件発明の構成要件1E4),2E4),3E5)が「前記係止片 は,前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し,」と規定していることをもって, 本件発明で小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」は「前記針 ハブに向かって傾斜した内側面」を有しているものに限られているなどと主張す る。
しかし,構成要件1E4),2E4),3E5)の「前記係止片は,前記針ハブに向 かって傾斜した内側面を有し」との文言は,本件明細書の段落【0061】の記 載(「・・・垂直面79a,79aの外周側に位置する傾斜面79b,79bが,外周 側になるにつれて先端側に傾斜していることから,垂直面79a,79aと基端 側規制面40とが傾斜面79b,79bに干渉されることなく当接することがで きて,針ユニット20と針先プロテクタ10の軸方向における相対移動防止効果 がより確実に発揮され得る。」との記載)も併せると,そのような大径部側に一体 形成される係止片の構成について,規定した針ユニットと針先プロテクタの軸方\n向における相対移動防止効果がより確実に発揮されるという効果を奏させるべく 規定されたものであると認められる。そうすると,当該文言は,大径部側に円筒 状部と一体形成される係止片について特定したものにすぎず,設けられていては ならない位置にある「係止片」の形状を限定するものではないというべきである。 したがって,被告製品の小径部側壁部が「傾斜した内側面」を有しないことは, 被告製品の小径部側壁部が本件発明において小径部側に設けられてはならないと されている「係止片」に当たることを否定する理由にはならない。原告の上記主 張は,採用することができない。
エ 以上によれば,原告の上記主張はいずれも採用できない。原告は,その他も縷々 主張するが,それらの主張内容を慎重に精査しても,上記説示を左右するに足り るものはない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2022.01. 7
平成30(ワ)1130 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月31日 東京地方裁判所
ア 前記前提事実によれば,本件発明の構成要件1Eは,「該印刷層は,白色の有機\n顔料,白色または黄色の無機顔料,蛍光染料,および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成1eは,「印刷層\nは,●(省略)●と●(省略)●を含有する●(省略)●印刷インキにより形成 されるが,」である。そして,被告製品の印刷層の●(省略)●印刷インキに含有 される●(省略)●は,「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは,本件発明については,印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば,それだけで構成要件1Eを充足するのではなく,これにより「色相を明\nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件1Eには,印刷層が「白色の有機顔料,および蛍光増白剤」\nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり,「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また,前記1のとおり,本件発明は,再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ,本件明細書の段落【0004】には,三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち,反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては,その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの,それ以外の再帰反射シートについては,外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また,本件明細書の【0014】,【0015】には,本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され,段落【0021】,【0 030】,【0032】には,印刷層の目的は「色相を調節」,「色相の調整」と記 載され,段落【0036】には,「本発明に用いられる着色剤は,特に限定される ものではないが,・・・色相を明るくすることができ,且つ,隠蔽性が得られるもの が良く,シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく,・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料,並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ,中でも, 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており,「色相を明るくすること」 は,「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで, あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため,本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は,色相の調節ないし調整を意味するも のであり,「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方, 本件明細書の実施例では,白色顔料が用いられているものの,その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく,比較例でも, 実施例とは印刷の模様のみを変えて,「Y値」すなわち「色相(明るさ)」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば,本件発明の構成要件1Eの「着色剤」が「色相を\n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば,本件発明の構成要件1Eの「着色剤」が「色相を明るくするこ\nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し,被告らは,本件特許の出願経過において,原告が,補正により本 件発明に構成要件1Eを追加し(乙21),本件発明の効果は,「色相,特に昼光\n下での色相(Y値=明るさ)が改善されて」いることであり,同構成要件の着色\n剤を用いることにより色相(Y値=明るさ)を改善したと主張しており(乙3), 同構成要件の「白色」,「黄色」,「蛍光」を用いて「色相(Y値=明るさ)」を改善\nする技術的意義を強調しているから,上記着色剤の意義は,色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし,原告が提出した乙21の内容を見ても,本件発明の構成要件1Eの技\n術的意義が,「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ,乙3には,本件発明の効果は,「十分な再帰反射性能\を有し,かつ色相, 特に昼光下での色相(Y値=明るさ)が改善されており,耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され,Y値と同義である「色相(Y値=明るさ)」 と,それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため,明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに,乙3には, 一般に用いられている着色剤は,再帰反射性の確保のために光透過性を有するが, 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して,本件 発明の構成要件1Eの着色剤は,光透過性を有するものではないこと,本件発明\nは,構成要件1Eの着色剤を用いることにより,再帰反射シートの昼光下での色\n相(Y値=明るさ)を更に改善したこと,本件発明では,印刷領域が構成要件1\nB〜1Dを具備する独立印刷領域であるため,印刷層が光透過性を有しない構成\n要件1Eの着色剤を含有しても,それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能\を 有することが記載されている。以上によれば,原告は,本件特許の出願経過にお いて,本件発明の構成要件1Eの着色剤について,明るさの改善だけでなく,そ\nれ以外の効果も主張していると解されるから,そのような主張をもって,本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他,被告らの主張を検討しても,採用すべきものはない。
エ したがって,被告製品(1)の構成1eは,それぞれ本件発明の構\成要件1E及び これを引用する構成要件2Bを充足する(なお,仮に同構\成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても,これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り,必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ,証拠(甲17)及び 弁論の全趣旨によれば,被告製品では,「白色」の「無機顔料」に当たる●(省略) ●を含有しない領域よりも,これを含有する領域の方が色相も改善●(省略)● による色相改善の効果を享受)していることがうかがわれ,被告製品の●(省略) ●印刷インキの色相が暗くなっているのは,●(省略)●で色相が明るくなった 一方で,●(省略)●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり,これに よって本件発明の構成要件1Eの充足性が否定されることにはならないというべ\nきである。)。
・・・
推定覆滅の事情
a 特許法102条2項における推定の覆滅については,同条1項ただし書の 事情と同様に,侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば,1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること (市場の非同一性),2)市場における競合品の存在,3)侵害者の営業努力(ブ ランド力,宣伝広告),4)侵害品の性能(機能\,デザイン等特許発明以外の特 徴)などの事情について,特許法102条1項ただし書の事情と同様,同条 2項についても,これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
b そこで,被告らが特許法102条1項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに,次のとおり,2割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは,本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は,顧客吸引には全く寄与しておらず,被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり,被告旧製品のカ タログでも,印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし, 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり,本件発明 は,被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし,前記1(9)で説示したとおり,本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は,再帰反射シートの印刷層について,「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており,連続層を形成せず」,「独 立印刷領域の面積が0.15mm2〜30mm2」,かつ,「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより,印刷層周辺の密着\n性を向上させ,耐水性・耐候性を向上させるとともに,色相の改善を図る ことにあるのであるから,その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は,その前提を欠くものである。また,被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果(乙45〜49)についても,その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから,これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして,証拠(甲3,4,9,10,23,67〜70)及び弁論の 全趣旨によれば,被告旧製品のカタログやウェブサイトには,本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記\n載が多数存在することも認められる。 したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に,被告は,本件発明は,被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず,むしろ,3Mブランドに裏付けられた被告らの信用,実績及び知名度 等こそが,被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり,現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし,仮に被告らが3Mグループとしてのブランド力を有するとして も,これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また,仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても,顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上,従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから,これをもって直ちに本件発明が顧客への販売\nに貢献していないということはできない。 したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また,被告らは,主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については,再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく,原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり,実際に,被告らの販売\nする被告製品並びにその他の製品(Diamondグレード及びEngi neeringグレードの再帰反射シート)の売上比がそれぞれ●(省略) ●であり,原告製品の売上比が10%であるから,仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば,そのうちの●(省略)●(=10/(10+● (省略)●))のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし,そもそも,競合品といえるためには,市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは,被告ら が販売するDiamondグレード及びEngineeringグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが,弁論の全趣旨 によれば,前者の価格は被告旧製品の●(省略)●以上であり,後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから,これらの製品の\n価格や性能等を捨象して,同様の用途に用いられる再帰反射シートである\nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると,被告 らが主張するDiamondグレード及びEngineeringグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず,それゆえに被告旧製品の需要がDiamondグレー ド及びEngineeringグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに,被告らは,仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても,原告の逸失利益は,被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ,原告製品の販売単価は被告旧製品の●(省 略)●程度の価格帯であり,原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●(省略)●程度であるはずであり,原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●(省略)●程度にすぎないことが推認されるから,特許法10 2条2項によって推定される損害額は,原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点,弁論の全趣旨によれば,原告製品の販売単価は,被告旧製品の ●(省略)●程度の価格帯であることが認められるところ,仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても,原告において,被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く,この点については,一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが,他方で,原告製品の販売単 価が低価格であることにより,その販売数量が,被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから,大幅な推定覆滅を認めるのが相\n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると,被告らが主張する推定覆滅事由のうち, 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ,推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり,その覆滅割合は2割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に,原告は,予備的主張として,特許法102条3項の適用を前提とする損\n害額の支払を求めているため,以下検討する。
・・・
a 特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については,平成10年法律第51号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ,「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して,同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で,被許諾者が最低保証額 を支払い,当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し,技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には,侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして,上記 のような特許法改正の経緯に照らせば,同項に基づく損害の算定に当たって は,必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく,特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき,実施に対し受けるべき料率は,むしろ,通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって,実施に対し受けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て,合理的な料率を定めるべきである。
b そこで検討するに,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,1)原告は,本 件訴訟の提起前に,被告らを含む3Mグループに対し,本件特許のライセン ス料率5%を提案していたこと(乙41),他方で,米国3Mは,過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において,再帰反射シートに関する特許の実施 料率は9%であると主張していたこと(甲71),米国3Mらは,過去に第三 者に提起した訴訟において,ロイヤルティ料率20%での合意をしたこと(甲 72,乙66),株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産(資産)価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」(平成22年3月)において,再 帰反射シート(樹脂シート)が該当する「化学」の最小値が0.5%,最大 値が32.5%,平均が4.3%であるとされていること(甲73,乙67), 被告3Mジャパンらは,原告に提起した特許権侵害訴訟において,実施料率 を10%と主張していること等が認められる。 また,2)本件発明は,前記のとおり,再帰反射シートの構成全体に関わる\n発明であり,相応の重要性を有しているといえ,これらの構成を備えた従来\n技術は存在せず,この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして,3)本件発明は,被告旧製品の全体について実施されており,これ によって向上される耐水性・耐候性は,需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから,本件発明を被告旧製品に用いることにより,被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに,原告と被告らは,いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり, 競業関係にある。
c 上記bの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると,本件特許\n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき,本件での実施に対し受ける べき料率は,10%を下らないものと認めるのが相当である。 したがって,本件特許権侵害について,特許法102条3項により算定さ れる損害額は,前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の10%になる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.01. 4
令和2(ネ)10029 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 原告は,1)本件発明1の「該平均重合度が,該セルロース粉末を塩酸2. 5N,15分間煮沸して加水分解させた後,粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より5〜300高いこと」との要件(差分要件)は,「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず, 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は,いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって,実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること,BATTIST A論文の記載に照らすと,「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると,本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から,差分要件の数値範囲において,本件発明の 1の課題を解決できると当業者が認識することはできない,2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は,「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より100低いと仮定した場合,実施例2ない し6において示されている差分の範囲は150〜255であり,その下限 値は150であること,差分5ないし10という数値は,粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり,実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと,当業者は,差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると,本件明細 書記載の差分が150以上の実施例のデータのみをもって,測定誤差のレ ベルである差分5ないし10を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明1の課題を解決できると認識することはできないとして, 本件発明1はサポート要件に適合しない旨主張するので,以下において判 断する。
(ア) 本件発明1の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,本件発明1の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが,本件明細書の【0 015】に,「本発明でいうレベルオフ重合度とは2.5N塩酸,沸騰温 度,15分の条件で加水分解した後,粘度法(銅エチレンジアミン法) により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は,本件発明1の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから(前記6(1)イ),本件発明1の「レベルオフ重合度」とは,2. 5N塩酸,沸騰温度,15分の条件で加水分解した後,粘度法(銅エチ レンジアミン法)により測定される重合度」をいうものと解される。 なお,本件明細書の【0015】には,レベルオフ重合度に関し,「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると,酸が浸透しうる結晶 以外の領域,いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため,レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており(I NDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMIST RY,Vol.42,No.3,p.502−507(1950)),その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を2.5N塩酸,沸騰温度,15分 の条件で加水分解した時,重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき,重合度の低下が起きれば,レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を2.5N塩酸,沸騰温度,15分の条件で加水分解した時, 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき, 重合度の低下が起きれば,レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は,本件出願当時,「レベルオフ重合度」とは,セルロースを 酸加水分解すると,その重合度は,酸加水分解初期に急激に200−3 00に低下した後ほぼ一定になり,このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと(前記(1)イ(ア))に照らすと,レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
a 本件明細書には,実施例2ないし7及び比較例1ないし11のセル ロース粉末について,それぞれの原料パルプ(市販SPパルプ,市販 KPパルプ等)のレベルオフ重合度が記載されている(【0039】な いし【0047】)。 前記(1)イ(ア)のとおり,本件出願当時,酸加水分解時に,非結晶部 分は酸で分解されやすいが,結晶部分は分解されず残り,残った部分 の化学構造と結晶構\造は,原料セルロースのままであって,分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると,本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は,原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和2年9月11日付け意見書(乙72) 中には,「3桁のLODPを報告するときの有効数字は2桁とするのが 一般的であるが,実際のところ,2桁目,3桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので,LODPについて十の桁,一の桁を議\n論することは技術的に意味がない。そして,同一のセルロースでもL ODPは酸加水分解条件等によって変化することも常識である,その ため,例えば,市販の木材パルプのLODPを測定したとしても,そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のLODP については,やはり実際に測定してみなければわからず,原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか,具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら,他方で,上記意見書中には,「LODPとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間(・・・)経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や,「BATTI STA論文でも同様であるが,「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に,例えば,「平均重合度が下がりきっている(これ以上全く低下し ない)」という含意はない。」,「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも2時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」,「こうした変化も含めて200 〜300程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると,上記意見書の上記記載部分は,市販の木材パ ルプのLODPとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のLODPとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で,木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のLODPについては,原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから,上記記 載部分によって,本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
b 加えて,本件明細書の表4には,実施例2ないし7及び比較例1な\nいし11のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると, 本件明細書に接した当業者は,上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また,本件明細書の表4には,「平均重合度」,「粒子の平均L/D(長\n径短径比)」,「平均粒子径」,「見掛け比容積」,「見掛けタッピング比容 積」,「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」(差分 要件)のいずれもが本件発明1の数値範囲内にある実施例2ないし7 のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明1の数値 範囲外である比較例1ないし11とのセルロース粉末の円柱状成形体 について,平均降伏圧[MPa],錠剤の水蒸気吸着速度Ka,硬度[N] 及び崩壊時間[秒]が示されている。 そして,実施例2ないし7のセルロース粉末は,いずれも,安息角 が55°以下,錠剤硬度が170N以上,崩壊時間が130秒以下で あり,ここで,安息角は,55°を超えると,流動性が著しく悪くな り(【0018】),錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり,1 70N以上が好ましく(【0019】),崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり,130秒以下が好ましい(【0019】)のであるか ら,実施例2ないし7のセルロース粉末は,成形性,流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ\nができる。
したがって,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から,実施例2ないし7のセルロース粉末は, 本件発明1の課題を解決できると認識できるものと認められるから, 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には,「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子L/Dが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」(【0015】),「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては,5〜300程度であることが 好ましい。さらに好ましくは10〜250程度である。5未満では粒子 L/Dを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。300を超えると繊維性が増して崩壊性,流動性が悪くなって 好ましくない。」(【0016】),「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと,製造工程における攪拌操作で粒子L/D が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し,L/Dが小さくなるので,乾燥前の粒子 の平均L/Dを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」(【0021】)との記載がある。 これらの記載から,セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと,乾燥前のセルロース粒子のL/Dが低下しやすく,そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して,得られるセルロース粉末 のL/Dが小さくなり,L/Dが小さくなると,成形性が低下すること を理解できる。 そして,本件発明1の差分要件は,レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを,セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分(差分要件)で表し,その下限を「5」としたこ\nとを理解できるから,当業者は,本件発明1の差分要件の数値範囲の全 体にわたり,本件発明1の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって,2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から,当業者は,本件発明1の差分要件の数値範囲の全体に わたり,本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また,これと同様の理由により,本件発明2も,発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。
◆判決本文
1審はこちら
◆東京地裁平成29年(ワ)24598号
キ 以上によれば,本件差分要件は,粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるところ,明細書の発明の詳細な説明には,実施例について,粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく,また,優先日当時の技術常識によっても,それが記載されているに等しい とはいえない。したがって,本件明細書の発明な詳細には,本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。そうすると,本件明細書の発明な詳細において,特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和1(ワ)8905 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月18日 大阪地方裁判所
(ア) 本件明細書の記載によれば,本件明細書においては,「針先の再露出」ない しこれと同旨の意味を含む表現(「針先再露出阻止機構\」等)と「針抜出し」ない しこれと同旨の意味を含む表現(「針抜出阻止機構\」等)がそれぞれ用いられてい る。その上で,「針先の再露出」等の表現は,針先プロテクタが留置針の針先側へ\nの移動位置において針ハブに係止された後に,針先プロテクタが留置針の基端側へ 後退(移動)すること(【0013】,【0027】,【0070】,【0073】)又は留置針 が針先側(先端側)へ前進(移動)すること(【0028】,【0029】,【0034】〜 【0036】)により針先が外部に露出することを意味する場合に用いられている。 他方,「針抜出し」等の表現は,留置針が基端側へ移動し,針先プロテクタの基端\n側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを意味する場合に用いられ るものと理解される(【0022】,【0028】,【0029】,【0034】,【0035】, 【0071】)。
このように,本件明細書では,「針先の再露出」等と「針抜出し」等の表現が明\n確に使い分けられていることを踏まえると,「留置針の針先の再露出」(構成要件\n1D 等)とは,針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において針ハブに係 止された後に,針先プロテクタが留置針の基端側へ後退(移動)すること又は留置 針が針先側(先端側)へ前進(移動)することにより針先が外部に露出することを 意味するものであって,留置針が基端側へ移動し,針先プロテクタの基端側から抜 け落ちることにより針先が外部に露出する場合はこれに含まれないと解される。こ れに反する被告の主張は採用できない。 したがって,「係止片」(構成要件 1D 等)は,上記の意味における「留置針の 針先の再露出」を防止する機構を構\成するものと理解される。構成要件 1E4)等の 「係止片」も,「前記係止片」として構成要件 1D 等を受けたものであることか ら,同様である。
(イ) 「係止片」(構成要件 1E4)等)につき,本件明細書には,針先プロテクタの 大径部側に形成されるものの形状及び機能等に関しては,それが「針ハブに向かっ\nて傾斜した内側面を有し」,「円筒状部と一体形成される」ことを含めて具体的に 記載されている(【0028】,【0034】,【0036】,【0058】,【0059】, 【0061】,【0065】,【0067】〜【0070】,図 9)。これに対し,「小径部側に 設けられ」ない「係止片」に関しては,その形状はもとより,係止片を小径部側に 設けないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害等につい て,本件明細書には何ら記載されていない。
また,本件特許の出願経過を見ると,本件意見書によれば,小径部に設けられて いない係止片の形状につき,原告は「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有」 するものを念頭に置いていると理解する余地もあるものの,本件各発明の進歩性を 主張するに当たり,本件通知書の引用文献2及び4に各記載の「針先プロテクタの 小径部側」に設けられている「係止部」の具体的な形状に言及してはおらず,小径 部に設けられていない係止片の形状についてはもとより,係止片を小径部側に設け ないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害についての言及 もない。そうすると,本件意見書の記載については,原告は,公知の発明と構成が\n異なることを示す趣旨で「係止片」が「小径部側には設けられて」いないことに言 及したに過ぎず,「係止片」の形状に関しては,拡開部の大径部側に設けられた係 止片Sが針ハブに向かって傾斜した内側面を有することを説明するにとどまり,小径 部側に設けられていない係止片に関しては何ら述べていないものと理解される。 このような本件明細書の記載及び本件特許に係る出願経過を参酌すると,「係止 片」(構成要件 1E4)等)につき,「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有 し」とは,「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」「係止片」の形状を 特定したものであって,「前記小径部側には設けられて」いない「係止片」の形状 を特定するものではないと理解される。これに反する原告の主張は採用できない。
(ウ) 小括
以上より,本件各発明の「係止部」とは,「該針先プロテクタに設けられた」も のであり,これが「該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が 防止される」,すなわち,針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において 針ハブに係止された後に,針先プロテクタが留置針の基端側へ後退(移動)するこ と又は留置針が針先側(先端側)へ前進(移動)することにより針先が外部に露出 することを防止するものであって(以上につき,構成要件 1D 等),針先プロテク タの有する「前記円筒状部の基端側に」設けられるものであり(構成要件 1E2) 等),かつ,「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し,前記大径部側に前記 円筒状部と一体形成される」が,その形状のいかんを問わず「前記小径部側には設 けられ」ない(以上につき,構成要件 1E4)等)ものであると解される。
(2) 構成要件の充足性\n
ア 被告各製品の小径部の側壁部の構成等\n
(ア) 被告各製品の小径部側壁部につき,針先保護部(針先プロテクタ)の基端側 に設けられていること,針抜出防止機構(針先プロテクタが留置針の針先側への移\n動位置において針ハブに係止された後に,更に留置針が基端側へ移動し,針先プロ テクタの基端側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを防止する機 構)として機能\すること,及び,少なくとも針管と針先保護部が相対移動してクリ ック感が生じる位置において,小径部側壁部の突端面により針基に設けられた縦リ ブの側面を挟持することで,針基が針先保護部に対して回動を防止する状態となる ことについては,当事者間に争いがない。
(イ) 証拠(甲3〜6,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製品において は,小径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持することで針基の回動を 防止しつつ,針先保護部が初期状態の配置位置から留置針の針先方向へ移動し,小 径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持した状態のまま,クリック感が 生じる位置(「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位 置」(構成要件 1D 等)に相当する。)である針基の受け部において大径部係止手 段が針基に対して係止されることによって,針管の針先が再度,針先保護部の先端 側から露出することが防止されることとなる。 また,証拠(乙63)及び弁論の全趣旨によれば,仮に被告各製品の小径部側壁 部が存在しない場合,針基の受け部においても針基は回動可能な状態にある。この\n場合,針基が回動したとしても,針先保護部の大径部係止手段に針基の縦リブが接 触することにより針基の回動がいったん停止することとなる。この状態ではなお大 径部係止手段と針基の受け部が接触しているため,直ちに針先保護部が基端側に移 動可能となるものではない。もっとも,この状態において一定の外力が加えられる\nと,縦リブが大径部係止手段を乗り越えて再び回動するなどして,針基の受け部と 大径部係止手段の係止が解除され,針先保護部が基端側に再度移動し,留置針の針 先が再露出する状態となり得ることが認められる。 しかも,被告各製品の添付文書(甲5)には,次のような記載がある。
「・針を収納する際は,ロックが外れたことを確認し,真っ直ぐ引くこと。(針 基が曲がったり,折れるおそれがある。)
・針が収納,固定された状態でグリップ部を強く引っ張る,回転させる操作をし ないこと。(針基が曲がったり,折れるおそれがある。)
・針が収納,固定された状態で針先が飛び出す方向に力を加えないこと。(針刺 し及び感染のおそれがある。)」 これらの記載によれば,被告各製品においては,留置針を収納する際や収納・固 定された状態において日常的な使用時に作用し得る程度の外力により,針基の屈曲 や針先再露出といった状態が生じ得ることがうかがわれる。まして,被告各製品の 小径部側壁部が存在しない場合は,更に小さい外力によりこのような状態が生じ得 ると考えられる。
(ウ) そうすると,被告各製品においては,針先保護部に大径部係止手段及び小径 部側壁部が設けられており,針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる 位置において,針先保護部に設けられた大径部係止手段が針基に対して係止される ことと,針基に設けられた縦リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが相互 に係合することにより針基が針先保護部に対して回動することが防止される状態に あることとが相まって,針基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前 進することができなくなっているものと認められる。すなわち,被告各製品は,大 径部係止手段のみならず小径部側壁部が針先保護部に設けられていることにより針 先の再露出が防止される構成となっている。\n以上のとおり,被告各製品の小径部側壁部は,針先再露出防止機構としての機能\ をも有するものと認められる。したがって,被告各製品の小径部側壁部は,「係止 片」(構成要件 1D 等)に該当し,これが小径部に設けられている以上,被告各製 品は,「前記係止片は,…前記小径部側には設けられておらず」(構成要件 1E 4))を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2021.11.30
令和3(ネ)10058 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお,事案に鑑み,念のため,被告製品の均等論の第1要件の充足につい て判断する。
本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書の開示事 項を総合すれば,本件発明1は,従来の遠隔監視システムでは,施設の侵入 者があったり,施設において異常が発生した場合に,当該施設の所有者や管 理責任者が一次的に当該侵入や異常発生を知ることができず,また,警備会 社からの二次的な通報により上記所有者や責任者が侵入や異常発生を知るこ とは可能であるが,これらの者が外出している場合等には警備会社が通報を\nすることができないといった課題があり,こうした課題を解決するために, 構成要件1Bないし1Gの構\成を採用し,施設の監視対象領域を監視する監 視装置からのメッセージと監視装置によって得られた画像の情報が当該施設 の所有者や管理責任者に対応する顧客の携帯端末に通知又は伝達されること により,顧客が何れの場所においても施設の異常等を適切に把握することが できるとともに,監視装置から受理された画像の略中央部分の画像からなる コンテンツを携帯端末に伝達することにより,表示装置が小さい携帯端末で\nも顧客により十分に認識可能\な画像を表示することができ,さらに,カメラ\nの「パンニング」を含む携帯端末からの遠隔操作命令により「パンニング」 に従った領域を特定し,その領域の画像を携帯端末に伝達するステップを備 え,顧客が参照したい領域を特定して携帯端末に提示することができるよう にしたことにより,施設の所有者や管理責任者が外部からの侵入や異常の発 生を知り,その内容を確認することができるという効果を奏するようにした ことに技術的意義があるものと認められる(【0004】ないし【0007】)。 このような技術的意義に鑑みると,本件発明1の本質的部分は,1)何れの 場所においても顧客が携帯し得るものとして,監視装置からの異常検出によ って監視装置により撮影された画像データの伝達を受ける端末を「携帯端末」 とし,2)「携帯端末」に伝達する画像は,略中央部分の画像領域から構成さ\nれ,3)携帯端末からの「パンニング」を含む遠隔操作命令を受理し,その領 域の画像を携帯端末に伝達するステップを含むことにより,4)表示装置が小\nさい携帯端末でも,顧客により十分に認識可能\な画像を表示することができ,\nさらに,携帯端末からの遠隔操作命令により,顧客が参照したい領域を特定 して携帯端末に提示することができるようにした点にあるものと認められる。 すなわち,単にセンサの情報伝達の宛先を警備会社の中央コンピュータから 施設の所有者等の携帯端末に切り替えたことのみに重きがあるわけではなく, 何れの場所においても顧客にとって携帯が容易で,操作等が迅速かつ簡便で あるためには表示装置が小さい端末とならざるを得ない面があるところ,そ\nうであっても,外部からの侵入や異常の発生を知り,その内容を確認するこ とが十分に可能\な構成を有することが本件発明1の本質的部分であるという\nべきである。なお,本件発明2及び3は本件発明1(請求項1)の従属項で あり,また,本件発明5は,本件発明1の遠隔監視方法の発明を監視制御サ ーバに関する発明としたものであるから,これらの発明の本質的部分もこれ に同様である。
これに対し,被告製品は,監視装置からの異常検出によって監視装置によ り撮影された画像データを伝達する端末は,携帯電話のような表示装置が小\nさい端末ではなく,また,端末からの遠隔操作命令により受理された画像の うち他の領域の画像を参照すること示す命令である「パンニング」を含む遠 隔操作命令を受理し,その領域の画像を携帯端末に伝達するステップを含ま ないため,顧客が何れの場所においても施設の異常等を適切に把握すること ができ,表示装置が小さい「携帯端末」でも顧客は十\分に認識可能な画像を\n表示することができ,顧客が参照したい領域を特定して「携帯端末」に提示\nすることができるようにしたことにより,施設の所有者や管理責任者が外部 からの侵入や異常の発生を知り,その内容を確認することができるという本 件各発明の効果を奏するものと認めることはできない。 したがって,被告製品は, 本件各発明の本質的部分を備えているものと認 めることはできず,被告製品の相違部分は,本件各発明の本質的部分でない ということはできないから,均等論の第1要件を充足しない。 よって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品は,本件各発 明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められない。\n
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.11.22
令和3(ネ)10007 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「室」という語は,一般的には,「へや」すなわち「物を入れる所」などを 意味する語であるところ(甲27),構成要件1A及び2Aの文言のほか,前記2(2)の本件各訂正発明の概要及び前記(1)の本件各訂正発明の課題を踏まえると,構成要件1A及び2Aの「複数の室を有する輸液容器」の要件は,複数の輸液を混合\nするのに用いられる従来技術であるそのような輸液容器を用いる輸液製剤であるこ とを示すことによって,本件訂正発明1及び2の対象となる範囲を明らかにするも のである。本件各訂正発明の課題は,そのような輸液容器を用いて,あらかじめ微 量金属元素を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤で,含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を\n提供することにあるから,本件各訂正発明における「室」の意義の解釈に当たって は,上記の一般的な意義のほか,輸液容器における「室」の意義も考慮するのが相 当である。
そこで検討すると,本件特許の出願当時には,輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構\成される空間であって,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた空間を「室」と呼んだ上で(乙31),その「室」の中に 収納される,薬剤を収容する構成部材を「容器」と呼んだり(甲25,乙17),その「室」の外側に付加して空間を構\成する部材を「被覆部材」と呼んだり(乙16),その「室」に連通される「ポート部材」が薬剤を収容し得る機能を備えるものとしたり(乙12),その「室」を分割したものを「区画室」と呼んだり(乙5)すると\nいった例があった。本件特許の出願後も,上記基礎となる一連の部材によって構成される「室」の中に収納される,薬液を収容する構\成部材を「容器」や「袋」などと呼ぶ例が複数みられるが(甲14,15,乙19),そのように,輸液等を収容す るという機能を有する部分を指す語として「室」以外の語が加えられている中においても,「室」という語は,基本的に,輸液容器全体の構\成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって,輸液を他の輸液と分離して収容しておくために仕切られた相対的に大きな空間を指すものとして用いられ,「容器」や「袋」の\n付加の有無にかかわらず,そのような「室」が複数あるものが「複室輸液容器」な どと呼ばれていたことがうかがわれる(なお,上記のうち,甲15は,大きな「隔 室」の中に「内袋」があり,その「内袋」が更に複数の「薬剤収容室」で構成されているというものであり,「室」の中に「室」があるという点では,やや珍しいもの\nともみられるが,各「隔室」と各「薬剤収容室」は,あくまでそれぞれ一連の部材 によって構成されている。)。そして,上記のような「室」の理解は,本件明細書の記載とも整合的である。\n
(イ) 上記(ア)の点を踏まえると,構成要件1A及び2Aにいう「室」についても,輸液容器全体の構\成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって,\n輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間をい うものと解するのが相当である。
イ 「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器」について\n
もっとも,本件訂正発明1の構成要件1A及び本件訂正発明2の構\成要件2Aに おいては,「複数の室を有する輸液容器」の前に,「外部からの押圧によって連通可 能な隔壁手段で区画されている」との特定が付加されている。そうすると,上記特定により,「室」が「連通可能\な」ものであることが明確にされているというべきであるから,構成要件1A及び2Aにおける「室」については,「外部からの押圧によって連通可能\な」ものであることを要するものである。
ウ 被控訴人製品について
(ア) 「室」について
a 先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第2の1(7)ア及び弁論の全趣旨 によると,被控訴人製品に係る輸液容器について,その構成の中で基礎となる一連の部材によって構\成される空間は,大室及び中室を直接構成するとともに小室T及\nび小室Vの外側を構成する一連の部材によって構\成される空間であるといえる。
b もっとも,小室Tに関しては,外側の樹脂フィルムによって構成される空間が,上記のとおり輸液容器全体の構\成の中で基礎となる一連の部材によって構成さ\nれる空間である一方で,連通時にも,内側の樹脂フィルムによって構成される空間(本件袋)にのみ輸液が通じることとされており,小室Tの外側の樹脂フィルムに\nよって構成される空間に輸液が直接触れることがない。そのため,小室Tの外側の樹脂フィルムによって構\成される空間が,前記の「室」の理解のうち,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間に当たるかどう かが問題となり得る。 しかし,輸液容器全体の構成を踏まえると,被控訴人製品における小室Tは,外側の樹脂フィルムによって構\成される空間の中に,内側の樹脂フィルムによって構\n成される空間(本件袋)を内包するという二重の構造になっているにすぎず,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための空間としての構\成において,外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間に機能の優劣等があるとはみられない。この点,小室Tと中室との間の接着部について,内側の樹脂フィルムの接着を剥離した\n場合のみならず,外側の樹脂フィルムの接着のみを剥離した場合であっても小室T の外側のフィルムの内側の空間に中室に収容された輸液が流入してこれが本件袋の 外面に直接触れることとなり,中室内の輸液と本件袋の中の液との分離の態様に少 なからず差異が生じるのであり,輸液同士の混合という点では専ら小室Tの内側の 樹脂フィルムの接着部分が意味を持つとしても,隣接する中室内の輸液からの分離 という観点からは,外側の樹脂フィルムにも重要な意義があることは明らかである。 そして,内側の樹脂フィルムによって構成される空間(本件袋)は,被控訴人製品に係る輸液容器において基礎となる一連の部材とは別の部材により構\成され,上記基礎となる一連の部材に構成を追加する部分である(このことは,小室Vの内側の樹脂フィルムによって構\成される空間と対比しても,明らかである。)。以上の諸点を踏まえると,小室Tについても,被控訴人製品に係る輸液容器の構成の中で基礎となる一連の部材である外側の樹脂フィルムによって構\成される空間(本件小室T)をもって,「室」に当たるとみるのが相当である。
c ところで,被控訴人製品の小室Tの外側の樹脂フィルムによって区画される 空間のように,輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構\成され る空間が,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大き な空間であるといえるか疑問があり得るような場合に,本件各訂正発明の「室」を どのように理解すべきかについて,本件訂正発明1及び2に係る請求項の文言上は, 必ずしも明らかであるといえないから,そのような場合における「室」の理解につ いて,本件明細書の内容を踏まえた検討も行うと,本件明細書の段落【0024】 は,「微量金属元素収容容器を収納している室」には,溶液が充填されていてもよ いし,充填されていなくてもよい旨を明記しており,同【0033】は,「本態様 の輸液製剤では,図1に示す輸液容器の第1室4に,溶液が充填されていてもよい し,充填されていなくてもよい」と明記しているところであるから,本件各訂正発 明においては,輸液が充填される空間であるか否かという点は,「室」であるか否か を決定する不可欠の要素ではないと解される。 それゆえ,前記bのような理解は,本件明細書における「室」の理解にも沿うも のであるといえる。
d 以上に対し,被控訴人らは,被控訴人製品において,小室Tの外側の樹脂フ ィルムによって構成される空間(本件小室T)は存在しないと主張するが,2枚の樹脂フィルムの間に空間が構\成されている(その空間中には,2枚の内側の樹脂フィルムの間の空間(本件袋)が包摂されている。)こと自体は,明らかであり,被控 訴人らの主張は採用することができない。
(イ) 「連通可能」について
a 前記(ア)のとおり,「室」については理解すべきものであるとしても,前記イ のとおり,構成要件1A及び2Aにおいては,「室」が「連通可能\」であることが要 件とされているところ,前記(ア)bで既に指摘したとおり,小室Tに関しては,連通 時にも,内側の樹脂フィルムによって構成される空間(本件袋)にのみ輸液が通じることとされており,「室」である外側の樹脂フィルムによって構\成される空間(本件小室T)に輸液が通じることはない。 そうすると,結局,被控訴人製品は,「室」が「連通可能」という要件を充足しないから,構\成要件1A及び2Aを充足しないというべきである。
b これに対し,控訴人は,本件小室Tに収納された本件袋に輸液が通じること は,本件小室Tに輸液が通じることといえる旨を主張する。この点,前記(ア)dのと おり,本件小室Tという空間が本件袋という空間を包摂していることは確かに認め られるが,そのことと,本件袋との連通をもって本件小室Tとの連通と評価し得る かは,別の問題である。本件訂正発明1及び2に係る請求項1及び2が「室」と「容 器」を明確に分けていることや,前記ア(ア)で指摘した「室」と「容器」についての 技術的な関係のほか,本件明細書の段落【0020】の「微量金属元素収容容器は, それを収納している室と連通可能であることが望ましい。」という記載は,容器の連通が室の連通とは異なるものとみる見方に沿うものであることからすると,控訴人\nの上記主張を採用することはできない。
(3) 争点(4)について
構成要件10A及び11Aの「複室輸液製剤」にいう「室」についても,前記(2) アと同様に解するのが相当である。 そして,構成要件1A及び2Aと異なり,構\成要件10A及び11Aについては, 「室」が「連通可能」であることは要件とされていない。したがって,先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第2の1(7)イ及び弁論 の全趣旨により,被控訴人方法は,構成要件10A及び11Aを充足するというべきである。\n
4 争点(2)(構成要件10C及び11Cに係る点に限る。)について
前記3(2)及び(3)で指摘した点を踏まえ,先に引用した原判決の「事実及び理由」 中の第2の1(7)イ及び弁論の全趣旨によると,被控訴人方法においては,「含硫ア ミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する溶液を収 容している室」である中室とは「別室」である小室Tの外側の樹脂フィルムによっ て構成される「室」(本件小室T)に,構\成要件10C又は11Cで特定された微 量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器である,小室Tの内側の樹 脂フィルムによって構成される本件袋が収納されていると認められる。したがって,被控訴人方法は,構\成要件10C及び11Cを充足する。
◆判決本文
1審は、構成要件1C、10Cを具備しないので、技術的範囲に属しないと判断していました。
◆平成30(ワ)29802
以上の記載によれば,本件各発明については,次のとおりのものである旨
認めることができる。
すなわち,まず本件各発明の技術分野は,経口・経腸管栄養補給が不能又は不十\分な患者に対して,経静脈からの各種輸液(糖製剤,アミノ酸製剤,電解質製剤,混合ビタミン製剤,脂肪乳剤等)の投与を行うための輸液製剤
に関するものである。この点,当該輸液製剤は,経時変化を受けることなく
保存し,その使用時に細菌による汚染なく混合するため,連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器に収容される。\nしかして,輸液中には,通常,銅等の微量金属元素が含まれていないこと
から,患者は,輸液の投与が長期になるときにはいわゆる微量金属元素欠乏
症を発症することとなる。しかるところ,これを予防するために必要な微量金属元素を輸液と混合した状態で保存すると,化学反応によって品質劣化の\n原因になり,これを防ぐべく含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填
し,微量金属元素収容容器を同室に収容すると,当該アミノ酸輸液と微量金
属元素とを隔離していても,微量金属元素を含む溶液が不安定となるという
技術的課題が生じていた。
本件各発明は,このような技術的な課題に対して,連通可能な隔壁手段で区画されている複室の一室に含硫アミノ酸を含有する溶液を充填し,これと\nは他の室に,微量金属元素を収容した容器を収納するという構成を採用することにより,上記技術的な課題を解決し,微量金属元素が安定に存在してい\nることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供するとい
う効果を奏するようにしたものであるというべきである。
そうである以上,本件各発明の課題解決の点における特徴的な技術的構成は,微量金属元素収容容器を,含硫アミノ酸を含有する溶液と同じ室ではな\nく,同室と連通可能な他の室に収納するという構\成を採用したところにある
ものというべきである。そして,これは,連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として,その複数の各「室」に\nついては,それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造となっており,上記の微量金属元素収容容器を収納する「室」は,含硫アミノ酸を含有する\n溶液とは異なる輸液の充填・保存のための構造となっている「室」であるという技術的構\成が採用されたものということができる。すなわち,本件各発明において,構成要件1Aの「複数の室」及び構\成要
件10Aの「複室」は,各種輸液を充填して保存するための構造となっている各空間を意味すると解されることから,輸液容器に設けられた空間がその\n一室である構成要件1C及び10Cの「室」に当たるためには,当該空間が輸液を充填して保存し得る構\造を備えていることを要すると解するのが相当であり,これに反する原告の前記主張は採用できない。
この点,証拠(甲2)によれば,本件明細書には,発明の詳細な説明とし
て,「(略)また,微量金属元素収容容器は,それを収納している室と連通
可能であることが好ましい。(以下,略)」(段落【0020】)との記載や,「上記『微量金属元素収容容器を収納している室』には,溶液が充填さ\nれていてもよいし,充填されていなくてもよい。(以下,略)」(段落【0
024】)との記載のあることが認められる。しかしながら,前者の記載に
ついては,前記で説示した本件各発明の技術的意義に照らせば,微量金属元
素収容容器が上記のような意味の「室」に収納されていることを前提とする
記載であり,同容器が輸液を充填して保存し得る構造を備えていない構\成の
ものに収納されている場合をも許容する趣旨であるとは解されない。また,
後者の記載についても,同様に,「微量金属元素収容容器を収納している
室」には,輸液が充填されていない構成のものも含まれることを述べたものにすぎず,そもそも輸液を充填して保存するための構\造となっていない構成\nのものまで含まれることを意味したものと解することはできない。
したがって,これらの記載によっては,前記判断は左右されず,その他,
本件明細書の記載内容を詳細に検討しても,前記判断を左右し得る記載は見
当たらない。
そこで,これを被告製品ないし被告方法について見ると,
及び弁論の全趣旨によれば,小室Tの内側の樹脂フィルムで形成された袋を
覆っている外側の樹脂フィルム2枚は,中室側及び小室V側の両端部におい
て内側の樹脂フィルムと溶着されており,使用時にも当該溶着部分は剥離し
ないと認められる。
そうすると,小室Tの外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の
空間は,使用時に中室及び小室Vと連通するものではなく,これに照らすと,
同空間が,輸液を充填して保存し得る構造を備えているものとは認められないといわざるを得ず,同空間が「室」に当たるということはできない。\nしたがって,被告製品及び被告方法は構成要件1C及び10Cの「室に・・・微量金属元素収容容器が収納」されている構成を具備するとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 間接侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.10.28
平成29(ワ)1390 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月16日 大阪地方裁判所
本件訂正発明1−1に係る特許請求の範囲の記載によれば,同発明に係るランプ は,「基板を保持する金属製の基台」(構成要件 1-1F’)をその構成要素の1つとして備えるところ,「前記基台は,前記長尺状の底部と,前記底部の短手方向の一\n方の端部に設けられた第1壁部と,前記底部の短手方向の他方の端部に設けられた 第2壁部とを有し」(構成要件 1-1I’),「前記第1壁部及び前記第2壁部は,前 記底部の前記基板側に衝立状に形成されて」(構成要件 1-1J’)いることが特定さ れている。 これによれば,基台の底部の短手方向の両端部にそれぞれ設けられた第1壁部と 第2壁部は,底部に対し基板側に形成されるものであり,その形状ないし状態が 「衝立状」であることが示されている。もっとも,いかなる形状等をもって「衝立 状」とするかについては記載がなく,その意味が一義的に明らかとはいえない。
イ 本件明細書1の記載等
「第1壁部」及び「第2壁部」について,本件明細書1【0055】には,第1基 台 50 が,長尺状の底部(底板部)と,底部における第1基台 50 の短手方向(基板 11 の幅方向)の両端部に形成された第1壁部 51 及び第2壁部 52 とを有すること, これらの壁部は,第1基台 50 を構成する金属板を折り曲げ加工することによって衝立状に形成されていることが記載されている。また,同段落には,同明細書図\n3B と合わせ,LED モジュール の基板 11 は第1壁部 51 と第2壁部 52 とによっ て挟持されており,LED モジュール は,第1壁部 51 と第2壁部 52 とによって 基板 11 の短手方向の動きが規制された状態で第1基台 50 に配置されることも記載 されている。本件訂正における本件訂正発明1−1の構成要件 1-1J'の追加は,こ の記載等を含む本件明細書1の記載による開示に基づいて行われたものである(甲 83)。 さらに,広辞苑(乙291)においては,「衝立」とは「衝立障子の略」であり, 「衝立障子」とは「屏障具の一。一枚の襖障子または板障子に台をとりつけ,移動 便ならしめたもの。・・・玄関・座敷などに立てて隔てとする。」と説明されている。 加えて,「衝立障子」は,一般に,それが設置される面に対して略直立するものと 把握される。他方,「状」とは,物事の形,姿,有り様,様子を意味し,「○○状」 とは,ある物事の形等を「○○」に例える際に用いられる表現である。以上の本件明細書1の記載等を踏まえると,第1壁部及び第2壁部は,基台の底\n部の基板側に衝立状に形成されることにより基板11を挟持し,短手方向の動きが 規制する機能を果たすものであるところ,その形状等は上記意味での「衝立障子」に例えられるものである必要があることが理解できる。\n
ウ 小括
以上より,本件訂正発明1−1に係る特許請求の範囲及び本件明細書1の記載等 並びに「衝立」の一般的な意味等に鑑みると,第1壁部及び第2壁部が「衝立状」 に形成されるとは,これらの壁部が基台の底部の基板側に,同底部に対して略直立 した形状に形成されていることを意味するものと解される。これに反する原告の主 張は採用できない。
(2) 被告製品1〜5,7〜10及び12の構成要件充足性
被告製品1〜5,7〜10及び12の断面図は,別添「被告製品断面図」のとお りである。 このうち,被告製品4及び5については,第1壁部及び第2壁部に相当すると見 られる部位は,基台の底部から基板側に形成された基台の一部が内側に向けて鋭角 に傾斜した形状に形成されており,底部に対して略直立した形状とはいえない。 次に,被告製品1〜3,7〜10及び12については,第1壁部及び第2壁部に 相当すると見られる部位には,基台の底部から基板側に略直立といってよい形状に 延出している部分もあるものの,これと一体のものとして,基板とほぼ同じ高さで 基台の底部に平行に形成された部分もあるため,全体としては「コの字」又は「T 字」と表現すべき形状に形成されているものというべきであって,底部に対して略直立した形状に形成されているとはいえない。\nしたがって,被告製品1〜5,7〜10及び12は,いずれも,第1壁部及び第 2壁部に相当すると見られる部位が底部の基板側に「衝立状」に形成されておらず, 本件訂正発明1−1の構成要件 1-1J’を充足しない。
(3) 小括
以上により,被告製品1〜5,7〜10及び12は,いずれも,本件訂正発明1 −1の技術的範囲に属しない。
4 充足論のまとめ
本件発明1−1,1−3,1−16及び1−17及び並びに本件訂正発明1−1 7につき,対象となる各被告製品が各発明の構成要件を充足し,その技術的範囲に属することは,前記(第1の5)のとおりである。\nまた,本件発明1−14並びに本件訂正発明1−18及び1−20については, 前記2のとおり,被告製品1〜5,7〜16は,対応する各発明の構成要件を充足し,その技術的範囲に属すると認められる。\n他方,本件訂正発明1−1については,被告製品1〜5,7〜10及び12は, いずれもその構成要件 1-1J'を充足せず,その技術的範囲に属しない。したがって, 本件訂正発明1−1については,その余の点を論ずるまでもなく,訂正の再抗弁は 認められない。
5 403W 製品に基づく先使用権の成否(争点10) 事案に鑑み,まず,403W 製品に基づく先使用権の成否(争点10)について検 討する。
(1) 403W 製品の先使用について
ア 証拠(以下に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら れる。
(ア) 被告は,平成24年4月23日頃,韓国で製造された 403W 製品480セッ トを輸入した(乙143,315)。
(イ) 被告は,同月25日,ミツワ電機株式会社関西支社に対し,403W 製品24 台を含む商品の見積書を作成,送付し,同月26日,同社関西特機営業所から受注 して,同月28日,これを井づつやに納品した(乙167,168)。 その後,井づつやに納品された上記 403W 製品24台は,同所のエントランスロ ビー等において使用されていたところ,被告は,平成30年7月23日までに,井 づつやからこれを入手した。この被告 403W 製品には,製造ロット番号として 「120416」が表示されているところ,これは,当該製品の製造年月日が平成24年4月16日であることを意味する。(乙166,弁論の全趣旨)\n
(ウ) 被告は,本件チラシ(平成24年1月発行)に,平成24年3月初旬発売予定の商品として 403W 製品を掲載した(乙138)。また,被告は,本件カタログ (同年2月発行)にも 403W 製品を掲載したところ,他の掲載商品には発売予定時期を明記したものが見られるが,403W 製品にはそのような記載はない(乙35)。
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば,被告は,遅くとも本件優先日である 平成24年4月25日以前に,403W 発明の実施である事業をしていたことが認め られる。
(2) 403W 発明の構成等
ア 403W 発明の構成のうち,上記第2「10」(被告の主張)(3)における構成 1- 3a10〜c及び e並びに 1-14a10〜f及び hについては,原告 PIPM も明ら かには争わないから,これを認める。 上記構成 1-3a10〜c及び eは,本件発明1−1の構成要件 1-1A〜C 及び E, 本件発明1−3の構成要件 1-3A〜C 及び E,本件発明1−16の構成要件 1-16A〜 C 及び F,本件発明1−17の構成要件 1-17A〜C 及び E 並びに本件訂正発明1− 17の構成要件 1-17B’〜D’にそれぞれ相当するものといえる。また,構成 1-14a10 〜f及び hは,本件発明1−14の構成要件 1-14A〜E,G 及び本件訂正発明 1−18の構成要件 1-18B’〜F’,I’にそれぞれ相当するものといえる。 さらに,403W 製品は,直管形 LED ユニットであり,樹脂(ポリカーボネート) 製カバー(筐体)の長手方向の両端に口金が設けられているところ,その一方には 電源内蔵ユニット用専用口金を備え,この口金のみが,電源内蔵用専用ソケット(給電側)を通じて交流電力を受けるものである(乙35,299)。そうすると,\n403W 発明は,本件発明1−16の構成要件 1-16E 並びに本件訂正発明1−17の 構成要件 1-17E’及び本件訂正発明1−18の構成要件 1-18G’,H’に相当する構成を備えていることが認められる。\n加えて,403W 製品は,既存の器具本体をそのまま残し,専用ソケット及び直管形LED ユニットをリニューアルして照明装置として使用する製品シリーズに含まれる製 品である(乙35)。したがって,ランプである 403W 製品に係る発明(403W 発明) は,そのランプが取り付けられた照明装置に係る発明に含まれるといえる。このため, 403W 発明は,本件発明1−17の構成要件 1-17F,本件訂正発明1−17の構成要件 1-17A’及び G’並びに本件訂正発明1−18の構成要件 1-18A’及び K’に相当する構成を備えていることが認められる。
イ 403W 製品の輝度均斉度等
(ア) 証拠(以下に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら れる。
a LED モジュールの寿命は,製造業者等が指定する条件下で点灯したとき, LED モジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間,又は全光束が点灯初期に測 定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間とされているとこ ろ,高光束 LED を1万時間連続通電してその光出力の変化を調査した実験データ によれば,1チップ方式の白色 LED の寿命(光出力が70%になる時間)は4万 5000時間と推定されるとの実験データがある。なお,原告パナソニックのカタログ(乙34)には,直管形 LED ランプについて,4万時間経過後の光束維持率 が95%であることが示されている。 また,LED を連続的に点灯し続けると,LED チップを封止する樹脂(以下 「LED 樹脂部」という。)が黄変し,光量の低下を招くことがある。さらに,LED 照明は,使用する場所の環境温度が高くなるほど劣化が加速されると共に,使用環 境下に硫化ガス等の発生要因がある場合,LED 樹脂部及び接合部にダメージを与 えることなどによっても,劣化が加速する場合がある。 (以上につき,上記のほか,甲37〜39)
b 被告 403W 製品は,平成24年4月28日の井づつやへの納品後,被告が平 成30年7月に入手するまで,6年以上の間継続的に使用されていたものと見られ るところ,その LED 素子の中央部分はやや黄変しており(乙217,218), カタログに記載された初期値を100%とした場合の被告 403W 製品の全光束(全 ての方向に放出する光束の総和)は89.0%,光効率は92.6%に減少してい る(乙216)。もっとも,被告 403W 製品の LED1個あたりの配光データは, 新品の LED の配光データが概ね120度(ランバーシアン配光の場合)であるの に対し,114度及び115度である(乙214,215の3,215の4)。 また,403W 製品のカバーと 402W 製品のカバーは,共通の部材(ポリカーボネ ート)を使用した同じ仕様のものであると認められるところ(乙35,298,2 99,315),被告 403W 製品と未使用の 402W 製品について,それぞれカバー を交換して全光束及び y/x 値を測定した結果,いずれも交換せずに測定した結果と の差は,1%以下(全光束)及び0.01(y/x 値)であった(乙316〜318, 弁論の全趣旨)。
(イ) 以上の事情を踏まえると,被告 403W 製品の LED 素子は,6年以上使用を 継続されているものであり,LED 樹脂部の黄変及び全光束や光効率の減少は生じ ているものの,その配光特性は,初期値(ランバーシアン配光)と大きく異ならず, 著しい経時変化は見られないものといってよい。403W 製品の光拡散性を有するカ バー部分についても,被告 403W 製品には,上記継続使用期間にもかかわらず,全 光束や y/x 値の測定値に影響を与えるような劣化等が生じているとはいえない。 そうすると,被告 403W 製品について,被告が平成30年7月23日に測定した y 値=15.7mm,x 値=11.7mm,y=1.34x との測定結果(乙166)及び令和2年1 月29日に測定した y 値=15.6mm,x 値=11.7mm,y=1.33x との測定結果(乙29 7)は,いずれも 403W 製品の初期値とほぼ同等のものと見るのが相当である。
(ウ) そうすると,403W 発明は,「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y(mm)とし,隣り合 う前記 LED チップの発光中心間隔を x(mm)とすると,y=15.7mm,x=11.7mm であり,y=1.34x」との構成すなわち構\成 1-3d及び 1-14g10)を有するといえる。 したがって,403w 発明は,本件発明1−1の構成要件 1-1D,本件発明1−3の 構成要件 1-3D,本件発明1−14の構成要件 1-14F,本件発明1−16の構成要素 1-16D 及び本件発明1−17の構成要件 1-17D 並びに本件訂正発明1−17の 構成要件 1-17F’及び本件訂正発明1−18の構成要件 1-18J’に相当する構成を有していると認められる。\n
ウ 以上より,403W 発明は,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及び1 −18の構成要件を充足する構\成を備えたものであり,これらの各発明と同一性が 認められる。
エ 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は,被告 403W 製品について,長時間の使用による経年変化,LED 素子の樹脂やせや黄変,使用環境の影響等により,被告測定時点での被告 403W 製 品の y/x 値等が初期値のものと同等とはいえない旨を主張する。 しかし,上記のとおり,被告 403W 製品については,長時間の使用による経年変 化等により,LED 素子の中央部に黄変が見られ,また,カタログ値と比較して全 光束や光効率が10%程度減少しているという事実は認められるものの,それ以上 に,LED 素子の劣化(凹み)をはじめ,配光特性に影響を及ぼし得るような LED 素子の劣化等を裏付ける具体的な事情は見当たらず,カバー部材についても,y/x 値等に影響を与えるような劣化が生じているといった事実の存在を具体的にうかが わせる事情は見当たらない。本件交換実験の結果に関しても,上記のとおり,交換 に係る製品が共通の部材を使用した同じ仕様のものであると認められることに鑑み ると,原告 PIPM が指摘する事情を考慮しても,その結果の信用性を直ちに疑うべ きものとまではいえない。 その他原告 PIPM が縷々指摘する事情を踏まえても,この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
(3) 先使用権の範囲
上記(1)及び(2)によれば,被告は,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及 び1−18の内容を知らないで自らこれらに含まれる 403W 発明をし,本件優先日 の際に,日本国内において,その発明の実施である事業をしている者と認められる。 したがって,被告は,403W 発明及び上記事業の範囲内において,本件各発明1並 びに本件訂正発明1−17及び1−18に係る特許権について,通常実施権を有す る。 また,403W 製品は,x 値及び y 値の関係性を特定する技術的思想が明示的ない し具体的にうかがわれるものではないものの,実際にはその x 値及び y 値の関係性 により,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及び1−18に係る構成要件に相当する構\成を有し,その作用効果を生じさせている。加えて,403W 発明につき, 照明器具としての機能を維持したまま,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及び1−18の特定する x 値及び y 値の関係性を充たす数値範囲に設計変更するこ とは可能と思われる。このため,被告製品1〜5及び7〜16は,いずれも,403W 発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式であるにとどまる ものといえる。 そうすると,被告による被告製品1〜5及び7〜16の製造販売は,被告の上記 通常実施権の及ぶ範囲内に含まれる。
(4) 小括
以上のとおり,被告は,403W 発明に基づく上記通常実施権により,業として被 告製品1〜5及び7〜16を製造販売し得ることから,その余の点につき論ずるま でもなく,原告 PIPM は,被告に対し,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17 及び1−18に係る本件特許権1を行使し得ない。
6 無効理由9(クラーテ製品2)の公然実施による新規性欠如)の有無(争点12)
(1) 公然実施の有無
ア 証拠(以下に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら れる。
(ア) リコーは,平成23年7月7日,直管形 LED ランプである「クラーテ P シ リーズ40形」を同月末発売予定である旨をプレスリリースした。また,同社は,平成24年1月現在の製品を掲載したカタログ「<クラーテ>P シリーズ」(乙1 71の1)にクラーテ製品2)を掲載しているところ,同カタログ掲載の仕様は,上 記プレスリリースに係る製品の仕様と概ね同一である。さらに,同社は,遅くとも 同月には,クラーテ製品2)を含むシリーズ製品を販売していた。(上記のほか,乙 170,172,173,368)
(イ) 被告は,令和元年9月12日終了のオークションにより,クラーテ製品2)1 4本(被告クラーテ製品2))を入手したところ,これらの被告クラーテ製品2)には, いずれも,製造ロット番号として「1203」が表示されている。これは,当該製品の製造年月が平成24年3月であることを意味する。(乙172,174,186,\n288)
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば,クラーテ製品2)は,遅くとも平成2 4年1月頃には,リコーから販売されたことによりその構造が解析可能\な状態に至 ったものと認められる。 これに対し,原告 PIPM は,クラーテ製品2)の上市時期が明らかでないこと,仮 に被告クラーテ製品2)の製造日が平成24年3月であっても,製品製造後すぐ出回 るとは考えがたいことなどを主張する。 しかし,上記のとおり,リコーがクラーテ製品2)を平成24年1月には販売して いたことが認められるのであって,それから約3か月が経過した本件優先日時点で は,クラーテ製品2)が実際に市場に出回っていたものと見るのが合理的かつ相当で ある。したがって,この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
ウ 小括
以上より,クラーテ発明2)は,本件優先日より前に日本国内において公然実施を された発明といえる。
(2) クラーテ発明2)の構成等
ア クラーテ発明2)が構成 1-20a’12〜f’12 及び h’12 を有すること,これらの構成がそれぞれ本件訂正発明1−20の構\成要件 1-20A’〜F’及び H’に相当すること については,原告は明らかに争わないことから,これを認める。なお,本件訂正発 明1−20の構成要件 1-20D’の「「基台の上に実装された」の意義について, LED チップが実装された容器が基板を介して間接的に実装された構成を含むことは上記2のとおりである。\nイ 被告クラーテ製品2)14本の構成 1-20g’12 に係るパラメータ(y/x)の被告 測定値は,1.208〜1.278 であった(乙289)。また,関連無効審判における検 証手続の結果によれば,被告クラーテ製品2)は,x 値は 8.6mm,y 値は 10.39mm であり,y≒1.208x であった(乙346,365,弁論の全趣旨)。 そうすると,クラーテ発明2)は,「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y(mm)とし,隣り合う 前記 LED チップの発光中心間隔を x(mm)とすると,y≒1.208x の関係である」(構成 1-20g’12)の構成を有するものと認められる。この構\成は,本件訂正発明1−20 の構成要件 1-20G’に相当する。
(3) したがって,本件訂正発明1−20は,本件優先日より前に日本国内におい て公然実施をされた発明であるクラーテ製品2)に係る発明と同一の発明であるから, 法29条1項2号に違反し,無効にされるべきものと認められる。すなわち,本件 訂正発明1−20に係る本件訂正によっては無効理由が解消されないことから,本 件訂正発明1−20に係る訂正の再抗弁は認められない。
(4) 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は,被告測定値のばらつきや経年変化等の事情を指摘して,被告測定 値が初期値と等しいとはいえない旨を主張する。 この点,被告クラーテ製品2)については,オークションの出品者による説明とし て,中古品であること,商品の状態として「やや傷や汚れ」があること,使用期間 が2年弱であること,電気工事業者による取り外し作業の際に「ざっくりと中性洗 剤で管だけ拭きあげた状態」で丁寧な梱包により発送すること,「RICOH ロゴマ ークあたり」が黒ずんで見えるものの,LED は使用が進んでも黒ずむことはない ため元々の仕様であることなどが記載されている(乙288)。 もっとも,クラーテ製品2)は,光束が70%まで低下するまでの定格寿命が4万 時間とされている(乙170の3,171の1)。このため,被告クラーテ製品2) につき,仮に25%に相当する1万時間使用された事実があったとしても,配光特 性に影響を与えるとは必ずしもいえず,現に,被告クラーテ製品2)のうち2本の配 光特性はいずれも117度である(乙320)。口金ピンやランプマーク側の管端 部の黒ずみについても,その存在から直ちに他の部位にも同様の黒ずみが存在し, 配光特性に影響を与えるとは必ずしも推認し得ないことから,同様である。また, クラーテ製品2)については,光触媒の膜が剥がれて本来の効果が得られなくなる場 合があるとして,製品の表面を強く擦らないようにとの注意喚起がされているものの(乙170の3),「ざっくりと中性洗剤で」「拭き上げ」るといった態様がこ\nれに含まれるとは考えられない。むしろ,LED ランプの手入れ方法としてこのよ うな方法が奨励されているとも見られる(乙35)。さらに,被告クラーテ製品1) (乙169,214,215によれば,未使用品と認められる。)と被告クラーテ 製品2)のカバー部材を交換した測定によっても,両者の半値幅等に有意な差異はな い(乙370)。 これらの事情等を踏まえると,被告クラーテ製品2)につき,経年変化等によりパ ラメータの値に変化が生じているとは考えられず,上記(2)での認定に係る被告ク ラーテ製品2)の被告測定値及び関連無効審判の検証手続における測定値は,初期値 と概ね等しいものと見られる。 したがって,この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
7 まとめ
以上のとおり,本件各発明1(並びに本件訂正発明1−17及び1−18)に係 る本件特許権1に基づく原告 PIPM の請求については,被告に 403W 発明に基づく 先使用権が成立することにより,原告 PIPM は,被告に対し,本件特許権1を行使 し得ない。他方,本件訂正発明1−1に係る訂正の再抗弁は,被告製品1〜5,7 〜16がその技術的範囲に属さないことにより,また,本件訂正発明1−20に係 る訂正の再抗弁は,クラーテ発明2)の公然実施を理由とする新規性欠如の無効理由 があり,本件訂正によって無効理由が解消されないことにより,いずれも再抗弁の 成立が認められない。 以上より,その余の点について論ずるまでもなく,被告による本件特許権1の侵 害は認められないから,原告 PIPM の本件特許権1の侵害に基づく請求は,いずれ も理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.10.21
令和3(ネ)10029 特許侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年10月13日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
足場が不要になることが本件発明の唯一の効果であるとはいえないことは,上記2のとおりである。また,同業他社の製品(乙60の各枝番)の施工方法は,証拠上は必ずしも明らかではなく,本件発明及び被告方法のように,倹鈍式によるガラス板の嵌め込み,ガラス板及び目地枠を摺動させることによる取付け,係止爪と被係止爪との係止,といった工程を可能にするものか否かは定かでない。また,控訴人が引用する裁判例は,本件とは事案を異にし,本件における損害額の算定において参考となるものではない。そうすると,控訴人の当審における上記主張は,原判決を引用して説示したとおり推定覆滅率2割を相当とするとの判断を左右するものではなく,採用することができない。\n
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成29(ワ)10716
以上によれば,本件発明は,施工コスト低減という効果(3))によりこれを
実施する製品の販売等に貢献するものであって,相応の顧客誘引力を有するといえ
るものの,その程度は限られているというべきである。また,効果1)及び2)に関し
ては,本件発明は,手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同
程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ア) 外観上の体裁の良さ等(1))について
証拠(乙27,29〜31,39,42。各枝番を含む。以下同じ。)によれ
ば,乙27製品等は,いずれも,手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数
のガラス板が取り付けられ,ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認
められる。これにより,これらの製品は,本件発明の効果1)と同様の効果を奏する
ものといえる。
(イ) 取付強度の高さ等(2))について
証拠(乙27,29〜31,39,42)によれば,乙27製品等は,いずれ
も,ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠(縦枠,竪枠)を用い,ガラス取付
枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる
(乙31製品については,「2辺支持タイプ」との記載もあるが(甲18),「4
辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある(乙31)。)。これにより,こ
れらの製品は,本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。
これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製
目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指
摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的
にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件明細書によれば,取付
強度及び耐久性に係る本件発明の効果は,「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係
合保持され,隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し
て」(【0013】)の強度に関するものに過ぎない。このほか,原告製品(証拠(甲
14,15)及び弁論の全趣旨より,本件発明に係る取付方法により取り付けられ
るものと認められる。)と同様に,これらの製品の施工例として高層マンション等
の複数階層を有する建築物が示されていること(乙30,31,42)に鑑みて
も,乙30製品,乙31製品及び乙42製品は,少なくとも,原告製品と競合し得
る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。
したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(ウ) 施工コストの低減(3))について
証拠(乙37〜42)によれば,乙27製品等は,いずれも,ガラス板とアルミ
製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり,ガラス板とアルミ製目地枠を\n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに
より,これらの製品は,本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。
これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製
目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指
摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程
度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件発明の効果の1つである施工コ
ストの低減は,足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって,
アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること(乙30製品,乙31製品)や手摺
笠木部分の取付方法が回転式であること(乙42製品)による製造コストとは無関
係である。
したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(エ) その他
原告は,乙27製品及び乙29製品につき,本件特許権を侵害する製品である可
能性が高い旨を指摘する。しかし,原告も可能\性を指摘するにとどまるし,これら
の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから,本件に
おいては,この点は考慮に含めないこととする。
(オ) 以上より,乙27製品等は,いずれも,本件発明の効果と同様の効果を有す
る製品として,原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当
である。
もっとも,原告は,原告製品を遅くとも平成24年3月までには販売していると
認められる(甲14,15,弁論の全趣旨)。他方,証拠(乙55)及び弁論の全
趣旨によれば,乙27製品等の販売開始時期は,乙31製品が平成24年,乙27
製品が平成26年,乙30製品が平成27年,乙29製品が平成28年3月,乙3
9製品が平成29年10月であることが認められる。
また,原告製品,被告製品及び乙27製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ
ットレール製品市場におけるシェアは,いずれも証拠上明らかでない。
これらの事情を総合的に考慮すると,アルミ製手摺製品の市場において原告製品
及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば,特許法102条2
項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの,被告に
よる主張立証の程度に鑑みれば,その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば,被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程
度は限られるものの,他方で,競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的
であり,他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから,本件におい
ては,2割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに
反する原告及び被告の各主張は,いずれも採用できない。
そうすると,特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額は,以下のと
おりとなる。
・・・
したがって,原告の損害額は合計5481万9267円となり(内訳は以下のと
おり),原告は,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づき,同額の損害賠
償請求権を有する。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.09.24
令和1(ワ)23407 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月10日 東京地方裁判所
本件発明の技術的意義や本件発明における調整手段の位置付けについて みると,従来の吊張り装置としては,略円弧状の天井部に沿って設けら れたウインチワイヤーと吊り上げワイヤーとを連結する連結体が,天頂 部との距離に応じてウインチワイヤーに沿って移動するよう構成されて\nいる装置が考えられたが,複数の停止体の設置等の調整作業を天井側で 行わなければならず費用がかかり煩雑である等の問題点があった(段落 【0006】【0008】)ところ,本件発明は,略円弧状の屋内の天 井部に沿ってウインチワイヤーを設け,吊り上げワイヤーを一端側でウ インチワイヤーに連結しその他端側に吊張体を設けるなどの構成をとる\nとともに,天頂部,又は天頂部に最も近接している基準となる吊り上げ ワイヤーのウインチワイヤーとの取付位置と,任意の吊り上げワイヤー のウインチワイヤーとの取付位置との「高さ方向の距離に対応した長さ」 (構成要件C),すなわち,取付位置の高さの差の長さ(以下「本件差\n分」という。)に基づく吊り上げワイヤー等の長さの変更,すなわち調 整を,ネット等の吊張体若しくは吊り上げワイヤーの下端(床面)側又 はその両方に調整手段を設け,あらかじめ行うことにより,上記問題点 を解決するものである(段落【0010】【0025】【0026】 【0045】。前記1(2))。
また,「調整」とは,「1)調子の悪いものに手を加えてととのえること。 2)ある基準に合わせてととのえること。過不足なくすること。3)釣り合 いのとれた状態にすること。折り合いをつけること。」(大辞林第4版) などとされる。 上記のとおりの本件発明の技術的意義,調整手段の意義や,「調整」の 一般的意味からすると,本件発明に係る吊張り装置において吊張体を過 不足なく適切に吊り張りするためには,本件差分が認識された上で,本 件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあら かじめ変更する必要があり,本件発明の「調整手段」は,そのためのも のであって,本件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー 等の長さをあらかじめ変更する構成であり,その調整を行うことにより,\n吊張体を過不足なく適切に吊り張りするための手段であると理解するこ とができる。 本件明細書の具体的な実施例についてみても,ネット吊張り装置におい て,天頂部の吊り上げワイヤー(9b)の取付位置と,他の吊り上げワ イヤー(9a)の取付位置との「距離に対応した長さ」であるL1等の長 さ(L)が認識された上で,一対の筒状体(15)を吊り上げワイヤー に挿通し,その一対(2個)の筒状体の間の距離を「距離に対応した長 さ」(L 本件差分)とすることによって,調整を行う調整手段が記載 されており(段落【0036】【0037】【図1】【図4】【図5】 等)ここでは,ネット体を過不足なく適切に吊り張りするため,吊り上 げワイヤーに挿通する一対の筒状体が設けられ,その筒状体の間の距離 を認識された差(L 本件差分)と同じにすることができることが記載 されており,本件差分(L)を基準としてこれに合うように筒状体の間 の距離の長さをあらかじめ変更する構成が調整手段として記載されてい\nる。以上のとおり,本件発明の「調整手段」(構成要件C)とは,吊張体を\n過不足なく適切に吊り張りするため,認識された本件差分を基準として これに合うように長さをあらかじめ変更するための手段であると解され る。
なお,吊張体の吊張り装置は,複数の部材を組み合わせて構成され,そ\nこには当然に連結部材や係止部材が含まれ,それらの連結部材や係止部 材において,何らかの長さの変更を行うことができる場合もあり得る。 しかし,本件発明の「調整手段」等の技術的意義は,上記のとおりのも のであり,吊張り装置に何らかの長さ変更を行う構成があったとしても,\n本件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあ らかじめ変更するための手段であると認められないものは,本件発明の 「調整手段」とはいえないと解される。仮に,本件発明において,単に 長さを変更する手段のみをもって調整手段に該当すると解するとすれば, 吊張体の施工やメンテナンスに際して吊り上げワイヤー等の長さを変更 するに当たり,他の手段によって,本件差分を基準としてこれに合うよ うにしなければならないことになるが,そのような作業を床面側のみで 行うことが可能であることは本件明細書の記載等によっても明らかでは\nなく,このような構成によっては本件発明の課題を解決することができ\nない。ここで,本件明細書には,吊り上げワイヤーにネット体への係止 体を設けることで,又は,ネット体に吊り上げワイヤーの係止体を設け ることで,吊り上げワイヤーの長さの調整を行うこともできることが記 載されている(段落【0058】)。これまで述べてきたところから, そのような係止体が,認識された本件差分を基準としてこれに合うよう に吊り上げワイヤー等の長さをあらかじめ変更するための手段といえる 場合には,本件発明の「調整手段」といえ,上記記載はその趣旨のもの と理解することができる。それに対し,そのような手段とはいえず,通 常の係止体としての構成,機能\を超える構成,機能\等を有しないものは, これまで述べたところに照らせば,本件発明と関係なく用いられている 係止体であり,本件発明の「調整手段」が有する効果を奏するものでは なく,本件発明の「調整手段」に該当するとは認められない。 他方,被告らは,本件発明の「調整手段」が筒状体など本件明細書に記 載された具体的な実施例に限られる趣旨の主張もするが,本件発明の技 術的範囲が上記の範囲に限定される理由はなく,前記のとおり,本件差 分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあらかじ め変更する構成を備えたものであれば,本件発明の「調整手段」といえ\nる。
・・・・
(3) 被告製品1が本件発明の技術的範囲に属するかについて
原告は,被告製品1において,各吊り上げワイヤーと各バトンを連結する シャックル,リングキャッチ,チェーン(以下,これらを「本件連結材」と いう。)が本件発明の調整手段であると主張する。 ここで,本件発明の「調整手段」(構成要件C)とは,吊張体を過不足な\nく適切に吊り張りするため,認識された本件差分を基準としてこれに合うよ うに長さをあらかじめ変更するための手段である(前記(1)イ)。 本件連結材は,ワイヤーとバトンを連結する際に通常用いられる連結材と 認められるところ,それは,単に連結のために通常用いられる複数の構成部\n品から成っているものにすぎず,認識された本件差分を基準としてこれに合 うように長さをあらかじめ変更する構成を有するものであるとは認められず,\nそのような調整作業をするための手段とはいえない。 また,被告製品1において,もともと各吊り上げワイヤーのウインチワイ ヤーへの連結位置から連結材の下端までの長さはほぼ同程度であり(前記(2) イ),天頂部に最も近接した吊り上げワイヤーが取り付けられたバトンが床 面に到達した状態においては,他の各吊り上げワイヤーはたわんだ状態とな るのであって(同エ),本件連結材によって吊り上げワイヤー等の長さの変 更は行っていない(同ウ)。本件連結材による長さの変更が想定されている ことを認めるに足りる証拠もなく,本件連結材は,そもそも長さの変更を行 うための手段ではないともいえる。 したがって,被告製品1の連結材は,構成要件Cの調整手段には該当しな\nい。 以上から,被告製品1は,構成要件Cを充足せず,本件発明の技術的範囲\nに属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2021.08.21
平成30(ワ)21900 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月20日 東京地方裁判所
(1) 推定される損害額
ア 前記前提事実(5)のとおり,被告は,本件特許権の登録日である平成29 年6月16日から令和元年10月31日までの間,被告各製品合計●省略 ●個を販売し,これにより●省略●円の売上げがあり,少なくとも●省略 ●円の経費を要した。 したがって,法102条2項の利益の額は,5652万1465円(消 費税込み)と認めるのが相当である。 イ 被告は,被告による被告各製品の販売がなかったならば原告が利益を得 られたであろうという事情は存在しないので,法102条2項の適用はな いと主張する。
しかし,証拠(甲12,35ないし38,乙17,33,107,10 8)及び弁論の全趣旨によれば,1) 電動ファン付きウエアの市場において, 平成29年当時,原告グループ(原告,株式会社空調服等。以下同じ。) は約30%,被告グループ(被告,株式会社サンエス等。以下同じ。)は 約40%,平成30年当時,原告グループは約33%,被告グループは約 33%,令和元年当時,原告グループは約40%,被告グループは約2 0%,令和2年当時,原告グループは約35%,被告グループは約20% の各シェアを占めていたこと,2) 原告は,首後部からの空気の排出口の大 きさを調整することができるように,空調服の販売を開始した当初は調整 紐型空調服を製造販売し,その後,2段階調整型空調服を製造販売してい るが,本件各発明を実施する空調服は製造販売していないことが認められ る。 上記認定事実によれば,原告グループは電動ファン付きウエアの市場に おいて大きなシェアを占め,原告は,首後部からの空気の排出口の大きさ を調整するために,調整紐型空調服又は2段階調整型空調服を販売してい たものと認められる。他方で,被告各製品のように複数段階で調整できる 空調服が多数販売され,他の電動ファン付きウエアの市場とは異なる独自 の市場を形成していたことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,原告製品は被告各製品の競合品であると認めるのが相当で あるから,被告が被告各製品を販売して本件特許権を侵害しなければ,原 告は原告製品をさらに販売して利益を得られたであろうという事情が認め られる。 したがって,本件には法102条2項が適用されるので,被告の上記主 張は採用することができない。
ウ 被告は,商品の運用及び管理を●省略●に委託しており,平均すると商 品1点当たり●省略●円の経費を要したから,売上げから合計●省略●円 (●省略●円×●省略●個)を控除すべきであると主張する。 法102条2項の利益の額とは,侵害者の売上高から,侵害者において 侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必 要となった経費を控除した限界利益の額をいうところ,証拠(乙62)及 び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成28年6月21日以降,●省略● に対し,被告の物流センターにおける衣料用繊維製品等の入出荷業務その 他これに付随する業務全般を,製品の点数にかかわらず一律の月額委託料 (平成29年8月1日以降は●省略●円)を支払うことを約して委託した ことが認められる。 そうすると,●省略●に対する委託料は,被告が被告各製品を製造販売 することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と は認められないから,前記アの被告各製品の売上げからこれを控除するの は相当でない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(2) 推定の覆滅事由
ア 本件各発明が被告各製品の部分のみに実施されていること
(ア) 前記1(2)のとおり,空調服は,送風手段を用いて外部から服内に空気 を取り込み,当該空気が服内を流通し,その間に人体から出た汗を蒸発 させ,気化熱により体表面の温度を下げようとするものであるところ,\n本件発明1は,空調服の襟後部又はその周辺に二つの調整ベルトを設け, 一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数ある取付部のうち いずれか一つを取り付けることによって,襟後部と首後部との間に形成 される開口部を広げたり,狭めたりすることを可能にし,より適切な空\n調服の冷却効果を,より簡単に得ることを目指したものである。 しかし,本件特許の出願当時,既に,空調服の襟後部の内表面に一組\nの調整紐を設け,これらを結ぶことによって上記開口部の大きさを調整 する技術があったところ(本件明細書【0004】),本件発明1は, 一組の調整紐を任意の長さに結ぶことが難しく,上記開口部の大きさを 求める冷却効果に応じた適正なものにすることが困難であったことを解 決しようとしたものであり(同【0006】及び【0009】),上記 開口部からの空気の排出の効率化という点では,従来技術の延長線上に 位置付けられるものである。そして,本件発明1は,主として,従来技 術における調整紐を「取付部」を有する「調整ベルト」に置き換えたも のであるが,前記5(2)のとおり,本件特許の出願当時,ボタン及びボタ ンホール等を使用し,衣服におけるサイズを複数段階で調整することが できる周知慣用の技術が存在したものである。 以上からすると,従来技術と比較したときの本件発明1の技術的意義 は,必ずしも大きいものではなかったといわざるを得ない。 なお,本件発明2は,本件発明1の空気排出口調整機構を備える空調\n服の服本体の発明であって,本件発明2につき本件発明1とは異なる独 自の技術的意義は認められない。
(イ) 従来技術に係る調整紐型空調服において,送風手段を作動させたとき の襟後部と首後部との間に形成される開口部の形状は,電動ファンの風 力,前部ファスナーの締め具合,着用者の姿勢や体格,服の布地や布ベ ルト,ゴムベルト等の素材,襟部の形状等の影響を受けると考えられる ところ,この点については,本件発明1を実施した空調服であっても異 なるところはない。そして,上記従来技術又は本件発明1に係る空気排 出口調整機構が,上記の諸要素と比較して,上記開口部の形状決定にど\nの程度の影響を与えるのか,ひいては当該空調服の冷却性能にどの程度\nの作用効果があるのかを確定するに足りる証拠はない。 また,調整紐型空調服の場合,結び目付近に調整紐の先端部分が集ま り,空気排出の障害となることが指摘されるが(本件明細書【000 8】),紐という形状から考えて障害の程度がさほど大きいものとはい えず,本件発明1により特に有意な作用効果が得られるとはいえない。 さらに,従来技術に係る調整紐型空調服においても,一定の技量があ れば調整紐を任意の長さに結ぶことは可能であり,本件発明はこの点に\nついて特段の技量を要しないこととしたところに発明の作用効果がある といえるものの,実際に空調服を使用するに際し,上記の調整紐の長さ につき,どれほどの頻度で,どの程度細かく調整することが必要とされ ていたのかは明らかではない。 そうすると,本件発明1は,容易に襟後部と首後部との間に空気排出 口を形成し,これを調整することができるものの,従来技術に比して大 きな作用効果があるものとは認められない。
(ウ) 証拠(乙34,35)及び弁論の全趣旨によれば,顧客が空調服を選 択する際,空調服の価格,デザイン,服の素材並びに電動ファン及びバ ッテリーの性能に着目することが多いと認められ,空調服の襟後部と人\n体の首後部との間の空気排出口を調整する機構の有無が特に着目された\nことを認めるに足りる証拠はない。 また,被告各製品のうちの本件各発明を実施する部分は,ボタン,ボ タンホール,ゴムベルト及び布ベルトで構成され,その製造がさほど困\n難であったとは認められず,証拠(乙19)及び弁論の全趣旨によれば, 被告各製品に上記部分を設けるのに要する費用は1着当たり41ないし 42円であり,被告各製品の販売価格の1ないし2%にすぎなかったと 認められる。 さらに,証拠(甲3,乙57ないし59)及び弁論の全趣旨によれば, 平成29年から令和元年までの被告の商品のパンフレット及びウェブサ イトにおいて,空調服の構造を紹介するページに,本件発明1に係るゴ\nムベルト及び布ベルトが取り付けられた部分の写真が掲載され,その機 能を紹介する記載があるが,同写真は,ファンの写真よりは小さく,フ\nァンの取り付け位置及び着脱方法並びにバッテリーの各写真と同程度の 大きさであったこと,個々の空調服を紹介するページに,空調服が備え る機能として,ペンを差すポケット,バッテリー用ポケット,袖口の複\n数のボタン,保冷剤用ポケット等の各写真と並んで,上記部分の写真が 掲載されていることが認められる。 そうすると,被告各製品が備える機能のうち本件発明1を実施した部\n分が占める割合は小さかったといえ,また,同部分の顧客誘引力が特に 高かったとはいえない。
(エ) 以上によれば,本件発明1の技術的意義や作用効果,被告各製品のう ち本件発明1が実施された部分の顧客誘引力等に照らすと,本件特許権 を侵害する同部分が被告各製品の販売に貢献したところは小さいといわ ざるを得ないから,この事情に基づき,法102条2項により推定され る損害額の80%について推定の覆滅を認めるのが相当である。
イ 市場における競合品の存在
(ア) 前記(1)イのとおり,平成29年から令和元年までの電動ファン付きウ エアの市場において,原告グループのシェアは約30ないし40%,被 告グループのシェアは約20ないし40%であり,原告は,襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することができるように, 2段階調整型空調服を製造販売している。 また,前記ア(ウ)のとおり,被告は,その商品のパンフレット等におい て,ペンを差すポケット,バッテリー用ポケット等の機能と並んで本件\n発明1に係る部分を紹介しており,購入者が本件発明1が実施された部 分のみに着目して被告各製品を選択したとはいい難い。 一方で,証拠(乙39ないし45)及び弁論の全趣旨によれば,原告 及び被告以外の業者も,首後部からの空気の排出をより効率的に行うた めの機能を備えた空調服や,その他種々の機能\を備えた空調服を販売し ていることが認められる。 そうすると,空調服のうちの特定のものだけが被告各製品の競合品と なるとは認められず,競合品に係るシェアは上記の原告,被告及びその 他の競業他社のシェアのとおりと認めるのが相当であり,これを踏まえ ると,被告が被告各製品を販売することがなかったとしてもその購入者 の全てが原告製品を購入したとはいえないから,この事情に基づき,法 102条2項により推定される損害額の50%について推定の覆滅を認 めるのが相当である。
(イ) 被告は,被告各製品を製造販売しなかったとしても,被告各製品を購 入しようとしていた顧客は,本件各発明の技術的範囲に属しない被告の 代替製品を購入するはずであるから,被告各製品の販売と原告の損害と の間には因果関係は認められず,仮に法102条2項が適用されるとし ても,この点は推定の覆滅事由になると主張する。 しかし,被告が被告各製品を製造販売しなかったとして,被告が他に いかなる空調服を製造販売したかは証拠上明らかではないから,被告の 上記主張は採用することができない。
ウ 被告の営業努力
被告は,独自のブランドである「空調風神服」の名称で被告各製品を販 売しており,「空調風神服」には強い出所識別力があるから,被告各製品 の販売には上記ブランドによる力が貢献していると主張する。 しかし,前記(1)イのとおり,遅くとも平成29年以降,電動ファン付き ウエアの市場において,原告グループのシェアと被告グループのシェアは 拮抗し,むしろ原告グループのシェアの方が伸びていることからすると, 原告製品の顧客吸引力と比較して「空調風神服」の名称に特に強い顧客吸 引力があるとは認められないというべきであり,他にこれを認めるに足り る証拠はない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
エ その他
被告は,1) 原告製品は本件発明1を実施しておらず,被告が被告各製品 を販売したことにより原告が損害を受けることはない,2) 原告製品はイン ターネットショッピングサイトにおいて酷評されていると主張する。 しかし,上記1)について,前記(1)イのとおり,原告は,電動ファン付き ウエアの市場において,被告各製品の競合品を製造販売していたから,原 告製品において本件各特許が実施されていなかったからといって,被告が 被告各製品を製造販売したことにより,原告が損害を被ったことを否定す ることはできない。 また,上記2)について,原告(原告グループ)が電動ファン付きウエア の市場において相当程度のシェアを占めていることは前記(1)イのとおりで あり,インターネットショッピングサイトにおけるごく一部の評価(乙4 6)をもって,被告各製品が販売されなかったとしても原告製品が売れる ことはなかったということはできない。 したがって,被告の上記各主張はいずれも採用することができない。 (3) 小括 ア 以上によれば,本件各発明の被告各製品の売上げに対する貢献の程度に より80%(前記(1)ア),電動ファン付きウエアの市場に競合品が存在す ることにより50%(前記(1)イ)の推定の覆滅を認めるべきであるから, 被告による本件特許権の侵害により,原告が被った逸失利益に係る損害額 は,565万2147円(5652万1465円×(1−0.8)×(1 −0.5))と認められる。 イ 被告の上記不法行為と相当因果関係の認められる弁護士費用相当額は6 0万円と認めるのが相当である。
ウ よって,原告が被った損害額は合計625万2147円である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2021.07.27
令和2(ネ)10044 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年6月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 非侵害論主張5)について
ア 自白の成否及び時機に後れた攻撃防御方法該当性
一審原告は,非侵害論主張5)は,原審の答弁書記載の認否によって成立 した自白の撤回に当たり,また,時機に後れた主張でもあるから,許され ない旨主張する。 たしかに,一審被告は,原審答弁書における構成要件1A等の認否に際\nし,被告給油装置の電子マネー媒体が本件発明の「記憶媒体」に当たると の対比を明確に争っていたわけではないが,従前から,被告給油装置が本 件発明の技術的思想を具現化したものでないことを主張しており,非侵害 論主張5)は,これを,使用される決済手段の差異(プリペイドカードと非 接触式ICカード)という観点から論じたものであるといえるから,一審 被告が充足論全体について単純に認めるとの認否をしていない以上,自白 を撤回して新たな主張をしているとはいえないし,この主張を時機に後れ たものとして扱うのも相当ではない。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
イ 非接触式ICカードの「記憶媒体」該当性
本件明細書において,本件発明の「記憶媒体」の具体的態様としては, 磁気プリペイドカード(【0033】)のほか,「金額データを記憶する ためのICメモリが内蔵された電子マネーカード」(【0070】)や 「カード以外の形態のもの,例えば,ディスク状のものやテープ状のもの や板状のもの」(【0071】)も開示されている。このように,本件発 明の「記憶媒体」は必ずしも磁気プリペイドカードには限定されない。 しかしながら,本件発明の技術的意義が上記1のとおりであることに照 らして,「媒体預かり」と「後引落し」との組合せによる決済を想定でき る記憶媒体でなければ,本件3課題が生じることはなく,したがって,本 件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことになら\nないから,上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は,本件発明 の「記憶媒体」には当たらない。 かかる見地にたって検討するに,被告給油装置で用いられる電子マネー 媒体は非接触式ICカードであるから,その性質上,これを用いた決済等 に当たっては,顧客がこれを必要に応じて瞬間的にR/Wにかざすことが あるだけで,基本的には常に顧客によって保持されることが予定されてい\nるといえる。そのため,電子マネー媒体に対応したセルフ式GSの給油装 置を開発するに当たって,物としての電子マネー媒体を給油装置が「預か る」構成は想定し難く,電子マネー媒体に対応する給油装置を開発しよう\nとする当業者が本件従来技術を採用することは,それが「媒体預かり」を 必須の構成とする以上,不可能\である。 そうすると,被告給油装置において用いられている電子マネー媒体は, 本件発明が解決の対象としている本件3課題を有するものではなく,した がって,本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから,本件 発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきである。むしろ,電子 マネー媒体を用いる被告給油装置は,現金決済を行う給油装置において, 顧客が所持金の中から一定額の現金を窓口の係員に手渡すか又は給油装置 の現金受入口に投入し,その金額の範囲内で給油を行い,残額(釣銭)が あればそれを受け取る,という決済手順(これは乙4公報の【0002】 に従来技術として紹介されており,周知技術であったといえる。)をベー スにした上,これに電子マネー媒体の特質に応じた変更を加えた決済手順 としたものにすぎず,本件発明の技術的思想とは無関係に成立した技術で あるというべきである。一審被告の非侵害論主張5)は,このことを,被告 給油装置の電子マネー媒体は本件発明の「記憶媒体」に含まれないという 形で論じるものと解され,理由がある。
ウ 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は,本件発明の「記憶媒体」は,構成要件1C及び1Fの動\n作に適した「記憶媒体」であれば足りる旨主張する。 しかしながら,発明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであ るから,発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義を解\n釈するに当たっては,発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果 に関する明細書の記載を参酌し,当該構成によって当該作用効果を奏し\n当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべ きである。しかるに,一審原告の上記主張は,かかる観点からの検討を せず,形式的な文言をとらえるにすぎないものであって,失当である。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 一審原告は,本件明細書の【0070】に「記憶媒体」として「金額 データを記憶するためのICメモリが内蔵された電子マネーカード」を 例示する記載があり,非接触式ICカードもこれに含まれる旨主張する。 しかしながら,上記記載は,【0033】の「プリペイドカード71 は,磁気カードからなり」等の記載を受けて,カードの記憶素子が磁性 材ではなくICメモリであっても良い旨を示すにとどまり,そのカード が非接触で動作することを示す記載ではない。また,上記記載において, ICメモリは「金額データを記憶するための」ものであって,非接触式 ICカードのように演算・通信の機能を有することは開示も示唆もされ\nていないから,上記記載を根拠に非接触式ICカードが本件発明の「記 憶媒体」に当たるとはいえない。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 一審原告は,非接触式ICカードが券売機に取り込まれて使用され得 ることは周知であり,本件明細書には設定器内部にカードを取り込んだ ままとしない記憶媒体を用い得ることが示されているから,非接触式I Cカードが本件発明の「記憶媒体」に当たらないとはいえない旨主張す る。 しかしながら,前掲前提事実のとおり,被告給油装置において電子マ ネー媒体を使用する際には,電子マネー媒体(非接触式ICカード)は R/Wにかざされるだけであって装置に「取り込まれ」ることはない。 非接触式ICカード一般に一審原告主張のような使用態様はあり得るも のの,被告給油装置ではそのような使用態様によらずに非接触式ICカ ードが「電子マネー媒体」として用いられているので,被告給油装置に おける「電子マネー媒体」の技術的意義は,本件発明における「記憶媒 体」のそれとは異なる。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(3) 充足論についての小括
以上によれば,一審被告の非侵害論主張4)及び5)は理由があるから,その 余の非侵害論主張の成否について判断するまでもなく,被告給油装置及び被 告プログラムは本件特許を侵害しない。
4 争点4(無効論)について
念のため,仮に,本件発明1の「先引落し」金額は顧客が指定する場合を含 み(上記3(1)イ(イ)参照),また,非接触式ICカードも本件特許の「記憶媒 体」に含まれる(上記3(2)イ参照)とした前提で,無効論につき検討する。 なお,本件において,無効論は,本件発明1及び本件発明3(本件訂正後の もの)について検討すれば足りる。このことは,上記「第3」4の冒頭に説示 したとおりである。
(1) 「時機に後れた攻撃防御方法」該当性について
無効主張A,B,Dは,原審における侵害論の心証開示後に主張されたも のであり,そのため,原審においては時機に後れたものとして取り扱われた わけであるが,既に充足論に関する項で指摘したとおり,構成要件1C1充\n足性(非侵害論主張4))及び構成要件1A,1C,1F3,1F4充足性\n(非侵害論主張5))に関する原審の主張整理には,本来は,争いがあるもの として扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったとい わざるを得ない。そして,無効論に関する主張の要否や主張の時期等は,充 足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるか ら,充足論について,本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えら れる本件においては,無効主張が原審による心証開示後にされたという一事 をもって,時機に後れたものと評価するのは相当ではない。 また,上記無効事由に関する当審における無効主張は,控訴後速やかに行 われたといえる。 以上によると,一審被告による上記無効主張は,原審及び当審の手続を全 体的に見た観点からも,また,当審における手続に着目した観点からも,時 機に後れたものと評価することはできない。 したがって,いずれの無効主張も,時機に後れた攻撃防御方法として却下 すべきものではない。
・・・
ウ 相違点の容易想到性
上記の表において一致点とされていない本件発明1の構\成は,相違点と なる。 しかしながら,いずれの構成も,セルフ式GSの給油装置において,審\n判甲B1装置の現金による支払を,電子マネー媒体による支払に置き換え る際には,当然に備わる構成である。すなわち,上記の各相違点をまとめ\nると,本件発明1においては装置がR/Wを備えること,電子マネーの金 額データはR/Wにより電子的に書き換えられること,の2点となるが, いずれの構成も,現金の場合は貨幣という有体物に化体されている金銭的\n価値を,電子的情報という無体物に化体させたことによって必然的に生じ る帰結である。 また,現金による支払を電子マネー媒体による支払に置き換えること自 体は,電子「マネー」という名称自体からも容易に着想することができる し,例えば乙16の12(電子商取引推進協議会「モバイルECに関わる 決済標準モデルの研究中間報告書」平成13年3月発行)には,非接触式 ICカードが「電子マネー」として利用されること,FeliCa内蔵の携帯電 話は「電子財布」になること等が記載されており,これらの記載は,現金 による支払いを電子マネー媒体に置き換えることを動機付ける。 そうすると,当業者にとって,上記各相違点にかかる本件発明1の構成\nに想到することは,通常の創作能力の発揮にすぎず,容易であったといえ\nる。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.07.16
平成29(ワ)36506 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月19日 東京地方裁判所
原告は,被告に対し,特許法102条3項に基づく損害賠償を請求していると ころ,同項は,「特許権者・・・は,故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を, 自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨規定してい るから,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準とし,そこに, 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 そして,かかる実施に対し受けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施許 諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の 相場等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内 容や重要性,他のものによる代替可能性,3)当該特許発明を当該製品に用いた場 合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,4)特許権者と侵害者との競業関係や 特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定め るべきである(知財高裁平成30年(ネ)第10063号令和元年6月7日大合 議判決参照)。
本件においては,被告アプリが無償で配信されており,被告アプリのユーザが 友だち登録をし,友だち等との間で被告システム等によるメッセージの送受信等 のサービスを享受すること自体により被告に売上げは発生しない(甲73)から, 「侵害品の売上高」をどのように確定すべきかがまず問題となり,次いで,実施 に対し受けるべき料率(相当実施料率)の算定が問題となる。 そこで,それぞれにつき,以下,検討する。
(1) 売上高について
ア 当事者の主張
原告は,被告の事業のうち,本件特許権侵害の対象となる事業は,コア事 業中の「アカウント広告」と「コミュニケーション」の売上げであり,本件 特許登録日である平成29年9月15日から被告が「ふるふる」の提供を終 了した日の前の日である令和2年5月10日までの間(以下「本件損害算定 期間」という。)の売上高(アカウント広告につき合計1519億5800 万円,コミュニケーションにつき767億2800万円)に基づいて損害額 を算定すべきであると主張する。 一方,被告は,主に被告アプリ上でアカウントを有する企業等からの売上 げであるアカウント広告の売上げは損害賠償額算定の対象とならず,仮に, コミュニケーションの売上げが損害賠償額算定の対象となり得るとしても, 対象となるのは本件機能と関係のある部分に限られると主張する。\n
イ 認定事実
そこで検討するに,前記前提事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると, 以下の事実を認めることができる。
・・・
(ウ) 企業等のアカウントとの間の「ふるふる」による友だち登録(被告シス テム等図面【図38】,甲61) LINE@等のサービスを導入している企業等が住所の位置情報をあ らかじめ登録している場合,一般ユーザが被告アプリの友だち追加画面で 「ふるふる」を選択して手元のスマートフォンを振ると,半径1km圏内 の上記企業等も友だち登録の候補として表示され,同ユーザが同企業等に\nつき友だち追加処理をすると,同企業等が同ユーザの友だちとして追加登 録される。
ウ 「ふるふる」以外の友だち登録及び海外企業への輸出に係る売上げ等につ いて
原告は,損害賠償の対象は,「ふるふる」による友だち登録及びこれによ り友だちとなったユーザとの交流等に限定されず,QRコードやID検索等 の他の友だち登録も含み,また,海外企業を含む連結売上高を対象とすべき であると主張する。 (ア) しかし,原告は,本訴提起当初から,一貫して「ふるふる」による友だ ち登録及びその後の交流が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張を していたのであり(前記前提事実(5),被告システム等図面【図2】〜【図 4】,【図34】〜【図44】),その余の友だち登録手段による友だち 登録等が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張立証は侵害論の対象 とされていないので,損害賠償の対象となるのは,「ふるふる」による友 だち登録と相当因果関係のある範囲の売上高に限定されるというべきで ある。
(イ) また,海外企業を含む連結売上高を対象とすべきとの点については,被 告から海外企業への実施品の輸出に係る売上高を対象とする趣旨と考え られるが,原告が侵害論において対象としていた被告の実施行為は,被告 システムの使用と,被告アプリの生産,譲渡及び譲渡の申出にとどまって\nおり,仮に被告システム等が輸出されているとしても,当該被告システム 等に本件機能が搭載されているかどうかといった点も本件の証拠上明ら\nかではないから,この点の原告の主張も採用し難い。
エ 損害賠償の対象となる売上高の範囲について そこで,前記イ(ア)〜(ウ)で認定した事実に基づき,本件において損害賠償 の対象となる売上高の範囲につき検討する。
(ア) アカウント広告の売上げについて
アカウント広告の売上げは,企業等からの売上げに関するものであると ころ,一般ユーザは,かかる企業等との間でも「ふるふる」による友だち 登録をなし得るものの,この場合は,企業等が住所の位置情報をあらかじ め登録している必要があり,また,その際,企業等はスマートフォンを操 作するとは考え難いから,そもそも,この場合に,「近くにいるユーザ同 士がスマートフォン(2)を操作して友だち登録することによりコンピュ ータ(14)を利用してコミュニケーションによる交流」(構成a等)を\n具備するとは認め難く,他にこの場合の被告システム等が本件各発明の技 術的範囲に属するという的確な主張立証はない。 また,前記イ(ア)aに記載されたアカウント広告を構成する各売上げの\n内容に照らすと,これらの売上げは,いずれも,一般のユーザ同士の本件 機能による友だち登録との関係がないか,関係があっても希薄であるとい\nうべきである。 そうすると,アカウント広告の売上げは,本件の損害賠償の対象となら ないと解するのが相当である。
・・・
b 前記aで認定した売上高は,「ふるふる」以外の友だち登録に関する 分も含まれているところ,被告の侵害行為は,「ふるふる」による友だ ち登録に関するものであるから,被告の侵害行為と相当因果関係にある 売上高は,上記売上高に,本件損害算定期間中の「ふるふる」による友 だち登録割合を乗じて算出するのが相当である。そして,前記イ(イ)の とおり,同割合は,●(省略)●であるから,被告の侵害行為と相当因果 関係にある売上高は,●(省略)●となる。 ●(省略)●
(ウ) 以上のとおり,被告の侵害行為と相当因果関係にある売上高は,●(省 略)●となる。
・・・
(2) 相当実施料率について
ア 本件各発明の実施許諾契約における実施料率やその相場等
原告は,原告代表者から専用実施権の設定を受けているが,その設定契約\nの詳細は本件の証拠上明らかでなく,また,原告が他人に本件各発明の実施 を許諾したことをうかがわせる証拠はない。 そこで,相場等につきみるに,証拠(甲157〜159,乙82)によれ ば,電子計算機に係るロイヤルティ(件数719件)は,平均値が33.2%, 最頻値が50.0%,中央値が40.0%とされている一方,「技術分類 コ ンピュータテクノロジー」,「対象となる製品・技術例 計算;係数,チェ ック装置等」におけるロイヤルティ料率の相場は,1%未満,1〜2%未満, 2〜3%未満,3〜4%未満がいずれも16.7%であり,4〜5%未満が 25.0%であるとされている。 しかし,本件においては,被告アプリは無償で配信され,被告アプリのユ ーザが「ふるふる」を使用して友だち登録をし,その後の交流を行うといっ た行為自体による被告の売上げは発生しないという特殊性があることから すれば,上記の相場等を重視することはできない。
イ 本件各発明の価値や代替可能性等\n
本件各発明は,前記1(2)に記載のとおり,初対面の人物同士が出会った 後互いにコンタクトを取ることができるようにする際に,極力個人情報を明 かすことなくコンタクトが取れるようにするためのコンピュータシステム 及びプログラムに関する発明であって,相手方に互いの個人情報を通知する ことなく後々コンタクトを取ることができ,かつ,相手方以外の他人がその 相手方に成りすましてコンタクトしてくる不都合をも防止できる理想的な 連絡可能状態を構\築する手段を提供することを目的として,現実世界で出会 ったユーザ同士がユーザ端末を操作し,コンピュータを利用して交流を行う に当たり,コンピュータ(サーバ)が各ユーザ端末の位置情報を取得し,該 位置情報に基づいて所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索 されたことを必要条件として,該検索されたユーザ端末を新たな交流先とし て交流先のリストに追加して表示させ,ユーザが表\示された複数の交流先の 内からコミュニケーションを取りたい相手を選択指定し,指定された相手と の間でメッセージを送受信できるようにするという手段を採用することで, 互いにコミュニケーションによる交流に同意したユーザ同士が連絡先の個 人情報を知らせ合うことなく交流できるという効果が得られるようにした ことを特徴とする発明である。 このような発明には一定のニーズが存在するものと考えられるから,本件 各発明には相応の価値があるものと認められる。 もっとも,前提事実(6)のとおり,本件特許に関する無効審判請求におい て,特許庁は,本件特許が進歩性を欠く旨の職権審理結果通知をしていると ころ,このことは,実際に本件特許が無効となるか否かはともかく,類似の 技術が存在することを示すものということができる。
ウ 本件各発明の被告の売上げや利益への貢献等
証拠(甲41・3丁)によれば,「ふるふる」を利用する場合の最大の特 長は,複数人と一度に友だちになれることであり,サークルや部活,仕事の チーム,パーティーなど,複数の人が集まる場で活躍しそうであるとされて いることが認められ,これらの事実に加え,前記(1)イ(イ)記載の事実関係に よると,既に友人等であるユーザ同士が友だち登録する方法が多く,実際に もそのようなユーザ同士により友だち登録がされることが多いことがうか がわれることからすると,被告システム等においては「ふるふる」による友 だち登録がされる場合であっても,それ以前に相互の個人情報を交換してい る場合も少なくないものと考えられる。
●(省略)●
被告による企業努力が大きく貢献しているとうかがわれるとこ ろである。 そうすると,被告システム等に係る売上げや利益についての本件各発明の 貢献の度合いは,かなり限定的なものであると認められる。 エ 以上の諸事情,とりわけ,本件各発明には相応の価値があると認められる ものの,これと類似の技術が存在することがうかがわれることや,被告シス テム等に係る売上げや利益についての本件各発明の貢献の程度は限定的な ものであることなどを総合的に考慮すると,本件における相当実施料率は● (省略)●と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.06.18
平成30(ワ)38504 特許権侵害差止等請求事件 令和3年3月30日 東京地方裁判所
これらの記載によれば,本件発明の目的は,各種の痒みを伴う疾患にお ける痒みの治療のために止痒作用が極めて速くて強いオピオイドκ受容体 作動薬を有効成分とする止痒剤を提供することにあるところ,本件明細書 には,まさしくその有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として,本 件発明に記載された本件化合物のほかに,その薬理学的に許容される酸付 加塩が挙げられることが,「オピオイドκ受容体作動性化合物またはその 薬理学的に許容される酸付加塩」というように明記されているほか,同化 合物に対する薬理学的に好ましい酸付加塩の具体的態様(塩酸塩,硫酸塩, 硝酸塩等)も明示的に記載されている。
そうすると,出願人たる原告は,本件明細書の記載に照らし,本件特許出 願時に,その有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として,本件化合物 を有効成分とする構成のほかに,その薬理学的に許容される酸付加塩を有効\n成分とする構成につき容易に想到することができたものと認められ,それに\nもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというべきである。 そして,本件発明につき,出願人たる原告の主観的意図いかんにかかわらず, 第三者たる当業者の立場から客観的にその内容を把握できる徴表である本件\n明細書においては,本件化合物の薬理学的に許容される酸付加塩という構成\nは,まさしく,各種の痒みを伴う疾患における痒みの治療のために止痒作用 が極めて速くて強いオピオイドκ受容体作動薬を有効成分とする止痒剤を提 供するという本件発明の目的を達成する構成として,当該目的と関連する文\n脈において,特許請求の範囲に記載された本件化合物と並んで,明示的,具 体的に記載されているものである。
これらによれば,出願人たる原告は,本件特許出願時に,本件化合物の薬 理学的に許容される酸付加塩を有効成分とする構成を容易に想到することが\nできたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったものである といえ,しかも,客観的,外形的にみて,上記構成が本件発明に記載された\n構成(本件化合物を有効成分とする構\成)を代替すると認識しながらあえて 特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるものというべき\nである。
そうすると,本件発明については,本件化合物の酸付加塩であるナルフラ フィン塩酸塩を有効成分とする被告ら製剤が,本件特許出願の手続において 特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの,被告ら製剤と 本件発明に記載された構成(本件化合物を有効成分とする構\成)とが均等な ものといえない特段の事情が存するというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2021.06. 6
令和2(ワ)2956 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月20日 大阪地方裁判所
本件各発明に係る特許請求の範囲及び本件訂正明細書の各記載によれば,本件各 発明の本質的部分については,以下のとおりと認められる。 すなわち,従来,硬貨の表面に描かれた模様は,硬貨を製造するプレス機に設置\nされるプレス金型に予め彫り込まれ,硬貨をプレス及び打ち抜きする際,硬貨の表\ 面に金型の凹凸が反転して表現されていたところ,プレス金型に対して硬貨の表\面 に浮き出る部分は,平面彫刻機で彫り込んで行われていた。しかし,平面彫刻機の ように厚み方向のみ切削する切削工具では,切削した部分及び切削を行わなかった 部分は平面仕上げであり,金属の地肌のままの色合いであるため,放電加工機で不 規則かつ微細に地金を削り取りいわゆるナシ地仕上げを行ったり,切削した部分を 細かく研磨して鏡面仕上げを行ったりし,また,立体彫刻機で人物や動物等立体的 な図形を彫り込み,得られた硬貨の表面の凸部に人物等を立体的に表\現して,硬貨 の装飾効果を高めていた。しかし,これらの方法によっても,図形等の部分を除い た硬貨の地模様に対応する部分は,平面仕上げ,鏡面仕上げ,ナシ地仕上げのいず れかであり変化に乏しく,また,メダル遊戯機で使用される硬貨は,コスト等の兼 ね合いがあり,高価な金属の使用が難しく,表面の輝きが鈍いものが多いという課\n題があった。本件各発明は,こうした課題に対し,硬貨の表面の地模様に立体彫り\nによる変化を起こし,硬貨の輝きを増し,硬貨の装飾価値等を高めることを目的と するものである。具体的には,本件発明1は,切削深さを任意に変えられる同時三 軸制御 NC フライス機を,硬貨表面に描かれる人物や動植物等の図形に用いるので\nはなく,金型の表面に対して一定パターンで切削を繰り返すことにより硬貨の地金\n部分に立体的な幾何学的模様からなる新たな地模様を描き出し,硬貨の装飾価値を 高めるものである。本件発明2は,本件発明1と同様の方法で硬貨の地模様を描き 出すことに加え,同じく同時三軸制御 NC フライス機により地模様以外の模様に対 応する部分をV溝状に切削することで,当該模様部分の表面積の増加等により硬貨\nの表面の輝きを増加させ,硬貨の装飾価値等を高めるものである。\n以上を踏まえると,本件各発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,少なくとも 「金型の厚み方向へ切削可能な」切削工具「を用い,金型に対して一定のパターン\nで切削深さと,水平面に対する金型の切削角度と,を変えながら金型表面上を移動\nさせ,傾斜面を含む特定のパターンを金型上に描き,これを金型表面全体に繰り返\nすことにより繰り返し模様からなる地模様を形成すること」は,従来技術には見ら れない特有の技術的思想を有する本件各発明の特徴的部分すなわち本質的部分であ るといえる。さらに,本件発明2においては,これに加え,上記工具「により硬貨 の表面に浮き出る文字,図形等の模様に対応する部分をV溝状に切削すること」も,\n特徴的部分すなわち本質的部分ということができる。
(3) 前記のとおり,本件各発明における「金型」(構成要件B,C,E及びF)は\nプレス金型を意味し,また,被告製造方法の構成については当事者間に争いがある\nものの,被告製造方法が原金型に関する工程とプレス金型に関する工程という2つ の工程を含むこと,被告機械を用いて原金型の表面に地模様及び地模様以外の模様\nに対応する部分を切削加工により作製することは,当事者間に争いがない。これを 踏まえると,本件各発明においては,プレス金型の厚み方向へ切削可能な切削工具\nを用い,プレス金型に対して一定のパターンで切削深さと,水平面に対するプレス 金型の切削角度と,を変えながらプレス金型表面全体に繰り返すことにより繰り返\nし模様からなる地模様を形成し,本件発明2においては,これに加えて,上記工具 により硬貨の表面に浮き出る地模様以外の模様に対応する部分をV溝上に切削して\nプレス金型を得るのに対し,被告製造方法においては,被告機械を用いて原金型の 表面に地模様及び地模様以外の模様に対応する部分を切削加工により作製し,こう\nして得られた原金型から(特定されない加工方法(被告方法1)又は放電加工(被 告方法2)により)プレス金型を得る点で相違する。そうすると,被告製造方法は, 本件各発明の本質的部分を共通に備えているとはいえない。 したがって,本件各発明と被告製造方法の相違部分は,本件各発明の本質的部分 に当たる。
(4) 原告らの主張について
これに対し,原告らは,本件各発明の本質的部分は,金型に対して一定のパター ンで切削の深さと,水平面に対する金型の切削角度と,を変えながら金型表面上を\n移動させ,傾斜面を含む特定のパターンを金型上に描くことと,地模様以外の模様 に対応する部分をV溝状に切削することであり,原金型とプレス金型の2つの金型 を用いるか否かは本件各発明の本質的部分ではないなどと主張する。 しかし,前記のとおり,原金型からプレス金型に対する転写等の工程につき,そ の構成を特定しなくても,本件各発明の作用効果を奏し得るものが行われることが\n当業者にとって技術常識であるとは認められないことをも踏まえると,金型につき 原金型とプレス金型の2つを用いるか否かは,本件各発明の本質的部分に係る相違 部分というべきである。 したがって,この点に関する原告らの主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2021.06. 4
平成30(ワ)8708 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月13日 大阪地方裁判所
本件発明の構成要件B1,B2及びB3は,「支持面」について規定するもので\nあり,その文言によれば,1)支持面は,水平支持部材の上面の略中央にある開口部 の端部にあり,2)支持面は,側溝蓋の当接部の曲面(断面凸状)と略相似の断面凹 状の曲面からなり,3)当接部の下端部とせぎり部との間に所定の隙間を形成するた め,4)支持面の下端に沿って連続的にせぎり部が形成されるというものである。 前記1のとおり,従来製品においては,側溝蓋の平面の当接部が,側溝本体の平 面の支持面によって支持されていたところ,本件発明においては,断面凸状の当接 部が,略相似の関係にある断面凹状の支持面で支持されることによって,側溝蓋に より受ける荷重が分散されるとともに密着性がよくなり,支持面に平面がないため に小石,砂利,土等が堆積しにくくなり,側溝蓋のガタツキや騒音の発生を抑制し, かつ,せぎり部により当接部の下端部と支持面の下端部との間に所定の隙間が形成 されるため,砂利,土等がその隙間に集まり,当接部と支持面との間の面接触状態 が維持され,堆積した小石,砂利,土等も除去しやすい,という効果があるとされ る。
そうすると,せぎり部は,本来であれば略相似の関係にある曲面が当接する関係 にあった当接部と支持面のうち,支持面の下端の形状を変更することによって,当 接部の下端部との間に隙間を設けるものであるから,せぎり部は,それが設けられ ていなければ支持面の一部として当接部と当接した部分に存することになるし,せ ぎり部と対応する位置には,断面凸状の曲面からなる当接部の下端部が存すること になる。逆に言うと,側溝蓋と側溝本体との間に隙間が存したとしても,その隙間 が,断面凸状の曲面からなる当接部の下端部に対応するのでなければ,それは本件 発明のせぎり部にはあたらないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2021.05.31
平成31(ワ)2675 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月18日 東京地方裁判所
以上によれば,被告製品は,そのほとんどが吹矢協会と関係がある需要 者により購入されたと認めることが相当である。そして,被告製品は,吹 矢協会の関係者において吹矢協会の公認用具であることを理由として購 入された割合が相当に高いと認められる。原告の製造販売する吹矢用具は 令和2年12月1日以降は吹矢協会の公認用具でなかったから上記の理 由で購入された被告製品の需要の全てが原告の製造販売する吹矢の矢に 向かうとは認められない。他方,原告の製造する吹矢の矢については,吹 矢協会の公認がなくとも購入するとする者もいたことがうかがわれ,被告 製品の需要が全く原告の製造販売する吹矢用具に向かわないとはいえな い。
被告は,原告の吹矢用具が吹矢協会の公認用具でないことを理由として 令和2年12月1日以降の被告の売上げについての推定覆滅を主張する ところ,上記事情に照らせば,同日以降の利益については,65%の割合 で損害額の推定が覆滅すると認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.05.11
平成30(ワ)19441 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月28日 東京地方裁判所
本件発明は,端部開口を含む「空気導入口」(構成要件D)から空気\nが導入されてその空気が「排出部」(構成要件E)から排出され,その\n空気の流れによってガス容器収容部,ガス容器を冷却するという空冷機 構を備え,ガス容器収容部,ガス容器に対する熱害の発生を防ぐという\nものである(前記(1))。 原告は,各被告製品の側面開口と底面穴が「空気導入口」であり,カ バー穴が「排出部」であると主張する。 原告は,原告実験1−1から1−3,2−1から2−3,3−1,3 −2,3−3(前記(2)オ,キ,ケ)を,被告は被告実験1−1,1−2, 2(同カ,ク)を行った(このうち,原告実験1−1,2−1,3−1, 被告実験1−1,2が標準ガス容器に関する実験であり,原告実験1− 2,1−3,2−2,2−3,3−2,3−3,被告実験1−2が小型 ガス容器に関する実験である。)。そして,これらの実験において,燃 焼中のガス容器上側側面,下側側面等の温度が測定されるほか,スモー ク粒子を用いて,器具周辺の空気の流れを示すことが試された。 ここで以下の(ウ)ないし(オ)のとおり本件に提出された証拠によって は,各被告製品について,ガス容器収容部,ガス容器を冷却するよう, 側面開口及び底面穴から器具本体内へ空気が導入され,その導入された 空気がカバー穴から排出されていることを認めるに足りない。
被告製品1については,スモーク粒子を用いた原告実験1−3(前 記(2)オ(ウ) において,カバー穴から空気がガス容器収容部外に流出して いるように見えるときが多いものの,そうでないときがあるほか,側面 開口においては,基本的にガス容器収容部から空気が流出しているよう に見え,側面開口から空気がガス容器収容部内部に流入する動きは観察 できるとしても,少しの間しか観察できない。また,被告製品1には, 作動部とガス容器収容部の間には仕切板が一部に設けられているにすぎ ない。作動部においては,空気が取り込まれて燃焼炎等の影響を受けて 熱せられるところ,本件各証拠によっても,作動部で燃焼炎の影響を受 けて熱せられた空気がどのような動きをするかを認めるに足りず,作動 部において燃焼炎等の影響を受けて熱せられた空気がガス容器収容部側 のカバー穴,側面開口から流出することがないことを認めるに足りる証 拠はない。 他方,燃焼の際には,ガス容器内の液化石油ガスの気化に伴い,ガ ス容器は気化冷却され,ガス容器内のガスの温度は低下する(前記(2)ア(イ) そして,気化冷却により液化石油ガスの気化が妨げられることか ら,ガス器具にはガス容器の加温機構を備える必要があり(同前),被\n告製品1においても,燃焼炎の熱や輻射熱を作動部からガス容器収容部 に伝達してガス容器を加温するための加温機構が備えられている(同\nイ)。したがって,ガス容器の気化冷却の程度や,燃焼熱や輻射熱の影 響は,ガス容器収容部及びガス容器の温度に影響を与え得る要因である と認められる。このうち,気化冷却に関して,原告が行った各実験のう ちガス容器内のガスを使い切るまで燃焼したものにおいて,いずれも, ガス容器上側側面及び下側側面の温度がガスを使い切る直前から急激に 上昇しており(同オ ,(ア)(イ))帰化冷却はガス容器を用いた燃焼の最 終段階まで継続しており,かつ,ガス容器下側側面の温度は,開口等の 一部を塞ぐ作為の有無にかかわらず,概ね室温以下で推移しているので あって(同前),その燃焼中のガス容器ひいてはガス容器収容部の冷却 に及ぼす影響は相当に大きいものと認められる。
以上のとおりの原告実験1−3における側面開口付近の空気の流れ, 被告製品1の構造に照らしてカバー穴等から流出する空気と燃焼炎の影\n響を受けた作動部側の空気との関係が不明なこと,燃焼中のガス容器, ガス容器収容部に影響を与え得る諸要因を考慮すると,ガス容器収容部, ガス容器を冷却するよう,側面開口及び底面穴から器具本体内へ空気が 導入され,その導入された空気がカバー穴から排出されていることを認 めるに足りない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2021.04. 9
平成31(ワ)3273 差止請求権不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月25日 大阪地方裁判所
イ 原告は,組画の逐次又は一斉の表示をして記憶する人の「作業」となる部分\nを削除しつつ,組画の表示を構\成要件 B2 の選択手段に限定して,明確性の欠如に 係る拒絶理由を補正すると共に,「組画を逐次又は一斉に表示して」とする構\成を 削除し,かつ,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を付加したとい う本件補正の経緯から,被告は,特許請求の範囲につき,「一の組画の画像データ を選択する画像選択手段」に客観的,外形的に限定し,これを備えない発明を本件 発明の技術的範囲から意識的に除外したなどと主張する。 しかし,本件通知書及び本件意見書の各記載を踏まえると,「それぞれの前記記 憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対象を記憶する」の\nは人間が行う作業であって,物の発明としての「学習用具」の構成をなしていない\nなどといった明確性要件に係る本件通知書の指摘に対し,被告は,本件補正におい て,作業の主体につき,画像選択手段,画像表示手段,音声選択手段,音声再生手\n段といった「手段」とし,人が行う作業を示す部分を削除することで,これらの手 段を含むコンピューターであることを明確にしたものと理解される。それと共に, 進歩性に係る本件通知書の指摘に対しては,上記のように作業の主体を明確にした ことに加え,組画記録媒体に記録される画像データを,「1又は複数種の記憶対象 から成る記憶対象群に含まれる個別の記憶対象を表現する原画及び該原画に関連す\nる関連事項又は関連像を表現する1又は複数種の関連画から成る組画の画像」(当\n初の請求項1)から「原画,該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭 を有し対応する語句が存在する第一の関連画,並びに,該原画及び第一の関連画に 似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在 する第二の関連画,から成る組画の画像データ」に限定すると共に,画像表示手段\nが第一の関連画,第二の関連画,及び原画をその順に表示することとし,さらに,\nその表示を,これらに対応する語句の再生と同期させることとして,情報の提示方\n法を限定したものである。
このような出願経過を客観的,外形的に見ると,被告は,本件補正により,人為 的作業を示す部分としての「逐次又は一斉に表示」という行為態様は意識的に除外\nしているものの,物及び方法の構成として,逐次又は一斉に表\示する構成を一般的\nに除外する旨を表示したとはいえない。また,「一の組画の画像データを選択する\n画像選択手段」との構成を付加した点は,本件明細書に「一の組画」の画像データ\nの選択,表示を念頭に置いた記載があることを踏まえたものと理解されるものの\n(例えば【0057】),これをもって直ちに,客観的,外形的に見て,複数の組画を 選択する構成を意識的に除外する旨を表\示したものとは見られない。 そうすると,原告指摘に係る本件補正の経緯をもって,被告は,特許請求の範囲 につき,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」に客観的,外形的に限 定し,これを備えない発明を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したと見るこ とはできない。この点に関する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.03.14
平成29(ワ)10716 特許権侵害差止等請求事件 特許権 令和3年2月18日 大阪地方裁判所
消費税は,国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されるものであるとこ ろ(消費税法4条1項),「例えば,次に掲げる損害賠償金のように,その実質が 資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当する ことに留意する。・・・(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財 産権の権利者が収受する損害賠償金」(消費税法基本通達 5-2-5)とされているこ とに鑑みると,特許権を侵害された者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金 を侵害者から受領した場合,その損害賠償金も消費税の課税対象となるものと推察 される。そうすると,特許権者が特許権侵害による損害のてん補を受けるために は,課税されるであろう消費税額相当分についても損害として受領し得る必要があ るというべきであるから,「利益」には消費税額相当分も含まれ得ると解される。 適用されるべき消費税率について,原告は,損害賠償支払時点の税率(10%) によるべきと主張する。
しかし,上記のとおり,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金に対する消費 税が課せられるのは,損害賠償金の実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認めら れることによる。ここで,資産の譲渡等に相当する行為と見られるのは,特許権侵 害行為である。また,消費税基本通達 9-1-21 では,「工業所有権等又はノウハウを 他の者に使用させたことにより支払いを受ける使用料の額を対価とする資産の譲渡 等の時期は,その額が確定した日とする。」とされている。これらのことに鑑みる と,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金は,特許権侵害行為時に直ちに損害 が発生して金額が確定するものであるから,資産の譲渡等の時期は,特許権侵害行 為時であると解される。 そうすると,本件においては,第1期間〜第4期間のいずれにおいても,本件特 許権侵害行為時の消費税率8%が適用されることとなる。
・・・・
本件明細書の記載によれば,本件発明の効果は,前記4(1)のとおりである。要 するに,本件発明の効果は,1)外観上の体裁の良さ及び室内側への風雨の進入防止 並びに2)取付強度の高さ及び風圧に対する耐久性の良さと,3)取付作業時に足場等 が不要となることによる施工コストの低減にあるといえる。もっとも,上記効果の うち1)及び2)は,手摺本体取付け後の効果であるため,取付方法に係る発明である 本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とは必ずしもいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ア) 本件発明は,手摺の取付方法に係る発明である。手摺を選択するのは,最終 的にはこれを取り付ける建築物の施主であるものの,手摺の取付方法そのものが施 主の関心を惹くとは考え難い。その意味で,本件発明に係る手摺の取付方法を実施 することは,製品選択の直接の動機となるとはいえない。 しかし,本件発明の効果1)〜3)は,いずれも建築物に取り付けるべき手摺製品の 選択の動機となり得る事情ということはできる。
(イ) もっとも,前記アのとおり,効果1)及び2)は,いずれも手摺本体取付け後の 効果であるため,取付方法に係る発明である本件発明によるのでなければ実現し得 ない効果とは必ずしもいえない。例えば,本件特許出願後に公開されたものである ものの,特開 2009-2283号公報(乙16。平成21年10月8日公開)には,手 摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数のガラス板等のパネルが取り付けら れ,パネル間にはパネル支持枠(アルミニウム系金属で構成されるものであり\n(【0012】),アルミ製目地枠に相当する。)を用い,パネルの上下左右全ての側 部が支持固定される手摺の構成が開示されている。そうすると,効果1)及び2)につ いては,本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たっては,必ずしも重視し得 るものではない。
(ウ) 他方,効果3)については,最終的な需要者(ないしこれに対して建築物に取 り付けるべき手摺を提案する手摺取付業者や建築物の開発業者等)にとって,顧客 誘引力を生じ得るものといってよく,本件発明の貢献の程度を評価するに当たって はこれを考慮に入れるべきである。 もっとも,複数階層の建築物の建築現場においては,手摺取付工事のための足場 は不要であっても,別工程のために足場の設置が必要となることは,当然あり得る (乙50〜54参照)。このため,このような場合は,結局は足場等設置に要する コストが発生し,施工コスト低減の効果がないか,あるとしても,設置期間短縮等 による限られた効果しか生じないものと合理的に推察される。 他方,このような事情は主として建築物の新築時や大規模修繕時のものであり, それ以外のメンテナンス時には,足場等を不要とすることによる施工コストの低減 という効果が発揮されることは考えられる。現に,乙42製品のカタログ(乙4 2)には,「パネルは室内側から取り付けられ,メンテナンス性に優れていま す。」と記載されている。また,原告製品のカタログ(甲15)においても,「ガ ラス嵌め込み工事における,外部足場が不要になります。」との記載があり,これ もメンテナンス性における優位性を指摘するものと理解される。ただし,建築物の 新築時及び大規模修繕時に比較すると,それ以外の機会にメンテナンスを実際に要 する例は,規模的にかなり少ないと推察される。 さらに,被告は,そのウェブサイト(甲3の1)において,被告製品の特徴とし て,ガラスの連続した意匠となること,4辺支持とすることでガラス厚を薄く設計 できるとともに,手すりの高耐風圧仕様となること,ガラスの縦枠への掛かり寸法 をガラス厚とし,安心な製品仕様としていることを挙げるものの,足場を組む必要 がないこと(その結果として施工費が安価になること)については触れていない。 加えて,本件発明に係る手摺取付方法によれば,ガラス取付業者においてガラス 板と目地枠を取り付けることができるとしても,それがどの程度施工コストの低減 に貢献する効果を有しているのかは明らかではない。
(エ) 以上によれば,本件発明は,施工コスト低減という効果(3))によりこれを 実施する製品の販売等に貢献するものであって,相応の顧客誘引力を有するといえ るものの,その程度は限られているというべきである。また,効果1)及び2)に関し ては,本件発明は,手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同 程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ア) 外観上の体裁の良さ等(1))について 証拠(乙27,29〜31,39,42。各枝番を含む。以下同じ。)によれ ば,乙27製品等は,いずれも,手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数 のガラス板が取り付けられ,ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認 められる。これにより,これらの製品は,本件発明の効果1)と同様の効果を奏する ものといえる。
(イ) 取付強度の高さ等(2))について 証拠(乙27,29〜31,39,42)によれば,乙27製品等は,いずれ も,ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠(縦枠,竪枠)を用い,ガラス取付 枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる (乙31製品については,「2辺支持タイプ」との記載もあるが(甲18),「4 辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある(乙31)。)。これにより,こ れらの製品は,本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指 摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的 にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件明細書によれば,取付 強度及び耐久性に係る本件発明の効果は,「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係 合保持され,隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し て」(【0013】)の強度に関するものに過ぎない。このほか,原告製品(証拠(甲 14,15)及び弁論の全趣旨より,本件発明に係る取付方法により取り付けられ るものと認められる。)と同様に,これらの製品の施工例として高層マンション等 の複数階層を有する建築物が示されていること(乙30,31,42)に鑑みて も,乙30製品,乙31製品及び乙42製品は,少なくとも,原告製品と競合し得 る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。 したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(ウ) 施工コストの低減(3))について 証拠(乙37〜42)によれば,乙27製品等は,いずれも,ガラス板とアルミ 製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり,ガラス板とアルミ製目地枠を\n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに より,これらの製品は,本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指 摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程 度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件発明の効果の1つである施工コ ストの低減は,足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって, アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること(乙30製品,乙31製品)や手摺 笠木部分の取付方法が回転式であること(乙42製品)による製造コストとは無関 係である。 したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(エ) その他 原告は,乙27製品及び乙29製品につき,本件特許権を侵害する製品である可 能性が高い旨を指摘する。しかし,原告も可能\性を指摘するにとどまるし,これら の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから,本件に おいては,この点は考慮に含めないこととする。
(オ) 以上より,乙27製品等は,いずれも,本件発明の効果と同様の効果を有す る製品として,原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当 である。 もっとも,原告は,原告製品を遅くとも平成24年3月までには販売していると 認められる(甲14,15,弁論の全趣旨)。他方,証拠(乙55)及び弁論の全 趣旨によれば,乙27製品等の販売開始時期は,乙31製品が平成24年,乙27 製品が平成26年,乙30製品が平成27年,乙29製品が平成28年3月,乙3 9製品が平成29年10月であることが認められる。 また,原告製品,被告製品及び乙27製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ ットレール製品市場におけるシェアは,いずれも証拠上明らかでない。
これらの事情を総合的に考慮すると,アルミ製手摺製品の市場において原告製品 及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば,特許法102条2 項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの,被告に よる主張立証の程度に鑑みれば,その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば,被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程 度は限られるものの,他方で,競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的 であり,他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから,本件におい ては,2割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに 反する原告及び被告の各主張は,いずれも採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2021.03.12
令和1(ネ)10074 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年2月10日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
前記(ア)bのとおり,インタ−ネット広告配信の技術分野において, 同じ広告を必要以上に見せることにより起きる「バナ−バ−ンアウト」 (広告に反応がなくなる状態)を防ぐために,利用者一人一人に対する 広告配信の回数をコントロ−ルすることは周知技術であった。 乙5発明は,インタ−ネットにおける広告配信という,上記技術と共 通する技術分野に属する。そして,乙5発明は,「モバイル・ウェブ・ クライアントによりウェブにアクセスしているユ−ザ−に対する広告の 効力を高めること」(乙5【0011】)を目的としており,広告の効 力を高めるという課題は,上記周知技術の課題と共通する。そのため, 乙5発明に,技術分野及び課題が共通する上記周知技術を組み合わせる ことには動機付けがあるものと認められる。
そして,乙5発明において,特定の広告オブジェクトについて各ユ− ザ−に配信する回数を1回に制限するためには,ウェブ・サ−バが,受 信したモバイル・ウェブ・クライアントの位置情報と広告オブジェクト (広告情報)に関連付けられた位置情報が一致したことにより(前記ア (イ)b4)〔本判決74頁〕)一度供給した広告オブジェクト(前記ア(イ) b5)〔本判決75頁〕)を,その後,上記モバイル・ウェブ・クライア ントの位置情報と広告オブジェクト(広告情報)に関連付けられた位置 情報が再度一致しても,上記モバイル・ウェブ・クライアントに送信し ないようにすればよいことは,明らかである。 したがって,乙5発明に,特定の広告を各利用者に配信する回数を1 回に制限するという周知技術を適用することができたものと認められる。 そうすると,乙5発明に,特定の広告を各利用者に配信する回数を1 回に制限するという周知技術を適用し,構成要件E(「広告情報管理サ\n−バが,無線通信装置が一旦指定地域の外に出た後再び指定地域内に戻 った場合であっても,指定地域内にとどまり続けた場合であっても,同 じ広告情報を無線通信装置に送信しないこと」を特徴とする無線通信サ −ビス提供システム,前記2(1)ア(ア)〔本判決48頁〕)を容易に想到 することができたものと認められる。
エ 控訴人の反論について
控訴人は,一般的に,広告は目に触れる回数が多ければ多いほど効果が あるので,乙5発明は,広告情報が関連付けられた位置情報及び時刻と一 致する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェブ・クライアントに対し, 可能な限り長い時間,繰り返し広告を表\示することを目的としており,回 数は無制限で広告情報を配信する発明であるとし,広告の配信回数を制限 するという公知技術又は周知技術を乙5発明に適用することには阻害事 由があると主張する(前記第3の4(2)イ(イ)b(b)〔本判決25頁〕)。 しかしながら,前記ウ(ア)b〔本判決83頁〕のとおり,インタ−ネッ ト広告配信の技術分野において,本件特許の出願時(平成12年9月5日) には,同じ広告を必要以上に見せることにより起きる「バナ−バ−ンアウ ト」(広告に反応がなくなる状態)を防ぐために,利用者一人一人に対す る広告配信の回数をコントロ−ルすることは周知技術であったから,本件 特許の出願時において,一般的に,広告は目に触れる回数が多ければ多い ほど効果があると認識されていたとは認められない。そして乙5発明は, 広告オブジェクト(広告情報)が関連付けられた位置情報及び時刻と一致 する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェブ・クライアントに対して 広告オブジェクト(広告情報)を配信することにより広告の効果を高める ものであると認めることはできるが(乙5【0011】,【0012】【0 017】),乙5には,広告オブジェクト(広告情報)が関連付けられた 位置情報及び時刻と一致する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェ ブ・クライアントに対し,可能な限り長い時間,繰り返し広告を表\示する ことが広告の効力を高めることである旨の記載はなく,かえって,広告の 繰り返しは,その効果を減ずるという認識を前提とする上記周知技術が存 在したことからすると,広告の繰り返しによって,その効力を高めること が乙5発明の唯一の目的であったということはできない。したがって,広 告の配信数を制限することにより広告の効果を高めることを乙5発明が 排斥するものであったと認めることはできないから,広告の配信回数を制 限するという公知技術又は周知技術を乙5発明に適用することに阻害事 由があるとは認められず,控訴人の上記主張は,採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
2021.03.10
令和2(ネ)10050 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年2月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお,控訴人は,当審において,乙第18号証に記載された発明を主引例 とする無効の抗弁を新たに主張した。
しかしながら,この新たな無効の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当た るかどうかは,原審及び当審における審理の経過を総合的に踏まえて検討す べきものであるところ,一件記録によれば,原審においては,平成31年3 月12日に第1回口頭弁論期日が開かれた後,審理が弁論準備手続に付され たこと,充足論及び無効論について当事者双方の主張立証が行われた後,令 和元年12月20日の第5回弁論準備手続期日において,当事者双方の主張 立証が尽くされたことが確認された上で,裁判所の心証開示が行われたこと が認められる。そして,裁判所の心証開示が行われた上記第5回弁論準備手 続期日までに,乙第18号証に記載された発明を主引例とする無効の抗弁を 主張することが困難であったことをうかがわせるに足りる証拠はない。そう であるとすれば,控訴人としては,上記第5回弁論準備手続期日までに新た な無効の抗弁を主張すること(あるいは,少なくとも,速やかにその主張を する予定である旨を告知すること)が可能\\\であったし,そうすべきものであ ったといえるから,それをしなかったことは時機に後れたものであり,また, 時機に後れたことについて重大な過失があったものといわざるを得ない。そ して,そのような評価は,控訴人が控訴をし,審級が変わったからといって 変わるものではないところ,当審において新たな無効の抗弁の成否を審理す ることになれば,訴訟の完結が遅延することは明らかである。
以上の次第で,当審としては,新たな無効の抗弁を時機に後れた攻撃防御 方法であるとして却下したものである。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.02.25
令和1(ネ)10078 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年2月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ A邸工事が「公然」実施されたものではないとの主張について 控訴人は,A邸は塀や草木に囲まれており,容易に外部からA邸をのぞ き見ることはできないこと,山に囲まれており,近隣の住民もわずかであ ること,作業が屋根上で行われるものであり,外部から容易にその作業の 内容を確認することができないことから,A邸工事は,公然と行われたも のとはいえないと主張する。 しかし,被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務を負わない不特 定の者によって技術的に理解されるか,そのおそれのある状況で実施され たのであれば,工事は公然と行われたと評価するのが相当であるところ, 本件においては,まず,A邸の屋根からストーブの煙突が突出している側 (煙突の正面側)の隣地は,本件工事の当時には駐車場であり(乙14の 10),同駐車場には10台を優に超える駐車スペースがあり,敷地もA邸 より高いことが認められるのであって(乙24の2),同駐車場からは煙突 についても十分視認が可能\であるし,当該工事が第三者から視認されるこ と等を拒むような態様で行われていたことはうかがえない。
また,乙12の資料4は,前記ア(イ)認定のとおり平成19年7月2日 に被告から住友林業に提出されたものであるところ,同図面にはインナー フラッシングが明記されており,これが,住友林業からニシカネにファッ クスで転送されている(乙32)。そして,前記ア(イ)において認定したと おり,住友林業の下請業者であるニシカネがA邸の煙突について不燃材の 装着を行うことになっていたが,その時点では,煙突の屋内からの引き出 し及び立ち上げ部分はまだ設置されておらず,住友林業又はニシカネにお いて煙突の屋根貫通部の構造を認識することは十\分可能であったといえ\nるところ,A邸工事の施工方法及び防水構造は,引用に係る原判決の「事\n実及び理由」第4の2(3)ア及びイ(ア)記載のとおりであって,いずれも複 雑なものではなく,当業者であれば,乙12の資料4や,II)期工事時の煙 突の屋根貫通部の構造から,これらの発明を技術的に理解できるものと認\nめられる。
以上によれば,A邸工事は,本件特許出願前に,被控訴人のために発明 の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者(少なくとも上記住友林業 やニシカネ等の下請業者等)によって技術的に理解されるか,そのおそれ のある状況で実施されたもので,公然実施された発明に当たるというべき であるから,控訴人の主張は採用できない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.02.19
令和2(ネ)10036 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 控訴人は,原判決は,特許法70条1項,2項等に反し,本件特許請求の 範囲に記載のある「問題のある実施例」を本件各発明の実施例とせず,「最善の実施 例」のみを本件各発明であるとした点に誤りがある旨主張する。
ア 本件特許請求の範囲の【請求項1】には,「ホストコンピュータが,前記 券情報と前記発券情報とを入力する入力手段と,該入力手段によって入力された前 記券情報と前記発券情報とに基づき,かつ,前記座席管理地に設置される指定座席 のレイアウトに基づいて表示する座席表\示情報を作成する作成手段と,該作成手段 によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と,該記憶手段によって\n記憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段と,」と記載されており,「券情報」\nと「発券情報」とを統合して「座席表示情報」を作成し,これを記憶手段に記憶さ\nせることが記載されていると認められるから,控訴人の主張する「最善の実施例」 が本件特許請求の範囲に記載されていると認められ,控訴人の主張する「問題のあ る実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認めることはできない。 また,本件特許請求の範囲の【請求項2】には,「ホストコンピュータが,前記券 情報と前記発券情報とを入力する手段と,該入力手段によって入力された前記券情 報と前記発券情報とを,複数の前記座席管理地又は前記端末機を識別する座席管理 地識別情報又は端末機識別情報別に集計する集計手段と,該集計手段によって集計 された前記券情報と前記発券情報とに基づき,かつ,前記座席管理地に設置される 指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表\示情報を作成する作成手段と,該 作成手段によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と,該記憶手段\nによって記憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段と,」と記載されており,\n「券情報」と「発券情報」とを統合して「座席表示情報」を作成し,これを記憶手\n段に記憶させることが記載されていると認められるから,控訴人の主張する「最善 の実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認められ,控訴人の主張する 「問題のある実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認めることはでき ない。
イ 上記のことは,本件明細書(甲2)の記載からも明らかである。 本件明細書の「発明の詳細な説明」は,補正して引用した原判決「事実及び理由」 の第3,1(1)のとおりであり,段落【0002】には,【従来の技術】として,「従 来,指定座席を管理する座席管理システムとしては,カードリーダで読取られた座 席指定券の券情報及び券売機等で発券された座席指定券の発券(座席予約)情報等\nを,例えば列車車内において,端末機(コンピュータ)で受けて記憶し表示して,\n指定座席の利用状況を車掌が目視できるようにして車内検札を自動化する座席指定 席利用状況監視装置(特公H5−47880号公報)が発明されている。」との記載 があり,段落【0004】において,「券情報」及び「発券情報」を地上の管理セン ターから受ける場合について,「伝送される情報は2種になるために通信回線の負 担を1種の場合と比べて2倍にするなどの問題がある。」ことが記載されている。 そして,本件明細書の段落【0005】には,【発明が解決しようとする課題】と して,「上記発明の座席指定席利用状況監視装置は上記券情報と上記発券情報とに 基づいて各座席指定席の利用状況を表示するにはこれ等の両情報を地上の管理セン\nターから受ける場合,伝送される情報量が2倍になるために,該情報を伝送する通 信回線の負担を2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度をともに2倍にす るなどの点にある。」として,控訴人の主張する「問題のある実施例」の問題点が指 摘されており,段落【0006】には,【課題を解決するための手段】として「本発 明は,上記管理センターに備えられるホストコンピュータが,カードリーダで読取 られた座席指定券の券情報と券売機等で発券された座席指定券の発券情報とを入力 して,これ等の両情報に基づいて表示する座席表\示情報を作成して,作成された前 記座席表示情報を,前記ホストコンピュータと通信回線で結ばれて,指定座席を設\n置管理する座席管理地に備えられる端末機へ伝送して,該端末機が,前記座席表示\n情報を入力して表示してするように構\成したことを主要な特徴とする。」と記載さ れており,段落【0007】に,【作用】として,「上記ホストコンピュータから上 記端末機へ伝送される情報量が上記券情報と上記発券情報との両表示情報から1つ\nの表示情報となる上記座席表\示情報にすることで半減され,これによって通信回線 の負担と端末機の記憶容量と処理速度とを半減する。」と記載され,段落【0008】 〜【0019】に,【実施例】として,控訴人が主張する「最善の実施例」(「座席表\n示情報」は,券情報と発券情報という二つの情報を一つに統合した実施例)が記載 されていることが認められる。さらに,段落【0020】に,【発明の効果】として, 「該端末機がする各指定座席の利用状況の表示を前記券情報と前記発券情報との両\n表示情報から1つの表\示情報となる前記座席表示情報で実現できるようになり,こ\nれによって前記ホストコンピュータから前記端末機へ伝送する情報量が半減され, 通信回線の負担と端末機の記憶容量と処理速度等を軽減するとともに,端末機のコ ストダウンが計られて,本発明のシステムの構築を容易にする。」と記載されている\nことが認められる。 これらの本件明細書の記載によると,本件各発明は,指定座席を管理する座席管 理システムに関して,地上の管理センターから券情報と発券情報の両情報を端末機 で受ける場合,伝送される情報が2種になることから,伝送される情報が1種の場 合と比べて,通信回線の負担が2倍となり,端末機の記憶容量と処理速度を2倍に するなどの技術的課題があることに鑑み,地上の管理センターに備えられるコンピ ュータが,カードリーダで読み取られた券情報と,券売機等で読み取られた発券情 報等を入力して,これらの情報から一つの座席表示情報を作成し,作成された座席\n表示情報を,コンピュータと通信回線で結ばれて,指定座席を設置管理する座席管\n理地に備えられた端末機に伝送して,端末機が座席レイアウトに基づき各指定座席 の利用状況を表示するという構\成を採用したものであって,この点に,本件各発明 の技術的意義があると認められる。 このような本件明細書の記載によると,控訴人の主張する「問題のある実施例」 は,本件各発明が解決すべき課題を示したものであり,その課題を解決したのが本 件各発明であるから,これが本件各発明の実施例であると認めることはできない。
・・・
また,控訴人は,被控訴人は,被告システム1の「OD情報」,「改札通過情報」 が,それぞれ,本件明細書の図2の「発券情報」,「券情報」に,被告システム1の 「マルスサーバ」及び「セキュリティサーバ」が,「地上の管理センター」に該当す ることを認めているから,被告システム1は,本件明細書の図2の構成を備えるも\nのであり,本件特許権を侵害するものであると主張するが,本件明細書の図2は, 控訴人の主張する「問題のある実施例」に関するものであり,被告システム1が, 上記図2の構成を備えるからといって,本件各発明の構\成を備えるということには ならない。
原判決(15頁〜24頁)が判示するとおり,被告システム 1 は,本件発明 1 の構\n成要件1−B及び1−C並びに本件発明2の構成要件2−B及び2−Cの文言を充\n足せず,被告システム2は,本件発明1の構成要件1−A,1−B及び1−C並び\nに本件発明2の構成要件2―\A,2−B及び2−Cの文言を充足しないから,被告 各システムが本件各発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
(4) 控訴人は,被告システム1と本件各発明との間の本件相違点(被告システ ム1は,本件各発明における,ホストコンピュータにおいて券情報と発券情報から 一つの「座席表示情報」を作成し,これを,指定座席を設置管理する座席管理地に\n備えられる端末機に伝送し,端末機において「座席表示情報」を表\示するという構\n成を有していないこと)は,本件各発明の本質的部分ではないと主張するが,控訴 人のこの主張を採用することができないことは,原判決(25頁〜26頁)が判示 するとおりである。 本件相違点は,本件各発明の本質的部分に係るものであるから,被告システム1 は,均等の第1要件を充足しない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.02. 8
令和2(ネ)10003 特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許請求の範囲の記載によれば,本件訂正発明の「アクセス制御手段」は, 携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し,保護することを希望 する被保護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段であって, RFIDインターフェースを有するRバッジを一意に識別できる識別情報を 受け取って,該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別\n情報との比較を行う比較手段で,前記アクセス要求を許可するという比較結 果が得られた場合は,前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過す るまでは前記被保護情報へのアクセスを許可するものである。
一方,被告製品の「画面ロック解除制御手段」は,上記1のとおり,画面 ロックを解除し,または画面ロックを継続する手段であって,背面にかざさ れたICカードの固有IDを受信し,その固有IDを用いて,当該ICカー ドが登録済ICカードであるか否かの比較を行う比較手段で,画面ロックを 解除するという比較結果が得られた場合(登録済ICカードであると判定さ れた場合)は,画面ロックが解除された後,無操作状態が一定期間継続しな い限り,画面を介して操作することができるものである。
ここで,被告製品の「背面にかざされたICカードの固有ID」が,本件 訂正発明の「RFIDインターフェースを有するRバッジを一意に識別でき る識別情報」に相当することに争いはないから,被告製品の「画面ロック解 除制御手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に係る構成要件を充\n足するというためには,1)被告製品の「画面ロックを解除し,または画面ロ ックを継続する手段」が,本件訂正発明の「携帯電話の所有者が第三者によ る閲覧や使用を制限し,保護することを希望する被保護情報(以下,単に 「被保護情報」という。)に対するアクセス要求を許可または禁止する手 段」に当たるとともに,2)被告製品において「画面ロックを解除するという 比較結果が得られた場合(登録済ICカードであると判定された場合)は, 画面ロックが解除された後,無操作状態が一定期間継続しない限り,画面を 介して操作することができる」ことが,本件訂正発明の「アクセス要求を許 可するという比較結果が得られた場合は,前記アクセス要求が許可されてか ら所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」こと に当たることを要するといえる。
(2) そこで,上記1)及び2)の2点に分けて,被告製品の「画面ロック解除制御 手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するか否かについて 検討する。
ア 上記1)の点につき
(ア) 証拠(甲4など)によれば,被告製品の「画面ロック機能」とは,ス\nマートフォンの画面をロックすることによって画面を介した操作が行え ないようにするためのものであり,画面ロックの解除とは,スマートフ ォンの操作(画面を介した操作)が可能な状態にするためのものであっ\nて,これらは被保護情報へのアクセスを許可するとか禁止するといった ことそのものを意味するわけではないし,それと同視すべき事柄である ということもできない。このことは,画面を介した操作が可能となった\nからといって,常に被保護情報へのアクセスが行われるわけではなく, 公開された地図の検索等,被保護情報には当たらない情報へのアクセス に終始する場合もあり得ることや,逆に,被保護情報そのものにパスワ ードが付されている場合等を想定すると,画面ロックを解除したからと いって直ちに当該被保護情報にアクセスできるようになるわけではない ことなどからも明らかである。 もちろん,被保護情報そのものにパスワード等が付されていない場合 には,画面ロックを解除した後,ユーザが画面を介して所定の操作を行 うことにより,スマートフォンに格納された被保護情報へのアクセスが 可能になるし,壁紙として,第三者に見られたくない写真を設定してい\nるような状況の下では,画面ロックの解除と同時に,被保護情報へのア クセスが起こり得ることとなる。しかしながら,これらは,画面が開か れたことそのものや,それによって画面を介した操作が可能になったこ\nとに付随して生じた結果というべきものであって,画面ロックやその解 除の直接の目的や効果といえるものではない(なお,1)の構成における\n違いが,2)の構成における違いにも反映していると考えられることにつ\nいては,後述のイ参照。)。
(イ) また,証拠(乙2)によれば,被告製品は,「画面ロック」状態にお いても,画面を介した操作によらないアクセス要求(例えば,自動改札 機の通過のために乗車券の情報にアクセスすること,電話着信があった ときに発信者の名前を画面に表示するために電話帳の情報にアクセスす\nること等)に対しては,アクセスを禁止していないことが認められ,こ の場合には,画面ロックの解除を経ないで被保護情報へのアクセスが可 能になることとなる。このことも,画面ロックやその解除が,被保護情\n報へのアクセスの禁止や許可そのものではないことを裏付ける一事情と いうべきである。なお,控訴人は,上記の例は,被告製品の構成を認定\nするための対象にはなっていない事例であるから考慮すべきではないと いう趣旨の主張をするが,画面ロックやその解除の意義を認定するため の事情として考慮することには何ら妨げはないものというべきである。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)に検討したところによれば,被告製品の「画面ロックを 解除し,または画面ロックを継続する手段」が,本件訂正発明の「被保 護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段」に当たるとい うことはできない。
イ 上記2)の点につき
本件訂正発明の「アクセス制御手段」の「前記アクセス要求が許可され てから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可す る」構成は,その記載のみからは,所定期間が経過した後の状態が明らか\nでない。しかしながら,本件明細書の【0009】に,本件訂正発明の目 的は,「個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該 情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを 提供することにある。」と記載されていることや,【0039】に,「タ イマを設けて一定のタイムラグを許容することで,ICアセンブリ130 とICアセンブリ140とを実際に使用するときの距離が比較的長い場合 であっても,通信可能距離の短い通信方式を採用することが可能\にな る。」と記載されていることからすると,上記の構成の意義は,所定時間\nに限ってアクセスを許容する構成を付加することで,第三者による被保護\n情報の不正使用を確実に防止しつつ,Rバッジと携帯電話とが離間してい ても,自動改札機等による被保護情報に対するアクセス要求を適切に処理 できるようにしたことにあると解される。そうすると,所定時間経過後に は,被保護情報の保護のために,再度アクセスを禁止することが必須とさ れているというべきであり,「前記アクセス要求が許可され」たときを起 点とし,それから所定の時間が経過した後は,たとえ被保護情報へのアク セスが継続している最中であっても,被保護情報へのアクセスは禁止され ることになるものと解される。
これに対し,被告製品の構成は,前述のとおり,「画面ロックを解除す\nるという比較結果が得られた場合は,画面ロックが解除された後,無操作 状態が一定期間継続しない限り,画面を介して操作をすることができる」 というものである。その一定期間の起点は,画面ロックが解除された後, 何の操作もしないという例外的な場合には,画面ロックが解除されたとき となるが,何らかの操作がされる多くの場合には,その操作が終了したと きとなるのであって,常にアクセス許可がされたときが一定期間の起点と なる本件訂正発明とは異なる。また,本件訂正発明においては,アクセス 許可がされた後,一定期間が経過すれば,被保護情報へのアクセスが継続 してDいたとしてもアクセスが禁止されることになるのに対し,被告製品に おいては,画面を介した操作が継続している限り,一定期間がカウントさ れることはなく,したがって,画面がロックされることはあり得ないので あり,この点においても違いが存するものというべきである。 そして,両者にこのような違いが生じているのは,本件訂正発明におい ては,アクセス許可が被保護情報へのアクセスという意味を有するため, 被保護情報の保護という観点から時間制限が設けられているのに対し,被 告製品の画面ロック解除は,単に,画面を介した操作を可能にするという\n意味しか持たないため,被保護情報の保護という観点から時間制限をする 必要はなく,無駄な電力消費を防ぐという観点から時間制限が設けられて いるのにすぎないからであり,両者の時間制限が持つ技術的意義が全く異 なるからであると解される(このように本件訂正発明におけるアクセス許 可と被告製品における画面ロック解除が持つ技術的意義に違いがあること は,被告製品が1)の構成要件をも充足しないことをも裏付けるものである\nといえる。)。
ウ 上記ア及びイに検討したところによれば,被告製品の「画面ロック解除 制御手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するとはいえ ない。
(3) 控訴人は,本件訂正発明の「アクセス」とは,携帯電話の正当なユーザと して被保護情報を閲覧・利用・更新することを意味しており,被告製品にお いては,画面ロック状態では,正当なユーザであることを確認できていない ため,被保護情報(電子マネー,電話帳,写真などのデータ)の閲覧・使 用・更新は禁止されているとして,被告製品が,本件訂正発明の構成要件を\n充足する旨主張する。 しかしながら,被告製品の画面ロック状態においては,被保護情報の閲 覧・利用・更新に制限があるとはいえ,それが全面的に禁止されているもの ではなく(上記(2)ア(イ)),画面ロック状態の解除後においても,それだけで 被保護情報へのアクセスが全面的に可能になるものでもない(上記・・・(2)ア(ア))。 被告製品の「画面ロック解除制御手段」は,まさに文字どおり,画面ロック 解除を制御しているにとどまり,被保護情報へのアクセスの制御との関連は 限定的なものにとどまる。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.12. 2
令和1(ネ)10081 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上の本件発明3の特許請求の範囲(請求項3)の記載及び本件明細書 の記載によれば,構成要件Bの「操作メニュー情報」は,「ポインタの座\n標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力 手段に表示するため」の「画像データ」であり,出力手段に表\示され,利 用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるよう\nに構成されていることを要するものと解される。\n
イ これに対し控訴人は,構成要件Bの「操作メニュー情報」は,命令の「対\n象」や「内容」のいずれかを,小さな絵で表現したものが,「実行される\n命令結果を利用者が理解できるという動作・作用を目的・目標として構成\nされている画像データ」であって,「画面上のどの座標位置・範囲に表示\nするかという表示位置・範囲に関する情報」を含むものである旨主張する。\n しかしながら,本件発明3の特許請求の範囲(請求項3)の記載中には, 「操作メニュー情報」が「実行される命令結果を利用者が理解できるとい う動作・作用を目的・目標として構成されている画像データ」であること\nの根拠となる記載は存在せず,控訴人の上記主張は,特許請求の範囲の記 載に基づかないものであるから,採用することができない。
(3) 被告製品における「操作メニュー情報」(構成要件B)の具備の有無につ\nいて
控訴人は,1)被告製品の本件ホームアプリにおける「上ページ一部表示」\n及び「下ページ一部表示」は,その内容や表\示位置からすれば,これを見た 利用者は上ページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえる から,利用者が,その表示の有無を視覚的に認識でき,その表\示内容から, 所望の命令を実行した結果についても理解できるような,画像データに当た り,「操作メニュー情報」に該当する,2)被告製品における「左上領域」(別 紙参考図の図1記載の左側の赤色の点線枠内),「右上領域」(同図1記載 の右側の赤色の点線枠内),「左下領域」(同図2記載の左側の赤色の点線 枠内,同図3のB記載の左側の画像)及び「右下領域」(同図2記載の右側 の赤色の点線枠内,同図3のB記載の右側の画像)は,「操作メニュー情報」 に該当する旨主張する。
ア そこで検討するに,被告製品の構成エ(ウ),(エ),オ(ウ)及び(エ)及び 別紙「乙2の2の説明図」によれば,被告製品においては,1)利用者が, 移動させたいショートカットアイコンをロングタッチし,ドラッグ操作を することにより当該ショートカットアイコンを移動させ,ロングタッチし た位置と当該ショートカットアイコンをドラッグしている指等のタッチパ ネル上の位置が約110ピクセル離れた場合に,その際のページ画面が縮 小表示されるとともに,そのページ画面のページ番号に応じて,当該ペー\nジが上端ページであれば1つ下のページの一部の画像である「下ページ一 部表示」のみが,下端ページであれば1つ上のページの一部の画像である\n「上ページ一部表示」のみが,それ以外のページであればこれらがいずれ\nもIGZO液晶ディスプレイに表示される「縮小モード」となること,2) 「縮小モード」の状態で,「上ページ一部表示」が表\示されているとき, 利用者が当該ショートカットアイコンをドラッグしている指等及びマウス カーソルの先端の座標位置を「左上領域」又は「右上領域」のいずれかの\n範囲に入れたときは,上ページスクロール1又は上ページスクロール2を 生じさせる命令が実行され,また,「縮小モード」の状態で,「下ページ 一部表示」が表\示されているとき,利用者が当該ショートカットアイコン をドラッグしている指等及びマウスカーソルの先端の座標位置を「左下領\n域」又は「右下領域」のいずれかの範囲に入れたときは,下ページスクロ ール1又は下ページスクロール2を生じさせる命令が実行されることが認 められる。
イ しかるところ,被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表\ 示」は,別紙「乙2の2の説明図」の図6等に示すように,「縮小モード」 の状態で,IGZO液晶表示ディスプレイの画面上に表\示される長方形状 上の画像データであるが,その表示には「実行される命令結果」の内容を\n表現し,又は連想させる文字や記号等は存在せず,利用者がその表\示自体 から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構成されているも\nのと認めることはできない。
また,利用者が,縮小モードの状態で,1つ上のページ又は1つ下のペ ージの一部を表示した画像である「上ページ一部表\示」又は「下ページ一 部表示」を見て,「上ページ一部表\示」又は「下ページ一部表示」までド\nラッグすれば,上ページ又は下ページに画面をスクロールさせることがで きるものと考え,実際にそのように画面をスクロールさせる操作をしたと しても,それは,「上ページ一部表示」又は「下ページ一部表\示」の表示\n自体から「実行される命令結果」の内容を理解するのではなく,操作の経 験を通じて,画面をスクロールさせることができることを認識するにすぎ ないものといえる。 したがって,被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表\示」 は,利用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解でき\nるように構成された画像データであるものと認めることはできないから,\n構成要件Bの「操作メニュー情報」に該当しない。\n
ウ 次に,前記アの認定事実によれば,被告製品における「左上領域」,「右 上領域」,「左下領域」及び「右下領域」は,いずれも,被告製品の出力 手段であるIGZO液晶表示ディスプレイの画面上の特定の座標位置で囲\nまれた領域であり,その領域は,画面上に画像データとして表示されてい\nるものではなく,利用者が画面上で認識できるものではない。 したがって,被告製品における「左上領域」,「右上領域」,「左下領 域」及び「右下領域」は,出力手段に表示され,利用者が「実行される命\n令結果」を理解できるように構成されている「画像データ」であるものと\n認めることはできないから,構成要件Bの「操作メニュー情報」に該当し\nない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.11.21
平成31(ワ)2210 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年8月11日 東京地方裁判所
本件発明1−1の特許請求の範囲の記載をみると,本件発明1−1は, 「患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1 取得部と」(構成要件1−1A),「前記第1患者識別情報と,患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否\nかを判定する第1判定部と」(構成要件1−1B)を有するものであり,第1判定部において第1判定をする。また,「前記第1判定部で一致すると\n判定された場合に,看護師または医師を識別するための第1医師等識別情 報を前記端末装置から取得する第2取得部と」(構成要件1−1D),「前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識別する情報としてあらか\nじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判 定部と」(構成要件1−1E)を有するものであり,第2判定部において第2判定をする。\n
ここで,第1判定と第2判定の関係について,特許請求の範囲には,「前 記第1判定部で一致すると判定された場合に」(構成要件1−1D),第1医師等識別情報が取得されて第2判定がされることが記載されている。こ\nのことから,第1判定で一致すると判定されることが,第2判定がされる ことの前提であることが記載されているといえる。もっとも,第1判定と 第2判定との時間的な接着性の有無等についての記載はない。 そこで,本件明細書1をみると,本件明細書1には,実施の形態1ない し4が記載されている。実施の形態1では,第1判定や,第1判定で一致 するとの判定がされて患者の医療情報を出力することについての実施の 形態(構成要件1−1Aないし1−1C)が記載されているが,第1判定で一致するとの判定がされた直後に第2判定がされるとか,第1判定は,\n第2判定がされる都度にされるものであるなど,第1判定と第2判定の時 間的関係やその機会についての記載はない。そして,実施の形態1では, 患者が,患者の手に巻いており識別情報を含むリストバンドのバーコード を端末装置の撮像部で撮像することによって第1判定がされる(段落【0 045】)。そして,第1判定で一致するとの判定がされた場合には,「患者 用画面」が生成,表示され(段落【0047】ないし【0050】),患者用画面には検査の予\定や患者への注意事項が表示されるなどし(【004\n3】【図7】,患者はその画面を確認することで患者に対して行われる医療 行為等を知ることができ(段落【0019】),その患者用画面に対し,患 者が,例えば,検査ボタンをタッチすると検査名欄や検査説明欄が表示された検査表\示画面が生成,表示されることが記載されている(段落【00\n51】等)。また,第1判定で一致するとの判定がされて患者用画面が表示(ステップS21)されると検査ボタンや手術ボタンの入力を受け付ける\nようになり,その入力がされた場合には対応する画面の表示処理がされるが,入力がされなかったり,上記対応する画面の表\示処理がされたりした後には,患者用画面の表示に戻ることが記載されている(段落【0065】ないし【0068】,【図12】)。\n
実施の形態2は,看護師が患者の医療情報を確認するための看護師専用 画面を表示部に表\示する実施の形態であり,主に構成要件1−1Dないし1−1Fに対応する実施の形態が記載され,特に説明する構\成等以外は実施の形態1と同じであることが記載されている(段落【0088】)。そこ では,患者用画面が表示部に表\示された後,看護師が,自身のリストバン ドに記載されたバーコードを撮像部で撮像し,第2判定がされることが記 載されている(段落【0091】)。また,第2判定が一致した場合には医 療スタッフ用画面が表示されるところ,医療スタッフ用画面である看護師専用画面,バイタル画面等の表\示後に終了処理(ステップS120)がされると,患者用画面の処理(ステップS23)に移ることが記載されてい る(段落【0122】【図26】【図12】)。そこには,上記の他に,第1 判定と第2判定との関係についての記載はない。 また,実施の形態3は主に第1判定に関係する記載であり(ただし,請 求項2に関する形態),実施の形態4は,第2判定に関係する記載である が,それらの記載も含めて,本件明細書1に,第1判定と第2判定との時 間的接着性についての記載はない。 本件明細書1における背景技術や発明が解決しようとする課題の記載 によれば,医療情報を医療用サーバから取得し,取得した医療情報に基づ いてピクトグラムを表示する端末装置という従来技術ではセキュリティを確保することが難しかったところ,本件発明1−1は,セキュリティを\n従来技術より向上させることができるというものである(段落【0003】 ないし【0006】)。本件明細書1には,本件発明1−1について,上記 のとおり,従来技術よりセキュリティを向上させることが記載されている が,その記載のほかには従来技術と比較した優れた効果についての記載は ない。
以上の特許請求の範囲の記載や本件明細書1の記載に照らせば,第2判 定は,第1判定で一致すると判定された場合にされるものである。しかし, 本件明細書1には,実施の形態として,患者がその手に巻いているリスト バンドのバーコードを端末装置の撮像部で撮像することによって第1判 定がされ,一致すると判定された場合に患者用画面が表示され,それに対して患者が一定の操作をする形態が記載されている。そして,患者用画面\nの表示後に,医療スタッフがそのリストバンドのバーコードを撮像部で撮像することで第2判定がされ,そこで一致すると判定されると医療スタッ\nフ用画面が表示されるが,その終了処理後は,患者の医療情報を表\示する 患者用画面の表示に戻ることも記載されている。これらに照らすと,本件発明1−1において,第2判定がされるのは,第1判定で一致すると判定\nされた場合ではあるが,第1判定で一致するとされた後に患者による一定 の操作がされ,その後に第2判定がされることや,第1判定で一致すると 判定されて第2判定がされて第2判定で一致するとされて看護師等が必 要とする医療情報を含む表示画面が出力された後に,第1判定で一致すると判定された後と同じ,患者の医療情報を表\示する患者用画面に戻り,その状態から再び第2判定がされることがあり得ることが記載されている といい得る。
以上によれば,本件発明1−1において,第2判定がされるのは第1判 定で一致すると判定された場合であるが,第1判定がされるのは第2判定 がされる直前に限られるとか,第2判定がされる前にその都度第1判定が されるとは限られないと解するのが相当である。このように解したとして も,第1判定がされてそこで一致すると判定されない限り第2判定はされ ず,第2判定において一致すると判定されない限り看護師等が必要とする 医療情報を含む表示画面が表\示されることはないから,本件明細書1に記 載されたセキュリティの向上という効果を奏するといえる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.11.21
平成30(ワ)21448 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年7月9日 東京地方裁判所
イ 本件発明の技術思想(課題解決手段)について
前記(1)によれば,本件発明は,鋼管等を回転して圧入する立坑構築機に\n関し,輸送する際に幅を狭くする必要があったところ,従来技術において は,円弧状歯車片同士の端部が当接されず,その隙間から内部の転動体が こぼれ落ちてしまうため,標準的なベアリングを使用することができない という課題が生じていたので,これを解決するため,構成要件Eに係る構\ 成を採用し,円弧状ベアリング片が隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成し,もって,分割して幅方向の寸法を狭くすることができると\n共に,転動体がこぼれ落ちなくなり回転を安定させることができ,標準的 なベアリングを使用して装置を安価に構成することができるようにした\nという技術的思想であるものと認められる。すなわち,本件発明において, 円弧状ベアリング片は,それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付 ベアリングを構成するという技術的意義を有しているものというべきで\nあり,このことは,前記のとおり,課題解決手段の欄(段落【0011】) において,「円弧状ベアリングは隙間なく接続して環状の歯車付ベアリン グを構成し,内輪及び外輪の間に配置された球やころ等の転動体がこぼれ\n落ちない構造になっている。かかる構\成によって,分割して幅方向の寸法 を狭くすることができると共に,標準的なベアリングを使用して回転を安 定させることができる。」と記載されていることからも根拠付けられるも のである。
ウ 構成要件Eへの被告製品の充足性について\n
しかして,構成要件Eには,円弧状ベアリング片が「それぞれの両端部\nを各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成する」との文言が記載され\nているところ,「接続」とは「つなぐこと。つながること。続けること。続 くこと。」を意味するものである(広辞苑第7版)。そうすると,その文言 の一般的意義,上記の本件発明の技術的思想(本件発明において,円弧状 ベアリング片は,それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成するという技術的意義を有しているものであること)に照らせ\nば,環状の歯車付ベアリングを構成するために隙間なく接続する部品,す\nなわち,つなぐ部品が円弧状ベアリング片であって初めて,円弧状ベアリ ング片が「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構\n成する」といえるものであると解するのが相当である。そうすると,環状 の歯車付ベアリングを構成した際に,円弧状ベアリング片の両端部に隙間\nが有るならば,「接続」とは評価し難いものというべきである。 しかるに,前記アによれば,被告製品においては,環状の歯車付ベアリ ングは,2つある分割フレーム14に設けられた内外輪部ケースそれぞ れの両端部及び回転リング部材51−3,51−4それぞれの両端部を 隙間なく接続して構成するものであって,分割内輪部23や分割外輪部\n24それぞれの両端部を隙間なく接続するものでも,つなぐものでもな く,円弧状ベアリング片である円弧状部材36,37それぞれの両端部 には,客観的に隙間があるから,被告製品の円弧状部材36,37は 「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成す\nる」ものであるとはいえず,被告製品は,構成要件Eを充足しないもの\nというほかない。
・・・
以上によれば,本件特許は当業者が乙2発明に基づいて容易に発明するこ とができたもの(特許法29条2項)であるから,特許無効審判により無効 にされるべきもの(同法123条1項2号)である。 なお,本件特許については,知的財産高等裁判所令和2年(行ケ)第10 102号事件同2年3月24日判決(裁判所ホームページ)が,特許無効審 判請求の不成立審決に対する取消請求を棄却しているところ,原告は,これ を理由として,口頭弁論再開の申立てをしているが,同判決は,乙2発明を\n主引用発明とし,乙20発明を副引用発明として適用することに基づく進歩 性の欠如については判断しておらず,上記判断は同判決と矛盾するものでは ないから,再開の必要性は認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2020.11.11
平成28(ワ)35157 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月24日 東京地方裁判所
しかして,前記第2のとおり,原告は,特許第5177317号(本件特 許権1)に基づく請求と,同第5610056号(本件特許権2)に基づく 請求をするところ,両請求の関係は,選択的併合の関係にあるものと解され る。そして,原告は,いずれの請求についても,損害額として,特許法10 2条2項により算定される損害額,弁護士費用相当額及びこれらに対する遅 延損害金を主張するものであるから,仮に本件特許権2の侵害が認められる 場合であっても,本件特許権1の侵害により算定される損害額と,本件特許 権2の侵害により算定される損害額とは,同一の額となるというべきである。 そうすると,本件特許権1の侵害による損害額の算定を行ったものが,原 告の請求の一部認容となる場合も,上記損害額が,仮に被告らの輸入販売等 の行為が本件特許権2を侵害するものであった場合の同侵害による損害額を 下回るものとは認められないものと考えられるから,本件特許権2の侵害や 損害額について判断するまでもなく,本件特許権1の侵害による損害額を, 原告の被った損害としてそのまま認容すべきこととなる。 そこで,原告の損害額として,本件特許権1の侵害による損害額について 検討する。
特許法102条2項により算定される損害額
ア 前記前提条件(4)(5)のとおり ,被告LEDは被告製品に搭載されて販 売されたものであるところ,被告LEDの主な用途は写真撮影時のフラッ シュライトであるが,被告らが販売している被告製品以外の機種にはかか るフラッシュライトの性能を特長にしたスマートフォンもあること(甲5),被告製品はデザインを重視し,機能\をシンプルなものにした製品として紹介・宣伝されており,被告製品の紹介や宣伝の中ではLEDライト の性能等について一切触れられておらず,被告製品の基本スペックとしてもLEDライトは挙げられていないこと(甲5,6の1,7)などの各事\n実がそれぞれ認められる。これらによれば,被告LEDについては,被告 製品の主要な特長として位置付けられているとは認められず,このような 被告LEDにつき被告製品の主要部として特に強い顧客吸引力があるとい うことは困難というべきである。 そして,前記前提条件(4)のとおり被告製品の販売による利益額は、被 告HTCについては●(省略)●円,被告兼松については●(省略)●円 であるところ,被告製品の市場想定価格は●(省略)●円(税別)である こと(甲7),被告製品自体の製造コストは明らかでないものの,被告製 品が発売された平成27年10月時点で既に販売されていた他のメーカー のスマートフォンについては,利益率は60%前後であるとされているこ と(乙52),他方,HTC台湾に被告製品を納入したメーカーが被告L EDを仕入れた価格は1個●(省略)●米ドルであったこと(乙47)が それぞれ認められる。
これらの事実からすれば,被告製品の製造コストは約●(省略)●円 (≒●(省略)●円×〔1−0.6〕)となり,これを被告製品が発売さ れた平成27年10月の平均の為替レート120.16円/米ドルで換算 すると,約●(省略)●米ドル(≒●(省略)●円÷120.16円/米 ドル)となるから,被告製品の製造コストに占める被告LEDの仕入価格 の割合は,約●(省略)●%(≒●(省略)●×100)となる。なお, 証拠(甲50)によると,50種類の単色LEDが1個約700円ないし 900円でインターネット販売されていることが認められるが,これらの 単色LEDは,砲弾型のものや複数のLEDチップが実装されたものであ るなど,被告LEDと同じ構成のものであるか明らかでないから,損害額を算定するに当たって事情として考慮するのは相当とはいえない。\n以上を総合すれば,被告LEDの販売による利益額は,被告HTCにつ いては●(省略)●円(≒●(省略)●円×0.25%),被告兼松につ いては●(省略)●円(≒●(省略)●円×0.25%)と認めるのが相 当である。
イ これに対し,原告は,被告製品1台当たりにおける被告LEDによる利 益額は100円を下回らない旨主張する。 しかしながら,前記前提条件(4)によれば 被告製品の販売による利益額 は,被告HTCについては1台当たり約●(省略)●円(≒●(省略)● 円÷●(省略)●台),被告兼松については1台当たり約●(省略)●円 (≒●(省略)●円÷●(省略)●台)となるところ,被告LEDによる 利益額を1台当たり100円とすれば,その割合は,前者との関係では約 ●(省略)●%,後者との関係では約●(省略)●%となるのであって, 上記アに説示した被告製品における被告LEDの位置付けや顧客誘引力に 照らすと,いずれの割合も相当とは認め難いから,原告の上記主張は採用 できない。
ウ 以上によれば,被告HTCに対する特許法102条2項による損害金の 額は,●(省略)●円と,被告兼松に対する特許法102条2項による損 害金の額は,●(省略)●円とそれぞれ認められる。
・・・
(3) 推定覆滅事由について
ア 証拠(甲68〜77,183〜186)及び弁論の全趣旨によれば,原告は, 自社の商品を,主に靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売 し,その小売価格は2000円から6000円程度の商品が中心であり,原告が, 対象期間中に原告各商標と同一ないし類似する商標を付したスニーカー(甲183) を販売した際の売上げは一足当たり3000円程度であったと認められる。 他方で,証拠(乙19)及び弁論の全趣旨によれば,被告商品は主に百貨店等の 店頭で販売されたものであり,別紙3被告商品販売一覧表記載のとおり,その小売\n価格は1万5000円から2万1000円,被告が百貨店等に販売する際の卸売価 格は●(省略)●円から●(省略)●円であったと認められる。 被告商品の販売による一足平均の限界利益は前記(2)エ(ウ)で認定した583万0 211円を,前記(2)イ(ウ)で認定した販売数量である●(省略)●足で除した● (省略)●円であり,原告が販売した競合品の一足当たりの限界利益を裏付ける証 拠はないが,上記の原告が販売した競合品の価格自体や,被告商品における一足当 たりの売上額が原告による競合品よりも大幅に高かったことからすれば,販売され た商品一足当たりの限界利益についても,被告商品の方が原告の商品よりも大きか ったものと推認される。 このような販売態様や販売価格の違い及び一足当たりの限界利益の違いは,被告 の限界利益額の一部について,商標法38条2項の推定を覆滅すべき事情として考 慮すべきである。
イ 他方で,被告が主張するその他の事情については,以下のとおり,いずれも 商標法38条2項の推定覆滅事情として考慮すべき事情とはいえない。 (ア) 原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことについて 被告は,原告が販売していた商品の多くには,原告各商標と同一又は類似の標章 が付されておらず,被告商品の販売によって,原告の売上げが減少したという関係 にないと主張する。
原告は,原告各商標と同一又は類似する標章を使用したスニーカーを販売してお り,被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益が得られたであろう という事情が原告に認められることは前記(1)のとおりであり,原告が上記のスニー カー以外に原告各商標と類似する標章が付されていない靴を販売していたとの事情 は,損害額の推定を覆滅すべき事情に当たるとも認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.10.12
平成30(ネ)10016 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年5月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(イ) これに対し被控訴人は,1)イ号製品においては,供給口(5)から 供給された液体は,空気口(10)から噴出された外部傾斜領域(7A ')に平行な方向に沿って流動する空気流の強い剪断応力と液体の自重で 下流側へ引っ張られて傾斜面(外部傾斜領域(7A'))に沿って流れ, 空気流によって傾斜面に液体を押し付ける力は作用しておらず,乙23 の鑑定書記載のとおり,流体力学の一般原理においては,傾斜面に対し て平行な高速気流によっては,傾斜面に供給された液体に対し,傾斜面 に押し付ける力は生じないから,イ号製品は,構成要件オの「液体を,\n高速流動する空気流で平滑面に押し付けて」の構成を備えていない,2) 構成要件オの「薄膜流を空気流で空気中に微粒子として噴射する」とは,\n「高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾 斜面から離れるとき」に「10μm以下の液滴の微粒子」になることを いうが,イ号製品は,気液体が混じった高速噴流が衝突することによっ て,微粒子を得られるものであり,この衝突前に微粒子を得られるもの ではないとして,イ号製品は,構成要件オを充足しない旨主張する。\n しかしながら,被控訴人の主張は,以下のとおり理由がない。
a 上記1)について
乙23の鑑定書には,1)液体が傾斜面に供給された場合,液体を傾 斜面側に押す力がなくても,液体は,その粘性による剪断応力と自重 とで傾斜面に沿って流れること,2)気体が傾斜面に平行に流れる場合, 気体は,傾斜面を押す力を発揮し得ないこと,3)液体には,高速の気 流との速度差によって傾斜面に平行な方向の剪断応力が作用し,液滴 の飛散を伴う流れとなるが,このような傾斜面に平行な気流では,該 傾斜面に液体を押し付けるような力は作用しないことは,流体力学の 一般原理である旨の記載がある。 しかしながら,乙23は,空気の直線流れの方向と平行に平板を設 置した場合における流体力学の一般原理について述べるものであって, イ号製品においては,「供給口(5)」から供給されたノズルの軸方 向(垂直方向)に直進する液体流が,空気口(10)から噴射する高 速流動する空気流によって,空気流と合流する時点で,外側傾斜領域 (7A')に沿って平行に進むように進行方向が曲げられており(前記 (ア)a),傾斜面(外側傾斜領域(7A'))に液体流を押し付ける力 が作用しているものといえるから,イ号製品には妥当しない。 したがって,被控訴人の上記1)の主張は理由がない。
b 上記2)について
本件発明4の特許請求の範囲(請求項4)には,「微粒子」の粒子 径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 次に,本件明細書には,微粒子の粒子径に関し,「図1に示すノズ ル」について「この構造のノズルは,液体を10μm以下の微細な粒\n子に噴射できる。」(【0003】),「図3に示すノズル」につい て「粒子径を5μmとする微粒子を得ることに成功した。しかしなが ら,この構造のノズルは,液体を噴射する供給口5の調整が極めて難\nしく,調整がずれると微粒子の粒子径は20〜30μm以上に急激に 大きくなった。」(【0011】),「図4に示すノズル」について 「この構造のノズルは,アトマイズエアーとスプレッディングエアー\nの衝突角を25度に設計すると,10μm以下の微粒子が得られる。」 (【0012】),「図11の拡大図に示すノズル」について「この 構造のノズルは,液体を極めて微細な,たとえば1〜5μmの微粒子\nとして噴射できる特長がある。」(【0052】),「ちなみに,本 発明者が試作したノズルは,1分間に1000gの液体を噴射して, 粒子径を10μm以下の微粒子の液滴を噴射することに成功した」(【0 072】)との記載があるが,これらの記載から,本件発明4の「微 粒子」の粒子径を「10μm以下」に限定する趣旨を読み取ることは できず,また,本件明細書には,本件発明4の「微粒子」の粒子径を 「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 さらに,本件意見書には,「内部混合タイプのノズルは,閉鎖され た空間内で液体の微粒子として噴霧します。このため,ノズルの内部 で極めて目詰まりしやすい欠点があります。・・・にもかかわらず,内部 混合タイプの噴霧ノズルが多用されますのは,外部混合タイプでは, 安定して液体を極めて小さい微粒子に噴霧できないからです。外部混 合タイプの噴霧ノズルであって,液体を微粒子として安定して噴霧で きます優れたノズルは実用化が困難です。」,「本願発明は,外部混 合タイプのノズルを改良したものです。本願発明の噴射方法とノズル は,前述の独特の構成で,液体を極めて小さい微粒子に安定して噴射\nできる特長があります。本発明の噴射方法とノズルは,液体を,10 μm以下の極めて小さい微粒子として,安定して噴射することが可能\nです。・・・それは,本発明の噴射ノズルが,液体を極めて小さい孔や, 極めて小さいスリットから噴射して微粒子に噴射するのではなく,平 滑面を極めて速い速度で高速流動する空気流で,液体を薄く引き伸ば して微粒子にして噴射するからです。」(以上,6頁16行〜7頁2 行)との記載がある。上記記載中には,「液体を,10μm以下の極 めて小さい微粒子として,安定して噴射することが可能です。」との\n記載があるが,上記記載全体として読めば,「本発明」は,「平滑面 を極めて速い速度で高速流動する空気流で,液体を薄く引き伸ばして 微粒子にして噴射する」構成により,液体を微粒子として安定して噴\n霧でることを説明したものであって,「本発明」が「10μm以下」 の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述 べたものではない。
以上によれば,構成要件オの「微粒子」とは,小さな粒子径の粒子\nを意味するものであって,粒子径の数値範囲に限定はなく,「10μ m以下」の粒子径のものに限定されるものでもない。そして,イ号製品においては,外側傾斜領域(7A')に沿って進む,液滴を含む薄膜流は,外側傾斜領域(7A')から離れるときに小さな粒子径の液滴(微粒子)となっていることは,前記(ア)b認定のとお りである。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2020.09.26
平成29(ワ)22010 実用新案権侵害差止等請求事件 実用新案権 民事訴訟 令和2年2月5日 東京地方裁判所
ア 構成要件Dは,取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け,「口紐により取出し筒から引き出した命綱の周囲を緊縛して,取出し筒の開口部を密閉する」というも\nのであり,それによって,取出し筒から空気が漏れるのを防止し,冷却効率を損な わないという作用効果を奏するものであるところ(前記1(1)ア(イ)),上記の「緊 縛」については,「きつくしばること」という一般的な字義(乙1)のとおり,口 紐により命綱の周囲をきつく縛ることを意味すると解するのが相当である。
イ 被告は,「緊縛」は,口紐を取出し筒の先端部に巻き付け,その両端を絡ま せてつなぎ合わせることを意味すると解すべきであるとし,その理由として,1) 「縛る」に「ひもや縄などを巻き付けて結び,離れたり,動いたりしないようにす る」という字義があり,「結ぶ」に「ひも・帯などの両端をからませてつなぎ合わ せる」という字義があること,2)本件明細書の図4に,口紐を筒部先端部に巻き付 け,その両端を絡ませてきつく縛り,筒部の開口部を密閉する態様の実施例が示さ れていることなどを主張する。 しかしながら,被告が主張するような態様によらなくとも,筒部の開口部を密閉 することによって,取出し筒から空気が漏れるのを防止し,冷却効率を損なわない という作用効果を奏することは可能であると考えられるところ,上記1)については, 「緊縛」の一般的な字義を離れて,その意味を過度に限定するものであり,上記2) についても,実施例にすぎず,本件明細書の考案の詳細な説明において,口紐を筒 部先端部に巻き付け,その両端を絡ませてきつく縛る態様のものでなければならな いとする説明もみられないことなどに照らせば,いずれの主張も採用することはで きず,「緊縛」がそのような態様のものに限定されると認めることはできない。
(2) 被告製品
これを被告製品についてみると,前記第2の2(6)のとおり,被告製品は,ランヤ ード取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け,「口紐をランヤード取出し筒から引き 出したランヤードの周囲に巡らせ,コードストッパーを用いて筒部先端部分を収縮 させることにより,ランヤードを固定して,ランヤード取出し筒の開口部を密閉す る」という構成(構\成d)を有するところ,コードストッパーを用いるものであっ たとしても,口紐により命綱の周囲をきつく縛ることにより,筒部の開口部を密閉 するものである認められるから,構成要件Dを充足する。したがって,被告製品は,文言上,本件考案の技術的範囲に属する。\n 3 争点3(被告製品3及び6は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物か)について
前記第2の2(6)イ認定のとおり,被告製品3及び6は,服本体のみで販売されて いる製品であり,ファン等を取り付け又は収納することによって,本件考案の技術 的範囲に属する被告製品と同様の構成を備えるものとなると認められるから,被告製品と同様に,構\成要件Dを充足する。
そして,被告製品3及び6は,ハーネス型安全帯を着用できるようにするために 空調服の背中部分にランヤード取出し筒を設けたものであり,そのような構成を有しない通常の空調服と比べて販売単価が高いものであること,具体的には,前記1\n(1)カ(イ)認定のとおり,被告各製品の販売単価とこれらに対応するものとして被告 が販売している通常の空調服の販売単価を対比すると,被告製品1及び4は約1 5%,被告製品2及び5は約23%,被告製品3及び6は約48%割高であること, 同(ウ)認定のとおり,被告の空調服のカタログに,「ウェアのみ」の製品は「洗い 替え用やファン・バッテリーなどをお持ちの方向けのウェアのみです。」と記載さ れ,被告製品3及び6は「フルハーネス安全帯着用者専用空調服です。背中部分か らランヤードを取り出すことができます。もちろん空気は逃がしません。・・・」など と記載されていることなどからすると,被告製品3及び6は,ハーネス型安全帯を 着用するために販売されている製品であると認めるのが相当であり,ハーネス型安 全帯を全く利用しない使用形態は,経済的,商業的,実用的な用途として想定され ていないというべきであるから,本件登録実用新案に係る物品である被告製品の製 造のみに用いるものと認めるのが相当である。 したがって,被告製品3及び6は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物(実用新案法28条1号)に当たる。
・・・
5 争点5(被告は先使用による通常実施権を有するか,又はセフト社の先使用 による通常実施権を援用することができるか)について
(1) 被告各製品の製造等に関し,被告らが先使用による通常実施権を有するとい うためには,被告らにおいて考案の実施である「事業の準備」(実用新案法26条, 特許法79条)をしていたこと,すなわち,その考案につき,いまだ事業の実施の 段階には至らないものの,即時実施の意図を有しており,かつ,その即時実施の意 図が客観的に認識される態様,程度において表明されていることを要するものと解される(特許法79条に関する最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日\n第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照)。
(2) これを本件についてみると,本件出願日までの被告らにおけるフルハーネス 対応空調服の開発状況等は前記1(1)エ認定のとおりである。すなわち,1)被告ら代 表者は,平成27年3月3日頃,背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け,その先端部分を紐様のものなどを用いて縛る構\成を有する空調服に係る着想を得て,その構成を手書きで図示した乙11図面を作成し,同月4日,そのデータをゼハロスに送信して,試作品の作成を依頼したこと,2)ゼハロスは,同月31日までに, 背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け,その先端部分を紐及びコードストッ パーを用いて縛る構成を有しており,被告各製品と同様の構\成を有する本件試作品 を作成したこと,3)被告らは,同年4月7日,被告において購入したハーネス型安 全帯を用いて本件試着品の試着をしたことが認められる。 しかしながら,フルハーネス対応空調服の構成に係る手書き図面が作成され,その試作品を作成して,社内でその試着をしたからといって,被告らにおいて,即時\n実施が可能な状況にあったかは必ずしも明らかとはいえないところ,前記第2の2(5)認定のとおり,被告らが被告各製品の製造,販売等を開始したのは平成28年5 月であり,本件試作品が作成され,試着された平成27年3月及び同年4月から1 年以上を要したことにも照らせば,本件出願日の時点では,少なくとも,本件考案 の実施に当たる被告各製品の事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識さ れる態様,程度に表明されていたということはできないというべきである。\n
(3) 被告は,1)被告ら代表者は,平成27年3月4日,本件考案の構\成が記載さ れた乙11図面のデータをゼハロスに送信し,試作品の作成を依頼しているところ, フルハーネス対応空調服が顧客のニーズ等を背景として作れば売れる製品であった こと,その開発又は販売の障害となるような事情は存在しなかったこと,被告らの 社内体制として,被告ら代表者の意思決定が重要な意味を持っていたことなどに照らせば,被告ら代表\者の上記の行為は,フルハーネス対応空調服の事業化を決定する旨の被告らの意思表示であるということができること,2)ゼハロスは,被告ら代 表者の上記の依頼を受け,他社に委託するなどして,平成27年3月31日までに,本件試作品を作成しているところ,被告らが,莫大な時間,労力,資金を投下して,\n既存の空調服を研究,開発し,商品化してきたこと,本件考案は,既存の空調服に 筒を取り付けるだけで完成するシンプルな構成であることなどに照らすと,被告らは,本件試作品の作成によって,フルハーネス対応空調服に係る事業活動のほとん\nどを完了しており,被告らによる即時実施の意図が客観的に表明されていること,3)被告ら代表者は,平成27年3月26日の空調服の会において,必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供する旨発言しており,被告らが同空調服\nを販売する意思を有していたことが示されていること,4)被告らは,平成27年4 月7日,本件試作品の試着を行い,被告ら代表者においてフルハーネス対応空調服は完成したと強い手応えを感じ,同空調服の販売の意思はより強固なものになった\nから,遅くともその時点で,被告らによる販売の意思は確定的なものとなったこと などを主張する。
しかしながら,上記1)について,乙11図面は,手書きの比較的簡略な図面であ り,そのデータを他社に送信して試作品の作成を依頼したというだけで,即時実施 が可能な状況にあったといえないことは明らかである。被告ら代表\者の意思決定が 重要であったというのは被告らの内部的な事情にすぎないことにも照らせば,ゼハ ロスへの乙11図面の送信等をもって,被告各製品の実施に係る被告らの即時実施 の意図が客観的に認識される態様,程度に表明されたということはできない。また,上記2),4)について,本件考案は既存の空調服の背中部分の構成を変更するにとどまるものであり,被告らは既存の空調服の研究,開発実績を有していると\n認められたとしても,試作品が一度作成され,社内でその試着がされただけでは, 製品化に耐えるものであるか未だ明らでなく,試着の結果を踏まえて設計の見直し 等の作業が必要になるであろうことは十分に考えられるところである。被告らが被告各製品の製造,販売等を開始したのはその後1年以上が経過した平成28年5月\nであったことなどにも照らせば,本件試作品が作成されたことや試着されたことを もって,被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態 様,程度に表明されたということはできない。さらに,上記3)について,被告が指摘する空調服の会における被告ら代表者の発言は,必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供するというもので\nあり,これをもって,被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に 認識される態様,程度に表明されたということはできない。
(4) 以上によれば,本件出願日である平成27年5月11日当時,本件考案の実 施に当たる事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度に 表明されていたと認めることはできないから,被告らにおいて,その「事業の準備」をしていたということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.09.10
平成29(ワ)28189 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年1月17日 東京地方裁判所
上記記載によれば,本件発明等の課題は,1)包装体の大きさを従来と同様 に維持しつつ,より大きなサイズのシート状物を積層できる構造を提供する\nこと,2)包装体同士を積み重ねた際の安定感のあるシート状物の積層体を提 供することにあり,本件発明等の効果は,3)従来と比較して第2の折片の面 積分だけ大きいサイズのシート状物によって,従来と変わらないサイズの積 層体を形成することができ,また,第2の折片が設けられた大きさ分だけ肉 厚部分が形成され,積層体同士を重ね合わせた際の安定感を向上することが できるという効果を得られることにあると認められ,本件発明等においては, 上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得るために第2の折片を設けてい るが,本件発明等に係るシート状物のサイズを従来のものより大きくするた めには,その前提として,第2の折片以外の部分を可能な限り大きくするこ\nとが必要となるものと解される。
すなわち,本件発明等の第1の中間片の幅は積層体の幅と略同じ長さと規 定されているところ,第2の中間片及びこれと略同じ幅の第1の折片の長さ を第1の中間片の幅の2分の1より小さくすると,第2の折片を設けたとし ても,シート状物全体のサイズがその分だけ従来のものよりも小さくなって しまい,上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得ることができなくなる一 方,第2の中間片の幅を第1の中間片の2分の1よりも長くすると,第2の 中間片同士が中央部で重なり合い,全体の嵩高状態が不安定なものになって しまい,上記2)の課題解決に支障が生じることとなる。そうすると,本件発 明等の上記課題1)及び2)を解決し,所期の効果を奏するには,第2の中間片 の幅を,第1の中間片の1/2を超えない範囲でこれに限りなく近づけるこ とが望ましいものと認められる。
エ 前記のとおりの「略」という語の通常の意義及び構成要件Cにおいて第2\nの中間片の幅寸法が規定されている技術的意義に照らすと,同構成要件にい\nう「略1/2」とは,正確に2分の1であることは要しないとしても,可能\nな限りこれに近似する数値とすることが想定されているものというべきで あり,各種誤差,シート状物の伸縮性等を考慮しても,第1の中間片の2分 の1との乖離の幅が1割程度の範囲内にない場合は「略1/2」に該当しな いと解するのが相当である。
オ これに対し,原告は,本件発明等は,容易に伸縮する素材を用いることを 前提とし,第2の中間片及び第1の折片の幅に誤差が生じた場合にも,第2 の折片によりその誤差を吸収して,積層体が所望とする幅寸法になるように 調整することに主眼があるのであって,本件発明等における「略1/2」の 語は,1/2を超える場合は含まないが,1/2より短いものは広く許容す る意味と解釈すべきであると主張する。
しかし,本件明細書等には,第2の中間片が第1の中間片の幅の1/2よ り小さい幅となったときに第2の折片がその誤差を吸収することにより積 層体の幅寸法を維持することが本件発明等の課題である旨の記載は存在し ない。むしろ,前記判示のとおり,本件明細書等には,積層体の幅を従来と 同様とした上で,第2の折片を設けることにより「第2の折片の面積分だけ 従来と比較して大きいサイズのシート状物」(段落【0011】)を形成す ることが本件発明等の課題である旨が記載されているのであって,その課題 解決のためには,前記のとおり,第2の中間片の幅を,可能な限り第1の中\n間片の1/2を超えない範囲でこれに近づけることが望ましいものという べきである。
・・・
3 相違点1の認定の誤りについて
(1) 前記2(1)の甲6の記載事項(図2ないし4を含む。)を総合すれば,甲 6には,本件審決が認定するとおり,甲6(審判甲1)発明が記載されてい ることが認められる。そして,本件訂正発明と甲6(審判甲1)発明を対比すると,本件訂正発明の第2の折片の幅と甲6(審判甲1)発明における「腰折ウェットテシュ ー11f,12f」(第2の折片に相当)の幅について,本件訂正発明は, 「上記第1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整する とともに,上記第1の中間片の幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の 幅より短い幅となる」のに対し,甲6(審判甲1)発明は,「腰折ウェット テシュー11,12の展開長の略五分の一の長さ,又は腰折ウェットテシュ ー11,12の幅方向の中心線Yを越えず且つこれに接近した長さ」である 点で相違すること(本件審決認定の相違点1)が認められる。したがって,本件審決における相違点1の認定に誤りはない。
(2) これに対し原告は,1)特許法施行規則24条の2は,特許発明の技術上の 意義ある部分は,「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」 により特定される旨規定していることからすると,発明は,解決課題(目的 あるいは作用・効果)と解決手段(構成)とで特定しなければならない,2) 本件訂正発明と甲6に記載された発明の相違点を捉えるには,第2の折片と 他の片との関係性をシート全体の折構造で把握する必要があるなどとして,\n本件審決における甲6(審判甲1)発明の認定は適切ではなく,本件審決認 定の相違点1は,原告主張の相違点1(前記第3の1(1))のとおり認定すべ きである旨主張する。
しかしながら,特許出願に係る発明の要旨の認定は,特許出願の願書に添 付した特許請求の範囲の記載に基づいてすべきものであるところ,原告主張 の相違点1は,本件訂正発明の特許請求の範囲(請求項1)記載の発明特定 事項以外の事項(本件明細書記載の「背景技術」,「発明が解決しようとす る課題」等)をも含めて本件訂正発明の要旨を認定することを前提として, 本件訂正発明と甲6に記載された発明とを対比するものであるから,その前 提において,採用することができない。また,特許法施行規則24条の2は, 特許法36条4項1号の経済産業省令の定めるところによる記載は,発明が 解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分 野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必 要な事項によりしなければならない旨規定し,明細書の発明の詳細な説明の 記載要件を定めた規定であるから,原告主張の相違点1が適切であることの 根拠となるものではない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
4 相違点1の判断の誤りについて
(1) 本件訂正発明の「上記第1の中間片から積層方向上側に折り返され上記第 1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとともに, 上記第1の中間片の幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の幅より短い 幅となる第2の折片」にいう「調整」の意義について ア 本件訂正発明の「上記第1の中間片から積層方向上側に折り返され上記 第1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとと もに,上記第1の中間片の幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の幅 より短い幅となる第2の折片とを有するように折り畳まれ」との記載から, 本件訂正発明の「第2の折片」は,「第1の中間片の幅の1/2未満で, かつ,上記第1の折片の幅より短い幅」であって,「第1の中間片から積 層方向上側に折り返され」,「第2の折片」によって「第1の中間片の幅 が所望とする積層体の幅寸法となるように調整」することができることを 理解できる。 一方で,本件訂正発明の特許請求の範囲(請求項1)には,「上記第1 の中間片から積層方向上側に折り返され上記第1の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように調整する」にいう「調整」について,具体 的な調整方法等について規定した記載はない。
イ 次に,本件明細書には,「調整」に関し,「調整」の語について定義し た記載はなく,「図1に示すように,シート状物10は,所望とする積層 体の幅寸法と略同じ長さに形成された第1の中間片11と,積層方向下側 に折られ,第1の中間片11の略1/2の幅に第1の中間片11に隣接し て形成された第2の中間片12と,第2の中間片12から積層方向下側に 折り返され第2の中間片12と略同じ幅に形成された第1の折片13と, 第1の中間片11から積層方向上側に折り返され第1の中間片11の幅が 所望とする積層体の幅寸法となるように調整する第2の折片14とから構\n成されている。」(【0014】)との記載がある。また,本件明細書に は,「第2の折片」に関し,「第2の折片14は,第1の中間片11と隣 接し,シート状物10の長さ方向に平行な長辺10a,10bと,第3の 折れ線17と短辺10cとによって囲まれる部分である。シート状物10 の長辺10a,10bの第2の折片14の長さにあたる部分,つまり第3 の折れ線17と短辺10cとの距離Dは,D<Cの関係を有する。つまり, 距離Dは,距離Aの半分より小さい値である。」(【0020】),「以 上のように構成されたシート状物積層体1は,従来の積層構\造においては ない第2の折片14を有することで,従来と変わらない積層体の幅として も,第2の折片14の面積分だけ従来よりもサイズの大きいシート状物1 0を積層させることができる。具体的には,シート状物10は,従来使用 されるシート状物の大きさと比較して,第2の折片14の面積分,つまり 上述のD<Cの関係を有する範囲内で大きさを変更することができ,約2 5%まで大きいサイズのシート状物を使用することができる。」(【00 26】)との記載がある。
ウ 以上の本件訂正発明の特許請求の範囲の記載,本件明細書の記載及び図 1によれば,本件訂正発明の「上記第1の中間片から積層方向上側に折り 返され上記第1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調 整する」にいう「調整」とは,シート状物の第1の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように,「第2の折片」の幅を「第1の中間片の 幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の幅より短い幅」となるように 設定することを意味するものと解される。
・・・
被告製品2)については,上記アの審理経過に照らし,信用性が高いと認め られる甲25及び乙A39に基づいて検討することが相当であるところ,原 告が被告製品2)(YRC24/3FM13:59)について測定した結果(甲25:別紙6 −2)によれば,同製品の各シート状物の第1の中間片の幅の2分の1に対 する第2の中間片の幅の比率(以下,単に「第2の中間片の比率」というこ とがある。)が90%〜100%の範囲内にあるものは,全80枚のうち3 枚にすぎず,その平均値(「平均値(1,80枚目除く)」欄のもの。以下 同じ。)も83%にとどまるものと認められる。また,被告PPJが被告製品2)(YRC24/3FM16:40)について測定した結果(乙A39:別紙6−4)によれば,第2の中間片の比率が90%〜100%の範囲内にあるものは,全80枚のうち30枚であるものの,同比率がその範囲内にあるものは,いずれも偶数番目のシート状物であって,奇数番目の シート状物にはこれが存在しない上,全体の平均値も84%にとどまるもの と認められる。
上記の被告製品2)全体における第1の中間片の幅の2分の1に対する第2の中間片の幅の平均比率,その比率が90%〜100%の範囲内にあるものの割合及びその分布等に照らすと,被告製品2)の第2の中間片が構成要件C「第1の中間片の略1/2の幅」との要件を充足するとは認められない。\n
◆判決本文
対応する審決取消訴訟はこちらです。こちらは、無効審決が維持されています。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.09. 7
令和2(ネ)10023 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年8月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「(1) 構成要件A等の「ホワイトカード」及び「使用限度額」の意義\nア 前記1(1)のとおり,本件明細書等では,段落【0002】〜【000 5】において本件発明の課題が説明されているところ,同課題は,クレジットカー ドについてのものであり,プリペイドカードサービスやデビットカードサービスに ついてのものではない。そして,段落【0006】において,「以上の課題を解決 するために,本発明は,・・・ホワイトカード使用限度額引き上げシステムを提供 する。」と記載され,さらに,段落【0007】〜【0009】において,上記課 題を解決するための具体的構成が記載されている。これらの記載に,「ホワイト\nカード」の用語は,クレジットカードに関して使用された場合は,「カード会社が 個人向けに発行する最もベーシックなクレジットカード」を意味するものと認めら れること(乙6,7)を併せ考慮すると,段落【0006】〜【0009】の「ホ ワイトカード」は,段落【0002】〜【0005】に記載されたカードであるク レジットカードを意味するものと認められる。 一方で,本件明細書等には「ホワイトカード」がプリペイドカードやデビット カードを含む旨の記載は存在しないから,本件明細書等の「ホワイトカード」には, プリペイドカードやデビットカードは含まれないものと解される。
イ 前記1(1)のとおり,本件明細書等には,段落【0002】〜【000 5】で,従来技術として,クレジットカードについて,ユーザの支払能力などに応\nじて所定期間内で使用可能な金額である「使用限度額」が契約時にある程度固定さ\nれ,使用限度額の引上げなどの変更がなかなかできない,あるいは煩雑な手続が必 要となるという課題があること,先行技術であるクレジットカード管理システムに 関する発明の乙8発明は,ユーザの利用実績により使用限度額を変更できるという ものであるが,同発明によっても,ユーザが他者から送金を受けた場合に使用限度 額を変更することはできないという課題があることが記載され,段落【0006】 で,上記の課題を解決するために,本件発明は,ユーザが他者から送金を受けたこ とにより使用限度額を引き上げることができるシステムを提供することが記載され ており,これらの記載からすると,本件発明における「使用限度額」は,従来技術 における「使用限度額」と同様に,クレジットカードの使用限度額を意味するが, ユーザに対する入金があると所定の手続を経ずに引き上げられるものであると解す るのが相当である。 したがって,本件発明における「使用限度額」は,ユーザが所定期間内に使用 することのできる金額の上限額を意味し,その額は,ユーザとの契約時には,その 支払能力(信用力)に応じて設定され,「ある程度固定される」ものであるが,そ\nの後,ユーザに対する入金があった場合,所定の手続を経ずに引き上げられるもの であると認められる。
ウ 以上のとおり,本件発明における「ホワイトカード」はクレジット カードを意味し,「使用限度額」は,「契約時に設定され,契約時には,ある程度固 定される,所定期間内で使用可能な金額」を意味するものというべきである。\n
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,本件発明の課題について「使用限度額に関しては契約時に ある程度固定されるため,限度額の引上げなどの変更がなかなかできない,あるい は煩雑な手続きが必要となる」という従来技術の課題(段落【0003】)は乙8 発明により解決済みであり,本件発明の課題は,他者からの送金の受金等による ユーザの所持金の増加を速やかに使用限度額に反映させることにある(段落【00 05】)と主張する。 しかし,本件明細書等の段落【0003】と段落【0005】の記載によると, 乙8公報に記載された従来技術は,「予め定められた使用限度額内での利用実績に\n応じて算出変更」することにより使用限度額を変更することを可能にするものであ\nるが,それでは「他者からの送金を受金することなどでユーザの所持金が当該クレ ジットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても,カード会社に逐一連絡など して所定の手続きを経なければそれが使用限度額に反映され」ないという課題を解 決し得ないことから,本件発明は,本件特許請求の範囲に規定された構成を採用す\nることにより,入金を受け付けた旨の情報に基づいて,所定の手続(煩雑な手続) を経ることなく,ホワイトカードの使用限度額を引き上げることを可能としたもの\nと認められる。
このように,乙8発明は,「使用限度額に関しては契約時にある程度固定される ため,限度額の引上げなどの変更がなかなかできない,あるいは煩雑な手続きが必 要となる」という従来技術の課題のうちの一部を「クレジットカードの使用限度額 を利用実績に応じて算出変更する技術」によって解決したにすぎず,本件発明は, 乙8発明により解決できなかった従来技術の「他者からの送金を受金することなど でユーザの所持金が当該クレジットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても, カード会社に逐一連絡などして所定の手続きを経なければそれが使用限度額に反映 されることは無い」という課題を解決したものであるから,控訴人の上記主張は理 由がない。
◆判決本文
原審はこちらです
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.08.17
平成30(ワ)31428 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月30日 東京地方裁判所
(3)ア 第1要件にいう特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請 求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する\n特徴的部分であり,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明 の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲 の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部\n分が何であるかを確定することによって認定される(知的財産高等裁判所平 成27年(ネ)第10014号同28年3月25日判決)。
ここで,本件明細書をみると,従来の技術においては,券情報と発券情報 の2つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送していたため情報量が2倍に なり通信回線の負担が2倍になっていた。本件発明は,このような従来の技 術と異なり,「ホストコンピュータ」において,券情報と発券情報という2つ の情報に基づいて1つの座席表示情報を作成するものであり,それによって,\n端末機へ伝送される情報量が半減されて通信回線の負担が軽減されるとい う効果を奏するものである(【0002】〜【0007】,【0020】)。
このような本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らせば,本件発明に おいて,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であ\nる本質的部分は,「ホストコンピュータ」が券情報と発券情報との2つの情 報に基づいて1つの「座席表示情報」を作成する作成手段を有し,そのよう\nにして作成された「座席表示情報」が「ホストコンピュータ」から端末機に\n伝送される点にあるといえる。 被告システムにおいては,券情報と発券情報との2つの情報に基づいて1 つの情報が作成されるサーバーはなく,したがって,それらの2つの情報に 基づいて作成された1つの情報を端末機に伝送するサーバーもない。そうす ると,本件発明の本質的部分において,本件発明の構成と被告システムの構\ 成は異なる。したがって,被告システムが均等侵害の第1要件を充足するこ とはない。
また,被告システムは,端末機に対して券情報と発券情報という2つの情 報に基づいて作成された1つの情報が伝送されるものではないから,券情報 と発券情報がそれぞれ端末機に伝送されるシステムに比べて通信回線の負 担と端末機の記憶容量及び処理速度を半減するものではない。したがって, 本件発明と同一の作用効果を奏するものではなく,第2要件を満たさない。
イ 原告は,第1要件について,本件発明の特許請求の範囲に記載された構成\nと被告システムの構成の異なる部分は,サーバーと通信回線の個数に関する\n相違であって,本件発明の本質的部分に関係するものとはいえない旨主張す る。
しかし,上記アのとおり,券情報と発券情報とに基づく情報が作成され, そのようにして作成された情報が伝送されるサーバーがあることは,均等侵 害の第1要件にいう本件発明の本質的部分であるといえ,被告システムは, その本質的部分において,本件発明と異なる。
また,原告は,本件発明の作用効果は,車掌が携帯する端末機に表示され\nる各指定座席の利用状況(自動改札通過情報及び発売実績情報の有無)を車 掌が目視で確認できるようにして,車内改札を本来空席であるはずの座席に 座っている乗客に対して従来のように切符の提示を求めるだけで足りるよ うにしたものであり,これにより車内改札の省略化を図るというものであり, 被告システムの作用効果と同じである旨主張する。
しかし,前記3(1)のとおり,本件明細書の記載に照らせば,従来技術と比較した本件発明の効果は,券情報と発券情報がそれぞれ端末機に伝送されるシステムに比べて通信回 線の負担と端末機の記憶容量及び処理速度を半減するところにある。したが って,被告システムが本件発明と同じ作用効果を有するとはいえない。 (4)上記(3)のとおり,被告システムは,少なくとも均等侵害の第1要件,第2要 件を充足せず,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明\nの技術的範囲に属するものであるということはできない。
◆判決本文
本件特許の訂正審判についての審決取消訴訟事件です。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.08.14
平成30(ネ)10085 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
争点2−1(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)
控訴人は,本件明細書の発明の詳細な説明には,構成要件Hに対応する「シ\nフト機能」に係る構\成について,「いったんスルー注文」及び「決済トレー ル注文」と組み合わせた,複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ1回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず,構成要件Hに含まれる「シフト機\n能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたも\nの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば,構\成要件 Hは,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから,特許 法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)に適合する とはいえない旨主張する。
ア そこで検討するに,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載中に は,構成要件Hの「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記\n複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ とを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において,「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから,当該「売り注文情報」は,複数の場合に限らず,一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,1)「シフト機能」につ\nいて,「金融商品取引管理装置1や金融商品取引管理システム1Aにお いて,既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち,「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能\である。この「シ フト機能」による注文は,上述した,「いったんスルー注文」や「決済\nトレール注文」や,各種のイフダン注文(例えば後述する「リピートイ フダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)等に基づいて,新 規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文 や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと(【0078】),2)「シフト機能」は,「相\n場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場 価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」(【0018】)という効果を奏すること,3)「発明の 実施の形態3」は,「この実施の形態3の金融商品取引管理システムに おいては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,「ら くトラ」による注文と組み合わせ,さらに「シフト機能」を行わせる状\n態を示す。」(【0138】)ものであるが,「上記の「シフト機能」\nは,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態2の構成において適\n用することもできる。」こと(【0151】)及び「上記各実施の形態 は本発明の例示であり,本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは,いうまでもない。」こと(【016 4】)の記載がある。
上記1)の記載から,「シフト機能」は,「新規注文と決済注文が少な\nくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文や決済注文が発注される 際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり,シ フトされる先に発注済の注文には,「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構\成が含まれること,先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価\n格帯」をシフトさせる構成のものが含まれることを理解できる。\nまた,上記1)ないし3)の記載から,「シフト機能」は,「相場価格を\n反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し,「いった んスルー注文」,「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文(例え ば・・・「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)」 等の注文方法とは別個の処理であること,「シフト機能」にこれらの各\n種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。 ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には,図35に示す「実施の形態 3」(【0144】ないし【0148】)として,シフト機能に決済\nトレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ, 決済注文S5,S4が約定した後に,元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文B5,B4及び元の売り注文S5,S4と同じ注文価格の売 り注文S5,S4が再度生成されるが,この時点ではシフトは発生せ ず,通常のリピートイフダン注文が繰り返され,その後相場価格が変 動して,S1ないしS3の売り注文価格がトレールし,S1ないしS 3が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると,再度生成 された売り注文S5,S4は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして,S1ないしS5のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は,構成要件Hに含まれる,「シフト機能\」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一\nつであることが認められる。
また,シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には,\n図35において,S2及びS3の売り注文価格がトレールしないため, それぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり,それぞ れ別々に約定し,その場合,実施の形態3の取引例でS5,S4が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に,S3,S2が約定 した段階ではシフトが生じず,その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのS1が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると,複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Hに係る構\成は,本 件明細書の上記記載から認識できるから,本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.08.14
平成30(ワ)4851 特許権侵害差止等請求事件 特許権 令和2年5月28日 大阪地方裁判所
本件拒絶理由通知記載の拒絶理由は明確性要件違反であり,具体的には,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1の記載につき,「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか,その外縁が明確に特定できない」こと,「「第2油路」が具体的に想定できない」こと及び「「流量調整弁」が具体的に想定できない」ことが挙げられている。換言すれば,スイングクランプ,リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載となっていることによって新規性又は進歩性が欠如するとの無効理由は指摘されていないことから,本件第2補正は,こうした無効理由を回避するためにされたものではない。また,明確性要件違反の指摘においても,スイングクランプ,リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載であるが故に不明確とされているわけでもない。 もっとも,上記拒絶理由のうち「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか,その外縁が明確に特定できない」とは,より具体的には,油圧シリンダの具体的な規定がなく,その油室の数が不明であり,そのために,第1油路,第2油路及び流量調整弁の機能ないし役割が不明であるといった問題点を指摘するものである。これは,当業者にとって,クランプ装置のタイプを含む装置の前提的な構\成の不明確さを指摘する趣旨のものと理解されると思われる。
(オ) 原告は,本件第2補正の際に提出した意見書(乙2の2)で,請求項1 に係る補正につき,本件拒絶理由通知での審査官の指摘に対して,「補正後の請求項 1では,「前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダ」と規定し ております。…補正後の請求項1に係る本願発明において,「第1油路」及び「第2 油路」や,両流路の接続部にある「流量調整弁」が,何のために在って何をしてい るのかという点については明確であると思料いたします。よって,ご指摘の記載不 備は解消し得たものと思料致します。」との補足説明をしている。
(カ) 以上の事情を踏まえて本件第1補正から本件第2補正に至る経緯を見る と,客観的,外形的には,原告は,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1の記 載によれば,その構成はスイングクランプとリンククランプいずれのタイプのクラ\nンプ装置も含むものであることを認識しながら,本件拒絶理由通知を受けて行った 本件第2補正により,敢えて補正後の特許請求の範囲にリンククランプのタイプの クランプ装置を含むものとして記載しなかった旨を表示したものと理解される。\nそうである以上,本件においては,本件第2補正においてリンククランプのタイ プのクランプ装置が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特 段の事情が存する。 したがって,被告製品群4〜6は,本件発明との関係で,均等の第5要件を充足 しない。この点に関する原告の主位的主張は採用できない。
ウ 原告の予備的主張について\n
原告は,予備的主張として,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1記載\nの「クランプ用の油圧シリンダ」は「アンクランプ用の油圧シリンダ」(本件第2補 正後の特許請求の範囲請求項3)を含まないとの理解を前提として,本件第2補正 後の特許請求の範囲請求項3は補正前の特許請求の範囲に含まれないものを手続補 正により追加したものであり,請求項3については意識的に除外されたものとはい えないなどと主張する。 しかし,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1記載のクランプ装置は,「クラ ンプ本体に進退可能に装着された出力ロッド」及び「出力ロッドを駆動するクラン\nプ用の油圧シリンダ」等を備えることは記載されているものの,「出力ロッド」が退 入側・進出側いずれに駆動することによってワークをクランプするものであるかを うかがわせる記載はない(なお,この時点での請求項2〜4にも,クランプのタイ プに関係する記載はない。)。このことと,従来技術としてはスイングクランプ及び リンククランプの両タイプが挙げられていることに鑑みれば,本件特許に係る明細 書においては出願当初よりリンククランプのタイプのクランプ装置も除外されてい ないといえることを併せ考えると,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1は, スイングクランプのみならずリンククランプのタイプのクランプ装置をも含むもの と理解される。本件第2補正後の特許請求の範囲請求項1において「クランプ用の 油圧シリンダ」とし,請求項3において「アンクランプ用の油圧シリンダ」とされ たのは,本件拒絶理由通知を受けた対応として,クランプ装置の構成をより具体的\nに特定したことに伴うものと理解することができるから,本件第2補正の前後で 「クランプ用の油圧シリンダ」を異なる意味に解することはなお合理的である。 したがって,原告の予備的主張はその前提を欠くから,これを採用することはで\nきない。
エ 小括
以上より,均等侵害として,被告製品群4及び6は本件発明1の技術的範囲 に属するとはいえず,また,被告製品群5は本件発明3の技術的範囲に属するとは いえない。そうである以上,被告らによる被告製品群4〜6の製造,販売等は,本 件特許権を侵害するものとはいえない。 したがって,被告製品群4〜6に係る原告の被告らに対する製造等の差止請求, 廃棄請求及び損害賠償請求は,いずれも理由がない。
3 争点3(被告製品群7及び8の製造,販売等に係る間接侵害の成否)につい て
(1) 前記(第2の2(4)オ)のとおり,被告製品群7及び8は,被告製品群1〜 3のクランプに取り付けて使用される場合にクランプ装置の生産に用いるものであ る。また,特許法101条2号の趣旨によれば,「発明による課題の解決に不可欠なも の」とは,それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決 されるような部品等,換言すれば,従来技術の問題点を解決するための方法として, 当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について,当該手段を特徴付けている特 有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が,これに該当するものと解される。\n本件発明において,作動油の流量の微調整を容易かつ確実に可能とすることなど\nの課題を解決する直接的な手段となるものは,相対移動可能な弁体部を有する弁部\n材をその構成に含む「流量調整弁」である。このため,「流量調整弁」は,本件発明\nが新たに開示する特徴的技術手段における特徴的な部品等ということができる。被 告製品群7及び8(スピードコントロールバルブ)は,この「流量調整弁」に相当 するものであるから,「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101 条2号)に該当する。
これに対し,被告らは,被告製品群1及び3が本件発明1の構成要件1K及び1Xを 充足せず,被告製品群2が本件発明3の構成要件3K及び3Xを充足しないことから, 被告製品群7及び8は本件発明の課題の解決に不可欠なものではないと主張する。 しかし,前記1のとおり,被告製品群1〜3は本件発明の上記各構成要件を充足す\nる。そうである以上,この点に関する被告らの主張はその前提を欠き,採用できな い。
(2) 被告らが,本件発明が特許発明であることを知っていたことについては,当 事者間に争いがない。 また,被告らは,被告製品群7を被告製品群1及び3の,被告製品群8を被告製 品群2のアクセサリとしてそれぞれ製造,販売していること(甲6,10,11, 乙9,10)に鑑みると,被告製品群7及び8が本件発明の実施品である被告製品 群1〜3に用いられることを知っていたことが認められる。 なお,被告製品群7及び8は,スイングクランプのほか,リンククランプ,リフ トシリンダ,ワークサポートにも使用可能なものである(甲6,10,乙4,5,\n9,10)。
しかし,特許法101条2号の趣旨に鑑みれば,発明に係る特許権の侵害品「の 生産に用いる物…がその発明の実施に用いられること」とは,当該部品等の性質, その客観的利用状況,提供方法等に照らし,当該部品等を購入等する者のうち例外 的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現 に存在し,部品等の生産,譲渡等をする者において,そのことを認識,認容してい ることを要し,またそれで足りると解される。 本件においては,後記6のとおり,被告製品群7及び8に属する製品がスイング クランプと組み合わせて販売される割合が大きいことに鑑みると,これを購入等す る者のうち例外的とはいえない範囲の者が被告製品群7及び8を特許権侵害に利用 する蓋然性が高い状況が現に存在するとともに,被告らはそのことを認識,認容し ていたものといえる。そうである以上,上記事情は本件における間接侵害の成立を 妨げるものではない。 これに対し,被告らは,被告製品群7が本件発明1の実施に,被告製品群8が本 件発明3の実施にそれぞれ用いられることを認識していないなどと主張する。しか し,被告らは,当然に被告製品群1〜3の構成を認識していると考えられるところ,\n被告製品群1〜3が本件特許権侵害を構成する以上,被告製品群7及び8について\nも,本件発明の実施に用いられるものであることを知っていたといえる。この点に 関する被告らの主張は採用できない。
(3) 小括
以上より,被告らが被告製品群7及び8を製造,販売する行為は,本件特許権 の間接侵害(特許法101条2号)を構成する。\n
◆判決本文
関連の審決取消事件です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> ピックアップ対象
2020.08.14
令和1(ネ)10059 特許権 民事訴訟 令和2年3月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「ア 均等侵害が成立するための第1要件にいう本質的部分とは,当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分であり,このような特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備 えていると認められる場合には,相違部分は本質的部分ではないと解される。 そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特 許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲 の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何\nであるかを確定することによって認定されるべきである。 ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているとこ ろが,出願時の従来技術に照らして客観的に不十分な場合には,明細書に記載され\nていない従来技術も参酌して,当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。\n
イ 本件特許出願の審査において,特許庁は,本件各発明は,平成15年 8 月 22日に公開された特開2003−234608号公報(甲30。以下「引用文献 1」という。)等の文献に基づき,当業者が容易に発明し得た旨の拒絶理由通知書 を送付した(乙6)ことから,引用文献1に記載された技術について検討する。
・・・
まず,引用発明1と比較して,本件発明1の本質的部分を検討する。
(ア) 本件発明1の内容は,前記1(2)で判示したとおりであり,その技術 的思想を構成する部分は,仮固定用ホルダの構\成を,可撓性樹脂で成形し,前記給 電用筒状部の外壁面に沿って下方に延びる複数のメインアーム部と,同メインアー ム部に対して下端部にて繋がったサブアーム部とを有し,同サブアーム部の下端部 は,同サブアーム部が外側に拡がるための支点となり,同サブアーム部の上端部は 前記メインアーム部の外側面よりも外方向に突出した係止爪をなし,かつ同係止爪 は上端に向かって肉厚が増加しているものとし,同構成を採用することにより,ア\nンテナ挿入時には,メインアーム部及びサブアーム部の両部材が内側に動くため, より小さい挿入力で取付孔への挿入が可能となり,また,抜け方向に荷重が加わっ\nたときは,車体パネルの内側面に係止爪の上端が当接し,サブアーム部が外側に拡 がるため,抜け力を増大させることができ,仮固定用ホルダの挿入力は小さいまま で,抜け力を大きくすることを可能としたことである。\n一方,本件特許の出願前に公開された引用文献1に記載された引用発明1の内容 は,前記イ(イ)で判示したとおり,固定板付き基板ブラケット9の構成を,円筒状\n突出部の外周面に沿って下方に伸びる複数の側板4を有し,側板4にコ字状の切溝 4eを設け,切溝4eに囲まれた矩形状のバネ片4aの上端が側板4から外側に向 かって離れるものとしたものであり,このうち,側板4は本件発明1のメインアー ム部に,バネ片4aは本件発明1のサブアーム部にそれぞれ相当するものであり, アンテナの挿入時には,側板4及びバネ片4aが内側に撓み,抜け方向に荷重が加 わったときは,ルーフパネル20にバネ片4aの上端部が当接し,バネ片4aが外 側に撓んで仮止めすることになると認められる。
(イ) そこで,本件発明1のうち,引用発明1に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分を検討すると,引用発明1は,抜け方向に荷重が加わった\nときに,サブアーム部に相当するバネ片4a全体が撓むため,十分な抜け力を確保\nできなかったことから,本件発明1は,仮固定用ホルダを可撓性樹脂で成形し,サ ブアーム部の上端部は上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとするこ とにより,抜け方向に荷重が加わったときに,サブアーム部の下端部を回転の支点 として,サブアーム部が外側に拡がるようにし,同下端部でサブアーム部の回転を 受け止めることにより,抜け力を増加させたものと認められる。そして,本件発明 1が,サブアーム部の上端部は上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるもの としたのは,上記のとおりサブアーム部の強度を増すためであると認められる。 以上からすると,本件発明1のうち,引用発明1に見られない特有の技術的思想 を構成する特徴的部分とは,可撓性樹脂で成形されたサブアーム部の上端部は上端\nに向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとし,これにより,抜け方向に荷重 が加わったときに,サブアーム部は,下端部を支点として回転するように外側に拡 がり,下端部において,サブアーム部の上記回転を受け止めて,抜けを防止すると いう部分であると認められる。そして,この部分が本件発明1の本質的部分に当た ることになる。
(ウ) 控訴人は,本件発明6の本質的部分は,「アンテナに抜け方向の荷重 が加わった際に,下端部を支点とした外向きの回転力がサブアーム部に発生するこ とにより,サブアーム部が内側に向かって変位することが防止されるため,サブ アーム部に設けられた係止爪が車体パネルから外れて抜けてしまう(すっぽ抜ける) ことがない」という構成にあると主張する。\nしかし,控訴人が主張する上記の構成は,引用発明1にも見られるから,同構\成 が本件発明1や本件発明6の本質的部分ということはできない。
エ 次に,被控訴人製品が,前記ウで認定した本件発明1の本質的部分を共 通に備えているかについて検討する。 被控訴人製品においては,サブアーム部は,可撓性樹脂で成形されており,車体 パネルに係止するための爪部を備えるが,同爪部は,サブアーム部の中間付近に位 置している(乙1,2,13)ため,その上部のサブアーム部であるフック部が, 抜け方向に荷重が加わったときに,サブアーム部がその下端部を支点として外側に 拡がることを阻止し,そのため,サブアーム部は,その下端部を回転の支点として 外側に拡がることはなく,したがって,同下端部で,サブアーム部の回転を受け止 めることによって抜け力を増大させるものではない。 そうすると,被控訴人製品は,本件発明1の本質的部分を備えているとは認めら れない。
オ 控訴人は,被控訴人製品において,抜け方向の荷重が加わると,サブ アーム部の下端部を支点とした外向きの回転力が発生することにより,サブアーム 部に設けられた爪部が内向きに変位して車体パネルから外れるという事象が防止さ れているから,被控訴人製品は,本件発明6の本質的部分を備えていると主張する。 しかし,前記エのとおり,被控訴人製品においては,抜け方向の荷重が加わり, サブアーム部が外側に拡がろうとしても,同動きはフック部によって阻止されるた め,サブアーム部は,その下端部を回転の支点として外側に拡がることはないから, 被控訴人製品は,本件発明1や本件発明6の本質的部分を備えておらず,控訴人の 上記主張は理由がない。
カ したがって,本件発明1と被控訴人製品との前記の相違点は,本件発明 の本質的部分ではないということはできないから,被控訴人製品は,均等の第1要 件を充足しない。」
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2020.07.17
平成31(ネ)10015 特許権 民事訴訟 令和2年6月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
このように本件明細書には,「発酵原料」として「大豆胚軸」を使用 した場合の発酵処理及び実施例の記載はあるが,一方で,「発酵原料」 として「大豆胚軸抽出物」を使用した場合の発酵処理及び実施例に関す る記載はない。
(エ) 前記(ア)ないし(ウ)によれば,本件明細書には,「本発明」(「大 豆胚軸発酵物」)の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」 とを明確に区別した上で,発酵原料として使用される「大豆胚軸」は, 「含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として,大 豆の産地や加工の有無について制限され」ず,「脱脂処理や脱タンパク 処理に供したもの」も使用することができ,発酵原料にイソフラボンを\n別途添加しておくことにより,得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール 含量をより高めることが可能となることを開示し,他方で,コストが高\nく,エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大 豆胚軸抽出物」は,「本発明」(「大豆胚軸発酵物」)の発酵原料に適 さないことの開示があることが認められる。
ウ 検討
以上の本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書 の記載を前提に検討するに,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)に は,本件発明1の「大豆胚軸発酵物」(構成要件1−C)を定義した記載\nはなく,その発酵原料となる「大豆胚軸」を特定の成分のものに限定する 記載もないが,一方で,本件明細書では,「大豆胚軸発酵物」の発酵原料 として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で,コス トが高く,エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる 「大豆胚軸抽出物」は,発酵原料に適さないことの開示があることに照ら すと,かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は,本件発明1 の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当である。 もっとも,本件明細書には,発酵原料に適さない「大豆胚軸抽出物」の 成分やイソフラボン含量等についての開示はないことは,前記イ(イ)aの とおりである。 しかるところ,大豆胚軸からイソフラボンを含有する成分の抽出処理は,\n一般に,水,アルコール(エタノール等)又は含水アルコールなどの溶媒 を用いた抽出によって行われるが,大豆胚軸から高濃度のイソフラボンを\n含有する「大豆胚軸抽出物」を得るには,このような抽出処理に加え,合 成吸着樹脂を用いた濃縮操作等の精製処理が必要であることは,本件特許 の優先日当時の技術常識であったことが認められる(例えば,甲43の【0 011】,【0012】,甲46の【0002】ないし【0005】,甲 49の【0013】ないし【0015】)。 そして,高濃度のイソフラボンを含有する「大豆胚軸抽出物」は,コス\nトが高く,エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる ことは自明であるから, かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発 酵物は,本件発明1の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと認めるのが 相当である。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2020.07.13
令和1(ネ)10063 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所も,電子メールに設定された複数の電子メールアドレスを個々の 電子メールアドレスに分割し,記憶手段に記憶されている制御ルール等に従 って,電子メールの送出に係る制御内容を決定し,決定された制御内容に従 って電子メールの送信制御を行うとの構成は,本件発明1における本質的部分に該当し,同様に,複数の送信先が設定された電子メールから電子メール\nアドレス単位で個別メールを生成することは,本件発明2における本質的部 分に該当するところ,被告装置はドメインごとに分割するものであるため, かかる構成を有さず,均等の第1要件を充足しないと判断する。その理由は,後記(2)のとおり控訴人の当審における補充主張に対する判 断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第4の3及び6(原判決72 頁20行目から74頁25行目まで,77頁25行目から78頁13行目) 記載のとおりであるから,これを引用する。
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア 控訴人は,本件発明1において,複数の送信先を分割する単位が, 個々の電子メールアドレス単位であることは,本件発明1の課題の解決 をするのにあたり不可欠ではなく,「メッセージ単位」より小さい単位 でかつ,制御ルールに従って送出を制御し得る単位で,複数の送信先を 個々に分割した上で,分割した電子メールの送出に係る制御内容を決定 及び送信制御を行い,上記単位に応じた電子メールの送出制御を行うこ とが,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的な部分であると主張する。\nしかし,本件明細書等1には,「特許文献1に記載の技術においては, 送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断 することができない。そのため,複数の送信先が記載された電子メール に対しては,誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば,その他の送信先に対するメール送信までもが保留,取り消しがされるこ\nととなる。」(段落【0004】),「本発明は上述の問題点に鑑みなさ れたものであり,ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に,宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電\n子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とする。」(段落 【0005】)と記載されている。 「送信先」及び「宛先」はいずれも電子メールアドレスを意味するこ とは前記1のとおりであるから,これらの記載によれば,本件発明1は, 誤送信の可能性がある電子メールアドレスが1つでも含まれていれば,その他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留,取消し\nされることとなることを課題として認識し,その課題に鑑みて,電子メ ールアドレスに応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく 電子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とするものと解さ れる。
このように,本件明細書等1には,誤送信の可能性がないその他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留,取消しされてしま\nうという従来技術である特許文献1の課題に対し,電子メールアドレス に応じた電子メールの送出制御を行うことによって課題を解決しようと することが記載されているのであるから,そのために必須の構成である電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割\nする構成が,本件発明1の本質的部分に含まれないとはいえない。
イ 控訴人は,本件発明1の課題は,従来技術では,本来保留される必要の ない「その他の電子メールアドレス」に対するメール送信が全て保留さ れてしまうことであって,それに比べれば,ドメインに応じた送出制御 を行った場合であっても,少なくとも一部の電子メールアドレスに対す る電子メールの送信が保留されない場合,「電子メールアドレスに応じ た電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出さ せる」効果を得ることができる旨主張する。 しかし,前記1(3)ウ(イ)のとおり,「誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば,その他の送信先に対するメール送信までもが\n保留,取り消しがされることとなる。」(段落【0004】(1))とは, 本来保留される必要のないその他の送信先(すなわち電子メールアドレ ス)に対するメール送信は全てなされるべきであるとの趣旨と解するの が自然である。 また,前記アのとおり,「効率よく電子メールを送出させる」ことは, 電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制御によってもたらされ るものとされている。電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制 御によれば,保留の必要がないその他の電子メールアドレスに対する送 信は全てなされるのであるから,本件発明の効果も同様と解すべきであ って,保留の必要がないその他の電子メールアドレスのうちの一部の電 子メールアドレスに対する電子メールの送信が保留されなくなることで は足りないというべきである。
ウ 控訴人は,文言侵害が否定された場合に,本件明細書等1の課題に記載 された「送信先」を「電子メールアドレス」と読み替えて,課題を認定 し,当該課題から直接的に本質的部分を認定することは,均等侵害の成 否の場面において,文言侵害が否定されることを理由に,均等侵害の成 立が直ちに否定され,均等侵害がその機能を果たさない結果となることから,かかる結果が著しく妥当性を欠く旨主張する。\nしかし,本質的部分の認定は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基 づいて,特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許 発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(大合議判決)。よって,本件明細書等1の記載に基\nづいて,本件発明1が,従来技術である特許文献1のどのような点を課 題として把握し,どのような解決手段を提示し,どのような効果をもた らすものなのかを把握することは,当然なされるべきことであるから, 控訴人の主張は理由がない。
エ 被告装置は,電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレ スごとに分割するという,本件発明1の本質的部分に含まれる構成を有していないから,均等の第1要件を充足しない。\n
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2020.05.11
平成29(ワ)24598 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月26日 東京地方裁判所
原告による測定結果
株式会社東洋環境分析センターが,平成30年2月,原告の依頼によ り,宮崎県食品開発センターが保有するPT−Rを用いて,前記イの記載 に従って,同じロットナンバーの被告製品2について,3回測定した結果 によれば,被告製品2(1ロット)の見掛けタッピング比容積は,いずれ も2.4cm3/g(2.45cm3/g,2.46cm3/g,2.46cm3/g)で あった(甲20の1,20の2)。
オ 被告による測定結果
株式会社住化分析センターが,平成30年2月,被告の依頼により, PT−Xを用いて,前記イの記載に従って,製造時期が異なりロットナ ンバーが異なる5つの被告製品についてそれぞれ1回ずつ測定した結果 によれば,被告製品2(製造時期の異なる5ロット)の見掛けタッピン グ比容積は2.2〜2.3cm3/g(2つの製品について2.2cm3/g, 3つの製品について2.3cm3/g)であった(乙11)。 被告が,平成30年10月頃,宮崎食品開発センターが保有するPT −Rを用いて,前記イの記載に従って,製造時期が異なりロットナンバ ーが異なる5つの被告製品2について,それぞれ3回ずつ測定した結果 によれば,その見掛けタッピング比容積は2.2〜2.3cm3/g(3つ の製品について3回とも2.3cm3/g,1つの製品について2.2cm3/ g,2.2cm3/g,2.3cm3/g),1つの製品について,2.2cm3/ g,2.3cm3/g,2.3cm3/g)であった(乙34)。
(2)本件明細書の特許請求の範囲には見掛けタッピング比容積の測定方法は記 載されていないが,発明の詳細な説明には,前記(1)イのとおり,実施例・比 較例における見掛けタッピング比容積はPT−Rを用いて測定された値であ る旨の記載がある。
原告は,PT−Rを用いて測定した結果(前記(1)エ)によれば,被告製品 2の見掛けタッピング比容積は2.4cm3/gであるから,構成要件1F及び2Fをいずれも充足すると主張する。\nて測定した結果によれば,製造時期の異なる5ロットの被告製品2につき, いずれも見掛けタッピング比容積が2.4cm3/gに達していなかった。その 実験の信用性が否定されることを裏付ける客観的な証拠はない。上記のとお り,5ロットという複数の被告製品2について,それぞれ3回ずつ検査した 結果,いずれも見かけタッピング比容積が構成要件1F・2Fの下限である2.4cm3/gに達していなかったというのであるから,被告製品2は構成要定対象,測定方法による測定結果に照らして,原告の同エの測定結果によっ\nて被告製品2の見掛けタッピング比容積が2.4cm3/gであることを認める に足りない。
・・・
本件発明1及び2は,前記のとおり,2.5N塩酸,15分,沸騰温 度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度(平均重合度) をレベルオフ重合度とするものである(そのような具体的な本件加水分 解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。)。したがって,本件では,本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解さ\nれた後に測定されるレベルオフ重合度について,優先日当時,当業者 が,技術常識に基づいて,発明の詳細な説明に記載された原料パルプの レベルオフ重合度と,原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉 末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題 となるといえる(なお,本件加水分解条件は,レベルオフ重合度を求め るものとして,当該酸濃度温度条件では比較的短時間といえる時間の加 水分解を定めたものであることがうかがえる。)。
ここで,優先日当時,本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合 度について,天然セルロースとそれを加水分解して生成されたセルロー ス粉末とが同じレベルオフ重合度となることを直接的に述べた文献があ ったことを認めるに足りる証拠はない。他方,本件明細書においてレベ ルオフ重合度の説明において現に引用されている文献であり,種々の対 象について本件加水分解条件を含む条件で加水分解をした上で本件加水 分解条件(2.5N塩酸,沸騰温度,15分)を提唱したBATTIS TA論文は,(1)木材パプルについて,温和な加水分解条件での加水分解 を経た後に2.5N塩酸,沸騰という過酷な条件で加水分解した重合度 と,温和な加水分解条件での加水分解を経ずに2.5N塩酸,沸騰温度 という条件で加水分解した重合度を実際に測定して,前者の値が後者の 値より低かったこと,(2)セルロースを加水分解した際には結晶化がされ るという他の複数の研究者による研究成果を紹介した上で,上記(1)等の 実験結果は温和な加水分解は重量減少を伴わない結晶化を誘導すること を示しているようであること,(3)温和な加水分解や過酷な加水分解で起 こるメカニズムを提唱した上で,温和な加水分解を経た後に過酷な加水 分解がされた場合には結晶化された短いセルロース鎖の残渣が保持され るため,温和な加水分解を経ずに過酷な加水分解がされた場合よりもレ ベルオフ重合度が低下すると予想されることなどを述べていた。なお,セルロースの加水分解において再結晶化が起こることは他の文献でも紹\n発明の詳細な説明の実施例2ないし7のセルロース粉末は,前記 のとおり,原料パルプを4N塩酸,40°C,48時間という条件,3N 塩酸,40°C,40時間という条件,3N塩酸,40°C,24時間とい う条件などで加水分解したものであり,天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。 前記のとおり,本件では本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が問 題となるところ,本件加水分解条件を提唱し,本件明細書でも引用してい るBATTISTA論文は,上記のとおり,他の複数の研究者による研究 成果を紹介した上で,本件加水分解条件によるレベルオフ重合度について は,温和な加水分解を経た場合にはその過程を経ていないものに比べて, 値が低下することが予想されると述べていた。その内容とは異なり,本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合度について,天然セルロースと,\nそれを温和な条件で加水分解して生成されたセルロース粉末とが同じレ ベルオフ重合度であるという技術常識があったことを認めるに足りる証 拠はない。 に述べられるレベルオフ重合度は本件加水分解 条件により測定されたものではないし,同文献の著者は,優先日頃におい ても,著者が考える「レベルオフ」するためには本件加水分解条件の時間 では足りないと考えられていた旨述べる(同 )。 また,本件明細書に記載された実施例のセルロース粉末は,原料パル プを加水分解した後,攪拌,噴霧乾燥(液供給速度6L/hr、入口温 度180〜220°C、出口温度50〜70°C)して得られたものであ る。当該セルロース粉末の本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度 の明示的な記載が明細書にない以上は,上記加水分解,攪拌,噴霧乾燥 の工程を経た当該セルロース粉末について,本件加水分解条件下でのレ ベルオフ重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識がある 場合に,当該セルロース粉末のレベルオフ重合度が本件明細書に記載さ れているに等しいといえる。上記の加水分解,攪拌や噴霧乾燥を経たセ ルロース粉末の本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度が原料パルプ のそれとの関係でどのような値になるかについての技術常識を認めるに 足りる証拠はない。 これらを考慮すれば,優先日当時,当業者が,本件明細書に記載され た原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセ ルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じである と認識したと認めることはできない。また,発明の詳細な説明の実施例 は,具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解,攪 拌,噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が,優先日 当時,技術常識に基づいて,記載されている当該原料パルプのレベルオ フ重合度に基づいて,上記具体的な条件で得られたセルロース粉末につ いて,本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することが できたとも認められない。
以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,セルロース粉末 について,本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度の記載があるの に等しいとは認められない。 カ 原告は,非晶質領域が分解されて結晶領域のみが残った状態に達したと きの重合度であるレベルオフ重合度は,途中に原料パルプから本件セルロ ース粉末という加水分解過程を経ると否とに関わらず同じ値となるのであ り,当業者であれば,原料パルプとそこから温和な加水分解によって得ら れる本件セルロース粉末のレベルオフ重合度は等しくなると当然に理解す ることができる旨主張し,また,BATTISTA論文における上記実験 結果における温和な加水分解の条件が,本件の実施例における原料パルプ からセルロース粉末を生成する温和な加水分解の条件と同じものではない ことを指摘する。
しかし,本件においては具体的な本件加水分解条件による加水分解がさ れたセルロースの重合度(平均重合度)が問題となる。本件加水分解条件 を提唱し,発明の詳細な説明でも引用されるBATTISTA論文が,本 件加水分解条件によるレベルオフ重合度について前記のように述べていた ところ,優先日当時,そこに記載されているのと異なる内容の技術常識が あったことを認めるに足りる証拠はない。また,BATTISTA論文 は,セルロースを加水分解した際には結晶化がされるという他の複数の研 究者による研究成果を紹介した上で,前記の予想をしているのであり,そこに記載されているのと異なる技術常識があったことを認めるに足りる証\n拠がない本件で,BATTISTA論文においてされた実験での温和な加 水分解の条件が,本件の実施例における原料パルプから粉末セルロースを 作成する加水分解の条件と全く同じものではないことは上記の結論を直ち に左右するものではない。
なお,原告は,実験をした結果,原料パルプを本件加水分解条件で加水 分解したときの平均重合度と,当該原料パルプを実施例2と同じ加水分解 条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解し たときの平均重合度は実質的に同じであったとして,平成30年8月頃に 測定された結果を記載した平成31年3月20日付け報告書(甲56の 1)を提出し,また,上記でセルロース粉末を得る際の写真やセルロース 粉末を得た際に80°Cの熱風を当てる工程を含む24時間の乾燥処理をし たことなどが記載された同年4月9日付け報告書(甲57)を提出する。 しかし,本件では,優先日当時,本件明細書に記載された加水分解,攪 拌,噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について,本件加水分解条 件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が 問題となるところ,上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認める ことはできない。
キ 以上によれば,本件差分要件は,粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるとこ ろ,明細書の発明の詳細な説明には,実施例について,粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく, また,優先日当時の技術常識によっても,それが記載されているに等しい とはいえない。したがって,本件明細書の発明な詳細には,本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。
そうすると,本件明細書の発明な詳細において,特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえ\nない。 以上によれば,本件発明1及び2は,発明の詳細な説明の記載により当業 者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないから,特 許法36条6項1号に違反する。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.04. 2
令和1(ネ)10082 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
控訴人は,本件発明1における構成要件E及びFの「フリップフロップ現象発生用軸体」について,「フリップフロップ現象を発生させる軸体を意味する。」との原判決の判断には誤りがあると主張する。\nしかし,本件発明1における構成要件E及びFの「フリップフロップ現象発生用軸体」は,その文言からフリップフロップ現象を発生させる軸体を意味することは\n明らかである。また,本件明細書を見ても,本件発明1はクーランド液が「フリッ プフロップ現象発生用軸体」を通過することによってフリップフロップ現象を発生 させるなどして,その課題を解決するものである(本件明細書の【0006】, 【0007】,【0041】〜【0045】)から,「フリップフロップ現象発生 用軸体」がフリップフロップ現象を発生させる軸体であることは明らかである。 したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 控訴人は,本件明細書の【0037】は,電子回路の用語を参考に記載 しているだけであるのに,原判決は,本件発明1が「フリップフロップ現象」を解 決原理としていると誤解していると主張する。 しかし,本件明細書の【0037】の記載が,電子回路の用語に基づく参考記載 にすぎないと認めることができないことは,原判決の「事実及び理由」の第4の2(1)イ(カ)bの通りである。
(1) また,上記アのとおり,本件発明1は,「フリップフ ロップ現象」を解決原理としているものである。 したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 「フリップフロップ現象」の意味について
ア 控訴人は,本件明細書の【0011】,【0043】及び【0007】 の記載によると,フリップフロップ現象とは,「フリップフロップ現象発生用軸体 を通過することにより当該現象の結果として『クーラント液等』が『乱流となり無 数の微小な渦を発生』した状態」を指すことを基本としていると主張する。 しかし,本件明細書の【0037】に,「フリップフロップ現象(フリップフロ ップ現象とは,流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象)」と 記載されている上,本件各発明と共通する技術分野において,本件特許出願前に 「フリップフロップ現象」の語が,おおむね,流体の流れの周期的な振動ないし方 向変換を意味するものとして使用されていること(原判決の「事実及び理由」の第 4の2(1)イ(ウ))からすると,本件発明1におけるフリップフロップ現象は,基本 的には,(1)「流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象」を意味 すると解釈することができ,(2)「クーラント液等」が「乱流となり無数の微小な渦 を発生」した状態を指す語としての使用は,上記(1)の意味におけるフリップフロッ プ現象の発生を前提とした,派生的な使用と位置づけられるべきである。控訴人が 指摘する本件明細書の【0011】,【0043】及び【0007】の記載は,こ の判断を左右するものではない。
イ 控訴人は,本件特許の出願当時の当業者の理解について主張する。 まず,乙14〜20は,いずれも公開特許公報であるが,これらの特許において は,A及びBのほか,C(乙16),D(乙17),E(乙18,20),F(乙 19)も共同発明者とされていることが認められるから,単に,A及びBの2名の 研究者,発明者がフリップフロップ現象を「流体の流れの周期的な振動ないし方向 転換を意味するもの」として使用しているとは認められない。 また,控訴人は,本件発明1の構成要件Dの記載によると,当業者は,本件明細書の【0037】の括弧内の記載の流れ(流体の流れる方向が周期的に交互に方向\n変換して流れること)が生じないことを理解すると主張する。 しかし,本件発明1の構成において,ひし形凸部がフリップフロップ現象発生用軸体の軸心に対してどのような傾きをもって設置されているかは特定されておらず,\n上記軸心に対してひし形凸部が傾きを持っていて非対称となっているかは明らかで はないから,当業者が,本件明細書の記載や,「フリップフロップ現象」の語につ いての当業者の一般的な理解に反して,本件明細書の【0037】の括弧内記載の 流れ(流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象)が生じないこ とを理解すると認めることはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2020.03.25
平成28(ワ)4815 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年1月20日 大阪地方裁判所
特許法102条2項は,民法の原則の下では,特許権侵害によって特許権者 が被った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発生及び額,こ れと特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなければならないところ,そ の立証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の填補がされないという不都合が 生じ得ることに照らして,侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは,そ の利益の額を特許権者の損害額と推定するとして,立証の困難性の軽減を図った規 定である。このような趣旨に鑑みると,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為 がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在する場合には,同項の 適用が認められると解すべきであるとともに,同項所定の侵害行為により侵害者が 受けた利益の額とは,原則として,侵害者が得た利益全額であると解するのが相当 であって,このような利益全額について同項による推定が及ぶと解される。
(イ) 証拠(甲13)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,被告による本件特許権 侵害行為の期間(平成20年〜平成28年)において,スクリュ圧縮機に相当する 圧縮機ユニット又はスクリュ圧縮機に凝縮器を備えたものに相当するコンデンシン グユニットである原告各製品を製造し,プラント業者等に販売していたことが認め られる。 他方,証拠(乙39,78,81,82,85,93,99,110)及び弁論 の全趣旨によれば,被告は,平成20年〜平成28年にかけて,油冷式スクリュ圧 縮機である被告製品2−2及び2−3が組み込まれたスクリュ式ガス圧縮システム であるNewTonシステムを使用した冷凍・冷蔵プラントである被告製プラントを販 売した一方,NewTonシステムや被告製品2−2及び2−3を,国内においては別 個独立に販売することはなかったこと(なお,国外向けには,被告のグループ会社 に単体又は単独で販売し,当該グループ会社がシステムを完成させて顧客に販売す ることはあった。)が認められる。 このように,被告は,基本的には,油冷式スクリュ圧縮機である被告製品2−2 及び2−3が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントを販売する という形で本件特許権侵害行為を行っているから,本件特許権侵害行為における侵 害品は,上記NewTonシステムとするのが相当である。 そして,NewTonシステムと原告各製品が組み込まれたシステムとは,上記のと おり,冷凍・冷蔵プラントの需要者を需要者とする点で共通する以上,NewTonシ ステムと原告各製品の需要者も,その面では共通する部分があるといえる。 したがって,本件においては,原告に,被告による本件特許権侵害行為がなかっ たならば利益が得られたであろうという事情が存在するといえることから,特許法 102条2項の適用が認められる。
(ウ) これに対し,被告は,原告各製品がスクリュ圧縮機等であるのに対し,被告 が販売するのは被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステムを使用し た被告製プラントであることを指摘して,特許法102条2項の適用は認められな いと主張する。 しかし,被告指摘に係る事情は,要するに特許権者である原告と侵害者である被 告との間の業務態様の相違(ひいては市場の非同一性)を指摘するものであるとこ ろ,このような事情を考慮しても,原告各製品と被告製品2−2及び2−3とは, 上記(ア)のような形で市場においてなお競合関係にあると見るのが相当であるから, 特許法102条2項の適用を否定すべき事情とはいえない。被告指摘に係る当該事 情は,同項に基づく損害額の推定を覆滅する事情として考慮すれば足りる。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額
(ア) 侵害者がその侵害の行為により受けた「利益の額」(特許法102条2項)は, 侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりそ の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ り,その主張立証責任は特許権者側にあると解される。 前記アのとおり,本件における侵害品は被告製品2−2及び2−3が組み込まれ たNewTonシステムであるから,本件特許権侵害行為により被告が受けた「利益の 額」は,その売上高から,被告においてNewTonシステムの製造販売に直接関連して 追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額を算定するのが相当である。 これに対し,被告は,本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であること, 原告自身が侵害品を圧縮機として特定していること,NewTonシステムから圧縮機だ けを分離可能であることなどを指摘して,本件の侵害品は,NewTonシステムではな く,圧縮機本体を中核とする被告製品2−2及び2−3であると主張する。 しかし,前記アのとおり,本件の侵害品はNewTonシステムとすることが相当であ り,このことは,本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であることなどに より左右されない。NewTonシステムから圧縮機を物理的に分離可能であるとしても,\n前記アのとおり,被告においては基本的にこれを別個独立に販売しておらず,この 部分の譲渡による利益を直接的に観念し得ない以上,同様であり,被告製品2−2 及び2−3がNewTonシステムの一部分であることは,損害額の推定を覆滅する事情 として考慮すれば足りる。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
(イ) NewTonシステムの販売台数
証拠(乙85,93,110)及び弁論の全趣旨によれば,被告が販売した NewTonシステムの販売台数は,別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜 「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「NewTon台数」欄に各記載のとおりであ ることが認められる。
b これに対し,被告は,被告が販売したNewTonシステムのうち,本件特許権の 存続期間中に受注し,存続期間満了後に製造を終えて納入したものについては,本 件特許権の存続期間中に,存続期間満了後に行われた適法な譲渡についての申出が\n行われたにすぎないから,本件特許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にすべ きではないと主張する。 しかし,被告は,本件特許権の存続期間中に「譲渡の申出」を行った上で受注し\nており,この時点で顧客との間の請負契約が成立している以上,製造及び納入の完 了が本件特許権の存続期間満了後であったとしても,これによる原告の損害は,な お本件特許権の存続期間中の侵害行為である「譲渡の申出」と相当因果関係にある\n損害というべきである。そうすると,これに係る「譲渡」による販売分も,本件特 許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にするのが相当である。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
(ウ) NewTonシステム1台ごとの売上額
a NewTonシステムは,前記ア(イ)のとおり,基本的に冷凍・冷蔵プラントとは 別個独立のものとして販売されていないものの,証拠(乙39,92,110)及 び弁論の全趣旨によれば,被告は,被告製品2−2及び2−3が組み込まれた NewTonシステムの「定価」を設定し,そのNewTonシステムを使用した被告製プラ ントを販売するに当たって,当該「定価」を見積書に記載するなどして顧客に対し 見積りを示した上で,被告製プラントを販売していることが認められる。 そうすると,NewTonシステム1台ごとの売上額を算定するに当たり,当該「定 価」に依拠することには合理性がある。
他方,証拠(甲23,乙100,119)及び弁論の全趣旨によれば,被告は, NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売に当たり,「出精値引」などと して,冷凍・冷蔵プラントを構成する部品価格の合計額から値引きして販売する例\nがあったことが認められる。もっとも,全ての取引において値引きが行われたこと を認めるに足りる事情はなく,また,プラントを構成するいずれの部品が値引き対\n象とされたかも不明であるから,上記売上額の算定に当たり値引き分を考慮するこ とは合理的でない。 以上を踏まえると,証拠(乙39)及び弁論の全趣旨によれば,NewTonシステ ム1台ごとの売上額は,別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTon システムの利益額算定表(4)」の「定価(単価)」欄に各記載のとおりであると認め られる。 これに対し,被告は,NewTonシステム1台ごとの売上額は,その実質的な販売 価格に相当する●(省略)●により算定すべきであると主張する。 しかし,証拠(乙39,92,93)及び弁論の全趣旨によれば,NewTonシス テムの●(省略)●は,被告の製造部門が販売部門に販売処理手続を行う際の設定 される価格にすぎず,被告は,この●(省略)●を上回る価格を「定価」として設 定した上で,NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売していることが認 められる。すなわち,●(省略)●「定価」においてこれが反映されているものと 理解される。そうすると,顧客に対する関係では,●(省略)●は実質的な販売価 格とはいえない。 したがって,NewTonシステム1台ごとの売上額の算定に当たりその●(省略) ●を基礎とすることは合理性を欠き,相当でない。この点に関する被告の主張は採 用できない。
b 593番代替機及び6048番転用機について
証拠(乙99)及び弁論の全趣旨によれば,別紙「NewTonシステムの利益額算 定表(5)」の対象となっている593番代替機は,106番機の代替機として,顧客 に無償で譲渡されたことが認められる。そうすると,106番機と593番代替機 の販売は一連の取引によるものといえる。このような経緯を踏まえると,106番 機と593番代替機の販売については,106番機1台分の売上額●(省略)●円 をもって2台合計の売上額として算定するのが相当である。 また,証拠(乙99)及び弁論の全趣旨によれば,別紙「NewTonシステムの利 益額算定表(6)」の対象となっている6048番転用機は,同一の顧客に対して61 8番機2台と共に合計3台として納品されたこと,この取引におけるNewTonシステ ムの代金は2台分の代金とされたことが認められる。このような経緯を踏まえると, 2台分の売上額である●(省略)●円(●(省略)●円×2)をもってこれら3台合 計の売上額として算定するのが相当である。 以上に反する原告の主張は採用できない。
(エ) NewTonシステム1台ごとの経費
a 前記(ア)のとおり,控除すべき経費は,侵害品の製造販売に直接関連して追加 的に必要となったものをいい,例えば,侵害品についての原材料費,仕入費用,運 送費等がこれに当たる。これに対し,例えば,管理部門の人件費や交通・通信費等 は,通常,侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たら ない。
b 控除すべき経費
(a) 製造原価
証拠(乙39,93,110)及び弁論の全趣旨によれば,NewTonシステム1 台ごとの製造原価は,別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTonシ ステムの利益額算定表(4)」の「製造原価(単価)」欄に各記載のとおりであること が認められる。
(b) その余の経費
被告は,上記製造原価のほかに,被告製品2−2及び2−3が組み込まれた NewTonシステムの製造工場に係る間接人件費並びに販売費及び一般管理費を控除 すべき旨を指摘する。 まず,間接人件費についてみると,間接人件費は,正に管理部門の人件費である ところ,被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステムの製品の製造 販売に直接関連して,間接人件費に相当する費用が追加的に発生したと見るべき事 情は見当たらない。そうすると,被告製品2−2及び2−3が組み込まれた NewTonシステムの製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず, 控除すべき経費に当たらない。 次に,販売費及び一般管理費についてみると,証拠(乙75,84,109)及 び弁論の全趣旨によれば,上記(a)の製造原価には,社内加工費及び艤装作業費が含 まれていることが認められるところ,これを除くと,証拠(乙78,101)及び 弁論の全趣旨によっても,被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシス テムの製品の製造販売に直接関連して,販売費又は一般管理費に相当する費用が追 加的に発生したと見るべき事情は見当たらない。そうすると,被告指摘に係る販売 費及び一般管理費は,被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステム の製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず,控除すべ き経費に当たらない。 したがって,被告の上記指摘は当たらない。
(c) 被告の主張について
そもそも被告は,最小二乗法を用いて限界利益率を算定するのが管理会計学上確 立した方法であるとして,本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額を算定 するに当たっても,最小二乗法を用いるのが合理的であると主張する。 しかし,前記(ア)のとおり,特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受 けた利益の額として算定すべき額は,侵害者の侵害品の売上高から,侵害者におい て侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要とな った経費を控除した限界利益の額であり,被告主張に係る管理会計学上の限界利益 の額とは必ずしも一致しない。また,算定の目的を異にする以上,侵害者が受けた 「利益の額」(特許法102条2項)の算定に当たり,管理会計学上の限界利益の 額の算定方法である最小二乗法を用いないとしても,不合理であることにはならな い。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
ウ 推定の覆滅について
(ア) 基礎となる事情
a NewTonシステム及び被告製品2−2及び2−3等について
(a) NewTonシステムの特徴及び販売促進活動
NewTonシステムは,平成19年にNewTon3000が商品化され,平成20年以降, 被告製プラントに使用される形で販売されており(甲8の3,乙45),基本的に, 冷凍・冷蔵プラントとは別個独立のものとしては販売されていない。被告製品2− 2及び2−3のみならず,被告製品2は,いずれもNewTonシステム専用の圧縮機で あり(甲3),NewTonシステムを使用した被告製プラントを購入する際には,必然 的に購入することになるところ,これらも,NewTonシステムと同様に,基本的に別 個独立のものとして販売されていない。また,NewTon3000は,IPMモーターを 搭載することなどにより,従来式に比べて20%の省エネを実現するとされ,発売 開始当初は年間200台,10年後には年間800台の販売を目標にしていた(乙 45,116)。 被告は,その後もNewTonシステムの開発を継続し,平成24年にはチルド専用の NewTonC,フリーザー専用のNewTonF等のシリーズ展開が行われ,平成28年ま でに累計●(省略)●台以上を販売した。さらに,被告は,平成28年7月,省エ ネ性を保ちつつ,冷媒充填量の削減,メンテナンス性の向上及び小型・軽量化を達 成したフリーザー専用の機種として,F-300,F-600等の販売を開始した(甲8の3, 乙45)。
NewTonシステムは,被告自ら開発したIPMモーターを搭載することなどによっ て,より高度な経済性と省エネルギー性を実現する点,令和2年に全廃されるフロ ン冷媒対策として,自然冷媒であるアンモニアで二酸化炭素を冷却するという間接 冷却方式を採用するとともに,アンモニアを機械室に閉じ込める構造によりその安\n全な利用を可能とし,さらに,漏洩センサー等を装備するなどしてアンモニアが漏\n洩しても素早い対応が取れるようにしている点,コンパクトなユニット設計を採用 することで導入を容易としている点,遠方監視システム及び保全診断システムなど 24時間365日のサポート体制を設けている点等に特徴があるとされ,これらの 点が強調された形で販売促進活動が行われていた(甲8の3,乙38,45)。 なお,NewTonシステムや被告製品2−2及び2−3の宣伝広告物には,本件明細 書記載の本件発明の作用効果に直接言及し,又はこれを具体的にうかがわせる記載 は見られない(甲3,8の3,乙38,66の1)。
(b) NewTonシステムを導入した業者によるNewTonシステムについての評価 被告は,その作成に係る「Customer’s Point of View」と題する記事において, NewTonシステムを導入した顧客の導入の動機,導入後の成果等を紹介していると ころ,これには,以下のような記載がある。
・・・
(b) 原告各製品の取扱業者による販売促進活動
・・・・
(イ) 検討
a 前記認定のとおり,被告は,基本的には,油冷式スクリュ圧縮機である被告 製品2−2及び2−3を独立して販売しておらず,また,これらを組み込んだ NewTonシステムについても同様であり,被告製品2−2及び2−3を組み込んだ NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売している。他方,原告は,スク リュ圧縮機又はこれに凝縮器を付加した原告各製品を販売しているにとどまり,プ ラントという単位でみると,「セットメーカ」などといわれる別の業者が需要者に 対して提案するパッケージに組み込まれて販売されるという関係にある。このよう に両者の業務形態が大幅に異なることは,本件の侵害品であるNewTonシステムへ の需要と原告各製品への需要とが質的に異なる面があることをうかがわせる。この ため,仮に被告製品2−2ないし2−3を組み込んだNewTonシステムが販売され なかったとしても,原告各製品のいずれかが被告製品2−2又は2−3に直接代替 されることは考え難い。他方,そのような場合に,被告製品2−2及び2−3の譲 渡数量に対応する需要の全部又は一部が原告各製品の組み込まれたシステムを使用 したプラントに向かうことはあり得ることから,その場合は,結果的に,上記需要 が原告各製品に向かったことになる。もっとも,原告は,プラントを構成する圧縮\n機を販売するにとどまり,プラント全体の構成及び価格の決定や需要者に対する販\n売促進活動において及ぼし得る影響力には限りがあると思われる。 以下では,このような観点も踏まえて,推定覆滅の有無及び程度を検討する。
b 被告製品2−2及び2−3は,本件発明の技術的範囲に属するものである以 上,基本的には本件発明の作用効果を奏すると考えられるところ,被告製品2−2 及び2−3において,本件発明の作用効果を奏していないという事情はうかがわれ ない。この点,被告は,被告製品2−2及び2−3が本件発明の作用効果を奏する ものではない旨主張するが,採用できない。 もっとも,本件発明の作用効果は,スラスト軸受の負荷容量を大きくすること, バランスピストンの受圧面積を大きくすること,逆スラスト荷重状態の発生をなく すことなど,単純かつコンパクトな構造で,振動,騒音を低減させることができる\nというものであり,技術的にはさておき,本件発明の実施品ないしこれを組み込ん だシステムの経済的価値に強いインパクトを及ぼすような性質のものとは必ずしも いえない。このことは,被告製品2−2及び2−3につき,被告がその販売促進活 動において本件発明の作用効果に直接的に言及していないこと,NewTonシステム に対する外部的な評価においても,本件発明の作用効果に直接的に関わるものは見 当たらず,これを示唆するものもないこと,特許権者である原告自身も,スクリュ 圧縮機等である原告各製品において本件発明を実施していないことによっても裏付 けられる。そうすると,本件発明の作用効果それ自体には,それほど強い顧客吸引 力はないと見るのが相当である。
また,弁論の全趣旨によれば,NewTonシステムは被告製プラントの顧客吸引力 の中核を成す部分であり,被告製品2−2及び2−3は,NewTonシステムを稼働 させるために不可欠な部品であることが認められる。そこで,NewTonシステムの 顧客吸引力を検討すると,被告は,NewTonシステムの販売促進活動において,省 エネ,安全性,サポート体制等を特徴とするものであるとの点を強調している。し かも,被告が強調するNewTonシステムのこれらの特徴は,表彰の受賞理由とされ,\nまた,その導入の動機となり,現にその実績も上がっているとされるなど,第三者 からも積極的に評価されていることがうかがわれる(なお,原告は,省エネや安全 性が本件発明の作用効果であるとも主張するけれども,NewTonシステムにおける 省エネや安全性はIPMモーターや間接冷却方式を採用するなどしたことによるも のであり,本件発明の作用効果とは無関係と見られることから,この点に関する原 告の主張は採用できない。)。
c 被告製品2−2及び2−3の製造原価がNewTonシステムの製造原価に占め る割合は,被告製品2−2及び2−3の技術的・商業的価値を直接的に反映したも のではないが,これを推し測る一事情とはなるところ,被告製品2−2及び2−3 がNewTonシステムを可動させるために不可欠な部分であるといっても,NewTonシ ステムの製造原価における被告製品2−2又は2−3の製造原価の割合は,●(省 略)●にとどまる。
d NewTonシステムを使用した被告製プラントとそれ以外の同様のプラントの 販売実績は,アンモニア/二酸化炭素冷媒・冷凍設備の冷凍機用途の油冷式スクリ ュ圧縮機市場が事実上被告と原告の二社寡占状態であることに鑑みると,原告及び 被告の各製造に係る圧縮機の納入実績におおむね対応するものと推察されることか ら,NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売実績の方が右肩上がりであ る●(省略)●。また,被告製プラントで使用されるNewTonシステムに組み込ま れる圧縮機として被告の製造に係るもの以外のもの(おのずと,原告の製造に係る 製品がその候補となる。)が組み込まれるという事態は考え難い。そうすると,被 告が非侵害品を販売していたり,販売することが容易であったりすれば,仮に被告 製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステムが販売されなかったとして も,需要の多くは被告の製造に係る非侵害品等を組み込んだNewTonシステムを使 用したプラントに向かったであろうと考えるのが合理的である。 そして,被告は,被告製品2−2及び2−3以外にも,本件発明を侵害しない NewTonシステム専用品として,被告製品2−1を製造しており,これによって被 告製品2−2及び2−3に代替することが考えられる。なお,原告は,被告製品2 −1が組み込まれたNewTonシステムの販売実績が少なかったことを指摘するけれ ども,現に納入実績がある以上,需要者の需要を満たすものである限り,被告製品 2−1による代替に需要が向かう可能性を否定することはできない。\nまた,被告は,本件特許権侵害行為当時,被告製品2以外にはNewTonシステム 専用の油冷式スクリュ圧縮機を製造していなかったものの,弁論の全趣旨によれば, NewTonシステムにおいて,本件特許権の侵害を回避するために,例えば油ポンプ を加えて加圧流路を設けることについての物理的な制約はさほどなく,また,コス ト的にも問題とすべき程度に至るとは見られない。そうすると,被告製プラントを 欲する需要者の要望に対し,既存機種をベースとしたカスタマイズ等の形で対応し, 本件特許権侵害を回避することは比較的容易であったとうかがわれる。実際には, 本件特許権の非侵害品であるNewTonシステム専用の圧縮機としては被告製品2− 1しかなく,また,上記カスタマイズといった対応も取られなかったとはいえ,推 定を覆滅すべき事情としては,この点も考慮するのが合理的である。この点につき, 原告は,競合品として考慮できるのは現実に市場に存在した製品に限られると主張 するが,上記のとおり,これを採用することはできない。
e 被告は,被告のNewTon事業の限界利益率が,原告の圧縮機事業の限界利益 率を上回ることを前提に,特許法102条2項により算定された利益の額が,特許 権者である原告がその実施能力に基づき得られたであろう利益の額を上回る場合は,\nその限度で覆滅されると主張する。 しかし,仮に被告のNewTon事業の限界利益率が原告の圧縮機事業の限界利益率 を上回るとしても,それをもって原告の圧縮機事業の実施能力が被告のNewTon事 業の実施能力に劣ることを意味するものではないから,被告の上記主張は,その前\n提を欠く。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
f 以上の事情を総合的に考慮すると,本件においては,被告製品2−2及び2 −3が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントの販売がなかった 場合に,これに対応する需要の全てが原告各製品やこれを組み込んだスクリュ圧縮 機,更にはこれを使用したプラントに向かったであろうと見ることに合理性はなく, むしろ,そのような需要はごく限られると考えられる。そうすると,本件では,9 割の限度で,特許法102条2項による推定を覆滅するのが相当である。 この点に関する原告及び被告の各主張は,いずれも採用できない。
エ 以上によれば,原告の逸失利益の額は,別紙「損害額算定表(裁判所認定)」\nの(3)欄のとおり,合計12億5428万1900円であると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.03.13
平成29(ワ)27238 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年2月28日 東京地方裁判所
本件では,本件LED又はその製造方法が特許発明の技術的範囲に属するということだけでなく,白色LEDはそれのみで販売の対象となるものであり,原告は白色LEDの製造,販売を行っていることなどから,特許法102条3項の金額の算定に当たって,まず,上記の平均的な価格の24個分の価格に,主として本件特許権1の侵害が問題 となる平成27年10月までの期間については5パーセントを乗じ,本件特許 権1に加えて本件特許権3(登録日平成27年10月23日)の侵害も問題と なる平成27年11月以降の期間(なお,本件発明2と本件訂正後発明3の内 容に照らし,損害の算定に当たり本件特許権2(登録日平成28年12月16 日)の侵害については特に期間を分けて考慮することをしない。)については 8パーセントを乗じると,それぞれ,10.80円及び17.28円となる(2 16円×5パーセント=10.80円 216円×8パーセント=17.28 円)。
そして,本件で特許権の侵害となるのは本件LEDを使用した被告製品の販 売であること,本件LEDはデジタルハイビジョンテレビである被告製品にと り不可欠のものであり,その機能,性能\において重要な役割を果たしていると いえること,原告の白色LEDの市場におけるシェア,原告が主張するライセ ンスについての方針,その他本件に現れた諸事情を考慮し,本件において,被 告製品1及び2を通じ,特許法102条3項の実施に対し受けるべき金銭の額 は,被告製品1台当たり,消費税相当額を含めて,平成27年10月までの期 間については,20円をもって相当であると認め,平成27年11月以降の期 間については,30円をもって相当であると認める。
以上のとおり,本件において,原告が実施に対し受けるべき実施料として被 告製品1台当たり,20円又は30円とするのが相当であるところ,これらは, それぞれ,被告製品の平均的な販売価格の0.058パーセント又は0.08 7パーセントである(20円÷3万4129円≒0.00058 30円÷3 万4129円≒0.00087)。これらに基づき,特許法102条3項に基づ く損害額は,以下のとおり,1645万6641円とするのが相当と認める。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.03. 9
令和1(ネ)10042 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年2月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
◆公報
該当特許は無効審判もありますが、2020年1月に、特許は有効と判断されています(無効2018-800140)。
3 争点2(均等論)について
控訴人は,仮に本件発明の構成要件Hは「社会保障給付」が「財源措置(C\n2)」に含まれる構成であると解した場合には,被告製品においては,「社会\n保障給付」が,「財源措置(C2)」に含まれておらず,「純経常費用(C1)」
に含まれている点で本件発明と相違することとなるが,被告製品は,均等の第
1要件ないし第3要件を充足するから,本件発明の特許請求の範囲に記載され
た構成と均等なものとして,本件発明の技術的範囲に属する旨主張するので,\n以下において判断する。
(1) 前記2(2)認定のとおり,被告製品は,少なくとも構成要件B3及びHを\n充足するものと認められないから,被告製品は,構成要件Hの構\成以外に,
構成要件B3の構\成を備えていない点においても本件発明と相違するものと
認められる。
しかるところ,控訴人の主張は,被告製品に構成要件B3の構\成について
も相違部分が存在し,被告製品と本件発明は構成要件B3及びHにおいて相\n違することを前提とするものではないから,その前提において理由がない。
(2)ア 次に,被告製品の第1要件の充足性について,念のため判断する。
本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び前記1(2)認定の本件
明細書の開示事項を総合すれば,本件発明は,国民が将来負担すべき負債
や将来利用可能な資源を明確にして,政策レベルの意思決定を支援するこ\nとができる「財務諸表を作成する会計処理のためのコンピュータシステム」\nを提供することを課題とし,この課題を解決するために「純資産の変動計
算書」(「処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)(C1〜C4)」)
を新たに設定し,当該年度の政策決定による資産変動を明確にできるよう
にしたことに技術的意義があり,具体的には,構成要件B1ないしIの構\
成を採用し,純資産変動額や将来償還すべき負担の増減額を「処分・蓄積
勘定(損益外純資産変動計算書勘定)(C1〜C4)」に表示し,当該年\n度の政策決定による資金変動を明確にすることができるようにしたことに
より,国民の資産が当期の予算措置で増えるのか又は減るのか,また,そ\nの財源の内訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのかを一
目で知ることができ,政策決定者は純資産変動額を勘案して政策を遂行す
ることができるという効果を奏するようにしたこと(【0002】,【0
005】,【0007】ないし【0010】,【0021】,図1)に技
術的意義があるものと認められる。
そして,本件発明の上記技術的意義に鑑みると,本件発明の本質的部分
は,「資金収支計算書勘定記憶手段及び閉鎖残高勘定(貸借対照表勘定)\n及び損益勘定作成・記録手段」から,国家の政策レベルの意思決定を記録
・会計処理するために,「処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)
(C1〜C4)」を作成・記録する損益外純資産変動計算書勘定作成・記
録手段を備え(構成要件B3),損益外純資産変動計算書勘定作成・記録\n手段の記録は,その期における損益外の純資産増加(C3,C4)と純資
産減少(C1,C2)の2つで構成され,損益勘定(行政コスト計算書勘\n定)の収支尻(貸借差額)である「純経常費用(B7)」が処分・蓄積勘
定(損益外純資産変動計算書勘定)の「純経常費用(C1)」に振替えら
れ(構成要件F),「処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)」\nの貸方と借方の差額(収支尻)が,「当期純資産変動額(C5)」という
形で,最終的には「閉鎖残高勘定(貸借対照表勘定)」の「純資産(国民\n持分)(B4)」の部に振り替えられて,「閉鎖残高勘定(貸借対照表勘\n定)」の借方(左側)と貸方(右側)がバランスし(構成要件G),「処\n分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)」の借方側(勘定の左側)
の「財源措置(C2)」は,具体的には社会保障給付やインフラ資産を整
備した際の資本的支出のような損益外で財源を費消する取引を指し(構成\n要件H),処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の貸方側(勘
定の右側)の「資産形成充当財源(C4)」は,財源措置として支出がさ
れた場合,財源は費消されるが,その一部分は,インフラ資産のように将
来にわたって利用可能な資産形成に充当されるため,その支出の時点で政\n府の純資産(国民持分)が何らかの資源が現金以外の形で会計主体として
の政府の内部に残っていると考えることができ,将来世代も利用可能な資\n産が当期どれだけ増加したかを示している(構成要件I)という構\成を採
用することにより,当該年度の政策決定による資金変動を明確にし,国民
の資産が当期の予算措置で増えるのか又は減るのか,また,その財源の内\n訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのかを一目で知るこ
とができ,政策レベルの意思決定を支援することができるようにしたこと
にあるものと認めるのが相当である。
しかるところ,被告製品においては,「資金収支計算書勘定記憶手段及
び閉鎖残高勘定(貸借対照表勘定)及び損益勘定作成・記録手段」から「処\n分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)(C1〜C4)」を作成・
記録する損益外純資産変動計算書勘定作成・記録手段を備えておらず,ま
た,「社会保障給付」が「財源措置(C2)」に含まれていないため,構\n成要件B3及びHを充足せず,当該年度の政策決定による資金変動を明確
にし,財源の内訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのか
を一目で知ることができるようにして政策レベルの意思決定を支援するこ
とができるようにするという本件発明の効果を奏するものと認めることは
できない。
したがって,被告製品は, 本件発明の本質的部分を備えているものと認
めることはできず,被告製品の相違部分は,本件発明の本質的部分でない
ということはできないから,均等論の第1要件を充足しない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品は,本件発
明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められない。\n
イ(ア) これに対し控訴人は,本件明細書の記載によれば,本件発明の本質
的部分(課題解決原理)は,(1)(C)の処分・蓄積勘定(純資産変動計
算書勘定)が損益外の純資産増加(C3,C4)(貸方)と純資産減少
(C1,C2)(借方)の2つで構成され(構\成要件F),期末にその
貸方と借方の差額(収支尻)が当期純資産変動額(C5)という形で閉
鎖残高勘定(貸借対照表勘定)の純資産(国民持分)(B4)の部に振\nり替えられる(構成要件G)ことで,国民が将来負担すべき負債を明確\nにするという点,(2)(C)の処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書
勘定)の貸方側において,将来世代も利用可能な資産が当期どれだけ増\n加したかを示している(財源が固定資産などに転化したもの,すなわち
税収等の財源が使用されて減少したが,将来世代が利用可能な資産の形\nで増加したと解釈できるものを計上する)資産形成充当財源(C4)の
金額が,将来利用可能な資源を明確にする(構\成要件I)という点,(3)
処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)と資金勘定(資金収支
計算書勘定),閉鎖残高勘定(貸借対照表勘定),損益勘定(行政コス\nト計算書勘定)との「勘定連絡(勘定科目間の金額の連動)」がプログ
ラムに設定されていることが,政策レベルの意思決定と将来の国民の負
担をコンピュータ・シミュレーションする会計処理を可能にするという\n点にあり,被告製品は,本件発明の本質的部分を備えている旨主張する。
しかしながら,本件発明の本質的部分は前記アのとおり認めるのが相
当であり,また,上記(3)の点については,本件発明は,請求項2に係る
発明とは異なり,「コンピュータ・シミュレーション」を行うことを発
明特定事項とするものではないから,本件発明の本質的部分であるとい
うことはできない。
したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。
(イ) また,控訴人は,「財源措置」とは,将来利用可能な資源の増加を\n伴うか否かにかかわらず,「当期に費消する資源の金額」を意味するも
のであり,「純経常費用(C1)」と「財源措置(C2)」を包括する
上位概念であるから,この意味で「純経常費用(C1)」と「財源措置
(C2)」は同質的であり,個別の政府活動が「行政レベルの業務執行
上の意思決定」と「国家の政策レベルの意思決定」のいずれに分類され
たとしても,処分・蓄積勘定(純資産変動計算書勘定)の借方の金額,
すなわち,「当期に費消する資源の金額」には変化はないから,本件発
明の課題解決原理として不可欠の重要部分である処分・蓄積勘定の収支
尻(貸借差額),すなわち「当期純資産変動額」に影響を及ぼすもので
はないことからすると,被告製品の構成要件Hに係る相違部分(被告製\n品においては,「社会保障給付」が,「財源措置(C2)」に含まれて
おらず,「純経常費用(C1)」に含まれている点)は,本件発明の本
質的部分とは無関係な些細な相違にすぎない旨主張する。
しかしながら,本件明細書には,(1)処分・蓄積勘定(損益外純資産変
動計算書勘定)の借方の「純経常費用(C1)」は,「損益勘定(行政
コスト計算書勘定)」の収支尻である「純経常費用」が振り替えられて
計上されるところ(【0026】,【0035】,図1),「損益勘定
(行政コスト計算書勘定)」は,主として行政レベルの業務執行上の意
思決定を対象とするもので,行政コスト(損益)計算区分に計上される
行政コスト(計上損益)は少なければ少ないほど効率的な行政運営であ
ることを意味するものであること(【0036】),(2)処分・蓄積勘定
(損益外純資産変動計算書勘定)の借方の「財源措置(C2)」は,社
会保障給付やインフラ資産を整備した際の資本的支出のような,「損益
外で財源を費消する取引」を指し(【0027】),「財源の使途」(損
益外財源の減少)に属する勘定科目群は,主として国家の政策レベルの
意思決定の対象として,現役世代によって構成される内閣及び国会が,\n予算編成上,どこにどれだけの資源を配分すべきかを意思決定するもの\nであり(【0037】,図2),社会保障給付は,上記勘定科目群の「移
転支出への財源措置」に計上される非交換性の支出(対価なき移転支出)
であること(【0040】)の開示があることに照らすと,本件発明に
おいては,「純経常費用(C1)」と「財源措置(C2)」は同質的な
ものであるとはいえず,「財源措置(C2)」に含まれる社会保障給付
にいくら財源を配分するのかは国家の政策レベルの意思決定の対象であ
るといえるから,控訴人の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
2020.02.27
令和1(ネ)10046 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当審における補充主張に対する判断
控訴人は,本件明細書等の記載によれば,本件各発明の効果は, ドラ イパビットの翼部の屈曲部l乙ネジの翼係合部の屈曲部が接触することに よるものであるとし,これを前提に,被告製品は本件各発明の効果を奏 しないと主張する。 本件明細書等の段落【0003), 【0004】, 【0008】, 【図1】の記載からは,従来技術においては,食い付き部分を有する ネジを含む従来のネジにおいて,翼係合部とドライパピットの翼部と の引っ掛かりが悪いことやドライパピットがネジに対して傾いた状態 であることにより更ネジを回転させようとするとき,カムアウト現象 が生じ易いという課題が存するところ,本件各発明の「側壁面」の構\n成を採用すると,対応する形状の翼部を有するピットを用いれば,ネ ジに対してドライパピットが傾きにくくなり,また,翼部の屈曲した 側面に,対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので, 前記側面が前記側壁面を確実に把握し,翼部と翼係合部との引っ掛か りがよくなるため, ドライバピットがカムアウトしにくくなり,上記 課題が解決されることが理解できる。 そして「食い込む」とは「他の領域へ入りこんで侵す。侵入す る。」 (乙10 1) ことであるから,本件明細書等の段落【0008】 の「翼部の屈曲した側面に,対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面 が食い込むJとは,回転力を加えることにより, ドライパピットの翼部 とネジの翼係合部が接触する箇所において, ドライパピットの翼部の側 面がネジの翼係合部の側壁面を確実に把握し,引っ掛かりがよくなるこ とを意味するものと解され,本件各発明の効果を奏するために, ドライ パピットの翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することが必須で あるということはできない。また,控訴人の指摘する本件明細書等の段 落【0014], 【0017]及び【0022]にも, ドライバピット の翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することの記載はない。 控訴人は,本件意見書2の図A,B等は, ドライパピットの翼部の屈 曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触することを裏付けると主張するが, 本件明細書等の上記記載に照らせば,本件意見書2の各図は上記判断を 左右するものではない。
(イ) 控訴人の主張によっても,専用ピットの翼部の先端が被告製品の 「先端部内側面Jに点状に接触するというのであるから,被告製品に おいても, ドライパピットに回転力を加えた際に当該接触した箇所で 食い込みが生じ,翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなり, ドライ パビットがカムアウトしにくくなるという効果を奏すると解され,被 告製品において本件各発明の効果を奏しないということはできない。
本件特許に係る無効理由の有無(争点2) について
(1) 本件特許に係る無効理由の有無(争点2) についての判断は,次のとお り補正し,後記のとおり当審における補充主張に対する判断を付加するほか は,原判決第4の・・・記載のとおりであるから,これを引用する。
ア原判決56頁24行目「動機」を「動機付け」と改める。
イ原判決57頁19行目冒頭から25行目末尾までを次のとおり改める。
「しかし,前記判示のとおり,ネジ及びドライパピットの食い付き部分は 周知技術であり,出願当初の明細書等の実施例に当該周知技術について記 載がされていないとしても,それは本件各発明が当該周知技術を備えるこ とを排除する趣旨であるとは解し得ない。そうすると,本件各発明の技術 的範囲に当該周知技術の構成を備えたネジが含まれるとしても,構\成要件 1D及び2Aの「ネジの中心側から外方に向かつて延びる平面状の基端側 部分」との発明特定事項を追加する本件手続補正が新規事項の追加となる ものではない。 また,本件明細書等の段落【0003], 【0004】, 【0008], 【図1】の記載からは,本件各発明の「側壁面」の構成を備えることによ\nり,対応する形状の翼部を有するピットを用いれば,ネジに対してドライ パピットが傾きにくくなり,また,翼部の屈曲した側面に,対応する形状 に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので,前記側面が前記側壁面を確 実に把握し,翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなるため, ドライパピ ットがカムアウトしにくくなるという本件各発明の効果が得られることが 理解でき(本判決第3の2(3)ウ(7)参照。), 「食い付き部分」の有無は 本件各発明の課題の解決に影響する構成とはいえない。したがって,控訴\n人主張の点は,サポート要件適合性を否定するものではないというべきで ある」
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア 乙13考案及び乙5-8公報に開示された周知技術による進歩性の欠如 (争点2- 1) について
控訴人は,食い付き部分に関し,屈曲した二平面とR面を相互に代替す ることは当業者の技術常識であると主張するo しかし,食い付き部分と本 件各発明の「側壁面」は,目的も機能も異なり,食い付き部分の構\成に関 する技術常識を側壁面に適用することはできなし、から,控訴人の主張は採 用できない。
イ 乙13考案並びに乙12考案及び乙5〜8公報に開示された周知技術に よる進歩性の欠知(争点2-2) について
控訴人は,乙12考案の効果は本件各発明の「食い込む」ことにより 「カムアウトがしにくくなる」効果と実質的に同質の効果であるから, 乙13考案と乙12考案とは,実質的な目的・課題及び作用・機能にお\nいて共通し,両者を組み合わせる動機付けがあると主張する。しかし, 乙12考案の「切込溝3Jは錆びついたピスを容易に抜くために設けた ものであるのに対し,乙13考案の「円弧E-Fからなる溝」は, ドラ イパーのねじ込み力を完全に受け止めるために設けられたものであって, これらの考案の課題は全く異なることは,上記引用に係る補正された原 判決第4の5に説示したとおりであり,乙13考案に乙12考案を組み 合わせる動機付けがあるということはできない。
ウ補正要件違反又はサポート要件違反の有無について(争点2-3) につ いて
控訴人は,本件各発明の「屈曲」について,翼部の屈曲した側面に,対 応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むことが可能な「屈曲J, すなわち, ドライパピットの翼部の屈曲部に,対応する形状に屈曲したネ ジの翼係合部の屈曲部が深く内部に入り込むほど接触することを要すると 限定解釈しないとすると,本件各発明の課題である「ドライパピットがカ ムアウトしにくい(回動部から外れにくい)ネジおよびドライパピットを 提供するJ (【0004】)を解決し得ると当業者が認識し得ないものを 特許請求の範囲に含むことになると主張する。しかし, ドライパビットが カムアウトしにくい(回動部から外れにくし、)ネジとの課題を解決するに つき, ドライパピットの翼部の屈曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触す る(食い込む)ことが必須であるといえないのは前記2(1)イ及び(2)に説 示したとおりでありこれを前提とする控訴人の主張は採用できない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成28(ワ)14753
被告は,本件意見書1における,「引用文献2〜4」のネジと本件各発
明のネジ穴とは構成が異なる旨の記載は,本件各発明の特許請求の範囲か\nら,ネジ穴の中心部に食い付き部分(円弧面状の部分)を有する構成を意\n識的に除外する趣旨であって,食い付き部分を有する構成が本件各発明の\n技術的範囲に属すると主張することは,禁反言の法理に照らして許されな
いと主張する。
イ しかし,本件意見書1には,以下の内容の記載がある。
(ア) 本件手続補正は,請求項1について「引用文献2〜4記載の発明との
相違が明確になるように締付側側壁面(10)の形状をより細かく限定
した」ものであり,請求項2について「引用文献2〜4記載の発明との
相違が明確になるようにネジの翼係合部(2)の緩め側側壁面(9)の
形状をより細かく限定したもの」である。(乙10の2頁)
(イ) 「引用文献2」(乙6)記載の発明は,「本来の意味においては,各
翼係合部は屈曲部を有していない。具体的には,引用文献2記載の発明
の場合,各翼係合部の両側壁面は,それぞれ全体が1つの平面状をなし
ており,全く屈曲されていない」点で本件各発明と異なる。
引用文献2記載の発明において「強いて回動部の中心部の円弧面状の
部分を翼係合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」,本願発
明のような優れた作用効果を全く果たさない。(乙10の4頁)
(ウ) 「引用文献3」(乙7),「同4」(乙8)記載の発明においても,
「本来の意味においては,各翼係合部は屈曲部を有していない。具体的
には,引用文献3,4記載の発明の場合,本来の意味での各翼係合部の
両側壁面は,軸方向から見ると扇形の両辺(直線状部)をなす平面状の
部分のみである」点で本件各発明と異なる。
引用文献3,4記載の発明における「ネジの中央部分において翼係合
部の基端側部分間をつなぐR部分は,円弧面状をなす部分であって,ネ
ジへのドライバビットの食い付きをよくするために設けられる所謂食い
付き部を構成する部分」であって,「前記R部分(食い付き部分)は,\nネジの締め付けおよび緩め動作自体には直接関係のない部分」にすぎな
い。
「引用文献3,4」記載の発明において,「強いて前記R部分を翼係
合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても,これらの部分は,平
面状ではなく,円弧面状の部分であり,かつネジの中心側から外方に向
かって延びていない」ので,本件各発明とは構成が異なる。\n 引用文献3,4記載の発明において,「強いて前記R部分を翼係合部
の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」,本件各発明の作用効果
は生じない。(乙10の5頁)
ウ 本件意見書1の上記記載によれば,原告は同意見書において,「引用文
献2〜4」記載の発明に係る構成と本件各発明に係る構\成が異なることを
説明するとともに,仮に同各文献の構成が対応する本件各発明の構\成に相
当するとしても,同各文献記載の発明が本件各発明の効果を奏しないとい
うことを説明しているにすぎないのであって,上記記載をもって,本件各
発明の特許請求の範囲から,ネジ穴の中心部に食い付き部分(円弧面状の
部分)を有する構成を意識的に除外しているということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> ピックアップ対象
2020.02.25
平成30(ワ)12609 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月9日 東京地方裁判所
被告は,(1)乙2公報は,音響IDとインターネットを用いて,放音装置から放音 された音響IDによって識別される識別対象の情報に対し,これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙2技術を開示しているところ,本件 発明1も乙2技術を採用するものであり,相違点1−1ないし同1−4は,識別対 象,複数の関連情報の選択条件,関連情報の内容に係る相違にすぎず,当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに,(2)当業者は,乙2技術を乙4課題の 解決に応用して,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成を容易に想到し得た旨主張する。\n
しかしながら,まず,被告の上記(1)の主張については,前記1(2)認定のとおり, 本件発明1は,コンピュータを,(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段,(ii)サーバに対し,抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段,(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し,情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求\nの言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段,(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明であり,乙2公報等に音響IDとインターネットを利用するという点で本件発明1と\n同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても,その手順や方法を具体的に特定し,使用言語が相違する多様な利用者が理解可能\な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。\nまた,被告の上記(2)の主張については,前記イのとおり,乙4公報に,発明が解 決しようとする課題の一つとして,システムを複数の言語に対応させること(以下, 単に「乙4発明の課題」という。)が記載されているものの,以下のとおり,乙2 発明1を乙4発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず,仮に,乙4発明の 課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなどして乙2発明1の構\成に変更を加え たとしても相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成に到達しないから,採用することができない。\n
(ア) 乙2発明1を乙4発明の課題を組み合わせる動機付け
a 前記のとおり,乙2発明1は,放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり,放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響IDを用い,ID解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し,前記イ(イ)のとおり,乙 4発明は,利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり,展示物に固有のIDを赤外線 等の無線通信波によって発信し,携帯受信器が発信域に入ると上記IDを受信し, 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり,サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから,両発明は,想定される使用場面や発明の基本的な構\成が異なっており,乙2発明1を乙4発明の課題に組み合わせる動機付けは認められない。
b 被告は,(1)乙4発明は,放音装置を利用した情報提供技術という乙2技術と 同じ技術分野に属するものであること,(2)乙2技術は汎用性の高い技術であり, 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと(乙11ないし13),(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と(乙2,5,6,8,11ないし13等)などによれば,当業者において,乙2 技術を乙4課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら,乙2発明1と乙4発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ,また,本件優先日1当時,音 響IDとインターネットを利用し,又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙2公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても,いず れも乙4発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記のとおりであり,乙4発明の課題の解決のみを取り上げて乙2発明1を適用する動機\n付けがあると認めるに足りない。
(イ) 乙2発明1に対する乙4発明等の適用
また,以下のとおり,乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなどして乙2発明1の構\成に変更を加えたとしても,本件発明1の構成に到達しない。\n前記第2の2(2)ア(ウ)認定の特許請求の範囲,前記(1)認定の本件明細書1の発明 の詳細な説明,図面,弁論の全趣旨に照らすと,本件発明1は,概要,以下のとお りのものであると認められる。
ア 本件発明1は,端末装置の利用者に情報を提供する技術に関する(【0001】)。
イ 従来から,美術館や博物館等の展示施設において利用者を案内する各種の技 術が提案されていたが,各展示物の識別符号が電波や赤外線で発信装置から送信さ れるものであったため,電波や赤外線を利用した無線通信のための専用の通信機器 を設置する必要があった。本件発明1は,そのような問題を踏まえてされたもので あり,無線通信のための専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供 することを目的とする(【0002】,【0004】)。
ウ 本件発明1は,(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ\nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段,(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段,(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段,(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより,赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに,案内音声である再生対象音の識別情報に対\n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする(【0005】)。
エ 以上に加えて,本件発明1は,前記送信手段が,当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し,前記受信手段が,情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用するこ\nとにより,相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指 定された言語に対応する関連情報を受信することができ,使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである(【0\n006】等)。
2 本件アプリの広告等について
証拠(甲6,7)によれば,次の事実が認められる。
(1) 被告作成の「Sound Insight(サウンドインサイト)」と題す る本件アプリを用いたシステムに関する広告(甲6。以下「本件広告」という。) には,次のとおり記載されていた。
ア (1)「映像・音声にのせて,情報配信」,(2)「動画・音楽などの音に人間には 聞こえない音波信号(音波ID)を埋め込み,テレビ・サイネージ・スピーカー等 から再生し,スマートフォンアプリで音波信号(音波ID)を受信する事により, 紐づいた情報をスマートフォン上に自動表示」,(3)(音波信号に紐づく情報を表示\nする手順の一つとして)「映像・音声に重畳した音波信号を発する」
イ (1)「音で情報を配信」,(2)「『Sound Insight』は,人には聞 こえない音波信号(音波ID)を使い,映像や音に合わせてアプリを連動できます。 利用者が信号音を意識することなくスマートフォン上に情報を表示します。」\n
ウ 「多言語で配信可能 日本語のほか,英語,中国語,台湾語,韓国語,ロシ ア語など多言語で情報配信できます。」
エ (使用例の一つとして)「バスの車内案内では 多国語で停留所情報や地域 の情報を案内できます。」
(2) 本件アプリのダウンロード用のウェブサイト(甲7。「本件ダウンロードサ イト」という。)には,次のとおり記載されていた。 「『サウンドインサイト』は,空港,駅,電車,バスなどの様々な場所に設置さ れた各種スピーカーから送信された音波を,専用アプリをインストールしたスマー トフォンで受信することで,関連する情報を自動で表示させることのできるサービ\nスです。・・・『サウンドインサイト』の活用により,・・・外国人観光客へ空港・駅などのアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する『言語支援用途』・・・などで活 用いただくことができます。」
3 争点1(本件アプリは本件発明1の技術的範囲に属するか)について
(1)争点1−1(本件アプリは構成要件1Bを充足するか)について\n
ア 構成要件1Bに対応する本件アプリの構\成に係る事実認定
(ア) 前記第2の2(5)ア(ア)のとおり,本件アプリは,スピーカー等の放音装置か ら,識別情報であるIDコードを表す音響IDを含む音響が放音されると,これを\n収音し,当該音響IDからIDコードを検出するものとしてスマートフォンを機能\nさせるものであるところ,前記2(1)のとおり,本件広告には,「映像・音声にのせ て」,「動画・音楽などの音」に埋め込んで,「映像・音声に重畳」させて音響I Dを放音することが記載されているほか,使用例の一つとして,バスの車内案内で は多言語で停留所情報等を提供することができることが記載されていること,同(2) のとおり,本件ダウンロードサイトには,本件アプリは,空港,駅,電車,バス等 に設置された放音装置から送信された音波を,スマートフォンで受信することで, 関連する情報を自動で表示させることのできるサービスを提供するものであること\nが記載されていることなどからすると,被告から音響IDの提供を受けた顧客にお いて,案内音声を識別するものとしてIDコードを使用し,これを案内音声ととも に放音装置から放音することは,本件アプリにつき想定されていた使用形態の一つ であるというべきである。そうすると,本件アプリは「案内音声と当該案内音声を 識別するIDコードを含む音響IDとを含有する音響を収音し,当該音響からID コードを抽出する情報抽出手段」(構成1b)を備えていると認めるのが相当であ\nる。
(イ) 被告は,本件アプリが構成1bを備えていることを否認し,その理由として,\n(1)被告サービスにおいて,被告は,放音される音響やIDコードの識別対象を決定 しておらず,これらを選択,決定しているのは顧客であって,いずれも「案内音声」 に限られるものではないこと,(2)本件アプリの利用場面の中で,最も多くの需要が 見込まれているのは商品説明の場合であるが,商品説明において,放音装置から音 声が発せられることは必須ではなく,かえって,音声が放音されるとスマートフォ ンに表示される情報を理解する妨げになることを主張する。\nしかしながら,被告の上記(1)の主張は,構成要件1B所定の音響が放音されない\n場合があることを指摘するにとどまるものであり,前記(ア)のとおり,本件広告に おいても,案内音声を収音する使用形態を回避させるような記述はなく,むしろ, そのような使用形態を想定したものとなっていたというべきであるから,前記認定 を覆すに足りないというべきである。 また,被告の上記(2)の主張について,本件アプリにつき最も多くの需要が見込ま れていたのが商品説明の場面であったとしても,被告において,そのような使用形 態に特化したものとして本件アプリを広告宣伝していたものでもなく,前記認定を 覆すに足りない。
イ 構成要件1Bに係るあてはめ\n
以上の認定を踏まえて検討すると,構成1bの「案内音声」は,本件発明1の\n「案内音声である再生対象音を表す音響信号」に対応し,構\成1bの「案内音声を 識別するIDコードを含む音響ID」は,本件発明1の「案内音声である再生対象 音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号」に対応する。 そして,本件発明1は,コンピュータを所定の手段として機能させるプログラム\nに係る発明であり,構成要件1Bは,放音された所定の音響を収音した収音信号か\nら識別情報を抽出する情報抽出手段を規定するものであるから,構成要件1B所定\nの音響が放音された場合に,これを収音し,識別信号を抽出する手段としてコンピ ュータを機能させるプログラムであれば,これと異なる用途でコンピュータを機能\ させ得るとしても,又は音響が放音されない場面があるとしても,同構成要件を充\n足すると解すべきところ,本件アプリは,同所定の音響を収音し,当該音響からI Dコードを抽出するものとしてスマートフォンを機能させるものであるから,放音\nされる音響やIDコードの識別対象を選択しているのが顧客であり,音響が放音さ れない使用方法が選択され得るとしても,構成要件1Bを充足する。\n
(2)争点1−2(本件アプリは構成要件1Dを充足するか)について\n
ア 構成要件1Dの「関連情報」の言語の解釈\n
(ア) 構成要件1Dは,「関連情報」について,「前記案内音声である再生対象音\nの発音内容を表す関連情報であって,前記情報要求に含まれる識別情報に対応する\nとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求の言語情報 で指定された言語に対応する関連情報」と規定しているから,「関連情報」の言語 は,相異なる言語に対応するものの中から情報要求の言語情報で指定された言語に 対応するものと解すべきである。
(イ) 被告は,「関連情報」は,第1言語で発音される案内音声の発音内容を第1 言語で表した文字列であると解すべきであるとし,その理由として,原告が本件訂\n正審判請求1の際に訂正事項が明細書の記載事項の範囲内であることを示す根拠と して本件明細書1の【0041】を挙げていたことを指摘するが,構成要件1Dは\n上記のとおりのものであるから,「関連情報」が案内音声の言語と同一のものであ ると解するのは文言上無理がある。また,同段落には,第2言語に翻訳することな く,第1言語の指定文字列のまま関連情報Qとする実施例が開示されているが,こ れは第1実施形態の変形例の一つ(態様1)にすぎず,原告が本件訂正審判請求1 の際に同段落を指摘したからといって,当該実施例の態様に限定して「関連情報」 の言語について解釈するのは相当でない。
イ 構成要件1Dに対応する本件アプリの構\成に係る事実認定
(ア) 前記第2の2(5)ア(ウ)及び同イのとおり,本件アプリは,管理サーバから, リクエスト情報に含まれるIDコード及びアプリ使用言語の情報に対応する情報の 所在を示すものとして送信されるアクセス先URLを受信するものとしてスマート フォンを機能させるものであり,管理サーバには,1個のIDコードに対応させて,\n6個までのアプリ使用言語に対応するURLを記憶することができるところ,前記 2(1)のとおり,本件広告には,日本語のほか,英語,中国語,台湾語,韓国語,ロ シア語など多言語で情報配信できることが記載されており,使用例の一つとして, バスの車内案内では多言語で停留所情報等を提供することができることが記載され ていること,同(2)のとおり,本件ダウンロードサイトには,外国人観光客に対して, 空港・駅等のアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する用途に用いること ができることが記載されていることなどからすると,顧客において,リクエスト情 報に含まれるIDコードに対応する案内音声の発音内容を表す情報について,当該\n案内音声とは異なる言語に対応する複数の情報を管理サーバに記憶させ,リクエス ト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報をスマートフォンに送信するよう にすることは,本件アプリにつき想定されていた使用態様の一つであるというべき である。そうすると,本件アプリは,「前記案内音声の発音内容を表す関連情報で\nあって,前記リクエスト情報に含まれるIDコードに対応するとともに,6個まで のアプリ使用言語に対応する複数の情報のうち,前記リクエスト情報のアプリ使用 言語に対応する情報を受信する受信手段」(構成1d)を備えていると認めるのが\n相当である。
(イ) 被告は,本件アプリが構成1dを備えていることを否認し,その理由として,\n
(1)被告サービスにおいて,被告は,本件スマートフォンが受信する情報を決定して おらず,これを選択,決定しているのは顧客であって,構成要件1D所定のものに\n限られないこと,(2)被告は,本件アプリに係る実証実験において,本件アプリを用 いて「案内音声である再生対象音の発音内容」を関連情報として出力したことはな く,外国語に翻訳した内容を関連情報として出力したこともないこと,(3)被告は, 今後,顧客に対し,案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報\nを提供することを禁ずる旨の約束をする意思があることを主張する。 しかしながら,被告の上記(1)の主張は,本件スマートフォンの受信する情報が構\n成要件1D所定の情報ではない場合があることを指摘するにとどまるものであり, 前記(ア)のとおり,本件広告及び本件ダウンロードサイトにおいても,案内音声の 発音内容を表し,リクエスト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報を受信\nする使用形態を回避させるような記述はなく,むしろ,そのような使用形態を想定 したものとなっていたというべきであるから,被告の実証実験では同構成要件所定\nの情報を受信しなかったこと(上記(2)),被告が今後も同構成要件所定の使用態様\nで本件アプリを使用しないことを約束する意思を有していること(上記(3))を併せ 考慮しても,前記認定を覆すに足りないというべきである。
ウ 構成要件1Dに係るあてはめ\n
構成要件1Bにおいて規定するとおりにコンピュータを機能\させるものであれば, 同構成要件を充足するとの前記(1)イにおける検討と同様に,構成要件1D所定の情\n報を受信する手段としてコンピュータを機能させるプログラムであれば,受信する\n情報が同構成要件所定のものではない場面があるとしても,同構\成要件を充足する と解すべきところ,本件アプリは,構成1dを備えており,スマートフォンを「前\n記案内音声の発音内容を表す関連情報であって,前記リクエスト情報に含まれるI\nDコードに対応するとともに,6個までのアプリ使用言語に対応する複数の情報の うち,前記リクエスト情報のアプリ使用言語に対応する情報を受信する受信手段」 として機能させるものであるから,本件スマートフォンが受信する情報を選択して\nいるのが顧客であるとしても,構成要件1Dを充足する。\n
4 争点4(本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか)につい て
(1) 争点4−1(本件発明1は乙2公報により進歩性を欠くか)について
・・・
(イ) 乙2発明1
前記(ア)によれば,乙2発明1は,放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり(【000 1】),テレビ番組の場面を識別する音声信号である音響IDを用い,ID解決サ ーバを介して当該場面に関連する情報を取得することを容易にした携帯端末装置等 を提供することを目的とするものであって(【0005】等),本件発明1に対応 する構成として,次の各構\成を有すると認められる。
「携帯端末装置を,
放送中のテレビ番組の放送音声と重畳して放音される,当該番組の場面を識別す る音声信号である音響IDを収音し,前記音響IDからIDコードにデコードする 情報抽出手段,
携帯端末装置に記憶されたIDコードをID解決サーバに送信する送信手段,
前記IDコード及び前記ID解決サーバが当該IDコードを受信した時刻に基づ いて当該ID解決サーバによりID/URL対応テーブルにおいて検索された対応 するURLを受信し,放送されたテレビ番組の場面に関連する情報を当該URLで 指示されるコンテンツサーバから受信する受信手段,及び,
前記受信手段が受信した情報を携帯端末装置上で表示する出力手段として機能\させるプログラム。」
(ウ) 乙2発明1と本件発明1の対比
乙2発明1と本件発明1を対比すると,これらは,次のaの点で一致し,少なく とも,次のbの点で相違すると認められる。
a 一致点
「コンピュータを,再生対象音を表す音響信号と識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段,前記情報抽出手段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段,\n前記情報要求に含まれる識別情報に対応する関連情報を受信する受信手段,および, 前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラム。」\n
b 相違点
(a) 相違点1−1(構成要件1B)\n
本件発明1では,「案内音声・・・を表す音響信号」と「当該案内音声である再生対\n象音の識別情報」が放音されるのに対し,乙2発明1では,「放送中のテレビ番組 の放送音声」と「当該番組に対応し,当該番組の場面を識別する音声信号である音 響ID」が放音される点
(b) 相違点1−2(構成要件1C)\n
本件発明1では,端末装置からサーバに送信される「情報要求」に含まれる情報 は,「識別情報」と「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」であるの に対し,乙2発明1では,携帯端末装置からID解決サーバに送信される情報は 「IDコード」のみであり,「端末装置にて指定された言語を示す言語情報」は含 まれない点
(c) 相違点1−3(構成要件1D(1))
本件発明1では,端末装置が受信する「関連情報」は,「案内音声である再生対 象音の発音内容を表す」のに対し,乙2発明1では,「放送されたテレビ番組の場\n面」に関連する内容を表す点\n
(d) 相違点1−4(構成要件1D(2))
本件発明1では,端末装置が受信する「関連情報」は,「相異なる言語に対応す る複数の関連情報のうち,前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関 連情報」であるのに対し,乙2発明1では,携帯端末装置がこれに対応する情報を 受信しない点
(エ) 相違点に関する被告の主張について
a 相違点1−1(構成要件1B)\n
被告は,乙2発明1の「IDコード」は,番組と同時に,番組の放送音声という 「再生対象音」も識別しているから,「再生対象音の識別情報」が放音される点で は本件発明1と相違しない旨主張する。 しかしながら,乙2公報に「この音響IDは,放送中の番組に対応するものであ り,放送音声に重畳されて放音される。」(【0014】)と記載されており,I D/URL対応テーブルを示す図4においても,受信時間帯に対応する番組の「シ ーン」が特定されていること(【0025】)などからすると,乙2発明1の「ID コード」は,放送中の番組に対応し,当該番組の場面を識別する音声信号であって, 番組の放送音声を識別するものではないから,本件発明1の「再生対象音の識別情 報」に対応する構成を有するものとは認められない。\n
b 相違点1−2(構成要件1C)\n
被告は,乙2発明1では,ユーザがボタンスイッチを押した時刻は「端末装置に て指定された・・・情報」に該当するから,「端末装置にて指定された・・・情報」が「言 語を示す言語情報」であるか「ボタンスイッチの操作タイミングを示す情報」であ るかの点でのみ本件発明1と相違する旨主張する。 しかしながら,乙2公報に「番組を視聴しているユーザ6は,番組を視聴し興味 ある場面が映し出されると,スマートフォン2を操作する(たとえばボタンを押下 する)。このときの操作により,スマートフォン2は記憶していたIDコードをI D解決サーバ4に送信する。」(【0014】)と記載されていることなどからする と,乙2発明1において,携帯端末装置から送信される情報はIDコードのみであ り,ID解決サーバは当該IDコード及び受信時刻で対応するURLを検索するも のであるから,本件発明1の「端末装置にて指定された・・・情報」に対応する構成を\n有するとは認められないというべきである。
c 相違点1−3(構成要件1D(1))
被告は,乙2発明1で,携帯端末装置が受信する情報は,番組の特定の場面に対 応する放送音声に関連するものであるから,端末装置が受信する「関連情報」が 「再生対象音」である点では本件発明1と相違しない旨主張する。 しかしながら,乙2公報に「この対応するURLは,ユーザ6がスマートフォン 2を操作したときに放送されていた(テレビ1の画面に映し出されていた,または 音声で再生されていた)場面に関連する情報を提供するインターネットサイトのU RLである。」(【0014】)と記載されていることなどからすると,乙2発明1 において,携帯端末装置が受信する情報は,放送されたテレビ番組の場面に関連す るものであり,放送音声に関連する情報であるとは認められない。
d 相違点1−4(構成要件1D(2))
被告は,乙2発明1では,番組中の相異なる場面に対応する「複数の関連情報」 が存在し,そのうち選ばれた情報を受信しているから,「関連情報」が対応してい るのが「言語」であるか「場面」であるかの点でのみ本件発明1と相違する旨主張 する。 しかしながら,乙2発明1において,携帯端末装置が受信する放送中の番組の場 面に関する情報は「相異なる言語に対応する」ものでもないから,ID解決サーバ に番組内の相異なる場面に対応する情報が複数記憶されていたとしても,これを構\n成要件1Dの「相異なる言語に対応する複数の関連情報」との構成に対応するもの\nと認めることはできない。
イ 乙4発明の内容等に係る事実認定
・・・
(イ) 乙4発明の概要 前記(ア)によれば,乙4公報には,概要,次のとおりの内容の乙4発明が開示さ れていると認められる。 すなわち,乙4発明は,利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館 や博物館等の展示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり(【000 1】),(1)電波によって情報を伝達する従来技術によると,対象物以外のガイド音 声を受信して利用者に誤った情報を提供するおそれがあったこと(【0005】) を踏まえ,展示物に固有のIDを赤外線等の無線通信波によって発信するID発信 機を展示物ごとに一定の間隔で設置し,利用者が携帯する携帯受信器が発信域に入 ると上記IDを受信し,展示物の音声ガイドが自動的に再生される構成を採用する\nことにより,情報提供するIDの受信範囲を限定することが容易になり,隣接する 対象展示物との混信を回避した音声ガイドシステムを可能とするという作用効果を\n奏するものであり(【0008】ないし【0010】,【0014】),また,(2) そのシステムを複数の言語に対応させようとすると,多数のチャンネルの割当てが 必要となり,その選択操作を利用者が行う必要があったこと(【0007】)を踏 まえ,多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信器に蓄積し,その中から 再生する言語を選択するという構成を採用することにより,多くの外国人利用者に\nも携帯受信器を操作することなくガイド音声を提供することができるという作用効 果を奏するものである(【0012】,【0020】)。
ウ 乙5発明の内容等に係る事実認定
・・・
(イ) 乙5発明の概要 前記(ア)によれば,乙5公報には,概要,次のとおりの内容の乙5発明が開示さ れていると認められる。 すなわち,乙5発明は,公共の場所等に掲載された文書等の掲載物を様々な言語 に翻訳して提供する情報提供装置等に関するものであり(【0001】),文書の 内容を様々な言語で利用者に正しく提供することを主たる課題とし(【000 6】),2次元コードと複数の言語に対応する言語コードをその内容として含むコ ード画像をユーザ端末装置によって読み取り,ユーザにおいて所望の言語を選択す るなどして,インターネットを介して,文書等の掲載物の翻訳ファイルにアクセス というものである(【0015】,【0025】,【0035】,【0038】)。
エ 容易想到性についての判断
被告は,(1)乙2公報は,音響IDとインターネットを用いて,放音装置から放音 された音響IDによって識別される識別対象の情報に対し,これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙2技術を開示しているところ,本件 発明1も乙2技術を採用するものであり,相違点1−1ないし同1−4は,識別対 象,複数の関連情報の選択条件,関連情報の内容に係る相違にすぎず,当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに,(2)当業者は,乙2技術を乙4課題の 解決に応用して,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成を容易に想\n到し得た旨主張する。 しかしながら,まず,被告の上記(1)の主張については,前記1(2)認定のとおり, 本件発明1は,コンピュータを,(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段,(ii)サーバに対し,抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段,(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し,情報要求に含まれる識別情報に\n対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段,(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明で\nあり,乙2公報等に音響IDとインターネットを利用するという点で本件発明1と 同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても,その手順や方法を具\n体的に特定し,使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供でき\nるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成が当業者において適宜設\n定できる事項であるということはできない。 また,被告の上記(2)の主張については,前記イのとおり,乙4公報に,発明が解 決しようとする課題の一つとして,システムを複数の言語に対応させること(以下, 単に「乙4発明の課題」という。)が記載されているものの,以下のとおり,乙2 発明1を乙4発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず,仮に,乙4発明の 課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなどして乙2発明1の構\成に変更を加え たとしても相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成に到達しないから,\n採用することができない。
(ア) 乙2発明1を乙4発明の課題を組み合わせる動機付け
a 前記のとおり,乙2発明1は,放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり,放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響IDを用い,ID解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し,前記イ(イ)のとおり,乙 4発明は,利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり,展示物に固有のIDを赤外線 等の無線通信波によって発信し,携帯受信器が発信域に入ると上記IDを受信し, 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり,サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから,両発明は,想定される使用場\n面や発明の基本的な構成が異なっており,乙2発明1を乙4発明の課題に組み合わ\nせる動機付けは認められない。
b 被告は,(1)乙4発明は,放音装置を利用した情報提供技術という乙2技術と 同じ技術分野に属するものであること,(2)乙2技術は汎用性の高い技術であり, 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと(乙11ないし13),(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と(乙2,5,6,8,11ないし13等)などによれば,当業者において,乙2 技術を乙4課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら,乙2発明1と乙4発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ,また,本件優先日1当時,音 響IDとインターネットを利用し,又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙2公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても,いず れも乙4発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記の\nとおりであり,乙4発明の課題の解決のみを取り上げて乙2発明1を適用する動機 付けがあると認めるに足りない。
(イ) 乙2発明1に対する乙4発明等の適用
また,以下のとおり,乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなど\nして乙2発明1の構成に変更を加えたとしても,本件発明1の構\成に到達しない。
a 相違点1−1(構成要件1B)\n
(a) 前記のとおり,乙4発明は,展示物ごとに設置されたID発信機から赤外線 等の無線通信波によって展示物に固有のIDが発信されるものであり,「案内音声 ・・・を表す音響信号」を放音するものではなく,「当該案内音声である再生対象音の\n識別情報」を含む音響信号を放音するものでもないから,乙4発明の構成を参照し\nて乙2発明1の構成に変更を加えたとしても,相違点1−1に係る本件発明1の構\ 成に到達しない。
(b) 被告は,乙4発明の音声ガイドは「案内音声」に相当するから,「案内音声」 を識別する構成を採用することは容易であった旨主張するが,上記のとおり,乙4\n発明のIDは展示物を識別するものであり,当該展示物に係る音声ガイドを識別す るものではないから,乙4発明は「案内音声」を識別する構成を開示するものでは\nない。
b 相違点1−2(構成要件1C)\n
前記のとおり,乙4発明は,サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しないものであり,端末装置からサーバに「識別情報」と\n「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」が送信されることはないから, 乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照して乙2発明1の構\成に変更を加 えることによって,相違点1−2に係る本件発明1の構成に到達することはない。\n
c 相違点1−3(構成要件1D(1))
前記のとおり,乙4発明は,サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しておらず,IDによって識別される展示物のガイド音声を\n再生するものであって,端末装置が「案内音声である再生対象音の発音内容を表す」\n情報を受信することはないから,乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照\nして乙2発明1の構成に変更を加えることによって,相違点1−3に係る本件発明\n1の構成に到達することはない。\n
d 相違点1−4(構成要件1D(2))
前記のとおり,乙4発明は,多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信 器に蓄積し,その中から再生する言語を選択することによって,IDによって識別 される展示物のガイド音声を所定の言語で再生するという構成を有するものの,サ\nーバに接続してインターネットを介して情報を取得するという構成を有していない\nから,端末装置が「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信することはなく,乙4発 明の構成を参照して乙2発明1の構\成に変更を加えることによって,相違点1−4 に係る本件発明1の構成に到達することはない。\n
・・・
5 争点6(差止めの必要性は認められるか)について
被告は,本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし,その理由とし て,(1)本件口頭弁論終結時点において,本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと,(2)被告は,平成30年5月以降,本件アプリの配信を中止し,多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており,本件訴訟の\n結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予定であること,\n(3)被告は,今後,顧客に対し,案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語\nの関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や,案内音声である第1言語の再生対 象音が表す発音内容を第2言語で表\現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,本件アプリは,本件発明1の技術的範囲に属 し,本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから, 前記第2の2(4)のとおり,被告は,少なくとも,平成29年5月頃から平成30年 6月頃まで,本件アプリを作成し,譲渡等及び譲渡等の申出をし,平成28年6月\nから平成29年3月までの間に3回にわたり本件アプリを使用することによって本 件特許権1を侵害していたものである。 これらに加えて,被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明1の技術的範囲 に属することを否認して争い,本件特許1について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること,弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も,ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ,被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなど\nも考慮すると,被告は,今後,本件特許権1を侵害するおそれがあるものというべ きであるから,原告が被告に対し,その侵害の予防のため,本件アプリの作成等の\n差止を求める必要性は認められるものというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.01.27
平成28(ワ)10759 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 東京地方裁判所(40部)
(3) 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
前記(1)の譲渡数量に前記(2)の単位数量当たりの利益を乗じた額は,以下 のとおりとなる。
ア 被告日本生化学について
原告長寿乃里
21万3457個×1225円=2億6148万4825円
原告イング
23万9658個×993円=2億3798万0394円
イ 被告ブレーンコスモスについて
原告長寿乃里
17万0132個×1225円=2億0841万1700円
原告イング
19万1015個×993円=1億8967万7895円
ウ 被告ビーシーリンクについて
原告長寿乃里
135個×1225円=16万5375円
原告イング
152個×993円=15万0936円
(4) 特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」の 有無
ア 競合品の存在
証拠(甲8,乙24)によれば,シラスが配合された洗顔料が原告製品 及び被告製品のほかに8銘柄が存在したことが認められるが,販売数が多 いものでも,株式会社メディカルドーズの「お茶!入ったよ〜わっぜ!! 火山灰石けん」が平成22年9月から平成27年12月までに2万754 8個を販売したにとどまり,他の銘柄は,販売数が約1000個から38 00個程度にとどまるか,販売数が明らかではないから,これらの洗顔料 の存在が,「販売することができないとする事情」に当たるということは できない。
イ 原告製品の販売経過
被告日本生化学は,被告製品を販売していない月でも原告製品の販売が 落ちている月があることから,原告製品の販売は被告製品の販売に影響を 受けていなかったと主張するが,原告製品についてそのような販売経過と なった原因としては様々なものが考えられるのであり,上記の販売経過が 直ちに「販売することができないとする事情」に当たるとはいえない。
ウ 薬機法上の区分及び本件発明1の作用効果
被告日本生化学は,原告製品及び被告製品について,薬機法上の区分が 異なること及び宣伝広告の内容から,本件発明1の作用効果は原告製品及 び被告製品の販売に寄与していないと主張する。 しかし,消費者が薬機法上の区分を意識して商品を選択するとは考え難 く,前記判示のとおり,原告製品と被告製品はいずれもシラスが配合され た石けんという同種の商品であり,かつ,被告製品は本件発明1の作用効 果を奏するのであるから,両者は市場で競合する製品であるということが できる。 また,被告ブレーンコスモスは,被告製品の説明において,原告製品は 発売以来700万個以上が売れた大ヒット商品であると紹介するととも に,被告製品には,人工皮膚成分「リピジュア」が配合され,原告製品と 同じ価格だが,内容量が多いという2点が異なることを挙げて,被告製品 の宣伝をしていたことが認められ(甲14),このような宣伝内容によっ て,原告製品ではなく被告製品を購入した消費者も相当数いるものと考え られる。 そうすると,被告日本生化学が主張する上記事情は,「販売することが できないとする事情」に当たるとはいえない。
エ 販売ルートの違いについて
被告ブレーンコスモスらは,原告らは消費者に直接販売する小売である のに対し,被告ブレーンコスモスは販売数のうち95%は企業に対する卸 売りであり,販売ルートが異なるから,競合しないと主張する。 しかし,原告製品及び被告製品はいずれも最終的には一般消費者によっ て購入され,使用される石けんであり,被告製品が一般消費者に販売され る段階では原告製品と競合すると認められるところ,被告製品が存在しな ければ,被告ブレーンコスモスが他の企業に被告製品を卸売りすることも なく,ひいては被告製品が一般消費者に販売されることもないのであるか ら,被告ブレーンコスモスが卸売りを主たる取引形態とするからといって, 原告製品と被告製品が市場において競合することは左右されず,「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
オ 東日本大震災の義援金に充てる旨のアテンションシールについて
被告ブレーンコスモスらは,売上げの一部を東日本大震災の義援金に充 てる旨記載されたアテンションシールを被告製品に貼っていた期間(平成\n23年4月1日から同年9月30日まで)の販売数がそうでない期間の販 売数を上回っており,同シールが被告製品の売上げに寄与した旨主張する。 しかし,平成23年4月1日から同年9月30日まで被告製品に上記シ ールが貼られていたことを認めるに足りる証拠はない上,仮に同シールが\n貼付されていたとしても,平成23年1月から同年9月までの被告製品\n(100gのもの)の販売数は毎月概ね1万個程度で推移しており(丙1, 21),販売数の増加が同シールによるものとは認め難く,被告ブレーン コスモスらの主張はその前提を欠き,採用できない。
カ 海外市場における競合
被告ブレーンコスモスらは,被告ビーシーリンクは専ら海外に被告製品 を販売しているところ,原告製品と被告製品は海外市場において競合しな いと主張する。 しかし,証拠(甲76,77,84〜87,108〜112,丙25〜 28)によれば,被告ビーシーリンクは,平成25年2月から11月にか けて,米国,中国,シンガポール,ラトビアに被告製品を販売していたこ と,原告長寿乃里は,自ら又は株式会社フェローシップ等を介して,以下 のとおり海外に原告商品を出荷したことが認められる。
・・・
以上の事実関係に照らせば,原告製品と被告製品は,少なくとも米国及 び中国の海外市場において競合していたことが認められるから,被告ビー シーリンクが専ら海外において被告製品を販売していることは,「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
キ 以上のとおり,被告らが主張する事情は,いずれも「販売することがで きないとする事情」に当たらないから,特許法102条1項に基づく損害 額の推定は覆滅されない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成30(ワ)8302 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年11月14日 東京地方裁判所
前記(1)の記載によると,次のとおり認められる。
ア 本件各発明以前にも,コンピュータシステムにおけるシステム利用者の 入力行為を支援する従来技術としては,マウスを右クリックすることによ り,マウスが指し示している画面上のポインタ位置に応じた操作コマンド のメニューが表示される「コンテキストメニュー」や,画面上でマウスポ\nインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマ ウスの左ボタンを押し,そのままの状態でマウスを移動させ,別の場所で マウスの左ボタンを離すマウス操作である「ドラッグ&ドロップ」などが あった。しかして,「コンテキストメニュー」には,マウスの左クリックを 行うまではメニューが画面に表示され続け,また,利用者が間違って右ク\nリックを押してしまった場合には,利用者の意に反して画面上に表示され\nてしまうので不便であるなどの課題があり,また,「ドラッグ&ドロップ」 には,継続的な動作,例えば,移動させる位置を決めないで徐々に画面を スクロールさせていくような動作に適用させるのが難しいという課題が あったところである(段落【0001】〜【0005】)。
イ 本件各発明は,このような課題を解決するため,入力手段における命令 ボタンが利用者によって押されてから,離されるまでの間に,ポインタの 位置を移動させる命令を受信すると,画像データである操作メニュー情報 を出力手段に表示させ,入力手段における命令ボタンが利用者によって離\nされると,出力手段に表示されていた操作メニュー情報の表\示を終了させ ることにより,普段は画面上に操作メニュー情報を表示させずに,利用者\nにとって必要な場合に簡便に表示させることを可能\にするという構成を\n採用したものといえる(段落【0022】,【0023】,【0051】)。そ して,スムーズな画面操作を可能とするため,操作メニュー情報が表\示さ れている状態において,これをポインタで指定した場合,すなわち,実行 される命令結果を利用者が理解できるように出力手段に表示した画像デ\nータである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲にポインタの座標 位置が入った場合に,「操作メニュー情報にポインタが指定された場合に 実行される命令」として特定された,例えば,出力手段に表示される画面\n(ビュー)をスクロールさせるような命令など,コンピュータシステムに 対する命令が実行され,操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に,ポ インタの座標位置が入らなくなるまで当該実行を継続するという構成を\n採用したものといえる(段落【0009】,【0012】,【0013】,【0 016】,【0023】,【0051】)。
ウ 以上のような,本件各特許請求の範囲の記載文言及び本件明細書の各記 載によれば,本件各発明は,コンピュータシステムにおけるシステム利用 者の入力行為を支援するため,「コンテキストメニュー」や「ドラッグ&ド ロップ」における,操作メニュー情報が利用者に意に反して表示されるこ\nとに関わる課題や,移動先を決めないで画面をスクロールさせるような継 続的な動作に関わる課題を解決すべく,操作メニュー情報については,普 段は画面上に表示させずに,利用者にとって必要な場合に簡便に表\示させ るという構成を採用し,その上で,物理的に操作メニュー情報が占める座\n標位置の範囲にポインタの座標位置が入っているときに,コンピュータシ ステムに対する命令が実行されるようにして,スムーズな画面操作が可能\nとなるという構成を採用したものといえる。このような構\成を採用した以 上,構成要件B,E,F及びGの「操作メニュー情報」とは,利用者にと\nって,その表示,非表\示を明確に認識できることが前提となっており,物 理的に操作メニュー情報が占める座標位置の範囲が明確になっている必 要があることは明らかである。 そうすると,構成要件B,E,F及びGの「操作メニュー情報」につい\nては,利用者にとっての,視覚的な見地からの,命令内容の表示や実行の\n簡便性を実現する構成を意味するものであるものといえ,そのような見地\nに照らし,同「操作メニュー情報」とは,利用者が,その表示の有無を視\n覚的に認識でき,その表示内容から,所望の命令を実行した結果について\nも理解できるような,画像データである必要があるものと解するのが相当 である。
そして,構成要件Fの,(1)「操作メニュー情報がポインタにより指定さ れる」と「操作メニュー情報に関連付いている命令」を「実行」する,及 び(2)「操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなるまで当該実行 を継続する」との文言については,画像データである操作メニュー情報の 座標位置が利用者に視覚的に認識できることを前提に,(1)画面上に表示さ\nれた画像データである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に,ポイ ンタの座標位置が入った場合に,特定の命令を実行し,(2)操作メニュー情 報が占める座標位置の範囲に,ポインタの座標位置が入らなくなるまで当 該実行が継続され,入らなくなった場合には,当該実行が継続されないこ とを意味し,かかる動作状況を満たす命令であることをもって,「操作メニ ューに関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当である。
(3) 「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F,G)の充足性\n
ア 以上を前提に,まず,「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F,G)\nの充足性につき検討するに,被告製品の構成のエ(イ)ないし(エ)及び\nオ(イ)ないし(エ)のとおり,本件ホームアプリにおける上ページ一部 表示及び下ページ一部表\示(以下「上ページ一部表示等」という。)は,画\n像データであり,その内容や表示位置からすれば,これを見た利用者は上\nページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえるから,利 用者が,その表示の有無を視覚的に認識でき,その表\示内容から,所望の 命令を実行した結果についても理解できるような,画像データに当たるも のというべきであって,「操作メニュー情報」を充足するものと認められる。 イ これに対し,被告は,上ページ一部表示等は,単にホーム画面が縮小表\ 示されることによって当該ホーム画面の隣のホーム画面が見えているに すぎず,実行される命令を表す文字も,矢印表\示等何らかの操作ができる ことを示す絵や記号も表示されておらず,表\示自体から上ページ又は下ペ ージにスクロールするといった実行される命令結果を理解できる画像で はない旨を主張する。 しかし,被告製品の構成エ(イ)及びオ(イ)のとおり,上ページ一部\n表示等が表\示されるのは,利用者が移動させたいショートカットアイコン をロングタッチして,ドラッグ操作をして同アイコンを移動させる等して, 縮小モードになった状態であることからすれば,同アイコンを移動したい 利用者が,1つ上のページ又は1つ下のページの一部を表示した画像であ\nる上ページ一部表示等を見て,上ぺージ又は下ページが存在することのみ\nならず,上ページ一部表示等までドラッグすれば,上ページ又は下ページ\nに画面をスクロールさせることができるものと理解することも可能とい\nうべきである。 以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
ウ 他方,原告は,上ページ一部表示等のみならず,「左上領域」「右上領域」\n又は「左下領域」「右下領域」(以下「左上領域等」という。)も「操作メニ ュー情報」に該当する旨を主張する。 しかし,左上領域等は,被告製品の構成エ(ウ)及びオ(ウ)のとおり,\n特定の座標位置で囲まれた領域にすぎず,利用者が,その表示の有無を視\n覚的に認識でき,その表示内容から,所望の命令を実行した結果について\nも理解できるような,画像データに当たるものとは認められない。前記ア の説示に照らしても,左上領域等が,「操作メニュー情報」に当たるとは認 められず,同説示のとおり,「操作メニュー情報」に該当するのは,上ペー ジ一部表示等に限られるというべきである。\n以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
(4) 「操作メニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報 に関連付いている命令」を「実行」する,及び「操作メニュー情報がポイン タにより指定されなくなるまで当該実行を継続する」(構成要件F)の充足性\n ア 被告製品においては,被告製品の構成のエ(ウ)(エ)及びオ(ウ)(エ)\nのとおり,左上領域等の占める座標位置の範囲に,原告が「ポインタの座 標位置」に当たると主張(前記第2の3(2)[原告の主張]イ)する「当該 ショートカットアイコンをドラッグしている指等のタッチパネル上の位 置」又は「当該ショートカットアイコンをドラッグしているマウスカーソ\nルの先端の位置」の座標位置(以下「指等及びマウスカーソルの先端の座\n標位置」という。)が入った場合に「上ページスクロール1」,「上ページス クロール2」,「下ページスクロール1」,「下ページスクロール2」を生じ させる命令(以下,併せて「ページスクロール命令」という。)が実行され, 左上領域等の占める座標位置の範囲に指等及びマウスカーソルの先端の\n座標位置が入らなくなるまでページスクロール命令が継続され,入らなく なった場合には当該実行が継続されないことが認められる。
しかし,前記(3)のとおり,被告製品において,「操作メニュー情報」に 該当するのは上ページ一部表示等であるところ,証拠(甲19,乙11〜\n13)によれば,上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲と左上領域\n等の占める座標位置の範囲とは必ずしも一致せず,上ページ一部表示等は,\n左上領域等と一部重なる座標位置に表示されているにすぎないことが認\nめられる。このため,(1)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に,\n指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていても,その位置が左\n上領域等の占める座標位置の範囲外であればページスクロール命令が実 行されず,また,(2)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に,指等\n及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていなくとも,その位置が左\n上領域等の占める座標位置の範囲内であればページスクロール命令が実 行・継続されることとなる。 このような被告製品の動作状況から検討すると,ページスクロール命令 の実行や継続は,指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が,利用者が\nその範囲を視覚的に認識することができない,左上領域等の占める座標位 置の範囲に入っているかどうかによるものであり,これが肯定されれば, 指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が上ページ一部表\示等の占め る座標位置の範囲に入っていなくても,ページスクロール命令が実行され 継続されるものである一方,上記が否定されれば,指等及びマウスカーソ\nルの先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入\nっていても,ページスクロール命令は実行され継続されないこととなるも のである。 すなわち,被告製品においては,指等及びマウスカーソルの先端の座標\n位置が,偶々,上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占める座\n標位置の範囲に入った場合に限って,ページスクロール命令が実行・継続 されているにすぎないものである。これに照らせば,ページスクロール命 令については,飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲 において実行・継続されるものであって,上ページ一部表示等の範囲にお\nいて実行・継続されるものではないのであるから,上ページ一部表示等に,\nページスクロール命令が関連付いているとまでは認めるに足りないとい うほかない。 したがって,上記のとおりの被告製品の構成は,構\成要件Fの「操作メ ニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報に関連付 いている命令」を「実行」する,及び「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」という文言(構成要件F)\nを充足するとは認められない。
イ 原告の主張について
(ア) まず,原告は,上ページ一部表示等のみならず左上領域等も「操作\nメニュー情報」に相当する旨主張するが,前記(3)に説示したとおり,左 上領域等は,「操作メニュー情報」には当たるとはいえない。
(イ) また,原告は,上ページスクロール1が生じるのは,処理手段が上ペ ージスクロール1を行うプログラムを実行していることを意味するとこ ろ,同プログラムは上ページ一部表示が表\示されていないと実行されな いから,上ページ一部表示と同プログラムとは関連付いている旨主張す\nる。 しかし,前記説示のとおり,本件発明の構成要件F(「関連付いている」)\nについては,画像データである操作メニュー情報の座標位置が利用者に 視覚的に認識できることを前提に,(1)画面上に表示された画像データで\nある操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に,ポインタの座標位置 が入った場合に,特定の命令を実行し,(2)操作メニュー情報が占める座 標位置の範囲に,ポインタの座標位置が入らなくなるまで当該実行が継 続され,入らなくなった場合には,当該実行が継続されないことを意味 し,かかる動作状況を満たす命令であることをもって,「操作メニューに 関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当であるところであ る。しかして,被告製品においては,指等及びマウスカーソルの先端の\n座標位置が,偶々,上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占\nめる座標位置の範囲に入った場合に限って,ページスクロール命令が実 行されているにすぎないものであって,ページスクロール命令について は,飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲において 実行・継続されるものであり,上ページ一部表示等の範囲において実行・\n継続されるものではないというのである。 以上によれば,原告の上記指摘をもって,直ちに,上ページ一部表示\nと上記プログラムとが関連付いており,上ページ一部表示等の有無とペ\nージスクロール命令の実行の可否が関連付いているとまで認めることは できず,他に,両者の関連付けを推認させるに足りる事情も見当たらな い。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 原告は,構成要件Fの「操作メニュー情報がポインタにより指定さ\nれなくなるまで当該実行を継続する」には,「終了」といった記載はない から,操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった際に当該 実行が終了することまで求めてはおらず,実行がいつ終了するかは同構\n成要件とは関係がない旨を主張する。 しかし,上記(2)ウで述べたとおり「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」とは,操作メニュー情報 がポインタにより指定されている場合に当該実行が継続されることのみ ならず,操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった場合に は当該実行が継続されなくなることまで意味するものと解すべきところ, 前記アで述べたとおり,被告製品において,指等及びマウスカーソルの\n先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入って\nいない場合であっても,左上領域等の占める座標位置に入っていればペ ージスクロール命令の実行が継続されるものである以上,被告製品は上 記の構成要件を充足しないというべきである。なお,原告の主張する「実\n行」の「終了」が何を意味するか必ずしも判然としないが,仮に,上記 構成要件の解釈として,操作メニュー情報がポインタにより指定されて\nいる場合に当該実行を継続することのみを意味し,操作メニュー情報が ポインタにより指定されなくなった場合に当該実行が継続されないこと までは含んでいないとする旨を主張する趣旨であるとしても,そもそも そのような解釈は,本件各特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載 に照らし,上記構成要件の解釈として失当と言わざるを得ない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成29(ワ)31544 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月30日 東京地方裁判所
上記グラフにおけるZn(青線)とPk(赤線)の線形性にほぼ差異はない 上,ZnとXcの差(Zn−Xc)のZnの値に対する比率((Zn−Xc)/Z n)は,Brix値が0%のとき約4.98%,10%のとき約3.82%, 20%のとき約2.75%,30%のとき約1.62%,40%のとき約1. 46%,50%のとき約0.99%であって,ZnとXcの値の差は全体的に かなり小さく,Zn≒Xcと評価しるものであって,そうすると,式(B)は, 重心であるZnの平均値を出しているにすぎないというべきである。 また,式(B)の分子の式(Zn+(Zn−Xc))については,(1)Xc値> Zn値の場合,(2)Xc値=Zn値の場合,(3)Zn値>Xc値の場合があり得るが, (2)の場合にはPkの値は重心位置と一致する上,上記計測結果のような(1)の 場合又は(3)の場合に,式(B)により算出されるPkの値(被告の主張によれ ば臨界角点)が理論上の臨界角点により近似することの合理的な説明はなさ れておらず,そのことを示す的確な証拠もない。そうすると,式(B)が臨 界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認めることはできず,む しろ,前記のとおり,ZnとXcの値の差は全体的にかなり小さく,Zn≒X cと評価し得るものであることを踏まえると,式(B)は重心であるZnの平 均値を出しているものというべきであり,さらに,被告製品において式(B) に基づき複数の試行を行っていることも,同製品が構成要件Eを充足すると\nの結論を左右しない。
ウ 式(C)について
本件発明における式(2)は,「Pc=Pc’+C」というものであると ころ,本件明細書等の段落【0035】〜【0038】,段落【0040】, 【0041】によれば,定数Cは,重心位置Pc’に加算して臨界角点Pc (=Pc’+C)を求めるための定数であり,屈折率が既知である試料を用 いた実験により予め決定された値であると認められる。そして,本件発明は,\nこのように式(1)と式(2)を組み合わせることにより,臨界角点を直接 求めるよりも,同点をより正確に求めることができるとの効果を奏するもの であると認められる。 他方,被告製品の用いている式(C)は,「ΔPc=PCT20−PC0」とい うものであるところ,被告製品説明書,証拠(甲7,8,乙1,9)及び弁 論の全趣旨によれば,PCT20は,式(A)により得られたZn値を式(B) により調整したPk値(前記判示のとおり,重心であるZnの平均値)を,2 0°Cの環境下での値に換算した値であるから,この値は,上記手順により調 整された光量分布曲線の一次微分曲線(あるいは一次差分曲線)の重心位置 のアドレス値(甲7・10頁における「ゼロセット後 10%測定」欄の「Bary T20」の値(30.146))であり,PC0は,20°Cの環境下で濃度0%の 水を用いて計測した重心位置のアドレス値(同頁における「水基準書き込み 後 水」欄の「CAL OffSet」の値(18.54758))であること,また, 水の屈折率は既知であるところ,被告製品の理論上の臨界角点のアドレス値 は18.50000であることが認められる。 そして,甲7によれば,被告製品は,(1)上記PCT20の値(上記「Bary T20」 の値)を入力し,(2)「Bary T20」の値から「CAL OffSet」(水書き込みアド レス値)を差し引いた値を計算する,(3)上記(2)の値をBrix値に換算し, 「Saccharin T20」(Brix値)を算出する,(4)ゼロセットオフセット値を 読み込む,(5)「Saccharin T20」(Brix値)から「ゼロセットオフ値」を 差し引き,その結果を「Brix Value」(Brix値)として算出する,(6)「Brix Value」(Brix値)を「Final Rfact」(屈折率)に換算するという順序 でプログラムが実行されているものと認められる。 上記のプログラム実行過程のうち(2)の計算式は,試料の重心位置のアドレ ス値である「Bary T20」(PCT20)の値から水の重心位置のアドレス値であ る「CAL OffSet」(PC0)の値を差し引くものであり,試料の重心位置のア ドレス値の原点を水の重心位置のアドレス値に改めるとの意味を有するも のであるところ,このPC0値(18.54758)は理論値(水の理論上の 臨界角点のアドレス値である18.50000)との差(0.04758) を含む値であるということができる。そうすると,上記(2)の計算式は,試料 の重心位置のアドレス値から水の重心位置のアドレス値を直接差し引くも のであるが,実質的には,PCT20及びPC0の双方から水の臨界角点の理論 値(18.50000)を控除していったん同理論値を原点とする試料の重 心位置と水の重心位置の各アドレス値を算出し,さらに前者から上記差の値 (0.04758)を調整しているに等しく,試料の重心位置のアドレス値 に,屈折率が既知である水を用いた実験により予め決定された定数(−0.\n04758)を加算する計算をしているのと同義であるということができる。 したがって,式(C)は,式(2)を充足する。
(3) 被告の主張について
ア 被告は,式(1)と式(A)が形式的に異なっているから,被告製品は構\n
成要件Eを文言充足しないと主張する。 しかし,式(1)は,光量分布曲線の一次微分曲線(あるいは一次差分曲 線)の重心位置Pc’を求めるものであって,式(A)と技術的思想を同じ くするものであり,かつ,式(A)は式(1)に変形し得るものであって, 当業者であれば,式(A)と式(1)が実質的に同一の式であると認識し得 るというべきである。 そうすると,式(1)の技術的範囲は式(A)を包含するものと認めるの が相当である。
イ 被告は,被告製品におけるZnは13回算出され,更にPkを5回算出して 臨界角点Pcを算出しているのに対し,本件発明は,重心位置Pc’を1回 算出し,これに定数Cを加えてPcを算出しているのであるから,技術的思 想が異なると主張する。 しかし,Znが重心位置を求める式であると認められるのは前記のとおり であり,これを13回にわたり求めて,平均値を算出するといった手法は当 業者が容易に採用し得る技術常識に属するものと解される。また,前記のと おり,式(B)が臨界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認め ることはできず,むしろ,重心であるZnの平均値を出しているものという べきであることは前記判示のとおりであるから,本件発明と被告製品の技術 的思想が異なるということもできないというべきである。
ウ 被告は,PC0はΔPcを算出するための基準数値にすぎないから定数Cに 対応する概念ではなく,ΔPcも本件発明の式(2)のPcに対応する概念 ではなく,フェーズが異なるなどと主張する。 しかし,ΔPcを算出する式(PCT20−PC0)が有する意義は前記のとお りであって,被告製品においても試料の重心位置につき差分を調整すること で臨界角点を求めている点で本件発明と変わりがないから,式(C)が式(2) と実質的に異なるということはできない。
エ 被告は,本件発明における式(2)に関し,Pc’は特定の装置における 測定値ベースの臨界角点であり,定数Cは当該装置毎の個体差を較正する値 にすぎないなどと主張する。 しかし,前記のとおり,式(1)により得られるPc’は光量分布曲線の 一次微分曲線(あるいは一次差分曲線)の重心位置であるから,臨界角点と は異なるものであって,本件発明がこれに定数Cを加えることで臨界角点を 求めるものであることは,前記判示のとおりである。
(4) 以上のとおり,被告製品は構成要件Eを充足し,また,被告製品が構\成要件 A〜D及びFを充足することは前記前提事実(3)ウのとおりであるから,被告 製品は,本件発明の技術的範囲に属する。
・・・
(1)特許法102条2項に基づく損害額について
ア 被告は,(1)平成28年9月9日から平成30年2月9日までの間に被告製 品を137個販売し,(2)その売上総額は204万4164円であり,(3)被告 製品1個当たりの製造原価は1万0249円であるが,(4)特許法102条2 項所定の被告の利益額を算出するに当たっては,(3)に加えて配送費合計16 00円を控除すべきと主張するところ,(1),(3)及び(4)については,当事者間 に争いがなく,証拠(乙10〜12)によれば,(2)の事実を認めることがで きる。 そうすると,原告の損害額は,特許法102条2項に基づき,63万84 51円(=204万4164円−(137個×1万0249円+1600円)) と推定される。被告がこれを超える利益を得たことを認めるに足りる証拠は ない。
イ 被告は,寄与率を考慮すべきと主張する。しかし,本件発明は,屈折率を 測定するための臨界角点の算定という,屈折計の本質的ないし根幹的技術に 関するものであって,その可分的な一部に関するものではないから,本件で 寄与率を考慮すべきとは認められない。被告主張の諸事情は,この結論を左 右しない。
(2) 弁護士・弁理士費用について
本件事案の難易,請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると,被告の侵 害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金として6万円を認めるの が相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成30(ワ)13400 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 東京地方裁判所
原告は,本件発明1のうち,挿入力の増加の防止のための構成がその本\n質的部分であるとした上で,被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから,被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず,同製品は本件発明1の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし,本件発明1は,特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて,従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり,他方, 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると,挿入力が強 くなり作業性が悪化することから,挿入力は弱いままで,抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる(本件明細書等の 段落【0009】,【0013】〜【0015】)。そうすると,本件発 明1の本質的部分は,挿入力は弱いままで,抜け力を強くするための構成\nにあり,従来技術との対比でいうと,特に抜け力の強化のための構成が重\n要であるというべきである。 そして,本件発明1は,上記課題の解決のため,(1)メインアーム部と, メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し,(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり,(3)サブアーム部の上端部を,上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより,取付孔 への挿入性の向上を図るとともに,アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が 加わったときは,係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる(特許請求の範囲,本件明細書等の段\n落【0017】,【0029】,【0032】,【0033】,【003 6】,【0037】)。
ウ 他方,被告製品においては,サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ,当該フック部と車体のルーフ孔の距離が0.3mmであると認め られるから(乙13),抜け方向に荷重が加わった際に,フック部は0. 3mm程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり,爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして,被告製品における抜け力に関し,被告が実施した実験結果(乙 5)によれば,本件発明1の実施品の抜け力は186Nであるのに対し, 被告製品の抜け力は,215.8N,227N,271N,295Nであ り,最小でも約30N,最大で約110Nの差が生じたことが認められる。 また,被告が実施した,被告製品のコの字型部材(サンプル(1))と,被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの(サンプル(2))を用 いた実験結果(乙14)によれば,前者の抜け力の平均値は227.60N,後者の抜け力の平均値は73.51N(いずれも10回実施)であり, フック部を備えたコの字型部材の方が,抜け力において約150N大きい ことが認められる。 前記のとおり,被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ,これに上記の各実験結果を併せて考慮すると,被告製品は, 本件発明1の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ,そ の抜け力の大きさは,同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり,少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。
なお,原告は,乙14実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が\nあるとして,乙14実験の信用性を争うが,サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり,上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり,乙14実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて10回ずつ実験を行っているところ,数値にば らつきはあるものの,サンプル(1)は200N以上であり,サンプル(2)は概 ね60〜100程度であり,全体的に100N以上の差が生じていること に照らすと,その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり,抜け力の増大という課題を解決するための構成は本\n件発明1の本質的部分ということができるところ,本件発明1はこの課題 をアンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し,被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ,そうす ると,被告製品は本件発明1と異なる構成により上記課題を解決している\nということができる。
そうすると,本件発明1と被告製品はその課題解決のための特徴的な構\n成において相違し,本件発明1と被告製品との相違点は,この課題解決に 必要な構成に関するものであるから,同相違点は本件発明1の本質的部分\nに関するものであるということができる。
オ したがって,本件発明1と被告製品の相違点は,本件発明1の本質的部 分に関するものではないということはできないので,被告製品は第1要件 を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
平成31(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記(1)の認定事実によれば,本件発明1は,PCSK9とLDLRタンパク 質の結合を中和し,参照抗体1と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を,本件発明2は,PCSK9とLDLRタンパク質の結 合を中和し,参照抗体2と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を,それぞれ提供するものである。そして,本件各発明の課題は, かかる新規の抗体を提供し,これを使用した医薬組成物を作製することをもって, PCSK9とLDLRとの結合を中和し,LDLRの量を増加させることにより, 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し,高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し,又は予防し,疾患\nのリスクを低減することにあると理解することができる。 本件各明細書には,本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し,スクリーニングによってPCSK9に結合する抗体 を産生する2441の安定なハイブリドーマが確立され,そのうちの合計39抗体 について,エピトープビニングを行い,21B12と競合するが,31H4と競合 しないもの(ビン1)が19個含まれ,そのうち15個は,中和抗体であること, また,31H4と競合するが,21B12と競合しないもの(ビン3)が10個含 まれ,そのうち7個は,中和抗体であることが,それぞれ確認されたことが開示さ れている。また,本件各明細書には,21B12と31H4は,PCSK9とLD LRのEGFaドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 21B12は参照抗体1に含まれ,31H4は参照抗体2に含まれるから,21 B12と競合する抗体は参照抗体1と競合する抗体であり,31H4と競合する抗 体は参照抗体2と競合する抗体であることが理解できる。そうすると,本件各明細 書に接した当業者は,上記エピトープビニングアッセイの結果確認された,15個 の本件発明1の具体的抗体,7個の本件発明2の具体的抗体が得られることに加え て,上記2441の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても,同 様のエピトープビニングアッセイを行えば,参照抗体1又は2と競合する中和抗体 を得られ,それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに,本件各明細書には,免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製,免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製,21B12や 31H4と競合する,PCSK9−LDLRとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され,当業 者は,これらの記載に基づき,一連の手順を最初から繰り返し行うことによって, 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,参照抗 体1又は2と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。
以上によれば,当業者は,本件各明細書の記載から,PCSK9とLDLRタン パク質の結合を中和し,参照抗体1又は2と競合する,単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため,新規の抗体である本件発明1−1及び2−1のモノ クローナル抗体が提供され,これを使用した本件発明1−2及び2−2の医薬組成 物によって,高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減するとの課題を解決できること\nを認識できるものと認められる。よって,本件各発明は,いずれもサポート要件に 適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と,「結 合中和することができる」という解決すべき課題(所望の効果)のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ,競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから,サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし,本件各明細書の記載から,「結合中和することができる」ことと,「参照 抗体と競合する」こととが,課題と解決手段の関係であるということはできないし, 参照抗体と競合するとの構成要件が,パラメータ要件であるということもできない。\nそして,特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において,アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり,特定の結合特性を有する抗体を得るために, その抗体の構造(アミノ酸配列)をあらかじめ特定することが必須であるとは認め\nられない(甲34,35)。 前記のとおり,本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和し, 本件各参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗体を提供するもので,参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びPCSK9と LDLR間の相互作用(結合)を遮断(「中和」)することができるものであること を構成要件としているのであるから,控訴人の主張は採用できない。\n
・・・
控訴人は,本件各発明は,抗体の構造を特定することなく,機能\的にのみ定義さ れており,極めて広範な抗体を含むところ,当業者が,実施例抗体以外の,構造が\n特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには,膨大な 時間と労力を要し,過度の試行錯誤を要するのであるから,本件各発明は実施可能\n要件を満たさない旨主張する。 しかし,明細書の発明の詳細な説明の記載について,当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求\nめられるのは,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が容易にその実施をできる程 度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていないことに帰\nし,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる からである。
本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ, PCSK9との結合に関して,参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり,機能的にのみ定義されているとはいえない。そし\nて,発明の詳細な説明の記載に,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和す ることができ,PCSK9との結合に関して,参照抗体1又は2と競合する,単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば,当業者は,その実施をすることが可能というべきであり,特許発\n明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ ることまで記載されている必要はない。 また,本件各発明は,抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから,LDLRが認識するPCSK9上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体(EGFaミミック)が発明の詳細な説明の記載から実施可能に\n記載されているかどうかは,実施可能要件とは関係しないというべきである。\nそして,前記(1)のとおり,当業者は,本件各明細書の記載に従って,本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,本件各特許の特許請求の範 囲(請求項1)に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから,本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために,当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって,控訴人の主張は採用できない
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 限定解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.12.27
令和1(ネ)10052 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人は,構成要件1Aは,画像情報を取得する機能\の有無に限らず, 「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」であると主張する。 本件発明1の構成要件1Aは,「画像情報,音声情報および言語を対応するパター\nンに変換するパターン変換器と,パターンを記録するパターン記録器と,」というも のであるところ,画像情報を取得する機能の有無に限らないという控訴人の主張に\nよると,本件発明1は,パターンに変換する画像情報が取得されたものでない場合 には,パターン変換器は,予め保持している画像情報を対応するパターンに変換す\nるものということになるが,このとき画像情報は,パターンに変換されることも,ま た,パターンとして記録されることもなく,画像情報として予め保持されていたも\nのということになる。 しかし,本件発明1の特許請求の範囲及び本件明細書等1には,画像情報が,パタ ーンに変換されることも,また,パターンとして記録されることもなく,予め保持さ\nれたものであるとは読み取ることができる記載はない上,かえって,本件明細書等 1の段落【0017】には,「【課題を解決するための手段】(請求項1に対応)」 として,「この発明における思考パターン生成機は画像情報,音声情報および言語を パターンに変換する。画像情報は画像検出器により検出され,対象物に応じたパタ ーンに変換される。・・・」と記載され,画像検出器により検出されるものとされて いる。 したがって,本件発明1の構成要件1Aが,画像情報を取得する機能\の有無に限 らないとの控訴人の主張を採用することはできない。 そして,本件装置が,外部から入力された表情等に関する画像をパターンに変換\nする機能を有していると認めるに足りる証拠がないことは,原判決「事実及び理由」\nの第4の2(2)イに判示するとおりである。 よって,本件装置が構成要件1Aを充足していると認めることはできない。\n
イ 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や被控訴人の主 張によると,本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関する情報(画 像情報)からディスプレイに表示するための画素データ(画像パターン)に変換され\nていることが分かると主張する。 しかし,構成要件1Aの「パターン変換器」が行うものとして記載された「画像情\n報・・・を対応するパターンに変換する」処理でいうところの「パターン」とは,画 像,音声及び言語に係る事象の特徴を,計算機たる検出器が識別することができる 「1」,「0」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味すると解されること は,原判決「事実及び理由」の第4の2(1)アが判示するとおりである。 そして,本件装置が,「本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関す る情報から,ディスプレイに表示するための画素データを作成する」としても,この\nことが,画像,音声及び言語に係る事象の特徴を,計算機たる検出器が識別すること ができる信号の組合せに変換する処理に当たらないことは明らかである。 したがって,控訴人の主張を採用することはできない。
ウ 以上によると,本件製品が構成1Aを充足すると認めることはできない。\n
(3) 争点2−2(構成要件1Bの充足性)について\n
ア 控訴人は,本件製品の紹介ビデオ(甲79)によると,顧客の銀行口座に 関する情報に対応するデータにパターンの変更が行われているから,本件装置はパ ターンを変更していると主張する。 しかし,「パターン」とは,画像,音声及び言語に係る事象の特徴が計算機たる検 出器が識別することのできる信号の組合せに変換されたものであり,「パターンの 変更」とは,このような信号の組合せ自体を変更するものである(原判決「事実及び 理由」の第4の2(3)ア)。顧客の銀行口座に関する情報に変更が行われているとし ても,このようなことは,パターンとパターンの結合関係を変更することによって も行うことができるから,本件装置の内部において,上記のような意味での「パター ンの変更」が行われていることを示すとは直ちに認められず,控訴人の主張を採用 することはできない。
イ 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や,本件製品の 紹介ビデオ(甲80)の説明によると,本件装置は「質問」に対し,学習の前と後で 回答内容が更新できるため,「回答内容」についてパターンの変更が実施されている と主張する。 しかし,本件装置が回答内容を更新しているということは,入力された言語情報 に対応する回答が変更されたということになるが,「言語に係る事象の特徴が変換 された信号の組合せ」が変更されたのか否かは明らかではないから,控訴人の主張 を採用することはできない。
ウ 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)や本件製品の紹介ペー ジ(甲81)に,「アメリアが文章をパーツに分解して,各単語の役割と,他の単語 との関係を解釈する」とある点について,本件装置は,「文章(=文,パターン)」 を「パーツ(文要素や単語)」に分解するという「変更」を実施していると主張する。 しかし,本件装置が,「文章(=文,パターン)」を「パーツ(文要素や単語)」 に分解するということは,文章を,文要素や単語に分解して認識していることを意 味しているにすぎないとも考えられ,言語の「パターン」を変更しているとは直ちに 認められない。
エ 以上によると,本件装置が構成要件1Bを充足するとは認められない。\n
(4) 争点2−4(構成要件1Dの充足性)について\n
ア 控訴人は,原判決が構成要件1Dについて,「有用と判断した情報のみを\n記録する」として,「のみ」を含むクレーム解釈をしたことが,請求項に記載のない ことを含めたものであり,誤りがあると主張する。 しかし,「有用と判断した情報のみを記録する」と解釈すべきことは,原判決「事 実及び理由」の第4の2(4)アが判示するとおりであり,控訴人の主張を採用するこ とはできない。
イ 控訴人は,甲31及び38に「業務に特化した情報を学習するため,業務 に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」との記載があることから,本件装 置が有用な情報のみを記録するとの機能を備えていると主張する。\nしかし,価値ある入力した情報のみを記録するということをしなくても,入力さ れたそれぞれの情報の結合関係を生成しながら知識体系を構築することは可能\であ る上,本件製品の紹介ビデオ(甲12の図5)には,「全ての質問がアメリアの経験 や知識に加えられる」との説明があるから,「業務に特化した情報を学習するため, 業務に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」からといって,本件装置が構\n成要件1Dの「有用な情報のみを記録している」とは認められない。
ウ 控訴人は,本件製品の紹介ビデオの説明(甲12の図5,甲79,80) やパンフレットの記載(甲11の2)によると,本件装置は,入力した情報の価値を 分析し,有用な情報を自律的に記録していると主張する。 しかし,上記の紹介ビデオの説明やパンフレットの記載は,アメリアが同僚と顧 客のやりとりを観察し,処理マップを自分で作成するというものや顧客に必要な質 問を投げかけ,それに対する顧客の回答に応答するというものであり,それから直 ちに有用な情報を取捨選択し有用な情報のみを記録しているとは認められない上, 本件製品の紹介ビデオ(甲12の図5)には,「全ての質問がアメリアの経験や知識 に加えられる」との説明があるから,本件製品が構成要件1Dの「有用な情報のみを\n記録している」とは認められない。
エ 以上によると,本件装置が構成1Dを充足すると認めることはできない。\n
(5) 争点3(構成要件2C等の充足性)について\n
ア 控訴人は,構成要件2C等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自\n律的に知識を構築」の関係は並列であると主張するが,控訴人の上記主張を採用す\nることができないことは,原判決「事実及び理由」の第4の3(2)ア及びイが判示す るとおりである。 したがって,構成要件2C等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自律的\nに知識を構築」の関係が並列であるとの控訴人の主張を採用することはできない。\n
イ 控訴人は,前記関係が直列の関係であるとしても,本件装置が構成要件\n2C等を充足すると主張する。 (ア) 意味の評価について
控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や本件製品の紹介ビデオ (甲12の図5)の説明などから,本件装置は,「同じ言葉の異なる用法」の中から 「最も文脈にあてはまる用法」がどれかを評価し,知識を構築しており,本件装置\nは,情報(意味)を評価し,知識の獲得を実施していると主張する。 しかし,本件製品のパンフレット(甲11の2の3頁)の「彼女は同じ言葉の異な る用法を見分けるために文脈をあてはめることで,暗示されている意味を完全に理 解します。」との記載は,本件装置が,文脈をあてはめて言葉の用法を見分けている というにすぎず,本件装置が情報(意味)を評価した上で,その評価を踏まえて妥当 性が確認された情報を知識として獲得していることを示していると認めることはで きない。 また,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質問がアメリア の経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,意味を評価した上で,その 評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると認めることは できない。 これに対し,控訴人は,本件製品の紹介ビデオ(甲12の図5)の上記説明につい て,意味を評価し,その結果に基づいて自律的に有益な知識を獲得する機能を有し,\n全ての質問を知識として加えるというケースはあり得ると主張するが,上記の説明 は,単に全ての質問を知識として加えるという意味に理解するほかなく,本件装置 が意味を評価した上で全ての質問を知識として加えるという意味に理解することは できないから,控訴人の主張を採用することはできない。
(イ) 新規性の評価について
a 控訴人は,本件製品のパンフレットの(甲11の2)の記載からする と,本件装置は,遭遇した状況が知識として記録している場面と似ておらず,自分で 問題に対処できないことを識別する機能を有するから,新規性を評価し,知識の獲\n得を実施している旨主張する。 しかし,本件発明2は,「自律的に知識を獲得」するというものであり,人の手を 介することを予定しているものではない。しかるところ,本件製品のパンフレット\n(甲11の2の9頁)には,「自力で問題に対処できない場合,人間の同僚にその問 題を引き継ぎます。」と記載されていて,人間の同僚が介入することが予定されてい\nる上,本件装置がその後同僚の様子を見て特定の状況に対する最善の手順を見つけ ることがあるとしても,本件製品の紹介ビデオ(甲80)では,「生成した処理ステ ップの使用を管理者が了承すると,直ぐに彼女は同様の質問に対して自分自身で対 応できるようになります」と記載されていて,管理者が了承しないと,知識として獲 得されないから,本件装置が「自律的に知識を獲得」するということはできない。 仮に,控訴人が主張するように,新しい処理ステップに関しては,本件装置の管理 者が了承する前に,既に生成し,記録しているとしても,本件装置の管理者が了承し なかった処理ステップまでが知識として獲得されるものではないから,本件装置が 「自律的に知識を獲得」すると認めることはできない。
b なお,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,新規性を評価 した上で,その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは,上記(ア)と同様である。
(ウ) 真偽を評価する機能\n
a 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)や紹介ビデオ(甲 12の図5,甲79,80)には,本件装置が的確な質問を発して,「真実を明らか にする」機能(=真偽を評価する機能\)を有していることが示されていると主張す る。 しかし,本件製品のパンフレット(甲11の2)には,「問題の根本を見極めるた めの的確な質問ができる能力を持った」,「問題を明らかにするために必要な質問を\n投げかけることで,答えを提示することができます。」(6頁)との記載や,「事実 を明らかにするための的確な質問を発し,人間と同じように問題の明確な性質を顕 在化させることができるのです。」(11頁)との記載があるところ,これらの記載 と本件製品の紹介ビデオ(甲79,80)によると,本件装置の質問は,顧客の要望 を明らかにするためのものであって,真偽を判断するためのものであるとは認めら れないから,本件装置が,真偽を判断した上で,自律的に知識を獲得していると認め ることはできない。
b 控訴人は,知識に対して論理を当てはめ,プロセス全体の各ステッ プを自律的に進め,論理的な結論を得るためには,本件装置は,何が真であり,何が 偽であるかを評価する必要があると主張する。 しかし,論理的な結論を得るためには,情報間の結合関係を正確にする必要はあ るが,必ずしも入力した言語情報の真偽の妥当性を評価する必要性は認められない。
c なお,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,真偽を評価し た上で,その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると 認めることはできないことは,前記(ア)と同様である。
(エ) 論理の妥当性について
a 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や,本件製 品の紹介ビデオ(甲79)によると,本件装置は,「積極的に論理を当てはめ」,「事 実を明らかにするための明確な質問を発し」,「問題の明確な性質を顕在化し」,「論 理的な結論を得て」,「事実を明らかにするための的確な質問」及び「回答」を記録 して知識を獲得するという一連の動作を実施していることが分かるから,本件装置 は,情報を評価(論理の妥当性)し,知識の獲得を実施していると主張する。 しかし,「論理的な結論」,「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより, アメリアは問題を解決することもできます。彼女が知っている情報の本体に立ち返 ることで,自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするための的確な質問 を発し,人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができるのです。」 との本件製品のパンフレット(甲11の2の11頁)の記載や,アメリアの「質問」 に対する顧客の「回答」が記録された本件製品の紹介ビデオ(甲79)からは,本件 装置が入力した言語情報の論理の妥当性を確認しているとまでは読み取れないし, また,論理的な結論を得るためには,情報間の結合関係を正確にする必要はあるが, 必ずしも入力した言語情報の論理の妥当性を評価する必要性は認められないから, 控訴人の主張を採用することはできない。
b 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載によると, 本件装置は,論理を適用し(=論理の妥当性を評価し),経験を通して学習している (=記録している),すなわち,言語情報の論理の妥当性を評価し,経験した内容を 知識として獲得していると主張する。 しかし,本件装置が,「・・・論理を適用し,暗示されている内容を推定し,経験 を通して学び,感情すらも察知」(甲11の2の3頁)するものであるとしても,こ のことから本件装置が入力した言語情報の論理の妥当性を評価しているとは直ちに 認められないから,控訴人の主張は採用できない。
c 控訴人は,本件製品の紹介ビデオ(甲79)には,本件装置が条件付 き処理を実施していることから,論理的に対応し,情報を記録していると主張する。 しかし,本件装置が,顧客の回答が「はい(yes)」なら,受取人リストに追加し, 回答が「いいえ(no)」なら,受取人リストに追加しないという処理をするとしても, このことは,顧客の回答に基づいた処理をしていることを示すにすぎず,本件装置 が論理の妥当性を評価しているとは認められない。 d なお,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,論理性を評価 した上で,その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは,前記(ア)と同様である。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12.23
平成28(ワ)2067等 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月28日 大阪地方裁判所
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって,特\n許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従 来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。\nこの本質的部分については,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許 発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何で\nあるかを確定することによって認定するのが相当である。その認定に当たっては, 特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応 じて定められることからすれば,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書記 載の従来技術との比較から認定することが相当である。 その上で,第1要件の判断,すなわち,対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には,上記のとおり確定される特許発明の本質的部分 を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し,これを備えていると認められ る場合には,相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件の場合
(ア) 本件各発明の本質的部分
a 前記1(1)のとおり,本件明細書によれば,本件各発明は,歯に付着したプラ ークの除去及び歯茎のマッサージに好適なロール歯ブラシの製造方法及びその製造 装置に関するものである。上記製造方法等に関する従来技術は,ナイロン等の多数 の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の 溶着部を形成し,溶着部を加圧して扁平状とし,扁平部の軸孔となる部分をカット して,加圧することにより素線群の全体を略円形とし,かつ扁平部を略円形とし, その後,扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し,シート状のブ ラシ単体を製作するというものである。この従来技術には,ブラシ単体の厚みを均 一とするには熟練を要し,ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密 度が不均一となり,工程数が多く複雑な工程を要するので,一貫した連続製造が困 難で回転歯ブラシの製造コストも高くなるという課題があった。そこで,これを解 決するため,本件各発明は,回転歯ブラシの製造方法として本件発明1の構成を,\n回転ブラシのブラシ単体の製造方法として本件発明2の構成を採用することで,各\n工程を画一的に処理することが可能となり,高度な熟練を要することなく均一な厚\nさのブラシ単体の製作を可能とし,また,本件発明1及び2の方法を容易に実施で\nきて,所期の目的を達成するため,回転ブラシのブラシ単体の製造装置として本件 発明3の構成を採用したものである。\n前記1(2)及び(3)のとおり,本件発明2及び3は,素線群の突出端の中央に,エア を素線群が突出させられる方向とは反対方向から吹き込んで素線群を放射方向に開 かせることとしている(構成要件G及びN)。これは,これにより,ブラシ単体を\n構成する素線同士の重なりがほとんどなくなり,均一な厚さのブラシ単体を製作す\nることができるとともに,ブラシ単体の製作速度を早くした場合にも素線を傷付け るおそれが少なくなるため,素線群の開きを高速度で行うことが可能となって,効\n率良くブラシ単体を製作することができるからである。この点に鑑みると,本件発 明2及び3の特許請求の範囲の記載のうち「素線群の突出端の中央にエアを吹き込 んで素線群を放射方向に開く」とある部分は,従来技術には見られない特有の技術 的思想を有する本件発明2及び3の特徴的部分であるといえる。
b これに対し,被告らは,本件発明2及び3の本質的部分が,エアを吹き込む ことにより素線群を簡易に均等に開くことができ,その状態で溶着,切除すること によりブラシ単体の製造を簡易かつ高速に行うことができるという点にあり,吹き 込むエアの方向が,素線群を送り出す方向とは逆方向かという相違部分は,本件発 明2及び3の本質的部分ではないと主張する。 しかし,本件発明2及び3は,上記課題の解決方法として,素線群をノズルから のエアを用いて放射方向に開くという構成を採用し,均一な厚さのブラシ単体を効\n率良く製作するために素線群を高速度で放射方向に開かせるため,素線群の突出端 の中央にエアを意図的に吹き込ませるものである。このような工程の所期の目的を 実現するための構成及び機序は,素線群を送り出す方向を基準としてエアを吹き込\nませる方向が順逆異なるのであれば,必然的に異なるものとならざるを得ない。そ の意味で,本件発明2及び3におけるエアを吹き込ませる方向は,本件発明2及び 3の特徴的部分というべきである。したがって,この点に関する被告らの主張は採用できない。
(イ) 前記1のとおり,原告製造方法は,素線群の突出端の中央にエアを吹き込ん で素線群を放射方向に開かせるという工程を備えておらず,また,原告製造装置は, 素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開かせる装置を備え ていない。すなわち,原告製造方法は本件発明2の,原告製造装置は本件発明3の 本質的部分をいずれも備えていない。このように,本件発明2と原告製造方法との 相違部分,本件発明3と原告製造装置との相違部分はいずれも本質的部分であるか ら,原告製造方法及び原告製造装置は,均等の第1要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2019.12.15
平成29(ワ)11147 損害賠償請求事件 特許権 令和元年11月11日 大阪地方裁判所
原告は,被告各製品の「第2の軸体8」が「流体の流れる方向が周期的に交互に 方向変換して流れる現象」の意味での「フリップフロップ現象」を発生させるため に使用される軸体であることを直接的に裏付け,これを認めるに足りる証拠を提出 しない。 かえって,証拠(乙40)によれば,被告が,「第2の軸体8」を通過するクー ラント液の状況を検証するため,被告製品(3/8inch)について,本来金属製である 接続機構6’を含む筒本体2及び入口側接続部材4を,下記【参考写真】のように\n透明プラスチック製のものにした上で(以下「実験対象物」という。),その内部 にクーラント液を通過させる実験を行ったところ,クーラント液につき,実験対象 物の入口側接続部材から流入し始めてから16分22秒の間,「第2の軸体8」の 軸部の外周面に形成された凸部32の間の交差流路を流れる際,その「流れる方向 が周期的に交互に方向変換して流れる現象」すなわち「フリップフロップ現象」の 発生が観察されなかったことが認められる。この実験結果の信用性につき,本来金 属製の部分を透明プラスチック製のものとしたことを考慮しても,疑義を差し挟む べき具体的な事情はない。
また,前記認定によれば,被告各製品の「第2の軸体8」の構成は,主として凸\n部32の形状につき各製品相互間で異なるものと見られる。もっとも,被告製品 (3/8inch)の「第2の軸体8」がフリップフロップ現象を発生させなかったにもか かわらず,他の被告製品(1/4inch,1/2inch,3/4inch,1inch)の「第2の軸体8」 がフリップフロップ現象を発生させるものであると見るべき具体的な事情はない。 原告自身,被告各製品の構成には,本件各発明の構\成要件充足性を検討するに当た って,有意な相違はないと主張しているところでもある。 以上によれば,被告各製品の「第2の軸体8」は,クーラント液を通過させても 「フリップフロップ現象」を発生させ得るものと認めることはできない。そうであ る以上,被告各製品の「第2の軸体8」は,「フリップフロップ現象発生用軸体」 (構成要件E,F)に当たらない(なお,仮に,被告各製品が,別紙「被告各製品\n構成目録(原告主張)」記載のとおりの構\成を有するとしても,その「第2の軸体 8」が,クーラント液を通過させると「フリップフロップ現象」を発生させ得るも のと認めることはできないことに変わりはないから,上記結論が異なるものではな い。)。 したがって,被告各製品の構成は,本件発明1の構\成要件E,Fを充足しない。 また,前記第2の2(4)のとおり,本件において,原告は,被告各製品の構成が本件\n特許の請求項2に係る発明の構成要件を充足するとの主張を撤回した。そうすると,\n被告各製品の構成は,本件発明3の構\成要件Mを充足しない。
(3) 原告の主張について
原告は,被告各製品の「第2の軸体8」が「フリップフロップ現象発生用軸体」 当たるとする根拠として,被告各製品のパンフレット(甲6)及び被告の特許に係 る特許公報(甲18の2及び3)の各記載を指摘する。 このうち,前者については,被告各製品である「ビックスは『フリップフロップ 流れ』を応用しています。水などの流体を菱型の柱を網目状に配列した四角の管に 通すと,管内に生じる渦により,管体から噴出する液体が,左右に規則正しくスイ ッチングする現象のことをフリップフロップ流れと言います。」などという記載が ある。しかし,ある性能等が製品のパンフレットに記載されているからといって,\n真実当該製品が当該性能等を有するとは限らない(そもそも,上記「フリップフロ\nップ現象」の説明は,原告主張に係る本件各発明での「フリップフロップ現象」の 意味とは異なる。)。 他方,後者については,そもそも被告各製品が後者の特許公報に記載された発明 の実施品であることを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,上記実験結果(乙40)にもかかわらず,これらの記載のみをもっ て,被告各製品の「第2の軸体8」がフリップフロップ現象を発生させ得ることを 認めること,ひいては被告各製品の「第2の軸体8」が「フリップフロップ現象発 生用軸体」であること(構成要件E,F)を認めることはできない。\nしたがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(4) 以上より,被告各製品の構成は,本件発明1の構\成要件E及びFを充足せず, 本件発明3の構成要件Mも充足しないから,被告各製品は,本件各発明の技術的範\n囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ネ)1008 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報\nを含む売り注文情報を生成する」の意義について (ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載から,構成要件Dの「注文情報生成手段」は,「前記金融商品の買い注文を行うた\nめの複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」(構成要件B)と「前記買い注文の約定によって保有したポジションを,\n約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を 生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され,「売り注文情報」を生成するのは,構\成要件Dの「注文情報生成手段」のうちの「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから,構成要件Gの「注文情報生成手段」及び構\成要件Hの「前記注文情報生成手段」は,いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理 解できる。
そうすると,構成要件Hの「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の\n売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は, 前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文 のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情 報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」,「前 記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」と の記載は,「売り注文情報生成手段」が,「前記約定検知手段」の 「前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が 約定された」との「検知の情報を受けて」,当該「最も高い売り注 文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含 む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり,「売り注 文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。 次に,本件明細書には,「シフト機能」による注文は,「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文\nや決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯と は異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注さ せる態様の注文形態」であること(【0078】),この「シフト 機能」は,「相場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一\n注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し,相場価格 を反映した注文の発注を行うことができる」(【0018】)とい う効果を奏することの開示がある。そして,構成要件Hの文言及び本件明細書の上記記載から,構\成要件Hは,「シフト機能」のうち,\n更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注済の「決 済注文」(売り注文)がシフトする構成のものを規定したものであることを理解できる。他方で,本件明細書には,「シフト機能\」のうち,更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注 済の「決済注文」(売り注文)がシフトする構成の場合において,新たな「買い注文」の発注やその約定によって,「シフト機能\」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。 以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項1)及び本件明細書の 記載を総合すると,構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」,「前記複数の売り注文\nのうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは,「売り注文情 報生成手段」(前記注文情報生成手段)が,「前記約定検知手段」 の「前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文 が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて,「さ らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生 成する」構成のものであれば,新たな「買い注文情報」の生成や「買い注文」の約定又はその検知に関わりなく,構\成要件Hに含まれるものと解される。
(イ) これに対し控訴人は,(1)本件発明の特許請求の範囲(請求項1) の記載によれば,構成要件Hの「前記検知の情報を受けて,…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成\nする」とは,直前の検知の情報を条件として,これに続いて,前記 の売り注文が発生するという意味であって,これらの間に他の処理 が介在する記載はないこと,(2)本件明細書には,従前の新規注文B 1ないしB5及び従前の決済注文S1ないしS5が全部約定したこ とを検知し,この検知の情報を受けて,新たな新規注文B1ないし B5及び新たな決済注文S1ないしS5を一括発注するものであり (【0142】ないし【0154】,図35),「前記検知の情報 を受けて」(構成要件H)と,「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」(構\成要件H)との間に,他の手続が介在するもの,例えば,新たな新規注文B1ないし B5と新たな決済注文S1ないしS5とを新規に一括発注せずに, まずは新たな新規注文B1ないしB5を発注し,その約定を検知し てから,新たな決済注文S1ないしS5を発注するようなものにつ いての開示はないこと,(3)本件出願の経過において,被控訴人は, 拒絶理由通知を受けて,本件手続補正書及び本件意見書を提出して, 本件出願に係る旧請求項1に構成要件EないしGを新たに加え,構\ 成要件Hを補正する手続補正を行うとともに,本件意見書において, シフトが生じるための条件として,最も高い売り注文の約定状況の みを監視することとし,それ以外の処理を監視することを除外する 旨を主張したことを総合すると,構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の\n売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高 い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう 「前記検知の情報を受けて」とは,「前記相場価格が変動して,前 記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文 価格の売り注文が約定されたことを検知すると」,他の処理を何も 介在せずに,直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り 注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張 する。
しかしながら,上記(1)の点については,本件発明の特許請求の範 囲(請求項1)の記載中には,構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数\nの売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ 高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に, 「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しな い。
次に,上記(2)の点については,前記(ア)で説示したとおり,構成要件Hは,「シフト機能\」(【0078】)のうち,更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注済の「決済注文」(売 り注文)がシフトする構成のものを規定したものであるところ,本件明細書には,「シフト機能\」のうち,更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注済の「決済注文」(売り注文)が シフトする構成の場合において,新たな「買い注文」の発注やその約定によって,「シフト機能\」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。また,控訴人が挙げる本件明細書の記載 (【0142】ないし【0154】,図35)は,「発明の実施の 形態の3」に係るものであるが,本件明細書には,「上記の「シフ ト機能」は,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態2の構\ 成において適用することもできる。」こと(【0151】)及び「上 記各実施の形態は本発明の例示であり,本発明が上記各実施の形態 のみに限定されることを意味するものではないことは,いうまでも ない。」こと【0164】の記載があることに照らすと,控訴人が 挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Hを限定解釈すべき理由はない。\n
さらに,上記(3)の点については,被控訴人は,本件手続補正書(乙 14)により,本件出願に係る旧請求項1について,「前記相場価 格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち, 最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると, 前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受 けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさら に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成 する」(下線は,補正箇所を示す。)と補正し,本件意見書(乙1 5)において,「本願発明においては,一の注文手続で生成された 複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情 報の生成…は,一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基 づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知され たことを基準に行われることになります。そのため,システムにお いては,特定の注文に係る注文情報(相場の移動方向側である,最 も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や,最も低い売 り注文価格の売り注文に係る売り注文情報)の約定状況のみを監視 すれば,新たな注文情報の生成(一の注文手続で生成された中で最 も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成 …を,ただちに生成することができ,システムの情報保持や情報監 視のための負担が大きくなることはありません。これにより,本願 発明においては,新たな注文情報の生成や,その注文情報に基づく 注文の発注等の処理を,システム負荷の軽い,簡易な手順によって 処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認 められるが,他方で,本件手続補正書及び本件意見書は,平成29 年4月11日付けの拒絶理由通知(乙18)において「引用文献1 に記載された発明に引用文献2に記載の技術を適用し,引用文献1 に記載された発明において,繰り返し注文を行う際,相場価格の上 昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成 するように構成することは,当業者ならば容易に為し得ることである。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに\n照らせば,本件手続補正書及び本件意見書は,本件発明が,複数の 売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて, 同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を 有し,進歩性を有する旨を主張したものであって,本件意見書の「約 定状況のみを監視すれば」,「ただちに生成する」といった記載か ら,両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する構\成を本件発明から除外したものということはできない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 構成要件Hの充足性について
(ア) 前記2(3)イ(イ)のとおり,(1)ないし(4)の売り注文のうち,最も高 い注文価格の番号113の売りの指値注文(指定価格114.90 円)が約定した後に,番号113の注文価格より「0.62円」高 い番号96の売りの指値注文(指定価格115.52円)がされて いることに照らすと,被告サーバにおいては,約定検知手段が複数 の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知す ると,注文情報生成手段が,この検知の情報を受けたことに基づい て,約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したこと が認められる。 したがって,被告サーバは,構成要件Hを充足するものと認められる。\n
・・・・
控訴人は,本件明細書の発明の詳細な説明には,構成要件Hに対応する「シフト機能\」に係る構成について,「いったんスルー注文」及び「決済トレー\nル注文」と組み合わせた,複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ1回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず,構成要件Hに含まれる「シフト機能\」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたもの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば,構\成要件 Hは,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから,特許 法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)に適合する とはいえない旨主張する。 ア そこで検討するに,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載中に は,構成要件Hの「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ\nとを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において,「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから,当該「売り注文情報」は,複数の場合に限らず,一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,(1)「シフト機能」について,「金融商品取引管理装置1や金融商品取引管理システム1Aにお\nいて,既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち,「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能\である。この「シ フト機能」による注文は,上述した,「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文(例えば後述する「リピートイ\nフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)等に基づいて,新 規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文 や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと(【0078】),(2)「シフト機能」は,「相場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場\n価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」(【0018】)という効果を奏すること,(3)「発明の 実施の形態3」は,「この実施の形態3の金融商品取引管理システムに おいては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,「ら くトラ」による注文と組み合わせ,さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。」(【0138】)ものであるが,「上記の「シフト機能\」は,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態2の構成において適用することもできる。」こと(【0151】)及び「上記各実施の形態\nは本発明の例示であり,本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは,いうまでもない。」こと(【016 4】)の記載がある。 上記(1)の記載から,「シフト機能」は,「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文や決済注文が発注される\n際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり,シ フトされる先に発注済の注文には,「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構\成が含まれること,先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価格帯」をシフトさせる構\成のものが含まれることを理解できる。また,上記(1)ないし(3)の記載から,「シフト機能」は,「相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し,「いった\nんスルー注文」,「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文(例え ば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)」 等の注文方法とは別個の処理であること,「シフト機能」にこれらの各種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。\n
ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には,図35に示す「実施の形態 3」(【0144】ないし【0148】)として,シフト機能に決済トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ,\n決済注文S5,S4が約定した後に,元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文B5,B4及び元の売り注文S5,S4と同じ注文価格の売 り注文S5,S4が再度生成されるが,この時点ではシフトは発生せ ず,通常のリピートイフダン注文が繰り返され,その後相場価格が変 動して,S1ないしS3の売り注文価格がトレールし,S1ないしS 3が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると,再度生成 された売り注文S5,S4は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして,S1ないしS5のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は,構成要件Hに含まれる,「シフト機能\」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一つであることが認められる。\nまた,シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には,図35において,S2及びS3の売り注文価格がトレールしないため,\nそれぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり,それぞ れ別々に約定し,その場合,実施の形態3の取引例でS5,S4が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に,S3,S2が約定 した段階ではシフトが生じず,その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのS1が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると,複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Hに係る構\成は,本 件明細書の上記記載から認識できるから,本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
(イ) これに対し控訴人は,図35には,S5,S4が約定した後に再 度S5,S4が生成されることの記載はなく,B5,B4には,直後 に「キャンセル」と記載されていることからすれば,S5,S4が約 定しても,元の買い注文B5,B4と同じ注文価格の買い注文B5, B4がそもそも生成されないか,生成されてもすぐにキャンセルされ ていると理解できること,加えて,本件明細書の【0144】ないし 【0147】にも,新たな新規注文B5及びB4は,個別に生成され るのではなく,(従前の)決済注文の全ての約定((従前の)決済注 文S1ないしS3の約定)を待って,新たな新規注文B1ないしB3 とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されている ことからすると,図35には,同図右上のS1ないしS3が同時に約 定し,もって,B5ないしB1及びS5ないしS1の全てが1回ずつ 約定した後に,「シフト機能」によるシフトが行われ,新たなB5ないしB1及びS5ないしS1が一括的に生成される場合が示されてい\nるに過ぎず,B5,B4に対応する決済注文S5,S4が約定すると, 元の買い注文B5,B4と同じ注文価格の買い注文B5,B4が再度 生成されることを看取できない旨主張する。 しかしながら,図35には,明示の記載はないが,決済注文S5, S4が約定した後に,元の買い注文と同じ注文価格の買い注文B5, B4及び元の売り注文S5,S4と同じ注文価格の売り注文S5,S 4が再度生成され,通常のリピートイフダン注文が繰り返されること は,「図30に示すように,相場価格64が上昇から下落に転じ,1 ドル=100.60円未満になると,約定情報生成部14は,決済注 文S4,S5を約定させる処理を行う。これにより,(新規注文情報 18114,18115に基づく)新規注文B4,B5と,(決済注 文情報18119,18120に基づく)決済注文S4,S5による イフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより,注文情報生成 部16は,元の新規注文B4,B5と元の決済注文S4,S5と同じ, 新たな新規注文B4,B5と元の決済注文S4,S5を生成する。」 (【0132】)との記載に照らしても明らかである。 したがって,控訴人の上記主張は,その前提において,採用するこ とができない。
エ 以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構\成のもの(実施の形態3)のほか,構成要件Hに含まれる,これ以外の構\成の もの(最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検 知すると,前記注文情報生成手段が,更に所定価格だけ高い「一の売り注 文情報」を生成するもの)についての開示があることが認められる。 したがって,構成要件Hは,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが認められ,本件発明はサポート要件に適合するものと認\nめられるから,これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ワ)9909 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月23日 東京地方裁判所
被告は,上記ア記載のA邸工事の施工方法又は防水構造は本件各発明の構\ 成要件をすべて具備すると主張するのに対し,原告は,同方法又は構造は構\ 成要件D等を充足せず,本件各発明と相違点1において相違するので新規性 は欠如しないと主張する。
(ア) 構成要件D等における「封止する状態にして固定」の意義\n
そこで,まず,構成要件D等の「封止する状態にして固定」の意義につ\nいて検討する。 本件発明1及び3の特許請求の範囲の記載(構成要件D及びK)によれ\nば,内部水切り部材は,その固定板下面と屋根に設けた開口部周囲の野地 板上面又は防水シート上面との間で液体の流通を封止する状態にして固 定して,水が開口部に侵入することを防止する機能を有するものであるか\nら,ここにいう「封止」とは,液体の流通を封じ,止めること,すなわち, 水等の液体が開口部に侵入しない状態にすることをいうものと解される。 また,本件明細書等の記載をみても,「開口部を固定板で直接的且つ内 外液密的に覆うように内部水切り部材(インナーフラッシング)を配置す る」(段落【0011】),「内部水切り部材の固定板を野地板又は防水 シート上に密着した状態で固定するものとした本発明」(段落【0017】), 「開口部12を完全に覆うことのできるサイズの固定板21を,その下面 端縁側が密着する状態で内部水切り部材20を固定」(段落【0022】), 「密着状態で接着・固定して,固定板21下面と防水シート11上面との 間で水が流通しない状態に封止する。」(段落【0031】),「固定板 21の防水シート11側への密着性(封止性)が極めて高いものとなり優 れた防水機能を実現」(段落【0035】)などとされているから,内部\n水切り部材は,その固定板の下面端縁側を野地板等に密着させることで, 水等の液体の開口部への侵入を防止する機能を有するものであると解さ\nれる。 そうすると,構成要件D等における「封止する状態にして固定」とは,\n内部水切り部材の固定板の下面と野地板等を,水等の液体が開口部に侵入 しない程度に密着させて固定する状態をいうものと解するのが相当であ る。 これに対し,原告は,構成要件D等の「封止」とは,「精密部品などを\n外気に触れないように,隙間なく包むこと。または,その技術。」を意味 すると主張するが,この定義は精密機械等に外気が接することを念頭に置 いたものであり,外気ではなく液体の流通が問題となる本件各発明におい ては妥当しない。
(イ) 構成要件F等における「前記固定板外周に沿って防水テープが貼\付され ている」の意義
更に進んで,構成要件F等における「前記固定板外周に沿って防水テー\nプが貼付されている」の意義について検討する。\n本件発明2及び4に係る特許請求の範囲の記載によれば,内部水切り部 材の固定板外周に沿って防水テープを貼付するのは,同固定板下面と開口\n部周囲の野地板上面等との間で液体の流通を封止する状態にして固定す るためであり,また,構成要件F等においては,「固定板外周に沿って」\n防水テープを貼付するものとされているから,「前記固定板外周に沿って\n防水テープが貼付されている」とは,内部水切り部材の固定板の外周全体\nに防水テープが貼付されていることを意味すると解するのが自然である。\n本件明細書等の記載をみても,防水テープ15で固定板21の外周に沿っ てその全周にわたって貼付する態様の実施例のみが記載されている(段落\n【0032】,【図4】)。 そうすると,構成要件F等の「前記固定板外周に沿って防水テープが貼\ 付されている」とは,内部水切り部材の固定板の外周全体に防水テープが 貼付されていることを意味するものと認められる。\n
(ウ) A邸工事と本件発明1及び3との対比
上記(ア)及び(イ)の解釈を前提として,A邸工事の方法等と本件各発明と を対比すると,A邸工事は,アルミフラッシングの「固定板の下面が開口 部周囲の野地板上面に密着して配置され」,かつ,「上記アルミフラッシ ングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及び左右両側には,粘着剤層を有 する防水テープを貼付する」構\成を有するのであるから,A邸工事は,上 記固定板の下面が,野地板上面と,水等の液体が開口部に侵入しない程度 に密着して固定されている構成,すなわち「アルミフラッシングの固定板\n下面と開口部周囲の野地板上面との間で液体の流通を封止する状態にし て固定する」構成を有するものと推認することができる。\n したがって,A邸工事は構成要件D等を具備し,本件発明1及び3は新\n規性を欠くこととなる。
(エ) A邸工事と本件発明2及び4との対比
前記のとおり,本件発明2及び4の構成要件F及びMの「前記固定板外\n周に沿って防水テープが貼付されている」とは,内部水切り部材の固定板\nの外周全体に防水テープが貼付されていることを意味するところ,A邸工\n事においては,アルミフラッシングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及 び左右両側には防水テープが貼付されているが,その軒側にはこれが貼\付 されていないから,この点で両者は相違することとなる。 したがって,本件発明2及び4が新規性を欠くということはできない。
ウ 進歩性の有無について
前記判示のとおり,A邸工事の方法と本件発明2及び4の構成要件F等は,\n固定板の外周のうち軒側に防水テープが貼付されているかどうかにおいて\n相違するところ,防水テープは,開口部に水が浸入しないようにするために 内部水切り部材の固定板に貼付するものであるから,四角形状の固定板の縁\n部分の上記3辺に防水テープを貼付した上,更に念を入れて軒側の下辺にも\n防水テープを貼付することについて,当業者であれば当然に想到し得たもの\nと考えられる。 これに対し,原告は,インナーフラッシングの固定板の3辺に防水テープ を貼付して固定していた構\成を,全周にわたり防水テープを貼付する構\成に 置き換えると,部材や工数が増加して過剰なコストや手間を要することにな るから,阻害要因があると主張するが,A邸工事の開口部は1辺が40cm程 度であること(乙12資料3)からして,軒側の1辺に防水テープの貼付す\nる部材のコストや工数の負担はごくわずかなものと考えられるので,原告の 主張するような阻害要因があるということはできない。 したがって,本件発明2及び4は,公然実施されたA邸工事に基づき当業 者が本件特許出願当時に容易に想到し得たものであるというべきである。
エ 小括
前記イのとおり,本件各発明に係る特許出願より前である平成19年6月 28日に公然と実施されたA邸工事は,本件発明1及び3の構成要件を全て\n充足するから,本件発明1及び3は新規性を欠く。 また,前記ウのとおり,A邸工事は,アルミフラッシングの四角形状の固 定板の軒側縁部分に防水テープが貼付されていない点で本件発明2及び4\nと相違するが,当業者は,同部分にも防水テープを貼付する構\成に容易に想 到し得るといえるから,本件発明2及び4は進歩性を欠く。 したがって,本件各発明は,いずれも特許無効審判により無効にされるべ きものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)12609 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月9日 東京地方裁判所
本件発明1は,(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ\nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段,(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段,(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段,(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより,赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに,案内音声である再生対象音の識別情報に対\n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする(【0005】)。
エ 以上に加えて,本件発明1は,前記送信手段が,当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し,前記受信手段が,情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用することにより,相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指\n定された言語に対応する関連情報を受信することができ,使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである(【0006】等)。\n
・・・
被告は,(1)乙9公報は,音響IDとインターネットを用いて,放音装置から放音 された音響IDによって識別される識別対象の情報に対し,これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙9技術を開示しているところ,本件 発明1も乙9技術を採用するものであり,相違点1−5ないし同1−7は,情報要 求に含まれる情報の内容,複数の関連情報の選択条件,関連情報の内容に係る相違 にすぎず,当業者が適宜設定できるものである旨主張するとともに,(2)当業者は, 乙9発明1に,乙10発明又は乙5公報及び乙10公報記載の周知技術,並びに周 知技術(乙14等)を組み合わせるなどして,相違点1−5ないし同1−7に係る 本件発明1の構成を容易に想到し得た旨主張する。しかしながら,まず,被告の上記(1)の主張については,前記(1)エと同様に,乙9 公報等に音響IDとインターネットを用いた同種の情報提供が開示されていたとし ても,本件発明1は,その手順や方法を具体的に特定し,使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるから,相違点1−5ないし同1−7に係る\n本件発明1の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。\n
・・・
5 争点6(差止めの必要性は認められるか)について 被告は,本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし,その理由とし て,(1)本件口頭弁論終結時点において,本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと,(2)被告は,平成30年5月以降,本件アプリの配信を中止し,多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており,本件訴訟の結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予\定であること,
(3)被告は,今後,顧客に対し,案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や,案内音声である第1言語の再生対\n象音が表す発音内容を第2言語で表\\現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,本件アプリは,本件発明1の技術的範囲に属 し,本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから, 前記第2の2(4)のとおり,被告は,少なくとも,平成29年5月頃から平成30年 6月頃まで,本件アプリを作成し,譲渡等及び譲渡等の申出をし,平成28年6月から平成29年3月までの間に3回にわたり本件アプリを使用することによって本\n件特許権1を侵害していたものである。 これらに加えて,被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明1の技術的範囲 に属することを否認して争い,本件特許1について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること,弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も,ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ,被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなども考慮すると,被告は,今後,本件特許権1を侵害するおそれがあるものというべ\nきであるから,原告が被告に対し,その侵害の予防のため,本件アプリの作成等の差止を求める必要性は認められるものというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)16555 特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟 令和元年10月29日 東京地方裁判所
ア 本件発明の特許請求の範囲の記載は「患者の血清中でプロカルシトニン3 −116を測定することを含む,敗血症及び敗血症様全身性感染を検出する ための方法。」であり,その構成要件Aは「患者の血清中でプロカルシトニン\n3−116を測定することを含む」というものであるところ,特許請求の範 囲には,その意義について規定する記載はないが,「測定」とは,一般的に, 「長さ,重さ,速さなど種々の量を器具や装置を用いてはかること」(大辞林 (第3版))との意味を有する。 そうすると,特許請求の範囲の記載からは,構成要件Aの「プロカルシト\nニン3−116を測定すること」とは,敗血症等を検出するため,血清中に 含まれるプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味する ものと解するのが自然である。
イ また,前記1(2)のとおり,本件明細書の記載によれば,敗血症等の患者の 血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンについて,従前プロシ\nカルシトニン1−116と暫定的,一般的にみなされるなどしていたところ, 本件発明は,敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカル\nシトニンが,プロカルシトニン1−116ではなく,プロカルシトニン3− 116であるという発見に基づき,新規な敗血症等の診断方法を提供するこ とを目的とするものである。そして,本件明細書の発明の詳細な説明には, 「プロカルシトニン3−116を測定すること」の意義について,特段の記 載はない。そうすると,本件明細書の記載からも,構成要件Aの「プロカル\nシトニン3−116を測定すること」とは,敗血症の検出のため,上記の発 見に基づきプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味し, その測定結果が敗血症等の検出に用いられることと理解できる。
ウ 原告は,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定すること」と\nは,プロカルシトニン3−116を敗血症等の検出に必要な精度で測定する ことをいい,プロカルシトニン1−116と区別してプロカルシトニン3− 116を特異的・選択的に測定することを必須とするものではない旨主張し, その根拠として,本件明細書の実施例において,プロカルシトニン3−11 6を特異的・選択的に測定することが困難なイムノアッセイによりプロカル シトニンの濃度を測定することが記載されていること,本件明細書の記載等 を踏まえると,患者の血清中でプロカルシトニン1−116とプロカルシト ニン3−116とを区別することなくプロカルシトニン一般を測定したと しても,その濃度は,おおよそプロカルシトニン3−116の濃度であり, 測定されたプロカルシトニン3−116の濃度は敗血症等の検出に必要な 精度になっていることを指摘する。 しかし,本件明細書のイムノアッセイによる測定に関する記載について, 正常者及び敗血症患者の血清中のプロカルシトニン濃度の測定結果と,これ と同時に行われたこれらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対 比することにより,正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニ ンにおいて際立っていることを示すものである旨の記載があることからす ると(段落【0059】【0062】【0063】【表3】),上記測定は,「敗\n血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の実施例であるとは認 められないから,原告の上記主張の根拠となるとは認められない。 また,仮に,敗血症患者の血清中に含まれるプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン3−116であるという関係があるとしても,プロカルシ トニン3−116を測定することとプロカルシトニン一般を測定すること が同義とはいえないことは明らかである,また,敗血症等であるかどうかが 明らかではない患者については,その血清中のプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン3−116であるかどうかは明らかではないといえるほ か,本件明細書には,患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定すること により敗血症等を検出する技術は本件発明の優先日前に従来技術として存 在したところ,本件発明は,従来技術に対して新規のものである旨が記載さ れているのであって,原告の主張は採用することはできない。 以上によれば,原告の主張には理由がなく,これを採用することはできな い。
エ 以上によれば,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定する\nこと」とは,プロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味す るものと解される。
(2)前記前提事実(第2の1(4)のとおり,被告装置及び被告キットを使用する と,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116とを区別する ことなく,いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することができ, その測定結果に基づき敗血症等の鑑別診断等が行われていると認められる。被 告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出する過程で,プロカルシトニ ン3−116の量が明らかにされているとは認められない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告方法は,構成要\n件Aを充足するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成29(ワ)7576 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
以上を踏まえ,顧客吸引力の観点から被告第2製品における本件第2 及び第3特許の技術的意義の有無及び程度を検討すると,まず,本件被告カタログ 記載の「6つの特徴」の1つとして,被告第2製品は「素手で持っても痛くありま せん。」との記載がある。「テーパ部」の解釈に関する被告の主張をも考慮すると, これは「テーパ部」の存在をうかがわせるものとも理解し得るものの,いかなる構\n成によって「素手で持っても痛く」ないことを実現しているのかは具体的に示され ていない。当該記載に付された写真では,製品のアンカーボルト挿通用の開口部に 手指を通して握る形で,当該開口部を囲む部材のうち長辺部分をなす部材のうちの 1つを掌全体で把持していること(甲4,乙32)に鑑みると,「テーパ部」の存在 故に「素手で持っても痛く」ないという効果を奏しているとも断じ得ない。また, 本件第2発明の効果2に言及する記載もない。 さらに,本件被告カタログには,「6つの特徴」の1つとして,「スピード施工」 が挙げられているところ,その部分には,被告第2製品の片方の端部の接続部につ いて「連結構造」との説明が付されている。もっとも,「連結構\造」とされる接続部 の構造や接続の仕方ないし効果に関する説明はない。\nむしろ,前記認定のとおり,本件被告カタログでは,被告第2製品の強度や換気 性能,供給・品質・価格の安定性,カットしやすい独自の形状を有する省施工商品\nであること等が強調されている。 この点は,原告や同業他社のカタログ等にも共通する。このうち,原告のカタロ グ等には「テーパ部」や「接続部」に関する記載も見られるものの,その構造は具\n体的に示されておらず,作用効果も,他の記載と比較すると,強調の度合いは低い。 むしろ,全周敷き込みの簡単施工や特殊構造の換気スリット・防鼠材といった点が\n前面に出されて強調されている。 以上の事情に加え,被告第2製品が本件第2発明の効果を奏しない形で使用され ることがあり得ることは否定できないこと(ただし,実務上そのような使用態様が 採られる割合は不明である以上,この事情を推定覆滅に当たって過大視することは できない。),前述のとおり,台輪の幅方向への移動を防止する別の方法もあること を踏まえると,本件第2及び第3発明は,施工容易性の実現という観点から一定の 顧客吸引力を有するといえるものの,本件第2発明の「テーパ部」の構成や本件第\n3発明の構成要件3C〜3Gの構\成を有することによる顧客吸引力は,相対的には 小さいというべきである。 なお,被告は,被告第2製品の形状変更後に売上げが増加したことを指摘してい るが,その裏付けとなる資料(乙60)は形状変更後の4か月の売上額を集計した ものにすぎないし,売上げの変動要因としては様々なものが考えられることから, 上記事情が直ちに本件第2及び第3特許が被告第2製品の需要に与える影響が小さ いことを裏付けると見ることはできない。 これらの事情を総合的に考慮すると,本件では,7割の限度で特許法102条2 項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の 各主張はいずれも採用できない。
エ ミサワホームに生じた損害
本件第2及び第3特許がいずれも持分2分の1の割合による原告とミサワホ ームの共有であることは当事者間に争いはなく,また,弁論の全趣旨によれば,ミ サワホームが自社施工工事分を除きこれらの特許を実施していないことが認められ る。そして,原告及び被告いずれも,特許法102条3項に基づき損害額を算定す る場合の本件第2及び第3特許の相当実施料率を4%程度とし,これを不合理ない し不相当と見るべき事情もないことから,相当実施料率は4%と認められるところ, 相当実施料率を乗じる対象となる売上額を消費税込の金額とすべき証拠はない。 そうすると,次のとおり,1463万7125円をもってミサワホーム(なお, 同社が本件第2特許の持分を取得する以前の損害賠償請求権を持分譲渡人が有して いるのであれば,その譲渡人を含む。)の損害額と認めるのが相当である。 そして,侵害された特許権が共有であったことにより侵害者の賠償すべき損害額 が単独保有の場合に比較して増額されるいわれはないことなどから,原告との関係 においては,更にこの限度で,特許法102条2項による推定が覆滅されるとする のが相当である。
(計算式) 売上額7億3185万6254円(税抜)×4%×1/2=146 3万7125円
オ 原告の損害額
以上より,特許法102条2項に基づく原告の損害額は,別紙「被告第2製 品に係る損害額(裁判所の認定)」の「原告の損害額」欄記載のとおり,4867万 8376円と認められる。
(計算式) 被告の利益の額2億1105万1670円×0.3−1463万7125円=4867万8376円
(4) 原告の予備的主張について\n
原告は,被告工場製品の製造販売について,特許法102条2項に基づき推定 される損害額が同条3項に基づくそれを下回る場合には,予備的に,同項に基づく\n損害額を主張する。 しかし,前記認定から明らかなとおり,特許法102条3項に基づき推定される 原告の損害額は,同条2項に基づくそれを上回るものではないから,この点に関す る原告の主張は採用できない。 仮に,原告の主張が,被告工場製品を除く被告第2製品の販売による損害につい ては特許法102条2項に基づき賠償請求しつつ,被告工場製品の販売による損害 については,同項に基づき算定される損害額が同条3項に基づくそれを下回る場合 に,予備的に同項に基づく損害額を主張する趣旨であったとしても,前記3(2)ウ (オ)で判示したとおり,被告工場製品とそれ以外の製品とで訴訟物が異なると見るべ き根拠はないから,原告の主張は採用できない。
(5) 弁護士費用(本件第1特許権の侵害分も含む。)について
原告は本件訴訟代理人弁護士に訴訟の提起・追行を委任したところ,被告の本 件第1〜第3特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,510万 円と認めるのが相当である。なお,逸失利益に係る損害の発生状況に照らし,弁護 士費用に係る損害賠償支払債務のうち,平成29年8月17日の時点で遅滞に陥っ ていたのは460万円の損害賠償債務であると認めるのが相当である。また,被告 の不法行為終了時期が平成30年10月末であることを踏まえると,残額の損害賠 償債務の遅滞損害金の起算日は同月31日とするのが相当である。
(6) 原告の逸失利益に対する確定遅延損害金について
原告が確定遅延損害金を請求している期間の,被告第2製品の製造販売による 損害に対する遅延損害金の金額は,別紙「被告第2製品に係る損害額(裁判所の認 定)」の「H31.2.28までの確定遅延損害金」欄記載のとおりの方法で計算すると,合 計1231万6870円である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成31(ネ)10031 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月10日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
本件訂正発明は,構成要件A〜Dからなる「薬剤分包用ロールペーパ」に係る\n発明であるところ(構成要件E),構\成要件Aには薬剤分包装置に関する事項が, 構成要件B及びDにはロールペーパ及びその中空芯管並びにロールペーパに配\n設される複数の磁石(以下,併せて「本件ロールペーパ等」という。)に関する 事項が,構成要件Cには薬剤分包装置及びロールペーパに関する事項が,それぞ\nれ記載され,構成要件Aにおいて,ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき,\n前者が後者に「用いられ」るものとして記載されている。 本件訂正発明は,「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら れるところ,物の発明の特許請求の範囲の記載は,物の構造,特性等を特定する\nものとして解釈すべきであること,「用いられ」が,構成要件Aの中で「・・・\nようにした薬剤分包装置に用いられ,」とされていることからすると,「用いら れ」とは,本件ロールペーパ等が構成要件Aで特定される薬剤分包装置で使用可\n能なものであることを表\していると解される。
(3) 被告製品の構成要件充足性について\n
ア 前記(2)を前提に検討すると,構成要件Aのうち「ロールペーパの回\n転速度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」との記載は,本件ロ ールペーパ等の「複数の磁石」につき,支持軸の片端に設けられた角度センサに よる検出が可能な位置に配設されるものであることを特定するものと理解でき,\nまた,構成要件Aのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその\n固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設 け」との記載は,本件ロールペーパ等について,薬剤分包装置の中空軸と接する 中空芯管の端に,中空軸と着脱自在に固定する手段を設けることで,そのような 態様で回転させられるものであることを特定するものと理解できる。 そうすると,本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は,構\n成要件B〜Eと,構成要件Aによる上記特定に係る事項によって画されるもの\nであるから,被告製品が構成要件A〜Eで特定される本件ロールペーパ等とし\nての構成を備えていて,構\成要件Aで特定される薬剤分包装置に利用可能なも\nのについては,被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ, 被告製品が構成要件Aで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かと\nいうことは,上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。\n
イ(ア) 被告製品は,前提事実(6)のとおりの構成を有するところ,弁論\nの全趣旨によると,被告製品の構成a,b,c,dは,本件訂正発明の構\成要件 B,C,D,Eをそれぞれ充足するものと認められる。
(イ) 弁論の全趣旨によると,被告製品の中空芯管内部に配設された 3個の磁石は,支持軸の片端に設置された角度センサによる信号の検出が可能\nな位置に配設されたものであり,また,被告製品は,薬剤分包装置の中空軸に着 脱自在に装着されて,固定時に中空軸と一体となって回転し得るものであって, その手段がロールペーパと中空軸が接する端に設けられているものと認められ る。
(ウ) したがって,被告製品は,本件訂正発明の構成要件B〜Eと構\成 要件Aによる上記アの特定に係る事項を充足し,構成要件Aで特定される薬剤\n分包装置で使用可能なものであると認められる。\n
ウ よって,被告製品は,本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認め られる。
(4) 一審被告らの主張について
ア 一審被告らは,本件訂正発明が用途発明であり,また,本件訂正発明 において保護されるべき特徴的部分は,薬剤分包装置側の構成又は機能\である ことなどから,被告製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられては\nじめて本件特許権に対する侵害が成立すると主張する。 しかし,前記(2)で検討したとおり,本件訂正発明は用途発明ではない。また, 本件訂正発明の技術的意義は,前記(1)認定のとおりであって,本件訂正発明の 特徴的部分が薬剤分包装置のみにあるということはできない。 したがって,一審被告らの上記主張は採用することができない。 なお,特許庁の審査基準(甲22)も,サブコンビネーション発明について用 途発明と同様に解釈することを求めているものとは解されない。
イ 一審被告らは,一審原告は,本件補正に際して,本件訂正発明の技術 的特徴が構成要件Aにあることを主張していたと主張する。\n一審原告は,本件補正に際しての意見書(乙9)において,本件補正に先立つ 拒絶理由通知の引用文献記載の技術に対して,「本願発明では『回転角度と測長 センサの検出信号を検出してロールペーパの巻量が検出可能な位置に配置され\nた磁石』の構成を有し,かつ『角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不\n一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸との ずれを検出するようにした』薬剤分包装置に用いられることを前提とするロー ルペーパについての発明であり,部分的な構成部材の抽象的,総論的な構\成が公 知,周知であるという理由だけで,本願発明の全体の構成が全て否定されること\nにはならないと考えます。」と主張しているものの,そのことから直ちに一審原 告が構成要件Aを充足する薬剤分包装置で用いられることが必要であるとまで\n主張していたとは解されないから,一審被告らの上記主張を採用することはで きない。
ウ 一審被告らは,原審裁判所の暫定的見解について主張するが,原審裁 判所の暫定的見解によって当審の判断が左右されないことは明らかである。
・・・・
一審被告らは,非純正品であることを明示して販売していたことや 購入者が調剤薬局であることなどからすると,購入者は被告製品が非純正品で あること,すなわち,一審原告の製品ではないことを正確に認識しており,出所 表示機能\や品質保証機能が害されていないから,商標法26条1項6号が適用\nされるか,実質的違法性を欠き,商標権侵害が成立しないと主張する。 しかし,以下の(ア)〜(オ)の各事情を考え併せると,購入者の全てが,被告製 品が非純正品であること,すなわち,一審原告の製品ではないことを正確に認識 していたとは認められず,一審被告らの上記主張はその前提を欠くものであっ て,採用することができない。
(ア) まず,前記(1)イのとおり,被告製品については,ウェブサイト のみならず,ダイレクトメールやFAX等による宣伝活動もされており,顧客が 一審被告らのウェブサイトを経由することなく被告製品を購入する場合もあっ たと認められるところ,ダイレクトメールやFAXにおいて,どのような態様で 宣伝がされていたのかは証拠上必ずしも明らかではない。
(イ) 一審被告らは,顧客に対し,非純正品であることを説明していた と主張するが,一審被告らの下で稼働していた従業員は,その点に関し,刑事事 件の公判廷において,「電話で口頭で説明するときに,『純正の紙と違うので』 と説明した。」,「電子メールで顧客に説明する際にも電話での説明の場合と同 様に非純正であることを顧客に説明したように思うが,よく覚えてない。」と曖 昧な供述をしている(乙4)上,同供述の裏付けとなるような顧客への対応マニ ュアルや顧客に送付された電子メールといったようなものは何ら証拠として提 出されていないから,一審被告らの主張するような説明が常に顧客に対してさ れていたとは認められない。
(ウ) 被告製品の購入を申し込むために顧客が一審被告らに対して送\n付する「注文書兼使用許可書」についても,「非純正」の文字(乙25の1・2) は,後から記載されるもので,常に記載されていたのかは証拠上明らかではない し,また,「非純正」の文字が取り立てて大きく表示されたり,強調されたりし\nていないことからすると,仮に記載されていたとしても顧客がこれに気付かな いこともあり得る。そして,前記(1)イのとおり,顧客から使用済み芯管の送付 を受けることなく,被告製品が販売された事例があることからすると,上記の 「注文書兼使用許可書」が常に使用されるものであったとも認められない。 納品書(乙26)についても,「分包紙はお客様からお預かりした芯で作りま した。」とだけ記載されており,非純正品であることが明示されているわけでは ない。
(エ) 前記(1)ウのとおり,一審被告らのウェブサイトには「非純正分 包紙」という記載があったものの,被告ネクストウェブサイトの非純正品ウェブ ページ1では,「ユヤマ分包機対応」との記載に続いて各種の製品が表示されて\nいるのみで,非純正品であることが明示的に記載されていなかった上,被告ヨシ ヤウェブサイトの非純正品ウェブページ2でも,「ユヤマ分包機対応」という記 載と共に各種の製品が表示されており,「非純正分包紙」という記載が左欄に小\nさく記載されているにすぎないことからすると,一審被告らのウェブサイトに 接した購入者の全てが,被告製品が非純正品であると正確に認識するとは認め られない。
(オ) 購入者が調剤薬局であるからといって,その注意力が常に一般 消費者に比して高いとまではいえず,購入者の一人が,被告製品が非純正品であ ると認識していたことがある(乙19,113)からといって,それにより全購 入者が同じ認識であったとは認められない。 なお,一審被告らは,調剤薬局の薬剤師の間では,当該調剤薬局で使用してい る薬剤分包用ロールペーパの仕入先や問合せ先に関する情報が共有されている と主張するが,上記(ア)〜(オ)で検討してきたところによると,そもそも,調剤 薬局において,被告製品を非純正品(一審原告の製品でないもの)として購入す るとは限らないというべきであるから,仕入先や問合せ先に関する情報が共有 されるかどうかは,本件の結論を左右するものではない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 消尽
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.11.17
平成31(ネ)10034 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
構成要件Gの「前記上位ノード変数データ」の意義について\n
a 本件発明の構成要件Fの「前記スクリプトは,当該ノードデータに\n含まれる変数データである自ノード変数データと,当該ノードの直系 上位ノードのノードデータに含まれる変数データである上位ノード変 数データを利用した演算を行って,前記自ノード変数データの値を求 める代入用スクリプトを含んでおり」との記載及び構成要件Gの「前\n記表示された木構\造のノードのうちの選択されたノードの前記自ノー ド変数データ,前記上位ノード変数データ及び前記スクリプトを表示\nするノードデータテーブル表示ステップ」との記載から,本件発明の\n「上位ノード変数データ」は,「当該ノードの直系上位ノードのノー ドデータに含まれる変数データ」であり,構成要件Fの「前記自ノー\nド変数データの値」を求める「代入用スクリプト」による演算に利用 される「変数データ」であることを理解できる。 次に,本件明細書には,「上位ノード変数データ」に関し,「変数 情報は,各ノードが保持するデータであって,変数名に対応させて記 憶される。記憶される変数は,下位ノードから参照される公開変数と, 自ノード内でのみ使用する限定変数を含む。また,変数の値(「変数 データ」と記述する場合もある。)は,固定値が設定されても,スク リプトの実行によって演算された値が設定されてもよい。また,UR Lが設定されてもよい。どのような値が設定されるかは任意である。」 (【0031】),「代入用スクリプトは,自ノードの変数の値を演 算するためのものである。代入用スクリプトは,自ノードの変数の値 である自ノード変数データと,そのノードの直系上位ノードの公開変 数の値である上位ノード変数データを利用して記述することが可能で\nある。」(【0032】),「公開変数表示領域に表\示される公開変 数は,自ノードの公開変数51と,直系上位ノードの公開変数52を 含み,直系上位のノードの公開変数52は,自ノードの公開変数51 と異なる色で表示される(図10では,フォントを変えて示してある。)。\nまた,公開変数には,固定値が入力される公開変数と,代入用スクリ プトの実行によって計算される公開変数があり,修飾領域に「なし」 あるいは「要計算」を表示することによりに区別される。」(【00\n65】)との記載がある。 そして,図10には,「直系上位ノードの公開変数の値である上位 ノード変数データ」として,「52」に「変数名」及びそれに対応す る「値」が示されている(例えば,「変数名」の欄「パネル色」・「値」 欄「KW−400」)。 これらの記載によれば,本件明細書には,「上位ノード変数データ」 にいう「変数データ」は,「変数の値」を含むデータであることの開 示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によ れば,構成要件Gの「前記表\示された木構造のノードのうちの選択さ\nれたノードの前記自ノード変数データ,前記上位ノード変数データ及 び前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表\示ステップ」に いう「前記上位ノード変数データ」は,「当該ノードの直系上位ノー ドのノードデータ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると解 される。
b これに対し控訴人は,本件明細書の【0032】における「変数の 値(「変数データ」と記述する場合もある。)」との記載は,「変数 データ」という用語を,文脈によって,変数の値を指す意味で用いる こともあるという注意書きであると理解できること,「変数データ」 は,変数名と変数の型を意味するというのが,プログラミングに関す る通常の用語であること(甲24),実質的にも,本件発明が「ノー ドデータテーブル表示ステップ」において上位ノード変数データを表\ 示させる目的は,表示された木構\造の個々のノードに対応付けられた 詳細情報を簡単に表示することができる(【0009】)ことにより,\n文書ファイル(プログラム)の編集を容易にする点にあり,変数名が 分かれば,その目的を達成することができることからすると,本件発 明の「上位ノード変数データ」は,本件明細書において文脈上変数の 値を意味すべき場合を除き,変数名を指すと解すべきである旨主張す る。 しかしながら,本件明細書には,「上位ノード変数データ」が変数 名のみで構成される場合を含むことについての記載や示唆はない。\nまた,前記aの本件明細書の記載に照らすと,【0032】の「変 数の値(「変数データ」と記述する場合もある。)」との記載は,「変 数データ」は「変数の値」を意味することを示した記載であると解す るのが自然であり,これが変数の値を指す意味で用いることもあると いう注意書きであるということはできない。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告プログラムにおける「ノードデータテーブル表示ステップ」の\n有無について
a 控訴人は,入力コネクタは,親ボックスから引き渡される値を記憶 する変数が図形化されたものであり,入力コネクタの名称が構成要件\nGにおける「上位ノード変数データ」に該当すること,インスペクタ 及びスクリプトエディタに表示される入力コネクタの名称に関する\n情報の表示は,上位ノード変数データを表\示するものであることから すると,被告プログラムは,「上位ノード変数データ」を表示する「ノ\nードデータテーブル表示ステップ」を備えている旨主張する。\nしかしながら,前記(ア)a認定のとおり,構成要件Gの「前記上位\nノード変数データ」は,「当該ノードの直系上位ノードのノードデー タ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると認められるところ, 入力コネクタの名称は,「変数の値」であるとはいえないから,控訴 人の上記主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。
b 控訴人は,被告プログラムの構成g’に関し,被告プログラムのS\nay Textボックスの「スクリプトエディタ」において「親から の変数を取得」機能を使う場合,上位ノードであるSayボックスの\n変数から利用可能なものを一覧表\示する機能があるから,被告プログ\nラムは,「上位ノード変数データ」を表示する「ノードデータテーブ\nル表示ステップ」を備えている旨主張する。\n しかしながら,控訴人の上記主張は,「スクリプトエディタ」にお いて,どのような「上位ノード変数データ」が表示されるのかについ\nて具体的に主張するものではないから,その主張自体理由がない。
c 以上によれば,被告プログラムは,「上位ノード変数データ」を表\n示する「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えているものと認\nめることはできないから,構成要件Gの「前記表\示された木構造のノ\nードのうちの選択されたノードの前記自ノード変数データ,前記上位 ノード変数データ及び前記スクリプトを表示するノードデータテーブ\nル表示ステップ」を備えているものと認めることはできない。\n
ウ まとめ
以上のとおり,被告プログラムは,構成要件Gの「木構\造を表示する木\n構造表\示ステップ」及び「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えて\nいるものと認められないから,構成要件Gを充足しない。\n
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.11. 6
平成30(ワ)7123 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月24日 大阪地方裁判所
ア そもそも,特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の 記載に基づいて定めなければならないとされている(特許法70条1項)。 そこで,本件特許の特許請求の範囲の請求項1をみると,構成要件Eとして,次\nのように記載されている。 「前記広告情報管理サーバは,前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た 後,再び前記指定地域内に戻っても,同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信 しないこと,を特徴とする無線通信サービス提供システム。」 ここでは, 「前記広告情報管理サーバは,同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信しな いこと,を特徴とする無線通信サービス提供システム。」 と記載されるのではなく,「前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後, 再び前記指定地域内に戻っても,」という文言(以下「本件指定地域に関する文言」 という。)がみられる。 このように,構成要件Eには本件指定地域に関する文言がわざわざ付加されてい\nるから,その文言には何らかの意味があるものとして理解すべきであり,構成要件\nEについて本件指定地域に関する文言がない場合と同じ解釈をすることは許されず, その文言によって本件発明1の構成が特定(限定)されているものと理解するのが\n相当である。
イ そこで,本件指定地域に関する文言の意義について検討すると,ここで いう「指定地域」とは,構成要件C及びDの記載を踏まえると,広告提供者から入\n手した配信先情報に含まれる,広告提供者が広告情報を配信する地域として指定し た地域のことである。 そして,構成要件Eは,構\成要件Dにおいて,無線通信装置が少なくとも1回は 広告情報の配信を受けたことを踏まえたものであるから,無線通信装置がその時点 で上記指定地域内に存在していたことが前提となるが,無線通信装置は,その性質 上,(1)その指定地域内に存在し続ける場合((1)の場合)もあれば,(2)指定地域外に 出る場合もあり,後者の場合については,指定地域外に出たままの場合((2)−1の 場合)もあれば,一旦指定地域外に出た後,再び指定地域内に戻る場合((2)−2の 場合)も想定される。 このうち,指定地域外に出たままの場合((2)−1の場合)に,無線通信装置に同 じ広告情報が送信されないことは明らかであるが(これは構成要件Eによるもので\nはなく,指定地域内の無線通信装置に広告情報を送信するという構成要件Dの構\成 による作用効果である。),指定地域内に存在し続けている場合((1)の場合)及び 一旦指定地域外に出た後,再び指定地域内に戻った場合((2)−2の場合)には,無 線通信装置に同じ広告情報が送信される可能性がある。\nそうすると,本件指定地域に関する文言は,無線通信装置に同じ広告情報が送信 される可能性がある場合のうち,上記(2)−2の場合だけを記載し,上記(1)の場合を あえて記載していないことになる。
ウ 以上のことを踏まえると,構成要件Eは,広告情報管理サーバが,特に,\n無線通信装置が一旦指定地域外に出た後,再び指定地域内に戻った場合に,同じ広 告情報を無線通信装置に送信しないことを特徴とするということを記載したものと 解すべきこととなる。 もっとも,これは,広告情報管理サーバが広告情報を無線通信装置に送信するも のであること(構成要件C)を踏まえ,同じ広告情報を再送信するかどうかという\n機能ないし作用効果に着目して記載されたものであり,その具体的構\成について, 当該広告情報管理サーバは,単に,同じ広告情報を無線通信装置に再送信しないよ うにする構成を備えているだけでは足りず,一旦指定地域外に出た後,再び指定地\n域内に戻ったことを把握して,当該無線通信装置に,同じ広告情報を再送信しない ようにする構成を備えていなければ,構\成要件Eを充足するとはいえないと解すべ きである。
エ 原告の主張について
(ア) 原告は,本件明細書の【0070】の記載を指摘し,構成要件Eは,\n広告情報管理サーバが,無線通信装置への広告の配信回数が0であるか1であるか を表す送信済フラグに基づいて,無線通信装置が一旦配信エリアの外に出た後,再\nび配信エリア内に戻った場合には,広告情報を再送しないようにする態様を含むも のと解すべきであると主張する。 原告の主張のように,構成要件Eが,無線通信装置への広告の配信回数のみによ\nって広告情報を再送信しないようにする態様を含むと解する立場をとると,無線通 信装置が一旦配信エリアの外に出た後,再び配信エリア内に戻った場合だけでなく, 無線通信装置が配信エリア内に存在し続けている場合にも,同じ広告情報が再送信 されなければ構成要件Eを充足することになる。\nしかしながら,「一旦前記指定地域の外に出た後,再び前記指定地域内に戻って も」という構成要件Eの用語は,一義的に明確というべきであるし,特許請求の範\n囲には,発明を特定するために必要な事項が記載され(特許法36条5項),特許 発明の技術的範囲が,特許請求の範囲の記載に基づいて定められることは前述のと おりであるから(同法70条1項),前記(2)−1と(2)−2の態様を区別する構成な\nしに,広告情報の配信回数を制限し得ることをもって,構成要件Eを充足すると解\nすることはできない。
(イ) 本件明細書の【0070】では,広告情報管理サーバによる広告情報 (広告メッセージ)の配信方法等について記載されており,広告を配信する際,「個 人情報データベースに項目として本広告メッセージに対応する広告IDを追加し, 送信済フラグを立てる。これにより,同じユーザに対して同一の広告メッセージを 重複して送信することがなくなる。即ち,携帯端末1Aが一旦指定地域の外に出た 後,再び指定地域内に戻っても,この送信済フラグが立っていれば,同じ広告メッ セージを送信しない。」と記載されている。 この記載のうち,「即ち」よりも前の記載は,個人情報データベースに配信した 広告メッセージに対応する広告IDを追加し,送信済フラグを立てると,その広告 メッセージの配信を受けたユーザーに対しては,同一の広告メッセージを重複して 送信することがなくなるとの当然の機能ないし作用効果を記載したものと解される\nが,「即ち」の後ろの記載は,「携帯端末1Aが一旦指定地域の外に出た後,再び 指定地域内に戻っても,この送信済フラグが立っていれば,同じ広告メッセージを 送信しない。」というものであり,前記イで判示したとおり,携帯端末1Aが指定 地域内に存在し続けており,同一の広告メッセージを重複して受信する可能性があ\nる場合があえて除かれていることから,「即ち」の前の記載と同視し得るものと認 めることはできず,「即ち」の前の記載と後ろの記載とは,本来,「即ち」という 接続詞を用いて接続することのできる関係にはないといわざるを得ない。 したがって,構成要件Eは,【0070】の「即ち」の後ろの記載に対応するも\nのであるが,上記検討したところによれば,「即ち」の前の記載が,構成要件Eの\n意味内容である,あるいは,本件発明1の実施例であるということはできない。 また,【0070】は【0069】の後に記載されているところ,【0069】 では,広告情報管理サーバが,広告配信サービス契約を結んだ全てのユーザの携帯 端末の位置情報を時々刻々更新しており,常にそれら端末の現在位置を把握してい ることが記載されている。そして,【0070】の「即ち」の後ろでは,無線通信 装置が指定地域内に存在し続けている場合が除かれていることからすると,そこで は,特に,無線通信装置が一旦指定地域外に出た後,再び指定地域内に戻った場合 に,同じ広告メッセージを送信しないということを記載したものと読むのが自然で ある。 以上のことを踏まえると,【0070】の記載内容によって,前記ウの解釈は左 右されないというべきである。
(ウ) 本件特許の出願経過について
・・・・
(d) 原告は,同日,特許庁審査官に対し,意見書を提出し,上記補正 後の特許請求の範囲の請求項1について,その内容を記載した上で,「特に,『前 記広告情報管理サーバは,前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後,再 び前記指定地域内に戻っても,同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信しない こと』に特徴付けられるものであります。」「本願発明は,かかる特徴的な構成を\n有機的に関連付けて具備することにより,明細書の段落0070に記載した通り, 『これにより,同じユーザに対して同一の広告メッセージを重複して送信すること がなくなる。即ち,携帯端末1Aが一旦指定地域の外に出た後,再び指定地域内に 戻っても,この送信済フラグが立っていれば,同じ広告メッセージを送信しない。』 という特有の作用・効果を奏するものであります。」などと説明した。また,原告 は,拒絶理由通知における引用文献との対比の項目でも,上記構成を含む構\成を「最 大の特徴」とした上で,引用文献にはこの構成についての記載や示唆は一切なく,\n補正後の請求項に係る各発明は,引用文献に記載された発明から当業者が容易に発 明することができたものではないと結論付けていた(乙1)。
(e) その後,上記請求項26を本件特許の設定登録時のもの(前記第 2の1(3)ウ参照)と同じ内容に変更する補正がされるなどした後,本件特許につい て特許査定がされた。
c 前記bで認定した本件特許の出願経過に照らし検討すると,確かに, 構成要件Eは本件明細書に【0070】の記載があることを踏まえて追加されたも\nのであることがうかがわれるが,原告は,上記補正に当たって,構成要件Eの構\成 を「特徴的な構成」などと位置付けた上で,この構\成を含む構成についての記載や\n示唆が引用文献には一切ないことを前提として,これを強調していた。 他方で,乙3の1の1ないし乙4の2によれば,本件特許が出願された平成12 年9月以前から,インターネットを利用した広告情報(バナー広告)の配信サービ スの分野においては,ユーザー(利用者)に対して同じ広告が配信(表示)される\n回数をコントロール(制限)することによって,「バナーバーンアウト」(広告に 反応がなくなる状態)ないし「バナー飽き(wearout)」を防止し,効果的な宣伝広 告を実現することが広く行われていたと認められる。この点,原告も,乙3の1の 1等で触れられているダブルクリック社の DART や乙4の1,2の公知技術が,広告 の配信回数を管理するものであることを認めている。 そうすると,原告が本件特許の出願経過において,単に,本件特許の出願前から 広く行われ,公知技術でもあった同じ広告の配信回数を管理するという構成による\n機能ないし作用効果を構\成要件Eに記載し,これを本件特許の「特徴的な構成」な\nどとして強調していたとは考え難い。 むしろ,前記認定の原告による本件特許の出願経過における説明内容に加え,本 件特許の出願当時,広く行われ公知とされていた技術を前提とすれば,原告は,特 に,無線通信装置が一旦指定地域外に出た後,再び指定地域内に戻った場合に,同 じ広告情報を無線通信装置に送信しないようにする構成を強調していたと理解する\nのが自然である。 したがって,先に判示した構成要件Eの解釈は,原告による本件特許の出願経過\nにおける説明等とも整合的ということができ,これに反する原告の主張は採用でき ない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2019.11. 1
平成31(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記(1)の認定事実によれば,本件発明1は,PCSK9とLDLRタンパク 質の結合を中和し,参照抗体1と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を,本件発明2は,PCSK9とLDLRタンパク質の結 合を中和し,参照抗体2と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を,それぞれ提供するものである。そして,本件各発明の課題は, かかる新規の抗体を提供し,これを使用した医薬組成物を作製することをもって, PCSK9とLDLRとの結合を中和し,LDLRの量を増加させることにより, 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し,高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。\n本件各明細書には,本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し,スクリーニングによってPCSK9に結合する抗体 を産生する2441の安定なハイブリドーマが確立され,そのうちの合計39抗体 について,エピトープビニングを行い,21B12と競合するが,31H4と競合 しないもの(ビン1)が19個含まれ,そのうち15個は,中和抗体であること, また,31H4と競合するが,21B12と競合しないもの(ビン3)が10個含 まれ,そのうち7個は,中和抗体であることが,それぞれ確認されたことが開示さ れている。また,本件各明細書には,21B12と31H4は,PCSK9とLD LRのEGFaドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 21B12は参照抗体1に含まれ,31H4は参照抗体2に含まれるから,21 B12と競合する抗体は参照抗体1と競合する抗体であり,31H4と競合する抗 体は参照抗体2と競合する抗体であることが理解できる。そうすると,本件各明細 書に接した当業者は,上記エピトープビニングアッセイの結果確認された,15個 の本件発明1の具体的抗体,7個の本件発明2の具体的抗体が得られることに加え て,上記2441の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても,同 様のエピトープビニングアッセイを行えば,参照抗体1又は2と競合する中和抗体 を得られ,それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに,本件各明細書には,免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製,免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製,21B12や 31H4と競合する,PCSK9−LDLRとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され,当業 者は,これらの記載に基づき,一連の手順を最初から繰り返し行うことによって, 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,参照抗 体1又は2と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば,当業者は,本件各明細書の記載から,PCSK9とLDLRタン パク質の結合を中和し,参照抗体1又は2と競合する,単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため,新規の抗体である本件発明1−1及び2−1のモノ クローナル抗体が提供され,これを使用した本件発明1−2及び2−2の医薬組成 物によって,高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって,本件各発明は,いずれもサポート要件に\n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と,「結 合中和することができる」という解決すべき課題(所望の効果)のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ,競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから,サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし,本件各明細書の記載から,「結合中和することができる」ことと,「参照 抗体と競合する」こととが,課題と解決手段の関係であるということはできないし, 参照抗体と競合するとの構成要件が,パラメータ要件であるということもできない。\nそして,特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において,アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり,特定の結合特性を有する抗体を得るために, その抗体の構造(アミノ酸配列)をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない(甲34,35)。\n前記のとおり,本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和し, 本件各参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗体を提供するもので,参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びPCSK9と LDLR間の相互作用(結合)を遮断(「中和」)することができるものであること を構成要件としているのであるから,控訴人の主張は採用できない。\n
(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性
なお,本件訂正発明1は,本件発明1の参照抗体1(構成要件1B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体1’(構\成要件1B’)とするものであり,本件訂正発明2は,本件発明2の参照抗体2(構成要件2B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体2’(構\成要件2B’)とするものであるから,本件各訂正発明も,いずれもサポート要件に適合するものと認められる。
(5) 小括
以上によれば,本件各発明及び本件各訂正発明は,いずれもサポート要件に適合 するというべきである。
4 争点(2)イ(実施可能要件違反)について
(1) 前記3(1)の認定事実によれば,本件各明細書の記載から,本件発明1−1及 び2−1の抗体及び本件発明1−2及び2−2の医薬組成物を作製し,使用するこ とができるものと認められるから,本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は,当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。\nしたがって,本件各発明は,いずれも,実施可能要件に適合するものと認められる。\n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,抗体の構造を特定することなく,機能\的にのみ定義さ れており,極めて広範な抗体を含むところ,当業者が,実施例抗体以外の,構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには,膨大な\n時間と労力を要し,過度の試行錯誤を要するのであるから,本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。\nしかし,明細書の発明の詳細な説明の記載について,当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が容易にその実施をできる程\n度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていないことに帰し,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる\nからである。 本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ, PCSK9との結合に関して,参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり,機能的にのみ定義されているとはいえない。そして,発明の詳細な説明の記載に,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和す\nることができ,PCSK9との結合に関して,参照抗体1又は2と競合する,単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば,当業者は,その実施をすることが可能というべきであり,特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ\nることまで記載されている必要はない。 また,本件各発明は,抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから,LDLRが認識するPCSK9上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体(EGFaミミック)が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは,実施可能\要件とは関係しないというべきである。そして,前記(1)のとおり,当業者は,本件各明細書の記載に従って,本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,本件各特許の特許請求の範 囲(請求項1)に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから,本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために,当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって,控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性
なお,前記3(4)のとおり,本件訂正発明1は,本件発明1の参照抗体1(構成要件1B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体1’(構\成要件1B’)とするものであり,本件訂正発明2は,本件発明2の参照抗体2(構成要件2B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体2’(構\成要件2B’)とするものであるから,当業者は,本件各明細書の記載から,本件訂正発明1 −1及び2−1の抗体及び本件訂正発明1−2及び2−2の医薬組成物を作製し, 使用することができるものと認められ,本件各訂正発明も,いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.10.28
平成30(ネ)10043 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月3日 知的財産高等裁判所
本件特許請求の範囲の請求項1(本件発明1に係る特許請求の範囲)の 記載は,「第IX因子または第IXa因子に対する抗体または抗体誘導体であって, 凝血促進活性を増大させる,抗体または抗体誘導体(ただし,抗体クローンAHI X−5041:Haematologic Technologies社製,抗体 クローンHIX−1:SIGMA−ALDRICH社製,抗体クローンESN−2: American Diagnostica社製,および抗体クローンESN−3: American Diagnostica社製,ならびにそれらの抗体誘導体を 除く)。」であり,請求項4(本件発明4に係る特許請求の範囲)は請求項1を引用 している。ここで,「凝血促進活性を増大させる」との記載の意義については,本件 明細書においてこれを定義した記載はない上,「血液凝固障害の処置のための調製 物を提供する」(段落【0010】)という本件各発明の目的そのものであり,か つ,本件各発明における抗体又は抗体誘導体の機能又は作用を表\現しているのみで あって,本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではない。\n特許権に基づく独占権は,新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示する ことの代償として与えられるものであるから,このように特許請求の範囲の記載が 機能的,抽象的な表\現にとどまっている場合に,当該機能や作用効果を果たし得る構\成全てを,その技術的範囲に含まれると解することは,明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含めて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが,そのような解釈は,発明の開示の代償として独\n占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきで ある。
したがって,特許請求の範囲が上記のように抽象的,機能的な表\現で記載されて いる場合においては,その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすること はできず,上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し,そこに開示された具 体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。もっとも,このことは,特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定す\nるものではなく,明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ,実施す ることができるのであれば,同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。\n
イ そこで,本件明細書において開示された具体的構成に示されている技術思想について検討する。\n
(ア) ある抗体が,FIX又はFIXaに結合し,FIXaの凝血促進活性 を増加するか又はFVIII様活性を有することを示すための試験方法としては, 凝血試験や色素形成試験等があり,これらによって評価が可能である(段落【0013】,【0014】,【0037】,【0065】)。そして,FIXaに対する抗体を\nスクリーニングし,色素形成アッセイによってFVIII様活性を有するモノクロ ーナル抗体(モノスペシフィック抗体)が複数作製されており(実施例4,9),そ の中でFVIIIインヒビターを有する血漿の凝血をもたらす抗体(193/AD 3)も確認されている(実施例7)。したがって,当業者は,FIXaに対する抗体 をスクリーニングすることにより,過度の試行錯誤を要することなく,一定の割合 で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)を作 製できたと認められる。 また,凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体) からの誘導体も複数作製されているから(例えば,CDR3領域由来ペプチド及び その誘導体〔実施例11,12〕,キメラ抗体〔実施例13〕,Fabフラグメント 〔実施例15〕,単鎖抗体〔scFv。実施例10,16,18〕,ミニ抗体〔実施 例17〕),当業者は,凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシ フィック抗体)からの誘導体も作製できたと認められる。
(イ) バイスペシフィック抗体については,本件明細書において,実施例と して作製された例は記載されておらず,FIX又はFIXaに結合するアーム以外 のアームが結合する対象の抗原がいかなるものかも開示されていない。 しかし,バイスペシフィック抗体は,抗体誘導体の一態様として明記されている (段落【0019】及び【0026】)。そして,バイスペシフィック抗体ではない ものの,凝血促進活性を増大させるモノスペシフィック抗体からの誘導体も複数作 製されている(実施例10〜13,15〜18)。 また,FIX又はFIXaに対するバイスペシフィック抗体の作製法は,本件出 願日当時に複数知られており,その中でも,クワドローマ技術は簡便な方法であり, 本件出願日当時の当業者にとって,合理的な時間及び努力の範囲内でバイスペシフ ィック抗体を作製できる手法であったのであり,また,バイスペシフィック抗体を 産生するクワドローマを融合し及び選択する種々の方法及びプロトコルは,199 9年において,利用可能であり,良好に確立され,二重特異性のIgG分子を作製するのに幅広く用いられていた(本件明細書の段落【0026】,甲97,100〜\n104,甲140の1)のであるから,当業者は,本件出願日の技術常識から,F IX又はFIXaに対するバイスペシフィック抗体を作製可能であったと認められる。\nさらに,前記3(2)のとおり,バイスペシフィック抗体のFVIII補因子活性と 抗FIXのモノスペシフィック抗体とは乏しい相関関係しかなく,バイスペシフィ ック抗体のFVIII補因子活性は,抗FIX抗体由来の構造だけなく,抗FX抗体由来の構\造にも影響を受けるのであるが,バイスペシフィック抗体においては,FIX又はFIXaに対する結合部位は1価になるものの,1価でも凝血促進活性 を増大させる効果があり(本件明細書実施例10〜12,15,16,18),バイ スペシフィック抗体の二つの抗原間で立体干渉が生じない限り,モノスペシフィッ ク抗体の活性は維持される(甲140の1)。FIX又はFIXa以外の結合部位が FXである場合を想定すると,本件出願日当時,FIXaとFXaの構造が明らかとなっており,FIXaとFXaの立体構\造からすると,当業者は,FIXaとFXに結合するバイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体)で,FIXa結合部位の活性に対する干渉は起こりにくいと予測できる(甲140の1)。\nしたがって,当業者は,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型 バイスペシフィック抗体)が,モノスペシフィック抗体が有する凝血促進活性を増 大させる作用を維持できると予測できたと認められる。そうすると,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体)についても,\nモノスペシフィック抗体の活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体の一態 様として「抗体誘導体」に含まれると解される。
(ウ) 以上によると,本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには, 「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子 に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であるものの,バイスペシフ ィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体)は「抗体誘導 体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。 もっとも,FIX又はFIXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィッ ク抗体)がFIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には,別 異に解すべきである。すなわち,本件各発明の技術的範囲に属するというためには, 「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子 に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であると解されるところ,こ れには,FIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものではないFIX又はF IXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)は含まれないし, このようなモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)から誘導される抗体誘 導体(バイスペシフィック抗体もこれに含まれる。)も含まれないというべきである。 このような抗体誘導体(バイスペシフィック抗体)は,たとえ,それ自体がFIX aの凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても,本件各発明の 課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされ ているのであって,本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し,実施できるもの とはいえないというべきである。
(エ) 被控訴人は,(1)非対称型バイスペシフィック抗体の著しく高い活性 は,一つの分子が2種類のアームを有するというバイスペシフィック抗体に固有の 機序によって初めて実現されたもので,非対称型バイスペシフィック抗体は,本件 明細書においてハイブリドーマ方法によって得られたモノスペシフィック抗体とは 活性及び機序の点で大きく異なっており,本件各発明の課題解決手段とは異なる手 段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたされていることになる,(2)FVI II補因子活性は,抗FX腕によって影響を受けるため,抗FIX(a)腕及び抗 FX腕の何れの組合せが非対称型バイスペシフィック抗体のFVIII補因子活性 を発現するのか,予測することが困難である,(3)現時点においてすら,非対称型バ イスペシフィック抗体の適切な評価手法が確立できていないことなどからすると, 本件明細書は,非対称型バイスペシフィック抗体を想定していなかったといえると 主張する。 しかし,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィ ック抗体)が抗体誘導体の一態様として「抗体誘導体」に含まれ得ることは,既に 判示したとおりであって,このことは,被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体の凝血促進活性を増大させる効果が大きいことや,抗FIX(a)腕と 抗FX腕の何れの組合せが効果があるかを予測することが困難であることや現時点において,非対称型バイスペシフィック抗体の適切な評価方法が確立していないこ\nとによって左右されるものではない。 (オ) 本件明細書においては,凝血促進活性を図る方法について,2時間の インキュベーション後のFVIIIアッセイ(例えば,COATEST(登録商標) アッセイまたはイムノクロム(Immunochrom)試験)において少なくと も3のバックグラウンドの対測定値の比を示すとされている(段落【0013】,【0 014】。なお,「バックグラウンドの対測定値の比」は,「ネガティブコントロール との比」と同義である。)が,色素形成アッセイ以外にも凝固アッセイなどFVII I活性を決定するために使用される全ての方法が使用でき(段落【0037】,【0 065】),同じ色素形成アッセイであってもインキュベーション時間が2時間では ない例も記載されている(実施例2,4,5,実施例11・図18〜22,実施例 15〜18)。
このように,本件明細書に記載された凝血促進活性の評価方法は,複数存在して おり,一般に,評価方法が異なればその基準が同一であるとは限らないとはいえる ものの,本件明細書では,段落【0013】及び【0014】に前記2(1)クのとお り記載され,色素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が,1.7 程度(例えば,段落【0081】・図11において,198/AP1はネガティブコ ントロールとの比が1.7程度であるが,凝血促進活性を示さないとされている。 段落【0067】・図7A(196/AF2 35μM Pefabloc Xa〔登 録商標〕),段落【0068】・図7B(198/AM1 35μM Pefablo c Xa〔登録商標〕)も同様。)や2程度(段落【0105】・図20において,A 1/5はネガティブコントロールとの比が2程度であるが,有意な凝血促進活性は ないと評価されている。)の場合においては,「凝血促進活性を増大させる」とは評 価されていない。 本件明細書のこれらの記載に加え,前記アのような本件各発明の請求項の記載を 考慮すると,当業者は,本件各発明の範囲に含まれる抗体又はその誘導体は,複数 の評価方法のうち,色素形成アッセイ(FVIIIアッセイ)を実施した場合には, 少なくとも3のバックグラウンドの対測定値の比(ネガティブコントロールとの比) を示すものが本件各発明の抗体及び抗体誘導体であると理解すると認められるから, 「凝血促進活性を増大させる」とは,色素形成アッセイを実施した場合には,ネガ ティブコントロールとの比が3を超えることを意味すると認めるのが相当である。 これに対し,控訴人らは,「凝血促進活性を増大させる」について,当業者は,ネ ガティブコントロールとの比が1を超えるものであるか否かで判断する旨主張し, 本件明細書の段落【0013】の記載は,「最終的に生成された物の評価をする際に 何らかの値を決めておく必要があるので,とりあえず3としたという程度の意味で ある」(甲131の3頁),「任意に設定された仮の基準であり,すべての候補物質に 適応すべき必須の条件ではない」(甲132の3頁),「ノイズや測定誤差の大きさに 関する記載がない以上,統計学的議論から根拠をもった基準として3を導くことは できない」(甲136の1頁)などの意見書を提出するが,これらの意見書によると, 本件各発明の技術的範囲が当業者にとって明らかでないことになるから,これらの 意見書の意見や控訴人らの主張を採用することはできないことは,既に判示したと おりである。
(2) 上記(1)のとおり,「凝血促進活性を実質的に増大させる」とは,色素形成 アッセイを実施した場合のネガティブコントロールとの比が3を超えることを意味 するが,色素形成アッセイの測定方法について,控訴人らは,本件明細書の記載及 び技術常識によると,コンティニュアス法によるアッセイを行うのであればインキ ュベーション時間を2時間とし,サブサンプリング法によるアッセイを行うのであ れば第1ステップのインキュベーション時間を5分とし,長時間のインキュベーシ ョン時間をとるのであれば,酵素の最大反応速度をみるために,継続的に測定すべ きである旨主張する。
ア コンティニュアス法及びサブサンプリング法について 証拠(甲210,甲229の1)及び弁論の全趣旨によると,サブサンプリング 法とは,FXaを生成させる第1ステップと,生成したFXaを定量する第2ステ ップを分離して実施する色素形成アッセイの方法であり,第1のステップではFX aを生成させるのに必要な試薬と被験抗体を混合させ,一定時間インキュベーショ ンさせてFXaを生成し,第1ステップで生成されたFXaの反応をみるために, 第2ステップに移行する前にFXaの生成を止め,第2ステップで,上記混合物に 発色性合成基質を添付することで,第1ステップで生成されたFXaが発色性合成 基質を切断し,発色する様子を測定するという標準的な FVIIIアッセイで用い られている方法であること,コンティニュアス法とは,第1ステップ(FXa生成 反応)及び第2ステップ(FXaによる発色反応)からなる一連の反応を1ステッ プで行う方法であり,被験抗体,FIXa,FX,リン脂質,カルシウムイオン, 発色性合成基質等の一連の反応に必要な試薬を全て最初から投入し,第1ステップ であるFXa生成反応と,第2ステップである生成したFXaによる発色反応とを 同時に進行させて,吸光度を経時的に測定することにより,FXa生成量の推移を 継続的に観察するものであることが認められる。
イ 証拠(甲208,211,213,乙39)及び弁論の全趣旨によると, 本件明細書の段落【0013】に記載されているCOATEST(登録商標)やイ ムノクロムは,サブサンプリング法の色素アッセイキットであり,コアテストの仕 様書や,イムノクロムの後継品であるテクノクロムの仕様書にはインキュベーショ ン時間は5分間とされていることが認められるが,本件明細書の段落【0013】 においては,インキュベーション時間は2時間とされているから,本件明細書の段 落【0013】においては,サブサンプリング法を用いつつも,インキュベーショ ン時間を2時間として色素形成アッセイを実施したところ,少なくとも3のバック グラウンドの比を示すものが本件各発明である旨記載されていることになる。 この点について,控訴人らは,インキュベーション時間を2時間とすると,イン キュベーションの途中で,基質の消費に伴い,反応速度は最大反応よりも低下し, 第1ステップのインキュベーション時間の間,FIXaが失活してしまい,その結 果,FXaの生成速度も低下し,さらに,生成物であるFXaも自己消化を起こし, 血液凝血性やアミド活性を持たないFXaγに変換してしまうので,FXaの産出 量は本来の産出量より少なくなっていて,適切でなく,インキュベーション時間は 仕様書のとおり5分が適切であると主張する。 しかし,本件明細書には,上記のとおり,インキュベーション時間を2時間とし たものしか記載されていないのであって,本件明細書においては,インキュベーシ ョン時間を仕様書の記載に反してあえて2時間とし,そのときのFXaの産出量を もって,3のネガティブコントロールとの比を評価するときの産出量としているの であるから,当業者は,3のネガティブコントロールとの比を評価するに当たり, インキュベーション時間が5分の場合を想定することはできないというべきである。 なお,本件明細書において,インキュベーション時間を2時間とした理由につい ては,本件明細書に記載はなく,本件の証拠によるも必ずしも明らかでないが,そ のことは上記判断を左右するものではない。 そうすると,当業者は,本件各発明の「凝血促進活性を増大させる」というため には,インキュベーション時間を2時間とする測定を要すると理解すると解される。
ウ 以上によると,本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには,「第 IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対 するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当 該抗体を改変した抗体誘導体」であり,インキュベーション時間を2時間とする色 素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が3を超えるものを意味す ると認めるのが相当である。
・・・
エ 以上によると,被控訴人製品は,「第IXa因子の凝血促進活性を実質的 に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペ シフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」に該 当するとは認められない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 機能クレーム
>> ピックアップ対象
2019.10.18
平成29(ワ)44181 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月18日 東京地方裁判所
原告は,制御ルールのリストの例示である【図5】の「条件定義部」の 「受信者」欄に,「*@zzz.co.jp」が定められており,これはドメインを表\nすものであるから,「送信先」には電子メールアドレスのみならず,ドメ インを含むと主張する。 しかし,前記のとおり,本件明細書等1には,制御ルールに関し,「「条 件定義部」は,「発信者(送信元)」,「受信者(宛先)」,「その他条 件」から構成される。…「受信者(宛先)」には,メール送受信端末11\n0から取得する電子メールの宛先(To,Cc,Bcc)の電子メールア ドレス(受信者情報) が設定されている」(段落【0040】),「「発 信者(送信元)」,「受信者(宛先)」には,それぞれ電子メールアドレ スを複数設定することができ,アスタリスクなどのメタ文字(ワイルドカ ード)を使うことによって任意の文字列を表すこともできる」(段落【0\n041】)と記載されており,これらの記載によれば,上記「*@zzz.co.jp」 は,ドメインを意味するのではなく,「*」に任意の文字列を含み,ドメイ ン名を「zzz.co.jp」とする複数の電子メールアドレスを意味するという べきである。
原告は,「*@zzz.co.jp」がドメインを意味することは,複数の特許文献 (甲24,30〜32,乙15)などの記載からも裏付けられると主張す るが,特許請求の範囲や発明の詳細な説明において使用される言葉の意義 は各発明により異なることから,構成要件11D等の「送信先」の意義は\n本件特許に係る特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に基づいて 解釈されるべきである。本件明細書等1の「*@zzz.co.jp」がドメインを意 味すると解し得ないことは上記判示のとおりであり,原告の挙げる他の文 献等の記載は上記結論を左右するものではない。
(イ) 原告は,本件明細書等の段落【0061】及び【図4】のステップS4 02には,「受信者」の「宛先」単位で電子メールの分割をすることを記 載しているが「受信者」の「宛先」にはドメインも含まれると主張する。 しかし,段落【0061】には「各宛先(受信者)のそれぞれを単一の 宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する」と記載されているところ, 同エンベロープの生成を説明する【図12】には,送信先(受信者) の電 子メールアドレスとして設定されている「A」,「B」,「C」のそれぞ れを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成することが図示 されているのであるから,同段落の「各宛先(受信者)」とは電子メール アドレスを意味するというべきである。
(ウ) 原告は,本件明細書等1の段落【0003】に記載の従来技術である乙 15公報における「宛先」には「電子メールアドレス」又は「ドメイン」 であることが記載されており,本件発明1において分割する単位をドメイ ンとしてもこの従来技術の課題を解決することができると主張する。 そこで,乙15公報をみるに,その段落【0032】には,【図2】の 「項目203,205にあっては,アカウントを*として,ドメインのみ を指定するとした設定も可能である」と記載されているが,ここにいう項\n目203は送信メールの一時保留機能を利用する場合であって,一時保留\nせずに,即配信したいメールアドレスの即配信リストを設定する項目であ り,同図の項目205は,全ての送信保留中メールを本人(送信者)に配 送する場合であって,配送を希望しない送信保留中メールを本人(送信者) に送信しないメールアドレスの送信不要リストを設定する項目である(段 落【0030】)。【図2】
このように,項目203及び同205は即配信又は送信不要リストを設 定するためのものであるから,段落【0032】の趣旨は,一時保留せず に即配信したいメールアドレスの即配信リスト(項目203)や,送信保 留中メールを本人(送信者)に送信しないメールアドレスの送信不要リス ト(項目205)に,任意のドメイン名を有する複数のメールアドレスを 一括して設定することも可能であることを述べたものにすぎず,電子メー\nルの「宛先」にドメインが含まれることを示すものということはできない。 そうすると,同段落の記載をもって従来技術である乙15公報における 「宛先」に「ドメイン」が含まれると解することはできないので,原告の 上記主張は前提において採用し得ないというべきである。
(エ) 原告は,電子メールをドメイン単位で分割する場合でも本件発明1の課 題を解決し得ると主張する。 しかし,電子メールをドメイン単位で分割するとなると,同一ドメイン の複数の電子メールのうち,一つのみの送出を保留すべきような場合に上 記課題を解決し得ないことは,前記判示のとおりである。 原告は,本件発明1はいかなる場合でも電子メールの送出制御を効率的 に行うことを課題と設定しているのではないと主張するが,本件発明1が その課題を解決し得ない構成を含むとは考え難く,特許請求の範囲及び本\n件明細書等1の記載に照らしても,「送信先」にドメインを含むとは解し 得ないことも,前記判示のとおりである。
エ 以上のとおり,構成要件11D等における「送信先」は「電子メールアド\nレス」のみを指し,「ドメイン」を含まないと解することが相当である。
・・・・
特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書 記載の従来技術との比較から認定されるべきであるところ(知財高裁平成2 7年(ネ)第10014号同28年3月25日判決),本件明細書等1には, 従来技術の「複数の送信先が記載された電子メールに対しては,誤送信の可 能性がある送信先が1つでも含まれていれば,その他の送信先に対するメー\nル送信までもが保留,取り消しがされることとなる」(段落【0004】) という課題を解決するため,電子メールに設定された複数の送信先を個々の 送信先に分割し,記憶手段に記憶されている制御ルール等に従って,電子メ ールの送出に係る制御内容を決定し,決定された制御内容に従って電子メー ルの送信制御を行うなどの構成を備えることにより,「ユーザによる電子メ\nールの誤送信を低減可能とすると共に,宛先に応じた電子メールの送出制御\nを行うことにより効率よく電子メールを送出させることができる」(段落【0 008】)などの効果を奏するものである。
イ 原告は,本件特許1の特許メモ(乙9)などを根拠に,本件発明1の本質 的部分は,「送出制御内容を,電子メールの送信元と送信先とに対応付けた 制御ルールと,分割された電子メールの送信先と送信元とに従って,分割さ れた送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」(構\n成要件11E)にあると主張する。 しかし,本件発明1の従来技術として挙げられているのは乙15公報であ り,本件明細書等1に記載されている課題は「複数の送信先が記載された電 子メールに対しては,誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれ\nば,その他の送信先に対するメール送信までもが保留,取り消しがされるこ ととなる」というものであるところ,同課題を解決するためには,電子メー ルに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割した上で,制 御ルールを適用することが不可欠である。そうすると,構成要件11D等に\n係る構成は本件発明1の本質的部分というべきである。\n 原告は,特許メモ(乙9)の記載を根拠とするが,同メモには,本件特許 の出願時の複数の公知文献に本件発明1に係る構成が記載されているかど\nうかが記載されているにすぎず,本件発明1の従来技術として挙げられた乙 15公報との対比がされているものではなく,また,本件発明1の本質的部 分の所在を検討するものでもないので,同メモに基づいて,本件発明1の本 質的部分が構成要件11Eに係る構\成にあるということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.10.16
平成30(ワ)24717 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月17日 東京地方裁判所(46部)
特許請求の範囲の「各ページを適宜に分割して区画化し,…住宅建物の所 在する番地を前記地図上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画 の記号番号と一覧的に対応させて掲載」という記載(構成要件D,E及びF)\nに照らせば,構成要件Dの「適宜に分割して区画化」とは,ページの特定の\n部分に記号番号を付し番地とこれに対応するページの特定の部分を一覧的 に示したりすることができるよう,検索すべき領域の地図のページを分割し, 認識できるようにすることといえる。 そして,本件発明は, 前記1(2)のとおり、地図上に公共施設や著名ビル等 以外の住宅及び建物は番地のみを記載するなどし,全ての建物等が所在する 番地について,記載ページと当該ページ内で分割された区画のうち当該番地 が記載された区画を一覧的に対応させて掲載した索引欄を設けることによ って,簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅地図の提供を可能\にする というものであり,本件発明の地図の利用者は,索引欄を用いて,検索対象 の建物等が所在する地番に対応する,ページ及び当該ページにおける複数の 区画の中の該当の区画を認識した上で,当該ページの該当区画内において, 検索対象の建物等を検索することが想定されている。そのためには,当該ペ ージについて,それが線その他の方法によって複数の区画に分割され,利用 者が該当の区画を認識することができる必要があるといえる。そうすると, 本件明細書に記載された本件発明の目的や作用効果に照らしても,本件発明 の「区画化」は,ページを見た利用者が,線その他の方法及び記号番号によ り,検索対象の建物等が所在する区画が,ページ内に複数ある区画の中でど の区画であるかを認識することができる形でページを分割することをいう といえる。
また 前記(2)のとおり、本件明細書には発明の実施の形態において,本件 発明を実施した場合における住宅地図の各ページの一例として別紙「本件明 細書図2」及び「本件明細書図5」が示されているところ,これらの図にお いては,いずれも道路その他の情報が記載された長方形の地図のページが示 されたうえで,そのページが,ページ内にひかれた直線によって仕切られて 複数の区画に分割されており,その複数の区画にそれぞれ区画番号が付され ている。また,本件明細書図4の索引欄には,番地に対応する形でページ番 号及び区画番号が記載されており,利用者は,検索対象の建物の番地から, 索引欄において当該建物が掲載されているページ番号及び区画番号を把握 し,それらの情報を基に,該当ページ内の該当区画を認識して,その該当区 画内を検索することにより,目的とする建物を探し出すことが記載されてい る(【0028】)。ここでは,上記の特許請求の範囲の記載や発明の意義に 従った実施の形態が記載されているといえる。 加えて,本件明細書には,本件発明の「区画化」の用語を定義した記載は なく,【0017】ないし【0032】及び別紙「本件明細書図1」ないし 「本件明細書図5」で記載された実施形態以外には本件発明の実施形態の具 体的記載はない。なお,後記イのとおり,本件明細書の【0033】【00 37】に記載された地図は,本件発明の実施形態を記載したものとはいえな い。
したがって,本件明細書における発明の実施の形態に係る記載からしても, 構成要件Dの「適宜に分割して区画化」とは,ページを見た利用者が,線そ\nの他の方法及び記号番号により,検索対象の建物等が所在する区画が,ペー ジ内に複数ある区画の中でどの区画であるかを認識することができる形で ページを分割することをいうと解される。
イ これに対し,原告は,本件明細書(【0033】【0037】)は,本件発明 の実施形態として,コンピュータが自動的に区画を探し出し,当該区画を画 面中央に配置し,当該区画内にある所望の建物をユーザが直接認識できる電 子住宅地図(全戸氏名入り電子住宅地図)を開示しており,このような構成\nを備える電子住宅地図では,ユーザが視覚的に地図内の位置を分かりやすく 探せるように仕切り線を設ける必要はないから,「区画化」もまたユーザが 目に見える形で仕切る構成に限定されない旨主張する。\n確かに,本件明細書には,全戸氏名入り電子住宅地図として「戸番地(住 所地番及び号)をキーとして,電子電話帳11の氏名データと,住所入り電 子住宅地図12のポリゴンデータとを連結する。」(【0035】),「この全戸 氏名入り電子住宅地図14は,パソコン13のキーボードから氏名を入力す\nれば,その人物の居住する建物を中心にした地図がパソコン13の表\示装置 に表示され,その人物の居住する建物にマークが付されて,そのマークが点\n滅する。」(【0037】)との記載がある。
しかし,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)には,上記【0037】 記載の動作に対応する構成の記載はない。また,本件明細書には,「公官庁\nや住宅関係の企業では,今まで通り氏名入りの住宅地図を必要とする場合も 考えられる。そのような場合でも,…全戸氏名入りの住宅地図を作成するこ とができる。」(【0033】)との記載があるところ,上記記載中の「今まで 通り氏名入りの住宅地図」とは,「建物表示に住所番地ばかりではなく,居\n住者の氏名も全て併記」された「従来の住宅地図」(【0002】)を指すと 解されること,【0037】の全戸氏名入り電子住宅地図14においては, 利用者がパソコン13のキーボードから氏名を入力することによりその人\n物が居住する建物を検索する場合,マークの付された建物に表示された氏名\nを視認することによって検索の目的とする建物との同一性を確認するもの と理解できることからすると,全戸氏名入り電子住宅地図14は,「全戸」 の氏名が表示された地図であるものと認められる。そうすると,全戸氏名入\nり電子住宅地図14は,構成要件Bの「検索の目安となる公共施設や著名ビ\nル等を除く一般住宅及び建物については居住人氏名及び建物名称の記載を 省略し」の構成を備えていない。\n
したがって,本件明細書記載の全戸氏名入り電子住宅地図14は,本件発 明の実施形態に含まれるとは認めることはできない。なお,本件発明の出願 経過によれば,本件特許出願の願書に最初に添付した明細書(乙8の2,8 の3)記載の特許請求の範囲は旧請求項1ないし11からなり,旧請求項7 ないし11には,「全戸氏名入り電子住宅地図作成方法」に係る発明の記載 があり,発明の詳細な説明中の【0014】ないし【0016】に旧請求項 7ないし11を引用した記載部分があったが,同年10月21日付けの手続 補正(乙9)により,旧請求項1の文言を補正し,旧請求項2ないし11及 び【0014】ないし【0016】を削除する補正がされたこと,上記補正 後の請求項1は,拒絶査定不服審判請求と同時にされた平成13年6月7日 付けの手続補正により本件発明の特許請求の範囲記載の請求項1と同一の 記載に補正されたこと(乙10)に照らすと,本件明細書の【0033】な いし【0038】記載の全戸氏名入り電子住宅地図14に関する記載は,平 成11年10月21日付けの手続補正により削除された旧請求項7ないし 11記載の「全戸氏名入り電子住宅地図作成方法」に係る発明の実施形態で あると認められる。 以上によれば,本件明細書記載の全戸氏名入り電子住宅地図14が本件発 明に含まれることを前提とする原告の上記主張は採用することができない。
・・・・
原告は,仮に縮尺レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図が,各ペー ジに線その他の方法及び記号番号を付されていない点において構成要件Dと相違\nするとしても,縮尺レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図は,均等の 成立要件(第1要件ないし第3要件)を満たしているから,本件発明と均等なも のとして,本件発明の技術的範囲に属する旨主張する。 前記2(1)のとおり,本件発明の技術的意義は,検索の目安となる建物を除く建 物名称や居住者氏名の記載しないため,高い縮尺度で地図を作成することにより 小判で,薄い,取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することや(構成要件B\n及びC),地図の更新のために氏名調査等の労力を要しないことによって廉価な住 宅地図を提供することを可能にするとともに,地図上に公共施設や著名ビル等以\n外の住宅及び建物は番地のみを記載し,地図のページを適宜に分割して区画化し たうえで,全ての建物等の所在する番地を,当該番地の記載ページ及び記載区画 を特定する記号番号と一覧的に対応させた索引欄を付すことによって,簡潔で見 やすく迅速な検索を可能にする住宅地図を提供すること(構\成要件DないしF) を可能にする点にあるものと認められる。\n
しかしながら、被告地図においては前記2(1)で認定したとおり,地図を記載した各ページを線その他の方法及び記号番号によりユーザの目に見える形で複 数の区画に仕切られていないため,ユーザが所在番地の記載ページ及び区画の記 号番号の情報から検索対象の建物等の該当区画を探し,区画内から建物を探し出 すことができないから,迅速な検索が可能であるということはできない。\nしたがって,縮尺レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図は,本件発 明の本質的部分を備えているものとは認めることができず,同被告地図の相違部 分は,本件発明の本質的部分でないということはできないから,均等の第1要件 を充足しない。よって,その余の点について判断するまでもなく,縮尺レベル「50m」「60m」「70m」の被告地図は,本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められないから,本件発明の技術的範囲に属すると認めることはで\nきない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
2019.10.11
平成30(ワ)13400 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 東京地方裁判所(40部)
均等論の本質的部分(第1要件)
本件発明1と被告製品との相違点は,本件発明1では,係止爪がサブアー ム部の上端部に位置するものであるのに対し,被告製品では,爪部の上部に フック部が設けられ,爪部がサブアーム部の上端部に位置するとはいえない 点にあるところ,被告は,原告の均等侵害の主張に対し,第4要件を充足す ることは争わないものの,その余の要件の充足性を争うので,以下検討する。
(2) 第1要件(非本質的部分)について
ア 均等侵害が成立するための第1要件にいう本質的部分とは,当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分であり,このような特許発明の本質的部分を対象\n製品等が共通に備えていると認められる場合には,相違部分は本質的部分 ではないと解される。
イ 原告は,本件発明1のうち,挿入力の増加の防止のための構成がその本\n質的部分であるとした上で,被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから,被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず,同製品は本件発明1の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし,本件発明1は,特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて,従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり,他方, 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると,挿入力が強 くなり作業性が悪化することから,挿入力は弱いままで,抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる(本件明細書等の 段落【0009】,【0013】〜【0015】)。そうすると,本件発 明1の本質的部分は,挿入力は弱いままで,抜け力を強くするための構成\nにあり,従来技術との対比でいうと,特に抜け力の強化のための構成が重\n要であるというべきである。 そして,本件発明1は,上記課題の解決のため,(1)メインアーム部と, メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し,(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり,(3)サブアーム部の上端部を,上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより,取付孔 への挿入性の向上を図るとともに,アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が 加わったときは,係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる(特許請求の範囲,本件明細書等の段\n落【0017】,【0029】,【0032】,【0033】,【003 6】,【0037】)。
ウ 他方,被告製品においては,サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ,当該フック部と車体のルーフ孔の距離が0.3mmであると認め られるから(乙13),抜け方向に荷重が加わった際に,フック部は0. 3mm程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり,爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして,被告製品における抜け力に関し,被告が実施した実験結果(乙 5)によれば,本件発明1の実施品の抜け力は186Nであるのに対し, 被告製品の抜け力は,215.8N,227N,271N,295Nであ り,最小でも約30N,最大で約110Nの差が生じたことが認められる。 また,被告が実施した,被告製品のコの字型部材(サンプル(1))と,被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの(サンプル(2))を用 いた実験結果(乙14)によれば,前者の抜け力の平均値は227.60 N,後者の抜け力の平均値は73.51N(いずれも10回実施)であり, フック部を備えたコの字型部材の方が,抜け力において約150N大きい ことが認められる。
前記のとおり,被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ,これに上記の各実験結果を併せて考慮すると,被告製品は, 本件発明1の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ,そ の抜け力の大きさは,同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり,少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。 なお,原告は,乙14実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が\nあるとして,乙14実験の信用性を争うが,サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり,上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり,乙14実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて10回ずつ実験を行っているところ,数値にば らつきはあるものの,サンプル(1)は200N以上であり,サンプル(2)は概 ね60〜100程度であり,全体的に100N以上の差が生じていること に照らすと,その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり,抜け力の増大という課題を解決するための構成は本\n件発明1の本質的部分ということができるところ,本件発明1はこの課題 をアンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し,被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ,そうす ると,被告製品は本件発明1と異なる構成により上記課題を解決している\nということができる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2019.10. 2
平成28(ワ)12296 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月10日 大阪地方裁判所
まず,被告が経費として主張する製造委託費,検査費等は,いずれ も侵害者である被告において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められるから,被告の利益額を算 定するに当たり,上記販売金額からこれらの経費の金額を控除すべきである。
b そして,乙53,56ないし61及び弁論の全趣旨によれば,製造 委託費(樹脂やプレートの材料代,プレートの組付費用を含み,金型の作成費用は 含まない。),検査費等として,別紙「被告の損害論における主張」の「被告の経 費額」欄記載の経費を支出したと認められる。
c 原告らは,被告主張の仕入価格には高すぎるなどの疑問があると主 張して,被告主張の経費のうち「製造委託費」の金額を争っている。 しかし,この主張は特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利 益の額の算定の問題に関連する主張であるが,そもそもその利益の額(限界利益の 額)の主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきであるから(知財高裁令和 元年6月7日判決・最高裁ウェブサイト),そのような観点から検討すると,原告 らは原告製品の製造販売に係る経費と対比をするのみで,被告製品の製造販売に係 る経費について具体的な立証をしているわけではない。 他方,被告製品の製造委託先は,被告と資本関係にあるわけではなく(乙62, 弁論の全趣旨),被告の主張する製品1個当たりの製造委託費は,別紙「被告主張 の被告製品1個当たりの経費額」の「製造委託費(材料費込)」欄記載のとおりで あるところ,その金額には一定の裏付け(乙56ないし61)がある。したがって, 原告らの上記指摘によって前記認定は左右されず,下記(ウ)で認定する金額を超え る利益が被告に生じていたことを認めることはできない。
(ウ) 被告の利益額
以上によれば,被告が本件特許権の侵害行為により受けた利益の額は,別 紙「被告の損害論における主張」の「被告の限界利益」欄記載のとおり,合計(中 略)円と認められる。
イ 推定覆滅事由の有無
(ア) 特許法102条2項における推定の覆滅については,侵害者が主張立 証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たると解され,例えば,(1)特許権者と侵害者の業務 態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),(2)市場における競合品の存在,
(3)侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),(4)侵害品の性能(機能\,デザイン 等特許発明以外の特徴)などの事情について,考慮することができるものと解され る(前掲知財高裁令和元年6月7日判決)。
(イ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 原告扶桑産業について(甲1,33) 原告扶桑産業は,資本金の額を2500万円とする会社であり,その従 業員数は30名程度である。そして,原告扶桑産業は,店装用備品等の企画,製造 販売,陳列器具及び店舗什器関連備品等の製造販売等を事業品目とし,全国スーパ ー量販店備品卸売業者,全国インテリア装飾・店装業者等を取引先としている。そ して,原告製品については,被告や他の企業に対して卸売販売され,そこを通じて 小売量販店に販売された(量販店の各店舗に設置された)ほか,原告扶桑産業から 直接,株式会社サンリオの直営店等の量販店に販売されることもあった。
b 被告について(乙1,53ないし55,65ないし66の5)
(a) 被告は,資本金の額を1億円とする会社であり,その従業員数は 3000人程度で,平成28年度の売上高は1220億円(グループ全体で346 0億円)であり,平成20年から東北楽天ゴールデンイーグルスのメインスポンサ ーとなっている。そして,被告は,生活用品の企画,製造,販売を事業内容として おり,販売している商品は,LED照明,家電,調理用品,日用品,収納用品,ハ ードオフィス・資材等多岐に渡っており,被告のこれらの商品は全国のホームセン ターで販売されている。
(b) 被告は,量販店等の店舗向けに,什器・備品を単体で販売するの ではなく,内装工事を含め,店舗のあらゆるスペースをデザイン・プロデュースし, 店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行っている。 そして,被告は,販売する什器について,500頁を超えるカタログ(乙1,5 4)を作成しており,そこに掲載されている什器は,カードケースを含むシステム 什器だけでなく,内装・棚下照明,陳列用什器,インフォメーション器具,販促用 品,オフィス家具,運営サポート用品及び照明・演出用品といったように,多岐に 渡っている。
(c) 被告が顧客との間で上記(b)の取引をする場合の流れは,次のと おりである。すなわち,まず顧客から要望についてヒアリングをした上で,それを もとに現地調査をする。その後,顧客から建築平面図等を取得し,什器の配置を検 討し,顧客と打合せをした上で,什器配置図等を作成するとともに,コストをシミ ュレーションする。そして,顧客の要望に応じた什器・オプションアイテムを提案 し,納品内容を確定した上で,現場への納品や施工の手配を行う。
(d) 被告が平成25年12月5日,ある株式会社に対して発行した見 積書(乙55)では,取引金額が合計(中略)万円(税抜)とされたが,そのうち カードケースの代金額は(中略)円(個数は合計(中略)個)であった。
(e) 平成26年の被告製品の販売金額は,合計(中略)円であったが, その大半((中略)円)はカードケースと他の店舗用品とを組み合わせて販売され るいわゆるバンドル取引によるものであった。
c 原告扶桑産業と被告との間の取引
(a) 被告は,遅くとも平成24年1月以降,原告扶桑産業から原告製 品を購入しており,同月から平成25年11月までの原告製品の販売数量は,次の とおりであった。
・・・・
(b) 上記(a)のうち平成25年の原告製品4(ただし,QPCII−65 を除く。)の販売数量・販売金額は次のとおりであったほか,平成26年ないし平 成28年の原告製品(ただし,QPCII−65を除く。)の販売数量・販売金額は, 次のとおりであった(乙78の2)。
・・・・
(ウ) 被告の主張について
a まず,被告は被告製品1,4,6及び10については,原告製品に 相当するものがないことを指摘している。 しかし,上記各被告製品は,原告製品と色やサイズが異なるだけであり,原告扶 桑産業が販売している他の色やサイズの製品が購入されなかったとまで認めること はできないし,原告扶桑産業が販売していた製品をみる限り,原告扶桑産業が被告 製品と同じ色やサイズの製品を製造し,販売することができなかったと認めること もできない。 したがって,被告の上記主張は推定覆滅事由とならない。
b 次に,被告は取引の実情として,被告製品の販売方法や,被告によ る販売力・営業努力・企業規模・ブランドイメージを理由とする推定覆滅を主張す る。
(a)(1) 前記認定のとおり,被告が販売している什器は多岐に渡ってお り,また量販店等の店舗向けに,什器・備品を単体で販売するのではなく,内装工 事を含め,店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行って いた。そして,前記認定事実によれば,被告製品は,その大半が他の店舗用品と組 み合わせて販売されるいわゆるバンドル取引によって販売されていた。 しかも,前記認定事実によれば,そのようなバンドル取引の取引額に占めるカー ドケースである被告製品の販売額はわずかであったと認められる。 このような被告製品に係る取引の実情によれば,被告製品の需要者の大半は,カ ードケースである被告製品に殊更に注目して被告製品を購入したというよりも,他 の店舗用品と組み合わせて購入できる利便性や,内装工事を含めて店舗全体又は売 り場全体の什器・備品を総合的に購入することができるという被告の販売体制に魅 力を感じて,被告と取引をするに至り,その取引の一環として被告製品を購入した と認めるのが相当である。
(2) 原告らの主張について
原告らは,被告がドン・キホーテの店舗内装を受注するに当たり, ドン・キホーテから原告製品を使用するよう指示されたため,原告扶桑産業と原告 製品の取引をするようになったとか,バンドル取引においても原告製品を組み込む 需要があり,被告がその需要に応え,顧客との取引を維持するために原告製品を侵 害品である被告製品に置き換えたなどと主張する。 確かに,被告は現在でも,原告扶桑産業から原告製品を購入しているから,本件 発明の技術的範囲に属する製品を購入し,エンドユーザーにこれを販売する一定の 需要があったというべきである。 しかし,原告らが主張する原告扶桑産業との取引開始の経緯や,被告が本件特許 のライセンスを求めたことについては,これを認めるに足りる証拠はないし,被告 が,被告製品のモデルチェンジをして,本件特許権の侵害とならないカードケース を販売するようになった後,被告のバンドル取引による売上げが減ったとの事情も 認められない。 以上の事情に加え,前記認定の被告製品の取引の実情を踏まえると,被告が顧客 との取引を維持するために原告製品を侵害品である被告製品に置き換えたとまで認 めることはできず,原告らの上記主張は採用できない。
(3) そうすると,被告主張の事情は,侵害者である被告が得た利益 と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を相当程度,阻害す る事情といえる。
(b) また,被告の企業規模や販売する製品の多様性は前記認定のとお りであり,被告が被告製品を販売するに当たり,被告自身の販売力や企業規模,ブ ランドイメージか需要者に与えた影響も小さくないものというべきである。 したがって,この事情も,上記(a)の事情と相まって,侵害者である被告が得た利 益と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を一定程度,阻害 する事情といえる。
(c) なお,被告はその他に自身の営業努力も推定覆滅事由として主張 するが,被告製品に関する事実関係が明らかではなく,事業者は,製品の製造,販 売に当たり,製品の利便性について工夫し,営業努力を行うのが通常であることを 踏まえると,推定覆滅事由として考慮すべきとまでいうことはできない。
c 被告は代替品・競合品(乙67ないし72)の存在を指摘している。 しかし,推定覆滅事由として考慮する競合品といえるためには,市場において侵 害品と競合関係に立つ製品であることを要するものと解される(前掲知財高裁令和 元年6月7日判決)。このような観点から被告主張の製品を検討すると,被告が指 摘する製品には,その具体的構成や使用方法が判然としないものも含まれているほ\nか,カードケースが上保持部と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本\n的部分を備えたものと認めることもできないから,被告指摘の製品を代替品ないし 競合品ということはできない。また,被告指摘の製品の販売時期等も不明である。 したがって,被告の上記指摘によって推定が覆滅されるとはいえない。
d 被告は,乙73ないし77の先行技術等の存在を指摘して,被告製 品の販売に対して本件発明の技術的意義が寄与する程度は低いということを主張す る。 しかし,被告が指摘する乙73ないし77はいずれも,カードケースが上保持部 と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本的部分を備えたものと認める\nことはできない。また,被告が指摘する乙77は,表示板支持棒の先端に表\示板が 取り付けられているものの,その取り付け方法は,指示棒の先端に平板部分を設け, その下面に突設されたピンに表示板を保持するというものであり(乙77の【考案\nの詳細な説明】の【0021】),本件発明の構成とは大きく異なっている。それ\nだけでなく,被告製品が販売されていた時期に,本件発明の作用効果の一部を奏す るとされる技術があったとしても,それだけで直ちに,原告扶桑産業において,本 件特許の全構成を備えた被告製品の販売による利益に相当する損害を被ったことが\n否定されるとはいえない。 したがって,被告の主張の技術的観点からの主張は採用できない。
e 以上より,本件では前記b(a)及び(b)記載の事情を推定覆滅事由と して考慮すべきところ,前記認定・判示の事情を踏まえると,6割の限度で推定が 覆滅されると認めるのが相当である。 この点に関し,被告は顧客が原告らに注文して原告製品を購入するという行動に 出たという可能性は皆無であったなどとして,推定覆滅率を99.09%とすべき\n旨主張する。 確かに,被告が原告扶桑産業から原告製品を購入すべき義務を負っていたという 事情はうかがえないから,被告が原告製品以外のカードケースを販売すること自体 は自由にできたことと認められる。 しかし,他方で,被告は遅くとも平成24年1月以降,原告製品を購入し,量販 店等のエンドユーザーに対して販売しており,以前原告製品を購入したことのある エンドユーザーがバンドル取引において原告製品を組み込むことを希望する可能性\nも否定できない。また,前記認定のとおり,被告製品の販売を開始した平成25年 2月以降も,原告製品の購入を完全にやめたわけではなく,量販店等のエンドユー ザーへの販売もされていたことが推認されるから,被告において原告製品を購入し, これをエンドユーザーに販売する必要性が全くなかったとまで認めることはできな い。むしろ,従前の経緯を踏まえると,被告が本件特許の侵害品を販売しなければ, 原告扶桑産業から原告製品を購入し続け,原告扶桑産業が利益を得ていた可能性も\n一定程度認められるものというべきである。 したがって,被告が主張するように99.09%もの推定覆滅を認めることは相 当でない。
f 他に共有者がいることによる控除(推定覆滅)
(a) 被告は,特許法102条2項に基づく原告扶桑産業の損害は,同 項に基づき算定される逸失利益の2分の1にとどまると主張する。 しかし,特許権の共有者は,それぞれ,原則として他の共有者の同意を得ないで その特許発明の実施をすることができるものの(特許法73条2項),その価値の 全てを独占するものではないことに鑑みると,特許法102条2項に基づく損害額 の推定を受けるに当たり,共有者は,原則としてその実施の程度に応じてその逸失 利益額を推定されると解するのが相当であり,共有持分の割合を基準に共有者各自 の逸失利益額を推定すべきものではない。本件においては,前記(1)オで検討したと おり,原告製品を製造して被告に販売するという実施による利益は原告扶桑産業に 帰属し,原告ソーグは,これに伴って金員を得ていたにすぎないから,原告扶桑産\n業の損害額を算定するに当たり,特許法102条2項に基づく利益額の算定から, 共有持分の割合に応じて2分の1を控除(推定覆滅)すべき理由はない。 しかしながら,原告ソーグについては,被告製品の販売により,特許法102条\n3項の実施料相当額の損害を観念し得ることは既に述べたとおりであり,この場合 に,特許権の共有者の一部(原告扶桑産業)が同条2項により侵害者に対し損害賠 償請求権を行使するに当たっては,同項に基づく損害額の推定は,不実施に係る他 の共有者(原告ソーグ)の同条3項に基づく実施料相当額(共有持分の割合により\n取得する。)の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である(知財高裁平成30 年11月20日判決・最高裁ウェブページ)。
(b) そこで,原告ソーグが被告に対して請求することができる特許法\n102条3項に基づく実施料相当損害金の額について検討する。 この点について,被告は原告らの間で支払われていた差益をもとに実施料率を算 定すべきと主張するが,原告らが指摘する差益は特許権の共有者間で支払われてい るものであり,その具体的内容や法的位置付けは判然としない(なお,原告らは訴 状において原告製品の原材料の売買による差益と主張していた。)から,この金額 を実施料相当損害金の額を算定するのに用いることは相当でない。 そこで,本件では業界における実施料の相場を考慮に入れつつ,相当な実施料率 を認定するのが相当である。 被告はそれを前提としつつも,本件発明の寄与度や被告による販売力等を考慮す ると,原告ソーグの共有持分(2分の1)に係る相当な実施料率は0.025%で\nあると主張するが,推定覆滅事由に関する前記判示によれば,本件発明の寄与度を 考慮するのは相当でない。そして,プラスチック製品(イニシャル・ペイメント条 件無し)の平成4年度から平成10年度までの実施料率の統計データによると,最 頻値は1%,中央値は3%,平均値は3.9%であること(乙83),本件発明の 構成によるとカードケースの使用者の操作性等が相当向上すると認められること,\n前記認定のとおり,被告による被告製品の売上には被告の販売力やブランドイメー ジ等が大きく影響したと認められること,その他本件に現れた事情に加え,さらに は特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,実施に対し受けるべき料 率は,通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと(前掲知財高裁令和 元年6月7日判決参照)をも考慮すると,本件で相当な実施料率は5%と認めるべ きであり,原告ソーグの特許法102条3項に基づく損害は(中略)円(計算式:\n被告製品の売上額(中略)円×5%×1/2(共有持分の割合))となる。
(c) そして,原告ソーグについて特許法102条3項により算定した\n(中略)円を,原告扶桑産業との関係では,前記eの推定覆滅に加え,さらに控 除(覆滅)すべきことになる。
ウ したがって,原告扶桑産業の特許法102条2項に基づく損害額は(中 略)円(計算式:(中略)円×4割(推定覆滅後)−(中略)円)と認められる。 なお,原告扶桑産業は特許法102条1項に基づく損害の主張もしているが,原 告ら主張の原告らの利益額は(中略)円であるところ,特許法102条1項ただし 書の「販売することができないとする事情」として考慮される事情は,同条2項の 推定覆滅事由として考慮される事情と変わるものではなく(前掲知財高裁平成27 年11月29日判決参照),本件では前記判示に照らすと,原告らの利益について 6割の限度で「販売することができないとする事情」があったと認めるのが相当で ある。そうすると,原告ら主張の利益額について立証されているかを検討するまで もなく,同条1項に基づく損害額が前記認定の同条2項に基づく損害額を下回るも のであることは明らかである。
エ 原告扶桑産業は,原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起 等を委任したところ,被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は(中 略)万円と認めるのが相当であり,原告扶桑産業の損害額は合計(中略)円となる。
(3) 原告ソーグの損害額\n
原告ソーグの特許法102条3項に基づく損害額は,上記認定のとおり,(中\n略)円と認められる。 そして,原告ソーグは,原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起等\nを委任したところ,被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は(中 略)万円と認めるのが相当であり,原告ソーグの損害額は合計(中略)円となる。\n
4 以上より,原告らの請求は,それぞれ主文第1項及び第2項に掲げる限度で 理由があるから,その限度で認容し,その余の請求はいずれも理由がないから,棄 却することとして,主文のとおり判決する。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2019.10. 1
平成30(ワ)5189 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
確かに,本件業務委託契約の第4条第1項では,中国の会社がカキ殻加工固形物 (「ケアシェル」)の製造技術指導等を受け,そのノウハウを利用して製造,販売 する一切の成果物を製造,販売することができることが明記されており,中国の会 社は共有特許の構成を有する養殖魚介類への栄養補給体を製造,販売することも可\n能と考えられる。\nもっとも,同項では,「日本国以外で」製造,販売できる旨明記されている上に, 共有特許権が存続する間は,原則として,上記成果物を日本国において製造,販売 することはできないものとされ,さらに違約金の定めもされている(同条第2項)。 それだけでなく,第8条第1項では,中国の会社は,共有特許権が存続する間は, 「ケアシェル」を日本で製造,販売,日本へ輸出しないことを誓約することが明記 されている。 この点に関し,第4条第1項ただし書及び第8条第1項ただし書では,被告会社 が文書により要請したときは,中国の会社は上記成果物を被告会社に販売できるこ とや,「ケアシェル」を日本に輸出できることが明記されているが,あくまでも中 国の会社がこれらをすることができるのは,被告会社が文書により要請する場合に 限られているから,上記各条項によって,中国の会社に対し,共有特許の日本国内 での実施が許諾されたものと認めることはできない。 そして,本件業務委託契約の他の条項を検討しても,中国の会社に対し,日本国 内での共有特許の実施を許諾することを内容とする条項が設けられているとは認め られないから,本件業務委託契約が中国の会社に対し,共有特許権についての通常 実施権を許諾することを内容とするものと認めることはできない。 以上より,これを前提とする原告の主張には理由がない。
(4) 次に,原告は,中国の会社が「ケアシェル」を製造し,これが共有特許発 明の技術的範囲に属していることを前提として,その製造が共有特許権の侵害に当 たると主張する。 しかし,中国の会社が「ケアシェル」を製造し,これが共有特許発明の技術的範 囲に属するもの(共有特許の実施品)であることを認めるに足りる証拠はないし, 中国の会社がこれを日本国内で製造したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって,中国の会社が共有特許権の侵害行為をしたと認めることはできない。
(5) 以上より,本件業務委託契約の内容とするところは,共有特許権の排他的 効力とは無関係であるから,被告会社が中国の会社と本件業務委託契約を締結した こと等が,共有特許権者である原告の権利を侵害したことを理由とする原告の請求 は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成29(ワ)41474 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月30日 東京地方裁判所
特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定められる ものであり(特許法70条1項),特許請求の範囲の記載の解釈は,明細書 の発明の詳細な説明の記載等を考慮して行うべきものである(同条2項)。 しかして,本件発明の構成要件Bにおける「タンパク質を抽出する」混\n合液との文言について解釈し,そのタンパク質抽出の態様を明らかにすべ く,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,1)従来,界面活性剤 の使用を前提とする方法により溶液中の対象物質(タンパク質等)を分離 (抽出)していたところ,界面活性剤を使用すると,分離(抽出)された 対象物質から界面活性剤を除去する工程が必要となり,煩雑さが生じてい たため,溶液中から対象物質を簡便に分離(抽出)するための混合液が求 められていたこと,2)そこで,上記課題を解決するため,界面活性剤を必 要的には含まず,所定の高級アルコール(第1の高級アルコール)と脂肪 酸を含む混合液によって,タンパク質と水性溶媒とを含む抽出対象液から タンパク質を簡便に分離(抽出)するという構成を採用したものが請求項\n1発明であり,本件発明は,かかる請求項1発明を前提としつつ,第1の 高級アルコールとは異なる高級アルコールと炭化水素を含む混合液によ って,タンパク質と水性溶媒と第1の高級アルコールと脂肪酸とを含む抽 出対象液からタンパク質を夾雑物の含有量が従来より少ない状態で抽出 するものであること,3)これによって,タンパク質と水性溶媒とを含む抽 出対象液からタンパク質を簡便に分離(抽出)できる混合液,及び,タン パク質の抽出方法が提供されることとなったこと,4)本件発明に係るタン パク質抽出剤には,従来使用されてきた対象物質の分離(抽出)のための エマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない量(例えば,タンパク 質抽出剤全体に対して0〜4質量%)の界面活性剤が含まれていてもよい こと,本件発明の目的を害さない限り,公知の添加剤(界面活性剤,炭素 数18未満の高級アルコール等)を添加してもよいことが記載されている 旨が認められる。
これらによれば,本件発明に係る,「タンパク質を抽出する」混合液とは, タンパク質と水性溶媒に加え所定の高級アルコールと脂肪酸を含む抽出対 象液から,上記とは別の高級アルコールと炭化水素を含むことによって, タンパク質を夾雑物の含有量がより少ない状態で分離(抽出)できる混合 液であり,界面活性剤の含有の有無を問わないが,従来のエマルション等 に含まれる界面活性剤よりも少ない量の界面活性剤の含有を,従来必要と されていた除去工程を不要にする限度において許容することによって,上 記の分離(抽出)を簡便に行うことができる混合液という技術思想に係る ものであるというべきである。そうすると,上記「タンパク質を抽出する」 混合液において,その含有される界面活性剤の程度は,分離等された対象 物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とするもので あり,そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解するのが相 当であり,分離(抽出)されたタンパク質から界面活性剤を除去する工程 が必要となるものは,上記「タンパク質を抽出する」混合液には当たらな いというべきである。 なお,この解釈は,本件特許の特許出願の経過(「早期審査に関する事情 説明書」(乙2),「意見書」(乙3))において,原告自身が,先行技術にお いては,タンパク質の抽出につき界面活性剤を使用することが必要的であ ったところ,本件原出願の実施形態は,界面活性剤を必要的に用いること はせず,高級アルコールを必要的に用いるものであり,この構成の差によ\nり,界面活性剤を抽出結果物から除去する工程を不要とすることが可能と\nなり,また,タンパク質への界面活性剤の悪影響を回避することが可能と\nなるという効果を奏し(乙2),さらに,界面活性剤を含まなくとも,抽出 対象液からタンパク質を簡便に分離できるという,従来技術からは予測し\n得ない異質な効果を奏する(乙3)旨述べていることにも沿うものであり, 何ら矛盾するものではない。
イ 原告の主張について
これに対し,原告は,本件明細書(段落【0056】)には,「本発明の 目的を害さない限り,公知の添加剤(界面活性剤,炭素数18未満の高級 アルコール等)を添加してもよい」と記載されているが,本件発明の目的 を害する場合とは,タンパク質の分離・抽出作用が機能しない場合,例え\nば,界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の全部が乳化して二層 に分離せず,結果として界面が生じない場合などの極めて例外的な場面を 指すものであって,上記のようなタンパク質の分離抽出においておよそ想 定されない添加物の添加以外は,むしろ広く公知の添加物の添加をさらに 許容することを明示したものと解釈されるべきである旨主張する。 しかし,上記説示のとおり,本件発明に係る「タンパク質を抽出する」 混合液において,その含有される界面活性剤の程度は,分離(抽出)され た対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とする ものであり,そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解する のが相当であるというべきであり,本件明細書の具体的記載を精査しても, 原告が主張するような,界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の 全部が乳化して二層に分離せず,結果として界面が生じない場合などの極 めて例外的な場面を除いて広く界面活性剤の添加を許容することが読み取 れるような記載は見当たらない。したがって,原告の上記主張は,本件明 細書の具体的記載から離れた独自の主張というほかなく,採用することが できない。
被告製品と構成要件Bとの対比\n
ア 証拠(乙18,28ないし31)によれば,被告製品は界面活性剤を「● (省略)●」質量%含むこと,従来,タンパク質の分離等のために使用さ れてきた界面活性剤の量は抽出剤と対象液とを合わせた全体量に対して 0ないし2質量%であったことが認められる。 そして,上記のとおり被告製品に含まれる界面活性剤の量からすれば, 「従来使用されてきた対象物質の分離等のためのエマルション等に含ま れる界面活性剤よりも少ない量(例えば,タンパク質抽出剤全体に対して 0〜4質量%)の界面活性剤が含まれていてもよい。」(段落【0041】) という本件明細書の記載との関係で見ても,また,上記のとおり従来使用 されてきた界面活性剤の量との関係で見ても,被告製品における界面活性 剤の含有量が,従来のエマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない 量であるものとは認められず,その含有される界面活性剤の程度が,分離 (抽出)された対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度 であるとは認めるに足りない。 そうすると,このような被告製品は,そのタンパク質抽出の態様の観点 からして,構成要件Bの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充\n足しないというほかない。
イ これに対し,原告は,従来の「抽出剤」を,「抽出対象液」に添加した総 量に対する界面活性剤の「終濃度」については,CMC(臨界ミセル形成 濃度)を意識して2ないし4%前後とされているところ,実験の操作性の 観点から,前段階である「抽出剤」における界面活性剤の濃度は,その1 0ないし20倍程度が概ね目安となることからすると,同濃度は,通常2 0ないし80%であることとなり,そうすると,界面活性剤を「●(省略) ●」質量%含む被告製品は,従来の「抽出剤」よりも界面活性剤の含有量 が少ないものといえる旨を主張する。 しかし,原告のいう界面活性剤の「終濃度」が「2ないし4%前後とさ れている」こと,「抽出剤」における界面活性剤の濃度がその10ないし2 0倍程度が目安となることを認めるに足りる的確な証拠はなく,従来使用 されてきた抽出剤における界面活性剤の含有量にかかる原告の上記主張 は採用しがたい。また,仮に,原告の上記主張(被告製品が,従来の「抽 出剤」よりも界面活性剤の含有量が少ないこと)を前提としても,そのこ とから直ちに,界面活性剤を「●(省略)●」質量%含む被告製品が,そ の界面活性剤の含有の程度につき,分離(抽出)された対象物質から界面 活性剤を除去する工程が不要である程度のものであると認められること とはならず,被告製品が,そのタンパク質抽出の態様の観点からして,構\n成要件Bの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充足しないとの 上記結論が左右されることにはならない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.09.11
平成30(ワ)2554 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月27日 大阪地方裁判所
被告は,「挟み込んで保持する」という文言について経時的に解釈し,これを, 第二保持部がブレースボルトをその軸方向に沿って外周側から挟み込み,これを仮 に保持した状態でブレースボルトの軸方向に移動して位置調整を行った後に,ナッ トで締め付けて保持するという操作方法に限定される旨を主張し,ブレースボルト を第二保持部が挿通する場合はこれに含まれないから,ブレースボルトを第二保持 部に挿通する被告製品は,本件発明の構成要件を充足しないと主張する。\nしかしながら,構成要件1Cの「挟み込んで保持する」は,物の発明の一要素と\nして,ブレースボルトが,これを包囲する包囲部によりベース板部に固定されるこ と,すなわち「狭着保持」(本件各明細書の段落【0044】,【0049】ない し【0052】等)を意味すると解するのが相当である(なお,被告は,「挟着」 と「狭着」の違いについて,前者は「挟み込む」という予備的動作を指すのに対し,\n後者は「狭める」という最終的操作を意味する,と主張する。しかし,本件各明細 書においては,「挟み込んで保持する」及び「挟み込んで狭着保持する」という2 通りの言い回しがみられるものの,これらが被告の主張のように明確に区別して用 いられているということはできず,「挟み込んで」,「挟着」及び「狭着」という 文言は基本的に同義であると解すべきである。)。 本件各明細書の段落【0008】に,「この構成によれば,(中略)固定片の孔\n部に第二棒状体を挿通させる必要がなく」との記載がある点については,従来技術 において,ブレースボルトが長過ぎる場合,これを切断する等して調整せざるを得 ないが,本件発明の場合,固定片のナットをゆるめて,外周側からブレースボルト を挟むことができるということを,特別な場合における利点として述べたにすぎず, ベース板部と固定片の間に形成される孔部にブレースボルトを挿通することのでき る通常の場合にまで,外周側からブレースボルトを挟み込むことを要件とする趣旨 とは解し得ない。 そうすると,被告の主張するような上記操作方法は,本件発明における構成要件\n充足性の判断を左右するものではない。
(3) 被告製品の施工方法について(甲19,乙4,22)
被告が,被告製品1の施工に際し,安全性確保等の見地から,ブレースボルトを 第二保持部に外周側から挟み込むことはせずに,第二保持部にあらかじめブレース ボルトを挿通できる程度の間隙を開けておき,ブレースボルトを第二保持部の当該 間隙に挿通させて使用する(被告製品2については,第二保持部が開口部の狭いル —プ状板部で構成されるため,ブレースボルトを第二保持部に挿通して使用するこ\nとは明らかである。)ことは当事者間に争いはないが,上記⑴及び⑵で検討したと ころによれば,上記施工方法の結果は,本件発明の「挟み込んで保持する」に該当 するというべきであり,これに反する被告の主張は採用できない。
・・・
被告は,乙13を適宜設計変更したものとして副引用発明を設定するところ, 乙13発明は,同一平面上に配置された2本の棒状体の交差する箇所において,乙 13に記載された物品(以下「本物品」という。)を2つ,各棒状体をそれぞれ覆 うようにして対向配置させて装着し,それぞれの本物品の角度調整用の弧形状の孔 (角度調整用長穴)を利用してボルトにより緊結することにより,2本の棒状体を 連結・固定するものである。 これに対し,副引用発明は,本物品と,本物品から包囲部を取り除いた状態の平 面の板状部材(以下「平面部材」という。)から構成されているところ,平面部材\nは棒状体を覆うことができないので,本物品と平面部材を組み合わせても乙13に 記載されたような交差連結具として使用することはできない(本物品1個と平面部 材1個を組み合わせた場合,保持可能な棒状体は1本のみである。)。また,本物\n品及び平面部材は互いの角度を調整する必要がないから,両部材に存する上記弧形 状の孔の存在意義がなくなってしまう。 したがって,当業者が,乙13発明から副引用発明を導くことは困難である。 また,被告は,乙13以外にも乙12,14ないし20を引用し,天井から 吊設機器を吊り下げるボルトが交差する部位を連結する揺れ止め用交差連結具も慣 用技術であると主張し,当業者は,乙1発明の両端の外側狭着体の平面域に,斜め 支持体に代えて副引用発明を適用して連結することで,被告製品1(すなわち本件 発明)を容易に発明することができる,と主張する。 しかし,乙12,14ないし20に記載された発明も,乙13発明と同様に,同 一平面上に配置された2本の棒状体を,その交差する箇所を覆うように装着するこ とで,連結・固定して振れ止めするための交差固定金具に係るものであって,被告 の主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。\nなお,被告は,このほかにも,乙8,10,24ないし28を引用して,1本の 棒状体を狭着して固定するにあたって,狭着する一方が棒状体を包囲する包囲部を 備えた部材,他方が平面上の部材である慣用技術である旨主張し,乙8ないし11 を引用して,2本の棒状体を狭着して固定する連結具も慣用技術である旨主張する が,いずれにおいても,一対の部材のうち,一方の部材にのみ包囲部を設け,もう 一方の部材を平面状とする交差固定金具の技術は開示されておらず(乙8及び乙2 6に開示された発明は,2つの固定具の間に平板の基板を挟み込む形を採るが,そ れぞれの固定部が包囲部を備えている点については上記の他の発明と同様である。), 被告が主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。\n以上より,副引用発明は,乙13を含めて乙8ないし20のいずれにも開示 されているとはいえない。
オ 容易想到性について(相違点1)
被告は,本件発明や乙1発明のようなコーナー固定金具と,乙12ないし20に 開示されるような交差固定金具とは,同一の技術分野に属し,また,施工現場で同 じ吊設機器において併用されることが多いから,当業者には,コーナー固定金具の 第二支持部に交差固定金具を適宜設計変更して適用する動機付けがある旨主張する。 乙12ないし20に記載される発明から,被告が主張するような副引用発明が導 けないことは上記エで述べた通りであるが,仮にこの副引用発明の具体的構成を措\nくとしても,交差固定金具とコーナー固定金具は,固定する棒状体の本数も固定の 態様も全く異なるものであるところ,単に吊設機器上の近い位置で用いられる2種 類の金具であるからといって,適用の動機付けを認めることはできない。 したがって,設計変更される副引用発明の具体的構成がどうあれ,乙1発明に上\n記刊行物記載の発明を適用する動機付けがあるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.08.22
平成29(ワ)15518 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月26日 東京地方裁判所
(2) 争点2−1(構成要件1Aの充足性)について\n
以下のとおり,本件装置が「画像情報を対応するパターンに変換するパター ン変換器」を有すると認めることはできないので,同装置は構成要件1Aを充\n足しない。
ア 構成要件1Aは,「画像情報,音声情報および言語を対応するパターンに\n変換するパターン変換器と,パターンを記録するパターン記録器と,」であ るところ,本件特許1の特許請求の範囲の記載によれば,「パターン」は, 本件発明1の自律型思考パターン生成機を構成する「パターン変換器」によ\nり画像等の情報から変換され,「パターン記録器」に記録され,「パターン 制御器」において設定,変更がされ,あるいはパターン同士の結合関係が生 成されるものであるから,これらにより処理可能なものであると解すること\nができる。
次に,本件明細書等1の記載を参酌すると,「パターン」は,「対応する 事象の特徴を検出器が識別する信号の組合せにより表現したもの」であり\n(段落【0017】),例えば,画像情報として「犬」を入力すると,犬の 画像パターンが生成され,パターン記録器に犬の画像パターンとして記録さ れることとなる(段落【0018】)。そして,本件発明の実施形態1につ いて説明した段落【0039】においては,画像,音声及び言語の情報をそ れぞれ識別する信号の組合せに変換したものをパターンと呼び,パターンの 要素を「ON」,「OFF」又は「1」,「0」で表現することにするとさ\nれ,【図2】には,画像パターンの例として「IG=[0.0.1.1.・・・] T,とのパターン例が例示されている。 これらの記載によれば,本件発明1における「パターン」とは,画像,音 声及び言語に係る事象の特徴を,計算機たる検出器が識別することができる 「1」,「0」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味し,構成要\n件1Aは,少なくとも,「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパ ターン変換器」,すなわち,画像情報を上記信号の組合せに変換する変換器 を有することを特定したものであるということができる。
イ 原告は,本件製品のパンフレットや動画において,アメリアが「感情的な 対応力」を有するとされ,アメリアの表情が「EQ(共感指数)」により変\n化させられ,ユーザがアメリアの感情を画像で確認できるようになっている ことなどを根拠として,本件装置は「画像情報・・・を対応するパターンに 変換するパターン変換器」を有していると主張する。 しかし,被告は,本件装置がアメリアの感情に対応した画像を予め保有し\nており,状況に応じてその場に適した表情の画像を表\示可能であるとしても,\n画像情報を対応するパターンに変換する機能は備えていないと主張すると\nころ,原告が指摘する本件パンフレットの記載や動画を総合すると,本件装 置が様々な感情に対応する表情のアメリアの画像を保有し表\示することが できるとは認められるものの,本件装置が,外部から入力された表情等に関\nする画像をパターンに変換する機能を有していると認めるに足りる証拠は\nない。
ウ 原告は,本件装置が,その感情に対応した画像を予め保有しており,状況\nに応じてその場に適した表情の画像を表\示可能な構\成を備えているにすぎ ないとしても,構成要件1Aの「画像パターン」とは,画像情報から生成さ\nれ,人工知能を構\成するソフトウェアが利用できる「一塊のデータ」の全て\nを含むのであるから,人工知能がアメリアの感情に対応する画像を表\示する 際に,画像作成時のデータ形式から別のデータ形式に変換する場合も同構成\n要件を充足すると主張する。
しかし,原告の主張する「パターン」の意義は,特許請求の範囲及び本件 明細書等の根拠を欠くものである上,本件装置がアメリアの感情に対応した 画像を予め保有しているのであれば,それは既にアメリアが利用できるデー\nタ形式で保有しているものと解するのが自然であり,更に異なるデータ形式 に変換する必要があるとは考え難い。そうすると,本件装置が様々な表情の\nアメリアの画像を表示し得ることをもって,本件装置が入力された画像情報\nからパターンに変換する機能を有するということはできず,他に本件装置に\nおいて,かかる変換をする変換器が存在することを認めるに足りる証拠はな い。
なお,原告は,アメリアとは別の画像処理用のコンピュータにより画像デ ータを作成したとしても,「アメリアの感情に対応した画像を計算機で処理 可能な形態(パターン)に変換する」という工程を実施していることになる\nから,アメリアが構成要件1Aを充足することに変わりはないとの主張もす\nるが,アメリアとは別のコンピュータが,アメリアが利用できるデータ形式 の画像データを作成する場合に,本件装置が上記工程を実施しているといえ ないことは明らかである。
エ 以上のとおり,本件装置は構成要件1Aを充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.08.15
平成29(ワ)4311 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月18日 大阪地方裁判所
後記検討する【図2】及び【図3】の問題を除けば,上記検討した本件明細 書の記載には,肘置き部が,施術部よりも上方部で施術部に連結していなければな らないことを積極的に示すような内容は存しないと思われるのに対し,本件発明の 効果の観点では,肘置き部は,施術の対象である被施術者の目の部分に近接する位 置で,施術部に連結されると解するのが合理的である。 そして,本件発明1の文言において,「上方位置」と「施術者の上方部」とは近 接する位置で使用されており,本件補正により追加された際にも,当然両者を認識 の上,別異の意味を有するものとして使用されたと解されるところ,前述のとおり, 「上方位置」が施術部よりも上方部の意味である以上,「施術部の上方部」はこれ とは異なる意味であると解され,このことに,上記検討した本件明細書の記載内容 を総合すると,構成要件Cの「施術部の上方部」は,施術部における上方部,すな\nわち,施術部の上下方向における略中心を想定し,それよりも上方の部分を指すと 解するのが相当である。 被告らは,構成要件Cが本件補正により追加された要件であるところ,特許\n請求の範囲の補正に当たって新たな技術的事項の導入は許されないとして,本件明 細書の【図2】及び【図3】においては,肘置き部の上方位置の背面に連結部であ る水平軸が設けられていることから,本件発明における「上方部」は,構成要件B\nの「上方位置」と同様,「施術部の,それより上の部分」(施術部を含まず,施術 部に対して上)と解釈せざるを得ないと主張する。 確かに,本件明細書の【図3】では,肘受け部の回転軸が,施術部の上縁より少 し上方に存するように見えるが,これが実施例にすぎないことは本件明細書にも明 示されているし(【0015】),回転軸が,施術部の上縁に接する状態であれば, これも,施術部における上方部に,肘置き部が連結されているといえなくもない。 その他の【図】で開示されている実施例では,肘置き部がどの位置で施術部に連 結され,回転軸がどの位置に存在するかは全く不明といわざるを得ないが,少なく とも,施術部における上方部に肘置き部を連結する構成と,明らかに矛盾するよう\nな内容は存しない。
イ 出願経過及び本件意見書の記載について
本件意見書には,「4.特許法第29条第2項の拒絶の理由がないことの説 明」という表題の下,「(a)本願第1発明の説明」として,本件発明1につき,\nアイメイクの施術部位は被施術者の目尻,目頭,瞼,まつ毛,眉毛等であるため, この施術部位の周辺に施術者の手を配置すれば,必然的に肘の位置は手の位置を基 点とした範囲内(被施術者の頭部周辺)になるところ,その範囲で肘を支える部材 として肘置き部を備えたのが本件発明1であること,肘置き部が施術部の上方部を 基点として,これを軸に施術部に対して回動することで施術部に対する角度が変化 するが,肘置き部がどのような角度に調整された場合であっても,回動する範囲は 施術部の周囲(頭部の左右位置,もしくは左右位置及び上方位置)において一定で あるため,肘置き部が回動する範囲は,施術部位周辺に施術者が手を配置した際に その施術者の肘が配置される範囲と常に一致すること,これにより,施術者は肘置 き部により肘を固定させて施術することができるため,施術が安定するとともに施 術効率を向上させることができる旨が記載されている。 また,原告は,上記に続く「(b)本件拒絶理由通知書における認定」にお いて,本件拒絶理由通知の概略を,1)「被施術者の頭部を載置する施術部が形成さ れている施術台において,前記施術部の周囲であって,載置される前記被施術者の 頭部の左右位置,もしくは左右位置及び上方位置に,施術者の肘を固定可能な肘置\nき部を設けることで施術者の施術における負担の軽減を図るものは,例えば,引用 文献2の第1図における肘掛け34a,34b(中略)にみられるように周知技術 (以下「周知技術1」という。)であり,引用発明1において上記周知技術1を適 用し,前記施術部の周囲であって,載置される前記被施術者の頭部の左右位置,も しくは左右位置及び上方位置に,施術者の肘を固定可能な肘置き部を設けたものと\nする(中略)ことは当業者が容易になし得たものである。」,及び2)「さらに,施 術者の肘を固定可能な肘置き部を水平を軸にして回動可能\なものとすることも,例 えば,引用文献3(中略),引用文献4(中略)にみられるように周知技術(以下 「周知技術2」という。)であり,引用発明1において上記周知技術2を適用し, 前記肘置き部は水平を軸にして回動可能であるものとすることも当業者が容易にな\nし得たものである。」とまとめた上で,それに続く「(c)本願第1発明と引用発 明との対比」において,引用発明2について,「ヘッドレスト33が傾倒するもの であり,肘掛け34a,34bは個別に回動するものではありません。また,肘掛 け34a,34bの取り付け位置は,ヘッドレスト33の左右方向です。」「した がって,引用発明1に,上記した各引用発明のいずれを適用したとしても,本件発 明1のように,『肘置き部が前記施術部の上方部に連結され,水平を軸にして前記 施術部に対して回動可能』な構\成とはならない」と記載した。 被告らは,上記原告の引用発明2に関する文章(「肘掛け34a,34bの 取り付け位置は,ヘッドレスト33の左右方向です。」)を理由に,本件意見書に おいて,原告は,肘置き部の取付け位置が施術部の左右である構成を排除した旨を\n主張する。 しかしながら,本件意見書の上記文章は,引用発明2について,肘掛けの取付け 位置がヘッドレストの左右であるものの,肘掛けが回動しない点で本件発明とは異 なる旨を指摘したものと解することができ,被告の主張は採用できない。
ウ まとめ
以上検討したところを総合すると,構成要件Cの「施術部の上方部」とは,施術\n部における上方部の意味に解すべきであるが,肘置き部の回転軸が施術部の上縁に 接するよう連結する構成も含み得るとすると,その範囲については,別紙原告図面\nのうち,赤で示された部分を指すと解すべきこととなる。
(2)構成要件Cの「連結」の意義について\n
ア 「連結」の字義的意味は,「つらねむすぶこと。むすびあわせること。」で あるところ,本件明細書には,特に「連結」についての定義や,具体的な連結方法 についての記載はない。 本件明細書の【図2】及び【図3】には,肘置き部と施術部が,それぞれ支持部 材と背面部材を介して,水平軸の位置でつながっている形態が示されており,段落 【0018】も上記形態について説明する。 また,本件意見書には,肘置き部が,施術部の上方部を基点として,これを軸に 施術部に対して回動すること,引用発明3及び引用発明4においては,枕F(また は head rest 2)と肘受24(または head rest 4)とが連動せず別々に動作するこ とが望ましいと考えられるため,引用発明1にこれらの発明を適用したとしても本 件発明1の構成要件Cのような構\成にはならないことが記載されている。 そうすると,構成要件Cにおける「連結」とは,施術部と肘置き部が別々に動作\nすることができない形態でつながっていることを意味し,それ以上具体的な連結方 法について定めるものではないと解するのが相当である。
イ 被告らは,本件明細書の【図1】及び【図6】に示される実施形態から,構\n成要件Cの「連結」とは,「肘置き部が,その上方位置の背面において,前記施術 部の上方部に連結され」と解釈すべきであると主張するが,同図は,1つの実施形 態にすぎないから,そこから具体的な連結部位についてまで定められていると解す べきではない。
(3) 被告製品の構成\n
ア 別紙被告製品写真1ないし4及び別紙「被告製品の説明書」によれば,構成\n要件Cに対応する被告製品の構成cは,施術部の左右側面のうち,上下方向におけ\nる中央線よりも上の部分において,回動部材を介して施術部とリクライニングアー ムとがつながる構成をとり,施術部を左右方向に横切るような仮想の回転軸を中心\nにリクライニングアームが回動するものであると認められる。
イ 被告らは,被告製品の肘置き部が施術部の「左右位置」において回転自在に 支持されていることから,本件発明の構成要件Cを充足しないと主張するが,構\成 要件Cの「施術部の上方部」が施術部の左右側面を排除しない概念であることは前 述のとおりであり,また,構成要件Cの「連結」が具体的な連結方法や連結部位を\n定めるものではないことも前述のとおりであるから,上記被告らの主張を採用する ことはできない。
ウ また,被告らは,被告製品について,仮想の回転軸が施術部を貫通している ことから,回転軸が施術部の背面にあり,また施術部よりも上方にある本件発明と 比較して,肘置き部を回転させた時に肘置き部の左右位置と施術部との間の距離が 比較的短く施術しやすい,という本件明細書から記載された発明からは導き出せな い技術的事項を有すると主張するが,本件発明の回転軸が施術部よりも上方にある との主張は採用できず,被告らの主張は理由がない。
(4) まとめ
以上より,被告製品のリクライニングアームは,施術部の上方部に連結され,水 平を軸として施術部に対して回動可能であると認められるから,本件発明の構\成要 件Cを充足する。
・・・
上記(1)及び(2)によると,被告製品の売上高(税込)から原価(税込)を控除した 額は,951万7032円(別紙被告計算表の「粗利(総計売上税込−総計原価税\n込)」欄参照。)であり,同額を被告らの利益の額と認め,原告の損害額を算定す る基礎とするのが相当である。 なお,消費税基本通達5−2−5に鑑みれば,知的財産権の侵害に基づく損害賠 償金は,消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当し,消費税の課税対象となると解 するのが相当であり(消費税法2条1項8号,同法4条1項),本件における損害 賠償金も,特許権の侵害に基づく損害賠償金として消費税の課税対象となると解さ れるところ,上記被告らの利益の額は,税込売上高から税込原価を控除したもので あり,消費税相当額を含む額であるから,原告の損害額を算定する際に,さらに消 費税相当額8%を加算する必要はない。
イ 被告らの主張について
被告らは,消費税に関し,特許法102条2項の「利益」の算定方法について主 張するほか,そもそも,同項により推定される損害賠償金は逸失利益であるから, 一般的に消費税の課税の対象とならないか,本件の個別事情に照らし,損害賠償金 は対価性がないため消費税の課税の対象とならないこと,仮に本件における損害賠 償金が消費税の課税の対象になるとしても,原告と被告との間において内税方式, 外税方式のいずれを採用するかについての合意がない以上,内税方式によるべきで あることを主張する。 しかしながら,特許権侵害に対する損害賠償請求訴訟では,典型的には,特許権 者のみが発明の実施品を製造,販売している状態を想定し,侵害品の販売により特 許権者側の売上等が減少したことを損害と捉え,認定又は推定の方法により算定し た損害賠償額金を得させることで,権利侵害のなかった原状に可及的に復させよう とするものであるところ,その回復の対象となる原状において,特許権者が発明の 実施品を製造,販売すれば,売上,経費いずれの面でも消費税は考慮されるはずで ある。 そうすると,本件のように,回復の対象である原状において,消費税が考慮され る事案においては,その回復の手段として逸失利益の損害賠償を算定する際におい ても消費税の負担は考慮すべきことになり,これに反する被告らの主張は採用でき ない。 そして,その計算としては,前述のとおり,消費税相当額を考慮した売上額から, 消費税相当額を考慮した経費額を控除すれば足りると解され,これによって算定し た損害額に,さらに消費税相当額を加算する必要はないし,当事者間に特段の合意 がなければ内税方式により計算すべきであるとの被告らの主張も理由がない。 また,被告らは,消費税相当額分の遅延損害金の起算日は,その額が確定した日, すなわち判決確定日であって不法行為時ではないと主張するが,上記アのとおり, 原告に支払われるべき損害賠償金は,消費税相当額を含むものの,全体としては特 許法102条2項により原告の損害と推定される額であるから,全部につき不法行 為の日から遅滞に陥ると解するのが相当である。
(4) 推定覆滅又は寄与率について
ア 被告らは,本件発明の被告製品に対する技術的寄与及び顧客吸引力は小さく, 寄与率は50%程度であると主張する。 しかし,本件発明3の構成要件Fは,リクライニング機構\が付与されていること とされており,本件明細書の段落【0020】及び【0021】にも,電動式を含 むリクライニング機構が付与されていることにより,異なるアイメイク施術を1台\nで済ませることができたり,被施術者が仰向けになったときの下半身の負担を軽減 したりすることができる旨の記載がある。また,本件発明はアイメイク用施術台全 体に関するものであって,リクライニングアームのみに関する発明ではない。 よって,本件発明の,被告製品に対する技術的寄与が少ないという上記被告らの 主張を採用することはできない。
イ また,被告製品の価格(11万8000円(税抜))と本件発明の実施品の 価格(18万2000円(税抜))との差は6万4000円であるところ(乙29), これが直ちに顧客吸引力に大きな差が生じるまでの金額ということはできない。ま た,被告らは,高田ベッド製作所がアイメイク用施術台の分野において特別なブラ ンド力を有することや,被告製品の広告宣伝において,高田ベッド製作所のブラン ド力を使用していること等の主張立証をせず,リクライニング機構が本件発明3の\n構成要件となっていることは,上記アのとおりである。\nよって,本件発明が,顧客の購買に寄与する要素が極めて小さいという上記被告 らの主張を採用することはできない。
ウ したがって,本件において特許法102条2項の推定を覆滅すべき事情は認 められない。
(5) 特許法102条4項後段に関する主張
原告は,平成28年10月31日付け及び同年12月5日付けで,被告アイラッ シュに対し,本件特許権の侵害について2回にわたり警告し,被告アイラッシュも これに回答していることから(甲5ないし8),被告らにおいて被告製品が本件特 許の権利範囲外であると考えたことについて,故意または重過失がなかったとして 損害賠償の額を定めるにつきこれを参酌すべき場合であるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2019.08.13
平成30(ワ)28391 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月12日 東京地方裁判所
原告は,平成31年2月21日,被告コーアイセイを相手方として,本件各 製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に含まれることを立証するため,本件製剤 1に関する平成30年2月15日付け医薬品製造販売承認書に記載されてい る「成分及び分量又は本質」に係る部分について,特許法105条1項に基づ く書類提出命令の申立てをした。\n当裁判所は,同年4月11日,同条2項に基づくインカメラ手続を行い被告 コーアイセイから対象書類の提示を受けた上,同書類には本件製剤1にクロス ポビドンが含まれるかどうかや,クロスポビドンの医薬組成物中の含有率等に 関する情報が記載されているが,本件製剤1の組成物又は含有率は本件訂正発 明に規定するものと異なっている一方,同情報は被告コーアイセイにとって秘 密性の高い重要な技術的情報であると認められるから,被告コーアイセイには 書類の提出を拒むことについて正当な理由があるなどと判断して,同申立てを\n却下した。
・・・・
本件訂正発明の構成要件Cは,「前記崩壊剤が,クロスポビドンであり,前記\nクロスポビドンの医薬組成物中の含有率が5.6〜12質量%であり,但し,崩 壊剤がGRANFILLER−D(登録商標)から成る錠剤は除く,」というも のであるところ,原告は,本件各製剤が構成要件Cを充足すると主張する。\n しかし,本件各製剤が,1)崩壊剤としてクロスポビドンを含有すること,2)そ の医薬組成物中の含有率が5.6〜12質量%であること,3)同崩壊剤がGRA NFILLER−D(登録商標)から成る錠剤でないことについては,これを認 めるに足りる証拠がない。 原告は,本件各製剤は原告製剤の後発医薬品であることや,原告による本件製 剤1の分析によっても,本件製剤1がクロスポビドンの含有を否定するデータは 得られていないことなども指摘するが,本件各製剤が原告製剤の後発医薬品であ るとしても,そのことから直ちに本件各製剤が構成要件Cを充足するということ\nはできず,また,本件製剤1がクロスポビドンの含有を否定するデータは得られ ていないことは,むしろ,同製剤が構成要件Cに規定された含有率のクロスポビ\nドンを含有すると認めるに足りる客観的な証拠が存在しないことを示すもので ある。 したがって,本件各製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に属すると認めること はできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.08. 8
平成31(ネ)10005 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお、「原判決30頁17行目から31頁3行目までを次のとおり改める。」とありますが、原審のどの部分を改めるのか?は、上記範囲とはズレていますので、不明です。
また,請求項1においては,係合部が設けられている揺動部材と他方の揺動部材が,それぞれ開閉機構を有することが規定されるのみで,いずれの開閉機構\をどのような手順で操作するかについては何ら特定がなく,前述の本件発明の技術的意義からもかかる点につき限定する理由はないから,係合部を設けた揺動部材の側に力を加えることによって,他の揺動部材が同時に開く仕組みになっていることは,本件発明において必須の構成ではない。\n以上を踏まえると,構成要件Eの「係合部」とは,これによって外力を伝達し,その結果,いずれか一方の揺動部材の開操作をもって,2対の揺動部材を同時に開くことを可能\にするものであるというべきである。
イ 「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義
次に,かかる係合部の意義を踏まえて,「揺動部材の一方に…係合部 が設けられている」の意義について検討する。 まず,「設けられている」との文言の一般的な意味は,「そなえてこ しらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず(広辞苑・甲 13),当該文言自体からは,「係合部」が一方の揺動部材と一体であ るのか,別の部品であるのかを読み取ることはできない。前記の本件発 明の技術的意義に照らしても,「係合部」が一方の揺動部材と一体のも のでなければその機能を果たせないとはいえず,別の部品によって係合\n部を設けることを除くべき根拠は見当たらない。そうすると,係合部が 揺動部材に「設けられている」という構成が,係合部が揺動部材の一部\nを構成しているものに限定されるとはいえない。\nそして,「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」という特許 請求の範囲の文言に照らすと,係合部が,「一方の」揺動部材に設けら れていることを要することは明らかである。このことは,特許請求の範 囲における請求項3及び4が,2対の揺動部材について,いずれに「係 合部」が設けられているかを区別できることを前提としていることから も裏付けられる。 以上によれば,「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」とは, 「係合部」が,揺動部材に設けられており,かつ,それが2対のいずれ の揺動部材に設けられているのか区別できることを要し,またそれをも って足りると解される。
・・・
被告製品の構成eは,「揺動部材1,2の各下側揺動部には後部に開\n口部が設けられ,各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿 通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材1と揺動部材2が 組み合わせられたときに,開口部に留め金の突起部がはめ込まれ,ピン 用孔に角度調整器の2本のピンを挿通された状態で揺動部材2の上側揺 動部と下側揺動部を相互に開いていくと,留め金の突起部と角度調整器 のピンがそれぞれ揺動部材1の下側揺動部と上側揺動部を押圧して,揺 動部材2と一緒に開くようになっている」ものである(前記第2の3に おいて引用した原判決「事実及び理由」の第2の2⑸)。 このように,被告製品における角度調整器の2本のピンと留め金の突 起部は,外力の伝達により,いずれか一方の揺動部材の開操作をもって, 2対の揺動部材を同時に開くことを可能にするものであるから,角度調\n整器のピン及び留め金の突起部は,構成要件Eの「係合部」を充足する。\nまた,上記のとおり,角度調整器のピン及び留め金の突起部は,開操 作の前に,組み合わせられた揺動部材1及び2の開口部に留め金の突起 部がはめ込まれ,ピン用孔に角度調整器の2本のピンが挿通された状態 に固定されるものである。このような固定態様に照らすと,「係合部」 である角度調整器のピン及び留め金の突起部が,揺動部材1又は2に設 けられているといえる。そして,証拠(甲3,乙6,10)によれば, 角度調整器は,施術者から視認できるように揺動部材1側からピンが挿 通されて揺動部材1に固定されることが認められるから,少なくとも角 度調整器のピンは,揺動部材1に設けられていると認識できることは明 らかである。そして,留め金の突起部も,角度調整器のピンと一体とな って揺動部材の開操作に関わっているのであるから,この両者は,全体 として揺動部材1に設けられていると評価するのが素直である。したが って,「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部をもって, 構成要件Eの「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」との要件\nは充足されることになる。 そして,「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部が, 2対の揺動部材の開操作の前にこれらの揺動部材に固定されることは上 記のとおりであって,これらを同時に開いていく間にかかる固定が解除 されることはない(乙6,10)。したがって,構成要件Eの「他方の\n揺動部材と組み合わせられたときに」揺動部材の一方に係合する係合部 が設けられているといえる。 控訴人は,被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部が,揺動 部材1及び2と別の部品であることから,直ちにいずれの揺動部材に上 記ピン及び上記突起部が固定されているのかの区別ができなくなるとい う前提で主張するが,上記説示したところに照らし,採用できない。
カ 結論
以上のとおり,被告製品は構成要件Eを充足し,他の構\成要件を充足 することについては既に説示したとおりであるから,被告製品は,本件 発明1及び2の技術的範囲に属する。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> ピックアップ対象
2019.08. 8
平成29(ワ)44053 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月29日 東京地方裁判所
(3) 本件明細書1及び3の発明の詳細な説明の記載
ア 本件明細書1及び3の【0015】,【0017】
本件明細書1及び3の発明の詳細な説明の記載は,前記1(1)のとおりであり,発 明を実施するための形態として,「本発明の併用療法は,治療法が同時に行われ, すなわち抗CD20抗体は,同時にまたは同じ時間枠(すなわち,治療は同時に進 んでいるが,薬剤は全く同時に投与されるわけではない)で投与される。本発明の 抗CD20抗体はまた,他の治療法の前または後に投与されてよい。」(【001 5】),「また本発明には,化学療法の前,その最中,または後に,治療上有効量 のキメラ抗CD20抗体を患者に投与することを含んでなる,B細胞リンパ腫の治 療法が含まれる。そのような化学療法は,少なくとも,CHOP,ICE,ミトザ ントロン,シタラビン,DVP,ATRA,イダルビシン,ヘルツァー(hoelzer) 化学療法,ララ(LaLa)化学療法,ABVD,CEOP,2−CdA,FLAG& IDA(以後のG−CSF治療有りまたは無し),VAD,M&P,C−Week ly,ABCM,MOPP,およびDHAPよりなる群から選択される。」(【0 017】)と記載されている。 しかしながら,上記において,抗CD20抗体ないしキメラ抗CD20抗体とし て示されるリツキシマブの投与時期について,【0015】では,「他の治療法の 前または後」と「同時にまたは同じ時間枠(すなわち,治療は同時に進んでいるが, 薬剤は全く同時に投与されるわけではない)」が併記されるにとどまり,また, 【0017】では,「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにと どまっており,化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされ ていないから,これらの記載をもって,リツキシマブをCHOP療法の各薬剤の投 薬期間中に投与するという本件発明1の用途を認識することは困難であり,もとよ り,リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各 サイクルの1日目に投与するという本件発明3の用途を認識することもできない。 このことに加えて,前記のとおり,本件発明1及び3は,いずれも,リツキシマ ブを含む医薬組成物について,対象疾患,併用される化学療法及び投与時期を特定 した用途発明であるところ,【0015】では,対象疾患及び併用される化学療法 が特定されておらず,【0017】でも,対象疾患が特定されておらず,併用され る化学療法であるCHOP療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっ ているから,その意味でも,これらが本件発明1及び3の用途を記載又は示唆する ものと認めるに足りない。
イ 本件明細書1の【0069】ないし【0071】,【0092】
(ア) また,本件明細書1の【0069】ないし【0071】及び【0092】の SWOGによる臨床試験に係る部分において,本件発明1の対象疾患である「低グ レード/濾胞性非ホジキンリンパ腫(NHL)」の患者に対するリツキシマブとC HOP療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの,次のとおり,これら は,リツキシマブを含む医薬組成物をCHOP療法の各薬剤の投薬期間中に投与す るという本件発明1の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。 a すなわち,まず,本件明細書1の【0069】ないし【0071】には, 「新に診断された再発性低悪性度NHLまたは濾胞性NHLにおけるCHOPとリ ツクシマブ(登録商標)との併用を評価するために第II相試験」(【0069】) について,「CHOPは,標準用量で3週間毎にリツクシマブ(登録商標)(37 5mg/m3)を6回注入する6サイクルを行った。リツクシマブ(登録商標)注入 1と2は,最初のCHOPサイクル(これは8日目に開始した)の前の1日目と6 日目に投与した。リツクシマブ(登録商標)注入3と4は,それぞれ第3および第 4のCHOPサイクルの2日前に投与し,注入5と6は,6回目のCHOPサイク ル後のそれぞれ134日目と141日目に投与した。」(【0070】)と記載さ れており,参考文献21として甲38文献が参照されていること(【0071】) などに照らすと,これらは,甲38文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試 験を記載したものと認められる(なお,【0070】の「第3および第4のCHO Pサイクルの2日前」は「第3及び第5のCHOPサイクルの2日前」の誤記であ ると認められる。)。 そうすると,【0070】の「リツクシマブ(登録商標)注入1と2」及び「注 入5と6」は,CHOP療法全体の開始前及び終了後の投与であり,また,「注入 3と4」も,Czuczmanらによる臨床試験の3回目及び4回目のリツキサンの投与と 同様に,CHOP療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって,当業者は,いずれに ついても,CHOP療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識する と認められる。 したがって,【0069】ないし【0071】は,リツキシマブを含む医薬組成 物をCHOP療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明1の用途を記載 又は示唆するものではない。
b また,本件明細書1の【0092】には,「SWOGにより行われた新に診 断された濾胞性リンパ腫でCHOPの後にリツクシマブ(登録商標)を使用する第 II相試験もまた,完了している。」として,SWOGによる臨床試験について記載 されているものの,同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「CHOP の後」であるから,リツキシマブを含む医薬組成物をCHOP療法の各薬剤の投薬 期間中に投与するという本件発明1の用途を記載又は示唆するものではない。 (イ) さらに,本件明細書1の【0092】には,「マントル細胞リンパ腫が未治 療の40人の患者でリツクシマブ(登録商標)とCHOPの第III相試験も,ダナ ファーバー研究所(Dana Farber Institute)で行われている。21日毎の6サイ クルで,リツクシマブ(登録商標)は1日目に投与され,CHOPは1〜3日目に 投与される。この試験の発生項目は完了している。」として,ダナファーバー研究 所による臨床試験について記載されているものの,本件明細書1には,同臨床試験 の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明1の対象疾患である「低グレード /濾胞性非ホジキンリンパ腫(NHL)」に含まれることは記載されておらず,そ のように認めるに足る証拠もないから,上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明 1の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ 本件明細書3の【0090】,【0092】
(ア) また,本件明細書3の【0090】において,本件発明3の対象疾患である 「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫(NHL)」の患者に対するリツキ シマブとCHOP療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの,その内容 は,「別の試験では,中または高悪性度NHLを有する31人の患者(女性19人, 男性12人,平均年齢49才)に,6回の21日サイクルのCHOPの1日目にリ ツクシマブ(登録商標)を投与した(35)。」というものであり,CHOP療法 の各薬剤の投与時期は記載されていない。 また,本件明細書3の発明の詳細な説明に,参考文献35として記載されている 乙9文献においても,前記1(2)イのとおり,Linkらによる臨床試験で,1サイクル 21日間(3週間)のCHOP療法を繰り返し実施するに当たり,リツキシマブは CHOP療法の各サイクルの1日目に投与されたのに対し,シクロホスファミド, ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの3日目に投与され,プレドニソ\ ンは各サイクルの3日目から7日目まで投与されたことが認められる。 したがって,【0090】は,リツキシマブとCHOP療法の各薬剤をCHOP 療法の各サイクルの1日目に投与するという本件発明3の用途を記載又は示唆する ものとは認められない。
(イ) さらに,本件明細書3の【0092】には,前記のとおり,ダナファーバー 研究所による臨床試験について記載されているものの,本件明細書3には,同臨床 試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明3の対象疾患である「中悪性 度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫(NHL)」に含まれることは記載されてお らず,そのように認めるに足る証拠もない。 また,「21日毎の6サイクルで,リツクシマブ(登録商標)は1日目に投与さ れ,CHOPは1〜3日目に投与される。」というだけでは,CHOP療法の各薬 剤が全て各サイクルの1日目に投与されたかは必ずしも明らかでないから,いずれ にしても,上記の臨床試験に係る記載部分がリツキシマブとCHOP療法の各薬剤 をCHOP療法の各サイクルの1日目に投与するという本件発明3の用途を記載又 は示唆するものとは認められない。
(4)原告らの主張について
ア 本件発明1
原告らは,本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は,化学療法 の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与する 異日投与レジメンによっていたところ,本件明細書1の【0015】,【0017】 には,異日投与レジメンと区別して,化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の 投薬期間中にリツキシマブを投与する同日投与レジメンが記載されていると主張す る。 しかしながら,本件原出願日当時,原告らが主張する異日投与レジメンによって リツキシマブと化学療法が併用されていたとしても,前記のとおり,【0015】, 【0017】には,化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る記載は なく,化学療法の開始前,終了後,化学療法に用いられる薬剤の休薬期間中にリツ キシマブを投与するレジメンと区別して,化学療法に用いられる薬剤の投薬期間中 にリツキシマブを投与するレジメンが記載されているとはいえないから,これらの 記載が本件発明1の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
・・・
被告製剤についてみると,前記第2の2⑸ウのとおり,被告製剤の添付文書には, 用法・用量欄に「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合」が記載され,用法・用量に関 連する使用上の注意として,「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は,先行バイオ 医薬品の臨床試験において検討された投与間隔,投与時期等について,【臨床成 績】の項の内容を熟知し,国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」 と記載されている。また,臨床成績欄には,被告製剤の臨床成績として,未治療 の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に,被告製剤又は先行バイオ医薬品がR−CVP レジメンによって投与されたことが記載されているほか,先行バイオ医薬品の臨 床成績として,国外臨床第III相試験(PRIMA試験)において,ろ胞性非ホジ キンリンパ腫(NHL)の患者に,R−CVPレジメンによる寛解導入療法等が 実施されたことが記載されている。 そして,証拠(甲12,35)及び弁論の全趣旨によれば,被告製剤の添付文書 に記載されているR−CVPレジメンは,リツキシマブを1日目に投与するととも に,シクロホスファミド(CPA)及びビンクリスチン(VCR)を1日目,プレ ドニゾロン又はプレドニソン(PSL)を1日目から5日目まで投与するレジメン\nであると認められる。 そうすると,被告製剤は,添付文書に記載されたR−CVPレジメンがシクロホ スファミドを1日目にのみ投与するものであり,1日目から5日目まで投与するも のでない点で,構成要件2Bの「CVP」を充足するとはいえない。\n
・・・
以上のとおり,本件特許1及び3は特許法36条6項1号に違反しており,いず れも特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから,同法104条の 3第1項により,本件特許1及び3に係る専用実施権者である原告による権利行使 は認められない。 また,被告製剤は本件発明2の技術的範囲に属するとはいえないから,被告製剤 の製造販売等が本件専用実施権2を侵害するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成29(ワ)43269 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月18日 東京地方裁判所
「空間を形づくる非伸縮性の接合部」の意義について,本件明細書には,マ スク布地の中央部に鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性の接合部 を形成したので,会話等で唇を動かしても,呼吸をしても,ニット布地による 拡大,縮小といった変化を生じることがなく,安定して会話や呼吸を行うこと ができること,非伸縮性の接合部を形成する手段として,マスク本体の中央部 を左右に分離させた上,鼻下及び唇部との間に一定空間を保つような外膨らみ の扇形状に裁断し,可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合するとの 記載がある(段落【0020】【0059】【0060】【0092】)。 そうすると,「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは,少なくとも,会話や 呼吸の妨げにならないように,マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない\n程度の空間が保たれるよう,マスク本体の中央部を左右に分離させ,外膨らみ の扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構\n成を含むと解するのが相当である。
証拠(甲5,21の1・2,乙37)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品 は,マスク本体の中央部を左右に分離させ,外膨らみの扇形状に裁断して縫合 する構成を有しており,それによって,マスク本体の中央部に非伸縮性の接合\n部が形成され,会話や呼吸の妨げにならない程度に,マスクの本体が鼻下及び 唇の表面に接触しない程度の空間が保たれていると認められる。\nしたがって,被告製品は,「空間を形づくる非伸縮性の接合部」(構成要件D)\nを充足するといえる。
これに対し,被告は,「非伸縮性の接合部」について,「非」とは,後に続く 語句について「そうでない」という意味であり,「非伸縮性」とは,伸縮しない, 又は,伸縮するものを除くという意味であると主張するが,本件明細書には, 前記のとおりの記載があり,他方,「非伸縮性」について全く伸縮性を有しない とは記載されていない。また,本件発明はニット生地のマスクに関する発明で あり,一切伸縮しない製品のみを想定しているとは考え難い。 被告は,本件明細書の記載(段落【0060】【0061】)から,「非伸縮性」 の接合部とは,二重の縫合であることが必須の構成であると主張するが,本件\n明細書の段落【0061】には,「例えば・・・二重の縫合を施すことで可及的 な非伸縮性を得ることができる。」との記載があるとおり,二重の縫合はあく まで実施形態の一つとして例示されているにすぎず,「非伸縮性」の接合部の 構成が二重の縫合に限定されるとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成31(ネ)10019 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び前記(2)の本件明細 書の開示事項を総合すると,本件発明の技術的意義は,従来の住宅地図に おいては,建物表示に住所番地及び居住者氏名も全て併記されていたため,\n肉眼でも判別可能な実用性を確保するために縮尺度を低いものにする必要\nがあり,これに伴って全体として地図の大型化や大冊化を招き,この大型 化や大冊化が氏名の記載変更作業の実地調査に係る人件費と相俟って住宅 地図を高価格なものとし,更に氏名の公表を希望しない住人についても住\n宅地図に氏名を登載してしまうこととなるため,プライバシーの保護とい う点からも問題を有し,また,従来の住宅地図の付属の索引は,住所の丁 目及びそれぞれの丁目に該当するページだけが掲載されていたため,「目 的とする居住地(建物)を探し出す作業」(検索)が,煩雑で面倒であり, 迅速さに欠け,非能率な作業となっていたという課題があったことから,\n本件発明の住宅地図は,この課題を解決するため,検索の目安となる公共 施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については,居住人氏名や建物 名称の記載を省略し,住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載すること により,縮尺度の高い,広い鳥瞰性を備えた構成の地図とし(構\成要件B 及びC),地図の各ページを適宜に分割して区画化した上で,地図に記載 の全ての住宅建物の所在番地を,住宅建物の記載ページ及び記載区画を特 定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索引欄を設ける構成(構\成要 件DないしF)を採用することにより,小判で,薄い,取り扱いの容易な 廉価な住宅地図を提供することができ,また,上記索引欄を付すことによ って,全ての建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容 易に分かるため,簡潔で見やすく,迅速な検索の可能な住宅地図を提供す\nることができるという効果を奏することにあるものと認められる。
イ この点に関し控訴人は,本件発明の技術的思想(技術的意義)は,「検 索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については 居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地のみ を記載すると共に,縮尺を圧縮して」(本件発明の構成要件B及び構\成要 件Cの前半)という構成により,「記載スベースを大きく必要とせず」(本\n件明細書の【0039】),これにより「広い鳥瞰性を備えた地図を構成」\n(構成要件Cの後半)する点にある旨(前記第2の4(1)エの「当審におけ る控訴人の主張」(ア))を主張する。
しかしながら,発明の技術的意義は,明細書に開示された従来技術の課 題について,特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づいて,当該発 明がその課題の解決手段として採用した構成及びその構\成による効果を踏 まえて認定すべきものと解されるところ,控訴人の上記主張は,本件明細 書において,従来の住宅地図の付属の索引には,住所の丁目及びそれぞれ の丁目に該当するページだけが掲載されていたため,「目的とする居住地 (建物)を探し出す作業」(検索)が,煩雑で面倒であり,迅速さに欠け, 非能率であるという課題があったこと(【0003】),本件発明は,上\n記課題を解決するための手段として,地図の各ページを適宜に分割して区 画化した上で,地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を,住宅建物の記 載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索 引欄を設ける構成(構\成要件DないしF)を採用したことにより,全ての 建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容易に分かるた め,簡潔で見やすく,迅速な検索を可能としたという効果を奏すること(【0\n039】)の開示があることを考慮しないものであるから,採用すること ができない。
・・・
控訴人は,仮に本件発明の構成要件Dの「区画化」の構\成が,地図が記載 されている各ページについて,記載されている地図を線その他の方法によっ て仕切って複数の区画に分割し,その各区画を特定する番号又は記号番号を 付し,利用者が,線その他の方法及び記号番号により,当該ページ内にある 複数の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割す ることを意味するものと解し,また,仮に構成要件Fの「索引欄に…住宅建\n物の所在する番地を前記地図上における…記載ページ及び記載区画の記号番 号と一覧的に対応させて掲載した」との構成が,索引欄に所在番地の記載ペ\nージ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載される構成に限られ\nると解した場合には,被告地図は,各ページに線その他の方法及び記号番号 が付されていない点及び「特定の緯度・経度を含む地点データと縮尺レベル 19ないし20を含むURL」が画面に「一覧的に」表示されていない点で\n本件発明と相違することとなるが,被告地図は,均等の成立要件(第1要件 ないし第3要件)を満たしているから,本件発明と均等なものとして,本件 発明の技術的範囲に属する旨主張する。 しかしながら,前記1(3)ア認定の本件発明の技術的意義に鑑みると,本件 発明の本質的部分は,検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住 宅及び建物については,居住人氏名や建物名称の記載を省略し,住宅及び建 物のポリゴンと番地のみを記載することにより,縮尺度の高い,広い鳥瞰性 を備えた構成の地図とし(構\成要件B及びC),地図の各ページを適宜に分 割して区画化した上で,地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を,住宅建 物の記載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属 の索引欄を設ける構成(構\成要件DないしF)を採用することにより,小判 で,薄い,取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することができ,また, 上記索引欄を付すことによって,全ての建物についてその掲載ページと当該 ページ内の該当区画が容易に分かるため,簡潔で見やすく,迅速な検索の可 能な住宅地図を提供することができる点にあるものと認められる。\n
しかるところ,被告地図においては,前記2(1)ウ及び(2)認定のとおり, 地図を記載した各ページを線その他の方法及び記号番号によりユーザの目に 見える形で複数の区画に仕切られておらず,索引欄に住宅建物の所在番地の 記載ページ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載されていない ため,構成要件D及びFを充足せず,ユーザが所在番地の記載ページ及び区\n画の記号番号の情報から検索対象の建物の該当区画を探し,区画内から建物 を探し当てることができないから,このような索引欄を利用した迅速な検索 が可能であるということはできない。\nしたがって,被告地図は,本件発明の本質的部分を備えているものと認め ることはできず,被告地図の相違部分は,本件発明の本質的部分でないとい うことはできないから,均等論の第1要件を充足しない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.07.22
平成30(ワ)10157 独占的通常実施権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月22日 東京地方裁判所
(1) 構成要件1Eは「前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は,0.5\nkg/cm2〜3.5kg/cm2の範囲であること」,同7Hは,「前記ノ ズルの噴射孔から前記溶出液が噴射されて前記ガラス基板の外面を0. 5kg/cm2〜3.5kg/cm2の範囲の圧力で衝撃する」という構\n成を含むものであり,いずれも,ノズルから噴射された溶出液がガラス 基板の外面を衝撃する際の圧力が「0.5kg/cm2〜3.5kg/c m2」の範囲内であることをその内容とするものである。
(2) 原告は,構成要件1E及び7Hの「圧力」の数値の意義について,1cm\n2当たりの平均の圧力ではなく,溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの 衝撃圧力を意味すると理解すべきであると主張する。 しかし,構成要件1E及び7Hの「圧力」の単位は「kg/cm2」であ り,これは,通常の意味としては,ある程度の面積を有する面に所定の時間 にわたり作用する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算したものと解 するのが自然である。 また,本件明細書等には,構成要件1E及び7Hの「圧力」の意義や測定\n方法に関する明確な定義は存在しないものの,段落【0034】には,「こ の際,各ノズル4の各噴射孔41と外面との距離(図3にdで示す)は重要 な要素である。距離dがあまり大きくなると,送液ポンプ54による送液圧 力をかなり高くしなければ,上記範囲内の圧力で外面を衝撃することができ なくなってしまい,実用的に難しくなる。」との記載が存在する。液滴の大 きさや衝撃力は距離により変化するものではないので,上記明細書の記載は, 上記各構成要件の「圧力」が単位面積当たりの作用力の大きさであることを\n示唆するものということができる。
(3) これに対し,原告は,本件明細書等の段落【0015】及び【0017】 における,ノズルから噴射された溶出液の衝撃により外面の材料が溶け出し, 溶出液が衝撃により流出していく旨の記載を根拠として,構成要件1E及び\n7Hの「圧力」は,溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの衝撃圧力を意 味すると主張する。しかし,上記記載は,構成要件1E及び7Hの「圧力」\nの測定について特定の方法によるべきことを含意するものではなく,同記載 をもって,同各構成要件の「圧力」が,ガラスを溶出液が衝撃するそのスポ\nットの衝撃圧力を意味すると解することはできない。
また,原告は,甲21の1〜3に依拠し,本件特許出願当時,本件特 許に近い技術分野においても,原告が主張するような意味で「圧力」と いう用語が用いられていたと主張する。しかし,甲21の1は,「気中ウ ォータージェットピーニング技術」であって,約1000MPaの非常 に高い衝撃圧力が生じるものであり,甲21の2及び3も,高速液体噴 流による洗浄・ピーニングに関する技術及び漁船等に付着した貝などを 除去するための高圧噴流ノズルに関する技術であって,本件特許のよう なガラスの基板の研磨に関する技術分野とは異なる技術分野であり,そ こで想定されている「圧力」の大きさも異なるというべきである。 むしろ,本件ノズルと同種のノズルを昭和30年代から製造している いけうち(乙4)においては,その測定に当たり,1cm×1cmの正 方形の圧力受領域を有する「受圧プレート」が使用されていると認めら れ(乙3),また,いけうちと同様に長年にわたりスプレーノズルを製造 している共立合金製作所においても,一定の面積の受圧部を使用してい ることが認められる(乙5参考資料1)。これによれば,本件特許出願当 時,ノズルから噴射された溶出液がガラス基板の外面を衝撃する際の圧 力の測定方法としては,一定面積を有する面に所定の時間にわたり作用 する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算することが標準的であ ったというべきである。
(4) 原告は,本件ノズルを製造したいけうちの作成したスプレーノズル流量線 図(甲8)などに基づき,被告NSCの用いる方法又は装置におけるフッ酸 の噴射圧力は約1.224kgf/cm2であるとした上で,ノズルからフ ッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラス基板に加わる衝撃の圧力は ほとんど変わらないので,被告方法は構成要件1E及び7Hを充足すると主\n張する。 しかし,証拠(乙1資料4〜6,乙2)によれば,本件ノズルは,ノズル 吐出口の直径は約3mm,吐出口の面積が約7mm2であり,ノズルの先端 とガラス基板との間には190mmの距離があり,薬液は65〜70°の噴 霧角度(噴角)に均等な流量分布で広がって円錐形に噴霧されるので(乙2 の1頁左上写真参照),ノズルから190mm離れたガラス基板上に噴霧さ れる領域は,ノズルの噴霧圧力が0.1〜0.2MPaの場合,直径約24 2〜約266mmの円形領域となり,その面積は約4万5973〜約5万5 543mm2であると認められる。 このように,本件ノズルは,65〜70°の噴霧角度に広がり均等な流量 分布で円錐形に噴霧されるものであり,液滴の分布は一様に広がりながらガ ラス基板の外面に到達するのであるから,その分薬液の単位面積当たりの圧 力は大幅に低減するというべきである。 そうすると,ノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラ ス基板に加わる衝撃の圧力がほとんど変わらないことを前提とし,被告方法 が構成要件1E及び7Hを充足するとの原告の主張は理由がない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.07. 2
平成29(ワ)30826 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月26日 東京地方裁判所(46部)
原告は,本件シールブックが「折り重ねることによって形成されるシール 領域」を有していないという相違点(本件相違点)があるとしても,本件シ ールブックは本件発明1の構成と均等なものとして,本件発明1の技術的範\n囲に属すると主張する。本件シールブックが本件発明1の構成と均等である\nというためには,特許請求の範囲に記載された構成中被告製品と異なる部分\nが特許発明の本質的部分でないことが必要である。 そして,特許発明における本質的部分とは,当該特許発明に係る特許請求 の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特\n徴的部分であると解すべきであり,特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細 な説明の記載に基づいて,特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把 握した上で,特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見ら れない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定するこ\nとによって認定されるべきである。
イ 本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと,本件発明1は,シール 付き印刷物に関する発明であり,それまで知られていた特許文献1ないし3 (特開2007−334037号公報,特開2006−82542号公報, 特開2004−314621号公報〔乙2〕)に開示されたシール付き印刷 物では,「シール及びシール台紙は平面状であるため,立体的な広がりのあ る使い方を提供できるものではな」く,また「通常のシールを製造する方法 が適用される」ため製造が容易でないとの課題が存在した(段落【0006】, 【0007】)。ここにいう「通常のシールを製造する方法」は,本件明細書 には直接記載はされていないが,上記各特許文献において,紙本体の少なく とも一箇所を折り重ねることによってシール領域を形成する方法が開示さ れていたと認めるに足りる証拠はない。 本件発明1は,従来技術における上記課題を踏まえ,「容易に製造するこ とが可能」なシール付き印刷物を提供することを目的の1つとしており(段\n落【0007】),本件特許請求の範囲記載の構成,具体的には,シール及び\n台紙となる印刷が施された紙本体と,その少なくとも一箇所を折り重ねるこ とによって形成されるシール領域との構成を有するシール付き印刷物とし,\n紙本体を折り重ねることで形成されたシール領域を有するもの(段落【00 13】)と認められる。 また,実施例である【図1】及び【図2】については,「シール(5,6) 及び台紙(4)となる印刷がされた紙本体2を折り重ねることでシール領域 3と台紙領域4が形成される。」(段落【0046】),「紙本体2を印刷する 工程の延長線上で,紙本体2にコーティング層32と粘着層31A,31B を形成して貼り合わせることでシール領域3となるため,起立シール5を含\nむシールブック1を容易に製造することができる」(段落【0049】)と説 明されている。 これらの本件明細書における記載からすれば,本件発明1が解決しようと する課題である「容易に製造することが可能」となるための構\成には,少な くとも,1枚の「紙本体2」の両面に印刷を施した上で(段落【0020】 【0021】,図3),「紙本体2」を折り重ねて貼り合わせることによって\nシール領域を形成することにより(段落【0021】【0046】),製造さ れたシール付き印刷物であるという構成を有することが含まれていると解\nすることができる。 したがって,本件特許請求の範囲の記載のうち,「紙本体の少なくとも一 箇所を折り重ねることによって形成されるシール領域」との構成は,従来技\n術に見られない特有の技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分である\nといえる。
ウ これに対し,原告は,本件発明の本質的部分は,同種の紙素材を重ねて貼\nり合わせてシール領域と台紙領域を形成することであり,「折り重ねること によって形成されるシール領域」は本件発明1の本質的部分ではないと主張 する。 しかし,前記イのとおり,「紙本体の少なくとも一箇所を折り重ねること によって形成されるシール領域」との構成は,従来技術に見られない特有の\n技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分であり,原告の主張は採用する\nことができない。 したがって,原告の上記主張は採用できない。
エ 前記のとおり,被告製品である本件シールブックは,構成要件1Cの「折\nり重ねることによって形成」との文言を充足しないから,本件発明1とはそ の本質的部分において相違し,少なくとも均等の第1要件を充足しない。 したがって,被告製品である本件シールブックは,本件発明1と均等なも のとして,その技術的範囲に属するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2019.06.25
平成30(ワ)10130 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年4月24日 東京地方裁判所(29部)
ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なか った技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想 に基づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にあることに照らすと,特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のう\nち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。\n
イ これを本件についてみると,前記のとおり,本件発明は,従来の現金主義に 基づく公会計では,政策レベルの意思決定に利用することは困難であったことに鑑 みて,国民が将来負担するべき負債や将来利用可能な資源を明確にして,政策レベルの意思決定を支援することができる会計処理方法及び会計処理を行うためのプロ\nグラムを記録した記憶媒体を提供することを課題とし,その課題を解決するための 手段として,純資産の変動計算書勘定を新たに設定し,当該年度の政策決定による 資産変動を明確にするとともに,将来の国民の負担をシミュレーションすることが できる会計処理方法を提案するものである。 そして,前記のとおり,本件発明の処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘 定)は,国家の政策レベルの意思決定を記録,会計処理するために設定された勘定 であるのに対し,資金収支計算書勘定は,従来の公会計において単式簿記システム で扱ってきた資金(現金及び現金同等物)の受入と払出を記録するものであり,閉 鎖残高勘定(貸借対照表勘定)及び損益勘定(行政コスト計算書勘定)も,企業会計における複式簿記・発生主義会計として用いられてきたものであるから,本件発\n明の課題解決手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民 の負担のシミュレーションは,国家の政策レベルの意思決定を対象とする処分・蓄 積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)によって行われるものと解するのが相当で ある。その上で,本件発明は,資金収支計算書勘定と閉鎖残高勘定(貸借対照表勘定),損益勘定(行政コスト計算書勘定)と処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計\n算書勘定),処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)と閉鎖残高勘定(貸 借対照表勘定)の各勘定連絡を前提として,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に,当該年度における純資産増加(C3,C4)及び純資産減少(C1,\nC2)並びにこれらの差額(収支尻)である純資産変動額(C5)が表示される構\ 成を採用しており,将来の国民の負担をシミュレーションするためには資産変動の 内訳も認識される必要があると認められることにも照らせば,本件発明の課題解決 手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミ ュレーションは,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に表示される純資産増加(C3,C4)及び純資産減少(C1,C2)並びにこれらの差額(収支\n尻)である純資産変動額(C5)によって行われるものと解するのが相当である。 また,上記のような解釈は,本件発明によるシミュレーションに関する本件明細 書の説明とも整合する。すなわち,本件明細書には,「次に,本発明の特徴である シミュレーションについて説明する。損益外純資産変動計算書には,行政コストと, 当期に費消する財源措置で国民の純資産として将来に残る資産の科目からなる財源 措置とそれ以外の科目からなる財源措置と,当期に調達する財源で国民の純資産と して将来に残る資産の科目からなる財源とそれ以外の科目からなる財源と,国民の 純資産として将来に残る資産の原因別増減額と,再評価による差額と,国民の純資 産として将来に残る資産の原因別増減額充当のために手当てされた財源と,会計処 理により,それらから導き出された現役世代の負担額と,将来世代の負担額,赤字 公債相当額,建設公債相当額などの金額が表の中に表\示される。」(【0069】), 「本発明によるシミュレーションは,現役世代の負担額と,将来世代の負担額,赤 字公債相当額,建設公債相当額などの金額に,目標とするべき金額を設定して,行 政コストや財源措置をどのように調整すれば目標とするべき金額が達成できるかを 演算するための手順を予め複数のプログラムとして設定する。」(【0070】)などとして,本件発明によるシミュレーションについて,損益外純資産変動計算書に表\示される行政コスト,財源措置,財源及び資産の原因別増減額等から導き出される 現役世代の負担額,将来世代の負担額,赤字公債相当額及び建設公債相当額等によ って行われることが説明されており,本件発明の課題解決手段である当該年度の政 策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミュレーションが処分・蓄 積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に表示される純資産増加(C3,C4)及び純資産減少(C1,C2)並びに純資産変動額(C5)によって行われるという\n上記の解釈と整合する。
そうすると,本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,国家の政策レベルの 意思決定に係る会計処理を対象とする処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘 定)を採用した上で,同勘定に表示される純資産減少(C1,C2)を構\成する勘 定科目の内容を具体的に規定する構成要件Hは,本件発明の課題解決手段を具体化する特有の技術的思想を構\成する特徴的部分であると認めるのが相当である。したがって,本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,社会保障給付等の損 益外で財源を費消する取引を「財源措置(C2)」に含める構成(構\成要件H)は, 本件発明の本質的部分であると認められる。
ウ この点,原告は,社会保障給付を処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書 勘定)の「財源措置(C2)」に含める構成は,本件発明の非本質的部分であるとし,その理由として,1)本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的原理は,純資産 変動計算書勘定の存在,4つの勘定の勘定連絡の設定,自動仕訳と勘定連絡を通じ 政策レベルの意思決定と将来の国民の負担をシミュレーションできる会計処理方法 のプログラミングにあり(本件明細書【0008】,【0010】,【0021】, 【0031】参照),社会保障給付を行政コスト計算書に計上する被告製品の構成は,本件発明の特徴的原理と無関係であること,2)社会保障給付を処分・蓄積勘定 (損益外純資産変動計算書勘定)の借方の財源措置に計上する構成を,損益勘定(行政コスト計算書勘定)に計上する構\成に置換したとしても,損益勘定(行政コスト計算書勘定)は処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に振り替えら れるから,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の借方と貸方の差額 (収支尻)に示されている損益外の純資産変動額は同額となり,純資産変動額や将 来償還すべき負担の増減額を財務諸表の中に表\示することにより当該年度の政策決 定による資産変動を明確にするとともに,将来の国民の負担をシミュレーションで きるという同一の作用効果を奏することなどを主張する。 しかしながら,前記のとおり,本件発明は,国家の政策レベルの意思決定を対象 とするものとして,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)という新たな 勘定を設定するものであり,当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の 国民の負担のシミュレーションを通じた政策レベルの意思決定の支援は,処分・蓄 積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)によって実現されるものと解するのが相当 であり,本件明細書においても,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定) 以外の勘定を用いて将来の国民の負担のシミュレーション等が行われることは説明 されていない(原告が指摘する本件明細書【0031】は,適切な勘定連絡を設定 することがシミュレーションをする前提として必要になることを説明するものであ り,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)以外の勘定を用いてシミュレ ーションを行うことを説明するものとは認められない。)。 そうすると,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の借方に計上され る金額の総額及び貸借差額が結果的に同一になるとしても,処分・蓄積勘定(損益 外純資産変動計算書勘定)以外の勘定を参照しなければ,国家の政策レベルの意思 決定に関する勘定科目(社会保障給付を含む)及びその金額が明らかにならないよ うな構成は,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)を通じて国家の政策レベルの意思決定を支援する本件発明とは作用効果が異なるというべきである。\n
エ また,原告は,従来技術に対する本件発明の貢献の程度は大きいから,本件 発明の本質的部分は,「処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の導入に より,将来世代に対して負担が現実的に先送りされた金額や将来利用可能な資源の増加額を可視化する」という構\成要件Hを上位概念化したものであって,被告製品は,そのような構成を備えていると主張する。原告の主張は必ずしも明確でないが,従来技術に対する本件発明の貢献の程度に\n照らし,本件発明の構成のうち,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の設定以外のものは非本質的部分であると主張する趣旨であれば,本件出願日前に\n頒布された刊行物である乙12文献において,資金収支計算書勘定,貸借対照表勘定及び行政コスト計算書勘定に加えて,納税者,すなわち,国民の資産の変動を明\nらかにするための勘定として,財源措置・納税者持分増減計算書勘定を設ける構成が示されていることに照らし,少なくとも,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計\n算書勘定)の設定のみを従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると認めることはできないから,採用することができない。\n
オ そこで,被告製品をみると,被告製品では,前記のとおり,社会保障給付が 行政コスト計算書に計上されており,純資産変動計算書には,行政コスト計算書の 収支を基礎付ける勘定科目(社会保障給付を含む)及びその金額が示されていない ことが認められ,「純経常費用(C1)と並んで財源措置(C2)という項目もあ るが,これは具体的に言えば社会保障給付や…を指しており」(構成要件H)を充足するとはいえないから,本件発明と本質的部分において相違する。したがって,\n被告製品は,均等の第1要件を満たすとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.06.21
平成29(ワ)9201 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月20日 大阪地方裁判所
特許法102条3項は,「特許権者…は,故意又は過失により自己の特許権 …を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨 規定する。そうすると,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準と し,そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 ここで,特許法102条3項については,「その特許発明の実施に対し通常受け るべき金銭の額に相当する額」では侵害のし得になってしまうとして,平成10年 法律第51号による改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。また,特 許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許の効力が明らか ではない段階で,被許諾者が最低保証額を支払い,当該特許が無効にされた場合で あっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなど,様々な契約上の制 約を受けるのが通常である状況の下で,事前に実施料率が決定される。これに対し, 特許権侵害訴訟で特許権侵害に当たるとされた場合,侵害者は,上記のような契約 上の制約を負わない。これらの事情に照らせば,同項に基づく損害の算定に当たっ て用いる実施に対し受けるべき料率は,必ずしも当該特許権についての実施許諾契 約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく,むしろ,通常の実施 料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべきである。 したがって,特許法102条3項による損害を算定する基礎となる実施に対し受 けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それ が明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該特 許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能\n性,3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態 様,4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。
(イ) 実施料の相場(1))
「実施料率〔第5版〕」(社団法人発明協会研究センター編,平成15年発行。 甲38)によれば,「医薬品・その他の化学製品」(イニシャル無)の技術分野に おける平成4年度〜平成10年度の実施料率の平均値は7.1%であり,昭和63 年度〜平成3年度に比較して上昇しているところ,その要因として,「実施料率全 体の契約件数は減少しているものの,8%以上の契約に限れば件数が増加しており, この結果,…実施料率の平均値が高率にシフトしている。」,「この技術分野が他 の技術分野と比較して実施料率が高率であることと,実施料率の高率へのシフト傾 向は,医薬品が支 れている。また,「バイオ・製薬」の技術分野においては,平均6.0%,最大値 32.5%,最小値0.5%とされている。
(ウ) 本件における実施料率を考えるにあたり考慮すべき事情(2)〜3))
a 原告は,本件各発明の技術的価値は極めて優れたものであり,また,速乾性 手指消毒剤の市場における泡状の製品の占めるシェアの動向から,経済的にもその 価値は高いなどと主張する。 泡状の速乾性手指消毒剤である被告各製品に係る宣伝広告(甲5,7,8),製 品情報(甲6,9)及び医薬品インタビューフォーム(甲10)では,液状の速乾 性手指消毒剤では手に取ったときにこぼれやすく,ジェル状の速乾性手指消毒剤で は増粘剤が配合されているためにポンプのノズルの詰まりや繰り返し塗布したとき の使用感が問題になることがあったところ,被告各製品は,これらの問題点を解決 する製品である旨がうたわれていることが認められる。 また,本件各発明の実施品である泡状の速乾性手指消毒剤(平成23年6月発売。 甲39,41の1〜41の5,弁論の全趣旨)の販売業者が医療関係者向けに開設 したウェブサイト(甲40)には,泡が目に見えるので消毒範囲が確認できるとと もに,泡が消えるまで塗り広げることが消毒時間の目安にもなる点や,増粘剤が入 っていないので,ポンプが詰まらず,手に擦り込んでもヨレ(増粘剤入りの消毒剤 や化粧品を手に擦り込んだ際に出る糊状の剥離物)が出ないことがうたわれている。 さらに,平成30年9月26日付け薬事日報ウェブサイトの新薬・新製品情報に関 する記事(甲44)においては,第三者の販売に係る「医薬品として日本で初めて 承認された低アルコール濃度72vol%の手指殺菌・消毒剤」の出荷開始予定について\n報じる中で,「同品の登場によって,手指消毒剤の課題であったアルコールによる 手肌への刺激が低減され,…このほか,▽きめ細かく弾力のある泡で,手からこぼ れるリスクを軽減する▽泡が目でしっかり見えるため,手指消毒の状態を確認でき る−といった使用感も特徴。」,「現在,医療分野における手指消毒剤市場は約1 60億円とされ,構成比は液状が6割,ジェル状が3割,泡状が1割という状況。\nただ,液状の構成比は年々減少しており,今後はジェル状と共に泡状も伸びていく\nことが見込まれている。」とされている。 加えて,被告サラヤが実施したアンケートによれば,アンケート対象者である医 療従事者の施設で使用されている速乾性手指消毒剤の種類は,平成25年にはジェ ルタイプ67%,液タイプ27%,泡タイプ6%であったものが,平成27年には それぞれ66%,24%,10%となっている(甲42,43)。 以上の事情を総合的に見ると,被告各製品と本件各発明の実施品に加え,第三者 の製品も,本件各発明の奏する作用効果(前記3(2)ア)と同趣旨と見られる効果を 利点としてうたっていることなどに鑑みれば,泡状の手指消毒剤において本件各発 明が持つ技術的価値は高いものと見られる。また,手指消毒剤の市場において,泡 状の製品のシェアが徐々に高まっていることがうかがわれることに鑑みると,本件 各発明の経済的価値も積極的に評価されるべきものといえる。もっとも,後者に関 しては,ジェル状の製品のシェアはなお維持されているといってよいことに鑑みる と,その評価は必ずしも高いものとまではいえない。実施料率の決定要因としては, 当該特許発明の技術的価値よりも経済的価値の方がより影響力が強いと推察される ことに鑑みると,このことは軽視し得ない。 これに対し,被告らは,本件各発明は平均的な発明に比して技術的に優れた発明 ではなく,また,泡状の手指消毒剤のシェアの拡大は直接的には当該製品の販売事 業者の営業努力によるものであり,シェア拡大をもって特許の経済的価値が高いと はいえないなどと主張する。 しかし,進歩性が認められる本件各発明の奏する作用効果と同趣旨と見られる効 果が実際の製品の利点としてうたわれていることなどに鑑みれば,上記のとおり本 件各発明の技術的価値は高いものと評価するのが相当である。また,販売事業者が 営業活動に当たって相応の営業努力を行うことは当然である上,泡状の手指消毒剤 に係る営業方法等が,ジェル状ないし液状のものに係る営業方法等と比較して,格 別のものであると見るべき事情もない。 これらのことから,この点に関する被告らの主張は採用できない。
b 被告各製品は,被告製品1(500mLの泡ポンプ付が定価1760円,3 00mLの泡ポンプ付が1200円,80mLの泡ポンプ付が670円,600m Lのディスペンサー用が2000円。甲5,28,乙13),被告製品2(500 mLの泡ポンプ付が1760円,300mLの泡ポンプ付が1200円,200m Lの泡ポンプ付が930円,80mLのものが670円,600mLのディスペン サー用が2000円。甲8,29,乙14)いずれも比較的低価格である。反面, これを踏まえて被告各製品の売上高を見ると,その販売数量は多いといえるから, 被告各製品はいわゆる量産品であり,利益率は必ずしも高くないと合理的に推認さ れる。この点は,本件各発明を被告各製品に用いた場合の利益への貢献という観点 から見ると,実施料率を低下させる要因といえる。
(エ) 小括
上記(イ)及び(ウ)の各事情を斟酌すると,特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき,本件での実施に対し受けるべき料率については,7%とするのが相当 である。これに反する原告及び被告らの各主張は,いずれも採用できない。 ウ 「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」 以上によれば,原告が被告らによる本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額 に相当する額は,売上高に7%を乗じて算定すべきこととなる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成30(ネ)10063 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月7日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(3) 推定覆滅事由について
ア 推定覆滅の事情
特許法102条2項における推定の覆滅については,同条1項ただし書の事情 と同様に,侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と特許権者 が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば, 1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),2)市 場における競合品の存在,3)侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),4)侵害 品の性能(機能\,デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について,特許法1 02条1項ただし書の事情と同様,同条2項についても,これらの事情を推定覆滅 の事情として考慮することができるものと解される。また,特許発明が侵害品の部 分のみに実施されている場合においても,推定覆滅の事情として考慮することがで きるが,特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の 覆滅が認められるのではなく,特許発明が実施されている部分の侵害品中における 位置付け,当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するの が相当である。
イ 控訴人らは,炭酸ガスを利用したパック化粧料全てが競合品であることを 前提に,他の炭酸パック化粧料の存在が推定覆滅事由となると主張する。 しかし,そもそも,競合品といえるためには,市場において侵害品と競合関係 に立つ製品であることを要するものと解される。 被告各製品は,炭酸パックの2剤型のキットの1剤を含水粘性組成物とし,炭 酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ,得られた二酸化 炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック 化粧料である。そして,化粧料における剤型は,簡便さ,扱いやすさのみならず, 手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり,各消費者の必 要や好みに応じて選択されるものであるから,剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用 したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人ら が競合品であると主張する製品は,その販売時期や市場占有率等が不明であり,市 場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。
ウ 控訴人らは,被告各製品が利便性に優れているとか,被告各製品の販売は 控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。 しかし,事業者は,製品の製造,販売に当たり,製品の利便性について工夫し, 営業努力を行うのが通常であるから,通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても, 推定覆滅事由に当たるとはいえないところ,本件において,控訴人らが通常の範囲 を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 控訴人らは,被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると\n主張する。 侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても,そのことから\n直ちに推定の覆滅が認められるのではなく,当該優れた効能が侵害者の売上げに貢\n献しているといった事情がなければならないというべきである。
・・・
(ウ) 被告各製品及び原告製品は,いずれも本件発明1−1及び本件発明2−1 の実施品であり,炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生さ せ,得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ,皮膚に 適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより,美肌,部分肥満改善等に 効果を有するものであると認められるのであり,上記(ア)及び(イ)に認定した事実に よっても,被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し,これが控訴人\nらの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず,ほかにこれを認める に足りる的確な証拠はない。
オ 控訴人らは,被告各製品が控訴人ネオケミアの有する特許発明の実施品で あるなどとして,これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべき であると主張する。 侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても,そのことから直ちに推定の覆 滅が認められるのではなく,他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献 しているといった事情がなければならないというべきである。控訴人ネオケミアが, 二酸化炭素外用剤に関連する特許である,1)特許第4130181号(乙A18), 2)特許第4248878号(乙A19),3)特許第4589432号(乙A20), 4)特許第4756265号(乙B全7)を保有していることは認められるが,被告 各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠は ないから,そもそも,被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができ ない。よって,これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない。 なお,被告各製品の中には,上記特許権の存在や,特許取得済みであることを 外装箱に表示したり,宣伝広告に表\示したりしているものがあったことが認められ る(甲7,8,17,20)が,特許発明の実施の事実が認められない場合に,そ の特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないか\nら,この点による推定の覆滅を認めることもできない。
カ 控訴人らは,従来技術との比較の観点から,本件発明1−1及び本件発明 2−1の技術的価値が低いことを主張するが,控訴人らが指摘するジェルと粉末を 組み合わせる化粧料の技術(資生堂614及び日清324)は,炭酸ガスを利用し た化粧料に係るものではないし(乙A103,乙E全9,35,36),2剤混合 型の気泡状の二酸化炭素を発生する化粧料(石垣発明1及び2)は,炭酸ガスの気 泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の技術であって,二酸 化炭素を気泡状で保持する二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのものではない (乙E全4,5,37,38)から,いずれも本件発明1−1及び本件発明2−1 を代替するものではない。そうすると,これらの従来技術の存在は,被控訴人の受 ける損害とは無関係であるから,推定覆滅事由に当たるということはできない。 キ 控訴人らは,乙A3の実験結果によれば,ブチレングリコールが配合され た被告各製品においては,本件発明1−1及び本件発明2−1の寄与は限定的であ ると主張する。しかし,本件発明1−1及び本件発明2−1は二酸化炭素含有粘性 組成物を得るための2剤型の化粧料のキットの発明であるところ,被告各製品は, 炭酸塩を含むジェル剤と酸を含む顆粒剤を混合して使用するパック化粧料のキット であるから,本件発明1−1及び本件発明2−1は被告各製品の全体について実施 されているというべきである。また,被告各製品にブチレングリコールが配合され たことによる効果が控訴人らの売上げに貢献しているといった事情も認められない 本件において,ブチレングリコールが配合されていることは,被控訴人の受ける損 害とは無関係であるから,控訴人らが指摘する乙A3の実験の結果は,控訴人らの 上記主張を基礎付けるものではない。
・・・
6 損害(特許法102条3項)(争点6−2)
(1) 特許法102条3項について
ア 被控訴人は,選択的に,別紙「損害額一覧表」の「被控訴人主張額」「3\n項による損害額」欄記載のとおり,特許法102条3項により算定される損害額も 主張している。特許法102条3項は,特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最 低限度の損害額を法定した規定である。
イ 特許法102条3項は,「特許権者…は,故意又は過失により自己の特許 権…を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す る額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」 旨規定する。そうすると,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準 とし,そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。
(2) その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
ア 特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については,平成10年法律第51号による改正前は「その特許 発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ, 「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして,同改正により 「通常」の部分が削除された経緯がある。
特許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許が無効に されるべきものか否かが明らかではない段階で,被許諾者が最低保証額を支払い, 当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることがで きないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施 料率が決定されるのに対し,技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものと はいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には,侵害者が上記のような契 約上の制約を負わない。そして,上記のような特許法改正の経緯に照らせば,同項 に基づく損害の算定に当たっては,必ずしも当該特許権についての実施許諾契約に おける実施料率に基づかなければならない必然性はなく,特許権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき,実施に対し受けるべき料率は,むしろ,通常の実施 料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって,実施に対し受けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施許諾 契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の相場 等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重 要性,他のものによる代替可能性,3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上 げ及び利益への貢献や侵害の態様,4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の 営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。
・・・・
ウ 実施に対し受けるべき金銭の額
上記のとおり,1)本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料 率は現れていないところ,本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平 均的な実施料率が,国内企業のアンケート結果では5.3%で,司法決定では6. 1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決 金を売上高の10%とした事例があること,2)本件発明1−1及び本件発明2−1 は相応の重要性を有し,代替技術があるものではないこと,3)本件発明1−1及び 本件発明2−1の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること, 4)被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど,本件訴訟に現れた事情を考慮す ると,特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,本件での実施に対し 受けるべき料率は10%を下らないものと認めるのが相当である。なお,本件特許 権1及び本件特許権2の内容に照らし,一方のみの場合と双方を合わせた場合でそ の料率は異ならないものと解すべきである。 したがって,本件各特許権侵害について,特許法102条3項により算定され る損害額は,別紙「損害額一覧表」の「裁判所認定額」「3項による損害額」欄記\n載のとおりとなる。
(3) 控訴人らの主張について
控訴人らは,被告各製品における本件各特許の寄与が限定されることを根拠に 実施に対し受けるべき料率を低くすべきであると主張するが,前記5(3)に説示し たところに照らし,本件発明1−1及び本件発明2−1を被告各製品に用いたこと による売上げ及び利益への貢献が限定されるとは認められないから,控訴人らの主 張は前提を欠く。 また,控訴人らは,被控訴人のビジネスモデルが不当に競争を制限するもので あると主張するが,前記5(1)イにおいて認定したとおり,被控訴人は本件各特許 の実施品を製造販売しているのであるから,被控訴人のビジネスモデルが不当に競 争を制限するものであると解する根拠がない。控訴人らの,MLMによる販売手法 に関する主張は具体的な主張を欠き,失当である。 控訴人らの主張するその余の点も,上記判断を左右するものではない。
7 総括
(1) 被控訴人キアラマキアート(被告製品5)については,上記6で認定した 特許法102条3項に係る損害額が,前記5で認定した同条2項に係る損害額より も高いから,同条3項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。 他方,その余の控訴人らについては,いずれも前記5で認定した同条2項に係 る損害額の方が高いから,この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。
なお,控訴人コスメプロらは,被告各製品を製造,販売するに至った経緯等に 照らし控訴人コスメプロらには故意又は重大な過失はなかったとして,同条4項に 基づき,このことを控訴人コスメプロらの損害賠償額を定めるについて参酌すべき であると主張する。しかし,控訴人コスメプロ,控訴人アイリカ,控訴人ウインセ ンス,控訴人コスメボーゼ及び控訴人クリアノワールは,化粧品の製造会社であり, 仮に同控訴人らの主張する諸事情があったとしても,同控訴人らにつき,特許権侵 害についての故意又は重大な過失がなかったということはできないから,控訴人ら の上記主張は採用できない。
◆要旨
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.05.31
平成31(ネ)10006 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
クレームが凄いですね。「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定することを含む,敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」です。
本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件発明 の「プロカルシトニン3−116」は,「患者の血清中」から「測定」 されるものであり,測定結果が「敗血症及び敗血症様全身性感染」の「検 出」のために用いられることを理解できる。 そして,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)には,「プロカルシ トニン3−116を測定すること」の意義について規定する記載はない が,「測定」とは,一般的に,「長さ,重さ,速さなど種々の量を器具 や装置を用いてはかること」(大辞林(第3版))との意味を有する。 したがって,特許請求の範囲の記載によれば,本件発明の「患者の血 清中でプロカルシトニン3−116を測定すること」とは,患者の血清 中のプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味するも のと解される。
(イ) また,本件明細書の発明の詳細な説明には,従来技術として,患者 の血清中のプロカルシトニンの測定が,敗血症の検出にとって有益な診 断手段であることが知られていたこと,「本発明」の開始点は,敗血症 等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが,プ\nロカルシトニン1−116ではなく,プロカルシトニン3−116であ るという発見であり,そこから新規な診断及び治療方法,そこで使用可 能な物質等を導き出したことの開示がある(前記1(1)イ)。一方,本件 明細書の発明の詳細な説明には,「プロカルシトニン3−116を測定 すること」の意義について明示した記載はない。 そして,このような本件明細書の記載に照らしても,本件発明の「患 者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定すること」とは,患者 の血清中のプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味 し,その測定結果が敗血症等の検出に用いられることを理解できる。
(ウ) 以上の特許請求の範囲及び本件明細書の記載事項を総合すると, 「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定すること」とは, 患者の血清中のプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを 意味するものと解される。
イ これに対し控訴人は,構成要件Aの「患者の血清中でプロカルシトニン\n3−116を測定すること」とは,敗血症患者の血清中でプロカルシトニ ン3−116を敗血症の検出に必要な精度で測定することをいうと解すべ きであり,プロカルシトニン1−116と区別してプロカルシトニン3− 116を測定することを必須とするものではない旨主張し,その根拠とし て,1)本件明細書の記載事項(【0002】〜【0008】等)から,患 者の血清中でプロカルシトニン1−116等とプロカルシトニン3−11 6を区別することなくプロカルシトニン一般を測定したとしても,敗血症 等の検出に必要な精度でプロカルシトニン3−116を測定できることが 当業者に明らかであること,2)本件明細書には,本件特許に係る「敗血症 及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例として,血中か ら検出されるプロカルシトニンの濃度を一般的なイムノアッセイにより測 定することが記載されているが(【0062】,表3),通常のイムノア\nッセイでは,プロカルシトニン1−116と区別してプロカルシトニン3 −116を測定することは不可能であることを挙げる。\nしかしながら,「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定す ること」とは,患者の血清中のプロカルシトニン3−116の量を明らか にすることを意味するものと認められることについては,前記アのとおり である。
上記1)の点については,患者の血清中のプロカルシトニン3−116を プロカルシトニン1−116等と区別することなく測定することとは,患 者の血清中のプロカルシトニンを測定することと同義であるところ,本件 明細書には,患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定することにより 敗血症等を検出する技術は,本件出願の優先日前に従来技術として存在し たものであり,「本発明」は,かかる従来技術に対して新規のものである 旨が記載されていること(前記1⑵イ,ウ)からすると,かかる従来技術 が本件発明に係る方法に含まれると解することはできない。 なお,本件明細書には,敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシ トニンの大部分がプロカルシトニン3−116であることを発見した旨 の記載があるが(【0009】,【0010】),たとえそのような関係 があるとしても,プロカルシトニン3−116を測定することと,プロカ ルシトニン一般を測定することとが同義とはいえないことは明らかであ る。更に付け加えれば,敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシト ニンの大部分はプロカルシトニン3−116であるとの知見が存在する としても,敗血症等であるかどうかが明らかではない(だからこそ,その 診断を要する)患者については,その血清中のプロカルシトニンの大部分 がプロカルシトニン3−116であるかどうかは明らかではないはずで ある。したがって,敗血症等であるかどうかの診断に当たり,検出された プロカルシトニン一般の大部分がプロカルシトニン3−116であると の前提に立つことはできないというべきであるから,上記知見の存在は, 前記アの判断を左右するものではない。 また,上記2)の点については,本件明細書には,正常者及び敗血症患者 の血清中のプロカルシトニン濃度を測定した旨が記載されているところ (【0062】),【0062】に明示の記載はないが,上記測定は,【0 023】と同様に,市販のプロカルシトニンアッセイを用いて行われたも のと理解することができる。 しかしながら,本件明細書には,かかる測定は,これと同時に行われた これらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対比することによ り,正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニンにおいて際 立っていることを示すものである旨の記載があることからすると(【00 59】,【0062】,【0063】,表3),上記測定が,本件特許に\n係る「敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例と して記載されたものであるとは認められない。したがって,上記2)の主張 は,その前提を誤るものである。 以上によれば,控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 被告方法について
前記前提事実のとおり,被告装置及び被告キットを使用すると,患者の 検体中において,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−1 16とを区別することなく,いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度 を測定することができ,その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行わ れていると認められるものの,本件全証拠によっても,被告装置及び被告 キットを使用して敗血症等を検出する過程で,プロカルシトニン3−11 6の量が明らかにされているとは認められない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告方法は,構\n成要件Aを充足するものとはいえない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 間接侵害
>> ピックアップ対象
2019.04.12
平成29(ワ)31706 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月27日 東京地方裁判所
そこで,被告プログラムが「木構造」を有するか,すなわち,被告プログラムを\n使用して表示されるフローダイアグラムの親子関係が示されている部分が「木構\ 造」であるかについて検討する。
原告は,前記イ(イ)の1)から4)までのSayボックスの接続関係について,木構\n造,すなわち階層リードで接続され,ノードの親子関係が示されている部分である と主張するのでこれをみると,前記イ(イ)のとおり,Sayボックスについて,S ayボックスのonStartコネクタから出発して,SayボックスのonSt oppedコネクタに接続されているのであり,SayボックスのonStart コネクタ及びonStoppedコネクタは,いずれも,Sayボックスの構成要\n素である以上,Sayボックスのフローダイアグラムにおけるボックスの接続関係 は,Sayボックスから出発してSayボックスに戻る閉路として表示されている\nことになり,木構造であるとはいえない。\nその他,階層リードで接続され,ノードの親子関係が示されている部分が全て木 構造であることを認めるに足りる証拠もない。\nそうであれば,被告プログラムは,「木構造」を有しているとはいえず,したが\nって,「木構造表\示ステップ」(構成要件G)を充足しないというべきである。\n
エ(ア) この点,原告は,「木構造」の意義について,ノード(点)とエッジ\n(線)から構成される図として表\示されるものであって,閉路を含まない概念であ るとした上で,前記イ(イ)でみたSayボックスの構成は,閉路ではないと主張す\nる。すなわち,被告プログラムのSayボックスのフローダイアグラムにおいて, 3)Say Textボックスの出力コネクタから1)Sayボックスの入力コネクタ に直接リードが接続されている場合には,SayボックスからSayボックスに戻 る閉路であるといえるが,3)Say Textボックスの出力コネクタは,4)Sa yボックスの出力コネクタに接続されており,1)Sayボックスの入力コネクタと 4)Sayボックスの出力コネクタは異なるものとして表示されているのであるから\n閉路ではない旨主張する。 しかしながら,「木構造」はコネクタの接続関係ではなく,ノード間の接続関係\nを表示するものであり,被告プログラムにおいて,それはボックス間の接続関係を\n表示するものであるところ,別紙6の図2は,別紙6の図1に表\示されたフローダ イアグラムのうち,Sayボックスの構成要素を表\示した図であって,前記認定の とおり,SayボックスのonStartコネクタとSayボックスのonSto ppedコネクタはいずれもSayボックスの構成要素であるから,Sayボック\nスのonStartコネクタとSayボックスのonStoppedコネクタの表\n示位置が離れているとしても,Sayボックスから出発してSayボックスへ戻る 接続関係がないとみることはできない。よって,原告の上記主張はその前提を欠き, 採用することができない。
(イ) また,原告は,出力コネクタであるonStoppedは,ボックスの動 作が終了したことを示すにすぎず,Say TextボックスのonStoppe dコネクタから出力されたデータは,Sayボックスを経由して流れることはない から,Sayボックスのフローダイアグラムは,データの流れの観点からみても閉 路ではない旨主張する。しかしながら,証拠(乙30,31)及び弁論の全趣旨に よれば,Say TextボックスのonStoppedコネクタから出力された データは,Sayボックスを経由していることが認められるから,原告の主張はそ の前提を欠き,採用できない。
オ 小括
以上のとおり,被告プログラムは,「木構造表\示ステップ」(構成要件G)を充\n足しない。
(2) 争点1−4(被告プログラムは,「自ノード変数データ,前記上位ノード変 数データ及び前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表\示ステップ」(構\n成要件G)を充足するか)について
ア 「ノードデータテーブル表示ステップ」及び「ノード変数データ」の意義について\n
まず,「ノードデータテーブル表示ステップ」の意義について検討すると,「テ\nーブル」は,表,一覧表\を意味するところ,本件明細書等(【0046】,【00 55】,【0057】,【0065】,【0066】,【図6】,【図10】)に おいて,「ノードデータテーブル」に相当するデザインテーブルは,自ノード変数 データ及び全ての直系上位ノード変数データを表示する領域(【図6】における公\n開変数表示領域)と,代入用スクリプトを表\示する領域を含む一覧表になっており,\n「図6に示した状態で,表示された木構\造及びノードデータの編集が可能であり」\n(【0054】),「ノードデータとして1まとまりになっている」(【005 5】)と記載されていることにも照らせば,「ノードデータテーブル」とは,「ノ ードデータ」の一覧表であり,上位ノード変数データ,自ノード変数データ及び代\n入用スクリプトを同時に表示するものと解するのが一般的かつ自然である。\n次に,ノードデータテーブルが表示する「ノード変数データ」の意義について検\n討すると,本件明細書等には,「変数の値(「変数データ」と記述する場合もあ る。)」(【0031】),「ノードの直系上位ノードの公開変数の値である上位 ノード変数データ」(【0032】)と記載されており,これと異なる解釈を導く ような説明がされていることは認められないから,「ノード変数データ」は,変数 の値を意味すると解するのが自然かつ合理的である。
イ この点,原告は,「テーブル」の意義について,本件明細書等に「デザイン テーブル20は,ツリービューア10に表示されたノードのうちの選択されたノー\nドが有する情報を表示する領域であり」(【0046】)と記載されているから,\n「テーブル」(構成要件G)は,情報を表\示する領域を意味すると主張する。しか しながら,この記載はデザインテーブルの性質を説明するものにすぎず,「テーブ ル」の意義を一般的意味より広く解釈すべきことを示唆する記載とみることはでき ないから,原告の同主張は採用することができない。 また,原告は,「ノード変数データ」の意義について,本件特許の請求項1及び 請求項9並びに本件明細書等の記載(【0008】【0017】)には,「前記自 ノード変数データの値」という文言があり,「変数データ」は,「変数データの 値」と区別して用いられているから,「ノードデータテーブル表示ステップ」にお\nいて,変数の値を表示することは必要ではなく,また,上位ノード変数データと自\nノード変数データとを同時に表示することも必要ではないと主張するが,同主張は,\n前記認定に照らして採用することができない。
ウ 被告プログラム
(ア) 被告プログラムの構成g\n
まず,原告は,被告プログラムのフローダイアグラム画面上のインスペクタに表\n示された入力コネクタの名称が「上位ノード変数データ」に当たると主張している ところ,入力コネクタの名称は変数の値ではないから,「上位ノード変数データ」 に当たると認めることはできない。よって,被告プログラムは,「上位ノード変数 データ」「を表示するノードデータテーブル表\示ステップ」を充足しない。
(イ) 被告プログラムの構成g’\n
また,原告は,被告プログラムのSay Textボックスのスクリプトエディ タにおいて親からの変数の取得機能を使う場合,上位ノードであるSayボックス\nの変数のうち利用可能なものを一覧表\示させることができる機能があるから,被告\nプログラムは,「上位ノード変数データ」「を表示するノードデータテーブル表\示 ステップ」を充足すると主張する。
この点,Say Textボックスにおいて親からの承継を選択した場合,別紙 3−1被告プログラム説明書図19のとおり,インスペクタ上に,Say Tex tボックスの変数Speed(%)の値が表示されるが,これはSay Text ボックスにおいて表示されるものであるから自ノード変数を表\示しているものと認 められ,「上位ノード変数データ」を表示しているとみることはできない。よって,\n被告プログラムは,一覧表として「自ノード変数データ」及び「上位ノード変数デ\nータ」を同時に表示しているということはできない。\nさらに,原告は,別紙6の図3のように,上位ノード変数と代入用スクリプトを 同時に表示することができる旨主張するが,同図の表\示形態を一覧表とみることは\nできない上,同図では,上位ノードの名称が表示されているにとどまり,上位ノー\nド変数の値が表示されていると認めることはできないから,「ノード変数データ」\nを一覧表として表\示しているということはできず,原告の同主張は採用することが できない。
加えて,本件全証拠によっても,behavior.xar内に,親からの承継 の機能に関して,自ノード変数データ及び上位ノード変数データを利用した演算を\n行って自ノード変数データの値を求める「代入用スクリプト」があると認めるに足 りる証拠はないから,被告プログラムは,「前記スクリプトを表示するノードデー\nタテーブル表示ステップ」を充足すると認めることはできない。\nエ 以上のとおり,被告プログラムは,「自ノード変数データ,前記上位ノード 変数データ及び前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表\示ステップ」 (構成要件G)を充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2019.04. 1
平成29(ネ)10090 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年4月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
実際に用いられていたアルミピロー包材と同じ品番のアルミピロー包材の中に は,底部の折り曲げ部分のアルミが剥がれているものもある(甲18,26)。ま た,防湿性を確保したアルミピローの製造は,医薬品メーカーの管理方法を含めた 製造方法に大きく依存する旨指摘されている(乙48)。実際に用いられていたア ルミピロー包材に対して,専門家による立会いの下,リーク試験が行われ,気密性 が担保されていることが確認された旨報告されているものの(乙49),同リーク 試験は,検体を水没させ,一定の減圧条件(槽内圧力−40kPa,保持時間30 秒間)において,気泡が発生しないことを目視検査するというものである。水没試 験による気泡確認によって医薬包装の完全性を試験する方法は,個人の技量による 判別量の差や水槽内の細菌・水の表面張力による検出限界などの問題を有する旨指\n摘されているほか,−40kPaの圧力下において,直径5μmの孔からは5分経 過後も気泡が確認できず,直径10μmの孔においても,気泡の発生にばらつきが みられるとされている(甲27)。上記リーク試験の結果をもって,実際に用いら れたアルミピロー包材が気密性を有していたと確定することはできない。そうする と,サンプル薬が,長期間にわたって,アルミピロー包装下で保管されている間に, 湿気の影響を受けて水分含量が増加した可能性も,十\分にあり得るものである。 なお,サンプル薬の測定時の水分含量と,実生産品の水分含量(後記ウ(ア))や, 203サンプル薬を再製造したとされる錠剤の水分含量(2.18〜2.26質量%。 乙54〜56)は,ほぼ同じである。しかし,そもそも,サンプル薬と,実生産品 や203サンプル薬の再製造品が同一工程により製造されたものとは認められない から,この事実をもって,サンプル薬の測定時の水分含量が,製造時の水分含量と ほぼ同じであったということはできない。
(ウ) したがって,サンプル薬の測定時の水分含量が本件発明2の範囲内である からといって,4年以上も前の製造時の水分含量も本件発明2の範囲内であったと 推認できるものではない。
・・・
以上のとおり,サンプル薬を製造から4年以上後に測定した時点の水分含量 が本件発明2の範囲内であるからといって,サンプル薬の製造時の水分含量も同様 に本件発明2の範囲内であったということはできない。また,実生産品の水分含量 が本件発明2の範囲内であるからといって,サンプル薬の水分含量も同様に本件発 明2の範囲内であったということはできない。かえって,サンプル薬の顆粒の水分 含量を基に算出すれば,サンプル薬の水分含量は本件発明2の範囲内にはなかった 可能性を否定できない。その他,サンプル薬の水分含量が本件発明2の範囲内にあ\nったことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,控訴人が,本件出願日までに製造し,治験を実施していた本件2m g錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量は,いずれも本件 発明2の範囲内(1.5〜2.9質量%の範囲内)にあったということはできない。
(3) サンプル薬に具現された技術的思想
ア 仮に,本件2mg錠剤のサンプル薬又は本件4mg錠剤のサンプル薬の水分 含量が1.5〜2.9質量%の範囲内にあったとしても,以下のとおり,サンプル 薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明であるということはでき ない。
イ 本件発明2の技術的思想
前記1のとおり,本件発明2は,ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含 量に着目し,これを2.9質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制 し,これを1.5質量%以上にすることによって5−ケト体の生成を抑制し,さら に,固形製剤を気密包装体に収容することにより,水分の侵入を防ぐという技術的 思想を有するものである。
ウ サンプル薬に具現された技術的思想
(ア) 控訴人が,本件出願日前に,サンプル薬の最終的な水分含量を測定したと の事実は認められない。
(イ) また,203サンプル薬及び303サンプル薬の製造工程では,A顆粒及 びB顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●●にする旨定 められているものの(乙23の1・2,25の1・2),A顆粒及びB顆粒以外の 添加剤の水分含量は不明である。また,サンプル薬には吸湿性の高い崩壊剤や添加 剤が含まれているにもかかわらず,打錠時の周囲の湿度,気密包装がされるまでの 管理湿度などは不明である。 そうすると,サンプル薬に含有されるA顆粒及びB顆粒の水分含量について,● ●●●●にする旨定められているからといって,控訴人が,サンプル薬の水分含量 が一定の範囲内になるよう管理していたということはできない。
(ウ) さらに,012実生産品及び062実生産品の製造工程では,B顆粒の水 分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●にすると定められており (乙24,26の1・2),サンプル薬と実生産品との間で,B顆粒の水分含量の 管理範囲が●●●●●●●●から●●●●●●●●へと変更されている。控訴人は, サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。
(エ) したがって,控訴人は,本件出願日前に本件2mg錠剤のサンプル薬及び 本件4mg錠剤のサンプル薬を製造するに当たり,サンプル薬の水分含量を1.5 〜2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたと も,1.5〜2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していた とも認めることはできない。
エ 以上のとおり,本件発明2は,ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分 含量を1.5〜2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものである のに対し,サンプル薬においては,錠剤の水分含量を1.5〜2.9質量%の範囲 内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく,また,錠剤の水 分含量を1.5〜2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存 在しない。 そうすると,サンプル薬に具現された技術的思想が,本件発明2と同じ内容の発 明であるということはできない。
オ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は,水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成する ことは技術常識であったから,控訴人は,本件2mg錠剤及び本件4mg錠剤の治 験薬製造前から,錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張する。 しかし,一般的に,医薬組成物において製剤中の水分が類縁物質生成の原因にな るという技術常識(乙8〜10)や,ピタバスタチンについては水分含量を調整し なければならないという技術常識(乙12〜14,20,57)が認められるとし ても,水分含量の調整方法は様々であるから,このような技術常識のみから,ピタ バスタチン又はその塩と特定の崩壊剤から成る錠剤であるサンプル薬について,錠 剤としての水分含量を一定の範囲内となるように管理することを控訴人が認識して いたといえるものではない。 したがって,本件出願日前の技術常識をもって,控訴人がサンプル薬の水分含量 を管理する必要性を認識していたということはできない。
(イ) 控訴人は,サンプル薬について,水分含量を調整することにより,水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない,長期安定な薬剤を製造する点は,確定し ていた旨主張する。 しかし,控訴人が,サンプル薬について,ラクトン体及び5−ケト体の生成の程 度について測定し,安定な製剤であることを確認していたとしても,前記のとおり, 控訴人が,サンプル薬を製造するに当たり,その水分含量を1.5〜2.9質量% の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも,1.5〜2. 9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることは できない。サンプル薬において,5−ケト体の生成を抑制できていたとしても,こ れをもって,控訴人が,サンプル薬の水分含量を1.5質量%以上に管理していた と推認できるものではなく,また,これが,控訴人がサンプル薬の水分含量を1. 5質量%以上に管理するという技術的思想を有していた結果として生じたものと評 価できるものでもない。 したがって,サンプル薬について,何らかの方法を採用することにより,水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない,長期安定な薬剤を製造する点が確定され ていたとしても,これをもって,サンプル薬に具現された技術的思想が,本件発明 2と同じ内容の発明であるということはできない。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成27(ワ)30872 (東京地裁29部)
本件出願日(平成24年8月8日)までに,被
告の社内において,本件発明2の内容を知らないでこれと同じ内容の発明がされて
いた(被告が被告の従業員等から当該発明を知得していた)と認めることは困難で
あるし,この点を措くとしても,後記(3)のとおり,本件出願日までに,本件2mg
製品及び被告製品(本件4mg製品)の内容が,本件発明2の構成要件Eを備える\nものとして,一義的に確定していたと認めることはできず,本件発明2を用いた事
業について,被告が即時実施の意図を有し,かつ,その即時実施の意図が客観的に
認識される態様,程度において表明されていたとはいえないから,被告に先使用権\nが成立したということはできない。
・・・
しかし,被告の提出に係る書証からは,実生産品とサンプル薬が同一の工程によ
り製造されたものであると直ちに認めることは困難である。すなわち,本件で問題
となるのは,「PTP包装してなる医薬品」を構成する「錠剤」の「水分含量」が\n「1.5〜2.9質量%」の範囲となるよう管理されていたか否かであるところ,
水分は,有効成分でないばかりか,積極的な添加物でもなく,不純物として扱われ
るものでもないため,錠剤が製造された後,PTP包装された状態で,錠剤の水分
含量がいかなる値となるかという観点から工程の同一性を論じるためには,被告の
提出に係る全ての書証をもってしても,情報が不足しているというほかはない(少
なくとも,打錠工程の湿度環境や打錠後の保管条件は,PTP包装された錠剤の水
分含量に影響するといわざるを得ないが,被告の提出にかかる書証では,これらの
条件は明らかにされていない。)。
イ 被告は,本件2mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:PTVD−203)及
び本件4mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:TVD−303)の水分含量につい
て,いずれも本件発明2の構成要件Eの数値範囲内にあったと主張し,乙32号証\n(以下「乙32実験報告書」という。)を提出する。
しかし,乙32実験報告書に示される本件2mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:
PTVD−203)及び本件4mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:TVD−30
3)の水分含量の測定値は,これらの錠剤が製造されたとされる日から4年以上が
経過した時点のものである。そして,被告ないし同報告書の説明するところによれ
ば,これらの錠剤は,その製造後,PTP包装とアルミピロー包装がされ,その状
態により,被告の中央研究所の検体保管庫に温度20℃,成り行き湿度(実測値:
75%RH)で保存されていたものであり,検体1錠をPTP包装から取り出して,
乳鉢で粉砕してカールフィッシャー法により水分測定を行ったというのであるが,
上記の条件下で4年以上が経過しても,錠剤の水分含量がそのまま保持されること
を直接裏付ける証拠はない。
かえって,1)本件2mg製品の使用期限が2年6か月とされ,本件4mg製品(被
告製品)の使用期限が3年とされていること(甲4〔52頁〕)からすれば,4年
以上という期間は,予定されている保存期間を大きく超えるものであって,水分含\n量を含む錠剤の状態に影響を及ぼす可能性を否定できないこと,2)ピタバスタチン
からラクトンが生成する反応は,脱水縮合であって,水が脱離することから,水分
含量増加の原因となり得ること,3)アルミピロー包装に使用される材料の防湿性が
高いことがうかがわれる(乙33)としても,PTP包装された上記サンプル薬を
収納したアルミピロー包装には,チャックがついていて(乙32,39),当該材
料のみでは構成されてはおらず,また,湿気等の影響を受けやすい商品の包装には\n充分に注意する必要があるとされていること(甲18),4)PTP包装やアルミピ
ロー包装が施された他の医薬品について,所定の保存期間経過後に水分含量が増加
しているとみられる例があること(甲15,19)などからすれば,PTP包装と
アルミピロー包装により,直ちに上記サンプル薬の水分含量の増加が完全に抑えら
れていたと断ずることは,困難である。
被告は,上記サンプル薬の水分含量がそれぞれ本件2mg錠剤の実生産品(ロッ
ト番号:B062)及び本件4mg錠剤の実生産品(ロット番号:B012)とほ
ぼ同じ値であることから,保存期間中の吸湿の可能性が否定される旨主張するよう\nであるが,かかる被告の立論は,本件2mg錠剤のサンプル薬が本件2mg錠剤の
実生産品と同一の工程により製造され,また,本件4mg錠剤のサンプル薬が被告
錠剤(本件4mg錠剤の実生産品)と同一の工程により製造されていたことを前提
とするものであるところ,既に説示したとおり,本件2mg錠剤のサンプル薬及び
本件4mg錠剤のサンプル薬が,それぞれ本件2mg錠剤の実生産品や本件4mg
錠剤の実生産品(被告錠剤)と同一の工程により製造されたと認めるに足りる証拠
はないものというべきである。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(ネ)10060 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
まず,構成要件Fの「入力」との文言の意味について検討する。
(ア) 本件明細書には,構成要件Fの「入力」の意味を直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらない。\n他方で,本件明細書には,複数の箇所で「入力」との文言が使用され ているところ,例えば,段落【0008】の「摩擦力による入力を,直 接的または間接的に検出する」のように「物理的な力を加えること」と の意味や,段落【0012】の「図14は,…文字を入力する例を示し た図である。」のように「コンピュータに情報を与えること」との意味 など,同一の文言であるにもかかわらず文脈によって異なる意味で使用 されている。 なお,本件訂正審決は,本件明細書の段落【0035】及び【006 2】の記載に基づいて,本件発明の「『当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの(判決注:原文のまま)記憶部に\n記憶させる』とは,(背景の変更などの)変更結果を,(フォルダYに 保存することなどの)表示対象に対する情報として記憶することを意味しているといえる。」と判断しているが,これは構\成要件Fの「入力」 は「コンピュータに情報を与えること」を意味すると解したものといえ る。
(イ) この点について,控訴人は,構成要件Fの「入力」は,「力入力検出手段」により検出された当該表\示対象に対する「力入力」,すなわち「物理的な力を加えること」を意味すると主張する。 しかし,この解釈は,構成要件H,A及びDでは,「物理的な力を加えること」として「力入力」との文言が明示的に使用されているにもか\nかわらず,構成要件Fでは敢えて「入力」のように異なる文言が使用されていることと整合しない。\n
また,構成要件Fの「入力」は,「当該変更結果」,すなわち,「保持された表\示対象以外の表\示態様を変更することにより,当該表\示対象を相対的に変更させた結果」を目的語としていると解し得るところ,こ の場合に「入力」を「物理的な力を加えること」と解釈することは不自 然である。さらに,「として」は,前に置かれた語を受けて,その状態, 資格,立場等であることを表す語であるところ,「入力」を「物理的な力を加えること」と解すると,「入力として・・・記憶させる」との文言が\n意味するところを理解できないというべきである。
(ウ) 控訴人は,本件訂正審決が「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として・・・記憶部に記憶させる」とは,「(背景の変更などの)変更結\n果を,(フォルダYに保存することなどの)表示対象に対する情報として記憶することを意味している」と判断したことを指摘して,当該判断\nは控訴人の上記主張と整合するとも主張する。 しかし,「物理的な力を加えること」と「コンピュータに情報を与え ること」とは別個の概念であるから,構成要件Fの「入力」を「物理的な力を加えること」と解した上で,本件訂正審決の判断のように「コンピュータに情報を与えること」との意味をも有すると直ちに理解することは困難である(物理的な力が加わったことをコンピュータに検出させる場合には,両者の意味が重なっているともいい得るが,本件においては,上記説示のとおり,少なくとも「物理的な力を加えること」と解することは不自然であるから,両者の意味が重なっている場合と断ずることもできない。)。\n
(エ) 以上によれば,控訴人の主張によっては,構成要件Fの「入力」の意味を一義的に理解することは困難であるというほかない。\n
イ 仮に,構成要件Fの「入力」を,本件訂正審決が判断したように,「コンピュータに情報を与えること」と解したとしても,次のとおり,構\成要件Fの意義は依然として不明確であるというべきである。
(ア) 構成要件Fの「当該表\示対象」は,構成要件Cの「前記位置入力手段にて検出された位置の表\示対象」をいうと解される。本件明細書には,この「表示対象」の意味についても,直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらないものの,発明の詳細な説明の記載に照らせば,アイコン等(【0021】),アイコンや文字列等(【0029】),アイコンや文字,記号,図形,立体表\示対象など(【0035】)がこれに当たるものと解される。 しかし,表示画面にアイコン等を表\示させ,利用者が当該表示画面に接触した位置を検出し,当該接触位置に応じて処理を行う入出力装置においては,表\示画面に表示するアイコン等のデータそのもの(例えば,スマートフォンの画面に表\示されているカメラ様の画像データ)と,当該アイコン等と紐づけされた実体(例えば,カメラアプリケーション) とは,別個のものとされていることが多いと解されるところ,本件明細 書の記載を精査しても,本件発明における「表示対象」が具体的にどのようなものであるのかは明らかといえない。\n
(イ) また,上記ア(イ)のとおり,構成要件Fの「当該変更結果」は,「保持された表\示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表\示対象を相対的に変更させた結果」と解し得るところ,「相対的に変更させた結果」についても,背景として設定されている画像が移動したピクセル数や,保持された表示対象と重なることとなったアイコン等の有無及びその種類など,さまざまなものがあり得る。\n そして,構成要件Fによれば,この「相対的に変更させた結果」は,「当該表\示対象」に対する情報として与えるものであるが,ある対象に与え得る情報は,当該対象がアプリケーションかデータかや,その実装方法によっても大きく異なるものと解される。 そうすると,上記(ア)のとおり,「当該表示対象」が具体的に意味するところが明らかでない上に,「相対的に変更させた結果」の意味内容も特定されていないことを考え合わせると,「当該変更結果を当該表\示対象に対する入力として記憶部に記憶させる」の意義も明らかでないというべきである。
(ウ) この点に関し,本件訂正審決は,本件明細書の段落【0035】及び 【0062】の記載に基づいて,「当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの(判決注:原文のまま)記憶部に記憶させる」とは,「表\示要素『B』のデータをフォルダXからフォルダYに移動させて保存することを意味している」と判断した。しかし,本件訂正審決の説示においても,「表示要素『B』のデータ」がいかなるデータであるのかが具体的に特定されているとはいい難い。\n また,本件明細書の段落【0035】記載の「フォルダX」及び「フォルダY」と段落【0062】記載の「WINDOW1」及び「WINDOW2」の関係も明らかでなく,いかなる情報が「相対的に変更させた結果」に該当し,「フォルダXからフォルダYに移動させ」ると理解することになるのかについても具体的な指摘がされているとはいえない。
ウ 以上検討したところによれば,結局のところ,構成要件Fの意義は不明確というべきである。そして,構\成要件Fの意義が不明確である以上,被告各製品が構成要件Fを充足すると認めることはできない。\n
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成30(ネ)10033 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1 争点3−4(乙64の1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由の有無)に ついて
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて\n
被控訴人は,控訴人が当審において追加主張した乙64の1を主引用例と する進歩性欠如(争点3−4)を無効理由とする特許法104条の3第1項 の規定に基づく無効の抗弁(以下「本件無効の抗弁」という。)について, 民事訴訟法157条1項に基づき,時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下することを求める申立てをしたので,以下において判断する。\n
ア 前記第2の1(前提事実等)の(6)及び一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 控訴人は,平成27年4月17日の原審第4回弁論準備手続期日に おいて,被告準備書面(2)に基づき,実施可能要件違反の無効理由(争点\n3−1)による無効の抗弁の主張をし,同年9月14日の原審第7回弁 論準備手続期日において,被告準備書面(5)に基づき,明確性要件違反(争 点3−2)の無効理由による無効の抗弁の主張をした。 その後,原審の受命裁判官は,同年10月27日の第8回弁論準備手 続期日において,本件の侵害論の審理を終了し,損害論の審理を進める と述べた上で,控訴人に対し,被控訴人の損害主張に対し具体的に認否 反論し,必要な書面を提出するよう求めた。
(イ) 控訴人は,平成28年5月19日,本件発明1,2,6及び8につ いての本件特許を無効にすることを求める別件無効審判を請求した。 同年12月13日の原審第12回弁論準備手続期日において,控訴人 は,被告準備書面(10)に基づき,別件無効審判と同一の無効理由(サポー ト要件違反(争点3−3)の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理 由を含む。)による無効の抗弁を追加して主張したのに対し,被控訴人 は,同期日において,上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下 することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は,被控訴人の上記\n申立てを容れて,控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。\n
(ウ) 特許庁は,平成29年12月15日,本件訂正後の請求項1,6及 び8に係る発明についての本件特許には,サポート要件違反(争点3− 3)の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして, 上記特許を無効とする別件審決をした。 同月20日の原審第18回弁論準備手続期日において,控訴人は,被 告準備書面(15)に基づき,別件審決が認めたサポート要件違反の無効理 由及び本件無効の抗弁に係る無効理由による無効の抗弁を再度追加して 主張したのに対し,被控訴人は,上記主張は時機に後れた攻撃防御方法 として却下することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は,被控訴人の上記申\立てを容れて,控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。 原審は,同日,原審第2回口頭弁論期日において,本件訴訟の口頭弁 論を終結した後,平成30年3月22日,被控訴人の請求を一部認容す る原判決を言い渡した。 この間の同年1月20日,被控訴人は,別件審決の取消しを求める別 件審決取消訴訟を提起した。
(エ) 控訴人は,平成30年4月9日,本件控訴を提起した。控訴人は, 同年6月5日付けの控訴理由書において,被告準備書面(10)及び(15)を 引用して,サポート要件違反(争点3−3)の無効理由による無効の抗弁 及び本件無効の抗弁を記載した。 同年7月24日の当審第1回弁論準備手続期日において,控訴人は, 控訴理由書に基づき,本件無効の抗弁を主張し,被控訴人は,控訴答弁 書に基づき,上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下すること を求める申立てをした。\n同年10月15日の当審第2回弁論準備手続期日において,控訴人は, 同年8月31日付けの控訴人準備書面(1)及び同年9月14日付けの控 訴人準備書面(2)に基づき,本件無効の抗弁の主張を補足し,被控訴人は, 同年10月1日付けの被控訴人第1準備書面に基づき,本件無効の抗弁に対する反論及び訂正の再抗弁を主張した。 その後,当裁判所は,同年12月10日の第1回口頭弁論期日におい て,本件口頭弁論を終結した。
イ 前記アの認定事実によれば,控訴人の当審における本件無効の抗弁の主 張は,原審において侵害論の審理を終了し,損害論の審理に入った段階で 提出されたため,時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨 のものであるが,控訴人は,原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る 無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされた のを受けて,当審において再度提出したものであること,控訴人は,控訴 理由書に本件無効の抗弁を記載し,当審の審理の当初から本件無効の抗弁 を主張していたことが認められるから,当審における控訴人による本件無 効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということはできない。また,当審の審理の経過に照らすと,控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出 により,訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。 したがって,当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張を時機に 後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
(2) 本件明細書の記載事項等について
ア 本件発明1,2及び6の特許請求の範囲(請求項1,2及び6)の記載 は,前記第2の1(前提事実等)の(2)のとおりである。
・・・
前記aの記載事項によれば,乙64の2には,押しボタン式バルブ の下側で不燃性液体の上側の位置に,通気性を有する「連続気泡状パ ッキング」を挿入した,不燃性液化ガスを充填した噴射口を有する「噴 気式清掃機」の記載があり,その「連続気泡状パッキング」は,缶体 を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れて液体 のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があるこ とが認められる。 そして,乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」は,連続気泡 を有する多孔質体であり,図2(別紙3)から円筒状の缶体内に挿入 された円板状の形状であることを理解できるから,「円板状多孔質 体」として,本件発明1の「通気性蓋状部材」に該当するものと認め るのが相当である。
(イ) 乙64の1には,スプレー缶を倒立状態で使用した場合や缶を倒立 状態で保管する場合に液漏れの原因となり,可燃性液化ガスの液漏れに より火炎が発生するおそれがあるため,吸収性能・保液性に優れた吸収\n体を提供することが課題であること(【0004】,【0054】)の 記載がある。 一方で,乙64の2には,乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」 は,缶体を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れ て液体のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があ ることは,前記(ア)bのとおりである。 そうすると,乙64の1及び乙64の2に接した当業者は,乙64の 1の第1発明において,スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸収体 に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にするために,乙6 4の1の第1発明に乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」の構成\nを適用する動機付けがあるものと認められる。 また,乙64の1の「具体的には,スプレー缶形状に合わせて,その 内径に適した大きさの円筒状の成形体とすると,充填が容易にできる上, 使用中も安定してスプレー缶内に保持することができる。」(【003 2】)との記載から,スプレー缶の使用中に吸収体を安定して保持する 必要性があることを理解できる。 以上によれば,当業者は,スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸 収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にし,吸収体を 安定して保持するために,乙64の1の第1発明において,乙64の2 の連続気泡状パッキングを適用する際に,乙64の2記載の連続気泡状 パッキングの構成のものを吸収体の表\面に密接に配置し,相違点2に係 る本件発明1の構成を容易に想到することができたものと認められる。\n
(ウ) これに対し被控訴人は,乙64の2記載の「連続気泡状パッキング4」は,バルブ2の下側に空間を形成するため缶体1に固定されている 必要があるため,肩部からバルブ側に押し込むように固定され(図2), バルブ2側に十分大きい空間が形成されないので,倒立状態では,比重\nの重い液体が下側(バルブ2側)へ移動し,バルブ側の空間に容易に液 が漏れることになって,倒立状態のまま噴射を継続することができない こと,乙64の2には,図2以外に,「連続気泡状パッキング4」の充 填状態について具体的に説明する記載はないことからすると,乙64の 1の第1発明に乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」を組み合わ せる動機付けはないし,また,乙64の1の第1発明に乙64の2記載 の「連続気泡状パッキング」を組み合わせたとしても,本件発明1の通 気性蓋状部材の構成に至ることはない旨主張する。\nしかしながら,乙64の1の第1発明において,スプレー缶を倒立状 態で使用した場合の吸収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防 止を確実にするために,乙64の1の第1発明に乙64の2記載の「連 続気泡状パッキング」の構成を適用する動機付けがあることは,前記\n(イ)のとおりである。 また,乙64の2には,連続気泡状パッキングが図2で示された位置 に配置することが不可欠である旨の記載はなく,連続気泡状パッキング の具体的な設置方法及び設置場所は,当業者が適宜決定すべき事項であると認められる。 さらに,乙64の2の【0012】の「連続気泡状パッキング4を挿 入し,たとえ缶体1を逆さまにして使用しても不燃性液体3が液体のま ま噴出することなく,ガスの整流性が良くなる。」との記載に照らすと, 乙64の2の「噴気式清掃機」が連続気泡状パッキングを挿入したため に倒立状態のまま噴射を継続することができないものと理解すること はできない。 したがって,被控訴人の上記主張は,採用することができない。
・・・
(7) まとめ
以上のとおり,本件発明1,2及び6は,乙64の1の第1発明及び乙6 4の2記載の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた ものと認められ,進歩性を欠くものであるから,本件特許には,特許法29 条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)があり,特許無効審判 により無効とされるべきものと認められる。
2 争点3−5(訂正の再抗弁の成否)(本件発明1及び6に関し)について
被控訴人は,本件訂正により,訂正前の請求項1及び6(本件発明1及び6) の無効理由は解消され,かつ,被告製品は,本件訂正発明1及び6の技術的範 囲に属するから,被控訴人は,控訴人に対し,本件特許権を行使することがで きる旨主張する。 そこで検討するに,本件訂正発明1(本件訂正後の請求項1)は,灰分含有 量を「1重量%以上12重量%未満」とするものであり,本件発明2と同一の 構成であるところ,前記1(5)のとおり,本件発明2は,乙64の1の第1発明 及び乙64の2の技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで きたものと認められるから,本件発明1の無効理由は,本件訂正により解消されるものとはいえない。 また,前記1(6)で説示したのと同様の理由により,本件発明6の無効理由は, 本件訂正により,解消されるものとはいえない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被控訴人の上記主張 は理由がない。
3 結論
以上によれば,本件発明1,2及び6は,進歩性を欠くものであり,本件特 許には,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)があ り,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから,被控訴人は, 同法104条の3第1項の規定により,控訴人に対し,本件特許権を行使する ことはできない。
◆判決本文
関連の審決取消し訴訟です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成29(ワ)34450 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月31日 東京地方裁判所(46部)
前記(1)によれば,本件発明の意義は以下のとおりであると認められる。 従来の住宅地図は,建物表示に住所番地だけでなく居住者氏名も全て併記さ\nれていたため,氏名を記載するためのスペースを確保するために住宅地図の縮 尺を高くすることができず,そのため,地図の大きさも比較的大きくする必要 があるとともに,地図に氏名が記載されることによるプライバシー侵害や利用 者の検索への支障を生じたり,地図の更新作業のための調査に膨大な労力と人 件費がかかったりするという課題があった。また,住宅地図に付されている索 引についても,住所のうち丁目と,それぞれの丁目に該当するページが掲載さ れているだけであったため,同一の丁目の中で番地が異なっている多くの建物 の中から目的とする建物を探し出す必要があった。 本件発明は,居住者氏名を記載しないため,高い縮尺度で地図を作成するこ とにより小判で,薄い,取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することや, 地図の更新のために氏名調査等の労力を要しないことによって廉価な住宅地 図を提供することを可能にするとともに,地図上に公共施設や著名ビル等以外\nは住宅番地のみを記載し,地図のページを適宜に分割して区画化したうえで建 物の所在する番地と記載ページと記載区画の記号番号を一覧的に対応させた 索引欄を付すことによって,簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅地図\nを提供することを可能にするものである。\n
2 争点1−4(構成要件D(「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画\n化し」)についての文言侵害の有無) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告地図プログラムは,ユーザが,インターネット上の「https:/ /以下省略」のURLにアクセスし,所定の操作をするなどすると,ユーザ の端末にインストールされているWebブラウザを介して,ユーザ端末のデ ィスプレイに地図を表示できるようにしたプログラムである。\n被告地図プログラムにより表示される地図では,縮尺レベルが1〜20の\n20段階に分かれており,縮尺レベル20が最も詳細(縮尺率が小さい)な もので,縮尺レベル1が最も広域(縮尺率が大きい)なものである。各縮尺レベルに応じて,地図用のデータが存在する。 りディスプレイの画面に表示さ\nれる地図の画面表示等は,別紙「被告地図プログラムの構\成(分説)」記載の とおりである。(以上につき,甲13ないし19,乙1,22,弁論の全趣旨)
イ 被告地図において,市区町村名,町名,丁目及び番の表示の右側に〔地図〕\nと表示された部分等にはハイパーリンクが設定されており,そのハイパーリ\nンクに係るURLは,冒頭に「https://以下省略」と記載され,そ の後の記載がパラメータであることを示す「?」が記載された後に,「lat =…&lon=…&ac=…&az=…」及び「z=…」という記載を含む ものである。前記のlat,lon,ac,azが示す各値は,それぞれ当 該地点に係る緯度,経度,都道府県及び市区町村の住所コード,町,丁目, 番又は号の番号を示し,zが示す値は縮尺レベルを示す。ユーザがディスプ レイ画面上で当該ハイパーリンクをクリックすると,その緯度経度を含む地点データと縮尺データを含むURLが被告地図の地図提供サーバに送信さ れる。地図提供サーバが,この地点データに係る地点を含み,かつ,縮尺デ ータに係る縮尺のメッシュ地図を地図データベースサーバから読み出し,ユ ーザのパソコンに送信することにより,ユーザのディスプレイ画面上におい\nて当該緯度経度を中心とした所定の縮尺の地図が表示される。(甲4ないし\n19,弁論の全趣旨)
ウ インターネットに接続した状態で被告地図をユーザのディスプレイ画面 に表示し,その後,インターネットの接続を停止した上で地図表\示画面をス クロールさせると,地図が表示されない部分が画面上に表\示される。(甲3 4,弁論の全趣旨)
エ 被告地図プログラムにおける縮尺レベル19の縮尺は,概ね1/1250 から1/2857の範囲であり,被告地図における縮尺レベル20の縮尺は, 概ね1/615程度である。(甲33,乙1,弁論の全趣旨)
(2)本件明細書には、前記1(1)記載のほか、(発明の実施の形態)として以下 の記載がある。なお,以下の図1ないし5は,それぞれ,本判決別紙本件明細 書図1ないし5である。 ア 段落【0017】
・・・
(3)構成要件Dの「適宜に分割して区画化」について\n
構成要件Dの「適宜に分割して区画化」の意義について,特許請求の範囲の\n「各ページを適宜に分割して区画化し,…住宅建物の所在する番地を前記地図 上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対 応させて掲載」という記載(構成要件D,E及びF)に照らせば,構\成要件D の「適宜に分割して区画化」とは,記号番号を付すことや番地と対応する区画 を一覧的に示すことができる区画を作成することが可能となるように,検索す\nべき領域の地図のページを分割し,認識できるようにすることといえる。 そして,本件発明は, 前記1(2)のとおり、地図上に公共施設や著名ビル等以 外は住宅番地のみを記載するなどし,全ての建物が所在する番地について,掲 載ページと当該ページ内で分割された該当区画を一覧的に対応させて掲載し た索引欄を設けることによって,簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅\n地図の提供を可能にするというものであり,本件発明の地図の利用者は,索引\n欄を用いて,検索対象の建物が所在する地番に対応する,ページ及び当該ペー ジにおける複数の区画の中の該当の区画を認識した上で,当該ページの該当区 画内において,検索対象の建物を検索することが想定されている。そのために は,当該ページについて,それが線その他の方法によって複数の区画に分割さ れ,利用者が該当の区画を認識することができる必要があるといえる。そうす ると,本件明細書に記載された本件発明の目的や作用効果に照らしても,本件 発明の「区画化」は,ページを見た利用者が,線その他の方法及び記号番号に より,検索対象の建物が所在する区画が,ページ内に複数ある区画の中でどの 区画であるかを認識することができる形でページを区分することをいうとい える。 前記(2)のとおり、本件明細書には、発明の実施の形態において,本件発明を 実施した場合における住宅地図の各ページの一例として別紙「本件明細書図2」 及び「本件明細書図5」が示されているところ,これらの図においては,いず れも道路その他の情報が記載された長方形の地図のページが示されたうえで, そのページが,ページ内にひかれた直線によって仕切られて複数の区画に分割 されており,その複数の区画にそれぞれ区画番号が付されている。また,本件明細書図4の索引欄には,番地に対応する形でページ番号及び区画番号が記載 されており,利用者は,検索対象の建物の番地から,索引欄において当該建物 が掲載されているページ番号及び区画番号を把握し,それらの情報を基に,該 当ページ内の該当区画を認識して,その該当区画内を検索することにより,目 的とする建物を探し出すことが記載されている(段落【0028】)。ここでは, 上記の特許請求の範囲の記載や発明の意義に従った実施の形態が記載されて いるといえる。そして,「区画化」の意義に関係して,他の実施の形態は記載さ れていない。
以上によれば,構成要件Dの「区画化」とは,地図が記載されている各ペー\nジについて,記載されている地図を線その他の方法によって仕切って複数の区画に分割し,その各区画に記号番号を付すことであり,索引欄を利用すること で,利用者が,線その他の方法及び記号番号により,当該ページ内にある複数 の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割するこ とを意味すると解するのが相当である。 原告は,被告地図において,縮尺レベル19の住宅地図及び縮尺レベル20 の住宅地図がそれぞれ構成要件Dの「該地図を記載した各ページ」に該当する\nと主張した上で,被告地図のデータは,画面に表示されるときに区分された形\nでその一部が表示されるから構\成要件Dの「適宜に分割して区画化」されると 主張するとともに,「メッシュ化」され,また,複数のデータとして管理されて いるから構成要件Dの「適宜に分割して区画化」することになると主張する。\nしかし,仮に,縮尺レベル19の住宅地図及び縮尺レベル20の住宅地図が それぞれ構成要件Dの「該地図を記載した各ページ」に該当するとしても,利\n用者は,画面に表示されている地図を見ているのであって,線その他の方法及\nび記号番号により,ページにある複数の区画の中で,検索対象の建物が所在す る地番に対応する区画を認識することができるとはいえない。被告地図におい て「メッシュ化」がされていて,また,被告地図に係るデータが複数のデータ として管理されているとしても,被告地図プログラムの構成(分説)及び前記\nアないしウに照らし,利用者は,「メッシュ化」されている範囲や区分された データを通常認識しないだけでなく,それらに対応する記号番号を認識するこ とはない。したがって,被告地図において,線その他の方法及び記号番号によ り,ページにある複数の区画の中で,検索対象の建物が所在する地番に対応す る区画を認識することができるとはいえない。そうすると,前記 に照らし, 被告地図において,「各ページ」が,「適宜に分割して区画化」されているとは いえない。 これらによれば,被告地図について,構成要件Dの「適宜に分割して区画化」\nがされているとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.02. 7
平成30(ワ)3018 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所(46部)
前記(2)のとおり、本件各名作書には、本件参照抗体と競合する,PCSK 9−LDLR結合中和抗体を同定,取得するための,免疫プログラムの手順 及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法,ハイブリドーマの作製 方法,スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載 されている。そして,当該方法によれば,本件各明細書で具体的に開示され た以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。 そうすると,本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が,本件各\n明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1 若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られる とはいえない。したがって,本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範\n囲が本権各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定のアミノ酸 の1もしくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限ら れることを前提として,本件各発明の技術的範囲が本件各明細書記載の具体 的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のア ミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるとの被告の主張 は採用することができない。
(4)また,被告は,1)本件各明細書では,本件参照抗体と競合する抗体であれ ば,PCSK9とLDLRの結合を中和することができるという技術思想を 読み取ることはできない,2)本件各明細書の実施例に記載された3グループ ないし2グループの抗体のみによって,本件参照抗体と競合する膨大な数の 抗体全てがPCSK9−LDLR結合中和抗体であるとはいえず,本件各明 細書には,本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体がPCSK9−LDLR 結合中和抗体であることの根拠は全く示されていないと主張する。 しかしながら,前記 のとおり,本件各明細書には,本件参照抗体がP CSK9−LDLR結合中和抗体であること,本件参照抗体がPCSK9に 結合するエピトープと同じエピトープに結合する抗体,又は,本件参照抗体 とPCSK9との結合を立体的に妨害するような上記エピトープに隣接する エピトープに結合する抗体である,本件参照抗体と競合する抗体は,本件参 照抗体と類似した機能的特性を有すると予\想されることが記載されている。 そして,前記 のとおりのスクリーニング等によって得られた本件各明細書の表2記載の30の抗体(21B12参照抗体と31H4参照抗体を除く。)\nのうち,24の抗体はPCSK9−LDLR結合中和抗体であり,かつ,本 件参照抗体と競合する抗体であること,表37.1.のビン1(21B12\n参照抗体と競合し,31H4参照抗体と競合しない抗体)に属する19の抗 体のうち16個,ビン2(21B12参照抗体とも,31H4参照抗体とも 競合する抗体)に属する抗体のうち2個及びビン3(31H4参照抗体と競 合し,21B12参照抗体と競合しない抗体)に属する10の抗体のうちの 7個は,表2に記載された抗体であり,これら16個と2個と7個の抗体の\nうち,27B2抗体並びに21B12参照抗体及び31H4参照抗体を除く 少なくとも20個はPCSK9−LDLR結合中和抗体であることが記載さ れている。そうすると,本件各明細書には,特定のスクリーニング等を経て 得られた抗体のうち,本件参照抗体と競合する複数の抗体がPCSK9−LDLR結合中和抗体であることが示されているといえる。 なお,この点に関係し,被告は,本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体 がPCSK9−LDLR結合中和抗体であることの根拠は全く示されていな いと主張するが,本件各明細書に記載された抗体以外に,本件参照抗体と競 合するがPCSK9−LDLR結合中和抗体ではない具体的な抗体が示され ているものではなく,また,本件参照抗体と競合する抗体中,PCSK9− LDLR結合中和抗体でないものの割合が大きいことも明らかではない。 さらに,被告は,本件参照抗体と競合する抗体は,PCSK9−LDLR 結合中和抗体であるとは限らないとも主張する。しかし,本件各発明は,P CSK9−LDLR結合中和抗体であることを構成要件とするものであるか\nら(構成要件1A,2A),上記のような例外的な抗体は本件各発明の技術\n的範囲に含まれない。
(5)証拠(甲5,7の1,2,甲8〜10)及び弁論の全趣旨によれば,本件 各発明について,被告が主張する限定的な解釈を採らない限り,被告モノク ローナル抗体は,本件発明1−1及び本件発明2−1の各構成要件を全て充\n足し,被告製品は,本件発明1−2及び本件発明2−2の各構成要件を全て\n充足すると認められるから,被告モノクローナル抗体は,本件発明1−1及 び本件発明2−1の技術的範囲に属し,被告製品は,本件発明1−2及び本 件発明2−2の技術的範囲に属すると認められる。なお,被告モノクローナ ル抗体は,本件訂正発明1-1及び本件訂正発明2−1の技術的範囲にも属 し,被告製品は,本件訂正発明1−2及び本件訂正発明2−2の技術的範囲 にも属すると認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成28(ワ)6494 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月18日 大阪地方裁判所
イ 構成要件Aの「用いられ」の意味
前記アを前提に検討すると,構成要件Aのうち「ロールペーパの回転速度を\n検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は,本件ロールペーパ等の「複 数の磁石」につき,そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき, また,構成要件Aのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固\n定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は,本件ロールペーパ等について,そのような態様で回転させられることを 特定するものと理解できるし,構成要件Cの「測長センサ」も,構\成要件Aの記載 によって特定されると理解できる。 そうすると,本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は,構成要件\nBないしDと,構成要件Aによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから\n画されるものと解されるから,一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって,一体化製品が構\成要件Aを充足する薬剤分包装 置に実際に使用されるか否かは,上記構成要件充足の判断に影響するものではない\nと解される。 被告らは,原告製使用済み芯管に,輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプ ラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Aの「用いられ」を充足するた\nめには,一体化製品に,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用\n途が存在しないことが必要であると主張し,予備的に,仮にこれが認められないと\nしても,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用\n効果を奏するものであるから,現実に構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いら\nれることが必要であると主張する。 しかしながら,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用可能\な構成を有し,そ\nの他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産,譲渡され\nれば,その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって,その後に構成要件Aを\n充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは,特許権侵害の成 否を左右するものではない。 被告らは,本件発明の出願経過に照らし,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に\n一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張 するが,原告が,手続補正の際に提出した意見書(乙25)において,本件発明は 構成要件Aを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。\nさらに,被告らは,本件無効審判において,本件訂正後の発明に新規性が認めら れるための構成が特定されたところ,その中には薬剤分包装置に関するものがある\nので,一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために,どのような 薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが,前記検討し た構成要件Aと,構\成要件BないしDとの関係に照らし,採用できないといわざる を得ない。
ウ まとめ
以上検討したところによれば,本件発明においては,構成要件Aの「用いられ」\nは,構成要件Aの記載によって構\成要件B以下の内容が特定されることを意味する ものとして使われているというべきであるから,そのように特定された構成要件を\n一体化製品が充足する場合には,構成要件Aの「用いられ」を充足すると解され,\nこれ以上に,構成要件Aの「用いられ」が,一体化製品が構\成要件Aを充足する薬 剤分包装置以外には使用されないこと,あるいは現実に構成要件Aを充足する薬剤\n分包装置が存在することを,要件として定める趣旨と解することはできない。
(2)争点(1)イ(一体化製品は「2つ折りされたシート」(構成要件A)を充足す\nるか。)について
ア 被告らは,構成要件Aの「2つ折りされたシート」とは,ロールペーパを薬\n剤分包装置内で2つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提として おり,あらかじめ2つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を 主張する。
イ そこで,検討するに,本件明細書【0018】には,「分包部は,三角板4 で2つ折りにされた際にホッパ5から所定量の薬剤が投入された後,ミシン目カッ タを有する加熱ローラ6により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシー ルするように設けられている。」との記載があるが,本件明細書【0011】の記 載によれば,本件発明は,一定の張力を保ったままシートを分包部に供給すること により,シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする\nものであり,この技術的思想に関しては,給紙部から分包部に送られてくるシート があらかじめ2つに折り畳まれたダブルタイプであっても,折り畳まれてい ション現象が生じるため,)張力変動により分包部でシートを2つ折りした際にシ ートの縁部が正確に重ならない,いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は,シング ルタイプのロールペーパを分包部において2つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入 した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても,ダブルタイプの ロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても,同様に生じ得る。 さらに,原告は,本件特許につき拒絶理由通知(乙24)を受けて本件補正を行 っているが,本件明細書【0018】の記載に基づくものであり,元の記載がシン グルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは 相当ではない(乙25)。
ウ 以上によれば,ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も,「2 つ折りされたシート」(構成要件A)を充足するというべきである。
(3) 争点(1)全体についての判断
ア 被告らは,一体化製品につき,構成要件Aのうち,「測長センサ」,「シー\nトを送りローラで送り出す給紙部」,「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」, 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが,原告製造 の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり,構\成要件Aと構成要件B以下\nとの関係を前述のとおり解する以上,意味のない主張といわざるを得ない。
イ 一体化製品は,前記第2の1(5)のとおりの構成を有するところ,被告らは,\n構成要件Aに関し,争点(1)ア及びイについて争うものの,構成要件B以下の充足性\nについては争うことを明らかにしておらず(当初,構成要件B及びDの充足を争っ\nたが,後に撤回した。),弁論の全趣旨によれば,一体化製品の構成aは本件発明\nの構成要件Bを,構\成bは構成要件Cを,構\成cは構成要件Dを充足すると認めら\nれ,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置において使用されることが可\n能な構\成を有すると認められる。
ウ 以上によれば,一体化製品は,構成要件AないしEをすべて充足するから,\n本件発明の技術的範囲に属すると認められる。
エ なお,原告は,被告日進が前訴において構成要件Aの充足性を争わなかった\nことから,本訴訟において構成要件Aの充足性を争うことは信義則に反する旨を主\n張するが(争点(1)ウ),被告日進は,前訴とは異なる製品の関係で,構成要件Aの\n充足性を本訴訟で主張したと認められるから,この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。
3 争点(2)(特許権侵害が成立するか。)について
(1) 問題の所在
ア 前記2によれば,一体化製品を完成して譲渡すれば,その時点において特許 権侵害が成立することになるが,前記第2の1(4)及び(5)のとおり,被告らは,一体 化製品それ自体を生産,譲渡しておらず,プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シ ートを巻き回したロールペーパ,すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のな い物を被告製品として生産,譲渡し,これを入手した利用者が,輪ゴムを介してロ ールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し,これを一体化製品とした上で,薬剤分 包装置に使用している。
イ この点について,原告は,1)被告製品は,一体化製品の生産にのみ用いる物 であるとして,特許法101条1号の間接侵害を主張するほか,2)被告らの行為は, 顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること,3)被告らの行為は,顧客の特 許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので,まず間接侵害の成否に ついて検討する。
(2) 争点(2)ア(被告製品は,一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められる か。)について
ア 被告製品の販売方法
証拠(甲4,5,21,36,文中掲記のもの)によれば,以下の事実が認めら れる。
被告日進の販売するロールペーパの製品には,商品名の冒頭に「A」の付く 製品(被告製品。以下「Aタイプ」という。)と「B」の付く製品(以下「Bタイ プ」という。)があり,両タイプは,それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙 又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成28年11月に公開していたウェブサイト(甲20)によれ ば,Aタイプの分包紙の芯管内径は67mmであって,「外径65mm前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ,Bタイプの分包紙の芯管内径は52mmであって,「外径 50mm前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。\n薬剤分包用ロールペーパとして,外径65mm前後の芯管を製造しているのは 原告のみであり,外径50mm前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみ である(弁論の全趣旨)。
前記ウェブサイトの「よくある質問Q&A」の欄には,「Q.他社分包機に 装着するには特別な道具が必要ですか?」という質問に対し,「A.弊社分包紙は, 『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって,お客様ご使用の分包 機に装着することができます。つまり,『使用済み分包機メーカー製芯管』が1個 お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成28年1月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明 資料(甲9)には,「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告 日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより,芯管の空回りを防止しながら被 告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に 説明されている。
まとめ
以上によれば,被告日進が販売する分包紙のうちAタイプ(被告製品)は,原告 製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として 生産され,原告製の薬剤分包装置を使用し,既に原告製使用済み芯管を保有してい る者に対し,購入の案内がされたものと認められる。
イ 他の用途について
被告日進製の薬剤分包装置
前記被告日進のウェブサイト(甲20)には,「複数メーカー機に装着可能」と\nいう文言と共に,「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり,各社分包機メーカー 及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で,承認を受けた製品ではありません。」 という記載があり,前記説明資料(甲9)にも同様の記載があることが認められる。 しかし,被告らの主張によっても,被告日進は,経済産業省により「平成25年 度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定され た後,平成26年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し,平成2 7年にカタログを作成し,平成28年5月12日に1台,同年10月25日に1台 の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる(甲17,乙 1,11,36)。 他方,被告製品は平成26年12月から販売されており,原告代理人は,平成2 8年1月頃に,被告らに対し,本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を 求める警告書(甲10)を送付し,同年7月4日に本訴を提起したことが認められ る。 前記時系列によれば,被告製品の販売が開始された当初,これを被告日進製 の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず,むしろ,原告との紛争\nが顕在化した後に,わずか2台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置(甲19,乙2,14〜16) 被告製品を,エルク製分包装置において使用されている芯管(外径約60mm。以 下「エルク製芯管」という。)に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するため には,被告製品の空回りを防止するために厚さ3.2mm程度のOリングを2個,エ ルク製芯管に装着することが必要であり,さらに,被告製品の外径(約193mm) が大きすぎるため,そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず,使用開始 に当たって長さ330mの分包紙中約88ないし100m分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって,被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無 駄を伴い,経済的に合理性のある使用とはいえない。
ウエダ製分包装置(甲23,乙17,18)
ウエダ製分包機については,特定の顧客が,その支持軸を独自に製作した支持軸 に取り換えるという改造を施すことにより,被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし,同顧客の保有するウエダ製分包機は20年以上前に販売が終了している 機種であり,ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品 を使用することは考えにくいし,改造を施さないウエダ製分包装置において,被告 製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって,被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは,一般的な使用 方法ということはできない。
タカゾノ製分包装置(乙20,21)
株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペ ーパが,被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。\n
まとめ
被告日進製の薬剤分包装置については,被告製品の販売が一定期間行われた後に, わずか2台が製造,販売されたにとどまるものであるから,被告製品が使用された としてもごくわずかといわざるを得ないし,被告以外の薬剤分包装置に被告製品を 使用することには困難が伴い,現実的ではないといわざるを得ないから,被告製品 については,原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は,実質的には存在しない といわざるを得ない。
ウ 争点(2)アについての判断
前記ア及びイで検討したところによれば,被告製品は,原告製使用済み芯管と一 体化し,一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産,譲 渡され,これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから,被告製品 は,一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。
(3) 特許権侵害についての判断
被告らが被告製品を生産,譲渡した段階では,回転角度の検出に用いる磁石を配 置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず,本件特許の構成要件の全部を\n充足するものではないが,前記(2)で検討した通り,被告製品は,原告製使用済み芯 管と一体化して,本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予\定されて おり,他の用途が実質的に存在せず,一体化製品の生産にのみ用いられるものと認 められるのであるから,被告製品の生産,譲渡は,特許権の直接侵害に至る蓋然性 が極めて高いものとして特許法101条 1 号の間接侵害に当たり,本件特許権を侵 害するものとみなすべきものである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> のみ要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成28(ワ)4759 不当利得返還請求事件 特許権 平成30年12月20日 大阪地方裁判所
(エ) 以上によれば,乙8には,「ホログラムの単位幅における格子部幅/非 格子部幅の比が,導光板の前面出射面から出射する光を効率よく,また,面内で均 一に出射されるように,管状光源から離れる側の方が増大せしめられている」構成\nが開示されているといえる。
ウ したがって,乙8発明は,本件発明の構成要件Bと同一の構\成を備える ものであるから,相違検討点2は相違点とはいえない。
エ 原告の主張について
原告は,乙8には,導光板に設けるホログラムの面積密度を増減させる技術思 想が開示されているだけで,回折格子の単位幅における格子部幅/非格子部幅の比を変化させる技術思想は開示されていないと主張する。 しかし,前記アのとおり,本件発明も,格子部の面積の変化を通じて,導光板の 表面における輝度を増大させ,かつ均一化させるものであり,本件発明と乙8発明\nはその解決課題と解決原理を共通にしている。 そして,上記のとおり,乙8には,本件発明の構成要件Bの構\成を備えたホログ ラムの構成が開示されていると認められるから,本件発明の構\成要件Bはこれを別 の表現で記述したものにすぎず,同一の構\成が開示されていることに変わりはない。 したがって,原告の主張は採用できない。
(6) 小括
以上によれば,本件発明と乙8発明とは,前記の相違検討点1において相違す るから,同一の発明とはいえず,乙8による特許法29条の2違反の無効理由が存 するとは認められないが,本件発明と乙8発明とは,その解決課題及び解決原理を 共通にしており,解決手段たる回折格子の種類についてのみ相違するにすぎないと いうことができる。
・・・
(ア) 本件明細書に記載された従来技術及びその課題
前記認定のとおり,本件明細書では,本件発明に関する従来技術として, 導光板の下面に多数の多面プリズムをもつ透明アクリル樹脂からなり,プリズムに よる光の全反射を利用する導光板が記載されており,その具体例として,特開平5 −127157号公報記載の平面照光装置(本件明細書の図6参照)が挙げられて いる。 そして,その従来技術によっても液晶表示パネルを下方から輝度ムラが少なく明るく照らすことができると記載されているが(【0003】),1)導光板の下面にある 多面プリズムの一辺が例えば0.16mmと,光の波長に比べて相当大きいものである うえ,各プリズムが協同することなく個別に光を全反射するものであるため,導光 板の輝度を全体に高めようとすると,各プリズムの間の谷間にあたる箇所で乱反射 が起きて上面に向かう光量が減り,照光面である上面に極端な明暗のコントラスト が生じるという課題,及び2)このような導光板を設けた平行照光装置を電池で駆動 される液晶表示装置に用いると,照光面に向かう上記光量の減少を補って高輝度を\n得るべく,光源を大電流で照らす必要があるため,電池の寿命が短くなって,長期 使用ができなくなるという課題があったことが記載されている(【0004】)。
(イ) 本件発明の課題解決手段
本件発明は,従来技術の上記課題を解決するため,「光の幾何光学的性質を 利用した従来のプリズムによる全反射でなく,・・・光の波動の性質に基づく回折現象 を利用して,従来より遥かに高く,かつ均一な輝度を照光面全体に亘って得ることが でき,ひいては光源の電力消費の低減による電池の長寿命化も図ることができる導 光板を提供すること」を目的として(【0005】),本件発明の構成を採用したもの\nである。その構成は,(a)透明な板状体である導光板の裏面に回折格子を設け,導光 板の少なくとも一端面から入射する光源からの光をその表面側へ回折させるという点(構\成要件A),(b)上記回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅/非 格子部幅の比の少なくとも1つを,上記導光板の表面における輝度が増大し,かつ\n均一化されるように変化させる点(構成要件B)である。
(ウ) 本件発明の作用効果
本件発明の導光板は,α 少なくとも一端面から光源からの光が入射する透 明な板状体の裏面に設けられた回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅 /非格子部幅の比の少なくとも1つが,上記導光板の表面における輝度が増大し,\nかつ均一化されるように変化せしめられているので,光の波長に比べて寸法が大き く互いに協同することなく個別に光を幾何光学的に全反射する従来の導光板裏面のプリズムと異なり,ミクロン単位の互いに隣接する微細な格子が協同,相乗して波動 としての光を格段に強く回折できるうえ,β 上記一端面から離れて光源から届く光 量が減じるほど,光をより強く回折するように上記断面形状または単位幅における 格子部幅/非格子部幅の比が調整されているので,導光板の表面は高輝度で非常に\n均一に照らされる。 したがって,γ この導光板を電池で駆動される液晶表示装置,液晶テレビ,非常口 を表示する発光誘導板などに適用すれば,従来に比して格段に少ない消費電力で明\nるく均一な照明を得ることができ,光源および電池の寿命を延ばし,長期使用を可 能にすることができる(【0009】,【0023】)
(エ) もっとも,本件の場合,本件明細書に従来技術が解決できなかった課 題として記載されているところは,以下のとおり,出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分なものと認められる。
a 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減るとの課題(上記(ア)1))を,導光板の裏面に回折格子を設け,回折現象を利用して解決する構成(上記(イ)の(a),上記(ウ)α)について
本件明細書では,導光板の従来技術として,プリズムによる全反射を利用したもののみが記載され,回折現象は今まで導光板に用いられることがなかった と記載されている。 しかし,原告は平成6年3月11日に自ら,発明の名称を「回折格子を利用した バックライト導光板」とし,特許請求の範囲(請求項1)を「成形加工及び印刷 (転写を含む)された回折格子を裏面に有する事を特徴とするプラスチック製のバ ックライト導光板。なをここで裏面とは,液晶面と反対側の面と定義する。」とする 特許の出願をし,その明細書では,【課題を解決するための手段】の項において, 「導光板裏面に光と干渉する程度に微細なスリット形状を成形加工ないし印刷(転 写を含む)し,この反射格子により導光板の一端から入射する光を液晶面側に回折 させる。」(【0006】)と記載し,【発明の効果】の項において,この発明によれば蛍光管からの光を回折格子という極小単位の形状(格子スリットのピッチがサブミ クロンから数十ミクロン)の大きさのものの作用により,導光板面を均一に輝らす\n事ができるので,従来からのドット印刷や全反射を利用した導光板裏面加工による 方式に比較して,格段の面輝度とその均一性が可能になる。」(【0017】)と記載\nしていた(特願平6−79172)(乙10,20)。そして,これは本件発明の構\n成要件Aと同じ構成を備えた発明と認められる。\nまた,前記1で技術的意義等を認定した乙8発明も,回折格子の種類は同じとは 認められないものの,導光板の裏面に回折格子を設け,回折現象を利用して光量の 増大を図る発明である(乙8発明のようないわゆる拡大先願発明も参酌すべきこと は後記のとおりである。)。 以上より,導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減ると の課題は,本件特許の出願日において,本件発明と同じく導光板の裏面に回折格子 を設け,回折現象を利用することによって既に解決されている課題であったと認め られる。
b 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題(上記(ア)1))を,回折格子の断面形状ま たは単位幅における格子部幅/非格子部幅の比の少なくとも1つを,上記導光板の 表面における輝度が増大し,かつ均一化されるように変化させることにより解決す\nる構成(上記(イ)の(b),上記(ウ)β)について 先に争点2−2(前記1)について述べたとおり,乙8発明も,導光板 の裏面にホログラムの回折格子を設け,回折現象を利用するものであり,かつ,本 件発明の構成要件Bと同一の構\成を備え,それにより,導光板の表面から出射する\n光を効率よく,また,面内で均一に出射されるようにするものである。もっとも, この乙8発明に係る特許の出願日は平成7年10月27日であり,本件特許の出願 よりも前に出願されたものであるが,乙8発明に係る特許について出願公開がされ たのは平成9年5月16日であり(乙8),本件特許の出願後であるから,乙8発明 はいわゆる拡大先願発明に該当するにすぎない。しかし,特許法29条の2は,特 許出願に係る発明が拡大先願発明と同一の発明である場合を特許要件を欠くものとしているところ,その趣旨の中には,先願の明細書等に記載されている発明は,出 願公開等により一般にその内容が公表されるから,たとえ先願が出願公開等をされ\nる前に出願された後願であっても,その内容が先願と同一内容の発明である以上, さらに新しい技術を公開するものではなく,そのような発明に特許権を与えること は,新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみ て妥当でないとの点がある。このように特許法が,先願の明細書等に記載された発 明との関係で新しい技術を公開するものでない発明を特許権による保護の対象から 外している法意からすると,均等侵害の成否の判断のために発明の本質的部分とし て従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定するに当た\nっては,拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当である。 そうすると,導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題は,本件特許の出願日において,回折格 子として刻線溝又はエンボス型のホログラムを用いるか体積・位相型のホログラム を用いるかの違いがあるとはいえ,本件発明と同じく,回折格子の単位幅における 格子部幅/非格子部幅の比を,導光板の表面における輝度が増大し,かつ均一化されるように変化させることによって既に解決されている課題であったと認められる。\n
c そして,本件発明の,少ない消費電力で明るく均一な照明を得るこ とができないとの課題(上記(ア)2))は,上記a及びbで述べた課題が解決されるこ とに伴い解決されるものである(上記(ウ)γ)から,やはり既に解決されている課題 であったと認められる。
d 以上からすると,本件発明が課題とするところは,いずれも本件特 許の出願時の従来技術によって,同様の解決原理によって解決されていたといえる。 本件発明がそれらの従来技術と異なる点は,回折格子の単位幅における格子部幅/ 非格子部幅の比を,導光板の表面における輝度が増大し,かつ均一化されるように変化させることについて,体積・位相型のホログラムではなく,刻線溝又はエンボ\nス型のホログラムを用いた点にあるが,回折格子としては後者の方がむしろ通常で あること(前記1(4)ウ(ア),(エ),(オ))からすると,本件発明の従来技術に対する 貢献の程度は大きくないというべきである。
ウ 以上よりすれば,本件発明の本質的部分については,特許請求の範囲の 記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。 この点について,原告は,本件発明の本質的部分は,光の波動の性質に基づく回 折現象を利用して,回折格子の断面形状又は単位幅における格子部幅/非格子部幅 の比に着目した点にあると主張するが,これまで述べたことに照らして採用できな い。
エ そうすると,被告製品の導光板では,前記のとおり,微細構造体が回折\nされた光が進行する側に設けられていることから,構成要件Aでいうところの「表\ 面」に微細構造体が設けられ,光源からの光が「表\面」側に回折させられている。 したがって,被告製品の導光板は構成要件Aの「板状体の裏面に設けられた回折格\n子」という部分を充足していない。よって,被告製品が本件発明の本質的部分を備えているということはできず,本件発明と被告製品とは本質的部分において相違すると認められるから,被告製品は,均等の第1要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.12.27
平成29(ワ)18184 特許権侵害行為差止請求 特許権 民事訴訟 平成30年12月21日 東京地方裁判所
第5要件に関し,被告は,構成要件Eは本件補正によって追加されたも\nのであるところ,本件拒絶理由通知に対する本件意見書における「本発明 25 は,2組の揺動部材を備える点,および,揺動部材の一方に,他方に係合 する係合部を備える点において,引用文献1に記載された発明…と相違し ています。」との記載によれば,原告は,被告製品のように係合部を別部 材とする構成を特許発明の対象から意識的に除外したと理解することが\nできるから,均等侵害は成立しないと主張する。
しかし,本件意見書には,「引用文献1には,端部が回転可能に連結さ\nれることにより開閉可能に5 設けられた一対のジョーを備えた開創器アセ ンブリが開示されています。」,「このような構成(判決注:本件発明に\n係る構成)によれば,2組の揺動部材を同時に開かせることにより,骨に\n形成した切り込みの拡大作業を容易にし,また,切り込みの切断面に局所 的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができる」,「2つの開創器 アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構\成を導く ことはできません。」「引用発明1には,切り込みの切断面に作用する押 圧力を低減するという課題,および,2つの開創器アセンブリを一体で開 動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません」などの記載が ある。
上記記載によれば,本件意見書の主旨は,特許庁審査官に対し,引用例 1が一対の揺動部材を開示していることを指摘し,それに対し,本件発明 は,開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ,一方の揺動部材を他方の揺\n動部材に係合するための係合部を設けることにより,両揺動部材が同時に 開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきで\nある。そして,同意見書には,係合部の構成,すなわち,係合部を揺動部\n材の一部として構成するか,揺動部材とは別の部材により構\成をするかを 意識又は示唆する記載は存在しない。
そうすると,被告の指摘する「2組の揺動部材を備える点,および,揺 動部材の一方に,他方に係合する係合部を備える」との記載は,上記説明 の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないというべきで\nあり,同記載をもって,同意見書の提出と同時にされた本件補正により構\n成要件Eが追加された際に,原告が,係合部を揺動部材とは別の部材とす る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2018.12.21
平成29(ワ)28884 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月28日 東京地方裁判所
(1)「プロカルシトニン3−116を測定すること」の意義
ア 構成要件Aは「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定すること\nを含む」というものであるところ,一般に,「測定」に,長さ,重さ,速さといっ た種々の量を器具や装置を用いてはかるという字義があることからすると,「プロ カルシトニン3−116を測定すること」は,プロカルシトニン3−116の濃度 等の量を明らかにすることを意味すると解するのが文言上自然である。 また,前記1(2)認定のとおり,本件発明は,敗血症等の患者の血清中に比較的高 濃度で検出可能なプロカルシトニンがプロカルシトニン1−116ではなく,プロ\nカルシトニン3−116であることが確認されたことを踏まえて新規な敗血症等の 検出方法を提供することを目的とするものであり,このような本件発明の目的に照 らせば,本件発明は,患者の血清中においてプロカルシトニン3−116が比較的 高濃度で検出されるか否かを見ることを可能とすることが求められているというこ\nとができる。 以上から,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定すること」は,プ\nロカルシトニン3−116の濃度等の量を明らかにすることを意味すると解するの が相当である。
イ この点につき,原告は,「プロカルシトニン3−116を測定すること」は, プロカルシトニン3−116を敗血症等の検出に必要な精度で測定ないし検出する ことができれば,プロカルシトニン3−116だけを特異的,選択的に測定するこ とに限られず,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116及びそ の他のプロカルシトニン由来の部分ペプチドとを区別することなく測定することも 含むと主張しており,その意味するところは明確でないが,血清中のプロカルシト ニン3−116を検出しさえすれば足りるものである旨の主張であるとすれば,そ れはプロカルシトニン3−116の存在を明らかにすることで足り,その量を明ら かにすることは必要ではないことをいうものであって,前記アでみた「測定」の文 言の解釈に反するものであり,採用することができない。 また,血清中のプロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116等と を区別することなく測定することがプロカルシトニン3−116を測定することに 該当すると主張するものであると解しても,そのような測定方法では,血清中にプ ロカルシトニン3−116が存在するかも明らかにならず,もとより,血清中のプ ロカルシトニン3−116の量も確認できないから,これを「プロカルシトニン3 −116を測定すること」に該当するというのは文言上困難である。
(2)被告方法
前記第2の2(5)ア認定のとおり,被告装置及び被告キットを使用すると,患者の 検体中において,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116とを 区別することなく,いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することが でき,その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行われていると認められるもの の,本件全証拠によっても,被告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出す る過程で,プロカルシトニン3−116の量が明らかにされているとは認められず, 更にいえば,プロカルシトニン3−116の存在自体も明らかになっているとはい えない。 したがって,被告方法は,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定す\nる」を充足するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.12.13
平成30(ワ)3018 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所(46部)
本件発明は,前記1のとおり,「ホルダ」に該当する部材によって回転体を支 持する支持軸を固定するものであるところ,原告は,被告製品のソーラーパネ\nル取付台が支持軸を固定していると主張するのに対し,被告はこれを否定する。 証拠(甲10,14)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,回転体の支 持軸の本体側先端部分にフランジが形成されていること,被告製品の本体内部 のソーラーパネル取付台の支持軸側先端部分には一対の段差及び半円形状の\n凹部が形成され,それらは回転体の支持軸及び支持軸に形成されたフランジの 形状に係合すること,ソーラーパネル取付台の先端部で回転体の支持軸を覆っ\nてソーラーパネル取付台を被告製品本体にネジで固定するとソ\ーラーパネル 取付台に支持軸のフランジが引っかかり,支持軸の先端部分がソーラーパネル\n取付台の段差及び半円形状の凹部に組み付けられること,その組付け後は回転 体を支持する支持軸に接着剤の塗布などはなかった被告製品においても支持 軸が本体から直ちには外れることがなかったことが認められる。これらによれ ば,被告製品のソーラーパネル取付台の先端部分の段差及び半円形状の凹部は,\n回転体の支持軸を固定するための構成であり,同部分が回転体の支持軸を覆い,\n支持軸を押し付けることによって支持軸を固定し,支持軸が抜けないようにし ていると認められる。
そうすると,被告製品のソーラーパネル取付台は構\成要件B及び構成要件C\nの「ホルダ」に該当し,被告製品は構成要件Bの「前記各支持軸の基端側をホ\nルダの両端部で押さえる」及び構成要件Cの「ホルダ」を充足するといえる。\nこれに対し,被告は,ソーラーパネル取付台の半円形状の凹部はリード線の\nハンダ付け部分をカバーするためのものであり,ソーラーパネル取付台をかぶ\nせただけでは支持軸は固定されず,支持軸を接着剤で被告製品本体内部に接着 固定しなければ,支持軸は簡単に抜けることからもソーラーパネル取付台は支\n持軸を固定する機能を有していないなどと主張する。\nしかしながら,ソーラーパネル取付台の段差及び半円形状の凹部の形状は,\n回転体の支持軸に係合する形状に形成されていて,リード線のハンダ付け部分 をカバーするために形成されていると認めるに足りる証拠はない。また,回転 体の支持軸を固定するために接着剤が塗布されている被告製品があるとして も,その塗布がされたことをもってソーラーパネル取付台が回転体の支持軸を\n固定する機能を有していることが直ちに否定されるものではなく,前記のとお\nりのソーラーパネル取付台の先端部の構\造,接着剤の塗布がなかった場合の回 転体の支持軸の被告製品本体からの着脱の状況等からすれば,ソーラーパネル\n取付台は回転体の支持軸を固定する機能を有しているということができ,被告\nの主張は採用することができない。
3 争点 −ア(乙11文献に基づく新規性欠如)
争点を検討するに当たり,まず,本件発明の「前記各支持軸の基端側をホル ダの両端部で押さえる」(構成要件B)の意義について検討する。\nア 「押さえる」とは,物に力を加えて,動かないように固定するという意味 を一般的に有する(乙3の1ないし3)。 そして,本件明細書には,前記1 アないしオの記載のほか,「発明を実施 するための形態」として,「図4及び図5に示すように,前記ベース体13の 両支持筒18には,金属製の一対の支持軸20がシールリング21を介して, 交差軸線L1,L2上に位置するとともに外側に突出した状態で嵌合支持さ れている。このシールリング21は,支持軸20の周りからハンドル12の 内部へ向かう水の侵入を防止している。各支持軸20の基端には,大径状の 抜け止め頭部20aが形成されている。図4及び図9に示すように,両支持 軸20の基端部間においてベース体13上には,ホルダ22が配置されてい る。このホルダ22の両端部には,各支持軸20の基端側を押さえるための ほぼ半円筒状の押さえ部22aが形成されている。ホルダ22の中間部には, 円筒状のネジ止め部22bが形成されている。そして,ホルダ22の両端の 押さえ部22aにより両支持軸20の基端が押さえられた状態で,ホルダ2 2の中間のネジ止め部22bがネジ23によりベース体13に固定される ことによって,各支持軸20がベース体13の支持筒18に対する嵌合支持 状態に抜け止め固定されている。すなわち,支持軸20の組み付け時には, ハンドル12のベース体13に形成された一対の支持筒18に外側(図4の 左側)から支持軸20をそれぞれ嵌挿して,交差軸線L1,L2上に位置す るように配置する。次に,図5及び図9に示すように,両支持軸20の基端 間におけるベース体13上にホルダ22を配置し,そのホルダ22の両端の 押さえ部22aにより両支持軸20の基端側を押さえる。これにより,図4 及び図9に示すように,各支持軸20の基端の抜け止め頭部20aが押さえ 部22aの端縁に係合される。この状態で,ホルダ22の中間のネジ止め部 22bをネジ23によりベース体13に固定すると,一対の支持軸20がベ ース体13に対して同時に抜け止め固定される。」(段落【0013】),「従っ て,この実施形態によれば,以下のような効果を得ることができる。(1)こ の美容器においては,ハンドル12の先端部に交差軸線L1,L2上に位置 する一対の支持軸20が設けられている。各支持軸20の先端側には回転体 27が回転可能に支持され,それらの回転体27により身体に対して美容的\n作用が付与されるようになっている。前記ハンドル12における両支持軸2 0の基端部間の位置には,ホルダ22がその中間部において固定されている。 そして,このホルダ22の両端の押さえ部22aにより,各支持軸20の基 端側がハンドル12に対して押し付け保持されるようになっている。このた め,1つのホルダ22からなる簡単な固定構成により,一対の支持軸20を\nハンドル12に対して容易に固定することができて,製造コストの低減を図 ることができる。」(段落【0019】)との記載がある。
上記のとおり,本件明細書の段落【0013】,【0019】には,ホルダ の両端部に各支持軸の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が 形成され,この押さえ部が支持軸の基端に接し,それをハンドルに押し付け ることによって支持軸を保持し,支持軸が抜けることがないように固定する という実施形態が記載されており,これは,前記のとおりの「押さえる」の 一般的な意味とも整合する。 そうすると,本件発明の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さ える」とは,支持軸の基端部をホルダの両端部に接するようにし,ホルダの 両端部から支持軸の基端部に対して押し付けること,すなわち力を加えるこ とによって,支持軸を抜けることがないように固定することを意味するもの と解するのが相当である。
イ これに対し,被告は,本件明細書の【図4】や段落【0013】の記載か ら,「押さえる」とは,支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部, その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するも\nのであると主張する。 しかし,本件明細書の段落【0013】の記載は前記アのとおりであり, ホルダが支持軸に力を加えずに,部材の勘合・係合のみによって固定する態 様が記載されているとはいえず,本件明細書のその他の記載中にも被告の主 張するような固定態様に関する記載はない。また,本件明細書の【図4】か らもそのような固定態様を看取することはできない。被告の主張は,「押さ える」の一般的な意味と一致するものでは必ずしもなく,かつ,本件明細書 にその主張を裏付ける記載はないといえるのであり,採用することができな い。
(2)。乙11発明と本件発明の対比
ア 本件特許の出願日前に公開されていた乙11文献には,1)ハンドルの先端 部に交差軸上に位置する一対の支持軸が設けられていること(乙11文献の 【図6】〜【図8】),2)腕部の先端側にマッサージを行うためのローラが回 転可能に支持されていること(乙11文献の段落【0001】【0013】),\n3)ローラ取付部材の左右両端部にそれぞれ腕部を含むローラ連結部の一端 を回転軸により軸支固定すること及び当該回転軸をローラ取付部材の穴に 挿通してEリングによって抜け止めすること(乙11文献の段落【0008】 〜【0010】),4)ローラ取付部材の中間部をローラ連結部を介してハンド ルに固定すること(乙11文献の段落【0008】【図1】【図2】),5)以上 の構成を有する美容器である乙11発明が開示されていることは当事者間\nで争いはない。 そこで,本件発明と乙11発明を対比すると,本件発明は,支持軸の基端 部をホルダの両端部で力を加えて支持軸を抜けないように固定する構成で\nあるのに対し(構成要件B),乙11発明の支持軸の固定方法はそのような\n構成を有していない点で相違する。
イ 被告は,本件発明の構成要件Bの「押さえる」とは支持軸の基端に設けら\nれた抜け止め頭部や押さえ部,その他支持筒等の部材との勘合・係合によっ て固定される構成を包含するものであることを前提として,本件発明の構\成 要件Bと乙11発明の構成3)とが同一であると主張する。 しかし,構成要件Bの「押さえる」に関する被告の主張を採用することが\nできないことは とおりであり,乙11発明の構成3)が本件発明の構\n成要件Bと同じであるということはできない。 したがって,乙11文献には構成要件Bの構\成が開示されているとはいえず, 乙11発明と本件発明は同一ではないから,本件発明が新規性を欠くというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.11.21
平成29(ワ)24174 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月24日 東京地方裁判所
イ 被告サーバにおける「注文情報」
(ア) 前記第2の2(4)イ認定のとおり,被告サービスにおいて注文が行われると, 別表のとおり被告サーバの処理が記録されるところ,前記2認定の被告サービスの内容,別表\の各欄の内容及び被告サーバの処理に照らすと,被告サーバにおいて,注文が行われた時点,すなわち,「注文日時」欄記載の日時に,同欄記載の注文を 識別するための注文番号,「注文日時」欄記載の注文日時,「取引」欄記載の新規 注文又は決済注文の別,「通貨P」欄記載の取引対象となる通貨の種類,「売」欄 記載の売り注文であるか否か,「買」欄記載の買い注文であるか否か,「新規注文」 欄記載のイフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,「執行条件」欄記載の成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別,「指定R」欄記載の指定価格,「期\n限」欄記載の注文の有効期限といった個々の注文の内容を規定する情報が生成され ていると推認することができる。 また,被告サーバにおいて,市場に発注された個々の注文が約定等したことが検 知されると,「注文状況」欄に,その注文が「無効」,「約定」,「取消」のいず れの状況にあるかが,「約定R」欄に,約定価格が,「約定等日時」欄に,注文が 約定等した日時が,すなわち,約定等の結果に係る情報が記録されていると推認す ることができる。 そうすると,少なくとも,被告サーバに記録されている注文番号,注文日時,新 規注文又は決済注文の別,取引対象となる通貨の種類,売り注文であるか,買い注 文であるか,イフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別,指定価格,注文の有効期限といった個々の注文の内容\nを規定する情報は,個々の買い注文又は売り注文を行うために必要となる情報であ るということができ,本件発明の「注文情報」に該当する。 (イ) 以上より,被告サーバでは,本件発明の構成要件BないしHの「注文情報」に相当する情報が生成されていると認められる。
ウ 小括
前記のとおり,被告サーバでは,構成要件BないしHの「注文情報」に相当する情報が生成されているところ,これらの構\成要件の充足性について,後記(2),(3)に おいて検討する構成要件G及びHを除いた構\成要件BないしFの充足性については 次のとおりであり,被告サーバは構成要件BないしFをいずれも充足する。すなわち,本件発明の「注文情報」に関する前記判示を踏まえ,被告サーバの構\成を構成要件BないしFと対比すると,被告サーバは,例えば,番号114,111,108,105の買い注文に係る買い注文情報のような複数の買い注文情報を\n生成する買い注文情報生成手段を備えるものであるから,「金融商品の買い注文を 行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段」(構成要件B)を備えており,また,例えば,番号113,110,107,104の売り注文に\n係る売り注文情報のような複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段を 備えるものであるから,「前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約 定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文 情報生成手段とを有する注文情報生成手段」(構成要件C及びD)を備えている。さらに,被告サーバは,別表\に「注文状況」欄及び「約定等日時」欄等があることから明らかなように,「前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検 知手段とを備え」(構成要件E)るものであり,また,例えば,番号113,110,107,104の売り注文のように,指定価格が114.90円,114.2\nなるものであるから,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は, それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)を備えている。
(2) 争点1−2(被告サーバは構成要件Hを充足するか)
ア 構成要件Hは,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する\nと,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記 複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する…」というものであり,文言上,「複 数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文」1個が約定したときに 「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り 注文価格の情報を含む売り注文情報」1個が生成される構成を含むと解するのが相当である。\nこれを被告サーバについてみると,前記2(2)認定のとおり,被告サーバは,約定 検知手段が,例えば,番号113,110,107,104の売りの指値注文のよ うな複数の売り注文のうち,指定価格を114.90円とする最も高い売り注文価 格の番号113の売り注文が約定されたことを検知すると,注文情報生成手段は, この検知の情報を受けて,指定価格を番号113の指定価格114.90円より0. 62円高い115.52円とし,これを含む売り注文情報である番号96の新たな 売りの指値注文を生成するものであるから,構成要件Hを充足する。
イ 被告は,構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味す\nると解すべきであるとし,その理由として,1)構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文注文が約定されたことを検知」したときは,「最も高い売り注文価格」\nより低い価格の売り注文が既に約定していることが明らかであるから,構成要件Gの「前記複数の売り注文情報」が全て約定したときを意味すること,2)本件明細書 の【0145】ないし【0147】においては,全ての売りの指値注文が約定して 初めて,新たな買いの指値注文(B1ないしB5)及び売りの指値注文(S1ない しS5)の全てが同時に行われていること,3)構成要件Hの「前記注文情報生成手段」が引用している構\成要件C及びDにおいて,「注文情報生成手段」は「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ものであるとされていることなどを主張する。 しかしながら,被告が理由として挙げる1)については,構成要件Hの文言にない限定を付すものである上,「注文情報生成手段」が「複数の売り注文情報」を「一\nの注文手続」で生成することを規定しているにすぎない構成要件Gについて,「注文情報生成手段」が常に「複数の売り注文情報」を生成することを規定するとの限\n定を加えた解釈を前提としていることから,採用することはできない。 また,被告が理由として挙げる2)についても,本件明細書の【0145】ないし 【0147】は,構成要件Hに対応する「シフト機能\」に「決済トレール機能」等を組み合わせた実施例にすぎないから採用し得ない。後記4(1)のとおり,全ての売 り注文が約定しなければ「シフト機能」を適用できないとするものでもない。したがって,被告の主張は採用することができない。
ウ また,被告は,被告サーバが「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報」に係る「売り注文情報を 生成する」時点は,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い 売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したときではなく,買いの成行 注文の約定を検知したときであるから,構成要件Hを充足しないと主張し,買いの成行注文が売り注文に先行して行われていることを示す事情として,別表\において,番号96の売りの指値注文が「2014/11/7 22:29」に約定すると, 同一時刻に番号89の買いの成行注文だけが行われ,約定しているのに対し,番号 85の売りの指値注文は「2014/11/7 22:30」に行われていること などを指摘する。 被告の主張の趣旨は必ずしも明確でないが,仮に,個々の注文が有効なものとし て市場に発注された時点で,被告サーバで「注文情報」が生成されると主張するも のであれば,前記2(3),3(1)イ認定のとおり,被告サーバにおいて,市場に発注前 の売りの指値注文及び逆指値注文であっても,他の注文とともに,注文が行われた 時点で,注文番号等の注文情報が生成されていることと整合せず,採用することが できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.11.16
平成29(ネ)10073 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記前提事実からすると,被控訴人サービスは,買い注文から入った場 合は,取引開始後の最初の買い注文を成行注文とし,同注文と対をなす売り注文を 指値注文とし,同売りの指値注文が約定することをトリガとして新たな価格帯での 取引として,買いの成行注文に係る注文情報を生成させることとし,その後,同買 いの成行注文と対をなす売りの指値注文が約定することをトリガとして,更に新た な価格帯での取引を行い,以降,これを繰り返すという構成を採用していることが\n認められる。
被控訴人サービスの上記構成を前提として,被控訴人サービスの構\成と本件発 明の構成とを比較すると,まず,本件発明においては,第一注文情報及び第二注文\n情報とも指値注文とする構成であるのに対し,被控訴人サービスにおいては,1)第 一注文情報のうち取引開始後最初の取引の第一注文情報と,相場価格の変動後の新 たな価格帯での最初の取引の第一注文情報のみを成行注文とする構成である点で異\nなり,この点で,被控訴人サービスは構成要件E2)を充足しないが,特定の事項を トリガとして生成する成行注文においては,トリガとなる事項をどのように構成す\nるかの点もその内容となっているものと解されること,被控訴人サービスにおいて は,2)相場変動後の新たな価格帯での最初の成行注文に係る注文情報の生成を,旧 価格帯における成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして行わせる構成と\nしたことが,上記1)の構成と一体となって技術的な意義を有するものと解されるこ\nとから,上記1)及び2)の構成(以下「本件相違構\成」)を本件発明の構成との相違\n点として把握して検討するのが相当である。 この点,控訴人は,被控訴人サービスと本件発明とは,本件発明が「検出され た前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合に」,新\nたな価格の「買いの指値注文」を設定するのに対し,被控訴人サービスは,「検出 された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となり,売りの指\n値注文が約定した場合に」,新たな価格の「買いの成行注文」を設定する点で相違 すると主張して均等侵害の主張をしているが,同主張は,被控訴人サービスにおい ては変動後の価格帯で生成されるすべての買い注文が成行注文であるとして,本件 設定できることからすると,相場価格が指定価格となることをトリガとする構成が\n想到し易いものと考えられる。
また,前記1のとおり,本件発明は,同じ価格帯でイフダンオーダーを自動的 に繰り返すことのできる従来の発明の課題を解決したものであり,同じ価格帯での イフダンオーダーを自動的に繰り返すことを前提としているところ,被控訴人サー ビスのように本件相違構成を採用すると,新たな価格帯における取引を行わせるた\nめに必要な相場価格の変動幅は,取引開始時に設定された第二注文情報の指値注文 と取引開始時の相場価格の差額と一致することになり,その結果,同じ価格帯での イフダンオーダーを継続させるためには,相場価格が変動した場合に,旧価格帯の 成行注文と対をなす売りの指値注文の約定をトリガとして,旧価格帯における指値 注文に係る注文情報群も生成させる構成を採用するなどの工夫をする必要が生じる\n(被控訴人サービスでは,同一の価格帯でのイフダンオーダーを継続させるために は,No.113の売りの指値注文の約定をトリガとして,新たな価格帯の取引で あるNo.97の買いの成行注文に係る注文情報を生成するだけでなく,旧価格帯 の取引であるNo.100及びNo.99の各注文に係る注文情報群をも生成させ る必要がある。なお,本件発明においても,顧客が「予め設定された値」を第二注\n文情報の指値価格と第一注文情報の指値価格の差額以下の値と設定することを可能\nとするのであれば,同じ価格帯でのイフダンオーダーを継続させるためには,相場 価格が変動しても,旧価格帯での取引を継続させる構成としておく必要があるが,\n上記の設定ができないようにすれば,上記の構成とする必要はない。)。このよう\nな理由から,被控訴人サービスは,本件相違構成を採用するためには,相場価格が\n変動した場合に,旧価格帯の成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして, 旧価格帯における指値注文に係る注文情報群も生成させる必要があり,この点を考 慮すると,本件発明に本件相違構成を適用するに当たっては,相応の検討が必要で\nあったというべきである。 以上のことに,本件全証拠によっても,被控訴人サービスが開始された時点に おいて,本件相違構成を採用した金融商品取引に係るサービスが存在したことや,\n本件相違構成を開示した文献があったとは認められないことを併せ考慮すると,本\n件相違構成に係る置換をすることは当業者が容易に想到することができたとは認め\nられないというべきである。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第3要件(置換容易性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.11.13
平成28(ワ)38103 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月17日 東京地方裁判所
(1)原告は,まず,原告が太陽光発電装置の請負契約を締結する場合の請負代金 額を基に,太陽光発電パネルの出力1kw当たりの請負代金額は32万円であると して,これに本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じた1億1581万440 0円を民法709条所定の損害であると主張する。 しかしながら,太陽光発電装置の施工について,被告が本件各土地で施工してい なければ,原告がこれらを受注して施工することができたと認めるに足る証拠はな いから,原告の主張する上記の損害は被告の行為と相当因果関係のある損害である と認めることはできない。
(2) 原告は,次いで,本件特許に係る「単位数量当たりの利益の額」(特許法1 02条1項)は太陽光発電パネルの出力1kwを1単位として算定すべきであると して,太陽光発電パネルの出力1kw当たりの利益の額は9万8000円であり, これに本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じた3546万8160円を特許 法102条1項による損害額であると主張する。
しかしながら,原告の上記の主張は,アルバテック又は原告による太陽光発電装 置の施工に係る見積書(甲22の1,甲23の1)等の書面に基づくものであり, これらが実際の取引金額を反映したものであると認めるに足る証拠はないから,本 件各土地における太陽光発電装置の施工に対応する原告の単位数量当たりの利益の 額を算定する根拠として不十分である。\nその他本件特許に係る単位数量当たりの利益の額を認めるに足る証拠はなく,し たがって,特許法102条1項による損害額として,原告の主張する上記の損害を 認定することはできない。
(3)ア 原告は,さらに,原告が本件特許の実施許諾をする場合の実施料は出力1 kw当たり3万円であるとして,これに本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗 じた1085万7600円を特許法102条3項による損害額であると主張する。 イ そこで検討すると,証拠(甲24)によれば,原告は,平成25年12月1 5日,他社との間で,本件特許に係る通常実施権を許諾する旨の特許権実施許諾契 約を締結しており,同契約3条(1)において,実施料については,本件特許に係る施 工方法を用いて施工された太陽光発電パネルの出力1kwに対して3万円を乗じた 額とされたことが認められる。そして,本件全証拠によっても,この実施料額が高 額にすぎて不相当であると認めることはできない。 したがって,本件発明の実施に係る実施料率としては,太陽光発電パネルの出力 1kw当たり3万円と認めるのが相当であり,本件における特許法102条3項に よる損害額は,3万円に本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じて算定するの が相当である。 そうすると,本件各土地の太陽光発電パネルの出力は,前記第2の2前提事実(4)のとおりであって,合計361.92kwであるから,本件における特許法102 条3項による損害額は合計1085万7600円(本件土地1につき3万円に84. 24kwを乗じた252万7200円,本件土地2につき3万円に277.68k wを乗じた833万0400円の合計)である。
ウ これに対し,被告は,特許権の実施料率が請負代金の10%強となることは およそ考えられず,請負代金を基準とした場合にはその1%程度の金額にとどまる 旨主張するが,その理由を具体的に主張しておらず,裏付けとなる証拠を提出して いないから,実施料率を基礎付ける事情として採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2018.11. 1
平成28(ワ)3856 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月19日 東京地方裁判所(29部)
以上のとおり,「第1の表示欄」は動画を表\示するために確保された領域(動画表\n示可能領域),「第2の表\示欄」はコメントを表示するために確保された領域(コメン\nト表示可能\領域)であり,「第2の表示欄」は「第1の表\示欄」よりも大きいサイズで いずれも固定された領域であると解されるところ,被告ら各装置においては,動画表\n示可能領域(被告ら装置1における「StageオブジェクトA」,被告ら装置2及\nび3における<iflame>要素又は<video>要素)とコメント表示可能\領 域(被告ら装置1における「CommentDisplayオブジェクトD」,被告 ら装置2及び3における<canvas>要素)は同一のサイズであるから,被告ら 各装置は,「第1の表示欄」及び「第2の表\示欄」に相当する構成を有するとは認め\nられない。したがって,被告ら各装置は,本件発明1−1の「第1の表示欄」(構\成要 件1−1C,1−1E,1−1F)及び「第2の表示欄」(構\成要件1−1D,1−1 E,1−1−1F)を充足するとは認められず,本件発明1−1の技術的範囲に属するとは認められない。 そして,被告ら各装置は,同様に,本件発明1−5の「第1の表示欄」及び「第2\nの表示欄」(構\成要件1−5J)を充足せず,そうである以上,「第2の表示欄」を構\ 成要素とする「コメント表示部」(構\成要件1−1D,1−2H,1−5J,1−6L)も充足しないから,本件発明1−2,1−5及び1−6の技術的範囲に属するとは認 められない。 また,本件発明1−9及び1−10は,発明の対象が「プログラム」であるが,発 明の対象を「表示装置」とする本件発明1−1及び1−2と対応するものである。したがって,被告ら各プログラムは,本件発明1−1及び1−2と同様に,「第1の表\ 示欄」(構成要件1−9B,1−9E)及び「第2の表\示欄」(構成要件1−9E)を\n充足せず,本件発明1−9を引用している本件発明1−10の構成要件1−10Hも\n充足しないから,本件発明1−9及び1−10の技術的範囲に属するとは認められない。以上のとおりであるから,被告ら各装置及び被告ら各プログラムは,文言上,本件 発明1の技術的範囲に属するとは認められない。
・・・
ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかっ た技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから,特許発明にお\nける本質的部分とは,当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に 見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。そして,\n上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて, 特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で,特許発明に係る特許請 求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部\n分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(知財高裁平成27年 (ネ)第10014号同28年3月25日特別部判決・判時2306号87頁参照。)。
イ これを本件についてみると,前記2(3)で説示したとおり,本件発明2は,複数 のコメントが書き込まれても,コメントの読みにくさを低減させることができる表示\n装置,コメント表示方法及びプログラムを提供することを目的とするものであって,\nコメント表示部によって表\示されるコメントが他のコメントと重なるか否かを判定 し,コメントが重なると判定した場合に,コメント同士が重ならない位置にコメント を表示させるようにし,複数のコメントが表\示される場合において,コメント同士が 動画上で重なってしまい,各コメントが判読できなくなってしまうことを防止するこ とができるようにするとともに,動画の再生中に他の端末装置から入力されたコメン トをリアルタイムに受信して当該動画上に表示し,そのコメントをダイナミックに変\n動させることにより,リアルタイムな双方向のコミュニケーションを可能にし,大人\n数でコメントを交換する面白みを増加させる発明である。上記の「動画の再生中に他 の端末装置から入力されたコメントをリアルタイムに受信して当該動画上に表示し,\nそのコメントをダイナミックに変動させることにより,リアルタイムな双方向のコミ ュニケーションを可能にする」という作用効果は,コメント配信サーバが端末装置か\nらコメント情報を受信してそれを送信するタイミングがリアルタイムに行われるこ と,すなわち,構成要件2−1Cに規定されているように「前記コメント配信サーバ\nが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信 されるコメント情報を受信」との構成によって実現されているのであり,本件特許2\nの出願経過においても,上記構成は,表\示すべき文字情報があらかじめ決定されてい る従来技術との比較において,「ユーザの端末装置から送信されるコメントを受信し て表示するものであり,コメントを受信する毎に,表\示するコメントがダイナミック に変動する点」が相違すると説明されている。そうすると,構成要件2−1Cは,動\n画の再生中に他の端末装置から入力されたコメントをリアルタイムに受信して当該 動画上に表示し,そのコメントをダイナミックに変動させることにより,リアルタイ\nムな双方向のコミュニケーションを可能にする」という作用効果を奏する構\成を具体 的な構成として特定したものであり,この構\成が従来技術にみられない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分であり,本件発明2における本質的部分であるというべき\nである。
ウ 他方,前記のとおり,被告ら各装置は構成要件2−1Cを充足せず,被告ら各\nプログラムは構成要件2−9Bを充足しないから,被告ら各装置及び被告ら各プログ\nラムが本件発明2の本質的部分を備えているということはできず,本件発明2と被告 ら各装置及び被告ら各プログラムは本質的部分において相違すると認められる。
(3) 第5要件(特段の事情)について
前記2(2)において認定したとおり,本件特許2の出願経過として,1)特許庁審査官 は,平成22年11月24日を起案日とする拒絶理由通知書(乙24)において,出 願当初の特許請求の範囲請求項1ないし6及び8ないし12に係る各発明について, 特許法29条2項の規定により特許を受けることができない旨を通知し,2)原告は, 平成23年1月31日付け手続補正書(乙25)において明細書を補正し,請求項1 に「前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信し,前記コメント情報記憶部に 記憶する受信部と,」との構成を,請求項9に「前記コメント配信サーバが前記端末装\n置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメン ト情報を受信し,」との構成を付加して変更し,3)特許庁審査官はこれに対して特許 査定をしたものである。 上記の出願経過からすれば,原告は,拒絶理由を回避するために構成要件2−1C\n及び構成要件2−9Bを備えた発明に限定して特許を受けたものといえるから,上記\n構成要件の全部又は一部を備えない発明について,本件発明2の技術的範囲に属しな\nいことを承認したか,少なくとも外形的にそのように解される行動をとったものと理 解することができる。 したがって,均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり,均等の第5 要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.10.26
平成29(ワ)22041 差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月19日 東京地方裁判所(40部)
原告は,被告製品の把持体外側の外郭部分全体の形状は「逆台形状」である から,構成要件Bを充足すると主張する。\n構成要件Bの「逆台形状」の意義に関し,本件明細書の段落【0008】,\n【0018】,【0023】,【0024】には,本件発明の把持部12が「逆 台形形状」である旨の記載があるが,その形状の定義や意義についての記載 は存在しない。そこで,一般的な用法を参酌すると,広辞苑第六版(乙1)に は,「台形」とは「一組の対辺が平行な四辺形」であると記載され,かつ,上 底が下底より短い四辺形の図が掲載されている。これによれば,「逆台形」と は,「上底が下底より長く一組の対辺が平行な四辺形」をいうと解するのが相 当である。 このような理解に立って本件明細書の図2に図示された把持部をみると, その上部(引き手から遠い部分を「上部」,引き手に近い部分を「下部」とい う。)の直線が下部の直線より長く,その側辺が直線状であるので,本件明細 書における「逆台形状」という語の意義は,上記の一般的用法に沿うものであ ると認められる。 他方,証拠(甲3)によれば,被告製品の把持体(前記第3の1(1)〔被告 の主張〕掲記の「被告製品の把持体」の赤線で囲まれた部分)は,下底は直線 状であるものの,下底から上部に向かう側辺は全体が曲線であり,把持体の 中央部分で最大幅となり,その後,上部に向かい先端部に行くほど幅が狭く なっている上,上底も直線状ではなく,曲線から構成されていることが看取\nされる。そうすると,被告製品の把持体は,平行な対辺もなく四辺形でもない ことから「逆台形状」ということはできず,むしろ「楕円形状」というべきで ある。 これに対し,原告は,「逆台形状」の「状」とは,「…のような形である」 の意味であるから,本件発明の「逆台形状」は必ずしも正確な「逆台形」に限 られないと主張する。しかし,被告の把持体が厳密な意味での「逆台形状」の 定義を満たすことは要しないとしても,少なくとも,逆台形としての基本的 な形状は備えていることを要すると解されるところ,被告製品の把持体は, 側辺及び上部が曲線で「四辺形」ということは到底できず,「楕円形状」とい うべきものであり,逆台形の基本的な形状を備えているということはできな いことは前記判示のとおりである。 したがって,被告製品の把持体は「逆台形状」とは言えず,構成要件Bを充\n足しない。
(2)争点1−2(構成要件Cの充足性)について
原告は,被告製品は,スライダーが10〜50%露出しているので,構成\n要件Cを充足すると主張する。 しかし,被告製品の写真である証拠(乙19の1の4枚目,19の2の5 枚目,19の3の3枚目,19の4の3枚目,19の5の4枚目,19の6 の4枚目,19の7の4枚目,19の8の3枚目,19の9の3枚目)によ れば,被告製品において,スライダーがファスナーカバーに収まった状態に おいて閉口端側に露出することはあるものの,その露出割合は10%を超え ないと認めることが相当である。 また,被告製品1の吊り下げヘッダー裏面にはスライダーをファスナーカ バーに収めた状態が図示されているが(甲3の1の図5),同図においても, スライダーはファスナーカバーから閉口端側に露出していない。これによれ ば,被告製品の通常の用法においては,スライダーがファスナーカバーに収 められた際に閉口端側に露出することは想定されていないものというべき である。
これに対し,原告は,被告製品1の実測値(別紙被告製品説明書の図1を 再度実測したとされるもの。原告第1準備書面11頁の図1)によれば,被 告製品1のファスナーカバーの長手方向の全長は約25mmであり,露出部 分が約3.5mmであるから,被告製品のスライダーは約14%(3.5/ 25×100=0.14)露出していると主張する。 しかし,原告が根拠とする上記の実測値は,被告製品の把持体を弾性のあ るファスナーカバーにどの程度強く押し込んだ上で実測されたかが明らか ではなく,訴状に添付された同製品に係る別紙被告製品説明書の図1(甲3 の1の図3)においては,被告製品1のスライダーの露出部分は約3mm程 度にとどまっている上,前記のとおり,吊り下げヘッダー裏面の図(甲3の 1の図5)においては,スライダーがファスナーカバーから閉口端側に露出 していないことなどに照らすと,上記の再実測図(原告第1準備書面11頁 の図1)は,被告製品1のスライダーを通常使用される態様より強くファス ナーカバーに押し込んで実測されたものであると推認される。 この点,原告は,本件発明の技術的範囲は,被告製品がスライダーをファ スナーカバーから所定の割合で露出させることが可能かどうかで判断され\nるべきであるから,スライダーを強くファスナーカバーに押し込んだ状態で 露出割合が10%を超えるのであれば構成要件Cを充足すると主張するが,\n被告製品におけるスライダーの露出割合は,当該製品が通常使用される状態 において測定されるべきであり,弾性を有するファスナーカバーにスライダ ーを強く押し込んだ状態においてスライダーの露出割合が10%を超える としても,それによって構成要件Cを充足するということはできない。\nしたがって,被告製品は構成要件Cを充足しない。
(3) 争点1−4(構成要件Eの充足性)について
原告は,被告製品は,ファスナーカバーに把持体が「収まった状態」となっ ているので,構成要件Eを充足すると主張する。\n構成要件Eの「収まった状態」との語に関し,本件明細書には,拡大把持体\nがカバー体にどの程度覆われていることを意味するかについての直接的な記 載はないが,本件発明に係る洗濯用ネットの開口部を開口及び閉口する際の 手順を記載した本件明細書の段落【0020】及び段落【0022】の記載に よれば,本件発明は,洗濯ネットの閉口時にはスライダ構成体を「確実にカバ\nー体に収」め,開口時には 閉口端側からスライダ3を押すことにより,拡大 把持体1の「先の部分」を一定量カバー体から露出させ,その部分を指でつか んで引き抜くことにより開口するものであると認められる。 このような,本件発明に係る洗濯ネットの開閉時の手順及び仕組みによれ ば,閉口時において拡大把持体は,その「先の部分」まで「確実に」カバー体 に覆われた状態にあるものと解するのが相当であり,本件明細書の【図4】 (C)にも,開口部を閉じた際に拡大把持体1が完全にカバー体に収められ た状況が図示されている。
そうすると,構成要件Eの「収まった状態」とは,拡大把持体がカバー体に\n完全に覆われた状態をいうものと解すべきであり,このような理解は,「収ま る」という語が,一般的には「ある範囲内に全部が残らず入る」ことなどを意 味すること(乙3)とも整合するというべきである。 また,仮に,原告の主張するように閉口時において拡大把持体がカバー体 に完全に覆われることを要しないと解し得るとしても,上記の開閉時の手順 及び仕組みによれば,少なくとも,拡大把持体は,開口時にその先の部分を指 でつまんでそのまま開口することができない程度までカバー体に覆われてい ることを要するというべきである。 以上に基づき被告製品についてみると,証拠(甲3,乙19)によれば,被 告製品はいずれも開口時に閉口端側からスライダーを押して把持体の先の部 分を露出することを必要とせず,そのまま把持体を指でつまんで開口するも のであり,これを可能にするように,開口部側において把持体のリング部分\nの一部が指でつまむことができる程度にファスナーカバーから露出している ことが認められる。 このように,被告製品は,閉口時に把持体がファスナーカバーに完全に覆 われておらず,少なくとも,把持体が指でつまむことができる程度に露出し ているのであるから,被告製品は構成要件Eの「拡大把持体が収まった状態」\nにあるということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.09.28
平成29(ワ)10742 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月19日 東京地方裁判所
構成要件Eのうち,「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義につい\nて検討する。 上記各文言は,調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり,\n文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから,本件明細 書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで,1⑴にお いてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると,本件明細書等(【0003】, 20 【0005】,【0021】,【0028】,【0029】,【0030】,【0 032】)には,リング状枠はトッププレート上に印刷表示され,調理容器を有効\nに加熱できる領域として使用者に示されるものであること(【0003】),リン グ状枠は加熱部の領域を示し,鍋の最大径と同径で,鍋の外殻を表すものであるこ\nと(【0005】,【0021】)及び加熱部は最大の鍋径と同径で,リング状枠 であること(【0028】,【0029】)が示され,これ以外に,上記各文言の 意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると,「最 大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し,\nまた,リング状枠と同径のものであり,また,「調理容器の外殻」と一致するもの であると解するのが一般的かつ自然である。 この点,被告は,構成要件Eの内容は不特定であるなどと主張するが,同主張は,\n前記認定に照らし採用することができない。
(2) 被告製品関連製品の構成\nア 原告は,別紙3被告製品説明書(原告)において,被告各製品は,「左IH ヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である 直径26cmの領域を示す外殻線11,12」という構成を有し,これが「調理容\n器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして,被告各製品を 除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。\nイ しかしながら,前記⑴において認定したとおり,「調理容器の外殻」及び「最 大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域\nの領域を示すリング状枠と同径のものであるところ,原告の主張する外殻線11, 12は,原告において付しているものにすぎず,トッププレート上に表示されてい\nるものではないから,これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であ るとみることはできない。そして,本件全証拠によっても,被告各製品には,加熱 部及び有効加熱領域を示す直径26cmのリング状枠が表示されているとは認めら\nれず,加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」 及び「最大径の調理容器」が直径26cmであると認めることもできない。 原告は,「調理容器の外殻」は,鍋底の最大径であり,被告は被告各製品におい て鍋底が直径26cmまでの鍋を使用することができる旨説明しているから,被告 各製品の「最大径の調理容器」は26cmのものであると主張する。しかしながら, 被告において上記のように説明することが,被告各製品で使用可能な最大径の鍋底\nを示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても,前記⑴において認定し たとおり,「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠 及び有効加熱領域は,トッププレートに表示される必要があるのであって,表\示さ れていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。
(3) 小括
以上のとおり,被告各製品は,原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最 大径である直径26cmの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められな\nいから,この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Eを充足するという原告の主張\nは採用できず,ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また,被告各製品を除く 被告製品関連製品が構成要件Eを充足することを認めるに足りる証拠もない。\nしたがって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品関連製品は,構\n成要件Eを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな い。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2018.09.28
平成29(ワ)22417 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年8月29日 東京地方裁判所
(2)本件各発明の意義
上記(1)の本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の特許請求の範囲請 求項1及び3の記載によれば,本件各発明は,より広範で深い人間関係を結ぶための, 人脈関係登録システム,人脈関係登録方法とサーバ,人脈関係登録プログラムと当該 プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体に関するものであり,より広\n範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートするために,上記人脈関係登録シス テム等を提供することを目的とするものであって,登録者相互間の合意によって人間 関係が結ばれたとき,記録手段を備えたサーバに,人間関係を結んだ登録者の個人情 報又は識別情報を関連付けて記憶することで,個人情報又は識別情報を含む検索キー ワードによって第二の登録者と人間関係を結んでいる第三の登録者の個人情報又は 識別情報を検索することができるようにするという発明である,と認められる。
2 被告サーバの構成について\n証拠(甲16,乙4,7)及び弁論の全趣旨によれば,被告サーバにおいて,人間 関係を記憶する手順は,次のとおりであり,これを図示すると,別紙「被告サーバの 動作フロー」のとおりである(同別紙では,アカウント1号を甲,アカウント2号を 乙と表記している。)と認められる。すなわち,他のユーザと人間関係を結ぶ申\請をす ることを意味する「友達申請」(以下,単に「友達申\請」という。)をするユーザを「アカウント1号」,友達申請をされるユーザを「アカウント2号」として説明すると,1) アカウント1号が「友達申請をする」と示されたボタンをクリックする(画面08),\n2)被告サーバがアカウント1号に確認画面を送信する,3)アカウント1号が「送信す る」と示されたボタンをクリックする(画面09),4)被告サーバが記憶手段に友達申\n請に係るデータを登録する,5)被告サーバが記憶手段にアカウント1号及びアカウン ト2号の人間関係が結ばれた旨の友達リストの仮登録をする,6)被告サーバがアカウ ント2号に友達申請がされたことを通知する(画面12),7)被告サーバがアカウン ト1号に友達申請の完了画面を送信する(画面11),8)アカウント2号が被告サー バにアカウント1号のプロフィールを要求する(画面13,14),9)被告サーバが記 憶手段からアカウント1号のプロフィールを取得する,10)被告サーバがアカウント2 号にアカウント1号のプロフィールを送信する,11)アカウント2号が「友達になる」 と示されたボタンをクリックする(画面15),12)被告サーバが記憶手段の友達リス トを更新して本登録をし,友達として関連付けることが完了する,13)被告サーバがア カウント1号に友達申請が承認されたことを示すメール(甲16)を送信する,とい\nうものである。 そうすると,被告サービスにおいては,被告サーバの記憶手段にアカウント1号と アカウント2号の人間関係が結ばれたとして関連付けられた後に,アカウント1号に 対して友達申請が承認されたことを示すメールが送信されるという処理がされるの\nであり,アカウント1号とアカウント2号が友達として記憶された後に,仮にアカウ ント1号に対し友達申請が承認された旨が通知されなかったとしても,被告サーバに\nおいては,アカウント1号とアカウント2号が友達であると記憶されているといえる。
3 争点1(被告サーバは,文言上,本件各発明の技術的範囲に属するか)について 事案に鑑み,まず,争点1−3(被告サーバは構成要件1D及び2Dを充足するか)\nについて判断する。
(1) 構成要件1Dは,「上記第二のメッセージを送信したとき,上記第一の登録者\nの個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段 と,」というものであり,本件発明1においては,サーバが,第二の登録者と人間関係 を結ぶことを希望する旨の第一の登録者からのメッセージである「第一のメッセージ」 を受信して同メッセージを第二の登録者の端末に送信し,第二の登録者からこれに合 意する旨のメッセージである「第二のメッセージ」を受信して,同メッセージを第一 の登録者に送信したことを条件として,又は送信した後で,第一の登録者の個人情報 と第二の登録者の個人情報とを関連付けて記憶手段に記憶するものとして規定して いるということができる。 そして,構成要件1Dの「個人情報」が「識別情報」に置き換えられているほかは,\n構成要件1Dと文言を共通にする構\成要件2Dについても,サーバが第二のメッセー ジを送信したことを条件として,又は送信した後で,第一の登録者の識別情報と第二 の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶するものとして規定していると 認められる。
(2) この点,原告は,構成要件1D及び2Dにおける「送信したとき」の「とき」\nは「ある幅をもって考えられた時間」という意味であるとして,構成要件1D又は2\nDは,第一の登録者の個人情報又は識別情報を第二の登録者の個人情報又は識別情報 とが関連付けられた後に第二のメッセージが送信される場合をも含む旨を主張する が,「送信したとき」とは,送信したことを条件とする旨表す表\現であると解釈するの が一般的かつ自然な解釈であるというべきであり,また,これが時を表す表\現である と解釈したとしても,送信という動作が完了していることを表す表\現が用いられてい ることからすると,送信することが関連付けることに先行すると解釈するのが一般的 かつ自然であって,本件明細書その他にも異なる解釈を導く説明は見当たらない。 したがって,構成要件1D及び2Dの記載は,送信の実行が先行し,その後に関連\n付ける旨の実行がされることを規定していると解され,原告の上記主張を採用するこ とはできない。
(3)そこで,被告サービスについてみると,前記2において認定したとおり,被告 サービスにおいては,被告サーバの記憶手段に第一の登録者に相当するアカウント1 号と第二の登録者に相当するアカウント2号が友達として登録されて関連付けるこ とが終了した後に,アカウント1号に対して友達申請が承認されたことを示すメール\nが送信されるという処理がされるのであるから,被告サーバは,「第二のメッセージ を送信したとき」に,「上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを 関連付けて上記記憶手段に記憶する手段」又は「上記第一の登録者の識別情報と第二 の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段」を有しているとい うことはできない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告サー バは,構成要件1D及び2Dを充足しない。\nよって,被告サーバは,文言上,本件各発明の技術的範囲に属すると認めることは できない。
・・・・
これを本件についてみると,前記1(2)で説示したとおり,本件各発明は,より 広範で深い人間関係を結ぶための,人脈関係登録システム,人脈関係登録方法とサー バ,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記\n録媒体に関するものであり,より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポート するために,上記人脈関係登録システム等を提供することを目的とするものであって, 登録者相互間の合意によって人間関係が結ばれたとき,記録手段を備えたサーバに, 人間関係を結んだ登録者の個人情報又は識別情報を関連付けて記憶することで,個人 情報又は識別情報を含む検索キーワードによって第二の登録者と人間関係を結んで いる第三の登録者の個人情報又は識別情報を検索することができるようにするとい う発明である。そして,登録者相互間の合意は,メールの交換によって行われるもの されている(段落【0011】,【0015】)。そうすると,本件各発明の構成要件1D及び2Dの「第二のメッセージを送信したとき,…関連付けて上記記憶手段に記憶\nする」という構成は,登録者相互間の合意(メッセージの交換)によって人間関係が\n結ばれたとき,記録手段を備えたサーバに,人間関係を結んだ登録者の個人情報又は 識別情報を関連付けて記憶するという課題解決手段を具体的な構成として特定した\nものであって,この構成が従来技術に見られない特有の技術的思想を構\成する特徴的 部分であり,本件各発明における本質的部分というべきである。 これに対し,原告は,より広範で深い人間関係を結ぶために共通の人間関係を結ん でいる登録者の検索を容易にするということが本件各発明の本質であり,本件各発明 における友達申請メッセージ(第一のメッセージ)や承認メッセージ(第二のメッセ\nージ)のやり取りに係る構成は,人間関係を結ぶための「合意の手段」としての意味\nを有するにすぎず,本件各発明において非本質的な部分である旨主張する。 しかしながら,本件各発明の構成要件1D及び2Dの「第二のメッセージを送信し\nたとき,…関連付けて上記記憶手段に記憶する」という構成が,本件各発明の課題解\n決手段を具体的な構成として特定したものであることは前記のとおりであるから,個\n人情報又は識別情報を関連付けて記憶する過程のみを切り離して,それらの処理のタ イミングを規定したものにすぎないということはできず,本件各発明の非本質的部分 であるということはできない。また,本件各発明は,個人情報又は識別情報を含む検 索キーワードによって第二の登録者と人間関係を結んでいる第三の登録者の個人情 報又は識別情報を検索することを内容とするものである(構成要件1Eないし1G,\n2E)が,それを超えて,共通の人間関係を結んでいる登録者の検索を容易にすると いうことが,本件各発明の課題又は目的とされて本件各発明の構成として具体的に反\n映されているとはいえず,原告の主張を裏付けるに足る本件明細書の記載その他の証 拠はない。 したがって,原告の主張は採用することができない。
ウ そうすると,本件各発明の構成要件1D及び2Dの「第二のメッセージを送信\nしたとき,…関連付けて上記記憶手段に記憶する」という構成は,本件各発明におけ\nる本質的部分であると解されるところ,前記説示のとおり,被告サーバは,メッセー ジを交換する前に,登録者相互間の関連付けが終了するのであって,上記構成を有し\nていないから,その相違部分が本件各発明の本質的部分ではないとはいえず,均等の 第1要件(非本質的部分)を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.09.27
平成29(ネ)10064 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記のとおり(引用に係る原判決「事実及び理由」第4の1(1)イ(原判決 65頁6行目〜21行目)),本件訂正発明1の1及び1の2の従来技術には,基 礎杭等の造成にあたって地盤を掘削する掘削装置として一般に使用されるアースオ ーガ装置では,オーガマシンの駆動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必 要となるが,リーダの長さが長くなると,傾斜地での地盤掘削にあっては,クロー ラクレーンの接地面とリーダの接地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長く とれず,掘削深さが制限されるという課題等があった。そこで,本件訂正発明1の 1及び1の2は,これらの課題を解決するために,掘削装置について,掘削すべき 地盤上の所定箇所に水平に設置し,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させる が,当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケーシ ング回り止め部材を備えるものとして,リーダではなく,ケーシング回り止め部材 によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明と認められる。 ここで,回転駆動装置の回転反力を受支するには,1)回転駆動装置の回転反力が 固定ケーシングによって受支されるとともに,2)固定ケーシングの回転反力がケー シング回り止め部材によって受支されなくてはならない。そうすると,1)を具体的 に実現する「固定ケーシングが,掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の 機枠に一体的に垂下連結される」構成及び2)を具体的に実現する「ケーシング回り 止め部材が,掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の 横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,固定ケーシングを上下方 向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシン グ挿通孔を有する」構成により,ケーシング回り止め部材によってケーシング,ひ\nいては回転駆動装置の回転反力を受支するようにしたことが,従来技術には見られ ない特有の技術的思想を有する本件訂正発明1の1の特徴的部分であり,その本質 的部分というべきである。
(ウ) したがって,固定ケーシングが回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結さ れる構成を有しない被告装置1−3〜1−8は,本件訂正発明1の1と本質的部分\nを異にするものであり,第1要件を満たさない。
・・・
このことから,本件訂正発明1の1の「固定ケーシング5」は,「固定ケーシン グ5が円筒状ケーシングからなるため,地盤への固定ケーシング5の打ち込み及び 引き抜きが容易となり」【0028】とも記載されているように,回転駆動装置1 の下部から垂下され,ケーシング回り止め部材7のケーシング挿通口8に挿入され, 掘削軸部材2及びダウンザホールハンマー4と共に地盤の掘削により地盤に打ち込 まれ,地盤を所定深度まで掘削したら,ダウンザホールハンマー4の作動を停止さ せた後,昇降操作用ワイヤーWを巻取り操作して,掘削軸部材2及びダウンザホー ルハンマー4と共に引き上げられることを前提としたものである。 そうすると,本件訂正発明1の1の掘削装置においては,掘削後に引き抜くこと を前提にケーシングと回転駆動装置の機枠とを一体的に連結することによって,回 転駆動装置とケーシングを掘削後に引き抜く際に,地盤内でケーシングにかかる土 圧による抵抗に抗してこれを引き抜くことが可能になるものということができる。\nこれに対し,ケーシングと回転駆動装置との機枠とを一体的に連結するのでなく 着脱自在の構成にした場合,そもそも着脱自在の構\成はケーシングを掘削後に残置 させることができるという作用,効果を奏するものであるし,仮にこの構成でケー\nシングを引き上げるとすると,ケーシングと回転駆動装置の機枠との連結部の強度 が十分でないために,引き抜くことが不可能\ないし極めて困難となり,本件訂正発 明1の1の目的を達成することができない。 したがって,掘削後にケーシングを引き抜くことを前提とした本件訂正発明1の 1の掘削装置において,回転駆動装置にケーシングを着脱自在に連結する構成を採\n用すると,本件訂正発明1の1の目的を達成することが困難となり,同一の作用効 果を奏しなくなる。 そして,被告装置1−3〜1−8の構成につき,いずれも回転駆動装置の下部に\n連結された中空スリーブに設けられたスリット状の切り欠きとケーシング外周軸方 向に固設された角鉄とを係合させることにより,中空スリーブとケーシングとを着 脱自在に係合するものであるとする限りでは,当事者間に争いがない。 (イ) 以上によれば,被告装置1−3〜1−8は,第2要件を満たさない。
◆判決本文
1審判決はこちら。
◆平成25(ワ)10958
関連の無効審決の取消訴訟はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 賠償額認定
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.09.26
平成29(ワ)40193 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月6日 東京地方裁判所
プレートがゲーム空間内の所定の範囲に適用されることがあることが記載さ れ,また,前記(2)イのとおり,本件明細書には,発明を実施するための形態と して,プレイヤがテンプレートの作成を指示したとき,「範囲選択画面」が表\n示され,そこにおいては,ゲーム空間の一部について,テンプレートが作成さ れる範囲が表示されていること,テンプレートが作成される範囲について,例\nとして,プレイヤが任意の2点をタップして,当該2点を対頂点とすることで 定められることがあること,ゲーム空間の一部に対して,そのテンプレートが 適用されることが記載されている。他方,本件明細書には,「ゲーム空間」の 選択に関して,上記内容とは異なる内容の記載はない。 さらに, 原告は,本件意見書において,補正により加えられた「プレイヤによって選択されたゲーム空間の全体」との記載について,プレイヤがゲーム空間のうちのテンプレートが作成される範囲を指定するという段落【0037】の記載を挙げた上で,プレイヤがゲーム空間の左上の点および右下の点をタップすることで,ゲーム空間の全部の範囲を選択することができることを意味する旨述べて,その記載が当初明細書から自明であると述べている。
以上によれば,本件明細書には,本件各発明のテンプレートはゲーム空間内 の所定の範囲について作成,適用されるもので,その範囲についてプレイヤが 定めることが記載されており,原告もそのことを前提として,プレイヤがゲー ム空間内の全部の範囲をテンプレートの範囲とすると定めることによりゲー ム空間の全体が選択されることになるという意見を述べたといえる。 上記の本件明細書及び本件意見書の記載を参酌すれば,構成要件1C及び2\nDの「プレイヤによって選択されたゲーム空間の全体」における「選択」とは, テンプレートの作成について,プレイヤがテンプレートとするゲーム空間内の 一定の範囲を選択することを前提として,テンプレートを作成する際に,プレ イヤがゲーム空間内の全部の範囲を選択することを意味するものと解釈する のが相当である。
これに対し,原告は,構成要件1C及び2Dにおける「ゲーム空間の全体」\nとは文字通りゲーム空間全体を意味するのであってゲーム空間のうちどの部 分を選択するかの決定権をプレイヤが有していることを必須の構成要素とは\nするものではないと主張し,また,本件明細書の第1及び第2実施形態は,テ ンプレートの作成,適用の具体例を示したにすぎないなどと主張する。 しかし,「ゲーム空間の全体」がプレイヤによって選択されるとしても,プレ イヤによってどのような態様による選択がされるかについては,特許請求の範 囲の記載からは明らかではない。本件明細書には,テンプレートの作成に当た って,プレイヤがゲーム空間内の一定の範囲を選択することは記載されている が,それ以外の選択に関する構成については何ら記載も示唆もないから,前記\nと異なる態様でのプレイヤによる選択について,本件明細書に記載や示唆が あるとはいえないし,原出願日の当業者の技術常識に照らして明らかであると もいえない。また,原告は,本件特許の出願経過(甲22)において,プレイ ヤがタップする任意の2点をゲーム空間の左上及び右下の点とすれば「ゲーム 空間の全体」になるなどと説明しており,この説明はプレイヤにおいてゲーム 空間内の一定の範囲を選択することを前提としているものといえ,前記 の解 釈に沿うものといえる。原告の主張は採用することができない。
上記(1)で認定のとおり,本件ゲームは,プレイヤが基本画面においてレイア ウトエディタのアイコンをタップしてレイアウトエディタ画面を表示させ,レ\nイアウトに対応する縮小画面を選択,保存することによって新たなレイアウト を作成するというものである。そうすると,そこにはプレイヤがゲーム空間内 の一定の範囲を選択するという機能や動作は全く存在していない。したがって,本件プログラム及び本件携帯端末は,いずれも構\成要件1C及び2Dを充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.07.24
平成30(ネ)10018 特許権に基づく差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年7月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明に係る特許請求の範囲には,「吸着面」について,1) 攪拌装 置から牌を取り上げる汲上機構を構\成する円筒回転体には円筒回転体の 一側端から「牌の横幅ほどの幅」の「吸着面」が配設されること(構成\n要件C,H,I),2) 「吸着面」の中心には磁石を埋没し,「吸着面」 に磁気力により牌を吸着して下方から上方に吸い上げるように円筒回転 体を回転させること(構成要件J),3) 汲上機構によって取り上げら\nれた牌を一方向に整列して送り出すための整列機構には,円筒回転体に\n吸い上げられた牌の方向を揃えるため「吸着面」の外側の軌道に沿って 配設した案内部材が設けられること(構成要件D,K)の記載がある。\nそして,自動麻雀卓における「牌」は,字面に垂直な方向からみて 「横幅」が「縦幅」より短い長さとなる長方形状であるから(原判決別 紙図2),構成要件Iの「牌の横幅ほどの幅」との特定は,「吸着面」\nの幅が「牌の縦幅」より「牌の横幅」に近い幅をもつことを特定するも のと解するのが文言上自然である。
イ もっとも,特許請求の範囲の記載のみからは「横幅ほど」の外延は必ずしも明らかではないことから,本件明細書の記載について検討する。 本件明細書には,上記1(2)のとおりの本件発明の課題の解決手段とし て,円筒回転体の周面部位に円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅 をもつ吸着面を配設し,磁性体を埋設した牌を,中心に磁石を埋没した 吸着面に磁気力により吸着し,円筒回転体に吸い上げられた牌の方向を 揃えるため前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材を設け, 前記円筒回転体によって下方位置にて取り上げられた牌は,前記案内部 材にそって牌の向きを揃えながら上方に移動する(段落【0008】) ことが記載されている。そして,円筒回転体は牌の縦幅と略等しい長さ の高さ寸法であり(段落【0009】,【0021】),円筒回転体の 一側端から「牌の横幅」と略等しい幅の吸着面が形成される(段落【00 21】)ことが記載されており,これらの記載からは,「牌の縦幅」と区 別される「牌の横幅」を「吸着面の幅」に相当するものとしていること が理解され,このような理解は特許請求の範囲の記載とも整合する。 さらに,本件明細書の段落【0033】〜【0035】には,吸着面 401Bに様々な角度で吸着した牌10につき,案内部材501の入り 口付近で吸着面401Bからはみ出た側面が,案内部材先端502に接 触して抵抗を受け,磁石により吸引されて回転しながら向きを変え,縦 長方向に整列することが記載され,図10及び図11における吸着面4 01Bの幅は牌の横幅に近似する幅であることが見て取れる。
ウ 以上のとおりの各構成要件相互の関係及び本件明細書の記載によれば,\n本件発明において「牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」とした技術的意義 は,吸着面の幅を「牌の横幅」分の幅とすれば,牌が少しでも斜めに吸 着した場合には牌が吸着面からはみ出るから,はみ出た牌の側面に吸着 面の外側の軌道に配設した案内部材を接触させ,接触による力学的な作 用と牌に埋設された磁石と吸着面の中心に埋設された磁石との吸引力に よって牌を回転させて長手方向の向きに揃えるようにしたことにあると 解することができる。 そして,このような技術的意義に照らせば,構成要件Iの「牌の横幅ほ\nどの幅」とは,吸着面の幅が,牌の横幅(短辺)と同一か,様々な角度 で吸着面に吸着した牌の側面が当該吸着面からはみ出る部分を有し,は み出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えること ができる程度の幅を意味し,牌の縦幅に近似する幅はこれに含まれない と解すべきである。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> ピックアップ対象
2018.06.28
平成30(ネ)10001 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (a) 1審被告Aは,1審被告白石の代表取締役であり,1審被告白\n石の事業全般を統括していたが,平成22年6月4日,1審被告白 石宛ての1審原告の通知書(親和製作所の装置の販売が本件特許権 侵害である旨を指摘するもの)を受領し,本件特許権の存在を知る に至った。さらに,1審被告Aは,平成24年1月12日,1審被 告白石宛ての1審原告の通知書(親和製作所と1審原告の和解に関 するもの)を受領した。(甲15の資料5,資料9,乙73)
(b) 東京地方裁判所は,本件仮処分申立事件についての平成26年\n10月8日の審尋期日において,被告装置(WK型)が本件特許権 に係る発明の技術的範囲に属する旨の心証開示をした。(甲18)
(c) 1審被告白石は,平成26年10月24日から同月28日まで の間に,渡邊機開から,被告装置(WK型)を合計14台,本件板 状部材153個及び本件固定リング123個を購入した。1審被告 白石の平成23年から平成25年にかけての本件固定リングの購入 数は合計20個未満であり,平成26年10月24日から同月28 日までの本件固定リングの購入量はこれまでの取引状況に比して突 出して多い。(甲17の1,2)
(d) 東京地方裁判所は,平成26年10月31日,渡邊機開による 被告製品(WK型),本件固定リング及び本件板状部材の販売等を 差し止める旨の本件仮処分決定をし,1審原告は,同年11月4日 付け通知により1審被告白石に対しその旨を通知した。(甲15の 資料10)
(e) 1審被告白石は,本件仮処分決定後は,平成26年11月14 日頃から平成27年4月1日にかけて被告装置を販売した。
(f) 1審被告白石は,平成27年2月26日,鶴商に型式名を「L S−S」とする被告装置(実質は「WK−550」)を販売し,ま た,同年5月までには,渡邊機開からWK型として仕入れた被告装 置(「WK−600」)に,構成の変更がないのに「LS−G」型\nの表示を付したものを取り扱っていた。(上記2(1),甲22)
c 1審被告Aは,1審被告白石の事業全般を統括していたのであるか ら,1審被告白石の取引実施に当たっては,第三者の特許権を侵害し ないよう配慮すべき義務を負っていたというべきである。この観点か ら1審被告Aの責任について検討してみると,まず,平成22年6月 4日及び平成24年1月12日の時点で,1審被告Aにおいて,被告 装置が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属することを知っていた ことを認めるに足りる証拠はない。なお,平成24年1月12日頃に 1審被告白石が1審原告から通知書を受領したことは上記b(a)のと おりであるが,その通知書の内容は親和製作所の装置に関するもので あり,渡邊機開製の被告装置とは直接関わるものではなかったのであ るから,1審被告Aが上記時点において被告装置につき専門家に問い 合わせるなどの調査等をせず,被告装置の販売を中止しなかったから といって,1審被告Aに重過失があったとすることはできない。 これに対し,上記b(d)によれば,1審被告Aは平成26年11月 初旬には本件仮処分決定について知ったものと認められるから,これ によって被告装置が本件特許権を侵害するおそれが高いことを十分に\n認識することができたと認められる。ところが,1審被告Aは,本件 仮処分決定を踏まえて,中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討 をした形跡もないまま,取引を継続し,さらに被告装置の型式名につ いて工作をするなどしているのであり,これら上記bに認定した本件 仮処分決定前後の経過に照らせば,同月以降の1審被告白石による被 告装置の販売を中止するなどの措置をとらなかった1審被告Aには, 1審被告白石による本件特許権侵害について悪意又は少なくとも重大 な過失があったというべきである。 よって1審被告Aは,1審被告白石による被告装置の販売に係る 同月以降の本件特許権侵害について,会社法429条1項の責任を負 う。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> ピックアップ対象
2018.06.25
平成29(ネ)10096 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本質的部分について、上位概念化できるかについての判断基準について言及しています。
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なか った技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想 に基づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって,\n特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち, 従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきで\nある。
そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許 発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範 囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が\n何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち,特許発明の 実質的価値は,その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定め られることからすれば,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記 載,特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。そして,従来 技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には,特許請求の 範囲の記載の一部について,これを上位概念化したものとして認定され,従来技術 と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には,特許 請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。
ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところ が,出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には,明細書に記載さ\nれていない従来技術も参酌して,当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には,特許\n発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に 比べ,より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり,均等が認められる範囲が より狭いものとなると解される。
・・・・
本件特許出願日以前に,キャラクター画像情報に対する課金方法として,携帯端 末自体を改めて販売する態様ではないもの,すなわち,毎月100円を支払うこと により携帯電話機へ毎日異なるキャラクタ画面データを配信するiモード上での上 記サービス「いつでもキャラっぱ!」が公知であったこと(乙6),及びiモード においてはコンテンツプロバイダー(情報提供者)がコンテンツの情報料をNTT ドコモから携帯電話の通信料と合わせて課金し得るシステムが採用されていたこと (乙9)が認められる。このことに鑑みれば,本件特許出願日において,「サービ ス提供者にとっても,…キャラクター画像情報を更新するには,携帯端末自体を改 めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情報により効率良く利益を得るの は困難であった。」(本件明細書【0003】)との課題が未解決のままであった とは認められない。
d しかるに,本件明細書には,乙6,8及び9記載の上記技術についての記載 はない。したがって,本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載さ れているところは,本件特許出願日における従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。\nそうすると,本件発明の本質的部分は,本件明細書の記載に加えて,乙6,8及 び9記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。
(オ) そして,本件明細書の記載並びに乙6,8及び9記載の前記技術によれば, キャラクター選択・変更等の態様に関する構成(前記1)並びに2)及び3)の組合せ) について,本件明細書は,複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラクターを 創作決定すること(前記2)及び3))を携帯端末サービスシステムで提供する(前記 1))という発想自体を開示するにとどまり,このようなシステムの実装における未 解決の技術的困難性を具体的に指摘し,かつ,その困難性を克服するための具体的 手段を開示するものではないので,従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さ いというべきである。 キャラクターの選択等に対する課金に関する構成(前記2)及び3)並びに4)の組合 せ)についても,本件明細書は,複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラク ターを創作決定し(前記2)及び3)),当該決定したキャラクターに応じた情報提供 料を通信料に加算する(前記4))という発想自体を開示するにとどまり,このよう な課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し,かつ,その困 難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので,従来技術に対する 本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。 そうすると,本件発明の本質的部分については,特許請求の範囲の記載とほぼ同 義のものとして認定するのが相当である。
・・・・
前記認定の出願経過によれば,控訴人は,構成要件A〜C及びHからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)及び構\成要件A〜E及びHからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項2に係る発明)については,特許 を受けることを諦め,これらに代えて構成要件A〜Hからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に同2及び5を統合した発明,すなわち本件発明)に限定\nして,特許を受けたものということができる。 そうすると,控訴人は,構成要件F及びGの全部又は一部を備えない発明について,本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか,少なくとも外形的にその\nように解されるような行動をとったものと理解することができる。 したがって,均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり,均等の第 5要件を充足しない。
ウ 控訴人の主張について
この点につき,控訴人は,被告システムは「仮想モール」に相当する構成を有しているから,本件特許の出願経過を参酌したとしても,均等の成立を妨げる特段の\n事情があるとはいえない旨主張する。 しかし,前記のとおり,本件発明の「仮想モール」は「ショップ」というカテゴ リーを選択することによってアイテムを購入する仕組みを包含するものではなく, また,本件明細書【0045】は本件発明の「仮想モール」を説明するものと見る ことができない以上,当該段落が当初から残存していたという本件特許の出願経過 も,本件発明の「仮想モール」の技術的意義を左右するものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2018.06.14
平成29(ネ)10033等 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年5月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許請求の範囲の記載によれば,構成要件Eの「前記背後壁」は,「既\n設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる」(構成要件B)ものであり,\n改修の前後でその「高さ」が変わるものではない。他方,同「改修用下 枠」は,その「室外寄りが,スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接 して支持されると共に,」その「室内寄りが,前記取付け補助部材で支 持され」(構成要件D)るものである。このため,構\成要件Eの「前記 背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」であることに寄与し ているのは,主ということができる。 この「取付け補助部材」について,本件明細書等の記載を見ると, 「既設引戸枠の形状,寸法に応じた形状,寸法の取付け補助部材を用い る」(【0018】),「その取付用補助部材106の高さ寸法を変え ることで,異なる形状の既設下枠56にも同一形状の改修用下枠56 (裁判所注,改修用下枠69の誤記であると認める。)を,その支持壁 89と背後壁104を同一高さに取付けることが可能である。」(【0\n091】)との記載がある。しかも,段落【0018】には,上記記載 に先行して,「既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去したので, 改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく,有効開 口面積が減少することがなく,広い開口面積が確保できる。」との記載 もある。 これらの事情を総合すると,構成要件Eの「同じ高さ」とは,「取付\nけ補助部材」で「改修用下枠」を支持することにより,「背後壁の上端」 と「改修用下枠の上端」とを,その間に高さの差が全くないという意味 での「同じ高さ」とした場合を意味するものと理解するのが最も自然で ある。 他方,「ほぼ同じ高さ」について,定義その他その意味内容を明確に 説明する記載は,本件明細書等には見当たらないが,以上に検討した点 を併せ考えると,ここでいう「ほぼ同じ高さ」とは,「取付け補助部材」 の高さ寸法を既設下枠の寸法,形状に合わせたものとすることにより, 「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを,その間に高さの差が全 くないという意味での「同じ高さ」とする構成を念頭に,しかし,その\nような構成にしようとしても寸法誤差,設計誤差等により両者が完全に\nは「同じ高さ」とならない場合もあり得ることから,そのような場合を も含めることを含意した表現と理解することが適当である。\n
イ(ア) このように解することは,本件明細書等の図1に示された実施の形 態につき「前壁102の上端部から室内68に向かって上方へ傾斜する …底壁103の最も室内68側の端部に連な」る「背後壁104」が, 「室内側案内レール67と同一高さまで立ち上がる」ものとされ(【0 027】),また,同図6に示された実施の形態につき「既設下枠56 の背後壁104の上端部に室内68側に向かう横向片104aを有し, この横向片104aと改修用下枠69の支持壁89の上端が同一高さで ある」と記載されている(【0069】)一方で,図1及び6の実施の 形態と比較すると「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」の「高さ」 に図面上明らかに差が認められる図10及び11の実施の形態について は,「例えば,図10に示すように取付け補助部材106の高さ寸法を 大きくして室内側壁部108を底壁103に当接し,かつ室内側案内レ ール115にビス110で取付ける。…この場合には,支持壁89が背 後壁104より若干上方に突出する。」(【0092】)と記載され, 「同一高さ」等の表現が用いられていないこととも整合する。\n
(イ) 本件特許の出願経過に鑑みても,構成要件Eについては上記のよう\nに解釈することが適当というべきである。 すなわち,被控訴人らが構成要件E「前記背後壁の上端と改修用下枠\nの上端がほぼ同じ高さであり」を追加したのは,拒絶査定不服審判の請 求と同時にされた手続補正書による補正後の請求項1〜6に係る発明に 対する進歩性欠如の拒絶理由通知,これを受けての被控訴人らによる補 正案の作成と特許庁審判官によるその了承,サポート要件違反の拒絶理 由通知という経過を経た後の手続補正においてである。そうすると,構\n成要件Eの追加は,上記サポート要件違反の拒絶理由を解消するために のみなされたか,これと同時に上記進歩性欠如の拒絶理由も解消するた めになされたかのいずれかの意図によるものと理解される。 そして,サポート要件違反の拒絶理由通知には「本願の請求項1〜6 には,広い開口面積を確保する本願の課題に対応した構成が記載されて\nいない。」と記載されている。本件明細書等の記載によれば,この「広 い開口面積を確保する本願の課題」については,1)既設下枠に存在した 室外側案内レールを切断撤去してできたスペースを利用することで広い 開口面積を確保し,「有効開口面積が減少することが少ない」(本件明 細書等【0060】)ようにすることを意味するものと理解することが できる一方で,2)「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「ほぼ 同じ高さ」とすることで「有効開口面積が減少することがな」い(【0 018】)ようにすることを意味するものと理解することも可能である。\nしかし,「広い開口面積を確保する本願の課題」を1)の意味に理解す る場合,このような課題は本件明細書等の記載から見て本件発明により 当然に解決されるべきものであるから,本件特許に係る出願の審査段階 の当初から拒絶理由として通知されてしかるべきものである。ところが, 実際には,サポート要件違反の拒絶理由は,審査段階のみならず審判段 階でも1度目の拒絶理由通知では指摘されず,審判段階での2度目の拒 絶理由通知で指摘されたのであり,このような経緯に鑑みると,「広い 開口面積を確保する本願の課題」の意味を1)の趣旨でサポート要件違反 の拒絶理由通知がされたものと理解することは不自然というべきである。 他方,上記経過につき,審判合議体が,進歩性欠如の拒絶理由は「前 記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」(構成要件\nE)との構成が追加されることで解消されると判断し,被控訴人らに更\nに補正の機会を与えるために,「広い開口面積を確保する本願の課題」 につき2)の意味を念頭にサポート要件違反の拒絶理由を通知したものと 理解するならば,2度目の拒絶理由通知の段階において敢えてサポート 要件違反の拒絶理由のみを通知したことも合理的かつ自然なこととして 把握し得る。現に,審判合議体は,「既設引戸を改修用引戸に改修する 際に有効開口面積が減少してしまうとういう課題を解決するものあっ て」,「当該構成は引用文献や他の文献から容易になし得たものである\nとはいえず」との審決書の記載から明らかなとおり,サポート要件違反 の拒絶理由通知を契機として「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端が ほぼ同じ高さであり」という構成要件Eが追加されたことによりサポー\nト要件違反及び進歩性欠如の拒絶理由がいずれも解消されたものとして 判断しており,このことは上記理解と整合的である。
ウ 被控訴人らの主張について
(ア) 被控訴人らは,本件発明において,改修用下枠の上端と背後壁の上 端との高さの差に一定の制限を設けないと,室外側案内レールを切断 撤去することにより従来技術に比べ開口面積の減少を少なくし,広い 開口面積を確保することが可能になったにもかかわらず,その取付け\nスペースを利用しないことにより改修用下枠が取付けスペース内に沈 み込まないために,本件発明の効果を達成し得ない構成も文言上包含\nされてしまうことから,本件発明の効果を達成できる範囲内において, 既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの関係を規定した のが構成要件Eの「ほぼ同じ高さ」であると主張する。\nしかし,取付けスペースを利用することを規定したいのであれば,例 えば,改修用下枠の一部が,既設下枠の室外側案内レール(切断して撤 去されている。)が存在した高さよりも低い位置に挿入されることを規 定するなど,端的に取付けスペースを利用することを明確にする補正を すればよいのであって,取付けスペースを利用しない構成を除外する目\n的で既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの関係を請求項 に記載することの合理性は乏しいというべきである。
(イ) また,被控訴人らは,改修用引戸枠を既設引戸枠にかぶせて取り付 けるものである以上,有効開口面積は必ず減少するのであるから,本 件発明の課題(作用効果)を既設引戸を改修用引戸に改修する際に有 効開口面積を減少することがないようにすること(本件明細書等【0 018】)と理解するのは誤りであるとする。 しかし,本件明細書等には「有効開口面積が減少することが少ない」 (【0060】)と「有効開口面積が減少することがな」い(【001 8】)という異なる表現が用いられているのであるから,両者を区別し\nた上で,「有効開口面積が減少することがない」ことの意味を探求しよ うとするのはむしろ当然である。そして,本件明細書等の記載からは, 本件発明は改修引戸装置の下枠の態様に重点が置かれたものと考えられ るのであるから,その作用効果の説明を理解するに当たり下枠に着目し, 改修用引戸の取付けにより客観的には有効開口面積が減少していても, 「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」を文字通り「ほぼ同じ高さ」 とすることにより下枠に関しては「有効開口面積を減少することがない」 という作用効果が得られることが表現されていると解することには十\分 な合理性があるといえる。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成26(ワ)7643
この特許権の無効審判の審取はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2018.06. 8
平成28(ワ)41720 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年5月31日 東京地方裁判所(47部)
緊急地震速報で発表する内容は以下のとおりである。
(ア) 緊急地震速報(警報)
・地震の発生時刻,震源の位置
・強い揺れ(震度5弱以上)及び震度4の地域の名称
(イ) 緊急地震速報(予報)
・地震の発生時刻,震源の位置,地震の規模(マグニチュード)
・強い揺れ(震度5弱以上)及び震度4の地域の名称
・予想される震度
・主要動の到達予想時刻
ウ 緊急地震速報の処理の流れは,以下のとおりである。
(ア) 観測点における震源推定処理
地震波を検知した観測点において地震波形を解析し,P波初動の時刻, 震央距離(B−Δ法による),震央方向(主成分分析法による),最大振幅, リアルタイム震度等を求める。この処理は地震検知を契機に実施され,そ の後毎秒,処理中枢(気象庁本庁・大阪管区気象台の処理中枢:EPOS) に送信される。
(イ) EPOS中枢処理における震源推定処理
EPOSにおいて震源を推定する処理では,最初にどこかの観測点で地 震波を検知してから,時間が経過して「地震波を検知する観測点が増える」 のに合わせ,様々な手法により震源計算を繰り返す。震源計算の手法には, IPF法,着未着法,EPOSによる自動震源決定処理があり,概ね時間 とともに精度が高くなる。
(ウ) マグニチュードの計算
前記の処理で推定した震源と観測した地震波の最大振幅を用いて,地震 の規模(マグニチュード)を毎秒推定する。
(エ) 震度等の予想
震源とマグニチュードを元に,地予想震度の精度も時間の経過とともに向上することが期待できる。
(オ) 情報の発表
震度等の計算結果が,発表条件・更新条件を満たすと,人手を介するこ\nとなく直ちに緊急地震速報を発表する。
(7) 上記(5),(6)のとおり,被告(気象庁)が行う緊急地震速報では,地震の観 測,データ処理,情報の発表を行うにすぎず,「受信」行為を行っていない(緊\n急地震速報を受信するのは,被告(気象庁)以外の第三者である。)。 また,仮に上記第三者の受信行為まで考慮に入れたとしても,被告の緊急地 震速報では,本件発明の「検出センタ」に相当する処理装置から「予想震度」\nや「到達予想時刻」が出力されており,受信機側で「予\想震度」や「到達時刻」 の演算が行われることは想定されておらず,したがって,個々の受信位置ごと に異なる個別の情報が提供されることもない。 さらに,被告の緊急地震速報で発表される情報は,上記(6)イのとおりであ り,その中に「地震の到来方向」は含まれていない。なお,インターネット検 索サイト Yahoo!JAPAN のニュースサイトに掲載された,高度利用者向け受信端 末の緊急地震速報に係る画像(甲5)上も,各地の予想震度を1つの地図内に\n図示しているにすぎず,地震データをそのまま告知に利用しており,個々の受 信機の受信位置ごとに異なる個別の情報である「地震の到来方向」を提供して いない。したがって,上記地図をみた者は,自らの所在地と震源地とを比較す ることで「地震の到来方向」を判断できるとしても,同地図上,「地震の到来方 向」自体が「警報・通報」されているものとはいえない。 このように,被告が行う緊急地震速報は,1)「受信」行為が含まれていない ほか,仮に第三者の受信行為まで考慮に入れたとしても,2)受信機側で「予想\n震度」や「到達時刻」の演算が行われることが想定されておらず,3)地震デー タをそのまま告知に利用しており,「地震の到来方向」を演算したり,これを警 報・通報することを想定していないから,いずれにしても,本件発明の構成要\n件(4)及び(5)を充足しない。これに反する原告の主張は,上記説示に照らして 採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.05.23
平成29(ネ)10102 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年5月21日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
本件各発明の意義は,充填された液体に臭いが移ることがな く,自立的に形状を維持でき,内部に空気を送り込むことなく,充填された液体の ほぼ全量を排出可能なウォーターサーバー用ボトルを提供するという課題を達成す\nるために,本件各発明の構成を採用することにある。すなわち,本件各発明は,全\n体をPET樹脂によって形成することで,液体を充填した際でも自立的に形状を維 持でき,液体に臭いが移ることがないようにし,胴部に上下方向に伸縮自在な蛇腹 部を設けることで,潰れやすさを向上させ,さらに,蛇腹部と底部との間に裾絞り 部を形成することで,ボトルが大気圧で押し潰れていく際に,裾絞り部が蛇腹部の 方に引き込まれていき,蛇腹部の内部の容積を削減する機能を有するようにしたも\nのである。 このような,本件明細書に記載された,蛇腹部と底部との間に裾絞り部を形成す ることの技術的意義に鑑みると,構成要件Hの「内部の液体の排出に伴って,前記\n裾絞り部がボトル内部に引き込まれること」とは,ウォーターサーバー用ボトル内 部の液体の排出に伴って,裾絞り部が蛇腹部の内部に引き込まれることを意味する ものと解される。 また,かかる解釈は,本件各発明の実施の形態として本件明細書に記載されてい る唯一の実施例において,内部の液体の排出に伴って【図4】(B),【図5】(A), 【図5】(B)と変化することが記載され,【図5】(B)において,裾絞り部が 蛇腹部の内部に引き込まれていることとも整合する。 ウ 以上のとおり,特許請求の範囲の記載,本件明細書の記載及び本件発明1に おける裾絞り部の技術的意義を総合すれば,構成要件Hの「内部の液体の排出に伴\nって,前記裾絞り部がボトル内部に引き込まれること」とは,ウォーターサーバー 用ボトル内部の液体の排出に伴って,裾絞り部が蛇腹部の内部に引き込まれること を意味するものと解される。
エ 控訴人の主張について
控訴人は,裾絞り部がボトル内部に引き込まれることの効果は,ボトル内の残水 を減らすことにあり,これを達するには,裾絞り部がボトル内部の方向に引き込ま れれば足り,蛇腹内部に裾絞り部が引き込まれることまで要求されるものではない から,構成要件Hの「裾絞り部がボトル内部に引き込まれる」とは,裾絞り部が蛇\n腹部の方向,つまり裾絞り部から見てボトル内部の方向に引き込まれることを意味 すると解される旨主張する。 しかし,前記イのとおり,蛇腹部と底部との間に裾絞り部を形成することの技術 的意義は,ボトルが大気圧で押し潰れていく際に,裾絞り部が蛇腹部の内部に引き 込まれていき,蛇腹部の内部の容積を削減する機能を有するようにしたことにある\nところ,単に裾絞り部がボトル内部の方向に引き込まれるというだけでは,本件明 細書に記載された本件各発明の上記効果を奏するものではなく,裾絞り部が蛇腹部 の内部まで引き込まれることによって,上記効果を奏するものである。 また,控訴人は,本件特許の出願時の請求項1を特許請求の範囲から削除し,出 願時の請求項2に構成要件Hを追加して請求項1とするなどの補正をした際に(乙\n6),審査官に対し,本件発明1は構成要件FないしHの構\成を備えることにより, 「ボトルが大気圧で押し潰れていく際,裾絞り部が蛇腹部の方に引き込まれていき, 蛇腹部の内部の容積を削減する機能があり(本件明細書【0020】),ボトル内\nの残水を減らす効果がある。」旨の意見を述べていたものであり(乙7),控訴人 の前記主張は,本件特許の出願経過における控訴人の主張とも異なるものである。 したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2018.04.25
北京市高等裁判所(2017)京民終454 号、判決日:2018 年3月28日
事件の概要など、詳しくは、林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所の
◆西電捷通VS ソニーのWAPI 特許侵害事件に関する検討
を参照ください。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> 外国
>> ピックアップ対象
2018.04.17
平成28(ワ)29320 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月29日 東京地方裁判所(46部)
上記(1)の記載によれば,本件発明1及び2は,熱可塑性樹脂発泡シートに 非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートを成形してなる容 器について,熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬さの差 により,容器に触れた際に,硬いフィルムで指等を裂傷するおそれがあるが, 突出部の上下面に凹凸を形成すると,蓋体を外嵌させる際に突起部が係合さ れる突出部の下面側にも凹凸形状が形成されることとなって強固な係合状態 を形成させることが困難となり,端縁部での怪我を防止しつつ蓋体などを強 固に止着させることが困難であるという課題を,本件発明1の構成,特に上記端縁部の上面に凹凸形状を形成する一方で下面は平坦とする形状とすることによって解決することとしたものということができる。\nまた,上記(2)の記載を参酌すると,本件発明1及び2は,上記端縁部を, 厚みが圧縮されて薄肉化されたもので,かつ,上面に凹凸形状が存在するも のとすることにより,その強度を強め,これによって蓋体を強固に止着させ るという課題を解決するものということができる。 以上によれば,本件発明1及び2は,容器の突出部の端縁部の形状につい て,上面に他の部分との厚みの差を付けて凹凸形状を形成するという形状と することで端縁部での怪我を防止するとの課題を解決し,端縁部につき上記 の端縁部の形状とすることに加えて下面を平坦にすることで,蓋の強固な止 着を実現するという課題を解決し,これによって上記各課題の双方を解決す ることを技術的意義とする発明である。
・・・・
以上によれば,本件明細書においても,発明の構成につき特許請求の範囲の記載と同様の記載がされ,その実施例においても,側周壁部の上端縁であり,被収容物が収容される収容凹部のへりといえる開口縁から外側に\n張り出して形成されているものが突出部とされている。実施例を示す図面 には突出部が水平で平坦な容器が示されているが,発明の詳細な説明欄に は,突出部が平坦であることについての説明はなく,本件発明1及び2の 突出部を突出部が平坦なものに限る趣旨の記載は見当たらない。これらに よれば,「開口縁」及び「突出部」については,上記アのように解するの が相当であり,「突出部」は水平で平坦なものには限られない。
ウ これに対して,被告は,出願経過に照らし,本件発明1及び2は突出部 が水平で平坦である容器に関する発明であると主張する。 原告は,前記1(2)のとおり,「前記突出部の端縁部の…且つ該端縁部の」 と補正をしたものであるところ,証拠(乙12〔2〕)によれば,審判請 求書において,上記補正の根拠として,突出部の端縁部において熱可塑性 樹脂発泡シートが圧縮されて薄肉とされたものであることを明確にしたも のであり,この点が本件明細書の例えば段落【0019】や【図3】b) に記載されているもので,願書に添付した明細書及び図面に記載された事 項の範囲内のものである旨記載したことが認められる。 上記認定事実によれば,補正の前後に係る特許請求の範囲をみても,補 正された部分は「端縁部の上面」と「収容凹部の開口縁近傍の突出部の上 面」の位置関係と端縁部における形状についてであって,突出部の形状が 水平で平坦である旨の明示的な記載も示唆も見当たらないし,原告が主張 したのは本件明細書において発明の実施の形態として記載(段落【001 9】や【図3】b))があることから補正の要件を満たすということであ るから,突出部の形状が水平で平坦なものに限定する趣旨を読み取ること ができない。したがって,本件発明1及び2の容器の突出部が水平で平坦 であると解することはできず,被告の主張は採用できない。
・・・・
上記記載によれば,本件発明1及び2は前記1(3)のとおりの技術的意義 を持つもので,端縁部の下面が平坦であることとその厚みが薄いことの双 方が備わることで,それぞれの効果が生じ,蓋の強固な止着が実現するの であって,端縁部が圧縮されて薄くなっていることと上面の位置との関係 に何らかの技術的意義があるものでないし,実施例においても何らの効果 も示されていない。そうすると,物の態様として「ように」の語が特段の 意味を有すると解することはできず,前記ア1)及び2)の各構成が両立していれば足りると解するのが相当である。
ウ これに対し,被告は,「突出部の端縁部において…薄くなっており」と いう構成によってのみ「前記突出部の…下位となる」構\成が実現しなけれ ばならないと解釈すべき旨を主張し,その根拠として本件明細書の記載 (段落【0019】),審判請求書(乙12)において上記部分に係る補正 の根拠を本件明細書の「例えば段落0019や図3(b)」と主張したと いう出願経過を挙げる。 しかし,上記の本件明細書の記載(段落【0019】)は実施例の記載 であり,こうした実施例があることから上記のとおり解釈することは相当 でないし,当該記載が引用する【図3】b)によれば端縁部の下面も端縁 部以外の突出部の下面に比して下位となっており,端縁部を圧縮して薄く しなくても端縁部の上面が端縁部以外の突出部の上面に比して下位となっ ているとみる余地がある。補正の根拠に関する主張は,補正に係る部分が 本件明細書の記載の範囲内であることを指摘したものであって,説明した 部分に補正に係る部分の解釈を限定する趣旨を読み取ることはできない。 被告の主張は採用できない。
・・・
上記 1)によれば,プラスチック製品や容器についての一般的な実施 料率は2〜4%程度ということができる。また,・・・によれば, 本件発明1及び2の技術的意義が現れているのは容器の一部である端縁 部の形状に限定されるところ,一般的には端縁部における手指の切創を 防止することは顧客吸引力を持ち得るといえるものの,原告の製品にお いて行われている上記「セーフティエッジ」加工は,蓋の端縁部の加工 であって本件発明1及び2の包装用容器に係る加工であるとは認め難く, 原告においても平成27年以降はこの加工の存在をカタログ等において 顧客に告知していない。被告においても,端縁部において手指の怪我が 生じ得るという課題を認識して顧客に告知する一方で,その部分の怪我 防止の措置について顧客に告知をしていない。そうすると,本件発明1 及び2の技術的意義が容器の売上げに寄与する程度は相当程度小さいも のとならざるを得ないから,上記の一般的な実施料率よりも相当程度低 くすべきである。 以上によれば,本件発明1及び2の実施によって受けるべき相当な実 施料率は●(省略)●と認めるのが相当である。
ウ 損害の額
上記ア及びイによれば,本件発明1及び2の実施に対し受けるべき金銭 の額に相当するのは,1694万4217円であると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2018.04. 4
平成29(ネ)10091 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月14日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
イ号製品の構造上,「フック部」に相当し得るのは,先端部2及び曲折部1であり,\n「ボディ部」に相当し得るのは,2枚の樹脂板からなる,本体部3であり,「腹部」 に相当し得るのは,それぞれの樹脂板の,眼瞼縁又は医療用ドレープと対向する矩 形状の底面部分である。 証拠(甲18〜20,甲24の1,乙5,9)及び弁論の全趣旨によると,イ号 製品において,フック部に導かれた液体のうち,それぞれの樹脂板の矩形状の底面 部分を伝うものもあるが,その大部分は,2枚の樹脂板が対向する側面の間を伝っ て排出されるものと認められる。したがって,それぞれの樹脂板の矩形状の底面部 分は,フック部により導かれた液体の大部分を伝わせて排出するものではないから, イ号製品は,構成要件Gを充足しない。
ウ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は,本件特許明細書における「腹部」とは,ボディ部の「腹側」 にあり,排液器と眼瞼縁との間で排液のための動力を生み出す「隙間」を形成する 部分を指し,「腹部」以外の「腹側」とは,上記「隙間」から離れたボディ部の側面 にあって,その形状によって大きな表面積を確保し,流路を拡大する機能\を営む部 分である,と主張する。 しかし,本件特許明細書の【図5】に係る実施例においては,腹部103aは, 丸みをもたせ,断面が略円形状であって,液体が表面を伝うに適した形状であると\n特定され(【0028】),【図11】に係る実施例においては,断面略V字形状に形 成されている箇所が腹部1103aと特定されている(【0041】)のであるから, これらの箇所は,控訴人が主張するところの「濡れ性を利用して流路を拡大する部 分」も含んでいると認められる。また,【図5】に係る実施例において,液体の流量 が増え液面が上昇すると,液面と腹部の表面との「接点」が上昇する(【0028】)\nとされていることから,本件特許明細書においては,液体の流量が少ないときに液 面が接していなかった,「濡れ性を利用して流路を拡大する部分」も「腹部の表面」\nの一部とされていると認められる。 さらに,上記【0028】,【0041】の記載に鑑みると,控訴人が指摘する「ボ ディ部103の腹部103aの表面と医療用ドレープ240とで形成された隙間が\n毛細管として機能し」(【0029】)及び「腹部1103aと眼瞼縁233との間に\n形成された隙間が毛細管として機能し」(【0042】)との記載は,腹部のうち眼瞼\n縁又は医療用ドレープに近接する部分が,眼瞼縁又は医療用ドレープとの間で毛細 管として機能していることを述べていると解すべきであって,これらの記載から,\n毛細管として機能する部分のみが腹部であるということはできない。【図5】の「1\n03a」の文字から出た線及び【図11】の「1103a」文字から出た線が指し 示す位置は,腹部の範囲(上限位置)を示すものとは解されない。 本件特許明細書の【図13】及び【図15】に係る実施例においては,控訴人が 主張するところの「毛細管現象を引き起こす部分」と「濡れ性を利用して流路を拡 大する部分」からなる凹凸の位置を説明するために「腹側」との表現が用いられて\nいるにすぎず,そのうちの「毛細管現象を引き起こす部分」を「腹部」であると解 する根拠とすることはできない。 したがって,毛細管として機能するか否かによって「腹部」が特定されていると\nも,「毛細管現象を引き起こす部分」か「濡れ性を利用して流路を拡大する部分」か で,「腹部」と「腹側」との表現を使い分けているともいえない。控訴人の主張には,\n理由がない。
◆判決本文
原審はこちら。平成28(ワ)6357
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.03.28
平成29(ネ)10092 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記1(2)のとおり,本件発明1の意義は,熱放散ブリッジに軸方向空気通 路を貫設せずに電力電子回路を冷却することにより,電子構成部品の配置に利用可\n能な空間を十\分に確保するという課題を達成するために,熱放散ブリッジの底面を 冷却流体通路の一方の壁とする構成を採用したことなどにある。すなわち,本件発\n明1は,冷却流体が,横方向に吸い込まれて,後部軸受けの中央スロット4b及び 4cの方に流れ,熱放散ブリッジの下方で冷却流体通路内を循環し,熱放散ブリッ ジの底面及び冷却フィンを,それらの全長にわたって掃引した後,後部軸受けの側 部スロット4a及び4dを通って排出される構成とすることにより,熱放散ブリッ\nジの上面に搭載された電力電子回路が,冷却フィン及び熱放散ブリッジを介して, 伝導によって冷却されるという効果を奏するようにしたものである。 そして,このように構成要件1Gの冷却流体通路が,熱放散ブリッジを冷却する\nための構成であり,同通路を流れる冷却流体が,熱放散ブリッジの底面をその全長\nにわたって掃引するものであることからすると,冷却流体通路の長手方向壁のうち, 少なくとも熱放散ブリッジの底面により形成される壁は,冷却効率の観点から,冷 却流体通路の全長にわたっている必要がある。
(イ) 一方,本件明細書1には,構成要件1Gの冷却流体通路が,同通路の他方\nの長手方向壁を形成している後部軸受けを冷却するための構成であることは何ら記\n載されていない。そして,前記1(2)のとおり,本件発明1は,軸方向を流れる冷却 流体によって,機械内の冷却流体全体の流量が増加し,オルタネータの内部部品を はるかに良好に冷却することができるという効果を奏するものであることからする と,後部軸受けの冷却は,冷却流体通路を通る空気によってではなく,主に,空間 22を通る軸方向空気流により機械内の空気流量全体が増加することによって達成 されるものであると認められる。 そうすると,後部軸受けをもって冷却流体通路の壁を形成する構成とすることは,\n空気の流れを冷却流体通路に沿わせる目的を持つのみということになるため,必ず しも,冷却通路全体にわたる必要はない。例えば,本件発明1の実施形態において, 後部軸受けの中央スロット4b及び4cの直上にある空気は,ファンによって後部 軸受け内部に流入し,絶えず側方からの空気と入れ替わるので,その直上の熱放散 ブリッジを冷却する空気流を形成することは,【図2】に示される構造から明らか\nであり,熱放散ブリッジを冷却するという機能に鑑みれば,中央スロット4b及び\n4cの部分には後部軸受けにより形成される壁はないものの,冷却流体通路に該当 するといえる。
(ウ) 以上のとおり,本件明細書1に記載された冷却流体通路の技術的意義に鑑 みると,構成要件1Gの冷却流体通路は,熱放散ブリッジの底面により形成される\n長手方向壁が全長にわたって設けられることを必要とする一方,後部軸受けにより 形成される長手方向壁が全長にわたって設けられることは,必ずしも必要ではない と解される。 また,かかる解釈は,冷却流体通路と冷却フィンとの関係とも整合する。すなわ ち,本件明細書1には,「この冷却手段は,通路17内に配置されて,選択された 通路に冷却流体を流す。」(【0054】)との記載があり,かつ,【図2】によ れば,冷却フィンが熱放散ブリッジの底面の半径方向全長にわたって配置され,後 部軸受けが対向しない箇所にも存在していることが読み取れるのであるから,熱放 散ブリッジと中央スロット4b及び4cとが対向する箇所は,冷却フィンが配置さ れる箇所という観点からも,熱放散ブリッジと後部軸受けとが対向する箇所と同様, 通路17の内部といえる。 加えて,仮に,熱放散ブリッジの底面及び後部軸受けの双方が壁をなしている部 分のみが冷却流体通路に該当すると解するならば,冷却流体通路の半径方向外側の 端部は,熱放散ブリッジの外周か後部軸受けの外周のうち軸側の部分となるところ, 【図2】を参照すると,後部軸受けの外周が保護カバー11に到達しておらず,後 部軸受けと保護カバーとの間に隙間が存在することは明らかであるから,冷却流体 通路は保護カバーと連通していないと理解される。しかし,本件明細書1には,「本 発明によれば,保護カバーは,流体通路17と向き合う位置に開口19を有する。 この開口は,通路17の外周と連通している。」(【0049】)として,通路1 7が保護カバーの開口と連通していることが記載されており,前記理解と整合しな い。
ウ 以上のとおり,特許請求の範囲の記載,本件明細書1の記載及び本件発明1 における冷却流体通路の技術的意義を総合すれば,冷却流体通路は,熱放散ブリッ ジの底面が冷却流体通路の全長にわたり長手方向壁を形成していることを要する一 方,後部軸受けにより形成される長手方向壁は冷却流体通路の全長にわたる必要は ないと解される。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.03. 5
平成29(ワ)5074 特許権に基づく差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年1月30日 東京地方裁判所
本件発明に係る特許請求の範囲の記載に加え, 上記(1)の本件明細書の各記載, 特に【課題を解決するための手段】として「該円筒回転体の周面部位には前記 円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面を配設し,」,「前記円 筒回転体に吸い上げられた牌の方向を揃えるため前記吸着面の外側の軌道に 沿って配設した案内部材」「を設け,前記円筒回転体によって下方位置にて取 り上げられた牌は,前記案内部材にそって牌の向きを揃えながら上方に移動す る」(段落【0008】)との記載を勘案すると,本件発明の構成要件I及びK\nは,それぞれ円筒回転体の周面部位に配設された「円筒回転体の一側端から牌 の横幅ほどの幅をもつ吸着面」上で,吸着面からはみ出た牌の部分に「前記吸 着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」を当接させることによって,牌 の向きを揃えるという技術的意義を有するものと認められる(なお,本件明細 書の「図10及び図11を参照して、吸着面401Bに様々な角度にて吸着し た牌10が、整列機構500により縦長方向に整列する動作について説明する。\n案内部材501の入り口付近で吸着面401Bからはみ出た側面が、案内部材 先端502に接触して抵抗を受けるが、牌10に埋設されている磁石11の中 心が、円筒回転体401に埋設されている磁石401Cの中心に吸引されて回 転しながら向きを変え、当該側面が案内部材501の内壁面501Aと並行状 態になって整列機構500の内部に進入する。」との実施例の記載(段落【00\n33】)も上記認定を裏付けるものといえる。)。 そうすると,本件発明の構成要件Iの「円筒回転体の一側端から牌の横幅ほ\nどの幅をもつ吸着面」は,吸着面の幅が,牌の横幅(短辺)と同一か,牌の吸 着面からはみ出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃え ることができる程度に狭くなっていることを意味し,少なくとも牌の縦幅に近 似した幅を有する吸着面はこれに含まれないと解するのが相当である。また, 構成要件Kの「前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」は,吸着\n面の幅が上記のようなものであることを前提として,吸着面からはみ出した牌 の部分に当接して牌の向きを揃えることができる位置に案内部材を配設する ことを意味し,少なくとも吸着面の外側の軌道に近似する線よりも内側に配設 された案内部材はこれに含まれないと解するのが相当である。 そこで,まず,構成要件Iの充足性について検討するに,各被告製品の吸着\n面の幅(円筒回転体の一側端からの幅)が32.6mmであるのに対し,牌の横 幅は24.0mm,牌の縦幅は32.9mmであって(乙4及び当事者間に争い がない事実),各被告製品の吸着面の幅はむしろ牌の縦幅に近似するものと認 められるから,構成要件Iの「円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をも\nつ吸着面」を充足しない。 これに対し,原告は,1)吸着面の幅は牌の横幅より9mmほど長めであるに すぎない,2)本件明細書の段落【0009】の記載からすると,円筒回転体の 幅が牌の縦幅と略等しい場合にも構成要件Iを充足することが強く示唆され ているなどと主張する。 しかしながら,まず,上記1)について,各被告製品は,吸着面の幅が牌の横 幅より9mmも長い一方で牌の縦幅よりわずかに0.3mm短いにすぎないの であるから,円筒回転体の周面部位に配設された「円筒回転体の一側端から牌 の横幅ほどの幅をもつ吸着面」上で,吸着面からはみ出た牌の部分に「前記吸 着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」を当接させることによって,牌 の向きを揃えるという本件発明の技術的意義(上記(2))を発揮させることができ ない。また,上記2)について,被告が指摘する本件明細書の段落【0009】 の記載は,「円筒回転体の幅は牌の縦幅と略等しい寸法でよく」としているに すぎず,吸着面の幅が牌の縦幅とほぼ等しい場合に構成要件Iを充足すること\nの根拠となるものとは認め難い(なお,本件明細書の段落【0021】及び図 7には,円筒回転体の幅が牌の縦幅と略等しい長さ(lL )であるのに対し, 吸着面の幅が牌の横幅分の長さ(ls )である実施例が開示されている。)。し たがって,原告の主張はいずれも採用の限りでない。 次に,構成要件Kの充足性について検討するに,乙2の写真3及び4並びに\n弁論の全趣旨によれば,各被告製品の案内部材は吸着面の外側の軌道から約5. 6mmも内側に配設されていると認められるから,前記(2)に説示したところに よれば,各被告製品は,構成要件Kの「前記吸着面の外側の軌道に沿って配設\nした案内部材」も充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.02. 5
平成29(ネ)10072 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年1月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は,当審の第1回口頭弁論期日において,民事訴訟法297条,1 57条1項に従い,上記均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たる ものとして却下した。その理由は次のとおりである。 すなわち,控訴人は,控訴理由書第2の部分(13〜21頁)において,構\n成要件1D,1F及び2Dに関し,原判決の「送信したとき」の文言解釈は明 らかに誤りであるが,仮に原判決のとおりに解釈したとしても,被控訴人サー バが少なくとも本件各発明と均等なものとして,その技術的範囲に含まれるこ とを予備的に主張するとして,新たに均等侵害の主張を追加した。\nしかしながら,前記のとおり,原審における争点整理の経過に鑑みれば,「送 信したとき」に関するクレーム解釈や被控訴人サーバの内部処理の態様如何に よって構成要件充足,非充足の結論が変わり得ることは,控訴人としても当初\nから当然予想できたというべきであり,そうである以上,控訴人は,原審の争\n点整理段階で予備的にでも均等侵害の主張をするかどうか検討し,必要に応じ\nてその主張を行うことは十分可能\であったといえる(特許権侵害訴訟において 計画審理が実施されている実情を踏まえれば,そのように考えるのが相当であ るし,少なくとも控訴人についてその主張の妨げとなるような客観的事情があ ったとは認められない。)。 ところが,控訴人は,原審の争点整理段階でその主張をせず,また,第4回 弁論準備手続期日(平成29年2月14日)において乙25陳述書が提出され た後も,その内容について特に反論することなく,第5回弁論準備手続期日(同 年3月23日)において「侵害論については他に主張・立証なし」と陳述し, そのまま争点整理手続を終了させたものである。 しかるところ,控訴人が,上記のとおり当審に至り均等侵害の主張を追加す ることは,たとえ第1回口頭弁論期日前であっても,時機に後れていることは 明らかであるし,そのことに関し控訴人に故意又は重大な過失が認められるこ とも明らかといえる。 また,予備的にせよ,均等侵害の主張がされれば,均等の各要件についてそ\nれぞれ主張と反論を整理する必要が生じるのであるから,訴訟の完結を遅延さ せることとなることも明らかである。 したがって,当裁判所は,上記のとおり,当審の第1回口頭弁論期日におい て,かかる均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却 下した次第である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
2018.01.18
平成29(ネ)10027 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所(2部) 東京地方裁判所
引用発明1は,前記ア(イ)のとおり,「毎度の自動売買では自動売買テーブルでの 約定価より真下の安値の買取り及び約定価より真上の高値の売込みが同時に発注さ れるよう設定されたものであって,それにより,先に約定した注文と同種の注文を 含む売込み注文と買取り注文を同時に発注することで,株価が最初の売買価の値段 の範囲から上下に変動する場合に,所定の収益を発生させることに加え,口座の残 高及び持ち株の範囲において,株の現在価を無視して株の値段への変動を一向に予\n測することなく,従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買い取り,買 取り値より株価が上がると所定量を売り込むこと」を特徴とするものである。 このように,引用発明1において,従前の株の買取り値より株価が下落すると所 定量を買い取り,買取り値より株価が上がると所定量を売り込む,という,連続し た買取り又は売込みによる口座の残高又は持ち株の増大をも目的とするものである から,このような設定に係る構成を,約定価と同じ価格の注文を含む注文を発注対\n象に含めるようにし,それを「繰り返し行わせる」設定に変更することは,「約定価 より真下の安値の買取り」及び「約定価より真上の高値の売込み」を同時に発注す ることにより,「従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買取り,買取り 値より株価が上がると所定量を売込む」という,引用発明1の特徴を損なわせるこ とになる。 そうすると,引用発明1を本件発明の構成1Hに係る構\成の如く変更する動機付 けあるといえないから,構成1Hに相当する構\成は,引用発明1から当業者が容易 に想到し得たものとはいえない。
エ 被控訴人の主張について
被控訴人は,本件発明1と引用発明1との相違点は,引用発明1が本件発明1の 構成1Fのうち「前記一の注文価格を一の最高価格として設定し」ていない点であ\nり,その余の点では一致していることを前提に,本件発明1は,引用発明1から容 易想到である,と主張する。 しかし,前記イのとおり,本件発明1と引用発明1とは,引用発明1が本件発明 1の構成1Hの構\成を有していない点について相違している。被控訴人の主張は, その前提を欠き,理由がない。
・・・・
4 なお,被控訴人は,口頭弁論終結後に,本件発明1が無効とされるべきであ ることが明白である事由があるとして,口頭弁論再開を申し立てるが,無効事由の\n根拠となるべき資料は10年以上前に作成されていたものであり,上記無効事由は, 被控訴人が重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であって, これによって訴訟の完結を遅延させることとなるから,却下されるべきものである から,口頭弁論を再開しない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 分割
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2017.12.13
平成29(ワ)393 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月30日 東京地方裁判所(46部)
被告製品の不織布が構成要件Aの「不織布シート」に当たることは当事者\n間に争いがないところ,原告は,その表面にシリカ(SiO2)が付着して\nいるから,構成要件Aの「表\面に吸着・乾燥剤を付着させた」を充足すると 主張する。
(2)本件発明の特許請求の範囲にはいかなる物が「吸着・乾燥剤」に当たるか は記載されていないが,本件明細書(甲2)には,「吸着・乾燥剤としては, 二酸化珪素(SiO2)等の吸水性,吸着性を有する無機粉体を採用するの が好ましい。」と記載されている(段落【0020】)から,吸水性,吸着性 を有するシリカ(SiO2。証拠(乙11)及び弁論の全趣旨によれば, 「シリカ」は二酸化ケイ素の通称であると認められる。)の無機粉体は「吸 着・乾燥剤」に当たり得ると解される。
・・・
イ 上記ア の認定事実によれば,剥離紙を除く被告製品に一定量のシリカ が含まれているということができる。 しかし,前記前提事実(3)のとおり,剥離紙を除く被告製品には不織布以 外の層があるところ,上記ア の計量においては,剥離紙を除く被告製品 全体を試料としているから,不織布の表面以外の部分に含まれるシリカが\n検出された可能性を否定することができない。加えて,同 の試験におい ては,被告製品から剥離紙,粘着剤及び粘着剤のついたフィルムを除いた 試料からシリカが検出されることはなかったこと,同 のとおり被告製品 の不織布層の表面において乾燥剤に該当し得ない物体以外のものが検出さ\nれなかったことにも鑑みると,被告製品の不織布の表面にシリカが付着し\nていると認めることはできない。また,被告製品に一定量のシリカ(Si O2)が含まれているとしても,それが吸収性,吸着性を有するものとし て被告製品に存在することを認めるに足りる証拠もない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2017.12.11
平成29(ネ)10038 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記イを踏まえて,構成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を\n移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」を検討\nすると,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とは,タ ッチパネルを含む入力手段から,画面上におけるポインタの座標位置を移動させる 命令(電気信号)を処理手段が受信することである。そして,利用者がマウスにお ける左ボタンや右ボタンを押す操作に対応する電気信号ではなく,マウスにおける 左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させる操作(ドラッグ操作)に対応 する電気信号を,入力手段から処理手段が受信することを含むものである。また, 本件発明1は,利用者が入力手段を使用してデータ入力を行う際に実行される入力 支援コンピュータプログラムであり,利用者が間違ってマウスの右クリックを押し てしまった場合等に利用者の意に反して画面上に操作コマンドのメニューが表示さ\nれてしまう等の従来技術の課題を踏まえて,システム利用者の入力を支援するため, 利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させる\n手段を提供することを目的とするものである。 そうすると,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」と は,タッチパネルを含む入力手段から,画面上におけるポインタの座標位置を,入 力支援が必要なデータ入力に係る座標位置(例えば,ドラッグ操作を開始する座標 位置)からこれとは異なる座標位置に移動させる操作に対応する電気信号を,処理 手段が受信することを意味すると解するのが相当である。 そして,前記第2の1(3)イのとおり,本件ホームアプリにおいて,控訴人が「操 作メニュー情報」に当たると主張する左右スクロールメニュー表示は,利用者がシ\nョートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであるが,ロ\nングタッチは,ドラッグ操作などとは異なり,画面上におけるポインタの座標位置 を移動させる操作ではないから,入力手段であるタッチパネルからロングタッチに 対応する電気信号を処理手段が受信することは,「入力手段を介してポインタの位置 を移動させる命令を受信する」とはいえない。 したがって,ロングタッチにより左右スクロールメニュー表示が表\示されるとい う本件ホームアプリの構成は,構\成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を 移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」という\n構成を充足するとは認められない。\n
エ 控訴人は,本件ホームアプリでは,タッチパネルに指等が触れると,「ポ インタの座標位置」の値が変化し,「カーソル画像」もこの位置を指し示すように移\n動するところ,ロングタッチは,タッチパネルに指等が触れるといった動作を含む から,被控訴人製品の処理手段はロングタッチにより「『ポインティングデバイスに よって最後に指示された画面上の座標』を移動させる命令」を受信するといえ,本 件ホームアプリは,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」 という構成を有していると主張する。\nしかし,本件ホームアプリにおいて,ロングタッチに含まれるタッチパネルに指 等が触れることに対応して,ポインタの座標位置を,「ポインティングデバイスによ って最後に指示された画面上の座標」位置から,指等がタッチパネルに触れた箇所 の座標位置に移動させることを内容とする電気信号が生じる(甲7の1・2)とし ても,前記ウのとおり,ロングタッチは,画面上におけるポインタの座標位置を移 動させる操作ではないから,上記電気信号は,画面上におけるポインタの座標位置 を移動させる操作に対応する電気信号とはいえない。また,「ポインティングデバイ スによって最後に指示された画面上の座標位置」は,ロングタッチの直前に行って いた別の操作に係るものであり,入力支援が必要なデータ入力に係る座標位置では ないから,上記電気信号は,画面上におけるポインタの座標位置を,入力支援が必 要なデータ入力に係る座標位置からこれとは異なる座標位置に移動させることを内 容とするものでもない。 そうすると,本件ホームアプリのロングタッチ又はこれに含まれるタッチパネル に指等が触れることに対応して,ポインタの座標位置を,「ポインティングデバイス によって最後に指示された画面上の座標」位置から,指等がタッチパネルに触れた 箇所の座標位置に移動させることを内容とする電気信号が生じることをもって,構\n成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とい う構成を充足するとはいえない。\n オ 控訴人は,タッチパネルでは,指等が触れていれば継続的に「ポインタ の位置を移動させる命令」である「ポインタの位置を算出するためのデータ」を受 信し,「ポインタの位置」が一定時間,一定の範囲内に収まっている場合にはロング タッチであると判断されるから,ロングタッチを識別するために入力されるデータ 群には「ポインタの位置を移動させる命令」が含まれると主張する。 しかし,前記第2の1(3)イのとおり,本件ホームアプリは,ロングタッチにより 左右スクロールメニュー表示がされる構\成であるところ,ロングタッチは,継続的 に複数回受信するデータにより算出された「ポインタの位置」が一定の範囲内で移 動している場合だけでなく,当初の「ポインタの位置」から全く移動しない場合を 含むことは明らかであり(甲8),ロングタッチであることを識別するまでの間に「ポ インタの位置」を一定の範囲内で移動させることを内容とする電気信号は,前者に おいては発生しても,後者においては発生しないのであるから,そのような電気信 号をもって,構成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を\n受信する」という構成を充足するとはいえない。\n カ 以上によると,本件ホームアプリが構成要件Eを充足すると認めること\nはできない。
(2) 均等侵害の成否
ア 控訴人は,本件ホームアプリにおける「利用者がタッチパネル上のショ ートカットアイコンを指等でロングタッチする操作を行うことによって操作メニュ ー情報が表示される」という構\成は,「利用者がタッチパネル上の指等の位置を動か して当該ショートカットアイコンを移動させる操作を行うことによって操作メニュ ー情報が表示される」という本件発明1の構\成と均等であると主張する。 そこで検討すると,前記(1)ア及びイによると,本件発明1は,コンピュータシス テムにおけるシステム利用者の入力行為を支援する従来技術である「コンテキスト メニュー」には,マウスの左クリックを行う等するまではずっとメニューが画面に 表示され続けたり,利用者が間違って右クリックを押してしまった場合等は,利用\n者の意に反して画面上に表示されてしまうので不便であるという課題があり,従来\n技術である「ドラッグ&ドロップ」には,例えば,移動させる位置を決めないで徐々 に画面をスクロールさせていくような継続的な動作には適用が困難であるという課 題があったことから,システム利用者の入力を支援するための,コンピュータシス テムにおける簡易かつ便利な入力の手段を提供すること,特に,1)利用者が必要に なった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させ,2)必要である間 についてはコマンドのメニューを表示させ続けられる手段の提供を目的とするもの\nである。 そして,本件発明1は,上記課題を解決するために,本件特許の特許請求の範囲 請求項1の構成,すなわち,本件発明1の構\成としたものであるが,特に,上記1) を達成するために,「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことに よる開始動作命令を受信した後…において」(構成要件D),「入力手段を介してポイ\nンタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示\nする」(同E)という構成を採用し,上記2)を達成するために,「利用者によって当 該押されていた命令ボタンが離されたことによる終了動作命令を受信するまで」(同 D),「操作メニュー情報を…出力手段に表示すること」(同E,F)を「行う」(同\nD)という構成を採用した点に特徴を有するものと認められる。\nそうすると,入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すること によってではなく,タッチパネル上のショートカットアイコンをロングタッチする ことによって操作メニュー情報を表示するという,本件ホームアプリの構\成は,本 件発明1と本質的部分において相違すると認められる。
イ 控訴人は,利用者がドラッグ&ドロップ操作を所望している場合に操作 メニュー情報を表示することが本質的部分であると主張する。\nしかし,前記(1)ア及びイのとおり,マウスが指し示している画面上のポインタ位 置に応じた操作コマンドのメニューを画面上に表示すること自体は,本件発明1以\n前から「コンテキストメニュー」という従来技術として知られていたところ,前記 (2)アのとおり,本件発明1は,この「コンテキストメニュー」がマウスを右クリッ クすることにより上記メニューを表示することに伴う課題を解決することをも目的\nとして,利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表\n示させるために,「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによ る開始動作命令を受信した後…において」(構成要件D),「入力手段を介してポイン\nタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示す\nる」(同E)という構成を採用した点に特徴を有するものと認められる。したがって,\n本件発明1において,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部\n分は,利用者がドラッグ&ドロップ操作といった特定のデータ入力を所望している 場合にその入力を支援するための操作メニュー情報を表示すること自体ではなく,\n従来技術として知られていた操作コマンドのメニューを画面に表示することを,「入\n力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令を受 信した後…において」(構成要件D),「入力手段を介してポインタの位置を移動させ\nる命令を受信する」(同E)ことに基づいて行うことにあるというべきである。 そうすると,入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すること によってではなく,タッチパネル上のショートカットアイコンをロングタッチする ことによって操作メニュー情報を表示するという,本件ホームアプリの構\成は,既 に判示したとおり,本件発明1と本質的部分において相違するというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.12. 7
平成29(ネ)10066 特許権侵害行為の差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 第1要件について
(ア) 控訴人は,本件発明1の本質的部分は,本件各作用効果を奏する上で重要 な部分であるピンの前方部が後方部から斜め前方向に方向づけられ,第2壁面の前 方部に向かって延在している点にあるところ,ピンの前方部7aが第2壁面9の前 方部9aに接触することの有無は,本件各作用効果を奏するための必須の構成では\nないから,ピンの前方部7aが第2壁面9の前方部9aに接触している否かという, 本件発明1と被告製品の相違点は,本件発明1の本質的部分ではなく,被告製品は 均等の第1要件を充足する旨主張する。
(イ) 特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載 のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解\nすべきであり,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明の課題及び 解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従 来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定す\nることによって認定されるべきである。 ・・・のとおり,本件発明1は,従来の固定手段では, ピンが作動可能位置から移動してしまうことで側面開口部を通る出口を見つけられ\nずにスリーブ内部で変形する危険性や,周囲の骨物質に移動するピンの前端部の部 分が有利に曲がった状態へ変形しない危険性があったことを従来技術における課題 とし,これを解決することを目的として,特許請求の範囲請求項1記載の構成,具\n体的には,ピン7の前方部7aが,ピンの後方部7eから第2壁面9に向かって斜 め前方向に延びて湾曲前端部7fに至り,案内面12に近接する第2壁面9の前方 部9aに至るようにすることを定めており,この点は,従来技術には見られない特 有の技術的思想を有する本件発明1の特徴的部分であるといえる。
(エ) 被告製品は,前記2(2)のとおり,構成要件Fの「(前方部(7a)は,)\nピンの後方部(7e)から斜め前方向に方向づけられて前記湾曲前端部(7f)に 至り,前記案内面(12)に近接する前記第2壁面(9)の前方部(9a)まで延 在する」との文言を充足しないから,本件発明1とは,その本質的部分において相 違するものであり,均等の第1要件を充足しない。
(オ) 控訴人の主張について
控訴人は,本件発明1の本質的部分は,本件各作用効果を奏する上で重要な部分 であるピン7の前方部7aが後方部7eから斜め前方向に方向づけられ,第2壁面 9の前方部9aに向かって延在している点にあり,ピン7の前方部7aの第2壁面 9の前方部9aへの接触の有無は本件各作用効果を奏するための必須の構成ではな\nく,上記相違点は本件発明1の本質的部分ではないと主張する。 しかし,本件発明1において,本件各作用効果を奏するのは,ピン7の前方部7 aが,ピンの後方部7eから第2壁面9に向かって斜め前方向に延びて湾曲前端部 7fに至り,案内面12に近接する第2壁面9の前方部9aに至ることで,ピン7 の前方部7aと第2壁面9との間の遊びがなくなり,ピン7の第2壁面に向かう方 向の移動が抑制されることによるものであり,ピン7の前方部7aが前方部9aの 付近に位置しているだけでは,本件各作用効果を奏するものとは認められないこと については,前記2(1)イ(イ)のとおりである。よって,ピン7の前方部7aが第2 壁面9の前方部9aに接触していることは,本件発明1の本質的部分であると解さ れる。したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2017.12. 6
平成28(ワ)7649 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月21日 大阪地方裁判所
「裾絞り部」の形状については,構成要件Gで特定されているとおり「底部に近\nづくに連れて先細りとなる」ものであり,本件明細書において,「裾絞り部」につ き,「垂直に延在するのではなく,裾絞り状に傾斜している」(【0015】)と 説明されている上,構成要件G及びHを含まない出願当初の特許請求の範囲の請求\n項 1 を削除した上記(2)認定の本件特許の出願経過に照らしても,裾絞り部は,それ が直線であっても,曲線であっても,少なくとも,垂直の部分を含むことなく,蛇 腹部から底部にかけて,徐々に先細りになっていくものに限定されていると解され る。
(5) まとめ
したがって,構成要件Gにいう「裾絞り部」とは,胴部において「蛇腹部」と「底\n部」の間にあって,それぞれに接続部で連続して存在するものであり,また「蛇腹 部」との接続部において「垂直に延在」する部分があっても許容されるが,それは 極く限られた幅のものにすぎないのであり,またその形状は,「蛇腹部」方向から 「底部」方向に向けて,徐々に先細りになっているものということになる。
(6) 以上の「裾絞り部」の解釈を踏まえ,被告容器が裾絞り部を備え,構成要件\nGを充足しているかを検討する。
ア 原告は,別紙「被告容器の構成(原告の主張)」記載の図面で「湾曲部」と\n指示した部分が「裾絞り部」に相当し,同部分の存在により構成要件Gを充足する\nと主張し,併せて,その上部にある垂直部分は,本件明細書の【0015】にいう 「接続部」にすぎないとしている。 しかしながら,上記検討したとおり,「裾絞り部」は,「蛇腹部」から接続部で 連続しているものであるが,この接続部は,極く限られた幅の範囲であるべきであ って,上記図面に明らかなように,被告容器における原告主張に係る「裾絞り部」 に相当する湾曲部と蛇腹部の間に存する,湾曲部と高さ方向の幅がほぼ一緒である 垂直に延在する部分をもって「接続部」にすぎないということはできない。 したがって,被告容器は,上記定義した「裾絞り部」で構成されるべき「蛇腹部」\nから「底部」にかけて胴部の大半が,「裾絞り部」に該当しない部分で構成されて\nいるということになるから,被告容器は,「裾絞り部」を備えているものというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2017.11.10
平成28(ワ)35182 特許権 平成29年10月30日 東京地方裁判所(29部)
これを本件について見ると,前記2で詳述したとおり,本件発明は,「その決定 したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」(構成\n要件C)ており,また,「表示部に仮想モールと,基本パーツを組み合わせてなる\n基本キャラクターとを表示させ」(構\成要件F),「基本キャラクターが,前記仮 想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」(構成要件G)構\成を有し ているのに対し(なお,「仮想モール」は,内部に複数の仮想店舗と遊歩のための 空間とが表示されるものをいい,「基本キャラクター」と同時に表\示される必要が あると解すべきこと,「仮想モール中に設けられた店」で「パーツ」を購入する際 にも「基本キャラクター」が表示される必要があると解すべきことも,前記2のと\nおりである。),被告システムは,少なくとも,「キャラクターに応じた情報提供 料」を「通信料」に「加算」する構成を備えていない点,「仮想モール」に対応す\nる構成を有していない点において,それぞれ本件発明と相違するところ,以下のと\nおり,これらの相違部分は,本件発明の本質的部分に当たるというべきであるから, 被告システムは,均等の第1要件(非本質的部分)を満たさない。
イ 本件明細書の前記1(2)アないしエの各記載によれば,本件発明は,携帯端末 の表示部に気に入ったキャラクターを表\示させることができる携帯端末サービスシ ステムに関するものであって(【0001】),あらかじめ携帯端末自体のメモリ ーに保存してある複数のキャラクター画像情報から,気に入ったものを選択して, その携帯端末の表示部に表\示するなどの従来技術では,携帯端末自体のメモリーに 保存できる情報量には限りがあるため,キャラクター選択にあまり選択の幅がなく, ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなく,サービス提供者にとっても,キ\nャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であったことから(【00 02】,【0003】),同問題点を解決し,「ユーザーが十分な満足感を得るこ\nとができ,且つ,サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシス テムを提供する」ため(【0004】),本件特許請求の範囲の請求項1記載の構\n成(構成要件Aないし同Hの構\成)を備えることにより,ユーザーにとっては,キ ャラクター選択をより楽しむことができ,また,サービス提供者にとっては,キャ ラクター画像情報の提供により効率良く利益を得ることができ(【0005】), さらに,ユーザーは,種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作するという ゲーム感覚の遊びをすることができ,十分な満足感を得ることができ,また,「仮\n想モールと,基本キャラクターとが表示された表\示部を見ながら,基本キャラクタ ーを自分に見立て,さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で, その仮想モール内に出店された店に入り,パーツという商品を購入することで,基 本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替えて,楽しむことができ,新た な楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる」(【0006】)というも\nのとされていることが理解できる。 そうすると,本件明細書では,本件発明は,サービス提供者がキャラクター画像 情報により効率良く利益を得るのは困難であったという従来技術の問題点を解決し て,サービス提供者が画像情報の提供により効率良く利益を得ることができる携帯 端末サービスシステムを提供することを目的の一つとするものであって,構成要件\nCの「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段 を備え」るとの構成は,まさに,従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決\n(サービス提供者がキャラクター画像情報により効率良く利益を得ることができる 携帯端末サービスシステムを提供すること)を実現するための,従来技術に見られ ない特有の技術的思想に基づく解決手段(課金手段)としての具体的な構成として\n開示されているものいうべきである。また,本件発明は,ユーザーに十分な満足感\nを与え得るものではなかったという従来技術の問題点を解決して,ユーザーが十分\nな満足感を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供することを他の目的 とするものであって,「表示部に仮想モールと,基本パーツを組み合わせてなる基\n本キャラクターとを表示させ」るとの構\成を含む構成要件F及び「基本キャラクタ\nーが,前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」との構成を含\nむ構成要件Gは,さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で商\n品を購入するなどして十分な満足感を得ることができるという本件発明に特有な作\n用効果に係るものであって,構成要件A,同B,同D及び同Eとともに,まさに,\n従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決(ユーザーが十分な満足感を得る\nことができる携帯端末サービスシステムを提供すること)を実現するための,従来 技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段(ゲーム感覚の実現)として の具体的な構成として開示されているものというべきである。\n他方で,後述する引用例1(乙6)の開示(iモード上に用意された複数のキャ ラクタ画像を受信し,これを待受画面として利用することができる携帯電話機)及 び引用例2(乙7)の開示(画像情報の提供に係る対価の課金を通話料金に含ませ るもの)に照らすと,本件明細書において従来技術が解決できなかった課題として 記載されているところは,客観的に見て不十分であるといい得るが,本件明細書の\n従来技術の記載に加えて,引用例1及び同2の開示を参酌したとしても,本件発明 は,ユーザーが十分な満足感を得ることができ,かつ,サービス提供者が利益を得\nることができる携帯端末サービスシステムを提供するものであり,従来技術では達 成し得なかった技術的課題の解決を実現するための具体的な構成として,構\成要件 AないしHを全て備えた構成を開示するものであるから,これら全てが従来技術に\n見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分に当たるというほかない。\n以上によれば,本件発明と被告システムとの相違部分は,いずれも本件発明の本 質的部分に係るものと認めるのが相当である(なお,上記認定判断は,後述する本 件特許の出願経過とも整合するところである。)。
・・・・
上記アの出願経過に照らせば,原告は,構成要件A,同B,同C及び同Hからな\nる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)及び構成要件A,同B,\n同C,同D,同E及び同Hからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項2に 係る発明)については,特許を受けることを諦め,これらに代えて,構成要件A,\n同B,同C,同D,同E,同F,同G及び同Hからなる発明(出願当初の特許請求 の範囲の請求項1に同2及び同5を統合した発明,すなわち本件発明)に限定して, 特許を受けたものといえる。 そうすると,原告は,構成要件F(「表\示部に仮想モールと,基本パーツを組み 合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」)及び同G(「基本キャラクターが,\n前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」)の全部又は一部を 備えない発明については,本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか,少 なくともそのように解されるような外形的行動をとったものといえる。 したがって,「仮想モール」に対応する構成を有していない被告システムについ\nては,均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり,同システムは,均 等の第5要件(特段の事情)を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2017.10.27
平成28(ネ)10074等 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年10月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審被告製品は,本件発明2の構成要件2Fを充足しないので,その技術的範囲\nに属するとは認められない。その理由は,以下のとおり原判決を補正するほかは, 原判決の第3の3記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決51頁6行目〜52頁6行目を,以下のとおり改める。
「ア 一審原告は,乙1のSIMS分析結果によると,一審被告製品において, 活性層のp型窒化物半導体層側の障壁層B11〜障壁層BLの領域に含まれる複数の 障壁層のSi濃度は,5×1016/cm3未満であると合理的に推認される旨主張する。 そこで,検討すると,乙1のSIMSチャート図では,Si濃度は,n型窒化物 半導体層側からp型窒化物半導体層側に向かって下降し,いったん5×1016/cm3 付近まで落ちた後,p型窒化物半導体層側に向かって上昇していることが観察され る。 この点について,一審原告は,Si濃度の上昇は試料の表面汚染の影響を受けた\nものであり,この表面汚染の影響を除外して考えれば,Siをアンドープにした後,\np側に向けて再びSiをそれよりも高い濃度でドープすることは考えられないから, Si濃度は,5×1016/cm3未満であると考えられると主張する。しかし,一審被告 製品における表面汚染の有無及び程度は明らかでなく,一審被告製品における表\面 汚染について定量的な主張立証がされているわけでもない。また,証拠(甲37, 39,乙44,45)と弁論の全趣旨によると,井戸層にはSiがドープされてい ないから,そのためにSIMSチャートでは障壁層のSi濃度が低く現れることが あること,Si濃度のプロファイルには,ノイズによる「ゆれ」があることが認め られるから,Si濃度がいったん5×1016/cm3付近まで落ちていることから,直ち に,一審被告製品において障壁層のSi濃度が5×1016/cm3を下回っていたと認 めることは困難である。 そうすると,乙1のSIMSチャート図から,p型窒化物半導体層側の障壁層B Lを含む複数の障壁層のSi濃度は,5×1016/cm3未満であると合理的に推認され ると認めることはできない。・・・」
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2017.10.10
平成28(ワ)24175 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年9月21日 東京地方裁判所(46部)
前記1(2)で述べたとおり,本件明細書の記載によれば,従来技術には, 気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ,過飽和の状態を安定に維持して外 部に提供することが難しく,ウォーターサーバー等へ容易に取付けること ができないという課題があった。本件発明1は,このような課題を解決す るために,水に水素を溶解させる気体溶解装置において,水素水を循環さ せるとともに,水素水にかかる圧力を調整することにより,水素を飽和状 態で水素水に溶解させ,その状態を安定的に維持し,水素水から水素を離 脱させずに外部に提供することを目的とするものである。 本件発明1では,水素を飽和状態で水に溶解させ,その状態を安定的に 維持するために,加圧型気体溶解手段で生成された水素水を循環させて, 加圧型気体溶解手段に繰り返し導いて水素を溶解させることとし,「前記 溶存槽に貯留された水素を飽和状態で含む前記水素水を加圧型気体溶解 手段に送出し加圧送水して循環させ」る(構成要件F)という構\成を採用 している。また,気体溶解装置において,気体が飽和状態で溶解した状態 を安定的に維持し,水素水から水素を離脱させずに外部に提供するために は,水素を溶解させた状態の水素水が気体溶解装置の外部に排出されるま での間に,水素水にかかる圧力の調整ができなくなることを避ける必要が ある。このため,本件発明1では「前記溶存槽及び前記取出口を接続する 管状路」(構成要件E)という構\成を採用し,水素を溶解させた水素水が 導かれる溶存槽と水素水を気体溶解装置外に吐出する取出口との間を管 状路で直接接続し,水素水にかかる圧力の調整ができなくなることを避け ているものと解される。 以上のような本件発明1の課題,解決方法及びその効果に照らすと,生 成した水素水を循環させるという構成のほか,管状路が溶存槽と取出口を\n直接接続するという構成も,本件発明1の本質的部分,すなわち従来技術\nに見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分に該当するというべ\nきである。 被告製品は,管状路が溶存槽と取出口を接続するという構成を採用して\nいないことは前記4のとおりであるから,被告製品の構成は,本件発明1\nと本質的部分において相違するものと認められる。
イ これに対し,原告は,本件発明1の本質的部分は,生成された水素水が 大気圧に急峻に戻るのを防ぐため,管状路を加圧状態から大気圧状態まで の圧力変動があり得る構成と構\成の間に接続することであり,被告製品で は,冷水タンクにおいて水素水にかかる圧力が大気圧となるから,カーボ ンフィルタと冷水タンクを細管で接続する構成は本件発明1と本質的部分\nにおいて相違しない旨主張する。 しかし,被告製品のように,溶存槽から取出口までの間に水素水にかか る圧力が大気圧となる構成を設けた場合には,被告製品の取出口から水素\n水が取り出される前に,生成された水素水に対する圧力の調整ができなく なって水素が離脱し得ることになってしまい,「水素水から水素を離脱させ ずに外部に提供する」という効果を奏することができない。したがって, 本件発明1において,溶存槽と大気圧状態までの圧力変動があり得る構成\nの間に管状路を接続することが本質的部分であると解することはできず, 原告の主張は採用することができない。
エ したがって,被告製品は,均等侵害の第一要件を満たさない。
第二要件及び第三要件
ア 原告は,第二要件につき,被告製品と本件発明1とは,管状路を通して 徐々に生成した水素水を大気圧に降圧することにより,水素濃度を維持す る点が共通するから,「管状路に当たる細管が,カーボンフィルタの出口と 気体溶解装置内に設けられた冷水タンクの入口を接続する」という被告製 品の構成を,管状路が溶存槽と取出口を接続するという本件発明1の構\成 に置換することができると主張する。 しかし,前記 で判示したとおり,被告製品の上記構成では,装置の内\n部において水素水にかかる圧力の調整ができなくなり,「水素水から水素を 離脱させずに外部に提供する」という効果を奏することができず,被告製 品の構成と本件発明1の構\成は作用効果が同一であるとはいえない。した がって,被告製品は,均等侵害の第二要件も満たさない。
イ 原告は,第三要件につき,取出口の前に冷水タンクを設け,この冷水タ ンクに管状路を接続することは容易であると主張する。しかし,取出口の 前に大気圧となる冷水タンクを設けることは,「水素水から水素を離脱させ ずに外部に提供する」という本件発明1の課題解決原理に反するものであ るから,当業者としては,本件発明1に被告製品の上記構成を採用するこ\nとの動機付けを欠くものといえる。したがって,被告製品は,均等侵害の 第三要件も満たさない。 以上で述べたとおり,「管状路に当たる細管が,カーボンフィルタの出口と 気体溶解装置内に設けられた冷水タンクの入口を接続する」という被告製品 の構成は,均等侵害の第一要件,第二要件及び第三要件を満たさないから,\n被告製品の上記構成が本件発明1の構\成要件Eと均等であるとは認められ ない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> ピックアップ対象
2017.09.12
平成28(ワ)13239 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月31日 東京地方裁判所(46部)
以上によれば,従来のオルタネータにおいてはブリッジ整流器が備える正 ダイオードを冷却するためにこれを熱放散ブリッジに取り付け,同ブリッジ にスロット(開口部)を設けることでその内部を冷却空気が循環するように し,同ブリッジの上面にフィンを設けることで同ブリッジの冷却を助けるこ ととしていたのに対し,電力用トランジスタ及びかさ高の制御装置を備える ブリッジ整流器があるオルタネータ/スタータにおいては,同ブリッジにス ロットを設けるための空間を確保できない問題に対応するため,同ブリッジ が外側後面に冷却フィンを有する後部軸受けに押し当てられる構成が知られ\nていた。しかし,この構成においては,後部軸受けに熱放散ブリッジ又は基\n部をしっかりと押し当てる必要があり,また,後部軸受けが非常に高温にな ると対流で冷却できなくなるという課題があった。本件発明1は,冷却流体 が機械の後部に横方向に導入され,熱放散ブリッジ及びオルタネータの後部 軸受け間に形成された流体流通路内を循環する目的のために熱放散ブリッジ の後部軸受け側の面を通路の長手方向壁,後部軸受けを上記通路の別の長手 方向壁とし,冷却手段としてフィンを上記通路内に配置する構成を採用した\n点に技術的意義があるということができる。
・・・・
原告は,被告製品のフィンが「前記流体通路(17)内に配置」されて いないという相違点があるとしても,被告製品は本件発明1の構成と均等\nなものとして,本件発明1の技術的範囲に属するというべきであると主張 する。被告製品が本件発明1の構成と均等であるというためには,特許請\n求の範囲に記載された構成中被告製品と異なる部分が特許発明の本質的部\n分でないことが必要である。 イ そこで本件発明1の本質的部分につき検討する。 本件明細書1における背景技術,発明が解決しようとする課題及び課題 を解決するための手段の記載(前記1(2))を参酌すると,前記1(3)のとお り,本件発明1は,熱放散ブリッジにフィンを設け,これに冷却空気を触 れさせて電気部品の冷却を図る構成につき,熱放散ブリッジと後部軸受け\nの間に冷却流体通路を設けて冷却空気を循環させることとし,当該通路内 に冷却フィンを設けるオルタネータ/スタータの構成とすることによって,\n熱放散ブリッジにスロットが設けられない場合であっても十分に熱放散ブ\nリッジを冷却させることができる効果を生じさせることとしたというもの である。このことに照らすと,冷却流体の通路及び冷却フィンの配置につ いて上記構成を採用したことに本件発明1の意義があるということができ\nるから,冷却フィンがどこに配置されるかを含めたその配置は,本件発明 1の本質的要素に含まれると解するのが相当である。 そうすると,被告製品において冷却フィンが冷却流体通路でなく,熱放 散部材の底面であって上側ベアリングの開口部と対応する部分に配置され ている構成は,本件発明1と本質的部分において相違するというべきであ\nる。したがって,被告製品が本件発明1の構成と均等であるということは\nできない。
ウ これに対し,原告は,本件発明1の本質的部分は後部軸受けと熱放散ブ リッジの間に長手方向の,回転シャフトと熱放散ブリッジの間に軸方向の 各冷却流体通路を備えた点にあると主張する。 しかし,上記イのとおり,本件明細書1は熱放散ブリッジにフィンを設 け,これに冷却空気を触れさせて電気部品の冷却を図る構成を従来技術と\nして明示しており,フィンによって熱放散ブリッジと冷却空気が触れる表\n面積を増やし,これによって冷却効果を図る構成を採用することが前提と\nされていること,フィンの配置は冷却効果の程度に影響すると解されるこ とに照らすと,当該配置も本件発明1の意義に含まれるというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> ピックアップ対象
2017.09.12
平成29(ネ)10041 特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明では,近用アイポイントから近用中心までの距離を小さくしているため, 近用アイポイントから近用部にかけて発生する収差が比較的小さく,良好な視覚特 性が得られ,視線を大きく下げることなく中間視から近用視へ移行することができ るとともに,近用部において広い明視域を確保することができる。 また,特定中心を基準とした近用アイポイントでの屈折力増加量(KE−KA)を 加入度(KB−KA)の60%〜90%に設定すると,近用アイポイントから近用部 に至る領域の側方領域における非点収差の集中が軽減され,像の揺れや歪みなどが 抑えられ,近用部及び中間部において広い明視域を実現することができ,さらに, 近用アイポイントから特定視部にかけて加入度の60%〜90%だけ屈折力を低下 させるとの構成により,近用アイポイントから特定視部にかけて視覚特性が改良さ\nれ,主子午線曲線の側方領域における収差集中が緩和される結果,像の揺れや歪み を軽減することができ,広い明視域を確保することができ,また,屈折力の変化の 度合いが比較的小さいため,近用アイポイントと特定視部との接続が連続的で滑ら かになるように構成することができ,特定視部の明視域を大きく確保することがで\nきる(【0018】【0019】)。
(エ) 以上によれば,本件発明は,「近用視矯正領域」と,「特定視距離矯正領 域」と,「近用視矯正領域と特定視距離矯正領域との間において両領域の面屈折力 を連続的に接続する累進領域」とを備えた累進多焦点レンズを前提に,目の調節力 の衰退が大きい人が長い時間にわたって快適に近方視を継続することを目的として, 近用アイポイントから近用中心までの距離を2mmから8mmと設定するとともに, 条件式(1)(2)の条件を満足することを特徴とする累進多焦点レンズを提供し た結果,視線を大きく下げることなく中間視から近用視へ移行することができ,近 用部において広い明視域を確保するとともに,特定視部の明視域を大きく確保する ことを実現したものであるから,本件発明の本質的部分は,近用アイポイントから 近用中心までの距離を2mmから8mmと設定したことと,条件式(1)(2)を 設定したことにあると認められる。 そして,条件式(1)(2)では,「近用視矯正領域の中心での屈折力」である KBと「特定視距離矯正領域の中心での屈折力」であるKAとの差(KB−KA)が用 いられているところ,「特定視距離矯正領域」の範囲を特定できなくては,「特定 視距離矯正領域の中心」が特定できず,その屈折力KA を求めることができない上, 条件式(2)では,前記(2)イのとおり,「特定視距離矯正領域」の範囲を特定する ことができなければ,「特定視距離矯正領域」の明視域の最大幅WFを特定すること ができない。したがって,条件式(1)(2)を満足させるためには,「特定視距 離矯正領域」の範囲を特定できることが必要であるから,「特定視距離矯正領域」 が,屈折力が一定ないしほぼ一定の領域を有する,ある程度広がりを持った領域で あることも,本件発明の技術的思想を構成する特徴的部分であり,本質に係る部分\nである。したがって,控訴人の主張は,採用できない。
(オ) 被告製品は,前記(1)(2)のとおり,いずれも「特定視距離矯正領域」,「特 定視距離矯正領域の中心」を充足せず,条件式(1)(2)を満足させるものでは ないから,本件発明とは,その本質的部分において相違することが明らかであり, 均等の第1条件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)35763 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月27日 東京地方裁判所(47部)
本件明細書の従来技術として上記ウの公知文献は記載されておらず,同記 載は不十分であるため,上記公知文献に記載された発明も踏まえて本件発明\nの本質的部分を検討すべきである。 そして,上記公知文献の内容を検討すると,上記ウ1),2)から,取引明細 情報は,取引ごとにマッチング処理が行われることからすれば,乙4に記載 されたSaaS型汎用会計処理システムにおいても,当該取引明細情報を取 引ごとに識別することは当然のことである。 また,上記ウ3)の「取得明細一覧画面上」の「各明細情報」は,マッチン グ処理済みのデータであるから,「取得明細一覧画面」は「仕訳処理画面」 といえる。 さらに,上記ウ3)の「仕訳情報入力画面」は,従来から知られているデー タ入力のための支援機能の一つに過ぎず(段落【0002】,【0057】),表示され\nた取引一覧画面上で各取引に係る情報を当該画面から直接入力を行うこと及 び該入力の際プルダウンメニューを使用することも普通に行われていること (特開2004-326300号公報(乙5)段落【0066】-【0081】)から すれば,「取引明細一覧画面」に仕訳情報である「相手勘定科目」等を表示\nし変更用のプルダウンメニューを配置することは当業者が適宜設計し得る程 度のことである。 以上によれば,本件発明1,13及び14のうち構成要件1E,13E及\nび14Eを除く部分の構成は,上記公知文献に記載された発明に基づき当業\n者が容易に発明をすることができたものと認められるから,本件発明1,1 3及び14のうち少なくとも構成要件1E,13E及び14Eの構\成は,い ずれも本件発明の進歩性を基礎づける本質的部分であるというべきである。 このことは,上記イの本件特許に係る出願経過からも裏付けられる。 原告は,構成要件1E,13E及び14Eの構\成について均等侵害を主張 していないようにも見えるが,仮に上記各構成要件について均等侵害を主張\nしていると善解しても,これらの構成は本件発明1,13及び14の本質的\n部分に該当するから,上記各構成要件を充足しない被告製品1,2並びに被\n告方法については,均等侵害の第1要件を欠くものというべきである。
・・・
(なお,本件においては,原告から「被告が本件機能につき行った特許出願にか\nかる提出書類一式」を対象文書とする平成29年4月14日付け文書提出命令の 申立てがあったため,当裁判所は,被告に対し上記対象文書の提示を命じた上で,\n特許法105条1項但書所定の「正当な理由」の有無についてインカメラ手続を 行ったところ,上記対象文書には,被告製品及び被告方法が構成要件1C,1E,\n13C,13E,14C又は14Eに相当又は関連する構成を備えていることを\n窺わせる記載はなかったため,秘密としての保護の程度が証拠としての有用性を 上回るから上記「正当な理由」が認められるとして,上記文書提出命令の申立て\nを却下したものである。原告は,上記対象文書には重大な疑義があるなどとして, 口頭弁論再開申立書を提出したが,そのような疑義を窺わせる事情は見当たらな\nいから,当裁判所は,口頭弁論を再開しないこととした。)
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)21346 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月20日 東京地方裁判所(46部)
原告は,上記2)の売りの指値注文が約定した時点が構成要件Eの「検出\nされた前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」\nに該当すると主張し,それによって,高値側の「新たな一の価格」及び 「新たな他の価格」の注文情報群が生成されているとする(原告第3準備 書面17,18頁等)。 そこで,このことを前提として検討すると,被告サービスにおいては, 上記のとおり,上記2)の時点の直後に高値側に買いの成行注文及び売りの 指値注文(上記4)の各注文)の注文情報が生成,発注された。 もっとも,上記4)の各注文のうち,売り注文は指値注文であるが買い注 文は成行注文であるところ,前記(2)のとおり構成要件Eの「注文情報」は\n指値注文に係る注文情報をいい,成行注文に係る注文情報を含まないと解 される。そうすると,4)の買い注文に係る注文情報は,構成要件Eの新た\nな「第一注文情報」に該当しないというべきである。 他方,上記6)の注文はいずれも指値注文であり,これらの注文に係る注 文情報は構成要件Eの「第一注文情報」及び「第二注文情報」に該当し得\nるものといえる。しかし,6)の各注文は,2)の時点の直後に3)の各注文が された後,3)の成行の買い注文の約定価格よりも高値側に価格が変動し, 3)の売りの指値注文が約定した5)の時点の後にされるものである。そうす ると,6)の各注文に係る注文情報は,「検出された前記相場価格の高値側 への変動幅が予め設定された値以上となった」時点である2)の時点におい て,成就の有無が判断できる他の条件の付加なく,また,直ちに生成され たものということはできない。別表1の取引においても,6)の注文は,2) の時点から約35時間50分後にされ,また,その間に5)の売りの指値注 文の約定等がされた後にされている。 そうすると,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定\nされた値以上となった場合」に,上記6)の注文に係る「第一注文情報」及 び「第二注文情報」が「設定」されたということはできない。 ウ 以上によれば,被告サービスは構成要件Eの「検出された前記相場価格\nの高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合,・・・高値側\nに・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設 定」を充足しない。
(6) これに対し,原告は,1)「注文情報」につき,ア)本件発明の特許請求の範 囲上,指値注文か成行注文を区別していない,イ)本件発明の効果に照らすと 注文が指値注文か成行注文かを区別する必要がない,ウ)発明の実施に形態に おける注文に成行注文が含まれる旨の記載がある,以上のことから成行注文 が含まれると解すべきであると,2)「場合」につき上記条件以外の条件を付 加することを排除する趣旨でないと,3)「設定」につき実際に注文情報を生 成するものでなく,情報を生成し得るものとして記録しておけば足りると, 4)被告サービスは指値注文のイフダンオーダーの中に本件発明を構成しない\n買いの成行注文を付加したものにすぎないと各主張する。 しかし,上記1)につき,ア)は,本件明細書において,「注文情報」の語そ れ自体は指値注文と成行注文の区別を明示していない一方で,前記(2)アのと おり,特許請求の範囲の記載全体をみれば,構成要件Eを含む特許請求の範\n囲の記載における「注文情報」は指値注文をいうと解されるのであり,イ)は 背景技術,発明が解決しようとする課題の各記載(前記1(1)ア,イ)の趣旨 を併せて考慮するとむしろ指値注文のイフダンオーダーに関する発明である ことが示唆される。ウ)は,本件明細書の発明の実施の形態の記載(前記1(2)) によれば,当該形態においては成行注文も生成され得る(段落【0031】) 一方で通常の成行注文につきイフダンオーダーの手順(ステップS21〜2 8)を行わないとされている(段落【0101】,【図3】,【図4】)から, 生成された成行注文はイフダンオーダーに関する注文を構成しないことが明\nらかである。そうすると,原告が指摘する上記ア)〜ウ)はいずれも構成要件E\nの「注文情報」に成行注文が含まれると解すべき根拠とならない。 上記2)及び3)については,前記(3)及び(4)において説示したところ 上記4)につき,前記?に説示したとおり,被告サービスにおける買いの成 行注文(注文番号97)は売りの指値注文(同96)と同時に注文されてい るから,当該成行注文がイフダンオーダーの一部を構成していると認められ\nるところ,前記の「注文情報」,「場合」,「設定」の各解釈に加え,本件発明 の意義が指値注文のイフダンオーダーを相場価格の変動にかかわらず自動的 に繰り返し行うことにあることを前提とすれば,イフダンオーダーにおいて 成行注文を介在させる構成は,本件発明において解決すべき課題と異なるこ\nと,成行注文によって直ちに金融商品のポジションを得る効果が得られるこ とにおいて本件発明の構成と異なるものであるから,これを本件発明外の付\n加的構成とみることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)14868 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月12日 東京地方裁判所(40部)
イ ところで,広辞苑第六版(甲9)によれば,「とき」とは,「(連体修飾 語をうけ,接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場 合。」を意味するものであり,また,大辞林第三版(甲10)においても 「(連体修飾句を受けて)仮定的・一般的にある状況を表す。(...する) 場合。」とされており,用字用語新表記辞典(乙22)では「『とき』は条\n件・原因・理由・その他,『場合』よりも小さい条件のときに用いること がある。」,最新法令用語の基礎知識改訂版(乙23)では「『時』は時点 や時刻が特に強調される場合に使われるのに対して,『とき』は一般的な 仮定的条件を表す場合に使われる。」と記載されている。これらからすれ\nば,構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」の「とき」は,条件\nを示すものであると解するのが相当である。
ウ この点に関して原告は,「送信したとき」の「とき」は「同じころ」と いう意義を有するものであり,「ある程度の幅をもった時間」を意味する と主張する。 たしかに,広辞苑第六版及び大辞林第三版には,上記イで指摘した意義 の他に,原告が主張するような意義も掲載されている(甲9,10)。し かし,広辞苑第六版(甲9)には「おり。ころ。」を意味する「とき」の用 例として「ときが解決してくれる」「しあわせなときを過ごす」といった ものが掲載されており,「送信したとき」のような具体的な行為を示す連 体修飾語を受けた用例は記載されていない。また,大辞林第三版(甲10) をみると「ある幅をもって考えられた時間」を意味する「とき」の用例と して,「将軍綱吉のとき」「ときの首相」「ときは春」などというものが 掲載されており,やはり「送信したとき」のような具体的な行為を示す連 体修飾語を受けた用例は記載されていない。 そして,抽象的で,空間的及び時間的に広い概念を表現した上記各用例\nと比べると,「送信したとき」という表現は,その指し示す行為が相当程\n度に具体的かつ直接的であることから,およそ用いられる場面が異なると いうべきである。 また,原告が指摘する審決(甲11)には,「とき」という用語につい て「ある程度の幅を持った時間の概念を意味する」旨の判断がされている が,当該審決は,「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始されるときに, 前記転送手段によって前記判定領域に転送された前記特定表示態様判定用\n数値情報を読み出して判定する」という記載における「前記9個の可変表\n示部の可変表示が開始されるときに」という文言について,「前記9個の\n可変表示部の可変表\示が開始されると『同時』又は『間をおかずに』」と いう意味ではなく,「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始され」た後, 「前記特定表示態様判定用数値情報を読み出して判定する」までの間に他\nの処理がされるとしても,「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始され るときに」に当たると判断したものであって,「前記転送手段によって前 記判定領域に転送された前記特定表示態様判定用数値情報を読み出して判\n定」した後に「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始され」たとしても, 上記文言を充足するなどと判断したものではないから,本件における「送 信したとき」の解釈において参酌することは相当ではない。 そうすると,構成要件1D及び1Fの「送信したとき」における「とき」\nが「ある程度の幅をもった時間」を意味するものということはできない。 また,本件明細書等1をみても,「送信したとき」の「とき」について, 「条件」ではなく「時間」を意味することをうかがわせる記載はない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
エ 以上から,構成要件1D及び1Fの「送信したとき」とは,「送信した\nことを条件として」という意義であると認めることが相当である。
・・・・
以上からすると,被告サーバは,第二のメッセージを受信したことを条件 として「マイミク」であることを記憶し,「マイミク」である旨の記憶をし たことを条件として「第二のメッセージ」を送信するという構成を有してい\nるものであって,第二のメッセージを送信したことを条件として「マイミク」 であることを記憶するという構成を有するものではないと認められる。\nしたがって,被告サーバは,「第二のメッセージを送信したとき」に「上 記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記 憶手段に記憶する手段」を有しているということはできないから,その余の 点について判断するまでもなく,構成要件1D及び1Fを充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成29(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
確かに,本件明細書の段落【0050】には「実施例18」との記載はあ るが,他方で,本件明細書における実施例18(b)に関する記載をみると,「比較 のために,例えば豪州国特許出願第29896/95号(1996年3月7日公開) に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を,以下のように調製した」 (段落【0050】前段)と記載され,また,実施例18の安定性試験の結果を 示すに当たっては,「比較例18の安定性」との表題が付された上で,実施例1\n8(b)については「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」と表現されている\n(段落【0073】)。そして,豪州国特許出願第29896/95号(1996 年3月7日公開)は,乙4発明に対応する豪州国特許であり,同特許は水性オキサ リプラチン組成物に係る発明であって,本件明細書で従来技術として挙げられる もの(段落【0010】)にほかならない。 上記各記載を総合すると,実施例18(b)は,「実施例」という用語が用いら れているものの,その実質は本件発明の実施例ではなく,本件発明と比較するため に,「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」,すなわち,緩衝剤が用いられていな い従来既知の水性オキサリプラチン組成物を調製したものであると認めるのが相当
◆原審はこちらです。平成27(ワ)28467
以下は類似案件です。
◆被告の異なる控訴審事件です。平成28(ネ)10046
こちらは、結論は非侵害で同じですが、1審では技術的範囲に属すると判断されましたので、それが取り消されています。また、控訴審における追加主張は時期に後れた抗弁として、却下されてます。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.07.28
平成29(ネ)10009等 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月12日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明1の構成要件1C(オキサリプラティヌムの水溶液からなり)\nが,オキサリプラティヌムと水のみからなる水溶液であることを意味するの か,オキサリプラティヌムと水からなる水溶液であれば足り,他の添加剤等 の成分が含まれる場合をも包含するのかについては,特許請求の範囲の記載 自体からは,いずれの解釈も可能である。そこで,この点については,本件\n明細書1の記載及び本件特許1の出願経過を参酌して判断することとする。
・・・
前記アの本件明細書1の記載によれば,オキサリプラティヌムは,種々 の型の癌の治療に使用し得る公知の細胞増殖抑制性抗新生物薬であり,本 件発明1は,オキサリプラティヌムの凍結乾燥物と同等な化学的純度及び 治療活性を示すオキサリプラティヌム水溶液を得ることを目的とする発明 である。そして,本件明細書1には,オキサリプラティヌム水溶液におい て,有効成分の濃度とpHを限定された範囲内に特定することと併せて, 「酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まない オキサリプラティヌム水溶液」を用いることにより,本件発明1の目的を 達成できることが記載され,「この製剤は他の成分を含まず,原則とし て,約2%を超える不純物を含んではならない」との記載も認められる。 他方で,本件明細書1には,「該水溶液が,酸性またはアルカリ性薬剤, 緩衝剤もしくはその他の添加剤」を含有する場合に生じる不都合について の記載はなく,実施例においても,添加剤の有無についての具体的条件は 示されておらず,これらの添加剤を入れた比較例についての記載もない。
しかしながら,前記イの出願経過において控訴人が提出した本件意見書 には,本件発明1の目的が,「オキサリプラティヌム水溶液を安定な製剤 で得ること」及び「該製剤のpHが4.5〜6であること」に加えて, 「該水溶液が,酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくはその他の添加 剤を含まないこと」にあること,さらに,水溶液のpHが該溶液に固有の ものであって,オキサリプラティヌムの水溶液の濃度にのみ依存するこ と,オキサリプラティヌムの性質上,本件発明1の構成においてのみ,\n「安定な水溶液」を得られることがわざわざ明記され,これらの記載を受 けて,審査官が拒絶理由通知の根拠とする引用文献1ないし3では,その ような「安定な水溶液」は得られないこと,すなわち,緩衝剤を含む凍結 乾燥物やクエン酸を含む水溶液では,「オキサリプラティヌムの安定な水 溶液」を得ることは困難である旨が具体的に説明されている。 その上で,本件意見書は,本件発明1が特許法29条2項に該当しない との結論を導いて審査官に再考を求めているのであり,その結果として控 訴人は,本件特許1の特許査定を受けているのである。 以上のような本件明細書1の記載及び本件特許1の出願経過を総合的に みれば,本件発明1は,公知の有効成分である「オキサリプラティヌム」 について,直ぐ使用でき,承認された基準に従って許容可能な期間医薬的\nに安定であり,凍結乾燥物を再構成して得られる物と同等の化学的純度及\nび治療活性を示す,オキサリプラティヌム注射液を得ることを課題とし, その解決手段として,オキサリプラティヌムを1〜5mg/mlの範囲の 濃度と4.5〜6の範囲のpHで水に溶解することを示すものであるが, 更に加えて,「該水溶液が,酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくは その他の添加剤を含まない」ことをも同等の解決手段として示すものであ ると認めることができる。 してみると,本件発明1の特許請求の範囲における「オキサリプラティ ヌムの水溶液からなり」(構成要件1C)とは,本件発明1がオキサリプ\nラティヌムと水のみからなる水溶液であって,他の添加剤等の成分を含ま ないものであることを意味すると解するのが相当である。
◆1審はこちらです。
関連事件(同一特許、異被告)です。
◆平成27(ワ)29158
同一特許の別訴事件で、1審(平成27(ワ)12416号)では技術的範囲内と判断されましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.06.30
平成28(ネ)10047 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年10月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ところで,特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と,当該特 許の新規性,進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレ ーム解釈とは整合するのが望ましいところ,確かに,本件特許2に係る審決取消請 求事件の判決(甲12)には,控訴人が指摘するとおり,「本件特許発明2は,ケ ーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクル コネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置 が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される。」旨の記載\nがある(39頁)。しかし,上記判決は,主引用例(本件における乙3)の嵌合過 程について,「…肩部56で形成される溝部49の底面に回転中心突起53が当た り,ここで停止する状態となる。…この状態で相手コネクタ33を回転させるので はなく,回転中心突起53を肩部56に沿って動かすことで,相手コネクタ33を コネクタ31に対してコネクタ突合方向のケーブル44側にずらした状態にして, 相手コネクタ33をコネクタ突合方向に直交する溝部方向に動かすことができない ようにし,その後,回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させている」 (36〜37頁)との認定を前提に,本件特許発明2と乙3発明とを対比するに当 たり,乙3発明には,「回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に 比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」,「回転 中心突起53の上方に肩部56の上面が位置するように,相手コネクタ33が傾斜 している状態で肩部56の前側から後側(ケーブル側)へ回転中心突起53を移動 させているものであって,相手コネクタ33の回転により回転中心突起56の最後 方位置が後方(ケーブル側)へ移動するものではない」(38頁)として,乙3発 明は,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケー ブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位 置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に 位置するものではないという点において,本件特許発明2と相違する。」旨認定し ている(38頁)。上記のように,乙3発明においては,ロック突部の突部後縁の 最後方位置の変化に,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿 勢への回転を伴う姿勢の変化が関係していないこと(「回転によって,回転中心突 起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載され ているとはいえない」こと)に照らせば,本件特許発明2と乙3発明とが相違する ことを認定するについては,本件特許発明2におけるロック突部の突部後縁の最後 方位置の変化が,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢へ の回転を伴う姿勢の変化によって生じるものであれば足り,「回転のみによって」 生じること,言い換えれば,ケーブルコネクタを上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合 終了姿勢へと変化させる際に,姿勢方向を回転させることに伴って生じる「ケーブ ルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一 切あってはならないことを要するものではないというべきである。なお,同一特許 に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は,侵害訴訟における技術的範囲の 確定に対して拘束力を持つものではない。 したがって,控訴人の上記限定解釈に係る主張は,理由がない。
(イ) 控訴人は,被控訴人が,特許の無効を回避するために,自ら,「本件特許 発明2は,「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が,「ケーブルコネクタが上向 き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最 前方位置よりも前方に位置し,また,「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢 にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」 旨構成要件e及びfを限定解釈すべきことを主張しているのであるから,その技術\n的範囲の解釈に際しては,被控訴人の上記主張が前提にされるべきである旨主張す る。 しかし,特許発明の技術的範囲を解釈するについて,相手方の無効主張に対する 反論として述べた当事者の主張は,必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。 そして,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限 定は規定されていないし,前記(1)イ記載の本件特許発明2の課題及び作用効果は, ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にある とき,すなわち,コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は,常にロック溝部の溝部後縁か ら溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏 し得ないというものではない。また,そもそも,本件明細書2には,本件特許発明 2に係る実施例の嵌合動作について,「ロック突部21’の下部傾斜部21’B− 2が,ロック溝部57’の後縁突出部59’Bの位置まで達すると,該後縁突出部 59’Bに対して下部傾斜部21’B−2が該後縁突出部59’Bの下方に向けて 滑動しながらケーブルコネクタ10はその前端が時計方向に回転して水平姿勢とな って嵌合終了の姿勢に至る。」(【0053】)と記載されているように,ケーブ ルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときであっても,嵌合終了姿勢(水平姿勢)に 近づくと,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内 方に突出する突出部の最前方位置よりも後方に位置することが開示されているとい えるから,構成要件eを,「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときは,ロ\nック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する 突出部の最前方位置よりも前方に位置する」ことを規定したものと解釈することは, 誤りである。
・・・・・
ア 控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は,控訴人 が請求した無効審判請求(無効2014−800015)と同一の事実及び同一の 証拠に基づくものであるところ,上記無効審判請求については,請求不成立審決が, 既に確定した(甲8,12)。したがって,控訴人において,本件特許2が,上記 明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として,特許無効審判により 無効にされるべきものと主張することは,紛争の蒸し返しに当たり,訴訟上の信義 則によって,許されない(同法167条,104条の3第1項)。
イ なお,控訴人は,本件特許発明2が「ケーブルコネクタの回転のみによって, すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対 位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構\n成に限定されている」ものと解釈されないとすれば,本件特許発明2は進歩性を欠 く旨主張する。 しかし,本件特許発明2の要旨を上記のように限定的に認定しない場合であって も,乙3発明における嵌合動作は,相手コネクタ33の回転中心突起53をコネク タ31の溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入し,次いで,回転中心突起5 3を肩部56に沿って動かし,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56 のケーブル44側に当接している状態にして,その後,回転中心突起53を中心に 相手コネクタ33を回転させ,嵌合終了姿勢に至るというものであり,本件特許発 明2と乙3発明とは,本件特許発明2では,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブル コネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき, 上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合 終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し」ているのに対し,乙3発明では,コ ネクタ嵌合過程にて相手コネクタ33の前端がもち上がって該相手コネクタ33が 上向き傾斜姿勢にあるときのうち,少なくとも,コネクタ突合方向のケーブル44 側の端までずらした状態で回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させ るとき,回転中心突起の突部後縁の最後方位置が,相手コネクタ33がコネクタ嵌 合終了姿勢にあるときと同一の地点に位置している点,すなわち構成要件eの点で\n相違する。そして,乙3には,乙3発明の上記嵌合動作に関し,回転によって,回 転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術的思想 が記載されているとはいえず(甲12・38頁),また,乙3発明と乙7ないし1 0に記載された各コネクタとでは,その構造や形状が大きく異なるから,乙3発明\nにおいて,上記各コネクタの嵌合過程における突起部と突出部との位置関係を適用 しようとする動機付けがあるということはできないし,仮に適用を試みたとしても, 乙3発明において,上記相違点に係る本件特許発明2の構成を備えることが容易に\n想到できたとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 分割
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成29(ネ)10005 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年6月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件各発明は,メラミン系樹脂発泡体からなる清掃具における「折り畳み可能な\n清掃具の変形能や,清掃対象面の形態に応じて変形可能\な清掃具の柔軟性等」が乏 しいという課題(【0006】)を解決することを目的とするものであり,その効 果は,「捩じり又は絞ったり,或いは,手指の動きに応じて多様な清掃対象物の汚 れを拭き取るといった布雑巾的な用法で使用可能な」ものを提供する(【0011】)\nというものであることからも,本件各発明における圧縮・加熱の工程を経たメラミ ン系樹脂発泡体が,加熱前のメラミン系樹脂発泡体「よりも柔軟な」ものになった ということは,圧縮・加熱前よりも,容易に折り畳みが可能で,清掃対象面の形態\nに応じて変形することができるようになったことを意味するということができる。 よって,本件各発明における「柔軟な」とは,容易に折り畳んだり,変形させた りできることを意味するものと認めることが相当である。
・・・
圧縮前後のメラミン系樹脂発泡体のサンプル平均を比較すると,甲45試験では, 圧縮前後の荷重の差は2.3Nであり,圧縮後のメラミン系樹脂発泡体の方が圧縮 前のものよりも,約5分の1の力で10mmたわんだとの結果になっている。しか しながら,乙11試験では,メラミン系樹脂発泡体の10mmたわみ時の荷重の圧 縮前後の差は0.06Nで,圧縮後の方がより弱い力でたわんだとの結果になって いるものの,約15%弱い力にすぎず,乙34試験では,その差は0.03Nとさ らに小さく,圧縮後の方が約5%弱い力でたわんだとの結果にとどまる。甲45試 験と,乙11試験,乙34試験の試験結果は,同一の試験機関によるものであると ころ,各試験で用いられた試料の圧縮の程度に差があることを考慮したとしても, 大きく異なるといわざるを得ないが,甲45,乙11,乙34の各報告書中には, これら試験結果に大きな差が生じ得たと考えられるような条件の記載はない。 圧縮後のメラミン系樹脂発泡体における10mmたわみ時荷重の平均値は,甲4 5試験において0.60N,乙11試験において0.41N,乙34試験において 0.62Nで,特に,甲45試験と乙34試験の数値は極めて近い。ところが,圧 縮前のものについての同数値は,乙11試験では0.47N,乙34試験では0. 65Nなのに対し,甲45試験では,2.90Nとされており,乙11,乙34の 各試験結果とは2.0N以上,約4倍の差となっているのであって,圧縮の条件等 による差が考えられない圧縮前の数値についてのみ,このような顕著な差があるこ とについて,合理的に理解することは困難といわざるを得ない。乙34報告書によ れば,厚さ40mmのメラミン系樹脂発泡体を10mmに圧縮したものについての 10mmたわみ時荷重は平均2.8N(サンプル数5)で,甲45試験と極めて近 接した数値となっていることも勘案すると,甲45試験の結果をもって,圧縮後の 方が「柔軟」になったと認定することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.06. 2
平成25(ワ)10958 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年5月17日 東京地方裁判所(40部)
本件訂正発明1の1及び1の2の意義
上記各記載によれば,本件訂正発明1の1及び1の2は,基礎杭等の造 成にあたって地盤を掘削する掘削装置に関するものであって,この種の掘 削装置として一般に使用されるアースオーガ装置では,オーガマシンの駆 動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必要となるが,リーダの長 さが長くなると,施工現場内でのリーダの移動作業や,現場へのリーダの 搬入及び現場からの搬出作業に非常な手間と時間を要するという課題及び 傾斜地での地盤掘削にあっては,クローラクレーンの接地面とリーダの接 地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長くとれず,掘削深さが制限 されるという課題があることから,本件訂正発明1の1及び1の2は,こ れらの課題を解決するために,掘削装置について,掘削すべき地盤上の所 定箇所に水平に設置し,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが, 当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケ ーシング回り止め部材を備えるものとして,リーダではなく,ケーシング 回り止め部材によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明 である,と認められる。
・・・・
原告は,本件訂正発明1の1の実施による被告の利益を算定するに当 たっては,本件発訂正明1の1を実施した工程の代金のみならず,請負 代金額の全額を基礎とすべきと主張する。 しかし,本件訂正発明1の1は,掘削装置に関する発明であり,掘削 工事以外の工程には使用されない。そして,前記「内訳明細書」(乙1 05)によれば,被告は,現場(1)について,本件訂正発明1の1を実施 した掘削工事である「先行削孔砂置換工」のみを受注したものではなく, 「道路改良工事」を受注し,上記掘削工事の他,本件訂正発明1の1を 実施していない工事である「場所打杭工」,「鋼矢板工」及び「桟橋盛 替工」の各工事を行っており,これらの工事の代金(直接工事費)につ いては,本件訂正発明1の1を実施していないのであるから,本件訂正 発明1の1の実施があったためにその余の工事の受注ができたなどの特 段の事情がない限り,本件訂正発明1の1を実施したことにより被告が 受けた利益に当たるということはできない。そして,本件において,上 記事情を認めるに足りる証拠はない。
また,被告は,現場(1)の工事について,上記直接工事費のほかに,間 接工事費として「重機組解回送費」,「重機回送費」及び「経費」の支 払を受けているが,これらについても本件訂正発明1の1の実施により 受けた利益に当たると認めるべき証拠がない。 したがって,被告が,本件訂正発明1の1を実施したことにより受領 した額は,本件訂正発明1の1の実施による先行削孔砂置換工(DH削 孔費)の14本分の代金140万円である。
イ 利益率
被告の利益率が18%であることについて当事者間に争いがない。 したがって,本件訂正発明1の1を実施したことにより被告が得た利益 額は,25万2000円(=140万円×0.18)である。
ウ 寄与率
被告は,本件訂正発明1の1の売上に対する寄与率は低いなどと主張す るので検討するに,特許法102条2項は,損害が発生している場合でも, その損害額を立証することが極めて困難であることに鑑みて定められた推 定規定であるから,当該特許権の対象製品に占める技術的価値,市場にお ける競合品・代替品の存在,被疑侵害者の営業努力,被疑侵害品の付加的 性能の存在,特許権者の特許実施品と被疑侵害品との市場の非同一性など\nに関し,その推定を覆滅させる事由が立証された場合には,それらの事情 に応じた一定の割合(寄与率)を乗じて損害額を算定することができると いうべきである。
本件では,たしかに,前記アのとおり,現場(1)において,15本のうち 1本のケーシングについては,本件訂正発明1の1を実施しない形態(下 部/1本のH形鋼)が用いられていることが認められるものの,これは, 被告の主張によれば,山(崖)側に位置するケーシングでは,下部で井桁 状を組むことが困難であることから「下部/2本のH形鋼」ではなく「下 部/1本のH形鋼」の構成が用いられているというのであって,「下部2本のH形鋼」の構\成により,「下部/1本のH形鋼」の構\成と同等ない\nしより優れた効果が得られるためではない。また,上記イで算出した利益 の額は,本件訂正発明1の1の技術的範囲に属する被告装置1を用いて行 った工事である先行削孔砂置換工(DH削孔費)により被告が得た利益額 そのものであり,それ以外の工事による利益の額は含まれていない。 さらに,被告は,各杭の「掘削長×掘削基本時間」の単価計算から求め られたものに(「掘削時間」/〔「掘削時間」+「準備時間」+「排土埋 戻し時間」〕)を乗じたものが,掘削に対しての時間の割り出し単価とな るなどと主張しており,工事費用について時間当たりの単価を算出して, 現実に掘削に要した時間に相当する分についてのみ本件訂正発明1の1が 寄与しているかのような主張をしているが,被告が「先行削孔砂置換工」 のうちの掘削作業のみを受注しているものではなく,また,一般に掘削作 業のみを受注する形態が考えにくいこと,掘削作業が「先行削孔砂置換工」 の重要部分を占めると考えられること,発注者は準備時間や排土埋戻しの ために被告に工事を発注しているものでなく,準備や排土埋戻しの作業が 利益をあげているとはいえないことなどからすると,被告の上記主張は採 用することができない。 そうすると,代替技術の存在を考慮に入れたとしても,上記額が原告の 損害であるという推定を覆滅させるに足りる証拠がないというほかないか ら,被告の寄与率に係る主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2017.05.25
平成28(ネ)10096 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年5月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 均等の第1要件における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であり,\n上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明の課題 及び解決手段(特許法36条4項,特許法施行規則24条の2参照)とその効果(目 的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項\n参照)を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見ら れない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによっ\nて認定されるべきである。ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題とし て記載されているところが,出願時(又は優先権主張日)の従来技術に照らして客 観的に見て不十分な場合には,明細書に記載されていない従来技術も参酌して,当\n該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定\nされるべきである。
イ 本件明細書によれば,本件発明は,従来技術では経路探索の終了時にいくつ かの経由地を既に通過した場合であっても,最初に通過すべき経由予定地点を目標\n経由地点としてメッセージが出力されること(【0008】)を課題とし,このよ うな事態を解決するために,通過すべき経由予定地点の設定中に既に経由予\定地点 のいずれかを通過した場合でも,正しい経路誘導を行えるようなナビゲーション装 置及び方法を提供することを目的とし(【0011】),具体的には,車両が動く ことにより,探索開始地点と誘導開始地点のずれが生じ,車両が,設定された経路 上にあるものの,経由予定地点を超えた地点にある場合に,正しく次の経由予\定地 点を表示する方法を提供するものである(【0018】【0038】)。また,前\n記2(1)エ(ア)のとおり,本件特許出願当時において,ナビゲーション装置が,距離 センサー,方位センサー及びGPSなどを使って現在位置を検出し,それを電子地 図データに含まれるリンクに対してマップマッチングさせ,出発地点に最も近い ノード又はリンクを始点とし,目的地に最も近いノード又はリンクを終点とし,ダ イクストラ法等を用いて経路を探索し,得られた経路に基づいて,マップマッチン グによって特定されたリンク上の現在地から目的地まで経路誘導するものであった ことは,技術常識であったと認められる。 このように,本件発明は,上記技術常識に基づく経路誘導において,車両が動く ことにより探索開始地点と誘導開始地点の「ずれ」が生じ,車両等が経由予定地点\nを通過してしまうことを従来技術における課題とし,これを解決することを目的と して,上記「ずれ」の有無を判断するために,探索開始地点と誘導開始地点とを比 較して両地点の異同を判断し,探索開始地点と誘導開始地点とが異なる場合には, 誘導開始地点から誘導を開始することを定めており,この点は,従来技術には見ら れない特有の技術的思想を有する本件発明の特徴的部分であるといえる。 したがって,探索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点の異同を判断する 構成を有しない被控訴人装置が本件発明と本質的部分を異にすることは明らかであ\nる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
>> ピックアップ対象
2017.04.27
平成26(ワ)34678 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年4月21日 東京地方裁判所(40部)
上記各記載によれば,本件発明の意義は,次のとおりであると認められる。 従前,シリンダボア内に冷媒を導入するためにロータリバルブが採用され たピストン式圧縮機においては,吐出行程にあるシリンダボア内の冷媒がこ のシリンダボアに連通する吸入通路からロータリバルブの外周面に沿ってシ リンダボア外に漏れやすいという課題があり,このような課題はバルブ収容 室の内周面とロータリバルブの外周面との間のクリアランスを極力小さくす ることにより解決されるものの,他方で,このクリアランス管理は非常に難 しいという課題があった。 そこで,本件発明は,吐出行程にあるシリンダボアに連通する吸入通路の 入口に向けてロータリバルブを「付勢」し,ロータリバルブの外周面を吸入 通路の入口に近づけるという構成を採用することによって,圧縮室内の冷媒\nを吸入通路から漏れ難くし,よって体積効率を向上させるという作用効果を 有するものである。
・・・・
まず,被告は,本件特許の出願過程における乙26意見書に「引用文 献1〔判決注:乙21公報〕に記載された発明とは,従来からのニード ルベアリングのような転がり軸受ではなく,ジャーナル軸受を採用する ことによって,回転軸側のジャーナル部とシリンダブロック側の滑り軸 受との間のクリアランスを極めて小さくし,その結果,ロータリバルブ からの冷媒漏れを抑制するというものです。あくまでも,ジャーナル部 と滑り軸受との間のクリアランス管理に基づいて冷媒漏れの抑制を実現 しているのであって,本願発明のように,ピストンに対する圧縮反力を ロータリバルブへの付勢力に変換し,ロータリバルブの外周面を直接, 吸入通路の入口に付勢することによって冷媒漏れを抑制する技術とは明 確に異なるのです。」と記載されていることを根拠に,原告が本件発明 の技術的範囲から「クリアランスが小さい場合」を意識的に除外してい ると主張する。 しかし,乙26意見書の上記部分は,その記載内容からも明らかなと おり,乙21発明の「ジャーナル軸受を採用することによって,回転軸 側のジャーナル部とシリンダブロック側の滑り軸受との間のクリアラン スを極めて小さし,その結果」冷媒漏れを抑制する技術と,本件発明の 「ピストンに対する圧縮反力をロータリバルブへの付勢力に変換し,ロ ータリバルブの外周面を直接,吸入通路の入口に付勢することによって」 冷媒漏れを抑制する技術とが相違することを述べたものにすぎず,「ク リアランスが小さい場合」を本件発明の技術的範囲から除外したものと 解することはできない。このことは,乙26意見書の上記部分の直前に 「引用文献1〔判決注:乙21公報〕に記載された発明は・・・ジャー ナル軸受をもってロータリバルブを支持する点に特徴があります。」と 記載され,さらに,乙21公報の「回転軸を支持する軸受がジャーナル 軸受であり,それが単にシリンダブロック内に設けられた滑り軸受と, 回転軸の一部であるジャーナル部によって構成される簡単な構\造である だけでなく,そのジャーナル軸受の構成部材自体に半径方向の吸入通路\nや吸入ポートを形成して,各シリンダに対して圧縮すべき流体を吸入さ せるための吸入弁を構成しているため,軸受構\造と吸入弁の構造が簡単\nになるだけでなく,滑り軸受の円筒内面の仕上げ加工が容易に行われて, ジャーナル部とのクリアランスをきわめて小さくすることが可能になり,\n圧縮された流体が吸入弁から漏洩することがない。」との記載が引用さ れていることからも明らかである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.04.24
平成28(ワ)20818 特許権侵害差止請求事件 特許権 平成29年4月19日 東京地方裁判所(29部)
被告らは,仮に,構成要件1Gの「切り残し突起(16)」が,本件明細書等の【図8】(b)に示す形態に限られず,例えば下図(平成23年6月27日付\nけ意見書〔乙19〕の参考図1)の符号16のような形態のものまでも含むという のであれば,かかる形態は,発明の詳細な説明に記載されたものでも示唆されたも のでもないから,本件発明1(並びに本件発明1の構成要件を発明特定事項として引用する本件発明2及び同3)についての特許は,発明の詳細な説明に記載されて\nいない発明についてされたものとして,サポート要件違反の無効理由があると主張 する。
イ 特許請求の範囲の記載が,発明の詳細な説明に記載したもの(特許法36条 6項1号)といえるか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と を対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発 明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識 できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時 の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきものである(知財高裁平成17年(行ケ)第10042 号同年11月11日特別部判決参照)。
ウ 本件特許の特許請求の範囲の請求項1には,前記前提事実(2)のとおり,連続 貝係止具において,「隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可 撓性連結材(13)で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連 結材(13)と一体に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止 め突起(3)よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)\nの夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心 よりも夫々のロープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13) を切断すると,その切り残し突起(16)が2本のロープ止め突起(3)の内側に 残るようにした」旨が記載されている。
エ 本件明細書等の発明の詳細な説明には,次の記載がある(末尾の【】は,段 落番号を示す。)。 「本発明の連続貝係止具は,隣接する貝係止具11の2本のロープ止め突起3間 が2本の可撓性連結材13で連結され,2本の可撓性連結材13は貝係止具11が 差し込まれる縦ロープCの直径よりも広い間隔で2本のロープ止め突起3寄り箇所 を連結するので,貝係止具11を一本ずつ切断するときに可撓性連結材13の一部 が図8(b)のように切り残し突起16となって基材1に残って基材1から突出し ても,図8(a)のように貝係止具11を縦ロープCへ差し込むときに切り残し突 起16が邪魔にならず,縦ロープCが2本のロープ止め突起3間におさまり安定す る。又,貝係止具11を手で持って貝へ差し込むときに手(指)が切り残し突起1 6に当たらないため手が損傷したり,薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をしても 手袋が破れたりしにくい。」【0008】 「(連続貝係止具の実施形態1)本発明の連続貝係止具は図8(a)のように前 記実施形態の貝係止具11を間隔をあけて数千〜数万本平行に配置し,上下に隣接 する貝係止具11の基材1間を丸紐状の可撓性連結材13で連結して樹脂成型して 図12(a)(b)のようにロール状に巻くことができるようにしたものである。 図8(a)の場合はハ字状の2本のロープ止め突起3の間を2本の可撓性連結材1 3で連結してあり,しかも,2本の可撓性連結材13をロープ止め突起3寄り箇所 に配置して,2本の可撓性連結材13の間隔を縦ロープCの直径よりも広くしてあ る。このようにすると貝係止具11を一本ずつ切断する場合に可撓性連結材13の 一部が切り残されて図8(b)のように基材1に切り残し突起16が発生しても, それが縦ロープCへの差込時に邪魔になることがない。また,一本ずつ切断された 貝係止具11を貝の孔に差し込むために手で持っても切り残し突起16の部分が手 に当たらないため手が怪我したり,手に嵌めた作業用手袋が破れたりしにくい。」 【0026】
オ 上記に認定したところによれば,本件明細書等の発明の詳細な説明には,2 本の可撓性連結材による連結箇所を,2本のロープ止め突起の間で,かつ,2本の ロープ止め突起寄りの箇所とする構成により,可撓性連結材を切断したときに切り残し突起が残ったとしても,貝係止具を縦ロープへ差し込むときに切り残し突起が\n邪魔にならず,また,貝係止具を手で持って貝へ差し込むときに手(指)が切り残 し突起に当たらないため手が損傷したり,薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をし ても手袋が破れたりしにくいとの作用効果を奏することが明確に記載されている。 そうすると,本件明細書等の発明の詳細な説明に接した当業者において,本件発 明1に係る特許請求の範囲に記載された構成,すなわち,2本の可撓性連結材(13)による連結箇所を,2本のロープ止め突起(3)のそれぞれから内側に離れた\n箇所であり,かつ,2本のロープ止め突起(3)間の中心よりもそれぞれのロープ 止め突起(3)寄りの箇所とする構成を採用することにより,可撓性連結材(13)を切断した際の切り残し突起(16)の高さにかかわらず,本件発明1に係る課題\nを解決できると認識できることは明らかであるから,本件発明1が,発明の詳細な 説明に記載されていないものということはできない。同様の理由により,本件発明 2及び同3が,発明の詳細な説明に記載されていないものということはできない。 したがって,被告らの主張する無効理由2は認められない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2017.03.24
平成28(受)1242 特許権侵害行為差止請求事件 平成29年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所
出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構\成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,特許出 願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,対象製品等が特許請求の範囲から除 外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人におい て,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるよう な行動をとったものとはいい難い。また,上記のように容易に想到することができ た構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,特許権侵害訴訟において,対象製品等と特許請求の範囲に記載された構\成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとする と,先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられる\nことと等しくなる一方,明細書の開示を受ける第三者においては,特許請求の範囲 に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるこ\nととなり,相当とはいえない。 そうすると,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構\成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それ だけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識 的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきで ある。
(2) もっとも,上記(1)の場合であっても,出願人が,特許出願時に,その特許 に係る特許発明について,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,特許請求の範囲に記載された構\成を対象製品等に係る構成と置き換\nえることができるものであることを明細書等に記載するなど,客観的,外形的にみ て,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構\成を代替すると認識し ながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,明細書の開示を受ける第三者も,その表\示に基づき,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから,当該出願人において,対象 製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動を とったものということができる。また,以上のようなときに上記特段の事情が存す るものとすることは,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もっ て産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない,出願人と第三者の利害を適 切に調整するものであって,相当なものというべきである。 したがって,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構\成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観 的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構\成を代 替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲か\nら意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。
そして,前記事実関係等に照らすと,被上告人が,本件特許の特許出願時に,本 件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき,客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構\成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表\示していたという事情があるとはうかがわれない。
6 原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は 採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2017.03.14
平成26(ワ)8922 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年2月17日 東京地方裁判所
甲4書簡には,原告製品について「本製品は添付の弊社保有特許(特許第 4444410号,発明の名称:歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケ ット用ツール)の請求項1に関連するものと思料しております。」と記載さ れているところ,本件発明に係る特許に「関連する」という文言は,本件発 明の技術的範囲に属する可能性があることを指摘するものと理解するのが素\n直である。そして,被告の常務取締役であるAが,バイオデントに送付した 甲23メールには,本件発明に係る特許について「使用許諾をすべきでない との意見が大勢を占めました。」と記載されており,被告がバイオデントに 対し,本件発明に係る特許の実施許諾をする意思がないことが明らかにされ ている。これらの事実を考慮すると,被告は,バイオデントに対し,原告製 品が本件発明の技術的範囲に属しているという事実及び被告が本件発明に係 る特許について実施許諾をする意思がないという事実を通知したということ ができる。そして,特許権は独占的排他的権利であり,特許権者において実 施許諾をする意思がない場合には,当該特許を業として実施している者は実 施行為を中止するほかないところ,実際にバイオデントは原告製品の販売を 中止しているから,バイオデントも,本件各告知は原告製品の輸入及び販売 の中止を求めるものと認識していたものと認められることからすれば,甲4 書簡による本件告知1の意義がやや不明瞭であるとしても,甲23メールに よる本件告知2を併せてみれば,本件各告知は,被告が,バイオデントに対 し,本件特許権侵害を理由として本件発明の実施行為である原告製品の輸入 及び販売の中止を求める侵害警告に当たると認めるのが相当である。 そして,被告の上記侵害警告は,バイオデントが原告から輸入して販売す る原告製品が特許侵害品である旨の告知であるから,原告の営業上の信用を 害する事実の告知であると認められる。 ところで,本件発明に係る特許については,冒認出願であることを理由と して,これを無効とすべき旨の審決が確定しており,同特許権は初めから存 在しなかったものとみなされるので(特許法125条),バイオデントによ る原告製品の輸入及び販売は,被告の特許権を侵害しないし,また,被告は 特許権に基づいて権利行使することはできない。 したがって,被告のバイオデントに対する本件各告知は,本件発明に係る 特許が存在しないにもかかわらず,原告製品の輸入及び販売がその特許権を 侵害するという事実を告知したものであって,虚偽の事実の告知に当たると 認めるのが相当である。
・・・・
被告は,権利侵害を疑われる行為を行う本人に対して権利侵害の事実を申\n述する行為は,不競法2条1項14号の不正競争行為に当たらないと主張す る。 しかし,バイオデントは権利侵害を疑われる行為を行う本人ではあるもの の,バイオデントに対し,本件各告知がされることにより,バイオデントで はなく,原告製品の製造元である原告の営業上の信用が害されるのであるか ら,上記告知は,「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知」に当た るというべきである。この点に関して被告は,バイオデントは原告と同一視 されるべき地位にあるなどとも主張するが,これを認めるに足りる証拠は ない。 また,被告は,本件各告知は正当な権利行使であり違法性が阻却されると も主張するが,上記(2)で説示したとおり,被告のバイオデントに対する本件 各告知行為には,登録された権利に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法が あるというべきであるから,本件各告知は,正当な権利行使には当たらない というほかない。したがって,被告の上記主張はいずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2017.03.10
平成26(ワ)8134 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月27日 東京地方裁判所
なお,原告は,本件明細書において,構成要件Aにいう「特定視距離矯正領\n域」は「近景よりも実質的に離れた特定距離に対応する面屈折力を有する」領域 (請求項1,【0016】)と定義されている旨主張するが,正確には,請求項1 や段落【0016】においても,「近景よりも実質的に離れた特定距離に対応する 面屈折力を有する特定視距離矯正領域」と表現されているのであって,「矯正」\n「領域」という語句が存する以上,これらの語句による意味の限定が加わり得るこ とは否定できない(すなわち,請求項1や発明の詳細な説明では,「領域A」とか 「第1領域」などといった記号的な用語を使っておらず,「矯正領域」という用語 を選択しているのであるから,その日本語の持つ意味合いをはなから無視すること はできない。)。そして,「矯正領域」という字義のほか,前記(ア)ないし(ウ)で説 示したところに照らすと,上記の「…対応する面屈折力を有する」という部分も, 眼鏡レンズ内の当該領域を視線が通過する場合に特定距離にある対象物が良く見え るような視力矯正を可能とする程度に当該領域内で一定ないしほぼ一定の面屈折力\nを有するという意味であると解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.03.10
平成28(ネ)10061 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件各発明の構成要件D1及びD2は,「出力画像データに対し中間的な周波数成\n分のみを分離するバンドパスフィルタリングを行なうことによって,同出力画像デ ータから高周波成分及び低周波成分を除いたバンドパスデータ」と規定するもので あるから,「バンドパスデータ」には低周波成分は実質的に含まれてはいない。そし て,構成要件Eは,補正データ生成手段が,この「バンドパスデータ」に「対応し\nた画像補正テーブル」を出力するものであるが,この「対応」というものが,いか なる技術的意義を有するものかは,特許請求の範囲の記載のみからでは明らかでは ない。 そこで,検討するに,本件各発明の解決課題・作用効果は,前記1(2)(4)(5)エのと おりであって,補正データに低周波成分に対する補正を加えようとすることによっ て生じる画面中心部の輝度の低下を防止することである。また,本件各発明の実施 形態をみてみると,バンドパスフィルタリングにより低周波成分及び高周波成分を 除いたバンドパスデータを算出し,このバンドパスデータを「反転させた」画像補 正テーブルを生成し(本件明細書1の【0033】,本件明細書2の【0032】), 補正された画像を表示する際は,画像補正テーブルから得た補正データを,入力さ\nれた画像信号に加算している(本件明細書1の【0037】,本件明細書2の【00 36】)。この実施形態は,緩やかな表示むら(出力画像データの低周波成分)や細\nかい表示むら(出力画像データの高周波成分)はそのままとし(本件明細書1の【0\n012】,本件明細書2の【0012】参照),中間的な周波数成分のみを目標とし て,これを消去するとの技術思想に基づくものといえる。そして,本件各明細書に は,これ以外の実施態様の記載はない。そうすると,構成要件Eの「バンドパスデ\nータに対応した画像補正テーブル」は,バンドパスデータを打ち消す作用を持つよ うな画像補正テーブルをいうものと解される。なお,本件各明細書には,「表示むら\nは,各ピクセルの明るさが理想値と異なるために発生するので,あらかじめ各ピク セルの理想値とのズレを測定しておけば,そのズレに従って各ピクセルへの入力画 像値を補正することで,表示むらをキャンセルすることが可能\である。」(本件明細 書1の【0038】,本件明細書2の【0037】)との記載があるが,本件各明細 書には,このための具体的な構成が記載も示唆もされておらず,この記載が目標値\nを定めて補正を行うような画像補正方法を開示するとはいい難く,このような実施 形態が本件各発明に含まれるとは認められない。 以上からすると,本件各発明において,補正前のデータである出力画像データに は,その定義より低周波成分,中間的な周波数成分又は高周波成分が含まれている ところ,バンドパスデータには中間的な周波数成分のみが含まれ,その中間的な周 波数成分は補正後の画像では消去されるから,補正後の画像には,補正前のままの 低周波成分又は高周波成分のみが残ることになる。そうすると,補正前後の画像の 差分をとると,中間的な成分のみが残るはずであって,この差分に低周波成分は実 質的には存在しないことになる。 すなわち,補正前後の画像の差分の中に低周波成分が含まれるシステムは,まず, 低周波成分を分離していないことにより構成要件D1 及びD2を充足しないものと 考えられ,仮に,そのように言い切れないとしても,「バンドパスデータに対応した 画像補正テーブル」を有しないことによって構成要件Eを充足しないものであり,\nいずれにしても,本件各発明の技術的範囲に属しないこととなる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2017.03. 8
平成29(ワ)13033 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月23日 東京地方裁判所
文言侵害の成否
ア 構成要件Eは,本件発明1の特許請求の範囲の記載によれば,処理手段\nが入力手段を介して「ポインタの位置を移動させる命令」を受信すると操 作メニュー情報を表示するものである。この「ポインタの位置を移動させ\nる命令」につき,本件明細書(甲2)には,1)「入力手段を介してポイン タの位置を移動させる命令を受信する」とは,入力手段としてのポインテ ィングデバイスから,画面上におけるポインタの座標位置を移動させる電 気信号を処理手段が受信することである(課題を解決するための手段,段 落【0020】),2)命令ボタンを押し続けたままで出力手段としてのデ ィスプレイの画面上に表示されているポインタの移動命令を行う,例えば,\n利用者がマウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動さ せる行為がこれに該当する(発明を実施するための最良の形態,段落【0 079】)と記載されている。これに加え,本件発明1におけるポインタ が画面上に表示され,画面上の特定の位置を指し示すものをいうことに鑑\nみると,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令」とは,利 用者が画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作を行うこ\nとを意味すると解するのが相当である。 一方,本件ホームアプリにおいて,原告が「操作メニュー情報」に当た ると主張する左右スクロールメニュー表示は,利用者がショートカットア\nイコンをロングタッチすることにより表示されるものであり(前記前提事\n,画面上に表示されているポインタ(ショートカットアイコン並\nびに青い線の交点及び白い円形の画像。前記1(3))の位置を移動させる操 作により表示されるとは認められない。\n以上によれば,本件ホームアプリが構成要件Eを充足すると認めること\nはできない。
イ これに対し,原告は,「ポインタの位置の移動」とは,ポインタが画面 上に表示されるか否かにかかわらず,コンピュータプログラムがポインタ\nの座標位置の情報の書換えを行うことをいうと主張するが,前記1(1)のと おりポインタは画面上に表示されるものであるから,原告の主張は前提を\n欠き,これを採用することができない。なお,本件ホームアプリにおいて は,タップ操作やスライド操作の際にもポインタの座標位置の書換えが行 われることが認められるが(甲8の1及び2),これらの操作では左右ス クロールメニュー表示は表\示されないのであるから,本件ホームアプリが 「ポインタの座標位置の書換え」により左右スクロールメニュー表示を表\ 示するものでないことは明らかである。 また,原告は,タッチパネルでは指等が触れていれば継続的にポインタ の位置を移動させる命令を受信しており,ロングタッチを識別するために 入力されるデータ群には「ポインタの位置を移動させる命令」が含まれる から,本件ホームアプリは構成要件Eを充足するとも主張する。しかし,\nこの主張は「ポインタの位置を移動させる命令」を受信してもロングタッ チと識別されるまでは左右スクロールメニュー表示が表\示されないことを いうものにほかならず,失当というほかない。
均等侵害の成否
ア 原告は,本件ホームアプリにおける「利用者がタッチパネル上のショー トカットアイコンを指等でロングタッチする操作を行うことによって操作 メニュー情報が表示される」という構\成は「利用者がタッチパネル上の指 等の位置を動かして当該ショートカットアイコンを移動させる操作を行う ことによって操作メニュー情報が表示される」という本件発明の構\成と均 等であると主張するので,この点について検討する。
・・・・
ウ 本件明細書の上記各記載によれば,本件発明1は,従来の技術において はドラッグ&ドロップを行うに際して継続的な操作に適用させるのが困難 であるなどといった問題点があったことから,1)利用者が必要になった場 合にすぐに操作コマンドメニューを画面上に表示させ,かつ,2)必要であ る間はこれを表示させ続けられる手段の提供を目的とするものである。そ\nして,上記1)を達成するために「入力手段を介してポインタの位置を移動 させる命令を受信すると」操作メニュー情報を表示し(構\成要件E),上 記2)を達成するために出力手段に表示した操作メニュー情報がポインタに\nより指定されなくなるまで命令の実行を継続する(同F)という構成を採\n用した点に特徴を有するものと認められる。そうすると,入力手段を介し てポインタの位置を移動させる命令を受信することによってではなく,ポ インタがロングタッチされることによって操作メニュー情報を表示すると\nいう構成は,本件発明1と本質的部分において相違すると解すべきである。\n
エ これに対し,原告は,利用者がドラッグ&ドロップ操作を所望している 場合に操作メニュー情報を表示することが本質的部分であると主張する。\nそこで判断するに,原告が操作メニュー情報に当たると主張する左右スク ロールメニュー表示は,ショートカットアイコンをホーム画面の別のペー\n一方,本件ホームアプリにおいてロングタッチがされた場合に常にショー トカットアイコンをホーム画面の別のページへ移動させるドラッグ&ドロ ップ操作が行われると認めるに足りる証拠はない。そうすると,ロングタ ッチがされたことをもって上記のドラッグ&ドロップ操作が所望されてい るとみることはできないから,本質的部分に関する原告の上記主張を前提 としても,均等による本件特許権の侵害をいう原告の主張は採用すること ができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.03. 7
平成27(ワ)4461 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月10日 東京地方裁判所
特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的\n部分であると解すべきである。 そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づ いて,特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定さ\nれるべきである。すなわち,特許発明の実質的価値は,その技術分野に おける従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれ ば,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に 明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。 ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されて いるところが,出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合\nには,明細書に記載されていない従来技術も参酌して,当該特許発明の 従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定さ\nれるべきである。 また,第1要件の判断,すなわち対象製品等との相違部分が非本質的 部分であるかどうかを判断する際には,上記のとおり確定される特許発 明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し,こ れを備えていると認められる場合には,相違部分は本質的部分ではない と判断すべきであり,対象製品等に,従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても,その\nことは第1要件の充足を否定する理由とはならないと解すべきである (知的財産高等裁判所平成28年3月25日(平成27年(ネ)第100 14号)特別部判決参照)。
イ 原告は,本件発明1の本質的部分は「一の注文手続で,同一種類の金 融商品について,複数の価格にわたって一度に注文を行うこと」及び 「その注文と約定を繰り返すようにしたこと」にとどまると主張する。 この点,確かに,本件明細書等1には,本件発明1の課題として, 「本発明は・・・システムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うこと なく指値注文による取引を効率的かつ円滑に行うことができる金融商品 取引管理方法を提供することを課題としている。」(段落【0006】) との記載がある。この記載に,「請求項1・・・に記載の発明によれば, ・・・一の注文手続きを行うことで,同一種類の金融商品を複数の価格 にわたって一度に注文できる。」(段落【0017】),「請求項1・ ・・に記載の発明によれば,・・・約定した第一注文と同じ第一注文価 格における第一注文の約定と,約定した第二注文と同じ前記第二注文価 格における前記第二注文の約定とを繰り返し行わせるように設定するこ とにより,第一注文と第二注文とが約定した後も,当該約定した注文情 報群による指値注文のイフダンオーダーを繰り返し行うことが可能にな\nる。」(段落【0018】)との各記載も併せれば,原告の主張する 「一の注文手続で,同一種類の金融商品について,複数の価格にわたっ て一度に注文を行うこと」及び「その注文と約定を繰り返すようにした こと」との部分が本件発明1の本質的部分,すなわち従来技術に見られ ない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であるように見えなくもな\nい。 しかし,本件発明1に係る特許(本件特許1)の出願時の従来技術に 照らせば,本件明細書等1に本件発明1の課題として記載された「シス テムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく指値注文による取 引を効率的かつ円滑に行うことができる金融商品取引管理方法を提供す ること」(段落【0006】)は,本件発明1の課題の上位概念を記載 したものにすぎず,客観的に見てなお不十分であるといわざるを得ない。\n以下,詳述する。
以上の各記載に,上記エのとおり,引用文献1には既に「一の注文手 続で,同一種類の金融商品について,複数の価格にわたって一度に注文 を行う」という技術が開示されていたことも併せれば,本件発明1は, 単に一の注文手続で複数の価格にわたって一度に注文を行うだけではな く,「請求項1・・・の発明」による「売買注文申込情報」,すなわち,\n「金融商品の種類」(構成要件1B−1),「注文価格ごとの注文金額」\n(構成要件1B−2),「注文価格」(構\成要件1B−3),「利幅」 (構成要件1B−4)及び「値幅」(構\成要件1B−5)を示す各情報 に基づいて,同一種類の金融商品を複数の価格について指値注文する注 文情報からなる注文情報群を生成することにより,金融商品を売買する 際,一の注文手続きを行うことで,同一種類の金融商品を複数の価格に わたって一度に注文できるという点にその本質的部分があるというべき である。
カ これを被告サービス1についてみると,被告サービス1では「利幅」 (構成要件1B−4)及び「値幅」(構\成要件1B−5)を示す情報が 入力されないのであるから,本件発明1と被告サービス1の相違点が特 許発明の本質的部分ではないということはできない。 したがって,被告サービス1については,均等の要件のうち第1要件 を満たさない。
(4) 第2要件(置換可能性)について
次に,均等の第2要件について検討する。 原告は,本件発明1の課題は「専門的な知識がなく,必ずしも正確に相場 変動を予測することができなくても,また,常に相場に付ききりとならなく\nても,FX取引により所望の利益を得ること」にある旨主張している。 しかし,仮に本件発明1の課題が原告の主張するところにあるとしても, 本件発明1と被告サービス1とは,課題解決原理が全く異なる。 すなわち,本件発明1では,顧客に利幅(構成要件1B−4)及び値幅\n(構成要件1B−5)をはじめとして全ての注文を直接的かつ一義的に導き\n出すに足りる情報を入力させた上,これにより,買いの指値注文及び売りの 指値注文からなる注文のペアを複数生成させ,この複数の注文のペアからな る注文を行うことで,上記課題を解決している。 一方,被告サービス1では,顧客が3)「参考期間」を選択しさえすれば, 4)「想定変動幅」を提案し,専門的な知識が必要である利幅(構成要件1B\n−4)及び値幅(構成要件1B−5)を顧客に入力させることなく,複数の\n注文のペアからなる注文を行うことで,上記課題を解決している。すなわち, 被告サービス1では,顧客に全ての注文を直接的かつ一義的に決定させるの ではなく,顧客には専門的な知識が必要とされる情報を入力させないまま, 注文を行わせるものである。 このように,本件発明1と被告サービス1は,金融商品の相場変動を正確 に予測することができなくてもFX取引による所望の利益を得るという課題\nを,顧客に利幅(構成要件1B−4)及び値幅(構\成要件1B−5)という 専門的な知識が必要である情報を入力させることで解決するか(本件発明 1),それともこれらの情報を入力させないまま解決するか(被告サービス 1)という課題解決原理の違いがあり,そのため作用効果も異なってくるも のといわざるを得ない。 したがって,均等の第2要件に関する原告の主張は理由がない。
(5) 第3要件(容易想到性)について
さらに,均等の第3要件について検討する。
ア 原告は,甲15公報及び甲17公報並びに他の証券会社の提供した 「クイック仕掛け(買いゲリラ100pips)」という機能に照らせば,値幅\nを直接入力せずに他の情報を入力してこれらの情報から値幅を算出して 決定するという構成や,あらかじめ設定された値を用いるという構\成は, 被告サービス1の提供開始時において既に公知の構成であったと主張す\nるので,以下検討する。
イ まず,甲15公報の「要約」欄には,以下の記載がある。
・「注文情報生成部は,取り引きの上限価格と,取り引きの下限価格と, 同時に生成される注文情報群の数とを取得し,取得された値に基づいて, 第一注文どうしの価格差が一定となり,第二注文どうしの価格差が一定 となり,かつ,同一の注文情報群に属する第一注文と第二注文との価格 差が一定となるように,第一注文及び第二注文の価格をそれぞれ演算す る。」 また,甲17公報には,以下の記載がある。
・「前記表示手段における上側の接触位置に対応して表\示された前記価 格情報に基づいて上限価格を設定すると共に前記表示手段における下側\nの接触位置に対応して表示された前記価格情報に基づいて下限価格とを\n設定させると共に,前記注文発注手段に対し,前記上限価格と前記下限 価格との間に形成された前記発注価格帯において前記注文情報を発注さ せることを特徴とする金融商品取引システム。」(【請求項1】)
・「前記注文発注手段は,前記任意の発注条件として,前記金融商品の 注文個数情報を備え,前記発注価格帯において,前記注文個数情報に基 づく複数の前記注文情報を,それぞれの価格差が均等な指値注文を発注 するように生成することを特徴とする請求項1乃至6の何れか一つに記 載の金融商品取引システム。」(【請求項7】)
・「ポジション・ペアの数は,第一形態注文入力画面33(図8)で注文個 数入力欄(図示せず)に入力された注文個数情報の数値,又は,発注価 格帯の数値を値幅入力欄(図示せず)に入力された数値で割った値のう ちの整数値と同じ個数に等しく設定される。」(段落【0082】)
ウ 上記各記載を踏まえ,原告は,甲15公報にはトラップを仕掛ける範 囲(「取引の上限価格」と「取引の下限価格」)と,トラップの本数 (「同時に生成される注文情報群の数」)を入力し,これらの情報に基 づいて値幅及び利幅(「第一注文どうしの価格差」及び「同一の注文情 報群に属する第一注文価格と第二注文価格との差」)を一定となるよう に演算して決定する構成が開示されており,また,甲17公報にも,ト\nラップを仕掛ける範囲(タッチパネルの上下の接触位置に対応する「発 注価格帯」)と,トラップの本数(「注文個数情報」)を入力し,これ らの情報に基づいて,値幅が均等となるように演算して決定する構成が\n開示されていると主張する。 しかし,被告サービス1においては,そもそも注文情報群の数(原告 の主張する「トラップの本数」)を顧客が入力する構成とはなっていな\nい。すなわち,原告の主張によっても,被告サービス1では,顧客は6) 「対象資産(円)」欄に金額を入力するのみであり,被告サーバにおい てその額の証拠金で生成可能な数の注文情報群を生成するというのであ\nる。 加えて,前述のとおり,本件発明1(構成要件1B)と被告サービス\n1の相違点は,本件発明1では構成要件1B−4(利幅を示す情報)及\nび構成要件1B−5(値幅を示す情報)を入力するのに対し,被告サー\nビス1では2)「注文種類」ないし6)「対象資産(円)」の五つの情報を 入力する点にあるところ,甲15公報及び甲17公報にはこれらの五つ の情報の入力については何ら開示されていない。 エ さらに,他の証券会社の提供した「クイック仕掛け(買いゲリラ 100pips)」という機能についてみても,原告によれば,同機能\では利幅 及び値幅はあらかじめ設定されていて,顧客が入力するものではないと いうのである。そうすると,利幅(構成要件1B−4)及び値幅(構\成 要件1B−5)が顧客の入力に係る本件発明1に対し,利幅(構成要件\n1B−4)及び値幅(構成要件1B−5)があらかじめ設定されている\n「クイック仕掛け(買いゲリラ100pips)」の技術を適用する基礎がそも そも存在しないものといわざるを得ない。 オ 以上によれば,本件発明1の構成を被告サービス1のものに置換する\nことについて,当業者が被告サービス1の開始時点において容易に想到 することができたとはいえない。 したがって,均等の第3要件に関する原告の主張は理由がない。
・・・・
原出願である本件特許2に係る本件明細書等2の段落【0005】ないし 【0008】の記載によると,本件特許2は,従来技術の課題として,取引 開始直後の注文が成行注文のイフダンオーダーをすることができなかったこ と及びイフダンオーダーを繰り返し行えなかったことを技術課題として設定 している。 この課題を解決する手段として,本件明細書等2では,取引開始直後に約 定する成行注文の約定価格を基準として,注文情報群を生成し,これに基づ いて,決済注文である指値注文及び逆指値注文を行い,当該指値注文が約定 すると,新たな注文情報群を生成させ,これに基づいて,先行する成行注文 の約定価格と同一の価格の指値注文を行い,当該指値注文が約定すると,当 該新たな注文情報群に基づいて,当該指値注文の決済注文であって,先行す る決済注文である指値注文及び逆指値注文と同一の価格の指値注文及び逆指 値注文を行うことが開示されている。 すなわち,本件明細書等2の段落【0044】では,「・・・成行リピー トイフダンでは,一回目のイフダンでは,第一注文で買い注文または売り注 文の一方を成行で行ったのち,第二注文で買い注文または売り注文の他方を 指値で行う。・・・この第二注文の約定の後,指値の第一注文(このときの 指値価格は一回目の成行注文での約定価格とする)と指値の第二注文とから なるイフダンが,複数回繰り返される。」とされ,段落【0062】では 「ここで,本実施形態の第一注文は,一回目は成行注文で行われるが,二回 目以降は指値注文で行われる。このため,約定情報生成部14は,当該成行 注文の約定価格を,二回目以降の第一注文の指値価格に設定する。」とされ た上,【図7】においても,2回目以降の指値の第一注文の価格を1回目の 成行注文の約定価格とする旨の記載がある。そして,証拠(乙11,13) 及び弁論の全趣旨によれば,これらの段落【0044】及び【0062】並 びに【図7】は,出願当初の明細書等から補正がされていないものと認めら れる。
(4) そこで,構成要件3F−2の「前記指値注文」の構\成と,本件明細書等2 の記載とを比較すると,本件明細書等2には2回目以降の指値の第一注文の 価格を1回目の成行注文の約定価格とすることしか開示されておらず,2回 目以降の指値の第一注文の価格を任意の価格にできるといった記載はない。 また,2回目以降の指値の第一注文の価格をどのような価格にするのか,言 い換えると,1回目の成行注文の約定価格以外のどのような価格に設定する のか,そのための方法等は一切開示されていない。 そうすると,本件明細書等2の出願当初及び分割直前の明細書等には,そ の技術課題及び課題を解決するための手段からみて,2回目以降の指値の第 一注文の価格を任意の価格に設定できることが形式的にも実質的にも記載さ れていないものといわざるを得ない。 したがって,本件発明3の構成要件3F−2は,分割出願の出願日が原出\n 願の出願日へ遡及するための要件である,上記1)及び2)の要件のいずれも満 たさないから,本件発明3に係る特許出願には特許法44条2項の適用がな く,分割要件違反となるものというべきである。
(5) 原告の主張に対する判断
この点に関して原告は,本件発明2及び3の技術思想は「顧客が煩雑な注 文手続を行うことなく複数のイフダンオーダーを繰り返し行うことができて, システムを利用する顧客の利便性を高めると共にイフダンオーダーを行う際 に顧客が被るリスクを低減させることができる。」ことにあり,2回目以降 の第一注文の指値価格をどのようなものにするのかは,上記技術思想とは直 接の関係がないため,当業者において適宜選択・決定すれば足りる事項であ ると主張する。 しかし,上記(3)において引用したところからすれば,本件発明2の技術 思想は,先行する成行注文の約定価格と同一の価格の指値注文を行うところ にもあるということになる。そうすると,本件明細書等2に対し,システム が2回目以降の指値の第一注文の指値価格を決定するという構成を追加する\nことは,新たな技術的事項を導入するものというべきであるから,原告の上 記主張はその前提を欠き,採用することができない。 (6) 以上によれば,本件発明3に係る特許出願の出願日は,原出願の出願日ま で遡及せず,現実の出願日である平成26年11月13日となるところ,本 件発明2に係る特許出願の出願公開の公開日は平成25年7月11日である から(甲4の2),本件発明3の新規性は,本件発明3を下位概念化した本 件発明2によって,否定されることになる。 したがって,本件発明3に係る特許は,特許法29条1項3号に違反して されたものであるから,同法123条1項2号によって特許無効審判により 無効にされるべきものである。
・・・・
(1) 特許制度は,明細書に開示された発明を特許として保護するものであり, 明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の 趣旨に反することから,特許法36条6項1号のいわゆるサポート要件が定 められたものである。 したがって,同号の要件については,特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ,開示されているこ\nとが求められるものであり,同要件に適合するものであるかどうかは,特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に 記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか,すなわち, 発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし,当該発明に おける課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な 技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべ きものと解される。
(2) これを本件についてみるに,原告の主張によれば,構成要件3F−2の\n「前記指値注文」とは,その価格については何の限定もなく,任意の指値価 格をその指値価格とする指値注文ということになる(前記10(3))。しかる に,前記10(3)で引用した本件明細書等2の段落【0044】及び【006 2】並びに【図7】は,本件明細書等3の段落【0042】及び【0060】 並びに【図7】に相当するところ,これらの段落等にも,その技術課題及び 課題を解決するための手段からみて,2回目以降の指値の第一注文の価格を 任意の価格に設定できることが形式的にも実質的にも記載されているとはい えない。 そうすると,当業者において,本件発明3の解決手段その他当業者が当該 発明を理解するために必要な技術的事項が,本件明細書等3の発明の詳細な 説明に記載されているものと認めることはできない。
(3) したがって,本件発明3は特許法36条6項1号に規定するサポート要件 を満たしていないことになるから,本件発明3に係る特許は同法123条1 項4号によって特許無効審判により無効にされるべきものである。
関連カテゴリー
>> 分割
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.03. 6
平成26(ワ)8133 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月27日 東京地方裁判所
ウ 本件明細書の上記イの記載からすると,1)装用時の光学性能を重視して処方面を非球面化した累進屈折力レンズは,測定基準点において面非点隔差が発生する\n結果,レンズメーターで測定される測定度数が処方度数と異なってしまうという課 題があったこと,2)乙4公報記載の累進屈折力レンズでは,処方度数と測定度数が 異なるという上記課題を解決するため,処方面の主注視線に沿った線上部分の一部 に面非点隔差の発生しない領域を設けることとし,当該領域をレンズをフレーム形 状に加工する際に不要部分として廃棄される位置としたこと,3)上記乙4公報記載 のものでは,不要部分として廃棄される領域において測定度数を得ることから,レ ンズの度数測定の本来の目的(装用者の処方どおりにレンズが正しく作成されてい るか否か)との関係で適切とはいえないという問題があったこと,4)本件各発明は, これらを踏まえ,装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レ\nンズを提供することを目的としたものであって,処方面の非球面形状により発生す る面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面又はトーリック面により発生する 面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための測定基 準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下に抑えられているとの構成を有することにより,処方面の非球面化により装用状態における光学性能\を補正する構成\nを採用しているにもかかわらず,例えばレンズメーターを用いて測定基準点を基準 として測定することにより処方度数とほぼ同じ測定度数を得ることができる,とさ れていることが認められる。 また,本件明細書の上記イの記載によれば,本件各発明の実施に際しては,上記 所定領域を広くすると,度数測定には有利となるが,その代償として光学性能が低下するため,この点を考慮して所定領域を定めなければならず,所定領域は,「装\n用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供するこ\nとを目的とする」という発明の目的を達成するように定められる必要があり,また, 装用者の処方や使用条件,製品の仕様,度数測定方法,測定器の仕様のうち少なく とも一つの条件を考慮して,平均値ΔASavを所定の値以下に抑えるべき測定基 準点を含む近傍の所定領域の大きさや形状を決定することによって,より優れた光 学性能と度数測定の容易さとの両方を得ることが可能\となる,とされていることが 認められる。
・・・・
このように,レンズメーターを用いて測定した球面度数及び乱視度数の値を処方 球面度数及び処方乱視度数と略同じ値にするため,本件各発明は,「測定基準点を 含む近傍の所定領域」とその領域における「所定の値」を設けたものであり,処方 面において改善された光学性能を犠牲にしても,レンズメーターによって測定する「測定基準点を含む近傍の所定領域」において局部的な面補正をし,面非点隔差成\n分を所定の値以下にしようとするものであるから,構成要件Cにいう「測定基準点を含む近傍の所定領域」とは,それ以外の領域とは区別された領域であることを当\n然の前提としているものというべきである。
・・・・
このように,被告製品1,2及び4は,遠用度数測定点を中心とした遠用部領域 全体(被告製品2のうち,上記図中の2)−2については,ほぼ全体),被告製品3 は近用度数測定点を中心とした近用部領域の領域全体において,面非点隔差の平均 値が本件各発明の構成要件Dにおける所定の値(0.15ディオプター)を大きく下回っている。
イ そうすると,被告各製品においては,レンズの測定基準点を含む処方面の非 点隔差は,光学設計上,一定の領域における光学性能を犠牲にしても所定の値以下とするような局部的な面補正,つまり,「所定の値以下」にされた「所定領域」を\n設ける必要がない構造であることが認められる。したがって,被告各製品は,構\成要件Cにいう「所定領域」に相当する構成を有\nしないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.02.23
平成26(ワ)20319 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月27日 東京地方裁判所(40部)
「暗号」とは,一般に,「通信の内容が第三者にもれないように,おたが いに約束して使う記号(のしくみ)」(三省堂国語辞典第7版52頁〔甲 2〕),「秘密を保つために,当事者間にのみ了解されるようにとり決めた 特殊な記号・ことば。あいことば。」(広辞苑第4版99頁〔甲5〕), 「第三者に通信内容を知られないように行う特殊な通信(秘匿通信)方法の うち,通信文を見ても特別な知識なしでは読めないように変換する表記法\n(変換アルゴリズム)のこと」(ウィキペディア〔乙1〕),「秘密にした い情報をかき混ぜて(暗号)特定の者以外にはその内容が解らないようにす ること。」(情報通信用語辞典13頁〔乙3〕),「情報の意味が当事者以 外にはわからないように,情報を変換すること」(エンサイクロペディア電 子情報通信ハンドブック〔乙17〕)との意味を有するとされている。 また,「コード」とは,「文字や記号,数字などをコンピューターが識別 するためにまとめられた符号」(IT用語辞典BINARY〔乙2〕), 「データを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づい\nて表現されたもの」(情報通信用語辞典100頁〔乙3〕)との意味を有す\nるとされている。 以上を前提にすると,本件発明4及び6の構成要件A4,B4及びB6に\nいう「暗号コード」とは,通信の内容が第三者に知られることのないように, 当事者間にのみ了解されるように取り決めた特殊な記号,文字ないし数字を まとめた符号を意味するものと解するのが相当である。
(2) これを被告製品3及び4についてみるに,被告によれば,被告製品3及び 4は「ID情報」を有しているが,この「ID情報」とは単なる数字にすぎ ないものと認められる(原告も明らかに争わず,これに反する証拠も存在し ない。)。そうすると,単なる数字にすぎない以上,その内容が「第三者に 知られることのないよう」にしたものではないのであるから,被告製品3及 び4の「ID情報」は,通信の内容が第三者に知られることのないよう,当 事者間にのみ了解されるように取り決めた特殊な記号,文字ないし数字をま とめた符号ではないのであって,「暗号コード」に該当するものとはいえな い。 そして,本件全証拠を精査しても,被告製品3及び4が「ID情報」以外 に「暗号コード」に該当するような符号を使用していることを認めるに足り る証拠はないから,本件においては,被告製品3及び4は,構成要件A4,\nB4及びB6にいう「暗号コード」を充足しないというべきである。
(3) 原告の主張に対する判断
この点に関して原告は,本件発明4及び6にいう「暗号コード」とは,コ ードの一部を任意の数字(信号)を組み合わせたものとしてリセットコード を設定し,送受信するものにすぎず,辞書等における「暗号」の意味とは異 なるものであって,このことは本件明細書等の記載からも明らかであると主 張する。 しかし,明細書の技術用語は,特に明細書の中で定義して特定の意味に使 用している場合を除き,原則として学術用語を用い,その有する普通の意味 を用い,かつ特許請求の範囲及び明細書全体を通じて統一して使用されなけ ればならないところ(特許法施行規則24条参照),本件明細書等において は,「暗号コード」の意義に関し,段落【0073】において「『暗号』は 4桁の暗号コードである。」と記載されているにすぎず,「暗号コード」な いし「暗号」の意味が原告主張のようなものであることにつき,何らの明確 な定義付けもされておらず,また辞書等における「暗号」の意味と異なるな どといった示唆もされていない。したがって,「暗号コード」とは電気通信 技術に関する技術的知識を有する当業者が理解する通常の意味で解釈すべき であるから,原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.02.10
平成28(ワ)37954 承継参加申立事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月31日 東京地方裁判所(第47民)
以上の特許請求の範囲や「発明の詳細な説明」の記載を総合すると,本 件発明は,デジタル格納部を含むユーザテレビ機器を備えた双方向テレビ 番組ガイドシステムに係る発明であるというべきである。 なお,明細書の【図1】(本件発明による例示的システムとされている。 段落【0011】ないし【0013】参照)においても,本件発明の「双 方向テレビ番組ガイドシステム」が,主設備(12),番組ガイドデータ ソース(14),テレビ配信設備(16),ユーザテレビ機器(22)を\n全て含むことが示されている。 イ 他方で,証拠(甲10の1及び2,14,16)及び弁論の全趣旨によ れば,被告物件である液晶テレビ製品は,単に放送を受信するだけで,い ずれもそれ自体に録画できるメモリー部分(デジタル格納部)を備えてお らず,録画先としては,外付けのUSBハードディスクやレグザリンク対 応の東芝レコーダーとされており,これらを被告物件に接続することによ って初めて,被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画する ことが可能であるものと認められる。
ウ 以上のとおり,本件発明は,デジタル格納部を含むユーザテレビ機器を 備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから,被告物件 (液晶テレビ製品)が本件発明の技術的範囲に属するというためには,被 告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要である\nところ,被告物件は,それ自体にテレビ番組をデジタル録画可能なメモリ\nー部分を有していないから,この点において,構成要件Cを充足しないと\nいうべきである。
エ これに対し,原告は,本件発明は「双方向テレビ番組ガイドシステム」 の発明であって,テレビ本体やデジタル格納デバイス自体の発明ではなく, 構成要件Aは「双方向テレビ番組ガイドシステム」が「ユーザテレビ機器\n(22)」自体を備えることを規定するものではないし,構成要件Cも,\nあくまで複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を構成要件の内容と\nして規定するものであって,デジタル格納デバイスを規定しているわけで はないから,被告物件自体がUSBハードディスクを備えているか否かは, 本件発明の構成要件充足性には無関係である旨主張する。\nしかしながら,原告の上記主張は,上記で説示した特許請求の範囲や明 細書の各記載(例えば,本件発明の目的が「従来双方向番組ガイドシステ ムにより提供されたものよりも高度な機能を提供するように番組ガイドを\n用いることを可能にするデジタル格納部を備えた双方向番組ガイドシステ\nムを提供すること」であるとの明細書の記載(段落【0006】)等)に 明らかに反するものであるから,採用することができない。
(2) 構成要件Dの充足性について\n ア 証拠(甲7,乙14,15)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が 認められる。
・・・
イ このように,本件特許の出願人であったユナイテッド社は,本件特許の 出願段階で,特許庁に対し,本件発明が「引用文献3」(本件の乙20に 相当する。)記載の発明とは異なり,進歩性を有することを示すことを目 的として,本件発明では,同文献記載の発明とは異なり,「番組データが 格納される前に,番組が格納される」旨主張していたものである。そして, 特許庁では,ユナイテッド社の以上のような主張をも考慮した上で,本件 発明は「引用文献3」記載の発明とは異なり,かつ同発明からは容易想到 ではないとして,特許査定をしたものと解される。そうであれば,本件発 明の構成要件Dにおける番組の格納と番組データの格納の先後関係につい\nては,ユナイテッド社の上記主張のとおり,「番組データが格納される前 に番組が格納される」ものと解すべきであり,上記特許出願人の地位を承 継した原告が上記特許出願人による上記主張内容と異なる主張を本件訴訟 においてすることは,禁反言の原則に反するものとして許されないという べきである。
ウ そうであるところ,被告物件において「番組データが格納される前に番 組が格納(録画)される」という先後関係があるものとは認められないか ら,被告物件は,構成要件Dを充足しない。
エ なお,原告は,回答書(乙14)における引用文献3についての説明は, 単に本件発明と引用文献3記載の発明の内容の違いを説明したにすぎない とも主張するが,原告の同主張を前提としても,上記特許出願人が本件特 許の出願過程において上記のような説明をしたことに何ら変わりはないか ら,原告の上記主張は上記説示を何ら左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.01.25
平成28(ネ)10046 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記アによると,本件各明細書には,樹脂組成物の屈折率について「硬化樹 脂層の屈折率測定方法は,JIS K 7142の「プラスチックの屈折率測定方 法」(Determination of the refractive in dex of plastics)に従う。具体的には,ガラス繊維織物が含まれ ていない硬化性樹脂のフィルムを,ガラス繊維織物を含む場合と同じ条件で作成し, アッベ屈折計を用いて測定する。」と記載されていることが認められる。したがって, 樹脂組成物の屈折率については,「JIS K 7142」(甲203)に規定され たA法(板状またはフィルム状試験片に適用)とB法(粉末状,ペレット状,顆粒 状サンプルに適用)のうち,アッベ屈折計を用いるとされるA法により測定される ことが記載されていると認められる。 これに対し,ガラス組成物の屈折率については,いくつかの測定方法があり,測 定方法が相違すると測定値も異なることがあることは前記認定のとおりであるけれ ども,本件各特許の特許請求の範囲の記載では,ガラス組成物の屈折率の測定方法 が特定されていないし,また,本件各明細書における発明の詳細な説明にも,ガラ ス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないことが認められる。 もっとも,このような場合であっても,本件各明細書におけるガラス組成物等の 屈折率に関する記載を合理的に解釈し,当業者の技術常識も参酌して,ガラス組成 物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができるときには,そのように解釈 すべきである。 まず,前記アの本件各明細書の記載においては,特に,ガラス繊維織物に織られ たガラス繊維の品番ECE225,ECG75,ECG37等が特定されているの に対し,そのガラス繊維であるECE225,ECG75,ECG37等の屈折率 が表示されていないこと,その原料であるEガラスの屈折率が1.558であると\n表示されており,表\1におけるガラス繊維織物の屈折率にもその1.558が用い られていることなどを考慮すると,本件各発明における「ガラス繊維織物中のガラ ス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」は,ガラス繊維の屈折率を測定して\n得られたものではなく,繊維化する前のガラス組成物(原料)の屈折率であると認 めるのが相当である。なお,Eガラスにも各種品目があり,Eガラスの屈折率につ いては,1.548(乙あ93),1.560(乙あ11)のものもあるところ,本 件各明細書においては,Eガラスの中でも,屈折率が1.558のものが用いられ たものと推認することができる。また,本件各明細書には,硬化樹脂の屈折率の測 定方法についての記載があるのに対し,ガラス組成物の屈折率の測定法についての 記載がないのは,ガラス組成物について,商品データベース(甲26)などから, その屈折率が得られることから,独自に測定する必要性がないことによるというこ とができる。前記のとおり,実測によらないガラス組成物の屈折率は,実際のシー ト状態となったガラス繊維の屈折率とは一致しない可能性はあるけれども,上記で\n認定した「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の商品カタロ\nグ等における「屈折率」を採用することで,硬化樹脂に埋め込まれたガラス繊維を 分離して,屈折率を測定する煩雑さを回避することができることを考慮すると,こ のような定め方も不合理であるとはいえないし,本件明細書の表1によれば,ガラ\nス繊維の原料であるEガラス組成物の屈折率である1.558を用いた上で,硬化 樹脂との界面の透明性を確保することが可能となっていることが認められる。\n以上によれば,「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈\n折率」は,繊維化する前のガラス組成物の屈折率を指すものと認めるのが相当であ る。また,前記認定のとおり,「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組\n成物の屈折率」は,素材メーカーが製品とともに公表したものであることを前提と\nすると,ガラス組成物の屈折率は「JIS K 7142」(プラスチックの屈折率 の測定方法)で測定されたものと解することはできず,むしろ,ガラス組成物(E ガラス)について素材メーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法により 測定されたものと解するのが自然な解釈であるといえる。そして,素材メーカーが Eガラスについて商品データベースにおいて表示している屈折率は,小数点以下第\n3位のものが多いことからすると(甲26,乙あ11,93),少なくとも有効数字 が小数点以下第4位まで測定できる測定方法である必要がある。また,証拠(甲4 5,乙あ27,89,108)及び弁論の全趣旨によれば,小数点以下第4位まで 測定できる測定方法としては,精度の高い最小偏角法(精度は約1×10−5)と,次 に精度が高いVブロック法(精度は約2×10−5)及び臨界角法(精度は1×10− 4)のいずれかであると認められるところ,このうち表示される屈折率が上記のとお\nり小数点以下第3位のものが多く,最も精度の高いものまで要求されないことや, Vブロック法による測定が最も簡便であって,試料の作成も容易であること(乙あ 89)を考慮すると,素材メーカーがEガラスについて一般に採用する合理的な屈 折率の測定方法は,Vブロック法であると推認するのが相当である。現に,本件に おいて,控訴人及び被控訴人ユニチカが,本件シートや本件各発明の実施品のガラ ス組成物の屈折率を,専門機関に依頼した上で,Vブロック法で測定していること (甲24,乙あ74,97の1)も,このことを裏付けるものである。 なお,本件各明細書には,樹脂組成物の屈折率については,「JIS K 714 2」に規定されたA法により測定されることが記載されていること,ガラス組成物 の屈折率の測定方法については明確な記載がないものの,「ガラス繊維織物中のガ ラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」としては,繊維化する前のガラス\n組成物の屈折率が記載されており,その測定方法は前記のとおりVブロック法であ ると推認されることからすると,樹脂組成物の屈折率の測定方法については,「JI S K 7142」の「B法」を追加する本件各訂正は新規事項の追加であり,ガ ラス組成物の屈折率の測定方法については,「JIS K 7142」を追加し,あ るいはその「B法」を追加する本件各訂正はいずれも新規事項の追加である。 したがって,本件各訂正請求は,特許法126条1項の訂正要件に反するもので あり,本件各訂正請求を認めた審決は未だ確定していないことからすれば(当裁判 所に顕著な事実である。),本件においては,本件防煙垂壁が本件各発明の技術的範 囲に属するか否かについて,本件各訂正請求の内容を考慮せずに判断すべきである (仮に,本件各訂正請求を認める審決が確定すると,本件各訂正発明は,特許法1 23条1項8号の無効理由を有するものとなる。)。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成26(ワ)10848
対応する審決取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2017.01.25
平成28(ネ)10046 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 法68条の2の「政令で定める処分の対象となつた物」に係る特許発明の 実施行為の範囲について
政令(特許法施行令2条)では,延長登録の理由となる処分は医薬品医療 機器等法の承認と農薬取締法の承認の二つの処分に限定されている。本件の ように「政令で定める処分」が前者の承認(医薬品医療機器等法所定の医薬 品に係る承認)に係るものである場合においては,次のとおりであると認め られる。すなわち,
ア 医薬品医療機器等法14条1項は,「医薬品…の製造販売をしようとす る者は,品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けな ければならない。」と規定し,同項に係る医薬品の承認に必要な審査の対 象となる事項は,「名称,成分,分量,用法,用量,効能,効果,副作用\nその他の品質,有効性及び安全性に関する事項」(同法14条2項,9項) と規定されている。 このことからすると,「政令で定める処分」が医薬品医療機器等法所定 の医薬品に係る承認である場合には,常に「用法,用量,効能及び効果」\nが審査事項とされ,「用法,用量,効能及び効果」は「用途」に含まれる\nから,同承認は,法68条の2括弧書の「その処分においてその物の使用 される特定の用途が定められている場合」に該当するものと解される。 医薬品医療機器等法の承認処分の対象となった医薬品における,法68 条の2の「政令で定める処分の対象となつた物」及び「用途」は,存続期 間が延長された特許権の効力の範囲を特定するものであるから,特許権の 存続期間の延長登録の制度趣旨(特許権者が,政令で定める処分を受ける ために,その特許発明を実施する意思及び能力を有していてもなお,特許\n発明の実施をすることができなかった期間があったときは,5年を限度と して,その期間の延長を認めるとの制度趣旨)及び特許権者と第三者との 衡平を考慮した上で,これを合理的に解釈すべきである。 そうすると,まず,前記のとおり,医薬品の承認に必要な審査の対象と なる事項は,「名称,成分,分量,用法,用量,効能,効果,副作用その\n他の品質,有効性及び安全性に関する事項」であり,これらの各要素によ って特定された「品目」ごとに承認を受けるものであるから,形式的には これらの各要素が「物」及び「用途」を画する基準となる。 もっとも,特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨からすると,医薬品 としての実質的同一性に直接関わらない審査事項につき相違がある場合に まで,特許権の効力が制限されるのは相当でなく,本件のように医薬品の 成分を対象とする物の特許発明について,医薬品としての実質的同一性に 直接関わる審査事項は,医薬品の「成分,分量,用法,用量,効能及び効\n果」である(ベバシズマブ事件最判)ことからすると,これらの範囲で「物」 及び「用途」を特定し,延長された特許権の効力範囲を画するのが相当で ある。 そして,「成分,分量」は,「物」それ自体の客観的同一性を左右する 一方で「用途」に該当し得る性質のものではないから,「物」を特定する 要素とみるのが相当であり,「用法,用量,効能及び効果」は,「物」そ\nれ自体の客観的同一性を左右するものではないが,前記のとおり「用途」 に該当するものであるから,「用途」を特定する要素とみるのが相当であ る。 なお,医薬品医療機器等法所定の承認に必要な審査の対象となる「成分」 は,薬効を発揮する成分(有効成分)に限定されるものではないから,こ こでいう「成分」も有効成分に限られないことはもちろんである。 以上によれば,医薬品の成分を対象とする物の特許発明の場合,存続期 間が延長された特許権は,具体的な政令処分で定められた「成分,分量, 用法,用量,効能及び効果」によって特定された「物」についての「当該\n特許発明の実施」の範囲で効力が及ぶと解するのが相当である(ただし, 延長登録における「用途」が,延長登録の理由となった政令処分の「用法, 用量,効能及び効果」より限定的である場合には,当然ながら,上記効力\n範囲を画する要素としての「用法,用量,効能及び効果」も,延長登録に\nおける「用途」により限定される。以下同じ。)。
イ 上記アによれば,相手方が製造等する製品(以下「対象製品」という。) が,具体的な政令処分で定められた「成分,分量,用法,用量,効能及び\n効果」において異なる部分が存在する場合には,対象製品は,存続期間が 延長された特許権の効力の及ぶ範囲に属するということはできない。しか しながら,政令処分で定められた上記審査事項を形式的に比較して全て一 致しなければ特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることがで きるとすれば,政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実 施をすることができなかった期間を回復するという延長登録の制度趣旨に 反するのみならず,衡平の理念にもとる結果になる。このような観点から すれば,存続期間が延長された特許権に係る特許発明の効力は,政令処分 で定められた「成分,分量,用法,用量,効能及び効果」によって特定さ\nれた「物」(医薬品)のみならず,これと医薬品として実質同一なものに も及ぶというべきであり,第三者はこれを予期すべきである(なお,法6\n8条の2は,「物…についての当該特許発明の実施以外の行為には,及ば ない。」と規定しているけれども,同条における「物」についての「当該 特許発明の実施」としては,「物」についての当該特許発明の文言どおり の実施と,これと実質同一の範囲での当該特許発明の実施のいずれをも含 むものと解すべきである。)。 したがって,政令処分で定められた上記構成中に対象製品と異なる部分\nが存する場合であっても,当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的 な差異にすぎないときは,対象製品は,医薬品として政令処分の対象とな った物と実質同一なものに含まれ,存続期間が延長された特許権の効力の 及ぶ範囲に属するものと解するのが相当である。
ウ そして,医薬品の成分を対象とする物の特許発明において,政令処分で 定められた「成分」に関する差異,「分量」の数量的差異又は「用法,用 量」の数量的差異のいずれか一つないし複数があり,他の差異が存在しな い場合に限定してみれば,僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異かど うかは,特許発明の内容(当該特許発明が,医薬品の有効成分のみを特徴 とする発明であるのか,医薬品の有効成分の存在を前提として,その安定 性ないし剤型等に関する発明であるのか,あるいは,その技術的特徴及び 作用効果はどのような内容であるのかなどを含む。以下同じ。)に基づき, その内容との関連で,政令処分において定められた「成分,分量,用法, 用量,効能及び効果」によって特定された「物」と対象製品との技術的特\n徴及び作用効果の同一性を比較検討して,当業者の技術常識を踏まえて判 断すべきである。 上記の限定した場合において,対象製品が政令処分で定められた「成分, 分量,用法,用量,効能及び効果」によって特定された「物」と医薬品と\nして実質同一なものに含まれる類型を挙げれば,次のとおりである。 すなわち,1)医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長 登録された特許発明において,有効成分ではない「成分」に関して,対象 製品が,政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき,一部において\n異なる成分を付加,転換等しているような場合,2)公知の有効成分に係る 医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において,対象製品が政令 処分申請時における周知・慣用技術に基づき,一部において異なる成分を\n付加,転換等しているような場合で,特許発明の内容に照らして,両者の 間で,その技術的特徴及び作用効果の同一性があると認められるとき,3) 政令処分で特定された「分量」ないし「用法,用量」に関し,数量的に意 味のない程度の差異しかない場合,4)政令処分で特定された「分量」は異 なるけれども,「用法,用量」も併せてみれば,同一であると認められる 場合(本件処分1と2,本件処分5ないし7がこれに該当する。)は,こ れらの差異は上記にいう僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異に当た り,対象製品は,医薬品として政令処分の対象となった物と実質同一なも のに含まれるというべきである(なお,上記1),3)及び4)は,両者の間で, 特許発明の技術的特徴及び作用効果の同一性が事実上推認される類型であ る。)。 これに対し,前記の限定した場合を除く医薬品に関する「用法,用量, 効能及び効果」における差異がある場合は,この限りでない。なぜなら,\n例えば,スプレー剤と注射剤のように,剤型が異なるために「用法,用量」 に数量的差異以外の差異が生じる場合は,その具体的な差異の内容に応じ て多角的な観点からの考察が必要であり,また,対象とする疾病が異なる ために「効能,効果」が異なる場合は,疾病の類似性など医学的な観点か\nらの考察が重要であると解されるからである。 しかし,特許発明の技術的範囲における均等は,特許発明の技術的範囲 の外延を画するものであり,法68条の2における,具体的な政令処分を 前提として延長登録が認められた特許権の効力範囲における前記実質同一 とは,その適用される状況が異なるものであるため,その第1要件ないし 第3要件はこれをそのまま適用すると,法68条の2の延長登録された特 許権の効力の範囲が広がり過ぎ,相当ではない。 すなわち,本件各処分についてみれば明らかなように,各政令処分によ って特定される「物」についての「特許発明の実施」について,第1要件 ないし第3要件をそのまま適用して均等の範囲を考えると,それぞれの政 令処分の全てが互いの均等物となり,あるいは,それぞれの均等の範囲が 特許発明の技術的範囲ないしはその均等の範囲にまで及ぶ可能性があり,\n法68条の2の延長登録された特許権の効力範囲としては広がり過ぎるこ とが明らかである。 また,均等の5要件の類推適用についても,仮にこれを類推適用すると すれば,政令処分は,本件各処分のように,特定の医薬品について複数の 処分がなされることが多いため,政令処分で特定される具体的な「物」に ついて,それぞれ適切な範囲で一定の広がりを持ち,なおかつ,実質同一 の範囲が広がり過ぎないように(例えば,本件各処分にみられるような複 数の政令処分について,分量が異なる一部の処分に係る物が実質同一とな ることはあっても,その全てが互いに実質同一の範囲に含まれることがな いように)検討する必要がある。 しかし,まず,第1要件についてみると,このような類推適用のための 要件を想定することは困難である。すなわち,第1要件は,政令処分によ り特定される「物」と対象製品との差異が政令処分により特定される「物」 の本質的部分ではないことと類推されるところ,実質同一の範囲が広がり 過ぎないように類推適用するためには,政令処分により特定される「物」 の本質的部分(特許発明の本質的部分の下位概念に相当するもの)を適切 に想定することが必要であると解されるものの,その想定は一般的には困 難である。また,第2要件は,政令処分により特定される「物」と対象製 品との作用効果の同一性と類推されるところ,これは,実質同一のための 必要条件の一つであると考えられるものの,これだけでは実質同一の範囲 が広くなり過ぎるため,類推適用のためには,第1要件やその他の要件の 考察が必要となり,その想定は困難である。 以上によれば,法68条の2の実質同一の範囲を定める場合には,前記 の五つの要件を適用ないし類推適用することはできない。
オ ただし,一般的な禁反言(エストッペル)の考え方に基づけば,延長登 録出願の手続において,延長登録された特許権の効力範囲から意識的に除 外されたものに当たるなどの特段の事情がある場合には,法68条の2の 実質同一が認められることはないと解される。
(3) 対象製品が特許発明の技術的範囲(均等も含む。)に属することについて 法68条の2は,特許権の存続期間を延長して,特許権を実質的に行使す ることのできなかった特許権者を救済する制度であって,特許発明の技術的 範囲を拡張する制度ではない。したがって,存続期間が延長された特許権の 侵害を認定するためには,対象製品が特許発明の技術的範囲(均等も含む。) に属するとの事実の主張立証が必要であることは当然である。なお,このこ とは,法68条の2が政令処分の対象となった物についての「当該特許発明 の実施以外の行為には,及ばない」と規定していることからも明らかである。
・・・
しかしながら,一審原告の主張は,要するに,医薬品の承認制度の面から, 後発医薬品として承認されたものは全て実質同一物等に当たる(先発医薬品 に係る特許発明の効力が及ぶ)と断じるに等しく,法68条の2の制度趣旨 や解釈論を無視するものであって,採用することはできない。 すなわち,後発医薬品は,先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み,同 一経路から投与する製剤で,効能・効果,用法・用量が原則的に同一であり,\n先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品をいい,両者の間に有 効性や安全性について基本的な相違がないことが前提である。また,先発医 薬品と異なる添加剤を使用することがあっても,薬理作用を発揮したり,有 効成分の治療効果を妨げたりする物質を添加剤として使用することはできず, 医薬品としての承認に当たっては,生物学的同等性試験により主成分の血中 濃度の挙動が先発医薬品と同等であることの確認が求められるものとされて いる(甲30,弁論の全趣旨)。このように,後発医薬品は,先発医薬品と 治療学的に同等であるものとして製造販売が承認されるものであり,先発医 薬品と代替可能な医薬品として市場に提供されることが前提であるから,そ\nもそも医薬品としての品質において先発医薬品に依拠するものであることは 当然である。しかし,これは飽くまで有効成分や治療効果(有効性,安定性 を含む。)が原則として同一であるということを意味するにすぎず,特許発 明の観点からその成果に依拠するかどうかを問題にしているわけではない。 これに対し,延長登録された特許権の効力範囲における実質同一は,特許 権の効力範囲を画する概念である。前記のとおり,1)法68条の2の規定は, 特許権の存続期間の延長登録の制度が,政令処分を受けることが必要であっ たために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目 的とするものであることに鑑み,存続期間が延長された場合の当該特許権の 効力についても,その特許発明の全範囲に及ぶのではなく,「政令で定める 処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が 定められている場合にあつては,当該用途に使用されるその物)」について の「当該特許発明の実施」にのみ及ぶ旨を定めるものであり,2)医薬品の成 分を対象とする物の特許発明の場合,法68条の2によって存続期間が延長 された特許権は,具体的な政令処分で定められた「成分,分量,用法,用量, 効能及び効果」によって特定された「物」についての「当該特許発明の実施」\nの範囲で効力が及ぶと解するのが相当であるものの,3)これらの各要素によ って当該特許権の効力範囲が画されるとしても,これらの各要素における僅 かな差異や形式的な差異によって延長登録された特許権の効力が及ばないと することは延長登録の制度趣旨に反し,衡平の理念にもとる結果となるから, これらの差異によっても,なお政令処分の対象となった医薬品と実質同一の 範囲で,延長された当該特許権の効力が及ぶと解すべきである。 したがって,延長登録された特許権の効力範囲における「成分」に関する 差異,「分量」の数量的差異又は「用法,用量」のうち「効能,効果」に影\n響しない数量的差異に関する実質同一は,当該特許発明の内容に基づき,そ の内容との関連で,政令処分において定められた「成分,分量,用法,用量, 効能及び効果」によって特定された「物」と対象製品との技術的特徴及び作\n用効果の同一性を比較検討して,当業者の技術常識を踏まえてこれを判断す べきであり,これを離れて,医薬品としての有効成分や治療効果(有効性, 安定性)のみからこれを論じるべきものではない。少なくとも,法68条の 2が,およそ後発医薬品であるが故に,すなわち,先発医薬品と同等の品質 を備え,これに依拠するが故に直ちに特許権の効力を及ぼそうとする趣旨の ものでないことは明らかである。 しかるに,一審原告の主張は,当該特許発明の内容に関わらず,いわば医 薬品としての有効成分や治療効果のみに着目して延長された特許権の効力範 囲を論ずるものであり,これは前記のとおりの法68条の2の制度趣旨や解 釈論に反することが明らかであって,採用することはできないというべきで ある。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2016.12.14
平成27(ワ)12415 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年12月2日 東京地方裁判所(40部)
(1) 本件発明2における「緩衝剤」は,添加されたシュウ酸またはそのアルカ リ金属塩をいい,オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「緩衝 剤」には当たらないと解することが相当である。理由は以下のとおりである。 (2)ア 化学大事典2(乙13)によれば,「緩衝剤」とは,「緩衝液をつくる ために用いられる試薬の総称」をいうものとされている。そして,広辞苑 第六版によれば,「試薬」とは「実験室などで使用する純度の高い化学物 質」であるところ,解離シュウ酸が「純度の高い化学物質」である「試薬」 に当たるとは考えがたいから,解離シュウ酸は一般的な意味で「緩衝剤」 とはいえないというべきである。
イ 次に,本件明細書2の段落【0022】には,「緩衝剤という用語は, 本明細書中で用いる場合,オキサリプラチン溶液を安定化し,それにより 望ましくない不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオD ACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸 性または塩基性剤を意味する。」と記載されている。 上記記載において,「緩衝剤」は,「酸性または塩基性剤」であると定 義されているが,広辞苑第六版によれば,「剤」とは「各種の薬を調合す ること。また,その薬。」を意味するから,「酸性または塩基性剤」は, 酸性または塩基性の各種の薬を調合した薬を意味すると考えることが自然 であるところ,解離シュウ酸は,「各種の薬を調合した薬」に当たるとは いえない。 ウ そして,本件明細書2の段落【0013】後段ないし【0016】には, オキサリプラチンが水性溶液中で分解してジアクオDACHプラチンを不 純物として生成することが記載されているが,オキサリプラチンが分解す ると,次の式のとおり,シュウ酸イオンとジアクオDACHプラチンが生 じる。また,証拠(乙39)によれば,分解により生じたシュウ酸イオン は,一部がプロトン化されてシュウ酸又はシュウ酸水素イオンになること が認められる。 したがって,オキサリプラチンの分解によりシュウ酸イオン等が生じた ということは,すなわちオキサリプラチン水溶液において不純物が生じた ことを意味するから,仮にオキサリプラチンの分解により生じた解離シュ ウ酸が「緩衝剤」に当たるとすると,緩衝剤が防止すべき分解により生じ たものが緩衝剤に当たるということになってしまい,上記イの「望ましく ない不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプ ラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得る」という緩衝剤の定 義と整合しない。 エ 前記3(2)のとおり,本件発明2は,乙14発明よりも不純物が有意に少 ない,より安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とす るものである。 ところが,本件明細書2をみると,実施例18において生成される不純 物の量と比較して,シュウ酸を添加した実施例(ただし,実施例1及び8 を除く。なお,実施例1及び8は,後記(3)エのとおり,本件発明2の技術 的範囲に含まれる実施例ではない。)において生成される不純物の量は有 意に少ないことが示されている。ここで,実施例18は,豪州国特許出願 第29896/95号(1996年3月7日公開)に記載されている水性 オキサリプラチン組成物であるが,上記出願は,乙14発明に対応するも のであるから,実施例18は乙14発明と実質的に同一であると推認され る。 したがって,本件発明2は,乙14発明とは異なり,オキサリプラチン 溶液組成物に緩衝剤を添加したことによって,不純物が少なく,より安定 な溶液組成物を提供することができたことを特徴とする発明と考えるのが 自然である。
オ 本件明細書2には,実施例1ないし17については,シュウ酸が付加さ れていることが明記されている。また,本件明細書2(段落【0039】, 【0041】〜【0045】,【0047】,【0064】)では,実施 例1ないし17について,添加されたシュウ酸のモル濃度が記載されてい るが,解離シュウ酸を含むシュウ酸のモル濃度は記載されていない。 さらに,本件明細書2は,「緩衝剤」である「シュウ酸」に,オキサリ プラチンが分解して生じた解離シュウ酸が含まれることを示唆する記載は ない。 この点に関して原告は,構成要件2Gの数値範囲の下限(5×10−5M)\nが,本件明細書2記載の実施例1及び8で示された下限(1×10−5M) よりも大きいことをもって,請求項1は解離シュウ酸を考慮したものであ ると主張するが,本件明細書2には,1×10−5Mのシュウ酸を添加した オキサリプラチン溶液中のシュウ酸イオン等のモル濃度がどの程度になる かに係る記載は何ら存在しておらず,原告の上記主張は裏付けを欠く独自 の見解というほかない。 以上からすると,本件明細書2の記載においては,解離シュウ酸につい ては全く考慮されておらず,緩衝剤としての「シュウ酸」は添加されるも のであることを前提としているというべきである。 カ また,本件明細書2における実施例18(b)に関する記載をみると,「比 較のために,例えば豪州国特許出願第29896/95号(1996年3 月7日公開)に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を,以 下のように調製した」(段落【0050】前段),「比較例18の安定性」 「実施例18(b)の非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物を,40℃で 1ヶ月間保存した。」(段落【0073】)といった記載がある。そして, 前記エのとおり,豪州国特許出願第29896/95号(1996年3月 7日公開)は乙14発明と実質的に同一であるから,上記各記載を総合す ると,実施例18(b)は,「実施例」という用語が用いられている部分 が多いものの,その実質は本件発明2の実施例ではなく,本件発明2と比 較するために,「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」,すなわち,緩 衝剤が用いられていない従来既知の水性オキサリプラチン組成物を調製し たものであると認めるのが相当である。 そうすると,本件明細書2において,緩衝剤を添加しない水性オキサリ プラチン組成物に関する実施例18は,本件発明2の実施例ではなく,比 較例として記載されているというべきである。 キ さらに,証拠(乙64,65)によれば,本件特許2の出願人が,本件 特許2に対応する米国特許出願(乙64)について,米国特許庁に提出し た意見書(乙65)において,「甲等の水溶液組成物(本願21頁に記載 されている甲等の組成物(比較例18)についての安定性データを参照) において見出されるよりも有意に少ない量でこのような不純物を生成する オキサリプラチンのより安定な溶液組成物が,オキサリプラチンの溶液組 成物に有効安定化量の緩衝剤を加えることにより得られることを,出願人 は予想外にも見出したのである。」などと記載し,緩衝剤が添加されるも\nのであること及び実施例18が比較例であることを前提とした主張をして いたことが認められる。 また,証拠(甲36)によれば,本件特許に対応するブラジル特許出願 に関し,出願人が,ブラジル特許庁に提出した拒絶処分に対する不服申立\nてにおいて,「本願発明にあるシュウ酸を緩衝剤として加えれば,不純物 が発生しないということである。」と,緩衝剤を添加する旨の主張をして いたことが認められる。 これらのことは,本件発明2においても,緩衝剤とは添加されたものに 限られると解されることの裏付けとなる事実であるというべきである。
◆判決本文
関連事件(同一特許、異被告)です。
◆平成27(ワ)29158
同一特許の別訴事件で、1審(平成27(ワ)12416号)では技術的範囲内と判断されましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.11.12
平成28(ワ)15355 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 民事訴訟 平成28年10月31日 東京地方裁判所
a 以上のとおり,本件明細書が,「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物」 を従来技術として開示し,これよりも,本件発明1の組成物は「生成される不純物, 例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体が少ない ことを意味する。」と記載していること,解離シュウ酸は,オキサリプラチンが溶 液中で分解することにより,ジアクオDACHプラチンと対になって生成されるも のであること,本件発明1の発明特定事項として構成要件1Gが限定する緩衝剤の\nモル濃度の範囲に関する具体的な技術的裏付けを伴う数値の例として,本件明細書 は,添加されたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの数値のみを記載し,解離シュウ 酸のモル濃度を何ら記載していないこと,本件明細書には,専ら,「緩衝剤」を外 部から添加する実施例のみが開示されていると解されること,請求項1は,「シュ ウ酸」と「そのアルカリ金属塩」とを区別して記載し,さらには「緩衝『剤』」と いう用語を用いていることなどをすべて整合的に説明しようとすれば,本件発明1 における「緩衝剤」は,外部から添加されるものに限られるものと解釈せざるを得 ない。
すなわち,本件発明1は,専ら,オキサリプラチン水溶液に,緩衝剤として,シ ュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加(外部から付加)することにより,オキサリ プラチン溶液中のシュウ酸濃度を人為的に増加させ,平衡に関係している物質の濃 度が増加すると,当該物質の濃度が減少する方向に平衡が移動するという原理(ル シャトリエの原理)に従い,結果として,オキサリプラチン溶液中におけるジアク オDACHプラチン及びジアクオDACHプラチン二量体などの望ましくない不純 物の量を,シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加(外部から付加)しない場合よ りも,減少させることを目した発明と把握するべきであり,そのように把握するこ とにより,初めて,本件明細書の段落【0031】が「本発明の組成物は,オキサ リプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明して おり,このことは,オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明 の組成物中に生成される不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオ DACHプラチン二量体が少ないことを意味する。」と記載していることや,本件 明細書には,シュウ酸又はシュウ酸ナトリウムを,構成要件1Gが規定する数値の\nモル濃度だけ,オキサリプラチン溶液に「添加」する実施例のみが開示されている こと,さらには,本件明細書に開示された実施例において,解離シュウ酸の量を明 記していないことや,他の不純物の量から解離シュウ酸の量を推計することを示唆 する記載すらないことなどを整合的に説明できるのである。 また,オキサリプラチン溶液に,緩衝剤として,シュウ酸又はそのアルカリ金属 塩を添加(外部から付加)して得られたオキサリプラチン溶液組成物は,これを添 加しないオキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも,ジアクオDACHプラ チン及びジアクオDACHプラチン二量体などの望ましくない不純物の量が減少す るから,客観的構成において異なる(すなわち,「物」として異なる。)ことにな\nるということもできる。
b 他方で,仮に,本件発明1を上記のように解することなく,原告らが主張す るように,解離シュウ酸であってもジアクオDACHプラチン及びジアクオDAC Hプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させているとみなすというのであれば, 本件発明1は,本件優先日時点において公知のオキサリプラチン溶液が生来的に有 している性質(すなわち,オキサリプラチン溶液が可逆反応しており,シュウ酸イ オンが平衡に関係している物質であるという,当業者には自明ともいうべき事象) を単に記述するとともに,当該溶液中の解離シュウ酸濃度として,ごく通常の値を 含む範囲を特定したものにすぎず,新規性及び進歩性を見いだし難い発明というべ きである。すなわち,本件優先日時点において,例えば,濃度が5mg/mLのオ キサリプラチン水溶液が公知であった(乙1の1)。そして,当該水溶液中のオキ サリプラチンが分解して解離シュウ酸が生成されることは,その生来的な性質であ り(本件明細書の段落【0013】ないし同【0016】参照),シュウ酸が平衡 に関係している物質であることも同様であるところ,種々の条件下である程度の期 間保存された濃度5mg/mLのオキサリプラチン水溶液中には,解離シュウ酸が 存在し,その量が,5x10−5M以上となることが多いことが,乙13の3試験,甲2 0試験(「5x10−5M」として,有効数字を1桁とする以上,「4.86x10−5M」又は 「4.94x10−5M」も,「5x10−5M」とみて差し支えない〔乙12参照〕。),乙3 2試験及び乙37試験の各結果から,さらには,本件特許権に係る原告デビオファ ームの延長登録出願の願書(乙33)の記載から認められる(なお,上記認定は, 上記各試験が乙1の1実施例の追試として妥当であるか否かはともかく,少なくと も,公知の組成物である濃度5mg/mLのオキサリプラチン水溶液において,解 離シュウ酸のモル濃度が5x10−5M以上となることは,ごく通常のことであると認め るのが相当であることを指摘したものである。)。そうすると,公知の組成物であ るオキサリプラチン水溶液中に存在し,同水溶液の平衡に関係している物質である シュウ酸イオン(解離シュウ酸)に,「平衡に関係している」という理由で「緩衝 剤」という名を付け,上記のとおり通常存在しうる程度のモル濃度を数値範囲とし て規定したにとどまる発明は,公知の組成物と実質的に同一の物にすぎない新規性 を欠く発明か,少なくとも当業者にとって自明の事項を発明特定事項として加えた にすぎない進歩性を欠く発明というほかはない。
c したがって,本件発明にいう「緩衝剤」には,オキサリプラチンが溶媒中で 分解して生じたシュウ酸イオン(解離シュウ酸)は含まれないと解するのが相当で ある。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.10.28
平成28(ネ)10042 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年10月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明の「押付部材」は,少なくとも一部に球状面を有するものでは足りず,その全体が球であるものに限られるということができる(仮に,一部にのみ球状面を有するものが含まれるとすれば,本件特許は違法な分割出願によるものとして新規性欠如の無効理由を有することが明らかである。)。
判決文の最後に、イ号と本件発明の対比図面が掲載されています。
証拠(甲4,甲32の1・2,乙38,54)及び弁論の全趣旨によれば,被告 製品の技術的意義につき,以下のとおり認められる。 プランジャーピンは,その大径部に略円錐面形状を有する傾斜凹部を備えている ものであるが,コイルバネにより付勢されて本体ケースの内周面に左右2箇所で接 触するように設計されている。コマ状部材は,導電性を有するものであり,その球 状部がプランジャーピンの大径部の傾斜凹部を押してこれと1点のみで接触するこ とによって傾き,本体ケースの内周面に左右2箇所で接触するように構成されてい\nる。プランジャーピン及びコマ状部材が確実に傾いて本体ケースに接触するよう, コマ状部材の中心軸とプランジャーピン底面の最深位置は,オフセットされている。 このように合計4つの電流経路を確保することにより,被告製品の電気抵抗が低 減し,被告製品を流れる電流についてコイルバネを通る経路以外の経路が存在しな いという事態が生じる可能性は低くなり,コイルバネに流れる電流量が抑えられる。\n加えて,コイルバネが●●●●●●●によって被覆されていることから,絶縁性ボ ールを使用する必要はない。 他方,本件発明においては,前記(2)のとおり,1)傾斜凹部を略円錐面形状とする ことによって,押付部材の球状面からなる球状部の中心を傾斜凹部の中心軸上に安 定して位置させることができ,それにより,押付部材を介してプランジャーピンに 伝達されるコイルバネの付勢に係る力の方向を安定させ,2)さらに,傾斜凹部の中 心軸をプランジャーピンの中心軸とオフセットさせることにより,コイルバネがプ ランジャーピンを本体ケースの中心軸に対して微小な角度を有する方向に付勢する ことを確実なものとすることによって,プランジャーピンの大径部を確実に本体ケ ースの管状内周面に接触させて本体ケースへ確実に電流を流すことを可能とするも\nのである。 以上によれば,被告製品と本件発明とは,押付部材とプランジャーピンとの接触 に関し,技術的意義を異にするものということができる。
(ウ) 控訴人の主張について
a 控訴人は,コマ状部材とプランジャーピンの材料である金属は,弾性変化す るものであるから,両部材は,必ず面で接触し,点で接触することはあり得ない旨 主張する。 しかし,甲第52号証によれば,球と平面が接触する場合,理論的には,接触部 分は点であり,接触面積を持たないものの,実際には,接触部分が変形することに よって接触面積を持ち,接触部の形状が円になり,このような接触は,「点接触」と 呼ばれる。前記(イ)において,被告製品のコマ状部材の球状部がプランジャーピン の大径部の傾斜凹部と1点のみで接触するというのも,上記点接触の趣旨であり, 控訴人主張に係る弾性変化した状態の接触を排除する趣旨ではない。
b 控訴人は,甲第4号証を根拠として,被告製品のコマ状部材は,コイルバネ から押圧されてその弾性力を受け止めており,同弾性力がコマ状部材と本体ケース との間の摩擦力よりも大きいときは,空滑りして傾かず,本体ケースに接触しない 旨主張する。 しかし,甲第4号証に掲載された被告製品の写真からは,コマ状部材が本体ケー スにわずかでも接触しているか,全く接触していないかは,必ずしも明らかではな い。また,コマ状部材の中心軸とプランジャーピン底面の最深位置がオフセットさ れていることに鑑みると,通常,コマ状部材が本体ケースに接触しないという事態 が頻繁に生じることは考えにくく,そのような事態は,被告製品の通常の用法にお いて想定されていないものと考えられる(乙54参照)。
c 控訴人は,プランジャーピンに流れる電流の総和は決まっているので,プラ ンジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができれば,コイルバネに流 れる電流量を相対的に減じることができ,コイルバネの焼切れの防止にもつながる 旨を主張する。 しかし,上記主張のとおりであったとしても,本件明細書には,被告製品のよう にプランジャーピンと本体ケースとの接触に加え,押付部材であるコマ状部材と本 体ケースとの接触により合計4つの電流経路を確保することによって被告製品の電 気抵抗を低減させるという技術的思想は,開示されていない。
d なお,控訴人は,乙第38号証に掲載された被告製品のプランジャーピンの 図においては,底部の形状が傾斜凹部をなしていないが,これは,正確なものでは なく,甲第32号証の1・2が,被告製品の正確な設計図である旨主張する。しか し,控訴人が指摘する乙第38号証の図面は,「マッシュルーム要素及びプランジャ ーの形状を大まかに描写した断面図」(乙38)であり,甲第4号証及び乙第38号 証に掲載された被告製品の写真並びに控訴人が被告製品の正確な設計図である旨主 張する甲第32号証の1・2により,前記(イ)のとおり認定することができる。
イ 構成要件Dの「押付部材」に該当する構\成の有無
前記アのとおり,被告製品のコマ状部材は,それ自体が本体ケースの内周面に左 右2箇所で接触して電流経路を確保している。 他方,前記(1)のとおり,本件明細書において,「押付部材」につき,小型化の要請 にこたえて接触端子の径(幅)を大きくすることなく,コイルバネを流れる電流量 を小さくしながら,比較的大きな電流を流し得る接触端子の提供という,本件発明 の課題を解決するための構成として,「大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部」内\nに収容されていることが開示されている。本件明細書において,「押付部材」自体が 本体ケースに接触して電流経路を確保することは,開示されていないものというべ きである。 したがって,被告製品のコマ状部材は,構成要件Dの「押付部材」に該当しない。\nほかに,被告製品の構成中,「押付部材」に相当するものはない。
ウ 「押圧」について
前記アのとおり,被告製品は,プランジャーピン及びコマ部材が確実に傾いて本 体ケースに接触するよう,コマ状部材の中心軸とプランジャーピン底面の最深位置 をオフセットしている。被告製品のコマ状部材の球状部がプランジャーピンの大径 部の傾斜凹部を押してこれと1点のみで接触することによって傾き,本体ケースの 内周面に左右2箇所で接触するという構成自体からも,通常,コマ状部材の球状部\nの中心が,プランジャーピン底面の最深位置,すなわち,傾斜凹部の中心軸上に位 置することは,考え難い。現に,別紙2は,コイルバネの付勢によって,コマ状部 材の球状部がプランジャーピンの大径部の傾斜凹部を押し,それによって,プラン ジャーピンの突出端部が本体ケースから突出するとともに,プランジャーピンの大 径部の外側面が本体ケースの内周面に押し付けられている状態であるが,コマ状部 材の球状部の中心は,明らかに傾斜凹部の中心軸からずれている。 よって,コマ状部材の球状部がプランジャーピンの傾斜凹部を押すことは,コマ 状部材の球状部の中心を傾斜凹部の中心軸上に安定して位置させるものではないか ら,構成要件Dの「押圧」に該当せず,ほかに,被告製品の構\成中,「押圧」に該当 するものはない。
・・・
しかし,特許請求の範囲に記載された構成中,相手方が製造等をする製品又は用\nいる方法と異なる部分が存する場合において,均等侵害の成立が認められるために は,上記異なる部分の全てについて均等の5要件が満たされることを要する。 前記2のとおり,本件特許請求の範囲に記載された構成と被告製品とは,1)構成\n要件Dの「押付部材」につき,本件明細書において,小型化の要請にこたえて接触 端子の径(幅)を大きくすることなく,コイルバネを流れる電流量を小さくしなが ら,比較的大きな電流を流し得る接触端子の提供という,本件発明の課題を解決す るための構成として,「大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部」内に収容されてい\nることが開示されており,「押付部材」自体が本体ケースに接触して電流経路を確保 することは,開示されていないのに対し,被告製品のコマ状部材は,それ自体が本 体ケースの内周面に左右2箇所で接触して電流経路を確保している点において異な るほか,2)構成要件Dの「押圧」は,押付部材の球状面からなる球状部の中心を傾\n斜凹部の中心軸上に安定して位置させるものであるのに対し,被告製品のコマ状部 材の球状部がプランジャーピンの傾斜凹部を押すことは,コマ状部材の球状部の中 心を傾斜凹部の中心軸上に安定して位置させるものではない点においても異なる。 控訴人は,これらの相違点のうち,構成要件Dの「押付部材」が球形であるのに\n対し,被告製品のコマ状部材が球形ではないという点についてのみ均等の5要件を 主張するにとどまるから,主張自体,失当である。 なお,前記2(4)のとおり,被告製品と本件発明とは,押付部材とプランジャーピ ンとの接触に関し,技術的意義を異にするものということができる。そして,前記 1のとおり,本件明細書には,従来技術として,金属製の本体ケースに設けられた 長穴にコイルバネを挿入した上でプランジャーピンを挿入し,本体ケースからプラ ンジャーピンの先端部分のみが突出する位置を保持されるという接触端子において, プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球を介在させ,プランジャーピンの本 体ケース内の端部が斜面となっていて,絶縁球がプランジャーピンを本体ケースの 長穴の内面に押し付けることができるようになっており,これによって,プランジ ャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができるとの構成が開示されてい\nる(【0002】,【0004】,【0006】)。したがって,本件発明においては,前記2のとおり,1)プランジャーピンの大径部に,単なる斜面ではなく,略円錐面形 状の傾斜凹部を設け,押付部材の球状面からなる球状部の中心を傾斜凹部の中心軸 上に安定して位置させるよう「押圧」すること及び2)傾斜凹部の中心軸をプランジ ャーピンの中心軸とオフセットさせることによって,コイルバネが,押付部材を介 して,プランジャーピンを本体ケースの中心軸に対して微小な角度を有する方向に 付勢することを確実なものとすることによって,プランジャーピンから本体ケース へ確実に電流が流れるようにすることが,従来技術に見られない,特有の技術的思 想を構成する特徴的部分に当たるというべきである。\n前記2によれば,本件発明と被告製品は,上記本質的部分において相違すること が明らかであるから,均等侵害の成立を認める余地はない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2016.10.11
平成27(ワ)7147 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年9月15日 大阪地方裁判所
すなわち均等侵害が認められるためには,本件発明と被告方法の構成に異な\nる部分が存在する場合であっても,その部分が本件発明の本質的部分ではないこと が要件となるところ,ここでいう特許発明における本質的部分とは,当該特許発明 の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成す\nる特徴的部分であると解すべきであり,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明 細書の記載に基づいて,特許発明の課題及び解決手段(特許法36条4項,特許法 施行規則24条の2参照)とその効果(目的及び構成とその効果。平成6年法律第\n116号による改正前の特許法36条4項参照)を把握した上で,特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴\n的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(知財高裁平成 28年3月25日特別部判決)。
・・・
本件発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと,本件発明は,本件 特許の特許請求の範囲請求項1の発明に係るおかゆ調理器を用いたおかゆの調理方 法として,「粉砕段階」,「加熱段階」を含む複数の動作段階を設定し,それら動 作段階の一部についてはその順序,時間,回数等を具体的に指定し,穀物の粉砕手 段及び加熱手段を一体化した組合せとすることにより,通常のおかゆの調理方法に おいて時間を要していたふやかしの時間及び全体の調理時間の短縮を図り,また, 通常の調理方法においてはかきまぜの継続によって解消していたおかゆの焦げ付き も防止するなど,より簡便,迅速に本来の風味を有するおかゆの調理ができるよう にしたものであると認められる。 ところでおかゆの調理方法として,加熱や粉砕の動作を適宜組合せることは,周 知であるから(本件明細書の【0005】),本件特許の特許請求の範囲請求項1 の発明に係るおかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法である本件発明における本質 的部分とは,調理方法を決定するところの「粉砕段階」,「加熱段階」,「待機段 階」という一連の動作段階の設定,及び各動作段階において具体的に規定された粉 砕及び加熱の動作並びに待機の順序,各動作及び待機の時間,各動作及び待機の回 数等を一体化した組合せそのものにあると認められる。 (6) これに対し,被告方法は,既述のとおり,少なくとも,その第1及び第2の 粉砕段階において,本件発明の構成要件として規定された粉砕と待機とは異なる時\n間,回数の粉砕と待機がなされるものであるから,動作等の組合せにおいて,本件 発明の一体化した組合せとは異なっており,この相違部分は本件発明の本質的部分 に存するものといわなければならない, したがって,被告方法は,均等の第1要件を充足するとは認められない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2016.10. 4
平成27(ネ)10016 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年9月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 前記2のとおり,1)本件発明1−1は,一次原反ロールから薬液が塗布され た二次原反ロールに至るまでの積層手段,薬液塗布手段,スリット手段及び巻取り 手段が順に連続した1つの製造ラインに組み込まれ,同製造ライン上をシートが上 記各手段を経ながら間断なく流れるように構成された二次原反ロールの製造設備で\nあるプライマシンを備えているのに対し,2)被告設備は,一次原反ロールから薬液 が塗布された二次原反ロールに至るまでの間,一次原反ロールRから積層連続シー トSを形成する積層手段であるシート合わせロール10,積層連続シートSをスリ ットするスリット手段であるスリッター101及びスリットされた積層連続シート Sを巻き取ってロール102とする巻取り手段である巻取り装置131から成る製 造ラインと,上記製造ラインとは別に設けられた薬液塗布手段であり,同製造ライ ンから移送されたロール102から繰り出される積層連続シートSに薬液を塗布す る薬液塗布装置11及び薬液が塗布された積層連続シートSを再度巻き取って二次 原反ロールRとする巻取り手段である巻取り装置132から成る製造ラインに分か れている。 そこで,本件発明1−1において一次原反ロールから薬液が塗布された二次原反 ロールを製造するプライマシンを,被告設備における上記2つの製造ラインと置き 換えても,本件発明1−1の目的を達成することができ,同一の作用効果を奏する かについて検討する。
イ 前記1のとおり,本件発明1−1の課題は,薬液塗布工程をプライマシンや マルチスタンド式インターフォルダとは別に設ける構成を採用した場合に起きる,\n薬液塗布のために原反を移送する手間や多大な設備コストが掛かるという問題の発 生を回避し,同構成よりも低コストで薬液塗布を行うことができ,かつ,薬液塗布\nの有無を容易に切替え可能である製造設備を提供することであり,その解決手段は,\n一次原反ロールから薬液が塗布された二次原反ロールに至るまでの積層手段,薬液 塗布手段,スリット手段及び巻取り手段が順に連続した1つの製造ラインに組み込 まれ,同製造ライン上をシートが上記各手段を経ながら間断なく流れるように構成\nされたプライマシンを備える構成とすることである。同構\成の採用によって,薬液 塗布手段をプライマシンやマルチスタンド式インターフォルダとは別に設ける場合 と比較して,その場合に起きる,薬液塗布のために原反を移送する手間や多大な設 備コストが掛かるという問題の発生を回避し,設備コストをより低く抑えることが でき,また,薬液を塗布しない製品を製造する場合は,プライマシンから薬液塗布 手段を省略すれば足りるので,薬液塗布の有無を容易に切り替えることができると いう効果を奏する。
ウ そして,被告設備は,前記アのとおり,一次原反ロールから薬液が塗布され た二次原反ロールに至るまでの間,一次原反ロールRからロール102を形成する 製造ラインとは別に,薬液塗布装置11が設けられており,上記製造ラインから原 反(ロール102)を薬液塗布のために薬液塗布装置11に移送するというもので ある。したがって,本件発明1−1において一次原反ロールから薬液が塗布された 二次原反ロールを製造するプライマシンを,被告設備における2つの製造ラインと 置き換えれば,少なくとも,本件発明1−1の目的のうち,薬液塗布工程をプライ マシンやインターフォルダとは別に設ける構成を採用した場合に起きる薬液塗布の\nために原反を移送する手間が掛かるという問題の発生を回避し,同構成よりも低コ\nストで薬液塗布を行うことができる製造設備を提供するという目的を達成すること ができず,薬液塗布手段をプライマシンやマルチスタンド式インターフォルダとは 別に設ける場合と比較して,その場合に起きる薬液塗布のために原反を移送する手 間が掛かるという問題の発生を回避し,設備コストをより低く抑えることができる という効果を奏しなくなることは,明らかである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> ピックアップ対象
2016.09. 8
平成26(ワ)25928 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年8月30日 東京地方裁判所
ウ さらに,本件特許の出願経過からも上記解釈は裏付けられる。すなわち, 原告は,本件特許の審査段階において,特許庁から平成15年1月21日 発送の拒絶理由通知(乙8)を受けたところ,そこには「…請求項1の記 載では本願発明の目的である通過すべき経由地点の設定中にすでにそれら の経由地点のいずれかを通過してしまった場合でも,正しい経路誘導を行 うための構成である『設定指令が入力された時点での車両現在位置を探索\n開始地点として記憶し,この記憶された探索開始地点と,経路データが設 定され移動体の経路誘導が開始される時点での移動体の現在位置を比較す る』点が明確に記載されていない。…よって,請求項1は,特許を受けよ うとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではな\nい。」とされていた。原告は,上記拒絶理由通知に対応して,同年2月5 日受付の意見書(乙9)を提出し,そこにおいて「審査官殿のご指摘の通 り,本願発明における探索開始地点と経路誘導地点に関する上述の点が不 明瞭であると考えますので,『設定指令が入力され,経路の探索を開始す る時点の前記移動体の現在位置を探索開始地点として記憶する記憶手段』 と構成要件を加えることにより,探索開始地点が記憶されることを明確に\nするとともに,経路データ設定手段が『記憶した探索開始地点を基に経路 の探索を行い,当該経路を経路データとして設定する』と補正して探索開 始地点と経路データの関係を明確にし,制御手段おける記憶された探索開 始地点と誘導開始地点を比較する点を明確に致しました。」(1頁下9行 〜2行)と記載し,併せて,同日受付の手続補正書(乙10)を提出して 上記記載に沿った補正を行い,探索開始地点と誘導開始地点とを比較する ことを明確にしたものである。以上の出願経過も,構成要件Gに係る上記\n解釈を裏付けるものである。
(2) しかるところ,被告装置において,「探索開始地点」と「誘導開始地点」 を比較して両地点が異なるかどうかを判断しているものと認めるに足りる証 拠はない。 かえって,証拠(乙16の1)によれば,被告装置においては,1)経路誘 導の計算が行われ,これが終了すると,出発地点P0から目的地Pnまでの 経路を示す経路リンクのリストがメモリに保存され,2)他方で,上記1)の経 路誘導とは独立して,継続的に,車両の現在位置Cと地図データの地図リン クとのマッチングが行われ,その際,車両の現在位置Cと,地図データのノ ード間を結ぶ地図リンクとを比較することで,車両の現在位置Cと一致する 地図リンクを特定し,3)上記2)のマップマッチングで特定されたリンクが上 記1)の経路リンクの一つと直接対応すると,道路境界領域の処理は行われず, その代わりに地図リンクと一致する経路リンクに基づいて誘導が行われ,他 方で,現在位置Cが,マップマッチングによって特定された経路リンクに載 っていない場合,所定の方法で絞り込んだ道路境界領域内のリンクと現在位 置とを比較してリンク上に載っているか否かの判定をするとの作業が行われ ていることが認められる。 なお,乙16の1は,補助参加人の関連会社所属のエンジニアが作成した 宣誓書であるが,同記載内容は,被告装置の制御に関する他の証拠とも矛盾 がなく,これを特段疑う理由もないから,信用できるものといえる。 以上からすれば,被告装置では,探索開始地点と誘導開始地点とを比較し て両地点が異なるか否かを判断するという作業は行われず,あくまで,車両 の現在位置が所定の経路リンク上に載っているか否かが判定されているにす ぎないから,被告装置は本件発明の構成要件Gを充足しないものというべき\nである。
・・・・
このように,本件発明が,車両が動くことにより探索開始地点と誘導開始 地点の「ずれ」が生じ,車両等が経由予定地点を通過してしまうことを従来\n技術における問題とし,これを解決することを目的として,上記「ずれ」の 有無を判断するために,探索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点の 異同を判断することを定めており,この点は,従来技術にはみられない特有 の技術的思想を有する本件特許の特徴的部分であるといえる。 そして,本件明細書(甲2)において,上記「ずれ」を判断する方法とし て,上記両地点を直接比較する方法以外の方法は何ら記載されておらず,そ れ以外の方法が想定されていたとは認められない。 また,前記2(1)ウ認定の本件特許に係る出願経過からも,探索開始地点 と誘導開始地点とを比較して両地点の異同を判断することが本件発明の本質 的部分であることは明らかである。 なお,原告自身も,本件発明においては「探索開始地点に関する情報」と 「誘導開始地点」とを比較する旨主張している(原告第9準備書面9頁参照) ところ,上記「探索開始地点に関する情報」の中核は「探索開始地点」自体 であるから,原告の上記主張を前提としても,本件特許において,探索開始 地点と誘導開始地点との比較が本質的部分であるといえる。 以上からすれば,探索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点の異同 を判断することが本件発明の本質的部分というべきであり,かつその比較方 法としては,両地点を直接比較することが当然に予定されているものであっ\nて,これに反する原告の主張は採用できない。 なお,原告は,従来技術において,経由予定地点を超えた地点となったこ\nとを判断する必要性すら認識されていなかった以上,この点に関する下位概 念的な具体的な手段まで本質的部分であるとはいえないとも主張する。しか し,前述のとおり,本件発明において探索開始地点と誘導開始地点の「ずれ」 を問題とし,その有無を判断するために,上記両地点を比較することが必須 であり,この点が本件発明を特徴付けているといえるものであって,その比 較の具体的手段が単なる下位概念であるとはいえないから,原告の上記主張 も採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2016.07. 7
平成27(ワ)6812 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月23日 東京地方裁判所
上記(ア)の本件明細書の記載によれば,圧力排出路の存在は本件発明が 解決すべき課題と直接関係するものではない。もっとも,本件発明の 効果等に関する上記 b,cの記載をみると,圧力排出路は,食材が 網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁 が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的と するものであり,汁を排出するための通路をハウジング底面において 防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余 地がある。しかし,上記の効果を奏するためには,上記通路が防水円 筒の下部縁に存在すれば足り,これをどのような部材で構成するかに\nより異なるものではない。そうすると,上記の異なる部分は本件発明 の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。
ウ 第2要件(置換可能性)について
前記イのとおり,本件発明における圧力排出路は,食材が網ドラム の底部で最終的に圧縮されて脱水される過程で生じる一部の汁が防水 円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐものである。また, これにスクリューギヤが挿入されて回転することにより,高粘度の汁 を効率的に排出することができる。 他方,前記前提事実 ウdの被告製品の構成及び別紙図17のとおり,\n被告製品のハウジングにスクリュー及び網ドラムを配置すると果汁案 内路が形成され,これが汁排出口と連通して,搾汁された汁の一部を 汁排出口へ案内する機能を果たすと認められる。また,被告製品のス\nクリュー下部に形成されたスクリューギアは,果汁案内路に挿入され て回転する(甲11)。そして,網ドラムはハウジングの上方から配置 されるものであり,果汁案内壁とハウジング底面との間に隙間が生じ ることもあり得るところ,その場合には当該隙間から汁が果汁案内路 の外側に流出するから,果汁案内路に流入した汁が内周側の防水円筒 を超えてハウジング外部に流出することはないものと考えられる。し たがって,被告製品の果汁案内路は本件発明の圧力排出路と同一の作 用効果を奏するということができる。 以上のとおり,被告製品の果汁案内路は圧力排出路と同一の作用効果 を奏するものとして,置換可能と評価するのが相当である。\nこれに対し,被告は,被告製品はハウジング底面を平坦化することに より清掃を容易にするという新たな効果が生じているから置換可能と\nはいえない旨主張する。しかし,仮にそのような効果が生じるとして も,ハウジング底面の清掃容易性は本件発明の前記課題とは無関係で あり,これをもって第2要件の充足性を否定することはできない。
エ 第3要件(置換容易性)について
本件明細書には,本件発明の実施例として,ハウジングに形成された 圧力排出路の外側のハウジング底面の上部に網ドラム底部に形成され た底部リングを載置し,その内周面と圧力排出路の外周面が上下に一 体となって,これと防水円筒の外周面により圧力排出路の上方に続く 空間を形成し,そこにスクリュー下方に突出形成された内部リング及 びその下端のスクリューギヤが挿入される例が記載されている(段落 【0045】,【0052】,【0056】,【図3A】,【図3B】)。この とき,水分(汁)の一部が内部リングと網ドラムの内部リング挿入孔 (底部リングの内側に当たる。)との間の隙間に押し込まれ,圧力排出 路に流入する(段落【0072】),すなわち,底部リング(網ドラ ム)内壁からそのまま圧力排出路の外周側の内壁を伝って圧力排出路 に流入しており,上記実施例において網ドラムの一部は圧力排出路の 外周側の壁の役割を果たしているといえる。また,本件発明と同じ技 術分野に属する搾汁機において,搾汁ケース(本件発明のハウジング に相当する。)のブッシング(同防水円筒に相当する。)の下部縁に流 路を形成せず,搾汁ケースの底部のこの部分を平坦にしたものは被告 製品の製造販売時に公知であったと認められる(甲26)。そうすると, 本件明細書の前記記載に接した当業者にとって,上記実施例の網ドラ ムないし底部リングを下方に伸長して圧力排出路の外周側の壁に代え るとともに,この部分のハウジングの底面を平坦にすることによって, 圧力排出路の外周側の壁全体を網ドラムで形成することに思い至るの は容易であるというべきである。 これに対し,被告は,ハウジングの底部を平坦にした被告製品は本件 発明と根本的に相違する旨主張するが,以上の説示に照らしこれを採 用することはできない。
オ 以上のとおり,被告製品の果汁案内路は本件発明の圧力排出路と均等で あるということができる。
・・・
3 争点 (原告の損害額)について
前記1及び2で判示したとおり被告製品は本件発明の技術的範囲に属す るところ,原告は,被告が被告製品の販売により1500万円の利益を得 たとして,特許法102条2項に基づき同額の損害賠償を請求する。これ に対し,被告は,被告製品の販売により316万9653円の損失が生じ ており,利益は得ていないと主張するところ,原告はこれに具体的に反論 せず原告主張を裏付けるに足りる証拠も提出しない。以上によれば,被告 が本件特許権の侵害行為により利益を得たと認めることはできないから, 独占的通常実施権の有無等の点について判断するまでもなく,原告の上記 請求は理由がないことになる。 本件事案の内容,経緯等に照らすと,本件において被告に負担させるべ き弁護士及び弁理士費用の額は200万円が相当であり,原告の被告に対 する本件特許権侵害による損害賠償請求はその限度で理由がある。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2016.07. 5
平成28(ネ)10017 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月29日 知的財産高等裁判所 知的財産高等裁判所
ところで,商品の基礎情報である価格等は変わる場合があるところ,顧客 の注文前に商品の基礎情報が更新された場合,Web−POSサーバ・システムが 有する情報は,更新された後の商品情報のみであるから,Web−POSサーバ・ システムは,顧客が注文した商品の価格等を把握することができない(乙20)。 また,Cookieを用いたWeb技術は,サーバ側で識別情報としてテキスト・ データをWebブラウザごとに割り当て,更に,そのテキスト・データをWebブ ラウザの情報と対応付けて管理することにより,Webサーバ側において,HTT Pリクエストの送信元を識別等するというものにとどまる(甲25)。よって,W eb−POSサーバ・システムは,Cookie情報を受信しても,顧客が注文し た商品の価格等を把握することはできない。 そして,前記(ア)のとおり,本件ECサイトの管理運営システム内のサーバは, 顧客が注文した商品の価格等を把握するために,顧客のコンピュータからリクエス ト情報とともに受信したCookie情報をもとに,顧客のコンピュータに表示さ\nれた「レジ」画面情報の原本に当たる情報を同サーバから呼び出すという制御方法 を追加で採用することにより,顧客が注文した商品の価格等を把握するに至ってい るものである。
(ウ) したがって,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する\n構成において,Web−POSサーバ・システムがCookie情報等は取得する\nものの,注文された商品に係る商品基礎情報を取得しないという本件ECサイトに おける構成を採用した場合には,本件発明のように,Web−POSサーバ・シス\nテムは,注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎情報をリアルタイム に管理することができないというべきである。
エ 小括
よって,本件ECサイトの制御方法,すなわち,オーダ操作が行われた際に,W eb−POSクライアント装置からWeb−POSサーバ・システムに送信される 情報に,注文された商品に係る商品基礎情報を含めずに,Cookie情報等を含 めるという方法では,本件発明と同一の作用効果を奏することができず,本件発明 の目的を達成することはできない。 したがって,均等の第2要件の充足は,これを認めることができない。
・・・・
前記1(2)ウのとおり,控訴人は,本件発明は,引用文献1に記載された発明に 基づいて容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定 により特許を受けることができないとの拒絶理由通知に対して,本件意見書を提 出したものである。 そして,前記1(2)ウ及びエのとおり,控訴人は,本件意見書において,引用文 献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないとい う点との相違を明らかにするために,本件発明の「注文情報」は,商品識別情報 等を含んだ商品ごとの情報である旨繰り返し説明したものである。 そうすると,控訴人は,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関\nする具体的な構成において,Web−POSサーバ・システムが取得する情報に,\n商品基礎情報を含めない構成については,本件発明の技術的範囲に属しないことを\n承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価す ることができる。 そして,本件ECサイトの制御方法において,管理運営システムにあるサーバが 取得する情報には商品基礎情報は含まれていないから,同制御方法は,本件発明の 特許出願手続において,特許請求の範囲から意識的に除外されたものということが できる。 したがって,均等の第5要件の充足は,これを認めることができない。
ウ 控訴人の主張について
これに対し,控訴人は,本件意見書において,POS管理を実現できる複数の構\n成の中から意識的にある構成を選択したり,ある構\成を排除したりしたものではな いと主張する。しかし,上記のとおり,控訴人は,本件意見書において,引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を 明らかにするために,本件発明の「注文情報」は,商品識別情報等を含んだ商品ご との情報である旨繰り返し説明していたものである。そうすると,控訴人は,本件 意見書において,本件発明のうち,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御\n過程に関する具体的な構成については,Web−POSサーバ・システムが取得す\nる情報には必ず商品基礎情報を含めるという構成を,意識的に選択したことは明ら\nかであるといえ,控訴人の上記主張は,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.07. 5
平成28(ネ)10007 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記イのとおり,控訴人は,本件特許の出願時,座席を連続して揺動させること が可能な乳幼児用の椅子等であって,揺動制御手段としてソ\レノイドを有するもの について,旧請求項1においては,座席支持機構を特段限定せず,旧請求項2にお\nいては,座席支持機構をロッド2点支持方式に限定し,旧請求項3においては,座\n席支持機構を,座席とベースとの間に,ベースに対して座席が「水平往復動可能\な スライド手段を設けたことを特徴とする」ものに限定していたものである。そして, 控訴人は,本件補正により,旧請求項1を,本件特許の特許請求の範囲から削除し, その範囲を旧請求項2及び旧請求項3に限定したものである。 このように,控訴人は,本件補正において,座席を連続して揺動させることが可 能な乳幼児用の椅子等であって,揺動制御手段としてソ\レノイドを有するものにつ いて,拒絶理由通知に対応して,座席支持機構を特段限定していない旧請求項1を\n削除し,座席支持機構にロッド2点支持方式を採用する旧請求項2(本件発明)及\nび座席とベースとの間に,ベースに対して座席が「水平往復動可能なスライド手段\nを設けたことを特徴とする」方式を採用する旧請求項3に限定したものである。そ して,本件発明の出願時には既に,座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児\n用の椅子等の座席支持機構として,コロと湾曲レールを利用した方式が存在するこ\nとは周知であり(乙3〜5),コロと湾曲レールを利用する方式に係る座席支持機 構は,上記のとおり削除された旧請求項1に係る座席支持機構\の範囲内に客観的に 含まれるものである。 したがって,控訴人は,コロと湾曲レールを利用する方式に係る座席支持機構に\nついても,本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそ のように解されるような行動をとったものと評価することができる。 よって,均等の第5要件の充足は,これを認めることができない。
エ 控訴人の主張について
控訴人は,本件特許の出願当時,動力機構としてソ\レノイドを用い,座席支持機 構としてコロと湾曲レールを利用するという各構\成を組み合わせた乳幼児用の椅子 等は存在せず,また,動力機構としてソ\レノイドを用いることから生じる課題も公 知ではなかったから,本件特許の特許請求の範囲に,座席支持機構としてコロと湾\n曲レールを利用する方式も含めることは容易ではなく,さらに,拒絶理由を回避す るために,座席支持機構についてロッドを利用した方式に限定したものでもないと\n主張する。 しかし,控訴人が,本件補正において,ロッド2点支持方式等を除く方式に係る 座席支持機構を包括的に削除したとの事実の評価は,客観的に判断されるべきもの\nである。 そうすると,このような控訴人の本件補正時における具体的な認識や本件補正の 目的は,均等の第5要件の充足に関する結論を左右するものではない。
(4) まとめ
よって,均等のその余の要件の成否について検討するまでもなく,各被告製品は, 均等の第1要件及び第5要件を充足しないから,各被告製品が本件発明と均等なも のとしてその技術的範囲に属するということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.06.15
平成27(ワ)8704 特許権 民事訴訟 平成28年5月12日 大阪地方裁判所
「電子ショッピングシステム」の意義についても,本件明細書中に明確な定 義はないが,「ショッピング」が一般的な意味において売買を指すことは明らかで あるし,加えて構成要件Fからすると,この電子ショッピングには,少なくとも「注\n文」と「受注」が起きることが必要であるし,また本件明細書の【0001】には, 【発明の属する技術分野】として「本発明は,例えばレコードショップ等が加盟す るフランチャイズ制の電子ショッピングシステムに関し,インターネットを利用し た電子商取引の技術分野に関する。」とあり,さらに【発明の効果】を記載した【0 042】に「受注データにしたがって当該会員に商品を引き渡すと共に代金を受領 することにより,自らホームページを所持しなくても,インターネットを利用した 商取引が可能となる。」とあることから,ここにいう「電子ショッピングシステム」\nとは,インターネットを利用してされる有償の商品の取引を指すものと解するのが 相当であり,その取引においては,「注文」と「受注」,すなわち売買契約締結に 向けて顧客からの具体的法律行為がなされ得ることが必要であると解される。 これに対し,原告は,電子ショッピングシステムの定義について,商品の広告, 受発注,設計,開発,決済などのあらゆる経済活動と捉えるもので,商品の宣伝で あってもこれに含まれる旨主張するところ,確かに,本件明細書には,「電子ショ ッピングシステム」でなす経済活動について,「電子商取引」(【0001】,【0 005】,【0038】,【0043】),「商取引」(【0013】,【004 2】)などとする記載があり,さらに証拠(甲19ないし21)によれば,「電子 商取引」の定義については上記原告主張に一部沿うものが認められる。 しかし,「宣伝」に触れる記載(甲19)は,取引ではなく,インターネット上 の商行為について触れるものであるし,「広告」を含む通商産業省の定義(甲20) は,その当時の郵政省の定義とは異なることからすると,これは省庁の規制目的で 対象範囲の定義をしていると理解でき,直ちに一般的に通用する定義に結びつくも のとはいえない。 そして,そもそも,ここでは本件発明の構成要件にいう「電子ショッピングシス\nテム」の定義を問題にしているのであるから,上記説示のとおり本件明細書の記載 を考慮して解すべきであって,したがって,「電子ショッピンング」に,少なくと も原告の主張するような宣伝,広告までを含んで解することはできないというべき である。 (イ) これを前提に被告システムにつき検討するに,被告システムは,前記認定の とおり,顧客は各提携企業のホームページにおいて,講演会の講師を選択し,当該 講師の「講演を依頼する」タグを選択することにより現れる問合せ画面に名称,住 所,電話番号等の自らを特定する情報を記載し,さらに講演の希望内容を入力する などして送信すると本部のサーバーがこれを受信し,それに伴って各提携企業サー バーにeメールが送信されることで各提携企業が得る上記情報を基に,顧客を訪問 する,電話ないしメール等で連絡を取り合うなど営業活動をして,顧客の希望に沿 った講演会の内容・レベル・対象・講師・構成などを聴取し,顧客と契約できるよ\nう交渉を行うという方式である。 すなわち,被告システムの役割は,講演開催運営を取り扱う各提携企業に対し, 講演開催希望者がインターネットを使ってアクセスするホームページを設けて,そ の潜在的需要を顕在化させ,もって各提携企業が営業活動をすべき講演開催希望者 の情報を得ることができるというところまでであり,その後の講演開催実現に至る までの営業活動は,インターネット外,すなわち被告システム外の接触交渉が予定\nされているというものである。また,その機会における顧客が被告システムを利用 して「お問い合わせ(講演依頼)」をする行為は,漠然とした講演開催希望に基づ くものであってもよく,したがって,これにより提携企業との間で講演開催に向け ての交渉が開始されたとしても,それだけでは当事者間に法的な関係が直ちに生じ たとはいえないから,被告システムは,それは最終的に締結されるだろう講演開催 委託契約に向けての各提携企業の営業活動の契機を与えるものにすぎないものとい える。そして,このように見ると,被告システムでされている内容は,潜在的需要 者をインターネットでアクセスさせ,その潜在的な需要を顕在化させ,その情報を もとに実際の営業活動に結びつけるという,一般的な広告宣伝の手法と何ら変わら ないものといい得る。 なお,被告システム利用者の中には,希望講師のみならず講演会開催の日時,場 所とも確定して利用する者が含まれることはあり得るところ,その場合,そのよう な「お問い合わせ(講演依頼)」によるアクセス行為は,商品購入の注文に極めて 似ているといえるが,その場合であっても,被告システムを介して,そのアクセス を受けた各提携企業は,自らが講演する主体ではなく,また掲載講師のスケジュー ルを管理している主体とも認められないから,直ちに承諾,すなわち「受注」する ことができるわけではなく,その後,講師との関係を調整して,具体的講演開催に 向けて交渉を重ねる必要があるはずであって,したがって,利用者の 「お問い合わ せ(講演依頼)」をいかに具体化しても,これを売買契約における「注文」に準じ るものということができるわけではない。 したがって,被告システムは,構成要件Aにいう「電子ショッピングシステム」\nには相当しないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.05.11
平成26(ワ)26079 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年4月27日 東京地方裁判所
この点,原告は,情報処理技術分野における用語法などからすれば,「選択」 には全てを選択することが含まれると主張し,ユーザ端末が全部のサブバンドを選 択することもこれに該当する旨主張する。 しかし,仮に,本件各発明に関連する技術分野において「選択」との文言が上記 のように用いられることがあるとしても,加入者が全部のサブバンドの差分CQI を報告する以外の選択肢がなく,常に全部のサブバンドの差分CQIを報告しなけ ればならない状態についてまで,「選択」の語義に含まれると解するのは妥当でな い。前記前提事実に記載のとおり,被告通信システム方法及び被告製品においては, 基地局により本件モードを選択している以上,加入者は,基地局からのパイロット 信号に対し,全てのサブバンドの差分CQIを報告する以外に選択の余地はないの であるから,原告の上記解釈は採用することができない。 また,原告は,本件明細書の段落【0028】,【0040】,【0069】に は,全部のクラスタが選択されることを包含する内容の記載があること,実質的に も,全部のサブバンドを選択してフィードバックした方がかえってフィードバック 情報量を削減できるといえることなども主張するが,原告が掲げた本件明細書の上 記各段落の記載によっても,常に全部のクラスタについての情報を「選択」すると いう実施形態は明示されていない。なお,本件明細書の段落【0028】には, 「フィードバック内の情報の順序を基地局が知っている限り,フィードバック内の どのSINR値がどのクラスタに対応しているかを示すためにクラスタインデクス が必要になることはない。」としか記載されていないから,仮に,この実施形態が 全部のクラスタについての情報をフィードバックする実施形態を含むとしても,こ のようなフィードバックの形態と加入者による「選択」との関係が不明であり,少 なくとも,常に全部のクラスタについての情報を報告する態様を「加入者による選 択」の一形態として含むことについて,本件明細書に明確な記載はないものという べきである。かえって,原告の主張する解釈1を採用すると,本件発明4の課題解 決のための一つの構成として規定された構\成要件4F,あるいは本件発明9の課題 解決のための一つの構成として規定された構\成要件9Eにおける「前記加入者が選 択した・・・クラスタのグループの中の・・・クラスタを・・・割り当てる」との 意義が失われるというべきで,上記の解釈1は妥当でないと言わざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.05. 1
平成27(ネ)10127 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年4月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記(2)の認定事実によれば,第1手続補正前の時点では,特許請求の範囲の請求項1において,「計算」については,「Web−POSサーバ・システム」で行われるのか,あるいは,「Web−POSクライアント装置」で行われるのかを含め,発明特定事項としては何ら規定されていなかったが,控訴人は,第1手続補正によって,特許請求の範囲の請求項1において,「計算」について,「Web−POSサーバ・システム」で行われる構成に限定し,その後にした第2手続補正において,特許請求の範囲を本件請求項1の構\成要件F4のとおり補正し,この第2手続補正に基づく特許請求の範囲の請求項1(本件請求項1)について,特許査定を受けたものであるということができる。そして,第2手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1(本件請求項1)の「該数量に基づく計算」,すなわち,本件特許発明の構成要件F4の「該数量に基づく計算」は,「Web−POSサーバ・システム」では行われず,「Webブラウザ」を備える「Web−POSクライアント装置」で行われるものと解さざるを得ないことは,前記1のとおりである。そうすると,本件出願手続において,第1手続補正前の時点では,「計算」について,発明特定事項として何らの規定もされていなかった特許請求の範囲の請求項1について,控訴人は,第1手続補正により,「計算」が「Web−POSサーバ・システム」で行われる構\成に限定し,その後の第2手続補正によって,この構成に代えて,あえて「該数量に基づく計算」が「Web−POSクライアント装置」で行われる構\成に限定して特許査定を受けたものということができる。上記事実に鑑みれば,控訴人において,「該数量に基づく計算」が,被告方法のように「Web−POSサーバ・システム」で行われる構成については,本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価することができる。したがって,均等の第5要件の成立は,これを認めることができない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.04.21
平成25(ワ)29520 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月30日 東京地方裁判所
ウ 以上の本件明細書1の記載によれば,「ICSネットワークアドレス」とは, コンピュータ情報/通信アドレスとして独自に定めたアドレスの付与規則を持つI CS(統合情報通信システム)において,これを構成するアクセス制御装置,アク\nセス制御装置とユーザ物理通信回線との接続点であるICS論理端子,中継装置, VAN間ゲートウェイ及びICS網サーバ等に付与される,それぞれICS内部で 唯一の識別符号を指すものであり,かつ,このうち,ICS論理端子に付されるア ドレスは,ICSネットワークフレームを構成するネットワーク制御部に格納され,\n同アドレスが直接参照されることにより,ICSネットワークフレームがICS網 内を転送されるものを意味すると認められる。
エ しかるところ,被告システムにおける「ラベル」,すなわち網内転送ラベル (outerラベル)及びVPN識別ラベル(innerラベル)の各値は,各事業所に設置 されているCEルータが,自身が接続しているVPNサイト内部のルート情報を接 続しているPEルータに配信し,これを受信したPEルータにおいて,当該VPN に属する他の事業所を接続するPEルータやPルータに配信することを繰り返すこ とにより,特定のホストアドレスを有するVPN内部のユーザへ情報を配信する場 合に通過する経路を各々のPEルータ及びPルータが蓄積した結果決定された情報 であって,被告システムにおいて「ICS論理端子」に該当しうる「PE−CEイ ンターフェイス」に網内で唯一付された識別子であるとは認められない。 加えて,網内転送ラベル(outerラベル)の値は,あくまでPEルータ又はPル ータがMPLSフレームを転送すべき次のPルータ又はPEルータを特定するため に設定された値である上,Pルータを経由するごとに貼り替えられていくのである\nから,仮に,被告システムの「PE−CEインターフェイス」に網内で唯一付され た識別子が存在しているとしても,同識別子が網内転送ラベル(outerラベル)の 値と一致するものとは認め難い。また,VPN識別ラベル(innerラベル)は,M PLSフレームが各Pルータを転送されて受信側PEルータに到着した際に同受信 側PEルータによって参照され,これによりパケットを出力すべきPE−CEイン ターフェイスが特定されるものではあるが,あくまで受信側PEルータ内部によっ てPE−CEインターフェイスを特定するものであるから,VPN識別ラベル (innerラベル)の値が,特定のPE−CEインターフェイスに網内で唯一付され た識別子と同一の値であるとは直ちには認められず,両値の同一性を認めるに足り る的確な証拠もない。
オ なお,原告は,網内転送ラベル(outerラベル)及びVPN識別ラベル (innerラベル)の「2つのラベルに含まれる情報」や「ラベルの組合せ」をもっ て,「ICSネットワークアドレス」に該当すると主張しているようにも思われる ところ,確かに,被告システムにおいて,網内転送ラベル(outerラベル)及びV PN識別ラベル(innerラベル)が付されたパケットは,最終的に所望のPE−C Eインターフェイスを経由して特定のユーザに送信されることとなるが,上記のと おり,「ICSネットワークアドレス」とは,コンピュータ情報/通信アドレスと して独自に定めたアドレスの付与規則を持つICS(統合情報通信システム)にお いて,これを構成するアクセス制御装置,アクセス制御装置とユーザ物理通信回線\nとの接続点であるICS論理端子,中継装置,VAN間ゲートウェイ及びICS網 サーバ等に付与される,それぞれICS内部で唯一の識別符号を指すものであり, かつ,このうち,ICS論理端子に付されたアドレスは,ICSネットワークフレ ームを構成するネットワーク制御部に格納され,同アドレスが直接参照されること\nにより,ICSネットワークフレームがICS網内を転送されるものを意味するの であって,単に「所望のICS論理端子にICSユーザフレームを到達させるため に同ICSユーザフレームに付される情報」一般を包括的に含む広範な概念を指す ものとは認められないから,原告の主張は採用できない。 カ したがって,被告システムは,「ICSネットワークアドレス」を有しない から,構成要件1−1A,同1−1B及び同1−2Aをいずれも充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.04.21
平成27(ネ)10126 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年4月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これに対し,控訴人は,「手順・プロセス」が含まれていても,「構造\n・構成」に発明性を備えるものは「物の発明」であるところ,本件特許発明\nは,「テーブル」と「緩衝材」によって構成される「構\造」によって,本件 明細書に記載された発明の作用効果を得ることを目的とする「物の発明」で あって,テーブルを「設置し」と建築物等を「配置する」の前後関係は,技 術的には何ら価値がなく,本件特許発明の構成要件ではないなどと主張する。\n しかしながら,これらの控訴人の主張は,あくまでも,本件特許発明にお ける「地盤強化工法」が構造ないし構\成を意味することを前提とするもので あり,前記アのとおり,かかる「地盤強化工法」が工事の方法を指すと解さ れる以上,控訴人の上記主張は,その前提において採用することができな い。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.04. 1
平成27(ネ)10107 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これらの記載によれば,本件特許発明1の特徴となる技術的意義の一 つは,弾性腕の接触部についての有効嵌合長が短くなるという課題を解決するため に(【0005】【0008】),複数の弾性腕が,いずれも,端子の基部から接触線 に沿って平行に延びるという解決手段を採用することによって(【0013】,【00 25】,【0042】),端子の基部から延びる弾性腕が接触線を跨ぐことで相手端子 と当接することを防ぎ,その結果,各弾性腕を長く形成することができ(【0013】), そのため,有効嵌合長を大きく確保することができるという効果を奏する(【001 9】)ものであるから,弾性腕が,端子の基部から接触線に沿って平行に延びること は,本件特許発明1の効果を奏するために必要となる,特徴的な構成であると認め\nられる。 これに対し,本件特許発明1において,弾性腕の間に設けられた中央壁15は, 実施例で言及されているだけであるから,本件特許発明1において発明特定事項と なる必須の構成ではなく,また,本件特許1の明細書に従来技術に関する文献とし\nて掲げられた特開平8−236187号公報(甲19)に加え,特開2003−1 68505号公報(乙12),特開平6−76896号公報(乙15),バーグエレ クトロニクスジャパン株式会社カタログ(乙19。平成10年1月ころ発行)から も明らかなとおり,本件特許1の出願日及び本件特許2の原出願日である平成20 年8月5日当時において,コネクタでは,2つの端子の接触部側の間に,相手端子 を当接して停止させる効果をもたらす中央壁が必ず設けられるという技術常識は存 在しないから,当業者にとって,上記中央壁の設置が当然の構成ということもでき\nない。そして,中央壁が存在しない場合には,弾性腕の根元部分が接触線を跨ぐと, 有効嵌合長が短くなるし,仮に,中央壁を設ける場合であっても,弾性腕の根元部 分が中央壁よりも常に高い位置に設けられるとは限らないから,例えば,弾性腕の 最も根元の部分が,中央壁よりも低い位置から開始し,かつ,接触線に対して端子 溝側にある場合であっても,弾性腕が屈曲形状を有していて,中央壁よりも高い位 置で接触線を跨ぐときには,有効嵌合長が短くなることも想定され,したがって, 有効嵌合長の長さは,常に中央壁よりも高い弾性腕部分の長さになるわけではなく, 弾性腕の根元部分の位置や弾性腕の形状等にも左右される。本件特許1の明細書に 記載された従来技術としては,特開平8−236187号公報(甲19)では,相 手端子が当接する中央壁が存在しないコネクタが実施例として,特開2002−1 75847号公報(甲20)では,相手端子が当接する中央壁が設けられたコネク タが実施例として開示されているから,これらの従来技術を踏まえた本件特許発明 1は,相手端子が当接する中央壁の有無にかかわらず,有効嵌合長を長くすること を確実にする効果を目指していた発明ということができる。 そうすると,本件特許発明1は,中央壁の有無にかかわらず,有効嵌合長を大き く確保することを課題とする発明である以上,当該効果を確実に実現するためには, 弾性腕の一部だけが接触線に対して一方の側に位置すれば足りるわけではなく,そ の全体が接触線に対して一方の側に位置することが不可欠であり,複数の弾性腕全 体が接触線の一方の側にあるという発明特定事項は,本件特許発明1の本質的部分 といえる。
(エ) これに対し,被控訴人製品1,2のいずれにおいても,内側接触子2 3(「上位に位置する弾性腕」)の内側湾曲部23Aの根元部分は,直線(接触線) Xを跨っているから,弾性腕が,接触線に対して一方の側に位置しているとはいえ ない。 したがって,被控訴人製品は,本件特許発明1の本質的部分である構成要件1B\nと相違するから,均等の第1要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2016.03.30
平成26(ワ)20422 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月17日 東京地方裁判所
本件発明の「押付部材」に対応する被告製品中の「コマ」は,別紙被告ポゴ ピン断面図のとおり,球形ではなく,一部に球状の面を有するにとどまる。被 告が押付部材は球に限られるので被告製品は構成要件D2を充足しない旨主張\nするのに対し,原告は押付部材の一部(プランジャーピンの傾斜凹部に押圧さ れる部分)が球状の面であれば足りる旨主張するので,以下,検討する。 (1) まず,特許請求の範囲の記載をみるに,本件発明は,コイルバネで付勢し てプランジャーピンを突出させる接触端子に関するものであり(構成要件A\n〜C),コイルバネがプランジャーピンを直接押圧するのではなく,コイル バネとプランジャーピンの間に「押付部材」が介在し,これがコイルバネか ら付勢を受けて,その「球状面からなる球状部」がプランジャーピンの傾斜 凹部を押圧することに特徴がある(構成要件D1〜3)。\nこの「押付部材」という語は当該部材が果たす機能をそのまま記述したも\nのであるところ,その形状に関しては,プランジャーピンの傾斜凹部に押圧 される部分が「球状面からなる球状部」であるとされるのみであり,それ以 外の部分(コイルバネから付勢される部分,コイルバネ側とプランジャーピ ン側の中間部分)の形状については特許請求の範囲に何ら記載がない。そう すると,上記押圧される部分が球状に丸くなっていればそれ以外の部分はい かなる形状でもよいと解する余地がある。他方,押付部材の形状は,上記機 能を果たし得るものに限定されると考えられる上,同機能\\を果たすものであ ればいかなる形状の部材でも本件発明の技術的範囲に含まれるとすることは, 現に発明をして明細書に開示した範囲で保護を与えるという特許制度の趣旨 に反しかねない。そこで,特許請求の範囲に記載された「押付部材」の語の 意義を解釈するため,本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明の記載及び図 面を考慮することとする。
(2) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,「押付部材」との語は一 切用いられていない。本件発明の接触端子においてプランジャーピンとコイ ルバネの間に介在する部材として開示されているのは「絶縁球」のみであり, 図面に示されたのも球のみである。 すなわち,本件発明は,背景技術として,コイルバネが直接プランジャー ピンに触れるとコイルバネに電流が流れて焼き切れてしまうので,プランジ ャーピンとコイルバネの間に絶縁球を介在させた接触端子が存在したことを 前提に(段落【0002】〜【0004】),比較的大きな電流を流し得る接 触端子を提供することを目的として(同【0008】),プランジャーピンの 大径部(コイルバネ側)の端部を切削して袋孔を形成し,その底部を円錐面 とするとともに,円錐の中心軸とプランジャーピンの中心軸をオフセットさ せることによって,プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周 面に強く押し付け,確実に電流を流すことができるようにしたものである (同【0009】,【0013】〜【0015】)。そして,実施例及び参考例 をみても,押付部材に相当する部材としては「絶縁球」のみが記載されてい る(同【0024】〜【0030】,【0032】,【0036】,【0039】 〜【0042】,【図2】,【図4】,【図6】)。 以上のとおり,押付部材として本件明細書に開示されているのは球のみで あり,これと異なる形状の押付部材があり得ることを示唆する記載は見当た らない。そうすると,本件明細書の記載を考慮すると,本件発明における押 付部材の形状は球に限られると解するのが相当である。
(3)さらに,本件特許の出願経過についてみるに,後掲の証拠及び弁論の全趣 旨によれば,1)本件特許は,特願2011−192407号を優先権の基礎 とする特願2011−271985号(原出願)から分割出願されたもので あること(甲2),2)上記優先権の基礎とされた出願及び原出願は,いずれ も名称を「接触端子」とする発明に関するものであり,特許請求の範囲,発 明の詳細な説明及び図面を通じ,プランジャーピンとコイルバネの間に介在 する部材として記載されているのは「絶縁球」のみであること(乙13,1 4),3)本件特許は平成25年4月19日に分割出願されたものであり,そ の特許請求の範囲に,プランジャーピンとコイルバネの間に「押付部材」を 介在させる旨記載されたこと(乙15),4)原告は,同年10月11日,押 付部材に係る特許請求の範囲の記載を「少なくとも一部に球状面を有する押 付部材の球状部」と補正したこと(乙17),5)これに対し,同月25日, 特許法36条6項1号違反を理由1(発明の詳細な説明には押圧部材に絶縁 球を用いることが記載される一方,請求項1には絶縁性を有しない押圧部材 が記載されていること),同法29条1項3号及び2項の違反を理由2及び 3(原出願に「押付部材」として記載されていたのは「絶縁球」のみであり, これを「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」とすることは適法な分 割出願でないので,請求項1記載の発明は原出願の公開特許公報により新規 性又は進歩性を欠くこと)とする拒絶理由通知が発せられたこと(乙4), 6)原告は,同年11月8日,上記4)の補正後の特許請求の範囲の記載を「押 付部材の球状面からなる球状部」と補正する旨の手続補正書と,絶縁性を有 しない押付部材でも本件発明の効果を奏するので,発明の詳細な説明に記載 されたものといえる旨の意見書を提出したこと(乙5,6),7)同月27日 に特許査定がされたこと(乙19),以上の事実が認められる。 上記事実関係によれば,本件発明の「押付部材」は,少なくとも一部に球 状面を有するものでは足りず,その全体が球であるものに限られるというこ とができる(仮に,一部にのみ球状面を有するものが含まれるとすれば,本 件特許は違法な分割出願によるものとして新規性欠如の無効理由を有するこ とが明らかである。)。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.03.26
平成27(ネ)10014 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
この点,特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして,\n出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり,\nしたがって,出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとして\nも,そのことのみを理由として,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載し\nなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということはできな い。
なぜなら,1)上記のとおり,特許発明の実質的価値は,特許請求の範囲に記載さ れた構成以外の構\成であっても,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質\n的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び,その理は, 出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ,出 願時に容易に想到することができたことのみを理由として,一律に均等の主張を許 さないこととすれば,特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を,上記と異なるものとす ることとなる。また,2)出願人は,その発明を明細書に記載してこれを一般に開示 した上で,特許請求の範囲において,その排他的独占権の範囲を明示すべきもので あることからすると,特許請求の範囲については,本来,特許法36条5項,同条 6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を充たしながら,明細 書に開示された発明の範囲内で,過不足なくこれを記載すべきである。しかし,先 願主義の下においては,出願人は,限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを 作成し,これを出願しなければならないことを考慮すれば,出願人に対して,限ら れた時間内に,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲\nとこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される 場合がある。これに対し,特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者 は,当該特許の有効期間中に,特許発明の本質的部分を備えながら,その一部が特 許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを,特許請求の範囲と明細書等の記載か ら容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法理 は,特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行 使を容易に免れるものとすると,社会一般の発明への意欲が減殺され,発明の保護, 奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず,社会 正義に反し,衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって,上記 に述べた状況等に照らすと,出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到す\nることができたとしても,そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外と することは相当ではない。
(イ) もっとも,このような場合であっても,出願人が,出願時に,特許請求の 範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構\成中の異なる部分に代替する ものとして認識していたものと客観的,外形的にみて認められるとき,例えば,出 願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができる\nときや,出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構\成による 発明を記載しているときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しな\nかったことは,第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。 なぜなら,上記のような場合には,特許権者の側において,特許請求の範囲を記 載する際に,当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの,すなわち,\n当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的\nにそのように解されるような行動をとったものと理解することができ,そのような 理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから,特許権者が後にこれに反し て当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは,禁反言の法理\nに照らして許されないからである。
イ 控訴人らの主張について
(ア) 控訴人らは,化学分野の発明では,特許請求の範囲が客観的かつ明瞭な表\n現で規定されており,第三者にはその範囲以外に権利が拡張されることはないとの 信頼が生じるから,当該信頼は保護されるべきであると主張する。しかし,前記の とおり,均等による権利は,特許請求の範囲の文言上規定された範囲以外であって も,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者\nが容易に想到することができる技術に及び,第三者はこれを予期すべきであり,禁\n反言の法理に照らし均等の主張が許されないのは,上記特段の事情がある場合に限 られるのであって,化学分野の発明であることや,特許請求の範囲が文言上明確で あることは,それ自体では「特段の事情」として均等の成立を否定する理由とはな り得ないから,控訴人らの主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.03.14
平成27(ネ)10104 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 均等侵害の第1要件は,特許請求の範囲に記載された構成と相手方が製造等をする製品又は用いる方法との異なる部分が特許発明の本質的部分でないことであ\nる。そして,特許発明における本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された構成のうち,当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部\n分であると解すべきである。
イ 本件各発明は,前記1(4)イのとおり,HMG−CoA還元酵素阻害剤として 高脂血症の治療に有用な,結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む 医薬組成物に関し,特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの 結晶性原薬を提供すること,同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題 とし,ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコ ントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態AないしCの 中で結晶形態Aが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというもので ある。 そうすると,特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶 性原薬を提供すること,同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とす る本件各発明において,特定の結晶形態をとることが,上記課題の特徴的な解決手 段であるといえる。 そして,本件各明細書には,結晶形態AないしCの3種類の結晶形態は,水分が 同等で結晶形態が異なる形態であり,結晶形態B及びCは,「いずれも結晶形態A に特徴的な回折角10.40°,13.20°及び30.16°のピークが存在し ないことから,結晶多形であることが明らかにされる。」(本件明細書1【001 4】,本件明細書2【0015】)とあるように,CuKα放射線を使用して測定 した粉末X線回折図において,結晶形態Aに存在する3本のピークの回折角が存在 しないことによって,結晶形態Aと区別されるものであることが記載されているの みで,結晶形態B及びCに係る回折角(2θ)の数値,相対強度や粉末X線回折図 を含めその粉末X線回折パターンについての開示は一切なく,他方で,結晶形態A については,CuKα放射線を使用して測定した粉末X線回折パターンとして,別 紙本件明細書1図表目録2記載のとおりの数値が記載され,同目録3記載の【図1】の記載があるのみで,それ以上の特定はされておらず,結晶形態Aに係る回折角に\nついて,その数値に一定範囲の誤差が許容されることや15本のピークのうちの一 部のみによって結晶形態Aを特定することができることをうかがわせる記載も一切 存しない。 以上によれば,本件各発明において,構成要件C・C’に規定された15本のピークの回折角の数値は,本件各明細書において,本件各発明の課題の特徴的な解決\n手段である特定の結晶形態を,他の結晶形態,すなわち本件各発明の課題の解決手 段とはなり得ない結晶形態と画する唯一の構成として開示されたものであるということができる。\nしたがって,本件各発明において,構成要件C・C’に規定された15本のピークの回折角の数値は,本件各発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核\nをなす特徴的部分であるというべきである。
ウ そうすると,控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩 における15本のピークの回折角であるとする数値は,前記1(5)のとおり,原判決 別紙物件目録(1)記載のとおりであり,控訴人の特定する数値によったとしても,1 5本の全てが構成要件C・C’の回折角の数値と相違するのであるから,被控訴人製品は,本件各発明と課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的\n部分において相違していることになる。 以上によれば,被控訴人製品は,均等侵害の第1要件を充足しない。
(3) 均等侵害の第5要件について
ア 均等侵害の第5要件は,相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許発 明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるな どの特段の事情がないことである。
イ 前記1(3)のとおり,控訴人は,本件特許1の出願経過において,拒絶理由通 知を受け,構成要件Cの15本のピークの回折角の数値を挿入する平成23年11月29日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相\n当するものであることを表明した。また,控訴人は,本件特許2の出願経過においても,拒絶理由通知を受け,構\成要件C’の15本のピークの回折角の数値を挿入する平成25年3月8日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の 限定的減縮に相当するものであることを表明した。控訴人は,本件特許1の出願経過における拒絶理由通知において,1本のみのピ\nーク強度でしか特定されず,他のピークの特定がないので,公知文献に記載された 結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対 して,上記補正を行ったのであるから,15本のピークの回折角の数値をもって本 件発明1の結晶を特定したというほかない。 そして,本件特許2は,結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む 医薬組成物に関し,特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの 結晶性原薬を提供することを課題とし,ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に 含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上す ること及び結晶形態AないしCの中で結晶形態Aが医薬品の原薬として最も好まし いことを見いだした本件特許1を原出願とする分割出願であって,本件特許1に係 る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり,その出願 当初の特許請求の範囲の請求項1には,上記補正後の本件発明1の結晶と同じ15 本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。 以上によれば,本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は,本件各発明 の技術的範囲を,回折角の数値が15本全て一致する結晶に限定するものであると 解されるから,構成要件C・C’の15本のピークの回折角の数値と,全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は,本件各発明\nの特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。 したがって,被控訴人製品は,均等侵害の第5要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.03. 7
平成27(ワ)12748 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年2月23日 東京地方裁判所
構成要件1Iにつき,本件発明の特許請求の範囲には,「レッグレストフレーム……の当接部材」が「座席フレームの湾曲部」に「滑らかに当接」して「徐々に停止する」ものであると記載されている。この「滑らか」は,本件明細書(甲1)において定義づけられていないので,「すらすらと通るさま。つかえないさま。よどみないさま」(広辞苑〔第六版〕2103頁),「物事がよどみなく運ぶさま。すらすらと進むさま」(大辞林〔新装第二版〕1924頁)といった意味を有すると解される。また,「徐々に停止する」とは,「徐々に」が「停止」を修飾していることに照らすと,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接すると直ちに停止するのではなく,当接した後も移動を続けつつも次第に減速して停止に至ることを意味すると解される。さらに,「座席フレームの湾曲部」が座席フレームの「開放する側の両端部」にあって「下方に鈍角状に折り曲げられた」構\造を有していること(構成要件1E。なお,構\成要件1B,1E及び1Fにいう「座部フレーム」は構成要件1Iにいう「座席フレーム」と同一の部材を指すと認める。)からすれば,レッグレストフレームの当接部材に対しては,引き出す方向に対する抵抗力が次第に大きくなる一方,下方に向かう力がかかっていくと考えられる。\n以上を総合考慮すると,「滑らかに当接して徐々に停止する」とは,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても直ちに停止することなく更に引き出され続けるが,湾曲部との当接後は湾曲部から受ける力により次第に減速して,当接から多少なりとも間を置いて停止することを意味すると解される。
(2)この点につき,念のため本件明細書の記載及び本件特許の出願経過を見るに,本件明細書(甲1)においては,「発明を実施するための形態」欄において,円形当接部材が座部フレームの湾曲部の基端部に滑らかに当接すること,及び,鈍角状の上記湾曲部により徐々に停止していくので強く引き出しても衝撃がないことが記載されている(段落【0032】)。また,本件の特許出願について,引用文献(登録実用新案第3046819号公報。乙3)に基づき容易想到であるとする拒絶理由通知(乙2)に対し,原告は,特許請求の範囲(構成要件1I)に「滑らかに」を加える補正をした上,平成25年3月28日付け意見書(乙4)において,本件発明が本件明細書の上記記載のとおりの作用効果を奏するものであり,上記引用文献記載の考案は当接部が屈曲部の下側の曲線部にいきなり当接するもので,滑らかに当接し徐々に停止していくものでは全くないと述べている。\nそうすると,構成要件1Iは,レッグレストフレームを引き出した際に衝撃を感じることがないという効果を奏するために,当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても突然停止するのでなく,その後に次第に速度を落として停止することをいうものと解するのが相当であるから,前記(1)の解釈と合致するということができる。
(3) 以上を前提に被告製品が構成要件1Iを充足するかどうかについて検討するに,証拠(甲9,乙7の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,レッグレストフレームを前方に引き出していくと,同フレームに取り付けられた側面視略L字型のストッパー部材の上端ないし引き出し方向先端の角の部分が座席フレームの湾曲部に当接し,その直後にレッグレストフレームが,次第に減速するのではなく,ほぼ一瞬にして停止するものと認められる。\nしたがって,被告製品は,「滑らかに当接して徐々に停止する」ものでないから,構成要件1Iを充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.02.28
平成26(ワ)17390 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年2月16日 東京地方裁判所 棄却 東京地方裁判所
そこで,上記ウの解釈を前提に,被告製品1及び2が構成要件1Bの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」を充足するかについてみる。・・ ローナル抗体はヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼと結合する。また,証拠(乙26,34)及び弁論の全趣旨によれば,このモノクローナル抗体(被告製品1につきIgG主抗体及びIgG副抗体,被告製品2につきIgM抗体)はSDS及び2ME(メルカプトエタノール)による変性処理並びに煮沸処理を経たカタラーゼを検出することが認められる。そして,これらの変性及び煮沸処理によってカタラーゼは完全に変性し,単量体となったものと考えられるから(本件明細書の段落【0116】参照),被告製品1及び2のモノクローナル抗体は変性剤で変性されたカタラーゼと結合するものであるということができる。 そうすると,被告製品1及び2のモノクローナル抗体は,ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼだけでなく,変性剤で変性されたカタラーゼとも結合するモノクローナル抗体であるから,構成要件1Bの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」に当たらない。したがって,被告製品1及び2が構\成要件1Bを充足すると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2016.02.25
平成27(ネ)10080 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年2月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 前記1(3)のとおり,控訴人は,本件特許1の出願経過において,拒絶理由通 知を受け,構成要件Cの15本のピークの回折角の数値を挿入する平成23年11\n月29日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相 当するものであることを表明した。また,控訴人は,本件特許2の出願経過におい\nても,拒絶理由通知を受け,構成要件C’の15本のピークの回折角の数値を挿入\nする平成25年3月8日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の 限定的減縮に相当するものであることを表明した。\n控訴人は,本件特許1の出願経過における拒絶理由通知において,1本のみのピ ーク強度でしか特定されず,他のピークの特定がないので,公知文献に記載された 結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対 して,上記補正を行ったのであるから,15本のピークの回折角の数値をもって本 件発明1の結晶を特定したというほかない。 そして,本件特許2は,結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む 医薬組成物に関し, 特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの 結晶性原薬を提供することを課題とし,ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に 含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上す ること及び結晶形態AないしCの中で結晶形態Aが医薬品の原薬として最も好まし いことを見いだした本件特許1を原出願とする分割出願であって,本件特許1に係 る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり,その出願 当初の特許請求の範囲の請求項1には,上記補正後の本件発明1の結晶と同じ15 本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。 以上によれば,本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は,本件各発明 の技術的範囲を,回折角の数値が15本全て一致する結晶に限定するものであると 解されるから,構成要件C・C’の15本のピークの回折角の数値と,全部又は一\n部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は,本件各発明 の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。
◆平成27(行ケ)10081 こちらは、本件特許発明についての無効審判の取消訴訟です。この事件では、特許無効とした判断が取り消されていますが、上記事件ではイ号は非侵害と判断されています。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成26(ワ)5210 損害賠償請求事件 民事訴訟 平成28年1月21日 大阪地方裁判所
本件特許発明が,シートによって鼻全体を覆うことを想定していることは先に述 べたとおりである。しかし,本件明細書の記載によれば,従来のシートでも鼻の上 部に切り込みは設けられておらず(【0005】,図2),鼻の上部に当たる目頭付近 部分は,従来技術によってもシートで覆うことが実現されていたのに対し,本件特 許発明の技術的課題は,従来のパック用シートでは,小鼻部分にシートで覆えない 大きな隙間が空き,また,シートの小鼻に対応した部分が浮き上がってしまう欠点 があったことから,顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもぴったりと覆うこと にあり,本件特許発明は,「ほぼ台形の領域」にミシン目状の切り込み線を配すると したことにより,不織布の横方向に伸びやすいという物性と相俟って,パック用シ ートが鼻筋や鼻の角度に沿って自然と横方向に伸び広がるようにし,隙間を生じる ことなく小鼻部分をもぴったり覆うようにしたものであると認められる。 これらからすると,本件特許発明は,鼻部にミシン目状の切り込み線を複数列配 することによって,従来技術では困難であった小鼻部分を覆うことを実現した点に 固有の作用効果があると認められる。そうすると,被告製品において,目頭の高さ からやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点は,このような本 件特許発明の固有の作用効果を基礎付ける本質的部分に属する相違点ではないとい うべきである。
イ 置換可能性について
証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,目頭の高さからやや下の 部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていなくとも,小鼻部分を含 めた鼻全体に密着するものであると認められる。 そうすると,被告製品も,本件特許発明の目的を達することができ,同一の作用 効果を奏するものであると認められる。 ウ 置換容易性について 前記のとおり,鼻の上部に当たる目頭付近部分は,従来技術によってもシートで 覆うことが実現されていたことからすると,切り込み線が配される台形状の領域の 上底の高さを,眼の付け根である目頭の高さよりも,目頭の1段分か2段分,下に 設けても本件特許発明と同一の作用効果を奏することは,当業者が,対象製品等の 製造等の時点において容易に想到することができたというべきである。
・・・・
(2) 被告製品の製造に関する実施料相当額
被告に納入されたパック用シート●●●●●●●●のうち,被告製品として譲渡 されたのは●●●●●●●●であり,その差である●●●●●●●●については, 納入されたが譲渡されなかったものである。しかし,被告製品のパック用シートが 特殊な形状をしていることからすると,被告は,シートの製造業者に発注して被告 製品用のパック用シートを製造させたと推認され,そうすると,被告は,パック用 シートの製造行為を行ったと評価すべきである。そして,パック用シートの製造も 本件特許発明の実施であり,侵害行為に当たるから,納入されたが譲渡されなかっ た分も損害賠償の対象とするのが相当である。 もっとも,被告は,これらについては,その価値を市場に提供して利用したわけ ではないことからすると,これを有償譲渡と同視し,前記の想定市場販売価格を基 礎として実施料相当額を算定するのは相当でない。そこで,これらシートについて は,その製造自体の価値を示すものとして,その納入価格を基礎として実施料相当 額を算定するのが相当であり,証拠(乙12)によれば,シート1枚当たりの納入 価格は●●円であると認められる。この点について,原告は,これらについても想 定市場販売価格を基礎にして実施料相当額を算定すべきであると主張するが,前記 に照らして採用できない。 また,前記(1)エにおいて考慮した事情に照らせば,これらシートの納入価格には, 美容液の価値が考慮されていないから,被告製品用のシートを製造したが譲渡しな かった場合の実施料率は,●●と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成26(ワ)25013 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年1月28日 東京地方裁判所
成人1日あたり0.15〜0.75g/kg体重のイソソ\ルビトールを経口投与されるように用いられる(ただし,イソソ\ルビトールに対し1〜30質量%の多糖類を,併せて経口投与する場合を除く)ことを特徴とする,イソソ\ルビトールを含有するメニエール病治療薬。
まず,特許請求の範囲の記載を見ると,本件発明は,所定量のイソソ\ルビトールを経口投与されるように用いられること(構成要件A)を「特徴とする,イソ\ソルビトールを含有するメニエール病治療薬」の発明であり,メニエール病治療薬を用法用量により特定したものであるが,イソ\ソルビトールの投与量が構\成要件A所定の範囲に含まれるような用法があれば足りるのか(その範囲未満又は超過の投与量での用法があってもよいのか),用法用量がそのような投与量のものに限られるのか(それ以外の用法用量をも有する治療薬は本件発明の技術的範囲から除外されるのか)については,特許請求 の範囲に明示的に記載されていない。 上記アの本件明細書の記載によれば,本件発明は,従来のイソソ\ルビトール製剤(これが被告製品1を指すことは明らかであり,その標準用量は1日当たりイソソ\ルビトール1.05〜1.4g/kg体重に相当する。甲3)の投与量が過大であり,そのために種々の問題が生じるところ,その投与量を構成要件Aに記載の0.15〜0.75g/kg体重という範囲にまで削減することによって上記の問題を解消したというものである。そうすると,本件発明の治療薬は,構\成要件A記載の範囲を超える量のイソソ\ルビトールを投与する用法を排除し,従来より少ない量を投与するように用いられる治療薬に限定されるということができる。換言すると,上記範囲を超える量のイソソ\ルビトールを投与するように用いられる治療薬は,「医師のさじ加減」個々の患者の特徴や病態の変化に応じて医師の判断により投与量が削減された場合には構成要件Aに記載された量で用いられ得るものであっても,本件発明の技術的範囲に属しないと解すべきである。このことは,上記?イのとおり,実施例又は参考例において,イソソ\ルビトールの投与量を時間的推移に着目して変動させたものが見当たらないことからも裏付けられると解される。 したがって,構成要件Aの「成人1日あたり0.15〜0.75g/kg体重のイソ\ソルビトールを経口投与されるように用いられる」とは,上記の用量を,患者の病態変化その他の個別の事情に着目した医師の判断による変動をしない段階,すなわち治療開始当初から,患者の個人差や病状の重篤度に関わりなく用いられることをいうものと解するのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成26(ワ)12198 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年12月24日 東京地方裁判所
このように,本件特許発明1において,加入者装置は,構成要件1Cで「候補サブキャリアのセット」の「選択」を行い,構\\成要件1Dで,上記「選択」した「候補サブキャリアのセット」に関して情報提供を基地局に行うものである。 一方,LTE規格の非周期的CQIレポートの高次階層設定サブバンドフィードバックモードにおいては,加入者装置(ユーザ端末)は,N個のサブバンドで構成されている全帯域の「N個のサブバンド全部」について,サブバンド差分CQI値を報告することとされている(当事者間に争いがない。また,前記(2)のとおり,LTE規格の仕様書には,高次階層設定サブバンドフィードバックの欄に,ユーザ端末が,各サブバンドセットについて1つのサブバンドCQI値を報告しなければならない旨の記載がある。)。 イ 原告は,本件通信システム方法において全部のサブバンドが選択されている旨主張するが(見解1),このように,LTE規格の上記モードにおいて,全てのサブバンドについて情報提供が義務付けられているとすれば,これは本件特許発明1の特徴である「選択したものについて情報提供を行う」との処理とは異なるものであって,構成要件1Cでいう「選択」や,それに引き続く構\\成要件1Dの「情報提供」があるとはいえない。 広辞苑第6版(乙3)によれば,「選択」とは,「えらぶこと。適当なものをえらびだすこと。良いものをとり,悪いものをすてること。」を意味するとされており,「選択」とは,何らかの基準を充たすものを選び出すことを意味すると解すべきである。 なお,前記(1)オ(ア)のとおり,本件明細書には,「各加入者は(中略)性能の良い(中略)複数のサブキャリアを選択して,それら候補サブキャリアに関する情報を基地局にフィードバックする。」と記載されており(甲4),これは実施例に関する記載ではあるが,各加入者が性能\\の良いものを選び出し,その選択したサブキャリアに関する情報を提供するという過程が記載されており,上記解釈を裏付けるものである。 また,選択を行う者が,何らかの基準に従って対象物につき選択を行った結果,全てが選ばれる場合も想定し得るが,上記のとおり,非周期的CQIレポートの高次階層設定サブバンドフィードバックモードにおいては,加入者装置(ユーザ端末)は,常に全てのサブバンドについてのサブバンド差分CQI値を報告することとされており,このような場合には「選択」の余地はないというべきである。 なお,前記(1)オ(ア)のとおり,本件明細書には「このフィードバックには,全てのサブキャリアについて又は一部のサブキャリアだけについてのチャネルと干渉の情報(中略)が含まれる」(段落【0010】)との記載があるが(甲4),これはあくまで,結果的に「全てのサブキャリア」が選択されることもあり得ることを前提とした記載というべきであって,常に「全てのサブキャリア」が選択されることを前提とした記載ではない。 原告は,情報処理技術分野においては,「全部の選択」等の用語の用い方はごく一般的であり,本件特許発明の「選択」の技術的意義については,単なる日本語の語義に基づくことは誤りであるとも主張する。しかし,本件特許の関連技術分野全てにおいて「選択」との文言が上記のように用いられることが通常であることを認めるに足りる証拠はないし,本件明細書においても,「選択」との文言の意義につき特段の説明はないから(甲4),原告の上記主張は採用できない。このほか,原告は,全サブバンドについてサブバンド差分CQIのフィードバックを行うことによって,情報量の低減効果があるとも主張するが,情報量の低減効果の有無と,サブバンドの「選択」の有無とは,直接関係がないことである。
ウ 以上のとおり,本件通信システム方法において全部のサブバンドが選択されているとの原告の主張(見解1)を前提にすると,本件通信システム方法では,加入者装置(ユーザ端末)において本件特許発明1の規定する「選択」をしていないから,構成要件1Cを充足せず,更に,選択したものについて「情報提供」をしているともいえないから,構\\成要件1Dも充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成26(ワ)371 債務不存在確認請求事件 特許権 平成27年12月25日 東京地方裁判所
(1) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1並びにこれを引用する同請求項2,同請求項4及び同請求項6においては,本件各発明が,「位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段」(構成要件C)を具備することを特徴とするタッチパネルシステムであることが規定されている。上記「複数の指示部位」には,当然,指示部位が2個である場合と指示部位が3個以上である場合の双方が含まれるところ,上記特許請求の範囲の記載の文理や,本件明細書において,入力検出面に3つの位置指示具が存在する場合に,当該3個所の位置(光量が0の領域)の中から最外端にある2個所の位置(光量が0の領域)を特定する実施例について説明がされていること(甲3の【0035】,【図7】)からすれば,当該タッチパネルシステムが具備するところの「距離算出手段」は,「位置検出手段により検出される指示部位が2個であれ3個以上であれ,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段」であると解される(換言すれば,「位置検出手段により検出される指示部位が2個である場合には,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出するが,位置検出手段により検出される指示部位が3個以上である場合には,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出するわけではない距離算出手段」はこれに当たらないと解される。)。なお,上記「最外端」という文言それ自体の意義については一義的でないようにも思われるが,本件明細書の【0035】,【0040】,【図7】,【図10】の記載及び弁論の全趣旨に照らせば,「最外端にある2個所」とは,「互いに最も離れた位置にある2個所」を指すものと解するのが相当である。\nそうすると,位置検出手段により検出される指示部位が3個以上である場合に,それら指示部位のうち最外端にある2個所(互いに最も離れた位置にある2個所)の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段を具備していなければ,当該タッチパネルシステムは,構成要件Cを充足しないというほかはない。
(2) これに対し,被告は,通常の用法である「2本指のピンチジェスチャ」(指示部位が2個である場合)においては,2つのタッチ位置が「複数の指示部位のうち最外端の2個所」にそのまま該当し,侵害となる以上,実用上特殊な場合である「3本指以上のピンチジェスチャ」(指示部位が3個以上である場合)を殊更取り上げることに意味はないなどと主張する。 しかしながら,前記(1)で説示したとおり,本件各発明の構成要件の充足性を判断するに当たっては,当該タッチパネルシステムが具備する距離算出手段がどのような距離算出手段であるのかが問われるのであって,被告の上記主張のように特定の使用態様(2本指のピンチジェスチャ)のみに着目することによって,「複数の指示部位」という文言が指すもののうちから「2個の指示部位」の場合のみを切り出し,その場合のみを基に侵害判断をすることは相当でない。そして,2本指のピンチジェスチャが通常の用法であるとしても,1)「複数の指示部位」という文言が「3個以上の指示部位」の場合をも含むことは当然である上,2)実際,頻度は少ないにせよ「3個以上の指示部位」が検出される場合があり得ること,3)被告自身,本件明細書(【0035】【図7】)において,3つの位置指示具が存在する場合について説明をしていることに照らすと,指示部位が3個以上である場合を取り上げることに意味がないなどということはできない。さらに,「最外端」の特定は,発明における動作原理にも関係することを考慮すると,被告の上記主張は到底採用することができない。
(3) 以上を前提として原告製品について検討すると,位置検出手段により検出される指示部位が3個以上である場合に,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段を原告製品が具備していることを示す証拠はない。 かえって,証拠(甲9,18,19)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品のタッチパネルに3本ないし5本の指で1本ずつタッチしてピンチ操作を行った場合,表示イメージの拡大縮小は,最外端にある2個所(互いに最も離れた位置にある2個所)の指の間の距離に基づいて実行されるものではなく,最初及び2番目にタッチされた2本の指に基づいて実行されることが認められる。
(4) そうすると,原告製品は,構成要件Cを充足しないというほかはない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成26(ワ)34145 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年1月14日 東京地方裁判所
本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明の欄には,本件発明の実施形態が記載されているところ(段落【0027】〜【0134】,【図1】〜【図21】),この実施形態においては,「Web−POSクライアント装置」の表示画面に「明細フォーム」(カテゴリ,メーカコード,商品番号,商品名,単価,数量,金額といった注文商品明細が表\示されているもの。【図10】〜【図12】,【図17】〜【図21】。)が表示され,「オーダ・ボタン」のクリックに応答して,「Web−POSサーバ・システム」へ明細フォーム中のカテゴリ,メーカコード等の全フィールドを送信し,「Web−POSサーバ・システム」においてこの明細フォームを受信することとなっているところ(段落【0056】,【0111】〜【0125】,【0127】,【図12】),「オーダ・ボタン」のクリックにより「Web−POSサーバ・システム」が受信するのが「注文情報」であることから(構\成要件F4),上記明細フォームは「注文情報」に相当するので,「注文情報」には商品名,価格等の商品基礎情報が含まれている。また,本件明細書には本件発明の他の実施形態の説明も記載されているが(段落【0134】〜【0139】),いずれも「明細フォーム」を利用するものであり,「注文情報」に商品基礎情報を含まない構成についての記載は見当たらない。\nこれら本件明細書の記載を考慮して「注文情報」の意義を解釈すると,本件発明は,「Web−POSクライアント装置」の表示画面に明細フォームその他商品基礎情報を含む情報を表\示した上で,「オーダ・ボタン」のクリックに応答して,これらの情報を「Web−POSサーバ・システム」に送信するという構成を採用したものと認められる。したがって,「Web−POSクライアント装置」が送信して「Web−POSサーバ・システム」が受信する商品の注文に関する情報にカテゴリ,メーカコード,商品名,価格等の商品基礎情報が含まれていない場合には,構\成要件F4,G及びHの「注文情報」に当たらないと解するのが相当である。 ウ 「注文情報」を上記のように解釈することは,本件特許の出願経過における原告の説明とも一致する。すなわち,原告は,平成23年10月9日付け意見書(乙20)において,引用文献1(乙11)との相違点につき,1)引用文献1における注文情報は購入者ごとに生成される情報であって,この購入者ごとの注文情報は,商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報である本件発明の「注文情報」とは異なる(乙20の11〜12頁),2)用文献1には,商品注文明細情報の生成及び表示過程に関する詳細な記載がなく,ユーザが注文した情報に売上管理等に必須となる商品識別情報及びこれに対応する商品基礎情報が含まれていないのに対し,本件発明では「注文情報」に商品識別情報とこれに対応する商品基礎情報が含まれている(同12〜13頁)と説明しており,これら1)及び2)の説明は上記の解釈と整合するということができる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.01. 6
平成26(ワ)23926 損害賠償 特許権 民事訴訟 平成27年12月11日 東京地方裁判所
本件明細書等をみると,本件各発明が適用される第1実施形態を説明する図1には,記憶再生装置に当たる「DVDレコーダ1」に「USB I/F」が具備されているものと図示されており,これについて「USBインターフェイス40は,USBポート41を介して接続される外部の機器と各種信号をやり取りするためのインターフェイスである。」(段落【0045】)と説明されている。そして,図1の「DVDレコーダ1」には,上記「USBI/F」とは別に,「無線LANモデム」が図示されており,これについて,「無線LANモデム60は,外部のネットワーク網と接続するためのモデムであ」り,「DVDレコーダ1は,この無線LANモデム60を介してネットワーク網に接続されるとともに,FTPサーバー3(a),及び通信局3(b)を介して,DVDレコーダ4,携帯電話5,及びパーソナルコンピュータ6と通信可能\なように構成されて」おり(段落【0047】),「無線LANモデム60が通信インターフェイスに相当」する(段落【0076】)と説明されている。そして,本件明細書等の図1には,第3の記憶媒体が,\n「DVDレコーダ1」(記憶再生装置)に内蔵された「HDD21〜HDD23」である場合と,無線LANモデム及び外部ネットワークを介して接続される「FTPサーバー3(a)」である場合の両方が図示されているにもかかわらず,通信インターフェイスについては,ネットワーク網に接続する無線LANモデムのみが記載されていること,本件各発明においては,記憶再生装置から動画情報を送信する先の端末が「通信端末」と呼称されており,ネットワーク網を経由した通信機能を有した端末であることが示唆されていると考えられ,ネットワーク網を経由した通信を想定していることがうかがえること,本件明細書等を精査しても,USBインターフェイスが通信インターフェイスに当たる場合があることを示唆する記載がないことなどからすると,本件明細書等は,通信インターフェイスからUSBインターフェイスを除外していると解するのが相当である。したがって,本件各発明における「通信インターフェイス」には,「USBインターフェイス」は含まれないというべきである。
(3) 以上によれば,USBインターフェイスを有しているにすぎない被告製品(イ〜ホ)は,構成要件B1,C1,H1,G2及びH2を充足しない。\n6 争点(1)カ(均等侵害の成否)について
原告の主張する均等侵害は争点(1)エ及びオに関し文言侵害が認められない場合の予備的主張であるところ,前記3及び4のとおり,本件では,その他の構\成要件において文言非充足であるから,原告の主張する均等侵害は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> コンピュータ関連発明
2015.12.14
平成27(行ケ)10119 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年12月8日 知的財産高等裁判所
1) 原告は,第1訂正後の本件発明では,スクラロースを,該飲料の0.00 12〜0.003重量%の範囲内に用いることを前提に,その範囲の中から,甘 味を呈さない量という限定を加えているため,0.0012〜0.003重量%の 範囲内に甘味の閾値が存在する場合が含まれることを前提とするものであり,甘味 閾値の具体的な数値を正確に測定する必要があるのに対し,本件訂正後の本件発明 では,甘味を呈さない範囲の量の範囲内で,客観的数値である該飲料の0.00 12〜0.003重量%のスクラロースを用いるという数値限定を加えているた め,0.0012〜0.003重量%は甘味を呈さないこと前提とするものであ り,スクラロースを用いる最大量である0.003重量%において,飲料が甘味 を呈する場合は,明確に排除されているから,具体的な甘味閾値を求める必要は ないとして,第1訂正後の本件発明と本件訂正後の本件発明は,実質的に同一でな いと主張する。
(2) しかしながら,第1訂正後の本件発明と本件訂正後の本件発明では,いず れも「であって」という用語によって,前後の発明特定事項が接続されているが, 「であって」における「て」は,対句的に語句を並べ,対等,並列の関係で前後を 結びつける作用を有する接続助詞であるから,両発明は,いずれも「該飲料の0. 0012〜0.003重量%の範囲」であること(条件A),及び「甘味を呈さな い量」であること(条件B)という2つの条件を共に満たしていることを要求して いると解される。したがって,両発明では,ただ条件の記載順序が異なるにすぎな い。そして,記載順序の違いは,2つの条件を共に満たす範囲に影響を与えるもの ではない。 原告の主張は,発明特定事項が「AかつB」と記載された場合には,条件Aを満 たす集合の中に条件Bを満たす集合が包含されていることが前提となるが,逆に「B かつA」と記載された場合には,条件Bを満たす集合の中に条件Aを満たす集合が 包含されていることが前提となるというものである。しかしながら,各集合に属す るための条件が相互に独立した項目であれば,ある特定の条件を満たす集合は,他 の条件を満たす集合から何ら影響を受けずに,当該特定条件を満たす集合の大きさ や帰属する要素を規律するはずである。そして,複数の条件を満たす集合体の大き さや帰属する要素は,いずれの条件を先に検討しても,それぞれの重なり合う範囲 となるのであり,同じ結果になるはずである。したがって,「AかつB」と「Bかつ A」は同じものを指すのであって,仮に条件Aを満たす集合の中に条件Bを満たす 集合全体が包含される関係にあるのであれば,「AかつB」も「BかつA」も条件B を満たす集合を指すことになり,条件Bを満たす集合の中に条件Aを満たす集合が 包含される関係にはならない。前記1のとおり,本件発明において,「該飲料の0. 0012〜0.003重量%の範囲」であることは,当該飲料の重量によって計算 上算定される値であり,かつ,「甘味を呈さない量」であることは,ヒトの味覚に よって検査される値であり,それぞれ独立した条件であり,一方の条件が論理的に 当然に他方の条件に影響するものではない。
・・・
(3) また,本件訂正後の請求項1は,「・・・スクラロースを,該飲料の0.0 012〜0.003重量%の範囲であって,且つ0,003重量%の場合において スクラロースの甘味を呈さない量を用いることを特徴とする渋みのマスキング方 法」ではなく,「・・・スクラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該 飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング 方法。」である。すなわち,本件訂正後の請求項1は,スクラロース0.003重量% の場合に甘味があるときがあることを前提としつつ,より少ない重量%として甘味 を呈さない場合をも,その発明特定事項の対象とするものである。したがって,0, 003重量%の場合に常にスクラロースの甘味を呈さないことを前提とした原告の 主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものといわざるを得ない。本件訂正後 の明細書(甲48)の記載を参酌しても,同明細書中には,ウーロン茶飲料におい てスクラロースを0.0012%用いた場合(【0018】)及び緑茶飲料において スクラロースを0.0014%用いた場合(【0019】)に渋みがマスキングされ ることは確認されているが,それぞれの飲料においてスクラロースを0.003重 量%使用した場合に,甘味を呈するか否かは確認されていない。 しかも,かかる主張は,甘味を呈する閾値と0.003重量%との大小関係が一 義的に定まることを前提とするものであるところ(原告は,0.003重量%にお ける甘味の有無だけを判断すれば足り,甘味の閾値を定める必要がないとも主張す るが,本件訂正前の請求項との違いを説明するに当たって,甘味を呈する閾値の上 下で甘味の有無を区別した上で,0.003重量%との大小関係を問題にしている から,このような前提に立つと解するのが相当である。),かかる前提自体は,前件 判決で採用できないことが明らかにされている。すなわち,前件判決は,明確性要 件違反である理由として,極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとは いえないこと,官能検査の方法等により甘味の閾値が異なる蓋然性が高いことを前\n提としつつ,「0.0012〜0.003重量%の範囲」は非常に狭く,「甘味を呈 さない量」が「0.0012〜0.003重量%」との関係でどの範囲の量を意味 するのか不明であると判示したのであって,最後の判示部分は,異なる官能検査方\n法を用いた場合の甘味の閾値が,「0.0012〜0.003重量%の範囲」におけ る上下限値と,一義的な大小関係が決まらないことを,明確性の観点から問題とし たものと解される。したがって,原告が主張するように,甘味の閾値が0.001 2〜0.003重量%の範囲内にあるような飲料を当然に除外することはできない し,甘味閾値を求める必要がないともいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2015.11.15
平成27(ネ)10076 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年11月12日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ア 前記1(2)によれば,円テーブル装置のクランプ機構においては,作業時にお\nける工具からの加圧又は振動に対して,確実に所定の回転角度の位置を保つことの できるクランプ力を得るために,油圧ピストンを使用して高い作動圧(油圧)でク ランプ部材を加圧していたが,油圧ピストンの使用には,部品コストが掛かり,メ ンテナンスにも手間が掛かるという課題があったことから,本件特許発明は,円テ ーブル装置において,空気圧のような低圧で使用する流体圧ピストンでも十分に回\n転軸をクランプすることができるクランプ機構の提供を目的としたものである。\nそして,本件特許発明は,クランプ機構を構\成する増力機構につき,第1段増力\n部及び第2段増力部を備えたものとし,流体圧ピストン(25)から可動側クラン プ部材(21)に働くクランプ方向の力を2段階にわたり増力することによって, 空圧ピストンのように低い作動圧のピストンでも十分に回転軸をクランプすること\nができるようにして,前記課題を解決するものである。
イ この点に関し,前記1(3)のとおり,本件明細書には,前記増力機構における\n2段階にわたる増力について,以下のとおり開示されている(別紙1【図2】参照)。 すなわち,1)流体圧ピストン(25)の第1段用テーパーカム面(28)とボー ル(26)との当接部P1において,F1(流体圧ピストン(25)のクランプ方 向の押圧力)が,ボール(26)を介してシリンダ形成部材(31)のテーパー面 (40)に対向している流体圧ピストン(25)の第1段用テーパーカム面(28) のカム作用により,F2(径方向の外方に向く力)に増力されてボール(26)に 伝達される(第1段の増力)。 次に,2)ボール(26)と可動側クランプ部材(21)との当接部P2において, F2が,ボール(26)を介してシリンダ形成部材(31)のテーパー面(40) に対向している可動側クランプ部材(21)の第2段用テーパーカム面(29)の カム作用により,F3(クランプ方向の押圧力)に増力されて可動側クランプ部材 (21)に伝達される(第2段の増力)。
ウ 第2段の増力に関し,前記2(3)ウ(ウ)のとおり,仮に,α3=0°,すなわ ち,第2段用テーパーカム面(29)が回転軸芯と直角を成すものとすると,径方 向の外方に向く力であるF2が,第2段用テーパーカム面(29)と完全に平行の 状態になることから,F2がクランプ方向の押圧力であるF3に増力されることは なく,「第2段増力部」が増力機構として機能\しなくなる。 したがって,第2段用テーパーカム面(29)が回転軸芯と直角,すなわち,傾 斜角度が「α3=0°」の場合を含まないという構成を,「α3=0°」の構\成に置 き換えれば,2段階にわたる増力により空圧ピストンのように低い作動圧のピスト ンでも十分に回転軸をクランプすることができるようにするという本件特許発明と\n同一の目的を達することも同一の作用効果を奏することもできなくなることは,明 らかというべきである。
エ 控訴人は,本件特許発明における2段式増力機構における増力の仕組みは,\n前記第3の2〔当審における控訴人の主張〕(5)のとおりであり,「α3=0°」の場 合に,F1からF3への増力は最大となるから,「第2段用テーパーカム面(29)」 の「30°以下の緩やかな傾斜角度」,すなわち,「0°<α3≦30°」を「α3 =0°」に置き換えても,増力を実現でき,かつ,低い作動圧下における高いクラ ンプ力の実現等の本件特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏す る旨主張する。 しかし,控訴人の主張は,第2段の増力につき,F2がシリンダ形成部材(31) のテーパー面(40)においてF3に増力され,この反作用として,テーパー面(4 0)からボール(26)を介して可動側クランプ部材(21)に対してF3と同等 の力が生じることを前提とするものであるところ,前記2(4)カ(イ)のとおり,特許 請求の範囲にも本件明細書の発明の詳細な説明にも,控訴人主張に係る増力の仕組 みは記載されておらず,したがって,同仕組みは,本件明細書の記載に基づかないものといわざるを得ない。
なお,控訴人の役員が作成した甲第15号証には,被告製品のクランプ機構の動\n作につき,「『クランプピストン』が正面部に動き,『鋼球』を『クランプシリン ダ』のテーパー面にそって動かし,『クランプシリンダ』のテーパー面に対向して いる『クランプピストン』のカム作用と,『鋼球』を介して,『クランプシリンダ』 のテーパー面に対向している『クランプリング』のカム作用による増力された力が 『クランプリング』に加わることになります。」と記載されているが,同記載によ っても,本件特許発明のように2段階の増力が行われているかは不明であり,増力 の測定値等の客観的な裏付けもない以上,被告製品において2段階にわたる増力が されていると認めるに足りないというべきである。
オ 以上によれば,被告製品は,前記(2)2)の要件を充たすものではない。
(4) 前記(2)1)の要件について
ア 前記(3)によれば,本件特許発明に係る円テーブル装置のクランプ機構が,2\n段階にわたり増力する増力機構を備えることは,前記課題解決に不可欠な構\成とい え,本件特許発明を特徴付けるものということができるところ,第2段用テーパー カム面(29)が回転軸芯と直角を成すものではないこと,すなわち,傾斜角度が 「α3=0°」の場合を含まないことは,上記増力機構を構\成する「第2段増力部」 における第2段の増力のために不可欠なものである。 この点に鑑みると,本件特許発明の構成要件E2の「第2段用テーパーカム面(2\n9)」は,傾斜角度が「α3=0°」の場合を含まないのに対し,被告製品の構成中,\n「クランプリング8の鋼球10と当接する面」は,回転軸芯と直角,すなわち,「α 3=0°」であるという相違部分が,本件特許発明の本質的部分でないということ はできない。
イ 控訴人は,F2からF3への増力において問題となる角度はα2であり,α 3ではないとして,「α3=0°」に係る相違部分は,本件特許発明の本質的部分で はない旨主張するが,控訴人の主張は,前記(3)のとおり,本件明細書の記載に基づ かない増力の仕組みを前提とするものであるから,採用できない。
ウ したがって,被告製品は,前記(2)1)の要件を充たすものともいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
2015.11. 1
平成26(ワ)27277 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年10月14日 東京地方裁判所
事案に鑑み,まず,前記1において認定説示した本件特許発明と被告方法とが相違する部分(構成要件F4と被告方法との相違部分)に関し,均等の第5要件(上記(1)5))の成否を検討する。
前記1(3)において認定説示したとおり,本件特許の出願人である原告は,本件特許の出願手続において,当初(分割出願時)は,「数量に基づく計算」を「Web−POSクライアント装置」により行うか,「Web−POSサーバ・システム」により行うかについて,本件特許請求の範囲により規定していなかったところ,第1手続補正により,本件特許請求の範囲に「3)商品オーダ内容の操作に関する表示制御,すなわち,上記Web−POSクライアント装置の入力手段を有する表\示装置に表示された上記商品の注文明細情報について,ユーザが,該入力手段により,オーダ内容(数量)を入力(選択)すると,該オーダ内容に基づく計算が上記Web−POSサーバ・システムにおいて行われると共に,その結果が上記Web−POSクライアント装置に通知され,また,ユーザが,該入力装置により,オーダ操作(オーダ・ボタンをクリック)を行うと,該商品の注文明細情報に対する該オーダ内容に基づく計算結果の販売情報または注文情報が該Web−POSサーバ・システムにおいて取得(受信)されること」との構\成を付加しようとしたこと,特許庁審査官は,同構成を付加する補正は,願書に最初に添付された明細書,特許請求\nの範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなく,特許法17条の2第3項に違反するなどの理由により,第1手続補正を同法53条1項により却下する旨の決定をしたこと,原告は,同却下決定を受けて,第2手続補正により,本件特許請求の範囲に「ユーザが,該入力手段により数量を入力(選択)すると,該数量に基づく計算が行われると共に,」との構成を付加したことが認められ,また,同補正により,本件請求項1記載の発明は,「該数量に基づく計算」が「Web−POSクライアント装置」により行われるものに限定されたと解すべきである。
そうすると,原告は,本件特許の出願手続において,被告方法のような「該数量に基づく計算」が「Web−POSサーバ・システム」により行われ,その結果が「Web−POSクライアント装置」に通知される構成について,これを明確に認識しながら,あえて本件特許請求の範囲から除外したものと外形的に評価し得る行動をとったものというべきである(なお,原告は,前記1において認定説示した本件特許発明と被告方法とが相違する部分〔構\成要件F4と被告方法との相違部分〕以外については,被告方法が本件特許発明と同一であるか,少なくとも均等であると主張しているのであるから,同主張を前提とする限り,被告方法は,客観的にみて,本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたることになるといえる。)。
この点,原告は,第1手続補正が却下されているとか,第2手続補正のうち,構成要件F4に関する部分は,サポート要件(特許法36条6項1号)違反の拒絶理由の解消を目的としたものであるなどと主張するが,第1手続補正が却下されたとの事実は,出願人である原告が,被告方法のような「該数量に基づく計算」が「Web−POSサーバ・システム」により行われ,その結果が「Web−POSクライアント装置」に通知される構\成を明確に認識していたとの上記認定を左右するものではなく,また,原告が当該構成を明確に認識しており,第2手続補正により本件請求項1記載の発明が「該数量に基づく計算」が「Web−POSクライアント装置」により行われるものに限定されたと解される以上,第2手続補正のうち,構\成要件F4に関する部分についての補正の目的が原告主張のとおりであったとしても,被告方法のような構成をあえて本件特許請求の範囲から除外したものと外形的に評価し得る行動をとったとの上記認定判断が左右されるものではない。\nしたがって,均等の第5要件の成立は,これを認めることができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
2015.10.16
平成27(ネ)10047 差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年9月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これを本件ホームアプリについてみるに,本件ホームアプリがイン ストールされた被告製品においては,利用者がタッチパネル上のショー トカットアイコンを指で長押し(ロングタッチ)すると,その際のホー ム画面のページ番号に応じて,画面上に左右スクロールメニュー表示が\n表示され,当該ページが,左端ページであれば「右スクロールメニュー\n表示」のみが,右端ページであれば「左スクロールメニュー表\示」のみ が,それ以外のページであれば「左右スクロールメニュー表示」がいず\nれも表示されるものであり(前記1(3)イ(ア)),左右スクロールメニュ ー表示は,利用者がタッチパネル上のショートカットアイコンを指で長\n押し(ロングタッチ)する操作を行うことによって表示されるものであ\nって,利用者がタッチパネル上の指の位置を動かすことにより,当該シ ョートカットアイコンを移動させる操作によって表示されるものとはい\nえない。 このことは,1)甲32の1及び2(控訴人作成の「被告製品の映像及 び映像説明書」)によれば,本件ホームアプリにおいて,タッチパネル 上のポインタ(ショートカットアイコン)を指で長押し(ロングタッチ) すると,ショートカットアイコンは,ぶるぶる振動する振動状態に遷移 し,振動状態になれば,ショートカットアイコンを移動させる操作(ド ラッグ操作)を行わなくても,画面右端に右スクロールメニューが表示\nされることが認められること,2)甲17の2(被控訴人作成の「IS04 取扱説明書」)によれば,「ロングタッチする」という項目に,「画面 の項目やアイコンを指で押さえたままにします。」と記載されているか ら,本件ホームアプリにおける「ロングタッチ」とは,ショートカット アイコンを指で押さえたままにすること,すなわち,指を移動しないま ま,ショートカットアイコンを押し続ける操作であり,指の移動を伴う ドラッグ操作は含まれないことからも明らかである。 したがって,本件ホームアプリにおいて,控訴人が主張する「操作メ ニュー情報」である左右スクロールメニュー表示を表\示させるための電 気信号は,ショートカットアイコンを押し続ける操作(ロングタッチ) が行われたことを検知した電気信号であって,ショートカットアイコン を移動させる操作(ドラッグ操作)が行われたことを検知した電気信号 ではない。 そうすると,本件ホームアプリにおいては,利用者が入力手段を介し て画面上のポインタ(ロングタッチをしたショートカットアイコン)の 位置を移動させる操作を行ったことを検知して,その操作をポインタの 座標位置を移動させる命令(電気信号)に変換し,処理手段がその電気 信号を受信することによって,控訴人が主張する「操作メニュー情報」 である左右スクロールメニュー表示を画面上に表\示させているものとは いえないから,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を 受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」(構\成要件E) 処理が実行される構成を備えているものと認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2015.09.10
平成26(ワ)25858 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年8月25日 東京地方裁判所
以上の本件明細書の記載によれば,本件発明は,講演者の立ち位置によってはスクリーンに投影される画像に干渉するという従来技術の問題点を解決するために,自動車のフロントガラスの前に置かれた物(これがフロントガラスの下にあることは明らかである。)がフロントガラス(観測者である運転者から見て上端が手前に,下端が奥にあることは明らかである。)に映り,フロントガラスの背景に存在するように見えるという物理原理をステージ等の背景に映像を表示することに利用したものであって,ステージの床に反射面(上記フロントガラスの例において背景に存在するように見える物が置かれる場所に相当する。)を配置し,フィルム(フロントガラスに相当する。)の上端を観客席側から見て手前に,その下端を奥に保持するとともに,表\示される物を反射面に直接置くのではなく,これに対面する天井に画像源を配置するとの構成を採用した点に,本件発明の本質的部分があるものと解される。
ウ これに対し,原告は,フィルムを反射面に向かい合うように傾斜させて配置したこと及び反射面の反対側に画像源を配置したことが本件発明の本質的部分であり,画像源と反射面の上下その他具体的な保持・配置関係は本質的部分でないと主張する。 そこで判断するに,本件明細書においては,自動車のフロントガラスの手前にある「保管場所」と本件発明の「反射面」をそのままの位置関係で対応させて面が床(下)にあるものとして記載されているのであって(第1図についても,支持部材22の形の下部保持部と巻取パイプ24の形の上部保持部とを伴うフィルム20(5欄35〜37行),第1図の左にいる観客(同41行)との記載によれば,観客から見た上下及び前後を踏まえた上で作図されたものであると解される。),画像源と反射面の位置関係が任意に変更可能であることを示唆する記載はない。かえって,反射面を床に設け書の記載上,特許請求の範囲に規定された画像源と反射面の上下関係等が本件発明の本質的部分に当たらないとみることはできないと考えられる。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2015.08.13
平成26(ワ)18842 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年7月28日 東京地方裁判所
まず,「接触圧」との文言について,原被告双方が異なる解釈を採って いるため,この点について検討する。 「圧」とは「おしつける力」を意味し,「接触」とは「近づきふれるこ と,さわること」を意味する(広辞苑第6版,乙1参照)。 そして,これらの文言の通常の解釈からすれば,本件特許発明1におけ る「接触圧」との文言は,複数の物体が互いに接触する際に生じる力ない し圧力を意味するものと解されるところ,次に指摘する本件特許1の明細 書の記載を参酌すれば,上記文言は,複数の物体が互いに接触する際に生 じる力を意味すると解すべきである。 すなわち,本件特許1の明細書(甲2)において,前記ア 「・・・上記複数の弾性腕の接触部はコネクタ嵌合時に相手端子と最初に 接触する接触部から順に相手端子に対する接触圧が小さくなっており,相 手コネクタを嵌合するときに,最初の接触部を圧したその勢いで,次の弾 性腕の接触部を圧することができるので,小さい挿入力で弾性変形させる ことができ・・・」「指圧(操作者がコネクタ嵌合時に相手コネクタを押 し込む力であり,接触部での接圧に比例する。)」などと記載されている ことからすれば,同明細書の記載は「接触圧」を力と同視しているものと いえ,「接触圧」が相手端子と各弾性腕の接触部との間で生じる力を意味 すること,すなわち「力」であることが明らかといえる。 これに対し,原告は,「接触圧」とは単位変位量当たりの反力(N/m m)を意味する旨主張する。しかし,これは通常の文言解釈に反する上, 原告の上記解釈を根拠付けるような明細書上の記載は存在しないため,原 告の上記主張を採用することはできない。 このほか,原告は,上記「接触圧」が,嵌合終了時点ではなく嵌合途中 の数値を指すとも主張するところ,既に検討したところによれば,この点 について判断するまでもなく,原告の同主張は採用できない。 ウ 原告は,「接触圧」に関する自らの解釈を前提として,被告製品が構成\n要件1Fを充足する旨主張するが,「接触圧」に関する原告の解釈を採用 できないことは前記イのとおりであって,被告製品が「接触圧」に関する 構成要件1Fを充足することを認めるに足りる証拠はない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
2015.07.20
平成27(ネ)10019 特許権に基づく損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年7月15日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,甲30文献を根拠に,テンプレートが,仮想マシンの情報等を含 むデータファイルであり,複写の対象となる実体を有するものであって,ハードウ エア資源を割り付けられることによって仮想マシンとして機能するものであるから,\n被控訴人商品のテンプレートは,本件発明の構成要件Aの「レンタルエンジン」に\n該当するものであり,さらに,インターネット接続も含めて総合試験が実施され動 作保証がされた被控訴人商品の「テンプレート」は,「インターネットに接続する」 「レンタルエンジン」に該当する旨主張する。 そこで,検討するに,甲30号証によれば,仮想マシンによる仮想システムは, ユーザーが,ユーザーインターフェース画面から,所望の処理能力を有する仮想マ\nシンとそのOSを選択し,この選択された仮想マシンとOSに対してハードウエア 資源内の必要なハードウエア資源を割り付けることで行われる(段落【0003】), 構築した仮想システムを別のユーザーに複写したい場合には,テンプレートファイ\nルを複写して複写テンプレートを作成し,その複写テンプレートに新たなハードウ エア資源を割り付けて,元の仮想システムと同じ仮想システムを生成することが行 われている(段落【0006】),データセンタは,管理サーバや複数のサーバと複 数のストレージ及び複数のネットワーク機器を有するハードウエア資源群を備えて おり,ユーザーが作成する仮想マシンを有する仮想システムの情報を有するテンプ レートファイルに,ハードウエア資源群内のハードウエアを割り付けて仮想システ ムを構築し運用する管理サーバを有する(段落【0014】),ユーザーが,仮想マ\nシンとそれにインストールするOS等を選択してオーダーすると,オーダーした仮 想マシンを有する仮想システムのテンプレートがハードウエア資源群内のサーバの ハードディスク領域内に生成され(段落【0022】),管理サーバが,ユーザーが 作成した仮想システムのテンプレート内の仮想マシンや仮想ストレージに,サーバ やストレージなどのハードウエア資源を割り付けることによって,仮想システムが 構築され,運用可能\になる(段落【0027】)ことが認められる。そして,「サー バ群#1内には,複数のサーバが設けられていて,それらのサーバはスイッチSW を介してネットワークで均質に接続され,コアスイッチC−SWを介してネットワ ークNWに接続され,インターネットからアクセス可能である(段落【0016】)」\nとされる。 そうすると,甲30文献におけるテンプレートについても,それのみでは,実体 のある仮想マシン・仮想システムであるとはいえないし,テンプレートにサーバや ストレージなどのハードウエア資源を割り付けることによって,初めて実体のある 仮想マシン・仮想システムとして,インターネットからアクセス可能となることが\n認められるのであるから,このテンプレートと,テンプレートにハードウエア資源 を割り付けることによって生成される仮想マシンは,コンピュータ技術上同一のも のということはできない。そして,前記認定のとおり,被控訴人商品のテンプレー トは,デザインスタジオの頁において,メニューとして表示されるものであるから,\n被控訴人商品におけるテンプレートは,被控訴人商品のサービスポータルの表示画\n面において,顧客が利用する仮想マシン及び仮想システムの構成のメニューとして\nの選択候補を意味するにすぎない。 以上によれば,甲30文献によっても,被控訴人商品の「テンプレート」が本件 発明の「レンタルエンジン」に該当するものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2015.07.14
平成26(ネ)10104 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年6月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 以上によれば,本件発明の技術的意義について,以下のことを認めるこ とができる。
本件発明は,基板となり得るような結晶欠陥の少ない窒化物半導体(InXAlY Ga1−X−YN,0≦X,0≦Y,X+Y≦1)を用いたレーザダイオード(LD) 等の電子デバイスに使用される窒化物半導体素子に関する(【0001】)。 従来,窒化物半導体は,サファイア基板上に格子不整合の状態で成長されている が,格子不整合で半導体材料を成長させると,半導体中に結晶欠陥が発生し,その 結晶欠陥が半導体デバイスの寿命に大きく影響するため,サファイア基板上に,結 晶欠陥が非常に多いGaN層を薄く成長させ,その上にSiO2よりなる保護膜を 部分的に形成し,その保護膜の上からハライド気相成長法(HVPE),有機金属気 相成長法(MOVPE)等の気相成長法を用いて,再度GaN層を横方向に成長さ せるというラテラルオーバーグロウス(LOG)と呼ばれる成長方法により,結晶 欠陥の少ない窒化物半導体を成長させる試みが行われた(【0002】〜【0004】)。 この従来の方法によると,保護膜の上部に結晶欠陥を集中させて,窓部に結晶欠陥 の少ない領域を作製すること,すなわち,意図的に結晶欠陥を偏在させることがで きるので,異種基板上に直接成長させた窒化物半導体よりも,結晶欠陥の数は減少 するが(【0006】),窒化物半導体表面に現れている結晶欠陥の数は多く未だ十\分 満足できるものではなく,また,窒化物半導体素子についても,結晶欠陥が偏在す るため,信頼性も十分とはいえず,そのため一枚のウェーハからレーザ素子を多数\n作製しても,満足できる寿命を有しているものはわずかしか得られないので,寿命 に優れた素子を作製するためには,窒化物半導体表面に現れた結晶欠陥の数を更に\n減少させる必要があった(【0007】)。 そこで,本件発明は,基板となり得る窒化物半導体の結晶欠陥を少なくして,信 頼性に優れた窒化物半導体素子を提供することを目的とし(【0007】),厚みが5 0μm以上であり,少なくとも下面から厚さ方向に5μmよりも上の領域では結晶 欠陥の数が1×107個/cm2以下である,ハライド気相成長法(HVPE)を用 いて形成されたn型不純物を含有するGaN基板と,前記GaN基板の上に積層さ れた,活性層を含む窒化物半導体層と,前記窒化物半導体層に形成されたリッジス トライプと,該リッジストライプ上に形成されたp電極と,前記GaN基板の下面 に形成されたn電極と,を備えるたものであり(【0008】,【0009】),その結 果,結晶欠陥が少ないGaN基板の上に活性層を含む窒化物半導体層を積層してい るので,非常に信頼性の高い素子が実現できるという効果を奏するものである(【0 061】)。 ウ 上記のように解されるから,本件発明において,結晶欠陥の数が多い高 キャリア領域にn電極を設けることによって,効率のよい素子を作製することまで がその技術的意義に含まれるとはいえず,したがって,この観点から,「GaN基板」 の解釈を導くことはできない。 また,本件発明は,物の発明に関するものであり,ハライド気相成長法(HVP E)を用いることを除き,結晶成長方法を特許請求の範囲に含めておらず,本件明 細書において,n型不純物を含有するGaN基板をハライド気相成長法(HVPE) で形成するに際し,新たに3族源のガスに対する窒素源のガスのモル比(窒素源/ 3族源)を2000以下に調整することで,結晶欠陥を横方向に伸ばすことが記載 されている(【0010】,【0019】,【0022】)としても,結晶成長方 法をこれに限定するものでない(【0016】)旨も記載されている。 エ(ア) しかし,その一方,上記【0016】は,「第2の窒化物半導体層の 結晶欠陥の多い領域と,少ない領域とが窒化物半導体積層方向に対してほぼ同じ方 向にあれば,」成長方法は特に限定されない旨が記載されているのであり,第2の 窒化物半導体層は,結晶欠陥の多い領域と少ない領域が積層する厚み方向に対して 上下方向に位置するものであることを前提としている。
・・・
そうすると,本件明細書では,下地層が除去されて素子構造を形成する場合には,\nn型不純物のドープと併せて,結晶欠陥の多い領域を残存させることによって,高 キャリア濃度を確保する手段が記載されており,結晶欠陥の少ない領域にドープを することによって適切なキャリア濃度に調整することや,そのようなドープのみで 適切なキャリア濃度を確保して動作をさせることが可能か否かについても明らかで\nはないといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2015.07. 8
平成26(ワ)23732 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年6月26日 東京地方裁判所
原告が本件訴訟の係属後にした訂正審判請求について付言しておく。
(1) 原告は,平成27年3月11日付けで訂正審判(訂正2015−39022。以下「本件訂正審判」という。)を請求し,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正を求めているが(甲8,9),明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものであってはならない(特許法126条6項)から,本件訂正審判の結果によって,被告製品が本件各特許発明の技術的範囲に属するものとは認められない旨の前記判断が覆ることは,理論上,あり得ない(仮に,誤ってそのような訂正が認められたときは,特許法123条1項8号所定の無効事由が生じたことになる。)。
(2) 原告が本件訂正審判において求めている特許請求の範囲の訂正には,本件特許発明1の構成要件1A―\(3)及び1−Bについて,「尾根構造体の短手方向に支柱を連結する複数のシザー組立体の中央部に前記幕体支持ポールを垂直に連結し」,「複数のシザー組立体」(下線部は,いずれも訂正箇所を示す。)などとすることが含まれる(甲8)。\nしかし,構成要件1A−(2)は,「シザー組立体は2本のバーをX字状に回動自在に連結してパンタグラフ状に折り畳み自在とした構造とし」としているから,シザー組立体は2本のバーをX字状に連結したものを1単位と解すべきであるところ,仮に,構\成要件1A−(2)を「複数のシザー組立体の中央部」と訂正したとしても,シザー組立体が三つ,又は,五つなど奇数単位存在する場合には,その中央部は,シザー組立体とシザー組立体の間ではなく,2本のX字状のバーの交差する箇所を中央部として幕体支持ポールを垂直に連結することを示すと解さざるを得ない。このような例は,本件明細書に記載されておらず,シザー組立体の単位数が奇数か偶数かで幕体支持ポールの位置が異なることになる。 したがって,本件訂正審判に係る訂正は,少なくとも,特許法126条5項に違反するものであって,認められるべきものではないと思われる。
(3) 原告は,本件訂正審判の請求後,特許庁長官に対し,審判請求書を補正する旨の同年4月7日付け手続補正書(甲9)を提出したが,同補正書によれば,原告が求めている特許請求の範囲の訂正には,構成要件1Cについて,「該補強フレームの一端は最も外側に位置する幕体支持ポールの上端位置に係止し,補強フレームの他端は隣接する幕体支持ポールに挿着されたスライトブラケットに上方から当接させることにより,幕体支持ポールを垂直に保持しながら,シザー組立体の伸張を維持しテント側面の強度を向上しつつ,直立する妻面を構\成するようにしたことを特徴とする」(下線部は,いずれも訂正箇所を示す。)などとすることが含まれるようである(同補正書の1頁には,「補正対象項目名」として「請求の理由」とあ り,「請求の趣旨」とは記載されていないが,訂正特許請求の範囲を含む同補正書2頁以下の記載によれば,請求の趣旨を補正することが当然の前提となっているものと考えざるを得ないし,原告の同月8日付け準備書面2〔4頁〕にも,これに沿う記載がある。)。 しかし,訂正審判における審判請求書について,請求の趣旨を補正することは認められていない(特許法131条の2第1項1号)。 なお,仮に,原告が本件訂正審判に係る請求の趣旨の補正を求めていないとすれば,同補正書の記載はおよそ無意味であるというほかはなく,原告がいかなる目的で同補正書を特許庁長官に提出し,また,本件訴訟において書証として申し出たのか,理解に苦しむところといわなければならない。
(4) 以上より,本件訴訟において,原告が本件訂正審判において求めている訂正を前提として,本件各特許発明の技術的範囲に被告製品が属するか否かを検討する必要がないことは,明らかである。
関連カテゴリー
>> 実質上拡張変更
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
2015.06. 3
平成26(ネ)10112 特許専用実施権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年5月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,本件相違点3に関し,1)本件発明の本質的部分は,「グリップベース」の上下方向の可動性であり,「スライドボルト」の上下方向の可動性ではない(第3の1【控訴人の主張】⑴ウ(ア)a),2)本件相違点3及び4に関し,「スライドベース」の固定用垂直面の縦長小判穴,「スライドボルト支持用垂直面」に形成され た縦長穴,「スライドボルト」及び「スライドタップ」の構成(構\成要件D3及びD4)は,「スライドベース」にリベット固定されたベースレールが島上部枠構造の下面にネジ留め固定される機構\(構成要件D1及びD2)と,「グリップベース」と「グリップアーム」とにより台枠上板が挟持される機構\(構成要件D5及びD6)の係わり合わせ方の1つにすぎず,その構\成自体は,本件発明の本質的部分ではない旨主張する(第3の1【控訴人の主張】⑴ウ(ア)c)。
イ しかしながら,前記⑶エのとおり,本件発明は,上部取付装置30の自動高さ整機能によって,島枠構\造の高さと台枠の高さとの間に差があっても,自動的に調整できる構造を備えたパチンコ台取付装置の提供という,従来の技術の問題点に係る課題の1つを解決するものであるところ,上記機能\に必須の要件といえるグリップベース35の上下方向の可動性は,グリップベース35が固定されたスライドボルト33が,「上下方向に移動可能に保持されること」という構\成によって確保されている。 この点に鑑みると,本件発明においては,「グリップベース」の上下方向の可動性よりも,その必要不可欠な前提である「スライドボルト」の上下方向の可動性が,本質的部分を構成するものとみるべきである。
ウ また,前記⑶ウのとおり,本件発明において,「スライドボルト」の上下方向の可動性は,スライドボルト33が,スライドベース31の固定用垂直面31bの縦長小判穴31eの長径とスライドボルト33の縦方向の径の長さとの差の範囲内において,上下方向に移動の自由が与えられた状態で,取り付けられているという構成によって,確保されている。\nさらに,グリップベース35が,スライドボルト33に螺合されたスライドタップ34に溶接固定され,スライドベース31の底面中央開口31dに吊り下げられた状態で取り付けられているという構成によって,グリップベース35を,上下方向の可動性が確保されたスライドボルト33の動きに追随させ,パチンコ台アセンブリの取付前は,重力により下がり,同取付時において台枠よりも低いときは,その高さまで押し上げられるようにしている。
以上によれば,本件相違点3及び4に係る本件発明の「スライドベース」の固定用垂直面の縦長小判穴,「スライドボルト支持用垂直面」に形成された縦長穴,「スライドボルト」及び「スライドタップ」のこれらの構成は,本件発明の課題の1つである上部取付装置30の自動高さ調整機能\を実現するためのものといえるから,本件発明の本質的部分に関わるものというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第3要件(置換容易性)
2015.05.29
平成27(ネ)10006 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年5月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記(3)イ(イ)認定のとおり,被告サーバーは,被告サイトにアクセ スしたユーザーのクライアント端末の要求に基づいて,そのディスプレ イ上に,予め被告サーバーに保管されていた過去に開催されたオークシ\nョン商品の縮小画像のアイコン2を含む画面3を表示させ(原判決別紙\n物件目録の別紙図9,12参照),ユーザーによってアイコン2がクリ ックされると,当該クリックされたアイコン2に対応する上記商品の画 像4,落札価格等の商品情報を主表示した画面5を表\\示(同原判決別紙 物件目録の別紙図9,12参照)させる構成を有するが,被告サーバー\nに予め保管されていた過去に開催されたオークション商品の縮小画像,\n画像,落札価格等の商品情報は,ヤフー社が一般に公開しているAPI に接続してヤフー社が運営管理するヤフーサーバーから送信された「ヤ フオク!」のオークション情報であるものと認められる。 しかるところ,ヤフーサーバーから送信された「ヤフオク!」の上記 オークション情報は,「ヤフオク!」のWebサイトのWebページの 情報であり,そのWebサイトの運営又は管理の主体はヤフー社である から,「商品の広告をネット上で紹介提供」する参加企業が運営又は管 理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページで ある「参加企業のホームページ」に該当するものと認めることはできな い。 控訴人は,この点について,ヤフーサーバーには,「ヤフオク!」の 個別のオークション商品ごとのWebページのデータがオークションコ ードごとの場所(ドメインないしURL)に保管されており,このオー クション商品ごとのWebページは,「ヤフオク!」における「出店者」 である参加企業が自由に編集可能なオークション商品ごとのWebペー\nジであり,その運用又は管理の主体は参加企業であるといえるから,「 参加企業のホームページ」に該当し,ヤフーサーバーには「参加企業の ホームページ」を保管する「バナーサーバー」が存在する旨主張する( なお,控訴人の上記主張は,前記第3の1(2)アのとおり,「争点1−イ」 に関するものであるが,その主張内容に照らし,「争点1−ア」におい ても主張するものと解される。)。
しかしながら,前記(3)ウ(イ)の認定事実によれば,「ヤフオク!」の サイトの個別のオークション商品のWebページには,「商品の情報」 (「即決価格」,「残り時間」,「入札件数」,「個数」,「開始時の 価格」,「最高額入札者」,「開始日時」,「終了日時」,「商品説明 を読む」等),「商品画像」(小さな画像をクリックすると,拡大表示\nされる。),「出品者の情報」(「出品者(自己紹介),「評価」,「 出品者への質問」,「出品者のその他のオークションを見る」),「商 品画像」等が掲載されるが,当該Webページは,ヤフー社が自ら運営 又は管理する自社のWebページであることが明らかである。 また,「ヤフオク!」のサイトのオークション商品のWebページに 掲載される「商品の情報」及び「出品者の情報」は出品者によって入力 され,「商品画像」は出品者によってアップロードされるが,その入力 項目はヤフー社によって設定され(甲74),Webページにおける各 情報の表示スタイルもヤフー社によって定められたものであり,表\\示さ れる情報の入力等が出品者によって行われるからといって,当該Web ページが出品者が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップペ ージとしてのホームページであるということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2015.05.24
平成26(ワ)4 特許権侵害差止等請求事件 平成27年4月28日 大阪地方裁判所
「テーパーカム面」の意義について,本件特許請求の範囲や本件明細書に具体的な記載はないところ,原告は,「テーパーカム面」は,不可分一体の用語であり,シリンダ形成部材テーパー面40と対向してセットになるカム作用を生じさせる面であり,傾斜角度がつけられていることは必須ではない旨主張するのに対し,被告は,「テーパー」で限定された「面」あるいは「カム面」である旨主張する。
(イ) 原告は,本件明細書において,「テーパー面(40)」と,「カム面(28,29)」及び「テーパーカム面」は明確に書き分けられていると指摘し,「カム面」を,カム作用を生じさせる面であるとして,前記のとおり主張する。 しかし,構成要件C5は,「カム面(28,29,40)よりなる増力機構\」と記載し(「40」は,訂正により加えられている。),ボールを介した増力機構における面40,面28及び面29を「カム面」として同列に記載していることからすれば,原告が主張するような明確な書き分けがされているとまではいえない。\nまた,本件明細書において,面28,29及び40については「カム面」との用語を使用しながら,構成要件E2において「テーパーカム面(29)」との用語を使用しているということは,当該面それ自体が,「カム」としての性格または機能\と「テーパー」としての性格または機能を有する趣旨と解するのが自然である。\n
(ウ) 原告は,「テーパー」の意味として,ピストン側のボールと接する面(28)及び可動側クランプ部材の面(29)と,シリンダ形成部材との各2両面で勾配を形成していることのように主張する。 しかし,本件明細書には,回転軸芯と面28とのなす角度α1を「テーパー角」,「シリンダ形成部材31のテーパー面40及び可動クランプ部材21のテーパーカム面29は,回転軸芯と直角な面に対して30°以下の緩やかな傾斜角度α2,α3」となっている旨の記載があり(【0018】),ボール26を囲む面の有する勾配については,回転軸芯ないしは回転軸芯と直角な面に対する勾配であることを前提としていることが認められるものの,複数の面の相関関係によって円錐状の勾配が形成されるとの意味で「テーパー」が用いられていると解し得る記載は存しない。 そして,本件特許は回転軸芯を中心とした円テーブル装置であり,その構造に関する本件特許請求の範囲の記載を解釈するものであることをあわせ考慮すれば,「テーパー」とは,回転軸芯あるいは回転軸芯と直角な面を基準として,傾斜角度を有することと解するのが相当である。\nこの点,原告は,面29の回転軸芯と直角な面に対する角度(α3)が0°の場合も含む旨主張し,当業者の認識理解や,α3が0°の場合のみ除くのは不自然であることなどを指摘するが,上記「テーパー」の意義からすれば,原告の上記主張は採用できないというべきである。
(エ) 前述のとおり,構成要件E2の「テーパーカム面」は,面29それ自体が,「テーパー」としての性格または機能\と「カム」としての性格または機能を有すべきところ,前記イ(イ)によれば,「カム」の典型的機能は,回転運動を直線運動に変換することであるから,広義では,方向等を変換しつつ力を伝達する部材と解する余地がある。\nまた,上記検討したところによれば,「テーパー」は,回転軸芯あるいは回転軸芯と直角な面を基準として傾斜角度(0°を含まない。)を有するとの意味になる。
ウ 被告製品の構成要件E2充足性
以上を前提に,被告製品が,構成要件E2を充足するかにつき検討するに,前記認定によれば,クランプリング8の鋼球10と当接する面は,増力機構\の一部として,鋼球10を介し,クランプピストン9の前進による力をクランプリング8に伝達するのであるから,カム面としての性質を有しているということはできる。 しかしながら, 被告製品において,クランプリング8の鋼球10と当接する面が回転軸芯と直角であること(α3=0°)は争いがなく(原告は,この面が傾斜している旨を主張するものではなく,この面の傾斜角度が0°であっても,テーパーカム面に該当する旨を主張する。),「テーパー」について前記イのとおり解する以上,この面は「テーパーカム面」に該当せず,結局,被告製品は構成要件E2を充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2015.05.19
平成26(ネ)10107 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年5月14日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
控訴人は,「一覧」とは「全体に一通り目を通すこと」という意味も包含するのであって,「全体を一目で分かるように」する場合に限る必要はないし,本件発明1に対する課題解決のための手段という観点からも,出願経緯からも,出力を1回に限定する必要もなく,被控訴人方法は構成要件1Dを充足すると主張する。\n確かに,「全体を一目で分かるように」するためには,全体が画面に表示される必要があるものの,その場合,画面への表\示までに送信されるデータが一度で出力されなければならない必然性はない。また,【0055】にあるとおり,本件発明1は,画面をスクロールする場合を含むのであって,この場合,画面上表示されない画像データについては事前に送信しなくても,表\示するためのスクロールの時点までに送信されていれば,全体を確認することができる以上,画面上表示されない画像データについては事前に送信しない方法も考えられ,このような観点からしても,画\n 像出力の回数を1回に限定する必要はない。また,本件発明1の目的,作用効果を果たすためには,事業者は,顧客に対し,預かった複数の品物の全てについて一目で分かるように,すなわち,複数の品物の全ての画像を含むように生成したウェブページとして1回の呼出操作で,ウェブページに含まれる品物に対応した画像を閲覧できるように提示する必要があるが,このことを表現するものとして,控訴人の主張するとおり,「一覧」は「全体に一通り目を通す」ものと解釈することも一応は可能\である。 しかしながら,そう解釈した場合であっても,顧客が自らの預かり品の「全体」の範囲を簡単に把握,理解できない方法では,すなわち,自分が行った1回の呼出操作で全ての商品の画像が同一ウェブページに表示されず,出力されていない画像が他に存在する構\成に基づく方法では,顧客が,表示されていない品物の存在を失念している場合には,他のカテゴリーにアクセスしたり,同一カテゴリー内にある他の画像を呼び出したりすることは考えられないのであって,自分が預けた品物を全て正確に把握するという上記課題を解決できないから,「全体に一通り目を通す」ことにならない。そうすると,1回の呼出操作で全ての商品の画像が同一ウェブページに表\示されない新旧いずれの方法についても,被控訴人方法がこの要件を欠くものとなる。 したがって,被控訴人方法は,本件発明1の技術的範囲に属しない。同様の理由で,被控訴人方法は,本件発明2及び3の技術的範囲に属さず,被控訴人装置も,本件発明4から6の技術的範囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2015.04.13
平成26(ワ)23512 差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年3月24日 東京地方裁判所
本件明細書の上記イの記載によれば,本件発明は,ホタテ等の貝殻を粉砕した炭酸カルシウム粉末の粒体が多孔質粒体であり,多孔質粒体は吸着効果が大きいことを利用して,洗浄する物品に付着した化学物質等を吸着することを技術思想とする発明であると認められる。そうすると,本件発明の「炭酸カルシウムの方解石型構造による結晶構\造体を備えた貝殻を粉砕した粉末からなる炭酸カルシウム粉末」とは,上記アのとおり,貝殻を粉砕した粉末そのものであることを要するものであり,ホタテ貝殻を粉砕した粉末を焼成して得られた酸化カルシウム粉末が化学反応を経て炭酸カルシウム粉末になったものは含まないものと解される。
(2) 原告は,これと異なる前提に立って,被告各製品がホタテ貝殻を使用した製品であり,酸化カルシウム,炭酸カルシウム及び水酸化カルシウムを含むことから本件発明の技術的範囲に属すると主張し,被告各製品が,ホタテ貝殻を粉砕した炭酸カルシウム粉末そのものを混合した構成であることを主張立証しない。\nしたがって,原告の主張は,均等をいう部分を含めて採用できず,被告各製品が本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。
2015.04. 8
平成26(ワ)11110 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年3月25日 東京地方裁判所
原告は,乙1発明は,役者やモデルのような舞台に上がる者を対象としたメイクアップの技術であるのに対し,乙4発明は,模型等を対象とした塗装技術であって,技術分野が全く異なること,また,乙1発明と乙4発明の解決課題が異なることから,乙1発明に乙4発明を適用する動機付けがないと主張する。しかし,証拠(乙1)によれば,乙1文献の「問題点を解決するための手段」には,「本発明者は,上記の問題点を解決するために,化粧料を,手作業によって塗布する代りに,工業的に吹き付けることに気が付き,塗料を噴霧して吹き付けるのと同様な方法によって化粧料を噴霧して吹き付けることを考え付いたのである。」との記載があり,この記載はまさに,塗料を噴霧して吹き付ける塗装技術を,化粧料を吹き付ける技術に応用することが可能であることを示唆するものであると認めることができる。したがって,上記記載に照らせば,化粧料の吹付けに関する乙1発明に塗装技術である乙4発明を適用する動機付けがあるというべきであり,これに反する上記原告の主張は採用することができない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
2015.03.18
平成24(ワ)15621 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年1月22日 東京地方裁判所
原告は,本件における差止めの対象を,被告合金1及び2のうち,X線ランダム強度比の極大値が6.5以上のものであると限定するが,同一の製造条件で同一組成のCu−Ni−Si系合金を製造した場合,当然に,X線ランダム強度比の極大値が同一になることまでをも認めるに足りる証拠はなく,かえって,前記のとおり,製造ロットや測定部位の違いによりこれが変動する可能性があることからすると,正確なX線ランダム強度比の極大値については,製造後の合金を測定して判断せざるを得ないことになるが,この場合,どの部位を測定すればよいか,また,ある部位において構\成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても,どこまでの部分が構成要件Dを充足することになるのかといった点について,原告は,その基準を何ら明らかにしていない。\nそうすると,被告の製品において,たまたま構成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとして,当該製品全体の製造,販売等を差し止めると,構\成要件を充足しない部分まで差し止めてしまうことになるおそれがあるし,逆に,一定箇所において構成要件Dを充足しないX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても,他の部分が構\成要件Dを充足しないとは言い切れないのであるから,結局のところ,被告としては,当該製品全体の製造,販売等を中止せざるを得ないことになる。そして,構成要件Dを充足する被告合金1及び2が製造される蓋然性が高いとはいえないにせよ,甲5のサンプル2のように,下限値付近の測定値が出た例もあること(なお,原告は,これが構\成要件Dを充足しないことを自認している。)に照らすと,本件で,原告が特定した被告各製品について差止めを認めると,過剰な差止めとなるおそれを内包するものといわざるを得ない。 さらに,原告が特定した被告各製品を差し止めると,被告が製造した製品毎にX線ランダム強度比の極大値の測定をしなければならないことになるが, これは,被告に多大な負担を強いるものであり,こうした被告の負担は,本件発明の内容や本件における原告による被告各製品の特定方法等に起因するものというべきであるから,被告にこのような負担を負わせることは,衡平を欠くというべきである。 これらの事情を総合考慮すると,本件において,原告が特定した被告各製品の差止めを認めることはできないというべきである。
2015.03.18
平成24(ワ)15621 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年1月22日 東京地方裁判所
原告は,本件における差止めの対象を,被告合金1及び2のうち,X線ランダム強度比の極大値が6.5以上のものであると限定するが,同一の製造条件で同一組成のCu−Ni−Si系合金を製造した場合,当然に,X線ランダム強度比の極大値が同一になることまでをも認めるに足りる証拠はなく,かえって,前記のとおり,製造ロットや測定部位の違いによりこれが変動する可能性があることからすると,正確なX線ランダム強度比の極大値については,製造後の合金を測定して判断せざるを得ないことになるが,この場合,どの部位を測定すればよいか,また,ある部位において構\成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても,どこまでの部分が構成要件Dを充足することになるのかといった点について,原告は,その基準を何ら明らかにしていない。\nそうすると,被告の製品において,たまたま構成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとして,当該製品全体の製造,販売等を差し止めると,構\成要件を充足しない部分まで差し止めてしまうことになるおそれがあるし,逆に,一定箇所において構成要件Dを充足しないX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても,他の部分が構\成要件Dを充足しないとは言い切れないのであるから,結局のところ,被告としては,当該製品全体の製造,販売等を中止せざるを得ないことになる。そして,構成要件Dを充足する被告合金1及び2が製造される蓋然性が高いとはいえないにせよ,甲5のサンプル2のように,下限値付近の測定値が出た例もあること(なお,原告は,これが構\成要件Dを充足しないことを自認している。)に照らすと,本件で,原告が特定した被告各製品について差止めを認めると,過剰な差止めとなるおそれを内包するものといわざるを得ない。 さらに,原告が特定した被告各製品を差し止めると,被告が製造した製品毎にX線ランダム強度比の極大値の測定をしなければならないことになるが, これは,被告に多大な負担を強いるものであり,こうした被告の負担は,本件発明の内容や本件における原告による被告各製品の特定方法等に起因するものというべきであるから,被告にこのような負担を負わせることは,衡平を欠くというべきである。 これらの事情を総合考慮すると,本件において,原告が特定した被告各製品の差止めを認めることはできないというべきである。
2015.03.16
平成26(ワ)65 差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年2月27日 東京地方裁判所
ア 振動状態のショートカットアイコンが移動可能な状態になることについて甲3,甲17の1,甲32の1・2及び弁論の全趣旨によれば,本件ホームアプリにおいて,振動状態でないショートカットアイコンにドラッグ操作を行っても指の動きに追従して移動することはないが,振動状態のショートカットアイコンにドラッグ操作を行うと,指の動きに追従して移動することが認められる。\nそうすると,ロングタッチは,「ポインタ(=ロングタッチ中の振動状態のショートカットアイコン)の位置を移動可能な状態に切り替える命令」とみることができる。原告は,「させる」とは「ある行為をするように仕向ける」という意味であるから,「ポインタの位置を移動させる命令」とは,「ポインタの座標位置を移動させる状態に切り替える命令」という意味であると主張する。\nしかし,「させる」とは「ある行為をするように仕向ける」という意味であるから(甲27),「ポインタの位置を移動させる命令」とは,「ポインタの位置を移動するよう仕向ける命令」すなわち「ポインタの位置を移動するよう指示する命令」を意味することは一義的に明確であって,これを「ポインタの位置を移動可能な状態に切り替える命令」であると解釈する余地はない。「ある行為をするように仕向ける」ことと,「ある行為が可能\な状態に切り替える」こととが異なることは明らかであるから,「させる」に前者の意味があるとしても,後者の意味があることにはならない。原告の主張は失当である。 本件明細書の段落【0052】〜【0101】の実施例の説明を見ても,構成要件Eにいう「ポインタの位置を移動させる命令」に対応するものとしては,「例えば,マウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させること(ドラッグ操作)や,キーボードにおける特定のキーを押しつつマウスを移動させる行為,等が該当する。」(段落【0079】)とされ,「ポインタの位置を移動するよう指示する命令」をもって「ポインタの位置を移動させる命令」としているのであって,「ポインタの位置を移動可能\な状態に切り替える命令」をもって「ポインタの位置を移動させる命令」とすることについては何らの記載も示唆もない。このような本件明細書の記載を参酌すれば,「ポインタの位置を移動させる命令」が「ポインタの位置を移動するよう指示する命令」を意味し,「ポインタの位置を移動可能\な状態に切り替える命令」を意味しないことは一層明らかである。\nしたがって,ロングタッチが「ポインタ(=ロングタッチ中の振動状態のショートカットアイコン)の位置を移動可能な状態に切り替える命令」であったとしても,構\成要件Eにいう「ポインタの位置を移動させる命令」に当たるということはできない。
イ 振動状態のショートカットアイコンがやや下に移動することについて ロングタッチにより振動状態となったショートカットアイコンは,元々の位置よりやや下に移動して振動するものと認められる。 しかし,甲32の1・2によれば,Facebookアイコンをロングタッチすると,ロングタッチ中のFacebookアイコンのみならず,ロングタッチしていないEvernoteアイコンやTwitterアイコンも元々の位置よりやや下に移動して振動状態となっていることが認められる。 そうすると,ロングタッチが,「ポインタ(=ロングタッチ中の振動状態のショートカットアイコン)の位置」を「元々の位置よりもやや下に移動させる」ことを指示する命令ということはできない。ロングタッチ中の振動状態のショートカットアイコンがやや下に移動するのは,他のショートカットアイコン(非「ポインタ」)の移動と同様,振動状態になったことを示す付随的な動作にすぎず,このような付随的な動作が生じることをもって,ロングタッチが「ポインタの位置を移動させる命令(=移動を指示する命令)」であるということはできない。
ウ 振動状態のショートカットアイコンが小刻みに振動することについて 甲32の1によれば,ロングタッチにより振動状態となったロングタッチ中のショートカットアイコン(=「ポインタ」)は小刻みに振動することが認められるが,これも,他のショートカットアイコン(非「ポインタ」)の振動と同様,振動状態になったことを示す付随的な動作にすぎず,このような付随的な動作が生じることをもって,ロングタッチが「ポインタの位置を移動させる命令(=移動を指示する命令)」であるということはできない。
(6) 「ポインタの位置」を「『Multi Touch』ソフトウェアがカーソ\\ルや数値で表示する座標位置」とした場合原告は,甲32の1・2において「Multi Touch」と題するソフトウェアが赤いカーソ\ルの位置や画面左上の数値で表示する座標位置の変化をもって,「ポインタの位置の移動」であるかのような主張をする(原告準備書面(2)42頁)。しかし,原告は,「Multi Touch」と題するソフトウェア(及びこれにデータを提供していると主張する「MotionEvent」と題するソフトウェア)がどのようなデータを検出しており,それが本件発明にいう「ポインタ」の定義を満たすのかについて主張立証をしないから(指を離した状態でも,また「ショートカットアイコンが指に追従する」状態でなくてもカーソ\ルが表示されているのであるから,「タッチパネル上の指の座標位置」でも,「指の動きに追従するショートカットアイコンの座標位置」でもないことは明らかである。),当該ソ\フトウェアが何を検出しているにせよ,それが本件発明にいう「ポインタ」に当たると認めることはできず,仮にロングタッチにおいて上記ソフトウェア上のカーソ\\ルや数値で表示される座標位置が変動するとしても,ロングタッチが「ポインタの位置を移動させる命令」に当たるとはいえない。(7) 本件ホームアプリが「ポインタ」を用いるものでない場合被告の主張するとおり,本件ホームアプリが「ポインタ」を用いるものでないと解釈した場合には,当然ながら,「ポインタの位置を移動させる命令」も存在しない。 (8) 以上のとおり,本件ホームアプリにおける「ポインタ」をどのように解釈するにせよ,ロングタッチが「ポインタの位置を移動させる命令」であるとはいえないから,その余の点につき判断するまでもなく,本件ホームアプリは,本件発明の構成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると……操作メニュー情報を……表\示する」出力手段を備えたコンピュータシステムにおけるコンピュータプログラムであるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2015.03. 3
平成26(ネ)10114 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年2月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被告ウェブサイトは,被控訴人が多数のファッションブランドの商品を販売するインターネットショッピングサイトであり,被控訴人は,ブランド各社から納入を受けた商品を被告ウェブサイトにアクセスしたユーザーに対し,被控訴人の名義で販売しており,被告ウェブサイトで商品情報画像のアイコン2(別紙1の図2)がユーザーによってクリックされると,関連商品が表示されるリンク先のページ(別紙1の図3及び図4)は,被控訴人の自社のページであること,被告ウェブサイトで表\示される他のページも,いずれも被控訴人の自社のページであり,被告ウェブサイトには,被控訴人以外の他の企業が管理するホームページに誘導するバナー広告が存在しないことが認められる。 したがって,被告ウェブサイトを使用する被告システムには,「商品の広告をネット上で紹介提供」する参加企業が運営又は管理する「Webサイト」又はそのトップページとしてのホームページである「参加企業のホームページ」が存在するものと認めることはできず,ひいては,被告システムにおいて,「参加企業のホームページ」を保管する「バナーサーバー」が存在するものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2015.03. 2
平成26(ワ)7856 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年2月24日 東京地方裁判所
前記前提事実及び上記認定事実に基づき構成要件1D並びに2C及び2Dにいう「第1記録領域」及び「第2記録領域」の意義についてみるに,まず,特許請求の範囲の「記録媒体の第1記録領域」及び「記録媒体の第2記録領域」との記載によれば,第1記録領域及び第2記録領域は,記録媒体が有する記録領域全体のうちそれぞれ一部分を占める領域であり,相互に区別されて存在するものであることが明らかである。また,「第1データを・・・第1記録領域に書き込み」,「第2データを・・・第2記録領域に書き込\nむ」との記載によれば,データを書き込む際には,それが第1データであるか第2データであるかに応じて,記録領域全体のうちどの領域に書き込まれるのかが定まっているとみることができる。 このような特許請求の範囲の記載によれば,記録媒体の記録領域は,第1記録領域及び第2記録領域(並びに管理領域その他の領域)に物理的に区分されており,第1データが記録される第1記録領域に第2データが書き込まれたり,第2データが記録される第2記録領域に第1データが書き込まれたりすることはないと解すべきものとなる。 そして,上記の解釈は,前記(1)イの本件明細書の記載,すなわち,半導体メモリには第1記録領域と第2記録領域が形成されており,第1データの書き込みは第1記録領域の書込可能容量に達した場合に終了し,第2データの書き込みは第2記録領域の書込可能\容量に達した場合に終了する旨の記載に沿うものであって,本件明細書(甲4)の発明の詳細な説明及び図面に,これと異なる構成(第1データが記録されるべき領域への第2データの書き込み又は第2データが記録されるべき領域への第1データの書き込みを許容するような構\成)を示唆する記載は見当たらない。 そうすると,第1記録領域及び第2記録領域は,記録媒体の記録領域を物理的に区分して形成された別個の領域であると解するのが相当である。
・・・
被告機器及び被告運行管理方法においては,センサから出力され,一次記録領域に記録された加速度データを,トリガ判定閾値を超えるなどの条件を満たすデータ(原告が第1データに当たると主張するもの。以下「甲データ」という。)であるか,事故判定閾値を超えるなどの条件を満たすデータ(原告が第2データに当たると主張するもの。以下「乙データ」という。)であるかに応じて,記録媒体(CFカード)に形成された別個のファイルに記録するとされている(別紙被告機器・・・)。そして,原告の認めるとおり,CFカードの記録領域は物理的に区分されておらず,甲データ又は乙データに対応するファイルが記録領域全体のうちどの部分に形成されるかは書き込みをする際に定まるというのであるから,CFカード中の空き領域には甲データ及び乙データのいずれもが書き込まれ得るということができる。 以上によれば,被告機器及び被告運行管理方法は本件各特許発明の「第1記録領域」及び「第2記録領域」に相当する構成を有していないと判断するのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2015.02. 8
平成24(ワ)15693 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年1月23日 東京地方裁判所
本件発明が物の発明であることに鑑みると,構成要件1Fの「…ステーションに搬送されて,…要求図書が取り出されたコンテナまたは…返却されたコンテナに対して…更新する」との文言から,上記更新手段は,\n ステーションに搬送された状態で,図書が取り出された状態のコンテナ又は図書が返却された状態のコンテナに対して,記憶手段の記憶内容を更新するという構成を示していると解するのが自然である。そして,本件明細書等には,「図書館員がコンソ\ール54を操作して返却完了の指示を中央処理装置39に入力すると,図書コードと,…コンテナ番号とを組み合わせ,その組み合わせたデータを…前記ハードディスク47等に登録する。」(段落【0051】),「…図書館員がコンソール54を操作して取り出し完了の指示を中央処理装置39に入力すると,…更新する。」(段落【0058】)というように上記解釈を裏付ける記載はあるが,その一方で,本件明細書等には,ステーションに搬送されていない状態で,図書の取り出し又は返却の完了していない状態のコンテナに対して更新するものとする更新手段の構\成については,記載されていないし,かかる構成の示唆すらない。\nさらに,前記の本件明細書等の記載には,「…図書の取り出しや返却が行われたコンテナが書庫に戻される際に,…記憶内容が更新される」(段落【0010】),「このようなサイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段を採用することにより,…同一寸法の図書ならば,その寸法の図書を収容するためのコンテナ内に任意に返却することが可能となるので,…自動化による図書の取り出し及び返却作業の能\率を効果的に向上させることができる」(段落【0011】)と記載されており,これらの記載から,本件発明において前提とされるサイズ別フリーロケーション方式は,同一寸法の図書ならばコンテナ内に任意に返却することが可能な構\成,すなわち,同一寸法の図書であればその寸法の図書を収容するためのコンテナ内に空きのある限り任意に収容することが可能な構\成とされているものと理解することができる。そして,コンテナ内に空きのある限り図書を任意に収容するためには,図書の取 り出しや返却が行われたコンテナが書庫に戻される際に,更新手段が記憶内容を更新する,すなわち,図書の取り出しや返却が行われた状態にあるコンテナに対して記憶内容を更新することが必要であり,そのような構成が本件発明におけるサイズ別フリーロケーション方式の前提となっているものと解される。
ウ したがって,構成要件1Fの「…ステーションに搬送されて,…要求図書が取り出されたコンテナまたは…返却されたコンテナに対して…更新する更新手段」とは,ステーションに搬送された状態で図書が返却された状態のコンテナに対して記憶内容を更新する構\成を具備する更新手段をいうものと解するのが相当である。
・・・
以上のイないしオによれば,乙22公報,乙26公報,乙23公報,乙27公報には,自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けること,又は,自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが記載されており,これらのことが従来周知の技術的事項であると認められる。 また,乙26公報及び乙27公報に記載されているように,自動倉庫に格納される収容物がコンテナ又は容器に収納した状態で格納されることは,周知の事項であり,乙27公報に記載されているように,収容物の寸法に応じて大きさの異なる容器を使い分けることも,従来から一般的に行われていることであると認められる。そして,このコンテナ又は容器が収容される棚領域が,収容物の大きさ(寸法)に対応したものとなることは自明の事項である。 以上によれば,前記イないしオから,「収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の収容物を収容する複数のコンテナを備えた自動公庫」との事項が周知技術であると認められる。 キ そして,乙12発明と上記カで認定した周知技術は,コンテナ等に収容物を収容し,このコンテナを,棚等を有する収容場所に格納するものであるという点で共通するから,乙12発明に上記周知技術を適用することは, 当業者が容易になし得たことであると認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
2015.02. 8
平成25(ワ)16060 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年1月16日 東京地方裁判所
上記アからすると,被告商品における「テンプレート」は,被告のサービスポータルの表示画面において,顧客が利用する仮想マシン及び仮想システムの構\成のメニューとしての選択候補を意味するにすぎないものと認められる。 この点,原告は,被告商品における「テンプレート」は,総合試験を経て動作保証された,即時稼働可能な状態で提供される仮想マシンそのものであり,予\め用意されたテンプレートのコピーにより仮想マシンが作成されるのであるから,構成要件Aの「レンタルエンジン」に該当する旨主張する。\nしかし,前記認定に係る本件発明の特徴からすれば,ユーザーからのリクエスト時にレンタルエンジンは実在するものでなければならないところ,上記のとおり,被告商品においては,ユーザーの選択により仮想マシンが配備される,つまり,ユーザーが選択しない限り仮想マシンは配備されず,ユーザー自らが必要な構成や機能\を選択してシステム構築を行うものであるから,ユーザーのリクエスト時に実在しない仮想マシンをレンタルエンジンととらえることはできない。まして,テンプレートをコピーすることにより仮想マシンが作成されることを前提としても,テンプレートを実在するレンタルエンジンととらえることもできない。ユーザーからのリクエスト時にテンプレート上に表\示されたリソースの動作保証がされていることと表\示されたリソースから構\成されるコンピューターが現実に存在することが異なることは明らかである。 ウ 以上のとおり,被告商品における「テンプレート」を,構成要件Aの「レンタルエンジン」ととらえることはできず,ほかに被告商品において構\成要件Aにいう「レンタルエンジン」に該当すると認めるべき構成は見当たらない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2014.12.18
平成25(ワ)3480 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年12月11日 大阪地方裁判所
前記3のとおり,本件特許発明4(請求項4)が,いずれも請求項1の従属項である請求項2または請求項3の発明に,「前記ユーザエージェントは,前記第三者エージェントと協働して仕事を行うマルチエージェントで構成されている」との構\成を付加していることから,本件特許発明1(請求項1)は,マルチエージェントシステムの構成を前提とするものではないと解する余地がある。\nしかしながら,本件特許発明1(請求項1)には,「自律的なソフトウェアモジュールとしてのエージェント」,「コンテンツ提供手段」,「プロフィール情報受付手段」,「マッチング判断を行うエージェント」,「中立性を有する第三者エージェント」,「コンテンツ提供システム」といった構\成が使用されており,単に「マルチエージェント」の言葉が使用されていないことのみを理由として,複数のエージェントが協働するマルチエージェントシステムの構成が開示されていないと即断することはできない。\nむしろ,上記のとおり,原出願はマルチエージェントシステムの構成を前提とするものであるから,その曾\孫出願をさらに分割してされた本件特許が,複数のエージェントの協働という限定のない,単にエージェントの存在のみを内容とするシステムを権利内容とするとは考え難い(仮にそうであるとすると,分割要件の問題となるほか,前記3(2)において認定した従来技術との関係において,新規性,進歩性も問題となる。また,上記のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,マルチエージェントシステムを前提に課題を解決する発明が開示されていると認められるが,請求項1に単なるエージェントの存在のみで構成される発明が記載されているものとした場合,サポート要件の点も問題となる。)。\nまた,前記3のとおり,原出願の明細書では,発明の実施の形態として,ゼネラルマジック社が開発した通信用言語であるテレスクリプトによる自律ソフトウェアとしてのエージェントを採用することなどが記載されているが,その前後の記載から,これがマルチエージェントシステムの採用を前提とする内容であることは明らかであるところ,本件明細書にも,前述のとおり,発明の実施の形態として,ゼネラルマジック社が開発した通信用言語であるテレスクリプトによる自律ソ\フトウェアとしてのエージェントを採用することが記載されており,これによれば,本件明細書は,原出願にかかる明細書同様,エージェント同士が協調して動作するマルチエージェントシステムを利用することで課題を解決するとの構成を開示するものと認められ,本件特許の特許請求の範囲の文言についても,これを前提に理解すべきものである。
(3) あてはめ
以上によれば,本件特許の構成要件A−1の「自律的なソ\フトウェアモジュールとしてのエージェント」については,他のソフトウェアモジュールとしてのエージェントと,課題解決のために協調して動作するマルチエージェントシステムの一部を意味するものと解するのが相当である。\n被告システムについては,前記2で認定したところであるが,携帯電話等のユーザー端末,被告が利用するサーバー群及びコンテンツ提供業者のそれぞれにソフトウェアがインストールされ,相互に情報のやり取りをする事実は認められるものの,被告システムのエージェントが,ユーザーのエージェントあるいはコンテンツ提供業者のエージェントと,課題解決のために協調して動作するマルチエージェントシステムが構\成されている事実は,本件で提出された証拠によっては認定することができない。 そうすると,被告物件イ−2(iコンシェル)は構成要件A−1を充足せず,本件特許発明1の技術的範囲に属しないというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2014.11. 7
平成25(ワ)32665 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年10月30日 東京地方裁判所
本件特許の特許請求の範囲には,構成要件Dとして「前記本体と可動的に接続されたガイド板」と,構\成要件Eとして「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または第2の刃が出る」と記載されており,その文言上は,本体がガイド板に対して動くとガイド板から刃が出てくるものであれば足り,本体とガイド板の接続態様や本体の動き方についての限定はないということができる。しかし,構成要件Eの上記文言は,発明の構\成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり,いわゆる機能\的クレームに当たるから,上記の機能を有するものであればすべてこれを充足するとみるのは必ずしも相当でなく,本件明細書に開示された具体的構\成を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である。そして,構成要件Dの「可動的に接続された」との構\成についても,構成要件Eと整合するように解釈すべきものと解される。\n
・・・
(3) 本件明細書の上記記載によれば,「前記ガイド板から前記第1の刃または第2の刃が出る」との機能を果たすための本体のガイド板に対する動き方として本件明細書に開示されているのは,本体をガイド板に対して傾けること(上記(2)オ,カ)及びスイングするガイド板を設けること(同カ)であり,要するに本体をガイド板に対して傾け,又は回転運動させるということである。そして,本体をガイド板に対して左右に傾け,又は回転運動させた場合には,本体の左下又は右下の端部がガイド板から外に出るから,本体の左下及び右下の端部に第1及び第2の刃の各先端を位置させて おけば,本体を傾けるだけで刃が出てきて,あとはノンスリップシート等の凹凸に沿わせて滑らせるだけで簡単,きれいかつ迅速に切断できるという本件特許発明の効果(同オ)を奏すると認められる。そうすると,構成要件Eの「動く」には少なくとも回転運動が含まれるとみることができる。\n次に,本体がガイド板に対して回転運動するように「可動的に接続」すること(構成要件D)についてみるに,2枚の板状の部材を回転可能\に接続する態様としては,1)それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成のほか,2) 一方の周辺部に円弧状の溝等を設け,この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構\成を採用し得る。このうち本件明細書に明示されているのは1)の構成のみであるが(上記(2)エ〜カ),いずれの構成であっても特許請求の範囲にいう「可動的に接続」に該当し,かつ,本件特許発明に係る課題を解決して上記の効果を奏すると考えられる。したがって,2)の構成も構\成要件Dの「可動的に接続」に含まれると解すべきものである。 (4) 被告製品は,前記前提事実(5)イのとおり,本体3(回転板)とガイド板6(固定板)が円弧状の溝を有する接続部7を介して接続され,本体を左右に傾けてこの溝に沿って円周方向に動かすと,刃1又は刃2がガイド板から外に出るように構成されている。したがって,被告製品は,構\成要件D及びEを充足し,本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる。 (5) これに対し,被告は,1) 本件特許発明の技術的範囲は本件明細書に開示された構成(本体とガイド板がシャフトにより接続され,本体がシャフトを軸にしてガイド板に対して回転する構\成)に限定して解釈されるべきである,2) 被告製品は本件特許発明とは異なる課題を解決するものであるから,本件特許発明の技術的範囲に属しない旨主張する。そこで判断するに,1)について,上記(3)に説示したところによれば,本体とガイド板を回転可能に接続するに当たり,シャフトにより軸着するか,円弧状の溝に摺動可能\に嵌合するかは,当業者が適宜選択し得る実施の形態にすぎないということができる。また,2)について,被告製品が本件特許発明の構成要件を充足し,その効果を奏することは上記(3)及び(4)のとおりであるから,被告製品が本件特許発明と異なる課題をも解決するとしても,この点は上記の判断に影響するものではない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 機能クレーム
2014.10. 6
平成25(ワ)5744 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年9月18日 大阪地方裁判所
(ア)「一覧出力形式」のうち,「一覧」には,「全体の概略が簡単にわかるようにまとめたもの」(甲14),「全体が一目で分かるようにしたもの」(乙4)という意味があり,「出力」には,「機器・装置が入力を受けて仕事をし,外部に結果を出すこと」(甲14),「原動機・通信機・コンピュータなどの装置が入力を受けて仕事または情報を外部へ出すこと」(乙4)という意味があり,「形式」には,「物事を行うときの,則るべき一定の手続きや方法・様式」(甲14),「事務などを進めるための,文書の体裁や執るべき手続」(乙4)という意味がある。 構成要件1Dには,第1通信装置の記憶手段に記憶された複数の品物の画像データの中から,ユーザ情報に対応するものを「一覧出力形式」で,すなわち,全体を一覧できるように,情報を外部へ出す方法で,第2通信装置へ送信する旨が記載されている。ここで,「全体」とは,「ユーザ情報に対応するもの」,すなわち,ユーザ情報に対応する複数の品物の画像データの全てであると読み取ることができる。
(イ)発明が解決しようとする課題,課題を解決するための手段及び発明の効果において,顧客がどの衣類を預けたか忘れてしまうことがあるが,事業者が預かっている対象物の内容を画像で視覚的に示すことによって,顧客が,預けている衣類を正確に把握でき,その中から,返却を要求したい衣類を事業者に対して容易かつ的確に知らせることができる旨が指摘されており,P1は,本件特許出願の過程で,同様の指摘や補正をしている。このような目的,作用効果のためには,事業者は,顧客に対し,預かった複数の品物の全てについて,1回の出力で,その画像を閲覧できるように提示する必要がある。 発明の実施の形態においても,預かり物の全ての画像データが読み込まれ,その結果,注文情報データベースから抽出した所定の注文情報と,預かり物画像データベースから読み込んだ衣類の画像データによって生成される「お預かり表」のウェブページに,抽出された全てのレコードに記述されている画像データパスの画像データが表\示され,全ての画像データを閲覧することが可能となる。
(ウ)前記(ア)及び(イ)を併せ考えると,「一覧出力形式」とは,ユーザ情報に対応する複数の品物の画像データが出力された場合,その画像データの全てが一覧できる状態,例えば,ディスプレーに表示される場合には,ひとつの画面上で閲覧できる状態(ディスプレーの大きさや画面の大きさにより,スクロールする必要が生じる場合を含む。)で,情報を外部へ出す方法を意味すると解される。
(2)構成要件1Dに対応する被告方法の構\成 証拠(甲6〜8,乙3)及び弁論の全趣旨によると,被告方法は,別紙被告方法目録記載第2の構成を備えていると認めることができる。 これによると,被告方法では,各画像データが「保管中アイテム」等のカテゴリーに分けられてサーバに記録されており,顧客があるカテゴリーのボタンをクリックすると,旧被告方法の場合,当該カテゴリーについてのみ,カテゴリー内の全ての画像が顧客側へ送信され,新被告方法の場合,当該カテゴリー内の1枚の画像のみが顧客側へ送信される。
(3)被告方法の構成要件1Dへの充足性
そうすると,被告方法は,ユーザ情報に対応する複数の品物の画像データの全てが一覧できる状態で,情報を外部へ出す方法をとっておらず,「一覧出力形式」との構成要件(構\成要件1D)を充足しない。 したがって,被告方法は,本件発明1から3までの構成要件を文言上充足すると認めることができない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> コンピュータ関連発明
2014.10. 3
平成25(ワ)5600 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年9月25日 大阪地方裁判所
もっとも,請求項1及び2の記載のみからは,「横向き管の最下面」,「延長線」の意味が明らかではない。横向き管は,上向き,下向き等の方向のものをも含むところ,本件明細書では,横向き管が水平である場合の「延長線」が図示されているのみで,上向きや下向きの場合の「延長線」は図示されていない。そうすると,横向き管が上向きや下向きの場合に,「最下面」がどの面を指すかという点や,「延長線」の始点,方向が明らかとはいえない。 イ そこで,前記(1)で指摘した本件明細書の記載内容を検討すると,従来の混合装置では,輸送短管の出口とレベル計との間に空間ができていたために,材料の一部が未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下していたところ,この問題を解消するため,本件各特許発明では,輸送開始時に必要とされる充填レベルに達するまで混合済み材料を充填させ,既に充填された混合済み材料によって,吸引輸送される材料が未混合のまま一時貯留ホッパー へ落下するのを阻止するようにしている。 また,充填レベルは,混合済み材料が縦向き管のどの高さまで貯留したかを示すものであるから,輸送開始時を定める充填レベルの基準は,混合済み材料の上表面によって示される必要がある(混合済み材料の上表\面は,必ずしも正確な水平面とは限らないが,レベル計によって,その上表面の位置が判断される。)。 充填レベルが,横向き管が縦向き管に接する出口の下端よりも下方にあって,充填レベルと横向き管の出口の下端との間に空間が生じていると,輸送された材料が未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下することになる。そのため,一時貯留ホッパーへの落下を防ぐには,材料の輸送が開始する時点で,横向き管が縦向き管に接する出口の下端に達するまで,混合済み材料が充填されている必要がある。 したがって,輸送開始時を定める充填レベルの基準となり,充填レベルを検出するためのレベル計の位置の基準ともなる「横向き管における最下面の延長線」とは,横向き管が縦向き管と接する出口の下端から,水平方向に向かって延長した線を意味すると解される。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2014.10. 1
平成23(ワ)26676 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年9月25日 東京地方裁判所
一般的な学術用語としての転位に該当する典型的な線状の結晶欠陥(前記(2)ア参照)であれば,STEMないしTEM観察により線状の画像が明瞭に認められる(甲23,24,30,乙6,21参照)のに対し,乙21写真において原告が「転位」であると指摘する箇所は,画像処理を行ってコントラストを強調すれば線状に見える余地があるとはいえ(甲34参照),上記の典型的な場合に比較すると不鮮明なものにとどまる。 また,本件明細書1には結晶欠陥(転位)密度をTEM分析により測定した旨の記載があり(段落【0046】),その発明者らはTEMを用いて「転位」の存在を確認したと推測されるものの,当時のTEM画像等は証拠として提出されておらず(その存在自体不明である。),発明者らが「転位」と認識したものと乙21写真に現れたものが同一であると認めるべき証拠はない。そうすると,乙21写真によって,被告製品の製造過程において機械研磨により原子レベルの線状の欠陥が発生したと認めることは困難である。
イ さらに,乙21写真に線状の結晶欠陥の存在を示す暗線状のコントラストが認められるとしても,これが構成要件C1にいう「転位」に当たるというためには結晶中の深い位置,すなわち,従来技術において除去されるものとされた加工変質層より深い位置に発生したことを要する。そこで,乙21写真に現れた深さ約0.2μmのコントラストがこれに当たるかについてみるに,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,加工変質層の深さは研磨剤の材質及び粒径等の加工条件によって異なり,例えば粒径に応じて約0.1〜1.7μmの範囲となり,又は9μm未満となる旨の報告があること(乙31),GaN基板を機械研磨すると,N面における約0.2〜0.3μmの表\面下層は激しくダメージを受け,多くの欠陥を含んでいると評価されたこと(乙34),基板を機械研磨した後にRIE法により1〜2μm程度エッチングするという技術が本件特許権1の出願日前に公知であったこと(乙2の11)が認められる。 また,本件明細書1には,発明の実施の形態として,機械研磨後にGaN基板の裏面をRIE法によりエッチングすると,機械研磨により発生した結晶欠陥を含む領域が除去されることによりコンタクト抵抗が低下する,エッチングの深さが0.5μmの場合のコンタクト抵抗は0.05Ωcm2(すなわち,構成要件D1に規定された最大値)であるが,1μmエッチングするとコンタクト抵抗が更に低くなる,0.5μmのエッチングでは結晶欠陥を含む領域を十\分に除去することができないと考えられるので,約1.0μm以上の厚み分を除去することが好ましい旨の記載がある(段落【0056】,【0059】,【表1】)。\nこれら事実関係に照らすと,乙21写真に現れた深さ約0.2μmのコントラストは,加工変質層と呼ばれる領域にとどまっていると考えられるのであって,結晶中の深い位置に存在すると認めるに足りないから,本件特許発明1及び1−2にいう「転位」に当たるとはいえないと解すべきである。
2014.09.25
平成25(ワ)19768 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年9月11日 東京地方裁判所
証拠(甲6,8,11,13,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,被告土木積算プログラムは,対象工事に含まれる作業を歩掛データベースで規定された作業に置き換えて積算データを作成することが認められる。これによれば,被告土木積算プログラムにおいては,操作者が,工程・種別・細別をそれぞれ入力して初めて一つの工程が対応し,これを繰り返して工事全体の工程の集合体である積算データ,すなわちSKF600が生成されるというものである。換言すれば,操作者は,設計書に基づき,工事全体のデータを入力する必要があるのであって,このようにして生成されるSKF600は,工事名称を入力することにより,工事名称と歩掛マスターテーブルを対応付けて,工事に含まれる要素を抽出するというステップで生成されるものではない。 そうであるから,被告製品のSKF600は,対象工事の全範囲における積算データであって,本件プログラム発明における「内訳データ」とは生成過程が異なり,その全体ないし一部をもって「内訳データ」に相当すると見ることはできない(被告製品のSKF600は,これを本件プログラム発明に対応させるとするならば,本件明細書記載の外部システムなどから得られる評価対象工事の情報に対応するものと解される。)。 (3) したがって,被告製品においては「内訳データ」が生成されないから,本件プログラム発明の構成要件1−Dを充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2014.09.16
平成25(ワ)6185 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年9月4日 大阪地方裁判所
前記証拠及び弁論の全趣旨によると,被告物件においては,本件機能を利用して,「一緒にボタンを押す」ボタンを押した他の利用者が検索・表\示された後に,友人申請及び承認を行う場合,他の方法によって検索・表\示された利用者に対する友人申請及び承認を行う場合と同様の処理が行われること,本件機能\を利用してマイミクとなったかどうかは,被告物件のシステム上区別されていないことが認められる。これによると,被告物件において,友人申請に対する承認があったことを確認する際に,その者が所定の地理的エリア内にいることの確認は行われていないことになる。
(5) まとめ
以上を総合すると,被告物件の利用者らが「一緒にボタンを押す」ボタンを押し,付近にいる者が「一緒にいる人一覧」に検索・表示される段階では,地理的情報の利用はあるものの,「コンタクト可能\状態にするための同意」の確認はされず,他方,利用者の友人申請を他の利用者が承認する際には,「コンタクト可能\状態にするための同意」はあるものの,「所定の地理的エリア内にいる」ことの確認はされない。したがって,被告物件は,「所定の地理的エリア内にいる者によるコンタクト可能状態にするための同意がとれたことを確認するための確認手段」であるとの,構\成要件Bを充足しない。
2 争点(3)(被告物件が,構成要件Dを充足するか)について
(1) 構成要件Dは,「前記アクセス要求受付手段によりアクセス要求が受付けられた\nときに,前記確認手段による同意がとれたことの確認が行なわれたことを条件に,同意した者同士がコンタクトを取るためのコンタクト用共有ページへのアクセスを許容するためのアクセス制御手段」というものである。以下,本件特許発明の具体的内容を考慮しつつ,被告物件が構成要件Dを充足するか検討する。\n(2) 上記構成要件Dの文言からして,構\成要件D中の「前記アクセス要求受付手段」とは,構成要件Cにいう「アクセス要求受付手段」であり,「前記確認手段」とは,構\成要件Bの確認手段をいうことは明らかである。 したがって,構成要件Dは,構\成要件Bにいう同意の確認とは別に,コンタクトを希望する相手方に対する「アクセス要求」を受け付ける手段があることを前提として,構成要件Cのアクセス要求が発生した際に,構\成要件Bの同意の有無について判定を行い,同意が確認された場合に,コンタクトを許容することをその要件とするものと認められる。 (3) 原告は,被告物件において,被告構成cの「各利用者の専用ホームページに表\示される「友人リストボタン」,「メッセージボタン」,「新着メッセージが1件あります」,「つぶやきボタン」等のフィールドに張られたリンクを介して画面遷移する操作が受け付けられることが,「アクセス要求受付手段」に該当すると主張する。 この点,前掲証拠及び弁論の全趣旨によると,被告物件において,上記アクセス要求が発生するのは,すでに利用者同士がマイミクの関係にあることを前提としているのであり,マイミクとなっていない利用者同士では,「メッセージ」や「つぶやき」を利用しようとすること(アクセス要求に相当する)すらできない仕様になっていることが認められる。 (4) すなわち,被告物件は,構成要件Bにいう「同意の確認」に相当する友人申\請の承認があってはじめて,「アクセス要求受付手段」を利用できる構成となっており,上記(2)にみたとおりの,同意があるかどうかにかかわらず,コンタクトを取りたい相手方にアクセス要求を受け付ける手段や,そのアクセス要求があったときに,同意の有無を判定した上でアクセスを許容するような構成を備えていないものと認められる。また,逆に,被告物件において,原告の主張する「アクセス要求」が発生した際には,コンタクト可能\状態にすることの同意が取れたことの確認は行われず,まして,その同意が,構成要件Bの要件である,「所定の地理的エリア内にいる者による」ことの確認は行われないものと認められ,この点からも,被告物件は構\成要件Dを備えないものというべきである。 (5) その他原告が主張する事情及び本件明細書を含む全証拠を考慮しても,上記判断を覆すほどのものはない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2014.08.20
平成24(ワ)14652 特許権侵害損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年7月23日 東京地方裁判所
そして,本件688明細書の上記(イ)e,fの記載に照らせば,本件688発明において,洗濯兼脱水槽から洗濯物が取り出され,槽内に洗濯物がない状態で上記槽乾燥工程を行うことで,脱水孔から空気が外槽内にスムーズに流れ,槽内の乾燥効率向上という作用効果が得られるものとされていることをうかがうことができるところ,本件688明細書に,上記(イ)gのとおり,温風供給手段を動作させるタイミングを,洗濯兼脱水槽から洗濯物を取り出した後とするためには,蓋の開閉動作があったことを条件とすればよい旨の記載があることも考慮すれば,蓋開閉検知は,洗濯兼脱水槽内から洗濯物が取り出された状態で槽乾燥工程が行われることを担保し,槽内の乾燥効率の向上という上記作用効果を確保するための構成であると解されるところである。そうすると,「検知を条件に」を,槽乾燥工程への自動移行を意味するものと解すべき理由はなく,同文言は,単に蓋開閉検知がされなければ槽乾燥工程に移行しないことを意味するにとどまるものと解するのが相当である。\n
・・・・
以上によれば,本件521特許及び本件893特許の侵害を理由とする原告らの請求は,争点(4)イ・ウについて検討するまでもなく理由がないことに帰着する。 そこで,以下においては,争点(4)ア(本件688特許の侵害による損害額)についてのみ検討する。
・・・・
そうすると,ロ号製品について,そのカタログやウェブサイト上の製品説明において,本件688特許登録前の製造販売に係る製品のように,「カビプロテクト」機能につき大きく取り上げる扱いがされていなかったとしても,従前の宣伝広告等により,需要者が当該機能\\を重視することは十分にあり得るものというべきである。なお,被告は,本件688特許登録前の製造販売に係る製品は,いわゆる縦型洗濯機であり,ドラム式洗濯乾燥機であるロ号製品とは無関係なものである旨主張するが,縦型洗濯機とドラム式洗濯乾燥機の需要者は共通するものと解されるのであって,前者に係る宣伝広告の効果が後者に波及することは十\\分にあり得るものと解されるところである。加えて,ロ号製品についても,機種名TW−G520L/Rの製品については,そのカタログにおいて,「カビプロテクト」機能により手軽に槽の手入れをすることができる旨が大きく取り上げられていること(甲36,乙64),機種名TW−Z370L,TW−G520Lの製品については,株式会社東芝のウェブサイトにおける上記製品の「商品情報」において,カビプロテクト機能\\を有する旨が記載されていること(乙66)に照らせば,ロ号製品においても,「カビプロテクト」機能はその宣伝広告において取り上げられることがあったものということができるのであって,本件688発明に係る機能\\が需要者の商品選択に寄与する割合が低いものであったとはいい難いものというべきである。
エ 他方,特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を具体的な構成をもって社会に開示した点にあるというべきところ,本件688発明がその課題解決のために具体的に開示した新たな技術的手段としての構\\成は,「前記検知工程による検知を条件に」槽乾燥工程へ移行するようにしたところであって,同発明は,蓋の開閉検知のほかには,「洗濯物が取り出された状態」とするための技術的手段を開示していないことは,前記1で見たとおりである。
オ 以上の事情を総合考慮すると,ロ号製品の売上高に1%を乗じた金額が,本件688特許の特許権者が本件688発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する金額(特許法102条3項)として相当であると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
2014.08.13
平成25(ワ)7569 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年7月17日 東京地方裁判所
本件特許の出願経過において,原告は,前記前提事実(2)エのとおり,引用文献1に基づく進歩性欠如等をいう本件拒絶理由通知に対し,特許請求の範囲の記載等を補正するとともに本件意見書を提出して,引用文献2及び同3はいずれもエジェクタを用いた技術であり,本件発明を示唆するものでない旨の意見を述べた。本件拒絶理由通知は,補正前の特許請求の範囲記載の発明と引用文献1記載の発明は,吸着具を上下動部材の先端に設けるか,正圧源からの正圧空気を着脱路と上下動部材を上下動させる空気圧シリンダに共用して供給するかの点で相違するが,これらの点は吸着搬送装置の技術分野において引例を示すまでもない周知技術であるとしつつ,括弧書きで「(不足であれば,例えば,引用文献2及び3等を参照されたい。)」と記載するものであった。原告は,本件意見書において,原告の特許出願に係る発明の構成,技術的意義等について説明し,引用文献1との比較をした後,引用文献2及び同3につき,これら文献に記載された技術内容や本件発明との具体的な相違点については何ら言及することなく,これ\nらが「エジェクタを用いた技術」であることのみを理由に,本件発明を示唆するものでないとの意見を述べた。(乙2〜5) ウ 上記イ(ア)〜(ウ)の事実関係によれば,本件発明は,大気開放ポートがなく,真空破壊のための空気が出力ポートのみから着脱路に流入し,かつ,出力ポートから供給される正圧空気が全て着脱路の吸着面から排出される従来技術を前提に,ワークを迅速に離脱させるとともに吹き飛ばしを防止して正確な位置決めをするという課題の解決のため,大気開放ポートを設けてこれを着脱路及び出力ポートと連通させることにより,着脱路が大気圧に達するまでは大気開放ポートからも空気を流入させてワークの離脱を迅速にし,これが大気圧に達した後は正圧空気が大気開放ポートからも流出するものとしてワークの吹き飛ばしを防止したものであり,この点の構成が本件発明の課題解決のための本質的部分に当たると認められる。そうすると,大気開放ポートがなくても排気口から大気の流入及び正圧空気の排出が行われるエジェクタを備えた構\成は,上記の前提を欠くものであり,本件発明が解決すべき課題も存在しないことになるから,本件発明とは本質的部分において相違すると解するのが相当である。 上記イ(エ)の出願経過における原告の意見は,エジェクタを用いたものは本件発明とは基本的な技術思想が異なる旨をいうものと解され,本件発明の本質的部分についての上記解釈を裏付けるものということができる。 そうすると,前記のとおりエジェクタにより構成されたロ号製品は本件発明の本質的部分を備えていないものとみるべきであり,前記1)の要件を充足しないから,ロ号製品について均等による特許権侵害は認められないと判断するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2014.07. 2
平成24(ワ)14227 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年05月22日 東京地方裁判所
これらの記載に前記(ア)認定の事実を併せ考えると,本件発明は,アニーリングという技術手段を採用して,これにより,p型不純物をドープした窒化ガリウム系化合物半導体から水素を出すという作用が生じ,p型窒化ガリウム系化合物半導体が製造されるという効果が得られるというものである。そして,この場合のアニーリング雰囲気は,真空中,N2,He,Ne,Ar等の不活性ガス又はこれらの不活性ガスの混合ガス雰囲気中で行うのが好ましく,さらに,アニーリング温度における窒化ガリウム系化合物半導体の分解圧以上で加圧した窒素雰囲気中で行うのが最も好ましいとされる。これに対し,アニーリング雰囲気中にNH3,H2等の水素原子を含むガスを使用したりキャップ層に水素原子を含む材料を使用することは,p型不純物に結合した水素原子を熱的に解離するというp型のための反応が進行せず,上記作用効果を奏しないことがあるので好ましくないとされるが,逆に,p型不純物に結合した水素原子を熱的に解離するというp型化のための反応が進行して,上記作用効果を奏することもあると考えられることから,アニーリング雰囲気中にNH3,H2等の水素原子を含むガスを使用したり,キャップ層に水素原子を含む材料を使用することが排除まではされていないということができる。そうであれば,構成要件Bの「実質的に水素を含まない雰囲気」とは,このような作用効果を奏するような雰囲気,言い換えれば,アニーリングにより低抵抗なp型窒化ガリウム系化合物半導体を得ることの妨げにならない程度にしか水素を含まない雰囲気を意味するものと解するのが相当である。\n
・・・
被告製品の売上額が51億7487万2414円を下らないこと,本件発明の実施に対し原告が受けるべき金銭の額が被告製品の売上額の5%に相当する額であることは,当事者間に争いがなく,これらの事実によれば,本件発明の実施に対し原告が受けるべき金銭の額は,2億5874万3620円を下らない・・・
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 102条3項
2014.07. 2
平成25(ワ)18288 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 平成26年05月22日 東京地方裁判所
上記認定に基づき検討するに,本件明細書の発明の詳細な説明及び本件図面においては,回動基部7自体が垂直面に投影したときに「コ」の字状の形状を備えるとされている一方(段落【0014】,【図2】),回動基部におけるアーム支持部を除く部分の構成や,回動基部自体が「コ」の字状又は「コ」の字型ではない構\成については何らの記載がない。また,本件発明は,従来技術の問題点(段落【0006】)を克服すべく,1) 第1と第2の多関節アーム手段を折り畳むことでハンドを待機位置に移動したときに決定されるガイドレール上で移動する際の干渉範囲を小さくする,2) 剛性を低下させずに第1と第2のハンドの機械的な干渉を防止する,3) 第1と第2のハンドの平行移動軌跡を設置面から低く設定するという目的を達成するものである(段落【0007】)。ところで,上記2)の目的は,回動基部を「コ」の字型にし,その上端天井部に第1アームの端部を回動自在に支持し,その下端側に第2の多関節アームの第1アームを支持することで達成される(段落【0019】)。そして,上記1)及び3)の目的は,第1及び第2の多関節アーム手段を同一垂直線上に並置したことにより達成されるものであって(段落【0019】,【0022】),回動基部を「コ」の字型にすることによりその目的の達成が阻害されることもないし,かえって,回動基部にアーム支持部以外の部分を設ける場合,とりわけアーム支持部よりも下に何らかの構成を設けるような場合には,上記3)の目的を阻害することにもなりかねない。そうすると,本件発明において,「前記回動基部が,上基部と,前記上基部と対向して配置された下基部と,前記上基部と前記下基部とに連結され,前記回動基部の前記主基部に対する回動中心線からずれて立設された支柱部と,からコ型に形成されたアーム支持部を有し」(構成要件B−1ないしB−5)とは,「前記回動基部が,上基部と,前記上基部と対向して配置された下基部と,前記上基部と前記下基部とに連結され,前記回動基部の前記主基部に対する回動中心線からずれて立設された支柱部と,からコ型に形成されたアーム支持部を構\成し」の意味に解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2014.06.30
平成24(ワ)15614 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年06月24日 東京地方裁判所
上記事実関係に基づいて判断するに,本件訂正発明2の特許請求の範囲にいう「以下」とは基準となる数量(45個)と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから,その文言上は,0個の場合を含むと解することが可能である。しかし,本件明細書の記載によれば,本件訂正発明2は,「介在物の分布の制御を行うことにより」従来技術の問題点を解決するものであり(前記(3)ア(イ)),5〜10μmの粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において45個/mm2未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見(同(ウ)参照)に基づくものである。そして,5〜10μmの粗大な介在物が0個であれば「粗大な介在物の分布」は問題とならないから,本件明細書の記載を考慮すると,上記大きさの介在物が0個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。これに加え,原告は,析出物及び晶出物粒子の粒径をすべて5μm以下とすることは容易である旨をいう本件拒絶理由通知に対し,本件意見書において,介在物を小さくすれば銅合金の特性改善が図れることは知られていたが,粗大な介在物が存在してもその個数が一定限度であれば良好な特性が得られるという,粗大な介在物の分布の概念を新たに導入した点に本件発明の意義がある旨を述べたものである。本件意見書の上記記載は,5〜10μmの大きさの介在物が存在する場合にのみ本件発明の技術的意義が認められ,5〜10μmの介在物が0個の場合はその技術的範囲に含まれないことを前提としているものと解される。そうすると,原告は,構成要件Fにいう「5〜10μmの大きさの介在物個数が…50個/mm2未満」であることの意義につき,これが0個/mm2の場合を含まない旨を本件意見書において言明し,これにより本件拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから,本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件F’’の「45個/mm2以下」に0個/mm2の場合が含まれると主張することは,上記出願手続における主張と矛盾するものであり,禁反言の原則に照らし許されないというべきである。したがって,構成要件F’’にいう「45個/mm2以下」には0個/mm2の場合が含まれないと判断することが相当である。
2 争点3(無効理由の有無)について
前記1で判断したとおり,構成要件F’’にいう「45個/mm2以下」には介在物個数が0個/mm2の場合を含まないと解すべきものであるが,その文言上はこれを含むと解することもできるので,そのように解した場合に本件特許に無効理由があるかについて念のため検討する。
(1) 乙3文献に基づく新規性欠如について
ア 乙3文献には次の趣旨の記載がある(乙3)。
・・・・
(ア) まず,乙3発明の「晶出物又は析出物」を本件訂正発明2の「介在物」と同視できるかを検討すると,証拠(乙32)及び弁論の全趣旨によれば,1)銅合金を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察すると,二次電子像(いわゆるSEM画像)により,晶出物,析出物,酸化物,硫化物等の粗大な粒子の大きさ及び個数を測定することができるが,晶出物,析出物,酸化物,硫化物等のいずれであるかの区別はできないこと,2)EPMA装置により特性X線を検出してS及びOを同定する分析を行い,これにより得られるSを同定したEPMA画像及びOを同定したEPMA画像とSEM画像とを対照すれば,SEM画像で観察した粒子から酸化物及び硫化物を除外することが可能であること,3) EPMA画像を撮影して分析するためには,単にSEM画像を撮影して分析するのに比し,数十倍の時間を要することが認められる。他方,乙3文献には,「晶出物又は析出物の大きさ」の測定のために,上記1)のSEM画像の観察のほかに,上記2)のEPMA装置による分析を行ったことの記載はない。また,乙3文献には,有害な不純物であるS及びO2の量を厳密に規定した(段落【0013】)ことの記載はあるが,酸化物及び硫化物の粒子の大きさに関する記載はなく,SEM画像で観察される粗大な粒子に酸化物及び硫化物が含まれていることを示唆する記載もない。そうすると,乙3発明について上記2)のEPMA装置による分析を行ったとは認められず,乙3発明の「晶出物又は析出物の大きさ」(前記イ(オ))は,上記1)のSEM画像により観察された粗大な粒子の大きさを意味するものと解される。さらに,本件明細書(甲40の3)には,介在物個数はSEMで観察したものであること(段落【0019】)が記載されているから,本件訂正発明2の「介在物」も,SEM画像により観察される粗大な粒子であると解される。以上によれば,乙3発明の「晶出物又は析出物」も本件訂正発明2の「介在物」もSEM画像により観察される粗大な粒子であり,測定の対象は同じであるから,乙3発明の「晶出物又は析出物」(前記イ(オ))は,本件訂正発明2の「介在物」(構成要件E及びF\\)と同視できるというべきである。
(イ) 次に,乙3発明の「大きさが1.3〜1.8μm」という構成(前記イ(オ))について検討する。乙3発明は「晶出物又は析出物の大きさが3μm未満」とする発明に係る実施例ないし比較例であること,乙3文献には,晶出物又は析出物の大きさが3μm以上だとめっき性等が悪化するとの記載がある(段落【0014】)ことからすれば,乙3発明における「晶出物又は析出物の大きさ」とは,これらの粒子の大きさの最大値をいうものと解される。したがって,乙3発明における「大きさが1.3〜1.8μm」には,粒子の大きさが5μm未満である構成が開示されているものと解される。そして,前記(ア)のとおり,乙3発明における「晶出物又は析出物」は,本件訂正発明2における「介在物」と同視できるから,乙3発明は,「介在物の大きさが10μm以下であり,かつ,5〜10μmの大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で45個/mm2以下(0個/mm2の場合を含む。)」(構成要件E及びF\\)の構\成を実質的に開示するものである。
・・・・
オ 以上によれば,乙3発明は本件訂正発明2と実質的に同一の構成を開示するものである。そして,乙3文献には乙3発明の製造方法が説明され,当業者が当該構\成を実施し得る程度の記載があると認められるから,本件訂正発明2は新規性を欠くものというべきである。(2) したがって,本件訂正発明2に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,特許法104条の3第1項により,原告は,本件特許権を行使することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
2014.06.10
平成24(ワ)28201 特許権 民事訴訟 平成26年05月27日 東京地方裁判所
本件発明によれば,ダクタイル鋳物を製造する際に,保持炉で貯留,滞留された元湯を取鍋に受け,次いで,黒鉛球状化処理装置に搬送してダクタイル鋳物用溶融鋳鉄に溶製し,さらに,必要に応じて取鍋内のスラグを除去するまでの工程において,取鍋をクレーン等によって吊り上げる必要性がないため,ほとんどの作業を自動化することが可能となり,極めて少ない操作員で一連の作業に対処することが可能\となる。その結果,省力化及び省力化に伴う生産性の向上が達成され,工業上有益な効果がもたらされる。(段落【0037】)
ウ 以上に基づいて構成要件Aの「保持炉」の意義を検討する。
(ア) 本件特許の特許請求の範囲には,保持炉とは「溶解炉で溶解された元湯を貯留する」(構成要件A)ものであると記載されているところ,前記イ(ア)の文献の記載によれば,本件発明の属する技術分野においては,保持炉は「溶解炉で溶解した溶湯を一定の温度に保持し,鋳造機又は鋳型に注湯するために設置される炉」を,溶解炉は「固体金属を熱源で加熱して溶融金属に変える炉」を意味するものとして,それぞれ別個の炉であると認識されていると認められる。そうすると,特許請求の範囲の文言上,構成要件Aの「保持炉」は,鉄源原料を溶解して溶融金属に変える溶解炉とは別に設けられ,溶解炉で溶解された元湯を貯留する炉を意味すると解される。さらに,本件明細書の発明の詳細な説明を検討すると,1)従来技術において,溶解炉で溶解された元湯をダクタイル鋳物用溶融鋳鉄に溶製する際には,通常,溶解炉で溶解された元湯を一旦保持炉に装入し,保持炉で貯留,滞留させて温度や成分等を均質化させた後に保持炉から所定量の元湯を取鍋に装入し,取鍋は,クレーンやホイスト等によって吊り上げられて,保持炉と黒鉛球状化処理装置の間を搬送されていたこと,2)本件発明は,従来技術における労働生産性を改善するために,溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化装置とを備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備において,取鍋が,保持炉から黒鉛球状化処理装置へ吊り上げられることなく移動されることを特徴とする構成を採用したものであること,3)実施形態において,保持炉は,キュポラや電気炉等の溶解炉で溶解された元湯(溶融鋳鉄)を一旦収容する容器で,低周波誘導等によって収容された元湯を加熱することが可能な炉であり,キュポラあるいは電気炉等の溶解炉で得られた元湯を一旦保持炉に収容するが,通常,溶解炉と保持炉との間には元湯の通過する湯道が設置され,元湯は連続的にあるいは間欠的に溶解炉から保持炉に供給されることが記載されている。これらの各記載は保持炉と溶解炉が別の炉であることを示していることが明らかである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2014.06. 4
平成25(ワ)18288 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 平成26年05月22日 東京地方裁判所
本件明細書の発明の詳細な説明及び本件図面においては,回動基部7自体が垂直面に投影したときに「コ」の字状の形状を備えるとされている一方(段落【0014】,【図2】),回動基部におけるアーム支持部を除く部分の構成や,回動基部自体が「コ」の字状又は「コ」の字型ではない構\成については何らの記載がない。また,本件発明は,従来技術の問題点(段落【0006】)を克服すべく,(1) 第1と第2の多関節アーム手段を折り畳むことでハンドを待機位置に移動したときに決定されるガイドレール上で移動する際の干渉範囲を小さくする,(2) 剛性を低下させずに第1と第2のハンドの機械的な干渉を防止する,(3)第1と第2のハンドの平行移動軌跡を設置面から低く設定するという目的を達成するものである(段落【0007】)。ところで,上記(2)の目的は,回動基部を「コ」の字型にし,その上端天井部に第1アームの端部を回動自在に支持し,その下端側に第2の多関節アームの第1アームを支持することで達成される(段落【0019】)。そして,上記(1)及び(3)の目的は,第1及び第2の多関節アーム手段を同一垂直線上に並置したことにより達成されるものであって(段落【0019】,【0022】),回動基部を「コ」の字型にすることによりその目的の達成が阻害されることもないし,かえって,回動基部にアーム支持部以外の部分を設ける場合,とりわけアーム支持部よりも下に何らかの構成を設けるような場合には,上記(3)の目的を阻害することにもなりかねない。そうすると,本件発明において,「前記回動基部が,上基部と,前記上基部と対向して配置された下基部と,前記上基部と前記下基部とに連結され,前記回動基部の前記主基部に対する回動中心線からずれて立設された支柱部と,からコ型に形成されたアーム支持部を有し」(構成要件B−1ないしB−5)とは,「前記回動基部が,上基部と,前記上基部と対向して配置された下基部と,前記上基部と前記下基部とに連結され,前記回動基部の前記主基部に対する回動中心線からずれて立設された支柱部と,からコ型に形成されたアーム支持部を構\成し」の意味に解するのが相当である。
ア 原告は,特許請求の範囲の請求項1の記載からすれば,本件発明のアーム支持部は回動基部の一部であると主張するが,本件発明の回動基部は,それ自体がコ型に形成されたアーム支持部を構成するもの,すなわち,それ自体がコ型に形成されたアーム支持部であると解するのが相当であり,このように解しても,「前記回動基部が,・・・アーム支持部を有し」の語義に反するものとはいえない。原告の上記主張は,採用することができない。
イ 原告は,前記第2の3(原告)ウ記載のとおり,本件図面の【図1】には,回動基部7が,第1の多関節アーム手段と第2の多関節アーム手段とを支持する青色部分を備えると共に,この青色部分の下に,主基部1に対する回転中心から水平方向に延びる赤色部分を備えていることが明示されていると主張する。しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0013】によれば,【図2】は【図1】のX−X線矢視断面図であるとされているが,この【図2】には原告主張の赤色部分に該当する部分の記載がない(なお,原告は,【図2】に示された回動基部全体の構造について,上辺に比べて下辺が長いからコの字型ではないとの主張もするが,【図2】に記載された程度に下辺が長くとも,回動基部7の全体がコの字型であると解し得る。)。また,原告主張の赤色部分の構\成や機能は,本件明細書や本件図面からは明らかでないというほかなく,仮に青色部分の下に赤色部分が存在するとすれば,第1と第2のハンドの平行移動軌跡を設置面から低く設定するという本件発明の目的(前記(3))を阻害することになってしまう。さらに,【図1】における多関節ロボット装置は,同図中の破線図示のウエハまたは基板22を図中の矢印Y方向に平行移動することにより一時保管のための装置100と,ウエハまたは基板22に対して所定処理を行なう装置200の間での出し入れを行うために,各装置100,200の略中心に配置され,第1の多関節アーム手段に取り付けられたハンド21と第2の多関節アーム手段に取り付けられたハンド121による処理前基板の取り出し,処理箇所への搬送及び処理済み基板の返送を同一垂直線上で互い違いの対称関係で同時進行するように構成されているものであるが(段落【0010】,【0019】),【図1】の記載を原告の上記主張のように解すると,青色部分のうち,第1及び第2の多関節アーム手段が取り付けられる上基部及び下基部の長手方向が,赤色部分の長手方向と平行でなく,一定の角度で接続されているものとして図示されていることになるから,この場合,両者を平行に設置した場合に比して,第1及び第2の多関節アーム手段における各第1アーム及び第2アームの長さを長くせざるを得なくなるおそれがあり,そうであるとすれば,ガイドレール上で移動する際の移動方向に沿う干渉範囲の短縮化を図るという本件発明の目的(前記(1))及び効果(段落【0022】,【0025】)を阻害することになりかねない。そうすると,【図1】における回動基部7に関する作図自体が,そもそも不正確,不適切なものであると解さざるを得ず,これを根拠として,回動基部7が原告の主張するような構造であると理解することはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2014.05.26
平成25(ネ)10099 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成26年05月21日 知的財産高等裁判所
控訴人の主張は,要するに,構成要件A,C及びI に記載された各プログラムの実行手順及び実行内容としての領域確保は,単なる画面表示上の表\現によって他と区別できる部分が表示されることでも十\分であるというものと整理される。しかしながら,前記認定判断(原判決引用部分)のとおり,本件発明は,初期フレームプログラムがクライアント装置において実行されて,商品カテゴリーリストの表示領域が表\示装置に第1フレームとして表示された上で,引き続き,クライアント装置からサーバ装置に対し,第1フレームをターゲットとして商品カテゴリーリストを表\示するためのカテゴリーリストプログラムを送信するよう要求するHTTPメッセージが送信され,これを受けてサーバ装置が読み出したカテゴリーリストプログラムがクライアント装置に送信され,これが実行された結果,商品カテゴリーリストがWebブラウザに表示されるという過程を経るという構\成をとった方法の発明なのである。また,前記認定判断(原判決引用部分)のとおり,本件発明は,初期フレームプログラムがクライアント装置において実行されて,商品PLUリストの表示領域が表\示装置に第2フレームとして表示された上で,引き続き,クライアント装置からサーバ装置に対して,第2フレームをターゲットとしてPLUリストサーバプログラムの実行を指示するHTTPメッセージが送信され,サーバ装置がPLUリストサーバプログラムを起動して生成したPLUリストプログラムがクライアント装置に対し送信され,これが実行された結果,商品PLUリストがWebブラウザに表\示されるという過程を経るという構成をとった方法の発明なのである。したがって,前記説示のとおり,画面上の表\現の前提として観念的には当該部分の表示のための表\示領域の確保が先行しているとみたとしても,構成要件の充足のためには,上記過程がその順序で順次実行されている必要があるところ,前記認定判断(原判決引用部分)のとおり,被控訴人システムにおいては,各画面は一つのHTML文書であって,サーバ装置からクライアント装置に対して一括して送受信されているものであり,各画面の各表\示とその表示領域の確保とは同時にされているのであるから,本件発明の構\成に従った過程が実行されているとみる余地はない。以上のとおりであるから,控訴人の上記主張は,採用することのできないものである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2014.05.22
平成25(ネ)10086 債務不存在確認請求本訴,損害賠償請求反訴請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成26年04月24日 知的財産高等裁判所
平成19年9月から発売が開始されたiPod touchではクリックホイールが採用されず,タッチパネルが採用されている(乙26)。タッチパネルはプッシュスイッチを有するものではなく,また,タッチパネルによる操作方法は,タッチパネル向けに最適化されており,コンテンツをCover Flowで表示するには,iPod touchを横に回転させ,アルバムカバーをブラウズするには,左右にドラッグするか,フリックし,任意のトラックを再生するには,再生したいトラックをタップする等というものであって,クリックホイールによる操作とは大幅に異なる(甲138)。そうすると,タッチパネルとクリックホイールとでは,小型携帯装置の入力手段であるという程度の共通性しか見出せず,両者が代替手段の範疇にあるとは認められない。
2014.04.22
平成24(ワ)9695 債務不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年03月25日 東京地方裁判所
そこで,構成要件1−B及び2−Bの「受信」の意義について検討すると,まず,本件特許の特許請求の範囲の記載によれば,本件各発明においては「第1の利得因子」を「受信」し(構\成要件1−B及び2−B),基準として決められた特定の第1の利得因子を用いて「第2の利得因子」を「計算」すること(1−D及び2−D)が必須の構成とされており,文言上「受信」と「計算」が区別されている。そして,「受信」とは他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けること(乙1)を,「計算」とは演算をして結果を求め出すこと,「演算」とは数式の示すとおりの所望の数値を計算すること(広辞苑〔第6版〕859,334頁参照)を意味するところ,二つの値を乗じることが「計算」に当たることは明らかである。そうすると,Aedとβcを乗じて参照利得係数を得ることは,第1の利得因子を計算するものということができる。
ウ 次に,本件明細書の発明の詳細な説明の欄をみると,以下の記載があることが認められる。(甲2)
・・・・
(カ) 以上を通じ本件明細書の発明の詳細な説明の記載中には,基準TFないし第1のTFの利得因子がシグナリングされることが記載される(段落【0047】,【0048】,【0053】〜【0055】,【0058】,【0062】,【0067】,【0071】)一方で,第1の利得因子を演算により求めることの記載はない。エ 以上の特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載によれば,構成要件1−B及び2−Bの「受信」とは,端末がネットワーク(基地局)から第1の利得因子そのものを直接受け取ることを意味し,複数の値を受け取った上でこれらの値を用いて演算処理を加えることにより第1の利得因子を求め出す場合,すなわち「計算」に当たる場合は含まないものと解すべきである。
・・・・
以上によれば,被告の主張する原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するとは認められず,また,本件各製品におけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法についてそのほかの構成の主張もないから,本件各製品が本件各発明の間接侵害品であるということはできない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告が本件各製品の輸入等に関し原告に対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとは認められない。\n
2014.04.11
平成25(ネ)10107等 特許権侵害行為差止請求控訴,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 平成26年03月26日 知的財産高等裁判所
また,控訴人は,補正において符号が付されたことにより,第三者が符号で特定された実施形態に限定されたものと認識する以上,本件発明の構成要件Eにおける金属収集機構\\は,符号により特定された実施形態に限定されるべきである旨主張する。しかし,上記において認定したところに照らすと,第三者において控訴人の主張するように認識するとは認められない。よって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 機能クレーム
2014.03.29
平成25(ワ)1470 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年03月13日 大阪地方裁判所
前記2(1)ウのとおり,原告は,本件特許出願の手続において,当初は,「活性成分及び界面活性剤を溶剤に溶解させた後,水を加える方法」以外の方法により製造された組成物も含むクレームについて出願をしていたものである。しかし,特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応するため,敢えて上記方法により製造された組成物に限定する補正をし,それにより特許を受けたことが認められる。このように,特許出願の手続において敢えて限定したクレームについて,その技術的範囲を拡張する主張は包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。したがって,被告製品の構成は本件特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
2014.03.29
平成25(ネ)10017等 特許権侵害行為差止請求控訴,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 平成26年03月26日 知的財産高等裁判所
さらに,掬い上げ部材について,本件訂正明細書2には,「尚,該板状の掬い上げ部材5c1及び5c2の傾斜角度は,図示の例では,回転軸5aの中心軸線に対し20°傾斜せしめたものを示したが,一般に10°〜80°の範囲が採用できる。」(段落【0015】)と記載されているから,回転軸5aの中心軸線に対して10°〜80°の傾斜があれば足り,その傾斜角は一定でなければならないものではない。すなわち,回転軸5aの中心軸線に対する角度が小さくなればなるほど,走行方向に対し直交する長矩形の板状で構成される従来の掬い上げ部材に近いものとなり,掬い上げの効果は大きくなる一方,堆積物の外側への拡散が増大するが,回転軸5aの中心軸に対する角度が大きくなると,掬い上げの効果は小さくなるが外側への拡散を防止できることとなるものと推測されるところ,本件訂正発明2のV字型掬い上げ部材において,これらの角度は適宜選択できるものとなっているから,V字状のみに限定されず,より頂点への角度が緩やかな逆への字状のもの等も含まれる。また,段落【0006】には,「本発明のパドルの変形例として,図5に示すようなパドル5b″に構\成しても良い。すなわち,先の実施例のそのV字状の傾斜板5c1及び5c2の一端部を当接し,互いに直接溶接する代わりに,その両傾斜板5c1及び5c2の一端部間を適当な距離離隔し,そのスペース内に板状などの補強梁5jを介在させ,その両端部を傾斜板5c1及び5c2の一端部とを溶接し,その前後一対の板状の掬い上げ板部5c1及び5c2はハの字状に対称的に傾斜した傾斜板に構成しても良い。」との記載もあり,必ずしもV字状の掬い上げ部材に限られるものではないことが明らかである。さらに,段落【0009】には,「また,その本発明のパドル5b′の夫々の傾斜板5c1及び5C2は長矩形状とし,同一形状,寸法であることが一般であり好ましく,また,通常のパドル5bの板状掬い上げ部材5cと同一形状,寸法であることが一般であるが,これに限定する必要はない。また,その各傾斜板5c1及び5C2の長さ又は高さ寸法は所望に設定される。」と記載され,しかも,本件発明1の掬い上げ部材について,本件明細書1の段落【0005】に「その先端には堆積物を掬い上げる板状,爪状などの掬い上げ部材5cを有し,その回転により堆積物の撹拌とその正転,逆転による往復動撹拌を行う作用を有する。」と記載されているから,堆積物を掬い上げるための形状も,平面な「板状」に限られるものではない。\n
(ウ) 以上に照らせば,堆積物の外側への掬い上げ時の拡散,崩れなどの不都合を解消するために,前後一対の板状の掬い上げ部材が,それぞれ回転軸の軸方向に対し所定角度内側(オープン式発酵槽の長尺壁の方向)を向くようにし,掬い上げ部材の内側に向いて傾斜した部材の外側が,その前方に堆積する堆積物の長尺開放面側の外端堆積部に当接し,斜め内側に向けてこれを掬い上げるよう,傾斜板を所定角度内側に向けて配置したことが,本件訂正発明2を基礎付ける特徴的部分であると認められる。そして,本件訂正発明2の攪拌機は,往復動走行に伴って正又は逆回転するものであることから,掬い上げ部が外端堆積部に当接する場合は,回転軸に直交する前後方向のいずれの場合もあり得ることから,そのいずれの場合においても,堆積物を掬い上げる必要があり,そのために,掬い上げ部材を前後にかつ前後方向に対し傾斜させて配置し,その前側の傾斜板の外面は斜め1側前方を向き,その後側の傾斜板の外面は斜め1側後方を向くように配向させて配設されたものと認められる。そうすると,掬い上げ部材が前後の両方向に傾斜されて配置されるとの構成も,本件訂正発明2を基礎付ける特徴的部分であるといえる。これに対して,本件訂正明細書2には,掬い上げ部材が2枚であることの技術的意義は,何ら記載されておらず,前記のとおり,傾斜板の外面が正又は逆回転時のそれぞれにおいて,外端堆積部に当接することが重要であるから,本件発明2の掬い上げ部材が2枚で構\成されることに格別の技術的意義があるとはいえず,本件訂正明細書2に記載されるように2枚の部材を直接溶接してV字状を形成することと,1枚の部材を折曲してV字状を形成することとの間に技術的相違はないから,この点は本質的部分であるとはいえない。また,前記のとおり,前後に傾斜させる角度が,回転軸5aの中心軸線に対して10°〜80°の角度であればよく,逆への字状が含まれることや,掬い上げる部材としても,平面な板状に限定されず,外端堆積部に当接して内側に掬い上げることができればよいことに照らすと,掬い上げ部材が,平面な板状で構成されていることも,本質的部分であるとはいえない。そうすると,上記アで述べた,本件訂正発明2のV字型掬い上げ部材が「2枚の板状の部材を傾斜させて配置されるもの」に対し,ロ号装置の掬い上げ部材105dは,「半円弧状の形状を有する1枚の部材から構\成されたもの」であるとの相違点は,本質的部分に係るものであるということはできない。
・・・・
原告日環エンジニアリングによる均等侵害の主張は,原判決において本件発明2の文言侵害が認められなかったことを受けて,平成25年5月23日に行われた当審の第1回口頭弁論期日以前に提出された同年4月30日付けの附帯控訴状において均等侵害に該当する旨が記載され,同年5月16日付け準備書面において均等侵害の5要件に関する主張が記載されていたものであり,その内容は,新たな証拠調べを要することなく判断可能なものであり,訴訟の完結を遅延させるものとはいえない。したがって,上記主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下はしない。なお,被告が,原告らが,原審において,請求原因を明確にせず,被告及び裁判所から1年間にわたり請求原因の補充を促され続けたことにより遅延した旨主張する部分については,仮にそのような事実があったとしても,上記判断を左右するものでない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 裁判手続
2014.03.26
平成24(ワ)24822 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年03月20日 東京地方裁判所
原告らは,特許権侵害に係る不当利得の額は不当利得対象期間の被告各製品の売上額4億1602万5629円に実施料率3.5%を乗じた額であり,損害の額は損害賠償対象期間の被告の利益額633万0671円に等しいと主張する。上記売上額及び利益額に争いはなく,被告は,不当利得についての実施料率は0.5%であり,損害賠償についての寄与率は10%にとどまる旨主張するので,以下,検討する。
・・・
被告は,不当利得対象期間中,本件発明の実施許諾を得ないまま,その技術的範囲に属する被告各製品の製造販売をしたのであるから,少なくとも実施料相当額につき法律上の原因なくして利益を得,原告ペパーレットはこれと同額の損失を被ったということができる。イ そこで,本件発明の実施料率についてみるに,上記事実関係によれば,カラーチェンジ機能は猫砂に求められる複数の機能\のうちの一つにとどまり,顧客がこれを他の機能より重視しているとはいえないものの,紙製の猫砂全体に占めるカラーチェンジ機能\を有する製品の割合が,固まり性や消臭性を備えた猫砂の商品化後も徐々に拡大し,5割程度に達していることからすれば,カラーチェンジ機能は,同種製品の販売上,不可欠ではないとしても有益な機能\とみるべきものである。そして,被告各製品の包装をみても,製品ごとに強調の程度は異なるものの,カラーチェンジ機能をセールスポイントとして扱っている。また,実施料率について調査した文献によれば,本件発明の実施品が属するパルプ,紙加工品等の分野における実施料率は3%程度の契約例が多いとされている(甲14)。これらの事情を総合すれば,本件における実施料率は,売上額の3%と認めるのが相当である。したがって,原告らが返還を請求し得る不当利得の額は,合計1248万0768円(4億1602万5629円×3%)となる。\n
・・・
イ そこで判断するに,上記事実関係によれば,本件発明の効果であるカラーチェンジ機能が被告各製品の販売に貢献していることは明らかといえるが,他方,被告各製品は,消臭性,固まり性といった機能\も併せ有するのであり,これらに着目して,本件発明の実施品である原告らの動物用排尿処理材や,商品名等により専らカラーチェンジ機能が強調されていた前訴対象製品ではなく,被告各製品を選択する消費者も少なからず存在したものと推認することができる。これらの事情を総合すると,被告の利益のうち5割は本件発明以外の要因が寄与して生じたものであり,この限度で上記推定が覆ると考えられる。したがって,寄与率を10%とする被告の主張を採用することはできず,原告らが請求し得る損害賠償の額は合計316万5335円(633万0671円×50%)であると解するのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
2014.03.18
平成25(ネ)10091 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成26年03月13日 知的財産高等裁判所
前記1(1)に認定した本件特許の出願経過を見ると,出願当初の請求項1は,弁杆の上下動あるいは連動とガス流通路の開閉との関係を特に限定していなかったところ,特許庁審査官から,出願に係る発明全体が公知文献から容易想到であるとの拒絶理由を通知され,同発明の構成のうち「押圧杆によりガスの供給を可能\とする点」については周知技術であるとして引例7の存在を指摘された。控訴人は,これを受けた補正2)の際には,弁杆の連動とガス流通路の開閉との関係について特に補正をせず,専ら本件特許発明が引例7等とは全く異なる技術的課題の解決を目的としているなどと主張して,本件特許発明が容易想到であるとする判断を争ったものの,かかる主張は採用されず,また,本件特許発明の構成が組合せの困難なものであると指摘した補正3)についても,誤記があったことから却下された。そこで,控訴人は,補正4)において,前記1(1)クのとおり特許請求の範囲を補正するとともに,補正後の請求項1の(f)は,補正前の構成である,「回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を連動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調整用摘子」の構\成を,さらに具体化し限定したものであると説明し,その結果,かかる構成については特許庁審査官から特許要件についてさらなる指摘を受けることなく,特許査定に至ったものである。\n
(2) 上記(1)の経過に加え,前記1(3)認定の公知技術によれば,引例7に係る発明は,弁杆に相当するバルブが上昇した際にガス流通路が閉塞され,バルブが下降した際にガス流通路が開通する機構を有するものであったことに照らせば,控訴人は,引例7の存在を理由とする拒絶理由を回避するために,本件特許発明における弁杆の連動とガス流通路の開閉との関係を補正4)のように補正することにより,引例7が開示するのと同様の構成,すなわち弁杆が上昇した際にガス流通路が閉塞され,弁杆が下降した際にガス流通路が開通する構\成を除外したものと認めることができる。よって,控訴人は,補正4)において,本件特許発明の構成から引例7が開示するのと同様の上記構\成を意識的に除外したということができる。控訴人は,本件特許出願に対する拒絶理由通知では,弁杆下降時にガス流通路が形成され,弁杆上昇時にガス流通路が遮断される構成を含むことが拒絶理由として具体的に指摘されたことはなく,控訴人も,引例7に係る拒絶理由を回避するために,ガス流通路の開閉機構\から上記の構成を除外したことはなかったと主張する。しかし,拒絶理由通知に控訴人の指摘するような具体的な指摘がなく,また,控訴人が,拒絶理由を回避するために補正を行う旨を明示的に述べなかったとしても,上記のとおりの経過や引例7の内容に照らせば,控訴人が,拒絶理由を回避するために,本件特許発明の構\成から引例7が開示するのと同様の上記構成を意識的に除外したと認めることができ,他にかかる補正を行った理由について首肯すべき事情は見当たらないから,控訴人の主張は理由がない。」\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
2014.02.25
平成25(ワ)1723 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年02月20日 大阪地方裁判所
上記ア及びイによれば,本件特許発明1の構成要件Dの「項目定義手段」は,複数のデータベース(テーブル)で用いることのできるデータ項目(フィールド)を定義するための構\成であり,構成要件Eの「データベース・項目関連付け手段」は,項目定義手段によってデータベース(テーブル)の作成とは独立して定義されたデータ項目(フィールド)を各データベース(データベース)に,「追加,削除又は変更する」,すなわち割り当てる構\成であると解される。本件特許発明1は,このような構成を採用したことにより,項目定義手段によってデータ項目(フィールド)の定義を変更すると,それが全てのデータベース(テーブル)に反映されることになる(データ項目(フィールド)を複数のデータベース(テーブル)で共用することができる。)という作用効果を奏するものであることも認められる。また,上記ウによれば,最初に何らかのデータベース(テーブル)を作成し,次にこのデータベース(テーブル)を構\成するデータ項目(フィールド)を作成する構成は,本件特許発明1の技術的範囲から除外されるものと解される。これに反する主張は包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。\n
・・・
上記アによれば,被告システムの「バインダ」は本件特許発明1の「データベース」(テーブル)に相当し,被告システムの「部品」のうち「文字入力ボックス」や「数値入力ボックス」等を用いて作成したフィールドは本件特許発明1の「データ項目」に相当するものであることが認められる。原告は,訴状別紙被告システム説明書の「被告製品の構成g」の記載において,被告システムでは,「部品」を任意に追加,削除又は変更することができるから構\成要件Gを充足する旨の主張をしている。これは被告システムの「部品」が「データ項目」に相当するものであることを前提とする主張である(前記第3の1【原告の主張】(1)gはこの主張を前提としたものである。)。しかし,上記のとおり,被告システムの「部品」のうち「文字入力ボックス」や「数値入力ボックス」等を用いて作成したフィールドが,本件特許発明1の「データ項目」に相当するものであり,「部品」自体は「データ項目」ではない。上記原告の主張は前提を誤るものである。・・・・そもそも,被告システムは,最初に「バインダ」(データベース)を作成し,次に「文字入力ボックス」や「数値入力ボックス」等の「部品」を用いてバインダを構成するフィールド(データ項目)を作成する構\成のものである。このようにして作成されたフィールド(データ項目)は,個々のバインダ(データベース)に専属するものである。前記(2)イ(イ)のとおり,本件特許発明1の「データ項目を共用する」とは,項目定義手段によってデータ項目(フィールド)の定義を変更すると,それが全てのデータベース(テーブル)に反映されることをいうものであるところ,上記のような被告システムの構成からすると,このような本件特許発明1の作用効果を奏するものとは認められない。しかも,前記(2)ウのとおり,原告は,本件特許出願の手続において,最初に何らかのデータベース(テーブル)を作成し,次にこのデータベース(テーブル)を構成するデータ項目(フィールド)を作成する構\成は,本件特許発明1の構成と異なることを明確に述べており,このことからすると,被告システムが本件特許発明1の技術的範囲に属する旨の原告の主張は包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。以上によれば,被告システムは,本件特許発明1の「複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」及び「複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段」を備えるものと認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2014.02.24
平成22(ワ)20084 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年02月20日 東京地方裁判所
前提となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断 は,本件第1特許権につき別添1,本件第2特許権につき別添2,本件第3特 許権につき別添3のとおりである。
第3 結論
以上によれば,本件第2特許権に基づく原告の請求は,本件記憶媒体の製造, 販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の 支払を求める限度で理由があるので,その限度で認容し,その余を棄却すべき ものであり,本件第1特許権及び本件第3特許権に基づく請求は,いずれも理 由がないので,これらを棄却することとする。
別紙2
原告は,被告はその顧客による本件第2特許権の侵害行為につき共同不法行為責 任を負う旨主張する。そこで判断するに,証拠(甲39,42,66,68,乙42,79)及び弁論 の全趣旨によれば,被告の顧客が被告製品等を使用して本件加工方法を実施してい ること,被告が顧客に対して被告製品の販売促進用のビデオ等により本件加工方法 を実施できることを示してその販売をしていたこと,被告の従業員(サービスマ ン)が顧客のもとを訪れて被告製品等の使用方法の説明や指導をしていたことが認 められる。一方,原告は,被告のサービスマンが本件加工条件ファイルの作成をし ていたとも主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。 また,被告の顧客は被告製品等を用いて金属の加工等を行う業者であるから(弁 論の全趣旨),顧客による本件加工方法の実施は,これが日本国内で行われる限り, 本件第2発明3を業として実施するものとして,本件第2特許権の侵害に当たる。 そうすると,被告は,顧客による特許権侵害行為を常助したものとして,共同不 法行為責任を負うと解するのが相当である。
(5)小括
以上によれば,被告は,本件第2特許権の侵害につき,原告に対して損害賠償責 任を負うと認められる。また,本件記憶媒体の製造,販売及び販売のための展示の 差止めを求める原告の請求は理由があるということができる。他方,被告が本件加 工条件ファイルの作成をしたと認めるに足りる証拠はないから,原告の請求のうち その作成の差止めを求める部分は理由がないと解すべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
2014.02.24
平成24(ワ)7887 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年02月06日 大阪地方裁判所
以上によれば,被告製品の各構成は,本件優先日において雨樋の技術分野でごく一般的であった構\成を単に組み合わせたにすぎないものであり,これらごく一般的で公知の構成を組み合わせることについて何らかの阻害要因等が存在したことを窺わせる主張立証も全くない。そうすると,被告製品について,当業者が公知技術から容易に推考できたものではないと認めることはできないから,被告製品について,本件特許発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
2014.02.17
平成24(ワ)5664 特許権侵害差止等請求事件 特許権 平成26年02月06日 東京地方裁判所
ところで,証拠(甲4)によれば,当初明細書等には「段差部」という語は用いられていないことが認められるほか,当初明細書の発明の詳細な説明には,「この目的を達成するために発明項1記載の育苗ポットは,底壁と,その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と,その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と,その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面と,前記側壁の一部であって,前記側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも前記収納空間側に窪む第1凹部と,その第1凹部の前記開口面を臨む部分に開口され,前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表\示板を差込む差込み口とを備えていることを特徴とする育苗ポット。」(段落【0011】),「この発明項1に記載の育苗ポットによれば,苗に関する情報が表示された表\示板は差込み口に差込まれることで育苗ポットに取付けられる。ここで,この差込み口は第1凹部の開口面を臨む部分に開口されているので,収納空間に培土を収納した後に,開口面からは差込み口を把握することはできない。一方,差込み口が開口されている第1凹部は,側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので,その第1凹部を目印とすることで,差込み口の位置は,育苗ポットの側壁側から把握される。また,第1凹部は,側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので,その所定間隔を開けた部分では,差込み口に差込まれた表示板は,側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。」(段落【0012】),「発明項1記載の育苗ポットによれば,差込み口が開口されている第1凹部は,側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので,その所定間隔を開けた部分では,差込み口に差込まれた表\示板は,側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって,表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。」(段落【0026】),「通常,表\示板2は,育苗ポット1に培土Bを収納した後に差込み口9に差込まれ,育苗ポット1に取付けられる。また,培土Bは第1凹部7よりも高い位置になるまで収納される。よって,育苗ポット1に培土Bを収納した後には,差込み口9は,培土Bに埋まり,開口面6からは,差込み口9の位置を把握することができない。」(段落【0068】),「また,第1実施例の育苗ポット1のように,側面4に形成された凹部が第1凹部7であるか第2凹部8であるかを判断する必要はなく,側面4に形成された凹部は全て第1凹部7であり,その第1凹部7には差込み口9が開口されているので,収納空間5に培土Bによって差込み口9が埋もれ,差込み口9の位置を外部から把握できなくても,第1凹部7の窪みを目印とすることで,表示板2を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」(段落【0079】)との記載があることが認められ,これらによれば,当初明細書における第1凹部は,側壁の一部であって,側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んでいて,収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没し,開口面を臨む部分に収納空間に収納される苗に関する情報が表\示された表示板を差込む差込み口を有するものであることが認められる。そして,証拠(甲4)によれば,当初図面には,第1凹部7について,【図1】及び【図6】のような内容が図示されていることが認められる。そうすると,当初明細書等の「第1凹部」(第1凹部7を含\nむ。)が本件発明の「段差部」に対応し,これ以外に,本件発明の「段差部」に対応するものは,当初明細書等において見出すことができない。イ そこで,第1凹部がどのような技術的意義を有するかについて検討するに,証拠(甲4)によれば,当初特許請求の範囲に記載された発明は,苗に関する情報が表示された表\示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に,育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても,その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表\示板付育苗ポットを提供することを目的とするものであり・・・このうち,目印としての機能は,「育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても,その表\示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という発明の目的を実現するための重要な機能であると解されるが,証拠(甲4)によれば,当初明細書の発明の詳細な説明の段落【0027】に,「また,差込み口が開口されている第1凹部は,側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので,収納空間に培土を収納し,差込み口が培土に埋もれ,開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても,第1凹部を目印とすることで,育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載され,実施例では他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪み,側壁4の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁3まで帯状に延びる形状とされる(段落【0049】,【0073】,【図1】ないし【図6】)ほか,例えば,えくぼ的に収納空間5側に窪むように形成していてもよいなどとされていること(段落【0082】)が認められるから,これらに照らすと,差込み口が開口される第1凹部は,垂直方向(高さ方向)においても水平方向においても目印としての機能\を果たすべきものであり,かつ,かかる目印としての機能を果たすための第1凹部は,側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する,側壁の一部分の窪みである必要があると考えられる。\nウ 本件発明の「段差部」が水平方向の一定の幅を有するものに限定されないことは,前記1イのとおりであり,本件発明の「段差部」は,第1凹部と異なるものであって,当初明細書等に記載のない事項であるといわざるを得ない。なお,証拠(甲4)によれば,当初明細書の発明の詳細な説明には,「また,上記実施例では,第1凹部7と第2凹部8とは,側壁4の外面から収納空間5側に窪むように形成する場合について説明した。しかしながら,第1凹部7と第2凹部8とは,側壁4の内面から収納空間5側に突出するように形成しても良い。但し,かかる場合には,側壁4の外面には,差込み口9の位置を示すような目印を設ける必要がある。」(段落【0083】)との記載があることが認められるが,この記載は,第1凹部7が側壁4の内面から収納空間5側に突出するように形成されることにより,側壁4の外面側から第1凹部7の位置を把握することができない場合に限定してのものであって,これを把握することができる場合についてのものではない。そして,上記段落は,その記載内容からして,第1凹部7と第2凹部8を有し,第1凹部が差込み口設置機能,目印としての機能\及び根巻き防止機能を有する実施例の改変例として記載されているものであり,このような実施例における第1凹部7は,他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪み,側壁4の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁3まで帯状に延びる形状のものであるから,この記載を根拠として,当初明細書等に段差部についての記載があるということはできない。\nア 原告らは,当初明細書の発明の詳細な説明の段落【0049】及び当初図面の【図2】及び【図5】には,側壁4に形成された他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪んだ段差部が記載,図示されていると主張する。これは,側壁4の1つの面全体に段差部を設けることが記載,図示されているとの趣旨を主張するものと解されるが,証拠(甲4)によれば,同段落は,「また,側壁4には,他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪み,側壁4の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁3まで帯状に延びる1つの第1凹部7と3つの第2凹部8とが形成されている。」というもので,これは,【図1】ないし【図4】に基づく実施例の説明としてであって,側壁4の1つの面の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁3まで延びる帯状の第1凹部についての記載であり,また,当初図面の【図2】及び【図5】は,上記のとおりの第1凹部を有する実施例の断面図を示すに過ぎないものであると認められるから,当初明細書等の上記の箇所に,側壁4の1の面全体に段差部を設けることが記載,図示されていると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 技術的範囲
>> 104条の3
2014.02. 6
平成23(ワ)27102 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年01月24日 東京地方裁判所
分割出願においては,分割出願に係る発明の技術的事項が原出願の特許請求の範囲,明細書又は図面に記載されていることを要し(特許法44条1項参照),分割出願において,原出願からみて新たな技術的事項を導入することは許されないのであるから,分割出願の特許請求の範囲の文言は,原出願の特許請求の範囲,明細書又は図面に記された事項の範囲外のものを含まないことを前提にしていると解するのが合理的であり,そうすると,分割出願の特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにおいては,原出願及び分割出願の特許請求の範囲及び明細書等の全体を通じて統一的な意味に解釈すべきである。したがって,本件においても,本件発明の技術的範囲を確定するに当たっては,原出願に係る明細書である原出願翻訳文の記載についても参酌することが相当である。
・・・
上記のとおり,原出願翻訳文の「特許請求の範囲」及び「発明の利点」には,アクセス閾値が,アクセス権限データに含まれて加入者局に伝送されること,加入者局において,アクセス権限データにアクセス閾値が含まれているか否かを検査すること及びアクセス閾値がランダム数又は擬似ランダム数と比較されることが記載されている。特に,上記「発明の利点」の段落【0003】では,原出願に記載された発明に係るアクセスコントロールにおいては,単にアクセス閾値を伝送すればよいため,情報信号を伝送するのに最小の伝送容量しか必要としないことが記載されており,そこで伝送されるものが「アクセス閾値」であることが明記されている。他方,「アクセス閾値ビット」の用語は,原出願翻訳文の「特許請求の範囲」及び明細書の「発明の利点」の中には記載されておらず,「ビット」に関する事項としては,請求項7において,アクセス権限データがビットパターンとして伝送されることが開示されているのみである。また,原出願翻訳文の明細書中の実施例においては,「アクセス閾値ビット」について,アクセス閾値がアクセス閾値ビットから検出されるものであることが記載されており,その更なる具体例として,アクセス閾値を2進符号化したものをアクセス閾値ビットとすること,及び,アクセス閾値ビットが「1 000 」である場合に,アクセス閾値として「8」の値が得られることが開示されているが,「アクセス閾値ビット」が上記実施例に記載された以外の技術的意義を有するものであることを開示し,又は示唆する記載は見当たらない。なお,原出願翻訳文の全体を通して,アクセス閾値がアクセス閾値ビットから「求め」られるものであること(本件発明の構成要件D)については,記載がない。原出願翻訳文の「特許請求の範囲」及び「発明の利点」におけるこれらの記載に鑑みれば,原出願翻訳文に記載された発明において,「アクセス閾値」とは,加入者局にRACHへのアクセス権限をランダム分配するための閾となる値として,シグナリングチャネル(BCCHとして構\成することができる。)を介して加入者局(移動局として構成することができる。)に対して伝送される値そのものであると解するのが相当である。
エ 検討
(ア) 上記ウのとおり,原出願翻訳文に記載された発明においては,「アクセス閾値」とは,BCCHを介して移動局に伝送される値そのものを意味すると解されるところ,このように解釈した場合,BCCHを介して伝送されるデータがビット形式で表記されていることが技術常識であることからすれば,その「アクセス閾値」の値は,BCCHを介して伝送するためにビット形式に置き換えられることになるが,そのように「アクセス閾値」の値を2進数表\記に置き換えたビットを,「アクセス閾値ビット」と表現することは,「アクセス閾値ビット」との用語から通常把握される意義にも合致するということができる。また,本件明細書等及び原出願翻訳文における実施例の記載についても,「アクセス閾値ビットにより,アクセス閾値は2進符号化され」ることやアクセス閾値ビット「1000」からアクセス閾値「8」が得られるとの実施態様など,上記解釈に沿う記載がある一方で,上記解釈とは異なる実施形態を具体的に開示し,又は示唆する記載は見当たらない。そうすると,本件発明における「アクセス閾値」及び「アクセス閾値ビット」の各用語の意義については,「アクセス閾値」とはBCCHを介して伝送されて,移動局において閾値として用いられる特定の値であり,「アクセス閾値ビット」とは,そのアクセス閾値を,BCCHを介して伝送するためにビット形式で表\記したものと解するのが相当である。(イ) 「アクセス閾値」及び「アクセス閾値ビット」の技術的意義がそれぞれ上記のように解されることから,本件発明の構成要件Dの「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることは,移動局において閾値として用いられる特定の値が,基地局からBCCHを介して移動局に伝送される際にビット形式に置き換えられるところ,移動局において,このビット形式で表\現されたデータ(アクセス閾値ビット)を受信して,このビット形式のデータから閾値となる上記の特定の値(アクセス閾値)を得ることを意味するものと解される。そうすると,例えば,ある特定の値(アクセス閾値)をビット形式に置き換えたデータ(アクセス閾値ビット)を受信した移動局が,そのビット形式のデータから元の値(アクセス閾値)を得ることは,構成要件Dの「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることに当たるが,その元の値を更に関数などに代入することによって算出される別の値は,それ自体がBCCHを介して伝送されたものでない以上,本件発明の「アクセス閾値」に当たるということはできないというべきであり,それゆえ,そのような別の値を求めることは,「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることには該当しないと解するのが相当である。
(2) 原告の主張について
この点に関して原告は,構成要件Dは,「アクセス閾値」が「アクセス閾値ビット」から「求められる」ことを要求しているだけであるから,アクセス閾値はアクセス閾値ビットから特定されれば足り,例えば,アクセス閾値ビットを関数に代入して別の値を求めるような場合も,「アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め」ることに当たると主張する。確かに,構\成要件Dは,アクセス閾値がアクセス閾値ビットから求められることだけを規定しており,「求め」との用語自体からは,求める方法が特段限定されていることは読み取れないが,他方,構成要件Dに規定される「アクセス閾値」の用語は,それ自体がBCCHを介して伝送される値であると解されるべきことは,前記(1)エのとおりである。そうすると,構成要件Dが,アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求めることしか規定していないとしても,そもそも「アクセス閾値」が,上記のとおりBCCHを介して伝送されるべき値として規定されている以上,BCCHを介して伝送された値を更に関数に代入して得られる別の値が「アクセス閾値」に該当しないことは明らかである。したがって,「求める」について特段の限定がないことを前提としたとしても,アクセス閾値ビットから「アクセス閾値と異なる別の値」を求めることが構\成要件Dに合致するというに等しい原告の上記主張は採用することができない。イ 原告は,移動局においてアクセス閾値ビットからアクセス閾値を求めて,当該アクセス閾値の評価に依存してRACHへのアクセス制限の有無が決定されることによって,ネットワーク側においてRACHへのアクセス権限を移動局に分配することが可能になるとの本件発明の目的並びに「アクセス閾値」及び「アクセス閾値ビット」の技術的意義に照らせば,アクセス閾値ビットに基づいてこれに対応するアクセス閾値が特定されれば足りるのであって,いかなる規則に基づいてアクセス閾値ビットからアクセス閾値が特定されるかは問題でないと主張する。しかし,特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず,その特許請求の範囲に記載された用語の意義は明細書の記載及び図面を考慮して解釈されなければならないところ(特許法70条1項,2項),本件特許の特許請求の範囲及び明細書等の記載を考慮した場合に,本件発明における「アクセス閾値」が,例えば,「アクセス閾値ビット」で表\現された値を更に関数に代入することによって特定される別の値であってもよいと解することができないことは,前記(1)エのとおりである。原告の主張は,「アクセス閾値」及び「アクセス閾値ビット」の用語の意義を,特許請求の範囲及び明細書等の記載から導き出される解釈を超えて,当該特許発明の目的や技術的意義に反しないからという理由だけで拡張して解釈するものであって相当でないから,採用することができない。
・・・
カ このほか,原告の提出にかかる平成25年(2013年)1月28日付け意見書には,原出願翻訳文(同意見書では「本件親出願当初明細書等」と表記されている。)の記載を基にしても,アクセス閾値ビットがアクセス閾値そのものを2進数表\記したものに限定されないとの意見が述べられている。同意見書は,原出願翻訳文に記載されている発明がRACHにおいて複数の移動局からの信号が衝突することを避けることを目的としていること,アクセス閾値が基地局から送信され,アクセス閾値の評価に依存してアクセスが許容されることによって,アクセス権限が移動局の間で分散されること,デジタル通信システムにおいては,アクセス閾値は通信プロトコルの一構成要素としてビットの形式で送信されることが当然であるから,アクセス閾値ビットは基地局がアクセス閾値を明示するビットであることなどを挙げて,このような発明の目的やコンセプトからすると,アクセス閾値を規定するアクセス閾値ビットとしてどのようなビットの構\成を用いるかは特に限定がないとする。しかし,原告が主張するような発明の目的やコンセプトだけを根拠として,特許請求の範囲に記載された用語の意義を拡張して解釈することが相当でないことは,前記イのとおりである。また,同意見書は,平成11年(1999年)当時,通信チャネルのアクセス制御の設計において,どのようなビットの構成(ビット位置の割当てとパラメータ値の割当て)を採用するかは,通信プロトコル設計の目的やコンセプトとは切り離して考えることができ,ビット構\成はプロトコルによって自由に定めることができたとするが,技術的にそのような自由な設計の可能性があったとしても,原出願翻訳文に記載された発明において,特許出願人が,あえて「アクセス閾値」をBCCH上で送信されるべき値として規定している以上,それと異なる可能\性があったことを理由として,実際に用いられた用語の意義を拡張して解釈すべきことにはならない。さらに,同意見書は,原出願翻訳文の段落【0027】等の「アクセス閾値を送信する」との表現について,アクセス閾値ビット以外の要素を考慮してアクセス閾値の値を調整する場合も含めてこのように表\現することは,特に不自然ではなく,平成11年(1999年)当時,通信チャネルのアクセス制御の設計において,制御の基本的な仕組みを定めた上で,様々な条件を追加的に考慮してきめの細かい制御を行う目的で,アクセス閾値ビット以外の要素を考慮してアクセス閾値の値を調整することは普通に考えることであったとする。しかし,そのような解釈に従えば,BCCHを介して送信されるアクセス閾値ビットによって表現される値は,アクセス閾値を求める上で考慮されるべき複数の要素のうちの一つにすぎないことになるが,そのように「アクセス閾値」を求めるための複数の考慮要素の一つをビットで表\現したものを,あえて「アクセス閾値ビット」と呼称することが用語の用い方として自然であるとの解釈は,直ちに首肯し難く,しかも,アクセス閾値の複数の考慮要素の一つにすぎない値をビット形式で送信することが,「アクセス閾値を送信する」ことと同義であるとか,「アクセス閾値を送信する」という文言から通常理解される技術内容であるということもできない。さらにいえば,同意見書が,アクセス閾値の値の調整にアクセス閾値ビット以外の要素を考慮できるか否かを論じる上では,アクセス閾値ビットがアクセス閾値をビット形式に置き換えたものに限られないことを前提としているところ,そのような前提を採ることができないことは,前記(1)のとおりである。
2013.12.26
平成24(ネ)10054 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成25年12月19日 知的財産高等裁判所
上記ウのとおり,乙27には,ヒトの肝癌組織片をヌードマウスで継代した肝癌腫瘍の継代2代目を,ヌードマウスの肝に移植したことで,右肺下葉に直径約2mmの球状の転移を認めた旨の記載があり(31頁右欄18行〜32頁右欄7行目),その上で,肝移植肝細胞癌が肺転移を惹起したことを明確に証明したものとする記載があるのであるから(33頁左欄11〜19行目),乙27には,ヒトの肝癌組織片を原発臓器であるヌードマウスの肝臓に同所移植することによって肺転移が生じるヌードマウス(モデル動物)を得られるとの知見が開示されているものと認められる。そして,1)乙14発明と乙27発明は,肝癌患者の肝臓から採取した肝腫瘍組織片をヌードマウスの皮下で継代移植して得られた腫瘍組織塊をヌードマウスに同所移植することによってモデル動物を作成するという同一の技術分野に属するものであり,その技術分野において,本件出願の優先権主張日当時,転移過程を再現できるヒトモデル動物を作製することは共通の技術課題とされていたこと,2)その技術課題に直接関するヌードマウスに肺転移が認められたとする部分について,乙14は乙27を参照文献として引用していることに照らすならば,乙14及び乙27に接した当業者であれば,乙14発明に乙27に記載された知見を適用して本訴マウスの構成とすることは,容易であるものと認められる。
キ 小括
以上のとおりであるから,本訴マウスは,本件出願の優先権主張日当時における公知技術から容易に推考できたものであり,均等の第4要件を満たさない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
2013.12.20
平成23(ワ)30214 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年12月19日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2013.12.13
平成24(ワ)33474 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年11月26日 東京地方裁判所
以上の記載内容を踏まえ,まず,争点(2)イ(構成要件A2及びD2の充足性)について検討する。ア 構成要件A2及びD2は「結着部分から引っ張ってもはがれない」ことを規定するところ,被告製品及びその製造方法においては,●(省略)●(前記1(1)ア(エ)及びイ(エ)。乙20参照)。原告は,本件各発明の目的がチーズの結着により型くずれや食品の漏れのない白カビチーズ製品を製造することにあることから,「結着部分」とは白カビが生育している部分,すなわち外縁部を意味するので,本件においては構成要件A2及びD2の充足が認められると主張する。イ そこで判断するに,本件各発明の特許請求の範囲の記載をみると,構成要件A2及びD2における「前記チーズカードを結着するように熟成させ」との文言は,その文脈上,構\成要件A1及びD1の「チーズカードの間に香辛料を均一にはさ」むことを受けたものであるから,構成要件A2及びD2にいう「結着する」とは,白カビが生育する外縁部に限られず,香辛料を挟んだ部分の全体を対象とすると解釈するのが特許請求の範囲の文言に沿うと解することができる。また,構\成要件A2及びD2には「上記チーズカードを結着するように熟成させ」との文言があり,本件各発明におけるチーズカードの結着は「熟成」により行われることが示されている。そして,前記前提事実(4)のとおり,カマンベールチーズの一般的な製造工程における「熟成」には,チーズカードの表面上にカビを発生させるもの(以下「チーズカード表\面の熟成」という。)と,これに続いてカビが生成する酵素の作用によってチーズカードを外側から内部に向かって軟化させるもの(以下「内部を軟化させる熟成」という。)とがあるところ,本件明細書において,構成要件A2及びD2の「熟成」がどちらか一方の熟成に限定されることをうかがわせる記載は見当たらない。そうすると,構\成要件A2及びD2における「熟成」とは,チーズカード表面の熟成と内部を軟化させる熟成の双方を含むものと解するのが相当であり,「熟成」により行われる「結着」も,チーズカード表\面の熟成により白カビが上下のチーズカードの表面を覆いそれらの外縁部において一体化すること(このことは当事者間に争いがない。)のみならず,内部を軟化させる熟成により上下のチーズカードがその接合面において一体化することをも含むと解すべきものとなる。かかる解釈は,本件明細書の【実施例1】(段落【0008】)及び【実施例2】(段落【0010】)において,熟成が完了した状態,すなわちチーズカード表\面の熟成のみならず内部を軟化させる熟成が十分に進んだ状態において結着が確認されていることや,【発明を実施するための最良の形態】欄(段落【0007】)において,加熱によって結着がより強固に一体となるとされ,加熱によりチーズが溶融する部分,すなわち上下のチーズカードが接合する面全体が既に(強固ではないとしても)結着していると示されていることからも裏付けられる。以上によれば,構\成要件A2及びD2における「結着部分」とは,外縁部を含む上下のチーズカードの接合面全体をいうものと解するのが相当である。 他方,上記1(1)ア(エ)及びイ(エ)認定のとおり,被告製品及びその製造方法における上下のチーズカードは,●(省略)●したがって,被告製品及びその製造方法が構成要件A2及びD2を充足するということはできない。ウ なお,原告は,上記「結着部分」を外縁部と解釈すべきことの根拠として,本件審決取消訴訟の判決がかかる解釈を採用しているとも主張する。しかし,同判決は,「上側のチーズと下側のチーズの内部の結着面について,二次熟成の過程で内部の組織が軟化して溶融することは,可能性としては考えられるが,熟成後,「分離せずに一体となった状態」となることは,甲1の2,2の記載及び画像から,読み取ることはできない。」とも判示しており(甲19),外縁部のみならず上下のチーズカードの接合面の全体を「結着面」とみていることは明らかである。そうすると,同判決が「結着部分」を外縁部に限定して判断したものとは解されないから,原告の上記主張を採用することはできない。
(3) さらに,争点(2)ウ(構成要件C及びFの充足性)についても検討する。ア 原告は,構成要件C及びFの「内包」とは,香辛料が内部に含まれていればよく,香辛料を内包することにより香辛料が見えない状態になるかどうかは,チーズ製品の外縁部から見て判断されるべきものであって,ポーションカットした部分から香辛料が見えることは構\成要件充足性を妨げないと主張する。イ そこで判断するに,「内包」とは,一般に「内部に含み持つこと」という意味であるが(乙2),特許請求の範囲の文言のみからは,チーズ製品の内部に香辛料が含み持たれていれば足りるのか,外面に露出していないことを要するのかについては明確であるといい難い。そこで,本件明細書の記載を参酌すると,【背景技術】(段落【0002】)及び【発明が解決しようとする課題】(段落【0003】)には,本件各発明は,ナチュラルチーズの一種である白カビチーズで,食品類である香辛料をチーズの内部に包含するが,見た目は通常のチーズと異ならないもの及びそのような白カビチーズの製造方法を提供することを目的とするものであることが,【発明の効果】(段落【0005】)には,本件各発明の完成品が通常のカマンベールチーズ製品(白カビチーズ製品)と外観上見分けがつかないものであることが記載されている。そして,構成要件C及びFにおける「香辛料を内包したカマンベールチーズ製品」とは,本件各発明を実施することにより製造されたチーズ製品の完成品を指すものと解すべきであるから,上記各構\成要件における「内包」とは,完成品であるチーズ製品の外観から香辛料が見えない状態で内部に含み持たれていることを意味するものと解するのが相当である。ウ 上記1(1)ア(カ)及びイ(カ)の認定のとおり,被告製品は,各個片の表面のうち上面,底面及び外縁部を構\成する面は白カビで覆われるものの,6ポーションカット切断面は白カビに覆われずに黒胡椒とチーズが露出しているカマンベールチーズ製品である。そのため,上面,底面及び外縁部から見た場合には香辛料は見えないが,6ポーションカット切断面から見た場合は香辛料が外部に露出している。したがって,被告製品及びその製造方法が構成要件C及びFを充足するということはできない。\n
2013.12. 7
平成25(ネ)10001 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成25年11月27日 知的財産高等裁判所
以上によれば,本件補正を客観的・外形的に見れば,控訴人らにおいて,腰下部における伸縮部材の配置について,構成要件Cの「前記腰下部の前記伸縮部材は,前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との実施形態が包含されるものに減縮し,従前の請求項1に記載されていた,これと異なる実施形態,すなわち,腰下部伸縮部材の一部が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され,その余の腰下部伸縮部材が製品の左右脇部において配置固定されるという実施態様を,本件補正により,本件発明1の技術的範囲から意識的に除外したものと認められる。そして,各被控訴人製品は,腰下部伸縮部材に当たるフィットギャザー221 の一部(221-1)が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され,その余のフィットギャザー221-2 が中央部を除く左右脇部において配置固定されるというものであるから,各被控訴人製品は,本件補正により請求項1から意識的に除外されたものに包含されるものといわざるを得ない。したがって,各被控訴人製品については,均等論を主張し得ない特段の事情が存在するものと認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
2013.11. 9
平成24(ワ)3817 特許権侵害行為差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年10月31日 東京地方裁判所
本件特許の特許請求の範囲には,構成要件Eとして単に「金属粉収集機構\\」と記載されており(なお,符号「(12H,16,19A,19B)」については後述する。),その文言上は,バリ除去用工具がトルシアボルトの破断面に生じたバリを除去する際に発生する金属粉を収集する機能を有する構\\造であれば足り,その構成に格別の限定はないということができる。また,本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると,本件発明は,フード部により金属粉が装置の外部に漏れ出して周囲に拡散することがなく,金属粉収集機構\\により装置の外部に金属粉が拡散する以前に金属粉が収集され,金属粉が装置外部に拡散してしまうことが確実に防止されるとの効果を有するものであるから(【0020】,【0022】),このような効果を奏するものであれば,「金属粉収集機構」に当たるとみることが可能\\である。しかし,特許請求の範囲の「金属粉収集機構」という上記文言は,発明の構\\成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり,いわゆる機能\\的クレームに当たるから,上記の機能を有するものであればすべて技術的範囲に属するとみるのは必ずしも相当でなく,本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構\\成を参酌しながらその技術的範囲を解釈すべきものである。そこで,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,金属粉収集機構としては,1)空気侵入系統及び空気排出系統を設け,空気流を発生させて金属粉を連行するようにした構成(第7及び第8実施形態)や,永久磁石又は電磁石を設け,磁力を発生させて金属粉を収集するようにした構\\成(第9及び第10実施形態)が開示され,これらの構成が好ましいと記載されているものの(【0014】,【0053】〜【0066】,図13〜16),これらに加え,2)フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成も記載されている(第1実施形態。【0025】,図1及び2)。そして,上記2)の構成については,例えば垂直に延在するトルシアボルトの破断面1cのバリを除去する際に発生する金属粉の収集には不充分であるとも記載されているが(【0053】),これは上記1)の構成と比較した場合に効果が劣る旨を記載しているにとどまり,2)の構成であっても金属粉を収集してその拡散を防止するという本件発明の効果を奏しないとはいえないから,上記記載をもって本件発明の構\\成要件Eにいう「金属粉収集機構」を上記1の構成に限定したとみることは困難である。以上によれば,構\\成要件Eにいう「金属粉収集機構」は,上記1)及び2)の各構成を含むものと解することができる。一方,前記(1)ウで認定したとおり,被告製品の凹部(12H’)は,円筒状のフード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって存在するものである。また,この凹部は,フード部のうち,被告製品においてトルシアボルトの破断面のバリを切削加工する際に切削屑が発生し,これが飛散する箇所,すなわち,別紙「被告製品の構成」の第3図,第4図及び第6図に示された専用刃(バリ除去用工具)(10CG’)の第1の刃(101C’)及び第2の刃(102C’)がトルシアボルトの破断面(1c’)に当接し,切削加工により切削屑が生じると,これがアウターソ\\ケット(22)側面の開口部(22a)を通って飛散する箇所に対応する部分に位置していると認められる。そうすると,被告製品の凹部(12H’)は,本件明細書に記載された上記2)の構成と同様に,金属粉を収容することによって金属粉を収集する機構\\であるということができるから,構成要件Eにいう「金属粉収集機構\\」に当たると解するのが相当である。
イ これに対し,被告は,(ア) 本件特許の特許請求の範囲には「金属粉収集機構(12H,16,19A,19B)」と記載されており,その出願経過に照らしても,これらの符号により特定される実施形態に限定されること,(イ) 被告製品を使用する向きによっては凹部(12H’)に切削屑がたまらないし,切削屑はカバー(24)内を移動するから,凹部には金属粉収集の機能はないこと,(ウ) 被告製品の蛇腹状のカバー(24)は,切削屑の外部への拡散を防止して切削屑を保持する機能及び伸縮により母材との密着性を高める機能\\を有するものであること,(エ) 本件明細書の第1実施形態の凹部(【0025】)と蛇腹の谷部である被告製品の凹部(12H’)は大きさが異なること,(オ) 本件明細書には,本件発明の第5実施形態(【0046】〜【0048】,図11)におけるベローズ120が金属粉収集機構であることを示す記載がなく,本件出願人において蛇腹状のカバーの内面の凹部が金属粉収集機構\\に当たるとの認識がなかったことを理由に,被告製品の凹部が構成要件Eにいう「金属粉収集機構\\」に当たらない旨主張するが,以下のとおり,いずれも採用することができない。
(ア) 特許請求の範囲の括弧内に符号を記載することに関しては,特許法施行規則24条の4及び様式29の2の〔備考〕14のロに「請求項の記載の内容を理解するために必要があるときは,当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。」と規定されているところであり,これによれば,特許請求の範囲中に括弧をして符号が用いられた場合には,特段の事情のない限り,記載内容を理解するための補助的機能を有するにとどまり,符号によって特許請求の範囲に記載された内容を限定する機能\\は有しないものと解される。この点に関し,被告は,本件出願人は,本件補正書に係る補正によってこれらの符号により特定される実施形態以外の構成を意識的に除外したから,「金属粉収集機構\\(12H,16,19A,19B)」は,これらの実施形態の構成に限られ,蛇腹状のカバーの内面の凹部は構\\成要件Eにいう「金属粉収集機構」に当たらない旨主張する。しかし,これらの符号は本件補正書に係る補正の前から明細書及び図面中で使用されていたものであり(乙1),前記(1)イ記載の本件特許の出願経過に照らし,本件出願人が拒絶理由の回避のために特定の構成を除外する意図でこれらの符号を付したとは認め難い。そうすると,本件において上記特段の事情があると認めることはできないから,符号「(12H,16,19A,19B)」の記載は,特許請求の範囲に記載された内容をこれらの符号により特定される実施形態の構\\成に限定するものではないと解すべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 機能クレーム
2013.11. 8
平成24(ワ)18038 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年10月30日 東京地方裁判所
「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」の意義\n
ア 被告は,「地表面」との文言が,二次元的な広がりをもった「面」を意味するものである上,本件発明が,「直線と地表\面との交点を算出」(構成要件L)するものであることから,「地表\面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」は,「面」の情報を含むデータである必要があると主張する。
イ しかし,構成要件Kは「地表\面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」というものであり,その文言からは,「高度情報」が地表面の起伏を反映したものであることを要することが読み取れるのみであり,地勢データ自体が「面」としての情報を含むことが,文言上,必ずしも要求されるものではない。\n
ウ また,確かに,本件明細書によれば,本件発明に係る位置特定装置は,機体の位置から撮影手段の向いている方向に延ばした直線と地表面との交点を算出し, 目標物の位置として特定するものであり( 【請求項7】),「三次元的な地勢データ」は,「地表面と直線との交点を算出」する際に用いられるものである(構\成要件L中段)。しかし,上記「地表面」(構\成要件L中段)は,「地表面記録手段からの出力に応答し」(構\成要件L前段),「三次元的に高度情報を含んで表される」(【0014】)ものであるから,「三次元的な地勢データ」は,その出力により,三次元的に高度情報を含んだ面を表\すことができるものであれば足り(なお,「三次元的に高度情報を含んだ面を表す」ことの意義については,構\成要件Lにおいて検討する。),「三次元的な地勢データ」自体が「面」としての情報を有するものである必要は必ずしもないものと解される。
エ 加えて,本件発明は,上記のとおり直線と地表面との交点を算出するに当たり,「地表\面」として二次元平面を用いると,目標物が三次元的な起伏のある地表面上に存在することにより,目標物までの直線を二次元平面まで延長した交点の位置が,目標物の位置を二次元平面に投影した位置と比較して,高度に対応する距離だけ異なる位置と判断してしまうことから(【0015】),「地表\面」として,二次元平面ではなく,三次元的な起伏のある地表面を用いることで,目標物の位置を,三次元的に精度よく特定することを可能\としたものである(【0014】,【0015】)。そうすると,「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」とは,緯度及び経度の情報のみを含む二次元平面データに代わるものとして記載されているにとどまるものであるから,緯度及び経度の情報に加えて,地表\面の起伏を反映した高度情報を含むことに意義を有するものということができ,「面」としての情報を有することに,その意義が見出されるものではない。
オ 以上によれば,「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」とは,三次元的な,すなわち緯度,経度及び高度の情報を含む地勢データであって,上記高度情報が,地表\面の起伏を反映したものであると評価することができるものであれば足り,これに加えて,「面」としての情報を含むものである必要はないものと解される。
(2) イ号装置における検討
ア イ号装置はメッシュデータが記録された記録媒体を有するところ(構成k),メッシュデータは,メッシュの位置情報(緯度・経度)及びメッシュ中心点の標高情報を含むモデルデータである(争いがない)。上記標高情報は,国土地理院が刊行する2万5000分の1地図に描かれている等高線を計測してベクトルデータを作成し,それから計算によって求めるものであるとされるから(甲10),地表\面の起伏を反映したものであると評価することができる。イ したがって,メッシュデータは,「地表面の起伏についての高度情報を含む三次元的な地勢データ」に相当し,上記メッシュデータが記録された記録媒体を有するイ号装置は,構\成要件Kを充足する。・・・・本件発明は,主として災害発生現場等の位置を特定するという民生分野における利用を目的とした発明であるが,乙24発明とは航空機による目的物の地図上における位置の特定という技術においては共通するものであり,かつ,軍事技術分野における技術が民生分野に転用されることが多いことは公知の事実であるから,本件発明が主として民生分野における利用を目的とするものであるとしても,乙24発明に乙4発明を適用して本件発明に至ることの妨げとなるものではない。
エ 以上によれば,本件発明は,乙24発明に乙4発明を適用することにより,本件特許出願当時,当業者において容易に想到することができたものであり,本件特許権は特許無効審判により無効とされるべきものであると認められる。
2013.11. 6
平成25(ワ)2464 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年10月31日 大阪地方裁判所
前記ア及びイの記載によれば,本件特許発明の「パッド」とは,通常の箸先とは異なるものであり,固形物をつかみ取るための部材(当て物)として箸先に取り付けられ,取り外しが可能なものであることが認められる。\n
エ 被告製品の構成及び構\成要件充足性 証拠(乙7)によれば,被告製品の箸先には滑り止め加工が施されていることが認められるものの,固形物をつかみ取るための部材(当て物)として箸先に取り付けられ,取り外しが可能な構\成を有しているとは認められない。したがって,被告製品は「パッド」に相当する構成を有するものとは認められないから,構\成要件B,D,G及びIを充足するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2013.11. 6
平成24(ワ)8053 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年10月31日 東京地方裁判所
,原告は,構成要件Cの「実行されることにより」という文言は,構\成要件Dの1)ないし4)の過程全体に係っているものと読むべきであるから,初期フレームプログラムの実行と,カテゴリーリストプログラム及びPLUリストプログラムのダウンロードとの間には,厳密な前後関係は要求されておらず,また,上記の文言は,因果関係を示すものでもなく,構成要件Dの1)ないし4)の過程が初期フレームプログラムの実行なしには行われないという程度の関係を示すものにすぎないと解すべきであると主張する。しかしながら,構\成要件Cにいう「より」は,因果関係等を意味する自動詞「よる」の連用形であって,動詞等に連なる語法において用いられるものであるから,構成要件Cの「ことにより」が,構\成要件Dの1)ないし3)の「送信される」及び4)の「問い合わされる」の各動詞にそれぞれ係っていることは文法上明らかであり,これと異なる読み方をすべき根拠は見当たらない。また,仮に,構成要件Cの「実行されることにより」を原告の主張のように解したとしても,前記ア及びイのとおり,被告システムにおいては,カテゴリーリスト及び個別商品リストの表\示領域を確保するプログラムと,その内容を表示するプログラムとが,それぞれ一つのHTML文書のプログラムの実行過程において同時に実行されており,構\成要件C及びDに記載された手順を順次実行するという形では実行されていないのであるから,いずれにせよ,上記ウの結論を左右するには足りないというべきである。オ よって,原告の主張は理由がなく,被告システムの実施態様1が,構成要件A,C,D及びJに記載された各プログラムの実行手順及び実行内容を充足すると認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2013.10.29
平成24(ワ)3276 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年10月17日 大阪地方裁判所
上記1,2に説示したところによると,本件特許発明と被告製品の相違点は,本件特許発明は,くさび形の空間部を,第1アームのケース部自体に形成して構成しており,その結果,くさび形金具が第1アームから脱落するのを防止するためのカバー(橋絡壁をもって橋絡される左右側壁 (34)(34) )を必要とするのに対し,被告製品は,これを,連結壁A2,A2 を付属させた中本体A と,中板B(保持板1c)によって構成し,かつ同構\成によってくさび形金具の脱落防止も達成している点にある。
(2) 上記相違点の評価
上記相違点は,いずれの構成も,くさび形金具との当接によるくさび作用をもたらし,角度調整金具を多段化,小型化することに資する構\成であって,同一の作用効果を発揮するものである(均等第2要件充足)。しかし,くさび作用をもたらすくさび形空間部の具体的構成方法が,発明の本質的部分に関するものでない(均等第1要件関係)かどうかはともかく,本件特許発明が,くさび形空間部を第1アームに設けられたくさび形窓部に形成することに主眼を置いた説明をしているのに対し,被告製品は,その構\成から解放され,中本体(受け部材)と中板をもってくさび作用をもたらすくさび形空間部を具体的に形成するという別の技術的構成を採用し,これによって,くさび形金具とくさび面の当接面積が増大する,あるいは,構\造材である中本体がくさび形金具の動きを案内し,脱落防止のための部材も別途要しなくなるといった付加的な作用効果も生じているから,このような構成に想到することが,被告製品の製造当初において,当業者にとって容易であったとは認められない(これを明らかにする証拠の提出もない)。この点につき,原告は,単なる部品の組換えであるとして,その想到容易性を主張するが,上記説示に照らし,採用することはできない。
(3) まとめ
以上の次第で,少なくとも均等第3要件を欠くから,被告製品が,本件特許の均等の範囲にあるということもできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第3要件(置換容易性)
2013.10.22
平成19(ワ)2525 債務不存在確認請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件 特許権 民事訴訟 平成25年09月26日 東京地方裁判所
(1) 証拠(甲95,98,127,128,計算鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば,平成18年10月1日から平成25年3月30日までの間の原告各製品の日本国内における売上高(消費税抜き)は,●(省略)●円であり,消費税込みの売上高は,●(省略)●円であると認められる。被告は,原告の平成23年5月26日付け準備書面(24)別紙1の記載を根拠に,原告各製品の売上高が5976億円であると主張するが,原告は,上記の記載が誤記であると述べている上,そもそも上記記載が売上高の記載であるかどうかも不明であり,他に原告の上記主張を裏付ける的確な証拠がないことに照らすと,これを採用することはできない。また,被告は,計算鑑定の結果等は,製品別売上台帳等の取引別の詳細データを用いていないから信用することができないと主張するが,原告は製品別売上台帳等の取引別の詳細データを常備していないというのであり,「<以下略>の追加陳述書」(甲98)及び「<以下略>の補充的陳述書」(甲128)の基となるデータは米国のアップル・インクに対する監査報告手続において会計監査人が依拠している会計データベース(SAPデータベース)から析出して得られたものであって,無作為に選択された25件の取引レベルのサンプルデータにより,上記データベースから抽出した販売数量及び売上データが請求システムのデータと一致することが確認されている上(甲127),鑑定対象期間である平成18年10月1日から平成23年9月24日までの売上高については上記データベースから抽出された製品別月次売上データと原告の計算書類上の売上高との整合性に特段の問題はないとされているから(計算鑑定の結果),原告の上記主張は,採用することができない。
(2) 本件各発明の実施に対し被告が受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を算出するに当たっては,前記消費税込みの売上高に相当な実施料率を乗じる方法によるのが相当である。原告は,クリックホイールの価格をベースとすべきであると主張するが,原告各製品の原価が証拠上不明であることに照らしても,採用することができない。
(3) そこで,相当な実施料率につき,以下検討する。
ア 実施料率〔第5版〕(乙54)によれば,「19.ラジオ・テレビ・その他の通信音響機器」に含まれる「電気音響機械器具」には,録音装置,再生装置,拡声装置及びそれらの付属品が含まれるところ,この分野の平成4年度ないし平成10年度の実施料率(イニシャルなし)の平均値は,5.7%である。なお,「20.電子計算機・その他の電子応用装置」の同様の平均値は,33.2%であるが,これは主にソフトウエアの実施料率が高率であることによるものとされているから,これを参考にすることは相当でない。なお,弁論の全趣旨によれば,被告が本件特許につき他に許諾した例はないことが認められる。イ 本件各発明は,1) リング状に予め特定された軌跡上にタッチ位置検出センサーを配置して軌跡に沿って移動する接触点を一次元座標上の位置データとして検出すること,及び,2) 前記軌跡に沿ってタッチ位置検出センサーとは別個にプッシュスイッチ手段の接点が設けられており,前記検出とは独立してプッシュスイッチ手段の接点のオン又はオフを行うことができることに特徴があると考えられるところ,1)については,同様の機能を有するタッチホイールを搭載したiPodが原告各製品の販売開始より前の平成14年7月に既に販売されていたものであり(乙3,26,36,37,39,41),2)については,甲5公報及び甲39公報に開示されていたほか,タッチ位置検出センサーの下部にプッシュスイッチ手段を設置し,タッチ位置検出センサーによる検出とは独立してプッシュスイッチ手段の接点のオン又はオフを行う構成については甲6公報,甲7公報及び甲31公報等に開示があり,このような構\成は,原出願当時,広く知られた技術であったと認められる。そうであるから,本件各発明の技術内容,程度は高度なものであるとは認め難いというべきである。ウ 代替手段については,平成19年9月から発売が開始されたiPodtouchではクリックホイールが採用されず,タッチパネルが採用されているが(乙26),これによる入力方法等の詳細は証拠上判然としないから,これをもって代替手段となるとは認め難い。原告各製品の販売開始前に販売されていたiPodは,前記のタッチホイール及びタッチホイールの上部(軌跡から外れた位置)等に配置しているものがあり(乙3,26),そのような構成で代替することは可能\であったということができるものの,それを採用したのでは操作性に劣り先進性を欠くことになると考えられるし(乙30ないし38),実際に原告各製品の販売開始後にそのような構成を採用したモデルがあることは窺えないから,この点を重視することはできない。エ 本件各発明の技術が原告各製品に対して寄与する程度について見る。(ア) 証拠(甲1の1)によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,発明の効果として,次の記載があることが認められる。「本発明は,以上のように構成されており,特に指先からの軌跡上のアナログ的な変移情報または接点の移動情報が電子機器へ確実に入力することができ,1次元上または2次元上もしくは3次元上の所定の軌跡上を倣って移動,変移する接触点の位置,変移値,及び押圧力を検知することができる。そして,操作性良く薄型でしかも少ない部品点数で電子機器を構\成することができるように1つの部品で複数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接触操作型電子部品を提供することができる。」(段落【0014】)「また,この操作部品により非常に多くの機能の選択を行ったり,例えばボリュームスイッチ等のスイッチ入力を繊細に行うことができる。さらにはセンサータッチのイベント数により入力を行うための接触検知スイッチとして使用された場合には,イベント入力数を人間の指の感覚でもって自在に調節させ,指を当てる場所に応じてイベント数を変更させることにより操作性と多機能\性を向上することができる。しかも,このような操作性を発揮する電子機器の構成部品として該機器の操作部の構\造を単純化でき且つメンテナンス性を向上することもできる。そして,単一の操作部品でもって接触操作型電子部品およびプッシュスイッチ夫々の機能を同時に操作することができる。さらに,従来のプッシュスイッチ付き回転操作型部品とは異なり,装置自体をスイッチ押下方向に薄くして形成でき,装置の中央に配することが可能\となり,片手で持って操作するような装置に組み込んだ場合でも,両手いずれでも操作を簡単に行なうことができる。また,以上の接触検出センサー付プッシュキーにより,単純なキーの押下以外に接触もしくは十分に弱い押圧によりイベント入力が行なえる。」(同【0015】)(イ) 移動する接触点の位置等を検知し,機能の選択等を行う点は,既にタッチホイールにより行われていた。1つの部品で複数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接触操作型電子部品を提供する点は,原告各製品は本件図面中の【図21】のようにプッシュスイッチの上部にタッチ位置検出センサーが配置されて1つの部品で複数の操作ができるようになっているものではなく,これらは別の部品で構\成されているのであり(別紙原告製品説明書,乙16),装置の薄型化は,バッテリや液晶ディスプレイとハードディスクとの配置の工夫やフラッシュメモリの採用等により果たされていることが窺える(乙16,26)。操作性の向上の点は,タッチホイールを採用していた従前のモデルの後に,クリックホイールを採用した原告各製品等が販売されたことや原告自身がクリックホイールによる操作性の向上を宣伝していること(乙30ないし38)からすると,一定の寄与があるとは考えられるが,クリックホイールの機能の割当てや本件各発明とは無関係のセンターボタンの存在の果たす役割も大きいと考えられるから,この点に関する本件各発明の寄与の程度が大きいとは認め難い。そうすると,本件各発明の技術が原告各製品に対して寄与する程度は大きくないというべきである。オ 本件各発明が原告各製品の売上げに寄与する程度について見るに,証拠(乙4,21,30,31,34,37,38,40,41,43)によれば,原告自身,クリックホイールを原告各製品の操作性の要と位置付け,新機能,セールスポイントとしてこれを積極的に宣伝し,好評を博してきたことが認められる。また,証拠(甲97,乙4,16,23,27,28,29,31,34,38,39,40,53,62)によれば,「アップル」のブランドの価値は非常に高く,原告各製品のデザイン,カラーバリエーション,iTunes,ビデオ再生,ゲーム,大型液晶,記憶容量,バッテリ容量,小型軽量といった点の訴求力がかなり強いものであり,平成18年11月16日時点におけるデジタルミュージックプレーヤー市場におけるiPodの国内シェアは約60%に達しているが,それには原告の販売努力が相当程度貢献していることが認められる。カ このような諸般の事情を総合考慮すると,相当な実施料率は,●(省略)●%と認めるのが相当である。(4) そうすると,被告が受けた損害の額は,次の算式のとおり,3億3664万1920円(円未満切捨て)となる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
2013.10. 1
平成24(ワ)7151 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年09月26日 大阪地方裁判所
原告は,本件特許の構成要件F,Gにつき,被告製品の構\成(f),(g)が均等の範囲内であると主張する。しかし,前記1(1)に認定した本件特許の出願経過からすると,原告は,本件特許発明のうちのガス流通路の開閉機構に関して,前記引例7(特開昭62− 226208公報,乙2の5の8)が公知文献であることを指摘された状況において,補正4)において前記1(1)クのとおり特許請求の範囲を補正し,審判請求書において,当初出願の構成であった「水平回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調節用摘子」の構\成を,更に具体化し限定したものである。(2) 前記1(1)の認定によると,前記引例7は,バルブが上昇した際に閉塞され,バルブが下降した際に開栓する機構を有していたのであるから,本件特許発明は,ガス流通路の開閉機構\に関して,引例7に開示された構成を意識的に除外したものといわざるを得ない。(3) これまで述べたところを総合すると,原告は,本件特許出願時に存在していた一定の技術について,これを含まないものとするよう特許請求の範囲の補正を行い,本件明細書においても同旨の記載をしたのであるから,特許権成立後に,前記除外された範囲について,均等の主張ができないことは明らかと言うべきであり,均等のその他の要件を検討するまでもなく,原告の主張には理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
2013.10. 1
平成24(ワ)11220 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年09月26日 大阪地方裁判所
前記(2)によれば,乙1発明のA からG までは,本件特許発明1の構成要件1A から1G にそれぞれ相当するものであり,乙1文献には,本件特許発明1の各構成要件をいずれも備えた発明(乙1発明)が記載されているものと認めることができる。原告は,乙1文献には構\成要件1C 及び1E に相当する構成(前記(2)C 及びE の構成)が記載されていない旨主張するので,以下,補足する。ア 本件特許発明1の構成要件1C に相当する構成(前記(2)C の構成)前記(1)のとおり,乙1文献には,「引張り試験の方法は,アムスラー万能試験機等に固定し,片端より管軸方向に加重をかけ,ブレード部分の離脱及び破断時の強度を測定するものとする。」という記載がある。この記載は,引張り試験において,ブレード部分の離脱及び破断が生じた後に,フレキシブルチューブの離脱又は破断が生じるという前後関係を当然の前提としたものである。そもそも,フレキシブルチューブ本体は蛇腹構\造のものであり,その名のとおり伸縮可能なものである(当事者間で争いがない。)のに対し,乙1文献のブレードはステンレス鋼(SUS304)であり,フレキシブルチューブの外面に均一に編まれたものであるから,構造上,フレキシブルチューブの伸長を防止する作用を奏するものであることが明らかである。本件特許1の出願時以前における技術常識についても,以下の点が認められる。昭和41年12月刊行の石井俊二著「螺旋管とベローズ型伸縮管継手のすべて」と題する論文(乙2)によれば,ブレードは,一般に,螺旋管に伸びを生じたり,外部からの衝撃から防護したり,美観を保持したりすることを目的とする部材である。また,平成9年7月1日発行の財団法人日本建築センター編『建築設備耐震設計・施工指針(1997年版)』(乙4)には,地震によるフレキシブル継手の破損状況が紹介されているところ,そこではブレードが破断したフレキシブル継手の写真が掲載されており,当該写真からはフレキシブルチューブがブレードの長さの約2倍の長さにまで伸長していることが読み取れる。以上のとおり,乙1文献には,フレキシブルチューブが破損するよりも先にブレードが離脱又は破断することを前提とした記載があること,乙1発明の構\造からすれば,必然的に当該構成が備わっていること,本件特許1の出願以前においても,当該構\成は公知のものであったことが認められる。そうすると,乙1文献に接した当業者であれば,乙1発明が本件特許発明1の構成要件1H に相当する構成(前記(2)H の構成)を備えていることについては,直ちに理解することができるものというべきである。\n
イ 本件特許発明1の構成要件1 に相当する構成(前記(2) の構成)\n
前記アのとおり,乙1文献には,フレキシブルチューブが破損するよりも先にブレードが離脱又は破断することを前提とした記載があること,フレキシブルチューブは蛇腹構造のものであり,その名のとおり伸縮可能\なものであるのに対し,ブレードはフレキシブルチューブの伸長を防止する構成のものであることが認められる。そうすると,乙1発明においても,ブレードが離脱又は破断した後,フレキシブルチューブは当然に伸長する。しかも,前記アのとおり,ブレードが離脱した後,フレキシブルチューブが約2倍の長さにまで伸長する構\成のフレキシブル継ぎ手が公知のものであったことも認められる。これらのことからすれば,乙1文献に接した当業者であれば,乙1発明が本件特許発明1の構成要件1 に相当する構成(前記(2) の構成)を備えていることについても,直ちに理解することができるものというべきである。\n
・・・
前提事実(3)イのとおり,構成要件2 は,「樹脂スリーブの小径内周の高さと金属スリーブの中間外周の高さおよび小径外周の高さの和を一致させ,」というものである。この文言からすると,樹脂スリーブの小径内周の高さと,金属スリーブの中間外周の高さ及び小径外周の高さの和は,同一であると解される。構成要件2Fにおいて「樹脂スリーブの大径内周径と金属スリーブの中間外周径をほぼ一致させたことを特徴とする」とされており,【特許請求の範囲】の記載において,「ほぼ一致」と「一致」とで書き分けられていることからも,上記のとおり解釈するのが合理的である。
・・・
前記のとおり,被告製品2−1が小径外周の構成を備えるか否かについては当事者間に争いがあるものの,樹脂スリーブの小径内周の高さが約13mmであり,金属スリーブの中間外周の高さ(又はこれと小径外周の高さの和)が約16mmであることについては当事者間で争いがない。そうすると,被告製品2−1において,樹脂スリーブの小径内周の高さは,金属スリーブの中間外周の高さ(又はこれと小径外周の高さの和)よりも短く,同一ではないから,構成要件2 を文言上充足するとは認められない。仮に,完全な同一を求めているとまではいえないとしても,上記3mmの違いは,全体の大きさや前記(1)に述べたことに照らしても,「一致」しているとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
2013.09.20
平成22(ワ)42637 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年08月30日 東京地方裁判所
(ウ) ところで,本件明細書においては,共焦点作用について,「第一の次元での共焦点作用」又は「部分的共焦点作用」と「第一及び第二の次元での共焦点作用」又は「完全な共焦点作用」とを区別している。この点について,発明の詳細な説明においては,「発明の開示」において,「前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光と分離して検出され,前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されていることを特徴とする」(4欄47行〜5欄3行)とされ,実施例に関する記載においては,「第3図の構成が部分的共焦点作用のみを発揮する理由は,CCDとコンピュータにより提供される空間フィルタリングが一次元でのみ起こり,二次元では起きないからである。これは,第1図のものと同じエレメントに空間フィルタ14を加えた第4図の実施例を使用することにより克服できる。…スリット30は一次元空間フィルタリングのみを提供し,ラマンバンド28のそれぞれが第5図の水平方向に空間的にフィルタリングされるようにしていることが認められるであろう。しかしながら,焦点19の外側からの若干の光が依然としてスリット30を通過し第3図の影を付けた領域に対応する第5図の領域において受領されることがある。これを克服するには,コンピュータ25を第3図の実施例におけると同様にプログラムして,線44同士の間にあるピクセルからのデータだけを処理し,線46同士の間にある他のピクセルを排除する。これにより,垂直方向における空間フィルタリングが得られ,スリット30により与えられる水平空間フィルタリングと一緒に,完全な二次元共焦点作用が達成される。」(6欄46行〜7欄33行)とされている。以上によれば,本件発明7は,焦点合わせの困難なピンホールを使用しない共焦点作用の技術において,Z軸方向の分解能\向上のために,単にCCDとコンピュータの組合せによる一次元空間フィルタリングを行うのみ(例えば,第1図の従来技術による部分的共焦点作用)ではなく,これにスリットによる空間フィルタリングを組み合わせることにより二次元の空間フィルタリングを行い,これによって完全な共焦点作用を達成しようとするものである。原告らは,完全な共焦点作用については,非分散性エレメントを用いる場合と分散性エレメントを用いる場合の2つに分け,部分的共焦点作用は分散性エレメントを用いる場合であるとするが,本件明細書において,そのような明確な区別をしているとみるだけの根拠に乏しく,いずれのエレメントを用いる場合においても,完全な共焦点作用と部分的な共焦点作用が生じるものと解するのが相当である。このような,本件発明7の技術的意義及び他に特許請求の範囲や発明の詳細な説明において「光」の意義を明らかにするような記載がないことに照らせば,構成要件Aの「光」の意義については,本件発明7の技術的意義を達成できるような光であるか否か,言い換えれば,本件発明7の構\成を備えた装置において,第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらす光といえるか否かという観点から検討するのが相当である。
ウ そこで,ライン照明が第一及び第二の次元での共焦点作用をもたらす光といえるか否かについて検討する。
・・・
スポット照明の場合には試料のスポット光が照射された点から出たラマン散乱光のみがCCDに到達するのであるから,線44間の領域を読み取ることにより,Z軸方向の分解能が高くなり,第二の次元の共焦点作用が生じるものと解される。しかし,ライン照明の場合には,これと同様ということはできない。線PP間を読み取るということは,線PP間に到達した光全てを一括して1データとして読み取るということであって,線PP間に到達した光を検出器の各画素位置ごとに分解してデータを読み取るのではないことを意味し,これは線QQについても同様であると解される(原告らの実験である甲18別紙2の1頁14〜16行参照)。そうすると,ライン照明の場合には,たとえ線QQ間を読み取ったとしても,原告参考図6のように,他の点からの光が含まれており,Z軸方向の分解能\が高まるとはいえない。以上のとおり,原理的にみて,ライン照明の場合においては,QQ間のデータを読み取ったとしても,第二の次元の共焦点作用は生じないものというべきである。
・・・
原告らの実験3及び4によれば,スポット照明では,検出器の列数が少なくなると,FWHMの数値が小さくなり解像度が上がっている。他方で,原告らの実験5によれば,一様なサンプルを用いたライン照明では,検出器の列数を3から1にするとFWHMが小さくなっているが,列数を7から5及び5から3にする過程ではFWHMが小さくなっているとはいえないから,原告らの実験によっても,一様なサンプルを用いたライン照明において共焦点作用が生じるとはいい難い。オ 以上のとおり,原理的には,ライン照明では,光検出器における所与の領域は,サンプルの所与の面からの光だけでなく,他の面からの光も相当量受光するから,「第二の次元」の「共焦点作用」が生じないものと解されるし,実験の結果からみても,ライン照明において「第二の次元」の「共焦点作用」が生じるとは認められない。そして,その他ライン照明において共焦点作用が生じることを認めるに足りる証拠はない。カ 以上を踏まえて,構成要件Aの「光」の意義について検討するに,上記オのとおり,ライン照明において「第二の次元」の「共焦点作用」が生じるとは認められない。そうすると,構\成要件Aの「光」は,スポット照明を意味すると解するのが相当である。
・・・
乙16発明では,前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は,前記入射スリットにおいて,入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過するものである。これは,回折格子(グレーティング)を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じる前記PS−PMT上での非点収差を,シリンドリカル・レンズにより補正するものである(上記アの乙16発明の認定を参照)。すなわち,「シリンドリカル・レンズ」の光学系によって,入射スリットにおいて,あえて非点収差を与え,この非点収差によって分光器により生じる非点収差を解消するものであると解される。このように,入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズが存在する限りは,それによって非点収差が与えられることにより,サンプルの所与の面の焦点からの散乱光がスリットにおいてスポットとして焦点に絞り込まれることにはならないものと考えられる。しかし,乙31号証には,「凹面鏡で光軸外に集光されることにより生じる非点収差を補正するために,CCDカメラの前に円柱レンズ(図1に図示されない)が用いられた。」(訳文2頁7〜9行)と記載されている(「円柱レンズ」はcylindrical lensの訳)。そして,乙16発明において設けられた「シリンドリカル・レンズ」は,球面鏡のような反射型光学素子により発生する非点収差の補正を行うものであるから,乙31号証の「円柱レンズ」は,乙16発明の「シリンドリカル・レンズ」と機能が同一であると認められる。そうすると,乙16発明の「シリンドリカル・レンズ」の位置を,乙31号証のように単に光検出器の前に移動させることは当業者にとって設計的事項というべきものであり,そのように構\成したことによる格別の効果も存在しない。そして,「シリンドリカル・レンズ」の位置を乙31号証のように光検出器の前に移動させることによって,乙16発明において,サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は,入射スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて入射スリットを通過し,サンプルの所与の面の焦点の前または後で散乱される光は,入射スリットにおいて焦点を結ばないことになる。なお,シリンドリカル・レンズが光検出器の前に置かれ,そこで非点収差が与えられるとしても,これはそれによって分光器によって生じた非点収差を解消するためのものであるから,「前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」という構成要件Dの構\成が阻害されるものではない。したがって,相違点4に係る構成は,当業者にとって容易想到であったと認められる。\n
・・・
乙16発明では,光検出器としてPS−PMT検出器が用いられているが,これは,CCDのようなアナログ検出器とは異なり,PS−PMTがデジタル検出器であり,宇宙線ノイズが入ったとしても,そのエネルギーに比例した応答がされるわけではなく,1カウントと数えられるだけであるため,超微弱信号の検出の目的に沿っているからである(乙16・3頁下から9行〜4頁6行)。回折格子(グレーティング)を使用した分光器では反射型光学素子を使わざるを得ないので非点収差が発生し,二次元検出器上でY方向への像の広がりが大きくなってしまうので,Y方向に信号を積算して(ビンニング),X方向の一次元検出器に変換して使用する。乙16発明では,ビンニングによりノイズを大量に取り込んでしまうと感度が低下するという問題が発生するために,非点収差を補正して,ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるものである(乙16・4頁10行〜5頁2行)。ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるという効果は,「PS−PMT検出器の場合により顕著である。」(乙16・4頁下から4〜3行)とされているが,CCDの場合にこの効果が生じないとされているわけではない。そして,乙16号証には,量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばCCD検出器の方が優れているなど,目的によって選択は異なってくることが記載されている(4頁6〜8行)。以上に照らすと,乙16発明において,PS−PMTに代えて,CCD検出器を採用することは当業者にとって容易に想到できることであったと認められる。これに対し,原告らは,超微弱信号の検出以外の目的でCCD検出器を用いることがあるとしても,かかる目的の場合は乙16発明を用いる必要はないから,乙16発明においてCCD検出器を用いる動機付けはないなどと主張する。しかしながら,PS−PMTを用いた乙16発明が超微弱信号の検出で有利であるとしても,上記のとおりCCD検出器の方が優れている部分もあるのであるから,他の目的のために,検出器をCCDに置換することが考えられるのであって,原告らの主張は採用できない。
2013.09.20
平成22(ワ)42609 特許権使用差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年08月30日 東京地方裁判所
次に,「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」の意義については,この要件が当初の請求項2の「ワイヤーを巻き取る一対のウインチ」(甲1)から減縮訂正されたものであること(甲6,8)から考えると,上方が拡開する状態で張設された(いわゆる逆ハの字の)ワイヤーを巻き取ることが不可能ではないという程度では足りず,一対のウインチが,「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る」のに適した構\造を有していることを要求しているものと解するのが相当である(甲8・16頁,乙19・18頁)。イ そこで,イ号物件が逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構造を有しているといえるか検討する。イ号物件において構\成要件Hの「ウインチ」に対応する後側ドラム6aは,それ自体としては特に逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構造を有しているとは認められない(なお,甲7・8頁の図は,10頁に「施工機にはウィンチ1台に主ワイヤー1本と補助ワイヤー2本があり」とあることなどからして,左右一対のウインチを有するイ号物件に関するものとは認められない。)。
ウ イ号物件は,車体前方にフェアリーダーを設置して使用されていたことが認められる(乙20)が,構成要件Hは,ウインチ自体の構\造として逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構造を要求しているのであるから,イ号物件における後側ドラム6aが逆ハの字のワイヤーを巻き取るのに適した構\造を有しておらず,構成要件Hにいう「上方が拡開する状態で張設された一対のワイヤーのそれぞれを巻き取る一対のウインチ」といえない以上,イ号物件が構\成要件Hを充足するとはいえない。
2013.09. 9
平成25(ネ)10030 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成25年08月22日 知的財産高等裁判所
控訴人は,本件手続補正書の「3−1)」及び「3−2)」は,伝達情報の内容の同一性を確認できるデータ,すなわち,原本性を証明するための署名に裏付けされた伝達情報の照合値(ダイジェスト)についての記述であって,原本性を証明してもらうためのデータを,原本性を証明する処理のために受け取ることを否定する陳述ではないから,ダイジェスト照合によって実現しているサービスに,原本性を証明してもらうためのデータを受け取り保管することを加えることをもって,構成要件6及び7の充足性を否定する根拠とはならない旨主張する。しかしながら,前記(1)及び(2)のとおり,控訴人は,本件特許の拒絶査定不服審判において,本件発明は,「伝達情報」等を発信者装置A及び受信者装置Bから内容証明サイト装置Cに送信せず,「伝達情報」を内容証明サイト装置Cが保管しないことによって,引用文献等記載の発明と異なり,通信量(情報量)が多くならず,多くの情報量を保管する構成でもなく,公証人等による伝達情報への不正関与の可能\性を高くしないという効果を奏すると陳述し,本件発明は,控訴人のかかる陳述を踏まえた上で,特許査定がされたものであるから,本件発明の構成要件6及び7の意義は,契約当事者双方が契約書の「原本」を管理し,内容証明サイト装置は原本が改ざんされていないことを伝達情報のダイジェスト又は伝達情報を暗号化した暗号情報のダイジェストのみに基づいて検証することで証明するサービスであると解するのが相当である。したがって,原本性を証明するためのデータではなく,原本性を証明してもらうためのデータであれば,「伝達情報」を受け取り保管することもできるとする控訴人の主張は採用することができない。また,本件処理ステップb及びe(甲7の6頁,9頁及び10頁)によれば,CECサーバにおける署名検証(文書が発信者A又は受信者Bから送られたものであるか,当該文書が誰かに改ざんされていないかの検証)は,発信者AからCECサーバに送信されたD及び[(D)a]SKaのうち,Dからダイジェスト(D)cを作成し,[(D)a]SKaを復号化して(D)aを作成して,両者を照合することによって行われ,また,受信者BからCECサーバに送信されたD’及び[(D’)b]SKbのうち,D’からダイジェスト(D’)cを作成し,[(D’)b]SKbを復号化して(D’)bを作成して,両者を照合することによって行われるものである。このように,CECサーバが署名検証を行うには,発信者及び受信者から,それぞれ伝達情報のダイジェストだけではなく,伝達情報をも受信する必要がある。したがって,CECサーバにおいて受け取り保管する伝達情報は,原本性を証明してもらうためのデータというにとどまらず,「伝達情報の内容の同一性を確認できるデータ」,すなわち,原本性を証明するためのデータに当たるものであるから,CECサーバについては,「伝達情報の内容の同一性を確認できるデータ」が,「伝達情報のダイジェスト又は該伝達情報を暗号化した暗号情報のダイジェストに限られ」ているとする構\成要件6及び7を充足しないことは明らかである。イ なお,控訴人は,CEC利用規約4条1項及び本件処理ステップeによれば,CECサーバは,電子署名の中の契約当事者の署名で裏付けされた契約書の照合値の真正を確認することによって,原本性を証明してもらうための当該デジタル・データの原本性を証明(検証)しているから,発信者署名データの中の契約書のダイジェスト(照合値)のみが,発信者が送信した電子契約文書の内容の同一性を確認できるデータであり(構成要件6の充足),受信者署名データの中の契約書のダイジェストのみが,受信者が受け取って復号化した電子契約文書の内容の同一性を確認できるデータである(構\成要件7の充足)旨主張するが,前記アで述べたとおりであって,控訴人のかかる主張にも理由がない。
2013.09. 9
平成24(ワ)16103 特許権に基づく差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年08月29日 東京地方裁判所
本件各発明の構成要件CないしFにいう「共用アプリケーションソ\フトウェア」がどのようなアプリケーションソフトウェアを意味するかについて検討すると,・・・本件各発明の「共用アプリケーションソ\フトウェア」は,少なくとも,1)情報データの文字数及び行数,2)印刷用紙に印字する前記情報データの個数,並びに,3)印刷用紙に印字する前記情報データの文字サイズ及び文字フォントを,統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能を有するものでなければならず,そのいずれかの機能\を欠くアプリケーションソフトウェアは,「共用アプリケーションソ\フトウェア」に当たらないものと解される。また,本件各明細書の記載をみても,前記(1)ア(ア)a及び同(イ)aのとおり,本件各発明は,従来の技術では,HTTPの記述言語と情報データを受信した端末装置との間に互換性の相違(端末装置の機種やOS,アプリケーションソフトウェア,フォント環境等の相違)があると,情報データが不規則に散在してディスプレイに表\示されたり,文字が入り乱れた乱雑な状態で印刷用紙に印字されてしまう場合があったところ,これを,情報データを中間データに変換して端末装置に送信し,端末装置にインストールされた共用アプリケーションソフトウェアの機能\により,統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力することによって,統一した所定の書式で表示又は印刷させることができるとの作用効果を有するものとされている。そして,本件各明細書において,共用アプリケーションソ\フトウェアは,「印刷用紙における文字数および行数,印刷用紙に印字する個別情報データのデータ数,文字サイズおよび文字フォント,印刷用紙の上下端縁および両側縁のマージン等を自動的に設定する機能を有し,個別情報データをディスプレイ7または印刷用紙に無駄なく最適なレイアウトで表\示または印字する機能」を有するものとされている。さらに,前記(1)ア(ア)b及び同(イ)bのとおり,本件各明細書には,本件各発明の実施例として,(ア)スポーツ用品の販売に供する紙票を出力する場合,(イ)宿泊施設の提供の取次ぎに供する紙票を出力する場合,(ウ)展示会や即売会等のイベントに参加した出展者がイベント会場に来場したユーザーに後日,紹介状や案内状等の郵便物を発送する際の郵便物に貼付する宛名ラベルを出力する場合が挙げられている。そして,このうちの(ア)を例に採ると,本件明細書1中の図6に掲記されたB5縦の紙票には,テニスラケットのメーカー名,商品名,キャッチフレーズ,性能,販売価格及び販売店名が所定の文字数以内,所定の行数以内,所定の列数以内に印字され,テニスラケットの形態(全体図)が所定の範囲に印刷されている。そして,販売店は,この紙票を,テニスラケットやショウケースに貼\付したり,広告として使用したり,紹介状や案内状と共に顧客に郵送したりすることもできる旨の作用効果が記載されている(【0079】,【0080】)。上記の1)ないし3)の一部でもレイアウトが崩れた場合は,このような作用効果を発揮することができず,各販売店が情報データを製造者から郵送やファクシミリ等で取り寄せなければならなくなり,本件各発明の課題(前記(1)ア(ア)a及び同(イ)a参照)を解決することができないこととなる。以上によれば,本件各発明にいう「共用アプリケーションソフトウェア」は,上記1)ないし3)の全てを統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能を有するものであることを要し,これらを設定する機能\を一部でも欠き,又は機能自体はあっても手動で設定しなければならないこともあるようなアプリケーションソ\フトウェアは,上記の「共用アプリケーションソフトウェア」には当たらないものと解するのが相当である。イ これを被告サービスについてみると,前記(1)エのとおり,被告サーバにおいては,あらかじめ用意されているテンプレートに従って利用明細に係るPDFファイルが作成され,これが利用者に送信されると,利用者は,元のレイアウトを変更することなく,単に,受信したPDFファイルをリーダーで表示又は印刷するにすぎないことが認められる。すなわち,被告サービスにおいて,共用アプリケーションソ\フトウェアが有するとされている基本的な機能(利用者端末の機種やOS,アプリケーションソ\フトウェア,フォント環境等の相違にかかわらず,情報データを統一された所定の形式で端末装置が出力することができるようなファイルを作成する機能)を有するアプリケーションソ\フトウェアに相当するのは,PDFファイルの作成機能を有するアクロバット等のアプリケーションソ\フトウェアであって(なお,それは,利用者端末ではなく被告サーバにインストールされているものと認められる。),利用者が利用明細に係るPDFファイルを表示又は印刷する際に使用する利用者端末のリーダーは,これには当たらないものと解される。
ウ これに対し,原告らは,リーダーにも,元の文書に使用されたフォントが端末装置に存在しない場合に代替フォントを用いて出力する機能,元の文書を縮小して印刷する際に文字サイズ,上下端縁及びマージンを変更して出力する機能\があると主張する。しかしながら,前記(1)ウ(イ)のとおり,リーダーのフォントの設定次第では,別の端末で表示・印刷したときに元のレイアウトを保持することができず,エラーや文字化けが発生する場合もあり,これを補正するためには手動で字形を埋め込むなどの作業をしなければならないこともあることが認められる。また,同(ウ)のとおり,リーダーを使用してPDFファイルを印刷する場合,その設定次第では,常に最適のサイズでの印刷がされるとは限らないことが認められる。そうすると,リーダーに原告らの主張するような機能があるとしても,リーダーが,文字サイズ及び文字フォントを常に一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能\(前記アの3))を有するとは断定することができないものというべきである。また,この点をおくとしても,原告らは,共用アプリケーションソフトウェアが有していなければならない前記アの1)ないし3)の機能のうち,1)の情報データの文字数及び行数並びに2)の印刷用紙に印字する前記情報データの個数については,リーダーにこれを統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能があることについて主張すらしていない。なお,この点に関し,原告らは,リーダーはPDFファイルについて印刷命令が出された場合,プリンタの機種に応じたページ記述言語データを作成するところ,これはページ記述言語データにデータ数,文字数,文字サイズ,文字フォント,行数,上下端縁,マージン等を設定するものであると主張するが,それも,元のファイルのレイアウトを最適なものに設定するものではなく,元のファイルのレイアウトを何ら変更することなく,そのとおりに印刷することしかできない機能\として主張されているものと解されるから,リーダーが上記1)及び2)の機能を有していることの根拠とはならないものというべきである。したがって,原告らの主張はいずれも理由がない。
エ 加えて,原告らを含む出願人は,本件各特許権の出願経過において,特許庁審査官の本件各拒絶理由通知書(前記(1)イ(ア))に対して本件各意見書を提出し,これには同(イ)のとおりの記載がされていた。これをみると,原告らは,本件各発明が乙5発明とは異なるもので,かつ,当業者が乙5発明から本件各発明を容易に想到することができないものであることを裏付けるために,リーダーを用いて印刷した場合,文字フォントを統一することができず,クライアントがサーバと同一の文字フォント,サーバと同一の文字数(情報データの個数)で帳票を出力することができない場合があるのに対し,本件各発明の共用アプリケーションソフトウェアにはこのような制約がなく,規則正しく最適なレイアウトで出力することができる旨主張しているのであるから,本件各発明の共用アプリケーションソ\フトウェアはリーダーとは異なるアプリケーションソフトウェアを想定している旨の主張をしていることが明らかである。そうすると,本件各特許の出願経過においてこのような主張をし,その登録を受けた原告らが,本件訴訟において,これを翻し,リーダーが本件各発明の共用アプリケーションソ\フトウェアに当たるとの主張をすることは,信義誠実の原則に反し,許されないというべきである。この点からも,原告らの主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2013.09. 9
平成24(ワ)16103 特許権に基づく差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年08月29日 東京地方裁判所
本件各発明の構成要件CないしFにいう「共用アプリケーションソ\フトウェア」がどのようなアプリケーションソフトウェアを意味するかについて検討すると,・・・本件各発明の「共用アプリケーションソ\フトウェア」は,少なくとも,1)情報データの文字数及び行数,2)印刷用紙に印字する前記情報データの個数,並びに,3)印刷用紙に印字する前記情報データの文字サイズ及び文字フォントを,統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能を有するものでなければならず,そのいずれかの機能\を欠くアプリケーションソフトウェアは,「共用アプリケーションソ\フトウェア」に当たらないものと解される。また,本件各明細書の記載をみても,前記(1)ア(ア)a及び同(イ)aのとおり,本件各発明は,従来の技術では,HTTPの記述言語と情報データを受信した端末装置との間に互換性の相違(端末装置の機種やOS,アプリケーションソフトウェア,フォント環境等の相違)があると,情報データが不規則に散在してディスプレイに表\示されたり,文字が入り乱れた乱雑な状態で印刷用紙に印字されてしまう場合があったところ,これを,情報データを中間データに変換して端末装置に送信し,端末装置にインストールされた共用アプリケーションソフトウェアの機能\により,統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力することによって,統一した所定の書式で表示又は印刷させることができるとの作用効果を有するものとされている。そして,本件各明細書において,共用アプリケーションソ\フトウェアは,「印刷用紙における文字数および行数,印刷用紙に印字する個別情報データのデータ数,文字サイズおよび文字フォント,印刷用紙の上下端縁および両側縁のマージン等を自動的に設定する機能を有し,個別情報データをディスプレイ7または印刷用紙に無駄なく最適なレイアウトで表\示または印字する機能」を有するものとされている。さらに,前記(1)ア(ア)b及び同(イ)bのとおり,本件各明細書には,本件各発明の実施例として,(ア)スポーツ用品の販売に供する紙票を出力する場合,(イ)宿泊施設の提供の取次ぎに供する紙票を出力する場合,(ウ)展示会や即売会等のイベントに参加した出展者がイベント会場に来場したユーザーに後日,紹介状や案内状等の郵便物を発送する際の郵便物に貼付する宛名ラベルを出力する場合が挙げられている。そして,このうちの(ア)を例に採ると,本件明細書1中の図6に掲記されたB5縦の紙票には,テニスラケットのメーカー名,商品名,キャッチフレーズ,性能,販売価格及び販売店名が所定の文字数以内,所定の行数以内,所定の列数以内に印字され,テニスラケットの形態(全体図)が所定の範囲に印刷されている。そして,販売店は,この紙票を,テニスラケットやショウケースに貼\付したり,広告として使用したり,紹介状や案内状と共に顧客に郵送したりすることもできる旨の作用効果が記載されている(【0079】,【0080】)。上記の1)ないし3)の一部でもレイアウトが崩れた場合は,このような作用効果を発揮することができず,各販売店が情報データを製造者から郵送やファクシミリ等で取り寄せなければならなくなり,本件各発明の課題(前記(1)ア(ア)a及び同(イ)a参照)を解決することができないこととなる。以上によれば,本件各発明にいう「共用アプリケーションソフトウェア」は,上記1)ないし3)の全てを統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能を有するものであることを要し,これらを設定する機能\を一部でも欠き,又は機能自体はあっても手動で設定しなければならないこともあるようなアプリケーションソ\フトウェアは,上記の「共用アプリケーションソフトウェア」には当たらないものと解するのが相当である。イ これを被告サービスについてみると,前記(1)エのとおり,被告サーバにおいては,あらかじめ用意されているテンプレートに従って利用明細に係るPDFファイルが作成され,これが利用者に送信されると,利用者は,元のレイアウトを変更することなく,単に,受信したPDFファイルをリーダーで表示又は印刷するにすぎないことが認められる。すなわち,被告サービスにおいて,共用アプリケーションソ\フトウェアが有するとされている基本的な機能(利用者端末の機種やOS,アプリケーションソ\フトウェア,フォント環境等の相違にかかわらず,情報データを統一された所定の形式で端末装置が出力することができるようなファイルを作成する機能)を有するアプリケーションソ\フトウェアに相当するのは,PDFファイルの作成機能を有するアクロバット等のアプリケーションソ\フトウェアであって(なお,それは,利用者端末ではなく被告サーバにインストールされているものと認められる。),利用者が利用明細に係るPDFファイルを表示又は印刷する際に使用する利用者端末のリーダーは,これには当たらないものと解される。
ウ これに対し,原告らは,リーダーにも,元の文書に使用されたフォントが端末装置に存在しない場合に代替フォントを用いて出力する機能,元の文書を縮小して印刷する際に文字サイズ,上下端縁及びマージンを変更して出力する機能\があると主張する。しかしながら,前記(1)ウ(イ)のとおり,リーダーのフォントの設定次第では,別の端末で表示・印刷したときに元のレイアウトを保持することができず,エラーや文字化けが発生する場合もあり,これを補正するためには手動で字形を埋め込むなどの作業をしなければならないこともあることが認められる。また,同(ウ)のとおり,リーダーを使用してPDFファイルを印刷する場合,その設定次第では,常に最適のサイズでの印刷がされるとは限らないことが認められる。そうすると,リーダーに原告らの主張するような機能があるとしても,リーダーが,文字サイズ及び文字フォントを常に一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能\(前記アの3))を有するとは断定することができないものというべきである。また,この点をおくとしても,原告らは,共用アプリケーションソフトウェアが有していなければならない前記アの1)ないし3)の機能のうち,1)の情報データの文字数及び行数並びに2)の印刷用紙に印字する前記情報データの個数については,リーダーにこれを統一された一定の規則性に基づいて規則正しい(最適な)レイアウトで出力する状態に自動的に設定する機能があることについて主張すらしていない。なお,この点に関し,原告らは,リーダーはPDFファイルについて印刷命令が出された場合,プリンタの機種に応じたページ記述言語データを作成するところ,これはページ記述言語データにデータ数,文字数,文字サイズ,文字フォント,行数,上下端縁,マージン等を設定するものであると主張するが,それも,元のファイルのレイアウトを最適なものに設定するものではなく,元のファイルのレイアウトを何ら変更することなく,そのとおりに印刷することしかできない機能\として主張されているものと解されるから,リーダーが上記1)及び2)の機能を有していることの根拠とはならないものというべきである。したがって,原告らの主張はいずれも理由がない。
エ 加えて,原告らを含む出願人は,本件各特許権の出願経過において,特許庁審査官の本件各拒絶理由通知書(前記(1)イ(ア))に対して本件各意見書を提出し,これには同(イ)のとおりの記載がされていた。これをみると,原告らは,本件各発明が乙5発明とは異なるもので,かつ,当業者が乙5発明から本件各発明を容易に想到することができないものであることを裏付けるために,リーダーを用いて印刷した場合,文字フォントを統一することができず,クライアントがサーバと同一の文字フォント,サーバと同一の文字数(情報データの個数)で帳票を出力することができない場合があるのに対し,本件各発明の共用アプリケーションソフトウェアにはこのような制約がなく,規則正しく最適なレイアウトで出力することができる旨主張しているのであるから,本件各発明の共用アプリケーションソ\フトウェアはリーダーとは異なるアプリケーションソフトウェアを想定している旨の主張をしていることが明らかである。そうすると,本件各特許の出願経過においてこのような主張をし,その登録を受けた原告らが,本件訴訟において,これを翻し,リーダーが本件各発明の共用アプリケーションソ\フトウェアに当たるとの主張をすることは,信義誠実の原則に反し,許されないというべきである。この点からも,原告らの主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2013.09. 5
平成24(ワ)8135 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年08月29日 東京地方裁判所
証拠(甲3の2,6の1ないし3,乙3,7)及び弁論の全趣旨によれば,(ア) 被告装置には,成膜材料の蒸発源として,ハースと呼ばれる電子銃により加熱するものとRHソースと呼ばれる抵抗加熱により加熱するものを備えているが,成膜材料は成膜される各層について一つしか選択することができないから,成膜材料がハースとRHソ\ースとの両方から同時に供給されることはなく,いずれか一方からしか供給されない,(イ) 被告装置には,ハースに隣接してハース用仕切り板が設けられ,RHソースに隣接してRHソ\ース用仕切り板が設けられているところ,ハース又はRHソースから蒸発した成膜材料は,ハース用仕切り板又はRHソ\ース用仕切り板により,蒸発の方向(角度)が制限され,その結果,ドームの基体保持面の全域には供給されない,(ウ) 被告補佐人は,被告装置を用いて,ハースから成膜材料SiO2 を蒸発させ,ハース用仕切り板を設置しない状態と設置した状態とに分けて,基板保持面に保持された基板に形成された膜の厚さを測定する実験をしたところ,ハース用仕切り板を設置しない状態では,ドームの左側10か所(A1ないし10)及び右側10か所(B1ないし10)いずれの基板についても膜が形成されたが,ハース用仕切り板を設置した状態では,左側10か所は,そのうちの3か所(A7,8及び10)の基板については全く膜が形成されず,その余の基板についても右側10か所と比較して膜が極めて薄くしか形成されなかったこと,以上の事実が認められる。原告は,被告補佐人がした実験について,1) ハース用仕切り板の形状からすれば,その効果をもたらす範囲は左側10か所のうちの5か所(A6ないし10)になるはずであるが,左側10か所全部に効果がみられる,2) 真空蒸着では,基板近傍に遮蔽板を設置しない限り,急激な膜厚変化は極めて困難であるのに,左側のA1から極端に膜厚が減少しているとして,ハース用仕切り板以外の手段を用いてデータを作為的に作出した可能性があり,信用性に欠けると主張する。しかしながら,1)については,上記実験に係る実験報告書(乙7)の図2(被告装置の図面)によれば,ハース用仕切り板の効果をもたらす範囲が左側10か所のうちの5か所(A6ないし10)になるはずであるというにとどまるし,2)については,真空蒸着において,蒸発源に隣接して仕切り板を設置したのでは,急激な膜厚変化が生じないことを裏付ける的確な証拠はないのである。そうであるから,原告の上記主張をもって,データを作為的に作出したということはできないし,他にデータを作為的に作出したことを窺わせるような事情も認められない。原告の上記主張は,採用することができない。
(2) 被告補佐人がしたハースを使用した実験結果は,RHソースを使用した場合においても当てはまると考えられるから,前記(1)認定の事実によれば,被告装置は,ハース及びRHソースの各蒸発源による成膜材料の供給範囲がそれぞれドームの基体保持面の一部の領域に制限され,かつ,成膜材料が両方の蒸発源から同時に供給されることはないと認められる。そうすると,被告装置は,基体保持手段の基体保持面の全域に向けて成膜材料を供給するというものではない。原告は,原告のした検証の結果(甲7)や「Coatings on Glass」(甲8)198頁の記載によれば,被告装置は,成膜材料が基体保持面の全域に供給されるものであると主張する。しかしながら,上記検証は,被告装置とは異なる装置を用いたものであるから,その結果が,当然に被告装置における成膜材料の到達範囲を示すというわけではないし,また,証拠(甲8)によれば,「Coatings on Glass」(甲8)198頁には,「起こりうる最も単純な現象(原子の減圧雰囲気における飛行において)は,不活性残留ガス原子との衝突である。これらによる通常の結果は,方向と速度の変化である。これらの原子は,もはや直線上にそって到達しない。残留圧力および蒸着源と基板の間の距離に応じて,蒸着原子は,殆どあらゆる方向から,基板表面に到達可能\である。」と記載されていることが認められるから,成膜材料が残留ガスとの衝突により自由な方向に拡散しながら基体に到達する性質を持つということができるとしても,このことは,残留圧力及び蒸着源と基板の間の距離に応じて到達可能な場合があるにすぎず,これをもって,被告補佐人のした実験における,ハース用仕切り板を設置した状態では膜が形成されない基板があったとの結果を否定することはできない。原告の上記主張は,採用することができない。
(3) そうすると,被告装置の稼働により使用する方法は,被告方法の構成aの「基体保持手段の基体保持面の全域に向け成膜材料を供給する」を充足しない。\n
2013.07.21
平成23(ワ)10590 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年07月16日 大阪地方裁判所
(ア) 原告は,かねてから商品名をワンタッチテーブルとする着脱自在の脚を備えたテーブル(以下「原告製品」という。)を販売している。原告製品は,本件特許発明の構成要件A,D〜Hを充足するが,被告製品同様,テーブル本体に有底円錐台形状の嵌合突起を備え,脚部上端の被固定部に備えられた嵌合孔へ挿嵌させた際,嵌合突起の外周面と嵌合孔の内周面とは接触せず,被告製品と同程度の隙間ができる。しかし,原告は,かかる挿嵌状態も本件特許発明の「緊密に挿嵌」(構\成要件C)に当たると考えており,原告製品を本件特許発明の実施品であると認識していた。被告ジャパンレントオールは,平成16年から平成19年にかけ,原告から原告製品を購入し,自社の賃貸事業に供していた。ところが,被告ジャパンレントオールと本店所在地及び代表取締役を同じくするジャパンイベントプロダクツ(平成19年5月21日設立)は,平成20年ころから,被告製品を販売するようになり,被告ジャパンレントオールも,原告製品ではなく,被告製品を賃貸事業で用いるようになった。被告ジャパンイベントプロダクツは,被告ジャパンレントオールの賃貸事業を通じて蓄積した知識や経験などを商品開発に活用する方針をとっており,被告製品の嵌合突起8及び嵌合孔10の形状は,原告製品の形状に依拠したものであった。(甲6,9)
(イ) 原告は,平成23年8月19日に提起した本件訴訟において,被告製品の構成を前記第3の1【原告の主張】(1)のとおり,すなわち,被告製品の有底円錐台形状の嵌合突起8を「有底短筒状の嵌合突起8」と,嵌合突起8を嵌合孔10に挿嵌させた際,嵌合突起の外周面と嵌合孔の内周面とは接触せず,隙間ができる状態であったにもかかわらず,これを「緊密に挿嵌」と表現した上,被告製品が本件特許発明の構\成要件B及びCを充足する旨主張した。これに対し,被告らは,平成23年12月9日の第1回弁論準備手続期日において,被告製品につき,被告製品の有底円錐台形状の嵌合突起8を「有底短円錐筒状の下方膨出部80」と,上記挿嵌の状態を「(下方膨出部80を)緊密に挿嵌させる嵌合孔10」と特定した上,被告製品は構成要件A及びDからHまでを充足しないと主張する一方,構\成要件B及びCの充足性について積極的に争う主張をしなかった。また,被告らは,乙1発明に基づき,本件特許発明は新規性又は進歩性を欠き,特許庁の審判において無効とされるべきものである旨の抗弁を主張した。この点,乙1発明の膨出部(5)と凹所(12)は,本件特許発明の嵌合突起8と嵌合孔10と同様,膨出部(5)が凹所(12)に挿嵌できるとはされているものの,乙1文献に,膨出部(5)の形状や挿嵌時の状態を限定する記載はなかった。しかし,原告は,被告らの乙1発明に基づく無効論への反論として,構成要件E及び構\成要件Hが相違し,かつ,当該相違点に係る構成が当業者にとって容易想到でない旨の主張をする一方,「有底短筒状の嵌合突起8」(構\成要件B)及び「緊密に挿嵌」(構成要件C)について相違しているとは主張しなかった。また,被告らは,乙2発明や乙3発明に基づく無効論も展開したが,やはりいずれの当事者からも,「有底短筒状の嵌合突起8」(構\成要件B)及び「緊密に挿嵌」(構成要件C)が相違点として主張されることはなかった。このように本件訴訟は,属否論においても,無効論においても,「有底短筒状の嵌合突起8」(構\成要件B)及び「緊密に挿嵌」(構成要件C)が明示的な争点となることのないまま,平成24年7月9日,損害論の審理をすることなく口頭弁論が終結され,同年9月13日に判決言渡期日が指定された。(甲12,乙1)
(ウ) 被告ジャパンレントオールは,本件訴訟と平行して,平成23年12月23日,特許庁に本件特許発明の無効審判を請求したところ,特許庁は,平成24年8月14日付けの審決において,本件特許発明と乙1発明との対比において,本件特許発明の嵌合突起が「有底短筒状」であり,嵌合孔が「嵌合突起8を緊密に挿嵌させる」ものであり,スリットの伸びる方向が「筒の径方向」であるのに対し,乙1発明は嵌合突起が「短筒状」でなく,嵌合孔が「嵌合突起を緊密に挿嵌させる」ものでない点を相違点1と認定した(原告は,同手続において,これを相違点と主張していたわけではなかった。)。そして,特許庁は,他に認定した相違点に係る構成に到達することは当業者が容易に想到し得たとする一方,相違点1に係る構\成については,乙1発明の膨出部(5)(本件特許発明の「嵌合突起8」に相当)と凹所12(本件特許発明の「嵌合孔10」に相当)が,支脚(3)の回転を支障なくするための機能を要求されておらず,他にも両者が相互に「緊密に挿嵌させる」ことを示唆する記載は乙1文献になく,他の刊行物にもその旨の示唆はないことから,当業者が到達することは容易ではないとし,相違点1を根拠として,乙1発明に基づく容易想到性の主張を排斥した。この審決は,被告ジャパンレントオールによる他の無効理由の主張も排斥し,無効審判請求不成立を結論とするものであった。
(甲12)
(エ) 当裁判所は,原告から特許庁の上記審決の写しが提出され,弁論再開の申出があったことを踏まえ,平成24年9月13日,弁論を再開した。原告は,弁論再開後の同年11月13日の第6回弁論準備手続期日において,上記審決において認定された相違点1を,本件特許発明と乙1発明との相違点として初めて主張し,当該相違点に係る構\成が容易想到でない理由についても,上記審決の判断を援用した。これに対し,被告らは,平成24年12月13日の第7回弁論準備手続期日において,上記相違点1が,本件特許発明と乙1発明との相違点であることを争い,また,仮に相違していても,設計事項に過ぎず,当業者であれば容易に想到できる旨主張すると共に,原告の新たな主張は,「緊密に挿嵌」を,嵌合突起8が嵌合孔10に挿嵌された際,被固定部5の上面と内側面が,固定部4に緊密に接触していることを意味すると解するものであるが,そうであれば,被告製品は「緊密に挿嵌」を充足しない旨主張した(原告が「緊密に挿嵌」の解釈について,属否論と無効論とで異なる主張をすることは禁反言の法理から許されないとも主張した。)。その後,原告は,同年5月24日の第10回弁論準備手続期日において,「緊密に挿嵌」の解釈及び被告製品の充足性について主張を追加すると共に,被告製品が「緊密に挿嵌」の構成を備えていることには自白が成立し,構\成要件B及びCを充足することも争いがなかったのであり,被告らがこれと矛盾する主張をすることは禁反言の法理から許されない旨主張するに至った。
イ 検討
原告は,被告製品の構成について,原告が被告製品の構\成を前記第3の1【原告の主張】(1)のとおりに主張したのに対し,被告らも構成要件Cに対応する構\成として「(下方膨出部80を)緊密に挿嵌させる嵌合孔10」と主張し,構成要件Cの充足性を争わなかったのであるから,被告製品が「緊密に挿嵌」との構\成を備えていることには自白が成立している上,構成要件Cを充足することも争いがなかったのであり,これを後日争うことは禁反言の法理に反して許されない旨主張する。しかし,自白(民事訴訟法179条)は,具体的な事実について成立するものであり,ある事実を前提とした抽象的な評価について成立するものではない。この点,被告製品の構\成に係る原告及び被告らの主張に係る「緊密に挿嵌」との文言は,嵌合突起8(下方膨出部80)を嵌合孔10に挿嵌させたときの状態を評価したものであり,事実そのものではない。また,前記ア認定の事実経過からしても,原告は,本件訴訟において,被告製品が原告製品と同様,有底短円錐状の嵌合突起8を嵌合孔10に挿嵌させた際,嵌合突起の外周面と嵌合孔の内周面とは接触せず,隙間ができることを念頭に置きつつ,このような状態も「緊密に挿嵌」に該当するとの認識のもと,被告製品の構成について「緊密に挿嵌」との文言を用いて特定したのに対し,被告らも,原告製品に依拠した形状を備える被告製品を販売等してきた経過もあり,原告と同一の認識のもとで,上記状態を「緊密に挿嵌」と表\現したものといえるから,やはり「緊密に挿嵌」は事実そのものを摘示したというより,上記のような物理的な状態を評価したものである。そのため,かかる抽象的な評価の前提となっている嵌合突起8や嵌合孔10の形状等の事実関係について自白が成立したと見る余地はあるものの,挿嵌時の状態が「緊密に挿嵌」と表現されるべきものとの点について自白が成立したとはいえないし,ましてや構\成要件Cの一部である「緊密に挿嵌」を充足するとの点について自白が成立したともいえない。また,原告の主張は,被告らが弁論再開前には争っていなかった「緊密に挿嵌」(構成要件C)の充足性を争うことにつき,自白の成否にかかわらず,禁反言の法理に反して許されない趣旨とも考えられるが,この主張も採用できない。すなわち,被告らは,弁論再開前において,構\成要件Cの充足性を積極的に争う主張をしなかったとはいえ,その充足性を明示的に認めていたわけではないから,これを後日争ったとしても矛盾した主張をしたとは言い難い。加えて,原告は,当初「緊密に挿嵌」の解釈について,嵌合突起の外周面と嵌合孔の内周面との接触の有無及び程度を特段限定するものではないことを前提とした主張をしていたが,弁論再開後においては,本件特許発明が進歩性を欠くとの判断を回避するため,「緊密に挿嵌」の意義を限定的に解釈するに至ったものである。つまり,被告らが「緊密に挿嵌」の充足性を積極的に争うに至ったのは,「緊密に挿嵌」の解釈に関し,原告が従前の主張と異なる新しい主張をしたためであり,十分に合理的な事情があったといえるから,被告らにおいて,禁反言の法理など信義則に反する訴訟活動を行ったとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
2013.06.27
平成24(ネ)10084 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成25年06月25日 知的財産高等裁判所
控訴人は,本件発明の「メディア情報」は「メディアアイテムに特有の情報」ではなく「メディアアイテムに関する情報」と解すべきであることを前提に,原判決で,ファイルサイズが構成要件G1及びG2における「メディア情報」には該当しないと判断したのは誤りであると主張する。この点についての判断は,原判決が37頁以下の(2),(3)で説示したとおりであるが,なお次のとおり補足して判断する。本件明細書(甲2)の記載によれば,本件発明は,「ホストコンピュータおよび/またはメディアプレーヤー上のメディアコンテンツをシンクロまたは管理するための改良されたアプローチのための改良された技術」(段落【0005】)として,メディアコンテンツのシンクロ処理において,ファイル名や更新日ではなく,「メディア情報」を比較することにより,シンクロを「データ転送の量が比較的低いか最小限にされるよう適切に管理されるよう」(段落【0022】)にし,「その結果,シンクロプロセスは,よりインテリジェントに実行されえる」(段落【0010】)ようにしたものであり,また,本件特許請求の範囲における文言上,「ファイル情報」と規定することなくあえて「メディア情報」と規定しているばかりか,本件明細書等においても,「メディアアイテムが有するファイル情報」などとの用語ではなく,あえて「メディア情報」の用語が用いられ,しかも,その用語は,「メディア情報は,メディアアイテムの特徴または属性に関する」(段落【0040】)などと,メディアアイテムに関連付けて表現されていることが認められるから,本件発明における「メディア情報」とは,一般的なファイル情報の全てを包含するものではなく,音楽,映像,画像等のメディアアイテムに関する種々の情報のうち,メディアアイテムに特有の情報を意味するものと解するのが相当である。「メディア情報」なる用語はその語そのものからいかなる情報までを包含するか明確でなく,当該発明の技術的課題や作用効果を参酌してその意義を解釈しなければならないところ,原判決は,特許請求の範囲における構\成要件の記載や本件明細書の記載等を踏まえて,「メディア情報」を上記のように解釈したものであり,引用した上記各記載に照らしても,その判断を支持することができる。以上の説示に照らし,ファイルサイズが「メディア情報」に含まれないことは,原判決も「原告の主張について」と題して39頁以下のイの項で詳細に説示しているとおりであり,当裁判所が付加すべき理由はない。控訴人の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2013.06.10
平成24(ネ)10094 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成25年06月06日 知的財産高等裁判所
被控訴人は,機能的クレームである本件各特許発明の技術的範囲に被告各製品が文言上属さないとされた以上,均等論を適用する余地はない旨主張する。しかしながら,文言上,特許請求の範囲に記載された発明と異なる構\成を被告各製品が有しているとしても,一定の要件を充たす場合には例外的にこれと均等と評価されるものとして侵害を認める考え方が均等論であり,この理は,クレームが機能的に記載された構\成であるか否かによって変わるものではないから,機能的クレームについてのみ,文言侵害が否定されたからといって,均等論の適用が当然に否定されるべき理由はない。したがって,被控訴人の上記主張は,採用することができない。\n
(2) 第1要件(非本質的部分性)について
均等の第1要件における特許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける技術的思想の特徴的な部分,すなわち,上記部分が他の構\成に置き換えられるならば,全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものである。本件各特許発明の特許請求の範囲の記載(請求項1,2及び5)と本件明細書によれば,従来,ノート型パソコンの本体ケーシングに開設されたスリットに連結する連結具として,先端に掛止部が形成された掛金具と,該掛金具に着脱可能\に嵌合する卵形のカバーから成る連結具があったが,従来の技術では,「掛金具の掛止部をスリットに挿入した後,掛金具から手を離すと,掛金具がスリットに吊り下がったり,スリットから脱落することがあり,カバーを装着できない。このため,掛金具を片手で押さえたままで,他方の手でカバーを挿入する必要があった。しかしながら,掛金具,カバーは共に小型であり,また,スリットは,ノート型パソコンの下面に近い側部に形成されているから,両手で連結具を取り付ける操作は困難であり,作業性が悪い問題があった。」(本件明細書の段落【0003】)ことから,本件各特許発明は,「片手で簡単に取付けできるノート型パソ\コン等の器具の盗難防止用のケーブル連結具を提供すること」(本件明細書の段落【0005】)を目的とし,上記課題を解決するための手段として,スリットへの挿入方向,すなわち差込片の突出方向ないし形状に沿って補助プレートを前進スライドさせることにより,主プレートと補助プレートとを相対的にスライド可能に係合し,かつ両プレートを分離不能\に保持する構成(構\成要件B,D,Eに係る構成)を採用することで,「片手で連結具を掴んで,主プレートの抜止め片をスリットに挿入して90度回転させ,そのまま,補助プレートの回止め片を差込片と重なるようにスリットに押し込むだけで,連結具をスリットに取付けできる」(本件明細書の段落【0007】)という作用効果を奏するようにしたものであると認められる。
本件各特許発明の上記の課題,目的,構成,作用効果等に照らすと,本件各特許発明は,スリットへの挿入方向,すなわち差込片の突出方向ないし形状に沿って補助プレートを前進スライドさせることにより,主プレートと補助プレートとを相対的にスライド可能\に係合し,かつ両プレートを分離不能に保持するものとして構\成することで,盗難防止用連結具を片手で簡単に取付け可能にした点に,本件各特許発明特有の課題解決手段を基礎づける技術的思想の特徴的な部分,すなわち本質的部分があるというべきである。しかるに,被告各製品は,補助部材が,主プレートに対して,スリットへの挿入方向,すなわち差込片の突出方向ないし形状に沿って前進スライドすることによりスライド可能\に係合するものではなく,一つの枢結点を中心として回転方向にスライド可能に係合する構\成を採るものであって,上記相違点は,本件各特許発明の本質的部分に係るものというべきである。したがって,第1要件である非本質的部分性については,これを認めることができない。
(3) 第3要件(置換容易性)について
控訴人は,二つの部材をピンによって枢結し回動させる構成や,あらかじめ大きさが規定された孔に対して回転方向から突起を挿入する場合には侵入する突起の外周形状を円弧状にせざるを得ないこと等は,いずれも技術分野を問わず汎用される慣用技術であること,技術分野を問わず部品点数を減らすことは自明の課題であり,当業者が部品点数を減らす観点から二つのスプリングピンを一つにすることは当然に検討されるべきことからすれば,本件各特許権の請求項又は本件明細書の記載から,主プレートと補助プレートとを一つのピンによって枢結し回動する方向でスライドする被告各製品の構\成とすることは,被告各製品の輸入販売時はもとより,本件出願時においても容易に想到することができたものである旨主張し,同主張に沿う証拠として,甲14ないし18,20,22ないし29,甲30の1及び2,甲34ないし39,43及び44を引用する。しかしながら,上記各書証の技術等の開示事項は,いずれも盗難防止用連結具という技術分野に関する発明である本件各特許発明とは技術分野及び技術的課題が異なるものである上,仮に二つの部材をピンによって枢結し回動させる構成や,あらかじめ大きさが規定された孔に対して回転方向から突起を挿入する場合には侵入する突起の外周形状を円弧状にせざるを得ないこと等が,いずれも技術分野を問わず汎用される慣用技術であるとしても,控訴人が慣用技術の根拠として引用する上記各書証に開示された技術等は,発明が解決しようとする課題,発明の目的,課題を解決するための手段,基本構\成及び使用態様等が,いずれも本件各特許発明とは異なるものであって,本件明細書には当該慣用技術を採用する動機付けが何ら開示も示唆もされておらず,上記各書証にも,本件各特許発明の技術的課題について何らの開示も示唆もされていないのであるから,本件各特許発明に当該技術等を適用して被告各製品の構成を採用する動機付けがなく,結局,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて,当業者が被告各製品を実施し得るものとは認められないことは前記のとおりであり,被告各製品の販売等の時点において,これが容易想到であったことを認めるに足りる証拠はない。また,技術分野を問わず部品点数を減らすことが自明の課題であったとしても,それだけでは,当業者が本件各特許発明から被告各製品の構\成を容易に想到することができることにつながるものではない。したがって,第3要件である置換容易性については,これを認めることができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 機能クレーム
>> 均等
2013.05.24
平成23(ワ)13054 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年05月23日 大阪地方裁判所
被告は,本件特許発明の切断刃は,交換装置と共に利用されて初めて技術的な貢献をするものであり,切断刃自体は,公知の切断刃の一部分に極めてありふれた単純な構造の付加を行っただけの物品であるから,本件特許発明は,被告製品全体のうち,せいぜい公知の切断刃の物品に付加された構\成による利用価値を高めるだけであり,被告製品の購買動機に影響を与えるものではないと主張する。確かに,被告製品は,剪断式破砕機用切断刃であり,対象物を切断することを目的とするが,本件特許発明は,切断刃の取外し作業の効率性を高めるものであり,切断の機能自体に関わるものではない。しかし,被告製品のような分割式の切断刃自体は公知のものであり(乙B1,本件明細書段落【0004】),本件特許発明の実施品たる構\成を備え,切断刃の取外し作業の効率性を高めている点を除き,格別の特徴を有するわけではないのであるから,本件特許発明の実施品であることこそが被告製品にとって最も重要な差別化要因であったといえる。現に証拠(甲5〜11,乙A29)及び弁論の全趣旨によれば,被告から被告製品を購入した顧客らは,被告製品の「輪形凹部3で形成した係合部」と係合する切断刃交換装置を保有しており,被告製品が本件特許発明の実施品であるからこそ発注,購入したものと認められる。したがって,本件特許発明の実施が被告製品の売上げに寄与した度合は,むしろ大きいというべきであって,損害額の推定の全部又は一部が覆滅されるべき事情があったとは認められない。なお,被告製品を購入した大栄環境株式会社の担当者は,切断刃交換装置を保有しておらず,ハンマーでたたいて切断刃の取り外しを行っていると述べる(乙A30)。しかし,前記1(2)のとおり,被告製品の構成を有する以上,本件特許発明の技術的範囲に属すると認められるところ,被告は,いずれも顧客から指示された仕様に従って被告製品を製造,販売したことが認められる。また,このような事情及び証拠(甲10,11)によれば,大栄環境株式会社は,原告の関連会社から切断刃交換装置を購入していたことも認められ,他にこの認定を妨げるに足りる証拠はない。そのため,ハンマーでたたいて切断刃の取り外しを行っているという上記担当者の陳述内容が真実であったとしても,損害額の推定の全部又は一部が覆滅されるべき事情とすることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
2013.03.24
平成23(ワ)6868 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年03月15日 東京地方裁判所
本件発明の真円度を測定するに当たっては,乾式の試料又は湿式処理をした試料のいずれを用いても差し支えないことは,前記ウで認定したとおりである。ところで,本件発明の真円度の測定に当たり乾式の試料を測定対象とするか,又は湿式処理をした試料を測定対象とするかによって真円度の数値に有意の差が生じる場合,当業者がいずれか一方の試料を測定対象として測定した結果,構成要件所定の真円度の数値範囲外であったにもかかわらず,他方の試料を測定対象とすれば上記数値範囲内にあるとして構\成要件を充足し,特許権侵害を構成するとすれば,当業者に不測の不利益を負担させる事態となるが,このような事態は,特許権者において,特定の測定対象試料を用いるべきことを特許請求の範囲又は明細書において明らかにしなかったことにより招来したものである以上,上記不利益を当業者に負担させることは妥当でないというべきであるから,乾式の試料及び湿式処理をした試料のいずれを用いて測定しても,本件発明の構\成要件Dが規定する粒径30μm未満の粒子の真円度の数値範囲(「0.73〜0.90」)を充足する場合でない限り,構成要件Dの充足を認めるべきではないと解するのが相当である。しかるところ,前記(ア)のとおり,原告測定データ3は,被告製品の乾式の試料を対象として粒径30μm未満の粒子の真円度を測定した場合に,被告製品が構成要件Dの数値範囲内にあることを示している。しかし,他方で,本件においては,被告製品の湿式処理をした試料を対象として粒径30μm未満の粒子の真円度を測定した場合に,被告製品が構\成要件Dの数値範囲内にあることを認めるに足りる証拠はなく,かえって,前記(イ)のとおり,湿式処理をした試料を対象にした被告測定データ1によれば,被告製品は構成要件Dに規定する数値の範囲外にあるというべきである。したがって,被告製品は,構\成要件Dを充足するものと認めることはできない。
(2) まとめ
以上のとおり,被告製品は,構成要件Dを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2013.02. 8
平成23(ワ)16885 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年01月30日 東京地方裁判所
ところで,乙6の【0007】には,「一般的に,望遠ズームレンズは,第1レンズ群が最も大型のレンズ群であり,フォーカシング時に繰り出されることが多い。このため,第1レンズ群を…補正光学系にすることは,保持機構及び駆動機構\が大型化し好ましくない。従って,本発明における正負負正負タイプも同様に,第1レンズ群を防振補正光学系にするのは好ましくない。」と記載されているから,第1群フォーカス方式が開示されていると解されるが,上記の「本発明」に対応する請求項1は,フォーカス方式を特定していない。そして,乙6発明の技術的意義に照らすと,乙6発明において第1群フォーカス方式であることが必須の前提であるとは解されない。そうすると,乙6発明は,第1群フォーカス方式以外のフォーカス方式を排除していないというべきである。また,証拠(乙8〜10)によれば,ズームレンズの技術分野において,1群フォーカスでは大型の構造になる欠点があるために,インナーフォーカスとすることは周知であることが認められる(乙8の【0003】,乙9の(従来の技術),乙10の[従来の技術と課題])。以上のとおり,乙6発明は第1群フォーカス方式の態様を含むのであり,上記の周知技術に照らすと,第1群フォーカス方式の態様において大型の構\造になるという課題を当業者は認識できる。
(ウ) 乙7には,上記アのとおり,望遠レンズにおいては,第1レンズ群以外の比較的レンズ系の小さなレンズ群を光軸上移動させてフォーカスを行う内焦式フォーカス方式(インナーフォーカス方式)を用いている場合が多いことが記載されるとともに,インナーフォーカス方式を用いた望遠レンズにおいて,一部のレンズ群を偏芯させて防振を行うと,偏芯収差の発生量が著しく多くなり,特にフォーカスに際しての偏芯収差の発生量の変動が多くなり撮影画像の光学性能を著しく低下させる原因となっていることが記載されている。そして,上記の周知技術に照らすと,当業者は,乙7では,第1群フォーカス方式のレンズが従来技術と位置付けられているとともに,その課題を解決するためにインナーフォーカス方式が採用されてきたことに加え,インナーフォーカス方式における防振レンズでは,撮影画像の光学性能\を著しく低下させるとの課題が生じることが示されていると認識できる。
(エ) そして,乙6と乙7はともに,本件特許発明の属する像シフトが可能なレンズの技術分野に属するものであるから,当該技術分野の当業者は,乙6と乙7とに同時に接することができる。そうすると,当業者は,1群フォーカス方式の態様を含む乙6発明において,1群フォーカス方式の欠点を解消するとともに,撮影画像の光学性能\を著しく低下させることのない防振レンズを構成するとの課題を認識することができるから,その課題を解決するために乙7発明を適用する動機付けがあると認められる。したがって,乙6発明に乙7発明を組み合わせることは容易であると認められる。\n
2013.01.28
平成23(ワ)4836 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年01月17日 大阪地方裁判所
前記(1)のとおり,被告各製品は,ジェル剤と顆粒剤のキットからなる化粧料であり,本件特許発明1の各構成要件を充足するが,被告各製品を購入した需要者は,上記2剤を混ぜ合わせて,自らジェル状の「部分肥満改善用化粧料」を調製し,生成することが予\定されており,それ以外の用途は考えられない。したがって,被告各製品を製造,販売する行為は,本件特許発明7に係る特許権の間接侵害に当たるといえる。また,上述のとおり,被告各製品の製造,販売は,本件特許発明7に係る特許権の間接侵害に当たるところ,後記(3)のとおり,被告各製品は,主に顔の部分肥満改善に使用されているので,被告各製品を製造,販売する行為は,本件特許発明8に係る特許権の間接侵害にも当たるといえる。
・・・
前記アの被告各製品に係る広告宣伝の内容からすれば,被告各製品は,小顔効果,顔やせ,部分痩せの効果を奏する化粧料として販売されていることが認められる。そうすると,被告各製品が本件各特許発明の「部分肥満改善用化粧料として使用される」という構成を文言上充足することは明らかである。被告らは,前記アの被告各製品に係る広告宣伝には関与していない旨主張する。しかしながら,上記各広告宣伝は,その体裁・内容自体からして真正に成立したものであると認めることができる(被告らも第三者の作成名義で真正に成立した文書であることについてまで争っているとは解されない。)。そして,被告各製品について上記のような類似した広告宣伝がされていることからすれば,被告らが,小売店等に対し,上記のような作用効果を奏する化粧料として被告各製品を販売していることは優に認められるものというべきである。\n
2012.12.18
平成23(ワ)3572 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年11月30日 東京地方裁判所
本件発明1−1の特許請求の範囲(請求項1)の文言と本件明細書1の「発明な詳細の説明」の前記(ア)の記載事項(図面を含む。)を総合すれば,本件明細書1には,1)従来,インターネットなどの通信回線網を介して提供される複数の番組を表形式に配列した番組表\には,各番組の詳細な内容を確認したり,希望する番組を録画予約したりできるものがあるが,このような番組表\の提供を受けた利用者が,番組表中からどのような番組を選んで視聴又は録画を行ったのかを知ることができなかったため,この種の番組表\を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという要望があったこと(前記(ア)b,c),2)本件発明1−1は,この要望に応えることを課題とし,番組表を利用して視聴率及び録画率を調査することができる技術を提供することを目的とするものであり,この課題を解決するための手段として,「利用者側」から「調査者側」に送信されるデータに基づいて,「調査者側」で現在放送中の番組に対応する視聴指標及び録画予\約指標を算出し,上記視聴指標及び録画予約指標を「利用者側」に送信し,「利用者側」に表\示される番組表上の番組に対応づけられて上記視聴指標及び録画予\約指標が表示されるようにするために,「調査者側」の「サーバ」において,上記データ(視聴状況情報及び録画予\約状況情報)の受信手段,上記視聴指標及び録画予約指標の算出手段及び送信手段の各手段を備える構\成を採用し(前記(ア)c,d),これにより「調査者側」においては番組の正確な視聴率及び録画率を調査することができ,「利用者側」においては利用者が番組表上で番組の視聴率及び録画率を簡単にチェックすることができるという作用効果を奏するようにしたこと(前記(ア)j,k,n,p)が開示されているものと認められる。上記認定の本件発明1 − 1 の目的及び作用効果に照らすならば,「調査者側」が行う視聴指標及び録画予約指標の調査についてはその中立性ないし客観性を確保することは当然の要請であって,かかる観点からみると,「調査者側」が自ら行う調査の調査対象となることは不合理であるから,本件発明1−1においては,「調査者側」の「サーバ」が「利用者側」の「利用者装置」を兼ねること,あるいは「利用者側」の「利用者装置」が「調査者側」の「サーバ」を兼ねることは,想定されていないものと認められる。また,本件明細書1記載の実施例は,前記(ア)lないしpのとおり,「調査者側装置10」と「利用者側端末」とは,別個独立の装置構成として記載されている。もっとも,本件明細書1には,「調査者側装置10」が「複数のコンピュータシステムで構\成されていてもよい。」(段落【0070】。前記(ア)q)との記載があるが,上記記載を段落【0070】の他の記載箇所と併せて読むと,上記記載は,「本実施形態」では「調査者側装置10が1のコンピュータシステムによって構成されたもの」を例示したことを指摘した上で,「調査者側装置10」が,「1のコンピュータシステム」ではなく,「複数のコンピュータシステム」によって構\成し得ることを説明したものであり,それ以上に,「調査者側装置」が「利用者側端末」をも含めて構成し得ることまで述べたものと解することはできない。さらに,本件明細書1を全体としてみても,「利用者側」の「利用者装置」が「調査者側」の「サーバ」の機能\の全部又は一部を兼ねることができることの記載や示唆はない。
ウ 本件発明1−1の「サーバ」の意義
(ア) 本件発明1−1の特許請求の範囲(請求項1)の記載(前記ア)を基礎に,本件明細書1の記載事項(前記イ)を考慮すると,本件発明1−1の「サーバ」(構成要件1−1F)は,「利用者装置」(構\成要件1−1A)とは別個独立の装置であって,「利用者装置」が「サーバ」の機能の全部又は一部を兼ねるものとして「サーバ」に含まれることはないものと解するのが相当である。(イ) これに対し原告は,1)「サーバ」とは,一般的に「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト,すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター。」を意味するものであり,本件発明1−1の特許請求の範囲(請求項1)は,本件発明1−1の「サーバ」の装置構\成について限定を付していないこと(以下「根拠1)」という。),2)本件明細書1の【0028】,【0029】,【0070】及び図1によれば,「調査者側装置10」及び「利用者側端末20」は,いずれも「インターネットに接続される周知のコンピュータシステム」であって,特に構成を異にするものではなく,「調査者側装置10」を複数のコンピュータシステムで構\成する場合,その一つのコンピュータシステムが,「利用者側端末20」と同様の周知のコンピュータシステムで構成されてもよいことが読み取れるから,本件発明1−1の「サーバ」は,「利用者装置」とは別異の構\成要素としての「調査者側」の構成要素である必要はないこと(以下「根拠2)」という。),3)本件原出願の出願時において,同一の機能又は異なる機能\を有する複数のコンピュータが協働してサービスを提供することは周知であり,「サーバ」の文言は,利用者側の端末を含み,複数のコンピュータからなる場合を含むものとして理解され,使われていたこと(甲34ないし43)(以下「根拠3)」という。)を総合すれば,本件発明1−1の「サーバ」は,「利用者装置」とは別異の構成要素でなければならないと限定解釈すべき理由はなく,この「サーバ」の機能\の一部を「利用者装置」が担ってもよいと解すべきである旨主張する。しかしながら,原告の上記主張は,以下のとおり理由がない。
a 根拠1)及び2)について
前記アで述べたとおり,本件発明1−1の特許請求の範囲(請求項1)の文言上,「サーバ」と「利用者装置」とは,本件発明1−1の構成要素として別個のものであることは明らかであり,一方で,請求項1には,「利用者装置」が「サーバ」の機能\の全部又は一部を兼ねることができることを規定した記載やこれをうかがわせる記載はない。次に,前記イ(イ)で述べたとおり,本件発明1−1の目的及び作用効果に照らすならば,視聴指標及び録画予約指標の調査の中立性ないし客観性の確保の観点からみて,「調査者側」が自ら行う調査の調査対象となることは不合理であり,本件発明1−1においては,「調査者側」の「サーバ」が「利用者側」の「利用者装置」を兼ねること,あるいは「利用者側」の「利用者装置」が「調査者側」の「サーバ」を兼ねることは,想定されていないものと認められる。また,原告が指摘する本件明細書1の段落【0070】における「調査者側装置10」が「複数のコンピュータシステムで構\成されていてもよい。」との記載は,「調査者側装置」が「利用者側端末」をも含めて構成し得ることを記載したものではなく,本件明細書1を全体としてみても,「利用者側」の「利用者装置」が「調査者側」の「サーバ」の機能\の全部又は一部を兼ねることができることの記載や示唆はない。以上によれば,原告が主張する根拠1)及び2)の点は,本件発明1−1の「サーバ」の機能の一部を「利用者装置」が担ってもよいと解すべきことの根拠となるものではない。b 根拠3)について原告は,根拠3)に係る具体的な裏付けとして,1)特開平10−207945号公報(甲34)の【図2】,特開平10−247177号公報(甲35)の【図1】には,「サーバ」の文言は,ネットワーク上の複数のコンピュータから構成されるものも含むことが開示されていること,2)「情報システムテクニカルガイド 分散システムのための」(1995年6月30日発行)(甲36)の「(それに対して,ピア・ツー・ピア・モデルではどのプロセスでも相互作用を開始することができる)サーバは,他のサーバに要求を発行することでクライアントになることもありえる。…クライアントとサーバは,…同一のマシンで走ることもあれば,別々のマシンで走ることもある。」(282頁)との記載,特開平10−161777号公報(甲37)の段落【0001】,特開平10−154030号公報(甲38)の段落【0010】,【0014】,特開平9−138810号公報(甲39)の段落【0231】,特開平9−51398号公報(甲40)の段落【0028】,特開平9−73410号公報(甲41)の段落【0003】には,「サーバ」の文言は,利用者側端末と機能を兼ねるコンピュータにも使われることが開示されていること,3)特開平9−91220号公報(甲42)の段落【0004】ないし【0006】,特開平10−149270号公報(甲43)の段落【0012】,【0017】には,サーバ機能とクライアント機能\を兼ねる利用者側コンピュータを「サーバ」と呼ぶことが開示されていることを指摘する。しかしながら,原告主張の上記1)ないし3)に係る開示事項(甲34ないし43)は,「サーバ」の文言が,サーバ機能とクライアント機能\を兼ねるコンピュータ(端末)に使用されていることを示すものにすぎず,サービスを提供する側が管理するサーバコンピュータの機能の一部をサービスの提供を受けるユーザー側が管理する端末に持たせることで,ユーザー側に対するサービスの提供を可能\とする構成を開示したものではない。したがって,原告主張の上記1)ないし3)に係る開示事項(甲34ないし43)は,根拠3)の裏付けとなるものではなく,結局,根拠3)は,本件発明1−1の「サーバ」の機能の一部を「利用者装置」が担ってもよいと解すべきことの根拠となるものではない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2012.12.13
平成23(ワ)2283 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成24年12月06日 大阪地方裁判所
本件明細書の記載(前記(1))によれば,本件特許発明は,「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」構成とすることで,攪拌羽根先端部の前端縁(上記アと同様,回転方向を前,逆方向を後とした場合の前端縁)の延長線と処理容器内側面の接線(攪拌羽根先端部の前端縁の延長線と処理容器内側面との交点における接線)との間の角度を90度よりも大きくし,その結果として,攪拌羽根先端部の外周面が処理容器内側面に生成された固着物を削り落とすとともに,遠心力を受けて円周方向に移動した粒子を,処理容器内側面に衝突しない方向へと案内するという作用効果を得るものである。このような作用効果からも,「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」とは,「基端部」の前端縁の延長線よりも,「先端部」が前(回転方向)に出ており,「先端部」の前端縁の延長線と処理容器内側面の接線との間の角度が90度よりも大きい構\成を求めているものと解される。
ウ 小括
以上からすると,「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」とは,「攪拌羽根」の回転軸から遠い部位である「先端部」が,回転軸に近い部位である「基端部」の前端縁よりも前(回転方向)に出ており,「先端部」の前端縁の延長線と処理容器内側面の接線との間の角度が90度よりも大きい構成を意味すると解するのが相当である。
(3)被告製品の充足性
被告製品の攪拌羽根の形状は,別紙参考図面2記載のとおりであるところ,その前端縁(回転方向の縁)は,回転軸付近から処理容器内側面にかけてほぼ真っ直ぐで,「先端部」が「基端部」の前端縁の延長線よりも前(回転方向)に出てはいない。そのため,上記のとおり解される「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」(構成要件D)を充足しているとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2012.12.12
平成22(ワ)12777 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年11月30日 東京地方裁判所
構成要件Nには,「複数の太さが620dtex以下,伸張応力が150%伸長時において4〜17gの腰下伸縮部材が,前記ウエスト伸縮部材の間隔より短い7mm以下の間隔を持って周方向に平行に,且つ,前記吸収コアの中央部では不連続に設けられ」との構成があり,このうちの「150%伸長時」について,まず検討する。
a 構成要件Nの「150%伸長時」の文言は,腰下伸縮部材の「伸張応力」に係る文言であり,甲4(本件第2特許公報)によれば,本件第2特許明細書の発明の詳細な説明には,構\成要件Dの構成と同一内容の記述(段落【0009】,【0010】参照)のほか,腰下伸縮部材の材質やその「伸張応力」に係る記述として,「また,これら腰下部伸縮部材21F,21Bとして使用する糸ゴムは,前述のウエスト伸縮部材20F,20Bとして使用する細い糸ゴムよりも伸張応力および断面外径が小さいか,あるいは実質的に同一のものとすることができる。ここにおいて使用する細い糸ゴムとしては,具体的には,伸張応力が,150%伸長時において4〜17gの範囲,特に5〜10gの範囲のものが好適に使用される。」(段落【0041】),「<伸縮部材について> 本発明の各伸縮部材としては,天然ゴムや合成ゴムなどの材質のほか,ウレタンなどの弾性伸縮性のものを用いることができる。また,細帯状の弾性伸縮性帯や,面積的に大きいシート状のものも使用できる。これらの例として,ウレタンなどの帯,フィルムまたはシートなどがある。フィルムとしては無孔フィルムや孔開きフィルム,さらにシートとしては前述のような網目状のシートなどを適宜選択できる。」(段落【0077】)との記載があることが認められる。しかしながら,本件第2特許明細書の発明の詳細な説明に,「%伸長時」の意味を定義する記載はない。
b ところで,「伸長」は,「長さや勢力などがのびること。また,のばすこと。」(広辞苑。乙2の2)を意味する言葉であり,「伸長時」は,伸びた時や伸ばした時を意味し,伸びに関する用語であるから,以下,繊維やゴムの伸びに係る用語についてみることとする。(a) 繊維やゴムに係る用語についてのJIS規格前記a認定の事実によれば,本件第2発明の各伸縮部材としては,天然ゴムや合成ゴムなどの材質のほか,ウレタンなどの弾性伸縮性のものが用いられるところ,繊維やゴムに係る用語についてのJIS規格は次のとおりである。繊維製品の試験に関する主な用語について規定する「繊維用語−試験部門」のJIS規格(JIS L 0208。乙44)は,「伸び率」を,「引き伸ばしたときの長さと元の長さとの差の,元の長さに対する百分率。伸度又は伸長率ともいう。」と定義している。ゴム工業において一般的に使用する用語について規定する「ゴム用語」のJIS規格(JIS K 6200。乙45)は,「伸び率」を,「試験片又は一様な断面をもつ部分の伸びで,元の長さに対する百分率。」と定義している。
・・・
(c) 前記(a)及び(b)認定の事実によれば,繊維やゴムについての伸びの度合いを表す用語としては,伸び率,伸度又は伸長率との語が一般的に用いられ,これらは,伸びの長さ(伸びたときの全体の長さと元の長さとの差)の元の長さに対する百分率を意味する,すなわち,自然長の時は0%と表\すものと認められる。c 次いで,おむつ等の吸収性物品に関する発明に係る特許公報における,弾性伸縮部材について用いられる「%伸長時」,「伸長率」の用法についてみる(なお,乙2の2によれば,「伸長時」と「伸張時」,「伸長率」と「伸張率」はそれぞれ同義であると認められるから,以下の(a),(b)では,それぞれ「伸長時」,「伸長率」と統一して表記する。)\n
(a) 「%伸長時」の用法について
甲26,乙18,25,28,29,43の特許公報では,「%伸長時」の語が用いられ,これらの公報で用いられている「%伸長時」の「%」は,伸びの長さの自然長に対する百分率であり,自然長の時には0%と表すものである。この用法は,上記b(c)に述べた伸び率,伸度又は伸長率の用法と同じである。
(b) 「伸長率」の用法について
i 乙16,18,27,28,29の特許公報では,「伸長率」の語が用いられ,これらの公報で用いられている「伸長率」は,伸びの長さの自然長に対する百分率であり,自然長の時には伸長率は0%と表すものである。この用法は,上記b(c)で述べた伸び率,伸度又は伸長率の用法と同じである。ii これらに対し,甲14,26,27,乙30,31,32,33,43の特許公報で用いられている「伸長率」は,伸ばしたときの全体の長さの自然長に対する百分率であり,自然長の時には伸長率は100%と表すものである。この用法は,上記b(c)に述べた伸び率,伸度又は伸長率の用法とは異なるが,上記の各特許公報において,伸長率の意味を定義する記載がある。
d 本件第2特許明細書の発明の詳細な説明には,構成要件Nの「150%伸長時」の「%伸長時」の意味を定義するような記載がなく,これを特定の意味で用いていることはうかがえないから,「%伸長時」との文言は,その有する通常の意味で用いているものと考えられる。そして,前記bで述べたところによれば,繊維やゴムの伸びの度合いについて,「伸び率」,「伸長率」又は「伸度」は,一般的に用いられ,伸びの長さの元の長さに対する百分率を意味するから,同じように伸びの度合いを表\す構成要件Nの「%伸長時」も,前記cの他の特許公報における通常の用法と同様に,伸びの長さの自然長に対する百分率を意味するものとして用いていると解するのが相当である。そうであれば,構\成要件Nの「150%伸長時」は,伸びの長さが自然長の150%になっている時,すなわち,自然長の2.5倍伸長時を意味するものである。
・・・
したがって,原告らの主張する事情があるとしても,当業者が「150%伸長時」を「自然長の1.5倍伸長時」を意味するものと理解するとは認められないから,原告らの上記主張は,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2012.11.27
平成23(ワ)8218 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年11月15日 大阪地方裁判所
乙1発明を本件特許発明と対比すると,1)乙1発明の「基板」は本件特許発明の「載置板」に,2)乙1発明の「金属ケース」は本件特許発明の「ケース層」に,3)乙1発明の「開口」部分は,本件特許発明の「接続挟持層」に,4)乙1発明の「基板」の底表面と「金属ケース」との間に存在する層は本件特許発明の「板底挟持層」に,5) 乙1発明の「接触子」は本件特許発明の「第1接続端子」に,6)乙1発明の外部電子機器に設けられた接続端子は本件特許発明の「第2接続端子」に,7) 乙1発明の基板の底表面に固定された「電子素子」は本件特許発明の「電子装置」に,それぞれ相当することが認められる。したがって,乙1発明は,USB規格に基づくものであるか否かが明らかではないものの,その他の点では本件特許発明と同一の構\成であると認めることができる(原告も明らかに争っていない。)。乙1文献には,プラグの規格に関する記載が見当たらないものの,USB規格を除くなど,限定的に解釈する理由は見当たらない。かえって,乙6によれば,本件優先日(平成16年11月1日)当時,USB規格は広く知られていたことが認められる。前記(1)図1,図2aのプラグの形状からしても,乙1文献に接した当業者は,乙1発明におけるプラグの規格として,USB規格も想起したことが明らかである。乙1文献のプラグの規格にUSB規格を採用することについて,何らかの阻害要因が存したことを窺わせる事情もない。そうすると,上記相違点に係る本件特許発明の構成(プラグがUSB規格によったものであること)は,実質的に乙1文献に記載されているものと同視することができる。したがって,本件特許発明は,乙1発明と同一であると認められる。\n2 争点6(訂正の再抗弁1)について 原告は,乙1発明に本件訂正発明の構成要件訂正I及び訂正Jが記載されていないから,本件訂正によって前記1の無効理由が解消される旨主張する。しかしながら,以下のとおり,乙1発明に本件訂正発明の構\成要件訂正I及び訂正Jが記載されていないとは認めることができない。結局,前記1で述べたところを総合すると,本件訂正発明も,乙1発明と同一であると認めることができる。
(1)本件訂正発明の構成要件訂正I
本件訂正発明の構成要件訂正Iは「前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け,」というものである。前記1(1)の乙1文献に記載された各図には,基板1のコネクタ11側の端部を支持する金属ケース3の開口部に設けた部材(図2bの左端下側の斜線で描かれた階段状部分)が図示されている。当該部材は,基板1の厚みを有する段を備え,基板1のコネクタ11側の端を幅全体にわたって支持するものである。そうすると,当該部材の上記構成自体からして,基板1を支持することで乙1発明の基板1の底表\面と金属ケース3とで画定される層(本件訂正発明の「板底挟持層」に相当)の変形を防止するものであることは明らかである。したがって,上記部材は,本件訂正発明の構成要件訂正Iの「支持装置」に相当するものであると認めることができるから,乙1文献には,本件訂正発明の構\成要件訂正Iが記載されているものというべきである。
(2)本件訂正発明の構成要件訂正J
本件訂正発明の構成要件訂正Jは,「該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特徴とする,」というものである。前記1(1)の乙1文献に記載された各図には,基板1のコネクタ11側の端部を支持する金属ケース3の開口部に設けた部材(図2bの左端下側の斜線で描かれた階段状部分)が図示されている。そして,当該部材の上記構成自体から,乙1発明の基板1の底表\面と金属ケース3とで画定される層(本件訂正発明の「板底挟持層」に相当)の外界との接続面のみに設けられた部材であることは明らかである。そうすると,上記部材は,本件訂正発明の構成要件訂正Jの「前端保護層」に相当する構\成であると認めることができるから,乙1文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Jが記載されているものというべきである。\n
2012.11.19
平成23(ワ)10341 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年11月08日 大阪地方裁判所
前記アのとおり,本件明細書には,主プレートと補助プレートのスライドに関する構成について,従来技術及び実施例のいずれにおいても,差込片をスリットへ挿入する方向(ないし差込片の突出方向)に向かって,直線的に互いに前後移動(スライド)する構\成のものしか開示されていない。このことからも,前記(1)のとおり,解釈すべきであると考える。
(4) 機能的クレームの解釈
仮に,上記原告の主張を前提としても,本件各特許発明の「スライド可能に係合」ないし「分離不能\に保持」という記載は,機能的,抽象的なものであるから,当該機能\ないし作用効果を果たしうる構成であれば,全てその技術的範囲に含まれるとすると,明細書に開示されていない技術思想(課題解決原理)に属する構\成までもが,本件各特許発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。したがって,上記のような,いわゆる機能的クレームについては,【特許請求の範囲】や【発明の詳細な説明】の記載に開示された具体的な構\成に示されている技術思想(課題解決原理)に基づいて,技術的範囲を確定すべきものと解される。また,明細書に開示された内容から,当業者が容易に実施しうる構成であれば,その技術的範囲に属するものといえるが,実施することができないものであれば,技術思想(課題解決原理)を異にするものして,その技術的範囲には属さないものというべきである。そこで検討すると,以下のとおり,被告各製品の構\成については,当業者が,技術常識等を参酌することにより,本件明細書の記載に基づき,容易に実施することができるものであったとは認めることができない。
ア 公知技術ではないこと原告は,2つの部材をピンによって枢結し,回動させる構成が公知技術である旨主張する。しかしながら,原告が公知技術として提出するのは,クレセントおよびそのクレセントを備えた戸(甲22),サイドガラスロック装置(甲23),スライド式ウィンドの開閉装置(甲24),自動車のスライド窓ロック装置(甲25),荷物掛けを有する扉の掛け金具(甲26),ライター(甲28),鼻輪(甲29),折畳み式携帯電話機(甲30の1),無線機(甲30の2),脱落防止付きバッジ(甲31)であり,本件各特許発明とは,明らかに技術分野を異にするものである。
イ 当業者が容易に実施することができるものではないこと等
原告は,当業者が,複数の部材を「スライド可能に係合」する手段として,複数の部材を1点でピンないしヒンジ等で係合する構\成を採用することに格別の困難はない旨主張する。しかしながら,被告各製品の構成では,補助部材が円弧方向にスライドする場合,突起部も円弧方向に移動するから,突起部は,スリットの周りの壁にぶつかるか,スリット内に挿入できたとしても,すぐにスリットの内壁にぶつかり,スリットに挿入することができない。そこで,被告各製品では,ピンと突起部との距離を離した上,突起部の外側縁部を円弧状とすることで,突起部をスリット内に挿入するようにしている。以下,ピンと突起部の距離が短い場合と長い場合及び突起部の外側縁部が円弧状でない場合の図を示す(赤点線は,突起部のスライドする軌跡である。)。上記のとおり,被告各製品の構\成(主プレートと補助部材とを,ピンによって一端を枢結し,回動自在に結合する構成)では,突起部とピンとの距離を離したり,突起部の形状を工夫したりしなければ,主プレートと補助部材とをスライド可能\にすることはできないものである。被告各製品の構成を採用した場合に生じる上記課題は,本件各特許発明には存在しないものであるところ,上記課題が自明ないし公知のものであるとはいえないし,その解決手段として,上記被告各製品の構\成を当業者が容易に採用しうるものであるとする主張立証はない。これらのことからすれば,被告各製品の構成は,当業者が,技術常識ないし公知技術等を参酌することにより,本件明細書に基づいて容易に実施突起部とピンとの距離が長い場合 突起部とピンとの距離が短い場合突起部の外側縁部が円弧状でない場合することができるものであるとは認めることができない。また,前記(3)で検討したところからすると,本件各特許発明が開示する技術思想(課題解決原理)は,一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し,他方のプレートにピンを固定し,当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められることにより「スライド可能\に係合」し,かつ「分離不能に保持」するものである。そうすると,上記被告各製品の構\成は,「スライド可能に係合」及び「分離不能\に保持」という機能を実現するため,本件明細書等で開示された技術思想とは原理的に異なる構\成を採用したものというべきである。結局のところ,被告各製品の構成と本件各特許発明とは,「スライド可能\に係合」及び「分離不能に保持」という構\成の点において,異なる技術思想(課題解決原理)によるものであると解される。
2 争点1−3(構成要件Dの充足性)について
前提事実(3)のとおり,本件特許発明1の構成要件Dは,「補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出方向(判決注:構\成要件Dでは「突出設方向」)に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片と重なり,逆向きにスライドさせたときに,差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え,」というものである。これによれば,1) スライド板は,差込片の突出方向にスライドすること及び2) 逆向きにスライドすることも可能なものであることが認められる。また,「方向に沿ってスライド可能\」というのは,上記1)及び2)の相反する方向への移動(スライド)が可能であることを表\現したものと解される。前記1と同様に,「突出方向にスライド」というのも,「突出方向」ないし「方向」という単語の意義からすれば,移動(スライド)の態様は,差込片の形状に沿った方向にスライドすることを指すと解される。前記1で述べたとおり,被告各製品の主プレートと補助部材のスライド方向は,差込片の形状に沿ったものとは言い難い。したがって,被告各製品は,構成要件Dを充足するとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 機能クレーム
2012.11.16
平成23(ワ)10341 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年11月08日 大阪地方裁判所
判決文が42ページで止まっていますので、そこまでで抽出しました。
前提事実(3)のとおり,本件特許発明1の構成要件Bは,「主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能\に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,」というものである。「挿入」とは,一般に,「さし入れること,さしこむこと」を意味し,「沿う」とは,一般に,「線状的なもの,または線状的に移動するものに,近い距離を保って離れずにいること」を意味する。そうすると,上記各構\成要件のうち「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能」とは,「スリットへさし入れる方向に,互いにスライドすることが可能\」であることをいうものと解される。また,「挿入方向」,すなわち「さし入れる方向」ないし「方向」という単語の意義からすれば,移動(スライド)の態様は,パソコン等の本体ケーシングに開設されたスリットに挿入される差込片(主プレートを構\成するベース板の先端に突設されたもの:構成要件C)の形状に沿った方向(差込片の形状が直線であれば,その直線に沿った方向となり,差込片の形状が曲線であれば,その曲線に沿った方向となる。)を指すと解される。
・・・
(2) 原告の主張について
原告は,本件各特許発明の構成要件のうち,主プレートと補助プレートをスライドさせる構\成について,公知技術等,当業者が適宜採用しうるあらゆる構成が含まれるとした上,被告各製品の構\成(主プレートと補助部材とを,ピンによって一端を枢結し,回動自在に結合する構成)もこれに含まれる旨主張する。確かに,主プレートの差込片と補助部材の突起部が重なり合う状態で,差込片,突起部及びその周辺のプレートだけを見ると,主プレートと補助部材は,差込片が差し込まれる方向(差込片の形状に沿った方向)に相対的にスライドしているということも可能\である。そこで,本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載に加え,本件特許発明1に係る特許請求の範囲の記載が,機能的構\成をもって記載されていることを踏まえながら,検討する。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2012.11.10
平成23(ワ)24355 特許権 民事訴訟 平成24年10月30日 東京地方裁判所
本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)の記載中には,「前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部」との記載があり,「発光部」が発光する「光」は,「受光手段に投光するための光」であると規定しているが,この「光」を特定の領域の波長に限定したり,可視光に限定する旨の文言は存在しない。加えて,甲18(岩波理化学辞典(第5版))に,「光」は,「可視光線に限定することもあるが,ふつうは紫外線,赤外線をあわせ波長が約1nm〜1mmの範囲にある電磁波を光とよぶ。」との記載があること,本件訂正明細書(甲24)の「発明の詳細な説明」中には,本件訂正後の請求項1の「光」の用語を定義する記載や,この用語を普通の意味とは異なる特定の意味で使用することを説明した記載がないことに照らすならば,本件訂正後の請求項1の「光」は,その文理上,可視光に限定されるものではなく,赤外線を含むものと解される。
b 次に,本件訂正後の請求項1の文言,前記(イ)の本件訂正明細書の「発明な詳細の説明」の記載事項及び各図面を総合すれば,本件訂正明細書には,i)従来,キャリッジに複数のインクタンクを搭載して使用する記憶装置としてのプリンタにおいては,インクタンクの誤装着を防止するために搭載位置を特定する構成として,インク色に対応するインクタンクの搭載位置を定めた上,搭載部とインクタンクが係合する相互の形状を搭載位置ごとに異ならせ,他のインク色のインクタンクが装着できないようにする構\\成や,インクタンクの電気接点とキャリッジ等の搭載位置における本体側の電気接点とが接続して形成される回路の信号線を,搭載位置ごとに個別のものとし,この個別の信号線を用いてインクタンクからインク色情報を読み出し,インクタンクが正しい位置に装着されているか否かを検出する構成が提案されていたが,これらの構\\成では,インク色ごとに異なる形状のインクタンクを製造したり,信号線の配線数を増す必要があり,コスト増の要因となるなどの課題があったこと,ii)一方で,信号線の配線数を削減するための配線方式としては,複数のインクタンクと記録装置との間に共通の信号配線を用いる共通バス接続方式が有効であるが,共通バス接続方式を採用した場合,全てのインクタンクからの信号が共通の信号配線で送信されてくるため,インクタンクからの信号を受信しただけでは当該インクタンクがキャリッジ内に装着されていることを検出することはできても,その搭載位置を特定することができず,それが正しい搭載位置に装着されているか否かを検出できないという課題があったこと,iii)本件訂正発明1は,共通バス接続方式を採用しながらも,各インクタンクがインク色に応じてキャリッジの所定の位置に正しく装着されているか否かを検出することを目的とし,上記課題を解決するための手段として,キャリッジに搭載された複数のインクタンクにそれぞれのインク色情報を保持可能な情報部と,本体側の記憶装置に設けられた受光部に投光するための光を発光する発光部と,その発光を制御する制御部とを設け,インクタンクが受光部に対向する位置で発光する場合には受光部が受光できるようにし,キャリッジを相対移動させることにより,所定の位置で各インクタンクと受光部とを対向させ,本来装着されるべき位置のインク色のインクタンクを順次発光させ,受光部が受光できたときは当該インク色のインクタンクが本来の正しい搭載位置に装着されていると判断し,受光部が受光できなかったときは受光部に対向する位置には誤ったインク色のインクタンクが装着されていると判断するという「光照合処理」(前記(イ)i)の方法を採用することにより,共通バス接続方式を採用しつつインクタンクの装着位置の誤りを検出するという作用効果を奏するようにした点に技術的意義があることが開示されているものと認められる。そして,上記「光照合処理」は,インクタンクの発光部が発する光が赤外線であっても行うことができること(甲3ないし12)からすると,本件訂正発明1の上記技術的意義に鑑みても,本件訂正発明1の「光」から赤外線を除外すべき理由はない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> 104条の3
2012.11. 8
平成23(ワ)6980 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年11月01日 大阪地方裁判所
構成要件A3は,「当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において」というものであるが,「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付具」との「接触」を「検出」する方法につき,「電気」や「電流」によって検出するとはせず,「電気的に」検出するとしている。一般に「的に」との用語を名詞の語尾に付けた場合,それそのものではないが,それと似た性質を持つものを含めた語感を持つことになるところ,「電気的に検出する」との表現は,「接触検出回路」が接触体,被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出する場合のみを指すのではなく,電気と似た性質を持つ媒体を介在させて検出した場合も含んだものと解するのが文言上自然である。イ 本件明細書の記載及び技術常識本件明細書においても,「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付具」との「接触」を「検出」する方法につき,接触体,被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出するものに限定する記載はない。むしろ,本件特許発明は,接触体に通電,非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う誤差発生防止を課題として掲げるものであることに照らせば,位置検出の過程で接触体への通電を利用する構成であれば足り,「接触検出回路」がその電流を直接検出しているか否かで技術的範囲の属否を左右させる合理的理由は見出しがたいというべきである。
ウ 被告の主張について
被告は,「電気的に検出する」の意味につき,接触体と被加工物との間に流れる電気を直接に検出する構成に限定されると主張するが,あえて「的に」という幅を持たせる文言が使用されていることと整合しない解釈といわざるを得ず,採用できない。
エ 小括
以上によると,構成要件A3の「電気的に検出する」とは,「接触検出回路」が接触体,被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出する場合のみを指すのではなく,電気と似た性質を持つ媒体を介在させて検出した場合も含んでおり,電磁気学の技術常識に照らし,少なくとも磁気を介在させて検出した場合を含むと解するのが相当である。そして,ハ号スタイラスを装着したロ号検出器の構\成ロa3は,「前記励起コイルをもって励起されている本体及び接触体と被加工物であるワークとの接触を,前記接触体,前記ワーク,及び機械主軸により閉ループ回路が形成されることにより,前記検出コイルに誘電電流が流れ,電気的に検出する位置検出器」であるが,接触体,被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流の電磁誘導によって検出コイルに誘導電流を流し,接触検出回路がこれを検出するというものである。そうすると,被加工物等との接触によって接触体などを流れた電流と接触検出回路が直接検出する電流との間には,磁気が介在することになるが,上記のとおり解釈したところの「電気的に検出する」構成といえる。したがって,ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は,「接触検出回路」が,接触体と被加工物等との接触を「電気的に検出する」ものであり,構\成要件A3を充足する。
(4) 構成要件A2の充足性
原告は,構成要件A2の「接続」につき,物理的に有線で接触している場合だけでなく,相互に情報を交信できるような状態をも含むと主張するのに対し,被告は,接触検出回路が接触体と直接電気的に接続されていることが必要とされている旨主張するので,この点を検討し,充足性を判断する。
ア 特許請求の範囲の記載
構成要件A2は,「当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,」というものであるが,「接続」の意味を明示的に表現する記載はない。しかし,特許請求の範囲の記載全体に照らして考えれば,「接触体」と「接触検出回路」の「接続」は,「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付軸」との「接触」を「電気的に検出する」ことを可能\とするために必要とされる構成であることが読み取れる。そうすると,「接触体」と「接触検出回路」との「接続」は,上記「接触」を「電気的に検出する」ことが可能\な構成であることを求めているとはいえるものの,接触検出回路が接触体と直接電気的に接続されている,つまり,接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れるような構\成であることまでは求めていないと解される。
イ 本件明細書の記載
本件明細書において,「接続」の意味や射程を説明する記載は特にない。しかし,本件特許発明は,接触体に通電,非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う誤差発生防止を課題として掲げるものであることに照らせば,「位置検出回路」が「接触体」と「被加工物」等との「接触」という情報を,「接触体」への通電を利用して「検出」できるものであることが必須であるところ,「接触体」と「接触検出回路」との「接続」も,かかる情報伝達が可能な構\成を求める趣旨であると解して矛盾はない一方,接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れるような構成に限定する合理的理由は見出しがたい。
ウ 被告の主張について
被告は,「接続」につき,接触検出回路が接触体と直接,電気的に接続されていることが必要とされている旨主張するが,その主な根拠としては,この「接続」が,構成要件A3の「電気的に検出する」の前提となる構\成であることを挙げる。この点,「接続」が「電気的に検出する」の前提として必要とされる構成であることは被告の指摘のとおりである。しかし,「電気的に検出する」の解釈につき,被告の主張が採用できないことは,前記(3)において論じたとおりであり,「電気的に検出する」を前記(3)のとおり解釈する以上,その前提となる「接続」についても,前記ア,イのとおり理解するのが一貫性のある解釈といえる。したがって,被告の主張は採用できない。
エ 小括
以上によると,「当該接触体に接続された接触検出回路」の「接続」は,「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物」等との「接触」という情報を,前記(3)で示した意味で「電気的に検出する」ことを可能とする情報伝達の構\成をとっていることを求めているものの,接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れるなど,物理的なつながりは求めていないと解するのが相当である。
・・・
(1) 特許法101条1号
証拠(甲2〜4)によれば,ハ号スタイラスは,これを備え付けても本件特許発明の技術的範囲に属することにはならない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有することが認められるから,本件特許発明の技術的範囲に属する製品の生産に「のみ」用いる物(特許法101条1号)であるとはいえない。この点,原告は,ハ号スタイラスを内部接点方式の位置検出器に用いることは,社会通念上経済的,商業的ないしは実用的であると認められる用途に当たらないため,「その物の生産にのみ用いる」との要件を否定する理由にはならない旨主張する。確かに,内部接点方式の位置検出器では接触体は通電されないため,その接触部の磁化による測定誤差発生という課題はなく,接触部を非磁性体とした接触体を使う必要性に欠ける。しかし,ハ号スタイラスは,超硬合金であることに由来し,被加工物等との接触を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が生じることを防止するという作用効果も有するのであるから,内部接点方式の位置検出器であっても,ハ号スタイラスを装着させる実用性は肯定されるというべきである。したがって,原告の主張は採用できない。
(2) 特許法101条2号
ア ハ号スタイラスは,本件特許発明の技術的範囲に属するハ号スタイラスを装着したイ号検出器及びハ号スタイラスを装着したロ号検出器の生産に用いるものである。加えて,本件特許発明は,その課題として,通電,非通電を繰り返すことで接触体が磁性化して誤差が発生することを防止するとともに,接触体が被加工物等との当接離隔を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が発生することを防止することを掲げ,その解決方法として,「接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されている」(構成要件B)との構\成を採るものである。そうすると,「接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる弱磁性として非磁性材であるHAN6で形成されている」(構成イb,ロb)ハ号スタイラスは,まさに本件特許発明の掲げる課題を解決する構\成を成しているといえる。したがって,ハ号スタイラスは,「物の発明」である本件特許につき,「その物の生産に用いる物」であり,かつ「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)といえる。イ そして,原告は,被告に対し,平成22年12月3日付の「催告書」と題する書面を送付し,被告はこれを遅くとも同月6日には受領したが,同書面には,本件特許の特許番号,登録日,本件特許発明の構成要件に加え,イ号検出器が本件特許権を侵害することなどが記載されていた(乙1,弁論の全趣旨)ところ,被告は同日以降,本件特許発明が「特許発明であること」及びハ号スタイラスが「その発明の実施に用いられること」を知っていた(特許法101条2号)といえる。ただし,同日より前の時点で,被告がそれら事実関係を知っていたと認めるに足りる証拠はない。
ウ 一方,被告は,ハ号スタイラスにつき,間接侵害(特許法101条2号)の除外要件である「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たる旨主張する。確かに,ハ号スタイラスの用途は,これを備え付けた場合に本件特許発明の技術的範囲に属することになるイ号検出器及びロ号検出器に限定されているわけではなく,本件特許発明の技術的範囲に属さない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有するものではある(甲2〜4)。しかし,結局のところその用途は,位置検出器にその接触体として装着することに限定されており,この点,ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。また,そのような用途の限定があるため,実際にハ号スタイラスを購入するのは,位置検出器を使用している者に限られると考えられる。このような事情を踏まえると,ハ号スタイラスは,市場で一般に入手可能な製品であるという意味では,「一般に流通している」物とはいえようが,「広く」流通しているとは言い難い。また,そもそもこのような除外要件が設けられている趣旨は,「広く一般に流通しているもの」の生産,譲渡等を間接侵害に当たるとすることが一般における取引の安全を害するためと解されるが,上記のように用途及び需要者が限定されるハ号スタイラスにつき,取引の安全を理由間接侵害の対象から除外する必要性にも欠けるといえる。したがって,ハ号スタイラスは「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらず,この点に関する被告の主張は採用できない。
(3) 小括
以上によると,被告によるハ号スタイラスの製造,販売は,本件特許発明との関係において,平成22年12月6日以降,特許法101条2号の規定する間接侵害の要件を満たすものといえる。
・・・
そこで次に,乙12発明の接触体の接触部について,「非磁性部材」の具体的材質の選択に当たり,乙14文献及び乙24文献の開示する技術的事項を適用して本件特許発明を想到することが容易であったかを検討する。まず本件特許発明の掲げる課題は,通電,非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う測定誤差発生の防止と,接触体と被加工物等との繰り返しの接触による接触体の摩耗や変形に伴う測定誤差発生の防止とであるが,前者は接触体の接触部を非磁性部材とすることで解決される課題であるから,乙12発明で未解決なのは後者の課題のみである。そして,乙12文献内に明示こそされていないものの,通電方式の位置検出器の接触体の接触部は,金属製の被加工物等と繰り返し接触することが当然に想定されていること,被告において,平成元年の時点で既に接触部を超硬合金とする接触体を製造,販売し,現在まで継続していること(甲2〜4,乙19〜23)からすると,接触体の摩耗や変形に伴う測定誤差という課題は,本件特許出願(平成11年4月7日)の時点で,当業者にとって周知の課題であったといえるし,また,その解決手法として,接触体の接触部を超硬合金とすることも周知技術であったといえる。一方,タングステンカーバイトにニッケルを結合材として焼結することで非磁性体の超硬合金が得られるとの技術的事項は,昭和45年には既に文献公知となり(乙24),平成2年頒布の「改訂5版金属便覧」と題する文献にも記載され(乙14),本件特許出願(平成11年4月7日)前に技術常識であったと認められることに加え,本件特許発明と用途や課題が異なるとはいえ,同一の技術分野において本件特許出願前に頒布された文献(乙17,18)中でも,同部材が利用されていた。そうすると,乙12発明の開示する「非磁性部材」の具体的材質を選択するに際し,上記周知課題及び周知技術の下で,「タングステンカーバイトにニッケルを結合材として焼結した非磁性の超硬合金」を選択することは,単に公知材料からの最適材料の選択に過ぎず,当業者の通常の創作能力の発揮であり,当業者が容易に想到することができたものといえる。したがって,乙12発明に,乙14文献及び乙24文献の開示する技術的事項を組み合わせて本件特許発明に想到することは容易であったといえる。
(5) 原告の主張について
この点,原告は,通電,非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う測定誤差発生の防止という本件特許発明の掲げる課題が,乙12文献ほか,本件特許出願前のどの文献にも開示されておらず,本件特許発明に至る動機付けに欠ける旨主張する。しかし,この課題は,乙12文献の開示する乙12発明の構成,つまり,「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことで既に解決されているのであるから,当該課題にかかる動機付けがなければ本件特許発明の構\成に至ることができないなどというものではない。言い換えれば,通電方式の位置検出器において,「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成は,主引例である乙12文献に開示されているのであるから,かかる構\成へ至るための課題の開示,動機付けの有無を問題とする必要はないといえる。また,「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成の具体的な材料選択をする前提として,そのような上位概念で表\現された構成を維持することへの動機付けが求められると解したとしても,あくまで既に公知となっている構\成を維持するだけの動機付けがあるか否かの問題であり,新規の構成へ至る動機付けがあったかが問われるわけではない。通電方式の位置検出器において,「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことでその磁性化を防止できることは,乙12文献でその構\成に触れた当業者にとって明らかであるが,通電方式の位置検出器における測定対象は通電性のある物質であること,乙12文献中の上記構成は強磁性の環境下における位置検出器で採用されたものであることからして,接触体の接触部の磁性化を避けることができれば,切削加工等で生じた切粉の付着など磁性化に伴う不都合を回避する効果が得られることも,乙12文献に触れた当業者が予\測し得る範囲内にある。そのため,「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成を採る技術的意義は,その構\成自体が示唆するものといえ,これを維持するだけの動機付けがあるといえる。なお,同様の理由により,当業者の予測し得ない顕著な作用効果や用途を見出したともいえず,かかる観点から本件特許発明の進歩性を肯定することも困難である。したがって,課題の示唆がないことを理由として本件特許発明の容易想到性を否定する原告の主張は採用できない。
(6) 小括
以上によると,本件特許は,進歩性欠如の無効理由を有しており,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,原告は,被告に対し,本件特許権に基づく権利を行使することはできない(特許法104条の3)。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
2012.11. 6
平成23(ネ)10081 不当利得金返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成24年10月30日 知的財産高等裁判所
本件特許発明は,本件明細書に,『・・・MAUとMAUを接続したり,あるいは,DTEとDTEを接続する場合には,送信線を受信側に,受信線を送信側に付け替えたクロス接続のツイストペア線を使用して配線しなければならない。このため,使用するLAN機器の内容を熟知していないユーザーでは送信線と受信線の誤接続を行う可能性がある。』(段落【0002】),『本発明は上述のような点に鑑みてなされたものであり,その目的とするところは,送信線と受信線の接続が間違っている場合には自動的に信号線を切り替えることが可能\な送受信線切替器を提供することにある。』(段落【0003】)と記載されているとおり,LAN機器の種類や通信線の種別に熟知しない者が,誤接続を行ってしまうという従来技術の課題を解決し,接続される通信機器の種別や信号線の種別に関係なく常に正常な信号伝送が可能となるように,信号線の接続を行うことができるようにすることを目的としたものである。そして,本件特許発明は,上記のとおり,上記課題の解決手段として,リンクテストパルス検出手段の検出結果から切替器に接続されている信号線のいずれが送信線で,いずれが受信線かを判断した後に,物理的な配線である信号線を切り替えるものである。これに対し,被告製品は,MDI/MDI−X自動切替機能\により,ネットワーク機器との接続において,ストレート/クロスケーブルを自動判別するため,結線ミスによる配線トラブルを回避することができるものである。そして,被告製品は,上記のとおり,上記課題の解決手段として,MDIモード(ストレート結線)とMDI−Xモード(クロス結線)とをランダムな時間間隔で繰り返し遷移させた上,リンクテストパルスが検出された時点で,この遷移を停止させる構成としたものである。以上のとおり,被告製品は,リンクテストパルスを検出した時点で,必ず,ストレート結線とクロス結線の遷移を停止させるものであって,本件特許発明のように,リンクテストパルス検出後,信号線を物理的に切り替えることは,その構\成上予定されておらず,本件特許発明とは課題解決原理が異なる。したがって,本件特許発明における,リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して,信号線を切り替える,信号線切替制御部との構\成を,被告製品の自動MDI/MDI−X構成に置き換えることには,置換可能\性はないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
2012.11. 3
平成23(ワ)11492 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年10月25日 大阪地方裁判所
原告の主張するとおり,被告製品のマニュアル(甲8)には,前記第3の1【原告の主張】(1)の構成fの内容が記載されていることは認められる。この記載によれば,被告製品がパラメータ(特性データ)の補正のための手段を有していることは窺えるものの,実測値のデータベースに基づいて特性データを修正する構\成を有することを窺わせるものとまではいえない。
イ 実験1ないし3に基づく原告の主張
原告は,被告製品を用いて次の実験を行い,その結果をもとに,被告製品が,実測値のデータベースに基づいてナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段を具備していると述べる(原告第4準備書面)。 その実験内容をみると,次のとおりである。(ア) 原告は,特定の金属を曲げ加工するに当たり,4種類の曲げ加工形状(60°,57!5°,45°,30°の4種類の角度で1回だけ曲げ加工したもの)を入力し,「角度曲げ角調整」のパラメータ(初期設定値)を表示させた上,その後,曲げ加工を実施し,その実測値と照合したところ,誤差が生じたことを確認した(甲43の1〜5:実験1)。(イ) その上で,ある特定の角度(実験では30°)に対応するパラメータの値を減少させて入力したり,増加させて入力したりした際,他の角度についての対応するパラメータが変更されていることを確認した(甲44,甲45の1:実験2)。 (ウ) さらに,変更された前記パラメータに基づき,実際に曲げ加工を行った(甲45の2〜5:実験3)。
ウ 実験1ないし3についての検討
(ア) 実験1について誤差が生じること自体は争いがなく,本件特許発明の課題の前提となる事象である。
(イ) また,実験2において,「角度曲げ角調整」のパラメータを変更しているが,これによれば,被告製品においては,所望の角度に応じた特性データを修正する(実測値と置き換える)ことができること,補正した以外の角度に対応する特性データも自動演算により修正されることが認められる。 しかしながら,特性データを実測値に基づいて修正する(又は実測値と置き換える)ことができる構成を有するとしても,そのことから実測値のデータベースが存在するなどとはいえないし,補正した以外の角度に対する特性データについて自動演算がされるとしても,これも実測値のデータベースの有無とは無関係の構\成である。
(ウ) 実験3については,実験2で得られた「角度曲げ角調整」のパラメータに基づき,曲げ加工を行ったというだけのことであり,その結果をもって,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを何ら裏付けるものではない。
エ 実験4について
また,原告は,実験1ないし3の追加実験(実験4)を行い,その結果をもとに,被告製品は,誤差の実測に基づき修正された特性データを記録し,それを呼び出すことができるデータベースを有する構造であると主張する。具体的には,「角度曲げ角調整」のパラメータの初期設定値が修正され,かつ,修正された結果が記憶されていると述べる(原告第4準備書面)。その実験内容は,実験1ないし3の後,被告製品に,実験1ないし3に用いた曲げ加工形状のデータとは別のファイルであるが,全く同じ形状を入力した結果,表\示される「角度曲げ角調整」のパラメータが,実験2の最終段階で表示されたパラメータと同じであったことを確認したというものである(弁論の全趣旨:実験4)。しかしながら,このことから,被告製品において,「角度曲げ角調整」のパラメータ(特性データ)が変更された場合に,その変更結果が記憶されるということはいえても,追加実験(実験4)において曲げ加工データを算出するに当たり,「実測値のデータベース」に基づいて「角度曲げ角調整」のパラメータ(特性データ)が修正されたものであるとはいえない。したがって,実験4の結果をもとに,被告製品が,実測値のデータベースに基づいて何らかのデータを修正する手段を有しているということはできない。
オ 実験5について
原告は,円弧曲げ調整のパラメータについても同様の実験(甲48の1〜6,甲49の1〜6:実験5)を行い,前記実験1ないし4と同様の主張をしている。 しかしながら,前記アないしウと同様,上記実験においても,被告製品について,「実際に加工した結果と曲げ加工データとの誤差」等である「実測値」を「データベースとして」記憶する構成が確認されたわけではなく,上記データベースに基づいて何らかのデータを修正しているともいえない。
カ まとめ
結局,原告の行った実験1ないし5によって認められる被告製品の構成は,構\成要件Fを充足するとはいえない。前記1の【図6】の記載(従来技術の構成)によれば,「(現物合せ)」との記載から「CADデータ」との記載に向かって矢印が引かれ,「現物打合せ結果のフィードバック」と付記されている。この記載によれば,従来技術においても,実際に加工した結果に基づいて曲げ加工データが修正されるものとされていることが窺われる。仮に,原告が,実測値に基づいて特性データを修正すること(又は実測値と置き換えること)をもって,構\成要件Fの「実測値のデータベースに基づいて」「特性データを修正する」を充足するというのであれば,文言から逸脱した解釈というべきであるし,上述した従来技術等からすれば,自明の構成,少なくとも当業者において極めて容易に想到することができる構\成をもって,構成要件Fに該当するというに等しいものである。
(3)構成要件Gの非充足
・・・のとおり,被告製品は,実測値のデータベースやその記憶部を有しているとはいえず(構成要件Eの非充足),上記実測値のデータベースに基づいてデータを修正する手段を有しているともいえない(構\成要件Fの非充足)。したがって,被告製品は,修正された(特性)データに基づいて曲げ加工データを算出するとはいえず,構成要件Gを充足することもない。
2012.10.26
平成23(ワ)10712 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年10月18日 大阪地方裁判所
前記(ア)の出願経過によれば,原告は,審査官から「前記制御手段は,前記ID番号が前記電話帳メモリに登録されている番号の一つと一致したら着信音を発生させる一方,一致しなければ所定時間だけ着信音を発生させず,その後所定時間経過したら着信音を発生させること」という構成が新規事項に当たるとして拒絶理由通知を受けたことから,この構\\成を含まないものとして手続補正をし,これにより特許査定を受けたものというほかない。前記アの原告の主張は,本件特許発明2−3の構成要件Jの意義について,上記拒絶理由通知を受けた構\\成と同一であるというものにほかならないから,上記出願経過に照らせば,包袋禁反言の法理により許されないものというべきである。
エ 小括
これらのことからすると,本件特許発明2−3の構成要件Jの「着信情報」とは, i)通信端末装置が圏外や電源がオフの場合に,ii) 通信ネットワーク側の交換制御装置に記憶されるものであり,iii) 少なくとも発呼側のID情報及び呼出継続時間情報を含むものをいうと解するほかない。
(2)被告製品の構成
被告製品について,i) 通信端末装置が圏外や電源がオフの場合に,ii) 通信ネットワーク側の交換制御装置に記憶されるものであり,iii) 少なくとも発呼側のID情報及び呼出継続時間情報を含むものとしての「着信情報」を受信する構成を有する旨の主張立証はない。この場合に,リンガーの発生を制御する構\\成を有する旨の主張立証もない。したがって,被告製品について,本件特許発明2−3の構成要件Jを充足するとは認めることができない。
2 争点3−1(先願発明の有無)について
以下のとおり,本件特許発明1は,乙14発明と同一であると認められる。(1)乙14公報に関する出願明細書には,以下の記載がある。
・・・
乙14発明の各構成は前記(2)のとおりであるが,同発明と本件特許発明1−1ないし1−3を対比すると,1Fを除いた乙14発明の構成が本件特許発明1−1ないし1−3の各構\\成要件と同一であることについて,原告は,これを明らかには争っていない。原告は,前記第3の5【原告の主張】のとおり,発呼側端末のID番号が格納されているのは,本件特許発明1−1では構成要件Fの「電話帳メモリ」であるのに対し,乙14発明では「電話帳及び/又は発信履歴」である点において相違する旨主張する。一般に,「及び」は,名詞相互をつなぎ,それらの指すものに一括して言及する場合に使われる接続詞であるのに対し,「又は」は,i) 複数のうち少なくとも一つが成り立つこと,ii) 複数のうちどれか一つだけが成り立つことをいう場合に使われる接続詞である。そうすると,乙14発明の「電話帳及び/又は発信履歴」という文言からすれば,電話帳と発信履歴のいずれか一つだけの場合も含まれることが認められ,これと異なる解釈をとるべき理由は見当たらない。そうすると,乙14発明の構成には,「電話帳」のみに発呼側端末のID番号が格納されているものとする構\\成も含まれるから,この点において,本件特許発明1−1と相違するとはいえない。よって,本件特許発明1−1ないし1−3は,乙14発明と同一であると認めることができる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 104条の3
2012.10.25
平成23(ワ)3850 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年10月11日 大阪地方裁判所
前記(ア)によれば,構成要件Bは,個々の容器をケース(段ボール箱等)に収容して内容物を充填して搬送したりする時に,ケース内壁と擦れたり,取扱いに際して他物と衝突したりしたときに,その箇所に孔(ピンホール)が開いてしまうことを解決するための構\成であることが認められる。その具体的な解決原理は,ケース内壁と接触する状態が発生したときに,補強リブがケース内壁と先に接触し,突条の頂部とケース内壁とが直接接触するのを避けることにある。そうすると,構成要件Bの「被覆する」とは,充填拡張時において,i) 補強リブが突条の側に傾斜する構成のものであること並びにii) 補強リブの長さ及び高さは,ケース内壁と接触する状態が発生したときに,補強リブがケース内壁と先に接触するものであり,突条の頂部とケース内壁とが直接接触するのを避けることをいうものと解される。(ウ) 被告は,本件明細書に記載された実施例では補強リブの先端が突条の頂部を超えてその反対側に到達しているから,構成要件Bは,「補強リブがケース内壁等からの外力が加えられていない状態で,先端が突条の頂部を超えてその反対側に到達していること」をいう旨主張する。しかしながら,本件の【特許請求の範囲】について,実施例に記載された構\成に限定する理由は見当たらず,上記被告の主張はそもそも失当である。また,前記(イ)で検討したところから明らかなとおり,構成要件Bは,充填拡張時において,ケース内壁と接触する状態が発生したとき,すなわち補強リブがケース内壁等からの外力を加えられた状態において,技術的意義を有する構\成である。したがって,ケース内壁等からの外力が加えられていない状態における構成を特定する意味はなく,上記被告の主張は,構\成要件Bの技術的意義を無視するものであることからしても,採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2012.10.15
平成24(ネ)10035 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成24年09月26日 知的財産高等裁判所
イ 第2要件
前記のとおり,本件発明1は,従来方法では,各視線上に位置するボクセル毎の色度及び不透明度を互いに積算する演算過程の高速化を図るために,一部のボクセルに関するデータを間引いて演算を行っていたため,可視化した画像において,生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現することができなかったことに鑑みて発明されたものである。本件発明1は,二次元平面上の各平面座標点と視点とを結ぶ各視線上に位置する「全ての前記平面座標点毎の色度および不透明度を該視線毎に互いに積算する」ことにより,放射線医療診断システムにより断層撮影して得られた画像データ値に基づき,生体組織間の微妙な色感や不透明感を表\現しつつ,相異なる生体組織を明確に区別することが可能な可視画像を生成し得る医療用可視画像の生成方法を提供することを目的とするものである。これに対し,被告方法においては,被告数式1の積算処理は,被告数式2で設定された閾値に達した時点で打ち切られるため,生体組織間の微妙な色感や不透明感を表\現する観点からは,画質に対して悪い影響を与えるものである。被告方法による可視画像の生成は,本件発明1の方法によるほど生体組織を明確に区別するという作用効果を奏するものとはいえないものと解される。したがって,被告方法は,本件発明1の目的を達し,同一の作用効果を奏するとまではいえないものであるから,均等の第2要件を欠くものである。
ウ 第5要件
(ア) 前記(1)のとおり,本件明細書によれば,従来技術は一部のボクセルに関するデータを「間引いて」演算を行っていたため,可視化した画像において,生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現することができなかったことから,上記課題を解決する手段として,本件発明1は,「全ての」前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し,当該積算値を当該各視線上の前記平面座標点に反映させることを特徴とするものである(【0006】〜【0008】)。仮に控訴人が主張するように,従来技術に係る「間引いて」の反対語が「間引かずに」ということであれば,出願人において特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することが容易にできたにもかかわらず,本件発明1の特許請求の範囲には,あえてこれを「全て」と記載したものである。このように,明細書に他の構\成の候補が開示され,出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず,あえて特許請求の範囲に特定の構\成のみを記載した場合には,当該他の構成に均等論を適用することは,均等論の第5要件を欠くこととなり,許されないと解するべきである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第5要件(禁反言)
2012.10. 8
平成23(ワ)7576等 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年09月27日 大阪地方裁判所
「物の生産」の通常の語義等も併せ考慮すれば,「物の生産」とは,特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し,具体的には,「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構\成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいうものと解すべきである。一方,「物の生産」というために,加工,修理,組立て等の行為態様に限定はないものの,供給を受けた物を素材として,これに何らかの手を加えることが必要であり,素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は「物の生産」に含まれないものと解される。前提事実のとおり,本件各特許発明の【特許請求の範囲】は,いずれも「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と,本件併用医薬品とを「組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。」というものである。したがって,本件各特許発明は,当該医薬品に関する発明,すなわち「物の発明」であると認めることができ,このこと自体は当事者間でも争いがない。なお,「組み合せる。」とは,一般に,「2つ以上のものを取り合わせてひとまとまりにする。」ことをいい,「なる」とは,「無かったものが新たに形ができて現れる。」「別の物・状態にかわる。」ことをいうものと解される。したがって,「組み合わせてなる」「医薬」とは,一般に,「2つ以上の有効成分を取り合わせて,ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解釈することができる。・・・,法101条2号の「物の生産」は,「発明の構\成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいう。すなわち,加工,修理,組立て等の行為態様に限定はないものの,供給を受けた物を素材として,これに何らかの手を加えることが必要であって,素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれない。被告ら各製品が,それ自体として完成された医薬品であり,これに何らかの手が加えられることは全く予\定されておらず,他の医薬品と併用されるか否かはともかく,糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬としての用途に従って,そのまま使用(処方,服用)されるものであることについては,当事者間で争いがない。したがって,被告ら各製品を用いて,「物の生産」がされることはない。換言すれば,被告ら各製品は,単に「使用」(処方,服用)されるものにすぎず,「物の生産に用いられるもの」には当たらない。\n
2012.10. 8
平成23(ワ)7887 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年09月27日 大阪地方裁判所
構成要件Dは,「少なくとも前記側壁部に柔軟性を持たせて,側壁部を折り畳み可能\とし」というものである。本件明細書の発明を実施するための最良の形態の欄には,側壁部について,「底部2,側壁部3および飲料の出し入れ口となる筒口部4の設けられた頂部5が,熱可塑性樹脂であるポリエチレン樹脂で一体に形成され」(【0011】),「前記底部2と側壁部3は柔軟性を持たせるために薄肉に形成され」(【0012】),「上述した実施形態では,カートリッジ容器の側壁部と底部を薄肉に形成したが,側壁部のみを薄肉に形成してもよい」(【0019】)といった記載はあるものの,特許請求の範囲の欄に,柔軟性の程度や柔軟性を実現する方法についての記載は存しない。そこで検討するに,本件明細書の記載及び前記1(4)で認定した補正の経緯によれば,全体に剛性のある従来の飲料ディスペンサ用カートリッジ容器は,使用後に再使用や廃棄のために運送するのに嵩張り,運送効率が悪いとされていたところ,原告は,まず,先行出願(特願2004−293288)により,少なくとも容器の側壁部に柔軟性を持たせ,側壁部を折り畳み可能とすることで前記課題を解決し得る旨を提案していたが,その後,容器の側壁部に柔軟性を持たせたために,飲料を充填する際に側壁部が直立せず,筒口部の位置も不安定になり,飲料の充填に非常に手間がかかるとの新たな課題,あるいはカートリッジ容器を下向きにして飲料ディスペンサに接続した際に,側壁部が下方に崩れるとの新たな課題が生じたため,筒口部を上向の状態で吊り下げ係止する係止部を設ける構\成要件E,筒口部を含む頂部を厚肉に形成する構成要件F,支持枠によって,筒口部の周りの頂部を支持する共に,側壁部が下方へ崩れないよう囲われるようにする構\成要件Gを加え,本件特許を取得したものと解される。そうすると,構成要件Dにおける側壁部の柔軟性は,運送効率が悪いとの剛性のある容器の課題を解決するものではあるものの,この点は前記先行出願と同じであり,むしろ,構\成要件E,F,Gで解決すべき課題の前提となる点に意義があると解されるから,ここにいう柔軟性は,飲料を充填する際に側壁部が直立せず,筒口部の位置が不安定となるような側壁部の柔軟性,あるいは,飲料ディスペンサに接続した際に,側壁部が下方に崩れるような柔軟性を意味するものと解さざるを得ないが,そのような柔軟性を実現する方法について格別の限定はなく,素材の強度,素材の厚み,形状,加工等のいずれの方法によってもよいと解される。
(2) 構成d及びその構\成要件充足性
イ号物件については,前記1(2)及び(3)で認定したとおり,側壁部に設けられた蛇腹を利用して,補助参加人がイ号物件を折り畳んで運搬すること,飲料充填の際に伸長すること,使用後は利用者がつぶして廃棄することが認められ,その意味における側壁の柔軟性はあり,折り畳むことも可能である。反面,前記1(3)のとおり,PETボトルの特徴は,缶やガラスに比べて軽量で,衝撃強度及び剛性に優れることであるとされ,証拠(乙3,4の1及び2)によれば,イ号物件の側壁部は,飲料を充填しない状態において直立していることが認められる。イ号物件に飲料を充填する際,折り畳まれた側壁は伸長されることになるが,これは,前記認定のとおり,運搬の便宜のために意図的に折り畳んだ結果であり,イ号物件の側壁に上記程度の剛性が認められることからすると,飲料を充填する際に,自然に圧縮されるなどして側壁部が直立せず,筒口部が不安定となるほど柔軟であるとは認められない。以上によると,イ号物件の構成dは,本件発明の構\成要件Dを充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2012.10. 8
平成23(ネ)10045 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成24年09月27日 知的財産高等裁判所
本件発明1の作用効果は,誤入力が生じやすい軸別の移動命令ではなく,駆動対象をロボットとする移動命令を用いて,複数のロボットを制御することにある(本件明細書1【0006】,【0010】)。したがって,本件発明1の「移動命令判別手段」の技術的意義は,駆動対象をロボットとする移動命令から,ロボットに対応するドライバーを選定するところにあると認められる。これに対し,イ号製品のMOVP命令は,前記認定(原判決第4の2(4))のとおり,「ポジションNO.によって指定されるポジションデータに従って,所定の軸をポイント・トゥ・ポイント(PTP)移動させよ」という命令であり,駆動対象となる軸が決定されれば,それに対応するドライバーは一義的に特定されるものであり,ドライバーを選定する必要がない。したがって,イ号製品は,構成要件1−Fを充足するとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
2012.09. 5
平成23(ワ)27941 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年08月31日 東京地方裁判所
上記記載によれば,本件発明は,従前のデータファイル等の一般的なファイルについて用いられていたファイル名や更新日などの情報の比較によるシンクロ方法には,シンクロが必要か否かの判定についての信頼性に課題があり,また,その処理が遅く非効率であったことから,特にメディアファイルについて,そのような課題を克服し,効率的でインテリジェントなシンクロを実現するために,上記のような一般的なファイルに備わるファイル情報ではなく,タイトル名,アーチスト名などの属性,あるいは,ビットレート,サンプルレート,総時間などの品質上の特徴という「メディア情報」に着目し,そのような「メディア情報」の比較に基づいて,メディアアイテムをシンクロする方法を採用した発明である,と認めることができる。
・・・・
原告は,本件発明の「メディア情報」には,当然に「ファイルサイズ」が含まれるから,被告方法は構成要件G1及びG2を充足すると主張する。しかし,前記(1)ウのとおり,本件発明における「メディア情報」は,音楽,映像,画像等のメディアアイテムに特有の情報を意味すると解すべきところ,証拠〈略〉によれば,楽曲ファイル,ワードファイル及びエクセルファイルにおいて,「ファイルサイズ」は,ファイル名や更新日時といった項目と同列に扱われている一方,楽曲ファイルにおいては,「ファイルサイズ」はアーチスト,アルバムのタイトル,トラック番号,ジャンル,タイトル,長さ,ビットレート,オーディオサンプルレートといった楽曲に特有の情報項目とは区別された項目として分類されていることが認められるから,「ファイルサイズ」は,ファイル名やファイル更新日と同様に,ワードファイルやエクセルファイルなどの通常のファイルに一般的に備わるものであって,音楽ファイル等のメディアアイテムに特有の情報とはいえないというべきである。したがって,「ファイルサイズ」は,本件発明における「メディア情報」に該当しないと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2012.05.22
平成23(ワ)8405 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年05月17日 大阪地方裁判所
上記各記載について検討すると,まず,上記(ア)の第1の実施形態に係るスライド側壁は,目地部側の側壁の端部を覆うことができるように断面コ字状に形成されたスライド側壁本体17と,このスライド側壁本体の両端部寄りの内壁面に取付けられた,側壁16の上面を移動するローラー18とで構成されているものである。これは,スライド側壁を目地部側の側壁と間隔を空けずに構\成したものであって,上記アのとおり,本件特許発明1の構成要件Dについて,通常の意味のとおり解釈した場合における,本件特許発明の技術的範囲に属する実施例を開示したものである。これに対し,上記(イ)の第6の実施形態に係るスライド側壁は,目地部側の側壁の内壁面に「位置させて前後方向にスライド移動可能に取付けた」ものとされている。しかしながら,上記図22ないし図24によっても,イ号製品のスライド側壁(手摺10a 及び10b)及び通路の目地部側の側壁(側壁9a 及び9b)とは異なり,スライド側壁と目地部側の側壁とが接触しているか否かが判然としない。目地プレート12と一体となったスライド側壁15が,渡り通路5の側壁16で囲まれた空間に嵌合しているものとみることが可能であり,その場合は,スライド側壁を側壁に取付けたということもできる。しかし,仮に,上記実施例についてスライド側壁と目地部側の側壁とが接触しない構\成を説明したものであると解釈する場合,何をもってスライド側壁15が側壁16に取付けられているといえるのか,本件明細書には具体的な説明はなく,この構成について本件特許発明1の技術的範囲に属する構\成として開示したと解することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2012.04.26
平成23(ワ)4131 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年04月12日 大阪地方裁判所
本件明細書【0004】及び【0010】の記載によれば,先行技術であるミッドロックには,コンテナの前方開口部にロック用留め具が係合して開口部をふさぐという欠点があること,先行技術である全自動デバイスには,可動ロック部材が特に汚れの影響をとても受けやすいという欠点があることが認められる。また,同【0005】の記載によれば,本件特許発明1は,上記各欠点(課題)の解決手段として,上下に載置したコンテナの連結片と配列,上下に載置したコンテナを連結させるための方法を創作したものであることが認められる。そして,同【0006】及び【0011】の記載によれば,上記解決手段の原理は,i) ロック用留め具が下側連結突起上にコンテナの長手方向視で横に配置されていること,ii) 連結片の形状のおかげで,上段コンテナが鉛直軸に対して旋回することにより,連結片の下側連結突起がロック用留め具によって下段コンテナのコーナーフィッティング内に係合するというものであることが認められる。そして,前記1(1)のとおり,上記ii)の「連結片の形状」は,構成要件Eの「導入面取り部」を意味するものと考えられる。そうすると,構\成要件Eの「導入面取り部」は,本件特許発明1の課題解決手段である上記ii)における基本的構成であり,特徴的原理を成すものであることが認められる。換言すれば,本件特許発明1において,全自動デバイスとして,上下のコンテナを連結する作用効果を奏させるには,構\成要件Eの「導入面取り部」によりロック用留め具をロック位置まで案内することが必要不可欠の構成であり,課題解決の原理そのものであるというべきである。これに対し,被告製品では,全自動デバイスとして,上下のコンテナを連結する作用効果を奏させるため,構\成要件Eの「導入面取り部」の構成によりロック用留め具を係合位置まで移動させる構\成ではなく,ロック用留め具そのものを可動突部とすることにより下段コンテナの溝穴と係合させる構成が採用されている。したがって,被告製品の課題解決手段は,本件特許発明1の解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものとはいえず,むしろ,異なる原理に属するものというべきである。
以上によれば,構成要件Eは,特許請求の範囲に記載された本件特許発明1の構\成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分であり,特許発明の本質的部分に当たる。このことは,前記1(1)エ(イ)のとおり,原告が,本件特許の出願手続において,「本件発明では構成要件AないしDが有機的に結合することにより,荷役者を介することなくコンテナの連結および分離ができ,全自動デバイスとして使うことができるという引用文献にはない顕著な効果を奏する」旨の意見書を提出していることからも明らかである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2012.04. 3
平成23(ネ)10002 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成24年03月22日 知的財産高等裁判所
被告は,被告製品について,i)平成15年9月ころから「サトウの切り餅パリッとスリット」との名称で販売し,切餅の上下面及び側面に切り込みが入り,ふっくら焼けることを積極的に宣伝・広告において強調していること,ii)平成17年ころから,切り込みを入れた包装餅が消費者にも広く知られるようになり,売上増加の一因となるようになったこと,iii)平成22年度からは包装餅のほぼ全部を切り込み入りとしたことが認められ,これらを総合すると,切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し,切り込みによりうまく焼けることが,消費者が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を選択することに結びつき,売上げの増加に相当程度寄与していると解される(甲4,21〜26,43,51,56の1〜22,甲60〜63,乙152,153,164〜167)。上記のとおり被告製品(別紙物件目録1ないし5)における侵害部分の価値ないし重要度,顧客吸引力,消費者の選択購入の動機等を考慮すると,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)の販売によって得た利益において,本件特許が寄与した割合は15%と認めるのが相当である。
・・・・
当裁判所は,被告代理人らが,控訴審の口頭弁論終結段階になって選任され,限られた時間的制約の中で,精力的に,記録及び事実関係を精査し,新たな観点からの審理,判断を要請した点を理解しないわけではなく,その努力に敬意を表するものである。しかし,特許権侵害訴訟は,ビジネスに関連した経済訴訟であり,迅速な紛争解決が,とりわけ重視されている訴訟類型であること,当裁判所は,原告と被告(解任前の被告訴訟代理人)から,進行についての意見聴取をし,審理方針を伝えた上で進行したことなど,一切の事情を考慮するならば,最終の口頭弁論期日において,新たな審理を開始することは,妥当でないと判断した。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
2012.03.31
平成21(ワ)17848 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年03月26日 東京地方裁判所
前記(2)ア(ア)ないし(ウ)のとおり,被告方法において,被告ソフトウェアは上記数式1及び2によりボリュームレンダリング処理を実行するものであるところ,上記ア(ア)の数式1の「V」は視線上の各ボクセルのCT値を,αは不透明度関数を,cは色関数を表すものであり,数式1は,視線上のボクセルにつき設定された色及びオパシティ値につき積算処理を行うものと認められるから,上記ア(ア)の数式1を用いて行う処理は,本件発明1の「空間座標点毎の前記色度および前記不透明度を該視線毎に互いに積算」するものに相当する。(イ) しかし,前記ア(イ)のとおり,被告方法においては,数式1の積算処理に関し,数式2による閾値の設定がされており,数式1の積算処理は,数式2で設定された閾値に達した時点で打ち切られるものと認められるところ,被告方法においては,上記計算打ち切り処理により,視線上のボクセルデータ中に,積算処理の対象とされないものが存在することが認められる。そうすると,被告方法は,「全ての」空間座標点毎の前記色度および前記不透明度を該視線毎に互いに積算するものに当たらないこととなる。
(ウ) したがって,その余の点について検討するまでもなく,被告方法は,構成要件1−Bを文言充足しない。これに反する原告の主張は採用しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2012.03.31
平成21(ワ)15096 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年03月22日 大阪地方裁判所
原告は,被告物件の構成を上記第3の1【原告の主張】(1)のとおり主張し,他方,被告は,これを同【被告の主張】(1)のとおり主張しているが,被告物件の縦断面図が,別紙被告物件説明書図2のとおりであることは当事者間に争いがない。したがって,被告物件の構成についての当事者の主張の違いは,被告物件の客観的構\成に争いがあることによるものではなく,同じ構成を異なる表\現を用いて記述するものと認められる。そして,後記(2)のとおり,被告物件が本件特許発明の構成要件A,C,Dを充足することは当事者間に争いがないから,結局,構\成要件Bに対応する構成bの特定のみを検討すれば足りるところ,構\成bについての当事者の主張の違いは,炉内に挿入されている炉内ヒータ(発熱体)の上側部分(発熱しない部分)の構成(このような構\成があることは争いがない。)について,被告主張のように「端部(天井の差し込み部及び天井への差し込み部から連続する発熱しない部分)」として記述すべきか否かという点にのみあると認められる(なお,当裁判所は,構成bについての被告の主張を前提としても,被告物件は構\成要件Bを充足すると判断することから,後記(2)イにおいて,被告物件の構成に係る被告の主張を前提に検討する。)。
・・・・
被告は,構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」については,本件明細書に記載された従来技術である【図6】の炉内ヒータを除外して解釈すべきであるから,「端部(天井への差し込み部及び天井への差し込み部から連続する発熱しない部分)を除いた部分に対し,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」と解釈すべきと主張する。しかしながら,上記(ウ)のとおり,「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」とは,熱処理空間内におけるヒータの配設態様のことと解釈されることからすれば,そもそも,天井への差し込み部の構成は,本件特許発明の技術的範囲を検討する上で考慮する必要がない。
・・・
したがって,ヒータの構成について,天井への差し込み部から連続する発熱しない部分(端部)を除いた部分という限定を付する被告の主張は採用できない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
2012.03.29
平成22(ワ)11353 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年03月22日 大阪地方裁判所
以上によれば,構成要件B−1の「スペーサー」とは,水位表\示板のタンクへの取り付けに介在して,その間に空間を確保する部品であり,形状は環状で,材質は弾性部材から構成されるものであり,また,その技術的意義は,水位表\示板が結露することのないように,タンク本体との間に断熱効果のある空間(間隔)を確保するためにあるものと解される。そして,さらに出願経過を参酌すれば,この「スペーサー」は,上記断熱効果を得るために,これによって確保する空間が完全に閉鎖されていることも必須の要件とされているものと解されるべきである。・・・
イ号製品に用いられている厚さ0.1mmの両面接着テープは,接着手段として用いる両面接着テープとして一般的な厚みを有するものと認められることも併せ考えると,イ号製品において用いられている両面接着テープに水位表示板取付台座部と水位表\示板を接着する手段以上の技術的意義があるものとは認められないというべきである。よって,両面接着テープをもって,水位表示板が結露することのない断熱効果のある空間(間隔)を確保する旨の技術的意義を有する「スペーサー」であるとする原告の主張は失当といわなければならない。\n
2012.02. 9
平成20(ワ)27920 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年01月31日 東京地方裁判所
そして,本件発明1の目的ないし作用効果のうち,人形を「所望箇所で屈曲動作ができる」とともに,「様々な姿態を一定時間維持できる」ものとするという点は,従来技術の問題点,すなわち,前記ビスクドールにおける「連結部位を屈曲させた状態のまま保持させておくことができないため,様々な動きのある姿態や人間的な動きを求める傾向のある需要者ニーズに十分対応し得なかった」との問題点や,前記マネキン人形における「頻繁に各箇所で屈曲作動を繰り返すと,その部分の針金が折損してしまう」との問題点の解決と直接結びつくものであって,本件発明1の目的ないし作用効果の重要部分に関わるものであることが認められる。してみると,本件発明1の構\成のうち,被告各製品との相違部分である「腰部骨格連結部」の「第一嵌入杆」と「胴部下端骨格連結部」の「嵌合穴」とを回動可能に連結する構\成は,本件発明1の目的ないし作用効果の重要部分を実現するために複合的に機能する構\成中の不可欠な部分をなすものということができるから,本件発明1の本質的部分に当たるものというべきである。
c これに対し,原告は,本件発明1の本質的部分は,人形全体を骨格構造(一連の骨格群)で支えることとしたという点にあり,人形の連結箇所の数箇所において揺動や回動をする構\成は付加的な作用効果にすぎない旨を主張する。しかしながら,平成11年2月1日発行の雑誌「月刊ホビージャパン1999年2月号」(乙105)に株式会社ツクダホビーが販売する商品として掲載されている女性型関節可動人形「フルアクションドール」の構成(乙105の113ページ記載の写真4参照)をみると,人形全体が硬質樹脂製の骨格構\造にソフトビニル製の外皮を被せて成るものであることが認められ,また,後記(イ)a及びbのとおり,平成9年11月ころから日本国内において販売されている第1商品においても,やはり硬質樹脂製の骨格構造にソ\フトビニル製の外皮を被せて全体が形成される人形の構成が採用されていることが認められる。してみると,原告の上記主張に係る「人形全体を骨格構\造(一連の骨格群)で支える」という構成は,人形玩具の技術分野において,本件出願1の出願前に周知技術となっていたものと認めるのが相当であり,そうである以上,このような構\成を採用したことをもって,本件発明1の本質的部分であるとすることはできない。他方,本件明細書1の「発明の詳細な説明」の記載を総合すれば,本件発明1における4箇所の揺動可能又は回動可能\な連結構造が本件発明1の目的ないし効果の重要部分を実現するための構\成とされているものと理解することができることは,前記bのとおりである。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2012.02. 9
平成20(ワ)27920 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成24年01月31日 東京地方裁判所
そして,本件発明1の目的ないし作用効果のうち,人形を「所望箇所で屈曲動作ができる」とともに,「様々な姿態を一定時間維持できる」ものとするという点は,従来技術の問題点,すなわち,前記ビスクドールにおける「連結部位を屈曲させた状態のまま保持させておくことができないため,様々な動きのある姿態や人間的な動きを求める傾向のある需要者ニーズに十分対応し得なかった」との問題点や,前記マネキン人形における「頻繁に各箇所で屈曲作動を繰り返すと,その部分の針金が折損してしまう」との問題点の解決と直接結びつくものであって,本件発明1の目的ないし作用効果の重要部分に関わるものであることが認められる。してみると,本件発明1の構\成のうち,被告各製品との相違部分である「腰部骨格連結部」の「第一嵌入杆」と「胴部下端骨格連結部」の「嵌合穴」とを回動可能に連結する構\成は,本件発明1の目的ないし作用効果の重要部分を実現するために複合的に機能する構\成中の不可欠な部分をなすものということができるから,本件発明1の本質的部分に当たるものというべきである。
c これに対し,原告は,本件発明1の本質的部分は,人形全体を骨格構造(一連の骨格群)で支えることとしたという点にあり,人形の連結箇所の数箇所において揺動や回動をする構\成は付加的な作用効果にすぎない旨を主張する。しかしながら,平成11年2月1日発行の雑誌「月刊ホビージャパン1999年2月号」(乙105)に株式会社ツクダホビーが販売する商品として掲載されている女性型関節可動人形「フルアクションドール」の構成(乙105の113ページ記載の写真4参照)をみると,人形全体が硬質樹脂製の骨格構\造にソフトビニル製の外皮を被せて成るものであることが認められ,また,後記(イ)a及びbのとおり,平成9年11月ころから日本国内において販売されている第1商品においても,やはり硬質樹脂製の骨格構造にソ\フトビニル製の外皮を被せて全体が形成される人形の構成が採用されていることが認められる。してみると,原告の上記主張に係る「人形全体を骨格構\造(一連の骨格群)で支える」という構成は,人形玩具の技術分野において,本件出願1の出願前に周知技術となっていたものと認めるのが相当であり,そうである以上,このような構\成を採用したことをもって,本件発明1の本質的部分であるとすることはできない。他方,本件明細書1の「発明の詳細な説明」の記載を総合すれば,本件発明1における4箇所の揺動可能又は回動可能\な連結構造が本件発明1の目的ないし効果の重要部分を実現するための構\成とされているものと理解することができることは,前記bのとおりである。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2012.01.29
平成23(ネ)10013 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成24年01月24日 知的財産高等裁判所
上記記載によれば,本件各特許発明は,「券情報」と「発券情報」という2種類の情報を地上の管理センターから受ける場合,伝送される情報が2種になるために通信回線の負担が1種の場合に比べて2倍になってしまうとともに端末機の記憶容量と処理速度も2倍になってしまうという従来技術の問題点を課題として,これを解決すべく,管理センターに備えられるホストコンピュータにおいて,「券情報」及び「発券情報」に基づき,かつ,「座席管理地の座席レイアウト」に基づいて,1つの表示情報である「座席表\示情報」を作成し,これをホストコンピュータから座席管理地に備えられる端末機に伝送し,当該端末機が,これを入力して,その表示手段(ディスプレイ等)において表\示するという構成を採用することによって,前記ホストコンピュータから前記端末機へ伝送する情報量が半減され,通信回線の負担と端末機の記憶容量と処理速度等を軽減するとともに,端末機のコストダウンが図られ,本発明のシステムの構\築を容易にするという効果を達成した発明であると認めることができる。 したがって,本件各特許発明の「座席表示情報」とは,ホストコンピューターにおいて,「券情報」,「発券情報」及び「指定座席のレイアウト」といった個々の情報を1つの情報に統合することによって,これを端末機に送信すれば,端末機において他の情報と照合する等の格別の処理を要することなく座席の利用状況を表\示し,目視することができる情報と認めるのが相当である。
・・・・
前記認定のとおり,本件各特許発明の「座席表示情報」とは,ホストコンピューターにおいて,「券情報」,「発券情報」及び「指定座席のレイアウト」といった個々の情報を1つの情報に統合することによって,これを端末機に送信すれば,端末機において他の情報と照合する等の格別の処理を要することなく座席の利用状況を表\示し,目視することができる情報と認められるところ,前記(1)イで認定した被告システムの構成からすれば,被告システムにおいては,センターサーバーから車掌用携帯情報端末に送信される情報は,「編成パターン情報」と「座席・乗車券情報」という別々の情報であって,本件各特許発明における「座席表\示情報」に相当する情報,すなわち,「端末機において他の情報と照合する等の格別の処理を要することなく座席の利用状況を表示し,目視することができる情報」は,上記「編成パターン情報」と「座席・乗車券情報」を統合処理す ることによって車掌用携帯情報端末において作成されているから,被告システムはホストコンピュータにおいて本件各特許発明にいう「座席表示情報」を作成・記憶・伝送するものでなく,かつ,車掌用携帯情報端末は伝送された上記「座席表\示情報」を入力・記憶・表示するものではないと認められる。したがって,被告システムは,本件各特許発明の構\成要件1−Cないし1−H,2−Cないし2−Hを充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2012.01.20
平成22(ワ)12227 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成23年12月22日 大阪地方裁判所
これらの画像によれば,本件分析方法において,2値化処理がされた結果,上記ラマンマッピングのうち,青色で表示された部分にエバスチン以外の成分が含まれているにもかかわらず,この部分にはエバスチンしか存在しないものとして処理され,逆に,緑や黄色で表\示された部分にはエバスチンが含まれているにもかかわらず,これらの部分にはエバスチンが存在しないものとして処理されたことが認められる。このような2値化処理をした理由については,本件各報告書にも前記(3)アないしウの各意見にも,それが画像処理の基本であるということ以外に,何ら合理的な説明がされていない。かえって,P5意見及びP6意見(前記(4))によれば,顕微ラマン分光法測定により得られたラマンマッピングは,あらかじめ標準品を用いて作成した検量線に基づいて評価した薬物の濃度を色の違いで表現するものであり,色の濃淡が示しているのは単位面積当たりの薬物の存在割合にすぎないことが認められる。そうすると,P5意見及びP6意見(前記(4))が指摘するとおり,顕微ラマン分光法測定(本件分析方法)により得られたラマンマッピングは,被告ら各製品に含有されるエバスチンのおよその存在の程度と定性的な分布を示しているにすぎないものというほかない。そうであるにもかかわらず,上記のような2値化処理をして得られた2値化イメージに係る打切り処理後画像からエバスチンドメインを観察し,そのサイズを測定したとする本件各報告書の分析は,P5意見(前記(4)ア)が述べるとおり,分布しているエバスチンの大きさなどに対する真の数値を表すものではなく,ある条件で評価した時にこのような数値を得られることができたという,調整可能\な選択された前提条件下での仮定の数値にすぎないというべきである。これらのことからすると,本件各報告書における分析結果,すなわちドメインサイズの分析結果が,被告製品1及び5に含有されるエバスチン粒子の状態,数,大きさなどを示すものであるとは認めることができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
2012.01.19
平成23(ネ)10056 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成24年01月16日 知的財産高等裁判所
本件特許発明の特許請求の範囲においては,(使用されている)「すべて」の市外局番及び市内局番という文言が用いられているのであって,範囲の広狭がある場合には,最も広い範囲を指すと解するのが自然であり,逆に,これを「調査対象となる一定の地域」に限定する記載はない。本件明細書(甲1,47)の記載をみても,【課題を解決するための手段】(段落【0009】)には,「調査対象となる一定の地域」の市外局番及び市内局番に限定する旨の記載はなく,唯一の実施例も,「ここまでは1台のパソコン1で北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアの調査を行うと説明した。同様にして,全国の電話網をいくつかの地域に分割し,それぞれの地域にて全国の電話番号の調査を複数の地域に分散した複数のパソ\コンで分担実行する。そして,それぞれに担当した地域の前記調査リストを通信などを通じて1つに集約することで,全国的な広域の調査リストを作成できる。」(段落【0032】)と記載されるように,全国を対象として調査するものである。なお,控訴人が主張の根拠とする記載(段落【0011】〜【0013】,【0026】)は,全国を調査する一環として,ある地域を分担したパソコンによる調査方法を説明したものであって,控訴人の主張するような,一定の地域に限定して調査を行う旨の記載であるとは認められない。また,控訴人は,訂正審決が本件明細書の段落【0013】を根拠に訂正を認めたと主張するが,審決は,当該段落に加えて上記の段落【0032】も引用して訂正事項が当初明細書に開示されていると認定したのであり(甲47),控訴人の主張に沿う判断をしたものではない。さらに,本件特許発明の解決課題・作用効果についても,従来技術の2つの課題のうちの1つである「交換局の輻輳の問題」(段落【0006】)に対して,本件特許発明では,全国を複数のパソ\コンで分担調査することにより,コンピュータに近い交換局の輻輳が起きないという効果を奏する旨記載されているのであって(段落【0034】,【0039】),この点においても,全国の調査を前提とするものである。したがって,構成要件Aの「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは,調査対象となる一定の地域において使用されているすべての市外局番及び市内局番を意味するという控訴人の主張は,採用することができない。そして,控訴人のその余の主張は,上記説示により排斥された解釈を前提として,一定の地域においては,被控訴人が調査対象としていない局番が存在せず,すべての局番を調査していることになるので,構成要件Aを充足しているというものであるから,その前提を欠くことになる。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
2012.01.12
平成22(ワ)43749 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成23年12月28日 東京地方裁判所
本件特許に係るこのような出願経緯からすると,既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅の大小については,上記(3)オの補正において,第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものに限定されたことにより,外形的には,これとは逆の第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より小さいものを本件特許発明1に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと解さざるを得ない。したがって,説明書記載方法は,均等侵害の要件のうち,少なくとも上記(2)の5の要件を欠くことが明らかであるから,その余の要件について検討するまでもなく,説明書記載方法が本件特許発明1の方法と均等な方法であるとする原告の主張は理由がない。 (5) 原告は,上記補正に引用例との抵触を避ける意図はなかった,手続補正上の制約から出願時の明細書と図面に記載されていない事項を追加する補正は許されなかったなどと主張する。しかし,上記(4)で認定したように,上記補正は拒絶理由を回避するためにされたものと認められ,また,上記(3)イで認定したように,本件特許の出願当初の明細書(乙1の1)には,「前記他方のスリットの水平方向の幅が前記一方のスリットの水平方向の幅より大きくなるようにスリットを形成することが好ましい。」と記載されていることからすると,仮に他方のスリットの水平方向の幅が一方のスリットの水平方向の幅より大きい旨の補正をしたとしても新規事項の追加に当たるということはできず,手続補正上の制約があったとは認められないことから,原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
2012.01. 7
平成20(ワ)12409 製造販売禁止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成23年12月27日 東京地方裁判所
上記i)ないしiv)を総合すると,本件明細書において,「せき止め空間」(液体せき止め空間)の用語は,「液体を静止状態に維持」し,あるいは「その中にある水が,擬似的に静止状態」となり,これにより「ノズル通路入口の上のフォーカス円錐先端の範囲に,熱レンズが生じ」あるいは「熱レンズの形成を助長」し,これによって「水ビーム内に結合されたレーザービーム」の一部が「ノズル通路入口の周範囲におけるノズルの壁に管理できない損傷を引起こす」作用を有するものとして用いられていることを理解できる。加えて,請求項1中には,「液体供給空間(35)へ供給される液体が,ノズル入口開口(30)の周りにおいてせき止め空間のないように導かれ」,「それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲(56)における液体の流速が,十分に高く決められるようにし」,「したがってフォーカス円錐先端範囲(56)において,レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで,熱レンズの形成が抑圧されること」(構\成要件エないしカ)との記載があるところ,上記記載が,「それにより」及び「したがって」といった接続詞を用いながら,「せき止め空間のない」ようにすること,液体の流速を「十分に高く」すること及び「ノズル壁の損傷」を生じさせない程度の「熱レンズの形成の抑圧」がされることを一体的なものとして,作用的,機能\的に捉えていることに鑑みれば,構成要件エの「せき止め空間のない」とは,液体供給空間内のレーザービームのフォーカス円錐先端範囲(の領域)において,ノズル壁の損傷に至る原因となる熱レンズの形成を抑圧する程度に液体の流速を十\分に高くし,当該液体が「静止状態」あるいは「擬似的に静止状態」にないことをいうものと解される。また,このような解釈によれば,構成要件オの「液体の流速が,十\分に高く」とは,「フォーカス円錐先端範囲(56)において,レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで,熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味するものと解される。そして,この「液体の流速が,十分に高く」するとの構\成は,構成要件エの「液体が,ノズル入口開口(30)の周りにおいてせき止め空間のないように導かれ」る構\成によってもたらされることによれば,被告製品を使用する加工方法における構成要件エないしカの充足性を判断するに当たっては,各構\成要件を個別に検討するのではなく,これらを一体的なものとして判断するのが妥当である。このような判断手法は,前記アで認定した本件明細書に開示されている本件発明1の技術的意義からみても合理性があるというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2012.01. 5
平成22(ワ)32858 損害賠償 特許権 民事訴訟 平成23年12月28日 東京地方裁判所
構成要件Fは,「外側の一部にはその切取りのための摘みを垂設し,」というものであり,身(環状突片)の外側の一部にその切取りのための「摘みを垂設」することを定めている。この「摘みを垂設」について,本件明細書には,「【0014】開蓋装置5については,環状突片11の基端に,下面開放形の切取溝13を設け,その切取溝13に沿って環状突片11を切り取り得るように,一端において環状突片11に摘み15を突設し,摘み15が下向きの舌片状に形成される。」と記載され,【図1】,【図2】及び【図5】には,摘み15が下向きの舌片状に形成された形状で図示されている。また,「垂設」という用語は一般的用語ではないが,「垂」については,「たれること。ぶら下がること。」という意味があり,「垂れる」については,「重みで下にだらりとさがる。先端がさがった状態になる。」という意味があるものと認められる(いずれも広辞苑第4版)。そうすると,構\成要件Fにおける「摘みを垂設」とは,垂れ下がるように,下向きに摘み15が形成されていることを意味するものと解するのが相当である。これを被告製品についてみるに,被告製品における摘みはいずれも水平方向(容器面に対して平行)に設けられており,垂れ下がるように下向きに形成されたものはない(弁論の全趣旨)。したがって,被告製品は,いずれも構成要件Fを充足すると認めることはできない。
イ 原告は,「摘みを垂設」とは,摘みが容器側面に対して略垂直方向(水平方向)に設けられていることを意味し,そのような構成を備える被告製品はいずれも本件発明の構\成要件Fを充足すると主張する。しかしながら,かかる用語の使い方は前記した「垂」の字の一般的な意味,用法に明らかに反しており,本件明細書に「垂」ないし「垂設」をそのような特別な意味,用法で使用することについての記載がない以上,上記解釈は採り得ない。したがって,原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 意匠その他
2011.12.13
平成23(ネ)10049 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成23年12月08日 知的財産高等裁判所
そして,前記(2)によれば,システム管理者が入力用データのファイルを作成する段階で,ネットワーク接続したイ号サーバシステムにおいては,各既存システム内に存在する製品に関する情報を,イ号ソフトの機能\を用いずに,各既存システムのアプリケーションなどを用いて部品情報テーブル,構成情報テーブル,属性情報テーブルで構\成される所定の形式に整理・記述して,入力用データのテキストファイル(CSV形式)を作成し,イ号ソフトをインストールしたサーバ内にコピーした後,イ号ソ\フトがその一部を専用のファイル形式にデータ変換し,イ号ソフトをインストールしたサーバ内にイ号データベースを構\築する方法を採用している。そうすると,ネットワーク接続したイ号サーバシステムは,画面表示手段によって製品の各部位を示す項目が部品表\に示された階層関係に従って画面に表示され,項目指示手段によって前記画面の任意の項目の表\\示部が指示されたうえで,その指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力処理を行うものではないから,本件発明の構成要件Fに係る「入力処理手段」を備えていない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2011.12. 7
平成22(ワ)40331 特権侵害差止等請求事件 平成23年11月30日 東京地方裁判所
原告は,無効理由4に係る被告の無効主張は時機に後れた攻撃防御方法であるから却下すべきと主張する。しかしながら,当該無効主張は,平成23年7月13日の第4回弁論準備手続において,同月12日付け被告準備書面(4)をもってなされたものであるところ,同時点では,いわゆる二段階審理における侵害論についての審理中であったから,当該無効主張についての審理がなければ直ちに弁論を終結できる段階になく,上記無効主張により訴訟の完結を遅延させることになるものとは認められない。原告は,無効審判請求の審理が終結した後に新たに無効主張を追加することは,侵害訴訟と審決取消訴訟におけるいわゆるダブルトラック問題を引き起こすと指摘するが,上記無効主張により訴訟の完結を遅延させることになるものと認められないことは上記のとおりであるから,原告の上記主張は採用することができない。
3 訂正を理由とする対抗主張について
原告は,平成23年9月22日付け原告第6準備書面をもって,本件訂正発明には無効理由がなく,かつ,被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属すると主張し,これに対し,被告は,原告の上記主張は,時機に後れた攻撃防御方法であるから却下されるべきであると主張する。そこで検討するに,原告の上記対抗主張は,前記平成23年7月12日付け被告準備書面(4)をもってなされた無効理由2〜4に対するものであるところ,受命裁判官は第5回弁論準備手続期日(同年8月5日)において,原告に対し,上記無効理由についても審理するので,これに対する反論があれば次回までに提出するよう促し,反論の機会を与えたにもかかわらず,原告は,第6回弁論準備手続期日(同年9月9日)までに上記対抗主張をすることなく,同期日で弁論準備手続を終結することについても何ら異議を述べなかったものである。無効理由2及び3は,いずれも既出の証拠(乙2及び乙3)を主引用例とする無効主張であり,無効理由4も,平成14年5月20日付け特許異議申立てにおいて既に刊行物として引用されていた乙6に基づくものであるから,原告は,上記無効理由の主張があった第4回弁論準備手続期日から弁論準備手続を終結した第6回弁論準備手続期日までの間に対抗主張を提出することが可能\\であったと認められる(原告は,乙6に基づく無効理由4を回避するために訂正請求を行うことができるのは第2次無効審判請求の無効審判請求書副本の送達日である平成23年8月19日から答弁書提出期限である同年10月18日までの期間のみであると主張するが,本件訴訟において対抗主張を提出することはできたものというべきである。原告は,対抗主張が認められる要件として現に訂正審判の請求あるいは訂正請求を行ったことが必要とする見解が多数であるとも主張するが,訂正審判請求前又は訂正請求前であっても,訴訟において対抗主張の提出自体が許されないわけではなく,理由がない。)にもかかわらず,これを提出せず,弁論準備手続の終結後,最終の口頭弁論期日になって上記対抗主張に及ぶことは,少なくとも重大な過失により時機に後れて提出したものというほかなく,また,これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> 裁判手続
2011.11. 4
平成22(ワ)3846 不当利得金返還請求事件 平成23年10月27日 大阪地方裁判所
ア 特許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分,言い換えれば,上記部分が他の構\成に置き換えられるならば,全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。そして,本質的部分に当たるかどうかを判断するに当たっては,特許発明を特許出願時における先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で,対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか,それともこれとは異なる原理に属するものかという点から判断すべきものである。イ 本件特許発明の構成要件A及びB,すなわち「10BASE-T に準拠するツイストペア線においてリンクテストパルスが伝送されること」が周知技術であることは,当事者間で争いがない。そうすると,本件特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで本件特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分は,本件特許発明の構\成要件Cであると解するよりほかない。そして,前記1のとおり,本件特許発明の課題の解決手段における特徴的原理は,「リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断」した後に「信号線を切り替える」というものである。これに対し,被告製品の備える解決手段は,「ストレート結線とクロス結線とをランダムな時間間隔で繰り返し遷移させた上,リンクテストパルスが検出された時点で,この遷移を停止させる構成」を採用したことにある。確かに,本件特許発明と被告製品とは,リンクテストパルスの検出結果を用いるという点では共通する。しかし,前記1(2)ウ(ウ)のとおり,本件特許発明では,ツイストペア線(リンクテストパルスが伝送されるもので,出願時周知であった。)を使用することが前提となっているのであるから,リンクテストパルスを使用すること自体は課題の前提条件にすぎず,課題解決手段における特徴的原理を共通するとはいえない。そして,これに基づく課題解決手段の原理は,本件特許発明が検査結果に基づいて信号線を自動的に切り替えるというものであるのに対し,被告製品は検査結果に基づいて信号線の切替えをやめるというものであって,原理として表裏の関係にある又は論理的に相反するものであり,異なる原理に属するものというほかない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2011.10.31
平成23(ワ)22310 特許料請求事件 平成23年10月28日 東京地方裁判所
請求の範囲ですが、出願後の補正で「可変スイッチを有する電気炊飯器」として登録されています。
平成18年3月14日付け手続補正書により補正された【図4】には,「可変スイッチ」に関して,「スイッチ1のタイマースイッチは1分から10分までの可変スイッチとする。これでもって,おこげごはんは自由に作れる。又水分を補給することによって,おかゆごはんも作れる。タイマースイッチは,普通ごはんの出来たあとに作動させるものである。タイマースイッチは,ONを1回おすと1分である。10回おすと10分である。」と説明されており,この記載を考慮すれば,「可変スイッチ」とは,「通常炊飯が完了した後に更に作動させる加熱(追い炊き加熱)を行う時間を可変とすることができるスイッチ」を意味するものと解するのが相当である。すなわち,本件考案は,i)通常炊飯による普通ごはん,ii)通常炊飯完了後に可変スイッチによって決定された任意の時間追い炊き加熱を行うことによるおこげごはん,iii)通常炊飯完了後に水分を補給して追い炊き加熱を行うことによるおかゆごはんの3種類のごはんを作ることを特徴とするものと認められる。
(3) 被告製品の構成について
被告製品取扱説明書(乙2)によれば,被告製品は,「芳潤炊き」,「エコ炊飯」,「炊込み」,「おかゆ」,「お急ぎ」,「やわらか」,「かため」,「ふつう」という炊飯メニューを有しており,被告製品上部の「操作・表示部」に設けられた「メニュー」ボタン(スイッチ)又は「芳潤炊き」ボタン(スイッチ)を操作することにより,上記各モードを設定するものであることが認められる。しかしながら,被告製品は,炊き上げに要する時間,消費電力等を上記各モードの設定に応じて変更することによって,上記のような様々な炊飯メニューを実現しているのであって(乙2,弁論の全趣旨),本件全証拠を検討しても,被告製品について,通常炊飯が完了した後に追い炊き加熱を行うような動作をしている事実は認められない。すなわち,被告製品における「メニュー」ボタン(スイッチ)や「芳潤炊き」ボタン(スイッチ)は,いずれも炊き始めから炊き上がりまでの条件を設定するもので,通常炊飯が完了した後の追い炊き加熱の時間を設定するものとは認められない。(4) したがって,被告製品に備えられているスイッチは,本件考案における「可変スイッチ」に該当するものではないから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属するということはできない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2011.10.28
平成22(ワ)23188 特許権侵害差止等請求事件 平成23年10月19日 東京地方裁判所
以上の明細書の記載及びその課題解決のためのカフとカラー部分との関係について示した構成要件Eの記載に照らして,「直接隣接する」の技術的意義を検討すると,本件発明は,従来技術において,カフ上端部の分泌物を吸引するについて,カラーの延在部よりも上部に吸引孔を設けざるを得ず,その結果,吸引孔とカフ上端部の位置が遠ざけられ,そのためカフ上端部の分泌物を十\分吸引できなかったのを,カラーに被せるようにカフを膨らませ,気管をシールすることによって,カラー部分の存在によるカフ上端部からの吸引孔の離間を回避し,カフ上端部と吸引孔の近接を可能にしたことにあると認めるのが相当である。したがって,「直接隣接する」の意義は,カラー部分の存在による吸引孔とカフ上端部との離間が防止されていること,すなわち,カラー部分の存在によりカラー部分を隔てて吸引孔とカフ上端部が隣接することが回避されていることを意味するものと介される。したがって,カフの近位端と吸引孔の間の空隙の有無が直ちに「直接隣接する」か否かの評価に結び付くのではなく,カラー部分に重なるようにカフが膨らむ構\成によって,カラー部分の距離がそのまま吸引孔を設けることの障害となっていた従来技術と比較して,カフの上端部(近位端)と吸引孔の間の空隙を短縮することができているのであれば,「直接隣接する」と評価することができるものというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
2011.09.13
平成21(ワ)35411 特許権侵害差止等請求事件 平成23年08月30日 東京地方裁判所
被告サービスが本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であるか否かについて検討するに,平成10年最判は,特許請求の範囲に記載された構\成中に対象製品等と異なる部分がある場合に,なお均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると認められるための要件の一つとして,「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」こと(第5要件)を掲げており,この要件が必要な理由として,「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど,特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,又は外形的にそのように解される行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないからである」と判示する。そうすると,第三者から見て,外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動を特許権者がとった場合には,上記特段の事情があるものと解するのが相当である。
(3) これを本件についてみると,本件訂正がされた経緯は前記1(1)イ(イ)のとおりであり,原告は,本件訂正前の特許請求の範囲請求項1では,単に,「ISDNに接続したコンピュータにより回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し」とされ,いかなる電話番号を調査対象とするのかについて特段制限は付されていなかったものを,本件訂正により,「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある4桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とするものに限定することを明記し,これにより,乙5資料等に記載された先行技術と本件発明との相違を明らかにして,乙5資料等を先行技術とする無効事由を回避しようとしたものであることが認められる。そうすると,原告は,本件特許発明について,本件訂正に係る訂正審判の手続において,被告サービスのように一部の局番の電話番号を調査対象としない構\成のもの,すなわち,調査対象電話番号が「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある4桁の数字のすべての組み合わせからなる」ものでない方法が,その技術的範囲に含まれないことを明らかにしたものと認めるのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
2011.08.30
平成20(ワ)831 特許権侵害差止等請求事件 平成23年08月26日 東京地方裁判所
特許法102条2項所定の「その者がその侵害の行為により利益を受けているときは」にいう「利益」とは,侵害品の売上高から侵害品の製造又は販売と相当因果関係のある費用を控除した利益(限界利益)をいい,ここで控除の対象とすべき費用は,侵害品の製造又は販売に直接必要な変動費及び個別固定費をいうものと解するのが相当である。本件計算鑑定は,被告各製品の製造及び販売に直接必要な変動費及び個別固定費につき次のaないしeのとおり,変動費の減少項目につき次のfのとおりそれぞれ認定・判断した上で,平成19年9月1日から平成21年9月30日までの期間における被告各製品の売上高(前記ア(ア))から控除すべき費用の合計額を3億7470万6005円,限界利益の合計額を2869万7562円と算定した(本件計算鑑定書添付の別紙1参照)。上記aないしeの費用について,本件計算鑑定は,被告が製造及び販売する猫砂全製品において被告各製品の占める割合(aにつき販売リッター数に占める割合,bないしeにつき製造リッター数に占める割合)で按分して算出している(本件計算鑑定書の「VII対象品の計算根拠と変動費の範囲について」(8頁),本件計算鑑定書添付の別紙7及び8参照)。
・・・・
これに対し原告は,i)本件計算鑑定書添付の別紙9によれば,経費の内容には,変動費3億3364万2241円のみならず,個別固定費5457万8946円も含まれているが,本件計算鑑定は,被告の製造する猫砂は,パッケージが違ったとしても,すべて同じ構造の製品で「生産工程,機械,人員」もすべて同じであること,25期(平成21年5月〜平成21年9月)における被告の全製品に対する被告各製品の販売割合が15.5%(本件計算鑑定書添付の別紙8)であることを前提に鑑定をしていることからすれば,被告各製品のためだけに被告ないしその特定の工場の製造ラインが使用されているわけではないのであるから,個別固定費はそもそも控除されるべきではない,ii)個別固定費のうち減価償却費として控除されている2647万2548円(本件計算鑑定書添付の別紙9)は,四国工場の費用を「全額」費用計上したのであるとすれば,被告各製品の販売割合が15.5%(四国工場内でも16.9%)しかない以上,明確な誤りである,iii)本件計算鑑定では,売上げはバルクで計算するのに対し,包装機械は減価償却費,人件費は加工費として経費に含めているが,これも過剰な経費計上である旨主張する。しかしながら,原告の主張は,以下のとおり理由がない。・・・ ・・・被告各製品は,他の猫砂(甲8)と比較して,吸尿によって変色し,それによって使用部分と未使用部分を視覚的に容易に判別することができる構成となっている点を重要なセールスポイントとしていることが認められる。そして,そのようなセールスポイントは,本件発明の構\\成によるものであるから,被告各製品の商品としての主たる価値は,本件発明からもたらされるものと評価できる。これに対し被告は,被告各製品と同等の原告製品は,被告各製品の1.5倍程度の価格で販売されており,被告各製品の主たる販売要因は,その価格競争力にある旨主張するが,本件においては,被告各製品の仕入値が原告製品に比して低いことを裏付けるに足りる客観的な証拠は提出されていないのみならず,仮に被告各製品の価格が同等の原告製品より低かったとしても,そのような価格は本件特許を無許諾で実施した結果形成されたものというべきであるから,本件発明の寄与率に影響するものとは認められない。以上のとおり,乙35ないし乙39の各特許の請求項1に係る各発明は,いずれもその構成において,原材料である廃材粉や粉砕物の「粒度」を規定しているところ,本件においては,被告各製品の原材料の粒度を具体的に特定するに足りる証拠は提出されていないことからすると,被告各製品が上記各発明を実施しているかどうかは定かでないといわざるを得ない。また,仮にこれらの発明が被告各製品に実施されているとしても,そのことが被告各製品の重要なセールスポイントとなるなど,被告各製品の販売に具体的に寄与していることを認めるに足りる証拠はない。(ウ) 小括以上のとおり,被告各製品のセールスポイントは,本件発明の構成によるものであり,被告各製品の商品としての主たる価値は,本件発明からもたらされるものといえるから,本件発明の寄与率は,100%と認めるのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
2011.07.20
平成20(ワ)33440 特許権侵害差止等請求事件 平成23年07月12日 東京地方裁判所
そして,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載と上記認定の本件明細書の開示事項を総合すれば,本件発明のデータ入力装置においては,部品表データベースに登録された部品表\を検索キーとし,「画面表示手段」(構\成要件D)によって上記部品表に示された製品の各部位を示す項目を階層関係に従って画面に表\示すること,「項目指示手段」(構成要件E)によって上記画面上の任意の項目を指示すること,「入力処理手段」(構\成要件F)によって上記指示のあった指示項目に対して登録する情報を所定の記憶領域に入力すること,「リンク設定手段」(構成要件G)によって上記入力された情報(登録する情報)に対して上記指示項目及びこれを含む上位の階層関係の項目をリンクさせる情報を付すこと,「メニュー表\示手段」(構成要件H)によって上記指示項目に対して入力する情報の用途別の種類が表\示されたメニューを画面に表示すること,「情報種類設定手段」(構\成要件I)によって上記メニューに表示された情報種類を選択することで,その選択された情報種類を,上記入力された情報(登録する情報)(本来の情報)に対して関連付けること,「情報登録手段」(構\成要件J)によって上記入力された情報(登録する情報)と,上記リンクさせる情報と,上記情報種類の情報とをデータベースサーバに送ってそのサーバ内の統合データベースに登録することを「一連の動作」として行うことができるようにしたことで,データ入力の負担を極力抑えて,各現場で発生する各種情報を誰でもが簡易に入力することができるようにするとともに,入力した情報を簡易に検索して利用できるようにしたことに技術的意義があるものと認められる。・・・そこで検討するに,ネットワーク接続したイ号サーバシステムは,前記(1)イのとおり,部品に関する情報がイ号サーバシステムとは別の複数の既存システムに保持されたまま各既存システムで個別管理され,かつ,その情報の入力・登録も各既存システムが有する入力手段・登録手段によって行われることを前提とし,これらの既存システムに保持された部品に関する情報の検索・参照を容易にすることを目的としたサーバシステムであって,クライアントの要求に従って,これらの既存システムに保持された部品に関する情報が整理・記述された入力用データをコピー及び一部データ変換してイ号サーバシステム内に構築されたイ号データベースを検索し,検索条件(文字列)に合致した部品の部品番号,部品名及び属性情報をクライアントの表\示装置に表示させ,更に指示された部品の上流又は下流にある部品の部品番号等を階層的に上記表\示装置に表示させる機能\(検索機能及び階層展開機能\)を有するものである。しかしながら,ネットワーク接続したイ号サーバシステムにおいては,上記検索機能及び階層展開機能\によりクライアントの表示装置(画面)に表\示又は階層的に表示させた部品の部品番号,部品名及び属性情報について,上記画面上の任意の項目を指示し,その上で,その指示項目に対して登録する部品に関する情報を所定の記憶領域に入力する「入力処理手段」(構\成要件F)を備えるものではなく,また,部品に関する情報を個別管理する既存システム内のデータベース及びイ号データベースのいずれに対しても,上記指示項目に対して登録する情報,上記指示項目と上位の関係の項目とをリンクさせる情報,及び情報種類の情報を登録する「情報登録手段」(構成要件J)を備えるものではない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 間接侵害
>> コンピュータ関連発明
2011.07. 4
平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成23年06月23日 知的財産高等裁判所
間接侵害について
特許法101条4号は,その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物についてこれを生産,譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ,同号が,特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を,「その方法の使用にのみ用いる物」を生産,譲渡等する行為のみに限定したのは,そのような性質を有する物であれば,それが生産,譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから,特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば,その方法の使用に「のみ」用いる物とは,当該物に経済的,商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。被告装置1は,前記のとおり本件発明1に係る方法を使用する物であるところ,ノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は,被告装置1においても,本件発明1を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。しかしながら,同号の上記趣旨からすれば,特許発明に係る方法の使用に用いる物に,当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても,当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら,当該特許発明を実施する機能\\は全く使用しないという使用形態が,その物の経済的,商業的又は実用的な使用形態として認められない限り,その物を製造,販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから,なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。被告装置1において,ストッパーの位置を変更したり,ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく,かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは,前記のとおりである。そうすると,仮に被控訴人がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても,例えば,ノズル部材が窪みを形成することがないよう下降しないようにストッパーを設け,そのストッパーの位置を変更したり,ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど,本件発明1を実施しない機能\のみを使用し続けながら,本件発明1を実施する機能は全く使用しないという使用形態を,被告装置1の経済的,商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって,被告装置1は,「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。
均等について
前記1の本件明細書の記載からすると,本件発明1は,その後に続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く,その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を,既に備わる封着用のシャッタで行う点,そして,別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に,その特徴があるということができる。本件発明1においては,シャッタ片及び載置部材と,ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが,いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって,本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し,被告方法2がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は,本件発明1の本質的部分とはいえない。エ 均等侵害の要件ii)についてノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに代えて,押し込み部材の下降はなく,シャッタ片及び載置部材を上昇させてノズル部材及び生地押え部材に接近させる被告方法2によっても,外皮材が所定位置に収まるように外皮材の位置調整を行うことができ,外皮材の形状のばらつきや位置ずれがあらかじめ修正され,より確実な成形処理を行うことが可能であり(【0008】【0013】),より安定的に外皮材を戴置し,確実に押え保持することができ(【0011】),装置構\成を極めて簡素化することができる(【0012】)といった本件発明1と同一の作用効果を奏することができる。本件発明1の構成要件1C及び1Dは,押え部材が外皮材を受け部材上に保持することができ,押し込み部材が,受け部材の開口部に内材を供給するため一定の深さに進入することにより,達することができるとするものである。そうすると,ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させる構\成を,シャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させる構成に置き換えたとしても,同一の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものということができる。オ 均等侵害の要件iii)について本件発明1と被告方法2の上記構成の相違は,ノズル部材及び生地押え部材を載置部材上の生地に接近させるための動作に関して,単に,上方の部材を下降させるか,下方の部材を上昇させるかの違いにすぎない。したがって,被告方法2の上記構\成に想到することは,当業者にとって容易である。・・・以上のとおり,被告方法2は,本件発明1の構成要件1Cの構\成と均等なものである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 間接侵害
>> のみ要件
2011.06.27
平成21(ワ)7821 特許権侵害行為差止等請求事件 平成23年06月23日 大阪地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
2011.06.14
平成19(ワ)5015 特許権侵害差止等請求事件 平成23年06月09日 大阪地方裁判所
ウ そこで,被告各物件における本件各特許発明が売上に与えた寄与率を検討する。
(ア) 裏異物検出機能の意義証拠(甲26,57)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。近時,コンビニエンスストアなどでおにぎりが多く売れるようになり,海苔の需要が高まるとともに,厳しい品質管理が求められるようになった。海苔の場合は,異物の混入の有無が品質にも大きく影響し,その検出が重要な課題となっており,また,そのための装置が開発されてきた。そして,原告製品1,2及び被告各物件は,いずれも,乾海苔を一度くぐらせるだけで,その表\面,中,裏面の異物を検出することができる機能を有しており,これが同時にできないと,同じ作業を繰り返す必要があり,検出作業に要する手間や時間が増える(仮に,1台の機械をもって検出作業をするのであれば,2倍近い時間がかかる。2台〔2種類〕の機械を同時に使用する場合は,同様の時間を要することはないが,検出機の購入代金が割高になることが予\想されることのほか,2台分の設置場所や,検出機から排出された乾海苔を,改めて別の検出機にセットする手間を要する。)。したがって,表面や中だけでなく,裏面の異物検出機能\を有し,1回の搬送で検出を終えることのできる機能は,海苔異物検出機の販売に際し,大きな貢献を果たしているというべきである。
(イ) 本件各特許発明と代替技術本件明細書によると,本件各特許発明の出願以前の海苔の異物検出に関する従来技術として,目視に頼るか,上下のローラーで挟んでその厚みにより異物を検出する方法が記載されている。しかし,その一方で,次に述べるとおり,海苔の異物を検出する機能を有した装置自体は,開発がすすみ,普及していったことが窺われる。被告各物件においても,裏面検出機能\のほか,表面検出機能\と中検出機能を具備しているところ,中検出は検出対象物が違うものの,少なくとも表\面検出機能については,その機能\において違いがあるわけではない(前述したとおり,裏返しした上での検出が議論されているが,そもそも,そのような検出方法が不可能であることを前提とした議論はされていない。)。
・・・
オ 以上を総合すると,被告物件1の後期型の販売における寄与率は20%,被告物件2の販売における寄与率は25%と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
2011.05.20
平成22(ワ)8024 実用新案権侵害差止等請求事件 平成23年04月28日 大阪地方裁判所
原告は,本件実用新案登録に係る請求項2の考案として,「横桟部材に掛合する掛合部が,靴収納用棚板の側面視においてフックもしくは下向きU字形に掛合部を形成されていることを特徴とする請求項1に記載の靴載置用棚板」が掲げられており,これからすると,請求項1における「掛合部」は,請求項2の掛合部以外の態様を広く含むものと理解することができるとも主張する。しかし,本件明細書の考案の詳細な説明欄に記載された掛合部は,前記ウのとおりであり,それ以外の掛合部の構成は記載されていない。請求項1における「掛合部」が,請求項2の「掛合部」以外の態様を含むものであるとしても,請求項2の考案は,掛合部の具体的な構\成として,「フックもしくは下向きU字形に掛合部を形成されていること」との構成を開示したにすぎず,請求項1における「掛合部」の解釈を,前記ウの解釈より広げる根拠とはならない。\n・・・ そこで,これを本件について見るに,前記1(2)ウで判示したとおり,本件考案の作用効果は,横桟部材を靴収納庫に設置したままの状態で,棚板を着脱可能に接合させることにより,既存の様々な靴収納庫や横桟部材に対応することができる点にあると解される。これに対し,被告棚板の円形の穴を横桟部材に取り付けるためには,いったん横桟部材を取り外して,上記穴に横桟部材を挿通させた上,棚板の付いた横桟部材を靴収納庫に取り付けなければならず,横桟部材を本来の取付位置にある状態のままで,被告棚板を接合させることはできない。そうすると,被告棚板の円形の穴では,本件考案の目的を達することができず,同一の作用効果を奏するものとは認められない。(3) また,前記1(2)ウで判示したところによると,上記接合部は,本件考案の本質的部分ということができる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2011.04.21
平成22(ネ)10014 各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等 意匠権 民事訴訟 平成23年03月28日 知的財産高等裁判所
以上を前提として,明細書のすべての記載や,その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮すると,本件発明が本件作用効果i)を奏する上で,蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たすことは明らかであって(段落【0009】【0020】等参照),『受枠には凹部が存在すれば足り,凹曲面部は不要である』との控訴人の主張は正当であると認められ,本件発明において,受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれないというべきである。なお,明細書の段落【0020】には,『閉蓋状態において,受枠上傾斜面部と蓋上傾斜面部および受枠下傾斜面部と蓋下傾斜面部は嵌合し,蓋凸曲面部と受枠凹曲面部および蓋凹曲面部と受枠凸曲面部は接触しないようにする』という構成を採ることにより,本件作用効果ii)を奏する旨記載されており,ここでは受枠の凹部が『曲面部』であるかどうかは問題とされていないといえ,本件作用効果ii)を奏する上でも,受枠の凹部が『曲面部』であることは本質的部分には含まれないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2011.02. 1
平成21(ワ)18507 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成23年01月21日 東京地方裁判所
前記(ア)のとおり,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件発明の「載置部」は,座面の周縁部を少しの高さだけ下方に湾曲させて周縁部に形成した部分であり,先端縁,両側縁部及び後縁部から構成されている。そして,i)「載置」とは,「物の上に他の物を置くこと」を意味すること(「特許技術用語集(第3版)」(日刊工業新聞社)67頁),ii)「幼児用補助便座」は,便器付属の便座に載置して使用する構成のものを指すこと(本件明細書の段落【0001】)からすれば,本件発明の「載置部」は,便器付属の便座の上に補助便座を置く部分をいい,換言すれば,補助便座において便器付属の便座の上面に接する部分を意味するものと解される。一方で,本件明細書の記載(前記(イ))によれば,本件発明は,従来の便座の構造は,座面全体を水平かつ平滑に形成し,排泄のための透孔部分のみを座面から透孔内周面に向かって円弧状に湾曲形成しただけのものであったが,近時の便座は,保温機能\や暖房機能を付加し,あるいは洗浄機能\付きのものは後方部分が上方に傾斜した形状となり,また,便座面の湾曲形状が前面位置と,後面位置では湾曲の態様を別異に形成したり,あるいは座面の外側位置から内周位置に向かって徐々に傾斜させるなど複雑な座面形状を採用したものがあり,これらの近時の便座の構造に対応するものであることに照らすと,本件発明は,座面全体を水平かつ平滑に形成した従来構\造の便座だけではなく,様々な座面の形状を有する近時の便座に対応することを前提とするものといえるから,本件発明の「載置部」は,その構成部分(先端縁,両側縁部及び後縁部)の全体が便器付属の便座の上面に接することまで想定したものではなく,少なくともその構\成部分の一部が便座の上面に接する部分として規定されているものと解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
2011.02. 1
平成22(ネ)10031 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成23年01月31日 知的財産高等裁判所
上記記載によれば,構成要件C1の「・・・後方側の壁面は,前記上側段部と前記中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面となっている」は,従来技術においては,前後の壁面の上部に上側段部が,深さ方向の中程に中側段部が形成されている流し台のシンクでは,上側段部と中側段部のそれぞれに,上側あるいは中側専用の調理プレートを各別に用意しなければならないという課題があったのに対して,同課題を解決するため,後方側の壁面について,上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とをほぼ同一の長さに形成して,それら上側段部と中側段部とに,選択的に同一のプレートを掛け渡すことができることを図ったものである。ところで,上記記載における「発明の実施形態」では,後方側の壁面は,上側段部から中側段部に至るすべてが,奧方に向かって延びる傾斜面であり,垂直部は存在するわけではない。しかし,本件明細書中には,「本発明は,上述した実施の形態に限定されるわけではなく,その他種々の変更が可能\である。・・・また,シンク8gの後方側の壁面8iは,上側段部8fと中側段部8nとの間が,第2の段部8bを経由して,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる上部傾斜面8pとなっていなくとも,上側段部8fと中側段部8nとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう,奥方に延びるように形成されているものであればよく,その形状は任意である。」と記載されていることを考慮するならば,後方側の壁面の形状は,上側段部と中側段部との間において,下方に向かうにつれて奥方に向かってのびる傾斜面を用いることによって,上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にすることができるものであれば足りるというべきである。そうすると,構成要件C1の「前記後の壁面である後方側の壁面は,前記上側段部と前記中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面となっている」とは,後方側の壁面の形状について,上側段部と中側段部との間のすべての面が例外なく,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面で構\成されている必要はなく,上側段部と中側段部との間の壁面の一部について,下方に向かうにつれて奥行き方向に傾斜する斜面とすることによって,上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にするものを含むと解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2011.01.27
平成21(ワ)25303 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年12月22日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2011.01.26
平成20(ワ)13709 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年12月24日 大阪地方裁判所
ところで,物の製造方法に係る特許についての特許権侵害が主張されている本件においては,侵害していると主張される製造方法について主張立証責任を負うのは,特許権者である原告であって被告ではないが,被告が積極的に明らかにして立証した被告製品の製造方法が矛盾に満ちていたり,不自然不合理であったりするため信用できないような場合には,そのことが翻って原告主張の製造方法の立証を補強することになる場合もあり得るところである。
イ そこで,以上の観点から,被告による被告製品底部がロ号方法により製造された旨の立証についてみると,証拠(乙16ないし24,検証の結果)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,本件訴訟における立証のため,直接取引をしていた貿易会社を介して被告製品を製造していた安諾靴工業有限公司(中華人民共和国)に対し,被告製品の製造方法を明らかにするよう求めたところ,ロ号方法によって製造していることが開示されたこと,さらに同工場において,その明らかにした製造方法であるロ号方法を用いて,被告製品と同様の靴を製造させたところ,その靴(以下「再現製品」という。)の底部外周部に形成された突状部分は,被告製品のそれに比べやや太いものの,突条の隆起の程度等を含めそれ以外の点では被告製品と概ね同様の形状であることが認められる(なお,原告は,安諾靴工業有限公司が被告製品の製造者であることも争っているが,証拠(乙18ないし乙24(枝番号を含む。))に加え,再現製品の靴が,その外観形状のみならず,その素材が被告製品と同じであり,さらには中敷きには被告製品と同じロゴが印刷されていることからすると,同工場が,被告製品を実際に製造していた工場であることは十分認められるというべきである。)。したがって,被告製品の直接の製造者ではない被告としては,被告製品の製造方法がイ号方法ではないことを明らかにするため,積極的にこれと異なるロ号方法である旨の主張立証は尽くしており,またその補強として,ロ号方法によって被告製品同様の製品が製造されることの立証も尽くしているということができる。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
2011.01. 7
平成21(ワ)34337 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年12月24日 東京地方裁判所
構成要件Fにおける「操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され」とは,「操作体が元姿勢に位置するときに可動歯の先端が固定歯の先端から離間する方向の回動(円運動)が規制(制限)される」ことを,「操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するよう揺動する」とは,操作体を復帰弾機に抗して強制移動することにより,上記規制(制限)をとりやめ,「可動歯の先端を固定歯の先端から離間して拡開するよう揺動させる」ことを意味するものと認められる。もっとも,本件明細書の特許請求の範囲請求項1には,回動規制を達成するために必要な具体的な構\成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能\的,作用的な表現を用いて記載されている場合において,当該記載から直ちに当該機能\ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解することは,明細書に開示されていない技術思想に属する構\\成までもが発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず,相当でない。したがって,特許請求の範囲に上記のような機能的,作用的な表\現が用いられている場合には,特許請求の範囲の記載だけではなく,明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し,そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。
・・・
上記発明の詳細な説明の記載及び図面によれば,本件発明は,操作者が指掛け部から指を離す,すなわち,操作部を操作しない状態において,魚の口(下顎)をしっかり挟持することができ,魚掴み操作の操作性が向上することを,効果として狙ったものであり(段落【0005】),その効果を奏するために,魚が釣れた場合,魚掴み器の握り部を把持した状態で操作体の引き上げ操作をして可動歯を固定歯から拡開させ,魚の針掛かりしている口の下顎を挟むようにしていずれかの歯を入れ,操作体を離すと,可動歯が揺動して閉じて下顎を両歯で挟持することになり,この状態で針を外せば,魚体を触ることなく針外しができ,魚にダメージを与えることがないという手法(段落【0017】)をとったものと認められる。・・・そうすると,構成要件Fの「回動規制」の技術的意義は,復帰弾機の付勢力によらずに,ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構\\成を採用し,操作体が元姿勢に位置していること自体によって,可動歯が動かないようにすることにあると認められる。
(5) 被告製品は,・・・別紙図面1及び別紙図面2のとおり,操作体をコイル弾機に抗して右方向に強制移動させると,上記回動規制の状態を脱し,可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するものであることが認められる。そうすると,被告製品における上記構成は,本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されたところの,操作体に左方向(固定歯向きの左方向)の力が掛かった際に,ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と,技術思想を同じくするものであると解され,当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて採用し得る範囲内の構\成であるといえる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 機能クレーム
>> 102条2項
2010.12.21
平成21(ワ)36145 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟平成22年12月03日 東京地方裁判所
以上のとおり,本件明細書の上記イの記載及び図示は,上記アの文言解釈と整合するものであり,これらの記載及び図示を考慮しても,本件発明は,構成要件Bで生成された番組ディレクトリ(記録された番組の位置を含んでいる。)をそのまま構\成要件Dで表示するものであると解釈するのが相当である。・・・他方,被告製品については,「録画番組一覧表\」において,「記録された番組の前記ディレクトリ」に含まれる情報のうち「記録された番組のタイトル」を表示していることは認められるものの,「記録された番組の位置」を表\示しているとは認められない。すなわち,被告製品では,番組を記録する記録媒体として,先頭から順次アクセスするテープではなく,任意の位置にランダムにアクセスすることが可能なHDDを利用しているのであるから,「録画番組一覧表\」に表示されている順序は,HDD上での記録位置とは何らの関連がないものであり,その他,本件全証拠を検討しても,被告製品について,「記録された番組の位置」を表\示していることを認めることはできない。オ したがって,被告製品方法は,本件発明の構成要件Dを充足するものと認めることはできない。2 以上のとおり,被告製品方法は,本件発明の構成要件Dを充足するものと認めることはできないから,被告製品は本件発明の方法の使用に用いられる物ということはできず,その製造,販売が特許法101条5号のみなし侵害に該当するということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2010.12.21
平成21(ワ)35184 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟平成22年12月06日 東京地方裁判所
以上のような被告サーバー及び本件携帯端末の構成からすれば,被告装置においては,現在地及び目的地を入力・設定して,経路探索を行い,その結果をディスプレイに表\示してユーザーに伝達するために,被告サーバーと本件携帯端末が,それぞれ次の機能を分担しているものと認められる。・・・以上のとおり,被告装置は,被告サーバーと本件携帯端末とによって構\成され,両者がそれぞれ機能を分担してナビゲーション機能\を果たしていることから,このような被告装置が「車載ナビゲーション装置」ということができるか否か,すなわち,本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」が,複数の機器に機能が分担され,かつ,その機器の一部が車両に搭載されていないものを含むか否かが問題となる。・・・・証拠(甲22ないし25)によれば,「車載」という語の一般的な意義は,「車に積みのせること」をいうと認められる。また,弁論の全趣旨によれば,「装置」という語の一般的な意義は,「ある目的のために機械・道具等を取り付けること。そのしかけ。」をいい,一定の機能\を持ったひとまとまりの機器をいうと認められる。エ検討(ア) 前記ウの「車載」及び「装置」という語の一般的な意義からすれば,「車載ナビゲーション装置」とは,車両に載せられたナビゲーションのための装置(ひとまとまりの機器)をいい,ひとまとまりの機器としてのナビゲーション装置が車両に載せられていることを意味すると解するのが,自然である。そして,本件各特許の特許請求の範囲の記載のように,A,B,C,Dとの「手段を含むことを特徴とする車載ナビゲーション装置」というとき,「ナビゲーション装置」がA,B,C,Dという手段を備えるとともに,そのような手段を備えたナビゲーション装置が「車載」,すなわち,車に載せられていることが必要であると解するのが,その文言上,自然である。また,本件各明細書に開示されている「車載ナビゲーション装置」の構成は,前記イのとおり,各構\成要素から成る一体の機器としての「車載ナビゲーション装置」であって,被告装置における被告サーバーと本件携帯端末のように,車両内の機器と車両外の機器にナビゲーション装置の機能を分担させ,両者間の交信その他の手段によって情報の交換を行い,全体として「ナビゲーション装置」と同一の機能\を持たせることは開示されていない。したがって,各機器をどのように構成し,また,各機器にどのように機能\を分担するか,各機器間の情報の交換をどのような手段によって行うかについても,本件各明細書には何らの開示もされていない。さらに,本件各特許発明はナビゲーション「装置」に関する特許発明であるから,「装置」の構成が特許請求の範囲に記載された構\成と同一であるか否かが問題となるのであって,同一の機能,作用効果を有するからといって,構\成が異なるものをもって,本件各特許発明の技術的範囲に属するということはできないことはいうまでもない。以上のことからすれば,本件各特許発明にいう「車載ナビゲーション装置」とは,一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であり,車両に載せられていない機器は,「車載ナビゲーション装置」を構成するものではないと解される。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 間接侵害
>> コンピュータ関連発明
2010.12. 7
平成21(ワ)13824 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年11月25日 大阪地方裁判所
このように,原告は,出願時明細書の段落【0033】ないし段落【0037】に記載された「フラップ部周囲領域」を「一の領域」に該当するものとして上記の特許請求の範囲の補正をしたことが明らかであるから(なお,補正後の特許請求の範囲の記載によれば,一の領域はフラップ部を備えるとされているから,フラップ部周囲領域とフラップ部を併せたものが一の領域とする趣旨であると考えられる。),かかる出願の経緯にかんがみれば,特許請求の範囲に記載された「一の領域」の意義については,出願時明細書の上記各段落に対応する本件明細書の記載部分(段落【0033】ないし段落【0037】)における「フラップ部周囲領域」に関する記載を参酌して解釈するのが相当である。(ウ) そこで,本件明細書の段落【0033】ないし段落【0037】について見てみると,本件明細書の上記各段落には,フラップ部周囲領域は,フラップ部周囲を取り囲む領域であり,蓋体本体部の外周輪郭形状を定める周縁領域と中間領域によって接続されていること,フラップ部周囲領域は,中間領域に対して上方に隆起しているが,その隆起は周縁領域の隆起よりも低いこと,フラップ部周囲領域には,フラップ部に形成された突起部と嵌合する開口部,フラップ部を収容する下方に窪んだ凹領域と,凹領域に隣接して形成されるとともに凹領域よりも深く窪んだ凹部を備えていることが記載されている。本件明細書のかかる記載は,特許請求の範囲から理解される「一の領域」の上記意味内容と整合するものであり,とりわけ,フラップ部周囲領域が上面(最も高い面)から窪んだ領域として凹領域に加えて凹部を備えていると記載されていることからすれば,「一の領域」は凹領域以外に窪んだ領域を有する態様を含むものと理解するのが素直である。そして,本件明細書の他の記載を見ても,「一の領域」あるいは「フラップ部周囲領域」に関して,上記で検討した意味内容と異なるような説明をしている個所は見当たらない。(エ) したがって,本件特許発明にいう「一の領域」とは,周縁部により囲まれる領域内部において,周縁部から離間して隆起し,空気抜き穴と,空気抜き穴を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部と,フラップ部を収容する凹領域を備える,周縁部の隆起よりも低い領域を意味し,凹領域のほかに一の領域の上面(最も高い面)から窪んだ領域を有する態様も含むものと解するのが相当である。(オ) そして,以上に基づいて「一の領域の縁部」の意義について検討すべきところ,「縁」とは字義的には「へり。ふち。」を意味し(広辞苑第6版),また本件明細書(段落【0034】,図1及び図2)においても,フラップ部の基端部がフラップ部周囲領域のへりの部分に接続している態様が記載されているから,「一の領域の縁部」とは要するに「一の領域」のへりの部分を指すものと解される。(カ) 以上の解釈を総合すると,構成要件Eにいう「前記フラップ部は,前記一の領域の縁部に一体的に接続する基端部を備える」とは,周縁部により囲まれる領域内部において,周縁部から離間して隆起し,空気抜き穴と,空気抜き穴を閉塞可能\な突起部を備えるフラップ部と,フラップ部を収容する凹領域を備える,周縁部の隆起よりも低い領域を意味し,凹領域のほかに一の領域の上面(最も高い面)から窪んだ領域を有する態様も含む「一の領域」のへりの部分にフラップ部が一体的に接続する基端部を備えていることを意味するものと解するのが相当である。
・・・・
以上を総合すると,本件各特許発明は,蓋体にフラップ部を設けるという公知の構成を前提に,煩雑な製造プロセスを要することなく製造可能\であり,蓋体からフラップ部が外れることのない蓋体を提供することを目的として,フラップ部が「一の領域の縁部」に一体的に接続する基端部を備えるという構成を採用したものであり,この点に本件各特許発明の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分があると認められ,上記構\成が本件各特許発明の本質的部分であると解される。そうすると,被告各製品のフラップ部が「一の領域」の縁部ではなく,その内部に一体的に接続する基端部を備えているという相違点は,本件各特許発明の本質的部分に係る相違というべきであることになるから,被告各製品は,本件特許の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものという原告の主張は採用できないことになる。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2010.12. 7
平成21(ワ)7718 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年11月30日 東京地方裁判所
原告は,焼き上がった後の切り込み部が「忌避すべき焼き形状とならない」ことについて述べる本件明細書の記載(段落【0034】等)は,単に「側周表面」に設けられた切り込み部が忌避すべき焼き形状とならないことを指摘したものにすぎず,「載置底面又は平坦上面」に切り込み部を設けるか否かについて何ら言及するものではない旨主張する。しかしながら,前記ア(イ)で述べたとおり,本件明細書には,加熱時の膨化による噴き出しを制御するための切り込み部を餅の表面(切餅では平坦上面)に設けた場合には,「人肌での傷跡のような焼き上がりとなり,焼き上がり形状が忌避すべき状態となってしまい,切餅への実用化がためらわれる」という従来の課題を踏まえ,当該切り込み部を,平坦上面の場合に比べて見えにくい上に,オーブンによる火力が弱い位置である「側周表\面」に設けたことによって,「焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することが記載されていることに照らすならば,原告の上記主張は,理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2010.12. 7
平成21(ワ)7718 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年11月30日 東京地方裁判所
原告は,焼き上がった後の切り込み部が「忌避すべき焼き形状とならない」ことについて述べる本件明細書の記載(段落【0034】等)は,単に「側周表面」に設けられた切り込み部が忌避すべき焼き形状とならないことを指摘したものにすぎず,「載置底面又は平坦上面」に切り込み部を設けるか否かについて何ら言及するものではない旨主張する。しかしながら,前記ア(イ)で述べたとおり,本件明細書には,加熱時の膨化による噴き出しを制御するための切り込み部を餅の表面(切餅では平坦上面)に設けた場合には,「人肌での傷跡のような焼き上がりとなり,焼き上がり形状が忌避すべき状態となってしまい,切餅への実用化がためらわれる」という従来の課題を踏まえ,当該切り込み部を,平坦上面の場合に比べて見えにくい上に,オーブンによる火力が弱い位置である「側周表\面」に設けたことによって,「焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することが記載されていることに照らすならば,原告の上記主張は,理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2010.11.30
平成19(ワ)10364 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年11月18日 大阪地方裁判所
以上のように,「単孔円筒状」の語義及び構成要件Cの数値限定の趣旨からすれば,「単孔円筒状」とは,貫通した孔を有する形状と解するのが自然であること,本件明細書において外側と内側から燃焼する形状として開示されているものは図1に示すような形状のみであり,他の形状について何らの開示や示唆もないこと,図1に示すような形状のほかに,本件特許発明の作用効果を奏する形状が当業者において自明であったとも認めがたいことに照らすと,構\成要件Bにおける「単孔円筒状」とは,1つの貫通した孔を有する円筒状の形状,すなわち図1のような形状を指すものと解するのが相当である。・・・そして,証拠(甲53)によれば,被告各製品のガス発生剤成型体が本件形状である以上,目視で孔を確認することはできない。また,証拠(乙109)によれば,被告各製品のガス発生剤成型体は,・・・を通すことにより,連続して両側から押し潰しながら切断し,乾燥して製造していると認められ,このような過程で製造された被告各製品のガス発生剤成型体は,通常は,その両端が押し潰されており,孔は開いていないものと考えられる。このように,本件形状のガス発生剤成型体には,そもそも孔が開いていないのであるから,構成要件Bにおける単孔円筒状に該当するとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2010.11.10
平成20(ネ)10056 各損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成22年10月25日 知的財産高等裁判所
原判決が被控訴人製品における「暗号化された固定値」は本件発明の構成要件B2ないしB4にいう「番号識別子」に該当しないから本件発明の技術的範囲に属さないとしたのと異なり,同製品は上記構\成要件のB2ないしB4要件における「番号識別子」は充足するもののB3要件における「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」は充足しないから,結局,被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属さないと判断する。その理由は,以下に述べるとおりである。・・・c 上記記載によれば,本件発明の課題はコンテンツの著作権保護を図ることにあり(段落【0003】),本件発明は,メモリカード等の外部記憶媒体に対するデータの記録・読出しが可能な携帯電話機において,外部記憶媒体に記録したデータが,その記録を行った携帯電話機の電話番号以外の電話機で利用されるのを禁止できるようにすることを目的とするものである(段落【0004】,【0023】)。そして,本件特許明細書に「番号識別子」を定義付ける記載はないが,特許請求の範囲には,「前記自局電話番号を識別するための番号識別子」との記載があり,また,本件特許明細書には,「請求項1記載の発明によれば,外部記憶媒体に記録されるデータには,自局電話番号に固有の番号識別子が関係付けられ,関係付けられた番号識別子が携帯電話機の自局電話番号に該当しない場合には,データの読出しが禁止される。」(段落【0006】)との記載がある。したがって,本件発明の特許請求の範囲に記載されている「番号識別子」の解釈としては,外部記憶媒体に記録したデータがその記録を行った携帯電話機の電話番号以外の電話機で利用されるのを禁止することを目的に,携帯電話機の自局電話番号がその記録を行った携帯電話機の自局電話番号であることを識別するためのものであるから,「自局電話番号がその記録を行った携帯電話機の自局電話番号であることを識別するとの目的を達成し得る機能\を有するもの」と解するのが相当である。・・・・被控訴人製品は,前記のとおり,所定の「固定値」をコンテンツデータの記録を行う携帯電話機の自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成された暗号鍵を用いて暗号化した記号(暗号化された固定値)をコンテンツデータに関係付けてSDカード(外部記憶媒体)に格納し,暗号化されたコンテンツを外部記憶媒体から読み出す前に,読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより復号鍵を生成し,「暗号化された固定値」を正しく所定の「固定値」と一致する値に復号することができた場合に暗号化されたコンテンツの読出しと復号を行うものであるから,上記のとおり正しく復号することができた場合は,記録を行った携帯電話機の自局電話番号及びその他の情報と,読出しを行う携帯電話機の自局電話番号及びその他の情報とが同一であると判定するものである。そうすると,「暗号化された固定値」は,コンテンツの読出しを行おうとする携帯電話機の自局電話番号等により生成された復号鍵により所定の「固定値」に復号されるか否かが判定されることにより,「自局電話番号がその記録を行った携帯電話機の自局電話番号であることを識別する」との目的を達成し得る機能があるから,本件発明の「番号識別子」に相当すると認めるのが相当である。よって,被控訴人製品は,構\成要件B2を充足する。
ウ B3要件該当性の有無
(ア) 「番号識別子が自局電話番号に該当するか否かを判定する」の意義B3要件は,前記のとおり「前記記録読出し手段が前記外部記憶媒体からデータを読み出す前に,そのデータに関係付けられて記録された番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する手段」とするものであるが,その素直な文理解釈からすると,そこでいう「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」とは,本件発明の実施例のごとく,番号識別子と自局電話番号とを直接対比して一致するか(該当するか)どうかを判別することを意味し,それ以上に,番号識別子によって携帯電話機の自局電話番号がその記録を行った携帯電話機の自局電話番号であるかどうかを判別する(番号識別子によって,データを記録した携帯電話機の自局電話番号が,データを読み出そうとする携帯電話機の自局電話番号に一致するか〔該当するか〕否かを判定する)ことも含んでいるとまでは意味しないと解するのが相当である。(イ) 被控訴人製品への当てはめa 本件発明の「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」とは,上記のとおり,外部記憶媒体に記録されているデータ(番号識別子)自体を直接の判断対象として,それが読出しを行おうとする携帯電話機の自局電話番号に当てはまるかどうか(一致するかどうか)の判定を行うこと,言い換えれば,番号識別子と自局電話番号とを直接対比して一致するか(該当するか)どうかを判別することを意味するところ,被控訴人製品においては,所定の「固定値」をコンテンツデータの記録を行う携帯電話機の自局電話番号等から生成された暗号鍵を用いて暗号化した記号(暗号化された固定値)が,読出しを行う携帯電話機においてその自局電話番号等から生成された復号鍵により正しく所定の「固定値」と一致する値に復号できるかどうかを見ることにより,記録を行った携帯電話機の自局電話番号と読出しを行う携帯電話機の自局電話番号が同一であるか否かを(いわば間接的に)判定するものであり,「番号識別子」である「暗号化された固定値」を直接の判断対象としてコンテンツデータの読出しを行おうとする携帯電話機の自局電話番号に当てはまるかどうか,言い換えれば「暗号化された固定値」と携帯電話機に記憶された自局電話番号を直接対比して一致するか(該当するか)どうかを判断するものではない。そうすると,被控訴人製品は,構成要件B3を充足しないというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2010.11. 9
平成20(ワ)36307 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年10月29日 東京地方裁判所
以上の検討によれば,原告主張の被告製品の走査型電子顕微鏡(SEM)観察,化学分析及び被告作成の竣工図等の記載から,被告製品の最外層に相当量のPTFEが存在することを認めることはできないというべきである。他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告製品は,本件発明1の構成要件Cを充足しないから,本件発明1の技術的範囲に属するものとは認められない。\n
2010.10.23
平成21(ワ)5717 損害賠償請求事件 特許権 平成22年10月15日 東京地方裁判所
。 (1)で説示したように,本件特許発明における「文法辞書」とは,現代仮名遣いの文法規則並びに歴史的仮名遣いの文法規則及び各仮名遣いに対する漢字候補を統合的に登録した「ファイル」であり,「ファイル」として仮名漢字変換部によって参照されるものであるが,被告装置における文法辞書の一部である「活用語尾テーブル」は,ファイルα(ATOK21W.IME)に格納されているデータではあるものの,仮名漢字変換に当たり参照される際にはメインメモリ上に展開されており,「ファイル」として存在するものではないため,被告装置の仮名漢字変換部は,「ファイル」としての「文法辞書」を参照するものと認めることはできない。そうすると,被告装置は,本件特許発明の構成要件B〜Dの上記「『ファイル』として仮名漢字変換部によって参照される」「文法辞書」の構\\成を有しないものであるから,上記構成要件を充足するものとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2010.09.16
平成21(ワ)1986 特許権 民事訴訟 平成22年08月31日 東京地方裁判所
本件発明の特許請求の範囲の記載中には,偶数番グローバルワードラインに対応する複数のローカルワードラインと奇数番グローバルワードラインに対応する複数のローカルワードラインとを交互に配置する旨の文言はなく,また,一般論として,特許発明の技術的範囲は,実施例に記載された構成に必ずしも限定されるものではない。しかしながら,原告が主張するようにグローバルワードラインに対応するローカルワードラインの並び順は問わないと解すると,本件発明には,例えば,前記ウの本件発明の実施の形態において,偶数番グローバルワードライン(EGWLi)に,順に並んだローカルワードライン(WL0ないしWL7)のうちWL0,WL1,WL2,WL3を対応させる構\成も含まれることになる。このような構成の下で,仮にWL2が選択される場合について考えると,前記ウ(コ)記載のとおり,選択されなかったローカルワードラインWL0,WL1及びWL3は,フローティング状態となるから,ローカルワードラインWL2の電位が選択電位に上昇すると,カップリング効果により,同じ偶数番グローバルワードラインに属する他のローカルワードラインWL0,WL1及びWL3の電位も一斉に上昇することになり,メモリ装置として正常に動作しない状態になってしまうことは明らかである。このような場合に生じるカップリングの問題を解決するための具体的な手段は,本件明細書中には一切開示されておらず,その解決手段が自明であると認めるに足りる証拠もない。
2010.08. 3
平成22(ワ)9664 補償金請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年07月22日 大阪地方裁判所
特許権に基づく独占権は,新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるものであるから,このように特許請求の範囲の記載が機能的,抽象的な表\現にとどまっている場合に,当該機能ないし作用効果を果たし得る構\成すべてを,その技術的範囲に含まれると解することは,明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含ましめて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが,そのような解釈は,発明の開示の代償として独占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきである。したがって,特許請求の範囲が上記のように抽象的,機能\的な表現で記載されている場合においては,その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず,上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し,そこに開示された具体的な構\成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきであり,具体的には,明細書及び図面の記載から当業者が実施できる構成に限り当該発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。・・・以上のとおり,本件明細書には,地震時ロック装置において,前後又は左右の方向で規定される地震のゆれによって係止体がその後部において回動が妨げられ,扉等が開き停止位置を超えてそれ以上開く動きを許容しない状態を生じさせるための具体的構\成としては,装置本体の震動エリアに収納された球により地震時に係止体の回動を妨げる構成が開示されていることが認められるが,それ以外の構\成は記載されておらず,またそれを示唆する記載もない。また,本件明細書の【背景技術】にも,従来技術として地震時ロック方法が紹介されているが,それはゆれによって球が動くことにより地震を検出するものであって,他に,振動エリア内に収容した球を用いる以外の構成を示唆するような記載は一切認められない。したがって,本件明細書には,装置本体の振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げるという技術思想だけが開示されているというべきである。以上によれば,本件明細書の記載から当業者が実施できる構\成は,振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成だけというべきであるから,かかる構\成に限り本件特許発明の技術的範囲に含まれる(構成要件Cを充足する)と解するのが相当である。\n
2010.07.26
平成22(ワ)4486 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年07月08日 大阪地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2010.06. 8
平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 その他 民事訴訟 平成22年05月27日 知的財産高等裁判所
特許出願人が出願公開後に第三者に対して特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後,特許請求の範囲を含めて補正がされた場合,その補正は,願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を明瞭にし又は減縮するものに限られ,拡張することは許されないから,補正がされることによって,発明の技術的範囲に属しなかった製品が,技術的範囲に属するようになることは想定できない。したがって,警告後に補正がされることによって第三者に対して不意打ちを与えることはないから,再度の警告を発しないと不意打ちに当たるというような特段の事情(そのような特段の事情を想定することは困難ではあるが)がない限り,補償金請求の前提としての警告をした後,補正がされたからといって,再度の警告をしなければならない理由はないといえる。・・・・被告は,警告が発せられたのは,補正前の特許請求の範囲に基づくものであるから,これに基づく補償金請求には,均等の手法による技術的範囲の解釈は適用されない旨を主張する。しかし,前記のとおり,本件特許の各補正は,特許請求の範囲を減縮し又は明瞭にする目的の範囲にとどまるものであること,被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについては,補正後の設定登録を経由した発明の技術的範囲に基づいて判断していることに照らすならば,被告の上記主張は,理由がない(なお,被告製品の具体的態様に照らすならば,本件各補正の内容は,被告製品が本件発明の技術的範囲に含まれるか否かの争点(均等を前提とした技術的範囲の解釈を含む。)に関係するものではないし,いわゆる侵害論において,このような観点からの当事者の主張もされていない。)。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 均等
2010.05.24
平成21(ネ)10055 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成22年03月30日 知的財産高等裁判所
以上によれば,本件訂正発明は,従来の無線電話装置と,携帯型コンピュータとGPS利用者装置とをすべて携帯することができず,かつ相互を組み合わせてそれらを複合した機能を得ることができないとの課題を解決するために,複合した機能\を,実用的に得ることを目的とするものである。そうすると,本件訂正発明は,携帯型の情報装置がこれらの装置の機能を複合させた機能\を有することに特徴があり,機能の一部を他のサーバ等に置くことを想定したものということはできない。そして,前記認定の本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,「携帯型コミュニケータ」は,CPUを備えた携帯コンピュータと無線電話装置とGPS利用者装置とを備えるとともに,地図情報を備えた地図データROMが接続されており,CPUにより実行される最寄発信処理においては,まず,現在位置の座標と発信先の名称が入力され,次に,地図データROMから現在位置から最も近い発信先番号を選択する処理を行い,それは,現在位置の座標と地図データROMから読み込まれた地図情報とに基づいて選択しているものと認められる。したがって,「選択手段」による「発信先番号の選択」は,携帯コンピュータのCPUが,携帯型コミュニケータ自体で取得できるデータを用いて,発信先番号の選択に係る処理を実行することを指すと解するのが相当である。・・・,本件訂正発明における「携帯コンピュータ」が,「位置座標データ入力手段の位置座標データに従って,所定の業務を行う複数の個人,会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」との構\成を被告製品における上記処理手段に置換することは,解決課題及び解決原理が異なるから,置換可能性はないものというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
2010.05.14
平成21(ワ)2208等 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年04月15日 大阪地方裁判所
以上の事実を総合すれば,本件2ピークは,白金ホルダーピークであるとしても説明が困難でなく,かつ,検出の原因として,白金ホルダーの使用以外には考えにくいから,白金ホルダーピークであると考えるのが合理的である。そうすると,本件2ピークは,本件発明の特定のためには余分な事項であるが,それにもかかわらず,特許請求の範囲に,その回折角及び強度が記載されていることになり,特許請求の範囲中,本件2ピークに係る記載は,事後的・客観的にみれば,誤った記載というべきである。誤記のなかには,特許法上の訂正審判や訂正の請求による訂正を待つまでもなく,誤記であることを前提として,特許請求の範囲を解釈することができる場合も存在するが,本件2ピークの記載は,単なる誤記(表記上の誤り)とは性格を異にする。すなわち,本件特許出願に際し,原告は,本件2ピークが本件エステル塩酸塩一水和物結晶のピークであると信じ,特許請求の範囲として表\示しようとしたとおりのクレームをしているのであって,後に,その信じていたところが誤りであったことが判明したに過ぎないと認めるのが相当である(原告が本件2ピークが本件エステル塩酸塩一水和物結晶のピークではなく,白金ホルダーのピークであると認識していたのであれば,その旨を本件明細書に記載したはずである。)。出願時において要件とした事項であっても,後に,実際には不要であったことが判明することは,一般に生じ得る事態であるが,特許請求の範囲の記載を前提とする第三者の行為は,このような出願人の調査不足や不注意によって規制されるべきではない。
・・・・ 本件明細書には「S-, 1108塩酸塩無水物は容易に水一分子を吸収して本発明のS-1108塩酸塩一水和物となる。」(段落【0021】),「S-1108塩酸塩無水物‥‥は吸水性で粉末化,製剤化などの操作中に部分的吸湿が起きて含水量が変動する」(段落【0003】)との記載がある。また,P2 准教授作成の鑑定意見書(乙8)では,本件標準品について,105℃から110℃付近まで昇温すると,水1分子が離脱して,本件明細書記載の本件エステル塩酸塩無水物結晶となり,この無水物結晶を大気中で室温まで降温すると,水1分子を吸収して,本件明細書記載の本件エステル塩酸塩一水和物結晶となることが明らかにされている。そうすると,本件エステル塩酸塩の結晶は,高温状態に置いて無水物結晶としない限りは,一水和物結晶の状態にあるといえる。そして,本件エステル塩酸塩水和物結晶が1種類しかないことは原告自身が主張し,立証するところであるから(甲19),前記イの工程により得られた本件エステル塩酸塩の結晶は,すなわち本件エステル塩酸塩一水和物の結晶であるといえる。
2010.05.11
平成20(ワ)18866 特許権侵害に基づく補償金請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年04月27日 東京地方裁判所
本件発明の特許請求の範囲の前記記載に上記本件明細書の記載及び図面(図面はすべて基礎杭は地表から突出しているものである。)を参酌するならば,本件発明において,「基礎杭」は,「コンクリート基礎」よりも低い位置に地表\がある斜面(傾斜面)に立設され,受梁とコンクリート基礎との上に床版を設置できるように「受梁」を当該斜面の地表より高い位置(コンクリート基礎と同じか又はこれに近い高さ)に支持するために斜面の地表\から突出しているものを指し,本件発明は,このように斜面の地表から突出して立設された基礎杭が地震等の水平力に対して構\造上弱いため,基礎杭上に設置された受梁とコンクリート基礎とを床版を介して連結することによって,基礎杭の耐震性能を向上させたものであると解するのが相当である。イ 被告構\造において,谷側鋼管杭が地中に埋まっており,その上に設置された谷側コンクリート構造物は地表\上に現場打ちコンクリートにより設置されたものであることは当事者間に争いがない。原告は,被告構造が構\成要件A−1「傾斜面に複数の基礎杭を立設し」を充足する理由として,本件工事において谷側鋼管杭は傾斜面に立設されたもので,その後,傾斜面に盛土を行うことにより水平面に整正されたものであると主張する。これに対し,被告及び補助参加人は,本件工事では掘削等によって水平面を作出した場所に谷側鋼管杭を没入させたものであり,谷側鋼管杭は傾斜面に立設されたものではない,と主張して争っている。原告は,谷側鋼管杭が傾斜面に立設されたことの証拠として,乙第11号証の1及び4の写真,丙第2号証の平面図及び横断図「断面え」,乙第2号証の金山地区構造物設計業務報告書の図面を挙げる。しかしながら,乙第11号証の1の写真は,既に谷側鋼管杭及び山側鋼管杭が没入された後のものであって,この写真からは谷側鋼管杭の没入時の地形がどのようなものであったのかは明らかではない。また,乙第11号証の4の写真は,6ブロックの谷側鋼管杭の1つであるPT12(別紙杭配置図参照)の設置工事状況を示すものであるものの,この写真によっても,同設置場所が傾斜面であると認めることはできず,かえって,同号証とPT12の設置工事状況を別の角度から撮影した丙第7号証とを合わせて見ると,PT12の谷側鋼管杭は,草木を除去して地表\を水平に整正した場所に設置されていることを認めることができる。・・・・ウ 以上のとおりであるから,原告の挙げる前掲各証拠によっては,本件工事において谷側鋼管杭が傾斜面に立設されたことも,その後に盛土により傾斜面が水平面に整正されたことも認めることはできず,他にこれらの事実を認めるに足りる証拠はない。かえって,前記のとおり,本件工事においては,掘削等によって水平面が作出され,その水平面に谷側鋼管杭が立設されたものと認められる。そうすると,被告構造において,谷側鋼管杭が傾斜面に立設されたとも,地表\面から突出しているともいうことはできないから,被告構造は,構\成要件A−1の「傾斜面に複数の基礎杭を立設し」を充足しないというべきである。
2010.05. 7
平成20(ワ)18566 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年04月23日 東京地方裁判所
平成5年7月15日付け本件特許出願の願書(甲5)に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」という。)の特許請求の範囲は,前記第2,2(10)アのとおり,コンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1〜5)とコンベア高さ調節を構\成要件として含む請求項(6)とが記載されていたところ,前記第2,2(2)のとおり,本件特許発明1(請求項1)又は本件特許発明2(請求項2)は,いずれもコンベア高さ調節を構成要件として含み(構\成要件E,G’),その余の請求項(3,4)も請求項1,2の従属項であるからコンベア高さ調節を構成要件として含み(甲2),したがって,本件明細書の特許請求の範囲からは,コンベア高さ調節を構\成要件として含まない発明はなくなっている。そして,コンベア高さ調節に係る構成要件E及び構\成要件G’が,特許庁での審査段階で審査官から通知された拒絶理由(乙2)に対応して,出願人たるAが当該拒絶理由を回避しようと意識的に加えたものであることは,前記第2,2(10)イ,ウの出願経過から明らかである。この認定に反する原告の主張は,前記第2,2(10)イ,ウに認定した手続補正書(甲6,乙3)及び意見書(甲7,乙9)の記載自体からみて,採用することができない。そうとすれば,Aのした上記補正は,コンベア高さ調節を含まない構成を意識的に除外したものと認められるから,コンベア高さ調節を含まない構\成である被告方法又は被告装置は,均等の第5要件を充足しないものというべきである。(2) 原告の主張についてア原告は,本件特許発明がすべてコンベア高さ調節を構成として含む発明になったのは,当初明細書に開示されていたコンベア高さ調節を構\成として含む発明を本件特許発明に取り込んだことによって生じた結果にすぎず,コンベア高さ調節を含まない構成を除外しようとしたことによるものではない旨を主張する。しかしながら,Aは,平成11年10月22日付け手続補正書(乙3)により,当初明細書のコンベア高さ調節を構\成要件として含まない請求項(1〜5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていた特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構\成要件として含むものに限定したことが,前記第2,2(10)に認定した出願経過から外形的に明らかであるところ,そうである以上,補正に際しての出願人の主観的意図にかかわらず,特許権者が後にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
2010.04.22
平成19(ワ)35324 特許権侵害差止請求 特許権 民事訴訟 平成22年03月31日 東京地方裁判所
本件特許の特許請求の範囲の各請求項は,物の発明について,当該物の製造方法が記載されたもの(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)である。ところで,特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づき定めなければならない(特許法70条1項)ことから,物の発明について,特許請求の範囲に,当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにもかかわらず,あえて物の製造方法が記載されている場合には,当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でないと解される。他方で,一定の化学物質等のように,物の構\\成を特定して具体的に記載することが困難であり,当該物の製造方法によって,特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ない場合があり得ることは,技術上否定できず,そのような場合には,当該特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定して解釈すべき必然性はないと解される。したがって,物の発明について,特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には,原則として,「物の発明」であるからといって,特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく,当該特許発明の技術的範囲は,当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって,物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり,当該物の製造方法によって,特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限り,当該製造方法とは異なる製造方法により製造されたが物としては同一であると認められる物も,当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。⑵ そこで,本件において,前記(1)の「特段の事情」があるか否かについて,検討する。・・・以上述べたように,本件特許の請求項1は,「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり,エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」と記載されて物質的に特定されており,物の特定のために製造方法を記載する必要がないにもかかわらず,あえて製造方法の記載がされていること,そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯(特に,出願当初の特許請求の範囲には,製造方法の記載がない物と,製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていたが,製造方法の記載がない請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受けたことにより,製造方法の記載がない請求項をすべて削除し,その結果,特許査定を受けるに至っていること。)からすれば,本件特許においては,特許発明の技術的範囲が,特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定されないとする特段の事情があるとは認められない(むしろ,特許発明の技術的範囲を当該製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な事情があるということができる。)。したがって,本件発明1の技術的範囲は,本件特許の請求項1に記載された製造方法によって製造された物に限定して解釈すべきであるから,次のとおりと解される。
2010.04.14
平成18(ワ)28244 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年03月25日 東京地方裁判所
以下,構成要件1Hの共通報知の解釈について,本件明細書1の記載を考慮しつつ検討する。
ア 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載によれば,構成要件1Gにおいて「前記可変表\\示開始手段によって前記可変表示が開始され,前記可変表\\示停止手段によって前記可変表示が停止される1回の遊技の中で,前記入賞態様決定手段で決定された入賞態様に対応した報知情報を所定確率で遊技者に報知する報知手段を備え」と定め,これを受けて構\\成要件1Hは,構成要件1Gの「入賞態様に対応した報知情報」を共通報知とその後の報知からなるものに限定するものであることは明らかであり,そうすると,2つの異なる報知態様の各組合せが入賞態様に対応していることが必要であると解される。そして,ハズレを含むすべての入賞態様に共通する演出については,その後の報知と合わせた報知全体として入賞態様の絞り込みが行われたとしても,それはその後の報知が入賞態様に対応していることによる結果にすぎず,ハズレを含むすべての入賞態様に共通する演出とその後の報知との組合せが入賞態様に対応しているとみることは困難である。そうすると,共通報知というためには,それ単独であっても,入賞態様を絞り込むことのできる情報を有していなければならず,ハズレを含むすべての入賞態様に共通する演出のような入賞態様を絞り込む情報を有しない演出については,共通報知に当たらないものと解するのが自然である。・・・上記のとおり,本件明細書1及び図面中には,遊技開始時に鳴る2種類の遊技開始音と,その後の各リール停止時における複数のリールランプ消灯パターンの組合せに対応して報知当選フラグが割り当てられ,「遊技が進行して行くのに伴って入賞態様が判明して行く」ものが開示されており,共通報知もそれ単独で,入賞態様の絞り込みができるものとなっている。また,発明の効果について「報知は各入賞態様に対して行われるため,例えば,停止ボタンの操作等が容易に行えるようになる」とし,これは共通報知により入賞態様について一定の絞り込みがされることを前提とした記載であると解される。このような本件明細書1及び図面の記載に鑑みても,共通報知というためには,それ単独であっても,入賞態様を絞り込むことのできる情報を有していなければならず,配当のない当選役(ハズレ)を含むすべての入賞態様に共通する演出のような入賞態様を絞り込む情報を有しない演出については,共通報知に当たらないものと解するのが相当である。・・・・以上のとおり,被告物件の各演出は,いずれも,共通報知を備えないか,又は,共通報知を備えていても,その後の報知を備えないものであるから,被告物件は,構\\成要件1Hを充足するものと認めることができず,本件発明1の技術的範囲に属するものということはできない。・・・・,本件発明2は,報知態様を遊技状態及び当選フラグを参照して選択するとされていたものを,現在の特許請求の範囲のとおり訂正されたのであって,この訂正は,遊技状態及び当選フラグを参照する方法について,これらの変数からなるデモ抽選テーブル選択テーブルを参照してデモ抽選テーブルを選択し,抽選値と乱数値を演算する方法に限定することで,特許請求の範囲を減縮するものである。すなわち,構成要件2Eは,報知態様を遊技状態及び当選フラグを参照して選択するという機能\\を果たすために,その計算処理過程を具体的に規定するものということができる。論理的には,遊技状態及び当選フラグの組合せごとにテーブル番号が割り当てられた表(デモ抽選テーブル選択テーブル)と,抽選値に報知態様が割り当てられた表\\(デモ抽選テーブル)とを1つの表に統合することは可能\\であり,かつ,これらのテーブルは,遊技状態,当選フラグ及び乱数という3つの変数によって報知態様を決定するという1つの機能を果たしていると見ることが可能\\なものである。そうであるにもかかわらず本件発明2において,デモ抽選テーブル選択テーブルとデモ抽選テーブルを別個のテーブルと位置付けていることに照らすと,本件発明2における「テーブル」は,論理的又は機能的に見て該当性を判断するのではなく,複数の変数から1つの値を抽出するための表\\を指し,あるアドレスの範囲において複数の変数から1個の値が抽出され,その抽出された値と他の変数を用いて別のアドレスの範囲において別の値が抽出される場合は,それぞれが別個のテーブルであるというべきである。以上のような解釈を前提とすると,原告が「デモ抽選テーブル選択テーブル」に当たると主張する被告物件の2つのアドレス範囲(アドレス0EC3C74Hないし0EC3F8BH及びアドレス0EC3180Hないし0EC3C73H)は,これを一体として本件発明2における「テーブル」に当たるとは評価することができず,被告物件が「デモ抽選テーブル選択テーブル」を具備するものと認めることはできない。エ また,2つのアドレス範囲を一体として「テーブル」と評価することができないことを措いたとしても,以下のとおり,被告物件は,構成要件2E−1を充足するものとは認められない。・・・以上のとおり,被告物件が「デモ抽選テーブル選択テーブル」を具備するものと認めることはできないから,その余の点について判断するまでもなく,被告物件は,本件発明2の技術的範囲に属するものということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2010.04. 5
平成17(ワ)26473 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年02月26日 東京地方裁判所
(ア) 特許法102条1項ただし書は,侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が「販売することができないとする事情」があるときは,同項本文の損害額から,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする旨規定している。被告は,本件においては,本件訂正発明の実施の有無が需用者の購買の動機付けとなっていないこと,原告各製品の市場におけるマーケットシェアを超える部分は,他の製品が代替して販売されたものと評価すべきであること,被告の営業努力,ブランド力及び販売力などの事情が存在し,これらの事情は,原告が原告各製品を「販売することができないとする事情」に該当するので,上記事情に相当する数量に応じた額を原告主張の損害額から控除すべきである旨主張する。・・・・以上・・事情を総合考慮すると,前記ア(ウ)認定の被告各製品の譲渡数量のうち,60%に相当する数量については,被告の営業努力,ブランド力,他社の競合品の存在等に起因するものであり,被告による本件特許権の侵害がなくとも,原告が原告各製品を「販売することができないとする事情」があったものと認めるのが相当である。したがって,前記ア(ウ)認定の被告各製品の譲渡数量のうち,60%に相当する数量に応じた額を,原告の損害額から控除すべきである。(イ)a これに対し被告は,原告各製品(5種類)が特許法102条1項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」であることを前提に,その「単位数量当たりの利益の額」を基に損害額を算定する以上,同項ただし書の「販売することができないとする事情」としての市場におけるマーケットシェア(市場占有率)を考慮する際には,上記5種類の原告各製品の市場占有率に限定すべきであり,当該市場占有率を超える部分は,他の製品が代替して販売されたものと評価すべきである旨主張する。しかし,i)ゴルフメーカー各社の営業努力及びブランド力は,市場占有率に反映されているといえるが,それを適切に評価するためには,ゴルフボール全体の市場占有率を考慮するのが相当であると考えられること,ii)本件においては,原告各製品と競合する他社メーカーの具体的な製品についての市場占有率に関する主張がされていないなど,被告各製品の譲渡数量のうち,原告各製品の市場占有率を超える部分は他の製品が代替して販売されたものと評価できることを基礎付ける事情はうかがわれないことに照らすならば,被告の上記主張は採用することができない。b また,被告は,原告各製品及び被告各製品の販売において,本件訂正発明の対象である添加剤の使用は,一切ユーザーには知らされておらず,本件訂正発明の使用の有無により,ユーザーが被告各製品の購買の動機付けとなることはあり得ないから,本件訂正発明の実施の有無が需用者の購買の動機付けとなっていないことを,原告が「販売することができないとする事情」として考慮すべきである旨主張する。しかし,前記(ア)b認定のとおり,ユーザーがゴルフボールを選択する際,ゴルフボールの性能(飛距離性能\,スピン性能等)を重視する傾向にあるといえるが,一般のユーザーはゴルフボールの性能\を発揮する原因となるゴルフボールを構成する具体的な成分等については特段の関心を抱いていないものとうかがわれることに照らすならば,原告各製品及び被告各製品の販売において本件訂正発明の対象である添加剤の使用がユーザーには知らされていないことを,前記ア(ウ)認定の被告各製品の譲渡数量を原告が「販売することができないとする事情」として考慮すべき余地はないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 限定解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
2010.03.31
平成21(ネ)10055 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成22年03月30日 知的財産高等裁判所
当裁判所は,被告製品は本件訂正発明の構成要件gの「選択手段」を具備せず,また,被告製品は,本件訂正発明の均等物ではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。・・・本件訂正発明の特許請求の範囲には,「上記携帯コンピュータは,・・・\n上記ディスプレイに表示された所定の業務名を文字画像で示す発信先一覧から選択された選択項目の名称に基づき,上記位置座標データ入力手段の位置座標データに従って,所定の業務を行う複数の個人,会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段と,・・・を備え」と記載されている。上記特許請求の範囲の記載によれば,「選択」は,「所定の業務を行う複数の個人,会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号」を対象としているが,「所定の業務を行う複数の個人,会社あるいは官庁」の発信先番号等の情報取得態様及び選択態様について,必ずしも明確であるとはいえない。そこで,本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参酌する。・・・以上によれば,本件訂正発明は,従来の無線電話装置と,携帯型コンピュータとGPS利用者装置とをすべて携帯することができず,かつ相互を組み合わせてそれらを複合した機能\を得ることができないとの課題を解決するために,複合した機能を,実用的に得ることを目的とするものである。そうすると,本件訂正発明は,携帯型の情報装置がこれらの装置の機能\を複合させた機能を有することに特徴があり,機能\の一部を他のサーバ等に置くことを想定したものということはできない。そして,前記認定の本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,「携帯型コミュニケータ」は,CPUを備えた携帯コンピュータと無線電話装置とGPS利用者装置とを備えるとともに,地図情報を備えた地図データROMが接続されており,CPUにより実行される最寄発信処理においては,まず,現在位置の座標と発信先の名称が入力され,次に,地図データROMから現在位置から最も近い発信先番号を選択する処理を行い,それは,現在位置の座標と地図データROMから読み込まれた地図情報とに基づいて選択しているものと認められる。したがって,「選択手段」による「発信先番号の選択」は,携帯コンピュータのCPUが,携帯型コミュニケータ自体で取得できるデータを用いて,発信先番号の選択に係る処理を実行することを指すと解するのが相当である。以上からすると,被告製品においては,専らナビタイムサーバが,そのデータベースを用いてディスプレイに表示される発信先番号の「選択」に係る検索処理を実行しており,被告製品は,地図情報も備えておらず,構\成要件gの「選択手段」に相当する検索処理を実行することなく,単に,施設カテゴリーの選択及び現在位置情報の送信と検索結果の取得のみを行っている。したがって,被告製品は,構成要件gの「選択手段」を具備するものではなく,同構\成要件を充足しない。・・・(ア) 原告は,構成要件gは,どのメモリ領域から電話番号を選択すべきかについて何らの限定も付していないから,ネットワークのいずれの記憶領域であっても,同構\成を充足する旨主張する。しかし,構成要件gは,前記のとおり,携帯コンピュータのCPUが,携帯型コミュニケータ自体で取得できるデータを用いて,発信先番号の選択に係る処理を実行する技術を提供するものであるから,これを外部のコンピュータにデータ処理を指令して,これが送り返される態様を含むものではない。したがって,原告の主張は,理由がない。(イ) 原告は,本件訂正明細書の段落【0074】,【0104】の記載には,構成要件gでは,先方のコンピュータにデータを処理を指令してこれが送り返される技術が開示されていると主張する。しかし,原告が指摘する本件訂正明細書の段落【0074】,【0104】の記載は,電話が接続されている相手方との間でデータ交換をするというにすぎず,一方のCPUで行うべき処理を接続先のコンピュータに命令して実行させ,その結果を得るとの技術事項は記載されていない。また,上記【0074】,【0104】の記載は,構\成要件gの「選択手段」に関する記載ではなく,前記認定の本件訂正明細書の記載に他の通信装置に指令を送りデータを受け取る場合についての記載や示唆は認められない。原告の上記主張は理由がない。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成20(ワ)12952 平成21年07月10日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2010.03.29
平成20(ネ)10085 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成22年03月24日 知的財産高等裁判所
被控訴人が本件特許権の侵害主体であるか否かについて検討する。本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」とされており,上記2(1)アのとおり,本件発明に係る特許請求の範囲の記載から,本件発明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの情報ページ」に対するものであることが明らかである上,構成要件BないしFに規定される各段階は,本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解されるから,このような本件発明の実施主体は,上記のような「アクセスを提供する方法」の実施主体であって,被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である。(2) この点について,被控訴人は,被控訴人方法を使用しているのはパソコンのユーザーであって,被控訴人ではないから,被控訴人は本件発明の実施主体ではないとして,本件特許権を侵害していないと主張するが,その主張は,要するに,「アクセス」はクライアント(ユーザーのパソ\コン)によって行われる行為であるから,本件発明の実施主体は,インターネットよりなるコンピュータネットワークのユーザーであるクライアントであって,被控訴人ではないという趣旨に解される。しかしながら,上記のとおり,本件発明は「アクセス」の発明ではなく,「アクセスを提供する方法」の発明であって,具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない。また,本件発明に係る「アクセスを提供する方法」が提供されている限り,クライアントは,被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり,クライアントの主体的行為によって,クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり,ならなかったりするものではないから,クライアントの個別の行為を待って初めて「アクセスを提供する方法」の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。そうすると,被控訴人による「アクセスを提供する方法」が本件発明の技術的範囲に属するのである以上,被控訴人による被控訴人方法の提供行為が本件発明の実施行為と評価されるべきものである。(3) そして,甲60及び弁論の全趣旨によると,平成21年10月19日の時点において,被控訴人は現に被控訴人方法を実施していることが認められるから,被控訴人は本件特許権を侵害する者であると認められる。したがって,控訴人は,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人方法による被控訴人サービスの提供の停止を請求するとともに,同条2項に基づき,被控訴人サービスに供された「NLIA サーバー」の除却及び「登録情報データベース」の消去を請求することができるといわなければならない。なお,控訴人は「NLIA サーバー」及び「登録情報データベース」のいずれについても除却を求めているが,「NLIA サーバー」について,これが除却の対象となり得るかどうかは同サーバーの設置・管理の状況によるものであり,共用サーバーの一部が当該サーバーとして利用されている場合,サーバー全体の除却ではなく,当該利用部分がその機能を果たさなくなるようにプログラムを削除したり消去したりすることによって対応すべきものである。上記において「NLIA サーバー」の除却とは,上記のような意味を含むものである。また,「登録情報データベース」については,「データベース」の性質上,除却の対象になじまないと考えられるところ,控訴人の請求はデータベースの機能を喪失させることを求めるものと解されるから,上記のとおり,同データベースの消去を認めるのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2010.03.16
平成21(ワ)5610 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年02月24日 東京地方裁判所
「そこで,構成要件C1の技術的意義を検討する。まず,特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないところ(特許法70条1項),特許請求の範囲に記載された用語の意義は,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈すべきであるから(特許法70条2項),構\成要件C1の意義を解釈するに当たっては,本件明細書中の「前記後の壁面である後方側の壁面は,前記上側段部と前記中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面となっている」との記載部分及びこれに関連する記載部分について検討するとともに,後記(2)のとおり,【請求項1】(本件発明1)は,本件特許の出願経過において,構成要件C1の部分が補正されているから,この点についても,併せて検討する必要がある。て特許請求の範囲に記載していたところ,特許庁審査官から,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとの拒絶理由通知を受け,【請求項1】を,「前後の壁面の,上部に上側段部が,深さ方向の中程に中側段部が形成されて,前記上側段部および前記中側段部のいずれにも同一のプレートを,掛け渡すようにして載置できるように,前記上側段部の前後の間隔と前記中側段部の前後の間隔とがほぼ同一に形成されてなり,かつ,前記後の壁面である後方側の壁面は,前記上側段部と前記中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面となっていることを特徴とする流し台のシンク。」と補正し,出願当初の【請求項1】の構\成のうち,構成要件C1の構\成を有するものに限定することにより,特許庁審査官の指摘した特許法29条2項の規定に該当するという拒絶理由を回避して,特許査定を受けたものであることが認められる。エ 以上のような本件明細書の記載,図面及び出願経過に照らせば,「前記後の壁面である後方側の壁面は,前記上側段部と前記中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面となっている」(構成要件C1)という構\成は,後方側の壁面の傾斜面が,中側段部によりその上部と下部とが分断されるように後方側の壁面の全面にわたるような,本件明細書に記載された実施形態のような形状のものに限られないと解されるものの,その傾斜面は,少なくとも,下方に向かうにつれて奥方に向かって延びることにより,シンク内に奥方に向けて一定の広がりを有する「内部空間」を形成するような,ある程度の面積(奥行き方向の長さと左右方向の幅)と垂直方向に対する傾斜角度を有するものでなければならないと解するのが相当である。したがって,構成要件C1の「下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面」とは,上側段部と中側段部との間において,下方に向かうにつれて奥方に延びることにより,奥方に向けて一定の広がりを有する「内部空間」を形成するような,ある程度の面積と傾斜角度を有する傾斜面を意味すると解するのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2010.02. 5
平成20(ワ)14169 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年01月27日 東京地方裁判所
このように,イソブチレン−無水マレイン酸共重合体は,無水マレイン酸環が全く開環しておらず,その開環により生ずるイソ\ブチレン−無水マレイン酸共重合体のアンモニウム塩とは,化学構造を異にするだけでなく,水溶性の点においても,その性質を異にする別異の物質である。したがって,本件発明の特許請求の範囲の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」(訂正後の「イソ\ブチレン−無水マレイン酸共重合体」)との用語の一般的な意義から,直ちに,化学構造を異にするだけでなく,水溶性においてもその性質を異にする別異の化学物質である「そのアンモニウム塩」が含まれると解することはできない。そこで,次に,本件明細書中の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」,「イソ\ブチレン−無水マレイン酸共重合体」についての記載を検討する。・・・原告は,請求項1の訂正に伴い,本件明細書の中の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」との記載部分のうちの対応部分を,「イソブチレン−無水マレイン酸共重合体」と訂正しているが,「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」は,「イソ\ブチレン−無水マレイン酸共重合体」を含むものであり,原告自身,この請求項1の訂正は,特許請求の範囲の減縮するものとしているのであるから(甲14),この訂正請求による特許請求の範囲,明細書の記載の訂正がされるか否かにより,「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」又は「イソブチレン−無水マレイン酸共重合体」に,その塩や中和物が含まれないという上記解釈が左右されるものではない。ウ この点,原告は,本件明細書3欄26〜31行の記載が,ゼラチンとオレフイン−無水マレイン酸共重合体のそれぞれを水溶液にして,しかも,中性にした状態で混合して反応させることを前提としており,オレフイン−無水マレイン酸共重合体又はイソ\ブチレン−無水マレイン酸共重合体を水溶液とするために,それを中和物とすることは慣用的な技術にすぎないから,本件発明の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」又は本件訂正発明の「イソブチレン−無水マレイン酸共重合体」は,その塩を除外しておらず,むしろこれを含むことを前提としており,「イソ\ブチレンーマレアミド酸アンモニウム共重合体」もこれに含まれると主張する。しかしながら,前記( )の1 とおり,イソブチレン−無水マレイン酸共重合体と,これをアンモニア変性させた「イソ\ブチレン−マレアミド酸アンモニウム共重合体」などの「イソブチレン−無水マレイン酸共重合体」のアンモニウム塩とは,その化学構\造や性質を異にする別異の物質であるから,直ちに,後者が前者に含まれると解釈することはできない。また,本件明細書は,前記アのとおり,ゼラチンとオレフイン−無水マレイン酸共重合体の反応方法として,それぞれの水溶液をあらかじめ調製した後,両者を混合することが,均一なゲルを得やすく好ましい方法として推奨するものにすぎず,そのような反応方法が推奨されているからといって,当初の成分である「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」にその塩や中和物が含まれるものと解することはできない。しかも,原告の指摘する本件明細書3欄26〜31行には,オレフイン−無水マレイン酸共重合体を中和するという記載は一切なく,かえって,本件明細書3欄29,30行の「反応時のpHは5〜9」との記載からは,pH5の酸性でもよい結果が得られるとも理解し得るのであって,この記載のみから,本件明細書の「オレフイン−無水マレイン酸共重合体」あるいは「イソブチレン−無水マレイン酸共重合体」が,その塩を含むことを前提としているとか,アルカリにより中和された中和反応物を含むことを示していると解釈することも困難である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2009.10.13
平成20(ワ)25354 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> 数値限定
2009.09.15
平成19(ワ)16025 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年09月10日 大阪地方裁判所
「特許請求の範囲において,加減圧手段は,「レンジ室内と連通されレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返す加減圧手段」というように,加減圧という作用,機能面に着眼して抽象的に記載されているだけであって,加減圧手段の具体的な構\成は明らかにされていない。このように,特許請求の範囲の発明の構成が機能\的,抽象的な表現で記載されている場合に,当該機能\ないし作用効果を果たし得る構成がすべてその技術的範囲に含まれるとすれば,明細書に開示されていない技術的思想に属する構\成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねず,特許権に基づく独占権が当該特許発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになり,相当でない。そこで,本件特許発明1の技術的範囲を確定するに当たっては,本件明細書1の発明の詳細な説明及び図面を参酌し,そこに開示された加減圧手段に関する記載内容から当業者が実施し得る構成に限り,その技術的範囲に含まれると解するのが相当である。・・・・本件明細書1には,上記調圧器5の具体的構\成や,それがいかなる作用,機能を有するものであるかについて,一切開示されておらず,当業者にとっても「調圧器5」がいかなる構\造,機能を有するものであるかを理解することはできない(本件明細書1の【図面の簡単な説明】の欄には「ポンプ4」が, 「加減圧手段としてのポンプ」と記載されているのに対し,「調圧器5」は単に「調圧器」と記載されているだけである。)。そして,本件明細書1には,加減圧手段として採り得る他の構成は開示されおらず,また,他の構\成を採用し得ることについての示唆もない。してみると,本件明細書1で加減圧手段として開示されている具体的構成は,気密室6を構\成する外枠1に接続された管路に接続し,ポンプ4の作動により,加圧と減圧を繰り返すものである。以上によれば,本件明細書1の発明の詳細な説明及び図面を参酌して,その記載内容等から当業者が実施し得る加減圧手段の構成は,ポンプ4のようなそれ自体の作動により加圧及び減圧を繰り返すことができるようなもの,すなわち,加熱手段によるレンジ室内の加熱に伴う圧力変化とは無関係にそれ自体の作動によりレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返し行うものと解するのが相当である」。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 限定解釈
>> 機能クレーム
2009.09. 9
平成20(ワ)19402 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年08月31日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
2009.09. 2
平成20(ワ)3277 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟 平成21年08月27日 大阪地方裁判所
「・・・原告は,構成要件Eの「枠台」の解釈において,裏返し脱型作業するという製造工程までも構\成要件とする方法の発明ではないとも主張する。たしかに,本件特許発明は特許法2条3項1号の物の発明と解されるところ,それにもかかわらず,特許請求の範囲に物の製造方法(構成要件E及びF)が記載されている。そこで,本件特許発明における構\成要件E及びFの位置づけについて最初に検討することとする。ア 特許法2条3項1号の物の発明において特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合であっても,原則として,同製造方法により得られる物と同一であれば,これと異なる製造方法を用いて製造された物であっても,同特許発明の技術的範囲に属するというべきである。しかしながら,証拠(乙18)によれば,本件特許に係る出願経過について,以下の事実が認められる。「・・・本件補正のうち,構成要件Bの金属線材受け入れ孔を設けることについては,もともと出願当初の特許請求の範囲【請求項2】に記載されていたものであり,同請求項に係る上記拒絶理由通知においても「結束用金属線材受け入れ孔を設けることは,引用文献2にも記載されている。」と指摘されているところである。また,原告も上記意見書においてこの点を特段強調してもいない。これに対し,成形キャビティを用いたコンクリートブロックの成形及び陥没数字の賦形手段については,上記意見書においても,原告が従来技術との相違点として特に強調していた点であり,本件補正がなされたことによって特許査定がなされていることからすれば,特許庁審査官も,その当否は措くとして,この点を考慮して特許査定したものと認められる。そうとすれば,原告が本件特許権を行使するに当たり,本件特許発明は物の発明であって,構\成要件E及びFの製造工程を構成要件とするものではないと主張することは,禁反言の法理に照らして到底許されるものではないというべきである。ウ よって,構\成要件E及びFの製造工程も,本件特許発明の技術的範囲を画する構成要件と解すべきであり,ここに記載された製造工程によって製造された鉄筋用スペーサーのみが本件特許発明の技術的範囲に属し得るものというべきである」
2009.08.27
平成20(ネ)10068 特許権侵害差止控訴事件 特許権 民事訴訟 平成21年08月25日 知的財産高等裁判所
控訴人は,拒絶査定不服審判の請求の理由として,「切削の対象が正方形または長方形の半導体ウェーハであること…が関連しあって,…独特の作用効果を奏するものである。仮に,切削対象が不定型なワークであるとすると,…」と記載し(乙8の17),その後,本件発明に係る特許出願は,特許査定された(乙8の19)。(ウ) 上記(ア)認定の本件明細書の記載に照らせば,控訴人は,被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外,フェライト等が存在することを想起し,半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず,本件発明の特許請求の範囲には,あえてこれを「半導体ウェーハ」に限定する記載をしたものということができる。また,上記(イ)認定の出願経緯に照らしても,控訴人は,圧電基板等の切削方法が開示されている引用発明1(乙9)との関係で,本件発明の切削対象物が「正方形または長方形の半導体ウェーハ」であることを相違点として強調し,しかも,切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどして,本件発明においては意識的に「半導体ウェーハ」に限定したと評価することができる。このように,当業者であれば,当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず,控訴人は,切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し,切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから,外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。(エ) そうすると,被控訴人方法は,均等侵害の要件のうち,少なくとも,前記5の要件を欠くことが明らかである。ウ均等侵害の要件4についてまた,仮に,被控訴人方法が「半導体ウェーハ」以外の本件発明の構成要件を充足するとすると,後記2(1)で判示するのと同様に,被控訴人方法も,引用発明1から容易に推考することができるというべきであるから,均等侵害の要件のうち,前記4の要件も欠くことに帰する 関連事件はこちらです
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
>> 第5要件(禁反言)
>> 間接侵害
>> 104条の3
2009.08. 7
平成20(ネ)10080 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成21年07月29日 知的財産高等裁判所
「原告らは,被告方法においては,「承諾しMUSIC.JP300に登録」 をクリックすることによって,当該携帯電話機から一旦MTIサーバに対し, 当該携帯電話機を特定する情報と30コイン分の楽曲の代金が315円である であるという情報とを含む30コイン分の楽曲が購入できる30コインの発行 を希望する希望信号を発信し,これを受信したMTIサーバは,当該携帯電話 機を特定する情報が記録されているか否かを判断していると主張する。 しかし,本件全証拠によっても,被告方法が,マイメニュー登録の段階で, MTIサーバが携帯電話機から上記の希望信号を受信した後に,当該携帯電話 機を特定する情報がMTIサーバのデータベースに記録されているか否かを判 断した上で当該携帯電話機をiモードサーバに接続させる処理経路が採用され ていることを認めることはできない。」 1審判断はこちらです
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2009.08. 2
◆平成20(ワ)8611 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年06月30日 大阪地方裁判所
「原告は,物理的,構造的な観点から構\成部分の一体性を判断するのであれば,本件特許発明も構成全体が一体ということになってしまい不合理であるから,機能\と位置を基準に各構成部分を判断するほかない,被告製品のA部分6’と補強片9’の機能\は異なるとして,両部分は独立した構成部分であると主張する。確かに,本件特許発明の掛止部材においては,構\造的に連続する周縁部,アーム部及び舌片部がそれぞれ別の構成部分とされており,構\成部分の区分に当たっては機能と位置が重視されているものと解されるところ,被告製品のA部分6’と補強片9’(保持部分)とは構\造的に連続しているだけではなく,上記のとおり,袋本体2’に一体的に貼着されているため,一体として把手部5’とともに袋本体2’を対向する2面からそれぞれ外向けに互いに反対方向に引っ張り,袋本体2’の開口部8’の開口形状を良好に維持し,袋本体2’の表\裏の矩形面2’a,2’bが撓んで開口部8’が閉ざされるのを防止するという共通の機能を有するのであるから,機能\的にも両部分を切り離して捉えることはできない。」
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2009.07.22
◆平成19(ワ)27187 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟 平成21年07月15日 東京地方裁判所
「被告は,原出願の拒絶査定に対する審判手続及び原出願審決に対する審決取消訴訟手続では,原告が,「テレビジョン番組リスト」の用語を「個々の番組単位における番組情報」の意味では使用しておらず,各手続における特許庁の主張及び裁判所の判決においても,「テレビジョン番組リスト」とは,テレビジョン番組のタイトルのリスト,すなわち,テレビジョン番組のタイトルが並んだものと解されているから,本件発明における「テレビジョン番組リスト」の文言についても,「テレビジョン番組のタイトルが並んだもの」を意味すると解すべきであり,分割出願に係る本件特許権による権利行使の際に,同用語の意義を違えて主張することは,信義則に基づく禁反言法理から許されないと主張する。しかしながら,分割出願制度は,一つの出願において二つ以上の異なる発明の特許出願をした出願人に対し,出願を分割する方法により,各発明につき,それぞれ元の出願の時に遡って出願がされたものとみなして特許を受けさせるものであるから,原出願で特許出願された発明と,分割出願で特許出願された発明は,本来,内容を異にするものであり,分割出願された発明の「特許請求の範囲」に記載された文言の解釈が,原出願の手続における文言の解釈と必ずしも一致する必要はないというべきである。したがって,本件特許の「テレビジョン番組リスト」の文言の解釈において,仮に,原出願の拒絶査定に対する審判手続及び原出願審決に対する審決取消訴訟手続において使用された「テレビジョン番組リスト」の文言の意味とは異なる解釈をしたとしても,禁反言法理から許されないとはいえず,被告の上記主張は採用できない。」
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
2009.07.15
◆平成20(ワ)12952 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年07月10日 東京地方裁判所
「構成要件Fは,「位置座標データ入力手段の位置座標データに基づいて,所定の業務を行う複数の個人,会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段とを備え」と規定されているところ,ここにいう「選択手段」とは,CPU及びプログラムがなし得る機能\を意味するにすぎず,当然に特定の処理を指し示すものではないから,その意義は特許請求の範囲からは一義的に明らかなものとはいえない。そこで,本件明細書の記載を参酌すると,本件明細書には次のとおりの記載がある(甲2)。・・・・以上からすると,本件特許発明1の「選択手段」とは,現在位置の位置座標データに基づいて最も近い施設を選択し,それと関連付けて記憶されている,同施設の発信先番号を取り出すことであり,また,「選択手段」による処理は,「携帯コンピュータ」自体のCPUが実行するものであって,「選択手段」は「携帯コンピュータ」自体が備えるものであると解釈するのが相当である。・・・以上からすると,被告製品の「選択手段」による処理は,ナビタイムサーバが実行しているものであって,被告製品においては,「選択手段」を「携帯コンピュータ」自体が備えてはいないものと認められる。したがって,被告製品は,構成要件Fを充足するものということはできない。」
◆平成20(ワ)12952 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年07月10日 東京地方裁判所
以下は、原告vs携帯電話会社との過去の事件です
◆平成15(ワ)28554 平成16年10月01日 東京地方裁判所
◆平成15(ワ)28575 平成16年10月01日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
2009.07.10
◆平成19(ワ)22715 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年06月30日 東京地方裁判所
「燕窩の含水溶剤抽出物」の製造方法としては,「燕窩乾燥物の粉砕品を,1〜 1000 倍重量,好ましくは5〜 500 倍重量,より好ましくは10 〜 100 倍重量の含水溶剤中において,0〜 180 ℃,好ましくは室温〜 120 ℃の範囲の温度において,10 分〜 50 時間,好ましくは1〜8時間抽出処理する」ものであり,「抽出処理は,常圧下および加圧下のいずれで行ってもよく,抽出装置としては,加熱抽出機等が利用できる」こと,抽出処理に用いる含水溶剤の例としては,「例えば,水を始め,水と水混和性有機化合物との混合物が用いられ,水混和性有機化合物としては,メタノールなどが挙げられる」こと,成分としては,「通常タンパク質が40 〜 80 重量%,糖質が20 〜 60 重量%およびシアル酸が0.1 〜 15 重量%の割合で含有されている」こと,作用としては,「優れた保湿作用、皮膚細胞におけるコラーゲン合成促進作用及び良好な皮膜形成能を有しており、皮膚に対して極めて安全性が高い」ことなどが説明されているにとどまり,燕窩の含水溶剤抽出に際し,単に目的物(燕窩中の成分)を抽出相(水や水と水混和性有機化合物との混合物)に溶解させて抽出する方法のほかに,タンパク分解酵素による加水分解反応等の化学変化を起こさせる方法も採り得ることや,このように化学変化を起こさせる方法により燕窩から取り出した物質が,燕窩から水等によって抽出した物質と同様の成分,作用を有することなどを示唆する記載は,存在しないことが認められる。また,本件明細書中には,「含水溶剤」及び「抽出物」という用語について,酵素を用いた加水分解のように,燕窩の中の成分に適当な化学変化を起こす場合をも含むものである旨の,格別の定義は記載されていない。したがって,本件明細書の記載からも,特許請求の範囲に記載された「燕窩の含水溶剤抽出物」は燕窩の酵素分解物を含むものであると解釈することは,困難である。」
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2009.07. 9
◆平成19(ワ)22715 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年06月30日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
2009.06.30
◆平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成21年06月29日 知的財産高等裁判所
「以上のとおりであり,本件発明の構成要件(d)における「(繊維強化プラスチック製の)縫合材」と被告製品の構成〈d〉における「(炭素繊維からなる)短小な帯片8」とは,目的,作用効果(ないし課題解決原理)を共通にするものであるから,置換可能性がある。(2)置換容易性 本件発明においても,被告製品においても,金属製外殻部材に設けられた貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことは共通であり,金属製外殻部材の複数の貫通穴に複数回通し,少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材を,一つの貫通穴に1回だけ通し,金属製外殻部材の上下において上部繊維強化プラスチック製外殻部材及び下部繊維強化プラスチック製外殻部材と各1か所で接着する部材に置き換えることは,被告製品の製造の時点において,当業者が容易に想到することができたものと認められる。したがって,置換容易性は認められる。(3)非本質的な部分か否かについて本件発明の目的,作用効果は,前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載によれば,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある。特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと,本件発明は,金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け,貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことによって上記目的を達成しようとするものであり,本件発明の課題解決のための重要な部分は,「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成にあると認められる。本件発明の特許請求の範囲には,接合させる部材について,「縫合材」と表\現されている。しかし,既に詳細に述べたとおり,i)本件発明の課題解決のための重要な部分は,構成要件(d)中の「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成部分にあること,ii)本件発明の「縫合材」の語は,繊維強化プラスチック製の部材を金属製外殻部材に通す形状ないし態様から用いられたものであって,通常の意味とは明らかに異なる用いられ方をしているから,「縫合」の語義を重視するのは,妥当とはいえないこと,iii)前記のとおり,「縫合材」の意味は,技術的な観点を入れると,「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し,かつ,少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材」と解すべきであるが,当該要件中の「一つの貫通穴ではなく複数の(二つ以上の)貫通穴に」との要件部分,「少なくとも2か所で(接合(接着)する)」との要件部分は,本件発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえないこと等の事情を総合すれば,「縫合材であること」は,本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的,特徴的な部分であると解することはできない。したがって,本件発明において貫通穴に通す部材が縫合材であることは,本件発明の本質的部分であるとは認められない。」
◆平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成21年06月29日 知的財産高等裁判所
原審はこちらです
◆平成19(ワ)28614 平成20年12月09日 東京地裁
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
2009.05.13
◆平成18(ワ)16119 特許権侵害差止 特許権 民事訴訟 平成21年04月22日 東京地方裁判所
「原告は,上記の事項を立証するために,種々の実験を行い,その実験の内容及び結果を説明した書面を証拠として提出しているが(甲4,5,19,20),それらの実験の実験方法に対しては被告から様々な問題点が指摘され,また,専門委員を交えた争点整理手続において,最適な実験方法についての協議がされ,上記の被告の指摘及び争点整理手続における協議の内容を踏まえて,原告が最終的に行った実験が甲24実験であって(弁論の全趣旨),原告も,上記の事項を立証するための実験としては,甲24実験のみを主張する旨の陳述をしている。このような経緯からすると,上記のとおり,甲24実験の結果から,上記の事項を立証できたということができない以上,本件において,上記事項の立証はされていないといわざるを得ない。また,ポリカルボン酸と,被告製品中のその他の二重結合を有する不飽和モノマーとが結合しているという事実も立証されていない。したがって,被告製品には,酸基を含む重合可能なプレポリマーが存在するということはできない。」
◆平成18(ワ)16119 特許権侵害差止 特許権 民事訴訟 平成21年04月22日 東京地方裁判所
2009.04.30
◆平成18(ワ)11429 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟 平成21年04月07日 大阪地方裁判所
争点1)
「原告は,本件明細書の発明の詳細な説明には,熱伝導性無機フィラーの全量がカップリング処理されていなければ本件各特許発明の効果が得られないとは記載されていないから,構成要件Bの「熱伝導性無機フィラー」全量がカップリング処理されることまで要求されていないとも主張する。確かに,本件明細書では,熱伝導性無機フィラーの全量がカップリング処理されていなければ本件各特許発明の効果が得られないとまでは明示的に記載されていない。しかし,他方で,本件明細書には,未処理の熱伝導性無機フィラーを加えてもよいことについて何らの開示も示唆もなく,実施例にも熱伝導性無機フィラーの全量がカップリング処理されたものだけが開示されており,未処理の熱伝導性無機フィラーを加えた場合にも,そうでない場合と同様の効果が得られることについて何ら記載されていない。むしろ,前記ウのとおり,未処理の熱伝導性無機フィラーは,その表\面が疎水性の長鎖アルキル基に全く覆われていないのであるから,これを加えた場合に本件各特許発明と同様の効果が得られるとは容易に想到できないと考えられる。この点,原告は,自ら実験した結果(甲6)を基に,熱伝導性無機フィラーの半量を処理した場合であっても,本件各特許発明の効果を奏するに十分であると主張する(原告第3準備書面15頁6行〜16頁9行)。しかし,特許請求の範囲の解釈(均等侵害の成否は別論)において,明細書の記載のほか,出願経過及び公知技術を参しゃくすることを超えて,当業者にとって自明でない実験結果を考慮することはできないというべきであるから,同実験結果の信用性にかかわらず,これを根拠とすることはできない。・・・以上からすると,本件補(ウ) 正における原告の主観的意図はともかく,少なくとも構成要件Bを加えた本件補正を外形的に見れば,カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものと解するのが相当であり,自らかかる補正をしておきながら,後になってこれと異なる主張をすることは,本件補正の外形を信用した第三者の法的安定性を害するものであり,禁反言の法理に抵触し許されないというべきである。
争点2)
「そうすると,特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても,第三者から見て,外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には,第三者の予測可能\性を保護する観点から,上記特段の事情があるものと解するのが相当である。そこで,かかる解釈を前提に,本件において上記特段の事情が認められるかどうかについて検討する。・・・前記1 において認定したとおりであり,本件補正をするに当たっての原告の主観的意図はともかく,少なくとも構成要件Bを加えた本件補正を外形的に見れば,カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものと解される。したがって,原告は,熱伝導性無機フィラーの体積分率が「40vol%〜80vol%」の範囲内にあるもの以外の構成を外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動をとったものであり,上記特段の事情に当たるというべきである。なお,本件拒絶理由通知は,単に組成物に係る発明だからという理由で,その組成比の記載がない本件出願は,特許法36条6項2号に規定する要件を充足しないと判断しているところ,この判断の妥当性には疑問の余地がないではない。しかし,第三者に拒絶理由の妥当性についての判断のリスクを負わせることは相当でなく,原告としても,単に熱伝導性無機フィラーの総量を定める意図だったというのであれば,その意図が明確になるような補正をすることはできたはずであり,それにもかかわらず,自らの意図とは異なる解釈をされ得るような(むしろそのように解する方が自然な)特許請求の範囲に補正したのであるから,これによる不利益は原告において負担すべきである。(3) 以上により,GR−b等について,「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」ことという要件を充たさないから,これらを本件各特許発明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると認めることはできない。」
争点3)
「原告は,信義則上,本件補正を通知する義務を負っていたと主張するところ,上記 イ・ウのとおり,出願段階では補正が認められて特許されるものかどうかが未だ確定しておらず,原告が本件補正書を提出したというだけでは直ちに本件実施契約上の権利義務に影響を及ぼすものではないと解すべきであるから,そもそも補正の事実を通知する実益に乏しく,信義則上,かかる義務を認めることはできない。他方で,補正によって特許請求の範囲が減縮された上で特許査定され,特許権が発生した場合には,本件実施契約上の権利義務にも影響を及ぼすことになるから,減縮の事実を被許諾者に通知する実益があることは否定できない。また,本件実施契約では,まず,被告において自己の販売する製品が「許諾製品」に該当するかどうかを判断すべきであるから,その判断に当たって特許請求の範囲が減縮されたことは重要な情報といえる。したがって,少なくとも,被告から本件出願の経過等について問合せがされた場合には,原告はこれに誠実に応答すべき信義則上の義務があったというべきである。しかし,さらに進んで,特許請求の範囲が減縮されたことについて,被告からの問合せの有無にかかわらず原告から積極的にこれを通知すべき義務があったか否かについては,これを容易に肯定することはできない。なぜなら,本件実施契約書においてかかる通知義務の存在を窺わせる条項は全く見当たらず,同契約書外においても通知義務を認める旨の合意の存在を推認させる具体的事情は何ら認められないのであるから,本件において通知義務を認めるということは,実施許諾契約一般において,これについての明示又は黙示の合意の有無にかかわらず,許諾者たる特許権者に信義則上の通知義務を負わせることになりかねないからである。もともと,出願段階で許諾を受けようとする者にとって,契約締結後の補正により特許成立段階で特許請求の範囲が減縮されることは,当然に想定できる事柄であり,減縮があった場合に許諾者から通知して欲しいというのであれば,契約交渉段階でその旨の同意を取り付けて契約書に明記しておくべきといえる(かかる交渉を経ずに許諾者一般にかかる義務を負わせることは,むしろ許諾者に予期しない不利益を被らせるおそれがある。)。また,被許諾者は,許諾者に特許請求の範囲を問い合わせたり(少なくとも許諾者には問合せに応答すべき義務がある。),特許公報等を参照するなどして,特許請求の範囲がどのようになったか調査することができるのである。上記のような事情を併せ考慮すれば,許諾者たる特許権者一般に,信義則上,特許請求の範囲が減縮された場合の通知義務を認めることはできないというべきであり,本件においても,原告に,信義則上かかる通知義務があったと認めるに足りる事情はない(なお,上記は特許請求の範囲が減縮された場合を前提としており,拒絶査定不服審判における不成立審決が確定した場合や,特許無効審判における無効審決が確定したような場合における通知義務については別途考慮を要するところである。)。」
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 実施権
2009.04.30
◆平成21(ワ)4394 損害賠償 特許権 民事訴訟 平成21年04月27日 大阪地方裁判所
「原告は,「地震時のロックが確実になる」との効果を奏する取付位置は,当業者が試行錯誤をしてみれば極めて容易に判明すると主張するが,かかる主張は「自由端でない位置」という特許請求の範囲の記載が本件明細書で記載された課題解決の手段である「自由端から蝶番側へ(一定程度)離れた位置」を超えるものであることに対する反論にはなっておらず,失当である。仮に,係止手段の大きさや地震検出感度,地震時の係止手段の作動速度や作動時間,開き戸の開口の大きさ,並びに地震時の開き戸の開口速度や開口時間等の条件が明らかであれば,当業者にとって,技術常識に照らし,一定の位置を特定することも可能であるといえるが,本件明細書には,これらの諸条件の記載や示唆すら全くないのである。さらに,原告は「自由端でない位置」では課題を解決する手段として十\分でなくても,「押すまで閉じられずわずかに開かれた」との構成要件により作動が確実との課題を解決できるとも主張するが,そのようなことは本件明細書の発明の詳細な説明において何ら記載されていない。また,段落【0005】の「開き戸の動きが最も大きい自由端ではないため地震時のロックが確実になる」との記載によれば,取付位置は確実に係合する(ひっかける)ための構\成と位置づけられるところ,原告の主張によれば「押すまで閉じられずわずかに開かれた」という構成は,一旦係合した後の係合状態を維持するためものと解されるから,かかる構\成をもって,自由端に近接した位置における係合が確保できるとは解されない。以上より,構成要件Dの「自由端でない位置」との記載は,発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものであり,特許法36条6項1号の定めるサポート要件を充たすとは認められない。」 ◆平成21(ワ)4394 損害賠償 特許権 民事訴訟 平成21年04月27日 大阪地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 機能クレーム
>> 104条の3
2009.03.13
◆平成19(ネ)10025 特許権に基づく差止請求権不存在確認等,売掛代金等請求控訴事件 特許権民事訴訟 平成21年03月11日 知的財産高等裁判所
「被控訴人製品(1)の「d 当該シート体には,アクリル系接着剤で接着された合わせ目を除いて,エポキシ樹脂の合成樹脂体が浸透して,シート体と合成樹脂体が一体化されている」は,アクリル系接着剤で接着された合わせ目において,固化したアクリル系接着剤が存在することにより,エポキシ樹脂の合成樹脂体が浸透することが妨げられるとしても,その余の大半の部分については,エポキシ樹脂の合成樹脂体が浸透するのであるから,本件発明1の構成要件Dの「該シート体には前記合成樹脂が浸透してシート体と合成樹脂が一体化されてなること」に該当する。エ そうすると,被控訴人製品(1)は,本件発明1の構成要件をすべて充足するから,本件発明1の技術的範囲に属する。」 ◆平成19(ネ)10025 特許権に基づく差止請求権不存在確認等,売掛代金等請求控訴事件 特許権民事訴訟 平成21年03月11日 知的財産高等裁判所
2009.02.21
◆平成20(ネ)10065 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権民事訴訟 平成21年02月18日 知的財産高等裁判所
「証拠(甲9)によれば,「メッセージ」とは「任意の量の情報」ないし「言語その他の記号によって伝達される情報内容」(広辞苑第6版2766頁)を指す。ところで,本件発明の詳細な説明には,実施例として,「応答音」を用いて3種類の番号に仕分けする手段が示されている。しかし,前記2で判断したとおり,構成要件Bにおける「接続信号」は,可聴信号に限られるものではなく,可聴信号及び非可聴信号の両者を含む上位概念と理解すべきであることに照らすならば,構\成要件Cにおける「応答メッセージ」も,可聴なものに限られると解すべき根拠はなく,応答を受けた可聴情報及び非可聴情報の両者を含む上位概念と理解するのが相当である。したがって,「応答メッセージ」とは電話を発したときに応答される言語その他の記号によって伝達される情報を指すものと解するのが相当である(「信号」と「メッセージ」はいずれも情報を指すものであり,「応答メッセージ」を「接続信号」と異なる性質を有するものとして,可聴のものに限定する根拠はない。)。」 原審はこちらです
◆平成19(ワ)32525 平成20年07月24日 東京地方裁判所
◆平成20(ネ)10065 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権民事訴訟 平成21年02月18日 知的財産高等裁判所
2008.12.15
◆平成19(ワ)28614 補償金等請求事件 特許権民事訴訟 平成20年12月09日 東京地方裁判所
「原告は,また,「縫合」の意味も,文字通りに縫い合わせるの意味ではなく,部材同士を「接合する(つなげる)」程度の意味に理解することが合理的であり,そもそも,本件発明と被告製品のいずれも,金属製外殻部材のみに貫通穴を穿つものであり,繊維強化プラスチック製外殻部材(FRP製外殻部材)について,一切貫通穴が作られていないから,「縫われていない」などと主張する。しかしながら,このような意味に「縫合材」を理解するのであれば,本件発明の特許請求の範囲の記載においては,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材の異種素材間の接合強度を高めるという課題を解決するための手段が何ら実質的に特定されていないというほかないから,本件発明のとらえ方として相当でないことが明らかである。本件発明の構成要素である「縫合材」を辞書的な意味において「物と物との間を左右に曲折しながら通る」と理解してこそ,整合的に本件発明の本質を理解することができることは,前記ウのとおりである。・・・そうすると,本件発明においては,縫合材により,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構\成であって,このような縫合材は,本件発明の本質的部分というべきである。したがって,本件発明の構成中の被告製品と異なる部分である「縫合材」は,本件発明の本質的部分であるから,本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものと解することはできない。」 ◆平成19(ワ)28614 補償金等請求事件 特許権民事訴訟 平成20年12月09日 東京地方裁判所
2008.06. 5
◆平成18(ワ)23787等 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成20年05月30日 東京地方裁判所
裁判所は、技術的範囲に属しないと判断しました。
被告製品の識別のやり方は、明確ではありませんが、以下のようなものです。記録時には、「コンテンツの記録時に「暗号化されたコンテンツ」のほか,「暗号化されたコンテンツ鍵」,「暗号化された固定値」をSDカードに記録しておく。読み出し時には、読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより,正しい復号鍵を生成し,「暗号化された固定値」を復号し、所定の「固定値」と一致するか否かを見分ける。
「イ 以上のとおり,各被告製品における「暗号化された固定値」は,所定の「固定値」を,記録を行う携帯電話機の自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成された暗号鍵を用いて暗号化した記号であり,暗号化されたコンテンツをメモリカードから読み出す前に,読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより,正しい復号鍵(記録を行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成した暗号鍵と同一の鍵)を生成し,「暗号化された固定値」を正しく(所定の「固定値」と一致する値に)復号することができるか否かを見分けることを目的として使われる記号であると認められる。そうすると,各被告製品における「暗号化された固定値」は,あらかじめ自局電話番号を見分けることを目的として設定されたものであるということはできないから,本件発明における「番号識別子」には該当しないというべきである」 ◆平成18(ワ)23787等 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成20年05月30日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2007.12.20
◆平成16(ワ)25576 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年12月14日 東京地方裁判所
「ア(ア) 本件発明3は,「眼鏡レンズの供給システム」であって,発注する者である「発注側」とこれに対向する加工する者である「製造側」という2つの「主体」を前提とし,各主体がそれぞれ所定の行為をしたり,システムの一部を保有又は所有する物(システム)の発明を,主として「製造側」の観点から規定する発明である。そして,「発注側」は,「製造側」とは別な主体であり,「製造側」の履行補助者的立場にもない(前提事実(3)ウ)。(イ) この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は,2つ以上の主体の関与を前提に,実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は,2つ以上の主体の関与を前提に,行為者として予\定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか,各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り,実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは,構成要件の充足の問題においては,問題とならない。(ウこれに対し,特許権侵害を理由に) ,だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか,すなわち発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれかは,構成要件の充足の問題とは異なり,当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。」 ◆平成16(ワ)25576 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年12月14日 東京地方裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2006.10.31
◆平成17(ワ)15455 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成18年10月30日 知的財産高等裁判所
「これらの記載及び前記ア(ア)e記載の本件補正の内容を考慮すると,本件意見書では,本件拒絶理由通知で指摘された本件引用例に記載された発明について,多種多様の数多くのモードの中から所望のものを選択する必要があるため,最終フォーマットの作成が面倒であるという難点があることを主張した上で,本件発明では,各種のデータの中から任意に選択した一つのパターンデータと一つのフォーマットデータとを組み合わせるだけで最終フォーマットを作成できる旨を述べたものであり,これは,各種のセットデータの中から,一つのセットパターンデータと一つのセットフォーマットデータを組み合わせるだけで最終フォーマットデータを作成できることを開示したものと認められる。そして,この意見書の開示に即応して,同日付けで行われた本件補正においても,本件発明の「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」を,セットデータを意味するものに限定して特許請求の範囲を減縮し,前記のとおり,本件発明の構成に至ったものと解するのが相当である。」 ◆平成17(ワ)15455 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成18年10月30日 知的財産高等裁判所
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2005.12.28
◆H17.12.27 東京地裁 平成15(ワ)23079 特許権 民事訴訟事件
裁判所は、「マップから2つの読出順序データを得,これを図形発生手段に供給しないと,当時の技術では図形の回転表示を行なうことができないといわざるを得ず,本件実施例以外の回転表\示方法による構成は,本件明細書中に一切開示されていない。すなわち,本件特許発明について,本件実施例以外の説明では,当業者がマップとキャラクタジェネレータとを用いて図形の回転表\示を行うこと,すなわち本件特許発明を実施することができる程度に明確かつ十分に特許請求の範囲が説明されているとはいえないから,開示されていない技術思想を特許請求の範囲に含ませることはできない。」と述べました。 ◆H17.12.27 東京地裁 平成15(ワ)23079 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2005.04. 6
◆H17. 3.30 東京地裁 平成15(ワ)1068等 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
2005.03. 7
◆H17. 3. 3 東京高裁 平成15(行ケ)530 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、「参加人は,「同時に」という用語を,「特定の情報フィールドの指示に『連動してないし自動的に』,あらかじめその特定の情報フィールドにリンクされている所定のツールを表示するということ」を意味するものと主張するが,「同時に」との日本語の意義は,「二つ以上のことがほとんど同じ時に行われるさま」であれば,様々な態様を広く含む意味を有するのであって,「一方のことが他方のことに『連動して』いるとか,一方のことから『自動的に』他方のことが生じる」などという意味ないしニュアンスを含むものではない。参加人主張の意義をもたせるには,特許請求の範囲の記載においてしかるべき表\記をすべきところ,本件においては,単に「同時に」とされて,特段の定義付けがされているわけではなく(明細書においても定義は見当たらない。),また,特許請求の範囲の記載全体を精査しても,上記日本語の通常の意義と異なる意味に使われていることをうかがわせる記載は存在しない。 よって,「同時に」の解釈に関する参加人の主張は採用し得ず,これを前提とする主張も採用することができない。」と判断しました。 ◆H17. 3. 3 東京高裁 平成15(行ケ)530 特許権 行政訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2005.02. 2
◆H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件
また、間接侵害についても、「被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は,本件各発明の構\成要件を充足するものであるところ,被告製品は,「被告製品をインストールしたパソコン」の生産に用いるものであり,かつ,「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や,知らないときに機能\説明サービスを受けることができない」という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。また,被告製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないことは明らかである。被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能\があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表\示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能\は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。」と間接侵害認めました。かかる間接侵害の規定の適用は知っている限りでは初めてです。 関連事件(当事者および該当特許が同じ)(H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件)こちら(当事者同じ)にあります。 また、こちらは、(H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)27420 特許権 民事訴訟事件)当事者のみ同じ事件です。 ◆H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 間接侵害
>> コンピュータ関連発明
2005.01.31
◆H17. 1.27 東京高裁 平成16(ネ)1664 特許権 民事訴訟事件
◆H17. 1.27 東京高裁 平成16(ネ)1664 特許権 民事訴訟事件
2005.01. 7
◆H16.12.28 東京地裁 平成15(ワ)19733等 特許権 民事訴訟事件
問題となったクレームは、以下の通りです。「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され,全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって,該アイスクリームは,外側の苺が解凍された時点で,柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」
裁判所は、「この「外側の苺が解凍された時点で,柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は,「新鮮な苺のままの外観と風味を残し,苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく,食するのに便利であ」る(本件明細書【0008】。本件公報3欄38行ないし41行)という本件特許発明の目的そのものであり,かつ,「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は,本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表\現しているだけであって,本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。 このように,特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的,機能\的な表現で記載されている場合において,当該機能\ないし作用効果を果たし得る構成であれば,すべてその技術的範囲に含まれると解すると,明細書に開示されていない技術思想に属する構\成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり,出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし,このような結果が生ずることは,特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。 したがって,特許請求の範囲が,上記のような作用的,機能的な表\現で記載されている場合には,その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず,当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し,そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」と述べました。 ◆H16.12.28 東京地裁 平成15(ワ)19733等 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> 104条の3
2004.12.23
◆H16.12.21 大阪地裁 平成16(ワ)3640 特許権 民事訴訟事件
裁判所は、以下のように判断しました。 「原告は、・・・改訂前審査基準の下で新規事項の追加とされるのを免れるためには、出願当初明細書に実施例として具体的に記載された、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方を記載するしかなかった旨主張する。 イ しかし、出願当初明細書の発明の詳細な説明の段落【0004】には、「すなわち本発明の考え方は、高周波トランスの三次巻線と定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードと二次電池とを直列に接続して充電回路を構成し、この充電回路の電流路の外側に、二次電池と三次巻線と三次側スイッチング素子とを直列に配列して放電回路を設け、放電時には、前記定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにする、というものである。」と記載され、段落【0009】には、放電時の作用として、「この時は、逆流防止ダイオード18のカソ\ード側が、逆流防止ダイオード9および三次側スイッチング素子11の順電圧降下によって二次電池14の負極に対して逆極性になるため、充電回路3cは自動的に停止し、充電は行われないことになる。」と記載されている。また、特許出願の願書に添付された図面の図2には、前記段落【0004】の記載に対応する回路図が示されている。したがって、放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードを設けることは、出願当初明細書の発明の詳細な説明に記載されていたと認められる。 そうであるとすれば、改訂前審査基準の下において新規事項の追加とされるのを免れることを前提としても、特許請求の範囲に「放電時には、定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにするものである」という作用効果に対応する構成を付け加えようとするならば、出願当初明細書の特許請求の範囲の「逆流防止ダイオード」という構\成要件を、例えば、「放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオード」と補正すれば足りたものと認められ、補正後の特許請求の範囲のように各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方まで記載しなければならなかったとは認められない。」 ◆H16.12.21 大阪地裁 平成16(ワ)3640 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2004.11. 2
◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)2101 特許権 民事訴訟事件
「原出願明細書には,以下のとおり,保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等」で一括して被覆されている場合に,テープ状光ファイバユニットの相互を,その側端部間に樹脂を介在させることなく,直接接触させた態様で連結させるという構成が開示されているとは到底いえない。すなわち,樹脂製の保護層により,テープ状光ファイバユニット相互の側端部を互いに接触させた状態で直接連結させたものにおいて,当該保護層をちぎれ易くしたとの構\成は,原出願明細書又は図面に記載されていない。また,樹脂製の保護層を「容易にちぎれる程度にテープ状光ファイバユニットより厚さを薄くして」との構成が,原出願明細書及び図面の記載から自明の事項であるともいえない。・・・変更出願明細書には,保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等で一括して被覆されている場合に,テープ状光ファイバユニット相互の側端部を,直接接触させる」構\成を含むことは明白である。そうすると,出願変更については,出願内容の同一性がなく,不適法であると解され,・・」 ◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)2101 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 要旨変更
>> 技術的範囲
2004.11. 1
◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)27420 特許権 民事訴訟事件
2004.09. 2
◆H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件
出願前の公知資料、明細書における記載を参酌して、「本件製品をインストールしたパソコンに表\示される「?」ボタン及び「表示」ボタン等は,本件各構\成要件にいう「アイコン」に該当しないから,本件発明の技術的範囲に属さず,同パソコンを製造等する行為は本件特許権を侵害しない」と認定されました。プログラムの販売行為が間接侵害に該当するのかも争点でしたが、こちらについては判断はなされていません。
◆H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
2004.04.28
◆H16. 4.23 東京地裁 平成15(ワ)9215 特許権 民事訴訟事件
裁判所は、「分割出願が適法と認められるためには,もとの出願が特許庁に係属し,かつ,もとの出願が2以上の発明を含むものでなければならず,2つ以上の発明を含むということは,単に特許請求の範囲に含まれている場合だけではなく,明細書に2以上の発明が含まれていればよいと解されていること,また,分割出願は,補正をなし得る期間内に出願されることが必要であること(特許法44条1項),さらに,分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなされ(同条2項),新規性・進歩性の判断等については分割出願の基になった特許出願時を基準とすることになることなどにかんがみると,出願の分割は補正(特許法17条)と類似した機能を持つものであるといえるから,分割出願をすることができる範囲についても,もとの出願について補正をすることが可能\である範囲に限られるものと解すべきであって(補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば,実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり,不合理である。),分割出願の明細書又は図面に,原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解するのが相当である。」と述べました。
◆H16. 4.23 東京地裁 平成15(ワ)9215 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 分割
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2004.03.29
◆H16. 2.25 東京地裁 平成14(ワ)16268 特許権 民事訴訟事件
「?@本件明細書には,特許請求の範囲に記載されている,ニッケル(Ni),ケイ素(Si),マグネシウム(Mg),銅(Cu)の他に,構成元素として,同等量のニッケル(Ni)と置換して,・・・記載されているが,その他の元素,特に,亜鉛(Zn),スズ(Sn)の添加について,これを示唆する記載はないこと,?A一般的に,合金は,成分元素や添加量を変化させた場合に合金の性質に与える予測可能\性が極めて低いこと,?B原告は,本件特許の出願過程において,Cu-Ni-Si基合金に,他の元素を増加させると電気伝導率や曲げ特性が悪化すると述べて,スズ(Sn)を0.39%含有する合金は電気伝導率が下がるので採用し得ないとして,本件発明の技術的範囲から除外すべきである旨述べていること等の事実に照らすならば,構成要件Aの「実質的に・・・から成る」とは,ニッケル(Ni),ケイ素(Si),マグネシウム(Mg)及び銅(Cu)以外の元素について,明細書中に具体的な記載がある元素,及び明細書の記載に基づいて当業者が容易に想到できる元素を含有させることを許容する趣旨と解すべきであるが,その範囲を超えた,合金の特性に影響を与える元素を含有させることを許容する趣旨と解することはできない。」
◆H16. 2.25 東京地裁 平成14(ワ)16268 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2004.01.29
◆H16. 1.28 東京地裁 平成14(ワ)28097 特許権 民事訴訟事件
2003.11.10
◆H15.10.16 東京地裁 平成14(ワ)15810 特許権 民事訴訟事件
裁判所は以下のように述べました。「原告は,上記構成要件Dは,出願当初明細書に記載された発明の詳細な説明及び図面の記載から当業者が明らかに理解できると主張するが,大きな空間があれば毛細管現象を防止できることは当業者にとって自明な事項であるといえても,大きな毛細管現象防止用の空間が,本来の軒側成形部が有する空間の略1/3以上の容積を占めることは明らかとはいえないし,特許図面は,設計図面や製造図面とは異なり,発明の理解を助ける概念図に過ぎないのであるから,本件明細書の図面の各部材の寸法等から空間の容積比率を割り出すこともできないのであって,構\成要件Dが出願当初明細書の説明及び図面から明らかであるということはできない。・・・本件発明は,本件リーフレットに記載された発明及び上記実公昭52−10190号公報に記載された発明に基づき,本件特許に関する当初出願時において当業者が容易に発明をすることができたものであるものと認められる。」 ◆H15.10.16 東京地裁 平成14(ワ)15810 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 要旨変更
>> 技術的範囲
2003.02.28
◆H15. 2.26 東京高裁 平成13(ネ)3453 特許権 民事訴訟事件
◆H15. 2.26 東京高裁 平成13(ネ)3453 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 用語解釈
>> 限定解釈
2003.02.28
◆H15. 2.26 東京地裁 平成14(ワ)6241 特許権 民事訴訟事件
裁判所は「緑色を維持しながらもそのような構成を達成できることは,格別の証拠の検討をするまでもなく,健全な社会通念ないし経験則上明らであるということができるから,本件発明出願当時の当業者にとって容易であったものといえる。・・・ブランチングの際の塩分濃度を高くしたり,加熱時間を長くしたり,加熱温度を高めたりすれば,緑色を維持しながらも「豆の中心まで薄塩味が浸透している」という構\成を容易に達成することができたことは,証拠上も認めることができる。」と権利行使を認めませんでした。
◆H15. 2.26 東京地裁 平成14(ワ)6241 特許権 民事訴訟事件
2003.02.12
◆H15. 2.10 名古屋地裁 平成08(ワ)2964 実用新案権 民事訴訟事件
裁判所は、以下のように均等論による救済を認めました。 「「おいて書き」に記載される構成は,公知技術や上位概念を表\示する場合の用語例として用いられることが多いことは否定できないが,本質的部分か否かは,その記載形式だけで決定されるものではなく・・・本件考案の本質的部分が,バレルのスリットを挟んだ両側の側壁のうち,一方のみに案内レールを突設して,片持ち状態でドライバーを案内することにあると認められるから,被告の主張は採用できない。・・・・ 被告は,原告はスリットを密封するものとして「シールバンド」を使用すべきところを誤って「スチールバンド」の名称を使用しながら,これを訂正することなく放置していると主張して,不作為による意識的除外(?Dの要件)ないし包袋禁反言の法理を援用する。しかしながら,・・・上記の法理は,例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して,権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく,権利の範囲を限定し,あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に,後日,これに反する主張をすることは,信義則によって禁じられるという内容であるところ,本件のように,より広義の用語を使用することができたにもかかわらず,過誤によって狭義の用語を用い,かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)というだけでは,均等の主張をすることが信義則に反するといえないことは明らかである(均等論は,限定された場面であるにせよ,正しくこのような場合における権利の救済を認める法理である。)。」
◆H15. 2.10 名古屋地裁 平成08(ワ)2964 実用新案権 民事訴訟事件
2003.02. 3
◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件
◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
2002.11.17
◆H14.11.15 東京地裁 平成13(ワ)24120 特許権 民事訴訟事件
「本件発明は,・・・という効果を有しているが,この効果は,請求項1及び同2の発明にはない,・・とした構成によるものと認められる。そうすると,本件発明は,吊り下げ荷重の上限を引き上げ,大きな荷重を吊り下げても,安全に使用可能\とするという技術課題を解決するために,補強曲板部を設け,補強曲板部を,「爪部とほぼ同じ長さで形成され,かつ,爪部と共にあり溝に嵌合するもの」としたものと認められ,この点が,本件発明に特有の解決手段であるということができるから,本件発明に係る構成要件Gは,本件発明の本質的部分であるということができる。 」と認定しました。
◆H14.11.15 東京地裁 平成13(ワ)24120 特許権 民事訴訟事件
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
2002.09.27
◆H14. 9.27 東京地裁 平成12(ワ)6610 特許権 民事訴訟事件
◆H14. 9.27 東京地裁 平成12(ワ)6610 特許権 民事訴訟事件