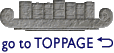知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
ピックアップ対象
ピックアップ対象 ┃ 2025年 ┃ 2024年 ┃ 2023年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2018年 ┃ 2017年 ┃ 2016年┃
最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、裁判所がおもしろそうな(?)意見を述べている判例を集めてみました。
内容的には詳細に検討していませんので、詳細に検討してみると、検討に値しない案件の可能性があります。
日付はアップロードした日です。
2025.02. 2
令和5(ワ)70022 商標権侵害行為等差止請求事件 商標権 民事訴訟 令和7年1月14日 東京地方裁判所
(1) 事案に鑑み、民訴法3条の3第5号に基づく国際裁判管轄の有無に先立ち、 同第8号に基づく国際裁判管轄の有無について検討する。
ア 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法3条の3第8号の規 定に依拠して我が国の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被 告が日本国内でした行為により原告の権利利益について損害が生じたか、 被告がした行為により原告の権利利益について日本国内で損害が生じたと の客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である(最高裁 平成12年(オ)第929号、同年(受)第780号同13年6月8日第 二小法廷判決・民集55巻4号727頁及び最高裁平成23年(受)第1 781号同26年4月24日第一小法廷判決・民集68巻4号329頁参 照)。
イ 民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」は、違法行為により 権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求 に関する訴えをも含むものと解される。そして、このような差止請求に関 する訴えについては、違法行為により権利利益を侵害されるおそれがある にすぎない者も提起することができる以上は、同号の「不法行為があった 地」は、違法行為が行われるおそれのある地や、権利利益を侵害されるお それのある地をも含むものと解するのが相当である。 違法行為により権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えの場合において、同号の「不法行為があっ た地」が日本国内にあるというためには、被告が原告の権利利益を侵害す る行為を日本国内で行うおそれがあるか、原告の権利利益が日本国内で侵 害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明されれば足りるというべ きである(前記最高裁平成26年4月24日判決参照)。
ウ 以上を踏まえ、本件各請求に係る訴えについて、民訴法3条の3第8号 に基づき、日本の裁判所が管轄権を有するか否かを検討する。
(2) 本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えについて
ア 原告は、被告が、本件被告ウェブサイトにおいて、契約書レビューサー ビスの提供に関する広告及び価格表に被告標章を付して電磁的方法により 提供すること(本件請求1、2及び6の1)、契約書レビューサービスの提 供に被告表示を使用すること(本件請求3、4及び6の2)により、原告 の権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの客観 的事実関係が証明されている旨及び原告の権利利益について日本国内で損 害が生じたとの客観的事実関係が証明されている旨を主張する。
イ 前記前提事実(2)ウによれば、被告は、本件被告ウェブサイト上の「AI に基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」についての広告及 び価格表に被告標章(被告表示)を表示していたことが認められるところ、 本件被告ウェブサイトは日本においても閲覧することができたものである (弁論の全趣旨)。 しかしながら、被告が、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく 契約書及び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用 者にサービスを提供していることを示す証拠は見当たらないところ、証拠 (甲2、8、乙1)によれば、1)本件被告ウェブサイトは全て英語で記載 されていること、2)本件被告ウェブサイトに掲載された価格表には、米国 ドルでの価格が表示されており、円での価格は表示されていないこと、3) 本件被告ウェブサイトには、被告に対する問合せ先として、メールアドレ ス((メールアドレス省略))とともに米国の住所及び電話番号が記載されており、日本の住所又は電話番号は記載されていないこと、4)本件被告ウェブサイトには、日本語で作 成された契約書又は日本法を準拠法とする契約書に関するレビューサービ スについての記載はないこと、5)本件被告ウェブサイトのサーバは米国に 所在すること、6)被告は、「LegalForce」の文字を含む標章を付 した役務の提供を日本において申し出る計画を有していないことが認めら れる。以上の点を考慮すれば、本件被告ウェブサイトを日本において閲覧 することができたことを踏まえても、本件被告ウェブサイトにおける被告 標章(被告表示)の表示が、日本の需要者を対象としたものであるという ことはできず、これによって、原告の権利利益が日本国内で侵害され、又 は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本国内で損 害が生じたということはできない。
ウ 以上に対し、原告は、被告のウェブサイトに、被告が日本において97 件の商標登録出願をした旨や、被告が日本の顧客44名について商標登録 出願をした旨が記載されているところ、商標登録出願と契約書レビューサ ービスとの間では顧客層が重複することを主張し、証拠(甲34、35、 乙2)及び弁論の全趣旨によれば、被告のウェブサイト(https:/ /以下省略。 以下「legalforcel awウェブサイト」という。)には、「LegalForce RAPCは、 世界100カ国以上のクライアントを代理しています。」「米国以外では、 LegalForce RAPC Trademarkiaの上位出願国 は以下のとおりである。/(・・・中略・・・)日本 97/」「Lega lForce RAPCは、2009年以降、世界88カ国での商標出願 を支援している/(・・・中略・・・)日本」との記載が英語でされてい ること、被告が日本の顧客44名について商標登録出願をしたことが認め られる。
しかしながら、legalforcelawウェブサイトは本件被告ウ ェブサイト(https://以下省略) とドメイン名を異にするところ、原告の指摘するlegalforcelawウェ ブサイトの記載は、被告による商標登録出願やその代理についての記載で あると理解され、これらの記載をもって、本件被告ウェブサイトにおける 「AIに基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」についての 被告標章(被告表示)の表示が、日本の需要者を対象としたものであるこ との根拠とすることはできないし、本件被告ウェブサイトの表示により、 原告の権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあること、 これらの権利利益について日本国内で損害が生じたと認めることもできな い。
さらに、原告は、原告の契約書レビューサービスと、被告の契約書レビ ューサービスとは、特に知的財産権に関する契約や英文契約について競合 するのであり、本件被告ウェブサイトの外観は本件原告ウェブサイトの外 観と酷似し、被告が悪意をもってこのような外観への変更をしたことによ り、日本の顧客が、原告が提供する契約書レビューサービスと被告が提供 する契約書レビューサービスを混同するおそれが高まっていること、原告 は外資系企業の顧客を有するところ、これら顧客は英語で記載されたウェブサイトを参照することを主張する。
しかしながら、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく契約書及 び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用者にサー ビスを提供していることを認めることができないのは前述のとおりである。 そして、本件原告ウェブサイトと本件被告ウェブサイトとを対比しても、 本件原告ウェブサイトは、日本語で記載され、その冒頭部分に「見落とし を無くそう、AIと。」とのキャッチコピー及び女性タレントの画像を掲載 するとともに、原告の商号及び日本における本店所在地を記載しているの に対し、本件被告ウェブサイトは、専ら英語で記載され、日本語での記載 はなく、本件原告ウェブサイトと同様のキャッチコピー又は画像は掲載し ておらず、被告の商号及び米国における本店所在地を記載しており、原告 の商号又は本店所在地を記載していないなど、これらウェブサイトの内容 は相違し、これらのウェブサイトが酷似しているということはできず、原 告の主張は当たらない。また、以上に述べたところに照らし、原告の主張 するその余の点も、上記判断を左右するには足りない。
エ 以上によれば、本件被告ウェブサイトにおける被告標章(被告表示)の 表示により、原告各商標権又は原告表示に係る権利利益が日本国内で侵害 され、又は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本 国内で損害が生じたとの客観的事実関係が証明されているということはで きない。そして、本件各証拠によっても、本件請求1から4まで、6の1 及び6の2に係る訴えについて、前記(1)ア及びイの客観的事実関係が証明 されているということはできない。
したがって、本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えにつ いて、民訴法3条の3第8号に基づき、日本の裁判所が管轄権を有すると 認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 裁判管轄
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2025.01.23
令和6(行ケ)10039 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年12月25日 知的財産高等裁判所
原告は、引用発明1において「艶消し梨地部位」は必須の課題解決 原理であり、これをストライプ状の複数の凹凸の列とすることは、引用 発明1の課題解決原理を没却するものであるから、引用発明1に引用文 献2記載事項を組み合わせることには阻害要因があるなどと主張する。 しかしながら、前記3(5)のとおり、引用発明1の「梨地部位」と引用 文献2記載事項の「複数の波の列」は、いずれも印刷工程を設けること なく、フィルム表面上に微小な凹凸を形成することで模様を表\現すると いう共通の作用、機能を有するものであるから、引用発明1の「梨地部\n位」による模様の表現に替えて、引用文献2記載事項の「複数の波の列」\nによる模様の表現を適用したとしても、引用発明1における「特別に印\n刷工程を設けなくとも、通常の製膜工程、製袋工程或いは製袋・充填工 程に組み込める簡易な図柄表現方法」という課題を解決し得るものとい\nえる。 そうすると、引用発明1の「梨地部位」が必須の課題解決原理とまで いうことはできず、引用発明1に引用文献2記載事項を組み合わせるこ とにつき、引用発明1の課題解決原理を没却するような阻害要因がある ということはできない。よって、原告の主張は前提を欠き、採用するこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2025.01.23
令和6(行ケ)10058 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年12月25日 知的財産高等裁判所
商標法3条1項3号は、形状その他の特徴を普通に用いられる方法で表示\nする標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない旨規定して いる。商品の立体的形状も、同号の「形状」に含まれている(同法2条1項、 5条2項参照)。指定する商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標\n章のみからなる商標の登録が認められないのは、通常の場合、このような商 標は、自他商品識別力を欠くと考えられるからである。もとより、同法3条 1項3号に該当する商標であっても、使用をされた結果、自他商品識別力を 有するに至ったと認められる場合には、商標登録が認められるが(同条2 項)、その場合でも、商品が当然に備える特徴と認められる立体的形状のみ からなる商標の登録は認められない(同法4条1項18号、商標法施行令1 条の2)。商品の機能を確保するために不可欠であるような立体的形状は、\n商品が当然に備える特徴と解されるのであり、このような立体的形状を有す る商品が、存続期間の更新が可能な商標権に基づき、事実上、半永久的に独\n占販売されることは相当ではないからである。
以上によれば、立体的形状のみからなる商標の商標法3条1項3号該当性 は、当該立体的形状が指定商品の形状を「普通に用いられる方法で表示」す\nるものであり、自他商品識別力を欠くものと認められるか否かという観点か ら判断されるのであり、同法4条1項18号のように商品の当然に備える特 徴である立体的形状(商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状)の\nみからなる標章であると認められることまでは要しない。 しかるところ、商品の形状は、多くの場合、商品に期待される機能をより\n効果的に発揮させ、又は商品の美観をより優れたものとする等の目的で選択 されるものである。また、これらの目的で選択された商品の形状は、通常、 同種の商品に関与する者であれば誰でも使用することを欲するようなもので あり、需要者からみれば、商品の形状そのものの範囲を出ないと認識される ものと考えられる。これらの点に照らすと、客観的にみて、商品の機能又は\n美観に資することを目的として採用されると認められる商品の形状は、特段 の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものと解\nするのが相当である。すなわち、商品の形状が、当該商品の用途、性質等に 基づく制約の下で、同種の商品について、機能又は美観に資することを目的\nとする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が他の\n特徴を有していたとしても、商標法3条1項3号にいう「普通に用いられる 方法で表示」したものに該当するというべきである。\n
・・・
ア 以上を踏まえて検討すると、本願商標の形状のうち、1) 略楕円状の上 面を有する直方体状の形状(底面は中抜きされている。)であり、2) 上 面及び側面に規則的に孔やくぼみ、突起などを配置した形状であることは、 一般的な支持台の形状ということができる。また、本願商標の形状のうち、 3)その上面において、中央に5つの孔が一列に等間隔に並べられ、長手方 向の両側縁の内側には、傾斜のある連続した突部が設けられ、その連続し た突部の傾斜部には、半円状の切欠きが複数設けられた形状(第1特徴的 形状)であること、前記連続した突部の一方と中央の連続した孔の間には、 複数の小突起が一列に点線状に設けられた形状(第2特徴的形状)である ことは、いずれも「歯科用歯形模型用支持台」(支持台)として、ともに 「歯科用作業模型」を構成する「歯科用模型固定用プレート」(固定用プ\nレート)の下面におけるダウエルピンの挿入だけでなく、切欠け部や突部 との嵌合等により、両者が連結して固定され、又は連結強度を高めて確実 に固定されるようにするという商品の機能に資することを目的とするもの\nと認められる。さらに、支持台の上面における第1特徴的形状及び第2特 徴的形状が、両側縁内側において連続的に突部が設けられたり、その一方 と中央の連続した孔の間においても一列に点線状に小突起が設けられたり するなど、その配置は美感を高めるものと認められる。そして、同業者の 同種の商品においても、上面の孔の周辺や縁辺等を含め種々の凹凸、くぼ み、突起等が設けられているものが多く製造販売されていることや、原告 が保有する特許の明細書において、本願商標の各特徴的形状と同様の立体 的形状を備える支持台が記載され、これらの複数の突部及び凹部が、連結 補助用のものであり、支持台と固定用プレートの連結強度をより一層高め るためのものであることが開示されていることなどに照らすと、本願商標 の各特徴的形状を含む形状は、客観的にみて、当該商品の用途、性質等に 基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資することを\n目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが相当で\nある。本願商標は、商品の立体的形状以外の標章は含んでいないから、本 願商標は、その需要者からみて、指定商品である歯科用歯型模型用支持台 の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、\n自他商品識別力を有さないというべきである。したがって、本願商標は、 商標法3条1項3号に該当し、商標登録を受けることはできない。
イ この点について、原告は、本願商標の形状は、他社の支持台上面の形状 とは一見して明らかに異なる特異かつ個性的な形状であるから、本願商標 は「独占不適商標」でも「自他商品識別力欠如商標」でもないとか、本願 商標の形状は、単に機能的役割を果たす形状ではないから、支持台として\n機能上又は美観上の理由から予\測される範囲を超えた形状であるなどと主 張する。 しかしながら、前記のとおり、本願商標の各特徴的形状は、支持台の孔 に固定用プレートのダウエルピンを挿入するだけでなく、支持台と固定用 プレートの連結強度をより一層高める機能を有する連結補助のための形状\nであるとともに、支持台の美観を高めるための形状であることが認められ、 同業者の同種の商品においても、上面の孔の周辺や縁辺等を含め種々の凹 凸、くぼみ、突起等が設けられているものが多く製造販売されていること が認められるのであるから、本願商標の支持台上面の凹凸やくぼみ、突起 等が、他社のものに見られないものであるとしても、当該商品の用途、性 質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資する\nことを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが\n相当である。したがって、原告の主張を採用することはできない。
ウ よって、本願商標に係る立体的形状は、支持台として、機能又は美観に\n資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認め\nられるから、本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用す る標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当するというべ きである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 立体商標
>> ピックアップ対象
2025.01.23
令和6(ネ)10038 不当利得返還等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和7年1月15日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人は、原判決が「構成要件1F及び1Hの「横G(Ghosei)」は、\n従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、車両の傾 斜走行状態での正確な横Gであると認められる。」と判断しているが、むしろ、本件 明細書において、「正確な横G」は、本件課題との関係で、タイヤでの荷重接地点変 化から生じる戻り角(ρ)を加味した正確な傾斜角及び加速度センサーと角速度セ ンサーの関連付けにより明らかになったロールによる速度変化の影響を加味して導 かれる、加速度センサーにおいて安定走行時に検出される横G(Gken)のこと を指すものとして説明されており、他方、「横G(Ghosei)」は、本件課題と の関係で、正確な横Gの検出が可能となったことを踏まえた、車両を安定化に導く\nブレーキシステムの構成要素の一つとして説明されていると主張する。\nそこで、控訴人が主張する「戻り角(ρ)」に着目すると、発明の詳細な説明には 「ハイブリットセンサー20 には、進行方向の加速度を検出する加速度センサー 21、 進行方向ロール速度を検出する傾斜角速度センサー22 及び ロール方 向の加速度を検出する加速度センサー23 が小型に内蔵されおり、ライダーの体 重を含めた合成重心に近いところにレイアウトされる。 ハイブリットセンサー2 0 には、傾斜時に生じる理論バンク角(Φ)及び傾斜によってタイヤでの荷重接 地点変化から生じる戻り角(ρ)が同時に存在している。 (図8も同時参照)セ ンサー20 に生じる力(ベクトルA)と 実際に生じる力(ベクトルA ’)とは ずれが生じている。 このずれ角(戻り角(ρ))によって、正確な横Gを検出する ことが解析された。」(【0060】)、「Gken = g・cosΦ・tanρ- Ψ・Rhenと変形でき、シンプルな式になる。ここで、表されるΦは 車両の理 論バンク角度であり理論傾斜角でもある、 傾斜角速度センサー22 から検出さ れる角速度Ψ(rad/sec) を時間積分して得られた角度であり、ρは傾斜 戻り角であり、RはGセンサー#23の実車取付けの高さ(図8b hsen ) をそれぞれ示している。」(【0063】)との記載が認められるが、この記載は、「横 加速度(Gken)」を解析した結果として、傾斜角Φ、傾斜戻り角ρ、傾斜角速度 Ψ等を用いた式で表すことができることを示すに尽きるのであり、他方で、特許請\n求の範囲の記載において、本件発明1の「横加速度(Gken)」は「横加速度を検 出する加速度センサー」により検出されたものとの特定がされているものの、傾斜 角Φ、傾斜戻り角ρ、傾斜角速度Ψ及びRhenに基づき、Gken=g・cos Φ・tanρ−Ψ・Rhenという演算から導き出されたことは特定されていない から、控訴人の主張はその前提を欠く。
また、仮に「横加速度を検出する加速度センサー」により検出された「横加速度 (Gken)」を正確な横Gであるとするならば、正確な横Gの検出は「横加速度を 検出する加速度センサー」が本来的に備えている機能であり、正確な傾斜角の検出\nとは無関係である。そうすると、控訴人が主張する「1)「走行時の横Gセンサーと 角速度センサーを関連付けること」及び「正確な傾斜角の検出」によって、走行状 態での「正確な横G」の検出を可能とすること」という課題とは矛盾することにも\nなるから、控訴人の主張は本件明細書の記載とは整合しない独自の見解であって採 用することはできない。
イ 「Ψ」を角加速度を表す記号「Ψ.」への訂正について\n(ア) 特許がされた特許請求の範囲、明細書又は図面における訂正について、特許 法126条1項ただし書2号は、「誤記又は誤訳の訂正」を目的とする場合には、願 書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが、 ここで「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいこと が、当該明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載全体から客観的に明らかで、 当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという 場合でなければならないものと解され、特許法134条の2第1項ただし書2号の 「誤記又は誤訳の訂正」も同様に解される。
したがって、明細書等の記載について、物理学上意味をなさないことが客観的に 明らかであることが認識できたとしても、物理学上意味をなさないことの一事をも って、ただちに同号の「誤記」と認められるわけではなく、当該物理学上意味をな さない記載について訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければ、 同号の「誤記」とは認められないと解するのが相当である。この点、控訴人は、請 求項に記載された計算式に係る誤記の訂正に関して、それを字義通り解すると、次 元の異なる物理量同士の減算となり、その技術的意味が理解困難となること等を理 由として、誤記の訂正が認められることを主張するが、技術的意味が理解困難とな ることの一事をもって誤記の訂正が認められるものとはいえないから、控訴人の上 記主張は採用できない。
(イ) 以上を踏まえ、本件明細書等の記載について検討する。
控訴人は「Ψ」を角加速度を表す記号「Ψ.」に訂正することを主張する。本件特\n許権に係る特許請求の範囲及び本件明細書には、「傾斜角速度(Ψ)」、「角速度検出 値(Ψ)」、「角速度Ψ(rad/sec)」、「角速度(Ψ)」「車両のロールによる角速度」、「ロール方向の角速度」、「角速度出力(Ψ)」、「ロール角速度Ψ」、「ロール速度Ψ」、「傾斜角速度Ψ」及び「ロール角速度(Ψ)」(請求項1〜4、【0055】、【0061】、【0063】、【0066】、【0073】、【0084】、【0085】、【0090】、【0127】、【0130】、【0131】)との記載が認められ、他方で、「該傾斜角速度(Ψ)の時間微分で得られる傾斜角加速度(dΨ/dt)」(請求項2)、「傾斜し始めの傾斜速度(ロール速度Ψ)を時間微分 dΨ/dt した角加速度を検知(図中ΔΨの部位)することにより」(【0131】)との記載も認められるから、本件明細書においては、傾斜角速度を「Ψ」、傾斜角加速度を「dΨ/dt」又は「ΔΨ」と表しているものと認められる。\n
そして、本件発明1では「横加速度を検出する加速度センサーのロールによる影 響を取り除く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法」と特定され、 本件発明2では「加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正 後の横G(Ghosei)の導出方法として、前記横加速度から前記加速度センサ ーの車両取り付け高さと前記傾斜角速度(A)または傾斜角速度(B)のいずれか の積、との差分を求め、」と特定されているところ、請求項1を引用して記載された 請求項4には「前記信号演算として、加速度センサーのロールによる影響を取り除 く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法として、前記検出された 横加速度(Gken)から加速度センサーの車両取り付け高さ(hsen)と前記 検出された傾斜角速度(Ψ)の積、との差分を求めること、の導出方法を有する事」 と記載され、本件明細書には「実際の走行傾斜時に検出される検出横G(Gken) は、傾斜角の時間的変化である傾斜角速度(Ψ)を用いた補正が必要であることか ら 補正後の横G(Ghosei)はGhosei = Gken−(Ψ・Rhse n)として表される。」(【0073】)、「2)、 走行時に変化する実際の検出横G(Gken)を少なくとも傾斜角の時間微分(dΦ/dt)値である傾斜角速度(Ψ) を用いた補正を行い、補正後の横G(Ghosei)をGhosei= Gken −(Ψ・Rhsen)の式を用いて補正した値の算出G値」(【0085】)、「項目2)は、走行時の傾斜により検出された検出G(Gken)は車両のロールによる誤差 が重畳されるため ロール成分を取り除くために角速度の補正を行うことが必要と なる。 すなわち、センサーからの検出G(Gken)から規範G成分の部位を実 際の検出される横G(Gken)に置換え、角速度による補正を行えば 規範同様 にロールによる影響を排除した 補正後の制御で使用できるG(hosei)が導 け、Ghosei=Gken−(Ψ・Rhsen) の様に表される。ここで補正項\nとして傾斜角速度を加味している理由は、前記したように制御上無視できない要素 になっているためである。」(【0087】)などと記載されている。
以上によると、本件特許権に係る特許請求の範囲及び本件明細書の記載は、傾斜 角加速度は傾斜角速度の時間微分で得られるという認識の下、両者を明確に区別し た上で、「加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 G(Ghosei)の導出方法」について、加速度の次元の物理量である実際の走 行傾斜時に検出される検出横G(Gken)から、速度の次元の物理量である傾斜 角速度(Ψ)にセンサー取付け高さRhsenを乗じた値を減算することで終始一 貫していると認められる。 そうすると、本件明細書等に記載された「加速度センサーのロールによる影響を 取り除く演算を行った補正後の横G(Ghosei)の導出方法」について、当業 者は本件明細書に物理学上意味をなさない導出方法が記載されていることを理解す るにとどまり、角速度Ψを角加速度Ψ.の趣旨に理解するのが当然であるとまでは認 められない。
・・・
(エ) 以上のことから、控訴人が主張する「Ψ」を角加速度を表す記号「Ψ.」への\n訂正は認められず、本件各発明のいずれについても、特許請求の範囲に記載された 発明が本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2025.01.15
令和6(ラ)10001 保全異議申立却下決定に対する保全抗告事件 特許権 令和6年10月22日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
当裁判所も、基本事件における相手方の申立ては、原々決定が認容した限度\nで認容するのが相当であると判断する。その理由は、後記1のとおり補正し、 後記2のとおり当審における抗告人の補充主張に対する判断を、後記3のとお り当審における抗告人の追加主張に対する判断を、それぞれ付加するほか、原 決定「理由」第4の1から7まで(6頁18行目から33頁7行目まで)に記 載のとおりであるから、これを引用する。当裁判所は、後記1の補正及び後記 2(1)の判断のとおり、乙1発明に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点2 −3、2−5)について、原決定とは異なり、当業者が、相違点1−1に係る 本件発明1の構成を容易に想到するとは認められないことから、本件発明の進\n歩性が欠如するとは認められないと判断するものである。
・・・
乙1公報の発明の詳細な説明には、「さらに、容器2およびその中味 は必ず薬用でなければならないというわけではない。衛生的あるいは 非酸化性の移送あるいは保管の状態を必要とする液体状あるいは固体 状の化学物質を充填した他のタイプの容器も本発明の方法によって処 理できる。」との記載がある。このうち「さらに、容器2およびその中 味は必ず薬用でなければならないというわけではない。」という第1文 は、その記載に基づいて、容器2及びその中味について、薬用でもよ いが、薬用であることが必須であるわけではなく、薬用以外でもよい という意味と解され、薬用とそうでない場合の双方を含むものと解さ れる。そのため、これに引き続く第2文の「衛生的あるいは非酸化性 の移送あるいは保管の状態を必要とする液体状あるいは固体状の化学 物質」についても、薬用とそうでない場合の双方を含むものと解され、 第1文によって、第2文にいう上記「化学物質」から薬用の物質が排 除されており、薬用以外の化学物質のみが含まれると解すべき根拠は 認められない。そうすると、乙1発明が、薬用の化学物質についての 非酸化性の移送を排除しているとは認められない。
しかしながら、乙1公報の発明の詳細な説明には、PTHペプチド 含有製剤の製造については何も記載されておらず、PTH類縁物質の 含量が低い高純度のPTHペプチド含有凍結乾燥製剤を得るとの課題 も開示されていないから、乙1発明に接した当業者が、乙1発明を、 「当該製剤中のPTHペプチド量と全PTH類縁物質量の和に対する いずれのPTH類縁物質量も1.0%以下であり、及びPTHペプチ ド量と全PTH類縁物質量の和に対する全PTH類縁物質量が5. 0%以下」であるPTHペプチド含有凍結乾燥製剤の製造方法に適用 することを想起するとは認められない。
抗告人は、PTHが酸化しやすい物質であることは本件特許の優先 日前の技術常識であり、当業者は、PTHペプチドを有効成分とする 凍結乾燥注射剤を製造するに当たり、「製剤開発に関するガイドライン」 (乙20)に基づき、酸化を防止して、高純度の医薬品を製造するこ とができるよう製造工程を確立することを検討するから、乙1発明を PTHペプチド含有凍結乾燥製剤の製造のために使用することを当然 検討すると主張する。
しかし、乙1に、抗告人の主張する上記技術常識を組み合わせ、更 に乙20の文献の記載を組み合わせたとしても、当業者が、典型的製 造過程によりPTHペプチド含有凍結乾燥製剤を工業的に製造しよう とするとPTH類縁物質を含んだ製剤が製造されてしまうという課題 を認識するとはいえず、乙1発明を「当該製剤中のPTHペプチド量 と全PTH類縁物質量の和に対するいずれのPTH類縁物質量も1. 0%以下であり、及びPTHペプチド量と全PTH類縁物質量の和に 対する全PTH類縁物質量が5.0%以下」の無菌注射剤であるPT Hペプチド含有凍結乾燥製剤の製造方法に適用することを想起すると も認められない。 その他、抗告人が主張する事情を考慮しても、乙1発明に本件特許の優先日前の技術常識を組み合わせることによって、当業者が、相違点1−1に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2025.01.15
令和6(ネ)185等 商標権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 令和6年10月18日 大阪高等裁判所
これに対し、一審被告は、一審原告の損害賠償額の推定の覆滅割合につ いて、一審被告の出資者の創始したカナダ法人が長年にわたり被告標章を使 い続けてきたこと、一審原告は本件商標以外にも自己の社名を用いた別の商 標を用いていること等からすると、上記の覆滅割合は90%を優に超えると いうべきである旨主張するが、一審被告の指摘する上記の事情は、上記認定 の覆滅割合の判断を左右するものであるとはいえない。 他方、一審原告は、1)ウェブサイトに「RobotShop」などと表示\nしてロボット関連商品をインターネット上で販売している会社は、一審原告 と一審被告の他には2社しかない、また、2)一審原告の販売商品である「S ota」というロボットは、日本経済新聞で取り上げられるなど著名であ り、本件商標は「Sota」の販売元のものとして知名度があるから、本件 商標の自他商品識別力は相当程度強いとして、一審原告の損害賠償額の推定 の覆滅割合は45%にとどまるなどと主張する。
しかし、上記1)の主張を踏まえても、ウェブサイトに「RobotSho p」などと表示してロボット関連商品をインターネット上で販売している会\n社は、一審原告と一審被告の他にも複数あるというのであり、また、上記2) の主張のとおり本件商標に一定の知名度があるとしても、本件商標そのもの は、「ロボットの店」などの意味で理解され得る一般的な語であることに照 らすと、それ自体の自他商品識別力が強いとはいえない。 したがって、一審原告の主張を踏まえても、一審原告の損害賠償額の推定 の覆滅割合を90%と認めるのが相当であるとの上記判断は左右されな い。
・・・
上記イ認定の限界利益額1億1306万8476円に10%(100%−90%)を乗じた額として計算された・・・
◆判決本文
1審はこちら
2025.01.15
令和6(ネ)10035 著作権 民事訴訟 令和6年12月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記引用の認定事実によれば、本件検定は、被控訴人の理事長兼本件財 団法人の理事であった Dの指示により、発足に向けた検討が始まったもの であり、関係団体としては被控訴人と本件財団法人の関与が想定されていた ところ、両者の関係は、最終的に、1)本件検定の実施主体は本件財団法人と するが、2)本件検定の標準テキストというべきガイドブック(本件書籍)は、 被控訴人を「発行」主体とし、被控訴人(文化服装学院)が内容を検討し、 その職員において執筆するという役割分担が整理されたこと、実際にも、本 件書籍の執筆を担当したのは、控訴人を含む被控訴人の従業員3名であり、 この3名に対しては、被控訴人から「原稿料」が支払われていることが認め られる。
以上の事実によれば、本件書籍は、被控訴人の従業員としての控訴人が、 その職務上作成したものと認めることができる。なお、控訴人も、本件書籍 の執筆に当たり、文化服装学院内において執筆することがあり、被控訴人の 職員と打ち合わせ、被控訴人が所蔵する資料を借り出し、調査等の目的で文 化服装学院の図書館を利用したことを認めている(甲19、弁論の全趣旨)。
(2) 以上の認定・判断に反する控訴人の主張は、以下のとおり、いずれも採 用できない。
ア まず、控訴人は、本件書籍の作成指示は、本件財団法人の当時の事務局 長兼理事であった Aから受けたと主張し、本件当時の文化服装学院の 教務部長の Bの陳述書(甲20)中には、控訴人が Aとやり取りを しており、自分としては本件書籍の執筆を被控訴人の業務として行って はならないと厳命していたとの記載もある。
しかし、本件財団法人作成の本件計画案(甲18)中に、本件書籍は 被控訴人(文化服装学院)の職員に「執筆願っている」旨の記載がある ほか、被控訴人と本件財団法人間の覚書においても、本件書籍は、被控 訴人(文化服装学院)側で執筆を含む編集・出版を担当することが明記 されている。 Bの陳述書は、これら関係証拠と矛盾するものであって、 採用できない。
イ また、控訴人は、本件書籍執筆当時の嘱託業務量からして、膨大な分量 のある本件書籍を執筆することはできなかったとも主張する。しかし、 嘱託業務としての所定の勤務時間内に本件書籍の執筆をすることが困難 であったとしても、講師としての本来の報酬とは別に相応の報酬を受け 取ることを前提に、付随業務として本件書籍の執筆を新たに引き受ける ということはあり得る話であり、控訴人の上記主張は、本件書籍の執筆 が被控訴人従業員としての職務(付随業務)に含まれないと解すべき理 由にはならない。
ウ さらに、控訴人は、本件書籍執筆に関して本俸を上回る原稿料が支払わ れていることから、本件執筆が嘱託専任講師業務とは別の性質のもので あると主張する。しかし、ここで重要なのは、「原稿料」が、本件財団 法人からではなく、控訴人の使用者である被控訴人から支払われている という事実である。本件財団法人( A)に指示されて執筆した旨をい う控訴人の主張は、この事実と整合せず、原稿料の支払に関する客観的 な事実関係は、むしろ、被控訴人従業員としての職務(付随業務)に基 づいて本件書籍の執筆がされたことを推認させるものである。なお、本 来の講師としての報酬と別枠での支払になっているという点に関してい えば、当該原稿料の支払は、付随業務の負担が重いことに配慮した補償 的な現金支給であったと理解できるから、いずれにせよ上記認定判断を 左右しない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和5(ワ)70607 特許権 民事訴訟 令和6年10月22日 東京地方裁判所
ア 本件発明に係る特許請求の範囲の記載によれば、「第 1 制御装置」(構成要\n件 J)は、自動回帰発動条件1)(「前記第 1 送受信アンテナにより一定時間以 上前記遠隔操縦装置からの信号を受信しなかったと判断された場合」)、又は、 同2)(「前記電源の残量が半分以下になったと判断された場合」)のうち、「少 なくともいずれか一方の判断が行われた場合」に、本件発明の遠隔操縦無人 ボートを、「前記初期位置に自動回帰させるため、前記現在位置および前記 初期位置に基づいて、前記推進動力源と前記操舵装置との動作を制御する」 ものである(いずれも構成要件 J)。
もっとも、この記載によっても、本件発明の「第 1 制御装置」は、自動回 帰発動条件1)及び2)の各場合に自動回帰のための動作制御を行い得る構成\nをいずれも備えたものである必要があるか、いずれか一方の構成を備えた装\n置であれば足りるかについては、必ずしも明らかでない。
イ そこで、本件明細書の記載を参酌すると、本件発明は、「ボートが波に乗っ て、リモコン(遠隔操縦装置)の電波が届かないような遠くまで流されてし まった場合」、「波により船体が激しく揺れて、遠隔操縦装置からの電波を受 信するアンテナが岩等に当たり破壊されてしまった場合」及び「ボートに搭 載されている電源の残量が少なくなって、駆動電力が供給され難くなった場 合」、すなわち、遠隔操縦装置との通信途絶(前 2 者)及び電源残量の不足 (後者)という事態を具体例として示しつつ、そのような事態においてもな お紛失することなく、必ず回収できる遠隔操縦無人ボートを提供することを 解決すべき課題とし(【0004】〜【0007】)、本件発明の構成を備えることに\nよって、「一定時間以上遠隔操縦装置地の間の通信が途絶えた場合、または、 電源の残量が半分以下になった場合」に、「自動的にボートを初期位置に回 帰させることができ」、「ボートを紛失してしまうことがない」として、この 課題を解決する作用効果が得られるとするものである(【0008】、【0009】)。
ここで、自動回帰発動条件1)の場合に初期位置に自動回帰させること及び 同2)の場合に初期位置に自動回帰させることは、前者が遠隔操縦装置との通 信途絶、後者が電源残量の不足という相互に原因の異なる危機的状況への対 処を想定したものである。このため、本件発明は、その作用効果を奏するた めに、いずれの危機的状況にも対処できるようにすることを要するものと理 解される。そうすると、本件発明における「第 1 制御装置」(構成要件 J) は、自動回帰発動条件1)に係る判断と同2)に係る判断のいずれもが行われ得 る機構を備えることを前提として、そのいずれかの条件が満たされた場合に\n自動回帰のための動作制御を行う装置を意味するものと解される。本件発明 の実施例としてはこのような装置のみが開示され、いずれか一方の機構のみ\nを備えるものが本件発明の技術的範囲に含まれることの明示的な記載も示 唆もない。これに加え、このように解することは、本件発明に係るボートが 電源の残量を検出する残量検出装置(構成要件 I)を備えることを発明特定 事項としていることによっても裏付けられる。仮に、自動回帰発動条件2)に 係る判断を行い得る機構がなく、同1)が満たされた場合に自動回帰のための 動作制御を行う機構のみを備えた装置も本件発明の技術的範囲に含まれる\nものと解した場合、本件発明の発明特定事項として電源の残量を検出する残 量検出装置を備える構成を採用したことの技術的意義が理解し難いものと\nなるからである。
ウ 小括
以上のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲及び本件明細書の記載によ れば、本件発明の「第 1 制御装置」(構成要件 J)は、自動回帰発動条件1)に 係る判断と同2)に係る判断のいずれもが行われ得る機構を備えることを前\n提として、そのいずれかの条件が満たされた場合に自動回帰のための動作制 御を行う装置を意味するものと解される。これに反する原告の主張は採用で きない。
3 争点 1-5(均等侵害の成否)について
原告は、仮に被告製品が本件発明の構成要件 J を充足しないとしても、電源の 残量に着目した自動回帰のための動作制御の条件として、電源の残量が半分以下 となった場合とするか他の所定量以下となった場合とするかの相違は、本件発明 の本質的部分の相違ではなく、本件特許の出願経過において意識的に除外された ものでもないことなどから、被告製品につき本件発明の均等侵害が成立する旨を 主張する。
しかし、前記認定事実(前記 2(1))によれば、本件特許の出願経過において、 特許庁審査官から、拒絶理由として、補正前請求項 1 発明の「所定の条件」につ き明確性要件違反及びサポート要件違反を指摘され、また、補正前請求項 6 発明 の「所定値」につき明確性要件違反を指摘されたことを受け、原告は、本件補正 により、自動回帰のための動作制御の条件につき、本件発明の構成要件 J のとお り補正したものである。原告によれば、本件補正は出願当初の明細書の記載内容 の範囲内で行ったものであるところ(乙 4)、本件明細書には、自動回帰発動条件 につき、本件発明の実施形態の 1 つとして、「上記実施形態では、自動回帰の際 に、障害物に衝突しないように、通ってきた経路を戻っている。しかし、通って きた経路を戻らなくてもよい。この場合、ボート に障害物を検知するセンサ を設け、自動的に障害物を回避できるようにすることが好ましい。電源 12 の残 量が少ない場合にボート を自動回帰させる場合、通ってきた経路を戻るので は、少なくとも電源 12 の残量が半分以上あることを条件に戻す必要がある。障 害物センサを設けることにより、電源 12 の残量が半分以下になって、自動回帰 させても操作者の下までボート が戻って来ることができる。」との記載があり (【0061】)、他に自動回帰発動条件としての電源の残量の数値に言及する記載は 見当たらない。この点を踏まえると、本件補正は本件明細書【0061】の記載に基 づいて行われたものと理解される。
そうすると、原告は、本件補正により、電源の残量に着目した自動回帰のため の動作制御の条件につき、ボート が通ってきた経路を戻るケースにも対応し 得るものとする趣旨で、「前記電源の残量が半分以下になったと判断された場合」 (自動回帰発動条件2))とする数値限定を行ったものとみるのが相当であり、「半 分以下」とするもの以外は特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべ きである。
したがって、本件発明の構成要件 J の文言非充足との関係における均等侵害の 主張については、少なくとも均等の第 要件を欠き、自動回帰発動条件2)に係る 「半分以下」の構成を備えない被告製品について、均等侵害が成立するとは認め\nられない。この点に関する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和4(ワ)8300 差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年10月10日 東京地方裁判所
ア 被告会社は、原告に対し、本件契約 3 条 2 項 4 号に基づき、「本サービスを …誤認されるサービスを行ってはならない」という競業避止義務を負う。また、本 件事業に関し、被告会社が原告との関係で代理商(会社法 16 条)の地位にあること は当事者間に争いがないところ、代理商は、許可なく「自己又は第三者のために会 社の事業の部類に属する取引をすること」を禁止されている(同法 17 条 1 項)。したがって、被告会社は、この観点からも、原告に対して競業避止義務を負う。
イ 前提事実及び前記各認定事実によれば、本件事業及びレキシル事業は、いず れも、広く採用活動を行う顧客から提供を受けた求職者等の履歴書や職務経歴書等 の情報を用いて、当該求職者等に係る WEB 調査及びその評価を行うサービスとい える。このため、レキシル事業は、本件事業と同種又は類似するサービスであり、 原告が事業として行う本件事業の部類に属する取引と認められる。なお、被告会社 は、レキシル事業として「レキシル」及び「レキシル+」を提供しており、それぞれ 別の商品として位置付けているとみられるものの、これらを併せた商品群を「レキ シル」と称して、一体的に宣伝広告活動等を行っていることがうかがわれることに 鑑みると、被告会社の原告に対する競業避止義務違反を考えるに当たっては、これ らの商品を区別して取り扱う必要はないというべきである。 また、本件提案書及び本件申込書とレキシル提案書及びレキシル申\込書の記載内 容の同一性又は類似性並びに本件契約締結及びその前後の経緯に鑑みると、被告会 社は、本件事業に関して原告から提供された資料に示された情報をもとにレキシル 提案書その他レキシル事業に関する資料等を作成し、レキシル事業に使用したもの と理解される。そうすると、被告会社は、原告に対する本件契約上の競業避止義務 にも違反したものといえる。
ウ これに対し、被告会社は、本件契約上の競業避止義務は代理商としての競業 避止義務よりも範囲を限定し、後者の適用を排除したものであり、また、仮に後者 が適用されるとしても、レキシル事業と本件事業とは内容や市場を異にすることな どを主張する。
しかし、上記のとおり、本件契約上の競業避止義務と代理商としての競業避止義 務とは内容を異にするところ、前者をもって後者の適用が排除されるとすべき理由 はない。また、本件事業とレキシル事業の内容や市場については、レキシル事業の うち「レキシル」は、本件事業とその内容及び市場を同じくすることは明らかとい ってよい。他方、「レキシル+」については、「第三者チェック」が実施されること もあって、「おすすめ対象」が中途採用者及び幹部社員採用候補者とされており、 その点では本件事業と異なる部分がある。もっとも、少なくとも中途採用者は「レ キシル」においても「おすすめ対象」とされており、また、幹部社員採用候補者に ついても WEB 調査が必要となる例のあることは容易に推察される。そうすると、 「レキシル+」を考慮に入れても、レキシル事業と本件事業とは、その内容及び市場 を共通にすると見るのが相当である。 その他被告会社が縷々主張する点を考慮しても、この点に関する被告会社の主張 は採用できない。
(3) 小括
以上より、被告会社は、レキシル事業の実施につき、原告に対する代理商として の競業避止義務(会社法 17 条 1 項 1 号)及び本件契約に基づく競業避止義務に違 反したものと認められる。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和5(行ケ)10132 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年10月30日 知的財産高等裁判所
前記(2)ウ、(3)アのとおり、甲1文献には、本件訂正発明1の地盤固結材 と同じ組成による固結体を得るための地盤注入用薬液が記載されている ものの、地盤改良工法における1次ゲル化時間の定義やその機能効果等の説明、注入の手順・条件等は一切記載されていない。そこで、当該地盤固\n結材を使用した地盤改良工法における本件訂正発明1の構成に係る当該地盤固結材の注入の条件について、各文献の記載事項等から、本件特許の\n出願当時、当業者が容易に想到し得たか否かが問題となる。
前記第4の2のとおり、本件訂正発明1及び引用発明の地盤改良工法で 使用される地盤固結材は、水ガラスと微粒子スラグを有効成分とする懸濁 液(懸濁型グラウト)であり、固結の原理は、「低モル比シリカ溶液中のア ルカリ分が微粒子スラグの潜在水硬性を刺激して固化するとともに、低モ ル比シリカ溶液のシリカ分が微粒子スラグのカルシウム分と反応してゲ ル化するため、土砂中においてスラグによる固結部分の間をシリカのゲル が連結することにより一体化した固結体が形成される」というスラグの水 硬性によるものである。他方、甲5文献、甲6文献及び甲9文献に記載さ れている地盤固結材は、「活性複合シリカコロイド」(甲5)、「溶液型活性 シリカグラウト」(甲6)又は「耐久シリカグラウト」(甲9)(溶液型グラ ウト)であり、その固結の原理は、注入液が「土粒子間浸透するにつれ、 土との接触部の pH が中性方向に移行するとともにゲル化が進行」(甲5) する、「注入された酸性の薬液は土中のアルカリ分と反応して、ほぼ中性に なると固結が始まる」(甲6)という地盤の pH によるものであり、本件訂 正発明1及び引用発明の地盤固結材とは固結の原理を異にする。
また、地盤改良工法の注入の条件について、甲5文献、甲6文献及び甲 9文献は、注入材(溶液型グラウト)について、注入された酸性の薬液は 土中のアルカリ分と反応して、ほぼ中性になると固結が始まるため、薬液 のゲル化時間は地盤中に注入された状態のものを測定し、この土中ゲル化 時間(GTso)よりも薬液の注入時間を長く設定することで、後続の注入液 が、先行する注入液のゲル化しかかった先端表面部を乗り越えて、又はゲル化しかかった注入液を外周方向に押しやりながら浸透し固結していく\nというマグマアクション法を説明している。しかし、当該マグマアクショ ン法は、あくまでも酸性の薬液が土中のアルカリ分と反応して固結する場 合の注入の条件について述べたものであって、薬液中のスラグの水硬性に より固結する本件訂正発明1及び引用発明の地盤固結材の注入の条件と して当然に妥当するものということはできない。固結の原理が異なる以上、 同じ地盤改良の技術分野であるからといって、同じ注入条件で大径の高強 度固結体を形成するという課題を実現することができるとは直ちにいう ことはできないからである。甲5文献、甲6文献及び甲9文献中にも、マ グマアクション法を、固結の原理を異にする懸濁型グラウトに適用し得る ことを示唆するような記載等は見られないから、当業者において、引用発 明及びこれらの文献から、本件訂正発明1及び引用発明の懸濁型グラウト の特性(1次ゲル化、疑塑性、2次ゲル化)に応じた注入条件を容易に想 到することはできないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和5(ワ)70346 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月10日 東京地方裁判所
前記前提事実に加え、証拠(乙9)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品は、ユーザーが自動車のドアを開けることで磁気センサーモジュールがド アに設置された磁石の磁気を感知しなくなると、バックライトモジュールが オン状態(点灯状態)になる一方で、ユーザーが自動車のドアを閉じること で磁気センサーモジュールが磁気を感知すると、バックライトモジュールが オン状態からオフ状態(消灯状態)になること、そして、バックライトモジ ュールがオン状態(点灯状態)のまま放置されると、徐々に減光しながら消 灯するが、これは、バックライトモジュールが、接続されているコンデンサ の充電又は放電による影響を受けるからであり、発光持続時間を正確に調整 するための制御回路や制御プログラムを用いることによって消灯までの時間 が制御されているものではないこと、点灯状態と消灯状態の時間間隔は、コ ンデンサの性能(静電容量)やその劣化(静電容量の低下)の程度によって\n左右されるため、製品の使用期間が長くなりコンデンサのエイジングが進む と点灯開始から消灯までの時間間隔が短くなり、所望の時間間隔で消灯させ ることはできないこと、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、被告各製品の発光持続時間は、コンデンサの性能\nやその劣化の程度によって左右されることになるのであるから、被告各製品 は、発光持続時間を正確に調整することができるものとはいえない。 これに対し、原告の主張は、構成要件Fにいう「調整可能\」の文言解釈に つき、前記判断とは異なる文言解釈に立つものであり、上記文言解釈に係る 前記説示に照らし、いずれも採用の限りではない。
・・・
前記3のとおり、被告各製品は、本件発明の構成要件Fを充足しないから、\n本件発明の技術的範囲に属するとはいえず、その余の争点を判断するまでもな く、原告の請求は理由がないことになる。もっとも、本件の事案に鑑み、本件 の中核的争点の一つである争点2−1に限り、念のため、以下判断を示してお くこととする。
・・・
前記(1)の乙8公報の記載によれば、乙8発明は、外部電源が完全に不要な 自動車スカッフプレートに適用される発光モジュールを提供することを課題 とするものであり(【0004】)、この課題を解決するための発光モジュ ールは、発光素子及びリードスイッチが設けられた「ランプ板」、及び電線 を介してランプ板に接続される「電池」が、いずれも「導光板」に埋設され る構成を有し(【0005】、【0015】ないし【0017】)、この構\ 成により「導光板10の内部に発光素子20に必要な電力を供給することが できる電池40を設置するため、完全に外部電源が不要となる」(【001 9】)ことによって、上記の課題を解決するものと認められる。その他に、 乙8公報には、上記課題の解決の手段として、上記以外の構成は記載されて\nいない。
そして、前記(1)及び前記(2)イのとおり、乙8発明の構成は、外部電源が完\n全に不要な発光モジュールである導光板10に、これに埋設されたランプ板 50、電池40等を密封するための収容溝カバー70を設け、スカッフプレ ート80の上面には凹部を設け、この凹部に発光モジュールである上記導光 板10を収容するものである。 そうすると、乙8発明においては、導光板10に係る上記構成(電池40\nを導光板10の内部に埋設して、導光板10の底面に電池40を密封する収 容溝カバー70を設け、この導光板10をスカッフプレート80の内部に収 容しているものをいう。)は、乙8発明の課題解決に直結した構成であるか\nら、乙8発明に接した当業者がこれを変更する動機付けを認めることはでき ない。
のみならず、乙8公報には、電池の交換についての記載はなく、乙8発明 に接した当業者が仮に電池の交換という課題を着想したとしても、相違点8 −1に係る構成とするためには、(a)収納溝カバー70を除いた上で、(b)\n導光板10に代えてスカッフプレート80に電池40を収容する収容孔を設 け、当該電池収容孔を底面側から開口するものとし、(c)当該収容孔を覆 うカバーを設け、当該カバーを取り外すことで電池40を交換可能とし、(d)\nスカッフプレート80に収容することになった電池と、導光板10内に埋設 されているランプ板50等との電気接続を行うという、複数回の変更が必要 になり、しかも、上記の変更内容には、乙8発明の課題解決に直結した構成\nの変更も含まれていることが認められる。 これらの事情の下においては、乙8発明に接した当業者において上記のよ うに変更する動機付けはないといわざるを得ず、当業者が本件発明を容易に 想到し得たものと認めることはできない。
これに対し、被告は、乙10文献には、無線車両発光ペダルの下表面から\n電池を交換可能にするために背面に取り外し可能\な電池カバーを設けること が開示されており、乙10文献及び乙11文献によれば、電池を内蔵する機 器一般において、電池を交換可能にするために、取り外し可能\な方式で電池 の収容孔を覆うカバーを設けることは周知技術であるから、乙8発明に乙1 0文献の技術事項や周知技術を組み合わせることにより、乙8発明の収容溝 カバー70を取り外し可能とすることは、当業者にとって容易想到であると\n主張する。
しかしながら、乙8発明に接した当業者において、スカッフプレート80 には、底板が設けられるものと理解するのが相当であることは、前記(2)イに おいて説示したとおりある。そうすると、底板が設けられるため、収容溝カ バー70は、スカッフプレート80の下表面に対して露出していないのであ\nるから、被告の主張は、乙10発明や周知技術を組み合わせるための前提を 欠く。
のみならず、乙11公報によれば、表示部を有し電池を電源とする電子機\n器において、表示部とは反対の裏側に電池交換のための取り外し可能\なカバ ーを設けることは技術常識であるといえるものの、当該技術常識を超えて、 乙8発明のように独立したモジュールが設けられ、底板(スカッフプレート 80)の凹部にモジュールを収容する電子機器において、底板の裏側から底 板に収容されているモジュール内部の電池を交換することまでが技術常識で あったものと認めるに足りない。 しかも、乙10文献については、乙8発明のスカッフプレート80に相当 する底板に相当する部材がないのであるから、下側から電池カバーを設ける という単純な技術常識によっては、乙8発明の電池の収容に係る構成と置換\nするなどして相違点8−1に係る構成に容易に想到することはできない。\nそうすると、被告の主張を考慮しても、乙8発明から出発して相違点8− 1の構成に至るための動機付けを認めることはできず、被告の主張は、前記\n判断を左右するものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和5(ワ)70272 特許権侵害排除等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月23日 東京地方裁判所
ア 本質的部分の認定について
第1要件にいう特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分であると解すべきであり、上記本質的部分は、特許請求の 範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効 果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に 見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定す\nることによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値 は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定めら れることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細 書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、 そして、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される 場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化した ものとして認定され、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程 大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のも のとして認定されるものと解される。 ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されてい るところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、\n明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術 に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきで\nある。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及 び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記 載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると 解される。
・・・
ウ 本件発明の本質的部分
(ア) 本件発明に係る特許請求の範囲及び本件明細書の各記載によれば、本 件発明は、フランジ幅の狭い形鋼の梁に親綱支柱を設置するのに手間が かからない、親綱支柱取付治具を提供するという課題を解決することを 目的として(【0006】及び【0007】)、矩形状の板の端部で上下 方向に間隔を開けてU字状に折り曲げられた折り曲げ部を含み(構成要\n件C)、かつ、矩形状の板の第1の方向端部より逆方向の端部までの長 さが、治具が取付けられる形鋼のフランジの幅より長い(構成要件E)\nという構成を採用したものであり、このような構\成を採用することによ り、U字状の折り曲げ部を幅の狭いフランジ部に係合した状態で、親綱 支柱の取付具を位置決めして固定でき、その結果、フランジ幅の狭い形 鋼の梁に親綱支柱を設置するのに手間がかからない、親綱支柱取付治具 を提供できるとの効果を奏する(【0013】及び【0014】)もので あると認められる。そして、上記の「U字状に折り曲げられた折り曲げ 部」は、これを幅の狭いフランジ部に係合した状態で親綱支柱の取付具 を位置決めして固定できることから、フランジ幅の狭い形鋼の梁に親綱 支柱を設置するのに手間がかからないようにするという課題解決に寄与 する構成であるということができる。\n
他方、本件明細書には、乙17発明の存在を明示ないし示唆する記載 は存在しないが、前記イのとおり、本件出願までに公知となっていた乙 17発明は、命綱取付装置を梁に簡単に取り付けるために、本体下部の U字形フック部を梁の下部と垂直方向で係合させるとともに、略L字状 本体の横片先端を下方に折り返して形成させたコ字形フック部を梁の上 部と水平方向で係合させるという構成を採用しており、このうちコ字形\nフック部(乙17文献図面目録の【第3図】2b)は、命綱支持具を梁 の長手方向に沿った任意位置に配置して命綱を建物外周壁上部に沿った 任意位置へ簡単に取付けることができるという、構成要件Cの「U字状\nに折り曲げられた折り曲げ部」と同様の効果を奏するものと認められる。 そうすると、乙17発明は、本件発明との関係で従来技術に相当する ものであり、かつ、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題とし て記載されている部分は、本件出願時の従来技術に照らして客観的に見 て不十分であったと認められるから、本件発明の従来技術に見られない\n特有の技術的思想を構成する特徴的部分の認定に当たっては、乙17発\n明の内容も参酌して認定されるべきである。
そして、上記のとおり、設置するのに手間がかからないようにすると の課題解決に寄与する構成要件Cの「U字状に折り曲げられた折り曲げ\n部」と同様の構成については、乙17発明が既に備えていたものである\nから、本件発明と従来技術である乙17発明との主な差異は、本件発明 では、折り曲げ部の存在する端部から逆方向の端部までの長さが治具を 取り付ける形鋼のフランジ幅より長いのに対し、乙17発明では、コ字 形フック部の存在する端部から逆方向の端部までの長さが同フック部と 係合させる梁の上部の幅(フランジ幅)と同一であるという点にすぎな い。
したがって、本件発明は、従来技術と比較してその貢献の程度が大き いとはいえないから、その特許請求の範囲の記載の一部について、これ を上位概念化したものとして認定することはできず、本件発明の本質的 部分は、特許請求の範囲に近接したものとなるというべきである。 (イ) 以上によれば、本件発明における従来技術に見られない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分については、原告が主張するように「1)U字 状に折り曲げられた折り曲げ部を有し、2)その反対方向における長さを フランジ幅よりも長くしている」という構成であると認めることはでき\nず、矩形状の板の端部で上下方向に間隔を開けてU字状に折り曲げられ た折り曲げ部を設けた上で、この折り曲げ部の存在する端部から矩形状 の板の逆方向の端部までの長さを治具が取付けられる形鋼のフランジ幅 よりも長くするという構成、すなわち、構\成要件C及びEにより近接し た構成であると認定されるべきである。\n
エ 被告製品の第1要件の充足性
前記2で説示したとおり、被告製品は構成要件C及びEをいずれも充足\nするとは認められず、本件発明の「治具」は、「上下方向に間隔を開けて U字状に折り曲げられた折り曲げ部」が「前記矩形状の板の前記第1の方 向の端部」と連続する(構成要件C)のに対し、被告製品は、本件発明の\n「折り曲げ部」に相当するフック部が、同「矩形状の板」に相当する底板 ではなく、側板の端部と連続しており、また、本件発明の「治具」は、 「前記矩形状の板の前記第1の方向端部より逆方向の端部までの長さは、 前記治具が取付けられる形鋼のフランジ幅より長い」(構成要件E)のに\n対し、被告製品は、「矩形状の板」の「第1の方向端部より逆方向の端部 までの長さ」に相当する、形鋼に取り付けられた際に形鋼のフランジの二 辺と平行になる二辺に係る底板の端部間の長さが、形鋼のフランジの幅よ り長いとはいえない。
したがって、本件発明と被告製品とは本件発明の本質的部分において異 なっているというべきであり、両者の異なる部分が本件発明の本質的部分 ではないといえないから、均等の第1要件を満たすとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和3(ワ)20229 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和6年10月30日 東京地方裁判所
前記(2)のとおり、原告意匠と被告意匠に係る物品は、いずれも生活 雑貨などの家庭用品を収納する容器であるから、その需要者は個人消費 者であると認められる。 そして、需要者である個人消費者は、収納容器として物を収納する際 には、その使用のしやすさや持ち運ぶ際の便利さの観点から、物を収納 し又は収納することなく床等に収納容器を置いた際には、その見た目の 美しさ等の観点から、それぞれ、両意匠に係る物品を観察し、選択する ということができる。 そうすると、両意匠に係る物品の性質、用途及び使用態様に照らし、 収納容器として物を収納する際の使用のしやすさ等観点からは、収納容 器全体の形状等である基本的構成態様1)が需要者の注意を惹く部分であ るとともに、物を収納し又は収納することなく床等に置いた際の見た目 の美しさ等の観点からは、収納容器としての外形を特徴付ける部分の形 態である具体的構成態様3)、4)及び6)が、最も強く需要者の注意を惹く 部分であるということができる反面、形状の細かな比率に係る具体的構\n成態様2)や収納容器本体底面の小さな突起に係る具体的構成態様5)は、 需要者の注意を惹く部分ということはできない。
・・・
前記aないしcのとおり、原告意匠の基本的構成態様1)の一部、具 体的構成態様3)、4)及び6)については、それぞれ類似する公知意匠が 存在するとは認められるものの、それらの構成態様を全て兼ね備えた\n公知意匠は見当たらない。
(ウ) まとめ
以上のような意匠に係る物品の性質、用途及び使用態様並びに公知意 匠の内容からすれば、原告意匠の収納容器全体の形状及びその外形を特 徴付ける部分の形態である基本的構成態様1)並びに具体的構成態様3)、 4)及び6)を組み合わせた部分がその要部であると認められる。
エ 差異点についての評価
(ア) 差異点1(正面視及び背面視における収納容器本体の上辺の長さと下 辺の長さと高さの比率、両側面視における収納容器本体の上端部の幅と 下端部の幅の比率が異なっている点)は、要部ではない部分の差異にす ぎない上、その比率の差はわずかなものにすぎない。 また、差異点2(正面視、背面視及び側面視における収納容器本体の 上辺の形状が異なっている点)については、要部の一部に関する差異で はあるが、前記ウ(イ)cのとおり、正面視、背面視及び側面視において、 収納容器本体の上辺を湾曲させることは、公知意匠にも見られた部分で あって、原告意匠の効力範囲を適正に確定する上で、この部分のみをも って要部ととらえるのは相当ではない。そして、別紙原告意匠公報図面 目録記載1ないし3の斜視図、正面図、右側面図によれば、上記部分の 湾曲の程度はさほど大きいと評価できない上、前記ウ(ア)のとおり、需 要者である個人消費者が収納容器を見た目の美しさ等の観点から観察す るのは、主として、物を収納し又は収納することなく床等に置いた際で あると考えられ、その場合、収納容器の斜め上方から見下ろされること が想定されるため、上記部分の湾曲や弧状の凸状面として突設した形状 は、際立ちにくいといえる。 したがって、正面視、背面視及び側面視における収納容器本体の上辺 の形状の違いが需要者の視覚を通じて起こさせる美感に与える影響は、 限定的なものにとどまるというべきである。 なお、証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば、具体的構成態様3)に ついて、イ号意匠ないしハ号意匠では、収納容器本体の外側に存在する 紐縄によって構成されているU字の高さが異なることが認められるが、\n仮にこの点を原告意匠と被告意匠の差異点であると捉えたとしても、そ の差が大きいとはいえず、このような差異が美感に与える影響は小さい ものと認められる。
(イ) 以上のとおり、差異点1及び2は原告意匠が看者に起こさせる美感に 決定的な影響を与えるものではないのに対し、要部の大部分において前 記アの共通点がみられることからすれば、両意匠は、差異点が共通点を 凌駕するものではないというべきである。
(5) 小括
したがって、原告意匠と被告意匠は、全体として需要者に一致した印象を 与えるものであって美感を共通にするといえるから、被告意匠は原告意匠に 類似すると認められる。
・・・
証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば、原告意匠と乙2意匠の意匠に係 る物品は類似するものと認められる上、両意匠は、略楕円形状で小判型の底 面とこれより大きい略楕円形状で小判型の上面とからなる中空の逆略楕円錐 台形状の上面が開口された形状をなす収納容器本体と、縄紐からなる一対の 把手から構成されている点(基本的構\成態様1))、同把手は、二本の短い縄 紐からなっており、収納容器本体の外周面に対向して穿設された左右一対の 小さな透孔に収納容器本体の外側からそれぞれ挿通しており、縄紐が収納容 器本体の外側にU字状に垂下して設けられている点(具体的構成態様3))に おいて、共通することが認められる。 しかしながら、両意匠の間には、原告意匠は、収納容器本体の長手方向に 把手が設けられているのに対し、乙2意匠は、収納容器本体の短手方向に把 手が設けられている点(基本的構成態様1))、原告意匠は、太さのある縄紐 が使用されており、収納容器内側に大きな止め結びが形成されているのに対 し、乙2意匠は細い縄紐が使用されており、収納容器内側に存在する止め結 びは大きなものとはいえない点(具体的構成態様3))、原告意匠においては、 収納容器本体の上辺が、正面視及び背面視においては、両端から中央部に向 かって緩やかに下方に湾曲した緩やかな円弧を形成しており、また、側面視 においては、中央部に向かって立ち上がり、全体が弧状の凸状面として突設 した形状であるのに対し、乙2意匠は、いずれも水平な直線形状になってい る点(具体的構成態様4)及び6))において、差異点が存在するものと認めら れる。
そして、上記の把手の取付位置、紐縄の太さ、止め結びの大きさ及び正面 視、背面視及び側面視における収納容器本体の上辺の形状は、物を収納し又 は収納することなく床等に置いた際の見た目の美しさ等の観点及び収納容器 として物を収納する際の使用のしやすさ等の観点から、いずれも需要者の注 意を惹く部分であるといえる。そうすると、これらの差異点が両意匠の美観 に与える影響は大きいものがあるというべきである。 したがって、原告意匠と乙2意匠は、全体として需要者に一致した印象 を与えるものとはいえず、両意匠が類似するとはいえないから、原告意匠に 係る意匠登録に新規性欠如(意匠法3条1項3号、2号)の無効理由がある とは認められない。
・・・
前提事実(5)、証拠(甲29ないし甲31、乙46ないし48)及び 弁論の全趣旨によれば、被告商品は、被告の各店舗において販売されて おり、その価格は、イ号(2リットル)が100円、ロ号(7リットル) が300円、ハ号(19リットル)が500円であったこと、原告商品 は、株式会社東京インテリア家具(家具やインテリアの小売店)、株式 会社ファミリア(子供用品等を扱う小売店。以下「ファミリア」とい う。)、アルファロメオ、アバルト等を扱う自動車ディーラー、株式会社 アダストリア(アパレル業者)等を通じて販売されており、その価格は、 最低で1210円、最大で4950円(サイズは不明なものが多いが、 ファミリアでは、7リットルの商品が1320円、19リットルの商品 が2200円で販売されている。)であったこと、原告商品は、楽天市 場等のインターネット上のショッピングサイトでも販売されており、そ の価格は、2リットルの商品について、最低で1680円、最高で23 06円であったことが認められる。
このように、原告商品と被告商品は、その販売経路が異なることに伴 って販売価格に差が生まれており、両者の価格を比較すると、最も小さ いものでも原告商品の価格が被告商品の価格の約4倍(ファミリアで販 売されている原告商品とロ号の比較)であり、大きなものでは原告商品 の価格が被告商品の価格の20倍を超えるもの(楽天市場等のインター ネット上のショッピングサイトで販売されている原告商品とイ号の比較) も存在しており、原告商品及び被告商品の上記の価格差は小さいとはい えない。そして、原告商品や被告商品は、生活雑貨などの家庭用品を収納する 容器であり、主に自宅で使用される実用品といえ、そうだとすれば、上 記の販売価格の差異は、需要者の購買動機に相当程度影響を与えている と認めるのが相当である。
他方で、原告商品と被告商品は、インテリア商品でもあることからす ると、その需要者の中には、価格を重視せず、デザイン性や色彩を重視 して、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少な からず存在するものと推認できる上、原告商品と被告商品の価格は、い ずれも数百円から数千円の範囲にとどまっており、比較的購入しやすい 価格帯であることに照らすと、上記の販売価格の差異による覆滅割合が 非常に大きなものになるとは考え難い。 これらの事情を踏まえると、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違 (市場の非同一性)は推定の覆滅事由に該当すると認められる。
(イ) 市場における競合品の存在
被告は、収納容器については数えきれないほど多数の競合品が存在し ていることが推定の覆滅事由になると主張する。しかしながら、競合品の存在について、証拠(乙38)及び弁論の全趣旨によれば、インターネット上のショッピングサイトで「収納 バスケット」などのキーワードで検索すると多数の商品が表示されることが\n認められるものの、これらの商品や原告商品の市場におけるシェアは明 らかではなく、単に他の収納容器が多数販売されているという事実のみ をもって、推定の覆滅を認めることはできないというべきである。したがって、被告の上記主張は採用できない。
(ウ) 被告の営業努力
証拠(乙39、43)及び弁論の全趣旨によれば、被告はいわゆる1 00円均一ショップを展開する企業であるところ、被告の令和4年の年 間売上高は5493億円、従業員数は合計2万4605人(正社員58 5人、臨時従業員数2万4020人)、日本国内の店舗数は4092店 舗であること、株式会社日経BPコンサルティングが実施した「ブラン ド・ジャパン2023」の一般生活者編の「総合力」ランキングにおい て、被告はUSJ(ユニバーサルスタジオジャパン)、Google、 UNIQLO(ユニクロ)、Disney(ディズニー)に次ぐ5位と なっていることが認められ、このような被告の企業規模の大きさや知名 度の高さは被告商品の売上げに相当程度影響を与えているものというべ きである。 そうすると、上記の事情は被告の営業努力の観点から推定の覆滅事由 に該当するものと認められる。
(エ) 侵害品の性能(機能\、性能等意匠以外の特徴)及び被告商品は原告意\n匠の一部のみを用いていること
被告は、1)需要者は、収納容器を購入するに際し、外観よりもその機 能面やその色彩を考慮すること、2)被告商品は、需要者が着目する「船 のようなカタチ」に相当する構成態様である具体的構\成態様4)及び6)を 有していないことが推定の覆滅事由になると主張する。
しかしながら、上記1)について、証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によ れば、被告商品は白色の商品しか存在しないことが認められ、本件全証 拠によっても、被告商品が収納容器として特別な色彩や機能を有してい\nということはできない。そうだとすれば、被告商品の色彩や機能が、そ\nの売上げに寄与したとは認められないから、侵害品の性能による推定の\n覆滅を認めることはできない。 他方、上記2)について、前記1(4)イのとおり、原告商品と被告商品 との間には、差異点1及び2が存在しており、特に差異点2(正面視、 背面視及び側面視における収納容器本体の上辺の形状が異なっている点) は、原告意匠の要部の一部に関する差異といえることを踏まえると、原 告意匠が被告商品の売上げに寄与した程度は限定的なものであったとい うべきである。 したがって、侵害品の性能(機能\、性能等意匠以外の特徴)は推定の\n覆滅事由であると認めることはできないが、被告商品は原告意匠の一部 のみを用いていることは推定の覆滅事由に該当するものと認められる。
(オ) まとめ
以上によれば、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違(市場の非同一 性)、被告の営業努力及び被告商品は原告意匠の一部のみを用いている ことは推定の覆滅事由に該当するものといえ、被告商品の購買動機の形 成に対する原告意匠の寄与割合は2割と認めるのが相当であるから、上 記の限度で推定が覆滅される。
(2) 意匠法39条3項による損害額の算定
ア 意匠法39条3項の適用の可否について
(ア) 意匠権者は、自ら意匠を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、意匠の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑 みると、侵害者の侵害行為により意匠権者が受けた損害は、意匠権者が 侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は 競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得 べかりし利益とを観念し得るものと解される。 そうすると、意匠法39条2項による推定が覆滅される場合であって も、当該推定覆滅部分について、意匠権者が実施許諾をすることができ たと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。
(イ) これを本件において見ると、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違 (市場の非同一性)及び被告の営業努力による推定覆滅部分については、 実施許諾をすることができたものと認められるが、被告商品は原告意匠 の一部のみを用いていることについては、原告意匠が売上げに寄与して いないことを理由に推定が覆滅されるものであるから、この部分につい て、実施許諾をすることができたものとは認められない。
(ウ) そうだとすれば、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違(市場の非同 一性)及び被告の営業努力に係る推定覆滅部分についてのみ、意匠法3 9条3項の適用があると解するのが相当である。
イ 登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相 当する額について
(ア) 登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に 相当する額を算定する際の基礎となる金額は、侵害行為に関する売上高 であると解されるところ、前提事実(6)のとおり、被告商品は日本国内 の売上高は5981万3900円であり、これに海外への輸出に係る売 上高を追加した金額は6358万8100円である。
そして、前記アのとおり、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違(市 場の非同一性)及び被告の営業努力に係る推定覆滅部分についてのみ、 意匠法39条3項の適用があるところ、前記(1)イ(ア)、(イ)及び(エ)で 説示した内容に加えて、原告意匠と被告意匠との差異点が美感に与える 影響は限定的なものにとどまること(前記1(4)エ)などを総合考慮す ると、上記の推定覆滅部分に相当する被告商品の売上高は、日本国内の 売上高の7割に相当する部分と認められる。 そうすると、本件において、上記の金銭の額を算定する際の基礎とな る金額は、上記の日本国内の売上高に海外での売上高を加えた4564 万3930円(=(5981万3900円×0.7)+(6358万8 100円−5981万3900円))となる。
(イ) 次に、使用料率について、証拠(乙59)及び弁論の全趣旨によれば、 株式会社帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許 等の活用の在り方に関する調査研究報告書〜知的財産(資産)価値及び ロイヤルティ料率に関する実態把握〜」には、特許権に関する「個人用 品または家庭用品」の使用料率(ロイヤリティ)の平均値は3.5パー セントであると記載されていることが認められる。 この点について、上記の「個人用品または家庭用品」の使用料率(ロ イヤリティ)の記載は特許権に関するものにすぎない上、そこにいう 「個人用品または家庭用品」の具体的な内容も明らかではなく、しかも、 上記の使用料率(ロイヤリティ)平均値は、収納容器とは異なる用品を 含めた数値であるものと推認される。
他方で、意匠権侵害をした者に対して事後的に定められるべき実施に 対し受けるべき使用料率は、通常の使用料率に比べて自ずと高額になる ものと解される。 以上の事情を総合考慮すると、本件において、登録意匠又はこれに類 似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を算定する際 の使用料率は、被告商品の売上高の3.5パーセントとするのが相当で ある。
(ウ) したがって、意匠法39条3項により算定される損害額は、159万 7537円(=4564万3930円×0.035)と認められる。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2025.01.13
令和5(ワ)8403 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月22日 大阪地方裁判所
事案に鑑み、まず第2要件及び第3要件について検討する。
イ 第2要件について
前記(1)で判示したとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体においては、\n傾斜部5)が、「笠木下部材」内に配置されたものに当たり得るとしても、少なくと もそれ自体が通気性能を有する「換気部材」ではないという点で、本件特許の特許\n請求の範囲に記載された構成とは異なる。\n原告は、本件発明の作用効果は、笠木下部分への取り付けが容易で、外壁下地材 の上端部の外方側に対して第1垂直部を当接させることにより笠木下部材の位置決 めが容易になることにあり、「換気部材」を傾斜部5)へと置き換えても、被告製品 が本件発明と同一の目的を達成し同一の作用効果を奏することを妨げるものではな い旨主張する。
しかし、本件発明が解決しようとする課題は、迅速な設置が困難であることに限 られるものではなく(前記(1)ア(ア)c)、本件明細書の記載からすると、本件発明 の目的ないし作用効果は、雨水や虫等の浸(侵)入を防止し、通気機能及び防水機\n能の信頼性の高い笠木下換気構\造体を提供することにもあると認められる(前記 (1)ア(ア)b(a)〜(c))。そして、別紙「図面」記載1及び2の各図面のとおり、被 告製品を部材とする笠木下換気構造体は、開口6)及び傾斜部5)と第1水平部2)との 隙間から建物内に雨水や虫等が浸(侵)入し得る構造となっているから、構\成要件 Cにおける「換気部材」を傾斜部5)に置き換えた場合、迅速な設置を可能にし、換\n気量を確保するという本件発明の目的は達成し得るとしても、雨水や虫等の浸(侵) 入を防止し、通気機能及び防水機能\の信頼性の高い笠木下換気構造体を提供すると\nいう本件発明の目的を達成することができないし、本件発明と同一の作用効果を奏 するともいえない。したがって、均等侵害の第2要件を認めることはできない。
ウ 第3要件について
本件発明は、従来技術である蛇行経路タイプの換気部材を用いた場合の課題(迅 速な設置が困難で換気量も少ないこと、蛇行経路を介して雨水や虫等が浸(侵)入 するおそれがあること等)を解決する換気部材を採用したものといえるところ(前記(1)ア(ア)b(a)、(b))、「換気部材」を従来技術である蛇行経路タイプに近い傾 斜部5)に置き換えることについては阻害要因があるものと認められる。原告は、通 気性能と防水性能\を生じさせるために、笠木下部材内に浸入する雨水を遮断する遮 蔽板を笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成することで同様の目的を達し得る\nことは広く知られており、当業者であれば、被告製品のように雨水を遮断する遮蔽 板と笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成する方法を用いることは容易に想到\nし得る旨主張する。しかし、そもそも本件発明の「換気部材」を被告製品の「傾斜 部」に置き換えると、第2垂直部に形成される「複数の開口」(その上下方向の位 置関係に特段の限定はない。)の「傾斜部」より上方部分において、笠木下部材内 に直通経路の通気路が形成され、防水性能を保持できなくなる可能\性がある。その ため、防水性能を保持するには「複数の開口」と「傾斜部」の位置関係や高さに創\n意工夫を要することとなるから、当業者が、被告製品の製造等の時点において上記 置換えを容易に想到することができたものとは認められない。したがって、均等侵 害の第3要件を認めることはできない。
エ 以上のことからすると、被告製品に関して、本件発明に対する均等侵害(間 接侵害)の成立を認めることはできない。
(3) 小括
以上のとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体は、本件発明の技術的範\n囲に属しないから、被告製品に関する間接侵害は認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> ピックアップ対象
2025.01.13
令和6(行ケ)10054 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年12月19日 知的財産高等裁判所
以上の点を踏まえ、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品」を「一括し て取り扱う」という指定役務の名称の文言をも考慮すると、「衣料品・飲食料品及び 生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる 顧客に対する便益の提供」とは、衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所 において扱っている場合であって、その取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、かつ、 継続的に行われている場合をいうものと解するのが相当であり、典型的には、百貨 店や総合スーパーが提供する役務が挙げられるものと解される。他方で、「一括して 取り扱っている」とはいい難い場合、具体的には、「衣料品、飲食料品及び生活用品 に係る」各種商品のうちの一部の商品しか小売等の取扱いの対象にしていない場合 や、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る」各種商品に属する商品を取扱いの対象 とする業態を行っている場合であったとしても、一部の商品の取扱量が僅少であり、 全体としてみると特定の商品等を主として取り扱っているとみられる場合や一部の 商品が各種商品の小売等に付随して取り扱われているすぎない場合などは含まれな いものというべきである。
なお、国際分類を構成する類別表\\注釈において示された商品又は役務についての 説明には特段の記載はないが、特許庁の類似商品・役務審査基準においても、「衣料 品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務 において行われる顧客に対する便益の提供」は「35K01」と定められる一方、 「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 は「35K02」、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する 便益の提供」は「35K03」、「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客 に対する便益の提供」は「35K06」とそれぞれ定められ、例えば「35K03」 などの同一コード内の小売等役務同士は互いに類似するものと推定される一方、「3 5K01」と「35K02」といった同じ35類であっても異なるコードの小売等 役務同士は類似しないものと推定されているところである。
・・・
エ 上記ウの各事実によると、原告店舗はパリの日用品店をアレンジしたライフ スタイルショップであり、ファッション、ファッショション小物やキッチン用品な ど衣料品や生活用品を中心とした商品を取り扱っており、これらの商品が店舗の売 上げに占める割合が相当程度多いものと認められるのに対し、前記ウ(イ)〜(エ)による と、飲食料品の販売数や売上金額は衣料品や生活用品に比して小規模である。これ に加え、証拠(乙13の1〜16)からうかがわれる本件要証期間及びその前後の 原告店舗における商品の展示方法をも考慮すると、本件要証期間における飲食料品 の販売については、コーヒーカップやマグカップのような食器類などと合わせて販 売されているものであって、生活用品の小売等に付随して取り扱われているものに すぎず、原告店舗において、衣料品、飲食料品及び生活用品の各商品を「一括して 取り扱っている」と評価することはできず、その他これを認めるに足りる証拠はな い。
また、前記ウ(エ)及び(オ)の各事実によると、原告店舗の売上金額が1か月間で10 0万円程度あったことが認められるものの、同(オ)については、取り扱っている食品 の内容に加え、前記ウ(カ)のバレンタイン前の期間の販売であったとの事実も考慮す ると、バレンタインの贈物のために一時的に売上げが増加しているものといえるこ と、前記ウ(エ)については、正月に向けて一時的に売上げが増加したものといえる ことからすると、原告店舗につき、一事業所において、衣料品・飲食料品及び生活 用品に係る各商品の取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、継続的に行われていると 認めることはできず、その他これを認めるに足りる証拠はない。
(3) 以上によると、本件要証期間において、原告店舗は、「衣料品、飲食料品及び 生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる 顧客に対する便益の提供」を行っていたものとはいえない。 したがって、本件要証期間において、原告が、「衣料品・飲食料品及び生活用品に 係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す る便益の提供」を行っているとは認めることができない旨を判断した本件審決に誤 りがあるとはいえない。
2 原告の主張について
(1) 原告は、本件商標を使用しそれによって業務上の使用が現に蓄積されている 以上、「飲食料品が総売上高に占める割合」によって商標法50条1項に係る商標の 使用・不使用を判断することは、同項の制度趣旨から逸脱しており、同項の不使用 取消審判において、商標登録要件の基準にすぎない「衣料品、飲食料品及び生活用 品の売上げがいずれも総売上高の10%〜70%程度の範囲内にあることが目安と される」との基準を採用し、それによって不使用取消しの審決をした本件審決は違 法であると主張する。
しかしながら、原告の上記主張のうち、原告が本件商標を使用しそれによって業 務上の信用が現に蓄積されているかは、指定役務である「衣料品・飲食料品及び生 活用品に係る各種商品を一括して取扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客 に対する便益の提供」について登録商標を使用しているかどうかの判断に直接の影 響を与えるものとはいえない上に、前記1(2)ウの原告店舗の商品販売状況等に照 らすと、本件商標の指定役務中の第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る 各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便 益の提供」について本件商標の使用による信用が蓄積されているとも認め難く、こ の点に関する原告の主張は採用できない。
2025.01.13
令和6(行ケ)10038 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年12月19日 知的財産高等裁判所
原告は、本願商標は「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせたも のであり、需要者等もそのように理解する旨主張する。 そこで検討するに、辞書によれば、「新生」の語は「新しく生まれ出るこ と」などを意味する語であり、「新生」の語の後に別の語を組み合わせた「新 生児」、「新生代」などの語が掲載されている(広辞苑第七版。乙82)。ま た、「甘酒」の語は「米の飯を米麹で糖化した甘い飲料」を意味する語であ る(広辞苑第七版。乙3)。
他方、辞書によれば、「新」は、「あたらしいこと」、「あたらしくするこ と」、「今年の新たな収穫・製造」などを意味する語であり、「新」の語の後 に別の語を組み合わせた語の例として「新発売」が挙げられている(広辞 苑第七版。乙1)。また、「生甘酒」の語は、加熱処理せずに製造した甘酒 を示す語として用いられている取引の実情があると認められる(乙4〜2 9、後記4(1)ア)。
以上によれば、本願商標に接した需要者等は、本願商標について、「新生」 の文字と「甘酒」の文字を組み合わせた商標であると理解する場合と、「新」 の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせた商標であると理解する場合と、 いずれもあり得るといえ、需要者等がどちらか一方の理解のみしかしない とは認められない。
イ 原告は、前記第3〔原告の主張〕1のとおり、本願の指定商品の需要者 等は、本願商標を「新」の文字と「生甘酒」の文字を結合させた商標であ ると認識することはない旨主張する。 しかし、「生甘酒」の語が「加熱処理せずに製造した甘酒」を示す語とし て用いられている取引の実情があり、かつ、「新」の後に別の語を付した語 を用いることがあって、辞書にもその例が掲載されていることからすれば、 「新生」が辞書に掲載される語として存在するとしても、本願商標が「新」 の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせた商標であると認識されることは 否定されない。
また、「生甘酒」の語が指し示す内容が「加熱処理せずに製造した甘酒」 であることからすると、これに「あたらしいこと」、「あたらしくすること」、 「今年の新たな収穫・製造」を意味する「新」の文字を組み合わせること が考え難いとはいえない。
原告が「新生」シリーズと称する商品を販売しているとしても、本願の 指定商品の需要者等の間で、「新生」の語が、原告の販売する商品の表示として広く認識されていると認めるに足りる証拠はなく、本願の指定商品の\n需要者等が、本願商標は原告の販売する「新生」シリーズの商品の名称と して用いられているものであると当然に認識しているとは認められない から、本願商標が上記「新生」シリーズに属する商品の名称として用いら れている事実をもって、需要者等が本願商標を「新」の文字と「生甘酒」 の文字を結合させた商標であると認識しないとはいえない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 以上によれば、本願商標が商標法3条1項3号に該当するか否かを検討 するに当たっては、本願商標が「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合 わせた商標であると解した場合と、本願商標が「新」の文字と「生甘酒」 の文字を組み合わせた商標であると解した場合との両方について、同号該 当性を検討すべきといえる。
3 本願商標を「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせた商標であると解 した場合
(1) 本願商標及び本願の指定商品に関する取引の実情 各項末に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件審決がされた令和 6年3月14日の時点での、本願の指定商品と関連する食品業界における「新生」の語に関する取引の実情として、次の事実が認められる。
・・・
前記(1)に挙げた各事実によれば、本件審決がされた当時、飲料の名称の前 に「新生」の文字を付して、当該飲料が「生まれ変わった」ものであること、 すなわちその原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくしたものであるこ とを示す表現として用いる取引の実情があったと認められる。そうすると、本願の指定商品の需要者等は、「新生甘酒」の語が「新生」の\n文字と「甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合、これが本 願商標の指定商品に使用されたときには、原材料、製法等を従前と変えて内 容を新しくした甘酒を一般的に指す名称であると認識すると認められる。そ して、「新生」も「甘酒」も、辞書に掲載された一般的な語であり、これらを 組み合わせた「新生甘酒」という語は、原材料、製法等を従前と変えて内容 を新しくした甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識す\nることができるものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3 条2項)のほかは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないもの と認められる。(なお、前記2(2)イで述べたとおり、本願の指定商品の需要者 等の間で、「新生」の語が、原告の販売する商品の表示として広く認識されていると認めるに足りる証拠はなく、また、「新生甘酒」という本願商標が、使\n用をされた結果、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識すること ができるものに当たることを認めるに足りる証拠もなく、本願商標が商標法 3条2項の要件を充足するとは認められない。もっとも、仮に、「新生甘酒」 という本願商標が、使用をされた結果、需要者が原告の業務に係る商品であ ることを認識することができるものとなった場合に、本願商標が商標法3条 2項に基づいて必ず商標登録を受けることができるか否かについては、本判 決の判断するところではない。)
したがって、本願の指定商品の需要者等が、「新生甘酒」の語を「新生」の 文字と「甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合、本願商標 は、その指定商品の需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の 品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる\nものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほか は、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされるものに該当 し、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)であると認められる。\n
・・・・
前記(1)アに挙げた各事実によれば、本件審決がされた時点で、「生甘酒」の 語を「加熱処理をせずに製造した甘酒」を示す語として用いる取引の実情が 存在していたと認められる。 また、前記(1)イに挙げた各事実によれば、本件審決がされた時点で、飲料 又は食料品を示す語の前に「新」を付して、当該飲料又は食料品がその年に 収穫されたもの又は作られたものであることを示し、あるいは従前販売され 前記(1)アに挙げた各事実によれば、本件審決がされた時点で、「生甘酒」の 語を「加熱処理をせずに製造した甘酒」を示す語として用いる取引の実情が 存在していたと認められる。
そうすると、本願の指定商品の需要者等は、「新生甘酒」の語が「新」の文 字と「生甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合、これが本 願商標の指定商品に使用された場合には、需要者等は、その年に製造された 生甘酒、又は製造方法や特徴が従前のものと異なる新しい甘酒を一般的に指 す名称であると認識すると認められる。そして、「新」は、辞書に掲載された 一般的な用語であり、飲料又は食料品を示す語の前に「新」を付すことにつ いて上記のような取引の実情が認められ、「生甘酒」も、「加熱処理をせずに 製造した甘酒」を示す語として用いる取引の実情があったから、これらを組 み合わせた「新生甘酒」という語は、その年に製造された生甘酒、又は製造 方法や特徴が従前のものと異なる新しい甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又\nは役務であることを認識することができるものについて商標登録を受けるこ とができる場合(商標法3条2項)のほかは、特定人によるその独占使用を 認めるのは適当でないものと認められる。
したがって、本願の指定商品の需要者等が、「新生甘酒」の語を「新」の文 字と「生甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合も、本願商 標は、その指定商品の需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品 の品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができ\nるものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほ かは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされるものに該 当し、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)であると認められる\n
5 結論
上記3及び4の説示によれば、本願商標を「新生」の文字と「甘酒」の文字 を組み合わせた商標であると解した場合、及び「新」の文字と「生甘酒」の文 字を組み合わせた商標であると解した場合のいずれについても、本願商標は、 その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)に当たると認められる。\n
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2025.01.13
令和6(行ケ)10034 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和6年12月19日 知的財産高等裁判所
こうした特別委員会等における議論を踏まえて、上記ウにおける意匠法 改正の過程では、上記ウ2)、3)のとおり、再度上記イにおける「びっくり 箱」を想定して動的意匠についての意匠法による保護が検討されたところ、 上記ウ2)のとおり、当初、「意匠に係る物品の形状・・・が・・・変化する 場合において、その変化の前後の形状」の意匠(下線は判決で付記)を出 願する場合を想定したのに対し、上記ウ3)のとおり「びっくり箱は複数の ものが同時にとれる。複数意匠ではないか。」との法制局審査における問題 提起や上記ウ6)のとおり複数意匠であるとの指摘を受けて、上記「変化の 前後の形状」との記載では複数意匠と捉えられかねないことから、これを 修整することとした。
そして、上記ウ3)のとおり物品自身が動くことは物品そのものであると 考え、上記ウ6)のとおり、動的意匠が一意匠であることを前提とした上で、 特別の例外規定を置くことなく、上記ウ7)のとおり、意匠法6条5項(現 同条4項)を、「その変化の前後にわたるその物品の形状」について意匠登 録を受けようとする(下線は判決で付記)との文言に修正して、意匠法改 正をすることとされたものである。
このように、昭和34年意匠法改正の過程においては、動的意匠につき、 物品の形状について「その変化の前後の形状」とするのでは、一意匠であ ることに疑義が生じることから、物品自身が動くことは物品そのものであ るとの認識のもとに、「その変化の前後にわたるその物品の形状」と規定さ れたものであり、特別の例外規定が置かれなかったことからしても、物品 の形状は、その変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の 物品に必要とされる形状についての要件を満たすことが前提とされてい たことは明らかである。
(5) 上記(3)、(4)を踏まえると、意匠法6条4項に定める動的意匠のうち物品の 形状が変化するものについて、その物品の形状は、変化の前後にわたるいず れの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性と して一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉え ることのできる定形性があり、その変化の態様に一定の規則性があるか変化 する形状が定常的なものであることが必要であると解される。
(6) 意匠法6条4項の解釈についての原告の主張に対する判断
原告は、前記第3〔原告の主張〕1のとおり、動的意匠は、物品の機能に\n基づいて、一定の規則性をもって変化する形態であれば、「定形性」を有する こととなるから、本件審決は意匠法6条4項の解釈を誤っている旨を主張す る。 しかし、意匠法6条4項の「意匠に係る物品の形状・・・がその物品・・・ の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるそ\nの物品等の形状等」を願書に記載しなければならない旨の出願の規定により、 意匠に必要とされる物品の形状の要件が直ちに変更されるとは解し難いとこ ろであり、上記(1)ないし(5)で検討したとおり、動的意匠について定める意匠 法6条4項の改正の経緯や、意匠一般に係る意匠法の定めにも鑑みると、上 記のとおり変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品と しての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、そ の形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性があり、その変化 の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必 要であると解されるところである。
・・・
エ 本願において登録を受けようとする意匠は、容器の蓋の開栓により変化 する形状等であって、変化前である閉蓋時は、容器上面の蓋部の周囲に位 置する大径リング状縁部の形状等であり、変化後である開蓋時は、大径リ ング状縁部の形状等に加え、その内方に現れる、容器内部の一部、濃褐色 の液体及び液体の上方を順次覆うように出現する乳白色の気泡の形状等で ある。 このうち、「変化の前後にわたるその物品の形状」である発泡状態の変化 を示す開蓋後の平面図1ないし10に基づく上記10秒間の発泡状態の 経時的変化は以下のとおりであり、これらは写真1枚につき概ね1秒ごと に生じる変化である。
(ア) 発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図1によれば、上記イの開蓋後の 平面図が大径リング状縁部内の飲料上部が全面濃褐色であるのに比べて、 缶周縁部液面上に沿って乳白色の泡が生じているところ、気泡の量が少 なく細い帯状となっていたり、泡がない箇所(図内右斜め上部分、下部 分等)と、気泡の量が多く太い帯状となっている箇所(上部分、右下部 分等)とがあり、中央部にはほのかに白い部分がある。
(イ) 発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図2について、泡が略円環状の輪 郭を形成しているものの、缶周縁に帯状となった気泡の幅は一定ではな く、その輪郭形状はいびつな円形である。 前記(ア)と比べて、気泡による帯の幅が増した箇所(右上部分)がある 一方、消滅ないし減少した箇所(右下部分)がある。また、中央部には 前記平面図1の白い部分が消えて、白い気泡の小さな集合が不規則に散 在する。
(ウ) 発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図3及び同平面図4に至り、円環 形状の径が漸次的に狭まっていくものの、輪郭形状の径が狭まる進行の 度合いは場所により一定ではなく、全体として缶の中心より上方向へそ れて行き、形状も円ではなくいびつな形状である。円環形状の中央付近 には白い気泡がある。
(エ) 発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図5において、円環形状の径はす ぼまって縦長になり、同平面図5及び同平面図6において、円環形状の 径が漸次的に狭まっていくものの、輪郭形状の径が狭まる進行の度合い はところにより一定ではなく、全体として缶の中心より上方向へそれて 行き、形状も円からはかけ離れたいびつな形状である。同平面図7及び 同平面図8において、形成された泡は次第に開口部全面を覆うが、中央 部付近にくぼみがあり、同平面図7から同平面図8にかけて小さくなっ ている。
(オ) 発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図9、同平面図10及び発泡後の 状態を示す開蓋後の開口部拡大斜視図においては、泡沫面が缶口部へ向 けて盛り上がっていき、缶口面上部に概ね円錐台状の立体形状を形成す るが、発泡の状態は一様ではなく、大きな単独の気泡が見え隠れする部 分(左部分)がある上、気泡が盛り上がった立体形状は、2段の円錐台 状である。
(2) 本願意匠の要旨認定に係る原告の主張についての判断
ア 原告は、前記第3〔原告の主張〕2及び3のとおり、本願意匠の要旨は 開蓋後の濃褐色の液体及び液体の上方を順次覆うように出現する乳白色の 「泡沫」の総体が、濃褐色の液体の上方を覆うように盛り上がって変化す る形状等にあり、本件審決の本願意匠の要旨認定は誤りである旨主張する。 しかし、前記2で検討したとおり、動的意匠におけるその物品の形状は、 変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品に必要とさ れる形状についての要件を満たすものであり、動的意匠として登録を受け ようとする意匠出願の要旨についても、それに沿い認定されるべきである ところ、原告の上記主張は、願書の記載及び添附された写真に基づき必要 にして十分なものとはいえない。\n
その上で、意匠の要旨は、願書に添附された説明及び写真に基づき認定 されるものであるところ、原告の上記主張は、上記(1)エ(ア)及び(イ)のとおり、 中央部付近に当初生じた泡の一部がいったん消えること(乳白色の気泡が 一旦生じた後に再度濃褐色の液体が現れる箇所)などについても記載され ているものではなく、原告の主張は、願書に基づくものとはいえない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、前記第3〔原告の主張〕4で主張するとおり、本件審決が認定 した乳白色の気泡が一旦生じた後に再度濃褐色の液体が現れる箇所などは 実際の物品を見た者において全く言及しないなど(甲28、29)、需要者 の注意を全く引かない部分であるとともに、上記「乳白色の気泡」は泡沫 と区別される気泡で液体中の気体の粒子であり、これが液面に浮上して缶 周縁部で泡沫に成長しているのであって消滅しているものではないから、 本件審決は要旨認定の手法としても技術的にみても誤りである旨を主張す る。
しかし、中央部付近に当初生じた泡の一部がいったん消えること(乳白 色の気泡が一旦生じた後に再度濃褐色の液体が現れる状況)を含め、本願 意匠の内容については、願書に添附された写真等に基づけば、前記(1)のと おり認定されるべきものである。そして、開蓋後の液面の状態は、通常、 需要者が見ているものであり、需要者の注意を全く引かないとはいえない。 一方、気泡と泡沫の区別について原告の主張する内容は、願書の記載及び 添付された写真に示された「発泡状態」からは把握できないものであって、 それらを意匠を受けようとするものの内容とすることはできない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない
4 本願意匠の意匠該当性について
(1) 既に検討したとおり、動的意匠は、出願に係る意匠が、意匠法2条1項の 「意匠」である状態を保ちながらその要素である形状等を変化させる場合に、 その変化の過程であるその前後の状況を含めて全体として一つの動的な形状 等として把握し、これを一つの意匠として保護しようとするものであり、変 化の前後にわたる物品の形状である中間状態も含め、全体として一つの物品 の形状等として把握できる定形性等が必要である。 具体的には、上記2(5)のとおり、物品の形状は、その変化の前後にわたる いずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属 性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を 捉えることのできる定形性があり、その変化の態様に一定の規則性があるか 変化する形状が定常的なものであることが必要である。
これを本願についてみると、前記3(1)エのとおり、発泡状態の変化を示す 開蓋後の平面図1ないし3において、缶周縁に帯状となった気泡の幅は一定 ではなく、その輪郭形状もいびつな円形であり、その過程において、気泡に よる帯の幅が増した箇所がある一方で、消滅ないし減少した箇所がある。ま た、中央部の白い部分が消えて、白い気泡の小さな集合が不規則に散在する 状態になった後、円環形状の径が漸次的に狭まっていくものの、輪郭形状の 径が狭まる進行の度合いも場所により一定ではなく、形状も円ではなくいび つな形状を示した後に、2段の円錐台形状に至る。このような気泡の発生及 び消滅の状況は、上記意匠ないし動的意匠の要件である一定の期間、一定の 形状を有し、境界を捉えることのできる定形性があるものとみられないほか、 変化の態様に一定の規則性があるか、あるいは変化の形状が定常的であると も認め難いものである。
なお、本願意匠を実施した商品とされる「生ジョッキ缶」についての公開 情報によっても、気泡の総体の形状及びその変化は、開栓ごとに異なり、缶 の周縁部に大きな泡が複数視認できる状態(甲31、15頁)、まだらに湧い た気泡が増加する状態(乙8)、泡の総体が球の一部を切り取ったようなドー ム形状に盛り上がった状態(乙9)、缶内部の液面の周縁部にかろうじて泡の 集合がみられる状態(乙10、4頁)などが認められるにとどまり、開栓の 都度、本願の願書の添付写真と同じ形状等が再現されるものとは認められず (甲1、17、31、乙7ないし10)、この点に照らしても、本願意匠に示 された気泡の発生及び消滅の状況が定形性を欠き、変化の態様に一定の規則 性はなく、変化の形状が定常的であるとも認め難いとの上記の認定は、相当 ということができる。 そうすると、本願意匠は、意匠登録を受けることのできる意匠には該当し ないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2025.01.13
令和6(ワ)70189 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和6年12月23日 東京地方裁判所
(1) 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであるから、思想、感\n情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でないもの又は表\ 現上の創作性がないものは、著作物に該当せず、著作権法上保護されるもの とはいえない。
これを本件についてみると、原告は、本件プログラムのソースコードのう\nち、1)製品名のドロップダウンリストを表示する機能\に関する部分(以下「1) 部分」という。)、2)顧客の名前を検索、確定する機能に関する部分(以下\n「2)部分」という。)、以上の2点を赤色でマーキングし、当該2点を創作 的表現部分として主張するものと解されるところ、原告は、裁判所からの繰\nり返しの釈明にかかわらず(第1回口頭弁論調書参照)、これらが創作的表\n現に該当する理由を具体的に主張するものではない。
この点を措き、原告の主張について精査しても、1)部分については、原告 の主張は、ActiveXコントロールのコンボボックスを使用し、フォン トやフォントサイズをカスタマイズ可能にするという、単なるアイデアをい\nうものにすぎない。念のため、1)部分の内容についてみても、証拠(甲14、 15)及び弁論の全趣旨によれば、エクセルにおいて標準仕様として用意さ れているActiveXコントロール及びActiveXコントロールのコ ンボボックスを用いて項目をドロップダウンリストとして選択可能とさせる\nものであって、これらを使用してフォント名及びフォントサイズをカスタマ イズする手法自体は、極めてありふれたものにすぎない。更に念のため、こ れらの機能に対応するソ\ースコードについてみても、使用されている指令及 びその組合せにおいて、原告の個性が表れているものといえないことは明ら\nかである。
また、2)部分についても、原告の主張は、ユーザフォーム画面のコンボボ ックスで、カタカナ行のドロップダウンリストから目的のカタカナ行をマウ スで選択して、表示されたリストボックスから目的の名前と電話番号をマウ\nスでクリックすることで顧客の名前を選択可能にするという、単なるアイデ\nアをいうものにすぎない。念のため、2)部分の内容についてみても、証拠(甲 14、16)及び弁論の全趣旨によれば、エクセルにおいて標準仕様として 用意されているユーザフォームのコンボボックスとリストボックスを用いる ものであり、コンボボックスとリストボックスを用いてマウスで値を選択さ せ、リストボックスの項目が選択されたときに実行されるChangeイベ ントを用いることにより、マウスで選択された値を取得することを可能とす\nるものであって、これらの手法自体は、いずれも極めてありふれたものにす ぎない。更に念のため、これらの機能に対応するソ\ースコードについてみて も、使用されている指令及びその組合せにおいて、原告の個性が表れている\nものといえないことは明らかである。 これらの事情の下においては、原告の主張は、アイデアをいうものに帰し、 本件プログラムに表現上の創作性を認めることはできない。\nしたがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10075 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年11月13日 知的財産高等裁判所
1 取消事由1(手続違背)について
原告は、特許庁の審判手続において、原告が答弁書副本を受領してから審理 終結通知の送付まで1週間もなかったとして、原告に反論の機会を与えなかっ た手続違背がある旨主張する。しかし、審判合議体には事件の審理が熟したと 判断するについて裁量権があるところ、本件の証拠を精査しても、上記の取扱 いが原告の防禦権を不当に制限することになるなどの事情は認められず、当該 裁量権の逸脱があったとは認められない。原告の主張は採用できない。
2 取消事由2(商標法4条1項6号該当性の判断の誤り)について
(1) 証拠(甲3、4、11〜13)及び弁論の全趣旨によれば、現在の独立行政 法人酒類総合研究所の前身である国税庁醸造試験所が仕込水の全部あるいは 一部に清酒を使用して発酵させることを特徴とした清酒の製法を開発し、開 発チームの故 A 博士がこれを「貴醸酒」と名付けたものであること、その 製法は、昭和49年に特許出願がされ、昭和53年に公告されたが、現在は存 続期間が満了していること、昭和51年に、貴醸酒の製造研究と普及を目的 に、被告を含む酒造会社等5社が貴醸酒協会を設立し、国税庁醸造試験所を 管轄する大蔵省(当時)と実施許諾契約を締結していたこと、特許権の存続期 間満了後は技術指導を国税局鑑定官室が行い、貴醸酒協会は商標の管理と加 盟各社に対して販売のアドバイスを行っていることが認められる。 そうすると、「貴醸酒」が、国税庁醸造試験所において開発された、水の代 わりに清酒で仕込んだ製法により醸造された清酒の名称であり、同試験所の 故A博士によって命名されたものと認めることはできるものの、当該清酒の名称が当然に事業の名称となるものではない。実際に「貴醸酒」として清 酒を製造販売してきたのは被告を含む貴醸酒協会加盟の酒造会社等であり、 「貴醸酒」の名称が国税庁醸造試験所又はその後身の独立行政法人酒類総合 研究所の団体自身やその事業で営利を目的としないものを表示するものとし\nて使用されたとはいえず、まして、そのような表示として本件商標の指定商\n品の取引者、需要者の間で著名であったことを認めるに足りる証拠はない。
(2) 原告は、「貴醸酒」は、新たな醸造方法の開発による醸造技術者の指導育成 を行う公益目的の事業であって、製法に関する特許権者も国税庁長官である 旨主張するが、貴醸酒を開発したのが国税庁醸造試験所であり、国税庁長官 が製法に関する特許権を有していたとしても、直ちに「貴醸酒」がその「事業」 を「表示」する標章であったということにはならない。\n原告は、本件商標についての商標登録出願は、商標法3条1項3号を理由 に拒絶されているとか、昭和51年の甲11、13の各論文には、「いわゆる 貴醸酒」と記載されており世間に知られていることを示しているなどと主張 するが、いずれも「貴醸酒」の名称が国税庁醸造試験所又はその後身の独立行 政法人酒類総合研究所の団体自身やその事業で営利を目的としないものを表\n示するものとして使用されたことを示すものとはいえず、また、そのような 表示として「清酒」の取引者、需要者の間で著名であったことを示すものとも\nいえない(「いわゆる」との表現は、その名称を取引者、需要者の中でどの程\n度の者が認識しているかを示すものではなく、また、その事業主体について は何ら示唆するものではない。)。かえって、貴醸酒の命名者を含む共同開発 者の論文には、「貴醸酒という名称は登録商標であり、一般名ではない。」(甲 11)、「貴醸酒という名称は登録商標(貴醸酒協会の会員だけが使用できる) であって、一般名でない」(甲13)との記載があり、国税庁醸造試験所において、「貴醸酒」を同試験所自身やその事業で営利を目的としないものを表示\nするものとして認識していないことが明らかであり、本件商標の登録の経緯 に鑑みても、本件商標を実際に業務に使用し識別力を取得させたのは被告を 含む酒造会社等であったものというべきである。なお、原告の指摘するとお り、これらの論文は、本件商標が設定登録を受けた昭和62年8月19日よ り前に発行されたものであるが、そのことは上記認定を左右するものではな い。
3 それ以外の原告の主張について
原告は、1)本件商標は商標法4条1項16号に該当するにもかかわらず、同 法3条2項の適用によって商標登録を認めた登録審決は誤りである、2)本件商 標は同法29条に該当するとの主張もしているが、これらは、いずれも本件の 無効審判手続において審理・判断されていないから、最高裁昭和51年3月1 0日大法廷判決・民集30巻2号79頁の趣旨に鑑み、審決取消訴訟の対象と することはできないものというべきである。
なお、上記2)に関していえば、商標法29条は登録が有効であることを前提 に使用の制限を定めるものであって、そもそも同法46条1項の無効審判請求 の理由とはならない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10028 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年11月11日 知的財産高等裁判所
(1) 事業者について
ア 証拠(甲12〜21、44、52、54〜57)によれば、株式会社ア ジアス、株式会社日本メディックス、フクダ電子株式会社、アイ・エ ム・アイ株式会社、株式会社三笑堂、さくらメディカル株式会社、株式 会社セントラルメディカル、ジーエムメディカル株式会社、株式会社ナ ンブ、中嶋メディカルサプライ株式会社、コニカミノルタ株式会社、株 式会社アールエフ、オムロンヘルスケアサービス株式会社、三井温熱株 式会社、伊藤超短波株式会社といった多数の医療機器メーカー等につい て、製造・販売と貸与(レンタル・リース)の両方の事業を行っている ことが認められる。 また、キヤノンメディカルシステムズ株式会社(製造・販売)とキヤ ノンメディカルファイナンス株式会社(リース)(甲50)、パラマウ ントベッド株式会社(製造・販売)とパラマウントケアサービス株式会 社(レンタル)(甲53)についても、同一のハウスマークを用いて営 業を行う系列会社であること、これらの需要者は、そうした系列会社間 の法人格の異同にさほど関心を持たないと考えられる一般の需要者が含 まれていること(後記(4)参照)等の事情を考慮すると、「商品の製造・ 販売と役務の提供が同一事業者によって行われている場合」に準ずるも のということができる。
この点、被告は、「同一事業者」とは、狭義の混同を生じさせる同一 の事業者のことであって、親子会社や系列会社等は含まれない旨主張す る。しかし、企業の経営戦略として、同じブランド(特にハウスマーク) を使用しつつ多様な事業展開を円滑に行う等の目的で、特定の事業部門 を分社化したり、持株会社(ホールディングス)が傘下の複数の事業会 社を統括するような法人格の運用は、ごく一般的なものであり、そのよ うな場合、形式的に見れば別法人が展開する事業であっても、外部の第 三者(特に一般需要者)からみて、同一の営業主体による事業と認識さ れることも珍しくないと解される。上記1で述べた商品・役務に係る営 業主体の誤認のおそれは、取引者・需要者の認識を基準に判断すべきも のであるから、上記のような理由により「別法人が展開する事業であっ ても同一の営業主体による事業と認識されても不思議でない場合」には、 「商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われている場 合」に準ずるものとして扱うのが相当である。 この点に関する被告の上記主張は、商品・役務に係る営業主体の誤認 のおそれは取引者・需要者の認識を基準に判断すべきことを看過したも のであり、採用できない。
イ 次に、証拠(甲7〜9)によれば、医療用機械器具の製造、販売、貸与 等を行う企業を会員とする団体である商工組合日本医療機器協会におい ては、医療機器の製造販売業又は販売・貸与業の許可等を受けている企 業が77社あり、そのうち、製造販売業と販売・貸与業の両方の許可等 を受けている企業は53社(68.8%)あることも認められ、約3分 の2の割合という多数の製造・販売業を行う事業者が、貸与業も行うこ とができる状況にあるといえる。
この点、甲43によれば、令和2年度末における医療機器の製造販売業 許可数が2799件となっていることが認められるが、上記協会に加入 している企業のうちの対象企業数77社が、サンプルサイズとして小さ すぎるとまではいえない。そして、商工組合日本医療機器協会の会員か 非会員かの違いが、販売・貸与業の許可等取得割合に実質的な違いを生 じさせているといった事情もうかがわれない。そうすると、比較対象た る企業集団の母数の違いのみから、上記の傾向、すなわち、医療機器の 製造・販売業を行う事業者の多数が貸与業についても許可等を受けてい るとの事実を否定することはできない。
加えて、証拠(甲10、42)によれば、東京都が用いている「高度 管理医療機器等販売業/貸与業許可申請」(様式第87)、「管理医療\n機器販売業/貸与業届出」(様式第88)の書式では、「販売業」と 「貸与業」の許可申請・届出を1通の書類で行う様式がデフォルトと\nなっており、販売業と貸与業の「どちらか一方の時は、不要の文字を消 してください」という記載例の注意書きが示されていることが認められ る。これは、医療機器の販売業と貸与業の双方の許可申請・届出を行う\n例が現実に多い実情を示すものと理解できる。
ウ また、被告は、国内の主要な医療用機械器具メーカー(甲33)と、主 要な医療用機械器具のリースサービスを提供する事業者(甲35、36) 又はレンタルサービスを提供する事業者(甲37)が一致していない点 を指摘し、同一事業者が機械器具の製造・販売と機械器具の貸与を行う ことは一般的でないと主張する。 しかし、業界における主要な事業者とは、企業の経済活動の規模(売 上等)や商品・サービスの内容から様々な基準によって選出されるにす ぎず、仮にある事業者が製造販売業と貸与業の両者の業務を行っている としても、企業の経営戦略等によってどちらに重きを置くのかは当然異 なり得るのであるから、製造販売業における主要企業と貸与業における 主要企業が一致していないからといって、このことから直ちに両者を同 時に行う事業者が少ないとまで断言できない。
(2) 用途について
医療用機械器具の貸与は、他人の求めに応じて当該機械器具を貸与する ことであるところ(甲34)、貸与という行為は、単に貸渡し行為をするこ とのみならず、需要者に当該機械器具を使用させることを当然に予定するも\nのである(民法601条参照)。よって、その貸与の用途は、医療用機械器 具の医療目的での使用ということができ、本件指定商品・医療用機械器具の 用途と共通するといえる。
(3) 提供場所・販売場所について
上記のとおり、多数の医療用機械器具の製造・販売を行う事業者が同時 に貸与も行っている取引の実情があることや、各事業者は、ホームページを 設けて申込みや問合せを受け付けており、その際には販売と貸与を共に説明\nしていること(甲68〜71)に鑑みると、医療用機械器具の販売場所と貸 与の提供場所は、いずれも当該企業の営業所所在地やインターネット上の ホームページ(同一のサイト)等であると認められる。そうすると、本件指 定役務・医療用機械器具の貸与と、本件指定商品・医療用機械器具について は、提供場所・販売場所が同じである場合が多いということができる。 これに対し、被告は、現代社会ではあらゆる物品がインターネット上の ウェブページで貸与、販売されているから、本件においても商品の販売や役 務の提供がインターネット上のウェブページで行われていることを理由とし て提供場所が一致するというのは暴論であると主張する。しかし、商品・役\n務の類似性判断の考慮要素として、商品の製造・販売と役務の提供が同一事 業者によって行われている実情の有無・程度等とは別に、その提供場所・販 売場所の同一性を独立の考慮要素としているのは、同一事業者が扱う商品・ 役務であっても、商品と役務とで全く異なる営業形態を取るような場合も考 えられるからである。そのような場合と異なり、同一事業者が、そのホーム ページ等の同一のサイトで商品の販売と役務の提供の両方の営業を行ってい るとすれば、その商品・役務の類似性を肯定する方向で考慮すべきことは当 然である。被告の上記主張は失当である。
(4) 需要者の範囲について
本件指定商品・医療用機械器具は、医療機関で用いられるものに限らず、 一般家庭内で健康状況に応じて使用されるものも含まれること、その需要者 には、医療機関のみならず、一般の需要者等が含まれることについては、い ずれも当事者間に争いがない。そして、証拠(甲48、53、56、57) によれば、本件指定役務・医療用機械器具の貸与においても、広く一般の需 要者(消費者)が想定されている場合があることが認められるから、両者の 需要者は実質的に重なるといえる。 これに対し、被告は、医療用機械器具の貸与の対象となるものは、専ら 高額な機械器具であり、その需要者は事業者、すなわち医療機関に限られる と主張する。確かに、貸与の対象となる医療用機械器具は、販売の対象とな る医療用機械器具よりも相対的に高額なものが多いであろうことは想像に難 くなく、それに伴う需要者の範囲の相対的な違いはあり得るとしても、医療 用ベッドや家庭用治療器、リハビリテーション機器等のレンタルサービスを 一般需要者向けの広告で扱っている事例が実際にあることは紛れもない事実 である(甲53、56、57)。本件指定役務・医療用機械器具の貸与の需 要者が「医療機関に限られる」という被告の主張は、証拠に基づかない極論 といわざるを得ない。 結局、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と本件指定商品・医療用機 械器具の需要者の範囲は、相対的な違いはあれ、医療機関と一般の需要者等 を含む点で実質的には重なっているというべきである。
(5) 小括
以上によれば、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と、本件指定商 品・医療用機械器具の製造・販売とは、同一事業者によって行われている例 が多数みられ、これらの用途は共通し、販売場所と提供場所は同一である場 合が多く、需要者の範囲は実質的に重なっているということができる。この ような取引の実情を踏まえると、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と本 件指定商品・医療用機械器具に同一の構成の商標(「AWG治療」)を使用\nする場合には、同一の営業主体の製造・販売又は提供する商品・役務と取引 者・需要者に誤認されるおそれがあるというべきである。 なお、本件指定商品・医療用機械器具は、「歩行補助器・松葉づえ」を 除くものとされており、このような除外のない本件指定役務・医療用機械器 具の貸与と異なっているが、この違いが商品・役務の類否に影響を及ぼすと はいえない。
3 商標権の効力の観点からの弊害について
原告は、先願に係る引用商標の商標権者であり、「AWG治療」の商標を医 療用機械器具に付した上でこれを引き渡す行為を第三者が行った場合、当該商 標権の侵害を理由に禁止権を行使することができるはずである(商標法36条、 37条1号、2条3項2号)。しかし、本件商標の登録が有効なものだとする と、「AWG治療」の商標を医療用機械器具に付した上でこれを貸与する行為 (当然に「引渡し」を包含する。)は、通常、本件商標に係る商標の使用と認 めるのが自然であり(同法2条3項3号)、商標権の及ぶ範囲の重複・抵触が 生じかねない。このような状況を招来させるのは、権利範囲の問題と登録要件 の問題が理論上は別個の問題であるにせよ、商標法全体の整合的解釈という観 点からは好ましいことでない。以上の理由からも、本件指定役務・医療用機械 器具の貸与と、本件指定商品・医療用機械器具とは、類似するものと判断する のが適切である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10006 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年10月29日 知的財産高等裁判所
ア 原告は、フランスに本社がある会社であり、我が国における原告の子会 社は日本エア・リキード社である。(甲3、4、24、42)
イ 原告及び日本エア・リキード社は、産業ガス・医療ガスに関する事業を 行う会社である。産業ガスは、鉄鋼、化学、機械・金属加工、自動車・輸 送機器、食品等の各産業における製品の製造の過程で用いられるガスの総 称であり、酸素、窒素、水素、アルゴンなどがこれに含まれる。また、医 療ガスは、病院で使用される酸素等のガスであり、「産業ガス」の語が医療 ガスを含む意味で用いられることもある。日本エア・リキード社は我が国 において、事業者に対して産業ガス・医療ガスを供給する事業を行ってい る。原告は、その子会社を含む売上げで、産業ガスの分野において、20 21年(令和3年)の世界の市場シェアで全体の2位を占めている。また、 日本エア・リキード社は、我が国における2018年(平成30年)3月 期の産業ガス事業において国内第3位のシェアを占めており、同社を含む 上位3社で産業ガスのシェアの約8割を占めている。(甲3、4、24、4 1、42、52)
ウ 日本エア・リキード社は、昭和5年(1930年)に「帝國酸素株式会 社」として設立された会社であり、その後同社の商号は、「帝国圧縮瓦斯株 式会社」(昭和18年)、「帝国酸素株式会社」(昭和21年)、「テイサン株 式会社」(昭和56年)と変更され、平成10年に「日本エア・リキード株 式会社」に変更された。また、平成5年8月頃から、別紙1「原告商標目 録」記載1ないし4の各「商標の構成」の箇所に掲げた図柄(「AIR LIQUIDE」の文字が入った図柄、以下「先代ロゴマーク」という。)が、 会社のロゴとして用いられるようになった。ただし、商号が「テイサン株 式会社」である間は、先代ロゴマークの右下に小ぶりの字で「TEISAN」 という文字を入れて使用していた(甲61、62)。その後、日本エア・リ キード社は、平成29年1月頃から、別紙1「原告商標目録」記載6及び 7の各「商標の構成」の箇所に掲げた図柄(「Air Liquide」の 文字が入った図柄、以下「現ロゴマーク」という。)を会社のロゴマークと して用いるようになり、現在も現ロゴマークを使用している。日本エア・ リキード社は、これらのロゴマーク(先代ロゴマーク、及び現ロゴマーク 採用後は現ロゴマーク)を、会社案内のパンフレット、ホームページ、設 置したタンク及び水素ステーション、使用するタンクローリー等に表示し\nている。(甲4、5、6、24、36、42、60〜68) 現ロゴマークを用いた日本エア・リキード社の広告が、日本経済新聞(甲 34、35)、日経産業新聞(甲31〜33)、雑誌「週刊エコノミスト」 (甲69、70)に掲載されたが、これらの広告には、日本エア・リキー ド社の親会社がフランス法人の原告であることは示されておらず、現ロゴ マーク又は引用商標がフランス法人である原告の業務に係る商品又は役 務を表示するものであることも示されていなかった。\n
(2) 周知性について
前記(1)の事実によれば、原告は、その子会社を含む売上げで、産業ガスの 分野において、2021年(令和3年)の世界の市場シェアで全体の2位を 占めている。そして、日本エア・リキード社が、我が国における産業ガスの 事業において大きなシェアを占めており、2018年(平成30年)3月期 においては、上位3社でシェアの約8割を占める産業ガス事業において第3 位のシェアを得ていたことが認められる。また、日本エア・リキード社は、 平成5年8月頃から「AIR LIQUIDE」の文字が入った先代ロゴマークを使 用し、平成29年1月頃からは、現在に至るまで「Air Liquide」 の文字が入った図柄の現ロゴマークを使用しており、先代ロゴマーク、及び 現ロゴマーク採用後は現ロゴマークを会社のパンフレットや設備等にも表示\nしていることが認められる。
しかし、我が国において、事業者に対して産業ガス・医療ガスを供給して いるのは、原告の子会社である日本エア・リキード社であって、原告自体が、 我が国において事業者に対して産業ガス・医療ガスを供給しているとは認め られない。また、日本エア・リキード社は、平成10年に商号が「日本エア・ リキード株式会社」となったが、それ以前は、昭和5年(1930年)の設 立以来、「帝國酸素株式会社」、「帝国圧縮瓦斯株式会社」、「帝国酸素株式会社」、 「テイサン株式会社」という商号を用いており、これらの従前の商号は、当 該商号の会社が原告の子会社であることや、外国の会社の子会社であること すら推知させないものであった。日本エア・リキード社は、平成5年8月頃 から「AIR LIQUIDE」の文字が入った先代ロゴマークの使用を開始した後 も、商号が「テイサン株式会社」である間は、先代ロゴマークの右下に小ぶ りの字で「TEISAN」という文字を入れて使用していた(甲61、62)。現 ロゴマークを用いた日本エア・リキード社の広告が、日本経済新聞(甲34、 35)、日経産業新聞(甲31〜33)、雑誌「週刊エコノミスト」(甲69、 70)に掲載されたことが認められるが、これらの広告には、日本エア・リ キード社の親会社がフランス法人の原告であることは示されておらず、現ロ ゴマーク又は引用商標がフランス法人である原告の業務に係る商品又は役務 を表示するものであることも示されていなかった。そして、日本エア・リキ\nード社がフランス法人である原告の子会社であることについて、これが広告 に記載されるなどして広く知らしめられた事実は認められない。これらのこ とを考慮すると、日本エア・リキード社がフランス法人である原告の子会社 であることは、広く認識されているとは認められない。
そうすると、我が国において産業ガス・医療ガスの供給を受ける事業者を 引用商標の需要者と解するとした場合、その中では、一定の範囲で、引用商 標が日本エア・リキード社の商標として認識されていることは認められるが、 フランス法人である原告の商標として広く認識されているとは認められない い。 また、本件商標の需要者は、一般消費者のうち喫煙者及びたばこに関心の ある者と解されるところ、産業ガス・医療ガスの供給を受ける事業者は、そ れに応じた設備等を有する者に限られることに鑑みれば、本件商標の需要者 の大半は、産業ガス・医療ガスの分野の知識をそれほど有しないと推認され、 本件商標の需要者の間では、引用商標が日本エア・リキード社の商標として 認識されているとは認められず、まして、引用商標がフランス法人である原 告の商標として広く認識されているとは認められない。
原告は、引用商標「Air Liquide」が原告の業務に係る商品又 は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると主張するが、\nこれまで述べたところによれば、この点に関する原告の主張は、採用するこ とができない。
(3) 商品の類似性について
商品が類似のものであるかどうかは、それらの商品が通常同一営業主によ り製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の 商標を使用する場合には、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認され るおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断するのが相当で ある(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷 判決・民集15巻6号1730頁)。
前記(1)の認定事実によれば、引用商標が使用されている商品は、産業ガス 及び医療ガスである。原告が商標登録又は国際登録を受けている商標であっ て「Air Liquide」又は「AIR LIQUIDE」の文字が構\n成に含まれるもの(別紙1「原告商標目録」記載1ないし7の各商標)は、 その指定商品及び指定役務として、産業ガス及び医療ガス以外の多様な種類 の商品及び役務が指定されているが(甲10、12、14、16〜22)、こ れは、日本エア・リキード社の製造、販売する産業ガスの製造過程等におい て用いられている商品及びこの産業ガスが使用されている役務を指定商品及 び指定役務として登録したものであって(弁論の全趣旨(令和6年2月22 日付け原告準備書面(第1回)17頁))、日本エア・リキード社が、上記各 商標の指定商品とされた多様な種類の商品の販売や多様な役務の提供を行っ ているとは認められず、産業ガス及び医療ガス以外について引用商標が使用 されていると認めることもできない。
他方、本件商標の指定商品は、前記第2の1(1)のとおり、第34類の「喫 煙用薬草、喫煙用ライター、喫煙用具、喫煙パイプ用吸収紙、電子たばこ、 水パイプ、電子たばこ用リキッド、喫煙者用の経口吸入器、たばこ、喫煙パ イプ、代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。)、シガーライ ター用ガス容器、シガリロ」である。これらの本件商標の指定商品と、引用 商標が使用されている商品である産業ガス及び医療ガスとは、それらの性質、 目的、用途、使用方法、使用者、製造者、販売者、取引態様等が大きく異な るものと認められ、これらが通常同一営業主により製造販売されているとの 事情は存在せず、その他、これらの商品に同一又は類似の商標を使用する場 合に、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると解 すべき根拠となる事情は認められない。
別紙1「原告商標目録」記載5及び6の商標の指定商品には、第5類の「医 療用又は治療用の喫煙用剤(単独で又はたばこと混ぜて販売されるもの)、 医療用又は治療用のたばこの代用品」が含まれているが(甲17〜20)、 原告又は日本エア・リキード社がこれらの商品を我が国で製造販売している とは認められず、その他、原告又は日本エア・リキード社が、本件商標の指 定商品である「喫煙用薬草、喫煙用ライター、喫煙用具、喫煙パイプ用吸収 紙、電子たばこ、水パイプ、電子たばこ用リキッド、喫煙者用の経口吸入器、 たばこ、喫煙パイプ、代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。)、 シガーライター用ガス容器、シガリロ」を製造販売しているとも認められな い。 したがって、引用商標が使用されている商品と、本件商標の指定商品との 間には、これらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合に、同一営業主 の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められないから、 引用商標が使用されている商品と本件商標の指定商品は、類似しているとは 認められない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和5(ワ)10237 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年11月14日 大阪地方裁判所
前記2(2)ア認定のとおり、本件発明は、非力な者であっても、危険な野生動物が 生息している場所において、簡単かつ確実に屠殺できるようにすることを解決すべ き課題とし「(【0008】ないし「【0012】)、このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで、対象動物との距離を調整できるようにし、例え\nば、猛禽類に対しては距離を長く取ったり、安全性を確保できる場合には距離を短 く取って確実に電極を動物の体に接触させたりすることができるという効果が得ら れるというものである。
一方、証拠(甲2、乙18)によれば、本件特許の出願時点で、野生動物を殺処 分する手段として、麻酔ガス等を用いることや電気スタナーを用いることなどが知 られていたことが認められる。これらの手段は、動物を殺害することはできるが、 即効性に欠けたり、即効性があっても動物に近づく必要があることから危険を伴っ たりするものであった。 そうすると、本件発明は、従来技術である電流を用いた屠殺手段を踏まえ、簡単 かつ安全確実な屠殺手段を提供するものであり、本件発明の構成中の本質的部分は、\nこのような屠殺手段を提供する竿体の伸縮構造(構\成要件Aの「伸縮自在の所定長 さの竿体」)、バッテリ部、電源昇圧部及びインバーター部の背負い構造(構\成要 件F)、双方の手でそれぞれ電源スイッチと竿体を把持できる通電コードの並列構\n造(構成要件G)に認められるものというべきである。\n
イ 前記2で検討したとおり、被告製品は、少なくとも、構成要件Aの「伸縮自\n在の所定長さの竿体」の部分、構成要件F及びGを充足しないのであるから、本件\n発明の構成中、被告製品と異なる部分が本件発明の本質的部分ではないとの均等侵\n害の第1要件は認められない。
(2) 第5要件について
ア 証拠(乙8ないし17)によれば、本件特許の出願経緯について、以下の事 実が認められる。
・・・
イ 以上の審査経緯に鑑みれば、原告は、当初、竿体の伸縮構造については固定\n長の竿体も含むものとし、バッテリ部、電源昇圧部及びインバーター部の背負い状 態の構成については携行可能\であるとするのみで背負い構造に限られないものと\nし、双方の手でそれぞれ電源スイッチと竿体を把持できる並列構造については双方\nの手でそれぞれ把持することが明示的に記載されていないものとし、土中の接地電 極と同電位とする回路構造については土中を閉回路に含まない回路構\造も含むもの として、特許請求の範囲を記載していたが、進歩性欠如及び明確性要件違反を指摘 されたことから、拒絶査定を回避するため、現在の特許請求の範囲の請求項1の記 載のとおりに限定したのであり、限定により除外された部分は、いずれも本件特許 の特許請求の範囲から意識的に除外したものであることが認められる。 そうすると、被告製品と本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載との相違点 は、いずれも原告が意識的に除外した部分に該当するから、均等侵害に関するその 余の原告の主張を前提としても、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特 許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときと の第5要件を満たさないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10023 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年11月13日 知的財産高等裁判所
当裁判所は、本件補正は本願発明の特許請求の範囲を減縮するものであって、 かつ、本件補正発明が明確でないということはできないと考える。したがって、 本件補正が特許請求の範囲を減縮するものではなく、仮に減縮するものだとし ても独立特許要件を満たしていないという理由で本件補正を却下した本件審決 は誤りであり、取消事由1が認められるので、その余の取消事由について判断 するまでもなく、本件審決は取り消すべきものと判断する。
・・・・
ア 本件補正に係る補正事項のうち、「決済以外の用途において適用可能な\n情報処理端末であって、」(補正事項1)の追加は、本件補正発明の情 報処理端末を、決済用媒体と非決済用媒体の双方を処理の対象とするも の(以下「決済・非決済共用端末」という。)及び非決済用媒体のみを 処理の対象とするもの(以下「非決済専用端末」という。)に限定する もの、すなわち決済専用の端末を本件補正発明の技術的範囲から除外す るものであり、これは特許請求の範囲の減縮に当たると認められる。 また、「前記接触型の読み取り部及び前記非接触型の読み取り部は、決 済に関する情報の入力がなされていない前記情報記憶媒体から読み取り 対象の情報を読み取り可能であり、」(補正事項3)の追加は、読み取\nり部の機能として、「決済に関する情報の入力がなされていない前記情\n報記憶媒体」を読み取り可能であることを限定するものであり、特許請\n求の範囲の減縮に当たると認められる。
原告は、上記の補正により決済用媒体を処理の対象としていないことを 特定していると主張するが、これらの補正事項は、それぞれ「決済以外 の用途において適用可能」、非決済用媒体から「読み取り対象の情報を\n読み取り可能」であることを特定するにとどまり、決済用媒体を対象に\n含む決済・非決済共用端末を除外しているとは解されないから、同主張 を採用することはできない。
イ その上で、本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」 を削除する補正事項4についてみると、文言上は、「前記接触型の読み取 り部及び前記非接触型の読み取り部のそれぞれを」「情報記憶媒体から情 報を読み取り可能な待ち受け状態に維持」する態様(以下「本件態様」と\nいう。)を限定していた事項を削除するものであるから、「『決済に関す る情報の入力』の有無が本件態様に関係する情報処理端末」は、本願発明 の範囲には含まれていなかったが、本件補正発明の範囲には含まれること になったと解釈する余地がある。
しかし、本願発明は、決済に関する情報(金額情報、支払方法、決済に 使用されるカードブランドの情報など)をユーザが入力してから決済に使 用されるカードの読み取り操作を促す処理及び表示を行うという従来技術\nの構成では、決済以外の用途への適用が難しいという課題を解決するため、\n決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、接触型・非接\n触型の別を問わず、情報記憶媒体から短時間で必要な情報を読み取り可能\nな情報処理端末を提供するものであり(【0004】〜【0007】)、 この点は、本件補正発明においても同様である。
そして、「決済に関する情報の入力の有無が本件態様に関係する情報 処理端末」としては、「決済に関する情報の入力」によって初めて本件 態様になるような情報処理端末が考えられるが、このような情報処理端 末を利用するためには、常に「決済に関する情報」の入力が要求される ことになるから、本願発明及び本件補正発明の趣旨目的に反するもので あるのみならず、例えば、マイナンバーカードのような非決済用媒体を 処理対象とする場合には、「決済に関する情報」そのものがないのであ るから、「決済に関する情報の入力」がない限り待ち受け状態とならな いとすると、いつまでも本件態様となることができず、非決済用媒体を 読み取ることができない。そのような端末は「決済以外の用途において 適用可能な情報処理端末」とはいえない。\n逆に「決済に関する情報の入力」により本件態様が終了するような情報 処理端末も一応考えられるが、このような端末は、当該入力後は読み取り 可能ではなくなり、決済・非決済共用端末の場合において、決済に関する\n情報を入力すると決済目的で情報処理端末を利用することができなくなる、 いい換えると、決済処理を行わないのに決済に関する情報を入力する手段 を設けるという、およそ不合理なものとなる。
補正事項4を含む本件補正後の発明が、これらの「決済に関する情報 の入力の有無が本件態様に関係する情報処理端末」をその技術的範囲に 含むと解することは、合理的な解釈とはいい難い。 むしろ、本願発明及び本件補正発明の技術的範囲の内容について、本 願明細書の内容を考慮して解釈するならば、本件補正の前後を通じ、本 件態様となるために「決済に関する情報の入力」が不要であることに変 わりはなく、本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」 との文言は、決済以外の用途において適用可能であることを特定してい\nたにすぎないものと解するのが相当であるから、補正事項4により、本 件補正発明に本願発明に含まれていなかった事項が含まれることにはな らない。
ウ 補正事項1及び3が特許請求の範囲の減縮に当たることは前記のとおり であり、補正事項4が新たな事項を追加するものではない以上、結局、本 件補正は、全体として特許請求の範囲を減縮するものに当たる。これに反 する被告の主張は、以上述べた理由により、採用することができない。 したがって、補正事項4を含む本件補正は特許法17条の2第5項2 号に規定する「特許請求の範囲を減縮」する場合に該当するから、同号 の補正要件を満たしていないとする本件審決の判断には、誤りがある。
(2) 独立特許要件(本件補正発明の明確性)について
進んで、本件補正が独立特許要件(特許法17条の2第6項、同法126 条7項)としての同法36条6項2号(明確性)の要件を充足するかどうか について検討する。 前記のとおり、本件補正発明の「決済以外の用途において適用可能な情報\n処理端末であって、」との記載は、非決済専用端末のみならず決済・非決済 共用端末を含むものと解される。このことは、本願明細書において、発明の課題及び効果は「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末」の提供であるとされた上で(【0005】、【0007】)、最初の実施例として決済・非決済共用端末の例が記\n載されていること(【0011】以下)及びほかの実施例として非決済専用 端末の例が記載されていること(【0072】)を参酌すれば、さらに明ら かであり、少なくとも、本件補正後の特許請求の範囲の記載が第三者の利益 を不当に害すほどに不明確ということはできない。
これに反する被告の主張は、以上述べた理由により、いずれも採用するこ とができない。したがって、本件補正発明の「決済以外の用途において適用可能な情報処理端末であって、」との記載は明確であり、本件補正発明は明確でないから\n特許法123条1項4号、同法36条6項2号の要件を欠き、独立特許要件 (同法17条の2第6項、126条7項)を満たしていないとする本件審決 の判断には、誤りがある。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 限定的減縮
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(ネ)10023 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年11月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 当審における控訴人の補充主張について
ア 控訴人は、被告方法において、一つの辺でも最大粒径より小さなバリがあれ ば、磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなっ ていることは原理・論理的に明らかであると主張する。 しかしながら、モールド樹脂内の磁性体粉末の具体的な粒子径の形状・分布、樹 脂の性質、隙間の形状・構造、加えられる圧力等により、隙間を通過する磁性体の\n量は変化するものと推測されるところ、被告方法においては、様々な粒子径、形状 の磁性体が使用されている(乙3,4)から、モールド樹脂内の磁性体粉末の具体 的な粒子径の形状・分布、樹脂の性質、隙間の形状・構造等がどのようなものであ\nる場合に隙間を通過する磁性体がどの程度あるのかについて、必ずしも一義的に明 らかではないといわざるを得ない。したがって、控訴人が主張する、磁性体粉末の 最大粒子径よりも小さなバリがあることをもって、当然に磁性体粉末容積比(バリ) の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなっているものとはいえない。
また、仮に被告方法における磁性体粉末の粒子径分布とバリの大きさとの関係性 から一定の事実を推認することができる余地があり、例えば、磁性体モールド樹脂 内の全磁性体粒子のうちの最小粒子径が隙間よりも大きい場合には、磁性体は隙間 を通過することができないため、樹脂のみが隙間から流出することが推測される一 方、逆に、全磁性体の粒子径が隙間よりも十分に小さい場合には、樹脂と共に磁性\n体も隙間を通過することから磁性体粉末容積比(コア)及び磁性体粉末容積比(バ リ)に変化がないものと推測される余地があるといえるとしても、被告方法におい て磁性体粒子のうちの最小粒子径が被告方法で使用されている●●及びパンチで形 成される隙間よりも大きいことを示すなど、被告方法における粒子径分布とバリの 大きさとの関係性を示す証拠はないから、控訴人の上記主張は裏付けを欠き、採用 することができない。
イ 控訴人は、原判決は、控訴人の主張を誤解し、かつ、控訴人提出の証拠評価 を誤ったものと考えられると主張し、樹脂の流出が止まる原因については、パンチ による加圧と樹脂からの抗力(硬化や樹脂と隙間との摩擦等による抗力)が均衡す ることと主張しており、原判決のように「被告方法の加圧・加熱過程で加圧を続け ても樹脂の流出が止まるのは、磁性体粉末が隙間を埋めることが理由であるから、 被告方法においては、樹脂が隙間から優先的に排出されるといった事象が生じたこ とが示されている」という主張はしていない旨を主張する。 しかしながら、樹脂の流出が控訴人の主張する機序によるものであるとしても、 前記アのとおり、被告方法において磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容 積比(コア)よりも小さくなっていることを認めることはできず、上記(1)の判断を 左右するものとはいえない。 したがって、控訴人の上記主張は採用できない。
ウ 控訴人は、甲27の実験結果によると、被控訴人主張の製造方法は、バリに おける磁性体粉末の容積比がキャビティ内の磁性体粉末の容積比より低くなること が明らかとなっているから、原判決の判断は妥当ではない旨主張する。 この点、甲27の第4(10頁〜)に記載されている実験方法で利用・設定され ている磁性体粉末の組成、樹脂の組成、磁性体粉末と樹脂の配合割合、予備成形し\nたコアの製造方法、加圧温度及び溶融粘度という条件が、実際の被告方法で用いら れているものと同一であると認めるに足りる証拠はなく、それらが実際の被告方法 と同じ条件であると客観的に裏付ける証拠もない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和5(ネ)10042 特許権 民事訴訟 令和6年12月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 乙9発明と乙10発明は、ともに制動保持装置(乙10においては坂道 発進補助装置)を備え、それらはブレーキがかかった状態を保持する機 能を有するものであることに照らすと、乙9発明及び乙10発明は、そ\nのような機能を用いる車両である点で共通する技術分野に属するといえ\nる。また、乙10発明と同様に、乙9発明においても、制動保持装置の 故障発生が想定され、それに対処する課題が存在することは当業者には 明らかである。
そうすると、乙9発明に触れた当業者は、上記の制動保持装置の故障 発生という課題を認識し、その課題を解決する点において、乙10発明 を乙9発明に適用する動機があるということができる。
イ これに対し、控訴人は、乙9発明は、制動保持装置26が故障している か否かを検出する技術思想を有しておらず、故障を検知する乙10発明 を適用する動機付けに欠ける旨主張する。 しかし、上記2(1)エのとおり、乙9発明は、エンジンおよび車両各部 の状態を検出するセンサ群を備えるものであり、車速零信号が出力され ているときに制動保持信号を出力し、エンジン始動後に制動解除信号を 出力する制動保持解除信号発生手段と、制動保持信号に応動して制動装 置を作動状態に保持し、制動解除信号に応動して作動状態にある制動装 置の作動を解除する制動保持手段とを具備している。そして、乙9発明 において制動保持装置の異常が検知された場合には、上記の乙9発明に おいて求められている状態、すなわち、制動保持装置の作動によりブ レーキ液圧が作用し、もってブレーキがかかった状態を保持できなくな ることは明らかである。そうすると、乙9発明に触れた当業者は、上記 の制動保持装置の故障発生という課題を認識し、その課題を解決するた め、乙10発明における制動保持装置の異常を検出する信号を付加する 動機付けがあるといえる。
ウ 以上によれば、乙9発明に乙10発明の制動保持装置の故障を検知して 運転手へ警報を発する技術を適用することは当業者が容易に想到し得る といえる。 そして、上記2(1)イ〜エのとおり、乙9発明が、エンジン自動停止に より発生する問題を、センサ群からの検出信号に基づいて制動保持装置 を作動させることにより解消する技術思想を有することに照らせば、制 動保持装置の故障を検知し、制動保持装置を作動させることができない 故障が生じた場合には、その検知結果をエンジン自動停止条件の一つと して用い、相違点1に係る「前記故障検出装置によって前記ブレーキ液 圧保持装置の故障を検出した時に前記原動機停止装置の作動を禁止する」 構成とすることは、当業者が容易になし得た事項といえる。\nよって、乙9発明に乙10発明を適用した際に、本件発明の相違点1 に係る構成を得ることは、当業者が容易に想到し得たものといえる。\n
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和3年(ワ)28206
対応する審決取消訴訟はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10066 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年12月10日 知的財産高等裁判所
原告は、本件商標のうち、「UNITED」の部分が要部として抽出される から、本件商標からは「ユナイテッド」の称呼も生じる旨を主張する。 この点、「UNITED」は、英語で、「結ばれた、団結した、連合した」 (甲7、30−1)などの意味を持つ形容詞、「GOLD」は、英語で、「(鉱 物)金、黄金」(甲8、30−2)などの意味を持つ名詞であり、我が国にお いても、それぞれの意味する英語の単語として、一般に知られているところ である。
本件商標は、「UNITED GOLD」の欧文字を同書体、同大で、「U NITED」と「GOLD」との間に一文字分の空白を空けるほかは等間隔 で横書きにしてなるものであり、特段「UNITED」の部分が強調されて いるものでもない。本件商標を構成する「UNITED」と「GOLD」は、\n前者はアルファベット6文字、後者はアルファベット4文字にとどまるから、 本件商標は全体として冗長なものとはいえず、それらの間に一文字分の空白 があるとしても、両者が別個独立の構成であるとの印象を受けるものではな\nく、前記のとおり、「UNITED」は「結ばれた」などの意味を有する形容 詞であるから、通常は他の語と一体となってその語を修飾するために用いら れるもので、単独では意味を取りにくい語である。そうすると、本件商標で ある「UNITED GOLD」の構成のうちの「UNITED」の部分のみが強く支配的な印象を与えるものではない。\n
加えて、本件請求商品役務の一部であり、本件商標と引用商標1の指定商 品等が重複する「被服」(類似群コード「17A01」)において、登録商標 に「UNITED」を含む商標であって原告が権利者でないものは155件 あり(乙1)、これらは、「UNITED ARROWS」、「UNITED C OLORS OF BENETTON」、「UNITED ATHLE」、「U NITEDWORKS」、「UNITED DOORS」、「UNITED A SH」、「UNITED CARR」、「UNITED RIVERS」、「UN ITED TOKYO」、「United Prime」などであるところ、 これら「UNITED」(文字列に小文字があるものを含む)を含む商標のう ちには、被服の業界でそれなりの知名度を有するものも多くある。このうち、 本件請求商品役務と関連のある指定商品又は役務に係るものとして、「UN ITED ASH」は、洋服、コートを指定商品として、「United P rime」は、運動用特殊靴、被服及び履物を指定商品として、「UNITE D TOKYO」は、靴クリーム、身飾品、貴金属製靴飾り、時計、文房具 類、被服、履物、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する 便益の提供、おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便 益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の 提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する 便益の提供等を指定商品及び指定役務として、それぞれ商標登録がされてい る(甲31の1ないし3)。
また、Amazonのサイトにおいて、「United スラックス メン ズ」の条件で検索をすると、原告に係る「UNITED」、被告に係る「UN ITED GOLD」のほか、「UNITED ARROWS」、「UNITE D DOORS」、「UNITED ARROWS green label」 等、上記「UNITED(United)」を含む商標に係る商品が数多く検 索結果に現れる(乙1、4)との取引の実情も認められる。そうすると、被 服やそれに伴う身の回り品等を取り扱うファッション業界及びそれらの小売 業界においては、「UNITED」という部分の識別力は弱いものと認められ る。 したがって、本件商標のうち、「UNITED」の部分に格別の識別力があ るものとは認められないから、本件商標は、「UNITED GOLD」との 一体不可分の構成の商標としてみるのが相当であり、「UNITED」と「G\nOLD」とに分離して観察されるものではないと認められるから、本件商標 からは「ユナイテッド」の称呼は生じないと解するのが相当である。
・・・
本件請求商品役務と、各引用商標の指定商品は、いずれもその指定商品・ 役務の内容から、需要者は一般の消費者であると認められるところ、一般の 消費者は、必ずしも商標の構成を細部にわたり記憶して取引に当たるものと\nはいえないから、そのような需要者が通常有する注意力の程度を踏まえて、 本件商標と各引用商標の外観、称呼及び観念の要素を総合勘案することとな る。 本件商標と各引用商標は、外観、称呼においていずれも異なる上に、観念 においても比較できないから、時と所を異にして離隔的に観察した場合、本 件商標と各引用商標とは互いに紛れるおそれのある類似の商標であるとは認 められない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和5(ワ)70425 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年12月12日 東京地方裁判所
前記前提事実に加え、証拠(甲5ないし10、14)及び弁論の全趣旨に よれば、被告プログラムは、GoPayというタクシー料金の決済機能を備\nえており、GoPayは、d払いと連携することによって初めてd払いを利 用することができるようになること、他方、d払いは、訴外ドコモが提供す る決済機能であり、タクシーを利用した際にその利用したタクシー料金に限\nり利用することができるにとどまり、これ以外の場面では決済手段として使 用することができないこと、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、被告プログラムにおけるd払いは、タクシー料金 の個別の支払ごとにその都度利用されるにとどまるものであるから、被告プ ログラム自体がd払いという決済機能そのものを提供するものとはいえない。\nしたがって、被告プログラムは、本件発明の構成要件Bにいう「前記アプ\nリケーションで提供されるサービス」を充足するものとはいえない。
(3) 原告の主張に対する判断
原告は、本件発明の特許請求の範囲の文言上「提供するサービス」という 記載にはなっていないから、「サービス」の提供主体と「アプリケーション」 の提供主体とが法的に同一主体でなければならないという限定はなく、本件 明細書等【0030】の記載によれば、各サービスが様々な主体によって提 供されるものであることは、当業者のみならず一般人にとっても技術常識に 属する事項であるから、アプリケーションと各サービスが異なる法的主体に よって提供される場合も当然に含まれるものである旨主張する。 しかしながら、本件発明の構成要件は、「アプリケーション」と「サービ\nス」の内容及び関係を一義的に規定するものではないから、本件明細書等を 参酌しない限り、その関係等が明らかにならないことは、上記において説示 したとおりである。そして、本件明細書等のうち、「アプリケーション」と 「サービス」の内容及び関係につき記載した部分(【0012】、【001 4】、【0030】)を参酌すれば、「アプリケーション」は、総合サービ スを提供するものであり、構成要件Bにいう「前記アプリケーションで提供\nされるサービス」は、アプリケーション自体がクレジット機能、クーポン機\n能その他の機能\そのものを提供するものに限られると解するのが相当である から、タクシー料金の個別の支払ごとにその都度利用されるd払いを含むも のではないと解するのが相当である。 したがって、サービスの提供主体の同一性についていう原告の上記主張は、 充足性の判断を左右するものとはいえず、採用することができない。
・・・
4 争点2−1−3(乙1−3発明に基づく新規性、進歩性の有無)について 前記2及び3のとおり、被告プログラムは、本件発明の構成要件を充足しな\nいから、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえず、その余の争点を判断 するまでもなく、原告の請求は理由がないことになる。もっとも、本件の事案 に鑑み、本件の中核的争点の一つである争点2−1−3に限り、念のため、以 下簡潔に判断を示しておくこととする。
・・・
前記(1)に加え、証拠(乙1、5)及び弁論の全趣旨によれば、乙1−3発 明におけるクーポンを選択・設定するという画面の表示について、「コマン\nドが処理されることで生成される」旨の開示はないものの、乙1−3発明に よれば、かざすクーポンで選択・設定された「クーポン」は、携帯電話の画 面に表示されるのであるから、当該表\示データは、アプリの利用者がクーポ ンを選択する操作に基づき生成されていると認めるのが相当である。 そうすると、乙1−3発明に接した当業者は、乙1−3発明に「コマンド が処理されることで生成される」という記載がないとしても、上記操作をコ マンドに置き換えて上記画面を表示させる構\成を容易に想到することができ るといえる。
したがって、乙1−3発明に接した当業者が乙1−3発明から出発して相 違点1−3−1の構成に至ることは、容易であるといえる。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10005 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年11月27日 知的財産高等裁判所
上記アの各刊行物(甲5、6、11、13、16、17)の各記載によ れば、「ウェブ・サービス」という用語は、「インターネット上に分散し た複数のウェブアプリケーションシステムをシステム同士で連携させる技 術であり、XML、UDDI、WSDL及びSOAPの規格に適合したも の」という意味で用いられ、本願の国際出願日の当時、技術常識となって いたと認められる。 また、この「ウェブ・サービス」との関係において、「トランザクシ ョン」という用語は、「複数の処理をひとまとまりにしたものであって、 同時にアクセスされる基礎データの一貫性を確保することができるもの」 という意味で用いられると認められ、そうすると、「トランザクショ ン・ベースのウェブ・サービス」とは、この「トランザクション」を基 礎とした「ウェブ・サービス」という意味の用語であって、これも、本 願の国際出願日(平成25年12月20日)の当時、技術常識となって いたと認められる。 したがって、出願当時における技術常識を踏まえると、本願各発明の 「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サー ビス」は、それぞれ、上記の意味で用いられているといえるから、本願 明細書において、これらの用語の具体的な説明がされていなかったとし ても、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不 明確であるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10055 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年11月25日 知的財産高等裁判所
原告は、本件商標が、日本国産であり、乳蛋白質が添加されていることか ら「ギリシャ国の伝統製法」ではないヨーグルトの商品、すなわち産地や製 法と関係がない製品に用いられており、需要者の信頼を裏切るものであるか ら、「指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の福祉に反し、 社会の一般的道徳観念に反する場合」に当たる旨主張する。 しかし、前記1のとおり、本件商標は、ギリシャという国あるいは地域か ら連想される抽象的なイメージを「至福の」という肯定的なイメージととも に需要者に連想させ、ギリシャと何らかの形で関連する商品であることを表\n示するに止まるものである。 また、本件指定商品における「ギリシャ国の伝統製法」とは、社会通念上、 およそ「ギリシャ国の伝統製法」という範疇に含ませることが相当なヨーグ ルトの製法を広く指すものであり、被告において、この意味における「ギリ シャ国の伝統製法によるヨーグルト」を製造販売する蓋然性はあり、本件商 標を本件指定商品に使用する意思もあったことは、前記3のとおりである。 そうすると、被告が本件商標を登録し、本件指定商品すなわち「ギリシャ 国の伝統製法によるヨーグルト」について使用することが、社会公共の福祉 に反し、社会一般の道徳に反するということはできない。
(2) 原告は、本件商標の登録を認めることは、日本の一事業者にすぎない被告 が一方的にギリシャ国に付した漠然としたイメージを、日本が国家として是 認することになり、「特定の国若しくはその国民を侮辱する場合」に当たる と主張する。
しかし、「特定の国若しくはその国民を侮辱する」かどうかは、イメージ の内容如何によるのであり、「至福の」という肯定的な修飾語を伴う本件商 標により想起される「この上もない幸せの国ギリシャ」というギリシャ国に 対する「漠然としたイメージ」がギリシャ国又はその国民を侮辱するものと いうことはできない。もとより、本件商標の登録を認めたからといって、商 標法上の保護が与えられるだけであり、ギリシャ国についての特定のイメー ジを日本が国家として承認するなどといった法的効果が発生することはない。 また、原告は、「ギリシャ国の伝統製法」なる指定商品を認めることは、 同様に、ギリシャ国における「伝統」を特許庁あるいは一事業者が一方的に これを定めることを認めることになると主張する。
しかし、本件指定商品である「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト」 の「伝統製法」がいかなるものであれ、本件指定商品を指定商品とする商標 登録を認めたからといって、「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト」の 具体的内容が一義的に決まるわけではないから、ギリシャ国における「伝統」 を特許庁又は一事業者が一方的に定めたことにはならない。 なお、将来、本件商標に係る不使用取消審判等の審判やその審決取消訴訟 において、具体的な商品が本件指定商品に当たるか否かについて、特許庁や 裁判所による判断がされることがあるとしても、その判断は、客観的事実を 踏まえ、社会通念に照らしなされるものであり、そのことが、直ちにギリシ ャ国又はその国民を侮辱することに当たるとは認められない。もとより、ギ リシャ国は、これに拘束されることなく、必要に応じ、自らが妥当と考える 「伝統製法」の内容を決めることは何ら妨げられない。 したがって、本件指定商品を認めたからといって、特許庁や一事業者がギ リシャ国の「伝統」を一方的に定めたなどということはできない。
(3) 原告は、地理的表示に関する国際的趨勢や動向を踏まえると、「ギリシャ\nヨーグルト」という用語ですら産地と結び付けて理解されるのであるから、 本件商標のように国家名のみが示されている場合は端的に産地を示している との考慮がなされるべきであるから、本件商標の登録は、「一般に国際信義 に反する場合」に当たると主張する。 しかし、「ギリシャヨーグルト」がTRIPs協定22条にいう地理的表\n示に当たるか否かはともかく、本件商標は国家名のみを示したものではなく、 「至福のギリシャ」という表示は、産地を示す表\現であると認めることはで きないことは前記のとおりである。すなわち、本件商標は、商品の原産地を 特定する表示であることを内容とする同条の「地理的表\示」に当たるもので はない。したがって、本件商標の登録を認めることが、一般に国際信義に反 するとは認められない。原告が引用する英国控訴院の判決(甲8、9)は、 米国の会社が米国で生産し、英国に輸入して販売していた「ギリシャヨーグ ルト(Greek yoghurt)」という商品に関し、英国内の購入者の多く(5 0%以上)が当該商品はギリシャ産の製品だと誤認しているという事実関係 のもとで、ギリシャヨーグルトの表示の差止めを認めた原審を維持したもの\nであって、客観的にみて表示自体では産地を表\示したものとは認められず、 本件商標を付した被告商品をギリシャ産であると需要者が一般的に認識する とも認め難い本件において、当然に妥当するものではない。
(4) 原告は、被告がギリシャ産のヨーグルトや本件指定商品に用いる意思がな いにもかかわらず本件商標の登録出願をしたことは、虚偽的かつギリシャ国 のイメージに積極的にフリーライドすることを企図していたとも評価し得る から、「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を 認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場\n合」に当たると主張する。 しかし、被告において、本件商標を本件指定商品に使用する意思があった ことが認められることは前記のとおりであるから、原告の主張はその前提を 欠くものである。その他、本件商標の出願の経緯等が社会相当性を欠くもの であったことを認めるに足りる主張立証はないから、原告の主張は採用する ことができない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2025.01.12
令和6(行ケ)10051 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年11月27日 知的財産高等裁判所
したがって、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、いずれも電子計算機に関連する商品として、電子計算機によ る処理を行う際に通常用いられるという商品であるという意味において、 共通性がある。
(2) 生産及び販売の実情
ア 本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフトウェアのよ\nうなディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェアは、いずれも製造業\nの同一事業者が生産、販売している例が多く認められる。
・・・
また、家電量販店やパソコン及び周辺機器を扱う専門店(ビックカメラ.\ncom、ヨドバシ.com、ヤマダウェブコム、エディオン公式通販、パ ソコン工房、TSUKUMO、ドスパラ、パソ\コンSHOPアーク〔乙3 7〜44〕)においても、ディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェア\nは、同一販売店において扱われていることが認められる。 したがって、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、同一営業主により製造及び販売され、又は、同一販売店によ り販売される実情にある。
イ この点について、原告は、本願指定商品と引用商標データ処理装置及び 引用商標ソフトウェアは、総務省日本標準産業分類において属する産業を\n異にするなどと主張する。しかしながら、引用商標データ処理装置は、電 子計算機であるから、本願指定商品と同じ「(中分類)情報通信機械器具製 造業」(甲25)に属するというべきであり、原告の主張する「(中分類) 業務用機械器具製造業」「(細分類)その他の事務用機械器具製造業」(甲2 6)に属するものと解することはできない。
また、原告は、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソ\nフトウェアは、いずれも専門的に製造する業者が多数存在する実情がある ので生産部門は共通しないとか、本願指定商品が一般需要者向けの直販サ イト又は家電量販店等で販売されるのに対し、引用商標データ処理装置及 び引用商標ソフトウェアは、企業間取引に対応する特定の専門業者により\n販売されるから、販売部門も共通しないなどと主張する。しかしながら、 前記のとおり、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、いずれもディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェアと\nいう電子計算機に関連する商品として同一営業主により開発され、製造及 び販売され、又は、同一販売店により販売される実情にあるから、営業主 の同一性を誤認させるような生産・販売形態における共通性があるものと 認めるのが相当である。よって、原告の主張を採用することはできない。
(3) 用途
ア 前記のとおり、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソ\nフトウェアは、それぞれディスクドライブ、電子計算機及びソフトウェア\nであり、いずれも電子計算機に関連する商品である。 そして、本願指定商品と引用商標データ処理装置は、いずれも電子計算 機に関連し、電子データを利用し、これを読み込み・再生し、又はこれを 処理することを目的とするものである。 また、本願指定商品と引用商標ソフトウェアは、いずれも電子計算機に\n関連し、本願指定商品は電子計算機を動作させて音楽・映像データの取り 込み・再生を行う周辺機器として、引用商標ソフトウェアは電子データを\n利用し、電子計算機の周辺機器又は電子計算機を動作させるためのプログ ラムとして、それぞれ電子計算機の機能を実現させることを目的とするも\nのである。
これらの点に照らすと、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引 用商標ソフトウェアは、それぞれ役割が異なるものの、いずれも電子計算\n機による処理又は電子データの利用を行うために用いられる商品という 意味において、その用途に共通点があるということができる。
イ この点につき、原告は、本願指定商品の用途は、光学ディスクに記録さ れた音楽・映像に関する電子データの読み取り・再生であり、引用商標デ ータ処理装置の用途は、運動に関するデータを取り込み表示するためのデ\nータ処理であって用途を異にし、また、引用商標ソフトウェアは、データ\nの読み取りという用途は、本願指定商品の用途と共通するが、ディスクド ライブとその動作のためのアプリケーションソフトは担う具体的な役割\nが異なるなどと主張する。しかしながら、前記のとおり、本願指定商品、 引用商標データ処理装置及び引用商標ソフトウェアは、電子計算機による\n処理又は電子データの利用を行うために用いられる商品であるという共 通点があり、およそ営業主の同一性誤認の可能性を否定するほど用途を異\nにするものということはできないから、原告の主張を採用することはでき ない。
(4) 需要者の範囲
ア 本願指定商品は「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライ ブ」であるから、電子計算機の周辺機器として、その需要者は、電子計算 機の利用者全般である一般の消費者を含むものということができる。 他方、引用商標データ処理装置は「ウエイトトレーニング機械器具で測 定された負荷重量・マシーンの変位量・回動数・回動スピードのうちいず れか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置、運動用トレッドミル\nで測定されたローラーベルトの傾斜角度・走行距離・運動経過時間・平均 走行速度・消費カロリ・利用者の体重・歩数・歩幅・ピッチ・心拍数のう ちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置」であるから、\n前記の情報を受信して表示するためのデータ処理装置(電子計算機)とし\nて、その需要者は、前記のウエイトトレーニング機械器具又は運動用トレ ッドミルの利用者である。そして、これらの運動用器具は、家庭用又は自 宅利用のためにも販売され(乙45〜47)、モバイル端末とともに利用さ れる場合もあることからすると(乙17、21)、その需要者は、前記の運 動用器具を利用する施設等の取引者のほか、一般の消費者を含むものとい うことができる。
また、引用商標ソフトウェアは「ダウンロード可能\なモバイル機器用の アプリケーションソフトウェア」であるから、モバイル端末を動作させる\nためのプログラムとして、その需要者は、モバイル機器を利用する取引者 のほか、一般の消費者を含むものである。よって、本願指定商品、引用商標データ処理装置及び引用商標ソフトウェアの各需要者は、いずれも広く一般の消費者を含むものとして需要者の範囲において共通している。\n
イ この点につき、原告は、本願指定商品の需要者の範囲は、一般家電需要 者であるのに対し、引用商標データ処理装置の需要者の範囲は、主に運動 用機械の使用施設を運営する専門的知見を持つ事業者等であるから共通 せず、引用商標ソフトウェアの需要者の範囲は、広く一般消費者のほか特\n定分野の専門家又は事業者等であるから、一部共通しても一致しないなど と主張する。 しかしながら、引用商標データ処理装置が、専門的知見を持つ事業者に より利用されている実情があるとしても、前記のとおり、一般消費者にお いても利用されている実情にあるから、需要者の範囲に係る原告の主張は、 利用態様の一部をいうにとどまる。また、引用商標ソフトウェアについて\nは、原告においても、需要者の範囲に一般消費者が含まれることを認める のであるから、本願指定商品の需要者の範囲と共通するものと認めるのが 相当である。そして、このように本願指定商品、引用商標データ処理装置 及び引用商標ソフトウェアの需要者にはいずれも一般消費者が含まれて\nいると認められる以上、これらの商品やソフトウェアには需要者の共通性\nが認められるというべきである。原告の主張を採用することはできない。
(5) 完成品と部品の関係等
本願指定商品と引用商標データ処理装置又は本願指定商品と引用商標ソフ\nトウェアは、いずれも完成品と部品の関係にはなく、需要者の範囲は共通し ている。その他、本願指定商品、引用商標データ処理装置又は引用商標ソフ\nトウェアについて、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそ れがないことを窺わせるような特段の事情も見当たらない。
(6) 小括
以上によれば、本願指定商品と引用商標データ処理装置及び引用商標ソフ\nトウェアは、その生産・販売形態、用途、需要者の範囲において共通性があ り、これらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製 造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にあると いうべきであるから、本願指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品に該 当すると認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2024.12.11
令和6(ネ)10033 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月29日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
これを本件についてみるに、本件発明において、従来技術の庇は、前記 2(2)のとおり、樋板9の幅wの分だけ庇板2の前方へ余分に突き出るため 庇の全長が必要以上に長くなる、樋板9が樋溝95a、95bを備えてい るので構造が複雑化して庇がコスト高となるとの課題のほか、樋溝95a、\n95bは上面が開放されているため塵芥が堆積しやすく、頻繁な保守、点 検が必要となること、樋溝95bに塵芥が堆積して雨水の通路が塞がれる と、突出部93と庇板2の下面との隙間98より雨水が外部へ浸出し、決 められた箇所以外の随所から雨水が漏れ出て流れ落ちるという課題があ り(段落【0006】)、本件発明は上記課題を発明が解決しようとする課 題とした。そして、本件発明は、この課題を解決するための手段として、 本件発明の構成要件A3ないしC3で特定される「前縁板」が、「庇板の開\n放された前端面を塞ぐように全幅にわたって取り付けられ」(構成要件A\n3)、「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド 面となっている縦板部」(構成要件B2)を備えることで、庇板の前方への\n突出部分をなくすことができ、庇の全長が短くなり小型化が図られ、構造\nの複雑化を招かないものとした(段落【0014】)。さらに、前縁板の一 部である縦板部について、上記構成要件B2のほか、「縦板部の下部内面に\nは、全幅にわたる凹部が形成され」(構成要件C1)、「凹部は開口部分の上\n部が庇板の中空部と連通するように庇板の開放された前端面と対向し」 (構成要件C2)、「開口部分の下部が外部と連通するように庇板の下方へ\n突出して」(構成要件C3)いることで、縦板部の凹部が縦板部の内面の側\nに開口することとなり、塵芥が堆積するおそれがなく、仮に凹部に塵芥が 付着しても雨水により外部へ洗い流される構造が実現されるものであっ\nて(段落【0014】)、このことは当業者であれば容易に理解し得るとい える。
以上によれば、本件発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見 られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、従来技術の上記課題\nを解決するために、本件発明の構成要件A3ないしC3で特定される前縁\n板を備え、かつ、前縁板の一部である縦板部が構成要件B2及びC1ない\nしC3の構成を備えていることにあると認められるから、構\成要件B2は本件発明の本質的部分であると認められる。 そして、被控訴人製品が本件発明の構成要件B2を充足しないことは、\n補正の上で引用した原判決「事実及び理由」第4の1(2)の説示及び前記2 のとおりであるところ、この相違点は本件発明の本質的部分であることに なる。
したがって、被控訴人製品は、本件発明の本質的部分を備えておらず、 均等の第1要件を満たさない。 控訴人は、庇板の内外の雨水をともに縦板部の下端まで導いて落下させ る構成が本件発明の本質的部分であり、構\成要件B2の被控訴人製品と異 なる部分は本件発明に特有の作用効果を生じさせるための部分でなく、本 件発明の本質的部分ではないと主張するが、前記説示に照らし採用するこ とができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> ピックアップ対象
2024.12. 5
令和6(行ケ)1004 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年10月31日 知的財産高等裁判所
(9) 本件商標の本件書換登録後の指定商品である「電子計算機」の意味につい て上記(7)で検討した結果を本件に当てはめると、まず、使用商品2について は、その仕様は「別紙1 使用商品2」記載のとおりであるところ、上記(8) のとおり、使用商品2は静電容量式のタッチペン付きの尾栓であって、人の 指などの導電性の物に代わる入力手段に過ぎないから、上記(7)のとおり、電 子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものだけを含むと\nする「電子計算機」に含まれるものとは解しがたい。加えて、「電子計算機」 につき、上記のとおり中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させ た電子回路等の周辺機器のみを含み、補助記憶装置であるハードディスクユ ニット等の電子計算機外部の周辺機器ですら含まれないと解されることから すれば、電子計算機の中央処理装置及び電子計算機用プログラムの記憶とは 何ら関係しない、多機能ペンの尾栓である使用商品2は、電子計算機に含ま\nれる周辺機器に当たるものとは解しがたいというべきである。
次に、使用商品1は、多機能ペンであって筆記具である上、静電容量式の\nタッチペン付きの尾栓を備えていることを考慮しても、上記と同様に、人の 指などの導電性の物に代わる入力手段に過ぎないから、電子の作用をその機 械器具の機能の本質的な要素としているものだけを含むとする「電子計算機」\nに含まれるものとは解しがたく、電子計算機の中央処理装置及び電子計算機 用プログラムの記憶とは何ら関係しない多機能ペンである使用商品1は、電\n子計算機に含まれる周辺機器に当たるものとも解しがたいというべきである。 その他、本件取消対象指定商品につき、本件要証期間における本件商標の 使用の事実の立証はされていない。
そうすると、本件取消対象指定商品について、本件要証期間における本件 商標の使用の事実は立証されていないこととなるから、これと同旨の本件審 決の判断に誤りはない。したがって、原告らの主張する取消事由には理由がない。
2 原告らの主張に対する判断
(1) 原告らは、前記第3の1〔原告らの主張〕(1)及び(2)のとおり、各使用商品 は「電子計算機」ないしそこに含まれる周辺機器に当たるから、本件商標の 本件取消対象指定商品についての使用の事実の立証がされていると主張する。 しかし、既に述べたとおり、本件商標の本件書換登録後の指定商品である 「電子計算機」は、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素として\nいるものだけを含み、その電子計算機に含まれる周辺機器も、中央処理装置 及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路等の周辺機器のみがこれ に当たり、ハードディスクユニット等の外部周辺機器はこれに当たらないと 解されるところ、各使用商品は、いずれもそこにいう「電子計算機」に該当 するものとは認められないというべきである。なお、原告らの主張のうち、 本件書換登録が書換登録ガイドラインに従ったものであるとする点について の判断は後記(3)のとおりである。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。
(2) 原告らは、前記第3の1〔原告らの主張〕(3)のとおり、「商品及び役務の区 分解説〔国際分類第9版対応〕」(甲56)によれば、本件書換登録の申請時\nにおいても、電子計算機は周辺機器を含むものとして考えられていたとし、 「周辺機器」についての辞書等の記載によれば、スタイラスペンが入力装置 として解説されていることなどから、各使用商品は、入力装置であるスタイ ラスペン(ペン型データ入力具)の性質を有するものとして、「電子計算機」 の周辺機器に含まれる旨を主張する。しかし、上記1(3)イの「商品及び役務の区分解説〔国際分類第9版対応〕」(甲56)の記載を含め、本件書換登録後の指定商品である「電子計算機」に含まれる周辺機器については、中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路等の周辺機器のみがこれに当たるものであり、ハード ディスクユニット等の外部周辺機器がこれに当たらないと解されることにつ いては既に述べたとおりである。そして、上記1(8)のとおり、使用商品1の 外箱には「Stylus pen」とのシールが貼付されていたけれども、各使用商品\nが本件書換登録後の指定商品である「電子計算機」に含まれないことについ ては、上記1(9)で述べたとおりである。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。
(3) 原告らは、前記第3の1〔原告らの主張〕(2)及び(4)のとおり、原告トンボ 鉛筆は、本件書換登録の申請に当たり、本件書換登録申\請日当時の書換ガイ ドラインに沿って書き換えを行ったに過ぎないから、本件書換登録後の指定 商品「電子計算機」は、本件書換登録前の「電子計算機〔中央処理装置及び その周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディス ク、磁気テープを含む)〕」と同義であるところ、書換前の「その周辺機器」 には各使用商品が含まれるから、書換後の「電子計算機」についても同様に 解すべき旨を主張する。
しかし、上記1(5)エのとおり、書換ガイドラインの一覧表上に昭和34年\n法に基づく商品として記載されているのは「電子計算機」であって、本件書 換登録前の本件商標の指定商品であった「電子計算機〔中央処理装置及びそ の周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、 磁気テープを含む)〕」と同一ではないから、原告トンボ鉛筆の行った書換は、 必ずしも書換ガイドラインの一覧表に示された通りの書換を行ったものとは\nいえない。加えて、そもそも書換ガイドラインは、上記1(5)ウにあるとおり、 基準的な性格のものに過ぎない上に、一覧表の書換表\示以外の書換表示であ\nっても、それが書換登録申請に係る商標権の指定商品の範囲内の適切な商品\n表示であれば、その書換表\示による書換も認められるのであるから、本件申\n請時の商品等区分に従い、本件書換登録前の指定商品の記載に基づいて原告 トンボ鉛筆が指定商品に含まれると考える商品について書換申請を行うこと\nも可能であったということができる(上記1(5)エ)。なお、本件書換登録申請\n日当時の「類似商品・役務審査基準」が適用される間における書換登録にお いても、書換前の第11類「電子計算機〔中央処理装置およびその周辺機器 (電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テー プを含む)〕」及びこれと類似する記載を、第9類「電子計算機〔中央処理装 置及びその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気 ディスク、磁気テープを含む)」などや、これと類似する記載に書き換えた例 も存するところである(乙47ないし49、51)。
さらに、上記の点を措くとしても、上記1(5)ウの書換ガイドライン利用上 の注意事項(「旧区分の1の商品に対して書換表示が複数の商品となる場合\nは、各商品の配列を五十音順とし、各商品間をカンマ(,)で区切っている。」)\nから明らかなとおり、そもそも同ガイドラインの一覧表に示された記載に沿\nって商品「電子計算機」の書換登録を行ったとする場合の書換後の商品は、 上記1(5)エのとおり「電子計算機」及び「電子計算機用プログラム」の二つ の商品であり、指定商品を実質的に超えない範囲で書換登録がなされるもの であること(上記1(5)ア、イ)に鑑みれば、二つの商品に書換えられた後の 一方の商品である「電子計算機」が、書換前の商品「電子計算機」と内容的 に全く同一とはいえないことも明らかである。 そして、商標法附則12条3項が「(書換の)申請書に記載されなかった指\n定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。」と規定するところから、書換 登録がなされた後にあっては、該商標の指定商品については、書換後の指定 商品の内容に従って客観的に定まるものと解される。これに沿って解した場 合の、本件書換登録後の本件商標の指定商品である「電子計算機」の意義、 及び各使用商品がこれに当たらないことについては、既に検討したとおりで ある。
2024.12. 5
令和6(ワ)70106 特許使用料請求事件 令和6年11月15日 東京地方裁判所
1 特許権者の同意を得ることなく他人に通常実施権を許諾した場合であっても、 契約締結後に特許権者から許諾を得ることは可能であるから、通常実施権を許\n諾する権限を有しない者が第三者に通常実施権を許諾した場合であっても、契 約を締結した当事者間においてその契約の効力を直ちに否定する必要はない。 しかしながら、このような実施許諾契約は、他人の権利を目的とした契約と いえるから、通常実施権を許諾する権限を有しないにもかかわらず、これを許 諾した者は、民法559条及び561条に基づき、通常実施権者のために通常 実施権を許諾する権限を取得すべき義務を負うものと解される。
2 本件においては、前提事実(2)のとおり、本件契約は、原告が、被告に対し、 本件各特許権について通常実施権を許諾することなどを約したものであるが、 証拠(乙11、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許権1は国土防災技 術株式会社及び日本ソフケンの共有に係るものであり、本件特許権3は、両社\nと日本ミクニヤ株式会社の共有に係るものであることが認められる。そうする と、原告は、被告に対し、本件契約に基づく債務として、上記の共有者から被 告のために通常実施権を許諾する権限を取得すべき債務(以下「本件債務」と いう。)を負っていたものと解される。
しかしながら、前提事実(3)のとおり、原告は、本件特許権2について、そ の単独の特許権者である日本ソフケンから専用実施権の設定を受けているもの\nの、弁論の全趣旨によれば、本件特許権1及び3については、上記の共有者か ら被告のために通常実施権を設定する旨の許諾を得ていないものと認められる。 したがって、原告には本件債務の不履行があるといえる。
これに対し、原告は、1)本件各特許権はいずれも被告の事業のために不必要 な特許であり、原告が被告に対して別の特許発明の実施を許諾していることや、 2)本件契約の契約書では、本件各特許権について、原告が「特許庁への登録保 全が出来ない」ものであると明記されていること(同契約書7条)から、原告 には債務不履行がないと主張する。 しかしながら、上記1)については、本件全証拠によっても、本件各特許権は いずれも被告の事業のために不必要な特許であり、原告が被告に対して別の特許発明の実施を許諾しているという事実を認めることはできないから、原告の 主張はその前提を欠くものである。
また、上記2)についても、本件契約は、原告が、被告に対し、本件各特許権 について通常実施権を許諾することを目的にした契約であること(前提事実 (2))からすると、原告の指摘する契約書の文言のみをもって本件債務の存在 を否定することはできないというべきである。 そうすると、原告の上記主張はいずれも採用できない。
3 そして、本件債務は期間の定めのない債務に該当するものと解されるところ、 前提事実(4)アのとおり、被告は、令和5年12月20日、原告に対し、書面 到達後1週間という期間を定めてその債務の履行を催告するとともに、その履 行がない場合は本件契約を解除する旨を記載した「催告兼解除通知書」を送付 して、この書面は、同月29日に原告に到達し、上記の催告期間は既に経過し ている。
4 以上によれば、原告による本件契約に係る債務不履行、被告による相当の期 間を定めての履行の催告、その期間内に履行がされなかったこと及び解除の意 思表示という、催告による解除の要件(民法541条本文)が充たされている\nから、本件契約の解除により、被告は本件許諾料の支払義務を負わないという べきである。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2024.11.19
令和4(ワ)3344 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年9月26日 大阪地方裁判所
被告は、本件発明が、テリボンの製造工程のごく一部でしか用いられないもので あることや代替可能であること、テリボンが最も顧客誘引力を有するのは、これま\nで毎日自己注射をしなければならなかったが、テリボンによって週1回の医療機関 における投薬で済むようになった点であること等を指摘する。 前示のとおり、本件発明において最も重要な効果は、骨粗鬆症の治療に必要な薬 剤そのものであるPTHペプチド含有凍結乾燥製剤を高純度で提供することができ るというものであり、PTHペプチド含有凍結乾燥製剤が安定して供給されるよう になったという事実それ自体が利益に貢献している。被告は、本件発明は、他の手 段で代替可能であるとも主張するが、被告自身、そのような試みに成功していない\nし、商品化ベースに載せられるほどに代替可能な方法を具体的に指摘するものでは\nなく、採用できない。 一方、投薬の負担を軽減するための方法を顧客が選択できるようになったことに より、投薬を開始しやすくなるという意味で、被告が指摘する用法 用量や効能の\n点に、顧客誘引力がないとはいえないことから、テリボンの販売により得られる限 界利益の全額を逸失利益と認めるのは相当でなく、10パーセント程度の推定覆滅 が認められるというべきである。
・・・
原告は、テリボンを販売することができないとする事情が認められる数量(特定 数量)が存する場合、特許法102条1項2号に基づく損害額の主張として、当該 数量につき、本件発明により、PTHペプチド含有凍結乾燥製剤が安定供給できる ようになったこと等を指摘し、実施料率は、被告製品薬価の20パーセントを下回 らないと主張する。一方、被告は、本件発明が製造方法の一部にすぎないこと、患 者にとって負担が軽い用法 用量の注射剤であることに顧客誘引力が見いだされる ことなどを指摘し、実施料率が0.5パーセントにすぎないと主張する。 本件発明は、PTHペプチド含有凍結乾燥製剤の純度を向上させ、市場に安定供 給できるようにするものであり、利益に直結する効果を有するものである。患者に とって負担が軽い用法 用量の注射剤を提供できるというのも、そもそもPTHペ プチド含有凍結乾燥製剤が大量生産できることが前提であることや、上記のとおり、 現時点において被告において代替技術を開発できていないこと等を踏まえると、本 件発明の実施料率は相応に高いものというべきであり、特許法102条4項の趣旨 をも考慮して、被告製品薬価の15パーセントとすることが相当である。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> ピックアップ対象
2024.11.19
令和5(ワ)70393 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年9月26日 東京地方裁判所
原告は、上記認定に係る本件明細書【0050】につき、「一般的に用 いられる円管又は角筒管の支柱に比べ、必要に応じて、短手方向の幅を薄 くすることができる」との一文は、「支柱」を主語とする記載であるから、 本件各発明は、短手方向の幅を薄くする必要がない場合には、円管又は角 筒管の支柱を排除するものではなく、「回動板状部材」には、角筒管も含 まれる旨主張する。
そこで検討するに、本件明細書【0050】には、「以上説明した仮設 防護柵1の効果を説明する。回動板4は板であり、短手方向に厚さを有し、 回動板4が定着板3,3の間に配置され、2つの回動軸により回動可能な\n構成であるので、ガードレール6と回動板4を倒した状態で、基礎架台2\nの上方に形成されたウェブ部22の短手方向の幅に収容することができ る。ガードレール6と回動板4を起立した状態で、ボルト、ナットにより、 定着板3により回動板4を固定できる。一般的に用いられる円管又は角筒 管の支柱に比べ、必要に応じて、短手方向の幅を薄くすることができる。 仮設防護柵1を小型化、軽量化、コンパクト化を達成でき、設置・撤去作 業の効率化を図ることができる。道路路肩、歩車道境界のみならず、上り 車線・下り車線を分離するためにも使用することができる。」と記載され ている。
上記記載によれば、「一般的に用いられる円管又は角筒管の支柱に比べ、 必要に応じて、短手方向の幅を薄くすることができる。」との一文は、板 である「回動板4」について説明する文脈に続くものであり、その直後に、 「仮設防護柵1を小型化、軽量化、コンパクト化を達成でき、設置・撤去 作業の効率化を図ることができる。」という本件各発明の効果が記載され ていることを踏まえても、上記一文の主語は、「回動板4」であると解するのが相当である。 仮に、原告の主張のように、「(円管又は角筒管を含む)支柱」を主語 にした場合には、本件各発明の効果を奏し得ない構成をも含むことになる\nから、本件明細書【0050】の効果に係る上記記載に矛盾する上、本件 各発明の課題を解決できない構成を含むことになるため、本件各発明の課\n題解決手段に照らし、相当であるとはいえない。そうすると、原告の主張 は、本件各発明の課題解決手段を正解するものといえない。
原告は、本件明細書【0032】に「回動板4の形状は矩形に限定され ず、楕円、小判等の縦長形状等、適宜の形状を取り得る。」との記載があ るほか、【0060】に「回動板4は中実板に限らず、中空板等、板から 構成される部材であれば、他の形態でもよい。」との記載があることから\nすると、中空の四角形に構成された角筒状の回動部材107も、上記「回\n動板状部材」に含まれる旨主張する。
しかしながら、原告引用に係る本件明細書【0032】には、かえって、 「回動板4は正面形状が矩形状で所定の厚さの存する薄板であり」と記載されていることからすると、上記明細書の記載は、「薄板」とはいえない 角筒状の回動部材107を含む趣旨ではないことは、明らかであるから、 原告主張は、その前提を欠く。また、【0060】についても、「中実板 に限らず、中空板等、板から構成される部材」という記載であるから、文\n字どおり、「中実板」、「中空板」その他の「板」の形状からなる部材を 意味するものと解するのが相当であり、前記認定に係る課題解決手段に照 らしても、上記記載は、「板」とはいえない角筒管を含む趣旨ではないこ とは、明らかである。そうすると、原告の主張は、本件各発明の課題解決 手段を正解するものといえない。
その他に、原告は、技術説明会においても、本件各発明の課題は、基礎 架台の短手方向の厚みを薄くするというものではなく、基礎架台に起伏す る部材が基礎架台に収納できるようにして設置・撤去の作業効率を上げる ものである旨主張するものの、本件各発明の課題は、本件明細書【000 7】等の記載を参酌すれば、文字どおり、仮設用防護柵の起伏する部材の 幅を小さくすることであって、基礎架台の短手方向の厚みを薄くすること にある。そうすると、その他の原告の主張を含め、原告の主張は、本件各発明の課題解決手段を正解するものといえない。したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
ウ 以上によれば、被告製品は、本件各発明にいう「回動板状部材」(構成\n要件1Dないし1G及び2Dないし2H)を充足するものとはいえない。
(2) 争点1−2(均等侵害の成否)について
原告は、仮に被告製品の角筒状の回動部材107が、本件各発明の「回動板 状部材」を充足しないとしても、被告製品の角筒状の回動部材107は、本件 各発明の「回動板状部材」と均等なものとして、その技術的範囲に属すると主 張する。
しかしながら、本件各発明の課題解決手段は、回動部材を板状にすることに よって、基礎架台(H形鋼)の短手方向の厚みを薄くするものであることは、 上記において繰り返し説示したとおりである。そうすると、本件各発明の「回 動板状部材」は、本件各発明の課題解決手段そのものであるから、本件各発明 の本質的な部分ではないということはできず、また、これを、被告製品の角筒 状の回動部材107に置き換えると、本件各発明の課題を解決することはでき ず、本件各発明と同一の作用効果を奏するものとはいえないことは、前記説示 に照らし、明らかである。 そうすると、被告製品は、本件各発明の特許請求の範囲に記載された構成と\n均等なものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> ピックアップ対象
2024.11.18
平成28(ワ)23327等 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年5月23日 東京地方裁判所
それぞれの事件の原告は商標権者です。第1事件の商標は「ブロマガ/BlogMaga」および「ブロマガ」「BlogMaga」の3件です。問題の指定役務は「サーバの記憶容量の貸与」です。第2事件は「ブロマガ」指定役務「電子出版物の提供」です。それぞれの被告の使用は、侵害と認定されました。
このサービスにおいて,ユーザーが自らのブログ記事を作成してウェブサイ トにアップロードした際には,ドワンゴが設置管理するサーバーの記憶領域に ブログ記事のデータを保存しており,ドワンゴは,サービス利用者に対し,サ ービス利用者自身のブログを開設し,ブログ記事を作成し,投稿するために必 要となるサーバーの記憶領域を提供しているといえ,ブログの開設及びブログ 記事の作成,投稿機能を含むドワンゴのブログサービスは,「インターネット\nにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」に類似するといえる。 これに対し,ドワンゴは,本件で問題となるブログに関するサービスにおい てサーバーの記憶領域への保存の過程があることは認めつつ,役務の提供に付 随して提供される業務は商標法上の役務には含まれないと解すべきであると ころ,ニコニコのブログサービスの中心となるのは「CHブロマガ」であり, ニコニコのブログサービスは購読者に対する記事コンテンツの配信が主たる サービスであること,ブログ記事の作成やウェブサイトでの閲覧機能は独立し\nたサービスではなく,ブログ記事の配信サービスと分離して取引されていない こと,ドワンゴはサーバーの記憶領域の保存過程について対価の支払を受けて いないこと等から,ブログ開設及びブログ記事作成,投稿機能は,他の役務の\n提供などに付随して提供される業務であって商標法上の役務ではない旨主張 する。
ある業務を行うに当たり必然的に伴う役務における標章の使用に対し,その 役務と同一又は類似する役務を指定役務とする商標の商標権者が商標権の侵 害を主張することができることが適当でない場合があるとしても,本件につい てみると,一般的に,利用者がブログを開設,投稿して他人にそれを閲覧させ るためのプラットフォームを提供するサービスは独立した役務といえるとこ ろ,前記 エのとおり,ニコニコのウェブサイトでは,会費を支払ったプレミ アム会員であれば享受することができるサービスの一つとして,自らブログを 開設し,ウェブサイト上にブログを投稿することができることが明確に表示さ\nれている。また,サービスの利用にあたっても,ブログを開設することができ ることが表示され,それに従い所定の操作を行うことで,ブログが開設され,\nまた,ユーザーがそのブログを閲覧することができる。ドワンゴが「CHブロ マガ」のサービスを提供し,また,ニコニコのウェブサイトでは,「CHブロマ ガ」に関する表示があることは認められるが,「CHブロマガ」は,著名人等の\nチャンネルオーナーが電子書籍形式の記事コンテンツの配信を行うものであ って,このような「CHブロマガ」と,一般ユーザーによるブログ開設,ブロ グ記事投稿,配信機能である「ユーザーブロマガ」とでは,サービスの内容が\n大きく異なる部分がある。また,前記 によれば,ニコニコのウェブサイトのトップページから「ユーザーブロマガ」を利用することができ,「CHブロマ ガ」とは別に自らブログを開設等できる「ユーザーブロマガ」を利用する者も 想定できる。これらに照らせば,「ユーザーブロマガ」が「CHブロマガ」に付 随するサービスとはいえない。また,「ユーザーブロマガ」においては,ブログ 記事をウェブでユーザーから閲覧することができるようにするだけでなく,ブ ログ記事をメール配信することができ,それが特徴となっていることが認めら れる。
しかし,「ユーザーブロマガ」において,ユーザーは全員がメール配信す るかしないかを選択することとなっていて,ブログを開設し,ブログ記事を投 稿し,閲覧させる役務は,一般にも独立したサービスとして提供されているも のである一方,「ユーザーブロマガ」において,ブログを開設しブログ記事を投 稿する者にとって,メールを配信しないことが例外的な態様であるとまではい えず,メールの配信が不可欠の要素となっているとはいえない。さらに,ニコ ニコのウェブサイトで提供するサービスについての対価は,ブログ記事を投稿 等する機能のみに対する対価として徴収されているものではないものの,そも\nそも,その対価はニコニコのウェブサイトにおいて提供されている多様なサー ビス全ての対価であり,そこには独立して提供し得る様々なサービスが含まれ ていて,ブログ記事の配信という特定のサービスのみについての対価ではない。 このことを考慮すると,ブログを開設等する機能のみに対する対価が徴収され\nていないことが,直ちにそれに関する役務が商標法上の役務といえないことの 根拠になるとはいえない。そして,対価を支払った会員が受けられるサービス の中には,上記のように独立したサービスとして提供されるブログ開設及びブ ログ記事作成,投稿機能も含まれていることなどを考えると,本件の事実関係\nの下においては,ドワンゴが主張するように「ユーザーブロマガ」サービスに おけるブログの開設及びブログ記事の作成・投稿機能が,他のサービスなどに\n付随して提供される業務であって商標法上の役務には含まれないということ はできないというべきである。
また,ドワンゴは,インターネットを利用するほぼ全てのサービスが,サー バーの記憶領域への保存を伴うから,ドワンゴが提供するサービスが,甲商標 の指定役務である「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領 域の貸与」と同一又は類似すると解釈することは実務に混乱をきたすと主張す る。しかし,インターネットを利用するサービスにサーバーの記憶領域への保 存を伴うものが多いとしても,そのサービスには様々なものがあり,それらの サービスの全てにおいてサーバーへの記憶領域への貸与が独立した役務と認 められるとは限らず,本件においては,本件で問題となっているサービスにつ いて,ブログのためのサーバーの記憶領域の貸与が商標法上の役務と認められ たものであり,ドワンゴの主張は採用することができない。
・・・
インターネットの検索エンジンの検索結果において表示されるウェブペー\nジの説明は、ウェブサイトの概要等を示す広告であるということができる。し たがって,その説明が表示されるようにHTMLファイルにメタタグを記載す\nることは役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行 為に当たるというべきであり,これに反するドワンゴの主張は採用することが できない。 そして,ドワンゴは,乙標章を,ニコニコのウェブサイトのトップページの HTMLソースコードの記述メタタグに記載していることは当事者間に争い\nがなく,乙標章は,ニコニコのHTMLファイルにメタタグとして記載された 結果、検索エンジンの検索結果において、ウェブサイトの内容の説明文ないし 概要やホームページタイトルとして表示され、これらがニコニコのウェブサイ\nトにおける,ブログ開設及びブログ記事作成,投稿機能を含む各種サービスの\n出所等を表示し、インターネットユーザーの目に触れることにより、顧客がニ\nコニコのウェブサイトにアクセスするよう誘引するのであるから、ドワンゴに よる乙標章のメタタグとしての使用は役務の出所識別機能を果たす態様で使\n用されているといえる。 以上によれば,ドワンゴによる乙標章の使用は甲商標の商標権を侵害する態 様での使用であるといえる。
・・・
ア ドワンゴは,FC2が提供するサービスが「電子出版物の提供」に該当す ると主張するのに対し,FC2は,これを否定する。 イ FC2の「ブロマガ」のサービスにおいては,ユーザーは,検索などをす ることによって,購入したい記事を選択し,FC2に対して所定の支払をし て「オリジナル小説」や「漫画」が例に挙げられる「限定記事」を購入する ことができ,その購入後,FC2のウェブページにおいて,購入した記事を 閲覧することができるようになり,また,購入した記事について,その後, FC2からHTML形式のメールの配信を受けることなどができた。
上記サービスにおいては,利用者は,FC2のサービスを利用することに よって,上記のような態様で,第三者が作成したまとまりのある文書・図画 を閲覧等することができるようになるのであり,同サービスにおいては,電 子出版物の提供又は通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊 行物の提供に,少なくとも類似した役務が提供されているといえる。
そして,前記 のブログ記事の購入に当たり用いられている甲標章の 使用態様によれば,電磁的方法により行う映像面を介したこの役務の提供に 当たり,映像面に乙商標と類似する甲標章が付されていたと認められる。 ウ FC2は,「電子出版物」とは,いわゆる電子書籍を意味してFC2のブログ サービスは「電子出版物の提供」に該当しないと主張し,また,ブログ記事の 配信を行う主体はユーザーであり,FC2ではなく,FC2はその媒介をして いるにすぎないから,ブログ記事の配信が「電子出版物の提供」に該当すると しても,FC2のブログサービスは「電子出版物の提供」の媒介であって,「電 子出版物の提供」には該当しないと主張する。
しかし,前記イの態様に照らせば,FC2の上記のブロマガの販売に関する サービスについては,少なくとも,前記役務に類似した役務が提供されている といえる。
◆判決本文
取消訴訟はこちら
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 役務
>> ピックアップ対象
2024.11.18
令和4(ワ)11025等 特許権侵害差止等請求本訴事件、不当利得返還請求反訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月21日 大阪地方裁判所
上記本件明細書の記載によると、本件発明は、大きなダニ捕獲能力を発揮\nすることを目的として、その手段は、ダニ誘引物質を含浸させた織物シート からダニ誘引物質を拡散させることで広い範囲のダニを誘引した上で、マッ トの内部にダニ捕獲用の粘着テープと、これに対して千鳥状に被着させたダ ニ用食餌を入れた多孔質通気性袋を配することで、ダニ誘引物質で誘引され たダニを、マットの表裏両面からさらに内部に侵入させ、粘着テープに触れ\nさせ、そこで捕捉するようにするというものである。 そして、ダニを誘引させる物質として、「香料」を織物シートに含侵させた 上、「食餌」入りの多孔質通気性袋を配置させる位置を両面粘着テープの表\n裏両面に配置させることにより、多孔質通気性カバーの内側に誘い込み、混 ぜ物のない粘着層に触れさせて補足させる構成をとるものであるから、本件\n発明において「多孔質通気性袋」は、食餌が同位置にとどまり、粘着層の粘着 力を低減させない機能を備えるべきことが想定されているといえる。加えて、\n多孔質通気性袋の構造上、一袋でこれらが実現でき、構\成材料の数も減らす ことができるようになっている。
以上を踏まえると、構成要件A−3にいう「多孔質通気性袋」とは、辞書\n的にも、本件明細書の記載からも、少なくとも内包物を内部で保持し、拡散 を防止することができる構造を有することが必要であると解することが相当\nである。一方、販売被告製品では、ダニ誘引物質が2枚の不織布シートやガ ーゼ等で重ねて挟み込まれているのみであり、その周囲からダニ誘引物質が 零れ落ちるようなものであるから、誘引物質を内部で保持することができる 構造であるとは認められない。\n
この点、原告は、本件発明における「袋」の意義について、ダニ食餌を入れ ることができ、かつ、一つの袋のみで粘着テープの表裏両面に配置すること\nができればよく、口を閉塞している必要はないから、被告製品も、多孔質通 気性袋を有すると主張するが、上記説示に照らし、採用できない。
(5) よって、販売被告製品は、構成要件A−3を充足せず、同構\成要件を充足 することを前提とする構成要件C、D、F及びGも充足しない。\n
3 争点A3(均等侵害が成立するか)について
上記2のとおり、本件発明は、ダニ食餌を零れ落ちさせることなく保持する ことができる「多孔質通気性袋」に収納することで、粘着テープの高い粘着力 を実現するとともに、構成材料の数を減らすことを実現しており、そのために\n袋構造を有することが本質的要素となっているものと認められる。\nそうすると、多孔質通気性袋に代わり、挟み込んだ物が零れ落ち得る2枚の 不織布やガーゼでダニ誘引物質を挟み込む構造を有している販売被告製品は、\n本件発明の非本質的部分で相違点があるに過ぎないとはいえないし、これらを 置換したときの作用効果が同一であるともいえない。
よって、第1要件(非本質的部分)及び第2要件(置換可能性)がいずれも\n認められないことから、均等侵害は成立しない。
4 小括(特許権侵害について)
(1) 以上の次第であり、被告製品は、本件特許の技術的範囲に属しないので、 原告の本件特許権侵害に関する主張(争点A1ないしA6)は、その余の争 点について判断するまでもなく理由がない。
(2) なお、被告は、原告の均等侵害の主張について、時機に後れた攻撃防御方 法として却下することを求めているが、その審理のために訴訟が遅延するも のとは認められないから、採用しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.11.15
令和6(ネ)10031 不正競争行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和6年10月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 被告各表示の商標法2条3項8号該当性について\n
前記(1)の本件ウェブサイトの構成と記載内容によれば、以下に述べるとお\nり、本件ウェブサイトは、全体として、被告を含むダイショーグループが東 南アジアにおいて日本食を提供する飲食店チェーンを展開するとともに、そ こで提供するための鮮度の高い良質な食材を日本から輸出する事業を営んで いることを紹介するものであると認められるから、被告各表示を付した本件\n各ウェブページについても、本件すし店の「役務に関する広告」に当たると 認めることはできない。
ア 「事業内容」のページ(前記(1)ウ)は、説明項目の記載順が「食材・食 品の輸出/提案」、「加工・流通」、「物産展・地域振興」、最後に1 0の飲食店チェーンの一つに被告各表示を付した「店舗開発・メニュー\n開発」となっており、それぞれ相応な分量の説明と写真があり、冒頭の 「食材・食品の輸出/提案」の末尾は、食材の海外輸出を検討する日本 国内の事業者に向けた呼びかけとなっている。そうすると、これに続く 「加工・流通」、「物産展・地域振興」、「店舗開発・メニュー開発」 は、輸出先の国における流通経路の川下に関する事業内容を順次紹介す ることにより、海外輸出を検討している国内の事業者に向けて、ダイシ ョーグループを通じた輸出の利点を記載したものといえる。
イ このような食材の輸出に関連する内容は、前記(1)のとおり本件ウェブサ イトの随所にみられ、特に「海外輸出をお考えの方」のページ(前記(1) カ)は、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けたものであること が明らかである。
ウ これに対し、被告各表示を付した部分は、上記「事業内容」のページに\nおいては、ページの最後に被告各表示と簡潔な説明文及び英文ウェブサ\nイトへのリンクがあるにとどまり、ページ全体に占める割合は少なく、 具体的なメニューの内容、価格、店舗の所在場所といった、一般消費者 に向けて本件すし店の役務の内容を知らせる内容は乏しい(これらの情 報は、リンクされた英文ウェブサイト(乙37)に掲載されていること が推認される。)。しかも、被告各表示は、ダイショーグループが展開\nしている飲食店チェーンを紹介した部分に掲載されている10種類の飲 食店(その中には簡潔な説明文中にシンガポールやクアラルンプールの 店舗であることが明記されているものもある。)の一つにすぎない。そ して、同ページの記載内容からも、本件すし店が東南アジアに所在する ことは比較的容易に読み取ることができる。 トップページ(前記(1)ア)において被告各表示を用いた部分をみても、\n英文ウェブサイトへのリンクがないことを除いては「事業内容」のペー ジと同じであり、ページ全体に占める割合が多いとはいえず、10種類 の飲食店チェーンの一つとして店舗情報が提供されていることは、前記 「事業内容」のページと同様である。 さらに、上記の「事業内容」のページや「ダイショーグループとは」 のページ(前記(1)イ)をみれば、本件すし店が東南アジアに所在するこ と、日本法人である被告が国内からの食材の輸出の事業を営んでいるこ とは、比較的容易に読み取ることができる。
エ これに対し、原告は、本件各ウェブページの被告各表示が、ダイショー\nグループの事業内容として本件すし店の役務を「広く世間に告げ知らせる」 ことを目的として使用されていること、その役務に係る出所表示機能\、自 他商品識別機能等を果たす態様で使用されていることは明らかであるから、\n本件すし店の「役務に関する広告」に該当する旨主張する。 しかし、前記の本件ウェブサイトの構成と記載内容によれば、被告各表\ 示を用いた部分が本件すし店の役務を「広く世間に告げ知らせる」とい う一面があることを全く否定することはできないとしても、全体からみ ると、本件各ウェブページは日本からの食材の輸出という役務の広告と いうべきであって、被告各表示を用いた部分は、ダイショーグループが\n展開する他の飲食店チェーンの紹介と併せて、国内の事業者に対し、ダ イショーグループを通じて輸出した場合の食材の使用先や使用状況を明 らかにし、これにより被告との間で食材の輸出取引を行うための誘因と する目的で使用されているというべきである。 このような使用態様については、本件すし店の役務に係る出所表示機能\、 自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていると評価することはで\nきない。
・・・
ク 以上によれば、被告各表示は、その態様に照らし、食材の海外輸出を検\n討する国内事業者に向けた本件各ウェブページの中で、被告の事業を紹 介するために使用されているにすぎず、本件すし店を日本国内の需要者 に対し広告する目的で使用されたものではなく、現にそのような効果が 生じている証拠もない。 したがって、本件ウェブページ掲載行為は、「本件すし店の役務に関 する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為」として商 標法2条3項8号に該当するものということはできない。
(3) 被告各表示と原告各商標権の侵害について\n
仮に、原告が主張するとおり、被告各表示の使用が本件すし店の存在を日\n本国内に広く知らしめるという点において「広告」に該当し、商標的使用に 該当すると考えた場合でも、以下のとおり、被告各表示は、日本国内におけ\nる役務の提供について使用されているものではないから、原告各商標権を侵 害するものではない。 ア すなわち、被告各表示は、日本語で記載された本件各ウェブページに掲\n載されているから、これが本件すし店の広告に該当すると考えたときは、 日本国内において商標法2条3項8号に該当する行為がされたものと一応 いうことができる。
イ しかるところ、前記のとおり、本件各ウェブページは、食材の海外輸出 を検討する国内事業者に向けたものであると認められ、被告各表示は、本\n件各ウェブページの中でダイショーグループが海外で日本の食材を用いた 飲食店チェーンを展開していることを示す際に使用されている。本件各ウ ェブページには、本件すし店の具体的なメニューの内容、価格など、一般 消費者に向けて本件すし店の役務を知らせる内容は一切記載されておらず、 「事業内容」のページの被告各表示の下のリンクから誘導されるのは英文\nのページのウェブサイトである。
ウ また、証拠(乙17、21)及び弁論の全趣旨によれば、本件すし店は、 日本国外(シンガポール、マレーシア)で飲食物の提供等の役務を提供し ていることが認められ、シンガポールやマレーシアで商標登録されている 被告各表示(甲8、乙14、15。商標権者はスーパースシである。)は、\n現地でその役務を提供するに当たり、使用されている標章である。本件す し店が、日本国内で同様の役務を提供している事実は認められない。
エ そうすると、被告各表示は、本件すし店の日本国内における役務の提供\nについて用いられているものではない。被告各表示を見た日本国内の消費\n者が被告各表示により役務の提供の出所を誤認したとしても、本件すし店\nが日本で役務を提供していない以上、その誤認の結果(原告の店であると 誤認して、本件すし店から指定役務の提供を受けること)は、常に日本の 商標権の効力の及ばない国外で発生することになるはずであり、日本国内 で原告各商標権の出所表示機能\が侵害されることはない。なお、証拠(甲 10、11)によれば、クアラルンプールの本件すし店に入店する際、こ れを原告の支店であると誤認した日本人がいた事実が認められるが、当該 出所の誤認が本件各ウェブページの被告各表示を閲覧した結果生じたもの\nであることを認める証拠はない上、出所の誤認が国外で発生していること に変わりはないから、当該事実は、前記判断を左右するに足りるものでは ない。
オ もともと、一国において登録された商標は、他の国において登録された 商標から独立したものとされており(パリ条約6条1項及び3項)、かつ、 いわゆる属地主義の原則により、商標権の効力は、その登録された国内に 限られるものと解される。外国において適法に登録された商標である被告 各表示が当該外国における指定役務の提供を表\示するため本件各ウェブペ ージ上で使用された場合において、原告各商標権に基づき被告各表示の使\n用差止等を認めることは、実質的にみて、原告各商標の国内における出所 表示機能\等が侵害されていないにもかかわらず、外国商標の当該外国にお ける指定役務表示のための適法な使用を日本の商標権により制限すること\nと同様の結果になるから、商標権独立の原則及び属地主義の原則の観点か らみても相当ではないというべきである。
・・・
以上によれば、原告の主張を考慮しても、本件各ウェブページは、日本か らの食材の輸出という役務の広告というべきであり、仮に被告各表示を本件\nすし店の役務の広告であると考えた場合でも、当該役務は国外で提供される 役務であるから、原告各商標の国内における出所保護機能を害するものでは\nない。
・・・
(1) 前記2のとおり、本件各ウェブページにおいて、被告各表示は、日本から\nの食材の輸出という被告の事業に関連する情報の一つを示すために使用され ていると認められるから、他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表\示を 使用し、出所表示機能\、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されている\nと評価することはできない。また、仮に、被告各表示が、本件すし店の提供\nする役務を表示するために使用されていると考えたとしても、当該役務は日\n本国内の役務ではなく、国外で提供される役務であるから、日本国内におい て、出所表示機能\、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていると評\n価することはできない。
そうすると、本件ウェブページ掲載行為は、被告各表示を商品等表\示とし て「使用」するもの(不競法2条1項1号)に当たらないから、その余の点 を判断するまでもなく、不競法2条1項1号に基づく原告の請求は、理由が ない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> 外国
>> ピックアップ対象
2024.11.13
令和5(ワ)70178 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年9月26日 東京地方裁判所
(1) 「乾燥して造粒物を得る工程」の終期
本件の争点整理の経過に鑑み、主たる争点である争点1−2のうち、中核 的争点である「乾燥して造粒物を得る工程」の終期がいつであるかという点 につき、まず判断する。この点につき、原告は、「乾燥して造粒物を得る工程」 の終期とは、「打錠用粉体に適した造粒物を得るために必要な状態まで溶媒が 除去された時点」(原告はこの時点までの乾燥を「必要な乾燥」といい、これ 以降の乾燥を「余分な乾燥」として区分している。)である旨主張する(第4 回弁論準備手続(技術説明会)調書参照)。
そこで検討するに、本件明細書に係る前記認定事実によれば、本件明細書 の記載(【0010】、【0033】等)を踏まえると、本件発明の課題は、酢 酸亜鉛水和物中の結晶水が消失して無水物に転移することを防ぐことにあり、 その課題の解決手段としては、乾燥工程における品温を40゜C)未満とするも のであると認めるのが相当である。そして、「乾燥」とは、一般的に熱を与え るなどして不要の液体分を取り除くことを意味するものであり(甲9、10)、 本件明細書においても、上記と異なる意味で使用されているところはない。 そうすると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を 意味するものであり、その終期とは、文字どおり、全ての乾燥が終了した時 点であると解するのが相当である。 これを原告の上記主張についてみると、原告は、乾燥には「必要な乾燥」 と「余分な乾燥」に区分され、「余分な乾燥」では40゜C)を超えることが許容 される趣旨をいうものである。
しかしながら、本件発明の構成要件及び本件明細書を精査しても、原告が\n自認するように、「必要な乾燥」と「余分な乾燥」に区分されるという原告の 解釈を裏付ける記載や示唆は一切なく、上記の間にある「打錠用粉体に適し た造粒物を得るために必要な状態まで溶媒が除去された時点」という原告主 張に係る概念も、本件発明の構成要件及び本件明細書に一切記載されておら\nず、それ自体明確性を欠くことに鑑みても、原告の主張は、その根拠を欠く ものというほかない。
かえって、原告の主張によれば、「余分な乾燥」では40゜C)を超えることが 許容されることになるから、乾燥工程における品温を40゜C)未満とする本件 発明の課題解決手段に明らかに抵触するものとなり、本件明細書によれば本 件発明の課題を解決できないことになる。そうすると、原告の主張は、本件 発明の課題解決手段を正解しないものといえる。 したがって、原告の主張は、採用することができない。
(2) 被告方法への当てはめ
前記認定事実によれば、被告医薬品の医薬品製造販売承認書には「乾燥終 点における製品温度は《50゜C)》以下とする」と記載されており、被告医薬 品に係る製造指図記録書においては、いずれも、品温41.0゜C)以上で乾燥 終了との指示がされていることからすると、被告方法における「乾燥して造 粒物を得る工程」では、品温が41゜C)以上になることが認められる。そうす ると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を意味する ものであるから、被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温 が40゜C)未満」という構成要件を充足するものとはいえない。\nしたがって、被告方法は、構成要件1−1A及びC、1−3D、2−1A\n及びC、2−3Dを充足するものと認めることはできない。
・・・
3 争点1−1(特許法104条による推定の可否)
(1) 被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温が40゜C)未満」 という構成要件(構\成要件1−1A及びC、1−3D、2−1A及びC、2 −3D)を充足しないことは、前記2において説示したとおりである。 そうすると、仮に、被告医薬品が特許法104条に基づき本件発明に係る 製造方法により生産したものと推定された場合であっても、前記2において 説示したところによれば、当該推定は、覆されるものと認めるのが相当であ るから、争点1−1は、本件において結論を左右するものとはならない。 もっとも、当事者双方の主張の経過に鑑み、念のため判断するに、前提事 実及び前記認定事実によれば、本件発明の優先日前に出された本件ニュース リリースには、「NPC−02(酢酸亜鉛)ウイルソン病治療剤ノベルジン® 錠25mg及び50mgの製造販売承認(剤形追加)を取得」という記載が あるところ、本件ニュースリリース前から原告によって販売されているノベ ルジンカプセル25mg及び50mgは、ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害\n剤)であり、酢酸亜鉛水和物を有効成分とするカプセル剤である。そして、 前記認定事実によれば、剤形追加に係る医薬品とは、既承認医薬品等と有効 成分、投与経路、効能・効果及び用法・用量は同一であるが、剤形又は含量\nが異なる医薬品をいうことからすると、本件ニュースリリースに係る医薬品は、ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)であり、酢酸亜鉛水和物を有効成\n分とする酢酸亜鉛錠であるものと認められる。 これらの事情の下においては、本件ニュースリリースに係る医薬品は、本 件発明により生産される物と同一のものといえるから、本件ニュースリリー スの掲載により同医薬品の存在が対外的に公表されているといえる。そうす\nると、本件発明により生産される「物」は、本件発明の優先日前の時点にお いて、当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られたもので あったと認めるのが相当である。 したがって、被告医薬品は、特許法104条に基づき、本件発明に係る製 造方法により生産したものと推定することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2024.11.13
令和6(行ケ)10029 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年9月12日 知的財産高等裁判所
(3) 観念
ア 「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではない。 「マーくん」の語の意味に関して、ウィキペディアの「マーくん」の項 には、「1.プロ野球・千葉ロッテマリーンズのマスコット。」、「2.プロ 野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と(甲1 2)、ニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、日本のプロ野 球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマスコットについて解説。」とし た上で、「曖昧さ回避」として、「『千葉ロッテマリーンズ』のマスコット。 本項で記述。」、「『ヘタリア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。 →マー君」、「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の 表記揺れ」(甲11)とそれぞれ記載されており、「マーくん」の語は、そ\nれらのとおり多義的に理解される語として認識されていることが認めら れる。
また、「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについて報じ る報道(マイナビニュース)の「編集部が選ぶ関連記事」には、上記プロ 野球選手である楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関連する報道 が複数(4件のうち3件)紹介されているものもある(甲222)。そして、 原告の主張に係る千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターであ る「マーくん」についても、新聞の全国紙等において、「マー君」と表記し\nて報道されている例もみられる(甲220、256〔読売新聞〕)。 これらのことは、「マーくん」といえば千葉ロッテマリーンズのキャラク ターを指すものとして広く浸透し、一般に認識されているものであれば、 容易には起こり得ないことともいえる。
これらの事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又は意味合 いを表すものとして一般に広く認識等されているとの事実を認めること\nはできず、本願商標からは特定の観念は生じないものというべきである。 イ 原告は、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る取引の 状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーンズのマスコットキャ ラクター」の名称(「マーくん」)の観念が生じると主張し、本願商標は観 念において引用商標と異なり、両者は類似しない旨を主張する。
しかし、「マーくん」の語から、特定の観念が生じないことについては既 に述べたとおりである。加えて、原告の提出する証拠を検討しても、「マー くん」に関連する報道における「マーくん」に係る記載は、「ロッテ球団の マスコットキャラクターのマーくん」、「千葉ロッテマリーンズのマスコッ トキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマリーンズやロッテ球団 などと球団を示す語を伴って使用されていたり、「マーくん」のキャラクタ ーのイラストや着ぐるみの写真などとともに使用されているものである (甲16、18〜20、61など)。これらによれば、千葉ロッテマリーン ズの球団やそのマスコットキャラクターであることを表す語、あるいは球\n団のマスコットキャラクターの容姿(イラストや着ぐるみなど)が併記さ れていることではじめて、「マーくん」の文字が「球団のマスコットキャラ クターの名称」であると認識されるものと認められる。 また、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターである「マーく ん」による、野球とは関連性が希薄な活動への参加の実績についても、千 葉県及び球団の本拠地とされる千葉マリンスタジアム(ZOZOマリンス タジアム)(乙27〜30)におけるものであって、千葉市内を中心とした 千葉県内での活動にとどまり、これらの活動を報じる各種新聞も、そのほの地域に関する記事を掲載する紙面。乙31)の記事としての掲載であり (甲38、49、52など)、ウェブサイトへの掲載も、内容のほとんどが 球団やそのマスコットキャラクターを紹介する記事であって(甲28、3 1など)、特にこれらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示 す証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がない全国の 一般の消費者において、その多数がこれらの新聞記事やウェブサイトの掲 載を閲覧しているとは認め難いものである。 したがって、千葉ロッテマリーンズの公式マスコットキャラクターに関 する周知活動については、対戦相手の他球場における活動を除き、そのほ とんどは、千葉市内ないし千葉県内にとどまるものであって、その活動が 報道されている範囲についても、多くは、千葉県内ないしその周辺地域に とどまるものと認められる。
現に、千葉県佐倉市周辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉 ロッテマリーンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、 「千葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇!マーくんと、リーンちゃん という名前だそうです。」(甲387の1)と記載されており、これによれ ば、千葉ロッテマリーンズのロゴとマスコット(人形)により「千葉ロッ テマリーンズのマスコット」は認識されているとしても、知っていたのは そのキャラクターであって、「マーくん」の名称であるとはいい難い上に、 そのキャラクター自体を知る主体も、千葉ロッテマリーンズに関心がある 者に限られているものと理解されるところである。 原告は、「マーくん」についての報道は、千葉県外でも広く発行される新 聞記事にも掲載されている旨を主張するが、それらも千葉県内における活 動を報じるもの(甲388)や、同県内における製品の販売を報じるもの (甲396)、キャンプでの千葉ロッテマリーンズの活動やそこに登場し たマスコットキャラクターを報道するもの(甲399)など、千葉県内関 連のニュースとして報じられているにとどまる。 したがって、本願商標から「千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラ クター」の名称の観念が生じるとする原告の主張は採用することができない。 ウ そうすると、本件審決が本件商標から特定の観念は生じないとした認定 に誤りはない。
3 引用商標の構成等\n
(1) 外観
引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してなるものである。\n
(2) 称呼
ア 引用商標の構成中「Markun」の文字は、我が国に浸透している「M\nar」の文字を含む「マーケット」、「マーチ」、「マーブル」等の語(乙6、 7)との比較や、「kun」はローマ字読みで自然に「クン」と発音される ことからしても、「マークン」の称呼が生じるものといえる。 「Markun」の文字は、それに続く文字が省略されていることをう かがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文字であり、6文字で 構成されるその文字数や上記称呼からして完結した一語であると認めら\nれる。そして、引用商標の構成中の「.」は、その末尾に表\示されている。 これらのことから、構成中の「.」は、その位置から、アルファベットなど\nの横書の文の末尾に付する点である終止符(ピリオド)を認識させるもの(乙1)と認められる。そして、終止符(ピリオド)である「.」は、特段 の称呼を生じない。 そうすると、引用商標は、全体の構成より「マークン」の称呼が生じる\nものと認められる。
イ 原告は、引用商標の構成中の「.」を「ドット」と称呼する取引の実情が\nあるとして、これに沿う証拠を提出し、引用商標は「マークンドット」の 称呼を生ずると主張する。 しかし、既に述べたとおり、引用商標の構成からすると、構\成中の「.」 は終止符(ピリオド)を認識させ、特段の称呼を生じないものと認められ る。加えて、原告の提出する証拠は、「.」を「ドット」と読む例があると いうに止まり、「.」を「ドット」と称呼するのが一般的であることを示す ものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検討すると、「Dhya na.」ブランドについて、「メイドインジャパンのものづくりを大切にし たレディースシューズブランド『Dhyana.(ディアナドット)』」(甲342)、「R.」ブランドについて「・・・がコンセプトの『R.(アール ドット)』」(甲343)、「会社名 株式会社 be me.(ビーミードット)」(甲 356)などとわざわざ記載している例にみられるように、「ドット」を称 呼に含ませる場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリ\nオドと認識される語末の「.」を、ことさら「ドット」と称呼するのは一般 的でないものと認められる。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(3) 観念
引用商標の構成中の「Markun」の文字は、一般の辞書等に載録され\nている成語とは認められず、我が国において特定の事物又は意味合いを表す\nものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、 そこからは特定の観念は生じない。また、ピリオドと認識される語末の「.」 も特定の観念を生じない。 したがって、引用商標は、全体として、特定の観念を生じないものと認め られる。
4 本願商標と引用商標の類否について
(1) 外観の比較
本願商標と引用商標とは、外観において、本願商標は片仮名と平仮名とか らなる構成であるのに対し、引用商標は語頭の大文字及びその余の小文字の\n欧文字並びに記号からなる構成であり、文字種を異にする点で異なるととも\nに、引用商標の末尾に位置する「.」(ピリオド)の有無において相違する。 しかし、「DUMMY−KUN」と「ダミーくん」を並記する例(乙8)、「ルイザちゃん」と「RUIZAちゃん」を並記する例(乙9)などにみら れるごとく、商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で、文字種を相互\nに変換して表記することは一般的に行われており、「マークン」、「まーくん」、\n及び「マーくん」の店舗名を、それぞれ「MARKUN」、「マークン/Ma rkun」、「Markun」などと変換して表記する(乙10〜12)など\nの取引の実情もあることが認められるところである。 そうすると、本願商標と引用商標は、いずれも標準文字で表されてなるこ\nとから、両者における上記文字種の相違は、取引者、需要者に対し、出所識 別標識としての外観上の顕著な差異として、強い印象を与えるとはいい難い ものというべきである。 引用商標の構成中の「.」(ピリオド)についても、末尾に位置しており、\n他の構成文字に比べてもかなり小さく表\記されていることからすると、外観 上の顕著な差異として特に印象的なものとはいえないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.11.13
令和5(行ケ)10148 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年9月12日 知的財産高等裁判所
上記アないしウによれば、甲2ないし甲4には、構成要件(D)の「前\n記注文情報における、前記団体情報を特定する情報に基づいて前記注文者 の団体を特定して、複数の前記注文情報の中から前記注文者の団体が同一 の前記注文情報を抽出」することや、「抽出された前記注文情報に基づいて、 同じ団体の注文からなる注文リストを、当該団体の担当者が閲覧できる形 式で出力する」ことについて記載されているということはできず、甲3に は、構成要件(E)の「前記注文リスト出力手段は、前記注文リストとし\nて、各注文について前記注文商品及び注文者を表示するリストを出力する」\nことも記載されていない。
そうすると、甲1発明に甲2ないし甲4に記載された事項を適用したと しても(原告の主張は、甲2ないし甲4に記載の事項をそれぞれ副引用例 として甲1発明に組み合わせるとするものなのか、それとも周知技術を記 載したものとするのかについて明確ではないが、いずれにしろ甲2ないし 甲4には構成要件(D)及び(E)に関する記載がなく、これを甲1に組\nみ合わせても本件発明1には至らないから、結論を左右しない。)本件発明 1に到達することはできないから、本件発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
(3) 甲1発明との組み合わせの動機付けについて
甲1には、前記2(1)のとおり、甲1のシステムを介して、販売側(販売店、 メーカー、物流会社、金融機関)が顧客から商品の注文を受注し、注文され た商品を顧客へ配達し、決済するという取引形態の説明がされ、それにより、 発注、受注、物流及び入金管理を一括処理して販売店の業務負担を軽減する という目的を達成することが記載されている。また、実施例についても、前 記2(2)のとおり、顧客(学校)からの注文の方法に応じた、販売店の業務管 理についての記載がある。このような甲1の記載内容によれば、甲1には、 販売側と顧客という二者間の関係についての記載しかなく、学校と学生のよ うな、顧客が帰属する組織内の属性(階層関係)については想定されておら ず、そのような属性に合わせた情報処理を行うことについては記載も示唆も されていない。また、仮に甲2や甲4にみられるような、複数の顧客を共通 する属性別にリスト化する処理が周知技術であったとしても、前記第2(1)の とおり、甲1発明の目的は、販売店の業務負担を軽減するところにあるから、 そのようなリスト化を行い、それを学校の担当者が閲覧できる形式で出力するようにするのは、甲1発明の上記目的とは相容れないから、そうした動機 付けはない。
また、甲1に記載された具体的な実施形態に即して検討すると、顧客(学 校)は、学校名、住所、商品名、商品番号、注文個数を入力した後、学生の 氏名、身長、胸囲、胴囲等を個別に入力する手順で注文を行うことから(図 3及び段落【0028】)、学生の個別注文情報は学校により既に集約されて おり、学校別に抽出された注文情報は既得のものである。そうすると、販売 店の業務負担軽減を目的とする甲1発明において、学校側が個別注文情報を 集約して注文することに代えて、販売側が学生から個別に注文を受けて集約 し、学校別に抽出された注文情報を学校の担当者に閲覧可能な形式で出力す\nるように変更することは、甲1発明の上記目的に反し、そのような動機付け はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2024.11. 7
令和6(行ケ)10047 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年10月30日 知的財産高等裁判所
(1) 原告は、昭和29年以来のゴジラ・キャラクターの長年にわたる使用の結 果、本願商標の形状は原告の出所を表示するものとして著名となっている旨\n主張するのに対し、被告は、映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラ(第4形 態)以外のゴジラ・キャラクターの立体的形状は本願商標の立体的形状と同 一視することはできない旨主張するので、商標法3条2項該当性の判断に当 たり、本願商標を使用したものと評価できる商品の対象範囲を最初に確定し ておく必要がある。
そこで検討するに、上記1(2)ウで認定したとおり、シン・ゴジラの立体的 形状は、それ以前のゴジラ・キャラクターと比較して、頭部が小さくなり、前 脚(腕)の細さが一層際立つ一方、尻尾はより太く長くなっているなど、全体 のプロポーションに違いが生じているほか、背中から尻尾にかけての部分を 中心に赤みがった色彩が加わっている等の違いがあり、被告が主張するとお り、両者を同一(実質的に同一)と認めることは相当でない。 しかし、商標法3条2項の「使用」の直接の対象はシン・ゴジラの立体的形 状に限られるとしても、その結果「需要者が何人かの業務に係る商品である ことを認識することができる」に至ったかどうかの判断に際して、「シン・ゴ ジラ」に連なる映画「ゴジラ」シリーズ全体が需要者の認識に及ぼす影響を考 慮することは、何ら妨げられるものではなく、むしろ必要なことというべき である。
(2) 以上の枠組みに従って判断する。
ア まず、映画「シン・ゴジラ」は、平成28年7月に公開されると、日本映 画の歴代第22位にランクされる興行収入を上げる記録的な大ヒットとなり、本願商標に係る使用商品だけでも、売上数量102万個、売上額約26 億5000万円を記録する(上記1(5)ア)など、本件審決時までの約8年 間に、本願の指定商品に集中的に使用された事実が認められる。
イ 加えて、シン・ゴジラの立体的形状は、本件特徴を全て備える点を含め、 それ以前のゴジラ・キャラクターの基本的形状をほぼ踏襲しているところ、 当該基本的形状は、映画「シン・ゴジラ」の公開以前から、本願の指定商品 の需要者である一般消費者において、原告の提供するキャラクターの形状 として広く認識されていたことが優に認められる。
すなわち、1)昭和29年に始まった映画「ゴジラ」シリーズは、その後6 0年以上の長きにわたり全30作にわたる新作を次々と公開し、累計観客 動員数約1億2000万人を記録するなど、圧倒的な商業的成功を収めて いること、2)これらの映画の広告等には、原告の「製作・配給」であること 等が明記されていたこと、3)この間の映画「ゴジラ」シリーズのビデオグラ ム及びゴジラのフィギュア商品の売上金額は、それぞれ百億円を大きく超 えていること、4)上記フィギュア商品については、原告から商品化の許諾 を受けた第三者企業によって販売されているものも多いが、原告が商品化 の主体であることを示す本件著作権等表示が付されていたこと、5)原告の シンボル的なモニュメントとなっている巨大なゴジラ像は、繁華な商業施 設を含む都内の複数の場所に恒常的に設定されていることは、上記1で認 定したとおりである。
ウ さらに、「ゴジラ」の文字商標は、原告に係る映画のタイトル又は当該映 画に登場する怪獣の名称として著名となっているところ(上記1(6)、当裁 判所に顕著な事実)、「シン・ゴジラ」を含む「ゴジラ」シリーズでは、登 場する怪獣のキャラクターに一貫して「ゴジラ」の名称が使用されている。
エ 本願の指定商品の需要者は一般消費者であると解されるところ、そうし た需要者の認識としても、令和3年9月実施の全国の15歳〜69歳の男女を対象とするアンケート調査において、本願商標の立体的形状の写真を 示して「何をモデルにしたフィギュアだと思うか」との質問に対する自由 回答で、「ゴジラ」又は「シン・ゴジラ」と回答した者が64.4%とされ、 極めて高い認知度が示された(上記1(7))。この調査の対象者の選定、質 問方法等に特段の問題は見当たらず、その回答結果は、シン・ゴジラの立体 的形状の著名性を示すものといえる。
オ 以上を総合すれば、本願商標については、その指定商品に使用された結 果、需要者である一般消費者が原告の業務に係る商品であることを認識で きるに至ったものと認めることができる。
(3) 被告の主張について
ア 被告は、本願商標に係る使用商品の使用期間(販売期間)が「永年」とは いえない旨主張する。しかし、映画「シン・ゴジラ」が公開された平成28 年頃から本件審決時までの約8年間にわたって、原告が本願商標をその指 定商品に継続して使用した事実は認められるところ(上記1(5))、これ自 体、それなりの使用期間と評価することができる。 更にいえば、そもそも商標法3条2項の「使用」につき「永年」の要件が 課されているわけではないし、「需要者が何人かの業務に係る商品である ことを認識することができる」に至ったか否かは、使用期間だけでなく、商 品の販売数量、広告宣伝の規模、話題性等も総合して判断すべきものであ る。加えて、本件においては、本願商標の使用以前から、原告を商品化の主 体とするゴジラ・キャラクターの商品が需要者に広く深く浸透しており、 本願商標の立体的形状はこれとの連続性が認められるという特殊な事情も 存在している。 こうした点を考慮すると、本願商標について、上記使用期間が「永年」と までいえないとしても、同項該当性に係る前記判断が左右されるものでは ない。
イ 被告は、原告主張の使用商品の販売実績についてはこれを裏付ける客観 的証拠はなく、また、これが事実としても、本願の指定商品を扱う業界にお いてどの程度のものであるかの多寡を確認することはできない旨主張する。 しかし、甲53、77によれば、上記販売実績は、原告社内の信用性のある データに基づき作成されたものと認められ、不合理な点は認められない。 また、被告が、本件審決が判示したように、「玩具業界全体」における使用 商品の占有率を問題にするのであれば、極めて多様なジャンルが存在する 玩具業界の実情を無視して、大きすぎる分母に基づいた議論をするもので あり、採用できない。
また、被告は、使用商品は原告でなくライセンシーにより販売されてい るにすぎないこと、「東宝」の文字を冠した使用商品でも原告以外のメーカ ー名が表示されていること、使用商品本体への本件著作権等表\示について は、本体の足の裏側の目立たない位置に小さく表示されているにすぎず需\n要者の注目を惹かないこと等を主張する。しかし、出願人から許諾を受け た者による使用も、第三者による当該商標の使用態様が出願人によって適 切に管理されており、需要者が出願人の商品であると認識し得るような場 合には、商標法3条2項にいう「使用」に含まれると解すべきところ、原告 は前記1(3)ウのとおりライセンシーとの間に使用許諾契約を締結し、使用 商品の形態も含めて監修するとともに、フィギュア類の出所が原告である ことを示す適切な管理をしている。本件著作権等表示が、当該商品が原告\nの許諾に基づき製造されたことを示すことは特段の困難なく理解できるも のである。
ウ 以上のほか、被告は、使用商品が掲載された雑誌の種類が少ない、書籍や 展示即売会の来場者は限定されている、ゴジラ像の恒常的設置は東京都内 の4か所にとどまる、本件アンケートには本願商標の立体的形状と原告と の関連についての質問がないなど、原告の主張立証の逐一を論難するが、ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前では些末な問題にすぎず、上 記(2)の判断を左右するものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2024.11. 7
令和6(行ケ)10025 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年10月30日 知的財産高等裁判所
1 取消事由1(商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)について
(1) 原告は、被告は特許庁を欺いて本件商標権を取得したものであり、国際信義則及び公序良俗に反し、これは商標法4条1項7号に該当する旨主張する。\n
(2) まず、原告は、被告が A 又はその相続人から本件商標に係る商 品の著作権についてライセンス契約の締結を受けていないとして、これを問 題とするところ、商標法には、他人の著作権と抵触するような商標登録を禁 じる規定はなく、むしろそのような商標登録が発生し得ることを前提に、同 法29条により先行著作権との調整を図っているのであって、他人の著作権 との抵触の一事をもってしては、同法4条1項7号に該当しないというべき である。 A の相続人と被告との間の著作権に関するライセンス契 約の成否、有効性いかんの問題は、同号該当性に影響を及ぼすものではない (蛇足ながらあえて付け加えると、乙1、2に係るライセンス契約の成立及 び有効性を疑うべき事情は見当たらない。)。
(3) また、本件商標は、出願過程において、被告の業務に係る商品であること が広く認識されていたことが認められて商標法3条2項が適用されていると ころ、被告と A 又はその相続人との間で、本件商標に係る著作権 について紛争となっている等、その出願が国際信義に反するような事情が生 じていることの主張立証はない。本件は、単に、原告において、「被告による A のデザインの盗用」という根拠のない憶測を述べているにすぎ ない事案といわざるを得ない。
(4) 以上のとおりであって、本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとし た本件審決の判断に誤りはなく、取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)について
(1) 原告は、本件商標は、 A の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されている商標として、商標法4条1項10号に該当する旨主張\nする。 しかし、原告は、本件商標が「 A の」業務に係る商品を表示するものであることを表\示するものとして周知であることを示す具体的な立証をしない。甲25、26を含め、本件商標の形状をデザインした者が A であることを示す証拠はあるが、業務の主体が A であることを 示すものではない。
(2) 原告は、 A の相続人と被告の間で締結されたライセンス契約が 有効でないとすれば、デザイナーの有名な商品を盗用して商品化した業者が、 立体商標の登録出願をして権利を取得できるようになる旨主張するが、同主 張は商標法4条1項10号の要件とはかかわりのないものである(なお、上 記ライセンス契約の成立及び有効性を疑うべき事情がないことは上記のとお りである。)。
(3) 以上のとおりであって、本件商標が商標法4条1項10号に該当しないと した本件審決の判断に誤りはなく、取消事由2は理由がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 立体商標
>> ピックアップ対象
2024.10.28
令和4(ワ)70058 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年10月18日 東京地方裁判所
(ウ) 前記(イ)によれば、本件特許の出願時において、グラップルバケット装 置において、グラップルした木材が長尺である場合、所定以上の長さを 有する木材をチェーンソー等の切断装置を用いて作業員が所定の長さに\n切断しなければならないとの課題については、甲27文献において開示 された従来技術によって解決することが可能であったから、本件明細書\nにおいて従来技術が解決できなかった課題として記載されているところ は、出願時の従来技術に照らして客観的に不十分であると認められる。\nそうすると、本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分を認定するに当たり、甲27文献に記載されている技術 的事項も参酌することが許されるというべきである。
(エ) 前記(ウ)において検討したところによれば、本件特許の出願前に、甲2 7文献において、一方の側部に把持部、他方の側部に切断装置が装着さ れているバケットを備えた枝切り走行装置が開示されていたと認められ るから、本件発明と従来技術との相違は、当該切断装置の構成に係る部\n分にすぎず、グラップルした被グラップル材を切断できるようにしたグ ラップルバケット装置であること自体ではないと認められる。そうする と、従来技術と比較して本件発明の貢献の程度が大きいと評価すること はできないから、本件発明の本質的部分については、これを上位概念化 したものとして認定することはできず、特許請求の範囲の記載とほぼ同 義のものとして認定されるというべきである。
したがって、前記(ア)及び(イ)に照らし、本件発明における従来技術に 見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、グラップル装置\nに設けられた切断装置について、バケットの側壁の外側あるいは内側の 一方側に位置してバケットの開口縁から離れた位置からバケットの側壁 に沿う位置にわたって側壁に沿う方向に回動し、かつバケットの開口縁 側に対向する側の側縁に切刃を有してバケットの側壁に沿う位置にわたって側壁に沿う方向に回動し、かつバケットの開口縁側に対向する側の側縁に切刃を有してバケットの開口基端部に枢支された切断刃と、上記切断刃の回動基部に連結して上記切断刃を回動させる油圧シリンダとからなり、切断刃の切刃を、切断刃の回動中心と油圧シ リンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃の切断方向側にずれた位置に設 けるとともに、この切刃の切断方向への回動方向に対して後方へ円弧状 に反らせたとの構成、すなわち構\成要件C及びDに係る構成を採用する\nことによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾き 角度θの値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効 果を発揮できるようにしたことと認めるのが相当である。
イ 前記2のとおり、被告製品は構成要件D2を充足するとは認められない\nところ、前記アのとおり、本件発明の構成要件C及びDに係る構\成を採用 することによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾 き角度θの値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効 果を発揮できるようにしたことが本件発明の本質的部分であるから、被告 製品が本件発明の本質的部分を備えているとは認められず、本件発明と被 告製品とが異なる部分が本件発明の本質的部分ではないとはいえない。 したがって、被告製品は第1要件を充足しない。
◆判決本文
以下に、イ号図面などがあります。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2024.10.22
令和6(ネ)10010 損害賠償請求控訴事件(特許権侵害) 特許権 民事訴訟 令和6年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、前記第2の4〔控訴人の主張〕のとおり、原審において主張し ていた無効理由とは異なる新たな無効理由(当審において新たに提出する乙 31文献による新規性欠如、同文献を主引用例とする進歩性欠如)を主張し、 被控訴人は、これにつき時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下を申し立てている。\n
(2) そこで、まず時機に後れた攻撃防御方法に当たるかについて検討すると、 控訴人による当審における新たな無効理由の主張は、令和6年2月6日付け 控訴理由書においてなされたものであるところ、特許権侵害訴訟において、 無効の抗弁は、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続 内で迅速に解決するため、特許無効審判手続による無効審決の確定を待つこ となく主張することができるものとされており、特許無効審判とは別の手続 である民事訴訟手続内でのものであるから、審理の経過に鑑みて、審理を不 当に遅延させるものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下されるべきである。
これを基に原審における審理経過についてみると、一審被告である控訴人 は、原審において、令和3年10月27日提出の同月22日付け答弁書にお いて、被控訴人製品の本件発明の構成要件該当性を否認するとともに、乙8文献を主引用例とし、これと周知技術との組み合わせないし乙9文献を副引\n用例とする進歩性欠如の無効理由を主張した。これに対する一審原告である 被控訴人の反論等を受け、令和4年3月18日付け準備書面(3)において、乙 8文献による新規性欠如の無効理由を追加し、これに対する被控訴人の更な る反論を受けて、令和4年5月27日付け準備書面(4)において、更に乙8文 献を主引用例とし、乙10文献を副引用例とする進歩性欠如の無効理由を追 加した。これについての被控訴人の反論に対しては、更に令和4年8月29 日付け準備書面(5)において反論をした。
そして、侵害論について当事事者が主張立証を尽くしたことを前提とし、令 和4年8月31日に行われたウェブ会議の方法による書面準備手続において、 裁判所から損害論に審理を進める旨の心証開示を受けて(令和4年8月31 日の書面準備手続の経過表には、協議の結果欄に、「当事者双方 侵害論につ いての主張立証は尽くした。」「裁判長 今後、損害論についての審理を進め る。」との記載がある。)、損害論の審理が進められ、令和5年9月22日に行 われた口頭弁論期日において、控訴人は他に主張立証することはない旨を陳 述し、原審口頭弁論が終結されて原判決が言い渡されたものである。 こうした原審での審理経過に鑑みると、当審における新たな無効理由の主 張は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたこ とについて控訴人には重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、 被控訴人から、予備的にではあるものの、当審において提出された無効理由についての反論がされており、これに対する控訴人の再反論の主張はなく当\n審の口頭弁論終結に至っていることから、この限度では訴訟の完結を遅延さ せることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとする。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2024.10.20
令和6(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年8月27日 知的財産高等裁判所
なお、再審請求の審決却下が取り消されても、再審の審理がなされるだけです。 再審理由には該当しないとの審決がなされると思います。
確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる (特許法171条1項)が、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審は、 その再審請求が不適法であって、その補正をすることができないものについ ては、審決をもってこれを却下することができる(特許法174条2項、1 35条)とされている。そこで、本件再審請求が、不適法であって、その補 正をすることができないものであるか検討する。
ア 原審決については、原告が原審決の取消しを求める訴えを提起すること なく、原告に対する原審決の謄本の送達があった日(令和5年10月14 日)から30日、すなわち同年11月13日が経過したので、同日の経過 をもって原審決が確定したものと認められる。 原告が本件再審請求をしたのは令和5年11月9日であるから、その時 点では、原審決は確定していなかった。しかし、本件再審請求に対する判 断として本件審決がされたのは令和6年1月23日であり(前記第2の1 (6))、同日の時点では原審決は確定していたものである。そうすると、本件 再審請求については、請求の時点では原審決が確定していなかったという 瑕疵があったが、本件審決がされた時点では原審決が確定していたから、 上記瑕疵は治癒されたというべきであり、上記瑕疵を理由として本件再審 請求を却下することはできないと解するのが相当である。
イ そして、本件再審請求の再審請求書(甲4の8)によれば、原告は、同 請求書において、特許法171条2項が準用する民事訴訟法338条1項 の再審事由を主張していたと認められる。これらの再審事由が認められる か否かは別として、本件再審請求について、再審事由の主張がないという 違法性はない。 その他、本件再審請求について、補正をすることができない違法な点が あるとは認められない。
ウ 以上によれば、本件再審請求は、不適法であって、その補正をすること ができないものには当たらないというべきである。
(2) そうすると、本件再審請求が、不適法であって、その補正をすることがで きないものであるとした本件審決の判断は誤りであり、原告主張の取消事由 は理由がある。
2024.10.20
令和6(行ケ)10014 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年10月16日 知的財産高等裁判所
(1) 原告は、本願発明は、エネルギー保存の法則に反するものの、そもそも 同法則や作用・反作用の法則のような「古典力学」には欠陥があり、本願発 明はそのような古典力学以外の自然法則に従っている旨主張する。
しかし、本願発明に関して本願明細書で説明されている、リニアモーター カーを等加速度運動させた際、空気抵抗がない等の理想状態であれば、運転 開始からt秒後の消費エネルギーE1が時刻tの一次関数となること(前記 第2の2(2)イ(イ)、(ウ))は、何ら立証されていない。原告が提出する甲2 によっても、「無反動推進機の試作品」なるものが動作する(前進する)こ とが判明するのみで、その消費電力や運動エネルギーの状況は全く分からず、 上記の古典力学以外の自然法則を証明するものとは到底いえない。
(2) かえって、本願明細書によれば、本願発明は、定格運転角速度からの減 速の際に余剰エネルギーを回収することによって発電するものであり(上記 第2の2(2)イ(カ)〜(ケ))、その原理は、定格運転速度で運動エネルギーが 「損失+発電機出力分消費エネルギー」よりも大きくなるという事象に基づ くものである(上記第2の2(2)イ(オ))。この事象は、(単位時間当たり の)消費電力が一定で一方向力Fを発生させることを前提としているが(上 記第2の2(2)イ(ア))、これについては本願明細書【0003】(上記第 2の2(2)イ(イ))に記載のように、
F:リニアモーターがレールに対して発生させる力
m:リニアモーターカーの車体重量
a:リニアモーターカーの加速度
とすると
F=ma
であるから、力Fが一定であれば加速度aも一定となるため、リニアモーターカーは運転開始時刻t=0から等加速度運動を始める。この場合の変位xは
x=1/2at²
と表される(乙18の21頁)。そして、運転開始からの消費電力(消費エ\nネルギー)E1は物体がされた仕事Wに等しいから、
E1=W=Fx=(ma)×(1/2at²)=1/2ma²t²
と表され(乙18の78頁)、一定の力Fを発生させるには、運転開始から\nの消費電力(消費エネルギー)E1を時間tの二次関数に従って増加させる 必要がある。したがって、(単位時間当たりの)消費電力が一定で一方向力 Fを発生させるという前提に誤りがあることは明らかである。
以上のとおり、本願発明はエネルギー保存の法則に反するものであるから、 特許法2条1項でいう「自然法則を利用した」ものではなく、特許法29条 1項柱書に規定される「発明」に該当しない。
(3) よって、発明該当性を否定した本件審決に判断の誤りはなく、原告主張 の取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(実施可能要件についての判断の誤り)について\n
上記1のとおり、本願発明は、自然法則に反するものであるから、当業者が 本願発明を実施できないことは明らかである。したがって、本願明細書の発明 の詳細な説明の記載は特許法36条4項1号の実施可能要件を欠く。\n
関連カテゴリー
>> 発明該当性
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2024.10.17
令和5(ネ)10111 不正競争行為差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和6年9月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
そこで検討すると、被告各製品の形態は、別紙「被告各製品の形態」記載 の構成aから構\成fまで(以下、単に「構成 a」などという。)のとおりで あり、これによると、被告各製品は、本件顕著な特徴を構成している特徴1) から特徴3)までとの対比において、左右一対の側木の2本脚であり、かつ、 座面板及び足置板が左右一対の側木の間に床面と平行に固定されており(特 徴1))、左右方向から見て、側木が床面から斜めに立ち上がっており、側木 の下端が脚木の前方先端の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面 に接していることによって、側木と脚木が約66度の鋭角による略L字型の 形状を形成している(特徴2))が、側木の内側に溝は形成されておらず、側 木の後方部分に、固定部材と結合してネジ止めするための円形状の穴が多数 形成され、座面板及び足置板を側木の間で支持する支持部材、支持部材を側 木の間において掛け渡された状態で側木に固定する固定部材及びネジ部材を 備え、2本の側木後方に設けられた穴と固定部材を結合した状態でネジ部材 を閉めることで、支持部材と固定部材によって側木を前後から挟持して押圧 し、支持部材を側木に固定しており(構成f)、原告らの商品等表\示の特徴 3)を備えていないものと認められる。
なお、その他の形態上の諸要素を考慮しても、被告各製品は、側木及び脚 木からなる2本脚、背板、座面板及び足置板、横木のほかネジ部材、支持部 材、固定部材等から構成され、脚木は一直線であるが、側木は一直線ではな\nく、側木の上端部分は床面と垂直に折れ曲がっており、2本脚が、正面視で 床面に垂直で相互に平行となるように配置され、側木と脚木の結合部分から 離れた脚木中央部に横木が配置され、中央部に楕円形の穴が形成されている 背板は側木の最上部に配置され、座面板と足置板は楕円形の短辺を切り落と したような曲線的形状とされ、ネジ部材、支持部材及び固定部材等により側 木に固定されていることから、被告各製品の形態においては、曲線的な要素 とともに、座面板及び足置板の支持部分に複数の部材が利用され、その安定 性が特徴的となっており、その印象も、原告製品における、直線的な形態が 際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象とは異なるものとなっている。 よって、原告製品全体の形態の特徴である本件顕著な特徴について、被告各 製品は、これを備えていないものと認められる。
(3) したがって、被告各製品は、本件顕著な特徴を備えていないから、取引の 実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づ く印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれ があるものということはできない。よって、原告らの商品等表示と被告各製\n品の形態が類似すると認めることはできない。
・・・
著作権法2条2項は、「美術の著作物」には「美術工芸品」を含むものとする旨規定しており、同項の美術工芸品は実用的な機能と切り離して独立の美的鑑賞の対象とすることができるようなものが想定されていると考えられるのであって、同項の規定は、それが例示規定であると解した場合でも、いわゆる応用美術に著作物性を認める場合の要件について前記のように解する一つの根拠となるというべきである。\n
(2) 以上を踏まえ、本件について検討すると、原告製品については、特徴1)か ら特徴3)まで及び側木と脚木をそれぞれ一直線とするデザインという本件顕 著な特徴があり、これにより原告製品の直線的な形態が際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象を与えるものとなっていると認められることは、 前記のとおりである。しかし、本件顕著な特徴は、2本脚の間に座面板及び 足置板がある点(特徴1))、側木と脚木とが略L字型の形状を構成する点\n(特徴2))、側木の内側に形成された溝に沿って座面板等をはめ込み固定す る点(特徴3))からなるものであって、そのいずれにおいても高さの調整が 可能な子供用椅子としての実用的な機能\そのものを実現するために可能な複\n数の選択肢の中から選択された特徴である。また、これらの特徴により全体 として実現されているのも椅子としての機能である。したがって、本件顕著\nな特徴は、原告製品の椅子としての機能から分離することが困難なものであ\nる。すなわち、本件顕著な特徴を備えた原告製品は、椅子の創作的表現とし\nて美感を起こさせるものではあっても、椅子としての実用的な機能を離れて\n独立の美的鑑賞の対象とすることができるような部分を有するということは できない。また、原告製品は、その製造・販売状況に照らすと、専ら美的鑑 賞目的で制作されたものと認めることもできない。それのみならず、仮に、 原告製品の本件顕著な特徴について、独立の美的鑑賞の対象となり得るよう な創作性があると考えたとしても、前記のとおり、被告各製品は、本件顕著 な特徴を備えていないから、原告製品の形態が表現する、直線的な形態が際\n立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象とは異なるものとなっているの であって、被告各製品から原告製品の表現上の本質的な特徴を直接感得する\nことはできない。そうすると、結局、本件において、著作権侵害は成立しないといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2024.10.17
令和6(ラ)10002 発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告 その他 令和6年10月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
プロバイダ責任制限法9条1項3号は、我が国の裁判所が発信者情報開示命 令の申立てについて管轄権を有する場合として、同項1号及び 2 号に掲げるも ののほか、日本において事業を行う者を相手方とする場合において、申立てが\n当該相手方の日本における業務に関するものであるときを定めている。
ところで、近年における情報流通の国際化の現状を考えると、インターネッ ト上の国境を越えた著作権侵害に対する司法的救済に支障が生じないよう適切 な対応が求められている。地域的・国際的にオープンな性格を有するインター ネット接続サービスの特性を踏まえると、当該サービスを提供する事業者の業 務が「日本における」ものか否かを形式的・硬直的に判断することは適切でな く、その利用の実情等に即した柔軟な解釈・適用が必要になると解される。 こうした点を踏まえて、以下具体的に検討する。
2 相手方が「日本において事業を行う者」といえるか
一件記録によれば、相手方は台湾に所在し、電気通信業を営む法人であるも のの、日本国内において、主に台湾からの旅行者のために国際ローミングサー ビスを提供しており、日本の空港等では日本から台湾への旅行者向けにSIM カードを販売していることが認められる。そうすると、相手方は、「日本におい て事業を行う者」に当たるということができる。
3 「申立てが当該相手方の日本における業務に関するもの」といえるか\n一件記録によれば、本件各投稿がされたサイトである「BOOTH」は、日 本語が使用される日本向けのサイトであって、相手方が台湾で提供するインタ ーネット接続サービスが、当該サイトのサーバに接続され、その結果、本件各 投稿がされたこと、本件各投稿のうちの一部の投稿(甲4の1)には、「お初の オリジナルTL漫画です。よろしくお願いします」、「追加支援のお方ありがと うございます。今後もよろしくお願いします。」との流ちょうな日本語による記 載があることが認められ、本件各投稿は、日本人向けに提供されているSIM カードその他の相手方の日本人向けサービスを利用して行われた可能性が高い\nといえる。
そして、上記のとおり、当裁判所は、相手方に対して反論等の提出を求めた ものの、期限を過ぎても相手方からの応答はなかったのであり、本件において、 上記判断を覆すに足りる証拠もない。 以上によると、本件各投稿は、実質的に見て日本に居住する日本人向けとし か考えられないようなインターネット接続サービスを利用して行われたといえ る。そのような場合に、あえて国内のプロバイダを経由することなく、外国に 業務の本拠を置くプロバイダが利用されたからといって、当該業務が「日本に おける」ものでないとして我が国の国際裁判管轄を否定するのは相当でない。 本件申立ては、「申\立てが当該相手方の日本における業務に関するもの」に当た るというべきである。
4 以上のとおり、本件申立ては、日本において事業を行う者を相手方とし、当該相手方の日本における事業に関する訴えであると認められるから、プロバイダ責任制限法9条1項3号により、日本の裁判所に国際裁判管轄があるというのが相当である。そうすると、国際裁判管轄がないことを理由に抗告人の本件申\立てを却下した原決定は相当ではなく、本件抗告は理由がある。よって、原決定を取り消し、原審において更に審理を尽くさせるため本件を東京地方裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり決定する。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2024.10. 4
令和6(ラ)10003 閲覧等の制限申立却下決定に対する即時抗告申\立事件 令和6年9月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
抗告人は、和解条項は一体不可分に結びついて初めて意味を持つものであり、 本件和解条項においてもその全体について営業秘密性を判断すべきであると主 張するので、この点を踏まえつつ、営業秘密が認められるための要件(不正競 争防止法2条6項所定の1)秘密管理性、2)有用性、3)非公知性)の充足の有無 につき、以下順次検討する。
(1) 秘密管理性について
一件記録によれば、抗告人は、本件和解条項について、抗告人が定める秘 密管理規程上の「秘」情報と位置づけ、抗告人の代表取締役及び常勤監査役\n並びに抗告人の法務部門に属する者のみがアクセスすることができるように 制限を付し、これらの者が第三者に開示又は漏洩することを禁止して、一体 的に管理していることが認められる。 本件和解条項の一部につき、これと異なる扱いがされているような事情は 一切うかがわれず、以上によれば、抗告人は、本件和解条項の全部を、一体 不可分の秘密として管理しているものと認められる。
(2) 有用性について
一件記録によれば、抗告人は、本件和解条項を含む特許等紛争の和解条項 については、いかなる相手といかなる条件で和解の合意をするかという事業 方針に関わる有用な情報であるとの認識の下、和解条項全体として、上記(1) のような管理を行っていることが認められる。特に特許訴訟の帰趨は、知財 戦略に大きな影響を及ぼしたり、レピュテーションリスクにつながりかねな い機微が含まれる場合もあること、そうした影響を考慮しつつ、経営体とし ての和解に係る最終的な判断をするためには、和解条項全体を通じて検討す る必要があることを考えれば、抗告人の上記認識及び取扱いは首肯できるも のである。 以上によれば、本件和解条項は、その全体が、事業活動に有用な営業上の 情報に当たるものといえる。
(3) 非公知性について
本件和解条項は、いわゆる口外禁止条項を含むものであるところ、本件の 閲覧等制限等の申立ては、和解成立日から約1か月後に申\し立てられており その間に本件和解条項の閲覧等がされた事実は記録上確認できない。以上の 事実関係の下で、本件和解条項の全部又は一部が基本事件の当事者以外の者 に公然と知られるに至ったとは考えられない。よって、本件和解条項は、そ の全体につき、非公知性の要件を満たすと認められる。 基本事件原告は、和解条項に口外禁止条項があったとしても第三者からの 記録の閲覧申請は拒否することができない以上、非公知性を獲得することは\nあり得ないとの意見を述べるが、和解成立後速やかに閲覧等制限の申立てが\nされ、現に閲覧等が行われた事実も認められない本件において、上記意見は 採用できない。
(4) 以上によれば、本件和解条項は、その全体が不可分なものとして、営業秘 密に当たるというべきである。
2 裁判の公開原則との関係について
基本事件原告の意見は、民事訴訟法91条が憲法82条の裁判の公開原則に 由来するものであることを強調しているので、この点に関する当裁判所の考え を示しておく。 まず、憲法82条1項が裁判の公開を求めているのは、裁判の「対審」と「判 決」であるところ、「対審」とは、民事訴訟における口頭弁論手続及び刑事訴訟 における公判手続を指し、本件和解の手続が行われた弁論準備手続が当然に含 まれるわけではないし、訴訟上の和解が「判決」と異なり、公開の法廷で言い 渡すような性質のものでないことはいうまでもない。 そもそも、民事訴訟においては、私的自治の原則の反映として、訴訟物たる 権利関係を当事者に委ねる処分権主義が採用されており、当事者の自律的解決 を尊重することが求められている。本件の基本事件において、基本事件原告と 基本事件被告(抗告人)は、公開の要請が働く判決の手続ではなく、訴訟上の和解という非公開の手続による終局的な解決を選択するとともに、口外禁止条 項を合意し、本件和解条項に係る情報の流出、漏洩を防止しようとしているの である。それにもかかわらず、民事訴訟法91条1項の手続によって、和解条 項が第三者に閲覧されてしまうとすれば、上記のような和解を決断した当事者 の意図・期待に反する結果となることは明らかである。このような場合に、和 解条項の全部につき閲覧等制限決定をすることは、民事訴訟の基本原則である 処分権主義、当事者の自律的解決尊重の要請に沿うものであって、裁判の公開 の原則と何ら抵触するものではない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 営業秘密
>> ピックアップ対象
2024.09.24
平成26(ワ)12570 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年1月31日 大阪地方裁判所
使用済みのトナーカートリッジに、インクを詰めたリサイクル品の製造・販売等が,不正競争防止法の品質等誤認惹起行為に該当するとともに、商標権侵害となると判断されました。被告は、販売時に、RFIDをリセットすることで、トナー交換メッセージが表示されるのを解除していましたが、これにともない「シテイノトナーガソ\ウチャクサレテイマス」との表示がなされるようになり、これが品質誤認等に該当するとの判断です。\n
ア 被告は,経済常識によれば,原告京セラDSがリサイクル品を指定,すなわ ちお墨付きを与えることはあり得ないことから,需要者は,被告商品を原告プリン ターに装着したときにディスプレイに現れる「シテイノトナー」を原告京セラDS の主張するような意味に理解することはないと主張するが,原告京セラDSがいか なる場合にも他社の安価なリサイクル品を指定トナーとすることはあり得ないと断 定する根拠はないのであるから,当該表示が「誤認させるような表\示」であること は免れないというべきである。
イ 被告は,被告商品がリサイクル品であることが明らかとなるよう純正品であ ることを否定する打ち消し表示がされていること,プリンターメーカーの純正リサ\nイクル品であればその旨の表示があるはずであるのにそのような表\示がないこと, また,そもそも需要者はリサイクル品と純正品とを区別して購入しているものであ ること等を指摘し,本件指定表示が,「誤認させるような表\示」ではない旨主張する。 上記第2の2(3)ウのとおり,被告商品の包装や外箱には,被告商品がリサイクル 品であることが理解できる記載がされているが,プリンターメーカーが新品の純正 品だけでなく,リサイクル品を販売している例もあるし(甲10の1ないし3),プ リンターメーカーが定める品質が,プリンターメーカー以外が製造するリサイクル 品においてあり得ないとまで断定できない以上,需要者が,被告商品を原告プリン ターに装着することによりディスプレイに現れる本件指定表示によって,被告商品\nの品質,内容について誤認するおそれを完全に否定することはできない。そして, この点は,被告商品を原告らとは関係のない業者が製造したリサイクル品と明確に 認識して購入した需要者であっても同様であって,被告の上記主張は採用できない。
ウ 被告は,ステータスページのトナー残量を表示させるためRFIDをリセッ\nトすると,これに連動して本件指定表示が現れるようにする原告純正品にされた設\n定は,不正競争防止法の問題を生じさせるようあえて設定されたものであって,競 争者に対する取引妨害を禁止する独占禁止法の趣旨に反するとし,被告商品による 不正競争該当性を否定すべきである旨主張する。 確かに,原告純正品についてなされた設定が,使用済み原告純正品のカートリッ ジを再利用してリサイクル品とする場合に,商品として競争力を減殺するものであ れば独占禁止法上問題とされる余地はあると考えられる。しかし,そもそも,RF IDをリセットしない原告純正品のリサイクル品であっても,トナー残量が不足し てきた場合には,プリンターのディスプレイには,「トナーガスクナクナリマシタ」, 「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示がされ,業務上支障がないよう配慮さ\nれているのであるから,プリントする必要があるステータスページのトナー残量が 表示できるようRFIDのリセットをしなければ,原告純正品のリサイクル品の製\n造販売が阻害されるような前提でいう被告の主張は,その点で採用し難い。 また,原告純正品のステータスページにおけるトナー残量表示は,規定量の充填\nされた新品の「シテイノトナー」を前提に,各印刷物のドット量等から使用量を計 算するなどして表示しているというのであるから(弁論の全趣旨),そもそも原告京\nセラDSにおいて規定量が充填されているか否かを確認できないトナーカートリッ ジを前提にRFIDをリセットして使用することは想定されておらず,そのリセッ トを自由にさせるよう求めることになる被告の主張はこの点でも採用できない。 したがって,原告純正品にされた,本件指定表示とステータスページを関連づけ\nた設定が独占禁止法の趣旨に反する旨の被告の主張は採用できない。
・・・
(1) 被告商品2には,トナーカートリッジの底面に本件商標が付されており,そ の表示態様は,被告商品2において,商品の出所を識別表\示させるものといえる。 そして被告商品2は,本件商標の指定商品であるトナーカートリッジであるから, 被告商品2を製造販売する行為は,本件商標権の侵害行為を構成するといえる。\n
(2) これに対し,被告は,被告商品2には,原告らが流通に置いた商品であり, かつ,リサイクル品であることが一見して明らかな表示を幾重にも施しているから,\n需要者が被告商品2の出所を原告京セラ又はそのグループ会社であると誤認するこ とはあり得ないとして,被告の行為は本件商標権侵害の違法性を欠く旨主張する。 確かに,上記第2の2(3)ウ(ア)のとおり,被告商品2の本体及び梱包した箱には, 被告商品2がリサイクル品であることが明示されていることが認められる。また, 箱の中に入れられている,「ご使用前の注意」と題する書面,「リサイクルカートリ ッジトラブル調査票」によっても,被告商品2がリサイクル品であることは明らか にされていることも認められる。 しかしながら,被告商品2の本体には,製造元等の記載は全く存在しないから, 本体に付された上記のような表示ラベルだけでは,本件商品2の本体に付された本\n件商標の出所表示機能\を打ち消す表示として十\分なものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 誤認・混同
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.09.24
令和5(行ケ)10107 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年8月28日 知的財産高等裁判所
ウ 以上を踏まえ、相違点1について検討する。前記(2)のとおり、甲1発明 において、「加熱コイルを収容するケース」は、「コア10とソールプレ\nート26」から構成されるものと認められるところ、このうち「ソ\ールプ レート26」は、「アセンブリの底部に適用され、溶接されるべき非金属 複合アセンブリに含まれる金属サセプタに、コイルによって発生した渦電 流を印加するために設けられる」(甲1文献・訳文3頁)ものとされてい ることからすると、「ソールプレート26」は、コイルを収容するケース\nとしてコイルと加熱対象物との間に置かれ、コイルによって発生した磁束 を加熱対象物である金属サセプタに届かせるため、当該磁束を通過させる 材料で構成されているものと理解される。そして、前記の誘導加熱の原理\nからすると、電気絶縁性の非磁性材は、磁束に何ら影響を与えることなく、 磁束を通過させる性質を有するものであり、前記各文献によれば、電気絶 縁性の非磁性材の構成材料としてはセラミックや樹脂があったことが周知\nであったと認められる。 そうすると、甲1発明の「ケース」を構成する「コア10とソ\ールプレ ート26」のうち「ソールプレート26」について、磁束を通過させる性\n質を有する電気絶縁性の非磁性材として周知のセラミック又は樹脂を選択 し、「コア10と電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂」で構成され\nる「ケース」とすることは、当業者にとって容易想到であったというべき である。
エ この点に関し、被告は、本件発明1に係る特許請求の範囲の請求項1の 記載によれば「ケースの全て」や「ケースの一部」などの解釈がされる余 地はなく、本件審決は、フェライト材料又は粉末鉄で作られたコアを請求 項1のケースの構成に置き換えられるかを判断しているだけであるなどと\n主張する。 しかしながら、前記(1)のとおり、本件発明1に係る特許請求の範囲の請 求項1には「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加\n熱コイルを収容するケース」と記載されているにとどまるから、ケースの 構成が前記の要素「のみ」からなるものに限定されるものと解することは困難である。\nよって、被告の主張は前提となる本件発明1の特許請求の範囲の解釈を 異にしており、これを採用することはできない。
(5) 小括
以上によれば、本件発明1と甲1発明の相違点1については容易想到であ ったというべきであり、相違点2から4までについては、前記のとおり進歩 性は否定されるから、結局、本件発明1は、甲1発明に基づいて出願前に当 業者が容易に発明することができたとものと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2024.09.24
令和6(行ケ)10030 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年9月11日 知的財産高等裁判所
(1) 原告は、「遠隔シャンパン」の語は、キャバレークラブ、ホストクラブな どの特定の店舗のキャスト(接待するスタッフ等)等に対して、ゲストが実 際に店舗に来店しなくても、シャンパン等をプレゼントとして贈る行為を意 味し、著名な「シャンパン」とは意味合いが異なると主張する。 しかし、原告提出の証拠(原告が提供するアプリケーションを紹介するウ ェブサイト(甲3)、検索エンジンにおける「遠隔シャンパン」の検索結果 (甲4))によっても、「遠隔シャンパン」が原告の主張する意味で用いら れる例があることは認められるが、一般的に認識されているとまでは認めら れないし、生産地域、製造方法や品質等が厳格に管理された発泡性ぶどう酒 のみに使用することができるものとしてフランスで組織的に管理されてきた 著名な「シャンパン」の名称を、それ以外の商品や役務を示す名称の一部と して利用していることに変わりはない。原告主張の「遠隔シャンパン」の意 味自体、著名性かつ顧客吸引力を有する「シャンパン」の存在を前提とする ものと解され、本願商標の構成からは、「エンカクシャンパン」以外に、カ\nタカナ部分に基づき「シャンパン」の称呼及び概念が生ずることを否定する ことはできない。 原告は、いわゆる夜の接客業において「シャンパン」という言葉には「祝 杯や祝福の象徴」という意味合いがあり、単に酒類の名称を意味するもので はないとも主張するが、原告が提出したインターネット記事(甲5)は、酒類である「シャンパン」が「祝杯や祝福の象徴とされ」ると説明しているに すぎない。その他、原告の主張を裏付ける証拠はない。
(2) 原告は、「シャンパン」の文字を含む登録商標がなお存在し、フランスの 関係機関等からの無効審判請求等がない時点において、国際信義に反すると 評価することは、抽象的な危険を理由に私人の事業活動を著しく制限するも のとなり、産業の発展に寄与するという商標法の法目的に反すると主張する。 しかし、前記1の認定判断は、現時点で「シャンパン」の文字を含む登録 商標がほかに存在することや、(商標登録前であるから当然であるが)本願 商標についてフランスの関係機関等から未だ登録異議の申立てや、無効審判\n請求等がなされていないことによって左右されるものではないから、原告の 主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.09.24
令和5(行ケ)10124 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年9月11日 知的財産高等裁判所
a 変更フラグについて
変更フラグは、動きベクトル候補を示すリストを変更するための制 御情報であり(【0203】、【0205】、【0207】)、変更フ ラグによって動きベクトル候補が変更される場合に、結果として動き ベクトル候補の数が変更される場合があること自体は認められる(図 46〜図48)。また、時間動きベクトル候補はtemporal1つ しか存在しないため、時間動きベクトル候補だけが変更されると、必ず 動きベクトル候補の数が変更されるといえる(図46、図47)。 しかし、変更フラグをオンにすることは、変更後の動きベクトル候補 を示すリストを符号化して送信することにとどまるのであり(【020 3】、【0205】)、動きベクトルの数を制御情報として送信するこ とは本件明細書等に記載されていない。また、本件明細書等においてリ スト変更の具体的態様を制限する記載はなく、空間動きベクトル候補 はMV_A、MV_B、MV_C、medianの4つがある(【01 83】、【0184】、【0193】)ため、各々が候補に加わる、又 は候補から外れることにより、空間動きベクトル候補だけが変更され る場合には、空間動きベクトル候補の数は変更される場合と変更されない場合があるから、「変更フラグ」オンは、候補ベクトル数が変わる 場合と変わらない場合を含んでいることになる。そうすると、「変更フ ラグ」に係る制御情報は、動きベクトル候補の数の変更を目的とするも のと理解することはできず、変更フラグは、「動きベクトル候補の数を 変更するための制御情報」に当たらない。
b 閾値Th及び最大ベクトル数について
閾値は、本件明細書【0111】、【0139】によれば、「この場 合、例えば、複数のベクトル候補のうち、閾値Th以下の評価値SAD になる候補の全てを使用して予測画像を生成する方法が考えられる。」\nとあることから、予測画像の生成に使用する動きベクトル候補を選定\nするための設定値である。予測に用いるベクトルの本数は、評価値SA\nDが閾値Th以下となる候補ベクトルの本数となるが、評価値は符号 化対象となるブロックの各候補ベクトルについて算出されるものであ るから(【0068】、【0076】、【0077】、【0079】〜 【0081】、【0089】)、閾値を定めても、符号化対象となるブ ロックが具体的に特定されなければ、「動きベクトル候補の数」が変更 されたか否かは特定できない。そうすると、「閾値Th」に係る制御情 報は、ベクトル数の変更に関与する情報ではあるが、変更に結果的、間 接的に寄与するものにすぎず、動きベクトル候補の数の変更を目的と するものと解することはできないから、「動きベクトル候補の数を変更 するための制御情報」に該当しない。
また、本件明細書【0111】、【0139】によれば、最大ベクト ル数についても、「閾値Th以下の候補の全てを使用するのではなく、 スライスヘッダなどに、予め使用する最大ベクトル数を定めておき、評\n価値の小さい候補から最大ベクトル数分用いて予測画像を生成するよ\nうに」するというもので、予測画像の生成に使用する動きベクトル候補\nを選定するための設定値という点で閾値Thと同様であるから、「最大 ベクトル数」を定めても、符号化対象となるブロックが具体的に特定さ れ評価値が計算されない限り「動きベクトル候補の数」が変更されたか 否かは特定できない。そうすると、「最大ベクトル数」に係る制御情報 は、ベクトル数の変更に関与する情報ではあるが、変更に結果的、間接 的に寄与するものにすぎず、動きベクトル候補の数の変更を目的とす るものと解することはできないから、「動きベクトル候補の数を変更す るための制御情報」に該当しない。
さらに、最大ベクトル数について言及する本件明細書【0111】、 【0139】は、実施の形態1における画像符号化及び復号処理の変形 例である実施の形態2、3について記載したものである。実施の形態1 における復号処理(本件明細書【0086】〜【0093】、特に【0 089】)に【0111】、【0139】の「最大ベクトル数」を定め ておく方法を適用した場合、予め定められた候補ベクトルを全て復号\nし、評価値の小さい候補から最大ベクトル数分を用いて予測画像を生\n成することになる。その場合、動きベクトルの選択のために、インデッ クス情報を用いる(【0143】)のではなく、評価値と最大ベクトル 数をもとに選択した候補ベクトルを用いることになる。他方、本件明細 書中、インデックス情報を用いる実施の形態4、その変形例である実施 の形態6、7に関し、最大ベクトル数に関する記載はない。そうすると、 最大ベクトル数の使用に関する本件明細書の記載は、「動きベクトル候 補」が「当該インデックス情報に基づき選択される」ことを発明特定事 項とする本件発明に関わるものではないというほかない。原告は、実施 の形態6、7が実施の形態2、3の上位互換の関係に当たる旨主張する が、両者は別個の技術というべきであり、採用できない。
(イ) 以上によれば、本件明細書における「変更フラグ」、「閾値Th」及び 「最大ベクトル数」は、いずれも「動きベクトル候補の数を変更するため の制御情報」に該当せず、本件明細書等において、他に上記情報に該当す る情報に関する記載は見当たらない。 したがって、「当該インデックス情報に基づき選択される動きベクト ル候補の数を変更するための制御情報」との事項は、本件明細書等に記 載された事項ではない。訂正事項2による訂正は、本件明細書等に記載 のない事項を更に限定する訂正事項を含むものであるから、本件明細書 等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和6(ネ)10014 投稿削除及び損害賠償の請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和6年8月8日 知的財産高等裁判所(原審・東京地裁 令和4年(ワ)13396号)
3 争点4(不法行為の成否)について
(1) 被控訴人の主張 被控訴人は、控訴人による本件投稿が被控訴人に対する不法行為に当たる理由と して、不競法2条1項20号及び21号に該当する旨を主張する。これらのうち、前 者は本件投稿により控訴人の提供する役務の品質を誤認させて被控訴人の信用が毀 損された旨を、後者は本件投稿により被控訴人の信用が毀損された旨を、それぞれ 主張するものと解される。しかし、前者すなわち品質誤認を理由とする点について は、本件投稿は、控訴人の役務の質を誤認させるような表示に当たるとは認められ\nないから、これを不法行為に当たるということはできない。
(2) 信用毀損による不法行為について
本件投稿は、「被控訴人は、何度やり取りしても、控訴人担当者からの質問に明確に回答しない」、「被控訴人は、やり取りに際して、相手方の権限を確認した」、「被 控訴人は、「なんで答える必要あるの?」と、合理的な理由を示すことなく、質問へ の回答を拒否した」、「XDでモックを作成したのに、違うものが出来上がり、XD に合わせるには別料金が必要で、それが明らかに金額が高い」、「被控訴人が納品し た成果物は、仕様を満たさず、使用に耐えないものであった」等の事実を摘示し、ま た、控訴人の意見又は論評として、「引くに引けない状況で、この高額見積もりは、 守銭奴ビジネスとしては正解なのかも知れないが、人としてはどうなのかと思いま した。」、「いい勉強になりました。」と述べているものと認められる。 本件投稿のうち、事実を摘示する部分については、本件サイト(ランサーズ)を閲 覧する者の普通の注意と読み方とを基準とすると、被控訴人の社会的評価を低下さ せるものといえる。しかし、本件サイトは、社会において有用性のあるサービスとし て運営されている、インターネット上での個人間又は個人と法人との間での請負契 約に係るマッチングサイトであって、そこでされる投稿は、本件サイトを通じて契 約の申込みや締結等を行う者にとって、その相手方がどのような仕事をするか等の\n参考に供されるものであるから、そのような参考に供されるべき投稿の内容は公共 の利害に関するものであるとともに、目的の公益性が認められるというべきところ、 本件投稿につき特段これに反する事情はうかがわれない。そして、上記1で認定説 示したところに加え、控訴人は、本件サイネージ案件に関し、被控訴人に対して38 万円を支払ったのに十分な成果物を得られず(甲15、乙7、8、12)、被控訴人\nからは改修に要するとして合計40万9223円の見積りを提示され(甲21、乙 9)、結局は別業者に依頼して案件を完成させたこと(乙10の1・2)等、証拠上 認められる事実関係に照らすと、本件投稿により摘示された事実は、重要な部分に ついて真実であると認められる。
なお、被控訴人が、本件投稿部分1中の「なんで答える必要あるの?」との文言をそのまま記載し、又は発話した事実はないところ、同文言は、閲覧者において、やや 投げ遣りな感じを抱かせる言葉遣いであるといえる。しかし、前記1(1)ア(イ)のと おり、被控訴人は、控訴人担当者等からの複数回にわたる確認に対して、合理的な理 由を示すことなく、質問への回答を拒否し続けた状態であったことから、控訴人に おいて、このような被控訴人の対応を要約して同文言を使用したものであったこと に照らすと、本件投稿における同文言の記載をもって、いまだ不法行為が成立する ものと認めることはできない。 また、本件投稿のうち、意見又は論評にわたる部分については、「守銭奴ビジネ ス」との記載にやや穏当を欠く点があることは否定できないものの、既に認定説示 した事実経過等に照らし、いまだ意見又は論評としての域を逸脱したものとまでは 認められない。
(3) まとめ
以上によると、控訴人が本件投稿をしたことが、被控訴人に対する不法行為に当 たるということはできない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和5(行ケ)10128等 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年8月8日 知的財産高等裁判所
ア 以上のとおり、被告は、平成26年頃、サクラグループに対して本件ライセ ンス契約の解除を求め、令和2年頃には、本件ライセンス契約終了後はサクラグル ープとライセンスビジネスを継続する意思がないことを示し、全ての商標権の返還 を求めるなどした。これに対し、原告は、サクラグループから本件商標D〜Gに係 る商標権の移転を受けて、本件ライセンス契約の最終盤期である令和2年頃から、 日本、韓国、中国、台湾等で、「Mark Gonzales」、「(what it isNt)」等の文字列やエンジェルのデザインを含む商標の登録出願を多数行い、本件ライセンス契約が終 了したことが明白である令和4年1月1日以降も、ライセンシーを通じて「Mark Gonzales」やエンジェルが付された商品を販売等している。しかし、上記にみたと おり、原告は、MPSA契約によってエンジェル1、2及び本件サインの著作権を 取得したとはいえないし、本件ライセンス契約は事実上MPSA契約の内容を更改 することを含むものである。仮にMPSA契約がいまだ有効であるとしても、同契 約上、原告に許容されているのは本件アルバムの宣伝目的で、かつ、Tシャツ等へ のカバーアートの複製と被告等の氏名の使用にとどまっているのに、原告が現在行 っている「(what it isNt)」ブランドの展開は、本件アルバムの宣伝目的の範囲内や、カバーアートの複製の範囲を越えるものである。しかも、原告は、本件ライセ ンス契約の終了後、被告が自ら展開する日本国内のサブライセンシーや販売店に警 告書を送付するなどして、被告のブランド展開を阻止しようとしている。
このような令和2年以降の原告の動きからすると、原告は、本件商標A〜Cを出 願した時点(令和2年12月26日及び令和3年6月30日)において、原告等と 被告との紛争が顕在化し、本件ライセンス契約が終了した後はエンジェル1、2や 被告の名称が使用できなくなることを十分了知しながら、これらの商標の登録を得\nた後は、商標権に基づき、被告が自ら日本国内で展開するエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた商品の販売等の差止めを求めるなどして、原告等以外の 者がこれらの商品を販売することを妨害、阻止する不正の目的、意図を有していた と認められる。
そうすると、このような原告の本件商標A〜Cの登録出願は、商標登録出願について先願主義を採用している我が国の法制度を前提としても、「商標を保護するこ とにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に 寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同法1条)に反 し、公正な商標秩序を乱すものというべきであり、かつ、健全な法感情に照らし条 理上も許されないというべきであるから、本件商標A〜Cは、商標法4条1項7号 の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきで ある。
イ 原告は、MPSA契約により原告がエンジェル1、2及び本件サインの著作 権を取得したと主張するが、同主張が採用できないことは前記(1)イのとおりであ る。
原告は、エンジェル1、2及び本件サインには本件ライセンス契約が適用されな いと主張し、その理由として、1)本件アルバム制作時と本件ライセンス契約の先後 関係、2)原告とサクラグループが別法人であること、3)被告はエンジェル1、2及 び本件サインについて100%の著作権を有していないこと等を挙げる。しかし、 1)につき、既に制作されたデザイン等を後に契約の対象とすることはあり得ること であり、契約が遅れてされたからといって対象に含まれないということにはならな い。2)につき、サクラグループの代表者が原告代表\者の妻であること、原告代表者\nが本件ライセンス契約の締結に関与していることは原告自らが認めていること(原 告代表者の陳述書(甲156))、サクラグループと原告とは、互いに本件商標D〜\nGの移転を繰り返しており、被告に関するビジネスの関係では一体的に活動してい るとみられることから、原告が、形式的にサクラグループと別法人であることを理由に、本件ライセンス契約上の義務等を免れようとすることは、信義則上、許され ないというべきである。3)につき、MPSA契約によりエンジェル1、2及び本件 サインの著作権が原告に移転していないことは前記のとおりであり、原告が提出す る他の証拠等によっても、本件ライセンス契約時に、被告が、エンジェル1、2及 び本件サインの使用を許諾する権限がなかったとは認められない。
原告は、本件商標Aについて、有効に存続する既存の商標の組合せにすぎないか ら、商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くということはあり得ないと主張する。 しかし、構成自体は既存の商標の組合せであっても、前記のとおり、原告は、不正\nな目的、意図をもって登録出願しているといえるから、同主張は採用できない。
原告は、契約の解釈の相違や権利関係の紛争等の私的領域の問題は、商標法4条 1項7号該当性の判断に際しては考慮されるべき事項ではないと主張する。しかし、 本件商標A〜Cに関していえば、前記のとおり、原告は、原告等と被告との紛争が 顕在化してから、本件ライセンス契約の終了を間近に控えていることを了知しなが ら、契約終了後も原告等以外の者がエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた 商品を販売することを妨害、阻止する意図をもって登録出願したといえるのであっ て、このような登録出願を新たに許容することは、商標制度について無用の混乱をもたらし、社会公共の利益にも反するというべきであるから、その背後に契約上の 解釈の相違や権利関係の紛争等、私的領域の問題があるとしても、公序良俗に反す る商標と認めることは妨げられない。
ウ したがって、本件商標A〜Cは、商標法4条1項7号に該当するというべき であるから、原告が主張する本件審決A〜Cの取消事由2には理由がない。
(3) 本件商標D〜Gについて(被告の主張する取消事由について)
ア これに対し、本件商標D〜Gについては、前記(1)イのとおり、MPSA契約 には明示されていないが、同契約の実質的当事者というべき被告は、目的が限定さ れているとはいえ、Tシャツ等にアルバムカバーアート等を複製して販売する権利 や、被告の氏名を使用する権利を原告に許諾していたのであるから、当該販売が国 内で円滑に行われるべく、原告が商標登録出願をすることを少なくとも黙認してい たと推認できるし、原告による本件商標F、Gの登録出願に承諾を与えている。そ うすると、この頃(平成14〜15年)にされたエンジェル2を構成とする本件商\n標D、E及び「MARK GONZALES」の文字列からなる本件商標F、G(指定商品は、D 及びGが第18類(かばん類等)、E及びFが第25類(洋服等))の各登録出願について、原告に不正の目的、意図等を認めることはできない。
前記(1)及び(2)のとおり、その後、本件ライセンス契約が締結され、その最終盤 期においては原告等と被告との間で紛争となり、原告が、不正の目的をもって商標 登録出願するなどの事態となったが、少なくとも、平成26年頃に被告が本件ライ センス契約上のロイヤリティの受領を拒むようになるまでは、サクラグループによ る被告に関連する商品のライセンス事業は円滑に進められていたとみられ、また、 被告も、結局は令和3年12月31日までのロイヤリティ又はロイヤリティ相当額 を受領している。そうすると、原告等と被告との紛争が深刻になったのは、被告が 原告等に対して、本件ライセンス契約を更新等する意思がないとし、全ての商標権 の返還を求めるようになった令和2年頃からというべきであり、その間、本件商標 D〜Gに関しては、登録後15年以上の間、契約に沿って、安定的に使用されてき たということができる。
そして、出願時に不正の目的、意図等が認められない商標についてライセンス契 約を締結し、その利用関係等を整理するのであれば、その契約の定めにより、契約 終了時に当該商標権をどのように取り扱うか等を規律することができるのであっ て、現実に、本件ライセンス契約11条においても、登録した権利の返却に関する 条項が設けられているところである。本来、商標法4条1項7号は、商標の構成自\n体に公序良俗違反がある場合に商標登録を認めない規定であって、商標の構成自体\nに公序良俗違反がないとして登録された商標について、例えば、社会通念の変化に よって、その構成が善良の風俗を害するおそれがある商標となるなど反公益的性格\nを帯びるようになっている場合、後発的に同号に該当し、同法46条1項6号の規定により無効とすべき場合がないとはいえない。しかし、本件商標D〜Gに関して いえば、原告等と被告との間で後発的に法的紛争が生じたのは、当事者間の契約の 解釈の相違や、商標の使用態様等によるものであって、その商標の構成自体が、社\n会的妥当性を欠くことになったものではなく、また、いまだ社会通念に照らして著 しく妥当性を欠き、反公益的性格を帯びるようになったというものでもなく、これ らは本来的には民事訴訟等により解決されるべきものである。
そうすると、本件商標D〜Gの査定登録時以降の事情を考慮したとしても、本件 商標D〜Gが、商標法4条1項7号に該当するに至ったということはできない。
イ 被告は、本件商標D〜Gについて本件ライセンス契約が適用され、原告はこ れらに係る商標権を被告に返還すべき義務があるのにこれを怠っていると主張す る。確かに、上記のとおり、本件ライセンス契約は、本件商標D〜Gをも念頭にお いて締結されたものと認められるが、商標権の移転登録義務があるのであれば、そ の履行を請求すべきであって、これを拒んでいるからといって登録に係る商標が公 序良俗に反するとなるものではない。
被告は、原告等が本件ライセンス契約に伴う信義則上の義務に違反して、被告の ライセンスビジネスを妨害しているとか、原告は、被告の信用等にフリーライドする目的を有していると主張する。確かに、前記のとおり、原告は、令和2年頃以降、 原告等と被告との紛争が顕在化した後、不正の目的をもって本件商標A〜Cを出願 し、原告等以外の者がエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた商品を販売等 することを妨害、阻止しようとし、また、本件商標D〜Gに係る商標権等により、 被告のサブライセンシーや販売店に警告書を送付した事実も認められる。しかし、 前記のとおり、本件ライセンス契約を締結した時点で、本件商標D〜Gは、関係者 間において何ら問題なく存続していたのであるから、契約終了後の帰属等について は契約で規律することができたはずであるし、不当な権利行使については、別途権 利の濫用や不正競争防止法等の規律により、またパブリシティ権の問題についても、 民事訴訟等で解決されるべき筋合いのものである。本件商標A〜Cの登録出願に不 正の目的があったからといって、原告が本件商標D〜Gについて商標権を保持し続 けることまでもが、商標法の目的に反して公正な商標秩序を乱すとか、健全な法感 情に照らし条理上も許されないということはできない。
ウ したがって、本件商標D〜Gが、商標法4条1項7号に該当するに至ったと いうことはできないから、被告が主張する本件審決D〜Gの取消事由には理由がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和4(ワ)9112等 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年8月22日 大阪地方裁判所
ア 上記本件明細書の記載からは、経糸、緯糸、パイル糸の「径」を認識する 方法は見当たらず、また、経糸又は緯糸の径がパイル糸の径よりも細くされ ることについての技術的意義に関する記述はない以上、そこから上記の「径」 を認識する方法を推測することもできない(原告は【0043】の記載を指 摘するが、パイル糸に「多数の微細長繊維を含ませる」ことと、基布の経糸 又は緯糸の繊度(太さ・細さ)との関係は不明というほかない。)から、これ らは当業者の理解する技術常識によって決すべきこととなる。 イ この点、繊維の形態的な太さは、一般的にその断面が不規則な形状を示し ているので、正確な計測は困難であり、したがって、一定の長さ当たりの重 量で繊維の太さが示されているとされ、また断面の形状にあっては、天然繊 維の形状は、それぞれ特有の形をしており、化学繊維は、その形状も人為的 に自由につくることができ、断面は主として紡績方法によって決まり、円形・ だ円形その他複雑なものもある、とされている(乙4。三訂版「繊維」(昭和 61年刊行))。
また、繊維における細さ(繊度)にはいろいろの表し方があり、メートル\n法の番手(1グラムの糸が何メートルの長さを持つかを示すもの。番手が大 きいほど糸は細い。)や、デニール、テックス(いずれも一定長の糸の重量) が用いられ、デニールと繊維ごとの比重を用いて断面積を算出する方法もあ る(乙5。「繊維の科学」(昭和53年刊行))。撚りの強さによっても見た目 の太さが変わる(乙6。令和2年当時のウェブサイト。)。本件明細書におい ても、パイル糸の繊度に関し、デニールが用いられている部分がある。
ウ ところで、「径」の字義は、「1)さしわたし。直径。2)みち。小道。近道。」 というものである(乙7(広辞林第六版))。また、広辞苑第七版においては、 「まっすぐ結ぶ道。さしわたし。」とされており、「差渡し(さしわたし)」の 字義は、「1)さしわたすこと。一方から他方へかけ渡すこと。また、その長さ。 2)直径。わたり。けい。」とされている。これらを踏まえると、「径」とは「直 径」を意味するものと解される。「直径」の字義は、「円または球の中心を通っ て円周または球面上に両端をもつ線分。また、その長さ。さしわたし。」とい うものであるから(広辞苑第七版)、「直径」が認識されるためには、平面に おいては円又はそれに近い形状のものが想定されていると解される。 他方、前記のとおり、糸は繊維の集合体であって、繊維の断面は一般的に 不規則な形状を示すものであるから、少なくとも、「径」の大小の比較に、「断 面積」(空隙を除外するかどうかを問わない)を用いることはできないものと 解される。この点、原告は、糸の太さを断面積で表すことが当業者にとって\n一般的な手法となっていたとしてその旨の証拠(甲25から27まで)を提 出するが、それらは口輪筋線維、等方性黒鉛材料の気孔、血管について画像解析により断面積を測定した例にすぎず、技術分野が全く異なるもので、原告主張の事実は認めるに足りない。
(3) 構成要件1Cの充足の検討\n
ア 原告は、各糸の径は糸の断面積を測定することにより比較判断することが 可能であり、かつこれを製品状態で測定すべきものとした上で、かかる測定\n方法を採用した測定結果を証拠(甲19の1・2)として提出する。 この測定は、被告製品のシール材に対し、接着剤を滴下して浸み込ませ、 乾燥後、養生テープで固定し、パイル糸の配列方向に対し垂直となるように、 シール材に金尺を当てて、カット治具である剃刀刃を沿わせて一回のスライ スにより切断し、断面画像を撮像した上、該画像を解析して、緯糸とパイル 糸の断面積を求めるというものである。 イ しかし、本件訂正発明1の構成要件1Cは、糸の「径」の大小をその要素\nとしており、糸の太さの比較に断面積を用いることは文言の一義的な意味に 反し、また前述の当業者の技術常識にも合致しないものである。
また、具体的な測定手段をみても、上記測定は、被告製品を加工、破壊し た上で測定するものであって、原告が自らいう「製品状態での測定」とも前 提を異にするものである(そもそも、製品状態では糸に様々な方向から様々 な力が作用し、一定の「断面積」を得ることは困難であると考えられ、「製品 状態での測定」という前提自体、本件明細書や当業者の技術常識から導き得 るのかについて疑問なしとしない。)。加えて、上記切断方法は、繊維の方向 に垂直に正確に切断されることが保証されるものともいえず、切断角度、切 断箇所の違いによる断面積の変化が何ら考慮されていないと見受けられ、測 定の条件統制にも疑義がある。画像解析についても、糸(及びこれを構成す\nる繊維)の外郭のとらえ方や、空隙の有無等によって「断面積」が異なり得 ることが見て取れる。
これらのことからすると、甲19号証の1・2に示された測定手段は、画 像の作成過程、画像解析の双方において、測定の正確性、合理性が担保され たものとはいえないというべきである。 また、画像解析の結果報告される糸の断面(空隙を含む外郭)は、不定形 で円又はそれに近い形状を備えておらず、かかる画像から、「径」(といえる もの)を認識することも困難である。
ウ そうすると、甲19号証の1・2によって、被告製品について構成要件1\nCの充足が立証されたということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠 はない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和5(行ケ)10104 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年8月28日 知的財産高等裁判所
ア 技術常識1
ある種の物質をある温度(臨界温度)以下に冷やしたときに、抵抗値がゼロとなることを「超伝導」又は「超電導」ということ。
イ 技術常識2
2つの超伝導体を弱く結合したときに、電子対がトンネル効果によっ てその結合部を通過する現象を「ジョセフソン効果」といい、ジョセフ\nソン効果が生じるように2つの超伝導体を薄い絶縁膜で隔てるなどして\n弱く結合するようにしたものを「ジョセフソン接合」ということ。\n
(2) 前記2のとおり、本願発明は、本願層構造をとる「第1のELR導体」と\n「第2のELR導体」の間に「バリア材料」を配置して、「ジョセフソン接\n合」又は「ジョセフソン接合を含む回路」を構\成する発明であるから、前記 (1)の技術常識を踏まえると、本願発明においては、1)「第1のELR導体」 と「第2のELR導体」がいずれも超伝導状態、すなわち抵抗値がゼロの状 態にあり、かつ2)「バリア材料」にジョセフソン効果によるトンネル電流が\n流れていることとなる。
そうすると、本願明細書等の記載が実施可能要件を満たすというためには、\n本願明細書等に前記1)及び2)の各事項が記載されている必要があるというべ きである。
そして、前記1)の事項については、本願明細書等には本願発明の様々な実 施例とその試験結果が記載されているが、それらのいずれからも各実施例に おける導体の抵抗値がゼロとなったことを読み取ることはできず、本願発明 の「第1のELR導体」と「第2のELR導体」が超伝導状態にあることを 示す試験結果等は記載されていない。前記2)の事項については、本願発明の 「第1のELR導体」と「第2のELR導体」の間に配置された「バリア材 料」にジョセフソン電流が流れる旨の段落【0223】の記載は、超伝導状\n態にない導体の間に配置されたバリア材料にジョセフソン効果が発現すると\nいう前記技術常識2に反する内容であり、このような現象が生じ得ることを 裏付ける試験結果等が記載されていなければ、当業者は本願発明を実施する ことができると認識するものではないところ、前記「バリア材料」にジョセ フソン電流が流れることを示す試験結果等は記載されていない。したがって、\n本願明細書等に前記1)及び2)の各事項が記載されているといえないことは、 本件審決が認定するとおりである。
4 原告の主張に対する判断
(1) これに対し、原告は、以下のとおり、本願発明のELR導体又はその一部 が超伝導状態となっている旨主張するので、以下検討する。 ア まず、原告は、本願発明の第1のELR導体に含まれる修飾ELR材料 の臨界温度が150Kを超える旨主張する。 しかし、当業者が実施し得る程度にその構造、組成等が明らかであっ\nて、150Kを超える温度において超伝導状態すなわち抵抗値がゼロで あるELR材料は、本願明細書等に開示されていない。
イ 次に、原告は、本願明細書等で説明される抵抗現象、平均抵抗、おおよ その抵抗率、抵抗値等の表現が抵抗率を意味することを当業者は直ちに理解する、図14A〜図14AGが示す抵抗/抵抗率の急激な変化は、\n本願発明の材料が非超伝導状態から超伝導状態に変化することを示す、本願発明において超伝導状態のELR材料は0Ω・cmから3.36×10−8Ω・cmの範囲の抵抗率を有すると特定したと主張する。
しかし、抵抗率ρは「ρ=RS/L」の式(S:物質の断面積、L:長さ、 R:抵抗値)で表され(甲16〜18)、抵抗値Rと抵抗率ρの関係は\n物質の断面積Sと長さLに応じて変化するから、抵抗値Rと抵抗率ρは区 別されるものである。確かに、断面積S及び長さLの値が一定であれば、 抵抗値Rは抵抗率ρと正比例するから、抵抗値Rが減少するときは、抵 抗率ρも減少しているという関係にあるが、抵抗値と抵抗率の定義が異 なる以上、図14A〜図14Gが示す「抵抗値」をもって、本願発明の ELR材料が3.36×10−8Ω・cm以下の範囲の「抵抗率」を有す ると当業者が理解することはできない。
また、いずれにせよ、超伝導状態とは抵抗値がゼロの状態であり(技術 常識1)、その場合は抵抗率もゼロとなるが、本願発明の材料の抵抗値 がゼロとなった試験結果等が記載されていないことは、前記のとおりで ある。
図14A〜図14Gが示す抵抗の急激な変化が本願発明の材料が非超伝 導状態から超伝導状態に変化することを示すとの点については、裏付け となる試験結果等は本願明細書等に記載されていない(なお、段落【0 057】には、前記各図の「離散ステップ 1410」とされるもの以外につ いてであるが、部分的な超伝導状態以外の要因によって生じる可能性が\n記載されている。)。
ウ 原告は、さらに、改良ELR材料のサンプルの一部が非超伝導状態から 超伝導状態へ超伝導遷移することを実証した、A博士の宣誓書(甲19) もこれを支持すると主張する。しかし、改良ELR材料のサンプルの一部が非超伝導状態から超伝導状態へ超伝導遷移することが試験結果等により裏付けられたものでないこ とは前記のとおりであり、A博士の宣誓書(甲19)の内容をみても、 原告の主張を裏付けるに足りる具体的根拠は記載されていない。
仮に「改良ELR材料のサンプルの一部が非超伝導状態から超伝導状態 へ超伝導遷移」するとしても、本願発明はそのような「超伝導状態のサ ンプルの一部」を取り出して「第1のELR導体」、「第2のELR導 体」とするものではなく(その具体的方法も本件明細書等に記載されて いない。)、ELR導体そのものは超伝導体ではない(したがって、技 術常識2に照らすと、ジョセフソン接合を実施することはできない。)。\n
エ 以上によれば、本願発明のELR導体又はその一部が超伝導状態となっ ている旨の原告の主張は、採用することができない。 (2) 原告は、本願発明の「ジョセフソン接合」は従来技術の「ジョセフソ\ン接 合」を超えるものであり、ELR導体が超伝導体でなくともジョセフソン効\n果が発生している旨主張する。
しかし、超伝導状態にない導体の間に配置されたバリア材料にジョセフソ\nン効果が発現するというのは前記技術常識2に反する内容であり、このよう な現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等が本願明細書等に記載されてい ないことは、既に述べたとおりである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和5(行ケ)10053 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年6月24日 知的財産高等裁判所
1 取消事由1、2(引用文献1に基づく新規性、進歩性の判断の誤り)について 原告らが取消事由1、2を通じて主張するところの眼目は、1)引用文献1に は「自立CNTペリクル膜」の発明が記載されているとはいえない、2)引用発明 1には本件発明のRB0.4以上事項の記載がないところ、これらに係る本件発 明1との相違点は実質的なものであり、かつ、引用発明1にRB0.4以上事項 を持ち込むことは容易想到ともいえないという2点に集約される。 当裁判所は、1)に係る原告らの主張は採用できないが、2)の主張は理由があ るものと判断する。以下に詳説する。
・・・
(3) RB0.4以上事項の有無は実質的相違点か
ア 本件決定が認定した本件発明1と引用発明1の相違点1A(別紙3「本 件決定の理由」1(2)アの[相違点1A])の中には「引用発明1ではRB0. 4以上事項の構成が明らかでない」点が含まれているところ、本件決定は、\nこのRB0.4以上事項の有無に係る相違点は実質的な相違点ではないと判 断した。
イ しかし、引用文献1には、RBの数値を特定する記載は一切なく、その示 唆もない。また、CNT膜の面内配向性をRBによって特定すること自体も、 引用文献1その他の出願時の文献に記載されていたと認めることはできず、 技術常識であったということもできない。
ウ 本件決定の上記アの判断は、RBの値が、0.40以上では面内配向して おり、0.40未満では面内配向していないことを表す旨の本件明細書等\nの記載(【0104】)から、本件発明1のRB0.4以上事項が、CNT のバンドルが面内配向していることを特定するものであり、引用発明1は 面内配向しているものを想定しているから、RB0.4以上事項を満たすこ とになるとの理解に基づくものと解される。 しかし、本件発明1の特許請求の範囲に照らすと、CNTバンドルが面内配向しているという定性的構成(構\成1C)と、RB0.4以上事項とい うパラメータによる定量的構成(構\成1D)は独立の構成となっており、本\n件明細書の【0104】等の記載を踏まえても、引用発明1のCNTバンド ルが面内配向の特性を有しているからといって、RB0.4以上事項を当然 に満たすと判断することはできない。
エ 被告は、通常の発想のもとで、通常の性状のSWCNT及び通常用いら れるプロセスで製造された薄膜自立無秩序SWCNTシートであれば、膜 厚、バンドル径及び自立性のいずれの観点においても、本件明細書等にお ける比較例1よりは実施例1に相当程度似通っているといえる上、比較例 1のRBの値(0.353)がRB0.4以上事項の下限である0.4に相 当程度近いこと等を考慮すれば、比較例1よりも実施例1に相当程度似通 っている薄膜自立無秩序SWCNTシートであれば、RB0.4以上事項を 満たしている旨主張する。
しかし、被告の主張する「通常の発想のもとで、通常の性状のSWCNT 及び通常用いられるプロセスで製造された」との薄膜自立無秩序SWCN Tシートの製造方法や、当該薄膜自立無秩序SWCNTシートの「膜厚、バンドル径及び自立性」について具体的に特定する主張立証はされておらず、 したがって、「比較例1よりも実施例1に相当程度似通っている薄膜自立 無秩序SWCNTシート」の内容も明らかではないというよりほかない。 かえって、原告ら提出に係る甲40によれば、原告らが引用文献2記載 の方法で作製したCNT自立膜(サンプル1、2)ではそれぞれRBが−0. 38、−0.26であったのに対し、本件発明の完成当時に製造されたCN T自立膜では1.04だったのであり、薄膜自立無秩序SWCNTシート であれば、RB0.4以上事項を満たしているともいえない。
被告は、甲40について、1)RB測定サンプルの保管が実際にどのような 条件で行われていたか確認できず、サンプルの実在も確認できない、2)本 件明細書等に記載された実施例及び比較例と実験条件が異なる、3)当該各 RB測定サンプルは、特性が位置的にみて不均一となっている、4)RB0. 4以上事項を満たさないとされるサンプル1、2は一部破損がみられるか ら自立膜とみられないなどと論難するが、1)については、サンプル1、2は 平成29年4月の開発時に作製したものと推認され、2)については、甲4 0は、「面内配向していてRBが0.4未満の膜が存在するかどうか」の点 を検証する実験であるから本件明細書等の実施例及び比較例の条件によら ねばならないものではない。また、3)については、もともとRBの測定方法 は局所的な断面に対するものであり、RB0.4以上事項は、少なくとも一 つの断面で0.4未満以上となることを意味するのであるから、被告主張 の点をもって甲40に基づく上記判断は左右されない。さらに、4)につい ては、甲40では、サンプル1、2について製造過程で一部破損があったとしても、自立膜となったものを測定しているのであるから、やはり被告の 主張は採用できない。
(4) 以上のとおりであって、本件決定には、RB0.4以上事項を含む相違点1 Aが実質的なものであることを看過し、引用発明1に基づき本件発明1、3 〜5が新規性を欠くとした誤りがあり、取消事由1は理由がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和5(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年6月27日 知的財産高等裁判所
「登録を通じて」と「登録を通じずに」で、処理が異なる場合には技術的意義があると認定できる場合もあると思いますが、何か別の意図があったのでしょうか。 ちなみに分割出願もありません。
(1) 本願発明の認定について
ア 構成要件Dの「登録を通じてまたは登録を通じずに」の技術的意義について\n本願発明における「カラー反射率画像とOCTデータコンテンツ」の「結合」に おいて、本願明細書には、「カラー反射率画像とOCTデータコンテンツ」が同じ光 路を共有して取得され固有的登録がもたらされる形態では、「登録」するための追加 の処理が必要ではなく(【0035】、【0058】)、一方で、代替的アプローチである前記光路が共有されていない形態では「登録」を行うこと(【0059】、【0065】)が記載されているところ、前者の形態が本願発明の「登録を通じずに」に、後 者の形態が「登録を通じて」に、それぞれ該当する形態であると認められる。
そうすると、引用発明の特定事項が、少なくとも「前記カラー反射率画像とOC Tデータコンテンツとを結合すること」を満たすのであれば、そのような特定事項 は「登録を通じてまたは登録を通じずに」のいずれか一方を必ず満たすものといえ る。したがって、「登録を通じてまたは登録を通じずに」の有無により本願発明の特定 事項は実質的に何も変わらないとした本件審決の認定は、原告主張のように本願明 細書を拡張して行われたものとはいえず、誤りがあるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和3(ワ)1720 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年4月22日 大阪地方裁判所
(2) 相当な実施料率について
ア 該当技術分野における実施料率の状況
本件において、本件発明1の実施許諾契約の実例を認めるに足りる証拠は ないところ、証拠(甲43)によれば、アンケート結果による技術分類別ロ イヤルティ料率の平均値のうち、電気の技術分類では、平均2.9%、最大 値9.5%、最小値0.5%であること、日本の司法決定によるロイヤルテ ィ料率のうち、電気分野の平成9年から平成20年の累計は、平均値3.5%、 中央値3.0%、最高値8.0%であり、平成16年から平成20年は、平 均値3.0%、最大値7.0%、最小値1.0%であることが認められる。
イ 本件発明1の技術的意義等
本件明細書1によれば、従来の非水電解質二次電池は、作製が困難である という課題があったことに対し、本件発明1は、正極側及び負極側において、 電池外装体の外方に配置されるとともに外部接続端子に接続される端子接 続部材、及び、活物質未塗工部と端子接続部材とを接続する集電接続板とを 備え、集電接続板は、発電要素の端部から中央方向に水平に延びるとともに 端子接続部材と接続される本体部と、同本体部から突設されて、活物質未塗 工部の外側面のうちの端部と活物質塗工部との間に、表面が接合される接続\n板部とを有する構成をとることにより、作製を容易にすることができる電池\nを提供することを目的とし、かかる効果を奏する発明である(【0006】、 【0008】ないし【0010】)。
また、証拠(甲37)及び弁論の全趣旨によれば、本件発明1が端子接続 部材と集電接続板の本体部の構成を備えている技術的意義は、電池外装体の\n内外において、外部接続端子と集電接続板の接続板部との間の距離を長くす ることができるようになり、外部接続端子に加えられるトルクや衝撃を接続 板部と発電要素の活物質未塗工部との接合部分に伝わりにくくすることが 可能となり、当該接合部分を損傷させたり、当該接合部分での接合が外れた\nりすることを防止できることにあることが認められる。これらの事実関係に 照らすと、本件発明1は、電池製作を容易にし、電池の耐久性を高めること に資する電池に関する発明であることが認められる。
そして、被告が代替技術として指摘をする公開特許公報(乙66ないし69)は、いずれも発電要素からの集電を容易にする集電体を形成する構成を開示しているものの、本\n件発明1に係る構成要件B2及びC2(活物質未塗工部の端部と活物質塗工\n部との間に、表面が接合される接続板部とを有する構\成)や構成要件A4(電\n池外装体の外方に配置されるとともに外部接続端子に接続される端子接続 部材)に相当する構成を開示するものではないことから、本件発明1の代替\n手段であるとは認められず、その他これを認めるに足りる証拠はない(なお、 被告は、被告製品1及び3は、周知技術を用いているだけで本件発明1を用 いているわけではない旨を主張し、その証拠(乙75ないし82)を提出す るが、被告製品1及び3が本件発明1の技術的範囲に属し、本件発明1に無 効理由は存在しないことは、前判示のとおりであって、該主張は実質的に侵 害論を蒸し返すものにほかならず、かつ、約一年間をかけてされた損害論の 審理の終盤にされたものであるから、民訴法157条に基づき、時機に後れ た攻撃防御方法として却下することとする。)。
一方、本件発明1は、電池の機能に直接的に資するものではなく、また、\n被告製品1は蓄電システムであるところ、蓄電システムにおいて電池の占め る価格割合は、家庭用蓄電システムでは約65.6%であること(甲47)、 被告製品3は電池パックであり、電池はその一部を構成するものであること\nから、本件発明1が被告製品1及び3の売上げに占める貢献の程度は、その 限りにおいて限定的である。
ウ その他の事情
原告と被告は競合関係にあること、原告と被告は紛争関係にあることに加 え、本件においては、被告は、確定した文書提出命令によって提出を命じら れた文書の提出を拒み、原告は被告製品1及び3の正確な売上高の開示を受 けることができなかったことが当裁判所に顕著であるところ、この事情は、 実施許諾に当たり特許権者が実施権者の正確な販売数量、利益等を把握でき ないリスクに相当するものであって、実施料の算定にあたり考慮されるべき (上振れさせる)要因に当たるものというべきである。
エ 小括
上記アからウに述べた事情その他本件に表れた事情を総合考慮すると、本\n件発明1の実施に対して受けるべき料率としては「●(省略)●」を相当と 認める。これに沿わない原告及び被告の主張は、上記説示に照らし、いずれ も採用することができない。
(3) 実施料相当額の損害
本件特許権1の侵害による実施料相当額の損害は、(1)の金額に(2)の料率を 乗じた4億4250万円となる。 該当特許は以下です https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5713127/15/ja https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6493463/15/ja
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和4(ワ)19400 不正競争 民事訴訟 令和6年5月14日 東京地方裁判所
少し気になるのは、この訴訟ではなく、仮処分の提訴にかかった弁護士費用を全額認めている点です(55万円)。同じ理由で、著作権侵害がなされている場合の発信者情報開示手続きの弁護士費用も認められるのでしょうか?
1 争点1(本件情報の営業秘密該当性)について
前提事実(2)アないしウのとおり、原告においては、権限を有しない者が本 件情報にアクセスすることが物理的に困難な態様で管理されており、かつ、本 件情報にアクセスする権限を持つ者は限定されていたものであり、また、原告 は、FF社との間で秘密保持契約を締結した上で、FF社に対し、本件情報に アクセスすることができるナビタンを貸与していたところ、FF社においても、 ナビタンを操作することにより受信契約者の情報にアクセスできる従業員の範 囲を限定し、同従業員に開示する受信契約者の情報の範囲を必要な限度に絞る ことが徹底されていた上、ナビタンの操作状況は高い頻度で保存され、従業員 による受信契約者の情報へのアクセスの状況を監視できるようにしており、ま た、業務終了後は施錠したロッカーでナビタンを保管することで、物理的にも ナビタンへの不正なアクセスを防止しており、情報の流出を防ぐ対策が十分に\n行われていたものである。さらに、前提事実(2)エのとおり、FF社において は、Biを含むFF社の従業員に対し、採用時に、情報の適切な管理に関する 研修を実施して、Biは、同社に対し、本件情報を含む営業上知り得た情報を 第三者に開示しない旨の誓約書を提出していたものである。これらの事実に照 らすと、本件情報は、客観的に秘密として管理されていると認識できる状態に あったと認められ、秘密管理性の要件を満たすといえる。加えて、弁論の全趣旨によれば、本件情報の内容は公表されていないと認められるから、非公知性の要件を満たし、また、その内容は原告との契約の種別を含む顧客情報であると認められ、客観的に有用であるといえるから、有用性の要件も満たす。したがって、本件情報は、不競法2条6項の「営業秘密」に該当する。\n
・・・
4 争点4(原告の損害の発生の有無及び損害額)について
(1) 本件取得行為による損害について
前提事実(2)オ及びカの経緯並びに前記2で認定した事実に照らせば、被 告は、Biによる営業秘密不正開示行為を知りながら、本件取得行為に及ん だものであるから、故意の不正競争行為により原告の営業上の利益を侵害し たといえる。
そして、本件取得行為がなければ、原告は、本件仮処分申立てをすること\nもなく、これに伴い弁護士費用を支出することもなかったといえ、この支出 に係る原告の損害は、通常の損害であるといえるから、原告が本件仮処分申\n立手続のために支払った弁護士費用55万円は、本件取得行為と相当因果関 係のある損害であると認められる。
これに対して、被告は、原告が本件仮処分申立てをする必要はなかったか\nら、本件仮処分申立手続のために支払った弁護士費用は本件取得行為と相当\n因果関係のある損害とはいえないと主張する。しかし、前提事実(2)キの本件動画の内容及び本件動画がアップロードされた際に本件動画に付されたタイトル並びに本件業務妨害行為における被告の言動に照らすと、少なくとも被告が本件情報を自ら又は第三者をして開示するおそれがあったと認めるのが相当であり、原告が本件仮処分申立てをす\nる必要はなかったとの被告の主張は採用できない。 また、被告は、原告が支払った着手金は高額にすぎるから、本件取得行為 と相当因果関係の認められる損害額は、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬 基準に沿って24万5000円とすべきであるなどと主張する。 しかし、上記報酬基準が廃止された後は弁護士や事案の性質によって着手 金の額が異なり得ることは、当裁判所に顕著な事実である上、55万円とい う着手金の金額が上記報酬基準に照らして相当性を逸脱するほどに高額であ るとまではいい難いことから、被告の指摘する事情は相当因果関係を否定す るには足りず、被告の上記主張は採用できないというべきである。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和5(ネ)10101 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年6月18日 知的財産高等裁判所 (原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)24476
オ 上記ウ及びエによれば、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題 として記載されている従来技術(特許文献1)は、出願時の従来技術に照 らして客観的に不十分であるから、乙3に記載されている技術的事項を参\n酌することが許されるというべきである。 そうすると、本件発明は、上記課題を解決するために「覚醒度合生体情 報取得部で取得した人の覚醒度合に関する生体情報に応じて前記三つの 発光手段の発光量の総和を略一定にしたままそれぞれの発光手段の発光 量比を変化させるための調節部」との構成を採用したものであるが、他方、\n乙3には、上記エのとおり、「覚醒度合生体情報取得部で取得した人の覚醒 度合に関する生体情報に応じて複数(二つ)の発光手段の発光量の総和を 一定としたままそれぞれの発光手段の発光量比を変化させるための調節 部」が開示されており、その相違は「三つの発光手段の発光量の総和」か 「複数(二つ)の発光手段の発光量の総和」かの差でしかない。 したがって、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいとはい えず、本件発明の本質的部分は、特許請求の範囲に近接したものとなると いうべきであり、具体的には、本件特許の課題を解決するために採用され た構成が構\成要件C/Dであることから、「覚醒度合生体情報取得部で取 得した人の覚醒度合に関する生体情報に応じて、赤色、青色及び緑色の三つの発光手段の発光量の総和を略一定としたままそれぞれの発光手段の 発光量比を変化させるための調節部」を有していることが本件発明の本質 的部分であると解するのが相当である。
これに対し、本件各照明装置は、「覚醒度合生体情報取得部で取得した人 の覚醒度合に関する生体情報に応じて、赤色、青色及び緑色の三つの発光 手段の発光量の総和を略一定としたままそれぞれの発光手段の発光量比 を変化させるための調節部」を有していないから、本件発明と本件各照明 装置とは本質的な部分において異なっているというべきである。
カ 上記アないしオによれば、本件各照明装置が本件発明の本質的部分を備 えているとはいえず、均等の第1要件を満たさない。
キ 控訴人は、前記第2の5(1)アのとおり、本件発明は、ヒト(人)の覚醒度 合に応じて照度を略一定にしつつ色温度を変化させる点がその本質的部 分であると主張する。 しかし、上記オに説示したとおり、特許発明の貢献の程度は従来技術と 比較して大きいとはいえないから、控訴人が主張するようにこれを上位概 念化することはできないというべきであり、控訴人の上記主張を採用することはできない。また、仮に、控訴人の主張するとおり、人の覚醒度合に応じて照度を略 一定にしつつ色温度を変化させる点が本件発明の本質的部分であると解 したとしても、本件各照明装置は、人の覚醒度合に応じて照度を略一定に しつつ色温度を変化させる構成を有していないから、均等の第1要件を満\nたさないとの結論を左右しない。
すなわち、本件マットレス(1)は、当該マットレスを使用する人の睡眠の 状態を計測する機能を備えており、本件発明の構\成要件B(「人の覚醒度合 に関する生体情報を取得する覚醒度合生体情報取得部と、」)を充足するも のであり、本件マットレス連携アプリは、本件マットレス(1)を使用した人 の睡眠深度、睡眠スコア、睡眠効率、寝つき時間、中途覚醒回数、目覚め の状態及び深い睡眠を表示する機能\を備えているが(原判決第2の2(6)ア 及びウ、同(7))、本件各照明装置は、本件マットレス(1)等により取得された 人の覚醒度合に関する生体情報に応じて照度を略一定にしつつ発光手段 の発光量比又は色・温度を変化させる機能を有していない。\n
本件各照明装置の使用者が、任意に本件各照明装置の発光手段の色・温 度を変化させる操作をすることが可能であるとしても、そのことをもって、\n本件各照明装置が人の覚醒度合に応じて照度を略一定にしつつ発光手段 の発光量比又は色・温度を変化させる構成を有していることにはならない。\nしたがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
ク 以上によれば、本件各照明装置は、均等の第1要件を充足しないから、 その余の要件について判断するまでもなく、本件発明と均等なものとして、 その技術的範囲に属するということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2024.09.16
令和5(ネ)10053 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年7月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所(原審・東京地方裁判所令和2(ワ)17104号)
(1) 特許法102条2項の適用の可否について
ア 特許法102条2項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、 その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権 者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。 同項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵 害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、 同項の適用が認められると解すべきである(知財高裁平成24年(ネ)第10015号同25年2月1日特別部判決、知財高裁平成30年(ネ)第10063号令和 元年6月7日特別部判決)。
イ これを本件についてみると、1審原告の完全子会社(株式会社マネースクエア) はFX事業を提供しており、「トラリピ」という名称の原告サービスを提供している ところ、証拠(甲30)によると、トラリピとは、イフダン(新規と決済を同時に 発注する注文)に、リピート(注文を繰り返す機能)とトラップ(一度にまとめて\n発注できる仕組み)を搭載したFXの発注管理機能をいい、トラリピの専用機能\と して「決済トレール」(決済価格が値動きのトレンドを追いかけることで、利益の極 大化を狙う機能)があることが認められ、被告サービスと競合するものであるとい\nえる。そして、原告サービスを提供しているのは1審原告の完全子会社であって、 特許権者である1審原告とは別法人であるものの、1審原告は、原告子会社の株式 の100%を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をするこ とにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社で ある(甲33。以下、持株会社である1審原告と原告子会社を併せて「1審原告グ ループ」ともいう。)。そうすると、原告子会社は、1審原告のグループ会社として 持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであ り(甲24、27)、本件特許は原告ライセンス契約に含まれていないものの、これ は国際出願に伴う不都合を回避するためにそのような体裁とすべきであったことに よるものにとどまり、1審原告が原告子会社に本件発明の実施許諾をしていないこ とを意味するものとはいえないことも踏まえると、原告子会社が本件発明を実施し ているものといえ、1審原告グループは、本件特許権の侵害が問題とされている平 成29年7月から平成31年3月までの期間、持株会社である1審原告の管理及び 指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価 することができる。 したがって、1審原告グループにおいては、本件特許権の侵害行為である被告サ ービスの提供がなかったならば利益が得られたであろう事情があるといえる。
そして、1審原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、1審原 告は1審原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利 行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのよ うな立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利 行使をしているということができ、1審原告グループにおいて1審原告のほかに本 件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件につ いて、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたで あろうという事情が存在するものといえるから、特許法102条2項を適用するこ とができるというべきである。
ウ 1審被告の主張について
(ア) 1審被告は、1審原告が主張する「グループ全体として特許を保有・管理し、 グループ全体として特許を活用した事業を展開しているという実態」の内容は不明 瞭であると主張する。
しかしながら、上記イで説示するとおり、1審原告と原告子会社は、いわゆる純 粋持株会社と完全子会社の関係にあるところ、実際に持株会社制を採用する企業が 多数存在する実情にあること(甲32)、純粋持株会社と完全子会社は法人格が別で あるものの、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即し た課税の実現を目的としたグループ法人税制や支配従属関係にある二つ以上の企業 からなる企業集団を単一の組織体とみなして親会社が企業集団の財政状態、経営成 績、キャッシュフローの状況を総合的に報告するための連結財務諸表など、企業グ\nループを、親会社を中心とした経済的一体性に着目して捉える制度が採用されてい る実情があることも踏まえると、本件事実関係の下においては、1審原告の管理及 び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価 することができるから、1審被告の上記主張は理由がない。
(イ) 1審被告は、持株会社が特許権者であっても、事業会社も共有者として特許 権者となるか、又は専用実施権を設定したり、いわゆる独占的通常実施権を許諾することにより、当該事業会社自身が損害賠償請求の主体として、損害賠償を請求す ることによって、事業会社の損害賠償請求が認められないとする不都合は回避可能\nであるから、特許法102条2項の適用を認める必要はない旨を主張する。 しかしながら、前記のとおり、本件においては1審原告の管理及び指示の下でグ ループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができ る以上、1審被告の上記主張に係る事情は特許法102条2項の適用の妨げにはな るといえず、実施能力を有しないことにより得べかりし利益が存在しない等の個別\nの事情から生じるところは、推定覆滅の問題として考えるのが相当である。 そもそも1審被告の上記主張は、1審原告のほかに原告子会社が本件特許権の侵 害に係る損害賠償請求の主体として認めるべきかどうかの問題に関わる事情であっ て、本件における1審原告の本件特許権の侵害に係る損害賠償請求における特許法 102条2項の適用を否定すべきものとはいえない。
・・・
(3) 推定の覆滅について
ア 1審被告は、1)本件発明の技術的価値は乏しく、1審被告の利益に対する本 件発明の貢献は乏しいこと、2)1審原告はそもそも金融商品取引業者としての登録 を受けておらず、FX取引を業として行うことができなかったこと、3)本件発明と 代替性が認められる競合サービスが多数存在したこと、4)被告サービスにおいて一 定の売上げ及び利益を獲得できたのは、1審被告による格別の営業努力があったた めであることなどを、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張するので、以下におい て判断する。
イ 1)本件発明の技術的価値は乏しく、1審被告の利益に対する本件発明の貢献 は乏しいとの主張について 証拠(乙38)及び弁論の全趣旨によると、人気がある五大リピート系注文とし てトラリピ(原告子会社によるサービス)、ループ・イフダン、iサイクル注文(被 告サービス)、トライオートFX、オートレールが挙げられているところ、それぞれ のサービスの比較の項目として、取扱い通貨ペアの多さ、注文方法(指値・逆指値 か、成行注文か)、値幅・利益幅の設定の自由度、売買方向(同一通貨ペア・同一売 買方向・同一値幅の複数の注文ができるかなど)、ポジション数、自動損切の仕様、 手数料・スプレッドの金額、スワップ金利の多寡、トレール機能の有無、相場追尾\n機能の有無、スマホ対応の有無、独自コンテンツの有無などが挙げられており、こ\nれらがFX取引のサービスを利用する際の比較項目になるものと認められる。そし て、本件発明の内容は上記比較項目のうち「相場追尾機能」に相当するものと認め\nられるところ、「リピート系注文で最も大事なのが自動損切りの仕様です」、「サービ スの特徴が最も出るのがこの値幅と利益幅の設定方法」、「長期運用が基本となるリ ピート系注文で成績に直結するのがこの手数料とスプレッド」、「スワップ金利は長 期間ポジションを保持し続けるリピート系注文においては大きな収入源となります」 などと「自動損切りの仕様」「値幅と利益幅の設定方法」「手数料とスプレッド」「ス ワップ金利」を評価する記載がある一方、「相場追尾機能」についてはそれに類する\n記載はない。
そうすると、相場追尾機能をもってFX取引の利用者が重視する項目とまでは認\nめられず、被告サービスの使用の動機の形成に対する本件発明の寄与は限定的であ るというべきであるから、1審被告が被告サービスの使用により得た限界利益額に は、本件発明が寄与していない部分を含むものと認められる。 以上によると、同部分が含まれることは、本件推定の覆滅事由に該当するものと 認められる。
この点に関し、1審被告は、これに加えて、仮に本件発明が被告サービスの売上 げに寄与していると解するのであれば、被告サービスにおいて実施されていた1審 被告の各発明も被告サービスの売上げに貢献しており、当該各発明の寄与率により 1審被告の利益の額を按分すべきと主張するが、1審被告が主張する1審被告の各 発明が被告サービスの利益に具体的に寄与していたと認めるに足りる証拠はないか ら、1審被告の上記主張は採用できない。
・・・
カ 以上のとおり、市場において競合するサービスが存在していたこと、被告サ ービスの使用の動機の形成に対する本件発明の寄与は限定的であるというべきであ ること、1審被告が被告サービスの使用により得た限界利益額には、本件発明が寄 与していない部分を含むものといえることなどを総合考慮すると、1審被告の使用 動機の形成に対する本件発明の寄与割合は●割と認めるのが相当であり、上記寄与 割合を超える部分については、1審被告の限界利益額と1審原告の受けた損害額と の間に相当因果関係がないものと認められる。 したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるから、特許法 102条2項に基づく控訴人の損害額は、1審被告の限界利益額の●割に相当する 合計●●●●●●●●●円と認められる。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和2(ワ)17104
関連の侵害事件です(当事者が同じ)
◆平成28(ワ)21346
こちらは、原告被告が逆の侵害事件です。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.09. 2
令和5(ネ)10112 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和6年7月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上の各事情を総合すれば、控訴人が、控訴人商品の製造元を被控訴人 と表示し、控訴人商品の販売実績として実際よりも多い数値を表\示した品 質誤認表示によって、控訴人商品及び被控訴人商品の売上げに影響が及び、被控訴人の営業上の利益が侵害され、損害が発生したものと認められる。\nそして、控訴人の品質誤認表示による被控訴人の損害については、不正競争防止法5条2項が適用され、令和元年5月8日から令和5年4月30\n日までの期間において控訴人が控訴人表示によって受けた利益の額が被控訴人の受けた損害の額であると推定される。\n上記期間における控訴人の限界利益の額は1億2368万8021円 であると認められる(前提事実(4)。なお、被控訴人は、損害が発生した期 間を令和元年5月10日から令和5年4月30日と主張するが、この期間 としても限界利益の額は上記金額となる。)。この限界利益の額は、乙76 に基づくものであるが、乙76に記載された控訴人商品の売上日によれば、 上記限界利益のうち、令和4年2月2日(被控訴人の請求金額のうち49 28万円に対する遅延損害金の起算日)までに発生したものは6355万 9921円、同月3日以降に発生したものは6012万8100円となる。
イ 控訴人の主張について
控訴人は、前記第2の4(3)〔控訴人の主張〕アのとおり、被控訴人は控 訴人との取引終了後における被控訴人商品の販売実績を主張立証してお らず、被控訴人に売上減少等の逸失利益が生じているのか不明であるから、 損害額が不正競争防止法5条2項によって推定されるということはない と主張する。 しかし、被控訴人と控訴人との間の販売代理店契約が終了した後の被控 訴人商品の販売台数や売上高が明らかでないとしても、本件で認められる 前記アの各事情を総合すれば、控訴人が控訴人表示をしたことによって被控訴人の営業上の利益が侵害されたものと認定することができるという\nべきであり、被控訴人が上記販売台数や売上高を主張立証しないことをも って、被控訴人の利益が侵害されたと認められないことにはならず、その 他、上記認定を左右する事情は認められない。
また、控訴人は、前記第2の4(3)〔控訴人の主張〕イのとおり、被控訴 人商品には顧客吸引力はなく、控訴人ウェブページ上の記載によって、被 控訴人の販売実績の低下は生じないとか、仮に、被控訴人商品の売上げが 減少したとしても、それは被控訴人による一方的な出荷停止の必然的な結 果であり、控訴人が控訴人表示を掲載したこととの因果関係はないと主張する。\n
しかし、前記アのとおり、被控訴人商品は、被控訴人と控訴人が販売代 理店契約を締結していた時期において、長期にわたって一定程度の台数の 販売があり、ある程度の市場占有率を獲得していたのであって、被控訴人 商品についてこのような実績が形成されていたことからすれば、控訴人商 品の製造元が被控訴人であるとの表示及び控訴人商品の販売実績を実際よりも多い数値とした表\示を控訴人ウェブページに掲載し、控訴人商品の製造元及び販売実績に関する誤認混同を需要者に生じさせたことによっ て、被控訴人商品の売上げに影響が及んだと認められるのであり、これら の間に因果関係がないとは解されない。 したがって、控訴人の上記各主張は採用することができない。
(3) 推定の覆滅及び覆滅事由について
ア 不正競争防止法5条2項が適用されるためには、被侵害者に、侵害者に よる不正競争がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存 在することが必要と解されるから、そのような事情が認められない場合に は、同項による推定が覆滅されるものと解される。そして、同法2条1項 20号による不正競争においては、市場において競業他社が複数存在する 状況において、侵害者の品質誤認表示がなかったとした場合に、特定の被侵害者の売上げのみが増加するという定型的な関係を認めることは困難\nであるから、他の類型の不正競争の場合に比較して、推定の覆滅が広く認 められるべきであり、推定覆滅の事由としては、1)侵害者と被侵害者の業 務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)、2)市場における競合品 の存在及び被侵害者の市場占有率、3)侵害者の営業努力(ブランド力、宣 伝広告等)、4)侵害品の性能(機能\、デザイン等品質誤認表示以外の性能\) など、被侵害者の現実の損害が、侵害者の得た利益よりも少ない事情を考 慮すべきである。
イ 控訴人は、本件表示による被控訴人の損害につき、不正競争防止法5条2項による損害の推定が覆滅されると主張する。これに対し、被控訴人は、前記第2の4(3)〔被控訴人の主張〕ウ(ア)のとおり、控訴人は原審において不正競争防止法5条2項の損害の推定の覆滅の主張を撤回しており、当審における推定の覆滅の主張は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして、これを却下するよう申し立てている。
そこで検討するに、控訴人は、原審及び当審を通じ、第一次的には、被 控訴人に損害が発生したことを否認するとともに、損害が発生していると しても控訴人の行為によって生じたものではないとして、因果関係を否認 しており、不正競争防止法5条2項が適用されないとの主張もしていると 解されるが、原審で提出した令和5年2月9日付け「準備書面(兼求釈明 書)」と題する書面の第1の5の末尾(同書面6頁)において、「『抗弁事由』 というも『積極否認』というも、法定要件充足の主張・立証責任分配の問 題であり、どちらにせよ被告としてはこれを積極的に主張・立証する意思 であることに変わりはない。」と記載するなど、控訴人が原審で提出した準 備書面には、同項が適用されることを前提に、推定の覆滅を主張している ものと解される記載がある。原審で令和4年12月22日に行われた書面 による準備手続の協議について作成された経過表には、控訴人(第1審被告)の述べた内容として、準備書面(4)に主張した事実は、損害発生の否認 の理由であるとともに同項の推定を覆滅する事由である旨の記載がある
(当裁判所に顕著な事実)。
他方、原審で令和5年2月6日に行われた書面による準備手続の協議に ついて作成された経過表には、控訴人の述べた内容として、損害は発生していないので、被控訴人(第1審原告)の主張に対して覆滅事由は主張し\nていない旨の記載がある(当裁判所に顕著な事実)。 被控訴人が証拠として提出した、同日の協議に関して被控訴人代理人が 作成したものであるとする「期日報告書(7)」と題する書面(甲43)には、 覆滅事由については主張しない旨控訴人代理人が述べたことを示す記載 がある。 しかし、上記経過表は、口頭弁論期日又は弁論準備手続期日の期日調書と異なり、これに記載された当事者の陳述が法的効果を有することはない。\nまた、上記経過表及び上記甲43の書面のいずれにも、控訴人代理人が、同日以前における覆滅事由の主張を撤回すると述べた旨の記載は存在し\nない。 。 そして、上記甲43の記載によれば、控訴人代理人は、損害が発生して いるとの心証が開示されたら覆滅事由について主張したい旨述べ、受命裁 判官から、裁判所の心証次第で反論することは許されないと言われたのに 対し、それであれば覆滅事由については主張しないと述べたとされている。 そうすると、控訴人代理人としては、損害が発生していると認められるの であれば覆滅事由を主張したいとの考えを有しており、そのことを明らか にしていたと認められる。
さらに、前記令和5年2月9日付け「準備書面(兼求釈明書)」は、同月 6日の上記協議の後に提出されたものである。 これらの事情を総合すれば、控訴人代理人が、令和5年2月6日に行わ れた書面による準備手続の協議において、上記甲43の書面に記載された 内容の発言をしたとしても、控訴人が、原審において、不正競争防止法5 条2項による損害の推定の覆滅を主張していないとか、推定覆滅の主張を 撤回したということはできない。 そうすると、控訴人が当審でした推定覆滅の主張が、時機に後れて提出 した攻撃防御方法であるとは認められない。 また、控訴人は、当審において、令和6年4月11日付け準備書面(控 訴審第2)及び同年5月9日付け準備書面(控訴審第3)により推定覆滅 の主張をしているが、これらの準備書面が陳述された同月16日の第2回 口頭弁論期日において弁論が終結されているから(当裁判所に顕著な事 実)、上記各準備書面における推定覆滅の主張によって訴訟の完結が遅延 したとは認められない。以上によれば、控訴人が当審でした推定覆滅の主張が時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下を求める被控訴人の申立ては、理由がないからこれを却下する。\n
ウ 控訴人が推定覆滅の事由として主張するのは、前記第2の4(3)〔控訴人 の主張〕イの1)ないし9)(主張1)ないし9))である(令和6年4月11日 付け準備書面(控訴審第2)第1)。
そこで検討するに、主張5)及び6)に関し、まず、控訴人商品及び被控訴 人商品の市場においては、前記(2)アのとおり、複数の競業他社が存在し、 被控訴人商品はある程度の市場占有率を獲得していると認められるもの の、その市場占有率は高いとはいえないから、推定覆滅事由にあたると認 められる。 また、控訴人代表者は保育園業界との人脈を有しており、控訴人は、被控訴人との間で被控訴人商品に関する販売代理店契約を締結していた時\n期において、この人脈を生かすとともに、保育関係の研修会等において被 控訴人商品を展示するなどして、保育園に被控訴人商品を販売するための 営業努力を行い、保育園に対して被控訴人商品を販売していたと認められ る(乙36、39、71、弁論の全趣旨)。そして、このような営業努力は、 被控訴人と控訴人との販売代理店契約が終了し、控訴人がテクノウェーブ 製の控訴人商品を取り扱うようになった後も行われており、控訴人が、保 育関係の研修会等において控訴人商品を展示したこともある(乙40〜4 4、71、弁論の全趣旨)。これらの事実によれば、控訴人による控訴人商 品の販売先には保育園が含まれることが推認される。 以上によれば、控訴人による控訴人商品の販売については、控訴人の営 業努力もこれに寄与したと認められるのであって、品質誤認表示(控訴人表\示)のみによってその販売が達成されたとは認められないから、推定覆滅事由にあたると認められる。
もっとも、控訴人が控訴人商品の販売についてした営業努力については、 保育関係の研修会等における控訴人商品の展示以外には、その具体的内容 の主張立証があるとはいえない。また、控訴人が営業努力を行った相手で ある保育園等において、控訴人商品を購入するか否かの判断に当たり、控 訴人ウェブページに掲載された控訴人商品に関する情報を確認し、控訴人 表示を認識した可能\性があるから、控訴人の営業努力があったからといっ て、控訴人表示が控訴人商品及び被控訴人商品の売上げに影響を与えなかったと認められることにはならない。そして、主張1)ないし4)及び7)ないし9)は、覆滅事由に当たるとは認められず、その他、不正競争防止法5条2項の損害の推定を覆滅する事由の主張立証があるとは認められない。以上の事情を総合すると、控訴人表示による損害額の算定における推定覆滅の割合は、5割と認めるのが相当である。
(4) 前記(2)アのとおり、令和元年5月8日から令和5年4月30日までの期間 における控訴人の限界利益の金額は1億2368万8021円であり、この うち令和4年2月2日までに発生した分が6355万9921円、同月3日 以降に発生した分が6012万8100円であるところ、上記(3)ウのとおり、 控訴人表示による損害額の算定における推定覆滅の割合を5割と認めるのが相当であるから、控訴人表\示による被控訴人の損害の金額は、同月2日までにつき3177万9960円(小数点以下切り捨て)、同月3日以降につき3 006万4050円となる。 また、控訴人の品質誤認表示と相当因果関係のある弁護士費用は、令和4年2月2日までの品質誤認行為に係るものとして317万円、同月3日以降\nの品質誤認行為に係るものとして300万円を認めるのが相当である。
したがって、被控訴人は、控訴人に対し、不正競争防止法4条に基づく損 害賠償請求として、6801万4010円及びうち3494万9960円に 対する令和4年2月2日から、うち3306万4050円に対する令和5年 5月27日から、各支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅 延損害金を請求することができると認められる。 4 その他、当事者が主張する内容を検討しても、当審における上記認定判断(原 判決引用部分を含む。)は左右されない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.09. 2
令和6(行ケ)10009 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年6月18日 知的財産高等裁判所
前記1の認定事実によれば、本願商標の構成である「サプリ処方箋」は、サ\nプリメントの略である「サプリ」の語と「処方箋」の語とを組み合わせた語である。そして、本願商標の需要者は、一般の消費者であると認められるところ、 「サプリ処方箋」が「サプリ」の語と「処方箋」の語とを組み合わせたもので あることは、本願商標の取引者又は需要者が容易に認識できる事実であるとい うことができる。 「処方箋」は「医師が患者に与えるべき薬物の種類・量・服用法などを記した書類」を意味する語である。法令上も、医師が患者に対し治療上薬剤を調剤 して投与する必要があると認めた場合に、患者又は現にその看護に当たってい る者に対して処方箋を交付することとされ(医師法22条1項本文)、薬剤師は 医師等の処方箋によらなければ販売又は授与の目的で調剤してはならないとさ れており(薬剤師法23条1項)、「処方箋」の語は、医師が患者に与えるべき 薬物(医薬品)の種類・量・服用法等を記載した書類を指すものとして用いら れている。
しかし、一般的には、「処方箋」という語は、例えば「改革の処方箋」のよう に広く比喩的に使用される語であって(乙5)、「医師が患者に与えるべき薬物 (医薬品)の種類・量・服用法等を記載した書類」に限定して使用されるもの ではなく、現に、上記2(2)及び(3)の認定事実によれば、複数のウェブサイトや 新聞の記事において、医師又はそれ以外の者が、患者、顧客等に適切なサプリ メントの種類や量等を提示、提供することを「サプリメントを処方」、「サプリ メントの処方」あるいは「サプリを処方」と記載した例があり、医師又はそれ 以外の者がこのようなサプリメントの種類や量等の提示、提供に際して作成す る書面を「サプリメント処方箋」あるいは「サプリメントの処方箋」と記載した例があると認められる。 これらの事実によれば、本願商標の取引者又は需要者は、「サプリ処方箋」の 語が本願商標の指定商品及び指定役務のうち第35類役務群又は第44類役務 群に使用された場合には、患者、顧客等に適切なサプリメントの種類や量等を 記載した書類を一般的に指す名称であると認識するものといえ、原告が提供する役務を認識するとは認められない。 したがって、本願商標は、少なくとも本願の指定商品及び指定役務のうち第 35類役務群及び第44類役務群との関係において、自他識別力を有しておら ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商 標であると認められる。
4 原告の主張に対する判断
(1) 原告は、前記第3〔原告の主張〕(1)のとおり、本願商標の「サプリ処方箋」 の語は、本願商標の指定商品及び指定役務に関し、他で一般的に使用されて いるという実例はないことから、本願商標は造語であり、指定商品及び指定 役務との関係で識別性を有すると主張する。25 しかし、本願商標の「サプリ処方箋」が「サプリ」の語と「処方箋」の語 を組み合わせたものであること及び「サプリ」が「サプリメント」の略であ ることは、本願商標の取引者又は需要者が容易に認識し得る事実であるから、 本願商標の取引者又は需要者は、「サプリ処方箋」の語句から「サプリメント 処方箋」あるいは「サプリメントの処方箋」を連想し、「サプリメント」の「処 方」に関する書面であると認識するということができる。そして、上記2(2) 及び(3)のとおり、複数のウェブサイトや新聞の記事において、医師又はそれ 以外の者が、患者、顧客等に適切なサプリメントの種類や量等を提示、提供 することを「サプリメントを処方」、「サプリメントの処方」又は「サプリを 処方」と表現し、これに関して医師又はそれ以外の者が作成する書面を「サ\nプリメント処方箋」又は「サプリメントの処方箋」と表現している事実が認められることからすれば、本願商標の「サプリ処方箋」は、少なくとも本願\nの指定商品及び指定役務のうち、第35類役務群及び第44類役務群との関 係では、識別性を有するとは認められない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(2) 原告は、前記第3〔原告の主張〕(2)のとおり、「処方箋」はサプリメントのような健康食品で用いられる書類ではなく、「サプリ」と「処方箋」とは本来 的に結びつかない用語であり、「サプリメントの処方箋」との意味が生じたと しても、需要者はこれを造語として捉えるから、本願商標には識別性が認め られると主張する。 しかし、前記1及び3のとおり、「処方箋」の語は、本来「医師が患者に与えるべき薬物の種類・量・服用法などを記した書類」を意味する語であるが、 広く比喩的に用いられる語であって、現に医師以外の者が医薬品以外のもの に関して作成する書類についても使用されているものである。そして、栄養 補助食品であるサプリメントについては、医師又はそれ以外の者が、患者、 顧客等に適切なサプリメントの種類や量等を提示、提供することが想定され るのであって、この行為について「処方」の語を用いることがあり、かつ、 このようなサプリメントの種類、量等の提示、提供に際して作成される書類 を「処方箋」と称することがあると認められるから、「サプリ」と「処方箋」 が結びつくことのない語であるとはいえず、本願商標に識別性を認めること もできない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(3) 原告は、前記第3〔原告の主張〕(3)のとおり、少なくとも、本願商標の指 定商品及び指定役務のうち、第35類役務群については、本願商標が使用さ れたとしても識別性が認められると主張する。 しかし、第35類役務群には、「サプリメントの小売又は卸売の業務におい て行われる顧客に対する便益の提供」の役務が含まれており、前記3の説示に照らせば、本願商標の取引者又は需要者は、「サプリ処方箋」の語が上記役 務に使用された場合には、患者、顧客等に適切なサプリメントの種類や量等 を記載した書類を一般的に指す名称であると認識することは明らかであると いえ、原告が提供する役務を認識することはない。そうすると、仮に、第3 5類役務群のその余の役務の中に、「サプリ処方箋」の語が当該役務に使用された場合に、本願商標の取引者又は需要者が、患者、顧客等に適切なサプリ メントの種類や量等を記載した書類を一般的に指す名称であると認識すると はいえないものが含まれていたとしても、第35類役務群との関係において も本願商標が自他識別力を有しないとの結論は左右されない。
また、前記3のとおり、「サプリメントを処方」、「サプリメントの処方」、「サプリを処方」、「サプリメントの処方箋」及び「サプリメント処方箋」と の語句が、サプリメントという商品に関し、一般の消費者に含まれる患者や 顧客に適切なサプリメントの量などの情報を提供することに関連して使用さ れる例があると認められること、サプリメントは栄養補助食品であって、「加 工食料品」、「食餌療法用飲料」及び「食餌療法用食品」とは同一ではないものの、加工して製造される食品である点、あるいは栄養面に配慮した食品で ある点で類似した面を有していること、医師が上記情報提供に際して「サプ リメントの処方箋」と称される書類を作成することがあることが認められ、 これらの事実によれば、第35類役務群のその余の役務(前記第2の1(1)イ) についても、「サプリ処方箋」の語がこれに使用された場合には、本願商標の 取引者又は需要者は、患者、顧客等に適切なサプリメントの種類や量等を記 載した書類を一般的に指す名称であると認識すると解され、原告が提供する 役務を認識するとは認められない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2024.09. 2
令和4(ワ)11921 特許権侵害に基づく差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年7月11日 東京地方裁判所
ア 前提事実及び前記認定に係る経緯を併せ考慮すれば、本件に関する一連の経緯については、以下のように要約し得る。
すなわち、原告は、平成 21 年 1 月の本件三社契約締結後間もない時期からリタッ グ、被告その他会員企業から、原告が供給する製品の品質及び安定供給に関する問 題点等を繰り返し指摘されたものの、これを解消し得ず、むしろ平成 23 年 3 月の東日本大震災の発生や平成 24 年 6 月の原告による民事再生手続開始申立てを受けて、\nより具体的な対応を強く求められるようになった。具体的には、遅くとも平成 24 年 7 月面談において、リタッグが、原告に対し、ヤマウ及び被告を委託先とする OEM 製造による二次蓋の供給を強く求め、原告もこれに応じ、原告はヤマウとの協議を 開始し、リタッグは、被告に対する委託を検討するようになった。しかし、原告とヤマウとの OEM 製造に関する協議は価格面の問題等から契約締結には至らず、原 告自身、平成 年 月会議において、複数社による二次蓋の製造の必要性を認める 発言や、製造に伴う責任と関連付けてその場合の許諾料に関する自己の意見を述べ、 被告による二次蓋の製造販売を許容する趣旨のものと理解し得る発言をした。これ を受けて、リタッグは、本件三社契約 18 条に基づく措置として、被告との間でリタッグ許諾契約を締結し、被告は、これに基づき、被告製品の製造販売を開始した。 他方、この頃、原告とヤマウとの OEM 製造に関する協議は具体的に進展していな い状況にあった。このような状況の中で、リタッグは、原告に対し、引き続き原告 による二次蓋の安定的な供給等につき強い懸念を示し、他方、原告は、被告による 被告製品の製造販売を問題視する姿勢を示すようになっていた。ところが、令和 3 年 2 月に原告が二次蓋を製造していた中国工場の閉鎖を関係取引先に通知するとい う事態を受け、令和 3 年 3 月会議が開催されることとなった。この際、原告は、被 告による被告製品の製造販売という事情をもって、原告中国工場の閉鎖の一因と示 唆しつつも、同事情を閉鎖により取引先に対する商品の供給に支障が生じないこと を示すものと位置付けて会員企業に説明し、さらに、原告としても、その後の二次 蓋の供給は被告による被告製品の製造販売に依存せざるを得ないとの考えを明示的 に示した。また、同会議において、原告は、被告による被告製品の製造販売と本件 各特許権との関係につき、被告による本件各特許権の侵害の問題ではなく、原告と リタッグとの契約(原告・リタッグ基本契約)に関する問題であるとの認識を示し た。
イ こうした一連の経緯を踏まえると、原告は、遅くとも令和 3 年 3 月会議において、リタッグに対し、同社と被告とのリタッグ許諾契約につき、その契約締結時 に遡って同意をしたものとみるのが相当である。 なお、リタッグ許諾契約締結の契機となったとみられるのは、平成 年 月会議 での原告の発言であるが、当時リタッグ許諾契約は未だ締結されておらず、また、 その契約内容に即した検討等がされたといった事情も見当たらないことなどを踏まえると、この時点では、原告は、リタッグが被告に対し二次蓋の OEM 製造を委託 するという方向性の確認ないし承認をしたにとどまるものとみられる。
(2) 原告の主張について
これに対し、原告は、リタッグ許諾契約に係るリタッグに対する同意又は被告製 品の製造販売に係る被告に対する本件各特許権の許諾のいずれも行っていない旨を主張する。
しかし、原告は、令和 3 年 3 月会議の時点で約 年の長きにわたり、リタッグ、 被告その他会員企業から本件工法に係る二次蓋の品質や安定供給に関する問題を指 摘され続けたにもかかわらず、会員企業の納得を十分に得られる対応を実現できな\nいまま、民事再生手続開始申立てや二次蓋の製造を行っていた中国工場の閉鎖に追\nい込まれた状況にあった。このため、原告は、同会議において、本件三社契約(及 び被告以外の会員企業との同様の契約)に基づく二次蓋の供給に係る原告の責任を 免れ、又は軽減するには、当時既に約 年の実績のあるリタッグ許諾契約に基づく 被告による被告製品の製造販売を承認するほかに方法がない立場に置かれていたも のと推察される。また、被告による被告製品の製造販売につき、本件各特許権の侵 害の問題ではなく、原告・リタッグ基本契約に関する問題であるとする発言も、同 契約ではリタッグが自ら製造し、又は第三者に製造させることを想定していないと みられること(20条等)を踏まえると、合理的であり首肯し得る問題意識と考えら れる。
2024.08.27
令和4(ワ)22517 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年8月21日 東京地方裁判所
被告は、トイレットペーパーの表面、裏面の各シートをそれぞれ表\面に凹凸 をつけるエンボス処理した後、それぞれのシートの凸部同士を内側にして2プ ライにするようなダブルエンボスでは、表面と裏面のシートのエンボスが干渉\nし、これらを常に干渉しないようにすることはほぼ不可能であり、付与された\n後のエンボスの形状、深さを明確に測定することができないので、本件発明1 は、シングルエンボスのトイレットロールのみに限定されると主張する。 しかしながら、本件明細書1記載の方法でエンボス深さDを測定することが でき、そこで測定されたエンボス深さDに本件発明1の技術的意味があるもの であれば、本件発明1のトイレットロールが、シングルエンボスのトイレット ロールに限定されるとは認められない。また、トイレットロールにおけるエン ボスであるという性質上、各エンボスの形状については一定のばらつきがある ことが想定されているといえる。
もっとも、本件発明1のエンボス深さDは、X−Y平面上のエンボスの高さ プロファイルを得ることができ(【図5】(a))、エンボスの周縁frやその最 長部aがどこに位置するのかを特定できるトイレットロールについて、【図5】 (b)、【図6】のような断面曲線を得た上で、測定されたものであり、そのよう にして測定されたものであるエンボス深さDが一定の数値のトイレットロール について本件発明1の効果を奏するとしているものといえる。各被告製品は、 各シートのエンボスの凹凸の位置関係を特に調整しないまま、プライボンディ ングした通常の2プライのダブルエンボスである(弁論の全趣旨)。このような ダブルエンボスのトイレットロールにおいては、表面と裏面にそれぞれ付され\nたエンボスが重なるとは限らず、エンボスの周縁が一致することが保証されて いないことから、エンボスの周縁が明確にならず、また、エンボスの凹凸の位 置がずれることにより干渉し、その形状が明瞭でないエンボスが生じ得る。そ して、甲51報告書によれば、各被告製品については、原告がエンボスとして 特定した部分の中央に、断面曲線で上に凸の曲率極大点が認められるなど、そ のエンボスが本件発明1のエンボス深さDを測定する際に想定されていた凹部 形状のものであるかが必ずしも明らかではないほか、X−Y平面上のエンボス の高さプロファイルによって、エンボスの周縁frやその最長部aがどこに位 置するのかを確定できるものとは必ずしもいえない。そうすると、そのような エンボスが付された各被告製品のトイレットロールについてエンボスを10個 選んで測定を行い、それらの平均値として一定の深さDを求めたとしても、本 発明1におけるエンボス深さDが測定できたということはできない。
(7) 以上によれば、原告測定方法は、本件明細書1に記載されたエンボス深さの 測定方法とはいえず、原告測定方法に基づいた甲10報告書によって、各被告 製品が構成要件1Bを充足するとは認めることはできない。甲51報告書その\n他の証拠によっても、各被告製品について、本件発明1におけるエンボス深さ Dが明らかであってその数値が構成要件1Bを充足するということを認めるに\n足りない。したがって、各被告製品はいずれも構成要件1Bを充足するとはいえない。\n
・・・・
構成要件2Eは、「前記把持部には、ほぼ中央に上向きに非切抜部を有するほ\nぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴、又は上向きに非切抜部を有して横方向 に沿って並ぶ二個の指掛け穴が形成されており、」というものであり、特許請求 の範囲の「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴」 との文言は、その「指掛け穴」が既に「形成」されているものであることから も、その「形成」されている「指掛け穴」が「ほぼ長円の一つのスリット状」で あり、また、そのほぼ長円の上部輪郭が非切抜部であると理解することができ るものであるところ、本件明細書2の上記部分には、そのような理解に沿う構\n成が記載されているということができ、そのような理解を前提として、その「ス リット状のほぼ長円」の上部輪郭の非切抜部を固定端とする片部がスリットの 切り抜きにより上方に折り返されるものであることが記載されているといえる。 また、【図1】に記載された指掛け穴も上記の理解に沿ったものである。そうす ると、構成要件2Eの「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット\n状の指掛け穴」とは、同構成について本件明細書2において記載されている、\n上記に述べたとおりの構成のものであると認められる。\n
(2) 被告製品1の包装袋のスリットは、写真2の左側の写真の赤破線で示された とおりのものであり、被告製品3の包装袋のスリットは、写真2の右側の写真 の赤破線で示されたとおりのものである。 前記(1)のとおり、構成要件2Eについては、その「指掛け穴」が「ほぼ長円の\n一つのスリット状」であって、その「スリット状」の「ほぼ長円」の上部輪郭の 非切抜部を固定端とする片部がスリットの切り抜きにより上方に折り返される ものであり、その非切抜部は、「スリット状」の「ほぼ長円」の一部を構成する\nものである。そして、非切抜部を固定端とする片部が上方に折り返されるため には、その非切抜部の固定端が、「スリット状」の「ほぼ長円」の上部輪郭にあ る必要がある。
被告製品1及び被告製品3の包装袋のスリットをみると、その両端部はそれ ぞれ外側に湾曲して下方に向かい、終端が内側に位置しているから、このよう なスリットの両端部の終端の位置を考慮すると、被告製品1及び被告製品3に おいては、形成されている「スリット状」の「指掛け穴」の下部輪郭が「非切抜 部」であるともいえ、その非切抜部を固定端とする片部がスリットの切り抜き により上方に折り返されるものではない。また、原告主張の熱融着部(写真3 参照)とスリットとを見ると、スリットは、その中央が、その上方に対しては、 弧状であるとしても、その左右には、上方への折り返しとなる頂点が存在せず、 それ自体「ほぼ長円」を形成しているとはいえず、「スリット状」の「ほぼ長円」 が形成されていないから、原告主張の上記熱融着部の円弧が「スリット状」の 「ほぼ長円」の上部輪郭にあるとはいえず、そこを構成要件2Eの「非切抜部」\nであるということはできない。そうすると、被告製品1及び被告製品3には、 「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴」に相当 する構成があるとはいえない。\n
(3) 原告は、被告製品1及び被告製品3のスリットが切り抜かれることで把持部 に下に凸の円弧が生じ、スリットと熱融着部などによって形成される非切抜部 によって、ほぼ長円の形状の指掛け穴が形成されると主張する。 しかし、前記(1)のとおり、構成要件2Eにおいては、形成されている「指掛\nけ穴」が「ほぼ長円の一つのスリット状」であって、その「スリット状」の「ほ ぼ長円」の上部輪郭の非切抜部を固定端とする片部がスリットの切り抜きによ り上方に折り返されるのであり、その非切抜部は、「スリット状」の「ほぼ長円」 の一部を構成するものである。被告製品1及び被告製品3においては、「スリッ\nト状」の「ほぼ長円」が形成されているとはいえず、被告製品1及び被告製品 3において、スリットの上方の熱融着部などによって形成される部分が構成要\n件2Eの非切抜部であるとする原告の主張は採用できない。
原告は、本件発明2では指掛け穴の有するスリットが内側に回り込んでいるの に対し、被告製品1及び被告製品3ではスリットが内側に回り込んでいない点で、 被告製品1及び被告製品3が本件発明2と文言上相違するとした上で、この点に ついて均等侵害が成立する旨主張する。
しかしながら、被告製品1及び被告製品3においては、スリットは、その中央 部分のみが上方に対して弧状であり、本件発明2の構成とは基本的な形状が異な\nるといえるものなのであって、これが直ちに被告製品1及び被告製品3の製造時 において本件発明2から容易に想到することができたとは認めるに足りず、また、 原告は、本件異議申立事件の決定の予\告後に、指掛け穴を構成要件2Eの構\成に 限定したと述べて構成要件2Eの構\成を加えて、他の構成の指掛け穴の形状を意\n識的に除外したといえる。したがって、均等侵害をいう原告の主張には理由がな い。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第3要件(置換容易性)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2024.08.26
令和5(ネ)10052等 特許権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴、民訴法260条2項の申立て事件 特許権 民事訴訟 令和6年4月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は、原審と異なり、本件においても特許法102条1項及び2項の 適用は否定されない一方、同条3項につき原審が適用した相当実施料率30% は過大であると思料し、これを前提に、当審における請求原因(侵害の対象取 引)の追加も踏まえて、同条2項に基づいて認められる損害8億3191万6 753円の限度で損害賠償請求を認容すべきものと判断する。その理由は、以 下のとおりである。
・・・
(3) 以上の事情を踏まえて検討する。
SDダイサーのメーカーは、国内では、控訴人と、被控訴人からSDエ ンジンの供給を受けるディスコ社に限られている。 EO社等の国外メーカーの販売実績は明らかではないが、サムスン社が 被控訴人による特許権侵害との指摘を受けてEO社との取引を中止するに至 っていることに鑑みれば、競合メーカーの参入は、不可能とまではいえないまでも、相当限定されたものと推認される。\nそうすると、ステルスダイサーの販売者は、控訴人と上記ディスコ社で 大部分を占める状況にあると認められる。
また、本件において、被控訴人製SDエンジンは、本件訂正発明1並び に本件発明2−2及び本件発明2−3の技術の中核をなすものであり、そ の侵害品である被告製品にとっても、その技術の中核的部分に相当すると いえる。そうすると、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する\n部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解される。 このように、ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、 被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されてい ること、被控訴人製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品に とどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品 の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争\n力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵 害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたで あろうという事情が認められるというべきである。 これを他の表現でいえば、被控訴人が主張するとおり、特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同\n一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品 相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、 当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品(完成 品)の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるということもできる。
(4) 控訴人は、知財高裁令和4年10月20日判決(椅子式マッサージ機事件) は、特許権者が、侵害品と「需要者を共通」にする「同種の」「競合品」で あって「市場において・・・競合関係にある製品」を輸出・販売していた場合 に初めて、特許法102条2項による推定が正当化されることを踏まえたも のである旨主張するが、同判決の事案が、控訴人の指摘する場合であったと いうにすぎず、そのような場合以外に同項が適用されないことまでは判示す るものではない。 被控訴人製SDエンジンの1個当たりの利益の額は、(1)の被控訴人製S Dエンジンの1個当たりの価額から(2)の原価を控除した●●●●円である。 その●●台分は●●●●●●●円であり、前記の特許法102条2項に基づ き算定される損害額7億5628万7981円を下回るから、本件において 同条1項に基づく損害は、採用の限りでない。
・・・ 特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度 の損害額を法定した規定であって、同項による損害は、原則として、侵害品 の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべ きである。そして、平成10年法律第51号による改正により、「通常受け るべき金銭の額」という同項の規定のうち「通常」の部分が削除された経緯 に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも特許権につい ての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、 特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべ き料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと を考慮すべきである。
したがって、実施に対し受けるべき料率は、1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て、合理的な料率を定めるべきである。
(2) 本件における当てはめ
ア 当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らか でない場合には業界における実施料の相場等(1))、特許権者と侵害者 との競業関係や特許権者の営業方針等(4))
(ア) 前記のとおり、被控訴人は、その開発に係るステルスダイシング技術 の中核的ユニットであるSDエンジン一式の製造については、自社製造 を必須とし、一切製造ライセンスを許諾せず、SDエンジンの販売利益 により先端技術の研究開発を継続するものであり、そのため、被控訴人 は、アライアンスパートナーに対し包括ライセンスを付与するに当たっ ては、被控訴人製造に係るSDエンジンの販売を大前提として、当該販 売とSD技術関連特許に関する特許発明のロイヤリティの支払を不可分 一体の条件とするものであり、被控訴人は、アライアンスパートナーに 対しては、本件特許発明を含めたSD技術関連特許につき、SDダイサ ーの最終販売価格の●%という実施料率に基づき、包括ライセンスを行 っており、他方、被控訴人からSDエンジンを購入しないSDメーカー に対しては、SD技術関連特許を包括ライセンスすることは一切ないも のである。したがって、被控訴人と控訴人の間では、当初本件業務提携契約に よりライセンス料が●%とされ、その後、●●●%に値下げされたが (乙15)、この実施料率を相当実施料率算定の基準とするのは相当 でない。
(イ) 前述のとおり、ステルスダイサーの販売者としては、控訴人と、被 控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社が大きな割合を占 めており、両者の競合関係は明らかである。
・・・
以上のとおり、被控訴人と控訴人の間では、当初ライセンス料が●%と され、その後、●●●%に値下げされたが、これは、控訴人において被 控訴人製SDエンジンのみを使用してSDダイサーを製造販売すること が前提となっているから、この前提を欠く場合に、上記ライセンス料の みをもって受けるべき料率とするのは相当でなく、他方、被控訴人製の SDエンジンの利益そのものを特許法102条3項の料率の基準とする ことも相当でないこと、一般的なライセンス料の傾向、控訴人と被控訴 人は競合状態にあること、本件訂正発明1については本件発明2−2や 本件発明2−3により補わなければならない点があるところ、被告製品 (低追従)は本件発明2−2及び本件発明2−3の技術的範囲に属さな いこと等の事情を総合すれば、本件において被控訴人が実施に対し受け るべき料率としては、15%と認めるのが相当である。
・・・
本件において特許権の侵害が認められるNo.●●●●の販売額合計は、別紙 6認容額計算表のとおり●●●●●●●●●●●●円であり、これに15%を乗じると、●●●●●●●●●●●円となる。これは、特許法102条2\n項に基づき算定される損害額7億5628万7981円を下回るから、本件 において、同条3項に基づく損害は、採用の限りでない。
◆判決本文
1審はこちらです
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.08.26
令和5(行ケ)10087 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年7月8日 知的財産高等裁判所
前記(イ)の各事実によれば、デ社は、遅くとも昭和23年の設立から 平成13年末までの約53年間「三金工業株式会社」の商号を、平成1 4年から平成28年末までの約15年間「デンツプライ三金株式会社」 の商号を、それぞれ使用し、長年にわたり歯科用材料、歯科用医療機器 等を製造販売しており、その事業実績は少なくとも業界の中堅規模以上 であったと認められる。また、デ社は、歯科医療関係者を中心とする需 要者に会社名を表示する広告宣伝を継続的に行い、「三金」、「サンキ\nン」又は「SANKIN」を商品名に含む商品についても、本件商標が 出願された平成29年まで長年にわたり継続的に製造販売され、年間数 千万円程度の純売上額を恒常的に上げていたことが認められる。 デ社の事業譲渡に係る経緯をみても、被告及びギコウ社は、デ社の歯 科技工所等の事業を譲り受ける価値があるものと判断するとともに、 「三金」、「SANKIN」の知名度、ブランド力をも評価していたと みるのが相当であり、このことは、歯科医療関係者の認識の程度を裏付 ける事情の一つといえる。 そうすると、本件商標の指定商品に含まれる歯科用材料、義歯等の取 引者、需要者である歯科医療関係者の間では、「三金」の表記及びその\n称呼の表記である「サンキン」、「SANKIN」は、デ社又はその製\n造販売する商品を表すものとして、広く認識されていたと認められる。\n
(エ) 以上の事実を前提に判断すると、本件商標は、「工業」の部分が出所 識別標識としての称呼、観念が生じないのに対し、「三金」の部分は、 取引者、需要者のうち歯科医療関係者に対しては現に出所識別標識とし ての印象を強く与えているということができる。そうすると、当該部分 は、その他の取引者、需要者からみても同様に出所識別標識としての称 呼、観念が生じ得るものである。これらの点に鑑みると、本件商標の 「三金」と「工業」とは、分離して観察することが取引上不自然である と思われるほどに不可分的に結合していると認めることはできず、「三 金」の部分を抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも 許されると解するのが相当である。
・・・
ア 本件商標とデ社の表示との類似性の程度\n
前記1(1)イ、ウで述べた理由から、「三金」、「サンキン」及び「S ANKIN」の表示(以下「三金」等の表\示という。)は、歯科医療関係 者の間では、デ社又はその製造販売する商品を表すものとして広く認識さ\nれおり、「三金」等の表示と本件商標「三金工業」は類似し、その類似性\nの程度も相当程度高いといえる。
イ 「三金」等の表示の周知著名性及び独創性の程度\n
前記1(1)イのとおり、「三金」等の表示は、歯科医療関係者の間では\n周知であったと認められるが、これ以外の取引者、需要者の間では、周知 であったとまでは認められない。また、独創性が認められないことは、デ 社及び被告が関係するもの以外にも「とんかつ三金」、「サンキン」又は 「SANKIN」の文字を図案化等した商標、「株式会社三金」、「サン キン株式会社」等の例が多数存在することからも明らかである(乙1の1 〜3)。 なお、引用商標自体については、「三金」等の表示以上の周知性、独創\n性を有するとは認められない。
ウ 本件商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との関連性等
(ア) デ社は、歯科医療関係者を需要者とする歯科用材料、歯科用医療機器 等を製造販売しており(前記1(1)イ(イ))、少なくとも本件商標の指定 役務のうち「義歯の加工」については、デ社の製造販売する商品との類 似性が認められることは前記のとおりである。しかるところ、証拠(甲 116、117)及び弁論の全趣旨によれば、「金属の加工」「セラミ ックの加工」は、金属又はセラミックを材料とする歯科用材料及び歯科 用医療機器の製造と関連性が高いこと、近年、歯科用材料等を作製する ための3Dプリンターの導入が進んでおり、デ社を含む原告グループに おいても、歯科医療のために設計された3Dプリンターを利用し、自動 化した歯科治療システムを提供していることが認められるところ、この ような実情は、本件出願日である平成29年10月30日の時点でも存 在していたことが推認され、これに反する証拠はない。これを踏まえる と、本件商標の指定役務のうち後で述べる「義肢の加工」及び歯科用材 料等との類似性が認められる「義歯の加工」(前記1(2)ア)を除く各 役務(第40 「金属の加工、セラミックの加工、金属加工機械器具の 貸与、化学機械器具の貸与、3Dプリンターの貸与、材料処理情報の提 供」。以下「本件金属加工等役務」という。)は、デ社又はそのグルー プ会社の業務に係る商品又は役務と密接に関連しているものと認められ、 その取引者及び需要者も歯科医療関係者であるという共通点が認められ るというべきである。
(イ) 他方、本件商標の指定商品のうち、本件薬剤等商品以外のもの(第5 類「乳幼児用粉乳、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、 乳幼児用食品」、第10類「睡眠用耳栓、防音用耳栓、業務用美容マッ サージ器、家庭用電気マッサージ器」)及び指定役務のうち「義肢の加 工(「医療材料の加工」を含む。)」の役務については、デ社又はその グループ会社の業務に係る商品又は役務との性質、用途又は目的におけ る関連性は乏しく、取引者及び需要者の共通性も認め難い。 原告は、本件薬剤等商品以外の指定商品も医療用品又は衛生用品とい う歯科用材料及び歯科用医療機器と同じ性質を有し、同一又は類似の商 品である旨主張するが、これらの指定商品が医療又は衛生の用途で通常 用いられることを裏付ける証拠はなく、デ社その他の歯科用材料及び歯 科用医療機器を製造販売する事業者がそれらの商品を通常製造販売して いる等、商品・役務の出所の混同を生じさせるような事情も認められな い。
エ 以上の事情を総合すると、本件商標は「三金」等の表示と類似しており、\n「三金」等の表示は、歯科医療関係者の間において、デ社又はその製造販\n売する商品を表すものとして広く認識されている上、デ社又はそのグルー\nプ会社の業務に係る商品又は役務は本件金属加工等役務と密接に関連して いるのであるから、本件商標を本件金属加工等役務に使用するときは、そ の取引者及び需要者である歯科医療関係者において、その役務がデ社又は 同社と緊密な関係にある事業者の業務に係る役務であると誤信されるおそ れがあるということができる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.08.26
令和5(ワ)70654 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年7月8日 東京地方裁判所
(1) 不競法2条1項1号及び2号は、「商品等表示」につき、人の業務に係る\n氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を 表示するものと定義している。そうすると、同各号にいう「商品等表\示」と は、商品又は営業を表示するものであるから、出所表\示機能を有するものに\n限られるというべきである。そして、書籍には発行者等の表示が付されるの\nが通例であり、書籍の出所は、一般に上記発行者等の表示が示すものである\nから、書籍の題号は、その書籍の内容を示すものにすぎず、出所表示機能\を 有するものとはいえない。
そうすると、書籍の題号は、特段の事情がない限り、同各号にいう「商品 等表示」に該当しないと解するのが相当である。\nこれを本件についてみると、証拠(甲2ないし10、19)及び弁論の全 趣旨によれば、「牧野日本植物圖鑑」という本件題号は、牧野執筆に係る日 本の植物図鑑という書籍の内容を端的に示すものにすぎず、牧野という執筆 者に特徴があるのは格別、書籍の題号としてはありふれたものであるから、 本件題号には出所を示すような顕著な特徴はない。 そして、証拠(乙1、2)及び弁論の全趣旨によれば、一般に題号を同じ くする書籍であっても、別々の発行者等により発行されているものも少なか らず存在することが認められる。当該認定に係る取引の実情に鑑みると、本 件題号に接した需要者又は取引者が、これを書籍の出所を示すものとして直 ちに理解するものとはいえない。 これらの事情を踏まえると、本件題号は、出所表示機能\を有するものとは いえず、上記特段の事情があるものと認めることはできない。
したがって、本件題号は、不競法2条1項1号又は2号にいう「商品等表\n示」に該当するものと認めることはできない。 のみならず、被告書籍についてみると、仮に「牧野日本植物圖鑑」という 牧野執筆に係る植物図鑑が全国的に知られていたという立場を採用したとし ても、本件全証拠によっても、原告が本件図鑑を出版していた事実までも全 国的に知られているものとして著名であると認めるに足りない。 他方、仮に、原告が本件図鑑を出版していた事実が、一部の専門家や研究 者の間で周知であるという立場を採用したとしても、前記前提事実及び証拠 (甲19)によれば、被告書籍の表紙には、本件題号の左下欄に「三四郎書\n館」という発行所を示す表示が付されていることからすると、被告書籍に接\nした需要者又は取引者は、被告書籍の発行所が、原告ではなく「三四郎書館」 であると理解するのは明らかである。 そうすると、被告書籍の出版は、本件図鑑との混同を生じさせる行為とは いえないことは、明らかである。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2024.08.26
令和5(行ケ)10019 特許権 行政訴訟 令和6年8月7日 知的財産高等裁判所
以上の本件明細書の記載及び技術常識を総合すると、本件明細書には、 1)mAb1は、抗IL−4Rアンタゴニスト抗体であって、IL−4Rに結 合し、IL−4のシグナルを遮断する作用を有するものであること、2)mA b1が投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎における臨床症状が改善 したこと、3)mAb1が投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎のバイ オマーカーであり、IL−4によって産生・分泌が誘導されることが知られ ているTARC及びIgEのレベルが低下したことが開示されていることか ら、これに接した当業者は、本件患者にmAb1を投与した際のアトピー性 皮膚炎の治療効果は、mAb1のIL−4Rに結合しIL−4を遮断する作 用、すなわち、アンタゴニストとしての作用により発揮されるものと理解す るものといえる。そうすると、IL−4Rに結合しIL−4を遮断する作用を有する抗IL −4Rアンタゴニスト抗体(本件抗体等)であれば、mAb1に限らず、本 件患者に対して治療効果を有するであろうことを合理的に認識でき、前記 (2)に記載した本件訂正発明の課題を解決できるとの認識が得られるものと 認められる。
(6) ところで、本件明細書に開示された薬理試験結果はmAb1に関するも ののみであることは、原告の指摘するとおりである。しかし、サポート要件 の適合性につき、「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明 に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」等を判断するに当 たって、どの範囲の実施例等の裏付けをもって十分とするかについては、当\n該課題解決の認識がいかなるロジックによって導かれるかという点を踏まえ て検討されるべきであり、特許の権利範囲に比して実施例が少なすぎると いった単純な議論が妥当するものではない。
これを本件についてみるに、本件においては、1)mAb1は、抗IL− 4Rアンタゴニスト抗体であって、IL−4Rに結合し、IL−4のシグナ ルを遮断する作用を有するものであること、2)mAb1が投与された本件患 者では、アトピー性皮膚炎における臨床症状が改善したこと、3)mAb1が 投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎のバイオマーカーであり、IL −4によって産生・分泌が誘導されることが知られているTARC及びIg Eのレベルが低下したことが開示されていることから演繹的に導かれる推論 として、本件患者にmAb1を投与した際のアトピー性皮膚炎の治療効果は、 mAb1のIL−4Rに結合しIL−4を遮断する作用、すなわち、アンタ ゴニストとしての作用により発揮されるものと理解されるものであって、課 題を解決できると認識できる範囲が幅広い実施例から帰納的に導かれる場合 とは異なる。上記作用機序は、本件抗体の一つであるmAb1がIL−4R に結合し、IL−4のシグナルを遮断する作用を有するものであり、mAb 1が投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎における臨床症状が改善し、 アトピー性皮膚炎のバイオマーカーも低下したのであるから、mAb1以外 の抗IL−4Rアンタゴニスト抗体である本件抗体等(mAb1以外の32 種)も同様の作用効果を有すると当業者が理解できることは明らかである。 本件明細書に開示された薬理試験結果はmAb1に関するもののみであ るとの原告の指摘は、上記認定判断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2024.08.26
令和6(行ケ)10007 商標権 行政訴訟 令和6年8月5日 知的財産高等裁判所
これを本件について見るに、確かに、Jimny商標(「Jimny (ジムニー)」)がスズキ社の製造販売するオフロード車の名称を表示\nするものとして、我が国の幅広い年齢層の自動車ユーザー等の間で広く 知られていたことは上記のとおりであり、したがって、仮に、Jimn y商標が「自動車」に使用された場合を想定すれば、商品の出所識別標 識として強く支配的な印象を与えると判断することには十分な理由があ\nるといえる。しかし、本件で問題とすべきは、本願商標を本願補正商品 に使用したときに、取引者・需要者が出所識別標識としていかなる認識 を有するかということである。
このような観点から考えると、まず、客観的な事実として、スズキ社 を含む自動車メーカーが自ら又は系列ディーラー等を通じて、「オフ ロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」を発行して いる事実は認められない。のみならず、原告代表者によれば、スズキ社\nを含む自動車メーカーは、前述したジムニーのカスタマイズ市場(上記 2(2)ア参照)等に係る業務に対して、第三者の活動を側面から援助する ことはあっても、主体的に関わることは避けていることがうかがわれる。 このような中、本願商標を使用した本願補正商品に接した取引者・需要 者において、スズキ社を含む自動車メーカー又はその系列ディーラー等 が発行主体となっている(可能性がある)と認識するとは考え難い(そ\nのような認識を基礎づける証拠は一切提出されていない。)。
なお、オフロード車の改造に関心を有しているであろう本願補正商品 の取引者・需要者が本願商標に接した場合、本願商標中の「Jimny」 及び「ジムニー」の部分が、改造のベースとなる車両として強く支配的 な印象を与えることは想像に難くないが(実際、本件雑誌がそれを意図 していることは明らかである。)、それは「出所識別標識」とは次元の 異なる問題であり、「Jimny」及び「ジムニー」の部分を結合商標 の要部として抽出する根拠となるものではない。 本件審決が、「本願商標は、その構成中の『Jimny』の欧文字及\nび『ジムニー』の片仮名が強く支配的な印象を与えるものであり、引用 商標との類否を判断するに当たって、当該文字を本願商標の要部として 抽出し、これを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許され る」とした判断は、「商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を 与える場合」に結合商標の要部認定を認める前記最判の趣旨を正解しな いものといわざるを得ない。
・・・
(1) 上記1(2)の枠組みに従って判断するに、まず、Jimny商標がスズ キ社の製造販売するオフロード車の名称を表示するものとして、我が国の幅\n広い年齢層の自動車ユーザー等の間で広く知られていたことは上記のとおり であり、また、「Jimny(ジムニー)」は普通名詞に由来しない造語と 理解されるものである。したがって、Jimny商標の周知著名性及び独創 性の程度は、いずれも高いものと評価される。
(2) そこで、次に、本願商標の指定商品(本願補正商品)とスズキ社の業務 に係る商品・役務との関連性について検討する。
ア 上記1(3)でも述べたように、自動車メーカーが自ら又は系列ディー ラー等を通じて自動車の関連グッズを販売したり付随サービスを提供し たりすることは珍しくないと解され、スズキ社においても、オフロード 車(ジムニー)そのものにとどまらない一定の商品・役務につき、周知 のJimny商標に係る信用を利用して、ジムニー関連ビジネスという べき業務を展開することは十分考えられる。\n
イ しかし、本願商標の指定商品(本願補正商品)は、第16類「オフロー ド車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」という極めて ニッチな商品であるところ、取引の実情として先に認定したとおり、ス ズキ社を含む自動車メーカーが自ら又は系列ディーラー等を通じて、 「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」を発 行している事実はなく、また、本願商標を使用した本願補正商品に接し た取引者・需要者において、スズキ社を含む自動車メーカー又はその系 列ディーラー等が発行主体となっている(可能性がある)と認識すると\nも考え難い。 加えて、スズキ社は、原告が本願商標の構成と同じ題名の本件雑誌を\n10年以上にわたって発行していることを知悉しながら、Jimny商 標との関係での誤認混同を生じさせるといった警告、クレームを原告に 伝えたことがないばかりか、原告に広告料を支払って本件雑誌にジム ニーの広告を掲載するなどして本件雑誌の発行を援助していることも前 述のとおりである。
ウ 以上の事実関係に原告代表者の供述を総合すると、スズキ社がJimn\ny商標の下で展開する業務としては、オフロード車(ジムニー)そのも のにとどまらない関連グッズ、付随サービスを含み得るものではあるが、 「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」に係 る業務は、スズキ社又はその系列ディーラー等とは直接関係のない第三 者によって提供されているのが実情であり、スズキ社とは抵触関係に立 たない「棲み分け」が成立していると認められる。
(3) 以上によれば、本願商標を本願補正商品に使用したとしても、スズキ社 のJimny商標に係る商品・役務との混同を生ずるおそれは認められない というべきである。よって、本願商標は、商標法4条1項15号に該当する ものではない。
◆判決本文
車関係の似た事件では、「スバリスト」事件がありました。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.08.26
令和5(ワ)70422 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 令和6年8月1日 東京地方裁判所
ア 前提事実及び上記各認定事実によれば、原告Aは、原告社団代表者との関係性を前提として、原告社団から対価(7 万円)の支払を受けて本件写真を含む写真 の撮影を行い、原告社団は、原告Aから本件写真の納品を受け、その後、原告Aか ら個別に許諾を得ることなく、本件写真を利用していたといえる。また、上記認定 事実からうかがわれる原告社団とEないし Colabo との関係性を踏まえると、E及 び Colabo による本件写真の利用は、原告社団の包括的又は個別の許諾に基づき行 われたものであることがうかがわれる。 他方、原告社団の原告Aに対する利用許諾料の支払その他原告社団による本件写 真の利用が原告社団と原告Aとの利用許諾契約に基づくものであることをうかがわ せる具体的な事情は見当たらない。
このような本件写真の利用態様に鑑みると、原告社団による本件写真の利用は、 原告Aによる本件写真の納品及び原告社団によるその対価の支払によって原告社団 が本件写真の著作権を取得したことに基づくものと理解される。このような理解は、 原告社団代表者、原告A及びCの各陳述ないし供述(甲 2〜4、14、証人C)に沿う ものでもある。また、これらの陳述ないし供述については、いずれもその信用性に 疑義を抱くべき具体的な事情はなく、また、相互に矛盾するものでもない。加えて、 原告社団及び原告Aは、前訴から一貫して、本件写真に係る著作権は原告Aから原 告社団に譲渡された旨主張している。 これらの事情を総合的に考慮すると、本件写真に係る著作権は、原告Aの原告社 団に対する本件写真の納品及び原告社団の原告Aに対するその対価の支払により、 原告Aから原告社団に譲渡されたとみるのが相当である。
イ これに対し、被告は、著作権譲渡を裏付ける契約書等がないことその他の事 情を縷々指摘して、原告Aから原告社団に対し本件写真に係る著作権の譲渡はない 旨主張する。 確かに、原告Aから原告社団に対する著作権譲渡を直接的に裏付ける契約書その 他の客観的な資料は存在しない。また、原告Aは、前訴において、本件写真につき、 原告社団に対して「写真の使用権」を譲渡したとの認識である旨や、被告の本件写 真の利用をもって「私や「のりこえねっと」の著作権を侵害していることになる」 旨陳述したところ、これらの陳述は、原告Aが本件写真の著作権を有することを前 提とする趣旨と理解し得ないものではなく、少なくとも、著作権の帰属につき判然 としない内容のものであるとはいえる。原告社団が原告Aに支払った対価の額も、 Eを含む 3 名の写真撮影に関するものであることや交通費を含むことを考えると、 原告A及び原告社団代表者も陳述するとおり、著作権譲渡の対価としては相当に低廉であると評価し得る。\n
しかし、契約書その他直接的に著作権譲渡を裏付ける客観的な資料がないことは、 もとより直ちに著作権譲渡がなかったことを意味するものではない。原告社団と原 告Aとの関係性に鑑みれば、そのような資料の不存在は必ずしも不自然ないし不合 理とはいえない。同様の理由から、支払われた対価が著作権譲渡の対価としては相 当に低廉であるとしても、これをもって著作権譲渡がなかったことをうかがわせる 事情とは必ずしもいえない。前訴における原告Aの陳述も、趣旨は判然としない部分はあるものの、「譲渡」や「原告社団の著作権の侵害」という表現を含むものである。そもそも、上記陳述は、原告社団が本件動画 33 及び 34 の著作権を主張する前 訴において原告社団により提出されたものであることや、原告社団と原告Aとの関 係性に加え、原告Aは法律の専門家ではなく、法的事項につき不正確な表現をすることも十\分にあり得ることをも考慮すると、前提として原告社団に対する著作権譲渡を含意するものと理解するのが相当である。
2024.08.26
令和6(行ケ)10032 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年7月31日 知的財産高等裁判所
ウ 本願文字部分について
本願文字部分中「i」の欧文字は英語アルファベットの第9字であり(乙 6、9)、「i」の欧文字部分の上に配された「アイ」の文字が、同欧文字 部分の読み仮名(ルビ)を表したものであることは明らかであるから、本願\n文字部分からは「アイデンタルクリニック」の称呼が生ずる。 そして、「デンタルクリニック」の文字が「歯科医院」の意味を有する外 来語であることは、現在の日本における英語の普及度合からみて、一般的 に理解されているものと解され(乙7、14、15)、任意の文字と合わせ て、歯科医院の名称の一部として実際に使用されている実情にある(乙8、 16)。「デンタルクリニック」の文字に関する上記使用の実情から、本願 文字部分は、歯科医院の名称を連想させるものの、本願文字部分全体とし て一般の辞書等に掲載されているものではなく、具体的な意味合いを認識 させるものであるとはいえない。また、本願商標の指定役務である「歯科医 業」等の需要者は、その役務における他のサービスと区別する目印として、 その提供者に係る歯科医院等の名称に着目してそのサービスの選択に当た ることが一般的と解され、本願商標に接する需要者は、いかなる植物を図 案化したものか自体明らかでない本願図形部分に着目するのでなく、「歯 科医院の名称」を表していると考えられる本願文字部分に、より一層着目\nし、当該文字(語句)より生ずる称呼によって、取引に当たるのが自然であ るといえる。
エ 本願商標の要部
以上に認定したところに鑑みれば、本願図形部分からは出所識別標識と しての称呼、観念が生じないと認められ、また、本願図形部分と本願文字部 分は間隔を大きく開けて配置されており、商標全体としての構成上の一体\n性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、本願文字部分 から生ずる称呼によって取引に当たる結果、本願文字部分が独立した出所 識別標識としての機能を果たすということができるから、本願文字部分が\n本願商標の要部に当たるというべきである。
オ 原告の主張について
(ア) 原告は、本願商標は、本願図形部分の中心部を頂点とし、本願文字部 分の最初の文字と最後の文字が他の2頂点となるような、正三角形状に 間隔を空けて配置されたものであり、外観における全体の配置の一体的 なバランスがあり、また、本願図形部分は、本願文字部分における「i」 を象形様に図形化したもので、本願図形部分に係る五つ葉のクローバー の花言葉の一つである「愛」・「愛情」と、本願文字部分における「i」 のフリガナ「アイ」とに称呼や観念における関連性があるから、本願商標 について分離観察するのは不適当である旨主張する。 しかし、本願商標に、本件図形部分の一番上でなく中心部が頂点であ る正三角形の存在を認識するような手がかりは何ら存在しない。
また、原告は、本願図形部分について、「iの上部点丸」が五つ葉のク ローバーの葉の部分、「iの下部棒」が五つ葉のクローバーの茎の部分を 表すというのであるが、本願図形部分の大きな葉の部分が「iの上部点\n丸」に当たり、これと接着して小さく横に伸びる茎の部分が「iの下部棒」に当たるというのは、「i」の欧文字の構造(上部点丸が下部棒に比\nべ小さく、両者は分離しており、下部棒が直立している。)に鑑み無理が あるというほかなく、本願図形部分が「i」の図形化であるとは認められ ない。また、五つ葉のクローバー自体一般に認識されていると認められ ないことは上述のとおりであるから、ましてその花言葉が一般に認識さ れているともいえない。原告の主張は採用できない。
(イ) また、原告は、本願文字部分のうちの「デンタルクリニック」は、本願 商標の指定役務との関係において単なる役務の提供の場所等を記述的に 表示するものであり、本願文字部分のうちの「i」は、アルファベット一\n文字で識別力がないから、それらをつなげた本願文字部分についても識 別力がなく、「iデンタルクリニック」(アイデンタルクリニック、I D ENTAL CLINIC)と称される歯科医院及びこれに類する歯科医 院は、国内に数多く存在する旨主張する。
たしかに、「iデンタルクリニック」は、歯科医院を意味する「デンタ ルクリニック」にアルファベット1字の「i」を結合させたにすぎないも のであり、それ自体として、高い識別力を発揮しているとまではいえな いと解される。しかし、「アイデンタルクリニック」の称呼を生ずる歯科 医院の使用例(甲9の2〔特に、番号21、22、32、34、36、3 7、43〜46、51、61、62、64、69〜71、74、80〕、 乙20〜22)を踏まえても、「i(アイ)デンタルクリニック」が出所 識別機能を有しないといえるほど一般的でありふれたものとまではいえ\nず、少なくとも、本願商標の要部認定という観点から、本願文字部分を要 部と認定するに妨げはないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.08.26
令和5(行ケ)10146 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年7月25日 知的財産高等裁判所
原告は、甲1には卵パックの搬送方向を変更することにつき、記載も示唆もない と主張する。しかし、上記(2)イのとおり、引用発明に係る装置において、コンベア や関連する装置の配置を最適化することは、当業者において自明の課題といえると ころ、同一の技術分野及び作用機能に係る甲2には、パックの搬送方向を変更でき\nる旨が明記されているから、引用発明及び甲2に接した当業者が、引用発明におけ る卵パックの搬送方向につき、甲2に記載された構成を適用する動機付けが認めら\nれる。原告の主張は採用することができない。 原告は、引用発明ではラベルが空気抵抗の影響を受けて挙動が不安定になり落下 位置がずれやすいのに対し、甲2発明ではラベルが空気抵抗の影響をほとんど受け ないとして、前提の異なる甲2記載の構成を引用発明に採用することはできないと\n主張する。しかし、甲1には、従来の装置の課題として「ラベルを水平方向にしたま ま落下させるとラベルは空気抵抗でどこに落下するか予測できない」(明細書2頁1\n3〜15行目)ことを挙げ、引用発明は「ラベルを水平方向にしたまま落下させな いで、ラベルを斜めにした状態で落下させると、ラベルはその傾斜の下方延長方向 に確実に落下すると云う原理に基(づ)いている」(同3頁1〜4行目)として課題 を解決する旨が記載されている。甲1の記載を総合しても、このようにして課題を 解決することとした引用発明において、それにもかかわらず、ラベルが空気抵抗の 影響を受けて挙動が不安定になり、ラベルの落下位置がずれやすいと認められるも のではなく、少なくとも、引用発明における卵パックの搬送方向を変更することに 阻害要因があるとは認められない。原告の主張は採用することができない。
原告は、引用発明では、ラベルが落下していく傾斜の下方延長方向と、コンベア による卵パックの搬送方向とが交わるようにすることで、発明の目的を達成してい るところ、卵パックの搬送方向を変更することはその目的に反することになり、阻 害要因があると主張する。しかし、甲1には、ラベルが落下していく方向と卵パッ クの搬送方向とが交わるようにすることにより発明の目的を達成している旨の記載 はないし、甲1の記載を総合しても、卵パックの搬送方向が変更された場合に、引 用発明の目的が達成されないと認めることはできない。また、パックが輸送される タイミングに合わせてラベルを投入することは、当該技術分野における技術常識と いえ、パックの搬送方向を変更させた上で、タイミングに合わせてラベルを投入で きるようにすることは、当業者が通常採用し得る事項といえる。引用発明における 卵パックの搬送方向を変更することに阻害要因があるとはいえない。 原告の主張は採用することができない。
・・・
原告は、本件審決が引用発明につき、「ラベルLは、保持を解除された後も、上ベ ルト3と接してベルトの駆動方向に押し出されるようになる」とした点につき、ラ ベルLは、上下ベルト3、4の挟持が解除された後、再び上ベルト3に接すること はないから、本件審決の認定は誤りであると主張する。しかし、本件審決の上記認 定部分は、ラベルLが上ベルト3との接触を離れた後に再び上ベルト3に接触する 旨をいうものとは解されない。引用発明において、ラベルLは、上下ベルト3、4の 運動によって輸送されていくから、その前端部分から後端部分にかけて、徐々に上 下ベルト3、4の挟持から離脱していくこととなるが、その間も、少なくとも後端 部分は上ベルト3に接してその運動により駆動方向に押し出されていく。本件審決 の上記認定部分は、これと同旨をいうものと理解できる。原告の主張は採用するこ とができない。
原告は、卵パックにラベルを投入する直前にラベルを一旦保持する構成は技術常\n識であるから、引用発明においても、ラベルLの後端部がプーリ7、10の位置に 到達した際、上下ベルト3、4は駆動を止めてラベルLを一旦保持し、その後、上下 ベルト3、4が駆動を再開することで保持が解除され、ラベルLは、傾斜の下方延 長方向(ラベルの短辺に沿った方向)に落下すると主張する。しかし、仮に引用発明 において上下ベルト3、4が駆動を止めてラベルLを保持し、その後駆動を再開し てラベルLの保持を解除するとしても、上下ベルト3、4の駆動の再開により、ラ ベルLには上下ベルト3、4の駆動による同駆動方向への駆動力が働くのであるか ら、ラベルLがその長辺に沿った方向に押し出されることは否定できない。原告の 主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2024.08.21
令和5(行ケ)10145 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年7月10日 知的財産高等裁判所
本件補正は、特許請求の範囲の請求項2に対する「前記開放空間は、前記 封止部材と前記レンズ部材の間において、前記レンズ部材の外縁を環状に一 周することなく前記接着剤が配されることで形成される」との請求項2補正 事項を含むものであり、この請求項2補正事項が、新規事項の追加に当たる かが問題となっている。そして、請求項2補正事項は、その文言から、開放空 間が「前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着剤が配され ること(本件接着剤配置)で」形成されるのであるから、本件接着剤配置が開 放空間の形成に寄与することを要すると解される。そこで、以上の趣旨が、当 初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項といえる かを、以下検討する。
ア 当初明細書等のうち、まず、実施形態3に係る【0037】〜【0039】 の記載及び図7によれば、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配 されていることが明らかであるから、これが本件接着剤配置、ひいては請 求項2補正事項を開示するものでないことは明らかである。
イ 次に、当初明細書等のうち、実施形態4に係る記載について検討する。 実施形態4では、図8から、レンズアレイ20の外縁と、レンズアレイ2 0が接着剤により封止部材80に固定される領域との関係から、接着剤は レンズ部材の外縁を環状に一周していないことが理解できるので、本件接 着剤配置については、図8から見て取れる事項といえる。
しかし、当初明細書等の「レンズアレイ20は、平面視において、レンズ アレイ20の外縁の一部が凹部82bの内側に位置するように配置されて いるとともに(図8中の開口部Gを参照)、凹部82bの外側において接着 剤により封止部材80に固定されている。」(【0040】)との記載及び 「開口部Gの数及び配置は、レンズアレイ20の外縁の一部を凹部82b の内側に位置させるものであればよく、図8に図示した数及び配置に限定 されるものではない。」(【0041】)との記載によれば、実施形態4に 係る記載は、レンズアレイ20の外縁の一部を凹部82bの内側に位置さ せるという位置関係によって開放空間を形成するのであって、そこでは、 そもそも接着剤の配置は問題とされていない。また、当初明細書等の【0042】の記載は、発明が実施形態3、4に限定されないことを示すにすぎない。
ウ 原告は、当初明細書等の【0040】の記載から直接的に「レンズアレイ 20の外縁の一部が凹部82bの内側に位置するように配置されていると ともに、凹部82bの外側において接着剤により封止部材80に固定され ている」ことにより、レンズアレイ20と封止部材80との間の空間が開 放空間となっていると理解できる旨主張するところ、これは、「レンズアレ イ20の外縁の一部が凹部82bの内側に位置するように配置されている」 ことと、「凹部82bの外側において接着剤により封止部材80に固定さ れている」ことが相まって、レンズアレイ20と封止部材80との間の空間が開放空間となっているとするものである。しかしながら、【0040】 の当該記載は、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配されている ものであり、本件接着剤配置を前提としない実施形態3を説明する【00 37】の「レンズアレイ20は、平面視において、凹部82bの内側に貫通 孔Fを有するとともに、凹部82bの外側において接着剤により封止部材 80に固定されている。」という記載と、「レンズアレイ20は、平面視に おいて、・・・とともに、凹部82bの外側において接着剤により封止部材 80に固定されている」という文言で一致しており、接着剤の配置が開放 空間の形成に寄与することを示すものとは認められない。
また、原告は、実施形態3において、レンズアレイ20に貫通孔Fが設けられていない構造は、封止部材80とレンズアレイ20の間の空間は開放空間とはならない構\造であることが理解できることを前提に、当業者は、請求項2補正事項を明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより、導くことができる旨主張する。しかし、実施形態3に係る当初明細書等【0037】〜【0039】及び図7、特に【0038】の「これに対して、接続部24に貫通孔Fを設ければ、レンズアレイ20と封止部材80との間の空間が開放空間となるため、接着剤から気化したガスを当該空間外へと逃がし、有機物の堆積(集塵)を抑制しやすくなる。開放空間とは開放された空間をいう。」との記載に鑑みれば、貫通孔Fを開放空間形成の手段としていることが明らかであり、貫通孔Fが設けられていない構成についての記載や示唆もなく、ほかに、実施形態3に関する記載から貫通孔Fが設けられていない構\成を当業者が理解することができることを示す証拠もないことから、上記前提自体が認められない。
エ 以上のとおり当初明細書等の全ての記載を総合しても、本件接着剤配置が開放空間の形成に寄与するという技術的事項を導くことはできない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2024.08. 9
令和5(行ケ)10084等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年7月17日 知的財産高等裁判所
甲8文献は、平成15年9月19日公開された発明の名称を「ロータおよびその製造方法」とする特許出願の公開公報(特開2003−264963)である。甲8文献に記載された技術は、ロータ軸に接着剤を用いて焼結磁石を固定したロータおよびその製造方法に関するものであり(甲8文献の段落【0001】)、甲8文献の図1(a)及び(b)には、ロータ10は、ロータ軸12の外周面上に周方向に沿って配列された複数の磁石片20と、複数の磁石片20を外周面に固定する接着剤層14とを備えていること(甲8文献の段落【0021】)が記載され、甲8文献の図1において、複数の磁石片20がロータ10に互いに隙間を空けて貼設されていることが記載されている。\n
(エ) 甲9文献(日本接着学会誌 Vol.39、No.9〔2003/9/1〕「構造接着技\n術の応用展開と最適化技術の構築」原賀康介)には、モーターの磁石接\n着について、甲9文献の図7は、モーターのロータ―の構\造を示してお り、スパイダーにセグメント状の永久磁石が接着されており、磁石の接 着には、従来から加熱硬化型エポキシ系接着剤が使用されてきたが、ネ オジウム系磁石は線膨張係数が0からマイナスであるため、加熱硬化では熱応力が大きく耐ヒートサイクル性に劣ることや加熱硬化で作業性に劣るため、最近は生産性に優れた2液室温硬化型の耐熱性アクリル系接着剤に変わりつつあることが記載されている。
(オ) 甲5文献は、平成17年6月2日公開された発明の名称を「回転電機 のロータ」とする特許出願の公開公報(特開2005−143248) である。甲5文献に記載された技術は、発電機やモータ等の回転電機に 使用されるロータに関するものであり(甲5文献の段落【0001】)、 その実施形態である甲5文献の図1及び図3のアウターロータ5は、ロ ータ本体50と、ロータ本体50に固定された複数個の磁石部7とを有 し、磁石部7は、ロータ本体50のリング部55の内周領域57におい て周方向に間隔を隔てて保持された永久磁石で形成されていること(甲 5文献の段落【0030】〜【0034】、図3)、磁石部7は接着剤 等により 方向に間隔を隔てて形成された着座溝61に接合されている (甲5文献の段落【0034】)、上記実施形態は、回転電機として働 くモータのアウターロータ、インナーロータに適用しても良いこと(甲 5文献の段落【0072】)が記載されている。そして、甲5文献の図 1には実施形態の発電機の断面図が、甲5文献の図3には発電機のアウ ターロータのうち磁石部をリング部が保持している状態の異なる方向の 部分断面図が、それぞれ記載されている(甲5文献の段落【007 8】)。
(カ) すなわち、甲5文献においては、磁石を保持する態様として、アウタ ロータ型電動モータでは、ステータの外周側(ロータの内周側)に複数 の磁石が相互に隙間を空けて配置されることが記載されている。また、 甲8、9文献においては(甲70、71文献にも同様の記載があること から、当時の技術常識と認められる。)、接着剤固定法では、通常、エ ポキシ系やアクリル系などの接着剤で固定する方法により貼設されるこ\nとが、それぞれ記載されている。
イ 以上を踏まえ、相違点II)について検討すると、アウタロータ型電動モー タにおいて、磁石を保持するために、複数の磁石をステータの外周側(ロ ータの内周側)に沿って配置し、接着剤固定法等により「貼設」すること\nは、周知技術であると認められる(甲5、8、9)。したがって、上記周知技術を適用して、相違点II)の構成とすることは当業者にとって容易想到であったというべきである。\n
ウ この点について、被告は、主引例の甲1発明と、副引例(甲5、8、9) の各技術の課題は相互間でも異なるから、組み合わせることに動機付けを 肯定する余地はないなどと主張する。しかしながら、前記のとおり、これ らの副引例(甲5、8、9)に記載された磁石の配置及び固定方法は、周 知技術であると認められるから、これを適用することの動機付けを肯定す ることが困難ということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2024.08. 9
令和5(ワ)5412 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和6年7月2日 大阪地方裁判所
原告各作品は、コーヒー豆等を収納するガラス製の保存容器(キャニスター)で あるから(争いなし)、実用目的を有する量産品であるといえる。原告各作品が、 保存容器という実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して、美術 鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているか否かについてみると、原告各作品は、 ストレートガラスカップと木製の蓋から構成されており、ストレートガラスカップ\nに装飾のある木製の蓋を組み合わせること自体はアイデアであるところ、前者(ス トレートガラスカップ部分)には、保存容器として必要な機能に係る構\成と分離し て、美術鑑賞の対象となり得る美的特性が備わっているとは認められない(原告も この部分について、創作的表現が備わっている旨の主張はしていない。)。また、\n後者(木製の蓋部分)は、先端側から順に略球形、円盤型、円錐型からなる3段か ら構成され、各段の境目はくびれの構\成となっているところ、このような構成は持\nち運びや内容物の収納、ストレートガラスカップに対する蓋の着脱を容易するため に必要な構成であるから、実用目的を達成するために必要な機能\に係る構成と分離\nして、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとはいえない。また、仮に、 保存容器(キャニスター)の実用目的を達成するために、その蓋部分の構成をフィ\nニアル状にする必然性はないとして部分的には実用目的を達成するために必要とは いえない構成が含まれると解するとしても、略球形、円盤型及び円錐型を組み合わ\nせていくつかの段を構成し、各段の境目がくびれている木製の装飾は、骨董品に用\nいられるなど、かなり前から家具等で広く用いられていたこと(乙3、4)、原告 がP10を制作する以前の平成25年時点において、略球形や円盤の形状のいくつ かの段が設けられ、各段の境目がくびれている木製の蓋が細いガラス瓶に接着され た作品(乙2・5枚目)が存在していたことなどの事情も踏まえると、原告各作品 の上記蓋部分の構成はありふれたものであって、美術鑑賞の対象となり得る美的特\n性である創作的な表現を備えているとはいえない。したがって、原告各作品は、創作性がなく、著作物であると認めることはできな\nい。
2 争点2(複製又は翻案の有無)について
なお、事案にかんがみ、依拠性についても検討する。 原告は、被告各作品は原告各作品に依拠している根拠となる事情として、被告P 2が令和2年1月に原告各作品の取扱いを求めたが原告がこれを断ったこと、令和 4年10月以降に被告店舗で被告各作品が展示、販売されていること、及び、被告 P3が原告のインスタグラムのアカウントをブロックしたことを挙げる。 しかし、上記1のとおり、原告各作品の蓋部分のフィニアル状の装飾は、従来か ら類似の装飾が広く存在するありふれたものであること、原告各作品と被告作品1 及び同2を比較しても、木製の蓋部分の形状は、先端部分や2段目の円盤部分、3 段目の円錐部分など複数の点において相違し、作品の印象にも相応の差異がもたら されていること、被告各作品の制作にあたって実施された両被告間の話合いにおい て、原告各作品に言及された事情はうかがわれないこと(乙8)などを踏まえると、 原告主張の上記各事情を前提としても、依拠性を認めることはできず、他に、依拠 性を認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2024.08. 8
令和6(行ケ)10004 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年5月28日 知的財産高等裁判所
上記(4)アによれば、本件審決がされた時点において、本願商標の指定商品 等につき、「商品の原材料が粗くこされたものであること(粗くこした原材料 を使用した商品であること)」を表現するための語として、「あらごし」の文\n字や、「あらごし」の同義語である「粗濾し」「粗ごし」等の文字が広く使用 されている実情があるものと認められる。 その中には、「粗くこしたみかん」を原材料とする商品を含め、原材料であ る果実(梅、りんご、ゆず及び桃など)をあらくこして、果実の繊維や果肉 などを残した商品の事例も存在する(上記(4)ア(ア)、(エ)、(カ)ないし(ソ)など)。 また、本願商標の指定商品中の「日本酒」に含まれる商品「にごり酒」に ついては、原材料である醪(もろみ)を「あらごしして」ないし「粗くこし て」製造するものであること(上記(4)ア(ウ)、(オ)など)からも、「あらごし」 の語が、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、広く親しまれている ものということができる。
さらに、本願商標の指定商品と関連する、ジュース飲料を取り扱う分野に おいて、「みかん」を原材料とする飲料に「あらごしみかん」の文字が使用さ れている事例(上記(4)ア(タ))もあることが認められる。 そして、上記(4)イによれば、本願商標の指定商品中の「リキュール」等に おいて、「みかん」を原材料とする商品が多数販売されていることが認められ る。
本願商標は、「あらごし」の文字と、「みかん」の文字とを組み合わせてな るところ、上記のとおりの本願商標の指定商品等についての取引の実情によ れば、本願商標をその指定商品に使用するときは、それに接する需要者、取 引者において、「粗くこしたみかん(みかんを粗くこしたもの)」ほどの意味 合いが認識されるものということができる。 そうすると、本願商標は、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、 単にそれが「商品の原材料であるみかんが粗くこされた商品(粗くこしたみ かんを使用した商品)」であること、すなわち、商品の品質を表してなるもの\nと理解、認識されるというべきである。
以上によれば、「あらごしみかん」の語は、本願商標の指定商品との関係で、 商品の質を表示するものとして取引に際し必要適切な表\示であり、本願商標 の需要者、取引者によって当該商品に使用された場合には、商品の質を表示\nしたものと一般に認識されるものというべきであるから、本願商標の指定商 品について商品の質を普通に用いられる方法で表示する標章であるといえる。\nしたがって、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を 普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法\n3条1項3号に該当する。本願商標の商標法3条1項3号該当性について、 本件審決の判断に誤りはないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.07.29
令和3(ネ)10086 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年4月25日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すると、402W製品は、遅くとも被控訴人 からカナデンに納品された平成24年4月17日頃には、同社に譲渡されたことに よりその構造が解析可能\な状態に至ったものと認められる。 これに対し、控訴人パナソニックは、上記アの認定事実を認めるに足りる証拠が\nないことを指摘すると共に、仮に平成24年4月17日頃に被控訴人からカナデン に対して402W製品が納品されたとしても、被控訴人とカナデンとの間に秘密を 保持することが暗黙のうちに求められていたため、公然実施されたとはいえないな どと主張する。
しかし、本件申請書は、その書面の体裁等に鑑みると、被控訴人において内部的\nに定形化された書式に基づき作成されたものと見られ、日常的な業務の一環として 作成されたものであることがうかがわれる。また、その記載内容並びに「申請者印」\n欄及び「完了印」欄の押印は、平成24年4月16日付け「見本品引取書」(乙7 8)及び同月17日付け「判取票」(乙88)の記載又は押印と一致ないし整合す ることから、本件申請書の作成日は、上記認定のとおり、同年2月10日と認めら\nれる(なお、同様の理由及び筆跡の字体そのものから、判取票の作成日付は、同年 9月17日ではなく同年4月17日であることも認められる。)。また、上記「判 取票」は、カナデン担当者(乙148)の姓と同一の印影が存在することから、平 成24年4月17日に同社に402W製品が納品されたことを裏付けるものといえ る。
また、本件申請書には、「処理方法」の「渡し切りサンプル(点灯試験・分解テ\nスト)」欄にチェックがされているものの、カナデンは、電気工事業等の建設業許 可を得ている事業会社であり(乙76)、また、被控訴人による402W製品の商 品開発に共同研究その他の形で関与していたことをうかがわせる事情も見当たらな いこと、本件チラシ及び本件カタログの記載からは、カナデンに納品された平成2 4年4月頃又はこれに極めて近接した時点で、402W製品は既に一般向けに販売 されていたことがうかがわれることによると、カナデンに対する402W製品の納 品が、その構成等につき同社に守秘義務を負わせることを前提として行われたもの\nであるとは考え難い。その他控訴人パナソニックが主張する点を考慮しても、この点に関する控訴人パナソ\ニックの主張は採用できない。
ウ 小括
以上によると、402W発明は、本件原出願日2より前に日本国内において公然 実施された発明といえる。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.07.29
令和3(ワ)18031等 特許権 民事訴訟 知的財産裁判例 令和6年3月22日 東京地方裁判所
ウ 乙12の各構成が本件発明の構\成要件JないしMの構成にそれぞれ相当\nするか否かを検討する前提として、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電\n話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 原告らは、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信す\nるための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能\を特定して いるから、請求項1ないし4の解釈を踏まえて請求項5に係る本件発明 の構成を認定すべきであると主張するものと解される。\n
そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記 載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するた めのRFIDインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の 発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信 し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報 であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ 以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わ される受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本 件発明に係る特許請求の範囲の請求項5には、受信装置とは別の他の装 置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記 載されているものと理解できる。
そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求 項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構\成要素、組成、 作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に\n係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲 を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能\等を何ら特 定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を 特定するために意味を有しないといえる。
本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Jの「RFIDインター\nフェースを有し、」との記載は、受信装置が「RFIDインターフェース を有し」ていることを、構成要件Kの記載は、受信装置が「個別情報の発\n信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要\n件Lの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求し た個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成\n要件Mの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記 要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理 を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件\nJの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、 上記の構造、機能\等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機\n能等を請求項4記載の構\成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機\n能等自体を何ら特定していないから、「請求項4記載の携帯電話」との記\n載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認 めることはできない。
以上によれば、上記の「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するた めの」を除外して請求項5に係る本件発明の要旨を認定することが相当で あるというべきであって、原告らの上記主張を採用することはできない。
・・・
以上によれば、本件発明は、乙12発明と同一の構成を有しているから、\n新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの と認められ、原告らは被告に対してその権利を行使することができない(特 許法104条の3第1項、123条1項2号、29条1項3号)。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 要旨認定
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.07.29
令和6(行ケ)10002 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年5月23日 知的財産高等裁判所
本件明細書等における、白色繊維と黒色繊維の混合比率を変えた実施例 1ないし7と比較例1及び2による試験によれば、この混合比率と、繊維 の縦及び横の強度及び伸度とは、相関関係はないといえる(段落【004 8】の試験結果)。また、光の反射性は、黒色繊維の混合比率を高めるほど 眩しさを感じにくくなる(段落【0050】)。そして、本件明細書等にお いて、黒色繊維を10%未満の割合で混合した比較例との対比は行われて おらず、比較例1及び2は、全て白色繊維のもの及び全て黒色繊維のもの であるから、白色繊維と黒色繊維の混合比率を、10ないし90%の範囲 とした場合と、10%未満とした場合との効果の差異は、本件明細書等に 記載された実施例及び比較例による試験からは明らかでない。
以上によれば、本件発明2について、黒色繊維の混合比率を高めると、 1)斑が形成され、これを用いて不織布の伸び率を把握することが可能とな\nり、2)光の反射を抑えて眩しさを感じにくくなり、3)耐候性及び耐摩耗性 が高まり、他方、黒色繊維の混合比率を高くしすぎると、全体の色が濃く なって斑を識別するのが困難になるという結果が生じるが、本件発明2に おいて黒色繊維の混合比率を10ないし90%の範囲としたことに特段 の技術的意義があるとは認められない。
エ 上記ア及びイのとおり、カーボンブラックが、耐候性、耐摩耗性及び遮 光性の向上、光の反射による作業者への作業上の障害の防止、景観を損な うことの防止等を目的として、所望の効果が発揮できる量で土木工事用不 織布を含む土木工事用シートに添加されているものであること、及び、土 木工事用の防砂シート(不織布又は織布)として用いられる製品の色の濃 さが一様でなく、白色の製品、灰色の斑模様の製品とともに濃灰色ないし 黒色の製品も使用されていることが、本件出願日の時点における技術常識 であったと認められ、白色繊維と黒色繊維を混合した土木工事用不織布に おける黒色繊維の混合比率が多様なものであると当業者が認識していた ということができる。
また、上記ウのとおり、本件発明2についても、黒色繊維の混合比率を 10ないし90%の範囲としたことに特段の技術的意義があるとは認め られない。
そうすると、引用発明1の土木工事用不織布において、耐候性、耐摩耗 性及び遮光性の向上、光の反射による作業者への作業上の障害の防止、景 観を損なうことの防止、並びに不織布の伸び率測定のための斑模様の明確 さを好適なものとするために、カーボンブラックにより着色した黒色繊維 の比率を増減することは、当業者の設計事項にすぎないというべきである。 また、白色繊維と、カーボンブラックにより着色した黒色繊維を混合し た土木工事用不織布において、黒色繊維の割合を高めれば、斑模様が濃く なって、斑点の間の距離の測定に基づく不織布の伸び率の測定が容易にな るほか、耐候性、耐摩耗性及び遮光性の向上、光の反射の抑制といった効 果があることが、上記のとおり本件出願日の時点における技術常識であっ たといえるから、黒色繊維の比率を7.5%より高める動機付けがあった ということができる。
以上によれば、引用発明1について、黒色繊維の混合比率が7.5%と されているところ、これを10ないし90%の範囲とすることによって、 相違点2に係る構成を導くことは、当業者が容易に想到することができた\nものというべきである。
オ 本件審決は、800Z製品は一定の品質を保って製造されるものであり、 白色繊維と黒色繊維の比率を変えるような設計変更は通常行わないとか、 800Z製品の製品仕様書(甲22)では黒色の綿の混率が5%と記載さ れていることを指摘した上で、製品仕様における黒色繊維の比率5%を桁 の異なる10%以上にすることには阻害要因があると判断している。 しかし、800Z製品について、製品の同一性あるいはその品質を維持 するために、仕様書で定められた仕様の遵守が求められるとしても、同製 品を基に、仕様の一部を変更して、新たな仕様の土木工事用不織布の製品 を開発、製造しようとすることは当然に行われることであって、800Z 製品の仕様として黒色繊維の比率が特定の値に定められているからとい って、この値を変更することに阻害要因があると認められることにはなら ず、800Z製品の使用における黒色繊維の比率が1桁である5%とされ ていることから、この比率を2桁の10%にすることに阻害要因があると 解することもできない。
そして、前記ウ及びエのとおり、黒色繊維の比率を特定の割合又は特定 の範囲に定めることについて特段の技術的意義があるとは認められず、か つ、カーボンブラックにより着色した黒色繊維の比率を高める動機付けが あったといえることからすれば、引用発明1について、その黒色繊維の比 率を、上記仕様書に記載された数値から変更することに阻害要因があると は認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2024.07.21
令和5(行ケ)10123 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年5月21日 知的財産高等裁判所
(2) 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕のとおり、本件商標が商標法4条1 項7号に該当すると主張するが、この主張の根拠の一つとして、被告が、被 告と原告との混同を生じさせる目的で本件商標の登録出願を行ったものであ り、被告が本件商標を使用することによって被告と原告との混同が生じてい ることを挙げているので(前記第3の1〔原告の主張〕(1)、(2)、(4)エ、オ)、 まずこの点について検討する。
ア 本件商標は「世界メシア教」の文字を横書きしてなるものであり、「セカ イメシアキョウ」との称呼が生じ、「教」が宗教を意味し、宗教団体の名称 の末尾に付されることがある事実は周知であるといえるから、何らかの宗 教団体との観念が生じるといえる。 これに対し、引用標章は、「世界救世教」の文字よりなり、「セカイキュ ウセイキョウ」との称呼が生じ、何らかの宗教団体との観念が生じるとい える。
本件商標と引用標章の類否について検討する。
まず、外観に関し、両者は、「世界・・・教」という点で外観が共通する 点があるものの、本件商標は6文字で構成され、引用標章は5文字で構\成 されていて、全体の構成文字数が異なる上、本件商標の3文字目から5文\n字目の「メシア」の文字と、引用標章の3文字目及び4文字目の「救世」 の文字が相違していることから、本件商標と引用標章は全体として外観が 相違する。
また、称呼に関して、両者は「セカイ・・・キョウ」という点で称呼が 共通する点があるものの、本件商標から生じる称呼である「セカイメシア キョウ」と、引用標章から生じる呼称である「セカイキュウセイキョウ」 は、その音の数が異なる上、各呼称を構成する「メシア」の音と「キュウ\nセイ」の音が相違していることから、本件商標と引用標章は、全体として 称呼が相違する。
さらに、観念に関し、本件商標と引用標章は、いずれも何らかの宗教と の観念が生じるという点で観念において共通する点があるが、どのような 宗教であるかは本件商標及び引用標章からは明らかではなく、また本件商 標の「メシア」の語は世の人々を救う「人物」を意味する語であるのに対 し、引用標章の「救世」の語は「世の人々を苦しみの中から救うこと」と いうように「行動」を意味する語であるから、観念において類似するとは いえない。したがって、本件商標と引用標章は、外観及び称呼が異なり、観念にお いて類似するとはいえないから、その類似性の程度は低い。
イ(ア) 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)及び(2)のとおり、原告を指し 示すものとしての「世界メシヤ教」、「世界メシア教」あるいは「メシヤ 教」、「メシア教」との名称が社会に浸透しており、本件商標はこれらの 名称に類似していると主張する。 しかし、原告が「世界救世教」の「救世」に「メシヤ」と振り仮名を 付して「セカイメシヤキョウ」と称していたのは、Aが宗教団体として 世界救世教を設立した昭和25年から、原告が「世界救世教」を「セカイキュウセイキョウ」と呼ぶように改めた昭和32年までであり、その 期間は約7年にすぎない上、本件商標の登録出願及び登録査定の時点か ら60年以上も前のことである。 本件商標の需要者は、その指定役務との関係から、宗教に関心のある 者のみならず、広く一般の消費者と認められるところ、上記の事情から すれば、本件商標の登録出願及び登録査定の時点において、「世界メシヤ 教」が原告を指す名称であるとの事実が本件商標の需要者に周知であっ たとは認められない。
また、同様に、本件商標の登録出願及び登録査定の時点において、「世 界メシア教」、「メシヤ教」又は「メシヤ教」が原告を指す名称であると 本件商標の需要者に周知であったとも認められない。
(イ) 原告は、原告について記載した書籍、雑誌、インターネット上の記事等 において、「世界メシア教」等の名称が原告を示すものとして表示されて\nいると主張し、複数の書籍の写し等(甲13〜17、78、80〜83、 107〜109)を証拠として提出する。 しかし、書籍、雑誌、インターネット等に宗教法人あるいは宗教団体 に関して説明した記載があったとしても、当該説明に記載された事実が 広く一般に知られた事実であると直ちに認められることにはならない。 また、原告が証拠として提出した各書籍等の内容について検討すると、 まず、甲13の添付資料とされている書籍又は印刷物は、いずれも原告 又は「世界救世教いづのめ教団」が編集したものであり、その信者を対 象として発行された書籍又は印刷物であると認められ、信者以外の者が これらの書籍又は印刷物に記載された内容を広く認識するに至ったとは 認められない。
甲14ないし16及び107ないし109の書籍等は、いずれも辞典 又は事典(インターネット上の記載を含む。)であり、「世界メシア教」、「メシヤ教」又は「メシア教」の項において、「世界救世教」の項を参照 すべき旨の記載が存在することが認められるものの、これらの記載は、 原告が過去に「世界救世教」を「セカイメシヤキョウ」と称していた事 実を踏まえたものにすぎないと考えられる。 それ以外の書籍の写し等(甲17、78、80〜83)には、「世界救 世教」が「メシア教」若しくは「世界メシヤ教」とも称されている旨の 記載、又は原告を指す名称として「メシア教」の語を用いているものと 解される記載が存在すると認められるが、これらの書籍等については、 その発行日から相当の時間が経過していると認められるか、又は書籍の 発行若しくはインターネット上の記載がされた時期が不明である。 以上を総合すると、原告が証拠として提出する上記書籍等をもって、 「世界メシヤ教」、「世界メシア教」あるいは「メシヤ教」、「メシア教」 の名称が原告を指すものであると広く一般に知られているとは認められ ない。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)によれば、本件商標の登録出願及び登録査定の時点にお いて、「世界メシヤ教」、「世界メシア教」あるいは「メシヤ教」、「メシア 教」との名称が原告を指すものであるとの事実が、本件商標の需要者に 周知であったとは認められない。 そうすると、「世界メシヤ教」、「世界メシア教」あるいは「メシヤ教」、 「メシア教」が原告を指す名称であることが社会一般に広く知られてい るために、本件商標をその指定役務に使用することによって、その出所 が原告であるとの混同が生じるとは認められない。
ウ 上記ア及びイによれば、本件商標をその指定役務に使用することによっ て、その出所が原告であるとの混同を生じるおそれがあるとは認められな い。 熱海新聞が、被告に関する記事において、その名称を「世界救世教」と 記載した事例(甲95)をもって、本件商標をその指定役務に使用した場 合に出所の混同が生じると認められることにはならない。 そして、本件商標をその指定役務に使用することによって上記内容の混 同を生じるおそれがあると認められないことからすれば、被告が、上記内 容の混同を生じさせる目的で本件商標の登録出願をしたとも認められな い。 前記(1)の認定事実によれば、原告が被告との包括・被包括関係を廃止し、 被告がこれを争っており、現在でも原告と被告との間の訴訟が係属してい るなど、原告と被告との間に対立関係があることが認められるが、このこ とをもって、被告が被告と原告との混同を生じさせる目的で本件商標の登 録をしたと認められることにはならない。
(3) 原告は、本件商標が商標法4条1項7号に該当するとの主張の根拠の一つ として、被告が本件商標を使用すれば、取引者及び需要者をして、「世界メシ ア教」なる名称を有する宗教団体が存在し、その宗教団体が商品又は役務を 提供しているとの誤解を生じさせるとともに、被告がその規則に定めた名称 と異なる「世界メシア教」の名称を用いて活動を行うことは宗教法人法に違 反しており、本件商標の登録を認めることは被告の違法な行為を助長するも のであって、商取引の秩序を混乱させるものであることを挙げる(前記第3 の1〔原告の主張〕(3)、(4)アないしオ)。
この点について検討すると、被告が本件商標をその指定役務に使用した場 合に、本件商標の取引者及び需要者が、「世界メシア教」という名称の宗教団 体が当該役務を提供していると認識するとしても、被告とは別の「世界メシ ア教」という名称の宗教団体が存在しており、当該宗教団体が当該役務を提 供していると認識するとは認められない。仮に、被告とは別の「世界メシア 教」という名称の宗教団体が存在するとの認識を有する者がいたとしても、 そのことをもって、本件商標が公正な商標秩序に反し、著しく社会的相当性 を欠くものであると解されることにはならない。
また、宗教法人が、その規則において定める名称と異なる別称を用いて活 動することが宗教法人法に違反するか否かと、当該宗教法人が当該別称と同 一の文字からなる商標の登録を受けることが商標法上許容されるか否かとは、 関連性のない別個の問題であって、仮に前者が違法であると解されるとして も、そのことによって、当該別称と同一の文字からなる商標が商標法4条1 項7号に該当することにはならない。なお、文化庁による宗教法人の管理運 営に関する書籍(甲85、86)は、宗教法人の規則に定める運営方法と実 際の運営方法が一致することが必要である旨記載しているにすぎないのであ って、宗教法人の管理運営上、規則で定めた名称と活動名称が一致すること まで要求しているものではなく、現に、規則上の名称と異なる名称で活動す る宗教法人は、被告以外にも現実に複数存在することが認められる(乙7〜11)。 原告が挙げる商標審査便覧42.107.36「『会社』等の文字を有する 商標の取扱い」(甲96)については、そもそも商標審査便覧は何ら法規範性 を有するものではないが、この点を措くとしても、上記商標審査便覧42. 107.36は、その表題にあるとおり、「会社」等の文字を有する商標に関\nする基準であり、その(2)に「自己の商号と異なる商号を自己の商標として採 択・使用すること」とあるのは、会社の商号と異なるが「株式会社」などの 会社の種類を示す文字が含まれる標章を採択・使用することを指すと解され るところ、本件商標には会社や法人の種類を示す文字は含まれない。また、 上記商標審査便覧42.107.36は、会社がその商号とは異なる名称(会 社の種類を示す文字を含まない名称)を用いて活動をしている場合に、当該 名称と同一の文字からなる商標が商標法4条1項7号に該当すると述べてい るものではない。したがって、上記商標審査便覧42.107.36の記載 内容をもって、本件商標が公正な商標秩序に反し、著しく社会的相当性を欠 くものであると解することはできず、本件商標が商標法4条1項7号に該当 すると解すべきということにもならない。
以上によれば、被告が「世界メシア教」の名称を用いて活動することが宗 教法人法に違反するか否かを判断するまでもなく、被告が規則において定め る名称と異なる「世界メシア教」の名称を用いて活動していることは、本件 商標が商標法4条1項7号に該当すると解する根拠とならないというべきで ある
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.07.21
令和3(ワ)2873 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年5月30日 大阪地方裁判所
原告は、被告が、本件書類提出命令にもかかわらず、正当な理由なく、本件提出 対象書類を提出しなかったなどとして、民訴法224条3項により、本件証明事実 を真実であると認めるべきであって、前記被告製品10台に係る限界利益を157 3万8528円と認定すべきである旨主張する。 この点、確かに、被告が本件書類提出命令に応じて本件提出対象書類を提出した とは認められないものの、本件証明事実に係る原告の主張によると、被告製品10 台の利益率は6割を超えるものとなって、合理的とは言い難いことから、被告の限 界利益の額を前記のとおり認定するのが相当である。
(3) 損害の不存在ないし推定覆滅について
ア 被告は、佐賀県畜産公社においては、被告製品の購入に当たって競争入札が 行われたところ、原告と被告が入札して被告が落札したのであって、落札により販 売業者は1社に決定されるから、原告と被告が競合するような市場は存在せず、侵 害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情は存在しないとした上 で、ミヤチク、いわちく及びフードパッカー津軽についても同様であって、原告に 損害はなく、特許法102条2項は適用されない旨主張する。 しかしながら、そもそも、被告が主張する競争入札の存在や具体的内容が明らか ではないところ、佐賀県畜産公社においては、競争入札自体は行われたとしても、 原告も同じ競争入札に参加していたというのであるし、その他の入札についても原 告に参加資格があり、落札したとされる被告が参加していなければ(本件特許権の 侵害品である被告製品がなければ被告は参加できなかったと考えられる。)、原告 が落札した可能性もあることを考慮すると、原告において被告の侵害行為がなかっ\nたならば利益が得られたであろうという事情は存在しない旨の被告の主張は採用で きない。
イ 被告は、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」が本件発明の 唯一の特徴的部分であるといえるところ、仮に被告製品がこの構成要件を充足する\nとしても、利益に対して貢献しているのはその余の侵害品の性能(機能\、デザイン 等特許発明以外の特徴)であって、損害の推定覆滅事情に当たる旨主張する。しか しながら、筒状容器の「内壁が平面視で多角形状に形成される」部分以外で顧客誘 引力のある被告製品の具体的性能や、その性能\の顧客に対する訴求の程度は明らか でないから、被告の主張は採用できない。
ウ さらに、被告は、本件発明では旋回流を利用するのに対して(甲5)、被告 製品(乙15)では、突部9(別紙「被告製品写真・図面」の図2参照)が邪魔 板(バッフル)となって旋回流を阻害することで、上下循環流発生を発生させ、豚 足をランダムな動きとするものであり、また軸流においては豚足が下方へ潜り込ん でいくこと、邪魔板(バッフル)に衝突することによる脱毛、豚足同士の水平方向 及び上下方向の衝突による脱毛の効果が甚だ大きく、性能において本件発明と比較\nして顕著な相違があるから、特許法102条2項の推定は覆滅される旨主張する。 この点、原告製品の動画(甲5)と被告製品の動画(乙15)とを比較すると、 豚足の動きに一定の差があり、被告製品では豚足が下に潜り込むような動きをして いるように見え、被告が主張する上下方向の動きがあることがうかがわれる。かか る動きによる豚足の脱毛効果への影響の程度や、その性能の被告製品の売上げへの\n貢献の程度は必ずしも明らかでなく、前記の性能を理由とする推定覆滅が認められ\nるとしても、その割合は、5%を超えるものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2024.07.21
令和6(行ケ)10011 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年7月8日 知的財産高等裁判所
(1) 本願商標は、「デジタル医療モール」の文字を標準文字で表してなるも\nのであるところ、本願商標の構成中、「デジタル」の文字は「情報や命令を、\n0と1〔=スイッチオフとスイッチオン〕の信号の集まりで表現する<こと\n/もの>」、「コンピュータを(めいっぱい)使うようす」(以上、乙1) を、「医療」が「医師・看護師が患者の治療やせわをすること」(乙2)、 「モール」が「(屋根つきの)大きな商店街」など(乙3)を意味する平易 な語であるから、本願商標の構成を元に観察すれば、「デジタル」の語と\n「医療モール」の語からなると理解することも、あるいは「デジタル医療」 の語と「モール」の語からなると理解することも不可能ではない。\nしかしながら、証拠(甲17、18、25〜29、乙8〜15)によれ ば、「デジタル」の文字は、他の語と結合した「デジタル〇〇」の態様で 「デジタル技術を用いた〇〇」ほどの意味合いで汎用的に広く用いられてい ることが認められ、デジタル技術を利活用した医療や治療に関して、「デジ タルセラピー」(甲17)、「デジタル医療」(甲18、26〜29、乙8 〜11、14、15)、「デジタル治療」(甲25、乙8、12、13)、 「デジタルヘルス」(乙8)と称されている実情があることが認められる。 また、証拠(甲20〜22、乙16〜23)によれば、「医療モール」 の文字は、「診療科が異なるいくつかのクリニックが1カ所に集まっている 運営形態」(甲20)といった語として広く使用されていることも認められ る。
(2) 以上のような実情を踏まえると、本願商標は、「デジタル」技術を利活 用して行われる仮想的な「医療モール」、すなわち「様々な医療機関に係る サービスを、デジタル技術を用いて構築した 1 か所のプラットフォーム上で 提供又は利用できる仕組み」といった意味合いを容易に理解・認識させるも のと認められる。そして、本願商標に接し、上記意味合いを理解・認識した 需要者は、本願商標について上記の仕組みの下で提供される商品又は役務で あることを表現するための語句であると理解、認識するにとどまり、自他商\n品役務の識別標識としては認識しないといえる。
(3) これに対し、原告は、本願商標について、「デジタル医療」 と「モール」 との言葉の結合であるのか、「デジタル」と「医療モール」との言葉の結合 であるのか、需要者によって認識が異なる言葉の結合からなる商標であると する主張する。
しかし、上記(1)のとおり、「デジタル〇〇」の語が、「デジタル技術を 用いた〇〇」という意味で、汎用的に広く用いられているのに対し、「〇〇 モール」の語については、ショッピングモール、医療モールといった定型的 な用法を超えて広範囲な用い方をされているとまでは認められない。そうす ると、本願商標に接した需要者の一般的な理解としては、上記(2)のとおり、 「デジタル」技術を利活用して行われる仮想的な「医療モール」という意味 合いで認識するのが自然であると解され、これと異なる前提に立つ原告の上 記主張は採用できない。なお、原告が引用する知財高裁の裁判例は、本件と 事案を異にし適切でない。
2 次に、原告は、仮に本願商標を「デジタル」と「医療モール」の結合と理 解し、上記1(2)における意味合いが想起されるとしても、「デジタル技術」 というものは様々に活用されており、一義的な技術ではなく、本願商標もい ずれの技術を利用したのか明らかでないから、本願商標からは特定の観念が 生じないと主張する。この点、デジタル技術を用いて提供されるものには原告が指摘するようなIoT、ビッグデータ、AI、ICTなどの様々な技術が考えられるが、デジタ ル技術が様々に活用されているからといって、上記1(2)の認定判断が左右さ れるものではない。原告の上記主張は、本願商標を造語と理解すべき根拠とな るものではない。
3 さらに原告は、本願商標である「デジタル医療モール」という語が、本願 商標の指定商品役務に関し、他で一般的に使用されているという実例がない ことから、本願商標は造語であり、指定商品役務との関係で識別性を有する と主張する。この点、デジタル技術を用いて提供されるものには原告が指摘するようなIoT、ビッグデータ、AI、ICTなどの様々な技術が考えられるが、デジタ ル技術が様々に活用されているからといって、上記1(2)の認定判断が左右さ れるものではない。原告の上記主張は、本願商標を造語と理解すべき根拠とな るものではない。
3 さらに原告は、本願商標である「デジタル医療モール」という語が、本願 商標の指定商品役務に関し、他で一般的に使用されているという実例がない ことから、本願商標は造語であり、指定商品役務との関係で識別性を有する と主張する。 しかし、商標法3条1項6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務 であることを認識することができない商標につき、商標登録を受けることがで きないとしたものであり、同号の適用において当該商標が現実に使用されてい ることを要求するものではない。本願商標に関して他の使用例がないことは、 上記2の認定判断を妨げるものではない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2024.07.21
令和6(行ケ)10010 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年7月8日 知的財産高等裁判所
証拠(甲11〜13、乙10〜20)によれば、「オン ライン」の文字は、他の語と結合した「オンライン〇〇」の態様で「ネット ワーク上で提供される〇〇」、「ネットワーク上で利用できる〇〇」ほどの 意味合いで汎用的に広く用いられていることが認められ、「オンラインモー ル」(乙7)、「オンラインショッピングモール」(乙8)といった用法で 使用されていることも認められる。
特に、上記「オンラインショッピングモール」は、「様々な商品の小売 販売に係るサービスをネットワーク上の1か所のプラットフォーム上で提供 又は利用できる仕組み」といった意味で用いられているものと理解され、本 件の参考になるものといえる。
また、証拠(甲14〜16、乙21〜28)によれば、「医療モール」 の文字は、「診療科が異なるいくつかのクリニックが1カ所に集まっている 運営形態」(甲14)といった語として広く使用されていることも認められ、 「オンライン上で自由診療の医療モールを作る」、「e−メディカルモール」 (いずれも甲17)といった用法で使用されていることも認められる。
(2) 以上のような実情を踏まえると、本願商標は、「オンライン」で行われ る仮想的な「医療モール」、すなわち「様々な医療機関に係るサービスを、 ネットワーク上の 1 か所のプラットフォーム上で提供又は利用できる仕組み」 といった意味合いを容易に理解、認識させるものと認められる。そして、本 願商標に接し、上記意味合いを理解・認識した需要者は、本願商標について、 上記の仕組みの下で提供される商品又は役務であることを表現するための語\n句であると理解、認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認 識しないといえる。
(3) これに対し、原告は、本願商標について、「オンライン医療」 と「モー ル」との言葉の結合であるのか、「オンライン」と「医療モール」との言葉 の結合であるのか、需要者によって認識が異なる言葉の結合からなる商標で あると主張する。
しかし、上記(1)のとおり、「オンライン〇〇」の語が、「ネットワーク 上で提供される〇〇」という意味で、汎用的に広く用いられているのに対し、 「〇〇モール」の語については、ショッピングモール、医療モールといった 定型的な用法を超えて広範囲な用い方をされているとまでは認められない。 そうすると、本願商標に接した需要者の一般的な理解としては、上記(2)の とおり、「オンライン」で行われる仮想的な「医療モール」という意味合い で認識するのが自然であると解され、これと異なる前提に立つ原告の上記主 張は採用できない。なお、原告が引用する知財高裁の裁判例は、本件と事案 を異にし適切でない。
2 次に、原告は、仮に本願商標を「オンライン」と「医療モール」の結合と 理解し、上記1(2)における意味合いが想起されるとしても、オンライン上で どのようなサービスが提供されるのか不明であるとして、需要者は本願商標 を造語として理解すると主張する。 この点、関係証拠によれば、オンラインで提供される医療サービスとしては 「オンライン診療」(甲11〜13、18、乙4、5、9〜15、19、20。 スマートフォンなどを使って病院の予約から決裁までをインターネットで行う\nもの。)、「遠隔健康医療相談」(甲13、乙16〜18)、「オンライン服 薬指導」(乙10)、「電子処方箋」(乙10)のほか、自由診療を提供して いる医療機関を集めて、オンラインメディカル(医療)モールを提供する(検 索・予約・決済・オンライン診療を提供する)もの(甲17)など、様々なも\nのがあることが認められる。
しかし、このようにオンラインで提供される医療サービスの内容が様々なも のであることは、上記1(2)で認定した「様々な医療機関に係るサービスを ネットワーク上の 1 か所のプラットフォーム上で提供又は利用できる仕組み」 という概念と何ら矛盾するものではなく、むしろ、当該理解に沿うものである。 原告の上記主張は、本願商標を造語と理解すべき根拠となるものではない。
3 さらに原告は、本願商標である「オンライン医療モール」という語が、本 願商標の指定商品役務に関し、他で一般的に使用されているという実例がないことから、本願商標は造語であり、指定商品役務との関係で識別性を有す ると主張する。
しかし、商標法3条1項6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務 であることを認識することができない商標につき、商標登録を受けることがで きないとしたものであり、同号の適用において当該商標が現実に使用されてい ることを要求するものではない。本願商標に関して他の使用例がないことは、 上記2の認定判断を妨げるものではない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2024.07.16
令和6(ネ)10011 令和6年6月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 以上のとおり、本件各発信者は、本件複製ファイルのピースを保有してい たこと、これが自動公衆送信の可能な状態にあったことは認められるが、当\n該ピースが再生可能なものか、著作物としての表\現の本質的特徴を直接感得 できるものかどうかは明らかでない。被控訴人は、そのような情報を自動公 衆送信し得るようにしても送信可能化権の侵害が明白とはいえない旨主張す\nるので、以下検討する。
ア 著作物たるファイルの自動公衆送信において、元のファイル(デジタル データ)を分割したり暗号化するなどして送信するという仕組みも想定さ れるところ、そのような形で自動公衆送信の対象となったデータだけを取 り上げた場合、デジタルデータの特性もあって、映像その他のファイルと して復元・再生できないことも、十分あり得るものと考えられる。このよ\nうなもの全てについて、当然に公衆送信権の侵害が認められるものでない としても、少なくとも、送信されるデータが著作物性の認められる元のフ ァイルの一部を構成するピースであり、かつ、これらピースを集積するこ\nとで元のファイルに復元・再生することが可能なシステムの一環としてピ\nースの送受信が行われていると認められる場合には、当該ピースの送信を もって公衆送信権の侵害があったと評価すべきである。
このような全体像を踏まえることなく、個々の公衆送信の対象となった ピースを断片的に取り上げて、著作権(公衆送信権)の侵害が認められる ためには当該ピース自体での再生が可能で、表\現の本質的特徴を直接感得 できることが必要であるとする解釈は、「木を見て森を見ない」議論とい わざるを得ず、公衆送信権の保護を形骸化させるものといわざるを得ない。 以上の議論は、送信可能化権の侵害についても妥当するものと解される。\n
イ これを本件について見るに、ビットトレントネットワークは通常一つの シーダーから始まるところ、本件動画と本件複製ファイルのハッシュ値が 一致することから、本件複製ファイルは本件動画を複製したものであるこ と、本件各発信者の保有するピースは本件複製ファイルを細分化したもの であることが認められる。本件各発信者は、ビットトレントネットワーク を形成するピアとして、本件複製ファイルの必要なピースを転送又は交換 し合うことで、最終的に本件複製ファイルを構成する全てのピースを取得\nするという目的に沿って、そのシステムの一環として、ピースの送受信を 行っているものである。 そうすると、以上のようなビットトレントネットワークの仕組みの下で 本件複製ファイルのピースの送受信が行われている本件においては、当該 ピース自体での再生が可能とはいえず、それだけでは表\現の本質的特徴を 直接感得できないとしても、公衆送信権、送信可能化権の侵害の成立を妨\nげないというべきである。
3 争点3(本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性)につい て
(1) 基本的な視点
ア プロバイダ責任制限法5条1項が発信者情報の開示請求を規定している 趣旨は、特定電気通信(同法2条1号)による侵害情報の流通は、これに より他人の権利の侵害が容易に行われ、ひとたび侵害があれば際限なく被 害が拡大する一方、匿名で情報の発信が行われた場合には加害者の特定す らできず被害回復も困難となるという、他の情報の流通手段とは異なる特 徴があることを踏まえ、侵害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、 表現の自由及び通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通\n信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に 対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより、 加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解さ\nれる。
ところで、令和3年法律第27号による改正により、従前の発信者情報 開示請求に加え、「特定発信者情報」の開示請求制度が創設された。これ は、個別の書き込みごとのIPアドレス等が記録されることが多い従来型 の電子掲示板等とは異なり、サービスにログインした際のIPアドレス等 (ログイン時情報)は記録されているものの投稿した際のIPアドレス等 を記録していないタイプのSNSサービスが現れ、そのような場合のログ イン時情報の開示につき、従来の発信者情報開示請求の枠組みで対応でき るか解釈上の疑義が生じていたことを踏まえ、立法的な解決を図ったもの である。上記改正法は、ログイン時情報を含む特定発信者情報についても 開示請求の道を開く一方、その対象となる「侵害関連通信」(プロバイダ 責任制限法5条3項、同法施行規則5条)は、それ自体としては権利侵害 性のない通信であることを踏まえ、一定の補充的な要件を求めることとし たものである(プロバイダ責任制限法5条1項)。 このような改正法の趣旨も踏まえると、それ自体として権利侵害性のな い通信を「特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求」の手続に安易に 乗せるような運用は、上記改正後のプロバイダ責任制限法5条の予定する\nところではないと解される。
イ 他方、本件においては、送信可能化権が有する特殊な性格についても、\n十分な配慮が必要となる。すなわち、著作権法は、公衆送信権を著作権の\n支分権と定めるところ(同法23条1項)、インターネットのウェブサイ ト等における公衆送信は、自動公衆送信(同法2条1項9号の4)として 行われることになる。ここでは、閲覧者(公衆)からの閲覧請求信号に応 じてサーバから情報が送信されるが、そのような自動公衆送信が実際に行 われたかどうかを著作権者が把握するのは困難である。そこで、現実の送 信の前段階における準備行為である「送信可能化」を公衆送信権の侵害行\n為類型に含めることとし(同法23条1項括弧書き)、もって権利保護の 実効化を図ったものである。送信可能化権の侵害を理由とする発信者情報開示請求の解釈適用においても、送信可能\化権の上記の意義が没却されないよう留意が必要である。
(2) 以上を踏まえて検討するに、UNCHOKE通信は、送信可能化がされた\nことを前提として、相手方ピアが保有するピースのアップロード(そのピー スを欲するピアにとってはダウンロード)が可能であることを伝えるもので\nあり、それ自体によって侵害情報の流通がされるわけでないことはもとより、 当該通信が送信可能化惹起行為(著作権法2条1項9号の5イ、ロ)に当た\nるともいえない(この点は、原判決が14頁1行目〜3行目で判断するとお りである。)。しかし、送信可能化権の侵害とは、将来に向けて想定される自動公衆送信の準備が整ったことをもって公衆送信権の侵害類型と位置付けられたもので\nあるから、自動公衆送信が可能な状態が継続している限り、その違法状態は\n継続していると解するのが相当である。著作権法2条1項9号の5イ、ロは、 上記のような違法状態を招来するいわば入口としての行為を定義したものに すぎない。
このような送信可能化権の特性に照らすと、送信可能\化権の侵害を理由に 発信者情報の開示を求める場合において、「権利の侵害に係る発信者情報」 (プロバイダ責任制限法5条1項柱書)を、送信可能化惹起行為そのものの\n通信に係る発信者情報に限定して解釈する必要はないし、それが適切ともい えない。送信可能化が完了し、その後引き続き送信可能\な状態が継続してい る限り、そのような状態であることを直接的に示す通信であれば、当該通信 に係る発信者情報を「権利の侵害に係る発信者情報」と認めることができる というべきである。そのように解さないと、著作権法が送信可能化権の侵害\nを公衆送信権の侵害行為類型として認めた趣旨が没却されることになりかね ない。他方、開示の対象とする発信者情報を上記の限度にとどめれば、情報 の発信者のプライバシー、通信の秘密等が不当に損なわれることにはならな いと解される。
SNSでの投稿により名誉毀損等の権利侵害が生ずるような場合であれば、 侵害情報の流通そのものに係る当該投稿に係る通信以外についてまで「権利 の侵害に係る発信者情報」の範囲を安易に拡張解釈すべきではないが、本件 をこれと同列に論ずることはできない。
(3) 以上の枠組みに基づいて検討するに、上述したビットトレントネットワー クの仕組み(上記第3の1(3)ウ)、本件調査会社による調査結果(同(4)イ) に照らすと、本件におけるUNCHOKE通信は、本件複製ファイルを共有 するビットトレントネットワークに参加した本件各発信者において、その保 有するピースにつき送信可能化が完了し、引き続き自動公衆送信が可能\な状 態にあることを明らかにする通信にほかならない。そうすると、UNCHO KE通信をもって特定された本件各通信に係る発信者情報は、「権利の侵害 に係る発信者情報」に該当するというべきである。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2024.07. 3
令和5(ネ)10105 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和6年6月12日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件各写真(特に本件写真3)、5))が芸術作品と呼ぶにふさわしいもの であることは、当裁判所も全面的に認めるものであり、その価値が損なわれ るのは許せないとする控訴人の心情は理解できる。
しかし、当然ながら、被控訴人は、控訴人の芸術作品を紹介したくて本 件各写真の利用を申し出たのではなく、主役である本件たばこを引き立てる道具として本件各写真を利用しようとし、NDCを通じてその対価の支払を\n提案しているのである。そして、自動販売機で最も目に付きやすいガラス面 アイキャッチャー(販売商品の見本〔たばこパッケージ〕が並んでいる部分) にたばこパッケージと同じ大きさになるようにトリミングした写真を使用す るという本件各写真の利用方法は、本件販促活動の重要な柱となっていたの であるから、仮に、控訴人がこのようなトリミングを許諾しないという意思 を明確にしていたとすれば、控訴人の写真作品を本件販促活動に利用すると いう構想自体が白紙となり、800万円の許諾料の支払合意も合意解除されることが当然予\想されるところ、現実には、本件トリミング手法を使った写真の利用がされ、控訴人は許諾料800万円を受領しているのである。
さらに、控訴人がAから本件販促用写真が使用されている自動販売機の 写真の提供を受けて、自身の写真作品について意に反した改変があったと考 えるに至ったのは令和2年秋頃である(上記1(5)ウ)ところ、その時点ま でに、控訴人とBらが本件販促活動の内容の打合せを行っていた平成16年 〜17年から15年以上もの年月が経過している。この間、本件各写真の利 用方法を巡る打合せの経過及び内容につき、控訴人の記憶が変容し又はあい まいになっていたとしてもやむを得ないところである。十数年ぶりに本件販促用写真を見て、原作品とのギャップに強い違和感を抱いたという控訴人の\n心情に偽りはないとしても、これを「意に反した改変」が行われた根拠とす ることが適切とはいえない。
2024.06.16
令和4(ワ)2058 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年5月30日 大阪地方裁判所
(1) 特許法102条2項に基づく主張について
ア 限界利益額 被告は、少なくとも令和2年6月1日から令和5年6月末までの間、被告各製品 を販売し、この間の限界利益額(被告各製品の全体)は合計8557万2953円 (税込)である。(争いなし) 被告は、被告各製品における本件訂正発明2−1、同2−3及び本件発明3の実 施部分は一部であるから、損害額算定における限界利益額は、上記一部に相当する 限界利益額を基準とすべきであると主張するが、被告の指摘する事情は、推定覆滅 事由として考慮すべきであるから、上記主張は採用できない。
イ 推定覆滅事由
特許法102条2項は損害額の推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得 た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠ける ことを主張立証した場合には、その限度で前記の推定は覆滅される。
(ア) 部分実施(本件特許2及び同3の寄与の程度等)
被告各製品は、外枠(床開口用枠体及び取付部材)、蓋セット、ビスセット、梱 包ケース、断熱材により構成されるところ、本件訂正発明2−1、同2−3及び本\n件発明3の実施部分は上記外枠のみである。(争いなし) 原告は、原告製品(高気密型床下点検口・収納庫)における本件訂正発明2−1、 同2−3及び本件発明3の実施部分の構成である「スライドコア」は、原告製品の\n使用において不可欠であり、容易かつ精度のよい施工を実現するといった重要かつ 優れた効果を有し、顧客誘引力の源泉となっているところ、「スライドコア」と強 い類似性を有する被告各製品の「外枠」も顧客誘引力の源泉となるから、上記部分 実施による推定覆滅は大きいものではない旨主張する。 確かに、原告製品のパンフレットには「スライドコア方式が簡単施工で高い気密 性を実現する」ことが記載されているが、他にも顧客を誘引するための特徴(例え ば、耐荷重性に優れていること、蓋枠パッキンによる気密性の確保、肌に優しい樹 脂一体成形品であること、バリアフリープラン対応であることなど)を有すること が記載されている(甲11の19)。また、被告各製品にも、外枠以外の構成にお\nいて、薄型化・軽量化設計であることやバリアフリー設計であること、抗菌仕様で あることといった顧客の誘引に影響する特徴がある(甲4)。外枠に関する施工の 容易性や高い気密性は需要者が注目する特徴であると考えられるものの、他の特徴 と比較して特に重視される事項であるとまでは認めるに足りず、原告製品の「スラ イドコア」ないしこれに相当する部材といえる被告各製品の外枠が、各々の製品に おいて強い顧客誘引力を有していると評価することはできない。 そうすると、被告各製品における発明の実施部分が外枠のみであるとの点は、相 当程度の推定覆滅事由になると解するのが相当である。
(イ) 市場の同一性及び市場における競合品
被告各製品及び原告製品は、樹脂枠を備えた床下点検口・収納庫である。本件訂 正発明2−1、同2−3及び本件発明3の効果は、施工の容易性や気密性及び断熱 性の確保、ガタ付きの防止であるところ、被告各製品のカタログ(甲4)によれば、 被告各製品は、床開口寸法が606×606mm(外形寸法622×622。高さ は67.5mm、182.5mm、463mmのものなど複数の型がある。)であ り、施工が容易でバリアフリー設計であり、気密性及び断熱性等を訴求している。 また、原告製品のカタログ(甲11、12〔枝番を含む。〕)によれば、原告製品 は、床開口寸法が606×606mmのものなどであり(幅広サイズなど複数の型 がある。)、防腐高気密型、高耐久、高断熱、バリアフリー等を訴求している。 これらによれば、被告各製品及び原告製品の需要者は、各製品において、床下点 検口・収納庫の形状、性能や操作の容易性を重視するものと解されるから、被告各\n製品と同程度の形状、性能、機能\及び操作性を実現し、同種の用途に用いられる製 品は競合品に該当するというべきである。
被告が競合品であると主張する製品(甲14ないし18〔各枝番を含む。以下同 じ〕、乙32、33)のうち、少なくとも、Panasonic製の床下収納ユニ ットの「高気密・高断熱住宅用」(甲14)と、DAIKEN製の「ホーム床点検 口」(甲15)は、被告各製品の寸法と同程度の型であるものがあり、性能や機能\、 操作性において同程度であるといえるから、被告各製品及び原告製品と性能、用途\n等において共通する競合品であると認められる(その余の製品については、形状や 訴求されている性能や機能\、操作性が一部被告各製品と合致するものの、同程度と までは認められない。)。他方で、床下収納点検口・収納庫の市場における被告各 製品や原告製品の市場占有率が明らかではなく、また、上記競合品の販売価格と乙 第35号証から推知される被告各製品の販売価格との間には一定の差があることは 否定できない。
以上によれば、市場において上記競合品が存在することは推定覆滅事由となるが、 これをもって大幅な推定覆滅を認めることは相当ではない。
(ウ) 被告の営業努力
特許法102条2項の推定を覆滅する事由として認められる被告の営業努力とは、 通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をいう。被告は、被告各製品の売上につ いて被告の営業努力によるところが大きいと主張するが、これを認めるに足りる証 拠はないから、この点は覆滅事由として認めることはできない。
(エ) 推定覆滅の程度
被告は、上記のほかにも被告製品の機能や工夫をもって推定覆滅事由に該当する\nなどと主張するが、証拠がなく、当該主張を採用することはできない。 以上の検討した諸事情を総合考慮すると、部分実施であること及び一定数の競合 品が存在することによる推定覆滅が認められるところ、本件においては8割の限度 で損害額の推定が覆滅されると解するのが相当である。これに反する原告及び被告 の主張はいずれも採用できない。
(2) 特許法102条3項に基づく主張について
原告は、同条2項の推定覆滅が一部でも認められたとしても、推定覆滅の理由が 「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている」という推定覆滅事由でない限り は、当該推定覆滅部分については、同条3項を適用することができると主張する。 この点、同条2項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者 が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の 売上げの減少による逸失利益に相当するものであるのに対し、同項による推定の推 定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、 特許権者は、売上げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による 実施料相当額の損害を受けたものと評価できるから、同条3項の適用が否定される ことにはならないと解される(知的財産高等裁判所令和2年 第10024号・令 和4年10月20日特別部判決参照)。 本件においては、上記競合品が存在することは同条2項による推定覆滅事由の一 つとなるが、当該推定覆滅部分について原告に実施許諾の機会があったと認めるに 足りる証拠はない。したがって、当該推定覆滅部分について、同条3項を適用する ことはできないというべきである。
(3) 以上によれば、上記(1)アの限界利益額8557万2953円から8割の推 定覆滅がされた1711万4590円(税込)が、被告の被告各製品の販売による 原告の損害であると認められる。 また、本件の事案の内容、経過等にかんがみ、原告の弁護士費用及び弁理士費用 171万円は、被告の特許権侵害行為と相当因果関係がある原告の損害と認める。 したがって、原告の損害額は1882万4590円となる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2024.06.16
令和5(行ケ)10086 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年6月5日 知的財産高等裁判所
(2) 原告は、仮に相違点5が認められるとしても、周知技術1(皮膚に電気刺 激を与えるブラシ型の美容機器において、ブラシの櫛歯を肌の形状に合わせ て屈曲できるようにすること)を考慮して相違点5に係る構成を採用するこ\nとは容易であると主張する。
ア しかし、甲1公報の「動作する際には、通常の髪をとかすように髪をと かして、シリコンスリーブ9の底端が頭皮に接触すると、ばね8が圧縮 され、スライドスリーブ4がシリコンスリーブ9を収縮させ、シリコン スリーブ9全体の底端が頭皮に接触し」([0023])の記載などか ら明らかなように、甲1発明では、櫛としての通常の使用により櫛歯の 底端が頭皮に接触することで櫛歯がスムーズに伸縮することが前提とさ れているところ、スライドスリーブ4を径方向に屈曲する構成とすると、\nスライドスリーブ4と電流ガイドロッド3及びストッパー5との間の抵 抗・摩擦の増大等により、スライドスリーブ4が電流ガイドロッド3に 沿ってスムーズにスライドすることを妨げることは明らかである。そう すると、原告主張の周知技術1を甲1発明に適用することには阻害要因 があるというべきである。
イ これに対し、原告は、電流ガイドロッド3及びストッパー5の摺動(ス ライド)とスライドスリーブ4及びシリコンスリーブ9が径方向に屈曲す ることは両立する旨主張するが、根拠を欠くものといわざるを得ない。す なわち、原告が挙げる甲2公報は、「電極41が配設された先端部40」 が上下左右に動くことが可能な「育毛剤導入装置」に係るものであり、軸\n方向に摺動する構成を有するものとは認められない(甲2)。\nまた、原告は、スライドスリーブ4が屈曲できない部材であればストッ パー5と磁石6の位置を「固定」する必要がないと主張するが、本件審決 が認定する甲1発明のとおり「電流ガイドロッド3の底端にストッパー5 が固定して接続され」ていなければ、シリコンスリーブ9からなる櫛歯が 電流ガイドロッド3から抜けることになるし、製造時の手間を考慮しても ストッパー5を電流ガイドロッド3に、磁石6をスライドスリーブ9に固 定する方が自然といえるから、スライドスリーブ4が屈曲することの根拠 にはならない。
原告は、その他、髪をとかす動きをする際や「頭部の曲率の変化に応じ て、シリコンスリーブ9の底部が常に頭皮にフィットするように調整する」 ([0022])ためには径方向に屈曲することが必要である等主張する が、シリコンスリーブ9の屈曲により底部の放電孔が常に頭皮にフィット するとは認め難いし、いずれにせよ甲1公報の記載に基づく主張ではなく、 上記アの認定を左右するものではない。
(3) したがって、本件発明1は、甲1発明及び原告主張の周知技術1に基づい て当業者が容易に想到できるものではないから、本件発明1の発明特定事項 を全て含み、更に減縮したものである本件発明2〜10についても同様であ って、本件審決の甲1発明に基づく進歩性の判断の誤りはなく、原告が主張 する取消事由2には理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2024.06.11
令和3(ワ)22564等 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 知的財産裁判例 令和6年3月22日 東京地方裁判所
原告はかかる行為は、不正競争行為(不競法2条1項21号)に該当すると提訴しました。被告も反訴しています。 裁判所は、特許は無効だが、不正競争行為には該当しないと判断しました。
なお、サブコンピネーション発明の「〜のための」という文言も発明を限定するのかが問題となっています。
ウ 甲32発明の各構成が本件発明の構\成要件JないしNの構成にそれぞれ\n相当するかを検討する前提として、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電\n話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 被告らは、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信す\nるための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能\を特定して いるから、請求項1ないし4の解釈を踏まえて請求項5に係る本件発明 の構成を認定すべきであると主張するものと解される。\n
そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記 載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するた めのRFIDインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の 発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信 し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報 であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ 以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わ される受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本 件発明に係る特許請求の範囲の請求項5には、受信装置とは別の他の装 置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記 載されているものと理解できる。
そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求 項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構\成要素、組成、 作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に\n係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲 を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能\等を何ら特 定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を 特定するために意味を有しないことになるから,これを除外して当該請求 項に係る発明の要旨を認定することが相当であるといえる。
本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Jの「RFIDインター\nフェースを有し、」との記載は、受信装置が「RFIDインターフェース を有し」ていることを、構成要件Kの記載は、受信装置が「個別情報の発\n信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要\n件Lの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求し た個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成\n要件Mの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記 要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理 を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件\nJの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は 上記の構造、機能\等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機\n能等を請求項4記載の構\成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機\n能等自体を何ら特定していないから、「請求項4記載の携帯電話」との記\n載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認 めることはできない。
以上によれば、上記の「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するた めの」を除外して請求項5に係る本件発明の要旨を認定することが相当で あるというべきであって、被告らの上記主張を採用することはできない。
・・・
(2) 小括
以上によれば、本件発明は、甲32発明と同一の構成を有しているから、\n新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの と認められ、被告モビリティは原告に対してその権利を行使することができ ない(特許法104条の3第1項、123条1項2号、29条1項3号)。
3 争点1−3(被告らによる虚偽告知の内容)について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記2のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和3年6月23日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上(前提事実(5)エ)、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。 なお、被告らは、原告の前訴訟代理人であった弁護士Ci作成に係る令和3 年7月26日付け意見書について、文書提出命令を申し立てているところ(東\n京地方裁判所令和4年(モ)第264号)、本訴のいずれの争点との関係でも 取調べの必要性が認められるとはいえないから、上記申立てを却下する。\n4 争点2(被告らと原告との間の競争関係の有無)について 事業者間の公正な競争を確保するという不正競争防止法の目的(不正競争防 止法1条)に照らすと、同法2条1項21号の「競争関係」は、現実の市場に おける競合が存在しなくとも、市場における競合が生じるおそれがあれば認め られると解するのが相当である。
そして、前提事実(2)及び(3)並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、決済 に利用される通信端末及びインターネットを利用した決済システムを開発して 販売していること、被告モビリティは、決済システムに利用され得る本件発明 に係る特許権を有し、同特許権について実施権を許諾してライセンス収入を得 ることを業としていることが認められ、被告モビリティ自身が決済端末の開発、 販売をしておらず、現実の市場における競合が存在しないとしても、市場にお ける競合が生じるおそれはあるといえる。
3 争点1−3(被告らによる虚偽告知の内容)について
前提事実(5)オのとおり、本件通知行為は、原告が被告モビリティの特許権 を侵害しているとの原告の営業上の信用を害する事実を告知するものであると ころ、前記2のとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの であり、原告が被告モビリティの特許権を侵害しているとの事実を通知した本 件通知行為は、不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実を告知」するも のといえる。
他方で、前提事実(5)オのとおり、本件通知行為により、被告モビリティは、 岡三証券に対し、被告モビリティが別件訴訟を提起した旨も通知したものであ るが、実際に、本件通知行為の前日である令和3年6月23日、東京地方裁判 所に対し、別件訴訟を提起している以上(前提事実(5)エ)、別件訴訟について の通知内容は、同条の「虚偽の事実を告知」したものとはいえない。
(2) 不正競争行為に係る過失について
本件全証拠によっても、被告らにおいて本件通知行為時までに本件特許が 無効となることを具体的に認識し得たことを基礎付ける事情は認められない。 他方で、前提事実(5)のとおり、被告モビリティは、原告がマザーズ市場に 上場する約2週間前に、岡三証券に対して本件通知行為をしたものであると ころ、同時点においては、原告から本件特許が無効である旨の主張は一切さ れておらず、原告が初めて具体的な引用例を示した上で本件特許の新規性又 は進歩性欠如の主張をするに至ったのは、本件訴訟係属中に前訴訟代理人弁 護士らを解任して現在の訴訟代理人弁護士に本件を委任した後であった。以 上の事情に加え、一般に、特許権は特許庁においていったん特許要件ありと して特許査定を受けた権利であることを考慮すると、本件通知行為時点にお いて、被告らに本件特許の無効理由を調査する義務まで負わせることが相当 であるとはいい難い。したがって、被告らに不正競争行為につき過失があるとの原告の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> 営業誹謗
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和1(ワ)30628等 損害賠償請求本訴・損害賠償請求反訴 著作権 民事訴訟 令和6年3月28日 東京地方裁判所
(1) 著作物性の有無(争点1−1)
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、\n美術又は音楽の範囲に属するものであり(著作権法2条1項1号)、美術の 著作物には、美術工芸品が含まれる(同条2項)。そして、美術工芸品以外 の実用目的の美術量産品であっても、実用目的に係る機能と分離して、それ\n自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えている場合には、美術の範 囲に属するものを創作的に表現したものとして、著作物に該当すると解する\nのが相当である。 これを本件についてみると、被告商品は、原告A制作に係る本件絵柄をタ オルに付して商品化した上、量産されたものであるから、美術工芸品以外の 実用目的の美術量産品であるといえる。そして、被告商品は、先に制作され た本件絵柄を利用し製作されたタオル商品であるから、被告商品のうち本件 絵柄と共通しその実質を同じくする部分(本件絵柄部分)は、何ら新たな創 作的要素を含むものではなく、本件絵柄とは別個の著作物として保護すべき 理由がない。
このような観点から、被告商品のうち、本件絵柄部分を除き、新たに付与 された部分(本件タオル部分)の創作性の存否につき検討するに、被告商品 は、本件タオル部分において、凹凸、陰影、配色、色合い、風合い、織り方 その他の特徴があったとしても、凹凸、陰影、配色、色合いなどは、本件絵 柄と共通しその実質を同じくする部分であると認めるのが相当であり、また、 風合い、織り方などは、タオルとしての実用目的に係る機能と密接不可分に\n関連する部分であるから、当該機能と分離してそれ自体独立して美術鑑賞の\n対象となる創作性を備えているものとはいえない。 そうすると、被告商品において、美的鑑賞の対象となるのは、飽くまで原 告A制作に係る美術的価値の高い本件絵柄部分であると認めるのが相当であ り、被告一広の製作に係る本件タオル部分には、タオルとしての実用目的に 係る機能と分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備え\nているものと認めることはできない。 のみならず、仮に被告一広の製作に係る本件タオル部分に著作物性が認め られるという立場を採用したとしても、本件タオル部分は、原告らの主張を 前提としても、第三者にとって著作権侵害を構成する範囲が明らかになる程\n度に、被告商品ごとに個別具体的に明確に特定されているものとはいえず、 表現、創作活動等の自由の保障という観点からしても、本件タオル部分につ\nいては、そもそも新たに付与されたとされる創作的部分の特定を欠くものと して、著作物性を認めるための前提を欠く。加えて、原告会社が本件絵柄の 使用を許諾した基本契約の内容をみても、1条5項によれば、被告一広にお いて許諾された本件絵柄の使用は、著作物を構成するタイトル名、サブタイ\nトル名、登場キャラクター、コレクションの名称、形状、シンボル、ストー リー、プロット等を、許諾商品の使用価値を高めるために捺染、印刷、彫塑、 撮影その他の技法を用いて、許諾商品に具現化することをいうと規定されて いるのであるから、上記基本契約に係るその他の条項違反を主張するのは格 別、原告会社は、被告タオル美術館及び被告一広に対し、本件絵柄を複製及 び翻案してタオルとして商品化し、これを製造販売することにつき許諾した ものと解するのが相当である。したがって、仮に被告商品において新たに付 与された創作的部分を認める立場を採用し、かつ、仮に原告会社が当該創作 的部分を表現したという立場を採用したとしても、原告会社は、そもそも基\n本契約において、被告一広に対し当該創作的部分に係る著作物の使用を許諾 していたものと認めるのが相当である。 以上によれば、本件タオル部分に著作物性を認めることはできず、本件タ オル部分に係る著作権侵害に基づく原告らの請求は、いずれも理由がない。
(2) 著作者該当性(争点1−2)
仮に、本件絵柄部分を除いた本件タオル部分に著作物性を認める立場を採 用したとしても、証拠(甲7、甲33の2ないし5、甲35の2、3、甲3 8の2、3、甲40の2、3、乙6、乙27、乙113)及び弁論の全趣旨 によれば、原告Aは、配色指示書、配色指示図案等により、配色や糸、織り 方等を指示していることまでは認められるものの、具体的な糸の番手や本数、 密度、織り上がりの重量等を決定し、現実に被告商品のタオルを製作したの は、タオルの製造に関する専門的技術を有する被告一広であることが認めら れる。 そうすると、仮に本件タオル部分自体における上記工夫に創作性が認めら れる立場を採用したとしても、原告Aの上記指示等はアイデアの域を超える ものとはいえず、美的鑑賞の対象となる創作性を表現した著作者は、被告一\n広であると認めるのが相当である。 したがって、原告らの主張は、いずれも採用することができない。
2024.06. 9
令和4(行ケ)10057等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年4月25日 知的財産高等裁判所
ア 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、 発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆によ り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、ま た、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するものと解す るのが相当である。
本件明細書における本件各発明の課題及び解決手段は、前記2(2)のとおりであ る。ここで、前記2(2)のとおり、本件パラメータは、直線近似式であるところ、そ の統計的な性質上、予測値にすぎないものであることは、当業者の技術常識の範ちゅ\nうであるといえる。 かかる技術常識に照らして、当業者は、本件パラメータが規定する関係を満たす 場合には、1.09≦y/x≦1.21の数値範囲において85%から90%程度 の輝度均斉度が、1.21≦y/x≦1.49の数値範囲において90%から95% 程度の輝度均斉度が、1.49≦y/xの数値範囲において95%程度の輝度均斉 度がおおよそ得られることが期待できることが本件明細書に記載されていると理解 するものであるといえる。 また、輝度均斉度が、おおむね85%程度を超えていると、粒々感は、解消でき ることも周知の技術であるといえる(甲10【0001】【0024】【0074】)。
そうすると、本件明細書に接した当業者は、上記技術常識も踏まえて、本件パラ メータが1.09<y/xであれば、粒々感を抑制するという課題を解決できると 認識するものである。 他方、本件訂正後の特許請求の範囲に特定された本件各発明における本件パラ メータについてみると、1.09<y/xの範囲で、y/xの下限や上限を適宜特 定し、さらには、x値(請求項5〜8)の範囲を特定するものであるから、本件訂 正後の特許請求の範囲に記載された発明は、輝度均斉度がおおよそ85%以上とな る範囲を特定するものであることを理解できる。
以上を踏まえて、本件訂正後の特許請求の範囲の記載と本件明細書の記載とを対 比すると、同特許請求の範囲に記載された本件各発明が、本件明細書に記載された 発明であって、発明の詳細な説明の記載により、当業者は、同特許請求の範囲に特 定された全数値範囲で、粒々感を抑制するという課題を解決できると認識できる範 囲のものであるといえるから、本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、特許法36 条6項1号のサポート要件を満たすものであるといえる。
イ この点、原告は、本件明細書の実験結果【図7A】には、y=1.09xの 段階で輝度均斉度が85%に達していない試料(上段から10番目及び13番目) が記載されていること等から、実験結果から当業者が課題を解決できると認識でき ないなどと主張するが、前記2(2)オのとおり、当業者は、直線近似式と実測データ には残差が存在するという出願時の技術常識を踏まえて、本件各発明を理解すると ころ、原告が指摘する試料番号10、13等についても、このような技術常識を踏 まえて、おおよそ所望の輝度均斉度が得られ、本件各発明の課題を解決できると理 解できるものである。よって、原告の上記主張には理由がない。 したがって、サポート要件に違反しないとした本件審決の判断に誤りはない。
(2) 実施可能要件について\n
物の発明における発明の実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから (特許法2条3項1号)、物の発明について実施可能要件を充足するか否かについ\nては、当業者が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づい て、過度の試行錯誤を要することなく、その物を製造し、使用することができる程 度の記載があるかどうかで判断するのが相当である。 前記2(2)オのとおり、本件パラメータは、直線近似式であって、発光中心間隔x と半値幅yが、本件パラメータの数式の範囲内にあれば、おおよそ所望の輝度均斉 度が得られるとしたものである。 ここで、粒々感を解消した直管形LEDを得ることは、本願出願前に周知の技術 的課題であるし(甲1の3、甲47、甲52)、この課題を解決して粒々感を抑制す るためには、輝度均斉度がおおよそ85%程度以上であればよいことは技術常識で ある(甲10)。
さらに、直管形LEDにおいて、LED素子を選定し、コストの関係でLEDの 個数を適宜決定し(x値を変えること)、その上で、拡散カバーを適宜選択すること (y値を変えること)で、粒々感を解消することが、本件特許の出願当時の技術常 識であったこと、また、x値やy値の計測やy/x値の計算(【0080】)も格別 困難なものではないことに照らすと、当業者は、本件明細書等の記載及び技術常識 に基づいて、過度の試行錯誤を経ることなく、使用するLED素子、拡散部材、又 は素子と拡散部材の距離などにつき、粒々感を抑制し得るような組合せを適宜選択 して、本件各発明に係る本件パラメータを充足するy値及びx値を備えるランプを 実施することができるというべきである。 この点、原告は、過度な試行錯誤を経なくては、発明の課題とする所望の輝度均 斉度を得ると当業者が理解できないと主張するが、上記判断に照らし、原告の主張 は採用できない。したがって、実施可能要件に違反しないとした本件審決の判断に誤りはない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和5(行ケ)10101 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年4月25日 知的財産高等裁判所
上記記載によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、「ユーザー4は、 アプリケーション[B]10を用いて、要鑑定製品1に付与された秘密鍵α1、 およびギャランティカード2に付与された秘密鍵β1を使用して、専用プラッ トフォーム8のブロックチェーンデータ8bに書き込まれた、要鑑定製品1 の製品情報および取引情報を読み込むことができ」ることが記載されている。 また、上記1のとおりの、「要鑑定製品1およびギャランティカード2を所 有する真のユーザーだけが、信頼性の高い鑑定証明を簡単に行うことができ る」との本件各発明の奏する効果を考慮すると、本件明細書の発明の詳細な 説明には、「ユーザー4が要鑑定製品1およびギャランティカード2を所有す る真のユーザーであるという認証を行った後に、認証されたユーザー4だけ が、専用プラットフォーム8のブロックチェーンデータ8bに書き込まれた、 要鑑定製品1の製品情報および取引情報を読み込むことができ」ることも記 載されているといえる。
(3) 本件特許の出願時の技術常識
本件特許の出願時における技術常識を示す文献である甲2(新版暗号技術 入門 秘密の国のアリス、2012年〔平成24年〕7月25日第7刷発行) には、「公開鍵信号・・・では、『暗号化の鍵』と『復号化の鍵』を分けます。 送信者は『暗号化の鍵』を使ってメッセージを暗号化し、受信者は『復号化 の鍵』を使って暗号文を復号化します。」、「『復号化の鍵』は・・・あなだだ けが使うものなのです。ですから、この鍵をプライベート鍵・・・と呼びま す。」「公開鍵で暗号化した暗号文は、その公開鍵とペアになっているプライ ベート鍵でなければ復号化できません。」、「デジタル署名では、署名の作成と 検証とで異なる鍵を使います。署名を作成できるのはプライベート鍵を持っ ている本人だけですが、署名の検証は公開鍵を使いますので、誰でも署名の 検証を行えます」との記載があり、甲1、3、乙2ないし4にもこれと同旨 の記載がある。 そうすると、本件各発明の属する暗号技術分野において、秘密鍵で暗号化 し、その秘密鍵と対の関係にある公開鍵で復号化することにより、本人認証 を行う公開鍵暗号方式によるデジタル署名技術は、本件特許の出願当時の技 術常識であったことが認められる。
(4) 判断
そうすると、上記(2)の本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業 者は、上記(3)の出願当時の技術常識に基づくと、要鑑定製品1に付与された 秘密鍵α1及びギャランティカード2に付与された秘密鍵β1は、それらと対 の関係にある公開鍵と共に、ユーザー4が要鑑定製品1及びギャランティカ ード2を所有する真のユーザーであるという本人認証に使用されることが自 然であると理解できるから、本件明細書の発明の詳細な説明には、アプリケ ーション[B]10を用いる許可を得るための本人照合の手段として、要鑑 定製品1に付与された秘密鍵α1及びギャランティカード2に付与された秘 密鍵β1で暗号化し、秘密鍵α1及び秘密鍵β1と対の関係にある公開鍵で復号 化することで本人認証を行うデジタル署名技術により、ユーザー4が要鑑定 製品1及びギャランティカード2を所有する真のユーザーであるという認証 がなされ、認証されたユーザー4だけが、専用プラットフォーム8のブロッ クチェーンデータ8bに書き込まれた、要鑑定製品1の製品情報および取引 情報を読み込むことができることが記載されていると理解できる。 したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が、本件明細書 の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の出願当時の技術常識に基づいて、 過度の試行錯誤を要することなく、構成要件E、Fを含む本件発明1の鑑定\n証明システムを製造し、使用することができる程度に、明確かつ十分に記載\nされているものと認められる。 よって、本件発明1について、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は実 施可能要件を満たしているといえ、本件発明2ないし7についても同様に解\nされる。 したがって、原告の主張する取消事由1は理由がない。
(5) 原告の主張に対する判断
ア 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)のとおり、本件明細書の発明の 詳細な説明には、構成要件E及びFを具現すべき機能\等について記載され ておらず、不明瞭であり、出願時の技術常識に基づいてもその具現すべき 機能等を当業者が理解できないから実施可能\要件を欠く旨を主張する。 しかし、上記(2)ないし(4)で検討したとおり、本件明細書の発明の詳細な 説明の記載は、当業者において、技術常識に基づいて過度の試行錯誤を要 することなく特許請求の範囲に記載された本件各発明を実施できる程度 に明確かつ十分に記載されているものと認められる。\nしたがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(2)のとおり、本件審決の挙げる「例」 は誤りであり、秘密鍵を有するユーザーにパスワードが設定された適切な アプリケーションをダウンロードにより入手させることもできないから、 「例」について実施可能要件違反がある旨を主張する。\nしかし、本件審決は、「例」につき、ユーザーが要鑑定製品1及びギャラ ンティカード2を所有する真のユーザーであるという認証について実施 可能であることを示す例として示したにすぎず、仮にこの「例」が誤りで\nあったとしても、直ちに本件審決の結論に誤りがあることにはならないか ら、原告の主張は前提を欠くものである。 また、本件明細書の段落【0023】には、「要鑑定製品1の小型記録媒 体(a1)1aに記録された秘密鍵α1、製品情報を含む情報、および、ギ ャランティカード2の小型記録媒体(b)2aに記録された秘密鍵β1、製 品情報を含む情報の読み取りは、図2に示すように、パーソナルコンピュ\nータ5−1のリーダー5−2や、スマートフォン6−1を接触させて行う こともできるし、NFC(NearField Communicati on)、RFID(Radio Frequency IDenticif ier)等の近距離無線通信により非接触で行うこともできる。」との記載 があり、要鑑定製品1の小型記録媒体(a1)1a又はギャランティカード 2の小型記録媒体(b)2aから、秘密鍵α1及び秘密鍵β1のほかに、製 品情報も読み取られているから、この記載に接した当業者であれば、秘密 鍵α1及び秘密鍵β1ではなく、製品情報に基づいてアプリケーション[B] がダウンロードされると考えることも自然であるということができる。 る。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(3)のとおり、仮に、本件審決が想 定する上記「例」が実施可能であるとしても、本件発明1に含まれる当該\n「例」以外の部分について、本件明細書の発明の詳細な説明には記載され ておらず、暗号化/復号化をすることが、「アプリケーション[B]」、「読 み込み」及び「鑑定証明を行う」等とどのような関係にあるのかも不明で あり実施可能要件違反がある旨を主張する。\nしかし、上記(2)ないし(4)で検討したとおりであり、本件明細書の発明の 詳細な説明の記載は、当業者において、技術常識に基づいて過度の試行錯 誤を要することなく特許請求の範囲に記載された本件各発明を実施でき る程度に明確かつ十分に記載されているものと認められる。\nしたがって、原告の上記主張は採用することができない。
3 取消事由2(実施可能要件の判断の論理構\成の誤り)について
原告は、取消事由2として、本件審決の論理構成は、本件明細書とは別の書\n面である本件特許請求の範囲が理解できるとの判断に依拠する誤ったもので あり、実施可能要件の判断に当たって、本件審決の論理構\成には誤りがある旨 を主張する。
しかし、本件審決は、「第6 当審の判断」として、本件明細書の発明の詳 細な説明の記載を摘記した上で、本件各発明の技術的意義を明らかにし(第6 の1(1)及び(2))、第6の2において、「物の発明について実施可能要件を満たす\nためには、明細書の発明の詳細な説明の記載が、当業者において、その記載及 び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、当該発明 に係る物を作り、使用することができる程度のものでなければならない。そこ で、以下、これを前提に判断する。」(本件審決13頁4行目ないし同頁8行目) との判断の基礎を示した上で、本件各発明の構成要件と本件明細書の発明の詳\n細な説明の記載の対応関係を検討し(第6の2(1))、続く第6の2(2)イにおい て、「上記(1)アのとおり、本件発明1の構成要件Eと対応する本件明細書の発\n明の詳細な説明の記載は、【0021】、【0022】及び【0036】である。」 (本件審決14頁12行目ないし同頁14行目)、「そうすると、構成要件Eに\n対応する本件明細書の発明の詳細な説明の上記【0021】、【0022】及び 【0036】は、当業者であれば、明確かつ十分に理解し得るものである。」\n(本件審決15頁9行目ないし同頁11行目)とし、これを基に、同第6の2 (2)ウにおいて、「以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者 において、本件発明1に係る物を作り、使用することができる程度に、明確か つ十分な記載があるから、本件発明1について、本件明細書の発明の詳細な説\n明は、実施可能要件を満たしている。」(本件審決15頁13行目ないし同頁1\n6行目)との結論を示したものである。そうすると、本件審決は、本件明細書 の発明の詳細な説明(特に、段落【0021】、【0022】及び【0036】) の記載に基づき、実施可能要件を満たす旨を判断する構\成を取っているもので ある。そして、上記2の検討結果によれば、その判断の内容に誤りはなく、本 件審決の実施可能要件の判断の論理構\成に誤りはない。 したがって、原告の主張する取消事由2は理由がない。
4 取消事由3(実施可能要件の判断の理由不備(理由不存在)・審理不尽)につ\nいて
原告は、取消事由3として、本件審決には、結論のみがあってそれに対応す る理由が存在しないから、理由不備(理由不存在)、審理不尽又は判断遺脱など の手続上の瑕疵が存在し、本件審決は取り消されるべきである旨を主張する。 しかし、上記2のとおり、本件審決には、結論に至る過程において、対応する 理由が記載されており、本件審決には、理由不備(理由不存在)、審理不尽及び 判断遺脱の違法は存せず、上記2、3によれば、その理由付けにも誤りはない。 したがって、原告の主張する取消事由3は理由がない。
5 取消事由4(本件発明1の認定・解釈の誤り)についいて
原告は、取消事由4として、本件発明1の構成要件Eについて、特許請求の\n範囲の記載の文言に従って解釈すれば足り、それ以上に限定して解釈したり、 特許請求の範囲に記載されていない事項を導入して解釈したりすることは許さ れないから、本件審決の本件発明1の認定・解釈は誤りである旨主張する。 原告の主張するところの本件審決における本件発明1の認定・解釈の誤りが、 本件審決を直ちに違法とするものであるかについて明確ではないものの、被告 が主張するとおり、本件発明1の実施可能要件を判断するに当たり、本件発明\n1に対応する本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは、法70 条1項・2項の規定に基づき当然に行われるべきことであり、原告の主張は前 提を欠くものである。そして、前記2ないし4のとおり、本件審決の判断に技 術常識に反する点もなく誤りはない。 したがって、原告の主張する取消事由4は理由がない
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和5(行ケ)10002 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年4月25日 知的財産高等裁判所
ア 本件発明1について
まず、本件発明1の要旨認定につき当事者間に争いがあるため、以下検討する。
(ア) 本件発明1の特許請求の範囲の記載によると、「取付部材」は、構成要件B\n「前記LED基板が取り付けられる取付部材と」、構成要件C「拡散性を有し且つ前\n記LED基板を覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備え た」、構成要件E「前記カバー部材は、前記取付部材に取り付けられる一対の突壁部\nと」、構成要件F「を有し」、構\成要件I「前記取付部材は、前記複数のLEDが前 記収容凹部の外側を向くようにして前記LED基板を前記器具本体に取り付けるた めの部材であり」と特定されているところ、「取付(け)」とは、「1)機器・器具など をとりつけること。装置すること。」(広辞苑第六版)を意味する名詞であるから、 「取付部材」とは、機器・器具などをとりつけること、装置することに関わる部材 であると理解できる。
また、「取り付ける」とは、「1)機器などを一定の場所に設置したり他の物に装置 したりする。」(広辞苑第六版)を意味する動詞であり、構成要件Bにおいて、「られ\nる」という受け身を表す文言とともに用いられているから、構\成要件Bにより、「取 付部材」は、LED基板が装置される対象物であると理解できる。 さらに、構成要件Cにおいて、「取付部材」は、LED基板を覆うようにしてカバー\n部材が取り付けられる対象物であることが特定されており、そのための構成として、\n構成要件E及び構\成要件Fによると、カバー部材が一対の突壁部を有することが特 定されている。そして、「にして」とは状態を表すものであり、「ため」とは「目的」を意味するものである(広辞苑第六版)から、構\成要件Iによると、「取付部材」は、複数のLEDが収容凹部の外側を向いた状態でLED基板を器具本体に取り付ける ことを目的とした部材であることが特定されていると理解できる。
以上によると、本件発明1の各構成要件の特定事項から、本件発明1の「取付部\n材」は、カバー部材が装置されて一体となること、及び、LED基板が取り付けら れ、それが収容凹部の外側を向く状態で器具本体に取り付けることを目的とした部 材であると認められる。 他方、本件発明1では、カバー部材を取付部材に取り付けるための手段として、 カバー部材が一対の突壁部を有することが特定されている(構成要件E)ものの、\n「取付部材」を器具本体に取り付けるための具体的な構成、例えば、ボルトやフッ\nクなどの構成についての特定はされていないものといえる。\n
そうすると、本件発明1では、「取付部材」を器具本体に取り付けるための具体的 な構成の特定がない以上、当業者は、「取付部材」を器具本体に取り付けるための構\ 成として、技術水準を踏まえて任意のものを採用し得るものと解される。例えば、 本件出願日前に公開された甲2の図13の「係止部材4」、甲202(実用新案登録 第3126166号公報)の「取付部材4」、甲204(特開2012−18598 1号公報)の「係止部材40」及び「係止穴84」、甲205(ワイドキャッツアイ 器具ERK8775W/WEHP108Mに係る報告書)の「キックバネ3」、乙1 の「取付ばね18」及び「取付金具13」(乙2、3も同様)の取付部材と器具本体 の間に係止又は嵌合させる手段を介在させる構成を含め、カバー部材を介在するよ\nうな態様を排除するものではないと解することができる。
(イ) もっとも、特許請求の範囲の記載の意味内容が、本件明細書において、通常 の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されていれば、異なる解釈をする余 地があるため、以下検討する。 この点、本件明細書によると、「取付部材」については、従来技術の説明(【00 03】)、課題を解決するための手段(【0007】、【0008】、【0012】)、実施形態(【0021】、【0024】〜【0028】、【0030】、【0032】〜【0035】、【0037】、【0044】、【0046】、【0047】、【0051】など)に、それぞれ記載があるが、いずれの記載によっても、前記(ア)の特許請求の範囲の記載の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されているものとはいえない。 ここで、更に本件明細書の実施例についてみると、取付部材について以下のよう に説明されている。図1に係る実施形態における取付部材21は、複数のLED基板22が取り付けられ、LED基板22を覆うようにしてカバー部材23が取り付けられること(【0021】)、板金に曲げ加工を施すことで形成され、所定の形状、穴、LED基板を取り付けるための係止爪(図示せず)を有すること(【0024】〜【0026】)、電源装置24や端子台ブロック25を取付部材21に取り付けるための構成を有す\nること(【0030】、【0032】〜【0035】)、さらに、例示として、器具本体1と取付部材21にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)により光源ユニット2を\n器具本体に取り付ける(【0037】)ものである。 また、図5に係る実施形態の別の例における取付部材21は、器具本体として構\n成された反射板5及び取付部材にそれぞれ設けた嵌合構造(図示せず)により光源\nユニット2を反射板5(器具本体)に取り付ける(【0044】)ものである。 このように実施形態では、図示はないものの取付部材21と器具本体には嵌合構\n造が設けられていることが理解でき、「嵌合」とは、「〔機〕軸が穴にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係をいう語」(甲201)である から、取付部材21と器具本体とは、はまり合うための構造を有し、これにより取\nり付けられることが記載されているものと理解できる。もっとも、かかる実施形態 における取付部材21と器具本体が、はまり合うための具体的な構造については図\n示されておらず、何ら具体的な構造が開示されていないことに照らすと、実施形態\nにおいて取付部材21と器具本体との間にカバー部材を介する態様も包含している といえる。
(ウ) 被告は、本件発明における「取付部材」は、特許請求の範囲の文言上、直接 器具本体にLED基板を取り付ける部材として特定されており、この点に関する本 件審決の認定に何ら誤りはないと主張するが、上記(ア)のとおり、かかる主張は首肯 できない。 また、被告は、実施形態において開示されているのは、カバー部材を介すること なく、取付部材と器具本体に設けられた嵌合構造により両者が取り付けられている\n構造のみであって、カバー部材を介する構\造は存在しないとも主張するが、上記(イ) のとおり、かかる実施形態における取付部材21と器具本体が、はまり合うための 具体的な構造については図示されておらず、何ら具体的な構\造が開示されていない ことに照らすと、実施形態において取付部材21と器具本体との間にカバー部材を 介する態様も包含しているといえるから、被告の上記主張も採用できない。
・・・
(ア) 本件審決は、相違点1−1−3(1)として、「LED基板を器具本体に取り付 けるための部材について、本件発明1では、これが「取付部材」であるのに対して、 甲3−1発明では、これが「蓋部3」であって、絶縁板13は基板10をこの蓋部 3に取り付ける部材である点。」を認定しているところ、原告はこの相違点の認定を 争っていることから、以下検討する。
(イ) 相違点1−1−3(1)について
本件審決は、本件発明1と甲3―1発明との対比において「後者の「絶縁板13」\nと前者の「取付部材」とは「部材」において共通する。」としながらも(本件審決8 3頁末から2行目〜末行)、相違点1―1―\3(1)の判断において「甲3−1発明で は、「絶縁板13」は、基板10を蓋部3に取り付けるためのものであって、器具本 体に取り付けるための部材(取り付ける機能を有する部材)は「蓋部3」である。」\n(同86頁4〜7行目)と認定・判断しており、本件発明1では、「器具本体」と「取 付部材」との間に取り付けに資する構造が介在することが排除されていることを前\n提としている。
しかしながら、前記(1)の本件発明1の要旨認定のとおり、「器具本体」と「取付 部材」との間に取り付けに資する構造が介在することを含むものであってこれが排\n除されていると解することはできない。 以上を前提とすると、本件発明1は、甲3−1発明のように「絶縁板13」と「取 付ベース1」との間に「蓋部3」が介在する取付構造を排除するものではないし、\n甲3−1発明の「絶縁板13」には、LED2を配設した基板10が配設されてい るのであるから、「絶縁板13」が存在しなければ、LED2は「取付ベース1」に 配設することができないことに照らしても、「絶縁板13」は、「LED基板を器具 本体に取り付けるための部材」に相当するものと認められる。 そうすると、本件発明1と甲3−1発明と対比において、相違点1−1−3(1)は、 相違点とはいえない。
(ウ) 相違点2−1−3(1)について
次に、カバー部材に関して、本件発明1では、「拡散性を有」するのに対して、甲 3−1発明では、「アクリル樹脂やガラス等の透明な絶縁材料からできて」いるもの の、拡散性を有するか否かは不明であるとの相違点2−1−3(1)についてみると、 LED照明器具のカバー部材が拡散性を備えることは周知技術であり(甲1[00 32]、甲2【0022】、甲6)、甲3−1発明において、適宜採用して相違点2− 1−3(1)に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得ることで\nある。
(エ) 小括
そうすると、本件発明1は、甲3−1発明に基づいて当業者が容易に発明をする ことができたものと認められるから、本件審決は、進歩性の判断において、結論に 影響を及ぼす誤りがあったものといえる。 987/092987
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和3(ワ)15964 特許権 民事訴訟 知的財産裁判例 令和6年3月22日 東京地方裁判所
3 被告ダンパは、「入力」を受けるものであるか(構成要件G)(争点1−1)\nについて ア 本件発明1の構成要件G、Hは、「前記剪断部は、入力により荷重を受けた\nときに、変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とする弾塑性履歴型ダン パ」というものであり、本件発明1の対象となる「弾塑性履歴ダンパ」につ いて「剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収 を行うことを特徴とする」ものであるとされている。したがって、本件発明 1のダンパは、上記に記載された特徴を有するダンパであるところ、その「入 力」がどのようなものであるかについて、本件発明1の特許請求の範囲では 何ら定められていない。
イ ここで、前記1 で説示したとおり、本件各発明は、上部構造物、下部構\ 造物に分離できる橋梁等の建築物において、地震のときに、その接続部にお いて橋軸方向に限らず、複数方向の水平力がかかってしまうところ、同接続 部においては、I字形ダンパでは単一方向の入力にしか対応できないという 課題について、同課題を解決するために、複数の剪断面を持ち、かつ、その 向きが異なるダンパを適用するというものであり、本件各発明は、そのよう なダンパが本件各発明の構成をとることによって、剪断部が、入力により荷\n重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うというものである。 本件明細書に記載された本件各発明の課題は、上記のとおりであり、従来 から知られていた剪断パネル型ダンパである単純なI字形ダンパに対して 単一方向からの入力しか想定されない場面においては、本件各発明における 解決すべき課題は存在しない。単一方向からの入力でなく複数方向からの入 力が想定される場合に、本件各発明が解決すべき課題が存在することとなる。 そして、本件明細書には、前記1 に記載のとおりの本件各発明の意義が記 載されているほか、本件明細書に記載された実施例は、全て、複数方向から の入力が問題となり、そのような複数方向からの入力に対し、本件発明1の 構成をとることによって対応することができるものであると認められる。本\n件明細書のその他の部分にも、単一方向からの入力に対応することに関する 記載はない。これらの本件明細書の記載及び構成要件G、Hの記載から、本\n件発明1に係るダンパは、ダンパに対して複数方向からの入力が想定される 構造物等の部位に用いられ、ダンパの剪断部に対して複数方向からの入力が\nあり、これに対して対応することができるダンパであると解するのが相当で ある。
ウ 以上によれば、本件各発明におけるダンパは、その剪断部に複数方向から の入力があり、その剪断部がそれに対する入力により荷重を受けたときに、 変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするもの(構成要件G、H)で\nあると解するのが相当であり、構成要件Gに係る「入力」は、「複数方向か\nらの入力」を意味し、本件各発明のダンパは、ダンパに対して複数方向から の入力があることを前提として、その剪断部が複数方向からの入力により荷 重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするダンパ であると認められる。 被告ダンパについて検討すると、本件において、原告は、被告ダンパ単体の 譲渡等を問題にするのではなく、被告ダンパが住宅である被告製品に用いられ て、そのような被告製品が販売されていることを特許発明の実施として、被告 製品の販売額を基礎として実施料率相当額の損害を請求する。
被告は、6種の被告ダンパを4種の耐力パネルのいずれかに組み込み、これ を住宅である被告製品の部材として用いている(前提事実 )。被告ダンパは各 平行板部及び各ウェブ部の一端又は両端が耐力パネルに溶接されているので あって、耐力パネルから取り外して使用されることはおよそ想定されておらず、 各耐力パネルも、建物の水平方向に延びる梁や土台等にはさまれるように固定 されて設置されており、住宅販売後に耐力パネルのみを取り外して別の用途に 使用するということはおよそ想定されていない(前提事実 )。すなわち、被告 ダンパは、耐力パネルに物理的にも溶接され、取り外されることはおよそ想定 されず、耐力パネルと不可分一体となっているものといえる。 そうすると、本件において問題となる被告の行為は、被告ダンパが不可分一 体の一部となった被告製品の製造、販売等であって、被告ダンパが組み込まれ た被告製品が本件発明1の技術的範囲に属するか否かが問題になるというべ きである。
なお、被告は、Σ型の形状の鋼材である被告ダンパを作成し、これを他の部 材に組み込むことで耐力パネルを製造していることがうかがえる。もっとも被 告ダンパ単体には「一対のプレート」は接続されておらず、耐力パネルに組み 込まれることによって初めて、「一対のプレート」の具備が問題になるのである から、耐力パネルに組み込まれる前の被告ダンパ自体が本件発明1の技術的範 囲に入ることはないと解される。 被告製品に組み込まれ、被告製品と不可分一体となった被告ダンパに対して 加わる力について検討する。
ア 被告ダンパはいずれも4種類の耐力パネルのいずれかに組み込まれてい るところ、耐力パネルは、その構造上、耐力パネルが接続している梁の方向\nの力(耐力パネルが平行四辺形に変更する方向の力)が加わると、いずれの 耐力パネルについても、被告ダンパに鉛直方向の力が加わり、所定レベル以 上の力が加わると剪断変形によって地震力を吸収する。このとき、被告ダン パに対しては、鉛直方向の力以外の力は加わらない。他方で、耐力パネルに 梁と垂直方向の力が加わっても、被告ダンパには力が加わらず、地震力を吸 収することができない。地震力のうち、これらの力の合力については、いず れも上記二つの力に分解できるから、結局、被告ダンパには鉛直方向の力の みが加わるということになる(乙33)。被告製品においては、建物の特定 の方向に複数の耐力パネルを設置するとともに、これと直交する方向にも複 数の耐力パネルを設置しており、このように複数の耐力パネルを直交方向に 設置することによって、個々のパネルの被告ダンパには鉛直方向の力のみが 加わり、その方向の力のみしか吸収できないとしても、各方向に沿って設置 された耐力パネルが、両方向に対応する地震力の分力を吸収することで建物 全体では任意の方向の地震力を吸収できるように設計されているといえる (乙3)。
イ 被告ダンパに対しては、一応、前記アのとおりの力のみが加わるといえる が、耐力パネルが設置されている上下の梁がねじれる(回転する)力が加わ った場合には、耐力パネルの構造上、被告ダンパに対し鉛直方向とは異なる\n方向の力が加わる可能性がないわけではない。そこで、被告製品において鉛\n直方向からどの程度ずれる力が加わり得るのかについて検討する。
被告は、被告ダンパを搭載した実物大の住宅サンプルに対して、過去最大 級の地震の一つである兵庫県南部地震の際にJR鷹取駅で観測された地震 波(以下「鷹取地震波」という。)を適用して地震時挙動を測定する実験を行 ったところ、その結果によれば、1階に対する2階床の最大回転角は、0. 14°(乙40)、これにより耐力壁に設置されたダンパに対して加わる力 の鉛直方向からのずれは、0.022°であったこと(乙41)が認められ る。
ウ 以上を前提に、被告ダンパの剪断部に本件発明1における複数方向から の入力があり、その剪断部が複数方向からの入力により荷重を受けたとき に変形してエネルギー吸収を行うものといえるか否かについて検討する。 特許請求の範囲にも本件明細書にも、前記の複数方向のうち1つの方 向といえる角度範囲をどの程度のものと想定しているかについての直 接的な記載はない。しかし、そもそも、本件発明1のダンパは、建築物 や橋梁等の建物、建造物で用いられるものであるところ、従来のI字型 ダンパは、想定する角度からわずかでもずれれば機能しなくなるという\nものではない。I字形ダンパは、入力方向のずれが生じている場合でも、 パネルと平行し、面内を通る方向の分力については、入力がパネルと面 内を通る方向と平行だった場合と同様に作用することになるから、実際 の入力と面内を通る方向とのずれがごくわずかであれば、実際の入力と ほとんど変わらない力が面内を通る分力として剪断パネルに作用する。 例えば、入力方向が0.1°ずれた場合には、
Cos0.1°=約0.9999985
により、約99.99985%の力が面内を通る分力として剪断パネル に作用することになり、この程度の入力方向のずれでは、I字型ダンパ に生じる効果に観測できるほどの差は生じないことは明らかである。ま た、建築の分野において橋梁や住居などの一定の大きさの建造物を建築 するに当たって、施工誤差が生じることは当然であり(原告は、後記の とおり耐力パネル設置に当たって少なくとも±0.82°の据え付け誤 差が生じると主張している。)、I字型ダンパもそのことを前提に用いら れるものとして想定されており、施工の限界を超えた小さい角度差は、 単一方向の入力として想定されているというべきである。さらに、I字 型ダンパはパネルと平行し、面内を通る方向から力が加わることによっ て、平行四辺形に剪断変形することによってその力を吸収するというも のである(前記2 )が、I字型ダンパの剪断パネルにも一定の厚さが あり、少なくとも厚さの中に納まるような入力方向の小さなズレであれ ば、パネルの面内を通る方向からの力と評価し得、少なくともこの程度 の入力方向のずれは、同一方向からの入力として想定されているともい える。
本件明細細書においても、本件各発明のダンパは、図面上、いずれも一 見して複数の剪断部の方向が異なることが明らかなもののみであり、そ の入力方向のズレが相当に小さいことを想定した場合の記載、図面はな い。そのずれが相当に小さく、例えば、0.1°程度の差を複数方向か らの入力と想定した場合、複数のパネルを連結しながらどのように配置 すれば効率的に入力を吸収できるかは、本件明細書によっても明らかで はない。上記のような差の入力の場合、厚みのある鋼板を用いて、2枚 の剪断パネルを0.1°程度の角度をつけて接合し、ダンパを作成する ことを実現することが現実的であるとはいえない。 以上に述べたところに、前記 で記載した本件発明1の意義を考慮す ると、本件発明1で対象としている複数方向からの入力は異なる方向か らの入力であるというべきところ、その異なる方向からの入力には、少 なくとも、従来のI字型ダンパにおいて同一方向からの入力として想定 されていたといえる入力を含まないものと認められる。
前記イで認定したとおり、被告製品は、少なくとも鷹取地震波を前提 にすると、これによって剪断パネルに一定のねじれが生じ、被告ダンパ に鉛直方向からずれた方向からの力も加わることが認められる。しかし、 そのずれは0.022°(なお、cos0.02°=約0.9999999 26)と極めて小さいものである。この程度のずれは、その小ささから もこれによって被告ダンパに生じる効果に観測できるほどの差が生じ るとは認めるに足りないし、このずれは、被告製品が用いられる分野の 施工の限界を超える程度であるといえる。また、そのずれは、被告ダン パのウェブ部を形成する鋼板の厚みの中に収まるような小さなもので あることがうかがえる。 これらによれば、上記実験結果によれば、本件においてねじれによっ て加わり得る入力方向の違いは、従来のI字型ダンパにおいて同一方向 からの入力として想定されていたといえる範囲のものであり、前記 で 説示した本件発明1が異なる入力方向として想定しているものではな いというべきである。 また、被告製品が鷹取地震波を超える地震波に遭遇することは想定さ れ得る。しかし、上記実験で用いられたのが過去最大級の地震の一つで ある鷹取地震波であり、その場合であっても上記のとおり入力方向の違 いが極めて小さいことからすると、現実に想定し得る鷹取地震波を超え る地震においても、被告ダンパに対して本件発明1が想定する程度の鉛 直方向からのずれが生じる剪断パネルのねじれが生じるとも認められ ない。
以上によれば、被告製品で用いられている被告ダンパの剪断パネルに 対してねじれの影響によって生じる入力方向の違いは、その小ささから、 本件発明1が想定する程度に達するような、異なる方向からの入力であ ると評価できるものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和5(行ケ)10056 承継参加申立事件 特許権 行政訴訟 知的財産裁判例 令和6年3月25日 知的財産高等裁判所
d 本件適用に係る動機付けの有無についての参加人のその余の主張に対する判断
参加人は、1)甲11記載の発明における第1の濾過工程と第2の濾過工程は段階 を異にする別個の工程である、2)前者の工程と後者の工程は濾過の条件(高温高圧 条件下での実施の要否)、用いる濾過膜の性質(細菌保持力の強弱)及び濾過のタ イミング(バルクの充填工程の前後)を異にするものであるとして、甲11記載の 発明に接した当業者において、前者の工程と後者の工程を1つの濾過工程(本件製 品の膜を用いた工程)に置き換えることが容易であったとはいえないと主張する。 しかしながら、前記イ(イ)において説示したとおり、参加人が主張する工程(III)) (アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程)は、アジュバン トエマルジョンを抗原溶液と組み合わせる場合とこれらを組み合わせない場合とが あることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、少なくとも後者の場合にお いては、当該工程を経ることが技術的に必須であるとまでいえないと考えられるの であるから、甲11記載の発明において第1の濾過工程と第2の濾過工程を連続し て行うことは、同発明の技術的思想と何ら背馳するものではない(この評価は、甲 11(前記ア)に、第1の濾過工程(大きな粒子を除去する工程)につき「安定性 を有するエマルジョンの製造のために重要である」旨の記載が、第2の濾過工程に つき「滅菌濾過を行った上、アジュバントを単回投与用のバイアルに充填する」旨 の記載がそれぞれあることによっても妨げられるものではない。)。そうすると、 甲11記載の発明の第1の濾過工程と第2の濾過工程が連続して行うことができな い別個の工程であるということはできないから、上記の1)の点を根拠とする参加人 の主張を採用することはできない。
また、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲11には、第1の濾過工程におけ る濾過と第2の濾過工程における濾過がどのような温度や圧力の下で行われなけれ ばならないかについての記載はなく、その他、濾過が行われるべき温度又は圧力を 第1の濾過工程と第2の濾過工程とで別異にすべきであることを認めるに足りる証 拠はないから、甲11記載の発明に接した本件優先日当時の当業者において、第1 の濾過工程における濾過は高温高圧下で行う必要があるが、第2の濾過工程におけ る濾過は高温高圧下で行う必要がないなどと認識するものとは認められない。細菌 保持力の点についてみても、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲11には、第 1及び第2の濾過工程において使用される各膜につき、これらの細菌保持力の強弱 についての記載はなく、その他、細菌保持力を第1の濾過工程において使用される 膜と第2の濾過工程において用いられる膜とで別異にすべきであることを認めるに 足りる証拠はないから、甲11記載の発明に接した本件優先日当時の当業者におい て、第2の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要があるが、 第1の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要がないなどと認 識するものとは認められない。濾過のタイミングの点についてみても、参加人が主 張する工程(III))(アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程) を経ることが技術的に必須であることを認めるに足りる証拠がないことは、前記イ
(イ)において説示したとおりであるから、甲11記載の発明に接した本件優先日当 時の当業者において、第1の濾過工程はアジュバントエマルジョンのバルクの大き な瓶への充填の前に行う必要があり、第2の濾過工程は当該充填の後に行う必要が あるなどと認識するものとも認められない。したがって、上記の2)の点を根拠とす る参加人の主張も採用することはできない。
e 本件適用に係る動機付けの有無についての小括
以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者において、甲11発明(認定) に本件周知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。
(オ) 本件適用に係る阻害要因の有無
a 参加人は、甲11記載の発明の第1の濾過工程において用いられる膜の孔サ イズが0.22μmであるのに対し、本件周知技術の予備濾過膜の孔サイズは0.\n45μmであるところ、甲11記載の発明における第1の濾過工程の目的(安定性 を有するエマルジョンのバルクを得るために径が1.2μmを超える大きな粒子を 十分に除去すること)に照らすと、甲11記載の発明の第1の濾過工程において用\nいられる膜に代えて、孔サイズが2倍以上になる本件周知技術の予備濾過膜を適用\nすることには阻害要因があると主張する。
しかしながら、前記(イ)c(a)のとおり、甲65には、「膜の実際の孔径よりも大 きい粒子や微生物は、効果的に除去される。」との記載があり、孔サイズが0.4 5μmである本件周知技術の予備濾過膜を採用した場合であっても、径が1.2μ\nmを超える大きな粒子を十分に除去し、もって、安定性を有するエマルジョンのバ\nルクを得ることができるものと認められる。また、前記(エ)bのとおり、甲11発 明(認定)は、1)細菌を効果的に保持するとの課題のほか、2)総処理量を大きくす るとの課題及び3)流速を妥当なものにするとの課題を内在しているところ、当該2) 及び3)の課題の解決のためには、目詰まりの防止等の観点から、適当な範囲で膜の 孔サイズを大きくすることも十分に考え得ることであるから、甲11発明(認定)\nに接した本件優先日当時の当業者は、本件課題を解決するため、甲11発明(認定) において用いられる各膜の孔サイズを適当な範囲で大きくすることも小さくするこ とも検討するものと認められる。
以上のとおりであるから、本件周知技術における予備濾過膜の孔サイズが0.4\n5μmであることは、本件適用に係る阻害要因ではない。
b 参加人は、本件製品の膜につき、丙4にはこれをスクアレン含有水中油型エ マルジョンを含む水中油型エマルジョンの滅菌濾過に用い得る旨の記載がないとし て、甲11記載の発明の第1の濾過工程において用いられる膜に代えて、本件周知 技術の予備濾過膜を適用することには阻害要因があるとも主張する。\nしかしながら、甲11発明(認定)と本件周知技術とが技術分野を共通にしてお り、甲11発明(認定)が本件課題を有しており、かつ、本件製品が備える膜を用 いることにより本件課題を解決することができることは、前記(エ)aからcまでに おいて説示したとおりであるから、丙4に参加人が主張する記載がないことは、本 件適用に係る阻害要因があることを根拠付けるものではない。
c なお、参加人は、本件製品が製品歩留まりの点で他の製品に劣るとして、本 件優先日当時の当業者による本件適用に阻害要因がある旨の主張をするが、丙4の 102頁及び110頁の各「Highest product yield」の記載は、高価なたんぱく 質溶液や吸着(adsorption)に敏感な医薬品を高い回収率(product recovery rates)で濾過するのに適した膜に係る記載であると解されるから、これらの記載 が、たんぱく質を含有しないMF59C.1の製造方法に係る甲11発明(認定) に本件周知技術を適用することを否定したり、その阻害要因になったりするなどと 認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和1(ワ)24736 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月15日 東京地方裁判所
前記aないしdの各記載によると、本件出願当時、被服の技術分野 においては、二つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、 そもそも二つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容 易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる(な お、前記1(1)のとおり、本件明細書にも、本件出願当時に存在した課 題として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは 非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調整 することができないとの記載がみられるところである。)。 そうすると、被服の技術分野に属する本件公然実施発明の構成\n(「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第\n一の位置に取り付けられた紐1と」、「前記紐1が取り付けられた前記 第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付 けられた紐2とを備え」、「2本の紐(1、2)を結ぶことによって、 空気排出量を調節することができる」との構成)自体からみて、また、\n乙46説明書に「首と襟足の間隔を広くし」との記載及び紐が首の後 ろにある旨の図示(前記(1)イ )があることからすると、本件公然実 施発明に接した本件出願当時の当業者は、上記の課題を認識するもの と認めるのが相当である。
乙33発明’が解決する課題
前記(3)アの記載のとおり、乙33発明’は、「帯紐6a」に「ボタン 7a」を、「帯紐6b」に複数の「ボタン7b」をそれぞれ設け、「ボタ ン7a」を複数ある「ボタン7b」のいずれか一つにはめ込むとの構成\nを採用することにより、「帯紐6a」及び「帯紐6b」の装着長さを調 整し、もって、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツ1を 装着することを可能にするというものであるところ、乙33公報に装着\nの容易さについての記載(【0008】、【0009】、【0011】)があ ることや、前記 eのとおりの周知かつ自明の課題が本件出願当時に被 服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件出願当 時の当業者は、乙33発明’につき、これを二つの紐状部材を結んでつ ないで長さを調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手 段として認識するものと認めるのが相当である。
課題の共通性についての結論
前記 及び のとおりであるから、本件公然実施発明から認識される 課題と乙33発明’が解決する課題は、共通すると認めるのが相当であ る。
ウ 本件公然実施発明に乙33発明’を適用することについての動機付けの 有無
前記ア及びイのとおりであるから、被服の技術分野に属する本件公然実 施発明に接した本件出願当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調 整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調 整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するた め、同じ被服の技術分野に属する乙33発明’を採用するよう動機付けら れたものと認めるのが相当である。
エ 原告の主張について
原告は、本件公然実施発明は、排出する空気の量に応じて、中に支え る物体がない、空気を排出するスペースを調整するのに対して、乙33 発明’は、体型等に応じて中に支える物体があるものの周りを調整する ものであるから、その目的や機能が異なると主張する。\nしかしながら、本件公然実施発明と乙33発明’とは、紐状の部材の 締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし する。
しかしながら、本件公然実施発明と乙33発明’とは、紐状の部材の 締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし機能\nにおいて異なるものではないから、本件公然実施発明が空調服の首回り の空気排出スペースの大きさを調整するものであるのに対し、乙33発 明’が介護用パンツの腰回りの大きさを調整するものであること、すな わち、両者が何を調整するのかにおいて異なることは、前記ウに係る結 論を左右するものではない。 また、原告は、1)空調服は、世の中に存在しなかった革新的技術であ ることや、2)本件発明1は従来技術に比して有利な効果を有しており、 本件公然実施発明と異なる技術的意義を有することを主張している。 しかし、上記1)について、本件発明1は、本件公然実施発明等によっ て既に実用化されている空調服における空気排出口の開口度の調節方法 に係る発明であり、従来技術の延長線上に位置付けられるものと評価で きるところ、上記の調節方法が被服の技術分野で周知といえることは前 記(3)で説示したとおりである。そうだとすれば、空調服という製品自体 が革新的技術であることは、本件発明1の進歩性を基礎付ける事情とは ならないというべきである。 上記2)について、本件全証拠によっても、本件発明1がその進歩性を 基礎付けるほどの有利な効果や技術的意義を有しているとは認められな い。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和5(ネ)10037 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 特許法102条2項の適用について
ア 特許権者が特許権侵害を理由に民法709条の不法行為に基づく損害賠償を 請求する場合には、特許権者において、侵害者の故意又は過失、自己の損害の発生、 侵害行為と損害との間の因果関係及び損害額を立証する必要があるところ、特許法 102条2項は、特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵 害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害 の額と推定すると規定している。
イ この規定の趣旨は、特許権者による損害額の立証等には困難が伴い、その結 果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者 が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と 推定し、これにより立証の困難性の軽減を図ったものであり、特許権者に、侵害者 による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在 する場合には、特許権者がその侵害行為により損害を受けたものとして、特許法1 02条2項の適用が認められると解すべきである(知的財産高等裁判所平成25年 2月1日特別部判決(同裁判所平成24年(ネ)第10015号)、同裁判所令和元 年6月7日特別部判決(同裁判所平成30年(ネ)第10063号)、令和4年特別 部判決参照)。
ウ これを本件について、前記(1)の認定事実を前提として検討すると、本件では、 原告のSDエンジンは、SD装置が本件各発明を含むステルスダイシング技術を用 いたレーザ加工機能を実現するために必須となる部品であって枢要な機能\を担うも のであり、被告による被告旧製品(侵害品)の製造及び輸出・販売行為がなかった ならば、原告は自らのSDエンジンを被告又は他のSD装置の製造者に販売するこ ならば、原告は自らのSDエンジンを被告又は他のSD装置の製造者に販売するこ とにより、輸出・販売された被告旧製品に対応する利益が得られたであろうという ことはできる。しかしながら、原告はSDエンジンを販売していたものであって、 侵害品と同種の製品であるSD装置を製造・販売していたものではない。また、原 告において自らSD装置を製造する能力があり、具体的にSD装置を製造・販売す\nる予定があったことを認めるに足りる証拠もない。原告の逸失利益はあくまでもS\nDエンジンの売上喪失によるものであって、SD装置の売上喪失によるものではな い。そして、SD装置とSDエンジンとは需要者及び市場を異にし、同一市場にお いて競合しているわけではない。したがって、SD装置の売上げに係る被告の利益 全体をもって、原告の喪失したSDエンジンの売上利益(原告の損害)と推定する 合理的事情はない。
エ この点、原告は、被告旧製品の限界利益のうち、SDエンジン相当部分の限 界利益が原告の損害と推定されるべきであるとも主張する。しかし、SDエンジン は、SD装置の一部を構成する部品であって、その対価は製造原価を構\成する多数 の項目の一つにすぎない。そして、本件において、SD装置の限界利益のうちのど の程度の部分が、それぞれの部品に由来するものであるかを特定するに足りる事情 はなく、「SDエンジン」に由来する部分を特定することは困難というほかないので あって、「SDエンジン相当部分」の限界利益を一義的に特定することはできない。
仮にこれを算出する場合にも、確立した算出方法があるわけではなく、どのような 要素を考慮し、どのような論理操作を行うかによって様々な結論を導くことが可能\nであるから、このように算出された限界利益の「SDエンジン相当部分」をもって 本件における原告の損害を推定し、覆滅事由の主張立証責任を転換するための合理 的な基礎とすることはできないというべきである。したがって、原告の前記主張は 採用することができない。
オ 以上によれば、本件において、侵害者による特許権侵害行為がなかったなら ば利益が得られたであろうという事情があるとして特許法102条2項の規定の適 用が認められるとはいえるものの、SDエンジン相当部分の限界利益を特定するこ とができないから、同項の推定規定により本件における原告の損害を認定すること はできない。前記各知的財産高等裁判所特別部の判決は、いずれも特許権者等にお いて特許実施品又は侵害品と市場及び需要者を共通にする製品を販売等していたと いう事情が存在する事案について判断したものであるから、本件について、上記の ように解することと矛盾するものではない。原告は、知的財産高等裁判所令和4年 8月8日判決(同裁判所平成31年(ネ)第10007号)も引用するが、同判決 の事案は、特許権者が完成品を販売し、侵害者が間接侵害品である部品を販売して いた事案であって、本件のような完成品の限界利益中の当該部品に相当する部分の 特定が問題になった事案ではないから、同項の適用に関する前記結論を左右するに 足りるものではない。
そうすると、本件における原告の損害の認定は、特許法102条2項の推定規定 の適用以外の方法で行うのが相当である。
(3) 別件訴訟2(965特許)の考慮について
被告は、別件訴訟2の対象特許である965特許による侵害を考慮し、本件と別 件訴訟2において損害額を2分の1とするのが相当であると主張するが、各対象製 品の製造・販売等が965特許を侵害するものであるか否かという点は、本件訴訟 の審理対象となっているものではなく、仮に本件において原告に生じた損害のうち、 965特許の侵害による損害と重なる部分があるとしても、本件において965特 許の侵害が成立することを前提として損害額を算定することは相当ではないから、 損害の算定方法にかかわらず、被告の上記主張は採用することができない。
(4) 特許法102条1項(令和元年法律第3号による改正後のもの。本件は改正 法の施行日(令和2年4月1日)前の事案であるが、経過規定は設けられていない から、以下においては、改正後の条文を適用する。)による損害額の算定 ア 特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益 の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害者の譲 渡した物の数量(譲渡数量)に特許権者がその侵害行為がなければ販売することが できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者の実施の能力の限度で\n損害額とするが、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売するこ とができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応 じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の 立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規 定である(知的財産高等裁判所令和2年2月28日特別部判決(同裁判所平成31 年(ネ)第10003号)参照)。
特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者が「侵害の行為が なければ販売することができた物」(同項1号)とは、侵害行為によってその販売数 量に影響を受ける特許権者の製品であれば足り、特許権者が特許実施品又は専ら特 許実施品の生産のために用いる物(部品)を販売しており、侵害行為がなければ、 特許権者は自らの製品を販売することができたという関係にある場合には、特許権 者は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品を販売していたというこ とができるから、同項の適用が是認される。
そして、本件では、前記(2)のとおり、被告の侵害行為がなければ、原告はその製 造する原告エンジンを販売することができ、これにより利益を得ることができたも のと推認され、原告は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品である 原告エンジンを販売していたということができるから、同項を適用することができ る。
イ 限界利益
原告は、原告エンジンの限界利益について●●●●●●●●●円であると主張す るが、前記認定事実のとおり、原告は被告に対し、●●●●●円で原告エンジンを 販売していたのであるから、上記の限界利益額をそのまま採用することはできない。 そして、原告従業員の陳述書(甲73)によると、被告旧製品(対象製品1(2)B) のSDエンジンの競合品である原告エンジン(800DS一式)の原価は●●●● ●円(1万円未満切り捨て)であり、これを前提とすると、原告エンジンの一台当 たりの限界利益は●●●●●円(=●●●●●円−●●●●●円)、●●台分の限界 利益は4億1280万円となる。 なお、LDモジュールは侵害行為がなければ特許権者である原告が販売できた物 であると認めるに足りないから、LDモジュールに係る部分は考慮しない。
ウ 推定の覆滅
本件各発明は、ステルスダイシング機能そのものに係るものではなく、同機能\を 用いて加工対象物をレーザ加工する際の端部の処理に関するものであること、本件 各発明に係る技術については、AF低追従を用いるという代替技術や、端部におい てはレーザ加工をしないという手法(エッジオフ)が存在し、現に、被告がAF低 追従を用い、エッジオフ機能を有する被告新製品を販売していることからすると、\n本件各発明自体の顧客吸引力が高いとは認められないこと、原告エンジンを組み込 んだ被告又はディスコ社のSD装置が被告旧製品と全く同じ性能や機能\を有するも のではないこと、被告が個々のユーザの製造プロセスや加工対象物の形状に応じて
SD装置の仕様を変更し、モジュールを開発して提供するなどして被告製品を販売 していたこと等、本件に表われた事情を総合すると、特許法102条1項1号の「特\n許権者が販売することができないとする事情」に相当する数量は、7割であると認 めるのが相当である。
エ 損害額
以上によると、特許法102条1項により算定される損害額は、1億2384万 円(=4億1280万円×(1−0.7))であり、同条3項により算定される損害 額(後記(5)イ)を上回る。
なお、原告は、同条1項による損害額の算定においては、原告エンジン一台当た りの限界利益額に侵害品の販売台数を乗じた金額に、1台当たり300万円の実施 料相当額を加算すべきであると主張し、同項2号の規定は、同項1号の実施相応数 量を超える数量又は特定数量がある場合において、一定の条件で実施料相当額の損 害を加算することを認めている。しかし、前記ウで認定した「特許権者が販売する ことができないとする事情」に相当する数量は、その性質上、特許権者が実施許諾 をし得たものとは認められないから、本件では、同項2号の規定を適用して、実施 料相当額を加算することはできない。したがって、原告の主張は採用することがで きない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和5(ネ)10096 損害賠償請求控訴事件 その他 民事訴訟 令和6年3月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審(東地判令和4年(ワ)10717)はアップされていません。
控訴人は、前記第2の3(1)のとおり、本件準備契約6条は、ステルスダイ シング技術に関する本成果については、控訴人と被控訴人の共有とする旨を 定めたものである旨を主張する。 しかし、本件準備契約6条の解釈については、補正の上で引用した原判決 第3の1(2)のとおりである。 控訴人は、補正の上で引用した原判決第3の1(1)イの控訴人による修正申\n入れにより、ステルスダイシング技術に関する「本成果」は、控訴人と被控 訴人の共有とする旨定める本件準備契約6条1項(2)に移されて本件準備契約 の締結に至ったものであるから、ステルスダイシング技術に関する「本成果」 も、控訴人と被控訴人の共有となる旨主張する。
しかし、ステルスダイシング技術に関する「本成果」についても控訴人と 被控訴人の共有とする旨の合意の下に、本件準備契約が締結されたと認める に足りる的確な証拠はない上、補正の上で引用した原判決第3の1(2)アのと おり、本件準備契約6条1項(1)及び(2)は、いずれも同条柱書に記載された「本 成果」の帰属等について定めるものであるところ、同項(2)は、もともとSD エンジンに「関しない本成果」を控訴人と被控訴人の共有とする旨定めてい たものであるから、同項(2)にステルスダイシング技術に関する定めを移すこ とが、直ちに「ステルスダイシング技術に関する本成果」を控訴人と被控訴 人の共有とする旨定めるに至ったことを意味するものともいえない。「ステル スダイシング技術」は、被控訴人が作成した契約書の第1ドラフト(甲22) においても、「乙(判決注:被控訴人)が基本特許を有するレーザを用いたダ イシング技術」と定義されており、本件準備契約作成時点において被控訴人 に帰属する固有の技術であったのであるから、これが控訴人と被控訴人の共 有になることはないというべきである。 したがって、控訴人と被控訴人の共同開発に至る経緯を考慮しても、上記 解釈を左右するものではないから、控訴人の上記主張は採用することができ ない。
(2) 控訴人は、前記第2の3(2)、(3)及び(4)アのとおり、SDエンジンに関する 本成果とは、発明・考案等の課題解決のため必須の構成全部を、SDエンジ\nンが備えるものをいうと解すべきと主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第3の1(3)のとおり、本件準備契約の 目的、趣旨や文理等に鑑みると、「SDエンジンに関する本成果」とは、発明 の特徴的部分がSDエンジンに関する発明等(本成果)をいうものと解され る。したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(3) 控訴人は、前記第2の3(4)イ(ア)のとおり、「SDエンジンに関する本成果」 に関し、仮に「発明の特徴的部分」を基準として発明の帰属を判断するもの と解したとしても、本件発明1は控訴人と被控訴人の共有とすべきものと主 張し、それに沿う証拠として甲51、52を提出する。
しかし、補正の上で引用した原判決第3の1(4)のとおり、本件発明1は、 いずれも発明の特徴的部分がSDエンジンに関するものとして、その成果は 被控訴人に属するものというべきであるところ、控訴人が当審において提出 する甲51、甲52はいずれもCPUボードないしコンピュータソフトウェ\nア設計に係る証拠であり、本件発明1の内容は補正の上で引用した原判決第 2の1(3)及び同第3の1(4)ア(ア)のとおりであって、本件発明1は、レーザ加 工方法の手順をレーザ加工装置のコンピュータに実行させるためのコンピュ ータソフトウェアに係る発明ではない。そうすると、上記の控訴人の主張及\nびこれに係る証拠は、本件発明1の特徴的部分ないし発明特定事項である特許請求の範囲の記載と関係しないものである。 その点を措いても、本件試作機は、●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」(平 成14年10月2日付け打合議事録。甲26)とされていることから、本件 試作機においては、それまでレーザエンジン側で行っていたことを装置本体 側のCPU162で行えるようにしたものであるところ、控訴人のCPU1 62に係る主張は、レーザ加工装置の制御を行うCPUの所在場所をいうも のにすぎず、そのプログラムの前提となる本件発明1の前記特徴に係るもの ではない上、本件準備契約1条(3)の「SDエンジン」の定義には、キーコン ポーネント部及びソフトウェア設計も含まれているのであるから、CPU1\n62の所在場所及びそのソフトウェアとしての機能\をもって、本件発明1を 控訴人と被控訴人の共有とすべき根拠とすることはできないというべきであ る。
また、控訴人は、本件発明1は、X軸上のステージの動作とその制御を発 明の特徴的部分に含み、加工対象物の端部というステージのX軸上の特定の 位置においてレンズのZ軸上の所定の動作を行うものであり、これはSDエ ンジンに関する発明に該当しない旨も主張する。 しかし、805特許に係る明細書(甲48)は補正の上で引用した原判決 別紙3のとおりであるところ、その明細書の段落【0045】、【0058】 及び【0075】の記載によれば(記載内容は原判決別紙3参照)、805特 許において、既にZ軸ステージをZ軸方向に移動させることにより、加工対 象物(シリコンウェハ)の内部にレーザ光の集光点を合わせることができ、 X軸ステージやY軸ステージを移動させることにより、集光点を切断予定ラ\nインに沿って移動させ、これにより、改質領域を切断予定ラインに沿うよう\nに加工対象物の内部に形成することが示されているから、これと本件発明1 の内容(補正の上で引用した原判決第2の1(3)及び第3の1(4)ア)とを対比 すると、805特許に示されたX軸ステージの移動に係る制御と特段異なる 内容は示されておらず、本件発明1の内容にはX軸ステージの移動に係る制 御に関して805特許に示されたX軸ステージの動作を超える新規の技術的 事項は何ら示されていない上、控訴人の主張するX軸上の特定の位置の検出 それ自体は、X軸ステージの制御を意味するものでもないから、これをもっ て、X軸ステージの制御に本件発明1の特徴的部分があるとはいえない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(4) 控訴人は、前記第2の3(4)イ(イ)のとおり、「SDエンジンに関する本成果」 に関し、仮に「発明の特徴的部分」を基準として発明の帰属を判断するもの と解したとしても、本件発明2は控訴人と被控訴人の共有とすべきものと主 張する。
しかし、補正の上で引用した原判決第3の1(4)イのとおり、本件発明2は、 いずれも発明の特徴的部分が「SDエンジン」に関するものとして、その成 果は被控訴人に属するものというべきである。 本件発明2に係るパルスピッチは、レーザ光の繰り返し周波数及びX軸な いしY軸ステージの移動速度との関係により決まるものであるところ(本件 明細書2の段落【0015】及び【0057】)、前記(3)のとおり、805特 許において、既にX軸ステージやY軸ステージを移動させることにより、集 光点を切断予定ラインに沿って移動させ、これにより、改質領域を切断予\定 ラインに沿うように加工対象物の内部に形成することが示されており、これ と本件発明2の内容(補正の上で引用した原判決第2の1(4)及び第3の1(4) イ)とを対比すると、805特許に示されたX軸ステージやY軸ステージの 移動に係る制御と特段異なる内容は示されておらず、本件発明2の内容には X軸ステージやY軸ステージの移動に係る制御に関して805特許に示され たX軸ステージやY軸ステージの動作を超える新規の技術的事項は何ら示さ れていない。そうすると、X軸ステージ及びY軸ステージの制御に本件発明 2の特徴的部分があるとはいえない。
また、控訴人の提出に係る証拠において、パルスピッチが明記されている ものは、甲38(「浜松ホトニクス殿・出張報告―14」と題する文書)に、\n「改質層ピッチ」として本件発明2の数値範囲内である●●●●μmとの記 載があるのみであり、その甲38においても、パルスピッチが記載されてい る箇所は、「hpk SDL_100V での最新(〜7/11)の加工状況」における「現在の 最適条件」の欄であって、パルスピッチに関し控訴人が知見を得たことを示 すものとはいえないところ、乙12ないし14、16及び18には、例えば 乙12(平成15年6月13日被控訴人作成の「スケジュール」と題する書 面)に、「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」 などとあり、乙13(平成15年6月13日被控訴人作成の実験資料)には、 パルスピッチごとに改質領域の形成状況が示された実験結果があるように、 被控訴人において、パルスピッチ及び微小空洞に着目して実験を繰り返し、 最適なパルスピッチ等につき検証を行っていたことが認められる。そうする と、こうしたパルスピッチの最適化に関し、控訴人に具体的な貢献があった と認めるに足りる証拠はないから、控訴人の主張はその前提を欠くものというべきである。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2024.06. 9
令和6(行ケ)10003 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年6月3日 知的財産高等裁判所
原告は、法3条1項柱書及び3号は条文上需要者の認識を何ら問題として いないのに、本件審決は、取引者、需要者の認識を基準として本願商標は役 務の質を表示したものと判断したとして、その誤りを主張する。\nこの点、法3条1項3号は「その役務の質を普通に用いられる方法で表示す\nる標章のみからなる商標」を商標登録できない商標として掲げているところ、 出願商標が何を表示するものであるかを客観的に把握する上では、取引者、需\n要者の認識を基準として判断せざるを得ないことは当然であり、そのような解 釈は、法1条の趣旨にも沿うものといえる。
原告は、法3条 1 項3号と、同項6号及び2項との条文の違いを上記主張の 根拠としているが、同条1項6号の「前各号に掲げるもののほか、需要者が何 人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」と の文言、同条2項の「前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、 使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識 することができるものについては」の文言に照らすと、同条1項3号の解釈上 も、需要者の認識が判断基準として想定されていると理解することができ、そ の趣旨をいう本件審決の判断に誤りはない。
2 原告は、1)法3条1項3号における「役務の質」は「『労働勤務』や『他人に利益があるようにする行為』の質」を指すとして、あるいは2)「質」に ついて「内容、中身」の意味を含むと解釈するのは古い時代の解釈であると して、本願商標は「役務の質」を表していないと主張する。\n
しかし、同号に掲げる商標が商標登録要件を欠くと規定されている趣旨は、 このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質等の特 性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表\示として何人もそ の使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公 益上適当でないなどの理由によるものである。このような趣旨に鑑みれば、 同号の「役務の質」を原告主張のように限定的に解釈すべき理由はない。 しかも、証拠によれば、本願商標「骨格診断7タイプ」がその指定役務に使 用された場合、そうした役務が労働の対価を得て有料でなされ得るもの(乙 6・骨格診断アドバイザー、乙7・骨格診断ファッションアナリスト、乙1 1・骨格診断士〔骨格診断資格〕)があることも認められ、原告の上記主張を 前提にしても、本願商標が同号にいう「役務の質」を表示するものであるとい\nえる。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2024.06. 7
令和5(ネ)10063 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年5月15日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
イ 本件適用2に係る動機付けと阻害要因の有無
前記(4)イ(ア)のとおり、乙15発明は、回転駆動源に電動モータを使用したトル ク制御式パルスツール(ねじ締めツール等)の技術分野に属するものである。また、 前記アによると、本件周知技術は、電動モータに使用される磁石の固定方法に関す るものであるから、電動モータの技術分野に属するものである。そして、相違点B に係る本件発明等の構成の内容は、磁石がステータに隙間を設けて貼\設されている ことであるから、本件適用2との関係では、乙15発明(電動モータに係る部分) と本件周知技術は、その属する技術分野を共通にするものである。さらに、乙15 発明(乙6発明Aを適用したもの)に接した本件優先日当時の当業者は、磁石をど のようにして筒状のロータの内周面に保持するかという課題に直面することになる ところ、接着剤を用いて磁石をロータに隙間を設けて貼設する技術である本件周知\n技術は、当該課題を解決することのできる手段(技術)となる。したがって、本件 優先日当時の当業者において、乙15発明(乙6発明Aを適用したもの)に本件周 知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。 本件適用2をするに当たり、阻害要因があることを認めるに足りる証拠はない。
ウ 相違点Bに係る本件発明等の構成の容易想到性についての小括\n
(ア) 以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者は、乙15発明に乙6 発明A及び本件周知技術を適用することにより、相違点Bに係る本件発明等の構成\nに容易に想到し得たものと認めるのが相当である。
(イ) この点、原告は、乙15発明に乙6文献記載の発明を適用し、その後に周 知技術を適用して相違点Bに係る本件発明等の構成を導出することは「容易の容易」\nに当たるから、本件優先日当時の当業者において、相違点Bに係る本件発明等の構\n成に容易に想到し得たとはいえないと主張する。 確かに、前記イのとおり、本件適用2は、乙6発明Aを適用した乙15発明を前 提とするものである。しかしながら、電動式衝撃締め付け工具において、電動モー タをアウタロータ型のものとすること(相違点A関係)と当該電動モータにおいて 磁石を筒状のロータの内周面に隙間を設けて貼設すること(相違点B関係)は、そ\nれらの内容に照らし、相互に関連する技術ではなく、互いに独立した別個の技術で あるといえるから、原告の主張は、相違点Bに係る本件発明等の構成の容易想到性\nを左右するものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.06. 6
令和3(ワ)13623 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年4月14日 東京地方裁判所
(2)ア 本件投稿者は、原告写真の複製物であり被告各写真を本件記事の文章と ともに被告に送信した。
イ もっとも、本件投稿者が被告に上記送信をしたことにより、直ちに、被 告各写真が公衆送信されることになったとは認められない。 本件ウェブサイトでは、会員が被告に送信した記事を被告地域パートナ ーが承認して、初めて、その記事を本件ウェブサイトの一般の閲覧者が閲 覧できるようになる(前記1(1)ウ )。本件投稿者が被告に送信した被告 各写真を含む本件記事についても、被告の地域パートナーが、その内容等 を審査して、それを承認したことにより、その承認後、被告各写真や本件 記事を本件ウェブサイトの一般の閲覧者が閲覧できるようになったと推認 することができる。
ウ 被告は、旅行に関する情報提供サービス及びそのコンサルティング業等 を目的とする株式会社であり(前記前提事実(1)イ)、本件ウェブサイトに は、「ジャパントラベルは、日本の魅力を世界に発信するメディアであり、 その他コンサルティングビジネスおよび第二種旅行業登録の訪日専門トラ ベルエージェンシーを運営」(前記1 ア)、「「インバウンド専門旅行会社 経験豊富な外国人・日本人スタッフがカスタマイズツアーを主力とした インバウンドツアーをサポートします。」(同イ )と記載されていること、 本件ウェブサイトを通じて、ホテル又は飛行機を予約したり、鉄道切符や\n施設入場券、各種パッケージツアー、体験型ツアーを購入したり、オーダ ーメイドの旅の予約をしたりすることができること(同イ )からすれ ば、本件ウェブサイトは、会員から記事の送信を受けて、その記事を表示\nすることで観光地の情報を提供しつつ、それを利用してツアーの企画など の旅行関連事業を行うことも目的としたものといえる。したがって、本件 ウェブサイトは、被告の旅行関連事業の営業のために設けられているとい う性質も有するといえる。
本件ウェブサイトでは、被告が利用者コンテンツを審査し、編集等する 旨の規定が設けられている(前記1 ウ )だけではなく、実際に、会員 が記事を被告に送信しても、被告地域パートナーの承認がない限り当該記 事は本件ウェブサイトに掲載されず、会員が被告に送信した写真は、被告 地域パートナーが承認という作業をすることによって、自動公衆送信装置 といえるサーバーに蔵置、記録され、送信可能化されるに至り、公衆送信\nされることになったといえる。また、前記 ウによれば、本件ウェブサイ トは、被告が行う旅行関連事業の営業のために設けられているという性質 も有するといえる。会員による記事の送信は、そのような被告のための記 事の提供という面も有していた。被告地域パートナーは、本件ウェブサイ トにおいて、会員から送信された記事の内容について、上記のとおりの本 件ウェブサイトの目的に沿うものであるかやその目的との関係でその質を 維持するものであるかなどを広く審査して、承認の可否を決定し、また必 要な修正を行っていたと推認でき、また、これらの作業を被告の営業のた めに被告の履行補助者として行っていたと認められる。 これらによれば、本件投稿者が被告に送信した被告各写真は、被告の履 行補助者である被告地域パートナーが被告の営業のために内容を広く審査 して承認という作業をしたことによって、サーバーに蔵置、記録され、送 信可能化されるに至り、公衆送信されたといえる。これらを考慮すると、\n被告が、被告各写真の複製、公衆送信をしたと認めることが相当である。 被告の主張について 被告は、1)記事の修正等をする被告地域パートナーはボランティアであ ること、2)被告各写真の投稿者は、被告から経済的利益を得たり、また、 指示等を受けておらず、任意に被告各写真を投稿したことを挙げて、被告 は、複製、公衆送信の主体ではないなどと主張する。
ア 上記1)について、被告地域パートナーがボランティアであったとして も、本件ウェブサイトは被告の旅行関連事業の営業のために設けられて いるという性質も有し、被告地域パートナーによる記事の承認等は、そ のような被告の営業のために行われるものと推認できることを併せて考 えれば、被告地域パートナーは、被告からの直接の報酬の支払を受けて いなかったとしても、被告の履行補助者とみるのが相当である。 したがって、被告の上記1)の主張を採用することはできない。
イ 上記2)について、本件ウェブサイトが前記のとおり被告の営業目的の ために設けられているという性質も有し、また、被告各写真についても、 他の記事と同様に、被告地域パートナーが内容を広く審査して承認し、 公衆送信されるようになったと認められることに鑑みれば、被告各写真 が被告に対して送信されたのは会員の自由な意思に基づくものであった としても、被告各写真を複製し公衆送信したのは被告とみるのが相当で ある。したがって、被告の上記2)の主張も採用することはできない。
(5)著作者人格権侵害について
前提事実 のとおり、本件ウェブサイトにおいて、原告の氏名(ペンネー ム)を表示せずに被告各写真が表\示され、また、別紙URL目録記載1のウ ェブページにおいて原告写真の左右が切除されていたと認めることができる。 これらと、本件ウェブサイトにおいて被告各写真が掲載されるに至る過程 に照らせば、前記(3)と同様の理由により、被告は、原告の氏名表示権及び同\n一性保持権を侵害したといえる。 以上によれば、被告は、原告が保有する原告写真の複製権及び公衆送信 権を侵害し、また、氏名表示権及び同一性保持権を侵害したといえる。\n
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2024.06. 6
令和4(ワ)4104 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年12月23日 東京地方裁判所
(1) 不競法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示(人の業務に係る氏名、\n商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示\nするものをいう。以下同じ。)と同一又は類似の商品等表示を使用等する\nことをもって、不正競争に該当する旨規定している。この規定は、周知な 商品等表示の有する出所表\示機能を保護するという観点から、周知な商品\n等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧\n客を獲得する行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保するものと解 される。そして、商品の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有す\nる場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所表示機能\ を有するものではないから、上記規定の趣旨に鑑みると、その形態が商標 等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能\を発揮するような特 段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべきである。そう\nすると、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴 (以下「特別顕著性」という。)を有しており、かつ、2)特定の事業者に よって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強 力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の出所 を表示するものとして周知(以下「周知性」という。)であると認められ\nる特段の事情がない限り、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当し\nないと解するのが相当である。 そして、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のも\nのと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止するという同号の上記趣旨 目的に鑑みると、商品の形態が、取引の際に出所表示機能\を有するもので はないと認められる場合には、特定の出所を表示するものとして特別顕著\n性又は周知性があるとはいえず、上記商品の形態は、不競法2条1項1号 にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。\n
(2) これを本件についてみると、前記認定事実によれば、1)本件製品は、中 圧B供給用ガス遮断弁であるところ、その国内における需要者は、ガスボ イラーメーカーやガスバーナーメーカーの専門業者約30社に限られ、一 般消費者が店頭において商品を見比べて購入するという性質の製品ではな いこと、2)本件製品は、その性質上、高度の安全性が求められる製品であ り、不具合があると、多大な損失が生ずる可能性があるため、需要者であ\nる専門業者は、購入に当たって、製品の安全性、信頼性を重視しているこ と、3)現に、需要者は、2〜3年かけてテストを繰り返しながら慎重に製 品の採否を検討するのであり、その検討のためには、製品内部の動作や構\n造についても詳細な情報を要求するのが通例であること、4)被告製品自 体、原告製品の機能やアフターサービスに対する需要者の要望を受けて、\n原告製品の互換品として開発されるに至ったものであること、5)被告製品 の価格は、約50万円と高額であり、原告製品も同程度であると推認され ること、6)原告自身、原告製品に関する宣伝広告に当たって、原告製品の 形態上の特徴それ自体を強調しておらず、被告においても、被告製品の形 態をセールスポイントとするものではないこと、以上の事実が認められ る。
上記認定事実によれば、本件製品の需要者は、約30社の専門業者に限 られるのであり、当該専門業者は、長期間費やし製品をテストするなどし て、専ら安全性、信頼性の観点から本件製品を購入していることが認めら れることからすると、需要者である本件製品の専門業者は、取引の際にそ もそも製品の形態自体に着目して本件製品を購入するものとはいえない。 上記認定に係る本件製品の取引の実情に鑑みると、原告製品の形態は、 一定程度の周知性があるとしても、出所表示機能\を有するものではなく、 不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当であ\nる。 仮に、原告製品の形態が商品等表示に該当するという見解に立ったとし\nても、上記認定に係る本件製品の取引の実情を踏まえると、需要者である 本件製品の専門業者は、長期間費やし製品をテストするなどして、専ら安 全性、信頼性の観点から本件製品を購入しているのであるから、当該需要 者において原告製品と被告製品の誤認混同が生じないことは、明らかであ る。 したがって、被告が被告製品を製造又は販売する行為は、不競法2条1 項1号の不正競争行為に該当するものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2024.06. 6
令和3(行ケ)10108 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年7月14日 知的財産高等裁判所
ア 本件商標は、「チロリアンホルン」の文字をゴシック体で横書きに書して なり、「チロリアン」の文字部分と「ホルン」の文字部分とから構成される\n結合商標である。本件商標を構成する文字は、外観上、同書、同大、同間\n隔で一連表記されており、構\成文字に相応して、「チロリアンホルン」の称 呼が生じる。
次に、「チロリアン」の文字部分は、「チロルの人々。オーストリア西部 からイタリア北東部にまたがるチロルの山岳地帯に住む人々の用いる独 特の民族服」(ブリタニカ国際大百科事典)、「チロル地方の。チロル風の」 (広辞苑第七版)といった意味を有する語として、「ホルン」の文字部分は、 「角笛。金管楽器」(広辞苑第七版)といった意味を有する語として、一般 に理解されていることが認められる。このような上記各文字部分の観念及 びそれぞれの称呼に照らすと、本件商標を構成する文字は、外観上、同書、\n同大、同間隔で一連表記されていることを勘案しても、本件商標において、\n「チロリアン」の文字部分と「ホルン」の文字部分とを分離して観察する ことが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているもの とは認められない。
そして、前記1(2)認定のとおり、標章「チロリアン」は、本件商標の登 録査定日(平成29年1月10日)当時、福岡県を中心とした九州地方に おいて、菓子の取引者、需要者の間で、特定の菓子(菓子「チロリアン」) のブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたこ とに照らすと、本件商標がその指定商品中の「菓子」に使用された場合に は、本件商標の構成中の「チロリアン」の文字部分は、菓子のブランド名\nを示すものとして注意を惹き、取引者、需要者に対し、相当程度強い印象 を与えるものと認められる。そうすると、本件商標の構成中「チロリアン」の文字部分は、独立して商品の出所識別標識として機能\し得るものと認められるから、本件商標か ら上記文字部分を要部として抽出し、これと引用商標1とを比較して商標 そのものの類否を判断することも、許されるというべきである。
イ これに対し、被告は、1)本件商標は、「チロリアンホルン」の文字を横書 きしてなり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔 に1行でまとまりよく表されており、その文字構\成は一連一体であること からすると、「チロリアン」の部分と「ホルン」の部分は、分離して観察す ることが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合している、2)標章 「チロリアン」、「TIROLIAN」は、本件商標の登録出願時及び登録 査定時において、原告の業務に係る商品を表すものとして、取引者、需要\n者の間に広く認識されていたとはいえないから、本件商標の構成中の「チ\nロリアン」の文字部分が、本件商標の指定商品の取引者、需要者に対し、 原告の商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはい えない、3)菓子「チロリアン」については、発売後ほどなくして、標章「チ ロリアン」を使用して独自に販売を行う事業主体が複数生じ、平成8年以 降は、標章「チロリアン」を使用する事業主体間で多数の紛争が生じてお り、標章「チロリアン」について統一的な管理が行われていなかったこと に照らすと、取引者、需要者は、本件商標の構成中の「チロリアン」の文\n字部分が、複数の事業主体のいずれに係る表示であるかを認識することが\n困難であるから、「チロリアン」の文字部分は、原告の出所識別標識として 強く支配的な印象を与えるものに該当しない、4)菓子「チロリアン」を製 造販売する複数の事業主体について、経済的・組織的な一体性を持つグル ープといったものが形成されたことはないから、「チロリアン」の文字部分 が、上記のようなグループの識別標識として強く支配的な印象を与えると 評価する余地もない、5)「チロリアン」の文字部分に出所識別機能がない\nにもかかわらず、これがあるかのように評価して結合商標の分離観察を行 い、その結果として、標章「チロリアン」について他の事業主体に比べて 不十分な使用実績しか有しない原告に引用商標1ないし3を含む「チロリ\nアン」の登録商標を独占させるような帰結は、社会的妥当性に欠けるなど と主張して、本件商標から「チロリアン」の文字部分を要部として抽出す ることは許されない旨主張する。
しかしながら、前記(1)で説示したとおり、商標の各構成部分がそれを分\n離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結 合しているものと認められない商標においては、商標の構成部分の一部が\n取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印 象を与えるものと認められる場合などのほか、商標の構成部分の一部が取\n引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商 品の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合においても、商\n標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較し\nて商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当であ る。
そして、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い\n印象を与えるものであり、独立して商品の出所識別標識として機能し得る\nか否かについての判断は、商標に接した取引者、需要者において、商標の どのような構成部分について注意を惹き、どのような印象を受けるかなど\nの観点から判断されるべきものであることに照らすと、その判断において は、取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識\nし得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体(例えば、特定の事業\n主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等)について正確に認 識することまでは要しないと解するのが相当である。 被告主張の1)については、前記アのとおり、「チロリアン」の文字部分の 観念及び称呼、「ホルン」の文字部分の観念及び称呼に照らすと、本件商標 を構成する文字が、外観上、同書、同大、同間隔で一連表\記されているこ とを勘案しても、本件商標において、「チロリアン」の文字部分と「ホルン」 の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほ ど不可分的に結合しているものとは認められない。
被告主張の2)ないし4)は、取引者、需要者において、本件商標の構成中\nの「チロリアン」の文字部分に係る出所自体(特定の事業主体の名称等) について正確に認識することまで必要であることを前提とし、上記文字部 分が原告の出所を示す出所識別標識として認識されることを求めるもの であるから、その前提において採用することができない。 また、被告主張の5)については、結合商標の構成部分の一部を要部とし\nて抽出することができるかどうかの判断は、上記のとおり、当該結合商標 に接した取引者、需要者の認識及び印象に係る問題であって、本件商標と の関係では、原告による標章「チロリアン」の使用実績の規模等によって その判断が左右されるものではないから、その前提において採用すること ができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2024.06. 4
令和5(行ケ)10122 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年5月16日 知的財産高等裁判所
本件商標は、「雨降」の文字を筆文字風で、右上方から左斜め下へ書してなるとこ ろ、当該文字は「[あめふり]雨の降ること。雨が降っている間。」、「[うこう]雨降り。」の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して、「アメフリ」又は「ウ\nコー」の称呼を生じ、「雨の降ること。雨が降っている間。雨降り。」の観念を生ず るものである。
別紙2引用商標目録記載の商標登録第6245408号商標(以下「引用商標」 という。)は、「AFURI」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、辞書類に 載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているとも いい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「アフリ」の称呼を生じ、特定\nの観念は生じない。
本件商標と引用商標との類否について、両者は、漢字と欧文字と文字種が異なる ものであるから、外観において明確に区別できる。また、称呼については、本件商 標から生ずる「アメフリ」の称呼と、引用商標から生ずる「アフリ」の称呼とは、 2音目において「メ」の音の有無に差異を有するものであるが、4音と3音という 比較的短いこれらの称呼を一連に称呼するときは、互いの語調語感が異なり聞き誤 るおそれはない。そして、本件商標から生ずる「ウコー」の称呼と、引用商標から 生ずる「アフリ」の称呼とは、音構成が相違することから、両者は、称呼上、明瞭\nに聴別し得るものである。さらに、観念については、本件商標は「雨の降ること。 雨が降っている間。雨降り。」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は観念 が生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても 相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。したがって、本件商標は、 商標法4条1項11号に該当しない。
(2) 商標法4条1項10号及び15号該当性について
原告が、本件商標の登録の無効理由において、商標法4条1項7号、10号、1 5号及び19号に該当するとして引用する商標は、原告の業務に係る「ラーメンの 提供」に使用する「AFURI」の欧文字からなる商標(以下「使用商標」という。) である。
使用商標は、本件商標の登録出願時において既に、原告の役務を表示するものと\nして需要者の間に広く認識されていたとは認められず、また、使用商標は引用商標 と同じつづりからなるものであるから、本件商標と使用商標とは、前記(1)と同様の 理由により、非類似の商標である。 そうすると、被告が、原告の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして\n需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標を、その商品若しく は役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものではなく、 また、被告が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者 は、当該商品が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の 業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混 同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項10号又は同項15号のいずれにも該 当しない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2024.06. 4
令和5(ネ)10110 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和6年5月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 前提事実(訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」の第2の2)によると、 共有対象となる特定のファイルに対応して形成されたビットトレントネットワークに ピアとして参加した端末は、他のピアとの間でハンドシェイクの通信を行って稼働状 況やピース保有状況を確認した上、上記特定のファイルを構成するピースを保有する\nピアに対してその送信を要求してこれを受信し、また、他のピアからの要求に応じて 自身が保有するピースを送信して、最終的には上記特定のファイルを構成する全ての\nピースを取得する。
そして、証拠(甲5〜9、11)及び弁論の全趣旨によると、ビットトレントネッ トワークで共有されていた本件複製ファイルが本件動画の複製物であること、原判決 別紙動画目録記載の各IPアドレス及びポート番号の組合せは、本件監視ソフトウェ\nアが、本件複製ファイルを共有しているピアのリストとしてトラッカーから取得した ものであること、同目録記載の発信日時は、上記IPアドレス及びポート番号を割り 当てられていた各ピアが、本件監視ソフトウェアとの間で行ったハンドシェイクの通\n信において応答した日時であることがそれぞれ認められる。
そうすると、上記各ピアのユーザーは、その対応する各発信日時までに、本件動画 の複製物である本件複製ファイルのピースを、不特定の者の求めに応じて、これらの 者に直接受信させることを目的として送信し得るようにしたといえ、他のピアのユー ザーと互いに関連し共同して、本件動画の複製物である本件複製ファイルを、不特定 の者の求めに応じて、これらの者に直接受信させることを目的として送信し得るよう にしたといえる。これは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動 公衆送信装置である各ピアの端末の公衆送信用記録媒体に本件複製ファイルを細分化 した情報である本件複製ファイルのピースを記録し(著作権法2条1項9号の5イ)、 又はこのような自動公衆送信用記憶媒体にビットトレントネットワーク以外の他の手 段によって取得した本件複製ファイルが記録されている自動公衆送信装置である各ピ アの端末について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行った(同号ロ) といえるから、本件動画につき控訴人が有する送信可能化権が侵害されたことが明ら\nかである。
(2) 被控訴人は、各ピアのユーザーが送信可能化権を侵害したことが明らかという\nには、当該ピアのユーザーのピース保持率が100%又はこれに近い状態に達してい ることを要すると主張する。しかし、上記(1)のとおり、ビットトレントネットワーク に参加した各ピアは、共有対象となったファイルの一部であるピースをそれぞれ保有 してこれを互いに送受信し、最終的には当該ファイルを構成する全てのピースを取得\nすることが可能な状態を作り出しているのであるから、各ピアのユーザーは、他のピ\nアのユーザーと互いに関連し共同して、当該ファイルを自動公衆送信し得るようにす るものといえる。そして、ハンドシェイクの通信に応答したピアは、当該ファイルの 一部であるピースを保有してこれを自身の端末に記録し、他のピアの要求に応じてこ れを送信する用意があることを示したものと認められるから、その保有するピースの 多寡にかかわらず、上記送信可能化行為を他のピアと共同して担ったものと評価でき\nる。被控訴人の主張は採用することができない。
・・・・
(1) 前記1(1)のとおり、原判決別紙動画目録記載のIPアドレス、ポート番号及び 発信日時により特定される通信は、各ピアが本件監視ソフトウェアとの間で行ったハ\nンドシェイクの通信において応答した通信であって、他のピアとの間で本件複製ファ イルのピースを送受信し、又は本件複製ファイルを記録した端末をネットワークに接 続する通信そのものではない。このような通信に係る発信者情報(本件各発信者情報) も、法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるかが問題となる。
(2) そこで検討すると、法5条1項は、開示を請求することができる発信者情報 を「当該権利の侵害に係る発信者情報」とやや幅を持たせたものとし、「当該権利の 侵害に係る発信者情報」のうちには、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害 関連通信に係るものとして総務省令で定めるもの。)を含むと規定しているところ、 特定発信者情報に対応する侵害関連通信は、侵害情報の記録又は入力に係る特定電気 通信ではない。上記の各規定の文理に照らすと、「当該権利の侵害に係る発信者情報」 は、必ずしも侵害情報の記録又は入力に係る特定電気通信に係る発信者情報に限られ ないと解するのが合理的である。
また、法5条の趣旨は、特定電気通信による情報の流通には、これにより他人の権 利の侵害が容易に行われ、その高度の伝ぱ性ゆえに被害が際限なく拡大し、匿名で情 報の発信がされた場合には加害者の特定すらできず被害回復も困難になるという、他 の情報流通手段とは異なる特徴があることを踏まえ、特定電気通信による情報の流通 によって権利の侵害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信\nの秘密に配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信 設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することがで きるものとすることにより、加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図るこ\nとにあると解される(最高裁平成21年(受)第1049号同22年4月8日第一小 法廷判決・民集64巻3号676頁参照)。なお、令和3年法律第27号による改正 により、特定発信者情報の開示請求権が新たに創設されるとともに、その要件は、特 定発信者情報以外の発信者情報の開示請求権と比して加重されている。その趣旨は、 SNS等へのログイン時又はログアウト時の各通信に代表される侵害関連通信は、こ\nれに係る発信者情報の開示を認める必要性が認められる一方で、それ自体には権利侵 害性がなく、発信者のプライバシー及び表現の自由、通信の秘密の保護を図る必要性\nが高いことから、侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内において開示を認 めることにあると解される。 さらに、著作権法23条1項は、著作権者が専有する公衆送信を行う権利のうち、 自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含むと規定する。その趣旨は、著作権者\nにおいて、インターネット等のネットワーク上で行われる自動公衆送信の主体、時間、 内容等を逐一確認し、特定することが困難である実情に鑑み、自動公衆送信の前段階 というべき状態を捉えて送信可能化として定義し、権利行使を可能\とすることにある と解される。
ビットトレントによるファイルの共有は、対象ファイルに対応したビットトレント ネットワークを形成し、これに参加した各ピアが、細分化された対象ファイルのピー スを互いに送受信して徐々に行われるから、その送受信に係る通信の数は膨大に及ぶ ことが推認できる。しかるところ、ピースを現実に送受信した通信に係るものでなく ては「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとすると、ビットトレントネット ワークにおいて著作物を無許諾で共有された著作権者が侵害の実情に即した権利行使 をするためには、ネットワークを逐一確認する多大な負担を強いられることとなり、 前記のとおり法5条が加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることとし\nた趣旨や、著作権法23条1項が自動公衆送信の前段階というべき送信可能化につき\n権利行使を可能とした趣旨にもとることになりかねない。\n
他方、ハンドシェイクの通信は、その通信に含まれる情報自体が権利侵害を構成す\nるものではないが、専ら特定のファイルを共有する目的で形成されたビットトレント ネットワークに自ら参加したユーザーの端末がピアとなって、他のピアとの間で、自 らがピアとして稼働しピースを保有していることを確認、応答するための通信であり、 通常はその後にピースの送受信を伴うものである。そうすると、ハンドシェイクの通 信は、これが行われた日時までに、当該ピアのユーザーが特定のファイルの少なくと も一部を送信可能化したことを示すものであって、送信可能\化に係る情報の送信と同 一人物によりされた蓋然性が認められる上、当該ファイルが他人の著作物の複製物で あり権利者の許諾がないときは、ログイン時の通信に代表される侵害関連通信と比べ\nても、権利侵害行為との結びつきはより強いということができ、発信者のプライバシ ー及び表現の自由、通信の秘密の保護を図る必要性を考慮しても、侵害情報そのもの\nの送信に係る特定電気通信に係る発信者情報と同等の要件によりその開示を認めるこ とが許容されると解される。
以上によると、本件各発信者情報は、法5条1項にいう「当該権利の侵害に係る発 信者情報」に当たると解するのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> 公衆送信
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和5(ネ)10090 職務発明対価相当請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月25日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
特許法2条1項は、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想 の創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち、技 術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考え れば、その技術内容は、当該技術が属する技術分野における当業者が反復実施して 目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして 構成されていなければならないものと解するのが相当であるから(最高裁昭和52\n年10月13日第一小法廷判決(昭和49年(行ツ)第107号)民集31巻6号 805頁)、発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した 者、すなわち、当業者が当該技術的思想を実施することができる程度にまで具体的 ・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。\nそして、ある者が発明者であるというためには、必ずしも発明に至る全ての過程に 一人で関与することを要するものではなく、当該過程に共同で関与することでも足 りるというべきであるが、当該者が共同発明者であるというためには、課題を解決 するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的 に寄与したことを要するものと解される。この場合において、発明の特徴的部分と は、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち従来技術にはみられない部分、\nすなわち、当該発明に特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解するの が相当である。以上を踏まえ、以下、本件について検討する。
(ア) 原告が本件発明2に係る発明者(又は共同発明者)であるというためには、 前記アのとおり、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、本件 各部分の完成に創作的に寄与することを要するところ、当該着想は、具体的な発明 の完成に向けられたものである以上、単に課題を抽象的に想起するだけでは足りず、 課題及びその解決のための手段又は方法を具体的に認識することを要するものと解 するのが相当である。
・・・
(エ) 検討
a 前記(ウ)のうち、市場調査等に基づいて本件OD錠化を提案するなどした原 告の行為は、その内容に照らし、新製剤の企画や方向性に関する提案であり、経営 判断に資するものではあっても、課題及びその解決のための手段又は方法に関する 具体的提案ではないから、構成3)(塩酸アンブロキソールを含む制御放出微粒子等\nの混合物を配合し、かつ、制御放出微粒子等の平均粒子径を300μm以下とする との構成を満たした上で、OD錠が従来のカプセル剤の溶出規格に合致する溶出特\n性(シグモイド型溶出)を示すように、制御放出微粒子等及びこれらを配合したO D錠の各成分や構造を設定したこと)又は構\成4)(同様の構成を満たした上で、錠\n剤を製造する過程の加圧圧縮操作に対し割れにくいプロテクト層を形成したこと) のいずれに対する関与であるとも認めることはできない(なお、認定事実2による と、本件OD錠化は、塩酸アンブロキソールに係る医薬品の開発に関し、平成19\n年当時に知られていた手法の一つであり、特段新規の開発方針ではなかったという べきである。)。
b また、前記(ウ)のうち、本件OD錠化に関して瀬踏み実験を行った原告の行 為についてみるに、当該瀬踏み実験は、「徐放顆粒の粒子径を200μm以下とし て溶出実験を行ったところ、既存のカプセル剤の溶出に近い徐放顆粒が得られた」 というものにすぎず、原告において、制御放出微粒子等及びこれらを配合したOD 錠の各成分や構造を設定するための具体的な方法を認識するなどしたとはいえない\nから、当該瀬踏み実験の実施をもって、原告が構成3)に係る着想及びその具体化の 過程において創作的な寄与をしたものと認めることはできない。その他、当該瀬踏 み実験の内容に照らし、当該瀬踏み実験を行った原告の行為が本件各部分に対する 関与であると認めることはできない。
c さらに、前記(ウ)のうち、「今後、徐放顆粒に他の原料を混合して打錠し、 錠剤化した場合に溶出に変化が生じるかを検討する」などと発言した原告の行為も、 その発言の内容に照らし、原告において、制御放出微粒子等及びこれらを配合した OD錠の各成分や構造を設定するための具体的な方法を認識するなどしたとはいえ\nないから、当該発言をもって、原告が構成3)に係る着想及びその具体化の過程にお いて創作的な寄与をしたものと認めることはできない。その他、当該発言の内容に 照らし、当該発言を行った原告の行為が本件各部分に対する関与であると認めるこ とはできない。
d なお、本件発明2に係る特許出願をすることを考えている旨の発言をした原 告の行為(前記(ウ)f)及び当該特許出願をするよう提案した原告の行為(認定事 実2エ(オ))が本件各部分に対する原告の関与であると認められないことは明らかで あるし、当該特許出願に係る明細書の案を作成した原告の行為(認定事実2エ(オ)) についても、当該行為のみをもって直ちに、本件各部分に対する原告の関与があっ たものと認めることはできない。
e その他、原告が本件チームの行う試験・実験に関与していたことを認めるに 足りる主張立証はなく、原告が本件各部分に対して関与をしたものと認めるに足り る的確な証拠はない。
2024.05.26
令和5(ネ)10078 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これを本件において検討するに、前記(1)イのとおり、本件発明1は、「底部 に取り付けられた安定補助板により支えられてテーブルなどの上に立たせら れる」「折畳式コップ型容器」(段落【0003】)であって「安定補助板が例 えば紙や合成樹脂などから形成され、後から容器本体に取り付けられる構成」\n(段落【0005】)を採用した従来技術を前提とし、「成形が簡便な自立型 の包装容器の提供を目的とする」(段落【0006】)ことを発明が解決しよ うとする課題とし、当該課題を解決する手段として「前記包装容器を容器と して形成した状態において、前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自 立片が載置面に沿って前記奥行の方向に突出し、前記自立片によって前記載 置面に自立させられる」(本件発明1の構成要件B)という構\成を採用するこ とにより、「包装容器を自立させる自立片が底面片に連なっているため、一体 的な成形が簡便である」(段落【0013】)という効果を奏するものである。 そうすると、本件発明1において従来技術に見られない特有の技術的思想 を構成する特徴的部分は、従来技術における安定補助板が、底部に一体的に\n成形された構成である、「前記包装容器を容器として形成した状態において、\n前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片が載置面に沿って前記奥 行の方向に突出し、前記自立片によって前記載置面に自立させられる」こと にあると考えられる。
そして、本件発明1と被控訴人製品とは、包装容器を容器として形成した 状態において、本件発明1の「底面片」が筒状の底部を形成するのに対し、 被控訴人製品は、包装容器を自立させる舌状片が、包装容器の底部を形成す る六角片と同一面に連なっておらず別に構成されている点において相違する\nものと認められるところ、この相違に係る本件発明1の構成、すなわち「底\n部を形成する底面片」が「自立片」と同一面に連ねられていることは、これ までの検討によれば、本件発明1の本質的部分に当たるものということがで きる。
そうすると、上記相違点に係る本件発明1の構成については、本件発明1\nの本質的部分ではないということはできない。そして、前記(1)ウのとおり、 上記の点については、本件各発明について共通するものということができる。 したがって、被控訴人製品は均等侵害の第1要件を充足しないから、その 要件について検討するまでもなく、均等侵害は成立しない。
イ 控訴人は、前記第2の3(4)ウのとおり、本件各発明の本質的部分は、「自立 片」によって載置面に自立させられる構成を採用した点にあり、当該「自立\n片」が内容物に直接接触してこれを支える片という意味における「底面片」 と、同一面に連なることにあるのではないと主張する。 しかし、本件各発明の本質的部分については上記アのとおりと認められる から、本件各発明と被控訴人製品とは、その本質的部分において異なるもの というべきである。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和5(行ケ)10119 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年3月28日 知的財産高等裁判所
ア 本願商標は、前記第2の1(1)のとおりの構成からなる商標である。\n腕時計においては、文字盤に刻まれた目盛りや数字をインデックスなど というところ(乙1)、本願商標は、腕時計からベルト及び針(時針等)を 除いた、ラグ(時計本体とベルトを固定する部分、乙1)、ケース、風防、 インデックスの記載がある文字盤、リューズ及びベゼル等より構成され、\nこれらの形状を文字盤の上部方向から平面視して表した図形である。しか\nも、上記図形は、ベゼル、ラグ、リューズ、文字盤の格子状模様等の全て において陰影が施され、立体的な形状として表現されている。したがって、\n本願商標は、上記時計の構成部分を平面視した図形として表\されてはいる ものの、時計の一部の形状を出所識別標識とすべく登録出願されたものと 認められる。 これを前提に、本願商標の構成を検討すると、以下のとおりである。\n本願商標のラグには、腕時計において金属ベルトを繋ぐ位置に上下二つ の凹部がある。ラグの中央には、外側が八角形で内側が円形のベゼルがあ り、そのベゼルのそれぞれの角に六角形のマイナスネジが配置されており、 全体の色は銀色である。文字盤内のインデックスは、数字ではなく、格子 模様から隆起して見える目盛りからなり、各定時においては1本線であり、 上部中央においては2本線である。文字盤にはリューズ近くの位置に腕時 計において通常日付けが表示されている位置に空白があり、中央上部にブ\nランド名を示す部分があるほかは、文字盤の全面にわたり立体的に見える ように陰影を施した格子模様が示されている。
イ 本願商標の指定商品は「時計」であるから、腕時計のほか、置時計や掛 け時計等も含まれるものであり、その需要者は一般の消費者であると認め られる。本願商標は、腕時計からベルト、針を除いたものであるとの形状 に係る上記アの各事情は、需要者がこれを容易に認識することができると いえる。
ウ 腕時計においては、別掲2の1(1)ないし(4)、2(1)ないし(2 9)及び乙4のとおり、腕時計のバンド及び針(時針等)を除いた部分の 形状として、ラグ、ケース、風防、インデックスのある文字盤、リューズ 及びベゼル等から構成され、八角形のベゼルやビス、文字盤の格子模様な\nどを、それぞれ備えるものが相当数存することが認められる。
エ 上記アないしウの事情を総合すれば、本願商標の形状は、客観的に見て、 商品の機能又は美感に資することを目的として採用されたものであり、か\nつ、本願商標の需要者である一般の消費者において、同種の商品等につい て、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予\測し得 る範囲のものであると認められる。 そうすると、本願商標に係る形状は、商品等の形状を普通に用いられる 方法で使用する標章のみから成る商標として、商標法3条1項3号に該当 するというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和5(行ケ)10117 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年4月9日 知的財産高等裁判所
本願商標の構成中の「東京TMSクリニック」の文字部分は、前記(1)ア、イのと おり、我が国の首都を意味する「東京」、経頭蓋磁気刺激のアルファベット略語であ る「TMS」及び診療所を意味する「クリニック」の語を明朝体風の同書体、同じ 大きさ及び等間隔にて一連に書してなるものである。 ここで、「TMS」(経頭蓋磁気刺激)による治療(経頭蓋磁気刺激療法。以下「T MS治療」という。)は、成人の鬱病への新たな治療方法として、我が国において、 平成29年に適応が承認され、令和元年には保険適用が認められたものである(甲 1〜5、14、15、21)。もっとも、東京都保健医療局が提供する東京都医療機 関案内サービス「ひまわり」の検索結果(令和5年11月7日及び同月10日実施) によると、「精神科」の検索ワードにより該当する医療機関が2470件であったの に対し、「精神科」及び「TMS」の検索ワード(and検索)により該当する医療 機関は4件にとどまった(乙7、8)。また、原告が提出する証拠によっても、令和 5年12月頃時点において、東京都内でTMS治療を提供する医療機関は11か所 程度しか認められない(甲16。原告と被告補助参加人がそれぞれ設置する医療機 関を除く。)。そうすると、TMS治療が平成15年から令和5年にかけて合計23 本の雑誌記事で掲載、紹介されたことや、令和元年7月にNHKクローズアップ現 代で特集、紹介されたこと等、TMS治療について原告が主張する事情を考慮して も、本願商標の指定役務の取引者、需要者のうち、少なくとも精神疾患等を有する 患者やその関係者等は、本件出願日のみならず現在においても、「TMS」の語から、 直ちに「経頭蓋磁気刺激」や、鬱病の治療方法としての「TMS治療」を想起する とは認められない。むしろ、精神疾患等を有する患者やその関係者等が必ずしも医 学・医療用語に精通していないと推認されることや、「TMS」が日本語ではなく欧 文字(アルファベット)の並びであることからすると、これを何らかの造語と認識 する可能性が高いと認められる。\n
さらに、医療役務の提供に当たり、「クリニック」の語は、「中目黒○○クリニッ ク」のように、地名、医師の姓、主たる診療科目等の文字と組み合わせて使用され ることにより、一連の文字列として特定のクリニック(診療所)の名称を表すもの\nとして使用されている実情が認められる(甲12、16〜18、乙7〜10、16、 18、23〜46、丙5〜7)。
以上のとおり、本願商標の構成中の「東京TMSクリニック」の文字部分は、こ\nれを構成する文字が同書体、同じ大きさ及び等間隔で一連に書されていること、本\n願商標の指定役務の取引者、需要者の一部(精神疾患等を有する患者及びその関係 者等)は「TMS」の語から直ちに「経頭蓋磁気刺激」や「TMS治療」を想起す るとは認められず、むしろ何らかの造語と認識する可能性が高いこと、「クリニッ\nク」の語が他の語と組み合わされて特定の診療所の名称を表す取引の実情が認めら\nれること等に照らすと、単に提供される役務の場所や方法、内容等を示すにすぎな いものとはいえず、それ自体が一連となって、役務の提供主体としての診療所の名 称を表すものとして、出所識別標識としての機能\を果たすものといえる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和5(ネ)10084 特許権侵害損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は、第1審原告の請求のうち、1755万3642円及びうち12 69万1831円に対する平成21年9月27日から、うち25万3585円 に対する平成22年9月26日から、うち170万7608円に対する平成2 4年9月30日から、うち290万0618円に対する平成25年9月29日 から、各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理 由があるからこの限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきで あると判断する。その理由は、当審における当事者の主張も踏まえて原判決を 後記1のとおり補正し、後記2のとおり当審における第1審原告の補充主張に 対する判断を付加し、後記3のとおり当審における第1審被告の補充主張に対 する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」第4(原判決45頁2行目 から94頁12行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
・・・
原判決92頁1行目の・・・、同頁5行目の「0.5%」を「0.2%」に、それぞれ改める。
◆判決本文
原審はこちら。
◆令和2(ワ)13317
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和4(ワ)19222 特許権移転登録手続請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年4月17日 東京地方裁判所
(1) 特許法74条1項に基づく移転登録手続請求がされた場合における民法9 4条2項類推適用の可否について
被告は、ライツフォルによる本件特許権の取得について民法94条2項が 類推適用されることにより、原告は本件発明について特許を受ける権利を有 していることを主張することができないと主張する。 これに対し、原告は、特許法74条及び79条の2第1項の趣旨からすれ ば、特許を受ける権利を有する者が同法74条1項に基づく移転登録手続請 求を行った場合において、冒認者からの譲受人等の関係で民法94条2項を 類推適用することはできないと主張する。
この点について、特許法は、同法123条1項6号等の要件に該当すると きには、特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、その特許 権者に対し、当該特許権の移転を請求することができると定めつつも(特許 法74条1項)、その特許権の移転の登録前に、同号等に規定する要件に該 当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をし ているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をして いる発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権 を有するものと定めている(同法79条の2第1項)。
他方、民法94条2項の類推適用は、権利外観法理を根拠として、虚偽の 外観が作出され、その作出について真の権利者の積極的な関与又は承認があ る場合のほか、当該権利者にこれらと同視し得るほど重い帰責性が認められ る場合に、当該権利者は、その外観が虚偽であることについて善意又は善意 無過失である第三者に対し、当該第三者が権利を取得していないと主張する ことができないとする理論構成である。\n
このように、特許法74条1項及び79条の2第1項は、真の権利者の帰 責性にかかわらず、一定の要件を満たす善意の第三者に通常実施権を認める ものであり、他方、民法94条2項の類推適用は、虚偽の外観作出に係る真 の権利者の帰責性と第三者の善意又は善意無過失とを要件として、当該権利 者が権利を失ってもやむを得ないと判断できる場合に、当該権利者から当該 第三者への権利主張を許さないとするものであって、両者の要件及び効果は 異なっている。 そして、特許法79条の2第1項は、善意の第三者が通常実施権を有する と規定するのみであり、民法の第三者保護規定を上書きするような性格であ ることはうかがわれず、また、特許法全体をみても、同法79条の2第1項 が民法の第三者保護規定に対して優先する関係に立つことを示す規定は見当 たらない。
以上によれば、特許法74条1項に基づく移転登録手続請求がされた場合 においても、冒認者からの譲受人等との関係で民法94条2項を類推適用す ることは可能であると解される。\n
(2) 本件における民法94条2項類推適用の要件充足性について
・・・・
以上のように、そもそも、Aが本件譲渡契約1)を締結し、Bが本件特 許に係る特許権者であるとの虚偽の外観を作出するに至ったのは、原告 自身の内部事情や行為にその一因があるといえる上、原告の真の代表者\nとされるDが、遅くとも平成28年11月29日の段階で、上記の虚偽 の外観が存在していることを認識していたにもかかわらず、令和3年ま での約4年間、本件各株主総会決議の不存在確認の訴え等を行っておら ず、さらに、令和3年8月5日に本件各株主総会決議の不存在を認める 判決が確定してからも、Bからライツフォルに本件特許権が譲渡される までの約半年の間、Bに対して何らの措置もとっていないのである。 このような事情からすれば、原告には、虚偽の外観作出について、自 ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置し た場合と同視し得るほど重い帰責性が認められるというべきである。 これに対し、原告は、令和3年8月5日に本件各株主総会決議の不存 在を認める判決が確定してからの行動について、嘱託登記が完了したの が同年10月中旬頃であり、かつ、同判決の確定後、Bが更に本件特許 権を譲渡することは考え難かったことからすれば、F弁護士に対して資 料の引渡しを求めていた原告(D)の対応に何ら問題はないと主張する。
しかしながら、同年8月5日の段階で、本件譲渡契約1)の締結から既 に約6年が経過していたこと、Bは、Dと面識はなく、Aと協力関係に あったと考えられることからすれば、本件各株主総会決議の不存在を認 める判決が確定した段階で、Bに対して特許権移転登録手続請求等の法 的な措置を速やかにとる必要性は高かったものといえる。 また、前記 k及びlのとおり、F弁護士は、本件損害賠償請求訴訟 において、その訴えを却下する判決が確定した後も、Dからの資料の引 渡請求に応じなかったこと、本件各株主総会決議不存在確認の訴えにお いて、原告の代表清算人とされていたF弁護士は、適式な呼出しを受け\nたにもかかわらず、口頭弁論期日に出頭しなかったことが認められ、こ のようなF弁護士の対応や訴訟態度を踏まえると、本件各株主総会決議 の不存在を認める判決の確定後であっても、同弁護士がDの資料の引渡 請求に応じることは望めない状況であったものと認められる。
以上の事情に加え、原告としては、F弁護士に対して資料の引渡しを 求めつつ、それと並行してBに対して特許権移転登録手続請求等を行う ことも可能であったといえることからすると、令和3年8月5日に本件\n各株主総会決議の不存在を認める判決が確定してからの原告(D)の対 応に何ら問題はなかったという原告の主張は採用できないというべきで ある。
さらに、原告は、Bは原告を不正に乗っ取った当事者であり、その代 理人弁理士もBの意向に沿って行動することが想定され、Dに協力する ことはあり得ないから、仮にDがBやその代理人弁理士に働きかけたと しても、何ら虚偽の外観を取り除くことにはつながらず、場合によって は逆効果となる可能性すらあるとも主張する。\n
しかしながら、そもそも、B自身が原告を不正に乗っ取った当事者で あることを認めるに足りる証拠はない上、DがBに対して接触した事実 がない以上、Dからの働きかけに対してBがどのような態度に出るのか については、それを示す兆候もなく、虚偽の外観を取り除くことにつな がらないとか、逆効果となるといった結末に至ると断定するのは無理が ある。さらに、Bやその代理人弁理士がDからの働きかけに応じないと いうことであれば、それは本件特許権の帰属について、BとDとの間で 争いがあることを意味するものにほかならず、そのような場合、Dとし ては、速やかに本件各株主総会決議の不存在の確認の訴え等を行うべき 状況にあったものといえる。
2024.05.26
令和3(ワ)15964 特許権 民事訴訟 令和6年3月22日 東京地方裁判所
3 被告ダンパは、「入力」を受けるものであるか(構成要件G)(争点1−1)\nについて
ア 本件発明1の構成要件G、Hは、「前記剪断部は、入力により荷重を受けた\nときに、変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とする弾塑性履歴型ダン パ」というものであり、本件発明1の対象となる「弾塑性履歴ダンパ」につ いて「剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収 を行うことを特徴とする」ものであるとされている。したがって、本件発明 1のダンパは、上記に記載された特徴を有するダンパであるところ、その「入 力」がどのようなものであるかについて、本件発明1の特許請求の範囲では 何ら定められていない。
イ ここで、前記1 で説示したとおり、本件各発明は、上部構造物、下部構\ 造物に分離できる橋梁等の建築物において、地震のときに、その接続部にお いて橋軸方向に限らず、複数方向の水平力がかかってしまうところ、同接続 部においては、I字形ダンパでは単一方向の入力にしか対応できないという 課題について、同課題を解決するために、複数の剪断面を持ち、かつ、その 向きが異なるダンパを適用するというものであり、本件各発明は、そのよう なダンパが本件各発明の構成をとることによって、剪断部が、入力により荷\n重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うというものである。
本件明細書に記載された本件各発明の課題は、上記のとおりであり、従来 から知られていた剪断パネル型ダンパである単純なI字形ダンパに対して 単一方向からの入力しか想定されない場面においては、本件各発明における 解決すべき課題は存在しない。単一方向からの入力でなく複数方向からの入 力が想定される場合に、本件各発明が解決すべき課題が存在することとなる。 そして、本件明細書には、前記1 に記載のとおりの本件各発明の意義が記 載されているほか、本件明細書に記載された実施例は、全て、複数方向から の入力が問題となり、そのような複数方向からの入力に対し、本件発明1の 構成をとることによって対応することができるものであると認められる。本\n件明細書のその他の部分にも、単一方向からの入力に対応することに関する 記載はない。これらの本件明細書の記載及び構成要件G、Hの記載から、本\n件発明1に係るダンパは、ダンパに対して複数方向からの入力が想定される 構造物等の部位に用いられ、ダンパの剪断部に対して複数方向からの入力が\nあり、これに対して対応することができるダンパであると解するのが相当で ある。
ウ 以上によれば、本件各発明におけるダンパは、その剪断部に複数方向から の入力があり、その剪断部がそれに対する入力により荷重を受けたときに、 変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするもの(構成要件G、H)で\nあると解するのが相当であり、構成要件Gに係る「入力」は、「複数方向か\nらの入力」を意味し、本件各発明のダンパは、ダンパに対して複数方向から の入力があることを前提として、その剪断部が複数方向からの入力により荷 重を受けたときに変形してエネルギー吸収を行うことを特徴とするダンパ であると認められる。
被告ダンパについて検討すると、本件において、原告は、被告ダンパ単体の 譲渡等を問題にするのではなく、被告ダンパが住宅である被告製品に用いられ て、そのような被告製品が販売されていることを特許発明の実施として、被告 製品の販売額を基礎として実施料率相当額の損害を請求する。 被告は、6種の被告ダンパを4種の耐力パネルのいずれかに組み込み、これ を住宅である被告製品の部材として用いている(前提事実 )。被告ダンパは各 平行板部及び各ウェブ部の一端又は両端が耐力パネルに溶接されているので あって、耐力パネルから取り外して使用されることはおよそ想定されておらず、 各耐力パネルも、建物の水平方向に延びる梁や土台等にはさまれるように固定 されて設置されており、住宅販売後に耐力パネルのみを取り外して別の用途に 使用するということはおよそ想定されていない(前提事実 )。すなわち、被告 ダンパは、耐力パネルに物理的にも溶接され、取り外されることはおよそ想定 されず、耐力パネルと不可分一体となっているものといえる。
そうすると、本件において問題となる被告の行為は、被告ダンパが不可分一 体の一部となった被告製品の製造、販売等であって、被告ダンパが組み込まれ た被告製品が本件発明1の技術的範囲に属するか否かが問題になるというべ きである。
なお、被告は、Σ型の形状の鋼材である被告ダンパを作成し、これを他の部 材に組み込むことで耐力パネルを製造していることがうかがえる。もっとも被 告ダンパ単体には「一対のプレート」は接続されておらず、耐力パネルに組み 込まれることによって初めて、「一対のプレート」の具備が問題になるのである から、耐力パネルに組み込まれる前の被告ダンパ自体が本件発明1の技術的範 囲に入ることはないと解される。 被告製品に組み込まれ、被告製品と不可分一体となった被告ダンパに対して 加わる力について検討する。
ア 被告ダンパはいずれも4種類の耐力パネルのいずれかに組み込まれてい るところ、耐力パネルは、その構造上、耐力パネルが接続している梁の方向\nの力(耐力パネルが平行四辺形に変更する方向の力)が加わると、いずれの 耐力パネルについても、被告ダンパに鉛直方向の力が加わり、所定レベル以 上の力が加わると剪断変形によって地震力を吸収する。このとき、被告ダン パに対しては、鉛直方向の力以外の力は加わらない。他方で、耐力パネルに 梁と垂直方向の力が加わっても、被告ダンパには力が加わらず、地震力を吸 収することができない。地震力のうち、これらの力の合力については、いず れも上記二つの力に分解できるから、結局、被告ダンパには鉛直方向の力の みが加わるということになる(乙33)。被告製品においては、建物の特定 の方向に複数の耐力パネルを設置するとともに、これと直交する方向にも複 数の耐力パネルを設置しており、このように複数の耐力パネルを直交方向に 設置することによって、個々のパネルの被告ダンパには鉛直方向の力のみが 加わり、その方向の力のみしか吸収できないとしても、各方向に沿って設置 された耐力パネルが、両方向に対応する地震力の分力を吸収することで建物 全体では任意の方向の地震力を吸収できるように設計されているといえる (乙3)。
イ 被告ダンパに対しては、一応、前記アのとおりの力のみが加わるといえる が、耐力パネルが設置されている上下の梁がねじれる(回転する)力が加わ った場合には、耐力パネルの構造上、被告ダンパに対し鉛直方向とは異なる\n方向の力が加わる可能性がないわけではない。そこで、被告製品において鉛\n直方向からどの程度ずれる力が加わり得るのかについて検討する。 被告は、被告ダンパを搭載した実物大の住宅サンプルに対して、過去最大 級の地震の一つである兵庫県南部地震の際にJR鷹取駅で観測された地震 波(以下「鷹取地震波」という。)を適用して地震時挙動を測定する実験を行 ったところ、その結果によれば、1階に対する2階床の最大回転角は、0. 14°(乙40)、これにより耐力壁に設置されたダンパに対して加わる力 の鉛直方向からのずれは、0.022°であったこと(乙41)が認められ る。
以上を前提に、被告ダンパの剪断部に本件発明1における複数方向から の入力があり、その剪断部が複数方向からの入力により荷重を受けたとき に変形してエネルギー吸収を行うものといえるか否かについて検討する。
・・・
前記イで認定したとおり、被告製品は、少なくとも鷹取地震波を前提 にすると、これによって剪断パネルに一定のねじれが生じ、被告ダンパ に鉛直方向からずれた方向からの力も加わることが認められる。しかし、 そのずれは0.022°(なお、cos0.02°=約0.9999999 26)と極めて小さいものである。この程度のずれは、その小ささから もこれによって被告ダンパに生じる効果に観測できるほどの差が生じ るとは認めるに足りないし、このずれは、被告製品が用いられる分野の 施工の限界を超える程度であるといえる。また、そのずれは、被告ダン パのウェブ部を形成する鋼板の厚みの中に収まるような小さなもので あることがうかがえる。
これらによれば、上記実験結果によれば、本件においてねじれによっ て加わり得る入力方向の違いは、従来のI字型ダンパにおいて同一方向 からの入力として想定されていたといえる範囲のものであり、前記(ア)で 説示した本件発明1が異なる入力方向として想定しているものではな いというべきである。
また、被告製品が鷹取地震波を超える地震波に遭遇することは想定さ れ得る。しかし、上記実験で用いられたのが過去最大級の地震の一つで ある鷹取地震波であり、その場合であっても上記のとおり入力方向の違 いが極めて小さいことからすると、現実に想定し得る鷹取地震波を超え る地震においても、被告ダンパに対して本件発明1が想定する程度の鉛 直方向からのずれが生じる剪断パネルのねじれが生じるとも認められ ない。
以上によれば、被告製品で用いられている被告ダンパの剪断パネルに 対してねじれの影響によって生じる入力方向の違いは、その小ささから、 本件発明1が想定する程度に達するような、異なる方向からの入力であ ると評価できるものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和5(行ケ)10141 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年4月10日 知的財産高等裁判所
(3) 本願商標の構成中の「知財実務」の文字は「知的財産に関する実務」を意\n味する一般的な用語であり、また、「オンライン」の文字は「コンピュータ ーの入出力装置などが、中央処理装置と直結している状態。また、通信回線 などによって、人手を介さず情報を転送できる状態。」を意味する用語であ り(大辞泉第2版)、英語の「online」とともに、「インターネットに接続 した状態」、「インターネットを利用した」等を意味する用語として一般的 に用いられていると認められる(乙1〜4、弁論の全趣旨)。 さらに、「〇〇オンライン」と「オンライン」の文字を末尾に配する標章 (「〇〇オンライン」標章)の一般的な実情をみると、当事者が主張におい て挙げるものに限っても、別紙2「『オンライン』を末尾に付す標章の一覧 表」に記載の用例がある。これらの用例を大別すると、1)「オンライン」の 前の文字が、提供される商品又は役務の一般的名称と理解されるもの(事例 1〜5、16,18,20〜25、27〜29)と、2)「オンライン」の前 の文字が、それ自体としても識別力を有する標章として機能すると同時に、\n「オンライン」の文字と組み合わされて全体として一つの標章ともなってい るもの(事例6〜11、14,15、26、30、34、35)に分けられ る(分類の部妙なものは例示から除いた。)。 このような標章に接した需要者の一般的な認識としては、上記1)の事例で あれば、「オンライン」の前の一般的な名称に係る商品又は役務をオンライ ンで提供するものと認識し、上記2)の事例であれば、「オンライン」の文字 の前に示される識別標識に係る商品又は役務をオンラインで提供するものと 認識するものと認めるのが相当であり、いずれにおいても、「〇〇オンライ ン」標章中の「オンライン」の文字が果たす意味合いは本質的に同じといっ てよい。
そうすると、「オンライン」の前に「知的財産に関する実務」を意味する 一般的な用語である「知財実務」を結合させた本願商標は、上記の一般的な 取引の実情からみて、「知的財産に関する実務の情報をオンラインで提供す るもの」、すなわち商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されると\nともに、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであ\nると認められる。そして、本願指定商品役務の取引の分野において、これと 異なる取引の実情があることを窺わせる証拠はない。
(4) 上記認定と異なる原告らの主張は、以下の理由により、いずれも採用でき ない。
ア 原告らは、本願商標が第三者に使用されていない事実を取引の実情とし て考慮すべきであると主張する。 しかし、上記のとおり、本願商標は「知財実務」と「オンライン」の文 字の意義及び「オンライン」の文字を末尾に付する標章の一般的な実情か らみて、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されると認められ、\nこの認定は、第三者が使用する事実があれば更に裏付けられるということ はできても、第三者が使用する事実がないからといって左右されるもので はない。
イ 原告らは、本願商標は商品又は役務の特徴等を間接的に表示するもので\nある、あるいは一定の意味を有しない造語であると主張する。 しかし、本願商標は「知的財産に関する実務の情報をオンラインで提供 するもの」として需要者に認識され、その内容に一定の幅があるとしても、 いずれにせよ商品の品質又は役務の質を表示したものと理解されることに\n変わりはなく、一定の意味を有しない造語であるとはいえない。
ウ 原告らは、商品、役務名又はブランド名の語尾に「オンライン」の文字 を付した標章は、ウェブサイトやYouTubeのチャンネルにおいて出 所識別標識として認識される態様で使用されていると主張する。 しかし、別紙2の各事例は、「オンライン」の前の文字がそれ自体とし て出所識別標識として機能しているものを除き、「オンライン」の文字を\n付すことによって出所識別標識として認識される態様で使用されていると は認められない。事例16の「神社仏閣オンライン」に係る甲3のSNS の投稿は、この認定を左右するものではない。
エ 原告らは、本願指定商品役務の性質及び取引の実情は定期刊行物と共通 するから、本願商標については定期刊行物の題号と同様に自他商品役務識 別力を認めるべきである旨主張する。 しかし、新聞、雑誌等の定期刊行物の商品については、個人の著作物で ある書籍と異なり、主として特定の新聞社・出版社が継続的に編集・発行 するものであって、その内容は新聞社・出版社ごとに異なり(題号と関わ りの薄い記事が掲載されることも含まれる。)、その題号が品質・内容を 示すものであっても出所識別標識としての機能を果たし得るという、他の\n商品と異なる取引の実情が認められるものである(原告らの引用する大審 院昭和7年6月16日判決も、これと同旨と解される。)。 そして、このような定期刊行物を電子化した電子定期刊行物については ともかく、本願指定商品役務について、定期刊行物と同様の取引の実情が あると認めるに足りる証拠はない。
例えば、オンラインによる映像等の提供を内容とする指定役務10)、11)に ついていえば、YouTubeなどに代表されるインターネット上の動画\n投稿・共有サービスは原則として誰もが簡便に動画を投稿できるものであ るから、「知的財産に関する」、「各回異なる内容のものが定期的又は逐 次的に提供される」といった限定が付されたからといって、新聞、雑誌等 の定期刊行物と同様の取引の実情があると認めることはできない。 原告らは、商標審査基準改訂における放送番組の番組名に係る議論に言 及して、「番組」に関する商品・役務のうち「各回異なる内容のものが定 期的又は逐次的に提供されること」が明確になっているものは定期刊行物 と同様であると主張するが、そもそもオンラインによる映像等の提供につ いては、映像等の内容、性質に多様なものが含まれることからすれば、 「放送番組」の一部がオンラインでも提供されている現状を考慮しても、 放送番組そのものと同様の取引の実情があるとは認められない。
また、知的財産に関する定期的に発行される電子出版物(指定商品5)) についても、このうち個人の著作する書籍に相当するものについては、直 ちに新聞、雑誌等の定期刊行物と同視することはできない。 なお、近年の電子技術や通信技術の発達に伴い、情報コンテンツ及びそ の伝達手段が拡大・多様化しており、新聞社・出版社による「定期刊行 物」、テレビ局・ラジオ局による「放送番組」といった従来からの商品役 務とそれ以外のオンラインにより伝達される情報コンテンツとの境界も変 容しつつあることは事実であるが、そうであるからといって、従来からの 取引において長年にわたり形成された「定期刊行物」に係る取引の実情が、 オンラインによる映像等の提供について直ちに認められることにはならな い。
(5) 以上のとおり、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした本件審決 の判断に誤りはなく、原告らの取消事由1の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2024.05.26
令和4(ワ)70009 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年5月15日 東京地方裁判所
(2) 原告が主張する原告神棚板の特徴1)から7)のうち、特徴7)は、商品の機能を\nいうものであり、また、特徴6)も金具の形状を問題とするものではなく商品の 機能をいうものといえる。このような機能\自体が商品の形態による商品等表示\nとなることはないと解される。
特徴1)から5)のうち、特徴1)から3)は壁面に取り付け可能な棚としては基本\n的な形態のものであることがうかがわれ、また、特徴4)、5)も、商品の一部分 の特徴で、かつ、それぞれの形態自体は独特のものとはいえないことがうかが われる。もっとも、本件証拠上、原告神棚板の販売が開始された平成16年よ り前の同種の商品の形態についての証拠はない。しかし、仮に、特徴1)から5) の組合せが他の同種の商品と異なる顕著な特徴であったと認められるとしても、 後記(3)のとおり、原告神棚板の特徴1)から5)の組合せが原告の出所を示すもの として周知になったことはなく、遅くとも令和2年10月までに原告神棚板の 形態が原告の出所を示すものとして周知となっていたとの原告の主張には理由 がない。
(3) 原告が主張する原告神棚板の特徴が原告の出所を示すものとして周知になっ ていたか否かについて検討する。
平成27年4月には、NHKの番組で原告神棚板が取り上げられた。しかし、 他に、全国的なテレビ番組で原告神棚板が取り上げられたことがあったことを 認めるに足りず、この一回の放送によって、原告神棚板の特徴1)から5)の組合 せが原告の出所を示すものとして需要者に周知になったとはいえない。また、 原告の神棚が写っている写真が、日刊紙、雑誌等に掲載されたことが認められ るが、それらは合計数回であり、これらによって、原告神棚板の特徴1)から5) の組合せが原告の出所を示すものとして需要者に周知になったとはいえない。 さらに、原告神棚板は、ホームセンター、神具店、仏具店、神社、原告の直 営店及びオンラインショップで販売されていた。主な販売先であるホームセン ターでは、原告の商品が多く取り扱われ(原告代表者は、ホームセンターの実\n店舗での原告の神棚、神具の展示、販売のシェアは70%を下回ることはなく、 80%を超えていると推計している。甲122)、原告の商品が、まとまって 展示、販売されている店舗もあった。しかし、原告は、神棚や関係する商品と して多種類の商品を販売していて、ホームセンターでもそのような多種類の商 品が販売されていた。原告神棚板は、原告が販売する複数の種類の神棚のうち の一つであり、その展示、販売に際しても、多種類の商品の中の一つとして展 示、販売されているのであって、原告神棚板の上記特徴が他の同種の商品とは 異なることを述べる宣伝文言によって強調されて展示、販売されていることも 認めるには足りない。これらからすると、原告神棚板の展示、販売によって、 原告神棚板の特徴1)から5)の組合せが原告の出所を示すものとして需要者に周 知になったとはいえない。
また、前記1(3)によれば、原告が主張する特徴1)から5)のうちの複数の特徴 を備える神棚板も販売されていて、原告が主張する特徴のいくつかやその組合 せについては原告が長期間独占的に使用していたと認めることもできない。 以上によれば、原告神棚板について、各報道や公刊物の記載、展示、販売に よって原告神棚板の特徴1)から5)の組合せが原告の出所を示すものとして需要 者に周知になったとは認められず、また、報道等の回数の少なさや、展示、販 売の際も多種類の商品の一つとして展示、販売されているにすぎないことから も、関係する事情を総合して考慮しても、原告神棚板の特徴1)から5)の組合せ が、原告の出所を示す表示として周知になったことはないと認められる。\n
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2024.05.22
令和5(行ケ)10109 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年4月24日 知的財産高等裁判所
本件において、拒絶の原査定及びこれに先立つ拒絶理由通知の根拠条文と しては3条1項3号が掲げられていたのに対し、本件審決は同項6号を拒絶 の理由としているが、本件審決に先立って新たな拒絶理由通知は行われてい ない(以上は争いがない。)。そこで、本件審決の理由が55条の2第1項 にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」に当たるか否かを検討する必要が ある。
(2) 商標法は、商標登録出願に対して拒絶査定をすべき場合を15条各号に おいて限定的に列挙し、法定の期間内に拒絶の理由を発見しないときは商標 登録の査定をしなければならない旨を定める(16条)。このような商標法 の構造に照らして、拒絶理由通知にいう「拒絶の理由」とは、商標法が定め\nる具体的な登録拒絶事由(根拠条文)を示して、これに該当することの説明 をするものと解すべきであり、根拠条文が異なれば、原則として、それのみ をもって「異なる拒絶の理由」に当たるというべきである。 この点、被告は、3条1項は出所表示機能\を欠く商標を列挙するところ、 例示的列挙である1号〜5号による拒絶と総括規定である6号による拒絶と では、判断内容が実質的に相違するものでないから、本件審決の理由と査定 の理由は「異なる拒絶の理由」に当たらない旨主張している。しかし、3条 1項各号の実定法上の意義としては、それぞれが独立した別個の登録拒絶事 由を定めるものであり、同項6号の「前各号に掲げるもののほか」の文言か らも明らかなように、同項6号と同項1号〜5号との間に概念上の上下関係、 包摂関係があるわけではない(参考までに、本来的な意味での例示列挙の立 法例として、著作権法30条の4、同法47条の4第1項があるが、3条1 項がこれらと異なることは明らかである。)。 被告の上記主張は、3条1項の全体としての趣旨、各号の担う実質的な 役割・機能を説明する文脈であれば、誤りとはいえないが、行政庁による公\n権力の行使(本件では商標登録出願の拒絶)は、具体的な根拠条文に基づい て行われるのが法治国家の基本であり、「拒絶の理由」の異同についても、 拒絶の根拠条文が第一義的な基準になると考えるべきである。根拠条文の異 なる拒絶について、その背景にある立法趣旨において共通性があるからと いって、「異なる拒絶の理由」に当たらないなどということはできない。
(3) 以上の原則を踏まえつつも、個別具体的な事情により、査定と審決とで 拒絶の根拠条文は異なっても、両者の判断内容が実質的に同一(大が小を兼 ねる関係を含む。)であり、改めて弁明の機会を付与する必要がないといえ る特段の事情が認められる場合には、「異なる拒絶の理由」に当たらないと 解釈する余地もあり得るので、以下、この点について検討する。
本件において、原査定を不服として本件審判を請求した原告の立場で考 えると、原査定で示された理由(上記1(3))を争うべく、「本願商標の 『奇跡の』は『栄養素が豊富な』という意味を表すものではなく、したがっ\nて品質等表示(3条1項3号)に該当するものではない」という反論に注力\nするのが自然な対応と解される。現に原告は審判請求書でその趣旨を含む主 張をしている一方、3条1項6号が適用される可能性まで視野に入れた主張\nはしていない。これに対し、本件審決の判断(上記第2の2)は、本願商標 の「奇跡の」について、「常識では考えられないような」程の意味合いで理 解されるとして、原査定と異なる前提に立って、同項6号に当たるとの判断 をしている。これらは、大きな意味において、出所表示機能\を欠く商標かど うかという議論として括れないわけではないが、議論の出発点となるべき 「奇跡の」の意味するところの認定に変更が生じているため、出願人・審判 請求人に求められる防御の対象及び範囲も大きく異なったものとなっている。 そうすると、原査定と本件審決の理由を対比する限りにおいて、その判断内 容が実質的に同一であるなどということはできず、改めて弁明の機会を付与 する必要があったと考えざるを得ない。本件において、上記特段の事情は認 められないというべきである。 なお、本件において、本件審尋書面の送付により反論の機会が事実上付 与されているという事情は認められるものの、原査定の理由と本件審決の理 由が客観的に同一といえるかという議論とは次元の異なる問題であるから、 手続上の違法が審決に結論に影響を及ぼすか否かの場面(後記3参照)で考 慮されることは格別、「拒絶の理由」の異同に関する上記判断を左右するも のではない。
(4) 被告は、本件審判の手続を正当化する理由として、3条1項の適用上、 識別力を有しない商標であること自体は明らかであっても、同項のいずれの 類型に分類することが適切か明らかでなく、複数の号に重複して分類し得る 商標もあり得る点を挙げる。
しかし、そのような問題があるとすれば、最初の拒絶理由通知・拒絶査 定において、複数の根拠条文を掲げておけば(本件に即していえば「3条1 項3号又は6号」など)足りることであり、「異なる拒絶の理由」に当たる 場合を限定的に解釈すべき根拠となるものではない。
なお、この点につき、被告はさらに、多数の拒絶理由を列挙することに なり、拒絶理由相互の関係が不明確で複雑なものとなり、出願人にとっても 防御の観点から不利益となるとも主張する。しかし、本件で問題となってい る3条1項各号の選択に関していえば、合理的に適用が考えられる複数の号 の組合せは限定的と解されるし、出願人の防御という観点からいっても、被 告が主張するように3条1項各号の拒絶理由はどれも実質的に異ならないと いう前提での運用よりも、防御の範囲はむしろ明確になるといえる。 以上のとおり、被告の上記各主張は失当である。
(5) 次に、被告は、拒絶査定に対する審判の段階においては、実際上、16 条(商標法施行令3条1項)の期間を経過しているのが大半であるから、新 たな拒絶理由通知が必要になるとすると、実体上は登録要件に適合しない商 標の登録も自動的に認めざるを得なくなり、不当である旨主張する。
仮に、被告が述べる上記のような実情が避け難いものだとすれば、拒絶理 由通知の手続(15条の2)が審判手続について準用(55条の2第1項) される際に、16条所定の期間制限がどのように作用するのかを再検討する ことを含めた吟味が必要になると解されるが、それ以前の問題として、上記 (4)で述べたように、最初の拒絶理由通知・拒絶査定において複数の根拠条 文を掲げておくという実務上の運用による対応をまずは行うべきものであり、 かつ、それで基本的に対処可能と考えられる。いずれにせよ、被告の上記主\n張は、「今更新たな拒絶理由通知ができないから異なる拒絶の理由ではない と強弁する」というに等しいものであり、採用することはできない。
(6) 以上に述べたところをまとめると、原査定の理由と本件審決の理由は、 そもそも拒絶の根拠条文が異なる上、両者の判断内容が実質的に同一で改め て弁明の機会を付与する必要がないといえる特段の事情も認められないから、 両者は「異なる拒絶の理由」に当たると認めるのが相当である。 そうすると、本来、55条の2第1項、15条の2所定の新たな拒絶理由 通知が必要であったところ、この手続を履践することなく本件審決に進んだ 本件審判の手続には瑕疵があるというべきである(仮に16条の期間制限の ために新たな拒絶理由通知をすることが許されなかったという事情があると しても、瑕疵があることに変わりはない。)。
3 審決の結論に影響すべき瑕疵といえるか
審判手続に瑕疵(違法)があっても、それが審決の結論に影響を及ぼすよう なものと認められない場合には、審決取消事由とはなり得ないと解される(手 続上の違法に限らず、実体上の違法がある場合であっても、この理に変わりは ない。)。
そこでこの点を検討するに、本件審判手続においては、本件審尋書面が原告 に送付され、本件審決の理由が事前に明らかにされ、曲がりなりにも弁明の機 会が与えられていたということができる。もちろん、本件審尋書面の送付を もって法定の手続である拒絶理由通知と同視することはできず、適式な弁明の 機会が付与されていたということはできないが、審決の理由について何らの予\n告のないまま、不意打ち的に判断が示された場合とは状況が大きく異なる。 加えて、本件審尋書面及び本件審決で示された拒絶の理由は、原告が本件意 見書中で主張していた内容(本願商標は「常識では考えられない神秘的な果 物:ラカンカ」という意味を普通に用いられる方法で表示している標章である\nとの趣旨)を逆手に取って、本願商標の意味するところについては原告の主張 を全面的に採用した上で、そのような意味に理解される本願商標は3条1項6 号に該当することになると切り返したものである。そして、当裁判所は、後記 4で判断するとおり、取引者、需要者が理解・認識するであろう本願商標の意 味内容について原告が本件意見書で主張したところを前提とすれば、やはり3 条1項6号に該当することになると判断する。そうすると、仮に、原告に適式 な弁明の機会が付与されていたとしても、本件意見書で自ら主張していた内容 を覆すのでない限り有効な反論はなし得ないし、本件意見書と矛盾する内容と なることを承知の上であえて反論をしたとしても、禁反言の原則に反する主張 又は合理的理由のない場当たり的な対応と受け止められる状況が容易に予想さ\nれたところである。
本件における以上の事情を総合すれば、本件審判の手続に上記2で述べた瑕 疵はあるものの、その手続上の違法は、審決の結論に影響を及ぼすものではな いと解するのが相当である。よって、原告主張の取消事由は採用できない。
4 本願商標の3条1項6号該当性について
念のため、本願商標の3条1項6号該当性についても検討しておく。 本願商標は、「奇跡のラカンカ」の文字を横書きしてなるところ、その構成\n中の「奇跡」や「ラカンカ」の文字の意味を一般に理解し得る意味(乙3〜5) として理解すれば、「ラカンカ」は中国に産するウリ科の植物「羅漢果」の片 仮名表記であり、本願商標は全体として「常識では考えられない神秘的な羅漢\n果」程の意味合いを認識させるものである。以上は、原告自身が本件意見書の 中で主張しているとおりである。
そして、証拠(乙6〜35)によれば、「奇跡」の文字は、「奇跡の果物」、 「奇跡の野菜」、「奇跡のブドウ」、「奇跡のイチゴ」などといったように、「常 識では考えられないような」といった程度の意味合いで広く一般に使用されて おり、飲食料品を取り扱う業界において商品ないしその原材料の宣伝広告に使 用されていることが認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、 需要者は、商品の宣伝広告に一般に使用されるような「常識では考えられない ような羅漢果」程の意味合いを表示したものと認識するにすぎず、何人かの業\n務に係る商品であることを表示したものと認識することはないといえる。した\nがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識する ことができない商標であるから、3条1項6号に該当する。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2024.05.16
令和5(行ケ)10091 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年4月22日 知的財産高等裁判所
(2) 相違点の容易想到性についての判断の誤りについて
ア 原告は、本件決定が相違点1−1から同1−3までを関連付けずに判断 している点が誤りであると主張するところ、当裁判所は、相違点1−1は ともかく、少なくとも相違点1−2と相違点1−3は一体として検討する 必要があると判断する。その理由は、以下のとおりである。 本件発明の内容は前記第2の2のとおりであって、ポリプロピレンフィ ルムと蒸着膜との間に、密着性に優れた極性基を有する樹脂材料を含む表\n面コート層を備えることにより、層間の剥離を防止し、また、シランカッ プリング剤とともに用いられる場合も含め金属アルコキシドと水溶性高 分子との樹脂組成物からなるバリアコート層を蒸着膜上に設けることで、 蒸着膜のクラック発生をも防止し、さらには、ボイル又はレトルト処理が 行われる場合であってもガスバリア性の低下の抑制が図られるように、バ リアコート層表面の珪素原子と炭素原子との割合を特定の範囲にしたも\nのであって、高いガスバリア性を有するボイル又はレトルト用バリア性積 層体を提供するという技術的意義を有するといえる。そして、本件明細書 によれば、珪素原子と炭素原子の比(Si/C)の上限は、バリア性積層 体を屈曲させてもガスバリア性の低下を抑制できるという観点から定め られ、下限は、バリア性積層体を加熱してもガスバリア性の低下を抑制で きるという観点から定められているのであるから(【0076】、表5〜\n表7)、ボイル又はレトルト用であるか否かに係る相違点1−3と、珪素\n原子と炭素原子の比の数値範囲に係る相違点1−2は、一体として検討さ れるべきものである。
イ 以上を前提に、相違点1−2と相違点1−3に係る容易想到性につき一 括して判断するに、まず、本件決定が副引用例とする甲4には、別紙6の 記載があり、ここから本件決定の認定に係る甲4記載事項(別紙4の1(2)) を認定できることについては争いがない。
甲4は、電気製品等の機器の消費エネルギーを削減するための真空断熱 材用外包材等に関するもので、外包材により形成された袋体内に芯材を配 置し、上記芯材が配置された袋体の内部を減圧して真空状態とし、上記袋 体の端部を熱溶着して密封し、上記袋体内部を真空状態とすることにより、 気体の対流が遮断されるため、真空断熱材は高い断熱性能を発揮すること\nができるというものである(【0001】〜【0003】)。 甲4記載事項は、第1フィルム(金属酸化物リン酸層付きフィルム。第 1樹脂基材と金属酸化物リン酸層から成る。)、オーバーコート層付きフ ィルム(樹脂基板、無機層、オーバーコート層から成る。)、熱溶着可能\nなフィルムから構成される真空断熱材用外包材のうち、オーバーコート層\n付きフィルムの中のオーバーコート層及び無機層をもとに抽出されたも のである。
ウ 本件決定は、甲3発明に、甲4記載事項のオーバーコート層における炭 素原子に対する珪素原子の比率を適用するものである。 しかし、甲4記載事項は、前提とする積層構造が、甲3発明と異なる上、\n以下のとおり、甲4は、甲3発明とは技術分野が共通するものとはいい難 く、さらに、相違点1−3に係る構成(ボイル又はレトルト用)を開示又\nは示唆するものでもない。すなわち、甲4は、高温高湿な環境においても 長期間断熱性能を維持することができる真空断熱材用外包材等の提供を\n目的とするものであるが(【0008】)、高温多湿な「環境」を想定す るにとどまり、物を入れて積極的に加熱殺菌処理をする行為であるレトル トやボイル(一例として、優先日前の公知文献である特開2007−13 7438号公報〔乙4〕では、レトルト処理について110゜C)〜130゜C) 位、圧力、1〜3Kgf/cm 2 ・G位で約20〜60分間程度の加熱加 圧殺菌処理、ボイルについて90゜C)位で30分間位の加熱殺菌処理〔【0 002】〕等が挙げられている。)を想定しているとはおよそ考えられず、 実際、甲4には、レトルトやボイルを前提とする記載はない。
その上、甲3の【0044】には、「炭素の割合が50%より多い場合、 バリア性が温度、湿度の影響を受け易く、15%より少ない場合、バリア 性が悪くなり、膜質が脆くなる。」として、炭素が少なすぎると膜質が脆 くなることが示唆されているのに対し、甲4の【0111】には、「オー バーコート層を構成する原子における、炭素原子に対する金属原子の比率\n(金属原子数/炭素原子数)は、0.1以上、2以下の範囲内であり、中 でも0.5以上、1.9以下の範囲内、特には0.8以上、1.6以下の 範囲内であることが好ましい。」という炭素原子に対する金属原子の比率 (金属原子数/炭素原子数)を示す記載に引き続いて、「比率が上記範囲 に満たないと、オーバーコート層の脆性が大きくなり、得られるオーバー コート層の耐水性および耐候性等が低下する場合がある。一方、比率が上 記範囲を超えると、得られるオーバーコート層のガスバリア性が低下する 場合がある。」として、金属原子に対して炭素原子の数が過剰に多くなる とオーバーコート層の脆性が大きくなって、ガスバリア性の低下につなが る旨の記載があるところ、これは、上記甲3の【0044】の記載と正反 対の内容である。
そうすると、当業者において、甲3発明の食品包装材料についてボイル 又はレトルト用途とすることを想起したとしても、甲4におけるオーバー コート層を構成する原子における金属原子の比率は加熱によってもガス\nバリア性が維持されるかどうかとは関わりのないものであること、甲4に は、炭素原子と金属原子の比率と、膜質の脆性について、甲3と正反対の 記載があることに鑑みても、甲3発明とは技術分野も積層構造も異なる真\n空断熱材用外包材に関する甲4の積層体の中から、オーバーコート層付き フィルムの中のオーバーコート層及び無機層に関する記載に着目した上、 オーバーコート層における炭素原子に対する金属原子の比率(金属原子数 /炭素原子数)を参酌して、甲3発明に適用する動機付けを導くには無理 があるというほかなく、本件決定の判断には誤りがある。
エ 被告は、Si/Cの数値範囲に特段の技術的意義はなく、層構成に係る\n共通の技術について「Si/C」を用いて数値範囲を検討することが甲4 にあるとおり公知であることを併せると、甲3発明において甲4記載事項 を参考にして、相違点1−2に係る本件発明の構成とすることは、当業者\nが容易に想到し得た旨主張する。 被告が、Si/Cの数値範囲に特段の技術的意義はないと主張する根拠 は、1)本件発明1の発明特定事項が「バリアコート層が、金属アルコキシ ドと水溶性高分子との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜で\nあるか、または、金属アルコキシドと、水溶性高分子と、シランカップリ ング剤との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜」と択一的なも\nのになっており、シランカップリング剤には珪素が含まれるにもかかわら ず、本件明細書上効果が確認されているのはシランカップリング剤を含む バリアコート層だけであるという点、2)本件発明1の数値範囲は甲3から 簡単に算出でき、甲4にも同数値範囲内のものが例示されているという点 にある。
しかし、上記1)についていえば、シランカップリング剤が珪素を含むと いうような一般論だけで、シランカップを含むものであるバリアコート層 の効果に係る【表4】〜【表\7】の結果、及びSi/Cの数値範囲の効果 に係る【表5】〜【表\7】が、シランカップ剤を含まないバリアコート層 について技術的意義がないとは直ちにいえないし、そもそも、技術的意義 が裏付けられているかどうかと、構成が容易想到といえるかどうかの問題\nは直結するものではない。 また、上記2)についていえば、甲3発明の「X線光電子分光分析法」の分 析における「炭素と酸素と珪素が、それぞれ15〜50%、30〜65%、 5〜30%の割合で存在すること」から、珪素原子と炭素原子の比(Si/ C)は、0.1以上、2以下と算出することができ、この数値範囲は、本件 発明1の数値範囲である「0.90以上1.60以下」を包含するからとい って、炭素と酸素と珪素の数値範囲で一定の技術的意義を示している甲3 の記載から、炭素と珪素だけを抽出すべき合理的な理由、技術的な必然性 は認められない。
甲4の表1には、30質量部(Si/C比率1.58)、38.5質量部\n(同比率1.25)及び50質量部(同比率1.03)という、本件発明1 の数値範囲内のものが開示されているが、同表では膜特性は示されておら\nず、このSi/C比率で、本件発明1の数値範囲外の他の質量部より優れ ていることが示されているわけでもないから、当業者が当該数値に着目す るともいえない。 そして、甲3とは「層構成に係る発明である」という程度の共通性しかな\nい甲4に「Si/C」を用いて数値範囲を検討することが記載されていた からといって、当業者において甲4記載事項を参考にして相違点1−2、 相違点1−3に係る構成とすることが容易に想到できるとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2024.05.16
令和5(行ウ)5001 出願却下処分取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年5月16日 東京地方裁判所
1 我が国における「発明者」という概念
知的財産基本法2条1項は、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、 意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明 がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、\n商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘\n密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうと規定している。 上記の規定によれば、同法に規定する「発明」とは、人間の創造的活動により 生み出されるものの例示として定義されていることからすると、知的財産基本法 は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、 自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。 そして、特許法についてみると、発明者の表示については、同法36条1項2\n号が、発明者の氏名を記載しなければならない旨規定するのに対し、特許出願人 の表示については、同項1号が、特許出願人の氏名又は名称を記載しなければな\nらない旨規定していることからすれば、上記にいう氏名とは、文字どおり、自然 人の氏名をいうものであり、上記の規定は、発明者が自然人であることを当然の 前提とするものといえる。また、特許法66条は、特許権は設定の登録により発 生する旨規定しているところ、同法29条1項は、発明をした者は、その発明に ついて特許を受けることができる旨規定している。そうすると、AIは、法人格 を有するものではないから、上記にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利 の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当で ある。
他方、特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合には、AI 発明をしたAI又はAI発明のソースコードその他のソ\フトウェアに関する権 利者、AI発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管 理する者その他のAI発明に関係している者のうち、いずれの者を発明者とすべ きかという点につき、およそ法令上の根拠を欠くことになる。のみならず、特許 法29条2項は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識 を有する者(以下「当業者」という。)が前項各号に掲げる発明に基いて容易に 発明をすることができたときは、進歩性を欠くものとして、その発明については 特許を受けることができない旨規定する。しかしながら、自然人の創作能力と、\n今後更に進化するAIの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断するのは困\n難であるから、自然人が想定されていた「当業者」という概念を、直ちにAIに も適用するのは相当ではない。さらに、AIの自律的創作能力と、自然人の創作\n能力との相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間は、AIがもたらす社\n会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法による存続期\n間とは異なるものと制度設計する余地も、十分にあり得るものといえる。\nこのような観点からすれば、AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会 経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねるこ\nととし、その他のAI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組み の在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方と みるのが相当である。グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制 度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちに AIが含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論 の全趣旨によれば、明らかである。
これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明者」は、自然人に限 られるものと解するのが相当である。
したがって、特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、原告が発明 者として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載して、発明者の\n氏名を記載しなかったことにつき、原処分庁が同条の5第2項3号に基づき補正 を命じた上、同条の5第3項の規定に基づき本件処分をしたことは、適法である と認めるのが相当である。
2 原告の主張に対する判断
(1) 原告は、我が国の特許法には諸外国のように特許を受ける権利の主体を発明 者に限定するような規定がなく、特許法の制定時にAI発明が想定されていな かったことは、AI発明の保護を否定する理由にはならない旨主張する。しか しながら、自然人を想定して制度設計された現行特許法の枠組みの中で、AI 発明に係る発明者等を定めるのは困難であることは、前記において説示したと おりである。この点につき、原告は、民法205条が準用する同法189条の 規定により定められる旨主張するものの、同条によっても、果実を取得できる 者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに 特定することはできないというべきである。その他に、原告の主張は、AI発 明をめぐる実務上の懸念など十分傾聴に値するところがあるものの、前記にお\nいて説示したところを踏まえると、立法論であれば格別、特許法の解釈適用と しては、その域を超えるものというほかない。
(2) 原告は、AI発明を保護しないという解釈はTRIPS協定27条1項に違 反する旨主張する。しかしながら、同項は、「特許の対象」を規律の内容とす るものであり、「権利の主体」につき、加盟国に対し、加盟国の国内特許法に いう「発明者」にAIを含めるよう義務付けるものとまでいえず、また、原告 主張に係る欧州特許庁の見解も、特許法に関する判断の国際調和という観点か ら一つの見解を示すものとして十分参考にはなるものの、属地主義の原則に照\nらし、我が国の特許法の解釈を直ちに左右するものとはいえず、本件に適切で はない。
(3) 原告は、知的財産基本法2条1項は「その他」と「その他の」の用法を混同 しており、「発明」が「人間の創造的活動により生み出されるもの」に包含さ れると規定するものではない旨主張する。しかしながら、特許法がAI発明を 想定していなかったことは、原告も認めるとおりであり、知的財産基本法2条 1項も、立法経緯に照らし、文言どおり、AI発明を想定していなかったもの と解するのが相当である。そして、当時想定していなかったAI発明について は、現行特許法の解釈のみでは、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏ま\nえた的確な結論を導き得ない派生的問題が多数生じることは、前記において繰 り返し説示したとおりである。
・・・
その他に、原告提出に係る準備書面及び提出証拠を改めて検討しても、前記に おいて説示したところを踏まえると、いずれも前記判断を左右するに至らない。 したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
なお、被告は、当裁判所の審理計画の定め(第2回弁論準備手続調書参照)に かかわらず、原告主張に係るAI発明をめぐる実務上の懸念に対し、具体的な反 論反証(令和5年11月6日提出予定の被告の再々反論、再々反証をいう。上記\n手続調書参照)をあえて行っていないものの、特許法にいう「発明者」が自然人 に限られる旨の前記判断は、上記実務上の懸念までをも直ちに否定するものでは なく、原告の主張内容及び弁論の全趣旨に鑑みると、まずは我が国で立法論とし てAI発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、AI発 明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、 最後に改めて付言する。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2024.05.15
令和5(ワ)691 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和6年4月18日 大阪地方裁判所
被告標章1は、別紙被告標章目録記載1のとおり、「香椎照葉こどもとママ の歯科医院」の同一字体の文字を1行の横書きにて配して成るものである。こ のうち、「こどもとママの歯科医院」の部分は、母子を歯科治療の対象としてい る意味合いを伝えるにすぎないことに加え、証拠(乙10ないし17)及び弁 論の全趣旨によれば、同趣旨の商標又は歯科治療の対象となる特定の属性を表\n現した商標は、多くの歯科医院において使用されていることが認められる。そ うすると、被告標章1のうち「こどもとママの歯科医院」の部分は、自他役務 の識別力が弱いというべきであるから、同部分が、取引者又は需要者に対し、 役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、同 部分だけを抽出して本件各商標と比較して類否を判断することは相当でない。
そこで、本件各商標と被告標章1全体を比較して類否を判断するに、別紙商 標目録及び同被告標章目録1記載のとおり、本件各商標と被告標章1の外観は、 少なくとも「香椎照葉」の有無という明らかな相違がある。また、本件各商標 からは「子供と母親のための歯医者さん」という観念が生じるのに対し、被告 標章1からは「香椎照葉にある子供と母親のための歯科医院」という観念が生 じる。そして、本件各商標は「コドモトママノハイシャサン」又は「ママトコ ドモノハイシャサン」という称呼が生じるのに対し、被告標章1は「カシイテ リハコドモトママノシカイイン」という称呼が生じる。したがって、本件各商 標と被告標章1は、外観、観念及び称呼のいずれをみても、明確に相違をして おり、取引の実情を考慮しても、需要者がその出所につき誤認混同を生じるお それがあるとはいえない。
2024.05. 1
令和5(ネ)10078 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(4) 当審における控訴人による均等侵害の主張に対する判断
ア 控訴人は、仮に被控訴人製品が、本件各発明に文言上はその技術的範囲に 属しないものとしても、これと均等なものとして、特許権侵害に当たる旨を 主張する。
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用い\nる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、 1)同部分が特許発明の本質的部分ではなく、2)同部分を対象製品等における ものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果 を奏するものであって、3)上記のように置き換えることに、当該発明の属す る技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製 造等の時点において容易に想到することができたものであり、4)対象製品等 が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同 出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、5)対象製品等が特許発明の 特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる などの特段の事情もないときは、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解する\nのが相当である。
そして、上記1)の要件(第1要件)における特許発明における本質的部分 とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない 特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求\nの範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効 果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見 られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定するこ\nとによって認定されるべきである(最高裁平成6年(オ)第1083号同1 0年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁、最高裁平成28 年(受)第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号 359頁参照)。
これを本件において検討するに、前記(1)イのとおり、本件発明1は、「底部 に取り付けられた安定補助板により支えられてテーブルなどの上に立たせら れる」「折畳式コップ型容器」(段落【0003】)であって「安定補助板が例 えば紙や合成樹脂などから形成され、後から容器本体に取り付けられる構成」\n(段落【0005】)を採用した従来技術を前提とし、「成形が簡便な自立型 の包装容器の提供を目的とする」(段落【0006】)ことを発明が解決しよ うとする課題とし、当該課題を解決する手段として「前記包装容器を容器と して形成した状態において、前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自 立片が載置面に沿って前記奥行の方向に突出し、前記自立片によって前記載 置面に自立させられる」(本件発明1の構成要件B)という構\成を採用するこ とにより、「包装容器を自立させる自立片が底面片に連なっているため、一体 的な成形が簡便である」(段落【0013】)という効果を奏するものである。
そうすると、本件発明1において従来技術に見られない特有の技術的思想 を構成する特徴的部分は、従来技術における安定補助板が、底部に一体的に\n成形された構成である、「前記包装容器を容器として形成した状態において、\n前記底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片が載置面に沿って前記奥 行の方向に突出し、前記自立片によって前記載置面に自立させられる」こと にあると考えられる。
そして、本件発明1と被控訴人製品とは、包装容器を容器として形成した 状態において、本件発明1の「底面片」が筒状の底部を形成するのに対し、 被控訴人製品は、包装容器を自立させる舌状片が、包装容器の底部を形成す る六角片と同一面に連なっておらず別に構成されている点において相違する\nものと認められるところ、この相違に係る本件発明1の構成、すなわち「底\n部を形成する底面片」が「自立片」と同一面に連ねられていることは、これ までの検討によれば、本件発明1の本質的部分に当たるものということがで きる。
そうすると、上記相違点に係る本件発明1の構成については、本件発明1\nの本質的部分ではないということはできない。そして、前記(1)ウのとおり、 上記の点については、本件各発明について共通するものということができる。 したがって、被控訴人製品は均等侵害の第1要件を充足しないから、その 要件について検討するまでもなく、均等侵害は成立しない。 イ 控訴人は、前記第2の3(4)ウのとおり、本件各発明の本質的部分は、「自立 片」によって載置面に自立させられる構成を採用した点にあり、当該「自立\n片」が内容物に直接接触してこれを支える片という意味における「底面片」 と、同一面に連なることにあるのではないと主張する。 しかし、本件各発明の本質的部分については上記アのとおりと認められる から、本件各発明と被控訴人製品とは、その本質的部分において異なるもの というべきである。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2024.05. 1
令和3(ワ)11358 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年3月19日 東京地方裁判所
原告は「すしざんまい」です。
ア 本件各掲載行為のうち本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為について\n
前提事実(1)イ及びウ、(4)ア、証拠(甲4、23ないし25)並びに弁 論の全趣旨によれば、原告各商標の指定役務は「すしを主とする飲食物 の提供」であること、被告は、魚介類及び水産加工品の輸出入等の事業 を行う株式会社であり、日本での食材の仕入れ及び東南アジアのダイシ ョーグループ各社への輸出を行っていること、ダイショーグループは、 シンガポール・マレーシア・インドネシアなどで「寿司」、「和食レスト ラン」などの店舗を展開していること、本件各ウェブページは、日本語 によって記載された主に日本国内の取引者及び需要者に向けたウェブペ ージであり、被告が管理していること、本件各ウェブページには、スー パースシが展開する本件すし店に関するものとして被告各表示が掲載さ\nれており、被告各表示とともに「手頃な価格で幅広い客層が楽しめる回\n転寿司。厳選した食材と豊富なメニューで、人気を集めています。」と の説明が掲載されていることが認められる。 このような事情からすれば、本件各ウェブページにおける被告各表示\nは、すしを主とする飲食物の提供を行う本件すし店を紹介するために掲 載されたものであり、「すしを主とする飲食物の提供」と類似の役務に 係るものといえるから、原告各商標の指定役務と被告各表示に係る役務\nとは類似するものといえる。 そして、被告が本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は、\n「役務に関する広告…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法によ り提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当するといえ、被告は原 告各商標を「使用」したものと認められる。
被告の主張について
被告は、被告各表示はスーパースシがマレーシアにおいて展開する本\n件すし店に関するものにすぎず、被告自身は「すしを主とする飲食物の 提供」を行っていないことなどから、被告各表示に係る役務は、原告各\n商標の指定役務である「すしを主とする飲食物の提供」とは類似してお らず、また、被告が原告各商標を「使用」したとはいえないと主張する。
そこで検討すると、商標法は、「商標を保護することにより、商標の 使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、 あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」と定めており、こ の目的を達成するため、商標は、標章をある者の商品又は役務に付する ことにより、その商品又は役務の出所を表示する機能\(出所表示機能\) や、取引者及び需要者が同一の商標の付された商品又は役務には同一の 品質を期待しており、商標がその期待に応える作用をする機能(品質保\n証機能)を有するものと解される。本件においては、前記 で説示した とおり、本件各ウェブページは主に日本国内の取引者及び需要者に向け たウェブページであり、かつ、被告各表示は「すしを主とする飲食物の\n提供」という役務に係るものといえるから、被告各表示がマレーシアの\n本件すし店に係るものであったとしても、本件各ウェブページに被告各 表示を掲載した行為は、日本における原告各商標の出所表\示機能及び品\n質保証機能を害し、ひいては、上記の商標法の目的にも反するものであ\nるといえる。
そして、被告各表示が被告自身の事業に関するものではなかったとし\nても、本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は被告が行った\nものと認められ、上記のとおり、そのような被告の行為によって日本に おける原告各商標の出所表示機能\及び品質保持機能が害されている以上、\n被告が原告各商標を「使用」していないと評価することはできない。 そうだとすれば、被告の上記主張はいずれも役務の類否や使用行為の 有無を左右するものではないというべきである。
・・・・
被告は、被告各表示はスーパースシがマレーシアにおいて展開する本\n件すし店に関するものにすぎず、被告自身は「すしを主とする飲食物の 提供」を行っていないことなどから、被告各表示に係る役務は、原告各\n商標の指定役務である「すしを主とする飲食物の提供」とは類似してお らず、また、被告が原告各商標を「使用」したとはいえないと主張する。
そこで検討すると、商標法は、「商標を保護することにより、商標の 使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、 あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」と定めており、こ の目的を達成するため、商標は、標章をある者の商品又は役務に付する ことにより、その商品又は役務の出所を表示する機能\(出所表示機能\) や、取引者及び需要者が同一の商標の付された商品又は役務には同一の 品質を期待しており、商標がその期待に応える作用をする機能(品質保\n証機能)を有するものと解される。本件においては、前記 で説示した とおり、本件各ウェブページは主に日本国内の取引者及び需要者に向け たウェブページであり、かつ、被告各表示は「すしを主とする飲食物の\n提供」という役務に係るものといえるから、被告各表示がマレーシアの\n本件すし店に係るものであったとしても、本件各ウェブページに被告各 表示を掲載した行為は、日本における原告各商標の出所表\示機能及び品\n質保証機能を害し、ひいては、上記の商標法の目的にも反するものであ\nるといえる。
そして、被告各表示が被告自身の事業に関するものではなかったとし\nても、本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は被告が行った\nものと認められ、上記のとおり、そのような被告の行為によって日本に おける原告各商標の出所表示機能\及び品質保持機能が害されている以上、\n被告が原告各商標を「使用」していないと評価することはできない。 そうだとすれば、被告の上記主張はいずれも役務の類否や使用行為の 有無を左右するものではないというべきである。
イ 本件各掲載行為のうち本件各アカウント写真として被告表示2を掲載し\nた行為について
前提事実(1)ウ、証拠(甲20、21)及び弁論の全趣旨によれば、スー パースシは、マレーシアにおいて本件すし店を展開していること、本件各 アカウントは、本件すし店に係るアカウントであることが認められるが、 本件全証拠によっても、被告が本件各アカウントを管理していると認める ことはできない。
したがって、本件各アカウント写真の掲載行為については、被告が行っ たものと認めることができないから、被告が原告各商標を「使用」したと はいえない。
なお、本件では、不競法違反に関して被告が原告各表示と類似の商品等\n表示を「使用」(不競法2条1項1号)したといえるか(争点2−3)も\n問題となっているが、上記で説示したとおり、本件各アカウント写真の掲 載行為は被告が行ったとは認められないから、被告が原告各表示と類似の\n商品等表示を「使用」したともいえない。\n
・・・
商標法38条2項による損害額の算定について
商標法38条2項は、商標権者等が侵害行為による損害の額を立証するこ とが困難であることから、その立証を容易にするために設けられたものであ ると解される。そうすると、同項の適用が認められるためには、侵害者によ る侵害行為がなかったならば商標権者等が利益を得られたであろうという事 情が存在する必要があるものと解される。
証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば、原告はマレーシアにおいてすし 店を展開していないことが認められるところ、本件全証拠によっても、日本 国内における原告すし店とマレーシアにおける本件すし店の市場が競合する と認めることはできないから、被告による侵害行為(本件各ウェブページに 被告各表示を掲載した行為)がなかったならば原告(原告すし店)が利益を\n得られたであろうという事情が存在すると認めることはできない。 したがって、本件では、商標法38条2項を適用することはできない。
(2) 商標法38条3項よる損害額の算定について
ア 前提事実(5)のとおり、平成26年から令和5年までの被告の本件すし 店に対する売上げは合計1億4475万8151円である。 そして、証拠(甲44、乙3)及び弁論の全趣旨によれば、株式会社 帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用 の在り方に関する調査研究報告書〜知的財産(資産)価値及びロイヤル ティ料率に関する実態把握〜」には、商標権における使用料率(ロイヤ ルティ料率)全体の平均値は2.6パーセント、第43類「飲食物の提 供及び宿泊施設の提供」に関する平均値は3.8パーセントであると記 載されていることが認められる。 この点について、前提事実(1)のとおり、被告は、スーパースシを含め たダイショーグループ各社に対して、日本で仕入れた食材の輸出を行っ ているところ、被告が本件各ウェブページに被告各表示を掲載すること\nによって本件すし店(スーパースシ)の売上げが増加した場合、それに 伴って被告の本件すし店に対する売上げ(輸出)も増加する関係にある ものと認められる。
他方で、前記(1)で説示したとおり、日本国内における原告すし店とマ レーシアにおける本件すし店の市場が競合すると認めることはできない ことに照らすと、本件各ウェブページへの被告各表示の掲載が被告の売\n上げに与えた影響は限定的なものであったことがうかがわれる。 このような事情に加え、本件各ウェブページにおける被告各表示は遅\nくとも平成26年12月頃から相当長期にわたって掲載されていたと認 められること(前提事実(4)及び弁論の全趣旨)及び商標権侵害があった 場合に事後的に定められるべき登録商標の使用に対し受けるべき金銭の 額は通常の使用料と比べて高額となることを考慮すると、被告による原 告各商標の使用に対し原告が受けるべき金銭の額に相当する額を算定す るための使用料率については、3.8パーセントと認めるのが相当であ る。 そうすると、上記の金銭の額は、被告の本件すし店に対する売上げで ある1億4475万8151円に使用料率3.8パーセントを乗じた5 50万0809円であると認められる。
イ これに対し、原告は、前記アの金銭の額を算定するに当たっては、被 告が被告各表示を被告各ウェブサイトに掲載することにより自己の取引\n上の信頼を高めて事業全般に及ぶメリットを享受していることから、被 告の全売上高をその基礎とすべきであると主張する。 しかしながら、上記の金銭の額を算定する際に基礎とすべきは、侵害 行為に関する売上高であると解されるところ、別紙被告ウェブページ目 録記載のとおり、本件各ウェブページに掲載された被告各表示は本件す\nし店に関するものであり(甲4及び弁論の全趣旨)、それを超えて被告の 事業全体に関するものであると認めるに足りる証拠はないから、原告の 上記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 役務
>> 類似
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2024.04.30
令和4(ネ)10117 商標使用料等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和6年4月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原告商標1についての商標登録出願につき、その登録前の平成17年12月6日 に、被告から原告へと出願人名義変更がされている(甲A419、乙113〜11 5)。原告商標1の商標登録出願により生じた権利を被告から原告に移転すること は、被告の取締役でありかつ原告代表者であるDが、原告のために行った取引であ\nるから、被告からみて利益相反取引に当たるところ、同取引について被告の取締役 会における承認はされていないから、被告は、原告に対し、当該移転に係る取引の 無効を主張することができることになる。しかしながら、原告商標1は平成18年 1月27日に設定の登録がされ(甲A203、204)、既に同日から5年が経過し ていることから、これを無効審判請求により無効とすることはできない(商標法4 7条1項、46条1項4号)。そうすると、被告は、原告商標1の登録について、無 効の抗弁(同法39条、特許法104条の3第1項)を提出することはできない(最 高裁平成27年(受)第1876号同29年2月28日第三小法廷判決・民集71 巻2号221頁参照)。 そして、本件において原告が原告商標1を取得した目的は、被告に使用許諾をし て足立物件に係る事業に用いるためであり、また、被告から原告に移転をしたのは 出願当初に予定していたとおりの帰属とするためであったと認められるから、原告\n商標1の出願により生じた権利の移転について被告の取締役会決議を経ていないこ とのみをもって、原告による原告商標権1に係る権利行使を制限すべきとは認めら れない。
(3) 原告各商標権について
原告各商標権の行使が権利の濫用に当たるか検討する。
まず、前記(1)のとおり、A、B、C及びDは、Aを被相続人とする相続時の税金 対策のために、被告において不動産事業を営むこととし、被告の株式の評価額を減 少させようとしていたところ、節税等の目的で、知的財産権を含む資産を関係会社 や子会社に分配して保有させるなどして利益を関係会社等に分散させることは、企 業経営者の経営判断として一般に採用し得る手法であって、商標権を、事業主体で ある被告ではなく、その事業運営を請け負う原告が取得し、被告からその商標使用 料の支払を受けることは直ちに不自然であるとはいえない。また、原告と被告との 間の本件商標使用許諾契約において定められた商標使用料は、平成25年9月期か ら平成27年9月期までの3年間の本件各物件に係る事業の売上額(甲A421) の平均に対し、商標権の全分類平均の使用料率2.6%(甲A422)を乗じた額 と比べても相当程度に低廉であり(本判決別紙「本件各物件売上額等」参照)、原告 各商標が一般的な普通名詞から構成されるものであってそれ自体の顧客吸引力が高\nいとまではいえないことを考慮しても、不相当に高額であるとはいえない。そして、 本件商標使用許諾契約の効力が認められないのは、Dが利益相反取引についての会 社法所定の手続を経ていなかったからであって、D以外の他の取締役らが、被告の 不動産事業の経営を事実上Dに任せていたという事情が認められる本件において、 本件商標使用許諾契約書が作成された平成20年10月当時、Dが当該手続に従っ て被告の取締役会の承認を得ることが困難であったような事情は見当たらないし、 仮に取締役会の承認を得ておれば、原告は、被告に対し、本件商標使用許諾契約に 基づき原告各商標の使用料を請求することができたはずである。しかも、平成21 年8月20日から平成28年2月10日までの間、被告は原告に対し、現に本件商 標使用許諾契約に定められた原告各商標の使用料の支払を行っていたことが認めら れ(補正の上引用した原判決の第2の2(7))、取締役であるA、B及びCは上記支 払について容易に知り得たといえるところ、この間、平成25年11月に死亡した Aが生前異議を述べていた事実は認められないし、B及びCにおいても、平成28 年5月に被告が本件各業務委託契約(原告と被告との間で締結された、被告が本件 各物件の管理等の事業全般に関する業務を原告に委託する旨の契約)等を解除する 旨の意思表示をするまでの間、本件商標使用許諾契約が有効であるという前提で行\n動していたことが推認され、これに反する証拠はない。
これらの事情及び前記(2)の事情を総合すると、原告が被告に対し、原告各商標権 の侵害を主張することが権利濫用に当たり許されないものと認めることはできない。 そして、被告は、少なくとも過失により、契約上の権限を取得することなく原告各 商標の使用を開始し、継続したことになるというべきであるから、被告は、原告に 対し、不法行為に基づき、使用料相当額の損害を賠償する義務があるというべきで ある。
なお、原告が使用料相当額の損害賠償金を請求する期間は平成28年4月1日か ら令和元年9月30日までであって、原告商標3の登録後であるから、本件商標使 用許諾契約書が作成された平成20年10月1日当時に原告商標3の商標登録出願 がされていなかったことは、上記判断を左右しない。
2024.04.30
令和5(ワ)70001 特許専用実施権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年4月17日 東京地方裁判所
以上のような本件明細書等から認められる本件各発明の目的、課題の解決手 段からすれば、本件各発明は、オゾンによる殺菌等を行った処理後の被処理水 に含まれる残オゾンの低減と、被処理水の生物処理の促進とを両立させること ができる廃水処理装置及び廃水処理方法を提供することを目的としており、そ の解決手段としては、第1の収容槽内にオゾンを含むマイクロナノバブルを供 給するオゾン供給手段を有するとともに、第1の収容槽とは別に、被処理水の 生物処理を行う第2の収容槽を設けることとした上で、そこに第1の収容槽に おいてオゾンによって処理された被処理水を残オゾンとともに収容し、生物処 理能力を低減させる原因となる残オゾンを積極的に酸素分子に化学変化させる\nために、第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給 手段と、所定の担体を有するというものである。
したがって、本件各発明においては、オゾンによる殺菌等を行った後の被処 理水に含まれる残オゾンの低減をも目的として第2の収容槽とそれに関する構\n成を設けているのであり、残オゾンを低減させるための構成ともいえる第2の\n収容槽内に、少なくとも積極的にオゾンを供給することは、課題の解決に至ら ず、本件各発明において第2の収容槽とそれに関する構成を有することとした\nことと相容れないものといえる。
そして、オゾン発生装置で製造されるオゾンは、純度100%のオゾンガス が製造されるものでないことは技術常識である上、本件明細書【0031】に おいて、オゾン発生装置29によって発生し、このオゾン発生装置29に接続 され吸気管を介し吸気されたオゾンは、複数分岐した枝管24を通って圧縮部 22内に噴出されるようになっていて、この圧縮部22内に噴出された気泡が オゾンを含むマイクロナノバブルとされていることからしても、第1収容槽内 に供給される「オゾンを含むマイクロナノバブル」については、当然に酸素(空 気)を含むものも想定されていたといえる。
以上に照らせば、本件各発明の特許請求の範囲の「第1の収容槽内にオゾン を含むマイクロナノバブルを供給するオゾン供給手段」と、「第2の収容槽内に 酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段」の記載は、特にオゾ ン供給の有無という点において上記課題の解決のための対照的なマイクロナノ バブルの供給手段として記載されているものと解するのが相当であり、「第2の 収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段」は、第1 の収容槽への供給手段と異なり、そのマイクロナノバブルにはオゾンが積極的 に加えられているものではなく、その供給手段には、オゾンが積極的に加えら れたマイクロナノバブルを供給する供給手段を含まないというべきである。し たがって、第2の収容槽内にオゾンが積極的に加えられたマイクロナノバブル を供給する酸素供給手段を有する装置は、構成要件Dを充足しないと解される。\n
(3) 被告システムは、前記第2の1(6)のとおり、構成要件Dの第2の収容槽に当\nたる曝気槽内に、酸素及びオゾンを含むマイクロナノバブルを供給する被告装 置を有しており、そのマイクロナノバブルには、オゾン発生装置から得られた オゾンガス、すなわちオゾンと酸素の混合ガスが用いられていて、オゾンが意 図的、積極的に加えられていると認められるから(甲16、18、21、弁論の 全趣旨)、構成要件Dを充足しない。\n
(4) 原告は、被告装置は、オゾンよりも多くの酸素が残存して含まれている上、 当該オゾン自体も活性炭により化学変化させて酸素となることにより、好気性 微生物及び通性嫌気性微生物を活性化させており、十分効果的である旨主張す\nる。
しかし、本件明細書に記載された本件各発明の目的、課題の解決手段等から すれば、本件各発明における「酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素 供給手段」は、前記(2)のとおり解するのが相当である。 また、原告は、オゾンは微量であるが、大気中に存在するし、「オゾン発生装 置」で生成されたオゾンは自然に消滅して酸素に置き換わるものなので、「第2 収容槽内においてはオゾンの量を早期に低減」させることは、2次的な効果に すぎない旨主張するが、前記(1)及び(2)で述べたところによれば、残オゾンを早 期に低減させることが本件各発明の2次的な効果にすぎないといえない。
(5) 以上によれば、被告システムは構成要件Dを充足せず、本件発明1の技術的\n範囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.04.30
令和5(行ケ)10115 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年4月11日 知的財産高等裁判所
商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと規定されて いるのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売 地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表\示と して何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を 認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、 多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される(最 高裁昭和53年(行ツ)第129号同54年4月10日第三小法廷判決・集 民126号507頁)。
そうすると、出願に係る商標が、その指定商品について商品の産地、販売 地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である\nというためには、審決がされた時点において、当該商標が当該商品との関係 で商品の産地、販売又は品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切\nな表示であり、当該商標の取引者、需要者によって当該商品に使用された場\n合に、将来を含め、商品の産地、販売地又は品質を表示したものと一般に認\n識されるものであるか否かによって判断すべきである。そして、当該商標の 取引者、需要者によって当該商品に使用された場合に商品の産地、販売地又 は品質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構\成やそ の指定商品に関する取引の実情を考慮して判断すべきである。
(2) 本願商標の構成\n
本願商標は「Nepal Tiger」の文字を標準文字で表してなる商\n標である。 「Nepal Tiger」は「Nepal」の文字及び「Tiger」 の文字を組み合わせたものであって、「Nepal」は国家(ネパール)を示 す語であり、「Tiger」は「トラ」を意味する語である(乙1〜4)。
(3) 本願商標及び本願の指定商品に関する取引の実情
ア 以下の新聞記事及びウェブサイトには、ネパールで手織りのじゅうたん の生産がされていることや、我が国で開催された展示会等においてネパー ルで生産された、又はネパールから輸入された手織りのじゅうたん、ラグ が展示、販売されたことに関する記載が存在する。
・・・・
イ 以下の新聞記事、書籍及びウェブサイトには、チベットにおいてじゅう たんの生産が行われている旨の記載、チベットで生産されたじゅうたんを 「チベットじゅうたん」又は「チベタンじゅうたん」と称する旨の記載と ともに、ネパールで生産されるじゅうたんも「チベットじゅうたん」「チベ タンラグ」などと称する旨の記載、又は、チベットからネパールに亡命し た者あるいはネパールに居住するチベット難民がネパールにおいてじゅ うたんの生産を行っている旨の記載が存在する。
・・・・
ク 上記アないしキに掲げた新聞記事、書籍及びウェブサイトのいずれにも、 「Nepal Tiger」又は「ネパールタイガー」との記載は存在し ない。
(4) 検討
ア 上記(3)に掲げた新聞記事、雑誌、ウェブサイトの記載によれば、以下の 事実が認められる。
(ア) ネパールにおいてじゅうたんの生産が行われていること。
(イ) チベットからネパールに移住した者、あるいはチベット難民がネパー ルにおいてじゅうたんの生産に従事しているとするウェブサイト等の 記載が複数存在すること。
(ウ) ネパールで生産されたじゅうたんを「チベットじゅうたん」あるいは これに類する「チベタンじゅうたん」「チベタンラグ」などの名称で表示\nするウェブサイト等の記載が複数存在すること。
(エ) トラの図柄が描かれたじゅうたん又はトラの形状を模したじゅうた んを紹介するに当たって「タイガー」の語を用いているウェブサイトの 記載が複数存在すること。
(オ) トラの形状を模した「チベットじゅうたん」(あるいは「チベタンじゅ うたん」「チベタンラグ」)を「チベタンタイガーラグ」又は「チベタン タイガーカーペット」との名称で表示するウェブサイト等の記載が複数\n存在すること。
(カ) ネパールで生産されたもの又はネパールから輸入したものであるト ラの形状を模したじゅうたんを紹介するウェブサイト等の記載が複数 存在すること。
イ しかし、上記(3)クのとおり、上記(3)アないしキに掲げた新聞記事、書籍 及びウェブサイトのいずれにも、「Nepal Tiger」又は「ネパー ルタイガー」との記載は存在せず、その他本件の全証拠によっても、本願 の指定商品に関連するウェブサイト等の記載において「Nepal Ti ger」又は「ネパールタイガー」の文字が一体として用いられたものが あるとは認められない。
したがって、「Nepal Tiger」の語句が、一体として「ネパー ルで生産された、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した、じ ゅうたん、ラグ」を意味するものとして、じゅうたんの取引者等によって 使用されている取引の実情が存在するとは認められず、その他の本願の指 定商品に関連して「Nepal Tiger」の語句が一体として用いら れる取引の実情が存在するとも認められない。
そして、「Nepal Tiger」は、前記(2)のとおりの意味を有する 「Nepal」の語及び「Tiger」の語を組み合わせたものであると いえるところ、「Nepal Tiger」の語句が一体のものとして辞書 等に採録されているとは認められず、トラに関する亜種の名称や通称名等 として「Nepal Tiger」、「ネパールタイガー」又は「ネパール トラ」と呼ばれるものがあるとも認められない。
そうすると、「Nepal Tiger」の語句は、通常は組み合わされ ることのない「Nepal」の語と「Tiger」の語とが組み合わされ、 まとまりよく一体的に表されたものであるといえることからすれば、これ\nを一体として組み合わされた一種の造語とみるのが相当である。
ウ 本願商標の指定商品は前記第2の1(1)のとおりであり、この指定商品の 内容からすれば、本願商標の取引者はじゅうたん類の製造業者及び販売業 者であり、需要者は一般の消費者であると認められる。 そして、前記イのとおり、「Nepal Tiger」の語句は、これが 本願の指定商品に関連して用いられる取引の実情があるとは認められず、 かつ、一体として組み合わされた一種の造語であるとみるのが相当である ことからすれば、本願商標の取引者及び需要者は、「Nepal Tige r」の語句について、指定商品に係る商品の産地、販売地又は品質を表示\nしたものであると直ちに認識するものではないというべきである。 そうすると、本願商標の取引者、需要者は、「Nepal Tiger」 の語句について「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、 あるいは、トラ形状を模したじゅうたん」、「ネパールで生産又は販売され る、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物」又は「ネ パールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形 状を模したラグ」を表示するものであると必ずしも認識するものではない\nから、本願商標は、その指定商品に使用された場合に、本願商標の取引者、 需要者によって、商品の産地、販売地又は品質を表示したものと一般に認\n識されるものであるとは認められない。
エ 以上によれば、本願商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もそ\nの使用を欲するものとはいえず、指定商品の産地、販売地又は品質を普通 に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、商\n標法3条1項3号に該当するものとは認められない。
◆判決本文
関連事件はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.04.23
令和4(ワ)18776 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和6年4月18日 東京地方裁判所
(1) 著作権法 114 条 3 項に基づく損害について
ア 原告らは、原告らが有する本件作品に係る出版権又は独占的利用権の侵害行 為を行った被告に対し、出版権の侵害については著作権法 114 条 3 項に基づき、ま た、独占的利用権の侵害については同項の類推適用により、本件作品の出版権又は 独占的利用権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の 額として、その損害賠償を請求することができるといえる。
イ 利用料率について
(ア) 本件サイトにおいては、ユーザーは無償で本件作品の閲覧が可能であり、ユ\nーザーから閲覧可能とすることの対価を得ていないという意味では、侵害による売\n上高は観念できない。 もっとも、本件作品は、原告らが、別紙作品目録 1〜3 の各「販売価額(税込)」 欄記載の金額で、原告ら又は原告 KADOKAWA の完全子会社の電子配信サイトで電 子配信され、又は、コミック単行本等として販売されていたものである(前提事実 (2))。そうすると、原告らは、本件作品に係る出版権又は独占的利用権に基づき、これらの販売による利益を受けていたものと認められる。
また、本件サイトでは、ファイルをユーザーの端末にダウンロード(複製(いわ ゆる端末のキャッシュは除く。))することなく、いわゆるストリーミング形式によ り無償で閲覧することが想定されていた。もっとも、閲覧にあたり、ユーザーは、 広告の視聴等の制約を受けることなく閲覧することが可能であった。また、本件サ\nイトにおいては、閲覧した画像ファイルの保存操作を制限するような技術や機能は\n採用されておらず、ユーザーにおいて、各画像ファイルをユーザーの端末の記録媒 体に保存することも可能であった(以上につき、前記 1(1)イ)。これらの事情に鑑み ると、ユーザーにとっては、ストリーミング形式での閲覧が想定されているとはい え、本件サイトを通じて本件作品の閲覧が可能である限り、本件サイトにアクセス\nしさえすれば何らの制限なく本件作品を無償で閲覧可能な状態に置かれるといえる。\nこれは、実質的には、ユーザーが本件サイトにアクセスする都度、電子配信された 本件作品を購入したのと異ならない状態が実現されているものと評価することがで きる。
これらの事情その他本件に表れた一切の事情を総合的に考慮すると、本件におい\nて、被告による侵害行為に対し、原告らが本件作品に係る出版権又は独占的利用権 の行使につき「受けるべき金銭の額に相当する金額」(著作権法 114 条 3 項)の算定 にあたっては、別紙作品目録 1〜3 の「裁判所認定損害額」欄記載のとおり、「販売 価額(税込)」欄の金額から 10%を控除した金額に、各作品の閲覧数を乗じた額とす ることが相当である。これに反する原告らの主張は採用できない。 (イ) 被告の主張について 被告は、本件サイトと同規模の漫画閲覧サイト運営者(漫画定額読み放題サービ スサイト)と原告らとの間で締結されるべきライセンス利用契約のライセンス料を 基礎に損害額を算定すべきである旨主張する。
しかし、そもそも、本件作品のうち電子配信の対象となっていない作品(別紙作 品目録 3 の番号 174〜221)については、この主張が妥当する余地はない。 また、その他の本件作品についても、上記のとおり、原告らは、自ら又は完全子 会社が管理・運営する電子配信サイトを通じて有償でのみ電子配信しているのであ って、これらの作品が漫画定額読み放題サービスの対象とされていることを認める に足りる証拠はない。そうすると、原告らにとっては、本件作品を同サービスの対 象とする動機はなく、仮に本件作品を同サービスの対象として利用許諾契約を締結 するとすれば、本件作品の販売価格と同額ないしこれに近い額を利用料として設定 すると考えることには合理性がある。 したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。
ウ 閲覧数
本件調査によれば、平成 29 年 6 月〜平成 30 年 4 月の間の本件サイトへのアクセ ス総数は 億 3781 万超と推計される。また、本件サイトの平均滞在時間は約 分程度でされるところ(前記 1(3)イ)、この平均滞在時間は、漫画作品 1 巻を閲覧する のに一応十分な時間といえる。これを踏まえ、本件サイトにアクセスしたユーザー\nが 1 アクセス当たり漫画 1 巻を閲覧したとすると、上記期間中、本件サイトにおい ては、合計 億 3781 万巻の閲覧があったと推計されるとみてよい。 また、本件調査時に本件サイトに掲載されていた作品巻数は 7 万 2577 巻とされ るから、本件サイトにおける本件作品 1 巻当たりの平均閲覧数は、74回を下回ら ないものとみられる。
この点、被告は、SimilarWeb によるアクセス数の推計は不正確である旨を指摘し て、これを損害額算定の基礎とすることはできないと主張する。 確かに、本件調査の推計が依拠する SimilarWeb による調査結果の信頼性について は、これを疑問視する見解も見受けられるが(例えば乙 6)、本件において、その調 査手法ないし結果の信頼性を疑わせる具体的な事情は証拠上見当たらない。その点 を措くとしても、本件調査においては、平成 29 年 6 月〜平成 30 年 4 月の間におけ る本件サイトへの月平均サイトアクセス数は 4889 万 2057 回とされている(前記 1(3)イ)。他方、被告は本件サイトの管理・運営に関与し、利用者数の状況を把握し 得る立場にあり、現に把握していたと考えられるところ(前記 1(2)、(4))、被告によ れば、令和 4 年 7 月時点の投稿ではあるものの、月間利用者は 8500 万人とされ(前 記 1(4)ア)、また、平成 30 年 2 月時点の本件サイトの月間アクセス数は 1 億 6000 万とされている(前記 1(4)イ)。被告の本件サイト利用者数に関する上記各言及には誇 張が含まれている可能性も否めないものの、上記各数値と本件調査での推計に係る\n数値との乖離の程度等を考慮すると、その可能性を考慮してもなお、少なくとも、\n本件調査結果として推計された閲覧数が本件サイトの現実の閲覧数を上回るものと はうかがわれない。したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。
エ 著作権法 114 条 3 項に基づき算定される損害額
以上によれば、本件において、原告らが「受けるべき金銭の額に相当する金額」(著作権法 114 条 3 項)は、別紙作品目録 1〜3 の「裁判所認定損害額」欄記載のと おり、「販売価額(税込)」欄記載の金額から 10%を控除した金額に、各作品の閲覧 数 74回を乗じた金額と認めるのが相当である。 このような損害額の合計額は、それぞれ、以下のとおりとなる。
・原告 KADOKAWA につき 3 億 6886 万 9059 円
・原告集英社につき 3 億 90万 9859 円
・原告小学館につき 8 億 1968 万 6790 円
(2) 弁護士費用相当損害金
原告らは、本件訴訟の提起に当たり訴訟代理人弁護士に委任せざるを得なかったものであり、本件に表れた一切の事情を考慮すると、被告の不法行為と相当因果関\n係のある弁護士費用相当損害金の額は、それぞれ、以下のとおりとなる。
・原告 KADOKAWA につき 3688 万 690円
・原告集英社につき 3902 万 098円
・原告小学館につき 8196 万 8679 円
(3) 小括
したがって、本件作品に係る出版権又は独占的利用権の侵害の不法行為に係る原告らの損害額の合計は、それぞれ、以下のとおりとなる。
・原告 KADOKAWA につき 4 億 057万 5964 円
・原告集英社につき 4 億 2923 万 0844 円
・原告小学館につき 9 億 016万 5469 円
なお、原告らは、予備的に著作権法 114 条 1 項に基づき算定される損害額をも主 張する。しかし、原告らの主張を前提としても上記認定に係る損害額を上回ること はないから、この点に関して判断する必要はない。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2024.04.22
令和5(ネ)10010 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(イ) 乙18分析及び乙24分析における分析対象物である公然実施発明
(引用発明)に基づく進歩性欠如の主張について a 公然実施発明は、公然実施品の具体的な構成又は組成等に基づいて認\n定されるため、通常、その公然実施品自体に課題が記載されていること はなく、何らかの課題があることを認識することは困難であるから、公 然実施発明に基づく容易想到性の有無を判断するにあたっては、公然実 施品から出願日(優先日)当時の技術常識を前提にして技術的思想や課 題を認識できるかどうか、その構成又は組成を変更する動機付けがある\nか否かを検討すべきである。
・・・
c 被控訴人の主張について
(a) 被控訴人は、前記第2の3(3)〔被控訴人の主張〕イ・ウのとおり、 本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人製品「無限七星FIS H」の重量平均分子量4.5×104との比較において、「1500 0」という上限値が技術的にいかなる意義を有するのかが不明であ り、本件優先日において、ポリアリルアミンの重量平均分子量上限値 の「15000」と、公然実施発明に係る同「45000」は、いず れもポリアリルアミンの重量平均分子量として広く知られ、一般的に 利用されている範囲内のものであるから、本件発明は、公然実施発明 に基づいて当業者が当然に予測することができたもので、進歩性を有\nしない旨を主張する。
この点につき、乙13(特開昭58−201811号公報)は、モ ノアリルアミンの重合体の製造方法について記載されたものである ところ、アリル化合物が通常のラジカル系開始剤によっては重合し難 いという問題があったことから、ラジカル系開始剤を用いて、モノア リルアミンの高重合度の重合体を製造する方法を提供することを目 的とするものであり、請求項1に記載の特定のラジカル系開始剤(分 子中にアゾ基とカチオン性の窒素原子を持つ基とを含む。)を用いれ ば、モノアリルアミンの無機酸塩が、極性溶媒中で極めて容易に重合 し、高収率で高重合度の重合体が得られることを見出したものであっ て(特許請求の範囲の記載、2頁左上欄及び3頁左下欄)、実施例に は、乙13記載の製造方法によって製造された数平均分子量(Mn) が「6500〜45000」のポリアリルアミンが記載されている。 しかし、乙13は、ポリアリルアミンを水に含有した際の機能につい\nて、また、数平均分子量の違いによる機能の差異について記載ないし\n示唆するものではないから、乙13の記載から、公然実施発明(引用 発明)の「無限七星FISH」について、含有成分であるポリアリル アミンの重量平均分子量等の物性を変更することが動機付けられる ものとはいえない。
また、乙12の1(メディカル社のウェブサイト)には、「PAA 🄬(ポリアリルアミン)」の製品紹介が記載されており、「日東紡が 世界で初めて工業的製法を確立したポリアリルアミン(PAA🄬)は、 一級アミンを主成分とする機能性カチオンポリマー」であり、「様々\nな素材のカチオン化や高機能化に最適」であることや、「お客様の使\n用目的・用途に応じてのご提案も可能」であることが記載され、「ア\nリルアミン塩酸塩重合体[1級アミン単独、水溶液]」として、重量 平均分子量(M.W.)が「1,600」(PAA−HCL−01)、 「15,000」(PAA−HCL−3L)、「100,000」(P AA−HCL−10L)等の製品が、また、「アリルアミン(フリー) 重合体[1級アミン単独、水溶液]」として、重量平均分子量(M. W.)が「1,600」(PAA−01)、「15,000」(PA A−15C)、「25,000」(PAA−25)等の製品が、それ ぞれ記載されている(1/3−2/3頁)。 また、乙12の2には、メディカル社の研究・開発の歴史について 記載され、「PAA🄬」に関して、「1984(昭和59)年 PA A🄬の(ポリアリルアミン)の重合方法発明および販売開始」、「1 991年(平成3)年 低分子PAA🄬を直接染料用固着剤として用 途開発・販売開始」等の記載がある。 しかし、乙12の1及び乙12の2も、ポリアリルアミンを水に含 有した際の機能や、重量平均分子量の違いによる機能\の差異について 記載ないし示唆するものではないから、乙12の1の記載から、公然 実施発明(引用発明)の「無限七星FISH」について、含有成分で あるポリアリルアミンの重量平均分子量等の物性を変更することを 動機付けられるものとはいえない。
そうすると、乙13、乙12の1及び乙12の2の各記載を考慮し ても、前記公然実施発明(公然実施品)の構成又は組成について、技\n術的思想や課題を認識できるような、本件優先日当時の技術常識があ ったとはいえないから、たとえ、重量平均分子量が「15000」又 は「45000」であるポリアリルアミンが市販されたものであり、 当業者に広く知られ、一般的に利用されているものであったとして も、そのことを根拠に、当業者が公然実施発明のポリアリルアミンの 重量平均分子量等の物性を変更することを当然に予測できるとはい\nえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(b) 被控訴人は、前記第2の3(3)〔被控訴人の主張〕エのとおり、本件 明細書にはポリアリルアミンの重量平均分子量につき本件訂正に係 る数値範囲は記載されていないから、当該数値範囲に特別な技術的意 義は認められず、本件明細書には重量平均分子量と発明の効果との間 に因果関係があることも記載されていないから、市販品として容易に 入手可能な重量平均分子量のポリアリルアミンを採用することに困\n難性はなく本件発明は進歩性を有しないと主張する。
そこで本件発明の技術的意義について検討すると、前記アのとお り、本件明細書には、簡便に調製でき、且つ優れた機能を有する機能\ 水を提供することを課題とし(段落【0002】ないし【0010】)、 当該課題を解決するために、機能水に、式(3)(式(3’)を包含\nする。)で表される不飽和アミンに由来する構\造単位を含むポリマー 等の多価アミン及び/又はその塩を機能成分として含有することを\n特徴とし、当該機能成分の機能\として、魚介類又は精肉の鮮度保持を 含む種々の機能を有することが開示されている(段落【0012】、\n【0013】、【0015】及び【0026】)。
また、式(3)で表される不飽和アミンに由来する構\造単位を含む ポリマーとして、本件発明のポリアリルアミン又はジアリルアミン重 合体に該当するポリマーBが例示されており、その重量平均分子量が 「例えば100〜200,000、好ましくは300〜100,00 0、さらに好ましくは500〜50,000である」こと(段落【0 052】ないし【0055】)、ポリマーBの市販品として、重量平 均分子量が「1600」であるポリアリルアミン(PAA−01)、 「15,000」であるポリアリルアミン(PAA−15C)及び「5, 000」であるジアリルアミン重合体(PAS−21)が開示されて いる(段落【0065】)。
そして、実施例において、具体的に、重量平均分子量が「1600」 若しくは「15,000」であるポリアリルアミン又は重量平均分子 量が「5,000」であるジアリルアミン重合体及び精製水を配合し た試験液を用いて、魚介類又は精肉の鮮度保持を含む種々の機能を確\n認したことが開示されている(段落【0108】ないし【0237】)。 そうすると、本件明細書の記載から、「重量平均分子量500〜1 5000」のポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体を含有する 機能水である本件発明には、前記のとおりの機能\を有する点で技術的 意義があることが認められる。
そして、前記(a)のとおり、公然実施発明(引用発明)に基づいて、 その含有成分であるポリアリルアミンの組成に着目し、重量平均分子 量等の物性をあえて変更することについて動機付けがあるとはいえ ないから、前記本件発明との相違に係る重量平均分子量の数値範囲の ものに置換することが容易に想到できたものとはいえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.04.22
令和5(行ケ)10095 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年3月11日 知的財産高等裁判所
2 色彩のみからなる商標と商標法3条2項等について
(1) 平成26年法律第36号による改正(以下「平成26年改正」という。) 前の商標法2条1項は、「商標」の定義として、「文字、図形、記号若しく は立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と規定して おり、文字、図形等と結合していない色彩のみの商標は商標法の保護の対象 外であった。しかし、色彩のみや音といった「新しい商標」を保護対象とす る諸外国の状況もあり、企業のブランド戦略の多様化が進む中で、我が国に おいてもこうした「新しい商標」の保護ニーズが高まることとなり、平成2 6年改正により、色彩のみからなる商標が商標法の保護対象として認められ ることとなった。
しかし、色彩は商品等に自ずと付随する特性という一面を不可避的に有す るところ、通常はこうした商品特性にすぎない色彩が自他商品役務識別力を 有するといえるためには、使用による識別力の獲得その他の特段の事情が必 要になると解される。この点について平成26年改正は何ら触れておらず、 商標法3条1項3号、6号、同条2項等の解釈・適用に(すなわち、色彩以 外の商品特性と同じ土俵での議論に)ゆだねている。その意味で、平成26 年改正は、色彩商標に係る識別力獲得について例外的な取扱いを定めたもの ではないが、同改正の背景に、企業の多様なブランド戦略を支援しようとい う観点があったことを踏まえ、そのような立法趣旨が損なわれないような解 釈運用が求められていると解される。
(2) このような観点から、本願商標の特徴を具体的に検討するに、本願商標は、 別紙商標目録記載のとおり、橙色(RGBの組合せ:R221、G103、 B44)と茶色(RGBの組合せ:R94、G55、B45)の色彩の組合 せからなり、箱全体において橙色、上部周囲に茶色とする構成からなるもの\nである。
願書の商標の詳細な説明の記載に照らすと、本願商標は、全体が橙色の 「箱」状の物品を想定して、その「上部周囲」(上面と側面が接合するライ ンを指すものと理解される。)に沿って、輪郭を縁取るように茶色が付され ている構成からなるものと理解され、その意味で、立体的形状と色彩の結合\n商標類似の要素も含まれているといえる。もちろん、同説明中に「商標見本 における破線は、箱の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素\nではない」と明記されていることから、本来的な意味での立体的形状と色彩 の結合商標ではなく、分類としては「色彩の組合せのみからなる商標」であ ることに変わりはないと解されるが、本願商標が「『立体的形状と色彩の結 合商標』類似の要素も含まれている『色彩の組合せのみからなる』商標」と いう特徴を有することを正しく理解し、その特徴に即応した判断が求められ るというべきである。
(3) 被告は、本願商標の橙色と茶色の色彩、組合せ及び色彩の付される位置は いずれもありふれたものであり、これに近似する表示全般を本願商標と見分\nけることは困難である、本願商標に近似する色彩は、様々な商品の包装箱に おいて多数の事業者によって使用されている実情がある(包装箱等の色彩に 関する被告提示事例)、などと主張する。
確かに、橙色と茶色は同系色で、ファッションの分野でも橙色と相性がよ く合わせやすい色とされている(乙16)と認められるほか、色彩のわずか な違い程度であれば、近似色との識別が困難な場合があること等は、被告の 主張するとおりといえる。
しかし、本願商標は、より商標登録のハードルが高いと考えられる単一色 の色彩商標と異なることはもとより、単なる橙色と茶色の組合せをもって特 定されるものでもなく、上記(2)で述べたとおり、箱全体の橙色とその上部 輪郭を縁取るように付された茶色を組み合わせた特有の構成を有するもので\nある。このような構成は、RGB比率の絶妙なバランスと相まって、明るい\n橙色と落ち着いた茶色のコントラストを通じて橙色の華やかさを強調し、茶 色の縁取りが箱の輪郭のシャープさを印象付けるものであり、特に、茶色を あえて上部周囲だけに使用するにとどめたことで、シンプルな中に気品を感 じさせる構成になっているといえる。これを単純な「ありふれた色彩の組合\nせ」というのは、適切な理解とはいえない。 また、被告は、本願商標が「ありふれた色彩の組合せ」にすぎないと評価 する根拠の一つとして、包装箱等の色彩に関する被告提示事例を挙げている が、この点の被告の主張を採用できないことは、後記5(1)に詳述するとお りである。
・・・
4 本願商標の使用による自他商品役務識別力の獲得について
(1) 前記3の認定事実によれば、原告が展開する「エルメス」ブランドは、我 が国においても相当の長期間にわたる直営店等での商品の販売や公式ウェブ サイトその他のウェブサイト、全国紙、駅構内や百貨店での屋外掲示、原告\nの店舗内外のディスプレイ等における広告宣伝により、著名なものとなって いると認められる。その著名の程度は、我が国における歴史の長さ、圧倒的 な販売実績、一般消費者への露出の多い活発な広告宣伝等を通じて、あるゆ るファッションブランドの中でもトップクラスの地位にあると解される。 また、「エルメス」ブランドの商品の販売時には本願商標を付した本件包 装箱(通称オレンジボックス)が用いられ、「エルメス」ブランドの広告宣 伝においても本件包装箱やその配色をデザイン化したものが意識的・戦略的 に用いられている。
以上の認定に弁論の全趣旨を総合すれば、本件包装箱、ひいては本願商標 は、原告のブランド戦略に明確に位置づけられた「エルメス」の象徴として 用いられているものと認められる。そして、このような本件包装箱の使用及 び宣伝広告を通じて、少なくとも、「エルメス」のような高級ファッション ブランド商品の購入者やこれに関心を有する消費者の間では、本願商標を付 した本件包装箱(オレンジボックス)は、原告の展開する「エルメス」ブラ ンドに係るものであるとの認識が広く浸透しているものと認められる。
(2) しかし、本願の指定商品及び指定役務は別紙商標目録のとおり多岐にわた り、その中には第3類の革用クリーム、第14類の時計、キーホルダー、第 16類の紙製箱等、文房具類、日記帳、写真立て、第18類のリュックサッ ク、カード入れ、傘のように、安価な日用品として取引されることが少なく ないものが含まれているから、その需要者は広く消費者一般であると解する のが相当であり、「エルメス」のような高級ファッションブランド商品の購 入者やこれに関心を有する消費者に限られないというべきである。 そのような一般消費者を基準に考えた場合、「エルメス」ブランド自体は 広く知られているにしても、これを認識させる具体的な標章としては、著名 な「HERMES」の文字商標や馬車と人を描いた図形商標である可能性も\nあり、これら文字商標や図形商標を離れて、色彩商標である本願商標それ自 体から「エルメス」ブランドを認識できるようになっているとまで、直ちに 認めることはできない。
・・・
(6) 小括
以上に述べたところを要約すると、第1に、本件包装箱の使用及び宣伝広 告を通じて、少なくとも、「エルメス」のような高級ファッションブランド 商品の購入者やこれに関心を有する消費者の間では、本願商標を付した本件 包装箱(オレンジボックス)は、原告の展開する「エルメス」に係るもので あるとの認識が広く浸透しているものと認められるが、本願の指定商品及び 指定役務に照らすと、本願商標の需要者としては一般消費者を想定すべきで あり、そうした需要者を基準に考えた場合、本願商標それ自体から「エルメ ス」ブランドを認識できるに至っていると即断することはできない。本件各 アンケート調査の結果も、この点の認定証拠として不適当である。第2に、 本願の指定商品のうち第3類の香料及び第16類の紙製箱等並びにこれらの 商品に係る第35類の小売等役務については、本願商標の使用の事実が認め られず、これら指定商品・役務について、本願商標の使用による自他商品役 務識別力の獲得を認めることはできない。 したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告主張の取消事 由は認められないことに帰する。本件審決が、指定商品との関係で商標法3 条1項3号該当性を認めた上同条2項の適用を否定した判断、指定役務との 関係で同条1項6号該当性を認めた判断に誤りはない。
5 その他の論点について
以下は、本件訴訟の帰趨に影響を及ぼすものではないが、包装箱等の色彩に 関する被告提示事例の評価及び独占適応性の問題について、当裁判所の考えを 示しておく。
(1) 包装箱等の色彩に関する被告提示事例の評価について
ア 商品の包装箱等についての取引の実情として、別紙2「商品の包装箱等 についての色彩の事例」にある包装箱等が、原告以外の事業者によって製 造、販売されていることが認められる。
イ そこで、被告提示事例を個別に検討するに、事例イ(イ)(乙39)、事 例イ(ウ)(乙40)及び事例ウ(ア)(乙50、51)は、本願商標の色彩 及びその配色の特徴が比較的類似していると解されるが、このうち、事 例イ(ウ)及び事例ウ(ア)は、本願の指定商品及び指定役務と異なる洋菓子 (キャラメル、パイ)の包装箱に関するものである上、証拠(甲170、 171)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、事例イ(ウ)の商品は原告の 知的財産権を侵害するものであるとして、警告書を送付して相手方事業 者と交渉したところ、相手方事業者は、令和5年10月までに、当該商 品の展示販売を中止するとともに、「本件色彩(箱全体に橙色、上部周 囲に茶色の色彩)がエルメスの商品及び役務を示す表示として広く認識\nされていることを理解し、今後は本件商品(本件色彩と類似する色彩を 付したギフト箱)及び本件色彩と類似の色彩を付したギフト箱を展示販 売しないことを誓約いたします」との誓約書を原告に差し入れたこと、 原告は、これ以外にも、侵害品と判断した商品を発見した場合、同様の 対応をしており、警告書の送付を行うケースは年間30〜40件程度あ ること、事例イ(イ)についても、対応を検討中であることが認められる。 これに対し、被告は、事例イ(ウ)の商品につき、販売中止の理由は明ら かでなく、これを模倣品とみるべき根拠はない旨主張するが、当該商品 の形態及び上記誓約書の文言を総合すれば、相手方事業者は、当該商品 の製造販売が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たることを自 認して販売を中止したものと推認できる。
そうすると、このような侵害品が市場に存在するとの事実は、本願商 標の色彩及びその配色の特徴がありふれたものであることを根拠づける ものではなく、むしろ、本件包装箱(本願商標)の色彩及びその配色の 特徴が高い顧客吸引力を有することを示唆するものといえる。
ウ 包装箱等の色彩に関する被告提示事例のうち、上記イで触れたもの以外 の事例は、本願商標の特徴である茶色の縁取りが全くないか、その範囲 が本願商標と異なり、「上部周囲」以外にも及んでいるようなものであ って(本願商標が茶色をあえて上部周囲だけに使用していることは上述 のとおりであり、その違いは全体の印象に大きく影響する。)、本願商 標の色彩及びその配色がありふれたものであることを根拠づけるものと はいえない。
この点に関し、被告は、商標の類否は離隔的観察を前提とすべきこと からすれば、箱の大部分に橙色、縁等にわずかに茶又は近似する色が使 用されているものも、本願商標と見分けることは困難であると主張する。 しかし、この主張は、前記2(2)で述べた本願商標の特徴を的確に踏まえ たものといえない上、本願商標の使用、宣伝広告等を通じて需要者の認 識が変化することも踏まえて検討すべきものであって、一概に被告主張 のように決めつけることはできないというべきである。
(2) 独占適応性の問題について
被告は、本願商標の登録を認めた場合、多数の事業者によって広く使用さ れている色彩について、本願商標に類似すると判断され得る使用態様が事実 上制限されることになり、ファッション分野を中心に、色彩使用の自由が著 しく制限され、他の事業者に著しい委縮効果を及ぼすことになる旨主張する。
しかし、まず、本願商標は、単なる橙色と茶色の組合せをもって特定され るものではなく、箱全体の橙色とその上部輪郭を縁取るように付された茶色 を組み合わせた特有の構成を有するものであって、その商標登録を認めたか\nらといって、単純に色彩の独占がもたらされるわけではないし、このような 特有の構成を備えた色彩の組合せが多数の事業者によって広く使用されてい\nるという取引の実情が認められるわけでもない(上記(1)参照)。また、仮 に本願商標の登録が認められたとしても、これに類似すると判断される使用 態様は、実際上、不正競争防止法2条1項1号の不正競争にも当たる場合が 少なくないと解され(被告提示事例イ(ウ)の販売中止の経緯参照)、その委 縮効果を過大に評価すべきでない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2024.04.17
令和5(行ケ)10034 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月27日 知的財産高等裁判所
(2) 甲53の1文書について
ア 甲53の1文書は、ベルベット織りの立毛シートの製造工程を示すものとし て交付されたものであり、別紙2のとおり、「「生機投入」→「スチームセット」→ 「ドライセット」→「糊抜き」→「脱水」→「染色」→「脱水」→「乾燥(ブラシ)」 →「ブラシ※ブイテック様」」との工程が記載されている。
イ 「生機投入」の部分により、製織工程と切断工程が開示されているといえる かという点について争いがあるので検討するに、「生機」とは「織り上げて織機から はずしたままの織物」を意味するところ(甲114・大辞林第四版)、ベルベット織 りの織り機は、織ると同時に切断も行うことから一度に2枚分が織り上がるもので あって、「織り機からはずしたままの織物」は、切断後の織物であると認められるか ら(甲40、112)、「生機投入」との記載から、甲53の1文書を受領した当業 者は、当然に、製織工程と切断工程を経た生機が投入されると理解すると認めるの が相当である。そして、甲53の1文書の「生機投入」の使用機器欄に記載された 「ZQ40 4mm」はパイル長4mmのポリエステル製パフ用の立毛シートの生 機の品番を意味するものと認められ(証人C〔28頁〕)、ポリエステルは熱可塑性 繊維であるから(本件明細書【0020】等)、甲53の1文書の「生機投入」工程 の記載により、本件各発明の製織工程と切断工程が開示されていると認められる。
ウ そして、甲53の1文書の「スチームセット」は本件各発明の「蒸し工程」 に、「ドライセット」は本件各発明の「プレセット工程」に、「糊抜き」は本件各発 明の「精練工程」にそれぞれ相当する(証人A〔5〕)。また、「染色」は本件各発明の「染色工程」に相当し、「染色」の次に記載された「脱水」は、真空脱水とあるか ら脱水機を用いたものであることが明らかであって、本件各発明の「脱水機により 前記染料を脱水する脱水工程」に相当する。さらに、「乾燥(ブラシ)」はドライセ ッターで150゜C)で乾燥させるものであるから、本件各発明の「前記立毛シートを 熱風で乾燥させる乾燥工程」に相当する。なお、特許請求の範囲の記載及び本件明 細書の記載を総合しても、本件発明1の乾燥工程から、ブラシを用いるものが除外 されているとは認められない。
エ そうすると、甲53の1文書に記載された工程は、本件発明1を構成する工\n程を全て含むものであるから、本件発明1を開示するものといえる。 オ この点、被告は、甲53の1文書記載の工程では、精練工程の後に脱水をし ていること、タンブラー乾燥をしていないこと、使用液剤に酸性の液剤が含まれて いないこと等から、本件各発明とは異なると主張する。しかしながら、本件発明1 の特許請求の範囲の記載に照らすと、請求項1に記載された工程を全て含む必要が あるとはいえるものの、同工程のみを含むものに限定されており、別の工程が付加 されたものが除外されているものと理解することはできない。そして、本件明細書 の記載に照らしても、本件発明1は、請求項1に記載された工程のみを含むものに 限定されていると理解することはできない。そうすると、「精練工程の後に脱水」を していることをもって本件各発明とは異なるということはできない。また、タンブ ラー乾燥は本件発明3を構成する要素ではあるものの、本件発明1を構\成するもの ではない(なお、前記2(5)(8)のとおり、タンブラーを利用した乾燥工程は、平成 18年頃から新栄染色で行われていたものと認められるが、当時、当該乾燥工程の 存在及び内容が秘密事項として管理されていたことをうがわせるような主張立証は ない。そもそも、甲12(パイル織編物の仕上げ方法に関する公開特許公報(昭6 2−191566号))中にもパイル織物の染色加工後、タンブラー乾燥機で乾燥す る旨の記載があることにも照らすと、本件各発明の出願時において、少なくとも、 熱可塑性繊維のパイル織物についてタンブラーを利用して乾燥する工程自体は公知 であったと考えられる。)。さらに、酸性の液剤を使用することは本件各発明の技術 的範囲に含まれるものではなく、その他の被告の指摘する事項はいずれも本件各発 明を構成する事項ではない。したがって、上記被告の主張はいずれも前記エの判断\nを左右するものではない。 被告は、甲53の1文書の工程は開発途中のものであって技術として確立してい なかったとも主張するが、前記2(9)のとおり、同工程は、平成23年10月頃、新 栄染色において、現に商品の製造に用いられていた工程なのであるから、これが発 明に当たるとすれば、発明として完成していたのは明白である。
(3) 甲2文書について
甲2文書は、前記2(11)のとおり、ベルベット織りによる立毛シートの製造工程 を示すものとして交付されたものであり、別紙3のとおり、「織り」→「蒸しセット」→「PS」→「精練」→「染色」→「乾燥」の各工程が記載されたものである。甲 2文書に記載された工程について前記(2)と同様に検討すると、甲53の1文書に 記載された工程と同じであり、本件発明1を開示するものであると認められる。な お、「織り」が製織工程と切断工程を含むことについては前記(2)イと同様であり、 「PS」はプレセットを意味するものと認められる(証人A〔34頁〕)。また、甲 2文書の工程には「乾燥」の前の「脱水」が記載されていないものの、乾燥する前 に脱水を行うことは当然であるから、当業者は、甲2文書により、脱水工程を含む ものが開示されているものと理解すると認められる。
(4) 小括
そうすると、本件発明1は、平成23年10月頃には公然知られていたと認めら れるから、本件発明1に係る特許は特許法29条1項1号の規定に違反してされた ものであって、特許法123条1項2号の無効理由がある。 したがって、甲2生産工程(甲2文書に記載された工程であり、かつ甲53の1 文書に記載された工程)が公然知られたものとはいえず、本件発明1が特許法29 条1項1号に該当しないとする本件審決の判断には誤りがあるから、取消しを免れ ない。
4 取消事由4(冒認出願についての判断の誤り)について
(1) 冒認出願を理由として無効審判請求をすることができるのは特許を受ける権 利を有する者に限られるから(特許法123条2項、1項6号)、原告は、自らが特 許を受ける権利を有する者であることを証明する必要がある。そして、原告が主張 する本件各発明に係る特許を受ける権利は、Bが発明者として有していた本件各発 明に係る特許を受ける権利に由来するものであるから、原告が特許を受ける権利を 有する者であるといえるためには、Bが本件各発明の発明者であると認められる必 要がある。
(2) ここで、発明者とは、発明の技術的思想の創作行為に現実に加担したもので あって、課題の解決手段に係る発明の特徴的部分の完成に現実に関与した者をいう ところ、前記1(2)によると、本件各発明の特徴的部分は、蒸し工程と乾燥工程の双 方を用いることにより、高い立毛性を得ることにあり、本件発明3については、こ れに加えて、タンブラーを使用することでブラッシング付き乾燥機を要しないもの となったことにあると認められる。
(3) 前記2(9)及び前記3(2)のとおり、本件発明1は平成23年10月までに完 成していたということができる。前記2の経緯及びAが、新栄染色のAとして作成 した平成21年7月1日付け文書(甲128の3)に、「現況のB流を60点とする と80点迄は持っていける」と記載していたことからすると、新栄染色では、平成 21年7月当時、Bが指導した工程により染色加工が行われていたことが認められ、 これに反する証拠はない。そして、前記2のBの職歴や本件訴訟に提出されたBが 作成したメモ(甲132)、Bが、新栄染色設立以前にも昌和染色に対し染色工程を 指導するなどしていたこと(甲1の1、証人C〔29頁〕)に照らすと、Bは、立毛 シートの染色加工に関し、創意工夫を凝らして発明をするに足る十分な知見を有し\nていたことが推認されるのであり、Bが、その陳述書(甲1の1)において、昭和 40年代の後半、プレセットの前に蒸し工程をするという工程を開発した経緯等と して、株式会社杣長からポリエステルなど合成繊維のパフ用ベルベット織物(立毛 シートの半製品)の製造委託を受けたが、ポリエステルでは、シルクやレーヨンと は異なり、ピン式ヒートセッターでピン止めして吊るしてプレセットを行うとピン 付近とそれ以外の部分が不均質になるという問題があったことから、プレセット前 に蒸し工程を行い、ポリエステルを収縮させてからプレセットをしたところ、パイ ルが立毛になるという効果があったこと、蒸しは蒸し箱内にベルベット織物を垂下 させて高温水蒸気で蒸すものであり、Bが条件を90〜110゜C)、2時間と指示し て行ったこと、パイル長が2〜3mmであったことなど、開発の経緯及び内容を具 体的に陳述していることは、これと整合するものである。
また、Bは、昭和50年代から、京都において、日本化工有限会社の従業員とし てハセガワベルベットから委託を受けた染色加工工程に関与し、平成元年に有限会 社新栄テキスタイルを設立した後も、同社において被告から染色加工の委託を受け ていたこと、同年頃までにBが作成したとされるメモ(甲132の2)には、染色、 脱水後の乾燥をタンブラーで行う旨の記載があること、平成18年に、新栄染色が 設立された際、BはAからの誘いにより代表取締役に就任したこと、その頃、Bが\n京都からタンブラー乾燥機を新栄染色に持ち込んで設置したこと、新栄染色におい ても、Bは染色加工業務を担当し、被告代表者であったCに対し、染色加工の具体\n的内容を指導していたことは、前記2(3)から(6)までのとおりである。以上を総合 すると、Bは、遅くとも新栄染色を退職する平成21年3月よりも前に、本件各発 明をいずれも完成させていたものと推認するのが相当である。 なお、被告は、Bの陳述書(甲1の1)にパイル長が2〜3mmであったとある から、Bには短いパイル長のものに係る知見しかなかったと主張するが、本件各発 明の特許請求の範囲(請求項4)には「切断工程後のパイル糸の長さを、織物基布 から3〜10mmの範囲で突出させる」とあるから、パイル長が3mmのものは、 本件各発明の技術的範囲に含まれるものであり、上記被告の主張は、Bが本件各発 明をするに必要な知見を有していたとする上記判断を左右しない。
(4) これに対し、Aは、本件の審判手続における尋問では、本件各発明のキーポ イントは蒸し工程であり、蒸し工程の後にヒートセット(プレセット)を加えるこ とにたどり着いた、長い間、蒸し工程をいれないでやっていた(甲74の3・06 4項目、130項目、131項目、149項目)と述べ、本件訴訟においても、被 告は、令和5年11月8日付け被告準備書面(2)2頁においては、本件各発明をする 前の短いパイル糸のベルベットに関する新栄染色の染色工程には蒸し工程及びプレ セットが含まれておらず、長いパイル糸のベルベットを製造することができなかっ た旨主張し、それに沿う内容のAの陳述書(乙8)を提出した。ところが、被告は、 同年12月19日付け被告準備書面(3)5頁では、本件各発明をする前にも新栄染 色では長いパイル糸のベルベットの製造をしており、その工程には蒸し工程が含ま れていたがプレセットが含まれていなかったと主張を変更し、更に、令和6年1月 22日付け被告準備書面(4)では、短いパイル糸の染色工程にも蒸し工程が含まれ ていたと主張を変更し、変更後の主張に沿う内容のAの陳述書(乙11)を改めて 提出した。この主張内容及び陳述内容の変更は、発明の課題そのものや発明の必要 性、発明の創作過程に極めて大きな影響を与えるものであるから、真にAが発明者 であるのであれば、単なる記憶違いなどによって上記のごとくその内容を変遷させ るとはおよそ考え難い。なお、前記2(6)のとおり、新栄染色では当初は外注により、 遅くとも平成19年からは自社で蒸し工程を実施していたのであるから、新栄染色 が以前は「蒸し工程をしていなかった」との被告の従前の主張は事実とは認められ ない。
さらに、被告の主張によると、従前の新栄染色の染色工程においてはプレセット を行っていなかったことになるが、Aが述べる試行錯誤の内容は、プレセットにつ いては、それを行う順番を試行錯誤したというものであって、プレセットを入れる こととした理由については何ら説明をしていない。このことは、当時、既にプレセ ット工程自体は存在しており、Aは専らその工程の順番について試行錯誤していた ことをうかがわせるものである。また、Aが蒸し工程について試行錯誤した内容と して述べる条件は、「90゜C)の蒸気で、0分、30分、60分、120分」と試した というものであって、「95〜110゜C)で2〜3時間蒸す」(【0022】)という本 件明細書の記載と合致しない。Aは、本件の審判手続の尋問において、自ら発明ノ ートを作成したことはないことを前提とした発言をしているが(甲74の3・13 5項目)、これは試行錯誤を繰り返していたはずの発明者としておよそ不自然とい うほかない。
被告は、本件各発明においては乾燥工程にタンブラー乾燥機を用いることが重要 である旨主張する。しかし、前記2(5)(8)のとおり、新栄染色には、平成18年頃 から既にタンブラー乾燥機が設置されており、平成23年頃にはその台数が3台に 増加していたことが認められる。Bらが作成し、平成21年8月20日に被告大阪 営業所からFAX送信されたものと認められるメモ(甲106)によっても、遅く とも同日までには、新栄染色では、乾燥工程にタンブラー乾燥機を用いていたこと がうかがえる。前記2(10)のとおり、A自身が作成した平成24年1月10日付け メモ(甲100の3)にも、新栄染色に関し、タンブラー方式はコストが高いこと から平成24年中旬にテンター方式へ変更する旨の記載がある。これらの点に照ら すと、遅くとも、平成24年までには、ベルベット織物の製造分野において乾燥工 程にタンブラー乾燥機を利用することは普通に行われていたと認めるのが相当であ るから、本件各発明において創作されたものとは認められない。Aは、中和剤を用 いることで精練工程の後の脱水工程を省略し、ウィンス機で精練工程と染色工程が できるようになったと証言しているが(証人A〔6頁〕)、そもそも中和剤を用いる ことは本件各発明の特許請求の範囲に記載された事項ではなく、本件明細書には「ウ ィンス機を使用して、」「立毛シートを処理液(例えば、アルカリ剤、非イオン活性 剤)中に順次送り込んで洗浄する」(【0024】)との記載があるものの、中和剤を 用いることで脱水工程を省略することができる旨の記載はないから、結局、上記A の証言は、それが発明について述べたものだとしても、本件各発明とは関係のない 別の発明について述べるものにすぎない。Aは、小型、大型、中型のタンブラーで 試し、中型のタンブラーを用いることで目的を達成することができたとも証言して いるが(証人A〔9頁〕)、本件発明3の特許請求の範囲にはタンブラーの大きさに ついての言及はなく、本件明細書の記載を考慮しても、「タンブラー」の大きさは不 明であり、特許請求の範囲に記載された「タンブラー」が「中型のタンブラー」で あり、タンブラーの大きさが何らかの技術的意義を有するものであると解すること ができるような記載もない。
以上を総合すると、Aが染色工程につき様々な工夫をしたことがあったとしても、 いずれも本件各発明に係る特許請求の範囲の内容に含まれるものではないから、本 件各発明の発明者がAであるとの被告の主張を採用することはできない。他にBが 平成21年3月よりも前に本件各発明をいずれも完成させていた旨の前記認定を覆 すに足りる主張立証はない。
(5) したがって、本件各発明に係る発明者はBであると認めるのが相当であるか ら、本件の出願は冒認出願に当たり、本件特許には特許法123条1項6号の無効 理由がある。また、原告は、Bから特許を受ける権利の一部について譲渡を受け(甲 16)、残部はBの相続人の全員が相続放棄したことにより原告に帰属したから(甲 110、111)、本件各発明に係る特許を受ける権利を有する。 よって、本件特許について冒認出願の無効理由がないとした本件審決の判断には 誤りがある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2024.04.17
令和5(行ケ)10131 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年3月27日 知的財産高等裁判所
(1) 商標法4条1項16号について
商標法4条1項16号の趣旨は、商標を構成する文字、図形等が直接的に\n特定の商品の特性を表示したものであるため、当該商標が特定の商品以外の\n商品に使用された場合に、取引者、需要者が商品の品質を誤認して、商品を 購入することがないように取引者、需要者の保護を図ることにある。取引者 又は需要者において、本願商標の構成から将来を含め一般に認識される特性\nを有する特定の商品と指定商品とが関連し、かつ、本願商標が表示している\n特定の商品の特性と指定商品が有する特性が異なるため、本願商標を指定商 品に使用した場合に、本願商標が使用された「商品の品質の誤認を生ずるお それ」があることになる。
(2) 本願商標について
ア 本願商標は、「hololive Indonesia」の文字を標準 文字で表してなるものであり、「hololive」の文字と「Indo\nnesia」の文字との間には、1文字分の空白があり、「hololi ve」の文字と「Indonesia」の文字を組み合わせたものと理解 される。 「hololive」の文字は辞書に載っていない造語であり、自他商 品の識別力を有するものである。「Indonesia」の部分は、我が 国における英語ないしローマ字の普及度からみて、需要者において、「イ ンドネシア」と読むこと、「東南アジア群島部にある共和国」(乙1)で あるインドネシアを欧文表記したものであることが容易に理解できるも\nのと認められる。 そして、我が国において、国名としてのインドネシアは広く知られてい る(乙2〜4)。
イ 各種ウェブサイトによれば、自他商品又は自他役務の識別力を有する文 字と、「インドネシア」あるいは「Indonesia」の文字を組み合 わせたものとして、「(Zalora Indonesia ザローラ・ インドネシア)」(乙8、ファッション)、「(Reebonz Ind onesia リーボンツ・インドネシア)」(乙8、主にバッグ、靴、 ジュエリー)、「(Ree Indonesia リー・インドネシア)」 (乙8、インドネシアのデザイナーが製作した衣料ブランドを取り扱う。)、 「マクドナルドインドネシア」(乙9、ファストフード)、「丸亀インド ネシア」(乙10、うどん)がある。そして、これらは、いずれも、イン ドネシアで生産される物又はインドネシアで提供される役務に関するも のである。
ウ 本願の指定商品及び指定役務には、例えば、第3類「化粧品」「香料」、 第9類「スマートフォン用ストラップ」「コンピュータ用ゲームソフトウ\nェア(記憶されたもの)」「コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通\n信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」「眼鏡の部品及び 附属品」、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」「キ ーホルダー」「身飾品」「時計」、第16類「文房具類」、第18類「か ばん類」「傘」、第21類「貯金箱」「お守り」、第24類「布製身の回 り品」「布団」、第25類「被服」「履物」、第26類「頭飾品」、第3 5類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す る便益の提供」「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供」「楽器及びレコードの小売又は卸 売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第41類「電子出 版物の提供」「インターネットを利用して行う映像の提供、映画の上映・ 制作又は配給、オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないもの に限る。)」「ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配\n給、映画の演出(広告用映画の演出を除く。)」「オンラインによるゲー ムの提供」及び第43類「飲食物の提供」等、一般消費者が需要者となる ものが含まれている。
各種ウェブサイトには、これらの指定商品又は指定役務に対応する商品 又は役務であって、インドネシアで生産等されたもの、あるいはインドネ シアに由来するものとして、例えば、化粧品、香水(乙31)、香油(乙 35)、携帯ストラップ(乙38)、コンピュータゲーム(乙32、36)、 眼鏡スタンド(乙37)、宝石(乙39)、キーホルダー(乙24)、宝 飾品(乙28)、時計(乙29)、ペンケース(乙27)、かごバッグ(乙 26)、傘(乙40)、貯金箱(乙43)、お守り石(乙41)、ブラン ケット、タペストリー、テーブルクロス(乙30)、布製インテリア(乙 42)、クッションカバー(乙44)、被服(乙25)、パンプス(乙4 6)、ヘアアクセサリー(乙47)、電気敷毛布(乙45)、置物(乙4 9)、楽器(乙48)、インドネシア制作の映画(乙34)、インドネシ ア料理(乙33)等が、我が国で販売ないし提供されていることが示され ている。
エ 以上のとおり、1)本願商標のうち「hololive」の部分は造語で あり自他商品又は自他役務の識別力を有するのに対し、「Indones ia」の部分は、一般に知られた東南アジアの共和国であるインドネシア を意味することは需要者において容易に理解できること、2)自他商品又は 自他役務の識別力を有する文字と、「インドネシア」あるいは「Indo nesia」の文字を組み合わせたものがインドネシアで生産される物又 はインドネシアで提供される役務に関して使用されていること、3)本願の 指定商品及び指定役務には一般消費者が需要者となるものが含まれ、これ に対応する商品又は役務でインドネシアで生産等されたもの、ないしはイ ンドネシアに由来するものが我が国で販売ないし提供されていることが 認められるのであって、そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役 務について使用するときは、これに接する需要者は、その構成中の「In\ndonesia」の文字から、インドネシアで生産又は販売された商品や、 インドネシアに関する役務といった商品の品質又は役務の質を通常理解 するものというべきである。 一方、本願の指定商品及び指定役務は、インドネシアに関するものに限 定されていないから、インドネシアで生産又は販売された商品以外の商品 やインドネシアに関する役務以外の役務も含むことになる。 以上によると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、インドネシア で生産又は販売された商品以外の商品や、インドネシアに関する役務以外 の役務に使用した場合には、商品又は役務の質の誤認を生じさせるおそれ があるから、本願商標は、商標法4条1項16号に該当するというべきで ある。
(3) 原告の主張について
ア 原告は、本願商標の使用に係る指定商品及び指定役務は、バーチャルア イドルであるVTuberグループ関連の商品及び役務、いわゆるキャラ クターグッズ等であり、当該グループ又はその構成員キャラクターのファ\nン以外の者が、本願商標を構成する「Indonesia」の文字が前記\nグループ及びキャラクターの活動拠点であることを知らずに、「インドネ シアで生産された商品」あるいは「インドネシアに関連する役務」等と認 識して購入することは考えられず、本願商標の使用に係る指定商品及び指 定役務は、原告のウェブサイトを中心に提供されていることからも、上記 ファン以外の者が本願商標に触れることは考えにくい旨主張する。 しかし、本願商標の指定商品及び指定役務の需要者はVTuberグ ループのファンに限られるものではなく、また、原告の主張からしても、 原告のウェブサイトのみでこれらの商品が提供されているわけではない のであって、原告の主張は採用できない。
イ 原告は、本願商標は、仮想的アイドルグループの名称として使用され、 かつ、当該仮想的アイドルグループ関連の商品及び役務に使用されるもの であるところ、地域的名称を含む芸能人グループの名称の使用に係る商品\n等において、当該地域的名称は、当該商品の生産地等とは認識され得ない 旨主張する。 しかし、一般需要者において、本願商標が芸能人グループの名称である\nと認識するような事情は認められず、原告の主張は前提を欠くものである。
ウ 原告は、YouTubeにおける「hololive」、「holol ive Indonesia」及び「hololive Indones ia」に属する個々のVTuberのチャンネルの登録者は延べ806万 人以上になるから(甲14〜24)、本願商標は原告のVTuberのア バターであるキャラクターのグループ名称を表すものとして需要者に広\nく認識されている旨主張する。
しかし、「hololive」のチャンネルの登録者は185万人である (甲14)ものの、その他の各チャンネル(甲15〜24)については、映 像等の多くが欧文字で投稿されていることから、登録者のうちどの程度が 日本の需要者であるのかの裏付けはないというべきで、「hololiv e」、「hololive Indonesia」が原告のVTuberの アバターであるキャラクターのグループ名称を表すものとして我が国の需\n要者に広く認識されていると認めることはできない。
エ 原告は、商標に国名が含まれる場合に直ちに誤認混同を生じると認定す る国は日本のみであり、不当である旨主張する。 しかし、本件審決は、商標に「Indonesia」の文字が含まれるこ との一事をもって本願商標が商標法4条1項16号に該当すると認めたわ けではなく、本願の指定商品及び指定役務に係る需要者の範囲とその認識 等について個別に検討・判断しているところ、その判断手法は相当である から、原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.04.17
令和5(行ケ)10068 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年3月27日 知的財産高等裁判所
別紙登録商標目録記載のとおり、本件商標は、「O」、「!」、「O」、「i」、 「M」、「A」、「I」及び「N」の各文字又は符号を同じ書体(やや斜字のゴシ ック体様の黒の書体)、同じ大きさ及び等しい間隔で一連に横書きしてなるもので あり、これらの文字又は符号は、まとまりよく一体的に構成されている。もっとも、\nその中の「M」、「A」、「I」及び「N」の各文字は、「主要な」等の意味を有 し、我が国において日常的に広く用いられる「メイン」の語に相当する英単語であ る「MAIN」の語を構成するものであるから、この「MAIN」の語は、ひとま\nとまりの単語として強く認識されるというべきである。
(ウ) O!Oi部分
「O!Oi」が辞書等に搭載された語であり、又は一般的に用いられている語で あると認めるに足りる証拠はないから、O!Oi部分は、特定の意味合いを有しな い一種の造語であり、それゆえに、平易な英単語のみからなるMAIN部分との対 比において視覚的に目立つものである。そして、前記(ア)のとおり、被告が代表者\nを務めるファインドフォーム社は、その製品に「OIOI」、「OiOi」、 「O!Oi」等の標章を付して販売するなどしている。このような取引の実情(な お、「OIOI」又は「OiOi」の標章と「O!Oi」の標章とが変わりのない ものと理解し得ることについては、後記ウ(ア)のとおりである。)を併せ考慮する と、O!Oi部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識としての印象を強 く与えるものであると認めるのが相当である。
(エ) MAIN部分
「MAIN」の語は、前記(イ)のとおり、「主要な」等という意味を有する英単 語であり、かつ、それが多くの場合、形容詞として他の語を修飾するために広く用 いられている語であることは、公知の事実である。「O!Oi」の語が特定の意味 合いを有しない一種の造語であり、視覚的に目立つものであって(前記(ウ))、前 記(ア)の取引の実情において商品の出所識別標識としての印象を強く与えるような 形で使用されているのに対し、「MAIN」の語については、そのような事情は見 当たらない。すなわち、MAIN部分は、「MAIN」の語の通常の意味に照らし ても、取引の実情においても、商品の出所識別標識としての印象は、O!Oi部分 が与えるそれと比較して、相当程度に弱いというべきである。
(オ) 本件商標の分離観察の可否についての小括
以上によると、本件商標のO!Oi部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識 別標識として強く支配的な印象を与えるといえ、前記(イ)の本件商標の構成を考慮\nしても、本件商標の各構成部分(O!Oi部分及びMAIN部分)は、それらを分\n離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合してい ると認められないから、本件商標については、その構成部分の一部であるO!Oi\n部分を抽出し、O!Oi部分だけを各引用商標と比較して商標の類否を判断するこ とも許されると解するのが相当である。
ウ 本件商標のO!Oi部分と引用商標3の類否 事案に鑑み、本件商標との類否判断の対象として、引用商標3を取り上げる。
(ア) 外観
別紙登録商標目録記載のとおり、本件商標のO!Oi部分は、「O」、「!」、 「O」及び「i」の各文字又は符号を同じ書体(やや斜字のゴシック体様の黒の書 体)、同じ大きさ及び等しい間隔で一連に横書きしてなるものであり、これらの文 字又は符号は、まとまりよく一体的に構成されている。\n別紙引用商標目録記載3のとおり、引用商標3は、「〇」、「|」、「〇」及び 「|」の各記号を同じ書体(ゴシック体様の赤の書体)、同じ大きさ及び等しい間 隔で一連に横書きしてなるものであり、これらの記号は、まとまりよく一体的に構\n成されている。
ここで、引用商標3の「|」の記号は、「I」の文字を図案化したものとして、 両者は実質的には変わりのないものとの印象を与え得るものであり、また、「I」 の文字と「i」の文字は、互いにアルファベットの大文字・小文字の関係にあるに すぎないから、これらも、実質的には変わりのないものと理解され得るといえる。 さらに、証拠(甲65〜77)及び弁論の全趣旨によると、企業名、ブランド名、 サービス名、芸名等を表すロゴや文字列の中で、「I」の文字又は「i」の文字に\n代えて「!」の符号又は縦若しくは斜めの棒状の図形の下部に「●」、「■」、 「★」等の図形を配した記号を用いる例が多数あるものと認められ、「!」の符号 も、アルファベットの文字列の中に配されたときは、「I」の文字又は「i」の文 字と変わりのない文字であると理解され得るものである。加えて、「〇」の記号も、 「O」の文字を図案化したものとして、両者は実質的には変わりのないものとの印 象を与え得ること、前記説示したところを踏まえると、その取引者、需要者からみ れば、本件商標のO!Oi部分と引用商標3の字体の相違(色彩の相違を含む。) が類否判断に当たって大きな意味合いを有するものとは認め難いことを併せ考慮す ると、取引者、需要者は、本件商標のO!Oi部分を見た場合、これが「〇|〇|」 と実質的には変わりのないものを指すと理解し得るということができるから、本件 商標のO!Oi部分の構成と引用商標3の構\成との間に厳密には前記のような相違 があるとしても、隔離観察を前提とすると、両者は、外観上極めて相紛らわしいも のであると認めるのが相当である。 被告は、「F!T」等の文字列の場合と異なり、「O!Oi」の文字列について は、「!」の符号を「I」の文字等に置換して認識すべきことが強く示唆されてい ないなどと主張するが、迅速を貴ぶ商取引において、アルファベットの文字列の中 に配された「!」の符号は、その形状(縦棒上の図形とその下部に小さく点様の図 形を配してなるもの)に照らし、当該文字列からの示唆の大小にかかわらず、「I」 の文字等と変わりのないものと理解され得るというべきである。被告の主張を採用 することはできない。
(イ) 称呼
本件商標のO!Oi部分は、途中に感嘆符を含む一種の造語であるが、証拠(甲 37〜41、45、52〜54、56、58)及び弁論の全趣旨によると、O!O i部分からは、「オーアイオーアイ」又は「オアイオアイ」の称呼が生じるものと 一応認められる。 別紙引用商標目録記載3及び別紙ハウスマーク目録記載のとおり、引用商標3は、 原告標章と外観上同一視し得る形状のものであるところ、前記1のとおり、原告標 章が原告らのロゴマークとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであ ることからすると、引用商標3からは、「マルイ」の称呼が生ずるものと認めるの が相当である(この点は、当事者間に争いがない。)。そして、本件商標のO!O i部分と引用商標3とが、前記のとおり、外観上極めて相紛らわしいことを踏まえ ると、O!Oi部分についても「マルイ」の称呼が生じ得るというべきである。
(ウ) 観念
本件商標のO!Oi部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語である。 別紙引用商標目録記載3及び別紙ハウスマーク目録記載のとおり、引用商標3は、 原告標章と外観上同一視し得る形状のものであるところ、前記1のとおり、原告標 章が原告らのロゴマークとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであ ることからすると、引用商標3からは、「丸井又はマルイのロゴマーク」などの観 念が生ずるものと認めるのが相当である(この点は、当事者間に争いがない。)。 そうすると、本件商標のO!Oi部分が特定の意味合いを有しないとしても、同部 分は引用商標3と外観上極めて相紛らわしいから、同部分からは、引用商標3と同 様の観念が生じ得るものということができる。
(エ) 検討
以上のとおり、本件商標のO!Oi部分と引用商標3は、外観、称呼及び観念の 点で極めて相紛らわしいものであり、加えて、前記1のとおり、引用商標3と外観 上同一視し得る形状を有する原告標章が原告らのロゴマークとして取引者、需要者 の間に広く認識されていることなどを併せ考慮すると、本件商標のO!Oi部分と 引用商標3については、両者が同一の商品又は役務について使用された場合、その 商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるものと認めるのが相当で ある。したがって、本件商標のO!Oi部分と引用商標3は、取引の実情に基づき、 外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し て全体的に考察すると、互いに類似するものと認められる。
◆判決本文
関連です。
こちらは商標「5252byO!Oi」と「OIOI」の類否です。こちらも商標類似と判断されました。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2024.04.14
令和5(ワ)3375 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月21日 大阪地方裁判所
前記(ア)のとおり、構成要件B2は、「縦板部」について、「庇板の開放された\n前端面に当接され」ていることと「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」 こととをいずれも備える旨規定している。当該当接部分と、「前面が雨水を下方へ 導くガイド面となっている」部分との位置関係については、構成要件B2の文言か\nらは一義的には明らかでないものの、本件明細書において、前記(イ)のように、本 件発明が、庇の全長が必要以上に長くなるなどの従来の庇の問題に着目して小型化 と構造の簡易化を実現し、保守、点検に手数を要さない庇を提供することを目的と\nしていること、その問題を解決するための手段として、前縁板は、「庇板の開放さ れた前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている縦板部」と、 「庇板の上面に当接され上面が雨水を縦板部のガイド面へ導くガイド面となってい る横板部」とが一体に形成されて成り、前記縦板部の下部内面には凹部が形成され るとの構成が示されていること、当該構\成において、庇板の上面に溜まった雨水は、 庇板の上面を伝って前縁板まで導かれ、横板部のガイド面を経て縦板部のガイド面 を伝って縦板部の下端より落下し、庇板と横板部との隙間より浸入した雨水は、縦 板部の内面を伝って下方へ流下して凹部内に流れ込み、凹部から溢れ出て縦板部の 下端より落下する旨が記載されていることからすれば、構成要件B2の「縦板部」\nは、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面が雨水を下方へ導くガ イド面となっている」ことを要するものと解するのが、当業者にとって合理的であ る。
そして、「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」部分と、「庇板の開 放された前端面に当接され」た部分とがいずれも備わっているが、両部分が離間し て存在し、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面が雨水を下方へ 導くガイド面」となっていない構成が「縦板部」に含まれるとの解釈は、本件明細\n書に示される本件発明の目的(庇の小型化や構造の簡易化)や作用に整合しないし、\n本件明細書上、これを許容するような記載や示唆も見当たらない。したがって、少 なくとも、かかる構成は構\成要件B2の「縦板部」を充足しないものというべきで ある。
イ 被告製品についてみると、被告製品の構造(形状)の概要は、別紙「イ号製\n品」及び「ロ号製品」の各図面記載のとおりであるところ(前提事実(4)ア)、両 別紙の各【図7】のとおり、庇板102の開放された前端面129に、先端見切1 04(「前縁板」に相当する。)の当接部145の板部が当たって接している、す なわち当接しているものと認められる。 しかしながら、雨水を下方へ導くガイド面140aは、中間に横方向へ延びる張 出部142を介して当接部145の板部とは離間して存在しており、当接部145 の板部の「前面」が雨水を下方へ導くガイド面となっているとは到底いえない。そ うすると、被告製品には、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面 が雨水を下方へ導くガイド面となっている」構成が備わっておらず、被告製品は、\n構成要件B2の「縦板部」を充足しない。\n
ウ これに対し、原告は、被告製品の折れ板部140(別紙「図面」の【原告主 張図1】及び【原告主張図2】の橙色部分)は、前端面129に当接する当接部1 45及び前面が雨水を下方へ導くガイド面140aを備えるから、構成要件B2の\n「縦板部」に該当する、構成要件B2の「縦板部」は、雨水を縦方向に導くガイド\n面を備えているから「縦板部」との語が用いられたにすぎず、被告製品が前方へ張 り出す張出部142を有するからといって、非充足になるとはいえない旨主張する。
しかし、前記アに述べたとおり、本件特許の特許請求の範囲の請求項及び本件明 細書の各記載からすると、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面 が雨水を下方へ導くガイド面」となっていない構成を、構\成要件B2の「縦板部」 に含めることはできないというべきであるから、被告製品の折れ板部140が当接 部145及びガイド面140aを備えるとしても、当接部145の板部の前面が、 ガイド面140aとは離間し、雨水を下方へ導くガイド面となっていない以上、折 れ板部140が構成要件B2の「縦板部」に該当するとは認められない。\nしたがって、被告製品が構成要件B2を充足する旨の原告の主張は採用できない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.04.11
令和5(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月26日 知的財産高等裁判所
(4) 本件訂正発明1(害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む)の要旨 となる技術的事項が、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超 えるものであるか
ア 上記(2)イで認定したとおり、優先権出願1の明細書等には、ディートに代わ る害虫忌避成分として、3−(N−n−ブチル−N−アセチル)アミノプロピオン 酸エチルエステル(EBAAP)、p−メンタン−3,8−ジオール、1−メチルプ ロピル 2−(2−ヒドロキシエチル)−1−ピペリジンカルボキシレート(イカリ ジン)に共通して、「使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合さ れているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提 供する」という課題を有し、前記(2)イ(ウ)に認定した1)〜3)の特徴を有すること、 すなわち、所定量の揮発抑制成分を添加するなどして、50%平均粒子径r30と粒 子径比(r30/r15)がそれぞれ所定の値以上(粒子径比(r30/r15)が0.6以上、50%平均粒子径r30が50μm以上)となるよう調整することにより、上記課題 を解決することが記載されている。
また、前記1(2)ア〜ウ及びオのとおり、本件訂正発明1に関する背景技術、課題、 解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義につ\nいては、本件明細書の【0001】、【0002】、【0004】〜【0007】、【0009】、【0012】〜【0015】、【0023】及び【0024】等に記載され ているが、ほぼ同一の記載が、前記(2)イ(ア)〜(ウ)及び(オ)のとおり、優先権出願1 の明細書の【0001】、【0002】、【0004】〜【0008】、【0012】〜【0015】、【0017】、【0018】、【0026】及び【0027】において記載されていたものといえる。
イ また、本件訂正発明1の発明特定事項は、いずれも優先権出願1の特許請求 の範囲の請求項1又は2に記載されており、害虫忌避成分としてEBAAPと同様 にイカリジンも明記されていたものといえる。
ウ 前記(2)イ(エ)及び(3)イ(イ)のとおり、優先権出願1の明細書等において、実 施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてEBAAPを含む噴射製品の みであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権 出願2の明細書等(実施例5及び7)により追加されたものであるが、当該実施例 は、本件訂正発明1の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願1の特許請求 の範囲の請求項1又は2に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例 を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願1の明細書等に記載された 技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
エ したがって、本件訂正発明1の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む 部分も含めて優先権出願1の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超え るものではないから、本件訂正発明1は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分に ついても、優先権出願1に基づく国内優先権主張の効果が認められる。
(5) 原告の主張について
ア 害虫忌避成分をイカリジンとする部分は本件第1優先日時点で完成してい るかについて(前記第3の1(1)イの主張について) まず、国内優先権主張の効果が認められるかどうかは、前記2(1)の説示のとおり、 後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものと いえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初 明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特 許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書 等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分につ いては優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。 この点、優先権出願1の明細書等において、実施例として記載されているのは、 害虫忌避成分としてEBAAPを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイ カリジンを含む噴射製品に係る実施例自体は、優先権出願2の明細書等(実施例5 及び7)により追加されたものであるものの、優先権出願1の特許請求の範囲の請 求項1又は2に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に 記載したものと理解できるから、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項 との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないことは前記(4)の判 断のとおりである。
そして、前記のとおり、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1に関する 背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件\nの技術的意義が記載されており、これらはEBAAP、p−メンタン−3,8−ジ オール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すな わち、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1について、害虫忌避成分をイ カリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知 識を有する者(当業者)が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる 程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。\n
これに対し、原告は、EBAAPとイカリジンとは物質として害虫忌避作用があ るということのほかには類似性がないこと等により、イカリジンを害虫忌避成分と する場合にEBAAPと同様の結果となるかどうかは判断できず、優先権出願2の 出願時にイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の 裏付けがされ完成したものであることを主張する。
この点、本件訂正発明1では、害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、成分 の揮発によって小さくなることを抑制するために、蒸気圧が小さい揮発抑制成分(2 0゜C)での蒸気圧が2.5kPa以下)を配合しているところ(本件明細書の【00 14】)、一般に、物質の揮発しやすさ(揮発性、揮発度ともいう。)は、その成分の 蒸気圧によって決定されるものであり(甲64)、蒸気圧が小さいものは揮発しにく く、蒸気圧が大きいものは揮発しやすいものであるといえる。そこで、20゜C)にお けるEBAAPやイカリジンの蒸気圧についてみると、EBAAPが0.0001 5kPa(=0.15Pa、甲27)、イカリジンが0.000034kPa(=3. 4×10−4hPa、甲28)であるのに対し、揮発抑制成分の蒸気圧は、1,3− ブチレングリコールが0.008kPa(=0.08hPa、甲39)、プロピレン グリコールが0.0107kPa(=0.08mmHg、甲40)、水が2.336 6kPa(甲3の1・2)であり、溶剤の蒸気圧は、無水エタノールが5.8kP a(甲65)であって、EBAAPとイカリジンの蒸気圧は、揮発抑制成分の蒸気 圧や溶剤の蒸気圧に比べて極めて小さいものといえる。これらのことからすると、 EBAAPとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両 者の蒸気圧の違いは、粒子径比(r30/r15)や50%平均粒子径r30に対して与え る影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、EBAAPとイカリジ ンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてEBAAPとイカリジンのいずれを 使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比(r30/r15)への影響は 変わらないものと理解できる。
したがって、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少 なくとも優先権出願2におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初め て実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用 できない。
イ 「実施可能であるか」について(前記第3の1(1)ウの主張)
(ア) 前記(1)の「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術 的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否か という判断は、実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が 先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断する\nものと解される。
(イ) 優先権出願1の明細書等には、EBAAP、p−メンタン−3,8−ジオー ル又はイカリジンを含む害虫忌避成分について、噴射された粒子が使用者やその周 囲の者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすく、その結果、使用者等は、粘膜に違和感を 感じたり、咳き込んだりしやすいという問題があることから、使用者の鼻や喉等の 粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激 が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することを課題とするものであり、この 課題を解決するために、優先権出願1の明細書等に記載された発明は、前記害虫忌 避成分を含むものについて、さらに、1)噴射後の揮発を抑制するため、20゜C)での 蒸気圧が2.5kPa以下となる揮発抑制成分を、害虫忌避組成物中10質量%以 上含み、かつ、2)前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌 避組成物の50%平均粒子径rと、前記噴口から30cm離れた位置における噴 射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)が、 0.6以上となるよう調整され、3)前記噴口から30cm離れた位置における噴射 された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、50μm以上となるよう調 整されたという特徴を有するものであることが記載されている。そして、その効果 を発揮するメカニズムとして、噴射された害虫忌避剤の中には、皮膚や髪等の適用 箇所に付着せずに、適用距離(例えば噴口から15cmの距離)を超えて更に離れ た位置(例えば噴口から30cm離れた位置)に到達し、浮遊するものがあり、そ のような離れた位置では、粒子径が小さくなるため、粘膜刺激を起こしやすく、害 虫忌避組成物中に揮発抑制成分を添加して、適用距離における粒子径だけでなく、 それを超えた位置における粒子径にも注意を払い、当該粒子径が小さくなりすぎな いよう、50%平均粒子径r30と粒子径比(r30/r15)がそれぞれ所定の値以上(粒 子径比(r30/r15)が0.6以上、50%平均粒子径r30が50μm以上)となる よう調整したことが説明されている。
また、優先権出願1の明細書等の【0013】〜【0031】に、本件訂正発明 1に係る噴射製品の組成物の各成分の説明及びポンプの構造の説明が詳細に記載さ\nれており、【0017】及び【0018】には、揮発抑制成分を配合することで、噴 射後の揮発が抑制され、適用箇所を超えた範囲(例えば、噴口から30cm)にま で噴射された場合であっても粒子径が小さくなりにくいことや揮発抑制成分の配合 量が記載されており、また、【0027】には、粒子径比(r30/r15)を上記範囲に 調整する方法は特に限定されず、例えば、害虫忌避組成物の処方(例えばそれぞれ の成分の種類及び含有量、忌避抑制成分の有無、含有量等)、アクチュエータの形状、 寸法(例えば噴口の大きさ、形状等)、又は単位時間当たりの噴射量(噴射速度)、 噴射圧等の各種物性が調整されることにより調整できることも示されている。
さらに、優先権出願1の明細書等の【0051】の表1の実施例及び比較例を見\nると、害虫忌避成分としてEBAAPを、揮発抑制成分として、1,3−ブチレン グリコール、プロピレングリコール又は水の少なくとも1の成分を10質量%以上 配合した害虫忌避組成物が充填された噴射製品が記載されており、実施例1及び2 並びに比較例1〜3から、揮発抑制成分の含有量が増えるほど揮発による50%平 均粒子径r30の小型化が抑制され、粒子径比(r30/r15)が大きくなっていること が理解できる。
そして、実施例1〜4においては、揮発抑制成分の含有量が10質 量%以上、粒子径比(r30/r15)が0.6以上、50%平均粒子径r30が50μm 以上の害虫忌避組成物が実現されていることが理解できる。 以上のことからすると、当業者であれば、優先権出願1の明細書の実施例及び比 較例において具体的な製造方法が示されているEBAAPを配合した害虫忌避組成 物及び噴射製品と同様にして、イカリジンを配合し、粒子径比(r30/r15)が0. 6以上、50%平均粒子径r30が50μm以上を満たす噴射製品を製造することが できると解される。
この点、原告は、EBAAPとイカリジンの蒸気圧が異なることを主張している が、前記アの各成分の20゜C)における蒸気圧によると、EBAAPやイカリジンの 蒸気圧の違いは、粒子径比(r30/r15)や50%平均粒子径r30に対して与える影 響を無視できるものといえるから、当業者であれば、害虫忌避成分としてEBAA Pを含む害虫忌避組成物を充填した噴射製品の実施例と同様にして、過度の試行錯 誤を要することなく、イカリジンを含む害虫忌避組成物を作成し、これを充填し、 粒子径比(r30/r15)を0.6以上、50%平均粒子径r30を50μm以上に調整 した噴射製品を製造することができるといえ、原告の上記主張は採用できない。
また、本件訂正発明1の噴射製品は、害虫忌避組成物を含む噴射製品、いわゆる 虫よけスプレーであり、優先権出願1の明細書等の【0006】、【0025】等の 記載を見ると、使用者が、一般的な虫よけスプレーと同様にして、噴口から害虫忌 避組成物を適用箇所に向けて噴射をすることができること、噴口から噴射される害 虫忌避組成物は、所定の粒子径、より具体的には、所定の粒子径比(r30/r15)及 び50%平均粒子径r30に調整され、霧状に噴射されること、及び、所定の粒子径 に調整されているため、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合で あっても、粘膜への刺激が低減されることが認められ、このことは、害虫忌避成分 がEBAAPであっても、イカリジンであっても変わることはないものといえるか ら、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分としてイカリジンを含む部分が、優先権出 願1において、過度の試行錯誤を要することなく使用できるように記載されている ということができる。
この点、原告は、「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例 えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上 の意義のある態様で使用することができることを要すると主張する。 しかし、原告の上記主張は独自の見解であって採用できない。また、仮にこれを 前提としても、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1の効果を発揮するメ カニズムについて、十分な記載があり、さらに、害虫忌避成分としてEBAAPと\nイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比(r 30/r15)への影響は変わらないことを理解できるから、当業者は、EBAAPとイ カリジンのいずれを使用しても、同様に「粘膜への刺激が低減された噴射製品及び 噴射方法を提供することができる」という作用効果を奏する態様で用いることがで き、技術上の意義のある態様で使用することができるものと理解することもできる。 したがって、当業者であれば、優先権出願1の明細書の実施例及び比較例におい て具体的な製造及び使用方法が示されているEBAAPを配合した害虫忌避組成物 及び噴射製品と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを配合 した害虫忌避組成物や噴射製品を製造し、粒子径比(r30/r15)を0.6以上、r30を50μm以上とすることができ、かつ、当該噴射製品を使用することができる といえる。よって、原告の上記主張は理由がない。
(ウ) 以上によると、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分 が、優先権出願1の明細書等の記載事項との関係において実施可能であるといえる\nから、「実施可能であるか」についての原告の主張(前記第3の1(1)ウの主張)は 理由がない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2024.04.11
令和5(ネ)10086 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、化合物自体が公知文献に明記されており、当該化合物を初めて 製造できたことに技術的意義が認められる物質特許の発明については、化合 物自体は公知であるから、その発明は新規性を欠くと解すべきであり、仮に 新規性を有するのであれば、その発明の技術的意義は当該化合物を製造でき たことについて認められるものであるから、その技術的範囲は、発明者が現 実に発明した製造方法によって製造された物か、単離された高純度の化合物 に限定されるべきであると主張するが、以下に述べるとおり採用できない。
ア 発明が技術的思想の創作であること(特許法2条1項参照)にかんがみ れば、特許出願前に頒布された刊行物(同法29条1項3号)に物の発 明が記載されているというためには、同刊行物に発明の構成が開示され\nているだけでなく、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の 創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその\n技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されてい ることを要する。
特に当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造 方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、 刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当 該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理解\nし得る程度の記載があることを要するというべきであり、刊行物に製造 方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業 者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時\nの技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことがで きることが必要であるというべきである。
そして、本件において、公知文献である本件引用例に5−アミノレブ リン酸リン酸塩の製造方法に関する記載は見当たらず、乙16〜18の 各論文によっても、特許出願時の技術常識に基づいて当業者がその製造 方法その他の入手方法を見出すことができたとは認められない(以上は 原判決「事実及び理由」第3の3(1)イ〔14頁〜〕に同じ。)。
イ 他方、本件明細書には、5−アミノレブリン酸リン酸塩の物質の構成が\n開示されている(【0009】、【0014】〜【0016】)にとど まらず、当業者がその製造方法を理解し得る程度の記載があるところ (【0007】、【0019】〜【0028】、【0034】〜【00 36】)、これは、新規の化学物質の発明である本件発明について、当 業者が実施し得る程度の発明の技術的思想を開示するものであって、単 なる製造方法としての技術的意義にとどまるものではない。
そして、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の 効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法\nにかかわらず及ぶこととなる(最高裁平成24年(受)第1204号同 27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照)。
ウ なお、控訴人が指摘するような、本件特許の出願の際に製造等していた 者については先使用による通常実施権(特許法79条)により、本件特 許の出願後に製造方法等の発明をした者については通常実施権の設定の 裁定(同法92条)により、特許権者との利益の調整が図られることに なる。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和4(ワ)9716
本件特許の無効審判に関する審決取消訴訟です。
結論は本件と同じです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2024.04.11
令和5(ネ)10103 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記認定のとおり、原告は、前件訴訟において、被告の代表者であったAの原告\nに対する行為(前件主張等に係るパワーハラスメント)が不法行為を構成すると主\n張し、会社法350条に基づいて、被告に対し、損害賠償金の支払を求めたところ、 前件訴訟の裁判所は、前件主張について「本件国内移行手続を執ることを中止する 旨決定したAの行為は、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであったとはいえ ず、原告に対するパワーハラスメントに当たるとはいえない」旨認定判断し、原告 の当該損害賠償請求を棄却する旨の判決をした。同判決は、最高裁判所による上告 棄却決定及び上告不受理決定により確定した。
しかるところ、本件訴えは、原告において、被告が本件国内移行手続を執らなかった行為及び本件発明の権利化の機会を原告に与えなかった行為(本件行為)が本件譲渡契約上の債務不履行を構成すると主張し、被告に対して、債務不履行に基づく損害賠償金の支払を求めるものであり、形式的にみれば前件訴訟と訴訟物を異にするものであるが、実質的にみれば、本件発明に係る本件国内移行手続が執られず、これが権利化されることがなかったという同一の社会的事実について、前件訴訟ではこれを被告の代表\者であったAの 原告に対する不法行為と構成し、本件訴えでは被告の債務不履行と構\成したものに すぎない。本件訴えにおいて原告の主張する債務不履行の成否は、結局のところ、 Aが本件発明について本件国内移行手続を執らない旨決定したことが、当時の状況 に照らし、業務上必要かつ相当な判断であったかによって決まる性質のものであり、 前件訴訟において、この点に関する原告の主張が排斥されることにより、本件訴訟 において原告が主張するような債務不履行が成立しないことについても、実質的な 判断がされているといえる。したがって、前件訴訟について原告の請求を棄却する 旨の判決が確定したにもかかわらず、同一の社会的事実について、請求の法的根拠 を債務不履行に変更して訴えを提起した本件訴えは、前件訴訟の蒸し返しといわざ るを得ない。
また、前記認定事実によると、原告は、前件訴訟において、本件訴えに係る請求 と同様の請求をすることにつき何らの支障もなかったものと認められるにもかかわ らず、更に原告が被告に対して本件訴えを提起することは、前件訴訟において全部 勝訴の確定判決を得た被告の法的地位を不当に長く不安定な状態に置くことになる。 その他、本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件訴えの提起は、信義則に反 し許されないものと解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.04.11
令和5(ワ)893 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年3月18日 大阪地方裁判所
不競法2条1項21号の「虚偽」とは、客観的事実に反する事実であるところ、 本件各申告の内容は、原告各標章を付した原告各商品の販売が被告商標権を侵害\nするというものであるから、以下、当該内容が客観的事実に反するか、すなわち、 原告各標章の使用が被告商標権を侵害しないといえるかにつき検討する。
なお、商標権侵害の判断の前提となる商標の類否は、対比される両商標が同一 又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混 同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、使用され た商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、 連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品又は役務に係る取 引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断される (最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民 集22巻2号399頁参照)。また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と\n解されるものについて、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は\n役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、 それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場 合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると\n思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、その構成部\n分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断する ことも許される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小 法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同 5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年 (行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号56 1頁参照)。
(1) 原告標章1ないし同10と被告商標との対比
ア 原告標章1ないし同10について
原告標章1ないし同10は、「Qbit」、「いつでも」、「簡単」、「トイレ」 の文字(同1、4、5、7、8)及びこれらの文字と丸い絵柄(円の外から 中央右下に向けて濃紺から淡い青を経て白色にグラデーションが施され、円 の内部に「Q」の字を模した白抜きがされたもの)から構成される結合商標\nである。これらの標章のうち、「いつでも」、「簡単」の文字部分は、順に、商 品の使用の時期、使用の方法又は効能を表\示するものにすぎず、「トイレ」部 分は普通名称であるから、これらが「いつでも簡単トイレ」と一体として表\n示されていることを踏まえても、これらの文字部分が商品の出所識別機能を\n有しているとはいえず、「Qbit」又は「Qbit」と上記丸い絵柄部分が 強い出所識別機能を有しているといえる。よって、被告商標との類否の判断\nにあたっては、文字部分を抽出するのは相当でなく、上記「Qbit」と丸 い絵柄の部分を抽出して対比することが相当である(なお、これらの標章の 中には、Qbitや上記絵柄部分と他の文字部分が、横並びになる構成のも\nのや上下の構成のものもあるが、これらの構\成の相違は、上記結論に影響し ないというべきである。)。 そして、「Qbit」及び丸い絵柄からは「きゅーびっと」との称呼が生 じ、特定の観念は生じない。
イ 被告商標について
被告商標は、片手で長い布様のものを所持する赤ちゃん様の絵柄と「いつ でも」、「どこでも」、「簡単」、「トイレ」との各文字部分から構成される。こ\nのうち、文字部分は、前記長い布様のものの上に「いつでもどこでも」と「簡 単トイレ」が2段に配置され、「いつ」「どこ」がロゴ化され、「トイレ」のレ の字には、用が足される様子を模式的に示す絵柄が付加されているものの、 商品の使用時期、提供の場所、使用の方法又は効能を表\示するものにすぎず、 「トイレ」部分は普通名称であるから、これらが一体として表示されている\nことをも踏まえても、これらの文字部分が商品の出所識別機能を有している\nとはいえず、赤ちゃん様の絵柄部分が強い出所識別機能を有しているという\nべきである(仮に文字部分の識別力を考慮するとしても、前記の配置やロゴ 化、絵柄の付加といった要素を捨象して考えることはできない。)。よって、 原告標章1ないし同10との類否の判断にあたっては、(標準文字としての) 文字部分を抽出するのは相当でなく、上記赤ちゃん様の絵柄を抽出して対比 することが相当である。そして、当該部分からは特定の称呼、観念は生じない。
ウ 対比
原告標章1ないし同10の「Qbit」又は「Qbit」と丸い絵柄部分 と被告標章の赤ちゃん様の絵柄部分とを比較すると、外観、称呼、観念のい ずれにおいても類似しない(双方の標章の文字部分と上記図柄の組合せを全 体として観察しても同様である。)。この点、被告商標の商標登録後に出願さ れた原告商標1及び原告商標2がいずれも商標登録されるに至ったことは、 上記判断と整合する。
(2) 原告標章11ないし同15について
これらの標章は、「いつでも」、「簡単」、「トイレ」の文字から構成されている\nが、上記のとおり、これらの文字部分は、商品の使用の方法や効能を表\示する ものや普通名称であり、出所識別機能を有しているとはいえないから、商標法\n26条1項2号の商標に該当すると認められる。よって、これらの標章に被告 商標権の効力は及ばない。
(3) 小括
したがって、原告各標章を付した商品の販売は、被告商標権を侵害する行為 に当たらないから、これに反する本件各申告の内容は「虚偽」であると認めら\nれる。
(4) 争点1のまとめ
以上に加え、前記1、2を総合すると、本件各申告は、不競法2条1項21\n号の不正競争に当たる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.04.10
令和5(行ケ)10056 承継参加申立事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月25日 知的財産高等裁判所
(エ) 本件適用に係る動機付けの有無
a 技術分野
(a) 前記アの甲11の記載によると、甲11発明(認定)は、ワクチンアジュ バントのエマルジョンを製造する技術の分野に属する発明であると認められる。 他方、前記(イ)のとおり、甲65には、「導入」として、「合成ポリマーの微小 多孔性膜を使用する通常のフローフィルタ等は、多種多様なバイオ医薬液体の濾過 用途に広く使用され、これらのフィルタの主な目的は、製品中の細菌汚染の可能性\nを減らすことである」旨の記載、「濾過膜は、血液分画、血清の処理、大容量非経 口剤(LVP)等の従来の製薬用途でも日常的に使用され、ここでの目標は、バイ オ医薬品プロセスと同じであり、製品の細菌汚染の可能性を低減させることである」\n旨の記載等があり、甲65は、これらの膜を備えた具体的な製品として、本件製品 に言及している。また、前記(ア)のとおり、丙4には、本件製品が「広範囲の医薬 製品を濾過できるように設計されたものであり、広範囲の化学的適合性を備えるも のである」旨の記載がある。これらによると、本件製品は、少なくとも上記の「従 来の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製造にも 当然に適用し得るものであると認められるから(なお、前記(ア)のとおり、丙4に は、本件製品の用途の例として「バルク医薬品」が挙げられている。)、本件周知 技術は、甲11発明(認定)が属する技術分野を包む技術分野に属する技術である と認めるのが相当である。
以上のとおりであるから、甲11発明(認定)と本件周知技術とは、その属する 技術分野を共通にするといえる。
(b) 参加人は、甲65は「バイオ医薬品」(遺伝子組換え技術等を用いて製造 したたんぱく質を有効成分とする医薬品)について言及するものであるところ、ワ クチンアジュバントのエマルジョンは「バイオ医薬品」に当たらない、丙4には本 件製品がスクアレン含有水中油型エマルジョンの滅菌フィルタに使用し得る旨の記 載がないとして、甲11発明(認定)が属する技術分野と本件周知技術が属する技 術分野とが異なる旨主張するものと解される。 しかしながら、前記(a)のとおり、本件製品は、少なくとも甲65にいう「従来 の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製造にも当 然に適用し得るものであるから、甲11発明(認定)が属する技術分野と本件周知 技術が属する技術分野とが異なるとはいえない。参加人の主張は失当である。
b 甲11発明(認定)が有する課題
(a) 甲11には、前記アにおいて認定した箇所を含め、本件適用を動機付ける ような課題の記載はみられない。 しかしながら、甲20(日本ワクチン学会編「ワクチンの事典」(平成16年)) の「無菌性の保証 ワクチンは通常、…無菌製造、無菌充填が行われる。」との記 載、前記(イ)のとおりの甲65の記載(「プレフィルタと最終フィルタの組合せを 正しく選択することで、流速、濾過時間及び全体的な濾過コストの最適なバランス が得られる」旨の記載、「膜濾過の主な目標である滅菌濾液の提供を評価する基準 として、1)細菌の効果的な保持がされること、2)高い総処理量を有することによる 濾過コストの削減がされること、3)許容可能な範囲の流速による妥当な時間枠にお\nけるバッチ全体の濾過がされることなどが挙げられる」旨の記載、「本件製品の製 造業者が製造する本件製品と同種の製品のプレフィルタ層は、非常に高い処理量を 実現し、10インチエレメント当たりの有効濾過面積を30%以上向上させ、0. 2μmの最終フィルタ層は、本件製品の組合せと同じで、信頼性の高い細菌保持を 提供する」旨の記載等)に加え、甲11発明(認定)と本件周知技術とがその属す る技術分野を共通にすること(前記a)に照らすと、ワクチンアジュバントのエマ ルジョンの製造に用いられる濾過膜については、その品質を向上させるため、1)細 菌を効果的に保持すること、2)総処理量が大きいこと及び3)流速が妥当なものであ ることが求められているものと認められる。それのみならず、そもそもワクチンア ジュバントのエマルジョンの製造に用いられる濾過膜において、上記1)から3)まで の要請が達成されることにより当該濾過膜の品質の向上につながることは、これら の要請の内容に照らし、本件優先日の当業者にとって自明であったというべきであ る。したがって、甲11発明(認定)には、これらの要請を達成するとの課題(以 下「本件課題」という。)が内在しており、甲11発明(認定)に接した本件優先 日当時の当業者は、甲11発明(認定)が本件課題を有していると認識したものと 認めるのが相当である。
(b) 参加人は、ここでも甲65は「バイオ医薬品」(遺伝子組換え技術等を用 いて製造したたんぱく質を有効成分とする医薬品)について言及するものであり、 ワクチンアジュバントのエマルジョンは「バイオ医薬品」に当たらないから、甲6 5の記載をもって甲11記載の発明の課題を認定することはできないと主張する。 しかしながら、甲11発明(認定)は、ワクチンアジュバントのエマルジョンを 製造する技術の分野に属する発明であり、甲65は、従来の製薬用途でも日常的に 使用され、製品の細菌汚染の可能性を低減させることを目的とする濾過膜について\n述べた文献であるから、甲65記載の事項(本件課題)は、少なくとも甲65にい う「従来の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製 造にも当然に当てはまるものというべきである。それのみならず、そもそもワクチ ンアジュバントのエマルジョンの製造に用いられる膜において、本件課題が本件優 先日当時の当業者にとっての自明の課題であったことは、前記(a)のとおりである。 参加人の主張を採用することはできない。
c 本件課題の解決手段
(a) 前記(ア)のとおりの丙4の記載(「本件製品のフィルタカートリッジは、現 存する滅菌フィルタカートリッジのいずれと比較しても優れた特性を持ち、広範囲 の化学的適合性、高耐熱性、高処理量、高流速の特性を全て備えている」旨の記載、 「本件製品のカートリッジは、0.45μm膜を用いた「組み込み予備濾過」によ\nる分画濾過のため、非常に高い総処理能力を持ち合わせている。ポリエーテルスル\nホン膜の非対称的孔構造は、低い圧力下で、高い流速を提供する」旨の記載、「本\n件製品のフィルタカートリッジは、HIMAやASTM F−838−83ガイド ラインに従う滅菌グレードのフィルタエレメントとして十分検証されている」旨の\n記載、95%閉塞時における総処理量において本件製品が最も優れている旨のグラ フ等)、前記(イ)のとおりの甲65の記載(「本件製品の製造業者が製造する本件 製品と同種の製品の0.2μmの最終フィルタ層は、本件製品の0.45μm/0. 2μmの組合せと同じで、信頼性の高い細菌保持を提供する」旨の記載等)及び弁 論の全趣旨によると、本件製品が備える親水性異質二重層ポリエーテルスルホン膜 をワクチンアジュバントのエマルジョンの製造(濾過)に用いることにより、本件 課題をいずれも解決することができるものと認めるのが相当である。
(b) 参加人は、丙4の記載は本件製品の特性に関する一般論を述べるものにす ぎず、丙4には本件製品がスクアレン含有水中油型エマルジョンを含む水中油型エ マルジョンの滅菌濾過を用途とし得るものである旨の明記がないとして、丙4記載 の本件製品の特性をもって甲11記載の発明が有する課題を解決することができる ものであると認めることはできないと主張する。 しかしながら、本件製品は、広範囲の医薬製品を濾過することができるように設 計され、広範囲の化学的適合性を備えるものであり(前記(ア))、また、ワクチン アジュバントのエマルジョンの製造にも当然に適用し得るものである(前記a)と ころ、甲65及び丙4には、本件製品をワクチンアジュバントのエマルジョンの製 造に用いた場合に、本件製品が持つ本来の性能が十\分に発揮されないものとうかが わせる記載は一切なく、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はないから、 甲65及び丙4に記載された本件製品の性能は、本件製品をワクチンアジュバント\nのエマルジョンの製造に用いた場合にも発揮されるものと認めるのが相当である。 参加人の主張を採用することはできない。
d 本件適用に係る動機付けの有無についての参加人のその余の主張に対する判 断
参加人は、1)甲11記載の発明における第1の濾過工程と第2の濾過工程は段階 を異にする別個の工程である、2)前者の工程と後者の工程は濾過の条件(高温高圧 条件下での実施の要否)、用いる濾過膜の性質(細菌保持力の強弱)及び濾過のタ イミング(バルクの充填工程の前後)を異にするものであるとして、甲11記載の 発明に接した当業者において、前者の工程と後者の工程を1つの濾過工程(本件製 品の膜を用いた工程)に置き換えることが容易であったとはいえないと主張する。 しかしながら、前記イ(イ)において説示したとおり、参加人が主張する工程(III)) (アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程)は、アジュバン トエマルジョンを抗原溶液と組み合わせる場合とこれらを組み合わせない場合とが あることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、少なくとも後者の場合にお いては、当該工程を経ることが技術的に必須であるとまでいえないと考えられるの であるから、甲11記載の発明において第1の濾過工程と第2の濾過工程を連続し て行うことは、同発明の技術的思想と何ら背馳するものではない(この評価は、甲 11(前記ア)に、第1の濾過工程(大きな粒子を除去する工程)につき「安定性 を有するエマルジョンの製造のために重要である」旨の記載が、第2の濾過工程に つき「滅菌濾過を行った上、アジュバントを単回投与用のバイアルに充填する」旨 の記載がそれぞれあることによっても妨げられるものではない。)。そうすると、 甲11記載の発明の第1の濾過工程と第2の濾過工程が連続して行うことができな い別個の工程であるということはできないから、上記の1)の点を根拠とする参加人 の主張を採用することはできない。
また、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲11には、第1の濾過工程におけ る濾過と第2の濾過工程における濾過がどのような温度や圧力の下で行われなけれ ばならないかについての記載はなく、その他、濾過が行われるべき温度又は圧力を 第1の濾過工程と第2の濾過工程とで別異にすべきであることを認めるに足りる証 拠はないから、甲11記載の発明に接した本件優先日当時の当業者において、第1 の濾過工程における濾過は高温高圧下で行う必要があるが、第2の濾過工程におけ る濾過は高温高圧下で行う必要がないなどと認識するものとは認められない。細菌 保持力の点についてみても、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲11には、第 1及び第2の濾過工程において使用される各膜につき、これらの細菌保持力の強弱 についての記載はなく、その他、細菌保持力を第1の濾過工程において使用される 膜と第2の濾過工程において用いられる膜とで別異にすべきであることを認めるに 足りる証拠はないから、甲11記載の発明に接した本件優先日当時の当業者におい て、第2の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要があるが、 第1の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要がないなどと認 識するものとは認められない。濾過のタイミングの点についてみても、参加人が主 張する工程(III))(アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程) を経ることが技術的に必須であることを認めるに足りる証拠がないことは、前記イ (イ)において説示したとおりであるから、甲11記載の発明に接した本件優先日当 時の当業者において、第1の濾過工程はアジュバントエマルジョンのバルクの大き な瓶への充填の前に行う必要があり、第2の濾過工程は当該充填の後に行う必要が あるなどと認識するものとも認められない。したがって、上記の2)の点を根拠とす る参加人の主張も採用することはできない。
e 本件適用に係る動機付けの有無についての小括
以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者において、甲11発明(認定) に本件周知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2024.04.10
令和5(行ケ)10112 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年3月14日 知的財産高等裁判所
ア 引用商標に関する原告の認識について
原告は、ハキハナ社の販売代理店として本件商品を含む同社の商品を販 売していたのであるから、同社が本件商品を含む同社の商品に引用商標を 使用していることを認識しながら、引用商標と構成文字を共通にする本件\n商標について、引用商標が用いられている商品と同種の商品である第18 類「愛玩動物用引きひも、愛玩動物用のハーネス」を指定商品として、商 標登録出願を行い、登録を受けたものと認められる。
イ 原告が本件商標の登録出願を行った意図及び目的について
(ア) 前記(1)の認定事実によれば、原告がハキハナ社との間で締結した本件 契約は原告に独占的販売権を与える内容ではなかったが、原告は、自ら が行った本件商品の広告宣伝や、本件商品の販売促進のための方策によ って、日本国内における本件商品の知名度が上がり、販売が増えたもの であって、このような貢献を行った原告にはハキハナ社の商品に係る独 占的販売権などの契約条件や待遇が同社から与えられるべきと考えて いたが、同社はそのような意向を有さず、原告以外の者が並行輸入によ り入手したハキハナ社の商品を日本において販売することを問題視し ない販売戦略を採っており、原告にもこれを伝えていたこと、その後、 アブレイズが原告よりも安価で本件商品を販売するようになり、原告は、 アブレイズの販売活動は、原告の宣伝活動や方策によって向上した知名 度にただ乗りするものであって、アブレイズへの対応が必要であると考 え、ハキハナ社に対し、一時的な独占的販売権を原告に与えるなどの手 段によって、原告がアブレイズに対応することに協力するよう求めたが、 ハキハナ社がこれを拒絶したこと、そのわずか数日後、原告は、ハキハ ナ社が引用商標又はこれに類似する商標につき国際商標登録出願をし ていたものの、我が国においては商標登録していないことを奇貨として、 同社に一切知らせることなく、秘密裏に本件商標の登録を出願したこと が認められる。
原告が本件商標の登録を得た後、ハキハナ社が原告との取引を打ち切 ると伝えてきた際、原告は、本件商品が日本の市場に出なくなることは 残念であるとハキハナ社に伝えている。これは、原告が、原告以外の者 による日本国内における本件商品の販売を認めないこと、すなわち、こ のような者による本件商品の販売を妨害、阻止する意向を有しているこ とを示したものといえる。 以上の事情に加え、原告が、本件商標の登録を取得したのと近接した 時期に、本件商標権に基づき、アブレイズに対して本件商品の販売を中 止するよう実際に求めたことも考慮すれば、原告は、本件商標の登録出 願の時点から、本件商標の登録を得た後、本件商標権に基づき、アブレ イズによる本件商品の販売を差し止めるとともに、将来的に、並行輸入 等で入手した本件商品等のハキハナ社の商品を日本国内で販売する者が 現れたときに、その販売活動を差し止めるなどして、原告以外の者が日 本国内においてハキハナ社の商品を販売することを妨害、阻止する意図 を有していたものと認めることができる。
(イ) 原告が本件商標の登録出願をする以前に伝えられていたハキハナ社 の意向の内容からすれば、原告は、ハキハナ社の意向に反して無断で本 件商標の登録を得れば、ハキハナ社が原告に対する信頼関係を喪失し、 原告との取引を打ち切る可能性があることを容易に認識することがで\nきたといえる。
そして、原告は、ハキハナ社から、本件商標権をわずかな費用でハキ ハナ社に譲渡することなどの条件を満たさない限り原告との取引を打ち 切る旨伝えられたが、これに対する原告の応答(前記(1)ス)は、ハキハ ナ社との契約あるいは取引の継続を模索するものではなく、原告の貢献 に報いる内容の条件を出すようハキハナ社に迫る内容であるといえ、ハ キハナ社が原告との取引を終了すると伝えてきたことに対しても、契約 や取引の継続のための交渉を行おうとしなかった。 また、本件商標は引用商標と同一の文字で構成されているから、原告\nは、原告が本件商標の登録を受けた場合、本件商標権をハキハナ社に譲 渡しなければ、同社が、本件商品など引用商標を用いた商品を日本国内 で販売することができなくなると認識していたものと認められる。 これらの事情を総合すれば、原告は、本件商標の登録出願を行った時 点で、原告が本件商標の登録を受ければハキハナ社が引用商標を用いた 本件商品等を日本国内で販売することができなくなる事態が生じ得るこ とを認識し、そのような事態が生じても構わないと考えていたと認めら\nれ、かつ、原告の本件商標の登録出願は、ハキハナ社との契約関係や取 引における原告の利益を守ることよりも、むしろ原告以外の者による本 件商品の販売を妨害、阻止することに主たる目的があったと認めること ができる。
ウ 上記ア及びイの事情を総合すると、原告は、ハキハナ社が本件商品を含 む同社の商品に引用商標を使用していることを認識し、かつ、原告が本件 商標の登録を受ければ、ハキハナ社が引用商標を用いた本件商品等を販売 することができなくなることも認識しつつ、そのような事態が生じても構\nわないと考えて、原告以外の者が日本国内で本件商品を販売することを許 容するハキハナ社の意図ないし販売戦略に反し、本件商標権に基づいてア ブレイズによる本件商品の販売を差し止め、将来的にも、並行輸入等で入 手したハキハナ社の商品を日本国内で販売しようとする者の販売活動を 妨害、阻止することを主たる目的として、本件商標の登録出願を行ったも のと認められる。
このような原告の本件商標の登録出願は、商標登録出願について先願主 義を採用している我が国の法制度を前提としても、「商標を保護すること により、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の 発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同 法1条)に反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであり、かつ、健 全な法感情に照らし条理上も許されないというべきであるから、本件商標 は同法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商 標」に該当するというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.04.10
令和5(行ケ)10069 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月25日 知的財産高等裁判所
前記第2の1(特許庁における手続の経緯等)並びに証拠(甲39、乙22)及 び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(1) 原告は、令和元年11月12日、本件各発明に係る本件特許について特許 無効審判の請求をした。
(2) 特許庁は、令和3年10月8日、本件訂正を認めた上、本件発明1等に係 る本件特許を無効とし、本件発明4に係る本件特許に対する審判請求は成り立たな い旨の第一次審決をした。第一次審決においては、次の点がその理由とされた。
ア 本件発明1等は、いずれも本件出願日前に当業者が甲1引用発明に基づいて 容易に発明をすることができたものである。
イ 本件発明4は、本件出願日前に当業者が甲1引用発明に基づいて容易に発明 をすることができたものとはいえない。
(3) 被告は、令和3年11月13日、第一次審決のうち本件発明1等に係る本 件特許を無効とした部分の取消しを求める訴えを提起し、原告は、同月16日、第 一次審決のうち本件発明4に係る本件特許に対する審判請求は成り立たないとした 部分の取消しを求める訴えを提起した。
(4) 知的財産高等裁判所は、被告の訴えに係る事件及び原告の訴えに係る事件 を併合審理した上、令和4年8月31日、被告の請求を認容し、第一次審決のうち 本件発明1等に係る本件特許を無効とした部分を取り消すとともに、原告の請求を 棄却する旨の第一次判決を言い渡し、第一次判決は、その後確定した。第一次判決 においては、次の点がその理由とされた。
ア 本件発明1等は、いずれも本件出願日前に当業者が甲1引用発明に基づいて 容易に発明をすることができたものとはいえない。
イ 本件発明4は、本件出願日前に当業者が甲1引用発明に基づいて容易に発明 をすることができたものとはいえない。
(5) 特許庁は、令和5年5月22日、本件訂正を認めた上、本件各発明に係る 本件特許についての審判請求は成り立たない旨の本件審決をした。本件審決におい ては、次の点がその理由とされた。
ア 本件発明1等は、いずれも本件出願日前に当業者が甲1引用発明に基づいて 容易に発明をすることができたものとはいえない。 イ 本件発明4は、本件出願日前に当業者が甲1引用発明に基づいて容易に発明 をすることができたものとはいえない。
(6) 原告は、令和5年6月29日、本件審決のうち審判請求を不成立とした部 分の取消しを求めて本件訴えを提起した。本件訴訟における原告の主張は、前記第 3のとおりであるが、結局、次のとおり要約することができる。
ア 本件発明1等と甲1引用発明との間に本件構成に係る相違点2及び相違点4\nは存在しないというべきである。しかるところ、本件審決は、このような相違点が あることを前提に、本件発明1等に係る本件構成は、いずれも本件出願日前に当業\n者が甲1引用発明に基づいて容易に想到し得たとはいえないと判断した点において 判断を誤っている。
イ 本件発明4は、本件出願日前に当業者が甲1引用発明に基づいて容易に発明 をすることができたものであるから、その進歩性を認めた判断は誤りである。
2 本件発明1等に係る本件特許について(審決取消判決の拘束力)
(1) 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が 確定したときは、審判官は、特許法181条2項の規定に従い、当該審判事件につ いて更に審理を行って審決をすることとなるが、審決取消訴訟は、行政事件訴訟法 の適用を受けるから、再度の審理又は審決には、同法33条1項の規定により、当 該取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに 必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は、取消判決の当該 認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手 続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につき、こ れを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは、当該主張を裏 付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束 力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟におい てこれを違法とすることができないのは当然である。
このように、再度の審決取消訴訟においては、審判官が当該取消判決の主文のよ って来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上、その拘束力に従ってされた 再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは、確定した取消判 決の判断自体を違法として非難することにほかならず、再度の審決の違法(取消) 事由たり得ない。
以上を特許発明の進歩性判断が問題となる特許無効審判事件の審決の取消訴訟に ついて具体的に考察すると、特許無効審判の対象とされた特許発明が、特許出願前 に当業者において特定の引用例に記載された発明に基づき容易に発明をすることが できたとはいえないとの理由により、当該特許発明に係る特許を無効とした審決の 認定判断が誤りであるとして当該審決を取り消す旨の判決がされ、これが確定した ときは、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は、同一の引用例 に記載された発明に基づく進歩性の判断に当たり、当該判決と異なる認定判断をす ることは許されない。したがって、再度の審決に係る審決取消訴訟において、関係 当事者が、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断が誤りである (当該特許発明は特許出願前に当業者において同一の引用例に記載された発明に基 づき容易に発明をすることができた)として、これを裏付けるための新たな立証を し、また、裁判所が、これを採用して取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決 を違法とすることは許されないと解するのが相当である(前掲最高裁平成4年4月 28日第三小法廷判決参照)。
(2) これを本件についてみるに、前記認定のとおり、第一次審決(本件発明1 等に係る本件特許を無効とした部分。以下、この(2)及び後記(3)において同じ。) は、本件発明1等につき、これらがいずれも本件出願日前に当業者において甲1引 用発明に基づき容易に発明をすることができたものであると判断して、本件発明1 等に係る本件特許を無効としたところ、第一次判決(第一次審決を取り消した部分。
以下、この(2)及び後記(3)において同じ。)は、本件発明1等につき、これらがい ずれも本件出願日前に当業者において甲1引用発明に基づき容易に発明をすること ができたものとはいえないと判断して、第一次審決を取り消したものである。また、 第一次判決の確定後にされた本件審決(本件発明1等に係る本件特許に対する審判 請求は成り立たないとした部分。以下、この(2)及び後記(3)において同じ。)は、 本件発明1等に係る甲1引用発明に基づく進歩性について、第一次判決と同様の判 断をして、本件発明1等に係る本件特許に対する審判請求は成り立たないとしたも のである。
ここで、前記(1)によると、再度の審判請求において、本件発明1等が本件出願 日前に当業者において第一次判決が認定判断した同一の引用例(甲1)に記載され た発明に基づき容易に発明をすることができたか否かにつき、審判官が第一次判決 とは別異の事実を認定して異なる判断を加えることは、第一次判決の拘束力により 許されないのであるから、本件審決は、第一次判決の拘束力に従ってされた限りに おいて適法であるとされなければならない。 そして、前記(1)によると、第一次判決の拘束力に従ってされた本件審決の取消 訴訟(本件訴訟)において、第一次判決の認定判断(本件発明1等が本件出願日前 に当業者において甲1引用発明に基づき容易に発明をすることができたものとはい えないとの認定判断)を否定する関係当事者の主張立証は許されないことになるか ら、原告は、本件訴訟において、このような主張立証(本件発明1等の甲1引用発 明に基づく進歩性欠如の主張立証)をすることができないというべきである。 したがって、甲1引用発明に基づいて本件発明1等が進歩性を欠く旨原告が主張 することは許されない。
(3) 原告は、本件訴訟における原告の主張(取消事由1及び2)につき、これ は「相違点2又は4に係る本件発明1等の構成のうち本件構\成に係る部分は、本件 発明1等と甲1引用発明との相違点ではない」との第一次判決が判断していない事 項についての本件審決の判断の誤りを指摘するものであるから、本件訴訟において 取消事由1及び2を提出することは第一次判決の拘束力に反しないと主張する。 確かに、乙22によると、第一次判決においては、原告が本件訴訟において取消 事由1及び2として指摘する事項(相違点2又は4に係る本件発明1等の構成のう\nち本件構成に係る部分の実質的相違点性)についての判断がされなかったものと認\nめられる。しかしながら、本件発明1等に係る甲1引用発明に基づく進歩性の判断 は、本件発明1等及び甲1引用発明の各認定並びにこれを前提とする一致点及び相 違点の認定を踏まえて行われる法律判断である。前記のとおり、拘束力は、判決主 文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、甲1 引用発明に基づく進歩性欠如を否定した第一次判決の法律判断の前提となった本件 発明1等と甲1引用発明との間の相違点に係る事実認定についても、第一次判決の 拘束力は及ぶというべきである。したがって、本件審決の審判官が、同じ甲1引用 発明に基づく進歩性の判断に当たり、第一次判決とは別異の事実を認定して異なる 判断を加えることは、第一次判決の拘束力により許されず、第一次判決の拘束力に 従ってされた本件審決は適法なものである。原告の主張は、第一次判決の拘束力が 及ぶ事実認定及び法律判断部分について、本件審決が誤りである旨主張し、本件審 決の取消事由とするものにほかならず、前掲最高裁平成4年4月28日第三小法廷 判決に照らし、採用することはできない。
3 本件発明4に係る本件特許について(請求棄却判決の既判力)
行政処分の取消訴訟については、請求棄却判決が確定すると、処分に違法性がな いことについて既判力(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法114条)が生じるから、 審決取消訴訟についても、請求棄却判決が確定すると、審決に違法性がないことに ついて既判力が生じる。 しかるところ、最高裁昭和51年3月10日大法廷判決(昭和42年(行ツ)第 28号)民集30巻2号79頁の趣旨を踏まえると、特許発明の進歩性判断が問題 となる特許無効審判事件の審決の取消訴訟における請求棄却判決の既判力は、審決 に違法性一般がないことではなく、特許無効審判事件において審理された特定の引 用例に記載された発明(公知技術)に基づく進歩性の有無について判断した審決に 違法性がないことに関して生じるものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、前記認定のとおり、第一次判決(原告の請求を棄却 した部分。以下同じ。)は、本件発明4につき、これが本件出願日前に当業者にお いて甲1引用発明に基づき容易に発明をすることができたものとはいえないと判断 して、これと同じ判断をした第一次審決を是認し、原告の請求を棄却したものであ る。そして、第一次判決は、その後確定したのであるから、甲1引用発明に基づき、 本件発明4が進歩性を欠くとはいえないとした第一次審決に違法性がないことは、 既判力をもって確定されているというべきである。
本件で問題となっているのは、本件審決の違法性であって、第一次審決の違法性 ではないが、原告が、本件訴訟において、甲1引用発明に基づき、本件発明4が進 歩性を欠く旨主張(取消事由3)し、進歩性欠如を否定した本件審決の判断部分が 違法である旨主張することは、実質的にみれば、第一次審決の違法性に関し既判力 が生じている部分(同じ引用発明に基づき進歩性がないとはいえないとの判断)に ついて、これと異なる判断を求めるものとして、許されないというべきである。 仮にこの点を措くとしても、甲1発明の半田鏝は、先端部の開口部の径が1.0 mmであり、後端部の貫通孔の径が2.5mmであり、この貫通孔内に半田片が落 下し溶融できるように半田鏝筒内のテーパが構成され、これにより、半田片は、途\n中で引っかかって溶融してしまうことなく、そのまま先端まで落下して溶融するも のである(甲1の段落【0006】、【0031】、【0034】)。そうすると、 甲1発明の半田鏝については、甲11から13までに記載されたように半田鏝先端 部の内径を半田鏝後端部の内径より大きくすることには、阻害要因があるというべ きである。したがって、いずれにせよ、本件発明4について、甲1引用発明に基づ いて進歩性を欠くとは認められない旨の本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.04.10
令和4(行ケ)10084 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月21日 知的財産高等裁判所
(4) 相違点に係る容易想到性について
ア 相違点1について
(ア) 「心不全の患者」及び「心不全の治療薬」について
前記2(1)、(2)、(5)及び(6)のとおり、本件優先日当時、利尿薬は、心不全の症 状の一つである体液貯留、うっ血、浮腫等を改善する治療薬として、急性心不全(慢 性心不全の急性増悪期を含む。)と慢性心不全とを問わず、また心不全の重症度を問 わず、広く用いられていた薬剤である。また、代表的な利尿薬として用いられるフ\nロセミド等のループ利尿薬は、利尿作用が強い反面、塩化ナトリウムの再吸収を抑 制するために低ナトリウム血症等の電解質異常をきたし得るとの副作用がある上、 利尿薬抵抗性の問題も認識されており、加えて、特に重症心不全患者においては、 体液貯留の管理が重要とされていた。 そして、前記(2)ア(ア)のとおり、甲2には、体液貯留のある心不全患者(NYH AクラスI)〜III))に対し、フロセミドに上乗せして、異なる部位に作用し、また、 ナトリウムを排泄せずに水のみを排泄する選択的バソプレシンV2受容体拮抗薬と\nしてのトルバプタンを投与したところ、良好な忍容性とともに、血清電解質の有害 な変化なく、体重減少、尿量増加及び浮腫改善等の効果が得られた旨が記載されて いる。 そうすると、本件優先日当時、甲2発明及び甲2の記載に接した当業者において、 前記2に認定した技術常識も考慮して、甲2発明のトルバプタンを、「急性心不全ま たは慢性心不全の急性増悪期にあるニューヨーク心臓協会の分類:重症度IV)の患者」 における体液貯留等を改善するための治療薬とすることには、十分な動機付けがあ\nり、容易に想到し得たということができる。
(イ) 「活性成分の投与」について
甲2発明における「安定したフロセミド用量(20〜240mg/日)」が、フロ セミドを必要に応じて投与することを制限する趣旨と読み取れないことは、前記 (2)ウ(イ)bのとおりであるから、この点は実質的な相違点とはいい難い。また、前 記(2)ウ(ウ)のとおり、対象患者の症状や投与方法等を捨象した、単に治療薬を投与 する際に患者が入院下であるか否かという点も、実質的な相違点とはいい難い。 次に、前記2(1)ウのとおり、本件優先日当時、トルバプタンは、経口投与で強力 な水利尿薬として作用する薬物として知られていたのであるから、甲2発明では経 口投与されたか不明であるトルバプタンを本件発明1の対象患者に投与するに当た り、これを経口投与とすることは、当業者が適宜なし得た事項というべきである。
(ウ) 原告の主張について
原告は、1)医薬分野における容易想到性は、「当該発明の治療及び治療効果につい て、優先日当時における科学的根拠をもって当業者がこれを容易に評価・確認でき るか」という観点から判断されるべきであるとした上で、本件優先日当時の技術常 識として、2)ADHFの重症患者と慢性心不全の慢性期の軽症〜中等症患者とは、 その症状、治療内容・態様、治療薬の適応・治療効果が大きく異なっていた、3)同 じ心不全治療薬であっても、NYHAクラスI)〜III)の患者には有効だがクラスIV)の 患者には効果がない又は悪化させる例があった上、NYHAクラスIV)の患者は利尿 薬抵抗性の問題がより深刻であって治療に限界が生じており、トルバプタンにも利 尿薬抵抗性の問題が認識されていた、4)既存の利尿薬の作用機序・薬理作用と、ト ルバプタンの作用機序・薬理作用は異なるものである、5)ADHFの重症患者に対 して、トルバプタンを含む選択的バソプレシンV2受容体拮抗薬の投与実績は存在\nしていなかったところ、選択的バソプレシンV2受容体拮抗作用は、内因性バソ\プ レシンレベルの上昇を誘引し、それがバソプレシンV1a受容体を刺激することに\nより、心血管系や腎臓に悪影響を及ぼすことが理解されていたから、選択的バソプ\nレシンV2受容体拮抗作用を有するトルバプタンを、NYHAクラスIV)のような重 症患者に投与すれば、心不全の症状をさらに悪化させ、最悪の結果にもつながりか ねないと認識されていた、6)本件試験のような「最適の治療」(併用薬の用量増加、 投与経路変更を含む。)に対する上乗せ試験では、甲2試験のような併用薬の用量固 定・経口投与のみ等の制約されたデザインの試験と比して、上乗せ治療薬の治療効 果が得られにくいと理解されていたなどと主張し、これらの技術常識によると、甲 2発明から相違点1に係る本件発明1の構成に想到する動機付けはなく、又は阻害\n要因があると主張する。
しかし、1)について、進歩性についての判断基準として独自の見解というほかな く、採用の限りではない。2)について、急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含 む。以下この項において同じ。)と慢性心不全とで、また重症患者と軽症〜中等症患 者とで、治療の内容が異なる点は指摘のとおりであるが、前記2のとおり、利尿薬 に関していえば、急性心不全と慢性心不全とを問わず、また重症と軽症〜中等症と を問わず、心不全の症状の一つである体液貯留、うっ血、浮腫等を改善する治療薬 として広く用いられていたのであるから、甲2に記載されたトルバプタンの水利尿 効果が、体液貯留等の症状を呈する急性心不全の患者や重症患者にも得られるであ ろうことを、当業者は当然に想起するというべきである。3)について、NYHAク ラスI)〜III)の患者とクラスIV)の患者とで取扱いを異にする例として原告が挙げてい る例(甲38、43、47、70〜77、88)には、利尿薬とは異なる心不全治 療薬が含まれているほか、利尿薬に関するものであっても、NYHAクラスIV)であ ることを理由に利尿薬の取扱いを異にすべき旨が記載されているとは読み取ること はできない。前記2(6)のとおり、重症心不全患者では、特に体液貯留等の管理が重 要とされており、重症度の高さや利尿薬抵抗性の問題から利尿薬が十分に効果を発\n揮しない場合があるとしても、また、仮にトルバプタンにも利尿薬抵抗性の問題が あるとしても、当業者は、NYHAクラスによる重症度を問うことなく、体液貯留 等の症状を改善するために利尿薬の使用を試みるというべきである。4)について、 既存の利尿薬とトルバプタンとの作用機序・薬理作用が異なることは、上記(ア)のと おり、むしろ動機付けとなるといえる。5)について、本件優先日前に頒布された刊 行物である甲149(Florence Wongほか「A Vasopression Receptor Antagonist (VPA-985) Improves Serum Sodium Concentration in Patients With Hyponatremia: A Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Trial 」37 Hepatology 182 (2003))には、NYHAクラスIV)のうっ血性心不全患者に対し、ト ルバプタンと同じ選択的バソプレシンV2受容体拮抗薬である「VPA−985」\nを既存の利尿薬と組み合わせて投与したところ、低用量群(25mgを1日2回投 与)では、起立性血圧、血清クレアチニン値及び血清バソプレシン濃度の有意な変\n化なしに、プラセボ対照群と比して有意な水利尿反応及び血清ナトリウム値の増加 が得られた旨が記載されている。同記載からすると、原告が主張するように、選択 的バソプレシンV2受容体拮抗薬につき、血中バソ\プレシン濃度上昇による悪影響 がある可能性を指摘する文献があったことを考慮しても、適切な用量設定等により\n安全に効果を得られることが示されていたのであるから、トルバプタンをNYHA クラスIV)の重症患者に、また急性心不全の患者に適用することが禁忌であったとは いえず、阻害要因となるべきものとは認められない。6)については、前記(3)ウ(ウ) のとおり、トルバプタンと組み合わされる本件発明1の「最適の治療」と甲2発明 の「水分制限なしの標準治療」に実質的に異なるところはなく、また、前記(2)ウ(イ) bのとおり、甲2発明における「安定したフロセミド用量(20〜240mg/日)」が、治療の制限を意味するものとは読み取れない。 したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2024.04.10
令和5(ワ)70114 不当利得返還等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月27日 東京地方裁判所
2 サポート要件違反があるか(争点4−1)について
本件発明1について
ア 本件発明1の構成要件1Fは、「前記信号演算として、横加速度を検出す\nる加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 G(Ghosei)の導出方法を少なくとも有し、」というものであり、構\n成要件1Hは、「当該車両において、前記傾斜角速度(Ψ)と前記補正後の 横G(Ghosei)の組合せにより、車両挙動が判断され、・・・」とい うものであり、本件発明1は、算出された補正後の横G(Ghosei)を 利用するECUによって車輪を適切に制動し、これによってロール方向の挙 動の抑制を図る車両ブレーキ制御装置(構成要件1I)であるとされている。\nそして、本件発明1は、前記1のとおり、自動二輪車等の制御装置につ いて、従来は、正確な傾斜角の検出ができなかったという課題を解決して、 車両の走行状態での正確な横Gを検出できるようにしたというものである。 これらからすると、構成要件1F及び1Hの「横G(Ghosei)」は、\n従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、 車両の傾斜走行状態での正確な横Gであると認められる。 ここで、制動指令の前提となる「横G(Ghosei)」は、「横加速度を 検出する加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った」(構\n成要件1F)ものであるとされていることから、「横G(Ghosei)」 は、横加速度を検出する加速度センサーの検出値を基に、これに補正をか けて得られる値であると理解できる。もっとも、本件発明1の特許請求の 範囲には、「横G(Ghosei)」について、単に加速度センサーの値か ら「ロールによる影響を取り除く演算を行った」(構成要件1F)と記載す\nるのみで、どのような演算をするかは明示されていない。そうすると、特 許請求の範囲には、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載さ れ、その解決のための構成は記載されていないといえる。\n
イ 本件明細書には本件発明の意義として前記1のとおりの記載があり、車両 の正確な傾斜角の検出ができず、正確な横Gを検出できなかったという課題 を解決して、車両の走行状態での正確な横Gを検出できるようにしたという ものであるとされている。
もっとも、本件明細書には、従前は検出できなかった正確な傾斜角の検出 をどのようにするかや、その傾斜角が判明した場合に正確な横Gを算出する ためにどのような補正を行うかについての記載はない。
他方、本件明細書には、センサーによる検出結果を補正して横Gを算出す る方法として、Ghosei = Gken − (Ψ・Rhsen) (式A) との記載がある(【0073】)。本件明細書の【0073】では、「Gken」 は、実際の走行傾斜時に検出される検出横Gであるとされ、「Ψ」は傾斜角 速度、「Ghosei」はΨを用いたGkenの補正後の横Gであるとされ ていて(なお、「Rhsen」について、本件明細書には定義がないものの、 「hsen」について路面とセンサとの距離であることを示唆する記載があ ったり(【0050】【0058】【0061】、図8、9)、「RはGセンサー #23の実車取付けの高さ(図8b hsen)」(【0063】)との記載、 Ψ・Rhsenについて、Rhsenに1を代入した上で「但し、センサー 取り付け高さ Rを1mとする。」との記載(【0074】)があったりする ことから、「Rhsen」車体を垂直にしたときのセンサ取り付け位置の高 さであることを一応推測できる。)、その「Ghosei」は、本件発明の課 題として言及されている「正確な横G」であると理解することができる。そ して、式Aは、その体裁から、本件発明の意義(前記1参照)として記載さ れている、「横Gセンサー」で検出されたGkenと「角速度センサー」で 検出されたΨを用いて「正確な横G」を算出する方法を記載した式であると 理解できる。
しかしながら、「Ψ・Rhsen」からは、傾斜角は算出されないし、式 Aから、傾斜角を算出することなく「正確な傾斜角の検出ができなかった諸 問題」が解決されていると理解することもできない。さらに、Ghosei 及びGkenは、加速度の次元(長さ/時間2)を有し、Ψ・Rhsenは 速度の次元(長さ/時間)の次元を有していることから、式Aは物理学上、 明らかに意味を持たない式である(弁論の全趣旨)。 そして、本件明細書には、式Aの他に、センサーによる測定値を基に「正 確な横G」を算出する方法についての記載はない。
ウ 本件明細書によれば、本件発明は、車両制御のためには「正確な横G」の 取得が必要であるところ、横加速度を検出する加速度センサーの値をその まま用いることができないこと、当該値から正確な横Gを算出するために は傾斜角度を取得することが必要だがそれができないことが課題として記 載され、本件発明はその課題に対して、車両の傾斜走行状態での正確な横 Gを算出したものであるとされており、「横加速度を検出する加速度セン サーのロールによる影響を取り除く演算を行った」という「横G(Ghos ei)」についての、当該演算が、本件発明の課題解決の根幹に当たる部分 であるといえるといえる。 しかしながら、特許請求の範囲には、その演算について、従来の課題を 解決するに足りる構成は記載されていない。また、本件明細書の発明の詳\n細な説明をみても、関係する記載は前記イのとおりである。本件明細書の 式A(【0073】)が、一応、上記の演算であると理解することはできる が、他に、関係する記載はない。そして、前記イのとおり、式Aは本件発明 の課題とされている傾斜角を算出しない上、そもそも物理学上意味をなさな い式であり、当業者はおよそ式Aを用いて車両制御に利用可能な横G(Gh\nosei)が算出できると理解できるものではない。
エ 原告は、本件明細書の記載は、別紙対比表のとおり誤記があり、正しく\nは同表の「訂正後」欄記載のとおりであると主張する。構\成要件1Fの「演 算」については、式Aのみが当たり得るところ、式Aは前記イで認定した とおり、次元の異なる物理量の差し引きをしていることから物理学上意 味をなさない式であり、当業者は、式Aに何らかの誤りがあると理解する ことができるといえる。この点について式Aについて、原告が主張すると おりGhosei=Gken−(Ψ.・Rhsen) (式A´)(ただし、「Ψ .」は傾斜角加速度)の誤記であると理解すれば、減算される物理量の次元が異なるという問題については解消される。しかし、次元を整える目的のみであれば、その訂 正の方法は式A´とすることに限られるものではないのであり、他に解消 方法を考え得るのであり、その考え得る解消方法が物理法則やそれを踏ま えた技術常識等に照らして不合理であることを認めるに足りる証拠はな い。そうすると、式Aの記載のみから、どのような誤記であるかのかが一 義的に定まるものであるとはいえない。 さらに、原告は、式Aについて「Ψ」を「Ψ.」に訂正するに当たって、 そのままでは式Aに関する説明が記載されている【0073】のその他の 記載と矛盾が生じるため、式Aのみならず、同段落における他の「Ψ」の 記載も「Ψ.」に訂正し、1か所の「傾斜角速度」との記載も「傾斜角加速 度」に訂正するものとしている。
しかし、原告が主張する訂正により、訂正後の【0073】は、「この補 正後の横G(Ghosei)は、(0063)式のGkenから傾斜角加速 度(Ψ.)を用いた補正であり、(0067)の式に対して、傾斜角が変化しない状況である。すなわち、式の「Ψ.・Rhsen」の項については、ゼロとなることから二つの式を整理し記述すると、・・・」との記載を含むことになるが、傾斜角加速度(Ψ.)がゼロであっても、傾斜角速度(Ψ)がゼロでないとき(定速傾斜時)は傾斜角が変化する状況なのだから、傾斜角加速度(Ψ.)に関する項「Ψ.・Rhsen」がゼロであることは直ちに「傾斜角が変化しない状況」を意味するものではないから、原告が主張する訂正をすると同記載部分の趣旨が理解できなくなってしまう。他方で、当該箇所について、「Ψ」を「Ψ.」に訂正しなければ、その内容は理解可能である。\n
同様に、原告が主張する訂正後の【0073】の「・・・この様に、式 の「Ψ.・Rhsen」の項について、ゼロにしたデーターは、定常円旋回 時に得られたデーターと呼ばれることがある。・・・」との記載についても、 定常円旋回時には、傾斜角が一定になるため、「傾斜角速度」が0になると ころ、「傾斜角加速度」に関する項が0になっても、「傾斜角」が変化しな いとは限らない(傾斜角加速度が0の場合には、定速傾斜の場合も含まれ る。)のであるから、訂正すると同記載部分の趣旨が理解できなくなって しまう。この点についても、当該箇所について訂正しなければその内容は 理解可能である。\n
さらに、式Aは、測定された加速度(Gken)を角速度(Ψ)の値に よって補正する式であるといえるが、これは、「走行時の横Gセンサーと 角速度センサーを関連付けることによって、従来は、正確な傾斜角の検出 ができなかった諸問題を解決」(前記1)という本件明細書に記載されて いる課題解決の基本的な方法として明示されている手法に文言上最も沿 うものである。他方、式Aを式A´に訂正すると少なくとも直接的にはこ れに文言上最も沿うものとはいえない内容になってしまう。 また、原告は、誤記を訂正した後の【0063】の記載によれば、傾斜 走行時に検出される検出横G(Gken)には、ロール速度の変化の影響 である加速度成分(Ψ.・Rhsen)が重畳されていること、重畳された 当該加速度成分は、傾斜角速度センサーの速度変化である傾斜角加速度 (Ψ.)を減算することで取り除くことができることが分かるなどと主張す る。
しかし、前記イで説示したとおり、本件明細書においてセンサーで取得 した加速度の値を修正して得られる制御に用いる加速度として言及され ているのは【0073】の横G(Ghosei)のみであり、【0063】 には、本件発明1の「横G(Ghosei)」の算出方法は記載されてい ない。仮に、【0063】に本件発明1に係る「加速度センサーのロール による影響を取り除く演算」が「Ψ.・Rhsen」を減算する趣旨であることを示唆する記載があると評価できるとしても、【0073】の方がより直接的な制御に用いる修正後の加速度を算出する方法に関する記載であると評価できるにもかかわらず、式Aについては、前記イで説示した問題がある。
また、【0063】には、Gken=g・cosΦ・tanρ−Ψ・Rhen (訂正後は「Gken=g・cosΦ・tanρ+Ψ.・Rhsen」)という式が記載されており、訂正後の式には「Ψ.・Rhsen」という項が含まれているものの、これを減算(訂正後は加算)した「g・cosΦ・tanρ」が物理学上、本件発明で算出することが課題とされている「正確な横G」に当たり、同物理量が判明すれば「正確な傾斜角の検出ができなかった諸問題」を解決できるものと理解できると認めるに足りる証拠はない。そうすると、仮に【0063】の記載が原告の主張するとおりの誤記であると認定できるとしても、当該式のみからでは、センサーによる検出値である「Gken」から「Ψ.・Rhsen」を減算することが課題解決につながり、構成要件1Fの「ロールによる影響を取り除く演算」に当たるものであると理解できるとはいえない。\n
また、原告の主張中には、【0063】より前の【0061】、【0062】の記載から【0063】の記載が誤記であることが理解できると主張する部分があるが、【0061】、【0062】にも多数の誤記があり、「Ψ」と「Ψ.」に関する誤記のみならず「−」と「+」に関する誤記まであり、どの部分が誤記であるのか容易に理解できるとは認め難い。もともと、本件明細書では、その全体にわたって、その説明の当初から基本的に一貫して加速度の次元の物理量から角速度(周速度)の次元の物理量を加算ないし減算するという式を前提とする内容で説明が記載されていて、前記エで説示したとおり、当該式に直接関連しない部分についてもこれと矛盾しない内容になっていた。そのような本件明細書について、当該式を訂正すると別の部分と矛盾が生じる内容になっている。これらからすると、当業者は、本件明細書に記載の誤りがあることを理解するとしても、本件明細 書において、本来どのようなことが記載されようとしていたのかや、どの部分がどのような誤記であるかを理解することができるとは認められない。
以上のとおり、当業者は、式Aに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Aの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式A´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Aの訂正と整合するように、本件明細書の式Aに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。
これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Aが式A´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Aについて式A´の誤記であると理解できることを前提とする原告の主張はその前提を欠く。
オ 本件発明1の意義は前記1のとおりである。そして、本件発明1の構成\n要件1Fには、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載され、 その解決のための構成は記載されていないといえるところ、前記ウのと\nおり、その課題の解決のための構成について、本件明細書に記載がある\nとはいえない。また、その記載がないにも関わらず、当該課題について、 当業者がそれを解決できると認識できることを認めるに足りない。そう すると、本件発明1は、本件明細書に記載された説明で、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるとはいえないし、当業者が技術常識に照らし発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。よって、本 件発明1は、本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
本件発明2について
ア 本件発明2は、算出された補正後の横G(Ghosei)を利用する、自 動二輪車の車両解析装置であるとされており、横G(Ghosei)の算出 方法については、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと傾斜 角速度の積との差分を求めるものとされている。 本件明細書においてこれに関する記載としては式Aに関する記載がある が、当該記載は本件明細書に記載された課題を解決する発明であると理解で きないものであることについては、前記 で説示したとおりである。他に本 件明細書には当該部分に係る記載があるとはいえない。よって、本件発明2 は本件明細書に記載されている発明であるとはいえない。
イ この点について、原告は、構成要件2Eの補正後の横G(Ghosei)\nの算出方法について、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと 「傾斜角速度」の積との差分との記載は、横加速度から加速度センサーの 車両取り付け高さと「傾斜角加速度」の積との差分の誤記であると主張す る。 しかし、本件明細書には、補正後の横Gに関する記載は式Aに関する記 載しかなく、ここには、「傾斜角加速度」の積との記載はない。原告は、式 Aが式A´の誤記であると主張するが、これが誤記であると理解できない ことについては前記 エで説示したとおりである。そうすると、仮に構成\n要件2Eが2E´の誤記であると理解できるとしても、本件発明2が本件 明細書に記載された発明であるとは認められない。 よって、本件発明のいずれについても、本件明細書に記載された発明であ るとはいえず、サポート要件を欠くものであると認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.03.28
令和4(行ケ)10127等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月18日 知的財産高等裁判所
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2は、「セレコキシブ粒子が、 ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」との発明特定事項 (以下「本件ピンミル構成」ということがある。)を含む(削除された請求\n項を除く他の請求項も、請求項1又は2を直接又は間接的に引用することで 本件ピンミル構成を含むことになっている。)ところ、本件ピンミル構\成を 巡っては、そのクレーム解釈(PBPクレームといえるか否か、「ピンミル のような」は衝撃式ミルの単なる例示か、衝撃式ミルの一部に限定する構成\nかなど)と、当該クレーム解釈を前提とした明確性要件の適合性の議論が重 層的に争われているので、以下、順次検討していく。
(3) まず、本件ピンミル構成がPBPクレームに当たるかについて検討するに、\n本件ピンミル構成に関する本件明細書の【0024】、【0190】の記載\nが、セレコキシブ粒子を粉砕する製造工程、製造方法を開示していることは 明らかであり、したがって、本件訂正によって特許請求の範囲の発明特定事 項とされるに至った本件ピンミル構成についても、「ピンミルのような衝撃\n式ミルで粉砕」するという製造方法をもって物の構造又は特性を特定しよう\nとするもの(その意図が成功しているかどうかはともかく)と理解される。 この限度では、被告が主張し、本件審決が判断を示しているとおりである。 第1事件原告は、製薬組成物の製造には複数の工程が必要であるなどとし てこれを争うが、そのような工程の全てを特定することがPBPクレームと しての必須条件とはいえない。実質的に製造方法の明確性を問題にしている とすれば、この点からの検討は後に示すこととする。
(4) 次に、本件ピンミル構成の意味するところ(例示か限定か)を検討するに、\n「ピンミルのような衝撃式ミル」との特許請求の範囲の文言自体に着目して 考えた場合、1)ピンミルは単なる例示であって衝撃式ミル全般を意味すると いう理解、2)衝撃式ミルに含まれるミルのうち、ピンミルと類似又は同等の 特性を有する衝撃式ミルを意味するという理解のいずれにも解する余地が あり、特許請求の範囲の記載のみから一義的に確定することはできない。 そこで、本件明細書の記載を参照するに、本件明細書の【0024】には、 「セレコキシブと賦形剤とを混合するに先立ち、ピンミル(pin mil l)のような衝撃式ミルでセレコキシブを粉砕させて、本発明の組成物を作 製することは、改善された生物学的利用能を提供するに際して効果的である\nだけでなく、かかる混合若しくはブレンド中のセレコキシブ結晶の凝集特性 と関連する問題を克服するに際しても有益であることを発見した。ピンミル を利用して粉砕されたセレコキシブは、未粉砕のセレコキシブ又は液体エネ ルギーミルのような他のタイプのミルを利用して粉砕されたセレコキシブ よりは凝集力は小さく、ブレンド中にセレコキシブ粒子の二次集合体には容 易に凝集しない。減少した凝集力により、ブレンド均一性の程度が高くなり、 このことはカプセル及び錠剤のような単位投与形態の調合において、非常に 重要である。これは、調合用の他の製薬化合物を調合する際のエアージェッ トミルのような液体エネルギーミルの有用性に予期せぬ結果をもたらす。特\n定の理論に拘束されることなく、衝撃粉砕により長い針状からより均一な結 晶形へ、セレコキシブの結晶形態を変質させ、ブレンド目的により適するよ うになるが、長い針状の結晶はエアージェットミルでは残存する傾向が高い と仮定される。」との記載が、【0135】には、「セレコキシブは先ず粉 砕される若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕機若し くは破砕機が利用することが可能であるが、セレコキシブのピンミリングの\nような衝撃粉砕により、他のタイプの粉砕と比較して、最終組成物に改善さ れたブレンド均一性がもたらせる」との記載がある。
以上の記載に上記(3)の解釈を併せて考えると、本件ピンミル構成は、被\n告が主張(第3の3(6)ア)するように、本件訂正発明に係る薬剤組成物の含 むセレコキシブ粒子が、ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子に見られる のと同様の、長い針状からより均一な結晶形へと変質されて、凝集力が低下 し、ブレンド均一性が向上した構造、特性を有するものであることを特定す\nる構成であって、したがって、「ピンミルのような衝撃式ミル」とは、ピン\nミルに限定されるものではなく、上記のような構造、特性を有するセレコキ\nシブ粒子が得られる衝撃式ミルがこれに含まれ得るものと理解するのが相 当である。
(5) 以上を前提に、本件ピンミル構成を含む本件訂正発明の特許請求の範囲の\n記載が明確性要件を満たすかどうかを検討する。
ア 衝撃式粉砕機に分類される粉砕機としては、本件審決も認定していると おり、多種多様なものがある(ハンマーミル、ケージミル、ピンミル、デ ィスインテグレータ、スクリーンミル等が知られており、ハンマーの形状 によっても、ナイフ型、アブミ型、ブレード型、ピン型等がある。甲イ1 11、112、136)ところ、上記(4)で示したクレーム解釈によると、 衝撃式粉砕機によって粉砕されたセレコキシブ粒子を含む薬剤組成物で あっても、本件特許の技術的範囲に属するものと属しないものがあること になるが、本件明細書に接した当業者において、「ピンミルで粉砕された セレコキシブ粒子に見られるのと同様の、長い針状からより均一な結晶形 へと変質されて、凝集力が低下し、ブレンド均一性が向上した構造、特性\nを有するセレコキシブ粒子」を製造できる衝撃式粉砕機がいかなるものか を理解できるとは到底認められない。すなわち、一般に、明細書に製造方 法の逐一が記載されていなくても、当業者であれば、明細書の開示に技術 常識を参照して当該製造方法の意味するところを認識できる場合も少な くないと解されるが、本件の場合、本件明細書には、「ピンミルで粉砕さ れたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均 一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がない ため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、 ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるもの なのかも明らかとなっていない。そのため、技術常識を適用しようとして も、いかなる特性に着目して、ある衝撃式ミルが本件ピンミル構成にいう\n「ピンミルのような衝撃式ミル」に当たるか否かを判断すればよいのかと いった手掛かりさえない状況といわざるを得ない。
イ そうすると、本件明細書等に加え本件出願日(明確性要件の判断の基準 時)当時の技術常識を考慮しても、「ピンミルのような衝撃式ミル」の範 囲が明らかでなく、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」するというセ レコキシブ粒子の製造方法は、当業者が理解できるように本件明細書等に 記載されているとはいえないから、本件訂正発明は明確であるとはいえな い。
ウ ところで、PBPクレームは、物自体の構造又は特性を直接特定するこ\nとに代えて、物の製造方法を記載するものであり、そのような特許請求の 範囲が明確性要件を充足するためには、不可能・非実際的事情の存在が要\n求されるのであるが、本件においては、不可能・非実際的事情を検討する\n以前の問題として、前記ア、イに示したようにそもそも特許請求の範囲に 記載された製造方法自体が明確性を欠くものである。
(6) 本件審決は、「ピンミルのような衝撃式ミルは、いわゆる衝撃式粉砕機で あり、粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕機と は異なる粒度分布の粉体を作製する装置であることが理解できるから明確 である」としており、これは、「ピンミルのような」について、「いわゆる 衝撃式粉砕機」のなかでも、さらに、「粉砕された粉体は、ジェットミルの ような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」こと のできる装置であるとの意味づけを与えた認定であると解される。 そして、「ピンミルによる」粉砕が、「粉砕された粉体は、ジェットミル のような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」も のであることについて、本件審決は、本件明細書の、ピンミルと、エアージ ェットミルのような他のタイプのミルとの粉砕物の凝集力の違いに関する 記載(【0024】)、及び、粉砕装置の粉砕機構が異なれば得られる粒子\nの粒度分布が異なるという技術常識を認定したことにより、導き出している ものと認められる。
しかし、本件明細書には、凝集力の違いが、粉砕装置の違いに基づく粒子 の粒度分布の違いに起因するものであるとの記載も示唆もない。粉砕装置の 違いが、粒度分布の違い以外の粒子特性を導くことも当然考えられるところ である(これを否定する技術常識があるとは認められない。)。そうすると、 「ピンミルのような」が、「衝撃式ミル」に対して、さらに「粉砕された粉 体は、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の 粉体を作製する装置」であるとの意味づけを与えた本件審決の解釈は、本件 明細書等の記載及び技術常識を考慮しても、無理があるものといわざるを得 ない。
(7) 以上より、不可能・非実際的事情の検討をするまでもなく、本件訂正後の\n請求項1、2、4、5、7〜13、15、17〜19の記載は明確性要件に 違反するものであり、取消事由3は理由がある。
3 取消事由2(サポート要件に関する判断の誤り)について
上記2のとおり、取消事由3が認められる以上、本件審決(原告らが取消しを 求めている請求項に関する部分)は既に取消しを免れないものである。しかし、 明確性要件違反の原因となった本件ピンミル構成は、前訴判決がサポート要件\n違反を肯定する判断をしたことを受けて、その瑕疵を回避するために特許請求 の範囲に加えられたという本件の経過を踏まえると、本件訂正後の特許請求の 範囲を前提としたサポート要件の適合性の問題(取消事由2)についても、併せ て判断を示すことが適切と考えられることから、以下に当裁判所の判断を示し ておくこととする。
なお、その場合、本件ピンミル構成を含む特許請求の範囲は明確性要件を欠\nくことが前提となるから、サポート要件の判断においても、本件ピンミル構成\nを発明特定事項として考慮しない前提で検討することとする。
(1) 前訴判決がサポート要件違反を認めて第1次審決を取り消したことは前 述のとおりであるところ、本件においては、前訴判決の拘束力がいかなる範 囲に及ぶかが問題となっているので、まずこの点を検討する。
ア 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判 決が確定したときは、審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判 事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は 行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法3 3条1項の規定により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束 力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる ものであるから、審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断を することは許されない(最高裁判所昭和63年(行ツ)第10号平成4年 4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁)。
この拘束力は、行政庁が裁判所の判断に反して同一の処分を繰り返し、 同一の案件が行政庁と裁判所の間を往復することを避けるためのもので あり、原則として主文についてのみ生ずる既判力と異なり、判決理由中の 判断であっても、主文に直結する認定判断、すなわち主要事実の認定及び その法規範への当てはめの判断にも及ぶものである。他方、判決の結論と 直接関係のない傍論の説示はもとより、主要事実を確定する過程における 間接事実の認定やその評価にまで及ぶものではなく、また、結論に至る推 論過程を基礎づける論拠、反対主張を排斥する理由等の説示についても同 様である。取消判決の理由中の説示の全てが拘束力を有するとした場合、 結論に影響する意味合いや程度も様々な議論が独り歩きを始め、その解 釈・適用を巡って新たな紛争を拡大させることとなり、そのような状況は、 行政事件訴訟法33条1項の想定するところではないというべきである。
イ 以上を前提に、前訴判決(甲イ86)の判断構造をみておく。\n
(ア) 前訴判決は、まず、サポート要件適合性について、「所定の数値範囲 を発明特定事項に含む発明について、特許請求の範囲の記載が同号所定 の要件(サポート要件)に適合するか否かは、当業者が、発明の詳細な 説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含まれる数値範囲の 全体にわたり当該発明の課題を解決することができると認識できるか 否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である」とし、「これ を本件発明1についてみると・・・『粒子の最大長において、セレコキ シブ粒子のD90が200µm未満である粒子サイズの分布を有する』こ とを特徴とするものであるから、所定の数値範囲を発明特定事項に含む 発明であるといえる。」としているので、「D90が200µm未満であ る粒子サイズの分布を有する」本件発明1について、その数値範囲の全 体にわたりその課題を解決できるものであるかどうかを検討している。
(イ) そして、前訴判決は、(a)一方で、本件明細書の【0022】、【01 24】、【0135】の記載から、未調合のセレコキシブを粉砕し、「セ レコキシブのD90粒子サイズが約200μm以下」とした場合には、セ レコキシブの生物学的利用能が改善されること、セレコキシブのピンミ\nリングのような衝撃粉砕により、他のタイプの粉砕と比較して、最終組 成物に改善されたブレンド均一性がもたらせることを示したものとい えるとしつつ、(b)他方で、1)本件発明1の請求項1には、セレコキシブ を微細化する具体的な方法は記載されておらず、本件発明1の「微粒子 セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉砕」により粉砕された ものに限定する旨の記載もなく、かえって、本件明細書の【0135】 には、さまざまな粉砕機・破砕機が利用可能とされていること、2)本件 明細書の【0008】には、長く凝集した針を形成する傾向を有する結 晶形態を有する未調合のセレコシブは、錠剤成形ダイでの圧縮の際に、 融合して一枚岩の塊になり、他の物質とブレンドさせたときでも、セレ コキシブの結晶は、他の物質から分離する傾向があり、セレコキシブ同 士で凝集し、セレコキシブの不必要な大きな塊を含有する、非均一なブ レンド組成物になるとの記載があること、3)本件優先日当時、粉砕によ り溶出は改善されるが、難溶性薬物は凝集して溶解速度が遅くなること があることが周知又は技術常識であったことを踏まえると、(c)難溶性 薬物であるセレコキシブについて、「『セレコキシブのD90粒子サイズが 約200μm以下(「未満」の誤記と認められる。)』の構成とするこ\nとによりセレコキシブの生物学的利用能が改善されることを直ちに理\n解することはできない」(以下「説示(c)」という。)とした。 また、本件明細書には、(d)「D90」の値を用いて粒子サイズの分布 を規定することの技術的意義や「D90」の値と生物学的利用能との関係\nが説明されていないことを述べた上で、(e)難溶性薬物の原薬の粒子径 分布が化合物によって種々の形態を採ることに照らすと、「200μm 以上の粒子の割合を制限しさえすれば、90%の粒子の粒度分布がどの ようなものであっても、生物学的利用能が改善されるものと理解するこ\nとはできない」(以下「説示(e)」という。)とした。そして、(f)本件 明細書の例11及び例11−2の実験結果の記載は、微粉化したセレコ キシブを含有する「組成物A」及び「組成物B」(これらに含まれるセ レコキシブのD90粒子サイズは約30μmと推認される。)の生物学的 利用能は、未粉砕、未調合のセレコキシブである「組成物F」の生物学\n的利用能より高いことを示しているが、「組成物A」及び「組成物B」\nに加湿剤として含まれるラウリル硫酸ナトリウムが、生物学的利用能の\n実験結果に影響した可能性が高いものと認められ、この実験結果から、\n本件発明1の「セレコキシブ粒子のD90が200μm未満」の数値範囲 の全体にわたり、未調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善\nするものと認識することはできないとした。
(ウ) 前訴判決は、以上を踏まえた結論として、本件明細書の発明の詳細な 説明の記載及び本件優先日当時の技術常識から、当業者が、本件発明1 に含まれる「粒子の最大長において、セレコキシブ粒子のD90が200 μm未満」の数値範囲の全体にわたり本件発明1の課題を解決できると 認識できるものと認められないから、本件発明1は、サポート要件に適 合するものと認めることはできないとした。
(エ) 前訴判決の本件発明2〜4のサポート要件の適合性に関する判断は、 以下のとおりである。
本件発明2は「前記粒子の最大長において、前記セレコキシブ粒子の D90が100μm未満であること」を、本件発明3は同40µm未満で あることを、本件発明4は同25µm未満であることをそれぞれ発明特 定事項とするものであるところ、セレコキシブ粒子のD90が200µm 未満である本件発明1がサポート要件に適合するものと認めることが できないことは前記のとおりであると指摘した上で、例11及び例11 −2の実験結果も、ラウリル硫酸ナトリウムが生物学的利用能の実験結\n果に影響した可能性が高いものと認められることに照らすと、上記実験\n結果から、D90が約30µmよりも小さい値とした場合において、未調 合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善するものと認識する\nことはできないとして、本件発明2〜4はサポート要件に適合するもの と認めることはできないとした。
(オ) 前訴判決は、本件発明5、7〜19については、請求項1記載の製薬 組成物を発明特定事項に含むものであるところ、「本件発明1がサポー ト要件に適合するものと認めることができないことは前記‥のとおり であるから」という理由により、サポート要件に適合するものと認める ことはできないとした。
ウ 取消判決の拘束力の範囲に関し上記アで述べたところに従って、前訴判 決の拘束力の生ずる部分を検討するに、主文に直結する認定判断(主要事 実の認定及びその法規範への当てはめの判断)は、本件訂正前の特許請求 の範囲及び本件明細書の記載並びに本件優先日当時の技術常識(主要事実 の認定に当たる。)を前提に、本件訂正前の特許請求の範囲によって特定さ れる発明(本件発明)が特許法36条6項1号の要件に適合しないとした 判断(法規範への当てはめに当たる。)にほかならず、前訴判決中、拘束力 が生ずるのは当該部分であると解される。
他方、前訴判決の判断過程では、結論に至る推論過程を基礎づける論拠 として、説示(c)、(e)等の様々な理由が示されているが、その逐一について 拘束力が生ずるものではないことは、上記アで述べたとおりである。
エ そもそも、サポート要件は、明細書の記載(特許を受けようとする発明の 開示)から見て広すぎる特許請求の範囲を防ぐ役割を果たすものであると ころ、被告は、本件訂正前の本件発明につきサポート要件違反を認めた前 訴判決を受けて、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正の請求をし ており、これが訂正要件を充足することは前記1のとおりである。 その結果、本件では、本件訂正後の特許請求の範囲(ただし、本件ピンミ ル構成は発明特定事項として考慮しない。)に基づく本件訂正発明のサポ\nート要件の適合性が問題となっているのであって、同じサポート要件の適 合性の問題であっても、本件訂正前の特許請求の範囲を前提とする前訴判 決とは判断対象が異なる。それにもかかわらず、「前訴判決の説示(c)、(e) 等に照らせば、本件訂正後の本件訂正発明についても、前訴判決と同様の 判断が妥当する(はずである)」といった推論を戦わせるのは、取消判決の 拘束力の問題とは異質の議論といわざるを得ない。
オ 本件審決は、前訴判決の説示(e)(難溶性薬物の原薬の粒子径分布は・・・、 200μm以上の粒子の割合を制限しさえすれば、90%の粒子の粒度分 布がどのようなものであっても、生物学的利用能が改善されるものと理解\nすることはできない旨の判示)について、これは、生物学的利用能の改善の\n観点では、90%の粒子の粒度分布も重要であることを述べたものである との理解を示している。そして、ピンミルのような衝撃式粉砕機(衝撃式ミ ル)により粉砕された粉体と、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕 機により粉砕された粉体は、異なる粒度分布の粉体となるという一般的な 知見をもとに、この粒度分布の差異は粉砕機構の差異に由来するものであ\nり、本件明細書に記載されたピンミルのような衝撃式ミルでの粉砕は、他 のタイプのミルとは異なる粒度分布を形成することにより、凝集性及びブ レンド均一性の改善に寄与するとして、説示(c)、(e)を本件訂正発明1が サポート要件に適合する理由の1つにしている。 これに対し、原告らは、D90を30μmにし、「セレコキシブ粒子が、 ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」との発明特定事 項を加えても、90%の具体的な粒度分布は明らかにならないとして、説 示(c)、(e)を本件訂正発明1がサポート要件に適合しない理由としている。 これらは、いずれも、前訴判決の説示(c)、(e)を独立して取り上げ、同判 断に拘束力が生じることを前提とするものと解されるが、失当というべき である。
拘束力の問題を離れて考えても、前訴判決の当該部分の判示は、製薬組 成物の特徴が、実質的に「D90が200µm未満である粒子サイズの分布を 有する」ことで特定されていた本件発明1について、未調合のセレコキシ ブに対して生物学的利用能が改善されるという課題を解決できるものであ\nるかどうかを検討する過程において、上記特定事項で特定しさえすれば、 課題を解決できるものと理解することはできないと判断したものであって、 前訴判決が、本件発明1がサポート要件に適合するには、90%の粒度分 布を示すことが必須の要請であると判断しているとの趣旨まで読み込むこ とには無理がある。
カ よって、前記ウのとおり、前訴判決の拘束力は、本件訂正前の特許請求の 範囲及び本件明細書の記載並びに本件優先日当時の技術常識を前提に、本 件訂正前の特許請求の範囲によって特定される発明(本件発明)が特許法 36条6項1号の要件に適合しないとした判断について生じることを前提 に、サポート要件の適合性について判断する。
(2) 特許法36条6項1号は、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細 な説明に実質的に裏付けられていなければならないというサポート要件を 定めるところ、その適合性の判断は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な 説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な 説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該 発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して 判断すべきものと解される。特に、所定の数値範囲を発明特定事項に含む発 明について、特許請求の範囲の記載が同号の要件に適合するか否かは、当業 者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含ま れる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができると認 識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。
ア 前記第2の2(3)の本件明細書の開示事項によれば、本件訂正発明の課題 は、未調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経\n口運搬可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することであり、\n取り分け、水溶液に溶解しにくいセレコキシブ粒子の特質から、混合中に セレコキシブ同士で凝集し、非均一なブレンド組成物になるとの問題の解 決にあるものと認められる。
具体的には、本件明細書の【0008】では、「・・・セレコキシブは、 水溶性媒体には異常なほど溶解しない。例えば、カプセル形態で経口投与 させた場合、未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために、 容易には溶解せず、分散もしない。加えて、長く凝集した針を形成する傾 向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは、通常、錠剤成形ダイ での圧縮の際に、融合して一枚岩の塊になる。・・・」として、セレコキシ ブが、水溶性媒体には異常なほど溶解しないこと、未調合のセレコシブが 長く凝集した針を形成する傾向を有することを解決すべき問題として挙げ ている。
イ 上記課題に関係する技術常識として、証拠(甲イ7、16、23、65〜 68、80、103)及び弁論の全趣旨によれば、本件出願日当時、1)粉砕 によって薬物の粒子径を小さくし、比表面積(有効表\面積)を増大させるこ とにより、薬物の溶出が改善されるが、他方で、難溶性薬物については、溶 媒による濡れ性が劣る場合には、粒子径を小さくすると凝集が起こりやす くなり、有効表面積が小さくなる結果、溶解速度が遅くなることがあるこ\nと、2)疎水性の難溶性物質であっても、界面活性剤が存在すると、微粒子は 凝集せずに均一に溶液中に分散され、粒子サイズが小さいほど溶出速度は 大きくなることは、周知又は技術常識であったものと認められる。
ウ 上記技術常識を踏まえて、本件訂正発明が上記課題を解決できると認識 できる記載が本件明細書に開示されているかどうかにつき、さらに検討す る。
(ア) 本件明細書の【0022】には「本発明の組成物は微粒子の形態のセ レコキシブを包含する。セレコキシブの一次粒子は、例えば、製粉若し くは粉砕により、又は溶液から沈殿させて生成させ、凝集して二次の集 合体粒子が形成される。本願で利用する用語「粒子サイズ」とは、特に 本願で指摘しない限り、一次粒子の最長の大きさのことをいう。粒子サ イズは、セレコキシブの臨床的効果に影響を与える重要なパラメータで あると考えられる。よって、別の実施例では、発明の組成物は、粒子の 最長の大きさで、粒子のD90が約200μm以下、好ましくは約100 μm以下、より好ましくは75μm以下、さらに好ましくは約40μm 以下、最も好ましくは約25μm以下であるように、セレコキシブの粒 子分布を有する。通常、本発明の上記実施例によるセレコキシブの粒子 サイズの減少により、セレコキシブの生物学的利用能が改良される。」、\n【0124】には「カプセル及び錠剤中でのセレコキシブの粒子サイズ カプセル若しくは錠剤の形で経口投与されると、セレコキシブ粒子サイ ズの減少により、セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見し\nた。したがって、セレコキシブのD90粒子サイズは約200μm以下、 好ましくは約100μm以下、より好ましくは約75μm以下、さらに 好ましくは約40μm以下、最も好ましくは25μm以下である。例え ば、例11に例示するように、出発材料のセレコキシブのD90粒子サイ ズを約60μmから約30μmに減少させると、組成物の生物学的利用 能は非常に改善される。加えて又はあるいは、セレコキシブは約1μm\nから約10μmであり、好ましくは約5μmから約7μmの範囲の平均 粒子サイズを有する。」としており、セレコキシブの粒子サイズを減少 させることで、セレコキシブの生物学的利用能が改善されることが記載\nされている。
(イ) また、本件明細書の【0024】の「セレコキシブと賦形剤とを混合 するに先立ち、ピンミル(pin mill)のような衝撃式ミルでセ レコキシブを粉砕させて、本発明の組成物を作製することは、改善され た生物学的利用能を提供するに際して効果的であるだけでなく、かかる\n混合若しくはブレンド中のセレコキシブ結晶の凝集特性と関連する問 題を克服するに際しても有益であることを発見した。ピンミルを利用し て粉砕されたセレコキシブは、未粉砕のセレコキシブ又は液体エネルギ ーミルのような他のタイプのミルを利用して粉砕されたセレコキシブ よりは凝集力は小さく、ブレンド中にセレコキシブ粒子の二次集合体に は容易に凝集しない。減少した凝集力により、ブレンド均一性の程度が 高くなり、このことはカプセル及び錠剤のような単位投与形態の調合に おいて、非常に重要である。これは、調合用の他の製薬化合物を調合す る際のエアージェットミルのような液体エネルギーミルの有用性に予\n期せぬ結果をもたらす。特定の理論に拘束されることなく、衝撃粉砕に より長い針状からより均一な結晶形へ、セレコキシブの結晶形態を変質 させ、ブレンド目的により適するようになるが、長い針状の結晶はエア ージェットミルでは残存する傾向が高いと仮定される。」との記載から、 粉砕により粒子サイズを減少させるについて、ピンミルのような衝撃式 ミルを使用して長い針状からより均一な結晶とし、ブレンド目的により 適するものとすることが記載されている。
(ウ) 本件明細書の【0075】には「加湿剤 セレコキシブは水溶液にか なり溶解しにくい。したがって、本発明の製薬組成物は、任意であるが、 好ましくは、キャリア材料として、一つ又はそれ以上の薬剤学的に許容 な加湿剤を含む。かかる加湿剤は、水と親和性があるようにセレコキシ ブを維持させるように選択することが好ましく、その状態が製薬組成物 の相対的生物学的利用能を改善させると考えられる。・・・」、【00\n76】には「ラウリル硫酸ナトリウムは好ましい加湿剤である。存在す るならば、ラウリル硫酸ナトリウムは、組成物の全重量の対して、約0. 25%から約7%、好ましくは約0.4%から約6%、より好ましくは 約0.5%から約5%の量を含む。」として、セレコキシブは水溶液に かなり溶解しにくいために、水と親和性があるようにセレコキシブを維 持させる加湿剤を含むことが好ましいこと、好ましい加湿剤はラウリル 硫酸ナトリウムであること、そのような加湿剤を添加することにより相 対的生物学的利用能を改善できることが記載されている。\n
(エ) 例11−2では、犬モデルでの調合の相対的生物学的利用能の試験\nがされている。 組成物A、Bは微粉化され、ラウリル硫酸ナトリウムが添加されてい る(【0173】、【0174】、表11−2A)。本件明細書の【0\n124】に「・・・例えば、例11に例示するように、出発材料のセレ コキシブのD90粒子サイズを約60μmから約30μmに減少させる と、組成物の生物学的利用能は非常に改善される。・・・」と記載され\nていることから、組成物A、BのD90粒子サイズは約30μmと認めら れる。他方、参考例である組成物Fは、未粉砕、未調合のセレコキシブ である(【0172】)。 生物学的利用能は、メス犬について、組成物Fが16.9%であるの\nに対し、組成物Aは31.2%、組成物Bは24.9%であり(【01 76】、(表11−2C)、オス犬について、組成物Fが16.9%で\nあるのに対し、組成物Aは49.4%、組成物Bは54.2%である(【0 177】、表11−2D)とされ、D90粒子サイズを約30μmに減少\nさせた組成物A、Bにおいて生物学的利用能が明らかに高い結果が示さ\nれている。
エ 以上を総合すると、本件訂正発明1は、粒子の最大長においてD90が3 0μmであるセレコキシブ粒子、及び加湿剤としてのラウリル硫酸ナトリ ウムを含有することを特定するものであるところ、これは、1)セレコキシ ブが長い針状の結晶形態を有することに対応するため、粉砕によって薬物 の粒子径を小さくし、比表面積を増大させることにより、薬物の溶出を改\n善させるために、セレコキシブの粒子サイズを「D90が30μm」に減少 させ、また、2)セレコキシブのような難溶性薬物については、粒子径を小さ くすると凝集が起こりやすくなり、有効表面積が小さくなる結果、溶解速\n度が遅くなるが、界面活性剤が存在すると、微粒子は凝集せずに均一に溶 液中に分散され、粒子サイズが小さいほど溶出速度は大きくなることから、 セレコキシブに、界面活性剤同様水に親和性を持たせる湿潤剤であるラウ リル硫酸ナトリウムを含有させることとしたものである。そして、3)具体 的な実験結果においても、D90粒子サイズは約30μmとし、ラウリル硫 酸ナトリウムを含有させたセレコキシブ組成物が、未粉砕、未調合のセレ コキシブに対して優れた生物学的利用能を示しているのであるから(例1\n1−2)、本件訂正発明1は、本件ピンミル構成を発明特定事項として考慮\nしなくても、本件明細書及び技術常識から、「未調合のセレコキシブに対し て生物学的利用能が改善された固体の経口運搬可能\なセレコキシブ粒子を 含む製薬組成物を提供する」という課題を解決できると当業者が認識でき る範囲の発明であるといえる。
本件訂正発明2は、D90が30μmよりも減少した数値範囲である「D 90が30μm未満」と特定されたものであるから、上記本件訂正発明1に ついて述べたところと同様、本件明細書及び技術常識から、上記課題を解 決できると当業者が認識できる範囲の発明であるといえる。 本件訂正発明4、5、7〜13、15、17〜19も、本件訂正発明1及 び本件訂正発明2を直接的又は間接的に引用してこれらをさらに限定する 発明であるから、本件訂正発明1及び本件訂正発明2と同様に、本件明細 書及び技術常識から、上記課題を解決できると当業者が認識できる範囲の 発明であるといえる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.03.27
令和5(行ケ)10111 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年3月11日 知的財産高等裁判所
(1) 「田中」と「箸店」の組合せからの一般的理解について
ア 本願商標は、「田中」の文字と「箸店」の文字を結合した結合商標である ところ、その構成中の「田中」の文字は、「全国名字大辞典」(平成23年 9月20日発行、乙1)によれば、日本を代表する地形姓で、沖縄を除く西\n日本では全て15位以内、東日本でも全て50位以内に入っていること(乙 1)、2)「名字由来net」のウェブサイト(乙2)において、全国順位が 4位であること、3)「姓名分布&姓名ランキング」のウェブサイト(乙3) によれば、平成19年10月までに発刊された全国の電話帳に掲載されて いる世帯を基準にすると、全国で4番目に多い氏であることがそれぞれ認 められ、日本国内ではありふれた氏と認められる。
イ 本願商標の構成中、「箸店」の「箸」の文字は、「中国や日本などで、食\n事などに物を挟み取るのに用いる細長く小さい二本の棒。」(乙4)の意味、 「店」の文字は、「品物を置き並べて商売するところ。その品物を商うみ せ。」(乙5)の意味をそれぞれ有する語として辞書に登載されている。そ うすると、本願商標の構成のうち「箸店」の部分は、箸を取り扱う店程度の\n意味を有するものと理解される。 各種ウェブサイトによれば、「箸店」の語が、「箸を取り扱う店」の店舗 名や商号の一部として広く採択、使用されており、「岩多箸店」(乙6、4 2)、「株式会社 伊勢屋箸店」(乙7)、「やまご箸店」(乙8)、「(有) 府中宮崎箸店」(乙9)、「有限会社せいわ箸店」(乙10)、「小山箸店」 (乙11)、「フクイチ箸店株式会社」(乙12)、「タケダ箸店」(乙1 3)、「神戸屋箸店」(乙14)、「坂田箸店」(乙15)等がある。
ウ そうすると、本願商標は、ありふれた氏である「田中」と、箸を取り扱う 店を表すものとして広く使用されている「箸店」を組み合わせた「田中箸\n店」を標準文字で表したものであり、「田中」の氏又は当該氏を含む商号を\n有する法人等が経営主体である箸を取り扱う店というほどの意味を有する 「田中箸店」というありふれた名称を、普通に用いられる方法で表示する\n標章のみからなる商標で、本願商標の指定商品のうち、第21類「台所用品 (「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」には、「箸」 が含まれる(乙43、44)ことも考慮すれば、販売実績に基づく識別力の 獲得が認められるなどの特別の事情がない限り(この点は後記(2)において 判断する。)自他商品の識別力を有しないものと解される。
エ 原告は、本願商標は、外観と称呼の一連性により、一体不可分として扱わ れるべきものである旨主張するが、一連一体の商標であっても、自他商品 の識別力を有するか否かを検討する上では、個々の構成部分の意味を検討\nするプロセスが否定されるものではなく、原告の主張は採用できない。 また、原告は、iタウンページの検索において、東京都では「田中箸店」 に該当するものがなく、原告の本社がある福井県では原告のみが該当する 旨主張するが、上記ウの判断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2024.03.26
令和5(ネ)10085 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 令和6年3月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被控訴人は、控訴人に対し支払義務を負うとしても、本件訴状が原審裁判所に提 出された令和3年10月14日時点で、平成23年10月14日以前に支払われた 出演料に相当する部分6万9420円(=41万6521円÷(1−0.1)÷7% ×1.05×7%−41万6521円)は消滅時効が成立していると主張し、その 時効を援用していることは記録上明らかであるため、この点について検討する。10 控訴人は、上記主張につき、時機に後れた攻撃防御方法であることや時効援用が 信義則に反することを主張するが、被控訴人の時効主張は、原審での審理経過及び 判断内容を踏まえてされたものであるところ、その主張内容からすると、その審理 のために訴訟の完結を遅延させることとなるものとは認められず、時機に後れたも のとはいえないし、時効援用が信義則に反するものともいえない。 そして、本件訴訟提起時(令和3年10月14日)から遡って10年内に履行期 が到来した債権については、時効期間が経過していないものの、それ以前に履行期 が到来した債権については、本件訴提起時までに時効期間が経過し、かつ、権利行 使が可能であったといえ、時効中断等の事情もうかがわれないことからすると、平\n成23年10月14日以前に支払われた出演料に相当する未払部分6万9420円 (=41万6521円÷(1−0.1)÷7%×1.05×7%−41万6521 円)は消滅時効が完成し、被控訴人の時効の援用によって同額について時効により 消滅したものといえる。
(3) したがって、被控訴人は控訴人に対し、1万5177円(=8万4597円 (訂正の上引用する原判決第5の4(3))−6万9420円(上記(2)))及びこれに 対する履行期の到来後で控訴人の請求する令和3年11月16日から支払済みまで 民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
5 著作権侵害(当審における新たな請求原因の主張)について
控訴人は、当審における令和5年9月20日付け控訴理由書において、新たな請 求原因の追加的変更に当たる主張として、被控訴人の本件大会ビデオ・DVDの制 作・販売が控訴人の演武の著作権を侵害するとの主張を行ったが、被控訴人は、か かる主張は原審において提出できたことは明らかであり、控訴審において更に審理 することは訴訟の完結を遅延することなるため、却下すべきと主張する。 上記請求原因の追加的変更については、原審においてその主張ができなったとい うやむを得ない事情はうかがわれず、上記請求原因の追加的変更を許せば、控訴人 の演武の著作物性、著作権侵害の有無、仮に侵害が認められる場合においては損害 の有無等を新たに審理しなければならず、著しく訴訟手続を遅滞させることとなる から,当該請求原因の追加的変更は不当であると認められる。 したがって、控訴人の著作権侵害に係る請求原因の追加的変更の申立ては、民訴\n法297条、143条1項及び4項に基づき、許さないのが相当である。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.03.25
令和5(ネ)1384等 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和6年1月26日 大阪高等裁判所
写真集及び卓上カレンダーに係る被告画像1、2及び4ないし10は、 インターネットショッピングサイトにおいて販売する商品がどのような ものかを紹介するために、芸能人を被写体とする写真が印刷された平面\n的な表紙及び裏表\紙を、できるだけ忠実に再現するため真正面から撮影 した画像であり、上記表紙及び裏表\紙以外に背景や余白はないのであっ て、被写体の選択・組合せ・配置、構図・カメラアングルの設定、背景\n等に選択の余地がなく、上記表紙及び裏表\紙ひいてはそこに印刷された 芸能人を被写体とする写真を忠実に再現する以外に、その画像の表\現自 体に何らかの形で撮影者の個性が表れているとは認められないから、上\n記各被告画像には創作性が認められない。したがって、上記各被告画像 は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)\nとはいえず、著作物とは認められないから、一審被告が上記各被告画像 について著作権を有するとは認められない。
(イ) 被告画像3について
単語帳に係る被告画像3も、インターネットショッピングサイトにお いて販売する商品がどのようなものかを紹介するための写真ではあるが、 芸能人を被写体とする写真が印刷された表\紙及び裏表紙を金具のリング\nから取り外し、各写真を表にして平面上に上下に並べ、その右側に一部\n裏表紙と重なる形で、63枚の単語カードを写真側を表\にして金具のリ ングを要として扇状に広げたものを撮影したものであり、正面から撮影 されたものではあるものの、上記単語カードを扇状に広げることによっ てその重なり合いによる陰影が表現され、また、2枚目以降の単語カー\nドの白い縁取りからわずかに各写真が垣間見えるように広げることによ って各単語カードにそれぞれ異なる写真が印刷されていることを表現し\nており、白い背景によって表紙及び裏表\紙の写真等を浮き立たせる効果 も生んでいるといえる。このような手法が商品としての単語帳を紹介す る際にまま見られるもの(乙62、63)であったとしても、その被写 体の選択・組合せ・配置、光線の調整・陰影の付け方、背景の選択には 複数の余地があり、被告画像3の表現自体に撮影者の個性が表\れている と認められる。したがって、被告画像3は、「思想又は感情を創作的に 表現したもの」といえ、著作物性が認められるから、その撮影者である\n一審被告は被告画像3について著作権を有すると認められる。
(ウ) 以上に対し、一審被告は、被告画像1、2及び4ないし10についても、 手ブレ補正、露出補正、ホワイトバランス等の細かい調整を行い、光の 入り方に気を配って撮影場所にこだわり、複数の写真を撮影してその中 の一番良い写真について彩度、色合いを編集するなどの独自の工夫を凝 らしている旨主張するが、一審被告が主張するそのような工夫は、商品 である写真集ないし卓上カレンダーの表紙及び裏表\紙、ひいてはそこに 印刷された芸能人を被写体とする写真を忠実に再現するためのものであ\nって、上記工夫の結果、それらが忠実に再現された各被告画像が得られ たとしても、その表現自体に何らかの形で撮影者である一審被告の個性\nが表れているとは認められない。したがって、上記一審被告の主張は上\n記(ア)の判断を左右しない。
・・・
ア 上記のとおり、被告サイト上の被告各画像及び商品名のうち、そもそも著 作物性が認められるのは被告画像3のみであり、その余については著作物性 自体が認められず、一審被告が著作権を有しないから、一審原告がその著作 権を侵害した事実はおよそ存在しない。そこで、原告画像3の掲載が被告画 像3についての一審被告の著作権侵害に当たるかにつき、以下検討する。
イ 被告画像3の表現上の本質的特徴は、前記(3)ア(イ)のとおり、本件商品3 を撮影する際の被写体の選択・組合せ・配置、光線の調整・陰影の付け方、 背景の選択等を総合した表現に認められるところ、画像テンプレートを利用\nして作成された原告画像3は、単語帳から取り外した一部の表紙等を並べて\nその横に単語帳を扇状に広げて置くなどの点で商品の見せ方に関する基本的 なアイデアに被告画像3との共通点はあるが、取り外して並べられたのが表\n紙や裏表紙の写真面か、単語カードの韓国語単語が記載された面か、その枚\n数、色彩及び配置、金具のリングを要として扇状に広げられた単語帳がその 右側に配置されているか左側に配置されているか等の配置、同単語帳の1枚 目のカードに印刷された写真内容、同単語帳の単語カードの枚数、色彩、扇 状の広がり方及び陰影等で異なっていることが一見して明らかであって、そ の素材の選択・組合せ・配置、光線の調整・陰影の付け方、色彩の配合、素 材と背景のコントラスト等において被告画像3と異なるから、被告画像3の 表現上の本質的特徴を直接感得させるものとはいえない。なお、原告画像3\nで選択された素材のうち、本件商品3の表紙を正面から撮影した画像部分の\nみは被告画像3と共通するが、その画像自体は、被告画像1、2及び4ない し10について検討したと同様、平面的な上記表紙を忠実に再現したのみで\n創作性が認められない部分であるから、同画像部分が共通しているからとい って、原告画像3が被告画像3と類似しているとは到底認められない。した がって、一審原告が原告画像3を原告サイトに掲載したことが、被告画像3 に係る一審被告の著作権を侵害するものとは認められない。
以上によれば、一審被告が、本件各申告によってアマゾンに告知した、一\n審原告が被告サイト上の被告各画像及び商品名についての一審被告の著作権 を侵害しているとの本件各申告の内容は、全て虚偽の事実であったというこ\nとになる。そして、前記第2の2で原判決を補正した上で引用した前提事実 (1)によれば、一審原告と一審被告は競争関係にあるといえ、また、上記著 作権侵害の事実を申告する行為は一審原告の営業上の信用を害する虚偽の事\n実を告知する行為といえるから、本件各申告は、客観的に不競法2条1項2\n1号に該当するということになる。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.03.24
令和5(行ケ)10113 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和6年2月19日 知的財産高等裁判所
1 原告は、本件南京錠は本件登録意匠の要旨ではなく、意匠の要部を構成しな\nい旨主張する。
しかし、本件登録意匠は、別紙意匠公報のとおり、本件南京錠を付したもの として登録されているのであるから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるお それ(意匠法5条2号)があるか否かについて、登録された意匠の形状等のう ち、特に他人の周知・著名な商標に類似する部分が問題となることは当然であ り、この点は、意匠同士の類否(同法3条1項3号)等の判断に当たって考慮 される意匠の「要部」であるか否かとは別問題であるから、原告の主張は失当 である。なお、本件において、添付図面等の南京錠又は南京錠の正面の態様を削除す る補正をすることは、添付図面等の要旨を変更するものに当たると解される。
2 原告は、審査段階で意匠法5条2号の拒絶理由を指摘されていない旨主張す るが、そのような事情は、本件登録意匠が同号に当たるか否かの実体判断を左 右するものでないことはもとより、無効審判手続の違法を根拠づけるものでも ない。
3 原告は、正面が無地の南京錠を付したかばんを販売しているとして、本件南 京錠を付したかばんを販売していない旨主張するが、仮にそのような事実が認 められるとしても、本件登録意匠が被告の業務に係る物品であるハンドバッグ 等と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たる ものではない。
2024.03.24
令和4(ワ)16062 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和6年1月17日 東京地方裁判所
裁判所は、「御所仙修」は非類似、それ以外は類似すると判断しました。
(1) 被告標章1について
本件商標と被告標章1の外観についてみると、いずれも漢字二文字で一文 字目の字が「仙」の字で同一であり、二文字目の字も本件商標が「脩」、被 告標章1が「修」の字であり、右側下部のみが、本件商標が「月」と同じ形 状をしているのに対し、被告商標1が「彡」の形状をしており、異なってい るものの、それ以外の左側及び右側上部は同一形状をしており、似た形状を している。そうすると、本件商標と被告標章1の外観は類似しているといえ る。
本件商標と被告標章1の称呼についてみると、両者はいずれも「せんしゅ う」で同一である。 そして、観念についてみると、本件商標も被告標章1もいずれも「せんし ゅう」としては広辞苑(第7版)に掲載されていない。もっとも広辞苑(第 7版)によれば、「仙」の部分は「仙人」の意味とされる。「脩」は、前記 1(3)のとおり、本来の意味は干し肉を指すものであったが、現代では音が同 じ被告標章1の二文字目の「修」と同じ「おさめる」の意味をも有している とされ、「修」の簡体字ないし異字体として使用されることもあるものであ る。これらの事実に照らすと、本件商標も被告標章1も、いずれもそれ自体 で特定の観念を有するとはいえないが、それぞれを構成する漢字は、共通す\nるものと、共通する意味を有するものであり、それらの漢字から想起される 観念も類似していると評価することができる。
被告は、特に医薬品の需要者からは、「脩」の字は乾燥させた生薬や原料 を想起させる文字であり、医薬品として「虎脩六神丸」と「虎修六神丸」の 両商品名を販売している会社も存在していることなどを指摘する。しかし、 「脩」の字には「修」と同じ「おさめる」の意味も有しているとされる。ま た、原告は医薬品の小売業であり(前記第2の1(1)及び(4))、被告の卸売の 販売先が、被告各商品をインターネット上のサイトで販売していること(前 記第2の1(6))からすると、被告各商品の市場は全国に及び、かつその対象 も消費者に及ぶといえ、被告各商品の需要者には消費者も含まれ、また、医 薬品に精通する者のみが需要者であるとはいえないので、この点に関する被 告の主張は採用できない。 これらの事情を総合的にみれば、本件商標と被告標章1は類似している といえる。
(2) 被告標章2について
本件商標と被告標章2の外観についてみると、本件商標は漢字二文字であ るのに対し、被告標章2は漢字5文字であり、「仙」の字が同一であり、 「脩」と「修」の字が類似しているとしても、全体として外観が類似してい るとはいえない。また、本件商標と被告標章2の称呼についてみても、「せ んしゅう」と「せんしゅうろくしんがん」であり、一部共通するとしても、 全体として称呼が類似しているともいえない。 もっとも、被告標章2のうちの「六神丸」の部分は、前記1(1)のとおり、 古くから特定の漢方薬を指す用語であるとされ、広辞苑(第7版)において も「漢方薬の一つ」として説明されているものであり、その他想起される意 味はなく、実際にも、漢方薬として、多くの会社から六神丸という名称の商 品が販売されている。そうすると、需要者にとって、「六神丸」の部分は、 特定の内容の漢方薬を指すものといえる。 そうすると、被告標章2において、「六神丸」の部分は出所識別力を有さ ず、主に出所識別力を有するのは、「仙修」の部分であるといえる。そこで、 本件商標と被告標章2の「仙修」の部分を被告して商標の類否を検討すると、 本件商標と被告標章2の「仙修」の部分については、前記 のとおり、外観 が類似し、称呼が同一である。また、観念についても、本件商標の「仙修」 と被告標章2の「仙脩」のそれぞれの漢字から想起される観念は類似すると いえる。 これらの事情を総合的にみれば、本件商標と被告標章2は類似していると するのが相当である。
(3) 被告標章3について
本件商標と被告標章3の外観についてみると、本件商標は漢字二文字であ るのに対し、被告標章3は漢字4文字であり、「仙」の字が同一であり、 「脩」と「修」の字が類似しているとしても、全体として観察した場合は、 外観が類似しているとはいえない。 もっとも、被告標章3は、「御所」と「仙修」の間に空白があり、かつ 「御所」の文字は、四角形の枠で囲まれていて、そのような枠がない「仙修」 の部分と「御所」の部分は、外観上、明確に分離して観察することができる ものといえる。そして、本件商標と被告標章3の「仙修」部分の外観が類似 しているのは、前記アで述べたとおりである。 また、本件商標と被告標章3の称呼についてみても、「せんしゅう」と 「ごせせんしゅう」又は「ごしょせんしゅう」であり、全体の称呼は異なる ものの、分離して観察することができる「御所」部分を除いた「せんしゅう」 の部分は同一である。 本件商標と被告標章3の観念についてみると、「御所」は、前記1(2)のと おり、古くからの薬の生産地である奈良県の被告所在地の市を意味するもの であり、文献等において言及されることはあるが、本件証拠上、言及されて いる文献は奈良県に関する文献か医薬品に関する論文等の専門誌であり、 「御所」が、需要者に特に広く知られていて、需要者が当然に特定の市を想 起するとまでは認めるに足りない。そして、「御所」は、広辞苑(第7版) においても、「ごせ」と読ませる場合、「奈良県西部、大阪市に接する市」 と記載されている一方で、「ごしょ」と読ませる場合、「天皇の座所を意味 する」と記載されている。これらの事実からすると、「御所」は、「ごせ」 と読ませる場合は奈良県の市名として理解されるものの、需要者が必ずその ように理解するとまでは認めるに足りず、「ごしょ」と読む天皇の座所の意 味を想起する者もいるといえる。もっとも、被告標章3では、前記のとおり 「御所」と「仙修」は外観上明確に分離しているところ、本件商標の「仙修」 と被告標章2のうちの「仙脩」のそれぞれの漢字から想起される観念は類似 するといえる。
以上の事情をみると、被告標章3は、全体として不可分一体のものとはい えず、その構成上、被告標章3の「仙修」の部分も出所識別標識となるもの\nであり、この部分と本件商標との類否を判断することができるというべきで ある。そして、前記 に述べたのと同じ理由により、本件商標と「仙修」の 部分は類似しているといえるから、本件商標と被告標章3は類似していると いえる。
(4) 被告標章4について
本件商標と被告標章4の外観についてみると、本件商標は漢字二文字であ るのに対し、被告標章3は漢字4文字であり、「仙」の字が同一であり、 「脩」と「修」の字が類似しているとしても、全体として観察した場合は、 外観が類似しているとはいえない。そして、被告標章4は、被告標章3とは 異なり、「御所」と「仙修」の間に空白もなく、かつ「御所」の部分も四角 形の枠で囲まれるなどしていないから、外観上、「御所」の部分と「仙修」 とが分離して観察されることはない。
また、本件商標と被告標章4の称呼についてみても、「せんしゅう」と 「ごせせんしゅう」又は「ごしょせんしゅう」であり、一部重なる部分はあ るものの、全体として観察した場合、称呼は異なる。 そして、本件商標と被告標章4の観念についてみると、前記ウで述べたと おり、「御所」について、「ごせ」と読ませる場合は奈良県の市名として理 解されるものの、需要者が必ずそのように理解するとまでは認めるに足りず、 「ごしょ」と読む天皇の座所の意味を想起する者もいるといえるものであり、 「御所」の部分にも一定の観念が生ずるものといえる。 そして、被告標章4の「御所仙修」が外観上分離されない一連のものであ るところ、そのうちの「御所」の部分に出所識別標識としての機能がないと\nは直ちにはいえないし、「仙修」の部分が出所識別標識として強く支配的な 印象を与えるとはいえない。 これらの事情を総合的にみれば、本件商標と被告商標4は類似していると はいえない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2024.03.24
令和4(ネ)10018 職務発明の対価請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月8日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
「(4) 本件発明A2の自己実施による独占の利益の有無及び額についての検討
ア 被控訴人においては、平成13年頃、CODEX5%ルールの認可や、東南ア ジアの経済発展等に伴い、国際的なCBEの需要増加が見込まれる一方、国内製造 拠点の生産能力が限界に達しているとの現状認識のもと、米国に所在する子会社で\nあるFVOにおいて、EE技術を利用してヒマワリ油からSOSパーツを製造する 設備を有する工場を新設し、被控訴人グループ内での安定供給を図る方策を立案し ていたが、当初、当該工場における油脂分別方法としては、溶剤分別法を用いること を想定していた。しかるところ、控訴人を含むNTメンバーが主導となって、本件各 発明を含む改良された乾式分別法によると、SOSパーツの品質は溶剤分別法によ るものと比して大差なく、現にパイロットレベルの試作品においては同等以上とな っていること、分別収率や生産量等の生産効率も溶剤分別法との間にさほどの差は ないこと、コスト面においては設備費及び比例・加工費ともに大幅な削減が可能で\nあること等が報告された。そこで、被控訴人は、平成14年9月頃、本件乾式分別法 を採用した(本件発明A2を実施する)本件設備を備えた本件工場を米国にてFV Oに新設、稼働させる旨を意思決定し、平成15年に着工が始まり、平成16年4月 頃から稼働が始まったものである。(前記(3)イ(ア)〜(カ)) ところが、本件設備及び本件工場に係る設備投資については、●●●●●●●● ●であったのに対し、●(省略)●を要することとなった。しかも、本件工場は、稼 働当初、稼働能力や生産効率に課題を抱えていたほか、品質低下も指摘されており、\nその原因として●●●●●●●●●●●●ことが指摘された。このため、FVOは、 平成18年頃から、品質を確保するため、●(省略)●こととし(ただし、平成27 年以降は、●●●●●●●●●●●●●●こととしたが、これが、品質の改良や生産 効率の改善によるものであるかは不明である。)、また、更に●●●●●●●●を負 担して本件増設工事を行うことを余儀なくされたものである。(前記(3)イ(キ)〜(コ )、ウ(ア)c)
イ FVOパーツ品の品質についてみると、●●●●●●●●●●●●●を予定\nしていたところ、本件増設工事が完了した平成19年3月頃には同程度と報告され ていることや(前記(3)イ(サ))、現実にFVOがFVOパーツ品を被控訴人グループ ●(省略)●世界CBE市場における被控訴人のシェア獲得にも寄与していると認 められること(前記(3)ウ(イ)e、エ)に照らすと、FVOパーツ品が、そもそも販売 に耐えないほど低品質のものであったということはできない。他方で、FVOパー ツ品やFVO品が、溶剤分別法により製造されたSOSパーツやこれらを原料とし たCBEとの比較において、品質面で上回っていることを認めるに足りる証拠もな い。そうすると、本件発明A2を実施したことにより、被控訴人がその実施品である FVOパーツ品やFVO品について、品質面で優位に立ったということはできない。
ウ 次に、本件発明A2を実施したことによりFVOが得た利益についてみると、 そもそも、本件乾式分別法を採用したFVOの●(省略)●は、直ちに分別方法によ る利益の相違を示すものではないが、その算出に際してその時々の相場と過去の実 績等が考慮され、変動費に相当する見込み額として位置付けられるものであり、分 別方法の差異による採算性を考慮する際の参考にすることは妨げられないというべ きである。
さらに進んで、FVO、FOJ及びFOSにおけるSOSパーツの加工費及び比 例費の各試算を比較すると、●(省略)●るのに対し、●(省略)●、大きな差が発 生しているのに、原料コストや収率等を考慮して試算された比例費では、●(省略) ●相対化されている(前記(3)ウ(イ)b)。しかも、この数値は、約9年間にわたり実 際には支払われていた●●●●●●●●●●●●を考慮していない上、FVOの現 実の収率よりも高い収率である●●●を収率として試算されたものであり、実数値 によると更に差は小さくなるものである。 このことに加え、前記アのとおり、被控訴人内部では、当初、本件乾式分別法を採 用することにより設備費においても大幅なコスト削減が見込まれるとの認識(溶剤 分別法による場合の投資試算額●●●●●に対し、●●●●●の投資試算額と見込 まれていた。)の下で、本件施設及び本件工場の新設に踏み切ったものの、現実には これに●●●●●●●●●を要し、加えて、本件設備につき、稼働能力、生産効率、\n品質低下等の課題が指摘されたことから、更に●●●●●●●●●を要する本件増 設工事まで余儀なくされたこと等も併せて考慮すると、FVOが本件乾式分別法を 採用したことによる効果として、当初予定していた溶剤分別法による以上に利益率\nを向上させることができたとか、現実に利益を上げることができたとは認められな い。
エ さらに、本件特許権A2を含む特許権に基づく禁止権の効果により他社を排 除することができたかについてみると、競合他社であったIOFは平成23年に、 LCは平成27年に、それぞれシア脂からSOSパーツを分別できる工場をガーナ に新設し、稼働させたが、いずれの工場においても溶剤分別法が用いられており、本 件各発明に関連する特許による禁止の効力が及ばない地域においても、競合他社は、 いまだ溶剤分別法を採用している上、本件各特許権がいずれも消滅した現在におい ても、被控訴人又は競合他社が、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新 設、稼働し、又はその準備をした等の事実は認められないのであって(前記(3)オ)、 控訴人が主張するように、溶剤分別法が危険を伴い、時に重大な事故を引き起こし 得るものであるとしても、被控訴人又は新不二製油が、本件特許権A2を含む特許 権に基づく禁止権の効果により、競合他社による本件乾式分別法の採用を排除し、 これにより使用者として有する通常実施権に基づく実施によって得られる利益を超 えた利益を得たと認めることは困難である。
なお、本件施設の稼働後、CBE市場における被控訴人のシェアが増加したのは、 被控訴人が、規制緩和や経済動向をみて国際的なCBEの需要増加を見込み、FV Oを拠点に生産施設を新設し、これが現実に稼働したことに伴う結果とみられ、本 件乾式分別法を採用したことにより特にシェアを拡大できたことをうかがわせる事 情はないというべきである。 オ 以上を総合すると、被控訴人が、本件特許権A2につき有する通常実施権に 基づいて本件発明A2を実施して得られる利益の額を超えて、特許による独占的、 排他的な実施により超過して利益を得たと認めることはできない。したがって、被 控訴人につき、本件発明A2による独占の利益は認められない。
◆判決本文
原審はこちら
2024.03.24
令和5(行ウ)5002 特許料納付書却下処分取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年2月16日 東京地方裁判所
2 原告が本件追納期間を徒過したことについて、旧特許法112条の2第1項の 「正当な理由」があったか(争点2)について
旧特許法112条の2第1項所定の「正当な理由があるとき」とは、特許権者 (代理人を含む。)として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的 にみて追納期間内に特許料を納付することができなかったときをいうものと解 するのが相当である。
甲11号証によれば、原告の専務取締役であるBは、遅くとも令和4年2月9 日までに、原告への出資を検討していた会社から、原告が保有している多くの特 許について特許料の不払いによって登録が抹消されているとの連絡を受け、同日、 特許料の支払も含めて原告が原告の保有する特許の管理を委任していた本件弁 理士に連絡をとったところ、本件弁理士から、うつ病等を理由に業務をすること が難しい状況にあると告げられたことが認められる。
そうすると、原告は、遅くとも令和4年2月9日には、原告が保有し、本件弁 理士がその特許料等の納付を管理していた特許権について本件弁理士において 適切な管理をしていないものがあること、そのため、当時原告が多数保有してい る特許権について特許料の納付期限が到来しているものについては特許料の納 付が滞っている可能性が高いこと、所定の期間に特許料が納付されなければ特許\n権が消滅することを認識したと認められる。そうすると、原告は、遅くとも同日 の時点で、保有している特許権を今後も維持したいというのであれば、即座に、 原告が保有している特許の特許料の納付状況等について確認すべきであること や、仮に納付されていない場合にはその対処について速やかに検討すべきである ことを認識したか、少なくともこれらを極めて容易に認識できる状況にあったと いえる。そして、本件特許についてこれらの点について検討し、必要な相談(今 後の長期的な特許関係の事務の委任ではなく、このような緊急事態への対処のみ を委任するのであれば、同日に近い時期に原告が弁理士に相談することは難しく なかったといえる。)等をしていれば、本件特許について、本件追納期間満了まで に特許料等を納付すべきことについて容易に知り得て、これを納付することがで きたといえる。そうであるにもかかわらず、原告は、上記の認識をした令和4年 2月9日から本件追納期間の満了まで1か月以上の期間があったにもかかわら ず、同期間満了までに特許料等を納付しなかったのであるから、当時、新型コロ ナウイルスによる感染症が問題になっていたことを考慮しても、その余を判断す るまでもなく、原告は、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみ て追納期間内に特許料を納付することができなかったとはいえない。よって、原 告が本件追納期間を徒過したことについて旧特許法112条の2第1項の「正当 な理由」があったとはいえない。
◆判決本文
関連事件です。
2024.03.24
令和4(ワ)16072 不正競争防止法に基づく差止請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年2月21日 東京地方裁判所
(ア) 判断基準について
不競法2条1項20号は、商品や役務に、その品質や内容を誤認させ るような表示をし、又はその表\示をした商品を譲渡等することにより、 需要者の需要を不当に喚起するとともに競争上不当に優位に立とうとす ることを防止する趣旨の規定であるといえるから、本件表示が本件商品\nの品質及び内容について誤認させるような表示に当たるか否かは、本件\n表示によって、本件商品についての需要者の需要を不当に喚起し、被告\nらが不当に競争上優位に立つことになるか否かによって判断すべきと解 される。
(イ) 本件表示の目的について\n
本件商品は、一般消費者向けの茶葉を原料とする非たばこ加熱式ステ ィックであり(前提事実(2))、本件商品に係る広告においては、本件商 品はたばこであるか否か、有害な成分が入っているか否かについての質 問及び回答が掲載されている(前提事実(3))。このような事実に照らす と、本件表示の目的は、ニコチンの含有量を科学的な正確さをもって示\nすためのものではなく、本件商品が含有する成分は茶葉と同様であって、 たばこのように身体及び精神に悪影響を与えるような程度の量の成分を 含有していないことを示すためのものと認められる。
・・・・
(カ) まとめ
前記(イ)ないし(オ)のとおり、1)本件表示は、ニコチンの含有量を科学\n的な正確さをもって示す目的のものではなく、本件商品が含有する成分 は茶葉と同様であって、本件商品に身体及び精神に悪影響を与えるよう な程度の量の成分を含有していないことを示す目的のものと考えられる こと、2)本件商品が含有するニコチンは、茶葉そのものに含まれていた 内因性由来のものであって、その含有量は、人が摂取しても安全と評価 されており、生理活性がない可能性も指摘されている水準にとどまるこ\nと、3)茶葉を原料とする他の複数の非たばこ加熱式スティックに係る広 告においても、定量下限を1ppmとした分析によりニコチンが検出さ れなかったことを根拠として「ニコチン0」との記載がされているとこ ろ、これらの商品にも当該定量下限を下回る量の内因性由来のニコチン が含まれている可能性を当然に否定することはできないことを指摘する\nことができる。
以上の点に照らせば、本件表示に接した需要者は、本件商品が、ニコ\nチン含有の有無及びその量に関し、身体及び精神に与える影響との観点 から、他の非たばこ加熱式スティックと比較してより優れたものである と認識するものではないというべきである。 したがって、本件表示が、本件商品についての需要者の需要を不当に\n喚起し、被告らが不当に競争上優位に立つことになるものであるという ことはできず、よって、本件表示が本件商品の品質及び内容について誤\n認させるような表示に当たると認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.03.24
令和5(ネ)10071 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月21日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
当裁判所は、本件請求原因の追加は攻撃方法の提出であって、民事訴訟法 143条ではなく同法157条の規律に服するものではあるが、結論的には 時機に後れたものとして却下を免れないと判断する。その理由は、以下のと おりである。
(1) 控訴人の本件請求は、特許法100条1項、3項に基づく差止請求、廃 棄請求及び不法行為に基づく損害賠償請求である。そのいずれも、被控訴人 による被控訴人製品の譲渡等が控訴人の有する「本件特許権」を侵害すると の請求原因に基づくものである。
そして、特許法は、一つの特許出願に対し一つの行政処分としての特許査 定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許 権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が\n付与されるものではない。そうすると、ある特許権の侵害を理由とする請求 を法的に構成するに当たり、いずれの請求項を選択して請求原因とするかと\nいうことは、特定の請求(訴訟物)に係る攻撃方法の選択の問題と理解する のが相当である。請求項ごとに別の請求(訴訟物)を観念した場合、請求項 ごとに次々と別訴を提起される応訴負担を相手方に負わせることになりかね ず不合理である。当裁判所の上記解釈は、特許権の侵害を巡る紛争の一回的 解決に資するものであり、このように解しても、特許権者としては、最初か ら全ての請求項を攻撃方法とする選択肢を与えられているのだから、その権 利行使が不当に制約されることにはならない。
(2) 以上によれば、控訴人による本件請求原因の追加は、訴えの追加的変更に 当たるものではなく、新たな攻撃方法としての請求原因を追加するものにと どまるから、本件請求原因の追加が民事訴訟法143条1項ただし書により 許されないとした原審の判断は誤りというべきである。
(3) もっとも、被控訴人は、本件請求原因の追加が攻撃方法に該当する場合に は民事訴訟法157条1項に基づく却下を求める旨の申立てをしている(引\n用に係る原判決の第3の2「被告の主張」欄(2))から、以下この点につい て判断する。
ア まず、本件請求原因の追加に至るまでの原審における手続等の経緯とし て、別紙「本件請求原因の追加に至る経緯」記載の事実が認められる (本件記録から明らかである。)。
すなわち、被控訴人は、答弁書(令和4年2月28日付け)の段階で、 乙1公報及び乙3公報等の公知文献を具体的に示して、均等論の第4要 件の充足を争う詳細な主張を提出した。その後、控訴人と被控訴人は、 同年11月までに、当該争点に関する議論を含む主張書面を2往復させ 主張立証を尽くしてきた。この間の書面準備手続調書には、被控訴人の 「均等論の第4要件を中心に反論書面を提出する」との進行意見が記載 されるなど、均等論の第4要件の充足性は、少なくとも本件の中心的な 争点の一つと認識されていた。そうして、侵害論に関する主張立証が一 応の区切りとなった同月28日のウェブ会議による協議(書面による弁 論準備手続に係るもの。以下同じ。)において、裁判所から双方当事者 に被控訴人製品は本件発明1の技術的範囲に属さないとの心証開示があ り、双方は和解を検討することとなった。その後間もなく和解交渉は不 調に終わったところ、令和5年1月27日の協議において、控訴人は、 消弧作用についての再反論(注・均等論の第2要件関係)及びこれまで の主張の補充等を記載した準備書面を提出すると述べた。ところが、控 訴人は、同年2月27日付け準備書面をもって、本件請求原因の追加の 主張をするに至った。これに対し、被控訴人は、同年4月13日付け準 備書面をもって、時機に後れた攻撃方法としての却下又は著しく訴訟手 続を遅延させる訴えの変更としての不許決定を求める申立てをした。\n
イ 以上に基づいて、まず、本件請求原因の追加が「時機に後れた」ものと いえるかどうかを検討するに、本件において、控訴人が本件請求原因の 追加を求めた理由は、請求項1に係る本件発明1の技術的範囲の属否を 問題とする限り、被控訴人が提出した公知文献(特に乙1公報及び乙3 公報)との関係で均等論の第4要件(公知技術等の非該当)は満たさな いと判断される可能性が高いことを踏まえ、本件付加構\成を備える請求 項3に係る本件発明2を議論の俎上に載せることで、均等論の第4要件 をクリアしようとしたものと理解される。
しかし、上記アのとおり、均等論の第4要件を争う被控訴人の主張は、 既に答弁書の段階で詳細かつ具体的に提出されており、これに対する対 抗手段として、本件請求原因の追加を検討することは可能であったもの\nである。その後、約9か月にわたり双方が主張書面を2往復させてこの 点の主張立証を尽くしていたところ、その後に裁判所からの心証開示を 受けた後に、しかも、控訴人自ら、補充的な書面提出のみを予定する旨\nの進行意見を述べていたにもかかわらず、突然、本件請求原因の追加を 行ったものであって、これが時機に後れた攻撃方法の提出に当たること は明らかである。
ウ 次に、故意又は重過失の要件についてみるに、本件請求原因の追加は、 当初から本件特許の内容となっていた請求項3を攻撃方法に加えるとい う内容であるから、その提出を適時にできなかった事情があるとは考え 難い。外国文献等をサーチする必要があったケースとか、権利範囲の減 縮を甘受せざるを得なくなる訂正の再抗弁を提出する場合などとは異な る。控訴人からも、やむをえない事情等につき具体的な主張(弁解)は されていない。そうすると、時機に後れた攻撃方法の提出に至ったこと につき、控訴人には少なくとも重過失が認められるというべきである。
エ そして、本件請求原因の追加により、訴訟の完結を遅延させることとな るとの要件も優に認められる。すなわち、本件発明2の本件付加構成を\n充足するか否かについては、従前全く審理されていないから、本件請求 原因の追加を許した場合、この点について改めて審理を行う必要が生ず ることは当然である。そして、被控訴人は、仮に本件請求原因の追加が 許された場合の予備的主張として、本件発明2の本件付加構\成のクレー ム解釈及び被控訴人製品の特定に関する詳細な求釈明の申立てをする\n(控訴答弁書19頁〜)などしていることを踏まえると、この点の審理 には相当な期間を要し、訴訟の完結を遅延させることとなることは明ら かである。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.03.24
令和5(ネ)10097 営業侵害行為差止請求等控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和6年2月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 原告は、EL社が営業秘密又は限定提供データの保有者であり、被告AI及 び被告SAIはEL社から営業秘密又は限定提供データの開示を受けたと主張する が、そうであるとすれば、開示された営業秘密又は限定提供データが原告の営業秘 密又は限定提供データであるということはできないはずである。もともと、前記補 正の上引用した原判決のとおり、スマホ留学の顧客情報は各組合員に帰属するもの であり(本件組合契約5条1項)、被告AI及び被告SAIが自らに帰属する顧客 情報を使用することは、不正競争行為に当たるものではない。
イ さらに、本件組合契約は、スマホ留学以外の特定の商品又はサービスを「対 象案件」として、その紹介をするため、スマホ留学の顧客情報を用いることを予定\nしている(本件組合契約6条4項等)。したがって、被告らが、顧客情報をケンペ ネEnglishやオンライン留学の紹介に用いたことをもって、直ちに本件組合 契約に違反すると認めることはできない。
ウ 原告は、本件組合契約7条2項を文字通り解釈すると本件組合契約締結以前 に提供された情報は、同項の「機密情報」には該当しなくなるから不合理である旨 主張する。しかし、原告及び被告らとの間で平成29年3月1日に締結された業務 委託契約書(乙A102)によれば、本件組合契約締結前のスマホ留学事業に関す る機密情報については、上記業務委託契約書9条に本件組合契約7条2項と同じ内 容の機密保持に関する条項が設けられていることが認められ、本件組合契約の締結 により当該条項の効力が失われたと解すべき理由は見当たらない。したがって、当 事者の合理的意思解釈として、本件組合契約締結前の機密情報については前記業務 委託契約書9条に基づく保護の対象となると解するのが相当であるから、原告の主 張する点は、本件組合契約7条2項をその文言どおり解釈することの妨げとなるも のではない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.03.23
令和4(ワ)9521 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月26日 大阪地方裁判所
ア 本件各発明は、耐熱性透明材料として好適な熱可塑性樹脂組成物と、当該 組成物からなる樹脂成形品ならびに樹脂成形品の具体的な一例である偏光 子保護フィルム、樹脂成形品の製造方法に関する発明である(【0001】)。 アクリル樹脂の透明度の低下を防止するためにUVAを添加する方法が 公知であったが、成形時の発泡やUVAのブリードアウト、UVAの蒸散に よる紫外線吸収能の低下との問題につき、従来技術として、アクリル樹脂に組み合わせるUVAとして、トリアジン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物およびベンゾフェノン系化合物が用いられていた(【0003】、【00\n05】、【0006】)。しかし、これらの従来技術として例示されたアクリル 樹脂(【0006】記載の特許文献)には、いずれも分子量が700以上のU VAは開示されていなかった。
イ 本件各発明は、従来技術の化合物には、主鎖に環構造を有するアクリル樹脂との相溶性に課題があり、高温成形時の発泡やブリードアウトの発生の抑制が不十\分であったことから、これらの課題を克服するため(【0007】、【0008】)、樹脂組成物を構成要件1B記載の構\成とし、その製造方法を構成要件6B記載の構\成とし(【0009】、【0010】)、これにより11 0゜C)以上という高いTgに基づく優れた耐熱性や高温成形時における発泡 及びブリードアウトの抑制、UVAの蒸散による問題発生の減少との効果を 奏することとなった(【0015】)。
ウ したがって、本件各発明の本質的部分は、ヒドロキシフェニルトリアジン 骨格を有する、分子量が700以上のUVAが、主鎖に環構造を有する熱可塑性アクリル樹脂と相溶性を有することを見出したことにより、110゜C)以 上という高い優れた耐熱性や高温成形時における発泡及びブリードアウト の抑制、UVAの蒸散による問題発生の減少という効果を有する樹脂組成物 を提供することを可能にした点にあると認められる。
エ 数値をもって技術的範囲を限定し(数値限定発明)、その数値に設定する ことに意義がある発明は、その数値の範囲内の技術に限定することで、その 発明に対して特許が付与されたと考えられるから、特段の事情のない限り、 その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分に当たると解す べきである。
上記検討によれば、分子量を「700以上」とすることには技術的意義が あるといえるうえ、本件において、上記特段の事情は何らうかがえない。 オ そうすると、被告UVAの分子量が「700以上」ではないとの相違点は、 本件各発明の本質的部分に係る差異であるというべきであるから、被告製品 及び被告方法について、均等の第1要件が成立すると認めることはできず、 均等侵害は成立しない。
カ 原告は、本件各発明におけるUVAの分子量である「700」に厳格な技 術的意義はなく、本件各発明の本質的部分は、分子量が十分に大きいという上位概念であると主張する。 しかし、このような上位概念化は、前述の数値限定発明の技術的意義に関 する考え方と相容れず権利範囲を不当に拡大するものである。また、本件証 拠上、本件各発明におけるUVAの分子量が十分に大きいということが当業者にとって自明であるとも認められないし、分子量が十\分に大きいことと、被告UVAの分子量との比較における本件各発明の数値の臨界的意義との 関係は何ら明らかにされていない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 数値限定
>> ピックアップ対象
2024.03.23
令和4(ワ)9461 著作権 民事訴訟 令和6年2月7日 東京地方裁判所
証拠(甲5、11、15、27、原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、\n本件各写真は、賃貸物件の外観・内観及び周辺環境等を撮影したものであるこ と、本件各写真の撮影は、賃貸物件の内容を分かりやすく需要者に伝えるため、 明るさや撮影角度等を調整して行われたものであること、本件各写真の中には、 対象を広く写真に収めるため、パノラマ写真を撮影できるカメラを利用して撮 影されたものも含まれていることが認められる。 このような本件各写真の内容や撮影方法に照らすと、本件各写真は、被写体 の構図、カメラアングル、照明、撮影方法等を工夫して撮影されたものであり、\n撮影者の個性が表現されたものといえる。\nしたがって、本件各写真は、いずれも思想又は感情を創作的に表現したもの\nと認められ、「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当し、これに反する被告 らの主張は採用できない。
・・・
証拠(甲27、原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、通常、管理会社\n等を通さずに物件写真を取得する際には、自社の従業員などが現地を訪問し、 賃貸物件の外観や内観等の撮影した上で、必要に応じて写真の加工等を行っ ていることが認められるところ、被告会社は、本件侵害対象写真を使用する ことによって、上記の作業に係る支出等を免れたものといえる。
そして、証拠(甲23の3、25、26、乙3、5)及び弁論の全趣旨に よれば、物件写真の撮影代行サービスの料金については、1)広角一眼レフカ メラ撮影の外観・内観セット(単発発注)については、3600円から45 00円、360度パノラマ撮影(単発発注)については、3200円から4 000円(写真の加工等には別途オプション料金が必要)とするもの、2)内 観(画像15枚程度)2750円、外観・共用部セット3300円、高品質 撮影5500円、交通費2000円程度とするもの、3)外観・エントラン ス・看板7枚以上で2750円〜5500円、外観・共用部・室内全て7枚 以上で1万3200円(いずれも一眼レフカメラ、広角カメラで撮影。1回 の撮影枚数は30枚以上。)、シータによる撮影(8枚以上)は1件4400 円(写真の加工等には別途オプション料金が必要で、徒歩15分以上の撮影 の場合は1650円が加算される。)とするもの、4)マンション一眼レフカ メラ広角レンズ撮影について、外観のみ(10枚程度)3500円、内観の み(20枚程度)4000円、外観・内観(30枚まで)4500円、オプ ションとして360度パノラマ撮影について、1枚500円、5枚まで10 00円〜2000円(ただし、駅から徒歩16分以上の場合は1000円が 加 算 さ れ る 。) とするもの、5)外観 の み (5枚 か ら 10枚程度)1 200円から1800円、外観・内観セットについて10枚から15枚程度 の場合は2200円から2500円、30枚程度の場合は2500円から2 800円とするものなどがあることが認められ、このような料金の定めから すれば、物件写真の撮影代行サービスを利用する場合、写真1枚当たりに換 算すると数百円程度の費用が必要となるほか、交通費や写真の加工等のため のオプション料金が別途発生し得ることが認められる。
上記の事情に加え、本件侵害対象写真の掲載期間は最大で2か月弱であっ てさほど長くないこと(前記3)、他方で、著作権侵害があった場合に事後 的に定められるべき「著作権の行使につき受けるべき金銭の額」は通常の使 用料に比べて高額となることといった事情を併せ考慮すると、本件侵害対象 写真の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(著作権法11 4条3項)は、写真1枚当たり1000円の合計7万1000円と認めるの が相当である。
(2) これに対し、原告は、NHKエンタープライズ(甲19)、毎日フォトバ ンク(甲20)やアマナイメージズ(甲21)の写真使用料の定めからすれ ば、本件侵害対象写真の使用料相当額は1枚当たり2万円とすべきであると 主張する。
しかし、NHKエンタープライズや毎日フォトバンクの提供する写真は、 報道等のために撮影された写真であり、また、アマナイメージズの提供する 写真はウェブ広告や動画配信広告等に用いられるものであって、その撮影対 象や撮影方法は、賃貸物件の紹介を目的とした物件写真とは大きく異なるも のといえるから、上記各社の写真使用料の定めを本件で参考にすることは相 当ではない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2024.03.23
令和5(行ケ)10108 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年2月27日 知的財産高等裁判所
証拠(甲7の1〜63)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件商標が 登録出願される前から、使用商標を原告の製造、販売に係る「せっけん類」 及び「化粧品」に用いていることが認められる。 このうち、「せっけん類」については、本件審決が、本件商標の指定商品及 び指定役務のうち第3類「せっけん類」について、商標法4条1項10号に 該当すると判断している。 原告は、本件商標の指定商品及び指定役務のうち第5類「サプリメント」 についても、同号に該当すると主張するので、使用商標が用いられる商品が 上記のとおりであることを前提に、以下検討する。
(3) 特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕」(乙 1)は、指定商品の分類において第5類とされる「サプリメント」について、 「この商品は、人体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和 脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもので、『医薬品』に該 当しない商品です。」と説明している。また、内閣府消費者委員会による「消 費者の『健康食品』の利用に関する実態調査(アンケート調査)」(甲17) では、「サプリメント」は「健康食品のうち、錠剤型、カプセル型、又は粉状 のもの」と定義され、「健康食品」は「健康の保持増進に資する食品として販 売・利用される食品(野菜、果物、菓子、調理品等その他外観、形状等から 明らかに食品と認識される物を除く。)」と定義されている。
これに対し、「商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕」は、指 定商品の分類において第3類とされる「化粧品」について、「この商品には、 薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する『化粧品』の大部分及び『医 薬部外品』のうち『人体に対する作用が緩和なものであって、身体を清潔に し、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保 つことを目的として、身体に塗擦、散布等の方法で使用するもの』が含まれ ます。『化粧品』は、女性用のみならず、男性用又は乳児用の商品も含まれま す。」と説明している。薬事法は、平成25年法律第84号によってその名称 が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 (薬機法)に改められたところ、薬機法2条3項は、「この法律で『化粧品』 とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若 しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似す る方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和 なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三 号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部 外品を除く。」と定義している。
これらの説明及び法律上の定義によれば、「サプリメント」は、人体に欠乏 しやすいビタミン・ミネラル等の栄養素を経口投与によって体内に摂取する ための食品であり、その使用の目的は健康の保持増進にあると認められる。 これに対し、「化粧品」は、身体に対して塗擦、散布等をする方法で使用する ものであり、その使用の目的は人の身体を清潔にし、美化し、容貌を変え、 又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことにあると認められるから、「サプ リメント」と「化粧品」とはその使用方法及び使用目的の根本的部分におい て明確に異なっていると認められる。
(4) 「サプリメント」と「化粧品」については、これら双方を製造する会社及 び双方を販売する会社が複数存在することは認められるものの(甲13の1・ 2、14の1〜13、甲20の1〜72)、通常同一の営業主により製造又は 販売されているとの事情があるとは認められない。 また、前記(3)のとおり、「サプリメント」が経口投与によって体内に摂取す る方法で使用し、「化粧品」が身体に塗擦、散布等をする方法で使用するとい う違いがあることからすれば、「化粧品」には経口投与による体内への摂取に は適しない成分を使用することも可能であると認められ、「サプリメント」と\n「化粧品」について、同一の成分を含む商品が存在するとしても、その原材 料が通常一致するといった関係にあるとは認められない。 需要者については、それぞれの使用目的から、「サプリメント」の需要者は 健康の保持増進に関心のある一般消費者であり、「化粧品」の需要者は身体を 清潔にし、美化し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つこと に関心のある一般消費者であって、これらは一部において一致すると考えら れるが、完全に一致するとは認められない。
(5) 上記(3)及び(4)の事情を総合すると、本件商標の指定商品のうち第5類「サ プリメント」と、使用商標が用いられている商品のうち「化粧品」とは、こ れらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合に、同一営業主の製造又は 販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められず、商標法4条1項 10号にいう「類似する商品」に当たるとは認められない。
・・・
イ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(2)のとおり、本件商標の指定商品 のうち「サプリメント」と原告が製造・販売する「化粧品」に同一又は類 似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品 又は役務と誤認が生じるから、本件商標の指定商品のうち第5類「サプリ メント」は商標法4条1項10号に該当すると主張する。 しかし、「サプリメント」と「化粧品」の両方を製造又は販売している企 業が複数存在しており(前記(4))、その中には、当該企業が運営する同一の ウェブサイトで「サプリメント」と「化粧品」を販売する企業や、「サプリ メント」と「化粧品」に同一のブランド名を付して販売している企業があ ることが認められるが(甲13の1・2、甲14の1〜13等)、「サプリ メント」と「化粧品」が通常同一の営業主により製造又は販売されている との事情があるとは認められないことは前記(4)のとおりであり、「サプリ メント」を販売する企業の多くが化粧品を製造又は販売している、あるい は「化粧品」を販売している企業の多くが「サプリメント」を販売してい るといった事情があるとも認められない。そうすると、「サプリメント」と 「化粧品」について、使用の目的及び方法の双方について相違があること (前記(3))からすれば、上記のとおり認められる事実の限度では、これら の商品に同一又は類似の商標を使用する場合に、同一営業主の製造又は販 売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認めるに足りない。
「サプリメント」と「化粧品」とにおいて、同一の成分を含む商品が販 売されているとしても、通常成分が一致するといった関係にあるとは認め られず、「サプリメント」は経口投与によって体内に摂取する食品であり、 「化粧品」は身体に塗擦、散布等をする方法で使用するという違いがある ことによって、含まれる成分にも差異があると考えられる。
「化粧品」の使用の目的は、前記(3)のとおり、人の身体を清潔にし、美 化し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことにあるので あり、これらを達成することによって心身の健康維持の効果があると説か れることがあるとしても、そのような効果はあくまで間接的なものである といえる。これに対し、「サプリメント」は健康の保持増進が使用の直接の 目的であるといえるから、「サプリメント」と「化粧品」で使用の目的や用 途が一致するとはいえない。
「サプリメント」の需要者と「化粧品」の需要者は、その使用の目的が 異なることからすれば、一部において一致する者があるとしても、完全に 一致しているという事情は認められない(前記(4))。
以上によれば、原告が前記第3の1〔原告の主張〕(2)のとおり主張する 事情を考慮しても、「サプリメント」と「化粧品」について、同一又は類似 の商標を使用する場合には、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認 されるおそれがあると認められる関係があるとは認められない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.03.23
令和5(ネ)10091 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和6年3月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は、第1審原告の請求は、当審における請求の拡張を踏まえると、 第1審被告らに対し被告各標章を付した出版物の出版、販売等の差止め、第1 審被告NPOに対し被告出版物1(1)〜(5)の廃棄、第1審被告らに対し被告出 版物2(1)〜(26)の廃棄、第1審被告らに対し24万8570円及びこれに対す る被告出版物2(26)の発売日以降の遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由 があると判断する。その理由は、以下のとおりである。
1 争点1〜4に関する当裁判所の判断は、原判決の第3の1〜4(18頁〜) のとおりであるから、これを引用する。
すなわち、本件各商標及び被告各標章はそれぞれ類似しており(争点1)、 被告各標章を印刷物に付して使用する行為は、本件各商標権の指定商品又はこ れに類似する商品についての使用ということができる(争点2)。そして、本 件商標2の商標登録無効の抗弁(商標法4条1項19号違反等をいうもの、争 点3)及び第1審被告NPOの先使用の抗弁(争点4)は、「現代の理論」の 標章が第1審被告NPOの業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとはいえない等の本件の事情の下では、いずれも\n理由がない。
2 争点5(権利濫用の抗弁)について
(1) 第1審被告らは、第1審原告が本件各商標を使用して雑誌を発行すること は一切なかったし、将来においてもその予定はないにもかかわらず、本件各商標権の行使をするのは、第1審被告らによる雑誌「現代の理論」の発行を\n妨害することを主たる目的としたものであることが明白であり、第1審原告 が第1審被告NPOの編集委員会に所属していたことがあり、第1審被告N POが創刊当時の精神を引き継いで設立されたことを認識していたことを併 せ考えれば、上記権利行使は権利の濫用に当たる旨主張する。
しかし、第1審被告らが被告各標章を印刷物に付して使用する行為は、少 なくとも、本件商標1の指定商品である第9類「電子印刷物」に類似する商 品についての使用ということができるから、第1審原告は、雑誌等「印刷物」 としての「現代の理論」の発行予定がないにしても,「電子印刷物」を指定商品とする商標権に基づき,第1審被告らの上記行為についての差止請求を\nなし得るものである。また、第1審原告において、競合関係となり得る被告 各出版物が販売されている状況において、本件各商標を使用した雑誌を現に 販売していないからといって、将来においても販売することがないとは直ち にいえない。
また、雑誌「現代の理論」の創刊当時の精神を誰が引き継いでいるか否か といった事項は、権利関係の帰属の問題と異なり客観的に判断することが困 難であり、本件においてこれを確定するに足りる証拠もない。第1審被告N POが明石書店に雑誌「現代の理論」の出版権を譲渡した後に発行していた 雑誌「FORUM OPINION」に「NPO現代の理論・社会フォーラ ム」という名称を付記していたとか、第1審被告NPOの名称に「現代の理 論」が含まれているといった点は、第1審被告NPO側の認識を示すものに すぎないし、購読者らからのメッセージ(乙13)は、雑誌「現代の理論」 を懐かしむ一定の者がいることを示すものとはいえても、第1審被告NPO が需要者から雑誌「現代の理論」創刊当初からの精神を引き継いでいると広 く認識されていることを意味するものではない。
(2) 第1審被告らは、第1審原告の権利行使を認めるとすれば、「現代の理論」 という雑誌名がなくなることになり、商標法1条の規定する「産業の発達」 や「需要者の利益」に反する旨主張する。しかし、商標法1条の定めるとこ ろは、一定の商標を使用した商品等が一定の出所から提供されるという取引 秩序を維持することによって、産業の発達に寄与し、需要者の利益を保護す ることにあるのであって、伝統ある名称を有する雑誌が存続するかどうかと いった事項は、これとは異なる問題である。 また、第1審被告らは、差止・廃棄請求を認めることは、経済的自由権で ある商標権によって、憲法上優越的地位を有する表現の自由を制約することになる旨主張するが、差止・廃棄請求を認めたからといって、被告各標章を\n用いない意見表明や出版の機会が制約されるわけではない。\n
◆判決本文
原審はこちら
2024.03.23
令和4(ワ)9100 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月21日 東京地方裁判所
被告方法では、磁性体モールド樹脂で成形されているEコア及びIコア並び にコイルを合体させたコアを、●(省略)●に形成されたキャビティに配置し、 加圧しつつ加熱して樹脂を硬化させてモールドコイルを作成する(以下「加圧・ 加熱過程」という。)ところ、加圧・加熱過程で●(省略)●から磁性体モール ド樹脂が漏れ出し、これが硬化してバリが形成される(第2の2前提事実 )。 原告は、上記の被告方法において、キャビティに配置されるEコア、Iコア を形成する磁性体モールド樹脂(以下「磁性体モールド樹脂(コア)」という。) が構成要件Fの「該キャビティ内に充填した磁性体モールド樹脂」に該当し、\n加圧によって漏れ出してバリを形成する磁性体モールド樹脂(以下「磁性体モ ールド樹脂(バリ)」という。)が「該排出した磁性体モールド樹脂」に該当 し、磁性体モールド樹脂(バリ)を構成する磁性体粉末の容積比(以下「磁性\n体粉末容積比(バリ)」という。)が磁性体モールド樹脂(コア)を構成する\n磁性体粉末の容積比(以下「磁性体粉末容積比(コア)」という。)よりも小 さいと主張するものと解される。
もっとも、被告方法を用いて被告製品を製造する過程において、磁性体粉末 容積比(コア)と磁性体粉末容積比(バリ)について、これらを直接測定して 比較し、後者の容積比の方が小さいものであったことを示す証拠はない。他方、 被告からは、被告方法で作成されたモールドコイルにおいて、磁性体粉末容積 比(バリ)と磁性体粉末容積比(コア)がほぼ同じである旨の電子顕微鏡で撮 影された画像の分析結果(乙4)が提出されている。
ア 原告は、磁性体粉末容積比(コア)と磁性体粉末容積比(バリ)について、 磁性体粉末の粒子径が、磁性体モールド樹脂が漏れ出す隙間よりも大きけれ ば、樹脂が隙間から優先的に排出されるために磁性体粉末容積比(バリ)の 方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなるところ、被告方法の加圧・ 加熱過程で加圧を続けても樹脂の流出が止まるのは、磁性体粉末が隙間を埋 めることが理由であるから、被告方法においては、樹脂が隙間から優先的に 排出されるといった事象が生じたことが示されていると主張する。これに対 して、被告は、被告方法において加圧・加熱過程で加圧を続けているにもか かわらず樹脂の流出が止まる理由について、磁性体によって隙間が埋められ たためではなく、触媒等を利用した上で加熱により樹脂が硬化したためであ ると主張している。
原告は、被告が主張するような短時間で硬化は生じない旨主張するが、被 告方法における樹脂の硬化につき、この原告主張を裏付けるに足りる証拠は ない。また、樹脂の流出が止まったのが磁性体粉末が隙間を埋めたものであ ることを裏付ける証拠はない。被告が実際に使用している被告方法において、 原告が主張するのとは異なる理由により樹脂の流出が止まったことを否定 できず、被告方法において、原告が主張する事象が生じたことによって樹脂 の流出が止まると認めるには足りない。そうすると、原告の主張はその前提 を欠く。
イ(ア)原告は、加圧・加熱過程において磁性体モールド樹脂が漏れ出す隙間が 磁性体粉末の粒子径よりも小さければ、樹脂が優先的に流出するために 磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さく なるという原理を前提に、被告方法で生じている隙間は十分に小さいも\nのであると主張する。
(イ)しかし、被告方法において隙間に相当するものの幅、形状・構造等は不\n明である。原告は、バレル研磨跡に生じている被告製品の角に生じた研磨 跡に着目し、バリの幅は研磨跡を超えることはないなどとして、研磨跡か らバリの幅を推計し、バリの厚さは●(省略)●を超えるものではないな どとも主張する(甲8)。しかし、研磨跡によりバリの幅を正しく把握で きるかは明らかでなく、原告指摘の事実によっても、隙間に相当するもの の幅、形状・構造等は不明である。\n
(ウ)被告方法で用いられる磁性体粉末の大きさについても、被告が用いた磁 性体のD99は、●(省略)●D90は、●(省略)●であることは認め られる(乙3)が、被告方法においては、様々な粒子径、形状の磁性体が 使用され、具体的な粒子径の分布は不明である。そして、被告方法で作成 されたモールドコイル及びバリの電子顕微鏡で撮影された画像(乙4)に よれば、被告方法で隙間に相当するものの幅に比べて格段に小さな磁性体 粒子が多数含まれていることが認められる。
(エ)原告が前記(ア)で主張する原理について、全磁性体粒子のうちの最小粒子 径が隙間よりも大きい場合には、磁性体は隙間を通過することができない ため、樹脂のみが隙間から流出することは推測できる。逆に、全磁性体の 粒子径が隙間よりも十分に小さければ、樹脂と共に磁性体も隙間を通過す\nることから磁性体粉末容積比(コア)及び磁性体粉末容積比(バリ)に変 化がないものと推測でき、隙間より大きな磁性体粒子の割合が極めて小さ い場合にも同様である。他方で、これら以外の場合には、磁性体粉末の具 体的な粒子径の形状・分布、樹脂の性質、隙間の形状・構造、加えられる\n圧力等により、隙間を通過する磁性体の量は変化するものと推測される。 そして、それらについて、どのようなものであった場合に隙間を通過する 磁性体がどの程度あるかについて、これを認めるに足りる証拠はない。
(オ)以上によれば、被告方法においては、様々な粒子径、形状の磁性体が使 用されているところ、その全磁性体粒子のうちの最小粒子径が被告方法 で使用されている●(省略)●よりも大きいことを認めるに足りない。ま た、そのように全磁性体粒子のうちの最小粒子径が被告方法で使用され ている●(省略)●よりも大きいことが認められない場合、被告方法にお いて、どのような割合で磁性体と樹脂が被告方法における隙間に相当す る部分を通過するかは明らかではなく、特に本件のように隙間よりも小 さな粒子径を有する磁性体粒子が多数含まれる場合には、原告が主張す る原理によって、被告方法において磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性 体粉末容積比(コア)よりも小さくなっているという事実を認めるに足り ない。
ウ 以上によれば、被告方法において磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体 粉末容積比(コア)よりも小さくなっていることを認めるに足りる証拠はな い。かえって、前記 のとおり、被告からは、被告方法で作成されたモール ドコイルにおいて、粉末容積比(バリ)と粉末容積比(コア)が変わらない 旨の電子顕微鏡で撮影された画像の分析結果(乙4)が提出されている。
(3)よって、被告方法において粉末容積比(バリ)の方が粉末容積比(コア)よ りも小さくなっていることを認めることはできず、被告方法が構成要件Fを充\n足するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.03.23
令和5(ワ)70052 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年2月26日 東京地方裁判所
原告は、本件において虚偽の事実を告知等されたことによって、経済的損害に つき不正競争防止法2条1項21号に基づく損害賠償請求権が発生するほかに、 併せて人格的利益を侵害するものとして、別途不法行為に基づく損害賠償請求権 が発生する旨主張する。そこで検討するに、人格権ないし人格的利益とは、明文上の根拠を有するものではなく、生命又は身体的価値を保護する人格権、名誉権、プライバシー権、肖像権、名誉感情、自己決定権、平穏生活権、リプロダクティブ権、パブリシティ 権その他憲法13条の法意に照らし判例法理上認められるに至った各種の権利 利益を総称するものであるから、人格的利益の侵害を主張するのみでは、特定の 被侵害利益に基づく請求を特定するものとはいえない。しかしながら、原告は、 裁判所の重ねての釈明にもかかわらず、単なる総称としての人格的利益をいうに とどまることからすると、原告の主張は、請求の特定を欠くものとして失当とい うほかない。
もっとも、原告は、原告主張に係る人格的利益とは、最高裁平成16年(受) 第930号同17年7月14日第一小法廷判決・民集59巻6号1569頁(平 成17年判決)にいう著作者の人格的利益と同趣旨のものであり、大阪高裁令和 4年(ネ)第265号、第599号同4年10月14日判決(令和4年判決)も、 その趣旨をいうものである旨主張する。
仮に、原告主張に係る人格的利益が、上記判例を引用する限度で特定されてい るものと善解したとしても、平成17年判決は、著作者の思想の自由,表現の自\n由が憲法により保障された基本的人権であることに鑑み、公立図書館において閲 覧に供された図書の著作者の思想、意見等伝達の利益を法的な利益として肯定す るものであり、その射程は、公立図書館の職員がその基本的義務に違反して独断 的評価や個人的好みに基づく不公平な取扱によって蔵書を廃棄した場合に限定 されるものである。そうすると、私立図書館その他の私企業における場合は、明 らかにその射程外というべきものであるから、平成17年判決は、私企業である YouTubeにおける投稿動画に係る伝達の利益が問題とされている本件に は、適切なものといえない。
また、原告が引用する大阪高裁令和4年(ネ)第265号、第599号同4年 10月14日判決(令和4年判決)は、人格的利益に関わるものと説示しつつも、 投稿者の営業活動を妨害するという側面をも踏まえたものであるから、精神的価 値という法益に限定して法的利益性が主張されている本件には、必ずしも適切で はない。のみならず、平成17年判決が、上記のとおり、伝達の利益を法的な利 益として肯定する場面を、公立図書館の職員による極めて不公平な取扱等の場合 に制限している趣旨に照らしても、憲法で保障されている表現の自由から、直ち\nにYouTubeにおける投稿動画に係る伝達の利益を肯定するのは相当では ない。その他に、原告は、著作権法、電気通信事業法その他の法令を縷々指摘して、 原告主張に係る人格的利益が重要性の高い法益である旨主張するものの、原告が 掲げる法令は、原告主張に係る人格的利益を保護するものとはいえず、上記にお いて説示したところに鑑みると、原告の主張は、その特定及び根拠を欠くもので あり、採用の限りではない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.03. 8
令和3(ワ)16043 損害賠償請求事件 商標権 令和6年1月26日 東京地方裁判所
6 争点4(損害の発生及び数額)について
(1) 前記2のとおり、本件商標と被告標章は類似するから、被告による被告商 品の販売行為は、本件商標権の侵害行為を侵害したものとみなされる(商標 法37条1号)。
(2) 商標権者に、侵害者による商標権侵害行為がなかったならば利益が得られ たであろうという事情が存在する場合には、商標権者がその侵害行為により 損害を受けたものとして、商標法38条2項の適用が認められると解される。 原告は、前記第2の1(4)のとおり、原告の商品を販売するウェブサイトに おいて、本件商標を商品名の一部として付した原告商品を法人向けに販売し ていた。これに対し、被告は、同(3)のとおり、販売サイトや小売店の店頭に おいて、被告商品を販売していた。もっとも、原告商品も被告商品も新年の 挨拶における贈答品として用いられる衛生マスクであり、一般的な衛生マス クとは販売のコンセプトが異なることをも踏まえると、原告商品の顧客とな るべき法人において、被告商品を被告の販売サイトや小売店の店頭から商品 を購入するものがいなかったとはいえない。そうすると、被告の侵害行為に より原告商品の売上げが減少したものと評価でき、原告に、被告による商標 権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する。 したがって、商標法38条2項の適用がある。
(3)ア 商標法38条2項により侵害者が受けた利益の額が原告の損害と推定さ れる。もっとも、同規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が 得た利益の一部又は全部について、商標権者が受けた損害との相当因果関 係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅され る。
イ 被告は、令和2年8月から令和3年1月までの間に、被告標章が付され た包装箱に入れた衛生マスク4種類を販売していた。被告商品について、 前記第2の1のとおり、その売上額は合計1596万1281円であり、 そのための経費は1215万0844円であったから、限界利益は381 万0437円である。
ウ 被告は、本件において、推定覆滅の事由に該当する事実がある旨主張す る。 被告は、原告商品は業者等の法人のみが購入でき、原告商品の想定 される利用方法は、原告商品を購入した法人の従業員や取引先への年始 の贈り物であるのに対し、被告商品は一般消費者が他の衛生マスクと比 較しながら購入するものであり、衛生マスクという物品の性質上最終的 に使用するのが個人であるとしても、当該個人が取得するまでのルート は両者において全く異なると主張する。
この点に関係し、原告は、原告の販売先が法人であるとした上で、当 該法人は、当該法人の従業員や取引先への年始の贈り物とするノベルテ ィ商品としてこれを使用するほか、個人に対して販売する旨主張する。 しかし、原告の販売先である法人が、個人に対して販売した数量等につ いては何ら主張立証されておらず、当該法人が個人に対して販売してい たことを認めるに足りない。したがって、原告商品は、法人によって、 当該法人の従業員や取引先への新年の挨拶における贈答品とするという 目的で購入されたと認められる。 被告商品は被告の販売サイトや小売店の店頭において販売されていて、 法人だけでなく、一般消費者も自由に購入できた。そうすると、原告商 品の顧客となるべき法人に、被告商品を被告の販売サイトや小売店の店 頭から商品を購入するものがいなかったとはいえないものの(前記 )、 原告商品は上記のとおり法人がそのノベルティ商品として購入するもの であるのに対し、被告商品は、基本的には、一般の消費者が購入すると いえ、その市場は異なる部分が非常に大きく、この事情は、前記推定を 覆滅させる事情であると認める。被告は、本件商標の顧客吸引力は皆無に等しく、被告商品が売れたのは、被告商品名や被告商品の品質に関わる表示によるものである旨主\n張する。
しかし、被告商品名を付した商品が一定数販売され、また、報道機関 などで取り上げられたことがあったとしても、極めて多種の製品が大量 に販売されている衛生マスクの需要者において、被告商品名が広く知ら れていたとは認められないし、また、衛生マスクにおいては品質に関す る表示がされることも多いところ、被告商品の品質に関する表\示が特に 顧客吸引力を有するものであることを認めるに足りない。他方、被告標 章は、被告商品の包装箱の正面の右上部分及び上面の2か所に目立つよ うに記載されていて、包装箱の上面においてはその中央部分に記載され ているのであり、その顧客吸引力がないとはいえない。 本件については、前記 の事情により推定が大きく覆滅すると認めら れるという事情があるところ、それに加えて被告が主張する上記推定覆 滅についての事情があるとは認められない。 以上のとおり、原告商品と被告商品は、市場が非常に大きく異なっ た。原告商品の市場は被告商品の市場に比べて小さく、被告商品の市場 のうち、ごく一部が原告商品の市場と重なっていたといえる。このよう な事情によれば、被告商品を購入した者のうち、被告商品に被告標章が 付されていることによって原告商品に代えて被告商品を購入したといえ る者の割合はかなり低いと認められ、被告が主張する事由のうち、上記 の理由により、原告は被告商品の販売数量のうちの相当多くのものにつ いて販売することができたとはいえない事情があり、商標権者が受けた 損害との相当因果関係が欠けると認める。上記の理由により、原告は被 告商品の販売数量の95%について販売することはできたとはいえず、 被告が得られた限界利益のうち、原告の損害との相当因果関係のあるも のは、5%であったと認めるのが相当である。
エ そうすると、商標法38条2項による原告の損害は次のとおり、19万 0521円である(小数点以下切り捨て)と認められる。
(計算式)381万0437円×0.05=19万0521円(小数点以下 切り捨て)
(4) 商標法38条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅 部分について、商標権者が使用許諾をすることができたと認められるときは、 同条3項の適用が認められると解される。 前記(3)によれば、本件の事情の下においては、原告が販売することができ ない事情があるとされた数量に相当する被告商品については、原告が使用許 諾をすることができたと認められる。 そして、商標法38条3項の使用の対価を算定するにあたっては、当該商 標権の侵害があったことを前提として当該商標権を侵害した者との間で合意 をするとしたらならば、当該商標権者が得ることとなるその対価を考慮する ことができる(同条4項)。第10類の商標の使用料率の平均値は売上高の 3%とされるが、その最大値は5.5%とされ(乙61)、この使用料率の 平均値には、非侵害者との間の合意による使用料率も含まれており、侵害し た者との間で合意をする場合平均値より高い使用料率になり得ることを踏ま えると、原告の使用機会の喪失による得べかりし利益は、対象となる商品の 売上高の5%は下回らないものと認める。そうすると、商標法38条2項による推定が覆滅される部分についての商標法38条3項の損害は、以下のとおり、75万8160円となる。
(計算式)1596万1281円×0.95×0.05=75万8160円(小数点未満切り捨て)
(5) そうすると、原告の損害額は94万8681円となる。
2024.03. 8
令和5(行ケ)10050 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年2月5日 知的財産高等裁判所
ア 被告は、平成24年8月29日、「biyou-ikyoku.com」のドメイン名を取得し、 その頃、「美容医局」の商標(引用商標)が表示された美容クリニック専門の医師転\n職サイトを開設して、本件サービスの事業を開始し、以後、現在に至るまで本件サ ービスの事業を継続している。(甲5、乙8、11)
イ 令和元年度における医師向けの有料職業紹介事業の総売上高が約212億円 (乙19の1中の「職業紹介事業 運営状況(令和元年度)」の16頁)であり、医 師総数に対する美容外科医及び皮膚科医の数の割合が約4.7%(=(平成30年 12月31日現在の皮膚科医数1万4244人+同日現在の美容外科数1176人 の合計1万5420人)÷同日現在の医師総数32万7210人。乙20の1の4 頁及び11頁。以下、各年の美容外科医及び皮膚科医向けの有料職業紹介事業の売 上高を推計する際の医師数は、同日現在の数字を用いる。)であることからすると、 美容外科医及び皮膚科医向けの有料職業紹介事業の売上高は10億円程度と推計さ れる。(乙19の1、乙20の1) そして、令和元年の本件サービスの売上高は●●●●●●万円(乙23の1)で あるから、美容外科医及び皮膚科医向けの有料職業紹介事業における本件サービス のシェアは●割近いものであると推認される。(乙23の1)
ウ 同様に令和2年度の医師向けの有料職業紹介事業の総売上高が約227億円 (乙19の6中の「職業紹介事業 運営状況(令和2年度)」の16頁)であること から、前記美容外科医及び皮膚科医の数の割合を乗ずると、美容外科医及び皮膚科 医向けの有料職業紹介事業の売上高は10億6700万円程度と推計されるところ、 令和2年の本件サービスの売上高は●●●●●●万円(乙23の1)であるから、 そのシェアは●割近いものと推認される。(乙19の6、乙23の1)
エ 平成27年度から平成30年度までの各年の医師向けの有料職業紹介事業の 総売上高は、約154億円、約174億円、約166億円、約197億円であるの に対し、平成27年から平成30年までの各年の本件サービスの売上高は●●●● 万円、●●●●万円、●●●●●●万円、●●●●●●万円であるから、本件サー ビスは、医師向けの有料職業紹介事業全体の総売上高の増加率よりも大きな増加率 をもって、売上げが上昇した。(乙19、23)
オ 平成25年から令和2年までの各年において、本件サービスに新規登録した 医師の数は、●●人、●●●人、●●●人、●●●人、●●●人、●●●人、●● ●人、●●●●人であった(令和2年における累計●●●●人)。なお、平成30年 12月31日現在の美容外科又は皮膚科の診療科に従事する医師の数は前記のとお り合計1万5420人である。(乙20の1、乙25)
カ 被告は、本件サービスの一環として、平成24年9月に、第1回の医師転職 支援セミナーを実施した後、たびたび転職セミナーを開催し、令和2年度には「転 科不安解消セミナー」「研修医向けノウハウセミナー」など合計30回のセミナーを 実施し、令和3年度には「初期研修医のための就活ガイダンス」など合計32回の セミナーを実施した。被告は、「美容医局」に登録した美容医療関係者のためのスキ ルアップセミナー、オペ見学・解説セミナーの提供といった役務も行っている。(甲 5の2、甲15、甲18、甲51、甲62の1、2、18及び19)
キ 被告は、Yahoo!ディスプレイアドネットワーク、Facebook、Twitter といっ たインターネットにおいて、引用商標を用いた本件サービスの広告を出稿しており、 令和2年5月から7月までの間に、●●●万回を超える表示がされ、●万を超える\nクリックがされた。(甲51)
ク 令和3年8月2日付けのインターネット上の「【転職のプロが教える】美容外 科おすすめ医師転職エージェントランキング」と題する記事において、本件サービ スが、美容外科・美容皮膚科転職エージェントおすすめ求人数ランキングで、全1 2エージェント中1位として掲載されている。同記事によれば、「美容医局」の求人 数3692件は、全12エージェントの合計求人数1万1682件の約31.6% を占めている。(甲13)。
(3) 前記(2)を総合すると、本件サービスは、遅くとも令和2年頃までには、美容 外科及び美容皮膚科に転職しようとする医師並びに医師を求める美容外科及び美容 皮膚科の医療施設にとって多く利用されているサービスとなっていたということが でき、本件サービスを表すものとして使用されている引用商標は、本件商標の出願\n時である令和2年7月31日及び登録査定時である令和3年6月2日において、本 件サービスを表すものとして、その需要者である美容外科医、美容皮膚科医及びそ\nの医療施設関係者の間で広く認識されていたと認めるのが相当である。
原告は、医師全体の有料職業紹介事業に対するシェアからすると、本件サービス に周知性があるとはいえないと主張するが、そもそも本件サービスの対象とする美 容外科又は美容皮膚科の医師の数の医師全体数に占める割合が前記のとおり約4. 7%にすぎないことからすると、本件サービスの医師全体の有料職業紹介事業に対 するシェアが少ないことをもって、本件商標の知名度が低いということはできない。 そして、「美容医局」との商標が本件商標の指定役務である「職業のあっせん、求人 情報の提供、人材派遣による職業のあっせん、人材派遣による求人情報の提供」に おいて用いられる場合には、美容外科又は美容皮膚科に関係する医療関係者以外を 対象とするものとは考え難いのであるから、美容外科又は美容皮膚科に転職する可 能性のない医師までを需要者とみるのは相当ではなく、上記原告の主張は採用する\nことができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.03. 8
令和5(行ケ)10116 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年2月28日 知的財産高等裁判所
原告は、日本における取引者・需要者にとってチベットという地名は必 ずしも著名ではなく、チベットトラという亜種(分類)も存在しないなどと して、本願商標は「Tibet Tiger」という造語として認識される 旨主張する。しかし、本願商標の構成中の「Tibet」の文字は「チベット(中国南西部の自治区)」を意味する英語であり(乙1、3)、「Tiger」の文字\nは「トラ」を意味する英語であって(乙2、4)、これらはいずれも平易な 英単語として我が国においても一般に親しまれている。これらの文字を空白 一字分間に挟んで並べた本願商標は、構成全体として「チベットのトラ」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものと認められ、その旨をいう本件\n審決の判断に誤りはない。日本の取引者・需要者にとってチベットという地 名が必ずしも著名でないことを認めるに足りる証拠はなく、また、チベット トラという亜種(分類)が存在しないことは上記認定を妨げるものではない。
(3) 原告は、本願商標の指定商品はトラの体等を直接的に使用した商品では ないから、本願商標は指定商品との関係で商品の特徴等を直接的に表示するものではない旨主張するので、以下検討する。\nア 証拠(甲15〜17、乙5〜16)によれば、ウェブサイト上では、本 願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、チ ベットやネパールはじゅうたんの生産地及び販売地として知られており、 じゅうたんはチベット民族の伝統的な手工芸品であるとされ、チベット 民族やネパールに在住しているチベット難民によって手織りされている じゅうたんは「チベットじゅうたん」と称され、世界4大じゅうたんの 一つに数えられ、丈夫で耐久性に優れているなどと紹介されていること が認められる。
また、同様にウェブサイト等では(甲6〜9、18〜21、23、2 4、乙23、25〜52)、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラ グ」との関係において、トラ柄又はトラの図柄等を表す語として「Tiger」又は「タイガー」の文字が使用されており、「チベットじゅうた\nん」の中でも、トラのモチーフは、位の高い僧侶のために作られていた ことから格の高い文様、由緒あるものといわれ、トラの図柄を描いた、 あるいは、トラの形状を模した「チベットじゅうたん」は、生産地及び 販売地の地域を表す語(チベタン〔Tibetan〕、チベット〔Tibet〕)と、トラを意味する「Tiger」とを組み合わせて「Tibe\ntan Tiger(Rug)」、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チ ベットタイガー(カーペット)」などと称されて多数販売されていること も認められる。
イ 上記アのような取引の実情を踏まえると、「Tibet Tiger」 の文字よりなる本願商標をその指定商品中、トラの図柄又はトラの形状 のチベットじゅうたん、チベット製ラグ等に使用した場合、これに接す る取引者、需要者は、単に商品の産地又は販売地であるチベット、ある いはトラの図柄又は形状といった品質を表示したものと理解するにとどまるというべきである。\n
ウ この点につき、原告は、本件で提出されている証拠がインターネット上 の情報にすぎず、出所不明の情報であるとも主張するが、前記アの認定 証拠について、その信用性を疑わしめる事情は見当たらない。 そもそも原告が自らの販売実績を示すために提出した証拠(甲6〜9) からも、ヤフオク(ヤフーオークション)というメジャーなサイトにお いて原告の取扱商品以外のものも含め、「チベタンタイガーラグ」、「チベ タンタイガー絨毯」という用語を「商品タイトル」(商品の一般名称)に 掲げた取引が行われている事実が客観的に認められるところである。
(4) 原告は、自身の事業において「チベタンタイガー」という標章を使用し て商品を販売してきたとして、原告が本願商標に係る商標権を取得すること は公益的な観点からも許されるべきであると主張する。 しかし、後述する商標法3条2項の規定による識別力の獲得が認められる 場合は別として、公益性の観点から商標法3条1項3号該当性を否定する原 告の主張は独自の見解に基づくものであり、採用できない。
(5) 以上のとおりであって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとし た本件審決の判断に誤りはなく、原告の取消事由1の主張は理由がない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2024.02.24
令和5(行ケ)10054 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年2月13日 知的財産高等裁判所
カ 甲8発明と本件発明1との相違点として本件審決が認定したもの(前記 第2の4(2)ア(イ))のうち、甲8相違点2は、前記エの説示によれば、甲8 発明と本件発明1との相違点となるとは認められない。 また、甲8相違点3は、甲8発明における台車用安全カバー及び本件発 明1における保護部材の用途を特定する物としての手押部材の違いを述 べるものであって、甲8発明における台車用安全カバーと本件発明1にお ける保護部材との相違点とはいえない。したがって、甲8発明と本件発明 1との相違点は、甲8相違点1及び取付位置に係る相違点のみであると認 められる。
キ 前記第2の2(3)のとおり、1)本件発明2は、本件発明1の構成要件1A\nないし1Fを全て含み、2)本件発明3は、本件発明1の構成要件のうち、\n1Eを「前記保護部は、円板状である。」(構成要件2E)に変更したもの\nであり、3)本件発明4ないし7は、本件発明1の構成要件1Aないし1F\nを全て含むか、又は本件発明3の構成要件1Aないし1D、2E及び1F\nを全て含むものである。
そうすると、本件発明2ないし7は、いずれも、甲8発明との関係で、 甲8相違点1及び取付位置に係る相違点があると認めることができる。
ク 以上のとおり、甲8発明と本件各発明との一致点及び相違点に係る本件 審決の判断には相当でない部分があるものの、これによって直ちに本件審 決の判断が違法となることはなく、甲8相違点1を前提に、当業者が、本 件優先日の技術水準に基づいて、これらの相違点に対応する本件各発明を 容易に想到することができたかどうかを判断すべきである。
(3) 容易想到性について
前記(1)のとおりである甲8発明の内容によれば、甲8発明の台車用安全カ バーは、その本体、すなわち甲8発明の全体が保護部を構成しており、作業\n者の手挟み事故を防止するとともに、手押部材の掌握部、すなわち台車のコ 字状のハンドルのグリップ部の位置を使用者に認識させる作用をもつもので あるといえる。このことは、甲8商品2と同一の構成の商品を含む甲8商品\n1に係るパンフレット(甲8の2)に、「台車に取り付けることで、作業員の 手挟み事故を防止!掌握部もわかりやすくなり、安全指導がしやすくなりま す」との記載があることからも裏付けられる。 このように、甲8発明の台車用安全カバーは、コ字状のハンドルの水平部 分をグリップ部とすることを前提として、コ字状のハンドルのカーブ部分に 取り付ける台車用安全カバー(保護部材)であって、これによって手挟み事 故の防止を図るものであるから、甲8発明の台車用安全カバー(保護部材) にグリップ部を設けることは全く想定されていないといえる。 そうすると、仮に、台車の手押部材にグリップ部を設けること、又は台車 等の保護部をグリップ部と一体化したものとすることが、本件優先日の時点 で周知技術であったとしても、甲8発明の台車用安全カバー(保護部材)に 接した当業者において、これらの周知技術を甲8発明に適用する動機付けが あったとは認められない。 したがって、引用発明である甲8発明に基づいて、甲8相違点1に係る本 件各発明の構成が容易に想到できたとは認められず、甲8発明を前提とする\n進歩性に関する本件審決の判断に誤りがあるとは認められない。
(4) 前記第3の1〔原告の主張〕について
ア 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)のとおり、甲8発明の台車用安 全カバーは、直線の棒にも装着可能であり、コ字状のハンドルのカーブ部\n分に対してのみ取り付け可能な製品ではないから、本件審決における甲8\n発明の認定は誤りであると主張する。 この点、長岡産業代表取締役である甲の陳述書(甲53)には、甲8商\n品2は、甲8商品1とともに、カーブ部分に装着することに特化した形状 (特に孔の形状)となっておらず、曲がっていない直線の棒にも装着可能\nなものであった旨の陳述がある。
しかし、甲8商品2の本体及び取付穴の形状から、物理的には直線の棒 に装着することが可能であるとしても、甲8商品2のパンフレット(甲8\nの3)及び甲8商品2と同一の構成の商品が含まれる甲8商品1のパンフ\nレット(甲8の2)の各記載及び掲載された写真からすれば、甲8商品2、 すなわち甲8発明の台車用安全カバーは、コ字状のハンドルのカーブ部分 に取り付けることにより、使用者の手がハンドルの上下方向の直線部分に 掛からないように規制し、これによって手挟み事故を防止するものである と認められる。
上記各パンフレットに掲載された、各商品が台車のハンドルに装着され た状態の写真は、いずれもコ字状のハンドルのカーブ部分に装着されたも のを撮影したものであって、直線の部分に装着した写真ではないと認めら れる。また、甲8の2には、「ハンドルのカーブ部分に挟み込み、テープを はがして包むだけ!」と表記されているのであって、カーブ部分に挟み込\nむことが単なる使用の一例にすぎない旨の記載はされていない。 以上のとおり、甲8発明に関する本件審決の認定に誤りがあるとは認め られない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 相違点認定
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2024.02.24
令和5(ネ)10069 職務発明対価請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月1日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 前記第2の3(1)の主張について
控訴人は、本件就業規則60条(3)は職務発明に関する規定であると解すべ きであり、このような規定に基づいて平成24年6月末にクオカードが交付 されている以上、この時点をもって消滅時効の起算点とすべきであると主張 する。
しかし、本件就業規則60条は、「表彰」に関する規定であると明示され、\nその表彰事由は職務発明に関するものだけでなく業務上の功績と認められる\n事情が広範に表彰の対象とされており、表\彰として経済的利益を供与すると 決められていることはなく、表彰の内容や時期についても同条その他本件就\n業規則において定められていないことからすれば、同条(3)が職務発明の対価 に関する規定であると解することができないのは、補正の上で引用した原判 決「事実及び理由」第3の1(1)ウの説示のとおりであり、被控訴人が本件発 明に基づく利益を得たこと及び被控訴人が控訴人に対して金銭的価値を有す るプリペイドカードの一つであるクオカードを支給したことをもって、同条 (3)を職務発明の対価に関する規定であると解することはできない。
勤務規則等において職務発明に係る対価の支払に関する規定が存在する 場合でも、支払時期の定めがなければ、職務発明について特許を受ける権利 を使用者に承継させた従業者は、権利の承継の時点から使用者に対して職務 発明対価請求権を行使することができるから、原則として同時点が消滅時効 の起算点となる。勤務規則等において支払時期の定めがあるときに、上記支 払請求権の消滅時効の起算点が当該支払時期となるのは、同支払時期までは 権利行使について法律上の障害があり、上記支払請求権を行使することがで きないことによる(補正後の原判決第3の1(1)ア)。これらの事情からすれば、 本件において控訴人の被控訴人に対する相当の対価の支払請求権の消滅時効 が特許を受ける権利の承継の時点から進行すると解することが、発明者に対 するインセンティブを与えるために職務発明対価請求に関する規定を定めた 使用者に比べ、発明者に対するインセンティブを与えない使用者である被控 訴人に対して消滅時効の起算点に関して手厚い保護を与える結果となって不 当であるとはいえない。
被控訴人において、本件就業規則60条に基づく表彰を毎年6月末に行う\n運用又は慣行があったとして、そのことは、同条(3)の規定が職務発明に係る 対価の支払に関する規定であると解する根拠とはならない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) 前記第2の3(2)の主張について
控訴人は、本件において「権利を行使することができる時」(民法166条 1項)とは、控訴人が被控訴人を退職した時点、あるいは、どんなに早くて も、本件同意書の有効性について検討するのに必要な合理的な検討時間であ る捺印後6か月経過後であるから、本件では消滅時効は完成していないと主 張する。 しかし、「権利を行使することができる」とは、その権利の行使につき法律 上の障害がないこととともに、権利の性質上、その権利行使が現実に期待の できるものであることをも必要とすると解されるが(補正の上で引用した原 判決「事実及び理由」第3の1(1)ウ)、権利行使について事実上の障害がある 場合に常に「権利を行使することができる時」に当たらないことにはならな い。
控訴人が被控訴人の従業員であったことをもって直ちに退職前に職務発 明対価請求権の行使が現実に期待できなかったとはいえない。控訴人の陳述 書(甲13)には、被控訴人は典型的なオーナー企業であって、従業員が会 社に自由な意見を言うことができなかった旨の陳述があるが、客観的裏付け がなくこの陳述を採用することはできないことは、補正の上で引用した原判 決「事実及び理由」第3の1(3)の説示のとおりである。したがって、控訴人が主張する内容を考慮しても、控訴人が被控訴人を退職するまで、被控訴人に対して職務発明対価請求権を行使することが現実に期待できなかったと解することはできない。 また、本件同意書の有効性について検討する必要があるために、本件同意 書に控訴人が捺印した後6か月が経過するまで、職務発明対価請求権の行使 が現実に期待できなかったと解すべき根拠となる事情は認められない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(3) 前記第2の3(3)の主張について
控訴人は、被控訴人の控訴人に対するクオカードの交付は、職務発明対価 の支払債務の一部承認であり、消滅時効が中断すると主張する。 しかし、本件就業規則60条が表彰制度について定めた規定であり、クオ\nカードはこの規定に基づき交付されたものであること、及び、このクオカー ドの交付に先立って控訴人が被控訴人に本件同意書を提出しており、控訴人 及び被控訴人のいずれも、控訴人が職務発明対価請求権を放棄したと認識し ていたのであり、その状況の下でクオカードの交付がされたことからすれば、 クオカードの交付を職務発明の対価の支払であると認めることはできず、職 務発明対価の支払債務の一部承認であると解することもできない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(4) 前記第2の3(4)の主張について
控訴人は、被控訴人が消滅時効の完成を主張することは権利濫用に当たる と主張する。
しかし、本件同意書の作成に当たり、控訴人が、被控訴人の代表者又は従\n業員から、同意書の作成を強制された事実が認められないこと、控訴人の陳 述書(甲13)には、被控訴人は典型的なオーナー企業であって、従業員が 会社に自由な意見を言うことができなかった旨の陳述があるものの、この陳 述内容について客観的な裏付けはなく、上記陳述の内容を採用することはで きないことは、補正の上で引用した原判決「事実及び理由」第3の1(3)の説 示のとおりであり、被控訴人が従業員である控訴人が在職中に使用者に対し て自由な意思表示をすることが不可能\である等の状況を利用し、被控訴人が 控訴人に対して在職中に本件同意書に捺印させたとは認められない。 控訴人が、被控訴人の従業員であることにより、心理的・精神的に職務発 明対価請求権の行使が困難であると感じていたとしても、そのことをもって、 被控訴人による消滅時効の援用が権利濫用であるとはいえない。 まして、控訴人は、被控訴人を退職した後に被控訴人に対して内容証明郵 便により本件各発明に係る相当の対価の支払を求めており、この支払請求は 被控訴人の令和3年5月14日付け回答書により拒絶されたが(前提事実(6))、 控訴人が上記回答書を受領した時点では、遅くとも控訴人が本件各発明に係 る特許を受ける権利を被控訴人に承継したと認められる平成23年9月13 日から10年を経過していなかったから、控訴人の被控訴人に対する職務発 明対価請求権の消滅時効が完成していたとは認められない。それにもかかわ らず、控訴人は、令和4年6月1日まで本件訴訟を提起しなかった(当裁判 所に顕著な事実)。上記内容証明郵便は弁護士(本件の控訴人訴訟代理人弁護 士)が控訴人の代理人として送付しており(甲3の1)、控訴人が、上記内容 証明郵便の送付の時点までに、被控訴人に対する職務発明対価請求に関して 弁護士に相談していたと認められるのであって、これらの事情によれば、控 訴人が、弁護士にも相談した上で、自らの判断で、前記回答書の送付から約 1年後に本件訴訟を提起したものと認められる。控訴人は、陳述書(甲15) において、本件同意書が無効であるといえるのか自信をもてず、弁護士費用 を払って訴訟を提起することを躊躇していたため、令和4年6月まで訴訟を 提起することができなかったと陳述するが、仮にこの陳述どおりであったと しても、そのことをもって、被控訴人による消滅時効の援用が権利濫用に当 たるとはいえない。
◆判決本文
原審はこちら。
2024.02.24
令和5(ワ)70454 特許権侵害等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月9日 東京地方裁判所
(1) 「検査分析装置」及び「検査分析」の意義について
本件発明に係る特許請求の範囲においては、構成要件A、D、F及びGに\n「検査分析装置」との記載があり、構成要件A、B、C、E及びHに「検査\n分析」との記載があるものの、それらの意義は、当該特許請求の範囲の記載 からは明らかではない。
そして、本件明細書には、技術分野に関し、「半導体集積回路装置…の開 発、製造などの検査分析工程で用いられる走査型電子顕微鏡(SEM)、共 焦点レーザ顕微鏡などの検査分析装置の利用方法に関」する(【0001】) との記載が、背景技術に関し、「半導体ウェハ、半導体チップなどの検査分 析においては、検査分析対象となる試料と検査分析装置の性能が合致しない\nと全く有効な検査分析とならない。」(【0004】)及び「半導体ウェハ、半 導体チップの検査分析においては、そのコスト増が著しく、半導体集積回路 装置の開発、製造コストの増大の要因になっている。」(【0005】)との記 載が、課題に関し、「本発明の目的は、半導体集積回路装置などの開発、製 造を効率的に行うために用いられる検査分析工程において、低コストで効率 的に検査分析が行える技術を提供することである。」(【0015】)との記載 が、課題を解決するための手段に関し、本件発明は、検査分析装置の管理者 側と検査分析を希望するユーザ側のそれぞれにセキュリティ確保手段を講じ た上、ユーザが、離れた場所にある検査分析装置を、リアルタイムでリモー ト操作する、又は、ユーザが事前に作成した操作レシピーデータに基づいて 検査分析を行う旨(【0016】ないし【0019】)の記載に加え、「本件 発明の検査分析は、細く絞ったレーザビームを試料面へ照射してその反射光、 散乱光、透過光の少なくとも一つを検出すること、または電子ビームを照射 して二次電子、散乱電子、透過電子の内の少なくとも一つを検出することに より、試料上の所望の箇所を分析するものである。」(【0024】)との記載 が、発明の効果に関し、「本件発明により、検査分析を所望する複数ユーザ に対し、ユーザは個別に検査分析装置の導入のための投資することなく、ユ ーザ試料の検査分析が効率よく行うことが可能となった。」(【0026】)と\nの記載が、それぞれある。これらの記載に照らすと、「検査分析装置」とは、 試料を装填等して、ユーザのリモート操作によりその試料を分析し、検査す る検査分析ユニットを有する装置を意味し、「検査分析」とは、試料を装填 等して、ユーザのリモート操作によりその試料を分析し、検査する工程を意 味すると理解することができる。
これに対し、原告は、「検査分析装置」について、「インターネットを介し たリモート操作が検査分析の対象となるコンピュータ装置であり、当該検査 分析に異常がないことを条件とし、リモート操作した情報を提供するコンピ ュータ装置」と、「検査分析」について、「インターネットを介した検査分析 装置に対するリモート操作に異常がないかの検査分析」と、それぞれ解すべ きである旨主張し、検査の対象が「リモート操作」であることを前提として いるものと解されるが、本件明細書には、原告が主張する解釈の根拠となる 記載はないから、同主張は理由がない。
(2) 被告方法の構成要件充足性について\n
原告の主張は明確ではないものの、被告の動画配信サービスを提供するサ ーバが、「検査分析装置」に該当し、同サービスにおいて、視聴者が動画配 信の内容についてコメントを付したり、高評価ボタンを押下したりすること が、「検査分析」であると主張するものと理解することができる。 しかし、被告の動画配信サービスを提供するサーバは、検査分析の対象と なる試料の装填等を想定したものではなく、ユーザからリモート操作される ことによりその情報等を分析し、検査する検査分析ユニットを備えているも のと認めることはできないから(弁論の全趣旨)、同サーバは、構成要件A、\nD、F及びGの「検査分析装置」に該当しない。 同様に、被告の動画配信サービスにおいて、視聴者が、動画配信の内容に ついてコメントを付したり、高評価ボタンを押下したりすることは、試料を 装填等することを前提とするものではなく、ユーザが同試料について情報等 を分析し、検査するものでもないから、構成要件A、B、C、E及びHの\n「検査分析」に該当しない。 その他、原告の主張する被告方法の内容に照らし、被告方法が「検査分析 装置」又は「検査分析」に該当する装置又は工程を備えるものとは認められ ない。以上のとおり、被告方法が構成要件AないしHを充足すると認めることは\nできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.02.24
令和5(ネ)10070 損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 令和5年12月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、本件商標はスイスの国旗に類似しており、商標法4条1項1号 違反の無効理由があると主張する。
しかし、本件商標の形状は原判決「事実及び理由」第4の1(2)のとおりで あり、やや丸みを帯びた縁(辺)を有する略四角形(略正方形)と、これに 囲まれた略相似形であるやや丸みを帯びた縁(辺)を有する略四角形と、そ の内部(中央)に位置する幅広の十字からなり、前者の略四角形の縁と後者\nの略四角形の縁とがなす部分(外縁部分)と、上記十字部分は、いずれも白\n色であり、後者の略四角形の内部は、上記十字部分を除き黒色であり、上記\n十字の幅は外縁部分の3倍程度である。
これに対し、スイスの国旗は、原判決「事実及び理由」第4の2のとおり、 正方形と、その内部(中央)に位置する幅広で白色の十字からなり、正方形\nの内部は、白色である上記十字部分を除いて赤色である。\nしたがって、スイスの国旗は、正方形であって白色の外縁部分がなく、内 部の十字部分を除いた部分が赤色である点において、本件商標と相違してお\nり、本件商標とスイスの国旗は、控訴人が指摘する共通点を考慮しても、中 心的かつ全体的構成を占める図形の形状及び色彩において明らかに相違する。\n被控訴人が、本件商標と同様の形状であるが、地色が赤色で十字部分が白\n色の標章を使用したことがあるとしても、そのことをもって、地色が赤色で 十字部分が白色のものも本件商標に含まれることにはならず、本件商標とス\nイスの国旗がその色において共通するとはいえない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆令和3(ワ)13895
当事者が同じ関連訴訟です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2024.02.24
令和5(ネ)10038 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年12月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「確かに、乙14の4から13、乙15ないし20、22によれば、紙 におけるにじみなどの模様は模様付きの和紙としてカタログで販売される ものにも見られるものではある。しかし、控訴人は、楮を原料とし、にじ みが良く、染め方に深みを出すことができる和紙に、膠、明礬及び水を混 合した礬砂を刷毛で和紙の片面又は両面に引いて乾かし、その際、礬砂の 配合量や引き方等を調整したり、複数の刷毛を使い分けたりすることによ り、紙上に、水のにじみにくい部分や染料の染みにくい部分を生み出し、 毛質、長さ、大小が異なり、特別に注文した複数の刷毛を使い分け、主に 柿渋、胡桃、墨、土など自然の染料で和紙を染め、刷毛のあと、にじみに より紙上に色を配置するなどの手法を用いて和紙に模様や色彩を施し、一 点ずつ異なる模様の染描紙を制作しており、創作ノートに構図のためのス\nケッチ、色、染料の選択、配置、濃淡、線や動き等を記載することもあっ た(前記1(3))こと、そして、本件染描紙15から20のうち、本件染描 紙18は約65cm×約180cm、それ以外は約74cm×約100c mという大きさを備えるものであって、控訴人は空の情景を意識して本件 染描紙15から20を制作していること(前記1(2)、(3))、それぞれの模様 は原判決別紙本件染描紙(15〜20)一覧の各写真のとおりであって、 控訴人が、特定の色彩を選択して、構図を考えた上で模様を配置し、全体\nとしてまとまりのある図柄を作り上げたものといえることを考慮すれば、 創作的表現がされていると認められる。これらの事情を総合すれば、本件\n染描紙15から20の上記創作的表現は、模様のついた和紙として通常想\n定される模様とはいえず、実用的な目的のためのものといえる特徴と分離 して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備える部分を把握することが できるといえる。したがって、本件染描紙15から20は、控訴人の著作 物であると認められる。」
(2) 翻案について
翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質な特徴の同一\n性を維持しつつ、具体的な表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想\n又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の\n表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行\n為をいう(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法 廷判決・民集55巻4号837頁参照)。
これを本件において検討すると、被控訴人Y’が制作した本件展示物15 から20は、本件染描紙15から20に依拠し、原判決別紙染描紙(15〜 20)一覧において、四角い枠を付したものとして示した写真における、四 角い枠で囲んだ部分を利用して、補正した上で引用した原判決第3の2(3)で 認定した制作過程を経て制作されたものと認められ、また、本件展示物15 から20は、作品の全体像として、「Yアートワークス/天空図屏風シリーズ」 と題する一連の作品として、屏風様式を取り入れ、上記作品より一回り大き い茶色のアルミ複合版製の下地とともに設置され、晴天の日の日中は、各展 示場の上方の天井にそれぞれ存在する天窓から日差しが差し込むように配置 され、本件展示物15から20が展示されている各壁面の正面付近の各床に は、本件展示物15から20について、本件説明とともに、それぞれ各和歌 (原典及び口語訳)が記載された説明書きが埋め込まれていて、これらの構\n成要素が組み合わされて仕立てあげられた作品であることが認められるから、 本件染描紙15から20の具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新た\nに思想又は感情を創作的に表現するものと認められるものの、本件展示物1\n5から20の屏風の部分の表現と本件染描紙15から20の上記四角い枠で\n囲んだ部分の表現とを対比すると、前者は後者と比較して、全体的に青系の\n色彩が強調され、また、刷毛のあとや染色の境目などの輪郭が鋭く明確化さ れているなど、両者は色合いや色調に多少の相違が認められるものの、刷毛 状の模様、にじみ具合及びこれらの構成や配置は極めて類似しているから、\n本件展示物15から20に接する者が本件染描紙15から20の表現上の本\n質的特徴を直接感得することが十分に可能\であるということができる。 したがって、本件展示物15から20は、本件染描紙15から20を翻案 したものであると認めるのが相当である。
・・・
6 当審における当事者の補充主張に対する判断
(1) 被控訴人Y’の前記第2の5(1)の主張について
被控訴人Y’は、本件染描紙15から20は著作物に当たらないと主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決「事実及び理由」第3の4(2)のとおり、 本件染描紙15から20については創作的表現がされていると認められる。\n前記のとおり、本件染描紙15から20の模様は、単なる和紙の染みやに じみではなく、控訴人は、膠、明礬及び水を混合した礬砂を刷毛で和紙の片 面又は両面に引いて乾かし、その際、礬砂の配合量や引き方等を調整したり、 複数の刷毛を使い分けたりすることにより、紙上に、水のにじみにくい部分 や染料の染みにくい部分を生み出し、毛質、長さ、大小が異なり、特別に注 文した複数の刷毛を使い分け、主に柿渋、胡桃、墨、土など自然の染料で和 紙を染め、刷毛のあと、にじみにより紙上に色を配置するなどの手法を用い て模様や色彩を施すなどして、一点ごとに模様の異なる染描紙を制作してお り、本件染描紙15から20は空の情景を意識して制作したものである(補 正の上で引用した原判決「事実及び理由」第3の1(3))。
実際、被控訴人Y’も、控訴人店舗以外の店でも和紙を購入したが、控訴人店舗で購入した染描紙の模様が「空」や「雲」の世界観を見出しやすいと認識し、さらに、本件 染描紙15から20の中に「空」や「雲」の世界観を見出すことのできる部 分があると認め(補正の上で引用した原判決「事実及び理由」第3の2(3)、 乙24)、その部分を選定して切り出し、染描紙の色合いや色調の変化等を調 整、刷毛のあとを際立たせるといった加工を行い、その上で、紙をスキャナ で読み込んでスキャンデータを作成し、これを拡大し、電子データ上で色付 けし、縦横比を調整するなどして「天空図屏風シリーズ」と題する一連の作 品を制作したのであって、本件染描紙15から20の模様を変えることなく、 これを強調することによって「空」をイメージさせる作品を作ったといえる。 これらの事情からすれば、本件染描紙15から20については、創作ノート その他染描紙の構成や色彩に関して控訴人が記載した資料は証拠として提出\nされていないものの、控訴人は、これらの染描紙の制作にあたり、特定の色 彩を選択して、構図を考えた上で模様を配置して図柄を作り上げ、完成した\nこれらの染描紙は、実用的な目的のためのものといえる特徴と分離して、美 的鑑賞の対象となり得る美的特性を備える部分を把握することができる。
原審で行われた控訴人本人尋問の結果によれば、控訴人は、染描紙を制作 する際に用いる刷毛に含まれた水が紙の上でどのように動くのかについて完 全にコントロールすることはできず、染料を紙に染み込ませた後にどのよう な模様が浮かび上がるのかを事前に完全に予想できるわけではないと認めら\nれる。しかし、上記のとおり、本件染描紙15から20については、控訴人 が空の情景を意識して制作し、実際に空の情景を見出し得る模様が作り出さ れていると認められるのであって、制作過程の中に一部控訴人のコントロー ルが及ばない部分があることや、完成した模様が控訴人の事前の想定と完全 には一致しないことがあるとしても、そのことをもって、本件染描紙15か ら20が著作物と認められないことにはならない。
・・・
控訴人は、染描紙につき、和紙と分離して無体物である「染描」部分だけ を利用することを包括的に許諾したことはなく、翻案等も含めた利用を包括 的かつ黙示に許諾してはいないと主張する。 しかし、控訴人が控訴人店舗に掲げていた本件注意書きは、「無断転用、模 倣、複写による商業行為」を禁ずるとの内容である。この「無断転用、模倣、 複写」に、控訴人がいう「無体物」としての利用、すなわち、染描紙の購入 者が染描紙の紙自体を使わずに模様をデータ化するなどして絵画等の作品制 作において利用する行為が含まれることが明らかであるとはいえない。控訴 人は、控訴人店舗で販売された染描紙にアーティストが絵を描いたものを控 訴人ウェブサイトに掲載しており(原判決「事実及び理由」第3の1(4))、染 描紙の購入者が染描紙を自らの作品に使用することが可能である旨を示して\nいたといえ、それにもかかわらず控訴人がいう「無体物」としての利用を明 示的に禁じていなかったのであるから、控訴人店舗で染描紙を購入した者が、 本件注意書きを見て、染描紙の模様をデータ化するなどして利用する行為が 禁じられていると理解することはできなかったといえ、かつ、控訴人も、こ うした行為を禁ずる意図を有していなかったと推認することができる。 また、控訴人は、被控訴人Y’が染描紙を利用して雑誌「和樂」の「源氏 物語」の挿絵を作成して掲載することを被控訴人Y’から伝えられながら、 被控訴人Y’による染描紙の利用を問題とせず(原判決「事実及び理由」第 3の1(5)ク)、被控訴人Y’が染描紙を利用して実際にどのような絵を制作し て雑誌に掲載したのかを確認しなかった(控訴人本人、弁論の全趣旨)。この 事実からも、控訴人が、染描紙の購入者が染描紙を利用して他の作品を制作 することに関し、染描紙に直接絵を描くことは許諾し、染描紙の模様をデー タ化するなどして利用することは禁じていたとの区別をしていたとは認めら れない。
控訴人のいう「無体物」としての利用であっても、それによって作品を制 作しようとする者は和紙である染描紙を購入するのであるから、控訴人が染 描紙を制作する目的が手漉き和紙の販売の促進にあるとしても、控訴人が「無 体物」としての利用も含めて黙示に許諾することと矛盾しない。 控訴人が、染描紙について「無体物」としての利用をしようとする者に対 して明示的な許諾の意思表示をしたことがあるとしても、そのことは控訴人\nが「無体物」としての利用を含めて他の作品制作への染描紙の利用を黙示に 許諾していたことと矛盾しない。控訴人が、明示的な許諾をする際に、「無体 物」としての利用を希望する者と何らかの条件交渉を行ったことがあるのか 否か、どのような条件交渉を行ったのかは不明であり、仮に何らかの条件交 渉を行った上で明示的な許諾の意思表示をしたことがあるとしても、事前に\n利用態様を認識した場合に控訴人がその者に対して一定の条件を求めること はあり得るといえ、やはり、控訴人が「無体物」としての利用を含めて他の 作品制作への染描紙の利用を黙示に許諾していたことと矛盾しない。 以上の事情に加え、原判決「事実及び理由」第3の5に挙げられた事情も 併せ考慮すれば、控訴人は、複製に当たる場合を除き、「無体物」としての利 用を含め、染描紙を用いて他の作品を制作することを黙示的に許諾していた と認められる。
◆判決本文
1審はこちら。
◆平成30(ワ)39895等
こちらに、問題となった展示物などがあります。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2024.02.23
令和5(行ケ)10018 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年1月30日 知的財産高等裁判所
ア 被告は、前記第3の2〔被告の主張〕(1)のとおり、平成3年最高裁判決 は、本件において適用されるべきではなく、本件訴訟において、原告によ る本件訴訟の使用に関する新たな立証を許すべきではないと主張する。 しかし、商標法50条2項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求が あった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を 証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、 登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件と し、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、 もって審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたも のであり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって、 商標登録の取消しを免れるための要件としたものではないと解される(平 成3年最高裁判決)。平成3年最高裁判決の事案も、本件と同様、審判手続 段階において、商標登録取消請求の被請求人が商標使用の事実について何 ら主張立証しなかったものであり、本件において原告が本件審判手続の中 で本件商標の使用に関する主張立証をしなかったことにより、平成3年最 高裁判決が説示した商標法50条2項本文の上記趣旨が本件に当てはま らないとは解されない。したがって、被告の上記主張は採用することができない。
イ 被告は、前記第3の2〔被告の主張〕(2)アないしエのとおり、本件商標 の使用の事実が立証されたとはいえない旨主張する。
(ア) 前記第3の2〔被告の主張〕(2)アについて
証拠(甲13〜15)及び弁論の全趣旨によって、「Pleasure」の文字 が記載された本件眼鏡フレームを、オリエント眼鏡が原告の下請けとし て製造し、原告に納入したものであると認められることは、前記(4)のと おりであり、原告が、本件眼鏡フレームを使用した眼鏡を、原告の経営 する店舗で販売したことは、商標法50条2項にいう「登録商標の使用」 に当たると認められる。
甲1の1ないし3の写真は、本件眼鏡フレームが存在することを立証 するものであり、甲2の1ないし5等その他の証拠と併せて、要証期間 内に原告が商標を使用した事実を立証するものであるから、甲1の1な いし3の写真の撮影日が要証期間内ではないことをもって、原告が要証 期間内に商標を使用した事実が立証されていないとはいえない。 甲1の1ないし3の写真に撮影されている眼鏡が眼鏡フレームのみな らずレンズにも「Pleasure」の文字が存在している一方、原告のウェブ サイトに掲載された「オグラ眼鏡店オリジナル」の商品の中に眼鏡のレ ンズ部分に商標が刻印されているものが存在しないとしても、甲1の1 ないし3の写真に撮影されている眼鏡が実際に販売されたものであると 認められないことにはならない。
(イ) 前記第3の2〔被告の主張〕(2)イについて
甲2の1ないし5の「お客様カード」は、「Pleasure」の文字が記載さ れた本件眼鏡フレームを用いた眼鏡の販売の事実を立証する証拠である。 原告は、これらの「お客様カード」に上記商標を記載したことが商標法 2条3項8号にいう「取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し」 た行為に該当するなどとは主張立証していないから、上記「お客様カー ド」が同号にいう「取引書類」に該当しないとしても、前記(2)ないし(6) の認定及び判断は左右されない。 ジャーナル(甲7の1ないし4)及び日計表(甲8の1・2)には、\n「オグラ眼鏡店亀有店」との記載があるが、これらの書類に記載された 店舗の電話番号は、原告のウェブサイトに記載されたオグラ眼鏡店イト ーヨーカドー亀有駅前店の電話番号と同一であるから(乙4の1ないし 6)、上記資料に記載された「オグラ眼鏡店亀有店」はオグラ眼鏡店イト ーヨーカドー亀有駅前店を指すと認められ、このことからすれば、甲2 の1ないし5の「お客様カード」に記載された「亀有店」もオグラ眼鏡 店イトーヨーカドー亀有駅前店を指すと認めることができるのであって、 これらの「お客様カード」は、オグラ眼鏡店イトーヨーカドー亀有駅前 店における売上げに関する資料であると認められる。 ジャーナル(甲7の1ないし4)は、これのみをもって本件眼鏡フレ ームを用いた眼鏡の販売の事実を立証するものではなく、甲2の1ない し5の「お客様カード」等の証拠を併せて上記販売の事実が立証されて いるといえるから、甲7の1ないし4に本件商標あるいは「Pleasure」 の商標が記載されていないとしても、前記(2)ないし(6)の認定及び判断は 左右されない。
(ウ) 前記第3の2〔被告の主張〕(2)ウについて
前記(2)ないし(6)のとおり、甲4以外の証拠により、「Pleasure」の記載 のある眼鏡フレームを用いた眼鏡の販売の事実が立証されているといえ るから、甲4に関する被告の主張は前記(2)ないし(6)の判断を左右しない。 なお、被告は、甲4が「商品に関する広告、価格表若しくは取引書類」\n(商標法2条3項8号)に該当しないから、商標の使用を立証するため の証拠とならないという趣旨の主張をする。しかし、原告は、甲4を同 法2条3項8号にいう「取引書類」に該当すると主張するものではなく、 「Pleasure」の記載のある眼鏡フレームを用いた眼鏡の販売が同法50 条2項の使用に該当する旨主張しているのであり、このような使用を立 証するために証拠として提出する資料が上記「取引書類」に該当する必 要もないから、被告の主張は失当である。
(エ) 前記第3の2〔被告の主張〕(2)エについて 現在の原告のウェブサイトの「オグラ眼鏡店オリジナル」の箇所に 「Pleasure」又は「PLEASURE」という名称の商品が掲載されていない としても、そのことをもって、前記(2)ないし(6)の認定及び判断は左右さ れない。
乙3の1ないし6及び乙4の1ないし6のウェブサイトの画面が、甲 2の1ないし5において「Pleasure」の記載のある眼鏡フレームを用い た眼鏡が販売されたとされる時期(令和2年11月11日から令和3年 3月7日)の原告のウェブサイトの画面であるか否かは、乙3の1ない し6及び乙4の1ないし6の画面の内容からは明らかでない。また、仮 に上記画面が上記時期における原告のウェブサイトの画面であり、この ウェブサイトに「Pleasure」又は「PLEASURE」の名称の商品が掲載さ れていなかったとしても、このことから、上記時期において原告の店舗 で「Pleasure」の記載のある本件眼鏡フレームを用いた眼鏡が販売され たことがあり得ないということはできない。 「オグラ眼鏡店新宿サブナード店」の店員が、令和5年4月29日、 被告代理人に対し、「『Pleasure』という商品は扱っていない、在庫切れ ではなく全ての店舗において既にその商品はない、昔はあったが現在は 取り扱いがない。」という趣旨の回答をしたとの事実を裏付ける証拠は何 ら提出されていない。また、仮に、上記店舗の店員が上記発言をしたと しても、その発言の根拠は明らかでなく、前記(2)ないし(6)の認定及び判 断を左右するものではない。
2024.02.23
令和5(行ケ)10079 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年12月26日 知的財産高等裁判所
ア 前記1において認定した事実によると、引用標章1の周知性に関し、次の事 情が認められるというべきである。
すなわち、原告商品は、外国の会社が製造する菓子であり、その名称を「Tro lli Planet Gummi」、「Planet Gummi」などとする ものであって、原告商品又はその包装若しくは個包装には、日本語からなる「地球 グミ」との文字は記載されていない。しかしながら、原告商品は、平成30年頃、 動画投稿者及びその閲覧者を中心に韓国において大流行したところ、この流行が日 本にも飛び火し、原告商品は、令和2年頃からは、日本においても、動画投稿者及 びその閲覧者を中心に大流行し、遅くとも原告が原告商品の輸入販売を開始した同 年10月までには、全国に店舗を展開する小売業者の中に、原告商品を「地球グミ」 と称してこれを宣伝する者が現れるようになった。原告が原告商品の輸入販売を開 始した後についてみても、原告商品は、大人気を誇り、小売業者の店舗における販 売開始後すぐに完売となるという事態が相次ぎ、その入手が極めて困難な商品とな った。原告が原告商品の輸入販売を開始して以来、全国に店舗を展開する小売業者 らは、原告商品を「地球グミ」と称してこれを繰り返し宣伝し、また、原告商品は、 動画投稿サイトにおいても、「地球グミ」と称する商品として大人気を博していた。 そのような原告商品は、令和3年6月、「地球グミ」と称する大人気商品として、 全国紙による新聞報道及び在阪の準キー局によるテレビ報道がされるまでに至り、 同テレビ報道においては、同年上半期にはやった飲食物としてZ世代が選ぶランキ ングにランクインした。原告商品は、翌7月、同様の人気商品として、在京のキー 局によるテレビ報道がされるに至り、20代前半の若者が皆知っていることとして 紹介された(なお、原告は、遅くとも同年6月には、テレビ番組において、原告商 品を「地球グミ」と称しており、また、遅くとも同年9月には、原告商品を「地球 グミ」と称する宣伝をするようになった。)。
さらに、「地球グミ」と称する原告商品は、同年11月、動画投稿サイトへの投稿がきっかけで人気となった作品又は商品の例として、著名作家の小説、有名シンガーソングライターの楽曲等と並べて紹介されるとともに、渋谷区にある著名な商業施設の運営会社による調査(15歳から24歳までの女性545名を対象としたもの)の結果である「SHIBUYA109lab.トレンド大賞2021」なる賞においても、その「カフェ・グルメ部門」の2位に入賞した。このような「地球グミ」と称する原告商品の令和3年までの動向を踏まえ、令和4年1月に発行された「現代用語の基礎知識2022」においては、令和3年中に注目された物(食に係るヒット商品)として、原告商品の俗称たる「地球グミ」の語が取り上げられるに至った。\n
以上の事情に照らすと、「地球グミ」の語(引用標章1)は、遅くとも本件査定 日(令和4年2月22日)までには、原告又は原告商品の製造業者の業務に係る商 品(原告商品)を表示するものとして、需要者(引用標章1が使用される商品の内\n容及び性質並びに前記1の事実に照らすと、若者を始めとするグミキャンディの消 費者であると認められる。)の間に広く認識されている商標に該当していたものと 認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.02.23
令和5(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年12月11日 知的財産高等裁判所
ウ 甲1発明と甲2の技術的事項とを組み合わせる動機付けについて 前記イのとおり、甲2発明の気体吹込羽口の周囲に使用するマグネシ ア−カーボン煉瓦は、酸素吹込みによって生じるホットスポットによる 高熱や不活性ガス吹込みによる冷却作用により、激しい温度勾配や熱衝 撃が加えられるという過酷な環境下の内張煉瓦として使用される前提に おいて、目地損傷原因の目地開きを生じせしめるクリープ変形を防ぐこ とによって、損傷防止が図られるものとなっている。 これに対し、甲1発明のN2ガスを吹き込むガス吹き込み用マグネシ ア・カーボン質耐火物は、前記第2の2(3)アの[甲1発明の内容]記載の とおり、それ自体が気体を吹き込む部材となっている点において、甲2 発明の内張煉瓦とは態様が異なる上に、甲2発明の気体吹込羽口のよう にホットスポットによる高熱を生じさせる酸素を吹き込むことは想定さ れていないものということができる。 そうすると、温度勾配や熱衝撃の点において、甲2発明の煉瓦のほう が甲1発明の耐火物よりも損傷しやすい過酷な環境にさらされる蓋然性 が高いということができ、そのような甲2発明の煉瓦では目地開きを生 じせしめるクリープ変形を防ぐことが特性として重要であるとしても、 それとは使用態様や使用環境の異なる甲1発明の耐火物にも、当然同じ 特性が求められるものとはいえないというべきである。 そうすると、当業者であっても、甲1発明と甲2の技術的事項とを組 み合わせて、相違点2に係る特定事項を得る動機付けがあるとはいえな いということができる。
なお、この点につき、甲3には、前記第2の4記載のとおり、「ごく一 部の大型煉瓦などは800゜C)から1200゜C)程度の還元雰囲気下で焼成 し」、「焼成後に消化防止、低気孔率化のためピッチ含浸されることが多 い。」と記載されているのであって、その記載内容が相違点2に係る特定 事項を得る動機付けについての認定を左右しないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2024.02.23
令和5(ワ)70028 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年12月22日 東京地方裁判所
以上のような本件調査会社の説明を前提とし、本件調査結果について本件調 査会社の説明のとおりの事実が認められる場合、本件各通信をしたピアにおい ては、「UNCHOKE」の通信をする時点より前の時点で、既に本件動画のフ ァイルの少なくとも一部が複製されて当該ピアに記録された上で、当該ピアが インターネットに接続されビットトレントのネットワークにも接続されるな どして、本件動画のファイルのピースが他のピアに自動公衆送信(アップロー ド)し得る状態になっていたこととなる。 そして、既に述べたとおり、ある行 為により自動公衆送信し得るようにされた著作物について、別途、著作権法2 条1項9号の5のイ又はロに該当する行為がされたときに再び「送信可能化」\nに該当する行為がされたといえると解されるが、本件においては、「UNCH OKE」の通信がされたとされる時点において、本件動画について、更に、同 号のイ又はロに該当する何らかの行為が行われたことを認めるに足りない。
なお、特定電気通信による情報の流通によって権利が侵害されたことに関し、そ れ自体では権利侵害性のない通信について、プロバイダ責任制限法は、「侵害 関連通信」(プロバイダ責任制限法5条3項)を総務省令で定めるとして、その 範囲を明らかにしている。特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者情報の開示に関する法律施行規則5条は、侵害関連通信として複数の通 信を定めるところ、そこに上記の「UNCHOKE」に該当する通信が規定さ れているとは認められず、また、「UNCHOKE」の通信時点において、本件 調査会社の端末に対して本件動画のファイルのピースが送信(自動公衆送信) されているともいえない。
(3) 原告は、本件各通信が「UNCHOKE」の通信であると特定した上で、本 件各通信に係る発信者情報についてプロバイダ責任制限法5条1項に基づき その開示を請求しているところ、以上に述べたところによれば、本件調査結果 に至る手法と本件調査会社の説明に基づく「UNCHOKE」の通信の内容に よると、直ちに本件各通信に係る情報の流通によって、公衆送信権が侵害され たと認めることはできない。また、その他、本件各通信に係る情報の流通によ って、公衆送信権が侵害されたことを認めるに足りる事情の主張、立証はない。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2024.02.23
令和5(ネ)10058 特許権移転登録抹消登録請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年12月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記認定事実に基づき、控訴人が、被控訴人の取締役会決議がないこと を知り、又は知ることができたかについて、以下検討する。 本件特許権の譲渡が会社法362条4項1号に規定する「重要な財産」 として、本件特許権の譲渡当時取締役会設置会社であった被控訴人におい て取締役会決議を経る必要があったことについては当事者間に争いがな い。
前記認定事実によれば、令和2年10月5日頃に、Dは、Aに対し、本 件特許権の譲渡につき取締役会議事録の提出を要求しているところ(乙1 1)、Dの供述によれば、同日、Aから「Bも了解しているし、社内手続も 大丈夫です」との説明を受けた(原審における控訴人代表者Dの陳述記載\n書面3頁)とするが、仮にDの上記供述が事実であったとしても、Dは、 そもそも本件特許権の譲渡について取締役会の決議が必要であると十分\nに認識していたのであるから、Aの上記説明だけを聞いてそれをうのみに したというのであればあまりに軽率というほかなく、上記説明を前提とす れば同日から本件移転登録申請までの間にその提出を求めることも十\分 可能であったし、議事録の提出が得られないのであれば、B本人に確認す\nることも容易であったというべきである。にもかかわらず、そのような行 動に出ることはなく、本来、特許権譲渡の移転登録手続を急がなければな らない事情は何ら存しないのに、Aとの間で本件特許権の譲渡の話に及ん だ翌日には、弁理士に譲渡証書の作成を依頼し、その二日後にはAに対し 本件譲渡証書に改印後被控訴人代表者印を押印させ、その翌日には本件移\n転登録申請手続に及ぶというように、移転登録申\請を早急に進めたことは 極めて不自然というほかない。
この点に関して、控訴人は、被控訴人において適時適切に取締役会議事 録を作成していたかは疑わしいから、Dにおいて、本件特許権の移転登録 手続を経る前に取締役会議事録の提出を求めることは現実的ではなかった し、移転登録手続を急いだ理由は、「早急な解決を図りたい」というAの意 向を受けてそれが妥当だと考えたからにすぎないなどと主張する。 しかし、取締役会議事録が作成されていないとの疑念を抱いていたので あれば、なおさらのこと、本件特許権の譲渡につき取締役会の承認があっ たかどうかをA以外の被控訴人の取締役などに確認しなければならないは ずであるし、ましてや、控訴人はB以外の被控訴人の取締役は名目的な存 在にすぎないと主張するのであるから、Bが本件特許権の譲渡を承認して いない限り、取締役会の承認は得られないと認識していたはずであるから、 B本人に確認すべきであったというべきである。また、いかに早急な解決 を図りたいといわれたとしても、会社内の十分な意思疎通を確認すること\nなく、被控訴人の取締役会の承認が必要な本件特許権の移転登録手続を上 記のような異常な速さで実現しなければならない理由にはならないという べきであるから、控訴人の上記主張は採用することができない。
また、本件特許権が被控訴人にとって重要な財産であることは控訴人も 認めるところであり、前記イ(イ)ないし(エ)に照らせば、控訴人は、被控訴 人が本件特許権を実施することにより収益を得ようと企図していたと認 識していたとするものである。これらの事情に照らすと、控訴人において、 被控訴人が競合他社である控訴人に対し本件特許権を無償で譲渡するこ とはないと考えるのが通常である。仮に、Bが控訴人に対して競業避止義 務違反となる行為又は海外医療旅行株式会社の代表取締役として本件販\n売業務委託契約違反となる行為を行った事実があるとしても、本件特許権 の特許権者は被控訴人であり、被控訴人がB又は海外医療旅行株式会社の 上記義務違反の責めを負う理由はないし、仮に被控訴人として上記Bの義 務違反に責任を感じ、謝罪の意味で何らかの対応をとるべきと認識したと しても、たとえ謝罪の意味であったとしても本件特許権を無償で譲渡しな ければならない必然性はないというべきであるから、Aにおいてこれを理 由として本件特許権を控訴人に譲渡するとDに話したのであれば、Dとし てはまずはそれが真実なのかを確認するのが当然といえ、D自身もそう思 ったからこそ、Aに対して取締役会議事録を要求したものと認められる。 そして、そのことは、前記イ(エ)のとおり、本件特許権に関し特許情報を検 索して確認していた控訴人においても、当然に認識していたものというべ きである。
この点に関して控訴人は、被控訴人の実質的な経営者はBであり、被控 訴人の株主や取締役の構成に照らしても、被控訴人の行為はBの行為と同\n視できるから、被控訴人が上記義務違反の責任を負うなどと主張する。 しかしながら、本件全証拠を精査しても、被控訴人の法人格を否認して、 被控訴人の行為をBの行為と同視することを認めるに足りる証拠は存しな いというべきであるから、被控訴人の上記主張は採用することができない。 加えて、そのような本件特許権の譲渡について、契約当事者双方が署名 し押印する譲渡契約書が作成されていないのは、会社間の契約として著し く不自然であるし、それを措くとしても、本件譲渡証書の作成に当たり、 Aが被控訴人代表者印を改印したこと自体も極めて不自然というべきであ\nる。なぜなら、当時、改印前被控訴人代表者印はBが保管していたのであ\nるから、もし、Dが、Aから「Bも了解しているし、社内手続も大丈夫で す」との説明を受けたというのが事実であるならば、本件譲渡証書の押印 に当たり、AがBから改印前被控訴人代表者印を借りるなどして押印すれ\nばよく、特許庁に本件譲渡証書を提出する前日にわざわざ代表者印を改印\nしなければならない必要性は何ら認められないからである。
以上の事実を総合考慮すると、上記のような極めて不自然な本件特許権 の移転に関し、取締役会議事録の提出を受けず、A以外の取締役に取締役 会の承認の事実を確認することもなく、あえて本件移転登録申請を早急に\n進めた控訴人代表者のDは、本件特許権の譲渡がAの単独行為であって、\nBの承諾なしにされたこと、すなわち、取締役会決議が存しないことを知 っていた(悪意)ものと認めるのが相当である。
以上によれば、控訴人は、本件特許権の控訴人への譲渡につき、被控訴 人の取締役会決議を経ていないことについて悪意であったと認められる から、本件特許権の譲渡は民法93条1項ただし書に準拠して無効となる と認めるのが相当である。
◆判決本文
原審はこちら。
2024.02.23
令和5(ネ)10026 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年1月31日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ア 控訴人は、構成要件2Bを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表\面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で2.0μm以下であることを要する」と解する根拠は、特許請求の範囲の文言にも本件発明2の課題にも なく、当業者の技術常識等からみても非現実的である旨主張する。
イ しかし、構成要件2Bは「前記排水溝の壁面の表\面粗さが、算術平均粗 さ(Ra)で、2.0μm以下であることを特徴とする」と規定してお り、本件発明2の特許請求の範囲の文言全体をみても、排水溝壁面の表面粗さについて、一部は2.0μmを超えるが製品の一定範囲や所定の\n測定箇所が2.0μm以下であるものを含む、あるいは全体の算術平均 粗さ(Ra)の平均値が2.0μm以下であるものを含むと解すべき文 言はない。
この点は、本件明細書2の記載をみても同様である。控訴人が指摘す る本件明細書2の記載や図面は、従来技術や実施例に係る排水溝の性状 等を特に留保なく説明するものであり、控訴人が主張するように、作業 過程で異常(イレギュラー)が発生した箇所があることを前提とし、こ れを除いた「任意の箇所」を示すものであることを窺わせる記載はない。 控訴人は、1)製紙用弾性ベルトの排水溝は、作業前に設定した加工条 件に基づいて均一的に連続加工されるものであること、2)作業時の諸要 因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないこと、3)排 水溝の壁面を全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって製品の性状を把握\nするという、当業者の技術常識を考慮すべき旨主張する。
しかし、上記のとおり明確な構成要件2Bの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な\n拡張解釈というべきであって、特許請求の範囲の解釈に当たって当業者 の技術常識を考慮するという枠組みを超えるものといわざるを得ない。 控訴人の主張は、当業者が定める自社製品の品質基準としてはともかく、 独占権が付与される特許請求の範囲の解釈としては採り得ない。 なお、控訴人が指摘する大阪地方裁判所平成15年(ワ)第10959号 同17年2月28日判決は、控訴人の主張を裏付けるものではない。
ウ したがって、原判決判示のとおり、構成要件2Bは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表\面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で2.0μm以下であること」を要すると解するのが相当である。
そうすると、控訴人が主張する<ステップ1>から<ステップ2の2 B>まで、すなわち「各測定結果に係る9溝ないし18溝のデータ数値 を参照し、特定の溝壁面の表面粗さ数値が他の溝の同一壁面に比して突出して高くなっている」ものを「当業者からみて明らかに溝加工作業時\nに生じた異常(イレギュラー)」として除外すること、及び「測定結果 に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ(Ra)で2.0μm以下である結果が得られているか否か」(控訴人の他の主張と併せると、\n任意の測定箇所の算術平均粗さの「平均値」が2.0μm以下であるこ とを意味すると解される。)により充足性を判断する判断手法は、構成要件2Bを逸脱する独自の解釈に基づくものといわざるを得ず、採用で\nきない。
・・・
(2) 公然実施発明Bに基づく本件発明1の新規性欠如の有無について
イ 公然実施をされた発明に当たるかについて
(ア) 控訴人は、本件特許1の出願当時、当業者は、ベルトBの外周面にD MTDA(エタキュアー300)が使用されていることを通常利用可能な分析方法によって知ることができなかった旨主張する。\n
(イ) しかし、まず、証拠(乙37、124、128、129)によれば、 エタキュアー300は、本件特許1の出願前から実用化され、ウレタン 用の硬化剤として注目されていたことが認められる(原判決44頁〜)。 控訴人は、上記文献等はシュープレス用ベルトに使用される硬化剤に ついて言及するものでないと主張するが、上記文献等はポリウレタン全 般向けの硬化剤としてエタキュアー300を説明するものであるところ、 シュープレス用ベルトに利用される硬化剤が他の一般的なポリウレタン の硬化剤と異なるとみるべき根拠はない(上記文献等には、代表的な従来品が本件明細書1【0003】に従来のシュープレス用ベルトの硬化\n剤として記載されているMOCAである旨の記載も複数ある。)。
また、被控訴人は、遅くとも平成9年7月時点ではエタキュアー30 0を使用していたところ(原判決45頁)、上記ア(イ)の認定事実によ れば、被控訴人は硬化剤としてDMTDAを使用することを独自に見出 したのではなく、エタキュアー300を製造販売するアルベマール社の 国内関連会社との取引を契機として知ったと認められる。この事情は、 他の当業者が硬化剤の候補としてエタキュアー300に着目する蓋然性 を裏付ける事情となることは明らかである。 控訴人は、さらに、ポリウレタンの硬化剤はDMTDAの他にも約8 0種類存在し(甲43)、その全てについて標準品を準備して分析依頼 を行うことは非現実的であると主張する。
しかし、「ポリウレタン樹脂ハンドブック」(乙128)に「実用化 されている熱硬化PUエラストマー用芳香族ジアミン架橋剤」として記 載された5種類、あるいは特開2000−248040号公報(乙12 7)にポリウレタンプレポリマーと反応させるアミン硬化剤組成物とし て記載された芳香族ポリアミンの15種類、その中でも好ましいと記載 された4種類には、いずれもエタキュアー300又はDMTDAが含ま れており、当業者は、従来用いられているMOCA(本件明細書1【0 003】)と同類であるこれらの硬化剤を想定するとみるのが自然であ る。
(ウ) 控訴人は、ベルトの外周面に着目し、外周面のみを切り出して分析を 依頼することは、当業者が通常に利用可能な分析技術とはいえない旨主張する。\nしかし、本件特許1の出願日前において、外周層、内周層等の複数の 層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリマーと硬化剤と を混合してベルトの弾性材料とすることは技術常識であり(原判決44 頁)、自由に解析等をなし得る状態に置かれたベルトを解析して構造等を特定することは可能\であったと認められる(このことは甲25に記載された断面写真から明らかであり、原判決の認定に問題はない。)。 したがって、ベルトBの外周層を切り出して分析を依頼することは、 本件訴訟において控訴人(甲10の1〜4)及び被控訴人(乙1〜3) が行ったのと同様、本件特許1出願前の当業者にも可能であったと認められる。\n
なお、当業者が仮に外周層と内周層に異なる硬化剤を用いる製造方法 を認識せず、これらを区別せずに分析を依頼した場合、全体について硬 化剤としてDMTDAが使用されているという分析結果を知ることにな り、この結果はベルトBの正しい構成なのであるから(乙32)、「外周面を構\成するポリウレタンは、」「ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている」との構成を含め、本件発明1の内容を知り得たといえることに変わりはない。\n
(エ) したがって、本件特許1の出願当時、当業者は、ベルトBの外周面に DMTDA(エタキュアー300)が使用されていることを通常利用可 能な分析方法によって知ることができたと認められる。ベルトBが公然実施された発明とはいえない旨をいう控訴人の主張は採用できない。\n
◆判決本文
原審はこちら。
◆大阪地裁平成29(ワ)4178
原審では、被告は、一旦、損害論に入ってから、2.0μm以下である」との構成要件を充足しないとして、非侵害の主張を行いましたが、これは「時機に後れた」とは認定されませんでした。
原告は、第15回弁論準備手続期日から損害論の審理が開始されたにもかかわ
らず、被告は、被告製品1〜3及び5と同じシリーズの製品等における排水溝壁
面の表面粗さの測定結果(乙152〜159)を新たに証拠提出するとともに、非侵害の主張を行ったことが時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張する。\nしかし、被告が前記証拠等を提出したのは、原告が、訴状においてはイ号製品
が本件発明2の技術的範囲に属する旨を主張しつつも、被告製品1〜3及び5の
排水溝壁面の表面粗さに限定して立証活動をしていたが、裁判所が本件発明2については損害論に入る旨の心証開示を行ったことを受けて、被告製品1〜3及び\n5の各製品と同じシリーズの製品等についても本件発明2の技術的範囲に属する
旨を改めて主張したことに対応するものであって、必ずしも時機に後れたものと
は認められない。したがって、原告の前記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2024.02.19
令和5(行ケ)10076 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和6年1月30日 知的財産高等裁判所
商標法3条2項は、同条1項3号から5号までに該当する商標であっても、 「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを 認識することができるもの」については、商標登録を受けることができる旨 を規定している。同条2項の趣旨は、同条1項3号から5号までに該当する 商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用 した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて自他商品識別力 又は自他役務識別力をもつに至ることが経験的に認められるので、このよう な場合には商標登録を受けることができるとしたものと解される。 そして、立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得した かどうかは、当該商標の形状の斬新性、当該形状に類似した他の商品の存否、 当該商標の使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣 伝のされた期間・地域及び規模等の諸事情を総合考慮し、立体的形状が需要 者の目につき易く,強い印象を与えるものであったかなどを総合勘案した上 で,立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを 判断するのが相当である。
・・・
ア 本願商標の立体的形状の構成は前記第2の1(1)及び前記1(2)アのとおり であり、その形状は、ラベルプリンター用テープカートリッジとしての商 品の機能又は美感に資することを目的として採用されたものであると認\nめられる。 しかも、原告以外の者が取り扱うラベルプリンター用テープカートリッ ジにおいても、印字用テープをロール状にして収納する部分や、印字用テ ープの巻取りや送り出しをするための輪状の部分を有し、ケースの覆いが 透明又は半透明となっている製品が複数存在し(前記1(2)ウ)、本願商標の 形状と、原告以外の者が取り扱うラベルプリンター用テープカートリッジ の形状とは、一定の差異はあるが、主要な構成要素が共通しており、本願\n商標の形状の斬新性は乏しく、本願商標の形状に類似した他の商品が存在 すると認められる。
イ 「『テプラ』PRO」シリーズのラベルプリンターは平成4年から販売さ れており(前記(2)ア)、同時期に「『テプラ』PRO」シリーズのラベルプ リンター用テープカートリッジである本件商品も販売が開始されたもの と推認される。本件商品の形状が販売当初において現在と異なるものであ ったと認めるに足りる証拠はなく、本件商品はその販売当初から本願商標 の形状が用いられていたと認められる。 しかし、本件商品について、原告カタログに掲載されていることは認め られるものの、本件商品のみを扱った広告宣伝がされたとは認めるに足り る証拠はない。
また、本件商品は箱に入った状態で販売されており(前記(2)ウ)、店舗に おいて本願商標の形状が顧客に示されないと認められる。箱には、原告の 社名を示す「KING JIM」の文字や、「TEPRA」、「PRO」等、 「『テプラ』PRO」シリーズのラベルプリンター用テープカートリッジで あることが分かる文字の記載、テープの幅や色等を示す記載等がされてい る。原告のウェブサイトで本件商品を紹介する画面には、箱から出された 本件商品が表示されており、本願商標の形状が示されているが、「KING\nJIM」、「TEPRA」、「PRO」等の文字が記載されたシールの貼られ\nた状態の写真であり、箱も表示されている上、ウェブサイト上の記載とし\nても「『テプラ』PRO」シリーズのラベルプリンターであることが示され ている(甲102〜104)。原告カタログも、箱から出されてシールの貼\nられた状態の本件商品とともに、箱が表示されている(前記(2)ウ)。
そして、本件商品は、「『テプラ』PRO」シリーズのラベルプリンター 用のテープカートリッジであり、「『テプラ』PRO」シリーズのラベルプ リンターを所持する者が、新たなテープカートリッジが必要となった場合 に購入する商品であるといえ、需要者は、「『テプラ』PRO」シリーズの ラベルプリンター用テープカートリッジであること及びテープの色、幅等 の情報を基に、本件商品の中から特定の商品を購入すると考えられるので あり、これらの情報は、本件商品の箱やインターネット上の記載において 表示されている。したがって、需要者である一般の消費者は、本願商標の形状からではなく、箱やシールに記載された文字、あるいはウェブサイト上に記載された\n説明の記載から、本件商品を他の商品と識別すると考えられる。
ウ 本件調査の結果は、本願商標の形状が明らかな写真を示した上で回答さ せたところ、自由回答では、写真に撮影された商品を販売する企業名及び 商品名の両方を誤った者が回答者全体の約6割を占め、選択肢に「テプラ (TEPRA)」を入れて商品名を選ばせる質問を含めても、自由回答によ る質問及び選択問題の全てを誤った者が全体の約半数にのぼった。 また、本件調査では、設問の中で、回答の理由を聴取し、その理由から 明らかにいい加減な回答(ノイズ)をしたと判別できる調査対象者を除い た集計も行ったが、ノイズを除くと、上記写真に撮影された商品を販売す る企業名又は商品名のいずれか一方を正答した者は回答者全体の31. 0%にすぎず、選択肢を示して回答させる質問でも、ノイズを除くと、上 記写真から「テプラ(TEPRA)」の商品名を選択した者は回答者全体の 35.8%にすぎないという結果となった。
エ 上記アからウまでの事情を総合すれば、本件商品が販売開始から約30 年が経過していること及び販売地域が全国であることを考慮しても、本願 商標が需要者の目につき易く,強い印象を与えるものであったということ はできないから、本願商標が使用により自他商品識別力を有するに至った と認めることはできず、この判断を覆すに足りる事情は認められない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 立体商標
>> ピックアップ対象
2024.02.19
令和5(ネ)10089 損害賠償等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和6年1月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これに対し、一審原告は、本件合意書9条1項にいう『著作権を有する 音源又は著作権使用許諾を受けた音源』については、著作権の有無にかか わらず、一審原告が保有する全ての音源を指すものであると主張する。 しかし、一審被告はこれを否定しているところであり、B’も、本件合 意書締結に向けての2度の面談において、一審原告の上記立場を説明した とはするものの、これについて一審被告が明確に同意した旨を証言等する ものではない(原審における B’の尋問調書、甲38(B’の陳述書))。ま た、一審被告が退職に当たり一審原告のもとにおいて使用した音源データ の全てを返却したとすることについて、仮に B’と一審被告との間で、一 審原告が著作権を保有し、又は著作権使用許諾を受けた音源に限らず、一 審原告在職中に一審被告が取得した音源のデータの全てを返却する旨の 合意ができた事実に基づくものとしても、これは本件合意書3条に基づく 平成29年12月末日と8条の業務終了日のいずれか早い方までの音源 のデータの返却についてのものであり、これにより直ちに、本件合意書9 条4項の、その使用につき損害賠償義務の発生する音源の対象についても、 上記同旨の合意ができたものとすることはできない。
さらに、一審原告の主張するように、本件合意書9条についても、その 著作権との文言にかかわらず、一審原告の保有する全ての音源を指すもの として当事者間に合意が成立したのであれば、その旨を本件合意書に加筆 するか訂正をすればよく、この点、一審原告においても、音源について著 作権法上の著作権が成立するか分からないものが含まれていることを明 確に認識していたのであるから(原審における証人 B’の尋問調書)、なお さら、そのようにするのが自然であるということができる。現に、本件合 意書の作成日付けについては、手書きで訂正がされ、その上に各当事者の 押印がされているところである(甲1)。このような加筆訂正等がされてい ないことは、そのような合意が存しないことをうかがわせるものである。 そもそも一審原告においても、本件訴え提起の段階においては、本件合意 9条4項の、一審原告が『著作権を保有しまたは著作権使用許諾を受けた 音源』とは、1)一審原告がレコード製作者の権利を有するもの、2)一審原 告が著作権を有するもの、3)一審原告が音の使用につき権利を有する者か ら使用の許諾を受けたもの(当該音が著作物であればその著作権を有する 者及びレコード製作者の権利を有する者から、効果音等著作物性が明確で ないものについてはレコード製作者の権利を有する者から許諾を受ける などして使用が可能となったもの)、の『1)から3)を指していることは容易 に理解できる』(訴状2ないし4頁)と主張していたところであり、一審原 告が保有する全ての音源を指すなどとは主張していなかったものである。 したがって、一審原告の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
一審はこちら。
◆令和3(ワ)17298
被告が、原告が保有していた「朝の雀6mmテープ」について、自身の保有
する記録媒体にこれを複製し、その後、別紙主張整理表作品1記載4の場面の音響に使用するために複製したことについては当事者間に争いがない。\n原告が被告のこの行為について本件合意に違反する旨主張するのに対し、被
告は、「朝の雀6mmテープ」については、被告と原告の間で、被告が原告在籍
時から音響を担当していたアニメ「サザエさん」に使用することを目的として、
被告が原告の音源を被告が保有する記録媒体に複製し、これを音響効果に利用
することが許諾されていて、「朝の雀6mmテープ」を被告が保有する媒体に
複製することは本件合意で禁止される「持ち出し」には当たらないと主張する。
しかし、仮に被告が主張するとおり、原告が被告に対し、アニメ「サザエさ
ん」に使用するために「朝の雀6mmテープ」を使用することを許諾したとし
ても、その許諾は、原告からの退職後に被告がアニメ「サザエさん」を引き続
き担当することについて、当初はこれに難色を示した原告も同作品のクライア
ントが同作品に関する作業を被告に委託すると決定したために最終的にこれ
を了承したという状況(乙20、弁論の全趣旨)の下で、アニメ「サザエさん」
に使用する限度で「朝の雀6mmテープ」を使用することを許諾したと解する
のが合理的である。その許諾が、同音源を、アニメ「サザエさん」に限らず、
自由に使用して良いという趣旨であるとするのは、上記状況に照らしても不合
理である。被告が主張する許諾は、仮にあったとしても、本件合意所定の「持
ち出し」や「音源」の意義を一般的に修正する合意などではなく、上記のとお
り、「朝の雀6mmテープ」をアニメ「サザエさん」に使用する場合には被告が
本件合意で定められた債務不履行責任を問わないという限度で本件合意の内
容を修正する趣旨のものと解される。
被告は、「朝の雀6mmテープ」をアニメ「サザエさん」とは異なる作品であ
る別紙主張整理表作品1記載4の場面の音響に使用した。これは、本件合意書9条1項で禁止された「持ち出し」であり、同4項所定の「音源」の「使用」\nに当たると認められ、本件合意に違反する。
2024.02.19
令和5(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年1月31日 知的財産高等裁判所
(1) 原告は、引用例2及び引用例3に開示されたイメージファイバを介して照 明光を導く周知の方法はイメージファイバを振動させないものであるのに対 して、引用発明はイメージガイド2の接眼側の端部を振動させるものである から、イメージファイバの前提構成が異なるものであって、引用発明に上記\nの周知の手法を適用する動機付けがあるとはいえない旨主張する。
(2) しかし、引用例2及び引用例3によれば、集光レンズを介して入射した光 源からの光をイメージファイバにより伝送することは、本件審決が認定する とおり周知の手法であると認められるところ、引用例3の【0008】、及 び特開2000−121460号公報(乙2)の【0018】、【001 9】、【0029】の記載によれば、内視鏡の技術分野において挿入部を細 径化することは周知の課題であると認められるから、その課題は引用発明に も内在していると認められる。 そして、本件審決の認定する周知の手法は、引用発明にも内在する上記の 課題の解決手段となるものであるから、引用発明にこれを適用する動機付け はあるというべきである。
(3) 原告は、さらに、照明光を被観察物体に導くイメージガイド2の接眼側の 端部を振動させると、被観察物体の撮像にどのような影響を与えるのかが不 明であることを考慮すれば、上記周知の方法を引用発明に採用することには 阻害要因がある旨主張する。 しかし、イメージファイバを振動させる技術と、光源からの光をイメージ ファイバにより伝送する技術とを同時に採用できないとする技術的根拠は見 当たらず、上記(2)のとおり周知の課題を解決する手段である周知の方法を 採用することは、当業者であれば容易に着想して試みるものと認められる。
(4) したがって、引用発明に引用例2及び引用例3の周知の手法を適用するこ とによって、相違点1及び相違点2に係る構成は容易に想到し得るとした本\n件審決に誤りは認められず、原告主張の取消事由2は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2024.02.19
令和5(ネ)1657 実験装置使用差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和6年2月9日 大阪高等裁判所
1 争点(1)(被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか)に ついて
(1) 前記前提事実(4)アのとおり、本件物件は関係規定に基づき控訴人らから被 控訴人に寄付されたものであるところ、控訴人らは、上記寄付を受け入れた 研究機関である被控訴人としては、本件科研費契約上、補助事業者である研 究者に代わり本件物件を科研費の交付目的に従って適切に管理することが求 められるのであり、本件物件に化体している本件情報に関する権利について は、同契約に付随して、信義則上、上記目的外で自ら使用したり、第三者に 漏洩・開示等したりしてはならない義務(秘密保持義務)を負っている旨を 主張する。
(2) そこで検討するに、公金である補助金により購入された設備等の取り扱い については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を始めとする\n関係各規定により詳細が定められ、本件物件もこれに従い控訴人らから被控 訴人に寄付されたものであるところ、まず寄付とは、一般的に、公共性、公 益性を有する事業や団体などに対し、財産を贈与することであり、その目的 が物であれば、その所有権の無償による譲渡を意味するものである。そして、 大学共同利用機関取扱要領22条によると、寄付を受けた設備等は、固定資 産管理規則に基づき管理するものとされているところ、同規則11条には、 「資産管理責任者は、固定資産等を寄附により取得する場合」との記載があ ること、平成18年12月26日付けで作成された文部科学省の「研究費の 不正対策検討会報告書」には、「現在の競争的資金等の制度においては、例え ば機器を購入した場合(中略)個人補助の科学研究費補助金の場合、所有権 はいったん研究者に帰属し、所属する研究機関に寄付することになっており」 との記載があること(甲63の1・2)、振興会作成の科研費ハンドブックに 掲載された「科研費FAQ」には、「直接経費により購入した設備等は、研究 代表者又は研究分担者が所属する研究機関に寄付しなければなりません。【Q\n4405】」、「科研費により購入した設備等は、購入後直ちに研究機関に寄付 することとしていますので、研究期間終了後も、研究機関の定めに従い、別 の研究等で使用することは差し支えありません。【Q44071】」との記載 があること(甲21)がそれぞれ認められ、これらの記載はいずれも、科研 費により設備等を購入した研究者がその所属する研究機関に行う寄付が、留 保を伴わない所有権の無償譲渡を意味するものであることを前提としている と解するのが相当である。これらに加え、平成23年に締結された被控訴人、 RCNP、TRIUMF及びウィニペグ大学の4研究機関によるUCNの共 同研究に係る合意(2011年覚書)には、被控訴人が本件物件の所有権を 有している旨の定めが置かれており(原文は英文)、本件情報に関して控訴人 らが主張する権利について特段の留保は付されていないことも認められる(甲 8)。
そうすると、そもそも控訴人らによる寄付を義務付けた関係各規定にいう 寄付は一般的な寄付と同様の意味に解されるし、本件物件の寄付を受けるこ とでその所有権を取得した被控訴人が寄付を受けた本件物件の使用、収益及 び処分について制約を受けるべき根拠は関係各規定中に見当たらないから、 控訴人ら主張に係る本件科研費契約なるものが科研費の交付決定に伴い関係 者間に成立するとしても、これに付随して、信義則上、被控訴人が、その一 方的負担となる秘密保持義務を控訴人らに対して負うことになると解する余 地はないというほかない。
(3) この点に関し、控訴人らは、科研費により取得される設備等に関し、設備 等の寄付を行った研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合に\nおいて、当該研究代表者等に当該設備等の継続使用の希望があるときは、当\n該設備等を研究代表者等に返還しなければならない旨の「返還ルール」が定\nめられている旨を指摘し、同ルールは設備等(本件物件)の寄付を受けた被 控訴人において負担する上記制約の顕れである旨を主張する。
確かに、機関ルール2−3及び3−28には、上記趣旨の記載が存在する が、他方、上記科研費FAQには、補助事業期間中に他の研究機関に異動す る場合は、研究機関は研究機関の定めに基づき、当該設備等を当該研究者に 返還する旨【Q4405】、令和2年度以降に購入した設備等に関しては、研 究期間終了後(補助事業を廃止した場合を含む)5年以内の場合も同様に取 り扱う旨【Q4405、44071】、令和2年度以前に購入した設備等に関 しては、研究期間終了後も、研究機関の定めに従い、別の研究等で使用する ことも差し支えない旨【Q44071】がそれぞれ記載されている。 しかし、これらの記載からすると、少なくとも令和2年度以前において、 「返還ルール」は、補助事業期間中のルールであり、研究機関が異動する研 究者の返還請求に応じるべきであるのは、補助事業期間中に限られているこ とを前提としているものと解するのが相当であるところ、本件物件のうち、 本件物件1に係る基盤研究Aの補助事業期間は平成12年から同14年まで、 本件物件2に係る基盤研究Sの補助事業期間は平成21年から同25年まで、 本件物件3に係る基盤研究Bの補助事業期間は平成18年から同20年まで というのであって(甲4、16〜18、当審第1回口頭弁論調書)、本件物件 については、いずれも補助事業期間を経過している。
したがって、上記のような「返還ルール」の存在を斟酌しても、寄付によ り本件物件の所有権を取得した被控訴人が、その使用、収益及び処分に制約 を受けることになる秘密保持義務を、控訴人らに対して信義則上負うべきも のとは解されない。
(4) なお、本件科研費契約に付随する秘密保持義務違反にいう秘密とは、控訴 人らが本件において営業秘密と主張する本件情報と同じものと主張されてい るが(当審第1回口頭弁論調書)、後記3(2)でみるとおり、本件情報は、本 件物件の外観を見ただけでは解析が不可能であり、控訴人らの関与なしには\nこれを取得できないというのである。そうであるとすると、本件物件をトラ イアンフその他の第三者との共同研究の用に供しているとしても、控訴人ら 主張に係る秘密(本件情報)は明らかにされることはないことになる。まして や、第三者が本件物件を分解して主張に係る秘密(本件情報)を探索するこ とも想定できないから、仮に秘密保持義務を負うとしても、そもそも第三者 との共同研究の用に供されることをもって、秘密保持義務違反の状態が起き ることはあり得ないということが指摘できる。 また、控訴人らは、秘密保持義務を根拠づけるものとして、本件物件の所 有権の所在とそれに化体しているノウハウなどの技術情報の所在とは別次元 の問題であり、寄付により本件物件の所有権を被控訴人に無償譲渡したこと になるとしても、控訴人らにおいて本件情報に係る権利まで譲渡する意思は なかったから、被控訴人が本件物件に化体したノウハウを自由に使用してよ いことにはならないとも主張する。しかし、上記説示のとおり、本件物件を 研究の用に供することのみでは秘密保持義務違反の状態が起きないから、本 件物件が価値のあるノウハウを使用したものであるとしても、そのことを理 由に本件物件そのものの使用、収益及び処分に制限を及ぼすことは、結局、 設備等の寄付を無意味ならしめるものであるといわざるを得ず、控訴人らの 上記主張は採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.02.19
令和5(ネ)10001等 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 著作権 知的財産裁判例 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人による本件各動画の利用態様は、本件各動画からキャプチャした本件 静止画を本件各記事に貼り付け、これを本件ブログ上に投稿して掲載するというも\nのである。そうすると、その使用料相当額の算定に当たっては、他に映像からキャ プチャした写真の使用料に関する証拠がない以上、前記ア(ア)のとおりのNHKエ ンタープライズの規定を参酌するのが相当である。
なお、本件記事1ないし7は、30枚ないし70枚程度の本件静止画を用い、こ れらをそれぞれ本件動画1ないし7における時系列に従って貼り付けた上、各静止\n画の間に、直後の静止画に対応する本件動画1ないし7の内容を1行ないし数行で まとめた要約を記載したものであり、本件記事1ないし7の内容を見ただけで三十\n数分ないし五十数分の本件動画1ないし7の全体をほぼ把握できるようにするもの\nであって、その実質は、映像そのものに準ずるものとも解し得るが、前記アのとお りの各使用料によると、本来であれば、静止画(写真)を使用する枚数が多くなる と、その使用料(映像からキャプチャした写真の使用料)も高額になるところ、そ の枚数が更に多くなり、静止画を利用したコンテンツの実質が映像に準ずる域に達 した場合に、映像の使用料が参酌されることになってかえって使用料が低額になる というのは不合理であるから、本件記事1ないし7の上記内容を考慮しても、本件 各記事については、上記のとおり、映像からキャプチャした写真の使用料に係るN HKエンタープライズの規定を参酌するのが相当である。
映像からキャプチャした写真の使用料に係るNHKエンタープライズの規定によ ると、使用目的が「通信(モバイル含む)」の場合の基本料金は、5000円とさ れ、また、写真素材使用料は、「カラー」、「一般写真」及び「国内撮影」の場合、 1カット当たり2万円とされ、さらに、証拠(甲7の1ないし8、甲8の1ないし 8)及び弁論の全趣旨によると、控訴人が利用した本件静止画は、合計362枚 (話数♯054は59枚、♯044は45枚、♯043は54枚、♯042は29 枚、♯041は57枚、♯040は73枚、♯039は38枚、♯037は7枚) であると認められるから、これらによると、同規定に基づく使用料は、合計724 万5000円(2万円×362枚+5000円)となる。
そして、弁論の全趣旨によって認められるNHK(甲12によりNHKエンター プライズが取り扱う映像の制作者であると認められる。)と原告チャンネルとの相 違(規模、事業内容、社会的影響等)及びNHKが制作した映像と本件各動画との 相違(コンテンツが配信される媒体、視聴者数、映像ないし動画の制作に要する費 用、労力及び時間、コンテンツとしての社会的価値等)が大きく、上記の額をその まま採用することが相当とはいえないこと等の事情に加え、著作権侵害があった場 合に事後的に定められるべき「著作権の行使につき受けるべき金銭の額」(法11 4条3項)が通常の使用料に比べておのずと高額になることを併せ考慮すると、被 控訴人が本件各動画に係る「著作権の行使につき受けるべき金銭の額」は、これを 150万円と認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2024.02.19
令和4(行ケ)10081 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟__全文__知的財産裁判例 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
クレームは、「・・・前記バイアス層の合計重量をB(g)、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量をS(g)とした場合に、0.5≦B/(B+S)≦0.8を満たし、前記細径側バイアス層の重量をA(g)、前記バイアス層の合計重量をB(g)とした場合に、0.05≦A/B≦0.12を満たし、前記細径側バイアス層の重量をA(g)、前記太径側バイアス層の重量をC(g)とした場合に、1.0≦A/C≦1.8を満たす・・
本件明細書(【0014】)には、B/(B+S)を構成3の数値範囲(0.5\n≦B/(B+S)≦0.8)とすることにより所与の効果(技量が高いゴルファー やスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクを生み出 し、シャフトがねじれすぎること又はねじれないためにシャフトが折損してしまう ことを防止するとの効果(以下「【0014】記載の効果」という。))が得られ ると記載されているのみであって、【0014】記載の効果が得られる理由は記載 されていないし、B/(B+S)を構成3の数値範囲とすることで被告主張の課題\nを解決できるとする理由も記載されておらず、当該数値範囲のいずれの点において も被告主張の課題を解決できるとする理由も記載されていない。特に、B/(B+ S)の境界値を0.5及び0.8としたときに【0014】記載の効果が得られる 根拠並びに被告主張の課題を解決できるとする根拠については、本件明細書に何ら の記載もない。原告は、本件出願日当時の当業者はストレート層の重量の割合を2 0%以上としておけば、シャフトが曲げにより折損すること(ねじれがないために シャフトが折損すること)を防ぎ得るものと理解できると主張するが、ストレート 層の重量の割合を20%以上とする根拠はなく、本件出願日当時の当業者であって も、当該割合につき20%以上を選択することが容易であるとはいえない。また、 【0014】記載の効果と被告主張の課題との関係及びストレート層の重量の割合 を20%以上とすることと被告主張の課題との関係も不明である。さらに、実施例 1及び比較例1をみても、B/(B+S)を構成3の数値範囲とする理由は理解で\nきない(なお、比較例1におけるバイアス層の重量の割合は40%であり、実施例 1におけるバイアス層の重量の割合は60%であるところ、原告は、B/(B+S) の下限値が0.5であることの根拠を示していない。)。原告が挙げる証拠(甲1 2、21、23)をみても、B/(B+S)を構成3の数値範囲とする理由は理解\nできないし、これらの証拠には、当該数値範囲とすることで被告主張の課題を解決 できるとする理由及び当該数値範囲のいずれの点においても被告主張の課題を解決 できるとする理由は記載されておらず、当該数値範囲とすることで【0014】記 載の効果が得られることについても記載されていない。
以上のとおり、本件明細書の記載に加え、原告が技術常識であると主張する内容 を踏まえても、B/(B+S)を構成3の数値範囲とすることで被告主張の課題を\n解決できるとは理解できず、また、当該数値範囲のいずれの点においても被告主張 の課題を解決できるものと評価することもできない。当該数値範囲により【001 4】記載の効果が得られる理由も不明である。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> パラメータ発明
>> ピックアップ対象
2024.02.19
令和3(ワ)31840 職務発明対価金請求事件 特許権 民事仮処分 令和5年5月26日 東京地方裁判所
3 争点1(原告が本件発明の発明者であるか)について
本件発明は、本件構成を有するストレーナに関する発明である。被告では、平成26年5月22日までに、F向けに本件構\成を含む本件発明の構成が記載\nされた本件図面やその他の図面が作成された上で、原価についての概算見積も りがされ、平成27年2月13日にはFの甲工場において、実際に本件発明の 構成を有するストレーナの性能\実験がされ、同ストレーナは、実験対象の5件 の中で一番の性能ではないものの、一定の吹き戻し防止効果があることが確認された。そうすると、本件発明は、遅くとも同性能\実験の時点では完成していたと認められる。
ア 本件発明の特徴的部分は、本件構成であるところ(前記1 )、原告は、本 件構成の形状について、原告が発案したものであり、C等は原告の指示に基づいて図面を作成したにすぎないなどと主張する。\nしかし、原告は、前記2 で認定したとおり、本件訴訟の当初、本件発明 が着想され、完成するまでの具体的な経緯を説明せず、本件発明の特徴的部 分の完成に対する原告の具体的な関与の内容、時期が問題となったところ、 令和4年8月の準備書面で、平成25年初めころにジェットエンジンの形状 から着想したと主張したものの、原告が被告の社内において当該形状につい て言及したことについて、単にC等に図面等の製作を依頼したと主張するの みで、具体的な状況も、その時期についても明らかにしなかった。また、原 告は、本件特許の出願をした理由を記載するに当たりFに対し別の構成のストレーナの提案をしたことがあったことを述べつつ、本件構\成はDに提案したものであると主張した。しかし、前記2 ウ、エのとおり、本件構成は、Fの依頼に基づいて設計されて平成26年5月にはFに提案されたもので\nあった。また、原告が主張する平成25年初めの着想に関する証拠は何も提 出せず、それと本件図面が平成26年5月に作成されたこととの関係も不明 であった。被告はこれらの点を指摘したが、原告は、上記以上の主張をしな かった。
その後、原告は、発明者であることについての立証の最終段階として甲2 3陳述書を提出したところ、甲23陳述書には、原告が被告に初めて逆コー ン型の形状を提案したのは、平成26年8月末から同年9月初め頃にかけて であり、D向けのストレーナの開発過程において、Dの担当者に逆コーン式 のストレーナを提案したときであると記載され、また、それ以前に本件構成のストレーナの設計がされなかったと記載されていた。原告は、甲23陳述\n書をもって、本件構成を被告において明らかにした時期等について初めて本件訴訟において明示したところ、そこには、その時期は平成26年8月末か\nら同年9月初め頃にかけてであり、Dの担当者に対してであることや、それ 以前には本件構成のストレーナの設計がされなかったことが明確に記載されていた。\n
これに対し、被告が書面による準備手続に係る協議において、改めて、原 告の甲23陳述書の上記記載は本件図面が平成26年5月に作成されたこ とと矛盾することなど指摘したところ、原告は急遽陳述書を訂正したいとの 申出をし、本件図面が作成される前からもHの相談に応じて逆コーン式を提案していたなどと記載された甲25陳述書を提出した。しかし、甲25陳述\n書にもそのような提案をした具体的な時期についても状況についても記載 はなく、このことを裏付ける証拠も提出されなかった。 上記の原告の主張立証の経過及び原告が主張する原告の着想や具体的な 提案を客観的に裏付ける証拠が全くないことによれば、甲25陳述書の記載 うち、原告が、前記F向けの性能実験までの間に本件発明に実質的に関与していたと記載された部分はにわかに信用できない。\n
イ 他方、本件特許の出願に当たっては、原告がC及びBと共に発明者とされ、 前記2 キのとおり、出願を担当したIも原告を発明者として認識していた。 この点について、前記(1)で認定したとおり、本件発明はFに対するストレ ーナの開発過程で図面が作成され、実証実験を行って完成したものであると ころ、被告とFとの取引については本件構成を備えているものとは別の構\成 を備えるストレーナが採用され、本件構成を持つストレーナは採用されなかった。他方、平成26年5月の本件図面の作成後であり平成27年2月にF\nで行われた検証の直後には、被告とDとの取引では本件構成を有するストレーナが採用されたところ(前記2(1)オ)、上記開発過程やその採用の時期を 考えるとDに採用されたストレーナについては、Fとの関係で開発された本 件構成を備えたストレーナの知見が流用されたことが推認できる。なお、当時、本件図面を作成してF向けの実証実験をしていたCも、その開発過程で\nCの活動を承認等していたBも、Fのストレーナの開発を担当しており、D については担当していなかったことが認められる。また、前記2 エ、オの 原告の陳述書には、Dに本件構成を有するストレーナを採用させる経緯については試作図や3Dモデルの製作を指示したなど、やや具体的に記載されて\nおり、Dにおいて本件構成を有するストレーナが採用されたことについては、原告の指示や尽力が大きかったことがうかがえる。そして、前記2 キ の メールでのやり取りも考慮すると、被告は、本件構成を備えたストレーナについて、それを納入するDとの取引を始める前に、他人の特許出願にも対応\nすることができるように特許出願をしたことが認められる。
以上によれば、本件発明の構成を備えたストレーナは、Fの依頼に基づき平成26年5月に図面が作成されるなどしたもののFでは採用が見送られ\nた一方、原告の指示や尽力の下、Dとの取引において本件構成を有するストレーナが採用されて販売に至ったことがうかがわれること、Dとの取引の前\nに他人の特許出願にも対応することができるように本件発明が特許出願さ れたという経緯があること、被告において出願を担当していたIはFとの依 頼に基づき本件発明がされたという経緯について詳しい事情を直接見聞き したものではないことが推認できることなどから、Iは上記経緯等から原告 が本件発明に関与した者であると考えたか、又は本件構成を有するストレーナをDが採用する過程で尽力した者として発明者として取り扱うこととし、\n被告において、原告も発明者として本件特許の出願がされたことがうかがえ る。このことは、原告が、当初から、一貫してFではなくDとの関係で自身 が本件構成を提案していたと主張しながら、本件構\成が被告で具体化されて いった経緯について具体的に主張できなかったこととも整合する。 そうすると、Iが原告を発明者として扱い、被告が原告を本件発明の発明 者として出願したとしても、そのことが、前記 のとおり遅くとも平成27 年2月までに完成した本件発明の発明者が原告であることを裏付けるもの とはいえない。
関連カテゴリー
>> ピックアップ対象
2024.02.19
令和3(ワ)4658 損害賠償等請求事件 その他 民事訴訟知 的財産裁判例 令和5年7月10日 大阪地方裁判所
当裁判所は、争点1については、26万3368株が被告種苗1であり、被告 らは、これらの出荷について不法行為責任を負うと考えるが、争点4において判 断するとおり、前訴既判力の及ぶ部分を除く不法行為に基づく損害賠償請求権は 時効により消滅したと考える。 その上で、争点3の原告会社の不当利得返還請求権につき、これを肯定する余 地があるが、具体的に被告らが誰にどのような返還義務を負うか(争点2、3) は、本件においては育成者権者である原告P1も不当利得返還請求を行うことか ら、これとの相関において定まるものと考える。また、この検討と整合的な被告 らの不法行為に基づく原告P1に対する損害額(前訴既判力の対象となる請求権 等の内容)を算定する。 以下、上記の判断順序に沿って詳述する。 2 争点1(被告らが被告種苗1を使用した被告製品を販売した数量)について (1) 証拠(甲3、4、6、16、乙1、17、22、44。枝番のあるものは枝 番を含み、認定に沿わない部分を除く。)及び弁論の全趣旨によると、次の事実 を認めることができる。 ア 平成20年4月ころ、原告会社は、取引先であった商社を介して、被告会 社に本件品種に係る種苗の販売を始め、同年6月23日付けで、被告会社、 前記商社との間で、増殖を行わない、施工現場にて生育した麒麟草をカット した補植のみ認める、当麒麟草を親とし品種改良等を行わない等の「常緑麒 麟草に関する種苗登録禁止条項を厳守する」旨が記載された覚書を交わした。
イ 被告会社は、アの覚書に従って、原告会社から前記商社を介して本件品種 に係る種苗を仕入れていたが、被告P3に指示して、平成23年5月頃から、 覚書に反する態様で被告種苗1を育成するようになった。
ウ 平成23年11月2日に原告会社から被告会社に本件品種に係る種苗が 納品された後は、覚書に基づく取引がされることはなかった。
エ 被告P3は、被告P2の指示を受け、平成24年2月頃から公知のタケシ マキリンソウ種の増殖を始め、被告会社において、同種苗をどのように被告\n製品に使うか等の検討がされるようになった。
オ 平成25年4月頃、原告会社代表者は、同業者から、被告P3が本件品種\nに係る種苗を無断で増殖している旨を聞き、同月23日に、同業者の協力を 得て、被告P3の農場を訪問し、原告会社代表者の知見において、本件品種\nに係る種苗が増殖されている実態を見分するとともに、上記同業者が被告P 3に話を聞いた。
その際、被告P3は、前記商社から買ったものを挿し木にして増やしてい る、常緑キリンソウと言ったら種苗法違反になる、タケシマキリンソ\ウと言 って売っている、被告P2はこのことを知っているとの趣旨の発言をした。 同年5月、被告会社は、被告P3に、被告種苗1を使用した被告製品を廃 棄するよう指示した。 これ以降も、被告会社は、被告製品に用いる公知のタケシマキリンソウ種\nを入手し、被告P3以外の下請先で育成をすすめ、平成26年4月には、被 告製品に被告種苗1が用いられることがなくなった。 カ 鳥取県警察において、被告P3方への原告会社からの本件品種に係る種苗 の入荷状況及び被告P3から出荷されたキリンソウの総数につき捜査がさ\nれ、それらを対比した結果は、当初「P3及び下請け農家のキリンソウ取扱\nい状況について」(甲6調書の添付書面)として把握されていたが、後にこれ を訂正する捜査報告書(乙80)が作成された。 同報告書によると、平成26年3月末時点で、出荷数は、入荷数を26万 3368株上回る状態であった。
(2) (1)を総合すると、本件において、被告製品に用いられた被告種苗1の株数 は、前訴対象行為に係る被告種苗2である1812株を含め、26万3368 株であると認められる。 原告らは、甲6調書を根拠に、被告種苗1の株数は50万7733株である と主張するが、前記認定のとおり、被告会社は、公知のタケシマキリンソウ種\nの採用を検討し、平成26年4月には被告種苗1を使用することはなかったも のと認められるから、これを採用することができない。 被告らは、公知のタケシマキリンソウ種への切替は平成24年9月頃であっ\nたとの主張をするところ、確かに、被告会社が公知のタケシマキリンソウ種の\n採用の検討を始めたのは平成24年2月頃であって、平成25年5月の原告会 社代表者の被告P3の農場への訪問以降は、出荷された被告製品中に被告種苗\n1が使用されていないものが混在する可能性も考えられるが、なお抽象的な可\n能性にとどまり客観的な証拠はなく、公知のタケシマキリンソ\ウ種への切替が 平成26年4月以前に行われたことが的確に立証されたものとは言えないも のと判断する。 よって、前記数量に反する原告ら及び被告らの主張は、採用しない。
3 争点4(消滅時効が成立するか)について
(1) 認定事実
原告会社代表者は、平成25年4月頃、被告P3の農場に赴き、被告種苗1\nが原告らの許諾なく増殖されていると考え、同年5月頃、鳥取県警察に相談す るなどした。このことから、前提事実(6)記載の刑事事件に係る捜査が行われ、 平成27年2月8日、甲6調書が作成された。原告らは、同年11月16日ま でに甲6調書の写しを入手した(弁論の全趣旨)。同供述調書には、被告P2 が、被告P3に対し、平成23年5月頃、被告種苗1を違法に増殖するよう指 示したことが記載されており、同調書に添付の「P3及び下請け農家のキリン ソウ取扱い状況について」には、納品数と出荷数の差が50万7733株であ\nることが記載されていた。 また、1)原告P1は、平成26年11月11日には、被告会社に対し、無断 で被告種苗1を増殖していることを前提に、生産中止、在庫数及び取引の具体 的内容を照会する通知を発し(乙74)、2)同年12月26日には、被告会社 は、前訴請求を含む前訴を提起し、その頃訴状が原告P1に送達された(乙6 5、弁論の全趣旨)。
(2) 検討
ア 原告P1及び原告会社の当時の代表者(P4、本件品種の育成者)は夫婦\n関係にあり、原告P1と原告会社は、独占的通常利用権の設定者と利用権者 の関係にあって、本件品種に係る種苗に係る事業そのものや、被告らの無断 増殖行為の問題には、一体として対処していたと考えられることから、原告 らの損害及び加害者の認識について差があるとは考えられない。これを前提 とすると、原告らは、甲6調書に接するまでに、被告らが原告らの承諾なく 被告種苗1の増殖をしていること(不法行為該当性は自明である。)につき 疑念を持っており、警察の捜査により、その範囲が甲6調書によっておおむ ね判明したものであるから、原告らは、遅くとも同調書を入手した時点(遅 くとも平成27年11月16日)で、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を 提起できる程度に、損害及び加害者を知ったものというべきである。
イ 原告らは、損害及び被害者を知ったのは前訴が確定したときであると主張 するが、権利行使に関し抗弁がないことの確証を得ないと時効が起算されな いとするのは時効制度の趣旨に沿わないものであって、かかる見解は取り得 ない。
原告らの主張を、前訴に応訴したことによる中断(民法147条1号)を いうものと解したとしても、前訴は、前訴対象行為に限定された不法行為に 基づく損害賠償請求権の不存在確認訴訟であることが明示されているので あって、それ以外の被告らの行為に係る損害賠償請求権の時効の進行に対し 何らかの法的効果を持つとは考えられない(仮に何らかの効果があり得ると してもせいぜい催告の効果にとどまる。)から、前訴対象行為以外の行為に 係る請求権の消滅時効に関する再抗弁にもならないと解される。
・・・
(1) 独占的通常利用権者が不当利得返還請求できるかについて
原告会社は、本件育成者権の独占的通常利用権者であり、専用利用権者では ないものの、本件育成者権を独占的に利用して利益を上げることができる点に おいて専用利用権者と実質的に異なることはないから、当該利益の得喪につい ては民法703条の「利益」及び「損失」に該当する場合があると解するのが 相当である。
2024.02.19
令和5(ワ)70139 著作権侵害差止請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年12月7日 東京地方裁判所
さらに念のため、本件渡世人に係る記述自体をみても、原告ら主張に係る 本件渡世人は、1)通常より大きい三度笠を目深にかぶり、2)通常よりも長い 引き回しの道中合羽で身を包み、3)口に長い竹の楊枝をくわえ、4)長脇差を 携えた渡世人というものである。そして、証拠(乙1ないし15)及び弁論 の全趣旨によれば、渡世人が、三度笠を目深にかぶり、引き回しの道中合羽 で身を包み、長脇差を携えていたというのは、江戸時代の渡世人の姿として ありふれた事実をいうものであり、口に長い竹の楊枝をくわえるという部分 を更に加えたとしても、これがアイデアとして独自性を有するかどうかは格 別、著作権法で保護されるべき創作的表現という観点からすれば、その記述\n自体は明らかにありふれたものである。仮に、本件渡世人に対しその後本件 テレビ作品で加えられた表現をもって二次的著作物とする原告らの主張に立\nって、「通常より大きい」三度笠で、「通常よりも長い」道中合羽で身を包 んでいるという記述を加えて更に検討したとしても、これらの記述も同じく 極めてありふれたものであり、原告らの上記主張の当否を判断するまでもな く、本件渡世人に係る上記記述は、全体として、ありふれた事実をありふれ た記述で江戸時代の渡世人をいうものにすぎず、これを創作的表現であると\n認めることはできない。
・・・・
不正競争防止法2条1項1号又は2号にいう「商品等表示」とは、人の業務\nに係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営 業を表示するものをいう。\nこれを本件についてみると、原告ら主張に係る商品等表示とは、前記1)ない し4)の特徴を備えた本件渡世人に係る表示をいうところ(第1回口頭弁論調書\n参照)、本件渡世人がありふれた江戸時代の渡世人をいうにすぎないことは、 上記において説示したとおりであり、本件渡世人に係る表示は、そもそも不正\n競争防止法2条1項1号又は2号にいう「商品等表示」に該当するものとはい\nえない。
仮に、原告らの主張が、本件渡世人の図柄又は写真に「紋次郎」という名称 が付された表示をいうものとしても、商品等表\示として具体的な特定を欠くの みならず、一般に「紋次郎」という名称は、本件書籍、本件漫画作品、本件テ レビ作品及び本件映画作品に登場する中心人物を示す、いわゆるキャラクター に関する識別情報であり、本来的に商品又は営業の出所表示機能\を有するもの ではない。そして、本件全証拠をもっても、原告ら主張に係る上記表示が、キ\nャラクターに関する識別情報を超えて、原告らの営業を表示する二次的意味を\n有するものと認めるに足りず、まして原告ら主張に係る上記表示が、原告らの\n営業等を表示するものとして周知著名であるものとは、本件全証拠\nを踏まえても、明らかに認めるに足りない。
のみならず、証拠(乙20ないし28)及び弁論の全趣旨によれば、被告図 柄は昭和52年に、「紋次郎いか」は昭和57年に、「げんこつ紋次郎」は平 成20年に、それぞれ商標登録を受け、被告がこれらの商標を付するなどして 被告商品を販売し、その信用を長年にわたり蓄積してきた実情及び実績を踏ま えると、仮に原告らの主張に立ったとしても、原告らの営業等と誤認混同を生 ずるおそれを直ちに認めることはできず、これを覆すに足りる証拠はない。 そうすると、仮に上記キャラクターに関する識別情報に一定の財産的価値が 化体していたとしても、実在の人物としてパブリシティ権侵害をいうなら格別、 被告が被告図柄を付して被告商品を製造販売する行為は、不正競争防止法2条 1項1号又は2号に掲げる「不正競争」に該当するものとはいえない。 したがって、原告らの主張は、いずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2024.02.16
令和4(ワ)3577 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年12月4日 大阪地方裁判所
原告商品1と被告商品1は、通帳ケースの外側のすべての形態(通常全体 の大きさ及び形状、正面外側部に設けられたポケットの形状、大きさ及び位 置、背面部の形状)、マチ部の上面及び側面部のすべての形態(開閉可能なフ\nァスナーの配置)及び内部の形態の大部分(仕切り板の枚数及び大きさ、内 側ポケットの数)において共通しているから、各商品から受ける商品全体と しての印象が共通し、両商品の商品全体の形態が酷似しているといえる。他 方で、上記のとおり、両商品は、正面側及び背面側の各外装部裏面の裏面ポ ケットの有無、各外装部裏面の表面に設けられたカード等を収納するための\n小サイズのポケットの数(原告商品1は6個、被告商品1は4個)及び配置 位置(高さ約1ないし2センチメートルの範囲内)の点で相違するが、いず れも些細な差異であり、商品の全体的形態について需要者に与える印象に影 響するようなものではない。 したがって、原告商品1と被告商品1の形態は実質的に同一であると認め られる。
イ これに対し、被告は、原告商品1の販売前から同商品内側の特徴を備えた 商品を販売していたことや、被告の従前の販売商品や伊達衿のデザインが存 在することに照らせば、原告商品1はありふれた形態であり、不競法2条1 項3号により保護すべき形態に該当しないと主張する。 証拠(乙1、2)によれば、被告が、令和元年9月3日以降、楽天市場に おいて、1)外側の平面視で縦幅約12センチメートル、横幅約18.5セン チメートルの寸法で、厚み約2.5センチメートルの横長四角形状、2)正面 側外装部及び背面側外装部の各裏面(ケースの内部側の面)には、カード等 の小サイズの収納物を上部から挿入可能な小ポケットが4個設けられてい\nる、3)マチ部の上面及び両側面には、ファスナーにより開閉自在の開口部が 設けられており、開口することにより、底部を軸として側面視扇状に正面部 分と背面部分が展開する、4)内部には、上記小ポケットとは別に、仕切板7 枚により等間隔に8個の内側ポケットが設けられている、との原告商品1に 共通又は類似する構成を有する通帳ケースを販売していた事実、及び、令和\n2年9月29日から、外側に入口部分を斜めの形状にしたカードケースを販 売していた事実、がそれぞれ認められる。 しかしながら、原告商品1には、外側部に入口部分が斜めに交差するポケ ットが設けられており、これは商品の全体的形態について需要者に与える印 象に影響する形態であるところ、上記通帳ケースには当該構成が設けられて\nいない。また、上記カードケースの外側ポケットの入口部分は斜めに交差す る形態ではない。また、通帳ケース外装に和装の伊達衿(乙32)のデザイ ンを採用し得るとしても、態様は多様なものが考えられるのであって、その ことから直ちにそのような通帳ケース自体がありふれたものといえるわけ でもない。そして、本件記録上、原告商品1の外側ポケットの形態がありふ れた形態であると認めるに足りる証拠はない。 したがって、被告の上記主張を採用することはできない。
(2) 依拠性について
ア 前記前提事実第2の1(2)アのとおり、原告は、遅くとも令和3年6月2 2日から、第三者が自由に閲覧可能なECサイトである楽天市場で原告商品\n1を販売しており、被告において容易に原告商品1にアクセス可能であった\nといえ、証拠(甲22、23)によれば、実際に、被告代表者が令和3年8\n月7日に原告商品1を購入した事実が認められる。また、前記前提事実第2 の1(3)アのとおり、被告商品1の販売開始時期は原告商品1の販売開始か ら約8か月後の令和4年2月25日である。 以上によれば、被告商品1は原告商品1に依拠して製造販売されたと認め られる。
イ これに対し、被告は、原告商品1の販売前から同商品と同様の内部の形態 を有する通帳ケースを販売していたことや、原告の取締役が原告商品1の販 売前に被告の販売する通帳ケースを購入したことから、被告商品1は原告商 品1に依拠していないなどと主張する。
しかしながら、上記(1)イで検討したとおり、原告商品1と同商品の販売 前に被告が販売していた通帳ケースとは需要者に与える印象に影響を与え る形態である外装部の形態が相違しているから、両商品の内部の形態が同一 又は類似することや原告の取締役による購入履歴がある旨の被告主張の事 情を踏まえても、依拠性に係る上記判断は左右されない。
2024.02.16
令和5(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年12月21日 知的財産高等裁判所
原告は、スカッフプレートにおいて電池の交換は必要不可欠であるから、 電池交換のための電池カバーを設ける動機がある、電池カバーを表示部の表\ 側に設けることはさまざまな事情から好ましなく、甲8公報の技術常識等を 適用して、裏側に電池カバーを設ける動機がある、本件審決指摘の(a)〜(d) の変更は、電池交換のため必要であれば当業者は容易に想到し得る旨主張す る。 しかし、甲1公報によれば、甲1公報の「実用新案登録請求の範囲」に記 載された考案は、外部電源が完全に不要な自動車スカッフプレートに適用さ れる発光モジュールを提供することを課題とし(【0004】)、この課題 を解決するための発光モジュールは、発光素子及びリードスイッチが設けら れた「ランプ板」、及び電線を介してランプ板に接続される「電池」が、い ずれも「導光板」に埋設される構成を有し(【0005】、【0015】〜\n【0017】)、この構成により「導光板10の内部に発光素子20に必要\nな電力を供給することができる電池40を設置するため、完全に外部電源が 不要となる」(【0019】)ことで、上記の課題を解決するものと認めら れる。 甲1公報には、上記課題の解決の手段として、上記以外の構成は記載され\nていない。 そして、本件審決が認定した甲1発明の構成は、外部電源が完全に不要な\n発光モジュールである上記「導光板10」に、これに埋設された「ランプ板 50」、「電池40」等を密封するための「収容溝カバー70」を設け、本 件発明1の「底板」に相当する「スカッフプレート80」の上面には「凹部」 を設け、この「凹部」に発光モジュールである上記「導光板10」を収容す るものである。
そうすると、甲1発明においては、電池40が導光板10内に埋設される ことを含め、「導光板10」に係る上記構成は課題解決に直結した構\成であ ると理解するのが自然であり、本件審決のいう「甲1電池収容構成」もこれ\nと同趣旨と認められる。 加えて、甲1公報には、電池の交換についての記載はなく、甲1発明に接 した当業者が仮に電池の交換という課題を着想したとしても、相違点1に係 る構成とするためには、(a)収納溝カバー70を除いた上で、(b)導光板10 に代えてスカッフプレート80に電池40を収容する収容孔を設け、当該電 池収容孔を底面側から開口するものとし、(c)該収容孔を覆うカバーを設け、 該カバーを取り外すことで電池40を交換可能とし、(d)スカッフプレート 80に収容することになった電池と、導光板10内に埋設されているランプ 板50等との電気接続を行うという変更が必要になることは、本件審決が認 定するとおりである。
甲1発明をこのように変更することは、課題解決に直結した構成である\n「甲1電池収容構成」を変更するものであることと併せると、動機付けはな\nいといわざるを得ず、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。 また、甲8公報からは、表示部を有し電池を電源とする電子機器において、\n表示部とは反対の裏側に電池交換のための取り外し可能\なカバーを設けるこ とは技術常識であるといえるが、甲1発明のように独立したモジュールが設 けられ、底板(スカッフプレート80)の凹部にモジュールを収容する電子 機器において、裏側からモジュール内部の電池を交換することまでが技術常 識であったとは認めるに足りない。 甲2公報については、甲1発明のスカッフプレート80、すなわち底板に 相当する部材がないから、下側から電池カバーを設けるという抽象的な点を もって「甲1電池収容構成」と置換可能\ということはできない。
(2) 原告は、甲1発明において収容溝カバー70の取外しは想定されており、 外部から電池40を交換することは当業者が想起し得る旨主張するが、甲1 発明において収容溝カバー70の取外しが可能か否かは不明であるし、仮に\n取外しが可能であれば、取り外すことにより電池交換が可能\と考えられるか ら、むしろ、電池交換のため底板(スカッフプレート80)に電池収容孔と 電池カバーを設ける構成に変更する必要性は乏しいといえる。\nそうすると、原告の上記主張を考慮しても、上記の構成変更に係る動機付\nけは否定せざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2024.02.16
令和4(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年12月21日 知的財産高等裁判所
相違点2〜4は密接に関連するものであるから、事案に鑑みこれを一括し、 甲1発明に周知の技術的事項1及び周知の技術的事項2を適用して、相違点 2〜4に係る本件発明1とすることが容易になし得るかについてまず検討 する。
ア 甲1発明への周知の技術的事項1の適用について
(ア) 周知の技術的事項1は、半導体ウェーハの表面を加工する際の焦点の\n位置を調節するものであり、甲3〜5には、半導体ウェーハの表面以外\nの部位を加工する際の課題や解決手段についての記載はない。また、周 知の技術的事項1は、加工対象物に反りがあることを課題とする解決手 段である。
一方、甲1発明は、前記(1)オのとおり、加工対象物の内部に集光点を 合わせて改質領域を形成し、切断予定ラインに沿って加工対象物を割る\nというものである。また、甲1には、加工対象物の反りについての記載 はない。加えて、甲1には、溶融処理領域を切断予定ラインに沿うよう\nに加工対象物の内部に形成する工程において、レーザ光の集光点につい てZ軸方向の制御をすることについての記載もない。 そうすると、甲1発明に周知の技術的事項1を適用すべき動機付けは 認められないというべきである。
(イ) 原告は、前記第3の1(1)ア(ア)(イ)のとおり、焦点の位置が加工対象 の表面か、内部であるかにかかわりなく、振動などの外的要因により、\n集光が不安定になることから、加工中の集光点のAF制御が必要になる のは、当業者の技術常識であり、甲1において、周知の技術的事項1(A F制御)が明示的に記載されていないとしても、当業者であれば記載さ れているに等しいと認識し、また、シリコンウェハは一般に反るもので あり、当業者は反ったシリコンウェハが加工対象となることも認識する 旨主張する。 しかし、甲1発明は、加工対象物の内部に集光点を合わせて改質領域 を形成し、切断予定ラインに沿って加工対象物を割るというものであり、\nその目的や機序からして、加工対象物の表面からレーザ加工する従来技\n術と本質的に異なるのであるから、甲1に半導体ウェーハの表面の加工\nの際の技術である周知の技術事項1が記載されているに等しいとはい えないし、甲1にはシリコンウェハの反りについて何らの言及もないの であって、原告の主張は採用できない。
(ウ) 原告は、前記第3の1(1)ア(ウ)のとおり、本件審決が、甲1発明にお ける集光点のZ軸方向のずれの許容幅の大きさを指摘し、これを根拠に 周知の技術的事項1の適用を否定する判断をしたのは誤りであるとし、 その理由として、1)本件出願日の時点において、厚さ30μmまでの薄 型シリコンウェハも甲1発明の加工対象となり得るところ、加工中の集 光点をウェハ内に収める必要があること、2)甲1の105頁15〜23 行に、比較的厚いウェハの場合にも、改質領域のZ方向の位置が割断精 度に影響を与える旨の記載があること、3)セミフルカットでも改質領域 の深度のばらつきによりクラック等の問題が生じることからすれば、セ ミフルカットより改質領域以外の部分が大きいステルスダイシングに おいて、改質領域の深度がばらつけば、チップ分割に支障を来すであろ うことから、当業者がAF制御の必要性を理解する旨を主張する。 しかし、1)に関し、甲38、39は、薄型シリコンウェハがステルス ダイシングの加工対象となることを示すものであるが、それが直ちに甲 1発明においてZ方向のAF制御の必要性を導くものではない。
また、原告が2)において引用する甲1の記載は、「クラック領域9と 表面3の距離が比較的長いと、表\面3側においてクラック91の成長方 向のずれが大きくなる。これにより、クラック91が電子デバイス等の 形成領域に到達することがあり、この到達により電子デバイス等が損傷 する。クラック領域9を表面3付近に形成すると、クラック領域9と表\ 面3の距離が比較的短いので、クラック91の成長方向のずれを小さく できる。よって、電子デバイス等を損傷させることなく切断が可能とな\nる。但し、表面3に近すぎる箇所にクラック領域9を形成すると、クラ\nック領域9が表面3に形成される。このため、クラック領域9そのもの\nのランダムな形状が加工対象物の表面に現れ、表\面3のチッピングの原 因となり、割断精度が悪くなる。」というものであるが、これは、改質 領域を形成する深さ方向の位置は加工対象物の表面に近いことが望ま\nしいが、近すぎてもいけないという程度のことを述べるにすぎず、形成 位置を特定したり、それが一定でなければならないとするものではなく、 まして、AF制御の必要性を示すものでもない。また、甲1には、「図 98に示すクラック領域9は、パルスレーザ光Lの集光点を加工対象物 1の厚み方向において厚みの半分の位置より表面(入射面)3に近い位\n置に調節して形成されたものである。クラック領域9は加工対象物1の 内部中の表面3側に形成される。」(105頁1〜4行)、「なお、パ\nルスレーザ光Lの集光点を加工対象物1の厚み方向において厚みの半 分の位置より表面3に遠い位置に調節してクラック領域9を形成する\nこともできる。この場合、クラック領域9は加工対象物1の内部中の裏 面21側に形成される。」(105頁24行〜106頁1行)等の記載 もあり、甲1発明においては、シリコンウェハ内部の改質領域の位置は シリコンウェハの厚み方向において厚みの半分の位置より表面に近い\n位置の近くから、厚みの半分の位置より表面に遠い位置まで、ある程度\nの幅をもって設定され得ると理解できるのであり、当業者が、甲1発明 において、X、Y軸ステージの振動やウェハの反りにより、レーザ光の 集光点がずれること、すなわち改質領域の位置がずれることが、直ちに シリコンウェハの割れに影響を及ぼすと理解することはないというべ きである。
そして、3)に関し、セミフルカットとステルスダイシングは切断の原 理、機序が異なるのであり、前者で改質領域の深度のばらつきにより問 題が生じるからといって、後者においても同様であると当業者が認識す るとはいえない。
(エ) 以上のとおりであって、原告の主張するところを踏まえても、甲1発 明に周知の技術的事項1を適用することが当業者にとって容易になし 得たとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2024.02.16
令和5(行ケ)10046 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年12月21日 知的財産高等裁判所
以上の甲5の1〜3の記載を総合すれば、角栓除去用クレンジング組成 物において、クレンジング機能(洗浄性)、ウォッシュオフ機能\(水での 洗い流し性)、角栓除去機能、皮膚への負担を考慮して、界面活性剤を1\n0〜20質量%程度、すなわち10体積%を超える量で配合することは、 本件優先日前における当業者の技術常識であったと認められる。 他方、甲5の1には「5〜10質量%」、甲5の2には「10質量%」 の界面活性剤を含むクレンジング剤等が記載されていること自体は、原 告の主張するとおりであるが、本件除く構成における「0〜10体積%\nであるものを除く」との特定は、「0体積%〜100体積%」から「0〜 10体積%であるものを除く」範囲のものであるため、結局、「10体 積%超」の範囲である(「10体積%より多く配合する」)ことを意味す るものにほかならない。そうすると、構成の容易想到性を判断するに当\nたっては、甲1発明において、界面活性剤の配合量を「10体積%超」 とする(「10体積%より多く配合する」)ことを、当業者が容易に想到 できたことの論理付けができるかを検討すれば足りる。甲5の1〜3が 「0〜10体積%」の界面活性剤を配合したものを含むとしても、その ことが本件発明と甲1発明との相違点に係る容易想到性を判断する上で、 どのような意味を有するのか、原告の主張によっても明らかでない。
ウ また、本件除く構成の数値限定が顕著な効果を有するものであれば格別、\n本件発明はそのようなものとも認められない。 すなわち、本件明細書によれば、本件発明の効果は、「タンパク質を簡 便に抽出できるため、皮膚に付着したタンパク質を抽出洗浄することが 可能な液状化粧品(「タンパク質洗浄用の液状化粧品」)として好適に使\n用できる」というものであり(【0064】)、「また、本発明のタンパク 質抽出剤は、界面活性剤等を含まなくとも、優れたタンパク質抽出効果 を奏する」ことから、「本発明のタンパク質抽出剤によれば、皮膚への負 担を低減しつつ、所望の洗浄効果が得られる」というものである(【00 65】)。
しかしながら、界面活性剤配合量に関しては、本件明細書の実施例1 6、18及び20が界面活性剤(Tween 80、Span 80)を含む組成の溶液 であるが、「全量に対して0〜10体積%であるものを除く」量で配合し たものが存在しないことは前記のとおりである上、試験管内でタンパク 質抽出作用を確認しただけで、皮膚に対する洗浄効果は確認されていな い。角栓の除去については、実施例13において角栓のある皮膚に対す る洗浄効果を確認する唯一の実施例が記載されているものの、第2のタ ンパク質抽出剤Aを含むタンパク質抽出剤を使用した結果、石けんと比 較して「高い洗浄効果を示した」こと、「本発明のタンパク質抽出剤は、 クレンジング剤として好ましく使用できる」ことが示されているのみで (【0149】)、その組成は界面活性剤を含まないものである(【007 3】、【0138】〜【0141】、【0149】)。そうすると、本件発明 において界面活性剤を「全量に対して0〜10体積%であるものを除く」 量で配合することにより、「角栓除去用液状クレンジング剤」が具体的に どのような顕著な効果を奏するのかは不明であるといわざるを得ない。 以上に加え、甲1には「角栓やメラニンを含む古い角質や酸化した汚 れもすっきり。」との角栓の除去機能についての記載があることからする\nと、本件発明による上記程度の効果は、当業者が予測し得たものにすぎ\nない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2024.02.16
令和2(ワ)7918 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和5年12月14日 大阪地方裁判所
証拠(乙1〜3)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件商標の出願に当 たり、「第7類 工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボッ ト」、「第28類 ロボットおもちゃ並びにその部品」等、「第35類 工業用ロ ボットの小売」等を指定商品及び指定役務としていたが、特許庁から、本件商標は、 「ロボットの小売店」程の意味合いを容易に認識させるものであるところ、ロボッ トの販売及び修理等を取り扱う業界において、「Robot Shop」及び「ロ ボットショップ」の文字が、ロボットを取扱商品とする小売店であることを示す語 として一般的に使用されている実情があることから、本件商標を第35類の工業用 ロボットの小売等の指定役務に使用することは、商標法3条1項3号に該当するこ と等を理由とする拒絶理由通知書の送付を受け、前記商品及び役務を指定商品等か ら除外して、本件商標の登録を受けたことが認められる。
被告は、被告各サイトにおいて、被告販売商品を販売しているところ、このよう な本件商標の出願経過に照らすと、原告が、被告販売商品のうちロボットと同一又 は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則(民法 1条2項)により許されないと解するのが相当である。
(2) ロボットの字義は、「複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。 一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械又は装置」(広辞 苑第七版)であるほか、証拠(甲24、25、乙31)及び弁論の全趣旨によれば、 日本産業規格(JIS規格)は、ロボットについて、二つ以上の軸についてプログ ラムによって動作し、ある程度の自律性をもち、環境内で動作をして所期の作業を 実行する運動機構と定義し、産業用ロボットについて、産業オートメーション用途\nに用いるため、位置が固定又は移動し、3軸以上がプログラム可能で、自動制御さ\nれ、再プログラム可能な多用途マニピュレータ(互いに連結され相対的に回転又は\n直進運動する一連の部材で構成され、対象物をつかみ、動かすことを目的とした機\n械)と定義していることが認められる。これらの字義等に照らすと、所定の目的の ために自律性をもって動作等をする機械又は装置は、少なくともロボットに類似す るものであるといえる。
別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告サイトにおける説明」欄によれば、 非類似商品を除く被告商品のうち、「被告商品」欄の「2.無人機・ドローン」の 「(1)無人機・ドローンキット/ARF/RTF」、「(2)完成品(RTF)/半完 成品(ARF)」、「(3)無人機・ドローン 完成品(RTF)」、「(4)小型/超小 型無人機」、「(6)Vテール」、「(7)クワッドコプター」、「(8)ヘキサコプター/ オクタコプター」及び「(9)飛行機」(以下、これらを「ロボット類似品」と総称す る。)は、所定の目的のために自律飛行が可能なものが含まれるものと認められ、\n少なくともロボットに類似するものといえる。一方、ロボット類似品を除くその余の被告商品は、いずれもロボット製作に使用する部品や汎用的な部品、製作機器等であって、ロボットに類似するとはいえない。
(3) 以上から、原告が、ロボット類似品に対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則により許されない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 役務
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2024.02.16
令和5(ワ)70102 特許権侵害差止及び特許権侵害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年12月4日 東京地方裁判所
ア 本件発明の構成要件BないしDは、ポリフェノールの重量、EGCGとE\nCGの合計重量又は総カテキンの重量につき、各構成要件記載の重量%以下\nに限定するものであるが、上記構成要件にいう「茎が取り除かれた」とは、\n本件発明の半発酵茶葉が茎を含まないことを意味するのか、あるいは、茎を 含む半発酵茶葉のポリフェノール等の重量%を測定するための条件を示す ものか、文言上必ずしも明らかではない。そのため、本件明細書の記載を考 慮して、その用語の意味を解釈すると、本件明細書の記載【0079】には、 「サンプリング方法:できた各号のお茶の茎を取り除き、篩い分けて12メ ッシュパス20メッシュオンの砕茶を各800g採取する。」として、本件 発明の半発酵茶葉は、その茎が取り除かれることが明確に記載されている。 そして、本件明細書の他の実施例をみても、官能試験によって本件発明の効\n果が確認されている茶葉は、いずれもサンプリングの段階で茎が取り除かれ たものであり、本件明細書全体の記載によっても、茎が含まれた茶葉につい ては、本件発明の効果を確認するような記載が一切存在せず、本件発明の茶 葉に茎が含まれることを示唆する記載も一切認められない。 上記各構成要件及び本件明細書の記載を踏まえると、上記各構\成要件にい う「茎が取り除かれた」とは、本件発明の半発酵茶葉が茎を含まないことを 意味するものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、前記認定事実及び弁論の全趣旨(被告各製品 (双方当事者持参に係るもの)に係る茎の有無の確認結果〔第3回弁論準備 手続期日及び第4回弁論準備手続期日〕を含む。)によれば、被告各製品の 茶葉には、いずれも多くの茎が含まれていることが認められる。 したがって、被告各製品は、本件発明の構成要件BないしDを充足するも\nのと認めることはできない。
のみならず、原告による本件各試験は、被告各製品において茎を除いてポ リフェノール等の重量%を測定していることまで立証するものではなく、上 記構成要件BないしDを立証する前提を欠くものといえる。しかも、原告に\nよる本件各試験は、被告らが釈明したとおり(第1回弁論準備手続調書参照)、 本件各試験に係る具体的な実施条件等が明らかにされていないため、上記構\n成要件BないしDにいう成分重量を的確に立証するものとはいえない。その 上、原告が採用した測定方法は、本件明細書【0082】に記載された測定 方法(カテキンにあってはISO14502、ポリフェノールがGB/T8 313をいう。)とは異なるものであるから、上記構成要件BないしDに各\n規定する成分重量を立証するに適切なものとはいえない。 この理は、原告が時機に後れて提出した本件試験その2(甲19、20) についても、測定に当たり茎が除かれていない点、具体的な実施条件等を欠 く点において同様に当てはまるものであり、同試験も上記認定判断を左右す るに至らない。
したがって、原告の立証は、上記各構成要件の充足性を裏付けるに的確な\nものとはいえず、このような観点からしても、被告各製品は、本件発明の構\n成要件BないしDを充足するものと認めることはできない。 イ これに対して、原告は、1)仮に茎を取り除かなければ、被告各製品には全 体の13重量%から18重量%の茎が含まれているはずであり、見た目も悪 くなるはずであるが、実際にはそうではないこと、2)仮に茎が完全には取り 除かれていなかったとしても、少々の茎は、この業界では茎が取り除かれた ものとみなされていること、3)仮に茎が取り除かれていないとしても、被告 各製品の半発酵茶という性質に何ら変わりはないことを主張する。 しかしながら、本件特許に係る茶葉は、茎が取り除かれているものである ことは、上記において説示したとおりであり、原告の主張は、本件特許の構\n成要件の用語の意義を正解しないものである。また、被告各製品には、少々 とはいえない茎が含まれていることも、上記において認定したとおりであり、 原告の主張は、その前提を欠くというほかない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2024.02.15
令和4(ワ)4903 商標権 民事訴訟 令和5年11月30日 大阪地方裁判所
2 被告標章につき被告に先使用権が認められるか(争点1)について
(1) 被告は、葬儀会社の需要者は、主として葬儀会館の周辺地域に居住する者 であるとした上で、一般に、葬儀会社の商圏は、葬儀会館を中心として半径2km 程度といわれているから、当該地域を周知性が求められる地理的範囲として、被告 標章に係る先使用権の有無を判断すべきである旨主張する。
(2) この点、葬儀はその施行の必要が予測不可能\である一方で、一旦不幸があ れば直ちにその施行が求められるという性質を有することを踏まえて、主として葬 儀会館の周辺地域に居住する者が需要者として想定されるということについては、 一定の合理性が認められる。
しかしながら、ある標章につき先使用権が認められた場合、未登録でありながら、 登録商標が有する禁止権の効力を排除して当該標章の使用が許されることになり、 商標権の効力に対する重大な制約をもたらすことになる。かかる重大な制約に鑑み ると、法32条1項前段にいう「需要者の間に広く認識されている」の地理的範囲 につき、法4条1項10号におけるものよりも緩やかに解する余地があるとしても、 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するウェブサイトにおける「業種別開業\nガイド」の「葬祭業」のページにおいて「斎場事業は、商圏範囲が2キロメートル、 人口3万人に1会館を1つの目安とする。」と記載されていること(乙25)をも って、葬儀会社の商圏が半径2km程度であるとして、被告標章につき本件会館を 中心として半径2km程度の範囲で周知されていれば足りると判断することは相当 ではない。 前記認定の事実によれば、本件会館における平成28年から令和2年までの葬儀 の全施行件数(567件)のうち、葬儀申込者の居住地が半径2km圏内に存在す\nる件数が約82%(464件)を占めている(認定事実(2)イ)が、上記圏外の件 数が2割弱も存在すること、みと大協が近隣地区のみならず大阪地域ないし東大阪 ・八尾の相当程度広い地域を対象とした宣伝広告活動も行っていたこと(認定事実 (5))を考慮すると、みと大協が被告標章と同一の「久宝殿」との標章をその業務 (葬儀業)に使用していた地理的範囲は、おおむね東大阪市及び八尾市の全域(本 件会館から最大で約10km圏内に相当する。乙169)と考えられるから、先使 用権が認められるための要件としての周知性についてはその範囲において検討され るべきである。
(3) そして、認定事実(2)ア及び(3)によれば、平成28年から令和2年までの みと大協の葬儀の施行実績(年順に、127件、102件、137件、124件、 77件〔令和2年8月頃まで〕)は、東大阪市及び八尾市における死亡者数の8割 (年順に、6258人〔1人未満切捨て。以下同じ。〕、6211人、6452人、 6522人、4481人〔令和2年8月までとして、年全体の3分の2〕)を基準 とした場合、そのうち約2%にすぎない上、認定事実(4)のとおり、本件会館の半 径2km圏内における他社の葬儀会館の数は、東大阪市内に4件、八尾市内に5件 であって、これらの葬儀会館における本件会館のシェアは明らかではないところ、 上記の範囲が半径3km圏内に拡大するだけでも、他社の葬儀会館の数は東大阪市 内に12件程度、八尾市内に14件程度に増加し、これらの葬儀会館における本件 会館のシェアはより縮小することになる。しかも、認定事実(1)イのとおり、みと 大協は、平成28年頃から経営状況が悪化し、福田商事に支払う本件会館の使用料 も以前より大きく減少していることから、令和2年当時の本件会館のシェアはさら に縮小していた可能性がある。\n以上のことからすると、仮に、東大阪市及び八尾市全域という地理的範囲におけ る先使用権の成立が許容され得ることを前提として、本件会館が、平成12年から 「メモリアルホール久宝殿」との名称で約20年にわたり葬儀会館として使用され てきたこと、「久宝殿」との標章(被告標章)が一定程度の識別力を有すること (前提事実(4)ア参照)を考慮しても、被告標章は、本件商標の登録出願(令和2 年9月17日出願)の際、当該範囲において、現に需要者の間に広く認識されてい たとは認められない。
(4) したがって、被告が、みと大協から「当該業務を承継した者」(法32条 1項後段)に当たるか否かを検討するまでもなく、被告標章につき被告に先使用権 が認められるとの被告の主張(抗弁)は理由がない。
2024.02.15
令和5(ワ)70276 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年1月30日 東京地方裁判所
(2) 原告表示の周知性について\n
ア 原告書籍の需要者について
原告書籍の需要者については、証拠(甲 5、9、10、15)及び弁論の全趣旨によれ ば、原告書籍が一般的な書店及び書籍販売サイトで販売されていること、電子書籍 の有料配信が行われていること、原告書籍の新聞広告が全国紙、地方紙及びスポー ツ紙に広く掲載されたこと、一般向けのウェブ記事で紹介されたことなどに鑑みる と、原告書籍は、広くノンフィクション・エッセイに関心を有する者を需要者とす るとみるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
イ 原告書籍の販売実績等について
原告書籍の販売実績に関し、原告は、シリーズとしての原告書籍の累計発行部数 は 46 万部以上である旨を主張する。これを裏付けるに足りる的確な証拠はないも のの、令和 4 年 月 31 日付け「DIAMOND online」の記事(甲 の 1)では、同 年 4 月時点での原告書籍(コミカライズ版 2 作を含む。)の発行部数は累計 40.4 万 部とされ、また、原告書籍 1(交通誘導員ヨレヨレ日記)は「7 万 6000 部のベスト セラー」と紹介されている。令和 2 年 8 月 29 日付け「幻冬舎 GOLD ONLINE」の 記事(甲 の 2)にも、原告書籍 1 につき、「昨年 7 月に発刊するや、1 年余りで 7 万 6000 部を突破した。」と紹介されている。さらに、令和 4 年 月 6 日付け「中央公論.jp」の記事(甲 の 3)では、原告書籍の累計発行部数は 4万部と紹介さ れている。なお、書籍の一般的な流通形態に鑑みると、販売実績は、発行部数以下 ではあるものの、これに比較的近い数字であることが合理的に推認される。また、 原告書籍は、インターネット上で電子書籍として販売ないし有料配信されているこ ともうかがわれる。
ウ 原告書籍の宣伝広告等について
前記のとおり、原告書籍についてはインターネット上に複数の紹介記事が掲載さ れているほか、証拠(甲 9)及び弁論の全趣旨によれば、別紙「原告書籍の広告実 績」のとおり、令和元年 7 月〜令和 年 4 月の間、毎月のように原告書籍に関する 新聞広告が全国紙、地方紙及びスポーツ紙に広く掲載されていたことが認められる。 もっとも、新聞広告につき仔細にみると、令和 2 年 1 月までは原告書籍 1 のみの 広告であり、原告書籍 2 以降は、それぞれの書籍が発売されるたびに個別に又は既 刊の原告書籍と共に広告が掲載された。その広告には「3 段 8 割」がかなりの割合 を占めるところ、「3 段 8 割」とは、新聞の 1 面下部にある文字だけの書籍広告欄を 指すものと理解される(甲 の 3)。「全 段」、「段 2 割」といった広告も少なからず見受けられるが、これらは基本的に原告書籍を含む原告の発行する複数の書籍 を一括して掲載したものとみられる。その具体的態様は必ずしも詳らかではないも のの、仮に令和 年 3 月 2 日付け読売新聞に掲載された広告(甲 8)と類似するも のであるとすると、原告書籍の各表紙と共通する一部のイラスト及びコメントは掲\n載されているものの、掲載された原告書籍の全てにつき、原告書籍の表紙(甲 3) にみられる原告表示の要素全部が掲載されてはいない。上記広告掲載の直近に発売\nされた原告書籍 12 については、原告書籍 12 の表紙(甲 3)と同一書体による題号 並びに同一内容のイラスト及びコメントが示されているものの、原告書籍 12 の表\n紙とは配置(コメントの一部につき、縦書きか、横書きか)が異なり、表紙が白色\nを基調とするものであることをうかがわせる記載等はなく、さらに、原告書籍 12 の 表紙には存在しない読者等のコメントの記載がある。すなわち、「全 段」の新聞広 告において、原告表示の表\紙における要素の全て(1)〜4))が表紙と同じ配置で掲\n載されていることを認めるに足りる証拠はない。
エ 以上の事情を総合的に考慮すると、原告書籍については、仮に原告主張のと おりシリーズ累計発行部数が 46 万部であったとしても、その需要者が広くノンフ ィクション・エッセイに関心を有する者であることをも踏まえると、原告書籍それ 自体が周知といえるほどの販売実績があるとまではいい難い。その点を措くとして も、その販売期間はシリーズを通算しても 4 年半程度に過ぎず、原告表示につき原\n告によって長期間独占的に使用されたものとは認められない。また、その宣伝広告 の実情等をみても、極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者で あるノンフィクション・エッセイに関心を有する者において、原告表示をもって、\nこれを有する原告書籍の出所が特定の事業者である原告(ないし「原告書籍の発行 者」)であることを表示するものとして周知になっていたとは認められない。\n以上より、原告表示は、一般消費者にとって、原告書籍の出所として原告を表\示 するものとして周知になっているものとはいえないから、「商品等表示」に該当する\nとはいえず、また、「需要者の間に広く認識されている」ということもできない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2024.02.15
令和1(ワ)10940 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和6年1月29日 大阪地方裁判所
ア 本件プログラム1は、マンロック(高圧室作業場所への作業員の出入り用 気密扉)内の気圧、二酸化炭素濃度等を記録するペーパーレスレコーダー(最 大10機)を集中管理(レコーダーで記録された情報を遠隔地のパソコンで\nリアルタイムに表示し、データを蓄積するとともに閾値を超えた場合は警告\nを発することが可能)するシステムプログラムであり、統合管理画面(メイ\nンフォーム画面)、個々のレコーダーの監視画面(レコーダーフォーム画面。 表示形式はレコーダーと同様。)、レコーダーの通信ルーチン、データベース\n(レコーダーの情報を集積する部分)などを構成要素とするものである。(甲\n28、弁論の全趣旨)
この点、画面構成や、レコーダーのデータをどのように扱うかについては、\nプログラムの目的、環境規制の態様、ハードウェアやオペレーティングシス テムなどに由来する制約等により、表現の選択の余地の乏しいものもあると\n考えられるが、データ処理の具体的態様(クラス、サブルーチンの利用等の 構造化処理を含む)、レコーダーとの通信プロトコルの選択及びそれに応じ\nた実装、データベース化の具体的処理手順などについて、各処理の効率化な ども意識してソースコードを記述する過程においては、相応の選択の幅があ\nるものと認められる。
イ 原告は、このような選択の幅の中から、データ処理の態様を設計した上、 A4用紙で約120頁分(1頁あたり60行程度。以下同様)のソースコー\nドを作成したことからすると、ソースコード(甲28)の具体的記述を全体\nとしてみると、本件プログラム1は、原告の個性が反映されたものであって、 創作性があり、著作物であるということができる。
ウ 被告は、本件プログラム1のソースコードの多くの記述が公開されたサン\nプルプログラムであり、単純な作業を行う機能の複数の記述であり、計測上\nの管理基準に対応させた記述の順序や組合せであるから、ソースコードの記\n述に創作性はない旨を主張する。しかし、ソースコードに既存のサンプルが\n含まれることについて的確な立証はない上、仮にそのような記述が含まれる としても、プログラム全体としての創作性を直ちに否定するものともいえな いから、被告の主張は採用できない。
・・・
前提事実及び認定事実によると、本件各プログラムの中には、明示的に 異なる現場で用いることを前提とする仕様が採用されたものがあること、 本件各プログラムはいずれも発注の原因となった現場と異なる現場で用 いることについてプログラムの仕様上の制限はないとうかがわれること、 原告自身、一つの現場が終了したと見込まれる後も、プログラムの修正に 応じるなどしていること、原告自らソースコードを納品したものもあるこ\nとに加え、原告が、平成2年に独立した後、多数回にわたって被告から依 頼されたプログラムを制作、納品し、平成20年12月から平成21年4 月までの間は、被告に採用されてプログラム制作業務に従事していたこと からすれば、計測業務における被告のプログラムの利用実態(プログラム を一つの現場で利用するだけでなく他の現場においても複製、変更又は改 変(カスタマイズ)して利用していたことを含む。)から、自己が制作して 納品したプログラムが被告により複数の現場で利用され得ることを認識 していたものとみられることが認められる。これらの本件においてうかが われる事情からすると、本件各プログラムの開発に係る各請負契約におい て、成果物が、少なくとも被告の内部で使用される限りにおいては、他の 現場における使用や改変を許容する旨の黙示の合意があったものという べきである。
・・・
(1) 氏名表示権が侵害されたか(争点3−3、5−2)及び被告に故意又は過失\nがあったか(争点3−4、5−3)
ア 本件プログラム3(争点3−3、3−4)
前記前提事実のとおり、本件プログラム3を複製、変更した被告プログラ ム3の起動画面やバージョン表示画面においては、被告の社名が表\示され、 原告の氏名は表示されていない(甲9)。そして、本件プログラム3と被告プ\nログラム3を比較すると、ソースコードの大部分において同一であり、被告\nプログラム3には本件プログラム3に時間率評価機能を果たす計算処理や\ndB値の時系列変数の計算処理の機能が追加された点において相違するが\n(甲8の3)、この相違点から被告プログラム3が本件プログラム3と別個 のプログラムであるということはできない。 したがって、被告による上記表記により、本件プログラム3について、原\n告の氏名表示権が侵害され、その態様から、被告に故意があったと認められ\nる。
・・・
(3)損害の有無及び額(争点3−5、5−4)
(1)の被告の行為により原告の被った損害は、本件に顕れた一切の事情を考 慮し、10万円と認め(なお、原告は、本件プログラム5についての氏名表示\n権侵害固有の損害を主張しないが、弁論の全趣旨から、相当の損害賠償を求め る趣旨と解される。)、被告は、相当因果関係のある弁護士費用1万円を加えた 11万円及びこれに対する遅延損害金を支払う義務を負う。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> 複製
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2024.02.15
令和5(行ケ)10020等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年1月23日 知的財産高等裁判所
クレーム1は「・・外力に対して鋼管杭に生じる曲率が大きい少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分を、前記鋼管杭の直径Dと前記鋼管杭の全塑性モーメントに対応する曲率φpが、φp≧4.39×10−3/Dという関係を満足するものとし、・・・」でした。
(3) 相違点3Aに係る容易想到性についての検討
前記1に認定した本件各発明の概要によると、本件発明3の相違点3Aに係る構\n成は、杭の全塑性の要求性能を満足させようとする際に試みる板厚又は径の増加に\n伴う建設コストの増加との課題に対し、鋼管杭の局所的な変形性能を上げることに\nより解決を図るべく、変形性能の指標として曲率φpを用い、少なくとも陸側に対\n面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分にのみ変形性能の\n高い鋼管杭を用いて、当該鋼管杭が地中部において曲率φpを越えないようにした ものである。
ここで、前記(2)のとおり、甲1発明が属する鋼管杭式桟橋においては、鋼管杭に 高強度鋼管を採用することは周知技術であって、また、本件出願日当時、技術1)(直 杭式横桟橋の性能照査では、杭に発生する応力、杭の支持力、変形量を適切に設定\nして検討すること、杭の断面力は深さ方向に変化し、地中部の深いところでは小さ くなるのが一般的であるため、経済性の観点から鋼管杭の板厚又は鋼種を変更する ことがあること)、技術2)(鋼管杭に生じる軸力及び曲げモーメントに応じて杭の曲 げ剛性を低下させて解析を行うこと)、技術3)(杭の断面力は、深さ方向に変化し、 地中部の深いところで小さくなるため、経済性の観点からは鋼管杭の板厚及び材質 を地中部の発生断面力に応じて変更することが望ましいこと)、技術4)(計画水深が 深い岸壁では、強度の大きいSTK490の鋼管杭を用いている例が多くなるこ と)、技術5)(陸側の地中部において下杭よりも上杭の板厚を大きくすること)及び 技術6)(鋼管杭の部材として、一般に用いられているSKK400及びSKK49 0よりも基準降伏点の高い鋼管杭が、高支持力杭が普及し始めている建築分野にて 商品化されていること)等の技術が公知であったことが認められるが、いずれの技 術によっても、杭の全塑性の要求性能を満足させつつ建設コストの増加を回避する\nため、甲1発明の「鋼管杭」を、変形性能の指標として曲率φpを用いた上で、少\nなくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分 にのみ、局所的に変形性能の高い鋼管杭を用いて、当該部分での発生曲率が曲率φ\npを越えないようにすることは導出できないといわざるを得ないし、このような構\n成を得ることが甲1発明及び上記周知技術又は各公知技術に接した当業者が通常行 うべき試行錯誤の範囲内のものということもできない。 したがって、当業者であっても、甲1発明の「鋼管杭」につき、相違点3Aに係 る構成にすることが容易想到であったということはできず、本件発明3は、甲1発\n明並びに上記周知技術及び各公知技術に基づいて当業者が容易に発明することがで きたものということはできない。
(4) 相違点3Bに係る容易想到性についての検討
本件発明3の相違点3Bに係る構成は、前記(3)のとおり、杭の全塑性の要求性能\nを満足させようとする際に試みる板厚又は径の増加に伴う建設コストの増加との課 題に対し、鋼管杭の局所的な変形性能を上げることにより解決を図るべく、変形性\n能の指標として曲率φpを用い、鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分に\nのみ変形性能の高い鋼管杭を用いて、当該鋼管杭が地中部において全塑性モーメン\nトに対応する曲率を越えないようにしたものである。 甲13発明の「鋼管杭」は、少なくとも陸側の鋼管杭の地中部は、φ1300m m×16tのSKK490からなる上杭の下方にφ1300mm×13tのSKK 400からなる下杭で構成されており、技術3)及び4)によると、上杭部分の強度は 下杭部分よりも大きいといえる。しかし、前記(3)と同様に、前記周知技術及び公知 技術(技術1)〜6))によっても、杭の全塑性の要求性能を満足させつつ建設コスト\nの増加を回避するため、上杭と下杭とからなる甲13発明の「鋼管杭」を、変形性 能の指標として曲率φpを用いた上で、少なくとも陸側に対面して配置された鋼管\n杭の地中部における発生曲率が大きい部分にのみ、局所的に変形性能の高い鋼管杭\nを用いて、当該部分での発生曲率が曲率φpを越えないようにすることは導出でき ないといわざるを得ないし、このような構成を得ることが甲13発明及び上記周知\n技術又は各公知技術に接した当業者が通常行うべき試行錯誤の範囲内のものという こともできない。 したがって、当業者であっても、甲13発明の「鋼管杭」につき、相違点3Bに 係る構成にすることが容易想到であったということはできず、本件発明3は、甲1\n3発明並びに上記周知技術及び各公知技術に基づいて当業者が容易に発明すること ができたものということはできない。
(5) 被告の主張について
ア 被告は、「杭の断面力(曲げモーメントを含む概念である。)は深さ方向に変 化するため、深さや発生断面力に応じ杭の材質・鋼種を変更することがある」との 周知技術が認定でき(技術1)、3)参照)、これは典型的には降伏強度の異なる鋼管杭 を用いることである上、「強度の観点のみならず経済性の観点から鋼管杭の板厚及 び鋼種をその設置位置や部位ごとに変更すること」、「杭全体のうち、大きい曲げモ ーメントがかかる部分についてだけ高降伏強度の鋼管杭を用いること」、「杭に生じ る曲げモーメントが大きい箇所において全塑性モーメントに達しないように設計す ることが望ましいこと」がいずれも技術常識であり、鋼管杭の設計に際しどのくら いの降伏強度の鋼管杭とするかは周知技術に基づき適宜設計されるものだから、相 違点3A又は3Bに係る構成は、周知技術又は技術常識から導出し得る旨主張する。\nしかし、本件審決が説示するとおり、被告は、「強度の観点のみならず経済性の観 点から鋼管杭の板厚及び鋼種をその設置位置や部位ごとに変更すること」や「杭全 体のうち、大きい曲げモーメントがかかる部分についてだけ高降伏強度の鋼管杭を 用いること」が技術常識であることをいかなる証拠の記載から認定できるかを具体 的に指摘していない上、仮に、これらが技術常識であるとしても、これらを組み合 わせる動機付けや、組み合わせた結果からどのようにして相違点3A又は3Bに係 る構成が導出されるかにつき、技術的視点に基づいた具体的な主張をしていない。\nそして、前記のとおり、周知技術及び公知技術(技術1)〜6))によっても、甲1発 明の「鋼管杭」又は甲13発明の「鋼管杭」を、相違点3A又は3Bに係る構成に\nすることは導出できず、そのような構成を得ることが、当業者が通常行うべき試行\n錯誤の範囲内ということもできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> パラメータ発明
>> ピックアップ対象
2024.02.15
令和4(ワ)13396 不正競争 民事訴訟 令和6年1月17日 東京地方裁判所
裁判所は、これを認めて50万円の損害賠償および投稿削除を命じました。
(イ) 前記(ア)の各事実を前提として、本件投稿部分1が摘示する「何度やり とりしても、原告は、被告担当者からの質問に明確に回答しない」との 事実が客観的真実に反するものであるか否かについて検討する。 a 前記(ア)aのとおり、本件アナライザー案件において、被告が仕様の 確定を行うべきとされていたことについては、当事者間に争いがない。 また、本件全証拠によっても、原告が、被告の作成した仕様を評価す る立場にあったと認めることはできない。
そして、前記(ア)cの原告と被告担当者とのやりとりの内容に照らせ ば、原告は、被告担当者からの質問に対し、一貫して、原告が「課題 管理表」の項番13において指摘した事項の趣旨を説明しつつ、本件アナライザー案件において原告が受注していない業務である仕様の評\n価にわたる事項については回答することができないとの趣旨を明確に 回答していると認めるのが相当である。
b また、原告が、被告担当者に対し、「なんで答える必要あるの?」と の文言どおりの回答をしていないことも当事者間に争いがない。 この点に関し、被告は、当該回答は、「今回当方へのご依頼は管理画 面の開発で、くじら IT サービス様でご用意される資料の評価は含まれ ていないという認識です。」との原告の回答を簡潔にまとめた表現であると主張する。\n
そこで検討すると、不競法2条1項21号所定の告知又は流布の内 容は、その相手方の普通の注意と読み方・聞き方を基準として判断す べきと解されるところ、本件サイトは、ソフトウェアやITシステムの開発業務を営んでいる者や、このような開発業務を依頼しようとす\nる者が専ら閲覧していると考えられる。そして、これらの者の普通の 注意と読み方を基準とすると、「なんで答える必要あるの?」との表現は、理由を一切説明することなく、回答を拒否したとの意味に理解で\nきるものである。これに対し、被告が指摘する原告の上記回答は、原 告が受注した業務の内容について説明した上、被告が用意する資料の 評価にわたる事項については回答することができないとの趣旨を回答 するものといえる。 したがって、「なんで答える必要あるの?」との表現は、原告の上記回答を要約したものとはいえず、被告の上記主張を採用することはで\nきない。
(ウ) 以上によれば、本件投稿部分1が摘示する「何度やりとりしても、原 告は、被告担当者からの質問に明確に回答しない」との事実は、客観的 真実に反するもの、すなわち虚偽のものと認められる。
・・・
(1) 無形損害について
前記1(2)のとおり、ソフトウェアやITシステムの開発において、受注者が、発注者との質疑応答に適切に対応できる資質や能\力を備えているか否かは、受注の可否にも直結する重要な事柄であると考えられるところ、本件投 稿部分1が摘示する事実は、これを閲覧した者に対し、原告がそのような資 質や能力を欠くとの印象を与えるといえるから、本件投稿は、原告の営業上の信用を大きく毀損するものと認められる。\nそして、前記1(1)イのとおり、原告の納品した成果物が、被告と合意した 仕様に合致するものであることについての立証がされているとはいえず、本 件投稿部分2及び3について不正競争及び不法行為が成立するとは認められ ないものの、被告は、成果物が仕様に合致していないことを意味する他の表現を採用することは極めて容易であると考えられるのに、「ゴミを納品され、\n捨てました。」と、原告による作業や成果物が有する価値のすべてを否定する かのような表現を敢えて用い、同業者が多数閲覧する可能\性のあるインター ネット上のマッチングサイトの評価画面に本件投稿をしたものであるところ、 不正競争に該当する本件投稿部分1と上記の表現とが一連一体のものとして本件投稿を構\成している以上、無形損害の額を算定するに当たり、この事情も考慮することができるというべきである。 以上の事情によれば、本件投稿によって原告に生じた無形損害の額につい ては、50万円と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 営業誹謗
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.02.15
令和5(ワ)6100 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和6年1月30日 大阪地方裁判所
(1) 氏名権侵害について
氏名は、個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものというべきで\nあるから、人は、その氏名を他人に冒用されない権利を有する。 前提事実(3)並びに証拠(甲5〜9)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件 アカウントを通じて本件各投稿を行っているところ、本件投稿1では、本件アカウ ントにおける名前(原告の氏名である「P1」)及びユーザー名(原告が経営する 法人グループの総称である「(省略)」)が表示されており、本件投稿2ないし4\nでは、「P1」がリツイートした旨が表示されていることに加え、所定の操作によ\nり本件アカウントにおける名前等が表示されることが認められ、本件各投稿に接し\nた閲覧者は、投稿者として原告の氏名を認識するものと認められるから、被告は本 件各投稿において原告の氏名を冒用したといえる。したがって、本件各投稿は、原 告の氏名権を侵害する。 被告は、本件アカウントのプロフィール欄には「フィクションのため実在の人物 とは一切関係がございません」と記載されているから、閲覧者は、実在の人物とは 関係がないとの結論に至り、原告本人ではないと認識をする可能性がある旨を主張\nする。しかし、閲覧者は、アカウントに表示された氏名やユーザー名によって投稿\n者を特定するものと解されるから、被告指摘の記載があったとしても、閲覧者は、 原告がその旨を記載していると理解するにすぎず、前記判示に影響を与えるもので はない。被告の前記主張は採用できない。
(2) 本件著作権の侵害について
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美\n術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいう。 本件イラストは、P3氏が、ツイッター上の交流において原告を表すためにふさ\nわしいイラストとして制作したものであり、腹ばいになるアザラシの様子をイラス トにし、その下部に「(省略)」と記載したものであるところ、全体的に丸みを帯 びた輪郭で、頭部を大きくし、ヒレを頭部付近に小さく描くことにより、親しみや すくかわいらしい印象を与えている点、大きな頭部いっぱいに両目、鼻及び口を描 くことでアザラシの表情に存在感を与えている点、これらに「(省略)」という表\ 記を欧文字で加えることで、その性格(原告の人柄)を示しつつイラストとしての 一体感を感じさせる点において、選択の幅がある中から作成者によってあえて選ば れた表現であるということができる。したがって、本件イラストは、作成者の思想\n又は感情が創作的に表現された、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えたもの\nであると認められ、「著作物」に該当する。 証拠(甲20、21)及び弁論の全趣旨によれば、P3氏は、本件イラストを制 作し、原告に対し、本件イラストに係る著作権を譲渡したことが認められ、原告 は、本件イラストに係る著作権を有していると認められる。 本件黒塗りイラストは、本件イラストの両目部分に黒の横線が入れられ、「(省 略)」という表記が黒塗りされたものであるが、被告がかかる改変を行ったことを\n認めるに足りる証拠はない。一方、前記改変は、前記目線等を加えたことに限られ るから、本件黒塗りイラストは、本件イラストに依拠し、かつ、その表現上の本質\n的な特徴の同一性を維持しつつ、これに接する者が本件イラストの表現上の本質的\nな特徴を直接感得することができるものと認められ、本件黒塗りイラストは本件イ ラストの複製物又は翻案物であって、原告が著作権を有するものといえる。そうで あるところ、被告は、本件各投稿によって、本件黒塗りイラストに改変等を加える ことなくツイッター上に投稿して、少なくとも不特定の者に対して閲覧可能な状態\nにしたことから、本件各投稿は、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害す るといえる。
・・・
(4) 名誉感情侵害について
本件投稿1について検討するに、本件投稿1は、原告の氏名及び原告が経営する 法人グループの名称を表示するとともに、その存在はフィクションであり、実在の\n団体人物とは関係がない旨が記載されたものであるところ、一般閲覧者の普通の注 意と読み方を基準として判断した場合、本件投稿1に接した閲覧者は、原告自身が 原告や(省略)とは関係がない旨を投稿したと認識するものと認められる。したが って、本件投稿1は、閲覧者に対し、原告は趣旨不明な投稿をする人物であるとの 印象を与え、原告の名誉感情を侵害するものといえる。被告は、本件各投稿は司法 書士として品位に欠ける言動をやめさせる公益目的で行った旨主張するが、仮にそ のような目的があったとしても、原告になりすまして本件投稿1を行うことが正当 化される理由にはならない。 本件投稿2ないし4について検討するに、原告は、被告がP4アカウントを作成 したことを前提として、本件投稿2ないし4の閲覧者は、原告があたかもP4氏の 名誉権を侵害したり、プライバシー権を侵害したりする投稿を平気で行う人物であ ると受け止めることから、これらの投稿は原告の名誉感情を侵害する旨を主張す る。しかし、被告がP4アカウントを作成したことを認めるに足りる証拠はない。
また、P4アカウントによる投稿に接した閲覧者は、P4氏が自身のアカウントで 投稿していると認識するものと認められるところ、仮に被告が同氏になりすまして P4アカウントを作成し投稿していたとしても、P4アカウントによる投稿をリツ イートすること自体によって、直ちに同氏の名誉権やプライバシー権が侵害される ことにはならないから、原告の前記主張はその前提を欠く。そして、本件投稿2 は、名前を「P4」、ユーザー名を「(省略)」とするP4アカウントによる「ば ればれだよ。ことP4です。」という投稿を本件アカウントでリツイートしたもの であるところ、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断した場合、本件 投稿2に接した閲覧者は、P4氏が自身のユーザー名及び氏名を紹介した投稿に対 して原告が注目し閲覧者に伝えようとしたと認識するものと認められる。したがっ て、本件投稿2は、原告の名誉感情を侵害するものとはいえない。また、本件投稿 3及び4は、P4アカウントによる「ネコではなくタチのP4です。」及び「バリ タチのP4です。」という投稿を本件アカウントでそれぞれリツイートしたもので あるところ、「ネコ」、「タチ」及び「バリ」が同性愛者を指す用語として用いら れることがあること(甲19)を踏まえ、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準 として判断した場合、本件投稿3及び4に接した閲覧者は、P4氏が自身が同性愛 者であることを摘示した投稿に対して原告が注目し閲覧者に伝えようとしたと認識 するものと認められる。したがって、本件投稿3及び4は、原告の名誉感情を侵害 するものとはいえない。
(5) 以上から、本件各投稿は原告の氏名権及び本件著作権(複製権及び公衆送 信権)を侵害し、本件投稿1は原告の名誉感情を侵害するものとして、不法行為を 構成する。\n
2 争点2(損害の発生及びその額)について
前記1認定の本件各投稿による権利侵害の内容及び態様の一切を考慮すると、本 件各投稿により、原告が被った精神的苦痛を慰藉する金額は、15万円が相当と認 められる。ただし、原告は本件イラストの著作者ではなく、本件著作権(複製権及 び公衆送信権)侵害により原告に精神的苦痛が生じたとは認めるに足りない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2024.02. 9
令和5(ワ)73 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年12月14日 大阪地方裁判所
原告ソール1が、合成樹脂を用いた厚底ソ\ールであり、原告主張の特徴1な いし特徴4の形態を備えていること、一部の溝の形状が略コの字状となってい ることについては、当事者間に争いがない。そこで、これらの形態やその組み 合わせが、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴といえるか、以下検討 する。
ア 合成樹脂を用いた厚底のソールであるとの形態について\n証拠(乙20)によれば、イタリアのVibram社(ソールのメーカー)\nが、原告商品1の販売の相当前である昭和59年(1984年)にカジュア ルシューズ向けの合成樹脂(EVA)製の超軽量ソールの製造を開始したこ\nとが認められるところ、合成樹脂製のソールの厚みを厚くすることが製造技\n術上困難であるような事情は見当たらない(令和5年7月時点では、複数の 他社から合成樹脂製の厚底ソールを使用した婦人靴が販売されていた(乙2\n1、22)。)。そうすると、合成樹脂を用いた厚底ソールである形態が、従来\nの同種商品と異なる形態とはいえない。
イ 特徴1(靴底裏面に複数の縦溝1及び横溝2、3を有することで、裏面視 において全体として略格子状のイメージを奏すること)について
証拠(乙7の1、7の3ないし7の6)によれば、原告商品の販売開始前 に、複数の他社から靴底裏面に複数の縦溝と横溝が施されて全体として略格 子状の形態の靴底の意匠登録出願がされ、その後、いずれも意匠登録がされ たことが認められるから、特徴1の形態はありふれた形態というべきである。 また、ソールの溝の深さを深くすることによって排水機能\や防滑機能が実現\nされることは一般的な知見といえる(乙8)から、特徴1の形態は技術的機 能に由来する形態といえる。\n
ウ 特徴2(靴底裏面の前方部分に、i)左右一対の2本の前記縦溝1と、i i)左右端から形成され前記各縦溝1とそれぞれ交差し、先端(中央側端部) 同士が対向する左右3対の前記横溝2と、iii)前記左右3対の横溝2よ りもつま先側において左端から右端にかけて形成される横溝3とが配され ていること)について
証拠(乙7の1、7の4、7の5)によれば、原告商品の販売開始前に、 複数の他社から靴底裏面の中央より前方(つま先)部分に概ね2本の縦溝と、 左右端から形成され上記縦溝と交差し、先端同士が対向する左右3ないし5 対の横溝と、同横溝よりつま先側において左端から右端に形成される横溝と が配された靴底の意匠登録出願がされ、その後いずれも意匠登録されたこと が認められる。また、上記横溝の数を原告ソール1の「横溝2」のように3\n対とすることに特別な意義があると解する理由は見当たらない。そうすると、 特徴2の形態は、ありふれた形態というべきである。また、特徴2の形態は、 上記イと同様の理由から、技術的機能に由来する形態ともいえる。\n
エ 特徴3(靴底裏面において、つま先部分から指の付け根に相当する部分に、 横方向に伸びる畝状の複数の段部4を有し、この段部4が、後方につれて裏 面側に傾斜するテーパー面4aを有すること)について 証拠(乙7の4、7の6、10の1、10の5)によれば、原告商品の販 売開始前に、複数の他社から、1)つま先から指の付け根付近に複数の横方向 の段部が配され、2)この段部が後方につれて裏面側に傾斜するテーパー面を 有する靴底の意匠登録出願がされ、その後いずれも意匠登録されたことが認 められる(ただし、乙7の4の登録意匠の靴底には、上記2)の構成は含まれ\nていない。)。そうすると、特徴3に係る形態は、ありふれた形態というべき である。
オ 特徴4(靴底裏面において、踵に相当する部分に、横方向に伸びる畝状の 複数の段部5を有し、この段部5が、後方につれて表面側に傾斜するテーパ\nー面5aを有すること)について
証拠(乙7の4、10の5)によれば、原告商品の販売開始前に、複数の 他社から、靴底裏面の踵に相当する部分に横方向に伸び、後方につれて表面\n側に傾斜するテーパー面を有する複数の段部が配された靴底の意匠登録出 願がされ、その後いずれも意匠登録されたことが認められる。そうすると、 特徴4に係る形態は、ありふれた形態というべきである。
カ 一部の溝の形状が略コの字状となっているとの形態について 当該形態は、原告の主張によっても、原告代表者の名字の頭文字「F」を\nなぞったデザインの一つにすぎない。また、当該形態が施された範囲は、親 指から薬指にかけた部分及び小指部分であって、原告ソール1全体の約6分\nの1程度と非常に狭く(甲5)、需要者が着目するとは解し難い。
キ 以上によれば、原告ソール1の形態は、客観的に他の同種商品とは異なる\n顕著な特徴を有するとはいえないから、原告ソール1の形態に特別顕著性が\nあると認めることはできず、原告の主張は理由がない。
(3) 周知性又は著名性について
なお、周知性について、念のため検討する。 原告は、原告商品の販売開始後、1)平成30年以降に複数の展示会に原告商 品を出展したことや、2)多数の業界雑誌や業界外雑誌に原告商品が紹介された こと、3)国内直営店舗や複数のECサイトで原告商品が販売されたこと、4)平 成28年以降の原告の靴製品の売上高が伸び、業界内で上位となったことなど から、原告ソール1が令和2年秋頃には周知になったと主張する。\n しかしながら、そもそも原告主張の原告商品の販売開始時期をその通り認定 できないことは前記のとおりであるが、原告ソール1の需要者は、婦人靴の購\n入を検討する一般消費者(及びその取引業者)であるところ、当該需要者は、 靴全体のデザイン(中でも人目を引くアッパーの部分)や着用感に着目し、仮 にソールに注意を払うとしても、その注意はおおむね機能\的な観点で向けられ るものと解され、ソールの形態や材質それ自体から出所を認識するとの一般的\nな経験則は認め難いものと解されるから、原告主張の事情は直ちに原告ソール\n1が周知であることを基礎づけるものではない。
その上で検討すると、上記1)については、各展示会に原告商品が出展された としても、原告ソール1がどのように展示されていたかは明らかではない。\n上記2)については、令和2年5月号から令和4年1月号の業界雑誌「フット ウェア・プレスFW」には原告ソール1の画像が掲載されているが(甲22の\n2ないし22の22)、同誌は一般消費者向けの媒体としての性質は薄いもの と認められるうえ、原告商品が掲載された業界外雑誌(甲26、28、30(い ずれも枝番を含む。))は、大半において通信販売の媒体としてのものであって、 商品それ自体を紹介するものとは性質を異にするうえ、原告ソール1は掲載さ\nれておらず、掲載されている場合でも掲載範囲は小さく(甲24の1ないし2 4の4、26の1ないし26の4、28の1、28の2、30の1、30の2、 32)、需要者が原告ソール1の形態に着目するとは解し難い。\n上記3)については、原告の国内直営店舗数は10店舗にとどまる(甲53)。 また、複数のECサイトに原告ソール1を用いた商品が掲載されているが、原\n告ソール1の画像が掲載されていない例も多数存在するうえ、掲載されている\n場合も、複数の商品画像中の3枚目以降に掲載されているから、需要者が原告 ソール1の形態に着目するとはいえない。また、ECサイトに掲載された原告\nソール1を用いた商品は、原告とは異なる他社ブランド名で販売されているも\nのが多く、このような掲載方法によって、掲載されたソールが原告のソ\ールで あると需要者が認識するとはいえない(甲44の1ないし47の6、弁論の全 趣旨)。
上記4)については、原告の主張を前提としても、業界内における売上高が 極めて上位にあるものとはいえない。 以上によれば、原告ソール1の形態が周知であると認めることはできず、\n他に、本件証拠上、原告ソール1の形態が周知性又は著名性を有すると認め\nるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2024.02. 9
令和4(ワ)9818 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和5年12月19日 大阪地方裁判所
2 本件商標の法3条1項3号に基づく無効理由の有無(争点1)について
(1) 本件商標が、その指定商品について商品の用途を普通に用いられる方法で 表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件査定日(令和4年2月28日)の時点において、当該商標が当該商品との関係で商品の用途を表\示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者によって当該商品に使用された場合に、将来を含め、商品の用途を表\示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。そして、当該商標の取引者、需要者に よって当該商品に使用された場合に商品の用途を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構\成やその指定商品に関する取引の実情を考慮して判断すべきである。
(2)ア 本件商標は、「熱中対策応急キット」の文字を標準文字で表してなり、本件商標を構\成する文字は、同じ大きさ及び書体で、等間隔かつ横一列にまとまりのある態様で並べられている。そうすると、本件商標は、取引者及び需要者に、こ れを構成する文字の全体をもって、一連一体の語を表\すものとして理解されると考 えられる。
イ 本件商標中の「熱中」、「対策」、「応急」及び「キット」の4つの語は、 それぞれ、「物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、熱烈に思う こと。」、「相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。」、「急場のまにあわ せ。」、「組立て模型などの部品一式。工具・用具一式。」といった意味を一般に 有するところ(いずれも広辞苑第七版、平成30年1月発行)、これらの語を字義 どおりに捉えると、「熱中対策応急キット」の語全体から、熱中症の対策又は応急 処置に用いる物品ないしそれらをバッグに入れて一まとめにしたものといった意味 合いが直ちに導かれるものではない。 もっとも、「熱中」との語は、「熱中症」との3文字の語のうち、「症状」を示 すものと解される「症」の文字を除く2文字と一致しており、「熱中症」との語の 一部を示すものとみても不自然とはいえない。
ウ 取引の実情をみると、前記認定事実のとおり、「熱中対策応急キット」との 標章が付された商品(本件商標に係る商品の区分ごとに本件指定商品と同一又は類 似の商品を含んでいるもの)は、平成24年頃から本件査定日(令和4年2月28 日)までに、ミドリ安全を中心とする多数の法人(被告を含む。)において、熱中 症に応急的に対応するための物品一式として広告販売されている状況が認められる。 一方、前記イの「熱中」の語の意味(物事に心を集中すること。夢中になってする こと。また、熱烈に思うこと。)を踏まえて、これに対応するといった用途に用い られる商品が、「熱中対策応急キット」ないし「熱中対策」との標章を付して広告 販売されている事実を認めるに足りる証拠はない。なお、原告も、平成31年(令 和元年)から、熱中症に対応するための物品一式が収納されたポーチに「熱中対策 キット」との標章を付して広告販売している上、令和5年には、熱中症に応急的に 対応するための物品一式がポーチに収納された「熱中対策応急キット」との名称の 商品の広告販売を開始している(前記認定事実(7))。
エ 以上を総合すると、「熱中対策」の語は、本件査定日の時点で、「熱中症対 策」との意味でも一般的に理解され、「熱中対策応急キット」の語は、熱中症の対 策又は応急処置に用いる物品一式ないしそのような物品を含む商品との意味を有す ることが一般に認識されていたことが認められる。そして、本件指定商品は、熱中 症の対策又は応急処置に用いる物品ないしそれらを収納するポーチ等(それらの全 部又は一部を組み合わせたものを含む。)の商品に含まれると認められるところ、 標準文字で表される「熱中対策応急キット」との本件商標がかかる商品に使用された場合、当該商品の取引者又は需要者によって、当該商品の用途を示すものとして\n一般に認識される状態となっていたといえる。そうすると、「熱中対策応急キット」 との本件商標は、指定商品に使用された場合、商品の用途を普通に用いられる方法 で表示する標章のみからなる商標として、法3条1項3号に該当するものと解するのが相当である。\n
(3) したがって、本件商標は、法3条1項3号に違反して登録されたものであ り、無効審判により無効とされるべきものであるから、原告は、被告に対し、本件 商標権を行使することができない(法46条1項1号、39条、特許法104条の 3第1項)。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2024.02. 9
令和5(行ケ)10072 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和5年12月14日 知的財産高等裁判所
前記第2の1の事実によれば、本願は、日本国を指定締約国とする国際出願 であって、令和3年1月22日、本件国際登録について、ジュネーブ改正協定10 条(3)(a)の規定による公表がされた(乙3の1・2)ことにより、意匠法60条の6第1項の規定により、本件国際登録の日である令和元年9月9日にされた意匠登\n録出願とみなされる(なお、原告は在外者であるから、意匠法68条2項において 準用する特許法8条1項の規定により、出願に係る補正書や意見書の提出その他の 手続を行う場合には、意匠管理人を選任して行う必要があったことになる。)。
(2) ジュネーブ改正協定12条(1)本文によれば、指定締約国の官庁は、国際登録 の対象である意匠の一部又は全部が当該指定締約国の法令に基づく保護の付与のた めの条件を満たしていない場合には、当該指定締約国の領域における国際登録の一 部又は全部の効果を拒絶することができる。国際登録の効果を拒絶する場合、指定 締約国の官庁は、所定の期間内に国際事務局に対しその拒絶を通報し、国際事務局 は、名義人に拒絶の通報の写しを遅滞なく送付する(12条(1)、(2)(a)、(3)(a))。 同条(2)の「拒絶」は、拒絶の最終決定を意味するものではないと解されており、指 定締約国の官庁に要求されているのは、保護拒絶の原因となり得る理由を表示することだけである(乙5)。そして、拒絶の通報の対象となった名義人は、拒絶を通報\nした官庁に適用される法令に基づいて保護の付与のための出願をしたならば与えら れたであろう救済手段を与えられ、救済手段は、少なくとも拒絶の再審査若しくは 見直し又は拒絶に対する不服の申立ての可能\性から成るものとされている(12条 (3)(b))。指定締約国を日本とした場合、拒絶の通報は、国際登録の公表日から12か月以内にされることになる(乙4、5)。\n
ジュネーブ改正協定上、このような「拒絶の通報」をすること及びこれに対する 指定締約国の国内法令に基づく救済手段を与えるべきことを超えて、指定締約国に おける最終的な拒絶査定の告知方法や不服申立ての手続等(これらの事項は、ジュネーブ改正協定12条(1)ただし書の「国際出願の形式若しくは記載事項に関する 要件」には該当しないと解される。)について定めた規定は見当たらない。したがっ て、これらの点については、ジュネーブ改正協定上、指定締約国の国内法に委ねら れていることになる。前記のとおり、日本の意匠法によれば、本願は、日本の意匠 法に基づく意匠登録出願とみなされるのであるから、これに対する最終的な拒絶査 定の通知方法や不服申立て手続等も意匠法によるべきものと解される。
(3) しかるところ、本件において、特許庁は、本願について、令和3年10月2 2日に国際事務局に対し、「III) 拒絶の理由」の標題を付して具体的な拒絶の理由を 明らかにした本件拒絶の通報を発送しており(甲9)、国際事務局は、同年11月5 日、WIPOのウェブサイトにおいて、本件拒絶の通報を掲載した(乙3)。本件拒 絶の通報には、「国際登録の名義人は、この通報を発送した日から3か月以内に、「III)拒絶の理由」について、意見書を提出することができます。審査官は意見書の内容 を考慮し、保護を付与するかどうかについて決定いたします。なお、日本国内に住 所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者は、日本国内に住所又は居所 を有する代理人によらなければ、日本国特許庁に対して手続をすることはできませ ん。」旨の英文の記載があり、本件拒絶の通報に付された注意書(Appendix)にもこ れと同旨の記載のほか、関連する意匠法の条文の英訳も記載されていた(甲9)。
(4) しかし、原告は、本件拒絶の通報後に意見書を提出せず、特許庁は、令和4 年4月5日付けで本件拒絶査定をした(甲10)。原告は、在外者であり、意匠管理 人を選任していなかったことから、特許庁は、意匠法68条5項において準用する 特許法192条2項の規定により、本件拒絶査定の謄本を、令和4年4月8日、航 空扱いとした書留郵便により発送した(甲10、乙6、7)。この結果、同条3項の 規定により、当該謄本は、発送の時に送達があったものとみなされた。当該書留郵 便は、同月10日には米国の国際交換局に到着していたが、同年9月21日までの 間、同局に保管され、原告に配達されたのは同月26日であった(甲1、2)。
(5) 意匠法上、拒絶査定に対する不服審判請求は、その査定の謄本の送達があっ た日から3月以内にしなければならない(意匠法46条1項)。本件拒絶査定の謄本 は、令和4年4月8日に原告に送達されたものとみなされたから、原告は、その日 から3か月以内に不服審判請求をすべきであったところ、本件審判請求期間が経過 した後である同年11月18日に本件審判請求をしたものである。
2 以下、本件審判請求期間内に原告が本件審判請求をすることができなかった ことについて、意匠法46条2項の「その責めに帰することができない理由」があ ったかどうかについて検討する。
(1) 原告は、本件拒絶査定の謄本を原告が現実に受領した令和4年9月26日に 本件拒絶査定がされているのを知ったのであり、本件審判請求期間の経過後に本件 審判請求をすることになった原因は郵便の配送遅延にあるから、原告の責めに帰す ることができない理由があると主張する。
しかし、そもそも意匠法68条5項において準用する特許法192条3項の規定 によれば、法律上、原告は現実に受領していなくても本件拒絶査定の謄本の発送の 時である令和4年4月8日に当該謄本の送達を受けたものとみなされるのであるか ら、意匠法46条2項の原告の責めに帰することができない理由の有無は、原告が 同日に当該謄本の送達を受けたことを前提にした上で検討されるべき問題である。 原告が現実に当該謄本を受領した日が本件審判請求期間後であったことや、その理 由が郵便の配送遅延にあったこと(ただし、当該謄本に係る書留郵便が同年4月に 米国交換局に到着した後、同年9月まで原告に配達されなかった理由は、証拠上明 らかではない。)があったとしても、これらの事情が存在することをもって直ちに原 告に「その責めに帰することができない理由」があると解することはできない。な ぜなら、これらの事情は、みなし送達を定めた法の前記規定の想定範囲外の事態で あるとは考えられない上、仮に、在外者の場合にこれらの事情のみをもって「その 責めに帰することができない理由」になると解したときは、拒絶査定の謄本が現実 に審判請求期間内に配達されなかったときは、同項所定の期間内(当該理由がなく なった日から2か月以内で、同条1項の期間の経過後6か月以内)であれば、常に 拒絶査定不服審判を請求することを認めるのと実質的に同じ結果になるからである。 このような解釈は、拒絶査定の謄本等の書類の発送の時に送達を受けたものとみな し、法律関係の安定を図る法の趣旨に反するものであるから、採用することができ ない。同条2項の「その責めに帰することができない理由」とは、通常の注意力を 有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認め られる事由により審判請求期間内に請求することができなかった場合をいうのであ り、原告が令和4年4月8日に法律上、本件拒絶査定の謄本の送達を受けたことを 前提としたとき、本件審査請求期間の末日である同年7月8日までに原告が通常期 待される注意を尽くしてもなお本件審判請求をすることが困難であったことを示す ような客観的な事情は見当たらない。したがって、原告の責めに帰することができ ない理由の存在を認めることはできない。 それのみならず本件においては、前記1のとおり、本件国際登録の公表から12か月以内に拒絶の通報がされる可能\性があることは、ジュネーブ改正協定により国際出願を行った以上、原告又はその代理人において当然知り得たはずである。また、 少なくともWIPOのウェブサイトには本件拒絶の通報が掲載されていたから、原 告は、同ウェブサイトを確認することにより、本件拒絶の通報がされていることを 知り、日本国の意匠法に従って拒絶査定が行われるであろうことを容易に予測することができたはずである。それにもかかわらず、原告は、これらの点に注意を払う\nことなく、本件審判請求期間内に本件審判請求をしなかったのであるから、原告が、 意匠登録出願人として、通常の注意力を有する当事者に通常期待される注意を尽く していたと認めることはできない。
(2) 原告は、意匠法46条2項の文言から、法定の期間内(同条1項の期間内) に審判請求をする機会が与えられるに至った経緯については問われていないことが 明らかであると主張する(取消事由1)。原告の主張する「法定の期間内に審判請求 をする機会が与えられるに至った経緯」の意味は、必ずしも明らかではないが、同 条1項によれば、原告は本件拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に不 服審判を請求することができ、同法68条5項において準用する特許法192条3 項の規定によれば、法律上、原告は本件拒絶査定の謄本の発送の時である令和4年 4月8日に当該謄本の送達を受けたものとみなされる。したがって、本件における 意匠法46条2項の「前項に規定する期間」は、その日から3か月以内の期間であ る。しかるところ、同項の解釈上、当該期間中に原告が本件拒絶査定を受けたとい う事実を知らなかったというだけで同項の「その責めに帰することができない理由」 に該当すると解することはできない一方、当該理由の存否の判断に当たり、原告が 本件拒絶査定のされたことを知ることができる事実的状況にあったことを考慮する ことは、何ら同項の文言及びその趣旨に反するものではない。そして、これらの点 を考慮した上で本件審判請求期間を徒過したことにつき原告の責めに帰することが できない理由の存在が認められないことは、前記(1)のとおりであるから、原告の主 張は採用することができない。
なお、原告代表者の宣誓供述書(甲1)によると、原告は、令和3年10月頃に、知的財産ポートフォリオの管理を、A氏の法律事務所からScheefに移管した\nが、その際、A氏が、本願について、数年先の更新期限まで更なるアクションをす る必要がない旨の引継ぎをしており、このことが、原告又はScheefをして、 本件拒絶査定を受ける可能性があることを認識しなかった原因であることがうかがえる。しかしながら、前記1のとおり、本願については、国際公表\後に特許庁がその登録を拒絶する可能性があり、このことはジュネーブ改正協定の規定上明らかであったのであるから、上記引継ぎ内容は誤りであったというべきである。A氏及び\nScheefには、知的財産の管理者として意匠の国際登録に係る手続に精通すべ きところ、これを怠っていたために上記誤りに気が付かなかったという過失がある。 また、日本国内の手続において、在外者に意匠管理人がいない場合には、書留郵便 等により拒絶査定の謄本が送達され、発送の時に送達があったものとみなされるこ とは、意匠法の規定上明らかであるから(意匠法68条5項において準用する特許 法192条2項、3項)、A氏及びScheefは、現実に本件拒絶査定の謄本を受 領するよりも前に、送達の効力が生じることを認識し、それに備えるべきであった ところ、これを怠ったという過失もある。そして、原告は、自らの経営判断により、 A氏及びScheefに対し、本願に係る管理を委任していたのであるから、A氏 及びScheefの過失があったことは、本件において原告の責めに帰することが できない理由の存在は認められない旨の前記判断を左右するに足りるものではない。
(3) 原告は、本件審決の判断について、意匠法68条5項において準用する特許 法192条2項の規定に基づいて拒絶査定の謄本が書留郵便等により在外者に発送 された場合には意匠法46条2項の適用は認められないと述べているのに等しく、 法的根拠を欠くとも主張する(取消事由2)。しかし、拒絶査定の謄本が書留郵便等 により在外者に発送された場合には、みなし送達により原告が現実に謄本を受領し ていなくても発送日から同条1項に定める法定の期間が開始することになるだけで、 この場合に同条2項の適用が排除されるわけではない。当該法定の期間内に拒絶査 定不服審判請求をすることができないような客観的な事情があるときなど、なお期 間の徒過につき審判請求人の責めに帰することができない理由が存在することはあ り得る。すなわち、同法68条5項において準用する特許法192条2項の規定に 基づく拒絶査定の謄本の発送がされた場合に、意匠法46条2項を適用して不変期 間の例外が認められる余地がなくなるなどということはできない。したがって、原 告の主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 意匠その他
>> 特許庁手続
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2024.02. 9
令和5(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年11月22日 知的財産高等裁判所
前記(2)のとおり、本願発明は、患者が医師の診察を受ける際に、前回処方 された医薬品が患者の元に残っている場合であっても、医師がこれを考慮す ることなく、診察の日を起算日として医薬品の投与期間を定めて処方をして いたことを課題として、これを解決するため、処方箋に「患者保有分」の項 目、すなわち患者が保有している医薬品に関して記載する項目を設け、既に 患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法の 発明であって、これによって、重複処方を防止する効果が得られるとされる ものである。
しかしながら、本願発明のうち、「処方箋」の記載事項は、医師法施行規則 21条で規定されているから、「分量、用法、用量」の記載は法令に基づく規 定、すなわち人為的な取決めと解され、したがって、「分量、用法、用量」と して記載される「投与日数」も人為的な取決めであり、本願発明において、 処方箋に「投与日数」として「患者保有分」の項目を設けることもまた、処 方箋に医師が記載する事項を定めた人為的な取決めにすぎず、自然法則を利 用したものであるとはいえない。 また、本願発明は、患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与 期間を算定する方法として、パターン1及びパターン2に分け、さらにパタ ーン1についてイ、ロa・b・c、パターン2についてイa・b・c、ロa・ b・cにそれぞれ分けて、算定方法を具体化しているが、いずれの算定方法 も、医師が患者に対して医薬品を処方し、投与する際の投与期間の算定の方 法を定めた人為的取決めであって、自然法則を利用したものであるとはいえ ない。 以上によれば、本願発明は、全体として人為的な取決めであって、自然法 則を利用したものとはいえないから、特許法2条1項にいう「発明」には該 当しない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)ないし(4)のとおり、本願発明は、 人為的な取り決めではなく、自然法則を利用したものであると主張する。 しかし、原告が指摘する内容のうち、医薬品の重複なく投与日数と服用 日数が一致することが継続することで自然法則が成り立つとの点は、本願 発明による投与期間の算定を行うことによる結果を述べているにすぎず、 投与期間の算定方法自体が人為的な取決めであって自然法則を利用した ものではないとの結論を左右しない。 また、1年が365日であることについても、これが自然法則に該当す るか否かの問題を措くとしても、本願発明は1年が365日であることを 前提に医薬品の投与日数の算定方法を決めたというにすぎず、1年が36 5日であることを利用して何らかの技術的手段を示したものとはいえな いから、これによって、本願発明が自然法則を利用したものと解すること はできない。
さらに、電子処方箋の時代を想定して、本願発明の算定方法をPC用プ ログラムにして医師のパソコンに取り込んで医薬品及び受診予\約日を入 力すれば自動で処方箋が完成するとの点については、そもそも本願明細書 等には「処方箋」が「電子処方箋」であることについての記載も示唆も一 切ないし、「PC用プログラム」に関する記載も示唆も一切ないから、「電 子処方箋」及び「PC用プログラム」に関する原告の主張は本願発明と関 係がないというべきである。 最後に、本願発明の場合分けによれば医師の判断が入る余地がないとの 点についても、人為的な取決めである本願発明を結果として医師の判断部 分が減少するというにすぎず、この主張によって、本願発明が自然法則を 利用したものであると解すべき理由にはならない。
イ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(2)及び(4)のとおり、本願発明が画 期的なものであるから特許として認められるべきであると主張する。 しかし、ある発明が画期的であることによって当該発明が自然法則を利 用したものと解されることにはならず、特許法2条1項の「発明」に該当 するとの結論が導かれることはない。
2024.02. 9
令和5(ワ)70056 差止等請求事件 その他 民事訴訟 令和5年11月30日 東京地方裁判所
被告らは、「エンリケ」という用語はスペイン語又はポルトガル語の男性名 に使用される一般用語であり、原告が著名であるとしてもキャバクラのホステ スという狭い世界で著名性を有するにすぎないため、原告の名称には顧客吸引 力がない旨主張する。
しかしながら、前記前提事実並びに証拠(甲1、16ないし18,21、2 2)及び弁論の全趣旨によれば、1)原告は、キャバクラでホステスの仕事をし ていたところ、次第に売上げを稼ぐことができるようになり、平成29年には 2日間で1億円以上、平成30年には3日間で2億5000万円以上、令和元 年には引退式4日間で5億円を、それぞれ売り上げた旨周知されたこと、2)原 告は、平成30年には「日本一売り上げるキャバ嬢の指名され続ける力」とい う書籍を、平成31年には「日本一売り上げるキャバ嬢の億稼ぐ技術」という 書籍を、令和2年には「結局、賢く生きるより素直なバカが成功する 凡人が、 14年間の実践で身につけた億稼ぐ接客術」という書籍を、次々に出版し、令 和3年には著書累計15万部を突破したこと、3)さらに、原告は、あらゆる職 業に役立つコミック実用書として、令和3年には、上記「日本一売り上げるキ ャバ嬢の億稼ぐ技術」をコミック実用書として出版し、全ての仕事に通じる稼 ぐ技術を広く紹介したこと、4)原告は、伝説のキャバクラ嬢として、テレビの バラエティ番組にも出演するようになり、平成21年から令和4年にかけて2 0本以上のテレビ番組に出演したこと、5)原告のインスタグラムでは、令和5 年2月4日時点におけるフォロワー数が66万人を超えていること、以上の事 実が認められる。
上記認定事実によれば、原告は、被告らの主張するような一キャバクラ嬢に とどまらず、書籍を多数出版しテレビにも多数出演しフォロワー数も極めて多 く、日本一稼いだ伝説のキャバクラ嬢として、世の中に広く認知されているこ とが認められる。 これらの事情を踏まえると、原告名称又は原告肖像には、商品の販売等を促 進する顧客吸引力があるものと認めるのが相当である。 したがって、被告らの主張は、いずれも採用することができない。
(2) 被告らは、当裁判所の釈明にかかわらず、ピンク・レディー判決にいう3類 型該当性につき反論しないものの、念のため、以下検討する。 前記前提事実及び前記認定事実によれば、原告名称及び原告肖像には、商品 の販売等を促進する顧客吸引力があるところ、原告名称及び原告肖像の掲載態 様等を踏まえると、被告らが提供する全てのサービスに共通してエンリケとい うブランド価値を全面に押し出していることからすれば、被告らは、エンリケ 空間にあっては内装の設計等の事業につき、エンリケスタイルにあってはエス テティックサロンの経営等の事業につき、エンリケスタッフにあっては労働者 派遣事業等の事業につき、上記顧客吸引力により他の同種事業に係るサービス との差別化を図るために、商号、標章、ウェブページ、ドメイン名において原 告名称又は原告肖像を付したものと認めるのが相当である。 したがって、被告らが原告名称又は原告肖像を使用する行為は、ピンク・レ ディー判決の第2類型に該当するものとして、パブリシティ権を侵害するもの といえる。
2 争点2(原告の同意の有無)について
被告らは、原告が被告らによる原告名称の使用に同意していた旨主張する。し かしながら、被告らは、同意があった旨抽象的に主張するにとどまり、その同意 の時期、内容等を具体的に主張していないのであるから、その主張自体失当とい うほかなく、被告らの提出に係る全証拠によっても、上記同意を裏付ける客観的 証拠はない。 仮に、少なくとも原告と訴外Bが婚姻中においては、原告名称の使用の合意を していたとしても、被告らは、原告と訴外Bが離婚し、原告が被告エンリケ空間 の代表取締役を辞任した後でも、なお原告名称に係る使用の同意が継続する事実\nを具体的に主張立証するものではない。かえって、被告らの主張によっても、訴 外Bが原告と離婚した際に、原告名称を使用しない旨述べたことがうかがわれる ことからすれば、被告らの主張を前提としても、現在まで上記同意が継続してい る事実を認めるに足りないことは明らかである。したがって、被告らの主張は、 いずれも採用することができない。
2024.02. 8
令和5(ワ)3171 損害賠償請求事件 その他 民事訴訟 令和5年12月11日 東京地方裁判所
1 争点1(パブリシティ権侵害の有無)について
(1)肖像等を無断で使用する行為は、1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象 となる商品等として使用し、2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等 に付し、3)肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する 顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害する ものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である(最高裁平成 21年(受)第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2 号89頁)。
これを本件についてみると、前提事実並びに証拠(甲11、乙1、7)及 び弁論の全趣旨によれば、芸能プロダクションである被告は、被告に所属す\nるタレントを紹介するために、そのホームページにおいて、他の所属タレン トと併せて原告の氏名及び肖像写真(本件写真等1)をトップページに掲載 するとともに、原告のプロフィール及び肖像写真(本件写真等2)を所属タ レントのページに掲載したことが認められる。
上記認定事実によれば、被告は、所属タレントを紹介する被告のホームペ ージにおいて、原告が被告に所属する事実を示すとともに、原告に関する人 物情報を補足するために、本件写真等を使用したことが認められる。
そうすると、本件写真等は、商品等として使用されるものではなく、商品 等の差別化を図るものでもなく、商品等の広告として使用されるものともい えない。 したがって、被告が本件写真等を使用する行為は、専ら原告の肖像等の有 する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず、パブリシティ権を侵害 するものと認めることはできない。
(2)これに対し、原告は、本件写真等の掲載は原告の肖像写真等を写真集等に 利用する行為と同視し得ると主張し、また、被告が取引先を介して原告の肖 像写真等を広告等に利用する行為と同視し得る旨主張する。 しかしながら、本件写真等は、被告が所属タレントを紹介するために使用 されたにすぎないことは、上記において説示したとおりである。 そうすると、本件写真等が写真集等や広告等に利用されたといえないこと は明らかである。したがって、原告の主張は、いずれも採用することができ ない。
2 争点2(肖像権侵害の有無)について
(1)肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するも のとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を 撮影等された写真等をみだりに公表されない権利を有すると解するのが相当\nである(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷 判決・刑集23巻12号1625頁、最高裁平成15年(受)第281号同 17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁、前掲最高 裁平成24年2月2日判決各参照)。他方、人の容ぼう等の撮影、公表が正\n当な表現行為、創作行為等として許されるべき場合もあるというべきである。\nそうすると、容ぼう等を無断で撮影、公表等する行為は、1)撮影等された 者(以下「被撮影者」という。)の私的領域において撮影し又は撮影された 情報を公表する場合において、当該情報が公共の利害に関する事項ではない\nとき、2)公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合におい\nて、当該情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するもの であるとき、3)公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合\nにおいて、当該情報が公表されることによって社会通念上受忍すべき限度を\n超えて平穏に日常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるときなど、 被撮影者の被る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超える場合に限り、 肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当で ある。
(2)これを本件についてみると、前記認定事実によれば、被告は、所属タレン トを紹介する被告のホームページにおいて、原告が被告に所属する事実を示 すとともに、原告に関する人物情報を補足するために、本件写真を使用した ものである。そして、証拠(甲11)及び弁論の全趣旨によれば、本件写真 の内容は、白色無地の背景において、原告の容ぼうを中心として正面から美 しく原告を撮影したものであることが認められる。 そうすると、本件写真は、私的領域において撮影されたものではなく、原 告を侮辱するものでもなく、平穏に日常生活を送る原告の利益を害するもの ともいえない。 したがって、被告が本件写真を使用する行為は、原告の肖像権を侵害する ものと認めることはできない。 これに対し、原告は、自らの意思に反して芸能事務所の所属タレントとし\nて肖像が利用された場合には、精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超 える場合に当たる旨主張する。しかしながら、原告は、肖像権侵害を主張す るものの、肖像に化体しこれに紐づけられた法律上保護される利益(民法7 09条参照)を具体的に特定して主張するものではなく、主張自体失当とい うほかない。仮に、原告の主張を前提としても、前記前提事実によれば、本 件契約に係る解除が有効であるとする別件訴訟の棄却判決が、令和5年4月 18日に確定したところ、被告は、同日には、自社のホームページから、本 件写真を削除したことが認められる。そうすると、原告の主張を十分に斟酌\nしても、本件契約の解除の有効性が訴訟で争われていた事情を考慮すれば、 その間に本件写真を掲載した行為が、受忍限度を超える侮辱ということはで きず、その他に、原告主張に係る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を 超えることを裏付ける的確な証拠はない。したがって、原告の主張は、採用 することができない。
3 争点3(不正競争防止法2条1項1号該当性)について
不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」とは、人の業務に係る氏\n名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示\nするものをいう。
これを本件についてみると、原告の氏名又は肖像は、原告を示す人物識別情 報であり、本来的に商品又は営業の出所表示機能\を有するものではない。そし て、前記前提事実によれば、原告は、芸能プロダクションである被告に所属す\nる一タレントであったにすぎず、原告自身がプロダクション業務等を行ってい た事実を認めるに足りない。そして、本件全証拠をもっても、原告の氏名又は 肖像が、その人物識別情報を超えて、原告自身の営業等を表示する二次的意味\nを有するものと認めることはできず、まして、原告の氏名及び肖像が、タレン トとしての原告自身の知名度とは別に、原告自身の営業等を表示するものとし\nて周知であるものとは、明らかに認めるに足りない。 したがって、原告の氏名又は肖像が周知な商品等表示に該当するものと認め\nることはできない。
これに対し、原告は、原告の氏名又は肖像が商品の出所又は営業の主体を示 す表示である旨主張するものの、原告は、芸能\プロダクションである被告に所 属する一タレントであったにすぎず、本件全証拠によっても、原告自身が営業 等の主体である事実を認めるに足りないことは、上記において説示したとおり である。したがって、原告の主張は、不正競争防止法2条1項1号にいう「商 品等表示」を正解するものとはいえず、採用することができない。\n
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 肖像権等
>> ピックアップ対象
2024.02. 8
令和5(ワ)4333 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年11月29日 東京地方裁判所
1 被告商品の形態は原告商品の形態と実質的に同一か(争点1)について 甲1によれば、原告商品と被告商品の形態等は次のとおりである。
ア 原告商品及び被告商品は、50枚の不織布製の使い捨てマスクが青色の紙 製の直方体のパッケージに入ったものである。原告商品及び被告商品のパッ ケージの上面(以下「上面」という。)は、いずれも縦長の長方形に構成さ\nれており、上部に商品名、中部にマスクを斜め方向から見た図(商品の説明 をするポップアップが二つ付されている。)、下部に商品の特徴が掲載されて いる。パッケージの側面のうち、略正方形の面(以下「略正方形面」という。) には、いずれも、商品名とその特徴が掲載されている。いずれのパッケージ も、パッケージの側面のうち、長方形の面は、横長に構成されており、その\nうち一方(以下「長方形面1」)については左半分に前記略正方形面とほぼ 同様の記載が、右半分にマスクを斜め方向から見た図が掲載されており、他 方の面(以下「長方形面2」という。)には、左側に商品の特徴及び基本情 報が、右側に使用上の注意事項、保管上の注意事項及び販売元が記載されて いる。
イ 原告商品と被告商品のパッケージの上面のデザインは、中部のマスクの色 合いが被告商品の方が若干青みかかっており、被告商品のみに小さく「※イ ラストはイメージです」という文言が付されている点、下部の商品の特徴を 列挙している4つのブロックを貫く青線の太さ及び濃さが多少異なる点を 除いて、基本的に同じデザイン(マスクの形状についても差異が認められな い。)になっている。上面の上部についても、上から順に、各商品のロゴ、 商品の特徴、「肌にやさしい素材」、「99%カットフィルターでブロック」、 商品の名称となっている点は共通しており、ロゴ、商品の特徴(原告商品は 「−耳にやさしい−」、被告商品は「個包装 携帯に便利」との記載)、商品 名(原告商品は「らくらくマスク」、被告商品は「不織布マスク」)に異なる 部分があるが、文字のデザインは基本的に同じである。
ウ 略正方形面については、原告商品、被告商品のいずれも、上から、前記イ 記載の各上部の記載(ただし、片面について被告商品は商品名の欄に「らく らくマスク」と記載されている。)があり、基本的に上面の下部分と同じデ ザインとなっている。
エ 長方形面1については、原告商品、被告商品のいずれも、左側が略正方形 面と基本的に同じデザインで、右側は上面の中部分と基本的に同じデザイン になっている。
オ 長方形面2については、原告商品、被告商品のいずれも、左上の商品特徴 を記載した4つのブロックを貫く線が、原告商品が白抜きで被告商品が青抜 きである点及び販売元に関する記載と商品バーコードの有無以外の点は、記 載内容が同一である(商品は、原告商品と被告商品のいずれも「らくらくマ スク」とされている。)。 不正競争防止法2条4項所定の商品の形態とは、「需要者が通常の用法に従 った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の 形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」である。 原告商品及び被告商品につき、パッケージの中の不織布製の多数枚(50枚) のマスクは、その性状からもそれぞれのマスク単体ではなくパッケージに入っ た状態で流通し、販売されて消費者がこれを購入することが予定されており、\n原告商品及び被告商品のパッケージ全体は、中に入ったマスクと一体となって 「商品」を構成し、そのパッケージのデザインは、商品の「模様、色彩」に当\nたるとするのが相当と解する。
前記 で認定したとおり、原告商品と被告商品は、そのパッケージの基本的 なデザインが同じであるほか、マスクの写真に付されたポップアップのデザイ ン及び説明文言、商品特徴の説明文言及び配置、商品の特徴を列挙している4 つのブロックを青色の線が貫くデザイン等の細かい点まで一致している。原告 商品と被告商品のパッケージは、商品名やロゴ、販売元に関する記載等につい て一部異なる点があるものの、それらの記載等が商品全体において占める部分 は非常に小さく、全体的な印象に与える影響は限定的であり、原告商品と被告 商品の形態は実質的に同一であるというべきである。 被告は、原告商品のパッケージのデザインがありふれたものである旨主張す る。
原告商品のパッケージにおける個々の模様のデザイン、説明文言等は、その それぞれに着目すると同種商品に同じデザイン、文言等が記載されているもの もある(乙4〜9)。しかし、原告商品のパッケージは多数の具体的な模様、表\n示等からなり、それらを組み合わせたデザインがありふれたものであることを 認めるに足りる証拠はなく、原告商品のパッケージのデザインが全体としてあ りふれたデザインであるとは認めるには足りない。
2 被告商品は原告商品に依拠したものか(争点2)について
被告商品は原告商品の後に発売されたものであり(前提事実 、 )、前記1で 認定したとおり、原告商品と被告商品のパッケージは細部まで一致している。ま た、原告商品のマスクの画像に付されたポップアップの誤記(「側は肌にやさし い滑らか素材」との記載について、原告は、「内側は肌にやさしい滑らか素材」と すべきであったところ誤植したと述べる。)が被告商品にもそのままあり(被告 商品の記載も「側は肌にやさしい滑らか素材」との記載である。)、被告商品では、 商品名として、上面及び長方形面1、略正方形面の一方では「不織布マスク」と 記載されているものの、略正方形面の他方及び長方形面2では「らくらくマスク」 (原告商品の商品名)と記載されていて、これらは、いずれも原告商品の記載を そのまま利用してしまい、変更することを失念したものと推認できることを考慮 すると、被告商品は原告商品に依拠して製造されたものと認められる。
3 故意、過失(争点3)について
弁論の全趣旨によれば、被告は、別会社にデザインまで含めた商品の内容につ いて指示を出し、被告商品の製造を委託したことが認められる。前記2で認定し たとおり、被告商品は原告商品に依拠してデザインされ、製造されたものである。 原告商品のデザインに依拠したパッケージデザインを具体的に発案した者は必 ずしも明らかではないが、被告商品の内容について最終的な決定権を有するのは 被告であったといえ、原告商品に依拠してこれと実質的に同一の被告商品を販売 したことについて、被告には少なくとも過失があったというべきである。
4 損害及び因果関係(争点4)について
証拠によれば次の事実が認められる。
・・・・
イ 本件取引会社は、令和2年10月16日付けで、原告に対し本件売買契約 を解除する旨記載された契約解除通知書(以下「本件通知書」という。)を 送付した。本件通知書には、「貴社と締結いたしました商品売買契約につき まして、下記の理由をもちまして、本書面をもって解除いたします。」と記 載され、下記の記載があった。当時、被告商品を999円/箱で販売してい る小売店が存在した。原告は、本件通知書の内容を了承して、本件売買契約 は履行されなかった。(甲5、6、15)
記
「1.雑貨店で同じ包装の商品が安く売られていることが判明しました。
2.雑貨店の定価(税別999円/箱)は貴社からご提示いただいた価格 (税込1400円/箱)よりも低いことが判明しました。
3.貴社は当該商品売買契約(判決注:本件売買契約)の第8条に違反し ました。」
以上
原告は、被告商品が販売されたことが原因で本件売買契約が解除されたので、 本件売買契約に基づく履行利益(売買代金から経費を控除した額)が損害に当 たると主張する。 前記 で認定したとおり、本件取引会社は、被告商品が、本件売買契約にお ける単価(1400円/箱)よりも安価に販売されていることを指摘して、本 件通知書を送付したことが認められる。
しかし、本件通知書には、本件売買契約8条に違反したとの記載はあるもの の、同条のいずれの項に違反したとも特定されていない。この点について、原 告は、本件売買契約は8条 で規定されている「信用状態の悪化」があったた め解除されたと主張する。しかし、一般的に取引契約における解除原因として 規定される「信用状態の悪化」は、当事者の支払能力等の経済的信用を問題と\nする趣旨で用いられるところ、原告にそのような事情があったことはうかがえ ず、また、被告商品の販売がこれに関連するとも認められない。仮に「信用状 態の悪化」を、当事者が信頼関係を損なう背信的行為をしたこと(道義的信用 が悪化したこと)を意味するとしても、その趣旨からして少なくとも原告に帰 責性のある事情があることが前提とされるところ、被告が原告商品の形態を模 倣して販売したことは、原告に何の帰責性もない。その他、原告において「信 用状態の悪化」が認められる事情が生じたことを認めるに足りる証拠はなく、 本件売買契約8条のその余の条項に当たる事情があったことを認めるに足り る証拠もない。原告は、原告代表者の配偶者の陳述書(甲15)を提出し、そ\nこには、令和2年10月、本件取引会社の販売先が原告商品と同じパッケージ のマスクを見かけ、本件取引会社は、原告は本件取引会社に1400円/箱の 卸価格で提案したのに、店で999円で売られていることがありえないことだ と怒っていて、これは本件売買契約8条に違反するので、キャンセルするなど と電話連絡をして、その後本件通知書が送付され、原告は、原告商品と被告商 品の販売価格に乖離があったためやむを得ずキャンセルを了承することとし たとの記載がある。
この陳述書によっても、本件取引会社は、本件取引会社へ の販売価格よりも低廉な価格で商品が販売されていたことを問題視している ことはうかがえるが、それにより、結局本件取引会社が何を問題としていたの かは必ずしも明らかではなく、原告が原告商品を本件取引会社以外の者に対し ては本件取引会社に対する価格よりも廉価で販売していたと誤解した可能性\nもうかがわれないではない。原告が本件取引会社以外の者に対して廉価販売し たと誤解したことについては誤解を解くべき話といえる。なお、被告商品の販 売が本件取引会社による原告商品の販売数量に影響を与えることはあり得る ものの、そもそも本件売買契約では当該商品について本件取引会社に対しての み販売することが定められてはおらず(甲4)、他社が同種の商品を販売した こと自体を本件取引会社は問題視できるものではない。これらによれば、本件売買契約については、契約において定められた解除理由は存在しなかったというべきであり、これが履行されなかったのは、原告と本件取引会社との間の合意によるものといえる。
被告商品を販売することは不正競争行為であり、被告は、これにより原告に 生じたといえる損害を賠償する義務がある。もっとも、侵害者は、侵害行為が 他社間の契約の存続に影響を与えることを当然に予見できるものではなく、ま\nた、他社間の契約の内容は当該他者間で自由に定められるもので侵害者がその 内容を通常は知ることはできず、侵害者にその契約の履行利益を前提とする損 害を負担させることは当事者間の衡平に反する場合があるといえる。少なくと も本件のように、原告と第三者との間に解除権の発生原因がないが、両者間の 合意によってこれを履行せず、また、本件売買契約における販売価格も当時の 相場に比べて高額といえるような場合(甲11は、マスクの平均価格は、令和 2年4月24日には1枚当たり78円だったが、その後急速に値下がりし、同 年8月13日には1枚当たり12円だったとする。被告の侵害行為の時点(前 記第2の2 )では、本件売買契約のマスクの単価は上記平均価格に比べて相 当に高かった。原告は本件売買契約によって相当多額の利益を得られたはずで あると主張している(前記第2の3 ))、本件で原告が主張する損害は、通常 生ずべき損害には当たらず、また、被告にはその発生が予見できなかったもの\nということが相当である。
以上の事情を考慮すると、本件において原告が主張する損害は、被告商品の 販売との間の因果関係を欠くというべきであり、被告がそれを賠償すべきであ るとは認められない。なお、原告は、本件において不正競争防止法5条に基づ く主張はしない旨述べた(令和5年9月12日付け原告第3準備書面)。
◆判決本文
双方のパッケージデザインはこちらです。
2024.02. 8
令和2(ワ)29523 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年11月15日 東京地方裁判所
(1) 特許法102条2項所定の「その利益の額」について 前記9において説示したとおり、被告とAAによる本件工事の施工に係る 本件特許権侵害について共同不法行為が成立するから、原告が受けた損害の 額と推定される特許法102条2項所定の「その利益の額」は、本件工事に よって、被告が受けた利益の額とAAが受けた利益の額との合計額となる。
(2) 被告の受けた利益の額
ア 売上高
前提事実(5)イのとおり、被告が受領した本件工事の施工についての請負 代金の額は、377万2224円(税抜代金349万2800円、消費税 相当額27万9424円)と認められる。 そして、消費税法基本通達5−2−5柱書及び(2)によると、「無体財 産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する 損害賠償金」は、資産の譲渡等の対価に該当するものとされていることか らすれば、特許法102条2項の「侵害の行為により利益を受けていると き」にいう「利益」には消費税相当分も含まれると解すべきである。 したがって、特許法102条2項所定の損害額算定の基礎となる売上高 は、377万2224円(消費税込み)というべきである。
イ 控除すべき経費
(ア) 材料費 100万3320円(消費税込み)
当事者間に争いがない。
(イ) 外注費 58万2740円(消費税込み)
証拠(乙64ないし69)によれば、被告は、本件工事の一部の施工 を下請業者に発注し、日当、残業代、ガソリン代及び高速料金代並びに\n飲料水代として、合計58万2740円(消費税込み)を支払ったこと が認められる。 そして、証拠(乙80)により認められる本件工事の施工期間、施工 内容等に照らせば、上記支払のうち、日当、残業代、ガソリン代及び高\n速料金代は、本件工事の施工に直接関連して必要となった経費に当たる ものと認められる。 また、証拠(乙80)によれば、上記の下請業者に対する支払のうち、 飲料水代については、暑い現場で作業している下請業者が水分補給でき るようにとの趣旨で購入されたものと認められるところ、その内容及び 金額の水準に照らせば、当該支払についても、本件工事の施工に直接関 連して必要となった経費に当たると認めるのが相当である。
(ウ) 交際費 7201円(消費税込み)
証拠(乙70、80)によれば、被告は、本件工事の施工期間中、前 記(イ)の下請業者の昼食代として合計7201円(消費税込み)を負担し たことが認められるところ、その内容及び金額の水準に照らせば、当該 負担は、本件工事の施工に直接関連して必要となった経費に当たるもの と認められる。
(エ) 消耗品費 1527円(消費税込み)
証拠(乙71)によれば、被告は、ポリ袋及びコピー用紙を合計69 7円(消費税込み)で、ナチ六角軸鉄工ドリル及び「リポビタンD」と いう商品名の栄養ドリンク剤を合計830円(消費税込み)で、それぞ れ購入したことが認められる。 そして、証拠(乙80)によれば、上記ポリ袋は、現場において発生 した廃材を処理するため、上記コピー用紙は、現場においてメモをとる ため、上記ナチ六角軸鉄工ドリルは、母屋材にビス孔を空けるドリルの 交換用として、それぞれ購入したものと認められるから、これらの支払 は、本件工事の施工に直接関連して必要となった経費に当たるものと認 められる。 また、証拠(乙80)によれば、上記「リポビタンD」は、暑い現場 で作業している下請業者が栄養補給できるようにとの趣旨で購入された ものと認められるところ、その内容及び金額の水準に照らせば、本件工 事の施工に直接関連して必要となった経費に当たると認めるのが相当で ある。
(オ) 旅費交通費 310円(消費税込み)
当事者間に争いがない。
(カ) 車両費 6000円(消費税込み)
証拠(乙78、80)によれば、被告代表者は、本件工事の施工期間\nである令和元年7月5日から同月9日まで、数名の作業員や様々な工具 類・装備品を同乗・積載させた車両を運転して、当時の被告所在地(省 略)と施工現場との間を往復したこと、当時の被告所在地と施工現場と の間の道のりは40キロメートル以上であることがそれぞれ認められる。 そして、弁論の全趣旨によれば、1キロメートル当たりのガソリン代\nは15円(消費税込み)を下回らないと認められるから、これらを基礎 として算定したガソリン代相当額6000円(=15円×40キロメー\nトル×2×5日)は、本件工事の施工に直接関連して必要となった経費 に当たるものと認められる。
(キ) 合計 160万1098円(消費税込み)
ウ 小括
前記ア及びイによれば、被告が本件工事の施工により受けた利益の額は、 217万1126円(消費税込み)と認められる。
(3) AAの受けた利益の額
ア 売上高 前提事実(5)アによれば、特許法102条2項所定の損害額算定の基礎と なる売上高は、472万3920円(消費税込み)と認められる。
イ 控除すべき経費
前提事実(5)イによれば、特許法102条2項所定の損害額算定の基礎と なる控除すべき経費は、377万2224円(消費税込み)と認められる。
ウ 小括
前記ア及びイによれば、AAが本件工事の施工により受けた利益の額は、 95万1696円(消費税込み)と認められる。
(4) 損害額
前記(2)及び(3)によれば、特許法102条2項により算定される原告の損 害額は、312万2822円と認められる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2024.02. 7
令和5(行ケ)10014 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年11月29日 知的財産高等裁判所
そうすると、訂正前の請求項1の発明においては、地点候補がシンボルマ ークで表示がされている間は、位置情報を取得し得る地点は、このシンボル\nマークに対応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ない こととなる。これは、本件明細書の発明の詳細な説明の【発明の効果】に、 「請求項1に記載の発明によれば、候補抽出手段によって地点候補を絞り込 み、絞り込まれた地点候補を地図画面上にシンボルマークで表示するととも\nに、そのシンボルマークの表示のある間、位置情報を取得可能\な地点をシン ボルマークに対応する位置に制限するので、表示されたシンボルマークを選\n択するだけで、地図画面上から所望の位置情報を取得することができる。」 (段落【0015】)と記載され、シンボルマークが表示されている間に位\n置情報が取得可能な地点は、シンボルマークが表\示されている位置のみとさ れていることからも明らかである。さらには、前記(1)イのとおり、本件発明 はユーザーに煩雑な操作を強いることなく地図画面上から所望の位置情報 を取得することのできるナビゲーション装置を提供するものとし、そのため 「地図画面上のカーソルで地点を指定することによって対象位置の位置情\n報を取得する位置情報取得手段46を備え」(段落【0030】)、「地点候補 以外のシンボルマークが消失する大縮尺の地図表示になっても、地点候補を\n示すシンボルマークが残るように設定されており、それによって利便性の向 上が図れている」(段落【0038】)、「経由地を設定する際には、シンボル マークに対応する位置以外は位置情報の取得が制限されるため、縮尺の大き い地図画面であっても不要な地点を誤って設定してしまうことがない」(段 落【0040】)及び「地図画面上のシンボルマークに対応する地点以外の 位置情報を取得できないようにしているが、単に、取得できないだけでなく、 位置情報の選択カーソルを地点候補(シンボルマーク)以外には移動できな\nいようにしても良い」(段落【0042】)とする本件明細書の各記載の内容 にも沿うものである。
エ 本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の発明の意義
これに対し、訂正後の請求項1の発明は、「前記地点候補がシンボルマー クで表示されている間は、」「地点候補の位置情報を取得し得る地点を前記シ\nンボルマークに対応する位置に制限する」とするものであるところ、前記イ のとおり、特許請求の範囲の記載によれば、候補抽出手段で抽出された後の 地点候補が地図画面上にシンボルマークで表示されているのであるから、\n「前記シンボルマークに対応する位置」とは、すなわち地図画面上にシンボ ルマークで表示されている地点候補の地球上の所在地であり、これは、地図\n画面上における「地点候補の位置情報を取得し得る地点」と同じものを意味 している。そうすると、訂正後の請求項1においては、位置情報を取得し得 る地点についての「制限」は何らなされていないこととなる。 加えて、前記イのとおり、位置情報取得手段は地点についての位置情報を 取得するものであり、地点候補についての位置情報を取得するものではない から、訂正後の請求項1においては、地点候補以外の地図画面上に表示され\nた任意の場所である地点について、地点候補がシンボルマークで表示されて\nいる間、位置情報取得手段により位置情報を取得し得るのか否かについて、 明らかにしないものとなる。
すなわち、訂正後の請求項1の発明では、「地点候補の」との文言を加え ることにより、位置情報を取得し得る「地点」についての「制限」をなくし、 位置情報を取得できる範囲を不明とするものであり、特許請求の範囲の記載 のうち、「前記表示手段の地図画面上に前記地点候補がシンボルマークで表\ 示されている間は、前記位置情報取得手段によって位置情報を取得し得る地 点を、前記シンボルマークに対応する位置に制限する」との文言(構成要件\nG)を無意味とし、発明特定事項の一部を削除するものということができる。 オ 本件訂正前の請求項1の発明と本件訂正後の請求項1の発明の対比 そうすると、訂正事項1により、請求項1に係る発明は、本件訂正前の請 求項1に記載される地点の位置情報を取得し得るのがシンボルマークに対 応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ないこととなる ものから、位置情報を取得し得る地点についての「制限」をなくし、位置情 報の取得範囲を不明として、発明特定事項の一部を削除するものに変更され ることになるから、この変更は、特許請求の範囲を変更するものであるとこ ろ、その変更は、減縮的な変更には当たらず、また、「明瞭でない記載の釈 明」を目的としたものともいえず、本件訂正前の請求項1の記載の表示を信\n頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。
したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を変更するものと認め られるから、特許法126条6項の要件に適合しないというべきである。こ れと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2024.02. 7
令和3(ワ)18262 損害賠償請求事件(特許権侵害) 特許権 民事訴訟 令和5年12月6日 東京地方裁判所
ア 証拠(乙18、29、30)及び弁論の全趣旨によれば、令和2年1月 22日から令和4年2月22日までの間の被告製品の売上高は、1億17 57万6451円であったと認められる。
イ(ア) 原告は、被告が、令和2年1月1日から同月21日までの間も被告製 品を販売したと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
(イ) また、原告は、被告の公式ホームページにおいて、被告製品の販売数 量について「27万着突破!」、「30万着突破!」と記載されていたこ とを指摘して、被告製品の販売数量は少なくとも27万着であり、これ に1着当たりの単価5980円を乗じると、被告製品の売上高は16億 1460万円を下らないと主張する。 そこで検討すると、確かに、証拠(甲4、14)によれば、被告の公 式ホームページにおいて上記の記載がされていたことが認められるもの の、同ホームページに記載されていた販売価格(5980円。弁論の全 趣旨によれば、この価格はブラジャーの一般的な販売価格として相当な ものと認められる。)を前提とすると、前記アにおいて認定した被告製品 の売上高は、請求書記載の被告製品の輸入数量(乙17)、被告製品に係 る販売管理データ記載の販売数量(乙18)、被告の損益計算書記載の売 上高(乙20、21)、被告における被告製品以外の売上高(乙22ない し24)と整合的であるといえる。これに対し、被告製品の販売数量が 27万着以上であることを示す資料は、被告の公式ホームページの記載 以外に存在しない。
これらの事情に照らせば、令和2年1月22日から令和4年2月22 日までの間の被告製品の売上高は前記アにおいて認定したとおりであっ て、被告の公式ホームページにおける販売数量の記載は虚偽のものであ ったと認めるのが相当である。
(ウ) したがって、原告の前記各主張を採用することはできない。
(2) 相当な実施料率について
ア 本件発明の実施に対し受けるべき料率については、1)本件発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界にお ける実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)本件発明自体の価値すなわち本 件発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)本件発明を被 告製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者 である原告と侵害者である被告との競業関係や特許権者である原告の営業 方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきで ある。
イ 本件についてみると、本件発明の実際の実施許諾契約における実施料率 は、5パーセントであることが認められる(甲15ないし18)。 また、本件発明は、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、 個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の 補正機能等に対応することが可能\な女性用衣料を低コストで提供すること を可能とするものであるところ(前記1(2)イ)、被告製品も、女性のバス トの補正を主たる機能としたものであるから(甲3、4、14)、本件発明\nを被告製品に用いることが被告の売上げ及び利益に大きく貢献していると 認めるのが相当であって、他のものによる代替可能性はうかがわれない。\nさらに、原告と被告は、いずれも女性用衣料を販売しているから(前提 事実(1)、(5)及び(6))、その市場において競業関係にある。 これらの事情に照らすと、特許権侵害をした者に対して事後的に定められ る本件発明の実施に対し受けるべき料率については、6パーセントと認め るのが相当である。
(3) 特許法102条3項により算定される額について
以上によれば、特許法102条3項により算定される本件発明の実施に対 し受けるべき金銭の額に相当する額は、705万4587円(1円未満四捨 五入)と認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.02. 6
令和4(ワ)70079 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和6年1月24日 東京地方裁判所
著作権法41条は、時事の事件の報道には、国民の知る権利に資する側面 があり、しかも、速報性が求められるため、事前に著作権者の許諾を得るこ となく、当該報道に伴う著作物利用を認める必要性があること、他方で、当 該報道に伴い利用することが避け難い著作物をその目的上正当な範囲内にお いて利用するにとどまれば、著作権者の利益を不当に害するものではないこ とに鑑み、著作権者の権利制限を認めたものと解される。 上記のような著作権法41条の趣旨に鑑みると、「時事の事件」とは、速 報性の要求される事件、すなわち、現在又は近時に起こった事件をいうと解 するのが相当である。本件において、社会活動家である原告が、社会的に注 目されたB元首相の射殺事件についてコメントをしたことは、本件記事の配 信の前日の出来事であるから、「時事の事件」に該当する。 また、上記著作権法41条の趣旨に照らすと、「当該事件を構成」する著\n作物とは、当該報道に伴い利用することが避け難い著作物、すなわち、事件 の主題となっている著作物をいうと解されるところ、「時事の事件」を社会 活動家である原告が、社会的に注目されたB元首相の射殺事件についてコメ ントをしたことと捉えると、原告のコメント内容すなわち本件各ツイートの 内容は、事件の主題となっている著作物であるといえる。 さらに、上記のとおり、著作権法41条の正当化根拠が、当該報道に伴い 利用することが避け難い著作物をその目的上正当な範囲内において利用する にとどまれば、著作権者の利益を不当に害するものではない点にあることに 照らすと、著作物の利用が「報道の目的上正当な範囲内において」行われる といえるかどうかは、著作物の利用の必要性及びその利用の態様に照らして 著作権者の利益を不当に害しないかどうかという観点から検討されるべきで ある。
本件において、被告は、本件各ツイートの内容をほぼ全文引用しているも のであるが、そもそも本件各ツイートは全体で400字前後とさほど長くな いものであり、原告がコメントした事実をその表現内容とともに正確に伝え\nるという報道の目的に鑑みると、要約や一部の切り取りをすることなく本件 各ツイートのほぼ全文を引用する必要性があったものと認められる。 他方で、本件各ツイートは、前記3のとおり原告の著作物として保護され るものであるものの、ツイッター上で公開され、誰もが無料で閲覧すること ができるものであり、原告も、自身の思想や意見をより多くの者に知っても らうために本件各ツイートを発信していると認められること(弁論の全趣旨) に照らすと、前記1のとおり、被告による本件見出しの選択に問題があった としても、本件各ツイートを全文引用すること自体が原告の利益を不当に害 しているとはいい難い。以上によれば、被告による本件各ツイートの利用は、「報道の目的上正当な範囲内」においてされたものといえる。
(2) これに対し、原告は、およそあらゆる著作物をいかなる場合でも無制限に 報道目的で利用できることになってしまい、著作権の保護が無意味となって しまうから、著作権法41条は、著作物の創作行為や公表行為そのものを\n「時事の事件」として捉え、当該著作物を「当該事件を構成し、又は当該事\n件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」として利用することは およそ想定していないと主張する。しかし、前記(1)で説示したとおり、著作権法41条は、「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」であれば、無制限に報道目的で利用することを認めているものではなく、その中で\nも「報道の目的上正当な範囲内」における利用を想定しており、それは、当 該報道に伴い利用することが避け難い著作物をその目的上正当な範囲内にお いて利用するにとどまれば、著作権者の利益を不当に害するものではないこ とを根拠とするものである。したがって、同条によって、あらゆる著作物を いかなる場合でも無制限に報道目的で利用できるわけではないから、原告の 上記主張は、独自の見解であるといわざるを得ず、採用することができない。
2024.02. 5
令和3(ネ)10084 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年11月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
【当審における双方の補充的主張に対する判断】
(1) 第1審原告の補充的主張について
ア 第1審原告は、計算鑑定書の別表において、1)対象期間における原反ロー ルの購入面積が第1審被告製品(1)の販売面積よりも大きかったり、2)原 反ロールの購入面積と第1審被告製品(1)の販売面積が一致するデータが 多かったりするなどといった不自然な結果が記載されていると指摘する。 しかし、1)については、加工する際の歩留まりやロス、仕損じがあること を考えれば、原反ロールの購入面積よりも販売面積が小さくなることは何 ら不自然ではない。2)についても、計算鑑定書は、第1審被告製品(1)の品 番毎の原反ロールの月毎の面積について、●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のであ り(計算鑑定書19頁)、基準量が1であるとき(例えば、原反ロールを特 段加工することなく転売する場合)、原反ロールの購入面積と第1審被告 製品(1)の販売面積が一致したとしても何ら不自然ではない。第1審原告 は、計算鑑定の結果が、第1審被告らが提出する調査報告書(乙58)や 製品説明書(乙1)の売上高等のデータと異なることも指摘するが、計算 鑑定人が中立的な立場からその職責において計算を行ったものであり、第 1審被告らの提出する資料と一部データが異なるとしても、そのことから 信用性が失われるものでもない。 また、第1審原告は、信用調査会社による競合会社の動向調査の結果で ある甲88を提出して第1審被告らの売上高等について独自の主張をす るが、外部の調査会社による調査結果にすぎず、その調査結果の信用性が 高いことを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ 第1審原告は、第1審原告製品の販売価格には第1審被告製品(1)の●● ●●のものがあることを指摘して、原判決の判断の前提には誤りがあり、 推定覆滅事由が認められないと主張する。しかし、そのような販売価格の 製品があることは、仮に第1審被告製品(1)が販売されなかった場合に、か えって第1審原告製品の販売の可能性を減少させるにすぎず、むしろ推定\n覆滅を肯定する事情であるにすぎない。
(2) 第1審被告らの補充的主張について
ア 第1審被告らは、限界利益の算定上、原判決別紙「売上高・経費一覧表」\nの番号6〜8、11〜14は第1審被告製品(1)の製造販売に直接関連し て追加的に必要になった経費であるから控除されるべきであると主張す る。しかし、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造 販売に直接関連して追加的に必要になった経費には当たらないというべ きであり、上記各経費を控除の対象とすることは相当でない。
イ 第1審被告らは、第1審被告らの利益額の90%又は少なくとも77% の推定覆滅を認めるべきであると主張する。しかし、その指摘する根拠と する理由(第1審被告製品(1)に耐候性等の本件発明の作用効果が確認で きないこと、設計変更が容易であること、第1審被告らの営業努力・ブラ ンド力・売上シェア等)については、本件証拠上、その事実が認められな いか、仮に認められたとしても、原判決が認定した限度を超えて特許法1 02条2項の推定を覆すに足りるものではない。
◆判決本文
1審における推定覆滅の事情は以下です
◆平成30(ワ)1130
b そこで,被告らが特許法102条1項ただし書の推定覆滅事由として主張
する点について検討するに,次のとおり,2割の推定覆滅を認めるのが相当
である。
(a) 被告らは,本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の
印刷領域の面積の限定は,顧客吸引には全く寄与しておらず,被告旧製品
と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり,被告旧製品のカ
タログでも,印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし,
原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり,本件発明
は,被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。
しかし,前記1(9)で説示したとおり,本件発明の従来技術とは異なる技
術的特徴は,再帰反射シートの印刷層について,「印刷領域が独立した領域
をなして繰り返しのパターンで設置されており,連続層を形成せず」,「独
立印刷領域の面積が0.15mm2〜30mm2」,かつ,「白色の有機顔料…着色
剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより,印刷層周辺の密着\n性を向上させ,耐水性・耐候性を向上させるとともに,色相の改善を図る
ことにあるのであるから,その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措
定する被告らの上記主張は,その前提を欠くものである。また,被告旧製
品と被告新製品の耐候性の実験結果(乙45〜49)についても,その実
験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから,これをもって
直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな
い。そして,証拠(甲3,4,9,10,23,67〜70)及び弁論の
全趣旨によれば,被告旧製品のカタログやウェブサイトには,本件発明の
技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記\n載が多数存在することも認められる。
したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当
ではないというべきである。
(b) 次に,被告は,本件発明は,被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら
ず,むしろ,3Mブランドに裏付けられた被告らの信用,実績及び知名度
等こそが,被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで
あり,現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き
く変化していないと主張する。
しかし,仮に被告らが3Mグループとしてのブランド力を有するとして
も,これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な
証拠は提出されていない。また,仮に被告旧製品から被告新製品に切り替
えた前後で売上高が大きく変化していないとしても,顧客において被告旧
製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上,従
前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた
可能性が否定できないから,これをもって直ちに本件発明が顧客への販売\nに貢献していないということはできない。
したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの
は相当ではない。
(c) また,被告らは,主要国道および高速道路等における道路標識に用いら
れる被告製品を含む長尺ロール製品については,再帰反射シートのパイオ
ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく,原告は被告旧製品
の販売数量分の実施能力を有していないのであり,実際に,被告らの販売\nする被告製品並びにその他の製品(Diamondグレード及びEngi
neeringグレードの再帰反射シート)の売上比がそれぞれ●(省略)
●であり,原告製品の売上比が10%であるから,仮に被告製品(1)が販売
できなくなったとすれば,そのうちの●(省略)●(=10/(10+●
(省略)●))のみが原告製品に向かうことになると主張する。
しかし,そもそも,競合品といえるためには,市場において侵害品と競
合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは,被告ら
が販売するDiamondグレード及びEngineeringグレード
の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが,弁論の全趣旨
によれば,前者の価格は被告旧製品の●(省略)●以上であり,後者の性
能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから,これらの製品の\n価格や性能等を捨象して,同様の用途に用いられる再帰反射シートである\nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると,被告
らが主張するDiamondグレード及びEngineeringグレー
ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認
めることはできず,それゆえに被告旧製品の需要がDiamondグレー
ド及びEngineeringグレードの再帰反射シートと原告製品の売
上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。
したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの
は相当ではない。
(d)さらに,被告らは,仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと
しても,原告の逸失利益は,被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益
率を乗じた額にとどまるところ,原告製品の販売単価は被告旧製品の●(省
略)●程度の価格帯であり,原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ
く●(省略)●程度であるはずであり,原告製品の限界利益率は被告製品
のそれの●(省略)●程度にすぎないことが推認されるから,特許法10
2条2項によって推定される損害額は,原告の逸失利益を大幅に超えるこ
ととなると主張する。
この点,弁論の全趣旨によれば,原告製品の販売単価は,被告旧製品の
●(省略)●程度の価格帯であることが認められるところ,仮に被告旧製
品が販売されなかったとしても,原告において,被告旧製品の限界利益と
同額の限界利益を得ることができたとは認め難く,この点については,一
定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが,他方で,原告製品の販売単
価が低価格であることにより,その販売数量が,被告製品の販売数量より
も大きくなる可能性もあるのであるから,大幅な推定覆滅を認めるのが相\n当であるともいえない。
(e)以上の事情を総合考慮すると,被告らが主張する推定覆滅事由のうち,
原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ,推定覆滅事由とし
て考慮するのが相当であり,その覆滅割合は2割と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.02. 2
令和5(行ケ)10024 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年1月22日 知的財産高等裁判所
ア(ア) 本願発明2に係る特許請求の範囲の記載は「前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションにより適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素被覆ポリマー、または10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満の水蒸気透過率を有する任意の材料のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のアプリケータ」というものである。当該記載からは、「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」が封止要素を構成する材料であると理解することができるものの、その余の特許請求の範囲の記載を踏まえても、上記の水蒸気透過率の単位が24時間単位であることをうかがわせる記載はない。\n
(イ) 次に本願明細書をみると、封止要素の水蒸気透過率については、【0008】、【0051】、【0144】、【0164】の各段落において、「水分(例えば、水蒸気)に対して不浸透性の任意の好適な材料、例えば、金属箔(例えば、アルミニウムもしくはチタン)、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションによって適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素で被覆されたポリマー」等と同様の不浸透性を有する材料の例として、「10グラム/100in^2未満または好ましくは1グラム/100in^2未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」又は「10グラム/100in2未満もしくは好ましくは1グラム/100in2未満の水蒸気透過率を有する任意の物質」との記載がされている。 しかし、これらの記載においても当該任意の材料の水蒸気透過率が24時間単位のものであるかは判然としない。したがって、本願明細書の記載からは、本願発明2の「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満」における「グラム/100in2」が、「グラム/100in2/24h」という24時間単位のものであることを直ちに読み取ることはできない。また、当該任意の材料は、封止要素に用いられるものであって、水分(水蒸気)に対して実質的に不浸透性の材料を意味するものと理解することができるものの、「実質的に不浸透性の材料」であるということから、当該任意の材料の水蒸気透過率を示す「10グラム/100in2」又は「1グラム/100in2」との記載が24時間単位であることを意味するものとは直ちに認めることはできない。
イ 本願の出願日当時の技術常識について検討するに、平成20年3月20日改正の日本工業規格「プラスチック−フィルム及びシート−水蒸気透過度の求め方(機器測定法) JIS K 7129」(甲9)には、エンボスなどのない表面が平滑な、プラスチックフィルム、プラスチックシート及びプラスチックを含む多層材料の感湿センサ法、赤外線センサ法及びガスクロマトグラフ法による水蒸気透過度の求め方について規定した規格について、「水蒸気透過度は、24時間に透過した面積1平方メートル当たりの水蒸気のグラム数〔g/(m2・24h)〕で表\す。」との記載があることが認められるが、本願発明2においては、封止要素の材料はプラスチック又はこれを含むものに限られるものではなく、また、水蒸気透過度の測定方法も特定されていないから、上記日本工業規格をそのまま本願発明2に適用することができるということはできない。
また、本願の出願日以前に公開されていた文献には、シートやフィルム等の水蒸気透過度について、「g/m2/24hr」「g/100in.2/24hr」(甲5・特表2009−503279号公報)、「g/100in2/日」(甲6・国際公開第2016/097951号、特表\2018−501127)、「g/1m2/24時間」「g/100in2/24時間」(甲7・特開2014−148361号公報)、「g/m2・day」(甲8・特開平11−43175号公報)、「g/24h/m2」(甲12・米国特許出願公開第2016/0058380号明細書)、「mg/日」(甲13・特表2012−519038号公報)などと、24時間又は一日当たりの値を示すものがある一方で、水分バリアーポリマーについて「g−mil/100in2/h」を用いるもの(乙1の1・2・米国特許第5799450号明細書)、絶縁基板について「g/m2/h」を用いつつ、樹脂封止シートについては「g/m2・day」を用いるもの(乙2・特開2014−67918号公報)、透明性樹脂シートについて「g/m2・1hr」を用いるもの(乙3・特開2010−284250号公報)、火傷創傷包帯の基材について「グラム/1h/1平方フィート」を用いるもの(乙4の1・2・米国特許第4820302号明細書)があり、1時間単位の値が用いられているものもみられるから、本願の出願日当時、水蒸気透過率について24時間単位で表\すことが通常であったということはできない。原告は、医療分野では24時間又は一日単位が一般的に使用されていると主張するが、そうであるとしても、前記の各文献における使用例に照らすと、本願の出願日当時、医療分野において、水蒸気透過率を表す場合に時間単位が用いられることはなかったということはできない。\n
そうすると、当業者が、本願発明2に係る特許請求の範囲及び本願明細書の「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満」との記載をもって、「10グラム/100in2/24h未満または好ましくは1グラム/100in2/24h未満」を意味するものと当然に理解するとは認められない(なお、本願発明2に係る本件補正は、特許請求の範囲を「10グラム/100in2/24h未満または好ましくは1グラム/100in2未満/24h」とするものであるが、「1グラム/100in2未満/24h」は「1グラム/100in2/24h未満」の誤記であることが自明である。)。
ウ もっとも、前掲各証拠上、水蒸気透過率について1時間単位又は24時間(1日)単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明2の「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満」との記載は、「10グラム/100in2/h未満または好ましくは1グラム/100in2/h未満」又は「10グラム/100in2/24h未満または好ましくは1グラム/100in2/24h未満」のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。そして、「10グラム/100in2/h未満または好ましくは1グラム/100in2/h未満」を24時間単位に換算すると「240グラム/100in2/24h未満または好ましくは24グラム/100in2/24h未満」となる。\n
そうすると、本願補正発明2は、本願発明2の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明2に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2024.01.30
令和5(行ケ)10071 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和5年12月25日 知的財産高等裁判所
(2) 意匠法4条2項は、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して同法 3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠に関し、その該当するに至った日か ら1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条1項及び2項の 規定の適用については、同条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみ なすとして、新規性喪失の例外を認めている。 このような新規性喪失の例外の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書 面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、意匠法3条1項1号又は2 号に該当するに至った意匠が同法4条2項の適用を受けることができる意匠である ことを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなけ ればならない(同条3項)。 したがって、原告が引用意匠について意匠法4条2項の適用を受けるためには、 原告が引用意匠について同条3項所定の証明書を提出していることがその前提とな る。
(3) この点、原告は、本件証明書に記載されている証明書記載意匠と引用意匠は 実質同一の意匠であると主張し、原告が特許庁長官に本件証明書を提出したことに より、引用意匠に係る公開行為は先の証明書記載意匠の公開に基づいてされたもの と認めるべきである旨を主張する。 そこで検討すると、証明書記載意匠は、甲1(別紙第3の添付画像1及び2)の とおりであり、これによると、その形状等は、全体としてマチのある略直方体の収 納部と、その収納部の上辺左右両側からアーチ状に持ち手を架橋し、収納部及び持 ち手はいずれも黒色の色彩が施されているものであり、収納部の正面上辺及び左右 辺の三辺を波状に形成し、上辺及び左右辺の山部が左右上角部のものを含めて各辺 三つずつあり、左右上角部には上辺及び左右辺の山部が合わさったように正面視左 右斜め上方向に突出した略半長円形状の山部、左右辺中央部には円弧状の山部、左 右下角部には下辺が直線状の略円弧状の山部と、計七つの山部を形成してなるもの であり、収納部上辺からやや離れた位置から左右辺に沿って直線状に上から下へ略 小円形状のスタッズを並べてなり、上から一つ目と二つ目の間の間隔よりも上から 二つ目と三つ目の間隔の方を長くして三つずつ配し、各スタッズは上から一つ目の スタッズが左右上角部の山部と左右辺中央部の山部との間の谷部上方寄りの位置、 上から二つ目のスタッズが左右辺中央部の山部の頂を直線で結んだ線上の位置、上 から三つ目のスタッズが左右下角部の山部の頂を直線で結んだ線上の位置に設けて なるものであると認められる。
他方、引用意匠は、甲2(別紙第2の2枚目及び3枚目)のとおりであって、上 記認定の証明書記載意匠と対比すると、両意匠の形状等についての相違点は、本件 審決が認定した前記第2の3(5)イのとおり、証明書記載意匠は、正面側のスタッズ を左右寄りに縦一列縦1列に、三つずつ設け、上から一つ目から二つ目よりも二つ 目から三つ目の間隔をやや長く配し、本体部及び把持部は黒色であるのに対し、引 用意匠は、正面側のスタッズを左右寄りに縦一列ほぼ等間隔に四つずつ設け、本体 部はアイボリーで把持部は茶色で、留め付け側に環状金具を配したものであり、両 意匠は、把持部の環状金具の有無、正面側のスタッズの個数及び配置態様並びに把 持部及び本体部の色彩が相違するものである。 そして、証明書記載意匠と引用意匠とは、以下の(4)において判断するとおり、少 なくとも正面視において、正面側のスタッズの個数及び配置態様の点で相違点を有 し、かかる相違点は、物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十\分 理解できる範囲内のものであると認められる場合とはいえないから、同一の意匠と はいえない。
(4) 原告は、両意匠の共通点の形状が特徴的なものであって、需要者に強い印象 を与えているため、正面側のスタッズの個数及び配置態様の相違点の印象は共通点 に比べて薄いものにならざるを得ないから、需要者は、スタッズがバッグの正面側 の態様に関わるものであっても、両意匠の相違点からスタッズの個数や配置を明確 に認識するよりも、両意匠からいずれも大雑把な「複数個のスタッズが並んでいる」 程度の印象を持つと考えるのが自然であり、両意匠の相違点から需要者が受ける印 象は異なるものではないから、両意匠は実質同一といえるものであって、同一の意 匠である旨を主張する。 しかしながら、意匠法4条3項は、同法3条1項の例外として、同法4条2項の 新規性喪失の例外の適用を受けるための特別の要件として規定されているもので あって、原則として意匠登録出願前に意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起 因して公開される意匠ごとに同意匠に係る証明書を提出すべきであり、それゆえ、 証明書に記載される意匠と引用意匠は同一でなければならないと解される。もっと も、証明書に記載される意匠と引用意匠との間に僅少な相違があるにすぎない場合 にも同一性を欠くとすることは相当ではなく、また、意匠登録出願者の手続的負担 も考慮すると、証明書に記載された意匠と引用意匠の相違点が、物品の性質や機能\nに照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内のものであると認めら\nれる場合には、証明書に記載された意匠と引用意匠はなお同一であると認められる と判断するのが相当である。
しかるところ、両意匠の相違点であるスタッズについては、スタッズを設けるこ と自体は、バッグという物品の性質上、ありふれたものであるといえるものの(甲 4〜11)、スタッズの数や配置態様は一様ではなく、その数や配置態様によっては 美観に影響を及ぼすものであるところ、両意匠の相違点であるスタッズの態様につ いては、十分肉眼で看取可能\であって、バッグの正面の意匠の装飾的な構成要素と\nして機能し、「上から一つ目から二つ目よりも二つ目から三つ目の間隔をやや長く」\n三つ配したものと「四つずつ、略等間隔に」配したものとでは、その構成が異なる\n上、両意匠の共通点である収納部の正面上辺及び左右辺の三辺の形状との関係にお いて、証明書記載意匠は、左右辺の山部三つに対して同数の三つのスタッズが配置 されており、二つ目のスタッズが左右辺中央部の山部の頂を直線で結んだ線上の位 置にあるのに対し、引用意匠は、左右辺の山部三つに対して一つ多い四つのスタッ ズが配置されており、二つ目のスタッズが左右上角部の山部と左右辺中央部の山部 との間の谷部下方寄りの位置にあり、上から三つ目のスタッズが左右辺中央部の山 部と左右下角部の山部との間の谷部中央やや上方寄りの位置にあることから、両意 匠の共通点である収納部の正面視の左右辺の山部との関係性からも、それぞれ異な る美観を有するものといえる。
そうすると、両意匠の相違点である正面側のスタッズの個数及び配置態様の点は、 物品の形状等による美観に影響を及ぼす相違点といえることから、証明書に記載さ れた意匠と引用意匠の相違点が物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であ\nると十分理解できる範囲内のものであると認められる場合とはいえない。\nしたがって、上記判断に反する原告の主張は採用できない。
(5) 以上によると、引用意匠が本件証明書に記載されている証明書記載意匠と同 一の意匠であるとは認められず、したがって、引用意匠の公開行為(甲2)は先の 証明書記載意匠の公開に基づいてされたものと認めることはできない。 そうすると、引用意匠については、意匠法4条3項所定の証明書が提出されてい ないことに帰するから、原告は引用意匠について同条2項の適用を受けることはで きない。 よって、本件審決が引用意匠について意匠法4条2項の新規性喪失の例外の適用 を認めなかった点に誤りがあるとは認められない。
2 以上によると、引用意匠は、本願出願前に公開された意匠であり、第2の3 (3)の本件審決の判断のとおり、本願意匠は、その引用意匠に類似するものであるか ら(なお、この点について原告は争っていない。)、本願意匠は意匠法3条1項3号 に掲げる意匠に該当するものであるとの本件審決の判断に誤りがあるとはいえない。 したがって、原告の主張する取消事由には理由がない。
2024.01.30
令和4(ワ)11394 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年1月16日 大阪地方裁判所
本件動画は被告の著作権を侵害するものではない(この点について被告は争って いない。)にもかかわらず、本件削除申請は、グーグル等に対し、本件動画が被告\nの著作権を侵害する旨を摘示するものであるから、客観的な真実に反する内容を告 知するものとして、「虚偽の事実の告知」に当たると認められる。 これに対し、被告は、本件動画は被告の営業上の利益その他何らかの権利を侵害 する旨を主張するが、本件削除申請が虚偽の事実の告知に当たるかどうかの判断と\nは無関係である上、本件動画により被告の何らかの権利が侵害された事実も明らか でないから、採用できない。
2 争点2(本件削除申請は原告の「営業上の利益」を侵害するか)について\n
前提事実に加え、証拠(枝番号があるものは各枝番号を含む。以下同じ。甲4〜 13、15、16)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、ユーチューブ及びツイキ ャスにおいて、本件動画を配信して収益を得ていたところ、本件削除申請は、グー\nグル等のプラットフォーマーに対し、本件動画が被告の著作権を侵害する違法なも のであることを摘示する内容であり、これによって、原告は、ユーチューブにおい ては、別紙「原告動画目録」の「配信停止期間」欄記載の期間、動画の配信が停止 されたことが、ツイキャスにおいては、動画配信によって収益を得ることが少なく とも一定期間停止されたことがそれぞれ認められる。そうすると、本件削除申請は、\n原告が本件動画の配信という営利事業を遂行していく上での信用を害するものとし て、原告の「営業上の利益」を侵害したと認められる。
これに対し、被告は、原告による本件動画の配信は、被告が配信する棋譜情報を フリーライドで利用するという著しく不公正な手段を用いて被告ら棋戦主催者の営 業活動上の利益を侵害するものとして不法行為を構成することを指摘して、本件動\n画の配信に係る営業上の利益は法律上保護される利益に当たらない旨を主張し、こ れを裏付ける証拠として「王将戦における棋譜利用ガイドライン」(乙2)を提出 する。しかし、棋譜は、公式戦対局の指し手進行を再現した「盤面図」及び符号・ 記号による「指し手順の文字情報」を含むものと認められるところ(乙2)、本件 動画で利用された棋譜等の情報は、被告が実況中継した対局における対局者の指し 手及び挙動(考慮中かどうか)であって、有償で配信されたものとはいえ、公表さ\nれた客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報であると解される。 同ガイドラインは、棋譜の利用権等を王将戦主催者が独占的に有する旨規定するが、 王将戦主催者が、原告を含めた被告の実況中継の閲覧者の関与なく一方的に定めた ものであり(乙2)、原告に対して法的拘束力を生じさせるものであるとはいえな い。また、前記1のとおり、本件動画は被告の著作権を侵害するものではなく、そ の他、原告が、被告の配信する棋譜情報を利用することが不法行為を構成すること\nを認めるに足りる事情はない。したがって、被告の前記主張は、その前提を欠き、 採用できない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2024.01.30
令和1(ワ)17622 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月14日 東京地方裁判所
被告は、本件発明1、5は、被告製品1、2の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品1、2は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明1、5を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は1対1として計算すべきであると主張する。
しかし、被告が販売する被告製品1、2は、本件発明1、5を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品1、2に対する一連の ものといえ、本件発明1、5を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法1、2によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品1、2を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2024.01.24
令和1(ワ)17622 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月14日 東京地方裁判所
本件発明6は、電鋳管についての物の発明であるところ、特許請求の範囲に おいて、当該電鋳管について、細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物 を形成する工程(メッキ工程)、細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させる工程(引っ張り工程)、変形させた細線材を除去する工 程(分離工程)を経て製造されることが記載されている。 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、\n特性等が同一である物として認定される。そして、物の発明についての特許に 係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、 当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表\しているのか、又は 物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限 定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当 該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占 権を有するのかについて予測可能\性を奪うことになる。したがって、出願時に おいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか、 又はおよそ実際的でないという事情が存在するなどの第三者の利益を不当に 害しない事情が存在するのでない限り、物の発明についての特許に係る特許請 求の範囲にその物の製造方法が記載されている特許請求の範囲の記載は、特許 法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するとは いえない(最高裁平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷 判決・民集69巻4号700頁参照)。本件発明6の特許請求の範囲において は、物の製造方法が記載されているところ、出願時において製造された物をそ の構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか、又はおよそ実際的 でないという事情についての主張はなく、また、同事情を認めるに足りる証拠 もない。
・・・
本件明細書には、本件発明6の電鋳管と同様の形状等を有する電鋳管につい て本件発明6の方法以外の複数の方法で製造できると記載されている【004 1】、【0042】)。そして、本件発明6の引っ張り工程及び分離工程の方法に よった場合の電鋳管の内面精度について、特許請求の範囲、本件明細書、図面 には記載はない。また、原告が主張する本件発明6の技術的範囲に属するとい う場合の電鋳管の客観的な内面精度自体が必ずしも明確ではなく、また、本件 特許の出願当時、引っ張り工程及び分離工程により製造された電鋳管の内面精 度を含む構造又は特性が、技術常識により明らかであったことを認めるに足り\nる証拠はない。
そうすると、電鋳管の発明である本件発明6について、少なくとも引っ張り 工程及び分離工程に関して電鋳管のどのような構造又は特性を表\しているの かが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明らかであるとは いえない。原告の主張は採用することができない。
・・・
被告は、本件発明1、5は、被告製品1、2の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品1、2は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明1、5を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は1対1として計算すべきであると主張する。 しかし、被告が販売する被告製品1、2は、本件発明1、5を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品1、2に対する一連の ものといえ、本件発明1、5を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法1、2によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品1、2を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。
◆判決本文
なお、本件については、控訴審判決はなさそうですが、対応する審決取消訴訟にて、請求項6は不可能・非実際的理由がなくても、PBPクレームだから自動的に明確性違反だとはならないと判断されてします(内面精度との技術的関係が不明として明確性違反と判断されています)。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載
されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に
いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時
において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\である
か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる(最高裁
判所平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集
69巻4号700頁)。
もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許
請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合(プロダクト・バイ・
プロセス・クレーム)、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され
た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ(前掲最高裁判\n決)、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表\して
いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に
より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を
読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が
その範囲において独占権を有するのかについて予測可能\性を奪う結果となり、
第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。
そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製
造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願
時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表\
しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義
的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不
可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ\nれる。
・・・
そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を
加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着
物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける
ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、
3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細
線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す
るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱
又は溶剤で溶かす方法が記載されている(【0041】、【0116】)が、
これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても
一切記載がなく、ましてや、本件発明6及び訂正発明9の製造方法(上記
3)の方法に含まれる。)が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の
内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上
記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し
たとも認められない。
そうすると、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電
鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2024.01.23
令和5(行ケ)10066 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和5年12月21日 知的財産高等裁判所
ア 瓦を葺いた施工後の状態からは看取できない構成態様について(相違点1、2、6、7関係)\n
相違点1(背面形状)、同2(女瓦の左端部の壁)、同6(男瓦の縮 径段差部の溝の有無及び右側端部の角度)、同7(1)女瓦の上端寄りの 凸部の形状、2)左下端の角度)は、瓦を葺いた施工後の状態からは看取 できない構成態様に関するものである。そこで、本件登録意匠の意匠に係る物品である瓦における、このような相違点の位置づけ、類否判断へ\nの影響の程度について、検討しておく。 そもそも瓦は、本来的に屋根等を葺くための建築部材であって、施工 を前提としない瓦単体のコレクターといった需要者を想定するのは現実 的でない。瓦屋根の建築物を注文し、その所有者等となる施主が中心的 な需要者であり、そうした需要者の求める美観が施工後の外観に係るも のであることは多言を要しない。瓦屋根を施工する建築業者、瓦の販売 業者等も需要者ではあるものの、そうした立場の需要者であっても、最 終的には施主の満足を得させる施工後の外観が最も重視されるものと考 えられる。そうすると、瓦を葺いた施工後の状態から看取できない構成態様が意匠の類否判断に及ぼす影響は相対的に小さいものにとどまると\nいうべきである。
被告は、瓦の需要者である建築業者等は葺き上がった状態で見えなく なる部分についても瓦の重要な機能につながる形状に注意を払い形状全体に目を通して選定する旨主張する。しかし、意匠の類否は基本的に\n「需要者の視覚を通じて起こさせる美観」に基づいて判断されるべきも のであり、機能と造形は両立し得るものではあるが、機能\のみに着眼し た被告の主張をそのまま採用することはできない。 よって、瓦を葺いた施工後の状態からは看取できない相違点1、2、 6、7が、類否判断に及ぼす影響は相対的に小さいものにとどまるとい うべきである。なお、相違点6、7に関しては、本葺一体瓦において採 用される公知の形状のバリエーションの範囲内の違いにすぎないもので あるから(前記1(3)ア〜ウ)、この点においても、当該相違点が類否判 断に及ぼす影響は限定的なものと解される。
・・・
ウ 男瓦の形状及び本件コの字模様の細部の形態等について(相違点3、5 関係)
(ア)本件審決は、本件登録意匠と引用意匠の各対応図面ごとに相違点を認 定しているため、立体形状として認識・把握すれば同じ特徴を、各方 向視ごとに別々に表現するような形式になっており分かりにくいので、相違点3、5に含まれる男瓦の形状及び本件コの字模様の細部の形態\nに係る相違点を整理・再構成すると、下記1)〜3)のとおりとなる(な お、本件審決は、相違点3、5として、下記1)〜3)以外の要素にも言 及している部分があるが、本件登録意匠と引用意匠のそれぞれの図面 における角度の違いや作図方法の違いによる見え方の違いにすぎない ものであり、実質的な相違点ということはできない。)。 1) 本件登録意匠の男瓦は上方に向かって逆ハの字状に広がる円筒形であるのに対し、引用意匠の男瓦は少なくとも真上から見る幅が均一の円筒形である。2) 本件登録意匠においては、引用意匠と比べて、本件コの字模様の両側部の幅が若干広く、本件長方形模様の幅は若干狭い。3) 本件登録意匠の本件コの字模様の部分は本件長方形部分と面一であるが、引用意匠の本件コの字模様はわずかに段差状に隆起している。
(イ)上記相違点1)〜3)は、いずれも、本件登録意匠及び引用意匠の構成態様のうち、看者の注意を強く引く部分である男瓦の連なりの形状及び\n模様に関するもの(上記(3))であるから、その相違点が、両意匠の類 否判断に一定の影響を及ぼすことは否定できない。 しかし、相違点1)は、本葺一体瓦において採用される公知の形態のバ リエーションの範囲内の違いにすぎないし(前記1(3)エ)、相違点2)、 3)は、従前の意匠には見られなかった新規な創作部分である本件コの 字模様に係る共通点を備えた上での、当該模様の些末な違いにすぎな い。もちろん、新規な形態を創作した先行意匠を下敷きとして踏襲し つつも、それにプラスして需要者の注意を一層強く引くような新しい 美観を取り入れたという評価ができれば、当該新しい美観に係る印象 が共通点に係る印象を覆し、類否判断にも相対的に強い影響を及ぼす ということもあり得るところであるが、相違点2)、3)が、両意匠の共 通点である本件コの字模様の持つ強い訴求力を覆すほどの新しい美観 を生じさせるものとは到底認められない。
よって、上記相違点1)〜3)は、類否判断に一定の影響を及ぼすもので はあるが、本件コの字模様に係る共通点4と比較して、意匠の類否判 断に及ぼす影響は相対的に小さいものと解すべきである。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2024.01.19
令和4(行ケ)10081 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟__全文__知的財産裁判例 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
a バイアス層の合計重量(B(g))をバイアス層の合計重量とシャフト全体 にわたって位置するストレート層(以下、単に「ストレート層」という。)の合計 重量の和(B(g)+S(g))の50%以上とすることにより得られる効果等に 関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明のゴルフクラブ用シャフトは、 シャフトに使用するバイアス層の合計重量をB(g)、シャフト全体に渡って位置 するストレート層の合計重量をS(g)とした場合に、0.5≦B/(B+S)≦ 0.8・・・(1)を満たすことが重要である。(1)は、技量が高いゴルファー やスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクTq(°) を生み出す要素を示している。つまり、(1)を満たさないゴルフクラブ用シャフ トは、シャフトが捩じれすぎたり、または捩じれないがためにシャフトが折損して しまう原因につながる。」との記載(【0014】)があり、また、本件効果が得 られたとされる実施例1及び本件効果が得られなかったとされる比較例1における 各B/(B+S)がそれぞれ0.6及び0.4であるとの記載(【表4】)がある。\nしかしながら、これらの記載は、本件各発明におけるB/(B+S)に係る0.5 との数値が実施例1における0.6及び比較例1における0.4の中間値であるこ とを含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重 量の和の50%以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切 に説明するものとはいえず、したがって、構成3のうちバイアス層の合計重量をバ\nイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の50%以上とするとの点につ いては、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本 件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
b 原告は、バイアス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小 さくできることは自明であり本件出願日当時の技術常識であるとして、本件出願日 当時の当業者は実施例1と比較例1との比較から、バイアス層の合計重量をバイア ス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の50%以上としておけば、その他 の条件を技術常識の範囲内で適宜調整して決定することで、容易にTq≦4.0° の構成(構\成2)が得られるものと理解し得ると主張する。しかしながら、バイア ス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小さくできることが本件 出願日当時の技術常識であったとしても、原告の上記主張は、実施例1と比較例1 を比較する点を含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート 層の合計重量の和の50%以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかに ついて適切に説明するものとはいえず、その他、バイアス層の合計重量をバイアス 層の合計重量とストレート層の合計重量の和の50%以上とすることにより本件課 題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、 構成3のうちバイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計\n重量の和の50%以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当 時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるという ことはできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 数値限定
>> パラメータ発明
>> ピックアップ対象
2024.01.19
令和5(行ケ)10079 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年12月26日 知的財産高等裁判所
ア 前記1において認定した事実によると、引用標章1の周知性に関し、次の事 情が認められるというべきである。 すなわち、原告商品は、外国の会社が製造する菓子であり、その名称を「Tro lli Planet Gummi」、「Planet Gummi」などとする ものであって、原告商品又はその包装若しくは個包装には、日本語からなる「地球 グミ」との文字は記載されていない。しかしながら、原告商品は、平成30年頃、 動画投稿者及びその閲覧者を中心に韓国において大流行したところ、この流行が日 本にも飛び火し、原告商品は、令和2年頃からは、日本においても、動画投稿者及 びその閲覧者を中心に大流行し、遅くとも原告が原告商品の輸入販売を開始した同 年10月までには、全国に店舗を展開する小売業者の中に、原告商品を「地球グミ」 と称してこれを宣伝する者が現れるようになった。原告が原告商品の輸入販売を開 始した後についてみても、原告商品は、大人気を誇り、小売業者の店舗における販 売開始後すぐに完売となるという事態が相次ぎ、その入手が極めて困難な商品とな った。原告が原告商品の輸入販売を開始して以来、全国に店舗を展開する小売業者 らは、原告商品を「地球グミ」と称してこれを繰り返し宣伝し、また、原告商品は、 動画投稿サイトにおいても、「地球グミ」と称する商品として大人気を博していた。 そのような原告商品は、令和3年6月、「地球グミ」と称する大人気商品として、 全国紙による新聞報道及び在阪の準キー局によるテレビ報道がされるまでに至り、 同テレビ報道においては、同年上半期にはやった飲食物としてZ世代が選ぶランキ ングにランクインした。原告商品は、翌7月、同様の人気商品として、在京のキー 局によるテレビ報道がされるに至り、20代前半の若者が皆知っていることとして 紹介された(なお、原告は、遅くとも同年6月には、テレビ番組において、原告商 品を「地球グミ」と称しており、また、遅くとも同年9月には、原告商品を「地球 グミ」と称する宣伝をするようになった。)。さらに、「地球グミ」と称する原告 商品は、同年11月、動画投稿サイトへの投稿がきっかけで人気となった作品又は 商品の例として、著名作家の小説、有名シンガーソングライターの楽曲等と並べて\n紹介されるとともに、渋谷区にある著名な商業施設の運営会社による調査(15歳 から24歳までの女性545名を対象としたもの)の結果である「SHIBUYA 109lab.トレンド大賞2021」なる賞においても、その「カフェ・グルメ 部門」の2位に入賞した。このような「地球グミ」と称する原告商品の令和3年ま での動向を踏まえ、令和4年1月に発行された「現代用語の基礎知識2022」に おいては、令和3年中に注目された物(食に係るヒット商品)として、原告商品の 俗称たる「地球グミ」の語が取り上げられるに至った。 以上の事情に照らすと、「地球グミ」の語(引用標章1)は、遅くとも本件査定 日(令和4年2月22日)までには、原告又は原告商品の製造業者の業務に係る商 品(原告商品)を表示するものとして、需要者(引用標章1が使用される商品の内\n容及び性質並びに前記1の事実に照らすと、若者を始めとするグミキャンディの消 費者であると認められる。)の間に広く認識されている商標に該当していたものと 認めるのが相当である。
イ なお、被告は、引用標章1は商標として使用されていなかったと主張するが、 前記1(13)、(15)、(16)及び(25)によると、原告は、原告商品に関する広告を内容 とする情報に引用標章1を付して電磁的方法により提供していたと認められるから、 被告の主張を採用することはできない。
(2) 本件商標と引用標章1の類否
前記第2の1(5)のとおり、本件商標は、「地球グミ」の文字を標準文字で表し\nてなるものである。これに対し、前記第2の3(1)ア(ア)のとおり、引用標章1は、 「地球グミ」の文字を書してなるものである。 このように、本件商標と引用標章1は、その外観において、極めて相紛らわしい ものである。 また、本件商標及び引用標章1からは、いずれも「チキュウグミ」の称呼が生じ るから、両者は、称呼を同じくする。 さらに、前記(1)アにおいて説示したところに照らすと、「地球グミ」は、需要 者の間において原告商品を指す語であると認識されるといえるから、本件商標及び 引用標章1からは、いずれも、「地球のグミキャンディ」などの観念のほか、「原 告商品」(商品名を「Trolli Planet Gummi」、「Plane t Gummi」などとするグミキャンディ)の観念が生じるといえ、両者は、観 念を同じくする。 以上によると、本件商標は、引用標章1と称呼及び観念を同じくし、外観におい て極めて相紛らわしいから、引用標章1に類似する商標であると認めるのが相当で ある。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2024.01.19
令和5(行ケ)10083 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年12月21日 知的財産高等裁判所
そして、商品の形状は、本来、商品の機能をより効果的に発揮させたり、\n美観を向上させるために選択されるものであるから、商品の形状からなる商 標は、その形状が、需要者において、その機能又は美観上の理由から選択さ\nれると予測し得る範囲を超えたものである等の特段の事情のない限り、商品\n等の形状そのものの範囲を出るものでなく、商品の形状を普通に用いられる 方法で表示する標章のみからなるものとして、商標法3条1項3号に該当す\nるものと解される。
(2) 本願商標は、白色の長方形を縦長に描き、その内側の中央に、辺の長さが 外側長方形部分の約半分程度の、影様の黒色の線で縁取りされた白色の縦長 の長方形を配し、内側長方形部分の右側長辺に影様の薄い灰色の直線を配し、 その左に上端から下端までの長さよりやや短く、縦に緑色の直線を描いてな るものである。そして、本願商標同様の形状を有する原告製造に係る「電気 スイッチ」に係るカタログ(甲3の1)には、「シンプルで、明瞭な要素で 構成されること。ミニマルで、偏りのない美しさを持つこと。ひとつの空間\nを超えて、建築が持つ思想へと向かう存在になること。」との記載があり、 JIS大角連用形スイッチとの取付互換性の確保も強調されている。
一方、メーカー、施工会社、ユーザ等のウェブサイト(乙1〜8、10〜 13)によれば、本願商標の指定商品である「電気スイッチ」を取り扱う業 界において、外側の縦長の略長方形の内側に、表示灯を施した縦長の長方形\nの押しスイッチを配した構成の電気スイッチは、広く使用されていること、\n表示灯の形状、位置、点灯した際の色彩は様々なものが採用されていること\nが認められる。そして、これらの電気スイッチの形状は、「もっと美しく、 使いやすく。/これからのくらしのスタンダード」(乙2)、「インテリア と響きあう/住まいに必要なものだから“美しさ”にこだわりたい。みんな が使うものだから“使いやすさ”を求めたい。」(乙6)といった謳い文句 からも理解されるとおり、商品の機能や美観を発揮させるために選択されて\nいるものと解される。
上記のような実情に鑑みると、本願商標の形状は、指定商品である「電気 スイッチ」の用途、機能、美観から予\測できないようなものということはで きず、需要者は、本願商標から、「電気スイッチ」において採用し得る機能\n又は美感の範囲内のものであると感得し、「電気スイッチ」の形状そのもの を認識するにすぎないというべきである。
原告は、前記第3の1(1)のとおり、アイコン等としての使用が予定され\nる図形商標(平面商標)について、立体商標と同様の厳格な基準を適用する べきではない旨主張するが、前記(1)に説示したところは立体商標か図形商 標かによって左右されるものではなく、採用できない。なお、本願商標が指 定商品の形状を表すのでなく、アイコン等としてのみ使用されるものと認識\nされると認めるに足りる証拠もない。
また、原告は、前記第3の1(1)のとおり、商品の形状のみからなる図形商 標が、当該商品を指定商品に含めて商標登録されている事例は、多々存在す る旨主張するが、登録出願に係る商標が商標法3条1項3号に該当するもの であるか否かの判断は、個別具体的にされるべきものである上、原告引用に 係る事例は、ゲームコントローラやタブレット端末であって(甲1、2)、 需要者層や商品形状の有する意味合いに関し本願商標と大きく異なる点が あると考えられるものであり、採用できない。
さらに、原告は、前記第3の1(2)のとおり、原告の電気スイッチは、幅広 な操作スイッチを持たず、表示灯を操作スイッチの右端において上端から下\n端まで一直線に設けるという独自の構成を有し、数々の受賞歴を有し、こだ\nわりのあるユーザに高い評価を得ている旨主張するが、視覚を通じて美観を 起こさせる物品の形状等の創作を奨励、保護する意匠法による保護の対象と すべき根拠とはなっても、自他商品の識別標識としての商標を対象とする商 標法の保護とは次元が異なる問題である。
(3) 以上のとおりであって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした 本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2023.12.19
令和5(行ケ)10067 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年12月4日 知的財産高等裁判所
ア 本件商標は、前記第2の1(1)のとおり、「5252byO!Oi」の数字、 欧文字及び感嘆符を黒色のゴシック体にて同じ大きさ、等しい間隔で一連に横書き してなるものである。もっとも、このうち「by」という語は、一般に「by 〇 〇〇」との用法により「商品や役務の出所が〇〇〇」であることを表す英語の前置\n詞として我が国において広く用いられ、親しまれていることや、「by」が小文字で 書されていることからすると、本件商標は、全体として、「by」の後の「O!Oi」 の部分を、独立して、見る者の注意を引くように構成されているといい得るもので\nある。また、本件商標のうち「5252」の部分は単に数字を羅列するものであっ て格別の識別力を有しないのに対し、「O!Oi」の部分は、欧文字を用いながらも 辞書等に載録される語ではない上、「オーオイ」又は「オーオーアイ」との称呼を生 じ得るものではあるが、感嘆符を用いていることからその称呼も一様に定まるもの ではなく、丸と縦線とが交互に用いられている点において視覚的に際立った印象を 与え、造語とも図形とも理解できる特徴的なものといえる。これらに加えて、上記 のとおり、「商品や役務の出所が○○〇」であることを示すものとして「by〇〇〇」 との用法が広く用いられ、親しまれていることからすると、「by」の後に配された 「O!Oi」の部分は、本件商標の構成の中でも、出所識別標識として強く支配的\nな印象を与えるというべきである。そうすると、「O!Oi」の部分は、本件商標の 一部分ではあるものの、商標全体の出所識別標識としての機能を果たしていると認\nめられるから、この部分を本件商標の要部として抽出し、この部分(以下「本件要 部」という。)だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されると いうべきである。
被告は、前掲最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決を引用し、同じ書体、同 じ大きさで隙間なく一連に横書きしてなる本件商標の構成部分の一部である本件要\n部のみを他人の商標と比較することは許されない旨主張する。しかし、上記のとお り、本件要部は、その後に続く語が商品等の出所であることを示す英語の前置詞と して我が国で広く用いられ、親しまれている「by」の後に配されていることによ り、独立して、商品等の出所を示すものとして、見る者の注意を引くように構成さ\nれているといい得るものである上、造語とも図形とも理解できる特徴的な形状を有 し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる一方、本件商 標の他の部分である「5252」「by」の部分は格別の識別力を有しないのである から、本件要部だけを他人の商標と比較することは許されるというべきである。被 告の主張は採用することができない。
イ 本件要部は、「O!Oi」の欧文字及び感嘆符を黒色のゴシック体にて同じ大 きさ、等しい間隔で一連に横書きしてなるものである。また、本件要部からは、そ の構成文字に相応して「オーオイ」「オーオーアイ」の称呼を生じ得る。他方、これ\nらの欧文字の配列は辞書等に載録されている語等を構成するものではなく、上記の\nとおり生じ得る称呼からも特段の意味合いを見いだせないことからすれば、本件要 部からは特定の観念を生じないものといえる。
ウ 本件商標の指定商品は前記第2の1(1)のとおりであり、被服やかばん類等 のファッション・アパレル関連商品や、携帯電話機用アクセサリー、ヘッドフォン、 眼鏡等の一般消費者が身に付ける物が中心となっている。
(3) 引用商標3について
ア 引用商標のうち、引用商標3の構成は別紙2の3の「商標の構\成」のとおり であり、赤色の丸ゴシック体にて同じ大きさ、等しい間隔で「OIOI」と書して なるものである。引用商標3からは、その構成文字に相応して「オーアイオーアイ」\n「オイオイ」の称呼を生じるほか、前記1に認定した事実関係によると、原告標章 は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、一般消費者を含むファッショ ン・アパレル関係の取引者、需要者において著名な商標であったと認められるから、 色彩のほかは原告標章と同一の構成を有する引用商標3からは、「マルイ」との称呼\nも生じ、「マルイのロゴマーク」との観念も生じるものと認められる。
イ 引用商標3の指定商品には、被服やかばん類等のファッション・アパレル関 連商品や、キーホルダーや眼鏡等の一般消費者が身に付ける物が含まれている。
(4) 本件商標と引用商標3の類否について
本件要部からは特段の観念を生じないのに対して、引用商標3からは「マルイの ロゴマーク」との観念を生じるので、両者の観念は同一とはいい難い。 次に、本件要部からは「オーオイ」「オーオーアイ」の称呼を生じ得るのに対し、 引用商標3からは「オーアイオーアイ」「オイオイ」及び「マルイ」の称呼を生じ得 るところ、本件要部に「!」が含まれていることの関係で厳密には称呼が異なるも のの、多くの音を共通にしており、相応に類似しているというべきである。 また、両者の外観についてみると、本件要部及び引用商標3は、いずれもゴシッ ク体にて四つの文字又は記号を書してなり、1字目と3字目はいずれも「O」で共 通している。2字目は「!」と「I」、4字目は「i」と「I」と異なる文字又は記 号が使用されているが、いずれも1本の縦線又は1本の縦線とその延長線上にある 点により構成される点において形状が類似している。加えて、各文字の字間を含め\nた配列も近似している。そうすると、両者の外観は、子細にみると異なる部分はあ るが、時と場所とを異にする隔離的観察の下では、互いに相紛らわしいというべき である。
以上に加え、本件商標及び引用商標の各指定商品は、いずれもファッション・ア パレル関連商品や一般消費者が身に付ける物であるから、その取引者、需要者には 一般消費者が含まれるところ、本件要部からは特段の観念を生じず、本件要部及び 引用商標3から生じ得る称呼は同一ではないが相応に類似している上、いずれも単 一の確たる称呼が生じるといい難いことから、取引者、需要者にとってみれば称呼 が出所識別標識として決め手とはなりにくいとうかがわれること、一般消費者は、 アパレル・ファッションや身に付ける物の出所につき、主として対象商品やロゴマ ークの外観等に注目するとみられること等も総合すると、上記のとおり、引用商標 3との関係で、称呼について相応に類似し、外観において互いに相紛らわしい本件 要部を持つ本件商標は、その構成全体が引用商標3と同一ではないことを考慮して\nも、両商標が本件商標の各指定商品に使用された場合には、取引者、需要者が両者 の出所を見誤る可能性は否定できず、その商品の出所において誤認混同が生じるお\nそれがあるものと認められる。 したがって、本件商標は、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、 その商品に係る取引の実情を踏まえて全体的に考察すると、引用商標3に類似する 商標と認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.12.14
令和4(ワ)5553 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年12月7日 大阪地方裁判所
前記認定事実アによれば、本件プレイヤードの部材Aは本件発明の縦枠に、 部材Bは側面シートに、部材Cは底面シートにそれぞれ相当し、部材Gに固定され た部材Aの下端部分は、部材Cの六角形の頂点にあたる部分に部材Dを介して固定 され、外側への移動が制限されているものと認められる。そうすると、本件プレイ ヤードは、「環状に配置され、それぞれが内側に傾斜する複数の部材A(縦枠)と、 隣り合う部材Aを渡すように張られメッシュ部B1を有する部材B(側面シート) と、底面に位置する非伸縮性の部材C(底面シート)と、を備え、部材Cは平面視 において多角形の形状を有しており、各部材Aの下端部分は非伸縮性の部材Cの多 角形の頂点にあたる部分に(部材Dを介して)固定され外側への移動が制限されて いる、プレイヤード」との構成を有するものということができるから、本件発明の\n各構成要件を充足する。\n
そして、特許法29条1項2号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多 数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記認定事実イ のとおり、被告は、本件特許出願前の平成17年頃、カタログに本件プレイヤード を掲載して需要者に対して販売していたから、その内容を不特定多数の者が知り得 る状況で本件発明を実施したものと認められる。
(4) 原告は、本件無効審判事件の進行状況等に照らすと、被告による乙第12 号証を証拠とする無効理由の主張は、時機に後れた攻撃防御方法として却下される べきである旨の申立て(民訴法157条1項に基づくものと理解される。)をする。\nしかし、攻撃防御方法の提出について時機に後れたかどうかは、本件訴訟の具体的 な進行状況等に即して判断されるべきである。そして、原告の訂正の再抗弁等に対 するものとして、乙第12号証及びこれに基づく無効理由を主張する被告の準備書 面(1)が令和5年2月15日に提出されたところ、その時点では、書面による準備 手続における協議が重ねられ、争点及び証拠の整理手続中(いわゆる心証開示前) であり、被告が故意又は重大な過失により当該攻撃防御方法を提出したとか、それ により訴訟の完結が遅延するなどの客観的な事情があったとは認められないから、 原告の前記申立ては理由がないものとして却下する。\n
(5) 以上のとおり、本件発明は、本件特許出願前に日本国内において公然実施 された発明であって、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきものである から、後記3で検討する訂正の再抗弁が成り立たない限り、原告は、被告に対し、 本件特許権を行使することができない(特許法123条1項、104条の3第1項、 29条1項2号)。
3 訂正の再抗弁の成否(争点3)について
本件訂正により、本件プレイヤードに基づく新規性欠如(前記2)の無効理由が 解消されるか否かにつき検討する。
(1) 原告は、本件訂正発明と本件プレイヤードを対比すると、1)本件訂正発明 の接続テープは各縦枠に対して取外しできるように構成されているのに対し、本件\nプレイヤードの部材Dは部材Aに対して取外しできるように構成されていない点、\n2)本件訂正発明の側面シート及び底面シートは各縦枠に対して取外し可能に構\成さ れているのに対し、本件プレイヤードの部材B及び部材Cは部材Aに対して取外し 可能に構\成されていない点の2つの相違点があるから、本件訂正により本件プレイ ヤードに基づく新規性欠如の無効理由は解消される旨主張する。
(2) しかしながら、前記2(2)ア認定のとおり、本件プレイヤードにおいては、 各部材Aの下端部分は、接地部材Gが受けて固定しているところ、部材Cに取り付 けられた部材D(テープバンド)が部材Gに挟み込まれて2か所でねじ止めされて (以下「本件ねじ止め」という。)、各部材Aの下端部分が(部材Dを介して)部 材Cに固定されている。そして、本件ねじ止めは、タッピングねじによるものであ るが、ねじの取外しをすることは可能であり、このねじを取り外せば、部材Dを部\n材Aの下端部分が固定されている部材Gから取り外すことができるから、部材Dは、 部材Aに対して取外し可能であると認められる。\nまた、前記のように部材Dを部材Aから取り外せば、部材Dが取り付けられてい る部材C及びこれと一体に形成されている部材B(前記2(2)ア)も部材Aから取 り外すことができるものと認められる。 そうすると、本件訂正発明と本件プレイヤードの対比において、原告が主張する 前記(1)の1)及び2)の相違点はいずれも認めることができない。
(3) これに対し、原告は、本件ねじ止めはタッピングねじによるものであると ころ、同ねじは、日常的に繰り返し取り外す必要がある部位には使用されないもの であるから、本件プレイヤードは、使用者が再組立できなくなる等のリスクを冒し てまで、部材Dや部材B及び部材Cの「取外し」を行うことは想定されていない旨 主張する。しかし、本件訂正発明の構成要件Xは「…各縦枠に対して取外しできる\nように構成されている接続テープを備え」、構\成要件Yは「前記側面シート及び前 記底面シートが…各縦枠に対して取外し可能に構\成されている」というものである ところ、取外しの具体的な態様や頻度等について何ら限定をしていない。そうする と、タッピングねじによる本件ねじ止めは、その構造上も実際上も取外し可能\であ る以上、本件プレイヤードの構成につき、本件訂正発明の前記各構\成要件との相違 点を認めることはできず、原告の主張は採用できない。
また、原告は、本件プレイヤードは「WATERPROOF」、つまり防水性の 製品であって、洗濯機での洗濯や脱水は危険であることから、市販製品の一般的な 意味での「取外し」はできず、このような製品を「取外し可能」と評価することは\nできない旨主張する。しかし、本件訂正発明の構成要件X及びYにおいて、「取外\nし」の目的が特定されているものではないし、本件明細書の段落【0013】の記載 (「この構成によれば、側面シートと底面シートを縦枠から取り外して洗うことが\nできるため、幼児用サークルを清潔に保つことができる。」)を参酌するとしても、 その洗い方が洗濯機によるものに限定されているものではないから、原告の主張は 採用できない。
(4) したがって、本件訂正によっても、本件プレイヤードに基づく新規性欠如 の無効理由は解消されないから、原告の訂正の再抗弁は成り立たない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.12.14
令和2(ワ)25892 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年11月29日 東京地方裁判所
イ 本件明細書には、「本発明の物品は、カートリッジの嵌合端部と嵌合す る受容端部を有する制御ハウジングも含むことができる。したがって、制 御ハウジングとカートリッジ本体は、機能可能\に連結されるものとして特 徴づけることができる。このような受容端部は特に、カートリッジの嵌合 端部を受容する開口端部を有するチャンバーを含んでよい。・・・特有の 実施形態では、カートリッジの嵌合端部を制御ハウジングの受容端部と嵌 合させると(カートリッジの嵌合端部を制御ハウジングのチャンバーの中 まで所定の距離だけスライドさせるなどすると)、吸引可能な物質媒体と\n電気加熱部材が整列して、吸引可能な物質媒体の少なくとも一部分を加熱\nできるようになる。」(【0008】)、「カートリッジ本体305は、 制御ハウジング200の受容チャンバー210と嵌合する嵌合端部310 と、」(【0040】)との記載がある。また、図4、図7、図9等には、 吸引可能な物質を消費者の方に運ぶように構\成された反対側の吸い口端と、 外面および内面を有する壁とを有する実質的に筒状のカートリッジの嵌合 端部310が示されるとともに、電気加熱部材に電力を供給する電気エネ ルギー源を含む制御ハウジングの端部として、中央部の円筒状の突出部を 取り囲むように、円筒形のカートリッジの外壁の外径よりやや大きい内径 を有する円筒形の受容チャンバー壁があり、カートリッジを受容チャンバ ーに挿入することで、カートリッジの外壁であり嵌合端部の外側が、受容 チャンバーの外壁の内側に、ほとんど隙間なく接する状態が示されている。 すなわち、本件明細書には、カートリッジの嵌合端部と制御ハウジング の嵌合端部(受容端部)が嵌合すると記載され、その実施形態として、カ ートリッジが制御ハウジングの受容チャンバーに挿入されることで、相補 形状を有するといえる、円筒形の外壁という形状を有するカートリッジの 嵌合端部と、円筒形の受容チャンバー壁という形状を有する制御ハウジン グの嵌合端部(受容端部)とが、カートリッジの外壁の外側の嵌合端部が 受容チャンバーの外壁の内側に接することで、ほとんど隙間なく配置され るという状態ではまり合っていることが示されているといえる。これは、 上記の「嵌合」についての一般的な意義に沿ったものである。他方、本件 明細書には、制御ハウジングの「受容端部」あるいは「受容チャンバー」 については、【0008】、【0040】以外に、本件明細書の【001 2】、【0018】、【0027】、【0059】、【0061】、【0 102】等にも記載があるが、カートリッジの嵌合端部の端面に接触又は 近接するのみで、それを制御ハウジングの「受容端部」とする記載はない し、上記アの一般的な意義と異なる意味で「嵌合」が使われていることを 示唆する記載もない。
ウ 本件発明は、前記1 のような技術的意義を有するところ、制御ハウジ ングとカートリッジの関係として、想定し得る様々な構成のうち、構\成要 件Dにおいて「前記制御ハウジングは、前記カートリッジに機能可能\に連 結されている嵌合端部を有する」として、それぞれの嵌合端部が「嵌合」 するものであることを明確に定めている。そして、そのような構成の下で、\n制御ハウジングとカートリッジが「機能可能\に連結され」、また、「吸引 可能な物質媒体と電気加熱部材が整列して、吸引可能\な物質媒体の少なく とも一部分を加熱できるように」なることがあるとしている。 本件発明においては、制御ハウジングとカートリッジの関係が上記のと おり定められているところ、「嵌合」の語句の一般的な意義(前記ア) や本件明細書の記載(前記イ)もその一般的な意義を前提としていると 解されることからも、「前記カートリッジに機能可能\に連結されている 嵌合端部」とは、その嵌合端部自体が一定の形状を有するとともに、ハ ウジングの嵌合端部も一定の形状を有し、それら両嵌合端部の形状が、 相補形状であり、それぞれの形状によって、互いにほとんど隙間なくは まり合うものをいうと解される。
(3) 被告製品の構成dについて\n
ア 被告製品の構成dは、「加熱式デバイスは、加熱式タバコスティックを\n受け入れるエンドキャップと、エンドキャップの底面に形成されたスリッ トを貫通してエンドキャップ内まで延びるヒータブレードのベース部上に 形成された導電トラックに電力を供給するバッテリーを含むメインボディ と、を有する加熱式喫煙デバイスであって、使用者はエンドキャップの底 面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入可能であり、該挿入によっ\nてヒータブレードのベース部が加熱式タバコスティックに挿入され、加熱 式喫煙デバイスのスイッチが入れられると、タバコロッドを加熱するため に、ヒータブレードの導電トラックがバッテリーと通電し、」である。 そして、構成要件Dの「カートリッジ」に当たり得るのは加熱式タバコ\nスティックであり、当該加熱式タバコスティックの篏合端部に当たり得る のは、加熱式タバコスティックの吸い口とは反対の先端部である。
イ 原告らは、エンドキャップに加熱式タバコスティックがぴったりとはま るから、エンドキャップの底面と、加熱式タバコスティックの先端面は、 ほぼ同径の円形であり、「形状が合った物」であり、「エンドキャップの 底面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入可能であ」ることは「は\nめ合わせる」ことである旨主張する。 しかしながら、加熱式タバコスティックの先端面の形状とエンドキャッ プの底面の形状自体はほぼ同径の円形であるとしても、エンドキャップ の底面に達するまで加熱式タバコスティックを挿入した状態は、加熱式 タバコスティックの先端面がエンドキャップの底面に突き当たって接し た状態になっているのみである。加熱式タバコスティックの先端面とエ ンドキャップの底面のそれぞれの形状は、相補形状ではなく、それぞれ の形状によって、互いにほとんど隙間なくはまり合うものであるとはい えない。
なお、制御ハウジングは、構成要件Dの文言上、「前記電技加熱部材に\n電力を供給する電気エネルギー源を含(む)」(構成要件D)ものであ\nるところ、被告製品における制御ハウジングはメインボディであるから、 エンドキャップそれ単独では、制御ハウジングに当たることはない。 ウ 原告らは、ヒータブレードのベース部が「篏合端部」に当たるとも主張 する。
しかしながら、前記のとおり、構成要件Dの「カートリッジ」に当たり\n得るのは加熱式タバコスティックであり、当該加熱式タバコスティックの 篏合端部に当たり得るのは、円筒状の形状を有する加熱式タバコスティッ クの吸い口とは反対の先端部であるが、当該先端部は、原告らが「篏合端 部」と主張するヒータブレードのベース部の形状と、相補形状ではなく、 それぞれの形状によって、互いにほとんど隙間なくはまり合うものである とはいえない、なお、このことは、ヒータブレードのベース部とエンドキャップ底面と を合わせた構成を考えても同様である。\n
エ 以上によれば、被告製品の構成dのヒータブレードのベース部とエンド\nキャップ底面は、いずれも構成要件Dの「篏合端部」に当たらず、その他、\nこれに該当する部分はないといえる。 そうすると、被告製品は、構成要件Dを充足する部分を有せず、その余\nを判断するまでもなく本件発明の技術的範囲に属さない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.12.12
令和4(行ケ)10109 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年11月30日 知的財産高等裁判所
(1) 特許法36条4項1号は、特許による技術の独占が発明の詳細な説明をも って当該技術を公開したことへの代償として付与されるという仕組みを踏 まえ、発明の詳細な説明の記載につき実施可能要件を定める。このような同\n号の趣旨に鑑みると、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するた\nめには、当該発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、 当業者が過度の試行錯誤を要することなく、特許を受けようとする発明の実 施をすることができる程度の記載があることを要するものと解される。
(2) そこで検討するに、まず前提として、本件明細書記載の第1実施形態によ り本件3条件を満たす防眩フィルムを製造することができることは争いが ないところ、被告は、本件特許発明は第2実施形態に係る防眩フィルムであ って、第1実施形態は本件特許発明に含まれない旨主張する。 しかし、本件明細書で第1実施形態を説明する【0056】の「防眩層3 は、マトリクス樹脂中に分散された複数の微粒子(フィラー)を含んでいて もよい。」との記載、【0058】の「微粒子の平均粒径は特に限定されず、 例えば、0.5μm以上5.0μm以下の範囲の値に設定できる。」との記載 及び【0059】の「微粒子の平均粒径が小さすぎると、防眩性が得られに くくなり、大き過ぎると、ディスプレイのギラツキが大きくなるおそれがあ るため留意する。」との記載を参酌すれば、第1実施形態には、スピノーダ ル分解による凝集と微粒子の凝集の両方により表面に凹凸の分布構\造が形 成されている防眩層を備える防眩フィルムが含まれているといえる。したが って、本件特許発明においては、スピノーダル分解による凝集のみにより表\n面に凹凸の分布構造が形成されている防眩層は含まないが、スピノーダル分\n解による凝集と微粒子の凝集の両方により表面に凹凸の分布構\造が形成さ れている防眩層は排除されていないのであり、第1実施形態に係る防眩フィ ルムが本件特許発明に含まれないとする被告の主張は採用できない。
(3) 以上を前提に実施可能要件の充足性について検討するに、第1実施形態は、\n防眩層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を 急峻化するとともに、凹凸の数を増やすことにより、ディスプレイのギラツ キを抑制しながら防眩性を向上させるものである(【0078】)。第1実 施形態と、第2実施形態とは、上記原理を共通にし、第1実施形態では、ス ピノーダル分解によって凹凸を防眩層に形成するのに対し、第2実施形態で は、複数の微粒子を使用し、防眩層の形成時に微粒子とそれ以外の樹脂や溶 剤との斥力相互作用が強くなるような材料選定を行うことで、微粒子の適度 な凝集を引き起こし、急峻且つ数密度の高い凹凸の分布構造を防眩層に形成\nするという点において異なる(【0079】、【0080】)。 そして、本件明細書には、第1実施形態に関して本件3条件に係る防眩層 の特性は、溶液中の樹脂組成物の組み合わせや重量比、調製工程、形成工程、 硬化工程の施工条件等を変化させることで形成できるものであることが記 載されており(【0068】)、第2実施形態について、微粒子や、防眩層 を構成するマトリクス樹脂の材料(【0086】〜【0094】)、マトリ\nクス樹脂と微粒子との屈折率差(【0081】)、粒径(【0082】)、 防眩層におけるマトリクス樹脂と微粒子の割合(【0085】)、製造方法 (【0095】〜【0102】)、調製に使用する溶剤(【0096】)が 具体的に記載されるとともに、実施例5においては、シリカ粒子がブタノー ルに対して斥力相互作用を生じたことにより、凹凸構造が強調されること\n(【0188】)が、記載されているから、当業者は、第1実施形態に係る 【0186】及び【0187】の記載に加え、【0068】及び【0079】 の記載を併せ考えれば、各生産工程における条件の適切な設定や、アクリル 系紫外線硬化樹脂とアクリル系ハードコート配合物Aを共存させること等 の調整を行うことによって、第2実施形態に関して、実施例として記載され た防眩フィルムをはじめとする様々な特性の防眩フィルムを得られること を理解するものということができる。したがって、仮に本件特許発明が、微 粒子の凝集のみにより表面に凹凸の分布構\造が形成された防眩層を備える 防眩フィルムであるとしても、当業者は本件特許発明に係る防眩フィルムを 製造することができるといえる。
被告は、凹凸を形成する方法(原理)が異なれば凹凸の形成に適した材料 は異なり、それに伴い斥力相互作用が生じる材料の組み合わせも異なるから、 微粒子とそれ以外の樹脂や溶剤との斥力相互作用が強くなるような材料選 定についての手がかりは本件明細書に開示されていないと主張する。しかし、 微粒子の凝縮によって形成される凹凸構造の形状は、スピノーダル分解の凝\n集が進行したことによる上記液滴相構造の形状と同様のものであると解さ\nれるから、第1実施形態の凹凸構造を参考にできるものと解される。そして、\n上記のとおり、本件明細書には、本件特許発明に係る特性を導く上で主要な 構造となる凹凸の急峻性を生み出す原理とその具体的方法、原材料から製造\nの工程に係る記載があり(特に【0079】)、当業者は、微粒子の凝集を 用いてより急峻な凹凸を形成する場合には、微粒子の重量部を大きくし、さ らに必要に応じてブタノールの重量部を大きくし、斥力を大きくするなどし て、通常の試行錯誤の範囲内で、シリカ粒子やブタノールの量などを具体的 に決定し、その実施品を作ることができるものというべきである。
(4) 被告は、本件明細書の【0005】、【0008】の記載から、本件特許 発明の目的のうち、「高い透過像鮮明度の設計自由度を有する防眩フィルム を提供すること」とは、外光の映り込みを防止すること(高いヘイズ値とす ること)と、ディスプレイの表示性能\を維持すること(高い透過像鮮明度と すること)とのトレードオフの相関関係に起因して、従来、透過像鮮明度の 設計自由度が制約を受けていたところ、ギラツキを所定の範囲にまで抑制さ れるとともに、前記制約を克服した領域ともいうべき領域である本件高ヘイ ズ・高鮮明度領域における透過像鮮明度を備えた防眩フィルムを提供するこ とであると当業者は理解するから、本件高ヘイズ・高鮮明度領域について製 造方法の記載が求められると主張する。 しかし、まず、本件明細書の【0005】の記載からは、外光の映り込み の防止とディスプレイの表示性能\の維持の間に厳格なトレードオフの関係 があるとまで認めることはできない。本件特許発明の第1実施形態に係る実 施例1〜4、比較例2〜3、10及び11、第2実施形態に係る実施例5、 比較例1、4〜9における防眩フィルムのヘイズ値及び透過像鮮明度の数値 (本件明細書【0183】の【表1】、【0184】の【表\2】)からは、 ヘイズ値が同程度であっても透過像鮮明度が異なる防眩フィルムや、透過像 鮮明度が同程度であってもヘイズ値が異なる防眩フィルムが製造できるこ とが示されている。なお、被告は、本件明細書には本件特許発明に対応する 実施例としては実施例5しか記載されていない旨主張するが、これは、第1 実施形態が本件特許発明に対応するものでないという誤った前提に基づく ものであるし、仮に被告の前提によるとしても、ここで問題となるのはヘイ ズ値と透過像鮮明度の相関関係であるから、実施例5以外の実施例を排除す る理由はない。また、被告は、比較例1に関しては、「平均粒径が0.5μ m以上5.0μm以下の範囲の値に設定された」本件特許発明の前提条件で あるμmオーダーの表面凹凸構\造を備えた防眩層ではなく、nmオーダーの 表面凹凸構\造を備えた防眩層を有するから、参酌すべきではない旨主張する が、仮に比較例1を参酌しなかったとしても、上記認定が左右されるもので はない。
加えて、JIS規格(K7374)(甲43)の「附属書(参考)像鮮明 度測定例」では、像鮮明度の透過測定例として「ヘーズ値によって像の鮮明 さを評価できないアンチグレアフィルムなどのフィルムの測定例」があり、 附属書表1の試料1−2「ヘーズ値14.11、像鮮明度80.0%」と試\n料1−4「ヘーズ値14.67、像鮮明度5.9%」を示すとともに、ヘー ズ値は像の鮮明度とは異なり視感を反映していないのに対して、像鮮明度は 視感と一致していることが記載されていることからみて、防眩フィルムのヘ イズと透過像鮮明度の間には一定の相関関係があるものの、強い相関性まで 認められているものではなく、製造条件などで調整が可能であり、設計自由\n度があるといえる。
さらに、本件明細書の【0008】には「そこで本発明は、ディスプレイ のギラツキを定量的に評価して設計することにより、良好な防眩性を有しな がらディスプレイのギラツキを抑制できると共に、高い透過像鮮明度の設計 自由度を有する防眩フィルムを提供することを目的としている。」と記載さ れ、本件特許発明は、防眩性、ギラツキの抑制、高い透過像鮮明度の設計自 由度という三条件の均衡を目的とするものと理解される。そして、本件明細 書の【0011】の「また、前記標準偏差を所定値に設定すると共に、防眩 層のヘイズ値を50%以上99%以下の範囲の値に設定することにより、デ ィスプレイのギラツキを抑制しながら、良好な防眩性を得ることができる。 また、防眩フィルムの光学櫛幅0.5mmの透過像鮮明度を0%以上60% 以下の範囲の値に設定することで、防眩フィルムの透過像鮮明度の設計自由 度を広く確保できる。」との記載は、良好な防眩性を示すヘイズ値が50% 以上であることを示すものであり、したがって、ヘイズ値は、ギラツキの抑 制や高い透過像鮮明度という他の条件との関係で上記数値範囲内で変動し てよいものである。上記のとおり、高いヘイズ値とすることとディスプレイ の表示性能\を維持することとの厳格なトレードオフの関係は認められず、甲 13添付の実験成績証明書3頁ではサンプル1(ヘイズ値96%、透過像鮮 明度65%)とサンプル2(ヘイズ値45%、透過像鮮明度2.0%)の防 眩フィルムが製造できたことが示されており、本件高ヘイズ・高鮮明度領域 の製造方法が具体的に記載されていなければ、本件特許発明が実施可能要件\nを欠くなどということはできない。
(5) 以上によれば、本件明細書には、当業者がその記載及び出願当時の技術常 識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件特許発明に係る物を 製造し、使用することができる程度の記載があるものと認められ、当業者が 本件特許発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載された\nものであると認められる。したがって、本件明細書につき実施可能要件を充足しないとした本件決定の判断には誤りがあり、取消事由2には理由がある。\n
3 取消事由3(サポート要件に関する判断の誤り)について
(1) 特許法36条6項1号は、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細 な説明に実質的に裏付けられていなければならないというサポート要件を 定めるところ、その適合性の判断は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な 説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な 説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該 発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して 判断すべきものと解される。
(2) 本件特許発明は、良好な防眩性を有しながらディスプレイのギラツキを抑 制できると共に、高い透過像鮮明度の設計自由度を有する防眩フィルムを提 供することを目的とする(【0008】)。 ヘイズ値が50%以上あれば良好な防眩性は確保でき(【0011】)、 ヘイズ値と透過像鮮明度との間には一定の相関関係があるから、適宜ヘイズ 値を変動させることにより、透過像鮮明度も調整することができる。 ディスプレイのギラツキを抑制しながら防眩性を向上させるには、 防眩 層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を急峻 化すると共に、凹凸の数を増やせばよい(【0078】)。 そして、上記のような防眩フィルムについて、本件明細書には、凹凸の急 峻性を生み出す原理とその具体的方法、原材料から製造の工程、実施例等が 記載されていることは前記2(3)のとおりであるから、当業者は、その記載 及び技術常識に基づき、特許請求の範囲に記載された範囲において、本件特 許発明の課題を解決できると認識できるということができる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2023.12.12
令和5(行ケ)10074 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年11月30日 知的財産高等裁判所
本願商標は、「ブランディングDX」の文字を標準文字で表してなると\nころ、構成中の「ブランディング」の文字は、「顧客や消費者にとって価値\nのあるブランドを構築するための活動」等の意味を有する語であり(乙1〜\n7)、「DX」の文字は、「情報通信技術の浸透に伴うビジネスや社会の構造\n的変革」、「デジタル変革」を意味する「デジタルトランスフォーメーション」 を表す語である(乙8〜10)と認められる。\nそして、日本政府によって平成30年5月に「デジタルトランスフォー メーションに向けた研究会」が発足し、同年12月に同研究会によって「D X推進ガイドライン」が発表されて以降、政府による「DX推進指標」が公\n表され(令和元年7月)、閣議決定された「骨太の方針」に「民間における\nDXの加速」が盛り込まれ(令和3年6月)、その頃、総務省によって「自 治体DX推進計画」が策定されるなど、様々な業務や事業活動、業種等にお いて、デジタル技術の活用を促進することによる業務の変革(DX、デジタ ルトランスフォーメーション(化))の取組がなされている(乙11〜22、 28、47〜50)。また、そのような取組を表す際に、「○○DX」と表\す ことがしばしば行われている実情があり(乙13、14、21〜37)、ブ ランディングに関わる業務においても、こうした取組に対して、端的に「ブ ランディングDX」と称する事例がある(甲28〜40、乙43、44、4 7〜50)。
(3) そうすると、本件関連役務に関し本願商標に接した取引者・需要者は、 「ブランディング」についてのデジタル技術の活用による業務の変革である 「デジタルトランスフォーメンション」であること、すなわち「ブランディ ングのデジタルトランスフォーメーション(化)」を表したものと認識し、\n理解するものというべきである。 よって、本願商標は、役務の特徴、質(内容)を普通に用いられる方法 で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当す\nると解するのが相当である。
(4) これに対し、原告は、「DX」の文字の理解が浸透していないと主張す るが、上記(2)の事実は、本件審決時までに「デジタルトランスフォーメー ション」を意味する「DX」の取組が広く啓発され、用語例として定着・普 及していたことを示すものにほかならず、上記主張は採用できない。原告は、 アンケートにおいて「DX」や「ブランディング」の理解が広がっていない 結果が出ていると主張するが(甲3〜5、18〜20、22、23)、例え ば甲3のアンケートでは、75%の回答者が少なくとも「DX」の言葉の意 味を理解しているとの結果が出ているなど、本件で証拠提出されたアンケー ト結果は必ずしも原告の主張を根拠づけるものとはいえない。 また、原告は、「ブランディングDX」の用語を使用する際、「プラン」 や「ソリューション」などの言葉で意味合いを補足している例がほとんどで\nあると主張するが、そうだとしても、「DX」の用語が本件関連役務の取引 者・需要者に理解されないと解すべき根拠になるものではない。
(5) 以上のとおりであって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとし た本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.12. 7
令和5(行ケ)10063 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年11月30日 知的財産高等裁判所
ア 引用商標は、中央上部に筆文字風の書体による「遊」の漢字を大きく配 し、底辺部にゴシック体風の書体による「VENTURE」の欧文字を配 した構成からなる結合商標である。\n
(ア) この外観に着目して具体的に観察すると、中央上部の「遊」の文字 は、「VENTURE」を構成する各文字よりも縦横とも約5倍の大き\nさで、面積にして約25倍相当となる。「遊」の文字と「VENTUR E」文字部分(7文字分)全体の面積を比較しても、前者が後者の約3. 5倍ということになり、「遊」の文字部分が「VENTURE」の文字 部分に対して圧倒的な存在感を示している。
また、「遊」の文字の書体は、勢いのある行書の筆文字風であり、 「遊」の語義と相まって、看者に躍動感と趣味感を印象づける書体で あるのに対し、「VENTURE」は、太目の文字をわずかに右に傾け たゴシック体風の書体という以上の特徴はみられない。
そして、「遊」の文字部分は、中央上部に配置され、これが商標の全 体構成の中心部分をなすとの位置づけを否応なくアピールするのに対\nし、「VENTURE」の文字部分は、底辺部で「遊」を支える台座の ような印象を与える外観となっている。
(イ) 次に、称呼及び観念に着目して検討するに、引用商標の構成中、「V\nENTURE」の文字部分からは、 (2)で述べたところと同様、「ベン チャー」の称呼及び「冒険」の観念を生ずる。そして、「遊」の文字部 分からは、「ゆう」又は「あそ」(び、ぶ)の称呼を生じ、「あちこち 出歩いてあそぶ」等の観念を生ずる(乙5)。 したがって、これを全体として観察した場合、一応は「ユウベンチャ ー」又は「アソベンチャー」の称呼を生ずるといえるが、一義的に明確\nとはいえず、一連一体の文字商標としての読み方は定まらない(よく 分からない)という印象を取引者、需要者に与えることも否定できな い。
また、「遊」の部分から生ずる観念(あちこち出歩いてあそぶ)と 「VENTURE」の部分から生ずる観念(冒険)とを統合する単一の 観念を見出すことは困難であり、造語としての「ユウベンチャー」又は 「アソベンチャー」から特定の観念が生ずるとも認められない。\nこの点、原告は、上記各部分を通じて、「気ままに冒険する」といっ た観念上のつながりが理解される旨主張するが、連想の域を出ない希 薄なつながりにすぎず、ここに商標の出所識別機能の根拠を求めるに\nは無理がある。
イ 以上の認定を踏まえ、上記(1)の3)で例示したところを参考に、引用商 標における分離観察の可否及び要部認定について検討する。
引用商標は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分からな る結合商標であり、原則として全体観察をすべきことは前述のとおりであ るが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」\nの文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全 体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘\nすることができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき 根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要 者は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して理解 ・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」\nの文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理 解することもあり得ると解される。
他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らか\nに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接し\nた取引者、需要者が、「VENTURE」の文字部分に着目し、これを引 用商標の略称等として認識するということは、常識的に考え難い。したが って、「VENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することは できないというべきである。本件審決の判断中、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTURE」の文字\n部分を要部と認めた部分は是認できない。
ウ 被告は、「遊」の文字部分が比較的大きく書されているとしても、「V ENTURE」の文字も需要者、取引者が認識するに十分な大きさで書さ\nれており、文字の大きさをもって「VENTURE」の文字部分が要部と なり得ないとはいえない旨主張する。確かに、相対的な文字の大小関係が あるにすぎない場合であれば、被告の上記立論も首肯できるものであるが、 本件における「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との大き さの違いは、相対的な大小関係とは次元の異なるものである上、書体の違 いからくる訴求力の差、配置上の位置関係からくる主従関係性などの要素 も総合すれば、被告の立論は本件に妥当するものとはいえない。
なお、「VENTURE」という文字が引用商標の指定商品(被服)と の関係で出所識別標識としての機能を一般的に果たすかどうかという問\n題は、上記判断とは関係がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.12. 1
令和5(行ケ)10060 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年11月15日 知的財産高等裁判所
イ 本願商標の全体を観察すると、文字部分は、図形部分の内部に配置されてい るものの、図形部分の中央の目立つ位置に、白抜きの読み取りやすい書体で明瞭に 記載されているから、外観上、図形部分とは明確に区別して認識できるものであっ て、図形部分と文字部分がそれぞれ視覚的に分離、独立した印象を与えるものとい える。
ウ 本願商標の図形部分は、一見して何を表すものであるか看取することは困難\nであり、直ちに特定の観念及び称呼が生じると認めることはできない。他方、本願 商標の文字部分は、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合い を認識させることのない一種の造語として認識されるものであって、特定の観念を 生じさせず、ローマ字読みした場合、「ポッポ」の称呼を生じるものといえる。 エ 以上を総合すると、本願商標は、図形部分と「POPPO」の文字部分とか らなる結合商標であるところ、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上\n不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから、 その構成部分の一部であり、「ポッポ」の称呼を生じる文字部分である「POPPO」の部分を抽出し、当該部分(以下「本願要部」という。)だけを他人の商標と比較し\nて商標の類否を判断することも許されるというべきである。
・・・・
(3) 本願商標の指定役務は第43類「鳥から揚げを主とする飲食物の提供」を含 むものであり、引用商標1の指定役務は第42類「らーめん・お好み焼・たい焼・ フライドポテト・アイスクリーム及び清涼飲料を主とする飲食物の提供」であり、 引用商標2の指定役務は第43類「飲食物の提供」である。しかるところ、これら を提供する者はいずれも飲食サービス業者であって業種が一致する。また、飲食サー ビス業者においては、同一店舗において、ラーメンと空揚げとフライドポテト、お 好み焼きと空揚げなどを提供することも行われており(乙34〜39)、さらに、提 供する飲食物が相違する様々な店舗を同一経営者が飲食店グループとして運営する ことも一般的に行われているところである。
(4) 以上によると、本願商標と各引用商標は、それぞれの指定役務において使用 された場合、営業主体、すなわち役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあ るというべきであって、互いに類似するものであり、また、本願商標と各引用商標 は、「飲食物の提供」の役務との点で共通するから、指定役務が類似するといえる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.11.29
令和3(ワ)26704 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和5年7月26日 東京地方裁判所
請求原因イ、ウ及び抗弁 (商標的使用)について
ア 甲18、34〜37によれば、本件大会ビデオ・DVDのケースの表紙・\n裏表紙、本件大会ビデオ・DVDの映像におけるテロップ、本件雑誌に掲載\nされた本件大会ビデオの広告、各種ウェブサイト上の店舗における商品であ る本件大会DVDのケースの表紙の画像やその説明において、「九鬼神流」、\n「九鬼神」、「高木揚心流」との記載があることが認められる。 もっとも、本件大会ビデオ・DVDのケースの表紙・裏表\紙における上記 「九鬼神流」等の記載の態様は前記1 ア 、 のとおりであり、本件大会 ビデオ・DVDの映像におけるテロップにおける「九鬼神流」等の記載の態 様は同 のとおりであり、本件雑誌に掲載された本件大会ビデオの広告にお ける上記「九鬼神流」等の記載の態様は同 のとおりである。「月刊 秘伝 WEB SHOP」における上記「九鬼神流」等の記載の態様は同 のとお りであり、甲34〜37によれば、各種ウェブサイト上の店舗における商品 である本件大会DVDの画像は前記1 ア の本件大会DVDのケースの 表紙のものであり、また、その説明文は、上記「月刊 秘伝 WEB SH OP」におけるものと同様のものであったと認められる。 そうすると、前記1と同様の理由により、それらの「九鬼神流」、「九鬼神」、 「高木揚心流」との表示は、関係する各記載やその使用態様から、日本武道\n国際連盟が主催した本件大会における演武を収録した本件大会ビデオ・DV Dに収録されている対象に関する説明をするものであり、本件大会ビデオ・ DVDの出所を示すものとはいえないから、これらの表示は需要者が何人か\nの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用され ていないものといえる。
2023.11.29
令和4(行ケ)10035 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 知的財産裁判例 令和5年7月19日 知的財産高等裁判所
(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を 生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使 用したときに,当該指定商品又は指定役務が他人の業務に係る商品又は役務 であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該指定商品又は指定役 務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係 又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主\nの業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標を含むもの と解するのが相当である。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は, 当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表\示の周知著名性及び独創 性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は 役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務 の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指 定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基 準として,総合的に判断されるべきものである(平成12年最判参照)。 そして、この「同一の表示による商品化事業を営むグループ」には、表\示 を指定された商品に付し役務に用いるなどして商品の販売等の事業を営む他 の営業主のように、他人の表示に係る使用許諾(ライセンス)契約を締結し\nて事業を営む者をも含むと解すべきであるから、そこにいう「誤信されるお それがある商標」(広義の混同のおそれのある商標)には、使用許諾に係る 他人の表示と同一ないし類似の商標であって、これが商品に付され又は役務\nに用いられることにより、他人の表示に関するライセンス契約を締結して事\n業を営むグループに属する関係にある複数の営業主のうちに、この同一ない し類似の商標を用いて事業を営む者に属する関係にあると誤信されるおそれ がある商標を含むものというべきである。 以下、この観点から判断する。
(2) 商標の類似性の程度
ア 外観
本件商標は、「GUZZILLA」と、8文字の欧文字から成る。本件 商標において、「G」と「A」の字体は、やや丸みを帯び、「U」と3文 字目の「Z」の上端及び7文字目の「L」と「A」の下端は、それぞれ結 合し、3文字目及び4文字目の「Z」は、両文字の左下が前下方に鋭く突 尖しているほか、やや縦長の太文字で表されることによって、デザイン化\nされている。 引用商標は、「GODZILLA」と、8文字の欧文字から成る。被告 が引用した引用商標の文字は、標準文字であって、デザイン化されていな いが、実際には、様々な書体で使用されている。 本件商標と引用商標の外観とを対比すると、いずれも8文字の欧文字か らなり、語頭の「G」と語尾の5文字「ZILLA」を共通にする。2文 字目において、本件商標は「U」から成るのに対し、引用商標は「O」か ら成るが、本件商標において「U」と3文字目の「Z」の上端は結合し、 やや縦長の太文字で表されているから、見誤るおそれがある。もっとも、\n本件商標と引用商標は、3文字目において相違するほか、本件商標は前記 のとおりデザイン化され、全体的に外観上まとまりよく表されている。\nそうすると、本件商標と引用商標とは、外観において相紛らわしい点を 含むものということができる。
イ 称呼 本件商標の語頭の2文字「GU」は、ローマ字の表記に従って発音すれ\nば「グ」と称呼され、我が国において、なじみのある「GUM」などの英 単語と同様に発音すれば「ガ」と称呼される。したがって、本件商標は、 「グジラ」又は「ガジラ」と称呼され、語頭音は「グ」と「ガ」の中間音 としても称呼されるものである。
・・・
ウ 観念 本件商標からは特定の観念が生じず、引用商標からは怪獣映画に登場す る怪獣「ゴジラ」との観念が生じる。
エ 本件商標と引用商標の類似性
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしいも のであって、外観においても相紛らわしい点を含むことから、類似性の程 度は高いものということができる。
◆判決本文
関連の審決取消訴訟事件です。
◆令和1(行ケ)10167
関連の不競法違反の事件です。
◆令和4(ネ)10063
1審です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.11.29
令和5(行ケ)10028 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年9月6日 知的財産高等裁判所
前記(3)に挙げた各事実によれば、本件審決がされた当時、1)インターネッ ト上の商品販売サイトにおいて、原告以外の者が製造したサメ軟骨(又はそ の代替として用いられる鶏軟骨等)を梅肉で和えた惣菜商品に、「梅水晶」の 名称が付されて販売されていたこと、2)多数の飲食店において、サメ軟骨を 梅肉で和えた料理の名称として「梅水晶」の語が用いられ、客に提供されて いたこと、3)料理レシピを掲載しているウェブサイトにおいて、サメ軟骨の 代わりに鶏軟骨等を用い、これを梅肉で和えた料理が「梅水晶」の名称で複 数紹介されていたことが認められる。 これらの事実によれば、本願の指定商品の需要者は、「梅水晶」の語が本願 商標の指定商品に使用された場合には、サメ軟骨又はその代替として用いら れる鶏軟骨等を梅肉で和えた惣菜の料理名又はこのような惣菜の商品を一般 的に指す名称であると認識するものといえ、原告の製造販売する商品を認識 するとは認められない。したがって、本願商標は、本願の指定商品との関係において、自他識別力を有しておらず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するこ とができない商標であると認められる。
(5) 原告の主張に対する判断
ア 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(2)のとおり、1)原告が原告商品の 商品名として独自に考案した「梅水晶」の名称を付し、現在まで25年以 上にわたって販売しており、原告の取引先は平成27年当時で1000社 を超え、これら多くの取引先を通じ、「梅水晶」標章を付した原告商品が全 国のホテルや飲食店に納入されていること、2)全国の原告の取引先が、「梅 水晶」の標章を付した原告商品の出所が原告であると認識できることを証 明する旨の書面に押印していること、3)原告商品を紹介した複数のテレビ 番組において、「梅水晶」の標章を付した原告商品の出所が原告であること が紹介されたこと、4)「大阪府珍味協同組合」が発行した冊子「食の都 大 阪 五十年の歩み」に掲載された年表\において、平成15年の「珍味組合 員の売筋商品」の欄に「梅水晶(サブ水産)/TVでの紹介があり人気商 品となる」との記載があること、5)原告よりも規模の大きい会社で、原告 商品と競合商品を販売する二つの会社が、「梅水晶」とは異なる標章を付し て商品を販売していることから、本願商標は、本件審決の時点で、原告の 業務に係る商品を示すものとして、原告商品を取り扱う業界の取引者、需 要者の間に広く知られるに至っていたと主張する。 しかし、原告の主張は、本願の指定商品の需要者が、ホテルや飲食店等 の事業者のみであることを前提としているところ、上記需要者には一般消 費者が含まれると解すべきことは前記(2)のとおりであり、原告の主張には その前提に誤りがある。
また、前記1)については、「梅水晶」の名称は原告が考案し、原告がサメ 軟骨に梅肉を和えた惣菜商品に本願商標を付して販売を開始した事実が 認められるが(甲93、弁論の全趣旨)、当初は特定の商品の名称として使 用されていた語が、一定期間使用され、当該商品と同種の商品等を指す一 般名称となり、自他商品を識別する標章としての機能を喪失することはあ\nり得るのであって、上記事実があることをもって、本願商標が商標法3条 1項6号に該当すると解し得ないことにはならない。前記2)については、原告が証拠として提出している「証明願」は、一般消費者を含まず、原告の取引先である業者のみの「証明願」にすぎないから、これをもって、「梅水晶」の名称が、原告の商品の出所表示として本願の指定商品の需要者の間で、全国的に認識されるに至ったことを示すもの\nとは認められない。前記3)から5)についても、本願の指定商品の需要者の一部の認識を窺わせる事情にすぎず、一般消費者を含む本願の指定商品の需要者において、 「梅水晶」の名称が原告の商品を表示するものと一般的に認識していたこ\nとを示すものとはいえない。
イ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(4)のとおり、「楽天市場」や「アマ ゾン」において「梅水晶」の語で検索して出てくる商品で、本願の指定商 品と関連するもののうち、原告の出所に係る商品であることが明らかなも のが、「楽天市場」については約38%、「アマゾン」については50%に 及んでおり、本件審決が別掲1として挙げた事例は少数のデータを恣意的 に抽出したものであって、これらの事例によって一般消費者の間で「梅水 晶」の名称が付された商品が原告の出所に係るものであると理解されてい るとは認められないと本件審決が判断したのは不当である旨主張する。 しかし、原告の主張を前提としても、「楽天市場」及び「アマゾン」にお いて「梅水晶」の語で検索して出てくる本願の指定商品と関連する商品の うち、原告の商品でないものが半数又はそれ以上を占めるのであって、こ のことからすれば、本件審決が少数のデータを恣意的に抽出して不当な判 断をしたとは解されない。同様に、本判決の前記(3)において挙げた事例も、 少数のデータを恣意的に抽出したものであるとはいえず、これらの事例に 照らし、本願商標が本願の指定商品との関係において自他識別力を有して いないと判断できることは、前記(4)のとおりである。
ウ 以上のとおり、原告の主張はいずれも採用することができない。 その他、原告がるる主張する事情を考慮しても、本願商標は、本願の指 定商品との関係において自他識別力を有しないとの結論は左右されない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2023.11.28
令和4(ワ)2551 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年11月10日 東京地方裁判所
(1) 不正競争防止法2条1項20号の誤認惹起行為が不正競争に該当し違法と されるのは、事業者が商品等の品質、内容などを偽り、又は誤認を与えるよ うな表示を行って、需要者の需要を不当に喚起した場合、このような事業者\nは適正な表示を行う事業者より競争上優位に立つことになる一方、適正な表\ 示を行う事業者は顧客を奪われ、公正な競争秩序を阻害することになるから である。 このような趣旨に照らすと、「品質」について「誤認させるような表示」に\n該当するか否かを判断するに当たっては、需要者を基準として、商品の品質 についての誤認を生ぜしめることにより、商品を購入するか否かの合理的な 判断を誤らせる可能性の有無を検討するのが相当である。\n
(2) 被告表示が「品質」について「誤認させるような表\示」に該当するかにつ いて
ア 令和元年5月8日から令和3年8月30日までの表示について\n
前提事実(5)ア4)の「全国導入実績2,500台以上」との表示は、被告\nが販売している業務用生ごみ処理機、すなわち被告商品は、全国で250 0台以上が販売されているとの事実を、「ゴミサー/ゴミサポーターはその 処理方法・性能が多くの企業・施設で認められ、おかげ様で現在、全国で\n2,300台以上が稼働しています。」との表示は、被告商品は、その処理\n方法及び性能が多くの企業や施設で認められたため、全国で2300台以\n上が販売されたとの事実を、「全国・海外での導入実績は3,500台以 上。」との表示は、被告商品は、全国及び海外で3500台以上が販売され\nたとの事実を需要者に対し認識させるものであると認められる。 他方で、前提事実(5)エによれば、被告が令和元年5月8日以降販売して いる被告商品の過去の累計販売数は2300台に達するものではないこと が認められ、少なくとも、上記「全国導入実績2,500台以上」、「ゴミ サー/ゴミサポーターはその処理方法・性能が多くの企業・施設で認めら\nれ、おかげ様で現在、全国で2,300台以上が稼働しています。」及び 「全国・海外での導入実績は3,500台以上。」の表示(以下、これらを\n併せて「本件誤認惹起表示1)」という。)は、いずれも、実際の販売実績と は異なるにもかかわらず、多数の被告商品が販売されており、このような 販売実績は、被告商品のごみ処理方法及びその性能が他の同種商品に比べ\nて優れたものであることに起因することを強調するものであって、その結 果、需要者に対し、被告商品がその品質において優れた商品であるとの権 威付けがされ、また、他の需要者も購入しているという安心感を与えるこ とになるため、需要者が商品を購入するか否かの合理的な判断を誤らせる 可能性があるというべきである。そうすると、本件誤認惹起表\示1)は、「品 質」について「誤認させるような表示」に該当すると認められる。\n
この点について、被告は、本件誤認惹起表示1)は、原告と被告との間の 取引が終了した後、一時的かつ短期的に残存していたものにすぎず、かつ、 被告が販売した原告商品の販売実績を記載したものであるから、虚偽では なく真実そのものであると主張する。しかし、前記のとおり、需要者は、 本件誤認惹起表示1)が被告が過去に販売していた製品についての記載であ ると認識することはなく、現在(被告ウェブページ掲載時)販売している 被告商品についての記載であると認識するといえるから、その表示の残存\nが一時的かつ短期的であったとしても、需要者が購入するか否かを決断す る時点において、その合理的な判断を誤らせる可能性は否定できない。し\nたがって、被告の上記主張は採用することができない。
・・・
(3) 被告の主張について
被告は、販売実績の違いは、商品の品質の違いを推認するものにすぎず、 原告商品及び被告商品の間に、性能及び機能\における違いがない本件におい ては、原告商品と被告商品の品質の違いが推認されるものではないと主張す る。 しかし、前記(1)で説示した不正競争防止法2条1項20号の誤認惹起行為 が不正競争に該当し違法とされる趣旨に照らすと、客観的な性能及び機能\に おける違いがないとしても、前記(2)のとおり、本件誤認惹起表示1)ないし3) は、いずれも、販売実績について事実と異なる表示をするとともに、同販売\n実績が品質の優位性に起因するものであるとの表示をすることによって、そ\nのような販売実績をもたらす「品質」であるとの誤解を需要者に与え、その 結果、公正な競争秩序を阻害するものである以上、同号の「品質」について 「誤認させるような表示」に該当すると認めるのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2023.11.28
令和5(ネ)10041 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年11月16日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
原告は、甲7公報に記載されたバー10が独立した運動器具の発明である といえるかに関し、1)甲7公報記載の発明は、従来技術であるバーベル装置(バー 部分と重り部分からなるもの)における問題(バーが長いことによってバランスを とることが困難であるとの問題)を解消するため、バー部分を短く改良した三頭筋 運動器具であるところ、バーベル装置においては、重りを着けずにバー部分のみで 運動を行うことが想定されているのであるから、バーベル装置を改良した甲7公報 記載の発明においても、バー10単独での使用が可能である、2)甲7公報には、発 明の目的及び別の目的に係る記載があるところ、前者の記載にある「中央に位置す る重り支持セクションを有する」との文言が後者の記載からあえて削除されている から、甲7公報記載の発明は、重り支持プラットフォーム及び重りを備えない状態 で使用することを当然の前提にしている、3)甲7公報記載の発明は、バー10を単 独で使用することによっても一定の作用効果を奏する、4)バー10は、三頭筋運動 において非常に重要な役割を果たしているとして、甲7公報記載の発明においては、 バー10を独立して捉えることが可能であり、それ自体が独立した運動器具の発明\nであると主張する。
そこで検討するに、1)甲7公報には、「比較的長いバーを有しバランスをとるこ とが困難であるなどの従来のバーベル装置が有していた問題を解消するため、本件 各発明は、両側にあるハンドルを備える中央の重り支持セクションを有し、各ハン ドルが複数の握持位置を有する」旨の記載があるが、補正して引用した原判決第4 の1(4)アにおいて説示したところに照らすと、仮に、従来のバーベル装置が重り を着けない状態で使用されることがあるとしても、そのことは、甲7公報記載の発 明においても、バー10のみの状態(重りのみならず支持クランプ組立体をも取り 外した状態)での使用が想定されていることの根拠となるものではない。
また、2)甲7公報には、「本発明の目的は、中央に位置する重り支持セクション を有する、三頭筋をエクササイズするための改善されたウエイトリフティング装置 を提供することである。本発明の別の目的は、複数の握持位置を備える両側にある ハンドルを有する、三頭筋をエクササイズするための改善されたウエイトリフティ ング装置を提供することである。本発明の別の目的は、end to endの手 の配置を可能にする、三頭筋をエクササイズするための改善されたウエイトリフテ\nィング装置を提供することである。最後に、本発明の全体的な目的は、安価であり、 高い信頼性を有し、その意図される目的を達成するのに高い有効性を有する、説明 した目的のための装置内にある改善された要素及び機材を提供することである。」 との記載があるが、これらの記載は、甲7公報記載の発明の目的について述べるも のであり、その具体的な構成について詳述するものではなく、補正して引用した原\n判決第4の1(2)イ(オ)のとおりの甲7公報記載の発明の具体的な構成に係る記載に\nも照らすと、「本発明の別の目的」及び「本発明の全体的な目的」に係る各記載中 に「本発明の目的」に係る記載中の「中央に位置する重り支持セクションを有する …ウエイトリフティング装置」などの記載がないことをもって、甲7公報記載の発 明において、バー10のみの状態での使用が想定されているということはできない。 さらに、3)前記1)において説示したのと同様、補正して引用した原判決第4の1
(4)アにおいて説示したところに照らすと、仮に、重りを取り外した状態で使用す ることによっても甲7公報記載の発明の効果を奏する場合があるとしても、そのこ とは、甲7公報記載の発明において、バー10のみの状態(重りのみならず支持ク ランプ組立体をも取り外した状態)での使用が想定されていることの根拠となるも のではない。なお、4)甲7公報記載の発明においてバー10が重要な役割を果たしているとしても、そのことは、原告の主張を直ちに根拠付けるものではない。以上のとおりであるから、原告の主張を採用することはできない。
(2) 原告は、相違点1)に係る本件各発明の構成の容易想到性に関し、リング状\nの器具をトレーニング器具として用いることは慣用技術であるから、リング状のバ ー10をトレーニング器具とすることは、単にスポーツ器具用部品であるバー10 に慣用技術を適用するだけのことであり、当業者にとって極めて容易な事柄である と主張する。しかしながら、これまで説示したとおり、本件においては、バー10のみ(甲7発明)が独立した引用発明であると認定することはできず、バー10のみならず重 り支持部分をも備えた甲7発明(被告)が引用発明であると認定するのが相当であ るから、甲7公報記載の発明を引用発明とする本件各発明の進歩性の判断(相違点 1)に係るもの)に当たっては、そのような甲7発明(被告)から重り支持部分を取 り除くことについての容易想到性が問題となるところ、甲7発明(被告)における バー10は、甲7発明(被告)を構成する部材の一部であり、重り支持部分と不可\n分の部材であるから、バー10のみをもって、原告が主張するリング状の器具であ るとみることはできない(なお、原告の主張も、リング状の器具として、甲8公報 記載のトレーニング用器具、甲9公報記載の体育器具のほか、ラタンリング、ピラ ティスリング、ヨガリング、フープ等を念頭に置いている。)。 以上によると、原告が慣用技術であると主張する技術の適用により当業者が相違 点1)に係る本件各発明の構成に容易に想到することができたとは認められない。\n
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2023.11.28
令和4(行ケ)10112 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年10月30日 知的財産高等裁判所
特許法17条の2第3項は、特許請求の範囲等の補正については、願書に最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなけ ればならない旨規定するところ、ここでいう「最初に添付した明細書、特許請求の 範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものとい うべきである。そして、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、出願当初にお ける発明の開示が十分に行われることを担保して先願主義の原則を実質的に確保し\nようとするとの見地からすれば、当該補正が、上記のようにして導かれる技術的事 項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正 は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの に当たるというべきである(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563 号同20年5月30日特別部判決参照)。
・・・
上記(3)のとおり、本件補正前の「前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前 記管理サーバへ送信する」こと(以下「監視して送信」という。)は、本件補正後の 「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力」す ること(以下「情報を出力」という。)に対応し、両者はともに当初明細書等に記載 された事項である。 ここで、監視のためには監視対象の情報を取得する必要があり、情報を出力する ためには出力したい情報に関するデータの入力が必要なことは自明のことであるか ら、上記「監視して送信」及び「情報を出力」のいずれの処理においても、その前 提として、ランドリー装置の動作に関係する何らかの信号を検知すること自体は当 然に行われることであり、当初明細書等において自明の前提であるといえる。そし て、この自明の前提は、検知する信号の種類(電流値、コイン信号等)や監視の具 体的な方法(計測値に基づく判断か、推測か等)を問わないものであり、本件補正 の前後で何ら変わることのないものであるといえる。 そうすると、本件補正前の請求項1の記載は、上記自明の前提を「前記有料自動 機の動作を検知するセンサーとを含み、」及び「前記センサーの検知信号に基づいて」 との事項によって更に特定したものであり、補正事項1において当該事項を削除す ることで、センサーの検知信号以外の情報に基づくものが含まれることになったと しても、上記自明の前提に照らせば、当初明細書等に記載された事項であって、新 たな技術的事項を導入するものとはいえない。またこの点は、上記自明の前提の具 体的な態様が「電流センサー」から他の手段に変わったとしても、「監視して送信」 や「情報を出力」する処理が行われる限り、本件発明1の課題(各設置場所を巡回 することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能な有料自動機の制\n御システムを提供する(甲2の【0005】))は解決され、効果に顕著な差が生じ ることがないことからも裏付けられる。 したがって、補正事項1は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと いえる。 そして、本件補正の内容に照らすと、上記検討した補正事項1及び2のほかにお いても、当初明細書等に記載した範囲を超えるものはないと認められる。
(5) 原告主張について
原告は、1)当初明細書等には、センサーの検知信号に基づく構成が具体的に記載\nされており、他の構成は記載されていないから、センサーの検知信号に基づく構\成 は単なる例示ではない、2)本件審決の判断と異なり、有料自動機内の有料自動機制 御部10内の動作状態を示す回路の監視結果を示す信号を送信する方法は自明とは いえない、3)補正要件違反を認めないとすれば、センサーを含まず、料金収受情報 から有料自動機が動いているかを推測する方法が含まれることになる旨を主張する。 上記1)の主張について検討すると、センサーの検知信号に基づく構成は、上記自\n明の前提を具体化した態様の一つではあるものの、本件発明1は「監視して送信」 又は「情報を出力」により巡回せずにランドリー装置の動作状態を確認するという 課題を解決するものであるから、センサーの検知信号でなければ課題を解決し得な いということはなく、「監視して送信」又は「情報を出力」するために必要な情報が 入力されていれば足りる。当初明細書等にセンサーの検知信号に基づく構成しか例\n示がないとしても、上記自明な前提に対応する構成がそれのみに限定されることに\nはならない。 上記2)の主張について検討すると、本件審決は、有料自動機制御部10内にある 回路や素子からの信号が、センサー以外の検知信号に基づくものを説明のために例 示したものであって、当該例示が自明であることを補正の根拠として評価したもの ではないから、当該例示が自明であるか否かは、本件補正の適否の判断を左右する ものではない。
◆判決本文
関連事件です(当事者が同じ)。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2023.11.19
令和4(ワ)6582 販売差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年10月31日 大阪地方裁判所
イ 実質的同一性について
(ア) 原告商品4の形態と被告商品4の形態を比較すると、両者は、形態A及びE、 並びに、形態B及びGの各一部(形態Bのうちウエスト部を絞ったとの形態、形態 Gのうちパンツのセンタープレスの折り目を中心に、左右に3個ずつ、計6個のパー ルの装飾が連なって施されている形態)において共通する。他方、両者は、1)ウエ ストのゴムの有無(形態B)、2)フロントのチャックの有無(形態C)、3)フロン トのタックの有無及びウエストから臀部のシルエット(形態D)、4)臀部のポケッ\nトの個数(形態F)、5)パールの大きさ(形態G)、6)パールの止め方(形態H) において相違する。
(イ) 原告は、両商品の全体的なシルエット及び裾のパール装飾があることにおい て同一であり、パールの大きさの差異はわずかであり、両商品の形態は実質的に同 一であると主張する。 上記4)の相違点については、上記(3)イ(イ)の検討と同様の理由から、上記6)の相 違点については、上記(2)イ(イ)の検討と同様の理由から、いずれも商品全体から見 ると些細な相違点である。また、上記5)の相違点については、上記(2)イ(イ)と同様 の理由から、商品全体に対する需要者の受ける印象に強く影響するものとはいえな い。しかしながら、上記1)及び2)の相違点は、上記(3)イ(イ)と同様の理由から、ま た、上記3)の相違点は、腰回り全体のシルエットの相違であり、いずれも需要者が 判別でき着目する点であるといえるから、いずれも商品全体に対して需要者の受け る印象に大きく影響するものといえる。 以上によれば、原告商品4と被告商品4の形態が実質的に同一であると認めるこ とはできない。
ウ ありふれた形態であるかについて
仮に、原告商品4と被告商品4の形態が実質的に同一であるとしても、次の理由 から、上記イの両商品の共通点に係る形態は、いずれもありふれた形態であると認 められる。すなわち、形態A及びE、並びに、形態Bの一部(ウエスト部を絞った との形態)については、従前から多数存在する商品形態である(弁論の全趣旨)。 また、形態G(裾のパールの装飾)については、上記ア(ウ)のとおり、原告商品4の 販売以前に裾にパール装飾を施したガウチョパンツが販売されていたところ、当該 商品と原告商品4とはパンツの形状やパールの配置、大きさが異なるが、上記(1)ア
(ウ)bないしdのとおり、平成30年から平成31年当時、パール装飾のある商品が 人気となって複数の商品が販売されていたことからすれば、ストレートパンツの裾 に形態Gのパールを施すことは容易に着想し制作することができる。
2023.11.19
令和3(ワ)4061 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年10月31日 大阪地方裁判所
ウ 相違点1−3について
「有効スティッチ速度」及び「規定されたスティッチ速度」は、本件発明3の構\n成要件3F2の「効果的ステッチレート」及び「所望の織物ステッチレート」と、 それぞれ同義と解され(前記2(5)ウ)、構成要件1G2は、タフティングされた物\n品の模様の外観が所望の模様となるように、模様として見えるタフトよりも実際に 打ち込むタフトが多くなるようにバッキング給送ロールを制御することを特定する のであるから(前記2(5)ア(ア))、前記4(1)イと同様の理由で、乙4公報に接した 当業者は、乙4発明から相違点1−3にかかる本件発明1の構成について容易に想\n到し得ると認められる。
エ 相違点1−4について
前記2(6)アのとおり、構成要件1G3は、規定されたスティッチ速度がゲージに\n従って決定されることを特定するものである。 証拠(乙2、13)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許1の優先日前において、 ゲージは、カーペット構造を制御する必須のパラメータの一つであり、タフティン\nグ機の単位当たりのニードル本数のことでもある。また、本件明細書1(【0049】) には、一部の従来のタフティングシステムにおいては、タフティング模様に対する スティッチ速度は概してタフティングマシンのゲージと一致し、タフティングマシ ンのゲージは縦糸方向の1インチ(2.54cm)当たりの針数に相当し、縦糸方 向の1インチ当たりの針数は概して横糸方向の1インチ当たりのスティッチの数に 等しい旨が記載されている。これらによれば、本件特許1の優先日前において、ゲ ージと模様として見えるタフトの密度を一致させること、すなわち、タフティング された物品の模様の外観において、横糸方向と縦糸方向の密度を一致させるように バッキング給送速度を制御することは、従来技術として存在したものと認められる。 そして、前記4(1)イのとおり、乙4発明は、バッキング材料の給送速度を任意に 変更し得る発明であることに照らすと、乙4公報に接した当業者は、乙4発明から、 規定されたスティッチ速度が、少なくともゲージに従って決定されることを容易に 想到し得るものと認められる。
(4) 顕著な効果の有無
原告は、本件発明1は、所望の位置に所望のヤーンをスティッチすることが可能\nであり、織物の見た目がずれることなく正確なゲージ範囲の模様となるという顕著 な効果を奏する旨を主張する。しかし、前記4(1)イと同様の理由で、タフティング された物品の外観が所望の模様となるように、模様として見えるタフトよりも実際 に打ち込むタフトが多くなるようにバッキング給送ロールを制御する技術である本 件発明1は、実質的に乙4発明に含まれるものであり、その効果についても顕著な 効果があるとは認められない。
(5) 以上から、本件発明1は、乙4発明から容易に発明することができたといえ るから、本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、原告 は被告に対してその権利を行使することができない(特許法104条の3第1項、 123条1項2項、29条2項)。
2023.11.19
令和5(ネ)10048 販売差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和5年11月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これに対し、控訴人は、黒を含む暗色系のウェルトと明るい色合いの縫 合糸との組合せによって明暗のコントラストを演出する靴製品にさしたる個 性や特異性はない旨主張する。確かに「黒色のウェルトと明るい黄色の糸の ステッチ」という形態だけを単独で取り上げれば、靴製品のパーツ(ウェル ト、ステッチ糸)において普通に使用されることが想定される、ありふれた 色彩のうちの任意の組合せにとどまるものであり、それだけから特別顕著性 を認めることは、過剰な独占を認める結果になり相当でない。黒と明るい黄 色とのコントラストによってウェルトステッチが明瞭に視認できるという効 果があるにしても、控訴人の主張するとおり、これに類する明暗のコントラ ストが採用されている靴製品は他にも普通に見受けられるところ(乙32、 33)である。
しかし、本件において、被控訴人は、被控訴人商品を「被控訴人主張形態 (ア)ないし(ク)の形態的特徴を全て有するもの」として定義し(原判決別紙 「原告商品目録」)、これらの「形態上の特徴を全て備える被控訴人商品の 全体の形態」が被控訴人の周知の商品等表示であるとして、不競法2条1項\n1号の不正競争に係る請求を組み立てているところである(原判決15頁2 3行目〜24行目)。
当裁判所は、被控訴人のこの主張を前提に、黄色のウェルトステッチ(形 態(ア))だけでなく、形態(ア)〜(ク)を全て備える被控訴人商品の全体の形態 が商品等表示に該当するかどうかを検討し、そのような観点から、被控訴人\n商品の特別顕著性を肯定したものである。控訴人の主張は、黄色のウェルト ステッチ(形態(ア))だけに着目した議論としては首肯できるにしても、当裁判所の上記判断を左右するものではない。
(4) なお、これに関連して、原審の判断について付言しておく。
原審は、被控訴人商品が備える形態のうち、黄色のウェルトステッチ(形 態(ア))だけを取り上げて、これが周知の商品等表示に当たると判断してい\nるところ、この判断は、控訴人が控訴理由で批判しているとおり、弁論主義 に反するものであったといわざるを得ない。もっとも、被控訴人は、当審に おいて、原審の判断は被控訴人の主張と異なるものではないとの趣旨を述べ ているから、その瑕疵は治癒されていると解されるが、実体判断として採用 できないことは上述のとおりである。
3 被控訴人商品の形態の周知の商品等表示該当性その2(周知性の有無)に\nついて
(1) 上記1の認定事実のとおり、被控訴人商品を含む「1460 8ホール ブーツ」は、昭和60年以降現在に至るまで、被控訴人の日本子会社である ドクターマーチンジャパンを通じて我が国において販売されていること、そ の販売チャンネルは、同社の運営する実店舗72店舗及び公式オンラインス トアのほか、靴小売りチェーン、セレクトショップ等の正規取扱店が含まれ ること、「1460」シリーズの売上げは、令和3年度だけで10万足近く、 販売額で14億円余りに上ること、ドクターマーチンジャパンは、ファッ ション雑誌を中心に「ドクターマーチン」の広告を継続的に掲出しており、 被控訴人商品の写真が掲載されたものもあること、被控訴人商品は、雑誌等 メディアにも再三取り上げられており、その中には、「一目でドクターマー チンだとわかる黄色のウェルトステッチやロゴ入りのヒールループなど…も 特徴」、「ドクターマーチンのトレードマークともいえるイエローステッチ」 など、特に形態(ア)に具体的に言及し、これがドクターマーチンのブーツの 最大の特徴であるとの趣旨のコメントをするものが多いことが認められる。
さらに、被控訴人の依頼により行われたアンケート調査(本件被控訴人 調査)では、「店舗、通信販売サイト、雑誌等で革靴やブーツを見たり、過 去1年以内に革靴やブーツを購入した15歳から59歳までの全国の男女」 を対象に(1019人から回答)、被控訴人商品の写真を示した上で、当該 写真のように靴の外周に沿って黄色のステッチのある革靴やブーツはどこの ブランドの商品だと思うかと質問したところ、「ドクターマーチン」を想起 できた者は、30.7%(自由回答式)〜37.6%(選択式)であったと いうのである(前記引用に係る認定事実)。 以上によれば、形態(ア)〜(ウ)の特徴を備える被控訴人商品の形態は、需 要者の間に広く認識されており、周知の商品等表示に該当するものと優に認\nめられる。
(2) これに対し、アンケートの対象者を「15歳から69歳までの全国の男 女」とする本件控訴人調査の結果では、アンケートで示された写真から「ド クターマーチン」を想起できた者は全回答者の5.47%などとされている (乙15〜18)ところ、控訴人は、これは周知性を否定するものであり、 アンケートの対象者として、控訴人各商品及び被控訴人商品の需要者である 一般消費者を広く対象とする本件控訴人調査の結果を採用すべきであると主 張する。
しかし、本件控訴人調査は、被控訴人商品の全体の形態を示すことなく、 ウェルト、黄色のウェルトステッチ及びアウトソールが写っている部分のみ\nを切り取った写真を示して質問が行われている(乙15の2〔2頁〕)とこ ろ、被控訴人商品全体の形態の周知性が問題となっている本件において、適 切な質問方法とはいえない。また、需要者の範囲に関しても、革靴又はブー ツに関心のある消費者という属性を求めるのが適切というべきであり、この 点、本件被控訴人調査の対象者はやや絞りすぎ(特に「過去 1 年以内」の要 件)のきらいはあるものの、本件控訴人調査よりは、実際の需要者に近い対 象者の選定になっていると評価できる。
◆判決本文
原審はこちら。
◆令和2(ワ)31524
#知財
#訴訟
#不競法
#不正競争行為
#周知
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.11.13
平成27(ネ)10069 売買代金請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年12月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
部品メーカが完成品メーカに対してした特許保証条項について、どのような義務があったのかが争われました。1審では、そもそも特許権侵害ではなかったのだから、払ったライセンス料相当額の損害との間に相当因果関係が認められないと判断しました。知財高裁は、侵害判断については同様ですが、相当因果関係ありとして、一定の範囲の損害賠償を認めました。ただ、過失相殺7割としました。
確かに,前記1のとおり,本件口頭弁論終結時においても,本件チップセットが 本件各特許権を侵害するものであると認めるに足りる証拠がない以上,結果的に見 れば,本件ライセンス契約が締結された時点において,控訴人がWi−LAN社と の間でライセンス契約を締結し,ライセンス料として2億円を支払う必要性があっ たということはできない。
イ しかし,以下の事情を総合すれば,被控訴人による本件基本契約18条2項 違反と,控訴人のライセンス料相当額の損害との間には,相当因果関係を認めるこ とができる。
(ア) 控訴人は,Wi−LAN社から本件各特許のライセンスの申出を受けたこ\nとから,被控訴人に対し協力を依頼した平成22年12月9日以後,継続して,被 控訴人又はイカノス社に対して,本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否 かについての回答を求めていたところ(前記2(1)ア,ウ,エ,サ),イカノス社か らは,平成23年3月22日には,コネクサント社等が詳細な技術分析の結果とし て,Wi−LAN社とライセンス契約を締結していることから,Wi−LAN社の 主張が妥当なものである可能性が高く,イカノス社において,多くの時間とリソ\ー スを費やして技術的分析を行うことは望んでおらず,コネクサント社製のチップ セットに比べてイカノス社製のチップセットの供給量は少ないことから,控訴人と Wi−LAN社とのライセンス契約が最良の解決であると考えていることが述べら れ(前記2(1)セ),同年8月には,技術分析の結果(乙20)に基づき,別件特許 については,これらの技術を使用していないとの報告がされたものの,本件特許1, 2,4,6及び9については,これらの特許がDSLAMに関連する特許であり, イカノス社が提供したCPEの機能に必要な技術とは無関係であるとの報告がされ\nたのみで,これらの技術を使用しているのか否かについての報告がなく,本件特許 3,5,7及び8については何らの報告もなく,かえって,Wi−LAN社に対し て支払うロイヤルティを3社で分担することが提案され(前記2(1)ト),同年10 月には,イカノス社の技術は,コネクサント社の技術と基本的に同じであって,コ ネクサント社が取得したライセンスでカバーされていない技術が残っているのか疑 問があり,Wi−LAN社の主張が妥当である部分については,掘り下げるつもり はないことが述べられ(前記2(1)ヌ),同年11月には,再度の技術分析の結果(乙 21)に基づき,別件特許については,これらの技術を使用していないとの報告が されたものの,本件各特許については,DSLAM送信機の請求項である,CPE の請求項と思われる,DSLAMの実装に固有の要素であり,CPEの実装には見 られない要素であるなどと,本件各特許の請求項についての簡単な報告がされたの みで,本件チップセットが本件各特許発明を充足しているのか否かについての報告 がされていない(前記2(1)ノ)。チップ・ベンダーであるイカノス社が,本件チッ プセットが本件各特許権を侵害するか否かについての調査依頼に対して,上記のよ うな対応をしたことから,控訴人は,同年12月には,ADSL Annex.C については明らかに本件各特許権を侵害するもので,技術的にこれが非侵害である ことを立証することはできない旨の認識を有するに至ったものである(前記2(1) ハ)。
(イ) また,同年4月には,被控訴人,控訴人及びイカノス社の間において,W i−LAN社とのライセンス契約締結に当たっては,ライセンス料,算定根拠等の 観点からの検討が必要であることが確認された。その際,控訴人からイカノス社に 対してロイヤルティ率の提示を要請し,イカノス社は,本件各特許のような特許権 に対する標準的な料率に関する情報を準備し,提示する旨述べたものの(前記2(1) タ,チ),同年7月13日には,合理的なロイヤルティ率については,具体的な数 字を提示することは困難であるとして,提示することができなかった(前記2(1) ツ,テ)。次に,イカノス社は,コネクサント社製のチップセットに適用されるロ イヤルティ率に基づく検討を提案し,同ロイヤルティ率を突き止めるよう努力して 結果を報告する旨述べたものの,これについても新たな情報を発見することができ なかったと報告するにとどまり(前記2(1)テ),結局,被控訴人又はイカノス社か ら,控訴人に対し,ライセンス料の算定に関する情報は何ら提供されなかった。
(ウ) そして,控訴人は,同年2月24日,Wi−LAN社に対し,チップ・ベ ンダーの一社であるコネクサント社がWi−LAN社との間でライセンス契約を締 結しているのであれば,ライセンス交渉の前提が変わるとしてその確認をしたい旨 通知したところ,同年3月1日には,Wi−LAN社から,コネクサント社にライ センス済みのものは控訴人とのライセンス交渉の対象外であること,控訴人に対す るライセンス料の提案額480万USドルは既に大幅に減額したものであって,コ ネクサント社とのライセンス契約の事実が影響するものではない旨の回答を受けた (前記2(1)コ)。さらに,控訴人は,同年3月13日,Wi−LAN社に対し,控 訴人のイカノス社からの購入数量に見合ったライセンス条件の再提示を求めたとこ ろ,同月23日には,Wi−LAN社から,コネクサント社に対するライセンス済 みの製品があることについては控訴人に対するライセンス料の提示において大幅減 額をした際に織り込み済みであること,控訴人が妥当であると考える数字を提案さ れたい旨の回答を受けた(前記2(1)ス,ソ)。控訴人は,同年4月頃に,Wi−L\nAN社に対し,コネクサント社とイカノス社から購入した各製品の数量を開示し(後 者は前者に比べて非常に小さい。),これらの数値を検討して新たな提案をするよ う求めたところ,その後,Wi−LAN社からは請求額を430万USドルに引き 下げる旨の回答を受け(前記2(1)タ,チ),さらに,同年7月ないし8月頃に,W i−LAN社に対し,ロイヤルティはチップセット数量に基づいて算出されるべき であり,現実的ロイヤルティ額は,例えば11万USドルから12万USドルの範 囲内にあるべきことを主張したところ,同年10月6日には,Wi−LAN社から, 控訴人とWi−LAN社の本件紛争の解決に対する見解には大きな隔たりがあると して,早期の解決をする場合にはどの程度の金額の提示が可能かを2週間以内に連\n絡するよう,Wi−LAN社は,控訴人からの提案を受け取った時点で,現在提示 している早期ライセンスのオファーを取り下げるか否かを決定し,2週間以内に回 答がない場合には,自動的に早期ライセンス交渉は終了することなどの回答を受け た(前記2(1)ナ)。さらに,控訴人は,同月7日には,Wi−LAN社に対し,W i−LAN社の要求する300万ないし400万USドルのロイヤルティは非ライ センス製品であるイカノス社からの控訴人の実際の購入量が小さいため適切でない 旨を説明したところ,同年12月には,Wi−LAN社からの提示額は290万U Sドルまで減額され(前記2(1)ハ),その後,本件ライセンス契約締結時には2億 円に減額されている。 このように,控訴人は,イカノス社からの購入数量は,コネクサント社からの購 入数量と比較して非常に小さいことから,イカノス社からの実際の購入数量に応じ てライセンス料も大幅に減額すべきであることを継続して主張していたが,Wi− LAN社からは,控訴人に対するライセンス料の提示に当たり考慮済みであるとさ れ,Wi−LAN社による提示額も漸減していたとはいえ,被控訴人及びイカノス 社からは,ライセンス料の算定に関する情報は何ら提供されなかったことから,こ れ以上は,減額交渉の材料が他に見当たらない状況であった。
(エ) 他方において,控訴人は,平成22年12月27日,Wi−LAN社から, 1)早期ライセンス,2)交渉された又は遅延したライセンス及び3)訴訟後のライセン スの3段階のライセンシングがあることを示され,平成23年3月15日までにラ イセンス契約を締結しない限り,早期ライセンスのオファーは撤回され,その後, 交渉された又は遅延したライセンス(第2ラウンド)(早期ライセンスが拒否され た場合又は遅延作戦が行われた場合,オファーは撤回され,ポートフォリオ全体に つき詳細な違反調査が行われ,ロイヤルティ率が著しく増加し,条件及び賠償金の 過去分について柔軟な対応を行いにくくなる。),さらには,訴訟後のライセンス (訴訟終了後,全ての既存のオファーは撤回され,交渉は振出しに戻り,ライセン スのオファーは裁判所により課された料率等でされ,全額賠償,増額賠償等の全て の費用を含み,裁判所により課された料率と係争中の条件を変更する柔軟性はほと んどない。)に進む可能性がある旨の申\出を受けた(前記2(1)イ)。控訴人は,同 年3月13日には,Wi−LAN社に対して,期限の猶予を求めたが(前記2(1) ス),同年10月6日には,Wi−LAN社から,控訴人とWi−LAN社の見解 には大きな隔たりがあり,早期解決のための金額提示が2週間以内になければ早期 ライセンス交渉は終了し,その後,特許権者としてのあらゆるオプションを留保す る旨の通知を受ける(前記2(1)ニ)などして,平成22年12月27日のライセン ス交渉以来,継続して,早期ライセンスのオファーが終了すれば,次のステージに 移行する可能性を告げられていた。そして,Wi−LAN社は,自らは保有する特\n許を実施しないNPE(Non Practicing Entity)として, それまで大手企業等を相手に差止請求を含めた多数の訴訟を提起し,結果としてラ イセンス料を得るなどの実績を有していたことから(甲8,9,乙2,5),早期 ライセンス交渉が決裂すれば,差止請求訴訟が提起される可能性があり,もし侵害\nの事実が認定された場合には,設計変更等を行うに当たっての損害額は2億円をは るかに超える可能性があった(前記2(1)ヘ)。
(オ) 以上のとおり,前記(ア)のとおりのチップ・ベンダーであるイカノス社に よる技術分析への対応等に照らせば,控訴人が,本件チップセットは,ADSL A nnex.Cに準拠し,Annex.Cに用いるものとしてFRAND宣言がされ ている本件各特許権を侵害する又は侵害する可能性が高いと考えたこともある程度\nやむを得ないところであって,前記(イ)のとおり,被控訴人又はイカノス社からラ イセンス料の算定に関する情報も提供されないことから,前記(ウ)のとおり,これ 以上,減額交渉の材料がない状況の下で,他方,前記(エ)のとおり,Wi−LAN 社からは,早期ライセンスのオファーが終了すれば,次のステージに移行する可能\n性を継続して告げられるなどして,差止請求訴訟を提起されるリスクを負っており, 侵害が認定された場合に被る損害は2億円をはるかに超えることが予想されたこと\nを総合的に鑑みれば,平成24年2月23日の時点において,控訴人が,本件ライ センス契約を締結し,ライセンス料2億円を支払うことも,社会通念上やむを得な いところであり,不相当な行為ということはできないのであって,被控訴人による 本件基本契約18条2項違反と,控訴人のライセンス料2億円相当額の損害との間 には,相当因果関係を認めることができる。
◆判決本文
1審はこちら。
2023.11.13
令和5(ネ)10044 商標権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和5年11月1日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件使用許諾契約は既に効力を失っており、在庫商品について例外的に本件商標の使用が許諾された期間も経過しているから、本件使用許諾契約が有効である間に製造され本件商標が付された商品であっても、これを販売することは、前記1のとおり、商標法2条3項2号の「商品に標章を付したものを譲渡し」たとして「使用」に当たり、本件使用許諾契約及び本件解約合意に違反するものである。
上記事実によると、破産会社は本件在庫商品を販売できる期間を自ら合意していながら、その期間内に本件在庫商品を販売せずに、販売可能な期間を徒過したものであり、控訴人はその地位を承継したものであるから、控訴人が主張する各事実をもって、信義則違反又は権利濫用に当たるものとはいえない。\n
◆判決本文
原審はこちら。
◆令和4(ワ)18610
しかし、商標法31条2項は、「通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内
において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有す
る。」と規定しており、通常使用権の範囲、期間、条件等は使用許諾契約によ
り定められることになるが、前記1のとおり、本件使用許諾契約は既に効力を
失っており、在庫商品について例外的に本件商標の使用が許諾された期間も既
に経過しているから、本件使用許諾契約が有効である間に本件商標が付された
商品であっても、今後、これを販売することは、本件使用許諾契約及び本件解
約合意に違反するものである。そうすると、現時点において、通常使用権者で
あった破産会社の地位を承継した原告が、商標権者である被告に対し、本件商
標を付した本件在庫商品を販売することは実質的違法性を欠くなどと主張し得
ないことは明らかである。
また、商標法は、商標を使用する者の業務上の信用及び需要者の利益を確保
することを目的とするところ(商標法1条参照)、需要者である一般消費者は、
登録商標が付された商品を商標権者から直接購入する場合ではなくとも、商標
権者の許諾に基づいて登録商標が付された商品を購入しようとする際には、商
標権者による技術指導や品質検査等を前提とする商品であると理解し、商標権
者が登録商標を付して流通に置いた正規の流通経路によった商品と出所及び品
質が同一の商品を購入することができる旨信頼するのが通常であり、その信頼
を裏切らないことにより、商標権者の業務上の信用が確保されるというべきで
ある。ところが、前記1のとおり、本件商標を付した本件在庫商品が市場に出
回ることは、商標権者である被告の許諾がないことから、正規の流通経路によ
らないものであるといえるし、本件商標を使用するに当たっての遵守事項を定
めた本件使用許諾契約が解約されたことにより、破産会社又は原告がこれに従
う法的根拠が失われ、被告は本件在庫商品の品質管理を行い得る立場にないこ
とになる。そうすると、原告が本件商標を付した本件在庫商品を販売すること
は、本件商標の出所表示機能\及び品質保証機能を害するものといえる。
さらに、平成15年最判は、商標権者から商標の使用を許諾された者が使用
許諾契約で定める条件に違反して当該商標を付した商品を製造したところ、別
の業者が当該商品を海外で仕入れて日本に輸入する行為、いわゆる並行輸入の
違法性が争われた事件に関する判断であるのに対して、本件は、かつて商標の
使用を許諾されていた者自身の行為の違法性が問われているから、事案を異に
する。原告が指摘する他の裁判例についても、同様である。
したがって、原告が本件商標を付した本件在庫商品を販売することについて、
商標権侵害の実質的違法性を欠くとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.11. 2
令和4(ネ)10113 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年10月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 本件明細書に記載された従来技術、発明の課題及び課題を解決するため の手段は、以下のとおりである(前記引用に係る補正後の原判決「事実 及び理由」第4の1(2)のとおりであるが、再掲する。)。
(ア) 従来技術では、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や 織り方を変えることで患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させてい たが、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができないとい う問題があった(【0002】)。先行特許文献に記載された逆U字 型のパッドを備える構成では、膝蓋骨を吊り上げて大腿四頭筋の機能\ を補助することができず、縦方向と横方向の伸長率を変化させてずれ にくくする構成はサポーター本来の機能\とは関係がないという問題が あった(【0003】)。
(イ) 本件発明は、膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節 を良好に固定するコンプレッションサポーターを提供することを発明 の課題とし(【0005】)、この課題を解決するための手段として、 本件発明の構成要件A〜Cの構\成を採用した(【0006】)。
(ウ) これにより、本件発明は、適切に膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持 して、膝関節を良好に固定し得るコンプレッションサポーターを提供 するという効果を奏する(【0020】)。
ウ 控訴人は、本件明細書の記載に基づき、本件発明の課題は「膝蓋靭帯を 圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するコンプレッ ションサポーターを提供すること」であり、当該課題は、低伸縮領域で あるほぼU字型の「正面吊り領域」が「膝蓋靭帯を圧迫」すると共に 「膝蓋骨を吊り上げ」て「大腿四頭筋の機能を補助」することで解決さ\nれるものであり(【0010】、【0011】)、このことから、本件 発明の本質的部分は、「低伸縮領域として、膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、 膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部\nを取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域」を備えると いう構成(構\成要件Bi)であると主張する。
エ しかし、本件特許の出願前に頒布された乙4文献には、別紙4「乙4文 献の記載」の事項が記載されている(乙4及びその訳文)。 これらの記載から、乙4文献には、伸縮性材料からなり着脱容易な膝サ ポータ(第1の1)であって、シリコーン材料、ゴムなどの弾性材料か ら形成され、膝蓋骨用開口部の横及び下から膝蓋骨の下部を取り囲み、 下部膝蓋靭帯の上に位置するU字形状パッドを備え付けることにより (第1の1、2、第2の1、3)、下部膝蓋靭帯の領域に押圧力を生じ させ、膝蓋骨の負荷を軽減するもの(第2の2、4)が開示されている と認められる。 なお、上記「パッド」は、伸縮性材料からなり着脱容易な膝サポータに おいて、シリコーン材料、ゴムが例示される弾性材料から形成され、こ れが位置する領域に押圧力を生じさせるものであるから、上記伸縮性材 料より伸縮性が低いと認められる。
また、乙4文献には、膝蓋骨を保持又は「吊り上げ」ることは明記され ていないが、本件発明においても「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋を補 助する」のは「膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設け た正面吊り領域」であり(構成要件Bi、本件明細書【0006】)、 この「正面吊り領域」は、「本発明においては、低伸縮領域として、膝 蓋靭帯を圧迫するために、膝蓋骨17の下部を取り囲むほぼU字型…に、 本体正面に設けた正面吊り領域を具備している。低伸縮領域である正面 吊り領域を、ほぼU字型に形成することにより、膝蓋骨を吊り上げ、大 腿四頭筋を補助するものである。」(【0010】)、「膝蓋靭帯15 を圧迫するために本体正面に設けた正面吊り領域22を具備する。正面 吊り領域22は、膝蓋骨17の下部を取り囲む湾曲部を有するほぼU字 型…に設けられており、膝蓋骨17の下部を取り囲む湾曲部を有するこ とにより、前述のように膝蓋骨17を吊り上げ、大腿四頭筋に好適な作 用を及ぼすものである。」(【0023】)というものである。
オ 以上の乙4文献の開示事項を考慮すると、本件明細書に従来技術が解決 できなかった課題として記載されているところは、出願時の従来技術に 照らし客観的にみて不十分というべきである。\nそして、乙4文献記載の従来技術をも参酌すると、従来技術に「膝関 節の任意の箇所に必要な押圧を加える」ことができないという問題があ り、「膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固 定するコンプレッションサポーターを提供する」という課題が未解決で あったということはできず、少なくとも、従来技術と比較した本件発明 の貢献の程度は大きいものではないと評価せざるを得ない。以上によれば、本件発明の本質的部分は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものと認めるのが相当であり、少なくとも、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した低伸縮領域の構成を定める構\成要件Cは本件発明の作用効果に直結する部分であって、その本質的部分に含まれるというべきである。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.11. 1
令和3(ワ)33526 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年12月22日 東京地方裁判所
◆登録5607340
本件の対象にはなっていませんが、少し表記が異なる「バレない\ふたえ」という別商標もあります。\n
◆登録5648844
1 争点 2-3(商標法 26 条 1 項 6 号該当性)について
事案に鑑み、まず、争点 2-3(商標法 26 条 1 項 6 号該当性)について検討する。
(1) 証拠(掲記したもの)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 「ばれない」、「バレない」、「バレナイ」の用例等
・・・
(イ) インターネット検索の結果によれば、二重瞼を形成する美容施術や二重瞼形
成用化粧品等の宣伝広告として、「作った二重だなんてバレない」、「バレにくい二
重」、「バレない自然な二重まぶたに!?」、「絶対バレない!自然な二重まぶたの作
り方」、「バレないコツ」、「本気でバレない二重の作り方」、「バレないふたえまぶた」「バレない・腫れない二重整形」といった表現が使用されていることが認められる\n(甲 16、乙 2〜5)。また、「【専門家監修】アイプチのおすすめ人気ランキング 選
【学生向けやバレないものも!】」と題して二重瞼形成用化粧品等をランキング形
式で紹介するウェブページ(丙 3)においても、「アイプチでは周りの人にバレてし
まうのが心配な方も多いはずです。」、「使っていることがバレないようにしたいで
すよね!バレにくさを重視するなら、ファイバーや皮膜式のアイプチがおすすめで
す。」といった記載がされている。さらに、原告商品及び被告商品以外の二重瞼整形
用化粧品等において、商品の説明として、「バレない整形級ふたえ」(丙 1-1)、「バレない!テカらない!」(丙 1-2・3)、「目をつぶってもバレない!」(丙 1-4)、「閉じてもバレにくい!」(丙 1-5)、「極細繊維ファイバーでバレないふたえ成形」(丙 1-6)、「バレない!!整形メイク」(丙 1-7)といった表現が見受けられる。加えて、二重瞼形成用化粧品等以外にも、鼻筋整形用の化粧品の説明として「バレない!カンタ\nン!自然な仕上がり!」との表現が(丙 2-1)、つけ爪(ネイルチップ)の説明とし
て「バレないつけ爪」との表現が(丙 2-2・3)、頬の美容整形施術の説明として「バ
レないリフト」との表現(丙 2-4)が、それぞれ使用されていることが認められる。
イ 被告商品における被告標章の使用態様等
証拠(甲 5)によれば、被告商品 1 の包装には、その表面の上部半分程度を占め\nる大きさの黒色ハート形の図形が配置され、その図形内の最上段には下線付きの「長
時間キープ」の文字が、中段には被告標章 1 が、いずれも包装のベース色であるピ
ンク色で表示されている。また、その最下段には緑色の帯状の図形上に黒色で「リ\nキッドタイプ」の文字が記載されると共に、当該帯状の図形の左端に接着した黒色
丸形の図形内に緑色で「細筆」の文字及び筆先の形状のイラストが記載されている。
さらに、同包装の下部左上側には、上下二段からなる「Eye Catching」、「Beauty」(なお、「Beauty」の「t」は、2 画の交点の左側及び下側が右側及び上側に比して長い十\n文字状にデザインされている。)との記載が、下部左中央には同じく上下二段からな
る「FUTAE」、「LIQUID」との記載が、下部右側には「♯目元サギメイク」との記載
が、それぞれ置かれている。加えて、下部のこれらの記載の間に存在する透明な窓
部からは被告商品 1 の本体を視認し得るところ、これには、下部左上側と同様の構\n成からなる「Eye Catching」、「Beauty」との表示が存在する(ただし、全ての被告商\n品 1 において上記窓部から上記表示が看取し得ることを認めるに足りる証拠はな\nい。)。他方、裏面には、表面と同様の構\成からなる「Eye Catching」、「Beauty」の記載と、一連一体に並べられた「FUTAE LIQUID」の記載のほか、「アイキャッチング
ビューティ ふたえリキッド(二重まぶた化粧品)」の記載等があるが、被告標章 1
の記載はない。
イ 上記(1)イ認定に係る被告商品の包装の表面及び裏面の各記載等を総合的に\n考慮すると、一般消費者からみて、被告商品の名称は、「Eye Catching Beauty FUTAE
LIQUID」及び「アイキャッチングビューティ ふたえリキッド」(被告商品 1)、「Eye
Catching Beauty FUTAE MESH TAPE」及び「アイキャッチングビューティ ふたえ
メッシュテープ」(被告商品 2)と認識されることがうかがわれる。
他方、被告標章については、上記(1)認定を踏まえると、以下のとおり理解される。
すなわち、「ばれない」、「バレない」、「バレナイ」は、その表記いかんにかかわらず、秘密等が露顕しないという意味である。また、被告商品が属する二重瞼形成用化粧\n品等や二重瞼形成のための美容施術の宣伝広告においては、化粧品や美容施術によ
り一重瞼を二重瞼に整えたことが他人に容易には露顕しないという当該化粧品ない
し美容施術の効能や役務の内容の説明又はそのような効能\等をうたうキャッチフレ
ーズと理解される表現として、「ばれない」等に「二重」を組み合わせたものが多数\nみられる。また、二重瞼形成用化粧品等以外の化粧品や美容整形施術等美容関係の
商品及び役務においても、「ばれない」等の語が、他人から当該化粧品や当該施術を
使用していることが露顕しないという説明ないしそのような効能等のキャッチフレ\nーズとして少なからず用いられていることがうかがわれる。これは、美容関係の商
品等の需要者の多くが、当該商品等を使用して人工的・意図的にその状態を形成し
ていることが他人には容易に明らかにならず、当該商品等を使用した結果が自然の
状態として見られることを欲することを踏まえ、当該商品等の提供者において、そ
の欲求にこたえる効果を訴求することを狙ったものと理解される。
「ばれない」等の語が美容関係の商品等においてこのように多く使用されている
実情を踏まえると、二重瞼形成用化粧品等の需要者である一般消費者は、「バレナイ」
に「二重」が組み合わされた被告標章につき、二重瞼を形成していることが他人に
容易に露顕しない化粧品等であるという被告商品の効能等の説明ないしそのような\n効能等のキャッチフレーズと認識・理解するのがむしろ通常といえる。被告商品の\n包装において、被告標章は、「長時間キープ」、「リキッドタイプ」(被告商品 1)又は「テープタイプ」(被告商品 2)という文字等の記載に挟まれるように配置されてい
ること、被告標章のほかに被告商品の名称と認識し得る記載が存在することなどを
考慮すると、なおさらである。このことは、被告標章をなす「二重」の「二」の文
字の下部が、その左端に二条の跳ねがあるかのように図案化されていることを考慮
しても異ならない。
以上より、被告標章は、被告商品の需要者である一般消費者にとって、被告商品
の効能等の説明ないしキャッチフレーズとして理解されるものであり、自他商品識\n別又は出所識別標識としての機能を有するものとは認められない。\n
2023.10.31
令和4(ワ)19876 商標権 民事訴訟 令和5年8月24日 東京地方裁判所
2 商品の類否(争点 2)について
(1) 本件商標 1 と被告各標章について
本件商標 1 の指定商品は、第 16 類「印刷物」(ただし、別件審判に係る予告登録の日までに限る。)のほか、第 9 類「電子印刷物」であるのに対し、被告各標章は紙媒体である雑誌すなわち印刷物に付して使用されるものである。
指定商品「電子印刷物」と商品「印刷物」とは、媒体を異にすることなどから、同一とはいえない。しかし、本件商標 1 の商標登録出願がされた平成28 年当時において既に、雑誌その他の出版物につき、同一人が同一内容の出版物を紙媒体及び電子版として出版することが広く行われていたことは、顕著な事実である。こうした事情等に鑑みると、被告各標章を印刷物に付して使用する行為は、少なくとも、本件商標 1 の指定商品である第 9 類「電子印刷物」に類似する商品についての使用ということができる。これに反する被告らの主張は採用できない。
(2) 本件商標 2 と被告各標章について
本件商標 2 の指定商品は第 16 類「印刷物」であることから、被告各標章を印刷物に付して使用する行為は、本件商標 2 の指定商品についての使用ということができる。
(3) 小括
以上より、被告各出版物に被告各標章を付して使用する被告らの行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標に類似する商標の使用(本件商標1との関係)及び指定商品についての登録商標に類似する商標の使用(本件商標2との関係)に該当し、本件各商標権の侵害と見なされる(商標法37条1号)。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.10.31
令和4(ワ)7920 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年8月25日 東京地方裁判所
他方、作成した動画をユーチューブに投稿し、これを公開して広くその内容 を伝える行為は、投稿者が行う表現活動や事業活動に関わり得るものであって、\nその動画が削除されることで表現活動や事業活動が制限され、投稿者の法律上\n保護される利益が害される場合があるといえる。ユーチューブの利用について は、上記の規約があり、また、グーグルには著作権侵害についての前記のポリ シーがあるところ、権利侵害の通知を行う者が著作権侵害がないにもかかわら ず侵害がされているという情報をグーグルに通知して、それによってグーグル が動画を削除した場合、権利侵害がないにもかかわらず動画を削除されるに至 った者は、本来動画を削除される理由がなくそれが削除され法律上保護される 利益を害されたといえる場合があるといえる。これらによれば、グーグルに対 して権利侵害の通知を行うことは、その内容や態様により、投稿者の法律上保 護される利益を害する違法な行為となる場合があるといえる。
本件通知は、著作権侵害を通知するためのフォームであり、フォームで用意 されていた文言である「私は侵害された著作権の所有者、または当該所有者の 正式な代理人です。」「私は、申し立てが行われたコンテンツの使用が、著作権\nの所有者、代理人、法律によって許可されていないことを確信しています。」と いう記載があり、また、フォームで用意された「著作権者名」、「著作権対象物 のタイトル」についてもそれぞれ記載している。
もっとも、「権利を侵害された作品についての説明」について「その他」とし た上で、「公演の種類」を「氏名」とし、「著作権対象物のタイトル」を「A(ひ らがな併記)」としている。そして、「補足情報」として、権利侵害の内容とし て「パブリシティ権侵害」と明記した上で、「顧客吸引力、宣伝、広告収益目的 のためにタイトルに無断で氏名を使用し、経済的利益を害している。」と記載 している。これらの記載のうち「著作権対象物のタイトル」が人の氏名そのも のであることは明らかであり、「公演の種類」が「氏名」であることや「補足情 報」の記載内容から、これらの記載は、「著作権者名」とされる、Aの氏名その ものを、対象動画のタイトルに用いることで、同人のパブリシティ権を侵害し たと通知していると理解できるものである。
被告Aは、著作権侵害の通知のフォームを利用して本件通知をしたところ、 そのフォームでは、「著作権者名」や「著作権対象物のタイトル」に記入する欄 があり、また、通知をする者が著作権者やその代理人であることなどを表明す\nる定型の文言があるため、上記各欄の記載やその定型の文言が本件通知に含ま れることとなっている。しかし、「著作権対象物のタイトル」や「補足情報」の 上記のような記載からすれば、被告Aは、ユーチューブにおいてパブリシティ 権侵害の通知をする専用のフォームがあったとは認められない状況において、 本件動画のタイトルに被告Aの氏名を用いたことがパブリシティ権侵害である ことを通知する意図で、本件通知をグーグルに送付したと認められる。
本件で、原告は、本件通知は本件動画が通知者の著作権を侵害されている旨 の通知をするものであり、通知者である被告Aには、著作権侵害の有無を事前 に確認する義務があったにもかかわらず、被告Aは、これを怠って原告が著作 権を侵害している旨の虚偽の通知をしたことを請求の原因として主張する。 しかし、ユーチューブにおいてパブリシティ権侵害の通知をするフォームが あったとは認められない状況において、前記 のとおり、被告Aは、本件動画 のタイトルに被告Aの氏名を用いたことが被告Aの顧客吸引力等を利用する パブリシティ権侵害であることを通知する意図で、その旨の記載をするなどし て、本件通知をグーグルに送付したと認められる。そして、本件通知は、著作 権侵害の通知をするフォームを利用したことに伴う記載はあるが、著作権対象 物のタイトルとして氏名のみが記載され、その補足情報の記載が上記のような ものであることからすると、通知者が自らの氏名が対象動画のタイトルに利用 されていることによるパブリシティ権侵害があると通知するものであると理 解できるものである。
前記のとおり、ユーチューブにおいて、グーグルに対し権利侵害の通知を行 うことは、その内容や態様により、投稿者の法律上保護される利益を害する違 法な行為となる場合があるといえる。原告は、本件の請求の原因を上記のとお り主張して被告Aが著作権侵害の有無を調査すべき義務があったと主張する ところ、本件通知の内容や態様が上記のようなものであったことに照らせば、 通知者である被告Aに原告が主張するような著作権侵害の有無を事前に確認 する義務があったとは認められず、同義務違反により原告の法律上保護された 利益が侵害されたことを理由とする原告の請求には理由がない。 なお、グーグルは、本件通知に基づき本件動画を再生できないようにしたが、 被告Aに原告が主張する義務があったとはいえず、被告Aに原告が主張する義 務違反行為があったとは認められないから、同事実は、上記判断を左右するも のではない。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 肖像権等
>> ピックアップ対象
2023.10.31
令和5(ネ)10059 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年10月12日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 判断手法(検討手順)について
ところで、控訴人と被控訴人は、複製又は翻案の有無を検討する手法 としての2段階テストと濾過テストの採否についてそれぞれの立場で主 張しているが、要は、創作性のある表現部分について同一性があるとい\nえるかどうかの判断がされれば足りるのであって、その判断に至る過程 で、最初に両著作物の共通部分の抽出を行うか、創作性の認められる表\n現上の特徴にまず着目するかという検討手順に関しては、合理的・効率 的な判断に資するための合目的的な観点から、事案に応じて適切に使い 分ければ足りる。本件では、控訴人の主張する手法(控訴人のいう2段階テスト)に沿 って(部分的に濾過テストの手法を併用する。)、以下、検討すること とする。
(2) 控訴人地図1の表現上の本質的特徴について\n
ア 控訴人は、控訴人地図1の表現上の本質的特徴として、別紙2記載の本\n質的特徴1)〜7)を主張するところ、別紙の各控訴人地図1(甲1)に照 らして、控訴人地図1がその主張する特徴を備えていると認めることは できる。そして、上記(1)アで述べたところに照らすと、上記本質的特徴1)〜7) は、それぞれを個別に取り上げれば、地理情報の取捨選択、その配置等 の具体的な表現につき、上記のような制約の下での狭い幅での選択が示\nされているにとどまるものであり、従来の地図に比して顕著な特徴を有 するといった独創性が含まれているとまでは認められない。
イ この点、控訴人は、特に本質的特徴1)、同3)、同4)、5)について、従来 の常識にとらわれない素材の取捨選択を行うなどしたものであって、そ の一部の組み合わせだけでも独創性のある表現が認められる旨主張する。\nしかし、まず、本質的特徴1)に関していえば、後述するとおり、そもそ も被控訴人各地図と共通するとは認められないものである(この点は濾 過テストの手法を用いた。)。そして、本質的特徴3)については、控訴 人地図1の作成当時、建物及び住宅の真上から見た形状を影なしのポリ ゴンで記載した地図は複数存在したと認められ(乙6,7,11,14, 15、25、32〜38)、本質的特徴4)、5)については、控訴人地図 1の作成当時、建物の名称及び住宅の番地が、建物及び住宅のポリゴン の中央付近に、(番地についてはアラビア数字で)折り返すことなく横 書きされた記載を含む地図は複数存在したと認められ(乙7,14、1 5、25、32〜38)、いずれもありふれた特徴にすぎない。
なお、控訴人は、上記証拠の地図は、新旧番地を対照するという特殊な 背景の下で作成されたものが含まれているなどと主張するところ、確か に、「番地」の取捨選択において、控訴人の主張する事情は重要な意味 を有するといえるが、上記の証拠の中には、住居表示新旧対照図以外の\nものも含まれているし(乙25、32〜34)、「番地」の取捨選択以 外の要素に関しては、従来のありふれた表現を示す証拠としての適格性\nを失うものではない。控訴人の上記主張は採用できない。
ウ 以上に述べたところを踏まえると、控訴人地図1は、別紙2の本質的特 ・徴1)〜7)を備える総体として表現上の創作性を認めることができるもの\nであり、その表現上の本質的部分の特徴を被控訴人各地図から直接感得\nできるかどうかも、これを断片的、部分的に捉えるのではなく、相違点 も含めた総体としての全体的な考察により検討する必要があるというべ きである。
(3) プロアトラス地図との比較検討
ア 各別紙のプロアトラス地図と控訴人地図1とを、控訴人主張の本質的特 徴の項目ごとに比較すると、以下のとおり認められる。
(ア) 控訴人主張の本質的特徴1)(共通要素a)について
まず、地理情報の取捨選択という観点からみるに、プロアトラス地 図では、控訴人地図1と同じく、「道路・河川」、「検索の目安とな る公共施設や著名ビル等の個別建物形」、「一般住宅及び建物の個別 建物形」、「検索の目安となる公共施設や著名ビル等の名称」、及び 「建物番地」を記載することを選択し、一般住宅及び建物に関する 「居住人氏名」、「地類界」(宅地の境等)、「等高線」を記載して いないことは認められる。しかし、その実際の適用(当てはめ)として、「検索の目安となる公共施設や著名ビル等の名称」等の選択は必ずしも一致していない。 また、プロアトラス地図では、控訴人地図1には記載されていない交 差点名の記載がある(別紙プロアトラス地図・Aの「潮平」等)ほか、 「一般住宅及び建物」に関する「建物名称」を記載している点(プロ アトラス地図・Aの「シャトレ喜鶴」「あけぼの」、プロアトラス地 図・Cの「タウン・ハウス」等)でも相違する。
次に、具体的な表現形式という観点からみても、プロアトラス地図\nは、1)ガソリンスタンドであれば「G」、飲食店であれば「R」、駐\n車場であれば「P」、学校であれば「文に〇の記号」など建物の種類 を示す記号が用いられている点、2)緑地部分が緑色、公共性の高い建 物は濃い灰色、商業施設等はオレンジ色、その他の建物及び住宅は薄 い灰色に塗り分けられ、道路が3色に塗り分けられている点で控訴人 地図1と相違しており、これらの点は、地理情報を表現する際の創作\n性に強く影響を及ぼす有意な相違と評価すべきものである。
控訴人は、これら相違点は、いずれも軽微な相違であり、表現の本\n質的特徴の同一性を失わせるものではないと主張する。しかし、地図 の著作物における地理情報の取捨選択、その配置等の具体的な表現方\n法には一定の制約があり、選択の幅が狭いと解されること(前記(1)ア) を踏まえると、上記のような相違点を軽微なものと評価するのは相当 といえない。控訴人の主張は採用できない。
・・・・
(4) ヤフー地図との比較検討
ヤフー地図は、プロアトラス地図と多くの点で共通する特徴を有するもの であり、したがって、控訴人地図1とプロアトラス地図との対比検討の項目 で述べたところは、ほぼそのままヤフー地図との対比検討に関しても妥当す る。なお、プロアトラス地図になく、ヤフー地図に認められる特徴として、 ガソリンスタンド、コンビニエンスストア及びファーストフードショップの\nチェーン店について、名称ではなく各チェーン店の標章が記載されている点、 名称を折り返して表示する例がある点(ヤフー地図・Aの「健孝クリニック\n南部整形外科」等)が挙げられるが、これは、プロアトラス地図以上に控訴 人地図との表現上の違いが大きいことを示すものである。以上によれば、ヤフー地図についても、控訴人地図1の表\現上の本質的部分の特徴を直接感得できるとは認められないというべきである。
(5) 小括
したがって、被控訴人各地図は、いずれも控訴人地図1を複製又は翻案 したものとは認められないから、その余の点を判断するまでもなく、控訴人 地図1に関する著作権侵害は認められない。
◆判決本文
1審はこちら
関連カテゴリー
>> 複製
>> 翻案
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2023.10.25
平成25(ワ)7478 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟__全文__ 平成28年10月14日 東京地方裁判所
また,本件明細書等には,「第二の割り溝」を形成する方法について, 手法は特に問わないとしており,エッチング,ダイシング,スクライブ 等の手法を用いることが可能であるとされ,このうち,線幅を狭くする\nことが可能であるなどの理由から,スクライブが特に好ましいとするに\nとどまっており(段落【0009】),「第二の割り溝」に関して,そ の形成の方法は特に限定されていない。 そして,本件においては,本件明細書等に従来技術が解決できなかっ た課題として記載されているところが,出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分であるという事情は認められない。\n
以上のような,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明 細書記載の従来技術との比較から導かれる本件発明の課題,解決方法, その効果に照らすと,本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分は,サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物\n半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当たり,半導体層 側にエッチングにより第一の割り溝,すなわち,切断に資する線状の部 分を形成し,サファイア基板側にも何らかの方法により第二の割り溝, すなわち,切断に資する線状の部分を形成するとともに,それらの位置 関係を一致させ,サファイア基板側の線幅を狭くした点にあると認める のが相当であり,サファイア基板側に形成される第二の割り溝,すなわ ち,切断に資する線状の部分が,空洞として溝になっているかどうか, また,線状の部分の形成方法としていかなる方法を採用するかは上記特 徴的部分に当たらないというべきである。
ウ 被告方法は,前記2で認定したように,サファイア基板上に窒化ガリ ウム系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当た り,半導体層側にエッチングにより切断に資する線状の部分を形成し, サファイア基板側にもLMA法のレーザースクライブによって切断に資 する線状の変質部を形成するとともに,それらの位置関係を一致させ, サファイア基板側の線幅を狭くしているのである。 そして,前記2(1)イで説示したとおり,LMA法でサファイア基板 を加工した場合,溶融領域が発生し急激な冷却で多結晶化し,この多結 晶領域は多数のブロックに分かれるが,加工領域中央に実質の幅が極端 に狭い境界が発生し,この表面に垂直な境界線の先端に応力集中するの\nで割れやすくなることが認められる。 そうすると,被告方法は本件発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分を共通に備えているものと認められる。\nしたがって,本件発明と被告方法との相違部分は本質的部分ではない というべきである。
エ 被告らの主張に対する判断
この点に関して被告らは,LMA法のレーザースクライブについて, 対象と「非接触」であるため,クラック等が発生せず,かつ,ほぼ垂直 に分割されることから,本件発明の課題自体が存在しないことになり, そのような方法を用いたとしても,本件発明の本質的部分に当たらない 旨主張する。
そして,乙14(再公表特許第2006/062017号。以下「乙\n14文献」という。)の段落【0039】には,【図9】,【図10】 に関して,LMA法により形成された変質領域に隣接する正常領域のブ レイク面が略垂直である旨の記載がある。 しかしながら,他方で,乙14文献の段落【0043】等には,同じ 【図9】,【図10】に関して,デフォーカス値によっては,正常領域 のブレイク面の垂直方向につき多少の傾斜や段差が存在する旨の記載も あるのであって,LMA法のレーザースクライブであるからといって, 切断面が斜めになることで不良品が生じるという本件発明の課題が発生 しないと認めることはできない。 したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
オ 以上のとおりで,被告方法は,均等の第1要件を充足すると認められ る。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.10.25
平成28(ワ)21762等 特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害差止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月28日 東京地方裁判所
ウ 以上からすれば,前記アのとおり,構成要件Bの「サーボバンドを特定\nするためのデータをエンコードする」とは,「サーボバンドを特定するた めのデータ」を「0」又は「1」の形式に変換することと解すべきところ, 被告製造方法において,上記の形式の変更を行っていることを示す証拠は 何ら存在しない
・・・
第1要件について
本件明細書に記載された従来技術は,隣接するサーボバンドのサーボパ ターンをテープ長手方向にオフセットさせ,それらのサーボバンドの信号 を同時に読み取って比較することで,サーボバンドの特定を行うものであ り(段落【0002】),片側のサーボ信号の読み取りが一時的又は恒久 的にできなくなった場合,サーボバンドの特定を行うことができなかった という課題があった(段落【0004】)。
そこで,請求項1発明は,隣接するサーボバンドに書かれたサーボ信号 を比較せずに,サーボバンドを特定するために,各サーボバンド内に書き 込まれた各サーボ信号に,そのサーボ信号が位置するサーボバンドを特定 するためのデータがそれぞれ埋め込まれ,前記各サーボ信号は,一つのパ ターンが非平行な縞からなり,各データは,前記縞を構成する線の位置を,\nサーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前記各サーボ信号中 に埋め込まれているようにした磁気テープであり(段落【0007】), 本件発明は,その製造方法である(段落【0017】)。
そうすると,本件発明の本質的部分は,構成要件A−3「前記各サーボ信号は,一つのパターンが非平行な縞からなり,各データは,前記縞を構\成する線の位置を,サーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前記各サーボ信号中に埋め込まれていることを特徴とする磁気テープ」にあるといえ,構成要件B「サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする第一工程と,」は本質的部分には当たらないというべきである(被\n告らも特に争っていない。)。よって,被告製造方法は,均等の第1要件を充足する。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 賠償額認定
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.10.25
平成28(ワ)25436 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年9月24日 東京地方裁判所
前記(2)ウのとおり,本件明細書2記載の従来技術と比較して,本件発明2 における従来技術に見られない特有の技術的思想(課題解決原理)とは,従来,グ ルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のyggB 遺伝子に着目し,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子 を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変する ことによって,グルタミン酸の生産能力を上げるための,新規な技術を提供するこ\nとにあったというべきである。また,前記(2)エで検討したとおり,本件明細書2に おける従来技術の記載が客観的に見て不十分であるとは認められない。\n
(ウ) 前記(3)アのとおり,19型変異使用構成は,本件発明2−5に含まれる,\n本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)の変異型yggB遺 伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する構成であり,前記(イ)の本件発明2にお ける特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば,19型変異使用構成の本質\n的部分は,「コリネ型細菌由来のyggB遺伝子に,コリネバクテリウム・グルタ ミカム由来のyggB遺伝子におけるA100T変異に相当する変異を導入し,当 該変異型yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し,ビオチンが過剰量存在す る条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。\n
(エ) 被告は,出願経過,本件優先日2当時の技術水準,19型変異使用構成の効\n果から,19型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては,特許請求の範囲の\n記載の上位概念化をすべきでなく,特許請求の範囲に記載された「変異後のygg B遺伝子の配列である配列番号22という特定のアミノ酸配列におけるA100T 変異」に限定して認定されるべきであると主張する。
しかしながら,前記(2)ア及びイの本件明細書2の記載内容によれば,本件発明2 は,特定の配列のyggB遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象 とするものではなく,また,その解決原理としても,グルタミン酸生産能力を上げ\nるために,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用い てメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変するという 新規な技術を導入するというものであったから,本件発明2の請求項1や請求項4 において変異を導入する前のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙され,請求項6 において変異後のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮して も,本件発明2及びそれに含まれる19型変異使用構成の本質的部分を認定するに\n当たっては,yggB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体 の変異前の具体的配列,あるいは,A100T変異に相当する変異を導入した後の yggB遺伝子の具体的配列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当で ある。これは,被告が指摘するように,本件特許2の出願当初の請求項1にはyg gB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種や変異前後のyggB遺伝子のアミノ酸 配列が特定されていなかったところ,補正によって,現在の請求項1のようにyg gB遺伝子のアミノ酸配列の配列番号が,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブ レビバクテリウム・フラバムを含む。)又はコリネバクテリウム・メラセコーラに 由来する配列番号6,62,68,84及び85に特定されるようになったこと(【0 033】,乙80〜84),請求項1に記載された配列番号6,62,68,84 及び85のアミノ酸配列が相互に相同性が高いこと(乙85)を考慮しても同様で ある。また,被告は,出願経過に関連して,本件特許2の再訂正後の請求項の記載 も考慮すべきとも主張するが,当該訂正の内容は,少なくとも訂正前の本件発明2 の本質的部分の認定には影響しないというべきである。 そのほか,本件優先日2当時の技術水準や19型変異使用構成の効果についての\n被告の主張が採用できないことは,前記(2)エ及び(3)イのとおりであり,これらを 理由として,19型変異使用構成の本質的部分を特許請求の範囲に記載された変異\n前後のyggB遺伝子の具体的配列に限定すべきともいえないから,この点の被告 の主張も,前記(ウ)の判断を左右するものではない。
イ 相違点1について
前記ア(エ)のとおり,19型変異使用構成の本質的部分については,yggB遺伝\n子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体の変異前の具体的配列,あ るいは,A100T変異に相当する変異を導入した後のyggB遺伝子の具体的配 列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当であることに加え,以下の(ア) 及び(イ)の点を考慮すれば,相違点1に係る違い,すなわち,導入されている変異型 yggB遺伝子が由来する細菌の種類の違い及びそれによるyggB遺伝子の具体 的な配列の違いは,19型変異使用構成の本質的部分とはいえない。\n
・・・
(エ) これらの点からすれば,相違点3に係る違い,すなわち相違点2に係るA9 8T変異に加えて,被告製法4の菌株ではV241I変異が導入されているという 点は,本件明細書2で開示された本件発明2の課題解決原理である膜貫通領域の変 異ないしC末端側変異と関連しない部位の1つのアミノ酸に保存的置換を加えるも のであり,A98T変異に加えることで課題解決に影響するものではないから,1 9型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。\nオ したがって,19型変異使用構成と被告製法4との相違点1ないし3は,い\nずれも,特許発明の本質的部分ではないから,(12)及び(13)の菌株を使用する被告製法 4は均等の第1要件を充足すると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 賠償額認定
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.10.23
令和3(ワ)31529 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年9月28日 東京地方裁判所
最後に、原告製品と被告製品の写真があります。
ア 商品の形態に係る「商品等表示」の特定について\n
不競法2条1項1号又は2号は、他人の周知又は著名な商品等表示(人の\n業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品 又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)と同一又は類似の商品等表\示 を使用等することをもって、不正競争に該当する旨規定している。この規定 は、周知著名な商品等表示の有する出所表\示機能を保護するという観点から、\n周知著名な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤\n認混同させて顧客を獲得する行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保 するものと解される。そして、商品の形態は、特定の出所を表示する二次的\n意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所 表示機能\を有するものではないから、上記規定の趣旨に鑑みると、その形態 が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能\を発揮するよ うな特段の事情がない限り、商品等表示には該当せず、仮にこれに該当した\n場合であっても、商品の形態は本来的には商品の出所表示機能\を有するもの ではないのであるから、商品の形態のうち出所表示機能\を発揮する商品等表\n示部分は、取引の実情等によって時間的にも場所的にも変わり得るものとい える。
そうすると、原告らが商品の形態の商品等表示該当性を主張する場合には、\n商品等表示として権利範囲を画する部分がそれ自体不明確であることに鑑\nみると、商品の形態のうち出所表示機能\を発揮する商品等表示部分を明確に\n特定する必要があるものと解するのが相当である(知的財産高等裁判所平成 17年(ネ)第10068号同17年7月20日判決参照)。
これを本件についてみると、原告らは、主位的に、原告製品全体の形態が 商品等表示に該当する旨主張して、商品の形態のうち出所表\示機能を発揮す\nるという部分を明確に特定していないことからすると、原告らの主位的主張 は、上記において説示したところに照らし、主張自体失当というほかない。 他方、原告らは、予備的に、原告製品の形態のうち、出所表\示機能を発揮す\nるという部分が本件形態的特徴であるという限度で特定して主張している ため、本件形態的特徴が商品等表示に該当するかどうか、以下検討する。\n
イ 本件形態的特徴の「商品等表示」該当性について\n
前記アのとおり、商品の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有す\nる場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所表示機能\を 有するものではないから、不競法2条1項1号又は2号の規定の趣旨に鑑み ると、その形態が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能\ を発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないという\nべきである。 そうすると、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特 徴(以下「特別顕著性」という。)を有しており、かつ、2)特定の事業者に よって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強力 な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を表\n示するものとして周知であると認められる特段の事情がない限り、不競法2 条1項1号又は2号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当であ\nる。
そして、不競法2条1項1号又は2号にいう商品等表示に該当すると主張\nされた表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品の形態が\n商品等表示に該当しないときであっても、上記表\示が全体として商品等表示\nに該当するとして、上記一部の商品を販売等する行為まで不正競争に該当す るとすれば、出所表示機能\を発揮しない商品形態までをも保護することにな るから、上記規定の趣旨に照らし、かえって事業者間の公正な競争を阻害す るというべきである。のみならず、不競法2条1項1号又は2号により使用 等が禁止される商品等表示は、登録商標とは異なり、公報等によって公開さ\nれるものではないから、その要件の該当性が不明確なものとなれば、表現、\n創作活動等の自由を大きく萎縮させるなど、社会経済の健全な発展を損なう おそれがあるというべきである。
そうすると、不競法2条1項1号又は2号にいう商品等表示に該当すると\n主張された表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態\nが商品等表示に該当しないときは、上記表\示は、全体として不競法2条1項 1号又は2号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。\nこれを本件についてみると、前記認定事実、検証の結果(検証調書参照) 及び前記認定に係る子供用椅子の販売状況によれば、原告製品は、1)左右一 対の側木の2本脚であり、かつ、座面板及び足置板が左右一対の側木の間に 床面と平行に固定されている点(特徴1))、2)左右方向から見て、側木が床 面から斜めに立ち上がっており、側木の下端が、脚木の前方先端の斜めに切 断された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、側木と 脚木が約66度の鋭角による略L字型の形状を形成している点(特徴2))と いう本件形態的特徴のほか、3)座面板と足置板を側木内側にはめ込んで固定 することによって、これらの部材を直接固定し、その余の固定部材を省いた 点(特徴3))、4)前後方向からみて、座面板、足置板、横木及び背板と、側 木が垂直に交わっており、側木内側の小さな略半円形状の溝部分を除き、直 線的要素が強調されている点(特徴4))、5)左右方向からみて、側木につい ては、これを一直線とし、その上端の2隅を直角とし、脚木についても、こ れを一直線とし、その先端側と後端側の各2隅の角度を略左右対称とした点 (特徴5))、6)上下方向からみて、身体に接触する曲線状の背板並びにこれ に対応する座面板及び足置板の後部波状部分を除き、座面板と足置板の前部 を直線状の形状とし、その2隅を直角とした点(特徴6))に特徴があるもの と認められる。
そうすると、原告製品は、これらの各特徴を全て組み合わせることによっ て、身体に接触する背板部分及びこれに対応する座面板及び足置板の後部波 状部分を除き、側木、脚木、横木、座面板、足置板及び背板という椅子を構\n成すべき最小限の要素を直線的に配置し、究極的にシンプルでシャープな印 象を与える直線的構成美を空間上に形成したという限度において、形態とし\nての特徴があるものと認められる。
他方、本件形態的特徴は、図面又は写真で特定されるものではなく(意匠 法6条、24条、意匠法施行規則3条各参照)、上記にいう特徴1)及び特徴 2)を文字で特定されるにとどまるものである。そのため、本件形態的特徴は、 それ自体複数の商品形態を含むところ、本件形態的特徴には、原告らが主張 するとおり被告各製品が含まれるほか、側木が曲線を含む形態、座面板や足 置板が曲線の形態その他の直線的構成美を欠く多種多様な形態を含むもの\nであるから、原告製品が形成する直線的構成美を欠く非類似の商品形態を広\n範かつ多数含むものである。しかも、原告らの主張によれば、本件形態的特 徴(特徴1)及び特徴2))は、本件形態的特徴のみに限るというのではなく、 例えば特徴3)が付加された形態も、本件形態的特徴に含むというものである から、本件形態的特徴は、座面板と足置板を固定するための複雑な部材を採 用する形態その他の究極的にシンプルな構成美を欠く多種多様な形態を含\nむものである。
したがって、本件形態的特徴は、そもそもその外延が極めて曖昧であり、 商品形態が商品等表示として認められる場合を限定する不競法2条1項1\n号又は2号の上記趣旨目的に鑑みると、原告らは、原告製品のうち出所表示\n機能を発揮する商品等表\示部分を明確に特定するものとはいえない。 のみならず、原告らにおいて本件形態的特徴をそのまま具備すると主張す る被告各製品についてみても、被告各製品は、座面板及び足置板を固定する ために、支持部材、丸みを帯びた固定部材及び略円形のネジ部材を設ける構\n成を採用し、特徴3)を有するものではない。そのため、被告各製品は、需要 者に対し、椅子全体として安定して使いやすい印象を与えるものの、複雑な 上記構成によって、究極的にシンプルな印象を与える直線的構\成美を欠くも のといえる。しかも、被告各製品は、前後方向からみると、背板中央に楕円 形の大きな穴が形成されており、かつ、固定部材を側木にネジ止めするため、 側木には円形状の穴が多数形成されていることからすると、被告各製品は、 直線的でシャープな印象を明らかに損なうものである。さらに、被告各製品 は、左右方向からみても、側木上部が床面と略垂直方向に折れ曲がっており、 一直線の側木で構成される原告製品の直線的でシャープな印象とは、全体と\nして大きく異なる印象を与えている。加えて、被告各製品は、上下方向から みても、座面板及び足置板の前部及び後部が端部から緩やかな曲線状に形成 されており、椅子全体として柔らかい印象を与えるものであるから、座面板 及び足置板の前部が直線で構成される原告製品の直線的でシャープな印象\nとは明らかに異なるものである。
これらの印象の相違を踏まえると、被告各製品は、座面板及び足置板の固 定において複数の部材を利用する点において、原告製品のような究極的にシ ンプルな印象を与えるものではなく、かつ、曲線的形状を数多く含む点にお いて、原告製品のような直線的でシャープな印象を与えるものではない。 したがって、直線的構成美を造形表\現する原告製品の高いデザイン性に鑑 みると、少なくとも被告各製品の形態は、究極的にシンプルでシャープな印 象を与える直線的構成美を欠くものであるから、原告らの出所を表\示するも のであると認めることができないことは明らかである。 以上によれば、本件形態的特徴に含まれる被告各製品の形態は、明らかに 原告製品の商品等表示に該当しないことからすると、本件形態的特徴は、全\n体として不競法2条1項1号又は2号にいう商品等表示に該当しないと認\nめるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 翻案
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.10.23
令和3(ワ)10991 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和5年9月29日 東京地方裁判所
(1) 証拠(甲10、12の2、12の4、12の5、12の6、13の3、1 4の2、14の3)によれば、原告は、原告ブランドの店舗開店当初から、 原告商標を、同店舗のポスター、看板、Tシャツ、パーカー、アクセサリー 等に印刷して使用していたこと、令和元年頃には、横浜、東京、千葉、名古 屋等に常設又は臨時店舗を開設し、同店舗及びオンラインショップで、原告 商標が印刷された商品を販売していたことが認められる。 また、前提事実(4)イのとおり、原告は、他のアパレル会社等とコラボレ ーションをし、原告商標を改変したり、同イラストの下部又は右下部にコラ ボレーションをしたアパレル会社のブランド名を記載したりしたものをTシ ャツ等の胸元に印刷して、販売することがあった。
これらの事実に照らせば、原告商標は、これを付した製品の出所を示す ものとして、一定の知名度を有していたと認められる。 そして、被告は、前記4のとおり、原告商標と誤認混同のおそれがある 被告標章を、前提事実(5)のとおり、被告製品に付して使用していたのである から、被告標章の使用は、自他識別機能を果たす態様での使用であるといえ、\n商標的使用に該当するというべきである。
(2) これに対し、被告は、被告製品は被告標章が胸部の中央に大きく印刷され たものであるところ、需要者は、通常、Tシャツの首後ろ部に印刷された被 告シリーズの名称や、被告製品販売時に付された紙製のタグにより被告製品 の出所を認識するから、被告標章により出所を認識するものではなく、被告 標章は自他商品識別機能を果たさない態様で使用されていたと主張する。\nしかし、商標がTシャツの首後ろ部の表示やタグだけではなく、胸元に\n大きく付された商品も多く存在すると認められること(当裁判所に顕著な事 実)に照らすと、需要者がTシャツの首後ろ部に印刷された名称や紙製のタ グにより被告製品の出所を認識するとの事実を直ちに認めることはできない というべきであり、本件全証拠によっても、被告主張の事実を認めることは できない。
2023.10.23
令和5(行ケ)10038 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年10月12日 知的財産高等裁判所
本願商標は、「athlete Chiffon」の文字を標準文字で表\nしてなるところ、その構成中の「athlete」の文字は、各種英和辞典\n(乙1〜4)により、「運動選手。スポーツ選手。アスリート。」等の意味 を有するものとして掲載され、その表音を片仮名で表\した「アスリート」の 文字は、国語辞典(乙5)に、「運動選手」を意味するものとして掲載され ている。また、その構成中の「Chiffon」の文字は、各種英和辞典(乙\n1,6)に「シフォン(絹、ナイロンの透けるような布)」「絹またはナイ ロンの軽くて柔らかい織物」を示す名詞や、「軽くてふんわりした。」「〔ケ ーキなどが〕軽くてフワフワした」等の意味を有する形容詞として挙げられ る「chiffon」に由来するものであり、また、その表音を片仮名で表\ した「シフォン」の文字は、国語辞典(乙7)に、「うすくやわらかい絹織 物」との意味の他、複合語として「シフォンケーキ(chiffon ca ke)」(たまごの白身をよく泡立てて加えた、ふんわりして口どけのいい スポンジケーキ。(用例)「紅茶―」)」が掲載されている。これらは、い\nずれも、平易な単語として一般に親しまれているものである。
(3) 各種ウェブサイトや新聞記事(甲4〜9、乙8〜59)によれば、菓子や パン類を含む飲食物や、各種の商品又は役務について、運動選手向けである という商品又は役務の種類を表すものとして「アスリート」「athlet\ne」(欧文字は語頭もしくは全体が大文字のものを含む。以下同じ。)の文 字を語頭に配した「アスリートケーキ」「アスリートパンケーキ」等の語が、 広く使用されている実情が認められる。そうすると、当該「アスリート」の 部分は、後半に続く商品又は役務が「運動選手向け」であることを示すもの として取引者、需要者に認識されるものといえる。 この点、原告は、「athlete」の語からは、「元気」「頑丈」「健 康」等の優れたイメージが想起され、「アスリート」の文字を語頭に配した 商品において、需要者として、運動選手以外の人も想定される旨主張する。
しかし、標章中の「アスリート」「athlete」が取引者・需要者に 「運動選手向け」の商品又は役務を示すものとして認識されるからといって、 その実際の需要者として運動選手のみが想定されることになるものではな く、両者は次元の異なる問題である。 また、原告が援用する「アスリート」「athlete」を含む商標登録 例又は使用例(甲22、30〜54、65〜69)も、上記の認定(語頭の 「アスリート」「athlete」の語は後半に続く商品又は役務が「運動 選手向け」であることを示すものとして取引者、需要者に認識されること) を妨げるものではない。
(4) 各種ウェブサイトや新聞記事(甲10〜12、14、75、乙60〜10 0)において、「シフォン」「chiffon」が「シフォンケーキ」の略 であることを前提に、語頭に、その提供対象を表す語を配した例(「お子様\nシフォン」「お一人さまシフォン」等)、原材料、味を表す語を配した例(「バ\nナナシフォン」「チョコシフォン」等)、行事等の名称を表す語を配した例\n(「バレンタインシフォン」「ひなまつりシフォン」等)が広く使用されて いることが認められる。なお、前掲乙8では、パンと菓子の教室のメニュー で、「アスリートシフォン」というシフォンケーキが提供されている。また、 各種ウェブサイトや新聞記事(甲75,79,80、乙101〜130)に よれば、シフォンケーキ専門の飲食店や店舗の店名に「シフォン」「chi ffon」が用いられていることが認められる。 そうすると、「シフォン」「chiffon」の語頭に、提供対象や原材 料、味を表す語が配された場合、語頭の部分は、後半に続く「シフォン(シ\nフォンケーキの略称)」の種類、内容を表すものであると容易に理解される\nとみるのが相当である。 この点、原告は、多数の商標登録例やグーグルで検索された実例から、飲 食物を販売又は提供する業界でも「Chiffon」がシフォンケーキを意 味しない例が多数存在する旨主張する。 しかし、「chiffon」を含む商標又は店名を使用してシフォンケー キ以外の飲食物を提供している実例があるからといって、飲食物の提供に係 る取引者、需要者の多くが、「chiffon」をシフォンケーキと認識す ることに変わりはないのであって(この認定を覆す反証としては不十分であ\nる。)、原告の主張は上記認定判断を左右するものではない。
(5) 以上によれば、前半に「athlete」の文字と、後半に「Chiff on」の文字とを表し組み合わせた「athlete Chiffon」と の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「運動選手向 けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、 これをその指定役務中、「運動選手向けのシフォンケーキの提供」に使用し ても、これに接する取引者、需要者に、当該役務において提供される飲食物 が運動選手向けのシフォンケーキであること、すなわち、役務の質(内容) を表示したものとして認識させるにとどまり、役務の質(内容)を普通に用\nいられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法3条1\n項3号に該当するといわざるを得ず、これと同旨の本件審決の判断に誤りは ない。
なお、原告の前記第3の1(1)ウの主張(「athlete Chiffo n」という名の実際の店でシフォンケーキ以外のスイーツも取り扱われ、ア スリートの顧客は4分の1程度であるなど)は、上記判断を左右するもので はない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.10.14
令和5(ネ)10047 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年10月3日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、授乳室は最適の場所に設置されるものであり、通常は移動が考 えられないから、乙6発明に授乳室の移動を容易にするという動機付けが内 在しているとはいえない旨主張する。 しかし、乙6文献の記載によれば、乙6発明に係る授乳室は設置場所の 壁と床から独立した部材からなる筐体であり、これを既存の建物内に搬入す る形で設置したものと認められるから、設置場所の変更や一時的な退避等の 理由による移動を行うことも十分想定されるものである。乙6発明は移動を\n容易にするという動機付けを内在しているというべきであり、控訴人の主張 は採用できない。
(2) 控訴人は、乙6発明と本件各引用文献記載の技術事項は技術分野が異なり、 乙6発明の属する「プライバシーに配慮した筐体内部に保育空間を形成する」 技術分野においては、筐体にキャスターを付けることが周知技術であるとは いえない旨主張する。 しかし、本件発明と乙6発明の相違点である「筐体を移動させるキャス ターを備えること」(本件発明の構成要件E)の技術的意義についてみると、\n本件明細書の記載(【0009】「キャスターを利用して授乳用ユニットを 適切な位置に移動させるという作業を行うだけで、授乳用空間が形成された 授乳エリアを設置することができる。」、「キャスターを利用して授乳用ユ ニットを移動させるだけで…授乳用空間のレイアウトの変更を容易に行うこ とができる。」、【0032】「…このように筐体4の底面7にキャスター 36が設けられているため、キャスター36を利用して、地面上で授乳用ユ ニット1を簡易に移動させることができる。」、【0033】「このように、 本実施形態に係る授乳用ユニット1は、キャスター36を利用して地面上を 移動させることができると共に、固定部材37により任意の位置に固定する ことができる。この構成のため、以下の効果を奏する。…本実施形態によれ\nば、所定の空間に、授乳用ユニット1を持ち込み、キャスター36を利用し て、適切な位置に授乳用ユニット1を移動させて、固定部材37で位置を固 定するという簡単な作業を行うのみで、授乳者がプライバシーが完全に保護 された状態で授乳を行うことが可能な授乳用空間3を設けることができ\nる。」、【0034】「さらに、本実施形態によれば、授乳用ユニット1は、 キャスター36を利用して地面上を移動させることができるため、授乳エリ アのレイアウトの変更も容易である。」)によれば、本件発明においても、 授乳中に筐体を移動させることまで想定しているとは認められず、単に内部 の空間に利用者が入ることが可能な筐体を簡易に移動させることができるよ\nうにすることにあると認められる。
このような構成要件Eの技術的意義からみると、本件各文献記載の技術\n事項において、筐体に人を収容する目的が異なるからといって本件発明と技 術分野が異なるなどということはできない。 さらに、本件各引用文献のうち、乙5公報に記載された発明の内容は、 「少なくとも周囲の人の視線を遮ると共に、内部に保育空間を画成する遮蔽 体からなる本体」と「扉」が取り付けられたものであるから(乙5)、「プ ライバシーに配慮した筐体内部に保育空間を形成する」ものと認められるし、 その他の本件各引用文献の記載内容も、筐体に人を収容する目的はそれぞれ 異なるものの(乙13公報は感染性疾患を有する患者の治療、乙14文献は 内部で仕事や読書をするためのパーソナル空間、乙15文献は高気圧酸素環\n境での有酸素運動、乙16公報は浴室、乙17公報は居室内の個室)、いず れも外部の視線を遮り、プライバシーを守る目的又は効果を有する筐体に関 するものである。控訴人の上記主張は、いずれにせよ採用できない。
(3) 控訴人は、乙6発明には、授乳室を当初設置した場所から移動することに よる利用者の利便性の低下、スペースが十分に確保されていない場所への移\n動による人の動線の悪化、人目の届かない場所等への設置による利用者の安 全性の低下又は巡回のための町役場職員の業務増加等、移動による支障が非 常に大きいという阻害要因がある旨主張する。 しかし、控訴人の主張する内容は不適切な場所に移動した場合の弊害に すぎないから、乙6発明に適切な場所への移動を容易にするための移動手段 を設けることについての阻害要因があるとはいえない。
(4) 控訴人は、本件発明は予測できない顕著な効果を有する旨主張する。\n しかし、1)簡易迅速な授乳室の移動を可能・容易にすること、2)授乳用空 間の増設やレイアウト変更を実現することは、いずれもキャスターを付ける ことによる通常の効果であり、3)利用者による授乳室周辺への回遊の促進を 実現すること(例えば、フードコート付近に設置することによるフードコー トの利用者の増加〔甲33〕)は、適切な場所に授乳室を設置することによ る効果であり、いずれも予測できない顕著な効果ということはできない。\n
(5) 以上のとおり、控訴人の当審における補充的主張はいずれも採用できず、 原審が判断するとおり、本件発明は、当業者が乙6発明に周知技術を組み合 わせることにより容易に発明をすることができたものと認められ、本件発明 は特許無効審判により無効にされるべきものである。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.10.11
平成27(ワ)25780等 特許権を受ける権利を有することの確認等請求,真の発明者ではない旨の宣誓手続請求反訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年1月22日 東京地方裁判所
納入業者がした発明について、納入先が特許出願をしました。発明者には当該納入業者は記載されていませんでした。東京地裁29部は、原告らは共同発明者であると認定しました。また人格的利益を侵害の慰謝料として33万円を認めました。
◆本件特許
原告らは、本件特許から遅れて、10ヶ月後、自ら別の出願していました。
◆原告ら特許
エ 被告は,Fが原告Aに対して,本件攪拌混合機ないし本件角堀掘削ヘッドに
ついて特許出願したい旨を伝えたところ,原告Aが「うちはいいから,会社で出し
て。」と述べた,また,原告Aは,平成25年12月21日,被告従業員らに対し,
本件特許出願の発明者について「私は年だから息子のほうをお願いします。」と述
べたなどと主張し,被告従業員らの各陳述書(乙30ないし32)があるほか,証
人Fも証人尋問において同旨の証言をする。
しかし,前者(原告Aが「うちはいいから,会社で出して。」と述べたとの事実)
については,それがいつ,どのような場面において原告Aからされた発言であるか
が主張上も,証人Fの証言上も明確でないから,同事実を認定するには至らない。
後者(原告Aが「私は年だから息子のほうをお願いします。」と述べたとの事実)
については,Fは,証人尋問において,「A社長と相談したら,自分じゃなくて若
い者にしてもらったらいいかなというふうに聞いた」,「ありがとうございますと
言われたような気がします。」,「島根に来られたときなんで,ちょっとはっきり,
日付までおぼえてないですけれども。」などと証言するにとどまり,原告Aがいか
なる文脈で,どのような趣旨で発言したのかについて明確に証言しないから,発言
した日時,場所等はもとより,原告Aが,本件各発明について,被告による本件特
許出願に際し,自らを発明者として記載せず,原告Bを発明者として記載すること
を了承する趣旨で上記のような発言をしたとまで認定することは困難である。
(3) 本件各発明の発明者について
ア 発明者の意義について
「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうか
ら(特許法2条1項),「発明者」というためには,当該発明における技術的思想
の創作行為に現実に関与することを要する。
そして,発明は,その技術内容が,当該の技術分野における通常の知識を有する
者(当業者)が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度まで具
体的,客観的なものとして構成されていなければならず(最高裁昭和49年(行\nツ)第107号同52年10月13日第一小法廷判決・民集31巻6号805頁参
照),また,特許法が保護すべき発明の実質的価値は,従来の技術では達成し得な
かった技術的課題を解決する手段を,具体的構成をもって社会に開示した点に求め\nられる。これらのことからして,「発明者」というためには,特許請求の範囲の記
載により画される技術的思想たる発明のうち,当該発明特有の課題解決手段を基礎
付ける部分(特徴的部分)につき,これを当業者が実施できる程度にまで具体的,
客観的なものとして構成する創作活動に現実的に関与した者であることを要すると\nいうべきである。
イ 本件発明1について
本件発明1は,「地盤を攪拌しセメントミルクを混合し硬化させて基礎杭を構成\nするためのものであって,先端部に該セメントミルクを噴射するノズル,進行方向
に掘削するための先端掘削翼,及び該先端掘削翼の回転軸と直角の回転軸を持つ横
掘削翼を,該先端掘削翼より根本側に中心軸を挟んで向かい合って少なくとも2つ
設けたことを特徴とする地盤改良装置。」との特許請求の範囲により画される発明
である。
本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の段落【0
006】ないし同【0009】の記載によれば,本件発明1は,従来技術が有する
課題(地盤を攪拌し,セメントミルクを注入して杭を生成する地盤改良装置におい
て,先端の攪拌翼〔掘削翼〕が回転するタイプであるため,重複して掘削する必要
があり,また,部分によりセメントの強度が異なるとの問題)を解決するため,従
来技術の構成(進行方向に掘削するための先端掘削翼)に加えて,先端部にセメン\nトミルクを噴射するノズル及び先端掘削翼の回転軸と直角の回転軸を持つ横掘削翼
を,先端掘削翼より根本側に中心軸を挟んで向かい合って少なくとも2つ設けたと
の構成を採用することにより,簡単に矩形状に杭を構\築できるとの作用効果を生じ,
上記課題を解決するものであり,これらの構成が本件発明1の特徴的部分というこ\nとができる。
しかるところ,前記認定事実((1)エ,なお(2)イも参照。)によれば,被告は,平
成22年1月10日,原告らに対して被告が新たに調達するリーダレス型のベース
マシンに取り付けるオーガモーターや掘削ヘッドの製作を依頼するに際して,市場
に一般に流通していたツインブレード型の地盤改良装置を参考に,現在1号機や2
号機で使用されている先端掘削翼を有する掘削装置に,デファレンシャルギアなど
を用いて回転軸と直角の回転軸を持たせこれに2枚の横掘削翼を設ける構成として\nはどうかなどと提案し,指示していることが認められるから,被告従業員らは,同
日に先立ち,水平掘削翼と,これと直角に回転する回転軸に設置された横掘削翼と
から構成されるという,本件発明1の特徴的部分に通じる着想を有していたものと\n認められる。
なお,この点に関連して,原告らは,被告が原告らに製造を依頼したのは,「水
平方向に地盤を広範囲に連続攪拌する機能を備えた地盤改良装置」であって,角柱\n杭を形成することは予定されておらず,原告らが平成25年8月10日に行った試\n掘により覚知したと主張する。前記認定事実((1)エ,オ,ク)によれば,被告は,
浅層ないし中層の地盤改良装置を原告らの参考とさせ,原告らに交付した注文書に
は「浅層改良機」との記載があり,また,平成26年に至ってから本格的に本件角
堀掘削ヘッドを深層まで杭を打ち込むことが可能な2号機において稼動させること\nを前提とした種々の発注等を行っていることなどが認められるから,被告は,当初,
角堀掘削ヘッドを浅層ないし中層の地盤改良用途を中心に用いることを構想してい\nた可能性が相応に認められる。しかし,浅層ないし中層の地盤改良であっても,杭\nを並べて打つことにより広範囲を改良する工法は一般的に行われているから(本件
明細書の段落【0007】の記載や,甲第45号証にもかかる工法をうかがわせる
記載がある。),被告が当初有していた着想が,角柱杭を形成することを予定して\nいなかったということはできない。
もっとも,被告は,原告らに対し,上記の基本的な構成のアイデアを示し,参考\n資料としてパワーブレンダー型地盤改良装置とツインブレード型地盤改良装置のパ
ンフレットを交付したにとどまり,これを超えて,簡易な模型や図面等を提供した
との事実は何ら認められないところ,前記認定事実((1)エ,オ)のとおり,原告ら
は,これら基本的な着想を基に使用するべきギアを決めるなどして仕様を定め,本
件見積書やCAD図を作成して本件角堀掘削ヘッドの構成を具体的に決定し,また\n製作においては地盤改良装置等の重機の製造等に長年従事してきた原告Aをもって
も半年以上の期間を要し,さらに,現実に動作する製品を製作するにはギアの調整
等に試行錯誤を要したことなどからしても,被告が平成25年1月10日に原告ら
にした着想の開示さえあれば,これを具体的,客観的なものとして構成し,反復し\nて実施することが,当事者にとって自明程度のものにすぎないということはできな
い。そうすると,被告従業員らにより示された本件発明1の特徴的部分の着想を当
業者が実施可能な程度に具体化する過程において,原告らが相応に創作的な貢献を\nしたものと認めるのが相当である。
したがって,本件発明1は,その特徴的部分の着想から具体化に至る過程におい
て,被告従業員ら及び原告らがそれぞれ創作的に貢献したものと認められるから,
その発明者は,被告従業員ら及び原告らの5名である。
ウ 本件発明2ないし同4について
本件発明2は,本件発明1に「該横掘削翼は,該先端掘削翼より根本側で,且つ
該先端掘削翼近傍に設けたものである」との発明特定事項を加え,本件発明3は,
本件発明1又は同2に「全横掘削翼の回転面と直角の攪拌面積が,該先端掘削翼が
掘削する面積の1/6以上である」との発明特定事項を加え,本件発明4は,本件
発明1ないし同3に「全横掘削翼は2つである」との発明特定事項を加えた発明で
ある。これらの発明の特徴的部分は,前記イに述べた本件発明1の特徴的部分のほ
か,上記発明特定事項にあるものと認められる。
そして,前記イに認定説示したところによれば,これらの特徴的部分の各着想か
ら具体化に至る過程においては,被告従業員ら及び原告らが相応に創作的な貢献を
したというべきであるから,本件発明2ないし同4の発明者も,被告従業員ら及び
原告らの5名である。
エ 共同発明者各自の貢献度について
これまで認定説示してきたとおり,本件各発明は,被告従業員ら及び原告らの共
同発明と認められるところ,各自の貢献度については,前記認定事実に認定したと
おりの本件各発明に至る経緯を総合し,本件各発明の特徴的部分に係る着想と,そ
の具体化の各過程の価値を等価なものとして,被告従業員らが2分の1,原告らが
2分の1として,さらに,被告従業員ら側内部における各人の貢献度,原告ら側内
部における各人の貢献度も,それぞれ等価なものと認めるのが相当である(なお,
仮に,本件各発明との関係で原告Bを原告Aの単なる補助者とみる余地があるとし
ても,弁論の全趣旨によれば,原告らは本件各発明についての特許を受ける権利の
共有持分につき,各2分の1とする旨合意したことが認められるから,上記認定が
判断左右されるものではない。)。
したがって,本件各発明についての共同発明者間の各貢献度は,原告A及び原告
Bが各4分の1,F,D及びEが各6分の1ということになる。なお,前記1の認
定事実によれば,被告従業員らは,本件特許出願に先立ち,本件各発明についての
特許を受ける権利の共有持分を,少なくとも黙示的に,被告に承継させたものと認
められるが,原告らが本件各発明についての特許を受ける権利の共有持分を被告に
承継させたと認めることは困難であり,ほかに被告が原告らから本件各発明につい
ての特許を受ける権利の共有持分を承継したと認めるに足りる証拠はない。
(4) 争点2の結論
以上によれば,原告A及び原告Bは,それぞれ,本件各発明について特許を受け
る権利の各4分の1の共有持分を有しているものと認められる一方,被告は,本件
各発明について特許を受ける権利の各2分の1の共有持分を有しているものと認め
られる。
2 争点2(発明者名誉権の侵害により原告Aが受けた損害の額)について
上記1のとおり,原告Aは本件各発明の共同発明者であるところ,前記前提事実
(第2,2(3))のとおり,被告は,本件特許出願に際して,本件各発明の発明者と
して原告Aの氏名を記載していない。この点に関して,原告Aが,本件特許出願に
関し,本件各発明の発明者として自らの氏名を記載しないことを了承したと認める
ことが困難であることは,前記(2)エのとおりであり,被告には,原告Aの氏名を記
載しなかったことにつき,少なくとも過失が認められる。
被告の上記行為は,原告Aが本件各発明について発明者として記載されるべき人
格的利益を侵害するものとして不法行為を構成するというべきであり,これにより\n原告Aが受けた損害を賠償する責任を負う。
そこで,原告Aが受けた損害につき検討すると,原告Aが本件各発明の共同発明
者と認定する本判決が確定すれば,原告Aは本件特許出願書類中の発明者の表記を\n訂正できる可能性があること,本件特許出願が公開されたのは平成27年8月3日\nであること,原告らは本件特許出願が公開される前に自ら本件角堀掘削ヘッドを基
にした発明について特許出願しており,原告らを発明者とする同特許出願は,平成
28年5月30日には公開されていることなどなどの事情によれば,発明者として
記載されるべき人格的利益を侵害されたことによる原告Aの損害としては,慰謝料
30万円,弁護士費用相当額3万円の合計33万円を認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2023.10.11
令和5(行ケ)10023 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年10月3日 知的財産高等裁判所
本件特許はこれです。多数の分割出願があります。
◆本件特許
(1) 本件発明は、上昇下降用プロペラの回転軌跡を複数の翼に内接させるこ
とでプロペラガードとして兼用するとの構成を備えるものであるところ、個別の取消事由の検討に入る前に、ここでいう「内接」及び「プロペラガード\nとして兼用」の意義を明らかにしておく。
(2) 「内接」とは、国語辞典に「多角形の各辺がその内部にある一つの円に
接する時、その円は多角形に内接する…」との用例が挙げられているとおり
(甲11)、図形の各辺とその内部の円などが接していることを表す用語である。\n
本件明細書の【0013】には、「図8は本発明第5の実施例で、上下用
プロペラ4つの回転軌跡39を全部内接させ、プロペラガードを設けずに4
枚の主翼24と先尾翼28と尾翼29をプロペラガードに兼用させたもので
ある」との説明が記載され、図8には、上昇下降用の4つのプロペラが示さ
れ、うち翼の間に配置された左右2つのプロペラの回転軌跡がそれぞれ前後
の主翼24と接するように示されている。
同様に、図7、9においても、翼の間に配置された上昇下降用の複数のプ
ロペラの回転軌跡が前後の翼に接するように示されており、これに本件明細
書の【0012】〜【0014】(前記第2の2(2)イ)の記載を総合すれ
ば、図7〜9に係る第4〜6実施例は、上昇下降用プロペラの回転軌跡を複
数の翼に内接させることでプロペラガードとして兼用するとの構成を示すものと解される。\nもっとも、プロペラの回転軌跡と翼が文字通り接する(接触する)場合、
プロペラの回転が妨げられることが明らかであるから、本件発明の「内接」
とは、プロペラの回転軌跡が翼と接触するには至らない限度で十分に近接していることを意味するものと解される。\n
(3) そして、本件発明の「プロペラガードとして兼用」とは、特許請求の範
囲の記載に示されているとおり、複数の翼の間に配置された上昇下降用プロ
ペラの回転をガードする機能をいうものであり、この機能\は、複数の翼の間
に配置された上昇下降用プロペラの回転軌跡を前方又は後方の複数の翼に内
接させることによって生じるものであると認められる。また、本件発明の上記第4〜6実施例(図7〜9)では、複数の翼の間に配置された上昇下降用プロペラの回転軌跡の一部のみが翼に内接する構成が示されていることから、上昇下降用プロペラの回転軌跡の少なくとも一部が翼に内接していれば、翼がプロペラガードとして機能\するものと解される。
(4) 原告は、「内接」とは「プロペラ軌跡が両翼に挟まれ、かつ両翼端部を結んだ線を出ないことを意味する」とも主張するが(上記第3の1(2)ア)、図7〜9の実施例がそのような構成を有するものだとしても、特許請求の範囲に当該構\成を加える訂正(減縮)をしたわけでもないのに、「内接」という文言自体をそのような限定的な意味で解釈することは許されないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> リパーゼ認定
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2023.10.10
令和5(行ケ)1004 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年9月28日 知的財産高等裁判所
そして、証拠(乙1〜21)及び弁論の全趣旨によれば、下段の「RaaS」 の欧文字は、ロボット・アズ・ア・サービス(「Robot as a S ervice」又は「Robotics as a Service」)の 略で、「ロボットをサービスとして提供・利用することができるサービスで あり、ロボット本体やロボットを制御するシステムを自社でつくり運用する のではなく、ロボット本体をレンタルし、クラウド上にある制御システムを 利用するしくみ」を意味するものとして、上段の「ラース」の文字はその読 み方として一般に用いられていること、このような意味における「ロボッ ト・アズ・ア・サービス(RaaS)」の概念は、本願の指定商品及び指定 役務に係る物流業界、製造業界、金属加工業界、食品加工業界を含む産業界 において注目を集め、実際に、一部の業界において、「RaaS(ラース)」 と称されてロボットが提供(貸与)されていることが認められる。 そして、本願商標は、上段に「ラース」の片仮名を、下段に「RaaS」 の欧文字を二段に表してなるものであるが、特に図案化がされているもので\nもなく、普通に用いられる方法で表示されたものである。\n
(3) そうすると、「RaaS」の欧文字及びその読み方を表した「ラース」\nの片仮名を二段に表したにすぎない本願商標に接した取引者、需要者は、\n「ロボットをサービスとして提供・利用することができるサービスのための ロボット並びにその部品及び附属品」及び「ロボットをサービスとして提 供・利用することができるサービスのためのロボットの貸与」を意味するも のと理解し、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、本願商標は、 商品の品質、用途及び役務の質、提供の用に供する物、提供の方法を表した\nものと認識するにとどまるというべきである。 よって、本願商標は、商品の品質、用途及び役務の質、提供の用に供す る物、提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標\nであるから、商標法3条1項3号に該当する。
(4) これに対し、原告は、「RaaS」自体に特定の意味がなく、「RaaS」 から商品又は役務の特徴等を認識できないと主張する。 しかしながら、前記のとおり、本願商標を構成する「RaaS」、「ラー\nス」の文字は、ロボット・アズ・ア・サービス(ロボットをサービスとして 提供・利用することができるサービス)を意味するものとして用いられてい ること、このような意味における「RaaS(ロボット・アズ・ア・サービ ス)」の概念は、本願の指定商品及び指定役務に係る物流業界、製造業界、 金属加工業界、食品加工業界においても注目を集めていることが認められる のであって、「RaaS」が頭文字の集合体であるからといって、それ自体 から特定の意味を認識させないとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.10.10
令和4(ネ)10094 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年10月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載には、分割出願が適法である か否かにかかわらず、サポート要件違反があり、本件訂正が有効であったとしても、 サポート要件違反があることが認められるから、結局、本件特許は特許法36条6 項1号違反により無効にされるべきものであり、同法104条の3第1項により、 原告は被告に対し、本件特許権を行使することはできないと判断する。その理由は、 以下のとおりである。
(2) 本件についてみると、本件明細書(以下、原出願当初明細書も同じ。)には、 「発明が解決しようとする課題」として、「出願人は、1234yf等の新たな低地 球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在すること を見出した。」(【0003】)との記載がある。また、「本発明によれば、HFO−1234yfと、HFO−1234ze、HFO−1243zf、HCFC−243 db、・・・caからなる群から選択される少なくとも1つの追加の化 合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも1つの追加の化合物の約 1重量パーセント未満を含有する。」(【0004】)、「HFO−1234yfには、いくつかある用途の中で特に、冷蔵、熱伝達流体、エアロゾル噴霧剤、発泡膨張剤 としての用途が示唆されてきた。また、HFO−1234yfは、V.C.Pap adimitriouらにより、Physical Chemistry Che mical Physics、2007、9巻、1−13頁に記録されているとお り、低地球温暖化係数(GWP)を有することも分かっており有利である。このよ うに、HFO−1234yfは、高GWP飽和HFC冷媒に替わる良い候補である。」 (【0010】)といった記載に、【0013】、【0016】、【0019】、【0022】、【0030】、【図1】の記載を総合すると、本件明細書には、HFO−1234yfが低地球温暖化係数(GWP)を有することが知られており、高GWP飽和HF C冷媒に替わる良い候補であること、HFO−1234yfを調製する際に特定の 追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一 つとして約1重量パーセント未満のHFC−143aがあること、HFO−123 4yfを調製する過程において生じる副生成物や、HFO−1234yf又はその 原料(HCFC−243db、HCFO−1233xf、HCFC−244bb) に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているということが できる。
しかるところ、HFO−1234yfは、原出願日前において、既に低地球温暖 化係数(GWP)を有する化合物として有用であることが知られていたことは、【0 010】の記載自体からも明らかである。したがって、HFO−1234yfを調 製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義がある のか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることにな るのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記 載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何 ら記載がなく、その余の記載をみても、本件明細書には、本件発明が解決しようと した課題をうかがわせる部分はない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開 示内容は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニ ング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよ びポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にあ る消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、2,3,3, 3,−テトラフルオロプロペン(HFO−1234yfまたは1234yf)また は2,3−ジクロロ−1,1,1−トリフルオロプロパン(HCFC−243db または243db)、2−クロロ−1,1,1−トリフルオロプロペン(HCFO− 1233xfまたは1233xf)または2−クロロ−1,1,1,2−テトラフ ルオロプロパン(HCFC−244bb)を含む組成物等の熱伝達組成物として有 用な組成物に関する。」(【0001】)との記載があるが、同記載は、本件発明が属 する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課 題を理解することはできない。
そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」 は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるというこ\nともできない。
(3) 仮に、上記【0001】の記載をもって本件発明の課題を説明したものと理 解したとしても、次に述べるとおり、本件明細書の記載をもって、当業者が当該課 題を解決することができると認識することができるとは認められない。
すなわち、この場合の本件発明の課題は、「2,3,3,3,−テトラフルオロプ ロペン(HFO−1234yfまたは1234yf)または2,3−ジクロロ−1, 1,1−トリフルオロプロパン(HCFC−243dbまたは243db)、2−ク ロロ−1,1,1−トリフルオロプロペン(HCFO−1233xfまたは123 3xf)または2−クロロ−1,1,1,2−テトラフルオロプロパン(HCFC −244bb)を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物を提供すること」 と理解されることとなるはずである。
そして、本件発明は、1)HFO−1234yf、2)0.2重量パーセント以下の HFC−143a、3)1.9重量パーセント以下のHFC−254ebを含む組成 物によって、当該課題を解決するものということになる。 しかるところ、本件明細書には、上記1)〜3)を含む組成物についての記載がされ ているとはいえない。すなわち、【0121】〜【0123】(表5(【表\6】))には、実施例15として、HCFC−244bbからHFO−1234yfへ、触媒無しで変換したところ生じた、HFO−1234yf、HFC−143a及びHFC− 254ebを含む組成物が4例記載されており(加熱された温度(゜C))がそれぞれ 550、574、603、626)、当該組成物に含まれるHFC−143aの量が それぞれ、0.1、0.1、0.2、0.2モルパーセントであること、及び同H FC−254ebの量がそれぞれ1.7、1.9、1.4、0.7モルパーセント であることが記載されている。しかしながら、表5(【表\6】)に記載された組成物 には「未知」のものが含まれており、その分子量を知ることができないから、同表において、モルパーセントの単位をもって記載されたHFC−143a及びHFC−254ebの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。\nそうすると、本件明細書には、上記1)〜3)の構成を有する組成物についての記載がされていないというほかない。それのみならず、本件明細書には、このような構\成を有する組成物が、HFO−1234yfの前記有用性にとどまらず、いかなる意 味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、 示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記1)〜3) の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解することもできない。したがって、当業者は、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することはない。
(4) 以上のとおり、分割出願が有効であり、出願日が原出願日(平成21年5月 7日)となると考えたとしても、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、サポー ト要件に適合するということができないから、本件発明に係る特許は、無効審判請 求により無効とされるべきものである(特許法123条1項4号、36条6項1号)。 そして、このことは、分割出願が無効であり、出願日が分割出願の日(令和元年9 月4日)となる場合でも同様である。
3 争点3(訂正の再抗弁の成否)について
本件訂正発明についても、本件発明に係る請求項1のHFO−1234yfにつ いて「77.0モルパーセント以上」という下限が設定されただけで、本件訂正後 の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合しても、当該下限にどのような技術 的意義があり、これによりどのような課題を解決することができるのかは明らかに されていない。また、前記2(2)及び(3)と同様、本件訂正発明に係る組成物の構成により解決しようとしている課題や、その解決方法が本件明細書に記載されていないことには変わりはない。したがって、訂正が有効だとしても、本件訂正発明に係\nる特許請求の範囲の記載には、前記2(2)及び(3)と同じ理由により、サポート要件 違反の無効理由が存在することとなるので、訂正の再抗弁によりサポート要件違反 の無効理由を解消することはできない。 そうすると、本件訂正の適法性及びその余の争点につき判断するまでもなく、特 許法104条の3第1項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することが できない。
本件特許の無効審決審決取消訴訟です。
◆令和4(行ケ)10125
侵害訴訟の1審はこちらです。
1審は、新規性違反を理由として、権利行使不能と判断していました(特104-3)。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 分割
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.10. 6
令和5(行コ)10001 特許分割出願却下処分取消請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和5年9月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
経過としては、7月7日特許査定謄本送達、同月20日特許料納付、同月29日設定登録、同月8月5日分割出願です。時期としては、分割出願日が設定登録の後となってます。査定謄本の送達日から30日以内(特44条1項2号)という要件は満たしていると争いましたが、設定登録後は「特許出願人」ではないと判断されました。
法解釈的には裁判所の解釈は正しいです。ただ、条文の規定も、ユーザフレンドリーからすると、同2号に「ただし、設定登録後は除く」と確認的に明記しておけば、このような問題は生じないと感じました。
特許出願の分割は、もとの特許出願の一部について行うものであるから、 分割の際にもとの特許出願が特許庁に係属していることが必要であり、法4 4条1項の「特許出願人」及び「特許出願」との文言は、このことを示すも のである。同項1号から3号は、これを前提に、分割の時的要件を定めるも のであり、これに反する控訴人の主張は、同項所定の「特許出願」、「特許出 願人」との文言を無視する独自の議論といわざるを得ず、採用できない。な お、控訴人は、法65条1項を「特許出願人」と記載されていても「特許権 者」と解釈すべき例として挙げるが、同項の「特許出願人」は「警告をした」 の主語でもあるところ、これが出願公開後、設定登録前の特許出願人を指す ことは明らかである。
また、控訴人は、設定登録後は分割出願できないとの処分行政庁の解釈は 法44条1項に関する改正法の立法趣旨に反する旨主張する。しかし、同項 2号が、特許料納付期限(法108条1項)と平仄を合わせる形で、特許査 定の謄本送達日から「30日以内」を分割出願の期限と定めたのは、同期限 内であれば、特許査定を受けた特許出願人の意思によって「特許出願人」た る地位を継続することが可能であることを踏まえて、当該特許出願人が、特\n許査定を受け入れてそのまま特許料の納付に進むのか、分割出願という選択 肢を行使するのかという表裏一体の判断を検討するための猶予\期間を付与 したものと理解することができる。したがって、改正法の内容は、特許出願 が特許庁に係属していることを分割出願の要件とするとの解釈と何ら矛盾 するものではなく、むしろこれと整合するものといえる。
また、中国、台湾における取扱いを述べる控訴人の主張は、各国工業所有 権独立の原則、工業所有権の保護に関するパリ条約4条G(2)第3文に照 らして、本件の判断に影響を及ぼすものとはいえない。
(2) 取消事由2について
控訴人は、特許登録について独占権発生という効果のほかに分割不可化という効果が生じるのであれば、当該効果の部分については特許出願人に通知されて初めて効果が生じる旨主張する。しかし、設定登録は分割不可化という効果を目的とする行政処分ではなく、設定登録によりもとの出願が特許庁に係属しなくなることの派生的効果として、結果的に適法な分割ができなくなるというにすぎないのであって、控訴人の主張は、前提を欠くというべきである。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 分割
>> 特許庁手続
>> その他
>> ピックアップ対象
2023.09.28
令和3(行ケ)10152 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年9月20日 知的財産高等裁判所
(4) 本件発明についてのサポート要件の検討
ア 従来技術の問題2を解決するための手段として、本件発明1は、前記2(2)ア のとおり、回転子積層鉄心を押圧する際の上型及び下型に対する回転子積層鉄心の 配置及び上型と下型との位置関係又は状態を特定する発明であるのに対し、本件明 細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、前記2(3)ウのとおり「回転子積層鉄 心12の下面25が当接する矩形板状のトレイ部26と、トレイ部26の中心部に 立設され、回転子積層鉄心12の軸孔11に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部 材27とを有している搬送トレイ16にセットされた回転子積層鉄心12を下型1 7上に搬送し」、「搬送トレイ16を回転子積層鉄心12と共に、下型17から取り 外し、回転子積層鉄心12が搬送トレイ16から取り外される」ものであるから、 本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、搬送トレイを不可欠の構成として\nいるものと解される。そうすると、本件発明1には、回転子積層鉄心を搭載する搬 送トレイを含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構\成の発明も含 まれており、搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、\n上記発明の詳細な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、 加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、 時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと(従来技術の問題2)を解決して、 生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提 供するという本件発明1の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。 そして、この点は本件発明2及び本件発明3も搬送トレイを構成に含まない発明を\n含むため、同様であるといえる。
イ また、段落【0010】には、「本発明に係る永久磁石の樹脂封止方法におい て、前記回転子積層鉄心は中央に軸孔を有し、前記回転子積層鉄心を前記軸孔に嵌 入するガイド部材を備えた搬送トレイに載せて、前記上型及び前記下型の間に配置 してもよい。」との記載があり、搬送トレイを不可欠の構成とはしていないことを前\n提とした発明の詳細な説明の記載があるが、前記2(4)アのとおり、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載によると、従来技術の問題2を解決するために搬送トレイを 不可欠の構成としているから、搬送トレイを用いずに本件発明の課題を解決するた\nめには搬送トレイに代わる構成が必要となるものと解されるところ、本件明細書の\n記載によっても搬送トレイの具体的構造に関する記載(【0047】【0048】)は\nあるものの搬送トレイに代わる構成を具体的に示唆する記載はなく、これに代わる\n構成が当業者にとって明らかであることを認めるに足りる証拠もないから、当業者\nが出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載が ないまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課 題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。この点、本件発明2 及び本件発明3も同様である。
ウ そうすると、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていな い発明を含むから、特許法36条6項1号の要件を満たさない。
エ この点、本件審決は、本件発明の課題は、本件発明1に係る特許請求の範囲 に記載された「前記回転子積層鉄心を、上型及び下型の間に配置して、前記上型及 び前記下型同士が当接することなく、前記下型及び前記上型で前記回転子積層鉄心 を押圧し・・・前記永久磁石を樹脂封止する」ことにより、解決すると認識できる から、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであると判断し、 被告も、搬送トレイを備えなくとも、サポート要件を満たすとした本件審決の認定 に誤りはないと主張する。 しかしながら、上記判断の前提は、本件明細書において、「このような課題を解決 する発明の実施の形態として、「(a)前工程から送られてきた、永久磁石14が磁 石挿入孔13に挿入され搬送トレイ16にセットされた回転子積層鉄心12を別途 搬送手段等を用いて下型17上に搬送し、上型21(以下、キャビティブロック7 4も含む)に対して位置決めして固定」(【0039】)し、「(b)下型昇降手段33により昇降プレート32を介して下型17を少し上昇し、回転子積層鉄心12とキャ ビティブロック74とを密着させ・・・」(【0040】)、「(c)原料18が加熱されて粘度が下がると、更に、下型昇降手段33により昇降プレート32を介して下 型17を上昇して、搬送トレイ16にセットされた回転子積層鉄心12を上型21 に押し付け」(【0041】、熱硬化性樹脂によって永久磁石を磁石挿入口に固定させ た上で、「下型昇降手段33により昇降プレート32を介して下型17を下降させ」 (【0044】)、「その後、搬送トレイ16を回転子積層鉄心12と共に、下型17 から取り外し、回転子積層鉄心12が搬送トレイ16から取り外され、搬送トレイ 16は別途搬送手段により後工程に送」(【0044】)ることが記載されており、こ れにより、「複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心に形成された複数の磁石挿入 孔に挿入された永久磁石を、樹脂部材を磁石挿入孔に注入して固定する際、上型及 び下型により回転子積層鉄心を押圧し、樹脂部材を磁石挿入孔に充填することによっ て、・・・簡単な工程で、短時間に行うことができ、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる」(【0011】)との効果を奏する発明が記載されている。」といえるものであるから、本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された 上記工程からなる本件発明の実施の形態が課題を解決できることを判断しているも のと認められる。
そうすると、本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された本件発明 の実施の形態について、当業者が課題を解決できると認識できることをいうにとど まり、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範 囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、その記載により当 業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、 その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解 決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断したものとはいえな い。したがって、本件審決は、特許法36条6項1号に規定される「特許を受けよう とする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を判断したものとはい えない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2023.09.28
令和2(ワ)12107 職務発明対価相当請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年8月29日 大阪地方裁判所
イ 超過売上高(超過売上率)
前記前提事実のとおり、被告は、自ら又は本件受託3社に販売委託をして本件製 品2を販売し、本件特許2を実施している。 本件製品2は、先発医薬品Lカプセルの後発医薬品であるが、1回の投与で長時 間シグモイド型の薬物放出を続けるアンブロキソール塩酸塩の徐放OD錠化の技術\nを用いた製品は、本件製品2以外には上市されていない。被告もアンブロキソール\n塩酸塩の徐放カプセル剤及び錠剤(普通錠)を販売し、本件製品2の販売開始後の 平成27年7月に先発医薬品メーカーからアンブロキソール塩酸塩の錠剤(徐放小\n型錠)が販売されたが(乙115)、本件製品2以外にアンブロキソール塩酸塩の\n徐放OD錠の製品が製造販売されている事情は見当たらない。 また、本件製品2は、市場占有率が平成30年に1位となった。 これらの事情を勘案すると、超過売上高(超過売上率)は40%と認めるのが相 当である。
ウ 仮想実施料率
実施料率の判断にあたっては、被告(特許権者)の実施許諾例があればまず検討 し、それがなければ業界相場等や発明の内容等を検討することになるが、被告にお ける実施許諾例がある事情は見当たらない。 医薬品の自己実施に係る実施料率に関する資料によれば、「医薬品では6%前後 の率に…上下1〜2%程度増減した率が大方の相場」とされるもの(乙116)、 「医薬品・その他の化学製品(イニシャル有)」では3〜5%が最も多いとするも の(乙117【図2−5−1】)、3〜5%未満が最も多いとするもの(乙118) が見られる。そして、本件発明2は、1回の投与で長時間シグモイド型の薬物放出 を続けるアンブロキソール塩酸塩の徐放OD錠に関する発明であるが、剤形が異な\nるものの治療学的に同等の有効性、安全性を有する医薬品は他にも存在する。 このような事情を総合考慮すると、本件における仮想実施料率は5%と認めるの が相当である。
エ 本件発明2の貢献度(寄与度)
本件発明2は剤形に関するものであり、服用の利便性から本件製品2の売上げに 貢献しているものと認められる。 他方で、本件製品2は後発医薬品であり、有効成分は先発医薬品(Lカプセル) と同じである。また、本件製品2には、本件発明2に開示されていない製剤化技術 も用いられているものと考えられる。加えて、本件製品2の売上げが好調である要 因は、国のジェネリック医薬品販売促進施策がとられており(乙119、120)、 薬価も先発医薬品に比して格段に安くなっている(乙121、122)ところが大 きい。 これらの諸事情を勘案すると、本件発明2の貢献度は、多くとも60%と認める のが相当である。
オ 共同発明者間における原告の貢献割合
原告は、口腔内崩壊錠の着想をしたのみならず、その具体化の過程である製 造開発の場面においても、自身の知見に基づき、結合剤や徐放被膜のコーティング に用いる添加剤、可塑剤等のあらゆる場面における技術の選定について、本件チー ムのP2らに指示ないし助言し、これを基に本件発明2が完成したことからすれば、 原告の貢献割合は100%に近いなどと主張する。 発明の着想は、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関す る思想として概念化されたものである必要があると解される。また、医薬品の開発 においては、発明を完成させるまでに、試行錯誤を経ながら、添加成分の種類や配 合比率、配合条件等について多数の試作、試験・実験を行い、これから見出される 問題点を改善し、その効能や安全性、利便性等を確立していくことが必要不可欠で\nあると認められる(証人P2、証人P5)。 これらの点を踏まえ、原告の上記主張について、以下検討する。 上記(1)の認定事実によれば、原告が、平成18年頃、アンブロキソール塩酸\n塩の徐放カプセルをOD錠とすれば医療現場から歓迎されると考え、平成19年か らは新製品創出の専属メンバーの一人として、他社製品の調査や技術的検討を行っ た上、OD錠化の発想を一定程度具体化して提案し、瀬踏み実験に関与して、本件 製品2の開発承認決定(平成20年2月)に貢献したことは認められる。 しかしながら、本件発明2は平成23年11月頃に完成したものと認められ るところ(上記(1)ウ m)、添加成分の選定や処方等に関する検討を実際に行った のは、上記(1)のとおり、P2をリーダーとする本件チームであった。すなわち、本 件チームは、本件発明2の特徴的部分の構成を実施可能\な程度に具体化するために 多数の試作、試験・実験を行うなど試行錯誤を繰り返し、その過程において、複数 回にわたって報告(中間報告及び技術説明会)を行い、報告時点における試作実験 の結果及び今後の課題を検討し、課題の解決を目指して3年余りにわたり検討を行 っている。 他方、原告は、本件チームに所属しておらず、開発月例会議等の会議には出席し ていたことが認められるものの、本件チームの行う試験・実験に関与していたとは 認められない。また、原告は、本件チームの発足後、製剤技術部の顧問の地位にあ り、本件チームの職員と接する機会はあったことから、本件チームのメンバーに対 し、その知識及び経験を生かして助言できることがあれば概括的に助言していたも のと認められるが(原告本人、証人P5)、以下のとおり、本件製品2の開発過程 において、具体的な指示に関する客観的な証拠はない。
a 原告は、徐放性微粒子の核粒子として、ハルナールD錠に使用されているセ ルフィアCP−102を用いるよう指示した、他に検討の余地はなかった旨を主張 する。 上記(1)ウ によれば、開発当初は核粒子として用いる添加剤はセルフィア(結晶 セルロース粒)で進めていたが、溶出性に影響する可能性があり、他の添加剤も試\nしてみたが期待した効果は得られなかったことが平成20年11月に報告され、そ の後、結晶セルロース粒の2種のグレードで試作検討した結果、平成21年3月に セルフィアCP−102が選定されたことが認められる。原告が、上記の検討過程 でセルフィアCP−102の使用を指示したことを明らかにする客観的証拠はない。 仮に原告がセルフィアCP−102の検討につき何らかの助言をしたことがあった としても、その選定には上記のような試行錯誤を経て数か月を要していることから すると、原告が他に検討の余地はないものとして選定を具体的に指示したとは認め られない。
b 原告は、薬物レイヤリング工程に関し、溶解法から懸濁法に変更になった際、 文献(甲19、20、22、66〜68等)からの知見に基づき、溶出改善のため 薬物レイヤリング層に崩壊剤を添加すべきこと、また、崩壊剤としてはクロスポビ ドンを検討することを指示した旨主張する。 上記(1)ウ によれば、懸濁法への変更後、平成22年11月から薬物レイヤリン グ層に崩壊剤を添加して、徐放性微粒子の溶出改善を検討し、同年12月には崩壊 剤としてクロスポビドンを添加することが有用と判明したことが認められる。上記 の検討過程において、原告が崩壊剤の添加やクロスポビドンの検討を指示したこと を明らかにする客観的証拠はない。同月の技術検討会の資料(乙55)では、レイ ヤリング層の改良検討の中で、シグモイド曲線を改善する工夫として、クロスポビ ドン等の崩壊剤添加を含むいくつかの工夫案が実験され、その結果としてクロスポ ビドン添加の有用性が報告されている。このような経過の中で、原告が行ったと主 張する指示は内容や経緯が不明確であって、具体的指示の存在を認めることができ ない。
c 原告は、薬物レイヤリングに用いる結合剤として、文献(甲18)を参考に してPVPを用いるよう指示した、他に選択の余地はなかった旨主張する。 上記(1)ウ 及び によれば、平成20年9月の段階では、結合剤としてPVPを 含む4種類が検討されたが、●(省略)●再検討の結果、PVPが選定されたこと が認められる。原告が上記の検討過程でPVPの使用を指示したことを明らかにす る客観的証拠はない。原告は、pH依存性のある化合物が先発製剤(Lカプセル) の中に含まれる場合、これと同じものを使用しなければ同等の溶出率を確保できな いというが、本件チームにおいて、平成20年11月には「結合剤についても先発 の溶出挙動にあわせる組み合わせに目処を得た」、同年12月には「pH依存性の 異なる結合剤を組み合わせることにより、溶出挙動をコントロールすることができ、 標準製剤と合致した溶出性を示す徐放性顆粒を得ることが確認できた」との報告が あり(甲61の1)、原告もそれを知っていたと認められる(甲90)。そうする と、仮に原告がPVPの使用に関する何らかの助言を行ったことがあったとしても、 他の選択の余地がないとして選定を具体的に指示したとは認められない。
d 原告は、平成22年12月頃、徐放性被膜の被覆(放出制御層)に関し、E CとTC−5に類似のグレードの混合被膜を用い、エタノールと水の8:2程度の 混合溶液に溶解して被覆する方法とすることを指示した旨主張する。 上記(1)ウ によれば、懸濁法に変更された後、徐放性被膜のコーティングに関し、 徐放カプセルに用いられている配合を参考にEC及びTC−5のグレードで試作し て溶出性を検討していたところ、平成23年2月の中間報告において、EC(ST D10)とTC−5Rを8:2.5の比率でコーティングすればシグモイド型の溶 出となる旨報告されたことが認められる。上記の検討過程において、原告が被覆の 方法を指示したことを明らかにする客観的証拠はない。また、コーティング剤の処 方につき、AQCを主成分とするものに問題があるとすれば、被告が既に製造販売 していた徐放カプセルの処方を参考としてECを主成分とする試行を行うこと自体 に困難性は認められないし、実際の混合比率は多くの試作,実験を経なければ選択 できないことは明らかである(本件では約50ロットの試作が行われた。)。この ような状況で、原告の主張する指示の内容や経緯は不明確であり、原告が具体的な 指示を行った事実を認めることができない。
e 原告は、文献(甲20)により導かれた知見に基づき、本件製品2の開発当 初から、加圧圧縮により徐放性被膜にひび割れなどの損傷が生じることを防止する ため、ある種の可塑剤が有用であることを認識し、文献(甲23)から得た知見に 基づき、PEG6000(マクロゴール)と薬物を混合して用いることで徐放性被 膜の耐圧性向上が図れると判断して、マクロゴールの添加を指示したと主張する。 しかし、上記(1)ウ によれば、平成21年9月には、プロテクト層(オーバーコ ート第1層)にECとTC−5RにTween80を添加した処方により顆粒の割 れ防止が可能と報告されており、また、上記(1)ウ によれば、平成22年12月か ら徐放層(放出制御層)の主成分をAQCからECに変更することが検討されたの に伴い、プロテクト層の処方も再検討されたことが認められるところ、原告が処方 について提案したことを示す客観的証拠はない。仮に原告もその検討に参加してP EG6000の使用について何らかの言及をしたことがあったとしても、結局は実 験による試行錯誤を経てプロテクト層に配合する薬剤の有効性や処方が明らかにな ったのであるから、原告が具体的な指示をしたとか、それによってマクロゴールの 添加が選定されたとの事実を認めることはできない(原告は「可塑剤」としてPE G6000を用いるというのは誤りであると指摘するが、「可塑剤」の意味合いは ともかく、ここではプロテクト層に配合される薬剤を検討していることに変わりは なく、原告の指摘の点は結論を左右するものではない。)。
f 原告は、崩壊促進層の被覆(粘着防止層)に関し、徐放性被膜に類似のEC を主体とする疎水性被膜を、溶出特性に影響しない程度に薄く被覆して、速崩壊性 を担保するよう指示した旨主張する。 上記(1)ウ によれば、徐放層の主成分がAQCからからECに変更され、オーバ ーコート層にPEG6000(マクロゴール)を用いることとされたところ、PE G6000が露出したままの微粒子を配合して錠剤化すると、水による粘性が生じ、 また崩壊にも悪影響を与えることから、検討の結果、平成23年4月の技術検討会 で、苦味マスキング層と同一処方で薄いコーティング(オーバーコート層第2層) を施すことになったことが認められる。上記の検討過程において、原告が被覆の必 要性や処方について具体的に指示したことを明らかにする客観的証拠はない。また、 原告の主張する指示は、内容が概括的である上、指示が行われた経緯も不明確であ るから、具体的な指示が行われた事実や当該指示の方法で実験が進められた事実を 認めることができない。
g 原告は,他にも本件製品2の開発過程で種々の指示をしたことにより本件発 明2の完成に多大な貢献をした旨主張する。しかし、いずれも原告が具体的に指示 したことを認めるに足りる証拠がなく、原告の上記主張は採用できない。 上記(1)の認定事実、並びに、上記 及び の事情に照らせば、原告のほか、 P2、P3ら本件チームにおいて本件発明2の完成に向けて実験、分析等に主体的 に関与した者も本件発明2の共同発明者というべきである。そして、原告は、アン ブロキソール塩酸塩のOD錠を製することを発想し、それを一定程度具体化して瀬\n踏み実験にも関与し、開発承認を得た点で、本件発明2の特徴的部分の一部につい て着想・具体化し、本件発明2の完成に貢献したといえる。しかし、原告は、その 後は概括的な助言を与えることがあるのみで、発明の具体化に直接的に関与したと は認められないから、本件発明2の特徴的部分の多くについては、着想もその具体 化もしていないといわざるを得ない。 これらの事情を総合すると、原告の共同発明者間における貢献割合は、20%と 認めるのが相当である。
カ 使用者貢献度
被告は、本件製品2の開発設備や費用、製造承認申請に要する費用をすべて負担\nし、本件特許2の出願及びその維持に係る費用もすべて負担している。また、本件 製品2の売上げの拡大に関する営業努力もすべて被告が行っている。さらに、本件 製品2は後発医薬品であり、先発医薬品とは異なって、獲得すべき有効成分や効能\n効果がすでに明らかとなっているところ、後発医薬品は、一般に、先発医薬品に比 べて開発期間は短く、開発費も相対的に少ない反面、薬価も先発医薬品に比べて安 価であって、先発医薬品ほどの利益は必ずしも期待できない。そして、先発医薬品 と治療学的に同等の有効性、安全性を有し、法定の厚生労働大臣の製造販売の承認 を得なければならず、かつ、先発医薬品に求められている改善点にも配慮した競争 力のある医薬品を開発することになる点においては、後発医薬品であっても大きな 開発リスクが生じるというべきであるところ、被告は、このような開発リスクをす べて負担している。 これらの事情に照らせば、使用者貢献度は90%を下ることはないと認めるべき である。
キ 小括
以上の検討によれば、本件発明2に係る相当の対価の額は、次の計算式により算 出された388万8000円となる。
【計算式】 162億円×40%×5%×60%×10%×20%
2023.09.25
令和3(ワ)33996 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年7月7日 東京地方裁判所
(1) 均等の第1要件にいう特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の 特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を 構成する特徴的部分であると解すべきである。\nそして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、 特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきであ る。 また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には、上記のとおり確定される特許発明の本 質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備え ていると認められる場合には,相違部分は本質的部分ではないと判断すべ きである。
・・・
これらの記載に照らすと、本件発明は、把持部を水平方向に軸回転させ て負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢する負荷を 軽くすることを可能にする構\成を採用することにより、使用者が、「弛緩」 と「伸張」の動作を加えながら適切な「短縮」のタイミングを出現させる ことができ、各筋肉群が「弛緩−伸張−短縮」のタイミングを得て、連動 性よく動作を行うことができることを可能にするとともに、両腕を屈曲さ\nせて把持部を引き下げることに伴い、両腕を外側に広げることに対する抗 力が減少する構成を採用することにより、筋の「共縮」を防ぐことを可能\ にし、もって、筋肉の硬化を伴うことなく、筋肉痛や疲労など身体への負 担が少なく、柔軟で弾力性の富んだ肩部や背部の筋肉等を得ることができ るトレーニング器具を提供し、従来技術の課題を解決するものといえる。 そうすると、これらの各構成については、従来技術に見られない特有の技\n術的思想を構成する特徴的部分であると認めることができる。\n
そして、本件明細書においては、上記の各構成のうち、上記把持部を軸\n回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢す る負荷を軽くすることを可能にする構\成について、「把持部60を昇降揺動 部材50に対して軸回転することにより、回転伝達部91及びクランク機 構部92を介して摺動軸57が上下動することに伴い、クランプにより連\n結されたウェイト31が上下動する。」(【0026】)、「把持部60を昇降 揺動部材50に対して初期状態である略正面方向から外側水平方向へ回転 付勢力に抗して軸回転することにより、摺動軸57が昇降揺動部材50に 対して下方向に摺動し、前記クランプにより連結されたウェイト31が引 き上げられる。」(【0027】)との記載がある。
これらの記載に照らすと、本件発明の特許請求の範囲において、上記把 持部を軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向 に付勢する負荷を軽くすることを可能にする構\成に対応する構成は、把持\n部の回転運動を伝達し、同伝達された回転運動を摺動軸の上下動に変換す るクランク機構部を具備する負荷伝達部であり、構\成要件Gの構成である\nと認められる。 本件においては、被告製品が構成要件Gに相当する構\成を備えていない こと(相違点B)に争いがなく、本件発明の本質的部分を被告製品が共通 に備えているとは認められないから、本件発明と被告製品の相違点Bが本 質的部分ではないということはできず、被告製品は、均等の第1要件を満 たさない。
その他にも原告はるる主張するが、いずれも上記結論を左右しない。 以上によれば、被告製品は、その余の要件を検討するまでもなく、本件 発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえないから、\n本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.09.25
令和3(ワ)11286等 損害賠償請求事件(第1事件)、債務不存在確認請求事件(第2事件) 特許権 民事訴訟 令和5年7月13日 大阪地方裁判所
(1) 腸内のpH値及び本件物質の効能に関する要素の錯誤について\n
ア 甲1契約、乙3契約の内容
前記前提事実及び認定事実、乙1によると、●(省略)●であるところ、 本件特許Aの特許請求の範囲請求項1は、「結晶子径が1nm以上100n m以下のシリコン微細粒子又は該シリコン微細粒子の凝集体を含み、且つ水 素発生能を有する経口固形製剤。」というものであり、本件特許発明Bは本\n件製品のいわゆる用途発明である(なお、本件特許発明Aに係る明細書にお いては、pH7以上の領域において、シリコン微細粒子が水素を発生させる ことが記載されている。)。
そして、具体的な用途や製品は、●(省略)●
イ 甲2契約、乙4契約の内容
●(省略)●契約当事者に明らかにされている。
ウ 検討
前記ア、イのとおりの契約内容に照らすと、被告の主張に係る腸内のpH 値や本件物質の効能、生体内での作用機序等は、何ら契約書上明記されてお\nらず、また契約交渉過程において規範として形成されたとも言えないのであ って、そもそも契約の内容となっていないと言わざるを得ない。すなわち、前記前提事実のとおりの本件各特許発明の内容及び上記認定事実に係る甲1契約等に至る過程によれば、被告は、平成30年3月に、第2事件被告代表者から、生体内で水素を発生させてヒドロキシルラジカルを除去するシリコン製剤の研究につき説明を受け、これを用いたペット用及び人用サプリメントの商品化の検討を始め、原告ら(第2事件被告代表\者)から 提供を受けたサンプルを自ら動物への投与等を行ってその効能に関する被\n告なりの具体的検証を実施し、その結果甲1契約を締結するに至ったもので あるが、その過程を通じ、第2事件被告代表者は、乙9資料(マウスによる\n動物実験の結果)の内容をベースに、シリコン製剤が体内で水素を発生させ てヒドロキシルラジカルを除去し、各種疾病に対する効能が確認されたこと\nから、動物や人にもその効果が期待されると説明していたにとどまり、乙9 資料の内容を超えて、効能・効果それ自体を保証したことがないことはもと\nより、腸内環境として想定すべきpH値の妥当性が問題となったり(なお、 本件特許Aの明細書においては、pH7以上で水素発生能を発揮することが\n示唆されていることは前記のとおり。)、前記被告による具体的検証の内容が 問題となったりしたことはないのであって、本件製剤の用途が基本的に健康 食品(サプリメント)であることや本件物質の性能を生かした製品化を行う\nのは被告であることも考慮すると、被告主張の腸内のpH値や本件物質の効 能に関してそもそも誤信があったとはいえないし、仮に何等かの思い違いが\nあったとしても、その実質は、専ら被告の希望的観測との齟齬をいうものに すぎず、甲1契約等の締結にあたって、被告に要素又は契約の効力に影響を 及ぼす動機の錯誤があったとは認められない。
(2) 海外販売に関する要素の錯誤について
ア 前記第2の2(3)(前提事実)のとおり、●(省略)●と規定され、文言上、 明確に国内における通常実施権に関する契約であることが明記されている。 この点については、被告の契約交渉担当であったP1すらも、契約書どおり 国内の通常実施権に関する合意であるとの認識であったと供述する(P1証 人)。 また、甲1契約締結に至る過程では、専ら国内市場における予測需要につ\nいて検討がされており、海外市場における予測需要を具体的に検討した事情\nは見当たらない。 以上に加えて、被告が甲1契約の締結後に初めて具体的な海外販売に向け た行動を講じていること、またその過程で第2事件被告代表者から甲1契約\nにおいて海外販売を承諾していないとの説明があった上でそれについて特 段契約当時の認識との齟齬を表明していないことをも考慮すると、被告自身\nも甲1契約が海外販売を前提としていたと認識していたとは認められず、被 告主張の海外販売に関する錯誤があったと認めることはできない。
イ これに対し、被告は、第2事件被告代表者が、甲1契約締結前に被告によ\nる海外販売を容認する発言をしており、国内販売のみならず海外販売を前提 とすると合計100トンのシリコン製剤を消化することができると判断し たからこそ、合計100トンを最低計画購入量とする原告らの提案に応じた とか、甲1契約締結後に第2事件被告代表者が海外販売を支持する発言をし\nていたことなどをもって、甲1契約において、シリコン製剤を用いた製品の 海外販売が前提となっていたなどと主張する。
しかしながら、第2事件被告代表者が甲1契約前に海外販売を容認する発\n言をしたことを認めるに足りる証拠はなく、また仮にそのような発言や、甲 1契約後に海外販売を支持する発言があったとしても、前記の甲1契約の文 言から認められる実施権の範囲が左右されるとも解されない。被告の主張は、 採用の限りでない。
2023.09.25
令和4(ワ)9090 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年6月12日 東京地方裁判所
(1) 前提事実(第 2 の 1)、証拠(甲 8〜10)及び弁論の全趣旨によれば、本件動 画は、動物等のイメージ画像等を繋ぎ合わせたスライドショー、BGM、本件テロッ プ及びこれを朗読したナレーションによって構成されるところ、スライドショー及\nび BGM のみではストーリー性が乏しく、本件動画の内容を正しく把握することは 困難であると認められる。その意味で、本件テロップ及びこれを朗読したナレーシ ョンは、その余の構成部分に比して、本件動画の中で重要な役割を担うものといえ\nる。また、このような役割を担う本件テロップの内容は、男性 2 人が群れを離れた 野生のライオンを保護し育てた後、野生動物の保護地区に戻したことや、後に男性 らの 1 名がこの保護地区を訪れた際の当該ライオンとの再会の模様等の一連の出来 事に関し、推察される各主体の心情等を交えて叙述したものである。表現方法につ\nいても、本件テロップは、動画視聴者の興味を引くことを意図してエピソード自体\nや表現の手法等を選択すると共に、構\成や分量等を工夫して作成されたものといえ る。 したがって、本件テロップは、その作成者である原告の思想及び感情を創作的に 表現したものであり、言語の著作物と認められる。\n
(2) 被告は、本件テロップと同様の文章の構成により本件テロップと同じエピソ\ ードを紹介するインターネット上の記事は本件テロップの公開前から散見されるな どとして、本件テロップの著作物性は認められない旨主張する。 証拠(乙 1〜4)によれば、本件テロップの公開前から、男性 2 人が野生のライオ ンを育て、保護地区に戻したことや、後に男性が保護地区を訪れた際の当該ライオ ンとの再会の模様等の一連の流れに関して、本件テロップと共通性を有する少なく とも 4 つの記事がインターネット上で公開されていることが認められる。そのうち の 1 つの内容は、おおむね別紙「既公開記事の内容」記載のとおりであり、本件テ ロップとその公開前から存在する記事とでは、アイデアないし事実を共通にする部 分があると認められる。しかし、その具体的な表現を比較したとき、各主体の心情\nその他の表現の内容及び方法においてこれらは表\現を異にし、本件テロップにおい ては、上記既存の記事には見られない創作性が発揮されているといってよい。した がって、この点に関する被告の主張は採用できない。
2 争点 1-2(複製権、翻案権及び公衆送信権侵害の有無)
本件テロップと本件記事の各内容を比較すると、本件記事には、本件テロップと 完全に一致する表現が多数含まれる。他方、相違する部分は、句読点の有無や助詞\nの違い、文言の一部省略等の僅かな相違のほか、例えば、本件テロップには、「ドイ ツ出身のCさんは幼い頃からずっと動物を大切に思ってきました。」とあるのに対 し、本件記事には、「この感動のストーリーは 2 人の人間から始まります。その 1 人 がCさん。Cさんはドイツ出身。幼い頃よりずっと動物を大切に思ってきました。」 とあるなどの相違部分が存在する。これらの相違部分は、表現の手法等に若干の違\nいが見られるものの、内容的には、本件テロップの表現を若干修正したり、要約又\nは省略したり、前後の表現を入れ替えるなどしているにとどまり、実質的にほぼ同\n一の内容を表現したものといえる。\n複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する ことをいうところ(著作権法 2 条 1 項 号)、著作物の再製とは、既存の著作物に 依拠し、これと同一のものを作成し、又は、具体的表現に修正、増減、変更等を加\nえても、新たに思想又は感情を創作的に表現することなく、その表\現上の本質的な 特徴の同一性を維持し、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を\n直接感得できるものを作成する行為をいうものと解される。また、翻案とは、既存 の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体\n的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表\現するこ とにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得でき\nる別の著作物を創作する行為をいうものと解される(最高裁平成 11 年(受)第 922 号同 13 年 6 月 28 日第一小法廷判決・民集 5巻 4 号 837 頁参照)。
本件記事は、記事中に本件動画が埋め込まれていること(甲 4)や、上記のとおり、本件テロップと完全に一致する表現を多数含み、相違する部分も、句読点の有無等の僅かな形式的な相違や本件テロップの表\現の僅かな修正、要約、前後の入れ替え等にとどまり、実質的にほぼ同一の内容を表現したものであることに鑑みると、本件テロップに依拠したものと認められると共に、著作物である本件テロップの表\現上の本質的な特徴の同一性を維持し、これに接する者がその特徴を直接感得できるものと認められる。したがって、被告が本件記事を被告サイト上に投稿する行為は、原告の本件テロップに係る複製権又は翻案権を侵害するものであると共に、本件記事を送信可能化するものとして公衆送信権を侵害するものと認められる。また、本件記事が本件テロップに依拠していることから、上記著作権侵害行為につき、被告には少なくとも過失が認められる。これに反する被告の主張は採用できない。以上より、原告は、被告に対し、著作権(複製権又は翻案権、公衆送信権)侵害の不法行為に基づき、損害賠償請求権を有することが認められる。\n
3 争点 1-3(原告が本件テロップの著作権を主張することの信義則違反の有無)
被告は、原告が第三者の著作権を侵害して作成した動画による収益が減少したと して損賠賠償を請求し、また、本件動画全体としては請求が認められない可能性が\nあるため、本件テロップのみを対象として権利侵害を主張しているとして、原告の 請求が信義則に反する旨主張する。 しかし、そもそも、本件動画につき第三者の著作権を侵害して作成されたもので あることを認めるに足りる的確な証拠はない。その点を措くとしても、本件テロッ プは独立した表現物として把握し得るものであること、本件記事もそのような本件\nテロップに依拠して作成されたものとみられることに鑑みると、原告が本件テロッ プの著作権侵害を主張することをもって信義則に反するということはできない。こ の点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
4 争点 2(原告の損害)
(1) 認定事実
前提事実、証拠(甲 14〜19(17 については枝番を含む。)、乙 11〜14)及び弁論 の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 原告は、令和 2 年 6 月 日に本件動画を投稿した。YouTube では動画の再生 回数等に応じて動画投稿者に収益が支払われるところ、上記投稿日から同年 月 日までの本件動画の再生回数は約 680 万 5000 回、推定収益は 309 万 6740 円で あった。また、推定収益の推移は別紙「推定収益の推移データ」のとおりであり、 上記投稿日から同年 11 月 30 日までの推定収益は 379 万 4863 円であった。
イ 令和 2 年 7 月 27 日、被告は本件記事を投稿して公開したが、同年 9 月 30 日 まで閲覧者はおらず、その後、原告の申入れを受けて本件記事を削除した同年 11 月 までの本件記事の閲覧回数は 154 回であった。
ウ 作家等文芸を職業とする者の職能団体であり、著作権管理事業を行う日本文\n藝家協会は、その著作物使用料規程である本件規程により、著作物を書籍として複 製し、公衆に譲渡する場合の使用料につき、本体価格の 15%に発行部数を乗じた額 を上限として利用者と協会が協議して定める額としている。
エ 原告は、本件訴訟に先立ち、本件記事につき発信者情報開示請求訴訟を提起 して発信者情報の開示を受けたところ、その際、原告は、弁護士に訴訟追行を委任 し、弁護士費用 44 万円(消費税込)、実費 1 万 4194 円を支払った。
(2) 逸失利益について
ア 主位的主張について
上記認定のとおり、本件記事の閲覧回数は、同年 月 1 日以降本件記事が削除 されるまでの間の 154 回にとどまる。このことと、本件動画の再生回数及び推定収 益、とりわけ推定収益の推移の状況に鑑みると、このような本件記事の投稿と本件 動画の再生回数ないし収益の減少との間に因果関係を認めることはできない。した がって、この点に関する原告の主張は採用できない。
イ 予備的主張について\n
原告は、本件記事により被告が得た収益の額ではなく、本件動画の経済的価値に 本件規程を参考にした仮想使用料率を乗じて、一回的な給付としての「著作権の行 使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法 114 条 3 項)を算出すべき 旨主張するものと理解される。他方、被告は、このような原告の主張を前提としつ つ、本件記事により被告が得た収益の額を本件動画の経済的価値(ただし、その算 定対象期間は原告の主張と異なる。)に加算したものに仮想使用料率を乗じて「著作 権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を算出すべき旨を主張する。そ こで、本件においては、本件動画の経済的価値を基礎とし、これに仮想使用料率を 乗ずることによって、一回的な給付としての「著作権の行使につき受けるべき金銭 の額に相当する額」を算出することとする。 まず、本件動画の経済的価値は、本件記事の投稿期間とは直接の関わりがないと 思われることから、原告の主張のとおり、本件動画の投稿日から本件記事の削除日 までの収益額 379 万 4863 円をもって本件動画の経済的価値とするのが相当である。 他方、上記本件動画の経済的価値及び本件規程の内容を参酌すると共に、本件テロ ップは、本件動画の中で重要な役割を担うものではあるものの、画像等と一体とな って本件動画を構成するものであること、ここでの仮想使用料率は著作権侵害をし\nた者との関係で事後的に定められるものであることその他本件に現れた一切の事情 を考慮すれば、仮想使用料率については 3%程度とみるのが相当である。そうする と、本件テロップに係る「著作権の行使につき受けるべき金銭の額」(著作権法 114 条3項)は、12 万円をもって相当とすべきである。これに反する原告及び被告の主 張はいずれも採用できない。
(3) 発信者情報の取得に要した費用
ウェブサイトに匿名で投稿された記事が不法行為を構成し、被侵害者が損害賠償\n請求等の手段を取ろうとする場合、被侵害者は、侵害者である投稿者を特定する必 要がある。このための手段として、非侵害者には、特定電気通信役務提供者の損害 賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律により発信者情報の開示を請求 する権利が認められているものの、これを行使するためには、多くの場合、訴訟手 続等の法的手続を利用することが必要となる。その際、手続遂行のために、一定の 手続費用を要するほか、事案によっては弁護士費用を要することも当然あり得る。 そうすると、これらの発信者情報開示手続に要した費用は、当該不法行為による損 害賠償請求の遂行に必要な費用という意味で、不法行為との間で相当因果関係のあ る損害となり得るといってよい。 本件では、上記認定のとおり、原告は、発信者情報開示請求訴訟に係る弁護士費 用 44 万円(消費税込)及び実費 1 万 4194 円の合計 4万 4194 円を支出した。発 信者情報開示手続の性質・内容等を考慮すると、このうち 万円をもって被告の 不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> ピックアップ対象
2023.09.25
令和2(ワ)13317 特許権侵害損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年7月13日 東京地方裁判所
特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者又は専用実施権者(以 下「特許権者等」という。)が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定 であって、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そ こに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして、特許 法102条4項は、上記料率を認定するに当たって、特許権者等が当該特許 権又は専用実施権(以下「特許権等」という。)の侵害があったことを前提 としてこれを侵害した者との間で合意をするとしたならば、特許権者等が得 ることとなるその対価を考慮することができる旨規定している。 したがって、実施に対し受けるべき料率は、1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を踏まえ、特 許権者等が当該特許権等の侵害があったことを前提としてこれを侵害した者 との間で合意をするとしたならば、特許権者等が得ることとなるその対価を 考慮して、合理的な料率を定めるべきである。
なお、被告は、本件各発明は被告各製品を構成する部品の一つであるクリ\nックホイールに関するものにすぎないから、実施料率を乗ずる売上高は、被 告各製品ではなく、クリックホイールの売上高とすべきである旨主張するも のの、その原価が証拠上必ずしも明らかではない上、本件各発明が被告各製 品を構成する部品の一つであるという事情は、上記において説示した判断基\n準のとおり、本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢 献という上記3)に係る考慮事情において、これを十分に斟酌するのが相当で\nある。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
(2) 当てはめ
前記認定事実、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、上記1)ないし4) に係る考慮事情として、次の事実を認めることができる。
ア 業界における実施料の相場
証拠(甲35、36)によれば、「ラジオ・テレビ・その他の通信音響 機器」に含まれる「電気音響機械器具」の平成4年度ないし平成10年度 の実施料率(イニシャルなし)の平均値は、5.7%であること、平成1 6年ないし平成20年の電気産業における司法決定ロイヤルティ料率の平 均値は3.0%、最大値は7.0%、最小値は1.0%であることが認め られる。そして、被告が提出した意見書(乙27)においても、本件各発 明に係るロイヤルティ料率を定めるに当たり比較対象となる契約のロイヤ ルティ料率は、中央値が2.65%、最小値が1.5%、最大値が4. 0%であることが認められることからすれば、本件各発明に係る電気産業 における近年のロイヤルティ料率は、3%程度と解するのが相当である。
イ 本件各発明の技術内容や重要性
上記1によれば、従来技術においては、接触操作するタッチパネル等の 電子部品と、プッシュ操作するスイッチ等を各々別個の部品として配置し ていたため、機器の小型化に対して不利であり、かつ、2つの別個の部品 を操作することになり使い勝手も極めて不便であるという課題があった。 このような課題を解決するために、本件各発明は、1)リング状に予め特\n定された軌跡上にタッチ位置検出センサーを配置して軌跡に沿って移動す る接触点を一次元座標上の位置データとして検出し、2)上記軌跡に沿って タッチ位置検出センサーとは別個にプッシュスイッチ手段の接点を設ける ものである。このように、本件各発明は、上記検出とは独立してプッシュ スイッチ手段の接点のオン又はオフを行うことによって、操作性良く薄型 かつ小型でしかも少ない部品点数で電子機器を構成することができるよう\nにし、もって1つの部品で複数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接 触操作型電子部品を提供するものであり、この点において重要性を有する ものである。
これに対し、被告は、本件各発明には、iPod Shuffleに採 用された操作ボタン、iPod Touchに採用されたタッチスクリー ン等の代替手段が存在する旨主張する。 しかしながら、証拠(乙30、31)及び弁論の全趣旨によれば、iP od Shuffleの操作ボタンにおいては、音量調節等はボタンを押 すことでしかできないものであって、リング状に指を動かして連続的に音 量調節等をすることができず、iPod Touchについては、タッチ スクリーンを用いるものであって操作の形態が大きく異なり、コストも高 くなるといえるから、これらが直ちに代替手段となるものと認めることは できない。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
ウ 本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害 の態様
本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 証拠(甲5、24)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品1について は、「新しいiPod classicではポケットに40,000曲 を入れることができます。より薄型の総金属製のボディと、さらに洗練 されたユーザインターフェイスにより、iPod classicは、 全てをiPodに入れて持ち歩きたい人に最適です。」と宣伝されてい ることが認められ、被告製品2についても、「さらにiPodが小さく なりました。鉛筆ほどの薄さのiPod nanoは、(中略)信じら れないくらい小さなボディ」、「手の中にすっぽりと収まるミニサイズ。 あざやかなカラー液晶ディスプレイ、親指で操作できるクリックホイー ルも自慢です。ヘッドフォンをつけたら、さっそくボリュームを上げて みましょう。iPod nanoが、小さくてもまさにiPodだとす ぐにわかるはず。」と宣伝されていることが認められる。 その上、証拠(甲21)及び弁論の全趣旨によれば、iPodに搭載 されたクリックホイール自体についても、被告は、「親指ひとつでコン トロール」、「いつでも完全主義を貫くアップルのエンジニアたちは、 iPodの操作ボタンをホイールの下に移動して『究極のシンプルさ』 を目指しました。それが大好評のクリックホイールです。(中略)耐久 性と感度の良さ、ホイール下側に組み込まれた操作ボタンの使いやすさ はこれまでどおり。この最小限のスペースを最大限に利用したクリック ホイールで、iTunesのミュージックコレクションから選んだ最大 1,500曲を親指だけで楽々とスクロールできます。このようによく 考えられた仕組みは、アップル製品ならでは。競合メーカーがどんなに 追いつこうとしても追いつけない部分です。」などとして、特に宣伝し ていることが認められる。
上記認定事実によれば、本件各発明は、操作性良く薄型でしかも少な い部品点数で電子機器を構成することができるように、1つの部品で複\n数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接触操作型電子部品を提供す るものであるところ、被告は、本件各発明の構成の中核であるクリック\nホイールにつき、競合他社の製品と差別化するために特に利用していた ことが認められる。そうすると、本件各発明を被告各製品に用いた場合 の売上げ及び利益への貢献の程度は、被告各製品の薄型化及び小型化並 びに操作性の向上に寄与するものとして、被告各製品の顧客吸引力の向 上という観点からすれば、少なくないものと認めるのが相当である。 他方、証拠(甲32、乙27)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の人気の理由は、上記において説示したとおり、クリックホイールと いう指先だけで操作できるインターフェイスを搭載し、携帯音楽プレー ヤの操作性を向上させたことにあるほか、音楽配信サービスであるiT unes Music Storeに対応するiTunesを、そのま ま持ち歩くような環境を備えたことや、デザイン、カラーバリエーショ ン、大容量のハードディスク及び長時間持続するバッテリーという被告 各製品の特長にもあり、これらのほか、「Apple」という極めて高 いブランド価値、被告の宣伝広告等が、被告各製品の売上げに相当程度 貢献したことが認められる。また、操作性については、上記のとおり、 被告自身がクリックホイールによる操作性の向上を宣伝していることか ら、クリックホイールの貢献は明らかであるものの、クリックホイール の機能の割当てや本件各発明とは無関係のセンターボタンの果たす役割\nも少なくないものと解される。 そうすると、被告各製品の本体(ハードウェア)の一部であるクリッ クホイールに係る本件各発明が、被告各製品の売上げに寄与した程度は、 主要なものとはいえない。
侵害の態様
前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば、被告は、別件訴訟において、 別件被告各製品の輸入及び販売を行うことが本件特許権の侵害に当たる 旨の第1審判決及び控訴審判決が言い渡された後も、なお別紙別件被告 製品目録記載3の被告製品(本件における被告製品1)を販売し続けた ことが認められる。したがって、その侵害態様は看過し得ないところが ある。
エ 特許権者の営業方針等
弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各発明を実施するものではなく、 被告に対し、本件各発明の許諾をする旨の申出をし、被告との間で、その\n交渉をしていたことが認められる。
オ 実施料率の算定
上記認定に係る業界における実施料の相場、本件各発明の技術内容や重 要性、本件各発明を被告各製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や 侵害の態様、特許権者の営業方針等その他の本件に現れた諸事情を踏まえ、 特許権者等が当該特許権等の侵害があったことを前提として、これを侵害 した者との間で合意をするとしたならば特許権者等が得ることとなるその 対価を考慮すれば、実施に対し受けるべき料率は、少なく見積もっても、 0.5%を下らないというべきである。
◆判決本文
関連事件はこちらです。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2023.09.25
令和4(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年7月26日 知的財産高等裁判所
1 取消事由1(手続違背)について
(1) 原告は、本件審決では、審査過程とは実質的に異なる論理によって進歩 性の判断を行っており、その上で審判請求人に意見を述べる機会を与える ことなく審決をしているから、本件審決は、特許法159条2項の規定に違 反する違法なものである旨を主張する。
(2) 前記第2の1のとおり、本件拒絶理由通知には、本願は新規性欠如(拒絶 理由1)及び進歩性欠如(拒絶理由2)により拒絶すべきものとし、1)本願 の請求項1ないし8の発明につき、引用文献1に記載された発明であるか、 その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、2)本願の請求 項1ないし4の発明につき、引用文献2に記載された発明であるか、その記 載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、3)本願の請求項1な いし4の発明につき、引用文献3に記載された発明であるか、その記載に基 づき当業者が容易に発明をすることができた、4)本願の請求項1、2、4の 発明につき、引用文献4に記載された発明であるか、その記載に基づき当業 者が容易に発明をすることができた、5)本願の請求項1、5の発明につき、 引用文献5に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に 発明をすることができた、6)本願の請求項1ないし4の発明につき、引用文 献6に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明を することができた、7)本願の請求項3の発明につき、引用文献4に記載され た発明に引用文献1ないし3、6に記載された周知の構成を適用すること\nにより容易に発明をすることができた、8)本願の請求項4の発明につき、引 用文献1ないし6に記載された発明に周知の構成を適用することは設計的\n事項に過ぎないから容易に発明をすることができた、9)本願の請求項5の 発明につき、引用文献2ないし4、6に記載された発明に引用文献1、5に 記載された周知の構成を適用することにより容易に発明をすることができ\nた、10)本願の請求項6ないし8の発明につき、引用文献2に記載された発明 に引用文献1に記載された発明の構成を採用することにより容易に発明を\nすることができた、11)本願の請求項8の発明につき、引用文献1、2に記載 された発明に周知の構成を適用することは設計的事項に過ぎないから容易\nに発明をすることができた、との理由が示され、引用文献1のほか、引用文 献2ないし6及びそれらに記載された発明の内容が示されている。 これに対し原告は、第1次補正を行うとともに本件意見書を提出している ところ、原告は、本件意見書において、引用文献1ないし6に開示された内 容を踏まえても、いずれも第1次補正後の本願発明に係る内容については記 載も示唆もされていないと主張した。
その上で、本件拒絶査定には、本件拒絶理由通知に記載した理由1(新規 性欠如)、同2(進歩性欠如)により本件出願を拒絶すべきものとし、備考 として、1)本願の請求項1ないし3の発明につき、引用文献1に記載された 発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、 2)本願の請求項1ないし3の発明につき、引用文献2、1の記載に基づき当 業者が容易に発明をすることができた、3)本願の請求項3の発明につき、引 用文献1、2の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとし、 本件拒絶査定を構成するものではないが、現在存在している拒絶理由として、\n請求項5の発明につき引用文献1に記載された発明に基づく新規性、進歩性 欠如、請求項4、5の発明につき、引用文献1、7に基づく進歩性欠如、請 求項4、5の発明につき、引用文献2、1、7に基づく進歩性欠如、請求項 5の発明につき明確性要件違反がある旨が記載されている。 これらによれば、本件拒絶査定は、本件拒絶理由通知に記載した新規性欠 如(理由1)及び進歩性欠如(同2)の各理由により本件出願を拒絶すべき としたものであり、本願発明は引用文献1に記載された発明であるか、その 記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとする本件拒絶理由 通知記載の新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由を維持するものである。 本件審決が示した新たな刊行物等(甲5ないし7)も、同審決において、 「加飾とは、クッション性等の機能性を付与したものも含むものであるこ\nとは技術常識である。このことは、・・・ の各資料からも確認できる。」 (9頁30行目ないし10頁2行目)とし、その「各資料」として甲5ない し7が示されているところから明らかなとおり、本件出願当時において、加 飾加工分野の当業者であれば当然知っている技術常識の裏付けとして示さ れたものであって、引用文献1から主引用発明を認定する場合における、本 件拒絶理由通知及び本件拒絶査定の拒絶理由の内容を変更するものではな い。 したがって、これらは特許法159条2項に規定する査定の理由と異なる 拒絶の理由を発見した場合に当たるものではないから、拒絶査定不服審判 の手続において、審判請求人である原告に意見を述べる機会を与えること が必要とされるものではない。 よって、本件審判に手続違背はなく、審判の手続に誤りはない。
(3) 原告の主張に対する判断
ア 原告は、本件拒絶理由通知と本件拒絶査定とでは主引用発明としている 引用文献が同一ではなく、新規性及び進歩性についての判断も異なると主 張する。 しかし、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定には、引用文献1による新 規性欠如及び進歩性欠如の理由が示されており、本件審決においても、引 用文献1による新規性欠如と進歩性欠如の判断理由が示されているから、 本件審決が、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由でされたと いうことはない。また、原告が本件拒絶査定で新たに引用されたとする引 用文献(甲14)は、前記第2の1(3)のとおり、本件出願当時の周知技術 を示す文献として引用されたものであり、本件拒絶査定において拒絶理由 を構成するものとされているものではない。\n したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、6個若しくは2個の引用発明から最も適した一つの引用発明を 選択するという認定手順を行わない進歩性の判断手法は、後知恵の判断に よる進歩性の否定につながると主張する。 しかし、進歩性判断に当たり複数の論理付けが可能な場合にそれぞれの\n論理付けを行うことについて問題があるものとは認めらないほか、前記 (2)のとおり、審決の判断には法に定める手続の違背もない。また、いわゆ る後知恵の問題とは、主引用発明から出発して当業者が発明に容易に想到 し得る論理付けができるか否かの判断を行う際には、請求項に係る発明の 知識を得た上で行うことから、当業者が請求項に係る発明に容易に想到し 得たかのように見えてしまう問題をいうところ、主引用例が一つであるか 否かの問題と、いわゆる後知恵の問題とは直接には関係がない。加えて、 本件審決の判断は、本願補正発明が新規性を欠如する旨も含むものである から、進歩性の判断手法に関する原告の主張は、直ちに審決の取消事由と なり得るものではない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 原告は、本件出願に対する進歩性の判断手法への対応によって本来対応 に注力すべき新規性及び進歩性の論点が曖昧かつ分散され、その結果とし て出願人である原告が不利益を受けた旨を主張する。 しかし、前記第2の1(1)及び(3)のとおり、本件拒絶理由通知及び本件 拒絶査定では複数の主引用例に基づいた拒絶の理由に対し、主引用例ごと に各発明の技術内容が記載されるとともに、引用文献1による新規性及び 進歩性を欠如する旨の理由が示されているから、原告の主張はそもそもそ の前提を欠くばかりか、原告は、これらを踏まえて本件意見書及び審判請 求書において反論しているのであるから、本来対応に注力すべき新規性及 び進歩性の論点が曖昧かつ分散されて、その結果として原告が不利益を受 けたとの事実は認められないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
エ 原告は、審判請求書で指摘したように、本件拒絶査定においては相違点 の認定と評価に関して重大な誤りがあったとする。 しかし、原告の上記に係る「6.原査定における相違点の認定と評価に 関する誤り」(甲20の13頁以下)の主張は、もっぱら引用文献2に記 載された発明を主引用発明とした場合の進歩性の判断における相違点の認 定と評価についての主張であり、審決の理由付けは、引用文献1を主引用 例としたものであって、引用文献2を主引用例としたものではないから、 本件拒絶査定につき原告の主張するところは、審決の結論に影響を与える ものではない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
オ 原告は、審決は、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定では引用されなか った引用刊行物(甲5ないし7)を更に引用して、本件拒絶理由通知及び 本件拒絶査定と異なる理由によって新規性及び進歩性の判断を行ったと 主張する。 しかし、これらの引用刊行物(甲5ないし7)は、前記(2)のとおり、本 願補正発明の「加飾」について技術用語の意味を明らかにすることで、本 件出願時の当業者の技術常識によれば、引用発明の「成形品の製造方法」 が、本願補正発明の「凸部加飾加工方法」に該当すると理解することを示 す資料として提示された文献であって、審決は、本件拒絶理由通知及び本 件拒絶査定と異なる理由によって本願補正発明の新規性及び進歩性の判断 を行ったものではない。
2023.09.24
令和5(ネ)10025 損害賠償請求控訴事件 その他 民事訴訟 令和5年9月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ウ 以上によると、控訴人らは、本件グループのファンクラブの関係者やファン の混乱を招いたり、迷惑をかけたりすることを防ぐため、被控訴人に対し、同ファ ンクラブの閉鎖時期を、課金システム上の理由から同ファンクラブの会員サービス の課金を停止して同会員サービスの提供を終了することができる時期まで延期する ことについて黙示の許諾をしたと認められ、また、同ファンクラブが存続する限り は、会費を支払った会員に対し、本件グループのメンバーや活動内容等を紹介する 記事を閲覧させるために、本件ファンクラブサイト及び本件ファンクラブサイトに リンクする本件被告サイトにも控訴人らの肖像等を掲載する必要があったといえる ことからすると、控訴人らは、本件ファンクラブサイトの閉鎖が可能となる時期まで、本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトに控訴人らの肖像等が掲載されることについても黙示の許諾をしていたと認められる。\n
他方、前記イ2)のとおり、控訴人らは、平成31年4月24日付けの書面におい て、被控訴人に対し、被告が管理するウェブサイトから控訴人らの肖像等を削除す るように求め、また、訂正して引用する原判決第3の1(7)のとおり、控訴人らが、 令和元年8月1日頃、東京地方裁判所に対して被控訴人を相手方として申し立てた仮処分申\立書において、「令和元年8月1日現在も、債務者管理の債権者らグループの旧ホームページが存在しており、契約終了以降も債権者らの肖像権が侵害され続 けている。…そのため、現在も債務者管理の旧ホームページが存在していること自 体も、債権者らの活動の妨害となるといえる。」と記載しており、本件専属契約が終 了したにもかかわらず、被控訴人がホームページ等で控訴人らの肖像等を使用し続 けることに負担を感じていたことなどに照らすと、前記イ4)の控訴人らから被控訴 人に対するファンクラブを閉鎖する旨の告知を延期する旨の通知は、控訴人らが、 課金システムにおける課金停止時期との兼ね合いで、関係者やファンたちのことを 考え、控訴人らにおいて、本件ファンクラブサイトの閉鎖が可能となる時期まで、やむなくファンクラブの閉鎖の時期を延期し、それに伴い本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトに控訴人らの肖像等が掲載されることとの限りにおいて黙示の\n許諾をしたものと認められるが、そのようなやむを得ない事情を超えて、控訴人ら において、本件専属契約終了後も、被控訴人が、本件グッズ販売サイトにおいて、 本件グループの公式ショップとして、控訴人らの肖像写真を表示した上で、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像等が転写されたグッズを撮影した写真を掲載するとともに当該グッズを販売し続けることを許諾していたと認めるに足りる合理的な\n理由はなく、また、同許諾をうかがわせる事情の存在も認められず、同許諾を認め るに足りる証拠は存在しない。
エ 控訴人らは、被控訴人が、本件専属契約終了後において、控訴人らの肖像等 を利用した目的は、控訴人らの活動を妨害することにあったものであり、被控訴人 による控訴人らの肖像等の利用態様及び目的は不当なものであって、被控訴人が控 訴人らの肖像等を使用する必要性や相当性があったとはいえない旨を主張する。し かしながら、前記ウのとおり、控訴人らも、本件専属契約終了後において、本件フ ァンクラブサイトの突然の閉鎖に伴う混乱を回避する必要があると考えていたこと、 また、少なくともファンクラブが存続する限りはその会費を支払った会員に対し、 本件グループのメンバーや活動内容等を紹介する記事を閲覧させるため、本件ファ ンクラブサイトのみならず、当該サイトに導く機能を有する本件被告サイトにも控訴人らの肖像等を掲載する必要があったことが認められることからすると、被控訴人による令和元年11月30日までの本件被告サイト及び本件ファンクラブサイト\nにおける控訴人らの肖像等の使用につき、控訴人らの黙示の許諾の下で行われたも のといえるから、これらのサイトにおいては、被控訴人が控訴人らの肖像等を使用 する必要性や相当性があったとはいえないとの控訴人らの上記主張は採用できない。 また、控訴人らは、控訴人らが被控訴人を相手方として申し立てた地位保全仮処分命令申\立事件の申立書において、控訴人らの活動が妨害されるおそれがあるとして、「令和元年8月1日現在も、債務者管理の債権者らグループの旧ホームページが\n存在しており、契約終了以降も債権者らの肖像権が侵害され続けている。」などとの 記載をしていたことをもって、控訴人らの肖像等の掲載を黙示に許諾していたとは いえない旨を主張する。しかしながら、同記載は、本件専属契約の6条及び9条(5) に係る約定が無効であることなどの仮の確認を求める地位保全等仮処分の申立ての主張の一環として記載されているにとどまり、このような事実をもって、同年11月30日までの間、会員向けサービスの提供及び本件被告サイトにおける情報提供\nがされる旨が告知されていたことに対して、控訴人らが、被控訴人に対し、本件被 告サイト及び本件ファンクラブサイトの閉鎖時期に関して特段の異議を述べたとま では評価できず、控訴人らの上記主張は採用できない。
オ 被控訴人は、本件専属契約終了後に、本件グッズ販売サイトにおいて控訴人 らの肖像等を利用したことについても、飽くまで会費を支払ったファンクラブ会員 に対してグッズの在庫を販売するためのものであり、控訴人らの肖像権等の侵害に ならないと主張する。しかしながら、前記アのとおり、控訴人らの肖像権等の使用 に関する約定がされた本件専属契約が終了し、かつ、本件専属契約には契約終了後 の同使用の取扱いに関する約定がないのであるから、控訴人らから被控訴人に対し て別に同使用についての許諾がない場合には、被控訴人による控訴人らの肖像等の 使用は無権原者による使用となるものであって、たとえ本件専属契約中に製造され たグッズを販売するものであり、被控訴人が在庫をさばくために製造済みの同グッ ズを販売して投下資金を回収しようとしたものであったとしても、本件専属契約終 了後には、控訴人らと被控訴人間において何らの取決めがない以上、本件グッズ販 売サイトにおいて控訴人らの肖像等を利用し、控訴人らの肖像等が転写されたグッ ズを販売できるものではない。
カ そして、控訴人らは本件グループのメンバーとして、訂正して引用する原判 決第2の2(2)ウのとおり、アーティスト活動を行っていること、被控訴人において グッズ販売による利益を得ることを目的としていたこと、被控訴人は、本件グッズ 販売サイトにおいて、本件グループの公式ショップとして、控訴人らの肖像写真を 表示した上で、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像をイラスト化した画像を転写したグッズを撮影した写真を掲載して、当該グッズを販売していたこと、被控訴人は、控訴人らからの肖像等の使用停止を求める要求があることを知りながら、本\n件専属契約終了後から令和3年12月31日までの相当長期間、控訴人らの許諾な く利用し続けたものであることなどを総合考慮すると、これらは控訴人らの肖像権 等の侵害となるものであって、被控訴人による控訴人らの肖像権等の侵害が社会生 活上受忍の限度を超えるものではないとすることはできない。
(3) 小括
したがって、本件専属契約終了後から令和元年11月30日までの間、被控訴人 が本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載し た行為は、不法行為法上違法と評価すべきものとはいえない。他方、本件専属契約 終了後から令和3年12月31日までの間、被控訴人が本件グッズ販売サイトにお いて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売した 行為は、不法行為上違法と評価すべきものといえる。
・・・
6 争点4(損害の有無及びその額)について
(1) 控訴人らの肖像権等の侵害による損害について
前記2(2)のとおり、令和元年7月14日以降令和3年12月31日までの2年 5か月18日間という相当の長期間、継続して、被控訴人が本件グッズ販売サイト において本件グループの公式ショップとして控訴人らの肖像等を掲載した行為によ り、控訴人らの意思に反して、控訴人らの肖像等が利用されていたものであり、控 訴人らは精神的な苦痛を受けたものと推認されるところ、その慰謝料は、控訴人ら の本件専属契約終了までの活動内容(訂正して引用する原判決第2の1(2)ウ)、控 訴人らの肖像等の使用が本件グッズ販売サイト及び販売グッズにおける利用という 営利目的によるものであったこと、上記の侵害態様や侵害期間などを考慮すると、 控訴人らそれぞれについて15万円を下らないと認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちら。
2023.09.22
令和4(ワ)15678 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年8月30日 東京地方裁判所
(1) 「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く」の意義について
構成要件Bの「4枚の略矩形状壁面の内、相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁が相互に折畳み可能\に順次連続して連結されるとともに、」との記載から、本件発明の折り畳み式テントには、「4枚 の略矩形状壁面」が設けられていること、その内の「相隣る2枚の略矩形状 壁面」において「互いに対応する側縁」が存在すること、この「互いに対応 する側縁」を「除く」「他の側縁」が存在し、この「他の側縁」が「相互に 折り畳み可能に順次連続して連結され」ていることが理解できる。
また、構成要件Cの「前記相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁は、着脱可能\な接合手段を介して接合されることにより、前記4枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成され、」との記載からは、構\成要件B の「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「着脱可能な接合手段」を備えていること、この「接合手段を介して接合されることによ\nり」、「前記4枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成される」ことが理解できる。また、このような解釈は、本件明細書の、「また、この筒状周壁\n部1における正壁面2の右側縁2aと右壁面3の左側縁3bには、接合・分 離が可能な面ファスナーのような接合手段23が設けられている。図7に図示されるように、正壁面2の右側縁2aと右壁面3の左側縁3bとは前記接\n合手段23により、一体に接合され、または分離される。前記分離された接 合手段23によって、図8に示されるように、両壁面開口部24が構成される。」(【0022】)との記載及び「筒状周壁部1では、図7に図示されるよ\nうに、4枚の壁面2、3、4、5の各両側縁2a、2b、3a、3b、4a、 4b、5a、5bの内、側縁3aと4b、4aと5b、5aと2bとを相互 に折畳み可能に連結し、側縁2aと3bとを後述する接合手段23で接合することで筒状周壁部1が構\成されている」(【0021】)との記載とも整合する。 そして、構成要件Bの「除く」の通常の語義は、「加えない。除外する。別にする。」(広辞苑第七版)であると認められる。\n加えて、上記「除く」は、その直前の「他の側縁」に限定を付す趣旨で あると理解するのが自然であることを踏まえると、構成要件Bは、「4枚の略矩形状壁面」が有する「側縁」から、「着脱可能\な接合手段を介して接合される」ことになる「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」を 除外又は別にした「他の側縁」が、「相互に折り畳み可能に順次連続して連結される」ことを規定するものであると解するのが相当である。\n
(2) 被告各製品が構成要件Bを充足するか否かについて
前記(1)のとおり、構成要件Bの、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」とは、構\成要件Cにおいて規定された、「着脱可能な接合手段\nを介して接合される」「側縁」であると解するのが相当である。 前提事実(3)イのとおり、被告各製品には、第1板状体10ないし第4板 状体40の4枚の板状体が形成されているところ、本件において、各板状体 が構成要件Bの「略矩形状壁面」に該当する。 また、前提事実(3)イのとおり、被告各製品の第1板状体10と第4板状 体40は、その対向部15a及び45bが、着脱可能な接合部60を介して接合されるから、対向部15a及び45bは、構\成要件Bにおいて除外又は別にするとされ、かつ、構成要件Cにおいて「着脱可能\な接合手段を介して 接合され」ると規定される、「前記相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応 する側縁」に該当する。 そうすると、構成要件Bにおいて、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁」は、被告製品の第1板状体10と第4板状体\n40の対向部15a及び45bを除外した他の側縁、すなわち、第1板状体 10の左右の側縁を構成する対向部15b、第2板状体20の左右の側縁を構\成する対向部25a及び25b、第3板状体30の左右の側縁を構成する\n対向部35a及び35b、第4板状体40の左右の側縁を構成する45aがこれに該当するものと解される。\n そして、証拠(甲6、乙1)によれば、これらの側縁は、相互に折り畳み 可能に順次連続して連結される構\成を有していると認められ、構成要件Bの「他の側縁が相互に折り畳み可能\に順次連続して連結される」に該当する。
(3) 被告の主張について
被告は、「除く」の「別にする」との語義に着目して、「別にする」もの と「別にされない」ものとでは、異なる性質・構成を有していることに照らすと、構\成要件Bは、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「相互に折り畳み可能」ではなく、「順次連続して」おらず、「連結され」てもいないことを規定するものと解すべきであり、被告各製品は、互いに対\n応する側縁が相互に折り畳み可能に順次連続して連結されるから、構\成要件 Bを充足しない旨主張する。
しかし、仮に、「除く」を「別にする」との意味であると解釈したとして も、「別」とは、「1)わけること。…2)異なること。そのものではないこと」 (広辞苑第七版)の意味を有するにすぎないから、別にされた「相隣る2枚 の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」とが、一部でも同じ 性質・構成を有していてはならないということにはならない。そして、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の構\成は、構成要件Cによ\nり要件が付加されているのであるから、これにより、「相隣る2枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」は、異なる構成を有しているといえる。\n
・・・
(ア) 構成要件Bについて
a 前記2(1)で説示したとおり、構成要件Bは、「着脱可能\な接合手 段を介して接合される」ことにより、「前記4枚の略矩形状壁面でも って筒状周壁部」を構成する「側縁」を除外した「他の側縁」が、「相互に折畳み可能\に」「順次連続して」「連結」されることを規定している。 そして、乙2発明においては、エンドパネルとサイドパネルの着脱 部となる側縁は、ジッパーや紐等の取付手段を介して取り付けられ (乙2c)ていることから、構成要件Bの「他の側縁」に相当する側縁は、上記「エンドパネルとサイドパネルの着脱部となる側縁」を除\n外した側縁(乙2c)であるところ、乙2発明においては、この側縁 が、相互に折畳み可能に順次連続して連結されている(乙2b)。したがって、乙2発明と本件発明は、構\成要件Bの構成の点におい\nて一致するものと認められる。
b これに対し、原告は、本件発明の「着脱可能な接合手段を介して接合される」「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が一\n組のみであるのに対し、乙2発明では、テントを容易に折り畳めたり することができるよう、対向する2枚のエンドパネルが2枚とも取外 し可能な構\成又は2枚とも一端がサイドパネルにヒンジ結合された構成のみが開示されているから、本件発明と乙2発明は、構\成要件Bの点で一致しないと主張する。しかし、本件特許の特許請求の範囲において、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の組数を限定する記載はない上、本 件明細書において、【0022】及び図8には「相隣る2枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」が一組である構成についての記載があるものの、これは一実施例にすぎず、そのような構\成に限定する旨の記載は存在しないから、「相隣る2枚の略矩形状壁面の互いに対応す る側縁」が、一組に限定されると解釈することはできない。 また、原告は、本件発明に係る折り畳み式テントは、災害時に体育 館等の避難所に設置されて利用されることを想定していることなどか ら、設置の利便性や強度を考慮し、あえて一組のみを分離可能としたと主張する。しかし、本件明細書には、原告の主張する課題や作用効果について\nの記載はない。以上によれば、原告の主張はいずれも採用することができない。
(イ) 構成要件Eについて
a 本件発明は、「前記接合手段を介して接合される側縁を有する2枚 の略矩形状壁面により開閉自在な両壁面開口部が設けられたことを特 徴とする」との構成(構\成要件E)を有しており、乙2発明は、「前 記手段を介して取り付けられる側縁を有する2枚の略矩形状のサイド パネル及びエンドパネルにより開閉自在な両壁面開口部が設けられた ことを特徴とする」との構成(乙2e)を有している。そして、本件特許の特許請求の範囲の記載において、「接合手段」\nにつき特段の限定は付されていないことから、壁面と壁面を接合する 手段であれば足りると解されるところ、前記(1)ア(オ)のとおり、乙2 文献においては、乙2発明の「取付手段」は、ジッパーが好ましい手 段であるが、単純な紐や布などの他の取付手段を使用してもよいとさ れており、それらはいずれも壁面と壁面を接合する手段であるといえ る。したがって、本件発明と乙2発明は、構成要件Eの構\成の点で一致 するものと認められる。
b 原告は、本件明細書の【0014】や【0028】には、壁面の開 放部分にテントのフレーム等が存在しないために、車椅子等がテント 内外に出入する際にフレームやファスナー等の変形・破れ・土砂の付 着等を阻止できる旨が記載されており、これらの記載に照らすと、構成要件Eの「開閉自在な両壁面開口部」は、壁面の開放部分にフレー\nムやファスナー等が存在しない構成であると解されると主張する。
しかし、本件特許の特許請求の範囲の記載において、4枚の略矩形 状壁面と床面との間の連結手段の有無を含め、「開閉自在な両壁面開 口部」が、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成に限定される旨の記載はない。\n また、本件明細書の【0014】は、本件発明の効果に関する記載 であり、同【0028】は、本件発明の実施例の効果に関する記載で あって、本件発明の両壁面開口部の構成を限定するものとは認められないから、構\成要件Eの文言を原告主張のとおり限定解釈する根拠とはならない。
また、仮に、構成要件Eが、底面にフレームやファスナー等が存在しない構\成に限定されるとしても、乙2文献には、ファスナーを紐に変更することも可能である旨が記載されているから(前記(1)ア(オ))、 乙2発明は、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成を含むものであるといえる。よって、原告の主張は理由がない。\n
c 原告は、本件明細書の【0022】及び図8の記載を考慮すると、 構成要件Eは、壁面開口部に設けられている接合手段を外すことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外方に向か\nって開放することができるという構成を示したものであると主張する。 しかし、本件明細書には、本件発明の実施例について「壁面2、3、 4、5の側縁上下端部は、…三角形に近い形状の上閉塞面20、下閉 塞面19でもってこの上下の空隙部は閉塞されるようになっている。 なお、正壁面2の右側縁2aと右壁面3の左側縁3bとの上下端部を 塞ぐ二等辺三角形状の分割上閉塞面20a、分割下閉塞面19aは、 三角形の頂角を通る中心線を境に2分割される。左右に分割された分 割上閉塞面20a、分割下閉塞面19aは、前記接合手段23と同様 な上閉塞面接合手段22、下閉塞面接合手段21によって、接合また は分離可能に接合される。」(【0023】)との記載があるところ、この記載に照らすと、同実施例は、正壁面2の右側縁2aと右壁面3の\n左側縁3bに設けられた接合手段に加え、上閉塞面接合手段22、下 閉塞面接合手段21を外すことによって初めて、壁面を外方に向かっ て解放することができる構成を有しているといえる。したがって、上記【0022】及び図8の実施例の記載を根拠として、構\成要件Eが、両壁面開口部について、壁面開口部に設けられている接合手段を外す ことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外 方に向かって開放することができるという構成を規定していると解釈することはできない。\n また、上記【0023】の記載によれば、「壁面2、3、4、5」 と、「三角形に近い形状の上閉塞面20、下閉塞面19」は別部材で あることは明らかであるから、構成要件Eが、接合手段について、「2枚の略矩形状壁面」のみに設けられていることにより、「両壁面\n開口部」が「開閉自在」となることを規定したと解釈することもでき ない。 以上によれば、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 小括
その他、原告が種々主張するところを検討しても、前記(1)の結論を左右 するものとはいえず、本件発明は、乙2発明と同一の構成を有しているから、新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの\nと認められ、原告は被告に対してその権利を行使することができない(特許 法104条の3第1項、123条1項2項、29条1項)。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.09.18
令和4(ワ)9660 債務不存在確認請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年8月31日 大阪地方裁判所
(1) 被告は、ビットトレントを通じてアップロード等をすることは社会的にも 実質的にも密接な関連をもつ一体行為に参加するものであるなどとして、原告は、 本件ファイルが最初にビットトレントにアップロードされて以降の全ての権利侵害 についての責任を負う旨を主張し、仮に、原告がビットトレントを通じて自ら本件 ファイルを他のユーザーに送信することができた期間に限り不法行為が継続してい たと解されるとしても、原告は、遅くとも令和3年10月25日に本件ファイルを アップロードし、早くとも令和4年4月8日以降に本件ファイルにつきアップロー ド可能な状態を終了した旨を主張する。\nしかし、共同不法行為(民法719条1項前段)が成立するためには、少なくと も行為者各自の行為が客観的に関連して共同していることを要する(最三小判昭和 43年4月23日民集22巻4号964頁参照)から、原告が自らビットトレント を通じて本件ファイルのデータのダウンロードを開始する前や、ダウンロードした 本件ファイルを削除したりビットトレントのクライアントソフトを削除するなどし\nてビットトレントを通じた本件ファイルのデータの送信ができなくなった後に発生 した本件著作権の侵害については、他の行為者の行為との客観的な関連共同性のあ る行為が存在せず、共同不法行為責任を負うと解すべき理由がない。すなわち、本 件において、原告と他の氏名不詳者との間で共同不法行為が成立するのは、原告が ビットトレントを通じて本件ファイルのデータを他のユーザーに送信可能な状態に\nある場合に限られるというべきである。
証拠(甲1、2の1、2の2、6)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、令和3 年当時、自宅の私用パソコンを、平日は2時間から3時間程度、休日前及び休日は\n3時間から5時間程度、インターネットに接続してネット情報の閲覧等(いわゆる ネットサーフィン)をするが、常時接続はせず、使用時以外はシャットダウンする という使用態様であったところ、同年10月25日、ビットトレントのネットワー ク及びビットトレントを利用するためのクライアントソフト「μTORRENT」\nを使用して、約3時間かけて本件ファイルのダウンロードを完了させた後、原告の パソコンからトレントファイルを削除し、翌日、本件ファイルを視聴したが、途中\nで原告のパソコンから本件ファイルを削除したこと、令和4年4月6日、原告が原\n告プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書の送付を受け、その頃、原 告のパソコンからビットトレントのクライアントソ\フト自体を削除したことが認め られる。以上の事実及び前提事実(3)記載のビットトレントの仕組みに照らすと、 原告がビットトレントを通じて本件ファイルを他のユーザーに送信可能な状態にあ\nったというためには、少なくとも、原告が原告のパソコンをインターネットに接続\nしてビットトレントのクライアントソフトを起動した状態で、ビットトレントを通\nじて本件ファイルをダウンロードしているか又はダウンロードを完了した本件ファ イルを原告のパソコンの送信可能\な領域に蔵置していることが必要と考えられる。 そうであるところ、原告が、原告のパソコンをインターネットに接続してビットト\nレントを通じて本件ファイルをダウンロードしていたのは約3時間に限られ、ダウ ンロード完了後の原告のパソコンのインターネットへの接続状況やビットトレント\nのクライアントファイルの起動状況は不明であり、その翌日、原告のパソコンに保\n存した本件ファイルを視聴したものの(このときのインターネットへの接続状態や ビットトレントのクライアントファイルの起動状況が不明であることは同様であ る。)、途中で原告のパソコンから本件ファイルを削除したのであるから、原告が\nビットトレントを通じて本件ファイルを他のユーザーに送信可能な状態にあったと\n認められるのは、本件ファイルをダウンロードしていた3時間に限られるというべ きである(なお、本件ファイルをパソコンから削除しても、キャッシュのデータ等\nが残存する可能性がないとはいえないが、そもそも原告のパソ\コンの送信可能な領\n域に本件ファイルのキャッシュのデータ等が自動的に保存されるものかは不明であ る上、原告が敢えてデータをパソコンに残存させる必要性は乏しく、その後、原告\nの端末から本件ファイルに係るデータがビットトレントを通じてアップロードされ た事実もうかがえないことから、原告は本件ファイルに係るデータをパソコンから\n全部削除したものと認められる。)。
したがって、原告が、本件著作物に係る著作権侵害について賠償責任を負う範囲 は、令和3年10月25日の3時間に発生した侵害行為による損害に限られるもの というべきであり、被告の前記主張は、いずれも採用することができない。
(2) 以上を踏まえて本件著作物に係る著作権侵害による損害額について検討す るに、前提事実(2)並びに証拠(乙3、4)及び弁論の全趣旨によれば、本件著作 物の「HD版ダウンロード及びHD版ストリーミング無制限」のダウンロード価格 (販売価格)は1450円であること、本件著作物の利益率は38%であること、 ビットトレントを通じた本件ファイルのダウンロード回数は、令和3年10月25 日時点で1206回、同月26日時点で1753回であり、同月25日の前記ダウ ンロード回数は547回であることが認められる。そうすると、原告が本件の共同 不法行為により負うべき損害の範囲は、3万7675円(≒547 回×1450 円×38% ÷24×3。1円未満四捨五入)となる。
(3) 原告は、被告が、令和3年10月25日から令和4年4月8日までの間、 原告による共同不法行為が継続していたことを前提として178万9097円の損 害賠償額を主張することは損害拡大防止義務違反がある、不誠実な対応であるなど 述べて、過失相殺及び権利濫用の主張をするが、かかる被告の主張は採用すること ができないことは前記(1)のとおりであって、原告の前記主張はその前提を欠く。 また、原告は、原告が、積極的に複製物を作成しようとする意思は希薄で、他者 のダウンロード行為による金銭的な利益を得てもいないことを指摘して、損害額に ついて減免責されるべきである旨を主張するが、原告が指摘する事情をもって、前 記認定の損害額を減免責すべき事情に当たるとはいえない。
(4) 以上から、原告の被告に対する本件著作物に係る著作権侵害に基づく損害 賠償債務は3万7675円を超えて存在しないものと認められる。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2023.09.18
令和3(ワ)11898 保証金返還請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年8月24日 大阪地方裁判所
(1) 被告は、原告が、代理店としての業務の中で被告の営業秘密である本件各情 報を取得し、不正の利益を得る目的で、又は、被告に損害を加える目的で、これを 使用している旨主張する。 そこで、まず、本件各情報が営業秘密に当たるかを検討する。
(2) 本件各情報が被告の営業秘密であるというためには、本件各情報が、秘密と して管理され(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって (有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)が必要である(不正競争防止 法2条6項)。そして、秘密管理性が認められるためには、秘密としての合理的な 管理方法が採られており、管理の意思が客観的に認識可能であることを要すると解\nされる。
そこでまず、秘密管理性について検討すると、本件各情報が記載された文書には、 いずれも被告の秘密情報であることを明らかにする表示はなく、むしろ株式会社ワ\nンワールドの資料であるかのような表示がある(乙12〜14)。また、前記1の\nとおり、本件秘密保持契約の定めに従った秘密情報としての特定が行われた事実や、 原告と被告との間で本件各情報が秘密情報であることが前提とされていた事実は認 められない。加えて、本件情報1)は、原告が被告から直接取得したものではなく第 三者から入手したものであるが(争いがない。)、P1の証言からしても図面のど の部分が秘密情報かがあいまいであり、また、本件情報2)及び本件情報3)は、被告 の主張によっても、被告製品の納入先や販売代理店には提供され、被告の営業スタッ フもアクセスすることができたというのであって、本件各情報は、それ自体、秘密 情報としての認識可能性が低いと考えられる。その一方、原告が被告の秘密情報で\nある旨を認識可能であったことを根拠付ける具体的事情は見当たらない。そうする\nと、本件各情報につき、被告による管理の意思が客観的に認識可能であったとは認\nめられない。
また、管理方法につき、被告は、平成30年頃に本件規定を定め、本件各情報を 本件規定の「機密情報」として管理していた旨主張し、これを裏付けるものとする 証拠(乙15、16、19、証人P1)がある。しかし、本件規定には、作成日や 施行日の記載がなく、同年当時の代表取締役はP3であったと考えられる(甲2、\n証人P1)にもかかわらず、「代表取締役社長」として令和3年2月に就任したP\n4氏が記載されているなど、作成時期に関し不自然な点がある。仮に本件規定が平 成30年頃に作成されたとしても、本件各情報が本件規定に沿って管理されていた 旨のP1の証言は、その内容が抽象的である上、客観的な裏付けを欠くから、本件 各情報の具体的管理状況は明らかとはいえず、本件規定に従って「機密情報」とし て管理されていたことを認定することはできないし、他に被告の前記主張を裏付け る証拠はない。したがって、本件各情報が秘密として合理的な管理方法が採られて いたともいえない。
(3) 以上のとおり、本件各情報は、秘密として管理されていたとはいえず、被告 の営業秘密とは認められないから、原告が被告の営業秘密を使用して不正競争行為 を行った旨の被告の主張は理由がない。
2023.09.18
令和4(行ケ)10133 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和5年9月6日 知的財産高等裁判所
1 認定事実
(1) 各項目末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
・・・
カ ユーアイの代表者が令和3年9月7日付けで作成した確認書(以下「本件確\n認書」という。)には、ユーアイが原告に対しトヨタハイエース用3Dマット(UI vehicle 「3D MAT」ワイドボディ用フロントマット、ワイドボディ 用リアマット)のOEM製造を委託していること、ユーアイが平成24年2月頃か ら令和元年7月23日までの間にワイドボディ用フロントマット(品番:UI−0 239、製品コード:OMUIR0239K)を6200セット、ワイドボディ用 リアマット(品番:UI−0103、製品コード:OMUIR0103K)を16 00セットずつ、顧客に販売するために原告から購入したことが記載されている。 また、本件確認書には、・・・有限公司が作成した「toyota-hiace-wide右駕 專用型踏塾」の設計図面が添付されており、同設計図面は、甲1の2の製品図面に おける「Clazzio」と書してなるロゴマークがなく、「UI vehicle」 と書してなるロゴマークが付されているほかは、上記アの設計図面と酷似している。 (甲2)
(2) 被告の主張について
ア 被告は、審決取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった新たな証拠 により登録されている権利の有効性を判断することは許されないから、原告が本件 訴訟で提出をした甲4及び5は、いずれも採用されるべきではない旨主張する。 意匠登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなか った公知事実との対比における無効原因を主張することは許されないと解される (最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻 2号79頁参照)。これを本件についてみるに、原告は、審判において、本件出願 日前に先行製品が一般に販売されたことにより先行製品の意匠である先行意匠1が 公然知られるに至った旨を主張しているところ、甲4及び5は、いずれも、先行製 品が本件出願日前に販売された事実を裏付ける証拠であって、同事実は審判により 審理判断されている事実にほかならないから、原告が甲4及び5を提出して同事実 を立証し、これらに基づき本件審決の誤りを主張することは許されるというべきで ある。被告の主張は採用することができない。
イ 被告は、甲4及び5が採用されるとしても、これらの証拠はウェブサイトと しての性質上、修正や改ざんの可能性が否定できず、信用性に乏しい旨主張する。\nしかし、上記証拠はいずれも公開されたウェブサイト及びそのアーカイブである から、その記載が修正又は改ざんされたというのであれば、被告において実際に公 開されているウェブサイトや信頼できるアーカイブを示した上、これと異なる点を 具体的に指摘できるはずであるが、被告はそのような指摘をしない。他に、甲4及 び5に、修正や改ざんをうかがわせるような点は見当たらない。被告の主張は採用 することができない。
2 先行意匠の認定に誤りがあること及び先行意匠1が本件出願日前に公知であ ったこととの点について
(1) 原告は、本件審決が、甲1の2〜4に表された意匠をまとめて先行意匠1の\n形状等として認定することはできないとした上で甲1の4のみから先行意匠を認定 した点に誤りがある旨主張する。 原告が主張する先行意匠1は、ユーアイが顧客に相当数量販売したという先行製 品(トヨタハイエースワイドボディ用3Dマット)の意匠である。 前記1(1)の認定事実によると、ユーアイは、遅くとも平成28年3月4日時点で、 そのウェブサイト(甲4の2)において、「ワイドボディ用 フロント3ピース」 「ワイドボディ用 リア1ピース」等のハイエースワイドボディ用フロアマットを 「3Dラバーマット」との商品名にて販売している旨を掲載しているところ、同ウ ェブサイトに用いられている「3Dラバーマット」の写真5枚のうち4枚は、本件 カタログで用いられている写真5枚のうち4枚と酷似しており、ユーアイは、本件 カタログ(甲1の1)に掲載された商品を一般に向けて現実に販売していたものと 認められる。
また、原告は、平成27年5月から同年6月にかけて、外注先から「UI ve hicle」のロゴマークが付されたハイエースWIDE用自動車フロアマットの 納品を受けたところ(甲1の4)、同フロアマットには「3Dラバーマット取扱説 明書」と題する文書が添付されていたほか、梱包箱に記載された品番及び製品コー ドが本件確認書に記載の品番及び製品コード並びに本件売上明細表に記載の品番と\nいずれも符合していることからすると、原告が納品を受けた上記フロアマットは、 上記のとおりユーアイが販売していた「3Dラバーマット」と同一の製品であると 認められる。
そして、本件確認書には、ユーアイが販売する「3D MAT」の設計が、本件 確認書添付の・・・有限公司作成に係る「toyota-hiace-wide 右駕專用型踏 塾」と題する設計図面のとおりである旨が記載され、その設計図面に記載されたフ ロアマットの形状等は、上記のとおりユーアイが販売していた「3Dラバーマット」 の形状等として矛盾のないものであり、かつ、原告がかつて所持していた・・・有限公司が作成した「HIACE WIDE右駕專用踏塾」及び「TOYOT A−HIACE−S−GL−WIDE右駕專用脚踏塾」の設計図面(甲1の2・3) と酷似していることが認められる。
以上の事実を総合すると、ユーアイが販売していた先行製品(「3Dラバーマッ ト」及び「3Dマット」)の形状等は、甲1の1〜4に表されているということが\nできる。これらの証拠から先行製品の意匠すなわち先行意匠1を認定すると、別紙 5のとおりとなる。したがって、本件審決が、甲1の2〜4に表された意匠をまとめて先行意匠1の形状等として認定できないとし、甲1の4のみから先行意匠を認定した点には誤りがある。\n
◆判決本文
関連事件です。
2023.09.18
令和5(行ケ)10031 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年9月7日 知的財産高等裁判所
1 商標法3条は商標登録の要件を規定するものであり、同条1項柱書及び同項 4号によると、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章の\nみからなる商標」は、商標登録を受けることができないものとされている。これは、 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章は、特定人によるそ\nの独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、多くの場合、自 他商品・役務識別力を欠くと考えられることから、このような標章のみからなる商 標については、登録を許さないとしたものと解される。 そして、ありふれた氏に業種名や会社の種別、屋号に慣用的に用いられる文字等 を結合し、普通に用いられる方法で表示したものは、当該ありふれた氏を称する者\n等が取引をするに際して、商標として使用することを欲するものと考えられ、同様 に特定人による独占的使用になじまず、かつ、その表示だけでは自他識別力を欠く\nものというべきであるから、特段の事情のない限り、「ありふれた名称」に当たると 解するのが相当である。
2 本願商標は、「池上」の文字と「製麺所」の文字からなる結合商標である。以 下、各構成部分について検討する。\n
(1) 「池上」について
「池上」は、我が国において氏として約4万4100人に用いられている文字で あり(甲16、39、乙4)、商標法3条1項4号所定の「ありふれた氏」に当たる。 原告は、「池上」は様々な意味を有する語であり、姓氏を表すと即座に認識されな\nいから「ありふれた氏」に当たらないと主張するが、前記のとおり、「池上」が我が 国において4万人以上の者に用いられている氏であることが認められる以上、「池 上」の文字が姓氏以外の意味を有することがあるからといって、それが「ありふれ た氏」に該当しなくなるわけではない。したがって、原告の前記主張は採用するこ とができない。
(2) 「製麺所」について
ア 後掲各証拠によると次の事実が認められる。 (ア) 「製麺所」は、「麺類を製造すること」を意味する「製麺」(乙6)に、場所を 意味する「所」が付されたもので、麺類を製造する所を意味する。
(イ) 香川県では、卸売りをする讃岐うどんの製麺所において、昼時に、セルフサー ビスで客がうどんを湯掻いて食べるという業態のうどん店が多く存在する。これら のうどん店は「製麺所タイプ」、「製麺所スタイル」などと呼ばれ、香川県内には、 原告が運営する「池上製麺所」の他に、「松下製麺所」、「多田製麺所」、「穴吹製麺所」、「藤村製麺所」、「日の出製麺所」、「讃岐製麺所」、「三嶋製麺所」(2か所)、「大川製麺所」、「宮川製麺所」、「上田製麺所」、「岡製麺所」、「上野製麺所」といった店名の製麺所タイプ(製麺所スタイル)のうどん店がある。(甲12、50、69、乙7、8、10、12、33〜35、45〜47、51)
(ウ) さらに、日本全国において、うどんやラーメン等の麺類を提供する飲食店にお いて、「○○製麺所」という名称が用いられていることが認められる。香川県内で「〇 〇製麺所」の名称を用いてうどんを提供している前記うどん店以外のこれらの飲食 店の具体的な所在地及び店名は別紙「製麺所」の使用状況記載のとおりである。(甲 12、41〜47、49〜54、乙9、11、13〜32、36〜42)
イ 前記アの各事実に照らすと、「製麺所」の名称は、もともとは、麺工場などの 麺類を製造する所を指していたものであるが、製麺所において飲食物であるうどん 等を提供するという業態が一般化するなどし、さらには、少なくとも本件審決時ま でに、全国的に、「○○製麺所」という名称のうどんやラーメン等の麺類を提供する 飲食店が少なくない数において存在するに至っているということができる。このよ うな実態に照らすと、本件審決時においては、本願商標の指定役務である「飲食物 の提供」の取引者、需要者は、「製麺所」の名称について、麺類を製造する所を意味 するものと認識、理解するのみならず、麺類を提供する飲食店を指す店名の一部と して慣用的に用いられているものと認識、理解すると認めるのが相当である。
ウ この点、原告は、全国のうどん店・ラーメン店の数からすると「〇〇製麺所」 の名称を用いた店舗数はごくわずかであり、「製麺所」の文字からうどんの麺やラー メンの麺等の商品を取り扱う業種が連想されるとしても、飲食物の提供という業種 は連想されないと主張する。しかしながら、前記ア(イ)(ウ)からすると、「○○製麺所」 という名称を用いた飲食店の数がごく僅かであるとはいい難い。また、前記ア(イ)(ウ) の各店舗のほかに、「〇〇製麺所」と近似した名称である「○○製麺」との名称を用 いるうどん店が存在することは公知の事実であり、食品の製造をする場所において、 製造した食品を用いた飲食物を提供することはよく行われることであるから、需要 者である一般消費者にとって、「製麺所」との文字から、製麺所で製造された麺を用 いた飲食店を連想することは容易であるということができる。これらの点に照らす と、本願商標の指定役務である「飲食店の提供」の取引者及び需要者は、「製麺所」 の文字から「麺類を提供する飲食店」すなわち「飲食物の提供」の役務を想起する というべきである。したがって、原告の前記主張を採用することはできない。
3 本願商標について
本願商標は、ありふれた氏である「池上」と、麺類を提供する飲食店を表すもの\nとして慣用的に用いられている「製麺所」を組み合わせた「池上製麺所」を標準文 字で表したものであり、「池上」氏又は「池上」の名を有する法人等が運営する麺類\nを提供する飲食店というほどの意味を有する「池上製麺所」というありふれた名称 を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認められるから、\n商標法3条1項4号に該当するというべきである。
原告は、過去の審決(甲55〜58)において示されたように、名称全体として 多数存在するものでなければ「ありふれた名称」に当たらないと主張するが、商標 法3条1項4号の文言上、「ありふれた名称」であると認めるために当該名称が現に 多数存在することは要件とはされておらず、ありふれた氏である「池上」と、麺類 を提供する飲食店を示すものとして慣用的に用いられている「製麺所」とを結合し、 普通に用いられる方法で表示した本願商標は、本件全証拠によっても、我が国にお\nける飲食店の取引者、需要者が、特定人の運営する飲食店(原告店舗)を意味する ものであることを認識することができるほどの自他識別力を有するに至ったことを 認めるに足りない。したがって、本願商標は、特定人の独占にはなじまず、自他識 別力を欠くものとして、同条1項4号の「ありふれた名称を普通に用いられる方法 で表示する標章のみからなる商標」と認めるほかはない。原告の指摘する各審決は、\nいずれも本件とは指定商品及び指定役務等を異にする事案である上、当該各審決に 係る商標登録の有効性(同法46条1項1号)について裁判所の判断がされたこと を認めるに足りる証拠はないから、本願商標が同法3条1項4号に該当する旨の前 記判断を左右するに足りるものではない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2023.09.18
令和5(行ケ)10029 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年8月31日 知的財産高等裁判所
本願商標は、別紙のとおり、縦長長方形風の枠の中に「熟成鰻」の文字を 筆文字風書体で縦書きしてなるものである。その構成中の「熟成」の文字は、広辞苑第7版(乙1)によれば、「1)十分に熟してできあがること。2)[化]物質を適当な温度に長時間放置して化学変化を行わせること。発酵の調節、コロイド粒子や沈殿の粒径の調節などにいう。時効。3)蛋白質・脂肪・炭水化物などが、酵素や微生物の作用によ り、腐敗することなく適度に分解され、特殊な香味を発すること。なれ。」 を、デジタル大辞泉(審査手続における手続補足書〔甲5〕で引用)によれ ば、「1 成熟して十分なころあいに達すること。「機運が熟成する」 2 魚肉・獣肉などが酵素の作用により分解され、特殊な風味・うまみが出るこ と。・・・3 物質を適当な温度などの条件のもとに長時間おいて、ゆっく りと化学変化を起こさせること。」を意味する。また、広辞苑第7版(乙2) によれば、「鰻」の文字は、「ウナギ科の硬骨魚の総称、またその一種。」 を意味するものであり、一般に親しまれた語であり、各文字の語義自体から 「熟成させた鰻」を意味するものということができる。
(3) 各種ウェブサイトによれば、「熟成」の語は、食品又はこれに関する役務 の分野では、化学変化や酵素等の作用により、風味やうまみをだすとの意味 において、魚一般について用いられているほか(乙3〜12。「熟成魚」と の表現もある。)、この意味における「熟成」を用いた、「熟成鰻」又は「熟\n成うなぎ」との端的な表現もある(乙23〜28、30、32。そのうち、\n乙23〔クラウドファンディング情報。令和3年10月26日募集開始〕、 25〔オークション結果。令和2年7月4日開始、同月5日終了〕、28〔「旨 味熟成うなぎ」を商品化したとの平成26年5月の記事が引用されている。〕 は、本件審決の日である令和5年1月30日より前に使用されたことが明ら かである。)。さらに、「熟成鮭」、「熟成鯛」、「熟成マグロ」、「熟成鰹」など、上記意味における「熟成」と魚の名前を組み合わせた用例は枚挙に暇がない(乙 33〜42)。
(4) 以上からすると,本願商標の「熟成鰻」からは,熟成させた鰻という意味 合いが生じ,本願商標に接した取引者,需要者は,通常,本願商標は,その 指定役務の質を示すものと認識するにとどまるものと解される。 これに対し、原告は、「熟成うなぎ」の「熟成」は、鰻が十分に熟してで\nきあがった状態、すなわち大きく成長した状態であること、あるいは、タレ が熟成したこととの意味も含みうる多義的な表現である旨主張する。\nしかし、原告の主張を前提としても、「熟成鰻」が識別力を有さない記述 的表示と解さざるを得ないことに変わりはないし、これを措くとしても、「大\nきく成長した状態」を示すのであれば、「成熟」を用いることがむしろ自然 であり、また、「熟成うなぎ」の語から、そこに何ら表示されないタレの熟\n成を想起するとはいえない。原告の提出する甲15〜17その他の証拠は以 上の認定判断を覆すものではない。原告の上記主張は採用できない。
(5) 次に、「普通に用いられる方法で表示」の要件についてみるに、各種ウェ\nブサイトによれば、飲食店一般において、提供される料理の質(内容)を筆 文字風の書体をもって四角囲みで表示することが普通に行われている(乙4\n3〜50)上、鰻を提供する飲食店のロゴ、看板、のれん等に限ってみても、 筆文字風の書体を四角囲みで表示することが普通に行われているものと認\nめられる(乙51〜60)。 原告は、本願商標は書家の手になるもので唯一無二のものであり、「熟成 鰻」の文字を囲む長方形も角が丸くかすれた部分があるなど独自の部分があ るなどと主張するが、「普通に用いられる方法で表示」の域を出るものでは\nない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2023.09.17
令和5(行ケ)10030 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年9月7日 知的財産高等裁判所
前記ア(イ)及び(ウ)のとおり、「前髪」及び「カーラー」の各語は、本件査定日当 時、それぞれ前記ア(イ)及び(ウ)の意味を有するものとして、我が国において高い信 頼性を有すると認められる国語辞典に掲載されていたものであるところ、弁論の全 趣旨によると、当該各語がそのような意味を有する語であることは、本件査定日当 時、本件商品に係る取引者又は需要者(以下、本件商品に係る本件査定日当時の取 引者又は需要者を「本件需要者等」という。)にとって極めて明確であったものと 認められる(以下、本件商標に接した本件需要者等の認識を検討するに当たり、 「前髪」及び「カーラー」の各語については、「額に垂れ下がる髪」、「頭髪を巻 き付けてカールさせるための円筒形の用具」などと敷えんすることはせず、これら の語をそのまま用いることとする。)。
他方、辞典に記載された「くるん」の語の意味及び用例(前記ア(ア))、本件査 定日前のウェブサイト及び新聞記事における「くるんと」等の語の使用例(前記イ 及びウ)並びに日本語の文法に照らすと、「くるんと」の語は、前髪を含む毛髪に ついて用いられるときは、通常、「(毛髪が)丸く曲がった様子」を示す語として 用いられている。また、ウェブサイトにおける「くるんと」等の語の使用例(前記 イ)に照らすと、「くるんと」の語と「くるんっと」の語は、促音の有無により互 いに意味を異にするものとは認められない。そうすると、「前髪」の語の直前に置 かれた本件商標の構成中の「くるんっと」の語は、それが副詞として修飾すること\nになる用言(動詞、形容詞等)が明示されていなくても、その内容は自明であって、 通常、「(前髪が)丸く曲がった様子」を示すものとして、本件需要者等に認識さ れるものと認めるのが相当である。
なお、ウェブサイトにおける「くるんと」等の語の使用例の中には、「くるんと」 等の語が、毛髪が丸く曲がった様子を示すというよりも、商品であるカーラーを回 転させる動作の様子を示す副詞として用いられていると認められるもの(1)「くる んと巻きます」(前記イ(セ))、2)「はさんでクルンとする」(前記イ(ソ))、3) 「はさんでくるっの超簡単ステップ」(前記イ(チ))、4)「挟んでくるっとするだ け」(前記イ(ツ)))がある。しかし、仮に、本件商標の構成中の「くるんっと」\nの語がカーラーを回転させる動作の様子を示す語として用いられていたとしても、 当該語は、カーラーを使用する者の当たり前の動作を表現するものにすぎないから、\n商標法3条1項3号該当性との関係では、商品の用途や使用の方法を普通に用いら れる方法で表示したことになるだけであり、かつ、当該動作によりカーラーを使用\nした結果は、前髪が丸く曲がった状態のはずであるから、本件商標に接した本件需 要者等の認識が前記したもの(「くるんっと」という語は、前髪が丸く曲がった様 子を示すものであるとの認識)と異なるものになるとは思われない。
以上によると、本件査定日当時、被告商品(甲14、15の1及び2、甲42、 44)及び商品名を「前髪くるんとカーラー」とする原告の商品(乙2)を除くほ か、「くるんっと前髪カーラー」の語句又はこれに準ずる語句を本件商品について 用いる例があったと認めるに足りる証拠がないことを考慮しても、「くるんっと前 髪カーラー」の語句に接した本件需要者等は、通常、当該語句が「丸く曲がった前 髪を作るカーラー」を意味するものと認識することになると認めるのが相当である。 なお、証拠(甲14、15の1及び2、甲42、44)及び弁論の全趣旨によると、 被告は、本件査定日当時、被告商品の品質、効能等をうたう宣伝文句として、「く\nるんっとカールした前髪ができちゃう!」及び「くるんっと内側にカールした前髪 をセットするためのカーラーを考えました」との文言を用いていたとの事実が認め られるが、これは、「くるんっと前髪カーラー」の語句に接した本件需要者等にお いて、当該語句が「丸く曲がった前髪を作るカーラー」などを意味するものと認識 したとの上記認定に符合するものである。
オ 被告の主張について
被告は、本件商標の構成中の「くるんっと」の語は副詞であるのに、本件商標の\n構成中にはこれを明確に受ける動詞が存在せず、本件商標が意味するところは一義\n的に特定することができるものではないと主張する。
確かに、「くるんっと」という擬態語は、文法上、用言(動詞、形容詞等)を修 飾する副詞であると考えられるにもかかわらず、本件商標の構成中の「前髪」及び\n「カーラー」の各語は、いずれも名詞であるから、「くるんっと」の語が修飾すべ き語が本件商標の構成中には見られないことになる。しかしながら、本件需要者等\nにおいて、「くるんっと」、「前髪」及び「カーラー」の各語の相互の修飾関係が 文法的に正確なものでなければ、これらの語を順番に並べた語句の意味を一義的に 把握することができないということはできない。実際、ウェブサイトにおける「く るんと」等の語の使用例の中にも、「前髪くるんっの仕方」との語句を用いた例 (前記イ(ケ))、「くるん前髪」との語句を用いた例(前記イ(シ))、「くるんがキ マる」との語句を用いた例(前記イ(チ))、「くるん前髪」との語句を用いた例 (前記イ(ツ))等がみられるところ、これらは、いずれも文法的に正しい表現では\nないが、そのことをもって、その意味するところが不明確になるということはでき ない。
被告は、「くるんっと前髪カーラー」の語句からは、1)「「くるんっと丸まった 弾力のある表面」を有する前髪用のカーラー」、2)「「くるんっと振り向いても」 キープされるカールを作る前髪用のカーラー」、3)「「くるんっと寝返りを打って も」前髪のカールを作ることができるカーラー」、4)「前髪を挟んで「くるんっと 回す」カーラー」などの様々な意味合いが想起されるとも主張する。 しかしながら、このうち、前記1)から3)までのような意味合いは、理論的にはあ り得るとしても、前記ウェブサイトの使用例その他本件に提出された全証拠によっ ても、「前髪」や「カーラー」と一緒に使用される場合の「くるんっと」という語 は、もっぱら「(前髪が)丸く曲がった様子」を示すために用いられていることが 認められ、被告が主張するような意味合いで用いられている例は見当たらない。ま た、前記4)の意味合いについては、そのような意味合いが生じる使用例(前記イ (セ)、(ソ)、(チ)及び(ツ))は存在するものの、前記エにおいて説示したところに照ら すと、商標法3条1項3号該当性に関する判断を左右するに足りるものではない。 以上のとおりであるから、被告の前記各主張を採用することはできない。
(3) 本件商標の商標法3条1項3号該当性について
前記(2)のとおり、「くるんっと前髪カーラー」の語句に接した本件需要者等は、 当該語句が「丸く曲がった前髪を作るカーラー」を意味すると認識することになる ところ、「カーラー」は、「頭髪を巻き付けてカールさせるための円筒形の用具」 であるから(前記(2)ア(ウ))、「くるんっと前髪カーラー」の語句は、単に本件商 品(電気式のものを除くヘアカーラー)の効能等を述べたものにすぎない。また、\n本件商標は、「くるんっと前髪カーラー」の語句のみからなり、当該語句を標準文 字で表すものであって、本件商品の効能\等を普通に用いられる方法で表示するもの\nである(「くるんと」の語に促音を付加した「くるんっと」の語を用いた表現が特\n殊なものであるということはできない。)。したがって、本件商標は、本件商品の 品質、効能等を普通に用いられる方法で表\示する標章のみからなる商標であるとい うことができるから、商標法3条1項3号に掲げる商標に該当する。 被告は、本件商標は本件商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはい\nえないから、同号に掲げる商標に該当しないと主張する。しかしながら、前記(2) において説示したところに照らすと、本件商標は、本件商品の品質、効能等を間接\n的に暗示するにとどまるものではなく、これを直接的かつ具体的に表示するもので\nあると認められるから、同主張は採用することができない。 また、被告は、「くるんっと前髪カーラー」の標章につき特定の者による独占使 用を認めても何ら弊害はないと主張する。しかしながら、「くるんっと前髪カーラ ー」が「丸く曲がった前髪を作るカーラー」などを意味するものとして、本件商品 の品質、効能等を普通に用いられる方法で表\示する標章である以上、他の事業者に おいて、本件商品に該当する商品の製造、販売等をするに当たり、「くるんっと前 髪カーラー」と同一又は類似の標章を用いようとすることは当然に想定されるとこ ろであるから、「くるんっと前髪カーラー」の標章につき独占使用を認めても何ら 弊害はないとの被告の主張を採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2023.09.17
令和5(行ケ)10032 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年8月31日 知的財産高等裁判所
3 本件商標と引用商標の対比
本件商標と引用商標の外観は、いずれも、黄色の円の中央上部に、黒色の縦 長な楕円形の点を上下左右2個ずつ合計4個配置して、人の目のように描き、 その下方に両端を上向きにした黒色の円弧を人の口のように描いた図柄であり、 4つ目の人の顔を、鼻、耳、髪等を捨象した黄色一色のシンプルな円形と点状 の目及び円弧状の口だけで表現したものである点において外観上共通している。\nなお、観念及び称呼を比較することはできない。 細部をみると、原告の主張する(前記第3の1(1)ア〜ウ)ように、目の形、 位置、口の線の曲がり具合、位置、線の太さ、口元のえくぼを想起させる線の 有無が異なるが、これらの相違は、本件商標と引用商標を並べて対比的に観察 してようやく認識できる程度のものにすぎない。現実の取引の場面においては、 取引者・需要者は、自己の記憶にある商標に基づいて商品・役務を選択するの であるから、時と場所を異にする離隔的観察を基本とすべきであり、このよう な観点からみる限り、本件取消指定商品の取引者・需要者が、その出所を識別 できるほどの相違とはいえない。 なお、引用商標の顔の表情はほほえんでいるように見えるのに対し、本件商\n標の顔の表情はわずかにほほえんでいるようにも、とり澄ましているようにも\n見える点で異なる印象を与える可能性はあるが、相対的、主観的な相違にすぎ\nず、上記の判断を左右するものではない。 そうすると、本件商標は、引用商標と類似するものと認められる。
4 原告のその他の主張に対する判断
(1) 原告は、本件商標及び引用商標は世界的に著名なスマイルマークをベース とするものであり、1)その基本構成は出所識別力・独占適応性を欠く表\示で あるから、原告主張の相違点をもって類似しないというべきである、2)スマ イルマークは数多くのバリエーションが生まれているから、需要者及び取引 者はわずかな差違であっても違いを認識し、出所混同を生ずるおそれはない 旨主張する。 しかし、本件商標と引用商標がいわゆるスマイルマークをベースとする ものだとすると、むしろ、これに接した取引者・需要者は、「4つ目のスマ イル」という本件商標と引用商標の共通点をより強く認識すると考えるのが 自然であり、それ以外のわずかな違いが注意をひくなどと解すべき根拠はな い。原告の主張は採用できない。
(2) 原告は、異議申立人との交渉経緯や本件商標及び引用商標の登録出願の経\n緯等を主張して、本件商標の取消は商標法の目的に反する旨主張する。 しかし、原告主張の経緯があるとしても、引用商標が商標法4条1項1 1号所定の先願に係る他人の登録商標としての適格を失うものではなく、現 在も商標として登録されている以上、これと類似している商標であれば同号 に該当し得るのであって、原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.09. 5
令和2(ワ)17104 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月16日 東京地方裁判所
ア 上記にいう「侵害品の売上高」につき、原告は、被告サーバを使用したF X取引の取引高(3項損害主張1))、被告サーバを使用したFX取引の取引 回数(3項損害主張2))、被告サーバを使用したFX取引による手数料収入 及びトレーディング損益(3項損害主張3))であると主張する。 そこで検討すると、前提事実、証拠(甲27、乙66、67)及び弁論の 全趣旨によれば、1)FX取引は、証拠金を預託し、差金決済(元本に相当す る金銭の受渡しを行わず、買い付けの対価と売り付けの対価の差額の授受に より決済することをいう。)により外国通貨の売買を行う金融取引であるた め、総取引額の金銭の受渡しは必要とされず、売買の損益の受渡しのみで取 引が完結すること、2)被告は、被告サーバを介してFX取引管理方法に係る 被告サービスを提供し、これによって顧客から手数料収入を得ていたこと、
3)顧客とFX業者が直接取引を行うFX取引では、FX取引による顧客の利 益は、FX取引におけるFX業者の損失となるため、そのリスクをヘッジす るために、FX業者は、顧客の注文に応じて、他の金融機関に対し同様の注 文を行う取引(以下「カバー取引」という。)を行っており、被告は、FX 取引を行う際に、被告サービスを含めた多数の顧客の注文を一定数量や一定 時間で合算し、売り注文と買い注文を相殺した後、差分数量について他の金 融機関とカバー取引を行うことによりトレーディング損益を得ていたこと、
4)原告ライセンス契約においては、●(省略)●と定められていたこと、以 上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、差金決済その他のFX取引の内容及び実施料率に 係る取引の実情等を踏まえると、特許法102条3項に基づく実施料相当額 算定の前提となる「侵害品の売上高」は、FX取引に関する手数料収入及び トレーディング損益であると認めるのが相当である。 これに対し、被告は、トレーディング損益については、被告サーバを用い た顧客との取引とは別個独立の取引によって得られるものであるから、「侵 害品の売上高」には含まれない旨主張する。しかしながら、カバー取引は、 当該FX取引のリスクヘッジのために行われるものであるから、被告がカバ ー取引により得ているトレーディング損益は、被告サーバを使用した顧客と の当該FX取引と密接不可分の関係にあり、●(省略)●トレーディング損 益も、上記にいう「侵害品の売上高」に含めるものとするのが相当である。 そして、この場合に、トレーディング損益は、被告の全取引数量に占める被 告サービスを用いた取引数量を按分することにより、算定するのが相当であ る。したがって、原告及び被告の各主張は、上記認定に抵触する限度で、いず れも採用することができない。
イ 本件発明の構成要件を充足しない取引を除外すべきとの被告の主張につ\nいて
被告は、1)買い注文を決済注文とする取引(以下「取引1)」という。) 2)取引開始時点において2個以下の新規買い注文しか生成されない取引 (以下「取引2)」という。)、3)売り注文が相場価格の上昇に追従する取 引(最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報を 生成した取引をいう。)以外の取引(以下「取引3)」という。)は、いず れも本件発明の技術的範囲に含まれないから、これらの各取引は、損害額 算定の基礎から除外する必要があると主張する。
取引1)について
a 本件特許において、特許請求の範囲の請求項3は、次のとおり記載さ れていることが認められる。
・・・
b 取引1)の除外の可否
上記認定事実によれば、本件特許においては、売り注文を決済注文と する本件発明と、買い注文を決済注文とする取引1)とは、表裏の関係と\nして明確に区分して規定されていることを踏まえると、本件発明に係る 実施料を算定するに当たっては、取引1)に係る収入は、損害額算定の基 礎から除外するのが相当である。 なお、弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば、原告は、被 告サーバが本件特許の請求項3を侵害すると主張し、本件訴訟係属中、 取引1)に係る損害賠償の支払を求めて別訴を提起していることが認め られる。
取引2)及び取引3)について
証拠(甲7ないし9)及び弁論の全趣旨によれば、被告サーバを用いた 取引は、顧客が「想定変動幅、ポジション方向、対象資産」を設定した上、 被告サーバは、複数の買い注文情報を前提とした買い注文情報を生成し、 相場価格が上昇した場合には、売り注文の価格を変更するものであること が認められる。そうすると、上記取引は、被告サーバにおいて、複数の買 い注文情報を生成させ、相場価格が上昇すれば売り注文の価格を変更させ ることを意図するのといえる。 これを被告サーバを用いた取引2)及び取引3)についてみると、当該各取 引は、結果としては、その内容が本件発明による取引に係るものとは異な るものの、いずれの取引においても、複数の買い注文情報が生成されて相 場価格が上昇したときは、本来売り注文の価格を変動させることを意図し たものであったことが認められる。 これらの事情を踏まえると、取引2)及び取引3)は、特許法102条3項 に基づく実施料相当額算定の前提となる「侵害品の売上高」に含まれると するのが相当である。もっとも、被告サーバを使用した取引のうち、結果 としてその内容が本件発明による取引に至らなかったもの(取引2)及び取 引3))については、実施料率の算定において考慮するのが相当である。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
ウ 本件における侵害品の売上高について
証拠(乙63の2、73の2)及び弁論の全趣旨によれば、本件期間から、 消滅時効に係る期間を除いた平成29年7月9日から平成31年3月2日 までの期間における被告サービスの手数料収入の合計額は、●(省略)●で あり、また、同期間におけるトレーディング損益の合計額は、被告の全取引 数量に占める被告サーバを使用した取引数量で按分すると、●(省略)●で あることが認められる。 そうすると、特許法102条3項に基づく実施料相当額算定の前提となる 「侵害品の売上高」は、上記手数料収入及びトレーディング損益の合計額で ある●(省略)●と認められる。
(3) 実施料率について
ア 実施許諾契約における実施料率等
証拠(甲27)及び弁論の全趣旨によれば、原告ライセンス契約において は、●(省略)●ことが認められる。 しかしながら、●(省略)●ことは、上記において説示したとおりである。 そして、原告ライセンス契約は、本件特許が登録された平成29年6月9日 より前の平成26年10月1日に締結されており、しかも、原告と原告の完 全子会社である原告子会社との間で締結されたものである。 これらの事情を踏まえると、本件特許の実施料率の算定に当たっては、上 記●(省略)●の実施料率を直ちに斟酌するのは相当とはいえない。 他方、証拠(甲26、乙74)によれば、株式会社帝国データバンクによ る平成22年3月付けの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在 り方に関する調査研究報告書〜知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率 に関する実態把握〜本編」においては、コンピュータテクノロジーの実施料 率の平均値は、正味販売高の3.1%とされていることが認められる。
イ 本件発明の技術内容や重要性
本件発明は、複数の売り注文価格がそれぞれ等しい値幅で異なるように した上で、複数の売り注文価格の情報を含む売り注文情報を一の注文手続 で生成し、その後相場価格が変動して、複数の売り注文のうち最も高い売 り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると、当該検知の情報を 受けて、複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも更に所定価格 だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することによっ て、元の売り注文価格よりも相場価格が変動した高値側に新たな売り注文 価格の売り注文情報を生成する構成を採用するものである。このような構\ 成により、本件発明は、コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取 引において、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させることにより 多くの利益を得る機会を提供するという点において、相応の技術的価値を 有するものと認められる。
証拠(甲7の1、8の1)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告サ ービスの広告宣伝において、被告サービスについて、予め指定した変動幅\nの中で、一定間隔の値幅で複数のイフダン+OCO注文を一度に同時発注 し、決済注文成立後、相場の変動に合わせて変動幅を追従させ、相場変動 に追従した新たな条件の注文をシステムが自動的に繰返し発注する連続 注文機能であって、トラップリピートイフダン注文に係る被告の別のサー\nビスでは、想定した変動幅から相場が外れた場合、利益を逸失する場合が あるのに対して、相場の上昇又は下落の変動に合わせて、自動追従して注 文を繰り返すため、利益を追求することが期待できる注文方法であること を説明していることが認められる。そうすると、被告は、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させるという本件発明の技術内容を被告サービスの特徴の一つとして広告宣伝していたことが認められる。 弁論の全趣旨によれば、本件期間から消滅時効に係る期間を除いた期間 (平成29年7月9日から平成31年3月2日まで)において、被告と顧 客との間で行われた被告サービスに係るFX取引のうちの、新規注文を買 い注文、決済注文を売り注文とし、売り注文が相場価格の上昇に追従する 取引(最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報 の生成)に対応する新規買い注文に係る手数料収入は、●(省略)●であ ることが認められる。そうすると、上記手数料収入は、上記期間における被告サービスにおける手数料収入の合計額●(省略)●にとどまり、被告サービスによる取引 のうち売り注文が相場価格の上昇に追従する取引(本件発明の構成要件を\n充足する態様での取引)の割合は、実際には●(省略)●にも満たないも のと認められる。したがって、本件発明による被告サービスの売上げへの 貢献は、上記割合をも斟酌するのが相当である。上記のとおりの本件発明の技術内容や重要性に照らせば、これを実施することは、被告にとって、相応に売上げや利益に貢献するものであるといえる。
ウ 侵害の態様
前提事実によれば、被告は、業として、平成26年10月1日から平成3 1年3月2日まで、被告サーバを使用していたこと、原告が、平成26年5 月1日を原出願とする出願につき分割出願をして本件特許が平成29年6 月9日に登録されたため、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すること になったこと、以上の事実が認められる。当該認定事実を踏まえると、被告 による本件発明に係る侵害の態様が、極めて悪質であるとまで認めることは できない。
エ その他の事情
前提事実によれば、原告は、本件期間を通じて、金融商品取引業者として の登録を受けておらず、FX取引業を営んでいなかったこと、原告の完全子 会社である原告子会社は、FX取引等を事業内容とする株式会社であること が認められる。 そうすると、原告自身は被告との間で競合関係がないとしても、原告の完 全子会社である原告子会社と被告との間では潜在的な競合関係が認められ るから、仮に、原告が、被告に対し、本件発明の実施を許諾するとすれば、 その実施料は相応に高額になったものといえる。
オ 実施料率の算定
上記認定に係る本件発明の技術内容や重要性、侵害の態様その他の本件に 現れた諸事情を総合考慮して、特許法102条4項の趣旨に鑑み、合理的な 料率を定めると、実施に対し受けるべき料率は、●(省略)●であると認め るのが相当である。
(4) 損害額
ア 特許法102条3項に基づく損害額
したがって、特許法102条3項に基づく損害額は、次の計算式のとおり、 ●(省略)●となる(小数点第一位で四捨五入)。
(計算式)
●(省略)●
イ 弁護士費用及び弁理士費用
本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因果関係があると認められる弁理士費用及び弁理士費用相当損害額は、●(省略)●の限度で認めるのが相当である。
ウ 合計額
以上によれば、本件の損害額は、2014万9093円●(省略)●となる。
◆判決本文
当事者が同じ侵害事件です。
◆平成29(ネ)10073
原審はこちらです。
◆平成28(ワ)21346
こちらは、原告被告が逆の侵害事件です。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2023.08.30
令和5(行ケ)10007 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和5年8月10日 知的財産高等裁判所
掲記の証拠、A作成の報告書(甲62、68、乙3)、B作成の陳述書(甲41 の3、甲43の4)及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。 (1) 石垣市は、同市の新庁舎を建設するに当たり、公募によるプロポーザル方 式により建設工事に係る設計者を選定することとし、平成28年7月14日、一次 審査により選定された5つの業者(被告隈研吾事務所を含む。)を対象に、二次審 査として公開プレゼンテーション・ヒアリングを実施した。Dは、同日の公開プレ ゼンテーション・ヒアリングに参加し、被告隈研吾事務所の提案の内容等について のプレゼンテーションを行った。石垣市は、同日、業者によるプレゼンテーション の結果も踏まえて審査し、特に優れた提案を行い新庁舎の建設工事に係る設計を委 ねるにふさわしい業者として、被告隈研吾事務所を選定した。なお、Dが上記のプ レゼンテーションにおいて使用した資料には、新庁舎の屋根につき赤瓦を使用する ことが記載されていた。(甲9、10、12)
・・・・
2 原告らの主張2(引用意匠が本件送付により意匠法3条1項1号に掲げる意 匠(公然知られた意匠)に該当するに至ったものではないこと)について
原告らの主張1(引用意匠について意匠法4条2項が適用されること)は、原告 らの主張2(引用意匠が本件送付により意匠法3条1項1号に掲げる意匠に該当す るに至ったものではないこと)に理由がないこと(引用意匠が本件送付により意匠 法3条1項1号に掲げる意匠に該当するに至ったものであること)を前提とするも のであるから、原告らの主張1に先立ち、原告らの主張2について検討する。
(1) ある意匠が他の者に知られた場合であっても、当該者が当該意匠について 秘密保持義務を負うと認められるときは、当該意匠は、いまだ意匠法3条1項1号 にいう「公然知られた意匠」に該当するものではない。もっとも、当該者が当該意 匠について秘密保持義務を負うといえるためには、必ずしも秘密保持義務の発生の 根拠となる契約が存在することまでは必要とされず、当該者とその相手方との関係、 当該者において知るに至った事項の性質及び内容等に照らし、当該者が当該意匠に ついて秘密にすることを社会通念上求められる状況にあり、当該者がそのことを認 識することができれば、当該者は、当該意匠について秘密保持義務を負うものと解 するのが相当である。
(2) 以上を前提に、本件について検討する。
ア 前記認定のとおり、引用意匠は、本件パンフレット等に掲載されているもの であるところ、AがB及びCに対して平成29年2月16日に本件パンフレット等 を送付したことから(本件送付)、引用意匠は、遅くとも同日、被告隈研吾事務所 の知るところとなったものである。
イ 原告らは、本件送付に係る本件パンフレット等に掲載された引用意匠につい て、原告らと被告隈研吾事務所との間で秘密保持契約が締結されたと主張するもの ではない。
ウ 前記認定のとおり、原告らの各代表者は、本件送付に先立つ平成29年2月\n1日、Dに対し、引用意匠を含む本件発明について、これを同月19日に行われる 予定の本件説明会(石垣市長及び石垣市民が参加するもの)において公開するよう\n依頼し、Dは、同日、当該依頼にも応じる形で、本件説明会において、石垣市の新 庁舎に使用する瓦として本件発明に係る瓦(引用意匠を含むもの)を発表したもの\nである。また、Aは、同月13日、Bから「Dは、同月19日の本件説明会におい てプレゼンテーションをする予定であり、当該プレゼンテーションにおいてちゅら\n瓦(引用意匠を含むもの)について説明したいので、石垣市役所に対してちゅら瓦 のサンプルを送付してほしい」との趣旨のメールを受信した際も、Dが本件説明会 において引用意匠を含むちゅら瓦について説明することに異議を述べるのではなく、 同月16日、Bの上記依頼に応じてちゅら瓦のサンプル及び本件パンフレットを石 垣市役所に送付した上、同日、本件パンフレット等をB及びCにも送付したもので ある(本件送付)。さらに、Aは、本件説明会が開催された日の翌日である同月2 0日、Bから本件説明会(本件発表)の様子等を知らせるメールを受信した際にも、\n特にこれに異議を述べるなどしなかったものである。加えて、Aにおいて、本件パ ンフレット等を添付ファイルの形式で送付したメールである本件メールに、引用意 匠や本件パンフレット等を秘密扱いにするよう求めるなどする記載をせず、かえっ て、被告隈研吾事務所が本件説明会において引用意匠を含むちゅら瓦を石垣市の新 庁舎に使用する瓦として提案することを前提とする記載をしたこと、Aにおいて、 本件パンフレット等に、引用意匠が開発中のものであるなどの記載や本件パンフレ ット等が秘密情報を含むものであることを示す「部外秘」などの記載をしなったこ となどの事情も併せ考慮すると、Aは、Dが同月19日に開催される本件説明会に おいて引用意匠を含む瓦(本件発明に係る瓦)を公開することを十分に知りながら、\nこれを容認し、被告隈研吾事務所の従業員であるB及びCに対して、そのように公 開を予定している引用意匠が掲載された本件パンフレット等を送付したものと認め\nられるところ、本件送付から本件発表までの僅かな期間においてのみ引用意匠を秘\n密にすべきとする事情はうかがわれないから、本件発表がされた同月19日の時点\nにおいてはもちろんのこと、本件送付がされた同月16日の時点においても、被告 隈研吾事務所が引用意匠について秘密にすることを社会通念上求められる状況にあ ったものと認めることはできない。
エ 前記認定のとおりの本件パンフレットの体裁によると、本件パンフレットは、 宣伝、広告等のための一般的なパンフレットであるといえ、加えて、本件写真が本 件パンフレットと同時にB及びCに送付されたものであること、本件パンフレット 等には、引用意匠が開発中のものであるなどの記載や本件パンフレット等が秘密情 報を含むものであることを示す「部外秘」などの記載がないこと、本件メールにも、 引用意匠や本件パンフレット等を秘密扱いにするよう求めるなどする記載がないこ と、Dは、原告らの各代表者から、本件送付に先立つ平成29年2月1日、引用意\n匠を含む本件発明について、これを同月19日に行われる予定の本件説明会におい\nて公開するよう依頼されていたこと、本件パンフレットは、Bが同月13日にした 引用意匠の公開を前提とする依頼(「Dは、同月19日の本件説明会においてプレ ゼンテーションをする予定であり、当該プレゼンテーションにおいてちゅら瓦(引\n用意匠を含むもの)について説明したいので、石垣市役所に対してちゅら瓦のサン プルを送付してほしい」との趣旨の依頼)に応じたAにおいて、ちゅら瓦のサンプ ルと共に石垣市役所に送付したパンフレットと同じパンフレットであること、原告 らにおいて、被告隈研吾事務所に対し、本件発明に係る本件原出願(特許出願)が された同年6月16日に先立って、引用意匠を含む発明、引用意匠等について特許 出願、意匠登録出願等をする予定がある旨を伝えたことがなかったこと、本件送付\nから本件発表までの僅かな期間においてのみ引用意匠を秘密にすべきとする事情は\nうかがわれないことなどを併せ考慮すると、本件パンフレット等を受領した被告隈 研吾事務所において、本件発表がされた同年2月19日の時点においてはもちろん\nのこと、本件送付がされた同月16日の時点においても、本件パンフレット等に掲 載された引用意匠を秘密にすることが求められる状況にあると認識し得たものと認 めることはできない。
オ 以上によると、被告隈研吾事務所が本件送付により知るところとなった引用 意匠について、被告隈研吾事務所が秘密保持義務を負うということはできないから、 引用意匠は、平成29年2月16日にされた本件送付により、意匠法3条1項1号 にいう「公然知られた意匠」に該当するに至ったものと認めるのが相当である。
◆判決本文
関連事件です。
2023.08.23
令和5(行ケ)10003 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年8月10日 知的財産高等裁判所
前記(2)を総合すると、本願商標の用いられた原告商品は、昭和60年頃以 降、日本全国において広く販売されており、本願商標の査定時までの販売期間は約 35年と相当程度に長く、販売数量や売上高も相当程度に大きいものと認められる。 また、本願商標は、全体が黒色の革靴又はブーツに用いられた場合には、視認性が 高く目を引く部分であるといえ、需要者及び取引者が、黒等の暗い色の革靴又はブ ーツに施された黄色のステッチから原告ブランドを想起する例があることが認めら れる。他方で、黒色の革靴又はブーツであって本願商標と同じ特徴を有する商品に ついては、原告の模倣品対策により、日本国内において流通する量が極めて少ない 状況にあるから、本願商標と同じ特徴を有する黒色の革靴及びブーツが多数市場に 存在するとはいえない。 本願商標の指定商品である革靴、ブーツは、広く一般の需要者を対象とする商品 であるにもかかわらず、本件アンケート調査は、本調査としてその対象者を「店舗、 通販サイト、雑誌等で革靴やブーツを見ることがある方」であり、かつ、「1年以内 に革靴やブーツを購入した方」と限定し、これによって革靴やブーツに関心のない 層が除外されることになるが、そのような層も必要に応じて生活必需品等として革 靴やブーツを買うことが予想されることに照らすと、本件アンケート調査における\n本調査の対象者の限定については相当性の有無との問題があるものの、本件アンケ ート調査の結果によると、本願商標の特徴を有する黒い革靴の黄色ステッチ部分の 写真を見た需要者(店舗等で靴やブーツを見ることがある者及び1年以内に革靴や ブーツを購入した者)のうち、30.7%が原告ブランド名を想起することができ、 選択肢を示された場合には37.6%が原告ブランドを選択することができており、 これらの割合は、原告ブランド以外のブランド名を回答した者と比べても有意に多 く、最も多く回答された他のブランド名であるティンバーランド(Timberland)を回 答した者の割合(7.9%)の4倍以上である。この点につき、ブランドの数が多 く、かつ、購入する頻度の低いファッション製品の場合は、一般消費者が、商品の 形状に触れ、その形状からブランド名を想起する機会が多いとはいえないことから すると、15%を超える認知度があれば、十分識別力があるといえるのと見解もあ\nること(甲59)を踏まえると、本件アンケート調査の結果からは、需要者(ただ し、上記のとおり、本調査としてその対象を限定された需要者層である。)のうち相 当程度の者が、黒い革靴に本願商標が用いられた場合に、本願商標から原告ブラン ド名を想起できる程度に、黒い革靴に用いられた場合の本願商標は、認知度が高い ものと認めることができる。
しかしながら、本願商標が黄色やベージュのアウトソール及びウェルトとともに\n用いられた場合には、必ずしも視認性に優れるものではなく、需要者の目を引くと はいえない。また、前記(2)アのとおり、原告商品の多くは、アウトソール及びウェ\nルトが黒又は茶系統の色であって、黄色のステッチの視認性が高くなる態様で本願 商標が用いられており、黒又は茶系統の暗い色のウェルトとのコントラストにより、 本願商標が強く印象付けられることで、需要者の認知度を得ているものと推認され るところ、雑誌やブログ等の記事においても「黄色のステッチは、暗い色の革と魅 力的なコントラストを生む」(前記(2)オ(イ))、「ツヤのあるブラックレザーにマーチ ンの象徴、イエローステッチが引き立ちます。」(同(エ))などと地の色とのコントラ ストにより黄色のステッチが目を引くものであることを指摘するものがあることか らして、地の色を問うことなく、本願商標が需要者の認知度を得ていると認めるこ とはできない。更に、本件アンケート調査は、黒色の革靴(アウトソール及びウェ\nルトも黒である。)に本願商標を用いたものについて、側面から撮影した写真の下部 分(黄色のステッチ部分)を示して質問がされたものであるから、本願商標が黒以 外の色のアウトソール及びウェルトとともに用いられた場合についての認知度を示\nすものとはいえない。そして、現に、令和5年2月頃、黒以外の色のアウトソール\n及びウェルトとともに本願商標と同じ特徴を有する第三者の商品が市場に流通して いたことが認められるところ(別紙「被告の主張する取引の実情」の(タ)及び(ツ))これらの商品の流通については原告も模倣品としては扱わず、通知書を送付するな どもしていないことから、同種の商品が、本件審決以前にも流通していた可能性が\n十分にある。\nそうすると、少なくとも黒い革靴に用いる場合には、本願商標は相当程度の認知 度を得ているということができるとしても、それ以外の色の革靴及びブーツに用い られる場合の本願商標の認知度が高いと認めるに足りる証拠はないというほかない。 なお、前記1(4)のとおり、商標権の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定め られるものであるところ(商標法27条)、本願商標の願書の記載によると、下地が 黒色であることは本願商標の範囲に含まれるものではないから、アウトソール及び\nウェルトが黒色である場合の本願商標の認知度をもって、本願商標自体の認知度を 評価することは相当ではない。
(4) 原告の主張について
原告は、本願商標について、1)視認性が低い態様で用いられた場合には、商標法 上の「使用」に当たらず、2)黄色の破線状の図形が需要者に特に強く識別されない ような態様で使用する場合には商標法26条1項2号又は6号により商標権が及ば ないから、他事業者の自由使用が殊更に制限されることはなく、むしろ、3)本願商 標の周知性からすると本願商標と類似する標章を使用した商品を販売等する行為は 不正競争防止法2条1条1号の不正競争に該当するから、本願商標を登録すること は公正な競争秩序に資すると主張する。 しかしながら、前記(3)で説示したとおり、本願商標の範囲を、黄色の破線状の図 形が需要者に特に強く識別される態様、すなわち、黒色のアウトソール及びウェル\nトとともに用いられる場合に限定して解釈することはできないのであって、本願商 標が、黄色やベージュ色のアウトソール及びウェルトとともに用いられる場合もそ\nの商標権の範囲に含まれるというほかない。また、商標法は、商標を保護すること により商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、産業の発展に寄与し、あ わせて需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ(同法1条)、商 標の本質は自他識別機能にあるから、これを欠くような商標については登録が認め\nられず(同法3条1項)、自他識別機能を有していないにもかかわらず過誤等により\n登録された場合や、登録後に自他識別機能を失った場合には、その権利が制限され\nるものである(同法26条 1 項等)。本件では、商標登録出願の登録の可否が問題と なっているところ、登録商標の範囲は願書の記載により画されるものであるから(同 法27条)、登録後に、本願商標又はそれと類似する商標を使用したとしても、商標 法上の「使用」に当たらないと解したり、同法26条1項各号に該当することなど を理由として、商標権の権利範囲が制限され得ることをもって、登録時において商 標権の範囲を狭く解釈して登録の可否を検討するなどということは、商標の本質で ある自他識別機能の有無を問わずに登録を認めることにもなりかねず、相当ではな\nい。
また、本願商標の周知性については前記(3)のとおりであり、アウトソール及びウ\nェルトの色を問わず、本願商標について周知性が高いとまでいうことはできない。 不競法地裁判決は、原告商品の形状のうち、「靴の外周に沿って、アッパーとウェル トを縫合している糸がウェルトの表面に一つ一つの縫い目が比較的長い形状で露出\nし、かつ、ウェルトステッチに明るい黄色の糸が使用されており、黒色のウェルト とのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認できるという原告 商品の形態」が、令和2年時点で不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」と\nして周知であると判断したものであって(甲113)、本願商標には含まれない特徴 である「黒色のウェルトとのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭 に視認できるという形態」を含めて商品等表示に当たるものとしている。そうする\nと、仮に上記形態について商品等表示性が認められたとしても、これをもって、本\n願商標について、使用により識別力を獲得したとして、商標法3条2項に該当する と認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.08.23
令和4(行ケ)10108 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年8月10日 知的財産高等裁判所
(2) 本件周知技術の甲1発明への適用に係る動機付けについて
甲1の記載及び弁論の全趣旨によると、甲1発明は、HDRビデオにおけるトー ンマッピングの方法に関する発明であると認められる。これに対し、甲2ないし4 の記載及び弁論の全趣旨によると、本件周知技術も、HDRビデオにおけるトーン マッピングの方法に関する技術であると認められるから、甲1発明と本件周知技術 は、その属する技術分野を同一にするといえる。
また、甲1の記載及び弁論の全趣旨によると、甲1発明は、トーンマッピングさ れたビデオの各フレームの間の輝度の差を小さくし、受信画像をより自然なものに するため、トーンマッピング関数を徐々にしか変化させないものとするとの課題を 有すると認められる。これに対し、本件周知技術は、その内容に照らし、トーンマ ッピングするビデオの各フレームに適用されるトーンマッピング関数を徐々に変化 させるための技術であると認められるから、本件周知技術は、甲1発明の上記課題 を解決するための技術であるといえる。 加えて、甲3の記載によると、本件周知技術(甲3にいうトーンカーブ補正部1 42の第2の構成例に係るもの)は、甲1発明のようにあらかじめ用意されている\nルックアップテーブル(LUT)により時間的な変化が小さいトーンマッピング関 数を使用するとの構成(甲3にいうトーンカーブ補正部142の第1の構\成例に係 るもの)に代えて採用し得るものと認められる。 以上によると、本件周知技術を甲1発明に適用することについては、十分な動機\n付けがあるものと認められる。 そして、本件全証拠によっても、本件周知技術を甲1発明に適用することについ て、これを阻害する要因があるものと認めることはできないから、当業者は、甲1 発明に本件周知技術を適用することができたものと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2023.08.23
令和4(行ケ)10118 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年8月10日 知的財産高等裁判所
(1) 技術分野
ア 前記3(5)イにおいて説示したところは、甲4に記載された技術のみならず、 リモートコントローラ3(制御端末装置)が無線通信を利用して再生装置1等の制 御を行うことを内容とする引用発明(前記2)についても同様に当てはまるといえ るから、引用発明及び本件技術は、いずれも無線通信を利用して電子機器の制御を 行うとの技術に係るものであり、その属する技術分野を共通にするものと認めるの が相当である。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は、「甲1に記載された発明と甲4に記載された技術は、制御主体、 操作場所、制御対象機器及び制御内容を異にするものであるところ、甲1に記載さ れた発明及び甲4に記載された技術が共に無線通信を利用して電子機器の制御を行 うとの技術分野に属するとすることは、技術分野を極めて抽象的なレベルで捉える ものであって相当でないから、甲1に記載された発明が属する技術分野と甲4に記 載された技術が属する技術分野との間に関連性又は共通性はない」と主張する。 しかしながら、前記3(5)イにおいて説示したとおり、無線を利用して電子機器 の制御を行うとの技術においては、制御主体、操作場所、制御対象機器及び無効な ものとされる操作の内容が具体的に何であるかにつき特段の技術的意義はないとい うべきであるから、当該技術において、制御主体、操作場所、制御対象機器又は無 効なものとされる操作の内容が異なれば、当該技術が属する技術分野が異なること になるということはできない。 原告は、無線通信を利用して電子機器の制御を行うとの技術において、制御主体、 操作場所、制御対象機器又は制御内容が異なれば、当該技術に係る当業者が異なる とも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない(かえって、前記3 (2)ないし(4)のとおりの乙1ないし3の記載(特に、前記(2)エ、前記(3)ア及びイ、 乙3の段落[0080]等)によると、無線通信を利用して電子機器の制御を行う との技術においては、制御主体又は制御対象機器が異なっても、当該技術に係る当 業者を異にしないことがうかがわれる。)。
(イ) 原告は、甲1に記載された発明が属する技術分野と甲4に記載された技術 が属する技術分野の関係を検討するに当たり、甲1及び4とは別の文献である乙1 ないし3の記載を参酌するのは相当でないと主張する。 しかしながら、ある発明ないし技術が属する技術分野が何であるかを認定するに 当たり、当該発明ないし技術の意義を検討するのは当然であるところ、当該意義に 係る証拠として、当該発明ないし技術が記載された文献以外の文献の記載を参酌す るのが相当でないということはできない。
(ウ) 原告は、特許庁における担当技術分野によると、スピーカとテレビは異な る技術分野に属すると主張するが、仮に、特許庁における担当技術分野が原告主張 のとおりであったとしても、そのことをもって、引用発明及び本件技術につき、無 線通信を利用して電子機器の制御を行うとの技術に係るものとして、その属する技 術分野を共通にするとの前記判断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2023.08.23
令和4(行ケ)10115 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年8月10日 知的財産高等裁判所
(ア) 本件訂正後の記載
前記第2の3のとおり、本件訂正後の記載は、「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても70゜C)とする非アミドワックス成分(B)と、」というものである。
(イ) 本件訂正による訂正後の記載としての他の選択肢の存在
前記イ(イ)及び(ウ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の 構成にいう非アミドワックス成分(B)の中に「重量平均分子量をポリスチレン換\n算で1,000〜100,000とし軟化点を低くても70゜C)とする」との条件を 満たすポリオレフィンワックスが含まれるものと理解し、他方で、「重量平均分子 量をポリスチレン換算で1,000〜100,000とし」との条件を満たすマイ クロクリスタリンワックス等が存在しないものと理解することにより、本件訂正前 の構成にいう非アミドワックス成分(B)の中にマイクロクリスタリンワックス等\nがおよそ含まれないものと理解し得るのであるから、仮に、当該当業者において、 本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、当該当業者にとっては、本件 訂正前の記載のうちポリオレフィンワックスに係る部分を全部削除した上、マイク ロクリスタリンワックス等に係る部分について重量平均分子量に係る条件(本件記 載)のみを削除するとの選択肢(本件訂正後の記載を採用するとの選択肢)のみな らず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部 削除した上、ポリオレフィンワックス(重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満 たすもの)に係る部分のみを維持するとの選択肢(本件訂正による訂正後の記載を 「重量平均分子量をポリスチレン換算で1,000〜100,000とし軟化点を 低くても70゜C)とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分(B) と、」などとする選択肢)も存在し得るものと理解すると認めるのが相当である。 そして、上記のとおり、当該当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス\n成分(B)の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ ックスは含まれるが、マイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと 理解し得るのであるから、当該当業者において、非アミドワックス成分(B)に含 まれていた物質を維持し、およそ含まれていなかった物質を除外する趣旨の記載が 正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないものと認めるのが相当である。
(ウ) 本件訂正後の記載が正しいことが当業者にとって明らかであるといえるか 否かについて
前記(イ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の記載から マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワ ックス(重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの)に係る部分のみを維 持する趣旨の記載が正しいとも理解することができるものであって、当該当業者に おいてこのような記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるか ら、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとして も、本件訂正後の記載については、当該当業者にとって、これが本件訂正による訂 正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の 記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできないというべきで ある。
エ 原告の主張について
(ア) 原告は、1)本件訂正により構成III)’(原告主張に係るもの。以下同じ。ま た、以下、構成I)’、II)’及びIV)’についても同じ。)が削除された結果、残った 構成I)’及びII)’に係る記載には誤記がある、2)本件訂正により構成III)’が削除さ れたのであるから、構成III)’に該当する物質が存在するとしても、そのことは、構\n成I)’及びII)’に係る記載に誤記が存在することと無関係である、3)本件決定は、 構成III)’が明確であることをもって構成I)’及びII)’も明確であるとすり替えるも のであるとして、構成I)’及びII)’に係る記載には誤記があると主張する。 確かに、構成I)’及びII)’をそれぞれ他の各構成と切り離し、これらをそれぞれ\n独立したものであるとみれば、前記イ(ウ)のとおり、マイクロクリスタリンワック ス等の分子量ないし重量平均分子量(ポリスチレン換算によるもの)がいずれも1 000未満であることは周知の技術的事項であるから、本件記載を含む構成I)’及 びII)’に係る記載のみに接した当業者は、本件記載が誤りであると理解するものと 認められる。しかしながら、前記イ(エ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミ\nドワックス成分(B)に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素 添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解される のであるから、構成III)’に該当する物質(重量平均分子量及び軟化点に係る条件を 満たすポリオレフィンワックス)が存在する以上、本件訂正前の記載の全体をみれ ば、当業者にとって、これが誤りを含むことが明らかであると認めることはできな い。本件訂正前の構成を構\成I)’ないしIV)’に分け、これらの各構成に係る記載を\n一つずつ分析的に検討することを前提とする原告の上記主張は、本件訂正前の構成\nが非アミドワックス成分(B)に含まれ得る物質について「マイクロクリスタリン ワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので」 と規定し、当該物質がマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリ オレフィンワックスのうちの一部であってもよいと解されること(これらの物質の 全てについて重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たす必要はないと解される こと)を看過するものであるし、また、本件訂正が構成I)’ないしIII)’についての 訂正(構成III)’の削除並びに構成I)’及びII)’に係る本件記載の削除)を同時に含 むものであるにもかかわらず、本件訂正によって構成III)’だけが論理的に先に削除 され、その結果、本件訂正前の構成に当初から構\成III)’が含まれていなかったかの ようにみなした上、構成I)’及びII)’のみをみて、これらに係る記載が誤記を含む か否かについて検討するものであるから、失当であるといわざるを得ない。 この点に関し、原告は、本件訂正前の構成が構\成I)’に該当する物質、構成II)’ に該当する物質及び構成III)’に該当する物質のいずれもが必ず存在することを規定 するものではないと解することは特許法36条5項前段に定める特許請求の範囲の 記載要件に反すると主張する。
特許法36条5項前段は、「第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、 各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認 める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定するところ、上記のとおり、 本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分(B)に含まれ得る物質がマイクロ\nクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一 部であってもよいと解されることに照らすと、本件訂正前の構成が非アミドワック\nス成分(B)に含まれ得る物質としてマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひ まし油及びポリオレフィンワックスの三つを挙げているにもかかわらず、本件訂正 前の構成にいう重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリ\nンワックス等が存在せず、その結果、本件訂正前の構成が当該条件を満たすポリオ\nレフィンワックスについてのみ規定していることになるとしても、本件訂正前の記 載につき、特許出願人(原告)が特許を受けようとする発明を特定するために必要 と認める事項の全てを記載していないということはできない。なお、仮に、本件訂 正前の記載が同条5項前段に規定する要件を満たしていないものであったとしても、 そのことをもって、本件訂正前の構成につき、これが重量平均分子量及び軟化点に\n係る条件を満たすマイクロクリスタリンワックス、当該条件を満たす水素添加ひま し油並びに当該条件を満たすポリオレフィンワックスの全てが必ず存在すると規定 するものではないとの上記解釈を妨げるものではない。
(イ) 原告は、本件訂正前の構成には非アミドワックス成分(B)に含まれる物\n質としてマイクロクリスタリンワックス等が明示され、また、マイクロクリスタリ ンワックス等は非アミドワックス成分(B)の構成成分として必須の事項であるか\nら、当業者において非アミドワックス成分(B)にマイクロクリスタリンワックス 等が含まれないと理解するはずがないと主張する。 しかしながら、前記イ(エ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス\n成分(B)に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし 油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解され、マイクロク リスタリンワックス等が非アミドワックス成分(B)の必須の構成成分であるとい\nうことはできないから、本件訂正前の構成において、マイクロクリスタリンワック\nス等が非アミドワックス成分(B)に含まれ得る物質として明示されているとして も、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者において、非アミドワッ クス成分(B)の中にマイクロクリスタリンワックス等がおよそ含まれないものと 理解し得るとの前記認定を左右するものではない。
(ウ) 原告は、当業者は本件記載が誤記であること及びマイクロクリスタリンワ ックス等につき誤記のない正しい物質(重量平均分子量による特定のないマイクロ クリスタリンワックス等)を認識することができ、また、本件訂正前の構成はこの\n世に存在しないものをあえて含むものであるから、当業者は構成I)’及びII)’に該 当する物質が存在しないとなると、そのことに論理的な矛盾や不自然さを必ず感じ ると主張する。 確かに、前記(ア)のとおり、構成I)’及びII)’をそれぞれ他の各構成と切り離し、\nこれらをそれぞれ独立したものであるとみれば、本件記載を含む構成I)’及びII)’ に係る記載のみに接した当業者は、本件記載に誤りがあると理解することになるし、 また、前記イ(ウ)のとおりの周知の技術的事項に照らすと、重量平均分子量に係る 特定がないマイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解し得るもの である(もっとも、当該当業者において、分子量ないし重量平均分子量(ポリスチ レン換算によるもの)につき、これを「1,000未満とする」などと特定された マイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解する可能性もある。)。\nしかしながら、構成I)’及びII)’に係る記載を一つずつ分析的に検討することを前 提とする原告の主張が失当であることは、前記(ア)のとおりであるから、本件記載 を含む構成I)’及びII)’に係る記載のみに接した当業者において、本件記載が誤り であると理解するとしても、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者 において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するものと認めることはできない。 また、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとし ても、前記ウ(イ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、 本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイ クロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワック ス(重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの)に係る部分のみを維持す るとの選択肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る 記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者に おいて、ポリオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等 に係る本件記載を削除した記載(本件訂正後の記載)のみが正しいものと理解する と認めることはできない。さらに、前記イ(エ)のとおり、本件訂正前の構成にいう\n非アミドワックス成分(B)に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、 水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解さ れるのであるから、本件訂正前の構成が非アミドワックス成分(B)に含まれ得る\n物質として重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリンワ ックス等(原告が主張する「この世に存在しないもの」)を挙げているとしても、 そのことは、上記解釈に反するものではない。以上のとおりであるから、構成I)’ 及びII)’に該当する物質が存在しないことについて、当業者が必ず論理的な矛盾や 不自然さを感じるとの原告の上記主張を採用することはできない。
(エ) 原告は、マイクロクリスタリンワックス等は分子量が特定された物質であ り、誤記(本件記載)を削除した後のマイクロクリスタリンワックス等は正規の意 味のマイクロクリスタリンワックス等を表示するものであると客観的に認められる\nから、当業者(特に本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いた当業者)において、 本件記載を含む本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨(本件記載がないもの) に理解するのは当然であると主張する。 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件記載は誤 りではないかとの疑念を抱いたとしても、前記イ(エ)のとおり、本件訂正前の構成\nにいう非アミドワックス成分(B)に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワ ックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一部であってもよ いと解され、また、前記イ(イ)のとおり、当該当業者において、非アミドワックス 成分(B)の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ ックスが含まれるものと理解する以上、本件訂正前の記載の全体をみれば、当該当 業者において、本件訂正前の記載が誤りを含むものと理解すると認めることはでき ないから、当該当業者が本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いたことをもって、 当該当業者が本件訂正前の記載の全体についても、これが誤りを含むのではないか との疑念を抱いたと認めることはできない。さらに、仮に、当該当業者において、 本件訂正前の記載が誤りを含むのではないかとの疑念を抱いたとしても、前記ウ (イ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、本件訂正後 の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス タリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス(重量平 均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの)に係る部分のみを維持するとの選択 肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る記載が正し いと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者において、ポ リオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等に係る本件 記載を削除した記載(本件訂正後の記載)のみが正しいものと理解すると認めるこ とはできない。以上のとおりであるから、原告の上記主張を採用することはできな い。
この点に関し、原告は、構成I)’ないしIII)’が択一的な関係に立つものであるこ と及びマイクロクリスタリンワックス等の分子量がいずれも1000未満であると の技術常識が存在することに照らすと、本件記載を削除するとの訂正をする必要が あることは当業者にとって直ちに明らかであり、また、構成III)’ではなく構成I)’ 及びII)’を削除するとの選択肢が存在することは構成I)’及びII)’に係る本件記載 が誤りであることと無関係であるから、本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載で あることは直ちに明らかであると主張する。 しかしながら、構成I)’ないしIII)’が択一的な関係に立つとの原告の主張(これ は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分(B)に含まれ得る物質はマイ\nクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうち の全部又は一部であるとの前記イ(エ)の解釈を否定するものでないと解される。) 及び原告が指摘する技術常識を考慮しても、前記ウ(イ)のとおりの認定(本件訂正 前の記載に接した当業者において、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみな らず、これと異なる選択肢(マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削 除した上、ポリオレフィンワックス(重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満た すもの)に係る部分のみを維持するとの選択肢)も存在し得るものと理解し、当該 当業者において後者の選択肢に係る記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さ くないとの認定)を左右するものではない。そして、当該当業者において、本件訂 正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢が存在し得るものと理解する蓋然 性が小さくないのであれば、本件訂正後の記載については、当業者にとって、これ が本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請 求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであるということはでき ない。
また、原告は、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の記載の うちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィ ンワックス(重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの)に係る部分のみ を維持するとの選択肢が存在するものと理解し得るとの被告の主張は本件決定にお いて触れられていない理由に係るものであり、当該主張を本件訴訟において提出す ることは適切でないと主張する。 しかしながら、前記第2の4(1)ア(イ)bのとおり、本件決定は、本件訂正前の記 載から、構成I)’及びII)’を削除するとの訂正(本件訂正の後の記載を「重量平均 分子量をポリスチレン換算で1,000〜100,000とし軟化点を低くても7 0゜C)とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分(B)と、」と するもの)が選択肢として存在すると認めた上、これを理由に、当業者にとって、 本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載として直ちに明らかであるとまではいえな いと説示しているのであるから、原告の上記主張は、前提を誤るものとして失当で ある。
さらに、原告は、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢の内容 に関し、要するに、マイクロクリスタリンワックス等は本件訂正前の構成において\nも明示されていたのであり、誤りは本件記載にのみ存在するのであるから、削除さ れるべきであるのは本件記載のみであり、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス タリンワックス等に係る部分を全部削除するとの選択肢に係る記載は訂正後の記載 として相当でないと主張する。 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の 記載のうちマイクロクリスタリンワックス等について「重量平均分子量をポリスチ レン換算で1,000〜100,000とし」との特定をする部分が誤りであり、 これにより、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、本件訂正前の記 載からマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除し、ポリオレフィン ワックス(重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの)に係る部分のみを 維持するとの訂正によっても、上記の誤りを解消することができるのであるから、 本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除す るなどする選択肢に係る記載が訂正後の記載として相当でないということはできな い。
オ 小括
以上のとおりであるから、本件訂正前の記載が誤りで本件訂正後の記載が正しい ことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識 等から明らかで、本件訂正前の記載に接した当業者であれば、そのことに気付いて 本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨に理解するのが当然であるということ はできない。 よって、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法120条の 5第2項ただし書2号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当するとい うことはできない。 なお、原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたもので あるから、本件記載を削除する本件訂正は特許法120条の5第2項ただし書2号 に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると主張するが、仮に、原告が主 張するような事情が存在するとしても、少なくとも本件においては、そのような事 情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書2号に掲 げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると認めるには不十分である。\n
(2) 本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法120条の5第2項ただし書各号に掲げる事項(「誤記…の訂正」を除く。)のいずれかを目的 とするものに該当するか否かについて
原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたものであるか ら、本件記載を削除する本件訂正は特許法120条の5第2項ただし書各号に掲げ る事項(「誤記…の訂正」を除く。)のいずれかを目的とするものであると主張す るが、前記(1)オのとおり、少なくとも本件においては、原告が主張するような事 情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書各号に掲 げる事項(「誤記…の訂正」を除く。)のいずれかを目的とするものであると認め ることはできない。 その他、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法120条の 5第2項ただし書各号に掲げる事項(「誤記…の訂正」を除く。)のいずれかを目 的とするものに該当するとの主張立証はない。
2023.08.14
令和3(ワ)4658 損害賠償等請求事件 その他 民事訴訟 令和5年7月10日 大阪地方裁判所
(1) 独占的通常利用権者が不当利得返還請求できるかについて 原告会社は、本件育成者権の独占的通常利用権者であり、専用利用権者では ないものの、本件育成者権を独占的に利用して利益を上げることができる点に おいて専用利用権者と実質的に異なることはないから、当該利益の得喪につい ては民法703条の「利益」及び「損失」に該当する場合があると解するのが 相当である。とりわけ、本件育成者権については、再通常利用権(サブライセ ンス)の設定をすることができる(原告P1と原告会社間の設定契約において は、この点は明示されていない(甲2)が、原告らがこのように主張する以上、 別異に解する理由はない。)とされていることにも照らすと、原告会社のかか る利用権設定機会の喪失に対応する被告らの利得を観念し得る。排他的独占権 を持つ育成者権者ではなく、独占的通常利用権者であることのみをもって不当 利得返還請求が否定される理由はなく、これと異なる被告らの見解は、採用す ることができない。
もっとも、独占的通常利用権者から利用権の設定を受けた者(サブライセン シー)は、重ねて育成者権者から利用権の設定を受けることはないし、再通常 利用権の設定によって再通常利用権者が通常利用権者に支払う利用料は、通常 利用権者が育成者権者に支払うべき利用料を含んでいるのが通常であると考 えられるから、本件において原告らがそれぞれ不当利得返還請求をしているの は、結局のところ被告らが返還すべき総体としての被告らの利用料相当の利得 の原告間における分配の問題に帰着するものというべきであり、本件育成権者 である原告P1と原告会社の各不当利得返還請求権がいずれも成立するよう な場合の各請求の関係は、いわゆる「不真正連帯債権」の関係に立つものと解 される。
(2) 相当利用料率等について
本件において、本件品種の利用料率について、原告P1が5パーセントの利 用料率を主張し、原告会社がこれを超える25パーセントの利用料率を主張し ていること、原告P1が本件育成者権の権利者となっているのは、育成者であ ったP4のある種の情誼によるもの(乙20)であって、本件育成者権の対象 品種を利用しているのは専ら原告会社であり、仮に被告らが利用権の設定を受 けるとすればその相手方は原告会社となると想定されることから、原告会社が 利用許諾するとすれば想定される料率を乗じる対象及び相当利用料率を検討 する。
ア 被告製品の概要(ただし、被告種苗1が使用されたもの) 被告製品1は、50センチメートル四方のトレイにメキシコマンネングサ を4株、被告種苗1を5株植えたものであり、このトレイを建物の屋上等に 必要数を並べて配置することにより、屋上緑化の用に供されるものであり、 被告製品2は、同じトレイに被告種苗1を5株又は9株植えたものである (甲3、7、乙67)。 被告が扱う製品には、同じトレイにメキシコマンネングサのみを植えた 「てまいらず」というものもあるが、メキシコマンネングサは、冬には枯れ るのに対し、本件品種に係る種苗は常緑性である(甲1、8、乙67)。
イ 一般に、知的財産権の利用許諾において、利用料率の算定方法につき、基 準の明確性や利用権者の開示する情報の性質等から、製品の販売金額を基礎 に、所定の料率を乗じる方法が取られることが相応に存することは公知の事 実に属し、上記被告製品の性質や、本件品種に係る種苗の用いられ方等を勘 案すると、本件においてもこのような方法によって利用料率を算定すること が相当である。これと異なる被告らの主張は、採用しない。
なお、被告製品の設置には工事が必要であり、そのための外注費は被告製 品の販売金額そのものではないと解されるから、売上から同費用を除いた部 分を販売金額と把握すべきである。他方、販売金額に設置に要する物品等が 含まれる(乙67)としても、それらは被告製品を構成するものであるから、\n販売金額から控除することはしない。もっとも、利用料率の設定においてか かる事情を考慮することはできると解する。 これによると、1株当たりの被告製品の販売金額は、外注費込みの1株当 たり販売金額である862円(甲7。なお、前記のとおり、「みずいらずスー パー」(被告製品2)には、被告種苗1を5株又は9株使用されているが、甲 7においては、一律に5株として計算されており、その意味で控えめな算定 となっている。)に外注工事費を除く割合58.6パーセント(乙69)を乗 じた505円と認められる。
ウ 製品の販売金額を基礎とする相当な利用料率については、本件品種に係る 種苗の特性、販売金額を料率算定の基礎としたこと、前記アのとおりの被告 製品における本件品種に係る種苗の用いられ方(前記イのとおり、設置には 別途物品が必要である。)、種苗の育成等を含む生産工程に要する費用、自然 環境の影響による生育不良等の危険等も勘案すると、利用料率については、 これを3パーセントと推認するのが相当である。なお、原告会社はこれを2 5パーセントと主張するが、そのような取引が成立する蓋然性について的確 な立証はなく、これを採用することはできない。また、仮に原告P1が利用 権を設定するとしても、原告会社が設定するとすれば想定される上記料率を 超えることはないと考えられるから、これも採用の限りでない。もっとも、 不当利得返還請求と異なり、原告P1が種苗法34条3項の適用を求める不 法行為に基づく損害賠償請求においては、利用に対し受けるべき金銭を算定 するに当たり用いるべき利用料相当額は、令和元年法律第3号による特許法 の改正の趣旨を参酌し、これを5パーセントとするのが相当である。
(3) 原告らの具体的な損害・損失額
ア 原告P1の損害賠償請求(主位的請求)
前訴対象行為である1812株に、単価505円と相当利用料率5パーセ ントを乗じた4万5753円及びこれに弁護士費用4575円を加えた5 万0328円を、種苗法34条3項により推定される損害と認め、被告らは、 連帯してこれを賠償する義務を負う(なお、前訴対象行為に関し、被告P3 も共同不法行為者として責任を負うことについては、甲3、4、乙1及び弁 論の全趣旨によりこれを認める。)。
イ 原告らの不当利得返還請求(予備的請求)\n
前記2(2)の26万3368株からアの1812株を除いた26万155 6株に、単価505円と相当利用料率3パーセントを乗じた396万257 3円を利得と認め、これを上限として、被告会社が不真正連帯債権として原 告らの請求に応じて支払うべきものと判断する。 他方、侵害行為は被告会社として行われ、その利得も被告会社に帰属して いるのであって、代表者である被告P2に利得が帰属するとの事情は認めら\nれないから、被告P2に対する請求は理由がない。また、本件において、被 告P3は被告会社の下請けとして関与したものであるところ、原告らは、被 告会社の出荷行為に基づく利得のみを主張し、被告P3に固有の利得や、そ れと被告会社の利得との関係は何ら主張していないから、被告P3に対する 請求も理由がない。
ウ なお、本件において、原告P1は5パーセントの、原告会社は25パーセ ントの利用料率に基づく不当利得返還請求するものであるが、前記のとおり、 本件において、相当な利用料率は相対的に低廉な料率を主張する原告P1の 主張を下回るものであるから、認容されるべき返還請求権の全額について不 真正連帯債権関係に立つものと解される。
2023.08.14
令和5(行ケ)10008 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和5年6月12日 知的財産高等裁判所
◆本件意匠はこれです。
無効審決には先行意匠図面は省略されています。
興味深いのは、本件意匠は、特許からの出願変更ということです。意匠にかかる物品は「瓦」ですが、特許出願時は斜視図しかありませんが、意匠出願時は6面図を提出し、遡及効が認められています。
(ア) 基本的構成態様\n
A 正面視において、左端部に壁が設けられ右側に連続する女瓦の凹み部
から他方部に向けて上がり勾配に連続して形成された半円筒形の男瓦を
一体化し、底面図において略S字型を270度回転させた瓦形状として
いる。
B 男瓦の上側隅角部には、他の瓦を直上に重ねて瓦葺きし面一状に重ね
合わせられるよう、径を縮小した段差(縮径段差部)が形成されている。
C 女瓦の中央部近傍に左右に横切る段差が設けられている。
D Cの段差は、瓦上辺から下辺の間におよそ6対4の割合の位置で形成
されている。
(イ)具体的構成態様\n
a 男瓦の両側部と上部に、コ字状のラインを270度回転して下方開口
とした縦長の模様が形成されている。
b 男瓦に形成されたコ字状のラインの模様において、コ字状のラインの
内側線が、男瓦の外側線と略平行に形成されている。また、左右と上側の
ラインの幅は、男瓦の横幅の約6分の1である。
c コ字状のラインの模様の部分が男瓦表面の他の部分と面一である。\n
d 右上端に位置する一段低く形成された円弧部分の表面は平坦に形成さ\nれている。また、円弧部分の右側端はやや左側に傾斜し、男瓦の右側端は
やや右側に傾斜している。
e 女瓦の上端に略小矩形状の凹部が五つ形成されている。
f 女瓦の左下端が直角に形成されている。
g 裏面に上側端と、下側端と、中央部に三つの凸部が横方向に形成され
ているか否かは本件パンレット及び本件写真からは不明である。
h 右側面から見ると、男瓦の外側線のほぼ中間位置に、クランク状の段
差が形成されている。
i 女瓦の左端部の壁には、瓦のほぼ中央に斜めの段差が現わされている。
エ 本件意匠と本件模様瓦の基本的構成態様は一致しており、具体的構\成態様
のうちのc、dのうちの一部、e、g及びiを除く、「男瓦の両側部と上部
に、コ字状のラインを270度回転して下方開口とした縦長の模様が形成さ
れている。」(a)、「男瓦に形成されたコ字状のラインの模様において、
コ字状のラインの内側線が、男瓦の外側線と略平行に形成されている。また、
左右と上側のラインの幅は、男瓦の横幅の約6分の1である。」(b)、「右
上端に位置する一段低く形成された円弧部分の表面は平坦に形成されてい\nる。」(d)、「女瓦の左下端が直角に形成されている。」(f)、「右側面
から見ると、男瓦の外側線のほぼ中間位置に、クランク状の段差が形成され
ている。」(h)との部分においても、一致している。
そして、具体的構成態様dのうちの一部である、右上端に位置する一段低\nく形成された円弧部分のうち、「右側端は、男瓦の右側端と略平行に形成さ
れている。」(本件意匠の具体的構成態様d)か、「右側端はやや左側に傾\n斜し、男瓦の右側端はやや右側に傾斜している。」(本件模様瓦の具体的構\n成態様d)との点、具体的構成態様eの「女瓦の上端に波線状の凸部が一本\n形成されている。」(本件意匠の具体的構成態様e)か、「女瓦の上端に略\n小矩形状の凹部が五つ形成されている。」(本件模様瓦の具体的構成態様e)\nとの点、及び、「裏面に上側端と、下側端と、中央部に三つの凸部が横方向
に形成されている。」(本件意匠の具体的構成態様g)か、「裏面に上側端\nと、下側端と、中央部に三つの凸部が横方向に形成されているか否かは本件
パンレット及び本件写真からは不明である。」(本件模様瓦の具体的構成態\n様g)との点は、いずれも、瓦の施工後は完全に隠れてしまう部分である(甲
5)ことに加え、瓦全体からすると小さくその差異も直ちには認識し難いこ
と(各具体的構成態様d及びe)、本件意匠公報の【A−A断面図】に示さ\nれた平置き時の状況と本件写真に示された本件模様瓦の平置き時の状況に変
わりがなく、裏面の凸部自体が瓦の美観に影響を与えるものとも認め難いこ
と(具体的構成態様g)から、需要者に異なる印象をもたらすものとは認め\nられない。
また、具体的構成態様iのうち、「左側面から見ると、女瓦の左端部の壁\nは、瓦のほぼ中央に斜めクランク状に現わされている。」(本件意匠の具体
的構成態様i)か、「女瓦の左端部の壁には、瓦のほぼ中央に斜めの段差が\n現わされている。」(本件模様瓦の具体的構成態様i)との点についても、\n左側面から見た女瓦の左端部の壁は、瓦の施工後は隠れてしまう部分である
(甲5)うえに、正面から見た場合に、女瓦のほぼ中央に斜めの段差が現わ
されていることから、本件意匠と本件模様瓦とで異なる点はなく、需要者に
異なる印象をもたらすものとは認められないというべきである。
その上で、本件意匠と本件模様瓦の意匠とで最も異なるのは、具体的構成\nのcに係る部分であり、本件意匠では、「コ字状のラインの模様の部分が男
瓦表面の他の部分から僅かに段差状に隆起している。」とされているのに対\nし、本件模様瓦の意匠では、「コ字状のラインの模様の部分が男瓦表面の他\nの部分と面一である。」とされているところである。
オ 本件意匠の具体的構成態様のうち、「男瓦の両側部と上部に、コ字状のラ\nインを270度回転して下方開口とした縦長の模様が形成されている」(具
体的構成態様a)、「男瓦に形成されたコ字状のラインの模様において、コ\n字状のラインの内側線が、男瓦の外側線と略平行に形成されている。また、
左右と上側のラインの幅は、男瓦の横幅の約6分の1である」(同b)との
部分は、いずれも男瓦の全面にわたる模様であり、施工後は特に施主を中心
とした需要者にとり最も目に付くものであり、下方開口構成に係るこうした\n瓦は知られていない。
本件意匠のその余の具体的構成のうち、「右上端に位置する一段低く形成\nされた円弧部分の表面は平坦に形成されている。また、円弧部分の右側端は、\n男瓦の右側端と略平行に形成されている。」(具体的構成d)、「女瓦の上\n端に波線状の凸部が一本形成されている。」(同e)、「女瓦の左下端が直
角に形成されている。」(同f)、「裏面に上側端と、下側端と、中央部に
三つの凸部が横方向に形成されている。」(同g)との部分は、前記エのと
おり、いずれも、施工後には完全に見えなくなる部分であることに加え、瓦
全体に比して小さいか、美観に影響を与えるものとは認め難い部分であり、
需要者が特に注目する部分とはいえない。
カ そうすると、本件意匠と本件模様瓦の意匠とで最も異なる具体的構成のc\nに係る、コ字状のラインの模様の部分が男瓦表面の他の部分から僅かに段差\n状に隆起している(本件意匠)との部分については、瓦全体からみると隆起
による差異はごくわずかであり、特に瓦屋根の施工後においては、その隆起
の程度も屋根全体からみて相対的に小さいことから、コ字状のラインの模様
には需要者の注意がいくものの、その隆起の程度にまでは注意がいくものと
は認め難い。
そうすると、前記需要者の観点からみた場合、本件意匠と本件模様瓦の意
匠は類似するというべきである。
そして、前記1 で認定した事実によれば、本件模様瓦(試作品B)は、平
成28年11月頃に、被告小林瓦が原告事務所に持ち込んで提供した後、同事
務所に保管され、平成29年2月16日に原告事務所に本件パンフレット及び
本件写真が送付されたところ、本件写真及び本件パンフレットには、本件模様
瓦の意匠が開発中のものであることや開発者に対する内部的なものであること
の記載はなく、また、「秘」、「部外秘」、「非公開資料」などの記載がないば
かりか、本件写真や本件パンフレットを添付した電子メールにおいても、その
本文などに、添付された本件写真や本件パンフレットの電子データが営業秘密
であるとか内部的なものであるなどの記載もなく、原告事務所及びその従業員
について、被告らとの間で、本件模様瓦の意匠に関し守秘義務を結んでいるな
どの事実は認められないから、遅くとも、同日には原告事務所の従業員らに対
して知られるところとなり、公然知られたものと認められる。
そうすると、本件意匠は、本件意匠の出願前に公然知られた意匠と類似する
から、意匠法3条1項3号に該当し、意匠登録を受けることができないもので
あり、同法48条1項1号により無効とされるべきものである。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2023.08.13
令和4(行ケ)10035 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年7月19日 知的財産高等裁判所
◆令4(行ケ)10035号(GUZZILLA)事件まとめ
以上によれば、引用商標は周知著名であって、「ゴジラ」を欧文字表記したにとどまらない点を含め、その独創性の程度も高いというべきであ\nる。
(4) 商品の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性
ア 商品の関連性の程度
本件商標の指定商品は、第7類「パワーショベル用の破砕機・切断機・
掴み機・穿孔機等のアタッチメント」であり、土木機械の一種である動力
ショベル用の附属装置(アッタッチメント)であって、示された破砕、切
断、掴み、穿孔等の土木作業の用途によって交換される動力ショベル専
用の装置であり、土木に関する専門的・職業的な分野において使用され
る機械器具である。
これに対し、被告の主な業務は、映画の制作・配給、演劇の制作・興行、
不動産経営等のほか、キャラクター商品等の企画・制作・販売・賃貸、著
作権・商品化権・商標権その他の知的財産権の取得・使用・利用許諾その
他の管理であり(甲159)、多角化している。被告は、百社近くの企業
に対し、引用商標の使用を許諾しているところ、その対象商品は、人形や
ぬいぐるみなどの玩具、文房具、衣料品、食料品、雑貨、遊戯具等、多岐
にわたるほか、宣伝広告等にも使用を許諾している(甲12、83、85
〜102、169〜181(枝番を含む。))。
また、被告は、平成17年以降、複数の大手ゼネコンから、工事現場や
工事中の壁面に引用商標を含むゴジラの表示やロゴ等を使用することにつき許諾を求められたり、あるいは実際にその許諾をするなど、本件商\n標の指定商品である作業現場で使用される動力ショベルのアタッチメン
トと同じか、あるいはこれに近い分野である、産廃業、解体業及び建築業
等について引用商標の使用許諾を行うなどしてきた(甲195〜212、
乙1、2、6〜17(枝番を含む。))。
その中には、住宅やビルの解体を手掛ける業者において、「ゴジラvs
コング(GODZILLA vs KONG)」として、「GODZIL
LA」を「破壊神」としてタイアップCMを放送したり、クレーン車が建
築物を運搬する場面が映画「ゴジラvsコング(GODZILLA v
s KONG)」の映像とともにCMとして放送するなどの企画もあった(乙6〜9、12、13)。
被告が引用商標の使用を許諾した商品等のうち、玩具、文房具、衣料
品、食料品、雑貨等については、日常生活で、一般消費者によって使用さ
れる物であるから、性質、用途及び目的における関連性の程度は高くは
ないものの、被告は、産廃業、解体業及び建築業等の業種にも引用商標の
使用を許諾するなどしているところ、これらは、本件商標の指定商品の
取引者・需要者と同じかこれと近い分野ないし業態であり、本件商標の
指定商品と共通する取引者・需要者も一定数存するものというべきであ
る。
よって、本件商標の指定商品は、被告の業務に係る商品等と比較した場
合、性質、用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれて
いるというべきである。
イ 取引者及び需要者の共通性
本件商標の指定商品は、第7類「パワーショベル用の破砕機・切断機・
掴み機・穿孔機等のアタッチメント」であり、土木機械の一種である動力
ショベル用の附属装置(アタッチメント)であって、示された破砕、切
断、掴み、穿孔等の土木作業の用途によって交換される動力ショベル専
用の装置であり、土木に関する専門的・職業的な分野において使用され
る機械器具である。なお、土木に関する機械器具においても、レンタルが
行われているものであるから(乙33、34、41〜49)、その取引者
は、これらの器具の製造販売や小売り、レンタル等を行う者である。
また、被告が引用商標の使用を許諾した玩具、雑貨、遊戯具等について
は、その需要者は一般消費者であり、その取引者は、これらの商品の製造
販売や小売り等を行う者であるが、被告が引用商標の使用を許諾した産
廃業、解体業及び建築業等については、本件商標の指定商品の取引者・需
要者と同じかこれと近い分野ないし業態であり、本件商標の指定商品の
取引者及び需要者の中には、被告から使用許諾を受けて事業を営む者の
業務に係る商品等の取引者及び需要者と共通する者が含まれる。そして、
商品の性質、用途又は目的を考慮しても、これら共通する取引者及び需
要者は、商品の性能や品質のみを重視するとまでいうことはできず、使用許諾関係も含む商品等に付された商標に表\れる業務上の信用をも考慮して取引を行うというべきである。
(5) 出所混同のおそれ
以上のとおり、「混同を生ずるおそれ」の有無を判断するに当たっての
各事情について、取引の実情などに照らして考慮すれば、本件商標の指定
商品に含まれる専門的・職業的な分野において使用される機械器具と、被
告の業務にかかる商品等との関連性の程度が非常に高いとはいえない。
しかし、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしいものであ
って、外観においても相紛らわしい点を含むものであることから、その類
似性の程度は高く、引用商標は周知著名であって、その独創性の程度も高
い。さらに、被告の業務は多角化しており、本件商標の指定商品に含まれ
る商品の中には、被告の使用許諾に係る商品及び業務等と比較した場合、
性質、用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれる。加え
て、これらの商品の取引者及び需要者と、被告の業務に係る商品の取引者
及び需要者とは共通し、これらの取引者及び需要者は、取引の際に、商品
の性能や品質のみではなく、商品等に付された商標に表\れる業務上の信用
をも考慮して取引を行うものということができる。
そうすると、本件商標の指定商品についても、本件商標を使用したとき
に、当該商品が被告又は被告との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊
密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあ\nるものが含まれるというべきである。
よって、本件商標は、法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」
のある商標として、法46条1項の規定により無効とされるべきである。
(6) 原告の主張に対する補足的判断
ア 取消事由1(引用商標が周知著名な商標に当たるとした認定及びこれ
に基づく判断の誤り)について
原告は、本件商標の指定商品は「第7類 パワーショベル用の破砕機・
切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」であるから、その取引者及
び需要者は、土木機械の一種である動力ショベル用の附属装置(アタッ
チメント)を使用する土木関連分野の業務に従事する専門業者及び当該
機械器具の製造販売やリースを行う者であり、特殊特定分野の業務に従
事する専門業者であるところ、被告及びそのライセンシーは、引用商標
を使用して本件商標の指定商品である「第7類 パワーショベル用の破
砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」を製造販売しておら
ず、引用商標が日本国内の広範囲にわたって本件商標の指定商品を使用
する土木関連分野の業務に従事する専門業者及び当該機械器具の製造販
売やリースを行う者の間に知られるようになったということはできない
から、本件審決の判断は誤りである旨を主張する。
しかし、引用商標の周知著名性についての認定及び判断は前記(3)のと
おりであり、これが本件商標の指定商品の取引者及び需要者について変
わるところがあるものとは認められず、引用商標は周知著名であるとい
うことができる。
◆判決本文
関連事件です。
別訴
◆令和1(行ケ)10167
不競法の侵害訴訟事件
1審
◆令和1(ワ)26105
控訴審
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2023.08.10
令和2(ワ)4272等 商標権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年12月5日 大阪地方裁判所
しかも、証拠(甲4、35〜44)によれば、被告は、平成27年頃か ら、被告が独自に海外工場に製造させて輸入販売する「LEADER BIKE」が旧 リーダー社製であるかのように装うばかりでなく、「正規代理店」を称して 旧リーダー社との本件販売店契約が存続しているかのように装っていたこと が認められ、原告が製造した旧リーダー社の正規品と酷似した類似商品を旧 リーダー社や原告ないし新リーダー社の許諾なく製造し無断で被告標章を付 して販売し続けた結果、そのような情を知らない需要者において被告標章が 旧リーダー社の商品を表示するものと認識され続けているにすぎないから、到底、被告が本件商標を含む「LEADER」ブランドに関する権利が正当に帰属 すべき者であるとはいえない。
(2) また、被告は、原告が旧リーダー社の破産に乗じて本件商標権を獲得し たことを奇貨として、被告を排除して被告が確立した日本国内の「LEADER」 ブランドを独占的に使用し類似商品を販売することによって利益を得ようと する不当な目的で本件商標権を行使していると主張する。 しかしながら、前記前提事実のとおり、原告は、旧リーダー社の商品の製 造元であったのであり、本件商標権や旧リーダー社の商品のブランド力を利 用して自己の製造する商品の販売を継続するために、旧リーダー社等の破産 手続において管財人を通じて米国の裁判所の許可を受けて本件商標権等を取 得することは、何ら不当であるとはいえない。また、前記(1)のとおり、被 告は、原告が本件商標権を取得する以前から、旧リーダー社の商品ではな く、旧リーダー社に無断で被告標章を付した類似商品を販売し続けており、 証拠(甲25)によれば、原告が本件商標権の移転登録を受けた後も、第2 事件被告の取引先に対し、被告が「LEADER BIKES」製品の輸入総代理店であ ると称して通知書を送付しており、需要者をして被告の販売する被告標章を 付した商品が商標権者の許諾を受けた商品であるかのように誤認させる行動 をしているとの状況のもとでは、原告が被告に対し、本件商標権を行使する ことは、むしろ商標法の趣旨に即した正当な目的に基づくものといえる。
(3) 以上によれば、原告の被告に対する本件商標権の行使が、権利が正当に 帰属すべき者に対する不当な目的による権利行使として権利濫用に当たると はいえない。
・・・
商標法47条1項は、商標登録が同法4条1項11号の規定に違反してさ れたときは、商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後はその 商標登録についての無効審判を請求することができない旨を定めており、そ の趣旨は、同号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものである が、商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは、 商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、 商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される(最高裁平 成15年(行ヒ)第353号同17年7月11日第二小法廷判決・裁判集民 事217号317頁参照)。そして、商標法39条において準用される特許 法104条の3第1項の規定(以下「本件規定」という。)によれば、商標 権侵害訴訟において、商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認 められるときは、商標権者は相手方に対しその権利を行使することができな いとされているところ、上記のとおり商標権の設定登録の日から5年を経過 した後は商標法47条1項の規定により同法4条1項11号該当を理由とす る商標登録の無効審判を請求することができないのであるから、この無効審 判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が 商標登録の無効理由の存在を主張しても、同訴訟において商標登録が無効審 判により無効にされるべきものと認める余地はない。また、上記の期間経過 後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項11号該当を理由とし て本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると、商標権者は、商標権侵害 訴訟を提起しても、相手方からそのような抗弁を主張されることによって自 らの権利を行使することができなくなり、商標登録がされたことによる既存 の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却され ることとなる。
そうすると、商標法4条1項11号該当を理由とする商標登録の無効審判 が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後において は、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる 商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが 許されないと解するのが相当である(最高裁平成27年(受)第1876号 同29年2月28日第三小法廷判決・民集71巻2号221頁参照)。 同様に、上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において、登録商標 が同号に該当するものとして何人に対しても商標の使用の差止め等を求める ことが権利の濫用に当たり許されないものと解すると、同法47条1項の趣 旨が没却されることになるから、同法4条1項11号該当を理由とする商標 登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過し た後においては、商標権侵害訴訟の相手方が同項11号該当性に係る「他人 の登録商標」の商標権者であるなどの特段の事情がない限り、その登録商標 が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、権利濫用 に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。
◆判決本文
なお本件商標、および類似すると主張した商標は、いずれも図形商標(以下参照)です。
仮に無効抗弁が認められたとしても、類似するとの判断になったかは、また別です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.08. 9
令和4(ワ)9716 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年7月28日 東京地方裁判所
(ア) 特許法29条1項は、同項3号の「特許出願前に」「頒布された刊 行物」については特許を受けることができない旨規定する。当該規定の 「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発 明の構成が開示されているだけでなく、発明が技術的思想の創作である\nこと(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者 が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の\n技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技 術的思想が開示されていることを要するというべきである。 特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製 造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないか ら、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、 当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理\n解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊 行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に 接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、\n特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出 すことができることが必要であるというべきである。
ここで、5−ALAホスフェートは、新規の化合物であり、上記アの とおり、本件引用例には、列挙された化合物の中に5−ALAホスフェ ートが含まれているものの、本件引用例にその製造方法に関する記載は 見当たらない(乙2)。 したがって、5−ALAホスフェートを引用発明として認定するため には、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤 等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づ\nいて、5−ALAホスフェートの製造方法その他の入手方法を見出すこ とができたといえることが必要である。
(イ) 被告は、乙16文献から乙18文献の記載からすれば、本件優先日 当時、5−アミノレブリン酸単体の製造方法は周知であった上、5−ア ミノレブリン酸をリン酸溶液に溶解すれば、弱塩基と強酸の組合せとな り、5−アミノレブリン酸リン酸塩を得ることができることは技術常識 であり、このことからすれば、本件優先日当時の当業者は、5−ALA ホスフェートの製造を容易になし得た旨主張する。 確かに、上記第2の1(5)イ及びエのとおり、乙16文献及び乙18文 献には、甲13の1文献を引用しつつ、「ALA生産が確立されてい る」、「ALAの産生に成功した」、「発酵の下流では、イオン交換樹 脂を使用するALA精製プロセスも確立されて」いるなどと記載されて いる。しかしながら、甲13の1文献には、同オのとおり、「発酵液か らのALAの精製」の項において、ALAが塩基性水溶液中では非常に 不安定であり、種々の検討の結果、5−アミノレブリン酸塩酸塩結晶を 得るプロセスを確立することに成功した旨が記載されているにすぎない。 そうすると、乙16文献及び乙18文献においては、細菌を培養して発 酵液中にALA(5−アミノレブリン酸)を産生させる技術は開示され ているものの、5−アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていな いといえる。 また、上記第2の1(5)ウのとおり、乙17文献には、発酵液中に培地 成分と混合した状態で存在するALAの濃度が開示されているにすぎな い。そうすると、乙17文献においても、5−アミノレブリン酸単体を 得る技術は開示されていないといえる。 以上のとおり、乙16文献から乙18文献までにおいて、5−アミノ レブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえない。これに加え、 上記第2の1(5)アのとおり、本件引用例においても「5−ALAは・・ ・化学的にきわめて不安定な物質である」、「5−ALAHClの酸性 水溶液のみが充分に安定であると示される」と記載されていて(【00 07】)、これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認めら れることも考慮すると、本件優先日当時において、5−アミノレブリン 酸単体を得る技術が周知であったとは認められない。
この点に関し、原告は、5−アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上 で、5−ALAが物質として取り出されている必要はなく、発酵液中に 培地成分等と混合した状態であってもよい旨主張する。 しかしながら、本件優先日当時、種々の成分を含む混合液に酸又は塩 基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識 であったとは認められないことからすれば、本件引用例に接した本件優 先日当時の当業者が、化合物である5−アミノレブリン酸リン酸塩を製 造する方法として、培地成分等と混合した状態で5−アミノレブリン酸 が存在する発酵液にリン酸を添加する方法(又はこの発酵液をリン酸溶 液に添加する方法)を、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮することな\nく見出すことができたとはいえない。 また、上記第2の1(5)ウのとおり、乙17文献において、培地に酵母 抽出物やトリプトン等が含まれることが記載されていることからも明ら かなように、培地成分等と混合した状態にある発酵液には種々のイオン が夾雑物として含まれているのであるから、このような発酵液にリン酸 を添加したとしても、等しい物質量の酸及び塩基の中和反応によって5 −アミノレブリン酸リン酸塩という化合物が製造されたと評価すること はできないというべきである。したがって、原告の上記各主張はいずれも採用することができない。そして、このほか、本件優先日当時の当業者が、5−ALAホスフェー トの製造方法その他の入手方法を見出すことができたというべき事情は 存しない。
(ウ) 以上によれば、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思 考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技\n術常識に基づいて、5−ALAホスフェートの製造方法その他の入手方 法を見出すことができたとはいえない。したがって、本件引用例から5−ALAホスフェートを引用発明として認定することはできない。
◆判決本文
本件特許についての審決取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.08. 3
令和4(ワ)2049 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年7月6日 東京地方裁判所
(ウ) 小括
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件発明 1 の「底部」 は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、「容器」として機能\nする筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでい\nる部分を指すものと理解される。また、「底面片」は、このような「底部」を形成す るものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下 側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。さらに、「自立片」は、このような「底 面片」と同一面に連なるものであり、かつ、載置面に沿って前記奥行の方向に突出 し、包装容器を前記載置面に自立させる機能を有するものということになる。\n
イ 被告製品の構成要件充足性\n
(ア) 被告製品においては、背面片が片(A)側に折られて筒状に形成される(構成 e1、e’-1)。その際、背面片の下端に連ねられた六角片(構成 d-3、d’-3)は、筒状部 分下端から内側に折り込まれ、この折り込まれた六角片は、筒状部分内部に収めら れる内容物の下部に位置し、筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止してい る(構成 e-2、e’-2)。このため、被告製品の六角片は、本件発明 1 の「底部を形成 する底面片」に相当するものといえる。
(イ) 被告製品の舌状片は、片(A)の下端に連ねられた部材であり(構成 d-4、d’-4)、 筒状部分の下端(六角片の接続箇所の反対側)から内側に折り込まれ(構成 e-3、e’- 3)、容器として形成した状態において、六角片と共に、略弧状に湾曲した状態とな り、片(A)に連なって、載置面に沿って背面側に突出し、載置面に置くと、舌状片に よって、被告製品は、載置面に背面方向に斜めに自立する(同 b、b’)。このため、 被告製品の舌状片は、本件発明 1 の「自立片」に相当するものといえる。 他方、筒状部分の下端から内側に折り込まれた六角片と舌状片とは接触しておら ず、両者の間には隙間がある(同 e-4、e’-4)。このことと、被告製品の筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止する機能を果たしているのは六角片であることを\n併せ考えると、舌状片は、筒状部分の下側を塞いでいるとはいえず、「底部を形成す る底面片」に相当するものとはいえない。
(ウ) 六角片と舌状片とは、六角片は背面片の下端に連ねられているのに対し、舌 状片は片(A)の下端に連ねられており、同一面に連なるものとはいえない。 したがって、被告製品は、「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片」(構\n成要件 B)を充足しないから、本件発明 1 の技術的範囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.07.31
令和4(行ケ)10111 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年7月25日 知的財産高等裁判所
審判では、被請求人(特許権者)は、「ほぼ水平に延びる段差部(13c)はモールをアウタパネルの上縁部に組み込む際に引掛けフランジ部(13)とモール本体部(11)との間隔(挟持力)を維持するのに重要となります。」と主張して、先行技術から容易ではないと判断されていました。
ア 相違点1
(ア) 相違点1は、「縦フランジ部の下部から内側方向に延びる段差部」が、本件発 明1においては、縦フランジ部の下部から内側方向に「ほぼ水平に」延びる段差部 であるのに対して、甲1発明1においては、縦フランジ部の下部から昇降窓ガラス 側方向に「やや下方に」延びる段差部であるというものである。甲1発明1のモー ルディングが取り付けられるドアパネルが、アウタパネルであることについては当 事者間に争いがなく、甲1発明1の「昇降窓ガラス側方向」は、本件発明1の「内 側方向」(車内側を指す。)と同じ方向を意味するものと認められるから、相違点1 においては、段差部が「ほぼ水平」に延びるか「やや下方」に延びるかという点の みが問題となる。
(イ) そこで検討するに、本件明細書には、段差部が縦フランジ部の下部から内側 方向に「ほぼ水平に」延びることの技術的意義についての記載はない。また、前記 1(2)のとおり、本件発明は、端末の剛性に優れるベルトラインモールを提供するた めに、ドアフレームの表面に位置する部分は縦フランジ部を残して、水切りリップ\nや引掛けフランジ部を切除できるようにし、モール本体部と縦フランジ部とで略C 断面形状を形成しつつ断面剛性を確保したというものであり、ベルトラインモール の端末では、ドアフレームの表面に位置する部分は縦フランジ部を残して切除され\nるものであって、段差部も切除されるのであるから、段差部が「ほぼ水平に」に延 びても「やや下方」に延びても、本件発明の作用効果に何ら影響するものではない。 そうすると、段差部が「ほぼ水平に」延びるものとすることについて何らかの技術 的意義があるとは認められない。 そして、甲1発明1においても、段差部が縦フランジ部の下部から昇降窓ガラス 側方向(内側方向)に「やや下方に」延びることに何らかの技術的意義があるとは 認められず、甲1発明1において「やや下方に」延びる段差部を「ほぼ水平に」延 びるように構成することは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎないというべ\nきである。 そうすると、甲2記載事項について検討するまでもなく、甲1発明1において段 差部に設計的変更を加え、これを「ほぼ水平に」することは、当業者が容易に想到 できたものと認めるのが相当である。
(ウ) したがって、本件審決には、相違点1に係る容易想到性の判断に誤りがある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2023.07.26
令和5(行ケ)10005 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年7月12日 知的財産高等裁判所
(3) 本願商標の中段の緑色の図形部分は、別紙1記載のとおり、頂点から左右 斜め下方向に同じ長さの二本の直線が二等辺三角形状に伸びるという欧文字 「A」の形状の特徴を備えており、両隣の「K」及び「ZE」の欧文字と、 同じような大きさ、同じような間隔で一連に表されていることからも、「A」\nの文字をデザイン化したものと認識されるから、本願商標に接した取引者、 需要者は、中段の構成部分は、全体として「KAZE」の欧文字を表\したも のと認識するといえる。
しかるところ、我が国においては、欧文字表記をローマ字読み又は英語風\nの読みで称呼するのが一般的であり、「KAZE」の欧文字は、既成の親しま れた英単語でもなく、ローマ字読みで容易に称呼できるものであり、「カゼ」 と読むのが最も自然というべきであるから、当該文字部分からは、「カゼ」の 称呼が生じる。そして、日本語において「カゼ」と称呼する成語から「空気 の流れ」を意味する「風」又は「感冒」を意味する「風邪」(広辞苑 第七版) が一般に想起されるから、「KAZE」の欧文字からは「風(空気の流れ)」 及び「風邪(感冒)」の観念が生じるものというべきである。 加えて、本願商標の構成態様においては、「KAZE」の欧文字部分は、他\nの構成文字に比して大きく顕著に表\され、平行線の間に配されることにより、 視覚的に際立った印象を与えるものであるから、看者の目をひく部分であり、 取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え るものと認められる。 そうすると、本願商標から「KAZE」の欧文字部分を要部として抽出し、 これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することは許される というべきである。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(4) これに対し、原告は、1)本願商標の中段部分の「緑色の麻葉文様図形」は、 格別特異な態様で書されており、また、当該図形が欧文字「A」をデザイン 化したものと容易に看取されることはなく、本願商標の中段部分の表示から\n「KAZE」なる欧文字をそもそも認識することはできない、2)仮に本願商 標の中段部分の表示から「KAZE」なる欧文字を認識することはできると\nしても、本願商標の上段部分の「−PRINTABLE HEMP WEA R−」なる表示は、本願の指定商品「被服」との関係において、原告のブラ\nンドである「PRINTABLE HEMP WEAR」シリーズの商品で あることを認識させるものであって、強い識別機能を有し、また、本願商標\nの構成中、最も強く支配的な印象を与える部分は、中段部分のうちの「緑色\nの麻葉文様図形」であることからすると、「KAZE」なる欧文字(中段部分) が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与 えるものとはいえないとして、本願商標から「KAZE」を要部として抽出 することはできない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記(3)で説示したとおり、本願商標の中段 の緑色の図形部分は「A」の文字をデザイン化したものと認識されるから、 取引者、需要者は、中段の構成部分を全体として「KAZE」の欧文字を表\ したものと認識するといえる。
2)については、「−PRINTABLE HEMP WEAR−」の構成部\n分は、別紙1記載のとおり、外観上、上下2本の平行線の間に配された「K AZE」の欧文字部分よりも小さく表示されており、取引者、需要者に与え\nる印象は、「KAZE」の欧文字部分よりも強いとはいえない。 また、本願の指定商品「被服」の需要者である一般消費者において、上記 構成部分が原告のブランドである「PRINTABLE HEMP WEA R」を示すものとして広く認識されていることを認めるに足りる証拠はない し、仮にこれが認められるとしても、本願商標の構成態様に照らすと、「KA\nZE」の欧文字部分が取引者、需要者に対して商品の出所識別機能として強\nく支配的な印象を与えるとの上記認定を左右するものではない。 さらに、「KAZE」の欧文字中の「A」の文字をデザイン化した部分のみ が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということもできない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.07.20
令和4(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
(イ) また、甲7、9、52、61、63、71及び73並びに乙7によると、 薬物の安定性を高める方法として、結晶の結晶化度を高めること、遮光、湿気の遮 断等を目的として薬剤に保護コーティングを形成すること、遮光を目的として遮光 剤(酸化チタン)を含むコート液をコーティングすることなどは、本件優先日当時 の周知技術であったと認められる。
(ウ) しかしながら、甲5、7、52、54及び61によると、本件優先日当時、 非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識が存在し、そのため、水難溶 性の薬物の溶解性を改善するとの目的で、かえって結晶化度を低くすることが一般 に行われていたものと認められるところ、前記(ア)及び(イ)のとおり、本件優先日当 時、経口投与される水難溶性の薬物の溶解性を高めるための周知技術として、結晶 の粒子径を小さくすること以外の方法も存在し、また、薬物の安定性を高めるため の周知技術として、結晶の結晶化度を高めること以外の方法も存在していたのであ るから、化合物1の溶解性及び安定性を高めるとの課題を認識していた本件優先日 当時の当業者において、化合物1の溶解性を追求するとの観点から、経口投与され る水難溶性の薬物の溶解性を高めるための周知技術(結晶の粒子径を小さくすると の周知技術)を採用し、かつ、化合物1の安定性を追求するとの観点から、薬物の 溶解性を低下させる結果となり得る周知技術(結晶の結晶化度を大きくするとの周 知技術)をあえて採用することが容易に想到し得たことであったと認めることはで きない。
(エ) この点に関し、原告らは、結晶の結晶化度を一定の数値以上に維持するこ とは特段の処理が不要で薬剤をそのまま使用するという最も基本的な態様を含むも のであり、他の手段よりはるかに容易な態様のものであると主張する。しかしなが ら、前記(ア)のとおり、本件優先日当時、結晶の粒子径を小さくするための主たる 手段として、ハンマーミル、ボールミル、ジェットミル等を利用した粉砕が考えら れていたところ、甲52によると、粉砕により結晶の結晶化度が低下し、結晶が非 晶質化することは、よく経験される事象であったものと認められるから、結晶の結 晶化度を一定の数値以上に維持することが特段の処理を要しないものであるという ことはできず、原告らの上記主張は、前提を誤るものというべきである。
また、原告らは、本件優先日の当業者であれば、薬物の安定性を向上させるとの 課題に基づいて結晶の結晶化度を一定の数値以上に維持することを検討しつつ、粒 子の微細化等の手段により溶解度を向上させるなど、結晶の結晶化度や平均粒径と いったパラメータを適宜調整することを十分に動機付けられると主張するが、上記\nのとおり、非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識が存在したことを 考慮すると、原告らの上記主張によっても、本件優先日当時の当業者において、相 反する効果を生ずる事項同士であると認識されていた、化合物1の結晶の平均粒径 を小さくし、かつ、その結晶化度を大きくすることが容易に想到し得たことであっ たと認めることはできないといわざるを得ない(この点に関し、本件明細書には、 実施例(試験例2、実施例2)として、化合物1の微細結晶Aの結晶化度が84. 6%であり、粒径がD100=8.7μmである場合(後記5(4)ア(ア)のとおり、化 合物1の平均粒径が数μmである場合)においても、結晶が凝集することなく、良 好な溶解性及び分散性を示したとの記載があるが、前記(2)イ(ウ)において認定した 技術常識(非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識)並びに甲6及び 52によって認められる技術常識(特に薬物が疎水性のものである場合には、結晶 の粒子径を小さくすればするほど凝集が起こやすくなり、その有効表面積がかえっ\nて小さくなる結果、溶解性が低下することがあるとの技術常識)に照らすと、上記 実施例が示す効果は、甲1結晶発明及び本件優先日当時の技術常識から予測し得な\nかったものといえる。)。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 特段の効果
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2023.07.20
令和4(行ケ)10081 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
前記(2)アによると、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件各発明について、 次のとおりの記載がされているということができる。すなわち、本件各発明は、繊 維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト(以下、単に「シャフト」ということがあ る。)に関するものである。ゴルフのスコアを良くするためには、打球の飛距離の 安定性及び左右への方向安定性を得ることが非常に重要であり、そのためには、三 つの要素(ボールの初速、打ち出し角度及びスピン量)のばらつきを減少させてこ れらを安定させる必要があるところ、ボールを打撃する瞬間のシャフトの変形(特 にシャフトの細径部の変形)がこれらの要素の安定性に大きな影響を及ぼすため、 シャフトの細径部のねじり剛性を上げることによりこれらの要素を安定させ得るこ とが従来から知られていた。しかしながら、単にシャフトの細径部のねじり剛性を 上げると、フィーリングが硬くなったり、ヘッドの返りが極端に悪くなったり、ヘ ッドのトゥダウンが抑制されすぎて飛距離が小さくなったりするなどのデメリット が生じるほか、弾性率の高い炭素繊維の使用量を多くしすぎることによるシャフト の強度の低下を招き、シャフトの折損が生じやすくなるという問題があった。本件 各発明は、このような問題を解決し、特にねじり剛性が高いシャフトにおいても、 スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されること なく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたシャフト(ねじり剛性の高いシャ フト(ロートルクのシャフト))を提供することを目的とするものである。本件各 発明は、前記第2の2のとおりの構成とすることにより、プレーヤーの力量に左右\nされることなく、飛距離の安定性及び左右へのばらつきの少ない方向安定性の双方 に優れたシャフトが得られるとの効果を奏する。
以上によると、本件各発明の課題は、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴル フクラブ用シャフト(ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト)で あって、スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右さ れることなく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたものを提供すること」 (以下「本件課題」という。)であると認めるのが相当である。
(4) 決定取消事由の1(構成2ないし5に係るもの)について\n
ア 構成2について\n
(ア) Tq≦4.0°について
a シャフトのトルク(Tq)を4.0°以下とすることにより得られる効果等 に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「トルク(Tq)を4.0°以下と することによって、ゴルファーの力量が飛距離の安定性や左右への方向安定性に与 える影響を低減させることができ、これらの両立を達成できる傾向にある。」との 記載(【0021】)があり、また、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴルフ クラブ用シャフト(ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト)であ って、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されることなく飛距離の安定性 と方向安定性の双方に優れたものが得られる」との効果(以下「本件効果」とい う。)が得られたとされる実施例1及び本件効果が得られなかったとされる比較例 1の各トルク(°)がそれぞれ2.4及び4.8であるとの記載(【表4】)があ\nる。しかしながら、これらの記載は、シャフトのトルクを4.0°以下とすること によりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、し たがって、構成2のうちシャフトのトルクを4.0°以下とするとの点については、\n本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を 解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
b 原告は、低トルクのシャフト(ねじり剛性が高いシャフト)が飛距離の安定 性及び方向安定性において優れていることは本件出願日当時の技術常識であり、本 件出願日当時の当業者は実施例1と比較例1との比較から、シャフトのトルクを4. 0°以下とすることにより飛距離の安定性及び方向安定性(比較例1よりも優れた 飛距離の安定性及び方向安定性)が得られるものと理解し得ると主張する。しかし ながら、原告の上記主張並びに原告が上記技術常識に係る証拠として提出する甲1 2及び21ないし23は、シャフトのトルクを4.0°以下とすることによりなぜ 本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、シャ フトのトルクを4.0°以下とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願 日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成2のうちシャフトのトル\nクを4.0°以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の 技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということ はできない。
c なお、原告は、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明であって、発\n明の実施方法や作用機序等を理解することが比較的困難な技術分野(薬学、化学等) に属する発明ではないとして、構成2の境界値の厳密な根拠が本件明細書に記載さ\nれている必要はないと主張するが、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明\nであることをもって、シャフトのトルクを4.0°以下とすることにより本件課題 が解決される理由を本件明細書の発明の詳細な説明において適切に説明する必要が ないということはできないから、原告の上記主張を採用することはできない(この 点については、以下の構成2のうちシャフトのトルクを1.6°以上とするとの点\n及び構成3ないし5についても同じである。)。\n
・・・
b 原告は、本件各発明は細径部のトルクを小さくすることが飛距離の安定性及 び方向安定性を高めるとした甲6発明の効果を前提としつつ、更に非熟練ゴルファ ーにとってのデメリット(フィーリングが硬くなったりヘッドの返り(トゥダウン) が悪くなったりすること)を克服するとの課題を解決するものであり、加えて、本 件各発明におけるA/Bに係る0.05以上0.12以下との数値範囲が実施例1 におけるA/B(0.08)をほぼ中央値とするものであることも併せ考慮すると、 本件出願日当時の当業者は細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の5% 以上とすることで、上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方向安定 性を高め得るものと理解し得ると主張する。しかしながら、甲6によっても、本件 出願日当時の当業者において、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の 5%以上とすることにより上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方 向安定性を高め得るものと理解し得たとの事実を認めることはできず、その他、そ のような事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件各発明におけるA/ Bに係る0.05以上0.12以下との数値範囲が実施例1におけるA/B(0. 08)をほぼ中央値とするものであることを考慮しても、原告の上記主張は、細径 側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の5%以上とすることによりなぜ本件 課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、細径側バ イアス層の重量をバイアス層の合計重量の5%以上とすることにより本件課題が解 決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成4\nのうち細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の5%以上とするとの点に ついては、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決 できると認識できる範囲のものであるということはできない。
オ 原告のその余の主張(決定取消事由の1(構成2ないし5に係るもの)に関\n連するもの)について
(ア) 原告は、低トルクのシャフト(ねじり剛性が高いシャフト)が飛距離の安 定性及び方向安定性において優れているとの技術常識並びにバイアス層を増やすこ とにより低トルクのシャフトが得られるとの技術常識を有する本件出願日当時の当 業者が本件明細書を読めば、実施例1及び比較例1における各トルクから、トルク を比較例1のそれよりも有意に小さい4.0°以下とし、実施例1及び比較例1に おける各バイアス層の割合(B/(B+S))から、バイアス層の割合(B/(B +S))を比較例1のそれよりも有意に大きい0.5以上とすることにより、比較 例1よりも良好な飛距離の安定性及び方向安定性が得られるであろうことを当然に 理解し得ると主張する。しかしながら、実施例1及び比較例1の記載から、本件出 願日当時の当業者において、トルクを比較例1のそれ(4.8°)よりも有意に小 さい角度とすること及びバイアス層の割合(B/(B+S))を比較例1のそれ (0.4)よりも有意に大きい値とすることにより、比較例1よりも良好な飛距離 の安定性及び方向安定性を示すであろうと推測し得るとしても、当該当業者におい て、トルクを具体的に(1.6°以上)4.0°以下とすること及びバイアス層の 割合(B/(B+S))を具体的に0.5以上(0.8以下)とすることにより、 本件課題を解決できると認識できるとは認められない。
(イ) 原告は、本件出願日当時の当業者は本件明細書の記載により、本件各発明 の構成要件を充足し、その他の条件につき当該当業者が技術常識の範囲内で決定し\nたシャフトであれば、その飛距離及び方向が比較例1のシャフトにおける飛距離及 び方向と比較してより安定したものとなることを容易に理解し得ると主張する。し かしながら、前記アないしエにおいて説示したところに照らすと、仮に本件各発明 の課題が飛距離及び方向において比較例1のシャフトよりも安定したシャフトを得 ることであるとしても、実施例1及び比較例1を含む本件明細書の発明の詳細な説 明の記載により、本件出願日当時の当業者において、本件各発明の構成要件を充足\nするシャフトであれば当該課題を解決できると認識できると認めることはできない というべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 数値限定
>> パラメータ発明
>> ピックアップ対象
2023.07.14
令和5(行ケ)10010 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年7月6日 知的財産高等裁判所
以上のとおり、本願商標の構成中の「リフナビ」の文字部分は、役務の出所識別\n標識として強く支配的な印象を与えるものであると認められる一方、本願商標の構\n成中の「大阪」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念が生じない から、本願商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取\n引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 したがって、本願商標については、その構成中の「リフナビ」の文字部分を抽出し、\n当該文字部分だけを他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるとい うべきであり、本願商標の要部は、「リフナビ」の文字部分であると認めるのが相 当である。
・・・
また、引用商標の上側先頭左側部分が原告主張に係るピンマーク(甲25)のよ うな形状(白抜きの円を内包した水滴状の形状)に図案化されたものであり、上側 先頭右側部分が文字(これが文字の全部(片仮名の「ノ」)であると認識されるか、 一部(片仮名の「ソ」又は「リ」の各右側部分)であると認識されるかについては、\n当事者間に争いがある。)を構成する部分であると認識されることも、当事者間に\n争いがない。
そこで、引用商標の上側先頭左側部分が文字(片仮名の「ソ」又は「リ」)を構\ 成する部分であると認識されるか否かにつき検討するに、1)証拠(乙8、24ない し48)及び弁論の全趣旨によると、商取引においては、文字の全部又は一部を図 案化して表示することが広く行われ、その中でも、片仮名の「リ」又は平仮名の\n「り」の各左側部分が図案化されている例や引用商標の上側先頭左側部分に類似す る形状の図形(原告主張に係るピンマークのような形状の図形)が文字の全部又は 一部として使用されている例が多数存在するものと認められること、2)引用商標の 上側先頭部分が一つの文字を表しているものと認識すると、上側部分において、片\n仮名の「ソ」(原告主張に係るもの)又は「リ」(被告主張に係るもの)、「フ」、\n「ナ」及び「ビ」の4文字が同じような高さ及び幅をもって均等に配置されている ように見え、自然であるのに対し、上側先頭左側部分が文字の一部でなく、上側先 頭右側部分のみが文字(片仮名の「ノ」)を表しているものと認識すると、上側先\n頭左側部分と上側先頭右側部分とが接近しているため、上側その余の部分のうち上 側先頭右側部分のみが縦長(細幅)で窮屈に配置されているように見え、上側その 余の部分において、片仮名の「ノ」、「フ」、「ナ」及び「ビ」の4文字の配置が 全体として不自然に見えることからすると、引用商標の上側部分については、上側 先頭右側部分と原告主張に係るピンマークのように図案化された上側先頭左側部分 とが一つの文字を構成し、「フナビ」の文字部分と併せ、全体として4つの文字か\nらなるものと認識されると認めるのが相当である。 そして、引用商標の上側先頭左側部分は、そのうちのとがった部分が略鉛直方向 を向き、真上から真下に向かって縦に下ろしたように配されており、片仮名の「ソ」\nの文字の左側部分(通常は左上方向から右下方向に配されるもの)ではなく、片仮 名の「リ」の文字の左側部分に近い形状をしていると認められることからすると、 大学でノートを取る観点から片仮名の「ソ」と「リ」を形がよく似た字の例として\n挙げるウェブサイト(甲34)及び校正の観点から片仮名の「ソ」と「リ」を字形\nの似た文字の例として挙げるウェブサイト(甲35)が存在することを考慮しても、 引用商標の上側先頭部分は、片仮名の「リ」の文字を表すものと認識されると認め\nるのが相当である。したがって、引用商標の上側部分は、「リフナビ」の文字を表\nすものと認識されるところ、当該部分は、引用商標において出所識別標識としての 機能を強く発揮するものと認められるから、前記(2)にも照らすと、引用商標の要 部は、「リフナビ」の文字部分であるといえる。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は、1)文字の一部を図案化して表すことが商取引の実際において行わ\nれているとの事実は、一般的に知られているものではない、2)文字の一部の図案化 が行われていることと図案化された部分が実際に文字の一部であると認識できるこ ととは、次元を異にする問題である、3)文字の一部を図案化したものであることが 分かるのは、当該部分を含む部分の読み方をあらかじめ知っているか、又は前後の 文字を基にした推測が可能であるからであるところ、引用商標においてはそのよう\nにいうことはできないとして、引用商標の上側部分につき、全体として文字を表し\nたものと認識されるとみるのが自然であるとはいえないと主張する。
しかしながら、上記1)については、前記ア(1))において挙示した証拠及び弁論 の全趣旨によると、文字の一部を図案化して表すことが商取引において広く行われ\nているなどの事実は、一般的によく知られているものと優に認めることができる。 また、上記2)及び3)についても、前記アにおいて説示したところに照らすと、具体 的な商標である引用商標の上側部分について、これに接した取引者、需用者は、そ の読み方をあらかじめ知らなくても、これが「リフナビ」の文字を表すものと認識\nすると認めるのが相当である(なお、この点は、引用商標において図案化された部 分(上側先頭左側部分)が文字部分(上側部分)の途中(文字と文字の間)ではな く先頭に配置されていること(当該図案化された部分の前後双方の文字による推測 が働かないこと)により、結論が左右されるものではない。)。 (イ) 原告は、ピンマークは記号として取引者、需用者に広く認識されているご く一般的なものであり、需用者が一見すれば、地図上の位置を示す記号であると認 識できるものであるから、取引者、需用者において、引用商標の上側先頭左側部分 を文字の一部と認識するのは極めて例外的な場合であると主張する。 確かに、前記アのとおり、引用商標の上側先頭左側部分は、原告主張に係るピン マークのような形状に図案化されたものであるが、当該部分は、地図上に描かれた ものではないし、また、前記アにおいて説示したところにも照らすと、引用商標に 接した取引者、需用者が上側先頭左側部分を文字の一部を図案化したものであると 認識するのは普通のことであるといえ、そのように認識するのが極めて例外的な場 合に限られると認めることはできない。 また、原告は、引用商標の上側先頭左側部分(ピンマーク)は線でない形状のも のであるから、上側先頭部分が一つの文字を表すものであるとすると、当該文字は\n線ですらない形状の部分を含むことになるとも主張するが、上記説示したとおり、 引用商標に接した取引者、需用者は、上側先頭左側部分につき、これが文字の一部 を図案化したものであると普通に認識するといえるから、上側先頭左側部分が原告 主張に係るピンマークのような形状に図案化されていることをもって、上側先頭部 分が線ですらない部分を含むことになるということはできない。
(ウ) 原告は、引用商標の上側先頭左側部分の色は上側その余の部分の色よりも 薄くなっており、引用商標に接した需用者は上側先頭左側部分と上側その余の部分 とが別々の構成のものであるとして両者を分離し、上側その余の部分だけが文字を\n表すものと認識するのであり、そのことは引用商標の実際の使用形態によっても裏\n付けられていると主張する。 しかしながら、引用商標を子細に観察しても、上側先頭左側部分の色は、上側そ の余の部分の色と比較して、ほぼ同じ濃さであるか(乙2)、かすかに薄い(甲1 2)としか見て取ることはできず、迅速を尊ぶ商取引において、引用商標に接した 取引者、需用者が上側先頭左側部分と上側その余の部分とを別々の構成のものであ\nるとしてこれらを分離し、上側その余の部分だけが文字を表すものと認識するほど\nに両者の色の濃さに有意な相違があるということはできない。なお、原告は、甲2 6に見られる引用商標の実際の使用形態(上側先頭左側部分及び下側部分並びに上 側部分の右肩に付された「○R 」のマークが緑色で表され、上側その余の部分が黒色\nで表されたもの)も上記主張を裏付けると主張するが、登録商標の範囲は、願書に\n記載した商標に基づいて定めなければならないところ(商標法27条1項)、願書 に記載された引用商標(甲12、乙2)においては、甲26に見られる色分けはさ れていないのであるから、引用商標の実際の使用の場面において当該色分けがされ ていることを根拠に、引用商標に接した取引者、需用者が上側先頭左側部分と上側 その余の部分とを別々の構成のものであるとしてこれらを分離し、上側その余の部\n分だけが文字を表すものと認識すると認めることはできない。\n
(エ) 原告は、引用商標の上側先頭右側部分とほとんど同じ角度及び長さで表記\nされたものが片仮名の「ノ」の文字を示すと認識させる登録商標(甲27)が存在 すると主張する。 しかしながら、原告が主張する事実は、本件における引用商標の上側先頭右側部 分がどのように認識されるかについての判断を左右するものではない。なお、甲2 7に記載された登録商標のうち仮名文字部分の最右端の部分(商標公報に記載され た称呼によると「ノ」と読まれる部分)と引用商標の上側先頭右側部分とを比較し ても、両者がほとんど同じ角度及び長さで表記されていると見て取ることはできな\nい。
(オ) 原告は、1)片仮名の「ソ」の文字は、片仮名の「リ」の文字と似ていると\n認識されていること、2)引用商標の指定役務の中に第35類「電子計算機・タイプ ライター又はこれらに準ずる事務用機器の操作」があること、3)「ソフ」で始まる\n語が多数存在し、これらは、「リフレーション」、「リフレーン」等よりも一般的 な語であることを根拠に、仮に引用商標の上側先頭左側部分が文字の一部を表すも\nのと認識されるとしても、引用商標を見た需用者は、その上側部分から「ソフトウ\nェア」と「ナビゲーション」の略語である「ソフナビ」の語を想起するとみるのが\n自然であると主張する。
しかしながら、上記1)については、前記アのとおり、引用商標の上側先頭左側部 分は、そのうちのとがった部分が略鉛直方向を向き、真上から真下に向かって縦に 下ろしたように配されており、片仮名の「ソ」の文字の左側部分(通常は左上方向\nから右下方向に配されるもの)ではなく、片仮名の「リ」の文字の左側部分に近い 形状をしていると認められることに照らして、当該主張が引用商標に該当するとは いえない。また、上記2)については、引用商標の指定役務には、「ソフトウェア」\nの語とは余り親和性がないと認められる役務(「リラクゼーションマッサージ」等) も含まれており、引用商標の上側部分のうち先頭の2文字を見た取引者、需用者が 普通に「ソフトウェア」の略語としての「ソ\フ」の語を想起すると認めることはで きない。さらに、上記3)についても、確かに、証拠(甲36)及び弁論の全趣旨に よると、「ソフ」で始まる語(「ソ\フトウェア」、「ソフトカバー」等)が複数存\n在することは認められるが、前記アにおいて説示したところに照らすと、これらの 語が存在することをもって、引用商標の上側部分のうち先頭の2文字を見た取引者、 需用者が普通に「ソフトウェア」の略語としての「ソ\フ」の語を想起すると認める ことはできない。そうすると、大学でノートを取る観点から片仮名の「ソ」と「リ」\nを形がよく似た字の例として挙げるウェブサイト(甲34)及び校正の観点から片 仮名の「ソ」と「リ」を字形の似た文字の例として挙げるウェブサイト(甲35)\nが存在するとしても、引用商標を見た取引者、需用者において、その上側部分から 「ソフトウェア」と「ナビゲーション」の略語である「ソ\フナビ」の語を想起する とみるのが自然であると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.07.13
令和4(行ケ)10099 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年7月6日 知的財産高等裁判所
イ 前記(1)イの相違点に係る構成を甲1発明において採用することが容易想到といえるか検討するに、甲1には、加工対象物の反りや、X、Y軸ステージの振動等\nにより、レーザ光の焦点ずれが生じ得ることについての記載はなく、加えて、前記 2(1)エのとおり、甲1(105頁)には「図98に示すクラック領域9は、パルス レーザ光Lの集光点を加工対象物1の厚み方向において厚みの半分の位置より表面(入射面)3に近い位置に調節して形成されたものである。クラック領域9は加工\n対象物1の内部中の表面3側に形成される。」「パルスレーザ光Lの集光点を加工対象物1の厚み方向において厚みの半分の位置より表\面3に遠い位置に調節してクラック領域9を形成することもできる。」といった記載があり、甲1発明においては、 シリコンウエハ内部の改質領域の位置は、シリコンウエハの厚み方向において厚み の半分の位置よりも表面に近い位置から、同半分の位置よりも表\面に遠い位置まで の、ある程度の幅をもった範囲に設定され得るものであると理解されることからす ると、甲1の記載に触れた当業者が、直ちに、X、Y軸ステージの振動等の外的要 因や加工対象物であるシリコンウエハの反りのために、レーザ光の集光点のZ軸方 向の位置がずれ、改質領域の位置がずれることによって、シリコンウエハの割れに 大きな影響を及ぼして品質低下を生じさせると理解するとはいえない。
そうすると、甲1発明において、AF制御をする動機付けがあると認めることは できない。また、周知の技術的事項1は半導体ウエハの表面の加工についてのAF制御をいうものであるところ、これが周知であるからといって、動機付けがないに\nもかかわらず、甲1発明のようなステルスダイシングに適用できるとはいえない。 したがって、甲1発明において「前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿 って相対的に移動させるように前記移動手段を制御して改質領域を形成する」構成を採用することについて、当業者が容易に想到できたと認めることはできない。\n
ウ(ア) 原告は、レーザ加工の技術分野において、加工時におけるレーザビームの 振動やテーブルの振動などの外的要因や加工対象物の凹凸や反りが、レーザ光の焦 点ずれの原因となることが知られており、高さ方向(Z軸方向)の集光点をAF制 御することは当然のことであり技術常識であったから、Z軸方向のAF制御をする ことは甲1に記載されているに等しく、少なくとも容易想到であると主張する。 しかしながら、甲1には、加工時に、レーザ光Lの集光点Pについて、Z軸方向 の制御をすることについての記載はない。また、前記2(1)ウのとおり、甲1(2頁) には「本発明に係るレーザ加工方法によれば、加工対象物の内部に集光点を合わせ てレーザ光を照射しかつ多光子吸収という現象を利用することにより、加工対象物 の内部に改質領域を形成している。加工対象物の切断する箇所に何らかの起点があ ると、加工対象物を比較的小さな力で割って切断することができる。本発明に係る レーザ加工方法によれば、改質領域を起点として切断予定ラインに沿って加工対象物が割れることにより、加工対象物を切断することができる。よって、比較的小さ\nな力で加工対象物を切断することができるので、加工対象物の表面に切断予\定ライ ンから外れた不必要な割れを発生させることなく加工対象物の切断が可能となる。」との記載があり、同記載に照らすと、甲1発明は、加工対象物であるシリコンウエ\nハの内部に改質領域を形成して、改質領域を起点として切断予定ラインに沿って加工対象物を割るというものである。そして、前記アのとおり、周知の技術的事項1\nは、半導体ウエハの表面を加工する際に、半導体ウエハに反りがあると加工位置に対して加工用レーザ光の焦点がずれることから、表\面の変位に基づいてAF制御をして表面を加工するというものであるところ、シリコンウエハの内部に改質領域を形成する際に、このような半導体ウエハの表\面加工に係る周知の技術的事項1をそのまま適用できるとはいえない。
(イ) 当業者が、甲1の記載から、甲1発明において、加工中の集光点AF制御が 当然に採用されるものと理解するといえるには、甲1発明において、シリコンウエ ハの反りやX、Y軸ステージの振動により、集光点のZ軸方向の位置がずれ、その 結果、改質領域が形成される位置がずれることとなり、その改質領域の位置のZ軸 方向のずれに起因して割断精度が悪くなる等の品質低下の問題を生じることが明ら かであり、そのために、AF制御が必要であることまでを当業者が認識することを 要するものと考えられる。ところが、当業者にとって、上記のような問題が生じる ことが明らかであると認識できたと認めるに足りる証拠はなく、そのような技術常 識は認められないところ、前記のとおり、甲1には、改質領域が形成される位置が、 ある程度の幅をもった範囲に設定され得ることを示唆する記載があるから、周知の 技術的事項1を考慮しても、また、甲1発明の加工対象物として、30㎛程度まで の薄いシリコンウェアが対象となり得ることを考慮しても、当業者が、甲1の記載 から、甲1発明において加工中の集光点のAF制御が当然に採用されると理解する とはいえない。
(ウ) 原告は甲1の「クラック領域9と表面3の距離が比較的長いと、表\面3側に おいてクラック91の成長方向のずれが大きくなる。これにより、クラック91が 電子デバイス等の形成領域に到達することがあり、この到達により電子デバイス等 が損傷する。クラック領域9を表面3付近に形成すると、クラック領域9と表\面3 の距離が比較的短いので、クラック91の成長方向のずれを小さくできる。よって、 電子デバイス等を損傷させることなく切断が可能となる。但し、表\面3に近すぎる 箇所にクラック領域9を形成するとクラック領域9が表面3に形成される。このため、クラック領域9そのもののランダムな形状が表\面3に現れ、表面3のチッビン\nグの原因となり、割断精度が悪くなる。」との記載(105頁15〜23行)をもっ て、比較的厚いウエハの場合には、改質領域のZ軸方向の位置が割断精度に影響を 与えるものであることが甲1に明記されていると主張するが、同記載をもって、シ リコンウエハの反りやX、Y軸ステージの振動に起因する改質領域の形成される位 置のZ軸方向のずれが、品質低下の問題を生じる程度のものであることが明らかと なるものではないから、上記記載部分を踏まえても、当業者が、甲1の記載から甲 1発明において加工中の集光点のAF制御が当然に採用されると理解するとはいえ ない。
(エ) 原告は、本件明細書(【0004】)に、従来技術に加工対象物の端部におい てレーザ光の集光点がずれる場合があるとの課題があると記載されていることから も、一般的なレーザ加工技術の課題として、甲1発明においても、加工中の集光点 のAF制御が必要であると主張するが、本件明細書の上記記載を踏まえても、前記 (イ)のとおり、当業者が、甲1発明において、加工対象物の内部に改質領域を形成す るために、加工時におけるAF制御としての加工中のZ軸方向の位置の制御が必要 であるとの課題を認識するとはいえない。また、原告が指摘する証拠はいずれも、 加工対象物の内部に改質領域を形成する甲1発明において、加工中のZ軸方向の位 置の制御が必要であることが技術常識であることを裏付けるものとはいえない。 そして、原告主張に係る被告の本件以外の出願の状況が、本件発明の進歩性の判 断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2023.07.10
令和4(ネ)10070 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年5月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
事案に鑑み、争点7(乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否)について、まず判断する。
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて\n
被控訴人は、前記第2の4(2)イ のとおり、乙22文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法であるとしてその却下を求めるが、この防御方法の提出が訴訟の完結を遅延させるものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討する。
(2) 無効理由の解消の有無等について
事案に鑑み、仮に、本件訂正が適法であり、本件訂正により本件訂正発明と乙22発明との間に当事者の主張に係る相違点が全て生じるとした場合、乙22発明に基づく進歩性欠如の無効理由が解消されるかをまず検討する。
ア 本件訂正発明1
相違点22−6ないし相違点22−8の容易想到性
相違点22−6ないし相違点22−8は、前記第2の4(1)イ aのと おり、本件訂正発明1において、1)閲覧者がWebブラウザに対して閲 覧指示を行った段階においては、Webブラウザは閲覧指示に対応する HTMLをサーバに要求するだけであること(相違点22−6)、2)サー バはWebブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行す\nる、HTMLに記述されたJavaScriptをWebブラウザに送信すること (相違点22−7)、3)WebブラウザがHTMLに記述されたJavaScr iptを受信する前に表示領域内に表\示する分割画像を特定する演算を行 わないこと(相違点22−8)というものであるのに対し、乙22発明 は、地図データの要求をサーバに送信するまでの間に、ディスプレイに 表示する地図データ(メッシュ地図)を特定する演算を行っているとい\nうものである。 Webブラウザを用いた表示では、閲覧者がWebブラウザに対して\n閲覧指示を行うと、Webブラウザが閲覧指示に対応するHTMLをサ ーバに要求し、サーバが要求に対応するHTMLをWebブラウザに送 信し、Webブラウザが受信したHTMLに基づいて表示を行うという\n表示ステップを経るというようなプログラム上の取決めがあることは顕\n著な事実であるところ、このようなHTMLを用いるWebブラウザの 処理におけるプログラム上の取決めがある以上、閲覧者がWebブラウ ザに対して閲覧指示を行った段階では、Webブラウザは閲覧指示に対 応するHTMLをサーバに要求するだけであり、WebブラウザがHT MLを受信する前の段階では、Webブラウザによって当該HTMLに 基づくいかなる処理も実行されることがないことは、上記取決めから生 じる当然の帰結にすぎない。 そして、JavaScriptは、HTMLに直接記述されるか、あるいはHT MLによって読み出される外部ファイルに記述されるかのいずれでもよ いものであることは、本件特許出願時の技術常識と認められるから(甲 46、48、49)、当業者は適宜それを使い分ければよく、Webブラ ウザにおいてJavaScriptを用いたときにJavaScriptがHTMLに直接記述されることは当業者の自然な選択の一つにすぎず、その選択をした場 合、WebブラウザがHTMLを受信する前に当該HTMLに直接記述 されたJavaScriptを実行しないことはいうまでもない。 そうすると、Webブラウザを採用して動的表示をJavaScriptを用い\nて実行しようとするならば、当業者が適宜になす自然な選択の結果、ほ ぼ必然的に相違点22−6ないし相違点22−8に係る本件訂正発明1 の構成をとることになるのであって、当該構\成についてとりたてて創意 を発揮する余地はない。そうであるところ、前記2(1)のとおり、本件特 許出願当時において、Webクライアントによる動的表示を行う処理を\nWebブラウザでJavaScriptを用いて行うことは周知慣用技術であり、 そして、この周知慣用技術を適用すればそれに起因して相違点22−6 ないし22−8の本件訂正発明1の構成となるというのであれば、上記\n相違点に係る本件訂正発明1の構成は容易に想到し得るものというほか\nない。
・・・
時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて\n
被控訴人は、前記第2の4(2)ア のとおり、被告地図表示方法の本件\n発明17の充足性に関する主張は、時機に後れた攻撃防御方法であると してその却下を求めるが、この攻撃方法の提出が訴訟の完結を遅延させ るものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討 する。
相違点22−17−1の容易想到性について
a 本件訂正発明17は、本件訂正発明1について、1)同じ内容の画像 データを2)複数の倍率で有すること、3)各倍率の画像を構成する分割\n画像の画素数は表示倍率に関わらず一定であること、4)分割画像の分 割数は倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多いこととの 限定を付したものであるところ、乙22発明は、上記のような構成を\n有するとは特定されていない。
b 乙10文献には別紙9のとおりの記載がある。これによると、乙10技術として、次のような技術が記載されているものと認められる。 クライアントから要求される画像の指定、表示範囲の指定の変化に\n関わらず、高速かつ一定時間内に高精細画像を表示するためのデータ\n構造を備える高精細画像表\示装置を提供することを目的とするもので あって(【0006】)、 サーバに格納される画像データのデータ構造が、複数段階の解像度\nの画像を有するものであり(【0024】ないし【0026】、【図2】)、 それぞれ解像度の画像はそれぞれpピクセル×pピクセルのブロッ クに分割されて保持され、個々のブロックを単位としてアクセスされ るものであって、個々のブロックを構成する画素数は解像度に関わら\nず同じであり(【0028】、【0029】、【図3】)、 ブロックの分割数は解像度が少ない画像ほど少なく、解像度が高い 画像ほぼ多い状態であり(【図3】)、 クライアント側の表示装置において表\示される表示枠に関連する各\nブロックの画像データを、サーバからクライアントに伝送して表示す\nる技術(【0031】、【0032】)。
c 本件訂正発明1が乙22発明により容易に想到できるものであるこ とは、前記アにおいて判示したとおりであるところ、乙10技術は、 相違点22−17−1の構成に係る分割画像の格納形態を開示するも\nのであり、本件訂正発明17と乙10技術は、分野を同一とするもの であって表示領域より大きい画像データを領域分割し、表\示装置に対 応する分割画像を送信して表示することにより表\示を高速化するとい う機能も共通するものであるから、乙22発明の分割画像の格納形態\nとして、乙10文献記載の分割画像の格納形態を採用して、相違点2 2−17−1に係る本件訂正発明17の構成とすることは容易に想到\nできる。
控訴人らの主張について
控訴人らは、前記第2の4(1)イ e(g)のとおり、乙10技術は、個々 の分割画像(ブロック)を送信しているわけでもないし、同じ画像を複 数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域で分割してサーバから送 信しているわけではないから、乙22発明に乙10技術を適用して本件 訂正発明17の構成とすることは容易に想到できない旨主張するが、乙\n10技術の分割画像の送信手法と分割画像の格納形態とは、特に必須に 結合しているわけではなく、それぞれ独立した技術事項であるから、乙 10技術の送信手法までを乙22発明に適用する必要はなく、乙10の 分割画像の格納形態のみを採用することに阻害要因も見当たらない。 したがって、上記主張を採用することはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.07. 5
令和3(ワ)14272 登録ドメイン名使用権確認請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年4月28日 東京地方裁判所
2 争点2(紛争処理方針4条a項(iii)号の要件を満たすか)について
当事者の主張に沿って、紛争処理方針4条b項(iv)号所定の事情の有無につ いて検討する。
商業上の利得を得る目的の有無について
原告が「商業上の利得を得る目的」で本件ドメイン名を使用していること は当事者間に争いがない。 商品の出所について誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネッ ト上のユーザーを本件サイト等に誘引するために、本件ドメイン名を使用し ているか否かについて
ア 証拠(乙1ないし5)によれば、本件販売契約2の終了後である令和3 年2月8日当時、本件サイトにおいて、「VENOSAN」ブランドの被告 の商品が販売されていたことが認められる。 そして、本件サイトには、当該商品の商品名として「VENOSAN5 000」、「VENOSAN6000」、「VENOSAN7000」などと 記載されるとともに(乙1・1頁、乙2・6頁、乙3・1頁)、当該商品に 関連して、「スイス医療ブランド」(乙3・4頁)、「スイスのデザイン力」 (乙3・4頁)、「区分スイス製・一般医療機器(医療機器届出番号13B 3X10094000001)」(乙3・6頁)、「最新の弾性ストッキング がスイスから上陸しました。」(乙4・2頁)と記載されていたことが認め られる。
イ(ア) 加えて、令和3年2月8日当時、本件サイトにおいて、次の記載がさ れていたことが認められる(乙5)。 「2020年、ベノサンから新しくFOOTNURSEが誕生しま す!」「FOOTNURSEは、医療用着圧ソックスとして大ブレイクし\nた『ベノサン』から新しく誕生したブランドです。もともと『医療用』 に開発されていたベノサンの着圧ソックスが、このたび『健康な女性用』\nに新たなブランドを立ち上げました。」
(イ) また、令和3年9月22日当時、ベノサンジャパンが開設していたウ ェブサイトには、次の記載がされていたことが認められる(乙13)。 「FOOTNURSEは、…一般医療機器としてもしっかり認定され ています(医療機器届出番号13B3X10094000001)。」(同 3枚目)、「その点FOOTNURSEは、創業1883年の医療用弾性 ストッキングを50年以上にわたって製造している着圧ソックスの本場\n『SWISSLASTIC社』と、『ベノサン・ジャパン』が企画力・技 術力を結集させて、丁寧に編み込まれていますので…」(同4枚目)。
(ウ) そして、原告は、令和3年9月3日当時、被告と関係のない「FOO TNURSE」ブランドの商品をインターネット上のオンラインストア で販売していたことが認められる(乙7)。
ウ 前記アにおいて認定した本件サイトの記載を見た需要者は、「VENOS AN」という標章は、本件サイトで販売されている医療用弾性ストッキン グについてのスイス所在の製造元又は同製造元が使用するブランド名を示 すものと理解するのが通常と考えられる。また、「ベノサン」は「VENO SAN」の日本語読みに相当することからすると、前記イ(ア)の記載を見た 需要者は、「FOOTNURSE」ブランドの商品についても、「VENO SAN」ブランドの医療用弾性ストッキングと同じ製造元の商品であると 理解するといえる。また、前記1(3)アにおいて認定したとおり、本件サイ トのヘッダー部分に本件サイトを運営する会社又は店舗の名称と解し得る 態様で「ベノサン」との標章が付されていたことも考慮すると、上記記載 を見た需要者は、「FOOTNURSE」ブランドの商品も、「VENOS AN」ブランドの医療用弾性ストッキングと同じ製造元の商品であると誤 信したり、本件サイトが当該製造元、当該製造元の正規販売代理店又は当 該製造元と提携する者などによって運営されていると誤信するおそれがあ ると認められる。 そして、前記イ(イ)のとおり、「FOOTNURSE」ブランドの商品は 被告と何ら関係がないにもかかわらず、ベノサンジャパンが開設していた ウェブサイトに、「FOOTNURSE」ブランドの商品に被告が関与して いると理解できる程度の記載がされていることからすると、本件サイトの 前記イ(ア)の記載は、原告が、「FOOTNURSE」ブランドの商品の出 所について誤認混同を生ぜしめることを意図して掲載したものと認めるの が相当である。
エ 以上によれば、原告は、「FOOTNURSE」ブランドの商品の出所に ついて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザ ーを本件サイト又はベノサンジャパンが開設していたウェブサイトに誘引 するために、本件ドメイン名を使用していると認められる。
原告の主張について
ア 原告は、令和3年2月当時、本件サイトにおいて「ベノサン」と「ベノ サンジャパン」との使い分けが適切にできていなかったにすぎないと主張 する。 しかし、前記イ(イ)のとおり、「FOOTNURSE」ブランドの商品は 被告と何ら関係がないにもかかわらず、ベノサンジャパンが開設していた ウェブサイトに、「FOOTNURSE」ブランドの商品に被告が関与して いると理解できる程度の記載がされていることからすると、本件サイトの 前記イ(ア)の記載が単なる使い分けに関する過誤によるものであるとは考え 難い。
イ また、原告は、「VENOSAN」という名称が被告のブランドとして日 本国内で認知されていないから、原告が日本国内で認知されていない被告 の商品との誤認混同を生ぜしめることを意図すること自体あり得ないなど と主張する。 しかし、本件サイトを見た需要者が、「FOOTNURSE」ブランドの 商品の出所は被告であると具体的に認識しなくとも、「VENOSAN」ブ ランドの医療用弾性ストッキングと同じ製造元の商品であると理解するこ とになれば、商品の出所について誤認混同が生ずることになるから、「VE NOSAN」との名称が被告のブランドとして日本国内で認知されている 必要があるとはいえない。
ウ したがって、原告の前記各主張を採用することはできない。
小括 以上によれば、紛争処理方針4条b項(iv)号所定の事情があると認められ るから、その余の点について判断するまでもなく、紛争処理方針4条a項 (iii)号の要件を満たす。
◆判決本文
関連事件です。
2023.07. 5
令和3(ワ)13895 損害賠償等請求事件 商標権 民事訴訟 令和5年4月27日 東京地方裁判所
2 争点2(商標法4条1項1号該当事由の有無)について
被告は、本件商標はスイスの国旗と類似するから、商標法4条1項1号に該当 する事由があると主張する。 しかしながら、本件商標は、前記1(2)認定のとおりであるのに対し、スイスの 国旗は、正方形と、その内部(中央)に位置する幅広で白色の十字から成り、正\n方形の内部は、白色である上記十字部分を除いて赤色である。そうすると、本件\n商標及びスイスの国旗は、幅広の十字を内部に有するという点において共通する\nものの、スイスの国旗は、正方形であって白色の外縁部分がなく、内部の十字部\n分を除いた部分が鮮やかな赤色である点において相違するものと認められる。 上記共通点及び相違点の形状及び色彩を踏まえると、本件商標とスイスの国旗 は、中心的かつ全体的構成を占める図形の形状及び色彩において明らかに相違す\nるものであることが認められる。そうすると、本件商標は、スイスの国旗と同一 又は類似の商標に該当するものと認めることはできない。
・・・
(3) 使用料率について
本件商標の実施に対し受けるべき料率を検討するに、前提事実、後掲各証拠 及び弁論の全趣旨によれば、1)経済産業省知的財産政策室「ロイヤルティ料率 データハンドブック」(平成22年)において、商標権におけるロイヤルティ 料率の平均値は2.6%であること(なお、商標分類の18類については、サ ンプル数は0とされている。)(乙32)、2)原告は、長年の間、「WENG ER」ブランドとして世界的に著名なアーミーナイフを製造販売していたが、 現在は同ブランドとして時計やバッグを製造販売し、本件商標を付したかばん 製品を販売していること(甲24ないし27)、3)インターネット上のショッ ピングサイトにおいて、本件商標が付された原告商品(かばん製品)が販売さ れており、原告商品と被告商品とは競合すること(甲16)、以上の事実が認 められる。
そして、商標法38条3項による「受けるべき利益」の算定の基礎となる相 当使用料率は、侵害があったことを前提として合意されるべきものであるから、 通常の料率よりも自ずと高くなることに鑑み、上記認定事実を含め本件に現れ た一切の事情を総合考慮すると、その料率は売上高の4%であると認めるのが 相当である。 なお、被告は、損害不発生の抗弁も主張するが、上記において説示したとこ ろによれば、その主張は、採用の限りではない。
(4) 損害額について
ア 商標法38条3項に基づく損害額
したがって、商標法38条3項に基づく損害額は、次の計算式のとおり、 1254万7659円となる(小数点第一位で四捨五入)。 (計算式) 3億1369万1471円×4%≒1254万7659円
イ 弁護士費用
本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当 因果関係があると認められる弁護士費用相当損害額は、1254万7659 円の1割(小数点第一位で四捨五入)である125万4766円の限度で認 めるのが相当である。
ウ 合計額
以上によれば、本件の損害額は、1380万2425円となる。
◆判決本文
関連事件です。
◆令和2(ネ)10060
本件商標の不使用取消審判の審取です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.06.30
令和5(ネ)10030 特許権移転登録手続請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年6月22日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ところで、控訴人の主張を前提とすると、本件各発明が完成したのは平成3 0年5月頃ということになるが、証拠(乙1)によると、同年5月時点において、 控訴人には就業規則(平成25年4月1日施行)が存在しており、職務発明につい て次のとおり規定されていた。
「(特許、発明、考案等の取扱い)
第84条 社員が自己の現在又は過去における職務に関連して発明、考案をした 場合、会社の要求があれば、特許法、実用新案法、意匠法等により特許、登録を受 ける権利又はその他の権利は、発明者及び会社が協議のうえ定めた額を会社が発明 者である社員に支払うことにより、会社に譲渡又は継承されるものとする。」 上記規定からすると、平成30年5月頃、控訴人とその従業員との間には、職務 発明について、控訴人の要求があるときに、控訴人が発明者である従業員に対し、 協議して定めた額の金員を支払うことにより、特許を受ける権利が発明者から控訴 人に移転する旨の合意があったものと認めるのが相当であり、控訴人とその従業員 の間に、職務発明についての特許を受ける権利を、控訴人が原始取得する旨の合意 があったと認めることはできない。
(3) 控訴人は、前記(2)の就業規則の規定は空文化されており、控訴人と従業員 との間で、職務発明について控訴人に原始取得する旨の黙示の合意があり、そのこ とは、1)控訴人において、就業規則の規定にのっとった手続が行われたことがなか ったこと、2)被控訴人代表者が、平成29年7〜8月に控訴人を出願人として職務\n発明について特許出願をしたが、控訴人は特許を受ける権利の移転を要求しておら ず、また、承継対価の額についての協議や対価の支払を行わなかったこと、3)従前 からの取扱いを確認する形で平成30年9月3日に甲12規程が制定されたこと、 4)本件各発明の共同発明者が、本件各発明についての特許を受ける権利が控訴人に 原始的に帰属する旨認めていること、5)被控訴人代表者が大王製紙と控訴人との間\nの取引を奪うことを目的として、控訴人において本件各発明についての特許出願を したことから、明らかであると主張する。
ア しかしながら、控訴人の就業規則の附則(4)により、同就業規則の改廃は 社員(従業員)の代表者の意見を聴いて行うものとされているところ(乙1)、控\n訴人において、就業規則の規定を変更するための手続が執られたことはなく、控訴 人とその従業員との間で、職務発明について就業規則の規定にかかわらず、特許を 受ける権利を控訴人に原始取得させることについての協議がされた等の事情もうか がえないのであるから、控訴人と従業員との間で上記黙示の合意が成立していたも のと認めることはできず、控訴人と被控訴人代表者との間でも、控訴人の主張する\n黙示の合意がされたことを認めるに足りる証拠はないというほかない。職務発明に 係る特許を受ける権利を使用者である控訴人に原始取得させることは、従業員にと って、就業規則を不利益に変更するものであるところ、控訴人において、職務発明 の出願に関して、就業規則の規定にのっとった手続が行われたことがなかったこと をもって、何らの協議を経ることもなく、直ちに、就業規則が変更されたとか、控 訴人と従業員らとの間で、就業規則とは異なる内容の合意が成立したなどと認める ことはできない(上記1))。
イ また、被控訴人代表者が、職務発明について、特許事務所に対して、控訴人\nを出願人とする特許出願手続を依頼したことがあったという事実については、控訴 人を出願人とする特許出願手続を依頼することにより、被控訴人代表者が、控訴人\nに対して、特許を受ける権利を移転する旨の意思表示をしたとみることもできるの\nであって、上記事実をもって、控訴人と被控訴人代表者との間に、職務発明につい\nての特許を受ける権利を控訴人が原始取得する旨の黙示の合意があったと認めるこ とはできない(上記2))。
ウ そして、甲12規程には、「職務発明については、その発明が完成した時に、 会社が特許を受ける権利を取得する。」との規定があり(第4条)、職務発明につい ての特許を受ける権利が控訴人に原始的に帰属する旨定められているものの、甲1 2規程が適法に制定されたものであったとしても、控訴人の主張する本件各発明の 完成日(平成30年5月頃)よりも後の同年9月3日に制定されたものであるとい うのであるから(甲12)、同日までに既に発生している特許を受ける権利の帰属 を原始的に変更することができるものではなく、このことは、甲12規程において、 平成26年1月1日以降に完成した発明に適用する旨規定されていることを考慮し ても変わりはない(上記3))。
エ さらに、共同発明者であるとされる控訴人従業員の現時点における認識や、 被控訴人代表者の本件各発明の特許出願時の意図について、仮に控訴人の主張する\nとおりであったとしても、これらの事項は、本件各発明の特許を受ける権利の帰属 に影響しない(上記4)及び5))。 そうすると、控訴人の主張はいずれも採用できない。
◆判決本文
1審はこちら。
2023.06.30
令和5(行ケ)10017 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年6月22日 知的財産高等裁判所
ウ 「I」又は「i」と「!」は、外観が類似していることから、日本国民にとって、「!」の文字から「I」又は「i」を連想して「アイ」又は「イ」と読むことが難しいとはいえないことに加え、前記イの各使用例においては、「!」又は「!」の文字をデザイン化(ただし、「!」の文字であることが容易に読み取れる限度におけるデザイン化である。以下同じ。)したものをもって、「I」又は「i」と読ませることを意図しているものであることが明らかであり、名称等を表すロゴや文字列において、「I」又は「i」に代えて「!」又は「!」の文字をデザイン化したものを用いる手法が一般的に用いられていることからすると、このようなロゴや文字列を見た取引者、需要者は、「!」又は「!」の文字をデザイン化したものをもって、「I」又は「i」と読むものと認識、理解すると認めるのが相当である。
エ そうすると、引用商標である「RE!GN」は、取引者、需要者をして「R EIGN」を意味するものと認識、理解されると認めるのが相当である。
・・
3 本願商標と引用商標の類否
(1) 本願要部(「REIGN」の文字部分)と引用商標とを比較すると、その外観はフォントがやや異なっており本願商標の方が太い文字であること及び3文字目が本願要部では欧文字の「I」であるのに対し、引用商標では「I」の下に「★」を配したもので、「!」の文字をデザイン化したものである点において異なるものの、本願要部と引用商標は、それが表す文字列が同一であること、引用商標の3文字目のデザイン化の程度が著しいとはいえず、欧文字の「I」に近いものであることを考慮すると、そのデザインの差異により見る者に与える印象の差異が大きいということはできず、外観において近似しているというべきである。そして、文字列が同一であって、称呼及び観念が共通することからすると、本願要部と引用商標は、外観において近似しており、また、称呼及び観念を共通にし、同一又は類似の商品又は役務について使用するときは、その商品又は役務の出所について誤認混同が生じるおそれがあるというべきであるから、互いに類似する。\n
◆判決本文
#知財
#訴訟
#商標
#結合商標
#抽出
#分離
#類似
#デザイン化
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.06.29
令和4(ネ)10046 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年5月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
損害額については、ほぼ伏せ字になっています。102条3項の侵害は料率2%で計算し、それよりも2項侵害の額の方が大きくて最終的に約1100万円の損害賠償が認定さられています。
なお、1審では、特許の技術的範囲には属するが、一部の構成要件が日本国外に存在するので、非侵害と認定されてました。概要だけはすぐにアップされていましたが、全文アップは約1ヶ月かかりました。
ア 被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行為が本件発 明1の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に該当するか否 かについて
(ア) はじめに
本件発明1は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末 装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の 発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」(特許法2条3 項1号)とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をい うものと解される。 そして、本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介 して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(以下「ネットワーク型システム」という。)の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構\成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能\を有す るようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいう ものと解される。 そこで、被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行 為が本件発明1の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に 該当するか否かを判断するに当たり、まず、被告サービス1のFLAS H版において、被告システム1を新たに作り出す行為が何かを検討し、 その上で、当該行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当するか及び 当該行為の主体について順次検討することとする。
(イ) 被告サービス1のFLASH版における被告システム1を新たに 作り出す行為について
a 被告サービス1のFLASH版においては、訂正して引用した原判 決の第4の5(1)ウ(ア)のとおり、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指定する(2))と、それに伴い、被控訴人FC2のウェブ サーバが上記ウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを ユーザ端末に送信し(3))、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、ユーザ端末のFLASHが、 ブラウザのキャッシュにあるSWFファイルを読み込み(4))、その 後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押す(5))と、上記SWFフ ァイルに格納された命令に従って、FLASHが、ブラウザに対し動 画ファイル及びコメントファイルを取得するよう指示し、ブラウザが、 その指示に従って、被控訴人FC2の動画配信用サーバに対し動画フ ァイルのリクエストを行うとともに、被控訴人FC2のコメント配信 用サーバに対しコメントファイルのリクエストを行い(6))、上記リ クエストに応じて、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイ ルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、 それぞれユーザ端末に送信し(7))、ユーザ端末が、上記動画ファイ ル及びコメントファイルを受信する(8))ことにより、ユーザ端末が、 受信した上記動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウ ザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能\と なる。このように、ユーザ端末が上記動画ファイル及びコメントファ イルを受信した時点(8))において、被控訴人FC2の動画配信用サ ーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末はインターネットを利用 したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザに おいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能\となる から、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明1の 全ての構成要件を充足する機能\を備えた被告システム1が新たに作り 出されたものということができる(以下、被告システム1を新たに作 り出す上記行為を「本件生産1の1」という。)。
b これに対し、被控訴人らは、1)被告各システムの「生産」に関連す る被控訴人FC2の行為は、被告各システムに対応するプログラムを 製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることに 尽き、いずれも米国内で完結しており、その後、ユーザ端末にコメン トや動画が表示されるまでは、ユーザらによるコメントや動画のアップロードを含む利用行為が存在するが、ユーザ端末の表\示装置は汎用ブラウザであって、当該利用行為は、本件各発明の特徴部分とは関係 がない、2)被告システム1において、ユーザ端末は、被控訴人FC2 がサーバにアップロードしたプログラムの記述並びに第三者が被控訴 人FC2のサーバにアップロードしたコメント及び被控訴人FC2の サーバにアップロードした動画(被告システム2及び3においては第 三者のサーバにアップロードした動画)の内容に従って、動画及びコ メントを受動的に表示するだけものにすぎず、ユーザ端末に動画やコメントが表\示されるのは、既に生産された装置(被告各システム)をユーザがユーザ端末の汎用ブラウザを用いて利用した結果にすぎず、 そこに「物」を「新たに」「作り出す行為」は存在しない、3)乙31 1記載の「一般に、通信に係るシステムはデータの送受を伴うもので あるため、データの送受のタイミングで毎回、通信に係るシステムの 生産、廃棄が一台目、二台目、三台目、n台目と繰り返されることま で「生産」に含める解釈は、当該システムの中でのデータの授受の各 タイミングで当該システムが再生産されることになり、採用しがたい」 との指摘によれば、被控訴人FC2の行為は本件発明1の「生産」に 該当しないというべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、被控訴人FC2が被告システム1に 対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをア ップロードすることのみでは、前記aのとおり、本件発明1の全ての 構成要件を充足する機能\を備えた被告システム1が完成していないと いうべきである。
2)については、前記aのとおり、被控訴人FC2の動画配信用サー バ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用し たネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受 信することによって、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能\を 備えた被告システム1が新たに作り出されるのであって、ユーザ端末 が上記ファイルを受信しなければ、被告システム1は、その機能を果たすことができないものである。
3)については、上記のとおり、被告システム1は、被控訴人FC2 の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインタ ーネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必 要なファイルを受信することによって新たに作り出されるものであり、 ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存されたファイルが廃棄され るまでは存在するものである。また、上記ファイルを受信するごとに 被告システム1が作り出されることが繰り返されるとしても、そのこ とを理由に「生産」に該当しないということはできない。 よって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(ウ) 本件生産1の1が特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否か について
a 特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、 移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が 当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであると ころ(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷 判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年(受)第580 号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参 照)、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解され る。 前記(イ)aのとおり、本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブ サーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人FC2の動画配\n信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サー バがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末 がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサ ーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国 に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。す なわち、本件生産1の1において、上記各ファイルが米国に存在する サーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信 することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、 新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在 するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、 我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題とな る。
b ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(以下、単に 「国外」という。)に設置されることは、現在、一般的に行われてお り、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システム の利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であ るネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構\成する端末が日本国内(以下「国内」という。)に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用するこ とは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義\nの原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえす\nれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る 特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。他方で、当該システムを構\成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を 生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。 これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許 権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り 出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについ ては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構\成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考\n慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができる ときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当 である。
これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的 態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが 送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、 国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム 1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観 念することができる。 次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサー バと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能\である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表\示されるように するために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能\と構成要件1Gの表\示位置制御部の機能を果たしている。
さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利 用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケー ションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現し ており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係る システムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るもので ある。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内 で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特 許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。
c これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の 効力が当該国の領域においてのみ認められる」のであるから、海外 (国外)で作り出された行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当 しないのは当然の帰結であること、権利一体の原則によれば、特許発 明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施することをいうことからすると、一部であっても海外で作り出されたものがある場合には、特許法2条3項1号の「生産」に該当しないというべきであ\nる、2)特許回避が可能であることが問題であるからといって、構\成要 件を満たす物の一部さえ、国内において作り出されていれば、「生産」 に該当するというのは論理の飛躍があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判例においては、 カードリーダー事件の最高裁判決(前掲平成14年9月26日第一小 法廷判決)等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、そ の例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきである旨主張する。\n
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に 関し、被疑侵害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法 2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システム を構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、前記bに説示した事情を総合考慮して、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生\n産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することがで きない。
2)については、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否か の上記判断は、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすというものではないから、2) の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特 許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定めら れ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意 味することに照らすと、上記のとおり当該行為が我が国の領域内で行 われたものとみることができるときに特許法2条3項1号の「生産」 に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しないというべ きである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たる ためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内において完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、また、我が国が締結した条約及び特\n許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」 に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用する ことができない。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(エ) 被告システム1(被告サービス1のFLASH版に係るもの)を 「生産」した主体について
a 被告システム1(被告サービス1のFLASH版に係るもの)は、 前記(イ)aのとおり、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画 を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存された上記SWF\nファイルによる命令に従ったブラウザからのリクエストに応じて、被 控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2 のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末 に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって、新たに作り 出されたものである。そして、被控訴人FC2が、上記ウェブサーバ、 動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、 これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファ イル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末によ る各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、 被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、 自動的に行われるものであることからすれば、被告システム1を「生 産」した主体は、被控訴人FC2であるというべきである。
この点に関し、被告システム1が「生産」されるに当たっては、 前記(イ)aのとおり、ユーザが、ユーザ端末のブラウザにおいて、所 望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指定すること(2))と、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すこと(5))が必要とされるところ、上記のユ ーザの各行為は、被控訴人FC2が設置及び管理するウェブサーバに 格納されたHTMLファイルに基づいて表示されるウェブページにおいて、ユーザが当該ページを閲覧し、動画を視聴するに伴って行われる行為にとどまるものである。すなわち、当該ページがブラウザに表\示されるに当たっては、前記のとおり、被控訴人FC2のウェブサーバが当該ページのHTMLファイル及びSWFファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が受信したこれらのファイルがブラウザのキャ ッシュに保存されること(4))、また、動画ファイル及びコメントフ ァイルのリクエストについては、上記SWFファイルによる命令に従 って行われており(6))、上記動画ファイル及びコメントファイルの 取得に当たってユーザによる別段の行為は必要とされないことからす れば、上記のユーザの各行為は、被控訴人FC2の管理するウェブペ ージの閲覧を通じて行われるものにとどまり、ユーザ自身が被告シス テム1を「生産」する行為を主体的に行っていると評価することはで きない。
b これに対し、被控訴人らは、1)米国に存在するサーバが、ウェブペ ージのデータ、JSファイル(FLASH版においてはSWFファイ ル)、動画ファイル及びコメントファイルを送信することは、被控訴 人FC2が行っているのではなく、インターネットに接続されたサー バにプログラムを蔵置したことから、リクエストに応じて自動的に行 われるものであり、因果の流れにすぎない、2)日本(国内)に存在す るユーザ端末が、上記ウェブページのデータ、JSファイル(SWF ファイル)、動画ファイル及びコメントファイルを受信することは、 ユーザによるウェブページの指定やウェブページに表示された再生ボタンをユーザがクリックすることにより行われ、ユーザの操作が介在しており、また、仮に被控訴人FC2が1)の送信行為を行っていると しても、特許法は、「譲渡」と「譲受」、「輸入」と「輸出」、「提供」 と「受領」を明確に区分して規定している以上、被控訴人FC2が上 記受信行為を行っていると解すべきではない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記aのとおり、被控訴人FC2 が、ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設 置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSW Fファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操 作を介することなく、被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプ ログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、 被告システム1を「生産」した主体は、被控訴人FC2であるという べきである。
また、2)については、前記aのとおり、ウェブページの指定やウ ェブページに表示された再生ボタンをクリックするといったユーザの各行為は、被控訴人FC2の管理するウェブページの閲覧を通じて行われるにとどまるものであり、ユーザ端末による上記各ファイルの受\n信は、上記のとおりユーザによる別途の操作を介することなく自動的 に行われるものであることからすれば、上記各ファイルをユーザ端末 に受信させた主体は被控訴人FC2であるというべきである。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(オ) 小括
以上によれば、被控訴人FC2は、本件生産1の1により、被告シス テム1を「生産」(特許法2条3項1号)したものと認められる。
・・・
8 争点8(控訴人の損害額)について
(1) 特許法102条2項に基づく損害額について
ア 主位的請求関係について 控訴人は、被控訴人らが、本件特許権の設定登録がされた令和元年5月 17日から令和4年8月31日までの間、被告各システムを生産し、被 告各サービスを提供することによって、●●●●●●●●●●円を売り 上げ、これにより被控訴人らが得た利益(限界利益)の額は、●●●● ●●●●●●円を下らず、このうち令和元年5月17日から同月31日 までの分(5月分)の売上高は●●●●●●●●円、限界利益額は●● ●●●●●●円を下らないと主張する。 しかしながら、控訴人が上記主張の根拠として提出する甲24によって、 上記の売上高及び限界利益額を認めることはできず、他にこれを認める に足りる証拠はない。 したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 予備的請求関係について
(ア) 本件生産1ないし3により「生産」された被告システム1ないし3 で提供された被告各サービスの割合 前記4のとおり、被控訴人FC2は、本件生産1により被告システム 1を、本件生産2により被告システム2を、本件生産3により被告シス テム3を「生産」し、本件特許権を侵害したものであり、本件生産1な いし3は、いずれも、サーバがユーザ端末に動画ファイル及びコメント ファイルを送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものである。 しかるところ、被告各サービスで配信される動画でコメントが付され ているものの数は限られており、令和3年1月11日の時点において、 被告サービス1で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、コメン トが付された動画は●●●●●●●個であり(乙85)、その割合は● ●●●パーセントであったこと、被告各サービスは、日本語以外の言語 でもサービスが提供されているものの、そのユーザの大部分は国内に存 在すること(甲9、弁論の全趣旨)からすれば、被告各サービスのうち、 本件生産1ないし3で「生産」された被告システム1ないし3によって 提供されたものの割合は、本件特許権が侵害された全期間にわたって● ●●パーセントと認めるのが相当である。
(イ) 被控訴人FC2の利益額(限界利益額)
a 被告サービス1関係
乙84によれば、令和元年5月17日から令和4年8月31日まで の期間の被告サービス1の売上高は、別紙6売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス1」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙7−1限界利益額等\n一覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス1」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産1により「生産」\nされた被告システム1によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産1による売上高は、 ●●●●●●●●●●●円(●●●●●●●●●●●●円×●●●● ●)と認められ、被控訴人FC2が本件生産1により得た限界利益額 は、別紙7−2限界利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産1」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。
b 被告サービス2関係
乙84によれば、令和元年5月17日から令和2年10月31日 までの期間の被告サービス2の売上高は、別紙6売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス2」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙7−1限界利益額等一\n覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス2」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産2により「生産」\nされた被告システム2によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産2による売上高は、 ●●●●●●円(●●●●●●●●円×●●●●●)と認められ、被 控訴人FC2が本件生産2により得た限界利益額は、別紙7−2限界 利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産2」欄記載のとおり、合計●●●●●●円と認められる。
c 被告サービス3関係
乙84によれば、令和元年5月17日から令和2年10月31日 までの期間の被告サービス3の売上高は、別紙6売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス3」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙7−1限界利益額等一覧表\の「限界利益額」欄の「被告サービス3」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であることが認められる。 このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産3により「生産」 された被告システム3によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産3による売上高は、 ●●●●円(●●●●●●円×●●●●●)と認められ、被控訴人F C2が本件生産3により得た限界利益額は、別紙7−2限界利益額算 定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産3」欄記載のとおり、合計●●●●円と認められる。
d まとめ
(a) 前記aないしcによれば、被控訴人FC2が本件生産1ないし 3により得た限界利益額は、別紙7−2限界利益額算定表の「限界利益額(消費税相当分(10%)を含む)」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●円と認められる。\n なお、被控訴人FC2は、仮に、本件において被控訴人FC2に 対する損害賠償の支払が命ぜられるとしても、消費税上輸出免税 の対象になる旨主張するが、被控訴人FC2による被告各サービ スの提供が輸出取引に当たることを認めるに足りる証拠はないか ら、被控訴人FC2の上記主張は理由がない。
(b) 以上のとおり、被控訴人FC2が本件生産1ないし3により得 た限界利益額は、合計●●●●●●●●●●●円であり、この限 界利益額は、特許法102条2項により、控訴人が受けた損害額 と推定される(以下、この推定を「本件推定」という。)。
(ウ) 推定の覆滅について
被控訴人らは、被告各サービスにおいて、本件各発明のコメント表示機能\が、システム全体の機能の一部であり、顧客誘引力を有していないことは、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張する。\n そこで検討するに、被告各サービスで配信されている動画で、その売 上高に貢献しているものの多くはアダルト動画であり(甲4の1及び2、 9、11、弁論の全趣旨)、動画上にコメントが表示されることが視聴の妨げになることは否定できないこと、令和3年1月11日の時点において、被告サービス1で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、\nコメントが付された動画は●●●●●●●個であり(乙85)、その割 合は●●●●パーセントにとどまっていることに照らすと、被告各サー ビスにおいて、コメント表示機能\が果たす役割は限定的なものであって、 被告各サービスの多くのユーザは、コメント表示機能\よりも動画それ自 体を視聴する目的で利用していたものと認められる。そして、本件各発 明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信システムにおいて、動 画上にオーバーレイ表示される複数のコメントが重なって表\示されるこ とを防ぐというものであり(前記1(2)イ)、その技術的意義自体も、上 記システムにおいて限られたものであると認められる。
以上の事情を総合考慮すると、被告各サービスの利用に対する本件各 発明の寄与割合は●●と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える 部分については、前記(イ)d(b)の限界利益額と控訴人の受けた損害額 との間に相当因果関係がないものと認められる。 したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるか ら、特許法102条2項に基づく控訴人の損害額は、上記限界利益額の ●割に相当するものであり、別紙4−2認容額内訳表の「特許法102条2項に基づく損害額」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。\n
(2) 特許法102条3項に基づく損害額について(予備的請求関係)
ア 特許法102条3項に基づく控訴人の損害額については、1)株式会社帝 国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の 在り方に関する調査研究報告書〜知的財産(資産)価値及びロイヤルテ ィ料率に関する実態把握〜」(本件報告書)の「II).我が国のロイヤルテ ィ料率」の「1.技術分類別ロイヤルティ料率(国内アンケート調査)」 の「(2) アンケート調査結果」には、「特許権のロイヤルティ料率の平均 値」について、「全体」が「3.7%」、「電気」が「2.9%」、「コンピ ュータテクノロジー」が「3.1%」であり、「III).各国のロイヤルティ 料率」の「1.ロイヤルティ料率の動向」には、国内企業のロイヤルテ ィ料率アンケート調査の結果として、産業分野のうち「ソフトウェア」については「6.3%」であり、「2.司法決定によるロイヤルティ料率調査結果」の「(i)日本」の「産業別司法決定ロイヤルティ料率(20 04〜2008年)」には、「電気」の産業についての司法決定によるロ イヤルティ料率は、平均値「3.0%」、最大値「7.0%」、最小値 「1.0%」(件数「6」)であるとの記載があること、2)前記(1)イ(ウ) のとおり、本件各発明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信シ ステムにおいて、動画上に複数のコメントが重なって表示されることを防ぐというものであり、その技術的意義は高いとはいえず、被告各サービスの購買動機の形成に対する本件各発明の寄与は限定的であること、\nその他本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると、本件生産1ないし3 による売上高に実施料率2パーセントを乗じた額と認めるのが相当であ る。
そして、本件生産1ないし3による売上高(消費税相当分(10パー セント)を含む。)の合計額は、●●●●●●●●●●●円(●●●●● ●●●●●●円+●●●●●●円+●●●●円(前記(1)イ(イ)aないし c記載の本件生産1ないし3の各売上高に消費税相当分(10パーセン ト)を加えた額の合計額))と認められるから、●●●●●●●●円(● ●●●●●●●●●●円×0.02)となる。 これに反する控訴人及び被控訴人らの主張はいずれも採用することが できない。
イ そして、控訴人の特許法102条2項に基づく損害額の主張と同条3項 に基づく損害額の主張は、選択的なものと認められるから、より高額な 前記(1)イ(ウ)の同条2項に基づく損害額合計●●●●●●●●●円が本 件の控訴人の損害額と認められる。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和元年(ワ)25152
関連事件はこちら
◆平成30(ネ)10077
1審です。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
>> その他
>> ピックアップ対象
2023.06.28
令和3(ワ)10032 特許権 民事訴訟 令和5年6月15日 大阪地方裁判所
そして、対象製品等が特許発明の構成要件の一部を欠く場合であっても、当該\n一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ前記均等の他の要件を充足するとき は、均等侵害が成立し得るものと解される。 これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用\nすることは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、 構成要件の一部を他の構\成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区\n別すべき合理的理由はないし、本件において、原告は、被告製品には構成要件 C の「消弧材部」に対応する消弧作用を有する部分が存在し、置換構成を有する旨\n主張していると解されるから、被告の前記主張を採用することはできない。
イ 第1要件ないし第3要件
原告は、別紙「均等侵害の成否等」の「原告の主張」欄記載のとおり、本件発 明の本質的な構成部分は構\成要件のうち A-1 ないし A-3、B-3 及び B-4 であり、 構成要件 C は本件発明の課題解決方法に資するものではないとして、第1要件は 満たす旨主張するところ、被告もこれを積極的に争っていない。
一方、第2要件及び第3要件に関し、原告は、被告製品の構成 c の「接着剤で 接着することにより形成された密閉された空間26」が本件発明の構成要件 C の 「消弧材部」と同一の作用効果(消弧作用)を有することを示す実験報告書等(甲 13、14、32)を証拠提出する。これらは、被告製品と同じ構造を有する製\n品につき、ヒューズエレメント部が密閉構造である場合と、非密閉構\造である場 合又は端子一体型ヒューズ素子を取り出して遮断試験用基板に実装して遮断試 験を行った場合の、各アーク放電の持続時間を対比した結果、密閉構造のものは、\n非密閉構造等のものに比べ、同持続時間が2分の1ないし3分の1になったとい\nうものである。しかし、これらは、被告製品の「密閉された空間」と本件発明の 「消弧材部」の各作用効果の対比自体を行うものではないことに加え、被告が証 拠提出する試験報告書(乙16)によれば、被告製品、被告製品に消弧材部を設 けたヒューズ及び被告製品のヒューズ素子のみを対象として、アーク放電の持続 時間を記録したところ、被告製品が最も同時間が長かったという結果であったこ とが認められ、被告製品とヒューズ素子の各アーク放電の持続時間について、原 告が提出する実験報告書(甲14)と相反する結果となっている。そうすると、 原告が提出する前記証拠その他の事情等から、被告製品の構成 c が本件発明の構\n成要件 C と同様の作用効果を有するとまでは認め難いから、少なくとも第2要件 が満たされるとはいえない。
ウ 第4要件
前記イの点は措くとしても、以下のとおり、第4要件も満たさない。 被告は、被告製品の構成は、本件発明の特許出願時における公知技術(乙1発\n明)と同一又は当業者が乙1発明から出願時に容易に推考可能であった旨を主張\nする。
(ア) 乙1公報は、発明の名称を「表面実装超小型電流ヒューズ」とする公開特\n許公報であり、発明の詳細な説明には次の記載がある(乙1)。
・・・・
(イ) 乙1発明の構成\n
乙1発明がα-1、β-1 ないしβ-4 及びδの構成を有することは当事者間に争\nいがなく(別紙「均等侵害の成否等」の「第4要件」欄)、乙1公報の段落【0008】 【0016】【0018】【0020】及び【図2】(A)の記載内容に照らすと、α-2 及び γの構成を有するものと認められる。\nまた、被告主張のα-3 の構成(金属電極2の可溶線挟持部22に挟み込まれる\nことにより一体形成されている電極一体型ヒューズ)に関し、原告は、電極とヒ ューズが同一の金属によって一体的に形成されているとの趣旨であれば否認す ると述べるところ、乙1公報には、可溶線5は、両端部を金属電極2に挟持され 本体1の空間6に架張された可溶線を示す旨(同【0016】)、可溶線5の端部は 第1板部221と第2板部222とにより挟み込まれ、金属電極2に固定される 旨(同【0018】)の記載があることから、可溶線5と金属電極2は異なる部材で 構成され、可溶線5は、可溶線挟持部22において挟持されることによって金属\n電極2に接続されているものと認められる(α-3’)。 以上から、乙1発明の構成は、別紙「裁判所の認定」の「乙1発明の構\成」欄 記載のとおりとなる。
(ウ) 被告製品の構成\n
被告製品が a-1 ないし b-4 及び d の構成を有することは当事者間に争いがな\nく、構成 c を有することも実質的に争いがないから、被告製品の構成は、別紙「裁\n判所の認定」の「被告製品の構成」欄記載のとおりとなる。\n
(エ) 被告製品と乙1発明の対比
被告製品の a-1、a-2 及び b-1 ないし d の各構成は、それぞれ、乙1発明のα1、α-2 及びβ-1 ないしδの各構成と同一であるものと認められる。\nそこで、被告製品の構成 a-3 と乙1発明の構成α-3'が一致するかを検討する。 「一体」の字義は、「一つになって分けられない関係にあること」であるところ (広辞苑第七版)、被告製品は、別紙「被告製品写真」の3及び4に示されるよ うに、ヒューズ本体4と2つの平板状部10の部材が連続し、一つになって分け られないように形成されていることが明らかである。一方、乙1発明の可溶線5 と金属電極2は、異なる部材で構成され、また、可溶線5は、可溶線挟持部22\nにおいて挟持されることによって金属電極2に接続されていることから、可溶線 5と金属電極2は、同一材料で形成されておらず、一つになって分けられないよ うに形成されてもいない。 したがって、可溶線5と可溶線挟持部22は一体に形成されているとは認めら れず、乙1発明は構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しており、被告製 品は、公知技術と同一であるとはいえない。
(オ) 乙1発明と乙3発明に基づく容易推考性
被告は、乙1発明が構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しても、被告 製品の構成 a-3 は、乙1発明の構成α-3’を乙3発明の構成に置換することによ\nり、当業者にとって容易に推考可能である旨を主張する。\n
a 乙3公報は、発明の名称を「面実装型電流ヒューズ」とする公開特許公報で あり、発明の詳細な説明には次の記載がある(乙3)。
(a) 技術分野
「本発明は、過電流が流れると溶断して各種電子機器を保護する面実装型電流 ヒューズに関するものである。」
・・・・
(b) 背景技術
「従来のこの種の面実装型電流ヒューズは、図7に示すように、セラミックか らなるケース1と、このケース1の内部に形成された空間部2と、前記ケース1 の両端部に形成された外部電極3と、この外部電極3と電気的に接続された断面 が円形のヒューズエレメント部4とを備え、前記ヒューズエレメント部4の溶断 部5を前記ケース1の内部に形成された空間部2内に配設した構成としていた。」\n(【0002】)
(c) 発明が解決しようとする課題
「上記した従来の面実装型電流ヒューズにおいては、ヒューズエレメント部3 として同じ線径のものや同じ材料のものを使用しているため、線径や材料によっ て決まる溶断電流等の溶断特性を調整することができないという課題を有して いた。」(【0004】) 「本発明は上記従来の課題を解決するもので、溶断特性の調整ができる面実装 型電流ヒューズを提供することを目的とするものである。」(【0005】)
(d) 課題を解決するための手段
「本発明の請求項1に記載の発明は、絶縁性を有するケースと、このケースの 内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部電極と、この 外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設したヒューズエ レメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一部を切削する ことによって設けたもので、この構成によれば、ヒューズエレメント部の切削に\nよって溶断部の線径を調整できるため、溶断特性を調整することができるという 作用効果が得られるものである。」(【0007】) 「本発明の請求項3に記載の発明は、特に、ヒューズエレメント部と外部電極 とを一体の金属で構成したもので、この構\成によれば、ヒューズエレメント部と 外部電極とを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができると いう作用効果が得られるものである。」(【0009】)
(e) 発明の効果
「以上のように本発明の面実装型電流ヒューズは、絶縁性を有するケースと、 このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部 電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設し たヒューズエレメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一 部を切削することによって設けているため、この切削によって溶断部の線径を調 整でき、これにより、溶断特性を調整することができるという優れた効果を奏す るものである。」(【0016】)
(f) 発明を実施するための最良の形態
「図4、図5において、本発明の実施の形態2が上記した本発明の実施の形態 1と相違する点は、ヒューズエレメント部15と外部電極13とを一体の金属で 構成した点である。この場合、外部電極13はケース11の底部11aの端面お\nよび裏面に沿うように折り曲げている。」(【0035】) 「上記構成においては、ヒューズエレメント部15と外部電極13とを一体の\n金属で構成しているため、ヒューズエレメント部15と外部電極13とを接続す\nる必要はなくなり、これにより、生産性を向上させることができるという効果が 得られるものである。」(【0036】) 【図4】 【図5】
b 容易推考性
(a) 乙3公報の発明の詳細な説明によれば、乙3発明は面実装型電流ヒュー ズに関する発明であり(段落【0001】)、従来の面実装型電流ヒューズにおいて は、ヒューズエレメント部4として同じ線径のものや同じ材料のものを使用して いるため、線径や材料によって決まる溶断電流等の溶断特性を調整することがで きないという課題を有していたこと(同【0004】)に対し、絶縁性を有するケー スと、このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成され た外部電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を 配設したヒューズエレメント部とを備え、ヒューズエレメント部の切削によって 溶断部の線径を調整でき、溶断特性を調整することを可能としたものである(同\n【0007】【0016】)。そして、特に、ヒューズエレメント部と外部電極とを一体 の金属で形成する構成をとることによって、ヒューズエレメント部と外部電極と\nを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができるという効果を 奏すること(同【0009】【0036】)や、発明の実施の形態として、外部電極13 がケース11の底部11a の端面及び裏面に沿うように折り曲げられた形態が記 載されている(同【0035】【図4】【図5】)。 以上によれば、乙3公報には、面実装可能な小型ヒューズにおいて、生産性の\n向上を目的として、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外部電極を一体の 金属で形成するという乙3発明が開示されているといえる。
一方、乙1公報の発明の詳細な説明によれば、乙1発明は表面実装超小型電流\nヒューズに関する発明であり(段落【0001】)、従来の表面実装小型電流ヒュー\nズは、可溶部あるいは可溶線が合成樹脂や低融点ガラス等の絶縁物に直接接触し た構造である場合、可溶部等が熱的中立性を保てず本来のヒューズとしての溶断\n性能がおろそかにされている問題(同【0002】〜【0004】)や、電極をケース内 に配置固定した後、電極間に可溶線を架張して半田付けする方式は、半田が固ま る際に生じる盛り上がりの差により電極間の長さ、すなわち、可溶線の長さにば らつきが生じるという問題があったこと(同【0005】)に加え、従来の小型ある いは超小型電流ヒューズは、各部品を一つ一つバッチ工程で加工組立てを行う必 要があり、部品が小さいためその作業は困難を極め、製造し難く、その結果、低 コスト化にも限界があるという問題があった(同【0006】)。これに対し、乙1 発明は、可溶線5を挟持した一対の金属電極2が箱型形状を有する本体1の両端 に取り付けられ、蓋部3を本体1の上面より僅かに沈む位置まで押し込み接着剤 を塗布して蓋部3を本体1に固定して内部を密閉し、可溶線は本体1の内部空間 に浮いた状態で架張されている構成をとることで(同【0008】)、溶断特性のば らつきを最小限に抑えることや従来型と比べて2倍以上大きい遮断能力を有す\nることを可能としたこと(同【0028】〜【0030】)に加え、連続工程で製作組立 を行うこと、特に、可溶線5を挟持した一対の金属電極2を組み立てた後に鞍部 21を本体1の双方の短側壁11に嵌合させて固定することにより、製造が容易 になって、大幅なコスト削減が可能となるという効果を奏するものである(同\n【0020】【0027】)。 そうすると、乙1発明と乙3発明は、いずれも表面実装型ヒューズに関する発\n明であり、その技術分野は同一である。また、乙1発明と乙3発明は、いずれも 生産性の向上という同一の課題に対し、予めヒューズと電極とを組み合わせた後\nに本体に固定するという技術思想に基づく課題解決手段を提供する発明である ことに加え、乙1発明の溶断時間のばらつきを抑えるという課題と乙3発明の溶 断特性を調整するという課題は、所望の溶断特性を実現するという点で関連して いるといえる。 したがって、乙1発明と乙3発明は、技術分野、課題及び解決手段を共通にす るから、乙1発明に乙3発明を適用する動機付けが存在するものと認められる。
(b) 原告の主張
原告は、乙1発明と乙3発明とは、その課題等が相違することのほか、乙3発 明において、ヒューズエレメント部の切削を容易にするためには、乙1発明のケ ース11は上下方向の中央で分割される必要があること、乙1発明の本体1の空 間部6内に乙3発明のヒューズエレメント部15を配置する場合、ヒューズエレ メント部15を切削する必要があるが、所望の抵抗値が得られるように切削する ことは実質的に不可能であることから、乙1発明に乙3発明を組み合わせること\nはその構成上不可能\であることなどの阻害要因があるとして、被告製品と乙1発 明の相違部分は、乙3発明から容易に推考できたとはいえない旨を主張する。 しかし、前記(a)のとおり、乙1発明と乙3発明の課題は同一又は関連してい る。また、乙3公報の発明の詳細な説明によれば、ヒューズエレメント部の切削 は、スクライブやパンチング等の機械的方法によって行うが、予めヒューズエレ\nメント部の切削をした後にケースに固定をしてもよい旨が記載されていること から(段落【0022】【0027】【0028】)、ヒューズエレメント部を切削するため に、ケースを上下方向の中央で分割する必要があることにはならない。また、乙 3発明を乙1発明に適用するに当たり、乙1発明の空間部6内に、外部電極と一 体の金属で形成され、溶断部を配設したヒューズエレメント部を配置することと なるが、空間部6内にヒューズエレメント部を配置する場合に、当該ヒューズエ レメント部を切削する必要が必ずしもあるともいえない(ヒューズエレメント部 の一部の切削は本体への配置前に行うことができる。)。その他、乙1発明に乙 3発明を組み合わせることについて阻害要因があることをうかがわせる事情は ない。 したがって、原告の前記主張は採用することができない。
(c) 以上から、乙1発明に乙3発明を適用する動機付けが存在し、これを阻害 する要因は認められないから、乙1発明の可溶線と金属電極は異なる部材で構成\nされる構成に代えて、乙3発明の、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外\n部電極部を一体の金属で形成する構成を採用して被告製品の構\成とすることは、 当業者が本件特許の出願時に容易に推考し得たものと認められ、被告製品は、均 等の第4要件を満たさない。
・・・
2 争点2(本件追加の可否)について
本件追加は、被告製品が、本件発明に係る請求項とは別の請求項記載の本件発 明2の技術的範囲に属するとして請求原因を主張し、本件特許権の侵害に基づく 各請求を追加するものであるから、訴えの追加的変更に当たると解するのが相当 であるところ、当裁判所は、本件追加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させ ることとなると認め、これを許さないこととする(民訴法143条1項ただし書、 同条4項)。
すなわち、本件追加に係る請求原因は、原告において、審理の当初から主張す ることが可能であったところ、令和4年11月28日の書面による準備手続中の\n協議において、当裁判所は、当事者双方に対し、被告製品は本件発明の技術的範 囲に属さないとの心証を開示して、話合いによる解決を検討するよう促し、その 後、和解協議を行ったものの、令和5年1月27日の同協議において、これ以上 の和解協議は行わないこととなり、口頭弁論の終結に向けて、原告は、これまで の主張の補充及び反論を記載した書面を提出する旨述べたが、同年2月27日付 けの準備書面5において、本件追加を行ったものである(当裁判所に顕著な事実)。 このように、本件追加が行われた時点で、本件訴訟は、被告製品が本件発明の技 術的範囲に属さないとの当裁判所の心証開示を踏まえた和解協議を終え、審理を 終結する直前の段階に至っていた。仮に、本件追加を許した場合、被告製品が本 件発明2の技術的範囲に属するか否かや、本件特許に係る無効理由の有無につい ても改めて審理を行う必要があり、そのために相当な期間を要することになるこ とは明らかである。そうすると、本件発明2が本件発明1の従属項であり、構成\n要件の一部が同一であること、その他原告が指摘する事情を考慮しても、本件追 加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることになると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.06.25
令和4(行ケ)10074 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年5月31日 知的財産高等裁判所
(2) 日本国内における引用商標の周知性の有無について
ア 原告主張の引用商標が付された「使用商品」は、「ボルト」であるから、 「使用商品」の需要者は、機械部品メーカー等を含む、工業製品を扱う業 者であると認められる。
イ 前記(1)の認定事実によれば、平成17年から平成19年までの間、「U nbrako」の「六角穴付きボルト」の広告が一定程度、業界誌に掲載 されており、その当時、「Unbrako」の欧文字が工業製品を扱う業者 間でPCCジャパン(当時の商号は「エス・ピー・エスアンブラコ株式会 社」(通称「SPSアンブラコ」))の商標として、一定程度認識されていた ことが認められる。他方で、前記(1)の認定事実によれば、平成20年以降、 本件商標の登録査定時(平成31年4月12日)までの間、「Unbrak o」又は「アンブラコ」が原告又はPCCジャパンの「ボルト」等の商品 を表示するものとして使用されていたことが証拠上認められるのは、「金\n属産業新聞」のあいさつ広告(前記(1)イ(シ)、(ス))にとどまり、他に引 用商標が原告又はPCCジャパンの業務に係る商品「ボルト」を表示する\nものとして使用された事実を認めるに足りる証拠はない。
以上によれば、引用商標は、本件商標の登録出願時(平成30年10月 20日)及び登録査定時(平成31年4月12日)において、日本国内に おいて、原告の業務に係る商品「ボルト」を表示するものとして、需要者\nの間に広く認識されていたものと認めることはできない。 これに反する原告の主張は採用することができない。
(3) 小括
したがって、本件商標が商標法4条1項10号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由1は理由がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.06.25
令和4(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年6月15日 知的財産高等裁判所
前記1(2)に下線を付したように、本件発明1の各構成要件の数値範囲は、いずれも発明の詳細な説明に記載されたものである。ただし、構\成要件A7) の上限値である「0.828」は、本件明細書【0026】の【表2】に記載された最も好ましい上限である「0.85」を下回るものであるから、や\nはり好ましい上限値といえ(【0020】参照)、構成要件A(12)の上限値であ る「0.50」は、本件明細書【0063】の【表22】に記載された最も好ましい上限である「0.6」を下回るものであるから、やはり好ましい上限値といえる(【0020】参照)。\n なお、本件発明は本件明細書に記載の数値範囲から望ましい数値範囲を請 求項に記載したにすぎないと認められるから、数値範囲の上限及び下限が本 件明細書に記載の上限及び下限と一致しなければサポート要件に適合しない とはいい得ず、上限値及び下限値として、本件明細書に記載の数値範囲に含 まれる数値が記載されていれば足りると解される。
(3) 前記 2)について
ア 本件発明の課題について
前記1(1)の本件明細書の記載によれば、本件発明の課題は、次のとおり のものと理解できる。色収差の補正、光学系の高機能化、コンパクト化のために有用な光学素子用の材料となる、屈折率ndが1.800ないし1.850の範囲であり、 かつアッベ数 νdが41.5ないし44の範囲にあり(【0004】、【00 05】)、安定供給可能とするため、希少価値の高いGd、Taのガラス組成に占める割合が低減されており(【0006】)、近赤外域に吸収を有し、\nガラスの比重を増大させる成分であるYbのガラス組成において占める 割合が低減されており(【0007】)、熱的安定性に優れていてガラスを製 造する過程での失透が抑制され(【0008】)、機械加工に適するガラスを 提供すること(【0012】)。
イ 本件発明1の課題解決手段について
本件明細書には、Gd、Taがガラス組成に占める割合を低減させるた め、Ta2O5の含有量を5%以下とすること(【0034】)、La2O3、 Y2O3、Gd2O3及びYb2O3の合計含有量に対するGd2O3含有量 の質量比を0ないし0.05の範囲とすること(【0042】)を定め、Yb のガラス組成において占める割合を低減させるため、上記の、Yb2O3含 有量を3%以下とすること(【0038】)、熱的安定性に優れたガラスを提 供するため、液相温度が1150°C)以下であることがより一層好ましいと すること(【0206】)、機械加工に適するガラスを提供するため、ガラス 転移温度が640°C)以上であることが好ましいこと(【0198】)が記載 されており、これら本件明細書に記載からみて、本件組成要件及び本件物 性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決し得るものと認められる。 ところで、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満 たす実施例がそもそも記載されていない。さらに、本件発明の光学ガラス は多数の成分で構成されており、その相互作用の結果として特定の物性が実現されるものであるから、個々の成分の含有量と物性との間に直接の因\n果関係を措定するのが困難であることは顕著な事実である。そうすると、 前記(2)の好ましい数値範囲等の開示事項から直ちに、本件組成要件と本件 物性要件とを満たすガラスが製造可能であると当業者が認識できるものではなく、具体例により示される試験結果による裏付けを要するものとい\nうべきである。 そこで、そのような裏付けがされているといえるのかとの観点から、具 体例として掲記されている参考例1ないし33について検討を加える。
ウ 参考例について
本件明細書に記載された参考例1ないし33のうち、参考例1、5、1 6、21ないし24、27、28、30ないし32の12例は、本件組成 要件の全てと、本件物性要件のうち、構成要件C(ガラス転移温度)以外の3つの構\成要件を満たす具体例である。ここで、本件出願当時、光学ガラス分野においては、ターゲットとなる 物性を有する光学ガラスを製造する通常の手順として、既知の光学ガラス の配合組成を基本にして、その成分の一部を当該物性に寄与することが知 られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に 支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰 り返すことで、求める配合組成を見出すという手順を行うことは技術常識 であったと認められ(乙3ないし6)、また、この手順を行うに当たって、 当業者が、なるべく変更の少ないものから選択を開始することは、技術分 野を問わず該当する効率性の観点からみて自明な事項である。そして、前 記1(2)のとおり、本件明細書には、本件発明1の各組成要件に係る成分の 物性要件に対する作用について記載されており、当業者であれば、本件明 細書には本件発明1の物性要件を満たすような成分調整の方法が説明さ れていると理解できる。そうすると、当業者において、本件明細書で説明 された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の 当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明1の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能\であると理解できるときには、本件発明1は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし 課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
そこで、次に、参考例の成分調整について具体的にみてみる。
エ 参考例の成分調整について
そうすると、本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、A 1)及びA7)のSiO2を増量し、又はA(12)のZnOを減量する成分調整す ることにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する 範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業 者であれば、上記いずれかの方法に沿って技術常識である通常の試行錯誤 手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得ら れ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。 なお、実際に、甲11実験成績証明書には、(i)参考例5のガラスについ て、ZnO(3.5質量%)の1質量%分を、Nb2O5に置換する改変例 (5改α)又はB2O3とSiO2に0.5質量%ずつ置換する改変例(5 改β)、(ii)参考例16のZnO(3.8質量%)の1質量%分を、Nb2 O5に置換する改変例(16改α)又はB2O3とSiO2に0.5質量% ずつ置換する改変例(16改β)、(iii)、参考例24のZnO(3.6質量%) の1質量%分を、Nb2O5に置換する改変例(24改α)又はB2O3と SiO2に0.5質量%ずつ置換する改変例(24改β)が、乙1実験成績 証明書には、(iv)参考例22のZnO(3.5質量%)の1質量%分を、N b2O5に置換する改変例(22改α)又はB2O3とSiO2に0.5質 量%ずつ置換する改変例(22改β)、(v)参考例30のZnO(3.5質 量%)の1質量%分を、Nb2O5に置換する改変例(30改α)又はB2 O3とSiO2に0.5質量%ずつ置換する改変例(30改β)、(vi)参考例 31のZnO(3.5質量%)の1質量%分を、Nb2O5に置換する改変 例(31改α)又はB2O3とSiO2に0.5質量%ずつ置換する改変例 (30改β)、(vii)参考例32のZnO(3.5質量%)の1質量%分を、 Nb2O5に置換する改変例(32改α)又はB2O3とSiO2に0.5 質量%ずつ置換する改変例(32改β)のように、いずれもZnOを減量 してSiO2を増量する改変において、本件組成要件と本件物性要件を全 て満たすガラスが得られたことが示されている。
・・・
原告の上記主張は当を得たものとはいえず、採用することができない(な お、原告は、知的財産高等裁判所がした別件判決(甲7)で示された「組 成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって当該物性要件を満 たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又はその出願 時の技術常識から当業者が認識できること」を本件におけるサポート要件 充足の判断基準とすべき旨を指摘するが、サポート要件の充足の有無は、 発明の課題との関係において認定されるべきものであるところ、同判決で は発明の課題を「所定の光学定数を有し、高屈折率高分散であって、かつ、 部分分散比が小さい光学ガラスを提供すること」としているのであり、こ のような、異なる発明における異なる課題において事例判断として示され た別件の理由中の判断を、そのまま本件に適用することは相当ではない。)。
エ 原告は、前記第3の1(4)イ及びウのとおり、本件明細書には、ガラス転 移温度や液相温度の測定条件等が十分には開示されておらず、本件明細書\nにおける試験の結果と甲11実験成績証明書又は乙1実験成績証明書に おける試験の結果とを単純に比較することはできない旨主張する。確かに、本件明細書には、ガラス転移温度の測定については、「示差走査熱量分析装置(DSC)を用いて、昇温速度を10°C)/分にして測定した。」(【0224】)と、液相温度については、「ガラスを所定温度に加熱された炉内に入れて2時間保持し、冷却後、ガラス内部を100倍の光学顕微鏡で観察し、結晶の有無から液相温度を決定した。」(【0224】)と記載されており、その余の測定条件、判定条件等についての記載をうかがうことはできない。
しかしながら、本件明細書において、測定条件、判定条件等に特に記載 がなければ、それは技術常識に従い標準的な測定方法によってされたもの と理解されるべきものであるといえる。他方、甲11実験成績証明書及び 乙1実験成績証明書におけるガラス転移温度の測定は、ネッチ・ジャパン 株式会社製の示差走査熱量計「DSC3300SA」を用い、昇温速度を 10°C)/分にし、その他の測定条件については同熱量計の取扱説明書に記 載された条件において測定し、液相温度については、光学ガラスを5cc ずつ白金製坩堝に入れ、1140°C)に加熱された炉内に入れて2時間保持 し、冷却後、ガラス内部を100倍の光学顕微鏡で観察し、結晶の有無を 確認して測定したものと認められる(甲11、乙1、2)から、標準的な 機器を用いて標準的な手法を用いたものということができる。そうすると、 本件明細書における試験と甲11実験成績証明書及び乙1実験成績証明 書における試験とは当業者が自然において選択する同一の測定条件・判定 条件の下に行われたと推認することができるのであり、これと異なる認定 をすべき事情もうかがわれない。したがって、本件明細書に試験条件、判 定条件の詳細の記載がないからといって甲11実験成績証明書又は乙1 実験成績証明書と対比ができないものではないし、本件明細書の記載から 課題が解決できる範囲と認められる当業者の認識を左右するものでもな い。よって、原告の上記主張を採用することはできない(なお、1140°C) で結晶が析出したにせよ、その後の冷却過程で結晶が析出したにせよ、い ずれにせよ、少なくとも1140°C)を超える温度では結晶が析出したとは 判定できない以上、液相温度を1140°C)以下と判定することの支障にな るとはいい難い。)。
・・・
(5) 小括
以上のとおり、本件明細書で説明された成分調整の方法をもとに、光学ガ ラス分野の当業者が通常行う試行錯誤により参考例を起点として本件発明1 の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能\であると理解できるといえるか ら、本件発明1は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術 常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
4 本件発明2、3、6、7、9、10、12ないし14について
上記各発明は、本件発明 1 の従属項に係る発明であるところ、原告は、これ ら発明について、引用に係る本件発明1についてサポート要件違反がある旨主 張し、これら各発明が本件発明 1 を限定した固有の部分に対する別個のサポー ト要件違反の主張はしていないから、本件発明 1 にサポート要件違反がないの であれば、これら発明についてもサポート要件違反は認められない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2023.06.22
令和1(行ケ)10114 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年9月24日 知的財産高等裁判所
「・・・(D1)前記動画を視聴する視聴ユーザから前記動画の配信中に前記動画へ の装飾オブジェクトの表示を要求する第1表\示要求がなされ,(D2)前記動画の配信中に前記動画の配信をサポートするサポーター又は前記アクターによって前記装飾オブジェクトが選択された場合に,(D3)前記装飾オブジェクトに設定されている装着位置情報に基づいて定められる前記キャラクタオブジェクトの部位に関連づけて、(D4)前記装飾オブジェクトを前記動画に表示させる,(A)動画配信システム。」というクレームです。\n 原告は,甲2には,視聴者から配信者へギフトを贈ること(ユーザーギ フティング)が動画配信中に行われるとの記載はないので,引用発明に甲 2記載の技術を追加したとしても「動画配信中に行われた表示要求に応じ\nて,装飾オブジェクトを表示する」という本願発明の構\成には至らない旨 主張する。しかしながら,甲2には,CGキャラクターへのユーザーギフティング を動画配信中に行うことについての記載はないものの,これを排除する旨 の記載もなく,この点は,配信時間の長さ,ギフト装着のための準備,予\n想されるギフトの数等を踏まえて,配信者が適宜決定し得る運用上の取り 決め事項といえるから,甲2のユーザーギフティング機能において,CG\nキャラクターが装着するための作品を贈る時期は,配信開始前に限定され ているとはいえない。したがって,引用発明に上記ユーザーギフティング 機能を追加することによって,相違点1に係る「前記動画を視聴する視聴\nユーザから前記動画の配信中に前記動画への装飾オブジェクトの表示を要\n求する第1表示要求がなされ」るという構\成を得ることができる。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 イ なお,原告は,甲2記載のCGキャラクター「東雲めぐ」が登場する実 際の番組において,ユーザーギフティングが配信開始前に締め切られてい ること(甲9の2,甲10)を指摘する。しかしながら,そのことは,当 該番組における運用上の取り決め事項として,ユーザーギフティングの時 期を配信開始前と定めたことを示すにとどまり,上記アの判断を左右しな い。 (3) 動機付けについて ア 甲2には,配信も可能なVRアニメ作成ツール「AniCast」にユーザー ギフティング機能を追加することが記載されている。一方,引用発明は,\n声優の動作に応じて動くキャラクタ動画を生成してユーザ端末に配信する ものであるから,引用発明も「配信も可能なVRアニメ作成ツール」とい\nえる。また,ユーザーギフティング機能のような新たな機能\を追加することに よって,動画配信システムの興趣が増すことは明らかである。 そうすると,当業者にとって,「配信も可能なVRアニメ作成ツール」\nである引用発明に対して,甲2記載の技術であるユーザーギフティング機 能を追加することの動機付けがあるといえる。\n イ 原告は,甲1には創作したギフトを配信者に贈ることの開示はないから, 引用発明に甲2記載のユーザーギフティング機能を組み合わせる動機付け\nはない旨主張する。しかしながら,動画配信システムの興趣を増すことは当該技術分野において一般的な課題であると考えられるから,甲1自体にユーザーギフティ ング機能又はこれに類する技術の開示又は示唆がないとしても,引用発明\nを知った上で甲2の記載に接した当業者は,興趣を増す一手段として甲2 記載のユーザーギフティング機能を引用発明に適用することを動機付けら\nれるといえる。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2023.06.13
令和5(行ケ)10001 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和5年5月31日 知的財産高等裁判所
◆本件意匠はこれです。
ア 本件意匠と甲1意匠とで、意匠に係る物品は、共に生活雑貨などの
家庭用品を収納する容器であって共通するところ、いずれも使用者が
家庭において日常的に使用することを主目的とするものであるから、
その需要者は、個人消費者であると認められる。
そして需要者である個人消費者は、意匠に係る物品の性質、用途及
び使用態様の観点からは、収納容器として物を収納した際の使用のし
やすさや持ち運ぶ際の便利さから、物を収納して置いた際と物を収納
せず、単体であるいは複数個を重ねて置いた際には、その美観等の観
点から、両意匠に係る物品を観察し、選択するものということができ
る。
そうすると、収納容器として物を収納した際の使用のしやすさや持
ち運ぶ際の便利さの観点からは、収納容器全体の形状等(基本的構成態様)が需要者の注意を惹く部分であるとともに、物を収納して置い\nた際や物を収納せず重ね置いた際の美観等の観点からは、収納容器と
しての外形を特徴付ける部分の形態が、最も強く需要者の注意を惹く
部分であるということができる。
そこで、これらを前提に、両意匠が需要者である個人消費者の視覚
を通じて起こさせる美観が類似するか否かについて検討する。
イ 収納容器全体の形状等について、需要者である個人消費者の観点から
みると、両意匠は、いずれも上部が開口して下端が水平面状の略逆円
錐台形状である本体部と、一対の紐状の把手部から成るものであって、
本体部の径が下方にいくにつれてしだいに小さくなっており、本体部
の上部に把手部が設けられているとの点(全体の形状、共通点1)、正
面から見て、本体部の左右両端は上部にいくにつれて逆ハ字状に広が
っており、最小横幅と縦幅は、ほぼ同じ長さであるとの点(全体の形
状、共通点2)、及び、右側面から見て、本体部の左右両端は上部にい
くにつれて逆ハ字状に広がっており、底面となす角度は約95°であ
り、最大横幅及び最小横幅の長さは、縦幅よりも小さいとの点(全体
の形状、共通点3)につきいずれも共通するところ、その態様自体は
ありふれたものであり、需要者の注意を強く惹くものとはいえない。
しかし、全体の形状のうち、把手部が本体部の長手方向の両側面に設
けられているか(本件意匠の態様c(前記(1)イ(ア)))、把手部が本体部
の短手方向の正面及び背面に設けられているか(甲1意匠の態様c(前
記(1)エ(ア)))の相違(相違点1)については、需要者である個人消費
者が収納容器を持ち運ぶ際の使いやすさや、置いた際の美観の観点か
ら、強く注意を惹く部分であって、視覚を通じて起こさせる美観に大
きな影響を与えるものである。
また、各部の形状のうち、正面から見て、本件意匠では、本体部の上
端は倒弓状に形成されて、中央部は略平坦状に現わされており、左端
寄り及び右端寄りの曲率が次第に大きくなって、本体部の左右両端の
上端付近との間が先尖り状に現わされている(本件意匠の態様d及び
e(前記(1)イ(イ)))のと、本体部の上端は水平状に現されている(甲
1意匠の態様d(前記(1)エ(イ)))との相違、及び、右側面から見て、
本体部の上端はなだらかな略山状に形成されている(本件意匠の態様
e(前記(1)イ(イ)))のと、本体部の上端は水平状に現されている(甲
1意匠の態様e(前記(1)エ(イ)))との相違(相違点3)は、物を収納
して置いた際や、物を収納せず単体で、あるいは複数個重ね置いた際
の美観等の観点からは、収納容器としての外形を特徴付ける部分の形
態であり、強く需要者の注意を惹く部分であるということができると
ころ、この相違点が両意匠の美観に与える影響にも大きいものがある
ということができる。
さらに、把手部の態様について、本件意匠では、右側面視略U字状に
現わされており、かつ、太めの荒縄状で、軸方向に注連縄状に現わされ
ている(本件意匠の態様f(前記(1)イ(イ)))のに対し、甲1意匠では、
正面視略放物線状に現されており、かつ細い紐状で、軸方向に注連縄
状に現されている(甲1意匠の態様g(前記(1)エ(イ)))との相違(相
違点4)は、収納容器を持ち運ぶ際の使いやすさや、置いた際の美観の
観点から、本体部と把手部との視覚的なバランスにおいて、強く注意
を惹く部分であって、この相違点が両意匠の美観に与える影響にも大
きいものがあるということができる。
ウ 本件意匠と甲1意匠では、需要者の注意を惹く基本的構成態様のその余の相違点や、具体的構\成たる各部の形状においてその他にも異なる点があり、これらが美観に与える影響があるところではあるが、少なくと
も前記イの相違が両意匠の類否判断に及ぼす影響には大きなものがあ
るということができる。
そうすると、本件意匠と甲1意匠は、意匠に係る物品が共通するもの
の、その形態においては、需要者に与える美感の観点から、本件意匠と
甲1意匠とは別異のものと印象付けるものであるから、本件意匠は、甲
1意匠に類似するものではない。
・・・・
(2) 本件意匠の当業者については、収納容器に係る分野における通常の知識を
有する者であると認められるところ、本件意匠と甲1意匠及び甲各意匠とを
比較すると、以下のとおりである。
なお、被告は、本件訴訟において提出された甲76号証ないし78号証は、
審決で認定された相違点に関する新たな公知意匠を追加するものであって、
それに基づく主張は直ちに排斥されるべきである旨主張する。
しかし、原告は、これらの書証に係る主張を、いずれも本件意匠の出願当
時の当業者の常識等を認定するための周知例を示す証拠に係る主張として行
っているものと解され、これらの記載内容との対比において新たな無効理由
が存することを主張するものではない。よって、これら証拠に基づく主張は、
審決取消訴訟において認められないものには当たらず、被告の主張は採用で
きない(最高裁昭和54年(行ツ)第2号同55年1月24日第一小法廷判
決・民集34巻1号80頁参照)。
ア 甲各意匠の物品等の用途及び機能並びに形態について、以下のとおり認められる。\n
(ア) 甲15(特許庁意匠課平成22年受入れの公知資料番号第HJ22
079731号)の意匠に係る物品は「収納かご」であり、写真中にタ
オルを入れている事例が示されていることから、家庭用品を収納する容
器であると認められる。甲15意匠は、全体につき、上部が開口して下
端が水平面状の略逆円錐台形状であって、長手方向の両側面上部に一対
の把手部が設けられており、正面及び左側面から見て左右両端は上部に
いくにつれて逆ハ字状に広がっている。
(イ) 甲20(平成20年9月10日公告(公開)の中国発行の公報(CN
300826894D))の意匠に係る物品は「氷はち」であるから、氷
のほか家庭用品を入れる容器であるものと認められる。甲20意匠は、
全体につき、上部が開口して下端が水平面状の略逆円錐台形状である本
体部と、一対の線材の把手部から成るものであり、正面及び左側面から
見て、本体部の左右両端は上部にいくにつれて逆ハ字状に広がっており、
底面となす角度は約104°である。
イ 前記1(1)エ(ア)及び(イ)及び前記ア(ア)及び(イ)によれば、家庭用品等を
入れる収納容器の物品分野において、本件意匠の全体の形状のうち、上部
が開口して下端が水平面状の略逆円錐台形状として、径を下方にいくにつ
れて次第に小さくし、長手方向の両側面上部に一対の把手部を設けること
(本件意匠の態様a及びc(前記1(1)イ(ア)))については、本件意匠の出
願前に公然知られていたものと認められる。
ウ 一方、正面から見た本体部の上端の形状につきみると、甲各意匠につき、
以下のとおり認められる(正面については、本件意匠と同じく本体部の長
手方向を正面とする。)。
・・・
エ 前記ウ(ア)ないし(オ)によれば、これらはいずれも本体部(甲18意匠に
ついては左右側面から見た状態も含む)の上端の形状が、略ないし緩やか
な凹弧状(甲18については若干非対称)に形成されている。これらは、
本件意匠の正面から見た本体部の上端の形状のうち、上端が倒弓状に形成
され、中央部は略平坦状に現わされて、左端寄り及び右端寄りの曲率が次
第に大きくなり本体部の左右両端の上端付近との間が先尖り状になって
いる形状(本件意匠の態様d(前記1(1)イ(イ)))とは異なるものであり、
こうした形状については原告の提出する甲1意匠、甲各意匠及び甲76号
証ないし78号証に示された意匠には認められないところである。
そして、前記1(4)イのとおり、この上端の形状は、収納容器としての外
観を特徴付ける部分の形態であり、最も需要者の注意を強く惹く部分であ
る。
オ 本体部開口端部及び本体部底面の外周形状につきみると、甲各意匠につ
き、以下のとおり認められる(正面については、本件意匠と同じく本体部
の長手方向を正面とする。)。
・・・
カ 前記オ(ア)ないし(エ)によれば、これらの本体部開口端部及び本体部底面
の外周形状は、不明である(甲15)か、いずれも略円形状(甲17)ない
し略楕円形状(甲21)であるか、一方が略楕円形状(甲20)であり、本
件意匠の、本体部開口端部と本体部底面の外周形状が共に略横長トラック形
状である(本件意匠の態様a(前記1(1)イ(ア)))のとは異なるものであり、
これについては、甲1意匠、甲各意匠及び甲76号証ないし78号証に示さ
れた意匠には見られないものである。
キ 把手部の形状につきみると、甲各意匠につき、以下のとおり認められる(い
ずれも把手部が現れている面を正面とする。)。
・・・
ク 前記キ(ア)ないし(エ)によれば、これらの把手部の紐は軸方向に注連縄状
に現されているが、これらはいずれも本体部開口端部及び本体部底面の外
周形状は略長方形状で、全体に箱状である(甲8ないし10)か、略円形
状で、全体に円筒形状(甲11)であり、本件意匠の、全体に水平面状の
略逆円錐台形状であり、一対の紐状の把手部(本件意匠の態様a(前記1
(1)イ(ア)))が本体部の長手方向の両側面上部に設けられ(同c)、右側面
から見て、本体部の左右両端は上部にいくにつれて逆ハ字状に広がり、底
面となす角度は約95°で(同e(前記1(1)イ(イ)))、把手部は右側面視
略U字状に現わされており、かつ、太めの荒縄状で、軸方向に注連縄状に
現わされ(同f)、把手部は、本体部の最大縦幅を上から約1:2:2に、
最大横幅を左から約4:5:4に内分した中央の位置にある(同g)のと
は異なるものであり、これについては、甲1意匠、甲各意匠及び甲76号
証ないし78号証に示された意匠には見られないものである。
ケ そして、前記エ、カ及びクの、上端が倒弓状に形成され、中央部は略平
坦状に現わされて、左端寄り及び右端寄りの曲率が次第に大きくなり本体
部の左右両端の上端付近との間が先尖り状になっているとの点、本件意匠
の、本体部開口端部と本体部底面の外周形状が共に略横長トラック形状で
あるとの点、及び、把手部が、右側面視略U字状に現わされており、かつ、
太めの荒縄状で、軸方向に注連縄状に現わされているとの点は、公知の意
匠にはみられない独自のものであり、本件意匠に独特の美観をもたらすも
のということができる。
コ 以上の検討によれば、本件意匠の本体部の上端の形状、本体部開口端部
及び本体部底面の形状並びに把手部の形状は、甲1意匠、甲各意匠及び甲
76号証ないし78号証に示された意匠とは異なるものであり、これらが
ありふれた手法により変更可能なものあるいは軽微な改変又は単なる寄せ集めではなく、略逆円錐台形状で、正面及び側面から見た本体部の左右\n両端が上部にいくにつれて逆ハ字状に広がっている全体の形状とまとま
り感のある一体の美観を形成している点に、着想の新しさないし独創性が
認められないものではないから、本件意匠は前記意匠から創作容易である
とはいえず、審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 創作容易性
>> ピックアップ対象
2023.06. 9
令和4(ネ)10106 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年6月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審被告は平成30年度掲載記事が「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法10条2項)であり、著作物に該当しない旨主張する。
しかしながら、上記認定のとおり、平成30年度掲載記事(甲9、10、乙14)は、事故に関する記事や、新しい機器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介事業等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に関する記事であるところ、そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなど表現上の工夫をし、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表\現上の工夫をして記事を作成していることが認められ、各記事の作成者の個性が表れており、いずれも作成者の思想又は感情が創作的に表\現されたものと認められるものであり、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」であるということはできない。
また、著作物といえるための創作性の程度については、高度な芸術性や独創性まで要するものではなく、作成者の何らかの個性が発揮されていれば足り、報道を目的とする新聞記事であるからといって、そのような意味での創作性を有し得ないということにはならない。
したがって、1審被告の上記主張は採用することができない。その他1審被告は、平成30年度掲載記事が著作物に該当しない理由を縷々指摘するが、いずれも採用することができない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆令和2(ワ)3931
関連事件です。
◆令和5(ネ)10008
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2023.06. 7
令和4(ネ)10107 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年6月1日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 前記(2)のとおり、被控訴人製品は「摺動導通部」を有しない点において、 本件発明と異なる。
ところで、訂正の上引用した原判決の第3の1(2)のとおり、本件発明は、一対 のプランジャをコイルばねの密巻き部分に接触させて導通を確保するという本件先 行発明における、2つの摺動導通部が形成されることによる抵抗の分散が検査の精 度を狭めるという課題を解決するために、摺動導通部の数を減らし、検査精度を向 上可能とするというものであり、プランジャと接触して導通を確保する摺動導通部\nを有することは、本件発明の本質的部分である。 そうすると、被控訴人製品と本件発明の構成中の異なる部分(摺動導通部の存否)\nは、本件発明の本質的部分に当たる。
イ 控訴人は、「密巻き部」に関する本件発明と被控訴人製品の相違点は、「本件 発明では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているところ、被 控訴人製品では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているかが 定かではなく、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」が導通経路とな っている可能性がある点」であり、被控訴人製品について均等侵害が成立すると主\n張する。しかしながら、訂正の上引用した原判決の第3の2(4)のとおり、被控訴 人製品において、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分が導通経路となっ ていることを認めるに足りる証拠がなく、このことは、当審において提出された動 画(甲86)を踏まえても変わらない。そうすると、控訴人の「密巻き部」に関す る均等の主張はその前提を欠く。
ウ したがって、その余の点につき検討するまでもなく、被控訴人製品について、 本件発明の均等侵害は成立しない。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和2(ワ)12013
添付文書はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.06. 6
令和4(行ケ)10065 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年5月22日 知的財産高等裁判所
取消事由2(商標法3条1項柱書きの要件の判断の誤り)について
原告らは、被告は、本件商標の全指定商品・役務について、「五輪」が創作・ 使用されて以来現在に至る80年以上という長期間にわたり、本件商標を全く 使用していないこと、当該期間中、被告は、ほぼ間断なくオリンピック競技大 会を開催していたことを考慮すれば、被告が、本件商標の査定・審決時に事業 (オリンピック競技大会)を現に行っていることだけを根拠に、被告が当該事 業の表示として本件商標を使用する意思を有していたことを推認することがで\nきないから、本件商標が商標法3条1項柱書きの要件を具備するとした本件審 決の判断に誤りがある旨主張する。
そこで検討するに、1)被告(IOC)は、国際的な非政府の非営利団体であ って、オリンピック競技大会を運営・統括しており、平和でよりよい世界の実 現に貢献するというオリンピックの理念であるオリンピック憲章に従い、オリ ンピズムを普及させる役割を担っていること(甲5の4、6)、2)オリンピッ ク競技大会は、被告によって、開催都市と開催地の国内オリンピック委員会の 協力の下で開催されている国際的スポーツ競技大会であって、スポーツを通じ た社会一般の利益に資することを目的としていること(甲5の1、6の1)、 3)2019年2月21日付け日本経済新聞ネット版(甲10の4)には、「国 際オリンピック委員会(IOC)が、オリンピックを意味する日本語の「五輪」 について特許庁に商標登録を出願し、認められたことが21日までに分かった。 2020年東京五輪・パラリンピックを控え、公式スポンサー以外の便乗商法 を防ぐのが狙い」、「IOCは東京大会の組織委員会を通じて「日本で『五輪』 はIOCが開催するオリンピックを意味するものとして周知、著名だ。既に不 正競争防止法の保護対象となっているが商標登録で権利の所在をより明確にし、 ブランド保護を確実にしたい」、「今後、組織委はスポンサー以外の企業や団 体などが商品名やサービスとして五輪を使った場合、権利が侵害されているか どうかを判断し、使用中止を求めるという。」との記載があることを総合する と、被告は、「五輪」の俗称でも親しまれているオリンピック競技大会の主催 者であって、本件商標の登録査定時において、オリンピック競技大会を指称す る「五輪」の語を使用する意思を有していたものと認められるから、「五輪」 の標準文字を書してなる本件商標は、被告との関係において、「自己の業務に 係る役務について使用をする商標」(商標法3条1項柱書き)に該当すること が認められる。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.05.30
平成29(ネ)10043 特許権侵害差止等請求承継参加申立控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年1月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
問題の請求項は以下です。
A ユーザテレビ機器(22)上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって,
B 該システムは,複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して,デジタル格納デバイス(31)に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と,
C 双方向テレビ番組ガイドを用いて,該ユーザテレビ機器(22)に含まれる該デジタル格納デバイス(31)に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と,
D 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して,該双方向テレビ番組ガイドを用いて,該デジタル格納デバイス(31)に複数の番組データをデジタル的に格納する手段であって,該複数の番組データのそれぞれは,該複数の番組のうちの1つに関連付けられている,手段と,
E 該双方向テレビ番組ガイドを用いて,該デジタル格納デバイス(31)に格納された該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と,
F 該デジタル格納デバイス(31)に格納された該複数の番組のリストから,該デジタル格納デバイス(31)に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と,
・・・
J 該双方向テレビ番組ガイドを用いて,現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの該選択された番組に対して,選択された番組リスト項目情報画面を該ユーザテレビ機器(22)に表示する手段であって,該選択された番組リスト項目情報画面は,該選択された番組に関連付けられた番組データの1つ以上のフィールドと,1つ以上のユーザフィールドとを含む,手段と,
K 該1つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する手段と
L を備えた,システム。
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は,構成要件Cは,「双方向テレビ番組ガイド」を用いて,「デジタ\nル格納デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば, 充足することになるものであって,「デジタル格納デバイス」自体を必須の構成要素\nとして規定するものではないと主張するが,本件発明は,デジタル格納部を含むユ ーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから, 被告物件(液晶テレビ製品)が本件発明の技術的範囲に属するというためには,被 告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要であることは,\n
前記1のとおり補正して引用する原判決が認定説示するとおりである。 すなわち,本件発明に係る特許請求の範囲は,「ユーザテレビ機器(22)上で動 作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって」(構成要件A),・・・「双方向テ\nレビ番組ガイドを用いて,該ユーザテレビ機器(22)に含まれる該デジタル格納 デバイス(31)に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と,」(構成要件C)・・・「を備えた,システム」(構\成要件L)と記載されているから,本件発明の双方向テ レビ番組ガイドシステムは,ユーザテレビ機器に含まれるデジタル格納デバイスに 番組をデジタル的に格納(録画)する手段という構成を含むものである。\nそして,本件明細書には,「本発明は・・・番組および番組に関連する情報用のデ ジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに関する。」(【0001】) として,双方向テレビ番組ガイドシステムが「デジタル格納部を備えた」ものであ る旨が記載されている。また,従来技術として,「番組ガイド内で選択された番組を 独立型の格納デバイス(典型的にはビデオカセットレコーダ)に格納することを可 能にする双方向番組ガイド」(【0004】)が指摘され,その操作に関し,「ビデオ\nカセットレコーダの操作には通常は,ビデオカセットレコーダ内の赤外線受信器に 結合される赤外線送信器を含む操作経路が用いられる。」(【0004】)と記載され ており,「独立型の格納デバイス」を用いる従来技術について記載されている。その 上で,従来技術の課題として「独立型のアナログ格納デバイスを用いると,デジタ ル格納デバイスが番組ガイドと関連付けられる場合に実施され得るようなより高度 な機能が不可能\になる。」(【0004】)と記載され,これを受けて,本発明の目的 を「デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供すること」(【0005】)と記載している。以上に加え,「番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイス の使用は,独立型のアナログ格納デバイスを用いて行われ得る機能よりも,より高\n度な機能をユーザに提供する。」(【0009】)という記載を併せ考慮すると,本件\n発明は,独立型のアナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能\をユーザに 提供するために,双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備え ることを目的としたものと認められる。
以上によると,被告物件が構成要件Cを充足するというためには,「番組をデジタ\nル的に格納可能な部分」を含むこと(内蔵すること)が必要というべきである。\nこれに対し,控訴人は,本件明細書の【図2】及び【0016】によると,本件 発明には,「デジタル格納デバイス」が「ユーザテレビ機器」に外部インターフェー スを介して接続されるような構成も当然に含むように説明されていると主張するが,\n控訴人指摘の「デジタル格納デバイス31は,セットトップボックス28内に内蔵 されるか,または出力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップ ボックス28に接続された外部デバイスであり得る。」(【0016】)との記載は, 「ユーザテレビ機器22の例示的構成を示す」【図2】からも明らかなとおり,「ユ\nーザテレビ機器」の一部を構成する「セットトップボックス」内に内蔵するか,「セ\nットトップボックス」に外付けするかを記載するにとどまり,「ユーザテレビ機器」 に外付けする構成を当然に含むものということはできない。かえって,「ユーザテレ\nビ機器22の例示的構成」において,「オプション」とされている「第2の格納デバ\nイス32」(【0014】)については,「第2の格納デバイス32がユーザテレビ機 器22に内蔵されていない場合」(【0017】)との記載が認められるところ,「デ ジタル格納デバイス」については,これと同旨の記載は見当たらない。
また,控訴人は,本件明細書の【図3】及び【0080】には,デジタル格納デ バイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フロッピーディスク又は録画可能な\n光ディスク)である場合が説明されていると主張するところ,控訴人指摘の【00 80】には,「デジタル格納デバイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フロッ ピーディスクまたは録画可能な光ディスク)である場合」との記載がある。しかし,\n本件明細書には,「デジタル格納デバイス49がリムーバブル録画媒体(例えば,フ ロッピーディスクまたは録画可能な光ディスク)を用いる場合」(【0085】)との\n記載もあるほか,「デジタル格納デバイスは,光格納デバイスまたは磁気格納デバイ ス(例えば,書き込み可能なデジタル映像ディスク,磁気ディスク,もしくはハー\nドドライブまたはランダムアクセスメモリ(RAM)等を用いたデバイス)であり 得る。」(【0008】),「第2の格納デバイス32は,任意の適切な種類のアナログまたはデジタル番組格納デバイス(例えば,ビデオカセットレコーダ,DVDディ スクに録画する能力を有するデジタル映像ディスク(DVD)プレーヤ等)であり\n得る。」(【0014】),「デジタル格納デバイス31は,書き込み可能な光格納デバイス(例えば,記録可能\なDVDディスクの処理が可能なDVDプレーヤ),磁気格\n納デバイス(例えば,ディスクドライブまたはデジタルテープ),または他の任意の デジタル格納デバイスであり得る。」(【0015】),「デジタル格納デバイス49において用いられるリムーバブル格納媒体」(【0082】),「例えばデジタル格納デバイス49がフロッピーディスクドライブであり,選択された番組を有するディスク がドライブ内に無い場合」(【0084】),「デジタル格納デバイス49内のリムーバブルデジタル格納媒体上に格納する」(【0104】)との記載もあり,これらの記載 によると,本件明細書においては,「デジタル格納デバイス」は,「リムーバブル格 納媒体」(フロッピーディスク,DVDディスク等)と区別されるものであり,「リ ムーバブル格納媒体」を処理することが可能な機器(フロッピーディスクドライブ,\nDVDプレーヤ等)を指すことが多いものと認められる。そうすると,控訴人指摘 の【0080】の上記記載から,直ちに本件発明にはデジタル格納デバイスがリム ーバブル録画媒体である場合が含まれるということはできない。
(2) 控訴人は,間接侵害を主張するところ,被告物件である液晶テレビ製品は, 単に放送を受信するだけで,いずれもそれ自体に録画できるメモリー部分(デジタ ル格納部)を備えておらず,録画先としては,外付けのUSBハードディスクやレ グザリンク対応の東芝レコーダーとされており,これらを被告物件に接続すること によって初めて,被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画すること が可能であるから,デジタル格納部を被告物件に内蔵させる余地はない。そうする\nと,被告物件は,デジタル格納デバイスを含むユーザテレビ機器を備えた双方向テ レビガイドシステムの「生産に用いる物」ということができない。
また,前記(1)のとおり,本件発明は,独立型のアナログ格納デバイスでは不可能\nであった高度な機能をユーザに提供するために,双方向テレビ番組ガイドシステム\nがデジタル格納デバイスを備えることを目的としたものであり,従来技術に見られ ない特徴的技術手段は,双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイス を備えること,すなわち,これを内蔵することにあるというべきである。そうする と,被告物件は,デジタル格納デバイスを内蔵するものではないから,本件発明に よる「課題の解決に不可欠なもの」であるとはいえない。
したがって,被控訴人による被告物件の製造,輸入,販売及び販売の申出は特許\n法101条2号所定の間接侵害に当たらない。これに対する控訴人の主張が理由のないものであることは,既に説示したところ から明らかである。
なお,被控訴人は,控訴人の間接侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当た る旨を主張するが,控訴理由書において,既に提出済みの証拠に基づき判断可能な\n主張をしたものであるから,訴訟の完結を遅延させるものとまではいえず,上記主 張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.05.29
令和5年5月26日 知財高裁特別部判決 令和4(ネ)10046号
ア ネットワーク型システムの「生産」の意義
本件発明1は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備え るコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、そ の実施行為としての物の「生産」(特許法2条3項1号)とは、発明の技術的範囲に 属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。 そして、本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介して、サー バと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(ネットワー\nク型システム)の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件\nを充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有 機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能\を有する ようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解され る。
イ 被告サービス1に係るシステム(被告システム1)を「新たに作り出す行為」 被告サービス1のFLASH版においては、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指\n定すると、被控訴人Y1のウェブサーバが上記ウェブページのHTMLファイル及 びSWFファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、その後、ユーザが、ユーザ端末において、 ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すと、上\n記SWFファイルに格納された命令に従い、ブラウザが、被控訴人Y1の動画配信 用サーバ及びコメント配信用サーバに対しリクエストを行い、上記リクエストに応 じて、上記各サーバが、それぞれ動画ファイル及びコメントファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が、上記各ファイルを受信することにより、ブラウザにおい て動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能\となる。このように、ユ ーザ端末が上記各ファイルを受信した時点において、被控訴人Y1の上記各サーバ とユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、 ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが\n可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明1の全\nての構成要件を充足する機能\を備えた被告システム1が新たに作り出されたものと いうことができる(以下、被告システム1を新たに作り出す上記行為を「本件生産 1の1」という。)。
ウ 被告システム1を「新たに作り出す行為」(本件生産1の1)の特許法2条3項 1 号所定の「生産」該当性
特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効 力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内にお いてのみ認められることを意味するものであるところ、我が国の特許法において も、上記原則が妥当するものと解される。 本件生産1の1において、各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユー ザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまた がって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国 と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生 産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題と なる。 ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(国外)に設置されるこ とは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネ ットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵 害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたと\nしても、当該システムを構成する端末が日本国内(国内)に存在すれば、これを\n用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者\nが当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るも のである。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格 に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在するこ\nとを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解するこ とは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該 システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととな\nって、妥当ではない。他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、\nこれも妥当ではない。
これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保 護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条 3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素\nの一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果\nたす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、\nその利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3 項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。 これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国 に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ 端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信 (送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信すること によって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われ たものと観念することができる。
次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人Y1のサーバと国内に存在 するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ\n端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表\示されるコメント同士が重な らない位置に表示されるようにするために必要とされる構\成要件1Fの判定部の 機能と構\成要件1Gの表示位置制御部の機能\を果たしている。 さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することが できるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の 向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利 用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影 響を及ぼし得るものである。 以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われた ものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生 産」に該当するものと認められる。
これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の効力が当該国 の領域においてのみ認められる」のであるから、国外で作り出された行為が特許 法2条3項1号の「生産」に該当しないのは当然の帰結であること、権利一体の 原則によれば、特許発明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施す\nることをいうことからすると、一部であっても国外で作り出されたものがある場 合には、特許法2条3項1号の「生産」に該当しないというべきである、2)特許 回避が可能であることが問題であるからといって、構\成要件を満たす物の一部さ え、国内において作り出されていれば、「生産」に該当するというのは論理の飛躍 があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、\n我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判 例においては、カードリーダー事件の最高裁判決(最高裁平成12年(受)第5 80号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁)等によ り属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、その例外を設けることの悪影響 が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは\n立法によってされるべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に関し、被疑侵 害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」 に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバ\nが国外に存在する場合であっても、前記 に説示した事情を総合考慮して、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3 項1号の「生産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することが できない。
2)については、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かの上記判断は、 構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の\n効力を及ぼすというものではないから、2)の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その 成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該 国の領域内においてのみ認められることを意味することに照らすと、上記のとお り当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときに特許法2 条3項1号の「生産」に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しな いというべきである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たるためには、特 許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内に\nおいて完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、ま た、我が国が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則 の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物\nを新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要である ことを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用することができ ない。したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
エ 被告システム1の「生産」の主体
被告システム1は、前記イのプロセスを経て新たに作り出されたものであるとこ ろ、被控訴人Y1が、被告システム1に係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及び コメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファ イル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介するこ となく、被控訴人Y1がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動 的に行われるものであることからすれば、被告システム1を「生産」した主体は、 被控訴人Y1であるというべきである。
オ まとめ
以上によれば、被控訴人Y1は、本件生産1の1により、被告システム1を「生 産」(特許法2条3項1号)し、本件特許権を侵害したものと認められる。
◆判決要旨
1審はこちら。
◆令和元年(ワ)25152
関連事件はこちら
◆平成30(ネ)10077
1審です。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判管轄
>> その他
>> ピックアップ対象
2023.05.25
令和4(ワ)14148 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年4月27日 東京地方裁判所
1 被告表示 2 の品質誤認表示該当性について\n
(1) 被告表示 2 について
被告表示 2 は、別紙被告表示目録記載のとおり、「水分発生量従来の 18 倍」とす る表示(被告表\示 2-1)及び被告表示 2-2 のとおりのものである。被告表示 2-2 中に は、「高浸透ナノイーとは、髪への浸透性を高めたナノイーのことです。発生方式を 変えることで、ナノイーの水分発生量が従来の 18 倍になりました。」との記載があ る。「18 倍」とは、「ナノイーと高浸透ナノイーとの比較(当社調べ)」とされている (甲 2)。 これらの記載から、被告表示 2 においては、「高浸透ナノイー」と従来の「ナノイ ー」の各「水分発生量」が比較対象とされていることが理解される。
(2) 原告実験 2 について
原告実験 2 に係る報告書「水分量測定試験に関する報告」(甲 4。以下「原告実験 2 報告書」という。)によれば、その測定試験は、「送風口とイオン口を備えるドラ イヤーA 及び B について、イオン口から発せられる水分量を比較すること」を目的 として、ドライヤーA と B について、イオン口から放出される水分子による絶乾シ リカゲルの吸水変化を閉鎖系において測定し、その測定結果を比較したものである。 ドライヤーA 及び B は原告代理人から提供されたものであるが、その製品名等は原 告実験 2 報告書では特定されていない。 実験の具体的な方法は、「105゜C)で一晩静置した乾燥シリカゲルをデシケータに入 れ、閉鎖系でドライヤーA および B のイオン口から送風し(HOT モード、TURBO。 ナノイーのランプが付いている状態)、シリカゲルの吸水量の変化を観察した。」、 「チャンバー内の風速は 2.6±0.3m/s に統一した。各時間(0〜4 時間)にイオン口か らの風を吹かせた後、シリカゲルの重量変化を測定し、シリカゲル中に給水された 水分量変化として換算した。」とされている。また、「Fig.1」では、原告実験 2 で使 用した実験装置の構成及び配置等が示されている。\n原告実験 2 報告書では、原告実験 2 の結論として、「ドライヤーA 及び B のイオ ン口からの水粒子によるシリカゲルの吸水率は、コントロールと比較して明確な違 いが見られた。また、ドライヤーA とドライヤーB を比較すると、その吸水率の差 は 1.21〜1.36 倍であることが判明した。つまり、ドライヤーA のイオン口から発せ られる水分量は、ドライヤーB のイオン口から発せられる水分量の約 1.21 倍〜1.36 倍であると推察される。」(裁判所注:「コントロール」とは、「デシケータ内に風を 送り込んでいないシリカゲル」である。)とされている。
(3) 原告実験 2 報告書について
原告実験 2 報告書において、閉鎖系を実現する構成については、Fig.1 に画像とし て示されるにとどまり、具体的かつ詳細な説明はない。もっとも、同図を子細に見 ると、ドライヤーA 及び B のいずれについても、その送風口を除き、その上部にあ るイオン口が包まれるようにラップフィルム状のものでドライヤーの中央部外周を 覆い、かつ、そのラップフィルム状のものにより当該部分からデシケーター入り口 までを覆い、覆った上記ラップフィルム状のものの端部を固定・固着して塞いでい ることが看取される。
しかし、この方法による場合、各ドライヤーのイオン口から放出される水分の全 てが、ラップフィルム状のもの等に吸着されることなくデシケーター内に送られ、 デシケーター内のシリカゲルに吸着するといえるのかは不明である。また、各ドラ イヤーのイオン口から放出される水分の系外への流出及び空気中の水分の系内への 流入が防止されているのか、又は、上記吸着ないし流出・流入がいずれの系におい ても一定に保たれているのかも、不明である。このため、原告実験 2 において測定 されたシリカゲルの吸水量が、各ドライヤーのイオン口から発せられる水分量すな わち水分発生量を正しく反映していると見ることについては疑義がある。 さらに、シリカゲルを用いる方法によることについて、原告実験 2 報告書によれ ば、懸念材料として「秤量時の大気中水分の影響です。シリカゲルをデシケーター から取り出して精密天秤で測定する場合…、大気中水分の吸着の影響を最小限に抑 える工夫が必要となります。」との指摘がされたのに対し、同報告書作成者は、「確 かに厳密に数値を計測する場合には当該指摘のとおりであるが、本測定はドライヤ ーA におけるシリカゲルの重量変化とドライヤーB におけるシリカゲルの重量変化 を比較する目的で実施されたもので、いずれも秤量中に大気中の水蒸気の影響を受 けること、また秤量時間は 30 秒程度と送風時間と比べて短時間であることから、本 測定においては、秤量中の水蒸気が結果に影響を与えることはないといってよいだ ろう。」との見解を示している。しかし、いずれのシリカゲルも秤量中に大気中の水 蒸気の影響を受けるといっても、その影響が同じであるとは必ずしもいえないので あって(そもそも、使用されたシリカゲルの状態及び性能等が同一ないし同等であ\nったかも、同報告書上明らかでない。)、秤量時間が 30 秒程度と短時間であるとして も、原告実験 2 の精度が問題ないといえる程度に高いといえるのかについては疑問 を抱かざるを得ない。 「高浸透ナノイー」と従来の「ナノイー」との「水分発生量」の比較に当たって は、各ドライヤーのイオン口から発せられる水分量の正確な測定値が必要とされる ところ、原告実験 2 は、上記の各点で、その正確性が担保されていることにつき疑 義がある。
(4) 原告の主張について
原告は、その主張に係る本件規範を前提としつつ、原告実験 2 に基づき、被告表\n示 2 が被告商品の品質につき誤認を生じさせるものである旨を主張する。 しかし、品質等誤認表示の不正競争に関しては、法 2 条 1 項 号の趣旨に鑑み、 広告等の表示内容の解釈に当たっては一般消費者の視点に基づき判断するのが相当\nであるとしても、その表示中に示されたデータ等については、客観的かつ科学的に\n実証されたものであることを要し、かつ、それで足りると考えられる。そのデータ 等の取得に当たって設定されるべき試験条件等についても、法 2 条 1 項 号の解 釈として何らかの規律が設けられているとは考えられない。 また、原告実験 2 の結果について、「コントロール」の存在を考慮しても、なお上 記(3)の疑義はいずれも解消されない。 その他原告が縷々指摘する点を考慮しても、この点に関する原告の主張は採用で きない。
(5) 小括
以上のとおり、原告実験 2 報告書は、被告表示 2 が被告商品の品質につき誤認を 生じさせるものであることを裏付けるに足りるものとはいえない。その他被告表示\n2 が被告商品の品質につき誤認を生じさせるものであることを裏付けるに足りる証 拠もない。 したがって、被告表示 2 は、被告商品の品質につき誤認を生じさせるものとは認 められない。
・・・
ウ 原告実験 1-1 においては、実験に使用した二組の 束の髪の毛につき、同一 の毛束の、水道水浸漬・乾燥処理前後の水分量が測定されている。その点では、原 告実験 1-1 においては、被告表示 1 の検証・確認実験として適切な対象の測定が行 われたものといえる。また、その結果、被告商品の場合には、水道水に浸漬・乾燥 後の毛束の水分量は未処理の毛束の水分量よりも増加しているのに対し、EH-NA9E の場合、処理の前後で髪の水分含有量に著しい変化がない可能性があるとされてい\nる。 他方、原告実験 1-2 においては、「濡らし/乾し処理前後の髪の水分含有量を定量 する」とされているものの、具体的には、同じ毛束から採取された別の毛髪を水道 水浸漬・乾燥処理前に水分量を測定する毛髪と処理後に測定する毛髪として使用し ている。しかし、同じ毛束に属していたといっても、毛髪が異なればその水分量は 当然異なるといえることから、原告実験 1-2 においては、同一の毛束(毛髪)にお ける髪を乾かした際の水分増加量に関する被告表示 1 の検証・確認実験として適切 な対象が測定されているとはいえない。 また、原告実験 1 報告書においては、FT-NIR 法は定性的、又はせいぜい半定量的 な測定方法であるなどとされている。しかし、証拠(乙 7、8)によれば、FT-NIR 法 は、定性分析や定量分析に利用されるものであること、従来の分析法に匹敵する正 確さと精度で多成分分析を行うことができる素早くシンプルな非破壊の分析手法で あり、初期より、農業から食品業界まで幅広い測定に応用できる非破壊の迅速な分 析手法として広く用いられるようになったものとの評価を受けているものであるこ とが認められる。 これらの事情を踏まえると、被告表示 1 の検証・確認実験における測定法として は、非破壊的に毛髪中の水分を定量でき、同一の毛髪につき、水道水浸漬・乾燥処 理前後の水分量を測定し得る FT-NIR 法の方が、KF 法よりも適切な方法と考えられ る。にもかかわらず、原告実験 1 においては、FT-NIR 法については定量的な測定方 法とは位置付けられておらず、また、KF 法の結果は同一の毛髪で水道水浸漬・乾燥 処理前後の水分量を測定していないこと、そのような不適切な方法を被告表示 1 の 検証・確認実験として採用したことから、原告実験 1 の結果が十分に信頼し得るも\nのであるかについては疑義があるというべきである。これに反する原告の主張は採 用できない。
(3) 小括
以上のとおり、原告実験 1 報告書は、被告表示 1 が被告商品の品質につき誤認を 生じさせるものであることを裏付けるに足りるものとはいえない。その他被告表示\n1 が被告商品の品質につき誤認を生じさせるものであることを裏付けるに足りる証 拠もない。
・・・
以上より、被告各表示は、いずれも被告商品の品質につき誤認を生じさせるもの\nとは認められない。したがって、原告は、被告に対し、法 3 条に基づき、被告各表\n示の差止請求権(同条 1 項)及び抹消請求権(同条 2 項)をいずれも有しない。
なお、事案に鑑み付言すると、原告は、被告各表示に関する裏付けとなるデータ\n等を被告が開示しないことにつき、具体的態様の明示義務(法 6 条)及び積極否認 の際の理由明示義務(民訴規則 79 条)に違反するものと指摘する。 しかし、「具体的態様」とは、侵害判断のための対比検討が可能な程度に具体的に\n記載された物の構成又は方法の内容等を意味すると解されるところ、本件において\nは、被告商品の品質につき誤認を生じさせるものとされる被告各表示に記載された\n表示内容は、その記載から明確であるといってよく、その基礎となる被告が保有す\nるはずのデータそれ自体及びこれを導く試験条件等につき、被告各表示において開\n示されたもののほかは開示されていないというに過ぎない。 このため、現に原告が各実験により試みているように、本件において主張立証すべき対象は、侵害判断のための対比検討が可能な程度に、被告各表\示において既に具体的に示されているといえる。そうすると、本件においては、「侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様」(法 6 条)が明らかでないとは必ずしもいえない。また、その点を措くとしても、具体的態様の明示義務に基づき相手方に対して具体的態様 の明示を求め得るためには、濫用的・探索的な提訴等を抑止する観点から、当該事 案の性質・内容等を踏まえつつ、提訴等を一応合理的といい得る程度の裏付けを要 すると解される。しかるに、本件においては、上記のとおり対比検討すべき表示内\n容は明確である上、原告実験 1〜は、その実験方法が被告各表示の検証・確認実験\nとして不適切であり、また、その結果にはそれぞれ疑義があることを踏まえると、 上記の程度の裏付けがされているとはいいがたい。そうである以上、被告の対応を もって具体的態様の明示義務等に違反するものとまではいえない。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2023.05.25
令和3(ワ)20472 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年5月18日 東京地方裁判所
・・上記小冊子に本件各写真を掲載することを許可した。なお、当該許可に当たり、原告と被告会社との間で契約書は作成され被告らは、本件各写真の高額な許諾料に鑑みれば、原告が被告会社に対し本件各写真の利用を許諾する契約(以下「本件契約」という。)には、実績紹介等のための利用を許諾する旨の合意(以下「本件合意」という。)が含まれていたと主張する。
そこで検討するに、原告が被告会社との間で本件契約を締結するに当たり、 契約書を作成しなかったことは、当事者間に争いがない。そして、原告は、 本件合意があったことを否定しているところ、本件契約に関して、原告と被 告会社間のやり取りなど本件合意がうかがわれるような書面等は存在せず、 被告らの主張を前提としても、上記合意がされた経緯、時期、場所その他の 事情は、具体的には明らかにされていない。のみならず、証拠(甲17、1 8)及び弁論の全趣旨によれば、別の会社に対して本件写真1の利用を許諾 した際は、これに関する契約書が作成されているところ、当該契約書におけ る本件写真1の許諾料は、本件契約における許諾料と同等のものであるのに、 実績紹介等のための利用を許諾する旨の合意は存在しなかったことが認めら れる。 これらの事情の下においては、本件合意があったことを裏付けるに的確な 証拠はなく、本件契約と同種の別件契約の内容に照らしても、本件合意があ ったものと認めるのは相当ではない。したがって、被告らの主張は、採用す ることができない。
これに対し、被告らは、写真家等のクリエイターにとっても、実績紹介と して写真等が使用されることにはメリットがあることなどから、広告デザイ ン業界においては、このような実績紹介として写真等を使用する場合には、 クリエイターに利用許諾を求めない慣行が存在する旨主張する。 そこで検討するに、証拠(甲11、12、34ないし38)及び弁論の全 趣旨によれば、被告会社は、本件各写真のデジタルデータに「透かし」を入 れ又は写真家の名前を浮き彫りにするなどの無断複製防止措置をせずに、本 件ウェブページに上記デジタルデータを掲載したものと認められるところ、 同デジタルデータは、グーグルの検索サイトの画像欄その他のインターネッ ト上に、原告の名前が付されずに広く複製等されるに至ったことが認められ る。そして、証拠(乙5、6)及び弁論の全趣旨によれば、実績紹介での利 用につき、デザインも含めての掲載であれば格別、画像を抜き出して利用す ることは許容されず、また、ウェブページにおいて、PDFを閲覧できたり ダウンロードできたりする場合はライセンス料金が発生する旨注意喚起する フォトエージェンシーが存在することが認められる。 これらの事情を踏まえると、少なくとも、被告会社が無断複製防止措置な く本件各写真のデジタルデータを掲載するような態様についてまで、クリエ イターに利用許諾を求めない慣行が存在するものと認めることはできない。 したがって、被告らの主張は、採用することができない。
2023.05.25
令和5(ネ)10009 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年5月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1 本件訴えの適法性(本案前の抗弁)について
(1) 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合に は、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解す るのが相当である(最高裁昭和49年(オ)第331号同51年9月30日第一小 法廷判決・民集30巻8号799頁、最高裁昭49年(オ)第163号、164号 同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁参照)。
(2) 令和2年事件について(乙1、2)
ア 令和2年事件は、控訴人が、スマートフォン(型番SHV39、SHV40、 SHV41、SHV42及びSHV43。以下併せて「前訴被告製品」という。) の被控訴人シャープによる製造、被控訴人KDDIによる販売が、本件特許権を侵 害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請 求をした事案である。 令和2年事件においては、前訴被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1、 3及び4の各発明の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には前訴被告製 品にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーション (以下「前訴アプリ」という。)における「操作メニュー情報」の有無が争点とな った(令和2年事件における争点1−3)。 この争点について、控訴人は、「・・・できるように」という言葉は、目標・目 的・基準等を示すものであるから、「操作メニュー情報」は実行される命令の内容 の全部を利用者において理解することができるものである必要はなく、実行される 命令の内容を利用者が理解できることを目標・目的としている程度の表現があれば\n足りるなどとして、前訴被告製品における前訴アプリによるページ一部表示(本件\nにおける「一部表示画像」に相当する。)が「操作メニュー情報」に当たると主張\nした。
イ 令和2年事件の第一審である東京地方裁判所は、前訴被告製品における前訴 アプリの動作について、「1)利用者が前訴アプリの画面上に表示されたアイコン画\n面に指で触れて一定時間待つ操作(ロングタッチ)をすると、当該アイコンを移動 できる状態に遷移し、2)当該アイコンが指に追随して移動し、アイコンが指に追随 して右又は左に移動した距離が一定距離を超えると、縮小モードとなって、表示中\nの当該ページの画面が90%の大きさに縮小され、画面の左端又は右端に隣接する ページの画面の一部(ページ一部表示)が表\示され、3)更に当該アイコンをその方 向に移動させると、移動方向に隣接するページの画面がスクロールされて表示され\nる」ものであると認定し、ページ一部表示である直方形部分を見た利用者は、それ\nがどのような命令を実行する表示であるのかを理解することができないから、前訴\n被告製品のページ一部表示の画像は、本件発明1及び3の構\成要件Bの「操作メニ ュー情報」を有するとは認められないと判断した(乙2。東京地裁令和2年(ワ) 第15464号同3年7月14日判決)。そして、上記判断は、控訴審である知財 高裁令和4年2月8日判決(乙1)においても維持され、同判決は、上訴されるこ となく確定している(弁論の全趣旨)。
(3) 本件について
ア 本件は、控訴人が、スマートフォン(型番SHV44、SHV45及びSH V46。被告製品)の被控訴人シャープによる製造、被控訴人KDDIによる販売 が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為 に基づく損害賠償請求をした事案である。 本件においては、被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の各発 明(本件発明)の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には被告製品にイ ンストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーション(本件ホ ームアプリ)における「操作メニュー情報」の有無が争点となった。 本件における争点1(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)についての 控訴人の主張は、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び前記第2の 3に記載するとおりである。
イ 被告製品における本件ホームアプリの動作は、概要次のとおりである(前提 事実(6)ウ)。
「1)利用者が本件ホームアプリの画面上に表示されたショートカットアイコンを\n長押しすると、当該ショートカットアイコンはタッチパネル上の指等の動きに追随 して移動できる状態になり、2)当該ショートカットアイコンの移動距離が一定距離 になった場合に、縮小モードとなって、表示中の中央ページ画面が縮小表\示され、 画面の左端又は右端に隣接するページの画面の一部(一部表示画像)が表\示され、 3)更に当該ショートカットアイコンを一部表示画像の範囲に入れると、隣のページ\nの画面が表示される。」\nなお、原判決は、一部表示画像を見た利用者は、それが左右のページの一部を表\ 示していることを理解できるとはいえず、仮に理解できたとしても、当該画像の領 域までショートカットアイコンをドラッグすることによって対応するページにスク ロールするという命令が表示されていると理解できるように構\成されているとはい えないから、被告製品の一部表示画像は「操作メニュー情報」に当たらず、被告製\n品が本件発明の構成要件B、E、F、Gの「操作メニュー情報」を有するとは認め\nられないと判断した。
(4) 令和2年事件と本件の比較
令和2年事件と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一で あり、その特許請求の範囲の請求項1及び3の各発明の技術的範囲への被疑侵害品 の属否が問題となっている点も共通する。 本件の対象製品である被告製品は、令和2年事件の対象製品である前訴被告製品 と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認さ れるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことはうかがえず、特に、 問題とされているアプリケーションは同一(いずれもAQUOS Home)であ って、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたこ\nともうかがえず、また、問題となる動作(前記(2)イ及び(3)イ)は同一又は少なく とも実質的に同一である。 そして、令和2年事件と本件における争点は、対象製品(前訴被告製品又は被告 製品)にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーショ ン(前訴アプリ又は本件ホームアプリ)における「操作メニュー情報」の有無であ るから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点 についての控訴人の主張も実質的に同一である。 そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が 存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法 行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和2年事件における 控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和2年事件判決 が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成\n(前訴アプリの動作)と、被告製品の構成(本件ホームアプリの動作)が実質的に\n同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由に より、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提\n起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、 被控訴人らの令和2年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著し く損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。
(5) 控訴人の主張に対する判断
この点、控訴人は、令和2年事件における対象製品である前訴被告製品の構成\na1 と、本件訴訟における被告製品の構成 a1、a1’、a1”が異なり、また、構成 a3、 a3’、a3”、p1〜p3 が追加されているから、新たな判断が必要であると主張する。 しかしながら、控訴人の主張する被告製品の構成 a1、a1’、a1”及び p1〜p3 は 「一部表示画像」に関するものではなく、構\成 a3、a3’、a3”は、「一部表示画像」\nの画面上の領域(座標)をより具体的に特定したにすぎないものであって、前記 (2)イの前訴アプリの動作を変更するものではないから、控訴人の主張する構成は、\nいずれも、「一部表示画像」が構\成要件B、E、F、Gの「操作メニュー情報」に 該当するかを検討するに当たり、その判断に影響を与え得るものとはいえない。 また、上記控訴人の主張する構成の差異が、前訴被告製品の前訴アプリと被告製\n品の本件ホームアプリにおける実質的な差異であると認めるに足りる証拠はない上、 仮に、当該構成部分において、前訴被告製品の前訴アプリと被告製品の本件ホーム\nアプリに差異があるものと認められたとしても、その差異は、被告製品の本件ホー ムアプリにおける「操作メニュー情報」の有無に係る判断を左右するものとはいえ ず、さらに、控訴人が、控訴審において追加した構成も、上記判断を左右するもの\nではない。 したがって、上記控訴人の主張は採用できない。
(6) 小括
したがって、控訴人が本件において本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償 請求をし、これに係る主張をすることは、令和2年事件における紛争の蒸し返しに すぎないというべきであり、同事件の当事者である控訴人と被控訴人らとの間で、 控訴人の請求について審理をすることは、訴訟上の信義則に反し、許されない。
◆判決本文
原審は令和4年(ワ)第11889号ですが、アップされていません。
上記別事件はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.05.24
令和4(行ケ)10119 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年5月18日 知的財産高等裁判所
(1) 本願商標
別紙商標目録記載1のとおり、本願商標は、上段に、楕円形の二重線の枠の中に 曲線で構成された欧文字風の2つのモノグラム図形を配するロゴ風の図形(本件図\n形)を表し、中段に、「GINZA」の欧文字をサンセリフ体様の書体で小さく表\ し、下段に、「CLEAR」の欧文字をセリフ体様の書体で大きく表してなるもの\nであり、本件図形及び上記各文字は、いずれも薄い茶色で表されている。\n
(2) 本件図形部分
本願商標の構成中の本件図形部分は、そのうちの欧文字風の2つのモノグラム図\n形を含め、図案化の程度が顕著であり、それ自体、出所識別標識としての称呼及び 観念を生じないものである。
この点に関し、原告は、本願商標の構成中の本件図形部分はカメオを彷彿とさせ\nるものであり、トレードマークとして極めて強い印象を与え、また、面積にして本 願商標全体の70%以上を占めるから、本願商標が全体として与える影響のうち本 件図形部分によるそれが占める割合は大きいと主張する。確かに、別紙商標目録記 載1のとおり、本願商標のうち本件図形部分は、面積にして全体の大きな部分を占 めており、また、ロゴ風の図形として取引者及び需要者の注意を引く面があること は否めない(この点は、被告も争うものではない。)。しかしながら、上記のとお り、本件図形部分は、その図案化の程度が顕著であり、そのうちの2つのモノグラ ム図形についても、取引者及び需要者においてこれが何の文字を図案化したもので あるかを一見して理解することはできないものといわざるを得ないから、本願商標 の構成中の本件図形部分が取引者及び需要者の注意を引く面があるとの点は、本件\n図形部分が出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものであるとの判断を左 右しない。
(3) 「GINZA」の文字部分
ア 本願商標の構成中の「GINZA」の文字部分が東京都中央区南西部にある\n地名である「銀座」をローマ字で表記したものであることは、当事者間に争いがな\nい。
イ 証拠(乙24)及び公知の事実によると、「銀座」は、日本を代表する繁華\n街であると認められるところ、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、「銀座」に 所在する店舗等については、以下のとおり、「GINZA」の文字が商品の販売地、 役務の提供場所、ブランドの発祥地等に相当する表示として使用されている例が多\n数あるものと認められる。
・・・
ウ 以上によると、本願商標の構成中の「GINZA」の文字部分は、商品の販\n売地、役務の提供場所、ブランドの発祥地等に相当するとの印象を与えるものにす ぎず、当該文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないという べきである。
エ この点に関し、原告は、本願商標の構成中の「GINZA」の文字部分から\nは「銀座の地に関連があり、高級感のある事業」の観念が生じると主張する。しか しながら、仮に当該文字部分から「銀座の地に関連がある事業」の観念が生じると しても、それは、商品の販売地、役務の提供場所、ブランドの発祥地等をいうもの にすぎず、出所識別標識としての観念であるということはできない。また、当該文 字部分から「高級感のある事業」の観念が生じるものと認めるに足りる証拠はない。 なお、原告は、その運営するエステティックサロンにおいて本願商標を使用する 際には「CLEAR」の文字部分のみを使用することは決してなく、必ず本件図形 部分を含む本願商標の全体又は「GINZA CLEAR」の文字部分を使用して いると主張するが、仮に、本願商標について原告が主張するような使用実態がある としても、上記ア及びイにおいて認定説示したところに照らすと、そのような使用 実態は、本願商標の構成中の「GINZA」の文字部分から出所識別標識としての\n称呼及び観念が生じないとの判断を左右するものではない。
(4) 「CLEAR」の文字部分
ア 証拠(乙22、23)及び弁論の全趣旨によると、本願商標の構成中の「C\nLEAR」の文字部分を構成する「CLEAR」の語は、「明快な」、「明晰な」、\n「澄んだ」などを意味する形容詞等であり、我が国においてよく親しまれた平易な 英単語であると認められる。そして、「CLEAR」の語は、本願商標の指定商品 又は指定役務との関係で、商品の産地、販売地、品質等や役務の提供の場所、質等 を具体的に表示するものではないから、本願商標の構\成中の「CLEAR」の文字 部分は、取引者及び需要者に対して強い訴求力を有するということができる。以上 に加え、前記(1)のとおり当該文字部分が「GINZA」の文字部分より大きく表\nされていることも併せ考慮すると、「CLEAR」の文字部分は、商品又は役務の 出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認められる。
イ この点に関し、原告は、「CLEAR」の語は造語でなく、特別印象的な意 味を有する語でもなく、特徴的な振る舞いをする文字からなる語でもなく、また、 本願商標の指定商品及び指定役務と親和性のある形容詞であるから、本願商標の構\n成中の「CLEAR」の文字部分は商品又は役務の出所識別標識として強く支配的 な印象を与えるものではないと主張する。しかしながら、商標において商品又は役 務の出所識別標識として機能する文字部分は、必ずしも造語、特別印象的な意味を\n有する語、特徴的な振る舞いをする文字からなる語等でなければならないというこ とはない。また、仮に本願商標の指定商品及び指定役務の中に「明快な」、「明晰 な」、「澄んだ」などを意味する「CLEAR」の語によって抽象的に形容され得 るものがあるとしても、そのことは、本願商標の構成中の「CLEAR」の文字部\n分が商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとの判断を左右 するものではない。
なお、原告は、本願商標を付して行っている現在の事業(エステティックサロン) 及び本願商標を付して行う予定である将来の事業(セルフケアを目的としたビュー\nティー系コンテンツの配信及び健康食品や健康グッズの小売等に関するECサイト の運営事業)に係る商品又は役務の需用者は当該商品又は役務の出所を注意深く確 認して取引関係に入るのが一般的であるから、本願商標の構成中の「CLEAR」\nの文字部分は出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないと主張す るが、原告の現在及び将来の事業に係る商品又は役務の需用者が原告の主張するよ うな者であると認めるに足りる証拠はないし、仮に、当該商品又は役務の需用者が 原告の主張するような者であるとしても、前記(2)及び(3)並びに上記アにおいて認 定説示したところに照らすと、当該商品又は役務の需用者に係るそのような属性も、 本願商標の構成中の「CLEAR」の文字部分が商品又は役務の出所識別標識とし\nて強く支配的な印象を与えるとの判断を左右するものではない。
(5) 小括
以上のとおり、本願商標の構成中の「CLEAR」の文字部分は、商品又は役務\nの出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認められる一方、本 願商標の構成中の本件図形部分及び「GINZA」の文字部分からは、出所識別標\n識としての称呼及び観念が生じず、また、本願商標の構成中の本件図形部分は、欧\n文字風の2つのモノグラム図形を含めて図案化の程度が顕著であり、その余の部分 (「GINZA」の欧文字をサンセリフ体様の書体で表してなる「GINZA」の\n文字部分及び「CLEAR」の欧文字をセリフ体様の書体で表してなる「CLEA\nR」の文字部分)と形態を異にするものであって、本件図形部分と上記その余の部 分は、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるところ、両者を不可分一体に 観察すべきとする取引の実情があるものと認めるに足りる証拠はないから、本願商 標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然で\nあると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。したがって、 本願商標については、その構成中の「CLEAR」の文字部分を抽出し、当該文字\n部分だけを他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきで ある。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.05.22
令和4(ネ)2081 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和5年4月27日 大阪高等裁判所
控訴人は、需要者は、うきの選択に際してその形状の微細な差に着目して 商品選択をするから、特別顕著であるといえるためには、かけ離れた特異な 形態を備えている必要はなく、他のうきにはない形態を備えていれば足りる と主張する。
しかし、証拠(甲155、156、乙26、証人P2(原審)、控訴人代 表者(原審)、被控訴人代表\者(原審))及び弁論の全趣旨によると、釣り 具のうきの形態は、時代によって変化してきているが、その変化は、他の商 品一般に見られるような需要喚起のための装飾的観点からのものではなく、 より良い釣果を上げるための技術的工夫がうきの形態に反映され、徐々に改 良されていった結果であると認められるところ、より良い釣果を求めてうき に対して加えられる技術的工夫は、機能及び効用の側面等から自ずと一定の\n範囲に収れんすることになるため、商品ごとの形態の差は細部に及ぶ上、そ の差は微細なものになることが認められる。 そうすると、需要者が、より多くの釣果を求めて釣り具の選択をする際、 その形状や色彩を釣り具の性能を推知する資料として観察するとしても、も\nともと形態の差が細部に及ぶ微細なものである上、そもそも外観から観察し てうきの性能の優劣自体を判断することには自ずと限度があることから(控\n訴人が自立うきの性能を決する上で重要である旨主張する錘の量及び錘の位\n置は、うきの形態からは分からないはずのものである。)、結局、需要者は、 棒うき、円錐うき等といったうきの種類を商品形態によって見分けるとして も、その中で、さらに微細な商品形態の差に依拠して商品選択をするとは考 えられず、それよりも、釣り仲間や雑誌等の情報から得られる商品やその製 造者の評判ないし評価を主に参考にして商品を選択しているものと考えられ る。そうすると、上記のような商品群の中における商品選択の在り方を前提 にして、商品形態に特別顕著性があるといえるためには、他のうきとはかけ 離れた特異な形態であることが必要であって、これに反する前提に立つ控訴 人の主張は採用できない。そして、原告商品が他社のうきとはかけ離れた特 異な形態であるとも認められないから、その商品形態に特別顕著性があると いうことは到底できない。
また、控訴人は、原告商品に用いられた色彩にも特徴があるように主張す るが、その付された色彩は、明らかに釣り人が遠方から見て判別が容易な色 が選択されており、その色彩は、そのような目的において採用され得る色彩 の中でありふれたものにすぎないから、その彩色部分が他のうきと少し異な っていたからといって原告商品の色彩が出所表示機能\を有するようになった とは到底認められない。
(2) なお、補正の上引用した原判決「事実及び理由」欄の第3の2(3)エ(原判 決21頁10行目から同頁26行目まで)の記載に係る認定事実及び甲16 3の1ないし121、甲165の1ないし27によれば、原告商品の製作者 である控訴人の前代表者のP1は、クロダイ(チヌ)釣りの世界で「名人」\nと称され、多くの雑誌で特集が組まれる程度に同業界で著名な人物であり、 原告商品がそのP1が製作したうきであるという事実も多くの雑誌で紹介さ れている事実が認められるから、原告商品は、P1が製作したうきとして釣 り愛好家の間で知られている商品であること自体は認められる。しかし、前 記のとおり、需要者は、主に商品やその製造者の評判ないし評価を参考にし て商品を選択すると考えられることからすると、需要者は、原告商品を、そ の商品名を手掛かりとして、有名なP1が製作したうきであると認識した上 で他の商品から識別して認識するものと考えられる(現に原告商品自体のみ ならず、そのパッケージには、P1が製作したうきであることが一目で分か るよう行書体からなる「遠矢」の文字が記載されており、これによって他社 の商品であるうきと識別されていると認められる。)。 そうすると、周知性という点では、原告商品について、これを認める余地 があるが、それはあくまで「遠矢」ないし「遠矢うき」という商品名と結び ついて知られているものと認めるのが合理的であって、その商品形態の周知 性を裏付けるものではないというべきである。
(3) したがって、原告商品1ないし11の形態は不競法2条1項1号に規定す る「商品等表示」に該当するとは認められないから、不競法2条1項1号該\n当を前提とする控訴人の被控訴人に対する請求は理由がないというほかない。
◆判決本文
一審はこちら。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.05.21
令和4(ネ)74 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年4月27日 大阪高等裁判所
控訴人は、P1から本件絵柄の著作権を譲り受けたことを前提に、被控訴 人らの布団製造販売行為が、控訴人が取得した著作権の侵害行為であると主張 して本件各請求をしている。しかしながら、以下に述べるとおり、本件絵柄は 著作権法上の著作物ということができないから、控訴人は著作権を譲り受けた といえず、したがって主張に係る著作権の侵害を前提とする控訴人の被控訴人 らに対する各請求はいずれも理由がないというべきである。
(2) 本件絵柄は、テキスタイルデザイナーであるP1によって販売目的で量産 衣料品の生地に用いるデザイン案として制作され、現にその目的に沿って控訴 人に対して販売され、実用品である原告商品の絵柄として用いられたものであ り(前記第2の2(2))、いわゆる応用美術に当たる。控訴人は、本件絵柄が、 いわゆる応用美術であるとしても、布団の絵柄は実用的機能とは全く無関係な\n部分であるし、またP1が本件絵柄を完成させた時点では、本件絵柄と布団は 分離されているから、本件絵柄は、他の著作物同様の創作性の判断基準で著作 物性が認められるべき旨主張する。
そこで検討するに、著作権法2条1項1号は、「著作物」とは「思想又は感情 を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する\nものをいう」と規定し、同法10条1項4号は、同法にいう著作物の例示とし て、「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」を規定し、同法2条2項は、「こ の法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする」と規定し ている。ここにいう「美術工芸品」は例示と解され、美術工芸品以外のいわゆ る応用美術が、著作物として保護されるか否かは著作権法の文言上明らかでな いが、同法が、「文化の発展に寄与すること」を目的とし(同法1条)、著作権 につき審査も登録も要することなく長期間の保護を与えているのに対し(同法 51条)、産業上利用することができる意匠については、「産業の発達に寄与す ること」を目的とする意匠法(同法1条)において、出願、審査を経て登録を 受けることで、意匠権として著作権に比して短期間の保護が与えられるにとど まること(同法6条、16条、20条1項、21条)からすると、産業上利用 することができる意匠、すなわち、実用品に用いられるデザインについては、 その創作的表現が、実用品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の\n対象となる美的特性を備えていない限り、著作権法が保護を予定している対象\nではなく、同法2条1項1号の「美術の著作物」に当たらないというべきであ る。そして、ここで実用品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の 対象となる美的特性を備えているといえるためには、当該実用品における創作 的表現が、少なくとも実用目的のために制約されていることが明らかなもので\nあってはならないというべきである。
これに対し、控訴人は、著作権法と意匠法による保護が重複することについ て何ら調整の必要がないとする前提で著作権法による保護を求めていると解 されるが、両法制度の相違に鑑みれば、両法制度で重複的に保護される範囲に は自ずと限界があり、美術の著作物として保護されるためには、上記のとおり の要件が必要であるというべきである。実用品における創作的表現につき、無\n限定に著作権法上の保護を及ぼそうとする控訴人の主張は、現行の法体系に照 らし、著作権法が想定しているところを超えてまで保護の対象を広げようとす るものであって採用することはできない。
(3) 以上の観点から、本件絵柄についてみると、本件絵柄それ自体は、テキスタ イルデザイナーであるP1によってパソコン上で制作された絵柄データであ\nり、また、実用品である布団の生地など、量産衣料品の生地にプリントされて 用いられることを目的として制作された絵柄であるが、その絵柄自体は二次的 平面物であり、生地にプリントされた状態になったとしても、プリントされた 物品である生地から分離して観念することも容易である。そして、本件絵柄の 細部の表現を区々に見ていくと、控訴人が縷々主張するようにテキスタイルデ\nザイナーであるP1が細部に及んで美的表現を追求して技術、技能\を盛り込ん だ美的創作物であるということができ、その限りで作者であるP1の個性が表\nれていることも否定できない。
しかし、本件絵柄は、その上辺と下辺、左辺と右辺が、これを並べた場合に 模様が連続するように構成要素が配置され描かれており、これは、本件絵柄を\n基本単位として、上下左右に繰り返し展開して衣料製品(工業製品)に用いる 大きな絵柄模様とするための工夫であると認められる(本件絵柄は、原告商品 であるシングルサイズの敷布団では上下左右に連続して約6枚分、掛布団では 同様に約9枚分プリントされて全体に一体となった大きな絵柄模様を作り出 すよう用いられている(弁論の全趣旨)。)から、この点において、その創作的 表現が、実用目的によって制約されているといわなければならない。\nまた、本件絵柄に描かれている構成は、平面上に一方向に連続している花の\n絵柄とアラベスク模様を交互につなぎ、背景にダマスク模様を淡く描いたもの であるが(本件絵柄に用いられている模様が、このように称される絵柄である ことは訴訟当初から当事者間に争いがない 。)、証拠(乙2、丙3ないし13) 及び弁論の全趣旨によれば、アラベスク模様はイスラムに由来する幾何学的な 連続模様であり、またダマスク模様は中東のダマスク織に使用される植物等の 有機的モチーフの連続模様であって、いずれも衣料製品等の絵柄として古来か ら親しまれている典型的な絵柄であり、これら典型的な絵柄を平面上に一方向 に連続している花の絵柄と組み合わせ、布団生地や布団カバーを含む、カーテ ン、絨毯等の工業製品としての衣料製品の絵柄模様として用いるという構成は、\n日本国内のみならず海外の同様の衣料製品についても周知慣用されているこ とが認められる。そして、本件絵柄における創作的表現は、このような衣料製\n品(工業製品)に付すための一般的な絵柄模様の方式に従ったものであって、 その域を超えるものではないということができ、また、販売用に本件絵柄を制 作したP1においても、そのことを意図して、創作に当たって上記構成を採用\nしたものと考えられるから、この点においても、その創作的表現は、実用目的\nによって制約されていることが、むしろ明らかであるといえる。 そうすると、本件絵柄における創作的表現は、その細部を区々に見る限りに\nおいて、美的表現を追求した作者の個性が表\れていることを否定できないが、 全体的に見れば、衣料製品(工業製品)の絵柄に用いるという実用目的によっ て制約されていることがむしろ明らかであるといえるから、実用品である衣料 製品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の対象となる美的特性を 備えているとはいえない。したがって、本件絵柄は、「美術の著作物」に当たるとはいえず、著作物性を認めることはできないというべきである。
(4) 以上によれば、控訴人が譲り受けたとする本件絵柄は著作物ではなく著作 権そのものが認められないから、控訴人が本件絵柄について著作権を有してい るとは認められず、その結果、被告製品に付された絵柄が、本件絵柄に依拠し て作成されたものであり、また同一性が認められる範囲内にあるとしても、被 控訴人らの被告製品の製造販売行為をもって著作権侵害であることを前提と する控訴人の被控訴人らに対する請求は、その余の争点について判断するまで もなく理由がないというべきである。なお、控訴人が、控訴人において本件絵 柄の背景のダマスク模様の一部を改変して制作した原告絵柄4及び同5の著 作権侵害をいう部分があるが、その主張が認められないことは上記と同様であ る。
2023.05.21
令和3(ワ)11472 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年5月11日 大阪地方裁判所
前記(1)アのとおり、被告各画像のうち、写真集又は卓上カレンダーに 係る画像である被告画像1、2及び4ないし10は、販売する商品がどの ようなものかを紹介するために、平面的な商品を、できるだけ忠実に再現 することを目的として正面から撮影された商品全体の画像である。被告は、 商品の状態が視覚的に伝わるようほぼ真上から撮影し、商品の状態を的確 に伝え、需要者の購買意欲を促進するという観点から被告が独自に工夫を 凝らしているなどと主張するが、具体的なその工夫の痕跡は看取できない 上、撮影の結果として当該各画像に表現されているものは、写真集等とい\nう本件各商品の性質や、正確に商品の態様を購入希望者に伝達するという 役割に照らして、商品の写真自体(ないしそれ自体は別途著作物である写 真集のコンテンツとしての写真)をより忠実に反映・再現したものにすぎ ない。
(イ) 単語帳に係る画像である被告画像3は、前記同様に商品をできるだけ 忠実に再現することを目的として正面から撮影された商品全体を撮影し た平面的な画像2点と、扇型に広げた商品の画像1点を配置したものであ り、当該配置・構図・カメラアングル等は同種の商品を紹介する画像とし\nてありふれたものであるといえ、被告独自のものとはいえない。
(ウ) 以上より、被告各画像は、被告自身の思想又は感情を創作的に表現し\nたものとはいえず、著作物とは認められない。 (エ) また、商品名については、前記(1)イのとおり、いずれも商品自体に付 された商品名をそのまま使用するか、欧文字をカタカナ表記に変更したり、\n大文字表記を小文字表\記にしたり、単に商品の内容を一般的に説明したに とどまるありふれたものであって、著作物とは認められない。 そのほか、被告は、本件各申告には被告サイト上の商品の説明文に関す\nる著作権侵害も含まれるかのように主張するが、具体性を欠く上、その説 明が創作性を有するとは想定できず、失当である。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2023.05.19
令和4(行ケ)10003 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年4月27日 知的財産高等裁判所
(3) 相違点1の容易想到性について
ア 相違点1のうち、甲1発明における有効塩素発生剤を二酸化塩素に置換 する動機付けがあることについては、一次判決の拘束力が及び、当事者間 に争いもない。
イ 甲1発明と甲5文献記載事項の組合せにより、相違点1のうち、本件数 値範囲を容易に想到することができるかについて 甲5発明は、前記(2)のとおり、甲1発明における塩素剤の添加により トリハロメタン類が生成されるという課題があることを前提として、工 業用海水冷却水系にあらかじめ過酸化水素剤を特定の濃度で分散させた 後、塩素剤を特定の濃度で添加するという解決手段を採用しているので あり、かつ、各特定の濃度について、過酸化水素剤は「0.01〜2mg /l」、塩素剤は「トリハロメタン類の生成を防止しうる濃度又はそれ以 下の濃度」である「使用される過酸化水素の1モル当り、0.03〜0. 8モル(ただし、有効塩素として)に相当する濃度で、かつ、海水冷却水 に対して0.01〜1.0mg/l(ただし、有効塩素として)」として いるのである(別紙3の【請求項1】及び【請求項2】参照)。そうする と、甲5発明は、甲1発明における上記課題を、それ自体で解決しており、 かつ、塩素剤の使用を前提としているのであるから、当業者において、甲 1発明における有効塩素発生剤を二酸化塩素に置換した上で、更に甲5 発明を組み合わせるという動機付けがあるとはいえない。
また、甲5文献は、二酸化塩素の添加を想定していないから、二酸化塩 素の特定の濃度割合を開示するものでもない。
したがって、当業者が、甲1発明と甲5文献の組合せにより、相違点1 のうち、本件数値範囲を容易に想到することができるとはいえない。 原告は、前記第3の1(1)ウ のとおり、甲5文献の実施例の16ない し20には、甲1発明における有効塩素発生剤濃度及び過酸化水素濃度 を、それぞれ「0.02〜0.4mg/L」及び「0.18〜1.05m g/L」とすることで、充分な海生生物の付着防止効果が得られること が開示されており、当業者が、これについて本件換算(有効塩素発生剤濃 度を2.6で除する。)により、有効塩素発生剤から置換した二酸化塩素 の濃度を「0.01〜0.15mg/L」という範囲とすることは容易で ある旨主張する。
甲1発明における有効塩素発生剤を二酸化塩素に置換した上で、更に 甲5発明を組み合わせるという動機付けがあるとはいえないことは前記 のとおりであるから、そもそも原告の上記主張は前提を異にするもの というべきであるが、この点は措くにしても、以下の理由で原告の主張 はいずれにしても採用し得ない。 甲5文献の【表3】及び【表\4】には、過酸化水素溶液と有効塩素発生 剤として次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用して、両者の併用によるムラ サキイガイの成長度合いを調査するため、実施例16ないし20では別 紙3の図1(過酸化水素の拡散器あり)、比較例21ないし24では別紙 3の図2(過酸化水素の拡散器なし)の塩化ビニル管のモデル水路を用 いて、塩化ビニル管に海水を一過式に通水する方法で試験を行い、ムラ サキイガイの殻長を計測して、試験前後の殻長差より成長度合いを求め た結果が示されている。
実施例16では過酸化水素0.35ppm、次亜塩素酸ナトリウム0. 40ppm(本件換算をすると二酸化塩素0.15ppm。小数点3桁以 下四捨五入。以下同じ)、実施例17では過酸化水素0.35ppm、次 亜塩素酸ナトリウム0.07ppm(本件換算をすると二酸化塩素0.0 3ppm)、実施例18では過酸化水素0.70ppm、次亜塩素酸ナト リウム0.40ppm(本件換算をすると二酸化塩素0.15ppm)、 実施例19では過酸化水素1.05ppm、次亜塩素酸ナトリウム0.2 0ppm(本件換算をすると二酸化塩素0.08ppm)、実施例20で は過酸化水素0.18ppm、次亜塩素酸ナトリウム0.02ppm(本 件換算をすると二酸化塩素0.01ppm)で試験が行われているとこ ろ(なお、溶媒が比重1の水である場合には、ppmとmg/Lの数値は 同等。)、確かに、これらの実施例については、本件換算をすれば、相違 点1に係る本件特許発明1の構成のうち、二酸化塩素0.01〜0.15mg/L、過酸化水素0.18〜1.05mg/Lとなるような組合せが\n開示されているといえる。しかしながら、これらは、甲5発明の実施例で あり、その課題解決手段である過酸化水素の拡散器を備えたことを前提 とするものであって、当業者が、このような拡散器を備えないまま、実施 例16ないし20に係る本件換算後の二酸化塩素濃度と過酸化水素濃度 の数値のみを甲1発明に単純に適用しようと考えるとは認められない。 かえって、過酸化水素と次亜塩素酸ナトリウムの添加量が同じである、
実施例18と比較例23を比較すると、1m3/hの海水を一過式に通水 し、その間両薬剤を所定濃度になるように24時間添加し、40日間試 験をした後におけるムラサキイガイの成長度(殻長mm)が、実施例18 では、注入点から0.5、4、8、16、24、48mのいずれの距離で も0.1mmであったのに対し、比較例23では、1.0mmから4.5 mmの範囲となっており、ムラサキイガイの成長度抑制結果において、 比較例23が実施例18より劣ることが示されているから、当業者は、 甲5発明のような改良がされる前の甲1発明について、甲5文献に記載 の数値範囲のみを適用しようとすると、比較例23のような結果しか得 られないと認識することになるといえる。
仮に、原告が、甲1発明において、甲5文献に記載の数値範囲を、過酸 化水素の拡散手段等、甲5発明の特定手段と併せて適用することの容易 想到性をも主張しているのであるとすれば、それは、甲5発明に基づき 本件数値範囲の容易想到性を主張しているのに等しい。そして、甲5発 明に基づき本件数値範囲が容易想到であるとの主張が採用できないこと は後記3のとおりである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 数値限定
>> ピックアップ対象
2023.05.19
令和2(ワ)4913 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年4月20日 大阪地方裁判所
(c) 原告は、前記の各製品について、アウタロータ型電動モータを採用しておら ず、被告製品及び原告製品と構造が根本的に異なること、被告製品及び原告製品は、\n主として車輌工場において重要保安部位向けに使用されるのに対し、瓜生製作のU BX−AFシリーズ以外は主にそれよりも重要度の低い部位に用いられること、デ ソータやエスティックの製品は電動式衝撃締め付け工具ではなくナットランナーと\n思われること等を理由に、いずれも競合品に該当しないと主張する。 しかし、被告カタログ及び前記競合品の各カタログ(乙52の4、54の3、5 6の1・2、58、73、74)には、工具に採用されているモータの型がアウタ ロータかインナロータかといった点に関する記載がないことや、モータの構造は製\n品の外部から確認できるものではないこと等を踏まえると、モータの構造それ自体\nが需要者の購入動機の形成に寄与する場合が多いとは認められず、アウタロータ型 電動モータを採用していないことをもって直ちに競合品から排除されるとするのは 相当でない。また、被告製品及び原告製品の各カタログを見ても、締め付け工具で あること以上に各製品の用途を限定する旨の記載はなく(甲35、36、乙58)、 これらの製品が主に車輌工場において重要保安部位向けに使用される一方、他の製 品が異なることについて的確に裏付ける証拠はない。また、証拠(乙1、4、34) によれば、一般に、ナットランナーは、インパクトレンチやパルスツールとはモー タの回転を締付力に変換する方式が異なることから、高精度である一方でトルクが 低く抑えられ、反力受けが必要であるという特徴を有し、パルスツールとは性能・\n用途が異なる場合があるといえるが、デソータ及びエスティックの前記各製品は、\n低反力で反力受けを要さず、作業者が直接手に持って締め付け操作を行うことが可 能な製品であり、かつトルク範囲も被告製品のものと重複するものであることから、\n被告製品及び原告製品と性能・用途等において共通する競合品であると認められる。\nしたがってこの点の原告の主張は採用できない。
(d) 以上によれば、被告製品及び原告製品と共通する電動式締め付け工具の市 場において競合品が一定数存在することが認められる。もっとも、当該市場におけ る被告製品や原告製品の市場占有率等が明らかではないことや、競合品と認められ る製品の中には、被告製品との価格差が比較的大きいものもあると考えられること 等を踏まえると、競合品の存在を理由とする大幅な覆滅を認めることはできないと いうべきである。
c 侵害品の性能\n
(a) 被告カタログ(乙58)によれば、被告製品は、その「主な特徴」として、 「バッテリーツール、高い生産性、高トルク、高精度、低反力、メンテナンス軽減、 多様な使用環境に対応」と記載されている。また、より具体的な特徴として、被告 製品は、バッテリー残量等を作業者から容易に確認できるLEDインジケータが表\n示されること、作業者の手になじむバランスのとれたツールであること、オイル漏 れの影響を軽減してメンテナンス周期を延ばす新型のパルスユニットを採用してい ること、効率的な冷却システムを搭載していること、予備バッテリーを内蔵し通信\nを維持したままバッテリー交換が可能であること、回転速度が6000rpmまで\n設定可能であること、独自のコントローラ「Power Focus 6000」及びソフトウェア\nにより容易に作業内容等を設定可能であること、内蔵されたブザーからの音でも締\nめ付けが可能であること、デュアルアンテナにより無線環境に対応しツールの接続\n性を向上していること、高速バックアップユニット機能を搭載していること等が記\n載されている。一方で、モータの構造や、被告製品がアウタロータ型電動モータを\n採用していることについての記載はない。 また、被告カタログでは、前記のメンテナンス軽減・周期の改善に関して、新し い特許技術と設計により、従来品よりもメンテナンス周期が長くなっていること、 オイル漏れ対策やエアセパレータの採用及び優れた冷却性能がパフォーマンスと稼\n働時間の向上に寄与していることの記載があるほか、「高いトルク性能」として、\n「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、「高度なモーター制御」により締付け 時間が早くなり生産性が向上する旨が記載されている。 そして、証拠(乙58、59)及び弁論の全趣旨によれば、ABは、次のとおり の技術(発明)について、特許を出願し、その多くが日本国内を含めて登録されて おり、これらの技術が被告製品に採用されていると認められる。
1) オイルパルスユニット内のオイルと空気を分離する機構を備え、オイルチャ\nンバから分離された空気が再びオイルチャンバに戻ることを防止する技術(乙 59の1)
2) 遠心作用によりオイルから空気を取り出すための分離手段を備え、パルスユ ニット内の空気の割合を低くすることにより、高いパルス発生効率を実現する 技術(乙59の10)
3) 作動流体を利用したヒートパイプにより、電動モータの熱を効率的に放散し て冷却する技術(乙59の2)
4) ステータ要素とロータ要素との間の相対変位を感知するセンサーに係る技術 でありモータ制御の精度に資する技術(乙59の3)
5) モータとパルスユニットとの接続を改良し、高い生産性、低反力、高トルク 及びメンテナンス周期を改善させる技術(乙59の4)
6) 電圧供給源の遮断時に、動作制御ユニット及び無線通信装置への電圧供給を 連続して維持することによりバッテリーユニットの交換立ち上げにおける遅 れを実質的に減少する技術(乙59の5)
7) 油圧パルスユニット内のオイルレベルが低すぎる場合に、警告信号を出す方 法及びシステムに関する技術(乙59の6)
8) トルク限度及び角度回転限度を超えて締結具が更に締め付けられることを防 止するため、締付具が事前に締め付けられていたか否かを検出する方法に係る 技術(乙59の7)
9) オイルパルスユニットについて機構及び各種部材の形状を工夫し、トルク衝\n撃が与えられた直後に高圧室の圧力を迅速に除去し、次のトルク発生のための 迅速な加速を可能とし、トルクの増大及びトルクの間隔の短縮を実現し、衝撃\n率の増加を実現する技術(乙59の8)
10) パルスユニットの部品の摩耗により生じた粒子を除去するための磁石を備え、 さらなる摩耗等を防ぎ、メンテナンス軽減を実現する技術(乙59の9) そのほか、コントローラである Power Focus 6000 及びソフトウェアにより多種\n類のツールを接続し、作業内容に合わせたコントロールが容易であるという特徴は、 被告カタログ等において、前記記載以外にもページを費やして強く訴求されている (乙58、85)。
(b) 衝撃発生部が油圧パルス発生部である電動式衝撃締め付け工具において、 アウタロータ型電動モータを採用するという本件訂正発明は、電動式衝撃締め付け 工具の基幹部分であるモータに関する発明であり、インナロータ型電動モータが採 用される場合と比較して、小型、軽量、低反力、耐久性実現の作用効果を有する点 で、相当の技術的価値があるといえる。実際に、被告製品のモータを本件訂正発明 の技術に属しない構造に変更するにはモータの構\造等を変更する必要があり、その 場合には製品全体の構造や技術を見直す必要があり、この点からの代替技術が採用\nされる可能性が高いとはいえない。\nもっとも、本件訂正発明の作用効果である「小型、軽量、低反力、耐久性」を実 現する技術及び被告製品で訴求される各特徴を実現する技術は、アウタロータ型電 動モータ以外にも存在する。被告製品においてアウタロータ型電動モータを採用し たことによる作用効果は、被告カタログにおいて訴求されている「高トルク」、「低 反力」及び「メンテナンス軽減」に関連し得るが、前記(a)のとおり、被告カタログ では、「高トルク」を実現する技術として「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、 「高度なモーター制御」が記載されており、実際に、被告が保有し被告製品で採用 されている技術においても実現されていると認められる。 そのほか、前記(a)のとおり、被告製品には、本件訂正発明以外にも多数の技術が 使用され、当該技術による作用効果が被告カタログにおいて被告製品の特徴として 記載されており、需要者に強く訴求されていることが認められる。
(c) したがって、被告製品は、本件訂正発明及びその作用効果以外にも、種々の 技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が、需要者の購入動機\nの形成に相当程度寄与していると認められる。被告製品が多彩な機能を有し、これ\nが顧客誘引力に寄与していることは、被告製品が、対応する原告製品よりも総じて ●(省略)●であるという価格差にも裏付けられているといえる。 (d) 以上より、被告製品の性能に係るこれらの事情は、特許法102条2項に基\nづく推定を、相当程度覆滅する事由であると認められる。
d 本件訂正発明は被告製品の一部のみに使用されていること
前記1(2)のとおり、本件訂正発明は、インナロータ型電動モータを搭載した従来 の電動式衝撃締め付け工具の有する課題を解決するため、出力トルクが大きいアウ タロータ型電動モータを採用し、小型及び軽量で、低反力かつ耐久性を有する電動 式衝撃締め付け工具を提供するというものであり、被告製品の特徴とされる「高ト ルク、低反力、メンテナンス軽減」(前記c(a))の作用効果の実現に使用されてい るといえるが、前記cで検討した諸事情からすれば、それらの作用効果は、本件訂 正発明のみによって実現されているとはいえない上、被告製品が備える種々の性能\nの一部にすぎないことが認められる。したがって、本件訂正発明が被告製品の一部 のみに使用されていることは覆滅事由に該当する。ただし、覆滅の基礎となる事情 は前記cの事情と重複することから、推定覆滅の程度の検討に当たっては被告製品 の性能を理由とする推定覆滅と実質的に重なるものとして評価するのが相当と解さ\nれる。
e 本件訂正について
本件訂正は、衝撃発生部について、油圧パルス発生部に限定するものであり、被 告製品における発明の作用効果やその実施に影響を与えるものではないこと等を踏 まえると、本件訂正の事実を覆滅事由として認めることは相当でない。
(ウ) 推定覆滅の程度
以上のとおり、本件においては、一定数の競合品の存在、被告製品の性能及び本\n件訂正発明が被告製品の一部のみに使用されていることを理由とする推定覆滅が認 められ、前記(イ)のとおりの事情を総合的に考慮すると、6割の限度で損害額の推定 が覆滅されるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はい ずれも採用できない。
(エ) 以上から、特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額は、被告製 品ごとに、別紙損害一覧表(裁判所認定)の表\1及び表2の各「2項損害額」欄記\n載のとおりとなる。
イ 特許法102条3項の重畳適用について
(ア) 特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第 三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、 侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為が なければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸 失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解され る。 そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該 推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき は、同条3項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆 滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超える\nこと以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情がある ことを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下におい て、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと 解される(知的財産高等裁判所令和4年10月20日特別部判決参照)。
(イ) これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは 競合品の存在、被告製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明が被告製品の\n一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力\nを超えること以外の理由により特許権者が販売等をすることができないとする事情 があることを理由とするものである。
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵 害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された 蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実 施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることが できたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明 の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用している\nと認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構\を有していると認め られるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪 失したとはいえない。
また、被告製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明は被告\n製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、被告製品 の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるもので あり、このような特許発明が寄与していない部分について、原告が実施許諾をする ことができたとは認められない。 したがって、本件においては、特許法102条2項による推定の覆滅部分につい て、同条3項の適用は認められない。
ウ 特許法102条3項に基づく損害額
(ア) 実施料率
本件訂正発明について実施許諾契約がされた事実はない(弁論の全趣旨)。 また、証拠(甲32、33)及び弁論の全趣旨によれば、平成15年9月20日 に社団法人発明協会が発行した「実施料率〔第5版〕」において、「金属加工機械」 の技術分野における平成4年度〜平成10年度の実施料率の平均値についてイニシ ャル有りが4.4%、イニシャル無しが3.3%であること、同様の最頻値が5%、 3%、中央値が4%、3%であること、平成22年8月31日に発行された経済産 業調査会が発行した「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プ ログラム著作権・技術ノウハウ〜」において、「成形」の技術分野における実施料 率の平均値が3.4%であることが認められる。これらに、原告と被告とが競業関 係にあること、本件訂正発明の内容、重要性、代替可能性、被告製品の売上に対す\nる貢献の程度のほか、本件訂正により特許請求の範囲が減縮されていること等本件 に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件における実施に対して受けるべき料率 としては、4%が相当であると認める。これに反する原告及び被告の主張はいずれ も採用できない。
(イ) 以上から、特許法102条3項に基づき推定される損害額は、被告製品ごと に、別紙損害一覧表(裁判所認定)の表\1及び表2の各「3項損害額」欄記載のと\nおりである。
エ 原告の損害額
(ア) 原告は、被告製品の型番ごとに、平成29年7月から令和3年10月の期間 につき、特許法102条2項に基づく損害額と、同条3項に基づく損害額のうち高 い方を選択的に請求していることから、被告製品の型番ごとに認められる損害額は、 別紙損害一覧表(裁判所認定)の表\1の「損害額」欄記載のとおりであり、合計す ると4078万9003円(平成29年7月から令和2年3月31日分までが28 12万1254円、同年4月1日から令和3年10月31日分までが1266万7 749円)となる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2023.05.16
令和4(ネ)10093 特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権不存在確認請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年5月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお、仮に二課長通知等に基づく運用によれば、本件各特許が存在するために原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされないことが控訴人にとって問題であるとしても、そのことは、厚生労働大臣が医薬品医療機器等法14条3項に基づく原告医薬品の製造販売についての控訴人の承認申請を認めるかどうかという控訴人と厚生労働大臣(国)との間の公法上の紛争であって、そもそも控訴人と被控訴人らとの私人間の法律上の紛争であるということはできないし、かかる公法上の紛争については承認申\請に対して不作為の違法確認の訴えの提起や厚生労働大臣等に対する不服申立て等の法的手段によって救済を求めるべきであるから、控訴人の有する権利又は法律的地位の危険又は不安を除去するため控訴人と被控訴人らとの間で本件訴訟において確認判決を得ることが必要かつ適切であると解することもできない。\n
(5) 控訴人は、当審において、1)パテントリンケージのシステムが発動するということ自体が、控訴人において、特許権の侵害の有無という法律的地位が問題になっている状況にあることを意味し、現に、「医薬品として原告医薬品が厚生労働省から承認されない」という「控訴人の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存在」している状況にあり、このような状況自体が現在の法的紛争であり、また、パテントリンケージは、あくまでも先発医薬品メーカの特許権が有効で、かつ、後発医薬品がその技術的範囲に含まれることを前提とする制度であり、被控訴人らに対し、裁判所による侵害の有無の判断(確認判決)さえ示されたならば、「医薬品として原告医薬品が厚生労働省から承認されない」という、控訴人の法律的地位に対する危険は除去されるのであるから、確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に該当する、2)控訴人は承認申請のため原告医薬品を製造しており、承認後に行う製造行為も事実行為としては同じであって、さらに、控訴人は、原告医薬品が承認され薬価収載さえされれば、すぐに原告医薬品の製造販売を行う意思を有しており、他方、被控訴人らは、現状において権利行使をする意思がないとは述べているが、実際に権利行使を行い得る状況にあり、また、確認の利益は客観的な状況によって判断されるべきであって、被控訴人らの主観によって左右されるべきではないから、侵害の有無を判断すべき客観的な状況が存在する以上、本件における確認の利益は認められるべきである、3)二課長通知に基づく実務がTPP11協定(第18・53条2項)に根拠を有するものとして許容されるためには、特許抵触の有無に疑義がある本件のような確認訴訟が提起された場合については、確認の利益を認めて裁判所が実体的な判断を示すことが必要であるなどとして、本件においては確認の利益が認められるべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、前記(4)のとおり、控訴人が主張する「医薬品として原告医薬品が厚生労働省から承認されない」という「控訴人の有する権利又は法律的地位」の「危険又は不安」とは、控訴人と厚生労働大臣との間で問題となる事柄であり、控訴人と被控訴人らとの間の「請求権の存否に係る法律上の紛争」に係るものではないし、また、かかる危険又は不安を除去するため控訴人と被控訴人らとの間で本件訴訟において確認判決を得ることが必要かつ適切であると解することもできない。
2)については、前記(4)で述べた事情を考慮すると、控訴人と被控訴人らとの間の本件差止請求権及び本件損害賠償請求権の存否について、現に当事者間に紛争が存在し、控訴人の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存しているとは認められないから、本件差止請求権及び本件損害賠償請求権の不存在確認請求に係る本件各訴えについて確認の利益があると認められないと判断したものであって、被控訴人らの主観のみによってこのような結論を導いているわけではない。
3)については、TPP11協定の第18・53条2項は、医薬品の販売承認に当たって、特許抵触の有無に疑義があるとして本件のような特許権侵害に係る確認訴訟が提起された場合に、裁判所が確認の利益を認めて実体的な判断を示さなければならない旨を規定するものではない。したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
◆判決本文
原審はこちら。
2023.05.10
令和4(ネ)10111 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和5年4月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人らは、本件通知書に記載されたキャタピラン+等が本件特許権を侵 害していると考えている旨の見解に関し、仮にこれが不正競争防止法2条1項21 号にいう「虚偽の事実」に該当するのであれば、特許権者としては、特許権の被疑 侵害者を発見した場合であっても、後日裁判所により特許権の侵害はない旨の判断 がされ、損害賠償を命じられるとのリスクを回避するため、被疑侵害者に対し訴訟 提起前に警告書を送付することがおよそできなくなるから、上記の見解が同号にい う「虚偽の事実」に該当するとの判断は誤りであると主張する。
しかしながら、特許権者が特許権の被疑侵害者を発見し、訴訟提起に先立って当 該被疑侵害者に対し警告書を送付したが、後日裁判所により特許権の侵害がない旨 の判断がされた場合であっても、当該警告書の送付が特許権者の正当な権利行使の 範囲内の行為であると評価されるときは、同送付は違法性を欠き、当該特許権者が 同送付を理由として損害賠償責任を負うことはないのであるから、特許権者が被疑 侵害者に対し訴訟提起前に警告書を送付することがおよそできなくなることを前提 とする控訴人らの上記主張は、前提を誤るものとして採用することができない。
(5) 控訴人らは、本件告知行為の違法性の有無に関し、1)控訴人らと被控訴人 との間の紛争の発端は、被控訴人が控訴人Xらとの間で締結した共同出願契約(乙 30の1及び2)における約定(事前の協議・承諾なく本件特許権に関わる製品を 販売した場合には、本件特許権を剥奪できるとするもの)に違反し、単独でキャタ ピラン等の製造・販売を開始したことであること、2)控訴人Xは、本件通知書にお いて、キャタピラン等とキャタピラン+等が別の商品であり、これらが異なる状況 にあることを分かりやすく明記していること、3)本件通知書の記載は、キャタピラ ン+等がキャタピラン等と同様に本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を与えるものではないことを根拠に、本件告知行為の目的は被控訴人の取引先が過 去に販売したキャタピラン等について損害賠償請求をすることであり、同目的が 「裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定したキャタピラン等の存在 を奇貨として、本件特許権を侵害しないように改良されたキャタピラン+等につい ても、裁判所による判断がされる前に、本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控 訴人の取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン+等を早期に「結 ばない靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優 位に立つこと」であるとの認定は誤りであると主張する。
しかしながら、控訴人Xは、本件告知行為をした時点において、被控訴人がその 製造・販売する商品をキャタピラン等からキャタピラン+等に入れ替え、「結ばな い靴紐」の市場においてキャタピラン等の販売が縮小していることを十分に認識し\nていたこと(補正して引用する原判決第4の4(2)イ)、被控訴人は、令和2年1 2月22日、前訴の控訴審判決において命じられたキャタピラン等に係る損害賠償 金(平成28年4月1日から平成30年8月31日までに生じたもの)を支払った ものと認められること(乙7の3、弁論の全趣旨)、キャタピラン等に係る損害賠 償金(平成30年9月1日から令和3年4月30日までに生じたもの)についても、 遅くとも本件告知行為の前までには、その額の確定等の手続が終了し、被控訴人か らその支払がされるのを待つ状況となっていたものと認められること(甲60、7 7、弁論の全趣旨)、控訴人Xは、本件包括協議において、直接又は間接に、被控 訴人が「結ばない靴紐」の市場から撤退することを一貫して求めていたと認められ ること(甲59ないし67、70ないし74)、本件通知書の送付を受けた被控訴 人の取引先は、キャタピラン等と同様にキャタピラン+等についても本件特許権を 侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたこと(補正して引用する原判決第4の 4(2)イ及びウ)、その他、補正して引用する原判決第4の4(1)において認定した 各事実に照らすと、控訴人らが主張する上記1)の事情や本件通知書の記載内容を考 慮してもなお、本件通知書においてされたキャタピラン等に係る本件特許権の行使 等についての言及は、あくまで名目的なものであったといわざるを得ず、本件告知 行為の真の目的は、補正して引用する原判決第4の4(2)イのとおり、キャタピラ ン等と同様にキャタピラン+等も本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控訴人の 取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン+等を早期に「結ばない 靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優位に立 つことであったと認めるのが相当である。
この点に関し、控訴人らは、キャタピラン+等の取扱いを停止した4社のうち2 社(株式会社シューマート及び株式会社チヨダ)は当初本件通知書に対して反論を したのであるから、両社は本件告知行為によりキャタピラン+等が本件特許権を侵 害するおそれがあるとの強い印象を受けたものではないと主張する。確かに、本件 通知書の送付を受けた株式会社シューマートは、「キャタピラン+等が本件発明の 技術的範囲に属するというのであれば、その説明をしていただきたい」旨の回答 (乙A2)をし、本件通知書の送付を受けた株式会社チヨダも、「株式会社チヨダ は、入手済みの弁理士の見解書を踏まえ、キャタピラン+等については本件発明の 技術的範囲に属しないと判断している」旨の回答(乙A6)をしたものと認められ るが、結局、両社は、本件告知行為の約4か月後に、それぞれ本件通知書において 求められたとおりにキャタピラン+等の取扱いを停止したものと認められるのであ り(弁論の全趣旨)、加えて、本件通知書の記載内容も併せ考慮すると、両社が本 件通知書の送付を受けた際に上記のような回答をしたことは、両社において本件告 知行為によりキャタピラン+等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を受けたとの認定を左右するものではない。
また、控訴人らは、キャタピラン+等の取扱いを停止した4社のうちその余の2 社(朝日ゴルフ株式会社及び株式会社Olympicグループ)は控訴人らと被控 訴人との間に紛争が生じていることを理由に、紛争が解決するまでキャタピラン+ 等の取扱いを一時的に停止したにすぎず、キャタピラン+等が本件特許権を侵害す ると認識してその取扱いを中止したものではないと主張するが、本件通知書の記載 内容及び両社が本件通知書の送付を受けた後速やかにキャタピラン+等の取扱いを 停止したものと認められること(弁論の全趣旨)に照らすと、株式会社Olymp icグループの回答書(乙A12)に「キャタピラン等及びキャタピラン+等に関 する控訴人Xと被控訴人との間の紛争が解決するまで、これらの商品の販売をしな い方針である」旨の記載があることを考慮しても、両社は、本件告知行為によりキ ャタピラン+等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたものと 認めるのが相当である。 以上のとおりであるから、控訴人らの主張を採用することはできない。
(6) 控訴人らは、本件告知行為に係る過失の有無に関し、被控訴人の第1主張 書面(本件仮処分の手続において提出されたもの)に記載された本件発明の構成要\n件B1)の「非伸縮性素材からなり」に係るクレーム解釈は特許請求の範囲及び本件 明細書等の記載から大きく外れた荒唐無稽なものであり、同主張書面を見てもキャ タピラン+等が本件特許権を侵害していないと判断することはできなかったから、 本件告知行為について控訴人らに過失はない旨の主張をする。
しかしながら、補正して引用する原判決第4の2及び前記(1)ないし(3)において 説示したところに照らすと、被控訴人が上記第1主張書面においてした主張(本件 発明の「非伸縮性素材からな(る)中心ひも」は「伸縮性素材からなるひも本体と 比較して伸縮性が乏しいもの」をいうところ、キャタピラン+等のひも本体(外層) と中心ひも(芯材)の伸縮性を比較した試験結果によると、キャタピラン+等は本 件特許権を侵害しない旨の主張(補正して引用する原判決第4の4(2)イ))は、 十分な説得性を有する相当なものであるといえ、加えて、補正して引用する原判決\n第4の4(2)イにおいて指摘した各事情も併せ考慮すると、控訴人らは、遅くとも 同主張書面を受領した時点で、キャタピラン+等の製造・販売が本件特許権を侵害 しない可能性が相当程度にあることを容易に認識し得たと認められるから、そのよ\nうな認識可能性があったにもかかわらず本件告知行為に及んだ控訴人らには、過失\nがあると認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2023.05. 2
令和4(ネ)10062 職務発明の対価請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月23日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ところで、旧特許法35条4項の「発明により使用者等が受けるべ き利益」は、使用者等が「受けた利益」そのものではなく、「受ける べき利益」であるから、使用者等が職務発明についての特許を受ける 権利を承継した時に客観的に見込まれる利益をいうものと解されると ころ、使用者等は、特許を受ける権利を承継せずに、従業者等が特許 を受けた場合であっても、その特許権について同条1項に基づく無償 の通常実施権を有することに照らすと、「発明により使用者等が受け るべき利益」には、このような法定通常実施権を行使し得ることによ り受けられる利益は含まれず、使用者等が従業者等から特許を受ける 権利を承継し、当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得する ことによって受けることが客観的に見込まれる利益、すなわち「独占 の利益」をいうものと解される。また、特許を受ける権利の承継の時 点では、将来特許を受けることができるかどうか自体が不確実であり、 その発明により将来いかなる利益を得ることができるのかを具体的に 予測することは困難であることなどに照らすと、発明の実施又は実施\n許諾による使用者等の利益の有無やその額など、特許を受ける権利の 承継後の事情についても、その承継の時点において客観的に見込まれ る利益の額を認定する資料とすることができるものと解される。 そして、使用者等が職務発明についての特許を受ける権利の承継後 に第三者との間のライセンス契約に基づいて当該発明の実施を許諾し ている場合には、その実施料収入が「独占の利益」に該当し、また、 使用者等が、第三者に当該発明を実施許諾することなく、自ら実施 (自己実施)している場合には、特許権が存在することにより、第三 者に当該発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が得ることがで きた利益、すなわち、特許権に基づく第三者に対する禁止権の効果と して、使用者等の自己実施による売上高のうち、当該特許権を使用者 等に承継させずに、自ら特許を受けた従業者等が第三者に当該発明を 実施許諾していたと想定した場合に予想される使用者等の売上高を超\nえる分(超過売上高)について得ることができたものと見込まれる利 益(超過利益)が「独占の利益」に該当するものというべきである。 この「超過利益」の額は、従業者等が第三者に当該発明の実施許諾を していたと想定した場合に得られる実施料相当額を下回るものではな いと考えられるので、「超過利益」を「超過売上高」に上記想定に係 る実施料率(仮想実施料率)を乗じて算定する方法にも合理性がある ものと解される。
したがって、かかる「独占の利益」をもって、「その発明により 使用者等が受けるべき利益」とし、これと1審被告の貢献の程度 (「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」)を考慮し て相当の対価の額を認定することは許されるものと解される。また、 特許法35条3項及び5項に基づく相当の対価請求権、同項の「その 発明により使用者等が受けるべき利益」についても、上記説示したと ころと同様に解すべきである。 以上を前提に、1審原告の本件発明1に係る相当の対価請求権の 存否について判断する。
・・・
「a 本件発明2−1は、空気調和機(ルームエアコン)の室内ユニットに 搭載される熱交換器の配置について、前面熱交換器の設置角度α及びク ロスフローファンの翼の出口角β2を、それぞれ所定の範囲に特定する ことで、室内ユニットから所定風量を得るのに必要なファンモータ入力 や回転数を低減することができ、省エネを図ることができる点にその技 術的意義がある。また、前面熱交換器の設置角度αを65°以上とする ことで、熱交換器からの水滴がファンへ流入して室内ユニットの外部へ 吹き出されること等を防止し、室内ユニットの奥行きをコンパクトにで きるという効果もある(【0024】)。 もっとも、省エネ、ドレン水の確実な処理及び室内ユニットのコンパ クト化という課題自体は、本件発明2−1の特許出願以前から存在する ものであり、上記課題に対して、熱交換器を逆V字状にすること、前面 熱交換器と背面熱交換器との連結部を送風ファンの中心軸よりも前面側 に位置させ、かつ前面熱交換器の傾斜を急な配置にすること、熱交換器 を通過した空気がファンの翼に当たる際の空気の流れ方向の変化を滑ら かにし、空気流の剥離等を防ぐために、翼形状を変更することといった 着想や技術自体は、従来から存在していた(前記(2)ウ)。 したがって、本件発明2−1は、ルームエアコンに備えられる基本的 な構成要素である熱交換器及びクロスフローファンについて、前面熱交\n換器の配置及びクロスフローファンの翼形状(出口角)を、同時に、具 体的な数値範囲をもって特定したところに技術的な意義があるものと認 められる。
b 他方で、ルームエアコンの省エネ性能の向上を図る技術には、室内\n機及び室外機それぞれを見ても、熱交換器、圧縮機、モータ、送風機 等に係る種々の技術が存在する。しかも、1審被告のほか、国内の競 合他社であるパナソニック、ダイキン、東芝、日立等は、それぞれ、\n省エネのための独自の基本的な技術を有しており、●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1審被告以上又は同等 の市場占有率を保持していたと認められる(上記(2)イ、キ(ウ)、ク (イ)及び(ウ))。 また、本件発明2−1は、前面熱交換器の配置及びクロスフローフ ァンの翼形状(出口角)を特定することによって送風の効率を高める ものであるところ、競合他社が、それぞれ独自に、ユニットの構造、\n熱交換器の配置、ファンの形状等を工夫して製品化をしていることか らすれば、競合他社の製品に本件発明2−1をそのまま実施すること により直ちにその性能が向上するものとは認められない。\n したがって、本件特許権2の存在により第三者に本件発明2−1の 実施を禁止したことに基づいて得ることができた利益は、限られた範 囲内のものと認められる。
c 加えて、1審被告は、対象製品群2の販売に当たり、被告カタログ 2)において、ムーブアイを大々的に取り上げるとともに、そのほかに も脱臭機能、換気機能\、サプリメントエアー機能といった付加価値的\nな機能をも顧客に対し強く訴求していること、対象製品群2が販売さ\nれた当時、既にルームエアコンは家庭に広く普及し、省エネ等に係る 技術は、競合他社の製品においても採用されていたと考えられること を踏まえると、付加価値的なものとはいえ、このような他社製品との 差別化を図る技術は消費者に対する訴求力を高め、対象製品群2の売 上げに大きく貢献したものとみるのが相当である。
(ウ) 小括
以上の事情を総合考慮すると、本件発明2−1に係る超過売上高は、 前記ウの売上高の0.5%と認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
2023.05. 2
令和3(ワ)6908 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月30日 大阪地方裁判所
前記本件明細書の記載によれば、本件特許発明は、落下物受取装置の基端部 の縁と足場構築体の作業空間の外側面の間に隙間が生じ小さい物品が落下し\n人体を負傷する危険があり、当該隙間を単純な板材で塞いだ場合には落下物受 取装置を格納する際に板材を取外す必要がある等姿勢変更の作業が困難であ るといった課題に対し(【0008】【0009】)、当該隙間を覆うことができ、 かつ落下物受取装置の姿勢変更等によって隙間が変化する場合でもそれに追 従し確実に隙間を塞ぐことができる隙間遮蔽装置を提供するものである(【0 014】【0038】)。本件明細書には、本件特許発明の実施例として、隙間遮 蔽装置は、固定部材を落下物受取装置の基端部に取付一体化した構成とする場\n合と、落下物受取装置に後付けされるユニットを構成する場合とを挙げており\n(【0016】)、後付け可能かつ着脱自在の隙間遮蔽装置の実施例の一つ(ユ\nニット20a)として、固定部材に枢結手段を介して遮蔽部材を回動自在に連 結するものが記載されている(【0039】【0040】【0043】)。 このような固定部材に枢結手段22を用いて遮蔽部材を回動可能に枢結す\nる方法は、本件明細書上、「図4に示す1実施形態において」(【0039】)、 「図示のようにユニット20aを構成する場合は」(【0043】)と記載され\nているとおり、後付けユニットタイプの隙間遮蔽装置の一実施例という位置付 けで記載されているに過ぎない。また、本件明細書には、固定部材の大きさ及 び形状並びに落下物受取装置への固定方法については適宜の方法を採用する ことができることが示唆されており(【0040】)、その余の本件明細書の記 載を見ても、「固定部材(21)」が、特定の構成を備えるべきものであるとか、\n枢結手段が、固定部材(21)と別途独立のもの(部材)であることが前提で あることをうかがわせるとかの旨の記載はない。 したがって、本件特許発明における「固定部材(22)」とは、実施例のよう に固定部材とは別の枢結手段が存在する場合に限らず、固定部材が枢結手段と 一体のもの、一つの部材が固定部材と枢結手段を兼ねるものなどもこれに当た ると解される。
むしろ、枢結手段が固定部材から独立して存在すること(独立した部材であ ること)等が要求されていないとの解釈は、上記のとおり実施例の一つとして 挙げられた固定部材に遮蔽部材を枢結する「蝶番」について、「枢結部材」では なく「枢結手段」と記載されていることと整合するといえる(【0039】【0 043】)。 なお、構成要件Cないし同Fには「固定部材(21)」として符号が記載され\nているものの、これは請求項の記載内容を理解するために補助的に付されたも のであると解され(特許法施行規則24条の4及び様式29の2の〔備考〕1 4のロ)、それ以上に本件特許発明における固定部材の構成を符号により特定\nされる実施形態に限定するものであると解すべき事情も見当たらない。 したがって、本件明細書の記載を参酌しても、本件特許発明において、上記 (1)のとおり、1)落下物受取装置の基端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成す\nる部材であること(構成要件C)、2)(隙間遮蔽装置使用時に)固定部材から足 場構築体に向けて遮蔽部材が延びていること(構\成要件D)、3)遮蔽部材が回 動自在に枢結されていること(構成要件E)、4)(隙間遮蔽装置不使用時に)遮 蔽部材が固定部材に向けて回動することにより固定部材の上に重ねられるこ と(構成要件F)という要素を充たせば「固定部材」(構\成要件C〜F)に相当 する部材であるといえ、これに加え、枢結手段とは独立して存在することを要 するものではないと解すべきである。
(4) 被告製品における「蝶番(の第1翼片)」が本件特許発明の「固定部材」に 相当するか(あてはめ)
別紙被告製品説明書のとおり、被告製品における蝶番は、第1翼片、第2翼 片及び回転軸から成り、第1翼片(図3右側のもの)が落下物受取装置の基端 部にリベット等で固着され、第2翼片(図3左側のもの)が遮蔽部材に固着さ れている。これにより、被告製品の蝶番の第1翼片は、1)落下物受取装置の基 端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成する部材であること(構\成要件C)、2) (隙間遮蔽装置使用時に)固定部材(第1翼片)から足場構築体に向けて遮蔽\n部材が延びていること(構成要件D)、3)遮蔽部材が回動自在に枢結されてい ること(構成要件E)、4)(隙間遮蔽装置不使用時に)遮蔽部材が固定部材に向 けて回動することにより固定部材の上に重ねられること(構成要件F)という\n要素を全て充たしているといえ、本件特許発明の「固定部材」に相当する部材 であるということができる。
被告は、このように解すると構成要件Fの構\成及びその構成の作用効果の説\n明と矛盾する旨主張するが、保管・運搬に便利となるとの作用効果は、遮蔽部 材を回動自在に枢結することによりもたらさせるものであって、固定部材の構\n成に由来するものではないから、その主張は失当である。 したがって、被告製品は、構成要件Cないし同Fを充足しており、構\成要件 A、同B、同Gを充足することは争いがないから、本件特許発明の技術的範囲 に属する。
・・・
(2) 推定覆滅事情
被告は、本件特許発明は、製品の一部のみに実施されるものであること、被 告製品には他の顧客誘引力がある一方、本件特許発明に顧客誘引力が乏しいこ と、本件特許発明以外の特許発明の実施や被告商品に付された商標が顧客誘引 力を持つことから、上記損害額の8割は推定が及ばないものと主張する。
ア 本件特許発明の意義
前判示のとおり、本件特許発明は、建設現場等で高所からの工具等の落下 による負傷等を防止するために設置される落下物防止装置(朝顔)において、 「落下物受取装置は、…該落下物受取装置の基端部の縁と、足場構築体の作\n業空間の外側面の間には、狭小な隙間を生じることが不可避である。このた め、…小さい物品が落下すると、前記隙間を通過することにより地上に向け て落下するおそれがあり、金属製等の落下物の場合、微小な物品であっても 人体を負傷する危険がある。」等の課題に対して、隙間(S)を覆う隙間遮蔽装 置を設け、前記隙間遮蔽装置は、前記落下物受取装置の基端部に固定される 固定部材と、該固定部材から足場構築体に向けて延びる遮蔽部材を備え、前\n記固定部材に対して前記遮蔽部材を回動自在に枢結しており、前記遮蔽部材 は、不使用時に前記固定部材に向けて回動することにより、該固定部材の上 に重ねられるように構成することにより該課題を解決するものである。\n この点、証拠(甲3、4(枝番を含む))及び弁論の全趣旨によると、被告 製品における遮断板によって遮蔽される隙間は、足場の設置態様によっては 相応に幅が広いものも想定され(少なくとも被告主張のような傷害結果が生 じることが極めて稀な小さなもののみが通過する隙間に限られないと認め られる。)、被告製品においても、朝顔において隙間を塞ぐことが重要な意義 を有するものと扱われていることが認められるのであって、本件特許発明は、 これを効果的に行うものとしての技術的意義を有し、実施品の顧客誘引力を 高めるものであると認められる。
イ 他方、朝顔の性能としては、被告主張のとおり、上部から外方への落下物\nを直接受け止める部分であるパネル部分(本件特許発明でいう落下物受取装 置)の性能が重要であろうことは商品の性質上当然であり、被告が、本件特\n許発明以外の特許を実施している点を指摘するのも、この趣旨をいうものと 理解することができる。また、作業効率性、美観性といった被告製品の他の 要素も顧客誘引力に相応に寄与することも理解できるところである。もっと も、被告商品2に付された被告商標については、これについて特段の顧客誘 引力があることをうかがわせる証拠はないため、本件において考慮すること は困難である。また、本件特許発明が製品の一部に実施されているという主 張は、落下物受取装置が遮断板に向かって傾斜を持った態様で運用されるこ とからすると、同装置で受け取られた落下物は遮断板に至り、遮断板によっ て更に下方への落下が阻止されることになるのであって、このように、遮断 板と一体となって落下物の下方への落下が防止されるという被告製品の構\n成からすると、本来的な意味で特許技術が製品の一部にのみ実施されたもの であるということはできない。なお、被告は、本件特許発明は、遮蔽部材を落下物受取装置の基底部に回動可能に固定することのみを特徴としている旨主張するが、抽象的には遮蔽部材を設置して隙間を塞ぐ構\成は他に考え得る趣旨をいうものと解したとしても、その具体的な競合品等に関する主張立証はされていないから、これを推定の覆滅に当たって考慮することは困難である。
ウ 本件において、イに述べた事情はあるものの、被告が指摘する事情はなお 同種の商品一般の顧客誘引力の重点の置き方を指摘するものにとどまって おり、これらの事情を特許法102条2項による推定を覆滅させる事情とし て重く見るのは相当でなく、総合的にみると、(1)で推定される原告の損害 のうち、3割の限度ではその推定の覆滅の立証があったものというべきであ る。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2023.05. 2
令和3(ワ)11118 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年1月26日 東京地方裁判所
本件同人誌は、本件ゲームの愛好者向け同人誌即売会である本件即売会に おいて販売された同人誌である。その内容も、本件ゲームそれ自体とは異な り、本件キャラクターを性玩具として扱うなどの本件キャラクター描写のよ うな卑猥なイラストやストーリーを含む漫画を主な内容とし、全体としては、 本件ゲームないし本件キャラクターを揶揄する趣旨も含むものと理解される。 しかも、本件同人誌は、随所に原告A個人を揶揄する趣旨のものと理解され るイラストや文言による描写をも含む。本件クレジット表記に「TwiFemis」 として 3 つのツイッターアカウントが挙げられているところ、この語がツイ ッター上でフェミニズムに関する言動を展開する人々又はその現象を指すイ ンターネットスラングであることに鑑みても、本件同人誌は、本件クレジッ ト表記に表\記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわ れる。
このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と 読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌 の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本 件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。 しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本 件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必 ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌 の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件 ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるとい う判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合 理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記\nに原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されているこ とは、このような理解を強めるものといえる。 この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクター に対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見る のが相当である。また、原告Aについても、本件ゲームのプロデューサーと して本件ゲームのユーザーの間では著名な人物であることなどに鑑みると、 原告会社とは別に個人としての社会的評価が同様に低下すると見られる。 このことは、本件店舗描写に関しても同様である。
(3) 小括
以上の事情に鑑みると、一般的な読者の普通の注意と読み方を基準とすれ ば、本件キャラクターに対する卑猥な描写をその内容とすると共に、クレジ ット表記に「SPECIAL THANKS」と付して原告らの名称等を記載した本件同 人誌を頒布する行為及び本件店舗描写は、原告らそれぞれの名誉を毀損する ものといえる。これに反する被告の主張は採用できない。
2 本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aのパブリシティ権侵害 の成否(争点 1-2)について
原告Aは、被告が本件マスクを着用しながら本件同人誌を頒布した行為及び 本件同人誌に本件マスクの写真を掲載した行為につき、原告Aのパブリシティ 権侵害を主張する。肖像等を無断で使用する行為については,1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商 品等に付し,3)肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有す る顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害する ものとして,不法行為法上違法となる(最高裁判所平成 24 年 2 月 2 日第一小 法廷判決・民集 66 巻 2 号 89 頁参照)。
本件の場合、そもそも、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であると しても、そのことから直ちに同原告の肖像等に顧客吸引力があることにはなら ないところ、この点について、同原告は何ら具体的な主張立証をしない。 この点を措くとしても、本件マスクは、原告Aの写真を顔面に着用できるよ うに山型に湾曲させただけの粗雑な作りのものにすぎない。そのため、本件マ スクやこれを撮影した写真は、同原告の肖像の写真(甲 10)とは相応に異なる 印象を与えるものであり、同原告の肖像それ自体を独立して鑑賞の対象とする 目的で作成されたものとはいい難い。また、本件同人誌における本件マスクの 写真は全 頁程度のうちの 8 頁目にのみ掲載されている(甲 5)。しかも、同 頁の本件マスクの写真は、「本邦初公開!これが【神】のリアルマスクだ――\―\nッ!」との宣伝文句と共に、「古来より人は儀式や祭礼に際し、自らに神格を宿 すために仮面をまとったという・だとすれば神である(省略)のマスクが作ら れるのは人間心理の必然的帰結であろう。」との説明文の記載と共に掲載され ており、これらは、本件同人誌の本編である漫画の内容と直接的には無関係に、 主に原告Aを揶揄する文脈で掲載されているものと理解される。これを踏まえ ると、本件即売会での本件同人誌の頒布にあたり被告が本件マスクを着用して いた点についても、同様に原告Aを揶揄する趣旨で行われたものと理解するの が相当である。
また、本件 3 コマ漫画における原告Aの氏名は、その素材となった別作品の 宣伝用画像(甲 148)の構図に擬して作成した最終コマに表\示されたものであ り、著作者として表示されたものとは理解し得ないと共に、当該コマの上部に\n小さく配置されているに過ぎないこともあって、原告Aの氏名の顧客吸引力の 利用を目的としたものとはいい難い。 そうすると、本件マスクの写真の掲載及び本件即売会での本件同人誌頒布時 における着用並びに本件 3 コマ漫画の氏名の記載は、上記1)〜3)のいずれにも 当たらず、その他専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる 場合に当たるとは認めるに足りない。 したがって、これらの行為は原告Aのパブリシティ権を侵害する違法なもの とはいえない。この点に関する原告Aの主張は採用できない。
3 本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aの肖像権及び名誉感情 の侵害の成否(争点 1-3)について
(1) 肖像権侵害の成否
人はみだりに自己の容貌,姿態を撮影されないことについて法律上保護さ れるべき人格的利益を有するところ,ある者の容貌,姿態をその承諾なく撮 影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位, 撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮 影の必要性等を総合的に考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会 生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決せられる (最高裁平成 17 年 11 月 日第一小法廷判決・民集 59 巻 9 号 2428 頁参照)。 撮影された写真が雑誌等に掲載されるなどして公開された場合も,同様の判 断枠組みが妥当すると考えられる。 前記 2 のとおり、本件マスクは、原告Aの写真を粗雑な方法で加工したも のであり、原告Aの肖像の写真(甲 10)とは相応に異なる印象を与えるもの ではある。しかし、本件同人誌では本件マスクが原告Aの「リアルマスク」 と紹介されていること、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であるこ と等の事情に照らすと、被告が本件マスクの写真が掲載された本件同人誌を 本件マスクを着用しながら頒布した行為は、原告Aの写真を無断で公開した 場合と同様に理解することができる。また、本件同人誌の内容、とりわけ本 件マスクの紹介の仕方等に照らすと、被告は、専ら原告Aを揶揄する目的で 本件マスクを作成し、これを着用の上、その写真を掲載した本件同人誌を頒 布したといえる。
以上のような写真の使用目的及び使用態様等に照らすと、本件マスクに係 る被告の各行為は、自己の容貌等の写真をみだりに公開されないことについ ての原告Aの人格的利益を侵害し、その侵害が社会生活上受忍すべき限度を 超えるものというべきであり、不法行為法上違法と認めるのが相当である。 これに反する被告の主張は採用できない。
(2) 名誉感情の侵害
前記のとおり、被告は、専ら原告Aを揶揄する目的で本件マスクを作成し、 これを着用の上、本件即売会にて本件同人誌を頒布した。加えて、本件同人 誌には、原告Aと同定される男性イラストに係る本件男性イラスト描写が掲 載されている(前提事実(3))。また、本件店舗描写についても、本件同人誌の 他の記載と合わせると、「(省略)」などの記載は原告Aを指すことが明確に理 解される。このような被告の行為は、原告Aに対する社会通念上許される限度を超える 侮辱行為であり、原告Aの人格的利益(名誉感情)を侵害する違法なものとし て、不法行為に当たるとするのが相当である。これに反する被告の主張は採用 できない。
4 本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否(争点 2)について
(1) 本件店舗に関する投稿について
被告は、別紙 4 投稿目録(4)のとおり、原告会社の運営する本件店舗を「キ ャバカレー」、「派遣型風俗キャバカ〇ー機関」などと呼んだ上、「キャバカレ ー」が違法風俗店として摘発され、セクキャバ「キャバカレー」経営者であ る「(省略)」が風営法違反の疑いで逮捕されたという内容の画像を、実在す るニュース映像風の画像のように表現して投稿した(前提事実(2)ア)。 一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告の上記各投稿は、 原告会社の経営する本件店舗が「違法風俗店」として捜査機関により摘発さ れ、原告Aと同定される者が風営法違反の疑いで逮捕されたという事実を摘 示したものと理解される。これにより、上記各投稿は、これを閲覧した者に おいて、原告らが違法な風俗店を経営し、その代表者である原告Aが逮捕さ\nれたという印象を与えるものであって、原告らの社会的評価をいずれも低下 させるものといえる。 したがって、被告の上記各投稿は、原告らそれぞれの名誉を毀損するもの であり、原告らに対する不法行為に当たると認められる。これに反する被告 の主張は採用できない。
・・・
以上のとおり、被告による本件同人誌の頒布等による原告Aの名誉毀損並 びに本件マスクを着用して本件同人誌を頒布等した行為による同原告の肖像 に係る人格的利益及び名誉感情の侵害は、いずれも同原告に対する不法行為 を構成するものと認められる。また、被告のツイッターにおける本件店舗に\n関する投稿による原告Aの名誉毀損並びに同原告の顔写真等の投稿による同 原告の肖像に係る人格的利益及び名誉感情の侵害は、いずれも原告Aに対す る不法行為を構成するものと認められる。\n他方、本件同人誌の頒布等による原告Aのパブリシティ権の侵害及び被告 のツイッターにおける被差別部落に関する投稿による同原告の名誉権の侵害 は認められない。
(2) 原告会社の請求について
以上のとおり、被告による本件同人誌の頒布等及び被告のツイッターにお ける本件店舗に係る投稿による原告会社の名誉毀損は、いずれも原告会社に 対する不法行為を構成するものと認められる。\n他方、被告のツイッターにおける本件キャラクターの人権等に言及する投 稿、本件キャラクターに関する卑猥な投稿及び被差別部落に関する投稿につ いては、いずれも原告会社の名誉を毀損するものとはいえず、原告会社に対 する不法行為を構成するものとは認められない。\n
◆判決本文
こちちに争点となった表記があります。\n
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 肖像権等
>> ピックアップ対象
2023.05. 2
令和2(ワ)8168 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年1月26日 大阪地方裁判所
ア 「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)といえるためには、客観的に秘密 として管理していると認識できる状態にあることが必要であり、管理方法が 適切であって、管理の事実が認識可能であることを要すると解される。\nイ 前記(1)によると、本件では、本件秘密保持等契約書以外に営業秘密を具 体的に明示した文書はなく、原告が被告らに対し「ロングキープラッシュ」 の施術方法を教示するに際して本件特許出願の願書や明細書その他の添付 書類等を示しておらず、まつ毛エクステンションの装着方法に関して具体的 にいかなる範囲が秘密とされるのかを明らかにした書面もない。しかも、「ロ ングキープラッシュ」は、被告らの原告在職当時、原告の各店舗において、 不特定多数人に対して何らの制限もなく公然と施術されていた。また、まつ 毛エクステンションの業界においては、まつ毛エクステンションの装着方法 が全て秘密にされるわけではなく、新規の装着方法であっても、公開され、 他のアイリストに教授されることもあり、装着方法を秘密とするか否かや装 着方法のうち具体的にどこまで秘密にするかは、自明なものではない。 そうすると、本件秘密保持等契約書に規定された「特許技術」以外の本件 特許情報及び本件手技情報は、原告において適切に秘密として管理されてい たとはいえず、秘密として管理されているとは認識できない状態であったと いわざるを得ない。また、原告は、被告らに対し、「ロングキープラッシュ」 を教示したのであって、本件特許出願に係る願書等を示したわけではないか ら、本件秘密保持等契約書の「特許技術」は、その文言どおり、「ロングキー プラッシュ」についての本件特許情報、すなわち、本件特許情報のうち、地 まつ毛の上部に2本又は3本のフラットラッシュを装着し、地まつ毛の下部 に1本のフラットラッシュを装着する実施例に係る情報を意味するものと 解される。
そして、当該情報は、不特定多数の顧客に対して公然と施術される装着方 法であり、施術を受ければ視覚的に認識できるものであるから、やはり秘密 として管理されていたとはいえず、秘密として管理されているとは認識でき ない状態であったということになり、結局、本件秘密保持等契約書上の「特 許技術」も、不正競争防止法上の営業秘密とはいえない。 ウ 原告は、「ロングキープラッシュ」の技術は本件特許情報だけではなく、文 書化されていない非公開の手技があり、それを含めて営業秘密と指定し、秘 密保持契約を締結したので秘密管理性があると主張する。 しかしながら、原告の主張する文書化されていない非公開の手技について は何ら具体的な主張立証がなく、前記イのとおり、本件秘密保持等契約書の 対象は、本件特許情報のうち、地まつ毛の上部に2本又は3本のフラットラ ッシュを装着し、地まつ毛の下部に1本のフラットラッシュを装着する実施 例に係る情報であって、文書化されていない非公開の手技や本件付加情報は 含まれないから、採用できない。
2023.05. 2
令和3(ワ)8940 特許権移転登録抹消登録請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年4月12日 東京地方裁判所
(1) 前記前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を 認定することができる。
ア Aは、海外医療旅行株式会社の代表取締役として、平成28年7月11\n日、被告との間で、委託期間を2年間とする本件販売業務委託契約を締結 し、被告装置の販売業務を遂行していたが、被告装置を販売する上で、A に、被告における役員の肩書を付与する必要があるとの理由から、平成2 9年11月30日、被告の取締役に就任した。
イ Aは、令和元年10月31日、本件特許に係る発明の開発並びに同発明 を実施して製品を製造及び販売するため、原告を設立して取締役に就任し、 遅くとも令和2年9月1日までには、被告に辞任届を提出して被告の取締 役を辞任した(甲16、25、26、乙4)。
ウ Aは、令和2年4月17日、発明の名称を「亜臨界水処理装置」とする 特許出願をし(特願2020―73937)、同年7月20日、本件特許権\nの設定登録を受けた。
エ 被告の取締役であるEは、令和2年9月下旬から10月初旬にかけて、 複数の第三者から、Aが被告製品とは異なる有機廃棄物処理装置を販売し ようとしているとの情報を得て、原告の代表取締役であるCに対し、事実\n関係の確認をするとともに、抗議をした(乙11)。
オ Cは、令和2年10月5日頃、被告の代表取締役であるDに電話をし、\n原告の代表取締役として、Aが原告に本件特許権を取得させて被告製品の\n競合品である原告製品を第三者に販売しようとしたことについて謝罪し、 事態を収拾するため、本件特許権を譲渡したい旨申し入れた。Dは、同申\ 入れを受け入れることとし、Cに対し、「取締役会決議等の社内決裁手続は 取れているんでしょうね?」と尋ねたところ、Cは、「Aも了解しているし、 社内手続も大丈夫だ。」と述べた。しかし、実際には、原告の取締役会にお いて本件特許権譲渡の承認決議はされていなかった。(乙11、被告本人、 弁論の全趣旨)
カ 被告は、令和2年10月8日頃、弁理士に本件譲渡証書の原案を作成さ せて、これをCに交付し、Cは、Cの記名の横に改印後原告代表者印によ\nり押印し、本件譲渡証書を作成した(甲5、7、8、乙11)。
キ 被告は、令和2年10月9日、特許権移転登録申請書に本件譲渡証書を\n添付した上で、本件特許権の移転登録を被告単独で申請し、本件特許権の\n移転登録手続をした。なお、同手続がされた時点において、原告は、取締 役会設置会社であった。
(2) 前記認定事実に基づき、被告が、原告の取締役会決議がないことを知り、 又は知ることができたかについて、以下検討する。 ア 前記(1)エによれば、Dは、本件特許権の譲渡時までには、Aが、原告を 設立して原告に本件特許権を取得させ、被告製品と競合する有機物廃棄処 理装置を販売しようとしていたことについて、認識していたものと認めら れる。そして、本件特許権が原告にとって重要な財産であることは被告も認め るところであり、前記(1)イないしエに照らせば、被告は、原告が本件特許 権を実施することにより収益を得ようと企図していたことについても認識 していたものと認められる。これらの事情に照らすと、被告において、原 告が競合他社である被告に対し本件特許権を無償で譲渡することはないと 考えるのが通常であるといえる。それにもかかわらず、前記(1)オのとおり、 Dは、Cに対し、「取締役会決議等の社内決裁手続は取れているんでしょう ね?」と尋ね、Cが「Aも了解しているし、社内手続も大丈夫だ。」と述べ たことのみをもって、承認決議が存在すると考え、本件特許権の移転登録 手続を経たというのである。
このような本件特許権の譲渡の経緯に照らすと、Dにおいて、本件特許 権の移転登録手続を経る前に、Cに対し、原告の承認決議があったことを 裏付ける取締役会議事録を提出させるか、又は、原告の実質的経営者であ るAに対し、真実本件特許権を譲渡することに承諾しているのかどうかを 確認しておけば、本件特許権の譲渡につき、原告の取締役会による承認決 議がされていないことを認識できたというべきである。そして、本件特許 権の移転登録手続を経ることが、被告にとって急を要するものであったと はうかがわれないこと、また、Aが被告の取締役であり、被告とAは既知 の関係にあったこと(前記(1)ア)に照らすと、本件特許権の移転登録手続 を経る前に、上記の確認をとることは容易であったといえる。したがって、Dは、少なくとも本件特許権譲渡について原告の取締役会における承認決議がなかったことを知ることができたといえるから、本件においては、民法93条ただし書の規定を類推して、原告はCによる本件特許権の譲渡は無効と解するのが相当である。
イ 被告は、本件特許権の譲渡は、Aが被告に対し、競業避止義務違反及び本件販売業務委託契約違反となる行為を行ったことから、それに対する謝罪の意味でされたものであるなどと主張して、被告が原告の当時の代表取締役であったCが述べたことを信じたのは正当である旨主張する。しかし、前記アのとおり、原告が被告に本件特許権を無償で譲渡することを承諾することは通常考え難い上、仮に、Aが被告に対して競業避止義務違反となる行為又は海外医療旅行株式会社の代表\取締役として本件販売業務委託契約違反となる行為を行った事実があるとしても、本件特許権の特許権者は原告であり、原告がA又は海外医療旅行株式会社の上記義務違反の責めを負う理由はないというべきである。したがって、そのような事実は、被告が承認決議の不存在を認識していなかったことを正当化し得るものではない。
2023.05. 2
令和4(行ケ)10120 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年4月25日 知的財産高等裁判所
前記1の認定事実によれば、【A】氏及び原タート社が販売する眼鏡フレーム等は、米国の著名な俳優等に愛用されてきたが、同社は1990年代には事業を停止していたところ、原告及び原告事業会社は、米国において「TART」の商標を付した眼鏡フレームの販売を開始し、その製造及び販売する眼鏡フレームは、2009年頃から我が国に輸出され、一部の雑誌には、米国の著名人に愛用されてきた【A】氏の事業を承継したブランドに係る眼鏡フレームであると紹介する記事等が掲載されていることが認められる。しかし、我が国に輸出された数量は、証拠上裏付けられる期間(2009年から2016年までの間)で合計約750個程度であって、我が国の眼鏡フレームの市場において主要な割合を占めているとは到底いえず、また、一部の雑誌媒体や眼鏡販売店等のウェブページ等において、原告らが製造販売する眼鏡フレームがかつて著名な俳優が愛用したブランドであり、復活したなどと取り上げられたり、原告らが開設するフェイスブック(ただし、英語版)において米国の著名な俳優や歌手等が愛用していることが取り上げられたりしているものの、頻繁に我が国のファッション関係の雑誌等で原告商品が取り上げられているといった事実や、「TART」ブランドに係る眼鏡フレームが原告らによる商品であるとの効果的な広告宣伝を行っており、これにより我が国の需要者等の認知度が高まっているといった事実を認めるに足りる証拠もない。したがって、少なくとも我が国においては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「TART」の商標を付した眼鏡フレーム(原告商品)が原告らの業務に係る商品を表示するものとして取引者及び需要者の間において広く認識されているものと認めることはできない。\n
本件商標の要部について
ア 複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、その構\成部分全体によって他人の商標と識別されるから、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは原則として許されないが、取引の実際においては、商標の各構\成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、必ずしも常に構成部分全体によって称呼、観念されるとは限らず、その構\成部分の一部だけによって称呼、観念されることがあることに鑑みると、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構\成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である(最高裁昭和37年 第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
これを前提として本件商標についてみると、本件商標の構成中「JULIUS」、「TART」、「OPTICAL」の単語の間には、それぞれ空白部分があるが、それぞれの文字は同書同大で、「TART」の文字部分は強調されていないのみならず、前記 のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「TART」(引用商標)は、本件商標の指定商品である「眼鏡フレーム」等との関係で周知な商標であるとはいえないから、本件商標の構成のうち「TART」が取引者及び需要者に商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。また、「OPTICAL」は、「目の」、「光学上の」と訳される(甲8、9)が、一般になじみのある英語であるとまではいえないから、指定商品との関係で識別力がないとまではいえない。むしろ、本件商標は、「JULIUSTART OPTICAL」の欧文字(標準文字)を同書同大でまとまりよく一体的に構成されているものであり、「ジュリアス タート オプティカル」とよどみなく称呼することが可能である。したがって、「TART」を要部として抽出することはできず、本件商標は一体不可分の構\成の商標としてみるのが相当である。
イ 原告は、前記第3の1 イのとおり、被告が本件商標中の「TART」の部分を強調して被告商品の広告及び宣伝をしている事実(甲4、51ないし55)を挙げて、「TART」が要部であることを示している旨主張するが、そもそも被告のウェブページ(乙3ないし5)では「TART」の文字部分を強調した構成で表\記されていないし、この点を措くとしても、商標の構成を離れて実際の商品の宣伝広告の方法から要部を認定すべきとする原告の主張は当を得たものではなく、本件において、仮に被告が「TART」の文字部分を強調した宣伝等を行っていたとしても、前記認定を左右するものではない。\n
◆判決本文
関連事件です。
令和4(行ケ)10121
こちらは商標が「JULIUS TART」と「TART」です。結論は非類似です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.04.27
令和4(行ケ)10098 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年4月20日 知的財産高等裁判所
(1) 本件審決が前記第2の3(1)アのとおり甲1発明を認定し、同(2)アのとおり 本件発明1と甲1発明における茶葉の移送方法を対比して一致点及び相違点1を認 定したのに対し、原告は、本件審決は、本件発明1と甲1発明が、「負圧吸引作用を 奏する背面風(W)を前記刈刃(22)の直後方から移送ダクト(6)に送り込む こと」で一致していることを看過したと主張する。原告の上記主張は、甲1発明の内容として、1)送風ダクト52からの吹出口が刈刃34の「直後方」から風を送り込むものであることと、2)送風ダクト52を介して吹き上げファン51から吹き出された風が「負圧吸引作用を有すること」が認められるべき旨をいうものと解されるが、次のとおり、甲1発明の内容として、上記1)及び2)のいずれも認めることができない。
ア(ア) まず、原告は、甲1の「なお刈刃34は、摘採機フレーム基板32の前方 ほぼ延長上に設けられるものである。そしてこの摘採機体3における摘採機フレー ムパイプ31と摘採機フレーム基板32とにより区画され、摘採された茶葉Aが中 継移送装置5によって上昇移送されるまでの部分を摘採作用部36とする。」との 記載(【0013】)及び「送風ダクト52は、摘採した茶葉Aを摘採作用部36た る刈刃34後方部から収容部4まで風送するものであり、具体的には吹き上げファ ン51から送り出された風が、茶葉摘採機1の側部を回り込むようにして摘採作用 部36に達し、この部分で茶葉Aと合流し、合流後この茶葉Aを茶葉移送路52a を経由させて収容部4まで風送するものである。」との記載(【0016】)を指摘し て、「刈刃34」で刈り取られた茶葉が直接「摘採作用部36」に送り込まれること から、「摘採作用部36」が「刈刃34」の直後方に位置することは明らかであると 主張する。
(イ) しかし、甲1の【0013】の上記記載は、「摘採作用部36」を区画するも のの一つである「摘採機フレーム基盤32」と「刈刃34」との位置関係について、 刈刃34が摘採機フレーム基盤32の「前方ほぼ延長上に設けられる」と示すにと どまり、摘採作用部36と刈刃34の位置関係について具体的に特定するものとは みられない。 また、同【0016】の上記記載も、「摘採作用部36たる刈刃34後方部」とい う部分において、摘採作用部36が刈刃34の後方に位置することを示しているも のの、摘採作用部36が刈刃34の後方のどの程度の距離にあるものか等について、 具体的に示すものとはみられない。 その他、甲1において、「摘採作用部36」が「刈刃34」の直後方に位置するこ とを認めるべき記載は見当たらない。
(ウ) また、仮に、甲1において、「摘採作用部36」が「刈刃34」の直後方に位 置することが認められるとした場合に、そのことから直ちに、「送風ダクト52風」 が「刈刃34」の直後方から送り込まれることが認められるものでもない。 この点、甲1に、吹き上げファン51から送り出された風が、送風ダクト52を 介して、刈刃34の後方に位置する摘採作用部36のどの部分に達するのかを具体 的に特定する記載は見当たらない。 むしろ、甲1の【図1】の左下部の丸枠内及び【図5】によると、送風ダクト5 2は、刈刃34の後方に位置するとされる摘採作用部36の後端部に位置付けられ ているところである。そして、【図4】によると、刈刃34と送風ダクト52との間 に少なからず距離が存することは、明らかである。
(エ) したがって、甲1発明について、送風ダクト52からの吹出口が刈刃34の 「直後方」から風を送り込むものであることが認められるべき旨をいう原告の主張 は、採用することができない。
イ(ア) 次に、原告は、「送風ダクト52からの吹出口は、摘採機フレーム基板32 後端部と茶葉移送路52aの下端部との間に開口」しており(甲1の【図5】等)、 この吹出口から送り込まれた「送風ダクト52風」が、「摘採作用部36」に達し、 「この部分で茶葉Aと合流し、合流後にこの茶葉Aを茶葉移送路52aを経由させ て収容部4まで風送する」(同【0016】)ところ、「摘採作用部36」において「送風ダクト52風」に負圧吸引作用がなければ、このような事象を説明することはで きない、甲1の【0016】の上記記載は、「摘採作用部36」が密閉又は半密閉状 態のダクトでなければ説明できない内容であるなどと主張する。
(イ) しかし、甲1の【0019】及び【図5】によると、摘採された茶葉は、ま ず、送風ダクト35から排出される風によって摘採作用部36の後方に送られ、次 いで、送風ダクト52を介して吹き上げファン51から吹き出された風により茶葉 移送路52a内を上昇移送されるのであって、送風ダクト52を介して吹き上げフ ァン51から吹き出された風に負圧吸引作用がなくとも、送風ダクト35から排出 される風により、上昇移送が可能となる位置まで茶葉が送られることは容易に理解される。\n
この点、同【0013】には、摘採作用部36について、摘採機フレームパイプ 31と摘採機フレーム基盤32とにより「区画」される旨が記載されているのみで、 それが密閉構造を有することはもとより、閉鎖的な構\造を有することも明記されて おらず、他に、甲1に、摘採作用部36の構造について特定する記載も見られない。そうすると、摘採作用部36は、送風ダクト35から排出される風によって茶葉\nを摘採作用部36の後方に送ることが可能な構\造となっていれば足り、原告の主張 するように、密閉又は半密閉状態にあることを要するものではないと解される。
(ウ) 上記に関し、原告は、摘採作用部36が密閉又は半密閉状態でないとすると、 送風ダクト35から排出される風によって周辺に分散して回収不能になってしまう茶葉が生じ、甲1発明における茶葉の中継移送機能\が低下することになるなどと主張するが、茶葉の分散を避けるためには、茶葉が通過しない程度の空隙を有する部 材で摘採作用部36を構成することで足りるといえるし、茶葉の損傷を避けるためという観点を更に考慮したとしても、直ちに摘採作用部36が密閉又は半密閉状態\nであることまで要するものとは解されない。
(エ) したがって、甲1発明について、送風ダクト52を介して吹き上げファン5 1から吹き出された風が「負圧吸引作用を有すること」が認められるべき旨をいう 原告の主張は、採用することができない。
(2) 前記2の甲1の記載事項によると、甲1には、前記第2の3(1)アのとおり本 件審決が認定した甲1発明が記載されていると認められる。その上で、本件発明1と甲1発明における茶葉の移送方法を対比すると、それらの間には、前記第2の3(2)アのとおり本件審決が認定した一致点及び次の相違点1が認められるというべきである
・・・・
(2) 前記3(3)で認定説示した点に照らし、新規性及び進歩性の判断の誤りをいう原告の主張は、採用することができない。
◆判決本文
同特許についての侵害訴訟です。
1審
「圧力風の作用のみによって」を備えず、構成要件Aを充足しない
◆令和2(ワ)17423
控訴審
均等主張もしましたが、第1要件を満たさないとして、控訴棄却。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2023.04.26
令和4(ネ)10125 損害賠償金請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年4月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 控訴人は、前記第2の4のとおり、1)本件各画像がウェブページごとに独立して利用されている以上、損害額はウェブページ数を基本に算定すべきである(同(1)及び(2))、2)第三者に許諾することを想定していない著作物にも相場の利用料を参酌して利用料を算出するべきである(同(3))旨主張する。上記主張に対して、引用に係る原判決の第4の3(補正後のもの)において説示するところを改めて敷衍すると、次のとおりである。
(2) 著作権法114条3項によって、著作権者が著作権侵害によって受けた損害の額とすることのできる「受けるべき金銭の額に相当する額」の算定に当たっては、当該著作物の利用回数あるいは当該利用から生じた利益等の、当該著作物の直接の侵害行為の物理的な分量に従うのみならず、当該著作物の利用期間、利用態様、当該著作物から享受できる内容又は価値、侵害者の内心の態様(同条5項参照)、当該著作物を利用する市場の状況、他の者への利用許諾の状況等の諸般の事情を総合考慮して定めるべきものである。
本件についてみると、ウェブサイトの閲覧上、本件各画像は、見かけ上、本件商品の数に相当するウェブページで閲覧されるものではあるが、それらは一定の目的をもって一体化された画像の一部が使い回されているとみることも可能なものであり、一体の利用とみることができるから、本件各画像又はウェブページごとに複製又は送信可能\化について損害額を算定することは妥当とはいい難い。そして、本件各画像の利用期間も短期間であって、たとえ通販サイトであろうとも、閲覧に供された回数は限定的なものと考えるのが自然である。さらに、本件画像2)中のフライパンで調理中の食材を写した写真と本件画像3)中のフライパンを製造している職人の写真は、スキャンパン社から提供を受けたものであることを控訴人は自認しており(スキャンパン社がこれら写真に係る著作権を控訴人に譲渡したことを認めるに足りる証拠はない。)、控訴人が著作権を有するものではないし、本件各画像は商業的実用用途を目的とする著作物であって、むしろ、本件各商品をありのままに表現することを主目的とするものと理解され、その表\現される思想又は感情は限定的なものであるといえる。このことは、本件各画像が文字、写真等の素材を組み合わせたものであったとしても変わるものではない。また、被控訴人に過失があることは免れないとしても、それは重大なものではなく、その利用目的も、控訴人の営業を殊更に妨害するためであったり、本件各画像に表現されたところから享受できる価値を損なうためであったりなどの、専ら害意に基づくものとは認められず、単純なる自己の営業のための商業的利用にすぎない。n
(3) 次に、写真又は画像についての利用許諾状況をみてみると、日本美術著作権協会の利用申請方法は、画像の利用許諾を原則として1用途1目的につき毎回申\請を要するものと定めていること(甲26)、株式会社東京美術倶楽部の使用料規程は、コンピューター・ネットワークにおける美術の著作物の利用料の額を、著作物1点あたり1回につき1か月当たり1万円(美術関係業態以外)、2か月目以降は5000円と定めていること(甲27)、朝日新聞社が運営するデータベースの利用規約は、収録された写真、動画等を提供するサービスにおける法人の利用条件を、1媒体につき1用途1回限りの非独占的使用に限り、重版、再放送その他の用途で再利用する場合には別料金が発生すると定めていること(甲28)、Imagenaviの利用ガイドは、画像素材について、使用になる用途、期間によって料金設定が決まり、複数媒体に使用する場合には1使用ごとに料金が発生すると定めていること(甲29)が認められるが、これらの規定が念頭に置く「目的」、「用途」、「回数」又は「使用」は何を基準とするかは一義的には明らかでなく、ましてや上記各証拠がウェブサイトという1媒体の中における利用料をウェブページを基準にして決めていると理解することも困難であるから、これら利用料の算定方法を直ちに本件における損害額の算定方法の参考とすることはできない(なお、控訴人から音楽又は音源の利用に関する利用許諾に関する証拠も提出されているが、著作物としての性質が大きく異なるものであり、その参酌は相当でない。)。
(4) さらに、写真又は画像についての利用料についてみると、毎日新聞社は、同社が権利を有する報道写真等をインターネット上で商業利用する者に対し、2万2000円から4万4000円の利用料の支払を求めることがあり(甲5)、朝日新聞社は、同社が権利を有する報道写真等をインターネット上で利用する者に対し、使用期間6か月までの場合に2万2000円、使用期間1年までの場合に3万3000円、使用期間3年までの場合に5万5000円の使用料の支払を求めることがあり(甲6)、株式会社アフロは、同社が権利を有する様々な種類の静止画像をインターネット上の広告やホームページなどに利用する者に対し、同一ウェブサイト内においては利用箇所を問わず、利用期間1年までの場合に2万2000円、利用期間3年までの場合に2万8600円、利用期間5年までの場合に3万3000円の利用料の支払を求めることがある(甲7)との事実が認められるものの、利用許諾される写真のサイズ、質等や、媒体の数、掲載場所等の利用許諾の際の利用条件の詳細が不明であり、これら利用料をそのまま本件における損害額の算定について参考とすることはできず、ましてや、上記利用料を参考として算定した額をウェブページ1ページ当たりの損害として損害額を算定すべきとする根拠ともならない。また、ペイレスイメージズは、印刷物又はウェブ用との用途における画像素材単品での購入価格を、解像度、大きさに応じて440円から5500円に設定しているとの事実は認められるものの(乙3)、どのような画像が想定されているのか不明であり、やはり、この購入代金をそのまま本件における損害額の算定について参考とすることができない。
(5) 以上のとおりであり、本件記録に顕れた諸般の事情を考慮すると、本件における損害額は、被告サイト全体における利用について5万円とするのが相当であると認められ、控訴人の前記(1)1)の主張を採用することはできず、同2)に主張するところを参酌しても、上記結論は左右されない。
3 当審における控訴人の追加主張に対する判断
控訴人は、前記第2の5のとおり、原審及び当審において生じた訴訟費用を不法行為に基づく損害として追加する旨を主張する。民事訴訟手続の遂行により要した費用のうち、民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものについては、専ら訴訟裁判所の裁判所書記官の処分を経て取り立てることが予定されているというべきであるから、当該訴訟における不法行為に基づく損害賠償請求において、民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されないと解される(最高裁判所平成31年(受)第606号令和2年4月7日第三小法廷判決参照)。控訴人は、訴え提起及び控訴提起の手数料や書類の送付に要した郵便費用を不法行為に基づく損害として主張するが、これらは民事訴訟費用等に関する法律2条1号、2号に定めるものであるから、これら費目を本件において損害賠償として請求することはできない。n
◆判決本文
原審はこちら
◆令和3(ワ)28410
関連事件です。
関連事件1
◆令和4(ネ)10105
原審
◆令和4(ワ)3313
関連事件2
◆令和4(ネ)10085
原審
◆令和3(ワ)15526
関連事件3
◆令和4(ネ)10086
原審
◆令和3(ワ)31909
関連事件4
◆令和5(ネ)10002
原審
◆令和3(ワ)21922
以下は地裁のみ
関連事件5
◆令和3(ワ)33431
関連事件6
◆令和3(ワ)28416
関連事件7
◆令和3(ワ)21533
関連事件8
関連カテゴリー
>> 複製
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2023.04.24
令和3(ワ)17636 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年4月14日 東京地方裁判所
(1) 複製及び翻案の判断方法
ア 著作物の複製(著作権法2条1項15号)とは、印刷、写真、複写、録 音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。また、著作物 の翻案(同法27条)とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表\現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表\現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして、著作権法は、思想又は感情の 創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照)、既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、\n事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表\現上の創作性がない 部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、複製 又は翻案には当たらないと解するのが相当である(最高裁平成11年(受) 第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁 参照)。
そうすると、プロアトラスSV及びYahoo!地図が原告地図1を複 製又は翻案したものに当たるというためには、原告地図1とプロアトラス SV及びYahoo!地図が、創作的表現において同一性を有することが必要であるものと解される。したがって、原告地図1とプロアトラスSV\n及びYahoo!地図との間で、アイデアなど表現それ自体でない部分でのみ同一性が認められる場合には、プロアトラスSV及びYahoo!地\n図は原告地図1を複製又は翻案したものに当たらない。また、原告地図1 とプロアトラスSV及びYahoo!地図との間に、表現において同一性が認められる場合であっても、同一性を有する表\現がありふれたものであるなど、その表現に創作性が認められない場合も、プロアトラスSV及びYahoo!地図は原告地図1を複製又は翻案したものに当たらないと解\nすべきである。
ところで、複製又は翻案の成否を判断するに当たっては、著作権を主張 する者が作成したものに着目して創作性を判断し、その上で、被疑侵害者 が作成したものを観察して、著作権の創作的表現と認められる部分が再製されているか否かを判断するとしても、原告地図1における創作的表\現がプロアトラスSV及びYahoo!地図に再製されていると認められるか 否かを検討する必要があるから、原告地図1とプロアトラスSV及びYa hoo!地図の共通部分が創作的表現であるか否かを検討した場合と結論を異にするものではないというべきである。\n
イ この点、地図は、地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号 によって客観的に表現するものであるから、個性的表\現の余地が少なく、 文学、音楽、造形美術上の著作物等に比して、著作権法上の保護を受ける 範囲が狭いのが通例である。しかし、地図において記載すべき情報の取捨 選択及び表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表\れ得るということができる。そこで、地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及 びその表示の方法を総合して判断すべきものであり、前記アの創作的表\現 の同一性についても、このような観点から検討すべきである。
(2) プロアトラスSVが原告地図1を複製又は翻案したものであるか
ア 証拠(甲1、4、63)及び弁論の全趣旨によれば、原告地図1は、沖 縄県糸満市周辺の地図であること、原告地図1及びプロアトラスSVにお ける同市潮平及び阿波根周辺の各記載は、別紙原告地図1・A及びプロア トラスSV・Aのとおりであること、同市照屋周辺の各記載は、別紙原告 地図1・B及びプロアトラスSV・Bのとおりであること、同市兼城周辺 の各記載は、別紙原告地図1・C及びプロアトラスSV・Cのとおりであ ることが認められる。そこで、別紙原告地図1・AないしC及びプロアトラスSV・AないしCを対比し、原告が主張する原告地図1とプロアトラスSVの共通部分 (前記第3の1(原告の主張)(1)ア(ア)a(a)1)ないし5)並びに(b)6)及び 7)。以下、この第4の1(2)アの検討においては、当該(原告の主張)で付 した頭書の番号に従って、「共通部分1)」などという。)が創作的表現と認められるかについて検討する。\n
(ア) 共通部分1)について
a 原告は、原告地図1とプロアトラスSVには住宅地図であるという 共通部分1)が存在すると主張するところ、別紙原告地図1・Aないし C及びプロアトラスSV・AないしCを対比すると、建物や住宅、道 路、河川等が記載されている点で一致するとは認められるものの、こ れらの具体的な記載が一致しているとは認められない。
b 前記aの一致点について検討すると、地図に建物や住宅、道路、河 川等を記載すること自体はアイデアにすぎず、共通部分1)は、表現それ自体でない部分で同一性を有するにすぎないというべきである。\n したがって、共通部分1)について、創作的表現において同一性を有するものと認めることはできない。\n
(イ) 共通部分2)について
a 原告は、原告地図1とプロアトラスSVが、いずれも、検索の目安 となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物について、居住 人氏名や建物名称の記載を省略し、住宅及び建物のポリゴン並びに番 地のみを記載し、当該ポリゴンは影なしのポリゴンであり、番地は当 該ポリゴンのほぼ中央に、紙面又は画面の水平方向に沿って横書きで、 折り返すことなく、必ずしも当該ポリゴンの内部に収まらずに、アラ ビア数字で記載されている点を、共通部分2)として主張する。しかし、別紙原告地図1・AないしC及びプロアトラスSV・Aな いしCを対比すると、原告地図1とプロアトラスSVで、同じ建物に ついて名称が記載されているものもあれば、一方の地図では名称が記 載されているが、他方の地図では記載されていないものもあり、公共 施設やビル等のうち検索の目安となるものや著名なものが異なるとい える。また、原告地図1とプロアトラスSVで、住宅及び建物のポリ ゴンの具体的な記載が全て一致するとは認められない。さらに、原告 地図1では、ほぼ全てのポリゴンにつき番地が記載されているのに対 し、プロアトラスSVでは、番地が記載されていないポリゴンが相当 数ある。
したがって、原告地図1とプロアトラスSVは、一部の住宅及び建 物のポリゴンの具体的な記載の点、一部の建物について建物名称が記 載され、住宅の居住人氏名やその他の建物の建物名称の記載は省略さ れている点、住宅及び建物がポリゴンで表現されており、当該ポリゴンには影が記載されていない点、一部の住宅及び建物の番地が、当該\nポリゴンのほぼ中央に、紙面又は画面の水平方向に沿って横書きで、 折り返すことなく、必ずしも当該ポリゴンの内部に収まらずに、アラ ビア数字で記載されている点でのみ一致すると認めるのが相当である。
b 前記aのとおり、原告地図1とプロアトラスSVで、一部の住宅及 び建物のポリゴンの具体的な記載が一致したとしても、それは、同じ 住宅又は建物を真上から見たときの外枠を記載したことによるもので あるから、住宅及び建物の形状という事実において同一性が認められ るにすぎない。また、原告地図1では、ポリゴンが淡い黄色であるの に対し、プロアトラスSVでは、ポリゴンは薄い灰色、濃い灰色又は オレンジ色であること、原告地図1では、番地は、黒色で、各数字が 鉛直方向に記載されているのに対し、プロアトラスSVでは、番地は、 薄茶色で、各数字が斜体で記載されていることを考慮すると、その他 の一致点は、具体的な表現において同一性を有するものとは認められず、地図の記載方法というアイデアにおいて同一性が認められるにす\nぎないといわざるを得ない。
さらに、共通部分2)が表現において同一性を有するものであるとしても、証拠(乙6、7、11、14、15、25、32ないし38)\nによれば、原告地図1の作成当時、建物及び住宅の真上から見た形状 を影なしのポリゴンで記載した地図は複数存在したと認められる。そ うすると、このような記載方法については、ありふれていたといえる 上、原告地図1の表示範囲である沖縄県糸満市周辺の地図において、建物及び住宅の形状をこのようなポリゴンで記載するとしても、ポリ\nゴンは建物及び住宅の形状に従って記載するものであるため、表現の選択の幅は狭いといわざるを得ないから、創作性は認められないとい\nうべきである。
その上、証拠(乙7、14、15、25、32ないし38)によれ ば、原告地図1の作成当時、建物及び住宅の番地が、建物及び住宅の ポリゴンの中央付近に、アラビア数字で折り返すことなく横書きされ た記載を含む地図は複数存在したと認められる。そうすると、このよ うな記載方法についても、ありふれていたといえる上、原告地図1の 表示範囲である沖縄県糸満市周辺の地図において、建物及び住宅の番地をこのように記載するとしても、番地はあらかじめ指定されている\nものであるため、表現の選択の幅は狭いといわざるを得ないから、創作性は認められないというべきである。したがって、共通部分2)は、表現それ自体でない事実又はアイデアにおける同一性を有するにすぎないか、表\現において同一性を有する としても、その表現に創作性は認められないから、共通部分2)につき、 創作的表現において同一性を有するものと認めることはできない。
c これに対して、原告は、乙第6及び32ないし34号証の各地図は 一般住宅の居住人名が記載された箇所があること、乙第7、14、1 5及び36ないし38号証の各地図は極めて特殊な状況の下で、一部 地域についてのみ作成されたものであること、乙第10号証の地図は そもそもポリゴンの記載がないこと、乙第18号証の地図はポリゴン を記載し、一般住宅の居住人名を記載せず、一部の建物の名称を記載 するという特徴を有しないこと、乙第24及び25号証の各地図は主 に自動車での移動等のために広域の道路情報や地理情報を得ることを 目的としたものであり、そもそも居住人名や番地を記載する必要はな いことからすると、原告地図1の記載がありふれていたことの証拠と ならないと主張する。
しかし、上記各地図は、いずれも、建物及び住宅の真上から見た形 状を影なしのポリゴンで記載したり、建物及び住宅の番地が、建物及 び住宅のポリゴンの中央付近に、アラビア数字で折り返すことなく横 書きされたりする部分を含んでいると認められ、他方で、本件全証拠 によっても、上記各地図が特殊な目的のために作成されたものである といった、ありふれていることを否定するような事情を認めることは できない。そうすると、上記の記載方法はありふれていたものといわ ざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2023.04.21
令和4(ネ)10104 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年4月17日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイート をした場合には、引用リツイートによる場合とは異なり、引用元に引 用の事実が通知されないため、ツイートを引用された者は自分が知ら ないところで議論がされてしまい、また、ブロックした人物からツイ ートを引用されてしまうことがある旨主張する。 しかしながら、ツイッターにおける上記の通知機能は、ユーザーの\n利便性を高めるための付加的な機能にすぎないというべきである。ま\nた、証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば、ツイッターにおける ブロック機能は、ブロック対象のアカウントがツイッターにログイン\nした状態においてのみ、ツイートの閲覧を制限するなどの効果をもた らすものにすぎず、例えば、ブロック対象者がツイッターにログイン せずに、又はブロックされた者とは異なるアカウントでアクセスした 場合には、ブロックした者が公開しているツイートを閲覧することが なお可能である。さらに、ツイッターにおいては、投稿されたツイー\nトがインターネット上で広く共有されて批評の対象となることも当然 に予定されており、ツイートを投稿した者も、自らのツイートが批評\nされることや、その過程においてツイートが引用されることを当然に 想定しているものといえる。
以上の事情を考慮すると、他のツイートのスクリーンショットを添 付したツイートがされた場合に上記の通知機能やブロック機能\が働か なくなるからといって、控訴人の著作者としての権利が、引用リツイ ートの場合と比較して殊更に害されるものということはできない。そ うすると、控訴人が指摘する上記の各事情をもって、本件ツイートに おいて原告ツイートが引用されたことにつき、公正な慣行に合致しな いものであるということはできない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.04.21
令和4(ネ)10060 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年4月13日 知的財産高等裁判所
しかし、そもそも本件規約は本来的にはツイッター社とユーザーとの間の約定であって、その内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではない。また、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規約違反に当たることも認めるに足りない。 他方で、批評に当たり、その対象とするツイートを示す手段として、引用リツイート機能を利用することはできるが、当該機能\を用いた場合、元のツイートが変更されたり削除されたりすると、当該機能を用いたツイートにおいて表\示される内容にも変更等が生じ、当該批評の趣旨を正しく把握したりその妥当性等を検討したりすることができなくなるおそれがあるのに対し、元のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする場合には、そのようなおそれを避けることができるものと解される。そして、弁論の全趣旨によると、現にそのように他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートするという行為は、ツイッター上で多数行われているものと認められる。以上の諸点を踏まえると、スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである。
(イ)これに対し、被控訴人は、引用ツイートによるべきことは、ツイッターの利用者において常識である旨を主張するが、当該主張を裏付けるに足りる証拠はない(なお、前記のとおり、本件規約の内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではないことからすると、ツイッターのユーザーにおいて本件規約の前記の定めを認識しているというべきことから直ちに、引用ツイートによるべきことがユーザーの共通の理解として前記公正な慣行の内容となるということもできない。)。また、被控訴人は、スクリーンショットの添付という方法による場合、著作権者の意思にかかわらず著作物が永遠にネット上に残ることとなり、著作権者のコントロールが及ばなくなるという不都合がある旨を主張するが、そのような不都合があることから直ちに上記方法が一律に前記公正な慣行に当たらないとまでみることは、相当でないというべきである。
(ウ)その上で、訂正して引用した原判決の第4の2(1)アで認定判断した原告投稿1の内容、同(2)アで認定した本件投稿1の内容や原告投稿1との関係等によると、本件投稿1は、Yが、本件投稿者1及び本件投稿者1と交流のあるネット関係者間で知られている人物(「A」なる人物)を訴えている者であることを前提として、更に多数の者に関する発信者情報開示請求をしていることを知らせ、このような行動をしているYを紹介して批評する目的で行われたもので、それに当たり、批判に関係する原告投稿1のスクリーンショットが添付されたものであると認める余地があるところ、その添付の態様に照らし、引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)は明確に区分されており、また、その引用の趣旨に照らし、引用された原告投稿1の範囲は、相当な範囲内にあるということができる。また、訂正して引用した原判決の第4の2(1)イ〜エで認定判断した原告投稿2〜4の内容及びその性質並びに同(2)アで認定した本件投稿2〜4の内容や原告投稿2〜4との関係等によると、本件投稿2〜4は、本件投稿者2を含むツイッターのユーザーを高圧的な表現で罵倒する原告投稿2、他のツイッターのユーザーを嘲笑する原告投稿3及び他のツイッターのユーザーを嘲笑する原告投稿4を受けて、これらに対する批評の目的で行われたものと認められ、それに当たり、批評の対象とする原稿投稿2〜4のスクリーンショットが添付されたものであるところ、その添付の態様に照らし、引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)は明確に区別されており、また、それらの引用の趣旨に照らし、引用された原告投稿2〜4の範囲は、それぞれ相当な範囲内にあるということができる。以上の点を考慮すると、本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付は、いずれも著作権法32条1項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能\性があり、原告各投稿に係るYの著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないというべきである。」\n
◆判決本文
原審はこちら
◆令和3(ワ)15819
令和4(ネ)10044も同趣旨です。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.04.18
令和4(行ケ)10010 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年4月6日 知的財産高等裁判所
6 取消事由1(優先権に関する認定判断の誤り)について
(1) 優先権について
ア 本件出願について、被告が基礎出願1又は2に基づく優先権を主張できるか 否かについて検討する。
イ(ア) 基礎出願1及び2がされた平成22年6月ないし7月頃時点で、一定のリ ソソ\ーム酵素に関する補充酵素である酵素の一定量をリソソ\ーム蓄積症の患者のし かるべき組織等に送達することができれば、治療効果を生ずること自体は技術常識 となっていた一方で、どのような方法で補充酵素を有効に送達することができるか について検討が重ねられており、本件出願がされた平成29年9月においても、そ のような状況がなお継続していたものと認められる(甲1〜4、16、17、55、 56、弁論の全趣旨)。
本件発明1は、リソソ\ーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成物 であって、脳室内投与されることを特徴とするものであるところ、上記の技術常識 及び前記1(2)の本件発明の概要を踏まえると、本件発明1の薬学的組成物につい ても、中枢神経系(CNS)への活性作用物質の送達をいかに有効に行うかという 点がその技術思想において一つの重要部分を占めているものというべきである。
(イ) この点、本件明細書の【0005】には、「髄腔内(IT)注射または脳脊髄 液(CSF)へのタンパク質の投与・・・の処置における大きな挑戦は、脳室の上 衣内張りを非常に堅く結合する活性作用物質の傾向であって、これがその後の拡散 を妨げた」、「脳の表面での拡散に対するバリア・・・は、任意の疾患に関する脳に\nおける適切な治療効果を達成するには大きすぎる障害物である、と多くの人々が考 えていた」との記載があり、【0009】には、「リソソ\ーム蓄積症のための補充酵 素が高濃度・・・での治療を必要とする対象の脳脊髄液(CSF)中に直接的に導 入され得る、という予期せぬ発見」という記載がある。\nまた、甲17の「発明の背景」においても、高用量の治療薬を必要とする疾患に ついて髄腔内ルートの送達に大きな制限があり、濃縮された組成物の調製にも問題 がある旨が記載されていた(前記5(2)カ及びキ)。
さらに、基礎出願2がされた翌年である平成23年に発行された乙6(「Drug transport in brain via the cerebrospinal fluid」Pardridge et al., Fluids and Barriers of the CNS 2011 8:7)においても、CSFから脳実質への薬物浸透 は極めて僅かであり、脳への薬物の浸透がCSF表面からの距離とともに指数関数\n的に減少するため、高濃度の薬物を投与する必要があるが、上位表面は非常に高い\n薬物濃度にさらされており有毒な副作用を示す可能性があることなどが記載されて\nいた。その更に翌年である平成24年に発行された乙13(「CNS Penetration of Intrathecal-Lumbar Idursulfase in the Monkey, Dog and Mouse: Implications for Neurological Outcomes of Lysosomal Storage Disorder」 Calias P. et al. PLoS One, Volume 7, Issue 1, e30341)には、「本研究は、組換えリソソ\ームタン パク質の直接的なCNS投与によって、投与されたタンパク質の大多数が脳に送達 され、カニクイザル、イヌ両方の脳および脊髄のニューロンに広範囲に沈着するこ とを、初めて示した研究である。」と記載されている。
そうすると、少なくとも基礎出願2がされた平成22年7月頃においては、CN S送達のための組成物として特定の組成物の組成等が開示された場合であっても、 当該組成等から直ちにその脳への送達の程度や治療効果を推測等することは困難で あることが技術常識であったものと認められる。 このことは、甲17に、「本明細書で用いる場合、「中枢神経系への送達に適して いる」という語句は、それが本発明の薬学的組成物に関する場合、一般的に、この ような組成物の安定性、耐(忍)容性および溶解度特性、ならびに標的送達部位(例 えば、CSFまたは脳)にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのよう な組成物の能力を指す。」(前記5(5)ナ)として、「標的送達部位(例えば、CSF または脳)にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのような組成物の能\n力」が「送達に適している」ということの意味内容に含まれることが明記されてい ることとも整合するものといえる。
(ウ) 他方で、本件明細書の【0085】には、「いくつかの実施形態では、本発明 による髄腔内送達は、末梢循環に進入するのに十分な量の補充酵素を生じた。その\n結果、いくつかの場合には、本発明による髄腔内送達は、肝臓、心臓および腎臓の ような末梢組織における補充酵素の送達を生じた。この発見は予期せぬものであ・・・\nる。」との記載があり、標的組織への送達について、【0132】には、「本発明の意 外な且つ重要な特徴の1つは、本発明の方法を用いて投与される治療薬、特に補充 酵素、ならびに本発明の組成物は、脳表面全体に効果的に且つ広範囲に拡散し、脳\nの種々の層または領域、例えば深部脳領域に浸透し得る、という点である。さらに、 本発明の方法および本発明の組成物は、現存するCNS送達方法、例えばICV注 射では標的化するのが困難である脊髄の出の組織、ニューロンまたは細胞、例えば 腰部領域に治療薬(例えば、補充酵素)を効果的に送達する。さらに、本発明の方 法および組成物は、血流ならびに種々の末梢器官および組織への十分量の治療薬(例\nえば、補充酵素)を送達する。」との記載があり、【0133】においては、実施形 態により、「治療用タンパク質(例えば、補充酵素)」が、対象の「中枢神経系」に 送達され、あるいは「脳、脊髄および/または末梢期間の標的組織のうちの1つ以 上」に送達され、また、「標的組織は、脳標的組織、脊髄標的組織および/または末 梢標的組織であり得る。」などと記載された上で、【0134】以下で特に「脳標的 組織」について説明がされ、そして、実施例においても、例えば、実施例1ではI T投与が、実施例3ではICV投与及びIP(腹腔内)投与が、実施例5、実施例 10及び実施例13ではIT投与及びICV投与が用いられるなどしている。
そして、証拠(甲2〜5。後記7(1)〜(4)参照)のほか、本件明細書の記載内容 に照らしても、CNSへの酵素の送達においては、ICV投与とIT投与とは、そ れぞれ別個の投与態様として取り扱われ、組織への酵素の送達に関する実験やその 結果の評価においても、それらは別個に取り扱われること、換言すると、ICV投 与とIT投与の相応に密接な関連性を考慮しても、ICV投与による実験データと IT投与による実験データとを直ちに同一視することはできないことが、平成22 年7月頃における技術常識であったことが認められるというべきである。
(エ) 前記(イ)及び(ウ)の技術常識を踏まえると、本件発明1が甲17に記載されて いた発明であると認められるためには、甲17に、本件発明1の組成物が実質的に 記載されていたものと認められるのみならず、甲17に、本件発明1の組成物によ る送達の効果が、ICV投与した場合のものとして、実質的に記載されていたと認 められる必要があるというべきである。
ウ(ア) その上で、甲17の記載を見るに、まず、「発明の背景」の記載(前記5(2)) は、専ら背景技術について説明するものである。「発明の概要」の記載(同(3))に は、本件発明1の組成物に含まれる組成物の記載があるといえるが、当該組成物が どのように送達されて治療効果を奏するのかについては記載がない。そして、「発明 の詳細な説明」(同(5))を見ても、組成物の構成やその使用方法に関する一般的な\n記載はみられるものの、どのように送達されて治療効果を奏するのかについて具体 的な記載はない。
(イ) 甲17の実施例1(前記5(6))には、15mg/mLのタンパク質濃度のリ ソソ\ーム酵素を含む組成物で、pH6〜7であってリン酸塩を含むものが記載され ていると見ることができるが、具体的にどのような酵素が用いられたかは不明であ り、また、どのような領域まで送達されて治療効果を奏するかについても記載がな い。
(ウ) 甲17の実施例2(前記5(7))には、「酵素治療薬の使用による繰り返しI T−脊椎投与の毒性及び安全性薬理を評価」や「酵素投与群」との記載はあるが、 酵素の種類も濃度も不明であり、また、どのような領域まで送達されて治療効果を 奏するかについても記載がない(なお、対照群との差異もみられていない。)。
(エ) 甲17の実施例3(前記5(8))には、用量1.0mL中酵素14mgとして 調製された酵素と、5mMのリン酸ナトリウム、145mMの塩化ナトリウム、0. 005%のポリソルベート20をpH7.0で含むビヒクルにより作成された製剤\nが髄腔内投与されたことの記載があるが、図5を含めて見ても、主に有害な副作用 の有無等が検討されたものと解され、治療効果については記載がない。
(オ) なお、甲17の図2には、30mg用量の髄腔内投与後のリソソ\ーム酵素の ニューロンへの分布が示され、尾状核のニューロンにリソソ\ーム酵素が認められた ことが示されているが、どのような組成物が投与されたのかも不明である。
(カ) さらに、甲17には、投与の態様としてICV投与とIT投与とが選択的な ものである旨は記載されているといえる一方で、いずれの方法によっても同様に送 達され得る旨等を明らかにする記載もないから、前記(ウ)〜(オ)は、ICV投与した 場合のものとして、本件発明1の組成物による送達の効果を記載するものでもない。
エ 以上によると、甲17には、本件発明1が記載されているものとは認められ ず、本件発明2〜8及び12についてこれと異なって解すべき事情も認められない から、本件出願について、基礎出願2に基づく優先権を主張することはできない。 基礎出願1についても、基礎出願2と異なって解すべき事情はない。
これと異なる被告の主張は、いずれも採用することができない。ICV投与とI T投与において、組成物はいずれの場合でもCSFに投与されるものであり、その ためそれらの間に処方としての共通性や標的組織等への送達における相応の関連性 があるということができたとしても、そのことをもって、具体的な送達の程度や治 療効果についてまで、一方の投与態様についての実験結果等の記載をもって直ちに 他方についての記載と実質的に同視することができるとの技術常識は認められない。 被告の主張は、甲16及び17の記載内容を、本件明細書の記載内容を前提にしな がら解釈しようとするものであって相当でない。
(2) 甲6が公知文献とされなかったことが直ちに取消事由に当たるかについて
ア 原告は、取消訴訟の審理範囲を根拠として、本件審決に当たり甲6を副引用 例として考慮しなかった本件審決は、優先権に係る判断の誤りによって直ちに取り 消されるべきである旨を主張するので検討する。
イ(ア) 証拠(甲61、62)及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件審判請求においては、本件発明1の進歩性に係る無効理由として、甲2発明ないし甲4発明にそれぞれ甲5〜10を適用すること(甲5の適用については、甲5技術と実質的に同一の内容が主張されていた。)により容易想到である旨を主張し、その中で、甲6については、甲6発明(製剤)と実質的に同一の内容を主張する一方、甲6発明(ビヒクル)については主張していなかったことが認められる。本件審決は、基礎出願2に基づく優先権の主張を認めたことから、副引用例としての甲6記載の発明の適用について検討するには至らなかったが、上記のとおり、甲6については、甲6発明(製剤)と実質的に同一の内容を副引用例とする範囲で、審判手続においても審理の対象となっていたものであって、甲2発明ないし甲4発明にそれぞれ上記副引用例を組み合わせることにより進歩性を欠くという無効理由自体は、審判手続において審理対象となっていたものである。
(イ) そして、本件審決は、甲2発明ないし甲4発明と本件発明の相違点について、 甲5及び7〜10を適用して容易想到であるといえるか否かについて判断した一方、 優先権主張を認めたことから甲6は除外し、それゆえ相違点に係る本件発明の構成\nについての甲6発明(製剤)の適用について具体的には判断しなかったものの、甲 2発明ないし甲4発明に甲6発明(製剤)を適用することにより本件発明は容易想 到であるという旨の原告の主張自体については、これを認めることができないとの 判断を示したものである。
(ウ) 原告は、本件訴訟において、甲2発明ないし甲4発明を主引用例とした上で、 前記(ア)及び(イ)のとおり本件審決で排斥された甲5技術の適用による容易想到性の 主張のほか、甲6に基づき、甲6発明(製剤)及び甲6発明(ビヒクル)を副引用 例として主張するとともに、甲6が技術常識(エリオットB溶液の技術常識及び高 濃度化の技術常識)を補足するものである旨を主張しているところ、本件訴訟にお いて、容易想到性が争いとなっている本件発明の構成(甲2発明ないし甲4発明と\nの間の各相違点)は、本件審決で判断されたものと基本的に同じであり、甲6発明 (製剤)や甲6発明(ビヒクル)の適用に当たり、本件審決で判断されたもの以外 の相違点が問題になるなどといった事情はない。
(エ) 前記(ア)のとおり、甲6の適用については審判手続においても問題とされ、当 事者双方において攻撃防御を尽くす機会はあったといえる。この点、証拠(甲6、 16、17、乙14、24。なお、訳文として甲6の2・3、乙36)及び弁論の 全趣旨によると、甲6は、基礎出願1及び2がされて間もない平成22年7月2日 に公衆に利用可能となった雑誌「注射可能\なドラッグデリバリー2010:製剤フ ォーカス」に掲載された「CNSが関与する遺伝学的疾患を治療するためのタンパ ク質治療薬の髄腔内送達」と題する論文であるところ、同論文は、基礎出願1及び 2に関わった研究者も関与して行われた研究発表に係るものであって、本件発明と\n同様の技術分野に属するもの、すなわち、酵素補充療法において、中枢神経系(C NS)病因を有する疾患の処置に係るリソソ\ーム酵素に関する補充酵素である酵素 を含む薬学的組成物に関連するもの(前記1(2)ア)と解されるほか、その記載内容 は、かなりの部分甲16及び17と重なり合うものである。そのような甲6の性質 や、甲16及び17と本件発明との関係についても優先権主張の可否という形では あるが各当事者において攻撃防御を尽くす機会があったというべきことを考慮する と、上記のように審判手続において各当事者に与えられていた甲6の適用について 攻撃防御を尽くす機会は、実質的な機会であったといえる。
(オ) 以上の事情の下では、本件審決においては副引用例としての甲6発明(製剤) の適用が具体的には判断されるに至らず、また、甲6発明(ビヒクル)については そもそも審判段階で問題となっていなかったこと(この点、被告は、甲6発明(ビ ヒクル)を適用しての容易想到性に係る原告の主張について、特にそれが審理範囲 外であるとして争ってはいない。)を考慮しても、本件訴訟において、審判手続にお いて審理判断されていた甲2発明ないし甲4発明との対比における無効原因の存否 の認定に当たり、甲6発明(製剤)及び甲6発明(ビヒクル)を適用することによ って容易想到性の有無を判断することが、当事者に不測の損害を与えるものではな く、違法となるものではない。最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月1 0日大法廷判決・民集30巻2号79頁は、本件のような場合について許されない とする趣旨とは解されない。
(3) 以上によると、取消事由1は、優先権の判断の誤りという限度において理由 があるが、それをもって直ちに本件審決を取り消すべきという結論において、理由 がない。そこで、以下、甲2発明ないし甲4発明を主引用例とする容易想到性の主張に係る取消事由5〜7について、検討する。
◆判決本文
当事者が同じ関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> その他特許
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2023.04.17
令和4(ワ)2237 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年3月30日 東京地方裁判所
1 争点1(著作権法41条の適用の可否)について
(1) 本件投稿1について
ア 証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1は、「『まとめサイ ト』でのインラインリンクに著作権侵害幇助の判決!:プロ写真家・A公式 ブログ…」との表題及び「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたると\nいう判決が出たそうです。」とのコメントと共に、本件写真が投稿されたも のであり、本件写真は、上記にいう著作権侵害幇助の判決(以下「別件訴訟 判決」という。)において、著作権侵害の成否が問題とされた写真そのもの であることが認められる。
上記認定事実によれば、本件投稿1は、別件訴訟判決の要旨を伝える目的 で本件写真を掲載しているところ、本件写真は、別件訴訟判決という時事の 事件において正に侵害の有無が争われた写真そのものであり、当該事件の主 題となった著作物であることが認められる。そうすると、本件写真は、著作 権法41条にいう事件を構成する著作物に該当するものといえる。\nそして、上記認定に係る本件写真の利用目的、利用態様、上記事件の主題 性等を踏まえると、本件投稿1において、本件写真は、同条にいう報道の目 的上正当な範囲内において利用されたものと認めるのが相当である。
イ これに対し、原告は、「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたると いう判決が出たそうです。」との記載は、抽象的に、インラインリンクが著 作権の幇助侵害に当たり得るという規範の問題を伝えるにすぎないもので あるから、本件投稿1は「報道」に当たらないと主張する。しかしながら、 前記認定事実によれば、本件投稿1は、著作物の利用に関して社会に影響を 与える別件訴訟判決の要旨を伝えるものであって、社会的な意義のある時事 の事件を客観的かつ正確に伝えるものであることからすると、これが「報道」 に当たることは明らかである。したがって、原告の主張は、採用することが できない。
また、原告は、本件元投稿においては本件写真がすぐに削除されたことや、 規範の問題を伝達するに当たり写真の掲載は不要であることからすれば、本 件投稿1における本件写真の掲載は、著作権法41条に規定する「報道の目 的上正当な範囲内」に含まれないと主張する。しかしながら、上記において 説示したとおり、本件写真は、別件訴訟判決という時事の事件の主題となっ た著作物であることからすれば、原告主張に係る事情を十分に考慮しても、\n原告の主張は、上記判断を左右するものとはいえない。したがって、原告の 主張は、採用することができない。
ウ 以上によれば、本件投稿1における本件写真の掲載は、著作権法41条に より適法であるものと認められる。
(2) 本件投稿2について
ア 証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿2は、「まとめサイト 発信者情報裁判Line上告棄却 敗訴確定ニュース プロ写真家 A公 式ブログ 北海道に恋して」との記載と共に、本件写真が投稿されたもので あり、本件写真は、上記にいう発信者情報裁判の上告棄却判決(以下「別件 最高裁判決」という。)において、著作権侵害の成否が問題とされた写真そ のものであることが認められる。
上記認定事実によれば、本件投稿2は、別件最高裁判決の要旨を伝える目 的で本件写真を掲載しているところ、本件写真は、別件最高裁判決という時 事の事件において正に侵害の有無が争われた写真そのものであり、当該事件 の主題となった著作物であることが認められる。そうすると、本件写真は、 著作権法41条にいう事件を構成する著作物に該当するものといえる。\nそして、上記認定に係る本件写真の利用目的、利用態様、上記事件の主題 性等を踏まえると、本件投稿2において、本件写真は、同条にいう報道の目 的上正当な範囲内において利用されたものと認めるのが相当である。
イ これに対し、原告は、本件投稿2は、悪質なスパムブログにユーザーを誘 導するために本件写真を利用するものであるから、「報道」に当たる余地は ないと主張する。しかしながら、証拠(甲14、15)及び弁論の全趣旨に よっても、Bloggerがスパムブログに悪用され得ることや、広告収入 を得る目的等でスパムブログが存在することなどが一般的に認められるこ とが立証され得るにとどまり、本件投稿2自体が悪質なスパムブログにユー ザーを現に誘導している事実を具体的に認めるに足りないものといえる。そ の他に、上記 イにおいて説示したところと同様に、上記認定に係る本件写 真の利用目的、利用態様のほか、本件写真が、著作物の利用に関して社会に 影響を与える別件最高裁判決という時事の事件の主題となった著作物であ ることを踏まえると、原告主張に係る事情を十分に考慮しても、原告の主張\nは、上記判断を左右するものとはいえない。 したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
ウ 以上によれば、本件投稿2における本件写真の掲載は、著作権法41条に より適法であるものと認められる。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.04.15
令和4(ネ)10073等 特許権侵害損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエ アロゾルを発生させる方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が、被控 訴人らに対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイスである原判決別紙物件 目録記載の被告製品(被告製品1〜3)の販売、輸出、輸入及び販売の申出をする\nことが本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為(民法709条)に基づき、 選択的に、1)特許法102条2項の損害額●●●●●●●●●円(同項の推定の覆 滅が認められた場合に当該覆滅部分について予備的に同条3項に基づく売上額の2\n0%相当の損害額)又は2)同条3項の損害額●●●●●●●●●円を請求するとと もに、3)弁護士・弁理士費用相当額●●●●●●●●円(上記1)の同条2項の損害 額の1割に相当する額)を請求するものとして、●●●●●●●●●円及びこれに 対する不法行為の後であり被控訴人らへの各訴状送達の日の翌日である令和2年3 月10日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5 分の割合による遅延損害金の連帯支払を原審で求めた事案である。
(2) 原審は、1)特許法102条2項による被控訴人らが受けている利益の額は3 706万0935円と推定されるが、被告製品の売上げにはそれらが別件発明の実 施品であることも貢献しているため5割の推定覆滅を認めるのが相当であり、同項 の損害額は1853万0467円となる(また、上記の覆滅の理由からして上記覆 滅部分についての同条3項の適用は認められない。)とする一方で、2)実施料率は 10%を下らないものと認めるのが相当であり、同条3項の損害額は1975万2 707円となるところ、より高額である上記2)の損害額をもって控訴人の損害額と 認め、これに弁護士・弁理士費用としてその1割である197万5270円を加え た2172万7977円及びこれに対する前記遅延損害金の連帯支払を被控訴人ら に求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却 した。
・・・・
(c) 同じくAmazon seller centralに係る手数料等について、控訴人は、令和元 年7月のFBA運搬費は異常に高額であり、少なくとも本件FBA配送代行手数料 ●●●●●●●●円は控除されるべきものではないなどと主張する。
そこで検討するに、証拠(甲10、甲A38、44、甲46、47、51、52、 53の1〜4、54の1〜5、甲55、62、乙25、26)及び弁論の全趣旨に よると、1)令和元年7月分のAmazonのFBA手数料(Amazon FBA/handling charge) は●●●●●●●円、FBA運搬手数料(Amazon FBA/haulage express)は●●● ●●●●●円であったこと、2)平成30年7月から令和元年12月までの期間中、 FBA運搬手数料又はこれに相当し得るとみられる費用は、平成30年11月から 令和元年9月までの間において計上されているところ(ただし、平成30年11月 及び12月においては「Amazon /FBA haulage handling charge」である。)、同年 11月分及び12月分は●●●●円程度、平成31年1月分は●●●●円余りであ ったものの、同年2月分から同年(令和元年)6月分まではいずれも●●●●円に 満たない額となっていたにもかかわらず、同年7月分として上記のとおり急激にそ の額が増大し、その後、同年8月分として●●●円余り、同年9月分として●●● 円余りが計上された後、同年10月分以降は、FBA手数料とともにゼロ円となっ たこと、3)同年4月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少し、同年5月において、「商品評価損」●●●●●●●円の計上と 「期末商品棚卸高」●●●●●●●●円の計上により、「商品」が●●●●●●● ●円増加し、同年6月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少したこと、4)同年7月30日及び同月31日の2日間に、「Fjp20190724PATENT-14」などの符号(末尾の数字のみ、3〜17の範囲で異なっている。) のある一律●●●円のFBA配送代行手数料(FBA Per Unit Fulfillment Fee)が ●●●●件計上され、その合計額は●●●●●●●●円に上ったこと(本件FBA 配送代行手数料)、5)同月におけるFBA配送代行手数料の支出において、そのよ うに同一の符号をもって一律の金額で同時期に多数のものが計上されている例は、 他に認め難いこと、6)控訴人は、別件仮処分決定に係る特許権侵害差止仮処分申立\n事件(東京地裁民事第29部にて審理)において、令和元年7月11日付けで、被 控訴人アンカーに対する申立てを取り下げ、その後、同月25日、別件仮処分決定\nがされたこと、7)控訴人は、別途、被控訴人らを債務者として、特許権侵害差止仮 処分命令の申立て(東京地裁平成30年(ヨ)第22123号(東京地裁民事第4\n0部にて審理))をしていたところ、当該事件で、被控訴人らは、令和元年9月3 0日付けの準備書面をもって、被控訴人ジョウズにおいては同月末までに被告製品 全ての在庫がなくなる予定であることから、保全の必要性がない旨を主張し、その\n後、それを疎明する資料として、被控訴人ジョウズが同月にAmazonに対し被告製品 の所有権放棄の依頼をしたことを示す書面を提出した上、同年11月5日付けの準 備書面をもって、保全の必要性がない旨を改めて主張したことが認められる。
前記1)〜7)の事情(なお、前記4)について、「20190724PATENT」の符号は、令和 元年7月24日付けのもので、特許に関連するものであることを強くうかがわせる ものである。)のほか、AmazonのFBAサービスに係る証拠(甲53の1〜4。余 剰在庫の管理等のために、Amazonフルフィルメントセンターに保管されている在庫 について、出品者、出品者の倉庫、仕入れ先又は販売業者に返送したり、その所有 権を放棄したりする旨を依頼するサービスがあることなどが記載されている。)や、 配送手数料等についてはその対象となる行為が行われた後に請求がされるのも合理 的であると解され、本件FBA配送代行手数料が平成31年(令和元年)4月ない し6月の在庫に係る会計上の処理と関連している可能性があることなども考慮する\nと、本件FBA配送代行手数料●●●●●●●●円については、別件仮処分決定の 発令に関連して、また、前記7)の仮処分命令申立事件に対する対応やその準備等の\nために、大量の被告製品について一律に、通常の販売とは異なる特別の取扱いがさ れたことから発生したものであることが強く推認され、この推認を覆すに足りる事 情は見当たらない。
したがって、Amazon seller centralに係る手数料等のうち、本件FBA配送代行 手数料●●●●●●●●円については、被告製品の販売に直接必要となった経費と して控除すべきものではなく、控除が認められる支払手数料額は●●●●●●●● ●円となる。
上記に反する被控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。なお、被 控訴人らは、当審で追加された特許法102条3項の損害に係る控訴人の主張に対 し、前記3)の商品評価損については、令和元年の期末の商品評価損調整でゼロとす る仕訳を行ったなどと主張するところ、そのような事実を認めるに足りる証拠はな いものの、仮に、そのような事後的な調整の事実があったとすれば、そのことは、 本件FBA配送代行手数料の支出が被告製品の販売とは直接関係なくされたもので あるとの前記推認を裏付けるものであるとみることができる。
◆判決本文
原審はこちら
◆令和2(ワ)4332
関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求
◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円
◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2023.04.12
令和3(ワ)28206 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年3月16日 東京地方裁判所
当裁判所は、本件発明は、進歩性を欠くものとして無効であると判断するものであり(争点2−1−2)、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないものと判断する。以下、進歩性については、争点2−1−2(後記7)を先に判断することとし、構成要件充足性については、当事者双方の主張立証の経緯及び内容を踏まえ、次のとおり、念のため必要な限度で判断の理由を示すこととする。なお、原告は、予\備的に訂正の再抗弁を主張するものの、弁論の全趣旨によれば、現実に訂正請求をするものではなくその予定もないというのであるから、その要件を欠くものであり、後記7において説示するところによれば、上記進歩性に係る判断を左右しないことは明らかである。\n
・・・
上記認定事実によれば、乙9発明と乙10発明は、共に安全性の観点から、 原動機付車両における車両停止時にブレーキがかかった状態を保持すると いう技術思想が共通するものといえる。そして、乙9発明は、安全性の観点 から、エンジン自動停止始動装置と制動保持装置の各作動の一体不可分性を 必須の特徴とするものであるところ、乙9(11頁2〜18行)によれば、 「ステツプS24では、ブレーキペダル信号の有無によりブレーキペダルが 踏込まれているか否かが判断される。・・・運転者が車両を停止させる意思 があると判断するためである。」、「更にステツプS25では、エンジンを 自動停止させるための他の停止条件、例えばターンシグナルが出されていな いこと、ヘツドランプが点灯していないこと、エアコンデイシヨナが作動し ていないこと、水温が所定以上であること、等が、ターン信号、ライト信号、 エアコン信号、水温信号等により判断される。」、「これらのステツプS2 1〜S25がすべて肯定判断されれば、エンジン自動停止条件が満足された こととなる・・・」が記載されていることからすると、乙9発明は、エンジ ン自動停止始動装置を安全な状態で作動させる観点から、各種検出信号を用 いていることが認められる。
そうすると、エンジン自動停止始動装置を安全な状態で作動させるために、 各種検出信号の一つとして、乙9発明に対し、制動保持装置の異常を検出す る乙10を適用する動機付けを認めるのが相当である。 したがって、エンジン自動停止始動装置と制動保持装置の各作動の一体不 可分性を必須の特徴とする乙9発明の技術的思想に鑑みると、制動保持装置 の異常を検出した場合には、安全性を欠くことは自明であるから、安全性の 観点から各作動の一体不可分性を確保するために、エンジン自動停止始動装 置を安全な状態で作動させるための判断用各種検出信号の一つとして制動 保持装置異常検出信号を加えた場合において、制動保持装置の異常が検出さ れたときは、乙9発明にいうステップS21〜S25が肯定判断されず、エ ンジン自動停止条件が満足されなくなる。
そのため、上記場合には、制動保持装置異常検出信号が、エンジン自動停 止始動装置を作動させないことになり、もってその作動を禁止することにな る。したがって、乙9発明に乙10発明を適用してエンジン自動停止始動装置 の作動を禁止することが、当業者の適宜なし得る設計事項の範疇であること は、上記一体不可分性に照らし、明らかである。 以上によれば、制動保持装置の異常を検出した場合には、エンジン自動停 止始動装置の作動を禁止する構成(相違点1に係る構\成)を容易に想到でき るものと認めるのが相当である。
実質的にみても、本件発明は、原動機停止装置の実行を判断するための各 種検出信号の一つとしてブレーキ液圧保持装置の故障検出信号を備えるも のであり、乙9発明に乙10発明を適用した構成との間に、技術思想におい\nて異なるところはない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.04.11
令和2(ワ)27972 特許権侵害損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月22日 東京地方裁判所
本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」(構成要件1D、1E\n等)について
本件各発明の特許請求の範囲には、「前記拡散レンズを複数のレンズ部か ら形成し、各レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並 設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、 光の経路と交差する所定の面上に並ぶように配置し、前記各レンズ部を、互 いに近傍に配置されたレンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異 なるように形成したことを特徴とする」(構成要件1D〜F)と記載されて\nいる。
これらによれば、本件各発明の照明装置の拡散レンズは、複数のレンズ部 から形成されていて、各レンズ部の各LEDの並設方向への曲率半径と、各 LEDの並設方向と直行する方向への曲率半径を比較することができるので あり、また、各レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なると いうというのであるから、本件発明のレンズ部は、拡散レンズにおいて、そ こに形成されているという複数のレンズ部のそれぞれのレンズ部について、 その位置、形状が特定された上で、それぞれのレンズ部(各レンズ部)につ いてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向 への曲率半径を把握することができるものであると理解するのが自然なもの である。
・・・
これら本件明細書の記載をみても、本件各発明の実施形態として記載され ているものは、本件発明の拡散レンズにあるという複数のレンズ部(各レン ズ部)のそれぞれのレンズ部について、その位置、形状を特定した上で、そ れらのレンズ部についてのLEDの並設方向への曲率半径及びLEDの並設 方向と直交する方向への曲率半径を把握することができるものであるといえ る。それぞれのレンズ部については、一方向に異なる曲率を有する複合曲面 を有するものも含まれるものの、その場合でも、そのレンズ部が特定された 上で、そのレンズ部に求められる機能を考慮し、そのレンズ部についてある\n方向において曲率半径(RY)を有するものとしている。そして、本件明細 書において、それぞれのレンズ部の位置、形状等が特定されないことを前提 とする記載はない。
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件各発明の 拡散レンズは、それぞれについてその位置、形状が特定される複数のレンズ 部を有するものであり、そのそれぞれのレンズ部についてのLEDの並設方 向への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握す ることができるものであるといえる。そして、特許請求の範囲及び本件明細 書の記載からも、本件各発明は、拡散レンズにおいてそのような各レンズ部 を有する発明について、前記1(2)のような効果を奏するという技術的意義を 有するものと認められる。
(2) 各被告製品において使用されているLSD(もっとも、各被告製品に実際 に使用されている各LSDの種類や具体的構成は明らかではない(前記2(2)、 (4))。)について検討する。各被告製品におけるLSDは、拡散レンズの機能を有するフィルム表\面の 構造体である数十\μm程度の微細な凹凸が、シームレスかつランダムに、す なわち継ぎ目なく不規則に配置されたものであり、かつ、凹凸の部分の個々 の大きさや形状を規定して作成されているものではなく、統計的に評価して フィルム全体として入射光を所定の角度で拡散する性能を有するように設計\nされているものである(同(1)〜(3))。
すなわち、各被告製品におけるLSDは、フィルムの表面に微細な凹凸の\n構造体を有し、それらが凸レンズと凹レンズがシームレスかつランダムに配\n置されたマイクロレンズアレイとして機能し、それぞれの微細な凹凸の構\造 体によって光がランダムに広げられるが、それらが重なり合うことによって、 統計的に評価して、フィルム表面全体が所定の性能\を有する拡散レンズとし ての機能を有するものである。そして、各被告製品におけるLSDがこのよ\nうなものであるところ、そこにおいて、前記(1)のとおりの本件各発明におけ るそれぞれの「レンズ部」を把握することは困難なものといえる。そして、 原告は、各被告製品について、その断面図の例を示すところ、その各例にお いても、別紙原告の示す例のとおり、LSDの表面は境目なく不規則に様々\nな形状の凹凸が連続しており、本件各発明におけるそれぞれの「レンズ部」 を把握することができない。 原告は、原告の示す各例において、LSDの表面の部分的に突出した複数\nの部分等はそれぞれレンズとして作用するから、それぞれが1つの「レンズ 部」であり、「複数のレンズ部」を備えることを主張する。しかし、前記(1) のとおり、本件各発明の「レンズ部」は、それぞれのレンズ部の位置、形状 が特定されるものであって、本件各発明は拡散レンズにそのような「レンズ 部」を有するものにより前記1(2)のような効果を奏するといえるものである ところ、原告の示す各例においても、上記のようなそれぞれのレンズ部(各 レンズ部)について、その位置、形状を具体的に特定するものではない(前 記第2の2(1)(原告の主張)イ、別紙原告の主張する凸部の例)。
以上によれば、各被告製品に使用されているLSDの形状によれば、各被 告製品において、本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」(構成\n要件1D、1E等)にいうそれぞれの「レンズ部」の範囲を特定することが できないものであって、各被告製品は本件各発明にいう「各レンズ部」を有 するということはできず、それぞれのレンズ部についてのLEDの並設方向 への曲率半径及びLEDの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握する ことができず、各被告製品は、本件各発明の曲率半径についての構成(構\成 要件1E、1F)を充足するともいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.04.11
平成30(ワ)10590 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月20日 大阪地方裁判所
◆本件特許
(7) 原告が販売することができないとする事情
ア 競合品の存在
被告が競合品であると主張する製品のうち、アツギが販売する「大人のス
ポパン」(乙60の2の1)、イーゲートが販売するショーツ(乙60の4の
1)、ワコールが販売する「すそピタショーツ」(乙61の1)、千趣会が販売
するショーツ(乙61の2、61の3)及びグンゼが発売する「超立体ぴっ
たりフィットショーツ」(乙61の5)は、脚口(裾口)ないし臀部部分が立\n体的な構造であり、脚口(裾口)部分のずりあがりが防止されることなど本\n件各特徴に相当する作用効果を有することを特徴とする商品であるといえ、
価格帯も、ワコールが販売する製品を除き、概ね同一であり、競合品である
と認められる。ワコールが販売する製品は、3000円前後と原告製品より
も高額であるものの、同社が女性用下着メーカーとして有名でありその商品
に高いブランド力があると認められること等を踏まえると、なお競合品に含
まれるといえる。
したがって、原告製品と被告製品とが販売される市場において、原告製品
と競合する製品が複数存在することが認められ、かかる競合品の存在は、原
告が販売することができない事情に該当するといえる。
もっとも、原告製品のうち、220番製品及び420番製品は、楽天市場
内の「ボックスショーツ」で区分される製品のランキングにおいて、平成2
5年5月15日から令和元年7月7日までの長期間にわたり連続1位を獲
得している(甲50、73)等、原告のブランドは需要者に相応に知られて
おり、かつ需要があると認められることを踏まえると、競合品の存在を理由
とする覆滅の程度が大きいとまではいえない。
イ 被告製品固有の特徴
証拠(甲3〜8、23、24、)によれば、被告製品は、本件各特徴に加え
て被告各特徴(1)ウエスト・脚口にはゴムを使用せず、2)綿の中でも、繊維
長が長く、吸湿性が高く、やわらかい風合い等の特徴を持つスーピマコット
ンを使用し、3)各パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たらない仕様であり、
4)品質表示を記載するタグをタグから製品本体に転写してプリントする方\n法に変更していること)を備えており、かつ当該被告特徴について、本件各
特徴に次いで、需要者に訴求されていることが認められる。
また、証拠(甲48〜50)及び弁論の全趣旨によれば、原告製品は、1)
少なくともウエスト部分にゴムを使用し、2)スーピマコットンは使用されて
おらず、3)パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たる仕様であり、4)品質表示\nを記載するタグが付けられていることが認められる。
原告商品及び被告商品は、余多ある女性用ショーツの中で、装飾的な意味
でのデザイン性よりも、履き心地、肌触り等の機能面、実質面を重視した商\n品を購入しようとする需要者を販売対象とした商品であると認められ、その
ような需要者にとって、被告各特徴は、購入動機の形成にそれなりに寄与す
るものであるといえる(乙67)。よって、被告製品が原告製品とは異なる被告各特徴を備えることは、原告
が販売することができない事情に該当すると言い得る。
ただし、被告各特徴に基づく顧客誘引力は、商品の形状・機能に直接かか\nわる本件各特徴と比較すると限定的であると考えられること、被告特徴2)に
ついて、素材それ自体で見れば、被告製品と原告製品のうち220番製品及
び420番製品は綿95%、ポリウレタン5%と同一であり、その余の原告
製品も綿92%、ポリウレタン8%と大差がないこと、被告特徴4)について、
本件対象期間中に販売された被告製品の一部はタグ付きである可能性があ\nること(甲40)等をふまえると、その覆滅の程度は限定的に解すべきであ
る。
ウ ハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品にない、ウエスト丈がハイウエストのもの(被告
製品3−1及び3−2。ハイウエストタイプ)が存在し、当該ハイウエスト
タイプの存在が、原告が販売することができないとする事情に該当すること
は争いがない。被告製品のうちハイウエストタイプは、被告製品の販売数量合計●(省略)
●のうち、●(省略)●であり、約26.8%である(計算鑑定の結果)。
被告製品においてハイウエストタイプを好む需要者が一定程度存在する
と認められることを踏まえると、被告製品にのみハイウエストタイプが存在
するという事情は、特許法102条1項1号に基づく推定を一定程度覆滅す
るものと認められる。
エ 販売価格
証拠(甲3〜8、48〜50、75)によれば、原告のウェブサイトで販
売される107番製品(ローライズ丈)及び407番製品(普通丈)の販売
価格は2500円(税込)、楽天市場で販売される220番製品(セミ丈)及
び420番製品(普通丈)の販売価格は1500円〜1520円(税込)で
あるのに対し、被告製品の一般向けの販売価格はレギュラー丈(被告製品1
−1及び1−2)が1080円(税抜)、ショート丈(被告製品2−1及び2
−2)が平均980円(税抜)、ハイウエストタイプ(被告製品3−1及び3
−2)が平均1280円(税抜)であると認められる。なお、原告製品のロ
ーライズ丈及びセミ丈と被告製品のショート丈、原告製品の普通丈と被告製
品のレギュラー丈が、それぞれ対応関係にある。
同種かつ同程度の機能等の製品相互間で価格が顧客誘引力に影響を与え\nること、これが女性用下着一般及びその中でも原告商品及び被告商品の想定
需要者層に妥当することは明らかである(乙67)。原告商品の販売数量を
見ても、価格以外の要素があり得るといえるものの、高額(2500円)の
407番製品及び107番製品の販売数量が●(省略)●枚、●(省略)●
枚であるのに対し、低価格(約1500円)の220番製品及び420番製
品が●(省略)●枚、●(省略)●枚と非常に高い比率を占める(計算鑑定
の結果)。
もっとも、販売量の多い220番製品及び420番製品と、被告製品(ハ
イウエストタイプを除く)の価格差は、420円〜540円であり、両製品
の価格帯自体が1000円〜1500円程度の範囲であること等を踏まえ
ても、その差が大きいとはいえず、顧客誘引力に大きな影響を及ぼすとまで
はいえない。したがって、被告製品が原告製品よりも低価格であることは、原告が販売
することができないとする事情に該当するといえるものの、当該事情を理由
として推定された損害が覆滅される程度は高いとは言えない。
オ 被告の営業努力
特許権者等が販売することができない事情として認められる侵害者の営
業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力を行い、製品の購買
動機の形成に寄与したと認められるものをいうところ、被告指摘の事情を勘
案しても、このような事情には該当しない。
カ 本件発明の技術的意義が被告製品の利益に貢献する程度
被告は、構成要件Dの「腸骨棘点付近」について、上前腸骨棘を中心とし\nつつ下前腸骨棘付近を含むものと解釈した場合、仮に被告製品が構成要件D\nを充足するとしても、本件発明の作用効果を奏さないため、被告製品に対す
る本件発明の寄与度が零であると主張する。
しかし、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近を含む場合でも本件発明の作
用効果を奏するものであることは前記2(1)のとおりであるから、被告の主
張は採用できない。
キ 実際の着用状態からみた本件発明の貢献度
被告は、一定以上の割合の被告製品については、需要者が着用した場合に
身体的個体差等の影響により着用状態において本件発明の技術的範囲に属
しない場合があり得、当該事情をもって原告が販売することができないとす
る事情に該当と主張する。
しかし、被告製品は、その設計時に想定された着用状態において、本件発
明の技術的範囲に属するものであり、実際の個別具体的な着用状況において、
被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置しない場合
があることをもって販売することができない事情が存すると解することは
相当でない。
ク 推定覆滅の割合(まとめ)
以上によれば、本件においては、競合品の存在、被告製品が被告各特徴を
有すること、ハイウエストタイプが存在すること及び原告製品よりも低価格
であることについて原告が販売することができない事情に該当すると認め
られ、前記イで認定した事情を踏まえると、当該事情に相当する数量は、全
体の15パーセントであると認めるのが相当である。
・・・
証拠(甲11、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の実施に対し
受けるべき実施料率は6パーセントと認めるのが相当である。
なお、被告は、原告がそのウェブサイトにおいて本件特許権侵害に基づく
訴訟を被告に提起し、徹底的に争う旨の意思表明をしていることから、ライ\nセンスの機会を自ら放棄したとして、特許法102条1項2号が規定する
「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しく
は通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」に該当し、同号
に基づく実施料相当額の損害は認められない旨主張する。
しかし、被告が主張する事情は、原告の被告に対するライセンスの機会の
喪失を否定する事情に該当するとはいえず、同号の括弧書に該当する場合で
あるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 102条1項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.04.11
令和4(ワ)15136 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年2月28日 東京地方裁判所
被告は、本件投稿画像につき、医療関係者の男性が患者の麻酔中に当該患者 の下を離れて外出している様子を収めたものであり、その様子を投稿すること は、医療現場の実態や、医療事故につながりかねない様子を捉えたものとして ニュース性があるから、「時事の事件」を構成するものである旨主張する。\nしかしながら、前記前提事実、証拠(甲6及び10)及び弁論の全趣旨によ れば、本件投稿画像は、ある男性が住宅地の道路上を走っている画像に、「麻 酔待ちの間にご近所に菓子折り渡しに走ってる。田舎過ぎて。笑」というテロ ップが付されるにとどまり、いつの出来事であるかどうか一切明らかではなく、 しかも、本件投稿画像は、Googleマップという地図アプリにおいて、本 件歯科医院の上にカーソルを動かし、クリックした場合に表\示されるものにす ぎないものであることが認められる。
上記認定事実によれば、本件投稿画像で表示された出来事は、これが生じた\n時期すら明らかではなく、地図アプリにおいて本件歯科医院の上にカーソルを\n動かし、クリックした場合に限り表示されるにすぎないことが認められる。\nそうすると、本件投稿画像の出来事は、著作権法41条にいう「時事の事件」 とはいえず、その投稿も、上記認定に係る表示態様に照らし、同条にいう「報\n道」というに足りないものと認めるが相当である。
これに対し、被告は、本件投稿画像で表示された出来事が医療現場の実態や、\n医療事故につながりかねない様子をとらえたものである旨主張するものの、一 般の利用者の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば、「麻酔待ちの間 にご近所に菓子折り渡しに走ってる。田舎過ぎて。笑」というテロップの内容 及び上記認定に係る本件投稿画像の内容を踏まえると、本件投稿画像は、医療 現場の実態や、医療事故につながりかねない様子であると理解されるものと認 めることはできず、上記各内容に照らしても、被告が主張するようなニュース 性を認めることもできない。したがって、被告の主張は、その前提を欠くもの であり、いずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.04.10
令和2(ワ)31524 販売差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和5年3月24日 東京地方裁判所
2 争点1−1(原告商標1と被告標章が同一又は類似であるか)について
(1) 原告商標1について
原告商標1の外観は、別紙商標権目録1の登録商標欄記載のとおりであり、 黒地に、左半分部分に手書き風の字体で「AirWair」と、右半分部分の上部に 約4文字分の間隔を空けてゴシック体で「WITH」及び「SOLES」と、右半分部 分の下部に下向きの弧を描くように丸みを帯びた字体で「Bouncing」と、い ずれもオレンジ色がかった黄色の英文字が配されて構成されるものである。\n原告商標1の上記記載から、「エアウェアウィズバウンシングソールズ」と\nの称呼が生じると認められる。 また、「AirWair」は原告の社名であるものの造語と解されるから、原告の 社名を知っている者においては当該部分から原告の社名である「AirWair」と の観念が生じるものの、原告の社名を知らない者においては当該部分から特 定の観念が生じない。そして、「Bouncing」及び「SOLES」は、それぞれ英語 で「弾む」及び「靴底(ソール)」との意味を有することからすると、原告商\n標1の上記記載から、「弾む履き心地のソールを持つ AirWair」又は「弾む履 き心地のソールを持つ」との観念が生じると認められる。\n
(2) 被告標章について
被告標章は、別紙被告標章目録記載のとおり、黒地に、左半分部分に手書 き風の字体で「AirWair」と、右半分部分の上部に約1ないし2文字分の間隔 を空けてゴシック体風の字体で「WITH」及び「SOLES」と、右半分部分の下部 に概ね水平に「Bouncing」と、いずれも黄色の英文字が配されて構成される\nものである。もっとも、被告標章は、被告商品1のヒールループに付されて いるものであるところ、当該ヒールループが履き口の踵部分に深く縫い付け られているため、需要者が通常の使用状況において視認できるのは、 「AirWair」の「Ai」を除いた部分に限られる(甲44・1、5頁)。したが って、原告商標1との類否を判断するに当たっては、被告標章のうち「Ai」 を除いた部分(以下「被告標章対比部分」という。)を対象として対比するの が相当である。被告標章対比部分の記載から「アールウェアウィズバウンシングソールズ」との称呼が生じると認められる。\n
また、「rWair」のうち、「Wair」は「用いる」や「費やす」との意味を有す る英単語であるが、我が国の一般人にとってなじみのある語ではない上、冒 頭に「r」が付されているため、「rWair」が何かしらの意味を有する語である と理解できないと解されるから、当該部分から特定の観念が生じない。そし て、前記(1)のとおり、「Bouncing」及び「SOLES」は、それぞれ英語で「弾む」 及び「靴底(ソール)」との意味を有することからすると、被告標章対比部分\nの記載から、「弾む履き心地のソールを持つ」との観念が生じると認められる。\n
(3) 原告商標1と被告標章対比部分との対比
原告商標1と被告標章対比部分の外観を比較すると、文字の色味に違いが あるほか、「Ai」の有無、「WITH」と「SOLES」との間隔の幅、「Bouncing」の 字体と配置に差異があるものの、いずれも黒地に黄色味の文字で「rWair」、 「WITH Bouncing SOLES」と記載されている点において共通しており、両者 の外観は類似していると認められる。
また、原告商標1と被告標章対比部分の称呼を比較すると、両者は、「ウェ アウィズバウンシングソールズ」の点において共通しているものの、原告商\n標1の冒頭が「エア」であるのに対し、被告標章対比部分の冒頭が「アール」 である点に差異がある。もっとも、原告商標1及び被告標章対比部分の文字 部分はいずれも英語で表記されており、「エア」も「アール」も英語風に発音\nするものと理解できるから、「エア」と「アール」の称呼上の違いは実質的に 「エ」の有無にとどまり、両者の差異はほとんどないといえる。したがって、 原告商標1と被告標章対比部分の称呼は類似していると認められる。 さらに、原告商標1と被告標章対比部分の観念を比較すると、前者は「弾 む履き心地のソールを持つ AirWair」との観念も生じるものの、両者とも「弾 む履き心地のソールを持つ」との観念が生じる点で共通している。したがっ\nて、原告商標1と被告標章対比部分の観念は類似していると認められる。
(4) 小括
以上のとおり、原告商標1と被告標章対比部分は、外観、称呼及び観念に おいて類似するものと認められ、原告商標1と被告標章対比部分を含む被告 標章とが同一又は類似の商品に使用された場合には、商品の出所について混 同を生じるおそれがあるといえるから、両者は類似しているものと認められ る。また、前提事実(5)のとおり、被告商品1は、ブーツであることから、原告 商標権1の指定商品に含まれる第25類「履物」と同一であると認められる。したがって、被告標章が付された被告商品1を販売等した被告の行為は、原告商標権1を侵害するというべきである。
3 争点2−1(原告商品の形態が原告の周知な商品等表示であるか)について\n
(1) 商品の形態と商品等表示該当性\n
・・・
以上によれば、靴の外周に沿って、アッパーとウェルトを縫合してい る糸がウェルトの表面に一つ一つの縫い目が比較的長い形状で露出し、\nかつ、ウェルトステッチに明るい黄色の糸が使用されており、黒色のウ ェルトとのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認 できるという原告商品の形態(ア)は、少なくとも被告が被告商品2を販売 した令和2年の時点において、原告の商品等表示として周知となってい\nたと認められる。
◆判決本文
原告被告商品、本件商標は下記へ。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.04. 7
令和4(ワ)16934 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年3月28日 東京地方裁判所
◆本件特許
「本発明」は、前記アの課題を解決するため、授乳者のプライバシーが
保護された状態で授乳を行うことができる授乳用空間が形成された授乳
エリアを簡易に設置できるようにすると共に、授乳用空間のレイアウト
の変更を容易にできるようにすることを目的とするものであり、「本発明」
の授乳用ユニットは、内部に空間が形成された箱状の筐体と、筐体に形
成された開口状の出入口と、出入口に設けられ、閉状態のときに出入口
を塞ぎ、筐体の内部の空間を遮蔽するドアと、筐体の内部の空間に設け
られ、授乳者が着座可能な1つの一人着座用の椅子と、筐体を移動させるキャスターと、を備えることにより、ドアを閉状態とすれば、筐体の内部の空間が遮蔽され、外部から筐体の内部が視認できない状態となる\nため、授乳者は、筐体の内部で、他人に見られることなく、プライバシ
ーが保護された状態で授乳を行うことができ、授乳エリアとなる空間に
授乳用ユニットを持ち込み、キャスターを利用して授乳用ユニットを適
切な位置に移動させるという作業を行うだけで、授乳用空間が形成され
た授乳エリアを設置することができることから、授乳エリアの設置に際
し、綿密な設計の下、各設備を適切な位置に固定的に設ける必要がなく、
授乳エリアの設置が簡易化し、キャスターを利用して授乳用ユニットを
移動させるだけで、授乳エリアにおける授乳空間のレイアウトの変更を
行うことができるため、授乳用空間のレイアウトの変更を容易に行うこ
とができるとの効果を奏する(【0007】ないし【0009】)。
・・・
a 原告は、乙6発明の技術分野は、「プライバシーに配慮した筐体内
部に保育空間を形成する技術」に関するものであり、前記(ア)の公報
及び文献に記載の発明の技術分野とは異なっているから、筐体の移動
を容易ならしめるため、筐体にキャスターをつけることは、乙6発明
の技術分野における周知技術であるとは認められないと主張する。
しかし、前記(ア)において認定したとおり、少なくとも利用者と機
器等を収納する筐体に係る技術分野においては、当該筐体の具体的な
用途にかかわらず、広く当該筐体の移動を容易ならしめる手段として
のキャスターが利用されている。そのような利用状況からすると、移
動対象が授乳室という「プライバシーに配慮した筐体内部に保育空間
を形成する」用途の筐体であるからといって、当業者において、当該
技術分野における周知慣用技術である筐体にキャスターを設けるとい
う構成を乙6発明に係る授乳室に適用することが困難であるとはいえない。
b 原告は、1)乙6発明に係る授乳室にキャスターを取り付けると、
設置面と授乳室の床面との間に段差が生じ、授乳室の安全な利用を図
るという目的に反する、2)乙6発明に係る授乳室においては、授乳用
チェア等の室内装備が固定・固着されていないから、乙6発明に係る
授乳室にキャスターを取り付けて移動可能にすると、授乳等を安全に行うことができなくなる、3)乙6発明に係る授乳室の安全性を保ちつ
つ、キャスターを取り付けることには技術的ハードルがあるとして、
乙6発明に係る授乳室に、キャスターを適用することを妨げる特段の
事情があると主張する。
しかし、1)については、乙6文献の記載から、乙6発明に係る授乳
室は、ロビーの床面と授乳室の床面との間の段差があり、これによる
弊害を解消するため、乙6発明に係る授乳室の出入口付近の床面から、
ロビーの床面に延びるスロープを備えているものと認められ、段差に
よる弊害は、同スロープの設置により解消することができるといえる。
また、技術常識に照らし、取り付けるキャスターのサイズや取付方法
を工夫することにより、上記のような段差が生じることを抑制するこ
とが困難であるとは考え難い。したがって、段差が生じることが乙6
発明に係る授乳室にキャスターを取り付ける阻害要因になるとは認め
られない。
次に、2)については、授乳者を授乳室に収容したまま授乳室を移動
させない限り、乙6発明に係る授乳室内の設備が固定されていない
ことによる授乳者の安全性への影響が生じるとは考え難く、実際に
そのような影響が生じると認めるに足りる証拠もない。むしろ、授
乳者を乙6発明に係る授乳室に収容したまま授乳室を移動させるこ
とは通常の使用方法ではないというべきである。したがって、室内
装備が固定・固着されていないことが乙6発明に係る授乳室にキャ
スターを取り付ける阻害要因になるとは認められない。
さらに、3)については、筐体にキャスターを取り付けることによ
って、不意に筐体が動き出すとの事象が生じ得ることは、容易に想定
できるところ、これによる弊害は、キャスターにストッパーを取り付
けることにより回避することができる。そして、筐体にキャスターを
取り付け、同キャスターにストッパーを取り付ける構成は、前記(ア)
e及び同fのとおり、乙16公報及び17公報において開示されてお
り、周知技術であると認められるから、当業者であれば、筐体にスト
ッパー付きのキャスターを取り付けるという周知技術を適用し、容易
に克服できる弊害であるといえる。したがって、安全性を保つ必要が
あることが乙6発明に係る授乳室にキャスターを取り付ける阻害要因
になるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.04. 7
令和4(ワ)3847 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年3月23日 大阪地方裁判所
◆該当特許
原告は、甲7公報の記載からバー10を抽出し、別紙「主張一覧表」の「無効理由1」の「原告の主張」欄記載の構\成a〜gを有するとして、これを引用発明(甲7発明)とし、本件各発明は甲7発明の構成を全て備える、本件各発明の構\成要件Fが甲7発明の構成fと相違するとしても、バー10を用いてトレーニングすることは可能\であるから相違点は軽微である旨主張する。しかし、甲7公報の記載から、バー10のみを分離して独立の運動器具としての発明と理解することは相当でない。すなわち、前記(2)イ認定のとおり、甲7
公報には、従来のバーベル機材およびダンベル機材において、比較的長いバーを
有する装置はバランスをとることが困難であり、重りを使用しない装置は本格的
なボディビルダーに対しては限定的な有効性しか有さないとの欠点や、三頭筋を
働かせるのに使用されるほとんどの器具が手のひらを上に向けることを必要とす
るが、このようなタイプのハンド・ポジションは、特に重い重りを持ち上げなが
ら肘を内側で維持することを困難にするとの欠点があったこと、甲7公報記載の
発明は、三頭筋をエクササイズするためのウエイトリフティング装置を提供する
ことにより従来技術の短所を解消するものであり、バランスをとることの問題を
有意に低減する中央に位置する重りプレート固定手段を有し、複数のハンド・ポ
ジションおよび間隔を可能にする三頭筋伸展装置を開示すること、装置は、バー・ハンドル組立体および支持クランプ組立体である2つの主要構\成要素を有すること、重り支持プラットフォーム26および解除可能なクランプ手段28が支持クランプ組立体を形成し、バー10が、中央に位置する重り支持プラットフォーム26に固定されること、プラットフォーム26をバー10に取り付けることが、\n好適には、故障を引き起こす可能性を排除するために、溶接によって達成されること、重り又は重りプレート40をプラットフォーム26上で位置決めするのに直立ポスト38が使用され、クランプ部材28がポスト38の周りで固定的に留\nめられ、それにより重りをプラットフォーム26上に固着することが記載される。
これらの記載からすると、甲7公報記載の発明において、重り支持プラットフォー
ム26を含む支持クランプ組立体はバー10とともに装置の主要構成要素であり、バー10は溶接等の方法によりプラットフォーム26に固定され、バー10は重り支持プラットフォーム26等と物理的に一体であることが前提となっていると\nいえる。また、甲7公報記載の発明は、従来のバーベル機材等における、比較的
長いバーを有する装置はバランスをとることが困難であり、重りを使用しない装
置は本格的なボディビルダーに対しては限定的な有効性しか有さないとの欠点を
解消するため、バランスをとることの問題を有意に低減する中央に位置する重り
プレート固定手段を有し、複数のハンド・ポジションおよび間隔を可能にする三頭筋伸展装置を提供するものであり、バー10は支持クランプ組立体と一体となって作用効果を奏するといえる。そして、バー10のみが独立してウエイトリフティ\nング・エクササイズにおける運動器具としての作用効果を発揮することは、甲7
公報には記載も示唆もされていない。
以上によれば、三頭筋運動器具の発明に関する甲7公報の記載から、その部材
の一つにすぎないバー10のみを抽出して独立の運動器具としての引用発明(甲
7発明)と理解することはできず、本件各発明の構成要件Fと甲7発明の構\成f
は明らかに相違する。
・・・
原告は、甲7公報の記載からバー10を抽出した甲7発明を主引用発明と
して、公知技術(甲8、9)を適用することにより、本件各発明は、当業者が容
易に発明することができる旨主張する。
しかし、前記(3)アのとおり、甲7公報の記載から、部材の一つにすぎないバー
10のみを分離して独立の運動器具の発明と理解することは相当でなく、トレー
ニング器具の発明である本件各発明とは技術的内容・性質の異なる甲7発明を主
引用発明として、本件各発明が進歩性を欠如する旨の原告の主張は認められない。
イ 前記(3)ウのとおり、被告は、本件各発明と甲7発明(被告)を対比する
と、少なくとも、相違点1)及び2)が相違する旨主張するところ、原告は、被告主
張の相違点を前提としても、相違点に係る本件各発明の構成は、公知技術(甲8、9)から容易想到である旨主張するので、以下、検討する。
ウ 容易想到性の検討
(ア) 相違点1)(本件各発明は、重り支持部分を備えないのに対し、甲7発明
(被告)は、重り支持部分を備える点)について
前記(3)アのとおり、甲7公報記載の発明は、ウエイトリフティング装置とし
て、バー10に重り支持部分(重り支持プラットフォーム26、クランプ部材2
8、直立ポスト38)を固定し、重り又は重りプレート40を重り支持プラット
フォーム26に固着して使用することを前提とした発明である。すなわち、バー
10は、重り支持プラットフォーム26等により形成される支持クランプ組立体
と物理的に一体となって作用効果を奏するものであるし、バー10が独立して運
動器具としての作用効果を発揮することは、甲7公報に記載も示唆もされていな
いから、甲7公報に接した当業者に、甲7公報記載の発明から重り支持部分を取
り外す動機付けがあるとは考え難い。したがって、相違点1)に係る本件各発明の
構成は甲7発明(被告)から容易想到であるとはいえない。
これに対し、原告は、甲7公報の明細書に溶接前の単独のバー10が記載され
ていること、甲7発明(被告)は重りのついた状態でも本件各発明と同様の作用
効果を奏すること、バー10の状態でも一定の三頭筋エクササイズの効果は得ら
れるところ、よりエクササイズの幅を広げる目的で甲7発明(被告)から重り支
持部分を取り外す動機付けはあることを根拠として、甲7発明(被告)から重り
支持部分を取り外すことは容易想到である旨主張する。しかし、前示のとおり、
甲7公報には、バー10が単独で運動器具としての作用効果を奏することは何ら
開示されていない。仮に甲7発明(被告)が本件各発明と同様の作用効果を奏す
るとして、甲7発明(被告)は、ウエイトリフティング装置として、バー10に
固定された重り支持部分を構成する重り支持プラットフォーム26に重り又は重りプレート40を固着して使用することを前提とした発明であるから、よりエクササイズの幅を広げる目的で重りを取り外して使用する可能\性はあるとしても、重り支持部分全体を取り外す動機付けがあるとはいえない。したがって、原告の主張は採用できない。
・・・
以上より、原告が主張する無効理由1〜3はいずれも認められず、本件各発明
について無効原因があるとはいえない。したがって、被告が本件特許権に基づい
て行った本件申立てが違法なものであるとは認められず、本件申\立てについて、
不法行為は成立しない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2023.04. 4
令和4(ネ)10098 不正競争防止法による差止請求、損害賠償請求と書類提出命令請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和5年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
商品の形態は、本来的には商品の機能・効用の発揮や美観の向上等の見地\nから選択されるものであり、商品の出所を表示するものではないが、特定の\n商品の形態が、他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有し、かつ、その 形態が長期間継続的、独占的に使用され、又は短期間でも効果的な宣伝広告 等がされた結果、特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機 能を獲得するとともに、需要者の間に広く認識されるに至ることがあり得る\nところであって、こうした商品の形態は、不競法2条1項1号によって保護 される他人の周知な商品等表示に該当するものと解される。\n
前記認定事実によれば、控訴人が日本国内で販売してきた原告各製品は、 平成22年以降発売されているところ、原告各製品を構成するもののうち、\n本体部分(発光部分、台座等)は、世代製品ごとに構成が異なるものである\nが、シェード部分の形状は、各世代製品間で共通しており、控訴人が開設し たオンラインショップのウェブページ上でも、原告各製品の構成のうち、シ\nェード部分の形状が他社製品と違う点を強調している(前記1 イ)ように、 その外観であるシェード部分に特徴的な商品の形態があるといえる。
他方で、原告各製品の第1世代製品を開始した平成22年から遅くとも被 控訴人が被告各製品を日本国内で発売を開始した平成30年10月までの間 における原告各製品の販売数量は明らかではなく、また、原告各製品の特徴 的部分であるシェード部分のうち、少なくとも、原告製品2は、レ・クリン ト社が製造及び発売するモデル30と類似のプリーツ状のシェードであって、 独占的にその形状が使用されてきたものとはいい難い。
これらの点を措くにしても、周知な商品等表示というためには、前記 の とおり、原告各製品が原告の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲\n得するとともに、需要者の間に広く認識されるに至ることが必要であるとこ ろ、これらの点を認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。控訴人は、長 期間にわたり原告各製品に係る広告宣伝を行った旨主張し、Faceboo kで行ったとする広告に関する資料(甲46)を提出するが、そのとおりで あるとしても、そもそも宣伝をすれば足りるというものではなく、宣伝等の 結果、遅くとも被告各製品が発売された平成30年10月の時点で、需要者 において原告各製品のシェードの形状が控訴人の商品であることを認識する に至ったことを証明する必要があるのであるから、控訴人の主張、立証は当 を得ないものというほかない。したがって、その他の点について判断するま でもなく、原告各製品の商品の形態が不競法2条1項1号に規定する「商品 等表示」に該当するとは認められない。\n
以上によれば、原告各製品の形態が不競法2条1項1号の周知な商品等表\n示に該当するものとして、被控訴人による被告各製品の販売が同号の不正競 争行為に当たることを前提とした控訴人の請求は、いずれも理由がない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2023.04. 4
令和4(行ケ)10092 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月27日 知的財産高等裁判所
当初明細書等及び第2次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義は、前 記2(1)イ及び(2)記載のとおり、ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の 強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、従来のように対戦相手をラ ンダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が出て勝敗がすぐに ついてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さに一定の ばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興 味を増大させることにある。 そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、 攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが 本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いがない(本件審決第 2の2(2)イ(ウ)〔本件審決12頁〕参照)。
上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユー ザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細 書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当で\nあり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態 としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえ て体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合 計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、 「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的 意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付 加的な事項にすぎないと認められる。 そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃 力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技 術常識に鑑みると、第2次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたも\nのとは認められず、第2次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認め られない。そうすると、第2次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内 においてされたものであると認められ、特許法17条の2第3項の規定に違反 するものではないというべきである。 したがって、本件審決が、第1次補正発明の「強さ」について、第2次補正 により「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と補正したことは新たな技術的事項を導入するものである\nとして、第2次補正は特許法17条の2第3項の規定に違反すると判断して第 2次補正を却下した(本件審決第2)のは誤りであると認められ、本件審決に は、原告主張の取消事由が認められる。
4 被告の主張に対する判断
(1) 被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定されるものであることは明らかである旨主張する(前記第3〔被告の 主張〕2(1)ア)。
しかし、前記3のとおり、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユ ーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテ ム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間 に争いがない。そして、当初明細書等に、「強さ」について「攻撃力及び防御 力の合計値」と記載された箇所があるとしても、発明の技術的意義に鑑みれ ば、「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りるものと解され、「強さ」から\n「攻撃力及び防御力の合計値」以外の要素を除外する理由は見出されない。 対戦ゲームには様々な形態があり得るものであり、技術常識に照らすと、ゲ ームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパラメータが 想定されるものと認められ、段落【0028】に記載の「攻撃力及び防御力 等」における「等」や図2(b)における「…」が、「強さ」の要素のうち、 攻撃力及び防御力以外の体力、俊敏さ、所持アイテム数等の要素を示すと解 することは十分に可能\である。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(2) また、被告は、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第2次補正後の請求項1、7及び8の\n文言によっては、「強さ」にどのようなパラメータが包含されるのかが具体的 に特定できず、第三者に不測の不利益を生じると主張する(前記第3〔被告 の主張〕2(1)イ)。
確かに、対戦ゲームには様々の形態があり得るものであり、技術常識に照 らすと、ゲームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパ ラメータが想定されるものと認められる。 しかし、各形態のゲームにおいてどのような「強さ」のパラメータを設定 するのが適当かは、当業者であれば適宜判断し得るものと推認され、ユーザ の強さを基準として所定範囲内の強さを有する他のユーザを対戦相手として 選択することにより、ユーザのゲームに対する興味の低下を防ぐという発明 の技術的意義に照らせば、ある形態の対戦ゲームにおいて「強さ」にどのよ うなパラメータが含まれるかは、当業者であれば想定し得るものと推認され る。そうすると、「強さ」が「攻撃力と防御力の合計値」に限定されていない としても、第三者に不測の不利益をもたらすものとは認められない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(3) 被告は、第2次補正によって「強さ」が広範な概念へと拡張され、新たな 技術的事項を追加するものとなったこと、「数値が高い程前記対戦ゲームを 有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第2次補正後の請求項1、7及び8の文言には、どのようなパラメータが包含されるの\nかが具体的に特定できず、第三者に不測の不利益をもたらすことから、第2 次補正は認めるべきでない旨主張する(前記第3〔被告の主張〕3)。 しかし、前記(1)及び(2)において述べたとおり、被告の上記主張は採用する ことができない。
(4) また、被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の 合計値」に限定されるものであることは明らかであると主張するが(前記第 3〔被告の主張〕4)、前記(1)のとおり、このような被告の主張は採用するこ とができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2023.04. 4
令和4(行ケ)10009 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月27日 知的財産高等裁判所
本件決定は、相違点1に関し、1)甲2技術的事項に接した当業者であれば、 「複数本数の容器弁付き窒素ガス貯蔵容器」を備えた「自動起動式の」甲1 発明において、「窒素ガス」が、過剰圧力がかかった状態で防護区画へ放出さ れ得ることを防ぐために、窒素ガスが、過剰圧力がかからないように制御さ れた速度で、防護区画に順次放出されるようにすればよいことを容易に認識 するといえる、2)甲2技術的事項では、「メインバルブ22」と、「ラプチャ ーディスク16a」と、「ラプチャーディスク16b」の開放時間をずらすこ とで、「過剰圧力がかからないように制御された速度で、保護された部屋14 に順次放出されるようにする」ことを実現しているが、「複数本数の容器弁付 き窒素ガス貯蔵容器」を備えた「自動起動式の」甲1発明において、窒素ガ スの過剰圧力がかからないように、制御された速度で防護区画に順次放出す るには、各「窒素ガス貯蔵容器」に付いた「容器弁」の開弁時期をずらすこ とによって実現でき、ラプチャーディスク等を用いるまでもないことは、当 業者であれば普通に予測し得たことである、3)本件明細書の【0025】の 記載を参酌すると、本件発明の「前記一つの容器の容器弁の第一の開弁タイ ミングと、前記別の容器の容器弁の第二の開弁タイミングであって前記第一 の開弁タイミングとは異なり消火剤ガスのピーク圧力が重なることを防止す る前記第二の開弁タイミングとを決定し」にいう「決定し」とは、制御部か らの信号により開弁のタイミングが決定づけられているということ以上を意 味していないと解さざるを得ず、そのタイミングを「前記一つの容器の容器 弁の第一の開弁タイミングと、前記別の容器の容器弁の第二の開弁タイミン グであって前記第一の開弁タイミングとは異なり消火剤ガスのピーク圧力が 重なることを防止する前記第二の開弁タイミング」とすることは、窒素ガス の過剰圧力がかからないように、制御された速度で防護区画に順次放出する ことを、各「窒素ガス貯蔵容器」に付いた「容器弁」の開弁時期をずらすこ とによって実現するための必然的なタイミングでしかないから、「前記一つ の容器の容器弁の第一の開弁タイミングと、前記別の容器の容器弁の第二の 開弁タイミングであって前記第一の開弁タイミングとは異なり消火剤ガスの ピーク圧力が重なることを防止する前記第二の開弁タイミングとを決定し、 前記各容器弁に接続される制御部をさらに備える」ことも当業者が容易に想 到し得たことである、4)甲7及び8の記載事項からみて、「複数の消火ガス容 器を備え、防護区画へ配管等の導入手段を介して消火ガスを導入する消火設 備において、複数の消火ガス容器のうちの一つの容器の容器弁と別の容器の 容器弁との開弁時期をずらして、防護区画へ消火ガスを導入し、容器弁の開 弁時期は制御部により決定づけられること」は、ガス系消火設備の技術分野 において、本件出願前、周知技術であったといえる、5)甲2技術的事項に接 した当業者であれば、甲1発明において、各「窒素ガス貯蔵容器」に付いた 「容器弁」の開弁時期をずらすことで、相違点1に係る本件発明の発明特定 事項(構成)とすることは、当業者が容易に想到し得たというべきである旨\n判断した。 しかしながら、本件決定の判断は、以下のとおり誤りである。
ア 1)及び2)について
・・・
(ウ) 以上のとおり、甲1記載の「容器弁」付き窒素ガス貯蔵容器の「容器 弁」と甲2技術的事項の「ラプチャーディスク」は、動作及び機能が異\nなること、甲1及び2のいずれにおいても貯蔵容器の容器弁又はガスシ リンダーのバルブの開閉時期をずらして複数のガスシリンダーからそ れぞれ順次ガスを放出することによって保護区域又は保護された部屋 の加圧を防止することについての記載や示唆はないことに照らすと、甲 1及び2に接した当業者は、甲1発明において、保護区域又は保護され た部屋の加圧を防止するために甲2記載のラプチャーディスクを適用 することに思い至ることがあり得るとしても、ラプチャーディスクを用 いることなく、各「窒素ガス貯蔵容器」に付いた「容器弁」の開弁時期 をずらして複数のガスシリンダーからそれぞれ順次ガスを放出するこ とよって加圧を防止することが実現できると容易に想到することがで きたものと認めることはできない。 したがって、本件決定の1)及び2)の判断は誤りである。
イ 3)について
本件決定の2)の判断は、本件発明の「前記一つの容器の容器弁の第一の 開弁タイミングと、前記別の容器の容器弁の第二の開弁タイミングであっ て前記第一の開弁タイミングとは異なり消火剤ガスのピーク圧力が重な ることを防止する前記第二の開弁タイミングとを決定し」にいう「決定し」 とは、制御部からの信号により開弁のタイミングが決定づけられていると いうこと以上を意味していないと解さざるを得ないことを根拠として、容 器弁に接続される制御部を備える甲1発明において、「前記一つの容器の 容器弁の第一の開弁タイミングと、前記別の容器の容器弁の第二の開弁タ イミングであって前記第一の開弁タイミングとは異なり消火剤ガスのピ ーク圧力が重なることを防止する前記第二の開弁タイミングとを決定し、 前記各容器弁に接続される制御部をさらに備える」こと(相違点1に係る 本件発明1の構成の一部)も当業者が容易に想到し得たことをいうものと\n解されるところ、本件発明1の「決定し」の用語のクレーム解釈から直ち にそのような結論を導き出すことには論理的に無理があり、論理付けが不 十分である。\n
ウ 4)について
仮に本件決定が述べるように甲7及び8の記載から、「複数の消火ガス 容器を備え、防護区画へ配管等の導入手段を介して消火ガスを導入する消 火設備において、複数の消火ガス容器のうちの一つの容器の容器弁と別の 容器の容器弁との開弁時期をずらして、防護区画へ消火ガスを導入し、容 器弁の開弁時期は制御部により決定づけられること」は、ガス系消火設備 の技術分野において、本件出願前、周知であったことが認められるとして も、当業者が、甲1発明において、上記周知技術を適用することについて の動機付けがあることを認めるに足りる証拠や論理付けがない。
エ まとめ
以上によれば、当業者は、甲1、甲2技術的事項及び前記周知技術に基 づいて、甲1発明において、相違点1に係る本件発明の構成とすることを\n容易に想到することができたものと認めることはできないから、これと異 なる本件決定の判断は誤りである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2023.04. 4
令和4(ネ)10095等 損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和5年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお、控訴人は、控訴人による控訴人商品の販売行為のうち、需要者が、特定 の販売チャネル(医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商品画像等 を通じて被控訴人商品の形態と極めて酷似する控訴人商品の形態に接した場合)を 経由したときに限り、不正競争行為に該当する旨主張する。
そこで検討するに、不競法2条1項1号が他人の周知の商品等表示と同一又は類似の商品等表\示を使用することを不正競争と定めた趣旨は、周知な商品等表示の主\n体である他人の商品又は営業との混同を生じさせる具体的な危険性がある行為を禁 止することにより、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得することを防止し、もって周知な商品等表\示が有する営業上の信用を保護し、事業者間の公正な競争を確保することにある。そして、 同号の「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」に当たると解されるために、 現実に混同が生じたことを要するものではなく、混同のおそれがあれば足り(最高 裁昭和44年(オ)第912号同年11月13日第一小法廷判決・裁判集民事97 号273頁参照)、また、同行為は、他人の周知の商品等表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と上記他人とを同一の商品又は営業の主体として誤信させる\n行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な 営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含するものと解される(最高裁昭和57年(オ)第658号\n同58年10月7日第二小法廷判決・民集37巻8号1082頁、最高裁平成7年 (オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判決・裁判集民事189号857 頁参照)。
本件についてみると、被控訴人商品の形態は、約34年間の長期間にわたり継続 的かつ独占的に使用されてきたことにより、需要者である医療従事者にとって、被 控訴人商品の出所を表示するものとして認識されるに至り、控訴人商品の販売が開始された平成30年1月頃の時点において、不競法2条1項1号所定の周知の商品\n等表示に該当するものであったと認められるところ、控訴人は、周知の商品等表\示 である被控訴人商品の形態と酷似した形態を有し、かつ、被控訴人商品と同一目的 において、同一の使用方法により使用される控訴人商品を、被控訴人商品と同一の 需要者に対し販売しており、需要者は、控訴人又はその販売代理店から控訴人商品 の実物を伴う説明を受けたり、カタログやオンラインショップに掲載された控訴人 商品の写真等を見たりすることによって、控訴人商品が被控訴人商品と同一又はほ ぼ同一の形態であると認識し、被控訴人商品の形態に化体された被控訴人の営業上 の信用により購入動機を形成し、控訴人商品を購入していたものと推認される。こ れらの事情を総合すると、控訴人商品の形態を認識した需要者をして、被控訴人商 品と混同させるおそれや、被控訴人商品の主体である被控訴人と、控訴人との間に 何らかの緊密な営業上の関係が存すると誤信させるおそれが具体的に存していたと いうべきである。そして、控訴人商品の販売がいかなる販売経路によるものであっ たとしても、需要者は、控訴人商品を購入するに当たり、周知の商品等表示である被控訴人商品の形態と酷似した控訴人商品の形態を認識することができるから、混\n同のおそれが存することは、販売経路によって異なるとはいえない。 また、差止請求がされる場合と損害賠償請求がされる場合において、不正競争行 為の成立する範囲を別異に理解すべき理由はない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.03.31
令和4(ネ)10092 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1 事案に鑑み、争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」 (プロバイダ責任制限法4条1項)又は「特定発信者情報」(改正法5条1項柱 書)に該当するか)から判断する。
(1) 改正法5条が発信者情報の開示請求を規定している趣旨は、特定電気通信 (改正法2条1号)による侵害情報の流通は、これにより他人の権利の侵害 が容易に行われ、ひとたび侵害があれば際限なく被害が拡大する一方、匿名 で情報の発信が行われた場合には加害者の特定すらできず被害回復も困難と なるという、他の情報の流通手段とは異なる特徴があることを踏まえ、侵害 を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由及び通信の秘密に\n配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信 設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求する ことができるものとすることにより、加害者の特定を可能にして被害者の権\n利の救済を図ることにあると解される。
そして、改正法5条1項柱書は、権利の侵害に係る発信者情報のうち、特 定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務 省令で定めるもの)も開示の対象とし、同条3項は、「「侵害関連通信」とは、 侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、 又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符 号・・・その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信 者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものを いう。」と規定し、同項の委任を受けた改正規則は、「法第5条第3項の総務 省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識 別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定す る侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」(5条柱書)とした上で、同 条2号で「あらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態に するための手順に従って行った・・・識別符号その他の符号の電気通信によ る送信」(改正規則5条2号)と規定する。その趣旨は、法4条1項に規定さ れた「当該権利の侵害に係る発信者情報」は、侵害情報の送信についての発 信者情報に限られると解するのが文理に忠実であったが、海外法人が運営す るSNSなどについては、侵害情報の送信について特定電気通信役務提供者 が通信記録を保有しない場合があることから、ログイン情報の送信について の発信者情報を開示の対象として明記することで、救済の実効性を確保する 一方、ログイン情報の送信は、侵害情報の送信そのものではなく、侵害情報 の発信者以外のログイン情報が開示される可能性があり、また、開示を可能\ とする情報を無限定とすれば、発信者のプライバシーや表現の自由及び通信\nの秘密が侵害されるおそれがあることから、ログイン情報の発信者情報の開 示を、侵害情報の発信者を特定するために必要最小限な範囲であるもの、す なわち当該権利侵害と相当の関連性を有するものに限定したものと解される。 そして、改正規則案5条1項では、発信者情報の開示が認められるログイ ン情報の送信については、侵害情報の送信より前で(2号)、侵害情報の送信 の直近に行われたものとする(柱書)旨規定されていたのに対し、改正規則 5条1項柱書が侵害情報の送信との「相当の関連性」を有するものとして、 幅のある文言としていることからすれば、「相当の関連性」の有無は、当該ロ グイン情報に係る送信と当該侵害情報に係る送信とが同一の発信者によるも のである高度の蓋然性があることを前提として、開示請求を受けた特定電気 通信役務提供者が保有する通信記録の保存状況を踏まえ、侵害情報に係る送 信と保存されているログイン情報との時間的近接性の程度等の諸事情を総合 勘案して判断されるべきであり、侵害情報の送信とログイン情報の送信との 間に時間的に一定の間隔があることや、ログイン情報の送信が侵害情報の送 信の直近になされたものではないことをもって、直ちに関連性が否定される ものではないというべきである。
(2) これを前提として本件についてみると、本件IPアドレス等に係る情報の ログイン日時(令和4年2月10日)と、本件ツイートが投稿された時点(令 和3年10月10日)との間には一定の間隔があることは明らかであるが、 本件のような事案において、控訴人が開示可能なより間近な時点でのIPア\nドレス等に係る情報が存在するかについては、控訴人本人において判断する ことは困難であるところ、原審において被控訴人や原審裁判所からこの点に 関する指摘があったことをうかがわせる事情も見当たらないことに照らせば、 本件においてこの点を重視することは相当でない。
他方、本件においては、前記第2の2(4)のとおり、被控訴人の意見照会に 対し、本件ログインに係る回線契約者とは別人であるとしつつも、回答者が、 本件ツイートをしたことを認めた上で、本件ツイートが控訴人の著作権や著 作者人格権を侵害するものであることを否定する回答をしているし(甲11)、 本件IPアドレス等に係る情報のログイン日時(令和4年2月10日)の後 の日である令和4年3月には、本件アカウントが削除された上に、同月23 日には、「タピオカちゃんを動かして」いたとする者が、ツイッター内のダイ レクトメッセージ(以下「本件メッセージ」という。)で控訴人に連絡をとり、 本件ツイートをしたことを前提として謝罪をしている(甲14)ことが認め られるのであるから、本件投稿者と本件ログインをした者が同一であること は明らかであるという事情がある。なお、本件回答書にいうように、本件投 稿者が本件ログインに係る回線契約者と別人であるとしても、本件投稿でも 【代/行】と記載され(甲2)、本件メッセージでも本件ツイートは「代行」 したものであることを前提としており、情報の送信は本件ログインに係る回 線契約者によってされたものと認められるから、本件ツイートや、本件ログ イン自体は、本件ログインに係る回線契約者によってされたものというべき である。 これらの本件特有の事情を総合勘案するとともに、本件事案のこれまでの 経緯に鑑みれば、本件ログインの通信は、本件ツイートと相当の関連性を有 し、侵害関連通信(改正法5条3項)に当たるものと解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.03.31
令和4(行ケ)10029 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月27日 知的財産高等裁判所
発明の詳細な説明が物の発明について実施可能要件を満たすためには、当\n業者が発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の 試行錯誤を要することなく、その物を製造し、使用することができる程度の 記載があることを要するものと解される。
(2) 本件では、長細状凸部ループ構造を有し、光学三特性を有する防眩層を備\nえる第1実施形態に係る防眩フィルムにより本件各発明を実施できることは 当事者間に争いはない。しかし、本件各発明は、光学三特性を満たす防眩層 を備えることを要するものの、特許請求の範囲においては、その構造は限定\nされておらず、長細状凸部ループ構造以外の構\造のものも本件各発明に含ま れるものと解される。そこで、本件明細書等の記載に長細状凸部ループ構造\n以外の構造のものが含まれているといえるか否かを検討する。\nまず、本件明細書等の段落【0034】には、[防眩層の構造]として、「第\n1実施形態の防眩層3は、複数の樹脂成分の相分離構造を有する。防眩層3\nは、一例として、複数の樹脂成分の相分離構造により、複数の長細状(紐状\n又は線状)凸部が表面に形成されている。長細状凸部は分岐しており、密な\n状態で共連続相構造を形成している。」と記載されている。それに続く段落\n【0035】には、「防眩層3は、複数の長細状凸部と、隣接する長細状凸部 間に位置する凹部とにより防眩性を発現する。防眩フィルム1は、このよう な防眩層3を備えることで、ヘイズ値と透過像鮮明度(写像性)とのバラン スに優れたものとなっている。防眩層3の表面は、長細状凸部が略網目状に\n形成されることにより、網目状構造、言い換えると、連続し又は一部欠落し\nた不規則な複数のループ構造を有する。」として、長細状凸部ループ構\造につ いて記載されているが、この段落【0035】の記載は、第1実施形態の防 眩層として、長細状凸部ループ構造以外の相分離構\造を否定しているものと は認められない。
また、本件明細書等には、第1実施形態において、共連続相構造だけから\nなる形状のほかに、相分離の程度によって、共連続相構造と液滴相構\造(球 状、真球状、円盤状や楕円体状等の独立相の海島構造)との中間的構\造も形 成できることが記載されているし(段落【0072】)、相分離により層表面\nに微細な凹凸を形成することで、防眩層中に微粒子を分散させなくても防眩 層のヘイズ値を調整できることが記載されており(段落【0073】)、共連 続相構造に限定しない微細な凹凸を形成することが示唆されているといえる。\nそして、本件明細書等の段落【0134】には「実施例1〜6は、相分離 構造を基本構\造として防眩層3を形成するものである。」と記載されている ものの、全ての実施例が長細状凸部ループ構造であるとは記載されていない\nし、甲47(実施例3及び6の防眩フィルムの顕微鏡写真)の実施例3の防 眩フィルムの表面形状・構\造を撮影した写真からは、長細状凸部ループ構造\nとまではいえない凹凸形状が形成されていることが認められるから、第1実 施形態の凹凸構造として、長細状凸部ループ構\造以外の凹凸構造をも製造す\nることができると認められる。さらに、長細状凸部ループ構造以外の凹凸構\ 造が形成され、かつ光学三特性を備える防眩フィルムとして、甲47の実施 例3の凹凸構造しか製造できないことを示す証拠はない。\nそうすると、第1実施形態の防眩層には、長細状凸部ループ構造以外の凹\n凸構造のものが含まれており、そのようなものも含め、当業者であれば、少\nなくとも第1実施形態により、光学三特性を満たす本件各発明に係る防眩層 を、過度の試行錯誤なく製造できるものと認められる。 したがって、本件明細書等には、当業者が発明の詳細な説明の記載及び出 願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を 製造し、使用することができる程度の記載があると認められる。
(3) この点に関し、被告は、本件各発明は、第1構造防眩層を備えた防眩フィ\nルムのみならず、第2構造防眩層及び第3構\造防眩層を備えた防眩フィルム を含むにもかかわらず、本件明細書等には、実施例として第1構造防眩層に\nついて示されているにすぎず、第2構造防眩層及び第3構\造防眩層について は、具体的製造例や光学三特性の測定結果等の記載はなく、凹凸をどのよう に形成すればよいか等について何らの示唆もない旨、原告が光学三特性を得 るための構造として主張する構\造は、第1構造防眩層を上位概念化したもの\nであり、それによって直ちに光学三特性を得られるものではない旨主張し、
そのため、光学三特性のパラメータの数値範囲を満たす第2構造防眩層及び\n第3構造防眩層を製造するには過度の試行錯誤を要すると主張する(前記第\n3の2〔被告の主張〕)。
しかし、第2実施形態または第3実施形態により、第1実施形態では製造 できない防眩フィルムを製造することは、本件明細書等には記載されていな い。むしろ、本件明細書等の段落【0079】には、「第1実施形態において 前述したスピノーダル分解によって、このような凹凸を防眩層に形成できる が、その他の方法によっても、このような凹凸を防眩層に形成できる。例え ば第2実施形態のように、防眩層の表面の凹凸を形成するために複数の微粒\n子を使用する場合でも、防眩層の形成時に微粒子とそれ以外の樹脂や溶剤と の斥力相互作用が強くなるような材料選定を行うことによって、微粒子の適 度な凝集を引き起こし、急峻且つ数密度の高い凹凸の分布構造を防眩層に形\n成できる。」と記載され、第1実施形態のような凹凸を他の方法で形成できる とした上で、その一例として第2実施形態の方法で形成することが示されて いるし、また、本件明細書等の段落【0079】には、上記の記載に続けて、 「そこで以下では、その他の実施形態の防眩層について、第1実施形態との 差異を中心に説明する。」と記載され、以下に、第2実施形態(段落【008 0】ないし【0102】)、第3実施形態(段落【0103】ないし【011 5】)の説明が続けてされているから、第3実施形態は、第1実施形態によっ て得られる凹凸を形成する「その他の方法」の一つであると解するのが自然 である。そして、本件各発明に含まれる防眩フィルムであって、第1実施形 態以外の方法により作成できない防眩フィルムの存在やその態様を裏付ける 証拠はない。そうすると、第1実施形態により作成できる防眩フィルムを、 第2実施形態や第3実施形態によっても作成できるものと認められ、仮に、 第1実施形態により作成できる防眩フィルムの中に、第2実施形態や第3実 施形態により作成できないものがあったとしても、それにより、第1実施形 態により本件各発明が実施可能であることが否定されるものではない。\n
なお、第2実施形態により製造された第2構造防眩層、第3実施形態によ\nり製造された第3構造防眩層の中に、第1構\造防眩層とは異なる形状・構造\nを有するものがあり、それらが本件各発明の光学三特性を満たさなかったと しても、それらは本件各発明を実施するものではないというにとどまり、そ れによって本件各発明の実施可能性が否定されるわけではない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2023.03.31
令和3(ワ)22287 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和5年3月9日 東京地方裁判所
◆登録5438059
ア 前提事実(6)のとおり、被告は、被告商品の販売によって合計515万0140円の利益
を得たことから、同金額が被告の商標権侵害によって原告が受けた損害の額と推定される
(商標法 38 条 2 項)。
イ もっとも、原告商品は、その販売価格がバーキンにおいては 100 万円を、ケリーに
おいては 50 万円を超えるものが大半という高級ハンドバッグである(前提事実(2))。他方、被告商品の販売価格はいずれも 1 万 5180 円であり(前提事実(6))、その価格差が大きいことは多言を要しない。また、証拠(甲 23、乙 1)及び弁論の全趣旨によれば、バーキンには複数のサイズのものがあるものの、最も小さいサイズのものの横幅は 25cm であるのに対し、被告商品 1 の横幅は 20cm であることが認められる(なお、ケリーも、横幅が cmのものを最小として複数のサイズのものが販売されており、他方、被告商品 2 の横幅は20cm である。甲 1、52)。
商標権は、特許権等の他の工業所有権とは異なり、それ自体に創作的価値があるもので
はなく、商品又は役務の出所である事業者の営業上の信用等と結びつくことによってはじめて一定の価値が生じるという性質を有する。このため、商標権が侵害された場合に、侵害者の得た利益が当該商標権に係る登録商標の顧客吸引力のみによって得られたものとは必ずしもいえない場合が多い。本件のようなハンドバッグの場合、需要者の購買動機の形成に当たっては、当該商品の属するブランドはもとより、その販売価格も考慮され、また全体のデザイン及びサイズといった要素も、デザイン性ないしファッション性の側面のみならず機能面からも考慮されると考えられる。これらの点を踏まえると、原告商標ないし原告商品の周知著名性からそのブランド及び全体のデザインが需要者の購買動機形成に及ぼす影響は相当に大きいとみられるものの、販売価格並びにデザイン及びサイズにおける相違が及ぼす影響もなお無視し得ず、上記推定を覆滅すべき事情として考慮するのが相当である。また、被告商品と同じ価格帯で「バーキン風」、「ケリー風」などと称するハンバッグが市場において取引されている事実が認められるところ(乙 17〜20、28、29)、これらの全てが原告商標権の侵害品であるとは必ずしも考えられず、侵害品でないものが含まれる可能性も少なからずうかがわれる。このうち原告商標権の侵害に当たるものがどの程度存在するかは必ずしも判然としないところ、他に原告商標権の侵害品が存在することを推定覆滅事由として考慮することは相当でないものの、上記事情は推定覆滅事由として一応考慮するのが相当である。さらに、バーキンの内側には、被告商品 1 にはないファスナーポケットが設けられていることが認められるところ(弁論の全趣旨)、その有無は、デザイン性という点では需要者の購買動機の形成に必ずしも寄与しないとしても、収納性という機能面の一要素としては考慮し得るものといえる。他方、被告は、ファッションショーへの出展、独自ブランドの商品販売、全国の主要都\n市への出店、SNS での宣伝活動等の営業努力をしていることが認められる(乙 21〜27)。
もっとも、これらの営業努力は、通常の営業努力の範囲を超える特別なものとまではいえないことから、この点を推定覆滅事由として考慮するのは相当でない。
ウ 以上の事情を総合的に考慮すると、被告商品の利益の額に対する原告商標の貢献割
合については、いずれも8 割と認めるのが相当である。これに反する原告の主張は採用できない。
したがって、本件における上記損害額の推定は 2 割の限度で覆滅されるから、被告の原
告商標権侵害による原告の損害額は、被告商品 1 及び 2 の各販売利益の額(276 万 2740 円及び 238 万 7400 円)のそれぞれ 8 割に相当する 221 万 0192 円及び 190 万 99円の合計412万0112 円と認められる。
エ これに対し、被告は、原告商品と被告商品との価格差、被告商品と同じ価格帯の原
告商品を模した商品の存在、被告商品の販売利益に対する被告の営業努力の貢献、原告商品と被告商品とのサイズやファスナーポケットの有無といった機能性の違い等を指摘し、被告商品の販売によって原告に損害が発生することはなく、仮に損害が発生したとしても少なくとも 95%の推定覆滅が認められる旨主張する。
しかし、原告商品と被告商品は、いずれも主に女性を需要者とするハンドバッグであり、販売方法には共通点があり、かつ、需要者にとってその形状(全体のデザイン)は購買動機を形成する主な要素の 1 つであるところ、原告商品と被告商品は形状が類似している
いった事情を踏まえると、被告が主張する上記各事情を踏まえても、原告商品と被告商品の顧客層には一定の重なり合いが認められるのであって、被告商品の販売によって原告に損害が発生すると認められる。また、これらの事情が商標法 38 条 2 項による推定を覆滅する程度については、上記のとおりである。
したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。
(2) 信用毀損による無形損害の額
原告は、高級ハンドバッグである原告商品の大半を、バーキンについては 100 万円以上、ケリーについては 50 万円以上という価格で販売している(前提事実(2))。他方、被告は、原告商品と形状において類似するものの、原告商品には使用されない安価な合成皮革等を用いて製作された被告商品を、1 個 1 万 5180 円で、百貨店の店舗や自社の運営する EC サイト等を通じて、令和元年 12 月 日から令和 3 年 2 月 13 日までの 1 年余りの間に、合計398 個(被告商品 1 が 214 個、被告商品 2 が 184 個)販売した(前提事実(6))。このような被告の行為は、高級ハンドバッグとしての原告商品及びこれを製造販売する原告のブランド価値すなわち信用を毀損するものであり、これによる原告の無形損害の額は 100 万円を下らない。無形損害の額に関する原告の主張は採用できない。
また、被告は、原告商品と被告商品との購買層の違いや、原告商品を模したハンドバッ
グが全国各地で廉価で販売されているのは周知の事実であることなどを指摘して、原告の信用毀損はない旨を主張する。しかし、仮にこれらの事情があるとしても、原告商標及び原告商品の周知著名性を考慮すると、その違いゆえに原告の信用が毀損されないという関係にはない。この点に関する被告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 立体商標
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.03.29
令和4(行ケ)10061 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月16日 知的財産高等裁判所
また、本件補正は、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの 動作とに対応させて危険である場合」との記載を削除し、「前記検知手段 が人を検知している場合」との記載を追加する補正を含むところ、「前記 検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動作とに対応させて危険であ る場合」であっても警報を行わない場合を含むことになるから、同5項2 号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものでない。
イ 原告は、前記第3の1(1)アのとおり、本件補正は、本件拒絶理由通知書 の指摘に応じ、「警報を行う」条件を「前記検知手段が人を検知している 場合」に特定することにより、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュ エータの動作とに対応させて危険である場合」の意味内容を明確にしたも のであるから、特許法17条の2第5項4号の明りょうでない記載の釈明 に当たる旨主張する。
しかし、本件補正後の「前記検知手段が人を検知している場合」との記 載は、本件補正前の「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動 作とに対応させて危険である場合」との記載の本来の意味内容に含まれる べき「前記油圧アクチュエータの動作」との対応関係を明らかにするもの と理解することはできず、本来の意味内容において「警報」を行う対象が オペレーターであったと理解することもできない。 そうすると、本件補正後の記載は本件補正前の記載本来の意味内容とは 異なるものになっているから、本件補正は、本件補正前の記載本来の意味 内容を明らかにするものにはなっておらず、明りょうでない記載の釈明に 当たるとは認められない。
(2) 小括
以上によれば、本件補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれ の事項を目的とするものにも該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
3 取消事由2(本件補正における新規事項の追加に対する判断の誤り)につい て
(1) 前記2において説示したとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項各 号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、認められないもの であるから、この点で既に却下されるべきものであるが、なお念のため、本 件補正が新規事項を追加するものであるかについても検討する。 本件補正では、「前記検知手段が人を検知している場合に」警報を行うこ と及び「オペレーターに対して」警報を行うことを発明特定事項として新た に導入するものであるが、当初明細書等には、そもそも、コントローラが何 らかの条件で警報を行う構成すら記載されていない。\n当初明細書における【0002】の「機械と周囲の作業員等の障害物との 接触を防止するため、障害物との距離や建設機械の切削や旋回などの動作に 対応させて危険である場合に警報を行う」との記載は、その前の「この技術 においては、」という主語からみれば、特許文献1に記載された従来技術に ついての説明であり、このような従来技術の構成を【発明を実施するための\n形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、このような構\ 成を前提としなければ【発明を実施するための形態】に記載の構成が成立し\nないという事情もなく、その他【発明を実施するための形態】に記載の構成\nが従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。\nそして、上記記載の本件補正による新たな発明特定事項は、当初明細書にお ける【発明を実施するための形態】に記載されていないことはもちろん、背 景技術に関する【0002】にも記載されていない。よって、本件補正は、新規事項を導入するものであるといえる。
(2) 原告は、前記第3の2(1)のとおり、補正前発明は従来技術が開示している 技術と関連している旨主張するが、仮に、補正前発明が従来技術が開示する 技術と関連性を有するとしても、当初明細書等に、補正前発明に関する構成\nとして、従来技術の構成が開示されているとはいえないことは明らかである\nから、いずれにしても、本件補正は、新規事項を導入するものというべきで ある。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 限定的減縮
>> ピックアップ対象
2023.03.29
令和4(行ウ)382 特許分割出願却下処分取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月23日 東京地方裁判所
法 44 条 1 項柱書きは、特許出願人は、一の特許出願中に二以上の発明が 含まれている場合、その特許出願の一部を新たな出願(分割出願)とするこ とができる旨規定する。ここで、「特許出願人」及び「特許出願」とされて いることに鑑みると、同項の規定は分割出願のもととなる特許出願が特許庁 に係属していることを前提とするものと理解される。他方、同項は、分割出 願の時期的要件につき、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面 について補正をすることができる時又は期間内にするとき」(1 号)や「拒 絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から三月以内にするとき」 (3 号)と定めるほか、「特許をすべき旨の査定…の謄本の送達があった日 から三十日以内にするとき」(2 号)と定めているところ、上記のとおり、 法 44 条 1 項はもととなる特許出願が特許庁に係属していることを前提とす るものと理解されることを踏まえると、特許査定の謄本の送達があった日か ら 30 日以内であっても、特許権の設定登録がされればその特許出願は特許 庁に係属しなくなる以上、これをもとに分割出願をすることはできないと解 される。 本件については、前提事実(1)のとおり、本件特許査定の謄本が原告に送 達されたのは令和 2 年 7 月 7 日であるから、原告は、同日から 30 日以内で ある同年 8 月 日に本件親出願をもとの特許出願とする分割出願(本件出願) をしたといえる。しかし、本件出願に先立つ令和 2 年 7 月 29 日に本件設定 登録がされたことにより、本件親出願は特許庁に係属しないものとなったこ とから、それ以降は本件親出願をもとの特許出願として分割出願をすること はできなくなっていたものである。
したがって、本件出願は、法 44 条 1 項所定の分割可能期間を経過した後\nにされたものであり、同項所定の要件を満たさないものと認められる。 以上のとおり、本件出願は、法 44 条 1 項所定の要件を満たさない不適法 なものであり、その補正をすることができないものといえるから、同法 18 条の 2 第 1 項本文に基づいて本件出願を却下した本件却下処分は適法と認め られる。
(2) 原告の主張について
ア 取消事由 1 について
原告は,法 44 条 1 項の定める分割出願について、特許査定謄本の送達 の日から 30 日以内であっても特許権の設定登録がされた後はすることが できないとの解釈は,明文の規定のない被告による解釈にすぎず,十分な\n合理性を有しないなどと主張する。 しかし,「二以上の発明を包含する特許出願の一部」(法 44 条 1 項柱 書き)のうちの「特許出願」及び「特許出願人」(前同)が、特許庁に係 属している特許出願及び同出願における特許出願人をそれぞれ意味するも のであることは文理上明らかである。 また、法 46 条の 2 第 1 項は実用新案制度に特有の事情を考慮して設け られたものであることなどに鑑みると、同条項の存在は、分割出願の時期 的要件に係る解釈に結び付くものでは必ずしもない。
関連カテゴリー
>> 分割
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2023.03.24
令和4(ネ)10049 不当利得返還、同反訴、損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年3月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
しかしながら、証拠(乙14、15、22、24、25、31、32、 原審証人B)及び弁論の全趣旨によると、1)被告音源データは、爆発音だ けでも約2000種類のものを含み、一審被告取締役Bが音響効果業務で 使用するハードディスクでは作業の効率化のため被告音源データの一部 を厳選して保存しているが、そのハードディスクに保管されている被告音 源データのデータ量でも約194ギガバイト、ファイル数3万1000個 超となるなど、膨大な数の音源データで構成されていると認められ、この\nように多種多様な音で構成されていることからみて、個々の音源の中には\n個性的な特徴を有するものが多数含まれるとうかがわれること、2)被告音 源データは、生音(人の手で音を作り出して収録した音)、シンセサイザー で合成した音等の効果音、環境音等からなるものであるが、シンセサイザ ーで制作される音については優に100を超える設定項目を設定しなけ ればならないこと、生音で制作される音については制作の際の個人差が想 定されること、屋外で録音した音については音の録音をするに適した場所、 環境、時間帯等を探し出して選択し、録音した部分から不要となる部分を 省く編集をしなければならないこと、同種の方法で制作された音同士を、 あるいは、異種の方法で制作された音同士を掛け合わせて融合するなどし て複雑な混成をさせていること、以上のことからして、単に発生している 音を録音するという機械的作業により制作され音が保存されているでは なく、その制作に当たって創造性を発揮させる余地が十分にある音が保存\nされていること、3)上記のような単純とはいい難い作業に基づいて制作さ れるほか、アナログ機材で様々な融合や設定をしてできた音であるのにそ の設定等が不明で、現在どのようにして制作するかも分からない再現不能\nな音源も多いことから、偶然に同一の音が再現される可能性は低く、世上\n耳にすることのある、ありふれた音そのものとは構成が異なること、4)被 告音源データのうち、少なくとも半分は上記のような制作過程によって一 審被告が制作したものであること、5)1音源の長さは、数秒程度のものあ れば、1分以上に及ぶものもあって、制作作業の過程で思想又は感情の表\n現を込め得る程度の長さのものも含むことが認められる。
以上によれば、被告音源データの中の個々の音のみであっても、幅のあ る表現の中から選択され、その表\現に個性の発露を認め得る音も決して少 なくないものと認められ、そのようにして制作された音には創作性を認め る余地があるといえ、一律に効果音の著作物性を否定できるものではない し、著作物性のある音がごくわずかであるともいい得ない。 そして、一審原告は、一審被告在職中に被告音源データを用いて音響効 果業務を行っていたのであるから、被告音源データに含まれる音と同一の 音あるいは類似の音を制作した場合には、明らかに依拠性が認められ、あ るいは容易に依拠性を認め得るのであるから、被告音源データに含まれる いずれかの音と同一の音を利用し、あるいは類似の音を制作して利用した 場合でも、一審被告の被告音源データについて一審原告による少なくとも 複製権又は翻案権の侵害が成立する可能性は否定できないといえる。\n
・・・
4 第1事件反訴に係る本件セッションデータの引渡請求について
一審原告は、一審被告から、本件再委託業務の再委託を受けて同業務 を履行したところ(前提事実(4)イ及びエ)、一審被告は、本件セッション データは本件合意書第14条の「成果物」に該当するとして、本件合意 に基づき一審原告に対して本件セッションデータの一審被告への引渡し を求めている。
(1) 本件合意の内容
本件合意書第14条は、一審原告に対し、一審被告から受託した業 務の「成果物」を特に区分けなく顧客及び一審被告に納入すべき義務 を定めるから(別紙「本件合意書(抜粋)」参照。以下本件合意書の条 項につき同じ。)、一審被告に納入すべき「成果物」は、顧客に納入す べきものと同じものと理解される。また、同第9条は、一審原告が一 審被告から音響効果業務を受託した場合の「成果物」の所有権及び音 源の著作権が一審被告に帰属することを定め、同第8条2項は、再委 託業務の対価には音響効果制作の過程で発生するいわゆる中間生成物 のものも含めて著作権譲渡の対価が含まれると定めるから、一審原告 が「成果物」を一審被告に納入すると、一審原告は、当該「成果物」 の所有権及び音源の著作権を失うものと理解される。
(2) プロツールスセッションデータについて
「プロツールス」は、音編集ソフトであり、作品の映像に合わせて\n音源データを編集して放映用の音源データを制作する手法が用いられ ており、一審原告もプロツールスを用いて一審被告から再委託を受け た業務を行った(前提事実(2)ア)。 証拠(甲12、乙15、22、34、原審証人B)によると、1)「プ ロツールスセッションデータ」とは、音響効果業務の作業の際にプロ ツールスが作成する「セッション」というファイルの中に記録された 音源データを含む各種データのことであり、効果音等が記録された放 映用の音源データや、台詞、音楽等が含まれる放映用の音声データと は別のファイルであること、2)音響効果業務の作業に当たっては、ま ず、映像に合うような音源データを選択し、セッションデータの中に これら音源データをコピーして取り込み、それら音源データの一又は 複数をそのままに、あるいはピッチを変えるなどして、作品の映像と 音との間のタイミング等を調整しながら各音源データを組み込んでい くこと、3)そのため、セッションデータの中には放映用の音源データ の制作に利用した音源データの全てが保存されていること、4)顧客に 納入される台詞、音楽等が含まれる放映用の音声データは、放映用の 音源データを調整しながら、放映用の音源データと台詞、音楽等の音 声データとをダビングしたミックスデータとして納入されること、5) セッションデータには音響効果業務を行う事業者のノウハウが詰まっ ているため、第三者や競業者にその内容が開示されることはないし、 顧客にもセッションデータが納入されることはなく、効果音等のみを 必要とする顧客からの要望については、セッションデータから音源デ ータをまとめて一つのファイルとして出力されるデータが納入される ことが認められる。
(3) 西田弁護士の発言
前記1(3)ウ(本判決第3の2(3)において補正されている。)のとおり、 Aらも立ち会っていた本件面談において、西田弁護士は、一審原告か ら本件再委託業務に関する質問があった際に、一審原告が一審被告に 対して渡さなければいけないものは、「一本化」しているものでよく、 「パーツは渡さなくていい」旨の回答をしており、これは、「一本化」 とは素材となる音源データをまとめあげた放映用の音源データのこと を指し、「パーツ」とは、上記音源データの制作に要した素材となる音 源データのことを指すと理解できるから、結局、本件セッションデー タの引渡しを不要であると回答したものと認められる。 これに対して、西田弁護士は、「パーツで渡さなくてよいと答えてい ます・・・X氏が自身で購入した音源一つ一つを、・・・渡さなくてよ い(権利譲渡しなくてよい)という意味合いです。」、「一本化して渡し てほしい・・・というのは、プロツールスのセッションデータとして 一本化して渡してほしいという意味です」旨を陳述するが(乙28)、 上記のとおりセッションデータはもともと一つであるし、前記(2)のと おり、セッションデータを引き渡せば個々の音源データも引き渡され ることになるから、関係証拠と整合しない陳述であり、採用すること はできない。
(4) 報酬の支払
本件合意書第8条1項は、同第6条2項の音響効果業務の再委託業 務について、一審原告に対する報酬の支払を「成果物」の納品月の末 締め当該締日の3か月後の月の5日限りとして、一審原告の先履行と 定めているところ、一審原告は、本件再委託業務に係る各作品に係る、 台詞、音楽等の音声データとを音源データとをダビングしたミックス データを顧客に納品しており(甲8、弁論の全趣旨)、これに対し、一 審被告は、前提事実(4)エのとおり、本件セッションデータの引渡しを 求めることなく、本件再委託業務に係る報酬を全額支払っている。本 件セッションデータの引渡しは、令和元年12月24日受理の第1事 件反訴状の一審原告に対する送達によって初めて求められた(弁論の 全趣旨、顕著な事実)。
(5) 本件セッションデータの引渡義務
前記(2)のセッションデータの性質を前提とする限り、セッションデ ータそれ自体は放映に用いる音源データではなく、顧客に納品される ものではない。そして、本件合意は一審原告が一審被告を退職した後 の法律関係を規律するものであるところ、前記(1)の本件合意の内容や 本件合意書第14条の「成果物」の解釈を前提とした場合、本件セッ ションデータも同「成果物」に含まれるとすると、一審原告は、本件 再委託業務の履行に際して利用した素材である各音源データについて、 たとえそれが自らの負担において新たに取得したものであっても、そ の権利一切を喪失することになり、その後自らこれらを利用すること ができなくなって業務遂行が困難となり、極めて不合理な結論に至る し、一般的な取引慣行にもそぐわないことになる。また、本件面談時 や本件再委託業務の履行過程における一審被告の言動も、本件セッシ ョンデータが本件合意書14条の「成果物」には該当しないことを前 提とするものと理解するのが自然かつ相当である。
以上によれば、本件合意書を合理的に理解しようとする限り、本件 合意によって本件セッションデータの引渡義務を根拠付けることはで きないというべきである。なお、一審被告は、一審原告が一審被告を退職する前に担当したものも含めて、過去に音響効果業務を受注して制作した作品のセッショ ンデータを保存、管理しているが(乙22、原審証人B)、それは自ら が制作したセッションデータを自らが保有していることを意味するに すぎない。一審原告は独立した事業者の立場においてセッションデー タを制作する者であってそのセッションデータを保有する者であるか ら、一審被告が過去に制作した作品のセッションデータを保存、管理 していることは、一審被告に対する一審原告の本件セッションデータ の引渡義務を何ら基礎付けない。
2023.03.24
令和4(ネ)10087 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 業界における実施料等の相場について
ア 一審原告は、前記第2の4(4)ア aのとおり、原判決が、甲55報告書 の例外的事象における実施料率を理由に、電気等の分野の実施料率の平均 値を採用しなかったのは不当である旨主張する。 しかし、原判決は、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となると いう甲55報告書の指摘に着目して、電気等の分野の実施料率の平均値を 採用しないとしたのであり、その判断は首肯できるものである。 イ 一審原告は、前記第2の4(4)ア bのとおり、乙13陳述書における実 施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙13陳述書は、具体 的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示したものと 理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を吟味する必要 があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や分割出願制度等を 利用した出願を全てまとめて1パテントファミリーとして、パテントファ ミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、1件当たりのライセンス 料率が過少にならない工夫をしていること等に鑑みると、その信用性が否 定されるべきものとはいえない上、そもそも原判決は、乙13陳述書にお ける料率をそのまま採用しているのではなく、その他の各種事情を総合勘 案した上で、料率を決定しているのであるから、一審原告の主張は採用で きない。
(2) 代替品の不存在について
一審原告は、前記第2の4(4)ア のとおり、本件訂正発明によらずに、 本件訂正発明の効果を奏することは経済的に現実的ではなかった旨主張す る。 しかし、これを的確に裏付けるに足りる証拠はないし、その他の各種事 情を総合考慮すると、そもそもこの点のみをもって本件結論が左右すると はいい難いから、一審原告の上記主張は採用できない。
・・・
一審被告は、「本来解像度」の用語の意義について、本件明細書等【00 32】に「「本来解像度」とは「本来画像」の解像度をする。」と定義され ているので、「本来画像」の意義が問題となるところ、「本来画像」の用語 の意義、内容は不明確であるから、本件特許明細書には、構成要件G’にお\nける「本来解像度」の意義を理解するための記載がなく、サポート要件に反 する旨、当審において新たに主張するが、本件明細書等の「本来画像」及び 「本来解像度」に関する関係記載(【0006】、【0032】、【007 9】、【0115】、【0118】、【0119】、【0124】ないし 【0126】、【0128】ないし【0130】等)を総合すれば、当業者 は、「本来画像」及び「本来解像度」が何を意味するかにつき十分に理解で\nきるというべきであるから、本件訂正発明は本件明細書等の発明の詳細な説 明に記載したものといえる。 その他にも、両当事者はるる主張するが、いずれも本件結論を左右し得な い。
第4 結論
以上によれば、一審原告の請求は、主位的請求である不法行為に基づく損害 賠償請求権に基づき819万9458円及びこれに対する令和元年12月13 日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を 求める限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由\nがないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及 び一審被告の控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとお り判決する。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和1(ワ)32239
関連審決取消訴訟事件です。
◆平成28(行ケ)10257
同一特許についての別侵害訴訟の控訴審と1審です
◆令和2(ワ)29604
この事件では、知財高裁は、損害額の算定について以下のように言及されています。
一審原告は、前記第2の3(4)ア aのとおり、甲26報告書の79頁
は、デバイスに関して、クロスライセンスの方式による場合において、
実施料率の相場が1%未満すなわち0.数%であることを示すにすぎ
ないから、原判決のこの点に係る認定には誤りがある旨主張する。
しかし、甲26報告書の79頁によれば、デバイス等においては、製
品が数百ないし数千の要素技術で成り立っていること、互いの代表特\n許をライセンスし合い、実施料率の相場は1%未満であることといっ
た一般的な事情が認められところ、これに加えて、引用に係る原判決
第4の11(3)イ 及び のとおり、一審被告が被告製品の製造販売の
ためにした複数のライセンス契約におけるアプリ特許(標準必須特許
以外の特許)に係るパテントファミリー1件当たりのライセンス料率
は平均●●●●●●●%であり、これを画像処理に関連する発明に限
定すると1件当たりのライセンス料率は、平均●●●●●●●●%と
なること等、本件特有の事情も考慮すれば、原判決の相当実施料率の
認定に誤りがあるとはいえない。
一審原告は、前記第2の3(4)ア bのとおり、ライセンス料は、主
として「代表特許」の価値によって決まるので、乙14陳述書の計算\nにおける標準必須特許を除く「全ての特許の件数で除した1件当たり
のライセンス料率」は不当にディスカウントされたものである旨主張
する。
しかし、乙14陳述書は、代表特許(甲26の79頁にいう「相互\nの代表的な特許」)ではなく、標準必須特許(携帯電話事業分野の標\n準規格の実施に不可欠な特許)と、アプリ特許(通信規格に適合する
ために不可欠とはいえない特許)を分けて扱っているのであり、それ
自体は合理的なことであって、このような方式を採ることが不当なデ
ィスカウントに当たるともいえないから、一審原告の主張は採用でき
ない。
一審原告は、前記第2の3(4)ア cのとおり、乙14陳述書におけ
る実施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。
しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙14陳述書は、
具体的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示し
たものと理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を
吟味する必要があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や
分割出願制度等を利用した出願を全てまとめて1パテントファミリー
として、パテントファミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、
1件当たりのライセンス料率が過少にならない工夫をしていること等
に鑑みると、その信用性が否定されるべきものとはいえない上、そも
そも原判決は、乙14陳述書における料率をそのまま採用しているの
ではなく、その他の各種事情を総合勘案した上で、料率を決定してい
るのであるから、一審原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.03.24
令和3(ワ)11152 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年3月16日 大阪地方裁判所
ア 競争関係の有無(争点1−ア)
(ア) 前記前提事実(1)及び認定事実(1)によれば、原告と被告会社は、いずれも ウェブサイトの作成(企画・開発)、運営及び保守業務、並びにインターネット上 の検索エンジンの最適化サービス(SEO対策)等の同種の事業を行っている。し たがって、両社は営業活動上需要者や取引先を共通にする可能性があるといえるこ\nとから、競争関係にあると認められる。また、被告P1は、被告会社の代表取締役\nであるから、その職務に関して原告と競争関係にあるといえる。
(イ) 被告らは、原告の事業と被告会社の事業が全く異なり競争関係に立たない 旨主張する。しかし、不競法2条1項21号における競争関係は、需要者又は供給 者を共通にする可能性があるなど、将来現実化し得る潜在的な競争関係であれば足\nりると解されるところ、前記(ア)のとおり、被告会社の登記事項証明書及びウェブ サイトに記載された被告会社の事業内容(甲5)と原告の事業内容とが重複してい ることから、当該主張は採用できない。
イ 摘示事実の虚偽性(争点1−イ)
(ア) 本件投稿1の内容は、「アイメシア 特定商取引法に関する知識はなく、 コンプライアンス担当者はおらず…何度も何度も電話してくる…さらに電話の人間 は嘘丸出し営業トーク」と記載し、原告について、特商法に関する知識がなく、コ ンプライアンス担当者がおらず、営業対象先に対し何度も電話をかけ、電話をした 従業員が事実に反した話をするという事実を指摘するものである。当該記載を閲覧 した本件ページの閲覧者は、原告が、法令を遵守せず営業対象先に何度も電話をか け、かつ営業担当者が事実に反する話をする営業活動を行う会社であると読み取る ものといえる。
被告P1による令和3年1月14日の投稿、本件各投稿及び本件書面等の各内容 等(前記前提事実(2)(3)及び認定事実(3)(4))を踏まえると、原告が、営業対象先 に係るインターネット上の口コミサイトの記事を印刷し、SEO対策の重要性や原 告の業務を紹介する文書と共に営業対象先に送付し、同じ頃に営業対象先に電話を した上で当該文書等に言及して原告への依頼を促す等の営業活動を行っていること、 被告会社に対し、同月及び7月に営業目的で2回電話をし、本件書面等を送付した ことが認められるものの、原告が法令を遵守せずに営業の電話をし、また原告の従 業員が事実に反する話をして営業活動を行ったとはいえず、本件投稿1の前記記載 は事実に反するといえることから、その虚偽性が認められる。
(イ) 本件投稿2の内容は、「自分でネットに企業の誹謗中傷を書いて、それをネ タにネットの誹謗中傷対策しますというマッチポンプ詐欺の会社」と記載し、原告\nについて、営業対象先を誹謗中傷する内容の記事を予めインターネット上に書き込\nむ等した上で、当該企業に対し、当該書き込みを契機としてその対策業務を行う原 告への依頼を促す旨の営業活動を行っているという事実を指摘するものである。当 該記載を閲覧した本件ページの閲覧者は、原告がこのような詐欺的な営業活動を行\nう会社であると読み取るものといえる。 しかし、本件証拠に照らし、原告が、自ら営業対象先を誹謗中傷する書き込み等 をし、その対策等を理由に営業活動を行ったとはいえず、本件投稿2の前記記載は 事実に反するといえるから、その虚偽性が認められる。
(ウ) 本件投稿3の内容は、「自前で悪評判を立てた上で対策しますという…営 業を行う詐欺会社」と記載し、原告について、自ら相手方の悪評判を立てた上で、\n当該評判を契機としてその対策業務を行う原告への依頼を促す旨の営業活動を行う という事実を指摘するものであり、本件投稿2と同様に当該記載は事実に反する。
(エ) したがって、本件各投稿に記載された事実は、いずれも事実に反し虚偽で あると認められる。
(オ) 被告らの主張について
被告らは、被告P1が本件各投稿をした目的は、原告の営業が悪質であることか ら、原告に警告を発したり、他の業者が原告の営業に引っかからないようにするた めであるなどと主張する。 しかし、本件資料に係る口コミサイトの記載について、書き込みの時期(平成2 8年及び平成29年)と、原告の被告会社に対する架電の時期(令和3年1月及び 7月)が相当程度離れていること(前記認定事実(3)(4)及び(6)ウ)等を踏まえる と、原告が営業手段として自ら当該口コミサイトの記載を行ったとは認められない。 前記(ア)の原告の営業手法及び被告会社に対する営業行為を前提としても、本件各 投稿の前記内容が全体として事実に反することに変わりはなく、被告らが主張する 目的により本件各投稿行為が正当化されるものではない。このことは、被告会社が そのウェブサイトにおいて営業目的の電話を固く断り、迷惑であると判断した場合 には本件サイト等にその旨を登録すること等を記載していた(前記認定事実(6) ア)としても、同様である。
・・・
(3) 損害の発生及びその額(争点3)
ア 無形損害
前記2(1)イのとおり、本件各投稿は、原告が法令を遵守せず営業対象先に架電 し、かつ営業担当者が事実に反する話をする営業活動を行う会社であるとの印象や、 営業対象先を誹謗中傷する内容の記事を予めインターネット上に書き込む等した上\nで、当該企業に対し、当該書き込みを契機としてその対策業務を行う原告への依頼 を促す旨の営業活動を行う会社であるとの印象を与えるものであり、原告の社会的 評価が一定程度低下したと認められること、本件各投稿が、一定数の不特定多数の 者に閲覧されたと推認されること、一方で、本件各投稿が掲載された期間は令和3 年7月2日又は3日から同年8月7日までの一か月余りであり比較的短期間である といえること、本件サイトの口コミの投稿は、氏名やメールアドレスの記載が任意 とされ、投稿者が特定されない形で書き込むことが可能であることから、本件サイ\nトの口コミ掲示板に記載された情報に接した閲覧者が当該情報について信頼性が高 い情報として受け取るとまではいえないこと等を考慮すると、被告P1の本件各投 稿行為による原告の無形損害は50万円と認めるのが相当である。 なお、本件ページにおいて、被告P1による投稿以外の投稿がされたことが認め られないことは前記認定事実(4)ウのとおりである。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2023.03.24
令和4(ネ)10100 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年3月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記第1のとおり、控訴人は、本件ログインがされた日時である令和3年 6月26日7時47分54秒(時刻の表記は、24時間制による。以下同じ。また、\n令和3年中の日付については、以下、年の記載を省略する。)頃に被控訴人から本 件IPアドレス(省略)が割り当てられていた契約者に係る発信者情報(本件発信 者情報)の開示を求めているところ、前記前提事実(補正して引用する原判決第2 の1(2))のとおり、本件ツイートが投稿されたのは、同月20日20時39分で あるから、本件ツイートは、上記のとおり控訴人が発信者情報の開示を求める本件 ログインがされた時期にされたものではなく、本件発信者情報は、本件ツイートの 投稿時に利用されたログインに係る発信者情報ではない。そこで、侵害情報である 本件ツイートの投稿時に利用されたログイン以外のログインに係るIPアドレスか ら把握される発信者情報が法4条1項にいう「当該権利の侵害に係る発信者情報」 に該当するかが問題となる。
(2) そこで検討するに、法4条の趣旨は、特定電気通信(法2条1号)による 情報の流通には、これにより他人の権利の侵害が容易に行われ、その高度の伝ぱ性 ゆえに被害が際限なく拡大し、匿名で情報の発信がされた場合には加害者の特定す らできず被害回復も困難になるという、他の情報流通手段とは異なる特徴があるこ とを踏まえ、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が、情 報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で、\n当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供 者に対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより、加害 者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解される(最高裁平\n成21年(受)第1049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号6 76頁参照)。そうすると、「当該権利の侵害に係る発信者情報」の範囲をむやみ に拡大することは相当とはいえないものの、これを侵害情報の投稿時に利用された ログインに係るIPアドレスから把握される発信者情報に限定するとなると、複数 のログインが同時にされているなどして投稿時に利用されたログインが特定できな い場合などには、被害者の権利の救済を図ることができないこととなり、上記の法 の趣旨に反する結果となる。そして、法4条1項の文言は、「侵害情報の発信者情 報」などではなく、「当該権利の侵害に係る発信者情報」とやや幅をもたせたもの とされていること、証拠(甲33、38)及び弁論の全趣旨によると、令和3年法 律第27号(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示 に関する法律の一部を改正する法律)による改正は、法4条1項の「当該権利の侵 害に係る発信者情報」に侵害情報を送信した後に割り当てられたIPアドレスから 把握される発信者情報が含まれ得ることを前提として行われたものと認められ、上 記の改正の前後を通じ、「当該権利の侵害に係る発信者情報」は、侵害情報を送信 した際のログインに係る発信者情報のみに限定されるものではないと解されること、 また、このように解したとしても、当該発信者が侵害情報を流通させた者と同一人 物であると認められるのであれば、発信者情報の開示により、侵害情報を流通させ た者の発信者情報が開示されることになるのであるから、開示請求者にとって開示 を受ける理由があるということができる一方、発信者にとって不当であるとはいえ ないことなどに照らすと、「当該権利の侵害に係る発信者情報」を侵害情報の投稿 時に利用されたログインに係るIPアドレスから把握される発信者情報に限定して 解釈するのは相当でなく、それが当該侵害情報を送信した者の発信者情報であると 認められる限り、当該侵害情報を送信した後のログインに係るIPアドレスから把 握される発信者情報や、当該侵害情報の送信の直前のログインよりも前のログイン に係るIPアドレスから把握される発信者情報も、法4条1項の「当該権利の侵害 に係る発信者情報」に該当すると解するのが相当である。
(3) これを本件についてみるに、本件アカウントのプロフィール欄(アカウン ト名の下部に表示される自己紹介の文章部分。甲11)には、「感謝するぜ、お前\nと出会えたこれまでの全てに」、「俺の手持ち」、「誕生日:1月8日」などの記 載があり、また、本件アカウントにおいてされた投稿(甲11)の内容は、単にY ouTubeの動画を引用するもののほか、「泣いてる」、「俺のグラグラの能力\nが発現してモーター」、「愛知県に地震きた」、「エドモンド本田美央」、「エド モンド本田たのし〜」、「スーパー頭突きじゃあ!!笑笑」、「ガチンコでごわ す!!笑笑」、「本田やばい」、「アイシールド21は神龍寺戦までね」、「やま ゆり園真実の名言集 ライフラインはいるだけで士気が下がる」、「これ使うなら 5cで良くね?」などといったものであり、上記プロフィール欄の記載内容や上記 投稿内容に照らすと、本件アカウントが複数の者によって管理されていたことはう かがわれず、むしろ、本件アカウントは、1名の個人によって管理されていたもの と推認するのが相当である。また、証拠(甲23、33)及び弁論の全趣旨による と、ツイッターは、いわゆるログイン型サービスであり、ツイートの投稿を行おう とする者は、アカウント名及びパスワード(8文字以上)を入力してログインをし なければならないものと認められるところ、通常、アカウント名やパスワードを第 三者と共有するという事態は余り考えられない。さらに、証拠(甲5、26、27、 35)及び弁論の全趣旨によると、本件アカウントについては、6月26日から9 月21日までの間、合計467回のログインがされているところ、そのうち本件I Pアドレスからは、毎日のようにログインがされており、ログインの回数(合計1 47回)においても、他の各IPアドレスからのログインの回数(例えば、被控訴 人が携帯電話回線に割り当てた各IPアドレスのうち本件アカウントへのログイン に使用された回数が最も多かったのは、「IPアドレス省略」及び「IPアドレス 省略」の各10回にとどまる。)を圧倒していたものと認められるから、本件IP アドレスは、本件アカウントへのログインに使用される最も主要なIPアドレスで あったと評価することができる。以上に加え、本件ログインが本件ツイートの投稿 の約5日半後にされたものであることも併せ考慮すると、本件発信者情報は、本件 ツイートの投稿の後のログインに係るIPアドレスから把握される発信者情報では あるが、本件ツイートを投稿した本件発信者の発信者情報であると認められ、した がって、法4条1項にいう「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると認め るのが相当である。
(4)ア この点に関し、被控訴人は、本件IPアドレスは固定回線に割り当てら れたものであるのに対し、本件ツイートはiPhoneにより投稿されたものであ るところ、本件アカウントへのログインに際しては固定回線に割り当てられたIP アドレスと携帯電話回線に割り当てられたIPアドレスとが別々に使用されている から、本件IPアドレスに係る契約者と本件ツイートの投稿の際に使用されたIP アドレスに係る契約者とは異なると主張する。
確かに、証拠(甲1、27、36)及び弁論の全趣旨によると、本件IPアドレ スは、固定回線に割り当てられたものであるのに対し、本件ツイートには、「Tw itter for iPhone」との表示がされ、本件ツイートは、iPho\nne向けのアプリケーションである「Twitter for iOS」を利用し てされたものであると認められる。しかしながら、証拠(甲36)及び弁論の全趣 旨によると、携帯電話を用いてツイッターのアカウントにツイートを投稿する場合、 当該携帯電話が5G回線等の携帯電話回線に接続されているとき又は固定回線を利 用した自宅等のWi−Fiに接続されているときのいずれであっても、当該ツイー トには「Twitter for iPhone」との表示がされるものと認めら\nれるから、本件IPアドレスが固定回線に割り当てられたものであるのに対し、本 件ツイートに「Twitter for iPhone」との表示がされていると\nの事実は、本件IPアドレスから把握される発信者情報(本件発信者情報)が本件 ツイートを投稿した本件発信者の発信者情報であると認められるとの前記結論を左 右するものではない。 なお、証拠(甲28、29)及び弁論の全趣旨によると、携帯電話を用いてイン ターネットに接続する場合、携帯電話回線を利用するときには携帯電話回線に割り 当てられたIPアドレスが使用され、自宅等におけるWi−Fi接続によるときに は固定回線に割り当てられたIPアドレスが使用されるものと認められるから、証 拠(甲5、26、35)によって認められる本件アカウントへのログインの状況に よっても、本件アカウントへのログインに関し、固定回線に割り当てられたIPア ドレス(本件IPアドレス)と携帯電話回線に割り当てられたIPアドレス(「省 略」等)とが別人によって使用されていたものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.03.24
令和4(ネ)10091 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和5年3月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人の本件各商標権に基づく各請求が権利の濫用に当たるか否かにつ いて、前記1の認定事実に基づいて検討する。
イ 被控訴人は、E及び同人の子らによって運営されていた山田石材店に係 る個人事業を法人化するために、Eの子ら全員が出資して設立された法人 であり、その後50年以上にわたって継続的に、多磨霊園正門の近隣に所 在する店舗において、墓石の販売等の事業を行ってきた。また、この間、 被控訴人は、法人化する以前と同様に、「丸忠」とも表記され得る漢字の「忠」\nを丸で囲んだ標章や「山田石材店」及び「つなぎ館」の標章等、各被告標 章と同様の標章を、被控訴人及びその事業を表示するものとして使用して\nきた。 これらの事情によれば、各被告標章には、多磨霊園正門の近隣における 墓石の販売等の事業に関する被控訴人の信用が化体しているものといえ る。
ウ 被控訴人は、控訴人代表者(A)の父であるC、被控訴人代表\者(B) の父であるF及びGの3名が設立時の代表取締役となるなど、いわゆる親\n族経営の法人であるといえる。また、控訴人及び被控訴人の各店舗は近隣 に所在する上、控訴人は、平成17年7月頃から被控訴人と同様に墓石等 の販売の事業を行うようになった。 これらの事情によれば、控訴人及び被控訴人は、山田石材店の事業に関 して密接な関係にあるというべきである。
エ 上記ウで挙げた事情を考慮すると、控訴人は、上記イのとおりの被控訴 人の事業内容及び標章の使用状況等を当然に知っていたものといえる。他 方で、控訴人は、平成18年に本件商標2及び3の登録出願をするなどし た後も、被控訴人による各被告標章と同様の標章の使用について、被控訴 人に対して本件各商標権を侵害する行為である旨の指摘をしたことはな く、AがBに対して平成31年1月に乙7の書面を送付した際に初めてそ のような指摘をしたものである上、BがE名義の土地に係る遺産分割協議 への協力を拒んだ後間もなく、被告商標1に係る商標登録無効審判を請求 し、また、本件訴えを提起したものである。
これらの事情を考慮すると、控訴人は、被控訴人が各被告標章と同様の 標章を長年にわたって使用してきたことを知りながら、これを殊更に問題 視することなく互いの事業を行ってきたにもかかわらず、本件各商標権の 登録出願がされてから10年以上が経過した後になって、E名義の土地に 係る遺産分割協議という本件各商標権とは何ら関係のない事柄をきっか けとして、被控訴人に対し、本件各商標権に基づく権利行使に及んだもの とみるのが相当である。
オ 以上のとおりの被控訴人による各被告標章の使用状況、控訴人及び被控 訴人の関係、控訴人が権利行使をするに至った経緯等を総合して考慮する と、控訴人の被控訴人に対する本件各商標権に基づく権利行使は、権利の 濫用として許されないというべきである。
◆判決本文
1審はこちらです。
2023.03.24
令和4(行ケ)10030 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月9日 知的財産高等裁判所
訂正事項2は、請求項1を引用する請求項4を新たな独立項である請求 項15とし、かつ、「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、 その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く。)」との 事項を追加するものである。
訂正前の請求項1においては、「積層体」について、「少なくとも2層を 有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積 層体には、「第1の層」、「第2の層」及びその他の任意の層からなる積層 体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に 設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任 意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項1における積層 体は、「第1の層」、「第2の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸 着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体(以下「積層体 A」という。)を含んでいたものである。
そうすると、訂正事項2は、「積層体A」を含む訂正前の請求項1におけ る積層体から積層体Aを除くものといえ、このように積層体を特定したこ とにより、訂正前の請求項4に係る発明の技術的発明が狭まることになる のであるから、訂正事項2が特許法120条の5第2項ただし書1号に規 定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。
イ 被告は、前記第3の1(2)ア のとおり、訂正事項2は、「積層体」から、 「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」 内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当す\nる「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにそ の上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となってい るから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件 発明は、「第1の層」及び「第2の層」で完結した積層体を特定事項とする ものではなく、特許を受けようとする発明を、「第1の層」及び「第2の層」 を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するもので あるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体\nの内外を形式的に区別しても意味がない(「第1の層」及び「第2の層」の 外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。)。そして、\n前記アのとおり、訂正事項2における「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜 が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」 の具体的な内容は、「第1の層」、「第2の層」並びに「無機酸化物の蒸着 膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」を備えた積層体であ るから、結局、積層体Aと区別できないものである。したがって、訂正事項 2は訂正前の積層体から積層体Aを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減 縮していることになる。
また、被告は、本件訂正事項2のような「除くクレーム」とする訂正は、 第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利\n益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告 主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、 明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題という べきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ち に訂正を認めない理由とすることは相当でない。
ウ 以上のとおりであるから、訂正事項2が特許請求の範囲の減縮を目的と するものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。 また、訂正事項3ないし9が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに 当たらないとした本件取消決定の判断にも誤りがある。
(2) 新規事項の追加の有無について
ア 仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加 の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項2は、新規 事項を追加するものとは認められない。 すなわち、訂正が、当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項 を導入しないものであるときは,当該訂正は,「明細書又は図面に記載した 事項の範囲内において」するものと解すべきところ、訂正事項2によって 「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリ ア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的 事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。 本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニ ュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を 提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された 積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積 層体を提供すること(【0008】)であるが、上記除外によってこの技術 的課題に何らかの影響が及ぶものではない。
イ 被告は、前記第3の1(2)ア のとおり、訂正事項2は、本件発明の課題 に、引用文献の課題解決手段である「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が 設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を追加することで新たな 技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするので あるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。 しかし、訂正事項2による除外がされて残った技術的事項には、本件訂 正前と比較して何ら新しい技術的要素はないから、被告の主張は採用でき ない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2023.03.24
令和4(ネ)10103 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年3月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(3) 原告文章2について
ア 原告文章2は、将棋の駒の準備や片付けに関して説明するものであるところ、 その記載内容は、いずれも将棋のルール又はマナーであって(乙19〜24、27、 弁論の全趣旨)、当該内容自体から創作性を認めることはできない。 もっとも、「「雑用は喜んで!」とばかりに下位者が手を出さないようにしまし ょう。」という部分については、控訴人自身の経験に基づき、初心者等が陥りがち な誤りを指摘するため、広く一般に目下の者が「雑用」を率先して行うに当たって の心構えを示したものといい得る表\現を選択し、これを簡潔な形で用いた上で、し かし、逆に、将棋の駒の準備や片付けに関してはこれが当てはまらないことを述べ ることで、将棋の初心者にも分かりやすく、かつ、印象に残りやすい形で伝えるも のといえる。この点、本件番組の制作時に参考にした書籍やウェブサイトである被 控訴人が当審において提出した証拠(乙15〜37。以下「当審提出証拠」という。) のうち駒の準備や片付けについて記載されたもの(乙20〜24、27)にも、類 似の表現は見受けられない。したがって、上記部分は、特徴的な言い回しとして、\n控訴人の個性が表現として現れた創作性のあるものということができ、著作物性を\n有するというべきである。これに対し、原告文章2のうちその他の部分における表\n現は、ありふれたものといえ、控訴人の何らかの個性が表現として現れているもの\nとは認められない。
そして、本件ナレーション等のうち原告文章2に対応する部分においては、正に 上記のとおり創作性のある部分が、感嘆符の有無と「下位者が」を「下位の者は」 と変更する点を除くと一言一句そのままの形で使用されている。 したがって、被控訴人は、原告文章2のうち創作性のある部分について、控訴人 の許諾を得ることなく、また、その著作者名を表示することもなく、これを含む本\n件ナレーション等を本件番組で放送したことにより、控訴人の著作権(公衆送信権) 及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したものと認められる。\nイ 被控訴人は、「雑用は喜んで!」という表現は、一般社会においても一般的\nに用いられるありふれたものであるなどと主張するが、駒の準備や片付けは上位者 が行うという将棋のルールを踏まえると、それらは将棋の対局において「雑用」と はいえないものである。そのようなものについて、あえて「雑用は喜んで!」との 表現を用いた上で、かつ、逆説的に説明するという特徴的な言い回しをしたという\n点に、控訴人の個性が現れているということができる。前記アの認定判断に反する 被控訴人の主張は採用できない。
・・・
原告文章5は、将棋の「待った」について説明するものであるところ、その 記載内容は、いずれも将棋のルール又はマナーであって(乙19、21、24、2 6、31〜32、34〜37、弁論の全趣旨)、当該内容自体から創作性を認める ことはできない。 もっとも、「着手した後に「あっ、間違えた!」「ちょっと待てよ・・・」など と思っても、勝手に駒を戻してはいけません。」という部分については、将棋を指 す者が抱き得る感情を分かりやすく簡潔に表現することで、将棋の初心者にも印象\nに残りやすい形で伝えるものといえる。この点、当審提出証拠のうち「待った」に ついて記載されたもの(乙19、21、24、26、32、34〜37)の中に、 類似の表現はほとんど見受けられず、唯一、「仮に駒から手を離した瞬間に「あ、\n間違っている」と気づいたとしても」という類似の表現が用いられているもの(乙\n32)はあるが、原告文章5は、控訴人自身の経験に基づき、感嘆符等の記号を用 いるほか、「あっ、間違えた!」という語と「ちょっと待てよ・・・」という語を 続けてたたみかけることで、将棋を指す者が抱き得る感情とルール又はマナーとし ての将棋の「待った」をより生き生きと分かりやすく、かつ、印象深く表現するも\nのといえる。したがって、上記部分は、控訴人の個性が表現として現れた創作性の\nあるものということができ、著作物性を有するというべきである。これに対し、原 告文章5のうちその他の部分における表現は、ありふれたものといえ、控訴人の何\nらかの個性が表現として現れているものとは認められない。\nそして、本件ナレーション等のうち原告文章5に対応する部分においては、正に 上記のとおり創作性のある部分が、感嘆符及び「・・・」の有無等の点を除き、ほ ぼそのままの形で使用されている。 したがって、被控訴人は、原告文章5のうち創作性のある部分について、控訴人 の許諾を得ることなく、また、その著作者名を表示することもなく、これを含む本\n件ナレーション等を本件番組で放送したことにより、控訴人の著作権(公衆送信権) 及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したものと認められる。\n
2023.03.24
令和4(行ケ)10037 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年2月7日 知的財産高等裁判所
前記aないしdの各記載によると、本件出願日当時、被服の技術分野におい ては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐 状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の 課題が存在したものと認められる(なお、前記1(1)のとおり、本件明細書にも、 本件出願日当時に存在した課題として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるよ うにすることは非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調 整することができないとの記載がみられるところである。)。 そうすると、被服の技術分野に属する本件公然実施発明の構成(「前記空調服の\n服地の内表面であって前記襟又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1と」、\n「前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟又はその周辺の第二 の位置に取り付けられた紐2とを備え」、「2本の紐(1、2)を結ぶことによっ て、空気排出量を調節することができる」との構成)自体からみて、また、甲41\nに「首と襟足の間隔を広くし」との記載(前記(1)イ(イ))及び紐が首の後ろにあ る旨の図示(同)があることからすると、本件公然実施発明に接した本件出願日当 時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である。
(イ) 甲30発明’が解決する課題
前記(3)アの記載のとおり、甲30発明’は、「帯紐6a」に「ボタン7a」を、 「帯紐6b」に複数の「ボタン7b」をそれぞれ設け、「ボタン7a」を複数ある 「ボタン7b」のいずれか一つにはめ込むとの構成を採用することにより、「帯紐\n6a」及び「帯紐6b」の装着長さを調整し、もって、個人差のある腰回りの大き さに応じて介護用パンツ1を装着することを可能にするというものであるところ、\n甲30に装着の容易さについての記載(段落【0008】、【0009】、【00 11】)があることや、前記(ア)eのとおりの周知かつ自明の課題が本件出願日当 時に被服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件出願日当時 の当業者は、甲30発明’につき、これを2つの紐状部材を結んでつないで長さを 調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手段として認識するものと 認めるのが相当である。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)のとおりであるから、本件公然実施発明から認識される 課題と甲30発明’が解決する課題は、共通すると認めるのが相当である。
(エ)a この点に関し、被告は、本件公然実施発明の課題は空気排出口の開口部 を形成することであり、甲30に記載された技術事項とは異質のものであり、かつ、 異なると主張する。
しかしながら、前記(1)ア及びイの各記載のとおり、本件公然実施発明は、空調 服の服地の内表面であって襟又はその周辺の第一の位置に取り付けられた「紐1」\nと、「紐1」が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟又はその周辺の第 二の位置に取り付けられた「紐2」とを備え、「紐1」及び「紐2」を結ぶことに よって、首と襟足との間に形成される空気排出スペースの大きさを調整するもので あるところ、前記(ア)eのとおりの周知かつ自明の課題が本件出願日当時に被服の 技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件公然実施発明に接した 本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段であ る「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で容易ではな いことが本件公然実施発明の課題であると認識するのに対し、前記(イ)のとおり、 本件出願日当時の当業者は、甲30発明’につき、これを2つの紐状部材を結んで つないで長さを調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手段として 認識するものと認められるから、本件公然実施発明から認識される課題と甲30発 明’が解決する課題は、共通すると認めるのが相当である。本件公然実施発明が空 調服の首回りの空気排出スペースの大きさを調整するものであるのに対し、甲30 発明’が介護用パンツの腰回りの大きさを調整するものであること、すなわち、両 者が何を調整するのかにおいて異なることは、課題の共通性に係る上記結論を左右 するものではない(両者は、紐状の部材の締結により被服が形成する空間の大きさ を調整するとの目的ないし効果において異なるものではない。)。 したがって、被告の上記主張を採用することはできない。
b 被告は、本件発明3の課題は斬新であり、これは本件公然実施発明の課題と 甲30に記載された技術事項の課題との共通性を否定する事情となると主張する。 しかしながら、仮に、本件発明3の課題が斬新であったとしても、そのことによ り、本件公然実施発明から認識される課題や甲30発明’が解決する課題に影響を 及ぼすものではないから、被告の上記主張を採用することはできない。
ウ 本件公然実施発明に甲30発明’を適用することについての動機付けの有無
(ア) 前記ア及びイのとおりであるから、被服の技術分野に属する本件公然実施 発明に接した本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するた めの手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間 で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するため、同じ被服の技術分野に 属する甲30発明’を採用するよう動機付けられたものと認めるのが相当である。
(イ) この点に関し、被告は、本件出願日当時に空調服の空気排出口の開口度を 調整できるとの技術常識は存在しなかったから、本件公然実施発明に甲30に記載 された技術事項を組み合わせることはできなかったと主張し、その根拠として、本 件明細書の段落【0006】の記載を挙げる。 しかしながら、前記1(1)のとおり、本件明細書の段落【0006】には、一組 の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しく、ほとんどの着 用者は空気排出口の開口度を適正に調整することができなかったことなどが記載さ れているにすぎず、この記載から、本件出願日当時に空調服の空気排出口の開口度 を調整することはおよそできないとの技術常識が存在したものと認めることはでき ない。その他、本件出願日当時に空調服の空気排出口の開口度を調整することはお よそできないとの技術常識が存在したものと認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2023.03.24
令和3(行ケ)10094 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年1月26日 知的財産高等裁判所
これらの開示事項を踏まえると、本件明細書の発明の詳細な説明には、 31H4抗体と競合するものであり、かつ、PCSK9とLDLRタン パク質の結合を中和する抗体として、31H4抗体とアミノ酸配列が異 なる互いにアミノ酸配列の同一性が高いグループの抗体が開示されてい ることが認められる。
ア 以上を前提に検討すると、前記 において説示したとおり、サポート要 件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載 とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記 載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示 唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決で きると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ ると解するのが相当であるところ、前記1 において示したとおり、本件 発明は、LDLRタンパク質の量を増加させることにより、対象中のLD Lの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を 奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレ ステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを\n低減すること、そのために、LDLRタンパク質と結合することにより、 対象中のLDLRタンパク質の量を減少させ、LDLの量を増加させるP CSK9とLDLRタンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医 薬組成物を提供することを課題とするものであり、PCSK9とLDLR タンパク質との結合を強く遮断する中和抗体である参照抗体と競合する抗 体は、PCSK9への参照抗体の結合を妨げ、又は阻害する単離されたモ ノクローナル抗体であることを明らかにするものであると理解される。
そして、前記 によれば、本件発明における「中和」とは、タンパク質 結合部位を直接封鎖してPCSK9とLDLRタンパク質の間の相互作 用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節する以外に、間接的な手段(リ ガンド中の構造的又はエネルギー変化等)を通じてLDLRタンパク質に\n対するPCSK9の結合能を変化させる態様を含むものであるが、前記1\nのとおり、参照抗体自体が、結晶構造上、LDLRのEGFaドメイン\n(PCSK9の触媒ドメインに結合するものであり、その領域内に存在す るPCSK9残基のいずれかと相互作用し、又は遮断する抗体は、PCS K9とLDLRとの間の相互作用を阻害する抗体として有用であり得る とされるもの)の位置と部分的に重複する位置でPCSK9とLDLRタ ンパク質の結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であ ると認められることを踏まえると、本件発明における「PCSK9との結 合に関して、31H4抗体と競合する」との発明特定事項も、31H4抗 体と競合する抗体であれば、31H4抗体と同様のメカニズムにより、L DLRタンパク質の結合部位を直接封鎖して(具体的には、抗体が結晶構\n造上、LDLRのEGFaドメインの位置と重複する位置でPCSK9に 結合して)、PCSK9とLDLRタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮 断し、低下させ、又は調節することを明らかにする点に技術的意義がある ものというべきであり、逆に言えば、参照抗体と競合する抗体は、このよ うな位置で結合するからこそ、中和が可能になるということもできる。こ\nの点は、被告自身が、前記第3の3 ウにおいて、本件明細書の発明の詳 細な説明によれば、当業者は、出願時の技術常識に照らし、参照抗体との 競合によってPCSK9上の複数の結合面のうち特定の領域内の特定の 位置(LDLRのEGFaドメインと結合する部位と重複する位置(又は 同様の位置))に結合する抗体は、PCSK9とLRLRタンパク質の結合 を中和することができると理解するものであり、発明の技術的範囲の全体 にわたって発明の課題を解決できると認識することができたといえる旨 主張していることからも裏付けられるところである。
また、前記1 において認定した甲1文献の開示事項によれば、家族性 高コレステロール血症は、血漿中のLDLコレステロールレベルの上昇に 起因するものであるところ、PCSK9は、細胞表面に存在するLDLR\nタンパク質の存在量を低下させるものであるため、PCSK9が治療のた めの魅力的な標的であり、血漿中のPCSK9に結合し、そのLDLRタ ンパク質との結合を阻害する抗体等が効果的な阻害剤となり得ることが 既に示されていたものと認められるのであるから、このような観点から見 ても、本件発明の技術的意義は、31H4抗体と競合する抗体であれば、 31H4抗体と同様のメカニズムにより、上記のようなLDLRタンパク 質との結合を阻害する抗体、すなわち結合中和抗体としての機能的特性を\n有することを特定した点にあるということもできる。そもそも本件発明の 課題は、前記1 イにおいて認定したとおり、LDLRタンパク質と結合 することにより、対象中のLDLRタンパク質の量を減少させ、LDLの 量を増加させるPCSK9とLDLRタンパク質との結合を中和する抗 体又はこれを含む医薬組成物を提供することであり、このような課題の解 決との関係では、参照抗体と競合すること自体に独自の意味を見出すこと はできないから、このような観点からも、上記のとおり、本件発明の技術 的意義は、31H4抗体と競合する抗体であれば、31H4抗体と同様の メカニズムにより、結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定\nした点にあるというべきである。
イ さらに検討すると、前記 イ のとおり、本件明細書の発明の詳細な説 明には、エピトープビニングを行った結果、31H4抗体と同一性が高い とはいえないアミノ酸配列を有するグループの抗体が31H4抗体と競 合するものとして同定されたことが開示されている。本件明細書には、上 記競合する抗体として同定された抗体の中で中和活性を有すると記載さ れる抗体がPCSK9上へ結合する位置についての具体的な記載はなさ れておらず、31H4抗体とアミノ酸配列が異なるグループの抗体につい ては、エピトープビニングのようなアッセイで競合すると評価されたこと をもって、抗体がPCSK9上に結合する位置が明らかになるといった技 術常識は認められない以上、PCSK9上で結合する位置が明らかとはい えない。
また、本件発明の「PCSK9との結合に関して、参照抗体と競合する」 との性質を有する抗体には、上記本件明細書の発明の詳細な説明に具体的 に記載される数グループの抗体以外に非常に多種、多様な抗体が包含され ることは自明であり、また、前記2 イのとおり、このような抗体には、 被告が主張するように、31H4抗体がPCSK9と結合するPCSK9 上の部位と重複する部位に結合し、参照抗体の特異的結合を妨げ、又は阻 害する(例えば、低下させる)抗体にとどまらず、参照抗体とPCSK9 との結合を立体的に妨害する態様でPCSK9に結合し、様々な程度で参 照抗体のPCSK9への特異的結合を妨げ、又は阻害する(例えば、低下 させる)抗体をも包含するものである。そうすると、その中には、例えば、 31H4抗体がPCSK9と結合する部位と異なり、かつ、結晶構造上、\n抗体がLDLRのEGFaドメインの位置とも異なる部位に結合し、31 H4抗体に軽微な立体的障害をもたらして、31H4抗体のPCSK9へ の特異的結合を妨げ、又は阻害する(例えば、低下させる)もの等も含ま れ得るところ、このような抗体がPCSK9に結合する部位は、抗体が結 晶構造上、LDLRのEGFaドメインの位置と重複する位置ではないの\nであるから、LDLRタンパク質の結合部位を直接封鎖して、PCSK9 とLDLRタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は 調節するものとはいえない。
なお、本件明細書には「例示された抗原結合タンパク質と同じエピトー プと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質及び断片は、類似の機能的\n特性を示すと予想される。」(【0269】)との記載があるが、上記のとお\nり、「PCSK9との結合に関して31H4抗体と競合する」とは、31H 4抗体と同じ位置でPCSK9と結合することを特定するものではない から、31H4抗体と競合する抗体であれば、31H4抗体と同じエピト ープと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質(抗体)であるとはいえ ず、このような抗体全般が31H4抗体と類似の機能的特性を示すことを\n裏付けるメカニズムにつき特段の説明が見当たらない以上、本件発明の 「PCSK9との結合に関して、31H4抗体と競合する抗体」が31H 4抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。\n前述のとおり、本件発明の技術的意義は、31H4抗体と競合する抗体 であれば、31H4抗体と同様のメカニズムにより、PCSK9とLDL Rタンパク質との結合を中和する抗体としての特性を有することを特定 する点にあるというべきところ、前記のとおり、31H4抗体と競合する 抗体であれば、LDLRのEGFaドメインと相互作用する部位(本件明 細書の記載からは、EGFaドメインの5オングストローム以内に存在す るPCSK9残基として定義されるLDLRのEGFaドメインとの相 互作用界面の特異的コアPCSK9アミノ酸残基(コア残基)、EGFaド メインの5オングストロームから8オングストロームに存在するPCS K9残基として定義されるLDLRのEGFaドメインとの相互作用界 面の境界PCSK9アミノ酸残基と理解され得る。)に結合してPCSK 9とLDLRタンパク質の結合部位を直接封鎖するとはいえず、他には、 31H4抗体と競合する抗体であれば、どのようなものであっても、PC SK9とLDLRのEGFaドメイン(及び/又はLDLR一般)との間 の相互作用(結合)を阻害する抗体となるメカニズムについての開示がな い以上、当業者において、31H4抗体と競合する抗体が結合中和抗体で あるとの理解に至ることは困難というほかない。
ウ 以上のとおり、「PCSK9との結合に関して、31H4抗体と競合する 抗体」であれば、31H4抗体と同様に、LDLRタンパク質の結合部位 を直接封鎖して(具体的には、抗体が結晶構造上、LDLRのEGFaド\nメインの位置と重複する位置でPCSK9に結合して)、PCSK9とL DLRタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節 するものであるとはいえないから、「PCSK9との結合に関して、31H 4抗体と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的特性を有\nすると認めることもできない。なお、前記 アのとおり、本件発明におけ る「中和」とは、PCSK9とLDLRタンパク質結合部位を直接封鎖す るものに限らず、間接的な手段(リガンド中の構造的又はエネルギー変化\n等)を通じてLDLRタンパク質に対するPCSK9の結合能を変化させ\nる態様を含むものではあるが、「PCSK9との結合に関して、31H4抗 体と競合する抗体」であれば、上記間接的な手段を通じてLDLRタンパ ク質に対するPCSK9の結合能を変化させる抗体となることが、本件出\n願時の技術常識であったとはいえないし、本件明細書の発明の詳細な説明 に開示されていたということもできない。
エ こうした点は、前記1 においてその信頼性を認定した【A】博士の実 証実験の結果及び同実証実験を踏まえた【B】博士の供述書 からも裏付 けられる。すなわち、この実証実験は、リジェネロンの63の抗体につい て参照抗体との競合及び結合中和性を実験したものであるが、競合に関し て50%の閾値を用いた結果、34の抗体が参照抗体と競合するが、うち 28の抗体(80%よりも多く)は結合中和性を有しないことが確認され ており(別紙3の資料B1及び前記1 ア b)、参照抗体と競合する抗体 であれば結合中和性を有するものとはいえないことが具体的な実験結果 として示されている。さらに、この実験結果に加え、「本件特許によれば、 31H4抗体の結合部位はhPCSK9上のLDLRの結合部位と部分 的にしか重複しないから・・別の抗体の結合部位は、LDLRの結合部位 と重複することなく31H4結合部位と重複し得るのであり、このように して、別の抗体は、hPCSK9−LDLRの結合部位と重複することな く31H4結合部位と重複し得」る(前記1 ア b)として、【B】博士 が、「31H4抗体と競合する抗体・・・の全てが結合を中和する効果を有 するだろうというのは確実に誤りである。」旨の意見を述べているところ である(前記1 ア c)。
オ 被告は、前記第3の3 ウにおいて、31H4抗体(参照抗体)と競合 するが、PCSK9とLDLRタンパク質との結合を中和できない抗体が 仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明1の技術的範囲から 文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理由 とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、31H4抗体と 競合する抗体であれば、31H4抗体と同様のメカニズムにより、PCS K9とLDLRタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有す\nることを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきであって、 31H4抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれるとする と、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである(本件のような事 例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解すれば、抗 体がPCSK9と結合する位置について、例えば、PCSK9の大部分な どといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、特許請求 の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることになるから、 相当でない。)。なお、被告が主張するように、本件発明1の特許請求の範 囲は、PCSK9との結合に関して、参照抗体と競合する抗体のうち、「P CSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」る抗体のみ を対象としたものであると解したとしても、前示のとおり、本件発明のP CSK9との競合に関して、参照抗体と競合するとの発明特定事項は、被 告が主張するような、参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に 結合する抗体にとどまるものではなく、PCSK9とLDLRタンパク質 の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体をも含 むものであるから、このような抗体についても結合中和抗体であることが サポートされる必要があるところ、参照抗体が結合する位置と同一又は重 複する位置に結合する抗体の場合とは異なり、PCSK9とLDLRタン パク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体 が結合を中和するメカニズムについては本件明細書には何らの記載はな く、また、ビニングによる実験結果(前記 イ )に基づく結合中和抗体 は、いずれも結合中和に係るメカニズムが開示されている、参照抗体が結 合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体である可能性が高く、\nその点を措くとしても、少なくともこれらが立体的に妨害する抗体である ことを示唆する記載はない。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明 には、参照抗体と競合する抗体のうちPCSK9とLDLRタンパク質と の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体が結合 中和活性を有することについて何らの開示がないというほかなく、この点 からも、本件発明はサポート要件を満たさない。
また、前記第2の3 のとおり、本件審決は、本件明細書には、本件明 細書記載の免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウ スの作製及び選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの 作製、本件明細書記載のPCSK9とLDLRとの結合相互作用を強く遮 断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングア ッセイを最初から繰り返し行うことによって、十分に高い確率で本件発明\nの抗体をいくつも繰り返し同定することが具体的に示される旨判断する が、【F】(【F】)教授(【F】教授という。)の第2鑑定書(甲230)に 「特定のマウスが特定の抗体を生成するかどうかは運に支配されるため、 候補となり得る抗体を全て生成しスクリーニングすることは不可能であ\nる」と記載されているように、本件明細書に記載された抗体の作製過程を 経たとしても、免疫化されたマウスの中でPCSK9上のどのような位置 に結合する抗体が得られるかは「運に支配される」ものであって、抗体の 抗原タンパク質への結合を立体的に妨害する態様で抗原タンパク質に結 合する抗体を製造する方法が本件出願時における技術常識であったとも いえないことからすると、本件明細書に記載された抗体の作製方法に関す る記載をもって、本件発明に含まれる多様な抗体が本件明細書の発明の詳 細な説明に記載されていたとはいえない。
カ そして、本件発明1のモノクローナル抗体を含む医薬組成物に係る発明 である本件発明5も、上記同様の理由から、サポート要件を満たすもので はない。
以上によれば、本件発明1及び5は、いずれもサポート要件に適合するも のと認められないから、これと異なる本件審決の判断は誤りである(なお、 原告の主張のうち前記第3の3 イ の「EGFaミミック抗体」に係る点 は首肯するに値するものを含み、サポート要件が満たされているとする被告 の主張に疑義を生じさせるものと考えるが、この点に関する判断をするまで もなく、上記のとおり、本件発明1及び5は、いずれもサポート要件に適合 するものとは認められないから、更なる判断を加えることは差し控えること とする。)。
以下、念のために付言する。
ア 本件発明を巡る国際的状況について、原告は、欧州では、異議申立抗告\n審において、令和2年に、本件発明と実質的に同じ対応欧州特許について、 進歩性欠如により無効であると判断されており、また、米国では、合衆国 連邦巡回区控訴裁判所において、令和3年2月11日に、本件発明より限 定された対応米国特許につき、実施可能要件違反により無効であると判断\nされており、現在、我が国は、本件特許の有効性が裁判所により維持され ている世界で唯一の国である旨主張し、他方、被告は、上記連邦巡回区控 訴裁判所の判断につき、連邦最高裁判所は、令和4年11月4日に、裁量 上告受理申立てを認めたので、上記判断が覆される可能\性が極めて高い旨 主張するが、もとより、他国における判断が本件判断に直ちに影響を与え るものではないことは明らかである(なお、米国については、仮に、連邦 巡回区控訴裁判所の無効判断が覆されたとしても、対応米国特許は、参照 抗体との「競合」を発明特定事項とするものではないと認められるから(例 えば、米国特許8829165特許の請求項1は、「PCSK9に結合する とき、次の残基:配列番号3のS153、I154、P155、R194、 D238、A239、I369、S372、D374、C375、T37 7、C378、F379、V380、又はS381の少なくとも1つに結 合し、PCSK9がLDLRに結合するのを阻害する、単離されたモノク ローナル抗体」との発明特定事項である(甲19)。)、いずれにしても本件 発明に係る判断に直接関係しない。)。
イ 本件発明に係る別件審決取消訴訟においては、前記第2の1 のとおり、 サノフィによるサポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、 これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、31H4抗体と競合する抗体は、 31H4抗体とほぼ同一のPCSK9上の位置に結合し31H4抗体と 同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによるもの\nと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【A】博士や\n【B】博士の各供述書、【F】教授の鑑定書等(甲18、230)による構\n造解析、「EGFaミミック抗体」に係る関係書証(甲4の1及び2)等の 新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわらず、 この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の結論 と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.03.22
令和4(ネ)10061 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月9日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(3) 争点3−1(引用発明1−1に基づく本件再訂正後発明1の拡大先願要件違 反の有無)について
ア 構成要件1D−1及び1D−4−1について\n
(ア) 控訴人は、引用発明1−1の押さえ部は可動であり、仮に可動ではない場合 を含むとしても、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体を巻き出 す又は巻き取る構成は乙10公報に開示されていないと主張する。\n
(イ) しかしながら、乙10公報には、押さえ部を固定する場合を排除するような 記載はない。そして、「スクリーン本体4が被磁着体90に近接した位置にあると、 スクリーン本体4が被磁着体90に磁着しやすくて引き出し操作をスムーズに行い 難いし、スクリーン本体4の表面に傷が付くことがあることから、引き出しを開始\nする前に、図4に示すように、ベース板11に可動片12を重ね合わせた状態(ロ ック状態)にして、押さえ部5を被磁着体90から離した態様(第1配置態様)に 固定する。」(【0043】)との記載は、特許請求の範囲の請求項3に係る発明の実 施例に係るものと認められる。また、上記記載からすると、スクリーン本体4の引 き出し操作をスムーズに行うことができ、スクリーン本体4の表面に傷が付くおそ\nれがない場合には、引き出し時に、押さえ部を非磁着体(本件再訂正後発明1にお ける「設置面」)から離す必要がないものと読み取ることができる。さらに、乙1 0公報には、請求項3に係る発明の実施例についての説明として、「前記押さえ部 5を被磁着体90から離した第1配置態様において、前記押さえ部5と前記被磁着 体90との離間間隔(距離)は、20mm〜70mmに設定されるのが好ましい (図4参照)。」(【0049】)、「前記押さえ部5を被磁着体90に近接させた第2配置態様において、前記押さえ部5と前記被磁着体90との離間間隔(距離)は、 1mm〜15mmに設定されるのが好ましく、中でも2mm〜8mmに設定される のが特に好ましい(図3、5参照)。」(【0050】)との記載があることからして、引用発明1−1においても、押さえ部と被磁着体との位置関係にはある程度の幅が あることが想定されているといえるところ、押さえ部と被磁着体との間の距離を調 整することによって、スクリーン本体の引き出し操作をスムーズに行うことができ、 かつ、スクリーン本体の表面に傷が付くおそれがないようにすることが可能\である ことは、当業者にとって明らかであるといえる。 そうすると、乙10公報には、押さえ部を固定した構成が開示されていると認め\nるのが相当である。
(ウ) 上記を前提とすると、乙10公報の【図5】のような構成で押さえ部を固定\nすることも当然に想定されるから、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリ ーン本体を巻き出す又は巻き取る構成も、乙10公報に開示されていると認められ\nる。乙10公報の【図1】〜【図6】は、いずれも押さえ部を可動とした場合(す なわち請求項3に係る発明)の実施例であると認められるのであって、これらの図 をもって、乙10公報に、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体 を巻き出す又は巻き取る構成が開示されていないということはできない。\n
(エ) したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 構成要件1D−4−2について\n
・・・
(ウ) ところで、乙10公報には、「前記可動体24の先端部26の横断面視での 外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体4と接触し得る部分が円弧面に形成さ れているので(図10参照)、引き出し操作の際のスクリーン本体4の傷付きを十\n分に防止することができる。」(【0062】)、「前記可動体24の先端部26の横断面視での外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体4と接触し得る部分が円弧面 に形成されているので(図10参照)、巻き取り操作の際のスクリーン本体4の傷 付きを十分に防止することができる。」(【0066】)との記載があり、これらの記\n載における「稼働体24の先端部26」は引用発明1−1の「押さえ部」に相当す る部分であることから、引用発明1−1において、押さえ部の横断面視の形状を円 弧面としているのは、引き出し操作及び巻き取り操作の際に、スクリーン本体が傷 付くことを防止するためであるものと認められる。そうすると、乙10公報には、 押さえ部の構成を工夫することによって、引き出し操作及び巻き取り操作の際にス\nクリーン本体が傷付くことを防止することが開示されているといえる。
(エ) そして、シートと接触する部分を回転可能とすることによる効果も、シート\nの移動時にシートが傷付くことを防止するというものである。 そうすると、引用発明1−1において、横断面視の形状が円弧面である押さえ部 を回転可能とし、その結果、押さえ部に接触しながら巻き出され又は巻き取られる\nスクリーンの摺動接触に起因して押さえ部が回転するものとすることは、当業者が 押さえ部の構成の工夫として適宜選択する範囲のものにすぎないと認めるのが相当\nである。
・・・・
ウ 構成要件1D−4−3について\n
・・・
(イ) 乙31(平成24年12月18日付けの株式会社ケイアイシーの商品カタロ グ)、乙32(特開2006−178916号公報)及び乙33公報には、ケース から巻き出す形態のスクリーン装置において、ケースに取手が設けられているもの が開示されており、本件特許1の出願当時、本件再訂正後発明1のようなマグネッ トスクリーン装置の技術分野において、ケースに取手を設けることは周知・慣用手 段であったと認められる。そして、引用発明1−1において収納ケースに取手を設 けることは、当業者が、運搬の便宜等のため、必要に応じて適宜選択できることで あると認められる。
(ウ) 控訴人は、本件再訂正後発明1においては、ケーシングを移動させてシート を巻き出す使用態様のために「取手部」が必須であるのに対し、引用発明1−1で は収納ケースを移動させてシートを巻き出すような使用形態は想定されていないか ら、収納ケースに「取手部」に相当する部材を設けることについては開示も示唆も ないと主張するが、本件再訂正後発明1においても、ケーシングではなく「操作バ ー」側を移動させてスクリーンを巻き出す態様も想定されているし(本件明細書1 の【0051】、【図12】)、また、取手部ではなく、ケーシング自体を保持して移 動させることが可能であることは明らかであるから、ケーシングを移動させてシー\nトを巻き出すために「取手部」が必須であるという上記控訴人の主張は採用できな い。
(エ) したがって、引用発明1−1は、構成要件1D−4−3に相当する構\成を含 むものと認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和2年(ワ)3297号
本件特許1は以下です。
◆第6422800号
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.03.22
令和4(ネ)10079 著作権侵害による損害賠償、損害賠償反訴請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和5年1月31日 知的財産高等裁判所 横浜地方裁判所
控訴人は、前記第2の3(1)アのとおり、設計図は、工事に携わる者の間の 共通言語であり、特に、設計者と施工者が異なる場合は、設計図面以外での 詳細な情報伝達手段はないから、原告設計図全体では創作性があると認めら れるべきである旨主張する。しかし、設計図が工事に携わる者に共通して利 用されるものであることは、むしろ、多くの場合、様々な関係者が施工内容 を理解することができるよう、作図上の表現方法や内装の具体的な表\現は実 用的、機能的でありふれたものにならざるを得ないことを示すものというべきであり、現に、原告設計図や原告設計図の具体的な表\現内容が実用的、機能的でありふれたものであることは、引用に係る原判決第4の2(3)における 説示のとおりである。 また、控訴人は、前記第2の3(1)イのとおり、原告設計図作成時点におい て被控訴人運営に係る既存店は、第三者が経営する店舗を譲り受けたものに すぎず、デザイン構築上準備段階のものであり、本件店舗が、被控訴人の経営する系列店舗で初の旗艦店であるから、原告設計図は創作性を有する旨主\n張する。しかし、ここで問題となっているのは、被控訴人運営に係る各店舗 に統一感を持たせる観点から、内装のデザインには一定の制約があったとい うことであり、各店舗の具体的な内装の先後関係ではないから、上記主張は 採用できない。
(2) 前記(1)によれば、原告設計図や原告内装について著作物性が認められない 以上は、その他の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない というほかないが、念のために、控訴人の前記第2の3(2)記載の主張につい ても触れると、建物やその内装の完成のための手段であり、通常それ自体が 鑑賞の対象となるものではない設計図の性質からして、設計に係る契約にお いては、特段の合意がない限り、設計報酬とは別に設計図ないし内装の著作 権についての使用料請求権が設計者に留保されるとは認め難く、本件で特段 の合意がされたと認めるべき証拠もない。これを裏返して言えば、控訴人は、 本件設計等契約において、被控訴人に対し、原告設計図に基づき、自ら又は 第三者をして本件店舗の内装工事を施工し、工事完了後は本件店舗で親子カ フェの営業を行うこと等を当然に了承していたもので、著作権ないし著作者 人格権を行使しないことが契約締結の前提となっていたものというべきであ る。 なお、原告設計図に基づき本件店舗の内装が施工されたことは事実であり、 また、補正の上引用した原判決第2の2(2)オのとおり、一審被告キャピタラ ンドと訴外アイ・イーエスとの間の本件店舗の内装工事に係る請負契約では、 デザイン・設計料は別途とされたものであるところ、それにもかかわらず控 訴人が誰からも設計図に係る報酬を得られないことについては同情すべき面 もあるが、報酬請求権が時効消滅した以上、やむを得ないというほかない。
2023.03.22
令和2(ワ)19221 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月28日 東京地方裁判所
以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して 製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。
ウ 「その物の生産に用いる物」について 前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属 マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的 範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物 であるといえる。
(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残 存する汚れ自体を、金属マグネシウム(Mg)単体の作用により減少させる ことによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり(【000 6】)、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム(Mg)単体と水と の反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進さ せることを見出し(【0007】)、構成要件1Aの「金属マグネシウム(M\ng)単体を50重量%以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用い る構成を採用したものであると認められる。\n
そして、被告製品は、前記(1)イ(ア)のとおり、構成要件1Aを充足するも\nのであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マ グネシウム(Mg)単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体 を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されている から、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の 課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について ア 特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通している もの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本 国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではな く、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状\n態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。 本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネ ットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をす る旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄 補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグ ネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものがより好ま しく(【0020】)、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウ ムの粒子の平均粒径は、4.0〜6.0mmであることが最も好ましい (【0022】)と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品 は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯 ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗\n濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の 実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規 格品や普及品であるということはできない。 以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通してい るもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構\n成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くと も口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通している ものになったといえると主張する。 しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、 市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡\n等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ま しくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立 法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、 これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に 該当するということはできない。 したがって、被告の主張は採用することができない。
(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請 求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。 そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和2年1月頃までに は、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被 告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和2年4月から 同年7月にかけてレビューを記載した購入者45人のうち、20人の購入者 が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、7人の 購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃ ん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解され る記載をしていることを認めるに足る証拠(甲111)が提出されているこ とからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る 金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品 が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる(当裁判所に顕 著な事実)。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件1Aの「網体」に\nは含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯 を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件 各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。 しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをと るために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編ん で造ったもの。」(広辞苑第7版)の意味もあると認められること、本件明 細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品 は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したもので あるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出 しやすいものとなっている。」(【0023】)、「この網体の素材は、耐水性 があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、 強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエス テル繊維を用いることが好ましい。」(【0024】)、「この網体自体の織り 方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」(【0 025】)と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されてい ないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する 態様による使用方法であることに変わりはないといえる。 したがって、被告が、購入者が構成要件1Aの「網体」には含まれない、\n布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法 が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に 用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> 汎用品
>> 不可欠性
>> ピックアップ対象
2023.03.21
令和4(ワ)1848 特許権移転登録手続 特許権 民事訴訟 令和5年2月6日 大阪地方裁判所
原告は、訴状とともに提出した令和4年3月4日付証拠説明書において、甲 12規程の作成年月日を平成26年1月1日としていたこと、被告は、令和4 年8月9日付準備書面において、甲12規程の存在を否認し、その根拠として、 甲12規程に用いられる「取得」「相当の利益」との文言は、平成27年7月に 公布され、平成28年4月1日に施行された特許法等の一部を改正する法律 (平成27年法律第55号)で初めて採用されたものであって、平成26年1 月1日時点でこのような文言が使われた規程が存したのは極めて不自然であ ると指摘したこと、原告は、平成4年9月20日付け原告第1準備書面におい て、前記第3「2」【原告の主張】のとおり主張したこと、はいずれも当裁判所 に顕著である。
(2) 本件において、甲12規程は、原告が本件各発明に係る特許を受ける権利 を原始取得する根拠として不可欠のものであって、訴え提起の段階で、甲12 規程が適用されるかどうかについては、その制定過程及び本件各発明の完成時 期や被告代表者の退職時期との関係で慎重に検討されるはずのものである。し\nかも、この経緯は、専ら原告の領域内の事情であり、かかる検討を阻むものは ない。 しかるところ、原告は、当初甲12規程の作成日時を平成26年1月1日と 特定したにもかかわらず、被告から文言の不自然さを指摘されるや、その制定 日は平成30年9月3日であって、平成26年1月1日にさかのぼって適用さ れると主張したものであって、このように主張が変遷した経緯自体、被告代表\n者が原告に在職中に甲12規程が制定されたことを疑わしめるに十分である。\nまた、そのように作成されたのであれば、甲12規程は、制定日を明らかにし た上、同規程の適用を定めた10条は「さかのぼって適用する」と表現するの\nが自然と思われるが、同条にはそのような遡及適用の趣旨は記載されていない し、制定日も書かれていない。遡及の限度が平成26年1月1日である根拠も 何ら示されていない。
加えて、甲12規程が、被告代表者の原告退職時期に近接した平成30年9\n月3日に真実制定されたというのであれば、原告と被告代表者間で当然に退職\n時に本件各発明に係る特許を受ける権利の帰属について協議ないし確認がさ れるものと考えられる。しかし、原告は、被告代表者が原告を退職した後本件\n各発明について特許出願がされたことを知った後も、本件各特許権に係る発明 の実施品と思料されるボックス容器に関する大王製紙、原告、被告の取引に継 続して関与していたことを自認しているのであって、かかる協議や確認がされ たこともうかがえないどころか、被告が権利者であることを前提とした行動を とっているものというべきである。
(3) その他原告の提出する証拠等も、前記認定の経緯に照らすと採用の限りで なく、結局、平成30年9月3日当時を含め、被告代表者が原告に在職する期\n間中に、甲12規程が適法に制定されたと認めるに足りる証拠はないといわざ るをえない。
2 前記1によると、争点1に関わらず、原告が甲12規程により本件各発明に係 る特許を受ける権利を取得したとは認められない。本件各発明に適用される就業 規則(乙1)によっても、原告が特許を受ける権利を承継したとは認められない し、また当該承継の事実を被告に対抗できない(特許法34条1項)。 なお、原告は、当裁判所が口頭弁論を終結する予定の期日として指定した令和\n4年12月16日の期日の直前に、同年11月29日付け準備書面により本件各 発明を原始取得させる旨の黙示の合意が存した旨の主張をした。同主張はそもそ も時機に遅れた攻撃防御方法というべきであるが、前判示のとおり、本件各発明 において適用されるべき就業規則(乙1)が存するところ、かかる明示の合意の ほかに、原告主張の従業員が原告名義の特許出願に異を唱えなかった等の事情か ら特許を受ける権利の移転等に関する黙示の合意が成立する余地はないという べきであって、原告の主張は、それ自体失当である
関連カテゴリー
>> 職務発明
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2023.03.21
令和4(行ケ)10089 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年1月31日 知的財産高等裁判所
2 単一の色彩のみからなる商標の商標法3条2項の該当性について 本願商標は、別紙1 及び の記載から特定される色彩のみからなるもの であり、女性用ハイヒールの靴底部分に赤色(PANTONE 18-1663TP)とす る構成からなるものである。\nこのように本願商標は、単一の色彩のみからなり、その色彩を付する位置 を上記部分に特定した商標である。 商標法3条1項は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商 標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる旨を 規定し、同項3号において、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、\n用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期そ の他の特徴、数量若しくは価格」を「普通に用いられる方法で表示する標章\nのみからなる商標」を掲げる。 同号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされる趣旨は、このような商 標は、商品の産地、販売地、品質その他の特性を表示記述する標章であって、\n取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、\n特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとと もに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、 商標としての機能を果たし得ないことによるものと解される(最高裁昭和5\n3年(行ツ)第129号同54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事1 26号507頁参照)。
そして、商品の色彩は、商品の特性であるといえるから、同号所定の「そ の商品の・・・その他の特徴」に該当するものと解される。そして、商品の 色彩は、古来存在し、通常は商品のイメージや美観を高めるために適宜選択 されるものであり、また、商品の色彩には自然発生的なものや商品の機能を\n確保するために必要とされるものもあることからすると、取引に際し必要適 切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、原則として何人も\n自由に選択して使用できるものとすべきであり、特に、単一の色彩のみから なる商標については、同号の上記趣旨が強く妥当するものと解される。 他方で、商標法3条2項は、同条1項3号に該当する商標であっても、「使 用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識 することができるもの」については、同項の規定にかかわらず、商標登録を 受けることができる旨規定する。 商標法3条2項の趣旨は、同条1項3号に該当する商標であっても、特定 の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標が その商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能\を持つに至り、公益上の 見地から不適当とされていた特定人による当該商標の独占的使用を例外的に 認めるということにある。
こうした商標法3条2項の趣旨に照らせば、自由選択の必要性等に基づく 公益性の要請が特に強いと認められる、単一の色彩のみからなる商標が同条 同項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務である ことを認識することができるもの」に当たるというためには、当該商標が使 用をされた結果、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益性の 例外として認められる程度の高度の自他商品識別力等を獲得していること (独占適応性)を要するものと解するべきである。
なお、色彩のみからなる商標等を商標登録の保護の対象とした平成26年 法律第36号改正附則5条3項には、不正競争の目的なく登録商標又はこれ に類似する商標を使用していた者に継続的使用権を認める旨の規定があるが、 これはあくまで「法律の施行の際に現にその商標の使用をしてその商品・・・ に係る業務を行っている範囲内において」その商品等に関する商標を使用す る権利を認めるにすぎず、こうした改正附則の規定があるからといって、色 彩のみからなる商標登録において特定人による色彩の独占適応性を考慮する ことを否定する理由にならないというべきである。
◆判決本文
不競法についての関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2023.03.21
令和4(行ケ)10095 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年2月22日 知的財産高等裁判所
(イ) 本願商標は、外観においては、全体として、輪郭線のほとんどが鋸歯 状になった、右下に伸びる帯が左上に伸びる帯より長い「X」型の十字形状といった印象を与えるものということができ、そのような漠然とし\nた印象によって需要者に記憶されるものといえる。そして、本願商標は、 「X」型の十字形状ではあるが、特定の文字又は事物を表\しているとは 直ちに認識できないから、これより特定の称呼及び観念は生じない。 他方、前記1(1)イ及び(2)イのとおり、引用商標1及び引用商標2は、 いずれも「X」型の十字形状ではあるが、特定の文字又は事物を表\して いるとは直ちに認識できないから、これより特定の称呼及び観念が生じ るとは認められない。
そうすると、本願商標と各引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念 を生じないため、称呼及び観念において相互に比較することはできない。
(ウ) このように、本願商標と各引用商標は、称呼及び観念において比較で きないが、外観において類似しているから、それによって需要者、取引 者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商 標と各引用商標は、これらを同一又は類似の商品について使用するとき は、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあり、類似する 商標であると認められる。 したがって、本件審決が、本願商標と各引用商標が類似である(本件 審決3(1)ア(ウ)〔本件審決3頁〕)とした判断に誤りはない。
(エ) なお、前記1(1)イ(ア)及び(2)イ(ア)のとおり、各引用商標は、その外観か ら、全体として、輪郭線のほとんどが鋸歯状になった、右下に伸びる帯 が左上に伸びる帯より長い「X」型の十字形状といった印象を与えるものであるところ、仮に、このような印象のみにより、各引用商標が「エ\nックス」の称呼及び観念を生じるとするならば、本願商標も、全体とし てそのような印象を与える点で共通するといえるから(前記(2)ア)、本願 商標も「エックス」の称呼及び観念を生じるということになる。 したがって、本願商標と各引用商標は、外観において類似し、称呼及 び観念において同一ということになるから、類似するといえる。
イ この点に関して、原告は、「X」をデザインする図形商標は多数存在し、 外観上識別し得るポイントが一つでもあれば、非類似とされている(甲1 4の1〜19、甲15、甲16)と主張するが(前記第3の2〔原告の主 張〕(3))、原告の挙げる証拠によっても、外観上識別し得るポイントが一つ でもあれば、非類似とされているとは認められず、原告の上記主張は採用 することができない。
また、原告は、本願商標と各引用商標を比較すると、本願商標が、組み 合わされた2本の帯状の図形を重ね合わせた幾何学的図形であり、重なり 合った部分に奥行き感があり立体風であるのに対して、各引用商標は、「X」 型十字の白抜きの図形であり平らな印象を与える点、「X」型の十\字の交点 から右下に伸びる部分と左上に伸びる部分の長さの比が大きく異なる点、 本願商標が図形内部に破線を有するのに対し各引用商標は図形内部を空白 で表している点等、外観上識別し得るポイントにおいて多々異なる点がある旨主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(3))。 しかし、前記(2)ア及びイで述べたところによれば、本願商標と各引用商 標は、いずれも「X」型の十字が左側(反時計回り方向)に傾いた形で組み合わされた2本の帯の図形からなり、帯の輪郭線のうち、短辺が直線、\n長辺が鋸歯状に表されている点、及び「X」型の十\字の交点から右下に伸 びる部分が左上に伸びる部分よりも長くなっている点において共通して おり、全体として、輪郭線のほとんどが鋸歯状になった、右下に伸びる帯 が左上に伸びる帯より長い「X」型の十字形状といった印象を与え、そのような漠然とした印象によって需要者に記憶されるという点において共\n通するものであり、原告の上記主張に係る相違点は、上記の共通点に比較 してささいな部分であり、殊更強い印象を与えるものではなく、それらの 相違点があることから、本願商標と各引用商標が非類似であるとはいえな い。
さらに、原告は、取引の実情を考慮すると、需要者は商品のデザインに 細部まで注意を払って確認するから、原告主張の外観上の差異は、顕著な 差異として看者に強い印象を与えるものであり、そのため、本願商標と各 引用商標を判然と区別することができ、これらが相紛れるおそれはないと 主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(3))。 しかし、前記(3)のとおり、原告の主張する取引の実情は、商品デザイン (意匠)に関するものであり、商標の類否判断に直接影響するものとはい えないし、指定商品全般についての一般的、恒常的な取引の実情ではなく、 商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情に該当すると はいえないから、原告の上記主張は採用することができない。 加えて、原告は、関連商標の登録異議決定(甲6)において、関連商標 が各引用商標と非類似とされていることを指摘し、関連商標と各引用商標 との間の相違点は、本願商標と各引用商標との間にも存在するから、統一 的な解釈の観点からも、本願商標と各引用商標は類似しないと判断すべき であると主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(3))。しかし、本願商標と各引用商標が類似することは前記アのとおりであり、関連商標の登録異議決定があるとしても、それにより、この結論が左右されることはない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.03.21
令和2(ワ)3473 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月23日 大阪地方裁判所
ア 本件各発明の技術的意義
本件明細書上、本件発明1には、ブラケットを放熱部に取り付けることに より外装部の変形及び破損を防止すること(本件意義1)及び放熱部製造時 の不良率の低減(本件意義3)があるものと読み取れる。原告はこれに加え、 外装部が放熱部におけるブラケットの接続部分よりも後方に延びている構\n造により、ユーザーが、ブラケットが取り付けられている位置よりも後方の 外装部を掴み、自らの手が照明器具の照射する光を遮らずに、照射範囲を正 確に把握しながら照射方向を変更することを可能とする技術的意義(本件意\n義2)がある旨主張するが、本件明細書に記載はなく、構成要件Hとして追\n加された経緯等をふまえると(甲11の1、14の1)、後付けの感をぬぐえ ず、本件各発明の直接の作用効果としての意義は乏しい。
イ 本件各発明の技術的意義が被告製品の売り上げに貢献する程度等
(ア) 本件意義1について
スポットライト製品一般は、本件特許発明より相当前から市場に存在 し、既に成熟した市場が形成されており(乙5、弁論の全趣旨)、市場動向 調査によれば、スポットライト製品は、演色性や色温度などにおいて高い 付加価値を有する製品の開発が期待されている状況にあり(乙30、3 1)、原告、被告、競合他社のカタログ等において、配光制御・特性、光色、 レンズ設計、省エネ、製品の大きさ、軽さ、デザイン等が訴求されている こともうかがえる(甲5、6、乙15、16、25ないし29) これに対し、外装部の変形及び破損防止という本件意義1は、いわば製 品として当然に担保されるべき機能及び要素であるといえ、また、材質、\nブラケットの取付方法及び取付部分の構造の工夫等、本件各発明以外の技\n術によっても実現可能であり、現に各照明器具メーカーにおいて一般に実\n現している効果であると考えられる。 また、原告は、平成26年以降、原告実施品と同じシリーズ名・製品名 で、ブラケットを放熱部ではなく外装部に取り付け、外装部を厚肉とする ことで外装部の変形及び破損の防止を実現した原告後継品を販売してい る(弁論の全趣旨)。すなわち、本件意義1は、これを欠いても、同一シリ ーズ・製品として顧客に販売することが可能な程度の顧客誘引力しか有し\nないと評価し得る。このことは、カタログに文言上本件意義1が明示され てないとしても、商品の写真から本件意義1に係る特徴を看取できること を考慮しても同様である。
(イ) 本件意義3
本件意義3は、不良率低減という製造コスト削減に寄与するものである といえるが、本件意義3によるコスト削減(製品価格への反映)の程度が 不明であること等を踏まえると、被告製品の利益に対する寄与度が大きい とは認められない。
(ウ) 以上のような事情を踏まえると、本件意義1及び3の顧客誘引力は限 定的であり、本件意義1及び3が被告製品の売り上げに貢献する程度は低 いと言わざるを得ない。
ウ 原告実施品の販売実績等
原告は、本件期間前に原告実施品の販売を開始した後、本件登録日(平成 28年8月5日)以降は在庫品限りとして原告実施品を販売するにとどまっ ており、平成28年以降の原告実施品の販売数は16個である(甲17、1 8)。 このように、原告が本件登録日以降原告実施品を製造しておらず、その販 売方法(販路)等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、原 告が原告後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技 術により本件各発明と同様の作用効果を奏していることは、前記(1)で説示 した特許法102条2項の推定の前提事実を欠くとまでいうことはできな いものの、本件推定を大きな割合で覆滅させる事情というべきである。
エ 競合品の存在
本件期間中、ブラケットが外装部ではなく、放熱部を含む別の部分に取り 付けられているという特徴を有する製品は、パナソニックのTOLSOシリ\nーズ(乙25)、オーデリックのC1000シリーズ(乙27の2ないし27 の4)、三菱電機のAKシリーズ、彩明シリーズ、鮮明シリーズ及びLEDス ポットライトシリーズ(乙29)をはじめ、複数存在する。これらの製品は、 原告実施品及び被告製品と価格帯も概ね同程度である。 以上の事情に鑑みると、被告製品には、競合品が存すると認められ、かか る競合品の存在も推定を覆滅させる事情に当たる。
オ 原告の市場占有率
被告は、スポットライト市場又は店舗用照明市場における原告の市場占有 率が低いとして、被告製品が存在しない場合、その需要の多くが競合他社の 製品へ流れ、原告実施品を販売できたはずであるとはいえない旨主張する。 しかし、被告が主張する原告を含む照明器具メーカーの市場占有率は、ス ポットライトを含む店舗用照明器具市場における機器全般ついてのもので あって、スポットライト以外の幅広い商品群を含むものと解されるから、原 告実施品等との関連が乏しく、推定を覆滅させる事情に当たるとはいえな い。
カ 覆滅の程度
以上の事情、とりわけ本件特許発明の技術的意義や実施品の販売状況を重 視した上総合的に考慮すると、本件においては、被告製品の販売がなかった 場合に、これに対応する需要が原告実施品ないし原告後継品に向かう蓋然性 はむしろ低いとみるべきであって、特許法102条2項により推定された損 害の8割について覆滅されるというべきである。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2023.03.20
令和4(ワ)70046 商標権 民事訴訟 令和5年1月31日 東京地方裁判所
関係法令の定めに照らせば、本件商標権の取得に通常要する費 用は1万2000円(特許法等関係手数料令4条2項の一)、維持に通常要 する費用は3万2900円(商標法40条1項、商標法施行令4条1項) と認められる。 したがって、商標法38条5項に基づく損害額は合計4万4900円と なる。
(2) 侵害行為差止めのための通知に要した費用
証拠(甲7、8、10)によれば、原告は、令和4年6月11日、被告に 対し、特定記録郵便により、本件ウェブページの削除のほか、本件商品の輸 入及び販売の停止並びに回収を求める内容の本件文書を発送したこと、被告 は、その頃、本件文書を受領したこと、その郵便料金が244円であったこ とがそれぞれ認められる。これらの認定事実に照らせば、本件文書の送付は、被告による違法な行為を排除するためのものといえるから、その送付に要した費用は、被告の不法 行為と相当因果関係がある損害というべきである。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.03.20
令和4(ネ)10078 不当利得返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 時機に後れた攻撃防御方法に当たるかについて
控訴人は、第4次訂正に係る訂正の再抗弁は、特許庁による令和4年4 月21日付けの審決の予告を受けてした第4次訂正請求に係るものであ\nって、本件特許に係る特許権侵害訴訟における手続においても当然に主張 できるものと考えるようである(同主張によって第3次訂正に係る訂正の 再抗弁が取下げ擬制されたとも主張している。)が、特許権侵害訴訟におい て無効の抗弁とその対抗主張ともいうべき訂正の再抗弁は、特許権の侵害 に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決するため、 特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことなく主張することが できるものとされたにすぎず、特許無効審判とは別の手続である民事訴訟 手続内でのものであるから、審理の経過に鑑みて、審理を不当に遅延させ るものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下 されるべきである。
そこで、原審における審理経過についてみると、控訴人は、原審におい て、第1回弁論準備手続期日(令和元年11月18日)における本件特許 が新規性及び進歩性を欠く旨の無効の抗弁の主張(被告第1準備書面)を 受けて、第3回弁論準備手続期日(令和2年7月27日)までに、第2次 訂正に係る訂正の再抗弁に係る原告第2準備書面を提出したが、本件無効 審判の手続における訂正請求に合わせて、第3次訂正に係る訂正の再抗弁 を記載した令和3年3月3日付け原告第5準備書面及び同年5月27日 付け原告第6準備書面を提出した(これらの準備書面は、第4回弁論準備 手続期日(令和3年12月16日)において、訂正書面を含めて陳述され た。)。原判決は、第2次訂正及び第3次訂正に係る訂正の再抗弁はいずれ も訂正要件を充足せず、本件特許は特許無効審判により無効とすべきもの と判断したところ、控訴人は、控訴理由書で、第4次訂正に係る訂正の再 抗弁の主張を追加したものである。 こうした原審での審理経過に鑑みると、第4次訂正は、時機に後れて提 出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたことについて控訴人に は重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、被控訴人から第4 次訂正については訂正要件を充足しないこと等を含め、第4次訂正に係る 訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅 延させることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとす る。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2023.03.20
令和3(ワ)4439 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和5年2月21日 大阪地方裁判所
原告は、本件早見表及び本件情報につき、被告P1が小堀鐸二研究所との契\n約上、本件早見表の利用許諾の対象を原告のみとしようとしたこと、原告が小堀鐸\n二研究所との契約上、秘密保持義務を負っていること、本件早見表のデータを保有\nしていたのは限られた人間だけであったこと、外部への持出しが禁止されていたこ と、被告P1が原告代表者として、原告内部で本件情報を共有するにあたり、取扱\nいを十分注意するよう呼び掛けていたこと、個別の現場において本件早見表\を用い るにあたって必要箇所以外はマスキングしていたこと、富士ネット工業において秘 密として管理されていたことから、原告において秘密として管理されていたと主張 する。
しかしながら、証拠(甲9、10)によれば、原告と小堀鐸二研究所との契約は 非独占的利用許諾の形式がとられている上、本件早見表の利用許諾の対象が、当初\n「原告及び原告の登録会員」であったものが、「原告及び原告の協力会社」と修正 されたにすぎないから、この変更が何ら原告や被告P1が本件情報を秘密として管 理していたことを示すものとはいえない。また、小堀鐸二研究所との契約上、原告 が秘密保持義務を負っているとしても、原告が現実に本件情報を秘密として管理し ていたかどうかには直接の関連性がない。前記(1)ア及びエ認定のとおり、本件早 見表を保有していたのは13名ないし14名の原告の従業員のうち、主に営業を行\nう5名ほどの者であったことが認められるものの、業務上必要のある者が保有して いたというにすぎず、他の従業員のアクセスが制限されていたとは認められない。 また、本件早見表の外部への持出しが禁じられていたこと、被告P1が原告におい\nて本件情報の取扱いを十分注意するよう呼び掛けていたことについては、いずれも\n被告P1が否定しているところ、原告の主張を裏付ける客観的な証拠は全くない。
さらに、個別の現場において本件早見表を取引先等に示す場合に必要箇所以外がマ\nスキングされていたからといって、本件情報の一部を担当者の判断で第三者に自由 に開示していることに変わりはなく、これをもって原告が本件情報を秘密として管 理していたとはいえない。加えて、富士ネット工業における本件早見表や本件情報\nの管理体制は、原告において秘密として管理されていたかどうかとは関連性がな く、被告P1が富士ネット工業在籍時に、本件情報の取扱いを注意するよう求める メールを他の従業員に送信していたとしても、富士ネット工業退職後、原告を設立 してからも同様の行動をしたことが推認されるわけではないし、前記(1)エ認定の とおり、被告P1が富士工業ネット工業在籍中に、本件早見表のデータにつき、そ\nの取扱いや電磁的記録媒体の紛失に注意を促す以外に、アクセス制限や拡散防止の 措置を講じていたものとも認められない。 本件情報の内容についても、天井部材落下防止ネットを張る際のいくつかの仕様 の組合せにより各支持部にかかる想定荷重について構造計算をした結果が一覧でき\nるため、便利ではあるが、仕様が異なればそのまま利用することはできないもので あるし、第三者が一級建築士等に依頼して独自に同種の早見表を作成することが困\n難とまではいえないから、本件情報を営業秘密として管理すべき必要性が客観的に 高いとは解されない。 そして、前記認定のとおり、本件早見表のデータは、営業秘密であることの表\示 等の措置のないままに、原告の従業員らの使用するコンピュータや持ち運び可能な\n電磁的記録媒体に保存されていたものであり、その使用後も、情報漏洩を防止する 何らの措置も採られなかったことなどに鑑みると、これらの情報は、いずれも秘密 として適切に管理されているとはいえず、秘密として管理されていると客観的に認 識可能な状態であったともいえない。\nその他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告の主張は採用 できない。
ウ そうすると、その余の点について検討するまでもなく、本件情報は、秘密管 理性が認められず、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2023.03.20
令和4(行ケ)10093 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年2月22日 知的財産高等裁判所
前記イのとおり、本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、\nその言葉の意味のみからしても、取引者、需要者に、電気器具や電力を使 って運転する機械を含む電気に関する事柄を支え、支持し、支援し、助け ることを意味すると理解される場合が少なくないものと認められ、前記ウ のとおり、実際に、電気及び電気工事に関する業界においては、「でんきサ ポート」又は「電気サポート」の語は、電気に関する工事、修理及びトラ ブル対応といったサービスを表す語として使用されており、それらの語は、\n電力会社、ガス会社などを含めた複数の会社のウェブサイトに掲載されて いることから、一般人を含む取引者、需要者にも、上記サービスを表す語\nとして認識し得る状態で使用されているものといえる。そうすると、本願 商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、需要者により、\n電気に関する工事、修理及びトラブル対応といったサービスを表す語とし\nて認識されるものと認められる。
他方、本願商標の指定役務(前記第2の1(1)イ及び(3))のうち、電気設 備設置工事、家庭用電熱用品類の設置工事、ポンプの修理又は保守、業務 用冷凍機械器具の修理又は保守、電子応用機械器具の修理又は保守、電気 通信機械器具の修理又は保守、民生用電気機械器具の修理又は保守、照明 用器具の修理又は保守、電動機の修理又は保守、配電用又は制御用の機械 器具の修理又は保守、発電機の修理又は保守、業務用食器洗浄機の修理又 は保守、業務用電気洗濯機の修理又は保守は、いずれも電気に関する工事、 修理及びトラブル対応といったサービスに該当するものと認められる。
そうすると、本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取\n引者、需要者により、本願商標の役務の内容、質を表しているものとして\n認識されるものと認められ、自他役務識別標識としての機能がないか、又\nは希薄な部分と認識されるものと認められる。 したがって、本件審決の同旨の判断(本件審決3(1))に誤りはない。
オ 原告の主張に対する判断
原告は、「デンキ」からは「電気」、「電器」及び「電機」が想起されると ころ、それらの内容は明確に異なり、「デンキ」の文字からは、その内容を 特定できないし、工事の対象であるとしても、工事の対象物が特定できな いから、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分が役務の内容を示\nしているということはできず、むしろ、その部分は一種の造語として認識 されるとし、したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「デンキサポ\nート」の部分は、役務の質を表したものとして、自他役務識別標識として\nの機能がないか、あるいは希薄な部分と理解されるにとどまるというのが\n相当であると判断したのは誤りである旨主張する(前記第3〔原告の主張〕 1(1))。 しかし、「デンキ」は、「電気」、「電器」及び「電機」のいずれにしても、 電気に関する事柄を意味すると理解され(前記イ)、電気及び電気工事に関 する業界における実際の用例(前記ウ)も考慮すると、本願商標の構成中\nの「デンキサポート」の部分は、取引者、需要者により、電気に関する工 事、修理及びトラブル対応といったサービスを表す語として認識され、本\n願の指定役務と照らし合わせると、取引者、需要者により、本願商標の役 務の内容、質を表しているものとして認識され、自他役務識別標識として\nの機能がないか、又は希薄な部分と認識されるものと認められるから(前\n記エ)、原告の上記主張は採用することができない。
(3) 「ハート」の部分の自他識別標識としての機能について\n
ア 本願商標の構成中の「ハート」の部分は、本願の指定役務の内容、質等\nとは関係がないから、本願の指定役務との関係で、自他役務識別標識とし ての機能を発揮するものと認められる。他方、前記(2)エのとおり、本願商 標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、需要者により、\n本願商標の役務の内容、質を表しているものとして認識されるものといえ、\n自他役務識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分と認識されるも\nのと認められる。そして、本願商標が標準文字からなり、その全体が一連 に表記されていること(前記(1))を考慮しても、本願商標の構成中の「ハ\nート」の部分と「デンキサポート」の部分は、それらを分離して観察する ことが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと は認められず、より強く自他識別標識として認識される「ハート」の部分 に着目し、その部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に当たる場合も 少なくないものと認められる。 したがって、本件審決の同旨の判断(本件審決3(1))に誤りはない。
イ 原告は、結合商標について、商標の構成部分の一部を抽出して類否を判\n断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別 標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外 の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合 などを除き、許されないというべきであるとした上で、本願商標は、全体 としてまとまりのある一体的な構成からなることに加えて、「ハー卜」の部\n分は、我が国において親しまれた片仮名語であり、広く使用されているこ とからも、その部分が強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、殊更 に「ハート」の部分に着目するというのは不自然でもあり、本願商標は構\n成全体をもって、特定の観念を生じない一体の造語を表したものと認識し、\n把握するというのが自然であるといえるとし、したがって、本件審決が、 本願商標の構成中の「ハート」の部分は、自他役務識別標識としての機能\ を発揮する部分であるから、より強く自他識別標識として認識される「ハ ート」の部分に着目し、この部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に 当たる場合も少なくないというのが相当であると判断したのは誤りである 旨主張する(前記第3〔原告の主張〕1(2))。 しかし、仮に本願商標が結合商標であるとしても、前記(2)エのとおり、 本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、需要者に\nより、本願商標の役務の内容、質を表しているものとして認識されるもの\nと認められ、自他役務識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分と\n認識されるから、本願商標の構成中、「ハート」という部分を抽出し、この\n部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは 許されるというべきである。そして、「ハート」という語が、我が国におい て親しまれた片仮名語であり、広く使用されているとしても、本願商標の 構成中の「ハート」の部分は、本願商標の指定役務の内容、質等とは関係\nがなく、本願の指定役務との関係で、自他役務識別標識としての機能を発\n揮するものと認められるから、原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.03.15
令和4(行ケ)10101 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年3月7日 知的財産高等裁判所
原告は、前記1 のとおり、パリ条約の解釈に相違があるときはフランス文 によるとの条項(29条(1)(c))を前提に、パリ条約6条の3(1)(a) の「a defaut d'autorisation des pouvoirs competents,」(所管官庁の許可 がない場合)が「, par des mesures appropriees,」(適当なる方法に依り禁止 する)だけに係るのではなく、「de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire,」(登録を拒絶し又は無効とし)にまで係るものと解釈される べきであり、同条項の公定訳(「同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の 記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上 それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し\n又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその 構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。」)は、誤訳で\nあって、これを前提とした商標法4条1項5号は、パリ条約6条の3(1)(a) の国内法実施の義務を履行していない旨主張する。
し か し 、 原 告 が 指 摘 す る 「 a defaut d'autorisation des pouvoirs competents,」(権限のある官庁の許可を受けずに)は、原文上、「l'utilisation,」 と「,」で続けて副詞句として挿入されており、文言において、この「a defaut d'autorisation des pouvoirs competents, 」 が 「 d'interdire ・ ・ ・ l'utilisation」(使用を禁止する)のみに係るものであるのか、「de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire,」(登録を拒絶し又は無効 とする)にも係るものであるのか、文法的には、どちらと読むことも可能であ\nることや、「権限のある官庁の許可を得ていない」という文言が、当初は 「d'interdire・・・l'utilisation」のみに係るものとして起草されていたと ころ、起草委員会が総会に示した条約案では、上記原文に書き換えられ、その まま確定したことにより、文法的には2通りの解釈が可能になったことは、【A】\n意見書も指摘するとおりであるから、日本語公定訳のとおり、「a defaut d'autorisation des pouvoirs competents, 」 が 、 「 d'interdire ・ ・ ・ l'utilisation」のみに係ることを前提としても、パリ条約6条の3(1)(a) の誤訳であると断じることはできない。
また、仮に、原告が指摘するような解釈、すなわち、「権限のある官庁の許 可を受けない」同盟国の紋章等の商標又はその構成部分としての登録を拒絶し、\n又は無効とするとの解釈を採用するとしても、同規定は、「権限のある官庁の 許可」を受けた登録出願をどのように取り扱うについてまで規定するものでは ない(これらの紋章等の「商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無\n効とし」とされていることの反対解釈として、それ以外の場合は当然に登録を しなければならない義務を本条約が締結国に課したと解することはできない。) から、そもそも同条に基づき、我が国が「権限のある官庁の許可」を受けた登 録出願を拒絶してはならない義務を負うものではないし、同条を根拠として商 標法4条1項5号の適用範囲を狭めて「登録をしなければならない」ものと解 釈されるべきものでもない。
3 その他に原告が種々主張する点を精査しても、権限のある官庁やその許可を 得た者がパリ条約6条の3(1)(a)に規定する監督用・証明用の記号や印 章について登録出願をした場合において、その登録をしなければならないこと を根拠付けるものは見当たらない。したがって、同条に基づく義務の不履行を 理由とする原告の主張は、いずれにしても失当というほかない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.03.15
令和4(行ケ)10122 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年3月9日 知的財産高等裁判所
本願商標は「朔北」と「カレー」からなる結合商標であるところ、前記のとおり、 「カレー」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということはでき ない一方で、「朔北」については、需要者、取引者をして、「北の方角」又は「北方 の地」を表す単語として理解されるにすぎず、具体的な地域を表\すものと理解され るものではないから、指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観 念が生じ得るといえる。そして、需要者、取引者をして、「朔北カレー」を一連一体 のものとしてのみ使用しているというような取引の実情は認められない。 そうすると、本願商標について、各構成部分がそれを分離して観察することが取\n引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないから、 「朔北」の部分のみを抽出して他人の商標と比較して商標の類否を判断することも 許されるというべきである。
(3) 本願商標と引用商標の類否 以上を踏まえ、本願商標における「朔北」の部分(本願要部)と引用商標を比較 して、類否を検討する。
ア 外観
本願要部は「朔北」という2文字の漢字からなるのに対し、引用商標は「サクホ ク」の4文字の片仮名からなり、外観が明らかに異なる。
イ 称呼 本願要部の称呼は「さくほく」であり、引用商標の称呼も「さくほく」であるか ら、同一である。
ウ 観念
本願要部からは「北の方角」「北方の地」の観念を生じるものであるのに対し、「サ クホク」は、辞書等に掲載されていない造語であって、特定の観念を生じないもの であるから、観念が明らかに異なる。
エ 以上のとおり、本願要部と引用商標は、称呼が共通するものの、外観及び観 念は明確に異なっているところ、需要者、取引者が「朔北」から引用商標である「サ クホク」や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく、また、本 願商標及び引用商標の指定商品において、需要者、取引者が、専ら商品の称呼のみ によって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められ ず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから、 本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につ き誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.03. 1
令和4(行ケ)10012等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年2月16日 知的財産高等裁判所
甲1発明は、前記(1)のとおり、従来の制御信号供給装置では、制御信号 を継統的に発生させることができず、 磁気テープに対する連続的な走行 制御が行えないという課題を解決するため、接触操作面を有するととも にこれに関連して円環状に配列された複数の接触操作検出区分が設けら れ、各接触操作検出区分から出力されるタッチパネルとの構成を採用し、\nテープ駆動系に供給される制御信号を、特殊変速再生モード状態におい て磁気テープを所望の一方向に、所望の速度で走行させる制御を任意の 時間だけ連続的に行えるようにしたものである。 一方、周知技術1は、タッチ位置検知手段(タッチパネル)により一次 元又は二次元座標上の位置データを検出することで画面上のカーソル等\nの位置データが設定され、プッシュスイッチ手段により当該設定された 位置データが確定されて入力情報となるものと理解できる。そうすると、 周知技術1は、位置データを入力する装置に関する技術であって、タッ チパネルとプッシュスイッチが協働して位置データを入力する機能を果\nたすものであるといえる。
磁気テープの走行方向や走行速度を制御するための甲1発明のタッチ パネルと、走行方向や走行速度という要素を含まない位置データを入力 する装置に関する周知技術1とは、制御する対象が異なるし、たとえ両 者がタッチパネルという共通の構成を有するとしても、磁気テープの制\n御信号供給装置である甲1発明において、位置データを入力する装置に 関するものである周知技術1を適用することが容易であるとはいえない。 結局のところ、甲1発明に、周知技術1を適用できるとする原告らの 主張は、実質的に異なる技術を上位概念化して適用しようとするもので あり、相当でない。 仮に、周知技術1を、タッチパネルによる選択をプッシュスイッチで 確定して何らかの入力情報を生成する技術であると上位概念化して理解 したとしても、甲1発明は、プッシュスイッチに割り当てるべき機能(選\n択を確定する機能)をそもそも有さないし、甲1文献には、タッチパネル\nにより磁気テープの走行方向や走行速度を連続制御することは記載され ているが、タッチパネルにより選択された走行方向や走行速度を確定す る操作や、当該操作に対応するボタン等の構成は記載も示唆もないから、\n甲1発明に、周知技術1を適用する動機付けがない。
原告らは、前記第3の1(1)ア のとおり、甲1発明のタッチパネル1 1も接触点を一次元座標上の位置データDpとして検出するものである し、本件特許発明であれ周知技術1であれ、タッチパネルの下にプッシ ュスイッチを設けることの作用効果は、タッチパネルの下にプッシュス イッチを設けること自体に由来するものであって、プッシュスイッチの 上にあるタッチパネルの形状等や操作態様等にも依存しないから、周知 技術1は、上位概念化するまでもなく甲1発明に適用可能であり、当該\n適用は、先行技術の単なる寄せ集め又は設計変更である旨主張する。
しかし、原告らの主張は、前記 において説示した、甲1発明において 選択を確定する機能がない点等を看過しているものであるし、周知技術\n1において、位置データを入力する機能はタッチパネルの形状や操作態\n様等には依存しないとしても、そのことが同周知技術におけるタッチパ ネルとプッシュスイッチの機能的又は作用的関連を否定する根拠とはな\nらないし、機能的又は作用的関連が否定できない以上、周知技術1を甲\n1発明に適用することが単なる寄せ集め又は設計変更とはいえない。し たがって、原告らの上記主張は採用できない。
◆判決本文
平成19(ワ)2525はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2023.03. 1
令和4(行ケ)10011 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年2月15日 知的財産高等裁判所
原告は、本願明細書等の段落【0222】及び【0223】の記載のほ か、段落【0014】の記載によれば、本願明細書等には、本願各発明 が従来のジョセフソン効果の原則を超越する存在であることが示唆され\nており、その他の段落において発明の構成例や各実施例も開示されてい\nるから、当業者は、電子対の生成過程や巨視的波動関数の位相特定の情 報が不明であっても、本願明細書等の記載を参照して、本願各発明を容 易に実施することができる旨主張する。 そこで検討するに、上記イで検討したとおりの本願明細書等の段落 【0014】の記載からすれば、本願各発明においては、「第1導体」及 び「第2導体」の抵抗値がゼロではない場合であっても、上記のような 範囲の抵抗率であれば、ジョセフソン効果を得ることができる旨が記載\nされているとみることもできる。 しかしながら、前記(2)のとおり、ジョセフソン接合が超伝導体である\n二つの導体を用いた接合であることは、本件原出願日当時の技術常識で あったと認められることからすれば、導体の抵抗値がゼロではない場合 であっても、上記のような範囲の抵抗率であればジョセフソン効果が得\nられるというのは、技術常識に反する現象である。そうすると、本願明 細書等において、このような現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等 が記載されていなければ、当業者は、本願各発明を実施することができ ると認識するものではないというべきである。そして、上記イで検討し たとおり、本願明細書等の段落【0051】ないし【0068】及び図 14Aないし21Bには、いずれも各実施例における導体が段落【00 14】に記載されているような範囲の抵抗率であることを示す試験結果 は記載されていないというべきである。そして、このほか、本願明細書 等において、導体の抵抗値がゼロではない場合であっても、上記のよう な範囲の抵抗率であればジョセフソン効果が得られることを裏付ける試\n験結果等は記載されていない。
以上によれば、本願明細書等において、本願各発明が従来のジョセフ ソン効果の原則を超越する存在であることが示唆されているとはいえな\nいし、当業者が、本願明細書等の記載を参照して、本願各発明を容易に 実施することができるともいえない。
・・・
(ア) 原告は、本願明細書等の図7、15ないし21から明らかなとおり、本 願各発明は、従来の技術常識としてのジョセフソン接合ではなく、抵抗\n値をゼロにしなくとも、極めて低い抵抗値の範囲内でジョセフソン接合\nを実現することを目的とする発明であるから、本願明細書等に抵抗値が ゼロの場合の記載がないことは当然の帰結であり、当業者は、本願各発 明につき、電流が非常に低い抵抗状態で流れる条件でジョセフソン接合\nを実現したものとして捉えることにより、本願各発明を実施することが 可能である旨主張する。\nしかしながら、上記ウで検討したところに照らせば、本願明細書等に おいて、本願各発明が、従来の技術常識としてのジョセフソン接合では\nなく、抵抗値をゼロにしなくとも、極めて低い抵抗値の範囲内でジョセ フソン接合を実現することは、何ら試験結果等により裏付けられていな\nいというべきである。そうすると、当業者が、本願各発明につき、電流 が非常に低い抵抗状態で流れる条件でジョセフソン接合を実現したもの\nとして捉えることにより、本願各発明を実施することが可能であると認\n識するものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2023.03. 1
令和2(ワ)13626 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月17日 東京地方裁判所
原告は、1) 本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には、浄化され たスクラバー流体を更に処理することなく、海に放出することを要する との記載はない、2) 本件訂正により、本件特許の【請求項1】の従属項 である【請求項10】を訂正するに当たり、浄化されたスクラバー流体 の品質が所定レベルより低い場合、浄化されたスクラバー流体を分離機 入口に戻す構成を維持しているから、本件発明は、分離機での浄化処理\n後、環境への放出前に、更に浄化処理を行う態様を予定している、3) 本 件明細書の「ディスクスタック遠心分離機をスクラバー流体に適用する ことによって、汚染物質相の大部分が濃縮形態で取り除かれ得る」 (【0014】)との記載によれば、ディスクスタック遠心分離機によ っても分離し得ない汚染物質相が残存し得る以上、補助的にフィルタ等 による分離を行うことは排除されないと主張する。
しかし、上記1)については、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細 書において、浄化されたスクラバー流体を更に処理することなく、海に 放出することを要することを明示した記載は見当たらないものの、前記 (ア)のとおり、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の各記載並びに 原告の本件異議申立事件における主張、さらには、本件明細書には、\n「ディスクスタック遠心分離機」により「浄化されたスクラバー流体」 を更に浄化するための装置を設けることを示唆する記載が見当たらない ことは、いずれも、「浄化されたスクラバー流体を前記第一の分離機出 口から環境に放出するための手段」(構成要件F)とは、「分離機」に\nより「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられた 浄化設備により浄化処理されることなく、船の外側に放出されるなどす るものをいうとの理解をもたらすものであるから、その点を明示する記 載が存在しないからといって、前記(ア)の解釈が左右されるものではない。
上記2)については、前記(ア)bのとおり、本件明細書の記載(【000 8】、【0009】及び【0014】)によれば、本件発明に係る浄化 設備について、「スクラバー流体」の浄化能力を向上させ、また、点検\n修理の必要性を最小とするために、「ディスクスタック遠心分離機」を 使用し、この「分離機」の動作により、「浄化されたスクラバー流体」 が規制を満たすことになり、環境への影響を最小にして環境に解放する ことができ、他の処理をするための設備を設ける必要がなく、機器の点 検修理や交換の必要性を最小にすることができるものであると理解する ことができる。そうすると、本件発明は、「分離機」の動作によって上 記の作用効果を実現するものであるから、「浄化されたスクラバー流体」 を再び「分離機」入口に戻すことを排除するものではないが、「分離機」 により「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられ た浄化設備により浄化処理されて、船の外側に放出されるなどすること を予定したものではないというべきである。したがって、本件訂正後の\n【請求項10】の記載をもって、本件発明が、「分離機」での浄化処理 後、環境への放出前に、別に設けられた浄化設備により更に浄化処理を 行う態様を予定しているということはできない。\n
上記3)については、本件明細書の記載からは、「ディスクスタック遠 心分離機をスクラバー流体に適用することによって、汚染物質相の大部 分が濃縮形態で取り除かれ」(【0014】)た「浄化されたスクラバ ー流体」について、「汚染物質相」が残存するため規制を満たさず、環 境に放出することができないとは直ちには読み取れない。そうすると、 本件明細書の【0014】の記載をもって、「分離機」により「浄化さ れたスクラバー流体」を補助的にフィルタ等により浄化処理することが 示唆されているということはできない。 したがって、原告の上記各主張は、いずれも採用することができない。
イ 小括
以上のとおり、被告製品1(主位的主張)及び被告製品2は、構成要件\nFを充足しないから、その余の点を判断するまでもなく、本件発明の技術 的範囲に属するとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年1月12日 知的財産高等裁判所
本願発明は、前記第2の2のとおりの構成を有するものであって、前記1(1)の【図 1】のような液体を入れた容器中に浮体を浮かべ、同浮体を鉛直方向に大きなもの とすることにより(同【図2】の3参照)、駆動動力が一定であっても、同浮体が上 下運動することによる発生動力を拡大させることで、「発生動力>駆動動力の関係」 が成立するというものである。 そして、本願明細書の段落【0036】によると、本願発明における駆動動力と は、液位を増減させて、浮体を上下運動に導く駆動方法を実行する装置を駆動する 動力のことをいい、電力が主体であるが、流水、圧縮空気、人力等も利用可能であり、具体的な駆動方法としては、浮体(例えば【図3】の6)を浮かべる容器中に\n物体(例えば【図3】の9)を挿入することが想定されているものと認められる。 次に発生動力についてみると、本願明細書の段落【0035】には、「浮体の上下 運動を「発生動力」とする」との記載があり、同段落【0018】〜【0020】 では、容器中への水の注入量が同一である場合の仕事(W)を、(浮体上の錘の重さ) ×(持ち上げられた距離)により計算しているところ、ここでいう仕事(W)は、 浮体の上下運動をいうものと推認されるから、本願発明における発生動力は、錘を 載せた浮体が移動する運動を指していると理解される。 ところで、本願明細書の段落【0018】〜【0020】に3つの例が記載され ているところ、同段落【0021】の記載と併せると、上記3つの例は、「発生動力 >駆動動力の関係」が成立することを説明するために記載されているものと認めら れる。そこで検討するに、上記3つの例においては、注入した水の量は一定である ものの、どのように水を注入するのか、また、その際に、水を注入するために要し た動力、すなわち本願発明における「駆動動力」に相当する液位を増減させる動力 の大きさや、それが、上記3つの例において一定であるかについては本願明細書に 記載がなく、示唆もない。さらには、【図2】の場合に浮体が浮かぶことが可能な程度に、十\分な浮力が生じているかも明らかではない。そしてその他の本願明細書の記載を総合しても、当業者が、どのようにして、本願発明の「発生動力>駆動動力 の関係」が成立する動力発生装置を製造することができるか理解できるとはいえな い。 そうすると、本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明を実施するこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 発明該当性
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(行ケ)10007 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年1月18日 知的財産高等裁判所
原告らは、本願発明は、多数の作用効果を有機的に組み合わせた統合 システムの発明であるのに対し、引用発明は、圧縮機の吸込容積を可変 とするものにすぎず、その具体的な課題や作用・機能は全く異なってお\nり、この観点からも、引用発明に他の技術を組み合わせて本願発明を想 到するための動機付けはないと主張するので(前記第3の3〔原告らの 主張〕(2)ウ)、この点について検討する。 原告らの上記主張の趣旨は必ずしも明確ではないが、容易想到性の判 断に当たり、請求項に係る発明と主引用発明との間に具体的な課題や作 用・効果の共通性を要するという主張であるとすれば、主引用例の選択 の場面では、そもそも請求項に係る発明と主引用発明との間で、解決す べき課題が大きく異なるものでない限り、具体的な課題が共通している 必要はないというべきである。これを本件についてみるに、本願発明の 課題は、「冷媒が循環する冷媒回路と水(熱搬送媒体)が循環する水回路 (媒体回路)とを有しており、熱搬送媒体と室内空気とを熱交換させて 室内の空調を行うチラーシステム(熱搬送システム)において、媒体循 環を構成する配管を小径化するとともに、環境負荷の低減及び安全性の\n向上を図ること」(段落【0005】)であって、格別新規でもなく、い わば自明の課題というべきものであり、二酸化炭素を熱搬送媒体として 採用した引用発明においては解決されているといえるものである。
また、原告らは、本願発明が奏する効果についても主張するので、こ の点について検討すると、本願発明の、冷房と暖房が可能であるという\n効果(段落【0007】及び【0061】)、及び複数の室内の冷房及び 暖房をまとめて切換可能であるという効果(段落【0062】)は、本願\n発明が、冷媒流路切換機及び第1媒体流路切換機を備えることによる効 果であるところ、引用発明においても、第1四方弁150と第2四方弁 250を備えるから、冷房と暖房が可能であるし、複数の室内空気熱交\n換器(相違点2に係る本願発明の構成)を備える場合には、第2四方弁\n250と連結された室内熱交換機の数が増えるのみであると考えられる から、複数の室内の冷房及び暖房をまとめて切換可能であるという効果\nも当然に奏されることになる。そして、1次側にR32冷媒(相違点1 に係る本願発明の構成)を採用した場合でも、そのような効果を奏する\nことに変わりはない。配管小径化、省スペース化・配管施工及びメンテ ナンス省力化、媒体使用量削減を図ることができるという本願発明の効 果(段落【0008】、【0063】)は、本願発明が熱搬送媒体として二 酸化炭素を採用したことによって奏するものであり、これは、引用発明 も、熱搬送媒体として二酸化炭素を採用するから、同様の効果を奏する ものである。着火事故を防止できるという本願発明の効果(段落【00 09】及び【0064】)は、室内側に配置される媒体回路に二酸化炭素 を用いていることによるものであるが、これは、引用発明も、熱搬送媒 体として二酸化炭素を採用するから、同様の効果を奏するものである(甲 11の段落【0062】)。また、本願明細書等には、HFC−32(R 32)を冷媒として採用する冷媒回路を構成する配管を室内側まで設置\nする必要がないとの記載もある(段落【0009】及び【0064】)が、 本願の特許請求の範囲の請求項1の記載及びその記載により認定される 本願発明では、冷媒回路が室内側に設置されていないことは特定されて いないので、上記の効果は、本願発明の特許請求の範囲の請求項1の記 載に基づくものとは認められない。さらに、技術常識D及びFに照らせ ば、引用発明のプロパンは強燃性であるのに対し、本願発明のR32は 微燃性であることから、着火事故を防止できるという効果は、引用発明 に比べると本願発明が優れていると解されるが、引用発明において相違 点1に係る本願発明の構成を採用することにより、自ずと奏するように\nなる効果である。環境負荷を低減するという本願発明の効果(段落【0 010】及び【0065】)は、R32と二酸化炭素を採用したことによ るものであるところ、引用発明において相違点1に係る本願発明の構成\nを採用することにより自ずと奏されるものである。そうすると、原告ら が本願発明の効果として主張するものは、引用発明も奏するものである か、又は相違点1に係る本願発明の構成を採用することにより自ずと奏\nするものであり、引用発明に他の技術を組み合わせて本願発明を想到す るための動機付けを否定するに足りるような顕著なものではない。 したがって、原告らの上記主張は採用することができない。
ウ 組み合わせの阻害要因について
原告らは、プロパンは、冷媒の能力として、寒冷地での使用が困難であ\nるから、これをR32に代替することには阻害要因があると主張する(前 記第3の3〔原告らの主張〕(3))。 しかし、本願発明においては、寒冷地での使用の可否など冷房又は暖房 の能力に関連する特定はなく、引用文献1にも、引用発明において、特に\n寒冷地での使用が困難なプロパンのような冷媒を採用することに技術的 意味があることをうかがわせるような記載はないから、引用発明のプロパ ンをR32に代替することに阻害事由があるとは認められない。 また、原告らは、着火事故の防止というビル用マルチの決定的課題に反 する選択となるので、引用発明をビル用マルチに使用することには阻害要 因があると主張する(前記第3の3〔原告らの主張〕(3))。
しかし、本願発明がビル用マルチに限定されたものでないことは前記3 (1)イのとおりであるし、仮に本願発明がビル用マルチに適用されるとして も、引用発明で採用されている強燃性のプロパンを微燃性のR32に置き 換えることは、ビル用マルチに要請される性能に必ずしも反するものでは\nなく、むしろそれにそう面もあるから、原告らの上記主張は採用すること ができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和3(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年1月26日 知的財産高等裁判所
以上を前提に検討すると、前記 において説示したとおり、サポート要 件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載 とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記 載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示 唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決で きると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ ると解するのが相当であるところ、前記1 において示したとおり、本件 発明は、LDLRタンパク質の量を増加させることにより、対象中のLD Lの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を 奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレ ステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを\n低減すること、そのために、LDLRタンパク質と結合することにより、 対象中のLDLRタンパク質の量を減少させ、LDLの量を増加させるP CSK9とLDLRタンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医 薬組成物を提供することを課題とするものであり、PCSK9とLDLR タンパク質との結合を強く遮断する中和抗体である参照抗体と競合する抗 体は、PCSK9への参照抗体の結合を妨げ、又は阻害する単離されたモ ノクローナル抗体であることを明らかにするものであると理解される。
そして、前記 によれば、本件発明における「中和」とは、タンパク質 結合部位を直接封鎖してPCSK9とLDLRタンパク質の間の相互作 用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節する以外に、間接的な手段(リ ガンド中の構造的又はエネルギー変化等)を通じてLDLRタンパク質に\n対するPCSK9の結合能を変化させる態様を含むものであるが、前記1\nのとおり、参照抗体自体が、結晶構造上、LDLRのEGFaドメイン\n(PCSK9の触媒ドメインに結合するものであり、その領域内に存在す るPCSK9残基のいずれかと相互作用し、又は遮断する抗体は、PCS K9とLDLRとの間の相互作用を阻害する抗体として有用であり得る とされるもの)の位置と部分的に重複する位置でPCSK9とLDLRタ ンパク質の結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であ ると認められることを踏まえると、本件発明における「PCSK9との結 合に関して、21B12抗体と競合する」との発明特定事項も、21B1 2抗体と競合する抗体であれば、21B12抗体と同様のメカニズムによ り、LDLRタンパク質の結合部位を直接封鎖して(具体的には、結晶構\n造上、抗体がLDLRのEGFaドメインの位置と重複する位置でPCS K9に結合して)、PCSK9とLDLRタンパク質の間の相互作用を妨 害し、遮断し、低下させ、又は調節することを明らかにする点に技術的意 義があるものというべきであり、逆に言えば、参照抗体と競合する抗体は、 このような位置で結合するからこそ、中和が可能になるということもでき\nる。この点は、被告自身が、前記第3の3 ウにおいて、本件明細書の発 明の詳細な説明によれば、当業者は、出願時の技術常識に照らし、参照抗 体との競合によってPCSK9上の複数の結合面のうち特定の領域内の 特定の位置(LDLRのEGFaドメインと結合する部位と重複する位置 (又は同様の位置))に結合する抗体は、PCSK9とLRLRタンパク質 の結合を中和することができると理解するものであり、発明の技術的範囲 の全体にわたって発明の課題を解決できると認識することができたとい える旨主張していることからも裏付けられるところである。
また、前記1 において認定した甲1文献の開示事項によれば、家族性 高コレステロール血症は、血漿中のLDLコレステロールレベルの上昇に 起因するものであるところ、PCSK9は、細胞表面に存在するLDLR\nタンパク質の存在量を低下させるものであるため、PCSK9が治療のた めの魅力的な標的であり、血漿中のPCSK9に結合し、そのLDLRタ ンパク質との結合を阻害する抗体等が効果的な阻害剤となり得ることが 既に示されていたものと認められるのであるから、このような観点から見 ても、本件発明の技術的意義は、21B12抗体と競合する抗体であれば、 21B12抗体と同様のメカニズムにより、上記のようなLDLRタンパ ク質との結合を阻害する抗体、すなわち結合中和抗体としての機能的特性\nを有することを特定した点にあるということもできる。そもそも本件発明 の課題は、前記1 イにおいて認定したとおり、LDLRタンパク質と結 合することにより、対象中のLDLRタンパク質の量を減少させ、LDL の量を増加させるPCSK9とLDLRタンパク質との結合を中和する 抗体又はこれを含む医薬組成物を提供することであり、このような課題の 解決との関係では、参照抗体と競合すること自体に独自の意味を見出すこ とはできないから、このような観点からも、上記のとおり、本件発明の技 術的意義は、21B12抗体と競合する抗体であれば、21B12抗体と 同様のメカニズムにより、結合中和抗体としての機能的特性を有すること\nを特定した点にあるというべきである。
イ さらに検討すると、前記 イ のとおり、本件明細書の発明の詳細な説 明には、エピトープビニングを行った結果、21B12抗体と同一性が高 いとはいえないアミノ酸配列を有する数グループの抗体のみならず、21 B12抗体と同一性が高いアミノ酸配列を有する抗体群が21B12抗 体と競合するものとして同定されたことが開示されている。本件明細書に は、上記競合する抗体として同定された抗体の中で中和活性を有すると記 載される抗体がPCSK9上へ結合する位置についての具体的な記載は なされていないものの、21B12抗体と同一性の高いアミノ酸配列を有 する抗体群については、21B12抗体と同様の位置でPCSK9に結合 する蓋然性が高いといえるとしても、それ以外のアミノ酸配列を有する数 グループの抗体については、エピトープビニングのようなアッセイで競合 すると評価されたことをもって、抗体がPCSK9上に結合する位置が明 らかになるといった技術常識は認められない以上、PCSK9上で結合す る位置が明らかとはいえない。
また、本件発明の「PCSK9との結合に関して、参照抗体と競合する」 との性質を有する抗体には、上記本件明細書の発明の詳細な説明に具体的 に記載される数グループの抗体以外に非常に多種、多様な抗体が包含され ることは自明であり、また、前記2 イのとおり、このような抗体には、 被告が主張するように、21B12抗体がPCSK9と結合するPCSK 9上の部位と重複する部位に結合し、参照抗体の特異的結合を妨げ、又は 阻害する(例えば、低下させる)抗体にとどまらず、参照抗体とPCSK 9との結合を立体的に妨害する態様でPCSK9に結合し、様々な程度で 参照抗体のPCSK9への特異的結合を妨げ、又は阻害する(例えば、低 下させる)抗体をも包含するものである。そうすると、その中には、例え ば、21B12抗体がPCSK9と結合する部位と異なり、かつ、結晶構\n造上、抗体がLDLRのEGFaドメインの位置とも異なる部位に結合し、 21B12抗体に軽微な立体的障害をもたらして、21B12抗体のPC SK9への特異的結合を妨げ、又は阻害する(例えば、低下させる)もの 等も含まれ得るところ、このような抗体がPCSK9に結合する部位は、 結晶構造上、抗体がLDLRのEGFaドメインの位置と重複する位置で\nはないのであるから、LDLRタンパク質の結合部位を直接封鎖して、P CSK9とLDLRタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下さ せ、又は調節するものとはいえない。
なお、本件明細書には「例示された抗原結合タンパク質と同じエピトー プと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質及び断片は、類似の機能的\n特性を示すと予想される。」(【0269】)との記載があるが、上記のとお\nり、「PCSK9との結合に関して21B12抗体と競合する」とは、21 B12抗体と同じ位置でPCSK9と結合することを特定するものでは ないから、21B12抗体と競合する抗体であれば、21B12抗体と同 じエピトープと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質(抗体)である とはいえず、このような抗体全般が21B12抗体と類似の機能的特性を\n示すことを裏付けるメカニズムにつき特段の説明が見当たらない以上、本 件発明の「PCSK9との結合に関して、21B12抗体と競合する抗体」 が21B12抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。\n前述のとおり、本件発明の技術的意義は、21B12抗体と競合する抗 体であれば、21B12抗体と同様のメカニズムにより、PCSK9とL DLRタンパク質との結合を中和する抗体としての特性を有することを 特定する点にあるというべきところ、前記のとおり、21B12抗体と競 合する抗体であれば、LDLRのEGFaドメインと相互作用する部位 (本件明細書の記載からは、EGFaドメインの5オングストローム以内 に存在するPCSK9残基として定義されるLDLRのEGFaドメイ ンとの相互作用界面の特異的コアPCSK9アミノ酸残基(コア残基)、E GFaドメインの5オングストロームから8オングストロームに存在す るPCSK9残基として定義されるLDLRのEGFaドメインとの相 互作用界面の境界PCSK9アミノ酸残基と理解され得る。)に結合して PCSK9とLDLRタンパク質の結合部位を直接封鎖するとはいえず、 他には、21B12抗体と競合する抗体であれば、どのようなものであっ ても、PCSK9とLDLRのEGFaドメイン(及び/又はLDLR一 般)との間の相互作用(結合)を阻害する抗体となるメカニズムについて の開示がない以上、当業者において、21B12抗体と競合する抗体が結 合中和抗体であるとの理解に至ることは困難というほかない。
ウ 以上のとおり、「PCSK9との結合に関して、21B12抗体と競合す る抗体」であれば、21B12抗体と同様に、LDLRタンパク質の結合 部位を直接封鎖して(具体的には、結晶構造上、抗体がLDLRのEGF\naドメインの位置と重複する位置でPCSK9に結合して)、PCSK9 とLDLRタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は 調節するものであるとはいえないから、「PCSK9との結合に関して、2 1B12抗体と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的特\n性を有すると認めることもできない。なお、前記 アのとおり、本件発明 における「中和」とは、PCSK9とLDLRタンパク質結合部位を直接 封鎖するものに限らず、間接的な手段(リガンド中の構造的又はエネルギ\nー変化等)を通じてLDLRタンパク質に対するPCSK9の結合能を変\n化させる態様を含むものではあるが、「PCSK9との結合に関して、21 B12抗体と競合する抗体」であれば、上記間接的な手段を通じてLDL Rタンパク質に対するPCSK9の結合能を変化させる抗体となること\nが、本件出願時の技術常識であったとはいえないし、本件明細書の発明の 詳細な説明に開示されていたということもできない。
エ こうした点は、前記1 においてその信頼性を認定した【A】博士の実 証実験の結果及び同実証実験を踏まえた【B】博士の供述書 からも裏付 けられる。すなわち、この実証実験は、リジェネロンの63の抗体につい て参照抗体との競合及び結合中和性を実験したものであるが、競合に関し て50%の閾値を用いた結果、13の抗体が参照抗体と競合するが、うち 10の抗体(約80%)は結合中和性を有しないことが確認されており(別 紙3の資料B1及び前記1 ア b)、参照抗体と競合する抗体であれば 結合中和性を有するものとはいえないことが具体的な実験結果として示 されている。さらに、この実験結果に加え、「本件特許によれば、21B1 2抗体の結合部位はhPCSK9上のLDLRの結合部位と部分的にし か重複しないから・・別の抗体の結合部位は、LDLRの結合部位と重複 することなく21B12結合部位と重複し得るのであり、このようにして、 別の抗体は、hPCSK9−LDLRの結合部位と重複することなく21 B12結合部位と重複し得」る(前記1 ア b)として、【B】博士が、 「21B12抗体と競合する抗体がLDLRに対する結合を中和」するだ ろうと言うのは、科学的に誤りである旨の意見を述べているところである (前記1 ア c)。
オ 被告は、前記第3の3 ウにおいて、21B12抗体(参照抗体)と競 合するが、PCSK9とLDLRタンパク質との結合を中和できない抗体 が仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明1の技術的範囲か ら文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理 由とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、21B12抗 体と競合する抗体であれば、21B12抗体と同様のメカニズムにより、 PCSK9とLDLRタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性\nを有することを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきで あって、21B12抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれ るとすると、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである(本件の ような事例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解す れば、抗体がPCSK9と結合する位置について、例えば、PCSK9の 大部分などといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、 特許請求の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることに なるから、相当でない。)。なお、被告が主張するように、本件発明1の特 許請求の範囲は、PCSK9との結合に関して、参照抗体と競合する抗体 のうち、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」 る抗体のみを対象としたものであると解したとしても、前示のとおり、本 件発明のPCSK9との競合に関して、参照抗体と競合するとの発明特定 事項は、被告が主張するような、参照抗体が結合する位置と同一又は重複 する位置に結合する抗体にとどまるものではなく、PCSK9とLDLR タンパク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する 抗体をも含むものであるから、このような抗体についても結合中和抗体で あることがサポートされる必要があるところ、参照抗体が結合する位置と 同一又は重複する位置に結合する抗体の場合とは異なり、PCSK9とL DLRタンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で 競合する抗体が結合を中和するメカニズムについては本件明細書には何 らの記載はなく、また、ビニングによる実験結果(前記 イ )に基づく 結合中和抗体は、いずれも結合中和に係るメカニズムが開示されている、 参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体である 可能性が高く、その点を措くとしても、少なくともこれらが立体的に妨害\nする抗体であることを示唆する記載はない。そうすると、本件明細書の発 明の詳細な説明には、参照抗体と競合する抗体のうちPCSK9とLDL Rタンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合 する抗体が結合中和活性を有することについて何らの開示がないという ほかなく、この点からも、本件発明はサポート要件を満たさない。
また、前記第2の3 のとおり、本件審決は、本件明細書には、本件明 細書記載の免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウ スの作製及び選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの 作製、本件明細書記載のPCSK9とLDLRとの結合相互作用を強く遮 断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングア ッセイを最初から繰り返し行うことによって、十分に高い確率で本件発明\nの抗体をいくつも繰り返し同定することが具体的に示される旨判断する が、【F】教授(【F】教授という。)の第2鑑定書(甲230)に「特定の マウスが特定の抗体を生成するかどうかは運に支配されるため、候補とな り得る抗体を全て生成しスクリーニングすることは不可能である」と記載\nされているように、本件明細書に記載された抗体の作製過程を経たとして も、免疫化されたマウスの中でPCSK9上のどのような位置に結合する 抗体が得られるかは「運に支配される」ものであって、抗体の抗原タンパ ク質への結合を立体的に妨害する態様で抗原タンパク質に結合する抗体 を製造する方法が本件出願時における技術常識であったともいえないこ とからすると、本件明細書に記載された抗体の作製方法に関する記載をも って、本件発明に含まれる多様な抗体が本件明細書の発明の詳細な説明に 記載されていたとはいえない。
カ そして、本件発明1のモノクローナル抗体を含む医薬組成物に係る発明 である本件発明9も、上記同様の理由から、サポート要件を満たすもので はない。
以上によれば、本件発明1及び9は、いずれもサポート要件に適合するも のと認められないから、これと異なる本件審決の判断は誤りである(なお、 原告の主張のうち前記第3の3 イ の「EGFaミミック抗体」に係る点 は首肯するに値するものを含み、サポート要件が満たされているとする被告 の主張に疑義を生じさせるものと考えるが、この点に関する判断をするまで もなく、上記のとおり、本件発明1及び9は、いずれもサポート要件に適合 するものとは認められないから、更なる判断を加えることは差し控えること とする。)。
以下、念のために付言する。
ア 本件発明を巡る国際的状況について、原告は、欧州では、異議申立抗告\n審において、令和2年に、本件発明と実質的に同じ対応欧州特許について、 進歩性欠如により無効であると判断されており、また、米国では、合衆国 連邦巡回区控訴裁判所において、令和3年2月11日に、本件発明より限 定された対応米国特許につき、実施可能要件違反により無効であると判断\nされており、現在、我が国は、本件特許の有効性が裁判所により維持され ている世界で唯一の国である旨主張し、他方、被告は、上記連邦巡回区控 訴裁判所の判断につき、連邦最高裁判所は、令和4年11月4日に、裁量 上告受理申立てを認めたので、上記判断が覆される可能\性が極めて高い旨 主張するが、もとより、他国における判断が本件判断に直ちに影響を与え るものではないことは明らかである(なお、米国については、仮に、連邦 巡回区控訴裁判所の無効判断が覆されたとしても、対応米国特許は、参照 抗体との「競合」を発明特定事項とするものではないと認められるから(例 えば、米国特許8829165特許の請求項1は、「PCSK9に結合する とき、次の残基:配列番号3のS153、I154、P155、R194、 D238、A239、I369、S372、D374、C375、T37 7、C378、F379、V380、又はS381の少なくとも1つに結 合し、PCSK9がLDLRに結合するのを阻害する、単離されたモノク ローナル抗体」との発明特定事項である(甲19)。)、いずれにしても本件 発明に係る判断に直接関係しない。)。 イ 本件発明に係る別件審決取消訴訟においては、前記第2の1 のとおり、 サノフィによるサポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、 これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、21B12抗体と競合する抗体 は、21B12抗体とほぼ同一のPCSK9上の位置に結合し21B12 抗体と同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによ\nるものと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【A】\n博士や【B】博士の各供述書、【F】教授の鑑定書等(甲18、230)に よる構造解析、「EGFaミミック抗体」に係る関係書証(甲4の1及び2)\n等の新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわら ず、この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の 結論と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(行ケ)10028 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年1月23日 知的財産高等裁判所
本件においては、本件特許出願の明細書及び図面の記載が、親出願、子出 願、孫出願の当初の明細書及び図面の記載、並びに子出願及び孫出願の分割 時の明細書及び図面の記載に対して新たな技術的事項を追加したものではな いということについて、当事者間に争いはない(本件審決第6の1(2)〔本件 審決25頁〕)。そこで、本件特許出願により請求項1に追加された「着脱可 能に」、「透光カバー」という事項、請求項2に追加された「弾性部材」とい\nう事項、請求項1に追加された「長尺状の基板」、「長尺状の透光カバー」及 び「長尺状の底板部」における「長尺状」という事項につき、親出願の当初 明細書等に対して新たな技術的事項を追加するものであるか否かについて判 断する。
(3) 本件特許の請求項1に記載の「着脱可能に」との事項について\n
ア 新規事項の追加の有無
(ア) まず、親出願の当初明細書等に開示されていた課題について検討する と、親出願の当初明細書等には、【発明が解決しようとする課題】に、「室 内がスマートであるとの印象を与えうるLED照明装置を提供する」 (段落【0010】)という課題が記載されており、また、【背景技術】 に関しては、「LED照明装置Xからの光は輝度むらを生じやす」く、「こ の輝度むらが顕著であると」、「個々のLEDチップ92が視認できてし まう場合があ」り、「見る者が見栄えがよくないと感じてしまう」(段落 【0004】)という課題が示され、第9実施形態に関して、「光のムラ を抑える」(段落【0151】〜【0155】)という課題が開示されて いる。
しかし、親出願の当初明細書等には、多数の実施形態(第1ないし第 24実施形態)が開示されており、そこで開示されている課題は、上記 の課題に限られるものではない。すなわち、親出願の当初明細書等には、 第1実施形態に関する「このようにLEDユニット2を容易に取り付け ることができる。」(段落【0044】)、「このように、LED照明装置A 1は、マウント1からLEDユニット2を容易に取り外すことができ る。」(段落【0046】)という記載、第7実施形態に関する「このよう に、LED照明装置A7は、ウイング部120からLEDユニット2を 容易に取り外すことができる。」(段落【0131】)という記載、第11 実施形態に関する「したがって、LED照明装置A11では、適切な時 期にLEDユニット2を交換可能となっており、常時見栄えのよい照明\nを提供することができる。」(段落【0177】)という記載、第12実施 形態に関する「このため、LED照明装置A12では、LEDユニット 2の交換を容易にかつ速やかに行うことが可能となっている。」(段落\n【0186】)という記載、第23実施形態に関する「また、解除レバー 161を用いれば、比較的接近して並列に配置された2つのLEDユニ ット21を個別に容易に取り外すことができる。」(段落【0261】)と いう記載があり、これらの記載に鑑みれば、親出願の当初明細書等には、 「LEDユニットを交換可能とする」ことが発明の課題として記載され\nていると認められる。
(イ) 前記(ア)のとおり、親出願の当初明細書等には、「LEDユニットを交 換可能とする」という課題が記載されており、この課題は、LEDユニ\nットが「着脱可能に」取り付けられていれば解決可能\なものであって、 着脱可能とする構\成について、特定の構成を採用しなければならないと\nする特別の要請があるとは認められず、具体的な構成まで特定しなけれ\nば解決できないということはなく、当業者であれば、技術常識に照らし、 着脱可能とする適宜の方法を選択して解決することができるものと認め\nられる。
そして、親出願の当初明細書等の段落【0025】、【0026】、【0 044】及び【0046】並びに図2、図10及び図11等には、LE Dユニット2をマウント1の凹部10aにホルダ11の可撓部11bの 弾性変形を用いて取り付け、取り外すことが記載されており、段落【0 250】及び【0251】並びに図103、図104及び図106には、 LEDユニット2をマウント1の凹部に、ワイヤホルダ161を介して 取り付け、取り外す構成が記載されている。そうすると、親出願の当初\n明細書等は、ホルダ11の可撓部11bの弾性変形を用いて取り付け、 取り外す構成と、LEDユニット2をマウント1の凹部10aにワイヤ\nホルダ161を介して取り付け、取り外す構成という複数の態様を開示\nしているということができ、これらの複数の取り付け、取り外す構成を\n包含する発明特定事項について、「着脱可能に」と特定することは、親出\n願の出願当初の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技 術的事項であるといえ、親出願の当初明細書等に記載された事項の範囲 内であるものといえるから、新たな技術的事項を導入するものとは認め られない。
・・・・
親出願の当初明細書等の段落【0030】には基板31が帯状である ことが記載され、段落【0034】にはカバー4が帯状であることが記 載されている。帯状とは、「ある幅をもって長くのびているさま。」(広辞 苑第6版、甲10)、「帯のようなほそながい形・状態。」(大辞林第4版) を意味するから、親出願の当初明細書等には、基板及びカバーが、ほそ ながい形であることが記載されていると認められる。 他方、「長尺」とは、「長さがあること。長いこと。」(大辞林第4版) を意味するから、「長尺状」とは、長さがある状態であること、長い状 態であることを意味するものと認められる。しかるところ、上記のとお り、親出願の当初明細書等には、基板及びカバーが、ほそながい形であ ること(帯状)が記載されているから、基板及びカバーは、また、長さ がある状態であり、長い状態である(長尺状)ともいうことができる。 そのため、親出願の当初明細書等には、長尺状の基板、長尺状の透光カ バー(前記(4)のとおり、「透光カバー」は、親出願の当初明細書等に記 載された技術的事項の範囲内にあるものと認められる。)が記載されて いたものと認められる。したがって、本件特許の請求項1に記載の「長 尺状の基板」、「長尺状の透光カバー」における「長尺状」との事項は、 親出願の当初明細書等に記載されていた技術的事項の範囲内にあるもの と認められ、新規事項を追加するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新たな技術的事項の導入
>> 分割
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(行ケ)10073 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年1月19日 知的財産高等裁判所
原告は、本件商標についても使用許諾する旨、知的財産権の取引サイト に出品している(乙1)。 上記114件の商標登録出願中、7件について、商標法3条1項柱書き 違反、同法4条1項7号、10号、15号又は19号該当等を理由として、 第三者から刊行物提出書による情報提供がされ(甲26)、本件商標を含 む12件について、無効審判請求や登録異議の申立てがされている(甲2\n7)。(4条1項7号)
・・・
前記 ア及びイによれば、本件商標の登録出願日である平成30年9月 24日以前に、被告は、引用商標ないしそれに類似する商標を付したスタ ビライザー等の商品について、海外において相当な売上げを得ており、我 が国においても、遅くとも平成28年7月13日以降、引用商標ないしそ れに類似する商標を付したジンバル雲台やスタビライザーがAmazo nジャパンで販売され、平成29年には見本市に参加し、平成30年には 日本市場に本格参入している。
また、同ウによれば、本件商標の登録出願は、平成29年9月25日か ら令和3年5月11日までの間に原告によりされた大量の商標登録出願 の一部であるところ、これらの出願のうち22件については、登録後1、 2年で移転され、そのうち少なくとも18件については原告による登録出 願が、類似する他人の商標の使用に後れるものであり、原告出願に係るこ れらの商標の多くが特徴的な造語で、先行する他人の商標と偶然に一致し たものとは考えられず、また、原告は本件商標についても使用料を得よう としていたことが認められる。
これらの事情によれば、原告は、先願主義に名を借りて、先行して使用 されてきた他人の商標と類似する商標を出願した上、金銭的利益を得るこ とを業とする者と認めざるを得ない。また、本件商標についても、日本語 とも英語とも考えられない造語であり、およそ原告が独自に考え出したも のとは認められないもので、原告は、被告が海外において、引用商標を付 したスタビライザーやジンバル雲台で相当の販売実績を有していること を知りながら、これらの商品と同じ商品を指定商品として、我が国で先に 商標登録を得ることで、金銭的利益を得ようとしていたものと推認し得る ものである。このような本件商標の登録出願に至る経緯等に照らせば、登 録を認めることは、商標法の予定する公正な取引秩序に著しく反するもの\nというべきであるから、本件商標の商標登録は、公序良俗に反するものと いうほかない。
イ 原告は、前記第3の2(1)イのとおり、出所混同のおそれのある商標や、 フリーライド等の不正の目的をもって使用する商標も商標法4条1項7 号に該当するとすれば、同項10号ないし15号や、同項19号の存在意 義がなくなる、あるいは、他人が使用する周知・著名でない商標が、我が 国で出願・登録されていないことを奇貨として、これと同一又は類似の商 標を先取り的に商標登録出願することが、同項7号に該当するとすれば、 先願主義に反する旨主張する。 しかし、公序良俗の維持は法の原則であり、社会秩序や道徳秩序に反す る商標を登録して助長すべきではないところ、剽窃的な商標登録出願が公 正な取引秩序を害するものとなれば、公序良俗を害すると評価されるに至 る場合があり、同項7号はこのような場合も想定しているものというべき である。
本件は、原告が、先願主義に名を借りて、商標権が本来持つべき出所識 別機能とは関係なく、剽窃的な商標出願を大量にした上、金銭的利益を得\nることを業とするという事案であって、単なる特定の当事者間の私的な問 題に止まるものではなく、公正な取引秩序そのものに関わる重大な違反が あると認められるものであるから、商標法が先願主義を採り、また、冒認 者による出願が登録拒絶理由として定められていないことを考慮しても、 その登録が公序良俗に反することは明らかといわざるを得ない。 なお、原告は、前記第3の1(1)ウのとおり、本件商標は、その指定商品 について使用実績がある旨主張する。 しかし、これらは単発的なAmazonジャパンへの出品や、売上げを 示すものにすぎない。また、例えば、原告が使用実績として挙げる甲47 の1には、1頁目に「ブランド:Muzili」、2頁目に「ブランド名 Muzili」及び「メーカー zhiyu」との記載があるが、「Mu zili」はオーディオ製品の専業メーカーの商標であり(乙5,6)、 しかも、前記(1)ウのとおり原告が平成29年9月25日から令和3年5月 11日までの間に大量に出願した商標の1つであって(甲13、商願20 18−122372)、極めて不自然である。 そうすると、原告の挙げる使用実績は、早期審査の認定を受けるためか、 商標登録異議や無効審判の請求に対応する名目的なものというべきで、前 記認定判断を覆すに足りる事情に当たるとは到底いえない。その他に原告 がるる主張する点も本件結論を左右し得ない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(ワ)2188等 不正競争行為差止等請求 不正競争 民事訴訟 令和5年1月23日 大阪地方裁判所
原告形態A、同B及び同Cは、いずれもその形態を特定するのに必要とさ れるスピーカー・アンプ内蔵型マイクの全体形状及びこれを構成する各パー\nツの具体的な形状、寸法、位置関係といった構成要素を何ら具体的に特定す\nるものではなく、その構成要素の一部についてのみ抽象的、断片的に指摘す\nるにとどまるものである。加えて、スピーカー部がマイク下部の竿体内に組 み込まれた形態(原告形態A)は、抽象的な位置関係のみをいうのであれば、 そのような配置をしようとすれば避けられない形態であるし(そのように配 置すること自体はアイディアであって、商品等表示とは性質を異にする。)、\nストラップを通すリングがあること(原告形態B)や、端子カバーを開閉可 能につけること(原告形態C)は、いずれも落下防止や端子の汚損等の防止\nのために行われるありふれた工夫であって、出所表示として機能\するものと は到底考えられない。
原告は、原告形態Aないし同Cを組み合わせた全体的な形状が一般的なワ イヤレスマイク(ハンド型)と同様の円筒状様の形態であることを指摘して いるにとどまり、円筒形状であることを超えて、その全体形状及び各構成要\n素について何ら具体的に特定するものではない。したがって、原告形態Aな いし同C及びその組み合わせが、商品等表示として機能\するものとして特定 されているとはいい難い。 この点を措くとしても、原告商品はスピーカー・アンプ内蔵型のマイクで あり、原告は、原告商品をマイクとして広告宣伝していること(甲9の1〜 9の13)に照らすと、スピーカーが内蔵されているか否かにかかわらず、 マイク全般が原告商品の同種商品に該当するものと認められる。そうである ところ、マイク自体が、実用品であって、需要者がその形態等を鑑賞するた めのものではないことに加え、原告が主張するとおり、原告商品は、全体的 な形状が一般的なワイヤレスマイク(ハンド型)と同様の形態とするもので あるから、原告商品が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕 著性)を有さないことは明らかである。 以上から、原告形態Aないし同C及びこれらを組み合わせた形態が原告の 「商品等表示」に該当するものとは認められない。\n
(2) したがって、本訴請求に係るその余の点を判断するまでもなく、原告の本 訴請求は理由がない。
2 反訴請求について
(1) 争点2−1(本件表示の内容が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」\n(不競法2条1項21号)に該当するか)について 本件表示は、原告が、原告商品を模造した被告商品を販売している被告に\n対して販売の中止と損害賠償を求める訴えを提起した旨を摘示するものであ る。この点、「模造」とは、「実物に似せて造ること」を意味し(乙3)、 その言葉自体、本物でない、まがいものを作出するといった否定的に捉え得 るものであることに加え、訴えを提起したという表現は、本件表\示の全体の 文意からすれば、相手方が違法行為に及んでいることを摘示するものと解さ れるから、これに接した閲覧者は、被告が、原告商品を違法に模造した被告 商品を販売していると認識するものと認められる。また、本件表示が掲載さ\nれた時期や記載内容に加え、本訴請求のほか、原告が被告に対して原告商品 に関する訴えを提起したことをうかがわせる証拠はないことに照らすと、本 件表示中の訴えの提起は、本訴請求を指していると解される。\n そうであるところ、前記1のとおり、本訴請求には理由がなく、その他、 被告商品が原告商品を違法に模造したことを裏付ける証拠はないから、本件 表示のうち、被告商品が原告商品を模造した違法なものであることを摘示す\nる部分は「虚偽の事実」に該当するものと認めるのが相当である。そして、 本件表示を閲覧した者は、被告商品が違法な模造商品であると認識し、本件\n表示は、被告商品の市場価値を明らかに低下させるものといえるから、被告\nの「営業上の信用を害する」ものと認めるのが相当である。 以上から、本件表示は「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」に該当\nする。これに反する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(ワ)10443 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年1月12日 東京地方裁判所
ア 本件調査会社は、原告から指定されたコンテンツの品番を含むファイルを トラッカーサイトで検索し、著作権侵害が疑われるファイルのハッシュ値 (データ〔ファイル〕を特定の関数で計算して得られる値のこと。ファイル からハッシュ値は一意に定まるので、ファイルの同一性確認のために用いら れる。)を取得し、本件検知システムに登録した。
イ 本件検知システムは、上記経緯により同システムの監視対象となった上記 ファイルのハッシュ値について、BitTorrentネットワーク上で監 視を行った。具体的には、本件検知システムは、トラッカーサーバーに対し、 上記ファイル(全部又は一部をいう。以下1において同じ。)のダウンロー ドを要求し、当該ファイルをダウンロードできる(所持している)ピアのI Pアドレス、ポート番号等のリストをトラッカーサーバーから受け取って、 本件検知システムのデータベースに記録した(別紙動画目録記載の「IPア ドレス」及び「ポート番号」欄は、当該IPアドレス及びポート番号である。)。 そして、本件検知システムは、上記リストを受け取った後、同リストに載 っていたユーザーに接続をして、同ユーザーが応答することの確認(Han dshake)を行っており、別紙動画目録記載の「発信時刻」欄の日時は、 当該Handshake完了時のものである。
もっとも、本件検知システムは、上記Handshakeの時点において、 上記ユーザーが保有している上記ファイルを実際にダウンロードしていな いものの、上記時点において上記ユーザーから返信された上記ファイルのハ ッシュ値によって、実際に上記ユーザーが上記ファイルを所持していること の確認を行っている。そのため、本件検知システムは、上記時点において直 ちに上記ユーザーから上記ファイルのダウンロードができる状態にあった ことになる。
ウ なお、BitTorrentにおいて、ファイルをダウンロードするよう になったユーザーは、BitTorrentクライアントソフトを停止させ\nるまで、トラッカーサーバーに対し、当該ファイルが送信可能であることを\n継続的に通知し、他のユーザーからの要求があれば、当該ファイルを送信し 得る状態になっている。
(2) 権利侵害の明白性
前記前提事実記載のBitTorrentの仕組み及び上記認定事実記載 の本件検知システムの仕組み等によれば、本件発信者は、本件動画をその端末 にダウンロードして、本件動画を不特定多数の者からの求めに応じ自動的に送 信し得るようにした上、別紙動画目録記載のIPアドレス及びポート番号の割 当てを受けてインターネットに接続し、Handshakeの時点である別紙 動画目録記載の「発信時刻」欄記載の日時において、不特定の者に対し、Bi tTorrentのネットワークを介して本件動画に係る送信可能化権が侵\n害されその状態が継続していることを通知したものと認めるのが相当である。 そして、当事者双方提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の 違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはで きない。
これらの事情を踏まえると、本件発信者は、Handshakeの時点にお いて、不特定の者に対し、BitTorrentのネットワークを介して本件 動画に係る送信可能化権が侵害されその状態が継続していることを通知して\nいるのであるから、本件発信者によるHandshakeに係る情報は、プロ バイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当する ものと解するのが相当である。また、本件発信者によるHandshakeに 係る情報は、上記のとおり、不特定の者において、本件動画に係る送信可能化\n権が侵害されその状態が継続していることを確認する上で、必要な電気通信の 送信であるといえるから、「特定電気通信」にも該当するものと解するのが相 当である。
(3) 被告の主張
ア 被告は、Handshakeは応答確認にすぎず、本件動画のアップロー ド又はダウンロードではないから、Handshakeに係る情報は、送信 可能化権の侵害に係る発信者情報には当たらないと主張する。しかしながら、\n本件発信者が、Handshakeの時点において、不特定の者に対し、本 件動画に係る送信可能化権が侵害されその状態が継続していることを通知\nしていることは、上記において説示したとおりであり、当該事実関係を前提 とすれば、Handshakeに係る情報が「権利の侵害に係る発信者情報」 に該当するものと認めるのが相当である。したがって、被告の主張は、採用 することができない。
また、被告は、本件発信者は、Handshake時までに、本件動画の ファイルのピースさえ保有していない可能性があると主張する。しかしなが\nら、前記認定事実によれば、確かに、本件検知システムは、Handsha keの時点において、ユーザーが保有しているファイルを実際にダウンロー ドしていないものの、本件検知システムは、上記時点において上記ユーザー から返信された上記ファイルのハッシュ値によって、実際に上記ユーザーが 上記ファイルを所持していることの確認を行っていることが認められる。そ うすると、本件発信者は、Handshakeの時点までに、少なくとも当 該ファイルのピースを所持しているものと推認するのが相当であり、これを 覆すに足りる証拠はない。したがって、被告の主張は採用することができな い。
イ その他に、被告提出に係る準備書面を改めて検討しても、上記認定に係る 本件検知システムの仕組み等を踏まえると、被告の主張は、上記判断を左右 するに至らない。したがって、被告の主張は、いずれも採用することができ ない。
(4) 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対し、損害賠償請求を予定し\nていることが認められることからすると、原告には本件発信者情報の開示を受 けるべき正当な理由があるものといえる。
(5) したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、 本件発信者情報の開示を求めることができる。
関連カテゴリー
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和3(ワ)13720 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和5年1月20日 東京地方裁判所
1 争点1(被告表紙等が原告表\紙を「原作のまま…複製」(著作権法80条1項 1号)したものであるか)について (1) 前記前提事実(2)イのとおり、原告は、Bとの間で、本件出版契約を締結し、 原告漫画について、紙媒体出版物(オンデマンド出版を含む。)として複製 し、頒布することなどを内容とする「出版権」の設定を受けることを合意し たところ、この合意内容によれば、原告は、原告漫画を目的とする出版権と して、「頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方 法により文書又は図画として複製する権利」(著作権法80条1項1号)を 取得したものと認められる。 そして、上記出版権は、著作物を「原作のまま…複製する権利」であるこ とからすると、出版権の目的である著作物を有形的に再製する行為には及ぶ が、上記著作物のうち創作的表現とは認められない部分と同一性のあるもの\nを作成する行為には及ばないし、翻案、すなわち、上記著作物の表現上の本\n質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加え\nて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が\n上記著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物\nを創作する行為(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第1 小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)にも及ばないと解される。 (2) 証拠(甲4、5)によれば、被告が作成した被告表紙等は、少なくとも以\n下の部分において、原告表紙と相違すると認められる(以下、これらの相違\n部分を「本件相違部分」という。)。
ア 原告人物1の髪は目及び耳にかかる程度の長さで描かれているのに対し、 被告人物1の後髪は肩にかかり、横髪は耳を隠し、前髪は頬にかかるほど の長さで描かれている部分
イ 原告人物1の右耳は飾りが付いていないように描かれているのに対し、 被告人物1の右耳はピアスのように見える飾りが付いているように描かれ ている部分
ウ 原告人物2の髪は自然に流れるようにウェーブした状態に描かれている のに対し、被告人物2の髪は、複数の束となっており、束ごとに髪先が直 線的に切りそろえられた状態に描かれている部分
エ 原告人物2の瞳は略楕円形で、眉毛は細い線のように描かれているのに 対し、被告人物2の瞳は略円形で、眉毛は太く描かれている部分
オ 原告人物2は口をほとんど開けていないように描かれているのに対し、 被告人物2は、口を開き、歯が覗くように描かれている部分 カ 原告人物1及び2は学生服及びワイシャツを着ているように描かれてい るのに対し、被告人物1及び2は学生服及びワイシャツとは異なる服を着 ているように描かれている部分
(3) 前記前提事実(1)イ及び(3)並びに前記(2)の認定事実によれば、二次創作同 人誌を発行していた被告は、自らの知識や経験に基づき、被告漫画のストー リーや登場人物の設定等を念頭に置きつつ、被告漫画の表紙及び中表\紙とし てふさわしいものとなるように考えながら、原告表紙との本件相違部分を含\nむ被告表紙等を作成したということができる。そして、本件相違部分は、人\n物の髪型、目及び衣服といった当該人物の外見を特徴付ける部分に関する表\n現であり、別紙対比表からも明らかなとおり、被告表\紙等における被告人物 1及び2の外見の描写のうち本件相違部分が占める割合は小さくない。さら に、本件相違部分に係る表現がありふれたものであることを認めるに足りる\n証拠はない。したがって、本件相違部分には、被告の思想又は感情を創作的 に表現した部分が含まれると認めるのが相当である。\n
そうすると、原告表紙と被告表\紙等との共通部分に創作的表現が認められ\nない場合には、被告表紙等は、原告表\紙のうち創作的表現とは認められない\n部分と同一性があるにすぎず、被告は、創作的表現を含む本件相違部分を備\nえた、原告表紙とは別の新たな著作物である被告表\紙等を創作したといえる。 また、上記共通部分に創作的表現が認められる場合には、被告は、新たに創\n作的表現を含む本件相違部分を加えることにより、原告表\紙の表現上の本質\n的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である被告表紙等を創作し\nたものであるから、原告表紙を翻案したものといえる。\n
以上によれば、被告表紙等は、いずれにしても、原告表\紙を「原作のまま …複製」(著作権法80条1項1号)したものとは認められないから、被告 が被告表紙等を作成したことにより原告漫画に係る原告の出版権が侵害され\nたとは認められない。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(行ケ)10087 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年1月17日 知的財産高等裁判所
ア 本願商標は、左向きの牛の全身を表した図形と、同図形の下側に、「EM\nPIRE STEAK HOUSE」の文字を表してなる結合商標である。\n そして、上記文字部分は同図形部分に比してかなり小さく表されてはい\nるものの、両者は、相互に重なり合うこともなく配置され、文字部分が図 形部分に埋没した印象を与えることもなく、文字として明瞭に認識できる ものであるから、文字の持つ本来的な訴求力の強さに鑑みて、同図形部分 と同文字部分は、それぞれが独立した構成部分として、視覚上十\分に分離 して認識され得るものである。
イ 前記アのように分離して認識される本願商標の構成中、左向きの牛の全\n身を表した図形部分は、何らかの行動をとる前の牛の全身を表\したものと は認識できるが、その様子が象徴的な態様又は具体的行動を表現したもの\nとは看取できず、また、この牛が特定のキャラクター等の主体を表したも\nのとは見受けられず、さらに、比較的写実的に牛を描いていることからそ の色合や形に印象的といえる部分も見受けられず、結局、「牛」の称呼及び 観念を生じさせるにとどまる。
そうすると、本願商標の構成中の牛の図形部分は、本願商標の指定役務\n中「ステーキ料理の提供」との関係においては、提供される料理の食材が 牛であるという印象を与えるにすぎないといえ、実際の取引においても、 ステーキハウスを含む牛肉等に関連した料理を提供する店舗において、食 材である牛の全身又は一部をモチーフとした図形を用いる例が見受けら れ(乙33ないし41)、このようなことは広く一般的に行われていること といえる。したがって、前記牛の図形部分は、本願商標の指定役務中、「ステーキ料 理の提供」との関係において、自他役務識別機能を有しないか又は同機能\ が極めて弱いものである。
ウ 前記アのように分離して認識される本願商標の構成中、「EMPIRE ST EAK HOUSE」の文字部分については、「EMPIRESTEAKHOUSE」な る1語が存在することはうかがわれない一方、「EMPIRE」、「STEAK」及 び「HOUSE」の文字の間に間隔が置かれていることからみて、「EMPIR E」、「STEAK」及び「HOUSE」の3語からなるものと認識されるところ、 「EMPIRE」の文字は、「帝国」を意味する英単語であるが、英和辞典にお いて高校学習単語とされる英単語であり、国語辞典においても「エンパイ ア」の見出し語の下に「帝国」の意味を有する語として掲載されており(乙 2ないし4)、我が国においても容易に意味が理解される親しまれた語と いえる。そして、「EMPIRE」の語から生じる「帝国」の観念や「エンパイ ア」の称呼が、本願商標に係る指定役務について、これら役務の提供の場 所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又は時期そ\nの他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないから、「E MPIRE」の文字は、「ステーキ料理の提供」を含む本願商標の指定役務と の関係において、自他役務識別機能が強いといえる。\n
他方、「EMPIRE STEAK HOUSE」の文字部分のうち「STEAK」と 「HOUSE」についてみると、「STEAK HOUSE」の文字が「ステーキ専 門店」の意味を有する英語であること(乙5)、この語が飲食物の提供の一 業態を示すものとして一般に用いられていることは当事者間に争いがな いことや、実際の取引においても、本願商標の指定役務のうち、「ステーキ 料理の提供」を行う業界においてこの語が普通に用いられている例が見受 けられこと(乙6ないし16)からみて、広く一般に定着した語と認めら れ、「STEAK」と「HOUSE」の語は、ステーキ専門店を意味する「STE AK HOUSE」を表すると認識されるものと認められる。\n そして、「STEAK HOUSE」の語が本願商標の指定役務中、「ステーキ 料理の提供」に使用される場合には、役務の提供の場所、質を意味するも のといえるから、本願商標の構成中「STEAK HOUSE」の文字部分は、 自他役務識別機能を有しないか又は同機能\が極めて弱いというべきであ る。このような場合、自他役務の識別のためにはそれ以外の部分が重視さ れ、自他役務識別機能を有しないか又は同機能\が極めて弱い部分は省略さ れることがあり得べきところ、実際の取引においても、「STEAK HOUS E」又は「ステーキハウス」を含むステーキ料理の提供を行う店舗名が、「S TEAK HOUSE」又は「ステーキハウス」の文字部分を除いて略称される 例が見受けられるから(乙17ないし31)、我が国において、「STEAK HOUSE」又は「ステーキハウス」の語は、ステーキ専門店を区別して指 示する際には省略されることが普通にあり得ることと認められる。
エ 前記イ及びウを踏まえると、取引者及び需要者の認識に対する影響力と いう点から見れば、本願商標は、「EMPIRE」の文字部分が外観上目立つも のではないにしても、取引者及び需要者に対して自他役務の識別標識とし て強く支配的な印象を与えるといえるから、本願商標より「EMPIRE」の 文字部分を商標の要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標の 類否を判断することが相当であるというべきである。そうすると、本願商標は、その要部の「EMPIRE」に相応して、「エンパ イア」の称呼及び「帝国」の観念が生じるものというべきである。
(2) 引用商標について
引用商標は、「EMPIRE」の文字を標準文字で表してなるものであるから、\nこれより「エンパイア」の称呼及び「帝国」の観念が生じるものである。
(3) 本願商標と引用商標の類否について
本願商標の要部である「EMPIRE」の文字部分と引用商標とを比較すると、 両者は、いずれも普通に用いられる書体で、「EMPIRE」と表してなるもの\nで、外観において紛らわしく、称呼(「エンパイア」)及び観念(「帝国」)は 同一であることから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしく、 互いに類似するというべきである。 したがって、本願商標全体の外観と引用商標の外観が相違することを考慮 しても、両商標は、同一又は類似の役務に使用された場合には、当該役務の 出所について混同を生じるおそれがある類似の商標と判断すべきである。
(4) 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務中、第43類「ステーキ料理の提供」は、引用商標の 指定役務中、第43類「焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」 と、役務の提供の場所や質(内容、業種)を共通にすることから、両者は同 一又は類似のものである。
・・・
2 原告の主張について
(1) 原告は、前記第3の1 のとおり、需要者、取引者は飲食店の選別に当た り屋号や店名の全体を注意深く観察するものであるところ、本願商標中の「E MPIRE STEAK HOUSE」の文字は、外観上まとまりよく一体的に配され ており、各語の間隔も同一であり、そこから生じる「エンパイアステーキハ ウス」の称呼もよどみなく一連に称呼され得るものであるから、上記文字部 分は、一連一体のものとして称呼、認識される旨主張する。 しかしながら、ステーキ料理の需要者がどの料理店を選択するかに当たっ ては、「STEAK HOUSE」の部分は当該選択に当たって何ら必要な情報を 与えるものではないから、「EMPIRE STEAK HOUSE」に外観上まとまり があって一体的であろうと、称呼がよどみなく一連に称呼できものであろう と、需要者が着目しているのは「EMPIRE」の部分といえる。 したがって、原告の主張は当を得たものとはいい難く、これを採用するこ とはできない。また、原告は、前記第3の1 のとおり、「EMPIRE」から一義的に「帝国」の観念が生じるとすることは誤りである旨主張するが、前記1(1)ウのとおり、 「EMPIRE」から「帝国」の観念が生じることは明らかであり、「帝国」に加 えて「帝国」以外の観念が生じる可能性があるからといって、「帝国」の観念\nが生じていないとはいえないから、原告の上記主張を採用することはできな い。
以上によれば、上記各主張を前提とする原告の主張(前記第3の1(3))に ついては、その前提に誤りがあるから、採用できないというほかない。 原告は、前記第3の1(3)のとおり、1)「EMPIRE BURGER HOUSE」 との商標の登録例、2)ある文字に「STEAK HOUSE」等が結合された商標 の登録例、3)ある文字からなる商標と当該文字に店名を表示する際の接尾語\nを結合した商標を非類似とする審決等の例からみて、本願商標の登録を認め ない本件審決は不合理である旨を主張するが、商標の類否判断は、商標の構\n成、指定役務、取引の実情等を踏まえて、商標ごとに個別に判断すべきもの であって、原告が指摘するような他の商標登録事例等があるからといって、 本願商標と引用商標の類否判断が影響を受けるものではないから、上記主張 は結論を左右しないものであり、採用することができない。
なお、あえて付言すれば、「EMPIRE BURGER HOUSE」との商標は、 「EMPIRE STEAK HOUSE」との本願商標とは、「BURGER」との語の部分が異なるほかは構成を共通にするものであるが、「BURGER HOUSE」 の語は、「STEAK HOUSE」の語と比してわが国での親和度は低いものと も考えられ、その場合、「EMPIRE」に対する「BURGER HOUSE」との語 の自他役務の識別能力は、「STEAK HOUSE」の場合と比すれば相対的に 高いとみることも可能であるから、語の構\成だけをみて「EMPIRE BURG ER HOUSE」と「EMPIRE STEAK HOUSE」とを同列に論ずることは妥当ではなく、「EMPIRE BURGER HOUSE」との商標が登録され「EM PIRE STEAK HOUSE」との本願商標の登録が拒絶されているからといっ て、これを直ちに不合理な取扱いであるとすることはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.02.17
平成29(ワ)4178 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月31日 大阪地方裁判所
被告は、平成11年5月から平成12年4月までの間に、日本製紙八代工場に ベルト4反(ベルトB)を納品し、ベルトBが同工場において平成11年6月1 1日から平成12年5月9日までの間に使用開始されており、ベルトBの構成は\n本件発明1の構成要件と一致し、納品によってその構\成が日本製紙に知り得る状 態となり、また、当業者はDMTDAの同定が可能であったとして、本件特許1\nの出願前にベルトBに係る発明が公然実施された旨主張するので、以下検討する。 (1)ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる(なお、 原告は乙32が真に平成11年に作成されたのか不明である旨を主張するが、そ の体裁等に照らすと、作成日等に関する疑義は認められない。)。 (ア) 被告は、昭和63年からベルトを製造していたところ、平成8年4月に新 工場を新設して、ベルトの製造を集約することとなった。それに伴い、被告では、 品質を一定の水準以上に維持するために、製造工程の一連の流れ、各ステップの 管理項目、品質特性(品質保証項目)及び管理方法を明確にしたルールを作成す ることとなり、平成11年2月26日、QC工程図が作成された。(以上につき、 乙32、83) QC工程図には、樹脂コーティング工程に関し、1)ビス(メチルチオ)−2, 4−トルエンジアミン、ビス(メチルチオ)−2,6−トルエンジアミン及びメ チルチオトルエンジアミンの混合物であるエタキュアー300(硬化剤)のほか、 イソシアネート基を末端に有するプレポリマーである、タケネートL2390及\nびタケネートL2395を受け入れ、10)1)の樹脂を調合し、11)基布(ベース)の シュー側(内周面側)にコートしてキュアし、その後、15)反転して、18)1)で受け 入れた樹脂を調合し、19)基布(ベース)のフェルト側(外周面側)にもコートし てキュアする旨の記載がある(乙32〜36、130〜132。なお、数字は工 程番号を指す。)。
(イ) 被告は、QC工程図に従って、平成11年3月1日から同月4日の間に反 番51+01349のベルト、同年8月5日から同月10日の間に反番51+0 4750のベルト、同年10月1日から同月5日の間に反番51+06801の ベルト及び平成12年2月15日から同月22日の間に反番52+00481の ベルトの各樹脂コーティング工程作業を行い、その頃、基布面を完全に被覆する 両面樹脂構造であり、かつ、排水溝を有するベルトBの製造を完了させ、日本製\n紙に対し、平成11年5月14日、同年9月3日、同年10月21日及び平成1 2年4月27日、それぞれ納品した(乙25、27〜31、83)。
イ 前記ア(ア)及び(イ)によれば、ベルトBは、ポリウレタンにより基布が完全 に被覆されており、内周面及び外周面のポリウレタンは、末端にイソシアネート\n基を有するウレタンプレポリマーとDMTDAを含有する硬化剤とを含んでおり、 熱硬化性であることが認められる。そうすると、公然実施発明Bは、基布を熱硬 化性ポリウレタンが完全に被覆してなり、前記基布が前記ポリウレタン中に埋設 され(構成B−a)、フェルト側およびシュー側が前記ポリウレタンで構\成され たシュープレス用ベルトにおいて(構成B−b)、フェルト側を構\成するポリウ レタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ビス(メ\nチルチオ)−2,4−トルエンジアミンおよびビス(メチルチオ)−2,6−トル エンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている(構成B−\nc)、シュープレス用ベルト(構成B−d)という構\成を有していることが認め られ、本件発明1の各構成要件を充足する。\n(2) 特許法29条1項2号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数 の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)ア(イ)の とおり、被告は、本件特許1出願前の平成11年5月14日から平成12年4月 27日までの間、日本製紙に対し、ベルトBを納品し、その内容を不特定多数の 者が知り得る状況で公然実施発明Bを実施したものと認められる。
(3) 原告の主張について
原告は、ベルトの現物自体からは当該ベルトが幾つの層によって構成されてい\nるか等を把握することは不可能であること、ベルトを構\成するポリウレタンは様々 な化学物質で構成されているから、外周面を構\成するポリウレタンに含有される 硬化剤に着目した分析が行われたとはいえないこと、当時、硬化剤として考え得 る候補物質は極めて多数存在していた上に、エタキュアー300を用いることで クラックの発生を抑制できることは当業者においてすら知られていなかったから、 硬化剤としてDMTDAに着目し、これをわざわざ入手してサンプルとして分析 機関に送付し、分析を依頼したとは到底いえないことを指摘して、ベルトBを日 本製紙に納品したとしても、ベルトBの外周面に硬化剤としてDMTDAが含有 されていたことが特定できたとはいえない旨を主張する。
しかし、前記(1)アのとおり、ベルトBは、日本製紙に納品され、自由に解析等 をなされ得る状態におかれたものであり、解析等によりベルトの構造等を特定す\nることは可能であるほか(甲25等参照)、本件特許1の出願日前において、外\n周層、内周層等の複数の層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリ マーと硬化剤とを混合してポリウレタンとし、ベルトの弾性材料とすることは、 技術常識に属する事項であった(甲2、乙26、27)。これに加え、証拠(乙 37、124、127〜133)及び弁論の全趣旨によれば、1)昭和62年に発 行された書籍において、実用化されている硬化剤として、MOCAのほかにエタ キュアー300が紹介されていたこと、2)米国の会社が平成2年に発行したエタ キュアー300のカタログにおいて、エタキュアー300は、新しいウレタン用 硬化剤であり、TDI(トルエンジイソシアナート。主にポリウレタンの原料と\nして使用される化学物質)系プレポリマーに使用した場合、MBCA(MOCA と同義。乙140、141)の代替品として、現在最も優れたものであると確信 している旨が記載されていたこと、3)米国の別の会社は、平成10年に日本向け のエタキュアー300のカタログを発行したこと、4)平成11年に日本国内で発 行された雑誌には、MOCAには発がん性があることが指摘されており、より安 全性の高い材料が求められていたが、1980年代後半には、既にMOCAに代 わる新しい硬化剤としてエタキュアー300が開発された旨の記事が掲載されて いたこと、5)被告は、平成3年頃からエタキュアー300の研究を開始し、遅く とも平成9年7月時点では、製紙用ポリウレタンベルトの硬化剤としてエタキュ アー300を使用していたこと、6)本件特許1の出願前に、エタキュアー300 と同様にウレタン用に使用された主要な硬化剤は、10種類前後であったことが 認められる。これらの事実関係に照らすと、本件特許1の出願前に、エタキュアー 300は、ウレタン用の硬化剤として注目され、実用化されていたものと認めら れ、分析機関のライブラリにDMTDAのマススペクトルが登録されていなかっ たとしても(平成29年時点において、ライブラリにDMTDAのマススペクト ルを登録している分析機関と登録していない分析機関がある(甲11、24)。)、 エタキュアー300をサンプルとして分析機関に送付して分析を依頼した蓋然性 があったといえ、当業者は、公然実施発明Bの内容を知り得たものと認められる。 証拠(甲39、40)及び弁論の全趣旨によれば、原告が、平成30年6月、 分析機関に対し、組成を明らかにすることなく被告製品3及び4のサンプルを送 付し、ポリウレタンの定性分析を依頼したところ、硬化剤について特定すること ができなかったことが認められる。しかし、同分析機関が硬化剤を特定すること ができなかったのは、同分析機関のライブラリにDMTDAのマススペクトルが 登録されていなかったこと(甲24の3)によるものと認められるところ、前記 のとおり、エタキュアー300をサンプルとして分析機関に送付して分析を依頼 した蓋然性があったといえることに照らすと、前記結果(甲39、40)は、当 業者が公然実施発明Bの内容を知り得たという結論に影響を与えるものではない。 したがって、原告の前記主張は採用できない。
(4) 以上から、本件発明1は、本件特許1の出願前に日本国内において公然実 施された発明であるから、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきもの であって、原告は、被告に対し、本件特許権1を行使することができない(特許 法123条1項、104条の3第1項、29条1項2号)。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和4(ネ)10071 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は、仮に本件発明7の構成要件Aの「圧力風の作用のみによって」\nの構成は、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移\n送が「圧力風」の「作用」だけで実現されることをいい、「圧力風」の「作 用」以外の作用が加わって上記移送が実現されるものは、「圧力風の作用の みによって」を備えるとは認められないと解した場合には、被告各製品にお いては、「圧力風」の「作用」にブラシの回転作用が加わることによって茶 枝葉が移送ダクト内に送り込まれている点で、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるとはいえず、本件発明7と相違することとなるとしても、被\n告各製品は、均等の第1要件ないし第5要件を充足するから、本件発明7の 特許請求の範囲(請求項7)に記載された構成と均等なものとして、本件発\n明7の技術的範囲に属する旨主張する。
そこで、まず、均等論の第1要件について検討するに、本件発明7の特 許請求の範囲(請求項7)の記載及び前記1(2)認定の本件明細書の開示事 項を総合すれば、従来の茶葉の摘採を行う摘採機は、「刈刃前方側に茶葉移 送のための分岐ノズル付き送風管を配し、分岐ノズルからの送風によって、 刈刃から収容部まで茶葉を移送するのが一般的であり、その移送路は、刈刃 のほぼ後方に延びる水平移送部と、その後に収容部の上部に臨むように接続 された上昇移送部を具えていたが、このような移送形態(送風形態)では、 水平移送部を要する分、移送装置、ひいては摘採機の前後長が長くなり、摘 採機の取り回し性を低下させてしまうという問題があったことから、本件発 明7は、上記問題を解決し、水平移送部を設けることなく、刈取直後、即、 茶葉を上昇移送できるようにし、摘採機の前後寸法の短縮化を図り、摘採機 をコンパクトに構成できるようにした茶枝葉の移送装置を開発することを課\n題とし、この課題を解決するための手段として、水平移送部を設けることな く、刈刃の後方から移送ダクト内に背面風を送り込む吹出口が設けられ、こ の吹出口から移送ダクト内に背面風を送り込むことによって、刈取後の茶枝 葉を刈刃から所定の位置まで移送する構成を採用し、具体的には、刈刃後方\nからの背面風によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この移送ダクト 内に流す圧力風の作用のみにより、負圧吸引作用によって刈り取り直後の茶 枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部な ど適宜の部位に移送する構成とし、これにより刈り取り直後、水平移送部を\n設けることなく、そのまま茶枝葉を上昇移送することができ、前後長の短縮 化が図れ、コンパクトな茶刈機が実現できるという効果を奏することに技術 的意義があり、水平移送部を設けることなく、刈刃の後方側から送風される 「圧力風の作用のみ」によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この負 圧吸引作用によって刈り取り直後の茶枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後 は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部4など適宜の部位に移送するようにした ことが、本件発明7の本質的部分であるものと認められる。
しかるところ、前記2(2)で説示したとおり、被告各製品においては、 「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が「圧力風」の作用に 「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が加わることによって実 現されているといえるから、被告各製品は、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるものとは認められない。\nしたがって、被告各製品は、本件発明7の本質的部分を備えているもの と認めることはできず、本件相違部分は、本件発明7の本質的部分でないと いうことはできないから、均等論の第1要件を充足しない。
◆判決本文
1審は、こちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.02.17
令和2(ネ)10009等 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟__全文__ 令和5年1月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人が平成11年5月頃に自らプログラムやレンタルサーバを準備した上 で本件電子掲示板を開設したこと(前記2(2)ア)、その後、利用者の増加に伴い、 ボランティアの協力によって本件電子掲示板の維持や機能向上等が図られるように\nなり、控訴人は不要なデータの削除作業等を行うようになっていったものの、本件 電子掲示板のプログラムの修正等に参加する技術的ボランティアは、控訴人から、 又は、NTテクノロジー社のサーバの使用を控訴人に申し出て控訴人の了承を得る\nなどして平成12年頃から本件電子掲示板の運営に関与していたBから、技術的ボ ランティアとして参加することの許諾を得るなどしていたこと(同(2)イ(ア)・(ウ))、 平成14年頃から平成26年2月に至るまで、本件電子掲示板の広告料収入は控訴 人が代表取締役を務める東京プラス社が取得し、その中から控訴人名義でNTテク\nノロジー社に送金がされるなどしていたこと(同(1)ウ、(2)エ(ア))、平成16年及 び平成17年に控訴人が対外的にも本件電子掲示板の管理人として活動し、平成1 8年5月12日発行の「2ちゃんねる公式ガイド2006」にも控訴人が本件電子 掲示板の生みの親であることなどが記載されていたこと(同(2)カ、キ)のほか、そ の後も控訴人が平成18年当時本件電子掲示板の管理人であったことに沿う事実が 認められること(同(2)ク〜シ・セ・ト)を考慮すると、前記(1)で原判決の第3の 4(3)を訂正の上で引用して認定したように「2ちゃんねる」の標章及び「2ch.net」 の標章が周知性を獲得したというべき平成18年の時点において、その役務の提供 の主体は、控訴人であったというべきである。
イ(ア) 他方で、本件全証拠をもってしても、平成18年の時点及びそれ以降平成 26年3月27日(原告商標2の出願日)までのいずれかの時点において、「2ち ゃんねる」の標章及び「2ch.net」の標章が、NTテクノロジー社又は被控訴人の業 務に係る役務を表示するものとなったとみるべき事情は認められない。\n
(イ) この点、NTテクノロジー社については、本件電子掲示板のサーバを提供し たこと(前記2(2)イ(ア))や、PINKちゃんねるを開設し、2ちゃんねるビュー アの販売及び運営を行うようになったこと(同(2)ウ)、平成14年頃以降、本件電 子掲示板の広告料の売上げからの送金を受けていたほか、2ちゃんねるビューア「●」 の売上げを取得していたこと(同(2)ウ・エ)、本件ドメイン名について平成17年 5月10日時点でAが運営面に関する連絡先として登録されたりNTテクノロジー 社が登録サービス提供者として登録されたりしていたこと(同(3)イ〜カ)が認めら れる。
しかし、サーバの提供者が直ちに当該サーバを用いた事業の運営者となるもので はないことは明らかである。また、PINKちゃんねるは、あくまで本件電子掲示 板とは別個のアダルト版の掲示板として運営されていたことがうかがわれるから (弁論の全趣旨)、それを開設等したことからNTテクノロジー社が本件電子掲示 板の運営者となったということはできない。2ちゃんねるビューアの販売及び運営 についても、本件電子掲示板の古いスレッドを閲覧できるなどといったその利点か らして、2ちゃんねるビューアは、掲示板の中核的な機能というべき文書等の掲示、\nすなわち、本件電子掲示板における書込みや直近の掲示板の閲覧という機能と比べ\nると補足的な機能に係るものにすぎないといえ、その販売及び運営が直ちに本件電\n子掲示板本体の運営者であることを基礎付けるものとはいえない(この点、被控訴 人は、NTテクノロジー社が2ちゃんねるビューアを開発したと主張するが、当該 事実を認めるに足りる証拠もない。)。本件電子掲示板の広告料の売上げからの送 金についても、NTテクノロジー社が本件サーバ(NT)を本件電子掲示板のため に提供していたことからすると、控訴人が主張するように同提供の対価とみること もでき、本件電子掲示板の運営者であることを基礎付けない(なお、平成26年2 月の段階でも、NTテクノロジー社は、東京プラス社に対し、「Internet Services」 名目で金員を請求していたところである(前記2(2)タ)。)。本件ドメイン名の登 録に係る前記事情についても、そもそもドメイン名の登録名義と当該ドメインを用 いた事業の主体が同一であるという経験則が確固として存在するとは解し難いこと に加え、NTテクノロジー社が本件サーバ(NT)の提供者であったことや、本件 電子掲示板の事業形態等に変動があったことが他の証拠から特段うかがわれない時 期においても本件ドメイン名の登録情報が頻繁に変更され、かつ、それには単に名 義のみの変更であったことがうかがわれる複数の会社が含まれていること(同(1) エ、同(2)コ・サ(ウ)・セ、同(3)ア〜カ)を踏まえると、NTテクノロジー社が本件 電子掲示板の運営者であったことを裏付けるものとはいえない。
上記に関し、Aの陳述報告書(乙10、11)及び尋問調書の写し(乙12)に は、NTテクノロジー社が本件電子掲示板のプログラミング等に関与していた旨の 陳述ないし供述の記載があるが、そのような関与をするに至る経緯や具体的な関与 態様について何ら触れるものでなく、上記記載からそのような関与の事実を認める には足りず、他に当該事実を認めるに足りる証拠はない。
また、被控訴人は、B及びその他のゼロ社の関係者が本件電子掲示板のプログラ ムの修正等に深く関わっていたことを主張するが、BがNTテクノロジー社の代理 人等として当該修正等を行っていたと認めるに足りる証拠はなく、また、ゼロ社と NTテクノロジー社を一体的なものとみるべき事情等も認められないから、被控訴 人の上記主張は、NTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営者であったことを根 拠付けるものとはいえない(なお、一般に、ウェブサイトのプログラムの作成や修 正等は、当該ウェブサイトに係る事業の運営者によって行われる場合もあれば、当 該運営者から委託を受けた第三者によって行われる場合等もあるのであって、単に 本件電子掲示板のプログラムの修正等に深く関与したという事実から、本件電子掲 示板の運営者であることが直ちに基礎付けられるものでもない。この点、本件電子 掲示板のボランティアについては、その関与態様のほか、少なくとも平成26年1 月25日当時、ボランティアには一切の義務も責任もない旨が本件電子掲示板に明 記されていたこと(前記2(2)イ(ウ))も考慮すると、ボランティアにおいて、自ら が控訴人とともに本件電子掲示板の運営者の一人であるとして本件電子掲示板のプ ログラムの修正等の作業に参加していたものとは解し難く、Bにおいては特に本件 電子掲示板への関与が深かったことがうかがわれることを考慮しても、なお、Bに ついても他のボランティアと異なるものとは直ちに認め難いところである。)。 付言するに、東京プラス社がNTテクノロジー社を被告として提起した訴訟の控 訴審判決において、NTテクノロジー社が共同事業と称するのも理解できる旨など が述べられているが(前記2(2)テ)、それは、2ちゃんねるビューアの販売収益等 も含めた評価であって、本件電子掲示板の運営に限らず、より広く本件電子掲示板 及びそれに関連する事業における東京プラス社とNTテクノロジー社の関係性につ いていうものとみることができ、NTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営者で あったとは認められないとの前記判断と矛盾するものではない。
(ウ) 被控訴人については、NTテクノロジー社が本件電子掲示板に関連して行っ ていた業務を引き継いだこと(前記2(2)オ)や、平成24年5月3日までに本件ド メイン名の登録者となったこと(同(3)カ)、世界知的所有機関の調停仲裁センター により被控訴人による本件ドメイン名の使用が正当なものと認められたこと(同(3) キ)が認められるが、前記(イ)のとおりNTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営 者であったとは認められない以上、被控訴人が引き継いだ業務(その内容は明確で はないが、少なくとも本件関与期間の開始時点前日である平成26年2月18日ま では、PINKちゃんねるに関する業務や、2ちゃんねるビューアに関する業務で あったとみられる。)をもって、被控訴人が本件電子掲示板の運営者であることを 基礎付けるものとはいえず(なお、Bやゼロ社の作業ないし業務をもって被控訴人 によるものとみるべき事情も見当たらない。)、本件ドメイン名の登録者となった ことについても、前記(イ)で指摘した点に照らし、被控訴人が本件電子掲示板の運営 者であったことを裏付けるものではない。また、上記調停仲裁センターの判断につ いても、あくまで当該事件について適用されるべき手続規則に基づく立証責任と当 該事件において提出された証拠に基づく判断であると解され、本件の判断を左右す るものではない。
2023.02. 9
令和4(行ケ)10090 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年1月31日 知的財産高等裁判所
以上によれば、商標法施行規則別表において定められた商品又は役務\nの意義は、商標法施行令別表の区分に付された名称、商標法施行規則別\n表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、\n国際分類を構成する類別表\注釈において示された商品又は役務について の説明、類似商品・役務審査基準における類似群の同一性等を参酌して 解釈するのが相当である(最高裁判所平成21年(行ヒ)第217号同2 3年12月20日第三小法廷判決・民集65巻9号3568頁)。 そうすると、商標法6条2項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 の類似の範囲を定めるものではないが(同条3項)、上記のような観点に 照らして各区分に属する商品又は役務の意義を確定しておくことは、商 品又は役務の類否の判断の前提として必要である。 商標法施行令別表は、第41類として「教育、訓練、娯楽、スポーツ及\nび文化活動」を、第43類として「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」を 規定している。
商標法施行規則別表によれば、第41類の中に「十\三 娯楽施設の提 供 囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場 の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の 提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供」が挙げられ、第43類の中 に「二 飲食物の提供 ・・・ (三) 中華料理その他の東洋料理を主と する飲食物の提供 インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提 供 上海料理の提供 北京料理の提供 (四) アルコール飲料を主とす る飲食物の提供」が挙げられている。 類別表注釈の「第11−2019版」の第43類の項(乙6)によれば、\n同類に属する「飲食物の提供」の役務は、「主として消費のための飲食物 を用意することを目的とする人又事業所が提供するサービス」とされる 一方、国際分類の「第11−2019版」(乙8)には、第41類として 「ナイトクラブの提供」が例示されている。また、類別表注釈の「第11\n−2022版」の第43類の項(乙9)には、「この類には、特に、次の サービスを含まない:」として、「例えば・・・ディスコ及びナイトクラ ブにより提供される、宿泊又は飲食物の提供が付随しうるものを含む、 知識の教授及び指導並びに娯楽の提供(第41類);」が挙げられ、第4 1類の項(乙7)には「娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とする サービス」が挙げられている。 以上の点を参酌しつつ、「ホストクラブ」は、「ホスト(クラブなどの 接客係の男性)が主に女性客をもてなす酒場。」(広辞苑第7版、平成3 0年1月12日発行、甲5)であり、飲食物の提供が付随する娯楽を提供 するものとしてナイトクラブと同様であることに鑑みると、本願商標の 指定役務の「ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言 ・相談若しくは情報の提供」は、娯楽サービスの提供(接待等)の面でな く、飲食物の提供の面から検討するのが相当である。
イ 提供の手段、目的又は場所
本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、いずれも飲食物を提供す る役務であるから、注文により直ちにその場所で料理や飲料を作ったり、 調理済みの料理を用意したりするといった提供手段及び料理や飲料を飲食 させるという目的において一致する。 提供の場所に関しては、引用商標の指定役務では通常インド料理店であ るが、それに限定されるものではない。ホストクラブで、インド料理店勤務 の経験もあるシェフが料理を提供している事例があり(乙13)、また、ホ ストクラブのオープン前の時間帯にカフェを営業する事例もある(乙22) ことからすると、引用商標の指定役務と本願商標の指定役務で提供の場所 が一致することがあることは否定し得ない。
ウ 提供に関連する物品
本願商標の指定役務と引用商標の指定役務に関連する物品は、飲食物の 提供という観点からすると、食材、各種食品、飲料、例えば、おしぼり等の 消耗品や、食器、スプーン、グラス等であり、共通する。
エ 需要者、取引者の範囲
本願商標の指定役務の需要者は、ホストクラブにおいて飲食の提供を受 けようとする女性であり、引用商標の需要者は飲食の提供を受ける者であ って、そこには女性も含まれるから、飲食の提供を受けようとする女性と いう点で共通する。また、前記ウのとおり、本願商標の指定役務及び引用商標の指定役務に関連する物品は共通するので、これらについての業者すなわち取引者も共 通する。
オ 業種
本願商標の指定役務と引用商標の指定役務に係る飲食店は、飲食の提供 という点で共通し、その提供者は食品衛生法3条にいう食品等事業者や、 食品リサイクル法2条4項2号にいう食品関連事業者に当たり、また、日 本標準産業分類において同じ大分類「飲食サービス業」であり、中分類「飲 食店」でも一致するから(乙18)、業種が共通する。
カ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律
本願商標の指定役務と引用商標の指定役務に係る飲食店は、食品衛生法 54条、55条、食品衛生法施行令35条1号により営業許可を受けなけ ればならず、また、食品リサイクル法2条4項2号、8条により、主務大臣 の指導及び助言の対象等となる。 また、本願商標の指定役務の提供は、風営法2条1項1号、3条より公安 委員会の営業許可を受けていることが前提となるが、引用商標の指定役務 も、営業所内の照度や構造によっては風俗営業に当たり得る(同法2条1\n項2号、3号)。
キ 営業主体について
飲食業界においては、提供する飲食物が相違する様々な店舗を同じ経営 者が運営することは珍しくない(乙27、28)。 また、本願商標の指定役務に係るホストクラブの経営者においても、カ フェ、炉端焼き、レストラン、タピオカ店、ピザレストラン、寿司屋、さら にインドカレー店等の飲食店を運営している場合もある(乙22、30な いし33)。
(2) 前記(1)によれば、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、飲食物 を提供するという点で共通し、当該役務に関する業務や事業者を規制する法 律も共通し、役務を提供する業種、役務の提供の手段、目的又は場所、役務の 提供に関連する物品、需要者等の範囲が共通し、かつ、同一の事業者が提供す る場合もあるから、これらを総合的に考慮すると、本願商標の指定役務と引 用商標の指定役務に同一又は類似の商標が使用されたときには、同一営業主 の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるといえる。原告は、前記第3の1(1)のとおり、本願商標の指定役務と、引用商標の指定 役務は、需要者、宣伝広告、価格帯、店舗の外観及び内装、提供に関連する物 品等において異なる旨主張するが、同主張は、本願商標の指定役務でないホ ストクラブにおける「接待の提供」に着目したものであり、直ちに採用できな い。
(3) そうすると、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、商標法4条1 項11号にいう類似の役務に当たるというべきである。原告がるる主張する 事情は、いずれも上記結論を左右するものにはなり得ない。
2 本願商標と引用商標の類似性について
(1) 本願商標について
本願商標は、「HEAVEN」の文字を標準文字で表してなるものであり、\n「HEAVEN」は、「天国」を意味する英語である(ベーシックジーニアス 英和辞典第2版。平成29年11月20日発行。乙3)。また、国語辞典(広 辞苑第7版。乙4)においても「ヘブン」(heaven)の語が「天。天国。」 の意味を有する語として掲載されているから、我が国の需要者においても容 易に意味が理解される親しまれた英語といえる。 そうすると、本願商標は、「ヘブン」の称呼及び「天国」の観念を生じるも のである。
(2) 引用商標について
ア 引用商標は、上段に、図形部分すなわち右手に器に入ったカレーを、左手 にナンを持っているインド人らしき人物の図形を配し、中段には、赤茶色 の二本の線の間を黄色で着色した円弧状の帯状図形中に同じ赤茶色で「イ ンドカレーヘブン」の片仮名を配し、下段に、大きく顕著に、黄色の太字を 赤茶色の線で縁取りして「Heaven」を配してなる、図形と文字との結 合商標である。
引用商標は、図形部分、中段及び下段の各文字部分からなるところ、各構\n成部分は重なることなく配置され、商標全体において占める大きさ、態様 が異なっている上に、中段の「インドカレーヘブン」及び下段の「Heav en」の各文字部分においても、書体や文字の大きさ、円弧状の帯状図形の 有無等の態様が異なっており、直ちに、三つの構成部分からなるものと認\n識し得るものであるから、三つの構成部分のそれぞれが、視覚的に分離し\nて把握されるものといえる。
イ 引用商標の構成中、下段の「Heaven」の文字部分は、黄色の太字を\n赤茶色の線で各文字を縁取りし強調するように、大きく表されていること\nに鑑みると、視覚的に、「Heaven」の文字部分を強く印象づける特徴 を備えているといえ、さらに、前記(1)のとおり、「Heaven」の文字は、 我が国においても容易に意味が理解される親しまれた英語である。そして、 「Heaven」の語から生じる「ヘブン」の称呼や「天国」の観念は、本 願商標と引用商標に共通する「飲食物の提供」という役務との関係で、役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又\nは時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できない から、「Heaven」の文字は、自他役務を識別する標識としての機能が\n強いといえる。
これに対し、引用商標の構成中、上段の図形部分は、インドカレーとナン\nを持ったインド人らしき人物を示すものであるであるところ、これは、提 供の対象となる飲食物を示すにとどまり、それを超えて特別な印象を与え るものとはいえないし、また、中段の「インドカレーヘブン」の文字部分は、 下段の「Heaven」の文字部分に比べて小さく、また、「インドカレー」 の部分は提供の対象となる飲食物を示すものであって、自他商品の識別機 能を有するものではなく、現に、引用商標の商標権者のホームページ(甲6\n3)では、「ヘブンで宴会いかがですか」との広告をしたり、店舗を「ヘブ ン深作店」と表示するなどしている。\n
ウ そうすると、引用商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取\n引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものといえず、 下段の「Heaven」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の 出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえるから、引用商 標の構成から「Heaven」の文字部分を要部として抽出し、他人の商標\nと比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきであ る。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.02. 1
令和4(行ケ)10078 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年1月17日 知的財産高等裁判所
(1) 本件商標について
本件商標は、別紙1のとおり「AROUSE」の文字をスクリプト書体風 に表してなるところ(本件審決は「U」が小文字である旨認定するが、「U」\nは大文字と小文字が同一であるところ、本件商標においては他の大文字と等 しい大きさで表されているから、大文字の「U」とみるのが自然である。)、\n同文字は、「アラウズ」と称呼され、「目覚めさせる、刺激する」等を意味す る英単語として英和辞典に載録されているものの、この語が我が国において 一般に広く親しまれた語であるとまではいい難いものであるから、広く一般 には特定の意味を有しない一種の造語として理解、認識されるというのが相 当である。そして、特定の意味を有しない造語にあっては、我が国において 広く親しまれているローマ字読み又は類似の英単語の読みに倣って称呼され るとみるのが自然であるところ、ローマ字読みに倣えば「アロウゼ」と称呼 され、また、「AROU」については、我が国において「around」(〜 の周囲、およそ〜)との語が非常に馴染み深い英単語として定着しているこ とを考慮すると、この英単語の読み「アラウンド」に倣えば「アラウゼ」と 称呼されると認められ、「アラウズ」との称呼は、前示のとおり、一般に広く 親しまれたものとはいい難い。 そうすると、本件商標は、一般には「アロウゼ」又は「アラウゼ」の称呼 を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2) 引用商標2ないし4について
引用商標2ないし4は、別紙2の2ないし4のとおり、いずれも、長方形 の図形の中に、上段に「Arouge」の文字を、下段にリング形状の図形 を配したものであるが、長方形の図形は背景図形として看取され、リング形 状図形部分は、一見して特定の事物を表したものと認識することは困難であ\nり、指定商品との関係においても特定の意味合いを想起させるものではない から、それ自体から直ちに特定の称呼及び観念を生じるものとはいい難い。 そうすると、これらの図形部分からは出所識別標識としての称呼及び観念は 生じないと認められる。
一方で「Arouge」の文字部分については、上段に目立つ態様で配さ れており、文字が本来的に強い訴求力を有することに鑑みると、需要者又は 取引者は、引用商標2ないし4のうち「Arouge」の文字部分に着目す るといえ、この部分が要部と認められるが、この文字は、辞書等に載録され た成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させるものとして一般 に知られているということもできない。もっとも、特定の意味を有しない造 語にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は類似の 英単語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるところ、ローマ字読 みに倣えば「アロウジェ」又「アロウゲ」と称呼され、また、前記 のとお り、我が国においては「around」(〜の周囲、およそ〜)との語が非常 に馴染み深い英単語として定着していることを考慮すると、「アラウジェ」又 は「アラウゲ」と称呼されると認められ、フランス語風に「アルージュ」と いう称呼が生じ得ないではないとしても、一般的なものとはいい難く、「アル ージェ」という称呼が生じることは、更に想定し難い。 なお、本件審決は、引用商標2ないし4の称呼を「アルージェ」と認定す るが、その理由は審決文からは必ずしも明らかではないものの、同2ないし 5を一体として捉え、同5の上段にカナ文字で併記された「アルージェ」の 文字をもって、同2ないし4についても「アルージェ」の称呼を生じると解 しているかのようにも読める。しかしながら、別個独立の商標についての称 呼等の判断はそれぞれ個別に行われるべきであるし、商標法は、商標のみの 移転を可能とし、同一の範囲のみならず類似の範囲まで商標権に排他的効力\nを付すなど、当該商標の商標権者の本来的使用範囲よりも広い範囲の効力を 付しているから、その認定は需要者又は取引者を基準として客観的にされる べきものであり、同一商標権者が有する他の商標(甲第29号証ないし33 号証によると、引用商標1及び5と引用商標2ないし4の商標権者はいずれ も原告である。)を参酌して、当該商標権者の意図にのみ従ってその認定をす ることは相当ではない。したがって、カナ文字が併記されている引用商標1 及び5が「アルージェ」と称呼されることは明らかであるが、そうであるか らといって、別個独立の商標である引用商標2ないし4の称呼を「アルージ ェ」と認定できるものではない。
そうすると、引用商標2ないし4は、「アロウジェ」若しくは「アロウゲ」 又は「アラウジェ」若しくは「アラウゲ」の称呼を生じ、特定の観念を生じ ないものである。
(3) 商標の類否について
前記(1)及び(2)のとおり、本件商標と引用商標2ないし4の要部の称呼を対 比すると、本件商標が「アロウゼ」と、引用商標2ないし4が「アロウジェ」 と称呼される場合や、本件商標が「アラウゼ」と、引用商標2ないし4が「ア ラウジェ」と称呼される場合があり得る。「ゼ」と「ジェ」はいずれもサ行濁 音で母音「e」を共通にするため、両商標を時と所を異にして全体として一 連に称呼するときは、相似た語韻・語調となり、明確には聴別することがで きず、称呼において酷似するといえる。
また、本件商標と引用商標2ないし4の要部の外観とを対比すると、それ ぞれの書体を異にし、本件商標はその構成文字中の5字が大文字で表\されて いるのに対し、引用商標2ないし4は語頭の文字以外は小文字で表されてい\nるとの差異はあるが、商標の使用に当たっては、書体の相違やアルファベッ トの大文字・小文字の相違があっても同一の称呼を生じる場合は社会通念上 同一の商標とみなされるのであるから(商標法38条5項かっこ書、50条 参照)、上記のとおり両商標が酷似する称呼を生じる場合がある以上、このよ うな相違を殊更に重視すべきものではない。一方で、本件商標及び引用商標 はいずれも6文字と同じ文字数で構成されており、文字数が僅少とはいい難\nいところ、文字の相違は語中の5文字目のみが相違するというのであるから、 5文字目が全体に埋没して、外観上、両商標を見誤ることも多いとみるのが 相当である。
そして、本件商標と引用商標2ないし4の要部は、いずれも特定の観念を 生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
・・・
以上からすると、本件商標と引用商標2ないし4の要部は、観念において 比較することができず、外観において見誤ることも少なくないと想定され、 さらに、称呼において酷似するものであるところ、引用商標2ないし4は、 それら要部に出所識別機能を有しない図形部分が加わっているにすぎないも\nのであるから、全体としても要部が与える印象を覆すものではない。そうす ると、本件商標を引用商標2ないし4の指定商品に使用した場合には出所を 混同させるおそれがあり、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標とい うべきである。
したがって、本件商標が商標法4条1項11号に該当しないとした本件審 決の判断には、誤りがある。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.01.28
令和4(行ケ)10062 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和5年1月24日 知的財産高等裁判所
前記認定事実によると、原告商品は、相当の長きにわたり新聞等の記事において 取り上げられ、また、様々な媒体において広告がされてきたのであるから、原告商 品(ユニ、ハイユニ又はユニスターと称する鉛筆)は、需用者の間において、相当 程度の認知度を有しているものと認められる。 しかしながら、前記認定のとおり、原告商品には、本願商標のみならず他の色彩 及び文字も付されているところ、前記1(2)のとおり、本件指定商品である鉛筆を 含む筆記用具について、ボルドー及びバーガンディーを含む本願商標の近似色が広 く使用されている実情も併せ考慮すると、原告商品に触れた需用者は、本願商標の みから当該原告商品が原告の業務に係るものであることを認識するのではなく、本 願商標と組み合わされた黒色又は黒色及び金色や、当該原告商品が三菱鉛筆のユニ シリーズであることを端的に示す「MITSU−BISHI」、「uni」、「H i−uni」、「uni☆star」等の金色様の文字と併せて、当該原告商品が 原告の業務に係るものと認識すると認めるのが相当である。 加えて、前記認定のとおり、鉛筆の市場においては、原告及び株式会社トンボ鉛 筆が合計で80%を超える市場占有率を有しており、比較的鉛筆に親しんでいる需 用者としては、本件アンケート調査における質問をされた場合、回答の選択の幅は 比較的狭いと考えられるにもかかわらず、本願商標のみを見てどのような鉛筆のブ ランドを思い浮かべたかとの質問に対し、原告の名称やそのブランド名(三菱鉛筆、 uni等)を想起して回答した者が全体の半分にも満たなかったことからすると、 本願商標のみから原告やユニシリーズを想起する需用者は、比較的鉛筆に親しんで いる者に限ってみても、それほど多くないといわざるを得ない。 以上によると、本件指定商品に係る需用者の間において、単一の色彩のみからな る本願商標のみをもって、これを原告に係る出所識別標識として認識するに至って いると認めることはできない。
(3) 小括
以上のとおり、本願商標については、これが使用された結果、原告の業務に係る 商品であることを表示するものとして需用者の間に広く認識されるに至り、その使\n用により自他商品識別力を獲得しているといえないから、原告による本願商標の独 占使用を認めることが公益上の見地からみて許容される事情があるか否かについて 判断するまでもなく、本願商標が商標法3条2項に規定する商標(「使用をされた 結果需用者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するもの」)に該 当するということはできない。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
3 原告の主張について
(1) 原告は、本願商標は原告が採択した独自の色彩であって、原告以外の善意 の取引者が偶然に使用することはあり得ないものであるから、自他商品識別標識と して機能すると主張する。\nしかしながら、原告が単一の色彩のみからなる商標(色彩)を採択した経緯や、 当該商標と同一の商標を一定の指定商品及び指定役務について使用する者がないこ とは、当該商標が自他商品識別標識又は自他役務識別標識として機能するか否かと\nは直接の関係がないことであるから、原告の上記主張を採用することはできない (原告は、本願商標が自他商品識別力を欠くというためには、本件指定商品につい て、本願商標と同一の商標が既に第三者によって当該商品の色彩として使用されて いることが必要であるとも主張するが、独自の見解であり、採用できない。)。
(2) 原告は、1)これまで数多くの新聞、雑誌等において、本願商標に係る記事 が掲載されてきたこと、2)これまで長年にわたり、新聞、テレビ等において、本願 商標が使用された原告商品の広告が行われてきたこと、3)原告は、鉛筆の市場にお いて極めて高い市場占有率を誇り、また、本願商標を使用した多数の原告商品が全 国の多数の店舗において販売されていること、4)別件商標1及び2について商標登 録がされていることからすると、本願商標は、著名な商標として、自他商品識別標 識として機能してきたと主張する。\nしかしながら、上記1)ないし3)の点については、前記2(2)のとおり、原告商品 が需要者の間において相当の認知度を有していることの根拠となるものではあるも のの、原告商品に付された本願商標以外の色彩及び文字の存在や、本件指定商品で ある鉛筆を含む筆記用具について、ボルドー及びバーガンディーを含む本願商標の 近似色が広く使用されている実情を考慮すると、上記1)ないし3)の事実が存在する としても、原告商品に触れた需用者は、本願商標のみから当該原告商品が原告の業 務に係るものであると認識するということはできない。また、上記4)の点について は、別件商標1及び2は、いずれも本願商標に係る色彩とそれ以外の色彩との組合 せからなるものであり、その色彩及び配色を特定してなるものであって(甲137、 138)、輪郭のない単一の色彩のみからなる本願商標とは相当に異なるものであ るから、別件商標1及び2について商標登録がされていることは、本願商標がそれ のみで自他商品識別力を有することの根拠になるものではない。 以上のとおりであるから、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 原告は、本願商標は「ユニ色」として、商品が原告の業務に係るものであ ることを直接表示するものとなっており、特別顕著なものであるから、自他商品識\n別標識として機能するものであると主張する。\n確かに、前記1(1)イのとおり、「DICカラーガイドPARTII)(第4版)第 5巻」に収録された「DIC−2251」(本願商標)については、色名が「un i色」とされており、また、「文具のこが屋」のウェブサイトにおいても、「ユニ ペンシルホルダー」なる商品の説明として、「本体軸部分には実際の木材を使用し、 ユニのイメージカラーである、…アレンジしたオリジナルカラー(通称「ユニ色」) と「黒」、「金」をあしらいました。」との記載があるが(甲29)、本願商標に 係る色彩を「ユニ色」と呼称する場合があるとしても、前記2(2)において説示し たところに照らすと、需用者において、この「ユニ色」のみで、本件指定商品であ る鉛筆が原告の業務に係るものであると認識するとはいえないといわざるを得ない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(4) 原告は、本願商標が使用された商品(鉛筆)に接した需用者は商品のうち の狭い部分に付された文字商標のみによって商品の出所を認識するのではなく、商 品の大部分を占める本願商標をもって商品の出所を認識するのであるから、このよ うな本願商標の重要性に照らすと、本願商標は自他商品識別力を有すると主張する。 しかしながら、原告商品に付された本願商標以外の色彩及び文字(なお、当該文 字は、当該原告商品が三菱鉛筆のユニシリーズであることを端的に示すものであ る。)の存在や、本件指定商品である鉛筆を含む筆記用具について、ボルドー及び バーガンディーを含む本願商標の近似色が広く使用されている実情を考慮すると、 原告商品に触れた需用者が本願商標のみから当該原告商品が原告の業務に係るもの であると認識することができないことは、これまで説示してきたところであって、 このことは、原告商品(鉛筆)の表面において本願商標に係る色彩が付された面積\nが他の色彩が付された面積に比して大きいことにより左右されるものではない(な お、証拠(甲47、48、148〜150)によると、原告商品に付された文字が 需用者の目を引くものでないということはできない。)。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(5) 原告は、原告商品の模倣品が存在することは本願商標が自他商品識別標識 として機能してきたことを意味すると主張する。\nしかしながら、原告が主張する模倣品(甲109、110)も、鉛筆の表面に本\n願商標に係る色彩又はその近似色のみを付したものではなく、帯状の黒色を配した り、金色様の文字を付したりしたものであるから、これらの模倣品の存在をもって、 本願商標に係る色彩のみで自他商品識別力を有するということはできない。したが って、原告の上記主張は、採用できない。
(6) 原告は、特許庁が別件商標1の見本として、別件商標1の見本に該当しな い鉛筆(ユニスター)を展示したことをもって、特許庁も専ら本願商標によって鉛 筆が原告の業務に係る商品であると認識している旨の主張をするが、仮に特許庁が 原告の主張するような取り違えをしたからといって、本願商標に係る色彩のみで自 他商品識別力を有するということはできない。したがって、原告の主張を採用する ことはできない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.01.28
令和3(ネ)10099 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年12月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被告製品1は第3要件を充足するか(争点1−2−3)
ア 被告製品1の製造開始時において、本件訂正発明6における「前記電解 室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構成を、被告製品1\nにおける「1)内タンク6の側壁の一部、2)流出孔3を有する内タンク6の 底部、3)4つの高分子膜10」との構成に置換することは、当業者が容易\nに想到し得たかについて検討する。
イ 前記2のとおり、本件訂正発明6においては、構成要件11Aの隔膜に\nよる区画は、隔膜によって電解室の内部と外部とが完全に区画されるもの であり、電解室の内部と外部とは、水が連通することがない独立した構造\nとなっている。また、本件明細書1においては、電解室の内部と外部を分 ける隔膜は、縦に設置されたもののみが開示され、陽極で発生する水素と 陰極で発生する水素は、別空間に排出されると理解される。 これに対し、被告製品1は、内タンク空間と外タンク空間の間を水が連 通する構成の下で高分子膜10を水平に配置し、高分子膜10の上側に保\n持された陰極電極板11で発生する水素ガスと、高分子膜10の下側に保 持された陽極電極板12で発生する酸素ガスの混合が起こり得る状態を 許容した上で、陽極電極板12で発生した酸素ガスは、枠体5内に集めて 大きな気泡を形成し、流出孔3から内タンク6内に進入するのを防止した 上、内タンク6と外タンク2の隙間内の水内を通って外部に排出するとい うものである(乙29の1・2)。そうすると、本件訂正発明6と被告製品 1は、その基本的発想を異にするものというべきであって、被告製品1に おける「1)内タンク6の側壁の一部、2)流出孔3を有する内タンク6の底 部、3)4つの高分子膜10」との構成への置換が本件訂正発明6の単なる\n設計変更とはいえない。
また、本件明細書1においては、「前記電解室の内部と外部とを区画する 一つ以上の隔膜」との構成を、被告製品1のような「1)内タンク6の側壁 の一部、2)流出孔3を有する内タンク6の底部、3)4つの高分子膜10」 との構成に置換した場合に生じ得る事項についての示唆もないから、本件\n明細書1において、上記のような置換をする動機付けとなるものも認めら れない。
ウ 控訴人は、前記第2の3(7)アのとおり、陽イオン交換膜を用いた固体高 分子水電解において、陰極室と陽極室を貫通孔により水を連通する構成は、\n被控訴人が製造販売を開始した平成29年11月以前から周知の技術で あるとして、甲36文献、甲37文献、甲40文献を提示するので、以下、 検討する。 甲37文献は、オゾン水製造装置、オゾン水製造方法、殺菌方法及び 廃水・廃液処理方法に関するものであり(【0001】)、電解反応を利用 した化学物質の製造において、多くの電解セルでは、陽極側と陰極側に 存在する溶液あるいはガスが物理的に互いに分離された構造を採るが、\n一部の電解プロセスにおいては、陽極液と陰極液が互いに混じり合うこ とを必要とするか、あるいは、混じり合うことが許容されることを前提 として(【0002】)、陽極側と陰極側が固体高分子電解質隔膜により物 理的に隔離され、陽極液と陰極液は互いに隔てられ、混合することなく 電解が行われる従来のオゾン水電解(【0005】)では、電解反応の進 行に伴い液組成が変化し、入側と出側で反応条件が異なるなどの問題点 があったことを踏まえ(【0006】)、電解セルの流入口より流入した原 料水がその流れの方向を変えることなく、直ちに電解反応サイトである 両電極面に到達し、オゾン水を高効率で製造できる等の作用を有するオ ゾン水製造装置等を提供することを目的としたものである(【001 6】)。
その技術分野(オゾン水製造装置)及び目的(オゾン水を高効率で製 造すること等)のいずれも本件訂正発明6と異なるし、その具体的構成\nも、貫通孔11が設けられた電解セル8(陽極1、陰極2及び固体高分 子電解質隔膜3)に直交して原料水(オゾン水)の流路が設けられると いうものであって(【0034】及び【0035】)、電極室の内部に被電 解原水が貯留され、電気分解が行われる本件訂正発明6とは異なる。し たがって、甲37文献に開示された事項を本件訂正発明6に適用する動 機付けは見い出せない。
甲40文献は、電源のない場所に持ち運び、水素の吸入や水素水の飲 用に使用することのできるポータブル型電解装置に係る技術分野に属す るものであり(【0001】)、電解ユニット3は、ケーシング31、高分 子膜32、電極板33、34、スプリング35からなること(【0028】)、 ケーシング31は、内部に反応室311となる容積が確保されており、 側部に外部と反応室311とを連通するように穿孔された連通孔314 が設けられていること(【0029】)、電解ユニット3の高分子膜32は、 イオンの通過を規制するイオン交換機能を有する薄膜からなるもの(例\nえば、ナフィオン)で、ケーシング31の窓孔311を閉塞する大きさ の方形に形成されていること(【0030】)が記載され、使用形態とし て、内部に原水Wが収容されたタンク1にキャップ2、ガイド筒4、水 素吐出管5を一体的に取付けられること(【0034】)、スイッチ9が入 れられると、原水Wが電気分解され、ケーシング31の反応室311の 内部にあるプラス極の電極板34で水素イオンと電子とが生成されて高 分子膜32を通過し、ケーシング31の窓孔312に露出しているマイ ナス極の電極板33で水素(ガス)が生成され、水素は、微細な気泡H を形成してタンク1の内部で水素水からなる電解水を生成すること、プ ラス極の電極板34で生成されたオゾン(ガス)は、高分子膜32を通 過することなくケーシング31の反応室311の内部に滞留され、ケー シング31の反応室311の内部の滞留圧力が大きくなると連通孔31 4から吐出されること(【0041】)が記載されている。 しかし、甲40文献には、陰極室及び陽極室についての記載はないか ら、これを見ても、陰極室と陽極室とを貫通孔により水を連通する構成\nが記載されているとはいえない。別紙2の図2において、マイナス極の 電極板33より上側部分を陰極室と、プラス極の電極板34より下側の 反応室を陽極室であると解釈すると、連通孔314は、陽極室とその外 部を貫通するものであって、陽極室と陰極室を貫通するものではない。 マイナス極の電極板33より上側部分と、ケーシング31側面の外側部 分はつながった空間であることから、ケーシング31側面の外側部分も 陰極室であるとみた場合には、連通孔314は、陽極室(反応室)と陰 極室(ケーシング31側面の外側部分)を貫通するものであるといえる が、酸素と水素が同じ陰極室内に排出されることになり、被告製品1の 構成に至らない。\n甲36文献に係る発明の公開日は平成30年11月22日であり、甲 36文献自体の発行日は令和2年3月11日であるから、その内容や位 置付けについて検討するまでもなく、甲36文献は、被控訴人が被告製 品1の製造販売を開始した平成29年11月時点における周知文献とは いえない。
エ 以上によれば、控訴人主張の周知技術は、いずれも、本件訂正発明6に おける「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構\n成を、被告製品1における「1)内タンク6の側壁の一部、2)流出孔3を有 する内タンク6の底部、3)4つの高分子膜10」との構成に置換する動機\n付けになるものとはいえない。
これらの事実関係によれば、このような置換が容易であったとはいえな いから、被告製品1は、均等の第3要件を充足しない。 前記(1)ないし(3)によれば、被告製品1は、均等の第1要件及び第2要件を 充足するものの、第3要件を充足しないから、第5要件について判断するま でもなく、本件訂正発明6の技術的範囲に属しない。
◆判決本文
1審はこちら。
1審では、構成要件を具備せず、また実施可能\要件違反の無効理由有りと判断されていました。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.01.25
令和4(行ケ)10067 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年12月26日 知的財産高等裁判所
ア 商標法4条1項6号は、同号に掲げる団体等の公共性に鑑み、その信用 を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護す ることに趣旨があり、そこでいう著名性は、同号所定の標章が、指定商品 の取引者、需要者の間に広く認識されていることを要するものというべき である。なお、被告は、前記第3の2 アのとおり、ここにいう著名性は、 一商圏以上の取引者、需要者に広く認識されていれば足りる旨主張するが、 引用標章のように地域性が問題とならず、また、指定商品特有の事情が主 張・立証されているわけでもない標章も含めて被告主張のように解すべき 理由はなく、この点が本件において結論に影響を与える事柄であるとも思 えない。
イ 引用標章は、前記(1)アのとおり、1991年には、オリンピック憲章上 独立した項が設けられ、付属細則上各NOCにその名称を保護すべき努力 義務が課され、2004年には、「OLYMPIC」、「オリンピック」 の文字及び五輪の図形と同様に、「オリンピック資産」とされている。 また、前記(1)イのとおり、平成25年1月7日に、招致委員会が、異議 申立人へ提出した立候補ファイルには、我が国において、引用標章が、オ\nリンピック・シンボル、「オリンピック」と並んで、オリンピック競技大 会、異議申立人及びJOCを表\示する著名な標章である旨記載されている。 しかし、前者は、あくまでオリンピック憲章上の規定にすぎず、その邦 訳が出版されるようになったとしても、広く本件商標の指定商品の取引 者・需要者の目に触れる性質のものとは認められない。また、後者につい ても、招致委員会の認識を示すものにすぎず、オリンピック大会を誘致す るために日本の法制度上引用標章が保護されることをアピールするとい う性質のものでもあるから、それが取引者・需要者の認識を反映したもの とは直ちにいえない。
ウ 次に、前記(1)ウのとおり、「Games of the XXXII Ol ympiad」の表示に関し、第32回オリンピック競技大会に関するウ\nェブサイトの記事や、組織委員会の資料に当該表示がされており、昭和3\n9年の東京オリンピックの記念映画のタイトルとして「東京オリンピック」 (Tokyo Olympiad)と併記されているとしても、日本語表記\nと同時にされているもの(乙4、22、28)や、「TOKYO2020」 の大きな表示と共にされているもの(乙20、21、23)であり、看者\nの注意を惹くものとはいい難い。また、同表示が、公式商品で用いられたとしても、英文表\記の必要に伴ってされたものとも考えられ、これにより引用標章が著名となったことを裏付けるに足りるものとまではいい難い。
エ また、前記(1)エのとおり、平成24年以降、「オリンピアード」が、オ リンピック大会が開催される4年毎の暦年であることを解説する趣旨の 新聞記事がみられるものの、そのような解説が必要なこと自体、「オリン ピアード」の意味はもちろん、「オリンピアード」という語そのものが一 般には知られていなかったことを示すものともいえる。昭和39年及び令 和3年に東京で開催されたオリンピック競技大会で、各時点の天皇が、開 会宣言において「オリンピアード」に言及したという記事等についても、 事実を客観的に報道するにとどまる。被告は、前記第3の2(1)キのとおり、日本の家庭の新聞購読率を挙げて、国民一般がこれらの記事により引用標章の意味を広く知るに至った旨主張するが、これらの記事を読む機会があったからといって、需要者の多く が「オリンピアード」に関心を持ち、さらに、これがオリンピック大会と 同義であると認識するに至ると直ちにいえるものではない。また、文化オ リンピアードについても新聞記事とされているところ、これらの記事は、 オリンピック大会に関連した文化行事として「文化オリンピアード」が存 在することを報道するものではあるが、需要者の間で記事の掲載以前から 引用標章が知られていたことを示すものでないことはもちろん、このよう な記事によって、需要者の多くが「文化オリンピアード」に関心を持つと まではいい難く、「オリンピアード」がオリンピック大会と同義と認識す るに至るともいい難い。
オ 前記1(2)の各種辞書における「OLYMPIAD」(「Olympia d」を含む。)及び「オリンピアード」の項では、古代ギリシアのオリュ ンピア紀あるいはこれに類する意味が冒頭に掲載されるものが多数であ り、「オリンピック競技大会」の意味だけが掲載されている英和辞典(乙 9)でも、「Olympic」の語が大きく表示されているのに対し、「O\nlympiad」の語は通常の大きさにとどまっている。 カ 以上の事情を総合すれば、引用標章は、関係者や識者等の間では著名な ものであると認められるが、それを超えて、本件商標の設定登録日におい て、商標法4条1項6号が規定する著名性を有する、すなわち本件商標の 指定商品の取引者、需要者の間で広く認識されているものであると認める ことについては、疑義も残るといわざるを得ず、少なくとも他の商標との 類似性の判断において、著名性が高いことを前提にすることは相当でない というべきである。
3 本件商標と引用標章の類似性について
(1) 検討
ア 本件商標は、「OLYMBEER」の欧文字と「オリンビアー」の片仮 名を2段に表示してなるものである。引用標章は、「OLYMPIAD」の欧文字又は「オリンピアード」の片仮名である。本件商標と引用標章は、2段か1段かという点において異なる。また、欧文字同士、片仮名部分同士を比較しても、欧文字部分では8文字中冒頭の4文字が共通するのみであり、片仮名部分では本件商標が6文字、引用\n標章が7文字であり、冒頭の「オリン」と、5文字目・6文字目の「アー」 が共通するが、これらの文字の間に、本件商標では濁点を付した「ビ」が、 引用標章では半濁点を付した「ピ」がある上、引用商標では語末に濁点を 付した「ド」があるという点で相違する。 以上によれば、本件商標と引用標章は、外観において相紛れるおそれは ない。
イ 本件商標は、欧文字と片仮名が2段となっており、片仮名部分が欧文字 部分の読み仮名となっていると理解されることから、「オリンビアー」の 称呼を生じる。引用標章からは「オリンピアード」の称呼を生じる。 両者は、「オリン」の部分と「アー」の部分を共通にするものの、両者 の間に本件商標では濁音「ビ」が、引用標章では半濁音「ピ」があり、さ らに、語末が、本件商標が長く伸びる母音で終わるのに対し、引用標章が 濁音の「ド」で終わるという点で相違する。 以上によれば、本件商標と引用標章は、称呼において相紛れるおそれは ない。
ウ 本件商標は、辞書に記載されておらず、造語と認められ、特定の観念を 生じない。 引用標章は、前記1(2)のとおり、辞書に記載されている「オリュンピア 紀」、「国際オリンピック競技大会」の観念を生じる。そうすると、両者は観念において比較できない。
エ 本件商標の指定商品の需要者と、引用標章が使用されるオリンピック競 技大会に関心を有する者とは、一般的な消費者ないし国民であるという意 味で共通性を有するが、前記アないしウのとおり、本件商標と引用標章は 外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できない のであるから、両者は類似しないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2023.01.24
令和4(ネ)10051 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和4年12月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
このように、被告商品と原告商品は、価格帯が大きく異なるものであ って市場種別が異なる。また、女性用ハイヒールの需要者の多くは、実 店舗で靴を手に取り、試着の上で購入しているところ、路面店又は直営 店はいうまでもなく、百貨店内や靴の小売店等でも、その区画の商品の ブランドを示すプレート等が置かれていることが多いので、ブランド名 が明確に表示されているといえ、しかも、それぞれの靴の中敷きにはブ\nランドロゴが付されていることから、仮に、被告商品の靴底に付されて いる赤色が原告表示と類似するものであるとしても、こうした価格差や\n女性用ハイヒールの取引の実情に鑑みれば、被告商品を「ルブタン」ブ ランドの商品であると誤認混同するおそれがあるといえないことは明 らかというべきである。
また、普段は被告商品のような手ごろな価格帯の女性用ハイヒールを 履く需要者の中には、場面に応じて原告商品のような高級ブランド品を 購入することもあると考えられるが、こうした需要者は、原告商品が高 級ブランド(控訴人らが主張するように「ルブタン」がラグジュアリー ブランドであり、日本だけではなく世界中の著名人や芸能人が履くとい\nうイメージがあればなおさらである。)であることに着目し、試着の上で 慎重に購入するものと考えられるから、被告商品が原告商品とその商品 の出所を誤認混同されるおそれがあるとはいえない。
なお、原告商品及び被告商品ともに、公式オンラインショップだけで はなく、二次流通品を含め、ECサイトで販売されていることもあり、 原告商品の二次流通品の中には価格帯が大きく下げられて販売される こともあるが、公式オンラインショップでの売上げ実績は全体の売上げ 規模からして僅少であって(そのことは、需用者の多くが実際に商品を 試着して購入していることを示すものである。)、それぞれのブランド専 用のサイトであるし、また、公式オンラインショップ以外のサイトでは、 商品の画像だけではなく、商品の詳細な説明において、ブランドや靴の 状態が説明されているから、こうした流通形態があり、仮に、被告商品 の靴底に付されている赤色が原告表示と類似するものであるとしても、\n被告商品が原告商品と誤認混同のおそれがあるとはいえない。
エ 加えて、近時では、高価格帯のブランドが価格帯の異なるブランドとコ ラボレーションした商品が販売されることもあるが、その商品にはそれぞ れのブランドのロゴが付されており(前記1 エ)、その商品がコラボレー ション商品であることが需用者にとって一目で分かるようになっている (そうでなければ、コラボレーション商品として企画し、販売する意味は ないともいえよう。)。そうすると、仮に、被告商品の靴底に付された赤色 が原告表示に類似するとしても、被告商品にはそうしたコラボレーション\n商品であることを示すようなロゴはないから、需要者が、被告商品が控訴 人らのライセンス商品又は控訴人らとの間で何らかの提携関係を有する 商品であると誤認混同するおそれがあるともいえない。
これに対して、控訴人らは、前記第2の3 ウ aのとおり、被告商品も 原告商品と同じ高価格帯の商品であることを前提として、店舗又はオンライ ンショップで原告商品と被告商品の双方が販売されていることがあり得ると し、ブランド毎に区別して展示されていない場合等では、需要者が販売され ているブランド名を意識しないまま購入することがあり得る旨主張する。 しかし、原告商品は最低でも8万円、10万円を超えるものも少なくない のに対して、被告商品は、1万6000円から1万7000円の価格帯であ るから、これだけの価格差がある商品形態において、仮に店舗又はオンライ ンショップで原告商品と被告商品が並べて陳列されており、一部店舗でブラ ンド毎に区別して展示されていないことがあるとしても、実店舗では、靴の デザイン性だけではなく、実際に手に取って試着することが多く、ECサイ トでは、ブランド名や商品の状態が詳細に説明されているといった取引の実 情に鑑みれば、需要者が、被告商品の靴底に原告赤色と類似する色を使用し ているからといって、被告商品の出所が「ルブタン」のブランドであると誤 認混同するとはいえない。したがって、控訴人らの主張は理由がない。 以上のとおり、仮に、被告商品の靴底に付された赤色が原告表示に類似す\nるとしても、原告表示を付した原告商品であると誤認混同するおそれ(広義\nの混同を含む。)があるとはいえないから、原告表示が不競法2条1項1号に\n規定する「他人の商品等表示」に該当するか否かについて判断するまでもな\nく、被告商品の販売等が同号の「不正競争」に当たるとはいえない。 そうすると、被告商品の販売等が不競法2条1項1号の「不正競争」に当 たることを前提とした控訴人らの請求は、その前提を欠くものであるから、 その他の争点について判断するまでもなく理由がない。
3 争点2(原告表示の周知著名性)について\n
前記1の認定事実によれば、控訴人Xは、会社を設立以後、全世界に店舗 を展開して、原告表示を付した高価格帯の女性用ハイヒール(原告商品)を\n販売し、数多くの著名人や芸能人に愛用され、また、日本でも、平成10年\n以降は路面店等のショップで販売が開始されて、年間30億円を超える売り 上げを誇り、数多くの雑誌、メディア等で原告表示は「レッドソ\ール」とし て取り上げられ、一定の需要者には「靴底が赤い」女性用ハイヒールは「ル ブタン」のブランドを指すものと認識されているといえる。 しかし他方で、靴底が赤色の女性用ハイヒールは、原告商品以外にも少な からず我が国においては流通しており(前記1 )、女性用ハイヒールの靴底 に赤色を付した商品形態を控訴人らが独占的に使用してきたものとはいえな い。
また、本件アンケートは、東京都、大阪府、愛知県に居住し、特定のショ ッピングエリアでファッションテム又はグッズを購入し、ハイヒール靴を履 く習慣のある20歳から50歳までの女性を対象としたものであるが、本件 アンケート結果によると、靴底が赤いハイヒール靴を見たことがないものを 含め、原告表示を「ルブタン」ブランドであると想起した回答者は、自由回\n答と選択式回答を補正した結果で51.6%程度にとどまる(なお、本件ア ンケート調査結果では、赤いハイヒール靴を見たことがある人に限定して認 識率を評価するのが適切であるとするが、本件アンケート調査は、主要都市 で、しかも、ファッション関係にそれなりに関心のあるハイヒール靴を履く 習慣のある女性を対象としたものであり、その当否についても疑義がある上、 そこから更にこうした限定を付すことは明らかに相当でない。)。この結果に よれば、原告表示は、一定程度の需要者に商品出所を認識されているとはい\nえるが、それが著名なものに至っているとまでは評価することができない。 そうすると、原告表示が不正競争防止法2条1項2号に規定する「他人の\n著名な商品等表示」であるとはいえないから、そうであることを前提とした\n
◆判決本文
1審はこちら
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.01.13
令和1(ワ)14320 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月7日 東京地方裁判所
前記(1)で検討したところによると、本件発明1の技術的意義は、固定プレ ートの孔自体が、橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側 面側という2箇所で支持する方向に突起を向かせて固定することができる構\n成となっているため、高度な医学的判断を要せずに、確実に軟骨下骨を背側 面側及び手掌側面側という2箇所で支持することを可能にすることにあると\n認められる。
そうすると、本件発明1の構成のうち、本質的部分であるといえるのは、\n橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という2箇所 で支持する方向に突起を向かせて固定することができる孔が設置されている ことを定めた構成要件1E、1J及び1Kであると解するのが相当である。\nそして、これまで検討したところによると、被告製品4は構成要件1J及\nび1Kを充足せず、これらの本件発明1の構成と異なる部分は、本件発明1\nの本質的部分ではないとはいえないから、第1要件を充足せず、均等侵害は 成立しない。
(3)原告の主張の検討
原告は、本件報告書(甲26)によれば、被告製品4は、ガイドブロック を用いて被告製品4の孔にロッキングスクリューを固定すれば、一組の平行 ピンを用いた従来の平板固定によっては達成できなかった遠位橈骨の軟骨下 骨及びその遠位側の関節表面の位置の安定化という課題を解決することがで\nきるから、本件発明1と技術的思想を共通にしているといえ、孔の軸線が遠 位橈骨内で交差するか遠位橈骨外で交差するかは本件発明の本質的部分では ないと主張する。
しかし、本件報告書の検証結果の信用性を肯定することができないことは 前記4(2)のとおりであるし、その信用性を肯定できたとしても、前記(1)の とおり、遠位橈骨の骨折を固定するための骨プレートであり、ネジを固定す るための固定プレートを貫通する複数のネジ孔が、固定プレート頭部の遠位 側と近位側の2列に概ね平行に並んで設置されている固定プレートは、先行 技術として存在していたのであるから、従来プレートが一組の貫通孔のみを 設けていたことを前提に、二組の貫通孔を設けていることが本質的特徴であ ると評価することはできない。 また、本件発明1は固定プレートの発明であるから、固定プレート自体の 構成、すなわち、固定プレートに設置された孔の構\成を比較すべきであり、 被告製品4にガイドブロックを用いることを前提に、被告製品4が軟骨下骨 を背側面側及び手掌側面側という2箇所で支持する方向にロッキングスクリ ューを向かせることができるかどうかという観点から比較することは相当で はない。
さらに、孔の軸線が遠位橈骨内で交差しないのであれば、孔に突起を挿入 しても、突起が当然に軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という2箇所で支 持することはなく、遠位橈骨の軟骨下骨及びその遠位側の関節表面の位置の\n安定化という課題を解決することはできないから、孔の軸線が遠位橈骨内で 交差する方向に突起を向かせる構成となっていることは、本件発明1の本質\n的特徴であるといえ、そのような孔の構成を有していない被告製品4に均等\n侵害が成立することはない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2023.01.13
令和2(ワ)32931 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年10月25日 東京地方裁判所
ア 被告は、被告サイトに掲載された被告製品に係るカタログの記載を訂正前数 値から訂正後数値に訂正するなどしたところ、訂正前数値が誤りであり、訂正後数 値が正確な数値であった。(争いのない事実)
イ 被告製品は空気圧制御機器の一種であり、その主な用途は、生産工場等の空 気圧システムを用いたオートメーション設備で使用されるエアシリンダに組み合わ せてエアシリンダの空気の流れを制御することにある。このため、被告製品の一般 的な需要者としては、上記オートメーション設備の製造者や同設備を導入する工場 経営者等(以下「工場経営者等」という。)が想定される。(争いのない事実)
ウ 空気圧制御機器は、それ自体が空気圧システムの回路を通過する空気の流れに対する抵抗となり、空気の流れに影響を与える。もっとも、空気の圧力条件が同じであっても、空気圧制御機器によって、機器を通過できる空気の流量は異なる。このような圧力条件と流量の関係は、空気圧制御機器の性質という観点から、空気圧制御機器の流量特性として把握される。空気圧システムに用いる空気圧制御機器を選定するにあたり、当該空気圧制御機器の流量特性を適切に把握することは必要かつ重要である。流量特性が適合しない空気圧制御機器を誤って選定すると、所定の出力が得られず、さらに、空気圧制御系が不安定になることも起こり得る。(以上につき、甲 12、13、18)
(2) 前提事実及び前記各認定事実によれば、被告製品は、空気圧システムを用い たオートメーション設備で使用されるエアシリンダの空気の流れを制御することを 主な用途とする空気圧制御機器であるところ、空気圧制御機器にとって、流量特性 とは、それを適切に把握しなければ空気圧システムにおいて所定の出力が得られな くなるなどの不具合を生じかねない重要な意味を持つ要素である。そうすると、空 気圧制御機器において、その流量特性は、機器の品質に関係する要素の 1 つといえ る。 したがって、被告製品の流量特性を表す有効断面積及び Cv 値についての不正確 な表示は、被告製品の品質を誤認させるような表\示に当たる。 本件では、被告は、被告製品の流量特性を表す有効断面積及び Cv 値について不 正確な数値を記載した本件カタログを配布すると共に、これを被告サイト上に掲載 したのであるから、被告製品の品質について誤認させるような表示をしたと認めら\nれる。
(3) これに対し、被告は、工場経営者等が電磁弁を購入する際に重視するのはシ リンダとの適合性や価格等であって、有効断面積や Cv 値ではないなどとして、本 件表示は品質誤認表\示に当たらない旨を主張する。 しかし、前記のとおり、空気圧制御機器の流量特性は、それを適切に把握しなけ れば空気圧システムにおいて所定の出力が得られなくなるなどの不具合を生じさせ かねない重要な要素であり、シリンダとの適合性もこれに基づいて定まるものとい える。そうである以上、空気圧制御機器の一般的な需要者である工場経営者等は、 当該機器の選定にあたり、流量特性を空気圧制御機器の品質に関係する要素と認識 し、評価要素の 1 つとしていることが強く推認される。このことは、本件カタログ で、少なくとも一部の被告製品について「優れたバルブの内部構造により、有効断\n面積を増大させ、流量をアップさせることができます」と記載し、被告自身が有効 断面積の増大をアピールしていること(甲 1)からもうかがわれる(なお、被告の カタログでは、有効断面積等の数値訂正後も同じ記載が維持されている。乙 3)。ま た、流量特性を評価要素の 1 つとすることは、工場経営者等が機器の価格等を重視 することと矛盾するものではなく、これと両立し得る。被告製品の通販サイト上の レビューで有効断面積について言及したものがないとしても、被告指摘に係るレビ ューはわずか 4 件に過ぎず、これらが言及した要素をもって被告製品の品質を網羅 したものとはいえないし、これらのレビューが有効断面積を空気圧制御機器の品質 に関係する数値と考えていないことをうかがわせるものともいえない。 エアシリンダの機種選定手順に関する原告の資料(乙 15)が有効断面積に言及し ていない点も、電磁弁はエアシリンダに組み合わせて用いる機器であってエアシリ ンダそのものではないこと、原告の自社製品カタログ(甲 3)には電磁弁の Cv 値及 び有効断面積に換算可能な C 値が掲載されていることなどに鑑みると、上記判断を 左右する事情とはいえない。
・・・
ア 本件カタログは、AirTAC グループの中国における拠点の一つである寧波エ アタックが作成したものであり、本件カタログに掲載された各製品の性能等に関す\nる数値は全て、寧波エアタックが運営する研究開発センターにおいて測定・算出さ れたものである。(乙 13、弁論の全趣旨)
イ 被告は、AirTAC グループの唯一の日本における拠点であり、同グループにお いて製造した被告製品を日本国内で自社製品又は自社グループ製品として販売して いる。(甲 1)
ウ 被告は、寧波エアタックから本件カタログの提供を受け、これを顧客に配布 すると共に被告サイトに掲載したが、その際、本件カタログに記載された数値の正 確性につき、改めて自ら測定し、又は研究開発センターに照会するなどして確認す ることはしなかった。(弁論の全趣旨)
(2) 前記各認定事実によれば、被告は、その取扱製品である被告製品を掲載した カタログ等の宣伝広告物を配布等するに当たり、被告製品の品質に係る数値として 正確な数値をカタログ等に記載すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠 り、本件表示に係る数値の正確性を確認することなく本件カタログを配布等したと\nいうのである。したがって、被告には、被告製品の品質を誤認させるような表示を\nしたことについて少なくとも過失が認められる。
(3) これに対し、被告は、本件カタログに掲載された数値の正確性を検証できる設備を有していないため研究開発センターの測定結果を信頼するしかないなどと指摘して、自己に過失はない旨を主張する。しかし、販売業者が自己の取扱製品の宣伝広告物としてカタログ等を配布等する場合、取引先に対して示すカタログ等の記載内容の正確性を確保すべき義務を販売業者が負うのはむしろ当然とも思われる。まして、被告製品は被告も属する AirTACグループ内で製造され、本件カタログ等に記載されたデータも同グループ内の企業による計測結果に基づくものである。これらの事情を踏まえると、少なくとも本件において、被告は、取引先等に対し本件カタログ等の記載内容の正確性を確保すべき義務を負うというべきである。被告自身は当該数値の正確性を検証できる自社設備を有しておらず、また、訂正前数値に特段不審な点がなかったとしても、それらの事情は、上記義務を免れることを基礎付けるものではなく、また、これを履行したことを示すものでもない。その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用できない。
4 損害の有無及び損害額について
(1) 本件は、被告の不正競争に係る訴訟であり、専門的・技術的側面を有するこ と、被告が本件の訴状副本の送達を受けて間もなく訂正前数値の不正確さを認め、 その訂正及び本件カタログの廃棄等を実施したこと(前記第 2 の 1(5)、第 3 の 2(1))、本件カタログは被告製品全てを掲載したものであること(前記第 2 の 1(2))、原告が弁護士費用相当額以外の損害について一切主張立証していないこと、その他諸般の 事情を総合的に考慮すると、被告の不正競争と相当因果関係のある弁護士費用に相 当する損害額は、15万円とするのが相当である。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2023.01.12
令和4(行ケ)10039 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年12月21日 知的財産高等裁判所
ア 前記(1)のとおり、相違点3は、施設端末に予約内容を通知した後、ユーザー\n端末に第2施設の情報を通知する処理を行うことにつき、本願補正発明では、前記 施設端末からの返信を有効に受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前\n記施設端末からの返信がない場合であるのに対し、引用発明では、施設端末から受 信する予約結果情報の予\約登録可否の結果がNGであった場合である点で相違する というものである。
イ ところで、施設の予約は、利用日又は利用日時を指定して行うものであり、\n予定される利用日又は利用日時よりも前に予\約を完了するという本来的な要請があ る。そして、引用発明は、ある特定の施設の予約を目的とするものではなく、利用\n者の希望する条件に合致した複数の施設を対象とし、一つの施設の予約ができなか\nった場合に、別の施設の予約をすることが可能\であるような施設予約システムにお\nける予約方法であるところ、前記2(1)イのとおり、引用発明における施設予約シス\nテムは、「施設予約情報サーバ30から、当該予\約情報に基づく、自動的、あるいは 宿泊施設の予約担当者により判断される予\約登録可否(OKかNG)の予約結果情\n報を受信し、」「受信した予約結果情報の予\約登録可否の結果がNGであった場合」 に、次の候補となる施設の検索をしてユーザーに送信して、ユーザーが別の施設の 予約を行うものとされているから、施設端末に当たる「施設予\約情報サーバ」から の予約結果情報の受信は、宿泊施設の予\約担当者による判断の時期によっては、相 当程度に遅くなる場合も想定され、その間に、当初の検索条件に合致する別候補の 施設の予約枠が埋まってしまうこともある。\nそうすると、引用発明には、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者\nの希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができ\nないおそれがあるといえる。
ウ 次に、前記2(2)イの引用文献2記載技術をみると、宿泊施設の仮予約におい\nて、「ホテル端末103が宿泊可否の通知を一定時間経過(タイムアウト)しても行 わなかった場合、ホテル端末103に対して、キャンセルの通知を送信し、次のホ テルへ空き問い合わせ情報を送信する」ものであるから、甲2には、施設端末が、 一定時間を経過しても予約可否の回答をしなかった場合には、キャンセルとして扱\nい(以下「タイムアウト処理」という。)、次の施設に問い合わせるという技術が開 示されているといえる。そして、予定される利用日又は利用時間よりも前に、タイ\nムアウト処理をして、次の施設に問合せをすることで、最初に問合せをした施設か らの回答を待っていたために、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者\nの希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができ\nなくなるという事態を回避するのに、一定の効果があると認められる。
エ ところで、引用発明と引用文献2記載技術とは、複数の施設を対象とした施 設予約システムにおける施設予\約方法という共通の技術分野に属するものであって、 第1施設に対して予約可否の問合せを行い、第1施設から予\約不可の返信を受けた 場合には第1施設に類似する他の施設を抽出するという手法も共通するところ、前 記イのとおり、引用発明において、第1施設から予約可否の返信が長時間送信され\nない場合には、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件\nに合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができないおそれがあ\nるところ、上記本来的な要請を満たすために、第1施設からの予約可否の返信を長\n時間待ち続けるという事態を回避しようとすることは、当業者であれば当然に着想 するものと認められるから、引用発明に引用文献2記載技術のタイムアウト処理を 適用する動機付けがあるといえる。 そして、引用発明に引用文献2記載技術のタイムアウト処理を適用すると、引用 発明は、施設端末からの返信を有効に受け付ける期間としてあらかじめ設定された 待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合には、予約結果情報の予\約登録可 否の結果がNGであった場合と同様に、予約内容に基づいて第1施設を除く一又は\n複数の第2施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第2施設の情報を前記 ユーザー端末に通知する処理を行うことになる。 そうすると、相違点3に係る構成は、引用発明に引用文献2記載技術を適用する\nことより、当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 特段の効果
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2023.01.12
令和4(行ケ)10068 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年12月14日 知的財産高等裁判所
ア 前記1(1)からすると、本願商標である「次世代3Dプリンタ展」は、「次の段階」等を意味する「次世代」の語、「三次元印刷機」等を意味する「3Dプリンタ」の語及び「展覧会」ないし「展示会」の略語である「展」の語から構成されるといえる。そして、「ピカソ\展」の用例からもうかがえるように、「展」の語が、当該展示会等で取り扱われる内容やそれに係る共通の特徴を示す語を冠して「○○展」という形で使用されることがあることは、公知の事実である。
イ 前記1(1)イによると、「次世代」の語は、「次の段階」等をいう場合に特に 「技術」等に関して用いられることが多いとの事情もうかがわれるところ、同(2)ア のように、「次世代」の語が、「3Dプリンタ」に対し、「次の段階」といった意 味を示す趣旨で付されて用いられている例があることも考慮すると、本願商標であ る「次世代3Dプリンタ展」に接した者は、本願商標が「次世代3Dプリンタ」の 語と「展」の語とから成るものと理解するというのが自然である。
ウ 前記ア及びイの点に加え、前記1(2)イ(ア)のように、「〇〇展」の語が、「〇 〇」の部分に当該展示会の主たる展示内容(製品、技術等)やそれに係る共通の特 徴を示す語を置く形で用いられている例があり、同(イ)のように、そのような「〇〇 展」の語の使用例の中に「3Dプリンタ」と「展」から成る例があることも考慮す ると、本願商標である「次世代3Dプリンタ展」の語については、「次の段階の3 Dプリンタを内容又はそれに係る共通の特徴とする展示会」という意味合いを容易 に認識させるものであるということができる。 そうすると、本件審決時である令和4年5月19日の時点において、本願商標で ある「次世代3Dプリンタ展」は、展示会等に係る本件役務について使用されると きは、これに接する需要者等において、「次の段階の3Dプリンタを内容又はそれ に係る共通の特徴とする展示会」を表したものと認識されるというべきであるから、\n役務の内容を認識させるものとして、役務の質を表示する標章に当たるということ\nができる。
エ そして、本願商標は、「次世代3Dプリンタ展」のみからなり、「次世代3 Dプリンタ展」の語を標準文字で記すという、普通に用いられる方法で表示する商\n標であるから、商標法3条1項3号に該当するというべきである。 なお、以上に関し、仮に、本願商標に接した需要者等において、本願商標が「次 世代」の語と「3Dプリンタ展」の語とから成るものと理解することがあったとし ても、その場合、「次世代3Dプリンタ展」は、本件役務について使用されるとき は、「3Dプリンタを内容又はそれに係る共通の特徴とする次の段階の展示会」を 表したものと認識され、役務の質を表\示するとともに、役務の提供の態様、提供の 方法又は時期その他の特徴を表示する標章に当たるというべきであるから、本願商\n標が商標法3条1項3号に該当するとの前記判断は左右されない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は、本件役務の分野において、「○○展」の語が、一般に、「特定人が 開催等する展示会等の固有の名称」として採択され、使用されていることが明らか であると主張する。 しかし、原告の主張する使用例(別紙2)全てを前提としても、前記(1)の判断は 左右されない。前記1(1)及び(2)イ(ア)の認定事実等を踏まえると、原告が主張する 使用例についても、「○○」展という展示会等の名称のうち「○○」の部分が展示 会等の内容又はそれに係る共通の特徴を示すものである場合には、当該名称に接し た者においては、当該展示会等の固有の名称という意味合いと同時に、当該展示会 の内容等を「○○」が示すものと認識するというべきであり、「○○展」が特定人 が開催等する展示会等の固有の名称を示すものであるということから、直ちに、当 該「○○展」が当該展示会等の内容等を示すものであるということが否定されるも のではない。
この点、原告は、JETROのウェブサイト(甲48、59)において「○○展」 の表示が固有の展示会名称として掲載されている旨を主張するが、展示会等の内容\n等を示す語であっても個々の展示会等の名称とされている以上は上記ウェブサイト に当該名称をもって掲載されることは当然であるといえ、上記ウェブサイトに「○ ○」の部分が直ちに展示会等の内容等を十分に示す語ではない「○○展」の使用例\nとみ得るものが掲載されているとしても、そこに掲載されている他の「○○展」に ついて「○○」の部分が展示会等の内容等を示すものであることを否定すべきもの とはならない。したがって、原告の前記主張は、前記(1)の判断に影響しない。
イ 原告は、需要者等の認識に係る使用例(別紙3)について主張するが、前記 アで述べたところに照らし、需要者等が「○○展」の文字を特定人の展示会等を指 称する語として用いている例があるとしても、そのことは、前記(1)の判断に影響し ない。
ウ 原告は、独占適応性に関し、展示会の業界において、本件役務の取引の実情 の下で、個別具体的な「○○展」の文字は、同種の展示会を開催等する取引者にと って、事前の調査検討の対象として容易に使用を回避できるものであり、また実際 に他者との重複使用が回避されており、取引に際し必要適切な表示として必ずその\n使用を欲するものとはいえないと主張する。
しかし、そもそも、商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと 規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の 場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表\示記述する標章であ って、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、\n特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないという理由も有するもの であって(前掲最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決参照)、単に、同種の展 示会を開催等する取引者の事前の調査検討によって他者との重複使用が回避されれ ば足りるというものではない。加えて、展示会等の内容等を示す語を冠して「○○ 展」の名称が用いられる場合、当該名称を使用する者において、複数の一般的な語 から成る名称であるため特に問題を生じないであろうと考えることは相応に合理的 であるといえ、そのような場合に、その者に、当該名称の使用例が他に存在するか どうかについて、登録商標の有無を調査する場合と同程度の法的な調査義務を課す ことは合理性を欠くというべきである。本件全証拠によっても、展示会に係る業界 において、一般に、「○○展」の文字の使用に当たり標章の使用と同程度の注意が 払われていると認めるには足りず、展示会等を開催等する者が同種の展示会の名称 を調査するなどしているという実態が仮にあるとしても、それは、基本的に、集客 力や独自性の発揮といった観点や、商標法3条2項により保護され得る標章の使用 を避けるといった観点から、事実上行われているとみるのが相当である。 したがって、原告の前記主張も、前記(1)の判断を左右するものではない。
エ 原告は、他に「○○展」という商標の登録例があることからして、「○○展」 との構成の商標が一律に識別性を欠くものとは解されないと主張するが、同主張は、\n前記1(1)の「次世代」や「3Dプリンタ」の語の意義や、同(2)の使用例を踏まえ た本願商標についての前記(1)の判断に影響するものではない。
オ その余の原告の主張は、いずれも、既に認定判断したところに反するか、前 提とする事情を欠くか、あるいはそもそも前記(1)の判断に影響しないものであっ て、いずれも同判断を左右するものではない。
◆判決本文
商標違いの関連事件です。いずれも識別力無しです。
商標「関西 次世代3Dプリンタ展」
◆令和4(行ケ)10069
商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」
◆令和4(行ケ)10070
商標「計測・検査・センサ展」(
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2023.01.11
令和3(ワ)4920 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年12月22日 大阪地方裁判所
ア 前記(1)アによれば、リベラル社は、平成30年7月5日時点において、別 件特許(「活量調質水溶液及び活量調質媒体の製造方法」)により、水酸化物イ オン活量調質水溶液を製造し、これを希釈して、旧ATWのほか「ATW−1、 ATW−001」を製造していたことが認められるところ、前記(1)イのとおり、 被告は、当初、リベラル社から購入した旧ATWをそのままボトルに詰め、又は、 ラベルを貼り替える方法により、旧被告製品や無限七星FISHを製造し、販売\nしていたのであるから、これらの製品は、前記水溶液を希釈したものであると認 められる。一方、前記(1)エ及びオのとおり、被告は、原告の本件特許出願の後か らは、リベラル社から購入した本件特許に規定される組成を有する現ATWを1 0倍希釈して被告製品や無限七星FISHを製造、販売するようになったところ、 本件代理店契約においては、現ATWを含めたATW水溶液は、別件特許の製造 方法による旨の合意がなされている。 また、原告が代表取締役を務めるATW社は、別件訴訟において、旧ATWと\n現ATWは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ATWを10 倍薄めたものが旧ATWである旨を記載した準備書面を提出しているところ、リ ベラル社が発行した請求書では、現ATWの1リットル当たりの単価は旧ATW の同単価の10倍になっていること、本件代理店契約においてATW水溶液の品 質として標準仕様と10倍濃縮仕様がある旨の記載があることのほか、原告も、 本件訴訟において、現ATWは旧ATWの10倍の濃度である旨を主張している (原告準備書面(4)第2の2(3)イ)。これらの事実関係に照らすと、旧ATW及び現ATWは、一貫して、同様の製造方法により製造された、アミノ基を含む成分が水溶、濃縮された水酸化物イオン活量調質水溶液を希釈したものであり、本件特許に規定される組成を有する現ATWを10倍希釈したものが旧ATWであると認められる。
イ また、証拠(乙2、18、24、25、33、36、37)及び弁論の全 趣旨によれば、次の事実が認められる。 すなわち、被告が平成30年11月10日にリベラル社に対して発注し同月1 2日に納品された旧ATWのボトル20本のうち、開封せずに保管していたもの (以下「保管ボトル」という。)について、被告がそのうち1本を開封し、10 0ml分(以下「分析対象物」という。)を小分けにして、愛媛大学のP2名誉 教授に提供した。同教授は、令和3年9月30日、分析対象物について、乙18 分析をした結果、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであることが判明し た。また、被告は、保管ボトルのうち1本(被告が「無限七星FISH」のラベ ルを貼付したもの)を、株式会社東ソ\ー分析センターに提供し、前記センターは、 同年10月19日、保管ボトルの内容物について乙24分析をした結果、その重 量平均分子量は、4.5×10⁴であった。
ウ 前記(1)イ及びウのとおり、無限七星FISHは、鮮魚の鮮度を保持する機 能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており、また、証拠(乙19)\n及び弁論の全趣旨によれば、リベラル社が被告に販売した旧ATWの成分表記に\nは「重合アミン、水」との記載があったことが認められる。
エ 前記ア〜ウの事実関係に照らすと、現ATWが10倍に希釈化された旧A TWと同一成分である無限七星FISHに係る引用発明は、ポリアリルアミン又 はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が95重量%\n以上である水であって(a’)、ポリアリルアミンの重量平均分子量が500〜 50000であって(b’)、魚介類の鮮度保持の機能を有する(c’)、機能\ 水(d’)という構成を有するものと認められるから、被告製品のみならず、旧\n被告製品や無限七星FISHも本件発明の各構成要件を充足するものと認められ\nる。したがって、引用発明は、本件発明の各構成要件を充足する。\n
(3) 公然実施について
特許法29条1項2号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者 が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)イのとおり、 被告は、本件特許の優先日前の平成30年10月から、無限七星FISHを製造 及び販売して、引用発明を実施した。
(4) 原告の主張について
ア 原告は、旧ATWは、別件特許に基づく方法により製造されているのに対 し、現ATWは、ポリアリルアミンを使用して製造されているから、両者の成分 は異なる旨を主張する。 しかし、両者の成分の違いを明らかにする証拠はなく、前記(1)オ及びキのとお り、被告は、本件代理店契約において、リベラル社及びATW社との間で、AT W水溶液の仕様は、別件特許の製造方法によることを合意したことや、ATW社 が、別件訴訟において、旧ATWと現ATWは、いずれもアミノ基という原子団 を含んだ水溶液で、現ATWを10倍薄めたものが旧ATWである旨を記載した 準備書面を提出したのであるから、旧ATWと現ATWの製造方法が異なる旨や 両者の成分が異なる旨の原告の主張は直ちに採用することはできず、その他、原 告の主張事実を裏付ける証拠はない。
イ また、原告は、乙18分析及び乙24分析は、いずれも、測定対象の水溶 液がどの時期に製造、販売され、どういう形で試験に供されたのか全く不明であ ることを指摘し、さらに、乙18分析の内容については、1)乙18のFig.1の スペクトルの面積比を理由に高分子化合物の繰り返し構造をCH₂−CH−CH₂ と推定することが困難なこと、2)3ppm付近のシグナルの変化を理由に当該シ グナルがアミン(CH₂−NH₂)であると推定できる根拠が不明であること、3) Fig.1とFig.4a)のスペクトルが異なることといった疑問点があるから、 いずれも信用性がない旨を主張する。
しかし、前記(1)認定の事実からすれば、乙18にいう「2018年10月に販 売が始まった初代無限七星」とは、旧ATWと成分を同じくする旧被告製品又は 無限七星FISHであると理解できるし、乙24は保管ボトルのうち1本を分析 した結果であることが明らかであり、これに反する証拠はない。そして、乙18 分析は、核磁気共鳴分光法及び質量分析法により、分析対象物の含有成分がポリ アリルアミンであることを推定した上で、それを踏まえて、分析対象物と市販の ポリアリルアミンの水溶液について核磁気共鳴分光法のスペクトルを比較して、 分析対象物の含有成分がポリアリルアミンであると結論づけているところ、原告 の主張1)について、原告主張のように、ポリマーのNMRはピーク(スペクトル) がブロードになりやすく、面積比を算出する切断箇所の設定によって面積比の値 が異なり得ることから、Fig.1のスペクトルの面積比「1.00:0.55: 0.80」が完全に「2:1:2」に一致しなくとも、同一環境の水素の数の比 を「2:1:2」とみなし、CH₂−CH−CH₂の部分構造が考えられるとする\nことは不合理ではない。また、原告の主張2)について、3ppm近辺のCH₂に対 応するシグナルの位置は、隣に窒素原子が繋がっていることを示唆するところ、 トリフルオロ酢酸を加えると、2.7〜3.3ppmのシグナルが3.0ppm のシグナルに変化したというのであるから、分析対象物にトリフルオロ酢酸によ り塩を形成するアミン(CH₂−NH₂)が存在すると考えて矛盾はないというべ きである。さらに、原告の主張3)については、確かに、Fig.1とFig.4a) のスペクトルは一致していないが、一方で、トリフルオロ酢酸塩のスペクトルで あるFig.2a)とFig.4b)は、ほぼ一致している(乙18、25)。こ の点について、証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば、ポリアリルアミンは、 共存物の影響でアミン部位が塩の状態になっている場合、スペクトルのピーク位 置の出現がシフトする可能性があり、ポリアリルアミンの塩の形成状況によって\nスペクトルの形状が変化し、複雑になるものと認められ、一方で、強い酸である トリフルオロ酢酸を加えて、全てのアミノ基をアンモニウムに変換し、均一な状 況にすることにより、一定の分析結果を得ることができたものと認められるから、 Fig.1とFig.4a)のスペクトルが異なるからといって、乙18分析の信 用性に疑義を生じさせることにはならない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2023.01. 6
令和3(ワ)5086 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年12月12日 大阪地方裁判所
3 争点2(被告各イラストが、原告各イラストを複製ないし翻案したものであり、 かつ同一性保持権を侵害するものであるかどうか)について(被告イラスト2に 関する判断)
前記2の認定によると、原告イラスト1は、現実の桜にみられる要素を原告な りの手法により適宜デフォルメして表現し、それらを組み合わせた上、認定に係\nる背景を付した所定の用紙上に配置するなどして1個のデザインとして完成さ せたものであって、認定した表現を含む表\現の総体としては原告の個性が現れた ものであって創作性があるといえ、著作物性を一応肯定できる(争点1)。 よって、進んで争点2について判断する。
この点、原告は、原告特徴1)〜9)が原告イラスト1の表現上の本質的な特徴で\nあり、そのうち原告特徴1)及び3)〜9)が被告各イラストと共通し、被告各イラス トに接した者が原告イラスト1の表現上の本質的な特徴を直接感得することが\nできると主張するところ、原告は、主に被告イラスト2との対比において複製な いし翻案を主張したので、まず被告イラスト2について検討する。
(1) 原告特徴1)について
原告主張の原告特徴1)は、前記第3の2(1)に主張のとおりであるところ、 ここでいう「背景全体」とは、花の白いスタンピング(かすれ要素A)が原告 特徴2)として特定されてこれが除かれていることから、原告イラスト1から、 正面視花要素A、側面視花要素A、つぼみ要素A、かすれ要素Aを除いた部分 をいうものと解される。
そして、前記認定によると、同部分の具体的態様は、「色調の異なるピンク色 や一部オレンジ色が、不明瞭にぼかし味をもちながら配色された」ものであっ て、これと対応する被告イラスト2の要素としては、「赤みのある紫、青みのあ る紫、オレンジ色などがグラデーション、ぼかしを伴って全体としてはマーブ ル状に彩色され、前記すかしを伴ったスタンピング要素Bがランダムに散りば められている」背景部分が該当する。
この点、原告イラスト1と被告イラスト2の背景部分は、そもそもの枠の大 きさが異なることに伴う広がりの規模や、背景として認識される部分の形状が 大きく異なって特段の共通点を見出し難い上、被告イラスト2における、赤み のある紫、青みのある紫、オレンジ色などがマーブル状に彩色されている点は、 原告イラスト1にはみられない被告イラスト2の特徴というべきであって、こ れらの相違点の与える影響は大きなものがある。したがって、原告特徴1)で指摘する内容は、被告イラスト2との共通点を構成しないというべきである。\n
(2) 原告特徴3)ないし同4)について
原告は、原告特徴3)及び同4)が被告イラスト2にもみられると主張するとこ ろ、前記認定によると、原告イラスト1には、5または6個の正面視花要素A 等で構成されるまとまりが台紙の略左中央上、略右上及び略右下の3か所にあ\nることが認められる。また、原告特徴4)中の「空きスペース」に描かれた「適 宜桜の花」が具体的に何を指すかは必ずしも明らかではないが、右上上端及び 左中下端に見切れた正面視花要素Aが各1個、台紙略左下のおおむね中央に正 面視花要素A1個をいうものと解され、これらが同位置に配されている。
一方、被告イラスト2においては、3個の正面視花要素B等で構成されるま\nとまり(別紙被告イラスト2分析図でいうγ及びεのまとまり)、4個の正面 視花要素B等で構成されるまとまり(同分析図でいうδのまとまり)、5個の\n正面視花要素B等で構成されるまとまり(同分析図でいうα及びβのまとまり)\nが、袋体正面では15から20個、前記αからεまでのまとまりが回転を加え たうえでやや不規則に被告イラスト2の枠を埋めるように配されている。また、 これらのまとまりが不整形な形状のためにできたまとまりのない部分に正面 視花要素Bが単独で配されている。 そして、原告イラスト1にみられるまとまりと、被告イラスト2におけるま とまりを、それ自体で相互に比較しても、各構成要素(正面視花要素、側面視\n花要素、つぼみ要素)の構成や形態において同一のものは認められない上、被\n告イラスト2においては、まとまりの数自体や、まとまりの繰り返しによって 与えられる印象が強く、後述の各構成要素の相違点と相まって、「5ないし6\n個の桜の花をまとまって描く」というアイデアのレベルを超えた具体的な表現\n上の共通性を認めることはできない。また、桜の花を数個まとめて描くこと自 体は、自然の桜を描写する際に自然に着想することであって、他の桜のイラス トにもみられるありふれたものといわざるを得ない。また、原告特徴4)につい ても、原告イラスト1においては、被告イラスト2との対比において、まとま りとまとまりの間隔というものは観念しづらく、むしろまとまりの配置のない 略左下部に1個の正面視花要素Aを配したとの印象が強く、具体的表現におけ\nる共通性を感得できない。 以上によると、原告特徴3)及び同4)で指摘される内容は、被告イラスト2に みられる特徴とはいえず、共通点は認められない。
(3) 原告特徴5)、同6)及び同7)について
原告は、正面視花要素Aに関して、原告特徴5)、同6)及び同7)が特徴であり、 同特徴が被告イラスト2にも存すると主張する。 この点、まず、正面視花要素Aと同Bの花弁についてみると、前記認定のと おり、原告イラスト1における花弁は、「白色で基部付近はピンクないし淡い ピンク色が不均一の色調でぼかしたように配されている」のであり、花弁の白 と背景のコントラストが強く意識される一方、被告イラスト2における花弁は 「ごく薄い赤みないし青みのかかった紫色の下地に透明感のある白の小さな おおむね丸いドットが重なるように多数配されて前記薄紫の下地が透けて看 取できる」態様で描かれており、花弁それ自体も淡く着色されている上、背景 とのコントラストは弱く、全体として正面視花要素Bは同Aと相当に異なった 印象を受けるものである。したがって、原告特徴5)が被告デザイン2にも備わ っているとは認められない。また、原告特徴6)及び同7)についてみると、完全 に開花した桜を正面視で「5枚の花弁を放射線状に一体に、花弁ごとに区切ら ずに描き、花弁の中央部に略放射線状にランダムな長さ及び角度で8本又は9 本描く」ことや、同様にやや斜方視で、「5枚の花弁を略扇形に一体に、花弁ご とに区切らずに描いた上で、弧の部分にランダムに山を複数描き、花弁の下寄 りの部分に茶色の細い線でおしべ等を略扇形状にランダムな長さ及び角度で 6本又は7本描き、その先端を茶色の小さい丸で描いている点」は、前記認定 に係る自然の桜の態様及び他のイラストの表現に照らすと、桜のイラストにみ\nられるごく一般的な表現であり、ありふれたものであって、そもそもかかる特\n徴は、原告イラスト1の本質的特徴に当たらない。
(4) 原告特徴8)及び同9)について
原告主張の「先端に白色のつぼみがついた茶色の花柄及びがく片を、花から 適宜飛び出して描いている点」(原告特徴8))及び「つぼみには完全に閉じた状 態のものと、半開き状態のものがあり、前者はふっくらとした雫形状で、先端 がやや尖っていて、がく片は3本であり、後者は略扇形で弧の部分にランダム に山を複数描き、がく片は基本的に4本となっている点」についても、前記認 定に係る自然の桜の態様及び他のイラストの表現に照らすと、桜のイラストに\nみられるごく一般的な表現であり、ありふれたものといわざるをえず、原告イ\nラスト1の本質的特徴に当たらない。
・・・
(6) まとめ
以上のとおり、被告イラスト2は、アイデアなど表現それ自体でない部分又\nは表現上創作性がない部分において原告イラスト1と同一性を有するにとど\nまり、これに接する者が、原告イラスト1の表現上の本質的な特徴を感得する\nことはできないから、依拠性を判断するまでもなく、原告イラスト1の複製及 び翻案に当たらない。よって、被告イラスト2を用いた被告製品2を被告が販 売した行為は、原告の原告各イラストに係る複製権及び翻案権を侵害するもの とはいえず、同様に、同一性保持権を侵害するということもない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2023.01. 6
令和4(ネ)10083 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年12月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 控訴人は、ユーザーにおいては、ツイートを削除していなくともプロフィール画像を変更すれば過去のツイートについても変更後のプロフィール画像が表示されること等を前提としてツイッターを利用していることや、プロフィール画像がツイート本文の内容とは独立して自身の個性を表\現するものであるなどと主張する。しかし、訂正して引用した原判決の第4の2(3)で説示したとおり、ユーザーは、自らのツイートの内容が当該ツイートをした時点におけるアイコンと一体的に表現主体及び表\現内容を示すものとして取り扱われ得ることについても、相応の範囲で受忍すべきものであり、控訴人の上記主張も、訂正して引用した原判決の第4の2(2)の認定判断を左右するものではない。
ウ 控訴人は、本文やユーザー名のほかアイコンまで掲載する必要があるのかには疑問があり、また、現在もツイッター上で閲覧可能な原告ツイートについて、これをあえてスクリーンショットで掲載する必要はないなどと主張する。\nしかし、控訴人においては原告アイコンが原告ツイートの内容と一体的に取り扱われ得ることを相応の範囲で受忍すべきことは既に説示したとおりであり、また、原告ツイートが現在も閲覧可能であるとしても、仮に本件投稿者が引用リツイート機能\を用いていた場合には、原告ツイートを削除等するという専ら控訴人の意思に係る行為によって引用に係る原告ツイートが削除等され、本件ツイートの趣旨等が不明確となるような事態が生じ得ることに照らして、原告ツイートが現在も閲覧可能であるか否かは、本件ツイートにおける引用の適否に直ちに影響すべきものではない。この点、原告ツイートが投稿されてから本件ツイートが投稿されるまでには約7年半という相応の長期間が経過しているところ、原告ツイートが現在も閲覧可能\であり(甲20)、その間に特に控訴人がプロフィール画像を変更したといったことも認められないものであるが、一般的に、引用元ツイートが投稿後変更されることなく相応の長期間が経過した後であっても、引用リツイートの投稿を契機として引用元のツイートが変更や削除等されたりする可能性もあるから、上記相応の長期間の経過をもって直ちに本件ツイートにおける引用の必要性や相当性が否定されるものではなく、また、閲覧可能\性や画像の変更の有無に係る上記各事情は、他方で、原告ツイートの投稿時から本件ツイートの投稿時までの間に、原告において原告アイコンを含む原告ツイートの変更や削除等をしなければならないような事情が他には生じておらず、本件ツイートにおける引用の必要性や相当性を判断するに当たり他に考慮すべき特段の事情がないことをうかがわせるものである。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2023.01. 5
令和3(ワ)6974 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年9月12日 大阪地方裁判所
(1) 本件サービスサイトの性質及び本件ウェブページの位置づけについて 後掲各証拠及び弁論の全趣旨に前提事実を総合すると、次の各事実を認めること ができる。
ア 被告は、平成30年、葬儀に関する困りごとの解決へ向け、葬儀サービスを 探している人々と葬儀社をマッチングする事業として葬儀社紹介サービスを提供す る本件サービスサイトの運営を開始した(甲3、4)。 本件サービスサイトは、被告との提携の有無にかかわらず、全国の葬儀社の情報 を掲載することとしており、被告と提携していない葬儀社のページには、葬儀社の 電話番号やウェブサイトのリンクを記載し、被告の提供するサービスを介さず直接 連絡できる設計としており、本サービスサイトのユーザー(葬儀希望者)が、提携 していない葬儀社を指定して被告に問合せをした場合は、当該葬儀社の電話番号を 案内する方針としている。なお、提携先の葬儀社については、見積り取得の手配や 代行を行っている(甲10、20)。
イ 本件サービスサイトにおいて、ユーザーが一定の地域を選択すると、被告が 把握するその地域に所在の葬儀社や斎場が一覧表示され(その他、費用・形式別の\nプランの紹介、葬儀の依頼や相談、一括見積を行うサイトへの遷移ボタン、当該地 域の葬儀に関するQ&Aや事例なども表示される)、その一覧の中から、個別の葬\n儀社等を選択すると、当該個別の葬儀社等に関する被告が把握した情報を提供する ページが表示され、本件葬儀場(セレモニートーリン)を選択した場合、本件ウェ\nブページが表示される(甲22の1・2、乙1)。\n
ウ 本件ウェブページは、その固定ヘッダーに「安心葬儀 葬儀のご依頼/ご相 談 一括見積なら|安心葬儀」「安心葬儀/葬儀相談コールセンター(無料)通話 無料<省略>」といった記載があるほか、ページの上部に「安心葬儀TOP」「葬 儀の種類」「宗教・宗派別葬儀」「葬儀の知識」という記載(リンク)や「安心葬儀 TOP>大阪府の葬儀社/斎場一覧>大阪市<以下略>>セレモニートーリン」と いう各ウェブページの階層を示す記載があり、また、「セレモニートーリン」と太 字で書かれた下部には、本件葬儀場の外観を撮影した写真が掲載され、「セレモニー トーリンとは」「セレモニートーリンの特徴」「セレモニートーリンの住所・地図・ アクセス」「セレモニートーリンの情報」「セレモニートーリンの口コミ・レビュー」 「セレモニートーリンの葬儀式場・休憩室情報」の各欄にはそれぞれ見出しに対応 した情報が記載されているほか、「当サイトは「セレモニートーリン」と提携して おりません。掲載している情報は、葬儀社様の公式サイトの情報など、一般に公開 されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになりま す(中略)。斎場に関する詳細・最新の情報につきましては公式の Web サイトや電 話で直接ご確認ください。」との記載がある。 これより下部には、「セレモニートーリンの近くにある他の斎場」「大阪府で経 験・実績の多い葬儀社」「大阪府の家族葬の葬儀事例」の欄には、それぞれ複数の 葬儀社や葬儀事例が記載されており、さらに、「葬儀社/斎場を地域を指定して検 索する」「葬儀社/斎場を大阪府の市町村から選ぶ」の欄においては、それぞれ選 択した対象エリアや地域に所在する葬儀社等を検索することが可能である(甲22\nの1・2。なお、以上の記載内容は、口頭弁論終結時のものである。)。
エ 検索サイトYahoo!において、「セレモニートーリン」とキーワード検 索すると、検索結果を表示するウェブページにおいて、広告であることが明記され\nた他の葬儀社等のリンクが表示された後、広告表\示のないものとしては一番目に原 告のウェブサイトへのリンクが「公式/セレモニートーリン・大阪市<以下略>、 東大阪のお葬式」等の見出しのもとに何件か表示される。それに引き続き、被告の\n本件ウェブページについての案内(その詳細は、「https<以下略>>大阪府の葬儀 社/斎場一覧>大阪市<以下略>」とドメイン部分等が小さく表示され、その下に\n見出し(リンク)部分として、「セレモニートーリン(大阪府)の斎場詳細|安心 葬儀」が表示され、「評価:4.3 1件のレビュー」との情報及び本件ウェブペー ジの説明文として、「セレモニートーリン(大阪府大阪市<以下略>)の口コミ、 写真、施設情報、アクセス・地図など詳しい情報をご紹介します。【安心葬儀】は お客様のご予算やご要望に合わせて、...」が表示され、「セレモニートーリンの特\n徴・セレモニートーリンの住所・地図...」との表示もされる。)が表\示される。な お、その下には、詳細は不明であるが、被告以外の他のサービスサイトと思われる サイトへのリンクも表示される(甲21の1・2)。\n
(2) 前記認定によると、本件サービスサイトは、その構成において、需要者であ\nる葬儀希望者に対し、その条件に見合った葬儀社等の情報提供を行い、また希望者 には葬儀の依頼や相談、一括見積を行うことなどを通して、葬儀希望者と葬儀社等 とのマッチング支援を行うサービス(被告役務)を提供するものであることが容易 に看取できる。
そして、本件ウェブページは、これを単独でみても、そのドメインや本件ウェブ ページのタイトル部分や末尾の「安心葬儀」等の表示、競合し得る近隣の斎場等の\n情報も表示されることに加え、本件葬儀場の情報については、ホールの外観、特徴\nや所在地、アクセス方法、設備情報等の客観的な情報が記載されているにとどまり、 これを超えて本件葬儀場の利用を誘引するような記載はみられないこと等の事情か らすると、本件ウェブページに接した需要者は、「セレモニートーリン」を、葬儀 場を紹介するという本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社(場)として 認識するものであり、原告が本件葬儀場において提供する商品ないし役務に関し、 被告がその主体であると認識することはないものというべきである(本件ウェブペー ジを含め、本件サービスサイトの運営者が原告であると認識することがないことも 同様である。)。
さらに、原告が問題とする本件ウェブページの html ファイル中のタイトルタグ及 び記述メタタグに記載された内容は、検索サイトYahoo!において「セレモニー トーリン」をキーワードとして検索した際の検索結果において基本的に各タグに記 載されたとおり表示されると認めることができるが、その内容は、いずれも本件サー\nビスサイトの名称が明記された見出し及び説明文と相まって、原告の運営するウェ ブサイトとは異なることが容易に分かるものと評価できる上、一般に、検索サイト の利用者、とりわけ現に葬儀の依頼を検討するような需要者は、検索結果だけを参 照するのではなく、検索結果の見出しに貼られたリンクを辿って目的の情報に到達\nするのが通常であると考えられるところ、需要者がそのように本件ウェブページに 遷移した場合には、前記のとおり、被告が運営する本件サービスサイトの一部とし て本件ウェブページを理解するのであって、やはり、被告標章を本件ウェブページ の各タグ内で使用することによって、原告と被告の提供する商品または役務に関し 出所の混同が生じることはないというべきである。 したがって、被告による被告標章の使用は、商標法26条1項6号の規定により、 本件商標権の効力が及ばないというべきである。
(3) 原告は、被告は、本件ウェブページの見出しやその説明文において被告標章 を表示させ、需要者をして本件ウェブページにアクセスするよう誘引し、本件ウェ\nブページにおいて本件葬儀場の建物の写真や情報を表示させることで、需要者をし\nて、本件ウェブページが原告(セレモニートーリン)のウェブページであると誤認 させ、出所の混同を生じさせている旨を主張する。 しかし、本件ウェブページの見出し、説明文及び本件ウェブページ自体の表示内\n容を踏まえると、見出し及び説明文に被告標章の表示があるからといって、出所の\n混同を生じさせることにはならないことは前述したとおりである。原告の主張は、 要するに、原告を紹介する本件ウェブページに被告の電話番号等が表示されること\nにより、原告が、その潜在的需要を失う不利益を被っていることをいうものと解さ れるが、そのような結果が仮に生じているとしても、前記認定に係る本件サービス サイトの性質及び本件ウェブページの記載(なお、反対にこれを参照して原告に依 頼する需要者も在り得ると考えられる。)からすると、自由競争の範囲内のものと いうべきである。原告の前記主張は採用の限りでない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2023.01. 3
令和3(ワ)21224 損害賠償金請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年11月21日 東京地方裁判所
本件において、原告が、本件各画像を含め、自己が著作権を有する著作 物を第三者に有償で利用許諾していたと認めるに足りる証拠はないから、 実際の利用許諾例に準じて使用料相当額を算定することはできない。 イ この点、原告は、新聞社や写真提供会社が提供する画像レンタルサービ スにおける使用料を根拠として、本件各画像の1ページ当たりの使用料相 当額は6万6666円を下らず、これに本件各画像が掲載されたウェブペ ージのページ数を乗じて使用料相当額を算定すべきであると主張する。 (ア) まず、ページ数を単純に乗ずることの当否について検討すると、原告 商品は、特長、材質、製造方法、メーカーなどが同一である複数のフラ イパンの一群からなる商品であるところ(甲12)、被告ストアにおける 本件各画像の利用態様も、複数の商品販売ページにわたって、原告商品 が等しく備える特長等を紹介する本件画像1)ないし7)の各画像の複製物 を共通して複製及び送信可能化し、本件商品画像については、当該ペー\nジで販売している商品に相当する画像1点を複製及び送信可能化したと\nいうものであることが認められる(前提事実(2)ア、イ、甲2)。このよ うな利用態様にかんがみれば、特に、全てのページにわたって原告商品 に共通する特長等を紹介する同一の画像7点については、異なる態様で 複数回利用された場合と同視することはできず、本件において、単純に ページ数(すなわち販売している商品の種類の数)を乗じて使用料相当 額を算定することが相当であるとはいえない。
そこで、更に検討すると、本件各画像は、商品群からなる原告商品の ネット通販用広告画像、すなわち販売促進資料として作成されたものと 認められることから(甲12)、原告商品の販売と無関係に本件各画像を 使用することは通常考え難く、仮に原告が第三者に本件各画像の利用を 許諾するとすれば、原告も主張するとおり、原告商品の日本国内の正規 代理店として、原告商品の再販売契約をするに当たり、その販売促進資 料として本件各画像全体を利用許諾するような場合が想定される。そし て、同一のオンラインショッピングモール上に出店しているとしても、 オンラインストア名が異なれば、商品の販売経路を複数有することにな るから、販売促進資料としての画像の利用許諾契約に当たっても、原告 商品を取り扱うオンラインストア数の多寡を考慮するのが合理的といえ る。アフロ社が提供している画像レンタルサービスにおいて、同一サイ トである限り、使用箇所を問わず同じ使用料が設定されている(甲7の 「ウェブ広告・ホームページ」欄の注記)ことも、オンラインストア数 に応じて使用料相当額を算定する方法の合理性を裏付けるものである。 以上のとおり、原告商品が一つの商品群からなるものであること、被 告ストアにおける本件各画像の実際の利用態様及び想定される本件各画 像の利用許諾の態様にかんがみれば、本件各画像の使用料相当額を算定 するに当たっては、本件各画像の複製物が掲載されたページ数(すなわ ち販売している商品の種類の数)ではなく、オンラインストア数を基準 とすべきであって、本件においては、被告ストアが一つであることから、 被告ストア全体にわたって本件各画像を1回利用したものとして算定す るのが相当というべきである。
(イ) 次に、本件各画像の具体的な使用料相当額について検討する。
a 原告が指摘する新聞社の画像レンタルサービスにおいて、具体的に どのような写真や画像が提供されているのかを認めるに足りる証拠は ない。しかし、新聞社が提供する写真は、いわゆる報道写真にみられ るように、ある事件や事象の一瞬を捉えているなど、構図やシャッタ\nーチャンス等に高度な工夫を凝らした創作性の高いものや、他の手段 では入手が困難な希少性の高いものである可能性があると考えられる。\nまた、アフロ社が提供する画像レンタルサービスについては、上記 のような報道写真とは異なる性格の画像も提供されていることがうか がわれるものの(甲7)、やはり、実際にどのような写真や画像が提供 されているのかは、本件証拠上認めるに足りない。
b その一方で、被告が指摘するシャッターストック社やピクスタ社の 画像レンタルサービスについてみると、証拠からうかがわれる具体的 な画像の内容(乙3、4)のほか、ピクスタ社では6200万点以上 の写真、イラストなどの素材について、料金が1か月間に利用できる 画像の点数に基づいて設定されていたり、未利用画像数を翌月以降に 繰り越せるといった条件で提供されていたりすること(乙2、4)に かんがみれば、これらのサービスにおいて低額な使用料で提供されて いるのは、汎用性のあるウェブサイト用の素材である可能性が高い。\n もっとも、商業的利用の可否など、その余の使用条件については、 本件証拠上判然としない。
c これに対し、前提事実(2)ア及び前記(ア)のとおり、本件各画像は、 商品販売ページを見た顧客の購買意欲を高めるように、原告商品を用 いて調理している様子を撮影した写真や特長等を述べた文言、画像な どを配置した原告商品に特化した販売促進目的の画像であって、報道 写真とも、シャッターストック社やピクスタ社が提供する汎用性のあ るウェブサイト用の素材とも、性格及び目的が大きく異なる。また、 前記(ア)において説示したとおり、原告が第三者に本件各画像を利用許 諾することが想定されるのは、原告商品の正規代理店として、原告商 品の再販売契約に当たって販売促進資料として利用されるような場合 であるから、専ら写真、画像等の利用許諾に伴う使用料をもって収益 を上げるというビジネスモデルに基づき設定された使用料の水準が妥 当するともいい難い。これらの事情に照らせば、原告及び被告の双方 がそれぞれ指摘する画像レンタルサービスにおいて規定されている使 用料の水準が本件においてそのまま妥当するとはいえない。
その一方で、前記(ア)のとおり、本件各画像は、原告商品の再販売契 約に伴う販売促進資料との位置付けで利用許諾されることが想定でき るから、本件各画像の使用料のみによって本件各画像の取得費用を回 収したり、原告商品の再販売によって得られる利益を超えたりするよ うな高額な使用料が設定されるとは考え難い。
このほか、本件各画像は、報道写真のように高度の創作性を有して おり代替可能性が小さいとまではいえないものの、原告商品に特化し\nた販売促進資料として工夫して作成されたものであり(前記(ア))、相 応に創作性を有する著作物であること(前記1)、被告ストアにおける 販売商品数は11点であり、本件各画像の利用期間が約3か月間であ ったこと(前記(1))、本件各画像の利用に当たっての将来の使用料額 を定める場面ではなく、原告の許諾を何ら得ることなく本件各画像を 利用した被告に対する損害賠償を請求する場面での金額の算定である ことなどを総合考慮すると、本件各画像の使用料相当額は合計5万円 と認められる。
ウ 当事者の主張について
(ア) 原告は、本件各画像の使用料相当額を算定するに当たり、いつも社に 本件各画像のデザイン制作料等として約700万円を支払ったことを考 慮すべきであると主張する。 しかし、原告がいつも社に委託したのは、ウェブサイト関連業務及び 検索エンジン最適化サービスであり、本件各画像の制作業務はその一部 を構成するにすぎないと認められるところ(甲12)、本件各画像のデザ\nイン制作のみに要した費用を認めるに足りる的確な証拠はない。 したがって、本件各画像の使用料相当額の算定に当たって、原告が主 張する金額を考慮することはできない。
◆判決本文
イ号はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2023.01. 3
平成30(ワ)33583 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 知的財産裁判例 令和4年1月28日 東京地方裁判所
イ 不競法5条2項の利益の意義
不競法5条2項所定の不正競争行為により侵害者が受けた利益の額は, 侵害者が不正競争行為によって製造販売した製品の売上高から,侵害者に おいて同製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加 的に必要となった経費を控除した限界利益の額であると解すべきである。
ウ 売上高(限界利益の算定の対象とすべき製品の範囲)
(ア) 1)の製品について
1)の製品の売上高は,前記(1)アのとおりであり,合計4272万36 27円が限界利益の算定の対象とすべき売上高となる。
(イ) 2)の製品及び3)の製品について
a 被告は,1)の製品の売上高のみを対象として限界利益の算定をする のは相当でなく,2)の製品及び3)の製品に関する事情も考慮して,被 告製品の販売による限界利益の計算をすべきであると主張するので, 以下検討する。
b 3)の製品は,製造したが販売されなかった製品であり,前記(1)ウ (イ)のとおり,被告製品の販売を終了する直前の令和2年3月の無償提 供も1)の製品の販売と一体として行われたものとはいえないから,3) の製品の存在やその無償提供に関する事情を被告製品の販売による被 告の限界利益の算定に当たって考慮するのは相当でない。
c 2)の製品は,原価(原材料費)未満の額で販売した製品であるとこ ろ,被告は,このような廉価販売がされた事情について,前記第3の 4(被告の主張)(2)イ(イ)のとおり,新製品のプロモーション等のた めの値引き,レンタル事業者に販売する際の値引き,代理店又は販売 店を通じた販売の際の値引き,無料お試しキャンペーンの際の値引き, 被告製品販売中止の検討時期の在庫処分のための値引きなど,各種の 事情により,被告製品の販売開始当初から販売中止時期までにかけて 廉価販売を行ったと主張する。
しかしながら,上記の各事情によって,いつどの程度の値引きでど の程度の個数を廉価販売したのかについて,具体的な主張立証はなく, 2)の製品の値引きのうち,本件訴訟において原告が差止及び廃棄を請 求したこととは関係なく,1)の製品の販売に伴って不可避的に生じた といえるものがどの程度あったのかは,明らかでない。さらに,前記 (1)アのとおり,1)の製品は,被告製品1が1個当たり平均1万265 9円,被告製品2が1個当たり平均1万2653円で販売されたとこ ろ,前記(1)イのとおり,2)の製品については,被告製品1が4分の1 程度の平均3236円,被告製品2が6分の1程度の平均2020円 で販売されており,1)の製品との販売価格の乖離が大きいこと,被告 製品は廃棄請求の対象となるべきものであるところ,被告の主張を前 提としても,上記のとおり,2)の製品の販売には,本件訴訟が提起さ れた平成30年10月以降の時期に,在庫処分の趣旨で行われたもの があること,証拠(乙42,43)によれば,令和2年2月以降の被 告製品の販売のほとんどは廉価販売であり,同月及び同年3月には被 告製品が合計1640個販売されていると認められ,廉価販売された 被告製品2163個の中で,上記の販売終了に伴う在庫処分の趣旨で 行われたものが大部分であったと考えるのが自然であることも考慮す れば,2)の製品の販売について,1)の製品の販売と一体とみることは できないというべきである。したがって,被告製品の販売による不競 法5条2項の損害の算定に当たっては,2)の製品の販売を考慮せず, 1)の製品の販売のみを対象として被告の限界利益を算定するのが相当 である。
エ 限界利益の算定に当たって売上高から控除すべき経費について
(ア) 原材料費について
1)の製品についての原材料費が以下の金額であることは当事者間に争 いがなく,これは1)の製品の販売による限界利益の算定に当たり控除す べき経費である。
被告製品1 2512万4308円
被告製品2 504万3521円
(イ) 保管費について
証拠(乙61)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,被告製品の製造 後から出荷までの保管費用として,平成30年7月から令和2年3月末 日までの間に合計979万6000円を支出したものと認められる。こ のうち1)の製品に係る保管費用が,1)の製品の製造販売に直接関連して 追加的に必要となったものとして,限界利益の算定に当たり控除すべき 経費に該当する。
前記(1)ウのとおり,被告製品の総製造数は7553個であるから,1) の製品に係る費用の額は437万7267円(979万6000円×3 375個/7553個)と認められる。
(ウ) 販売サイト関連費,お問い合わせ窓口に係る費用及びインターネット広告費について
被告は,被告製品のネット販売のサイトに係る費用として合計115 8万5000円を,お問い合わせ窓口に係る費用として合計454万3 375円を,インターネット広告に係る費用として合計1676万79 26円をそれぞれ支出したと主張し,これらの額の請求に係る見積書 (乙62)及び請求書ないし買掛票(乙64)を提出する。 しかしながら,上記の見積書等に係る費用と被告製品の販売との具体 的な関連を示す証拠はなく,また,被告の主張を前提としても,上記の ような費用は,通常,製造販売される製品の個数の影響を受けて変動す ることが想定されないというべきであり,実際にそのような変動が生じ たと認めるに足りる証拠もない。したがって,被告の主張する上記の各 費用は,1)の製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったもの とは認められず,限界利益の算定に当たり控除すべき経費に該当すると はいえない。
(エ) 運搬費について
証拠(乙61)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,被告製品の出荷 に係る被告製品の運搬費として,平成30年7月から令和2年3月末日 までの間に合計911万7059円を支出し,そのうち,購入者が送料 を負担した分が78万0610円であったものと認められるから,これ を控除すると,被告が運搬費として実質的に負担した額は833万64 49円と認められる。このうち1)の製品に係る費用は,1)の製品の製造 販売に直接関連して追加的に必要となったものとして,限界利益の算定 に当たり控除すべき経費に該当する。 前記(1)のとおり,1)の製品の販売数は3375個,2)の製品の販売数 は2163個であるほか,3)の製品のうち無償で提供されたものが10 00個あり,証拠(乙68)によれば,その送料は被告が負担したもの と認められるから,上記の運搬費合計のうち,1)の製品に係る費用の額 は430万3382円(833万6449円×3375個/6538個) と認めるのが相当である。
被告は,運搬費として支出した総額は963万9427円であると主 張し,被告作成の「スマポ発送運賃」等の項目や金額が記載された書面 (乙57)には,被告製品に係る運賃の合計額につき同主張に沿う記載 があるが,同書面記載の運賃のうち,請求書(乙61)が提出されてい るものの額は合計911万7059円にとどまる。また,被告は,1)の 製品に係る運搬費の額について,1)の製品の販売数と2)の製品の販売数 のみを考慮して算定すべきと主張するが,3)の製品のうち無償で提供し たものの送料を上記請求書(乙61)とは別途支出したことを認めるに 足りる証拠はないから,1)の製品に係る費用の額は上記認定の限度で認 めるのが相当である。
原告は,上記請求書(乙61)には,被告製品以外のものに係る請求 が含まれているから,その点も考慮すべきであると指摘するが,当該請 求書の件名としてはいずれも「スマポ 保管発送」と被告製品の名称の みが記載されていること,項目として「南京錠 開梱 同梱」等の記載 があるのは被告製品の付属品の取り扱いに関する記載と考えられること からすれば,上記請求書に係る運搬費はその全体が被告製品に係る費用 と認めるのが相当であり,原告の指摘は上記認定を覆すに足りるもので はない。
(オ) 金型費について
証拠(乙46,65)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,被告製品 の製造のために新規に金型を製作し,その製作費用及び被告製品の製造 を開始するための改造費用として,被告製品1について金型製作費47 81万円及び金型改造費717万2000円の合計5498万2000 円を,被告製品2について金型製作費5181万8000円及び金型改 造費671万6000円の合計5853万4000円を,それぞれ支出 したことが認められる(総合計1億1351万6000円)。 被告は,上記の金型費が,被告製品の製造・販売のために直接必要と なった直接固定費であり,全額が経費として控除されるべきであると主 張する。
確かに,被告製品の金型は被告製品の製造のために新規に必要 となったものではあるが,証拠(甲33,53,乙30)及び弁論の全 趣旨によれば,被告製品のような樹脂製品の製造に用いる金型には30 万ないし40万回程度使用可能なものがあると認められ,これに対して,1)の製品の製造数は,被告製品1について2813個,被告製品2につ いて562個にすぎないから,金型費の全額が1)の製品の製造販売に直 接関連して追加的に必要となったものということはできない。被告は金 型を廃棄済みであり,今後の使用予定がないことからも金型費の全額を経費と認めるべきと主張するところ,証拠(乙52ないし54)によれ\nば,被告は令和2年2月に被告製品の金型を廃棄していると認められる ものの,本件訴訟における被告製品の生産の差止請求を受けて廃棄され たものと考えられ,本件全証拠によっても,上記の金型の製作当時から 被告製品が少数のみ生産される予定であったとの事情は認められないか\nら,被告製品の金型が廃棄されていることを考慮しても,金型費の全額 が1)の製品の限界利益の算定に当たり控除すべき経費に当たるというこ とはできない。
そして,上記の金型の使用可能回数(少ない方の数値を採用)に対して,1)の製品の製造数が,被告製品1では0.9%程度(2813個÷ 30万回),被告製品2では0.2%程度(562個÷30万回)である ことからすれば,上記の金型の一部は共通部品の金型として被告製品1 と被告製品2の双方に使用されるものであったこと(乙52)を考慮し ても,上記金型費のうち,1)の製品の製造販売に直接関連して追加的に 必要な費用として限界利益の算定に当たり控除すべき経費に該当するの は,その1%に相当する113万5160円(1億1351万6000 円×1%)と認めるのが相当である。
(カ) 経費控除後の限界利益の額
以上によれば,1)の製品の製造販売により,被告が受けた限界利益の 額は,前記ウ(ア)の1)の製品の売上高合計4272万3627円から,前 記(ア)の原材料費合計3016万7829円,前記(イ)の保管費のうち4 37万7267円,前記(エ)の運搬費のうち430万3382円及び前記 (オ)の金型費のうち113万5160円を控除した273万9989円で ある。
オ 推定覆滅事由について
(ア) 不競法5条2項における推定の覆滅については,不正競争行為に及ん だ侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と被侵害 者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解さ れる。そこで,以下,被告が主張する事情について,上記の推定覆滅事 由に該当するか否かを検討する。
(イ) 原告が原告製品を販売していないことについて
被告は,原告製品は(省略)が販売する製品であって,原告は(省略) から請負契約に基づき製造の対価としての報酬を支払われる関係にある にすぎず,被告製品の販売による原告の逸失利益とは,(省略)から支払 われる報酬が喪失したというものであり,被告製品の販売による被告の 限界利益とは性質を大きく異にするものであるから,不競法5条2項の 推定は全部覆滅されると主張する。 しかしながら,原告において,被告による被告製品の製造販売がなか ったならば利益が得られたであろうという事情が存在することは,前記 アのとおりであり,原告製品を販売しているのが(省略)であって,原 告製品の販売による原告の利益が,その本体部分の製造について(省略) から受ける報酬であるとしても,そのような原告の利益の額が被告製品 の販売による被告の限界利益の額と乖離していることについて,具体的 な主張立証はない。したがって,被告の主張する上記の事情をもって, 推定覆滅事由に当たるとは認められない。
(ウ) 広告宣伝の効果について
被告は,GoogleやYahooといった検索サイト等にバナー広 告やリスティング広告を設置しており,被告製品の販売による限界利益 のうち,最低でも28.8%は広告宣伝が寄与したものであるから,不 競法5条2項の推定は28.8%覆滅されると主張する。 しかしながら,本件証拠上,被告が行った上記の広告の具体的な内容 は明らかではなく,競合品の販売における広告と比較して,被告製品の 販売を特に促進するような広告宣伝がなされたといった事情も認められ ないから,被告が主張する被告製品に係る広告宣伝の効果をもって,推 定覆滅事由に当たるとは認められない。
(エ) 原告製品以外の競合品の存在について
被告は,被告製品には原告製品以外の競合品が存在しており,被告製 品が販売されなかったとしても,被告製品の購入者は,原告製品よりも 安い他の競合品を購入し,あえて原告製品を購入する者は現実的にはほ とんどいないと予想されるから,不競法5条2項の損害の推定は少なくとも9割が覆滅されると主張する。\n原告製品と被告製品とが,自宅の玄関前等に設置可能な後付け型の荷\n物受取用樹脂製宅配ボックスという点で同種の製品であり,価格の違い にかかわらず,市場において競合する製品といえることは,前記アのと おりであるところ,被告製品が販売されていた平成30年7月から令和 2年3月までの間において原告製品以外の同種商品が販売されていた状 況やそのシェアについて,具体的な主張立証はない。したがって,被告 が主張する原告製品以外の競合品の存在についても,推定覆滅事由に該 当するとは認められない。
(オ) 以上によれば,1)の製品の製造販売による原告の損害について,不競 法5条2項の推定を覆滅すべき事情が存在するとは認められない。
カ 小括
よって,不競法5条2項によって算定される原告の損害額は,被告製品 のうち1)の製品の販売のみを対象とした被告の限界利益である273万9 989円と認められる。
(3) 不競法5条3項による損害額について
ア 不競法5条3項による損害額は,原則として,営業秘密を使用した侵害 品の売上高を基準とし,そこに営業秘密の使用に対し受けるべき料率を乗 じて算定するのが相当であるが,2)の製品については廉価販売がされ,3) の製品については無償提供又は廃棄がされており,同項の適用の可否及び 算定方法に争いがあることから,以下,まず,1)の製品についての同項に よる損害額を検討し,さらに,2)の製品及び3)の製品について,同項の適 用の可否及び適用される場合の算定方法について検討する。
イ 1)の製品についての不競法5条3項による損害額
(ア) 侵害品の売上高
1)の製品についての売上高は,前記(1)アのとおり,被告製品1につい て3561万2239円(販売数2813個),被告製品2について71 1万1388円(販売数562個)の合計4272万3627円である。
(イ) 使用料率について
a 使用料率の認定方法
不競法2条1項7号及び10号に係る営業秘密の使用及びこれによ って生じた侵害品の譲渡に対して受けるべき料率は,1)当該営業秘密 の実際の使用許諾契約における使用料率や,それが明らかでない場合 には業界における使用料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該営業秘密 自体の価値すなわち営業秘密の内容や重要性,他のものによる代替可 能性,3)当該営業秘密を製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様,4)営業秘密保有者と侵害者との競業関係や営業秘密保 有者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率 を定めるべきである。
b 使用料率の認定
(a) 原告による使用許諾の実績について
前記2(1)のとおり,本件データは本件新製品の最終試作品の製作 のための3Dデータであるところ,弁論の全趣旨によれば,原告が 本件データについて他社に使用許諾をしたことはないものと認めら れる。 また,原告が,他社に対して同種の3Dデータの使用を有償で許 諾した事例の有無や,その際の許諾の対価についての主張立証はな い。
(b) 原告による「設計費」等の請求について
証拠(乙1,2,30ないし35)及び弁論の全趣旨によれば, 原告は,通常,他社から受注を受けて樹脂製品を製作する場合に, CADの図面の製作費用を独立に請求することはなく,受注する製 品価格や製造のための金型価格を含めた全体で利益を確保するとの 方針を取っていること,本件新製品の製造については,当初原告に 製品と金型の発注がされる予定であったところ,本件新製品の開発協議の中で,金型を被告が調達することが検討され,その場合には\n原告に設計費を支払うことが協議されたこと,その後,原告におい て金型を調達する場合にも設計費を支払うよう原告が求めたこと, 原告は,前記1(14)のとおり,本件プロジェクトの終了後の平成2 9年10月に,本件新製品の「設計費」として203万2800円 のほか,「機会損失額」として1496万円の合計1699万280 0円を請求したが,当該支払について原告と被告間で合意に至らな かったこと,原告は,上記の「設計費」及び「機会損失額」の請求 に当たり,「設計費」については「設計工数:6,500円/H×2 96H=1,924,000円」,「モックアップ作成費:54,4 00円×2個=108,800円」と記載し,296時間分の設計 工数とモックアップ作成に要した費用の合計として合計203万2 800円を請求する旨を説明しており,「機会損失額」の算定根拠と して「製品:1,600セット/月×12カ月×2,600円× 5%×5年=12,480,000円」,「金型:49,600,0 00×5%=2,480,000円」の合計1496万円を請求す る旨を説明していたことが認められる。
上記の「設計費」及び「機会損失額」の請求は,その経緯からす れば,本件新製品について原告に製品と金型の発注がされる予定であり,原告はそれによる収益を見込んでいたところ,被告から原告\nへの発注がなくなったため,原告が作成した本件データを被告が使 用することの対価も含めて,原告への発注によって原告が得られた 利益に相当する額を算定し,その額を請求したものと認められる。 原告の上記請求内容は,被告との間で最終的な合意には至らなかっ たものの,本件訴訟前における原告の提案内容という限度で,本件 データの使用についての使用料率の算定の参考とすることができる というべきである。
被告は,本件データの使用料相当額について,上記の「設計費」 である203万2800円が上限である旨主張するが,上記のとお り,「設計費」のほか,併せて請求された「機会損失額」にも本件デ ータの使用の対価は含まれていたというべきであるから,原告の提 案内容として「設計費」の額のみを考慮するのは相当でなく,被告 の上記主張は採用することができない。 また,被告は,「機会損失額」の算定に当たり,上記のとおり「1, 600セット/月×12ヶ月×2,600円×5%×5年=12, 480,000円」との計算が示されていたことから,本件データ の使用料相当額について,被告製品1及び被告製品2の1セット当 たり130円(2600円×5%)が使用料相当額の最大値となる 旨も主張する。しかしながら,原告の「機会損失額」の提案は,本 件新製品について,原告が被告から受注する数を合計9万6000 個(1600個×12か月×5年)と想定した上で,1個当たりの 原告の損失を130円(2600円×5%)として算定しているも のであるが,被告製品の製造販売個数に応じて1個当たり130円 を支払うよう請求していたものではなく,また,「機会損失額」とし ては更に金型の受注についての機会損失額248万円を請求し,「設 計費」も併せて請求していたものである。そうすると,「機会損失額」 の算定根拠についての原告の説明内容から,被告製品の製造販売に ついての使用料相当額が1台当たり130円に限られるということ にはならず,被告の上記主張は採用することができない。
(c) 業界における使用料の相場等について
前記(a)及び(b)のとおり,本件データの使用許諾については,こ れを含む趣旨の原告から被告に対する訴訟前の提案があるにとどま り,原告の使用許諾の実績はないため,本件データの使用料率の算 定に当たっては,業界における使用料の相場等を考慮すべきである。 そして,本件報告書には,「技術ノウハウ」についてのロイヤルテ ィ料率の相場等について,アンケート調査結果として,技術分類の うち「成形」の分野においては,ロイヤルティ料率の平均値が3. 8%(最大値14.5%,最小値0.5%,標準偏差3.2%)で あることが記載されており,本件報告書以外に,本件データのよう なCADシステムのデータの使用許諾についての一般的な相場を示 す証拠は双方から提出されていないから,本件報告書に記載された 上記のロイヤルティ料率を本件データの使用料率の算定に当たって 考慮するのが相当である。
・・・
(f) 使用料率の認定
以上によれば,合理的な使用料率の算定に当たっては,前記(c)の 本件報告書に記載されたロイヤルティ料率の相場(平均値3.8%, 最大値14.5%,最小値0.5%,標準偏差3.2%)を考慮す べきであり,さらに,前記(d)の本件データの被告製品による利益へ の貢献や本件データの代替可能性,前記(e)の原告と被告とが競業関 係にあること,前記(b)の本件訴訟前の原告の提案内容といった事情 を総合考慮すれば,不正競争行為をした者に対して事後的に定めら れる,本件データの使用に対して受けるべき使用料率については, 6%と認めるのが相当である。
原告は,本件報告書について最大でロイヤルティ料率を14. 5%とする例があったことを指摘するが,本件報告書における平均 値は3.8%であり,前記(d)のとおり,本件データが同種製品の製 造に必須で代替不可能なほど重要なものであるとまではいえないことからすれば,本件報告書における最大値を基準とすべきとはいえ\nない。
(ウ) 使用料相当額
a 1)の製品についての使用料相当額を算定すると,前記(ア)の売上高合 計4272万3627円の6%に相当する256万3417円と認め られ,これが不競法5条3条による損害額となる。
b 前記aの使用料相当額の内訳は,被告製品1について213万67 34円(3561万2239円×6%),被告製品2について42万6 683円(711万1388円×6%)となり,被告製品1の販売数 が2813個,被告製品2の販売数が562個であるから,製品1個 当たりの使用料相当額を算定すると,次のとおり,被告製品1と被告 製品2のいずれについても759円となる。
213万6734÷2813個≒759円
42万6683円÷562個≒759円
ウ 2)の製品についての不競法5条3項による損害額
(ア) 1)の製品を対象として不競法5条2項による損害を算定する場合に, 2)の製品に同条3項を適用できるかについて
被告は,1)の製品を対象として不競法5条2項による損害を算定する 場合に,別途2)の製品について不競法5条3項による損害を算定して, これらを合算することは,填補賠償の原則に反して許されないと主張す る。 しかしながら,前記(2)ウのとおり,2)の製品の販売は,1)の製品の販 売と一体のものとして行われたものとはいえず,1)の製品の販売のみに 基づいて不競法5条2項による損害額を算定することは認められるとい うべきであるから,同項による損害の算定において対象となっていない 2)の製品について同条3項によって損害額を算定し,これと1)の製品に ついて同条2項により算定した損害額を合算しても,算定の対象とされ た製品が異なっている以上,損害を二重に評価していることにはならず, 填補賠償の原則に反するということにはならない。したがって,そのよ うな算定方法を採用することも認められるというべきである。
(イ) 2)の製品についての損害の算定方法について
2)の製品についての実際の売上高は,前記(1)イのとおりであるが,前 記(2)ウ(イ)cのとおり,2)の製品は平均すると1)の製品の販売価格の5 分の1程度の大幅に値引きされた額で販売されており,また,2)の製品 の販売については,被告製品の販売終了に近い時期に,在庫処分の趣旨 で行われたものが大部分であったと考えられる。さらに,このような在 庫処分の趣旨での廉価販売が,当裁判所により被告の行為が不正競争に 該当する旨の心証が開示された後に行われたことは当裁判所に顕著であ るから,2)の製品の販売の大部分については,本件訴訟における差止め 及び廃棄請求の対象となることを免れる意図に基づいて不相当な廉価に よってされたものと疑われてもやむを得ないというべきである。 しかも,2)の製品の販売は,営業秘密である本件データを使用して被 告製品を製造し,一般消費者向けに譲渡するものであり,その結果,被 告製品が原告製品と競合する市場に出回ってしまうことから,原告が相 当な使用料の支払なくそのような行為を許諾することはないという点に おいて,1)の製品の販売と共通している。 以上の事情を考慮すれば,2)の製品の販売について,原告が受けるべ き金銭の額を事後的に定めるに当たっては,前記(1)イの大幅に値引きさ れた実際の売上高に前記イ(イ)の使用料率を乗じて算定するのは相当では なく,被告製品1個の販売につき,1)の製品を1個販売した場合と同額 の使用料(前記イ(ウ)bのとおり,被告製品1と被告製品2のいずれにつ いても759円)をもって使用料相当額を算定するのが相当というべき である。なお,原告が主張する,2)の製品の売上高について,2)の製品 の1個当たりの販売価格を1)の製品の1個当たりの販売価格と同額とし て算定すべきとの算定方法も,これと同趣旨をいうものと解される。
(ウ) 使用料相当額
2)の製品についての使用料相当額を算定すると,1個当たりの使用料 相当額759円に,前記(1)イの2)の製品の販売個数(被告製品1につき 774個,被告製品2につき1389個の合計2163個)を乗じた1 64万1717円と認められ,これが不競法5条3条による損害額とな る。
エ 3)の製品についての不競法5条3項による損害額
(ア) 1)の製品を対象として不競法5条2項による損害を算定する場合に, 3)の製品に同条3項を適用できるかについて
被告は,1)の製品を対象として不競法5条2項による損害を算定する 場合に,別途3)の製品について不競法5条3項による損害を算定して, これらを合算することは,填補賠償の原則に反して許されないと主張す るが,しかしながら,前記(2)ウのとおり,3)の製品については,無償譲 渡された分を含めて1)の製品の販売と一体のものとはいえないから,前 記ウ(ア)と同様に,1)の製品の販売のみに基づいて不競法5条2項による 損害額を算定する場合に,同項による損害の算定において対象となって いない3)の製品について同条3項によって損害額を算定することも認め られるというべきである。 (イ) 3)の製品についての損害の算定方法について 前記アのとおり,不競法5条3項による損害は,原則として,侵害品 の売上高を基準とし,そこに営業秘密等の使用に対し受けるべき料率を 乗じて算定すべきところ,3)の製品については,販売されていないから, 売上高は存在しない。 しかしながら,被告は,前記(1)ウのとおり,被告製品の販売を終了す る直前の令和2年3月の時期に,3)の製品について,少なくとも,被告 製品1を1000個無償提供したことが認められるところ,当該無償提 供は,営業秘密である本件データを使用して被告製品を製造し,一般消 費者向けに譲渡することにより,被告製品が原告製品と競合する市場に 出回ることから,原告において相当な使用料の支払なく許諾することは ないという点において,1)の製品の販売と共通している。 しかも,その無償提供がされた時期が当裁判所により被告の行為が不 正競争に該当する旨の心証が開示された後であることは当裁判所に顕著 であり,本件訴訟における差止め及び廃棄請求の対象となることを免れ る意図によるものと疑われてもやむを得ないというべきである。 以上の事情に照らすと,被告による上記の行為に対し原告が受けるべ き金銭の額を事後的に定める場合には,3)の製品1個の無償提供につき, 1)の製品(被告製品1)を1個販売した場合と同額の使用料759円 (前記イ(ウ)b)をもって使用料相当額を算定するのが相当というべきで ある。
原告は,3)の製品全体が無償提供されたとして,3)の製品全体につい て不競法5条3項の損害の算定の対象とすべきと主張するが,無償提供 されたと認められるのが被告製品1の1000個に限られることは前記 (1)ウ(イ)のとおりであり,3)の製品のうちそれ以外のものについては, 既に廃棄済みであるか,本件訴訟における廃棄請求の対象となるものと 考えられるから,これを不競法5条3項の損害の算定の対象とするのは 相当ではなく,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 使用料相当額
3)の製品についての使用料相当額を算定すると,被告製品1の1個当 たりの使用料相当額759円に,前記(1)ウ(イ)の無償譲渡された3)の製 品の個数1000個を乗じた75万9000円と認められ,これが不競 法5条3条による損害額となる。
(4) 弁護士費用等を含めた損害のまとめ
ア 1)の製品について不競法5条2項,2)の製品及び3)の製品について不競 法5条3項を適用した損害額(原告の主位的主張)について 1)の製品についての不競法5条2項による損害額は前記(2)カの273万 9989円,2)の製品及び3)の製品についての不競法5条3項による損害 額は前記(3)ウ(ウ)及び同エ(ウ)を合算した240万0717円であり,被告 製品全体についての損害額は514万0706円である。
イ 被告製品全体について不競法5条3項を適用した損害額(原告の予備的主張)について\n
被告製品全体について不競法5条3項による損害額は,前記(3)イ(ウ)a, 同ウ(ウ)及び同エ(ウ)を合算した496万4134円である。 これは前記アの額を下回るから,被告が賠償すべき額は前記アの額に基 づいて算定する。
2023.01. 3
令和2(ワ)1129 債務不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年8月31日 東京地方裁判所
原告シプソルが、原告機械の製造、販売や、原告製品の製造等について\n被告の特許権ないし本件特許権を侵害しているとの内容は、原告シプソル\nの営業上の信用を害するものであることは明らかであるから、被告が送付 ないし送信した甲3通知及び甲21メールは、原告シプソルの営業上の信\n用を害する虚偽の事実の告知に当たる。 そして、原告シプソルと被告とは改正前不競法2条1項15号所定の\n「競争関係」にある(前提事実(1)ウ)。 したがって、被告による甲3通知及び甲21メールの送付ないし送信は、 いずれも同号所定の不正競争行為に当たる。
イ 原告シプソルの被告に対する差止請求について\n
前記アによれば、原告機械又は原告機械の製造する梱包体が本件特許権 を侵害する又は侵害するおそれがあるとの事実の告知又は流布の差止めを 求める原告シプソルの請求は理由がある。\n
ウ 原告シプソルの被告に対する損害賠償請求について\n
被告は、包装機器の設計、開発、製造及び販売等を目的とする株式会社 であるから(前提事実(1)イ)、この目的からうかがわれる業務内容に照ら せば、原告機械ないし原告シプソルの販売する自動梱包ラインが被告の保\n有する特許権を侵害するか否かを調査することは必ずしも困難とはいえな いから、被告には、甲3通知及び甲21メールを送付ないし送信したこと について、少なくとも過失があったというべきである。
争点5(原告シプソルに生じた損害の有無及びその額)について\n
無形損害について
前記4(1)及び(2)のとおり、甲3通知及び甲21メールの内容は、原告シ プソルが本件特許権を侵害している旨及びMYTHが原告シプソ\ルから購入 することを予定している自動梱包ラインが被告の保有する特許権を侵害する\n旨を告知するものである。そして、原告シプソルは、自動梱包ラインの専門\n会社であると認められるから(甲20、23)、主力商品ともいえる自動梱包 ラインが他社の保有する特許権を侵害するとの事実が告知されたことにより、 原告シプソルの信用が毀損されたことは明らかであり、その程度も必ずしも\n小さいとはいえない。
しかし、被告から原告シプソルの取引先に対して虚偽事実の告知がされた\n回数は、本件全証拠によっても、甲3通知及び甲21メールの送付ないし送 信の合計2回を超えて認められない。また、これらの通知等がされたことに より、原告M・Kロジ及びMYTHが原告シプソルとの取引を取り止めたと\n認めるに足りる的確な証拠はない(原告らは、原告M・Kロジが、甲3通知 を受領した後、自動梱包ラインを他社に発注したと主張し、この点に関連し て福岡パッケージ株式会社が発行した自動制函機、シュリンク包装装置等に 係る見積書を証拠(甲26)として提出するが、原告M・Kロジが、これに 相当する機械を原告シプソルに発注する予\定であったことを認めるに足りる 証拠はないから、原告シプソルが甲3通知を契機として原告M・Kロジから\nの受注を失ったとまで認めることはできない。)。 これらの事情を含む本件に現れた諸事情を総合考慮すると、原告シプソル\nに生じた無形損害の額は30万円と認めるのが相当である。
弁護士費用について
被告の不正競争行為と相当因果関係にある弁護士費用の額は5万円と認められる。
2023.01. 3
平成29(ワ)7384 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月15日 大阪地方裁判所
ウ 覆滅割合
(ア) 市場の同一性
原告と被告は、マッサージチェアの分野でシェアを競い合う企業でマッサージチ ェアという需要者を共通にする同種製品を取り扱う同一の市場で競業している。 被告の主張は、具体的な被告の製品と原告の製品とを比較し、個別の販売相手先 や販売ルートを細かく分断して、これらが異なるから「市場の非同一性」があるな どと主張している。しかし、このような立論が成り立つのであれば、個別の販売相 手先や販売ルートが共通の場合でない限り、市場は無意味に細分化されてしまう。 同種製品で共通する需要者層を対象にして潜在的に影響を受ける競争の場が想定で きるのであれば、市場が同一性を有しているといえる。 また、本件特許II)及びIII)の実施品である原告の製品(以下「原告製品」という。) には対象被告製品と同じような価格帯の製品も複数存在するから、この点からも市 場の同一性は否定されない。
(イ) 市場における競合品の不存在
侵害訴訟の損害論においては、特許権を侵害する製品が販売されることによって、 特許権者の特許実施製品の販売が減少するという関係があるか否かを問題とすべき であるから、侵害関係のない製品についての適法な同種製品のシェア自体は、推定 覆滅事由としては関係がない。 また、競合品の範囲は、本件特許II)及びIII)の特許権の技術的構成を踏えて、その\n目的・作用効果を把握した上で、当該目的・作用効果が同じで原告製品の販売数量 に影響を与える製品という前提に立脚して考察されるべきであって、「背メカで被 施療者の首元から背中、腰にかけてマッサージを行うマッサージチェア」であるか 否かによって範囲を画し、これを前提とすると、殊更に本件特許II)及びIII)の具体的 な構成や解決手段をその考慮対象から一切捨象することになる。\n
(ウ) 侵害者の努力(ブランド力、宣伝広告)
原告は、古くから一貫してマッサージチェアを製造販売している老舗であり、被 告ともシェアを常に争う信用力のある会社である。また、原告は、世界で各種の受 賞実績のある国際的にも認知された会社であり、被告に劣らずグッドデザイン賞を 受賞するデザイン性を備える複数の原告製品を販売している。 したがって、原告企業より被告企業の方が格別に信用力を有し、原告のブランド 力に比して侵害品が利用者にとって購買動機となるなどということはない。 また、開発段階において開発に携わる従業員を配することは、ごく通常のことで あり、原告においても日々機械によるマッサージを人間の揉み心地に近づけるべく 開発努力を重ねている。営業段階において、マッサージチェアの魅力を伝える為の 営業活動は、原告においても常時行っており、被告だけに特別の活動ではない。
(エ) 侵害品の性能\n
対象被告製品のカタログ等には、対象被告製品の仕様(発明の構成)が明記され\nており、本件発明II)及びIII)の作用の発現が示唆されていることから、需要者に一切 訴求されていない本件特許II)及びIII)の作用効果に関連する仕様、機能は、対象被告\n製品の購入動機になり得ない旨の被告の主張は失当である。 被疑侵害品である対象被告製品の具体的な実施態様に関するパンフレット等には、 利用者へ訴求する記載が多数ある。本件特許II)及びIII)の技術的構成を採用するから\nこそ、各種コースのマッサージや腕を含む人体全体のマッサージ効果を高めるマッ サージチェアを提供できるのであり、これらの技術的構成を回避してマッサージチ\nェアを提供することは製品の性能に大きな影響を及ぼし、仮に回避し得たと考えて\nも、その代替的構成を採用するには無視できない費用がかかる。\n
(オ) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されているものではないこと
本件特許II)及びIII)は、椅子式のマッサージチェアにあって身体のマッサージに関 する構成、構\造に係る基本的な技術である。被疑侵害品である対象被告製品の一部 に本件特許II)又は本件特許III)の発明が実施されていたとしても、対象被告製品は、 この実施部分を除いてしまえば、全体としての製品構成が成り立たない。すなわち、\n本件特許II)は、椅子式マッサージ機にあって肩を側方からマッサージする「肩また は上腕の側部」の技術的構成に関する重要な特許であり、本件特許III)は、「腕部」 をマッサージする技術的構成に関する重要な特許であって、この実施部分があるか\nらこそ利用者の需要が喚起されているといえる。 本件特許II)に関し、被疑侵害品である被告製品II)を利用する利用者は、様々な自 動コースを自由に判断して設定するのであり、その際に、「肩または上腕の側部」 に効果的なマッサージを行うことができる構成を有している製品か否かが製品選択\nには重要である。本件特許II)の構成の内容は、取扱説明書の中でもこれを織り込ん\nでしばしば説明されており、それが被疑侵害品である被告製品II)の全般に亘ること も明らかで、本件特許II)の構成を抜きにしては、被告製品II)の多くの自動コースも 成り立たないことも一見して明らかである。 本件特許III)に関して、開口の向きを考慮しつつ、腕のエアマッサージを行う本件 特許III)の技術的構成の具体的な実施態様は、これを採用する製品の外観にもマッサ\nージ効果にも大きな影響を及ぼす。
(カ) まとめ
以上を総合的に考慮すると、推定覆滅される割合は、少なくとも55%以上には ならない。
エ 損害額
(ア) 特許法102条2項に基づく損害額の算出ができる対象被告製品について 不当利得期間及び損害賠償期間を通じた限界利益の額(前記イ(ウ))について、前 記ウのとおり、推定覆滅される割合は、55%以上にはならないから、被告が開示 した限界利益率を前提とした場合は、●(省略)●を下らず、原告が主張する限界 利益額を前提とした場合は、●(省略)●を下らない。
(イ) 特許法102条2項に基づく算出ができない対象被告製品について 被告の開示によれば、被告製品12、30及び32の限界利益はマイナスであっ て、赤字が計上される製品であるので、これには特許法102条2項に基づく算出 ができない。前記3製品について、●(省略)●そして、前記3製品について、こ の限度で特許法102条3項の主張を行う。
・・・
(ウ) まとめ
前記(ア)及び(イ)を総合すると、被告の開示した限界利益額による場合、特許法102条3項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●(省略)●となり、原告が主張する修正限界利益額による場合、同条3項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●(省略)●となり、少なく見積もっても50億円を下らない。
(3) 特許法102条2項及び3項に基づく主張
ア 特許法102条1項と同条3項の関係と同条2項 特許法102条1項と3項の併用に関する令和元年法律第3号による改正(以下 「令和元年改正」という。)後の特許法に関する考え方として、産業構造審議会知\n的財産分科会特許制度小委員会の報告書(「実効的な権利保護に向けた知財紛争処 理システムの在り方」)において、わざわざ2項との関係でも「同様の扱いが認め られることと解釈されることが考えられる」と記載されており、その解釈可能性が\nあることへの言及があるから、2項と3項の併用については、条文に明示されなか ったとはいえ、全面的に併用適用が否定されたわけではなく、解釈に任されること を明らかにしている。 したがって、特許法102条2項に基づき主張された損害のうち推定が覆滅され た部分について、同条3項の重畳適用が認められるべきである。
◆判決本文(侵害論)
関連事件1です。
同じく富士医療器による特許権侵害を認定ししてるとして、約4800万円の損害を認めました。
◆平成30(ワ)1391
原告・被告が逆の侵害訴訟はこちら。
◆令和2年(ネ)10024
この1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2023.01. 3
令和3(行ケ)10156 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月29日 知的財産高等裁判所
◆特願2015-176188
ア 「下方導水路250内の液体がその管内を落下し、その落下により揚水
路200の頂上部が真空域に保たれ、その結果、大気圧によって貯液部1
00の液体が揚水路200に揚水される」との点について
(ア) 本願発明の特許請求の範囲(請求項1)には、「少なくとも下部が液
体で満たされた貯液部(100)と、下部が前記貯液部(100)の前
記液体の液面下部に沈み、上部が該液面上部に出る様に設置され、上端
部近傍の前記液面より所定の高さ位置に液取り出し口が設けられた揚
水路(200)と」、「発電開始前に前記圧縮気体貯蔵タンク(600)
に圧縮した気体を貯蔵するとともに、前記ゲート(300)を閉めて前
記揚水路(200)および前記下方導水路(250)内に前記液体を充
填しておき、発電時に前記ゲート(300)を開けて」との記載がある。
また、本願明細書には、「本システムの起動前に不図示の揚水ポンプで水
槽の水を揚水棟200の中全てを満たす様に揚水して揚水棟内を真空
域にしている」との記載(【0040】)がある。
これらの記載によれば、本願発明において、発電の開始前には、揚水
路200等に存在する液体(以下では、「液体」は「水」であるとする。)
は、「一端」が貯液部100の水面下にあり、そこから、揚水路200、
(実施例【0038】では上部導水路210を介し)下方導水路250
を経て、「他端」はゲート300まで存在しており、揚水路200等は水
で満たされていることが理解できる。また、本願明細書の「大気圧室4
00の水面は下部導水路260の下部より低く保つ」との記載(【004
1】)から、上記水の「一端」を上流側、「他端」を下流側とすると、ゲ
ート300よりも下流側の管内には水が存在しないことが理解できる。
(イ) 前記(ア)を踏まえ、ゲート300を開けたときの前記(ア)の水(「一
端」が貯液部100の水面下にあり、そこから、揚水路200、(上部導
水路210を介し)下方導水路250を経て、「他端」がゲート300ま
で存在する水)の挙動を検討する。
揚水路200内にある水と下方導水路250内にある水は、その上部
が(実施例(【0038】)では、上部導水路210内の水を介して)つ
ながっている。
そして、乙2に示されている考え方(被告はこれを「サイフォンの原
理」として説明し、原告もその説明を争っていない。)によれば、揚水路
200の下部が存する貯液部100の水面(図1の水槽100の水面)
には、大気圧(その圧力を「A」とする。)と貯液部100の水面から揚
水路200の頂部まで存在する水の圧力(水の重さによる圧力。その圧
力を「B」とする。)がかかる。他方、下方導水路250の下端には、水
平導水路260内の平均気圧(その圧力を「C」とする。)と下方導水路
250の下端から頂部までに存在する水の圧力(水の重さによる圧力。
その圧力を「D」とする。)が働く。
ここで、本願発明では、「発電時に前記ゲート(300)を開け」た際
に、「前記圧縮気体貯蔵タンク(600)に貯蔵されている圧縮気体」が
「前記水平導水路(260)から前記集液部(400)に射出される」
ため、水平導水路260内の平均気圧(C)は大気圧(A)より大きく
なる(C>A)。また、水による圧力については、貯液部100の水面か
ら揚水路200の頂部までの長さの方が下方導水路250の下端から頂
部までの長さよりも長いから、貯液部100の水面から揚水路200の
頂部まで存在する水の圧力の方が大きくなる(B>D)。
そうすると、水を持ち上げる向きを正の向きとして、揚水路200の
下部が存する貯液部100の水面に働く圧力(A−B)と、下方導水路
250の下端に働く圧力(C−D)とを比較すると、後者の方が大きい
から、ゲート300を開けると、下方導水路250内の水は、一旦上方
に持ち上がった後、揚水路200に流れ落ちていくものと考えられる。
なお、ゲート300を開けた際に、水平導水路260及び大気室40
0から空気が下方導水路250内に入り込むと、下方導水路250内の
ゲート300付近にあった水が水平導水路260側へ落下することがあ
り得るが、これは、入り込んだ上記空気と上記水が入れ替わることによ
って生じる現象であって、このことによって、下方導水路250や揚水
路200に真空域が生じることはなく、貯液部100から揚水路200
に向かって水が引き揚げられるといった現象も生じないものと理解され
る。したがって、本願明細書の記載から、原告が主張する「発電時に、重
力落下エネルギーの作用によって下方導水路250内の液体がその管内
を落下し、その落下により揚水路200の頂上部が真空域に保たれ、そ
の結果、大気圧によって貯液部100の液体が揚水路200に揚水され
る」ことが起こることを理解することはできない。
イ 「大気圧室400内において大気圧より低い低圧力空間が生成される」
との点について
原告は、本願発明では発電時、圧縮気体供給路670の出口より集液部
(大気圧室)400へ圧縮気体を射出することで、大気圧室400内にお
いて、その圧縮気体の体積分の大気圧の気体が押しのけられて、大気圧よ
り低い低圧力空間が生成されると主張し、更にその説明として、圧縮空気
の保有エネルギーが、大気圧の気体を押しのけるためのエネルギーよりも
大きいため、圧縮空気を大気圧室400へ連続的に供給することによって、
大気圧室400内の空気を常時押しのけることが可能となる旨主張する。しかしながら、本願明細書には、大気圧より高い圧力を有する圧縮気体\nを大気圧に維持された空間に放出することによって、当該空間に大気圧よ
り低い低圧力空間が形成されることについての記載はなく、また、これを
裏付ける技術常識についての立証もない。
さらに、前記アのとおり、ゲート300を開けた場合、下方導水路25
0内の液体は、水平導水路260の方向に流れないものと考えられるとこ
ろ、原告が主張する大気圧室400内の低圧力空間が、下方導水路250
内の液体を、水平導水路260を通って大気室400の方向に引き出すほ
どの力を生じさせることを認めるに足りる証拠もない。
そうすると、本願明細書の記載から、原告が主張する「大気圧室400
内において大気圧より低い低圧力空間が生成される」ことを理解すること
はできず、さらに、その低圧力空間の作用によって下方導水路250内の
液体がその管内を落下することが生じるものと理解することもできない。
関連カテゴリー
>> 発明該当性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2023.01. 3
令和3(行ケ)10114 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和4年9月29日 知的財産高等裁判所
甲1カタログの成立の真正について
ア 前記1の認定事実(1)によれば、甲1カタログは、新輝行を作成名義人と する文書であると認められるところ、本件においては、被告が甲1カタロ グの成立の真正を争っていることから、原告において、甲1カタログが新 輝行によって作成されたものであることを立証しなければならない。 イ そこで検討するに、前記1の認定事実(1)のとおり、本件各カタログの会 社紹介ページには、新輝行が、平成15年に設立された企業であり、自社 工場を有する上、ファスナー等の様々な製品を国内市場のみならず海外市 場においても販売している旨が記載されている。また、本件各カタログに は、新輝行の看板を掲げた3階建ての建物の外観の写真等や、工程ごとに 多数の機械類が並べられた工場内の様子を撮影した合計12枚の写真が 掲載されている。さらに、Eは、陳述書において、平成15年から平成1 6年末まで新輝行に勤務していたこと、当時の工場は3階建てであったこ と、新輝行には数十名程度の従業員がいたことを述べている(甲11、3\n0)。これらの事情によれば、新輝行は、平成16年当時、相当程度の規模 の企業であり、広く海外への輸出も行っていた企業であったと考えられる。 しかしながら、前記1の認定事実(2)のとおり、被告が令和2年に行った 調査によれば、公的機関においても新輝行に係る法人登録に関する情報は 全く得られなかったものである上、インターネット上においても新輝行に 関する情報は何ら存在しなかったものと認められるところ、新輝行が上記 のとおりの規模や事業内容であったとすれば、公的機関に法人としての新 輝行に係る記録が何ら存在せず、また、様々な情報が蓄積されるインター ネット上にも新輝行の企業活動に関する情報が全く残存していないとい うのは、極めて不自然である。
また、原告が、本件訴訟の係属後である令和4年に、Eに依頼して実施 した現地調査においても、Eが勤務していたとされる新輝行の工場兼事務 所の所在地が特定されなかったものであるところ(甲11、45、46)、 新輝行が上記のとおりの規模の企業であったにもかかわらず、しかも自ら が1年以上勤務していたにもかかわらず、Eが、その所在地を特定するこ とすらできなかったというのも、極めて不自然である。 以上のとおり、本件においては、新輝行が実在したことを強く疑わせる 事情が存するというべきである。
ウ 加えて、甲1カタログの体裁及び内容等についてみると、前記1の認定 事実(1)のとおり、表紙には、会社名と発行年度のみが記載され、会社紹介\nページには、「会社紹介」として会社の沿革や事業内容等について記載され ている上、1頁ないし2頁には、多数の機械類が並べられた工場内の写真 が工程ごとに分けられて複数掲載されていることからすれば、甲1カタロ グは、新輝行の企業全体を紹介することを目的とした冊子であるとみるの が自然である(なお、原告は、甲1カタログに係る証拠説明書において、 証拠の標目を「製品カタログ」等とするが、甲1カタログの表紙等には、\nかかる記載は存しない。)。しかしながら、他方で、前記1の認定事実(1)の とおり、甲1カタログの3頁には、「製品構造」として、スライダー胴体の\n拡大写真が掲載されるなどし、また、4頁ないし9頁には、様々な色及び 形状のスライダーの写真が多数掲載されており、これらは専らスライダー の製品紹介を目的とする内容であるといえる。このように、甲1カタログ は、表紙や会社紹介ページの内容とそれ以降のページの内容とが、その目\n的において合致しておらず、不自然な体裁及び内容であるといえる。 このほか、前記1の認定事実(1)のとおり、甲1カタログの会社紹介ペー ジには、新輝行がファスナー等の様々な製品を製造、販売している旨が記 載されているにもかかわらず、3頁以下においてはスライダーのみが紹介 されている点や、甲1意匠がそれ自体顕著な特徴を有する意匠であるとは いえないにもかかわらず、3頁において甲1意匠が殊更に採り上げられ、 その構造が詳細に紹介されている点も、不自然であるといえる。\n
以上によれば、甲1カタログには、様々な点において不自然な部分があ るといえる。
エ 以上のとおり、本件においては、新輝行が実在したことを強く疑わせる 事情が存するというべきである上、甲1カタログには様々な点において不 自然な部分があるといえることからすれば、甲1カタログにつき、新輝行 によって作成されたものであると認めるに足りる立証はされていないと いうべきである。
2023.01. 3
令和3(行ケ)10132 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月7日 知的財産高等裁判所
(1) 最初の親出願の出願時における積層された回転子の固定方法に関する技術常 識について
ア 前記2(1)〜(8)の各イの甲20、22、27、28、乙3〜6の各記載事項 を踏まえると、最初の親出願の出願日である平成17年1月12日当時の技術常識 として、磁石が挿入される回転子積層鉄心における積層の固定方法は、かしめを用 いるものに限られておらず、溶接や接着も選択肢として存在していたことが認めら れる。なお、本件全証拠をもってしても、上記技術常識について、それが本件特許 の実際の出願日である平成23年7月4日までの間に変更されたものとも認められ ない。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は、甲20の段落【0015】等における「抜きかしめ等」という記載 は、「かしめ」以外の固定方法を含むという趣旨ではなく、「抜きかしめ」以外の「か しめ」による固定方法を含むという趣旨であると主張するが、同段落の文言や、甲 20に係る発明の出願日である平成12年7月13日より前に公開されていた前記 2(1)〜(3)の甲22並びに乙3及び5の記載事項に照らし、上記「抜きかしめ等」 という記載を原告の主張するように限定的に解することは相当でない。 また、原告は、甲22について、永久磁石片の挿入後に回転子3を樹脂21を収 納した容器20内に浸漬していることを指摘して、甲22に開示された技術を最初 の親出願の明細書等に記載されている発明に適用することはできないと主張する が、上記主張は、前記アの技術常識の認定を妨げるものではない。 さらに、原告が甲27及び28について主張する点も、同じく前記アの技術常識 の認定を妨げるものではない。
(イ) 原告は、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の積層された鉄心片の固 定手段としては、かしめが技術常識となっていたと主張するが、原告がその根拠と する証拠(甲64〜69)を含め、本件全証拠をもってしても、最初の親出願の出 願当時、上記固定手段として、かしめが広く一般的に用いられていたという事情を 超えて、かしめ以外の溶接や接着といった固定方法がもはや選択肢となっていなか ったといった事情までは認められないから、原告の上記主張は、前記アの技術常識 の認定を左右するものではない。
上記に関し、原告は、積層鉄心を溶接すると溶接部で短絡することで渦電流が発 生し、効率が低下することが技術常識であり、接着にも問題があったから、溶接や 接着による固定方法は実用化されていなかった旨を主張する。しかし、溶接により 溶接部で短絡することを踏まえた上で、なお溶接が選択肢として検討されていたこ とは、甲27の段落【0068】(前記2(5))、乙6の段落【0031】(同(6))及び乙4の段落【0007】(同(7))の記載からも認められるところであり、接着につい ても選択肢として検討されていたことは、甲22(同(2))及び乙3(同(3))のとお りである。さらに、そもそも、仮に、実用化にまで至っていなかったとしても、そ のことをもって、直ちに技術としての選択肢から除外されるものでもない。
(ウ) 原告のその余の主張は、いずれも前記アの技術常識の認定を左右するもので はない。
(2) 最初の親出願の明細書等に記載された発明について
ア 前記1(1)の最初の親出願の明細書等の記載を踏まえると、次のとおり(な お、便宜のため、最初の親出願の明細書等及び原出願の明細書等の記載の共通部分 を基礎として検討する。)、本件発明は、最初の親出願の明細書等に記載されていた ものと認められる。
(ア) 少なくとも、段落【0005】、【0012】、【0014】及び【0017】 から、最初の親出願の明細書等には、「複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心の 複数の磁石挿入孔に挿入する永久磁石を、樹脂を前記磁石挿入孔にのみ注入して固 定する回転子積層鉄心の製造方法」に係る発明であることが記載されていると認め られる。
(イ) 少なくとも、段落【0004】、【0011】〜【0013】及び【0017】 〜【0019】並びに図1及び図2から、最初の親出願の明細書等には、「前記回転 子積層鉄心の上下に、いずれか一方には前記磁石挿入孔に前記樹脂を注入する複数 の樹脂ポットと該樹脂ポットにそれぞれ対応するプランジャとを備えた上板部材及 び下板部材を配置し、前記上板部材及び前記下板部材とで前記回転子積層鉄心を上 下から押圧して、前記永久磁石の樹脂封止を行うことを特徴とする」発明が記載さ れていると認められる。
(ウ) そして、最初の親出願の明細書等に、他に前記(ア)及び(イ)の認定を左右する ような記載はない。
(エ) したがって、本件発明は、最初の親出願の明細書等に記載されていたものと 認められる。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は、最初の親出願の明細書等について、発明が解決しようとする課題、
課題を解決するための手段、発明の効果及び実施形態に係る明細書の記載からする と、あくまで、かしめ部・逃げ空間あり構成に係る技術的事項が導かれるのであっ\nて、特に、発明が解決しようとする課題に照らし、かしめ以外の固定手段を用いる ことは同明細書等には記載されておらず、明細書の段落【0018】に、かしめ部 あり構成を前提とした逃げ空間あり構\成を必須とする旨の記載があることも考慮す ると、同明細書等に記載された発明は、逃げ空間あり構成を必須とするものである\nなどと主張する。しかし、最初の親出願の明細書中、発明が解決しようとする課題等において、かしめ部・逃げ空間あり構成に係る事項が特に取り上げられて深く検討されているとしても、そのことから直ちに、最初の親出願の明細書等に記載された発明が上記構\ 成を含むものに限定されるものではない。
前記(1)アのとおり、最初の親出願の出願当時、固定手段として溶接や接着も選択 肢として存在していたことが認められるのであるから、同明細書等における記載も それを前提に理解すべきものである。そして、前記ア(ア)及び(イ)のように最初の親 出願の明細書に記載されていたといえる本件発明に係る構成や、当該構\成における 複数の樹脂ポットとそのそれぞれに対応するプランジャとを備えた上板部材及び下 板部材による回転子積層鉄心の上下からの押圧並びに樹脂ポット内の樹脂を磁石挿 入孔へ注入しての永久磁石の樹脂封止といった機序自体が、かしめ部あり構成であ\nるか、かしめ部なし構成であるかによって影響を受けるものともみられない。そう\nすると、最初の親出願の明細書等には、1)本件発明を含む発明が記載された上で、 2)かしめ部あり構成の場合に当該発明を用いる際の問題点等について、逃げ空間あ\nり構成などが更に記載されているというべきであって、上記2)の記載の存在によっ て上記1)の記載が存在しないものとはいえないところである。
(イ) 上記に関し、原告は、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の積層され た鉄心片の固定手段として、かしめが技術常識となっていたことから、最初の親出 願の明細書等の記載について固定手段を特定の手段に限定するものではないとはい えない旨を主張するが、原告が主張する上記技術常識が認められないことは、前記 (1)イのとおりである。
(ウ) また、原告は、「かしめ積層されていても回転子積層鉄心の鉄心片の板厚が0. 5mm以下でないもの」(鉄心片の板厚が0.5mm超のもの)について、当業者は 通常想定しないなどと主張するところ、かしめ積層された回転子積層鉄心の鉄心片 の板厚が0.5mm以下でないものは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下い ずれかの面から少しの範囲で突出してしまうことをもって、同板厚が0.5mmを 超える全てにおいて、直ちに、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下いずれかの 面から少しの範囲で突出するとはいえないと理解できるものではないとしても、本 件全証拠をもってしても、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の鉄心片につ いて、板厚0.5mm以下のものが用られる場合が多かったという事情を超えて、 板厚0.5mm超のものが選択肢となっていなかったといった事情は認められない。 この点、板厚0.5mm超のものを用いる例があったことは、乙5の記載(前記2 (1))やその他の証拠(乙7〜10、17、18)からも認められるところである。 さらに、最初の親出願の明細書の段落【0004】には、「この特許文献1記載の 技術においては、回転子積層鉄心を形成する各鉄心片がかしめ積層された特に鉄心 片の板厚が0.5mm以下の薄いものでは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上 下いずれかの面から少しの範囲で突出してしまう」と記載されており、「鉄心片の板 厚が0.5mm以下の薄いもの」が全体の中から特に取り上げられた例であること が明記され、それ以外の場合(鉄心片の板厚が0.5mmを超えるもの)の存在が 示唆されているから、仮に、通常は板厚0.5mm以下のものを想定している当業 者においても、同段落の記載に接した場合には板厚0.5mm超のものを選択肢と して考慮し得るといえる。 したがって、原告の上記主張も、前記アの認定を左右するものではない。
(エ) 原告のその余の主張は、いずれも前記アの認定を左右するものではない。
(3) 原出願の明細書等に記載された発明について
前記1(2)のとおり、原出願の明細書等には、前記(2)ア(ア)及び(イ)で指摘した各 段落の記載がある。そして、同明細書等に、他に同(ア)及び(イ)の認定を左右するよ うな記載はない。 したがって、本件発明は、原出願の明細書等に記載されていたものと認められる。
2023.01. 3
令和3(ネ)10006 職務発明対価請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(25) 原判決143頁15行目の「あって、ほかに本件各発明の実施品が存在する と認めるに足る証拠はない。」を「ある。なお、本件発明7の実施品の売上げについ ては、後記3「その余の当審における当事者の補足主張等に対する判断」(3)で検討 する。」と、144頁19行目の「別紙10(判決注:「原判決別紙10」である。) 相当対価計算表(自己実施1)」を「別紙10「相当対価計算表\(自己実施1)」」と、145頁2〜3行目の「本件各発明」を「本件発明1及び2」と、146頁7行目 の「被告保有の特許」を「一審被告を含む同プログラムに参加する特許権者の保有 する特許」とそれぞれ改め、同頁7〜8行目の「ライセンスを求める者に対して、」 の次に「その選択に応じ、フィリップス社の保有する特許又はフィリップス社及び 本件ジョイント・ライセンス・プログラムに参加する特許権者の保有する特許につ いて、」を挿入し、同頁12行目の「本件特許1及び2は」を「本件各特許は」と、 同頁14行目の「被告は、」から同頁18行目末尾までを「一審被告は、上記各製品 カテゴリに属する製品を製造、販売しようとする者が、フィリップス社に対し、ラ イセンスを求めた場合には、フィリップス社における上記ライセンスポリシーに従 って、フィリップス社を通じ、当該製品カテゴリに属する製品を製造、販売するた めに必要とされた他の特許と一括して実施許諾をしていたものと認められる。」と それぞれ改め、同頁20行目冒頭から147頁9行目までを次のとおり改める。 「以上のとおり、本件発明1、2については、CD−R/RW等の規格必須特許 として扱われており、かつ、一審被告も現に実施していたことからすると、CD− R/RWレコーダー及び同機能を有するDVD・BD関連製品並びにCD−R/R\nWディスクを製造・販売していた者に広く実施されていたと考えられ、CD−R/ RW規格に準拠した製品に競合するものとして、CD−R/RWレコーダー機能を\n有しないDVD関連製品等が存在していたとはいえるものの、CD−R/RW規格 に準拠した製品を製造・販売する者にとっては、規格必須特許である本件特許1、 2の代替技術は存在していなかったということができること、一審被告は、本件ジ ョイント・ライセンス・プログラムにより、フィリップス社を通じ、本件特許1及 び2を必須特許として他の特許と一括して実施許諾しており、フィリップス社は、 本件ジョイント・ライセンス・プログラムについて、ライセンスを求める全ての企 業にライセンスを認めることを原則とするライセンスポリシーをとっていたものの、 全ての規格準拠製品を製造・販売する者が、フィリップス社を通じ又は一審被告と 直接、本件特許1、2についてライセンス契約を締結していたものではないこと、 そもそも、一審被告が、CD−R等の規格の策定に関与し、また、本件ジョイント・ ライセンス・プログラムに参加することができたのは、本件各特許を含む規格必須 特許を有していたからであると推認されること、一審被告が、例えば平成12年度 にはCD−R/RWドライブの世界出荷台数について21.3%と高いシェアを有 しており(甲25)、これについては本件各特許を含む規格必須特許を有していたこ とが一審被告の売上げに有利に働いていたものと推認されること等に照らせば、本 件特許1、2について、独占の利益がなかったということはできない。
そして、平成12年にDVD関連製品の販売が開始されるまで、CD−R/RW ディスク以外の光ディスクが広く販売されていたことはうかがわれず、また、フィ リップス社が採用していたライセンスポリシーにおけるライセンス料やライセンス 条件等の内容が明らかでないことなどにも照らせば、一審被告製品1及び2の売上 げの一部は本件発明1及び2を含む特許発明による独占的地位に起因する超過売上 げであったと認めるのが相当であり、本件に顕れた事情を総合的に考慮すると、そ の割合は一審被告製品1及び2の売上げの20%であったと認めるのが相当である。
もっとも、出願公開の後、特許権の設定登録がされる前においては、一定の条件 下での補償金支払請求権が認められ、特許法上の保護が与えられていることから、 独占的地位に起因する超過売上げが存在しないとはいえないものの、設定登録の可 否やその技術的範囲も確定していない上、独占的効力が制限的であることに照らす と、出願公開後登録までの間は、登録後の2分の1の割合で独占の利益を認めるの が相当であるから、当該期間については超過売上割合を10%とする。そうすると、 一審被告のCD−R/RWドライブ及びCD−Rディスクの売上げのうち、本件特 許1が登録された平成12年4月28日までの間の日本国内での売上げについては、 超過売上割合を10%とみることになる。」
(26) 原判決147頁25行目の「被告は、」の次に「本件ジョイント・ライセン ス・プログラムに参加し、フィリップス社を通じて、」を挿入し、148頁1〜2行 目の「フィリップス社が採用していたライセンスポリシー」を「同ライセンスポリ シー」と、同頁26行目〜149頁1行目の「国内同業他社のロイヤルティ料率に 関するアンケート結果に係る特許権のロイヤルティ率の平均値として」を「国内同 業他社に対してライセンスすることを想定するものとして行われたアンケートの結 果として、特許権のロイヤルティ料率の平均値が」とそれぞれ改め、同頁20行目 冒頭から26行目末尾までを削り、150頁8行目の「フィリップス社」を「フィ リップス社ら」と、151頁16行目の「そして、」から同頁20行目末尾までを「そ して、ライセンス対象特許リスト5)ないし7)の各パートに掲載された特許の数は、 58件、67件、144件、144件、119件、121件であるところ(なお、 ライセンス対象特許リスト6)については、前記(3)ウ(ア)bで述べたとおり、各19 件を控除した。)、その平均は108.83件であり、その9割に相当する97.9 4件であったと推認するのが相当である。」と、153頁2行目の「その実施特許は」 を「その実施特許の数は」とそれぞれ改め、同頁11〜12行目の「ことについて は」から同頁12行目の「とおりである」までを削り、同頁15行目の「上記の検 索に係る」から同頁16行目末尾までを「平成8年から平成14年までの間、毎年 同等の数の特許権の存続期間が満了したと仮定した場合の平均特許件数よりも相当 程度に少ないものと考えられ、上記の検索に係る2509件の3割に相当する75 2.7件であったと推認するのが相当である。」と、同頁26行目及び156頁17 行目の「別紙10(判決注:「原判決別紙10」である。)相当対価計算表(自己実\n施1)」を「別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」と、155頁9行目の「1\n505.4」を「752.7」と、同頁11行目の「501.8」を「250.9」 と、同頁12行目の「586.86」を「335.96」と、同頁13行目の「6 05.44」を「354.54」と、同頁15行目の「689」を「438.1」 と、同頁16行目の「532.16」を「281.26」と、同頁17行目の「5 16.65」を「265.75」と、156頁9行目の「前記(3)エ(イ)のとおりであ る。」を「前記(3)エ(イ)(aを除く。)のとおりであり、また、音楽用CDに係る特許 については、いずれも平成14年までに存続期間が満了していたものと推認される から、平成15年以降について、それらの特許の貢献があったと認めることはでき ない。」とそれぞれ改め、同頁19行目冒頭から157頁22行目末尾までを次のと おり改める。
「オ 争点2−2についての小括
ところで、後記2「争点1−4(本件発明7の実施の有無)に対する判断」(5)の とおり、一審被告は、本件発明7についても実施している。これを考慮に入れた一 審被告が受けるべき利益の額については、別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」\nのとおりと推定され、本件発明1、2及び7の実施により一審被告が受けるべき利 益の額は、同別紙の対象製品欄記載の製品の日本、米国及びオーストラリアでの売 上額に、日本における本件特許1の登録前の売上げについては、超過売上割合を1 0%、その他については超過売上割合を20%とし、仮想実施料率を2.5%とし て、同別紙【B】’欄記載のとおり超過利益が算出され、これを、同別紙【D】欄記 載の補正後の実施特許件数で除して、対象特許1件当たりの利益の額を算出し(同 別紙【E】欄)、これに、同別紙【F】欄記載の本件各特許の数を乗じると、同別紙 【G】欄及び【G】’欄記載のとおり算出され、合計●●●●●●●●●●円である。
なお、同別紙【F】欄記載の本件各特許の数は、ドライブについては本件特許1、 2及び7の3件、ディスクについては本件特許1及び7の2件であるところ、CD −R/RWドライブについては、別紙8「相当対価計算書(ライセンス1)」の【E】 欄と同様に、本件各特許の数を倍とした。また、本件発明7についてはDVDディ スクについても実施品に当たるが、これについては、一審原告がその売上げを相当 対価の算出対象に含めない旨主張するから、上記算定に含めないものとした。 そして、前記(3)オと同様に、別紙10「相当対価計算表(自己実施1)」の対象製\n品欄記載の製品についての全世界の市場に占める日本、米国及びオーストラリアの 市場の割合は、日本が10%、米国が25%、オーストラリアが2%であったと認 めるのが相当であるから、CD−R/RWドライブ、追記書換型DVDドライブ、 CD−R/RWドライブとDVD−ROMドライブの複合ドライブ、BDドライブ について、一審被告が受けるべき利益の合計額における本件発明1、2及び7の内 訳は、上記の市場の割合を踏まえて算定することができ、具体的には、別紙11「相 当対価計算表(自己実施2)」に記載するとおりである。\n
◆判決本文
1審はこちら。
2023.01. 3
令和4(ネ)10010 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年8月22日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人は、日本の伝統芸能や古武道における流派の意義、そして「小野派一\n刀流」の流派名の意義等を主張して、「小野派一刀流」は、流派の教え・系統を指す とともに、宗家を長とし門人によって構成される本流流派を継承する集団(団体)を\n指し、両者は密接不可分の関係にあるから、流派名としての「小野派一刀流」の使用 は、同時に集団(団体)としての「小野派一刀流」を想起させるもので、需要者が提 供される役務の出所を認識し得るような態様での使用に当たる旨を主張する。 しかし、本件全証拠によっても、日本の伝統芸能一般又はそのうち古武道一般に\nおいて、一つの流派について一つの集団(団体)しか存在しないという事情は認めら れない。この点、例えば、古武道振興会の「加盟流派」のページ(本件ウェブページ。 甲3の1)には、「荒木流拳法(K)」(代表はK)及び「荒木流拳法(L)」(代\n表はL)として、「荒木流拳法」という流派名を冠する加盟流派が代表\を異にして二 つ掲載されており、同様に「神道夢想流杖術」、「夢想神伝流居合術」及び「柳生心 眼流兵法」についても、同一の流派名を冠する加盟流派が代表を異にして複数掲載\nされている。また、古武道協会のウェブサイトにおける「各流派の紹介」のページ (甲33の1)にも、「天神真揚流柔術(新座市)」と「天神真揚流柔術(川越市)」 とが掲載されている。
そうすると、控訴人の主張するように、流派名と当該流派を継承する集団(団体) との間に密接な関係があることを前提としても、当該密接な関係により流派名が想 起させる集団(団体)が、直ちに特定の役務の提供等の一主体となるような特定の団 体であるということはできず、それは、当該流派を継承する複数の団体を含み得る より抽象的な集団にすぎないとみるのが相当である。 そして、本件全証拠をもってしても、「小野派一刀流」が古武道の流派の名称であ るということを前提にしてもなお、それが特定の役務の提供等の一主体となるよう な当該流派を継承する特定の団体を指すものであると認めるに足りず、「小野派一 刀流」について上記と異なって解すべき事情は認められない。 したがって、流派名としての「小野派一刀流」の使用が同時に集団(団体)として の「小野派一刀流」を想起させるものであるとの控訴人の前記主張は、訂正して引用 した原判決の第4の1における、本件標章使用が被控訴人らによる商標的使用であ るとは認められないという判断を左右するものではないというべきである。
イ 控訴人は、本件標章使用1)について、本件常識(小野派一刀流の教え・系統と これを継承してきた集団(団体)とが密接不可分であり、本流が宗家を長とし門人に よって構成される集団(団体)において継承されてきたこと、中でも正統は広範かつ\n強大な権限を有する宗家一人に継承されること)のほか、「小野派一刀流剣術」の名 称と共に「代表」等として被控訴人Y1が掲載されているという態様を特に指摘し\nて、本件標章使用1)が商標的使用に当たる旨を主張する。 しかし、訂正して引用した原判決の第4の1(2)(本件標章使用1)について)で認 定説示したとおり、「加盟流派」について掲載した本件ウェブページの記載の形式や 内容からすると、そこにおける「小野派一刀流剣術」の名称やその「代表」等の記載\nに接した者においては、その名称は古武道振興会において加盟を認められている古 武道の流派の一つの名称であって、併記された代表者の氏名及び連絡先もあくまで\nそのような流派の代表者及び連絡先として古武道振興会が把握しているものの記載\nであると理解するとみるのが合理的である(なお、前記アで指摘したとおり、本件 ウェブページには、同一の流派名を冠する加盟流派が代表を異にして複数掲載され\nている例があるところ、「小野派一刀流剣術」については代表を異にする同名とみら\nれる加盟流派が他に記載されていないことから、その記載に接した者においては、 加盟流派としては単一のものと理解することにはなるが、他方で、上記の例がある ことが同時に容易に看取できることからすると、「小野派一刀流剣術」に係る「代表」\n等の記載が、古武道振興会の加盟流派、換言すると古武道振興会の認識を離れて、客 観的に、流派としての「小野派一刀流剣術」の唯一の宗家や当該宗家から代表と称す\nることを許諾された者を示すものであると直ちに認識するとまではいえない。)。 また、訂正して引用した原判決の第4の1(1)(認定事実)からすると、本件ウェ ブページの記載に当たり、古武道振興会は、自律的に定めた「日本古武道振興会規 約」における会員に関する定めに基づき、会員資格や代表会員の資格の受継につい\nて判断しているもので、Bの死去後の受継の問題についても、平成30年度第1回 常任理事会において、自律的に判断がされたものとみられる(なお、その判断の前提 とされた事実関係について、本件証拠に照らし、明白な誤認があったというべき事 情や被控訴人らから古武道振興会を欺罔するような説明がされたといった事情も認\nめられない。)。そのような判断に基づいてされたとみられる本件ウェブページにお ける「小野派一刀流剣術」に係る記載(なお、古武道振興会規約は、古武道振興会 のウェブサイトにも掲載されていることが窺われる(甲3の1〜3)。)をもって、 当該流派に係る特定の団体が提供する何らかの役務の出所を認識し得るような態様 で被控訴人らが表示をしたものと認めることもできない。\n
したがって、「小野派一刀流剣術」の名称と共に「代表」等として被控訴人Y1が\n掲載されているという態様を特に指摘しての控訴人の前記主張は、訂正して引用し た原判決の第4の1(2)(本件標章使用1)について)の判断に影響を与えるものでは ない。控訴人が主張する本件常識も、前記アで説示した点に照らし、同判断を左右し ない。
ウ 控訴人は、本件標章使用2)について、「小野派一刀流剣術(G) Y1(東京 都)」との記載が太字でされていることや演武者名とは別に記載されていること、並 んで記載された流派について記載されている者が当該流派の宗家であることが需要 者に周知であること、本件常識や本件標章使用2)に係る武道大会等は古武道振興会 が主催等するものであること等を特に指摘して、本件標章使用2)が商標的使用に当 たる旨を主張するが、本件標章使用2)が被控訴人らによる被告商標の商標的使用と 認められないことは、訂正して引用した原判決の第4の1(3)(本件標章使用2)につ いて)で認定説示したとおりである。
前記アで説示した点に照らし、本件常識は、本件標章使用2)が被控訴人らによる 被告商標の商標的使用と認められないとの判断を左右するものではない。 また、訂正して引用した原判決の第4の1(1)(認定事実)のとおり、本件標章使 用2)がされた武道大会等は古武道振興会が主催等したものであること、古武道振興 会が主催する大会において使用されるパンフレットやめくりは、本件ウェブページ に掲載されている加盟流派の情報と同様に、古武道振興会に既に登録されている情 報に基づき、古武道振興会が主体となって作成、掲示、配布等するものであること (これは、古武道振興会が主催以外の態様で関与した武道大会等についても同様と 推認され、この推認を覆す事情はない。)や、本件標章使用2)に係るパンフレット の記載内容等を踏まえると、前記イで説示したのと同様、控訴人が指摘するその余 の点も、本件標章使用2)が被控訴人らによる被告商標の商標的使用と認められない との判断に影響を与えるものではないというべきである(なお、控訴人が指摘する 点のうち、本件標章使用2)に係る武道大会等は古武道振興会が主催等するものであ るという点は、むしろ、同判断の根拠となり得るものといえる。この点、本件全証拠 をもってしても、古武道振興会が、古武道の各流派の正当性について有権的に判断 する団体であるといった事情や、古武道の流派が加盟し得る唯一の団体であるとい った事情は見受けられない。控訴人の主張は、ひっきょう、被控訴人Y1について受 継を認めたという古武道振興会の判断を論難するものにすぎないというべきであ る。)。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2023.01. 3
令和2(ワ)21047 不正競争 民事訴訟 令和4年10月5日 東京地方裁判所
以上を踏まえて検討するに、原告においては、就業規則により、従業 員に対し、原告の許可なく原告の機密、ノウハウ等に関する書類等を私 的に使用したり、複製したり、原告の施設外に持ち出してはならない義 務を課し、行動規範にも同様の定めがあり、被告が原告を退職するに当 たっては、被告から本件誓約書を徴求しており、原告が情報の管理を徹 底しようとしていたものであり、そのことを従業員も認識可能であった\nということができる。そして、本件ファイル1ないし6には、原告又は 原告を含むグループ会社の販売数量、売上げ、単価、利益率、顧客名等 の、原告の事業遂行に関わる情報が詳細かつ網羅的に記載されていると ころ、これらの情報が他社に知られれば、原告の市場における競争力に 大きな影響を与えかねないことは明らかであるから、上記の各情報が就 業規則等による管理の対象となっていたことも、従業員に認識可能であ\nったといえる。その上で、原告の従業員は、ネットワーク管理システム により管理されたID及びパスワードを入力しなければ、貸与されたパ ソコンにログインすることができず、SharePointを含む原告\nの社内ネットワークにもログインすることもできなかったものであり、 このSharePoint上の電子データは、これを取り扱う部門に属 する従業員のみがアクセスすることができるように設定されており、本 件ファイル1ないし6は、このようなSharePoint上に管理さ れていたものである。
そうすると、原告は、パソコンを貸与し、ID及びパスワードを付与\nした従業員で、かつ、本件ファイル1ないし6を取り扱う部門に属する 者のみに、これらのファイルに対するアクセスを許可し、原告の従業員 は、就業規則等や本件ファイル1ないし6の内容からして、これらのフ ァイルを原告の外部に持ち出すことが禁止されていることを認識するこ とができたといえるから、本件ファイル1ないし6は秘密として管理さ れていたと認めるのが相当である。
(イ) これに対して、被告は、1) 同じビジネスユニット内での異動であれば、 従前所属していた部署のフォルダに継続してアクセスすることができ、 原告はSharePointのアクセス権限を適切に管理していなかっ たこと、2) SharePoint上で管理されていた情報も、その性質 や機密性の程度等は様々であり、「秘密」や「Confidentia l」等の秘密情報であることを示す記載のないものも多数あった上、S harePoint上で管理されている電子データをプリントアウトし たり、貸与されたパソコンに保存したりすることは禁止されていなかっ\nたことから、本件ファイル1ないし6が秘密として管理されていたとは 認められないと主張する。しかし、上記1)については、別の部署に異動した後も、業務上、従前所属していた部署のフォルダにアクセスする必要があることも十分考え\nられ、これをもって、直ちに、原告がSharePointのアクセス 権限を適切に管理していなかったということはできない。また、上記2)については、そのような事情があったとしても、前記(ア)で説示した原告における秘密管理に関する体制並びに本件ファイル1ないし6の内容及びこれらに対して施されていた具体的措置に照らせば、本件ファイル1ないし6について、秘密として管理されていたことが否 定されるものではないというべきである。
・・・
(1) 原告は、被告が、営業秘密である本件ファイル1にアクセスすることがで きなかったにもかかわらず、転職先であるSUDARSHAN社で利用する ことを想定して、本件ファイル1を取得するために、本件プロジェクトを手 伝うと説明するなどの不正の手段によって、Cからこれを取得したものであ るから、不競法2条1項4号の不正競争に該当すると主張する。
しかし、前記1(2)、(3)、(5)及び(6)のとおり、被告がCから本件ファイ ル1を受領したのは令和元年9月2日であり、被告が本件プロジェクトに参 加することになったのは同日頃と考えられるところ、被告がBからSUDA RSHAN社への転職を勧誘された同年8月頃から間もない時期であるし、 実際に被告がSUDARSHAN社と雇用契約を締結したのは、被告が本件 ファイル1を受領してから約1か月半が経過した同年10月15日であるこ とからすると、被告が本件プロジェクトに参加することになった同年9月2 日頃の時点において、被告がSUDARSHAN社に転職することが決まっ ていたとは認められない。このことは、被告が、同月頃、原告の一部の従業 員に対し、SUDARSHAN社への転職を勧誘していたこと(前記1(4)) を考慮しても、同様である。
また、被告が原告から本件プロジェクトに参加するよう指示されたことを 認めるに足りる証拠はないものの、前記1(1)及び(2)のとおり、本件プロジ ェクトは、プラスチックに係る売上げを拡大するために市場の調査分析を行 うものであり、被告が属するマーケティング部門は、顔料事業部門全体の活 動を強化するために設けられた部署で、市場情報を網羅的に収集すること等 の業務を担っていたことからすると、被告が本件プロジェクトに関わること は不自然であるとはいえない。原告代表者(当時は、顔料ビジネスユニット\nの統括責任者)も、被告が本件プロジェクトに多少なりとも関わっているこ とを知りながら、特段注意をしていなかったものと認められる(原告代表者\n本人)。
以上の事情に照らして検討すれば、被告が、原告のプラスチック部門に係 る営業秘密を持ち出し、転職先であるSUDARSHAN社にて使用するな どするために、Cに対して本件プロジェクトを手伝う旨を申し出たと認める\nことはできないというべきであり、他に、被告が不正の手段により本件ファ イル1を取得したことを基礎付ける事情を認めるに足りる証拠はない。したがって、被告が不正の手段により本件ファイル1を取得したとは認められない。
(2) なお、前記1(7)のとおり、被告は、令和元年10月28日、Cから送信さ れた本件ファイル1を、更に自らの私的なメールアドレスに送信している。 しかし、上記のとおり、被告がCから本件ファイル1を受領したことは、 不当な手段によるものとは認められないこと、被告は、本件ファイル1を自 らの私的なメールアドレスに送信したにすぎず、被告の支配下にあるという 状況を変更したものではないこと、被告がいかなる目的で当該送信を行った のかは明らかでないが、本件ファイル1の内容(前記2(1)ア(ア))からする と、マーケティング部門に所属し、同年11月18日までは原告に出勤して いた被告(前記1(1)及び(10))において、本件ファイル1を使用することが 業務上必要でなかったとまではいえないことからすると、上記送信行為も不 正の手段に該当するとは認められないというべきである。
(3) したがって、原告の本件ファイル1に係る不競法2条1項4号並びに3条 1項及び2項に基づく請求は理由がない
・・・
(2) そして、前記前提事実(3)のとおり、本件誓約書の「秘密情報」とは、「会 社又はその関連会社が所有又は使用している経済的に価値のあるすべての専 有情報で、公に知られていないもの」をいうところ、本件ファイル1ないし 6は、前記2(1)のとおり、「営業秘密」(不競法2条6項)に該当すること に鑑みると、本件誓約書の「秘密情報」にも該当すると認めるのが相当であ る。他方で、本件情報7ないし13については、具体的にいかなる内容である かが明らかでなく、また、電子データ、書類等のいかなる形で記録されてい たかも明らかでないから、本件誓約書の「秘密情報」に該当するとは認めら れない。したがって、被告は、原告に対し、本件秘密保持契約に基づき、原告の許 可なく、本件ファイル1ないし6を開示し、又は使用しない義務を負う。
(3) ところで、被告が、現時点までに、本件ファイル1ないし6を開示し、又 は使用したことを認めるに足りる証拠はないことからすると、原告の本件秘 密保持契約に基づき本件ファイル1ないし6の使用等の差止めを求める請求 は、将来における被告の不作為を求める訴えと解すべきであるから、「あら かじめその請求をする必要がある場合」(民事訴訟法135条)に該当する と認められなければならない。
まず、本件ファイル1については、前記1(7)のとおり、被告は、これを自 らの私的なメールアドレスに送信しているが、被告は、同メールアドレスの 利用に係る契約を既に解約し、本件ファイル1を含む電子データにアクセス することはできないと供述しており、これに反する証拠は見当たらない。そ うすると、被告に対して、あらかじめ本件ファイル1の開示又は使用の差止 めを請求する必要があるとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠は ない。
また、本件ファイル2ないし6については、前記4のとおり、被告がこれ らを取得したとは認められず、使用し又は開示したとも認められないから、 やはり、被告に対してあらかじめ開示又は使用の差止めを請求する必要があ るとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(4) 原告は、本件秘密保持契約に基づき、本件ファイル1ないし6が記録され た文書及び電磁的記録媒体(別紙物件目録記載1及び2の各USBメモリを 除く。)の廃棄を求めている。
しかし、本件誓約書の記載を精査しても、これによって締結された本件秘 密保持契約上、被告が原告に対してこのような廃棄義務を負うと解すること はできないし、他に、被告が原告に対して廃棄義務を負う旨の合意が成立し たことを認めるに足りる証拠はない。
(5) 以上によれば、本件秘密保持契約に基づき被告に対して本件ファイル1な いし6を使用し、又は、第三者に開示若しくは使用させてはならないことを 求める部分は、訴えの利益を欠くから不適法である。そして、原告の本件秘 密保持契約に基づくその余の請求は、いずれも理由がない。
6 争点6(被告に本件USBメモリが譲渡されたか)について
(1) 証拠(乙2、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、1) 原告は、販売促進 のために顧客に配布するグッズとして、ボールペン、付箋、傘、水筒等を用 意しており、その中に、販促用USBメモリがあったこと、2) 原告は、これ らの販促用品について、配布した数量や配布先等の管理をしていなかったこ と、3) 原告の従業員はこれらの販促用品のうち余ったものを自由に使用して おり、原告が当該従業員に対して当該販促用品を返還するよう求めたことは 一度もなかったこと、4) 被告は、平成30年頃から、本件USBメモリを使 用していることが認められる。
上記認定事実のとおり、本件USBメモリを含む販促用USBメモリは、 顧客に無償で譲渡する販促用品の一つであるから、さほど高価なものとは考 えられず、原告の従業員は、余った販促用品を自由に使用しており、原告は これに異議を述べていなかったこと、被告は、SUDARSHAN社への転 職を決意したときより前から、本件USBメモリを使用しており、原告は、 他の従業員に対するのと同様に、原告において勤務する被告に対して本件U SBメモリの使用に異議を述べていないことからすると、被告が本件USB メモリの使用を開始したときに、原告と被告との間で、被告に対して本件U SBメモリを無償で譲渡する合意が成立したと認めるのが相当である。 (2) これに対して、原告は、販促用USBメモリは、あくまで販売促進のため に顧客に配布して利用することが前提となっており、従業員が私物として利 用することは予定されておらず、原告の就業規則上、従業員は会社の施設及\nび物品を会社の許可なく私的に使用してはならないとされていると主張する。 しかし、前記(1)の原告における販促用USBメモリの管理や使用の実態か らすると、原告が指摘する上記各事情は、前記(1)の認定の妨げになるものと はいえない。
2023.01. 3
令和4(ネ)265等 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年10月14日 大阪高等裁判所
前記(2)のとおり、本件侵害通知は、いずれも法的根拠に基づかないもの であるが、前記(2)で述べたところに加え、上記(3)認定の各事実からすると、 以下に詳述するとおり、控訴人Bは、前記注意義務を怠った過失があるとい えるばかりか、著作権侵害通知制度を濫用したものということさえできるの であって、これにより、本件侵害通知の対象動画の投稿者である被控訴人の 法律上保護される利益を侵害したものであるから、控訴人Bが本件侵害通知 を提出した行為は、被控訴人の法律上保護される利益を違法に侵害したもの として不法行為を構成するというべきである。
イ すなわち、控訴人Bの提出した本件侵害通知の記載内容をみるに、本件侵 害通知1は、前記(2)アのとおり、被控訴人メランジ動画につき「編み目(ス ティッチ)の著作権侵害」があるというものであって、編み目の著作物性を いう点において、その通知内容自体から著作権侵害が認められないことが明 らかなものである。
また、本件侵害通知2は、前記(2)イのとおり、被控訴人トリニティ動画の 「動画全体」につき「著作権、翻訳権の侵害」があるというものであって、 控訴人Bは、被控訴人トリニティ動画の口頭説明部分が控訴人動画1)〜3)の 口頭説明部分の著作権を侵害すると考えて本件侵害通知2を提出した旨陳述 しており(乙10、控訴人B本人)、本件訴訟においては、その旨主張する ようであるが(これ自体が法的に失当であることは前記(2)イのとおりであ る。)、被控訴人トリニティ動画が控訴人動画のうちいずれの動画のいかなる 部分の著作権を侵害したかにつき、明確かつ具体的な主張をしているもので はないこと、控訴人Bの陳述も、要は、被控訴人動画において控訴人動画に おける編み目の作り方が同じであることを中心に著作権侵害があった旨を述 べるものであること、本件侵害通知2が本件侵害通知1と同日にされている ことに加え、前記(3)の各事実にも照らすと、むしろ控訴人Bは、本件侵害通 知2においても本件侵害通知1と同様、本来、著作権侵害が認められない被 控訴人トリニティ動画が編み目の著作権を侵害したことを根拠として、著作 権侵害通知をYouTubeに提出したものと認めるのが相当である(この ことは、控訴人Bの陳述(乙10)によれば、被控訴人トリニティ動画の2 5分47秒間のうち、著作権侵害に該当する部分は3分43秒間にすぎない にもかかわらず、控訴人Bが、削除依頼ウェブフォーム(甲18)において、 タイムスタンプで該当箇所を特定することもなく、被控訴人トリニティ動画 の「動画全体」が著作権侵害部分に該当するとして本件侵害通知2を行って いることからも裏付けられる。)。したがって、本件侵害通知2も、その内 容において著作権侵害が認められないことが明らかなものというべきである。
ウ しかし、そもそも編み物の編み目に著作物性が認められないことは前記(2) アで説示したとおりであるし、前記(3)アによれば、控訴人Bは、むしろ動画 の著作物性の有無の判断には困難が伴うことをかねてから認識していたこと が認められる。また、著作権侵害が肯認されるには依拠性が必要であるが、 前記(3)エによれば、控訴人Bが本件侵害通知を提出するに当たって依拠性を 検討した様子は全くうかがえない。 そればかりか、控訴人Bが本件侵害通知を提出するに当たり、著作権侵害 の有無を予め検討していたのであれば、それが法的に失当であろうとも、本件侵害通知後の被控訴人からの問い合わせに対して著作権侵害と考える理由\nを端的に回答できるはずであるが、被控訴人に対する回答ぶりは専ら困惑さ せることに終始するものであるし((3)エ)、本件訴訟を提起された後におい てすら、控訴人らは著作権侵害を理由に裁判手続をとろうとしていないこと、 その他前記(3)で認定した本件侵害通知提出前後の状況をも考慮すると、控訴 人Bは、本件侵害通知を提出するに当たり、編み目の著作物性が肯定される には困難を伴うことを十分認識していたと認められるにもかかわらず、控訴人動画で紹介した編み目と同一の編み目を説明する動画であれば、それが控\n訴人動画に依拠したものか否かを問わず、先行して動画を投稿した控訴人B の著作権を侵害するとの独自の見解を有し、この見解が法的に成り立つか否 かを検討することなく、すなわち、控訴人Bが著作権者等であることはもと より、著作権侵害通知の内容が正確であることについて検討することなく、 必要な注意義務を怠って漫然と本件侵害通知を提出したものと認めるのが相 当である。
エ なお、控訴人らは、専門家であるJ弁理士及びK弁護士にも相談した上で、 本件侵害通知を行った旨主張するが、控訴人らが本件侵害通知当時に上記専 門家に著作権侵害に関する相談をしていたことを認めるに足りる的確な証拠 はなく、また、仮に何らかの相談をしていたとしても、前記の本件侵害通知 の内容及び本件訴訟における応訴の内容に照らし、真摯な相談がされたもの ともおよそ考えられないから 、これによって控訴人Bが本件侵害通知を提出 するに当たって必要な検討をしたとは認められない。
オ そして、控訴人Bは、被控訴人に対する以外にも、本件侵害通知に相前後 して、他の複数のチャンネル開設者に対し、その投稿した編み物動画やアプ リケーション上での編み物作品の販売に対し、動画のコメント欄等に抗議を 書き込んだり、被控訴人に対すると同様に、編み目を含む編み方の模倣を理 由に一斉に複数の著作権侵害通知を提出したりすること((3)イ、ウ、オ)によ って、これらの者が、控訴人Bが動画で紹介している編み方と同じ編み方を 動画で投稿することを事実上抑止しようとしていたことがうかがわれる。 さらに、弁護士への依頼や著作権侵害警告に対する異議申立てを考えるようなチャンネル開設者に対しては、控訴人Bに加担する控訴人D又は控訴人\nB自身において、「一度痛い目見ないといけない」「詐欺で警察にも行けるお話」などと強迫的ともいえるメッセージを送信したり、独自の見解を一方\n的に押し付けるようなコメントを公表したりして((3)イ、オ、カ)、裁判手続 で著作権侵害の有無を明らかにするより、示談するよう強く求めていたこと も認められ、以上のような諸事情を総合すると、控訴人Bは、著作権侵害通 知制度を利用して、競業者であるといえる同種の編み物動画を投稿する者の 動画を削除することで不当な圧力をかけようとしていたとさえ認められる。
カ 以上によれば、控訴人Bは、本件侵害通知をYouTubeに提出するに 当たって、単に自らが著作権者であることや、著作権侵害通知の内容が正確 であることについて何ら検討することなく漫然と法的根拠に基づかない本件 侵害通知を提出したという点で必要な注意義務を怠った過失があるといえる ばかりか、前記のとおり著作権侵害通知制度を濫用したものということさえ できるのであって、これにより本件侵害通知の対象動画の投稿者である被控 訴人の法律上保護される利益を侵害したものであるから、控訴人Bが本件侵 害通知を提出した行為は、被控訴人の法律上保護される利益を違法に侵害し たものとして不法行為を構成するというべきである
・・・
ア 前記2(1)アで説示したとおり、YouTubeは、インターネットを介 して動画の投稿や投稿動画の視聴などを可能とするサービスであり、投稿者は、動画の投稿を通して簡易な手段で広く世界中に自己の表\現活動や情報を伝えることが可能となるから、作成した動画をYouTubeに投稿する自由は、投稿者の表\現の自由という人格的利益に関わるものであるといえ、控訴人Bによる違法な本件侵害通知により被控訴人動画が一方的に削除された ことにより、被控訴人はその人格的利益を侵害されたものと認められる。
イ そして、その削除期間が、令和2年2月6日から同年8月29日までの2 06日間に及ぶこと、被控訴人トリニティ動画の動画時間が25分47秒間、 被控訴人メランジ動画の動画時間が19分24秒間であって、テロップ挿入 や音声等の編集作業にも相応の労力、時間を要して作成されたものであるこ とがうかがわれること(甲56〜58)、被控訴人動画が投稿されたAのチ ャンネルには少なくとも1000人を超える登録者がいたことに加え、被控 訴人が、削除当日に、控訴人Bに対し、控訴人Bのどの動画の著作権を侵害 したことになるのか教えてほしい旨問い合わせたのに対して、控訴人Bは、 これに対する回答をしないばかりか(前記2(3)エ)、同年6月頃、Cのチャ ンネルにおいて、被控訴人に向け、本件侵害通知のことを取り上げて「2度 あることは3度ある、3度目は命取りです」などとのコメントを記載して、 控訴人Bが3回目となる著作権侵害通知をすることで、被控訴人のチャンネ ル停止・全動画の削除という事態が起きかねないことをほのめかすなど、被 控訴人をして専ら畏怖、困惑させるばかりで、事後的にも誠意ある対応をせ ず、原判決において控訴人らの指摘する被控訴人動画による著作権侵害が認 められない旨判断された後も、被控訴人動画が控訴人動画の盗作であるかの ような独自の見解に基づくコメントをYouTubeのチャンネルに記載し ていること(甲13、14、20、69〜77)など、本件に現れた一切の 事情を考慮すると、被控訴人が上記の人格的利益の侵害により受けた精神的 苦痛を慰藉する金額は20万円を下らないというべきである。
ウ なお、被控訴人は、前記第3の5(被控訴人の主張)(2)イ、ウに記載す る、本件侵害通知による被控訴人チャンネル全体の収益性の低下及び視聴者 に対する信頼毀損による視聴数低下について、慰謝料算定に当たっての根拠 としても主張するが、被控訴人は、上記各事情によって被控訴人チャンネル の収益性の低下による経済的損害が生じたことをいうものであって、その損 害賠償の可否は、そのような経済的損害の発生が認められるか否かの立証に 係るものであり、損害の発生が不明な場合に前記イで認定したところを超え て慰謝料として損害賠償を認めることはできないというべきである。したが って、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) 広告収益に関する経済的損害について
ア 被控訴人動画の広告収益の低下
被控訴人動画がYouTubeにおいて削除されていた期間は、前記のと おり令和2年2月6日から同年8月29日までの206日間であるところ、 証拠(甲31、32)によれば、被控訴人メランジ動画(投稿日は同年2月 3日)についての広告収益は、同年2月3日から同月6日までの4日間で合 計1463円(1日当たり365.75円)であったこと、被控訴人トリニ ティ動画(投稿日は令和元年8月1日)についての広告収益は、令和元年1 1月6日から令和2年2月6日までの93日間で合計1766円(1日当た り18.98円)であったことが認められる。
被控訴人トリニティ動画の削除により被控訴人が失った広告収益は、上記 のとおり1日当たり18.98円として算出するのが相当と認めるが、被控 訴人メランジ動画の上記収益単価は、投稿直後の4日間の広告収益に基づく ものである。広告収益は動画の視聴数等によって変動し得るところ、一般的 に、新たに投稿された動画の方が視聴者の耳目を集めやすく、投稿直後は視 聴数が多く、その後時間が経過するにつれて逓減する傾向があること自体は 否定し難いこと、編み物の編み方に関する動画の視聴は、季節柄、夏場には 視聴数が低くなる傾向がうかがわれ、通年で一定しているとはいい難いこと (甲83の1〜5)からすると、被控訴人メランジ動画の広告収益は、削除 後の当初30日間は1日当たり350円、その後は、被控訴人トリニティ動 画との対比を考慮して、1日当たり20円として被控訴人の損害を算定する のが相当と認める。
そうすると、本件侵害通知による被控訴人動画の削除により被控訴人が被 った広告収益に関する損害は、1万7929円(〔350円+18.98 円〕×30日+〔20円+18.98円〕×〔206日−30日〕)。端数 切捨て。)に限り、これを認めるのが相当である(なお、被控訴人動画の削 除又は復元の当日分については、一定程度の広告収益が得られている可能性がないではないが、特に上記認定を左右すべき事情ではない。)。\n
イ 被控訴人チャンネル全体の収益性の低下等 被控訴人は、被控訴人動画が本件侵害通知によって削除されたことは、被 控訴人チャンネルのステータスに影響を与え、被控訴人チャンネルの動画が 視聴者の画面に表示されにくくなったり、広告単価が低下したりするなどの不利益を生じさせ、被控訴人チャンネル全体の収益性を低下させている旨主\n張し、また、被控訴人チャンネルに対する視聴者の信頼が著しく低下し、視 聴数が減少して収益性が低下した旨主張する。
しかし、「YouTubeヘルプ」(甲8)において、著作権侵害の「警 告を複数回受けると収益化に影響を及ぼすおそれがあります。」との記載が されているものの、どのような場合にいかなる仕組みによって収益化に影響 を及ぼすかについては必ずしも明確になっているとは認められない。また、 被控訴人が影響を受けたとする被控訴人チャンネル全体の収益について、本 件侵害通知がされる前後、さらに被控訴人動画の復元後といった各時点の収 益が具体的にいかなるものであったかを認めるに足りる証拠は何ら提出され ておらず、被控訴人から数値を示すなどした具体的主張もされていない。Y ouTubeにおいては、各動画の収益に関する分析情報は期間を区切って 画面上に表示させることが可能\である(甲31、32、83の1〜5)から、 本件侵害通知がされる前後、被控訴人動画の復元後といった各時点で動画の 視聴数、収益等にいかなる変動があるかを立証することは容易であると認め られるにもかかわらず、被控訴人動画ないしチャンネルについてそうした立 証が全くされていないことに照らすと、本件侵害通知による被控訴人動画の 削除により被控訴人のチャンネル全体の収益性が低下するなどして被控訴人 が経済的損害を被ったとは認めるに至らないというべきである。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> その他
>> ピックアップ対象
2023.01. 3
令和4(ネ)10024 映画上映禁止及び損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年9月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人らは、同一性保持権侵害の被侵害利益は、著作者の名誉感情であ るとし、被控訴人Yが、慰安婦問題というデリケートな問題を扱った本件 利用映像等5の一部を切り出し、音声を削除し、ナレーションを加えるこ とは、控訴人X2が客観的証拠もなく偏った主張を述べているにすぎない かのような印象を与えかねないし、また、本件利用映像等6は、控訴人X 2が著作者である本件外部映像等6のうち、日本における人種差別につい てことさらに騒ぎ立てる者がいることを述べた部分のみが利用されてい て、控訴人X2が、日本に人種差別が存在すると指摘すること自体を批判し ているかのような印象を与えかねないから、いずれも通常の著作者であれ ば名誉感情を害されるものであり、控訴人X2の同一性保持権を侵害する 旨主張する。
イ しかしながら、仮に同一性保持権侵害の被侵害利益に著作者の名誉感情 が含まれるとしても、それによっておよそ一切の改変が著作者の名誉感情 を侵害し、同一性保持権の侵害となると解すべき根拠はなく、著作物の性 質や利用行為の態様等を考慮して、同一性保持権侵害の有無を考慮すべき である。
本件利用映像等5、6は、ユーチューブ上の映像である本件外部映像等 5、6の一部である。ユーチューブ上の映像は、無料でいつでもだれでも 閲覧することができ、どの映像を見るかはもとより、映像の全部を見るの か一部を見るのか、映像のどの部分を見るのかを、閲覧者が自由に選択し て見ることができるという性質を有する。 本件利用映像等5、6は、本件利用映像等2、3の後、本件利用映像等 4が3秒間表示された後に表\示されるものであるところ、本件利用映像等 2、3には、左上部に「YouTube」という表示があり、「X2´」という著作 者名が表示されており、被控訴人Yは、本件利用映像等5に先立って、イ\nンターネット上の投稿でビデオを見つけた旨のナレーションを入れてお り、本件映画1のエンドクレジットの「利用した映像及び写真の出所」に、 控訴人X2の氏名、本件外部映像等5、6の題名、ユーチューブに投稿され た動画であることの記載があるから、本件映画1を見る者にとって、本件 外部映像等5、6がユーチューブ上の映像の一部であることは明らかであ り、著作者名や題名から本件外部映像等5、6を検索することは容易に可 能である(乙38)。\n
本件利用映像等5、6は、被控訴人Yが慰安婦問題に関心を有するよう になったきっかけとなった動画を作成した人物であり、本件映画1中のイ ンタビューの対象ともなっている控訴人X2がどのような人物であるかを 紹介することを目的とするものであり、控訴人X2の主張を誤って伝えるも のであるとは認められない。 その他、原判決第3の9(1)イないしエ(原判決68頁19行目から70 頁14行目まで)、同(2)イないしエ(原判決70頁23行目から72頁9行 目まで)に記載された事情も考慮すると、被控訴人らが本件利用映像等5、 6を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X2の名誉感情を 害するとは認められず、本件利用映像等5、6の作成は、いずれも「やむ を得ないと認められる改変」(著作権法20条2項4号)であり、控訴人X 2の著作者人格権を侵害するものとは認められない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 肖像権等
>> その他
>> ピックアップ対象
2022.12.24
令和3(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月4日 知的財産高等裁判所
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項1は、本件訂正前 の請求項1の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解\nすることができるから、訂正事項1は、「特許請求の範囲の減縮」(特許法 134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものということができる、 2)訂正事項2は、本件訂正前の請求項3の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構\n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項2は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項2は、本件訂正前の請 求項3の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり(甲46)、本件訂正前の請求項1の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項3の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」(【00 06】)、「本実施形態の噴射製品は、噴口から15cm離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の50%平均粒子径r15と、噴口から30 cm離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r30との粒子径比(r30/r15)が、0.6以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成(たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の\n各種物性等)は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」(【0010】)、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比(r 30/r15)が0.6以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から30cm離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」(【0023】)、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比(r30/r15)が0.6以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」(【0024】)、「以上、本実施形態の噴射製 品(ポンプ製品)によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比(r30/r15)が0.6以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」(【0028】)、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比(r 30/r15)が0.6以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」(【0044】)、「表1に示されるように、粒子径比\n(r30/r15)が0.6以上となるよう調整された実施例1〜14の噴 射製品は、N,N−ジエチル−m−トルアミド(ディート)を配合した 噴射製品(たとえば表2に示される参考例1)と同程度まで粘膜刺激が\n低減された。また、たとえば実施例1〜3と実施例11〜13との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品(アクチ ュエータ)の寸法等(噴射方式、噴口径、1回吐出量等の諸条件)が異 なる場合であっても、粒子径比(r30/r15)が0.6以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」(【0052】)との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項1の 「前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の50%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子 径比(r30/r15)が、0.6以上となるよう調整され」との構成又は\n本件訂正前の請求項3の「前記噴口から15cm離れた位置における5 0%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置における5 0%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)が、0.6以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、\n本件明細書には、本件訂正前の請求項1及び3の上記各構成にした場合\nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。
そうすると、訂正事項1及び2により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項1及び3の上記各構成によって奏される作用効\n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項1及び2は、本件訂 正前の請求項1及び3の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項1及び2は、「特許請求の範囲の減縮」(特許 法134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項1は、害虫忌避組成物を充填した物の発明(本件訂正 前の請求項1)において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ\nれたものと理解することができ、また、訂正事項2は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明(本件訂正前の請求項3)において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると\nして、訂正事項1及び2は、本件訂正前の請求項1及び3の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 減縮
>> ピックアップ対象
2022.12.24
令和4(ネ)10055 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年12月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(ア) 前記(2)のとおり、本件発明と乙1発明との相違点は、「医薬組成物につ いて、本件発明では、『非外傷性である前腕部骨折を抑制するため』のも のであると特定されているのに対して、乙1発明では、『骨粗鬆症治療薬』 であると特定されている点。」にある(相違点1)ところ、控訴人は、本 件発明につき、前腕部骨折の抑制が特に求められる患者群において予測されていなかった顕著な効果を奏するものであり、エルデカルシトール\nの新たな属性を発見し、それに基づく新たな用途への使用に適すること を見出した医薬用途発明であるから、相違点1に係る本件発明の用途 (「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」)は乙1発明の「骨粗 鬆症治療薬」の用途とは区別される旨主張する。
(イ) そこで検討するに、公知の物は、原則として、特許法29条1項各号 により新規性を欠くこととなるが、当該物について未知の属性を発見し、 その属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出した 発明であるといえる場合には、当該発明は、当該用途の存在によって公 知の物とは区別され、用途発明としての新規性が認められるものと解さ れる。 そして、前記1(2)のとおり、本件発明の医薬組成物は、高齢者や骨粗 鬆症患者等の骨がもろくなっている者が転倒等した際に、前腕部である 橈骨又は尺骨に軽微な外力がかかって生じる骨折のリスク、すなわち前 腕部における非外傷性骨折のリスクに着目して、その用途が「非外傷性 である前腕部骨折を抑制するため」と特定されている(相違点1)もの である。
(ウ) しかしながら、前記(3)イの技術常識によれば、当業者は、乙1発明の 「骨粗鬆症治療薬」につき、椎体、前腕部、大腿部及び上腕部を含む全 身の骨について骨量の減少及び骨の微細構造の劣化による骨強度の低下が生じている患者に対し、各部位における骨折リスクを減少させるた\nめに投与される薬剤であると認識するものといえる。また、前記(3)ア、 エ及びオの各技術常識によれば、当業者は、エルデカルシトールの効果 は海綿骨及び皮質骨のいずれに対しても及ぶと期待するものであり、海 綿骨及び皮質骨からなる前腕部の骨に対してもその効果が及ぶと認識 するものといえる。さらに、前記(3)イ及びウの技術常識によれば、当業 者は、骨粗鬆症においては身体のいずれの部位も外力によって骨折が生 じるものであり、また、前腕部における骨折リスクは、骨強度が低下す ることによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他 の部位における骨折リスクと共通するものであると認識するものとい える。
以上の事情を考慮すると、当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の 骨の病態及びこれに起因する骨折リスクについて、他の部位の骨の病態 及び骨折リスクと異なると認識するものではなく、また、乙1発明の「骨 粗鬆症治療薬」としてのエルデカルシトールを投与する目的及びその効 果についても、前腕部と他の部位とで異なると認識するものではないと いうべきである。
(エ) さらに、本件優先日前に公開された乙12の文献には、エルデカルシ トールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑制す ることが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されているこ とに加え、前記(3)エ及びオの技術常識によれば、エルデカルシトールに よる前腕部を含む全身の骨折リスクの減少作用は、経口投与されて体内 に吸収されたエルデカルシトールが、骨に対して直接的又は間接的に何 らかの作用を及ぼすことによって達成されるものであるといえるとこ ろ、本件明細書には、骨折リスクを減少させようとする部位が前腕部で ある場合と他の部位である場合とで、エルデカルシトールが及ぼす作用 に相違があることを示す記載は存しない。そして、前記(3)ウ及びオの技 術常識を考慮しても、本件明細書の記載から、エルデカルシトールの作 用に関して上記の相違があると把握することはできない。 そうすると、当業者は、前腕部の骨折リスクを減少させるために投与 する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデカルシトールの作 用が相違すると認識するものではないというべきである。
(オ) 以上によれば、エルデカルシトールの用途が「非外傷性である前腕部 骨折を抑制するため」と特定されることにより、当業者が、エルデカル シトールについて未知の作用・効果が発現するとか、骨粗鬆症治療薬と して投与されたエルデカルシトールによって処置される病態とは異な る病態を処置し得るなどと認識するものではないというべきである。 そうすると、本件発明については、公知の物であるエルデカルシトー ルの未知の属性を発見し、その属性により、エルデカルシトールが新た な用途への使用に適することを見出した用途発明であると認めることは できないから、相違点1に係る用途は乙1発明の「骨粗鬆症治療薬」の 用途と区別されるものではない。
(カ) したがって、相違点1は実質的な相違点ではない。
イ 控訴人の原審における主張(原判決「事実及び理由」の第2の4(2)及び
(3))及び当審における補充主張に対する判断
(ア) 前記第2の3(1)〔控訴人の主張〕アの主張について
a 控訴人は、前腕部骨折は他の部位の骨折とは異なる特徴を有するこ と、乙1文献には前腕部骨折を抑制する骨粗鬆症治療薬が開示されて いるものではないことなどを理由に、本件発明の用途は乙1発明の用 途と客観的に区別することができる旨主張する。 しかしながら、前記(3)ウの技術常識によれば、前腕部骨折は、身体 的活動性が比較的高い前期高齢者等において好発する特徴があるとい えるものの、上記アで検討したとおり、前腕部の骨と他の部位の骨と で病態が異なるものとはいえず、また、前腕部の骨折リスクを減少さ せるために投与する場合と骨粗鬆症患者に投与する場合とで、エルデ カルシトールの作用が相違するともいえないことからすれば、前腕部 骨折に上記の特徴があるからといって、本件発明の用途は乙1発明の 用途と客観的に区別することができるものとはいえない。
また、前記(1)のとおり、乙1文献には、エルデカルシトールにつき、 動物実験において、骨密度増加効果がアルファカルシドールよりも強 力であるところ、骨密度の増加は骨強度の増加を伴っていると考えら れること、第II)相臨床試験において、腰椎骨及び大腿骨の骨密度の増 加が認められ、ビタミンD補充効果に依存せずに強力に骨密度を増加 させたものと考えられること、新規椎体骨折発生頻度を主要評価項目 としてアルファカルシドールの効果と比較する更なる臨床試験が進行 中であることが記載されているところ、前記(3)ウないしオのとおり、 エルデカルシトールがアルファカルシドールに比して有意に優れた骨 強度改善効果等を有していることや、前腕部の骨折リスクは他の部位 と同様に骨強度が低下することによって増加するものであることが技 術常識であったこと、上記ア(エ)のとおり、本件優先日当時、エルデカ ルシトールがアルファカルシドールよりも優位に椎体骨折の発生を抑 制することが第III)相臨床試験において確認されたことが記載されてい る文献(乙12)が存在したことを併せ考慮すれば、当業者は、乙1 文献の記載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前 腕部についても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制 するものであることを、合理的に予測し得たものといえる。
b したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ) 同イの主張について
a 控訴人は、一般に患者群の特徴に応じて薬剤が選択されており、骨 粗鬆症においても個々の患者の状態に応じて様々な薬剤が使い分けら れているところ、本件発明は、前腕部骨折の抑制が特に求められる患 者という限定された患者群に対して顕著な効果を奏するものとして、 従来技術とは区別された新規性を有する旨主張する。しかしながら、上記アで検討したとおり、前腕部の骨折リスクは、骨強度が低下することによって増加する点において、骨粗鬆症において骨折しやすい他の部位における骨折リスクと共通するものであるか ら、骨粗鬆症患者のうち、全身の骨折の抑制が必要とされる者と前腕 部の骨折の抑制が特に必要とされる者とを客観的に区別することはで きないというべきである。
b したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(ウ) 同ウの主張について
a 控訴人は、本件試験に係る結果において、エルデカルシトールが、 既存薬剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制 が特に求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されている旨主張する。\n
そこで検討するに、本件明細書には、アルファカルシドールを比較 薬とした無作為割付二重盲検群間比較試験である本件試験において、 非外傷性の前腕部骨折の3年間の発生頻度が、アルファカルシドール 投与群においては523例中17例(骨折確率3.63%)であり、 エルデカルシトール投与群においては526例中5例(骨折確率1. 07%)であったこと、これらの骨折発生頻度を層化ログランク検定 及び層化コックス回帰により比較した結果、アルファカルシドール投 与群の骨折確率を1とした際のエルデカルシトール投与群の骨折確率、 すなわちハザード比は0.29であったこと、これにより、エルデカ ルシトール投与群における前腕部骨折危険率が71%減少したことが 判明したこと、これらの試験結果の結論として、アルファカルシドー ル投与群に対するエルデカルシトール投与群の明らかな優越性が認め られたことが記載されている。
しかしながら、上記アで検討したとおり、当業者は、乙1文献の記 載に基づいて、エルデカルシトールが、他の部位と同様に前腕部につ いても、アルファカルシドールよりも優位にその骨折を抑制するもの であることを、合理的に予測し得たものといえることからすれば、エルデカルシトール投与群における前腕部骨折危険率が減少することも\n予測し得たというべきである。また、ハザード比を用いた解析においては、対照群におけるイベントの発生率が小さい場合には、臨床上の\nわずかな差が大きな数値に置き換えられてしまうことがあることが知 られているところ(乙20、22)、本件試験においては、対照群であ るアルファカルシドール投与群における骨折確率が3.63%と小さ かったことからすれば、ハザード比の値に基づいてエルデカルシトー ル投与群における前腕部骨折危険率が71%減少したと算定されたこ とについては、臨床上のわずかな差が大きな数値に置き換えられてし まった結果である可能性を否定することができない。また、本件試験において、アルファカルシドール投与群における骨\n折確率とエルデカルシトール投与群における骨折確率との差(絶対リ スク減少率)は、前腕部骨折については2.56%、椎体骨折につい ては4.1%であり、椎体骨折の方が前腕部骨折よりも大きな値とな る。
以上の事情を考慮すると、上記のハザード比の値のみに基づいて、 エルデカルシトールの前腕部骨折の抑制効果が、アルファカルシドー ルに比して格別顕著であり、当業者の予測し得る範囲を超えるものであると直ちに評価することはできないというべきである。\nb 以上によれば、このほかに控訴人が本件試験に関して縷々主張する 点を考慮しても、本件試験において、エルデカルシトールが、既存薬 剤であるアルファカルシドールと比較して、前腕部骨折の抑制が特に 求められる患者に対し、顕著かつ予想外の効果を奏することが確認されたものということはできない。\n
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.12.22
令和3(ワ)24148 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年11月24日 東京地方裁判所
被告は、本件各記事による本件各動画の利用は適法な引用(法 32条 1項)に当たる旨を主張する。しかし、証拠(甲 7)及び弁論の全趣旨によれば、本件各記事は、いずれも、約 30 枚〜60 枚程度の本件各動画からキャプチャした静止画を当該動画の時系列に沿ってそれぞれ貼り付けた上で、各静止画の間に、直後に続く静止画に対応する本件各動画の内容を 1 行〜数行程度で簡単に要約して記載し、最後に、本件各動画の閲覧者のコメントの抜粋や被告の感想を記載するという構成を基本的なパターンとして採用している。各静止画の間には、上記要約のほか、被告による補足説明やコメント等が挟まれることもあるが、これらは、関連する動画(URL のみのものも含まれる。)やスクリーンショットを 1 個〜数個張り付けたり、1 行〜数行程度のコメントを付加したりしたものであり、概ね、各静止画及びこれに対応する本件各動画の内容の要約部分による本件各動画全体の内容のスムーズな把握を妨げない程度のものにとどまる。また、本件各記事の最後に記載された被告の感想は、いずれも十数行〜二十\数行程度であり、本件各動画それぞれについての概括的な感想といえるものである。
以上のとおり、本件各記事は、いずれも、キャプチャした静止画を使用 して本件各動画の内容を紹介しつつそれを批評する面を有するものではあ る。しかし、本件各記事においてそれぞれ使用されている静止画の数は約 30 枚〜60 枚程度という多数に上り、量的に本件各記事のそれぞれにおい て最も多くの割合を占める。また、本件各記事は、いずれも、静止画と要 約等とが相まって、4分程度という本件各動画それぞれの内容全体の概略 を記事の閲覧者が把握し得る構成となっているのに対し、本件各記事の最\n後に記載された投稿者の感想は概括的なものにとどまる。 以上の事情を総合的に考慮すると、本件各記事における本件各動画の利 用は、引用の目的との関係で社会通念上必要とみられる範囲を超えるもの であり、正当な範囲内で行われたものとはいえない。 したがって、本件各記事による本件各動画の利用は、適法な「引用」(法 32条1項)とはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 争点(2)(時事の事件の報道の抗弁の成否)について
被告は、本件各記事における本件各動画の利用は、社会において有用で 公衆の関心事となりそうな新しい事業を計画している一般企業家が存在す る事実及びその事業計画に対する投資家の判断・評価という近時の出来事 を公衆に伝達することを主目的とするものであり、時事の事件の報道(法 41 条)に当たる旨を主張する。 しかし、そもそも、本件各動画は、その内容に鑑みると、一般企業家が 投資家に対して事業計画のプレゼンテーションを行い、質疑応答等を経て、 最終的に投資家が出資の可否を決定するプロセス等をエンタテインメント として視聴に供する企画として制作されたものというべきであって、それ 自体、「時事の事件」すなわち現時又は近時に生起した出来事を内容とする ものではない。本件各記事は、前記認定のとおり、このような本件各動画 の内容全体の概略を把握し得るものであると共に、これを視聴した被告の 概括的な感想をブログで披歴したものに過ぎず、その投稿をもって「報道」 ということもできない。 したがって、本件各記事は、そもそも「時事の事件の報道」とは認めら れないから、適法な「時事の事件の報道のための利用」(法 41 条)とはい えない。この点に関する被告の主張は採用できない。
ウ 争点(3)(権利濫用の抗弁の成否)について
被告は、原告が「切り抜き動画」制作者による本件各動画の拡散を積極 的に利用して原告チャンネルの登録者数の増加を図り、実際にその恩恵を 享受しているにも関わらず、被告に対して本件各動画の著作権を行使する ことは権利の濫用に当たる旨を主張する。 しかし、証拠(甲 29)及び弁論の全趣旨によれば、原告が利用する「切 り抜き動画」とは、原告が、特定のウェブサイトで提供されるサービスを 通じて、原告チャンネル上の動画をより個性的に編集して自己のチャンネ ルに投稿することを希望するクリエイターに対し、その収益を原告に分配 すること等を条件に、当該動画の利用を許諾し、その許諾のもとに、クリ エイターにおいて編集が行われた動画であると認められる。他方、弁論の 全趣旨によれば、被告は、本件各動画の利用につき、原告の許諾を何ら受 けていないことが認められる。
そうすると、原告が「切り抜き動画」の恩恵を受けているからといって、 被告に対する本件各動画に係る原告の著作権行使をもって権利の濫用に当 たるなどと評価することはできない。他に原告の権利濫用を基礎付けるに 足りる事情はない。したがって、この点に関する被告の主張は採用できない。
2 争点(4)(原告の損害及びその額)
(1) 「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」
ア 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、映像の使用料又は映像からキャ プチャした写真の使用料に関し、以下の事実が認められる。
(ア) 映像からキャプチャした写真の使用料
NHK エンタープライズが持つ映像・写真等に係る写真使用の場合の素 材提供料金は、基本的には、メディア別基本料金及び写真素材使用料に より定められるところ(更にこの合計額に特別料率が乗じられる場合も ある。)、使用目的が「通信(モバイル含む)」の場合の基本料金は 5000 円(ライセンス期間 3 年)、写真素材使用料は、「カラー」、「一般写真」、 「国内撮影」の場合、1 カットあたり 2 万円とされている(甲 12)。 なお、共同通信イメージズも写真の利用料金に関する規定を公表して\nいるが(乙 12)、ウェブサイト利用についてはニュースサイトでの使用 に限ることとされていることなどに鑑みると、本件においてこれを参照 対象とすることは相当でない。
(イ) 映像の使用料
・・・・
イ 本件各動画については、前記「切り抜き動画」に係る利用許諾と原告へ の収益の分配がされていることがうかがわれるものの、その分配状況その 他の詳細は証拠上具体的に明らかでない。その他過去に第三者に対する本 件各動画の利用許諾の実績はない(弁論の全趣旨)。そこで、原告が本件各 動画の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(法 114 条 3 項)を算定するに当たっては、本件各動画の利用許諾契約に基づく利用料 に類するといえる上記認定の各使用料の額を斟酌するのが相当である。 被告による本件各動画の使用態様は、本件各動画をキャプチャした本件 静止画を本件各記事に掲載したというものである。そうすると、その使用 料相当額の算定に当たっては、映像からキャプチャした写真の使用料を定 める NHK エンタープライズの規定(上記ア(ア))を参照するのが相当とも 思われる。もっとも、当該規定がこのような場合の一般的な水準を定めた ものとみるべき具体的な事情はない。また、本件各記事は、いずれも、相 秒以上の部分について 500 円(いずれも 1 秒当たりの単価)である(甲 21)。
・・・
当数の静止画を時系列に並べて掲載すると共に、各静止画に補足説明を付 すなどして、閲覧者が本件各動画の内容全体を概略把握し得るように構成\nされたものである。このような使用態様に鑑みると、本件静止画の使用は、 映像(動画)としての使用ではないものの、これに準ずるものと見るのが むしろ実態に即したものといえる。
そうである以上、原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべき金 銭の額に相当する額(法 114 条 3 項)の算定に当たっては、映像の使用料 に係る各規定(上記ア(イ))を主に参照しつつ、上記各規定を定める主体の 業務や対象となる映像等の性質及び内容等並びに本件各動画ないし原告チ ャンネルの性質及び内容等をも考慮するのが相当である。加えて、著作権 侵害をした者に対して事後的に定められるべき、使用に対し受けるべき額 は、通常の使用料に比べて自ずと高額になるであろうことを踏まえると、 原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額 (法 114 条 3 項)は、合計 200 万円とするのが相当である。
ウ これに対し、被告は、原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべ き金銭の額に相当する額は著作権の買取価格を上回ることはないことを前 提とし、本件各動画の著作権の買取価格(3 万円)のうち本件各記事にお いて静止画として利用された割合(2%)を乗じたものをもって、原告の受 けるべき金銭の額である旨を主張する。 もとより、著作物使用料の額ないし使用料率は、当該著作物の市場にお ける評価(又はその見込み)を反映して定められるものである。しかし、 その際に、当該著作物の制作代金や当該著作物に係る著作権の譲渡価格が その上限を画するものとみるべき理由はない。すなわち、被告の上記主張 は、そもそもその前提を欠く。 したがって、その余の点につき論ずるまでもなく、この点に関する被告 の主張は採用できない。
(2) 発信者情報開示手続費用
本件のように、ウェブサイトに匿名で投稿された記事の内容が著作権侵害の不法行為を構成し、被侵害者が損害賠償請求等の手段を取ろうとする場合、権利侵害者である投稿者を特定する必要がある。このための手段として、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律により、発信者情報の開示を請求する権利が認められているものの、これを行使して投稿者を特定するためには、多くの場合、訴訟手続等の法的手続を利用することが必要となる。この場合、手続遂行のために、一定の手続費用を要するほか、事案によっては弁護士費用を要することも当然あり得る。そうすると、これらの発信者情報開示手続に要した費用は、当該不法行為による損害賠償請求をするために必要な費用という意味で、不法行為との間で相当因果関係のある損害となり得るといえる。本件においては、前提事実(5)のとおり、原告は、弁護士費用を含め発信者情報開示手続に係る費用として 167 万 440円を要したが、発信者情報開示手続の性質・内容等を考慮すると、このうち20万円をもって被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2022.12.17
令和3(ワ)22940 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年10月28日 東京地方裁判所
これを本件についてみると、前記前提事実によれば、キャタピラン+等は、 裁判所が本件特許権を侵害すると判断したキャタピラン等を設計変更したも のであり、前記2のとおり、少なくともキャタピラン+等については裁判所 が本件特許権を侵害するものではないと判断するにもかかわらず、本件通知 書には、キャタピラン+等は本件特許権を侵害していると考えているなどと 記載されていることが認められる。そうすると、本件通知書の内容は、裁判 所においてキャタピラン+等が本件特許権を侵害しない旨の判断を示す前に 当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知するものとして、不正競争防止 法2条1項21号にいう「虚偽の事実」を含むものと認めるのが相当である。
これに対し、被告らは、本件通知書は、「通知人らが保有する本件特許権 を侵害していると考えております。」として単に被告Aの主観的見解を述べ たものにすぎないから、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」 を含まないと主張する。しかしながら、法的な見解を述べるものであっても、 公正な競争を阻害するものであり、上記にいう「虚偽の事実」に含まれると 解すべきことは、上記において説示したとおりである。そもそも、本件通知 書では、キャタピラン+等についても販売の即時停止及び損害賠償額の算定 に関する資料の開示まで求めているのであるから、単に主観的見解を述べた という被告らの主張は、当を得ないものである。そうすると、被告らの主張 は、後記4において違法性判断の考慮事情とされるのは格別、上記判断を左 右するに至らない。
2022.12.17
令和2(行ケ)10120 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年11月9日 知的財産高等裁判所
(1) 原告は,前記1(4)の本件ウェブページの記載を基に,本件商標が本件要証 期間中に,原告の商品である「Packard Bell Easy Note TK37 シリーズ」の本件液晶パ ネルを販売するために使用されていると主張する。 また,前記1(4)によると,本件ウェブページには,「Amazon.co.jpで の取り扱い開始日」が,本件要証期間中の平成29年8月8日と記載されているこ と,原告が販売する商品には,「Packard Bell Easy Note TK37 シリーズ」があること (甲23)が認められる。
(2) しかし,本件証拠上,CHIKAZOが本件商標権について,「商標権者, 専用使用権者,通用使用権者」(本件商標権者等)に当たると認めることはできない のはもとより,本件商標権者等といかなる関係にある者であるかは全く明らかでは ない。
また,CHIKAZOは,自らを米国からの直輸入品を扱う輸入業者であるとし ている(前記1(4))ところ,原告は,米国において,製品を販売しているとは認め られないこと(前記1(1),(2)),原告からCHIKAZOに原告の商品が流通した経 路が本件において全く明らかになっていないことを考慮すると,本件ウェブページ には,「Packard Bell Easy Note tk37 シリーズ 15.6」等の表示があるものの,本件ウェブページを用いてCHIKAZOが販売していた「Packard Bell Easy Note TK37 シ リーズ」が,原告の製品であるかどうかは本件の証拠上,明らかでないというほか ない。このことは,Amazonサイトにおいては,販売業者に,詐欺行為がないようにする制度を構\築し,ブランド名を使用する際のポリシーを定めていること(前記1(4))など前記1認定の事実によっても左右されない。 そうすると,仮に,本件ウェブページにおいて,本件商標が使用されているとし ても,上記のとおり,本件商標権者等との関係が全く不明であり,しかも,販売し ている商品も不明である商標の使用をもって,本件商標権者等による本件商標の使 用を認めることはできない。
(3) 以上によると,原告は,本件要証期間内に,日本国内において,商標権者, 専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件指定商品について,本件商標の 使用をしていることを証明したとは認められないから,本件指定商品に係る本件商 標登録は,取り消されるべきである。 なお,原告の主張するFashion Walker事件判決は,流通業者が, ウェブサイトなどを通じて,商標の通常使用権者の商品を販売していたことが認定 された事案であり,本件とは,事案を異にする。 3 原告は,被告の本件審判請求が信義則に反し権利の濫用であると主張する。 前記2のとおり,商標法50条は,一定期間使用されていない商標については, 商標権者等の業務上の信用の維持を図る必要はない上,かえって国民一般の利益を 害することになるため,第三者による商標登録の取消請求を認めたものであると解 される。
そうすると,一定期間使用していない商標について,第三者が,それと同一又は 類似する商標を商標登録することを目的として,商標法50条により,商標登録の 取消しを求めたとしても,商標権者等の商標登録を維持する必要性が認められない 以上,当該第三者が,商標権者等の登録商標の使用をあえて妨害するなどの特段の 事情がない限り,その商標登録の取消請求が信義則に反するとか権利濫用になると 認めることはできない。 本件において,前記1のような事実関係が認められるとしても,被告が,原告の 登録商標の使用をあえて妨害するなどの特段の事情があるとは認められないから, 被告の本件審判請求が信義則に反するとか権利濫用になると認めることはできない。
2022.12.17
令和1(ワ)11484 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年12月8日 大阪地方裁判所
(3) 原告商品の形態がありふれた商品形態であるかについて
原告商品の形態と前記(2)の各商品の形態とを対比すると、モアプレッシャー及 びパワーズドクターは、男性用下着であって、そもそも需要者が異なる別種の商品 であり、特に構成態様 A に係る胸部及びアンダーバストの形状が大きく異なる。 また、エクスレンダー、MONOVO マッスルプレス、エーユードリーム、パワー ズドクターは、いずれも、構成態様 B に係る腹部の形状について縦に3本の着圧部 ないし線を設けており、縦に1本のみ着圧部を設ける原告商品とは大きく外観が異 なる。 そして、これらの相違は、商品の正面視において一見して明らかであり、需要者 の注意を惹く特徴的な部分といえ、商品全体としての印象が異なるから、原告商品 は、同種の商品とは異なる形態を有しているものであり、原告商品の形態はありふ れたものとはいえない。
被告は、「腹筋の割れを看者に感得せしめるようにした形態」が同種の商品にあ りふれており、腹直筋をモチーフにして腹筋の割れを6つにするか8つにするかを 選ぶ程度であれば改変の着想はたやすく、改変の程度は小さく、改変によって形態 上の特徴がもたらされないと主張する。 しかしながら、腹筋の割れを表現する形態は多様であり、被告の主張する同種の\n商品は、前記のとおりいずれも原告商品とは大きく異なる形状を採用しているか ら、原告商品の形態と同種の商品の形態との相違の程度が小さく、形態上の特徴が もたらされていないとはいえない。 そうすると、原告商品の形態はありふれたものではなく、不正競争防止法2条1 項3号において保護される商品形態に当たるというべきである。
・・・
4 損害額(争点3)について
(1) 不正競争防止法5条1項により推定される損害額
ア 原告商品の単位数量当たりの利益の額
証拠(甲27〜29)によれば、原告が平成30年4月に輸入した原告商品(商 品コード 0-24325-001 のシックスパックシェイプインナーM 及び商品コード 0-2432 5-002 のシックスパックシェイプインナーL)の仕入れ値は、1万1088枚で37 2万7997円であり、輸入に係る通関手数料、運搬料等は、11万9620円、 関税、消費税、地方消費税は、61万4428円であるから、経費の合計は446 万2045円であると認められる。また、証拠(甲24の7)によれば、当該原告 商品と同種商品11万6914枚の売上総額は、9543万2759円であると認 められる。そうすると、原告商品の単位数量当たりの利益の額は、413円(≒ (9543万2759円/11万6914枚×1万1088枚−446万2045 円)/1万1088枚)と認められる。
原告は、平成30年4月に輸入した原告商品と異なる商品コード、商品名の商品 も含めた売上から単位数量当たりの利益の額を算出しているが、原告が明らかにし ている経費は、前記輸入した原告商品に係るもののみであり、その余の商品の経費 は明らかではないから、採用できない。 また、被告は、原告主張の売上額から商品原価のほか、輸送、配送費等の一切の 変動費を控除すべきと主張するが、前記のとおり、通関手数料のほか、運搬料等も 経費として算入されており、これらのほかに具体的に計上すべき変動経費があると は認められないから、前記認定を妨げるものではない。
イ 被告商品の譲渡数量
証拠(乙33)によれば、被告商品の譲渡数量は1万6096枚であると認めら れる。 原告は、被告商品の譲渡数量が5万4000枚であると主張するが、証拠(乙2 8〜32)によれば、被告が輸入した被告商品は1万7700枚であったことが認 められるから、被告商品の販売数量がこれを上回ることは考え難く、うち、令和2 年2月3日に納品された1500枚は、本件訴状送達日より後に納品されたもので あるから、被告が販売していないと主張しているものであって、これを差し引いた 1万6200枚は、前記譲渡数量と整合するものである。原告が被告商品を多数販 売した卸売先として20社を挙げて調査嘱託をした結果においても、およそ原告の 主張するような多数の譲渡数量を窺わせる販売数の回答はなく、むしろ、被告主張 の譲渡数量に沿う少数の販売数の回答にとどまっていることからすれば、被告商品 の譲渡数量が1万6096枚を超えるものとは認められない。
ウ 販売することができないとする事情
(ア) 市場の非同一性
証拠(甲1〜9)によれば、原告商品は、通販カタログや広告チラシに掲載され て販売されているのに対し、被告商品は、通販カタログにも掲載されているが、主 にインターネット上の通販サイトで販売されていたことが認められる。 被告は、インターネットの通販サイトで被告商品を購入しようとする者は、被告 商品がない場合でも、カタログ販売の原告商品を購入したとはいえないと主張する が、インターネットの通販サイトで被告商品を購入しようとする者のうち、通販カ タログを見ない者がどの程度存在するのかは明らかではなく、部分的に販売するこ とができないとする事情に当たり得るとしても、この点から市場が完全に異なると まではいえないというべきである。 他方で、証拠(甲1〜9)によれば、原告商品の小売価格は1980円である が、被告商品の小売価格は1280円であり、明らかな価格差がある。 原告は、原告商品の模倣である被告商品には商品開発の費用を要しないから、価 格差を販売することができないとする事情に含めるのは公平を害すると主張する が、販売することができないとする事情は、被告の不正競争と原告商品の販売減少 との因果関係を阻害する事情であるから、被告商品が廉価であることが当該事情に 当たることは明らかである。
(イ) 競合品の存在
前記1(2)のとおり、原告商品及び被告商品と同様に腹直筋(シックスパック) をイメージした商品が複数存在しており、エクスレンダー、MONOVO マッスルプ レス及びエーユードリームは、女性用下着として、原告商品及び被告商品と同種の 競合品ということができる。 原告は、これらの他社商品は、いずれも全体として原告商品や被告商品と形態が 異なっており、競合品に当たらないと主張するが、原告商品や被告商品と当該他社 商品は、商品としての形態の相違が需要者に認識できる程度に異なっているにすぎ ず、構成態様 B の具体的な形状以外はおおむね共通する類似商品であって、証拠 (甲1〜9、乙18)によれば、いずれもトレーニング効果や腹部の引き締め効果 を謳っている商品であって、市場において競合する商品であることは明らかであ る。
また、競合品は、証拠(乙18)によれば、エクスレンダーだけで販売枚数が7 0万枚を超えているとされているのであって、原告商品の累計販売枚数が12万0 628枚(甲24の7)であることと比較すると、原告商品の市場におけるシェア は低く、市場における競合品は、原告商品よりもはるかに多いものといえる。 そうすると、被告商品が存在しなかったとすれば、相当数の需要者が原告商品で はなく競合品を購入したものと考えられるから、競合品の存在は、原告が譲渡数量 の一部を販売することができないとする事情に当たるというべきである。
(ウ) 被告の営業努力
被告は、営業交渉により広く販路を拡大し、人気のダイエット整体師を広告等に 用い、展示会に出展するなどの販売努力をしたと主張する。 しかしながら、営業交渉や展示会の具体的な内容は明らかではなく、通常行われ る営業活動と異なるものとは認められず、ダイエット整体師の広告がどの程度販売 に結び付いているのかも不明であるから、これらの営業努力を販売することができ ないとする事情に当たるということはできない。
(エ) 以上によれば、本件においては、原告が譲渡数量の一部を販売することが できない事情があり、25%の推定覆滅を認めるのが相当である。
エ 損害額 以上によれば、被告の不正競争行為による原告の損害額は、498万5736円 (=413円×1万6096枚×0.75)と認められる。
2022.12.17
令和2(ネ)10017 商標権侵害差止等本訴,虚偽事実告知・流布行為差止反訴請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年11月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 前記(1)の事実を前提として検討するに、当裁判所は、控訴人が、被控訴人 標章2、5、9、10、12の使用に対して、本件商標権を行使することは権利の 濫用に当たるものの、「守半總本舗」の文字からなる被控訴人標章1、3、4、6 〜8、11の使用に対して本件商標権を行使することについては、権利濫用に当た らないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
・・・
イ 被控訴人標章1、3、4、6〜8、11の使用について
(ア) 前記(1)エ(エ)のとおり、被控訴人は、平成18年から新たに「守半總本舗」 という商号及び標章を使用するようになったものであるが、「總本舗」とは、「ある 特定の商品を製造・販売するおおもとの店」を意味する語であり(甲73)、その ような語を「守半」に結合させた「守半總本舗」は、従前、Eや被控訴人がしてい た「守半」の商号や標章の使用とはその意味合いを異にする。 すなわち、前記(1)ア、ウ〜オからすると、従前、控訴人ら及び被控訴人の三者 間では、守半本店(補助参加人)が「本店」という中心的な地位を占める屋号、商 号を一貫して用いており、控訴人及び被控訴人もそれを是認してきたということが できる。しかし、被控訴人が上記のような意味合いを持つ「總本舗」を「守半」に 結合させた「守半總本舗」の商号や標章を用いた場合、取引者、需要者に対し、あ たかも被控訴人が三者の中で新たに「本店」としての地位を獲得したかのような印 象を与えることとなり、平成18年以前に長年にわたって構築されていた三者の関係性を変質させるものといえる。\nそうすると、被控訴人によって平成18年以降、開始された「守半總本舗」の商 号・標章の使用は、本件商標権の取得以前から、長年にわたってEや被控訴人によ って行われてきた「守半」標章の使用とは、社会通念上、同一に考えることはでき ない。
(イ) 被控訴人は、「守半總本舗」という商号や標章の使用について、「本店」であ る補助参加人の当時の代表者であるAから承諾を得たと主張するが、Aはその事実を否定しており、また、被控訴人代表\者は、原審において上記主張に沿う供述をしたものの、Aから承諾を得た時期という重要な点について供述内で変遷しており、 直ちに信用することができない。また、補助参加人が異議を述べなかったというこ とから直ちに承諾があったと認めることはできない。そうすると、被控訴人の上記 主張は採用できない。 そして、仮に「守半總本舗」の使用について補助参加人の承諾があったとしても、 そのことから直ちに、被控訴人による「守半總本舗」の使用に対する本件商標権の 行使が権利濫用になるということはできない。
すなわち、「守半」の標章は守屋半助の開業した守半本店の事業に起源を持つも のであり、補助参加人は、守半本店の事業を承継したものであるが、「守半」標章 の知名度や信用が、需要者や取引者から見て、守屋半助の開業以来、三者の中で終 始、守半本店(補助参加人)にのみ集中的に帰属するような状況にあったのかは証 拠上必ずしも明らかではない。むしろ、前記(1)ク及び前記ア(ア)のとおり、控訴人 や被控訴人が、独自の立場で営業を行い、それによっても「守半」標章の知名度や 信用が蓄積されてきたと考えられることからすると、補助参加人が、控訴人ら及び 被控訴人の三者内において「守半」標章の使用許諾をする法的権限を、守半本店の 事業を承継したとか、代表者と守屋半助との間に血縁関係があるといった理由のみによって永続的に保持すると解するのは相当ではなく、平成18年当時、三者の中\nで補助参加人がそのような特別な権限を持っていたというためには、その時点にお いて、「守半」標章の知名度や信用が、需要者や取引者から見て、補助参加人にの み集中的に帰属するような状況にあったか、三者間で補助参加人がそのような権限 を持つことが明示又は黙示に合意されていたか、控訴人及び被控訴人が、補助参加 人が「守半」標章の使用を第三者に許諾することに同意していたなどの事情を要す るものと解されるところ、上記当時、これらの事情があったと認めるに足りる証拠 はない。
そして、前記(1)エ、オ、ク及び前記ア(ア)のとおり、三者がそれぞれの立場から 営業活動を行って「守半」標章の知名度と信用の獲得に貢献しているという客観的 状況があり、かつ、控訴人が昭和55年に本件商標権を取得しており、被控訴人が 遅くとも平成18年11月頃までには控訴人が本件商標権を取得していることを認 識していたこと、その頃、控訴人が被控訴人に対し、「守半總本舗」の使用に関し て異議を述べていたことからすると、被控訴人が「守半總本舗」の使用について、 本件請求における不法行為期間(対象期間)の始期である平成20年以降も継続す るためには、補助参加人の承諾のみでは足りず、商標権者たる控訴人の承諾も得る べきであったと解すべきである。しかし、前記(1)エ(エ)のとおり、被控訴人は、控 訴人の承諾を得ることなく、「守半總本舗」の使用を継続したものであった。
◆判決本文
原審はこちら。
2022.12.17
令和3(ワ)9530 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年11月28日 大阪地方裁判所
(2) 「中央部が突出する概略円錐状」の意義について
ア 構成要件Dは、「該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」と規定しているところ、「該複数のコニカルビット群」とは、3条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに取り付けられたコニカルビットを指す(構\成要件C)から、構成要件Dは、3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットのみにより、中央部が突出した概略円錐状に形成されていることを要すると解される。その他、本件発明に係る請求項において、「中央部が突出する概略円錐状」に関する記載はない。\n
イ 本件明細書には以下の内容が示される。
従来の掘削ヘッドは、複数の小形ビットが台金に固着されていたので、掘削中 に岩石等に当たった際、刃先が逃げることができず、損傷を受けやすいという問 題点や掘削によって生じた繰粉が穴底からうまく排出されにくいという問題点 があった(【0003】)。このような問題点を解決するものとして、直径方向に対 向するように設けられた2条の螺旋翼を有する掘削刃の螺旋翼の周縁部及び下 端に多数の小形ビットを取り付けたスクリューオーガ用掘削刃がある。これには、 軸回りに回転自在な小形のビット(コーン刃)が設けられていて、岩石等に当た った時に当該コーン刃が回転して逃げることができるため、損傷しにくいという 利点があるが、2条の螺旋翼が直径方向に対向するように設けられ、これら2条 の螺旋翼にそれぞれ設けた小型ビットで掘削を行うものであるから、掘削中に岩 石等に遭遇したときは、2条の螺旋翼に設けたビットが当該岩石に当たるたびに 断続的な衝撃を受け、スクリューオーガ装置全体が上下に振動して、円滑な掘削 ができなくなるおそれがあるほか、螺旋翼自体が先端側の外径が小さくなるよう に全体として円錐状の尖った形状となっているので、芯ぶれにより、掘削される 穴が曲がりやすいというおそれもある(【0004】)。本件発明は、掘削中に岩石 等に当たってもビットの刃先が損傷しにくく、断続的な衝撃をうけにくく、しか も穴曲がりが生じにくい掘削ヘッドを提供することを目的とし、基部がスクリュ ーオーガロッドに取り付けられる基軸の外周部に、外径の等しい3条の螺旋翼が 設けられ、これら3条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに、円錐状の 尖った刃先部を有する複数のコニカルビットが軸回りに回転自在にそれぞれ取 り付けられ、該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に 形成されていることを特徴とする構成をとるものである(【0005】【0006】)。 3条の螺旋翼が並列に設けられていることにより、掘削中に岩石等の掘削しにく い物体に当たっても、断続的な衝撃が比較的小さくてすむようになるとともに、 胴部における3条の螺旋翼の外径をほぼ一定にしておくことにより芯ぶれが生 じにくくなる結果、穴曲がりが少なくなるという効果を奏するものである(【0006】 【0007】【0020】)。これらの本件明細書の記載内容に加え、図面(【図1】〜 【図4】)に照らすと、外径の等しい3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複 数のコニカルビット群により、「中央部が突出する概略円錐状に形成されている こと」の技術的意義は、胴部における3条の螺旋翼の外径を変えることなく、該 複数のコニカルビット群により、基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状 の形状にすることで、穴曲がりが生じることを防ぎつつ、掘削効率を高めること にあるものと認められる。 また、本件明細書には、発明の実施形態に関して、「小型ビット20,…は、 それぞれが取り付けられている螺旋翼10の傾斜方向にほぼ沿うように傾けて 設けられている。また、前記ヘッド15には複数(図示例では3個)の小型ビッ ト20,…が設けられていて、掘削ビットの先端部は、これら小型ビット群によ って側面視概略円錐状を呈している。」(【0011】)、「掘削ヘッド1の先端部 には、全体形状が概略円錐状となるように多数のコニカルビット20,…が設け られているので、これらビットにより効率よく掘削が行われる。」(【0016】) との記載もある。
ウ 証拠(乙1、2)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成19年7月3 日付けの拒絶理由通知書(乙1)により、特許庁から、本件発明は、引用発明1 及び2に基づき進歩性を欠くとの拒絶理由を通知されたことに対し、構成要件D\nに該当する部分を付加して補正した上で、意見書(乙2)において、引用発明1 は、螺旋翼が2条で、円周方向における螺旋翼同士の間隔が大きく、ヘッド先端 部のビットの密度が低くなり、しかもヘッド先端部のビットの先端はほぼ同一平 面状に位置していて、仮想先端面が平板状を呈しているのに対し、本件発明は、 3条の螺旋翼の先端部に複数のコニカルビットが取り付けられ、ヘッド先端部が、 全体として中央部が突出する概略円錐状の外形に形成されているから、引用発明 1と本件発明とは構成が大きく相違している旨を主張したことが認められる。\nこのような出願経過に照らすと、原告は、構成要件Dに該当する部分を付加し\nて補正することで、3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビッ トにより、ヘッド先端部が全体として中央部が突出する概略円錐状の外形である ことを特定したものと解される。
エ 前記アないしウのとおり、構成要件C及びDの文言、本件明細書の内容、\n「中央部が突出する概略円錐状に形成されていること」の技術的意義、出願経過 に照らすと、「中央部が突出する概略円錐状」とは、3条の螺旋翼の先端部に取 り付けられたコニカルビットのみにより、側面視を含む全体形状において基軸先 端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしていることを意味しているものと 解するのが相当である。本件明細書には、発明の実施形態として、3条の螺旋翼 の先端側に、概略円錐状のヘッド15が、基部を基軸2に固定されており、ヘッ ド15に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を 呈しているものが示される(【0011】)ことから、発明の実施形態には、3条の 螺旋翼の先端部に取り付けられたコニカルビットが側面視を含む全体形状にお いて基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしており、かつ、ヘッド1 5に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を呈す る形態を含むものと解する余地があるが、前記アの構成要件C及びDの文言に照\nらすと、「中央部が突出する概略円錐状」の上記解釈は左右されない。
(3) 被告各製品について
ア 被告製品1
争いのない事実、証拠(甲5、乙10の1〜3)及び弁論の全趣旨によれば、 被告製品1は、その3条の螺旋翼20の先端部に設けられた3〜4基のコニカル ビット30により、側面視(基軸10先端方向を上に向けた場合。以下同じ。) において、中央部が平坦又は間隙のある、浅いハ字状に線が描かれていること、 全体形状として、基軸10から放射状に3本の緩やかな曲線(ほぼ直線)が描か れていることが認められる。
・・・
カ 以上のとおり、被告各製品の3条の螺旋翼の先端部に取り付けられたコニ カルビットは、いずれも、側面視を含む全体形状において、直線、緩やかな曲線 又は点を形成するにすぎず、同コニカルビットのみにより、基軸先端方向に向か って径が小さくなる円錐状を形成しているとはいえず、構成要件Dを充足すると\nは認められない。
(4) 原告の主張について
原告は、「中央部が突出する概略円錐状」とは、効率よく安定した掘削を行う という本件発明の技術的意義を有するか、これと同一の作用効果を奏するもの、 すなわち、3条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットが「概 略錐面状」に並んで配置されることを意味し、当業者は、本件明細書の記載から そのように理解する旨を主張し、当業者の認識や技術常識を裏付ける証拠として、 公開特許公報(甲23の1〜12)、パンフレット等(甲24の1〜3)、アン ケート結果(甲25の1〜8)、大学教授の意見書(甲28の1、29の1)を 提出する。
しかし、前記(2)のとおり、構成要件Dは「該複数のコニカルビット群により、\n中央部が突出する概略円錐状を形成」と規定しており、本件明細書や出願経過等 をみても、コニカルビットが概略錐面状に並んで配置していることと解すべき記 載等はないから、同構成要件を充足するには、コニカルビット群のみにより、(中\n央部が突出する)概略円錐状を形成する必要がある。 原告は、前記各証拠は、回転式の土木用掘削ヘッドにおいて、コニカルビット、 掘削刃などの掘削ビット類の配列、又は複数の掘削ビット類の全体形状を、当業 者は「概略円錐状」と表現することを示すものである旨述べる。しかし、原告が\n提出する公開特許公報(甲23の1〜12)に係る特許の中には、本件特許の出 願後に出願又は公開されたものが含まれており、それらは本件特許出願時の当業 者の認識を裏付けることにはならない。この点は措くとしても、これらの公報の 内容は、掘削爪等の配置、スクリュー刃全体、ヘッドの先端やヘッド部分全体、 掘削面や地盤改良体等の形状が、それぞれ円錐状であるなどと個別に特定するも のであり、これらの公報全体をみても、回転式の掘削ヘッドにおいて掘削ビット 類の配列や全体形状が一般的に「概略円錐状」と表現されているとは認められな\nい。そして、少なくとも、これらの公報の中に、被告各製品のようにコニカルビ ット(3条の螺旋翼の先端部に取り付けられたもの)が並んでいる形状を指して (中央部が突出する)概略円錐状と表現することを示すものはない。また、パン\nフレット等(甲24の1〜3)には、「円錐ヘッド」や「円錐型ヘッド」として、 螺旋翼の外周部から中心軸に近づくにつれてビットが先端に向かって高い位置 に取り付けられている掘削ヘッドの写真が掲載されているものの、どの部分を指 して円錐形状と表現しているかについては明らかでないし、被告各製品のように\nコニカルビットが並んでいる形状そのものを指して概略円錐状と表現するもの\nとも認められない。さらに、アンケート結果(甲25の1〜8)については、8 名の回答者の中に本件特許の発明者や同発明者の出身会社の代表者、原告と何ら\nかの取引関係があると考えられる者が含まれている(甲25の1、2、8、弁論 の全趣旨)など、アンケート対象者の中立性等に疑義があることに加え、質問の 形式も、被告各製品の螺旋翼先端部のコニカルビット群の形状をどう表現するか\nと問うのではなく、「「螺旋翼先端部のコニカルビット群」を見て「(概略)円 錐状」と認識できますか?」と一定の結論を示唆するものであって、適切とは言 い難い。回答者は、当該質問に対して、いずれも「できる」と回答しているもの の、その理由として、「ビットの高さが違う」「外側より先端部の方が飛び出し ている」「掘削後円錐に断面がなる」「写真より(中略)円錐形状を推定・想像 が行える」「日本テクノ製のコニカルヘッドと認識した」などとコメントしてお り、コニカルビットが並んでいる形状を概略円錐状と表現した趣旨か否かが不明\nである回答が含まれているほか、理由の説明内容が区々であり、このアンケート 結果から、当業者が一般的に被告各製品のようにコニカルビットが並んでいる形 状を(中央部が突出する)概略円錐状と認識するものと理解することは困難であ る。そして、大学教授の意見書のうち、甲第28号証の1には、ヘッドが回転し たときにどのような軌跡を描いているかを立体的にイメージすれば、ビットの軌 跡でトレースされる立体的形状が円錐状に近い形になることが指摘されている が、「複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成され ている」(構成要件D)ことに、「回転する複数のコニカルビット群の軌跡によ\nり、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」ことを含むと解釈すること は文理に沿わないし、当業者が一般的に、掘削ヘッドの「複数のコニカルビット 群」との文言から、その形状(配置)をヘッドが回転したときの軌跡でイメージ することを裏付ける資料もない。甲第29号証の1には、「概略円錐状」とは、 数学的(幾何学)な意味での円錐ではなく、中央が尖った錐状立体に近い概形を 意味していることが指摘されているが、その根拠は不明である。
以上から、原告が提出する証拠は、いずれも回転式の土木用掘削ヘッドにおい て、掘削ビット類の配列又は全体形状を、当業者が「概略円錐状」と表現するこ\nとを示すものとはいえず、被告各製品のようにコニカルビット(3条の螺旋翼の 先端部に取り付けられたもの)が並んでいる形状を、当業者が一般的に(中央部 が突出する)概略円錐状と理解することを裏付けるものでもないから、原告の前 記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.12.16
令和4(ネ)10067等 損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年11月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「ウ もっとも、前記1(3)オ並びに証拠(甲69、原審証人B・5頁及び6頁) 及び弁論の全趣旨を総合すると、櫻山及び被控訴人は、平成29年1月15日に代 表取締役を退任した控訴人からの引継ぎが十\分でなかったことなど、「商標登録の 問題」とは別の理由で、同年の御歳暮に係る商品を始め平成30年の御中元の前の 時期までの商品につき、これらをカタログ等に掲載してもらうことができず、「商 標登録の問題」を理由としてカタログ等への掲載が拒否された商品は、同年の御中 元以降のものであると認められる。そうすると、三越伊勢丹が被控訴人の商品をカ タログ等に掲載しなかったことによる被控訴人の逸失利益の計算上の始期は、同年 5月1日とするのが相当である。 被控訴人は、上記逸失利益の計算上の始期は平成30年1月1日であると主張す るが、上記のとおりであるから、これを採用することはできない。
エ 以上のとおりであるから、控訴人及びAが共同して本件申請をした結果として三越伊勢丹が被控訴人の商品をカタログ等に掲載しなかったことにより被控訴人\nに生じた損害(逸失利益)の額は、合計448万円(平成30年5月1日から令和 元年8月31日まで月額28万円)であると認められる。」
・・・
また、控訴人は、上記2)のとおり主張するが、上記のとおり、一般に、百貨店の カタログを利用した販売や百貨店のインターネット販売サイトを利用した販売にお いては、販売費及び一般管理費が低廉なものに抑えられると考えられ、また、証拠 (甲67、乙イ44)及び弁論の全趣旨によると、櫻山の売上げのうちの9割以上 が三越伊勢丹に係る売上げによって占められるところ、三越伊勢丹に係る櫻山の売 上げのうちカタログ等に掲載された商品に係る売上げが占める割合は、わずか数% であると認められ、これらの事情に照らすと、仮に、カタログ等に掲載された商品 に係る櫻山の営業利益率が決算報告書(乙イ33)から算定される櫻山の全体の営 業利益率を上回るとしても、直ちに不合理であるとはいえない。 以上のとおりであるから、カタログ等に掲載される商品について被控訴人に生じ た営業上の損害(逸失利益)の額を算定するに当たっては、その基礎収入の額を甲 65に記載された額に基づいて算定するのが相当である。
(6) 控訴人は、前掲最高裁令和2年4月7日第三小法廷判決は本件の控訴人の ような立場の者にも当てはまるとして、本件訴訟において、被控訴人が別件訴訟に おける費用(印紙、郵券及び仮処分登録免許税に係る費用。以下「別件費用」とい う。)を損害として主張することは許されないと主張する。 しかしながら、控訴人は、Aと連帯して、控訴人及びAの共同不法行為(本件申請)により被控訴人に生じた損害を賠償する責任を負うところ、補正して引用する\n原判決第4の3(2)イにおいて説示したとおり、被控訴人は、別件訴訟の当事者で ない控訴人を相手方として、別件費用を訴訟費用等の確定処分を経て取り立てるこ とができないのであるから、上記最高裁判決が別件訴訟の当事者でない控訴人にも 当てはまると解するのは相当でない。
控訴人は、控訴人があずかり知らない別件訴訟において発生した別件費用を控訴 人が負担するとなると、控訴人に予測できない負担が発生するとも主張するが、控訴人は、Aと共同して本件申\請をし、これにより、本件各商標権について櫻山からAに対する商標権移転登録がされたのであるから、その結果、被控訴人が、本件各 商標権に係る処分禁止の仮処分命令の申立て及び執行や、本件各商標権に係る商標権移転登録抹消登録手続請求訴訟の提起等を余儀なくされるのは当然のことである。\nしたがって、別件費用に係る被控訴人の損害は、控訴人及びAの共同不法行為(本 件申請)と相当因果関係のある損害であって、控訴人に別件費用の支払義務を負担させることは、控訴人に予\測できない負担を負わせるものではない。また、控訴人は、控訴人が本件訴訟において別件費用を負担するとなると、Aも 本件訴訟において別件費用を負担することになり、上記最高裁判決を潜脱すること になると主張するが、控訴人が本件訴訟において別件費用を負担することは、Aも 本件訴訟において別件費用を負担することを意味しない。 さらに、控訴人は、被控訴人はAにつき別件訴訟に係る訴訟費用等の確定処分を 経て別件費用に係る債務名義を取得することができるのであるから、控訴人につい てまで別件費用に係る債務名義を取得できるとなると、被控訴人が債務名義を二重 に取得することになって不当であるとも主張するが、共同不法行為に基づいて不真 正連帯債務を負う複数の者について、同一の損害に係る複数の債務名義が存在する ことは、何ら不当なことではない。
◆判決本文
1審はこちら。
2022.12.16
令和4(ネ)10008 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(4) 控訴人らによる訂正の再抗弁の主張について
当裁判所は、令和4年9月22日の当審第1回口頭弁論期日において、控訴人らが同月5日付け控訴人ら第4準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが、その理由は、以下のとおりである。\n
ア 一件記録によれば、1)被控訴人は、令和元年12月19日の原審第1回弁論準備手続期日において、本件発明5に係る本件特許に乙8を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由(本件の争点4−1及び4−3)等が存在するとして無効の抗弁を主張し、令和3年7月20日の原審第3回弁論準備手続期日において、本件発明1に係る本件特許に乙8を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由が存在するとして無効の抗弁を追加して主張したこと、2)その上で、控訴人らが、同年9月29日の原審第4回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述した後、同日、原審が、口頭弁論を終結し、同年12月9日、被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めて控訴人らの請求を棄却する原判決を言い渡したこと、3)その後、控訴人らは、当審において、令和4年7月21日に書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったことが認められる。
イ 以上を前提に検討するに、本件特許権の侵害論に関する抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであるところ、控訴人らは、原審において、令和3年9月29日の原審第4回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、当審で主張する訂正の再抗弁の主張をしなかったものである。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、当審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったものであることからすると、当審における上記訂正の再抗弁の主張は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきである。そして、当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。そこで、当審は、民事訴訟法297条において準用する同法157条1項に基づき、控訴人らの訂正の再抗弁の主張を却下したものである。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和1(ワ)25121
本件特許の審決取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2022.12.13
令和4(行ケ)10041 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年10月31日 知的財産高等裁判所
原告は、前記第3の 1 のとおり、本願商標の構成中の「御守」の文字は\n御守の内容・種類を表しているにすぎず、全体的なデザインとともに一体的\nに把握されるものであるから、本願商標がその指定役務に使用される場合、 本願商標からは役務の出所識別標識としての「オマモリ」の称呼及び「御守」 の観念は生じない旨主張する。 しかしながら、前記1(1)のとおり、御守袋の上に「御守」と表示されてい\nる本願商標は、御守袋の形状の図案それ自体からして、「御守」の観念を生じ、 「オマモリ」の称呼が生じるものといえるところ、その表面の「御守」の文\n字は、その表面中央にあって文字として記載され、かつ、文字としてはその\n記載しかない以上は、当然のこととして、当該御守袋が何であるかを示すも のというべきであり、そこからも「御守」の観念を生じ、「オマモリ」の称呼 が生じることは明らかである。そして、本願商標に係る指定役務のうち、少 なくとも、おむつ、食品、化粧品、ペット用品、ベビーオイル等を含む第3 5類の商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (以下「小売等役務」という。)について、御守が、これら商品の小売等役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又\nは時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないか ら、上記のように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼 が本願商標の当該指定役務の内容、対象そのものを示すものとは理解されな い。 このように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼が本 願商標の当該指定役務の内容、対象を示すものとはいえない以上は、これら の観念や称呼が役務の出所識別標識として生じる可能性を否定することはで\nきないから、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 商標の類否判断の誤りの主張について
本願商標の構成全体から格別の称呼、観念が生ずることはないことを前提\nとする原告の主張(前記第3の 1 ア)については、その前提に誤りがある ことは前記のとおりであるから、採用することができない。 次に、原告は、前記第3の 1 イのとおり、仮に、本願商標から「オマモ リ」の称呼、護符(御守)の観念が生じたとしても、本願商標は、全体とし て「白色の二重叶結びの紐を有し、ピンク色の桜の花弁模様を配し、『御守』 の文字を御守袋の表面に表\した赤色の御守」との印象を強く抱かせるもので あるから、本願商標と引用商標の外観上の顕著な相違から看取できる印象は、 称呼及び観念から看取できる印象を凌駕している旨主張する。
しかしながら、本願図形部分である、「白色の二重叶結びの紐、ピンク色の 花弁模様及び赤色の色彩」のうち、「白色の二重叶結びの紐」は御守袋の特徴 にほかならず、また、「ピンク色の花弁模様及び赤色の色彩」は御守袋として は格別印象に残るような形状・色彩を有するものではないから御守袋を構成\nする地模様と認識されるのがせいぜいのところであり、それらが単独で看者 に強い印象を与えるものではない。 そうすると、本願商標から生じる「オマモリ」の称呼及び護符(御守)の 観念が本願図形部分から看取できる印象に凌駕されることはない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 指定商品・指定役務の類否判断の誤りの主張について
原告は、引用商標1の指定商品の製造・販売と小売等役務の提供が同一事 業者によって行われていることは通常とまではいえないから、引用商標1の 指定商品を同指定商品に係る小売等役務を提供する事業者が製造又は販売す る商品であると誤認するおそれがあるとはいえない旨主張する。 しかしながら、ある製品の製造業者が当該製品の販売場を持つなどして、 当該販売場を置くとともに、同時に、顧客に対する当該製品の品揃え・陳列、 接客等のサービスを提供するなどして小売等役務の提供場所とし、当該製品 の販売行為を促進して最終的には当該製品の販売行為により収益を上げよう とすることは、自然な商業的取引の在り様といえ、これと異なる特殊な事情 がない限りは、通常行われることと推認されるものというべきである。
そして、引用商標1の指定商品について、その製造・販売と小売等役務の 提供が別事業者によって行われていることが通常であるとするような特殊な 事情は本件証拠からは認められず、かえって、本願商標の指定役務である「菓 子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットド ッグ、ミートパイ」の小売等役務に係る商品と、これに類似する引用商標1 の指定商品である「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除 く。)、パン」について、自社工場を持つ営業主がそれら製品を自社店舗で販 売するなど、その製造販売と小売等役務が同一営業主によって行われること がよくあるとの実情は公知の事実ともいえ、被告からも、その一例の指摘が ある(乙11ないし17)。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.12. 9
令和3(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所
一方で、本件明細書には、加工対象物の「シリコンウェハ」の表面又は\n裏面に溝が形成されていることについての記載や示唆はない。また、図1、 3、14及び15には、「切断予定ライン5」が示されているが、切断予\定 ライン5に沿った溝の記載はない。 そして、1)甲36(SEMI規格「鏡面単結晶シリコンウェハの仕様」) には、「6.1 標準ウェーハの分類」に「6.1.1.それぞれ標準化さ れたウェーハの寸法、許容寸法及びフラット・ノッチの特性は表3から表\ 9にて分類されている。」との記載があり、「6.1.2」には寸法等の特 性の異なる「鏡面研磨単結晶シリコンウェーハ」及び「鏡面単結晶シリコ ンウェーハ」(分類1.1ないし1.16.3)が掲載され(18頁)、「6. 9 表裏面目視特性」に「ウェーハは、発注仕様に規定された測定可能\な (目視または他の方法による)ウェーハの表裏面の品質要求をみたさなけ\nればならない。」、「表12 鏡面ウェーハ欠陥限度」の「2.8.11 く ぼみ」の項目の「最大欠陥限度」欄には「なし」との記載があること(4 1頁〜42頁)、2)「LSIに用いられるウェーハ表面は無ひずみで凹凸の\nない鏡面であることが必要であり…このような鏡面ウェーハは…鏡面研 磨することによって得られる」こと(「半導体用語大辞典」360頁))か らすると、本件優先日当時、半導体材料に用いられる標準仕様のシリコン ウェハは、単結晶構造であり、その表\面及び裏面に凹凸のない平坦な形状 であることが、技術常識であったことが認められる。 以上の本件明細書の記載(図1、3、14及び15を含む。)及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【0029】記載の「(A)加工対象物: シリコンウェハ(厚さ350μm、外径4インチ)」は、単結晶構造の標準\n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凹凸のない平坦な形\n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予\定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で ある。
そうすると、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合すること により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入す るものといえないから、本件明細書に記載した事項の範囲内にしたものと 認められる。 したがって、本件訂正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許 法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合するとした本 件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し、原告は、1)本件明細書には、「シリコン単結晶構造部分に前\n記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の明示\n的な記載がなく、その示唆もないのみならず、溝を形成するかしないか、 形成するとしてどこに、どのように形成するかといった観点からの記載も 示唆もないし、本件明細書を補完するものとして、図面を見ても、「シリコ ン単結晶構造部分に前記切断予\定ラインに沿った溝が形成されていない シリコンウェハ」が記載されているのと同視できるとする根拠も見当たら ない、2)本件明細書の【0027】には、「加工対象物がシリコン単結晶構\n造の場合」との記載があるだけであり、「シリコン単結晶構造部分に前記切\n断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の記載はな\nく、また、図1ないし4に示す「加工対象物1」が「シリコンウェハ」で あるとしても、どの部分が「シリコン単結晶構造部分」にあたるのか不明\nであり、「シリコン単結晶構造部分」が切断予\定ライン5に沿って存在する のかも不明である、3)【0033】は、「シリコンウェハは、溶融処理領域 を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコン ウェハの表面と裏面に到達することにより、結果的に切断される。」と記載\nしているだけであり、シリコンウェハの切断部位の形状(溝の有無)に関 係なく、溶融処理領域(改質領域)を起点としてシリコンウェハが切断で きるものであることの記載はないとして、本件訂正事項は新規事項を追加 するものでないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、前記アで説示したとおり、本件明細書の記載及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【0029】記載の「(A)加工対象物: シリコンウェハ(厚さ350μm、外径4インチ)」は、単結晶構造の標準\n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凸凹のない平坦な形\n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予\定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で あり、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと いえない。原告の挙げる1)ないし3)は、いずれも、上記判断を左右するも のではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> 減縮
>> ピックアップ対象
2022.12. 9
令和4(ネ)10033 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
法4条の趣旨は、特定電気通信による情報の流通によって権利の 侵害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密\nに配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求す ることができるものとすることにより、加害者の特定を可能にして被害者の\n権利の救済を図ることにあると解されること(最高裁平成21年(受)第1 049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676頁参照) に鑑みると、法4条1項の委任を受けた省令1号ないし8号の規定は、開示 の対象となる「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を限定的に列挙した ものと解される。以上を前提に、本件ログイン時IPアドレス等が省令5号及び8号に該当するかどうかについて判断する。
(2) 認定事実
前記前提事実と証拠(甲32、58ないし63)及び弁論の全趣旨によれ ば、以下の事実が認められる。
ア 本件各投稿の日時
本件投稿1は、令和2年11月12日午前7時52分にアカウント1を 利用して、本件投稿2は、同月7日午前4時57分にアカウント2を利用 して、本件投稿3は、同年12月18日午後7時3分にアカウント3を利 用して、本件投稿4は、同日午前10時35分にアカウント4を利用して、 本件投稿5は、令和3年3月7日午後5時52分にアカウント5を利用し て、ツイッターのウェブサイトにそれぞれ投稿された。
イ 本件訴訟に至る経緯等
(ア) 被控訴人は、令和2年11月17日、アカウント1について、控訴 人を債務者とする発信者情報開示仮処分の申立て(東京地方裁判所令和\n2年(ヨ)第22121号)をし、令和3年2月17日、アカウント1 にログインした際のIPアドレスのうち、本件投稿1の直前のログイン 時以降、控訴人が保有するIPアドレス及びそのタイムスタンプの全て の開示を命じる仮処分決定(以下「本件仮処分決定1」という。)がされ た。その後、控訴人は、本件仮処分決定1につき本案の起訴命令の申立\nてをし、同月25日、起訴命令が発せられた。 また、被控訴人は、アカウント2ないし4について、控訴人を債務者 とする発信者情報開示仮処分の申立て(令和2年(ヨ)第22125号)\nをし、同年3月2日、控訴人が保有するログイン情報のうち、侵害情報 の投稿直前のログイン時のIPアドレス及びそのタイムスタンプの開示 を命じる旨の仮処分決定(以下「本件仮処分決定2」という。)がされた。 その後、控訴人は、本件仮処分決定2につき本案の起訴命令の申立てを\nし、同月29日、起訴命令が発せられた。
(イ) 被控訴人は、前記(ア)の各起訴命令を受けて、令和3年3月3日、 原審に本件訴訟を提起した。その後、被控訴人は、同年10月12日、 アカウント5について、発信者情報の開示を求める訴えの追加的変更を した。
(ウ) 被控訴人は、本件仮処分決定1に基づき、間接強制決定を求める申\n立てをし、同月19日、間接強制決定がされた。 また、被控訴人は、本件仮処分決定2に基づき、間接強制決定を求め る申立てをし、同月24日、間接強制決定がされた。\n
(エ) 原審は、令和3年11月9日、口頭弁論を終結し、令和4年1月2 0日、原判決を言い渡した。 その後、控訴人は、同年3月4日、本件控訴を提起した。
(オ) 控訴人は、令和4年5月26日、被控訴人に対し、アカウント1に ついて、本件投稿1の直前のログイン時(日本時間令和2年11月12 日午前7時44分49秒)以降、令和4年5月24日午後3時49分5 0秒までのログイン情報に係るIPアドレス及びタイムスタンプを、ア カウント2ないし4について、本件投稿2ないし4のそれぞれ直前のロ グイン時のIPアドレス及びタイムスタンプ(アカウント2につき令和 2年11月7日午前4時46分29秒時、アカウント3につき令和2年 12月18日午前8時54分54秒時、アカウント4につき令和2年1 2月18日午前8時54分9秒時の各IPアドレス)を開示した。
(3) 本件ログイン時IPアドレス等の省令5号及び8号該当性について ア 省令5号及び8号の意義について (ア) 1)前記(1)のとおり、省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アド レス」は、「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を類型化したもの であること、2)前記(1)の法4条の趣旨に照らすと、被害者の権利行使 の観点から、開示される情報の幅は広くすることが望ましいが、一方で、 発信者情報は個人のプライバシーに深く関わる情報であって、通信の秘 密として保護されるものであることに鑑みると、被害者の権利行使にと って有益であるが不可欠ではない情報や開示することが相当とはいえ ない情報まで開示することは許容すべきではないと考えられ、このこと は、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報であっても同様 であること、3)省令5号の「侵害情報に係る」との文言を総合考慮する と、同号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」とは、侵害情報の 送信に使用されたIPアドレス又は侵害情報の送信に関連する送信に 使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために 必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当である。
次に、省令8号の「第5号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた 電気通信設備、…携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定 電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻」との文言に鑑み ると、省令8号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、「省令 5号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又はその 送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解するのが相 当である。
(イ) これに対し、被控訴人は、1)ツイッターにおいては、そのセキュリ ティの高さからログインした者が発信者であるという蓋然性が極めて高 い状況であり、特定のアカウントにログインしている以上、当該ログイ ンをした者は、発信者と同一人物であることが強く推認されるところ、 法4条の趣旨・規定ぶり、控訴人の提供するサービスの仕組みやセキュ リティの状況からすれば、ログイン情報等の開示において、発信者と投 稿者との主観的同一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求 められていないというべきであるから、ツイッターへのログイン時のI Pアドレス等は、法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に 該当する、2)本件ログイン時IPアドレス等の全面開示を認めないこと は、被控訴人の知る権利(憲法21条1項、13条、32条)を侵害し 違憲であり、「権利行使を確保するための手続を国内法において確保」し なければならないとするWIPO著作権条約14条2項の要請にも反す るから、憲法適合解釈のもと、法及び総務省令を憲法21条1項、13 条、32条に適合的に解釈し、本件ログイン時IPアドレス等を全面的 に開示すべきである、3)令和4年10月1日に施行される規則において は、投稿前のログアウト情報や投稿後のログイン情報など論理的に投稿 そのものに供された可能性がない通信情報も含めてアカウント開設から\n閉鎖までの全ての情報が理論上開示され得ることが定められ、開示対象 の発信者情報について、侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求め ておらず、通信情報が侵害情報の発信者のものと認められる場合には開 示を肯定する立場をとっていることからすると、規則施行前の省令にお いても、ログイン情報等の開示において、発信者と投稿者との主観的同 一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求められていないと いうべきである旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、法4条1項の委任を受けた省令 1号ないし8号の規定は、開示の対象となる「侵害情報の発信者の特定 に資する情報」を限定的に列挙したものと解されるところ、前記(ア)で 説示したとおり、省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」 とは、侵害情報の送信に使用されたIPアドレス又は侵害情報の送信に 関連する送信に使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を 特定するために必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当で あり、また、省令8号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、 「省令5号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又 はその送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解する のが相当であるから、ツイッターへのログイン時のIPアドレス等であ れば、省令5号及び8号に該当しないものであっても、法4条1項の「当 該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するということはできない。 そして、前記(ア)のとおり、前記(1)の法4条の趣旨に照らすと、被害 者の権利行使にとって有益であるが不可欠ではない情報や開示すること が相当とはいえない情報まで開示することは許容すべきではないと考え られ、このことは、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報 であっても同様である。
また、控訴人が挙げる憲法の規定やそれらの趣旨を考慮したとしても、 被控訴人に、法律に定められていない発信者情報の開示を求める権利が あると解することもできない。 次に、3)については、ログイン情報に相当する「侵害関連通信」につ いて規定する規則5条柱書によれば、「法第五条第三項の総務省令で定め る識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号 その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する 侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」と規定し、ログイン情報 の開示において「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に限定 しており、被控訴人が述べるように、開示対象の発信者情報について、 侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求めておらず、通信情報が侵 害情報の発信者のものと認められる場合には開示を肯定する立場をとっ ているとまでいうことはできない。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2022.12. 8
令和4(行ケ)10033 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年11月21日 知的財産高等裁判所
商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と 他人の表示との類似性の程度、他人の表\示の周知著名性及び独創性の程度、 当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目 的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取 引の実情等に照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普 通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。 商標法4条1項15号に該当する商標であっても、商標登録出願の時にこ れに該当しなければ、同号は適用されないので(同条3項)、本件において商 標登録出願がいつであるかが問題となる。
この点につき、原告は、前記第3の1(1)のとおり、商標法施行規則22条2 項は違憲違法であり、その結果、本願は商標法10条1項による商標登録出 願の要件を満たすものとなり、同条2項が規定する出願日遡及の効果が生ず るから、本件における出願日は、原々商標登録出願がされた平成26年9月 8日になる旨主張するので、以下検討する。
商標法10条1項は、「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若し くは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の 審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であって、かつ、当該商標登 録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付してい る場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登 録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。」 と定めている。
このように、分割出願においては、もとの商標登録出願の指定商品等を2 以上に分けることが当然の前提となっているから、もとの商標登録出願と分 割出願で指定商品等が重複するのを避けるため、もとの商標登録出願から分 割出願に係る指定商品等を削除する必要がある。 この点につき、平成17年最高裁判決は、「商標法10条は、「商標登録出 願の分割」について、新たな商標登録出願をすることができることやその商 標登録出願がもとの商標登録出願の時にしたものとみなされることを規定し ているが、新たな商標登録出願がされた後におけるもとの商標登録出願につ いては何ら規定していないこと、商標法施行規則22条4項は、商標法10 条1項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合においては、新 たな商標登録出願と同時に、もとの商標登録出願の願書を補正しなければな らない旨を規定していることからすると、もとの商標登録出願については、 その願書を補正することによって、新たな商標登録出願がされた指定商品等 が削除される効果が生ずると解するのが相当である。」旨説示して、新たな商 標登録出願がされたことにより、当然にもとの商標登録出願が補正されるも のとはいえないことを明らかにしている。そうすると、上記のように、もとの 商標登録出願と分割出願で指定商品等が重複するのを避けるためには、もと の商標登録出願から分割出願に係る指定商品等を削除する補正が必要となる ことは、商標法10条1項自体が想定しているものということができる。 そして、商標法施行規則22条2項は、特許法施行規則30条を準用し、商 標法10条1項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合におい て、もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは、その補正は、新 たな商標登録出願と同時にしなければならないとしているところ、これは、 もとの商標登録出願から分割出願に係る指定商品等を削除する必要が生ずる という、同項が想定する事態に対処するものであるというべきであり、上記 最高裁判決も、このような意味で、商標法施行規則22条4項(現2項)が商 標法10条1項に適合することを明らかにしていると理解される。 本件においては、そもそも、本願の商標登録出願時はもとより現在に至る まで、原商標登録出願について、本願に係る指定商品を削除する補正がされ たとは認められず、商標法施行規則22条2項の要件を欠くばかりか、もと の商標登録出願の指定商品等を2以上に分けるという前記 の分割の前提を も欠くものである。そうすると、本願の商標登録出願は、商標法10条1項の 規定による商標登録出願の要件を満たすものではないから、分割出願として 不適法であり、同条2項が規定する出願日遡及の効果は生じないものであり、 これと同旨の本件審決の判断に誤りはなく、出願時は平成27年9月24日 となる。
2 本願商標の商標法4条1項15号該当性について
(1) 引用商標の周知著名性について
トヨタ社は、平成25年11月20日から同年12月1日に開催された第 43回東京モーターショー2013にトヨタ燃料電池車を出展し(乙98)、 平成26年9月6日付けの日本経済新聞(乙34)では、トヨタ社がトヨタ燃 料電池車の名称を「ミライ」とし、米国の特許商標庁に「TOYOTA MI RAI」を商標登録する手続を進めていることが報じられている。 そして、トヨタ社は、同年11月18日、トヨタ燃料電池車を同年12月1 5日に販売し、その名称は「MIRAI(ミライ)」となる旨発表し、新聞各\n紙やウェブサイトで報じられ(乙4ないし6、35、36等)、これらの記事 のうち、写真が掲載されているものについては、モデル車両のボディやナン バープレートに引用商標が表示されている。\nまた、平成27年1月15日には、自動車関係のウェブサイトでトヨタ燃 料電池車が同年の受注目標400台に対し1500台を受注したことが報じ られ(乙9)、同月23日には、産経新聞で、トヨタ燃料電池車の生産能力を\n平成29年に増強することが報じられており(乙10、91)、その他、本件 出願前に、水素と空気中の酸素が反応して走る環境負荷の低い自動車として、 トヨタ燃料電池車が官邸や地方公共団体に納入されたことが報じられている (乙38、87、89、90)。これらの記事のうち、写真が掲載されている ものについては、モデル車両のナンバープレートに引用商標が表示され、そ\nれ以外のものについては、本文で「MIRAI(ミライ)」の表示があること\nが確認できる。
以上によれば、引用商標は、本願商標の商標登録出願時には、自動車の取引 者及び需要者の間で、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車を表示するも\nのとして周知著名だったものというべきである。 また、本願商標の指定商品「航空機、航空機の部品及び附属品、鉄道車両、 鉄道車両の部品及び附属品」と引用商標が使用される「燃料電池車」は、人や 物品の輸送を目的とするもので、商品の用途や取引者及び需要者に共通性が あるし、大手企業において多角経営が行われることは一般的であり、トヨタ 社の燃料電池車(MIRAI)の技術を応用した水素で走るハイブリッド鉄 道車両開発をトヨタ社、JR東日本及び日立製作所が進めていること(乙6 3、96)も考慮すると、本願商標の指定商品と引用商標が使用される「燃料 電池車」とは、密接な関連性を有しているといえる。このように、本願商標の 指定商品と引用商標が使用される商品の関連性並びに取引者及び需要者の共 通性が認められるから、本願商標の指定商品の取引者、需要者の間において も、引用商標は、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車を表示するものと\nして周知著名だったものというべきである。 そして、証拠(乙1ないし3、19ないし22、25ないし33、42ない し87等)によれば、本願商標の商標登録出願日以降も、トヨタ社はトヨタ燃 料電池車に引用商標や「MIRAI」の欧文字等を使用し、「MIRAI」や 「ミライ」の文字は、トヨタ社の取扱に係るトヨタ燃料電池車の名称を表示\nする商標として、新聞やウェブサイトに取り上げられており、上記周知著名 性は、現在に至るまで維持されているといえる。 なお、原告は、前記第3の1(2)のとおり、別件商標が平成25年12月25 日に出願され、その後商標登録されていることからすると、引用商標が、トヨ タ燃料電池車を表示するものとして、平成26年9月7日以前より、需要者\nの間においても広く知られていたとの本件審決の認定は疑わしいなどと主張 する。 しかし、別件商標の存在は、トヨタ燃料電池車が上記出願日及びそれ以降 に周知著名性を有するとの判断を左右するものではないから、原告の主張は、 当を得ないものというほかない。
(2) 本願商標と引用商標の類似性の程度について
ア 本願商標
本願商標は標準文字・ローマ字の「MIRAI」からなり、「ミライ」の 称呼を生じる。 また、本願商標は、日本語の「未来」に由来することが容易に理解でき、 同観念を生じるほか、前記(1)のとおり、引用商標がトヨタ燃料電池車を表\n示するものとして、本願商標の指定商品の取引者及び需要者並びに自動車 の取引者及び需要者の間で周知著名であることから、「トヨタ燃料電池車 のブランド名」の観念も生じる。
イ 引用商標
引用商標は「MIRAI」の文字をデザイン化したものと認識すること ができ、引用商標からは「ミライ」の称呼を生じる。 また、引用商標及び「MIRAI」の文字は、引用商標がトヨタ燃料電池 車を表示するものとして、自動車の取引者及び需要者並びに本願商標の指\n定商品の取引者及び需要者の間で周知著名であることから、「未来」の観念 と共に、「トヨタ燃料電池車のブランド名」の観念も生じる。
ウ 類否
引用商標は「MIRAI」の欧文字をデザイン化したものであるから、本 願商標と引用商標は外観上相紛れるものである。本願商標と引用商標は「ミライ」の称呼を共通にする。本願商標と引用商標は、「未来」及び「トヨタ燃料電池車のブランド名」という観念においても共通する。そうすると、本願商標と引用商標は類似し、その類似性の程度は高いものというべきである。
(3) 混同のおそれについて
以上(1)及び(2)において認定したとおり、引用商標は、本願商標の商標登録 出願日である平成27年9月24日には、本願商標の指定商品の取引者及び 需要者並びに自動車の取引者及び需要者の間で、トヨタ社の取扱に係る燃料 電池車を表示するものとして周知著名であり、現在に至っていること、本願\n商標と引用商標は類似し、その類似性の程度は高いことからすると、本願商 標は、原告がこれをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者をし て、引用商標を連想又は想起させ、その商品がトヨタ社あるいは同社と経済 的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのよ うに、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきで ある。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.12. 5
令和4(ネ)10019 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年10月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 控訴人は、前記アの本件被控訴人イラスト1の利用について、「引用」に当 たり適法であると主張するので検討するに、適法な「引用」に当たるには、1)公正 な慣行に合致し、2)報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われ るものでなければならない(著作権法32条1項)。
ウ(ア) 本件ツイート1−1をみると、前記(2)のとおり、乙1の2イラストと本件 被控訴人イラスト1を重ね合わせた画像2枚とともに、「これどうだろう ww」「ゆ るーくトレス? 普通にオリジナルで描いてもここまで比率が同じになるかな」と の文言が投稿されており、これは、被控訴人作成の本件被控訴人イラスト1が、乙 1の2イラストをトレースして作成されたものである旨を主張するものであって、 本件被控訴人イラスト1を検証し、批評しようとするものであると認められるから、 本件投稿者1が本件被控訴人イラスト1を用いた目的は、批評にあるといえる。
(イ)a 次に、本件ツイート1−1における被控訴人のイラストの利用方法をみ ると、乙1の2イラストと本件被控訴人イラスト1を重ね合わせて表示しているも\nの(本件投稿画像1−1−2、1−1−3)と、本件被控訴人イラスト1を含む複 数の被控訴人作成イラストを並べて表示しているもの(本件投稿画像1−1−4)\nがあり、これらの画像が、乙1の2イラストの画像(本件投稿画像1−1−1)と ともに前記(ア)の文言に添付されている。タイムライン上においては、原判決別紙タ イムライン表示目録記載1のとおり表\示されるなどしており、上記4枚の画像デー タは、ツイッターの仕様又はツイートを表示するクライアントアプリの仕様に応じ\nて、その一部のみが表示されているが、各画像をクリックすると、本件投稿画像1\n−1−1〜1−1−4のとおりの画像が表示される。\n
b 本件投稿画像1−1−4は、被控訴人が作成した女性の横顔のイラストを2 枚含むものであるが、この2枚のイラストのうち1枚は本件被控訴人イラスト1で あり、もう一枚は本件被控訴人イラストと複製又は翻案の関係にあるものと認めら れるから、本件投稿画像1−1−4をそのまま、本件投稿画像1−1−1(乙1の 2イラスト)とともに利用することは、イラストの類似性を検証するために必要で あり、かつ、文章のみで表現するよりも客観性を担保できる態様で利用されている\nということができる。
c 本件投稿画像1−1−2及び1−1−3は、乙1の2イラストと本件被控訴 人イラスト1を重ね合わせた画像であるが、2枚のイラストないし画像の類似性を 検討するに当たり、2枚のイラストを、それぞれのイラストが判別可能な態様で重\nね合わせ表示するのは検証のために便宜でかつ客観性を担保できる態様で利用され\nているということができ、加えて、当該画像には下部分に各イラストの色の濃さを 操作したことを示唆するアプリケーションの画面部分が記載されており、閲覧者を して、これらの画像が、2枚のイラストを重ね合わせたものであることや、色の濃 さが操作されていることが分かるような態様で示されている。本件では、本件投稿 画像1−1−2では乙1の2イラストの方を濃く表示し、本件投稿画像1−1−3\nでは本件被控訴人イラスト2の方を濃く表示しているが、このような表\示方法は、 2枚のイラストを重ね合わせた画像において、それぞれのイラストを判別して比較 するために資するといえる。
d そうすると、本件ツイート1−1の一般の読者にとって、本件ツイート1− 1における被控訴人のイラストの利用態様は、記事の内容を吟味するために便宜で かつ客観性を担保することができるものであるということができる。 そして、上記利用態様からすると、本件ツイート1−1において、被控訴人が作 成したイラストが、独立した鑑賞目的等で利用されているというような事情はなく、 本件被控訴人イラスト1と乙1の2イラストを比較検証する目的を超えて利用がさ れているとはいえない。
e したがって、本件ツイート1−1における被控訴人のイラストの利用方法は、 前記(ア)の引用の目的である批評のために正当な範囲内で行われていると認めるの が相当である。
(ウ) 証拠(乙5の1〜5、60、63、89、110の1、120の4・5)に よると、第三者が著作権を有するイラストや写真をトレースすることにより、イラ スト等を作成した可能性がある旨の事実を主張する場合に、記事中に、1)問題とな るイラスト等とトレース元と考えられるイラスト等を、比較するためにそのまま又 は比較に必要な部分において示すことや、2)2枚のイラストを重ね合わせて示すこ とは広く行われていることであり、また、前記(イ)のとおり、このように示すことは、 本件ツイート1−1の一般の読者にとって記事の内容を吟味するために便宜でかつ 客観性を担保することができる手法であるということができる。 上記に加え、後記(5)のとおり同一性保持権侵害の観点からも本件ツイート1− 1における被控訴人のイラストの利用が違法ということはできないことに照らすと、 本件ツイート1−1において、被控訴人作成のイラストを添付したことは、公正な 慣行に合致しているということができる。
(エ) そうすると、本件ツイート1−1における被控訴人のイラストの利用は「引 用」として適法である。
エ 以上によると、本件ツイート1−1の投稿による著作権侵害について、「権 利侵害の明白性」は認められない。
(5) 著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)について
ア 前記(2)のとおり、1)本件ツイート1−1に添付された画像のうち、本件投稿 画像1−1−2及び1−1−3は、本件被控訴人イラスト1と乙1の2イラストを 重ね合わせたものであり、また、2)ツイッターのタイムライン上に表示された本件\nツイート1−1における本件投稿画像1−1−2〜1−1−4は、被控訴人作成の イラストの一部のみが表示されているから、それぞれ、被控訴人のイラストの改変\n又は切除に当たると解する余地がある。
イ しかしながら、1)については、著作物がイラストであって重ね合わせて用い ることで、引用の目的である批評のために便宜でありかつ客観性が担保できること に加え、その利用の目的及び態様に照らすと、著作権法20条2項4号の「やむを 得ないと認められる改変」に当たるといえる。
ウ 次に、2)についてみると、証拠(甲49、乙113〜119、120の1・ 2、121の1・2)によると、ツイッターのタイムライン上の表示は、ツイッタ\nーの仕様又はツイートを表示するクライアントアプリの仕様により決定されるもの\nであって、投稿者が自由に設定できるものではなく、投稿者自身も投稿時点では、 どのような表示がされるか認識し得ないこと、投稿後も、ツイッターの仕様又はツ\nイートを表示するクライアントアプリの仕様が変更されると、タイムライン上の表\ 示が変更されること、ツイートに添付された画像データ自体は当該ツイートを閲覧 したユーザーの端末にダウンロードされており、タイムライン上の画像をクリック すると、画像の全体が表示されることが認められることに照らすと、投稿者が改変\n主体に当たるかという点を措くとしても、タイムライン上の表示が画像の一部のみ\nとなることは、ツイッターを利用するに当たり「やむを得ないと認められる改変」 に当たるというべきである。
エ そうすると、本件ツイート1−1の投稿による著作者人格権侵害(同一性保 持権侵害)について、「権利侵害の明白性」は認められない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2022.12. 1
令和3(行ケ)10140 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月16日 知的財産高等裁判所
審判における経緯ですが、請求項1、5、6及び9について、無効審判が請求され、無効の予告がなされたので、権利者は、請求項5及び9を訂正しました。かかる訂正が認められ、請求項1、5、6及び9について、無効理由なしとの審決がなされました。知財高裁は、PBP最高裁判決における「不可能\・非実際的事情」については、本件には適用されないが、「内面精度が一義的ではない」として明確性違反と判断しました。
(1) 判断基準
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時 において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\である か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる(最高裁 判所平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集 69巻4号700頁)。
もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許 請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合(プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム)、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ(前掲最高裁判\n決)、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表\して いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を 読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が その範囲において独占権を有するのかについて予測可能\性を奪う結果となり、 第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。 そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製 造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願 時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表\ しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義 的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不 可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ\nれる。
ア 本件発明6及び訂正発明9は、「電鋳管」に係る発明であるところ、本件 発明6は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層 を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成し、前記細 線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前 記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた 細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を 残したまま細線材を除去して製造される」という製造方法による特定が、 訂正発明9は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導 電層を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成する と共に、前記細線材の両端側に前記電着物または前記囲繞物が形成されて いない部分を形成し、前記細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を 形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞 物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される」という 製造方法による特定を含む。
イ そこで、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鋳管 の構造又は特性、具体的には被告が主張する電鋳管の内面精度が、一義的\nに明らかであるか否かについて検討する。
まず、特許請求の範囲の記載から本件発明6及び訂正発明9の製造方法 により製造された電鋳管の内面精度が明らかでないことはいうまでもな く、また、本件明細書には、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により 製造された電鋳管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。 そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を 加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着 物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、 3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細 線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱 又は溶剤で溶かす方法が記載されている(【0041】、【0116】)が、 これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても 一切記載がなく、ましてや、本件発明6及び訂正発明9の製造方法(上記 3)の方法に含まれる。)が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の 内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上 記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し たとも認められない。そうすると、本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。\n
ウ 以上のとおりであるから、本件発明6及び訂正発明9が明確であるとい えるためには、本件出願時において、本件発明6及び訂正発明9の電鋳管 をその構造又は特性により直接特定することについて不可能\・非実際的事 情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しない ことは認めている。
(3) 被告の主張について
被告は、前記第3の5(2)イのとおり、本件発明6及び9の製造方法により 製造された電鋳管の構造又は特性は、本件明細書の「細線材と電着物または\n囲繞物の間に、細線材を除去するのに十分な隙間が形成できるので、細線材\nが電着物または囲繞物から支障なく除去できる」(【0044】)との記載から 理解できるものであり、文献(甲1、2)の記載や試作分析報告書(甲29) の内容も参酌すれば、良好な内面精度を有するという構造又は特性を表\して いることが、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかであ る旨主張する。
しかしながら、被告が指摘する本件明細書【0044】の記載からは、細 線材と電着物等の間に、細線材を除去するのに十分な隙間が形成できると細\n線材を支障なく除去できる可能性が高いということが理解できるにすぎず、\n本件発明6及び訂正発明9の製造方法により製造された電鋳管が、良好な内 面精度の電鋳管という構造又は特性を表\していることまでを理解することは できない。また、被告が主張する甲1文献や甲2文献の記載は製造の難易さ を記述するにすぎないものであって内面精度については記載されておらず、 試作分析報告書(甲29)の分析結果は、本件出願時の技術常識それ自体を 示すものではないところ、同報告書に記載された内容が本件出願時の技術常 識であることは何ら明らかにされていない。
以上によれば、本件発明6及び9の製造方法により製造された電鋳管が良 好な内面精度の電鋳管という構造又は特性を表\していることが、特許請求の 範囲、本件明細書の記載及び技術常識から一義的に明らかであるとはいえな い。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2022.11.29
令和3(行ケ)10081 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年10月18日 知的財産高等裁判所
(ウ) 上記(イ)のとおり、平成12年度ないし平成18年度の業務用生ごみ 処理機全体の市場における原告商品の占有率は、概ね10%前後で推移 していたといえるところ、弁論の全趣旨によれば、平成19年度ないし 平成26年度も同程度の市場占有率であったと認められる。
(エ) 以上のとおり、平成12年度から平成26年度までの間、原告商品の 市場占有率は、概ね10%前後にとどまっていたことからすれば、本件 商標の出願時以前において、原告商品が高い市場占有率を有していたも のとはいえない。
ウ 原告商品の販売台数について
(ア) 前記1(1)エのとおり、原告商品は、販売を開始した平成4年から本件 商標が出願された前年である平成26年までの間に累計で2514台が 販売されたものの、年間の販売台数は、平成11年の284台をピーク に年々減少し、平成16年に100台を下回って以降は毎年70台前後 で推移していたものである。
(イ) 以上のとおり、原告商品の販売台数は、最も多かった年でも284台 にとどまる上、本件商標の出願時以前の約10年間は毎年70台前後で 推移してきたことからすれば、本件商標の出願時以前において、原告商 品の販売台数が多かったとはいえない。
エ 原告商品に関する報道、広告宣伝等について
(ア) 前記1(2)のとおり、原告は平成6年、平成8年及び平成12年に各種 の賞を受賞し、原告商品は平成9年、平成15年及び平成17年に新聞 報道において取り上げられたことがあったものの、これらはほとんどが 山形県内又は酒田市内における受賞歴又は報道歴である上、その後、本 件商標の出願時までの約10年間において、原告又は原告商品に関する 報道がされたなどの事情は存しない。
(イ) また、原告商品に係る広告宣伝活動についてみても、原告商品につい ては、販売代理店であった被告において通常の営業活動を超える広告宣 伝活動がされていたなどの事情は存せず、また、原告において多額の広 告宣伝費を支出していたなどの事情も存しない。
オ 引用商標の周知性について
(ア) 上記イ及びウのとおり、本件商標の出願時以前において、原告商品が 高い市場占有率を有していたものとはいえず、また、原告商品の販売台 数が多かったとはいえない。これに加え、上記エのとおり、原告の受賞 歴や原告商品に係る報道歴は、ほとんどが山形県内又は酒田市内におけ るものであった上、原告商品に関し、本件商標の出願時以前の約10年 間における報道歴はないこと、原告商品について特別な広告宣伝活動が されていたなどの事情は存しないことも考慮すると、原告商品が平成4 年から20年以上にわたって販売されてきた商品であることや、一般に 業務用生ごみ処理機が相当程度高額な商品であるとうかがわれること (甲7)などを考慮しても、本件商標の出願時及び登録査定時において、 原告商品が高い知名度を有する商品であり、原告商品の名称である引用 商標が周知であったと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.11.29
令和3(行ケ)10089 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月14日 知的財産高等裁判所
c 訂正明細書の【0075】には、基剤として使用可能な多糖類が、少\n量の水に溶解されると糊状になる「曳糸性を有する物質」であるとの記 載はあるが、その技術的意義の記載はない。また、訂正明細書の【00 93】では、引離法による経皮吸収製剤製造の初期段階で、フッ素樹脂 等からなる平板92の上に、目的物質を含有する基剤91を載せたと き、基剤として、水に溶解させると曳糸性を示す物質からなるものを用 い、糊状とすることが好ましいとの記載があるが、これは、目的物質を 含有する基剤を針状又は糸状に成形するという引離法における製造上 の便宜を示したものと解される。さらに、鋳型法による場合について は、訂正明細書の【0095】に、目的物質を含有する基剤が糊状であ れば孔から取り出した後に乾燥又は硬化させることができることが記 載されているところ、これも、粘度が低い場合には鋳型内で乾燥又は硬 化した後に取り出すことを要することと対照した製造上の利便性の記 載であると解される。
したがって、訂正明細書には、経皮吸収剤が「基剤、目的物質及び水 を含む曳糸性を示す糊状物が乾燥した物」であることと、経皮吸収剤そ れ自体の構造や特性との技術的関係についての記載は一切存在しない。\nd 甲2−1文献には、「液体溶液の粘度ならびに他の物理的および化 学的特性に依存して、さらなる力(例えば、遠心分離力または圧縮力) が、鋳型を満たすために必要とされ得る」(【0025】)と記載され、 さらに、粉末形態のマトリクス材料についての記載ではあるが、「粉末 形態がマトリクス材料のために使用される場合、この粉末は、有利に は、鋳型にわたって分離され得る。粉末の化学的および物理的特性に依 存して、次いで、粉末の適切な加熱が適用されて、鋳型内に粘稠性の材 料を融解または挿入し得る。」(【0026】)との記載もある。この ような記載に接した当業者であれば、鋳型で液体溶液を乾燥させる場 合、粘度が1つの重要な要素となり、粘度に応じた製法の調整をして対 応するほか、粘度自体も調整の対象となり得ること、粘稠性の材料であ っても鋳型に充填し得ることを理解するものといえる。
鋳型で乾燥させる液体溶液の粘度の調整については、当業者であれ ば、乾燥するという目的や、鋳型に充填する際の作業効率といった観点 から行うものであり、ヒアルロン酸水溶液が糊状であるか否かは、ヒア ルロン酸水溶液の粘度によって決定され、粘度がある程度以上高けれ ば、糊状になるといえることは前記bのとおりであるところ、上記のよ うに、甲2−1文献の記載から、粘稠性であっても鋳型に充填し得るこ とを理解することができるのであるから、乾燥するという目的も勘案 して、液体溶液の粘度を高いものとすることは容易に想到し得ること である。 そして、そのような液体溶液は粘度によって糊状にも粘稠な液体に もなり得るのであって、その差は相対的であり、いずれの状態になるよ うに調整するにしても、それは、当業者が適宜設定し得た事項にすぎな い。
ヒアルロン酸は曳糸性を有することは前記aのとおり技術常識であ る以上、当業者においてこのように適宜調整された液体溶液は、曳糸性 を示すものになるといえる。なお、甲57実験成績証明書及び乙19実 験報告書からみれば、希薄なヒアルロン酸水溶液は曳糸性を示さない が、鋳型で乾燥させてマイクロニードルを作るに当たって、乾燥させる という目的からみて、そのような希薄な溶液を使用することは想定さ れない。 以上によれば、引用発明2において、甲1−1文献に記載のヒアルロ ン酸を採用する際に、ヒアルロン酸と薬剤を含む液体溶液を、「曳糸性を 示す糊状物」とすることは、当業者が容易になし得たことというべきで ある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> 補正・訂正
>> ピックアップ対象
2022.11.29
令和4(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月21日 知的財産高等裁判所
ア 本件発明1は、「紙破現象を起こし得るように構成している」との発明特\n定事項を有しているところ、「紙破」又は「紙破現象」とは一般的な用語で はなく、その意義を特定するためには、本件明細書の記載を参照すること になる。 そこで、本件明細書の記載についてみると、本件明細書には、「・・・例 えば被着体を紙類とした場合、粘着製品或いは粘着剤を紙類から剥がそう とする剥離動作を行った際に、紙の表層を確実に損傷させることが要求さ\nれる場合がある。」(【0009】)、「以下本明細書において、このような紙 類の表面を損傷した状態を紙破と記載する。また、粘着製品の粘着剤層を\n剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し紙類が厚み方向に破断する\nことを紙破現象と記載することとする。」(【0011】)、「・・・「紙破」: 粘着剤層の表面に紙片の表\層部分を付着させて剥離(図12(a))、「界面 剥離」:粘着剤層と紙片との界面において剥離(同図(b))、「凝集剥離」: 粘着剤が紙類とステンレス板との両方に付着した状態で剥離(同図(c))、 「ナキワカレ」粘着剤層が紙類とステンレス板との両方に付着した状態で 剥離(同図(d))、の何れかに分類して行った。」(【0092】)との記載 があり、【0092】で引用されている図12は、以下のとおりであり、図 12の(a)には、ステンレス板上の粘着剤層の表面に紙類が厚み方向に\n破断した紙片の一部が付着した状態が描かれている。
上記で指摘した本件明細書の記載及び図面を総合すると、本件発明1に おける「紙破現象」とは、粘着製品の粘着剤層を剥離させた際に紙類の表\n層が粘着剤に付着し、紙類が厚み方向に破断する現象をいうものであると 理解することができる。そして、本件発明1の「紙破現象を起こし得るよ うに構成している」との発明特定事項は、その他の構\成要件を充足する「感 圧転写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起こし得る」ように構成されて\nいるものと解することができ、「紙破現象を起こし得ない」構成は、本件発\n明1の技術的範囲に含まれないものと理解することができる。 そうすると、「紙破現象」の発生割合や発生条件について本件発明1に係 る請求項1には特定されていないとしても、特許請求の範囲の記載が第三 者に不測の損害を被らせるほど不明確な記載であるとはいえない。 イ これに対して、原告は、前記第3の1 のとおり、1)「紙破」は、通常 の利用者が視認可能な態様で紙が破れることを指すものであり、「紙破現\n象」とはこうした「紙破」が起こる現象を指すべきものである、2)本件明 細書の記載及び技術常識からすると、「紙破現象を起こし得る」とは、ほぼ 確実に「紙破現象を起こすもの」でなければならないが、いかなる条件の 下で起こるのか不明確であり、同一の接着剤を同一の被着剤に用いた剥離 試験に関する技術常識に照らせば、「紙破現象が起こし得るように構成し\nている」かどうかは条件が特定されなければ不明確である、3)原告による 追実験(甲14)及び被告による「事実実験公正証書」(甲29)の各試験 結果からすると、本件明細書の試験結果は信用することができない旨主張 する。
しかし、前記アのとおり、本件明細書には、「以下本明細書において、こ のような紙類の表面を損傷した状態を紙破と記載する。また、粘着製品の\n粘着剤層を剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し紙類が厚み方向\nに破断することを紙破現象と記載することとする。」(【0011】)とあり、 粘着製品の粘着剤層を剥離させたときに紙類の表層が粘着剤に付着し、厚\nみ方向に紙類が破断していることを示す図(図12(a))があることから、 「紙破現象」とは、上記段落で記載されたとおりに解釈されるべきであり、 「通常利用者が視認可能な状態」で紙が破れることという条件を付加して\n解釈する必要はない。また、原告による追実験(甲14)は、紙類の表層\nが粘着剤に付着したかどうかの確認作業について言及がない(むしろ、視 認によって判断している可能性が高い。)ため、この追実験で本件明細書の\n実物剥離試験の結果が信用できないものであると判断することはできな いし、被告による「事実実験公正証書」(甲29)の試験結果において、「目 視では十分に確認できなかった」との記載があるとしても、そのことが「紙\n破現象」が起きていないことを意味するものではないことについては前示 のとおりであるから、上記1)及び3)の各主張は理由がない。
次に、上記2)について検討するに、本件発明1においては、粘着剤層を 介して紙類同士を止着させた後、粘着剤層を剥離させたときの条件及び方 法は発明特定事項には含まれておらず、他の構成要件を充足する「感圧転\n写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起こし得る」ように構成されている\nものが本件発明1として特定されているのであるから、任意の条件及び方 法で「紙破現象」が生じ得る構成であれば、本件発明1の技術的範囲に属\nするものといえ、他方、「紙破現象を起こし得ない」構成は技術的範囲に属\nさないことが明らかにされている。したがって、少なくとも上記 記載の 明確性要件との関係においては、剥離試験における条件や方法等について の特定がないとしても、第三者に不測の不利益を及ぼすものとはいえない から、上記2)の主張も理由がない。
◆判決本文
分割願についての判断です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2022.11.28
令和4(ワ)12062 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年11月17日 東京地方裁判所
弁論の全趣旨によれば、YouTubeの利用者がYouTube上でストリーミング形式により映画を視聴するためには所定のレンタル料を支払う必要があることが認められる。再生対象の映画の著作権者は、当該レンタル料から著作権の行使につき受けるべき対価を得ることを予定しているものと理解されることから、本件において、原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、YouTube上で視聴する場合の本件各映画作品それぞれのレンタル価格等を考慮して定める金額に、本件各動画のYouTube上での再生数を乗じて算定するのが相当である。
(2)YouTubeにおける本件各映画作品の各レンタル価格(HD画質のもの)は、1作品当たり400〜500円程度であり、400円を下らないこと、うち30%がYouTubeに対するプラットフォーム手数料に充当されること、本件各動画は、それぞれ、約2時間の本件各映画作品を10〜15分程度に編集したものであるものの、本件各映画作品全体の内容を把握し得るように編集されたものであることは、いずれも当事者間に争いがない。これらの事情を総合的に考慮すると、被告らが本件侵害行為によって得た広告収益が700万円程度であること(当事者間に争いがない)を併せ考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(法114条3項)は、原告らの主張のとおり、本件各動画の再生数1回当たり200円とするのが相当である。
関連カテゴリー
>> 翻案
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.11.25
令和4(行ケ)10041 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年10月31日 知的財産高等裁判所
原告は、前記第3の 1 のとおり、本願商標の構成中の「御守」の文字は\n御守の内容・種類を表しているにすぎず、全体的なデザインとともに一体的\nに把握されるものであるから、本願商標がその指定役務に使用される場合、 本願商標からは役務の出所識別標識としての「オマモリ」の称呼及び「御守」 の観念は生じない旨主張する。
しかしながら、前記1(1)のとおり、御守袋の上に「御守」と表示されてい\nる本願商標は、御守袋の形状の図案それ自体からして、「御守」の観念を生じ、 「オマモリ」の称呼が生じるものといえるところ、その表面の「御守」の文\n字は、その表面中央にあって文字として記載され、かつ、文字としてはその\n記載しかない以上は、当然のこととして、当該御守袋が何であるかを示すも のというべきであり、そこからも「御守」の観念を生じ、「オマモリ」の称呼 が生じることは明らかである。そして、本願商標に係る指定役務のうち、少 なくとも、おむつ、食品、化粧品、ペット用品、ベビーオイル等を含む第3 5類の商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (以下「小売等役務」という。)について、御守が、これら商品の小売等役務 の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又\nは時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないか ら、上記のように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼 が本願商標の当該指定役務の内容、対象そのものを示すものとは理解されな い。 このように本願商標から生じる「御守」の観念や「オマモリ」の称呼が本 願商標の当該指定役務の内容、対象を示すものとはいえない以上は、これら の観念や称呼が役務の出所識別標識として生じる可能性を否定することはで\nきないから、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 商標の類否判断の誤りの主張について
本願商標の構成全体から格別の称呼、観念が生ずることはないことを前提\nとする原告の主張(前記第3の 1 ア)については、その前提に誤りがある ことは前記のとおりであるから、採用することができない。 次に、原告は、前記第3の 1 イのとおり、仮に、本願商標から「オマモ リ」の称呼、護符(御守)の観念が生じたとしても、本願商標は、全体とし て「白色の二重叶結びの紐を有し、ピンク色の桜の花弁模様を配し、『御守』 の文字を御守袋の表面に表\した赤色の御守」との印象を強く抱かせるもので あるから、本願商標と引用商標の外観上の顕著な相違から看取できる印象は、 称呼及び観念から看取できる印象を凌駕している旨主張する。 しかしながら、本願図形部分である、「白色の二重叶結びの紐、ピンク色の 花弁模様及び赤色の色彩」のうち、「白色の二重叶結びの紐」は御守袋の特徴 にほかならず、また、「ピンク色の花弁模様及び赤色の色彩」は御守袋として は格別印象に残るような形状・色彩を有するものではないから御守袋を構成\nする地模様と認識されるのがせいぜいのところであり、それらが単独で看者 に強い印象を与えるものではない。 そうすると、本願商標から生じる「オマモリ」の称呼及び護符(御守)の 観念が本願図形部分から看取できる印象に凌駕されることはない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 指定商品・指定役務の類否判断の誤りの主張について
原告は、引用商標1の指定商品の製造・販売と小売等役務の提供が同一事 業者によって行われていることは通常とまではいえないから、引用商標1の 指定商品を同指定商品に係る小売等役務を提供する事業者が製造又は販売す る商品であると誤認するおそれがあるとはいえない旨主張する。
しかしながら、ある製品の製造業者が当該製品の販売場を持つなどして、 当該販売場を置くとともに、同時に、顧客に対する当該製品の品揃え・陳列、 接客等のサービスを提供するなどして小売等役務の提供場所とし、当該製品 の販売行為を促進して最終的には当該製品の販売行為により収益を上げよう とすることは、自然な商業的取引の在り様といえ、これと異なる特殊な事情 がない限りは、通常行われることと推認されるものというべきである。 そして、引用商標1の指定商品について、その製造・販売と小売等役務の 提供が別事業者によって行われていることが通常であるとするような特殊な 事情は本件証拠からは認められず、かえって、本願商標の指定役務である「菓 子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットド ッグ、ミートパイ」の小売等役務に係る商品と、これに類似する引用商標1 の指定商品である「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除 く。)、パン」について、自社工場を持つ営業主がそれら製品を自社店舗で販 売するなど、その製造販売と小売等役務が同一営業主によって行われること がよくあるとの実情は公知の事実ともいえ、被告からも、その一例の指摘が ある(乙11ないし17)。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.11.25
令和3(ワ)11507 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月28日 東京地方裁判所
ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧 迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周 囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上 方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」(構\n成要件Bii)と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大 腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。 そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポー ターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー(ゴムの収縮力、 即ち筋肉に対する圧迫強度)を変え、或いは織り方を変えることで患部に対 する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節 の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」 (段落【0002】)、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、 脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減 し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」(段落【0 020】)と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課 題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提 供するものであることが認められる。 そうすると、上記の構成要件Bii及び本件明細書等の各記載内容によれば、 構成要件Biiの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫す るものと解するのが相当である。
イ 被告製品17の構成要件充足性について\n
これを被告製品17についてみると、前提事実及び証拠(甲6)によれ ば、被告製品部分2は、被告製品部分2と接触する部分や大腿骨の周囲筋 腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証 拠によっても、被告製品部分2が大腿骨自体までをも圧迫することまで認 めることはできない。 したがって、被告製品17は、構成要件Biiを充足するものとはいえな い。
・・・
「固着」について 本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」(構\成要件C)と記載さ れている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法 を格別限定するものではない。 そして、証拠(甲11)によれば、「固着」という用語について、一般 的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。 また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮 性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸\n縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは\n印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、 あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写する ような方法も取り得る。・・・」(段落【0012】)、「正面吊り領域 22を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料34を本体20に固着した構成を有している。より詳細に図示\nした図4を参照して説明すると、図4において、35、36は縦糸と横糸 などから成る編織構造を示しており、37は固着手段を示している。樹脂\nより成る低伸縮性材料34は、本体20に固着すると固着手段37が上記 編織構造35、36の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化するこ\nとにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変える ことになる。」(段落【0031】)、「低伸縮性材料34は、例えば上 記正面吊り領域22の形状にあらかじめ形成され、それを本体20の表面\nに固着手段37を用いて固着する。図4Aに示す例では、低伸縮性材料3 4の下面に固着手段37があらかじめ固着されている。そして、図示の例 の場合、本体20は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編 織したもので、低伸縮性材料34はウレタン系樹脂材料のフィルムより成 る多層構造を有し、固着手段37には上記ウレタンフィルムより成る多層\n構造の内の一部を用いて本体20に固着させている。しかしこれは一例で\nあり、固着手段37として接着剤を本体20の表面に塗布すること、また、\nシート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体20の材 質と低伸縮性材料34の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる 場合には直接本体20に低伸縮性材料34を熱溶着する手段も選択し得 る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用 しても良い。」(段落【0032】)と記載されている。そうすると、本 件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる 方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解すること はできない。 上記の構成要件C及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」と\nいう用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の 方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされてい るものと解することはできない。
・・・
「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記 のとおり記載されている。そし て、証拠(甲17)及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成 樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合 成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認め られる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの(合成繊維)を 除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合 成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。 これに対して、被告は、証拠(乙1、2、7)によれば、「合成樹脂」 に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説 示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられ るものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。 また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維(段落【0 032】)と低伸縮性材料に用いる樹脂材料(段落【0012】)が明確 に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Cの「樹\n脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」 に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、 採用することができない。
・・・
これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提 事実(2)イのとおりであり、本件発明の意義は、前記1(2)のとおり、従来技術で は、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで 患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決す るために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸 縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、1)本体の正面に、膝蓋靱帯 を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝\n蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型の領域と、2)上記ほぼU字型の領域の左右両 端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具 備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという 構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を\n良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂 隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もっ\nて上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
(3) 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」(構成要件C)す\nる方法が、いわゆる別材料固着構造(膝を筒状に覆うサポーター本体の表\面の 一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、 伸縮性等の異なる部位を配置した構造)以外に、被告製品17が採用する一体\n編成・織成構造(サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分に\nよって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置 した構造(本件明細書等の段落【0002】記載の「サポーター本体に織り込\nまれているゴムのパワー(ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度)を変え、 或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を 含む。))をも含むと解されることは、前記2(4)ア において説示したとおり である。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポ\nーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、 本件明細書の段落【0002】によれば、一体編成・織成構造のサポーターに\nよっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明 の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。 そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造の\nサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし 本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。 これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解\n決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。 しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造の\nサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サ ポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体か らも自明であって、原告の主張は、採用することができない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.11.25
令和2(ネ)10024 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
原判決は、本件発明C−1の特許請求の範囲(請求項1)の記載 に基づく解釈として、1)構成要件Cの記載によれば、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」の3要素により形成された部分をもって成るものが「空洞部」であり、「空洞部」に「外側立上り\n壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在しない部分が許容され ると解されず、「空洞部」全体にわたって「内側立上り壁」が存在す ることを要する、2)構成要件Dの記載によれば、「空洞部の先端部」に「内側立上り壁の…前端部」が存在することは明らかであるところ、「内側立上り壁の…前端部」という記載は、更に「空洞部の先端\n部」以外にその後方部分にも「内側立上り壁」が存在することを示 唆するものと理解される、3)構成要件Bの記載によれば、「前腕挿入開口部」は、「空洞部」の一部ではなく、「空洞部」とは別の「肘掛部」の構\成部分でありつつ、「空洞部」に連続して設けられた部分であると解され、また、「前腕挿入開口部」と「空洞部」から成る「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の相対的な位置 関係は、「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する と解され、さらに、「前腕部を挿入保持する」ように「空洞部」が構成される、4)構成要件E、E−1、E−2の記載によれば、「前腕挿入開口部」が「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための」部分であるところ、そこに位置する施療部は「底面部」と「外側立上\nり壁」によりL型に形成されていることから、当該施療部には「内 側立上り壁」が存在しないと解されること、「前腕挿入開口部から延 設して…設けられ」ている「空洞部」が、「肘掛部」中の別の構成部分であることに鑑みると、「内側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画するものであるとの示唆を看取することもで\nき、そもそも、「前腕挿入開口部」につき、「内側後方から施療者の 前腕部を挿入するための」ものと特定されていること自体、「前腕挿 入開口部から延設して…設けられ」た「空洞部」の内側側方からは、 「空洞部」に「施療者の前腕部を挿入する」ことができないことを 示唆するものと解される、5)他方、請求項1の記載から、「空洞部」 中に「内側立上り壁」が存在しない部分があるとの示唆を読み取る ことはできないとして、本件発明C−1の「空洞部」(構成要件B、C)とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解される旨判断した。\n
しかしながら、1)及び5)については、構成要件B及びCから読み取れる事項は、「該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部」が「外側立\n上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」という3要素から形成さ れていることであり、他方で、「空洞部」のどの部分に、「外側立上 り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」を設けるべきかについては、 請求項1には何ら記載がない。「空洞部」が上記3要素から成ること と、上記3要素をどのように形成するかは別問題であるから、「空洞 部」に「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在し ない部分が許容されると解されないとの原判決の判断には、論理の 飛躍がある。
2)については、構成要件Dには、「空洞部の先端部」以外の後方部分における「内側立上り壁」の範囲については記載も示唆もなく、また、構\成要件Dの記載は、「空洞部の先端部」とその後方部分の一部に形成されている構成も、本件発明C−1の「空洞部」に該当すると解釈することと矛盾しないから、構\成要件Dから「内側立上り壁」が「空洞部」全体に及ぶべきことを読み取ることはできない。
3)については、構成要件Bの記載によれば、「前腕挿入開口部」は「肘掛部」の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」の部材であり、「空洞部」は「肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部\nを挿入保持するため」の部材であると定義されるところ、いずれも 「前腕」を「挿入」する機能を実現する部材であることで共通することからすると、「前腕挿入開口部」と「空洞部」は、「前腕部を挿入する部分」において重なることが示唆されているから、両者に厳\n密な線引きをすべき理由はない。また、仮に構成要件Bの記載について原判決の解釈を前提としても、「内側立上り壁」が「空洞部」の一部に形成されている構\成であっても、「肘掛部」に「空洞部」と「前腕挿入開口部」とが別構成として設けられ、「肘掛部」において「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する構\成とすることもできるから、本件発明C−1の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものでなければならないという結論 が論理必然的に導き出されるわけではない。
4)については、構成要件E、E−1、E−2は、「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の位置関係等を直接規定したものではなく、また、構\成要件E−2から読み取れる事項は、「前腕挿入開口部」に位置する施療部が底面部と外側立上り壁によりL型に形成されているということだけであり、そのことから直ちに、「内 側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画する ことを看取できるものではない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし5)は、本件発明C−1の「空 洞部」(構成要件B、C)は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することの根拠となるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。\n
(b) 次に、原判決は、本件発明C−1の「空洞部」(構成要件B、C)とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解されることは、本件明細書Cの記載及び本件特許Cの出願経過か\nらも裏付けられると述べ、具体的には、1)本件明細書C記載の本件 発明C−1の技術的意義に鑑みると、本件発明C−1は、肘掛部の 長さ方向全域に「外側立上り壁」と「内側立上り壁」が形成された 椅子式マッサージ機を前提として、肘掛部の内側後方から施療者の 前腕部を挿入可能となるように「内側立上り壁」を廃した「前腕挿入開口部」を設けたと認められるから、そのような肘掛部の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部」と、そ\nこから「延設して肘掛部の内部に…設けられ」ている「空洞部」と は、「内側立上り壁」の有無により画されるものと理解されるし、「手 掛け部」を設けたのは手部及び前腕部の広範を同時にマッサージす るために肘掛部の前端部にまで「内側立上り壁」が形成されている ことを踏まえたものである以上、本件発明C−1における「肘掛部 の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面 部とから形成され」た「空洞部」の「内側立上り壁」は、手部及び 前腕部の広範を同時にマッサージすることができるように、「空洞 部」全体にわたって存在することが想定されているといえる、2)本 件親出願の明細書(乙C8)の【0046】、【0047】及び図1 4は、本件明細書Cの【0046】、【0047】及び図14と同様 に、前腕部施療機構の中部に「内側立上り壁」が形成されていない実施例に関する記載であるところ、これらは、本件出願Cの出願に当たり、本件親出願の請求項からの変更の根拠として挙げられてい\nない、本件補正時に提出された平成23年5月9日付け意見書(以 下「本件意見書」という。乙C12)において、控訴人は、本件各 発明Cが、「肘掛部の長さ方向全域に前腕部施療機構として左右一対の立上り壁を設けた椅子式マッサージ機」に関する発明であり、「施療者の肘関節付近にまで左右一対の立上り壁が存在すること\nによる施療者の肘関節付近の圧迫による不快感を解消し、更に前腕 部施療機構を有していても施療者が起立及び着座を快適に行う事ができるようにした施療機を提供するもので」あるとした上で、「空洞部の先端部」に設けた「手掛け部」に関しては、そこに「内側立\n上り壁」が存在することを前提とした説明をしつつ、「前腕挿入開口 部」に関しては、そこには「内側立上り壁」がない形状にしたとす る説明をしている、他方、請求項2、すなわち肘掛部の中部に「前 記底面部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された 施療部」を設けることについても説明しているが、そこで言及され ている本件明細書Cの記載のうち、関係するのは【0046】のみ である、本件拒絶理由通知に示された「引用文献2」(乙C19)と 本件補正後の発明(本件発明C−1及びC−2)との相違について、 「引用文献2」に開示された前腕部施療部は「肘挿入用凹溝」であ り、その断面形状は略横向き「凹」字状であるのに対し、本件補正 後の発明においては、前腕挿入開口部に位置する施療部は「底面部」 及び「外側立上り壁」により形成された断面略「L型」であり、ま た、手掛け部が形成される空洞部に位置する施療部は、「底面部」、 「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「手掛け部」に囲われた形 状(実施の形態では「ロ型」)であるため、その構成が相違する旨説明している、断面が略「コ」字状の前腕部施療部の問題点として、前腕挿入開口部においては、上面に位置する部分が腕部の載脱をス\nムーズに行う上で障害となり、手掛け部においては「内側立上り壁」 が存在しないため、施療者の体重を掛ける上で不安が残ることを指 摘している、こうした説明内容に加え、本件補正により「前記底面 部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された施療部 を備え」る請求項2(本件発明C−2)を請求項1の従属項として 追加したにもかかわらず、当該発明における上記略「コ」字状の前 腕部施療部の問題点の有無等に関する説明が見当たらないことに 鑑みると、本件補正における控訴人の説明は、請求項2の追加にか かわらず、本件発明C−1の「空洞部」につき、その全体にわたっ て「内側立上り壁」が存在する構成を前提としていたと理解される、3)本件明細書Cの【0046】及び図14の記載が本件親出願から の分割出願(本件出願C)や補正(本件補正)にもかかわらず一貫 して存在する点については、本件発明C−1に係る特許請求の範囲 の請求項1の記載自体から「空洞部」につき、その全体にわたって 「内側立上り壁」が存在する構成と理解されることに鑑みると、分割出願や補正による本件特許Cの発明の内容の変化に応じてこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないと見るべきである\n旨判断した。
しかしながら、1)については、本件明細書Cには、本件発明C− 1の一実施形態(本件発明C−2の実施例)として、肘掛部の中部 に外側立上り壁、手掛け部、底面部よりコ型に形成された施療部を 設けたマッサージ機の記載があり(【0046】、図14)、図14で は、コ型に形成された施療部、すなわち、内側立上り壁が存在しな い部分が空洞部(62a)と図示されており、また、別の実施形態 を示す図8においても、内側立上り壁が存在しない部分が空洞部 (62a)と図示されている。これらの記載を参酌すれば、本件発 明C−1の「空洞部」は、肘掛部中の内側立上り壁が存在する部分 に限られるわけではなく、その全体にわたって「内側立上り壁」を 備えることを要しないことは明らかである。 また、本件発明C−1は、肘掛部の長さ方向全域に立上り壁を設 けることによる不都合(ア)上腕部内側の肘関節付近を圧迫し不快感 を与える、 腕部の載脱行為を妨げる、 快適な起立及び着座を妨 げるという不都合)を解決することを課題とし(【0005】ないし 【0008】)、(ア)及び の課題は、前腕挿入開口部の内側立上り壁 を廃したことにより、 の課題は、肘掛部に手掛け部を設けたこと により解決したものであり、それを超えて、「内側立上り壁」の有無 が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画し、空洞部はその全体に わたって内側立上り壁を備えるものであるという「空洞部」が備え るべき構成を導くことはできない。さらに、本件明細書Cの【0016】には、底面部及び外側立上り壁の二面において膨縮袋を備えることで前腕部に対するマッサ\nージを実施することができる旨が記載されていることに照らすと、 手部及び前腕部の広範を同時にマッサージするためには、「底面部」 及び「外側立上り壁」の二面が存在すれば足り、「内側立上り壁」が 「空洞部」の全体にわたって存在することは想定されていない。 次に、2)及び3)については、本件親出願の分割出願として本件出 願Cを出願するに際し、本件親出願の明細書(乙C8)の【004 6】、【0047】及び図14を分割要件を満たすことの根拠として 挙げられていないからといって、本件特許Cの出願経過において、 本件発明C−1の「空洞部」をその全体にわたって「内側立上り壁」 が存在する構成に限定したという控訴人の意思が客観的に表\され ているとはいえない。むしろ、控訴人は、本件意見書において、請 求項1及び2に係る本件補正の根拠として、本件出願Cの願書に最 初に添付した明細書(以下「本件出願Cの当初明細書」という。乙 C9)の【0046】を明確に挙げていること、当該段落は本件明 細書Cの【0046】と同じであり、「内側立上り壁」が備えられて いない部分を「空洞部(62a)」として指し示した「図14」の構成を説明していることからすると、「空洞部」についてその全体にわたって「内側立上り壁」が存在することを要しないことを前提とし\nていたことは明らかであり、本件明細書Cの【0046】及び図1 4の記載が存在することは本件特許Cの発明の内容の変化に応じ てこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないとの原判決 の3)の判断は誤りである。
また、被控訴人が2)で指摘する本件意見書における説明は、「空洞 部」と「内側立上り壁」の関係については何ら言及されておらず、 控訴人が、空洞部をその全体にわたって「内側立上り壁」が存在す る構成に限定する意思を客観的に表\明しているということはでき ない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし3)は、本件発明C−1の「空 洞部」(構成要件B、C)は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することを裏付けとなるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。\n
・・・
これを本件についてみるに、前記ウ認定の本件推定の覆滅事由は、特 許発明が被告製品1の部分のみに実施されていること及び市場の非同 一性であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。\nしかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅 部分については、被控訴人による被告製品1の各仕向国への輸出があっ た時期において、控訴人製品1は当該仕向国への輸出があったものと認 められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製 品1は、被告製品1の輸出がなければ輸出することができたという競合 関係があるとは認められないことによるものであり(前記ウ c)、控訴 人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすること ができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたも のと認められる。 一方で、本件各発明Cが侵害品の部分のみに実施されていることを理 由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に 係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品1に対し本件各発明Cが寄 与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このよう な本件各発明Cが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をす ることができたものと認められない。 そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由 に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法102条3項の適用を認める のが相当である。
(ウ)a これに対し、控訴人は、特許発明が侵害品の一部のみに実施されて いることを理由とする覆滅事由は、需要を形成する一要因にすぎず、 侵害品に向かっていた事情が全て特許権者の製品に向かうかどうかを 判断する一要素であるから、市場の非同一性等を理由とする覆滅事由 と区別する理由はないこと、覆滅事由ごとに特許法102条3項の適 用の有無を区別することは、実施料率の算定が煩雑になり妥当でなく、 そもそも製品の需要形成には様々な要因が複合的に絡み合っており、 覆滅事由ごとに覆滅割合を認定して当該覆滅部分にライセンス機会の 喪失による逸失利益が認められるか否かを認定判断することは実際上 困難であることからすると、本件各発明Cが侵害品の部分のみに実施 されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、 特許法102条3項の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、前記 で説示したとおり、上記推定覆滅部分は、個々 の被告製品1に対し本件各発明Cが寄与していないことを理由に本件 推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Cが寄与してい ない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものとは認 められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。 b また、被控訴人は、1)特許法102条1項において、特許権者が自 己実施できたと推定される部分(1号)とは別にライセンスをし得た 部分(2号)とを区別し観念できるのは、同項が、侵害者の販売する 「数量」に基づいて、権利者の逸失利益に係る損害額を算定する方法 を採用しているからであり、他方で、同条2項は、侵害者の「利益」 を権利者の逸失利益と推定する損害額算定方法をとっており、同項の 推定が覆滅されるのは、最終計算の結果としての損害額であり、計算 過程の途中数値である侵害品の数量の一部が計算の基礎から除かれる わけではなく、同項の推定を覆滅する過程において、権利者のライセ ンスの機会の喪失による逸失利益をも含む全ての逸失利益が評価し尽 されているというべきであるから、推定覆滅部分に対して同条3項を 適用することは、権利者の損害の二重評価となり、許されない、2)同 条1項2号が新設された令和元年改正特許法において、同条2項につ いて実施料相当額の損害が明文において規定されなかったのは、この ような趣旨によるものと解される、3)仮に推定覆滅部分について同条 3項の重畳適用が認められる場合が理論的にあり得るとしても、被告 製品1について、「市場の非同一性」を理由とする覆滅事由に係る推定 覆滅部分につき、輸出に際して海外市場の事業者から受け取る対価は、 あくまで海外市場に基づく利益であり、このような海外市場における 利益まで特許法102条2項の推定が及ぶものと解し、日本国内の特 許権に基づいて独占することは、特許権の保護範囲を逸脱しており、 法が予定していないものであり、また、日本国の特許権に基づいて仕向国への輸出行為のみを切り取り、ライセンスする場合は現実に考え\n難く、ライセンスによる実施料相当額の得べかりし利益を得られなか ったとは言い難いとして、本件推定の推定覆滅部分については、同条 3項を適用することはできない旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、前記 で説示したとおり、特 許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができるこ とに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特 許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた 実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の 喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解されるところ、特 許法102条2項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、 特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができ た実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するもので あるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が 実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上 げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施 料相当額の損害を受けたものと評価できるから、特許権者の損害を二 重に評価することにはならない。また、同条1項2号が新設された令 和元年改正特許法において、同条2項について、同条1項2号と同様 の法改正がされなかったからといって直ちに同条2項による推定の推 定覆滅部分について同条3項の適用を否定すべき理由にはならないと いうべきである。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.11.25
令和4(行ケ)10019 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月16日 知的財産高等裁判所
前記(3)によると、本件各発明が属する技術分野(線材の引抜加工機及びこれに 用いるダイス)においては、従来、多角形の断面を有する線材の製造に際し、ダイ スのベアリング部の開口部(以下「開口部」という。)の角部に潤滑剤がたまって 塊が発生し、その除去のために作業を一旦止める必要があるため、生産量が低下し て製造原価が下がらない一因となっていたところ、本件各発明は、潤滑剤の塊の発 生を極力防ぎ、また、ダイスのメンテナンスに要する時間を極力削減し、その結果、 多角形の断面を有する線材の製造コストの低減を図ることを目的として、当該角部 の全部又は一部につき、これを円弧とし、鈍角の集合とし、又は自由曲線とするこ とにより、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるようにしたものであるといえる。 加えて、本件明細書における「略多角形」の定義(段落【0057】)にも照らす と、本件各発明の「略多角形」とは、本件各発明の効果(開口部の角部に潤滑剤が たまりにくくなること)を得るため、「基礎となる多角形断面」の角部の全部又は 一部を円弧、鈍角の集合又は自由曲線に置き換えた図形(以下、角部を円弧、鈍角 の集合又は自由曲線に置き換えることを「角部を丸める」などといい、角部に生じ た円弧、鈍角の集合又は自由曲線を「角部の丸み」などということがある。)をい うものと解することができる。そして、前記(3)によると、「基礎となる多角形断 面」とは、従来技術における開口部(角部を丸める積極的な処理をしていないもの) の断面を指すものと解されるから、結局、本件各発明の「略多角形」とは、本件各 発明の上記効果を得るため、その角部を丸める積極的な処理をしていない開口部に つき、その角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をいうものと一応 解することができる。なお、これは、前記(2)の字義からみた「略多角形」の意義 とも矛盾するものではない。
(5) 「略多角形」と「基礎となる多角形断面」との区別
前記(4)のとおり、本件各発明の「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」の 角部の全部又は一部を丸めた図形をいうものと一応解されるから、両者の意義に従 うと、両者は、明確に区別されるべきものである。 しかしながら、証拠(甲31、32、36、37)及び弁論の全趣旨によると、 ワイヤー放電により、その断面形状が多角形である開口部を形成するくり抜き加工 をした場合、開口部の角部には、不可避的に丸みが生じるものと認められる。そう すると、「基礎となる多角形断面」も、くり抜き加工をした後の開口部の断面であ る以上、角部が丸まった多角形の断面であることがあり、その場合、客観的な形状 からは、「略多角形」の断面と区別がつかないことになる。 この点に関し、本件審決は、本件各発明の「略多角形」には、上記のように加工 に際して角部に不可避的に生じる丸み(例えば、曲率半径が0.3mm程度以下の 小さなもの)を有するにすぎない「基礎となる多角形断面」を含まないと判断し、 被告も、これに沿う主張をする。しかしながら、開口部の角部の丸みの曲率半径が 0.3mm程度以下であれば、当該角部に潤滑剤がたまりにくくなるとの本件各発 明の効果が得られないものと認めるに足りる証拠はなく、当該曲率半径が0.3m m程度以下の場合であっても、本件各発明の上記効果が得られる可能性があるから、\n当該曲率半径がどの程度を超えれば本件各発明の上記効果が得られるようになるの かは、客観的に明らかとはいえない。また、証拠(甲31、32、36、37)及 び弁論の全趣旨によると、上記のようにワイヤー放電加工に際して開口部の角部に 丸みが不可避的に生じるのは、加工に用いるワイヤーの断面形状が一定の直径を有 する円形であるからであると認められ、ワイヤーの断面の直径が小さくなれば、そ の分だけ、不可避的に生じる丸みの曲率半径は小さくなるといえるから、開口部の 角部の丸みについては、その曲率半径がどの程度まで小さければ不可避的に生じる 丸みであるといえ、どの程度より大きければ不可避的に生じる丸みを超えて積極的 に角部を丸める処理をしたものであるといえるのかを客観的に判断する基準はない というほかない。そうすると、客観的な形状からは、「基礎となる多角形断面」と 「略多角形」とを区別するのは困難であるといわざるを得ない。 以上のとおり、本件各発明の「略多角形」は、「基礎となる多角形断面」と区別 するのが困難であり、本件各発明の技術的範囲は、明らかでない。
(6) 「略多角形」の角部の形状
前記(5)のとおり、ワイヤー放電により、その断面形状が多角形である開口部を 形成するくり抜き加工をした場合、開口部の角部には不可避的に丸みが生じるから、 「基礎となる多角形断面」の角部を丸めるための積極的な処理をしようとしまいと、 開口部がくり抜き加工のされた後のものである以上、開口部の角部には、全て丸み があり得ることになる。 そして、前記(5)のとおり、開口部の角部の丸みについては、その曲率半径がど の程度まで小さければ不可避的に生じる丸みであるといえ、どの程度より大きけれ ば不可避的に生じる丸みを超えて積極的に角部を丸める処理をしたものであるとい えるのかを客観的に判断する基準はないし、また、当該曲率半径がどの程度を超え れば本件各発明の効果(開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなること)が得られ るようになるのかは、客観的に明らかとはいえない。 この点に関し、本件審決は、本件各発明の「略多角形」は「基礎となる多角形断 面」に対して潤滑剤がたまる角部がなくなるように更に積極的な処理をした状態の もの(例えば、少なくとも角部の円弧の曲率半径が0.8mm程度のもの)と解さ れると判断し、被告も、これに沿う主張をする。しかしながら、本件明細書には、 開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなるとの本件各発明の上記効果を奏する条件 について、1辺4mmの四角形断面の棒材を作成する場合に、開口部の1つの角部 を曲率半径0.8mm程度の円弧(曲線)で結ぶと、角部にたまっていた潤滑剤の 塊が1か所に固まりづらくなる旨の記載(段落【0055】)があるのみであると ころ、1辺4mmの四角形断面の開口部の角部を曲率半径が0.8mm程度より小 さい円弧とした場合に本件各発明の上記効果が得られないものと認めるに足りる証 拠はないし、その断面形状が1辺4mmの四角形以外の多角形である開口部も含め ると、開口部の角部にどの程度の丸みを帯びさせれば本件各発明の上記効果が得ら れるのかを客観的に明らかにするのは困難であるといわざるを得ない(なお、被告 は、開口部の角部における潤滑剤のたまりやすさは、作成すべき棒材の断面の大き さにかかわらず、当該角部の丸みの曲率半径によって決せられ、当該曲率半径が0. 3mm程度以下であれば、本件各発明の上記効果が得られないと主張する。しかし ながら、開口部の角部における潤滑剤のたまりやすさは、当該角部の丸みの曲率半 径の大きさのみならず、線材の種類、潤滑剤の種類、加工発熱の度合い等の様々な 要素によって左右されるものであると解され、当該曲率半径が0.3mm程度以下 であれば、一律に本件各発明の上記効果が得られないと認めることはできないから、 被告の主張を採用することはできない。)。 以上によると、本件各発明の「略多角形」については、特許請求の範囲の記載、 本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識を踏まえても、「基礎となる多角 形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものがこれに該当するのか が明らかでなく、この点でも、本件各発明の技術的範囲は、明らかでないというべ きである。
(7) 小括
以上のとおり、本件各発明に係る特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に よると、本件各発明の「略多角形」とは、本件各発明の効果(開口部の角部に潤滑 剤がたまりにくくなること)を得るため、その角部を丸める積極的な処理をしてい ない開口部につき、その角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をい うものと一応解することができるものの、客観的な形状からは、本件各発明の「略 多角形」と「基礎となる多角形断面」とを区別することができず、また、「基礎と なる多角形断面」の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものが本件各発明 の「略多角形」に該当するのかも明らかでなく、本件各発明の技術的範囲は明らか でないというほかないから、本件各発明の「略多角形」は、第三者の利益が不当に 害されるほどに不明確であると評価せざるを得ず、その他、本件各発明の「略多角 形」が明確であると評価すべき事情を認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2022.11.22
令和4(行ケ)10021 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月16日 知的財産高等裁判所
ア 事案の内容に鑑み、まず、相違点2−1−cに関する容易想到性について検 討する。
イ 前記4(1)及び(2)によると、甲2及び3には、前記第2の3(3)ア(ア)aのよ うに本件審決が認定する「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方 に延びる円柱部とからなるピンを備えた吹矢に使用する矢」(甲2・3技術事項) が記載されていると認められるが、それら甲2及び3に記載された矢は、いずれも、 (円錐形の)フィルムを備えたものではない。 また、前記4(3)によると、甲4において、重りの釘2)は頭部を矢の後方(プラス ティックフィルム1)が巻かれた側)に位置しており、フィルムに釘の円柱部全てが 差し込まれているものではなく、フィルムの先端部に重りの釘2)の頭部が接続され ているものでもない。 したがって、仮に、甲1発明に甲2〜4を適用しても、相違点2−1−cに係る 本件発明の構成には至らないから、甲2〜4は相違点2−1−cについての容易想\n到性を基礎付けるものではない。
ウ(ア) これに対し、甲5発明の矢については、釘4の円柱状部分全てがスカート 部6に差し込まれて固着されるとともに、スカート部6の先端部に連続して釘4の 丸い頭部4aが接続されているといえる。
(イ) しかし、甲1発明の矢は、矢軸5の後方に中空円錐状の羽根部6が篏合固着 されており、矢軸5を羽根部6に全て差し込む形で固着することについて、甲1に これを示唆し、又は動機付ける記載があるとは認められない。 この点、甲1において、矢じりは金属製とされ、標的台は台板と紙とクッション ボードから成るものとされ、クッションボードについては所定厚さ(約20mm)が 明記され、全長約10cmの吹矢の約5分の1程度を矢じり4及び矢軸5が占める第 3図が掲載され、吹矢の当たった状態を示すとされる第6図においては矢じり4の 先端が台板8に接している状態が示されていることを考慮すると、甲1において吹 矢が標的面に当たり「小気味の良い音」を発するについては、矢じり4の先端が台 板に到達することが少なからず寄与していることが窺われる。それにもかかわらず、 仮に矢軸5を羽根部6に全て差し込む形で固着した場合、第6図のように矢じり4 の先端が台板に到達するかには疑問を差し挟む余地がある。このことは、甲1発明 の矢について、矢軸5を羽根部6に全て差し込む形で固着するという構成を採用す\nることを阻害する事情となり得るところである。
(ウ) そうすると、甲1発明に甲5発明を適用することについては、示唆も動機付 けもなく、むしろ阻害要因があるともいえるから、甲1及び5に基づいて、当業者 において相違点2−1―cに係る本件発明の構\成とすることが容易になし得たもの とはいえない。
エ したがって、相違点2−1のうちその余の点について判断するまでもなく、 相違点2−1に係る本件発明の構成が容易想到であるとはいえない。\n
オ 原告の主張について
(ア) 原告は、羽根部分がピンから外れ、又は前側(円頭形部分側)にフィルムが ずれてしまうことから、甲1に接した当業者であれば、甲5に開示のようにフィル ムに円柱部を全て差し込む構成とする必要があり、動機付けがある旨を主張する。\n原告の上記主張は、動機付けとして、甲1や甲5の記載を根拠とするものではな く、物理法則ないし技術常識を指摘するものと解されるところ、原告が上記主張の 根拠として提出する実験結果報告書(甲12)については、実験に用いられた吹矢 の矢の素材や寸法等も明らかでなく(なお、甲1においては、羽根は、紙又は合成 樹脂材及び金属箔の単独又は組合せにより形成された最大外径10〜12mmの軽量 なものとされ、矢の全長は約10cmであるとされている。)、甲1発明の矢を適切 に再現した上でされた実験であることが担保されているとはみられない。また、そ の内容に沿わない被告提出の報告書(乙1)も存在する。さらに、接着剤の詳細に ついても不明であり、より強固な接着力を有する接着剤を選択するという方法が存 在しないことも裏付けられていない。したがって、前記報告書(甲12)に基づい て原告の主張するような動機付けがあると認めることはできず、その他、甲1発明 について矢軸5を羽根部6に全て差し込む形で固着するという構成を採る動機付け\nとなり得るような技術常識等を認めるべき証拠もない。 したがって、原告の上記主張は前記イ〜エの判断を左右するものではない。
(イ) 原告は、1)矢軸の途中にフィルムを巻き付ける構成とした場合、ピンの軸が\nフィルムの中央を通るように固定することが困難となり、上下方向で重心のブレを 生じ、命中精度に影響し得ること、2)上記構成とすると、吹矢を量産する際に差し\n込む部分の長さを一定にするための位置決めが困難であるのに対し、フィルムに円 柱部を全て差し込む構成とすると、同じ長さの吹矢を容易に製造することが可能\と なるといった点を踏まえても、甲1発明に甲5発明を適用する動機付けがあると主 張するが、命中精度や製造の容易性に関して甲1に示唆や動機付けというべき記載 は認められず、他に上記1)及び2)の点に関して甲1発明に甲5発明を適用する動機 付けとなり得るような技術常識等を認めるべき証拠もない。
◆判決本文
侵害訴訟の控訴審はこちら。
◆令和3(ネ)10049等
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2022.11. 8
平成31(ネ)10007 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年8月8日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(3) 特許法102条1項に基づく損害について
ア 適用関係
令和元年法律第3号による改正について 存続期間の満了により、本件特許権1の侵害行為は令和2年3月31 日までに終了しているところ、令和元年法律第3号による改正後の特許 法102条1項は令和2年4月1日から施行されたものであるが、改正 法附則には経過措置がないことから、本件特許権1の侵害行為には、上 記改正後の特許法102条1項が適用される。 一審被告は、改正法を遡及適用せずに旧1項を適用すべきであると主 張するが(前記第2の4(16)参照)、改正後の特許法102条1項2号は、 実施相応数量を超える数量又は特定数量(通常実施権を許諾し得た場合 に限る)に応じた実施料相当額を損害の額とするものであるところ、そ の実施相当額の損害が実体法上生じ得ないものとはいえないから、改正 法が実体法上の請求権を新たに創設したものとはいえない。したがって、 同号は、客観的には改正前から損害を構成するといえた実体法上の損害\nを推定する規定にとどまるものといえるから、一審被告の上記主張を採 用することはできない。
・・・
ウ 「単位数量当たりの利益の額」
原告の製品の1台当たりの限界利益の額が別紙1−1(1)のとおりである ことは、当事者間に争いがない。
エ 「その侵害の行為を組成した物」の譲渡数量等について
販売数
本件では、一審被告による被告表示器A及び被告製品3の生産、譲渡\n等の行為について間接侵害の成立が認められるが、被告製品3は、被告 表示器AにOSを提供することによって被告表\示器Aと原告の製品と同 等なものを生産するという限度において侵害行為を組成しているもので あるから、特許法102条1項の損害を算定するに当たり、被告表示器\nAと独立にその譲渡数量を論じる必要はない。 したがって、特許法102条1項の損害算定に当たっては、被告表示\n器Aの譲渡数量のみを算定基礎とすれば足りる。 そして、平成25年4月1日から令和2年3月31日までの被告表示\n器Aの販売数が別紙5に記載のとおりであることは、当事者間に争いが ない(なお、被告表示器Aについては、各月ごとの販売数は明らかでは\nないので、別紙5のとおり半期ごとの販売数量に基づき、以下、損害額 の算定を行うものとする。また、前記2(2)オのとおり、本件特許権1の 間接侵害が成立するのは平成25年4月2日以降であるところ、同月1 日の被告表示器Aの販売数の有無又はその数量が不明であるが、同日の\n譲渡等が7年にわたる期間の損害額全体に影響するのはごくわずかであ り、この1日分を含めるか否かの相違は以下の算定の中で吸収され、何 らかの影響を及ぼすことは想定し難いから、同日の販売数を改めて算定 することはせず、別紙5に記載の販売数をそのまま用いることとする。)。
譲渡数量
一審被告は、「その侵害の行為を組成した物」は直接侵害品であると ころ、被告表示器A及び被告製品3を購入した者の全てが本件発明1の\n実施品(直接侵害品)を生産しているのではないと主張する(前記第2 の4(16)参照)。しかしながら、間接侵害行為は特許権を「侵害するものとみなす」 (特許法101条)とされており、そして、特許権侵害の損害の額につ いて、「その侵害の行為を組成した物」(同法102条1項)とされてい るところ、前記ア のとおり、間接侵害にも同法102条の適用がある と解する以上、「侵害の行為を組成した物」とは間接侵害品を指すもの と解するべきである。
もっとも、特許法101条2号に係る間接侵害品たる部品等は、特許 権を侵害しない用途ないし態様で使用することができるものである。そ して、そのような部品等の譲渡は、当該部品等の譲渡等により特許権侵 害が惹起される蓋然性が高いと認められる場合には、譲渡先での使用用 途ないし態様のいかんを問わず、間接侵害行為を構成するが、実際に譲\n渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には、 結果的には、間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与していない。そう すると、そのような譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権 者の製品が販売できたとはいえないことになり、特許権者等に特許発明 の物の譲渡による得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲 渡によって得た利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定すること はできないというべきである。そして、このような場合は同法102条 1項1号の「販売することができないとする事情」に該当するものと解 するのが相当である。一審被告の主張は、仮に、直接侵害品の生産に用 いられた数量のみを損害算定の基礎とすべき主張が採用されない場合に は、同一の事情を「販売することができないとする事情」として主張す るとの趣旨も含むものと解され、その限度で採用することができる。 したがって、特許権者等の損害額の算定に当たっては、そのような販 売数量は、特許法102条1項の「譲渡数量」から控除されると解する のが相当である。
オ 「販売することができないとする事情」について
販売することができないとする事情(その1)
一審被告は、1)原告の製品が一審原告製のプログラマブル・コントロ ーラにしか接続できないこと、2)一審原告がプログラマブル・コントロ ーラ用表示器の市場において意味のあるシェアを有しておらず、本件発\n明1の技術的特徴による販売への貢献も極めてわずかであるから、被告 表示器A及び被告製品3の購入者のほとんどは、一審原告以外のメーカ\nーの製品を購入する、3)原告の製品は本件発明1の実施品ではないから 本件特許権1の侵害によって一審原告に損害が発生する余地はない旨を 主張する(以下、この主張に係る事情を「販売することができないとす る事情(その1)」という。)。
特許法102条1項1号の「販売することができないとする事情」と は、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する 事情をいうものである。
本件発明1の特徴的技術手段は、異常発生時におけるタッチによる接 点検索にすぎず、回路モニタ機能全体ではないことや、従来製品として、\nモニタ上に表示される異常種類のうち特定のものをタッチして指定する\nと、その指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラ ダー回路が表示され、異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定\nをタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して 行う製品が存在していたことは、前記2(2)イ において認定したとおり である。そうすると、本件発明1に係る機能を全て使用することができ\nる製品が原告の製品以外に存在していなかったとしても、コイルの指定 や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番 号を入力して行う製品は存在しており、そのような製品でも、異常現象 の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定した り、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりするこ と自体は可能であり、それほど複雑な操作を要するものではないといえ\nる。さらに、本件発明1の技術的範囲に含まれないものであっても、異 常発生時においてコイル検索のみを実施できるようにし、回路を戻る場 合には検索機能を用いずに戻る機能\を有する表示装置であれば、異常現\n象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定し たり、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりする という目的を達することに支障があるとは考えにくい。加えて、本件発 明1の特徴的技術手段である接点検索は、原告の製品にですら実施され ていないものであり、この特徴的技術手段が原告の製品の販売に貢献し ていないことは明らかである。しかも、この特徴的手段である接点検索 は、被告表示器A及び被告製品3の多数の機能\のうち、わずか一点に関 するものであって、その機能の極めて僅少な部分しか占めない。\n 以上からすると、本件発明1の技術的特徴部分が被告表示器A及び被\n告製品3の販売数に大きく寄与したものとはおよそ想定し難い。また、 一審原告のプログラマブル表示器(表示装置)における市場シェアは、\n別紙7−2の「その他」に含まれるにすぎない僅少なものである(甲3 1)上に、原告の製品は、一審原告製のプログラマブル・コントローラ にしか接続できない(争いがない。)のであるから、被告表示器A及び\n被告製品3が本件発明1の特徴的技術部分を備えないことによってわず かに販売数が減少したとしても、その減少数分を埋め合わせる需要が、 全て一審原告の方に向かうとも想定し難い。 したがって、本件では、被告表示器A及び被告製品3が本件特許1を\n侵害したことによって原告の製品が販売減少したとの相当因果関係は、 著しい程度で阻害されると認めるべきであり、被告表示器Aの販売数の\n99%について販売することができないとする事情があると認めるのが 相当である。
販売することができないとする事情(その2)
前記エ のとおり、一審被告が直接侵害品の生産に用いられた被告表\n示器Aの数量として主張するところは、「販売することができないとす る事情」の一要素として考慮することができるところ、一審被告は、前 記第2の4(16)(原判決第3の18(被告の主張)(1)ア c)のとおり、 1)輸出の除外、2)プログラマブル・コントローラに接続しない利用態様 の除外、3)一審被告製シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出 される事情、4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出さ れる事情、5)被告製品1−2についてオプション機能ボートを購入した\n割合から算出される事情、6)ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロ\nジェクトデータを有する被告表示器Aの割合から算出される事情を主張\nする(前記第2の4(16)参照。以下、この主張に係る事情を「販売するこ とができないとする事情(その2)」という。)。
そこで、検討するに、まず、一審被告が把握している被告表示器Aの\n輸出台数は、別紙7の1に記載したとおりであること、平成25年の一 審被告製のプログラマブル表示器の販売数量、販売金額、国内市場シェ\nアは、同7の2に記載したとおりであること、平成25年から令和2年 までの一審被告のプログラマブル・コントローラの国内総販売数、国内 市場シェアは、同7の3に記載したとおりであること、一審被告製シー ケンサ(プログラマブル・コントローラ)の販売実績、回路モニタ機能\nの実行が可能なシーケンサ等の割合は、同7の4に記載のとおりである\nこと、GT15(被告製品1−2)に装着可能なオプション機能\ボード の販売台数は、別紙7の5に記載のとおりであることが認められ(甲3 1、乙58ないし64、弁論の全趣旨)、これに反する証拠はない。 上記認定事実を前提に更に検討すると、1)国外に輸出された被告表示\n器Aについては、本件発明1が実施されるのが日本国外となり、属地主 義の原則から本件特許権1の侵害は生じ得ないから、一審被告から開示 された輸出台数は控除するのが相当であるが、その輸出台数を一審被告 は別紙7の1のとおり把握しているとし、これに疑念を差し挟む理由も ないところ、その台数が全体の販売数に占める割合は僅少である。2)プ ログラマブル・コントローラに接続しない被告表示器Aについても本件\n特許権1の侵害が生じないところ、その数量は、一審被告すらおおよそ の割合でしか示し得ていないものの(別紙2−1)、前記2(2)エ のと おり、ユーザは高額な機器である被告表示器Aの機能\を十全に利用する\nため回路モニタ機能等を利用しようと合理的に行動するものといえるか\nら、被告表示器Aをプログラマブル・コントローラに接続する割合は非\n常に高くなるものと推認される。3)一審被告製シーケンサ等に接続する 利用態様の割合については、前記2(2)エのとおり、プログラマブル・コ ントローラとプログラマブル表示器とを同一メーカのもので統一する傾\n向があると推認されることから、一審被告製シーケンサの国内市場シェ ア割合(別紙7−3)に従った割合で被告表示器Aが一審被告製シーケ\nンサに接続されるものとするのは不自然であり、当該シェア割合よりは 一定程度高い割合で一審被告製シーケンサと接続されるものと推認する のが相当であるが、他社の製品との組み合わせが僅少であるとまでは認 め難い。4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合については、被 告表示器Aがその仕様・機能\等からみて特定のシーケンサに用いられる とする特別な傾向があることまでもを認めるに足りる証拠はないから、 回路モニタ機能を利用できないシーケンサの販売割合(別紙7−4)は\nその割合のまま考慮することが相当である。5)被告製品1−2について オプション機能ボートを購入したユーザの割合(最大で約4分の1)に\nついては、一定の考慮をするものとするが、そもそも被告表示器Aに占\nめる被告製品1−2の割合は約●パーセントにすぎないから、いずれに しても、被告表示器A全体の中ではほとんど影響を及ぼさない。最後に、\n6)ユーザがワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロジェクトデータを\n作成する割合については、引用に係る原判決第4の2(2)(本判決前記1 (2)にて補正されたもの)において認定したとおり、一審被告がワンタッ チ回路ジャンプ機能を宣伝のポイントとしていたことや、被告表\示器A 及び被告製品3を購入等したユーザは回路モニタ機能等を用いることを\n強く動機付けられ、その機能がインストールされる可能\性もかなり高い といえること等に照らせば、ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いようと\nする者は相応の数に上るものと考えられるものの、具体的な割合を確定 するに足りる資料はない。
以上の観点から検討するところ、上記1)、2)、5)については、直接侵 害品の生産に用いられる被告表示器Aの数量に与える影響はわずか、あ\nるいは少ないが、上記4)及び6)については直接侵害品の生産に用いられ る被告表示器Aの数量に与える影響はかなり大きく、3)についても少な からぬ影響があるというべきである。なお、ここまでにおいて、これら の事情を独立の要素として考慮したが、例えば、ワンタッチ回路ジャン プ機能を用いるプロジェクトデータを作成するユーザは回路モニタ機能\ 等を使用できる機器を有しているなど、これらの要素は相互に関連性を 有する場合もあり得る。そこで、このような点も加味して、上記事情を 総合考慮すると、被告表示器Aの販売数の●●%が直接侵害品の生産に\nは用いられなかったものと推認することが相当である。したがって、こ の限度において、「販売することができないとする事情」があると認め る。
一審被告の主張について
一審被告は、ユーザからの不具合調査や技術支援の依頼への対応に応 じてユーザから取得しているプロジェクトデータから、本件発明1の実 施品の生産に用いられる被告表示器Aの数が推定できると主張する(前\n記第2の4(16)参照)が、これらのプロジェクトデータは、一審被告に対 して技術支援を求めるユーザ、不具合品として製品を返却してきたユー ザ、他社製表示器から一審被告製品に乗り換えたユーザから取得してき\nたプロジェクトデータというのであって(乙72)、全くランダム化さ れていないものであり、それらユーザが一審被告の製品を用いるユーザ の平均的な技術水準にあるとは認め難く、その主張を採用することはで きないそのほか一審被告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
一審原告の主張について
一審原告は、前記 3)の事情につき、引用に係る原判決第3の18(1) ア c(本判決前記第2の4(12)で補正されたもの)のとおり、プログラ マブル表示器を他社製のプログラマブル・コントローラに接続する利用\n態様は僅少である旨主張する。しかしながら、プログラマブル・コント ローラの市場シェアでは下位を占めるが、プログラマブル表示器のシェ\nアでは上位を占める社があり(乙58ないし64)、そのような社のプ ログラマブル表示器は他社製のプログラマブル・コントローラに接続さ\nれることを前提にされていると考えられる。このような点に鑑みると、 異なる社が製造するプログラマブル表示器とプログラマブル・コントロ\nーラとを組み合わせることも、当業界としてあり得る対応と推認される。 そうすると、プログラマブル表示器とプログラマブル・コントローラの\n親和性が好まれるといっても、他社製のものとの組み合わせることが僅 少であるとまでは認められないから、一審原告の上記主張を採用するこ とができない。
また、一審原告は、同c(b)(本判決前記第2の4(12)で補正されたもの) のとおり、1)被告表示器Aと接続できない場合がある「MELSEC Qn Aシリーズ」、「MELSEC Aシリーズ」、「MELDAS C6/C64」、「MELSE C iQ-Lシリーズ」及び「CNC C80シリーズ」などのシーケンサを購入 したユーザが被告表示器Aを購入するはずがない、2)単純な使用態様で あるスタンドアローン向けのシーケンサに回路モニタ機能等を有する高\n額な被告表示器Aを接続するユーザはいない旨主張するが、上記1)につ いていえば、仮に、一審原告の指摘するシーケンサが被告表示器Aと接\n続できないとしても、別紙7の4のとおり、一審被告製シーケンサ全体 に占めるその販売割合は●ないし●●●%と極めて僅少であって全体的 な傾向を全く左右させないものであるし、上記2)についていえば、一審 被告が主張するように言い切ることができることを認めるに足りる証拠 はない。そのほか一審原告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
以上のとおり「販売することができないとする事情(その1)」とし て、主に本件発明1の売上げへの貢献に関する観点からの99%の控除 と「販売することができないとする事情(その2)」として、直接侵害 品の生産に用いられていないとの観点からの●●%の控除が認められ、 両者は独立して考慮できる控除要素であるから、結局、別紙8に記載の とおり、被告表示器Aの譲渡数量から、99%の譲渡数量を控除し、更\nにその数量から●●%の譲渡数量を控除した数量(控除数量は、●●● ●%となる。)について「販売することがのできないとする事情」を認 めるのが相当である(この数値は、一審原告が自認する59/60≒0.98 3を下回るものではない。)。
カ 特許法102条1項1号の損害
前記イないしオの判断を踏まえると、特許法102条1項1号に基づく 一審原告の損害額は、別紙8のとおり、5062万9205円と認めるの が相当である。
キ 特許法102条1項2号の損害
特許法102条1項2号は、特定数量がある場合、その数量に応じた実 施料に相当する額を損害の額とすることができると定める一方で、同号括 弧書きは、特許権者等が当該特許権者等の特許権について実施権の許諾を し得たと認められない部分を除く部分を除外しているから、侵害者の侵害 行為により特許権者がライセンスの機会を喪失したとはいえない場合には 実施料に相当する額の逸失利益が生じるものではないことが規定されてい る。
前記オのとおり、本件において認められた特定数量は本件発明1の特徴 的技術部分が被告表示器A及び被告製品3の販売量に貢献しているとは認\nめられない数量、機能上の制約あるいは一審原告のシェア割合からみてユ\nーザの需要が原告の製品に向かず、一審原告以外の他社への購入に振り向 けられる数量、直接侵害品の生産に向けられず本件発明1の技術的範囲に 属しない表示器となる数量を合わせたものであるから、そのように本件発\n明1が販売数量に貢献し得ていない製品や一審被告以外の他社が販売する 製品について、一審原告が一審被告に本件発明1をライセンスし得るとは 認められない。そうすると、特許法102条1項2号の損害を認めることはできない。
(4) 特許法102条2項に基づく損害について
ア 本件の間接侵害への特許法102条2項の適用の可否
特許法102条2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ、この規定の趣旨は先 に同条1項について述べたのと同様であると解される。したがって、先に 同条1項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条2項 の適用を肯定するのが相当である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
平成25年4月から令和2年3月までの被告表示器A及び被告製品3の\n販売額が別紙3ないし6に記載されたとおりであること、被告表示器Aの\n限界利益率が20パーセントを下らないこと、被告製品3の限界利益率が 原判決別紙「被告の変動費の内訳、加重平均値及び限界利益率」に記載さ れたとおりであることは、当事者間に争いがない。
ウ 推定覆滅事由について
特許法102条2項は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が 得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果 関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅 されるものと解される。ここで、特許法101条2号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵 害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという 関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の 損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者 が受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、こ のような場合は同法102条2項の推定を覆す事情に該当するものと解 するのが相当である。そうすると、先に特許法102条1項1号につい て述べた事情(前記(3)オ 。以下「推定覆滅事由(その1)」という。) は、特許法102条2項の推定覆事由として捉えることができるから、 被告表示器A及び被告製品3の利益の99%について覆滅事由があると\n認めるのが相当である。さらに、被告表示器A及び被告製品3のうち、\n直接侵害品の生産に用いられなかった分については一審原告の受けた損 害額であるとの推定を覆す事情(以下「推定覆滅事由(その2)」とい う。)があるというべきであるところ、直接侵害品の生産に用いられな かった被告表示器Aの数は、前記(3)オ と同旨の理由により、全体の● ●%に及ぶと認められるから、●●%の利益について推定が覆滅される ものと認めるのが相当である。また、被告製品3についても、直接侵害 品の生産に用いられたものと、そうではないものとが生じるが、特にど ちらかに偏るべき事情はうかがわれないから、そのインストール先の表\n示器Aと同様の割合で、その●●%の利益について推定が覆滅されるも のと認めるのが相当である。
以上のとおりであり、推定覆滅事由(その1)として、主に本件発明 1の売上げへ貢献に関する観点から導いた99%の減額と推定覆滅事由 (その2)として、直接侵害品の生産に用いられているかの観点から導 いた●●%の減額が認められ、両者は独立して考慮できる減額要素であ るから、結局、受けた利益のうち、●●●●%の額について推定覆滅事 由を認めるのが相当である(この数値は、一審原告が自認する59/60 ≒0.983を下回るものではない。)。
エ 特許法102条2項の損害
前記イ及びウの判断を踏まえると、特許法102条2項に基づく一審原 告の損害額は、別紙9のとおり、合計2424万7080円と認めるのが 相当である。
オ 特許法102条3項の重畳適用について
仮に、特許法の解釈上、特許法102条2項と3項の重畳適用が排除さ れていないとしても、その適用は同条1項2号の趣旨にかなったものとな るのが相当と思料されるべきところ、本件においては、同条2項の覆滅事 由は前記ウ 及び のとおり、そもそも同条1項2号の適用のない場合で あるから、同条3項を重畳適用できる事案ではない。 したがって、いずれにせよ、一審原告の上記主張を採用することはでき ないものである。
(5) 小括
前記(3)及び(4)の判断を踏まえると、前記(3)にて認定の特許法102条1項 に基づく原告の損害額(5062万9205円)の方が高いことから、その 額を一審原告の損害と認める。
(6) 弁護士費用
一審原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ(当裁判 所に顕著な事実)、一審被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用は、500万円と認めるのが相当である。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.11. 8
令和4(ネ)574 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和4年9月30日 大阪高等裁判所
控訴人において、上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1 のみに限るとの規制はなく、上記ログインパスワードは、西脇支社の従業員 には周知のものであり、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員もこれを知って いた。
・・・
控訴人の就業規則第31条(12)(甲16)には、控訴人の「内外を問わず、 在職中または退職後においても、」控訴人、「取引先等の機密、機密性のあ る情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード、および会社の不利 益となる事項を他に開示、漏洩、提供しないこと、またコピー等をして社外 に持ち出さないこと。」と規定する服務心得があり、控訴人は、被控訴人P1 の入社時に同被控訴人から誓約書(甲17)を徴求しているものの、その内 容は上記就業規則を遵守する旨の内容にとどまるものである。そして、控訴 人において、被控訴人P1に対し、見積書記載の本件顧客情報及び本件価格情 報が、上記規定の対象になることはもとより、これら情報を含む見積書記載 の情報が営業秘密であることに関する注意喚起がされたことはなく、また取 引案件ごとに作成される見積書の取扱いに関する研修等の教育措置が行われ たこともない。
・・・
控訴人本社が直接発注業者に見積書を送付 する場合は、西脇支社に見積書がファックスで参考送信されることもあった が、そうした見積書の紙媒体の取扱いについては、控訴人において保管場所 や廃棄方法が定められていたとの事実はない。
・・・
「控訴人本社から本件見積書のデータが送信され、保存される西脇支社のコン ピューターにはログインパスワードが設定されていたが、控訴人において、 上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1のみに限るとの規 制はなく、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員も上記ログインパスワードを 知っていた。
2022.11. 8
令和4(ネ)1273 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月30日 大阪高等裁判所
ところで、民訴法6条1項は、「特許権」「に関する訴え」については、東 京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属する旨規定し、同条3項本文は、 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第1審として審理した「特許権」「に関 する訴え」についての終局判決についての控訴は東京高等裁判所の管轄に専属 する旨規定し、さらに知的財産高等裁判所設置法2条が、上記訴えは、同法に 基づき東京高等裁判所に特別の支部として設置された知的財産高等裁判所が取 り扱う旨規定している。上記各規定の趣旨は、「特許権」「に関する訴え」の 審理には、知的財産関係訴訟の中でも特に高度の専門技術的事項についての理 解が不可欠であり、その審理において特殊なノウハウが必要となることから、 その審理の充実及び迅速化のためには、第1審については、技術の専門家であ る調査官を配置し、知的財産権専門部を設けて専門的処理態勢を整備している 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属させることが適当であり、控 訴審については、同じく技術の専門家である調査官を配置して専門的処理態勢 を整備して特別の支部として設置した知的財産高等裁判所の管轄に専属させる ことが適当と解されたことにあると考えられる。 そして、このような趣旨に加え、民訴法6条1項が「特許権」「に基づく訴 え」とせず「特許権」「に関する訴え」として、広い解釈を許容する規定ぶり にしていることも考慮すると、「特許権」「に関する訴え」には、特許権その ものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に 関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴 訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関 係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽 象的に想定される場合も含まれるものと解すべきである。 なお、専属管轄の有無が訴え提起時を標準として画一的に決せられるべきこ と(民訴法15条)からすると、「特許権」「に関する訴え」該当性の判断は、 訴状の記載に基づく類型的抽象的な判断によってせざるを得ず、その場合には、 実際には専門技術的事項が審理対象とならない訴訟までが「特許権」「に関す る訴え」に含まれる可能性が生じるが、民訴法20条の2第1項は、「特許権」\n「に関する訴え」の中には、その審理に専門技術性を要しないものがあること を考慮して、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所において、当該訴訟が同法6 条1項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審 理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を 避けるため必要があると認めるときは、管轄の一般原則により管轄が認められ る他の地方裁判所に移送をすることができる旨規定しているのであるから、こ の点からも、上記「特許権」「に関する訴え」についての解釈を採用するのが 相当である。
3 そこで、以上に基づき本件についてみると、本件訴状の記載によれば、本件 が、本件契約の債務不履行に基づく損害賠償の訴えとして提起されたものであ ることは明らかであるが、訴状によって控訴人が主張する債務不履行に基づく 損害賠償請求は、本件発明が、本件契約に基づく研究(本件受託研究)により 得られた成果物であるのに、被控訴人がこれを本件研究者個人の発明であり控 訴人と共同出願することは出来ないとして、本件研究者単独で特許出願した行 為が、本件契約14条1項に規定する「被控訴人は、本件研究の実施に伴い発 明等が生じたとき・・・は、控訴人に通知の上、当該発明等に係る知的財産権 の取扱いについて控訴人及び被控訴人が協議し決定するものとする。」との協 議義務に違反し、また、控訴人が権利の承継について希望していたにもかかわ らず、被控訴人が控訴人と協議を行うことなく本件研究者による特許出願を強 行した行為が、本件契約14条2項に規定する「被控訴人は、前項の知的財産 権を控訴人が承継を希望した場合には、控訴人に対して相当の対価と引き換え にその全部を譲渡するものとする。」との義務にも違反し、その結果、控訴人 が本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀なくされた出捐をも って損害と主張するものである。
ところで、前者の本件契約14条1項の規定は「知的財産権」について規定 しているが、本件では、未だ特許がされていない特許出願された段階の本件発 明の取り扱いについて争われているから、本件発明に係る「特許を受ける権利」 が同項にいう「知的財産権」に含まれることを前提に同項違反が主張されてい るものと解されるし、また、後者の本件契約14条2項の規定関係についても、 ここで控訴人が主張している権利は、上記同様、本件発明に係る特許を受ける 権利と解されるから、ここでも同権利が同項にいう「知的財産権」に含まれる ことを前提に同項違反が主張されているものと解されるのであって、いずれも、 特許を受ける権利が本件の請求原因に関係しているといえる。 そして、控訴人は、本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀 なくされた出捐をもって、上記各条項違反を理由とする債務不履行により生じ た損害と主張し、その賠償を被控訴人に求めているのであるが、本件訴状の記 載によれば、被控訴人は、本件発明に係る特許を受ける権利が本件受託研究に より得られた成果物でないことを理由として、本件研究者のした特許出願が本 件契約14条1項、2項の債務に違反しないと争っていることが認められるか ら、本件訴状からうかがえる債務不履行に基づく損害賠償請求の成否は、本件 発明が本件受託研究により得られた成果物であるか否かが争点として判断され るべきことが見込まれ、その判断のためには、本件発明が本件受託研究の成果 物に含まれるかという専門技術的事項に及ぶ判断をすることが避けられないも のと考えられる。
したがって、本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟として訴訟提起 された事件であるが、その訴状の記載からは、その争点が、特許を受ける権利 に関する契約条項違反ということで特許を受ける権利が請求原因に関係してい るといえるし、その判断のためには専門技術的な事項の理解が必要となること が類型的抽象的に想定されることから、本件は「特許権」「に関する訴え」に 含まれると解するのが相当である(なお、前記1(3)のとおり、原審は、控訴人 主張に係る債務不履行の成否を判断する前提問題として、本件発明が、被控訴 人が本件契約に基づき協議義務を負うべき本件受託研究の成果物に含まれるか 否かの争点に関して、本件受託研究が、2ステップ(1)ヒトの血液を用いず、 培養細胞を用いて不活性型Gc−Proteinを合成、2)これを構成する二\nつの糖鎖(Gal(ガラクトース)及びSA(シアル酸))を、酵素の作用に より切断)を経る方法によって活性型GcMAFを生成する方法を研究すると いうものか、又は、本件発明のように、特定の細胞を特殊な培養条件下で合成 し、酵素処理を要することなく1ステップで活性型GcMAFを生成する方法 に関する研究をも含むものか、といった専門技術的事項にわたると考えられる 事項ついて審理判断をしている。)。
4 そうすると、大阪府内に主たる事務所を有する控訴人と神戸市内に主たる事 務所を有する被控訴人との間における、控訴人の被控訴人に対する債務不履行 の損害賠償請求である本件は、管轄の一般原則によれば債務の義務履行地であ る控訴人の主たる事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所又は被控訴人の主 たる事務所の所在地を管轄する神戸地方裁判所が管轄権を有すべき場合である から、本件訴訟は、民訴法6条1項2号により大阪地方裁判所の管轄に専属す るというべきであって、神戸地方裁判所において言い渡された原判決は管轄違 いの判決であって、取消しを免れない。
2022.11. 8
令和3(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月4日 知的財産高等裁判所
(1) 訂正の目的の判断の誤りについて
ア 「特許請求の範囲の減縮」の目的の有無について
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項1は、本件訂正前 の請求項1の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解\nすることができるから、訂正事項1は、「特許請求の範囲の減縮」(特許法 134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものということができる、
2)訂正事項2は、本件訂正前の請求項3の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構\n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項2は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項2は、本件訂正前の請 求項3の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり(甲46)、本件訂正前の請求項1の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項3の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」(【00 06】)、「本実施形態の噴射製品は、噴口から15cm離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の50%平均粒子径r15と、噴口から30 cm離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r30との粒子径比(r30/r15)が、0.6以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成(たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の\n各種物性等)は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」(【0010】)、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比(r 30/r15)が0.6以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から30cm離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」(【0023】)、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比(r30/r15)が0.6以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」(【0024】)、「以上、本実施形態の噴射製 品(ポンプ製品)によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比(r30/r15)が0.6以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」(【0028】)、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比(r 30/r15)が0.6以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」(【0044】)、「表1に示されるように、粒子径比\n(r30/r15)が0.6以上となるよう調整された実施例1〜14の噴 射製品は、N,N−ジエチル−m−トルアミド(ディート)を配合した 噴射製品(たとえば表2に示される参考例1)と同程度まで粘膜刺激が\n低減された。また、たとえば実施例1〜3と実施例11〜13との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品(アクチ ュエータ)の寸法等(噴射方式、噴口径、1回吐出量等の諸条件)が異 なる場合であっても、粒子径比(r30/r15)が0.6以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」(【0052】)との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項1の 「前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の50%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子 径比(r30/r15)が、0.6以上となるよう調整され」との構成又は\n本件訂正前の請求項3の「前記噴口から15cm離れた位置における5 0%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置における5 0%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)が、0.6以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、\n本件明細書には、本件訂正前の請求項1及び3の上記各構成にした場合\nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。 そうすると、訂正事項1及び2により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項1及び3の上記各構成によって奏される作用効\n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項1及び2は、本件訂 正前の請求項1及び3の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項1及び2は、「特許請求の範囲の減縮」(特許 法134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項1は、害虫忌避組成物を充填した物の発明(本件訂正 前の請求項1)において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ\nれたものと理解することができ、また、訂正事項2は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明(本件訂正前の請求項3)において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると\nして、訂正事項1及び2は、本件訂正前の請求項1及び3の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
(2) 小括
以上のとおり、訂正事項1及び2は、「特許請求の範囲の減縮」(特許法1 34条の2第1項ただし書1号)を目的とするものと認められないから、そ の余の点について判断するまでもなく、本件訂正は同号に適合しない。 そうすると、本件審決には、本件訂正の訂正要件の判断に誤りがあり、こ の判断の誤りは、本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る発明 の要旨認定の誤りに帰するから、本件審決は取り消されるべきものである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 減縮
>> ピックアップ対象
2022.11. 8
令和3(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月7日 知的財産高等裁判所
(ア) 原告は、最初の親出願の明細書等について、発明が解決しようとする課題、 課題を解決するための手段、発明の効果及び実施形態に係る明細書の記載からする と、あくまで、かしめ部・逃げ空間あり構成に係る技術的事項が導かれるのであっ\nて、特に、発明が解決しようとする課題に照らし、かしめ以外の固定手段を用いる ことは同明細書等には記載されておらず、明細書の段落【0018】に、かしめ部 あり構成を前提とした逃げ空間あり構\成を必須とする旨の記載があることも考慮す ると、同明細書等に記載された発明は、逃げ空間あり構成を必須とするものである\nなどと主張する。 しかし、最初の親出願の明細書中、発明が解決しようとする課題等において、か しめ部・逃げ空間あり構成に係る事項が特に取り上げられて深く検討されていると\nしても、そのことから直ちに、最初の親出願の明細書等に記載された発明が上記構\n成を含むものに限定されるものではない。
前記(1)アのとおり、最初の親出願の出願当時、固定手段として溶接や接着も選択 肢として存在していたことが認められるのであるから、同明細書等における記載も それを前提に理解すべきものである。そして、前記ア(ア)〜(ウ)のように最初の親出 願の明細書に記載されていたといえる本件発明1に係る構成や、当該構\成における 上板部材及び下板部材による回転子積層鉄心の上下からの押圧並びに樹脂ポット内 の樹脂の磁石挿入孔への充填といった機序自体が、かしめ部あり構成であるか、か\nしめ部なし構成であるかによって影響を受けるものともみられない。そうすると、\n最初の親出願の明細書等には、1)本件発明1を含む発明が記載された上で、2)かし め部あり構成の場合に当該発明を用いる際の問題点等について、逃げ空間あり構\成 などが更に記載されているというべきであって、上記2)の記載の存在によって上記 1)の記載が存在しないものとはいえないところである。
(イ) 上記に関し、原告は、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の積層され た鉄心片の固定手段として、かしめが技術常識となっていたことから、最初の親出 願の明細書等の記載について固定手段を特定の手段に限定するものではないとはい えない旨を主張するが、原告が主張する上記技術常識が認められないことは、前記 (1)イのとおりである。
(ウ) また、原告は、「かしめ積層されていても回転子積層鉄心の鉄心片の板厚が0. 5mm以下でないもの」(鉄心片の板厚が0.5mm超のもの)について、当業者は 通常想定しないなどと主張するところ、かしめ積層された回転子積層鉄心の鉄心片 の板厚が0.5mm以下でないものは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下い ずれかの面から少しの範囲で突出してしまうことをもって、同板厚が0.5mmを 超える全てにおいて、直ちに、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上下いずれかの 面から少しの範囲で突出するとはいえないと理解できるものではないとしても、本 件全証拠をもってしても、最初の親出願の出願当時、回転子積層鉄心の鉄心片につ いて、板厚0.5mm以下のものが用られる場合が多かったという事情を超えて、 板厚0.5mm超のものが選択肢となっていなかったといった事情は認められない。 この点、板厚0.5mm超のものを用いる例があったことは、乙5の記載(前記2 (1))やその他の証拠(乙7〜10、17、18)からも認められるところである。 さらに、最初の親出願の明細書の段落【0004】には、「この特許文献1記載の 技術においては、回転子積層鉄心を形成する各鉄心片がかしめ積層された特に鉄心 片の板厚が0.5mm以下の薄いものでは、かしめ部の一部が回転子積層鉄心の上 下いずれかの面から少しの範囲で突出してしまう」と記載されており、「鉄心片の板 厚が0.5mm以下の薄いもの」が全体の中から特に取り上げられた例であること が明記され、それ以外の場合(鉄心片の板厚が0.5mmを超えるもの)の存在が 示唆されているから、仮に、通常は板厚0.5mm以下のものを想定している当業 者においても、同段落の記載に接した場合には板厚0.5mm超のものを選択肢と して考慮し得るといえる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 分割
>> ピックアップ対象
2022.11. 8
平成31(ワ)2614 商標使用料等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年10月25日 東京地方裁判所
前記前提事実(6)のとおり、本件においては、原告代表取締役の肩書が付さ\nれたAの記名押印及び被告代表取締役の肩書が付されたDの記名押印のある\n本件商標使用許諾契約書が存在するところ、同契約書の印影が被告代表取締\n役印により顕出されたものであることについては、当事者間に争いはないも のの、被告は、同印影がDの意思に基づいて顕出されたことを否認し、Aが Dの承諾なく押印したものであると主張する。 本件において、Aが被告の代表取締役に就任した当初からB及びDの代表\ 取締役印をAが保管していたことについては、当事者間に争いがない。加え て、証拠(乙100及び112)及び弁論の全趣旨によれば、平成11年1 2月1日にAが被告の代表取締役に就任した頃から、被告の業務に実質的に\n関与していたのはAのみであり、他の代表取締役らが業務に関する意思決定\nを行うことはなかったものと認められる。そうすると、Aは、被告の他の取 締役らの同意を得ずに本件商標使用許諾契約書を作成することが可能かつ容\n易な状況にあったといえる。
また、前記1(1)ないし(3)のとおり、本件各物件は、被告所有に係る物件で あり、かつ、いずれの名称も被告内部においてか又は被告と自治体の協議に よって決定されたものであるにもかかわらず、本件各物件に係る事業の委託 を受けたにすぎない原告が、本件各物件の名称そのものである原告各商標の 登録出願をすることは不自然であるといわざるを得ない。 さらに、被告内部においてか又は被告と自治体の協議によって決定された 本件各物件の名称と同一の原告各商標の使用の対価を、その決定に何ら関与 していない原告に支払うことを被告が承諾するとは考え難く、本件全証拠に よっても、被告がこのような内容の本件商標使用許諾契約を締結することに 合理的な理由があったことを示す事実は認められない。
一方、原告は、本件商標使用許諾契約の締結により、被告から原告各商標 の使用料を得られるから、原告の代表取締役であるAにおいて、同契約に異\n議を述べることが予想されるDやBに諮ることなく、本件商標使用許諾契約\n書を作成する動機があるといえる。 そうすると、Aが本件商標使用許諾契約書にDの承諾なく同人の代表取締\n役印を押してこれを作成した可能性が認められるというべきであって、本件\n商標使用許諾契約書の被告作成部分が真正に成立したと推定することはでき ず、他に本件商標使用許諾契約書が真正に成立したことを認めるに足りる証 拠はない。 よって、本件商標使用許諾契約書が真正に成立したと認めることはできず、 同契約書によって本件商標使用許諾契約が成立したと認めることもできない。
・・・
商標権の行使も、商標の取得の経過やその意図、標章の利用の態様、その 行使の態様等諸般の事情を考慮し、権利の濫用に当たり許されない場合があ る。
本件においては、前記1(1)のとおり、原告各商標は、被告が被告の事業名 又は被告が所有する本件各物件の名称として決定したものであり、周辺住民 に対して本件各物件の名称として周知されていったものである上、前記1(3) の認定事実及び証拠(甲A210並びに乙37、38、40及び103)に よれば、本件各物件の貸与業務については、これまで、被告を事業主として、 又は原告と被告の名称が併記された上で、広告が出され、宣伝されていたと 認められることからすると、原告各商標によって表示される本件各物件の貸\n与業務の主体、すなわち、当該役務の出所は、被告であるか又は被告及び原 告であるといえる。
他方で、原告は、被告との関係において、本件各物件を利用した事業及び 本件各物件の管理の委託を受けた受託者にすぎないものであり、原告が原告 各商標の周知に貢献したことがあるとしても、それは受託業務の一環として 位置付けられるものにすぎない。このような立場にあるにすぎない原告が業 務の委託者である被告に対して原告各商標に係る排他的かつ独占的な権利を 主張できるとする正当な理由は認め難い。 また、原告が被告に対して原告各商標権を行使するに至った経緯は、前記 1(5)アないしエのとおりであるところ、かかる経緯に加え、同オの他の訴訟 の状況も併せ考慮すれば、原告の被告に対する原告各商標権の権利行使は、 原告の代表取締役であるAが被告の取締役を解任され、それに伴って被告の\n口座名義が変更されたことにより、本件各業務委託契約に基づく管理報酬が 支払われなくなったことに対する対抗手段としてされたものであって、今後 も原告及びその関連会社が本件各物件の事業及び管理業務を続けることを被 告に承諾させる目的に基づくものと推認することができる。 他方で、被告による被告ウェブサイトの開設及び同ウェブサイト上での被 告標章4ないし6の使用は、前記1(4)の経緯によるものであって、被告にと って必要かつ正当なものであるといえること、原告各商標は、本件各物件の 名称として周辺住民に周知されている上(弁論の全趣旨)、前記前提事実(1) オ(ア)のとおり、一部地方自治体の施設として利用されていることなどを考 慮すると、原告商標権を侵害することのないよう、被告に本件各物件の名称 を変更し、又は同名称を表示せずに、被告ウェブサイトにおいて本件各物件\nの貸館又は貸室に係る申込みの誘引をすることは、通常期待できないという\nべきであって、被告が被告ウェブサイトにおいて被告標章4ないし6を使用 することには、正当な理由があると認められる。
しかも、本件各物件の管理業務は、依然として全般的に原告又はその関連 会社が行っており、被告が被告ウェブサイト上で本件各物件の賃借等の申込\nみを受け付けていることはうかがわれず、被告は、事実上これらの物件の管 理ができない状態に陥っているといえるから、当該役務の出所の混同が生じ ることにより、原告が、現に損害を被っているとは認め難く、かつ、将来的 にも損害を被るおそれがあるとも認め難い。 以上のような事情を総合考慮すると、原告の被告に対する不法行為に基づ く損害賠償請求を認めることは、公正な競争秩序を害するといえ、権利の濫 用として許されないものと解するのが相当である。
(2) これに対し、原告は、被告において、原告が原告各商標の商標登録を行う ことを被告が認めていたこと、原告と被告との間で原告各商標に関して本件 商標使用許諾契約が締結されていること、被告は原告に対して長年にわたり 商標使用料を支払ってきたことに基づき、Aが被告の取締役を解任されたこ ととは関連がなく、原告は従前から原告各商標に係る権利行使をしたもので ある旨主張する。
しかし、前記2で認定したとおり、本件においては、本件商標使用許諾 契約の存在を認めるに足りず、また、Aが原告の名義で原告各商標を取得 すること及び本件各商標の使用料を被告が原告に支払うことにつき他の取 締役又は株主の承諾を受けたとの事実を認めるに足りないから、原告の主 張は、その前提を欠くものであって、採用することができない。
(3) したがって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は、権利 の濫用(民法1条3項)であるといえるから、原告は、被告に対し、同損害 賠償請求に係る権利を行使することができない。
2022.11. 4
平成30(ワ)17968 著作権 民事訴訟 令和4年8月30日 東京地方裁判所
以上のように、PMポータルを基盤としPMポータルのWebフレーム ワークを用いて作成されたことに起因して、(ア)部分の多くはPMポータル のWebフレームワークを構成するプログラムファイルから構\成されてお り、(ウ)部分は、PMポータルのWebアプリケーション部を参照して作成 され、データの処理や画面の表示などの中核的な機能\は(ア)部分を参照して 実行するため、その内容は、自由度が制約され、基本的な命令文を列挙し て、変数にデータを代入する処理や画面を表示するためのHTML文書が\n記述された部分が多くを占めていること(前記第2の1(5)イ、前記イ)、 作成、表示される医事文書の基本的な様式も通知により定められるなどし\nていることから、各プログラムにおいて変数に値を設定する処理や画面を 表示するためのHTML文書を記述するに当たっても個性を発揮する余地\nが乏しい。これらの(ア)及び(ウ)部分の特性から、電子カルテシステムに適用 するために、PMポータルを修正し新たに作成した部分があるからといっ て、そのことが直ちに本件31個の各プログラムの表現上の創作性につな\nがるとはいえない(前記ウ )。そして、原告は、本件各31個の各プロ グラムがそれぞれ著作物であり、それらに創作性があると主張するところ、 原告が本件31個の各プログラムの創作的表現であると主張する具体的な\n各点について、本件31個の各プログラムを含む(ア)及び(ウ)部分が上記のと おりの特性を有する部分でありそこにおけるプログラムもその特性の下に あるものであることにも関係し、原告が創作性があるとして主張する具体 的な記述等はいずれもありふれたといえるものなどであって、それらに独 自に著作物といえる程度の表現上の創作性を認めるに足りない(前記ウ\n〜 )。 以上のとおり、本件31個の各プログラムにPMポータルを離れた独自 の創作性があるとは認めるに足りない。
・・・・
原告プログラム4と被告プログラムにおいて共通する本件共通箇所は、原告 プログラム4においては、(オ)部分に用いられているORCAから受信したXM Lデータを解析する部分の一部である。 本件共通箇所のうち、オープンソースである「XML_Unserializer.php」を 用いた部分は、その仕様に基づくインスタンスを記述したものであり(前記1 (2)ウ )、その記述例もインターネットウェブサイトにおいて公開されている ものであって(乙56)、ありふれた表現であって、創作性が認められない。\nまた、本件共通箇所のその余の部分は、異なる施設間で診療情報を電子的に 交換するために制作された規約であるMML及びCLAIMにおいて定義され たタグ(用語)(前記1(2)ウ )を、「XML_Unserializer.php」の仕様に従 って記述した(乙62)ありふれた表現であって、創作性が認められない。\n以上によれば、本件共通箇所に創作性があると認めるに足りない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2022.10.26
令和3(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年10月17日 知的財産高等裁判所
訂正されたクレームは下記です。
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。\n
ア 訂正事項1について 訂正事項1は、前記第2の2(1)のとおり、本件発明1の「縦横方向に等 間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを 前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの 方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成を、本\n件訂正発明1の「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子 点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°の2 倍である90°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの 程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成に訂正するものであ\nる。
本件訂正前の上記構成は、任意の45°間隔による8方向をドットの配\n置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件\n訂正後の上記構成は、縦横の4方向をドットの配置に利用できる方向とし\nて、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ド\nットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異\nなる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には\n立たない。したがって、訂正事項1は、特許法134条の2第1項ただし 書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
イ 訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1による請求項1の訂正に伴い、特許請求の範 囲の記載と明細書の記載との整合を図るため、対応する本件明細書【00 09】の記載を訂正事項1と同様の内容で訂正するものであるところ、前 記アのとおり、請求項1に係る訂正事項1が認められない以上は、訂正事 項2は、その訂正に係る請求項について訂正をしないものと帰すから、訂 正事項2も訂正要件を充足しない(特許法134条の2第9項、126条 4項参照)。
ウ 原告の主張について
原告は、前記第3の1(1)ア のとおり、1)訂正事項1は、8方向のう ちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを4方向にする制限 を直列的に付加するものである、2)「いずれかの方向に、どの程度ずら すか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことの できる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請 求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第3の1(1)ア にて主張するように、 本件発明1の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内 容を定義し」との構成は、1つの単一な構\成としてデータ内容を定義し ているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされ る全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点 を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずら されていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定 義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情 報の定義に利用されているというものではない。この点、原告は、「縦横 方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情 報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした方向のう ちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」 との記載の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」を、ずらす方向の 数を規定するものである旨主張する。しかしながら、「方向の数」との趣 旨を「どの程度」との文言で表現したとするのは文言解釈として不自然\nであって、「等距離で45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、 どの程度ずらすか」とは、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」 とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該 格子点を基準として定義し得る情報を特定する際に、ドットをずらすの は等距離で45°ずつずらした各方向のうちどの方向にするのか、ずら されるドットは等心円上に配置されることになるが、この等心円の半径 をどの程度にするのかによってデータ内容を定義する趣旨であると理解 するのが自然である。また、本件明細書(本件訂正後)にも、1)「デー タは、図103に示すように、ドット605を格子領域内の中心点から どの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。 同図では、中心から等距離で45度ずつそれぞれずらした点を8個定義 することによって単一の格子領域で8通り、すなわち3ビットのデータ を表現できるようになっている。」(【0191】の前半)、2)「なお、さ らに中心点から距離を変更した点をさらに8個定義すれば16通り、す なわち4ビットのデータを表現できる。」(【0191】の後半)との記載\nがある(本件訂正前にも、別紙記載のとおり、「格子領域」とある部分の 一部が「格子ブロック」となっているほかは同旨の記載がある。)のであ るから、特許請求の範囲の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」は、 これらの記載に対応するものと解するのが自然であるし、上記1)及び2) のどちらも中心点からの距離についての記載であって、「どの程度ずらす か」が方向の数をいうものでないことは明らかである。 そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味 があるというものではなく、8方向全部が一体となり、中心点からの距 離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、8方 向を4方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることので きる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについ て選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端 的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきで ある。以上によれば、訂正事項1を発明特定事項の直列的付加又は択一的要 素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と 解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはでき ない。
原告は、前記第3の1(1)ア のとおり、数値による限定は、数値によ って限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、8方向 から4方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記 におい て説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又 は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるか ら、その主張を採用することはできない。
なお、本件審決には、「(逆に、4個しか定義できない構成を8個定義\nできる構成に変更する場合であれば、そのための構\成を付加し、上位概 念から下位概念に限定したといえる余地もある。)」(6頁)旨の説示がみ られるが、単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左 右するものではない。
エ 小括
以上のとおりであるから、その他の点について検討するまでもなく、本 件訂正は訂正要件を満たさないものであるから、これを認めなかった本件 審決の判断には誤りがない。
(2) 取消事由について
前記(1)のとおり、本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りはない ところ、原告は、本件訂正が認められなかった場合の本件審決の誤りを主張 するものではないから、本件訂正が認められた場合についての予備的請求の\n当否について判断するまでもなく、取消事由は理由がないことになる。
(3) サポート要件の充足について
ア 原告の予備的主張中には、前記第3の1 アのとおり、本件発明がサポ ート要件を充足する旨の記載があり、その趣旨や内容は判然としないもの ではあるものの、これは、本件訂正を認めず、その上で本件発明がサポー ト要件を充足しないとした本件審決の判断の誤りを主張する趣旨と善解 する余地もないではないから、念のために、同主張についての判断を示す。
前記2(2)及び(3)のとおり、本件明細書には、図5ドットパターンと図1 05ドットパターンについての記載がある。原告は、本件発明1のドット パターンは縦横4方向の図5ドットパターンに斜め4方向を付け加えた 設計上の微差でしかないドットパターンであるか、あるいは、8方向にド ットをずらす本件発明1のドットパターンの一例として図5ドットパタ ーンを位置付けることができるとして、本件発明1のドットパターンが図 5ドットパターンに基づくものである旨主張するので、以下、これを前提 に、本件発明1がサポート要件を充足するか検討する。
前記(1)アのとおり、縦横4方向をドットの配置に利用できる方向として 情報の内容を表現する図5ドットパターンの構\成と、任意の45°間隔に よる8方向をドットの配置に利用できる方向として情報の内容を表現す\nる本件発明1の構成は、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータ\nの表現方法を異にするものであるから、両者の差異が微差であるというこ\nとはできない。また、同ウ のとおり、本件発明1の構成は、8方向全部\nが一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いら れているのであり、縦横4方向の図5ドットパターンの構成とは異なる情\n報定義体系を採用するものであるから、図5ドットパターンを本件発明1 のドットパターンの一例として位置付けることもできない。以上からする と、図5ドットパターンに基づき、本件発明1のドットパターンが発明の 詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明1はサ ポート要件に適合しない。したがって、本件発明1の構成を全て含む本件\n発明2及び3もサポート要件を充足しない。
イ これに対して、原告は、前記第3の1(3)アのとおり、るる主張するとこ ろ、前示のとおり、いずれの点もその趣旨、内容は判然としないが、本件 訂正が認められるべきものであることを前提にする主張が採用できない ことは明らかであるし、本件明細書の記載が本件発明をサポートする内容 を含むものとは認められないことも前記アのとおりである。したがって、 この点に係る原告の主張はいずれも当を得ないものというほかない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 補正・訂正
>> 減縮
>> ピックアップ対象
2022.10.25
令和4(ネ)10011 商号使用差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年9月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学\n術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。そ して、商品又は営業の出所を表示するものとして文字から構\成される標章 は、商品又は営業の出所を示すという実用的な目的で作出され、使用され るものであり、その保護は、商標法又は不正競争防止法により図られるべ きものである。文字からなる商標の中には、外観や見栄えの良さに配慮し て、文字の形や配列に工夫をしたものもあるが、それらは、文字として認 識され、かつ出所を表示するものとして、見る者にどのように訴えかける\nか、すなわち標章としての機能を発揮させるためにどのように構\成するこ とが適切かという実用目的のためにそのような工夫がされているもので あるから、通常は、美的鑑賞の対象となるような思想又は感情の創作性が 発揮されているものとは認められない。商品又は営業の出所を表示するも\nのとして文字から構成される標章が著作物に該当する場合があり得ると\nしても、それは、商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識 別機能を超えた顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体\nが、識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視\nし得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えなければならない というべきである。
・・・
商標法などの標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた\n顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が、識別機能と\nいう実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美 的鑑賞の対象となり得る創作性を備えるものとは認められないから、著作 権法により保護されるべき著作物に該当するとは認められない。
ア 控訴人は、Bは、控訴人標章に、単なるロゴタイプ・デザインを超えた 美の表現・印象を強く感じ、ウェブでの被控訴人商品の販売に利用したい\nと考えて控訴人標章を模倣したものであり、このことからしても、控訴人 標章には個性があり著作物性があると主張する(前記第3の2(1)〔控訴人 の主張〕ア)。 しかし、Bは、被控訴人商品に関する事業を実施するに当たり、同事業 に対するBの様々な意図や願望を込め、禅宗の僧侶等にも相談するなどし て「アノワ」という語を含む被控訴人商号を考案して商号変更し、さらに そのローマ字表記である「ANOWA」を含む被控訴人商品の名称(「AN\nOWA41」)を考案したものと認められ(乙11)、控訴人標章を被控訴 人商品に使用するために、被控訴人の商号を、控訴人標章の「ANOWA」 の読みである「アノワ」とし、ドメイン名を「ANOWA」を含む「AN OWA41」としたものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって、Bが控訴人標章を模倣したと認めることはできず、控訴人 の上記主張は、その前提を欠き、採用することはできない。
イ 控訴人は、不正競争防止法によればTシャツの柄は保護の対象となるか ら、デザインも保護すべきであり、著作権法によってもデザインを保護す べきであると主張する(前記第3の2(1)〔控訴人の主張〕イ)。 しかし、Tシャツの柄が不正競争防止法による保護の対象となる場合が あるとしても、著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するもの\nであるから、著作権法によって当然にデザインの全てが保護されるべきで あるとはいえないし、標章は、Tシャツのデザインと性質を異にするもの であるから、控訴人の上記主張に基づいて、控訴人標章が著作権法により 保護されるということはできない。
ウ 控訴人は、控訴人標章は、文字を用いるものであるが、控訴人のロゴタ イプとしての利用を目的としてデザインされたものであり、控訴人の商号 と一致するアルファベットを強調していること、文字は誰でも使用できる ものであるから文字を強調するロゴタイプ・デザインは全て著作物とはな りえないとする合理的理由はないことを主張する(前記第3の2(1)〔控訴 人の主張〕ウ)。 しかし、控訴人標章は、標章としての機能を発揮させるためにどのよう\nに構成することが適切かという実用目的のために工夫がされているもの\nであり、美的鑑賞の対象となるような思想又は感情の創作性が発揮されて いるものとは認められないから、美術その他の範囲に属する著作物には該 当しないものというべきであり、控訴人の上記主張を採用することはでき ない。
エ 控訴人は、控訴人標章はポスターと等価値であり、著作権法制定当時、 ポスターは著作物又は著作物の複製として扱われるというのが著作権法 の解釈であったから、控訴人標章も著作権法上保護されるべきであると主 張する(前記第3の2(1)〔控訴人の主張〕エ)。 しかし、控訴人標章は、商品又は営業の出所を表示する標章であり、商\n標法や不正競争防止法の保護の対象となる余地があり得るとしても、ポス ターと等価値であるとはいえないから、控訴人の上記主張は、採用するこ とができない。
オ 控訴人は、控訴人標章が一品制作の図又は絵であるとしたら創作性のあ ることは議論の余地がなく、漫画の特徴的な表現を含む一こまを模倣して\nも著作権侵害となるのに、ロゴタイプ・デザイン(量産品の原画)である が故に著作権法の保護の対象とならない、あるいは高度の創作性がなけれ ば著作権法の保護の対象とならないというのは、著作権法上の著作物の定 義に反すると主張する(前記第3の2(1)〔控訴人の主張〕オ)。 しかし、控訴人標章は、商品又は営業の出所を表示する標章であり、商\n標法や不正競争防止法の保護の対象となる余地があり得るとしても、一品 制作の図又は絵や漫画とは性質を異にするから、控訴人の上記主張は、採 用することができない。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.10.25
令和3(受)1112 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 令和4年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所
2 本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。
3 所論は、生徒は被上告人らとの上記契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ているのに、被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。 そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。
また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。 なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
◆判決本文
控訴審はこちら
◆令和2年(ネ)第10022号
1審はこちら
2022.10.24
令和4(行ケ)10008 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月28日 知的財産高等裁判所
ア 本件訂正により、請求項1には、端末装置から取得された第1患者識別 情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報が一致すると判定された 場合に、1)端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第1 看護師等識別情報と、第2看護師等識別情報とが一致すると判定した場合 に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記 医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、2)端末か ら取得された医師を識別するための第1医師識別情報と、第2医師識別情 報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明 特定事項を含むものとなり、2)が訂正事項1−1−3に関するものである。
そして、本件明細書の【0143】ないし【0161】(実施の形態4) には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構\ 成に関する記載があり、この実施の形態4に関するフローチャート(図3 7、図38)についてみると、 端末装置から取得された第1患者識別情 報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報が一致すると判定された場 合に、端末装置に患者用画面を表示し(S21)(図11、図12)、 端 末装置から取得し出力されたIDを、医療用サーバを経て情報処理装置が 取得し(S85)、このIDが看護師IDであると判定される(S87、8 8)と、看護師用専用画面(図20ないし22)が表示され、 看護師I Dでなく(S87の「No」)、医師IDであると判定されると(S151)、 医師専用画面(図35、図36)が表示されるフローが開示されている。\n
この記載からすると、S87は看護師IDか否かを判定するステップであ り、S151は医師IDであるか否かを判定するステップであるといえる。 こうしたS87、S151は、端末装置から取得された看護師又は医師を 識別するための第1看護師等識別情報と、第2看護師等識別情報とが一致 すると判定した場合に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装\n置へ出力する(前記1))ことに対応するもの、すなわち、第2判定部及び 第2出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第1医師 識別情報を端末から取得して(第3取得部)、第3判定部及び第3出力部に 関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明 細書の【0088】ないし【0125】(実施の形態2)は、看護師IDの 判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師\nIDであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいと\nの記載があるものの(【0125】)、第2判定部及び第2出力部に続けて、 医師を識別するための第1医師識別情報を取得し(第3取得部)、第3判定 部及び第3出力部に関するフローが続けて行われることに関するもので はない。その他、本件明細書には、第2判定部及び第2出力部と、第3判 定部と第3出力部の両方を備え、また、1つのシステムで構成されること\nについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明 であるともいえない。
そうすると、前記2)、すなわち、訂正事項1−1−3は、本件明細書又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係 において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法134条の 2第9項が準用する同法126条5項の規定に反するものであり、訂正要 件を満たさないというべきである。
・・・
イ これに対し、原告は、前記第3の1 ア のとおり、本件訂正後の請 求項1は、本件明細書の【0066】ないし【0090】、図37及び図 38にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【006 6】ないし【0087】は実施の形態1、すなわち、患者用バーコード を読み取り、一致すると患者用画面を表示すること(構\成要件A1ない しC1)に関する事項であり、訂正事項1−1−3に関するものではな い。そして、実施の形態4に関する本件明細書の記載事項と図37及び 図38によれば、訂正事項1−1−3が新たな技術的事項を導入するも のであることは、前記アのとおりである。 また、原告は、前記第3の1 ア のとおり、本件明細書の【014 3】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態4は、実施の形態2を取 り込んだものであり、実施の形態2の構成及び作用に加えて、【0147】\nないし【0149】の記載からすれば、本件明細書には、第3取得部及 び第3判定部に関する構成が開示されている旨主張する。\n
しかし、【0143】は、「実施の形態4は医師が患者の医療情報を確 認するための医師専用画面30を表示部35に表\示する実施の形態に関 する。以下、特に説明する構成、作用以外の構\成および作用は実施の形 態2と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記ア で指摘した実施の形態4に関するフロー図(図37、図38)からする と、ここでいう記載の省略とは、前記アの (端末装置から取得し出力 されたIDを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し(S85)、こ のIDが看護師IDであると判定される(S87、88)と、看護師用 専用画面(図20ないし22)が表示されること)に関する説明(実施\nの形態2)を省略するものであり、【0146】ないし【0149】は、 端末装置から取得し出力されたIDが医師である場合に関する説明であ って、第2判定部で端末から取得した識別情報が医師IDであると判定 し(第2判定部)、看護師専用画面が出力(第2出力部)された後、さら に続けて、医師を識別するための第1医師識別情報を取得し(第3取得 部)、第3判定部及び第3出力部に関するフローが続けて行われる構成を\n開示するものではない。したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.10.20
令和3(ネ)10055 特許権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 知的財産裁判例 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審被告は,同年11月8日の当審第1回口頭弁論期日において,同年 7月9日付け控訴理由書に基づいて,本件各発明に係る本件特許に「無 効理由5」(別件無効審判の無効理由2と同じ),「無効理由6」(別 件無効審判の無効理由3と同じ),「無効理由7」(別件無効審判の無 効理由4と同じ),「無効理由8」(サポート要件違反)及び「無効理 由9」(実施可能要件違反)が存在するとして無効の抗弁の主張を追加\nし,また,権利の濫用の抗弁の主張を追加した。 これに対し一審原告は,同年8月26日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由5ないし9」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は,時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから,却 下を求める旨の申立てをした。\n
オ なお,別件無効審判は,当審の本件口頭弁論終結時(令和3年11月8 日)において,特許庁に係属中である。
(2)前記(1)の事実関係によれば,1)一審被告は,原審において,平成31年 3月7日の原審第3回弁論準備手続期日までに,本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由,乙2公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由(本件の争点2−1ないし2−3)が存在するとして無 効の抗弁を主張し,その上で,令和元年6月27日の原審第5回弁論準備手 続期日において,侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後,同年 7月19日の原審第6回弁論準備手続期日から,本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと,2)その後,一審被告は,令和2年10月22日の原審第14回 弁論準備手続期日において,本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由1ないし4と同一の無効理由が存在するとして,新たな無効の抗弁の 主張をしたが,原審が,同年12月18日の第15回弁論準備手続期日にお いて,上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と,3)一審被告は,令和3年11月8日の当審第1回口頭弁論期日において, 控訴理由書に基づいて,本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由2ないし4と同じ無効理由である「無効理由5ないし7」,原審で主張し なかった「無効理由8」(サポート要件違反)及び「無効理由9」(実施可 能要件違反)が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに,新たに権\n利の濫用の抗弁の主張をしたこと,4)別件無効審判は,当審の本件口頭弁論 終結時において,特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに,侵害論に関する抗弁の主張は,本来,原審に おいて適時に行うべきものであるところ,一審被告が,原審において,令和 元年6月27日の原審第5回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に,当審で主張する「無効理由5ないし9」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて, やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから,当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は,一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして,当審において,一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは,一審原告に対し,上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ,これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから,これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで,当審は,民事訴訟法297条において準用する同法157条1 項に基づき,一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2022.10.20
令和3(ワ)30051 損害賠償請求事件 その他 民事訴訟 令和4年9月28日 東京地方裁判所
原告は、被告によって、原告文章を無断転載して制作した本件番組が放送 されたことにより、原告の名誉が毀損される可能性が生じて、原告の平穏な\n日常を阻害され、原告が、これに対応するために金銭的及び時間的な負担を 負い、精神的苦痛を被り、人格権が侵害されたとして、不法行為に基づく損 害賠償を請求するものと理解することができる。そこで、この理解を前提に、 被告による本件番組の放送が原告の「権利又は法律上保護される利益を侵害 した」(民法709条)といえるか否かについて検討する。
前記前提事実(2)及び(3)のとおり、被告が原告文章に依拠して本件ナレー ション等を作成した結果、本件ナレーション等は、原告文章と類似しており、 原告文章中の「以下省略」といった比較的特徴のある表現についてもほぼ同\nじ内容となっている。そして、被告が、本件番組において本件ナレーション 等を流すことについて、原告から事前の了解を得ていたことや、本件番組を 放送するに当たり、原告文章が掲載されている原告ウェブサイトを参照した 旨を表示したことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告の上記行\n為は、公共の放送事業者として不適切なものであったといわざるを得ない。
また、原告が主張するように、原告ウェブサイト中の文章は、分かりやす く面白いものとなるように配慮され、独自性を有していると評価し得ること や、被告が放送法で定められた公共の放送事業者であることからすると、本 件番組を視聴した者が、原告文章を見たとき、被告が無断転載をするはずが ないと考えて、むしろ原告ウェブサイトの方が無断転載をしていると疑う可 能性を否定することはできない。しかし、前記前提事実(4)のとおり、被告は、本件番組が放送された4日後には、本件番組に係るウェブサイトにおいて、本件ナレーション等が既存の文章をほぼ転載したものであることを謝罪する旨の文章を掲載しており、こ れは、上記のような誤解が生じることを防止し得る措置であるといえる。そ して、本件全証拠によっても、実際に、上記のような誤解が広まったとは認 められない。しかも、名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を低下 させる事実を摘示することが必要であるところ、将棋の対局マナーについて 述べた本件ナレーション等において、原告の社会的評価を低下させる事実が 摘示されたとは認められない。そうすると、原告の主張する名誉毀損の可能\n性については、いまだ抽象的なものにとどまるものといわざるを得ない。
また、原告の主張に係る平穏に日常生活を送る利益について、上記のとお り、原告の懸念する誤解が実際に広まったとは認められず、原告の名誉が毀 損される可能性も抽象的なものに留まることに照らせば、被告に対する損害\n賠償請求を可能とする程度に、原告の平穏な日常生活が害されたということ\nはできず、不法行為の成立要件である「権利又は法律上保護される利益」の 「侵害」を認めることはできないというべきである。 なお、被告が原告文章と類似する本件ナレーション等を含む本件番組を放 送したことが原告の権利を侵害するかは、本来、原告文章に著作物性が認め られ、原告文章に係る原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたと認めら れるかという観点から検討すべきであるということができる。しかし、原告 は、本件訴訟において、著作権及び著作者人格権が侵害されたことを主張し ないとしていることから、その要件についての具体的な主張立証がされてい ないため、著作権侵害及び著作者人格権侵害の事実を認めることはできない。 (2) 以上によれば、本件番組の放送により、原告の人格権が侵害されたとは認 められず、また、原告文章に係る原告のそのほかの権利が侵害されたと認め
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.10.20
令和3(行ケ)10165 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月30日 知的財産高等裁判所
ア 本件発明1と甲2発明1との相違点1ないし4は、前記第2の3(3)イの とおりであるところ、これらはいずれも本件発明1における伸縮部を備え ているか否かをその内容とするものといえる。 そこで、以下、本件特許が出願された当時の当業者が、甲2発明1、甲 4発明及び甲5公報ないし甲7公報から認定される周知技術に基づいて、 甲2発明1について上記伸縮部を備えることを容易に想到し得たか否か について検討する。
イ まず、主引用発明である甲2発明1について検討するに、甲2公報にお いて、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能なものとすることが記載又は示唆\nされているというべき記載は見当たらない。 また、前記(1)のとおり、甲2発明1は、盗難防止用連結ワイヤの一方を ドアノブや玄関周り固定物に接続し、他方を宅配容器本体に接続するもの であるところ、甲2公報の段落【0022】並びに図3及び図4の記載に よれば、甲2発明1の盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側のドアノブや建 物内部の玄関周り固定物に接続するものであるといえる。さらに、甲2公 報の段落【0022】及び図3の記載によれば、甲2発明1において、配 達物を収納していないときの形態の宅配容器本体をドアノブに掛ける際 には、宅配容器本体に備えられた「宅配容器取っ手」を使用することとさ れている。
このように、甲2発明1においては、配達物を収納していないときの形 態の宅配容器は、「宅配容器取っ手」を使用して玄関外側のドアノブに掛け られ、他方で、宅配容器に接続された盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側 のドアノブや建物内部の玄関周り固定物に接続することとなるのである から、同ワイヤは、これを可能とするのに十\分な長さを確保する必要があ るといえる。そうすると、配達物を収納していないときの形態における甲 2発明1においては、盗難防止用連結ワイヤの長さを、ドアの一部に吊り 下げられるように短縮する構成は採用し得ず、そのような構\成を採る動機 付けは存しないというべきである。
以上によれば、甲2発明1において、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能\nなものとすることは動機付けられないというべきである。なお、上記に照 らすと、甲2発明1においては、少なくとも相違点3に係る本件発明1の 構成を採ることについて、阻害要因が存するというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2022.10.17
令和3(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月23日 知的財産高等裁判所
本件訂正前の請求項1の記載によれば、本件発明1の「浸水防止 部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されるこ と、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に 設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に 面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。し かし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは 明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空 所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には 限定されないと認められ、このことは「下層空間13の船尾側に推 進用エンジン14が配置されている」(段落【0026】)などの本 件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、 直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導 けない。また、SOLAS条約(「千九百七十四年の海上における人\n命の安全のための国際条約」、甲23)によれば、浸水率の計算にお いて、タンクは、0又は0.95のいずれか、より厳格な条件とな る方の値(もともと水で満たされているため浸水が0である場合と、 もとは空であるため浸水が容積の95%に及ぶ場合のうち、復原性 を悪くする方の値)を用いて計算すべきとされており、タンクであ ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを 前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水するこ と」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、 前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が 損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を 設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過 大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とする ものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面す る側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しな いような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防\n止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の 機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる\n証拠はない。かえって、甲17(実願昭49−19748号(実開 昭50−111892号)のマイクロフィルム)には、第1図及び 「本考案は、横置隔壁2の船側部両端に、船側外板1を一面とした 高さ方向に細長い浸水阻止用の区画7を備えているから、横隔壁数 を増加しなくても、船側外板1の損傷による船内への浸水を該区画 7内に、または該区画7と隣接する1つの船内区画内にとどめるこ とができ」(4頁下から7〜1行)との記載があり、本件発明の「浸 水防止部屋」の機能に類似する「空間7」を有する船舶の発明が開\n示されているところ、同文献には、「該区画7を小槽として利用する こともできる。」(5頁7行)とも記載されているから、浸水防止を 目的とした区画を、小槽(タンク)として利用することは、公知で あったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねるこ\nとを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の 目的に資するものである。
以上によれば、本件訂正前の請求項1の「浸水防止部屋」とは、 それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解\nするのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の 機能を備えることが許容されるものであると認められる。\n
b 「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加による新たな技術的 事項の導入の有無
前記aのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが\n許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、\nタンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等\nには、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載され\nていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能\nを兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水\n防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を\n兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸\n水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発 明であったから、訂正事項1により、特許請求の範囲の請求項1の「浸 水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋(ただし、タ\nンクを除く。)」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」\nを備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明 らかである。
なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の 近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋 に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水 を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計 の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏すること なく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのた め、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技 術的事項が導入されたと解する余地もない。
したがって、訂正事項1による「(ただし、タンクを除く。)」という 記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい て、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新 規事項追加(法134条の2第9項、法126条5項)に当たらない というべきである。
c 原告の主張に対する判断
原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによっ て、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自 由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋と いう空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計 算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新 たな作用効果を奏するから、「(ただし、タンクを除く。)」という記載 の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。 しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸\n水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部\n屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細 書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」ととも\nに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたもの\nと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何ら\nかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記 載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そ のことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加 えられたと解する余地はない。
◆判決本文
関連事件です。
令和3(行ケ)10150
◆判決本文
それぞれの1次審取訴訟です。
令和1(行ケ)10080
◆判決本文
令和1(行ケ)10079
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> 差戻決定
>> ピックアップ対象
2022.10.15
令和3(ワ)1390 特許権侵害差止請求権等不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年8月30日 東京地方裁判所
本件において、原告は、効能・効果を「手術不能\又は再発乳癌」等とする 「抗悪性腫瘍剤ハラヴェン静注1mg<エリブリンメシル酸塩製剤>」であ る被告医薬品の後発医薬品として、効能・効果を「手術不能\又は再発乳癌」 とする「エリブリンメシル酸塩静注1mg「ニプロ」」という販売名の原告 医薬品(別紙物件目録)の製造販売についての承認の申請をし、現在、原告\n医薬品の製造販売を予定して、製造販売についての承認の申\請及びGMP適 合性検査の申請のための原告医薬品の製造を行っている(前記第2の1(5)ア、 ウ)。
もっとも、二課長通知等は、後発医薬品(既に製造販売についての承 認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が\n同一性を有すると認められる医薬品)の製造販売について、先発医薬品の有 効成分に特許が存在する場合や先発医薬品の一部の効能・効果等に特許が存\n在する場合に、厚生労働大臣の承認はしない方針であるとし(前記第2の2 (4)ウ)、また、後発医薬品の薬価基準への収載についても、特許係争のおそ れがあると思われる品目の収載を希望する場合は、事前に特許権者である先 発医薬品製造販売業者と調整を行い、将来も含めて医薬品の安定供給が可能\nと思われる品目についてのみ収載手続をとる方針であるとしている(同エ)。 また、被告エーザイRDが特許権者である本件各特許が存在する。本件各特 許権を有する。原告は、これらによれば、本件において、被告医薬品の後発 医薬品である原告医薬品の製造販売について厚生労働大臣の承認がされるこ とはないと主張する(前記第2の2(1)(原告の主張))。
これらの状況と本件各証拠によっては、近い将来において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ、更に原告医薬品の薬価基準への収載がされる蓋 然性が高いことを認めるには足りない。原告が、医薬品医療機器等法等の定 め等(同1(1)、(4)ア、イ、カ)を前提として医薬品等の製造、販売等を目的 とする会社であり、上記法規等の定めに則った事業活動をすると推認される ことなどを考慮すると、近い将来において、原告が、製造販売についての承 認の申請及びGMP適合性検査の申\請のための原告医薬品の製造を除き、原 告医薬品を製造販売する蓋然性が高いとは認められない。
(3) 被告らは、原告が現に行っている製造販売についての承認の申請及びGM\nP適合性検査の申請のための原告医薬品の製造については、本件各特許権に\n基づく主張をしておらず、今後、本件各特許権に基づく主張をする意思もな いとし、現在、本件各特許権は侵害されていないから、被告らに損害は生じ ていないと主張する(前記第2の2(1)(被告エーザイRDの主張)、同(2)
(被告らの主張))。
したがって、承認の申請等のための原告医薬品の製造に関して、被告エー\nザイRDの原告に対する本件各特許権による差止請求権及び被告らの原告に 対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為による損害賠償請求権が存 在しないことについて、現に、当事者間に紛争が存在し、原告の有する権利 又は法律的地位に危険又は不安が存在しているとは認めるに足りない。
(4) 被告らは、原告が、現在、承認の申請等のための製造(前記(3))を除き原 告医薬品の製造販売をしておらず、そもそも製造販売に必要な厚生労働大臣 の承認を受けていないことから、本件各特許権の侵害もそのおそれもないと して、現在、原告に対し本件各特許権に基づく主張をしていない(前記第2 の2(1)(被告エーザイRDの主張)、同(3)(被告らの主張))。 被告らは、令和3年5月に、原告から原告医薬品の製造販売について本件 各特許権を行使しないことの確認をするよう求める旨の通知を受け、原告に 対し本件各特許権を行使する可能性がある旨の本件回答をした(前記第2の\n1(5)ア)。もっとも、原告と被告らの間にはそれ以前に何らのやり取りもな く、被告らにおいて、原告が原告医薬品の製造販売をした場合に本件各特許 権に基づく権利行使をしないと直ちに確約することはできなかったことから、 上記のような回答をしたものと認められ(乙3)、本件回答をもって、被告 らが、現在の本件各特許権による差止請求権や不法行為による損害賠償請求 権の不存在を争っているとは認められない。
また、原告は、現在において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働 大臣の承認を条件とする本件各特許権による差止請求権等が発生し得るから、 被告エーザイRDに対する現在の本件各特許権による差止請求権等の不存在 確認請求には訴えの利益がある旨も主張する。しかし、原告医薬品の将来に おける製造販売について、被告エーザイRDの現在の本件各特許権による差 止請求権は、本件各特許権の侵害又は侵害のおそれを理由として発生し得る ものであり、被告らの本件各特許権の侵害を理由とする現在の不法行為によ る損害賠償請求権は、本件各特許権の侵害及び損害の発生等を理由として発 生し得るものである。そして、上記に記載した本件における状況に照らせば、 現在において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ れば上記差止請求権等の権利を取得し得るという地位を被告らが有している と認めるに足りず、上記差止請求権等は、原告が原告医薬品の製造販売につ いての厚生労働大臣の承認を受けることを条件として発生しているものとは 解されない。
これらのことを考慮すると、被告エーザイRDの原告に対する本件各特許 権による差止請求権及び被告らの原告に対する本件各特許権の侵害を理由と する不法行為による損害賠償請求権が存在しないことについて、現に、当事 者間に紛争が存在し、原告の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存 在しているとは認めるに足りない。 なお、仮に、二課長通知等によれば本件各特許が存在するために原告医薬 品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされることがないとしても、 そのことによって、原告と被告らとの間に前記各請求権の存否に係る法律上 の紛争が存在することになるものとは解されない。
(5) 以上によれば、原告の被告エーザイRDに対する現在の本件各特許権によ る差止請求権の不存在確認請求及び被告らに対する本件各特許権の侵害を理 由とする現在の損害賠償請求権の不存在確認請求について、現に、原告の法 律的地位に危険又は不安が存在するとは認められず、これらの各訴えに、即 時確定の利益があるとは認められない。
2022.10.13
令和2(ワ)3931 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年10月6日 東京地方裁判所
ア 平成30年度掲載記事のうちの一部の記事について、被告は、その著作物 性を争っている。 しかしながら、平成30年度掲載記事は、事故に関する記事や、新しい機 器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業 等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に 関する記事である。そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報 について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなど されており、表現上の工夫がされている。また、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テー\nマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関 係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成している。したがって、平成30年度掲載記事は、\nいずれも創作的な表現であり、著作物であると認められる。
・・・
以上の事実に、平成30年度について被告が本件イントラネットに掲載し た原告が著作権を有する記事の数が前記 のとおりであることなどの状況 等を考慮すると、平成30年度掲載記事の選別を行ったC証人が選別した平 成28年度及び平成29年度については、被告による著作権侵害が認められ る記事の総数(自社及び沿線記事に分類した記事及びそれに分類していない 記事の合計)は、これら両年度の枠付き記事(自社及び沿線記事に分類した 記事の一部)の合計である52本の3倍に当たる156本を下らないもので あると認定するのが相当である。
・・・
原告は、本件個別規定に基づく損害額を主張するところ、上記によれば、原 告においては、少なくも平成20年以降は、本件個別規定を適用して原告が発 行する新聞の記事について利用許諾を検討する体制を整えており、これらの規 定を複数年にわたり、少なくとも1000件程度適用し、これに基づく使用料 を徴収してきた実績があることが認められる。また、本件個別規定には、社内 LAN(イントラネット)での利用を想定した文言がある。他方、本件で問題 になっているイントラネットでの掲載に関して本件個別規定に基づき支払われ た利用料の額等の実績については不明であり、また、本件個別規定には件数が 多い場合の割引に関する規定もあり、件数が相当に多い場合、どの程度本件個 別規定の本文で定める額が現実に適用されていたかが必ずしも明らかではない。 さらに、本件イントラネットによる新聞記事の掲載は、被告の業務に関連する 最新の時事情報を従業員等に周知することを目的とするものであったことから すると、掲載から短期間で当該記事にアクセスする者は事実上いなくなると認 められる。これらの事実に加え、本件に係る被告による侵害態様等を総合的に 考慮すると、本件については、原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額 (著作権法114条3項)は、掲載された原告の記事1本について掲載期間に かかわらず3000円として、原告に同額の損害が生じたものと認めるのが相 当である。
被告は、被告による使用が本件個別規定における「非営利で公共性のある使 用」に当たること、被告が取材対象者に当たる記事も存在することなどを指摘 する。本件個別規定の【割引】、【無料】の項目にはこれらの事情により原告が 無料での利用を許諾することが記載されている。しかし、株式会社である被告 にこれらの規定が適用されたかは明らかではなく、また、上記で定められてい る取扱いをしなければならないことが一般的であったことを認めるに足りる証 拠はない。また、被告は、本件は本件包括規定によるべきであると主張するが、 本件個別規定について前記 ア、イに認定した事情が認められる状況で、本件 包括規定の存在は、本件個別規定も参酌して上記のとおりの損額の額を認定す ることの妨げになるものとは認められない。 前記のとおり、平成30年度以前については、遅くとも平成30年3月31 日までに、原告が著作権を有する記事が458本掲載されたと認めるのが相当 であるから、これによる損害は137万4000円となる。平成30年度掲載 記事について、別紙損害金計算表の「掲載月」欄記載の月に対応する「記事数」欄記載の数の記事について侵害が成立すると認められる(なお、原告は、記事\n177、185、215について被告で2本分の記事が掲載されたことを理由 に2本分の損害を計上しているが、単一の記事に係る単一のイントラネットへ の掲載であることなどからすると、いずれも1本分の損害を計上するのが相当 である。)から、損害額は「損害額」欄記載のとおりとなり、その合計額は、3 9万9000円になる。
◆判決本文
原告新聞社が異なる関連事件です。こちらは約460万円の損害が認められています。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2022.10.12
令和3(ワ)2722 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年8月30日 東京地方裁判所
以上のとおり、漢字の「忠」を丸で囲んだもの、又は、これと、「山田石 材店」、「山田」、「つなぎ館」、「つなぎや」などの表示を組み合わせたものは、山田石材店及び被告において、長年にわたり、多磨霊園の近隣にお\nいて、墓石の販売、設置等その業務について使用されてきて(前記(1)ア)、 被告による使用によって同所においては関係する役務等について一定の信用 が蓄積されてきたものといえ、上記各表示を含む各被告標章もその中で使用されるようになったものである(同前)。被告は、山田石材店として創業以\n来、c及びその子孫によって運営されてきた(同イ)ところ、cの孫である aは、父であるdから被告の持分を相続し、平成7年頃に、被告を解散して 新たな組織により石材店を営むことを企図するなどしたことがあり(同ウ)、 被告に関係する者といえ、また、被告の使用する標章やその使用状況を知っ ていたと認められる。このような状況のもとで、aが設立した原告は、従前 被告の店舗が所在した土地の明渡しを受けて同所に原告店舗を構え、「c、dと続く「丸忠事業」を承継するために原告を設立した」のであるから「a\nすなわち原告が「丸忠ブランド」に関わる商標を商標登録出願するのは当然 のことである」と主張するなどして(前記2(8)(原告の主張))、被告が、 長年にわたり、「マルチュウ」との称呼が生じ「丸忠」とも表記され得る漢字の「忠」を丸で囲んだもの、「つなぎ舘」等を使用してきた中で、平成8\n年、上記の各標章に類似する本件商標1(漢字の「忠」を丸で囲んだもの) 及び原告商標(つなぎ館/指定役務・飲食物の提供等)を商標登録出願し、 被告が「有限会社つ ぎ館丸忠山田石材店」に商号変更した後の平成18年 に、同商号に含まれる文字列である本件商標2(丸忠山田)、本件商標3 (つなぎ館/指定役務・葬儀並びに法事のための施設の提供等)を商標登録 出願した(同ア、ウ)。
そうすると、原告の被告に対する本件各商標権に基づく各請求は、被告に 関係する者であるaが設立した原告が、被告の創業者であるcから続く事業 すなわち被告の事業を承継するためと主張して、被告が長年にわたり事業に 使用してきたことにより一定の信用が蓄積された標章に類似する商標につい て商標登録出願をして(なお、原告が、当時、これらの商標を各指定商品又 は各指定役務について使用していたことは認めるに足りない。)、被告に対 し、被告が上記の標章の使用の一環として使用するようになった各被告標章 を使用しないこと等を求めるものであって、このような被告による標章の使 用の状況、原告と被告との関係、原告の商標登録出願に至る経緯等に照らせ ば、仮に被告が本件各商標の指定役務に類似する役務に本件各商標に類似す る各被告標章を使用するものであったとしても(争点1)〜3))、権利の濫用 に当たると認められる。 したがって、原告の被告に対する本件各商標権に基づく各請求は、権利濫 用であって認められない。
2022.10. 1
令和4(行ケ)10038 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年9月28日 知的財産高等裁判所
前記1(2)の認定事実によれば、使用商標2のみならず、使用商標1につ いても、本件投資信託(「香港籍指数連動型上場投資信託」及び「私募外 国投資信託(香港ドル建)」)の名称であることは明らかであるから、使 用商標1は、要証期間を含む期間において、請求に係る指定役務中、第3 6類「証券投資信託受益証券の募集・売出し、投資、金融資産の管理」の 範ちゅうに含まれる役務に使用されていることになる。
エ 楽天証券のウェブサイトにおける使用商標1の使用が本件投資信託の販 売会社としてのものであることは明らかである。前記イ のとおり、被告 の本件投資信託の交付運用報告書では、運用報告書(全体版)については、 販売会社である楽天証券のウェブサイトで電磁的方法により提供されて いるとしてURLを表示しているのであるから、被告が、楽天証券におい\nて使用商標1をウェブサイトで使用していることを認識していることも 明らかである。そうすると、被告が楽天証券に使用商標1の通常使用権を 許諾していることは優に推認される。 そして、前記1(1)のとおり、楽天証券のウェブサイトでは、過去10年 の本件投資信託の価格等、本件投資信託に関する重要な情報が示され、本 件投資信託の売買も可能なのであるから、「役務に関する広告・・・を内\n容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が行われて いたことになる。
オ 以上によれば、本件商標の通常使用権者である楽天証券は、要証期間に 日本国内において、請求に係る指定役務中、第36類「証券投資信託受益 証券の募集・売出し」等に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社 会通念上同一の商標である使用商標1を付して、自社のウェブサイト上で 表示し、役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法\n(インターネット)により提供する行為(商標法2条3項8号)をしてい たものと認められる。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2022.10. 1
令和4(ネ)10052 特許権侵害に基づく損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記(ア)及び(イ)によると、乙12発明における「コーティング」は、酸 化や環境湿度等に敏感なスタチン類(HMG−CoAレダクターゼ阻害剤)を保護 し、これを安定化するために塗布される材料の層であるところ、従来から、固形医 薬品の安定性を高める目的で保護コーティングが施され、その材料として様々なも の(ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体ではないアミノアルキルメタアク リレートコポリマーEを含む。)が開発されていることが周知であり、特に、HM G−CoA還元酵素阻害剤のコーティング材料として、カルメロース及びその塩、 クロスポビドン等の崩壊剤と共に、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーE を用い得ることが知られていたものと認めることができる。 そうすると、乙12発明の「コーティング」の材料として、「カルボキシメチル セルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物」に代え、アミノアル キルメタアクリレートコポリマーE等の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘 導体」を含まない周知のものを採用することは、乙12公報に接した本件出願日当 時の当業者において適宜なし得たことであると認めるのが相当である。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は、乙12発明は「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィル ム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構\成とするもの であり、これを従来技術として知られている他のコーティングに変更することは想 定されていないから、上記の必須の構成を相違点2に係る本件訂正発明6の構\成に 変更することには阻害要因がある旨主張する。 しかしながら、乙12公報の記載(前記3(1)キ)を見ても、乙12発明の適切 な「膜形成剤」は、(環境影響に敏感な)粒子又は活性物質を含む医薬剤形のコア にコーティングの形態で塗布され、環境影響(酸化及び/又は環境湿度等)から活 性物質を保護する任意のものであり、最も好ましい「膜形成剤」は、活性物質を酸 化から保護する任意のものであるとまず理解され、当該任意の「膜形成剤」のうち 好適なものがポリビニルアルコール(PVA)及びセルロース誘導体からなる群か ら選択されるものであると理解するのが自然であるから、「ポリビニルアルコール 又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた 構成」が乙12発明の必須の構\成であると認めることはできない。したがって、こ の構成を相違点2に係る本件訂正発明6の構\成に変更することに阻害要因があると いうことはできない。
◆判決本文
原審はこちら
◆平成30(ワ)17586等
なお、当事者および該当特許が同じ別訴では、侵害が認定されています。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.09.28
平成30(ネ)10077 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決参照)。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線(被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。)上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線(ユーザが使用する端末装置を含む。)上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明1−9及び10のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
c これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって(甲3ないし5、44、46、47、丙1ないし3)、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明1−9及び10に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明1−9及び10の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
d 以上によれば、本件配信は、日本国特許法2条3項1号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為(形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの)についても当てはまるものである。
e 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる(特許法2条3項1号)。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス(令和2年9月25日以降は被控訴人らサービス1。以下同じ。)の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表\示しているところ(甲3ないし5)、これは、「提供の申出」に該当する(特許法2条3項1号)。\n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである(前記3(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容)。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置(令和2年9月25日以降は被控訴人ら装置1。以下同じ。)が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法101条1号により、本件特許権1を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明1の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産(端末装置における複製)
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産(開発)
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人HPSは、被控訴人FC2と共同して、被控訴人らプログラム1を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム1の生産に当たることは明らかである(特許法2条3項1号)。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人FC2は、被控訴人らサービス2及び3を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム2又は3を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム2及び3については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠(甲29の1及び2、30、36、37)を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス2及び3につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム2及び3の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス2及び3のアップデートの内容が本件発明1−9又は1−10の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権1を侵害する態様で被控訴人らプログラム2又は3を開発したと認めることはできない。\n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産(アップデートの際の複製)
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権1を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。\n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出(被控訴人HPSによる被控訴人ら各プログラムの納品)\n
前記(1)によると、被控訴人HPSは、被控訴人らプログラム1を開発し、これを被控訴人FC2に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム1を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人HPSが被控訴人FC2に対して被控訴人らプログラム1を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人HPSが被控訴人FC2 に対し被控訴人らプログラム2又は3を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム1の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権1の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権1の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。\n
15 争点7(差止請求及び抹消請求の可否)について
(1) 前記14(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス1に関し、本件特許権1を侵害する者に該当する。 もっとも、前記14(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置1の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権1を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置1の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス1については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム1の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム1の抹消を命じるのが相当である。\n
(2)ア 前記14(1)トのとおり、被控訴人FC2は、SN社に対し、令和2年9月25日、被控訴人らサービス2及び3に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス2及び3の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス2及び3について、被控訴人らが本件特許権1を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置2及び3の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム2及び3の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記14(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム2及び3を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム2及び3の抹消を命じるのが相当である。\n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス2及び3の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙99の1の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、SN社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス2及び3の再譲渡をする可能\性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム1の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。\n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額(1億円及びこれに対する遅延損害金)に加え、被控訴人らによる本件特許権1の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス1のうちFLASH版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス1のうちFLASH版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス1に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム1の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム1であり、被控訴人らプログラム1は、別紙被控訴人らプログラム目録記載1のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、FLASH版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文1項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム1からFLASH版に係るものを除外する必要はない。
◆判決本文
1審はこちらです。1審では、第1,第2の表示欄の大きさを特定した構\成が非充足と判断されています。
◆平成28(ワ)38565
以上のとおり,「第1の表示欄」は動画を表\示するために確保された領域(動画表示可能\領域),「第2の表示欄」はコメントを表\示するために確保された領域(コメント表示可能\領域)であり,「第2の表示欄」は「第1の表\示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ,被告ら各装置においては,動画表示可能\領域(被告ら装置1における「StageオブジェクトA」,被告ら装置2及び3における<iflame>要素又は<video>要素)とコメント表示可能\領域(被告ら装置1における「CommentDisplayオブジェクトD」,被告ら装置2及び3における<canvas>要素)は同一のサイズであるから,被告ら各装置は,「第1の表示欄」及び「第2の表\示欄」に相当する構成を有するとは認められない。\n
今回侵害となった特許4734471
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja
1審と同じく侵害とはならなかった特許4695583
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4695583/7294651F33633E1EBF3DEC66FAE0ECAD878D19E1829C378FC81D26BBD0A4263B/15/ja
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 間接侵害
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2022.09.26
令和4(ネ)10027等 損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件 その他 民事訴訟 令和4年8月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記認定によると、本件サービスサイトは、その構成において、需要者であ\nる葬儀希望者に対し、その条件に見合った葬儀社等の情報提供を行い、また希望者 には葬儀の依頼や相談、一括見積を行うことなどを通して、葬儀希望者と葬儀社等 とのマッチング支援を行うサービス(被告役務)を提供するものであることが容易 に看取できる。 そして、本件ウェブページは、これを単独でみても、そのドメインや本件ウェブ ページのタイトル部分や末尾の「安心葬儀」等の表示、競合し得る近隣の斎場等の\n情報も表示されることに加え、本件葬儀場の情報については、ホールの外観、特徴\nや所在地、アクセス方法、設備情報等の客観的な情報が記載されているにとどまり、 これを超えて本件葬儀場の利用を誘引するような記載はみられないこと等の事情か らすると、本件ウェブページに接した需要者は、「セレモニートーリン」を、葬儀 場を紹介するという本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社(場)として 認識するものであり、原告が本件葬儀場において提供する商品ないし役務に関し、 被告がその主体であると認識することはないものというべきである(本件ウェブペー ジを含め、本件サービスサイトの運営者が原告であると認識することがないことも 同様である。)。
さらに、原告が問題とする本件ウェブページの html ファイル中のタイトルタグ及 び記述メタタグに記載された内容は、検索サイトYahoo!において「セレモニー トーリン」をキーワードとして検索した際の検索結果において基本的に各タグに記 載されたとおり表示されると認めることができるが、その内容は、いずれも本件サー\nビスサイトの名称が明記された見出し及び説明文と相まって、原告の運営するウェ ブサイトとは異なることが容易に分かるものと評価できる上、一般に、検索サイト の利用者、とりわけ現に葬儀の依頼を検討するような需要者は、検索結果だけを参 照するのではなく、検索結果の見出しに貼られたリンクを辿って目的の情報に到達\nするのが通常であると考えられるところ、需要者がそのように本件ウェブページに 遷移した場合には、前記のとおり、被告が運営する本件サービスサイトの一部とし て本件ウェブページを理解するのであって、やはり、被告標章を本件ウェブページ の各タグ内で使用することによって、原告と被告の提供する商品または役務に関し 出所の混同が生じることはないというべきである。 したがって、被告による被告標章の使用は、商標法26条1項6号の規定により、 本件商標権の効力が及ばないというべきである。
(3) 原告は、被告は、本件ウェブページの見出しやその説明文において被告標章 を表示させ、需要者をして本件ウェブページにアクセスするよう誘引し、本件ウェ\nブページにおいて本件葬儀場の建物の写真や情報を表示させることで、需要者をし\nて、本件ウェブページが原告(セレモニートーリン)のウェブページであると誤認 させ、出所の混同を生じさせている旨を主張する。 しかし、本件ウェブページの見出し、説明文及び本件ウェブページ自体の表示内\n容を踏まえると、見出し及び説明文に被告標章の表示があるからといって、出所の\n混同を生じさせることにはならないことは前述したとおりである。原告の主張は、 要するに、原告を紹介する本件ウェブページに被告の電話番号等が表示されること\nにより、原告が、その潜在的需要を失う不利益を被っていることをいうものと解さ れるが、そのような結果が仮に生じているとしても、前記認定に係る本件サービス サイトの性質及び本件ウェブページの記載(なお、反対にこれを参照して原告に依 頼する需要者も在り得ると考えられる。)からすると、自由競争の範囲内のものと いうべきである。原告の前記主張は採用の限りでない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.09.16
令和4(行ケ)10034 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年9月14日 知的財産高等裁判所
本件契約書には、「『XPERIA 修理王』ブランドでの XPERIA 等修理経営 のための FC 契約関係を形成する」(第1条)、「『XPERIA 修理王』の商標… の使用を許諾する。」(第4条1項)とある(前記1 イ 、 )ものの、「本 契約において本部が加盟者に提供する FC サービスの内容は、次の各号とす る。…2)商標・商号・その他の表示の提供」(第2条)、「本部は、加盟者にお\nける XPERIA 等修理業経営について『XPERIA 修理王』の商標・サービスマ ーク、その他営業シンボル・著作物の使用を許諾する。」(第4条1項)、「第 1項に定める許諾に関しては、以下を条件とする。1)加盟者との本契約期間 中ならびに加盟者の事業所内に限る。」(第4条3項)とあり(前記1 イ 、 )、被告は、原告に対し、原告が本件フランチャイズ契約に基づいて運営す る店舗の屋号を「スマホ修理王 新宿店」、「XPERIA 修理王 新宿店」と指 定する旨を通知し(前記1 ウ)、原告は、少なくとも本件フランチャイズ契 約の契約期間中、運営するスマートフォンの修理業に関し「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」の名称を使っていた(前記1 オ)ことからすると、 本件フランチャイズ契約においてフランチャイザーである被告がフランチャ イジーである原告に提供し、許諾の対象となる「商標・商号・その他の表示」\nには、「XPERIA 修理王」だけでなく「スマホ修理王」の商標も含まれるもの と解される(なお、原告は、本件商標(標準文字の「スマホ修理王」)は本件 フランチャイズ契約で規定されていない旨主張するが、上記のとおりである から採用できない。)。
また、原告は、被告が開設する「スマホ修理王 FC 加盟申し込みホームペ\nージ」を利用して本件フランチャイズ契約の申込みをしていること(前記1\nア)、本件フランチャイズ契約終了後、被告より、ウェブサイト等から 「XPERIA 修理王」及び「修理王」の名称を削除するよう求められたのに応 じて、本件ウェブサイトの「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」(スマ ホ修理王の部分は引用商標2)の名称を「新宿駅前 XPERIA 修理専門店」と 変更していること(前記1 ウないしオ)からすると、原告は、「スマホ修理 王」の商標(引用商標1、2)は被告がフランチャイズ事業で使用しており、 その使用のためには被告の許諾が必要であることを十分に認識し、現にその\nような認識の下で、被告のフランチャイジーとして「スマホ修理王」の商標 を使用していたと解するのが相当である。
そうであるにもかかわらず、原告は、本件フランチャイズ契約に関し、平 成30年3月30日付けで、本件解除がされ、WEB サイト等から『XPERIA 修理王』および『修理王』の名称を削除するよう求められたその4日後に本 件商標の登録出願に及び、令和元年8月30日に本件商標の設定登録を受け ると、同年12月20日付けで、フランチャイザーであった被告に対し、被 告が展開するフランチャイズ事業で「スマホ修理王」の商標を使用すること が本件商標の商標権侵害に当たる旨を警告し(前記1 ア、イ)、本件商標の 放棄又は譲渡のために50万円(税別)を支払う用意があると通知した被告 に対し、本件商標の商標権買取価格を含め合計2670万円のライセンス契 約を提案し、代理人間の協議においても100万円から300万円程度では 受け入れられない旨回答した(前記1 イ、ウ)ことが認められる。こうした事実経過等に鑑みれば、本件商標の登録出願は、元フランチャイジーである原告が、被告から本件解除をされたわずか4日後に行ったものであり、これまでと同様の名称を使用することにより被告の顧客吸引力を利用し続けようとしたものと評価せざるを得ず、元フランチャイジーとして遵守すべき信義誠実の原則に大きく反するものであるのみならず、「スマホ修理王」の名称でフランチャイズ事業を営んでいる被告がその名称に係る商標登録を経ていないことを奇貨として、被告によるフランチャイズ事業を妨害する加害目的又は本件商標を高額で被告に買い取らせる不当な目的で行われたものというべきである。
このような本件商標の登録出願の目的や経緯等に鑑みれば、本件商標の出 願登録は、商標制度における先願主義を悪用するものであり、社会通念に照 らして著しく社会的相当性を欠く事情があるというべきであって、こうした 商標の登録出願及び設定登録を許せば、商標を保護することにより商標の使 用する者の業務上の信用を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要 者の利益を保護することを目的とする商標法の目的に反することになりかね ないから、本件商標は、公の秩序に反するものであるというべきであって、 商標法4条1項7号に該当する。 なお、原告は、本件審決は原告が享有すべき職業選択の自由を著しく狭く 解した不当な判断であると主張するが、事業において使用する特定の屋号等 の選択が職業選択の自由に含まれるものとしても、他人がその商標で築き上 げた信用の希釈又は特定の商標との混同等を理由として特定の商標の使用が 制限されることはやむをえないものであるし、もとより本件商標以外の屋号 等を選択することは可能であるから、原告の主張は当を得ないものというべ\nきであり、その他原告が縷々主張するところによっても、上記認定は左右さ れ得ない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.09.15
令和1(行ケ)10157 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年9月12日 知的財産高等裁判所
イ 商標法53条の2は、輸入者が権利者との間に存在する信頼関係に違背 して、正当な理由がなく外国商標を勝手に出願して競争上有利に立とうと する弊害を除去し、商標の国際的保護を図る規定というべきであり、この 観点からすると、ここにいう「代理人」に該当するか否かは、輸入者が「代 理人」、「代理店」等の名称を有していたか否かという形式的な観点のみ から判断するのではなく、商標法53条の2の適用の基礎となるべき取引 上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討す るのが相当である。
この点、原告は、被告商品を輸入して、日本国内でこれを販売するため に被告との取引関係に入ったものというべきところ、前記1(3)のとおり、 本件期間内の被告商品の納入は合計5回、1261万円に上り、決して少 ないものとはいえず、さらに、本件期間後の平成29年3月14日まで継 続している。そうすると、原告と被告の関係は、単発の商品購入にとどま るものではなく、継続的な取引関係の構築を前提とするものであり、この\nことは、原告がわが国におけるエスタッチ社商標の使用権を取得しようと したこと、さらには、本件商標の登録出願をしたこと自体からも裏付けら れるものである。以上の事情を総合考慮すると、原告と被告の間には、本 件期間内に既に、代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が 形成されたものと認めるのが相当であり、代理店契約の存否等にかかわら ず、原告は、同条の2にいう「代理人」に該当するというべきである。
・・・
(1) 原告は、前記第3の2(1)のとおり、被告は、本件商標の登録出願がなされ た平成28年9月5日の時点において、エスタッチ社商標に代わる商標の権 利取得を放棄していたのに等しく、他方、原告には、顧客に納入した被告製 品に付された商標に関する問題が生じることを回避する必要があったため、 原告が本件商標の登録出願をするについて正当な理由を有する旨主張する。 しかし、被告が、同年7月5日の時点でエスタッチ社商標の出願が登録料 未納付により却下されたことを把握していたとしても、原告による本件商標 の登録出願まではわずか2か月にすぎず、これをもって「長期間」放置した とか、原告のみならず任意の第三者においてエスタッチ社商標に代わる商標 を登録することが可能な状態を許容していたなどと評価できないことは明ら\nかである。なお、白岩物産は、前記1(4)のとおり、同日付けメールで、被告 が同月15日までに引用商標の商標登録出願をする予定であることを原告に\n告げているけれども、同日までに引用商標の商標登録出願がされなかったか らといって、被告が出願の意思を失ったと推認されるものでもない。 さらに、前記2(1)ウのとおり、原告は、エスタッチ社商標ないし将来被告 が日本において出願する予定の引用商標と同一の商標は、本来被告及びエス\nタッチ社が韓国において共有する商標に由来すること、また、被告が独占的 通常使用権の許諾には簡単には応じられないという意向であったことを知り ながら、独占的通常使用権をめぐる交渉中に本件商標の登録出願をしたもの であるから、原告が当該出願について正当な理由があるなどといえないこと も明白である。なお、原告のいう「被告製品に付された商標に関する問題」 とは、引用商標を付した商品が出回り値崩れを起こしているという趣旨と解 されるが(甲20の1・2、甲21の1ないし8)、これは、本来、独占的 通常使用権をめぐる交渉において解決されるべき問題であり、本件商標の登 録出願を正当化するものではない。
関連カテゴリー
>> 不正使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.09.15
令和2(ネ)10032 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
原審(平成28年(ワ)7678号)はアップされていません。
(ア) 原判決別紙「本件ソフト・ハード機器の売上額(裁判所の認定)」のとお\nり、本件において一審被告が受けた利益として認められる本件ソフト及びハードウ\nェアの売上額が合計2億5714万4027円であるのに対し、後記のとおり、本 件において一審被告が受けた利益として認められる月次利用料(被告システムない し本件ソフトの導入後5年以内に支払われるもの。以下同じ。)に係る売上額は、\n合計3億9531万1537円であり、月次利用料に係る売上額は、本件ソフト及\nびハードウェアの売上額の約1.5倍にも及ぶ高額のものであって、これを単なる データベースの更新費用等であるとみることは困難であること、一般に被告システ ムないし本件ソフトのように内容の更新が絶対に必要なデータベースを用いるシス\nテムないしソフトウェアにおいては、適時のデータベースの更新がなければシステ\nムないしソフトウェアとしての意味をなさないから、当該システムないしソ\フトウ ェアを導入する際に、更新があることを当然の前提にしてこれを含んだ価格設定を することには十分な合理性があること、弁論の全趣旨によると、一審被告は、被告\nシステムないし本件ソフトを導入した医療機関が月次利用料を3か月間支払わない\nときは、被告システムないし本件ソフトが起動しないような措置を執っているもの\nと認められること(一審被告第3準備書面5〜7頁)などの事情に照らすと、甲2 0及び48に月次利用料について「データベース更新料等」の記載があるとしても、 月次利用料に係る売上げは、被告システムないし本件ソフトの譲渡の対価(譲渡代\n金の延べ払い)の性質を持つものとして、これを一審被告が得た利益に含めるのが 相当である。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.09.15
令和3(行ケ)10110 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年7月14日 知的財産高等裁判所
ア 本件商標は、「ザプレミアムチロリアン」の文字を標準文字で表してなり、\n「ザ」「プレミアム」の文字部分と「チロリアン」の文字部分とから構成さ\nれる結合商標である。本件商標を構成する文字は、外観上、同書、同大、\n同間隔で一連表記されており、構\成文字に相応して、「ザプレミアムチロリ アン」の称呼が生じる。
次に、「ザ」の文字部分は、定冠詞「the」の片仮名表記であり、「プ\nレミアム」の文字部分は、「一段上等・高級であること」(広辞苑第七版) といった意味を有する語として、「チロリアン」の文字部分は、「チロルの 人々。オーストリア西部からイタリア北東部にまたがるチロルの山岳地帯 に住む人々の用いる独特の民族服」(ブリタニカ国際大百科事典)、「チロル 地方の。チロル風の」(広辞苑第七版)といった意味を有する語として一般 に理解されていることが認められる。このような上記各文字部分の観念及 びそれぞれの称呼に照らすと、本件商標を構成する文字は、外観上、同書、\n同大、同間隔で一連表記されていることを勘案しても、本件商標において\n「ザ」「プレミアム」の文字部分と「チロリアン」の文字部分を分離して観 察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい るものとは認められない。
そして、前記1(2)認定のとおり、標章「チロリアン」は、本件商標の登 録審決日(令和元年10月1日)当時、福岡県を中心とした九州地方にお いて、菓子の取引者、需要者の間で、特定の菓子(菓子「チロリアン」)の ブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたこと に照らすと、本件商標がその指定商品中の「菓子」に使用された場合には、 本件商標の構成中の「チロリアン」の文字部分は、菓子のブランド名を示\nすものとして注意を惹き、取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与 えるものと認められる。 そうすると、本件商標の構成中「チロリアン」の文字部分は、独立して\n商品の出所識別標識として機能し得るものと認められるから、本件商標か\nら上記文字部分を要部として抽出し、これと引用商標1とを比較して商標 そのものの類否を判断することも、許されるというべきである。
イ これに対し、被告は、1)本件商標は、「ザプレミアムチロリアン」の標準 文字を表してなり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が\n等間隔に1行でまとまりよく表されており、その文字構\成は一連一体であ ることからすると、「ザ」「プレミアム」の部分と「チロリアン」の部分は、 分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合し ている、2)標章「チロリアン」、「TIROLIAN」は、本件商標の登録 出願時及び登録審決時において、原告の業務に係る商品を表すものとして、\n取引者、需要者の間に広く認識されていたとはいえないから、本件商標の 構成中の「チロリアン」の文字部分が、本件商標の指定商品の取引者、需\n要者に対し、原告の商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える ものとはいえない、3)菓子「チロリアン」については、発売後ほどなくし て、標章「チロリアン」を使用して独自に販売を行う事業主体が複数生じ、 平成8年以降は、標章「チロリアン」を使用する事業主体間で多数の紛争 が生じており、標章「チロリアン」について統一的な管理が行われていな かったことに照らすと、取引者、需要者は、本件商標の構成中の「チロリ\nアン」の文字部分が、複数の事業主体のいずれに係る表示であるかを認識\nすることが困難であるから、「チロリアン」の文字部分は、原告の出所識別 標識として強く支配的な印象を与えるものに該当しない、4)菓子「チロリ アン」を製造販売する複数の事業主体について、経済的・組織的な一体性 を持つグループといったものが形成されたことはないから、「チロリアン」 の文字部分が、上記のようなグループの識別標識として強く支配的な印象 を与えると評価する余地もない、5)「チロリアン」の文字部分に出所識別 機能がないにもかかわらず、これがあるかのように評価して結合商標の分\n離観察を行い、その結果として、標章「チロリアン」について他の事業主 体に比べて不十分な使用実績しか有しない原告に引用商標1ないし3を\n含む「チロリアン」の登録商標を独占させるような帰結は、社会的妥当性 に欠けるなどと主張して、本件商標から「チロリアン」の文字部分を要部 として抽出することは許されない旨主張する。
しかしながら、前記(1)で説示したとおり、商標の各構成部分がそれを分\n離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結 合しているものと認められない商標においては、商標の構成部分の一部が\n取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印 象を与えるものと認められる場合などのほか、商標の構成部分の一部が取\n引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商 品の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合においても、商\n標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較し\nて商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当であ る。
そして、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い\n印象を与えるものであり、独立して商品の出所識別標識として機能し得る\nか否かについての判断は、商標に接した取引者、需要者において、商標の どのような構成部分について注意を惹き、どのような印象を受けるかなど\nの観点から判断されるべきものであることに照らすと、その判断において は、取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識\nし得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体(例えば、特定の事業\n主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等)について正確に認 識することまでは要しないと解するのが相当である。
被告主張の1)については、前記アのとおり、「ザ」「プレミアム」の文字 部分の観念及び称呼、「チロリアン」の文字部分の観念及び称呼に照らすと、 本件商標を構成する文字が、外観上、同書、同大、同間隔で一連表\記され ていることを勘案しても、本件商標において、「ザ」「プレミアム」の文字 部分と「チロリアン」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然 であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 被告主張の2)ないし4)は、取引者、需要者において、本件商標の構成中\nの「チロリアン」の文字部分に係る出所自体(特定の事業主体の名称等) について正確に認識することまで必要であることを前提とし、上記文字部 分が原告の出所を示す出所識別標識として認識されることを求めるもの であるから、その前提において採用することができない。 また、被告主張の5)については、結合商標の構成部分の一部を要部とし\nて抽出することができるかどうかの判断は、上記のとおり、当該結合商標 に接した取引者、需要者の認識及び印象に係る問題であって、本件商標と の関係では、原告による標章「チロリアン」の使用実績の規模等によって その判断が左右されるものではないから、その前提において採用すること ができない。
◆判決本文
関連事件です。
いずれも非類似とした審決が維持されています。
「ザリッチチロリアン(標準文字)」
◆令和3(行ケ)10109
「チロリアンホルン」
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.09.15
平成21年(ネ)第10024号 著作権確認等請求控訴事件 原審・大阪地方裁判所平成17年(ワ)第2641号
、 ア DHL車側プログラム(甲291)について
DHL車側プログラムのうち,「NL」「NL1」の処理(TC車の車番付けを 命ずる命令に関する処理)を行うための部分(甲291の8頁〜12頁(0286 番地〜0427番地))に関する部分は,200行前後のうちプログラムの実行順 序に係る制御を行う命令(JP命令とCALL命令)の行数が50行前後,つまり ステップ数で全体の4分の1前後が実行順序制御に係る命令に用いられている(甲 291,294)。 DHL車側プログラムには,ソースコード上では,「JP,・・・##」と示さ\nれる,飛び先の番地が指定されず,結果として0000番地が指定された場合と同 様の動作を行うJP命令(CA0000)が含まれている(なお,甲291及び後 述する甲292においては,上述したもの以外のJP命令については飛び先となる メモリのアドレス(番地)の値が具体的に示されており,甲289及び290と同 様に,ロードされるメモリ上のアドレス(番地)及びJP命令の飛び先となるアド レスが絶対的に定まったものとされている。)。 これらの命令は,変更後DHCフローチャート(甲189の1)や変更前のソー\nスコード(甲289)には含まれているものではないから,本件装置を動作させる ための最低限の機能を実現するために必要不可欠なものであったか否かは不明であ\nる。もっとも,昭和61年12月に「不連結時TC流動発生ブレーキ閉が作用しな い」という異常への対処としてプログラムが変更されたことからすると,変更を行 ったプログラム作成者は,何らかの意図,たとえば,当該プログラムの変更による 変更後の制御のタイミングを維持すべきであること等に基づいて,ほかに選択肢が あるにもかかわらず,あえて上記部分を挿入したままとしたものと推測されなくも ない。
そうすると,DHL車側プログラムには,上記命令が存在することにより,創作 性が認められる余地がないわけではない。 もっとも,1審原告は,本来,ソースコードの詳細な検討を行うまでもなく,本\n件プログラムは著作物性を有するなどと主張して,当初,本件プログラムのソース\nコードを文書として提出せず,当審の平成22年5月10日の第4回弁論準備手続 期日における受命裁判官の求釈明により,本件プログラム全体のソースコードを文\n書として提出するか否かについて検討し,DHL車側プログラムについては,ソー\nスコードを提出したものの,本件プログラムのいかなる箇所にプログラム制作者の 個性が発揮されているのかについて具体的に主張立証しない。 したがって,DHL車側プログラムに挿入された上記命令がどのような機能を有\nするものか,他に選択可能な挿入箇所や他に選択可能\な命令が存在したか否かにつ いてすら,不明であるというほかなく,当該命令部分の存在が,選択の幅がある中 から,プログラム制作者が選択したものであり,かつ,それがありふれた表現では\nなく,プログラム制作者の個性,すなわち表現上の創作性が発揮されているもので\nあることについて,これを認めるに足りる証拠はないというほかない。 以上からすると,DHL車側のプログラムには,表現上の創作性を認めることは\nできない。
イ TC車側プログラム(甲292)について
TC車側プログラムのうち,「LINK」の処理(TC車側における車番がつく までの処理)を行うための部分(甲292の4頁〜9頁(00F7番地〜0317 番地))は,294行中88行がプログラムの実行順序に係る制御を行う命令であ るとされている(甲294)ところ,当該部分の相当程度について,ソースコード\nが開示されていない。 DHL車側プログラムとTC車側プログラムとは,各プログラムが機能すること\nによって,本件装置を制御するものであるから,「不連結時TC流動発生ブレーキ 閉が作用しないという異常」を防止するために本件装置を制御するためには,両者 について同様の配慮が必要となると推測されることから,TC車側プログラムにも, DHL車側プログラムと同様に,本件装置を動作させるための最低限の機能を実現\nするために必要不可欠なものであったか否かは明らかではない命令が挿入されてい る可能性は否定できない。\nもっとも,仮に,このような命令が挿入されていたとしても,DHL車側プログ ラムと同様に,当該命令部分の存在が,プログラム制作者の個性,すなわち表現上\nの創作性が発揮されているものであることについて,これを認めるに足りる証拠は ないというほかない。 したがって,TC車側プログラムにも,表現上の創作性を認めることはできない。\n
ウ 1審原告の主張について
1審原告は,本件装置は,特許権を取得できるほどに新規で進歩性を有する画期 的な技術であり,新規な機能を有するものであるから,当該装置を稼働させるため\nの本件プログラムも,他の既存のプログラムの表現を模倣することにより作成する\nことはできないところ,特に,中核部分であるTC車の車番付けを行わせる部分は, 本件プログラムが有する多数の機能のうち最重要部分を実現するもので,新規のア\nイデアに基づき全くのゼロから開発されたものである,当該中核部分を構成する各\nパートは,それぞれ数十から百数十\もの命令数により記述されている上,多数のサ ブルーチンを用いた構成となっているところ,このような複雑なプログラムにつき,\nその表現が1つ又は極めて限定された数しかなかったり,だれが記述しても大同小\n異のものとなったりすることは到底あり得ないし,他にも多数の機能を実現するた\nめの部分が有機的に組み合わされてひとまとまりのプログラムとなっているのであ るから,本件プログラムは,本来,ソースコードの詳細な検討を行うまでもなく,\n著作権の保護を受けるプログラムの著作物に該当することは明らかであるなどと主 張する。しかしながら,本件装置が新規性を有するからといって,当該装置を稼働させるためのプログラムが直ちに著作物性を有するということができないことは明らかで ある。
また,先に述べたとおり,プログラムに著作物性があるというためには,プログ ラムの全体に選択の幅があり,かつ,それがありふれた表現ではなく,作成者の個\n性,すなわち,表現上の創作性が表\れていることを要するのであるから,新規のア イデアに基づきゼロから開発されたものであること,多くの命令数により記述され ていることから,直ちに表現上の創作性を認めることはできない。本件プログラム\nが多数の機能を実現するための部分が有機的に組み合わされているとしても,当該\nプログラムに表現上の創作性があることについて具体的に主張立証されない以上,\n当該プログラムにより実現される機能が多岐にわたることを意味するにすぎない。\nさらに,1審原告は,TC車側プログラムのうち,SOSUBサブルーチン(0 72F〜0792番地)のソースコードを例として,甲290及び292が機械語\nレベルでほぼ同一の命令構成となっているにもかかわらず,ソ\ースコードレベルで の具体的表現が異なること,SOSUBルーチンの行う仕事は,1)連結器のピンを 外すパワーシリンダを作動させる部分,2)パワーシリンダが正常に作動したか否か をチェックする部分,3)パワーシリンダの作動状況及びそのチェックの結果を操作 者に知らせるため表示灯の点・消灯を行う部分の3つに大別できるところ,本件プ\nログラムの極めて小さな一部分であるSOSUBルーチンのソースコードにおける\n具体的表現だけをみても,多数の選択肢の中から開発者の個性により選択された表\ 現が用いられているなどとも主張する。
しかしながら,甲290及び292におけるソースコードレベルでの具体的表\現 の相違は,CPUの機種変更に応じて必然的に定まる変更に基づくものにすぎず, 創作性の基礎になり得るものではない。また,上記1)ないし3)の機能を実現するそのほかの表\現に係る選択肢が存在する可能性があるからといって,直ちに本件プログラムにおけるSOSUBルーチンの具体的表\現について,創作性が認められるものでもない。1審原告が具体的に指摘する各事項は,いずれも本件装置が要求する仕様や機能を単にプログラムとして実現したものにすぎず,表\現上の創作性を基礎付けるものではない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2022.09.14
令和3(ワ)3418 不正競争 民事訴訟 令和4年8月26日 東京地方裁判所
(1) 不競法2条1項1号にいう「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、\n商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示す\nるもの」をいうところ、商品の形態は、「商標」等とは異なり、本来的には 商品の出所を表示するものではないが、商品の形態自体が特定の出所を表\示 する二次的意味を有するに至る場合がある。そして、このように商品の形態 自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し、「商品等表\示」に該当する ためには、その形態が「商標」等と同程度に不競法による保護に値する出所 表示機能\を発揮し得ること、すなわち、1) 商品の形態が客観的に他の同種商 品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、2) その形態が 特定の事業者によって長期間独占的に利用され、又は極めて強力な宣伝広告 や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定 の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要\nすると解するのが相当である。
(2) そこで、まず、原告各製品の第4世代製品の形態が有する特徴について検 討する。
証拠(甲1、2、27、28)及び弁論の全趣旨によれば、原告製品1、 2及び4のシェード部分の形状は、白色のポリプロピレンの平板を、中心部 から放射状に多数の山又は谷ができるように鋭角又は湾曲に折り畳み、これ を一層又は大きさの異なる複数層となるように配置した形状をしており、原 告製品3のシェード部分の形状は、多数の白色のポリプロピレンの平板を湾 曲に折り畳み、全体としてバラ様の略円形に整えた形状をしていることが認 められ、いずれの製品も、一般的なシーリングライト(甲22、32ないし 35、乙22)のシェード部分の形状とは異なる特徴を有しているといえる。 しかし、シーリングライトのシェード部分は、その外観を構成する主たる構\ 造である一方で、その実用目的である発光機能を直接担う部材ではないこと\nから、シーリングライトを設置する場所に合わせて、様々なデザインとする ことが可能であると考えられ(証拠(乙3、4)によれば、実際に、様々な\n形状のシェード部分を有するライトが販売されていることが認められる。)、 このようなシェード部分の性質に照らせば、原告各製品のシェード部分の形 状が他の同種商品と比べて顕著に異なることを基礎付ける事情を認めるに足 りる証拠はないというほかない。 また、前記前提事実(2)エのとおり、第4世代製品の本体部分の形状は、フ ラットな円形の台座に三つのU字型LEDモジュールが磁石で取り付けられ るなどし、台座側面に換気孔が設けられ、調光調温機能の付いたリモコンが\n付属するものであるが、一般的なシーリングライト(甲24、25、32な いし35、乙22)の本体部分の形状と比較して、特徴的なものとはいえな い。
(3) 次に、原告各製品の第4世代製品の形態の周知性について検討する。 前記前提事実(2)のとおり、第4世代製品のシェード部分は、第1世代製品 から変更がなく、第1世代製品の販売が開始された平成22年から既に10 年以上が経過しているが、原告各製品のこれまでの販売数を認めるに足りる 証拠はなく、Yahoo!等の媒体やFacebook等のSNSによる原 告各製品に係る宣伝広告の期間、内容及び効果を認めるに足りる証拠もない (Facebookで行ったとする広告に関する資料(甲46)を見ても、 具体的にどのような広告がどの程度行われたのかは明らかでない。)。また、 前記前提事実(2)エのとおり、第4世代製品の本体部分について、改良が加え られて販売が開始されたのは平成30年からであり、上記シェード部分ほど 時間が経過していない上、通常、シェード部分によって隠れているため、需 要者の注意を惹くことも少ないといえる。 さらに、証拠(乙17ないし19)によれば、1943年に創業した、デ ンマークのレ・クリント社が製造販売するシーリングライトは、そのシェー ド部分が、白色の平板を中心部から放射状に多数の山又は谷ができるように 鋭角に折り畳み、これを一層又は大きさの異なる複数層となるように配置し た形状をしていることが認められ、少なくとも原告製品1、2及び4のシェ ード部分とかなり似通っているということができる。このような事情からす ると、原告各製品のシェード部分の形状が、長年にわたり、原告により独占 的に利用されていたとは認め難い。 そして、他に原告各製品の形態が原告の出所を表示するものとして周知に\nなっていることを認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上を総合すると、原告各製品の第4世代製品の形態が、不競法2条1項 1号の「商標」等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能\を発揮 し得るとは認められないから、同号の「商品等表示」に該当するとは認めら\nれない。したがって、被告が被告各製品を販売したことは不競法2条1項1号の不 正競争には該当しない。
2 争点2(原告が「営業上の利益」(不競法3条、4条)を侵害された者に該当 するか)について
(1) 不競法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し 渡し、輸入するなどの行為が不正競争に該当すると規定するが、この趣旨は、 費用及び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者が、一定期間、 投下した費用等を回収することを容易にして、商品化への誘因を高めるため、 費用及び労力を投下することなく商品の形態を模倣する行為を規制しようと したものと解される。 したがって、同号の不正競争であるとして差止め等を請求することができ る「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」(同法3条 1項)及び「営業上の利益を侵害」された者(同法4条)とは、自ら費用及 び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者をいうと解するのが 相当である。
(2) この点、証拠(甲36ないし42、48)によれば、原告が、パーツメー カーとの間で、ライトに取り付ける安定器やリモコンへの印字方法等に関す るメッセージのやり取りをしたことが認められる。しかし、これらが原告各 製品に係るやり取りかは明らかではない上、これらのやり取りの大半(甲3 8ないし42)は、原告各製品の第4世代製品の販売が開始された平成30 年(前記前提事実(2)エ)よりも後の令和元年12月にされたものであり、そ の他のやり取り(甲36、37)はいつされたものかが明らかでない。
また、台座に係る設計図(甲50)が存在するものの、原告各製品に係る ものであるかは明らかでないし、マスキング部分に続いて「有限公司」との 記載があり、原告以外の法人の名称が記載されていたとも考えられることか ら、原告自身がこれを作成したとは認められない。 さらに、証拠(甲14、15、乙1ないし4、23)によれば、原告各製 品に付属するリモコンには、原告のブランド名である「A」と印字されては いるが、当該リモコンそのものは、中国のオンラインモールにおいて、誰で も購入することができることが認められることからすると、そのようなリモ コンに原告のブランド名が印字されていることをもって、原告が原告各製品 を開発したことを裏付けるものとはいえない。
一方で、本件中国法人を経営するBの陳述書(乙20)には、本件中国法 人は、被告各製品及びこれとデザインの似たシーリングライトを製造してい ること、これらのシーリングライトは約20年前にヨーロッパの会社が開発 したモデルの一つであり、それ以降、中国の多くの工場で類似する製品が製 造されていること、本件中国法人は、特定の顧客との間で独占販売契約を締 結することなく、各社に対して上記シーリングライトを販売していることが 記載されており、この記載内容は、原告が本件中国法人に対して原告各製品 を発注し、被告がGlobee(Hongkong)Limitedを介し て本件中国法人から被告各製品の供給を受けていること(弁論の全趣旨)、 被告各製品が原告各製品とそれぞれほぼ同一の形状をしていること(前記前 提事実(3)イ)と合致しており、一定程度、信用することができるといえる。 そうすると、原告各製品や被告各製品と同様のシーリングライトが本件中国 法人により製造販売されていたことがうかがわれる。 そして、他に、原告が自ら費用及び労力を投下して、原告各製品を開発し て市場に置いたことを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば、原告各製品の第4世代製品について、原告は、自らの費用 及び労力を投下してこれを開発して市場に置いた者とは認められないから、 原告各製品につき不競法2条1項3号の不正競争によって「営業上の利益を 侵害され、又は侵害されるおそれがある者」(同法3条1項)及び「営業上 の利益を侵害」された者(同法4条)であるとして、被告による被告各製品 の販売の差止め及び被告に対する損害賠償を請求することができない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2022.09. 8
令和2(ワ)4530 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年8月25日 大阪地方裁判所
(1) 法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表\示 を使用等することをもって不正競争に該当すると規定しており、これは、周知な商 品等表示の有する出所表\示機能を保護する観点から、周知な商品等表\示に化体され た他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止 し、事業者間の公正な競争等を確保する趣旨と解される。そして、色彩を含む商品 の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等と\nは異なり、本来的には商品の出所表示機能\を有するものではないから、その形態が 商標等と同程度に不正競争防止法による保護に値する出所表示機能\を発揮するよう な特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべきである。そうする\nと、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕著性) を有しており、かつ、2)特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、 又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品 が特定の事業者の出所を表示するものとして周知である(周知性)と認められる特\n段の事情がない限り、法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが\n相当である。
(2) 特別顕著性
ア これを本件についてみると、まず、原告商品1〜11は、釣り用のうきとし て、もっぱら釣果を得るための実用品であり、その性能を発揮するために形態が工\n夫されているものであって、基本的には、需要者が形状や色彩等のデザインを鑑賞 するためのものではない。また、使用時にはそのボディの大半が水中に隠れている 状態であり、実際の性能は外観のみでは判断し難いから、釣りをする一般的な需要\n者においては、購入時に、釣果に関する自らの経験や評判ないし価格を参考に選択 しているものと考えられ、少なくともボディの色や形状を主に観察して違いを見極 めるような商品ではないから、ボディの形態をもって特別顕著性があるというため には、他のうきとはかけ離れた特異な形態を備えている必要がある。 そして、前記認定事実によれば、昭和50年代に原告代表者が開発した「遠矢う\nき」の形態であり、原告商品に共通する形態でもある「B ボディ下部に膨らみが あり」、「D そのボディ上部に上方向にゴム管が突き出ており」、「E ボディ最 太部からボディ下端にかけて円錐状に窄まっており」、「F ボディ下端に金属製 の環が突き出ており」、「G ボディ上部、ボディの長手方向中央付近及びボディ の最太部の下方にそれぞれ二重線が引かれている」形態は、昭和57年7月30日 に登録された意匠であり、平成9年7月30日に意匠権の存続期間が満了し、それ 以降は当該形態について意匠権による独占は認められなくなっていたことが明らか である(なお、前記実用新案権についてはそれ以前に存続期間が満了していること が明らかである。)ところ、ZF 形態に係る原告商品1〜3の発売以前から、「B 木製黒色のボディ下部に膨らみがあり」、「C そのボディ上部に黄白色の樹脂塗 装がなされ」、「D そのボディ上部に上方向に黒色のゴム管が突き出ている」各 特徴の1つ又は2つを備えた棒うきが各メーカーから複数種類販売されていたこと が認められる。また、ボディの大きさについても、ボディ全長が10cm台〜20cm 台のものが存在し、ボディ最太部の直径も10mm台のものが存在したことが認めら れる。そうすると、ZF 形態は、その発売以前に存在した他のうきとかけ離れた特 異な形態を備えているとはいえず、特別顕著性が認められない。
また、SP 形態は、前記認定事実のとおり、従前の「2号」や「180s」等の 「遠矢うき」の形態を引き継いだ ZF 形態の特徴を維持しつつ、円錐うきに慣れた 需要者にも受け入れやすくするために開発されたものであって、原告商品12を含 めて「遠矢グレスペシャル」として販売されているものであり、客観的な形態も、 原告商品1〜9のボディ全長を数cm短く(原告商品10、11)又は長く(原告商 品12)、最太部の直径を2mm程度太くしたにすぎないから、ZF 形態のバリエー ションの一種というべきであって、ZF 形態と同様に特別顕著性があるとは認めら れない。
イ 原告は、ZF 形態及び SP 形態を備えた商品は、被告商品の登場まで他に存在 せず、被告商品以外の模倣品は短期間で市場から消えたと主張する。 しかしながら、原告において原告商品1〜3のボディ上部に黄白色の樹脂塗装を し始めたのは、原告の従来の遠矢うきと製造工程において区別するためであったと いうのであるから、ZF 形態のうち、「C ボディ上部の樹脂塗装」以外は従来から 存在した形態であることが明らかである。そして、前記認定事実のとおり、ボディ 上部に黄白色の樹脂塗装をしたうきが原告商品1〜12の発売以前から複数存在し ており、ボディ上部に黄白色の樹脂塗装をすることは何ら特異な配色とはいえない から、従来から存在する形態に黄白色の樹脂塗装を加えたからといって、特別顕著 性が備わるとはいえない。
また、前記認定事実のとおり、ZF 形態及び SP 形態と共通する特徴を備えた商品 は、原告商品1〜3の発売以前から複数存在し、商品カタログに掲載されているに もかかわらず全く販売されなかったとは考え難い上、原告代表者において、「遠矢\nうき」の模倣品が大量に出回った時期があったことを認めており、平成2年頃にお いてもなお、原告が類似品と認識するような商品が大量に出回っていることを前提 に、遠矢の名入りの有無で区別するよう注意を呼び掛ける広告をし、平成19年以 降も継続的に類似品が出回っている旨の広告をしていたのであるから、被告商品以 外の ZF 形態及び SP 形態を備えた商品が全て短期間で市場から消えたとは到底考え られない。 そうであれば、被告商品販売開始時において、ZF 形態ないし SP 形態と同一又 は類似する特徴を備えた商品は複数存在し、これらの形態はありふれたものとなっ ていたというべきである。 なお、原告は、個別の同種商品について、ZF 形態及び SP 形態と一部共通する特 徴を備えているとしても、特徴の全部が同一ではない旨主張するが、前記のよう に、うきの形態に特別顕著性があるというためには、他のうきとはかけ離れた特異 な形態であるといえる必要があり、形態上の特徴が同一又は類似の同種商品が存在 すれば、特別顕著性は認められないというべきである。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2022.09. 5
令和3(行ケ)10137 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月23日 知的財産高等裁判所
(1) 審決取消訴訟の拘束力
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が 確定したときは、審判官は法181条2項の規定に従い当該審判事件につい て更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟 法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法33条1項の規定 により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が 導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審 判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。 したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ 判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰 り返すこと、あるいはかかる主張を裏付けるための新たな立証をすることを 許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限 りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすること ができない(最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号2 45頁)。
(2)ア 一次審決取消訴訟の判断
(ア) 本件訴訟におけると同様に、一次審決取消訴訟においても、実施可能\n要件(法36条4項1号)に関して、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載は、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加す る所定角度範囲内において徐々に減少」するとの構成(構\成要件G)を 当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているか否かという\nことが争点となり、原告(一次審決取消訴訟の被告)は、本件発明に係 る作業機を自ら開発した被告(一次審決取消訴訟の原告)ですら、本件 明細書等の図7のグラフのデータを得た日に存在していた「当時の作業 機」を再現できないのであるから、構成要件Gが実施不可能\であること は明らかであると主張した(甲47〔20頁〕)。
(イ) この点について、一次判決は、特許発明が実施可能であるか否かは、\n実施例に示された例をそのまま具体的に再現することができるか否か によって判断されるものではないから、本件特許の原出願時に当業者が 本件明細書の記載に基づいて本件発明を実施することができたか否か は、本件明細書等の図7のグラフのデータを得た「当時の作業機」自体 を再現できるか否かによって判断されるものではなく、甲60(審判乙 14)、甲64(審判乙18)によれば、構成要件Gが実施可能\であるこ とが認められるから、原告の上記主張は採用することができない、と判 断した(甲47〔51〜52頁〕)。
イ 本件審決の判断
原告は、本件審決においても、前記ア(ア)と同様の主張を行ったが(本件 審決第4の3(4)カ)、本件審決は、一次審決取消訴訟のとおりの判断(前記 ア(イ))をし、そのような判断によれば、「一次審決は、図7のグラフを得た という作業機(実施品)が当時存在していたかについて審理判断していな いが、図7のグラフを得たという作業機が当時存在していたことを示す証 拠は皆無であり、架空の構成Gは当業者であっても実施不可能\である。」と いう原告の主張をもって、構成要件Gが実施可能\であるとの判断が左右さ れるものでないことは明らかであると判断した(本件審決第6の2(5)イ(イ) c〔本件審決111頁〕)。
(3) 原告は、本件訴訟において、取消事由3として、本件発明が、構成要件G\nの「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角 度範囲内において徐々に減少し」という構成を備えるものとして実施可能\で あるというためには、本件明細書等の図7のグラフに示された結果を得るた めの実測に用いられた本件発明に係る当時の作業機(本件発明の実施品)が 実際に存在していたことが前提であるとし、それにもかかわらず、構成要件\nGの根拠である図7のグラフを得たという当時の作業機自体及びそれに関す る資料が現在存在しないから、図7のグラフは、一体どのような作業機を用 いた実測結果であるのか全く理解できず、構成要件Gの根拠になり得ず、そ\nのため、構成要件Gは根拠がなく、当業者であっても実施不可能\であると主 張する(前記第3の9〔原告の主張〕)。 しかし、原告の取消事由3についての上記主張は、本件明細書等の図7の グラフのデータの実測に用いられた作業機に関する資料の存否に言及するも のの、資料がないためにそのような作業機の存在が認められなければ、構成\n要件Gは実施不可能であるとの趣旨の主張であり、実施可能\要件との関係に おいては、本件明細書等の図7のグラフのデータの実測に用いられた作業機 の存在が明らかにならなければ実施可能要件は認められないとの主張であっ\nて、原告が一次審決取消訴訟において行った主張(前記(2)ア(ア))と同じ内容 の主張であると認められる。そして、原告が一次審決取消訴訟においてした 主張は(前記(2)ア(ア))、一次審決取消訴訟の判決理由中で理由がないと判断 され(前記(2)ア(イ))、その判断には行政事件訴訟法33条1項の拘束力が生 じたものと認められ、本件審決は、一次審決取消訴訟の拘束力に従って、原 告の上記主張に理由がないと判断したものと認められる。 したがって、原告は、本件審決が一次審決取消訴訟の拘束力に従ってした 判断をもはや争うことはできないものというべきであるから、原告の取消事 由3の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2022.09. 5
令和3(行ケ)10136等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月31日 知的財産高等裁判所
前記1(2)のとおり、本件発明1は、溶融前の半田片をノズルの内壁及び端 子の先端に必ず当接させるとともに、溶融した半田片を必ず真球にならないまま端 子の上に載った状態で下方に移動しないように停止させ、ノズルからの熱伝導等に より半田片及び端子を十分に加熱し、これにより適正温度での半田付けを実現する\n結果、半田付け不良の防止という効果を奏するものである。これに対し、甲1には、 ランドに接地した糸半田が貫通孔の周壁から輻射熱、伝導熱及び対流熱により加熱 され、遜色なく溶解され、より的確な半田付けが可能になった旨の記載はみられる\nものの(段落【0023】及び【0042】)、溶融した半田が必ず真球にならな いまま停止すること、すなわち、溶融後も半田がノズルの内壁に当接し続けること により半田片及び端子が十分に加熱されることについての記載及び示唆はないから、\n甲1に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決\nしようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構\成を得る ためにフラックスの含有量が1wt%の半田をわざわざ採用しようとする動機付け はないものといわざるを得ない。
(6) なお、証拠(甲39)及び弁論の全趣旨によると、フラックスの含有量が 小さい半田を用いると、半田付け不良の原因になるものと認められる。
(7) 以上によると、使用する半田に含有されるフラックスの量についての記載 及び示唆がない甲1に接した当業者にとって、甲1発明においてフラックスの含有 量が1wt%の半田をわざわざ採用し、溶融した半田が必ず真球にならないとの構\n成を得ることが容易になし得たものであったと認めることはできず、その他、当業 者が甲1発明に基づいて溶融した半田が必ず真球にならないとの構成を得ることが\n容易になし得たものであったと認めるに足りる証拠はない。 なお、乙3(技術説明資料・17頁)には、甲1発明においてフラックスの含有 量が2wt%以下の半田を用いても必ず真球にならないとの構成を得ることができ\nる旨の記載があるが、半田が溶融した際に形成される球の直径を求めるに当たって は、フラックスの組成、半田の組成、半田の熱膨張、ノズルの熱膨張等の諸般の要 素につき詳細な検討が必要であるから、乙3が引用する甲33(原告の特許庁審判 長に対する回答書)の計算結果並びに残存するフラックスの影響及び半田の熱膨張 の影響のみを考慮することによっては、甲1発明においてフラックスの含有量が2 wt%以下の半田を用いた場合に必ず真球にならないとの構成を得るものと認める\nことはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2022.08.31
令和3(行ケ)10131 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月22日 知的財産高等裁判所
(3) 前記(2)の記載によると、甲4の「スクリーン保護膜30」が本件発明1の 「保護シート」に相当し、「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」が それぞれ本件発明1の「第2剥離部」及び「第1剥離部」に相当することは明らか である。そして、甲4の「第一の突起部343」及び「第二の突起部344」は、 それぞれ「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」から、「スクリーン 保護膜30」の外側に延びるように設けられ、「第一の離型膜341」及び「第二 の離型膜342」を剥がす際に手で持つ部分であるから(段落【0025】、【0 026】、【図4】〜【図6】)、いずれも本件発明1の「延出部」に相当すると いえる。
ここで、甲4において「第一の突起部343」及び「第二の突起部344」を設 けたのは、手で「第一の突起部343」又は「第二の突起部344」を持って、そ れぞれ「第一の離型膜341」又は「第二の離型膜342」を便利に剥がせるよう にするためである(段落【0025】)。そうすると、甲4に記載された発明とそ の属する技術分野を同じくする甲3−1発明(その内容は、前記第2の3(2)ア (ア)のとおり)においても、そのような利便性を図るため、甲4に記載された「第 一の突起部343」及び「第二の突起部344」の構成を適用して本件発明1の\n「延出部」を設けることは、本件優先日当時の当業者において容易に想到し得たこ とであると認められる。
(4) この点に関し、原告は、甲3−1発明に甲4に記載された「第一の突起部 343」及び「第二の突起部344」の構成を適用することには、阻害要因がある\n旨主張するが、以下のとおり、これを採用することはできない。
ア 原告は、まず、甲3−1発明はその貼付の対象として超大型のディスプレイ\nパネル(最低でも17インチのものであり、適するのは82インチのものであり、 更にそれより大きいものを含む。)を想定しており、その貼付を行うのは専門の技\n術者であるから、本件発明1の「延出部」のような部材は不要である旨主張する。 そこで検討するに、前記(1)のとおり、甲3には、甲3−1発明の光学フィルム を貼付する対象が「大型ディスプレイパネル」であり、「大型」とは17インチか\nら82インチ程度までのものをいう旨の記載がある(前記(1)イ、ケ等)。また、 特許請求の範囲においては、保護フィルムの貼付の対象となる大型ディスプレイパ\nネルが少なくとも17インチのものである旨の特定がされている(前記(1)ツ)。
さらに、実施例1においては、甲3−1発明の光学フィルムは40インチの大型液 晶テレビに貼付され、実施例2においては、甲3−1発明の光学フィルムは23イ\nンチのコンピュータディスプレイに貼付されている(前記(1)ソ及びタ)。これら\n甲3全体の記載を参酌すると、甲3の「要約」に、「この方法は、対角線208c m(82インチ)の可視領域を有するような大型ディスプレイパネルでの使用に適 している。」との記載があること(前記(1)ア)を考慮しても、甲3−1発明が8 2インチ程度の大型ディスプレイパネルのみをその貼付の対象としていると認める\nことはできず、甲3−1発明は、幅広い大きさの範囲(17インチないし82イン チ程度)のディスプレイパネルをその貼付の対象とするものであると認めるのが相\n当である。そして、17インチ程度の大きさのディスプレイパネルに光学フィルム を貼付することが専門の技術者でなければ行えないとみるべき事情もない。そうす\nると、甲3−1発明の光学フィルムの貼付については、専門の技術者がこれを行う\nことを常に想定しているということはできないから、原告の上記主張は、その前提 を欠くものとして失当である(なお、原告が主張する「把持部」(本件発明1の 「延出部」に相当する部材)は、甲4における「第一の離型膜341」及び「第二 の離型膜342」を剥がすのに便利な「第一の突起部343」及び「第二の突起部 344」と同様の機能を有するものであるところ(甲4の段落【0025】等参\n照)、甲4の「第一の離型膜341」及び「第二の離型膜342」は、甲3―1発\n明の分離剥離ライナーである「第1の部分38a」及び「第2の部分38b」に対 応するものである。専門の技術者であったとしても、分離剥離ライナーを剥がすた めに「把持部」を設けることは便利となるものであって、仮に、甲3−1発明の光 学フィルムがその貼付を専門の技術者が行うことを想定しているとしても、そのこ\nとから直ちに、甲3−1発明の光学フィルムにおいて、分離剥離ライナーである 「第1の部分38a」及び「第2の部分38b」を剥がすのに便利な「把持部」を 設けることが不要になるわけではない。)。
イ 原告は、また、甲3−1発明の光学フィルムの貼付作業に利用できるように\n「把持部」を形成する場合、最低でも10cm程度の大きさ(これは、「把持部」 と「第1の部分38a」又は「第2の部分38b」が接する部分の長さをいうもの と解される。)が必要になるところ、そのような大きさの「把持部」が形成される と、甲3が想定する精度で貼付作業を行うことができなくなる旨主張する。\nしかしながら、甲3−1発明の光学フィルムに「把持部」を形成する場合、最低 でも10cm程度の大きさを必要とするとの原告の主張は、何ら客観的な根拠を有 するものではないし、上記アのとおり、甲3−1発明の光学フィルムは、17イン チのディスプレイパネルをもその貼付の対象とするものであるから、その場合にも、\n「把持部」を形成するのであれば最低でも10cm程度のものが必要であるという ことはできない(なお、原告の上記主張は、甲3−1発明の光学フィルムの貼付の\n対象として、82インチ程度の超大型ディスプレイパネルのみが想定されているこ とを前提とするものと解されるが、その前提が成り立たないことは、前記アのとお りである。)。したがって、原告の上記主張も、前提を誤るものとして失当である。 ウ 原告は、さらに、甲3−1発明の光学フィルムは、ディスプレイパネルの周 囲に大きな段差のあるフレームがあるような場合に使用されることを想定している ところ(甲3の図面)、そのような場合に「把持部」を形成すると、フレームと 「把持部」が干渉してしまい、甲3−1発明の光学フィルムの位置決めが不可能に\nなる旨主張する。
確かに、甲3の図面の中には、ディスプレイパネルの周囲にフレームがあり、段 差が生じていると見て取れるもの(図7a等)がある。しかしながら、実施例1に おいては、甲3−1発明の光学フィルムは大型液晶テレビに貼付され、実施例2に\nおいては、甲3−1発明の光学フィルムはコンピュータディスプレイに貼付されて\nいるところ(前記(1)ソ及びタ)、大型液晶テレビやコンピュータのディスプレイ\nパネルの周囲に必ず段差のあるフレームが存在するわけではないから、甲3−1発 明の光学フィルムが、常にディスプレイパネルの周囲に大きな段差のあるフレーム があるような場合に使用されることを想定しているということはできない。したが って、原告の上記主張も、その前提を誤るものとして失当である。
エ なお、原告は、実験報告書(甲28の3、甲36)を根拠に、甲3−1発明 の光学フィルムを巨大なディスプレイパネルに貼付する場合、「把持部」があると、\nかえって作業に支障を来す旨主張する。
しかしながら、上記実験において用いられたのは、82インチの光学フィルムの みであるところ、前記アのとおり、甲3−1発明は、常に82インチ程度の光学フ ィルムであることを前提としているわけではないから、82インチよりも小さいサ イズの光学フィルムを用いた実験を省略する上記実験は、17インチないし82イ ンチ程度といった幅広い大きさの範囲でディスプレイパネルに貼付することを前提\nとする甲3−1発明の光学フィルムに「把持部」を設けることの不都合さを示す実 験としては、十分なものではない。加えて、23インチのディスプレイパネル及び\n82インチのディスプレイパネルに貼付することのできる2種類の光学フィルムを\n用いた被告の実験結果(「延出部」を設けても貼付作業に支障を来さず、むしろ有\n用であったとするもの。乙1、2)にも照らすと、原告の上記実験結果によっても、 甲3−1発明の光学フィルムに「把持部」を設けると貼付作業に支障を来すことに\nなると認めることはできず、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2022.08.24
令和1(ワ)16040 映画上映禁止及び損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年1月27日 東京地方裁判所
原告らは,被告Fは,政治プロパガンダ映画である本件映画1を制作し, これを商業映画として有料で一般公開することを計画していたにも関わらず, あたかも真摯な学術研究目的であるかのように装うなど前記第2の4(14)(原 告らの主張)のとおり欺罔行為を行い,原告らをその旨誤信させて原告らに\n取材に応じるという役務を提供させたと主張する(争点7)関係)。また,原 告らは,本件各許諾について,被告Fは,原告らに対する取材映像を利用し て商用映画(本件映画1)を製作しようと考えていたが,原告らに対しては, これを秘し,上智大学大学院の修士課程の一環である卒業制作のための真摯 な学術研究目的の活動であると説明して原告らを欺罔したため,原告らはそ\nの旨誤信して,本件各書面を作成したものであり,本件各書面による本件各 許諾は,詐欺取消し又は錯誤無効により存在しない旨主張する(争点1)−2 関係)。
以下,原告ら主張の被告Fの欺罔行為の有無について,検討する。\n
(2)ア 原告らは,大学院生である被告Fから,卒業制作として大学院に提出す るドキュメンタリー映画の製作に協力してほしいと頼まれたことや,製作 された映画が商用映画になるとは説明を受けていなかったことから,取材 に協力し,また,本件各映像の利用について本件各許諾をした旨の供述等 をする(原告C,原告D,原告E,甲6,7,35〜38,41)。
イ 被告Fが,原告らに対して取材に協力するよう求めた際の説明の内容等 は,原告Eについて前記1(2)ア,原告Cについて同(3)ア,原告Dについて 同(4)ア,原告Bについて同(5)ア,原告Aについて同(6)アのとおりである。 被告Fは上記の際,上智大学大学院の学生であることを述べて,「歴史 問題の国際化」についてドキュメンタリーを作成していてそのために取 材をさせてほしいことを述べた。また,その際,それが学術研究である こと,卒業プロジェクトであることを述べたりもしたこともあった。
(3) ここで,被告Fは,前記依頼の当時,実際に上智大学大学院の学生であっ て,修士論文に代わる映像作品として従軍慰安婦問題に関する映画を作成す ることとし,その映画ではこの問題において重要な役割を果たしていると考 えた者たちに対する取材映像を映画の主たる部分とすることを構想し(前記\n1(1)),この問題において重要な役割を果たしていると考える原告らへの取 材を行い,その際の映像である本件各映像を用いて,本件卒業制作映画を完 成して,これを修士論文に代わるものとして上智大学大学院に提出した(同 (7))。そして,被告Fは,本件卒業制作映画に,音楽,アニメーション,字 幕等を追加し,一部を訂正するなど,軽微な編集を加えて鑑賞性を高めて本 件映画1としたものであり,本件映画1は,本件卒業制作映画と,内容,構\n成において同じであって(前同),本件各書面にいう被告Fが製作する「歴 史問題の国際化に関するドキュメンタリー映画」(前記第2の2(2)イ)に該 当する。
被告Fは,当初から良い映画が製作できた場合には映画祭に応募すること を視野に入れてはいたが(この点は後記(4)で検討する。),上記のとおり, 本件各映像を利用して被告Fが製作した映画である本件卒業制作映画は,実 際に修士論文に代わるものとして大学院に提出されたのであり,本件映画1 も本件卒業制作映画と内容,構成において同じものである。したがって,被\n告Fが,原告らに取材を依頼したり本件各書面の作成を求めたりした際に, 上智大学大学院の学生として行うものであり,学術研究として作成されるも のであることを述べるなどしたこと自体は,被告Fが虚偽を述べたとはいえ ない。
(4) 被告Fは,当初から良い映画が製作できた場合には映画祭等に応募するこ とも視野に入れていた。もっとも,原告らに取材をした時点では,具体的な 映画の配給が決まっていたわけではなく,その後,本件映画1を応募したも ののその上映を断った映画祭もあった(前記1(1),(7))。被告Fは,原告E及び原告Dに対しては,同原告らが,被告Fの開設するユーチューブチャンネルの登録者など欧米の視聴者や研究者,学術世論に対して意見を発信できる場所を提供したいなどとして取材を申し込んでおり(同(2)ア,(4)ア),本件映像が大学への提出以外にも使用されることがあることを述べていた。そして,被告Fは,原告E,原告B及び原告Aとの間では「被告F又はその指定する者が,日本国内外において,映画を配給,上映,展示若しくは公共に送信し,又は,映画の複製物を販売,貸与することができる」旨が記載されている書面を,原告C及び原告Dとの間では「映画の公開前に,同原告らに確認を求める」旨が記載されている書面を交わした(本件各書面)(前記第2の2(2)イ,前記1(2)〜(6))。
原告らが署名押印した本件各書面は,文言上,被告Fが製作する映画につ いて,「配給」,「上映」,「販売」されることがあることや,「公開」さ れることがあることを前提とするものである。原告C書面及び原告D書面は, 原告Cが当初被告Fが示した承諾書案への署名を留保したり,原告Dが過去 にメディアから特定の観点だけを切り取られたりしたことなどを述べて被告 Fと合意書案の修正についてのやりとりをした上で,原告C及び原告Dが署 名押印したものであり,映画が公開される場合における被告Fの義務等が具 体的に定められているものである。本件各書面の上映や公開が,商用として の上映,公開を含まないことをうかがわせる記載はない。 そして,被告Fが,原告らに対して取材を申し込み,また,本件各書面へ\nの署名押印を求めるに当たって,本件各映像を利用して製作する映画が一般 に,場合によっては商用として,公開される可能性が排除されると述べたこ\nとは認められないし,被告Fがその可能性を秘匿したと認められる状況も認\nめられない。
また,その後,被告Fは,本件各映像を利用して製作した本件映画1が映 画祭で上映されたり,日本国内で上映されたりすることについて,自ら事前 に原告らに知らせていた。すなわち,被告Fは,平成30年9月30日には, 本件各映像を利用して製作した本件映画1が釜山国際映画祭において上映さ れる予定であること,将来日本と韓国で更に上映される可能\性があることを 各原告に対して告知し,平成31年2月28日には,本件映画1が日本国内 において上映される予定であることを,各原告に対し事前に告知した(前記\n1(8))。そして,上記の告知に対して,いずれの原告らからも一般に又は商 用として公開されることについて許諾をしていないなどとの抗議がされるこ とはなかった。むしろ,原告D及び原告Bは被告Fに対し祝意を表し,原告\nDは試写会に参加し(同ウ,エ),原告Aは,ツイッターに本件映画1の日 本国内における公開等を宣伝する好意的な投稿をしたほか,試写会に参加し て毎日新聞社の取材に感想を述べるなどした(同オ)。その後,原告らは, 本件映画1の上映中止を求めるようになったが,それは,本件映画1が日本 国内において上映されるようになり,原告らがそれぞれ本件映画1を鑑賞し その内容を認識した後,又は,その内容を認識してから少し経過した後であ る平成31年4月から令和元年5月頃からである(同(8),(9))。
以上のとおり,被告Fは,原告らに取材を依頼した際,製作した映画を映 画祭に応募することも考えていたが,具体的な映画の配給についての話はな かったところ,原告らとの間でも,取材の結果を一般に公開する話が出たこ ともあった。また,原告らと被告Fとの間の本件各書面には,製作した映画 の配給,上映や公開についても記載されていた。本件各書面に記載された映 画の上映や公開が商用での公開を含まないことをうかがわせる記載もない。 被告Fが,取材の依頼の際や本件各書面への署名押印の依頼に当たり,商用 を含む公開の可能性を排除したり,その可能\性を秘していたりしたとは認め られない。また,被告Fは,映画祭や日本国内での本件映画1の上映に先立 ち,その上映を原告らに告知し,原告らもそれに抗議をすることはなかった。 これらによれば, 被告Fが,製作した映画が原告らに対する取材の時点 から一般に,場合によっては商用として公開されることがあることを秘して いたということはできず,被告Fが原告ら主張の欺罔行為を行ったとは認め\nられない。原告らは,本件各映像を利用して製作される映画が一般に,場合 によっては商用として公開される可能性をも認識した上で,被告Fに対し本\n件各許諾をしたものと認められる。
(5) 以上によれば,被告Fが,原告らに対して取材を申し込み,また,本件各\n書面への署名押印を求めるに当たって,原告らが主張する欺罔行為によって\n原告らを欺罔したとは認めるに足りず,本件各許諾をするに当たって原告ら\nに錯誤があったとも認めるに足りない。 したがって,本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効であ\nるか(争点1)−3),及び,被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるとい\nう役務の提供をさせたか(争点7))について,原告らの主張には理由がない。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 肖像権等
>> その他
>> ピックアップ対象
2022.08.23
令和3(ワ)10987 著作権侵害損害賠償請求事件 著作権 令和4年2月24日 東京地方裁判所
そこで検討すると,著作物の複製(著作権法21条,2条1項15号)と は,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを 再製することをいい(最高裁判所昭和50年(オ)第324号同53年9月 7日第一小法廷判決・民集32巻6号1145頁参照),著作物の翻案(著作 権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特\n徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新た\nに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著\n作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創\n作する行為をいう。しかして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を\n保護するものであるから(著作権法2条1項1号),既存の著作物に依拠して 創作された著作物が思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表\n現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作\n物と同一性を有するにすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらないもの と解される(最高裁判所平成11年(受)第922号同13年6月28日第 一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。
このように,複製又は翻案に該当するためには,既存の著作物とこれに依 拠して創作された著作物との同一性を有する部分が,著作権法による保護の 対象となる思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である\n(著作権法2条1項1号)。そして,「創作的」に表現されたというためには,\n厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではなく,筆者の何 らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが,他方,文章自体\nがごく短く又は表現上制約があるため他の表\現が想定できない場合や,表現\nが平凡かつありふれたものである場合には,筆者の個性が表現されたものと\nはいえないから,創作的な表現であるということはできない。\n したがって,被告各記述を含む被告の雑誌記事,書籍等が,被告各記述に 対応する原告各記述との同一性により原告雑誌記事,原告ルポの複製又は翻 案に当たるか否かを判断するに当たっては,両者において共通する部分が, 思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部\n分又は表現上の創作性がない部分でないかどうかを検討する必要がある。\nそこで,以上の見地から,別紙1及び2の各対比表について個別に検討す\nることとする。
(2) 別紙1の対比表について\n
ア 「1−1あ」,「1−5あ」,「1−6あ」,「1−7あ」,「1−10あ」に ついて
この箇所の原告記述と被告記述とでは,1)奨学金の原資を確保するので あれば,元本の回収が何より重要であること,2)日本学生支援機構は20\n04年以降,回収金をまず延滞金と利息に充当するという方針をとってい ること,3)日本学生支援機構の2010年度の利息収入は232億円,延\n滞金収入は37億円に達し,これらの金は経常収益に計上され,原資とは 無関係のところにあること,といった点が共通している。 しかし,上記共通点のうち,1)は,原告雑誌記事が発行,公表される以\n前から既に問題になっていた奨学金の金融事業化についての一般的な考察 (乙5ないし7)であって,思想又はアイデアに属するものというべきで ある。2)と3)は,奨学金の回収方法や日本学生支援機構の収支に関する事\n実であり,3)の後段の,回収された金と奨学金の原資との関係についての 評価は,これもまた1)と同様に奨学金の金融事業化についての一般的考察 として思想又はアイデアに属するものというべきであって,原告記述と被 告記述とは,表現それ自体ではない部分において同一性を有するにすぎな\nい。また,1)ないし3)の記述順序は同一ではあるが,その記述順序自体は 独創的なものとはいえないし,文章の分量も短く簡潔で,表現も特徴のな\nいありふれたものといわざるを得ず,表現上の創作性が認められない部分\nにおいて同一性を有するにすぎない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2022.08.23
令和2(ワ)33027 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月25日 東京地方裁判所
上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成\nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも\nに、「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう\nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法17条の2第3項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において\nも訂正請求が認められているほか、当初明細書(【0038】)には、ICカ ードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載\nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記\n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 当業者自明
>> 新たな技術的事項の導入
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.08.18
令和1(ワ)20286等 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月30日 東京地方裁判所
前記(ア)のとおり、乙4文献には、使用時に表示板2を見易い傾斜角度\nに開くことができる折畳み式の小型電子機器において、表示板2を手で\n回転させると、回転軸8の溝aないしeに回転軸止め用シャフト10が 弾性的に圧入され、回転軸8の溝b、c、d、eのところで、夫々クリ ック音を感触させながら位置II)、III)、IV)、V)で停止して表示板2を固定\nさせることが開示されており、第5図からは、傾斜角度が約120度か ら約170度までの範囲内の予め決められた1つの傾斜角度に対応した\n位置で固定可能なことも理解できる。\nまた、前記(イ)のとおり、乙26文献においても、表示体ケース2を開\n閉可能な小型の電子機器において、回転軸6の凸凹10とクリックツメ\n12を設けることで、表示体ケース2を任意の位置で停止させることが\nできることが開示されている。 そうすると、乙4文献及び乙26文献により、折り畳み式の小型電子 機器において、表示板を含む2つの部材のなす角度が、ユーザーが行う\n表示板の回動により約120度から約170度までの範囲内の予\め決め られた1つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、 前記2つの部材の間を前記予め決められた1つの角度で固定する中間ス\nトッパであって、前記2つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広 げられて行く動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭\nめて行く動作をストップする機能を有する中間ストッパを設けることは、\n周知の技術(以下「本件周知技術」という。)であると認めることができ る。
(エ) 本件相違点への本件周知技術の適用
乙1発明’は、前記(1)イのとおり、第1のパネル12と第2のパネル 14が蝶番手段16によって接続され、ユーザーが座ったり、立ったり、 又は、歩いたりする位置にあるときに、片手でコンピュータを保持し、 もう片方の手でデータを入力することを許容するコンピュータノートブ ック10の発明であり、これは、折り畳み式の小型電子機器に関する技 術であるという点で、本件周知技術と共通する。したがって、乙1発明’ において、「第1のパネル12及び第2のパネル14の両方が蝶番手段1 6を中心とした多数の角度において配向する」場合に、本件周知技術の 中間ストッパを採用することにより、本件相違点に係る本件発明1の構\n成とすることは、当業者において容易に想到し得たことである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 減縮
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.08.18
令和3(ネ)10079 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 控訴人は、前記第2の5(1)アのとおり、本件発明の「係止片」は、1)所定 位置において、それ自体として針先の再露出を直接防止し、2)片状の部材で あり、3)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、4)大径部に円筒状部と一 体形成され、5)小径部側には設けられていないものをいうから、上記構成要\n素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられていても構成\n要件1E4)の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの主張もこのよ うな理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第3の2(1)(補正後のもの)のとおり、 本件発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機能\nを有する係止片は小径部側には設けられてはならず(係止片が小径部側に設 けられていないことに特有の技術的意義がある。)、したがって、小径部に設 けられることで構成要件1E4)の充足が妨げられる係止片は、その形状を問 われないものであるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小\n径部側に存することは、対象製品が構成要件1E4)を充足することを妨げる ものである。
また、控訴人は、係止片は針先の再露出を「それ自体」として、かつ、「直 接」に防止しなければならない旨主張するところであるが、特許請求の範囲 及び本件明細書の記載上、根拠を見いだし難い(いずれにせよ、大径部係止 手段と小径部側壁部から構成される「係止片」は、それ自体により直接に針\n先の再露出を防止していると認められる。)。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」(へん)状の部材であるから、「係止片」とは「片 状(へんじょう)の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判断 に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片 状のものに限定する意義は見いだせない。また、いずれにしても、被告製品 は、小径部側壁部の突端面により縦リブの側面を挟持するものであるところ (引用に係る原判決第2の1(3)イd(補正後のもの))、小径部側壁部の突端 面を「片」と理解することに支障があるとは思えない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2022.08.18
令和2(ネ)10069 特許法74条1項を原因とする特許権移転登録請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 本件発明11の完成時期について
本件発明11に係る請求項11の記載は、「経糸送出機構、緯糸供給機構\、 柄出し機構、編目形成機構\、及び、巻取機構を備えた経編機を使用して、\n請求項1〜10に記載のラップネットを連続して編成するラップネット の製造方法において、前記編目形成機構から連続的に編出される前記ラッ\nプネットを前記巻取機構の巻上げローラで巻き取るにあたり、当該巻上げ\nローラをその回転軸方向に所定の振幅で往復運動させることを特徴とす るラップネットの製造方法。」であるのに対し、本件出願の優先権主張の基 礎となる先の出願2の請求項6の記載は、「経糸送出機構、緯糸供給機構\、 柄出し機構、編目形成機構\、及び、巻取機構を備えた経編機を使用して、\n請求項1〜5に記載のラップネットを連続して編成するラップネットの 製造方法において、前記編目形成機構から連続的に編出される前記ラップ\nネットを前記巻取機構の巻上げローラで巻き取るにあたり、当該巻上げロ\nーラをその回転軸方向に所定の振幅で往復運動させることを特徴とする ラップネットの製造方法。」であり、先の出願2の請求項6の記載は、本件 特許の請求項11の記載と同内容である。
加えて、本件明細書の【0042】ないし【0044】、【0083】及 び【0094】の記載は、先の出願2の明細書の【0032】ないし【0 034】、【0070】及び【0081】の記載と同内容であることからす ると、先の出願2の請求項6に係る発明の技術的思想は、本件発明11の 技術的思想と同一であることが認められる。 そして、先の出願2の明細書の上記記載中には、巻上げローラを回転軸 方向に往復運動させる振幅の数値、1本のロールに巻き取ったラップネッ トの長さ、その直径の数値、発明の効果等の記載があり、かかる記載によ って、本件発明11の技術的思想は、先の出願2の請求項6に係る発明の 技術的思想において、既に具体化しているものと認められる。 そうすると、本件発明11は、遅くとも、先の出願2がされた平成25 年7月22日には完成していたものと認められる。
ウ 本件発明11に係る控訴人代表者及び甲の共同発明者性について\n
(ア) 前記1(1)の認定事実によれば、控訴人代表者、甲及び被控訴人代表\ 者は、平成25年5月31日、タカキタにおいて、控訴人が作成したラ ップネットの試作品について評価を受け、同日、控訴人、被控訴人及び タカキタは、以後の予定として、同年6月中旬をめどに、ラップネット\nの巻取りの際に綾振りをするなどの仕様で試作品を製造することを確認 したこと、控訴人は、同月以降、巻上げローラの前に綾振り装置を設置 する方法によって綾振りを施すことを試みていたことが認められる。 しかるところ、ラップネットの巻取りの際に綾振りをするなどの仕様 でラップネットの試作品を製造することが確認された同年5月31日ま でに、控訴人代表者及び甲が、ラップネットの製造に当たり、綾振りの\n技術を適用することを着想して、被控訴人代表者に提案等をしたことを\n認めるに足りる証拠がないことは、前記1(2)エのとおりである。 また、先の出願2の出願日である同年7月22日までに、控訴人が被 控訴人に対し、控訴人が行っていたとする綾振りの方法に関する情報を 提供したことを認めるに足りる証拠もない。 そうすると、本件発明11の技術的思想に係るラップネットを巻取機 構の巻上げローラで巻き取るに当たり、当該巻き上げローラをその回転\n軸方向に所定の振幅で往復運動させる構成について、控訴人代表\者及び 甲が着想したものであると認めることはできない。
・・・
控訴人は、1)本件明細書記載の本件発明11の経編機を用いたラップネ ットの編立技術(【0026】、【0040】、【0064】、【0066】、【0 071】、【0076】、【0089】、【0094】、【0106】、【0111】、【0147】、【0149】、【0158】、【0167】)について、控訴人及 び被控訴人が共同でした別件出願1の明細書(甲19の2)にも、同様の 内容の記載がある(【0012】、【0020】、【0028】、【0056】、 【0058】、【0059】、【0067】)ことからすれば、本件発明11の 製造方法は、別件出願1の出願時に開発されたラップネットの製造技術が 応用されたものであり、控訴人代表者及び甲は、別件出願1の出願日前に\n本件発明11の編立技術を着想し、その後のラップネットの試作、改良を 繰り返すことで、その着想を具体化し、上記編立技術の完成に深く関与し たといえること、2)本件発明11における綾振り技術の課題に関しても、 上記経編機を利用したラップネットの製造において素材に綿糸を使用す ることで新たに発見した課題であり、その解決手段である巻上げローラを 左右に振る方法も経編機の編立部分と一体不可分の解決手段であること、 3)控訴人による綾振り装置の具体的な開発経過( 巻上げローラを左右に 動かしながら巻上げする方式(偏芯平カムを上下に動かして使用)を採用 し、平成25年5月31日のサンプル(約200m〜250m)を試作す る、 巻上げローラを左右に動かしながら巻上げする方式(偏芯ドラムカ ムを使用)を採用し、同年6月21日の試験用サンプル(1000m)を 試作する、 同年7月6日以降、生地を左右に動かしながら巻上げする方 式(偏芯平カムは(ア)を再利用)を採用し、サンプルを試作する)によれば、 控訴人代表者及び甲は、本件発明11の特徴的部分を着想し、その具体化\nに創作的に関与した旨主張する。
しかしながら、1)については、控訴人が指摘する別件出願1の明細書の 記載は、いずれも、本件発明11の技術的思想に係るラップネットを巻取 機構の巻上げローラで巻き取るに当たり、当該巻き上げローラをその回転\n軸方向に所定の振幅で往復運動させることに関係するものではないから、 上記記載と共通する記載が本件明細書にあるとしても、このことから、控 訴人代表者及び甲が本件発明11の技術的思想の具体化に創作的に関与\nしたものと認めることはできない。
また、2)及び3)については、前記ウ(イ)の説示に照らすと、控訴人が、 本件発明11が完成した同年7月22日までに、ラップネットの試作品の 作成において、控訴人が巻上げローラの綾振りを採用していたことを認め ることはできない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2022.08.12
令和2(ワ)4331 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月13日 東京地方裁判所
同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠(乙A80)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法102条2項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、5割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法102条2項により算定される損害額は、1853万0467円(3706万0935円×0.5(1円未満切り捨てとする。以下同じ。))となる。
エ 覆滅部分についての特許法102条3項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法102条2項の推定の覆滅部分について同条3項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条3項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−3には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は3.8%(最大値5.5%、最小値1.5%)(4件)、「健康;人命救助;娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は5.3%(最大値14.5%、最小値0.5%)(54件)と記載されている(乙A73)。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和4年1月27日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の10%と判断した(乙A80)。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能\にする代替技術 が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、10%を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法102条3項により算定される損害額は、1975万2707円(1億9752万7078円×10%)となる。
◆判決本文
関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求
◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円
◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.08.12
令和1(ワ)21901 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月31日 東京地方裁判所
原告らは、乙22文献には、「枠要素」に相当する構成や画像を「当\nてはめ」る構成の開示がないと主張する。\n
そこで検討するに、乙22文献には、1)Webクライアントの記憶 装置につき、「記憶装置2は、…表示装置3に地図を表\示するために 必要なデータ種別及びデータ領域を管理する管理テーブルとサーバー 4から送信されてきた地図データを格納するものである。」、「管理 テーブルは、データ種別管理テーブルとデータ領域管理テーブルから なる。…データ領域管理テーブルは、データ領域のメッシュ番号とデ ータ種別のレイヤー番号により記憶装置2に格納された地図データを 管理するものであり」(段落【0010】)という記載が認められ、 2)メッシュ番号につき、「図2に示すように地図データを表示する領\n域(メッシュ)が識別できるデータ領域のメッシュ番号」(段落【0 014】)、「メッシュ番号は、地図のデータの範囲を含む矩形領域 を任意の矩形サイズで分割した領域に振られる番号であり、例えば北 海道の地図データを作成する場合の、メッシュ番号の採番状況を示し たのが図9である。」(段落【0026】)という記載が認められ、 3)表示領域につき、「Webクライアントからの地図データ要求では、\n図8に示すように…1データの表示領域(メッシュ番号)を指定する\n形式で、複数回の要求を行うことによって、必要範囲の地図データを Webサーバーから取得する。」(段落【0024】)、「1データ の表示領域の指定には、メッシュ・レイヤーインデックスファイルで\n管理するこのメッシュ番号を指定する。このことにより、表示領域を\n直ちに指示することが可能となる。座標単位は、任意に決定されるマ\nクロ座標であるが、原点位置(座標0,0)の緯度・経度とメッシュ の矩形サイズ(距離)は地図データ作成時に指定するため、各メッシ ュ原点(左下座標)の緯度・経度は計算により求められる。」(段落 【0026】)という記載が認められ、4)地図の表示につき、「地図\nデータを取得できたものから地図の描画処理を行うため、画面上の地 図表示領域には徐々に地図が表\示されていく」(段落【0032】) という記載が認められる。
上記各記載に加えて、【図1】、【図2】、【図8】、【図9】、 【図11】の記載を併せ考慮すれば、表示領域は、原点位置が計算に\nより求められるものであること、Webクライアントは、地図データ を表示するための矩形領域を識別するメッシュ番号の指定により、必\n要範囲の地図データをWebサーバーから取得し、表示領域を指示す\nること、取得された地図データは、メッシュ番号のある管理テーブル とは別の場所で記憶され、描画処理により、地図が画面上の表示領域\nに表示されること、以上の内容が乙22文献により理解されるものと\n認められる。 そうすると、乙22文献における「表示領域」は、メッシュ分割し\nた地図データを指定してWebクライアントのディスプレイ表示の所\n定の位置に地図を表示させるためのものであるから、乙22文献には、\n本件各発明における画像を「当てはめ」る「枠要素」に相当する構成\nが開示されていると認めるのが相当である。
b これに対し、原告らは、乙22文献における「地図データ」は、数 値データ(ベクターデータ)であるから、これに基づき表示を行う場\n合に「当てはめ」を行う「領域」をビューアに設定する必要はないと 主張する。しかしながら、上記にいう必要性の問題は、構成が開示さ\nれているかどうかという問題とは、必ずしも同一の事柄ではなく、乙 22文献における「地図データ」がベクターデータであることは、上 記発明の認定を左右するものではない。
●(省略)●
のみならず、乙22文献の「地図データ」がベクターデータである としても、これをいわゆるラスターデータに置き換えることは、技術 説明会における当事者双方の口頭議論の結果及び専門委員3名の各説 明内容を踏まえると、当時の技術常識に照らし、当業者が適宜になし 得る事項にすぎず実質的相違点に当たらず、又は明らかに容易に想到 することができるものといえる。そうすると、被告の主張はその趣旨 をいうものとして相当であり、原告らの主張は、結論において進歩性 の判断を左右するものとはいえない。
c 原告らは、乙22文献に地図データを「枠要素」に「当てはめ」て 表示する構\成の開示がないことを前提に、乙22文献には「表示でき\nる状態」の開示はないと主張するが、乙22文献には、画像を「当て はめ」る「枠要素」に相当する構成の開示があることは、上記におい\nて説示したとおりであり、原告らの主張は、前提を欠く。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> のみ要件
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.08. 9
令和3(ネ)10088等 特許権侵害差止等請求控訴事件,附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
被控訴人は、前記第2の3(2)ウ(イ) のとおり、競合品の存在を理由とする特 許法102条2項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、同条3 項を重畳適用して、被控訴人の許諾機会の喪失に係る逸失利益を想定すべき である旨主張する。しかし、競合品の存在を理由とする同項の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性 があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴 人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条3項に基づく実施 料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもなく、被 控訴人の主張は採用できない。
◆判決本文
1審はこちらです。1審も以下のように、重畳適用を否定しました。
特許法102条2項及び3項の重畳適用については,前記(2)ウのとおり,本件
において同条2項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは
競合製品の存在のみであるところ,被告による各被告製品の販売実績等と直接の関
わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては,同条3項適用の基礎
を欠く。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.08. 9
平成31(ネ)10027 職務発明対価支払い請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ところで、旧法35条4項は、職務発明に係る相当対価の額は、その 発明により「使用者等が受けるべき利益の額」及びその発明がされるに ついて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない旨規定 するところ、同項が「使用者等が受けるべき利益の額」と規定したのは、 使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利益の額をいうもの であり、発明の実施によって現実に受けた利益に必ずしも限るのではな く、自己実施等の場合を含め、使用者等が本来得ることのできた独占的 利益を指すものと解される。
これを前提として検討するに、SCEは、一審被告とSMEが共同出 資して設立された会社であり(前記1 カ )、一審被告がプレイステ ーションシリーズの製造及び販売に関し、フィリップス社との間で、そ れぞれの保有する特許のクロスライセンスを締結していれば、SCEは 本件ジョイントライセンスプログラムにおいて改めてライセンス料を支 払う必要のない一審被告の関連会社となり、こうしたクロスライセンス 契約における一審被告の得た利益が「使用者等が受けるべき利益の額」 となるといえるが、本件全証拠を検討してみても、一審被告がプレイス テーションシリーズの製造及び販売に関してフィリップス社との間でク ロスライセンスを締結したと認めるに足りず、むしろ、一審被告は、S CEに対し、プレイステーションシリーズの製造、販売又は開発等のた めに有用な一審被告保有の特許権(本件特許権1−5及び同2−1を含 む。)等の実施許諾に関するライセンス契約(SCEライセンス契約) を締結して、SCEを他社ライセンシーより優遇して同社から対価を得 ていることが認められる。
このように、一審被告が、フィリップス社と共に運用する本件ジョイ ントライセンスプログラムのライセンス対象製品であるプレイステーシ ョンシリーズの製造販売に関して、SCEを同プログラムの関連会社と してではなく1ライセンシーとして扱っている以上、同プログラムが開 放的かつ非差別的な条件でライセンスする、いわゆるオープンポリシー を採用している(前記1 エ )ことからすれば、PS1のゲーム機本 体及びゲームディスク、PS2のゲーム機本体の製造及び販売に当たっ て一審被告が本来得ることのできた独占的利益は、SCEがフィリップ ス社との間でプレイステーションシリーズの製造及び販売に関してライ センスを受けたものと仮定した上で、同ライセンスプログラムで定めら れたロイヤルティにより計算された額に一審被告の配分率を乗じたライ センス料額により算定した額(仮想積上げ方式)であるというべきであ り、一審被告がSCEライセンス契約により現実に得た利益に限る必要 はない。
なお、一審被告は、仮想積上げ方式を採用したとしても、資本関係の 全く存在しない第三者(競合他社を含む。)との関係と比較して資本関 係を有するグループ会社に特許ライセンスを行う場合には、ライセンス 料をはじめ条件面をある程度優遇することは当然であり、本件ジョイン トライセンスプログラムにおけるライセンス料がSCEライセンス契約 にそのまま適用されるわけではない旨主張するが、一審原告は、この主 張を受けて、ライセンス料に80%を乗じる範囲までは争わないものと する旨主張しており、当裁判所も、SCEが一審被告と資本関係にある ことに鑑みて、この限度での条件面の優遇の程度は不合理なものではな いものとして、以下試算する。
・・・
また、一審被告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●CDオーディオ及びCD-ROM ドライブの特許に対するロイヤルティは、独立して請求することがで きない旨主張する。しかし、この契約条項の趣旨については措くにし ても、この契約書は、平成16年(2004年)頃のDVDビデオプ レイヤーに関するライセンス契約に関するひな型であることがうかが われるところ、PS2が発売された平成12年10月26日から本件 特許1−5が満了となる平成17年3月22日までの間、このひな型 のとおりに実際にライセンス契約が締結され、また、DVDプレイヤ ーのロイヤルティにCD-ROMプレイヤーのロイヤルティが含まれ ることを明確に示す証拠は提出されていないから、一審被告の上記主 張を採用することは困難である(なお、前述のとおり、職務発明に係 る相当対価を算定するに当たって考慮すべき「使用者等が受けるべき 利益の額」は、使用者等に対する権利承継時の客観的に見込まれる利 益の額をいうものであり、発明の実施によって現実に受けた利益に必 ずしも限るのではないことに照らせば、仮に、上記条項に基づく形で ロイヤルティの支払がされていたとしても、そのことをもって当然に、 CD-ROMの再生機能に係る一審原告の相当対価請求権が制限され\nるとは認め難い。)。
c PS1のゲームディスクについて、PS1の発売開始日から本件特 許1−5の満了日までの各対象期間における北米販売数は、平成7年 (1995年)9月9日から平成16年(2004年)12月31日 までは3億7100万本であり(甲300)、平成17年(2005 年)1月1日から同年3月22日までは、平成17年1月1日から同 年3月31日までの北米販売数100万本(甲300)を基に日割り 計算すると、90万本であるところ、メキシコ、カナダ分を除いた米 国分を89%と見積もることは当事者間に争いがないから、米国販売 分は、別紙3の表2−1の左欄のとおりであるところ、●●●●●●\n●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●当該期間における平均為替レート (甲296)を乗じると、同表の「一審被告が支払いを受けるべきラ\nイセンス料」欄の記載のとおりとなるが、前記 のとおり、この8割 に相当する金額が各対象期間における一審被告が受けるべきライセン ス料の額となる(別紙4−2の「PS1ゲームディスク(CD-ROM ディスク)(本件発明1−5関係)」の「1)一審被告が受けるべき利 益」欄参照)。
そして、本件ジョイントライセンス契約におけるCD-ROMディス クの対象特許のうち本件特許1−5の貢献割合は、前記ア の「CD -ROM Disc」欄のとおり、平成14年度までは1/9であり、 平成15年度以降は1/3であるので(なお、厳密には、別紙4−2 の「PS1ゲームディスク(CD-ROMディスク)(本件発明1−5 関係)」の「1995.9.9〜2004.12.31」欄のうち、 平成15年度及び平成16年度に当たる期間(2003年4月1日か ら2004年12月31日)は1/3として計算すべきであるが、一 審原告は、「1995.9.9〜2004.12.31」のライセン ス料につき、一括して平成14年度までと同様にその貢献割合を3/ 6.6として計算しているところ(一審原告控訴第12準備書面61 頁参照)、この期間の販売本数を2003年4月1日を境にして区分 けして特定することは困難であり、また、一審被告に不利になる算定 ではないため、一審原告の計算手法を採用して算定する。)、これを 乗じると、一審被告が受けるべき独占の利益は、別紙4−2の「PS 1ゲームディスク(CD-ROMディスク)(本件発明1−5関係)」 の「2)本件特許1−5の一審被告の受けるべき利益」欄のとおりとな る。
・・・
本件発明1−5について一審被告が貢献した程度(争点1−2)
ア 本件ジョイントライセンスプログラム
本件発明1−5は、音楽用CDをコンピュータ分野に応用することを 可能とするためのエラー訂正技術であり、従来の音楽CDの誤り訂正率\nが訂正後10-9〜10-10であったのに対し、10-12まで改善すること ができ、データの信頼性が高まり、コンピュータのデータストレージと しての使用を可能としたものである(前記1 ウ )。本件特許1−5 は、CD-ROM等の規格必須特許に採用される(同1 ウ )など、技 術的価値は高いといえる。
他方で、本件発明1−5は、第1及び第2のクロスインターリーブ・ リード・ソロモン符号による誤り訂正(CIRC)に加えて、第3のリ\nード・ソロモン符号による誤り訂正を行うことを可能\とする発明特定事 項を含むものである(前記1 ウ )ところ、CIRCは、一審被告と フィリップス社が共同で音楽用CDの研究、開発の過程で発明されたも のであり(同1 )、本件発明1−5は、こうした一審被告に蓄積され た先行技術の一部が活用された面があることは否定することができな い。また、本件発明1−5が権利化されるまでの手続において、その優 先権の基礎となる本件特許1−1及び同1−2に係る手続を含め、一審 原告の貢献はなく、米国の事務所に依頼し、米国特許商標庁の拒絶理由 に対して適宜の対応をした点を含め、一審被告の知的財産部が相当の貢 献をしたものである(同1 イ)。
さらに、一審被告とフィリップス社は、非差別的かつ開放的なオープ ンライセンスポリシーを採用して広くライセンスの機会を与える(前記 1 エ )とともに、一審被告とフィリップス社が中心となって、CD -ROMの物理的フォーマットを作成しただけではなく、論理フォーマッ トを統一して互換性を持たせた(同1 オ )ほか、パソコンの周辺機\n器を接続するための伝送データ規格の統一を実現した(同1 オ )こ とにより、パソコンやゲームソ\フトとしてCD-ROMが広く利用される ようになったといえる。
加えて、一審被告は、CD-ROMディスクを受託生産するための製造 工場を設立し、CD-ROM駆動装置の生産能力の増産態勢を整え、また、\nCD-ROMを利用した様々な商品の企画・開発や、他業種との連携等を 行ったほか(前記1 オ )、マーケティングプロモーションとして、 ライセンシー会議の開催、コンテンツ業界への積極的なアプローチ、標 準規格を普及させるための装置の技術開発、ライセンシーに対するテク ニカルサポートを行い(同1 オ )、CD-ROMだけではなくCDR等のCDファミリー規格の改善のための研究開発やプロモーションを 行った(同1 オ )ことが認められる。
以上の諸事情に鑑みれば、本件ジョイントライセンスプログラムにお いて一審被告が得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、95%と するのが相当である。
これに対して、一審原告は、本件発明1−5に関し、着想から具体的 なフォーマットの完成に至るまで一審原告が1人で検討し、シミュレー ションを行い、一審被告の会社設備を利用することなく就業時間外で発 明を完成させた旨主張し、その旨供述及び陳述(甲165)する。しか し、一審原告本人が供述等するところの発明を完成させるまでの経緯に ついては、これを裏付ける客観的証拠に乏しく、他方、これを否定する 〈B〉の陳述書(乙132)等の関係証拠もあるのであるから、前記1 アで認定した一審原告の関与の限度を超えて、一審原告本人の供述等 のみに沿った認定をすることは相当でない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成27(ワ)11651
添付文書1
2022.07.31
令和1(ワ)26366 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
一般に、地図は、地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号に よって、客観的に表現するものであるから、個性的表\現の余地が少なく、文 学、音楽、造形美術上の著作に比して、著作権による保護を受ける範囲が狭 いのが通例である。しかし、地図において記載すべき情報の取捨選択及びそ の表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を\n果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表れ得るものということが\nできる。そこで、地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表\n示の方法を総合して判断すべきものである。
・・・
前記(2)によれば、本件改訂により発行された原告各地図は、都市計画図等 を基にしつつ、原告がそれまでに作成していた住宅地図における情報を記載 し、調査員が現地を訪れて家形枠の形状等を調査して得た情報を書き加える などし、住宅地図として完成させたものであり、目的の地図を容易に検索す ることができる工夫がされ、イラストを用いることにより、施設がわかりや すく表示されたり、道路等の名称や建物の居住者名、住居表\示等が記載され たり、建物等を真上から見たときの形を表す枠線である家形枠が記載された\nりするなど、長年にわたり、住宅地図を作成販売してきた原告において、住 宅地図に必要と考える情報を取捨選択し、より見やすいと考える方法により 表示したものということができる。したがって、本件改訂により発行された\n原告各地図は、作成者の思想又は感情が創作的に表現されたもの(著作権法\n2条1項)と評価することができるから、地図の著作物(著作権法10条1 項6号)であると認めるのが相当である。また、前記(2)アのとおり、本件改訂より後に更に改訂された原告各地図は、いずれも本件改訂により発行された原告各地図の内容を備えるものであるから、同様に地図の著作物であると認めるのが相当である。なお、本件改訂より前に発行された原告各地図については、原告は、本件訴訟において、被告らにより著作権が侵害された対象として主張していないので(前記第2の4(1)(原告の主張)エ)、著作物性についての検討を要しない(以下においては、「原告各地図」という場合、特に断らない限り、本件改訂以降に発行されたものを指す。)。
(5) これに対して、被告らは、1) 地図に著作物性が認められる場合は一般的に 狭く、住宅地図は他の地図と比較して著作物性が認められる場合が更に制限 される、2) 原告各地図は、江戸時代の古地図や既存の地図、都市計画図に依 拠して作成されたものであり、創作性が発揮される余地は乏しい、3) 原告各 地図は機械的に作成され、正確・精密であるとされることからすると、創作 性が発揮される部分は更に限定され、国土地理院は、2500分の1の縮尺 の都市計画基本図について、著作物性が認められる可能性は低いとの見解を\n示している、4) 過去に作成された住宅地図には家形枠が記載されたものがあ り、家形枠を用いた表現自体ありふれている、5) 原告は地図作成業務のうち 少なくとも6割を海外の会社に対して発注しており、原告各地図には独自性 がないとして、原告各地図には著作物性が認められないと主張する。 しかし、上記1)については、前記(1)のとおり、地図の著作物性は、記載す べき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して判断すべきものであると\nころ、前記(4)のとおり、原告各地図は、その作成方法、内容等に照らして、 作成者の個性が発現したものであって、その思想又は感情を創作的に表現し\nたものと評価できるから、地図の著作物であると認められる。 上記2)については、原告が古地図や都市計画図等を参照して原告各地図を 作成したものであったとしても、前記(2)アのとおり、原告各地図は、本件改 訂によって、都市計画図等をデータ化したものに、居住者名や建物名、地形 情報、調査員が現地を訪れて調査した家形枠の形状等を書き加えるなどして 作成されたものであり、その結果、前記(2)イの特徴を備えるに至ったもので あって、このような原告各地図の作成方法、特徴等に照らせば、原告各地図 は、都市計画図等に新たな創作的表現が付加されたものとして、著作物性を\n有していると認められる。
上記3)については、原告各地図が正確・精密であるとしても、前記(1)のと おり、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法等において創作性を発\n揮する余地はある。また、被告らの指摘する国土地理院の見解(乙63)は、 都市計画基本図について述べたものであり、住宅地図作成会社が作成する住 宅地図一般について述べたものではないし、上記2)について説示したとおり、 原告各地図は、都市計画図等を基図としてデータ化した上、これに種々の情 報を書き加えるなどすることで、住宅地図として完成させたものであるから、 国土地理院の上記見解は原告各地図に当てはまるものではない。さらに、前 記(2)イのとおり、原告各地図は、地図の4辺に目盛りが振られ、当該地図の 上、右上、右、右下、下、左下、左及び左上の各位置にある地図の番号が記 載されており、目的とする地図を検索しやすいものとなっている上、信号機 やバス停等がイラストを用いてわかりやすく表示されたり、建物等の居住者\n名や店舗名等を記載することにより住居表示についてもわかりやすくする工\n夫がされているなどの特徴を有するのに対し、証拠(乙70ないし73)に よれば、都市計画基本図にはこのような特徴が全くないことが認められ、原 告各地図と都市計画基本図とでは、そもそも性質が異なることから、同列に 論じることはできない。
上記4)については、住宅地図において家形枠を記載することがよくあると しても、原告各地図における家形枠の具体的な表現がありふれていることを\n認めるに足りる証拠はないから、直ちに原告各地図の著作物性を否定するこ とはできないというべきである。
上記5)については、原告が原告各地図の作成業務を海外の会社に発注して いることのみをもって、原告各地図の独自性を否定し、ひいては、その著作 物性を否定することはできないというべきである。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2022.07.31
令和3(行ケ)10069 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月22日 知的財産高等裁判所
本件明細書を見ると、実施例1において、高リスク患者 では、100単位週1回投与群における新規椎体骨折の発生率は、い ずれも実質的なプラセボである5単位週1回投与群における発生率に 対して有意差が認められるが、低リスク患者では、100単位週1回 投与群における新規椎体骨折の発生率は、いずれも、5単位週1回投 与群における発生率に対して有意差が認められなかったと記載されて いるのにとどまる(【0086】ないし【0096】、【表6】ないし【表\ 11】)ところ、誤記等を修正して再解析したとする数値(前記1(2)オ) に基づいても、低リスク患者の新規椎体骨折についていえば、100 単位週1回投与群11人と5単位週1回投与群10人について、それ ぞれ、ただ1人の骨折例数があったというものであり、このような少 ない症例数のもとでは、上記プラセボ投与群の骨折発生率と対比した 場合の骨折発生率の低下割合(RRR)は、骨折例数が1件増減した だけでその値が大きく変動することは明らかであるし、そもそも、低 リスク患者を対象とした場合は、5単位週1回投与群であっても骨折 例数が少なく、5単位週1回投与群の骨折発生率に対する、100単 位週1回投与群の骨折発生率の低下割合であるRRRの値が、高リス ク患者に対するそれに対して小さいのは当然のことといえる。
この点、被告は、3条件充足患者における骨折抑制効果がプラセボ に対する関係で有意差があり、非3条件充足患者における骨折抑制効 果がプラセボに対する関係で有意差が無ければ、直ちに、本件発明1 の骨粗鬆症治療剤が3条件充足患者に対して優れた効果を有するとい える旨主張する。しかしながら、有意差が無いということは効果が優れているかどうか不明であるということにすぎず、効果が優れていないということを直ちに意味するものではないし、有意差が無かったことが症例数が不足していることによることも否定できない(甲30、35)から、上記のような結論の導出は適当でない。したがって、実施例1をみても、高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が、低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2022.07.31
令和3(行ウ)381 その他 行政訴訟 令和4年6月28日 東京地方裁判所
前提事実によれば、原告は、平成29年12月16日頃、本件処分があった ことを知ったところ、原告は、令和3年9月17日、本件処分の取消しを求め る本件訴えを提起したことが認められる。そうすると、本件訴えの提起は、本 件処分があったことを知った日から6か月を経過してされたものであるから、 行訴法14条1項本文所定の出訴期間を徒過しているものと認められる。 したがって、本件訴えは、出訴期間を経過したものとして、同項ただし書に いう「正当な理由」がない限り、不適法である。 これに対し、原告は、本件処分について八丁組合が本件審査請求をしている ところ、八丁組合がした本件審査請求は、実質的には原告が行ったものと同視 することができるから、原告は行訴法14条3項本文に規定する「審査請求を した者」に当たり、本件訴えはその出訴期間を遵守するものである旨主張する。 しかしながら、前提事実によれば、本件審査請求をした者は八丁組合であり、 原告と八丁組合の法人格は異なるものであるから、原告が上記にいう「審査請 求をした者」に該当しないことは明らかである。そもそも、原告は、八丁組合 が本件審査請求をした場合であっても、行訴法14条1項にいう出訴期間経過 前に本件処分に係る取消訴訟を提起することができたのであるから、下記2に おいて検討するとおり、同項にいう「正当な理由」がある場合に限り、原告は 本件訴えを提起することができるものと解するのが相当である。そうすると、 原告の主張は、上記判断を左右するに至らない。
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> その他
>> ピックアップ対象
2022.07.31
令和3(行ケ)10070 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月28日 知的財産高等裁判所
本件審決は、甲2において、制御端末110から複数の家電機器に対す る制御命令は、家電機器の制御部に対して実行されるものであるから、制 御端末110は家電機器の駆動部に接続して制御する装置ではなく、また、 甲3において、AV用集中制御装置(12)から複数のAV用機器(14)に対す る制御命令は、家電機器の制御部に対して実行されるものであるから、A V用集中制御装置(12)はAV用機器の駆動部に接続して制御する装置では ないので、いずれも、本件発明1の「駆動部に接続されたマイクロコント ローラ」に相当するものではないと解釈した。しかし、甲2及び甲3に記 載された技術的事項は、前記(3)ア(イ)、イ(イ)のとおり認定されるものであ って、本件審決のように、制御端末110が家電機器の駆動部に接続して 制御する装置ではないこと、AV用集中制御装置(12)がAV用機器の駆動 部に接続して制御する装置ではないことと限定的に解釈すべき根拠はな く、本件審決による甲2及び甲3の記載事項から把握される技術の認定に は誤りがある。したがって、被告の上記主張は採用することはできない。
イ 以上のとおり、甲2及び甲3に記載された技術的事項は、前記(3)ア(イ)、 イ(イ)のとおり認定されるものであって、本件審決による認定は誤りであ るから、取消事由8は理由がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2022.07.31
令和3(ワ)3824 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年3月4日 東京地方裁判所
不正競争防止法2条1項21号は、競争関係にある者が他の事業者の営業上 の信用を害する虚偽の事実を告知するなどし、競争行為において有利な地位を 得ようとする行為を規定し、もって事業者間の公正な競争等を確保するもので ある。このような同号の趣旨、目的に鑑みると、不正競争防止法2条1項21 号に規定する「競争関係」とは、商品販売上の具体的な競争関係がある場合に 限定されるものではなく、虚偽の事実を告知又は流布した者が、他人の競争上 の地位を低下させることによって、不当な利益を得る場合をも含むと解するの が相当である。 これを本件についてみるに、前記前提事実によれば、原告はモバイルWiF iルーターという商品を自ら販売する事業者であるのに対し、被告はアフィリ エイターであり、原告商品と競合する商品を直接販売するものではない。 しかしながら、前記前提事実によれば、原告の需要者はモバイルWiFiル ーター等の契約を希望する者であるのに対し、本件サイトの需要者は、WiM AXの契約を希望する者であって、両商品は、いずれも携帯可能な無線通信の\nための規格であるという点において共通しているところ、本件サイトにおいて は、本件各商品のうち、原告商品及びBroad WiMAXを除いた本件W iMAX商品についてのみ、アフィリエイトリンクが設定されている。 そのため、本件サイトを閲覧した者が本件サイトを通じて商品を契約する場 合において、被告は、上記の者が原告商品を契約した場合には何らの経済的利 益を得られないのに対し、Broad WiMAXを除いた本件WiMAX商 品を契約した場合にはアフィリエイト報酬を得ることができることになる。 これらの事情の下においては、被告は、原告商品について虚偽の事実を告知 又は流布し、原告の競争上の地位を低下させることによって不当な利益を得る ことができる関係にあるものと認められる。 したがって、被告と原告は、「競争関係」にあるものと認めるのが相当であ る。 (2) これに対し、被告は、本件サイトにおいては、本件各商品の長所も指摘され ていること、本件各商品に関する原告の公式サイトへのリンクも紹介されてい ること、アフィリエイトリンクの設定されている本件WiMAX商品につき、 公式サイトを通じて契約することを強く推奨するような文章も記載されてい ないこと、以上の事情等を指摘して、原告と被告は競争関係にない旨主張する。 しかしながら、本件サイトを閲覧した者が本件サイトを通じて商品を契約す る場合において、被告は、原告商品が契約された場合よりも、Broad W iMAXを除いた他の本件WiMAX商品を契約された場合の方が、利益を得 られる関係にあるものと認められ、このことは、上記において説示したとおり である。そうすると、被告主張に係る事情を考慮しても、上記判断は左右され ないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2022.07.29
令和3(ネ)10096 競業行為差止等請求本訴・損害賠償請求反訴控訴事件、同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年6月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これに対し1審原告は、1審被告YとA間の「ギャラリーアートポイント」 の名称等に係る紛争に至る経緯や、1審原告が、1審被告Yとの婚姻中から、 個人事業主として、「ギャラリーアートポイント」の名称を自らの事業の表示\nとして使用してきたものであり、1審被告Yが主、1審原告が従であるよう な関係にもなく、双方が対等な立場にあったこと、1審原告の事業は、1審 原告と1審被告Yが別居した以降、1審被告Yと完全に独立していることか らすると、原告商標に1審原告独自の信用が化体しており、本件商号及び被 告ら標章1が正当に帰属すべきは1審被告Yであったものとはいえないから、 1審原告による1審被告らに対する原告商標権に基づく権利行使は、権利の 濫用に当たらない旨主張する。
しかしながら、前記(1)で説示したとおり、1)1審原告と1審被告Yは、1 審原告及び1審被告Yの両名が賃借人として契約した本件賃貸借契約が存続 する限りにおいては、別居後の合意に基づいて、1審原告及び1審被告Yが、 本件事務所において、それぞれ本件商号及び被告ら標章1あるいは原告商標 を使用した貸画廊(本件画廊)の営業を行うことを妨げてはならない旨の義 務を相互に負っていること、2)1審原告による原告商標に係る商標登録出願 は、1審原告が1審被告Yとの別居後の交渉を自己に有利に進める手段を得 るために行われたものとうかがわれ、1審被告Yとの関係では、正当なもの とはいえないことに照らすと、1審原告の上記主張は、原告商標に1審原告 独自の信用が化体しているかどうかを検討するまでもなく、採用することが できない。
(3) 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、1審原告の1審 被告らに対する原告商標権に基づく差止請求及び1審被告Yに対する原告商 標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は、いずれも理由がない。
◆判決本文
原審はこちら
2022.07.24
令和3(行ケ)10158 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和4年6月28日 知的財産高等裁判所
ア 創作容易性の判断方法
・・・
さらに、出願された意匠が、物品等の部分について意匠登録を受けよ うとするものである場合は、その創作非容易性の判断に当たり、「意匠登 録を受けようとする部分」の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの 結合や、用途及び機能を考慮するとともに、「意匠登録を受けようとする部分」を、当該物品等の全体の形状、模様若しくは色彩若しくはこれら\nの結合の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、 当業者にとって容易であるか否かについても考慮して判断すべきである。 そして、意匠法3条2項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフ を基準として、それから当業者が容易に創作することができる意匠でな いことを登録要件としたものであって、創作非容易というためには、物 品の同一又は類似という制限をはずし、上記周知のモチーフを基準とし て、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を要すると解す べきであり(最判昭和49年3月19日同45年(行ツ)第45号民集 28巻2号308頁、最判昭和50年2月28日同48年(行ツ)第8 2号最高裁裁判集民事114号287頁参照)、本願意匠に係る物品と厳 密には同一といえなくても、それと目的又は機能を共通にし、製造又は販売等する業者が共通している物品は、本願意匠に係る物品の当業者が\nその形状等を当然に目にするものと推認されるから、同一の物品分野に 属するものとして、創作容易性を判断する際の資料となるものと解すべ きである。
イ 本件審決における創作容易性の判断の適否
(ア) 物品分野について
a 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」は、一方を 人側に、他方を各種工具に取り付けて、人が所持する工具の落下を 防止するものであり、他方、引用意匠2に係る物品である「ハーネ スライン」(安全ベルト)は、一方をヨットのフレーム等側に、他方 を人側に取り付けて、ヨットから人が落下するのを防止するもので あって、落下防止を図るという目的において共通する。また、いず れも、全体が帯状で両端に取付具を有するという形状は共通してお り、一方の端を、落下の防止を図ろうとする目的物に取り付け、他 方の端を、固定された物の側に取り付け、固定された物から目的物 が落下するのを防止するという機能も共通する。いずれの材質・形態についても、目的物の落下を防ぐために必要十\分な強度を有し、取付けや落下の防止が確実・容易にできることが要請される。この ように、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」と引 用意匠2に係る物品である「ハーネスライン」(安全ベルト)は、目 的、機能、材質・形態に要請される事項が共通する。
b 本願意匠に係る物品等の製造販売の実態は、次のとおり認められ る。
(a)甲1(本件審決別紙第2)、乙6の1、2によれば、「播州三木 の道具屋『アルデ』」(以下「アルデ」という。)のウェブサイトに おいて、その一番上に「大工さんの道具箱!大工道具・金物の専 門通販なら三木金物オンラインショップ『アルデ』」との記載があ り、「カテゴリー一覧」の中に、「鋸(のこぎり)」、「ハンマー」、 「マリン」等とともに「安全用品・ロープ」の項目があり、「安全 用品・ロープ」の項目の中に、「その他」、「墜落制止用器具」等の 項目があり、「その他」の中に引用意匠1の「【NRK】布製安全コ ード 赤 3kg(落下防止コード)」が掲載されており、「墜落制 止用器具」の中にランヤード、安全帯などが掲載されている。 そうすると、アルデのウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、人の落下を防ぐ安全用コードが販売されていることが認め られる。
(b)甲4(本件審決別紙第5)は、「【プロ志向】職人の為の安全帯 ハーネス・作業用品専門店 梅春 いちや 総本店」(以下「いち や」という。)のウェブサイトであり、「CATEGORIES」(カテゴ リーズ)の中に、「ハーネス」、「ハーネス+ランヤードセット」、 「ハーネス対応ランヤード」、「1本つり安全帯」、「ランヤード」、 「安全帯胴ベルト・付属品」等の項目があり、「安全帯胴ベルト・ 付属品」の項目の中の「落下防止対策」、「安全コード」の細項目 の中に「【NRK】布製 安全コード 3kg 【セーフティコード】 落下防止コード」が掲載されている。 そうすると、いちやのウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、ハーネスやランヤードなどの人の落下を防ぐ安全用コード が販売されていることが認められる。
(c) 乙7は、作業服・作業用品専門店「ZOOM」(以下「ZOOM」と いう。)のウェブサイトであり、「Category」(カテゴリー)の中に、 「フルハーネス」、「安全帯」等とともに「ランヤード」、「落下防 止対策用品」の項目があり、「落下防止対策用品」の項目の中に、 工具の落下防止コードが掲載されている。 そうすると、ZOOM のウェブサイトでは、工具の落下防止コー ドと、ハーネスや安全帯などの人の落下を防ぐ安全用コードが販 売されていることが認められる。
(d) 乙8は、「第55回全国建設業労働災害防止大会 in 横浜」、「安 全衛生保護具・測定機器・安全標識等 展示会」のパンフレット であり、出展企業の一つである「スリーエム ジャパン(株)」の主 な取扱品目として、「工具落下防止用製品」とともに「ハーネス型 安全帯」、「ランヤード」が記載されており、工具の落下防止コー ドと、ハーネス、安全帯、ランヤードなどの人の落下を防ぐ安全 用コードの双方を製造又は販売している会社があることが認めら れる。
(e)甲5(本件審決別紙第6)は、株式会社 TOWA のウェブサイト であり、「高所作業&ガラスクリーニング」、「レスキュー&タクテ ィカル」、「マリン」の項目に分けられている。また、甲7(本件 審決別紙第8)は、株式会社 TOWA のカタログであり、「ツール ランヤード」(落下防止用ランヤード)が掲載されていることが認 められる(「ランヤード」という用語は、人の体を支えるものを指 すために用いられる場合が多いが、甲7(本件審決別紙第8)に 示されたものは、「ツールランヤード」と記載されているので、工 具の落下防止コードであると認められる。)。 本願意匠の「工具の落下防止コード」は、高所作業やガラスク リーニングで使われるものであり、他方、引用意匠2の「ハーネ スライン」は、ヨット用で、マリンスポーツで使われるものであ るところ、甲5(本件審決別紙第6)によれば、株式会社 TOWA でヨット用ハーネスが販売されているか否かは定かでないが、高 所作業やガラスクリーニングで使われるものとマリンスポーツで 使われるものが同一の業者により販売されていることは認められ る。 また、乙10、11によれば、コードとフック等による構成により落下防止が配慮された安全用のコードに係るものとして、工\n具の落下防止用のコードと人の落下防止用のコードが、高所作業 において同時に使用されていることが認められる。
c(a) さらに、甲9公報の【考案の詳細な説明】、【背景技術】、【00 02】には、「工具連結用索具として、従来、例えば実用新案登録 第3156504号の工具用安全策具や、特開2012−248 70号の工具用安全索具や、特開2012−200310号のラ ンヤードなどが提案されている。これらは、いずれも作業範囲に 余裕をもって届く範囲の長さで伸縮自在なスプリングに可撓性を 有する被覆体を被せ、その両端をフックやリングに連結した構成からなっている。」と記載されている。上記「特開2012−20\n0310号のランヤード」は、人体を吊下し得る強度を有するラ ンヤードであり(乙5)、引用意匠2の「ハーネスライン」と同様 に人の落下を防止する安全用コードであると認められる。上記甲 9公報の記載は、工具の落下防止コードである上記「実用新案登 録第3156504号の工具用安全策具」(乙3)及び上記「特開 2012−24870号の工具用安全索具」(乙4)と、人の落下 を防止するランヤードである「特開2012−200310号の ランヤード」(乙5)を、同様の構成を有するものとして同列に記載しており、これによっても、工具の落下防止コードと、人の落\n下を防止するハーネスライン等の安全用コードが、同じ種類の物 品として認識されていることが認められる。
(b) 乙9公報の考案は、【背景技術】【0002】及び【0003】 等の記載によれば、工具用落下防止安全ロープを実施対象の一つ にあげている安全用ロープに係る考案であることが認められ、【考 案の概要】、【考案が解決しようとする課題】、【0018】に、「図 7に示すのは、該連結部の両端がエクササイズハンドル80に設 けられる実施形態で、また、弾力ロープはそれぞれ、複数の連結 で使用される場合であり、本考案の弾力ロープの特性によって、 筋力トレーニング器具として用いられ、または、本考案の弾力ロ ープを海上でのサーフィンボードの安全ロープ(図示省略)とし て用いられてもよいが、弾力ロープの両端をそれぞれサーフィン ボードとプレヤーの踝につなぐことにより、プレヤーの安全性を 守り、サーフィンボードの漂流などを防ぐ効果がある。」と記載さ れていることから、マリンスポーツも危険を伴う分野の一つとし て、コードとフック等による構成により落下防止が配慮された、安全用のコードに係る物品が用いられる分野の一つとして想定さ\nれていることが認められる。
d(a) 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」と引用意 匠2に係る物品である「ハーネスライン」(安全ベルト)は、落下 を防止する対象において、工具と人体という違いがあり、対象の 重量等の違いに応じて、構成部材の寸法、材質、強度などが異なる場合があると推認される。また、本願意匠に係る物品である「工\n具の落下防止コード」は、主として高所作業において用いられる のに対し、引用意匠2に係る物品である「ハーネスライン」(安全 ベルト)はヨット用であり、マリンスポーツにおいて使用される ものである。そのため、本願意匠に係る物品と引用意匠2に係る 物品は、厳密には同一の商品とはいい難い面がある。
(b) しかし、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」 と引用意匠2に係る物品である「ハーネスライン」(安全ベルト) は、前記aのとおり、目的、機能、材質・形態に要請される事項が共通し、前記b(a)ないし(c)のとおり、工具の落下防止コードと、 人の落下を防ぐハーネスやランヤードなどの安全用コードが同じ 業者のウェブサイトで販売されていることが認められ、前記b(d) のとおり、工具の落下防止コードと、ハーネス、安全帯、ランヤ ードなどの人の落下を防ぐ安全用コードの双方を製造又は販売し ている会社があることが認められる。また、前記c(a)、(b)のとお り、工具の落下防止コードと、ハーネスライン、ランヤードなど の人の落下を防止する安全用コードが、同じ種類の物品として認 識されていることなども認められる。
そして、前記b(e)のとおり、高所作業やガラスクリーニングで 使われるものとマリンスポーツで使われるものが同一の業者によ り販売されていることが認められ、前記c(b)のとおり、マリンス ポーツも危険を伴う分野の一つとして、コードとフック等による 構成により落下防止が配慮された、安全用のコードに係る物品が用いられる分野の一つとして想定されていることが認められるこ\nとからすると、用途において、高所作業とマリンスポーツという 違いがあったとしても、それ故に、本願意匠に係る物品を取り扱 う当業者が引用意匠2に係る物品を目にすることが否定されるこ とはない。
そうすると、本願意匠に係る物品である工具の落下防止コード を取り扱う当業者は、人の落下を防ぐ安全用コードの形状等を当 然に目にするものと認められ、人の落下を防ぐ安全用コードに属 する引用意匠2に係る物品である「ハーネスライン」(安全ベルト) についても、その形状等を当然に目にするものと推認されるから、 引用意匠2に係る物品は、同一の物品分野に属するものとして、 本願意匠の創作容易性を判断する際の資料となるものと認められ る。
e 以上によれば、本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コー ド」と引用意匠2に係る物品である「ハーネスライン」(安全ベルト) は同一分野の物品であるとして、引用意匠2に基づいて本願意匠の 容易想到性を判断することができるものと認めた本件審決の判断に 誤りはない。
(イ) 創作容易性について
a 引用意匠1及び参考意匠(本件審決別紙第4)は、本願意匠に係 る物品である「工具の落下防止コード」に係るものであり、本願意 匠に係る物品について当業者に該当する者は、引用意匠1及び参考 意匠を当然に目にするものと認められる。また、上記(ア)eのとお り、引用意匠2に基づいて本願意匠の容易想到性を判断することが できるものと認められる。
b 本願意匠に係る物品である「工具の落下防止コード」を含む安全 用のコードという物品の分野において、コードの長手方向の一端を ナスカン状のフックとすることはごく普通に見られ、本願部分にお けるフック部の形状も、本願意匠に係る物品と同じ物品の公知意匠 である引用意匠1に示されていた。また、安全用のコードの物品の 分野において、二又に分岐する構造のものも、公知意匠である引用意匠2に示されていた。さらに、薄いテープをDカンに巻いて帯部\nとし、フック部の先端側と略同じ長さとする態様も、帯部より先を 蛇腹タイプの波形伸縮コードとする態様も、引用意匠1及び引用意 匠2に表れていた。甲2(3枚目)、乙12によれば、引用意匠2の分岐根元部において、蛇腹タイプの波形伸縮コードは、内側に一山、\n外側に一山の波打った形態を示していることが認められる。本願意 匠に係る物品である「工具の落下防止コード」において、帯部につ いて、引用意匠1のように糸を同色として目立たないようにしたも のもあり、また、縫い目を有さないようにしたものも、参考意匠(本 件審決別紙第4(図5、7))(甲3)のとおり公知であった。 そうすると、引用意匠2のフック部を、引用意匠1の形状のもの とし、帯部より先の二又に分岐した2方向のコードのうち、平たい テープ状のコードを蛇腹タイプの波形伸縮コードとし、分岐根元部 について、上下共に内側に一山、外側に一山の波打った形態とし、 帯部を縫い目がないようにして、本願意匠を創作することは、本願 意匠に係る物品と同じ安全用のコードの分野の公知の意匠(引用意 匠2)をもとに、その構成要素の一部を、同じ物品の分野で公知であった意匠と置き換え、又は同じ物品の分野で公知であった意匠を\n寄せ集めたにすぎないものであり、そのような置き換え又は寄せ集 めに関して、当業者の立場からみて意匠の着想の新しさや独創性が あるとは認められず、そのため、本願意匠は、その意匠の属する分 野におけるありふれた手法により創作されたものであると認めら れる。
以上に検討したところによれば、本願意匠は、当業者が、本願意 匠の出願前に公知であった引用意匠1及び引用意匠2に基づいて 容易に創作をすることができたものであると認められ、同旨の本件 審決の判断に誤りはない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 創作容易性
>> 部分意匠
>> ピックアップ対象
2022.07.24
令和2(ワ)17423 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
これらの記載から、送風機によって生起された圧力風が刈刃後方の吹出 口から背面風として移送ダクト内に送り込まれること、この背面風は、刈 刃の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉を移送ダ クトの吐出口まで搬送する移送作用を有すること、刈刃の後方から背面風 を吹き出すことにより、吹出口近傍に負圧が形成されて、茶葉が、負圧吸 引作用により、刈刃部分から吹出口側に引き寄せられ、その後、上昇流を 形成する背面風に乗って、移送ダクト内を上昇し、吐出口から収容部に設 けられた茶袋内に収容されること、刈刃から背面風の吹出口までの距離が 比較的長いものに本発明を適用する場合、背面風による負圧吸引作用は幾 らか低下することが考えられるため、圧力風を振り分けて生じさせた正面 風により、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましいことを理解 できる。
ウ 以上の各記載によれば、本件発明1の「圧力風」とは、移送ダクトの内 部に流される空気流であって、背面風及び刈刃前方からの補助的な送風で ある正面風を含むものであり、「圧力風の作用のみによって」とは、刈り 取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が上記のよ うな「圧力風」の「作用」だけで実現されることと解するのが相当であり、 「圧力風」の「作用」以外の作用が加わって上記移送が実現される場合に は、「圧力風の作用のみによって」を備えるとは認められないというべき である。
(2) 被告各製品が「圧力風の作用のみによって」(構成要件A)を備えるか\n
ア 証拠(甲4ないし6、乙6、8)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の回転ブラシはブラシシャフト及びこれに取り付けられたブラシから成 り、ブラシシャフトが回転することに伴ってブラシが回転する構造をして\nいること、被告各製品の回転ブラシR、刈刃(22')、移送ダクト(6')、吹出 口(38')及び収容部(4')の構造の概要は、別紙概要断面図記載のとおりであ\nり、被告各製品による摘採作業中、回転ブラシRは、160ないし300 rpmの回転数(1秒当たり2.6ないし5回転)で、茶枝葉を移送ダク ト(6')にかき込む向き(別紙概要断面図でいえば、時計回り)に回転し、 刈刃(22')後方の吹出口(38')から上方(W')に向かって吹き出した圧力風は、 移送ダクト(6')内を収容部(4')に向かって流れること、回転ブラシの高さ は、被告各製品のうち3段階調整方式のものは上下に約50mmずつ3段 階で、5段階調整方式のものは上下に約40ないし60mmずつ5段階で、 それぞれ調整することができることが認められる。これによれば、被告各 製品は、その摘採作業中、摘採する長さに合わせて高さを設定した回転ブ ラシが高速で回転して刈刃により刈り取られた茶枝葉を移送ダクト内にか き込み、移送ダクト内を流れる圧力風が茶枝葉を収容部まで移送する構造\nを有するということができる。
そして、証拠(乙9、10)によれば、被告各製品の取扱説明書には、 茶枝葉を長く刈り取る場合は回転ブラシを高く調整し、短く刈り取る場合 はこれを低く調整し、ブラシシャフトと芽の高さが同じくらいになるよう に設定する必要があり、回転ブラシの高さが適切に設定されなければ、茶 枝葉をスムーズに刈り取ることができない旨が記載されていたことが認め られ、これによれば、被告各製品は、刈り取る茶枝葉の長さに合わせて回 転ブラシを設定することが予定されていたということができる。さらに、被告各製品による摘採作業中、操縦者が回転ブラシを任意に回転させたり、回転させなかったりすることができることを認めるに足りる証拠はない。\n
以上によれば、被告各製品においては、回転ブラシを摘採する茶枝葉の 長さに応じて適切な高さに設定することを前提とし、刈刃により刈り取ら れた茶枝葉は、摘採作業中、常時回転するブラシに当たって移送ダクト内 に送り込まれ、その後、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風 により、移送ダクト内を通り、収容部に到達すると認めるのが相当である。 したがって、被告各製品においては、「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の 位置」までの移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることによって実現されているといえるから、被告各製品は「圧力風 の作用のみによって」を備えるものとは認められないというべきである。
イ これに対して、原告は、原告各実験結果によれば、回転ブラシを備える 被告各製品と回転ブラシを取り外した被告各製品とで摘採量に有意な差は なく、むしろ回転ブラシを取り外した被告各製品の方が摘採量が多いこと もあり、被告各製品は回転ブラシがなくても背面風(圧力風)の作用のみ によって茶枝葉を移送することができるので、「圧力風の作用のみによっ て」を備えると主張する。
しかし、前記(1)のとおり、「圧力風」以外の作用が加わって上記移送が 実現されている場合は、「圧力風の作用のみによって」を備えないという べきであるところ、被告各製品については、前記アのとおり、回転ブラシ を摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定した上で摘採すること が予定されており、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、常時回転する回転\nブラシに当たって移送ダクトに送り込まれた上で、上向きに吹き出し、移 送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達す ることからすると、「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることなく、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」 までの移送が実現されているということはできない。
また、前記(1)の「圧力風の作用のみによって」(構成要件A)の解釈に\nよれば、被告各製品が「圧力風の作用のみによって」を備えるというため には、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わっていない必要があるから、 回転ブラシを備える被告各製品における茶枝葉の移送態様自体が検討され るべきであり、回転ブラシを備える被告各製品による摘採量とこれを取り 外した被告各製品による摘採量とを比較することによっては、「圧力風の 作用のみによって」を備えるか否かを明らかにすることはできないという べきである。
以上によれば、被告各製品においては、刈り取られた茶枝葉、回転ブラ シ、移送ダクト等の位置関係等からして、回転ブラシの回転作用が加わっ て茶枝葉の移送が実現されているといえ、原告各実験結果については、直 ちにこれらを採用することは困難であるといわざるを得ない。したがって、 原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.07.23
令和2(ネ)10042 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
争点1−イ(「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に関する、構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D2への充足性)について\n
ア(ア) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は、原判決別紙の特許公報(特許第6 159845号及び特許第5769141号)の該当部分記載のとおりであり、「第 1の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリ アに出入りをする車両を検知することや、「第1の遮断機」が「第1の検知手段」に 対応して設置されたこと、「第1の検知手段」により車両の進入が検知された場合、 前記車両が通過した後に、第1の遮断機を下ろす旨の記載があるのみであって、そ れ以上に、「第1の遮断機」、「第1の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置 関係を特定する記載はないから、それぞれが設置される位置関係によって構成要件\n該当性が左右されるものではないというべきである。
(イ) これを前提に被控訴人各システムについてみると、車両検知器2)は、被控訴 人各システムにおいて車両の通過を検知するものであり(ステップS105、S2 04)、被控訴人各システムが設置されている「サービスエリア」である佐野SAス マートICに出入りする車両を検知するものであるから、「第1の検知手段」に当た り、車両検知器2)が車両の通過を検知すると発進制御機[開閉バー]1)が閉じるこ とから(ステップS105、S204)、発進制御機[開閉バー]1)は「第1の検知 手段」である車両検知器2)に対応して設置された「第1の遮断機」に当たる。そし て、車両に搭載されたETC車載器との間で無線通信を行う(ステップS103、 S202)路側無線装置3)が「通信手段」に当たり、路側無線装置3)がETC車載 器から受信したデータにより、無線通信が可能な場合と不能\又は不可の場合のいず れに当たるかの判定(ステップS104、S106、S203、S205)、すなわ ちETCによる料金徴収が可能か判定されているといえる。\nそうすると、被控訴人各システムは、構成要件B1、C1、D1、B2、C2、\nD2を充足する。
イ(ア) 被控訴人は、本件各発明においては、「通信手段」は、「第1の遮断機」及 び「第1の検知手段」より先に配置されるべきであるところ、被控訴人各システム においては、路側無線装置3)が発進制御機[開閉バー]1)の手前に配置されていて、 発進制御機[開閉バー]1)の手前に停止している車両に対して無線通信を行うから、 被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D\n2をいずれも充足しないと主張する。
(イ) しかし、前記ア(イ)のとおり、本件特許の特許請求の範囲には、「通信手段」 と「第1の遮断機」の位置関係については何ら特定されていない。 また、前記1(2)のとおり、本件各発明は、本件作用効果1(一般車がETC車用 出入口に進入した場合又はETC車に対してETCシステムが正常に動作しない場 合であっても、車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供すること)を奏する ものであるところ、「通信手段」がETC車載器から受信したデータにより、ETC による料金徴収が可能か判定され、各遮断機が適切なタイミングで動くことにより\n車両が安全に誘導できるのであれば本件作用効果1は奏するのであって、「通信手 段」がETC車載器からデータを受信するタイミングにつき、車両が第1の遮断機 を通過する前後のいずれであっても、本件作用効果1を奏することが可能である。\nまた、本件作用効果2(ETCシステムを利用した車両誘導システムにおいて、 逆走車の走行を許さず、或いは先行車と後続車の衝突を回避し得る、安全な車両誘 導システムを提供すること)についてみると、本件各発明にいう「逆走車」には、 料金不払などを目的として、ETC車用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡っ てETC車用レーンに逆進入する車両も含まれ、そのような「逆走車」の走行を防 止することと、「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係とは関係がないことは明 らかであるし、通信手段の位置にかかわらず、車両が第1の遮断機を通過した後に 第1の遮断機を下ろすことで、後退による逆走を防止することができる。 たしかに、本件明細書には、第1の遮断機(遮断機1)及び第 1 の検知手段(車 両検知装置2a)の先に通信手段(ゲート前アンテナ3)が位置する構成を有する\n例が記載されているが(【図4】)、これは実施例にすぎないというべきであって、上 記に照らすと、本件各発明について、上記構成に限定して解釈すべき理由はない。\nしたがって、本件各発明の課題及び作用効果との関係で、「通信手段」と「第1の 遮断機」の位置関係が、被控訴人が主張するように特定されるとはいえない。
(ウ) また、被控訴人は、本件各発明においては、第1の遮断機を通過した走行中 の車両に対して走行状態のまま無線通信を行うものであるところ、被控訴人各シス テムにおいては、発進制御機[開閉バー]1)の手前に停止している車両に対して無 線通信を行うから、本件各発明と構成や作用が異なると主張する。\nしかし、本件特許の特許請求の範囲においては、無線通信を行う際に車両が走行 中であるか停止しているかについては特定されていないし、本件明細書の段落【0 042】に「1台の車両が、遮断機1から車両検知装置2c、2dの区間に進入し ているときはこの区間は一種の閉鎖領域となり、1台の車両のみの存在が許される ようになっている。このため、この閉鎖領域では先行車と後続車の衝突は起こらな い。なお、ETCシステムが正常に働いている限り、遮断機1が閉じている時間は、 車両が遮断機1からETCゲート5を通過するまでの時間であり、ほんの数秒であ り、ETCシステム本来のノンストップ走行は実質的に確保されている。」とあるこ とからすると、本件各発明においては、先行車両が存在する場合、後続車両が第1 の遮断機の手前で停止することも予定されているといえる。そうすると、本件各発\n明について、第1の遮断機を通過した走行中の車両に対して走行状態のまま無線通 信を行うものであると限定的に解釈することはできない。 したがって、被控訴人各システムにおいて、無線通信を行う際に車両が停止して いるという点をもって、本件各発明の構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D\n2の充足性が否定されるものではない。
(エ) 以上のとおり、被控訴人の上記各主張は採用することができない。
(3) 争点1−ウ(構成要件F1、F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」と\nの文言への充足性)について
ア(ア) 被控訴人各システムにおいては、ETC車載器との「無線通信が不能又は\n不可の場合」、すなわち、ETCによる料金徴収が不可能な場合に、「運転者に対し、\nインターホンによる音声でその旨の報知がなされ、レーンd手前の発進制御機[開 閉バー]1)及び5)が人的操作によって開かれ、車両は退出ルートdに退出する」も のとされている(ステップS106、S205)。被控訴人各システムにおける退出 ルートdは、構成要件F1、F2の「ETC車専用出入口手前へ戻るルート」に当\nたる。また、被控訴人各システムは、ETCによる料金徴収が不可能な車両に対し\nて、レーンd手前の発進制御機[開閉バー]1)及び5)を人的操作によって開くこと によって、レーンdへと誘導しているから、構成要件F1、F2の「ETC車専用\n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第2のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて いるといえる。そうすると、被控訴人各システムは、構成要件F1、F2の「第2\nのレーンへ誘導する誘導手段」との文言を充足する。
(イ) そして、被控訴人各システムでは、路側無線装置3)が受信したデータの判定 結果によって、無線通信が可能な場合は、発進制御機[開閉バー]1)及び4)が開い てサービスエリア内に入るレーン又はサービスエリアから一般道に出るルートへ通 じるレーンに誘導するか(ステップS104)、データ取得区間(レーンe)へと誘 導する(ステップS203)が、データ取得区間(レーンe)はサービスエリアに 通じるルート上に存在するから、データ取得区間(レーンe)への誘導は、サービ スエリアに入るルートへ通じる第1のレーンへの誘導に当たる。また、被控訴人各 システムは、前記(ア)のとおり、無線通信が不能又は不可の場合は、「ETC車専用\n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第2のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて いる。したがって、被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件F1、F2を充足す\nる。
イ 被控訴人は、被控訴人各システムでは、車両が退出ルートdに自動誘導され るわけではなく、係員の手を煩わせることになってETC本来の目的が達成できな い状態となるから、構成要件F1、F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」と\nの文言を充足しないと主張する。 しかしながら、本件特許の特許請求の範囲の記載をみても、「第2のレーンへ誘導 する誘導手段」が自動誘導である旨の記載はなく、本件明細書をみても、「誘導手段」 に係員が関与することを除外する記載はない。そして、被控訴人各システムにおい ては、発進制御機[開閉バー]1)及び5)が人的操作によって開かれているものの、 インターホンで係員を現地に呼び出す必要はないし、また、発進制御機[開閉バー] 1)及び5)が開くことで、車両は第2のレーンの方向に前進することができるので、 バック走行によりレーンから出ようとするおそれはないから、「インターホンで係 員を呼び出す必要があるので渋滞が助長されること」、「車両がバック走行をして出 ようとすると後続の車両と衝突するおそれがあって危険であること」という本件各 発明の課題を解決することができ、「車両を安全に誘導する車両誘導システムを提 供する」、「先行車と後続車の衝突を回避し得る安全な車両誘導システムを提供する」 という作用効果を奏することができる。なお、本件各発明においても、車両が第1 の遮断機の手前で停止することが想定されているといえることは、前記(2)イ(ウ)で 説示したとおりである。そうすると、「第2のレーンへ誘導する誘導手段」について、被控訴人の主張するとおりに限定的に解釈すべき理由はなく、上記被控訴人の主張は採用できない。
・・・
(3) 上記から、被控訴人各システムの使用による売上額は、11億2320万5 685円(=245円×458万4513台)と計算される。
(4) 証拠(甲26、31、乙51、55)によると、1)被控訴人各システムはス マートICに設置されるものであるところ、被控訴人は、スマートICの導入によ り、従前10kmであったIC間の平均距離を欧米並みの5kmに改善し、地域生 活の充実・地域経済の活性化を推進しようとしていること、2)設置コストは、通常 のICが30〜60億円であるのに対し、スマートICが3〜8億円、管理コスト は、通常のICが1.2憶円/年であるのに対し、スマートICが0.5憶円/年 と、スマートICを設置することで、被控訴人はコスト削減ができていること、3) 既存のサービスエリアに被控訴人各システムを設置することで、出入口を増やすこ とができ、高速道路の利便性が上がるので、利用者増加につながる可能性があるこ\nと、4)もっとも、佐野SAスマートICの設置により東北自動車道の利用台数が顕 著に増加したとはいえないこと、5)被控訴人は、本件特許に抵触しないスマートI Cも設置しており、代替技術があること(控訴人の主張によると、本件特許に抵触 しないスマートICが半数弱存在する。)、6)控訴人は、自ら本件特許を実施してお らず、今後も実施する可能性がないこと、7)佐野SAスマートICの施設に占める 被控訴人各システムの構成割合(価格の割合)は7.8%であること、8)被控訴人 は、控訴人からの警告を受けた後も本件特許の実施を継続していること、がそれぞ れ認められる。上記各事情を総合すると、本件において、本件特許の実施料率は、2%と認めるのが相当である。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.07.22
令和3(ネ)10094 特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお、控訴人は、控訴理由書で、本件発明について訂正する(訂正の再抗弁) 旨主張するが、当裁判所は、これを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものと して却下した。その理由は、一件記録によると、当該訂正の再抗弁は、原審裁 判所が本件特許は無効であるとの心証開示をした後にされたものであるため、 原審で時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下されたものであると ころ、適宜の時機に原審で主張することができなかった事情は見当たらないか ら、当審における上記主張は、明らかに時機に後れたものであって、そのこと について控訴人には少なくとも重過失があり、また、この攻撃防御方法の主張 を許せば、本件訴訟の完結が著しく遅れることは明らかであるためである。
◆判決本文
原審はこちら(東京地裁40部)
2022.07.22
令和4(ネ)10004 不当利得返還請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年7月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(3) 前記(1)のとおり、本件社史部分が原告書籍を翻案したものに該当すると いうためには、原告書籍と本件社史部分とが、創作的表現において同一\n性を有することが必要であるものと解されるところ、前記(2)で検討した ところによれば、原告書籍と本件社史部分とは、番号1ないし20の各 記述において、事実、すなわち、表現それ自体でない部分において同一\n性が認められるにすぎないか、創作性が認められないありふれた表現に\nおいて同一性が認められるにすぎず、創作的表現において同一性を有す\nるものとは認められないから、被告社史中の本件社史部分は原告書籍を 翻案したものに当たらないというべきである。
(4) これに対し、控訴人は、当審において、1)ノンフィクション作品では、 著作者が取材を通じて発掘した事実こそが重要であり、自らの制作意図 にかなった事実をいかにして発掘し、発掘した事実から何を感じ取って、 どういうストーリーを見つけ出すかが、ノンフィクション作家の真骨頂 であるところ、原告書籍はこれまで公表されていなかった「NRプロジ\nェクト」の内実について明らかにしたものである、2)本件社史部分は、 原告書籍と同じテーマを取り上げたもので、原告書籍と同じ事実やエピ ソードが次々に登場していることからすれば、原告書籍と「表\現の本質 的な特徴」が完全に一致する、原告書籍を翻案したものに該当する旨主 張する。
控訴人の上記主張は、ノンフィクション作品においては、事実を見つ け出すこと及び見つけ出されたその事実が重要であって、原告書籍と本 件社史部分とは事実において共通する点が複数みられることを理由に、 本件社史部分は原告書籍を翻案したものに該当する旨を主張するものと 解される。
しかしながら、前記(1)のとおり、本件社史部分が原告書籍を翻案した ものに該当するというためには、その表現上の本質的な特徴である創作\n的表現の同一性が認められる必要があり、原告書籍と本件社史部分との\n間に事実において同一性が認められる部分が複数あるとしても、そのこ とによって両者が創作的表現において同一性を有することになるもので\nはない。控訴人の上記主張は、ノンフィクション作品自体の特徴や本質 についていうものにすぎず、その「具体的表現」における表\現上の本質 的な特徴について主張するものではないから失当である。 そして、前記(3)のとおり、原告書籍と本件社史部分は、創作的表現に\nおいて同一性を有するものとは認められないから、控訴人の上記主張は 理由がない。
2022.07.19
令和4(ネ)10021 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明2の特許請求の範囲の請求項2(「化合物が、式IにおいてR3およびR2はいずれも水素であり、R1は−(CH2)0−2−iC4H9である化合物の(R),(S),または(R,S)異性体である請求項1記載の鎮痛剤」)の記載に照らすと、本件発明2の化合物は、本件発明1の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明2の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが(前記1(2)及び(4))、一方で、本件発明2の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明2の化合物に該当するCI−1008及び3−アミノメチル−5−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、CI−1008を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明2の化合物に該当するS−(+)−3−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある(前記1(3)、(6)、(7)及び(9))。
しかし、前記(1)オ(ア)dの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明2の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明2の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明1の化合物の範囲に含まれる本件発明2の化合物が、本件発明1及び2の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明1及び2の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明1及び2は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明3は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するGABA類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第1要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載(前記1(4))によれば、本件発明3は、本件発明3の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の3つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと(前記2(1)オ(ア)a)に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明3において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明3の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明3に係る特許請求の範囲(本件訂正後の請求項3)に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明3の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第1要件を満たさない。\n
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19925等
特許権は同じで、被告(被控訴人)が異なる事件(1)です。
令和4(ネ)10009
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19927
被告(被控訴人)が異なる事件(2)です。
令和4(ネ)10002
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22283
被告(被控訴人)が異なる事件(3)です。
令和4(ネ)10012
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19924
被告(被控訴人)が異なる事件(4)です。
令和4(ネ)10020
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19929
被告(被控訴人)が異なる事件(5)です。
令和4(ネ)10013
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19917
被告(被控訴人)が異なる事件(6)です。
令和4(ネ)10016
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19918等
被告(被控訴人)が異なる事件(7)です。
令和4(ネ)10039
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19919
被告(被控訴人)が異なる事件(8)です。
令和4(ネ)10028
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19920等
被告(被控訴人)が異なる事件(9)です。
令和4(ネ)10015
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19922等
被告(被控訴人)が異なる事件(10)です。
令和4(ネ)10036
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19923等
被告(被控訴人)が異なる事件(11)です。
令和4(ネ)10017
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19926
被告(被控訴人)が異なる事件(12)です。
令和4(ネ)10003
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19928
被告(被控訴人)が異なる事件(13)です。
令和4(ネ)10037
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19931等
被告(被控訴人)が異なる事件(14)です。
令和4(ネ)10025
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19932
被告(被控訴人)が異なる事件(15)です。
令和4(ネ)10026
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22290等
本件特許の無効審判事件の審取です。
令和2(行ケ)10135
審決は、「訂正後の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効、請求項3,4に係る発明についての本件審判の請求は,成り立たない。」と判断していました。
知財高裁は、審決維持です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.07.14
令和4(ネ)10005 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年6月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 争点1−1(本件行為の幇助行為該当性等)について
・・・
a 控訴人らは、本件行為が本件ウェブサイトの運営者側に対して著作権侵害行 為自体を直接誘発し、又は促進するものではないから幇助行為には当たらないと主 張するが、訂正して引用した原判決の第3の1(2)アのとおり、広告料収入をほとん ど唯一の資金源とするという本件ウェブサイトの実態を踏まえると、本件行為は、 本件ウェブサイトの運営者において、原告漫画のうち既にアップロードしたものの 掲載を継続するとともに、さらにアップロードする対象を追加することを直接誘発 し、また促進するものというのが相当であるから、控訴人らの上記主張は採用する ことができない。 上記に関し、控訴人らは、幇助の適用範囲が広がりすぎて不当であるとも主張す るが、本件ウェブサイトの上記実態を無視して一般論として幇助の範囲が拡大され ることを前提とした主張にすぎず、また、客観的に幇助行為に該当することから直 ちに幇助行為について不法行為責任を問われるものでもないから、控訴人らの上記 主張も前記認定判断を左右するものではない。
b 控訴人らは、本件行為が既にアップロードされていたものについて、公衆送 信権の侵害行為を助長する行為とはいえないと主張するが、訂正して引用した原判 決の第3の1(2)アのとおり、上記主張も採用することができない。また、本件行為 を幇助行為とみることは本件ウェブサイトの運営自体を公衆送信権侵害行為と捉え ることである旨をいう控訴人らの主張や、平成13年最判で認められた幇助の解釈 と整合しないとの控訴人らの主張も、本件において判断の前提とすべき事情の理解 を誤るものであって採用できない。
c 控訴人らは、控訴人らが支払っていた広告料が本件ウェブサイトの運営者の 広告料収入のわずかな割合しか占めるものでなかったと主張するが、同主張の前提 となる割合を証拠上直ちに認めるに足りるかという点をおくとしても、前記のよう に広告料収入がほとんど唯一の資金源であったという本件ウェブサイトの実態に加 え、当該実態に照らすと、最終的に本件ウェブサイトの運営者に支払われる広告料 の金額の多寡にかかわらず広告を本件ウェブサイトに提供するとの行為自体が同運 営者による著作権侵害行為を助長するものであったというべきこと(なお、甲7及 び弁論の全趣旨によると、ウェブサイトの運営者に支払われていた広告料は、掲載 した広告の数等、広告の量によって単純に定められるものではなく、広告として掲 載された商品の広告を見た利用者が商品を購入したことが支払額に影響するなど、 広告の提供の程度と広告料の支払額は直接的に対応するものではなかったことがう かがわれる。また、広告主が拠出した広告料から広告代理店が差し引く手数料等の 額が多くなればなるほど、ウェブサイトの運営者に支払われる広告料が少なくなっ ていたことも容易に推測される。)のほか、後記イで認定判断する控訴人らの主観 的態様に照らしても、控訴人らが主張する前記の事情は、共同不法行為者間の求償 に係る問題にすぎず、被控訴人に対する不法行為責任がないことを基礎づける事情 にはならないというべきである。
・・・
イ 争点1−3(控訴人らの故意又は過失の有無)について
・・・
「(ア) まず、1)平成29年に至るまでの間に、広告収入が違法サイトの収入源と なっていることが大きな問題とされ、広告配信会社の多くにおいても一定の方法で 広告を出したサイトに違法な情報が掲載されていないかを調べるなどの手段を講じ ていたことや、官民共同の取組として、海賊版サイトを削除するという対策を継続 的に行うほか、周辺対策として広告出稿抑止にも重点的に取り組んでいくことが確 認されていたことが指摘できる。そのような状況において、2)本件ウェブサイトに ついては、平成29年4月までの時点で、登録不要で完全無料で漫画が読めるとさ れるサイトであり、検索バナーが必要な程度に大量の漫画が掲載されていることが 一見して分かる状態にあったもので、ツイッター上でも、違法性を指摘するツイー トが複数されていたところであった。また、3)本件ウェブサイトについては、遅く とも平成29年5月10日時点において、日本の著作物について、著作権が保護さ れないという前提で掲載されていること等が閲覧者に容易に分かる状態となってい た。 控訴人エムエムラボは、「MEDIADII」を利用して本件ウェブサイトに広告 の配信を開始するに当たり、本件ウェブサイトの表題及びURLの提示を受け、運\n用チームにおいて、それらを含む情報に基づいて登録の可否を審査して承諾し、手 動で広告の配信設定をしたものであるところ、前記1)〜3)の事情を踏まえると、遅 くとも平成29年5月までの時点で、控訴人らにおいては、本件ウェブサイトに掲 載された多数の漫画が著作権者の許諾を得ることなく掲載されているものであるこ とや、そのように違法に掲載した漫画を無料で閲覧させるという本件ウェブサイト が広告料収入をほぼ唯一の資金源とするものであること、それゆえ控訴人らが本件 ウェブサイトに広告を提供し広告料を支払うことは本件ウェブサイトの運営者によ る著作権侵害行為を支える行為に他ならないことを、容易に推測することができた というべきである。
そうすると、控訴人らは、遅くとも平成29年5月時点で、本件ウェブサイトの 運営者に著作権者との間での利用許諾の有無等を確認して適切に対処すべき注意義 務、又は、そもそもそのような確認をするまでもなく本件ウェブサイトの「MED IADII」への登録を拒絶すべき注意義務(既に本件ウェブサイトの「MEDIA DII」への登録作業を終えていた場合にはそれに係る契約を解除するなどして対応 すべき注意義務)を負っていたというべきであり、それにもかかわらず、本件行為 を遂行したことについて、控訴人らには少なくとも過失があったと認められる。 上記に関し、控訴人らが平成29年5月時点で上記の注意義務を怠り、その後、 安易に本件行為を継続的に遂行していたことは、控訴人グローバルネットが海賊サ イト対策の取組を推進していたJIAAの会員であり、また、「MEDIADII」 の利用規約によると本件ウェブサイトが第三者の著作権を侵害するものである場合 にはその利用に係る契約を解除し得る旨が定められていたにもかかわらず、その後、 同年10月31日に控訴人らの取引先に係る違法サイト「はるか夢の址」の運営者 の逮捕が報道されたり、本件ウェブサイトの違法性が社会的により大きく取り上げ られ、平成30年2月2日には取引先から本件ウェブサイトが海賊版サイトである と記載した上での問合せを受けたといった事情があった中でも、控訴人らにおいて、 本件ウェブサイトへの「MEDIADII」を利用した広告の提供等の当否について 検討したことが一切うかがわれず、かえって、取引先に対し、「漫画村」という名 称を明記しつつ、同年3月2日には本件ウェブサイトへの広告の掲載が可能である\nと回答したり、同月23日には広告の効果がいいという根拠の一つとして本件ウェ ブサイトの保有を挙げたりしていたもので、ようやく同年4月13日に本件ウェブ サイトを名指ししてブロッキングを行うという方針を政府が表明して以降に初めて\n本件ウェブサイトへの配信停止の検討を開始したといった事情によっても裏付けら れているというべきである。」
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.07.14
令和4(ネ)10015 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記1(1)オ、カ及びクのとおり、本件明細書には、薬理データ又はこれと 同視し得る程度の事項として、本件化合物がホルマリン試験、カラゲニン試験及び 術後疼痛試験において効果を奏した旨の記載がある。しかしながら、後記(5)にお いて説示するとおり、本件出願日当時、慢性疼痛は全て末梢や中枢の神経細胞の感 作という神経の機能異常により生じる痛覚過敏や接触異痛の痛みであり、原因にか\nかわらず神経細胞の感作を抑制することにより痛みを治療できるとの控訴人主張の 技術常識が存在していたとは認められないから、本件化合物がホルマリン試験、カ ラゲニン試験及び術後疼痛試験において引き起こされた各痛みの処置において効果 を奏した旨の記載があるからといって、そのことをもって、当業者において、本件 化合物が原因を異にするあらゆる「痛み」の処置においても効果を奏すると理解し たとは到底いえない。したがって、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛 試験の結果に係る上記記載をもって、本件明細書の発明の詳細な説明において、本 件化合物が「あらゆる全ての痛みの処置における鎮痛剤」の用途に使用できること につき薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の 当業者において、本件化合物が当該用途の医薬として使用できることを理解できた と認めることはできない。 その他、本件明細書の発明の詳細な説明に、本件化合物が「あらゆる全ての痛み の処置における鎮痛剤」の用途に使用できることにつき、薬理データ又はこれと同 視し得る程度の事項が記載され、本件出願日当時の当業者において、本件化合物が 当該用途の医薬として使用できることを理解できたと認めるに足りる的確な証拠は ない。
◆判決本文
関連事件はこちら。
◆令和4(ネ)10017
本件の1審はこちら。
◆令和2(ワ)19922等
関連事件の1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.07.14
令和3(行ケ)10111 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月22日 知的財産高等裁判所
ア 訂正前の請求項1の記載は、「加工対象物」である「シリコンウェハ」に ついて、その文言上、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予\定ラインに沿 った溝が形成されているシリコンウェハ」を概念的には含むものであった のに対し、訂正事項1により、そのようなシリコンウェハを除く形で限定 されるものであるから、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とす るものといえる。 別の観点からいえば、訂正前の請求項1の記載は、その文言上、「レーザ 加工装置」の構成として、切断予\定ラインに沿った溝が存在するシリコン ウェハを切断し得る性能を有するが、そのような溝が存在しないシリコン\nウェハを切断し得る性能を有するとは限らない「レーザ加工装置」(溝必須\n装置)を概念的には含むものであったのに対し、訂正事項1により、そのよ うな装置を除く形で請求項1に係る発明のレーザ加工装置を特定したので あるから、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものともい える。
イ 原告は、前記第3の1(1)ア のとおり、訂正事項1における「シリコン単 結晶構造部分に前記切断予\定ラインに沿った溝が形成されていないシリコ ンウェハ」については、加工対象物がシリコン単結晶構造の場合において、\n「シリコン単結晶構造部分」や溝の位置、どのような溝が形成されていな\nいのかが特定されておらず不明確であるから、訂正後の特許請求の範囲が 不明確であると主張するが、そのような具体的な事項まで特定されなけれ ば、訂正事項1が減縮か否かを判断できないほどに不明確であるとは考え られない。 また、原告は、前記第3の1(1)ア のとおり、訂正事項1によって、請求 項1の装置について、溝が形成されていないシリコンウェハを切断するこ とが用途になるとしても、レーザ加工装置の構成がそのような特定の構\成 に限られるものではないから、発明の構成を限定するものではないとか、\nいわゆるサブコンビネーション発明の理論によれば訂正の前後で発明の要 旨の認定は変わらない旨主張する。しかし、アに説示したとおり、訂正事項 1により概念上請求項1に係る発明が限定されることは明らかであり、特 許法134条の2第1項の「特許請求の範囲の減縮」への該当性を判断す るに当たっては、これで足りると解するのが相当である。また、本件発明を サブコンビネーション発明と解するかはさて措くとして、本件における上 記該当性を判断するに当たって、サブコンビネーション発明のクレーム解 釈や特許要件の考え方を直接参考にする必要性があるとは認め難いし、い ずれにしても本件においては、訂正事項1に係る事項は、加工対象物のみ を特定する事項にとどまらず、レーザ加工装置自体についてもその構造、\n機能を特定する意味を有するものと解するべきであるから(本件訂正前は、\n溝必須装置のように溝が形成されているシリコンウェハを切断する構造を\n有すれば、これをもって特許要件を満たし得たのに対し、本件訂正後はこ のような構造を有するのでは足りず、溝が形成されていないシリコンウェ\nハを切断する構造を有することが必要とされることになる。)、原告の主張\nするところは、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮であることを否定する に足りるものではない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 減縮
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2022.07. 4
令和2(ワ)13326 特許権侵害差止等請求事件 令和4年5月27日 東京地方裁判所
ア 本件発明1は、「エルデカルシトールを含んでなる非外傷性である前腕部 骨折を抑制するための医薬組成物」であるところ、前記(1)によれば、乙1文 献には、エルデカルシトールを骨粗鬆症治療薬として用いることが記載され ており、本件発明1と乙1発明とは、構成要件1A、1Cにおいて一致して\nいる。他方、本件発明1は、「非外傷性である前腕部骨折を抑制するための」 (構成要件1B)医薬組成物であるところ、乙1発明は骨粗鬆症治療薬であ\nり、この点において本件発明1と乙1発明が相違するといえるかが問題にな る。 イ 本件明細書によれば、「非外傷性骨折とは、転倒などの一般的な日常生活 で起こる軽微な外力により生じた骨折を示す」(【0035】)とあり、「前腕 部は、橈骨と尺骨からなる」(【0022】)とされ、また、「抑制あるいは予\n防は、骨粗鬆症にり患していない者あるいは骨粗鬆症患者のいずれにおいて も、新たな骨折が発生しないことを意味する。」(【0022】)とされている。 したがって、本件発明1の「非外傷性である前腕部骨折を抑制する」とは、 骨粗鬆症にり患していない者及び骨粗鬆症患者のいずれについても、転倒な どの一般的な日常生活で起こる軽微な外力によって橈骨又は尺骨に新たな 骨折が発生しないようにすることを意味しているといえる。
ここで、骨粗鬆症は、骨強度の低下を特徴として骨折のリスクが増大しや すくなる骨格疾患であり(前記2(1)ア)、骨粗鬆症治療薬は、骨粗鬆症を治療 することを目的とする薬物なのであるから、骨折のリスクを低下させること、 すなわち、新たな骨折を発生させないようにすることを目的としているとい える。そして、本件優先日当時、骨粗鬆症においては、骨強度の低下により、 通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで生ずる骨折である脆弱性骨折 が生ずることが問題とされており、骨折が生ずることがある具体的な部位と しては、大腿骨、椎体等と並んで、橈骨が含まれていたことが知られていた と認められる(前記2(1)イ)。 そうすると、乙1発明の骨粗鬆症治療薬とは、骨強度の低下によって通常 は骨折を生じさせない些細なきっかけで大腿骨、椎体、橈骨等に新たな骨折 を発生させないようにすることを目的とする治療薬であり、この中には、骨 粗鬆症患者に対する、通常は骨折を生じさせない些細なきっかけで橈骨に新 たな骨折を発生させないようにすることについても用途として含まれるこ とは明らかである。
これに対し、乙1発明の骨粗鬆症治療薬について、原告は、エルデカルシ トールに骨折抑制効果があることは知られていなかったと主張する。しかし、 乙1文献の表題は「骨粗鬆症治療薬」というものであり、その表\題からも、 そこに記載されたエルデカルシトールが骨粗鬆症の治療薬であること、すな わち、エルデカルシトールが骨粗鬆症患者に対する骨折抑制効果があること に関する文献であることが理解できる。そして、乙1発明のエルデカルシト ールは活性型ビタミンDの誘導体であり、活性型ビタミンDが体内のビタミ ンD受容体と結合して作用するのと同様にビタミンD受容体に結合して作 用するという、活性型ビタミンDと同一の機序によって骨粗鬆症に作用する ことが想定されていた。活性型ビタミンDは、前腕部を含む骨における骨形 成を促進し、骨破壊を抑制することによって骨量を増やして骨密度骨強度を 増加させるとともに、転倒自体を抑制するといった作用を有することが知ら れており(前記2(3)ア、(4))、実際に、乙1文献には、エルデカルシトール が骨密度を上昇させる効果を有することが記載されている。さらに、当時、 一般に、骨量が多いほど骨折しにくくなり、骨量の多寡が骨折リスクの指標 になると考えられていた(前記2(2) )。これらからすると、当業者は、乙1 発明の骨粗鬆症治療薬について、前腕部骨折予防効果があると理解すると認\nめられる。原告が指摘する文献や記載は、上記技術常識等に照らし、当業者 に対して乙1発明のエルデカルシトールが上記骨折抑制効果を有すること に対して疑念を抱かせるものとは認められない。
以上によれば、本件発明1のうち、骨粗鬆症患者において一般的な日常生 活で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用 途とする構成は、乙1発明のエルデカルシトールの用途と一致すると認めら\nれる。
ウ 原告は、公知の用途であってもその用途を限定することにより新規性が認 められると主張する。 しかし、本件発明1のうち、骨粗鬆症患者において、一般的な日常生活で 起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことを用途と する構成について、前記イに述べたところにより、乙1発明のエルデカルシ\nトールにおいても、当然に当該部位に係る骨折予防についても有効であるこ\nとが具体的に想定されていたと認められる。また、乙1文献には、エルデカ ルシトールを活性型ビタミンD3製剤であると記載されていて、乙1発明に おいても、既存の活性型ビタミンD製剤と同様の機序、すなわち、ビタミン D受容体への作用による骨強度の上昇及び転倒防止(前記2 ア、 )が想 定されていたと認められる。本件明細書には、本件発明1について、技術常 識から認められる上記機序と異なる機序によって作用していることについ ての記載もなく、本件発明1も、乙1発明と同一の作用機序を前提にしてい ると認められる。仮に年齢等によって第1選択として投与される薬剤の種類 が異なるとしても、エルデカルシトールが投与されたとき、乙1発明のエル デカルシトールが投与されたのか、本件発明1のエルデカルシトールが投与 されたのかを区別することができるものではない。本件発明1の一部の用途 は、作用機序の点からも、乙1発明の用途と区別することはできない。
なお、原告は、本件発明1において、エルデカルシトールの前腕部骨折抑 制に関する顕著な効果が初めて見出されたとも主張する。原告が本件明細書 で明らかにされた医学的に有用であると主張する具体的な知見は、1)前腕部 の骨折予防の観点からは、アルファカルシドールよりもエルデカルシトール\nの方が顕著に優れていること、2)前腕部以外の部位においては、エルデカル シトールとアルファカルシドールの効果の差は前腕部における差ほど顕著 ではないという2点である。しかし、仮に原告が主張する上記評価が統計学 上正当であると認められるとしても、1)については、本件明細書で明らかに されているのは、エルデカルシトールがアルファカルシドールに比べて骨折 抑制効果が高いことのみであり、このことのみからは、エルデカルシトール がプラシーボに比べて顕著に優れている可能性も、アルファカルシドールが\nプラシーボに比べて顕著に劣っている可能性も、どちらともいえない可能\性 もある。さらに、乙1発明において、エルデカルシトールの骨折抑制効果が アルファカルシドールを上回ること自体が想定されていたことも認められ る(前記3)。2)についても、本件明細書の実施例で記載されている前腕部 骨折以外に関する分析結果は椎体骨折に関するもののみ(【0069】)であ り、前腕部についてのみ良好な結果が得られたのか、椎体についてのみ良好 とはいえない結果が得られたのかすら明らかにされていない。これらによれ ば、何らかの顕著な効果の存在を理由に乙1発明に対する新規性等が認めら れる場合があるか否かは措くとしても、本件においてはその前提となる顕著 な効果を認めることはできない。
さらに原告は、65歳の患者群やI型骨粗鬆症患者群においては前腕部に おける骨折抑制が特に求められており、独立の用途を構成するなどと主張す\nる。しかし、乙1発明のエルデカルシトールにおいても、一般的な日常生活 で起こる軽微な外力によって橈骨に新たに骨折が生じさせないことに有効 であることが具体的に想定されていたと認められるなど、上記に述べた事情 に照らせば、原告が主張する上記知見は、本件において、乙1発明の用途を 前腕部の骨折予防に限定することに新規性を付与すべき事情に当たるとは\nいえない。
エ 以上によれば、本件発明1は、乙1発明で想定される橈骨の骨折抑制、大 腿骨の骨折抑制といった複数の骨折抑制部位に係る用途のうち、前腕部の効 果に着目したものと認められる。本件発明1において「非外傷性である前腕 部骨折を抑制するための」と限定した部分は乙1発明との相違点になるとは いえず、本件発明1は、乙1発明と同一であり、本件発明1は、新規性が欠 如しているといえる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.07. 4
令和2(ワ)29604 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月27日 東京地方裁判所
ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は1%以下であるとも記載されている。(甲26)
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 3.5% 9.5% 0.5%
コンピュータテクノロジー3.1% 7.5% 0.5%
電気 2.9% 9.5% 0.5%
司法決定 電気 3.0% 7.0% 1.0%
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、11社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある1社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー1件当たりのライセンス料率は、 平均●(省略)●%であると計算された。(乙14) また、前記 の10社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●(省略)●%から逓減する特殊な規定となっていた1社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、1件当たりのライセ ンス料率は、平均●(省略)●%と計算された。(乙16) 平成20年5月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「HDTV対応によって、大画面 テレビなど周囲のAV機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が\n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。(甲29・43頁) 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな4〜5型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精\n細化してHDTV対応にできる」」との記載もある。(甲29・59頁) 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。(弁論の全趣旨)
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を0.5%ないし9.5%程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許1件当たりで計算した実施料率が、0.01%を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品\nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、\nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、0.01%の限度で認めるのが相当である。\nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、24 00円程度の部品(甲31)を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その\n2400円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.07. 4
令和3(行ケ)10100 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年5月19日 知的財産高等裁判所
前記(1)の認定事実によれば、1)「Scrum(スクラム)」の語は、本件商 標の登録査定前に発行、作成されたコンピュータ、IT関連の事典、用語集 等において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つと説明されていること(前記(1)ア)、2)「Scrum Master(スクラムマスター)」の語 は、本件商標の登録査定前に作成されたウェブサイト上の辞典等において、 アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」における役割の名称として説明されていること(同イ)、3)「Scrum」の提唱者が執 筆した「スクラムガイド」において「スクラムマスター」の定義が説明され ていること(同ウ)、4)本件商標の登録査定前に発行されたコンピュータやI T関連の複数の書籍、雑誌、ウェブサイトやブログにおいて、「アジャイルソフトウェア開発」や「Scrum(スクラム)」をテーマとした記事等に「S\ncrum Master(スクラムマスター)」についての記載があること (同エないしカ)、5)平成21年から平成30年4月までの間に複数の団体 が、スクラムマスターの研修を複数回実施していること(同キ)、6)本件商標 の登録査定前に発行・作成された雑誌やウェブサイト等に「Scrum M aster(スクラムマスター)」の認定制度、研修やセミナー等に関する記 載があること(同ク)が認められる。
以上の1)ないし6)を総合すれば、本件商標の登録査定時において、「Scr um」の語は、コンピュータ、IT関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表\すものとして認識され、また、「Scrum M aster」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」における役割の一つを表\すものとして認識されていたものと認められる。
2 本件商標の商標法3条1項3号該当性について
(1) 商標法3条1項3号が、「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、 効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表\示する標章のみからなる商標」について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関 係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表\示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人\nもその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるの は公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場 合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、商標が、指定役務について役務の質を普通に用いられる方法 で表示する標章のみからなる商標であるというためには、商標が指定役務との関係で役務の質を表\示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であ\nり、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、 将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務に使用されて\nいることを要しないと解される。以上を前提に、本件商標の本件指定役務との関係における同号該当性について判断する。
(2) 本件商標は、「Scrum Master」の文字を標準文字で表してなり、「Scrum」の語及び「Master」の語から構\成される結合商標である。本件商標から「スクラムマスター」の称呼が生じる。 前記1(2)認定のとおり、本件商標の登録査定時において、「Scrum」の 語は、コンピュータ、IT関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表\すものとして認識され、また、「Scrum Maste r」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」における役割の一つを表\すものとして認識されていたものと認められる。
また、「マスター」(master)の語は、一般に、「あるじ。長。支配者」、 「修得すること。熟達すること」等(広辞苑第7版。甲391の2の2)の 意味を有することからすると、「Scrum Master」の語からは、ア ジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」を修得した者、「Scrum」に熟達した者などの観念をも生ずるものと認められる。\nそうすると、本件商標が本件指定役務に含まれる「教育訓練、研修会及び セミナー等」に使用された場合には、取引者、需要者は、当該教育訓練等が アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」を修得することや、「Scrum」における特定の役割に関する教育訓練等であることを\n示したものと理解するものといえるから、本件商標は、かかる役務の質(内 容)を表示したものとして一般に認識されるものと認めるのが相当である。そして、本件商標は、標準文字で構\成されており、「Scrum Mast er」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるといえるから、本件商標は、本件指定役務の質(内容)を普通に用いられ\nる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)に該当するものと認められる。\n
(3) この点に関し本件審決は、「Scrum Master(スクラムマスタ ー)」に特化した研修やセミナー等に関する証拠は限定的である上、その具体 的な内容についての説明や当該研修やセミナー等の開催規模や開催頻度等の 具体的な証拠はなく、また、「Scrum Master(スクラムマスター)」 の認定制度の有資格者数もさほど多いとはいえないから、本件商標は、その 指定商品及び指定役務中、第41類の教育訓練、研修会及びセミナー等に関 する役務との関係においては、「Scrum Master(スクラムマスタ ー)」を内容とする役務であることを理解させるものとはいい難いと述べた 上で、本件商標である「Scrum Master」の文字が、商品の品質 及び役務の質等を直接的に表すものとして一般に使用されているとまではいえず、また、本件商標に接する取引者、需要者が、本件商標を商品の品質及\nび役務の質等として認識するとみるべき特段の事情も見いだせないとして、 本件商標は、本件指定役務を含む本件商品・役務以外の指定商品及び指定役 務について商標法3条1項3号に該当しない旨判断した。 しかしながら、前記(1)で説示したとおり、本件商標が、本件指定役務につ いて役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件商標が本件指定役務との関係で役務の質を表\示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役\n務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも本件商標が現実に本件指定役務に使用されていることを要し\nないと解されるから、本件審決の上記判断は、その前提において誤りがある。
3 被告の主張について
被告は、1)商標法3条1項3号の趣旨によれば、同号により不登録とされる 商標は、「将来必ず一般的に使用されるもの」に限定されるところ、本件商標が 「将来必ず一般的に使用されるもの」であることについての立証はなく、また、 本件商標は、その登録査定時において、使用実績は僅かであり、周知性は全く なく、一般に認識されておらず、むしろ無名である、2)スクラムマスターのセミ ナー・研修の受講・参加、資格・認定取得が、本件商標の登録査定前に多数なさ れていた事実は認められず、「スクラムマスター」は、資格として世間一般に認 知されておらず、セミナーの開催数や資格者数もごく僅かである、3)本件商標 は、「Scrum」の語と「Master」の語を単に結合しただけの造語であ り、本件商標から、特段の観念は想起されない、4)証拠上「スクラムマスター」 の語の使用が確認される最も早い時期である平成16年10月から被告が本件 商標の登録出願をした平成29年6月までの12年8か月の間、原告らが本件 商標の登録出願をしなかったという事実は、誰もその使用を欲することがなか ったことの証左であり、本件商標は「何人もその使用を欲する」ような商標に 該当しないとして、本件商標は、本件指定役務について同号に該当しない旨主 張する。
しかしながら、1)ないし3)については、前記2(1)及び(2)で説示したとおり、 本件商標が、本件指定役務について同号に該当するというためには、本件商標 が本件指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表\示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、被告がいうように「将来必ず一\n般的に使用されるもの」に限定されるものではなく、また、必ずしも本件商標 が現実に本件指定役務に使用されていることを要しないと解されるから、その 使用実績の程度や周知性の有無が問題となるものではない。 さらに、前記1(2)で説示したとおり、本件商標の登録査定時において、「Sc rum Master」の語は、コンピュータ、IT関連の分野において、ア ジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」における役割の一つを表\すものとして認識されていたものと認められ、また、「Scrum M aster」の語からは、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」を修得した者、「Scrum」に熟達した者などの観念をも生ずるも\nのと認められるから(前記2(2))、本件指定役務の需要者において、本件商標が 一般に認識されず、無名であったとはいえないし、本件商標から、特段の観念 が想起されないとはいえない。4)については、ある用語の使用を必要とすることと、その用語について商標登録出願をすることとは別の問題であり、原告らが本件商標の登録出願をしなかったことをもって、本件商標が「何人も使用を欲する」ような商標に該当し ないものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2022.06.30
令和2(ワ)29897 相当の対価請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
原告は、使用者である被告は、従業者であった原告に対し、退職により相 当の対価請求権が消滅したとの誤解を生じさせて相当の対価請求権の行使を 妨害してはならない信義則上の義務を負うところ、原告は、本件退職条項の 存在により、被告を退職したことでもはや何らの請求権も行使することがで きないと誤解していたのであるから、被告は上記の義務に違反したものであ ること、被告は、被告発明規程について、カネカと同様に、実績補償金を支 払う旨の規定を置くべきであったし、これが容易であったことから、被告が 相当の対価請求権及び被告発明規程に基づく登録報奨金請求権について消滅 時効を援用することは、信義則違反又は権利濫用に当たるなどと主張する。
しかし、被告発明規程の本件退職条項においては、発明者である従業員が 退職した場合に「報奨金を受ける権利」が消滅する旨が定められており、こ の「報奨金」が「譲渡報奨金」及び「登録報奨金」(被告発明規程10−1) を指すことは明らかである一方、特許法35条3項に基づく相当の対価請求 権の消長に関する定めは存在しない。したがって、被告発明規程に本件退職 条項が置かれていたからといって、そのことによって直ちに、被告の従業者 に対し、被告を退職した場合に、被告発明規程に基づき支給されるべき報奨 金請求権に加え、特許法35条3項に基づく相当の対価請求権までも行使す ることができなくなるとの誤解を生じさせるものではない。加えて、原告の 陳述書(甲18)の記載からは、被告が、原告に対し、本件退職条項が被告 を退職した後は相当の対価請求権の行使ができないことを定めたものである 旨を積極的に説明したといった事実が存したとはうかがわれず、他の証拠に よっても、当該事実を認めることはできない。したがって、本件において、 被告が原告主張に係る信義則上の義務に違反したとは認められない。
また、使用者が契約や勤務規則において定めを置くか否かにかかわらず、 従業者は、特許法35条3項に基づく相当の対価請求権を行使することがで きるから、被告発明規程に実績に対応する相当の対価支払に関する定めが置 かれていなかったからといって、直ちに、被告の消滅時効の援用が信義に反 するということはできず、権利の濫用になるということもできない。
(2) なお、原告は、被告の親会社であるカネカが、本件各発明の実施品である EDコイルを有望な商品であると考えて、被告の研究者である原告をカネカ における製品開発に専従させたこと、被告から本件各発明に係る特許を受け る権利を譲り受けていること、本件について交渉段階から積極的に関与して いることに照らすと、カネカは、その子会社である被告を現実的統一的に管 理支配しているといえ、そのようなカネカが実績補償に関する規定を置いて いる以上、被告が、相当の対価請求権についての消滅時効を援用し、原告に 実績補償をしないことは、信義則上許されない旨を主張する。 しかし、カネカと被告との間に親会社と子会社の関係が存在するとしても、 それぞれは独立した法人であることに変わりはなく、両者の業種や雇用体系、 業務の実情などは異なり得るから、そうした実情に合わせて、被告が実績補 償に関する規定を設けるか否かを独自に判断したとしても、直ちに、問題視 されるべき事態であるとまではいえない。したがって、原告が主張する上記 の事情は、いずれも、被告による消滅時効の援用が信義則違反であることを 基礎付けるに足りるものではない。
(3) 以上によれば、原告の前記主張はいずれも採用することができず、被告が 原告の被告に対する特許法35条3項に基づく相当の対価請求について消滅 時効を援用することが信義則違反又は権利濫用に当たるということはできな い。
社内規定の該当部分です。
10−1 会社は発明の内、特許、実用新案及び意匠につき、発明者に対し以下に定める報奨金を支払うものとする。ただし、実用新案は自動登録なので登録報償金を支払わないものとする。
(1) 譲渡報奨金
会社が出願した発明1件(発明者が複数の場合でも1件とする)に対して金●(省略)●を支払う。社外発明者には支払わない。
(2) 登録報奨金(実用新案を除く)
登録になった発明1件(発明者が複数の場合でも1件とする)に対して金●(省略)●を支払う。社外発明者には支払わない。
・・・
10−3 発明者である従業員が定年以外の理由で会社を退職した場合、報奨金を受ける権利は、退職と同時に消滅する。
2022.06.30
令和2(行ケ)10143 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月23日 知的財産高等裁判所
ウ 原告は、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲は、「250〜600MP a」であるが、「250MPaから500MPaまで」の範囲については、 実施例による裏付けを欠いているから、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載から、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲うち、少なくとも上記範 囲については、本件発明の課題を解決できると認識することはできないと して、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら、前記イ(ア)bのとおり、本件明細書の【0039】の記載 から、「MD方向の引張弾性率」が、「250MPa以上」であれば、「鋸刃 でフィルムをカットするために力を加える際、フィルムのMD方向への延 びを抑制でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」 し、「600MPa以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に 沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の裂け目が発生す るのを抑制できる」ことから、「本実施形態のラップフィルム」(本件発明) の「MD方向の引張弾性率」を「250〜600MPa」の範囲としたこ とを理解できる。また、本件明細書には、MD方向の引張弾性率が「51 0MPa」ないし「540MPa」の範囲の本件発明の実施例(実施例1 ないし6)では、「裂けトラブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、 「カット性」の評価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、 「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット 性を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻 き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減する」という本 件発明の効果が確認されている。
一方、本件明細書には、「250MPaから500MPaまで」の範囲に ついては実施例の記載がないが、上記【0039】の記載が不合理である ことをうかがわせる証拠はないから、上記【0039】の記載から、上記 範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。 以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、 本件発明の「引張弾性率」の「250〜600MPa」の数値範囲全体に わたり、本件発明の上記効果を奏するものと認識できるものと認められる から、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供する という本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。 したがって、原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は、1)「低温結晶化開始温度」の「塩化ビニリデン系樹脂」への影 響について、公然知られた知見がないことを踏まえると、当業者は、本件 明細書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開始温度」を「40〜 60度」の数値範囲とすることにより、本件発明が裂けトラブル抑制効果 を奏することを認識することができない、2)本件明細書の記載によれば、 本件発明の「低温結晶化開始温度」は、「流通・保管時」の値と解されるが、 一方で、本件明細書の記載において、ラップフィルムが製造された後の「流 通・保管時」の低温結晶化開始温度の挙動は一切明らかではないし、「製造 時」から「流通・保管時」を経て、低温結晶化開始温度を「40〜60度」 に調節する方法についても明らかではないこと、本件明細書記載の実施例 1ないし6は、いずれも「流通・保管時」の条件が「28度に設定した恒 温槽にて1ヶ月間保管したもの」という特定の条件におけるものであり、 それ以外の「流通・保管時」の条件下においては、低温結晶化開始温度が 「40〜60度」の範囲になるとは限らないこと、本件明細書の記載から は、ラップフィルムの製造後の「流通・保管時」における流通・保管条件 なども不明であり、かつ、それらの流通・保管条件による「低温結晶化開 始温度」の挙動に与える影響も不明であることからすると、当業者は、本 件明細書の記載に基づいて、ラップフィルムの低温結晶化開始温度が、「流 通・保管時」において、「40〜60度」に属するかどうかを予測すること\nができないから、裂けトラブルの抑制やカット性の向上という本件発明の 課題を解決することができると認識することも困難であるとして、本件発 明は、サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記イ(イ)bで説示したとおり、本件明細 書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開 始温度」を「40〜60度」の範囲に制御することにより、「巻回体からの フィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出 し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告主張 の1)は、採用することができない。 次に、2)については、本件明細書の【0044】には、「ラップフィルム 製造後にガラス転移温度以下である−30度で保管した場合」、「すなわち、 ラップフィルムが製造後に全く熱を受けていないとみなせる場合の低温 結晶化開始温度は40度」であったことの記載がある。この記載から、低 温結晶化開始温度は、ラップフィルムが製造された後、外部から熱を受け ることによって「40度」から変化するものと理解できる。そして、本件 明細書の実施例1ないし6は、製造直後のラップフィルムの巻回体を2 8度に設定した恒温槽で1か月保管したものであるが、低温結晶化開始温 度が43度から53度までの範囲にあり、本件発明の数値範囲を満たすも のである。 そして、上記各実施例の上記の保管条件は、「ラップフィルムの出荷後の 流通、及び家庭での保管を想定」した(【0059】)ものであり、この条 10件の設定自体は、出荷後の流通及び家庭での保管を想定したものとして自 然なものである。
そうすると、当業者は、上記【0044】及び【0059】の記載と上 記各実施例の記載から、ラップフィルムが出荷後の流通及び家庭での保管 の過程で熱を受けると、低温結晶化開始温度が40度から上昇することを 理解し、上記各実施例の上記保管条件のみならず、他の保管条件であって も、一般的な流通及び家庭での保管の条件(温度及び保管する時間)の範 囲に沿うものであれば、低温結晶化開始温度が「40〜60度」の範囲内 に収まるラップフィルムを作成することができると認識できると認めら れる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 数値限定
>> ピックアップ対象
2022.06.30
令和4(行ケ)10002 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年6月16日 知的財産高等裁判所
原告は、原告が「温石灸」の語を使用して行っている施術は、平成26 年に施術を開始した、温石及びもぐさの両方を用いるオリジナルの施術で あり、「温石灸」の語は、「温石をもぐさの上に置いて行う施術」との意味 合いを有する造語であるから、本願商標の指定役務との関係で出所識別機 能を有する旨主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(1))。 そこで検討するに、証拠(甲9、10、33)及び弁論の全趣旨によれ ば、原告は、平成26年10月頃から、温めた石をもぐさの上に置いて患 部を温める施術を「温石灸」との名称で行っていること、原告がこのよう な内容の施術を「温石灸」との名称で行うことを許諾したのは、「MoMo Soはり灸院」のみであることが認められる。 しかしながら、本願商標が商標法3条1項3号に該当するか否かは、本 件審決がされた時点における取引の実情を考慮して判断すべきものであ るところ、上記(4)で検討したとおり、本件審決がされた当時の本件業界に おいて、温石を用いた施術が、火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用 いることにより、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石 灸」との名称でも広く行われている実情があったといえることからすれば、 原告がそれ以前から温石及びもぐさの両方を用いる施術を「温石灸」と称 して行っているなどの事情があるからといって、前記の結論が左右される ものではないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、本件業界において「温石」又は「温石灸」の語が使用されてい る例について、「温石」が「温めた石」ほどの意味合いを有するとしても、 施術において「温石」をどのように用いるかや、「温石」と肌にのせたもぐ さに火を点じて焼く施術である「灸」との関係性が明らかではないから、 使用されている「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内 容(効能)等が想起されるものではない旨主張する(前記第3の1〔原告\nの主張〕(2))。しかしながら、原告が指摘するとおり、商標法3条1項3号に該当する というためには、当該商標から具体的な役務の質(内容)が認識されるこ とが必要であると解されるものの、上記(4)で検討したとおり、本件審決が された当時の取引の実情を考慮すると、「温石灸」の語は、「火をつけたも ぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施術」を表すものと容\n易に理解されるものであったというべきである。そうすると、「温石灸」の 語からは、施術に用いる道具、施術の方法及び施術によって得られる効果 がいずれも容易に理解されるものといえるから、本願商標の取引者、需要 者は、「温石灸」の語から役務の質(内容)を具体的に認識することができ るものといえる。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 原告は、本件業界において行われている「温石灸」の施術について、1) 「灸」の語の一般的な意味とは異なる内容の施術であり、かつ、様々な施 術の方法及び内容(効能)等を含むものであること、2)「温石」や「温石 療法」等とも表示することができるから、「温石灸」の語は役務の質を表\示 記述するものとして取引に際し必要適切な表示であるとはいえないこと、\n3)全国に存在する「はり及びきゅうを行う施術所」の数からすれば、「温石 灸」の語を使用する事業者はごくわずかであることを理由に、本件業界に おいて「温石灸」が施術されている例があることをもって、「温石灸」の語 が示す役務の内容が一般に理解されるものとはいえない旨主張する(前記 第3の1〔原告の主張〕(3))。 しかしながら、上記1)については、上記(4)で検討したとおり、本件業界 において一般に行われている「温石灸」の施術は、火をつけたもぐさを使 用しない点において、本来的な意味における灸とは異なるものではあるも のの、火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることにより、灸に類 似する効果を得ることができる施術として行われていることなどからす れば、「温石灸」の語は、このような内容の施術を表すものとして容易に理\n解されるものといえる。 また、上記2)については、上記(4)で検討したとおり、本件審決がされた 当時の本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」や「温石」等 と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情があったといえるもの の、他方で、必ずしも灸と厳格に区別されていたものではなく、灸に類似 する効果を得ることができる施術として、「温石灸」との名称でも広く行わ れている実情があったといえることからすれば、温石を用いた施術が「温 石療法」や「温石」等とも表示されているからといって、「温石灸」の語が、\n役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表\示であるこ とが否定されるものではないというべきである。 さらに、上記3)については、上記(4)で検討したところに照らせば、全国 に存在する「はり及びきゅうを行う施術所」の数のみを根拠として、前記 のとおりの取引の実情があったことを否定することはできないというべ きである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
エ 原告は、材料等の名称を冠した従来の「味噌灸」等と原告が行っている 「温石灸」とでは施術内容が全く異なるものであり、「温石灸」の語を従来 の「味噌灸」等の語と同様の意味で捉えると、施術の方法及び内容(効能)\n等が理解し難いものとなるから、「味噌灸」等と称する灸が存在するからと いって、「温石灸」の語が、特定の役務の質・内容を直接的かつ具体的に示 すものであるとはいえない旨主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(4))。 しかしながら、本件において検討すべきであるのは、本件審決がされた 当時の本件業界において使用されていた「温石灸」の語から認識される内 容であるから、原告が行っている「温石灸」の具体的な施術内容が考慮さ れるものではないというべきである。そして、上記(4)で検討したとおり、 本件審決がされた当時の本件業界において、温石を用いた施術は、施術の 道具として温めた石を用いる灸と同種の施術であることから、「味噌灸」等 と同様に、「温石灸」とも称されるようになったものであり、「温石灸」の 語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施 術」を表す語として容易に理解されるものであったというべきである。\nしたがって、原告の上記主張は採用することができない。
オ 原告は、本件テレビ番組において「温石灸」と称された施術は、従来か ら広く使用されてきた「温石」又は「温石療法」と同義のものとして紹介 されたものにすぎないから、そのような内容の放送がされ、本件業界の関 係者がこれに否定的な意見を述べなかったとの事実をもって、「温石灸」の 語が、灸(施術)の一種を表したものとして、特定の役務の質・内容を示\nすものとして理解されたものとみるのは相当でない旨主張する(前記第3 の1〔原告の主張〕(5))。
しかしながら、上記(4)で検討したところに照らせば、原告が指摘すると ころによって、前記の結論が左右されるものではないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.06.30
令和4(ワ)3374 特許権侵害行為差止等請求事件(承継参加) 特許権 民事訴訟 令和4年6月20日 大阪地方裁判所
このように、甲6食品実験等と乙12実験等の結果は異なっているところ、 前記2(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるLED5)が青色 発光するのは、パーシャル室を(チルドではなく)微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−3度 から約−1度に保たれることになるから、乙12ないし乙15の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙12、13実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は5〜47.8度(至適増殖温度は30〜37度)であり、枯\n草菌の一般的な増殖可能温度域は5〜55度(最適発育温度帯は20〜4\n5度)であること(乙12、13に添付の参考資料)と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲6実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲15食品実験及び甲15培\n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙12実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲6食品実験等を採用 することはできず、乙12実験等によるべきである。 そして、乙12、13実験等によると、そもそも本件製品において青色L EDが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙15実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が6つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき(本件測定器具の精度については議論があるものの)精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色\n光の照射を受けなかった豚肉の方が3日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度(光量子束密度)は、白色光等他の波長域の光も含めて最大7μE/m2/s 程度であって(乙8)、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、LED4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと(光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと)を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」(構成要件B)を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。\n争点1についての原告の主張(請求原因)は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記2のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点3−7(乙36公報記載の乙36発明に基づく新規性欠如の有無) を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙36公報に記載された「FL-40SB(東芝電気(株))」 は、混在する光を発することを指摘して、乙36公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ400nm から490nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと(構成要件B)\nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す\nる。 しかし、前記(2)によれば、乙36公報の特許請求の範囲第2項は「500 nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙36公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも500nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、(中略)更に好ましくは、360nm か ら400nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、400nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−2についてはおよそ400nm〜500nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−11にあっては、枯草菌に前記光源−2を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙36公報に接した当業者は、波長が400 nm〜500nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙36発明が開示されていると容易に理解し得るものである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.06.28
令和2年(受)第1442号 投稿記事削除請求事件 令和4年6月24日 第二小法廷判決
本件事実は、他人にみだりに知られたくない上告人のプライバシーに属する事実である。他方で、本件事実は、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものとして、本件各ツイートがされた時点においては、公共の利害に関する事実であったといえる。しかし、上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており(刑法34条の2第1項後段)、本件各ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている。また、本件各ツイートは、上告人の逮捕当日にされたものであり、140文字という字数制限の下で、上記報道記事の一部を転載して本件事実を摘示したものであって、ツイッターの利用者に対して本件事実を速報することを目的としてされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであるとは認め難い。さらに、膨大な数に上るツイートの中で本件各ツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないものの、上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると検索結果として本件各ツイートが表示されるのであるから、本件事実を知らない上告人と面識のある者に本件事実が伝達される可能\性が小さいとはいえない。加えて、上告人は、その父が営む事業の手伝いをするなどして生活している者であり、公的立場にある者ではない。以上の諸事情に照らすと、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である。したがって、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができる。\n
◆判決本文
原審はこちら。なお、1審判決(平成30(ワ)66)は判決文がアップされていません。
◆令和1(ネ)4733
現時点(本件口頭弁論終結時)においては,広く利用されている検索事業者であるグーグルの機能を用いて検索しても(甲90,96,102),本件各投稿記事に関する情報が検索結果として表\示されることはない。本件各投稿記事が引用するインターネット上の報道記事も,すでに削除されている(乙23)。第1審原告が本件逮捕を理由に就職や交友関係などで不利益を受けたと考えている出来事は,いずれも平成▲年以前(刑の消滅前)の出来事であって,グーグルなど一般的な検索事業者の提供する検索機能により本件逮捕の事実が知られたことが原因と推定される。そして,ツイッターの検索機能\の利用頻度は,グーグルなど一般的な検索事業者の提供する検索機能ほどには高くないことは,公知の事実である。そうすると,本件逮捕の事実が伝達される範囲はある程度限られ,かつ,本件各投稿記事によって第1審原告が具体的被害を被る可能\性も低下しているということができる。なお,第1審原告は,平成▲年▲月に婚姻したが,配偶者やその家族には本件逮捕や罰金刑確定の事実は伝えていない。
エ 以上の事実を総合すると,罰金の納付(平成▲年▲月▲日)から5年が経過して刑の消滅の効果(刑法34条の2)が発生し,その後更に3年近くが経過したこと及び第1審原告が本件各投稿記事が一般の閲覧に供されることにより各種の社会的な不利益を受ける可能性が消滅したわけではないことを考慮しても,被疑事実の内容や本件各投稿記事が公共の利害に係り公益目的で投稿されたこと,既にグーグルなどの一般的な検索サイトでは本件逮捕の事実が検索結果として表\示されることはなく,具体的な不利益を受ける可能性が低下していることなどに鑑みれば,本件において,本件各投稿記事を一般の閲覧に供する諸事情よりも本件逮捕の事実を公表\されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。よって,第1審原告による本件各投稿記事の削除請求は理由がない。
2022.06.21
令和3(ネ)10102 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月8日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
当裁判所も、被告各製品は本件各発明の構成要件1E4)等をいずれも充足し ないものであるから、本件各発明の技術的範囲に属せず、したがって、その余 の点について判断するまでもなく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと 判断する。
その理由は、後記1のとおり原判決を補正し、後記2に当審における当事者 の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第4の 1及び2に記載されたとおりであるから、これを引用する。
・・・
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は、前記第2の5(1)アのとおり、本件各発明の「係止片」は、1)片 状の部材であり、2)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、3)大径部に円 筒状部と一体形成され、4)小径部側には設けられていないものをいうから、 上記構成要素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられて\nいても構成要件1E4)等の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの 主張もこのような理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第4の1(1)エ(補正後のもの)のとおり、 本件各発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機 能を有する係止片は小径部側には設けられていないこととされている(係止\n片が小径部側に設けられていないことに特有の技術的意義がある。)と理解 するのが相当であり、したがって、小径部に設けられることで構成要件1E\n4)等の充足が妨げられる係止片は、その形状を問われないものというべきで あるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小径部側に存する\nことは、対象製品が構成要件1E4)等を充足することを妨げるものである。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」(へん)状の部材であるから、「係止片」とは「片 状(へんじょう)の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件各発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判 断に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を 片状のものに限定する意義は見いだせない。以上によれば、控訴人の上記主張は、いずれも採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.06.21
令和1(ワ)9842 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月9日 大阪地方裁判所
(ウ) 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば、一定数の競合品の存在による推定覆滅がなさ れるものの、一方で、競合品に該当する商品数が多いとはいえないこと、被告製品 の売上に対する本件各訂正後発明の貢献の程度は大きいと認められること、被告独 自の販売ルートの点は限定的な影響に留まり、その他に推定を覆滅すべき具体的な 事情は見当たらないことから、本件においては2割の限度で損害額の推定が覆滅さ れるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採 用できない。
ウ 以上から、特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額は、1億4759万2498円(≒184,490,622 円×0.8)となる。
(2) 特許法102条3項に基づく主張について
ア 被告製品の売上
原告製品の販売開始前である平成25年から平成27年11月24日までの被告 製品の売上は合計1億3814万3836円である(当事者間に争いがない)。
イ 実施料率
本件において、本件各訂正後発明の実施許諾契約の存在を認めるに足りず、証拠 (乙26)及び弁論の全趣旨によれば、平成22年8月31日に発行された「ロイ ヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウ ハウ〜」において、光学機器及び家具、ゲームの技術分野における正味販売高に対 する実施料率は、光学機器については、平均が3.5%、最大値が9.5%、最小 値が0.5%、標準偏差が1.9%であり、家具及びゲームについては、平均が2. 5%、最大値が4.5%、最小値が0.5%、標準偏差が1.5%であることが認 められる。これらに、原告と被告は競業関係にあること、前記(1)イのとおり、本件 各訂正後発明の貢献の程度その他本件に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件 における実施に対して受けるべき料率としては6%が相当であると認める。
原告は、他社との和解内容等を考慮して、被告製品1台あたり1万円(実施料率 23.6%)が妥当である旨を主張する。しかし、種々の事情を総合的に考慮して 和解に至ることが通常であり、和解内容を実施許諾契約と同様に考えるのは相当で ないことに加え、証拠(甲42、43)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、和解 契約等において、相手方が、原告に対し、原告が実施料相当額であると主張してい る金員を支払う他に金員を支払う条項は存在しないことが認められ、特許法102 条3項及び同条2項の適用により損害の額を算定する本件とは条件を異にするとい うべきである。
ウ 以上から、特許法102条3項に基づき推定される損害額は、828万86 30円(≒138,143,836×0.06)となる。
(3) 特許法102条2項の推定覆滅と同条3項の適用について
特許法102条2項の推定が覆滅された部分について、特許侵害行為と被告の受 けた利益との相当因果関係が認められないとしても、当該部分について、特許権者 は、特許権侵害の際に請求し得る最低限度の損害額として同条3項の適用により算 定される損害額の賠償請求をし得るものと解される(この点につき被告も争ってい ない。)。 平成27年11月25日から令和元年7月までの被告製品の売上は3億3613 万9283円であるところ(当事者間に争いがない)、前記(1)及び(2)のとおり、 特許法102条2項の推定は2割覆滅され、同条3項の実施料率は6%である。 したがって、特許法102条2項の推定が覆滅された部分について同条3項が適 用されることによる損害額は、403万3671円(≒336,139,283×0.2×0.06) となる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.06.21
平成30(ワ)24818 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月23日 東京地方裁判所
ア 特許法102条3項の「受けるべき金銭の額」を算定する基礎となる相 当実施料率については、1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実 施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考 慮に入れつつ、2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や 重要性、他のものによる代替可能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた 場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競 業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理 的な料率を定めるべきである(知財高裁平成30年(ネ)第10063号 令和元年6月7日特別部判決参照)。
イ これを本件についてみると、本件訂正発明1の実際の許諾例は存在しな いものの、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、実施料の相場について、 「精密機器」の特許の実施料率が、平均3.5%(最大値9.5%、最低 値0.5%)であり、「その他」の分野の司法決定の実施料率が、平均7. 3%(最大値12.0%、最小値3.0%)であると報告された例がある こと(甲22)、原告が、第三者との間で、その発明の名称を「導電性ボ ール配列用マスク及びその製造方法」とする特許について、実施料率を1 0%とする旨の合意をしたことがあり(甲23)、その発明の名称を「ク リーム半田用メタルマスクおよびスクリーン印刷用スキージ技術」とする 特許について、実施料率を20%とする合意をしたことがあること(甲2 4)、以上の事実を認めることができる。 これに対し、被告は、これらの許諾例は、認識マークの電解処理とは無 関係なものを抽象的に一括するものであると主張するが、特許発明の属す る一定の範囲の分野を相当実施料率の考慮要素とすることは正当であり、 被告が指摘するような個別具体的な特許発明の内容については、特許発明 自体の価値や技術内容の観点から考慮するのが相当である。
ウ そして、本件訂正発明1は、前記1(1)のとおり、認識マークを形成する 従来の技術が、認識マークとして充填したトナーが凹部から脱落し、また、 箔物メタルマスクに適用することが困難であるという欠点があったため、 これを解消するものであって、本件訂正発明1と同一の作用効果を代替す る技術があることを認めるに足りる証拠はない。ただし、現在においても、 本件訂正発明1の電解マーキングよる認識マーク以外の認識マークの形成 方法も相当な割合で使用されており(乙93、99)、顧客によっては、 電解マーキング以外の方法を特に指示する場合があることも認められるこ とからすると、メタルマスクの認識マークに係る市場において、本件訂正 発明1の方法が、唯一の実用的な技術であるとまでいうことはできない。
エ 上記のような本件訂正発明1の技術内容や重要性に照らせば、これを実 施することは、原告及び被告にとって、相応に売上げや利益に貢献するも のであるといえる。そして、原告が、本件訂正発明1に係る技術を広く宣 伝等しているとは認められないとしても(乙97)、原告と被告が、本件 訂正発明1に係るメタルマスクの分野で競合する会社同士であることを考 慮すれば、仮に、原告が、被告に対し、本件訂正発明1の実施を許諾する とすれば、その実施料は相当に高額になったものといえる。
このような事情に加え、特許法102条3項の「受けるべき金銭の額」 を算定する基礎となる相当実施料率は、特許権侵害をした者に対し事後的 に定められるものであって、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるこ とをも踏まえると、被告製品1による本件訂正発明1の侵害に係る実施料 率としては、売上高の●(省略)●%を認めるのが相当である。
オ なお、被告は、侵害論に係る裁判所の心証開示後、損害論の相当実施料 率の考慮要素として、本件訂正発明1が、既知の技術であり、被告が、先 使用していたものであるなどとして、乙2メタルマスクとは別個の製品に 係る分析結果などを証拠提出した。しかし、当該主張は、実質的には先使 用の抗弁(争点2)の根拠となる事由を追加するものであり、訴訟の完結 を遅延させると認められたことから、当裁判所は、被告に対し、上記証拠 提出に係る主張を補充しないように訴訟指揮をした。そして、被告は、こ れを侵害論の段階で主張立証し得なかった理由を特に説明しないのである から、当該主張立証は、時機に後れた攻撃防御方法(民事訴訟法157条 1項)として、原告の申立てに基づき却下するのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.06.21
令和2(ネ)10057 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被控訴人らは,控訴人の本件請求は,控訴人が,原告電子部品(ICチップ) のメモリの書換えを技術的に困難にする本件書換制限措置という合理性及び必 要性のない行為により,被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取 り外して被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ,原告電子部品(IC チップ)のメモリを書き換える態様により原告製品をリサイクルしたリサイク ル品の原告電子部品についての本件各特許権の消尽の成立を控訴人の意思によ り妨げ,そのような結果を利用したものであるという点において消尽の趣旨を 潜脱し,また,リサイクル品が装着された場合にディスプレイ上に「?」が表\n示されるような設定と本件書換制限措置という妨害行為を組み合わせる方法で, 純正品と同等のリサイクル品を競争上劣位におき,リサイクル事業者である被 控訴人らの取引を不当に妨害しているから,公正な競争を阻害するものであり, 競争者に対する取引妨害として,独占禁止法(独占禁止法19条,2条9項6 号,一般指定14項)に抵触することを総合考慮すると,控訴人が,被控訴人 らに対し,被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請求権及び損害賠 償請求権を行使することは,権利の濫用に当たり許されない旨主張するので, 以下において判断する。
(2) 被控訴人ら主張の本件書換制限措置による競争上の不利益について
被控訴人らは,1)トナーカートリッジの消費者は,トナー残量表示の有無\nを製品選択における重要な要素であると考えており(乙25),いくら価格 が安くとも,トナー残量表示のないリサイクル製品は,純正品と同等ではな\nい「中途半端な再生品」として消費者に受け入れられない,2)ICチップを 書き換えずにトナーを再充填した場合には,トナー残量表示が常に「?」と\nなりトナー残量が分からなくなるという不都合にとどまらず,トナーが少な くなってきた時のカートリッジ交換予告メッセージが出ないため,トナーが\nなくなった時に突然トナーの補給を求める表示が出てプリンタが動かなくな\nるという不便をユーザーが被ることになり,その結果,リサイクル事業者に 大きな不利益を与えるものである,3)残量表示がされず,「?」が表\示され る製品がユーザーに受け入れられないことは,被控訴人らの実施した聴き取 り調査の結果(乙25,66)から明らかであり,また,残量表示がされな\nいことは,官公庁の入札条件を満たさない(乙67の1ないし4,68の1 ないし4)ことからも明らかであり,このことは,本件アンケート調査(乙 70)の結果及び東京国税局の回答書(乙71)からも,裏付けられる,4) 本件書換制限措置を回避できたというためには,大量に販売されるリサイク ルトナーカートリッジが長期間安定的にプリンタで使用できる必要があり, 実用に耐えうる程度の本件書換制限措置の回避は事実上不可能か,著しく困\n難である,5)したがって,本件書換制限措置は,リサイクル業者である被控 訴人らに対し,競争上著しい不利益を与えるものである旨主張するので,以 下において判断する。
・・・
以上のとおり,本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された 純正品の原告製品が装着された原告プリンタと使用済みの原告製品にトナー を再充填した再生品が装着された原告プリンタの機能を対比すると,再生品\nが装着された原告プリンタは,トナー残量表示に「?」と表\示され,残量表\n示がされず,予告表\示がされない点で純正品の原告製品が装着された原告プ リンタと異なるが,再生品が装着された場合においても,トナー切れによる 印刷停止の動作及び「トナーがなくなりました。」等のトナー切れ表示は純正\n品が装着された場合と異なるものではなく,印刷機能に支障をきたすもので\nはないこと,再生品が装着された原告プリンタにおいても,トナー残量表示\nに「?」と表示されるとともに,「印刷できます。」との表\示がされるので, 再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり,\nユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められないこと,\nユーザーは,残量表示がされないことについて予\備のトナーをあらかじめ用 意しておくことで対応できるものであり,このようなユーザーの負担は大き いものとはいえないことを踏まえると,残量表示がされない再生品と純正品\nとの上記機能上の差異及び価格差を考慮して,再生品を選択するユーザーも\n存在するものと認められる。また,前記認定のとおり,残量表示がされるこ\nとが公的入札の条件であるとはいえない。
一方,リサイクル事業者においては,残量表示がされないことについてユ\nーザーが不安を抱くことを懸念するのであれば,再生品であるため残量表示\nがされないが,印刷はできることを表示することによって対応できること,\n電子部品の形状を工夫することで,本件各発明1ないし3の技術的範囲に属 さない電子部品を製造し,これを原告電子部品と取り替えることで,本件各 特許権侵害を回避し,残量表示をさせることは,技術的に可能\であり,●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●からすると, 原告プリンタ用のトナーカートリッジの市場において,本件書換制限措置に よるリサイクル事業者の不利益の程度は小さいものと認められる。 次に,控訴人は,本件書換制限措置を行った理由について,原告電子部品 に本件書換制限措置が講じられていない場合には,原告プリンタに自ら品質 等をコントロールできない第三者の再生品のトナーの残量が表示され,残量\n表示の正確性を自らコントロールできないので,このような弊害を排除した\nいと考えて本件書換制限措置を講じたものである旨を主張し,経営戦略とし て,原告製プリンタに対応するトナーカートリッジのうち,ハイエンドのプ リンタであるC830及びC840シリーズに対応する原告製品に搭載され た原告電子部品を選択した旨を述べていること(甲75,76),その理由に は,相応の合理性が認められること,上記のとおり,本件各特許権侵害を回 避した電子部品の製造が技術的に可能であることを併せ考慮すると,控訴人\nが本件書換制限措置がされた原告電子部品を取り替えて使用済みの原告製品 に搭載した被告電子部品について本件各特許権を行使することは,原告製品 のリサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることは できない。
上記のとおり,本件書換制限措置によりリサイクル事業者が受ける競争制 限効果の程度は小さいこと,控訴人が本件書換制限措置を講じたことには相 応の合理性があり,控訴人による被告電子部品に対する本件各特許権の行使 がもっぱら原告製品のリサイクル品を市場から排除する目的によるものとは 認められないことからすると,控訴人が本件書換制限措置という合理性及び 必要性のない行為により,被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品 を取り外し,被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ,上記消尽の成 立を妨げたものと認めることはできない。 以上の認定事実及びその他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば,控訴人 が,被控訴人らに対し,被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請 求権及び損害賠償請求権を行使することは,競争者に対する取引妨害として, 独占禁止法(独占禁止法19条,2条9項6号,一般指定14項)に抵触す るものということはできないし,また,特許法の目的である「産業の発達」 を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものであるということはできないか ら,権利の濫用に当たるものと認めることはできない。 したがって,被控訴人らの前記主張は採用することができない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成29(ワ)40337
上記(1)ないし(5)によれば,本件各特許権の権利者である原告は,使用
済みの原告製品についてトナー残量が「?」と表示されるように設定した\n上で,本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて,十分な\n必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じ
ることにより,リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの
書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ,トナー残量の表示される再\n生品を製造,販売等することを制限し,その結果,被告らが当該特許権を
侵害する行為に及ばない限り,トナーカートリッジ市場において競争上著
しく不利益を受ける状況を作出した上で,当該各特許権の権利侵害行為に
対して権利行使に及んだものと認められる。
このような原告の一連の行為は,これを全体としてみれば,トナーカー
トリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をし\nた製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり,トナーカートリ
ッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告ら
とそのユーザーの取引を不当に妨害し,公正な競争を阻害するものとして,
独占禁止法(独占禁止法19条,2条9項6号,一般指定14項)と抵触
するものというべきである。
そして,本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと,同措置
を行う必要性や合理性の程度が低いこと,同措置は使用済みの製品の自由
な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると,
本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは,特許法
の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するもの
として,権利の濫用(民法1条3項)に当たるというべきである。
イ 損害賠償請求について
差止請求が権利の濫用として許されないとしても,損害賠償請求につい
ては別異に検討することが必要となるが,上記ア記載の事情に加え,原告
は,本件各特許の実施品である電子部品が組み込まれたトナーカートリッ
ジを譲渡等することにより既に対価を回収していることや,本件書換制限
措置がなければ,被告らは,本件各特許を侵害することなく,トナーカー
トリッジの電子部品のメモリを書き換えることにより再生品を販売して
いたと推認されることなども考慮すると,本件においては,差止請求と同
様,損害賠償請求についても権利の濫用に当たると解するのが相当である。
ウ したがって,本訴において,原告が,被告らに対して,本件各特許権に
基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び損害賠償等の請求をするこ
とは,いずれも権利の濫用に当たり許されないものというべきである。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 消尽
>> ピックアップ対象
2022.06. 8
令和3(行ケ)10160 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年5月31日 知的財産高等裁判所
原告は、本件商標について、特定の場所を示すものにすぎない「三 橋の森」の語と、識別力の強い造語である「一升パン」の語とが組み合 わされた結合商標であり、これらは不可分的に結合しているものではな く、また、「一升パン」部分が商品の識別情報として強く支配的な印象を 与えるから、同部分を要部として認定し、引用商標と対比すべきである 旨主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2))。
(イ) そこで検討するに、本件商標の構成全体をみると、「三橋の森」と「一升パン」との間の「の」は、所有や所属等を示す格助詞であるといえる\nから、本件商標は、「三橋の森」の語と「一升パン」の語とが格助詞であ る「の」で結合された結合商標であるといえる。 そして、「三橋の森」の語は、一般の辞書等に掲載されている語ではな く、また特定の地域や森の名称を指すものでもないことからすれば、造 語であるとみるのが相当である。また、証拠(甲27の1ないし3)及 び弁論の全趣旨によれば、「三橋の森」は、埼玉県内に所在する、結婚式 場やフレンチレストラン等が一体となった複合商業施設の名称であると 認められる。これらの事情を考慮すると、「三橋の森」の語は、単に「森 等の緑に囲まれた公園等の地域」を表すものとはいえず、「三橋の森」部分からは、商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じるものといえ\nる。
他方で、「一升パン」の語は、前記のとおり、一般の辞書等に掲載され ている語ではないことからすれば、造語であるとみるのが相当である。 また、一般に、「一升」の語は、米や日本酒、醤油の容量を表す単位として用いられるものの、パンの数量を表\す単位として用いられるものとはいえないことからすれば、「一升パン」の語は、通常は組み合わされるこ とのない「一升」の語と「パン」の語とが組み合わされたものといえる。 これらの事情を考慮すると、「一升パン」部分についても、商品の出所識 別標識としての称呼、観念が生じるものといえる。 このように、本件商標の「三橋の森」部分及び「一升パン」部分は、 いずれも商品の出所識別標識として機能する語であるといえる。
(ウ) しかしながら、「一升パン」の語は、旧来から1歳の誕生日を迎えた 子供のお祝いとして用いられてきた「一升餅」の「餅」の語を「パン」 に置き換えたものにすぎないといえる(甲4)上、このような「一升パ ン」と称する商品は、本件商標の登録査定時において、原告以外の少な くとも100を超える事業者によっても製造、販売されていたといえる こと(甲4、乙1ないし147)からすれば、「一升パン」の語は、通常 は組み合わされることのない二つの語を組み合わせた造語であること を考慮しても、それ自体が特徴的又は印象的な語であるとまではいえな い。また、前記のとおり、本件商標は、「三橋の森の一升パン」の文字を 標準文字で書してなるものであり、いずれかの部分が目立つ態様で記載 されているものではない上、後記3(2)で検討するところに照らせば、本 件商標の登録査定時において、「一升パン」の語が、原告商品を表示するものとして、本件商標の取引者及び需要者の間において広く認識されて\nいたものとはいえない。 以上の各事情を考慮すると、本件商標の「一升パン」部分は、取引者、 需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるも のであるとは認められない。
(エ) 以上によれば、本件商標について、「一升パン」部分が取引者、需要 者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと は認められず、また、「一升パン」部分以外の部分である「三橋の森」部 分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとも認められないか ら、本件商標の「一升パン」の部分を抽出し、この部分だけを引用商標 と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないというべ きである。
(オ) したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、本件商標のように「○○の△△」という商標出願については、 「の」の前後の語のいずれかが要部として抽出された上で、他の商標と類 似するとして拒絶された例が多数存在する旨主張する(前記第3の1〔原 告の主張〕(5))。しかしながら、商標登録の可否は、商標の構成、指定商品又は指定役務、取引の実情等を踏まえて、具体的な実情に基づき商標ごとに個別に判断すべきものであるから、原告が指摘するような他の例があるからといって、\n前記の結論が左右されるものではないというべきである。
◆判決本文
関連事件です。こちらは、本件原告が、本件被告の「一升パン」は3条1項3号、または4条1項16号違反として無効審判を請求し、無効理由無しと判断されています。知財高裁も同様です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.06. 8
令和3(行ケ)10082 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年5月31日 知的財産高等裁判所
しかしながら、前記1 で検討したとおり、本願発明は、被覆層を除 去してコア電線を露出させる作業の作業性に関し、コア材の外周面に粉 体が塗布された従来のケーブルには、コア材を取り出す作業の際に粉体 が周囲に飛散し、作業性が低下してしまうという課題があったことから、 コア電線と被覆層との間に、コア電線に巻かれた状態で配置されたテー プ部材を備える構成とすることにより、テープ部材を除去することによ\nって容易にコア電線と被覆層とを分離することができるようにして、上 記課題を解決しようとする点に技術的意義を有するものである。 他方で、前記2 イで検討したとおり、引用発明は、線心の取り出し を容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発明で あり、この点で本願発明と課題を共通にするものといえるが、電源用線 心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で被覆する構成とす\nることによって上記課題を解決しようとするものであり、本願発明とは 課題を解決する手段を異にするものといえる。
このように、引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発 明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該 課題解決手段に加えて、両線心をテープ部材で巻き、その結果、両線心 とシースとの間にテープ部材が配置される構成とする必要はないという\nべきである。そして、引用発明に上記のような構成を加えると、線心を\n取り出そうとする際に、シースを除去する作業のみでは足りず、更にテ ープ部材を除去する作業が必要となることから、かえって作業性が損な われ、引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまうものといえる。 加えて、甲1公報をみても、引用発明の効果を犠牲にしてまで両線心を テープ部材で巻くことに何らかの技術的意義があることを示唆するよう な記載は存しない。 以上によれば、引用発明に上記周知技術を適用することには阻害要因 があるというべきであるから、相違点3に係る「前記コア電線のみを巻 くテープ部材」という構成の意義について検討するまでもなく、本件原\n出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点 3に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。\n
イ 相違点4に係る容易想到性
相違点4に係る本願発明の構成は、相違点3に係る本願発明の構\成であ る「テープ部材」を含むものであるところ、上記アで検討したところによ れば、相違点4に係る「前記テープ部材上に形成された被覆層」という構\n成の意義について検討するまでもなく、本件原出願日当時の当業者が、引 用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点4に係る本願発明の構成を容\n易に想到し得たものとはいえない。
ウ 相違点6に係る容易想到性
相違点6に係る本願発明の構成は、相違点3に係る本願発明の構\成であ る「テープ部材」を含むものであるところ、上記アで検討したところによ れば、本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づい て、相違点6に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。\n
エ 相違点3、4及び6に係る被告の主張に対する判断
被告は、相違点3に関し、1)甲1公報には引用発明が簡素な構成を課\n題解決手段としたものであることについては何も記載されていない、2) 甲1公報に記載された電源用線心及び信号用線心の取り出しが容易に行 えるという効果は従来例と比較しての記載にすぎない上、線心がシース 内に埋め込まれている従来例及び線心をシースで覆う引用発明のいずれ が簡素な構成であるかは不明である、3)甲1公報に記載された実施例に ついて、両線心の外周がシースで覆われているのみであるとしても、甲 1公報には両線心の上に何らかの部材を介在させることを排除する記載 はないことを理由に、引用発明にテープ部材を介在させることについて、 原告が主張するような阻害要因があるとはいえない旨主張する(前記第 3の〔被告の主張〕3 エ)。
しかしながら、前記2 イで検討したとおり、引用発明は、線心の取 り出しを容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発 明であり、電源用線心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で 被覆する構成とすることによってこの課題を解決しようとするものであ\nるといえることからすれば、上記1)の主張は理由がないというべきであ る。 また、上記周知技術の適用が引用発明の効果に及ぼす影響については、 引用発明の構成を前提に検討すべきものであって、従来例と対比して検\n討すべきものではないから、上記2)の主張は理由がないというべきであ る。 さらに、甲1公報には、線心上に何らかの部材を介在させることを排 除する明示的な記載はないものの、上記アで検討したとおり、引用発明 における課題解決手段及びその効果を考慮すれば、引用発明に上記周知 技術を適用すると、線心の取り出しを容易に行うことができるようにす るという引用発明の効果を損なう結果となってしまうというべきである から、上記3)の主張も理由がないというべきである。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
被告は、相違点4及び6に係る容易想到性についても縷々主張するが、 これまで検討したとおり、当業者が相違点3に係る本願発明の構成であ\nる「テープ部材」を容易に想到し得たものとはいえない以上、相違点4 及び6に係る本願発明の構成も容易に想到し得たものとはいえないから、\nいずれの主張も前記の判断を左右するものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2022.06. 8
令和3(ネ)2663 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和4年6月1日 大阪高等裁判所
ア 具体的構成態様D/dにおける差異点について\n
1審原告は、原審が、円筒状中空本体の形状に関する差異点2)の与える印 象について、差異点3)と逆の認定をしたことについて、主観的な印象であり、 その理由が不明であると主張する。しかし、原告意匠の要部である具体的構\n成態様D3、被告意匠の具体的構成態様d3を対比した結果である差異点2) についてみると、前者は、円筒状中空本体が円周部(周辺部)まで厚みがあ ることから(十分な体積を感じることができる。)、存在感を感じさせると認\n定することに合理性があり、一方、後者の側面の厚みは、円周部(周辺部) に行くに従い、薄くなっていることから、すっきりとした印象を与えるとい える。上記と同様に原審が認定した差異点3)は、円筒状中空本体の中空部の 直径と本体の直径との違いであって、差異点2)とは異なる差異点であるから、 「すっきりした印象」が逆に認定されたからといって不合理ということはで きない。
また、1審原告は、差異点2)、3)が微差であると主張するが、差異点2)に つき、原告意匠では円筒状であるのに対し、被告意匠では、上半分が略梯形 状で、その形状の違いは大きく、微差ということはできない。また、差異点 3)についても、需要者の注意を最も引く部分である円筒状中空本体の下面部 に占める、中空部(ファンガード部分に相当する。)と透光部の割合の大小が 相当に異なることになるから、微差ということはできない。 なお、点灯した場合、差異点が明確でなくなることがあったとしても、需 要者は、常に点灯した状態で看取するわけではなく、上述した点が左右され ることはない。1審原告の主張は採用することができない。
イ 具体的構成態様E/eについて\n
1審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様E3、被告意\n匠の具体的構成態様e3を認定した上で指摘する差異点Aが微差であり、む\nしろ、円形板から放射状に多数のファンガードが面一に形成されているとい う全体的な印象の方が強いという。確かに、原審の認定した上記具体的構成\n態様(E3/e3)によると、1審原告が主張するとおり、いずれの意匠も、 多数のファンガードが円筒状中空部下面とほぼ面一に形成されているという 印象は受けるものの、このような形態を備えた先行意匠が存在することが認 められ(乙14〜16、乙17の1・2)、多数のファンガードが存在するこ とや、略面一であることもって特徴的ということはできない。むしろ、ファ ンガードの形状が直線的であるか、曲線的(渦巻き状)であるかについての 差異点は、より強い印象を与えるというべきであり、上記差異点を微差とい うことはできない。 なお、1審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識され なくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわ けではない。1審原告の主張は採用することができない。
ウ 具体的構成態様H/hについて\n
1審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様H3、被告意\n匠の具体的構成態様h3を認定した上で指摘する差異点6)が微差という。 しかし、原審の認定した上記具体的構成態様(H3/h3)によると、側\n面視の本体に対して透光部の占める割合は、原告意匠(約3分の1)と被告 意匠(約4分の3)とで相当に異なっており、この違いは異なる印象を与え るということができ、微差ということはできない。また、前記アのとおり、 被告意匠では円筒状中空本体側面の上半分が略梯形状であって、その部分の 与える印象が異なるため、原告意匠と被告意匠の側面における透光部の占め る割合(高さ)を、上記略梯形状を含めた円筒状中空本体側面に対する下面 からの高さとして、単純に比較することもできない。 なお、1審原告は、点灯した状態では、上記の差異点について、認識され なくなると主張するが、前記アのとおり、常に点灯した状態で看取されるわ けではなく、1審原告の主張を採用することはできない。
エ 具体的構成態様I/iについて\n
1審原告は、原審が、原告意匠の要部である具体的構成態様I3(ただし、\n口金部を除く。)、被告意匠の具体的構成態様i3(ただし、シーリングプラ\nグを除く。)を認定した上で、その差異点8)、9)から受けるとした印象につい て、支柱体は天井から吊り下げられる部位に関するものであり、しかも、支 柱体の下部には円筒状中空本体が存在するのであるから、支柱体が独立して、 原審が認定した印象を与えることはない旨主張する。しかし、円筒状中空本 体を天井から吊り下げる部位である支柱体は、同中空本体直径の約5分の1 (原告意匠)ないし約3分の1(被告意匠)という相当の存在感を示すもの であり、円筒状中空本体が上方突出体をもって角度調整可能であって下方の\nみを向いているものでもないことをも考えると、支柱体が天井と円筒状中空 本体に挟まれたものであったとしても、その支柱体から受ける印象は、原審 が認定するとおりであるというべきであって、1審原告の主張は採用するこ とができない。
オ まとめ
以上によると、1審原告が当審において主張する差異点は微差ということ はできない。そして、前記(1)で補正した上で原判決を引用して説示したとお り、要部を踏まえた原告意匠と被告意匠の共通点及び差異点を総合的に考慮 すると、原告意匠の構成は、平面視(底面視)が円形である点を除き、全体\n的に直線的で、すっきりとして洗練された印象を与えるのに対し、被告意匠 の構成は、全体的に存在感を示しつつも、柔らかく安定感のある印象を与え\nるものであって、これらの印象がそれぞれの意匠全体に与える影響は強く、 原告意匠と被告意匠に接した需要者は、両意匠から異なる印象を強く感じる ものとみられる。 したがって、原告意匠と被告意匠とは、基本的構成態様においておおむね\n共通するものの、具体的構成態様における差異点がその共通点により生ずる\n美感を凌駕し、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にする というべきであって、被告意匠は、原告意匠と類似するとはいえない。 このことは、原告意匠と被告意匠とで意匠の要部としての基本的構成態様\n(2か所)が全て共通していることを十分に参酌しても、判断が左右される\nものではなく、1 審原告の主張を採用することはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2022.06. 8
令和2(ワ)14627 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年5月27日 東京地方裁判所
原告は、三越伊勢丹から、原告の商標登録の問題を指摘され、商標登録に問題があるとカタログ等を作り直さなければならないとして、平成30年の御中元のカタログ等の掲載はできないことなどを告げられ、当該カタログ等の掲載による売上げを計上すること ができなかったことが認められる。 そうすると、少なくとも、原告がB商標2及び3に係る無効審決を得た 令和2年5月まで、原告の商品を当該カタログに掲載し得なかったことに よる損害は、被告による本件各商標権の移転に係る不法行為と相当因果関 係がある損害と認めるのが相当である。
これに対し、被告は、原告が、三越伊勢丹の実店舗での販売を継続し得 ていることからすれば、商標登録が問題であったとは考えられず、また、 原告が、原告の商品を当該カタログに掲載し得なかったのは、原告が、経 営陣を被告から交代するに当たり、三越伊勢丹の信頼を失ったことが主た る原因であるなどと主張する。しかし、被告も主張するとおり、原告は、 以後も実店舗での販売は継続し得ているのであるから、三越伊勢丹にカタ ログ等の掲載を拒否された理由が、原告がそもそも三越伊勢丹の信頼を失 ったことによるものとは、直ちに認め難い。そして、実店舗は、原告の従 業員が、原告専用のブースで販売するものであるのに対し(原告代表者・\n14頁)、カタログ等は、他の店舗の商品と一緒に掲載され、問題があれ ば全体を作り直さなければならないものであると認められることからする と(C・14頁から15頁)、商標登録に問題があるためにカタログ等の 掲載を拒否されたとするCの証言は、その内容に照らして信用することが できる。そうすると、上記拒否により生じた損害は、本件各商標権の移転 に係る不法行為と相当因果関係がある損害というべきである。 したがって、被告の主張は、採用することができない
2022.06. 6
令和3(ネ)10022 特許権侵害に基づく不当利得返還等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審原告は,本件各発明は「ユーザの発信地域ごとに異なるWebデー タの送信が可能なWebページ閲覧システムを提供することを目的とす\nる」(本件明細書等の段落【0013】)ことから,この目的を達成する ための地域判別の原理は,回線網の敷設地域とISPのサーバが保有する 一群のIPアドレスとの一定の対応関係の存在を利用したものであるとし て(原判決「事実及び理由」第3の1(原告の主張)(2)〔原判決12 頁〕),「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈として,第一義的 には,「ユーザ端末に割り当てたIPアドレスを所持しているアクセスポ イントに通常アクセスするユーザの地域」と解釈すべきであり,「IPア ドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷 設範囲に相当する地域」も同義であると主張し,また,本件各発明は,設 置場所に対応する地域がユーザ端末の存在する地域と対応することに基づ いて,その地域に関連する情報を提供するというエリアターゲティングを 目的とする発明であるから,そもそも,アクセスポイントの「設置場所」 といった地点を判別する意味はなく,「アクセスポイントの設置場所」 (アクセスポイントが属する地域)を判別するステップを介するかどうか を問題とすること自体が誤りであると主張する(原判決「事実及び理由」 第3の1(原告の主張)(5)ア(ア)〔原判決16頁〕)。
しかしながら,特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づい て定めなければならず,特許請求の範囲に記載された用語の意義は,明細 書及び図面を考慮して解釈すべきであるところ(特許法70条1項・2 項),構成要件1B2等において「判別」の対象となっているのは文言上\nあくまで「アクセスポイントが属する地域」であるから,本件特許請求の 範囲の用語の意義としてアクセスポイントの設置場所を無視することはで きない。また,本件明細書等の記載を考慮すると,本件各発明は,ダイヤ ルアップ接続を前提として,ユーザ端末がアクセスポイントの設置された 地点の近傍に所在する蓋然性が高いという経験則を利用して,そのアクセ スポイントの設置場所の近傍をユーザが所在する地域と想定することによ って,ユーザの所在する地域に対応した地域情報をある程度の確率で提供 することができるという技術的思想に基づくものであること,したがって, 「アクセスポイントに対応する地域」等は「アクセスポイントの設置され ている地点とその近傍の一定の地域」と解釈されるべきことは前記⑴のと おりであるから,まさにアクセスポイントの設置場所を判別することに意 味があるのであって,一審原告の上記主張は採用することができない。 そして,このことは,本件特許の出願経過からも明らかである。すなわ ち,本件特許の出願経過は原判決「事実及び理由」第2の2(2)イ記載のと おりであるが,一審原告は,出願経過中の本件補正により,「IPアドレ スと地域とが対応したIPアドレス対地域データベース」を「IPアドレ スとアクセスポイントに対応する地域とが対応したIPアドレス対地域デ ータベース」とし,さらに「IPアドレスが属する地域」を「IPアドレ スを所有するアクセスポイントが属する地域」(甲12の13)として, 自ら「アクセスポイントが対応する」及び「アクセスポイントが属する」 をあえて付加している。そして,一審原告は,意見書(甲12の14)に おいて,「アクセスポイントが属する地域を判別することについて は,・・・ユーザの発信地域は,ユーザ端末101aがアクセスポイント 109aに接続しているため,正確にはアクセスポイント109aに対応 する地域である」と説明し,さらに,本件拒絶査定不服審判における審判 請求書(甲12の16)において,「・・・,IPアドレス対地域データ ベースにおいてはIPアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域, 例えば県や市,さらには市よりも狭い地域を対応付けておくことによって, ユーザ端末が接続しているアクセスポイントの属する地域から,ユーザ端 末の地域を県単位,市単位または市よりも狭い地域単位で判別することが できるという顕著な効果を奏します」と述べている。このように,一審原 告自らが「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈につき,IPアド レス毎にアクセスポイントが設置された地域を対応付けることを意味する ものと主張していたものである。
さらに,一審原告が主張するところの「アクセスポイントに通常アクセ スするユーザの地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線 網等の敷設範囲に相当する地域」は,そもそもどのような範囲を意味する のか必ずしも明らかではないが(特に「物理的回線網の敷設範囲」という 用語は本件明細書等にはない用語であり,ダイヤルアップ接続を前提とす ると,ダイヤルアップ接続においてユーザは世界中のどのアクセスポイン トへも接続が可能であるから,「物理的回線網の敷設範囲」という限定の\n仕方はアクセスポイントの地域を限定する意味を持たないと解される。), 一審原告の主張から推測するに,NTT東西が構築した地域IP網を念頭\nに置いて,地域IP網を経由する接続においては,ダイヤルアップ接続と は異なり,アクセスポイントは各地域IP網エリア単位で固定されていて, ユーザがアクセスポイントを選択することができないことから,アクセス ポイントが設置されている場所がどこであるかにかかわらず,「アクセス ポイントの属する地域」を「アクセスポイントに通常アクセスするユーザ の地域」又は「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範 囲に相当する地域」と解釈しているものと推認される。しかしながら,前 記1(2)イのとおり,そもそも「地域IP網」が現れたのは,平成11年以 降のことであり,本件特許出願時(平成10年6月26日)には存在しな い仕組みであって,出願当時に存在した技術常識ともいえず,当然,本件 明細書等には記載も示唆もされていない。したがって,特許請求の範囲に 記載された用語の意義を解釈するに当たり,上記事実を参酌することはで きないというべきである。 この点に関して一審原告は,本件各発明は,実施例にあるダイヤルアッ プ接続に限定されるものではなく,地域IP網経由の接続も含むものであ る旨主張する。
しかしながら,本件明細書等には,「・・・もちろん,ユーザの発信地 域以外の地域の情報を閲覧したい場合には,ユーザが発信地域以外の地域 のアクセスポイントに接続するか,従来と同じ方法を用いて従来と同じ方 法を用いて選択すればよいことはいうまでもない。」(段落【003 8】)と記載されているところ,この記載は,ユーザが任意の地域のアク セスポイントを選択して接続することを意味するものであって,このよう なアクセスポイントのユーザによる選択はダイヤルアップ接続では可能で\nあるもの,地域IP網経由の接続では通常は想定されていないものである。 そうすると,本件特許の技術的範囲を,地域IP網経由の接続を前提とす る事項まで拡大することは,本件明細書等に開示された技術的範囲を逸脱 することになるというべきである。本件各発明がダイヤルアップ接続を前 提としているという解釈は実施例に限定した解釈ではない。 いずれにしても,上記「アクセスポイントに通常アクセスするユーザの 地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲 に相当する地域」との解釈は,本件特許請求の範囲の記載からかけ離れた 解釈であり,採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.06. 6
令和3(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年5月19日 知的財産高等裁判所
「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略5〜15mmとなるよう形成されたR部」→ 「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略5〜15mmとなるよう形成された,スプーンへの食物移載力転換機構としてのR部」に訂正しても,実質的に発明の範囲が減縮されるものではない。\n
次に、本件発明1の特許請求の範囲の請求項1には、本件発明1の「R 部」は、「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角 が半径略5〜15mmとなるよう形成された」構成を有することが規定さ\nれている。本件明細書には、「R部」に関し、本件発明1の実施形態とし て、「竹製食器100には、各収容部の立ち上がりと底面との取り合い部、 一つの立ち上がり部とこれに隣接する立ち上がり部との間の取り合い部、 に各々略10mm程度の半径によるRを設けてある。具体的に、たとえば 第4の収容部23において、底面部40と立ち上がり部33との取り合い 部に、図3に示されるような半径略10mmの曲線断面が図3の紙面と直 交する方向に延伸されて形成されている。また、平面においても、たとえ ば、立ち上がり70と立ち上がり13との間の取り合い部には、図1に示 されるような半径略10mmの曲線断面が図1の紙面と直交する方向に 延伸されて形成されている。」(【0030】)との記載があり、別紙1のと おり、図1及び3には、「R部」が図示されている。 そこで、「R部」に関する甲4の記載について検討するに、甲4文章部分 中の「φ23×H2.1(plate)」との記載から、甲4記載の「こども用 食器」は、直径(φ)23cm、高さ(H)2.1cmであることを理解 できるが、他方で、甲4の記載事項全体をみても、上記直径及び高さ以外 の寸法についての記載はない。
また、甲4全体写真及び甲4部分拡大写真(別紙2参照)のアングル、 解像度等に照らすと、甲4全体写真及び甲4部分拡大写真から、被写体で ある「こども用食器」の「R部」を形成する「立面と底面とのなす角」の 角度や「半径」の寸法についてまで認識することは困難である。 以上を総合すると、甲4に接した当業者において、甲4から、甲4記載 の「こども用食器」の「R部」は、「前記窪み部において穿削されて得ら れる立面と底面とのなす角が半径略5〜15mmとなるよう形成された」 構成を有することが開示されているものと認識することはできないとい\nうべきである。
・・・
原告は、1)甲4全体写真について説明した甲76の5枚目の左側の画像記 載のとおり、A(こども用食器の外径):B(こども用食器の竹の集成材から なる所定の厚みのある部分の内側の径):C(こども用食器の二層目の竹材平 板の内側の径)の比率は、100:94.8:88.3である、2)この比率 と甲4記載の実寸から、A´(Aの実寸)は230mm、B´(Bの実寸) は218mm、C´(Cの実寸)は203mm、D´(こども用食器の竹の 集成材からなる所定の厚みのある部分の幅の実寸)は6mm、E´(こども 用食器を真上から見たときの二層目の竹材平板の幅の実寸)は7.5mmと 算出される、3)甲76の5枚目中欄の「Rごとの見え方の違い」の表によれ\nば、E´が7.5mmである場合、その見え方は、R10の場合の見え方に 該当するから、甲4記載の「こども用食器」の立面と底面とのなす角は、半 径略10mm弱となるよう形成されたR部になるとして、甲4には、甲4記 載の「こども用食器」は、「立面と底面とのなす角が半径略10mm弱となる よう形成されたR部」の構成を有することの開示がある旨主張する。\nしかしながら、甲76は、原告従業員が作成した書面(作成日2021年 10月25日)であり、そもそも本件出願前に頒布された刊行物に当たらな いこと、甲4には、「こども用食器」の直径(φ)及び高さ(H)以外の寸 法についての記載はなく(前記(2)イ)、甲76記載のAないしCの比率やA ´ないしE´の寸法の記載もないこと、甲4には、甲76の5枚目中欄の「R ごとの見え方の違い」の表の記載はないことに照らすと、甲4に接した当業\n者において、甲4から、上記1)ないし3)の事項を認識し、又は理解すること はできないから、原告の上記主張は、その前提において採用することができ ない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 減縮
>> ピックアップ対象
2022.06. 1
令和4(行ケ)10006 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年5月25日 知的財産高等裁判所
本件商標は、その構成文字に相応して「オメコ」の称呼を生じるものであり、\nこの点は当事者間にも争いがないところ、その称呼の語は、「大辞林 第四版」 (2019年 三省堂。乙12)に「俗に、女陰の称」を、「大辞泉 第二版 上巻」(2012年 小学館。乙13)に「女性性器の俗称」を、「国語大辞 典 新装版」(1988年 小学館。乙14)に「女陰の異名」を、「精選版 日本国語大辞典」(小学館。乙15)に「女陰の異名。また、男女の交合」を 意味するとされているものである一方、その称呼から異なる意味合いを直ちに 想起させる語は見当たらない。加えて、現に、本件商標は、ドメイン名を「om eco.buyshop.jp」とする原告の運営に係るウェブサイトのページ上部左上に、「変態高級腕時計」の文字と、女性器を模した、二重丸とその中心を縦断する 縦線及び円の外側の放射状の短い線で構成される円状図形と一体となって、ロ\nゴマーク様の図形を構成する一部として表\示されているほか(甲10の1ない し甲10の3)、このウェブサイトでは、原告の販売に係る腕時計として、上 記円状図形及び本件商標が付された腕時計の画像や(甲10の1ないし甲10 の3)、「パイパンマン」等の性的な意味合いを認識させる表示が付されたT\nシャツの画像等の商品画像が多数掲載されているのであるから(乙22ないし 25)、本件商標は、上記各辞典に掲載されたそのとおりの意味合いで使用さ れていると認められ、それ以外の意味合いのものと理解され得る余地はない。 そうすると、本件商標は、その称呼から、少なくとも需要者に女性器を連想、 想起させるものであるから、その構成自体が卑わい又は他人に不快な印象を与\nえるようなものであって、その余の点について検討するまでもなく、公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。したがって、本 件商標は、商標法4条1項7号に該当するものであり、商標登録を受けること ができないものに当たる。
2 原告の主張について
(1) 原告は、本件商標の称呼が女性器等を示す俗語であったとしても、本件商 標は欧文字で表記されているから、女性器等が連想、想起されることはない、\nあるいは、このような俗語は関西地方で用いられる方言、俗語であり、日本 の社会一般で理解されるものであるとはいえない旨主張する。しかしながら、 本件商標の綴りからは自然に女性器が連想、想起される称呼が生じ、それ以 外の称呼が自然と生じるものとはいい難いし、また、仮に、関西地方で用い られる方言、俗語であったとしても、関西地方で用いられているならば、周 知の用語というに十分である。そして、何より、原告自身が女性器等を連想、\n想起させるものとして本件商標を使用していることは、前記1において説示 したとおりであるから、欧文字で表記されていることや関西地方で用いられ\nる方言、俗語であることが女性器を連想、想起させることを何ら妨げるもの ではない。 したがって、原告の上記主張は、いずれにしても採用し得ない。なお、本 件商標と同一の称呼を生じさせる原告の商号が現時点で維持されていること は、商標法に従い商標登録の適否を判断する本件の結論を何ら左右しない。
(2)原告は、本件商標が用いられても、取引の実情からみて、被告補助参加人 の業務との間に誤認混同は生じないから、引用商標の信用等又は被告補助参 加人の業務上の信用を毀損させるおそれはない旨主張するが、本件商標は、 その構成自体から卑わい又は他人に不快な印象を与えるような文字であるか\nら、引用商標の信用等又は被告補助参加人の業務上の信用を毀損させている か否かの点は、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商 標であるとの判断を何ら左右しない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.05.31
令和3(ネ)10091 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 特許法102条2項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい て、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特 許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるために は、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関 係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、 妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵 害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定 するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害 者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存 在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。
イ これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一 審被告製品1〜3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジ ンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、 前記(1)のとおり、一審原告は、その株式の100%を間接的に保有するZimme r Inc.の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グ ループ会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用 して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Zimmer I nc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしてい るのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題と されている平成28年7月から平成31年3月までの期間、Zimmer Inc. の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行してい ると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおい ては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被 告製品1〜3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。 そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループの ために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することがで きる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益 を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記 のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に 係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許 法102条2項を適用することができるというべきである。
(3) 推定の覆滅について
特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と 同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解されるところ、一 審被告は、1)本件特許権を保有・管理するだけの一審原告の利益は何ら害されてい ないこと、2)競合する第三者の製品があること、3)固定プレートの選択をする医師 は、一審被告製品がなかったとするならば、他の一審被告の製品であるP−Pla teを選択していたことが確実であることから、推定が覆滅されるべきであると主 張する。
そこで検討するに、前記(1)で認定したジンマー・バイオメットグループの一審原 告製品に係る事業遂行の状況を踏まえると、本件特許権を第三者が侵害することに よって一審原告製品の売上げが減少して、ジンマー・バイオメットグループの利益 が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害 されたということができる。また、一審被告は、第三者の競合品の存在を指摘する ものの、本件全証拠によっても、それらが本件特許権の特徴を具備する競合品であ るのか、また、一審被告の指摘する競合品の存在が、一審被告製品が存在しなかっ たとした場合に一審原告製品の販売に影響するといえるかは必ずしも明らかではな い。さらに、一審被告製品が存在しないとした場合に、医師がそもそも一審被告製 品を販売していない一審被告の製品を選択すると認めるに足りる証拠はない。 そうすると、本件において特許法102条2項における推定を覆滅する事由があ ると認めることはできない。
(4) 損害額
ア 平成28年7月から平成31年3月までの被告製品1及び2の販売額が●● ●●●●●●●であること並びにその限界利益率が●●●であることについて当事 者間に争いがない。そうすると、特許法102条2項により、一審原告の損害額は、 ●●●●●●●●●と推定される。
イ 事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌すると、本件の 不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は、●●●●と認められる。
ウ 上記ア及びイの合計額は、454万4478円である。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.05.21
平成29(ワ)7391等 職務発明の対価請求 特許権 民事訴訟 令和4年3月24日 大阪地方裁判所
被告は、本件発明2−1を国内において自ら実施している。 前記(1(2)ア)のとおり、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」 (同条4項)とは、使用者等が当該発明を実施することによって得られる利益の全 体ではなく、その全体の額から通常実施権の実施によって得られる利益の額を控除 した残額(独占の利益)をいうと解されるところ、特許権者が自ら特許発明を実施 している場合の独占の利益は、使用者等が自ら発明を独占的に実施し、他社に当該 特許発明の実施を禁止したことに基づいて得られた利益に相当する売上額(超過売 上)と解される。この場合、相当の対価は、「対象商品(実施品)の売上合計額× 超過売上の割合×仮想実施料率×対象特許発明の貢献の程度×(1−被告の貢献割 合)×共同発明者間における原告の貢献割合」によって算定するのが相当である。 また、特許の登録前であっても、特許出願人は、出願公開後発明を実施した第三 者に対して一定の要件の下に補償金を請求することができること等を踏まえると、 出願公開以降の売上額には一定の独占的利益があると見るのが相当である。もっと も、出願公開から登録までの期間においては、登録されて排他的な独占権を有する か否かが未確定であることに鑑み、売上の2分の1を独占の利益の検討の基礎とす るのが相当である。
・・・
エ 超過売上の割合
(ア) 対象製品群2の販売による市場占有率の変化等
対象製品群2は、平成16年10月から被告の 200シーズン年度モデルとして 販売され、●(省略)● また、被告のルームエアコンの国内の出荷台数は、2003 冷凍年度から 200冷凍 年度にかけて増加し、国内4位から3位に上昇するだけでなく、1位及び2位との 出荷台数の差が縮小したことを踏まえれば、200冷凍年度においては、その市場 占有率が上昇したものと認められる(前記(2)キ(ウ))。このような被告の市場占有 率の上昇には、当該時期に被告の製造販売する●(省略)●対象製品群2の販売が 直接貢献していることがうかがわれる。 なお、原告は 2004 シーズン年度モデルによる被告の市場占有率の上昇等につい ても指摘するが、本件発明2−1は当該モデルでは実施されていないことから(弁 論の全趣旨)、当該モデルの市場占有率の変動と本件発明2−1との間に関連性は 認められない。
(イ) 本件発明2−1の技術的意義及び代替技術等
a 本件発明2−1は、ルームエアコン室内機に搭載される熱交換器の配置につ いて、前面熱交換器の設置角度 α を特定すると共に、クロスフローファンの翼の出 口角 β2 を特定することで、所定風量を得るのに必要なファンモータ入力や回転数 を低減することができ、省エネを図ることができる点にその技術的意義がある。ま た、設置角度 α を 65°以上とすることで、熱交換器からの水滴がファンへ流入して 室内ユニットの外部へ吹き出されること等を防止し、また、ユニットの奥行きをコ ンパクトにできるという効果もある(前記(1)ア(オ)【0024】)。
b もっとも、省エネ、ドレン水の確実な処理及び室内機ユニットのコンパクト 化という課題自体は本件発明2−1の出願以前から存在するものである。また、当 該課題に対して、熱交換器を逆 V 字状にすること、前面熱交換器と背面熱交換器と の連結部を送風ファンの中心軸よりも前面側に位置させ、かつ前面熱交換器の傾斜 を急な配置にすること、熱交換器を通過した空気がファンの翼に当たる際の空気の 流れを滑らかにし、空気流の剥離等を防ぐために、翼形状を変更することといった 着想やその技術自体も、従来から存在した(前記(2)ウ)。 したがって、本件発明2−1は、熱交換器の配置とクロスフローファンの翼形状 (出口角)の双方を、同時に、具体的な数値をもって特定したところに技術的な意 義があるといえる。
c また、ルームエアコンの省エネ性能の向上を図る技術には、室内機及び室外\n機それぞれを見ても、熱交換器、圧縮機、モータ、送風機等に係る種々の技術が存 在する。しかも、被告のほか、国内の競合他社であるパナソニック、ダイキン、東\n芝、日立等は、それぞれ、省エネのための独自の基本的な技術を有しており、● (省略)●被告以上又は同等の市場占有率を保持していたと認められる(上記(2) イ、キ(ウ)、ク(イ)及び(ウ))。 加えて、本件発明2−1は熱交換器の配置とクロスフローファンの翼形状を特定 するものであるから、それぞれ独自のユニット、熱交換器、ファン等の形状や配置 を工夫して製品化している競合他社において、本件発明2−1をそのまま実施する ことにより直ちに性能が向上するといった性質の技術であるとは思われない。\n
d 以上の事情を総合的に考慮すると、本件発明2−1に係る超過売上の割合は 50%と見るのが相当である。
オ 仮想実施料率
本件発明2−1に係る仮想実施料率を検討するにあたっても、上記エの事情は同 様に考慮されるべきである。 また、経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブック」 (平成22年8月31日発行。乙 A4)によれば、技術分類を「機関またはポンプ」 とする対象例(16件)では、平均ロイヤリティ料率 3.1%、標準偏差 1.4%、最大 値 5.5%、最小値 0.5%である。また、技術分類を「照明;加熱」とする対象例(1 6件)では、平均ロイヤリティ料率 3.9%、標準偏差 2.2%、最大値 9.5%、最小値 1.5%である。 ●(省略)●
以上の事情のほか、本件発明2−1がルームエアコン室内機における熱交換器の 配置とクロスフローファンの翼の出口角の数値を限定したものであり、このような 最適な数値を検討する行為自体は当業者が自ずと行うものであること等を踏まえる と、本件発明2−1の仮想実施料率は、3.5%とするのが相当である。
カ 対象特許発明の貢献の程度
(ア) 対象製品群2には、本件発明2−1のほか、●(省略)●特許が実施されて おり(乙 A10、乙 B27)、また、被告カタログ2)で訴求されている代表的な技術に\n関連する特許は、●(省略)●(乙 A35、乙 B59)。 このうち、被告のポキポキモータに係る技術は、従来のモータ以上にコイルを密 に巻き、それによりモータ効率を向上させるという基本的・汎用的な技術である点 で、室外機の圧縮機モータ及び●(省略)●それぞれ重要な技術といえる。
(イ) また、被告は、対象製品群2の販売に当たり、被告カタログ2)においてムー ブアイを大々的に取り上げると共に、そのほかにも脱臭機能、換気機能\、サプリメ ントエアー機能といった付加価値的な部分をも顧客に対し強く訴求している。当時、\n既にルームエアコンは家庭に広く普及し、省エネ等に係る技術も各社製品において 採用されていたと考えられることを踏まえると、付加価値的なものとはいえ、この ような他社製品と差別化を図る技術は消費者に対する訴求力を高め、対象製品群2 の売上に大きく貢献したものと見るのが相当である。もとより、本件発明2−1も、 熱交換器の配置を工夫することで室内機のコンパクト化といった訴求力のある効果 を実現し、また、同時にシロッコファンの翼形状の角度を数値限定することで省エ ネ効果等を実現していることから、対象製品群2の売上に貢献したと見られるもの の、その貢献の程度が他の技術と比較して特に顕著であったことまではうかがわれ ない。
(ウ) 以上の事情のほか、対象製品群2の売上高には、室内機のみならず室外機の 売上高も含まれること等を踏まえると、対象製品群2における本件発明2−1の貢 献の程度としては、1%と見るのが相当である。
キ 使用者の貢献割合
●(省略)●
さらに、対象製品群2の開発にあっては、熱交換器やクロスフローファンの翼形 状のみならず、被告カタログ2)で訴求されたものをはじめとする種々の開発項目や 試験項目があり、これをクリアして製品化に至ることは、被告の有する多くの蓄積 された技術や物的・人的な体制があってこそ可能になるといえる。\nこのほか、量産化及び販売も含めて被告が●(省略)●多額の費用を投入してい ること、長年にわたりルームエアコンを販売してきた被告及び被告ブランドの知名 度が対象製品群2の販売実績に大きく貢献していると見られることなどを踏まえる と、被告の貢献割合は 95%とみるのが相当である。
ク 共同発明者間における原告の貢献割合
本件発明2−1は、熱交換器の配置及びクロスフローファンの出口角の数値を限 定した点に意義があるところ、原告は、流体解析の技術を用いて、その数値解析に 中心的に寄与したことが認められる(前記(2)ア(イ))。 もっとも、発明当時、被告においても既に流体解析の技術及びこれを支援する装 置等が存在し(乙 A16、乙 B44)、●(省略)●これらの事情に加え、●(省略)●(弁論の全趣旨)、●(省略)●などを踏まえると、共同発明者間における原告の貢献割合は 60%とみるのが相当である。
ケ 小括
以上のとおり、対象製品群2の国内実施分に係る●(省略)●、超過売上の割合 50%、仮想実施料率 3.5%、対象特許発明の貢献割合 1%、被告の貢献割合 95%、共 同発明者間における原告の貢献割合 60%と認められる。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。 その結果、本件発明2−1に係る相当の対価の額は、●(省略)●となる。 ●(省略)●*50%*3.5%*1%*(100-95%)*60%=●(省略)● もっとも、被告は、本件各発明2について、既に特許を受ける権利の承継を受け た対価として原告に対し●(省略)●を支払済みであることから(前記2の2(7) ウ)、これを差し引くと●(省略)●となる。 したがって、原告は、被告に対し、昭和34年法35条3項に基づき、●(省略) ●の相当対価請求権を有する。
・・・
(ア) 協議の状況
前記(2)のとおり、被告は、●(省略)●従業員側の意見を聴取する機会も十分\nに設け、これに対応した行動を取ったものといってよい。 したがって、●(省略)●原告を含む従業者と被告との間で行われた協議の状況 に不合理な点は認められない。 これに対し、原告は、被告規程が知財部門により一方的に定められ、少なくとも 原告が協議に関与していないなどと主張する。しかし、上記のとおり、●(省略) ●の過程において、被告の従業員に対する説明及び従業員からの意見聴取は十分に\n行われたものと見られることに鑑みると、被告規程●(省略)●が知財部門により 一方的に定められたとの評価は当たらない。また、原告も●(省略)●質問等の機 会を現に与えられていたことから、原告が協議に関与していないということもでき ない。そもそも、使用者等と従業員等との協議として、個々の従業員が規程内容の 作成に個別的ないし直接的に関与する手続を担保することまでが求められていると は解されない。その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告 の主張は採用できない。
(イ) 開示の状況
前記(2)及び(3)のとおり、被告は、●(省略)● 以上のような状況を踏まえれば、●(省略)●被告規程の基準の開示の状況に不 合理な点は認められない。 これに対し、原告は、開示された基準では従業員が自ら実績補償金を算定できず、 また、●(省略)●労力を要するため、開示の状況は不合理であるなどと主張する。 しかし、被告において被告規程に係る基準が開示されていることに争いはない。 その上、被告では、●(省略)●が開示されていたのであるから、従業員は、これ と被告規程を照合すれば、実際の実績補償金の算定過程についても一定程度理解可 能であったとうかがわれる。それ以上に、●(省略)●についてまで、基準として\n開示しないことをもって不合理とはいえない。 また、●(省略)●基準の開示として不合理とすべきほどに特段の労力を要する と見るべき具体的な事情も見当たらない。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
(ウ) 意見聴取の状況
●(省略)●最終的に、原告と被告との間で意見等の相違は解消されなかったと 見られるものの、原告からの意見聴取の状況という観点からは、被告による原告か らの意見聴取は実質的に尽くされたといってよい状況にあり、被告の一連の対応に つき不合理ないし不誠実と評価すべきものはないというべきである。 これに対し、原告は、十分な意見聴取や説明がなされなかったとして縷々主張す\nる。しかし、その内容は、被告細則の解釈や発明に対する評価の程度に対する不満 を述べるものであって、被告における原告からの意見聴取の手続自体が不合理であ ることを基礎付けるものではない。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
・・・
(ウ) 以上のとおりの●(省略)●基準の策定に際して使用者等と従業員等との間 で行われた協議の状況、策定された当該基準の開示状況のほか、●(省略)●の定 めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると評価することはできな い。
これに対し、原告は、被告が●(省略)●対して真摯に回答しなかった旨などを 主張する。しかし、被告は、●(省略)●協議が不合理であるとはいえない。その 他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告の主張は採用できな い。 なお、原告は、●(省略)●被告規程における実績報奨金の算定基準の内容面及 びその適用の不合理性をも主張する。しかし、●(省略)●これをもって不合理と は必ずしも認められない。この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると、被告の原告に対する●(省略)●支払は、い ずれも不合理であるとは認められない。これに反する原告の主張は採用できない。 したがって、本件各発明3に係る相当の対価支払につき、平成16年法35条5 項は適用されないから、本件発明3−2−2に係る不法行為に基づく損害賠償請求 も含め、その余の争点について判断するまでもなく、同項に基づく原告の請求はい ずれも認められない。
2022.05.19
令和3(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年5月11日 知的財産高等裁判所
(3) 上記(1)イ及びウの「Reflective ... Film」との用語に加え、上記(1)エ及 び(2)のとおり通常光下では黒色であった商品サンプルがフラッシュ光下では肌色 様に見えることや弁論の全趣旨も併せ考慮すると、甲4に貼付された黒色の商品サ\nンプルは、「黒色の再帰反射フィルム」であると認めるのが相当である。 また、上記(1)ウの「従来の印刷手法に加え、溶剤及びUVインクジェットに対 応しています」との記載は、甲4の黒色の再帰反射フィルムに溶剤インクジェット 印刷を施すことが可能であることを意味するものと解され、溶剤インクジェット印\n刷が施されれば、黒色の再帰反射フィルムの上に印刷層が形成されることは明らか であるから、甲4には「溶剤インクジェット印刷を施すことにより印刷層を形成す ることができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されているといえる。
(4) そこで進んで、甲4に「溶剤インクジェット印刷を施すことにより透光性 の印刷層を形成することができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されているかに つき検討する。
ア 上記(1)ウのとおり、印刷層の形成に関し、甲4には「従来の印刷手法に加 え、溶剤及びUVインクジェットに対応しています」との記載があるのみであり、 溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限られるとの記載又は 示唆はみられない。
イ ここで、溶剤インクジェット印刷の意義等に関し、下記の各証拠には、それ ぞれ次の記載がある。
(ア) 甲18(全日本印刷工業組合連合会(教育・労務委員会)編「印刷技術」 (平成20年7月発行))
「カラー印刷では基本的にCMYKの4色によって原稿の色を再現している。こ の4色をプロセスセットインキと呼び、このうちCMYは透明インキとなっている ので刷り重ねで印刷した場合、下のインキの色が一緒になり2次色、3次色が発色 する。」
(イ) 甲19(高橋恭介監修「インクジェット技術と材料」(平成19年5月2 4日発行))
「インクの色剤としては染料、顔料を挙げることができる。・・・ 染料は媒体である水に可溶であり、分子状態でインク媒体中に存在している。個 々の分子が置かれた環境はほぼ同一であるため、吸収スペクトルは非常にシャープ であり、透明性の高い印刷物が得られる。・・・ 従来、インクジェットプリンタ用色材としては、上記特徴とインク設計が容易で あるということで、染料が用いられた。」
(ウ) 甲20(Janet Best 編「Colour design Theories and applications」
(2012年発行)) 「CMYK:印刷業界で画像の再現に使用される減法混色プロセスであって、純 度の高い透光性プロセスカラーインク(シアン、マゼンタ、イエロー及びブラック) が網点様に重ね刷りされて、様々な色及びトーンを表現する。」\n
(エ) 甲21(特開2012−242608号公報)
「【0033】ここで、第1の装飾層20aを形成する印刷インクとしては、光 透過性を有し、屋外使用にも耐えられる有機溶剤系のアクリル樹脂インク、例えば、 市販のエコソルインクMAXのESL3−CY、ESL3−MG、ESL3−YE、\nESL3−BK(それぞれローランド社製)を用いることが望ましい。 そして、かかる第1の装飾層20aを形成するには、例えば、インクジェットプ リンタなどのインクジェット装置に、印刷インクをセットし、これを微滴化して表\n面フィルム12h上の所定場所に、吹き付け処理して行なうことが好ましい。」
ウ 上記イによれば、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷においては、透 光性(透明性)を有するCMYのインクが広く用いられていたものと認められるか ら、仮に、本件出願日当時、溶剤インクジェット印刷において非透光性のインクが 用いられることがあったとしても、溶剤インクジェット印刷に対応しており、かつ、 前記アのとおり、溶剤インクジェット印刷が非透光性のインクを用いたものに限ら れるとの記載も示唆もみられない甲4の記載に接した当業者は、甲4は透光性を有 するインクを用いた溶剤インクジェット印刷に対応しているものと容易に理解した といえる。
エ 以上によると、甲4には「溶剤インクジェット印刷を施すことにより透光性 の印刷層を形成することができる黒色の再帰反射フィルム」が記載されていると認 められるから、甲4発明は、そのように認定するのが相当である。これと異なる本 件審決の認定は誤りである。
オ この点に関し、被告は、甲4発明の用途(トラックを始めとする車両に貼付\nされるステッカー等)に照らすと、甲4発明に透光性の印刷層を設けることは考え られないと主張する。確かに、前記(1)ウのとおり、甲4には消防自動車様の車両を撮影した写真が掲 載されているが、車両に貼付して用いる黒色の再帰反射フィルムの上に透光性の印\n刷層を形成すると甲4発明の目的が阻害されるものと認めるに足りる証拠はないし、 また、甲4には甲4発明の用途が車両に貼付して用いるステッカー等に限られると\nする記載も示唆もないから、被告の上記主張を採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2022.05.19
令和3(ネ)2608 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和4年5月13日 大阪高等裁判所
控訴人は、商標権者である控訴人が控訴人標章を付した本件商品につい て、その譲渡を受けた卸売業者等である被控訴人らが、梱包箱に被控訴人ら シールを貼付し、本件商品とともに梱包されていた控訴人説明書を被控訴人\nら説明書に差し替えた行為は、本件商標の出所表示機能\及び品質保証機能を\n積極的に毀損するものとして、商標の剥離抹消行為と評価し得る本件商標権 侵害に当たる旨主張するとともに、上記譲渡によって本件商標権が消尽する とみるべきではないとして原審の判断を非難する(前記第2の5(1))。
(2) 商標法の目的は、信用化体の対象となる商標が登録された場合に、その 登録商標を使用できる権利を商標権者に排他的に与え、商品又は役務の出所 の誤認ないし混同を抑止することにあり、商標権侵害は、指定商品又は指定 役務の同一類似の範囲内で、商標権者以外の者が、登録商標と同一又は類似 の商標を使用する場合に成立することが基本である(商標法25条、37 条)。すなわち、商標法は、登録商標の付された商品又は役務の出所が当該 商標権者であると特定できる関係を確立することによって当該商標の保護を 図っているということができる。 商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売 業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通さ せる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の 出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止する ことは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。した\nがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害 を構成するとは認められないというべきである。\n
(3) また、その点を措くとしても、後半期間における被控訴人らの行為(被 控訴人らの行為2)及び3)に関する。)は、以下のとおり、控訴人標章の剥離 抹消行為と評価し得る行為には当たらないと解される。
ア 前記第2の2で補正した上で引用した前提事実によれば、控訴人が被控 訴人らに納入した本件商品の梱包箱の外側にはそもそも控訴人標章は表示\nされていないから、被控訴人らが仕入れ後に貼付した被控訴人らシールに\nよって控訴人標章が覆い隠されたという事実はない。控訴人が被控訴人ら シール1)によって覆い隠されたのを問題としているのは、控訴人の屋号で あって、控訴人標章ではない。また、被控訴人らの行為によって、本件商 品本体に英文字で印字された「Roller Sticker」という標章(称呼及び観 念において控訴人標章と同一のもの)に何らかの変更が加えられたという 事実もない(本件商品の品質にも変更はない。)。
イ そうすると、控訴人標章の剥離抹消行為として問題となり得る行為は、 被控訴人フジホームが、控訴人から本件商品を仕入れた際に梱包箱に同梱 されていた控訴人説明書を被控訴人説明書に差し替えた行為のみ(被控訴 人ら行為2)に関する。)であるが、控訴人説明書は、取引によって納入さ れた本件商品の梱包箱の中に、本件商品の使用方法を説明する書面として、 本件商品に貼付等されずに単に同梱されていたものにすぎないから、本件\n商品に標章を付した(商標法2条3項1号)とはいえず、控訴人説明書が 取引書類(同項8号)に当たると認めるに足りる事情も窺われない。した がって、控訴人説明書に「ローラーステッカー使用説明書」との記載があ るのは、控訴人標章を商標として使用したものとは認められず、控訴人説 明書を差し替えたことが控訴人標章の剥離抹消行為と評価すべきものとは 認められない。
ウ 以上のとおり、後半期間における被控訴人らの行為は、そもそも控訴人 標章の剥離抹消行為と評価される行為には当たらないから、その余の点を 判断するまでもなく、商標の剥離抹消を理由として商標権侵害をいう控訴 人の主張は採用できない。 なお、被控訴人らの行為2)及び3)における本件商品について、控訴人が 本件商品本体に付した標章(称呼及び観念において控訴人標章と同一の もの)と、被控訴人らが梱包箱に付した被控訴人ら標章とが併存してい るとしても、控訴人から適法に本件商品を仕入れた被控訴人らが、再販 売業者としての出所を明らかにするため本件商品に併存して自らの標章 を付すことが一般的に禁止される理由もない。
◆判決本文
1審はこちら。
2022.05.13
令和3(ワ)23928 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年4月15日 東京地方裁判所
前記前提事実(1)のとおり、原告が撮影した原告写真1及び2は「写真の著 作物」(著作権法10条1項8号)に該当するから、原告は、原告写真1及 び2に係る同一性保持権を有するところ、前記前提事実(3)のとおり、被告は、 原告写真1の上下左右を正方形になるようにトリミングして被告写真1を、 原告写真2の上下左右を正方形になるようにトリミングして被告写真2を、 それぞれ作成したものである。 したがって、被告は、原告写真1及び2に係る原告の同一性保持権を侵害 したと認めるのが相当である。
(2) これに対して、被告は、原告写真1及び2の中央位置はそのままにし、イ ンスタグラムの仕様に合わせて正方形にトリミングしたものであり、原告写 真1及び2の創作性及び特徴を害したものではないし、「やむを得ないと認 められる改変」(著作権法20条2項4号)に該当すると主張する。 そこで検討するに、原告写真1及び2は、列車が川に架かる鉄橋を走行す る様子を、列車をほぼ中心に据え、周囲に霧のかかった川及び連なる山々を 配置し、列車と比較して周囲の川及び山を大きく写すような横長の構図で撮\n影されたものであり、これらの点について創作性を認めることができる。そ して、被告写真1及び2は、上記のような原告写真1及び2の上下左右をト リミングして正方形にし、それらに写し出された左右の山を大きく切り取っ たものである。そうすると、被告が被告写真1及び2を作成したことにより、 原告写真1及び2について、その著作者である原告の意に反し、上記のとお り創作性の認められる表現部分に実質的な改変が加えられたことは明らかで\nあって、これが原告写真1及び2の創作性及び特徴を害さないものというこ とはできない。 また、本件全証拠によっても、被告が被告のインスタグラム上のアカウン トにおいて掲載するために原告写真1及び2をトリミングすることについて、 正当な理由を基礎付ける事実は認められないから、被告による上記改変が 「やむを得ないと認められる改変」に該当するとは認められない。
・・・
前記前提事実(1)のとおり、原告が撮影した原告写真1及び2は「写真の著 作物」に該当するから、原告は、原告写真1及び2に係る氏名表示権を有す\nるところ、被告は、前記前提事実(3)のとおり、原告写真1及び2をそれぞれ トリミングして被告写真1及び2を作成した上、前記前提事実(4)のとおり、 被告のツイッター上のアカウントにおいて、原告の氏名を表示することなく\n被告写真1の掲載を含む本件投稿1をし、また、被告のインスタグラム上の アカウントにおいて、原告の氏名を表示することなく被告写真1及び2の掲\n載を含む本件投稿2及び3をしたものである。 したがって、被告は、原告写真1及びに2に係る原告の氏名表示権を侵害\nしたと認めるのが相当である。
(2) これに対して、被告は、原告写真1及び2には原告に著作権があることを 示す原告のウォーターマークの表示はなく、被告がこれを削除したものでは\nないし、被告写真1に記載された「B以下省略」は被告のアカウント名でも 本名でもないから、これによって被告写真1の著作権者が被告であると理解 されるとはいえないと主張する。 しかし、氏名表示権とは、「その著作物の公衆への提供若しくは提示に際\nし、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表\示し ないこととする権利」(著作権法19条1項)をいうところ、前記前提事実
(4)のとおり、被告写真1及び2の掲載を含む本件投稿1ないし3において、 原告の氏名は表示されていなかったものであり、原告写真1及び2に原告の\n氏名が記載されていなかったからといって、原告が、原告写真1及び2を公 衆に提示するに際し、自身の氏名を著作者名として表示しない意思を有して\nいたということはできず、本件全証拠によっても、そのような意思を有して いたとは認められない。
2022.05.12
令和3(ネ)10072 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年4月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記(1)の認定事実によれば、1)控訴人アンカー及び控訴人ジョウズは、 いずれも中国法人の中国アンカー社を中核企業とする国際的な企業グル ープ「Ankerグループ」の日本法人であり、控訴人ジョウズの全株 式は、中国アンカー社の完全子会社である POWER MOBILE LIFE、 LLC が 保有していること、2)控訴人ジョウズの設立当時(平成30年2月28 日)の代表取締役は、控訴人アンカーの代表\取締役と同一人(A)であ ったこと、3)控訴人ジョウズの本店所在地のオフィスの利用契約は、控 訴人アンカーが契約し、同年4月16日、控訴人ジョウズに契約上の地 位が譲渡されたものであり、かつ、利用契約上の利用者はA1名のみで あること、4)令和元年9月時点の控訴人ジョウズの従業員数は2名であ り、そのうちの1名のBは、平成30年4月から平成31年4月末まで 控訴人アンカーに在籍し、令和元年5月から控訴人ジョウズに在籍して いたこと、5)控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、控訴人ジョウズ設立 日の翌日の平成30年3月1日付けで、控訴人ジョウズが控訴人アンカ ーに対し、控訴人ジョウズの喫煙具製品の開発補助業務及びそれに付随 する一切の業務、喫煙具製品のマーケティング及びそれに付随する一切 の業務、会計事務及び経営管理に関する一切の業務、その他控訴人ジョ ウズと控訴人アンカーの協議の上決定された業務の全部又は一部を委託 する旨の本件業務委託契約を締結したこと、6)被告製品は、同年6月以 降、控訴人ジョウズのウェブサイトで販売が開始され、同年11月当時 には、アマゾンサイト及び楽天市場のサイトで、控訴人ジョウズを販売 者として販売されており、また、被告製品の輸入手続は、控訴人ジョウ ズを輸入者として行われたこと(乙14、37)、7)アマゾンサイトでは、 被告商品について、「米国・日本・欧州のEC市場において、スマートフ ォン・タブレット関連製品でトップクラスの販売実績を誇る『Anke r』のサポートのもと、精密かつ均一な温度管理と・・・最適な加熱環境を 作り出し、たばこ本来の香りと味を忠実に再現」などと紹介され(甲4 の1、5の1)、また、Ankerグループのオフィシャルストアの海外 のウェブサイトでは、被告製品が「Anker Jouz 20」など として販売されていたこと(甲14)、8)被告製品1及び2の記者発表に\n関する同年6月20日付け記事等(甲13の1ないし4)には、「Ank erグループが技術的にサポートしたことから、アンカー・ジャパンの A社長がジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと掲載され、\n被告製品3の記者発表に関する2019年(平成31年)4月9日付け\n記事(甲32)には、当時控訴人アンカーの従業員であったBが「ジョ ウズ・ジャパン株式会社事業戦略本部マネジャー」との肩書きでプレゼ ンテーションを行ったことが掲載されたことが認められる。
上記認定の控訴人ジョウズと控訴人アンカーの人的及び物的な結合関 係(1)ないし4))、控訴人ジョウズの控訴人アンカーに対する本件業務委 託契約に基づく委託業務の範囲が控訴人ジョウズの業務全般にわたって いること(5))、被告製品の広告宣伝の態様(7)、8))その他前記(1)認定 の諸事情を総合考慮すると、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告 製品の販売等に関し、緊密な一体関係があるものと認められるから、被 告製品の販売及びその輸入手続が控訴人ジョウズ名義で行われていたこ と(6))を勘案しても、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、平成30 年6月以降、共同して被告製品の販売等を行っていたものと認めるのが 相当である。
そして、被告製品は、被告方法の使用に用いる物であって、本件発明 1による「課題の解決に不可欠なもの」に該当することは、前記のとお りであるところ、控訴人らは、遅くとも、本件仮処分命令の送達により、 本件発明1が特許発明であること及び被告製品が方法の発明である本件 発明1の実施に用いられることを知ったものと認められるから、控訴人 らによる被告製品の上記販売等の行為は、本件発明2に係る本件特許権 の侵害(直接侵害)に該当するとともに、本件発明1に係る本件特許権 の間接侵害(特許法101条5号)に該当するものと認められる。 したがって、控訴人らについて本件特許権侵害の共同不法行為が成立 するものと認められる。
・・・
そこで検討するに、本件業務委託契約書には、控訴人ジョウズは控訴人 アンカーに対し業務委託料として毎月100万円に消費税相当額を加算 した額を支払う旨の条項(5条1項)があり、同条項によれば、控訴人ア ンカーの業務委託料は固定額であるといえるが、一方で、前記(2)認定のと おり、控訴人ジョウズと控訴人アンカーは、被告製品の販売等に関し、緊 密な一体関係があるものと認められるから、控訴人アンカーの業務委託料 が固定額であるからといって、控訴人アンカーが被告製品の販売等に関す る業務を一切行っていないということはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和2(ワ)4332
関連事件です。
◆令和1(行ケ)10174
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.05.12
令和3(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年4月28日 知的財産高等裁判所
ア 特許法17条の2第5項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、 その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正(同条1項ただし 書4号)は、同条5項1号から4号までのいずれかの事項を目的とするもの に限ると規定し、同項2号は、「特許請求の範囲の減縮」(同法36条5項の 規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するも のであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該 請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同 一であるものに限る。)と規定している。同法17条の2第5項の趣旨は、拒 絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正 について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に 制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにある ものと解される。このような同項の趣旨及び同項2号の文言に照らすと、補 正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、 補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあること が必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求 項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該 請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。 また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新 しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を 限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当す るものと解される。 以上を前提に、補正事項1が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの に該当するかどうかについて判断する。
・・・
ア 前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1 0と対応関係にあることが認められる。 しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項8は、本件補 正前の請求項10の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記スト ラップの第1の部分に備えられた1個以上の第1接点と、前記ストラップの 第2の部分に備えられた1個以上の第2接点とを備えるか、あるいは、第1 接点および第2接点と通信可能であり、第1接点のうちの1個以上が、第2\n接点のうちの1個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じら\nれるか固定されたときに、第1接点の1個以上および第2接点の1個以上の 間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、\n第1接点と第2接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサ によって測定された前記測定回路の少なくとも1つの電気特性に基づいて、 前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するよ うに構成されている」との構\成を削除した請求項であるところ、この削除に よって、本件補正前の請求項10の発明特定事項を限定したものと認めるこ とはできず、かえって、本件補正前の請求項10に係る発明を上位概念化し たものといえるから、補正事項1は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする ものと認められない。
イ これに対し原告は、1)本件補正後の請求項8は、本件補正後の請求項1な いし7に従属し、本件補正前の請求項1に内的付加に相当する追加的要件を 規定したものであるから、本件補正前の請求項1に記載した発明を特定する ために必要な事項を限定するものである、2)本件拒絶理由通知では、本件補 正前の請求項1について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理 由の指摘はなく、本件補正前の請求項1に特許性が認められていることから すると、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1に対する従前の審 査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項1 についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが\n可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を\n生じさせないことも明らかである、3)厳密には、本件補正後の請求項8は、 本件補正前の請求項1と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに 準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項1は、既にされた審査結 果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法17条の2第 5項の制度趣旨に反するものではなく、同項2号が許容する増項補正に相当 するから、本件補正前の請求項1との関係で「特許請求の範囲の減縮」(同号) を目的とするものに該当する旨主張する。
しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項8は、本 件補正前の請求項1と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、 これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この 点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。 また、前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の 請求項10の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件に\nおいては、本件補正前の請求項10の発明特定事項から上記構成を削除した\n請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかが われず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後 の請求項8は、本件補正前の請求項1に対する従前の審査内容に沿って特許 性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の 上記主張は、その前提を欠くものである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 限定的減縮
>> ピックアップ対象
2022.05. 5
平成30(ネ)10034 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記の各種実験結果によると、被告製品は、長時間の塩水噴霧試験(乙 14実験)、試験紙を用いた湿気の流入実験(乙19実験、乙20実験) の結果からすると、端部部材だけで外部雰囲気(湿気や水等の流体物) の流入を遮断するものとはいえないが、同じ場所に10数滴の液体を滴 下したり(乙15実験の第2実験)、連続して液体を注入したり(甲4 9実験の実験2)、液体を滴下後に強い衝撃を加える(乙15実験の第 3実験、甲49実験の実験3)といった条件がない限り、少量の水滴を 滴下した実験では、端部部材だけでも液体の流入は抑制されており(甲 33実験、甲49実験の実験1)、また、湿気の流入も短時間であれば 抑制されている(甲58実験の試験1及び試験2)ことからすると、被 告製品の端部部材は外部雰囲気(湿気や水等)の進入を抑制するものと いえる(なお、乙15実験の第1実験は、被告製品の端部部材及びOリ ングのみならず弁本体側のOリングも外しており、甲50実験の試験結 果からすると、上記認定を左右するものではなく、また、乙16実験は、 圧縮機の取付孔側面に穴を穿設しており、実験条件の前提が異なるため、 上記認定を左右するものではない。)。
また、乙1実験、乙14実験、甲49実験、甲58実験、乙19実験 及び乙20実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材(Oリング) を備えた被告製品においては、外部雰囲気(湿気や水等)の流入が完全 に抑制されていることが認められる。 そうすると、被告製品は、端部部材(H)をボディ の上部側の開口部 に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材 の構\n成を備えることにより、ボディ と取付孔の間を密封して外部雰囲気の 流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は、構成要\n件B6の「『密封』嵌合」の文言も充足する。 したがって、被告製品は、構成要件B6を充足する。\n
・・・
引用に係る原判決第3の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 のと おり、被告製品の構成につき、控訴人は、原判決別紙被告製品目録(原告)\n(以下「原告作成目録」という。)記載のとおりであると、被控訴人は、 同被告製品目録(被告)(以下「被告作成目録」という。)記載のとおり であるとそれぞれ主張する。原告作成目録の写真2と被告作成目録の写真 1がそれぞれ被告製品の外観形状を、原告作成目録の図1と被告作成目録 の写真2がそれぞれ同内部構造を明らかにするものであるところ、これら\nを対比すると、被告製品の構成部材の名称や配置についてはほぼ争いがな\nく、争いがあるのは、ソレノイドと弁本体の境界をどの部分と位置付ける\nかに関してのみであり、この点に関する当事者双方の主張は、上記原判決 第3の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 及び のとおりである。 そこで、原告作成目録の図1と被告作成目録の写真2を見ると、いずれ においても構成要件B8の「プランジャ」は「プランジャ 」、「バルブ」 は「弁本体(V)」、「ロッド」は「作動ロッド 」にそれぞれ当たり、「作 動ロッド 」は電磁コイル を含むボディ やシール部材 より下部まで 上下に可動する構成となっている。そして、前記アにおいて説示したとお\nり、ロッドは、本件発明におけるソレノイドの一部を構\成するものといえ るから、本件発明における「ソレノイド」部は、控訴人が主張するとおり、\n原告作成目録の図1の「ソレノイド 」の矢印で示される範囲までを指す ものと理解するのが相当である。そうすると、同図1のとおり、被告製品 におけるシール部材 は、本件発明との対比におけるソレノイド の部分 (ソレノイド の下端側である弁本体(V)側)の外周に設けられたもので あり、弁本体(V)からの流体の進入を防止するものであるといえる。
・・・
被告製品は、構成要件B6及びCを充足するものであり、その他の構\成要 件の充足性については引用に係る原判決の第2の2 のとおりであるから、 争点2(均等論)について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属 するものである。
・・・
被告製品の実施料率について判断する。 甲79報告書によれば、日本国内で特許出願を行った国内企業・団体 のうち上位となっている企業・団体(対象2031件)及び株式会社帝 国データバンク保有データ信用調査報告書ファイル(約143万社収録) の中からライセンス契約を実施していると判断できる企業(対象975 件)につき、重複データを削除した合計3006件を調査対象とし、平 成21年11月5日から平成22年2月15日までを調査対象期間とし て、技術分類別ロイヤルティ率のアンケート調査を実施した結果(有効 回答は563件)によると、本件発明に最も近い技術分野である「精密 機械」のロイヤルティ率は、最大値9.5%、最小値0.5%、平均値 3.5%であった(同報告書52頁)ことが認められる。また、同報告 書によると、実施料の決定要因の重要度としては、1)当事者におけるラ イセンスの必要性、2)ライセンス対象(特許権の評価)の重要度が高い ことが挙げられている。
なお、控訴人は、前記第2の4 ウ【控訴人の主張】 のとおり、平 成4年度から平成10年までのデータによる実施料率〔第5版〕データ や平成10年3月30日言渡しの別件判決の説示を基にした主張もする が、平成27年から平成30年までの間の実施料率を問題とする本件で は参考とならず、採用の限りではない。
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合すると、本件 発明は、「ソレノイド」を備えた制御弁の発明であるが、その特徴的部\n分は、1)アッパーブレードの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を 塞ぐ端部部材と、2)取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材の 2つの構成を採用したことにあり、これらの構\成によって、外部雰囲気 (湿気や水等の流体)の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上\nさせるとともに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決め ができ、ボルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向 上するという効果を奏するものである。 これに対し、相手方ハウジング部材に取付孔を設けてこの部分に容量 制御弁を挿入するという技術は、本件発明の出願時には公知の技術であ る(乙8、9)。また、シール部材の配置については、原告製品2のよ うに、取付孔と端部部材の間のシール部材を設けることなく、腐食防止 のために鉄系材料にメッキを施して可変容量制御弁の耐久性を保つ代替 技術(従来技術。本件明細書の【0011】)があることから、ソレノ\nイドの耐食性の向上という観点からいえば、当事者のライセンスの必要 性の程度が高いとはいえず、特許としての重要度も高いとはいえない。 そして、被控訴人が●●●社向けに作成した、原告製品2との比較を 含む被告製品のプレゼンテーション資料(乙25)には、重要設計項目 として、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が 挙げられているように、弁本体の機能や動作性等が重視され、本件発明\nの上記特徴的部分については何ら言及されていないから、被告製品にお ける本件発明の実施の程度及びその価値は相対的に低いと言わざるを得 ない。
以上のような本件各事情を総合すると、前記 のとおり、控訴人と被 控訴人は、可変容量制御弁の分野では国際的にシェアを分かち合う競業 関係にあるといった事情を考慮しても、被告製品における本件特許の実 施料率は2%程度であると認めるのが相当である。 ウ ところで、前記 アのとおり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の共 有関係にあり、その持分割合について両社で特段の合意がされたと認める に足りないから、民法250条により共有持分は相等しい割合に推定され る。 そうすると、特許法102条3項による損害は、以下の計算式のとおり、 ●●●●●円であると認定するのが相当である。
[計算式] ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
特許法102条1項による損害について
・・・
c 原告製品2の限界利益額に関する覆滅事由について
前記3 イ のとおり、本件発明は、「ソレノイド」を備えた制御\n弁の発明であるが、その特徴的部分は、1)アッパープレートの外側で 取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材と、 2)取付孔と端部部材の間に配置されるシール部材の2つの構成を採用\nしたことにあり、これらの構成によって、外部雰囲気(湿気や水等の\n流体)の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上させるととも\nに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決めができ、ボ ルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向上すると いう効果を奏するものである。
前記 ウ のとおり、原告製品2は、取付性の向上及び端部部材に よる外部雰囲気(湿気や水等の流体)の進入の抑制といった本件発明 の作用効果を備えているといえるが、アッパープレードの外側で取付 孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備え ている(上記1)を備える。)ものの、端部部材と取付孔との間のシー ル部材(Oリング)を備えておらず(上記2)を備えておらず)、腐食 防止のために鉄系材料にメッキを施している。また、原告製品2は、 自動車に搭載するソレノイドを有する可変容量コンプレッサ制御弁で\nある以上、自動車メーカーとしては、外部雰囲気の進入の抑制という よりは、原告製品2の制御弁としての機能及び動作性に最も着目する\nものといえる。 このように、原告製品2は、本件発明の従来技術の課題とされてい る、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであるこ\nとや、原告製品2は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御 弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、\n原告製品2の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利 益と認めるのは相当ではないところ、原告製品2が備える機能等や顧\n客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利 益の全額から95%の覆滅を認めるのが相当である。
・・・
エ 控訴人が販売することができないとする事情
特許法102条1項1号に規定するところの侵害品の譲渡数量の全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少と相当因果関係を阻害する 事情であり、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存 在すること(市場の非同一性)、2)市場における競合品の存在、3)侵害者 の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、4)侵害品及び特許権者の製品の機 能(機能\、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在すること等の事 情がこれに該当するというべきである(前掲知財高裁大合議判決)。 以下これを前提として検討する。
前記第2の4 ア【被控訴人の主張】 aのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社の前身である●●●社及 び同社が買収した●社と被控訴人との間では、長年の取引関係があり、 被控訴人は、こうした取引関係を通じて構築された信頼関係に基づいて、\n●●●社との間で年間●●●●個に及ぶ被告製品の取引を行ってきたが、 控訴人は、●●●社の事業領域については何らの商圏を有していなかっ たのであるから、容量制御弁を年間●●●●個生産する能力があるとし\nても、せいぜい従前●●●社に納入していた程度の数量である●●万個 程度の数量しか販売することができなかったというべきである旨主張す る。
確かに、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社及び●社、●● ●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等の点で表彰を受\nけるなど、一定の信頼関係を築いてきたこと(乙36ないし40)は認 められるものの、前記 カ及びキのとおり、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●、こうした事情に照らせば、原告製品2 について本件侵害期間より前の期間に納入していた数量の限度でしか 販売することができなかったとはいえないから、被控訴人の上記主張は 理由がない。
前記第2の4 ア【被控訴人の主張】 bのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社は、防水手段についてメ ッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては 全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控 訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換する ことは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人が原告製品\n2を納入することができるというものではない旨主張する。 しかし、「販売することができない事情」で考慮されるべき事情は、 本件侵害期間中に原告製品2を被告製品の販売個数では販売することが できなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記の ような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由 がない。
前記第2の4 ア【被控訴人の主張】 cないしeのとおり、被控訴 人は、「販売することができない事情」として、●●●社の購入動機や 信頼関係の存否等につき主張する。 そこで、検討するに、前記 キによれば、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●被告製品を選択した理由の1つとして価格面を挙げている ことが認められる。実際、控訴人の担当部長が作成した報告書(甲67) の添付資料によると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●ことが認められる。被告製品が原告製品2と比 較して価格面で有利であったという点は、本件侵害期間中における原告 製品2の販売個数に少なからず影響する事情であるということができる。 また、前記 のとおり、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社 及び●社、●●●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等 の点で表彰を受けるなど、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係\nを築いてきており、実際のところ、●●●社が原告製品2から被告製品 に切り替えた理由の1つとして、被控訴人のサポート態勢等を挙げてい る。被控訴人が被告製品の販売個数を順調に維持することができた背景 には、こうした事情が影響しているものと認められるから、被控訴人と ●●●社との信頼関係の構築は、本件侵害期間中における原告製品2の\n販売個数に影響する事情であるといえる。 さらに、証拠(乙25、32、48)によれば、被控訴人は、原告製 品2と被告製品の起動性に関する対比実験を提示し(乙25)、●●● 社の仕様等に関する要望を受けて改良し、●●●社は、被告製品の制御 弁としての性能面を評価して被告製品を採用したことが認められるから、\nこうした事情は、本件侵害期間中において、被告製品の販売実績に相当 する原告製品2を販売し得たことを阻害する事情であるといえる。 以上で指摘した事情を総合考慮すると、侵害品である被告製品の譲渡 数量を控訴人が販売することができない事情に相当する数量は、譲渡数 量全体の2割であると認めるのが相当である。
・・・
なお、共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めを した場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をす ることができる(特許法73条2項。なお、本件では、控訴人が●●●● ●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠 はない。)ところ、特許法102条1項により算定される損害については、 侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなけ れば販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出さ れる額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲 渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情にも当たらないから、後記の同条2項による損害の推定における場合と 異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。
・・・
キ 特許法102条1項2号による実施料相当額ついて
前記エ のとおり、特許法102条1項1号の「その全部又は一部に相 当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができない とする事情」としては、侵害品である被告製品と原告製品2の価格差、被 控訴人によるサポート面や協力態勢の面で●●●社との間との一定の信 頼関係の構築、被告製品と原告製品2の性能\面の差異といった事情がある と認められる。
ところで、特許法102条1項2号は、括弧書で「特許権者・・・が、当該 特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許 諾・・・をし得たと認められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧 書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認めら れないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないこと を規定するものであると解される。 これを前提として本件についてみると、特許法102条1項1号に規定 する特定数量に該当するとされた事情は、上記のとおりであるところ、被 告製品と原告製品2の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被\n控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められな いが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前 提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセン スをし得たのに、その機会を失ったものといえる。 これらの事情を総合考慮すると、特定数量2割のうちライセンスの機会 を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の1割とするのが 相当である。
また、前記 アのとおり、本件侵害期間中の被告製品の1個当たりの販 売価格は●●●●●●●円(本件侵害期間の総販売金額●●●●●●●● ●●●●●●●円を、同期間における総製造数●●●●●●●●個で割っ た額(乙23参照)。)であり、前記 イのとおり、被告製品の実施料率 は2%程度とするのが相当であり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の 共有関係にあることも前記認定事実のとおりである。 以上を前提とすると、特許法102条1項2号により算定される控訴人 の損害額は268万円と認められる。
・・・
特許法102条2項による損害について
ア 覆滅事由について
本件侵害期間中における月別の被告製品の生産個数及び売上高は当事者 間に争いがないが、控除すべき経費の範囲及びその額について争いがある。 ところで、特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵 害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事 情がこれに当たると解され、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様等に 相違があること(市場の非同一性)、2)市場における競合品の存在、3)侵 害者の営業努力、4)侵害品の性能(機能\、デザイン等特許発明以外の特徴) 等の事情がこれに当たり、また、特許発明が侵害品の一部分のみに実施さ れている場合には、この点も、推定覆滅の事情として考慮することができ るが、特許発明が侵害品の一部分のみに実施されていることから直ちに上 記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の 侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的 に考慮して決するのが相当である(知財高裁令和元年6月7日大合議判 決・判例時報2430号34頁以下参照)。 控訴人は、特許法102条2項による損害の算定に当たり、覆滅事由は ないと主張しているところ、被控訴人は、1項ただし書と同様の事由、す なわち、1)●●●社における事情、2)代替品の納入が可能であること、3) 原告製品2と被告製品の性能に本件発明以外に相違があること、4)被告製 品が原告製品2と比較して低価格であること、5)被控訴人の市場開発努力、 営業努力、販売力の事情を指摘して、覆滅事由を主張するので、この点に つき、まず検討を加える。
前記 エで説示したのと同様に、●●●社が原告製品2の供給を打ち切 って被告製品を採用したのは、被告製品が原告製品2と比較して価格面で 有利であったこと、被控訴人は、●●●社及びその前身の●●●社(●● ●社が買収した●社を含む。)と長年取引関係にあって信頼関係を醸成し ており、被告製品の販売個数を順調に伸ばしてきたのはこうした事情が背 景にあるものと推認されること、被控訴人は、原告製品2と被告製品の起 動性に関する対比実験を提示し、●●●社の仕様等の要望を受けて改良し たことにより、被告製品の採用に至ったものと認められる。
こうした被告製品の価格面での優位性、被控訴人の企業努力等の事情に 加えて、被告製品における本件発明が実施されている部分の位置付け、本 件発明の顧客吸引力等の事情についてみると、被告製品は容量制御弁であ り、ソレノイドの耐食性や取付容易性といった本件発明の特徴的部分もさ\nることながら、弁本体の機能がむしろ重要であり(被控訴人が●●●社向\nけに作成した被告製品のプレゼンテーション資料(乙25)には、本件発 明の特徴的部分については何ら触れるところはないことは既に説示したと おりである。)、また、前記 イ のとおり、相手側ハウジング部材に取 付孔を設けてこの部分に容量制御弁を挿入するという技術は、本件発明の 出願時には公知の技術であり、密封構造に関しても、容量制御弁の高耐食\n性については、鉄製材料をメッキ処理するといった従来技術(代替技術) が存在していたことからすると、被告製品における本件発明の位置付けは 重要なものとはいえず、顧客吸引力も低いものと言わざるを得ない。 被控訴人の主張する覆滅事情は上記の限度で理由があり、これらの事情 を総合考慮すると、覆滅割合は9割とするのが相当である。
イ 本件特許が共有であることについて
本件特許権は、控訴人及び●●●●●●の共有に係るものであり、前 記 オで説示したとおり、●●●●●●は、少なくとも本件侵害期間中 において本件特許権を実施していない。 ところで、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定 めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施 をすることができる(特許法73条2項)。本件では、控訴人が●●● ●●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証 拠はないから、本件特許権の共有者である控訴人は、共有持分割合に応 じて特許法102条2項により推定される損害の按分割合に応じた損害 賠償を請求することができるにすぎない旨の被控訴人の主張は理由がな い。
他方で、実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず 請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施してい ない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法102 条3項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があ るところ、仮に、同条2項により推定される全額を共有に係る特許権を 実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利 益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る 特許権を実施する共有者が同条2項に基づいて侵害者が得た利益を損害 として請求するときは、同条3項に基づいて推定される共有に係る特許 権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、 侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条2項に より推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその 立証責任を負うというべきである。
次に、前記第2の4 イ【控訴人の主張】 のとおり、控訴人は、● ●●●●●が特許法102条3項に基づく損害賠償請求権について控訴 人が消滅時効を援用することにより、被控訴人は、控訴人に対して●● ●●●●の被控訴人に対する実施相当額を控除すべき旨を主張すること ができない旨主張する。 しかし、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、●●●●●● の被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分 であり、可分債権である●●●●●●の損害賠償請求権が時効により消 滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰 属したかのように控訴人がこれを行使することができるわけではないか ら、控訴人が●●●●●●の被控訴人に対して有する損害賠償請求権を 援用することができる正当な利益を有する者ではなく、控訴人の上記主 張は明らかに失当である。 もっとも、●●●●●●の特許法102条3項に基づく損害賠償請求 権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用するこ とにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重 払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリ スクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害 により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当 とはいえないというべきである。
ウ 損害額の算定
前記アのとおり、特許法102条2項に基づき、被控訴人が特許権侵害 により受けた利益の額を算定するに当たり、控除すべき経費については前 記第2の4 イ のとおり当事者間に争いがあり、仮に、被控訴人が主張 するところの覆滅事由を考慮せずに控訴人が請求する●●●●●●●● ●●●円を前提としたとしても、前記アの覆滅割合(約90%)分を控除 すると、●●●●●円である。そうすると、前記イ のとおり、●●●● ●●の特許法102条3項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅し ている場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する 余地があるものの、このような場合を仮定しても、特許法102条2項に より算定される損害額は、上記●●●●●円を上回ることはない。
小括
以上によれば、特許法102条1項による損害額は●●●●●円であり、 同条2項による損害額は●●●●●円を上回ることはなく、同条3項による 損害額は●●●●●円であるから、特許法102条により算定される損害額 は●●●●●円をもって相当と認める。 また、控訴人は、本件において弁護士及び弁理士に委任して訴訟を遂行し ているところ、被控訴人による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用及び弁理士費用は、本件事案の性質及び内容、認容額、本件事案の難易 度等を考慮すると、●●●●●円とするのが相当である。 そうすると、本件特許権侵害による損害額は8920万円となる。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成29年(ワ)3569号
「密封嵌合」とは,「ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもた\nらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度に,端部材が取付孔に対してぴっちり
と封をするように機械部品がはまり合う関係」を意味すると解されるところ,Oリン
グ(シール部材(13))を外した被告製品が,取付孔内部への水分の進入を抑制する効果
があるとは認められないのであるから,被告製品の端部材(H)が取付孔に「密封嵌合」
しているとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告製品は,構成要件B6の「該アッパープレートの外側で前記取付\n孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材」に係る構成を\n有しない。そうすると,被告製品は,その余の構成要件を検討するまでもなく,本件\n発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.05. 5
令和1(ワ)34096 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年3月18日 東京地方裁判所
そこで、前記1(結合商標の類否の判断基準)に基づき本件商標1と被告 標章I)の類否を検討するに、被告標章I)は、暖簾を模した図案の上に2段書 きされた文字を記載しており、図案と文字との結合商標であるといえる。そ して、図案部分についてみると、現実の暖簾には文字が記載されることも少 なくないという実情を踏まえると、単なる背景や文字枠として認識されるも のであり、図案部分自体には、出所を識別する機能があるとはいえない。\n他方、被告標章I)の文字部分についてみると、2段書きされており、各段 の文字を結合したものであるといえるところ、全体的に見て、上段の「宗右 衛門町趣味のお好み焼」が下段の「ぼてぢゅう総本家」に対し、小さい文字 で付されたものであることからすれば、その内容に照らしても、需要者は、 上段部分が、下段部分の説明書きであると理解するといえるから、上段部分 には出所を識別する機能があるとはいえない。\nそして、被告標章I)の下段の文字部分についてみると、「ぼてぢゅう」と 「総本家」とを結合したものであるといえるところ、前者は、お好み焼き店 のために創作された極めて特徴的な造語であるのに対し、後者は、「おおも との本家」を意味する一般的な日本語であって(甲28)、その前後に接続 する語句がある場合には、その語句に関連する「総本家」であると理解され るのが通常であるから、下段の文字部分中「総本家」の文字部分から出所識 別標識としての称呼、観念が生ずるものとはいえない。そうすると、「ぼて ぢゅう」の文字部分が、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として 強く支配的な印象を与えるものと認めるのが相当である。
(3) したがって、被告標章I)は、その構成中の「ぼてぢゅう」の文字部分を抽\n出し、この部分だけを本件商標1と比較して商標そのものの類否を判断する ことが許されるというべきである。そして、被告標章I)は、筆書きによる平 仮名「ぼてぢゅう」を同大同間隔に左横書きした外観を有するのに対し、本 件商標1は、別紙商標目録記載1のとおり、筆書きの「ぼてぢゅう」の文字 を同大同間隔で左横書きにした外観を有するのであるから、両者は、その外 観において類似するものであり、両者の称呼及び観念が同一であることも明 らかである。以上によれば、本件商標1と被告標章I)とは、類似するものと認めるのが 相当である。
(4) これに対し、被告は、「宗右衛門町」が著名であり、「趣味」が特徴的な 言葉であることを理由として、出所識別機能を有すると主張するが、「宗右\n衛門町趣味のお好み焼」という部分は、地理的名称、商品の性質、商品の種 類を示すものと理解されるのであるから、「ぼてぢゅう」が強く支配的な印 象を与えるという上記認定を左右するものとはいえない。 また、被告は、「総本家」が出所識別機能を有しないとする根拠は存在せ\nず、被告標章I)の2段の文字部分の1段に記載され、まとまりのある「ぼて ぢゅう総本家」という9音を分離観察する理由もないなどと主張する。しか し、「総本家」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生ずるものと はいえないことは、上記において説示したとおりである。のみならず、「ぼ てぢゅう」の5字は、「総本家」の3字に比し、大きく書かれ、視覚的にも それ自体十分区別し得る上、前者の文言は、後者の文言に対し、強く支配的\nな印象を与えるものといえる。これらの事情を踏まえると、「ぼてぢゅう」 と「総本家」とを分離して観察することが、取引上不自然であると思われる ほど不可分的に結合しているものともいえないのであるから、被告の主張は、 上記結論を左右するものとはいえない。
・・・
商標法38条2項は、民法の原則の下では、商標権侵害によって商標権者 が被った損害の賠償を求めるためには、商標権者において、損害の発生及び 額、これと商標権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならな いところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされ ないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利 益を受けているときは、その利益の額を商標権者の損害額と推定するとして、 立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、商標権者に侵害者による 商標権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在 する場合には、商標法38条2項の適用が認められると解すべきである。 これを本件についてみると、証拠(甲81ないし83)及び弁論の全趣旨 によれば、原告らの店舗は、外食市場が伸び悩む現状を踏まえ、コンビニや スーパーの弁当や惣菜を中心として着実に成長しているいわゆる中食市場に 進出することとし、平成29年11月又は12月以降、焼きそばやお好み焼 き等のテイクアウト販売及びデリバリー販売の事業を展開していることが認 められる。そうすると、原告らの事業に係る焼きそばやお好み焼き等の商品 が被告商品1)及び4)と同じ種類の商品であることを踏まえると、被告商品1) 及び4)が一定の調理を要することを考慮しても、少なくとも中食市場におけ る原告らの事業は、被告商品1)及び4)を販売等する被告事業と競業関係にあ るものといえる。 したがって、原告らに、被告による商標権侵害行為がなかったならば利益 が得られたであろうという事情が存在することが認められ、商標法38条2 項の適用が認められる。
・・・
商標法38条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害 者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することにより その製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益 の額であり、その主張立証責任は商標権者側にあるものと解すべきである。 そして、原告が、被告商品1)及び4)の限界利益の額を売上高の3割である と主張するのに対し、当該商品を実際に製造する被告は、その割合は24% であると主張するにとどまり、これを裏付ける証拠を何ら提出していない事 情を踏まえると、限界利益の額は、原告らの主張する上記3割を下回らない と認めるのが相当である。 そうすると、商標法38条2項の損害額と推定される侵害品の限界利益の 額は、原告東京フードについては、前記10(2)で認定した売上高2億482 0万8219円の3割に相当する7446万2465円であると認めるのが 相当であり、原告BGHDについては、前記10(2)で認定した売上高654 6万8493円の3割に相当する1964万0547円であると認めるのが 相当である。
(2) 商標法38条2項における推定の覆滅については、侵害者が主張立証責任 を負うものであり、侵害者が得た利益と商標権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たるものと解される。
これを本件についてみると、前記10(2)のとおり、原告らは、「ぼてぢゅ う」の名を付した店舗を出店し、主としてお好み焼きや焼きそばなどを提供 する事業を行っているところ、平成29年11月又は12月以降テイクアウ ト販売及びデリバリー販売の事業を展開しているものの、その事業規模は明 らかではなく、原告の業務態様は、基本的にはスーパーマーケットなどで商 品を販売するという被告の業務態様とは、大きく異なるものであること、他 方、前記前提事実、証拠(乙1、2、4)及び弁論の全趣旨によれば、被告 は、平成23年3月19日、最初に「ぼてぢゅう」のお好み焼き店を開業し た者が設立した株式会社ぼてぢゆう総本家から、被告保有商標1の譲渡を受 けてこれを使用し、被告保有商標1が失効した後も、被告保有商標2及び3 を保有して、お好み焼きや焼そば等を販売してきたことが認められ、被告は、 元祖「ぼてぢゅう」の信用をも引き継ぎつつ、相応の営業努力をして商品を 販売等してきたことが認められること、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、原告らと被告の業務態様等には大きな相違が存在 する上、被告も通常の範囲を超える格別の営業努力をして商品を販売等して きたことが認められ、その他に本件に現れた事情を総合考慮すると、原告ら に生じた損害については、商標38条2項による推定を覆滅する事情がある というべきであり、その推定の覆滅の割合は、上記諸事情を踏まえ、9割と 認めるのが相当である。
(3)これに対し、原告らは、「ぼてぢゅう監修」などと表記した商品(甲18\nないし25、62)を販売しており、被告による商標権侵害行為により、当 該商品の売上げも減少し、原告らに損害が生じた旨主張する。 しかし、証拠(甲18ないし25、62)及び弁論の全趣旨によれば、上 記商品の販売減による原告らの利益の減少は、ライセンス収入の減少に相当 するものにすぎず、しかも、原告らは、上記減少に係る具体的な額について 何ら主張立証していないことからすれば、原告らの主張は、上記判断を左右 するものとはいえない。したがって、原告らの主張は、採用することができない。
(4) 以上によれば、原告東京フードに生じた商標法38条3項で推定される損 害額は、前記(1)の限界利益の額7446万2465円の1割である744万 6246円と算定され、当該事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に 鑑み、これと相当因果関係あると認められる弁護士費用相当損害74万46 24円との合計819万0870円となり、原告BGHDに生じた商標法3 8条3項による損害額は、前記(1)の限界利益の額1964万0547円の1 割である196万4054円と算定され、当該事案の内容、難易度、審理経 過及び認容額等に鑑み、これと相当因果関係あると認められる弁護士費用相 当損害19万6405円との合計額は216万0459円となる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.05. 5
令和1(ワ)25152 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月24日 東京地方裁判所
2 争点1(準拠法)について
(1) 差止め及び除却等の請求について
特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された 国の法律であると解すべきであるから(最高裁平成12年(受)第580同 14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁)、本件の差止 め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日 本法が準拠法となる。
(2) 損害賠償請求について
特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題では なく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律 関係の性質は不法行為である(前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷 判決)。したがって、その準拠法については、通則法17条によるべきである から、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。 原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末 に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権 を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、 権利侵害という結果は日本で発生したということができるから、上記損害賠 償請求に係る準拠法は日本法である。
・・・
前記(1)のとおり、被告システム1は、構成要件1Bないし1F及び1Hを\n充足し、前記前提事実(6)アのとおり、被告システム1が構成要件1A、1G\n及び1Iを充足することは、当事者間に争いがない。 そして、前記(2)のとおり、被告システム2及び3は、構成要件1Aないし\n1F及び1Hを充足し、前記前提事実(6)イのとおり、被告システム2及び3 が構成要件1G及び1Iを充足することは、当事者間に争いがない。\nしたがって、被告システムは本件発明1の技術的範囲に属するものと認め られる。
(2) 被告FC2による被告システムの「生産」の有無について
ア 本件発明1の関係での被告システム1(被告サービス1のFLASH版) の「生産」について
本件発明1の「実施」として被告FC2による被告システム1の「生産」 があるといえるかを、まず、被告サービス1のFLASH版について検討 する。
(ア) 物の発明の「実施」としての「生産」(特許法2条3項1号)とは、 発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解され る。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること を意味する属地主義の原則(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年 7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12 年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7 号1551頁参照)からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに 限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当 たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内にお\nいて新たに作り出されることが必要であると解すべきである。
(イ) 前記3(1)のとおり、被告システム1は、本件発明1の構成要件を全\nて充足し、その技術的範囲に属するものであって、被告システム1にお ける構成1aないし1iは、本件発明1の構\成要件1Aないし1Iにそ れぞれ相当する。 また、被告サービス1のFLASH版においてコメント付き動画を日 本国内のユーザ端末に表示させる手順は、前記(1)ウ(ア)のとおりであっ て、被告サービス1がその手順どおりに機能することによって、上記の\nとおり本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムであ\nる被告システム1が新たに作り出されるということができる。 そして、本件発明1のコメント配信システムは、「サーバ」と「これと ネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とす\nる物であるところ(構成要件1A)、被告システム1においては、日本国\n内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これ\nとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存 在しているものといえる。
他方で、前記3(2)アによれば、本件発明1における「サーバ」(構成\n要件1A等)とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有\nするとともに(構成要件1B)、端末装置に「動画」及び「コメント情報」\nを送信する機能(構\成要件1C)を有するものであるところ、これに該 当する被告FC2が管理する前記(1)ウ(ア)の動画配信用サーバ及びコメ ント配信用サーバは、前記(1)イ(ア)のとおり、令和元年5月17日以降 の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在して いるものとは認められない。
そうすると、被告サービス1により日本国内のユーザ端末へのコメン ト付き動画を表示させる場合、被告サービス1が前記(1)ウ(ア)の手順ど おりに機能することによって、本件発明1の構\成要件を全て充足するコ メント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に 存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在 するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム(被告システ\nム1)が作り出されるものである。
したがって、完成した被告システム1のうち日本国内の構成要素であ\nるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことに\nなるから、直ちには、本件発明1の対象となる「物」である「コメント 配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることが できない。
(ウ) 原告は、被告システム1では、多数のユーザ端末は日本国内に存在し ているから、被告システム1の大部分は日本国内に存在している、被告 FC2が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外 の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大 部分は日本国内で行われている、本件発明1において重要な構成要件1\nHに対応する被告システム1の構成1hは国内で実現されている、被告\nシステム1については「生産」という実施行為が全体として見て日本国 内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバ を国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論とな るのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム1は、量的に見て も、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、 被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価すること ができると主張する。
しかしながら、前記(ア)のとおり、特許法2条3項1号の「生産」に該 当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内におい\nて作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止 権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、 明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出され\nるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲 を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム1の構成要\n素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム1 が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。 また、前記(1)ウ(ア)の2)−2及び5)からすれば、被告システム1にお いては、被告FC2のウェブサーバがユーザ端末に配信するSWFファ イルによって規定される条件に基づいて、2つのコメントが重複するか 否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示\n位置の指定が行われており、構成要件1Fの「判定部」及び構\成要件1 Gの「表示位置制御部」に相当する構\成1f及び1gの動作の実現は、 日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということ ができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成\n要件1Hに対応する構成1hのうち「前記ユーザ端末のディスプレイに\nは、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間におい て、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント1及び前記コ メント2とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に\n相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるも のということができるものの、構成要件1Hに対応する構\成1hのうち 「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記 ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国 内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現 されるものであり、構成1hが日本国内に存在するユーザ端末のみによ\nって実現されているとはいえない。前記1(2)イで検討したところからす れば、本件発明1の目的は、単に、構成要件1Fの「判定部」及び構\成 要件1Gの「表示位置制御部」に相当する構\成等を備える端末装置を提 供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメン トを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システ ムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信(構成要件\n1C及び1H)並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメ ント情報の送信(構成要件1B、1C及び1H)を行う「サーバ」は、\nこの目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。\nこの点からしても、本件発明1に関しては、ユーザ端末のみが日本に存 在することをもって、「生産」の対象となる被告システム1の構成要素の\n大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきで ある。 さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用 可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考\nえられ、同オのとおり、平成26年当時、日本法人である被告HPSが、 被告FC2の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサー ビスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全 証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年5月17日以 降の時期において、米国法人である被告FC2が本件特許権の侵害の責 任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本 国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論と して著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められな い。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(エ) 以上によれば、被告サービス1のFLASH版については、本件発明 1の関係で、被告FC2による被告システム1の日本国内での「生産」 を認めることができないというべきである。
・・・
オ 小活
以上のとおり、本件発明1の関係でも、本件発明2の関係でも、被告サ ービス(FLASH版及びHTML5版)において、被告FC2による被 告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2022.05. 2
令和3(行ケ)10148 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年4月25日 知的財産高等裁判所
本願商標は、別紙1の1のとおり、1)上段には「natural baby soap」の文 字が、水色の手書き風の書体で、下段部分の文字より小さく、また、下段部 分よりも幅が狭く、上側に湾曲する形で配され、2)下段には、Doodle Pen の 特徴を備えた書体で、上段の欧文字よりも目立つ大きさで「nico」の欧文字 が水色で横書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような 図形が配され、「o」の内側には、横並びに2つの点とその下に両端上がりの 弧線が配されて顔を表すように図案化された、結合商標である。\n ところで、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の\n出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、そ\nれ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる 場合等には、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商\n標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するの が相当である。そして、本件においては、要部が本件商標の下段部分である ことについては、当事者間に争いがなく、本願商標が、全体の構成からみる\nと、上段部分と下段部分とを分離して観察することが取引上不自然とはいえ ず、上段部分は下段部分と比して全体の大きさは小さく、出所識別標識とし て特定の称呼、観念を生じさせないものであること等に照らしても、本件商 標の要部は下段部分であるとするのが相当である
次に、本件商標の要部である下段部分について検討する。
前記(1)のとおり、本件商標の要部である下段部分は、「nico」の欧文字が横 書きに表され、「nico」の「o」の上部には「サボテン」のような図形が配さ れ、「o」の内側には、横並びに2つの点とその下に両端上がりの弧線が配さ れて顔を表すように図案化されているところ、店舗名や商品名等に含まれる\n欧文字の「o」の内側に横並びに2つの点とその下に両端上がりの弧線を配し て顔を表すように図案化したり(乙3ないし8、10、11、14)、「o」の 文字上部にイラストを配して図案化する(乙9ないし14)ことは慣用され ていることが認められる。そうすると、本願商標の下段部分に接した取引者 及び需要者は、末尾の欧文字は一般的に慣用されているものと同様に図案化 されたものと理解し、認識するものということができる。そして、この下段 部分からは「nico」の欧文字に相応して「ニコ」の称呼を生じるものである が、「nico」の欧文字は辞書等に載録されているものでなく、特定の観念を生 じさせるものではない。
これに対し、原告は、前記第3の1(1)のとおり、欧文字の称呼「ニコ」と イラスト部分が「にこにこ笑う」との共通の印象を与えるものであり、「nico」 ないし「ニコ」の欧文字は、これを含む商品が多数存在し、登録商標等が合 計30件あることから、必ずしも取引者及び需要者に強い印象を与えるもの ではないのに対し、イラスト部分は、独自性を有するものであり、イラスト 部分からは観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を与えること を前提とした類否判断をすべきである旨主張する。
しかし、「nico」ないし「ニコ」の欧文字は、原告が提出する証拠によれば、 本願商標の指定商品と同一又は類似する商品では2件しか使用されておらず (甲9、10)、少なくとも本願商標の指定商品と同一又は類似する分野にお いて、「nico」ないし「ニコ」が出所識別標識としての機能が弱いとまではい\nえない。また、前記(2)のとおり、欧文字の「o」の内側に横並びに2つの点と その下に両端上がりの弧線を配して顔を表すように図案化したり、「o」の文 字上部にイラストを配して図案化することは慣用されているところ、本願商 標の下段部分の「o」の部分も一般的に慣用されている態様と同様であるし、
また、サボテンのようなイラストも特定の観念を生じさせるような特異なも のとはいえず、その大きさや態様において強い印象を与えるものとはいい難 い。そうすると、特に商標の細部にまで注意を払うことがない一般消費者が、 取引に際して、下段部分のうちイラスト部分にことさら着目し、それにより 特異な観念が生じ、出所識別標識として強い支配的な印象を受けるものとは 認め難いから、原告の主張は理由がない。
・・・・
これに対し、原告は、前記第3の1(3)イのとおり、本願商標の下段部分は 特徴的なイラスト部分があるが、引用商標の欧文字はこうした特徴的なもの を備えておらず、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与え る印象を挙げて、本願商標と引用商標は、外観において、離隔的観察のもと でも称呼における類似性をしのぐほどの差異を取引者及び需要者に与える旨 主張する。
しかし、原告が指摘するイラスト部分は、欧文字の「o」を顔等の図案化す るものとしてこれまで慣用されてきたものと大きく異なるものではなく、イ ラスト部分が強い支配的印象を与えるものではないことは繰り返し説示して きたとおりであり、また、本願商標と引用商標の字体、イラスト、文字の与 える外観上の差異については、離隔的観察のもとでは、取引者及び需要者に 大きく異なる印象を与えるものであるとまではいえない。
また、原告は、前記第3の1(3)ウのとおり、本願商標の下段部分全体から、 「にこにこ笑った」印象を与えるものであるのに対し、引用商標は特定の観 念を生じさせない旨主張するが、前記1(2) において判示したところに照らせ ば、その前提を誤るものというべきである。
さらに、原告は、前記第3の1(3)エのとおり、本願商標を付した原告の商 品について、現在までに本願商標と引用商標その他の第三者の商標と混同し たような内容の問い合わせがないことを「取引の実情」として挙げて、称呼 が共通していても、外観及び観念の相違から誤認混同が生じていない旨主張 するが、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、そ の指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、該商 標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すも のではない(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日第一小 法廷判決参照)ところ、原告の上記主張は、本願商標が現在使用されている 商品についての取引の実情をいうものであるから、当を得ない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.04.28
平成31(ワ)8969 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年4月22日 東京地方裁判所
証拠(乙8)及び弁論の全趣旨によれば、原告及び被告は、いずれも中国 に住所を置く法人であり、日本に事務所等の拠点を有しないこと、被告ゲー ムの開発や配信に関する主要な作業は中国において行われたことが認められ る。これらの事情によれば、本件訴訟に関する証拠が中国に存在することが うかがわれるから、本件を日本の裁判所で審理した場合には、被告が、本件 訴訟の争点に関する主張立証をする際に、中国語で記載された書類を日本語 に翻訳したり、中国語を話す関係者のために通訳を手配したりするなどの一 定の負担を被り得ることは、否定し難い。
しかし、本件訴訟における原告の請求は、日本国内向けに配信された被告 ゲーム及びそれに関連する画像の複製を差し止め、被告ゲーム等のデータを 削除し、被告ゲームの売上げに基づき著作権法114条2項によって推定さ れる額の損害を賠償すること等を求めるというものである。そうすると、本 件訴訟における請求の内容は日本と密接に関連するものであり、かつ、原告 が主張する上記損害は日本において発生したものと解されるから、本件は、 事案の性質上、日本とも強い関連性を有するというべきである。 また、本件訴訟の争点は、前記第2の3及び前記第3のとおり、原告各画 像と被告各画像の表現の同一性ないし類似性(争点2−1)、被告による原\n告画像1に係る著作権侵害の成否(争点2−2)、被告が原告各画像に依拠 して被告各画像を作成したと認められるか否か(争点2−3)、差止め及び 削除請求の必要性(争点3)並びに損害額(争点4)である。この点、上記 争点2−1については、原告各画像と被告各画像の対比や同一性ないし類似 性が認められる部分が創作的な表現であるか否かに関する検討を要するとこ\nろ、それらの点に係る主張立証は、主として原告各画像及び被告各画像自体 に基づいて行うことになる。これに加えて、他の画像に基づき、上記同一性 ないし類似性の認められる部分がありふれた表現であることの主張立証を行\nうことも考えられるが、当該他の画像に関する証拠が中国に存在するとして も、その性質上、翻訳等の作業は必要とされないであろうから、被告に過大 な負担が生じるとは認め難い。上記争点2−2は、本件リンク設定行為が原 告画像1に係る原告の著作権を侵害するかどうかを、主として日本の著作権 法の解釈、適用によって判断するというものであるから、証拠の所在地が当 該争点の判断において重要な意味を持つものとはいえない。上記争点2−3 に関する証拠としては、原告ゲーム及び被告ゲーム以外のゲーム等の画像及 び公表時期に関する資料、ゲーム制作者の陳述書等が想定されるが、それら\nの全てが中国にのみ所在するとはうかがわれず、立証に際して被告に過大な 負担が生じるとまでは認め難い。上記争点3については、前記第3の3のと おり、被告ゲームの配信が中止された事実が重要な評価障害事実として主張 立証され得るところ、被告ゲームが日本国内向けに配信されたオンラインゲ ームであることを踏まえると、上記事実に関する主要な証拠は日本に所在す るものと認められる。上記争点4についても、上記のとおり、原告が主張す る損害は日本において発生したものと解されるから、損害額の算定の基礎と なる主要な証拠は日本に所在するものと考えられる。したがって、本件が日 本で審理されるとしても、本件の重要な争点に係る主張立証に当たり、被告 に過大な負担が生じるとまでは認められない。
(2) これに対し、被告は、1)本件訴訟と当事者、事案及び争点において密接な 関連性が存在する別件中国訴訟が中国の裁判所において係属していること、 2)原告と被告は、当然に、本件訴訟を中国の裁判所に提起することが最も適 切であり、本件が中国の裁判所での解決が図られると想定していたこと、3) 本件訴訟に関する客観的な事実関係は全て中国において発生したこと、4)本 件訴訟の証拠は全て中国国内に存在すること、5)本件を日本の裁判所で審理 する場合には被告に過大な負担を課すること等を根拠として挙げ、本件訴訟 には民事訴訟法3条の9所定の「特別の事情」があると主張する。 しかし、まず、上記1)についてみるに、本件訴訟と別件中国訴訟は、いず れも原告が当事者であるという点において共通するものの、被告は別件中国 訴訟の当事者の地位にはないから、当事者が完全に一致するものではない。 しかも、別件中国訴訟においては、原告ゲームの中国語版の表現と「C」と\n称するゲームの表現の類否等が争点とされているのであって、被告ゲームの\n表現との類否は争点とされていないばかりか、証拠(甲10)によれば、別\n件中国訴訟において争点とされている原告ゲームの表現はいずれも原告各画\n像とは異なる画像等に係るものであると認められる。そうすると、本件訴訟 と別件中国訴訟の事案及び争点はいずれも大きく相違するものといえるから、 本件訴訟と別件中国訴訟との間に強い関連性があるとまでは認められない。 次に、上記2)についてみるに、上記のとおり、本件訴訟と別件中国訴訟と の関連性は強くない上、原告ゲームと被告ゲームがいずれも日本国内向けに 配信されたスマートフォン向けのオンラインゲームであることに照らすと、 別件中国訴訟が本件訴訟に先立って中国国内の裁判所に係属していたとして も、原告ゲームと被告ゲームに関する著作権侵害に関する紛争の解決が中国 の裁判所で図られることが想定されていたとまでは認められない。 さらに、上記3)ないし5)についてみるに、前記(1)のとおり、本件の請求 の内容は日本と密接に関連するものであり、かつ、原告が主張する上記損害 は日本において発生したものと解されることから、本件に関する客観的な事 実関係が全て中国において発生したということはできない。また、前記(1) のとおり、本件の証拠が専ら中国に存在するとは認められないし、本件を日 本の裁判所が審理するとしても、立証に関して被告に過大な負担を生じさせ るものとまでは認められない。 したがって、被告の上記1)ないし5)の主張はいずれも理由がない。
(3) 以上の次第で、本件の事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の 所在地、原告を当事者とする中国の裁判所に係属中の訴訟の存在その他の事 情を十分に考慮しても、本件訴訟について、民事訴訟法3条の9所定の「特\n別の事情」があると認めることはできない。
・・・
ア 証拠(甲9、乙15ないし17)及び弁論の全趣旨によれば、本件リン ク設定行為は、本件動画の表紙画面である被告画像1をリンク先のサーバ\nーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示させるものにすぎず、\n被告は、本件リンク設定行為を通じて、被告画像1のデータを本件ウェブ ページのサーバーに入力する行為を行っていないものと認められる。そう すると、前記(2)アのとおり原告画像1を複製したものと認められる被告 画像1を含む本件動画をYouTubeが管理するサーバーに入力、蓄積 し、これを公衆送信し得る状態を作出したのは、本件動画の投稿者であっ て、被告による本件リンク設定行為は、原告画像1について、有形的に再 製するものとも、公衆送信するものともいえないというべきである。
イ これに対し、原告は、1)本件ウェブページに被告画像1を貼り付ける行\n為も、本件リンク設定行為も、本件ウェブページの閲覧者にとっては、何 らの操作を介することなく被告画像1を閲覧できる点で異なるところはな いこと、2)本件リンク設定行為は、被告画像1を閲覧者の端末上に自動表\n示させるために不可欠な行為であり、かつ、原告画像1の複製の実現にお ける枢要な行為といえること、3)本件リンク設定行為をすることにより、 被告ゲームを宣伝し、被告ゲームの販売による多大な利益を得たことを指 摘し、規範的にみて、被告が複製及び公衆送信の主体と認められる旨を主 張する。しかし、上記1)についてみると、単に、本件ウェブページに被告画像1 を貼り付ける等の侵害行為がされた場合と同一の結果が生起したことをも\nって、本件リンク設定行為について、複製権及び公衆送信権の侵害主体性 を直ちに肯定することはできないというべきである。 また、上記2)についてみると、仮に枢要な行為に該当することが侵害主 体性を基礎付け得ると解したとしても、本件リンク設定行為の前の時点で 既に本件動画の投稿者による原告画像1の複製行為が完了していたことに 照らすと、本件リンク設定行為が原告画像1の複製について枢要な行為で あるとは認め難いというべきである。なお、本件動画は、本件ウェブペー ジを閲覧する方法によらずとも、本件動画が投稿されたYouTubeの 「D」のページにアクセスすることによっても閲覧することができるから、 本件リンク設定行為が原告画像1の公衆送信にとって枢要な行為であると も認められない。 さらに、上記3)についてみると、本件全証拠によっても、本件リンク設 定行為により被告がどの程度の利益を得ていたのかは明らかではないから、 その点をもって、被告が原告画像1の複製及び公衆送信の主体であること を根拠付けることはできない。 したがって、上記1)ないし3)の点を考慮しても、被告を原告画像1の複 製及び公衆送信の主体であると認めることはできず、原告の上記主張は採 用することができない。
ウ また、原告は、仮に被告が著作権侵害の主体であると認められない場合 であっても、少なくとも、被告が本件リンク設定行為により上記著作権侵 害を幇助したものと認められると主張する。 しかし、前記アのとおり、被告による本件リンク設定行為は、被告画像 1をリンク先のサーバーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示\nさせるものにすぎず、本件動画の投稿者による被告画像1を含む本件動画 をYouTubeが管理するサーバーに入力・蓄積して公衆送信し得る状 態にする行為と直接関係するものではない。そうすると、本件リンク設定 行為が本件動画の投稿者による複製及び公衆送信行為自体を容易にしたと はいい難いから、被告による本件リンク設定行為が、被告画像1に係る原 告の著作権(複製権及び公衆送信権)侵害を幇助するものと認めることは できない。 したがって、被告を原告画像1の複製及び公衆送信の幇助者であると認 めることはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 公衆送信
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2022.04.25
令和3(ネ)10074 債務不存在確認請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年4月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 一審原告ら(一審原告X6及び一審原告X10を除く。)は、同一審原告らが 本件著作物をアップロードしたことの立証に欠けると主張するが、訂正の上引用し た原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2(4)のとおり、一審被告 は、BitTorrentを利用して本件著作物をアップロード及びダウンロード している者のIPアドレスを特定し、プロバイダから、上記IPアドレスに対応す る契約者の氏名及び住所の開示を受けていることが認められ、証拠(乙13の2・ 3・6・7)によると、プロバイダの回答書にIPアドレス並びに一審原告X2、 一審原告X4、一審原告X3、A、一審原告X7、一審原告X9の氏名及び住所の 記載があり、これら一審原告らの氏名及び住所の開示を受ける過程において、IP アドレスの混同がないことが認められる。なお、Aとの記載が、一審原告X8の行 為に係るものであることについては当事者間に争いがない。また、一審原告X1の 氏名及び住所が記載された株式会社TOKAIコミュニケーションズからの通知書 (乙13の1)には、IPアドレスの記載はないものの、「添付ファイル「接続記録 リスト」 No.49〜58」との記載があり、同記載は、一審被告作成の「調査結果一覧 (株式会社TOKAIコミュニケーションズ)」と題する書面(乙11の1)の49 〜58行目に対応するものと推認され、乙11の1の記載からIPアドレスの特定 ができることから、IPアドレスの混同がないことが認められる。そうすると、前 記(1)のとおり立証がされていないと認められる一審原告X5及び一審原告X11 を除き、一審原告ら(一審原告X6及び一審原告X10を除く。)について、本件著 作物をアップロードしたことについての立証がされていると認めるのが相当である。
(2) 争点1−2(共同不法行為性)について
ア 本件で、一審原告X1らは、本件各ファイルを、BitTorrentを利 用して送信可能な状態におくことで、一審被告の著作権を侵害した。ところで、訂\n正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2(3)のとお り、BitTorrentを利用してファイルをダウンロードする際には、分割さ れたファイル(ピース)を複数のピアから取得することになるところ、後掲の証拠 によると、一部のピアのみが安定してファイルの供給源となる一方で、大半のピア は短時間の滞在時(BitTorrentの利用時)に一時的なファイルの供給源 の役割を担うものとされるが、一審原告X1らは、常にBitTorrentを利 用していたものではないことから、一時的なファイルの供給源の役割を担っていた と考えられること(甲12、15、21)、あるトラッカーが、特定の時点で把握し ているリーチャーとシーダーの数は0〜5件程度と、特定時点における特定のファ イルに着目した場合には必ずしも多くのユーザー間でデータのやり取りがされてい るものではないこと(乙2〜4、8〜10)、BitTorrentを利用したアッ プロードの速度は、ダウンロードの速度よりも100倍以上遅く、また、ファイル の容量に比しても必ずしも大きくなく、例えば本件各ファイルの容量がそれぞれ8. 8GB、7.0GB、2.3GBであるのに照らしても、アップロードの速度は平 均0〜17.6kB/s程度(本件著作物以外の著作物に関するものを含む。)と遅 く、ダウンロードに当たっては、相当程度の時間をかけて、相当程度の数のピアか らピースを取得することで、1つのファイルを完成させていると推認されること(甲 5、6、乙2〜4、6)がそれぞれ認められる。これらの事情に照らすと、Bit Torrentを利用した本件各ファイルのダウンロードによる一審被告の損害の 発生は、あるBitTorrentのユーザーが、本件ファイル1〜3の一つ(以 下「対象ファイル」という。)をダウンロードしている期間に、BitTorren tのクライアントソフトを起動させて対象ファイルを送信可能\化していた相当程度 の数のピアが存在することにより達成されているというべきであり、一審原告X1 らが、上記ダウンロードの期間において、対象ファイルを有する端末を用いてBi tTorrentのクライアントソフトを起動した蓋然性が相当程度あることを踏\nまえると、一審原告X1らが対象ファイルを送信可能化していた行為と、一審原告\nX1らが対象ファイルをダウンロードした日からBitTorrentの利用を停 止した日までの間における対象ファイルのダウンロードとの間に相当因果関係があ ると認めるのも不合理とはいえない。
そうすると、一審原告X1らは、BitTorrentを利用して本件各ファイ ルをアップロードした他の一審原告X1ら又は氏名不詳者らと、本件ファイル1〜 3のファイルごとに共同して、BitTorrentのユーザーに本件ファイル1 〜3のいずれかをダウンロードさせることで一審被告に損害を生じさせたというこ とができるから、一審原告X1らが本件各ファイルを送信可能化したことについて、\n同時期に同一の本件各ファイルを送信可能化していた他の一審原告X1ら又は氏名\n不詳者らと連帯して、一審被告の損害を賠償する責任を負う。 なお、控訴人(一審原告)らは、原判決が、一審原告X1らが送信可能化した始\n期から終期までの期間のダウンロード数をひとまとめで判断したことが不相当であ る旨主張するが、原判決は、当該期間のダウンロード数をもってひとまとめの損害 が生じたと認定したものではなく、1ダウンロード当たりの損害額を認定した上で、 当該期間にダウンロードされた本件各ファイルの数を推定して、推定したダウンロ ード数に応じた損害額を算定しているのであって、この手法は相当である。
イ 控訴人(一審原告)らは、原判決が、一審原告らがBitTorrentの 仕組みを十分認識・理解していたと認定したことについて事実誤認であると主張す\nるところ、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判 断」の1(2)のとおり、控訴人(一審原告)らは、BitTorrentを利用して ファイルをダウンロードした場合、同時に、同ファイルを送信可能化していること\nについて、認識・理解していたか又は容易に認識し得たのに理解しないでいたもの と認められ、少なくとも、本件各ファイルを送信可能化したことについて過失があ\nると認めるのが相当である。 そうすると、控訴人(一審原告)らが、本件著作物の送信可能化に関し、不法行\n為責任を負うとした原判決の判断は相当である。
(3) 争点2−1(共同不法行為に基づく損害の範囲)について
ア 一審被告は、本件各ファイルが最初にBitTorrentにアップロード されて以降の権利侵害の全てについて、一審原告らが責任を負う旨主張するが、一 審原告らと本件各ファイルをアップロードしている他の一審原告ら又は氏名不詳者 との間に共謀があるものでもないのであるから、一審原告らは、BitTorre ntを利用して本件各ファイルのダウンロードをする前や、BitTorrent の利用を終了した後においては、本件著作物について権利侵害行為をしていないの は明らかである。また、本件各ファイルの送信可能化による損害は、1ダウンロー\nドごとに発生すると考えられるところ、一審原告らがBitTorrentの利用 をしていない時期におけるダウンロードについてまで、一審原告らの行為と因果関 係があるなどということはできない。そうすると、一審原告らは、BitTorr entを利用して本件各ファイルのダウンロードをする前及びBitTorren tの利用を終了した後については、本件著作物の権利侵害について責任を負わない というべきであり、一審被告の上記主張は採用できない。
イ 一審原告X1らによる本件各ファイルのアップロードの終期について、別紙 「損害額一覧表」の「終期」欄記載の日(プロバイダからの意見照会を受けた日)\nと認定できるのは、訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁 判所の判断」2(3)記載のとおりである。これは、一審原告X1らの陳述書(甲15、 20の1)に基づき認定したものであるが、プロバイダからの意見照会を受けたこ とで怖くなり、BitTorrentのクライアントソフトを削除したり、Bit\nTorrentの利用を控えるのは通常の行動であり、上記各陳述書の内容に不自 然な点はない。
ウ 一審原告らは、BitTorrentの利用者が、ファイルのアップロード を24時間継続することはまずないことや、シーダーやピアが数百以上散在してい ることなどを踏まえ、本件の損害額については、例えば原判決の認定する額の10 0分の1などとして算定すべきと主張する。しかしながら、前記(1)及び(2)に判示 したとおり、一審原告X1らは、BitTorrentを利用して本件各ファイル をダウンロードしてから、BitTorrentの利用を停止するまでの間の本件 各ファイルのダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者として責任 を負うと認めることが相当である。また、BitTorrentの仕組みに照らす と、本件各ファイルのダウンロードキャッシュを削除するか、BitTorren tの利用を停止するまでの間は、一審原告X1らの端末にダウンロード済みの本件 各ファイルが送信可能な状態にあったのであるから、一審原告X1らが本件各ファ\nイルのダウンロードキャッシュを削除したこと又はBitTorrentの利用を 停止したことが認められる時点までは、一審原告X1らの不法行為は継続していた と認めるのが相当であり、本件では、一審原告X1らが、別紙「損害額一覧表」の\n「終期」欄記載の日よりも前の特定の日に、本件各ファイルのダウンロードキャッ シュを削除したことを認めるに足りる証拠はない一方で、一審原告X1らが、同別 紙の「終期」に記載の日より後はBitTorrentの利用をしていないことが 認められるから、同日までの間は、一審原告X1らは、本件各ファイルの送信可能\n化による不法行為を継続していたと推認することが相当である。 ところで、一審原告らは、正確なダウンロード数についての立証がない旨指摘す るが、正確なダウンロード数は不明であるものの、一審原告X1らが本件各ファイ ルを送信可能化していた期間におけるダウンロード数は、令和元年10月1日から\n令和3年5月18日までの間にダウンロードされた数から、別紙「損害額一覧表」\nの「5)期間中のダウンロード数」のとおりに推計することができるから、本件にお いては、当該ダウンロード数の限度で立証されているというべきである。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.04.23
令和3(行ケ)10068 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年4月14日 知的財産高等裁判所
以上を総合すると、本件発明の「前記演出制御手段は、前記可動体演出 を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に 前記特典遊技状態となる場合には前記第2操作手段の選択率が高く、前記 当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態 とならない場合には前記第1操作手段の選択率が高い」との記載は、「前記 演出制御手段」が、「前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大 当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合」には、 前記第1操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をす るより、前記第2操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選 択をする割合が高く、「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の 終了後に前記特典遊技状態とならない場合」には、前記第2操作手段が操 作されることを起因に可動体演出を行う選択をするより、前記第1操作手 段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をする割合が高いこ とを規定したものと理解できる。 したがって、本件発明の「前記演出制御手段は、前記可動体演出を行う 際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特 典遊技状態となる場合には前記第2操作手段の選択率が高く、前記当否判 定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となら ない場合には前記第1操作手段の選択率が高い」との記載は、その記載内 容が明確である。
(2) これに対し、被告は、1)請求項1の「前記演出制御手段は、所定の前記変 動演出の実行中に、前記第1操作手段又は前記第2操作手段が操作されるこ とを起因に前記可動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行い」 との記載から、第1操作手段又は第2操作手段が操作されることを起因に可 動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行うことを理解できるが、 第1操作手段と第2操作手段の両方が操作される場合や、その他の操作手段 が操作される場合が排除されていないため、上記記載は、「第1操作手段又は 第2操作手段が二者択一で選択される構成」を特定しているとはいえないし、\n仮に「第1操作手段又は第2操作手段が二者択一で選択される構成」を読み\n取れるとしても、そのことから直ちに、記載j1の「前記当否判定の結果が 大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合には前記 第2操作手段の選択率が高く」との記載における「前記第2操作手段の選択 率」の比較対象や、記載j2の「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当 り遊技の終了後に前記特典遊技状態とならない場合には前記第1操作手段の 選択率が高い」との記載における「前記第1操作手段の選択率」の比較対象 が一義的に導かれるわけではない、2)本件明細書の【0012】及び【00 13】の記載は、請求項1の記載Jに対応しておらず、本件発明の解釈の根 拠とはならないから、記載Jを含む本件発明は、明確性要件に適合しない旨 主張する。
しかし、1)については、請求項1の「前記演出制御手段は、所定の前記変 動演出の実行中に、前記第1操作手段又は前記第2操作手段が操作されるこ とを起因に前記可動体を所定の可動態様で作動せしめる可動体演出を行い」 との記載が、「演出制御手段」が、第1操作手段と第2操作手段の両方が操作 される場合や、その他の操作手段が操作される場合について可動体演出を行 うことを規定しているものと読み取ることはできないし、請求項1の記載全 体をみても同請求項がそのように規定しているものと読み取ることはできな い。
また、前記(1)のとおり、本件発明の「演出制御手段」は、当否判定の結果 が大当りである場合、変動演出の実行中、第1操作手段が操作されることを 起因に可動体演出を行うか、又は第2操作手段が操作されることを起因に可 動体演出を行うかを選択するものと理解できることからすると、記載j1は、 「前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り 遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合」について、「前記第2操作手段 の選択率」が「前記第1操作手段の選択率」よりも高いことを規定するもの と、記載j2は、「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後 に前記特典遊技状態とならない場合」について、「前記第1操作手段の選択率」 が「前記第2操作手段の選択率」よりも高いことを規定するものとそれぞれ 理解できるから、記載j1及びj2のいずれの記載についてもその比較対象 は明確である。 2)については、前記(1)のとおり、記載Jの記載内容が明確であることは、 本件明細書の【0012】及び【0013】を根拠とするものではないから、 被告の主張は前提を欠くものである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2022.04.23
令和2(ワ)19920等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月19日 東京地方裁判所
医薬の用途発明においては,一般に,物質名,化学構造等が示されるこ\nとのみによっては,当該用途の有用性を予測することは困難であり,当該\n医薬を当該用途に使用することができないから,医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには,明細書の発明の詳細な説明にその医薬の\n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が,前記判示のとおり,本件明細書等には,本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には,本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば,神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること\nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また,侵害受容性疼痛, 神経障害性疼痛,心因性疼痛などの種類を問わず,痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり,いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば,他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は,本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり,その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ,上記 に摘示した各記載によれば,侵害受容性疼痛,神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は,その発症原因,痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり,痛みの種類を問わず,痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり,いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば,他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば,本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく, 本件明細書等の記載に接した当業者が,本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって,本件明細書等の記載は訂正前発明1及び2を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず,実施可\n能要件を充足しない。\n
(5) 原告の主張について
これに対し,原告は,本件特許出願当時,慢性疼痛は,それが侵害受容性 疼痛,神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても,末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛\nの痛みであるとの技術常識が存在したので,当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から,本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(オ) 以上によれば,上記(ア)ないし(ウ)の各記載から,侵害受容性疼痛,神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と,脊髄のNMDA受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても,本件特許 出願当時,本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛(炎症性疼痛,術 後疼痛,転移癌に伴う骨関節炎の痛み,痛風,火傷痛等)や神経障害性 疼痛(三叉神経痛,急性疱疹性神経痛,糖尿病性神経障害,カウザルギ ー等)により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難\nく,まして,これらの記載から,当業者が,薬理試験結果の記載もなく, 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は,被告医薬品が構成要件3B及び4Bの文言を充足しない場合であっ\nても,均等侵害が成立すると主張する。 しかし,相手方が製造等をする製品(対象製品)が,特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属すると認められる\nためには,当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特\n許発明の本質的部分ではないことを要する(第1要件)。 本件発明3及び4と被告医薬品との相違部分は,その用途にあるところ,同 各発明は,既知の薬物である本件化合物が,侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので,その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。\nしたがって,被告医薬品は,第1要件を充足しないので,均等侵害は成立し ない。
7 まとめ
以上によれば,訂正前発明1及び2に係る特許は,実施可能要件及びサポー\nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり,本 件訂正は訂正要件を具備せず,同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また,被告医薬品は,本件発明3及び4の技術的範囲に属しない。
◆判決本文
特許権は同じく、被告が異なる事件です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.04.23
令和3(ワ)5668 発信者情報開示請求事件 著作権 令和4年1月20日 東京地方裁判所
1 争点1(本件ログイン時IPアドレス等の「権利の侵害に係る発信者情報」 (法4条1項)該当性)について
(1) 原告が本件において開示を求める本件発信者情報は,本件各投稿に利用さ れた本件各アカウントを保有する者の電話番号及び電子メールアドレスのほか,本 件各アカウントにログインした際に割り当てられたIPアドレス及びそのタイムス タンプに係る情報であり,原告の本件各写真に係る公衆送信権侵害行為を構成する\n情報の送信時に割り当てられたIPアドレス及びそのタイムスタンプではない。そ こで,本件ログイン時IPアドレス等のようなログインする際に割り当てられたI Pアドレス及びそれが割り当てられたタイムスタンプが,法4条1項所定の「権利 の侵害に係る発信者情報」に該当するかが問題となる。
(2) 法4条1項は,特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害 されたとする者が開示関係役務提供者に対して開示を請求することのできる情報と して,「権利の侵害に係る発信者情報」と規定しており,権利侵害行為そのものに使 用された発信者情報に限定した規定ではなく,「係る」という,関係するという意義 の文言が用いられていることからしても,「権利の侵害に係る発信者情報」は,権利 侵害行為に関係する情報を含むと解するのが相当である。そして,法4条の趣旨は, 特定電気通信(法2条1号)による情報の流通には,これにより他人の権利の侵害 が容易に行われ,その高度の伝ぱ性ゆえに被害が際限なく拡大し,匿名で情報の発 信がされた場合には加害者の特定すらできず被害回復も困難になるという,他の情 報流通手段とは異なる特徴があることを踏まえ,特定電気通信による情報の流通に よって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバシー,表現の自由,通信\nの秘密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求すること ができるものとすることにより,加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を\n図ることにあると解され(最高裁平成22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻 3号676頁参照),かかる趣旨からすると,権利侵害行為そのものの送信時点では なく,その前後に割り当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報であっ ても,それが当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には,「権利の侵害に係 る発信者情報」に当たると解すべきである。 被告は,ログイン行為と侵害情報そのもの送信行為とは全く異なる性質のもので あること等を理由に,法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」には,ログイ ン時のIPアドレス等を含まないと主張する。 しかし,ログイン時のIPアドレス等であっても,当該ログインが侵害情報の発 信者のものと認められる場合には,当該ログイン時のIPアドレス等は侵害情報の 送信行為との関連性を有するということができ,したがって,当該ログインに係る IPアドレス等も法4条1項所定の発信者情報に当たるといえるのであるから,被 告の上記主張は採用することができない。 また,被告は,法4条1項の委任を受けた省令8号が「侵害情報が送信された年 月日及び時刻」と規定していることやログイン情報の送信が1対1の電気通信であ って,「特定電気通信」(法2条1号)に該当しないことからすると,ログイン時の タイムスタンプは開示が認められる発信者情報に該当せず,また,省令5号は省令 8号と整合的に解釈すべきであるから,省令5号にいうIPアドレスも侵害情報の 送信時に割り当てられたIPアドレスのみをいうのであって,ログイン時に割り当 てられたIPアドレスを含まないとも主張する。 しかし,省令5号及び8号に開示の対象となる発信者情報の特定を委任した法4 条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」は,権利侵害行為そのものの送信時点で はなく,その前後に割り当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報であ っても,それが当該侵害情報の発信者のものと認められるものをも含むと解するこ とができることは前記説示のとおりである。また,省令5号は,法4条1項所定の 発信者情報に該当するIPアドレスにつき,「侵害情報に係る」と規定しており,侵 害情報の送信の際に割り当てられたIPアドレスに限定する規定ぶりとはなってい ないことからすれば,ログインの際に割り当てられたIPアドレスも「侵害情報に 係るアイ・ピー・アドレス」に該当するというべきである。そして,IPアドレス の開示を受けるだけでは発信者を特定することが不可能ないし極めて困難であって,\n発信者の特定には,当該IPアドレスを割り当てられた年月日及び時刻(タイムス タンプ)を必要とすることからすれば,省令8号の規定するタイムスタンプは,ロ グインの際のIPアドレスが割り当てられた電気通信設備からのログイン情報の発 信時のものを含むと解するのが相当であるというべきであって,被告の上記主張は 採用することができない。また,本件各投稿は不特定の者の投稿・閲覧が認められ るツイッター上にされたものであり,不特定の者によって受信されることを目的と する電気通信の送信といえることに照らし,「特定電気通信」該当性を否定する被告 の上記主張も採用の限りではない。
(3) 続いて,本件ログイン時IPアドレス等から把握される発信者情報が本件 各投稿の発信者のものと認められるかどうかを検討する。 弁論の全趣旨によれば,被告が提供するツイッターを利用するには,まず,アカ ウントを作成する必要があり,アカウントの作成には,ユーザID及びパスワード の設定が必要となること,ツイッターを利用する際は,ユーザID及びパスワード を入力して当該アカウントにログインすることが必要であり,当該アカウントの管 理者はスマートフォン等の各種デバイスを利用してツイッターにログインして当該 アカウントにツイート(投稿)していることが認められる。このようなツイッター の仕組みを踏まえると,法人や団体においてその営業や事業に利用する場合を除き, 複数人が共有して特定のアカウントを利用する可能性は極めて乏しく,また,本件\nにおいて複数人が本件各アカウントを共有して使用していることをうかがわせる事 情は見当たらない。そうすると,本件各アカウントはそれぞれ特定の個人が利用し ていたものであるというべきであり,本件各アカウントにそれぞれログインした者 と本件各投稿の各発信者とは同一の者であると認められ,本件IPアドレス等から 把握される発信者情報が本件各投稿の発信者のものということができる。 被告は,本件各投稿がされる前のログイン情報もさることながら,本件各投稿が された後の情報であって,本判決確定の時点で被告が保有する本件各アカウントへ のログインの際のIPアドレス等から把握される情報(最新ログイン時の情報)ま でをも「権利の侵害に係る発信者情報」ということはできないと主張する。 しかし,前記認定したツイッターの仕組みからすれば,本件各投稿を本件各アカ ウントの設定者がこれを第三者に譲渡したことがうかがわれるなどの特段の事情の ない限り,本件各投稿と開示を求めるログイン時の情報との前後関係,その時間的 間隔の程度等を考慮することなく,本件各アカウントにログインした際のIPアド レス等は,本件各投稿による権利の侵害に係る発信者の特定に資する情報に該当す るというべきであるところ,本件全証拠に照らしても,上記特段の事情の存在はう かがわれない。 以上からすると,本件各アカウントにログインした際のIPアドレス等の情報は, 最新のログインの時のIPアドレス等も「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる というべきである。 そして,被告は,原告の著作権を侵害する本件各投稿に係る侵害情報の発信者と 同一の者によるものと認められる各通信を媒介し,その際に割り当てられた本件ロ グイン時IPアドレス等を保有する特定電気通信役務提供者であるから「開示関係 役務提供者」に当たるということができる
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2022.04.13
令和2(ワ)5616 特許権 令和4年1月25日 東京地方裁判所
2 争点1(被告各製品の20ライン分のラインバッファは,「単一のVRAM」 を充足するか(構成要件D及びHの充足性))について\n
(1) 「単一のVRAM」の意義
ア 本件特許の特許請求の範囲における構成要件Dにおいては,「グラフィ\nックコントローラ」が,「該中央演算回路の処理結果に基づき,単一のVR AMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い,「該読み 出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すると\n規定されている。 また,構成要件Hにおいては,「グラフィックコントローラ」が,「前記\n単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度 を有する画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出したビットマ ップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び「前記単\n一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出したビット マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」することが規定され\nている(なお,構成要件Hにおける「前記単一のVRAM」との文言から,\n構成要件Dと構\成要件Hの「単一のVRAM」は同一の意義を持つものと 解される。)。
さらに,構成要件F,H,Jによると,「ディスプレイパネルの画面解像\n度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」は,「外部ディス プレイ手段」に表示するためのものであるといる。\nこれらの記載によれば,構成要件D及びHの「単一のVRAM」は,「グ\nラフィックコントローラ」により,「ビットマップデータの書き込み/読み 出し」がされるものであって,外部ディスプレイ手段に表示するための「デ\nィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット マップデータ」の書き込み/読み出しがされるものであり,前記「ディス プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマッ プデータ」の全体を記憶することが可能なものと解するのが相当である。\nそして,前記1に認定した本件明細書の記載(特に段落【0115】,【0 117】,【0127】)も,その記載内容に照らせば,構成要件D及びHの\n「単一のVRAM」が,「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なも\nのであるとの上記クレーム解釈に整合しており,同解釈を裏付けるものと 評価することができる。
イ 原告は,構成要件Hは,ビットマップデータの読み出しの具体的な方法\nについて何らの特定もしておらず,ディスプレイパネルの画面解像度と同 じ解像度を有する画像のビットマップデータを一挙に読み出すことを規 定したものとは解されない旨を主張する。しかし,特許請求の範囲の記載, 明細書の記載を検討すると,上記アに説示したとおり,「単一のVRAM」 は,「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の ビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なものと認めるのが相\n当である。原告の上記主張は採用することができない。
(2) 「単一のVRAM」の充足性
以上のクレーム解釈を前提に,被告各製品が,構成要件D,Hの「単一の\nVRAM」を充足するかについて検討する。 前記前提事実のとおり,被告各製品は,データ処理手段としてのCPU(中 央演算回路)及び液晶コントローラ(グラフィックコントローラ)を備える ものであるところ,このCPU(中央演算回路)は,無線通信手段から受信 した信号(圧縮した通信信号)をデコードして画像データを展開し,拡大/ 縮小(補間/間引き)を適宜行って内蔵用表示データ及び外部用表\示データ を生成し,生成した表示データを同CPU(中央演算回路)に接続されたS\nDRAMに書き込み/読み出しを行い,その内蔵用表示データ及び外部用表\ 示データを液晶コントローラ(グラフィックコントローラ)に送信する構成\nを有している。しかして,この液晶コントローラ(グラフィックコントロー ラ)には,6個の2Mビット(256kバイト)DRAMが内蔵されている ところ,これは,外部表示用のラインバッファ(20ライン分)であり,画\n像全体を書き込み/読み出しするためのものではないというのである(被告 各製品の構成d)。\n
しかして,このような,被告各製品の液晶コントローラ(グラフィックコ ントローラ)が内蔵するDRAMは,少なくとも外部表示用にはラインバッ\nファ(外部表示手段に表\示するための画像全体を書き込み/読み出しするた めのものではない)として用いられるものであるから外部表示手段に表\示す るための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像 のビットマップデータ」の全体を記憶するものではないことは明らかである というほかない。 そうすると,被告各製品における上記DRAM(20ライン分のラインバ ッファ)は,「単一のVRAM」との文言を充足するものとは認められず,被 告各製品が,構成要件D及びHを充足するものとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.04.13
令和3(ネ)1005 特許権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記ア及びイの認定事実によれば,本件各発明が被告各製品の部分 にのみ実施されていること,電動ファン付きウェアの市場において, 他社の販売する被告各製品の競合品が存在していたことは,本件推定 の覆滅事由に該当するものと認められる。 そして,本件推定の上記覆滅事由に加えて,1)前記アで説示した とおり,本件各発明は,空調服の襟後部と首後部との間に形成される 開口部の大きさを襟後部の内表面に設けた一組の調整紐で調整する従来技術における一組の調整紐を,取付部を有する二つの調整ベルトに\n置き換えて,一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数あ る取付部のうちいずれか一つを取り付けることによって,襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することを可能にし,より適切な空調服の冷却効果を,より簡単に得ることを目指したもの\nであり,開口部からの空気の排出の効率化という点では,従来技術の 延長線上に位置づけられるものであること,本件特許の出願当時,ボ タン及びボタンホール等を使用し,衣服におけるサイズを複数段階で 調整することは,周知慣用の技術であったことに照らすと,本件各発 明の技術的意義は必ずしも大きいものとはいえず,その作用効果も従 来技術と比較して大きなものとは認められないから,被告各製品にお いて本件各発明を実施した部分の顧客吸引力は高いものとはいえない こと,2)電動ファン付きウェアの市場における一審原告,一審被告及 び競業他社のシェアの割合(前記イ(ア)),3)一審被告における被告 各製品の広告宣伝の態様(甲3の1,6,乙57等)を総合考慮する と,被告各製品の購買動機の形成に対する本件各発明の寄与割合は1 0%と認めるのが相当であり,上記寄与割合を超える部分については 被告各製品の限界利益の額と一審原告の受けた損害額との間に相当因 果関係がないものと認められる。 したがって,本件推定は上記限度で覆滅されるものと認められる から,特許法102条2項に基づく一審原告の損害額は,被告各製品 の限界利益の額(5652万1465円)の10%に相当する565 万2147円と認められる。
・・・
当裁判所は,令和3年11月8日の当審第1回口頭弁論期日において,一審 被告が同年7月9日付け控訴理由書に基づいて提出した「無効理由5ないし9」 に基づく無効の抗弁(同理由書第3ないし第6記載)及び権利の濫用の抗弁 (同理由書第8記載)の主張について,一審原告の申立てにより,時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが,その理由は,以下のとおりで\nある。
(1) 一件記録により認められる本件訴訟の経緯等は,次のとおりである。
ア 一審原告は,平成30年7月6日,原審に本件訴訟を提起した。 一審被告は,同年11月12日の原審第1回弁論準備手続期日におい て,同年10月31日付け被告第1準備書面に基づいて,本件各発明 (請求項3及び9)に係る本件特許に明確性要件違反の無効理由(本件 の争点2−1)が存在するとして,特許法104条の3第1項の無効の 抗弁を主張した。その後,一審被告は,平成31年3月7日の原審第3 回弁論準備手続期日において,同年2月28日付け被告第3準備書面に 基づいて,上記無効の抗弁について,乙2公報を主引用例とする新規性 欠如及び進歩性欠如の無効理由(本件の争点2−2及び2−3)を追加 して主張した。 一審原告及び一審被告は,令和元年6月27日の原審第5回弁論準備 手続期日において,侵害論についての主張立証は終了した旨陳述した。 その後,本件訴訟は,同年7月19日の原審第6回弁論準備手続期日 から,損害論の審理に入った。
イ 株式会社サンエスは,令和2年10月15日,本件特許のうち,請求項 3ないし10に係る特許について,明確性要件違反(無効理由1),冒 認出願又は共同出願要件違反(無効理由2),公然実施発明(結び紐タ イプの空調服に係る発明)を主引用例とする進歩性欠如(無効理由3), 乙2公報を主引用例とする進歩性欠如(無効理由4)(ただし,本件の 争点2−3とは,乙2公報記載の発明の内容,副引用例等の主張が異な る。)を無効理由として特許無効審判(無効2020−800103号 事件。以下「別件無効審判」という。乙104)を請求した。
ウ 一審被告は,令和2年10月22日の原審第14回弁論準備手続期日に おいて,同月16日付けの被告第10準備書面に基づいて,本件各発明 に係る本件特許に別件無効審判の無効理由1ないし4と同一の無効理由 が存在するとして,新たな無効の抗弁の主張をした。
原審は,同年12月18日の第15回弁論準備手続期日において,一 審原告の申立てにより,被告第10準備書面で追加された上記無効の抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。\n原審は,令和3年1月28日の第16回弁論準備手続期日で弁論準備 手続を終結した後,同年2月26日の原審第2回口頭弁論期日において 口頭弁論を終結し,同年5月20日,一審原告の請求を一部認容する原 判決を言い渡した。
エ 一審被告は,令和3年5月20日,本件控訴を提起し,一審原告は,同 年6月3日,本件附帯控訴を提起した。 一審被告は,同年11月8日の当審第1回口頭弁論期日において,同年 7月9日付け控訴理由書に基づいて,本件各発明に係る本件特許に「無 効理由5」(別件無効審判の無効理由2と同じ),「無効理由6」(別 件無効審判の無効理由3と同じ),「無効理由7」(別件無効審判の無 効理由4と同じ),「無効理由8」(サポート要件違反)及び「無効理 由9」(実施可能要件違反)が存在するとして無効の抗弁の主張を追加し,また,権利の濫用の抗弁の主張を追加した。\nこれに対し一審原告は,同年8月26日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由5ないし9」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は,時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから,却 下を求める旨の申立てをした。
オ なお,別件無効審判は,当審の本件口頭弁論終結時(令和3年11月8 日)において,特許庁に係属中である。
(2) 前記(1)の事実関係によれば,1)一審被告は,原審において,平成31年 3月7日の原審第3回弁論準備手続期日までに,本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由,乙2公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由(本件の争点2−1ないし2−3)が存在するとして無 効の抗弁を主張し,その上で,令和元年6月27日の原審第5回弁論準備手 続期日において,侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後,同年 7月19日の原審第6回弁論準備手続期日から,本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと,2)その後,一審被告は,令和2年10月22日の原審第14回 弁論準備手続期日において,本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由1ないし4と同一の無効理由が存在するとして,新たな無効の抗弁の 主張をしたが,原審が,同年12月18日の第15回弁論準備手続期日にお いて,上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と,3)一審被告は,令和3年11月8日の当審第1回口頭弁論期日において, 控訴理由書に基づいて,本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由2ないし4と同じ無効理由である「無効理由5ないし7」,原審で主張し なかった「無効理由8」(サポート要件違反)及び「無効理由9」(実施可 能要件違反)が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに,新たに権利の濫用の抗弁の主張をしたこと,4)別件無効審判は,当審の本件口頭弁論 終結時において,特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに,侵害論に関する抗弁の主張は,本来,原審に おいて適時に行うべきものであるところ,一審被告が,原審において,令和 元年6月27日の原審第5回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に,当審で主張する「無効理由5ないし9」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて, やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから,当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は,一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして,当審において,一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは,一審原告に対し,上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ,これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから,これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで,当審は,民事訴訟法297条において準用する同法157条1 項に基づき,一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2022.04.10
平成30(ワ)4329等 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月18日 東京地方裁判所
争点は、技術的範囲の属否、無効(104条の3)、損害額の認定、覆滅の程度などです。
被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに270万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成3 0年3月又は同年11月以降であり、前記(1)イ(ア)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠(甲82)によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠(乙75)及び弁論の全趣旨によれば、令和3年1月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数270万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ア)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ア)a及びdのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており(ただし、 商品ごとに、これを1個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。)、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法102条2項により推定される損害額の10%について\n推定の覆滅を認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.04.10
令和2(ワ)25127 著作権 民事訴訟 令和4年3月25日 東京地方裁判所
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学\n術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいい、 共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その 各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」(同項12号) をいう。
そうすると、本件地図1ないし4が原告及び被告の共同著作物であり、原 告がこれらについての共有著作権及び著作者人格権を有するというためには、 原告の思想又は感情が本件地図1ないし4に創作的に表現されたと認められ\nる必要がある。
(2) 前記1(5)及び(6)のとおり、被告は、平成12年頃に、原告と本件覚書を 交わし、原告との共同研究が終了した後、原告と面会したり、直接連絡をと ったりしたことはなかったところ、原告に相談することなく、平成21年に 本件発表をし、その頃に本件地図1及び2が掲載された本件論文1を、平成\n29年に本件地図3及び4が掲載された本件論文2を、それぞれ作成したも のであり、原告は、被告の本件発表並びに本件論文1及び2の作成の事実を\n知らなかったものである。また、原告は、その本人尋問において、本件地図1ないし4自体を作成し たのは被告である旨供述している。したがって、仮に本件論文1に掲載された本件地図1及び2並びに本件論 文2に掲載された本件地図3及び4に著作物性が認められるとしても、本件 地図1ないし4は、原告の思想又は感情が創作的に表現されたものではなく、\n被告のみの思想又は感情が創作的に表現されたものと認めるのが相当であり、\n原告及び被告の各氏名が記載された本件論文1に掲載された本件地図1及び 2について、著作権法14条に基づき、原告及び被告が著作者であると推定 されたとしても、その推定は覆されるというべきである。
(3)ア これに対して、原告は、1) 本件論文1及び2は、原告及び被告を共同発 明者とする本件出願1ないし3の各願書に添付した明細書に記載された内 容に基づくものであり、本件論文1及び2に掲載された本件地図1ないし 4は、本件出願1ないし3の各願書に添付した図面と基本的に同一である こと、2) 本件発表の発表\者として原告の氏名が挙げられ、本件論文1の冒 頭に原告の氏名が、末尾に原告に対する謝辞が、それぞれ記載されている ことからすると、本件地図1ないし4は原告及び被告の共同著作物である と主張する。
イ しかし、上記1)について、本件出願1ないし3の各願書に添付した明細 書に従って本件地図1ないし4を作成できるとの事実を認めるに足りる証 拠はない。
また、前記前提事実(2)ないし(4)のとおり、原告は本件出願1ないし3 の各発明者の一人として名前が挙げられているが、発明とは「自然法則を 利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)であり、 発明者はこのような技術的思想を創作した者をいうのに対し、著作物とは 「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)であ\nり、著作者は「著作物を創作する者」(同項2号)をいうことから、両者 が創作する対象は、それぞれ技術的思想と表現という異なるものである。\n仮に本件出願1ないし3が地図の作成方法に関する発明に係る出願であり、 本件出願1ないし3の各願書に添付した明細書に従って地図を作成するこ とができたとしても、上記発明に係る技術的思想の創作に関わったにすぎ ない原告の思想又は感情が当該地図において創作的に表現されたというこ\nとにはならない。
さらに、証拠(甲1、2、4ないし6)によれば、本件地図1及び3と 本件出願1の願書に添付した図面の【図10】のLC2、本件出願2の願 書に添付した図面の【図10】のLC2及び本件出願3の願書に添付した 図面のFIG.10のLC2とを比較すると、国境線及び地名の記載の有 無、各大陸の形状、位置関係等が少なからず異なっており、本件地図2及 び4と本件出願1の願書に添付した図面の【図9】、本件出願2の願書に 添付した図面の【図9】及び本件出願3の願書に添付した図面のFIG. 9とを比較すると、各大陸の形状、位置関係等が少なからず異なっている ことが認められる。地図が地形等を客観的に表現することを目的としたも\nのであることを考慮すると、仮に本件出願1ないし3の上記各図面に原告 の思想又は感情が創作的に表現されたといえるとしても、上記のような相\n違のある本件地図1ないし4にも同様に原告の思想又は感情が創作的に表\n現されたということは困難である。以上を総合すると、上記1)の事情をもって、原告の思想又は感情が本件地図1ないし4に創作的に表現されたというには足りないから、同事情は前記(2)の認定を左右するものではないというべきである。
ウ また、上記2)について、前記前提事実(5)のとおり、日本国際地図学会の 平成21年度定期大会のプログラムには、本件発表の発表\者として、被告 のみならず原告の氏名が記載されており、本件論文1の冒頭にも、被告の みならず原告の氏名が記載され、その末尾に「本研究の基礎はA氏との半 年間の共同研究によるものである。」と記載されている。しかし、被告は、その本人尋問において、被告が修士論文を作成した際、原告が被告に対してアイデアの盗用であるなどと主張したことがあったことから、原告に配慮して、上記のとおり、原告の氏名を記載するなどした旨供述しているところ、前記1(3)ないし(5)の経過に鑑みると、被告の上 記供述は信用することができるというべきである。そうすると、上記各記載の存在をもって、本件論文1に掲載された本件地図1及び2に原告の思想又は感情が創作的に表現されているということはできないから、上記2)の事情も前記(2)の認定を左右するものではない。
エ したがって、原告の前記アの主張は採用することができない。
(4) 以上によれば、本件地図1ないし4は、原告及び被告の共同著作物とは認 められないから、原告が本件地図1ないし4に係る共有著作権及び著作者人 格権を有するとはいえない。 087/091087
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作者
>> ピックアップ対象
2022.04. 8
令和1(ワ)5620等 特許権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月24日 大阪地方裁判所
イ 特許法101条1号について
間接侵害について検討するに、特許法101条1号の「その物の生産にのみ用い る物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上、経済的、\n商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他 の用途がないことをいうと解するのが相当である。 被告製品2)には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業 的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品 2)は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。
被告らは、被告製品には、本件仕様2)のみならず、本件仕様1)及び3)があること、 被告製品は蒸気タービン発電システムの計測器として使用されていること、被告製 品のメイン基板として使用されているコンピュータは汎用的な小型コンピュータで あることから、拡張ボードと組み合わせることにより種々の用途に使用することが できることを指摘して、被告製品には他の用途がある旨を主張する。 しかし、被告システムに使用され、本件特許権侵害が問題となるのは被告製品のうち本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働したものに限られるところ、前提事実(4)及び前記2 (1)のとおり、被告製品にインストールされている本件仕様1)〜3)に係るプログラ ムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働 することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、 いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って 同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかないのである。 そうであれば、本件仕様2)が稼働していない被告製品(本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない製品も含む。)に関しては、被告システムに使用されるとはいえないから、「その物の生産にのみ用いる物」(特許法101条1号)ないし「その物の生産に用いる物」(同条2号)に該当するとはいえない。
また、本件仕様1)ないし3)のいずれも稼働していない被告製品について、顧客の要望に応じて被告フィールドロジックが本件仕様1)又は3)に係るプログラムを解放する可能性はあり、そのような態様での被告製品の使用が、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途でないとも認められない。\n
一方、本件仕様2)に係るプログラムが現に稼働した被告製品2)については、前記のとおり、被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品2)の使用を続けながら、本件仕様1)又は3)に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品2)の他の用途ということはできないし、その他、被告らが指摘する用途は、いずれも被告製品2)の用途以外のものであるから、被告らの主張は採用できない。なお、被告らは、被告製品のうち本件仕様2)を稼働させた場合、太陽光発電システムのほかにも風力発電システム及び小水力発電システムにも使用される旨を主張するが、これを裏付ける証拠はなく、実用的な用途であるとは認められない。
ウ 前記イのとおり、本件仕様2)が稼働していない被告製品は、特許法101条 2号の「その物の生産に用いる物」に該当しない。また、本件仕様2)が稼働してい る被告製品2)については、同号に基づく間接侵害の成否を検討するまでもなく、前 記イのとおり、同条1号に基づく間接侵害が成立するものと認められる。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> のみ要件
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.04. 4
令和3(ワ)6266 著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月30日 東京地方裁判所
プロバイダ責任制限法は、4条1項において、「開示関係役務提供者」の 意義について「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる 特定電気通信役務提供者」と定め、「特定電気通信による情報の流通によっ て自己の権利を侵害されたとする者」は、「侵害情報の流通によって当該開 示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであ」り(同項1号)、 かつ、「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使 のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が あるとき」(同項2号)に限り、開示関係役務提供者に対し、当該開示関係 役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求するこ とができる旨を規定し、また、同条2項において、開示関係役務提供者がそ のような請求を受けた場合には、原則として発信者の意見を聴かなければな らない旨を規定する。
これらの規定の趣旨は、発信者情報が、発信者のプライバシー、表現の自\n由、通信の秘密に関わる情報であり、正当な理由がない限り第三者に開示さ れるべきものではなく、また、これが一旦開示されると開示前の状態への回 復は不可能となることから、発信者情報の開示請求につき厳格な要件を定め\nた上で、開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し、上記のような発信者 の利益の保護のために、発信者からの意見聴取を義務付けて、開示関係役務 提供者において、発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されること がないように十分に意を用い、当該開示請求が同条1項各号の要件を満たす\nか否かを慎重に判断させることとしたものと解される。 こうした「開示関係役務提供者」の意義及びプロバイダ責任制限法の定め の趣旨に鑑みれば、「開示関係役務提供者」については厳格に解すべきであ って、ある特定電気通信役務提供者が「開示関係役務提供者」に当たるとい うためには、当該特定電気通信役務提供者が用いる特定電気通信設備が侵害 情報の流通に供されたことが必要であると解すべきである。
(2) 判断
ア 被告TOKAIについて
(ア) 本件ツイート1の投稿について
原告らが被告TOKAIに対して開示を求める契約者の情報である本 件発信者情報1は、令和2(2020)年6月29日15時56分35 秒(UTC)頃及び同年8月16日7時49分52秒(UTC)頃に被 告TOKAIから(IPアドレスは省略)という発信元IPアドレスを 割り当てられていた契約者に関するものである。 この点、本件ツイート1が投稿されたのは、同年6月29日17時4 5分(JST。これをUTCに換算すると同日8時45分となる。)で あるから、本件発信者情報1のうち、同日15時56分35秒(UTC) 頃に関するものは、本件ツイート1の投稿から7時間余り後のものであ り、同年8月16日7時49分52秒(UTC)頃に関するものは、同 投稿から48日余り後のものである。したがって、被告TOKAIから 上記発信元IPアドレスを割り当てられた通信によるログインの状態下 で、本件ツイート1の投稿に係る通信がされたものと認めることはでき ない。
また、証拠(甲35、36、39、40、乙5の1)によれば、(I Pアドレスは省略)というIPアドレスに係るドメインには「t−co m.ne.jp」という文字列が含まれていたと認められるから、被告 TOKAIが割り当てるIPアドレスに係るドメインには、この「t− com.ne.jp」という文字列が含まれるものと推認される。そし て、当該文字列を含むドメインに係るIPアドレスが割り当てられた通 信によって本件アカウントにログインされた時刻は、その大半が17時 台から23時台までの間(いずれもUTC)であって、8時台(UTC) は見当たらない。したがって、本件ツイート1が投稿された令和2(2 020)年6月29日8時45分(UTC)頃に、被告TOKAIの電 気通信設備を経由する通信によって本件アカウントにログインがされた ものと認めることはできない。 かえって、証拠(甲40)によれば、本件ツイート1の投稿の直前の ログインに係る通信は「amazonaws.com」を含むドメイン のものであると認められ、これは、本件ツイート1の投稿に係る通信が、 被告TOKAIの電気通信設備以外の電気通信設備を経由してなされた ことをうかがわせる事情といえる。 以上によれば、被告TOKAIが用いる電気通信設備が本件ツイート 1の投稿に供されたことは認められないから、本件ツイート1の投稿に ついて、被告TOKAIが「開示関係役務提供者」に該当するとは認め られない。
・・・
ウ 原告らの主張について
(ア) 原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備とログイ ンの通信に用いられた電気通信設備が同一であれば、当該電気通信設備 を用いる特定電気通信役務提供者は「開示関係役務提供者」に該当する 旨を主張する。しかし、仮に原告らの解釈を前提にしても、前記ア及び イのとおり、本件各ツイートが被告らの電気通信設備を経由して投稿さ れたとは認められないから、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通 信設備とログインの通信に用いられた電気通信設備が同一であるとは認 められない。したがって、原告らの上記主張は理由がない。 さらに、原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備 が厳密に特定できなくとも、そのいずれかの電気通信設備を用いて投稿 されたことが明らかであれば、権利侵害を受けた者の権利回復を図ると いう観点からも、立証責任を緩和して、いずれの経由プロバイダに対す る発信者情報開示請求についても認められるべきであるとも主張する。 しかし、前記(1)のとおり、プロバイダ責任制限法4条1項は、情報の 発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件\nの下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特 定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することを認め たものと解されるから、権利侵害を受けた者の権利回復を図るという観 点のみを根拠として、その者の立証責任を緩和し、複数の経由プロバイ ダのうちいずれかの経由プロバイダの電気通信設備を用いて投稿された ことさえ立証されれば、いずれの経由プロバイダに対しても発信者情報 開示請求が認められると解するというのは、相当でないというべきであ る。原告らの主張は独自の見解というほかはなく、採用の限りではない。
(イ) 原告らは、さくらインターネット株式会社やアマゾンジャパン合同会 社が管理する通信網を経由した本件アカウントへのログイン(「sak ura.ne.jp」や「amazonaws.com」の文字列を含 むドメインによるIPアドレスが割り当てられた通信によるログインを 指すと解される。)は、本件ツイート1及び2の投稿者とは異なる別事 業者が提供する、本件アカウントと連携したツイッター専用アプリケー ションを用いて本件アカウントにログインしたものであって、上記投稿 者による通信ではないと主張する。しかし、本件全証拠によっても、原 告が主張する上記事実は認められないから、本件各ツイートの投稿の通 信に関する前記ア及びイの認定を何ら左右するものではない。
(ウ) したがって、原告らの前記(ア)及び(イ)の主張はいずれも採用すること ができず、その他原告らが種々主張するところを十分に考慮しても、前\n記(2)ア及びイの認定を左右するには至らない。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2022.04. 4
令和3(ネ)10049等 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
3 争点1−1(被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)\nである先端部を有しているか)について
(1) 「楕円形」の一般的な意味について
ア 「楕円形」とは,「楕円状をなした形」をいい,「楕円」とは,「円錐曲線 (二次曲線)の一つ。幾何学的には,一平面上で二定点(F,F’)からの距離の和 (FP+F’P)が一定であるような点Pの軌跡。」を意味する(「広辞苑 第六版」 (平成20年1月11日発行,株式会社岩波書店)1705頁,乙2参照)。この点, 被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠(甲 2。令和元年5月30日印刷)では,「楕円形」について,「楕円状をなす形,ある いは,それに近い形。」(デジタル大辞典の解説),「楕円のような形。また,そのよ うな形のさま。小判がた。長円形。側円形。」(精選版日本国語大辞典の解説)とさ れている。 上記を踏まえると,一般に,「楕円形」とは,「楕円状をなした形」をいい,幾何 学上の楕円の形状がそれに含まれることはもとより,同形状とは異なるがそれに近 い形についても用いられる語であると解される。 もっとも,幾何学上の楕円の形状とは異なるがそれに近い形として,どのような 形が「楕円形」に含まれるか,「楕円形」の意味の外延は,上記の辞書的な意味から は明確とはいえない。
イ 上記に関し,「卵形(たまごがた)」は,「鶏卵に似た楕円形。」を意味する語 である(上記「広辞苑 第六版」1756頁,甲78参照)。なお,被控訴人が提出 するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠(甲77。令和3年 7月29日印刷)では,「卵形(たまごがた)」について,「鶏卵のような楕円形。ま た,そのような形のもの。たまごなり。」(精選版日本国語大辞典の解説),「鶏卵に 似た楕円形。たまごなり。らんけい。」(デジタル大辞典の解説)とされている。 また,「卵形(らんけい)」は,「たまごのような形。たまごがた。」を意味する語 である(上記「広辞苑 第六版」2933頁)。なお,上記証拠(甲77)では,「卵 形(らんけい)」について,「卵のような形。楕円の一方が少し細くなっている形。 たまごがた。」(精選版日本国語大辞典の解説),「卵のような形。たまごがた。」(デジタル大辞典の解説)とされている。 そうすると,「楕円形」の語は,「卵形」を含むものとして用いられることもある ものの,他方で,前記アの「楕円形」の意味において,「卵形」と同義である旨の説 明はもちろん例示としても「卵形」という説明がみられないことや,上記のとおり, 「卵形」の意味においても,限定なしで「楕円形」と同義であることは何ら示され ず,「鶏卵に似た」,「鶏卵のような」といった限定を付して「楕円形」という語が用 いられたり,「楕円の一方が少し細くなっている形」との説明がされていることも踏 まえると,「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられる ところである。
ウ 以上によると,「楕円形」の語は,幾何学上の楕円の形状及びそれに近い形を いうものであるが,当該楕円の両端(当該楕円とその長軸が交わる2点をいう。)付 近の曲線を比較した場合に,その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状(「卵形」 など。当事者の主張における「長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状」。 以下「曲率に差のある形状」という。)を含むものとして「楕円形」の語が用いられ ているか否かは,明細書(図面を含む。)における当該「楕円形」の語が用いられて いる文脈等を踏まえて判断する必要があるというべきである。
エ これに対し,被控訴人は,「楕円形」の語が卵形等を含むものであると主張し て,インターネットでの画像検索の結果(甲10の1〜6)やウェブサイト等にお ける語の使用例(甲79〜84)を指摘するが,それらは一般に「楕円形」の語が どのような形を説明する際に用いられているかといった事情を示すものにすぎず, 「楕円形」の語が上記各証拠で示される各種の形をその意味として当然に含むこと を示すものとは解されない。
(2) 本件明細書における「楕円形」の語について
ア 本件明細書に,「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。 ただし,請求項1の発明においては先端部が「球形」とされ,本件明細書でも「球 形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると,少なくとも,本件発明 の「楕円形」は,円形(球形の断面)を含むものではなく,円形を含み得るような 広い意味の語ではないことは理解されるといえる。
イ(ア) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」 の1(2)を踏まえると,本件発明が解決しようとする課題は,従来技術について,矢 の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた,1)矢を的から外すときに 丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と,2)ダブ ル突入の場合に後ろの矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け,後ろの 矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題(以下,併せて「ピン抜 けの課題」という。)のほか,矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルム の重なりにより生じていた,3)上下方向の重心に偏りがあるという課題(以下「重 心の課題」という。)であると解される。
(イ) 本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は,ピン抜けの課 題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると,ピ ン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ,「かえ し」の存在をなくすという観点からは,先端部の形状は,幾何学上の楕円の形状で 足り,曲率に差のある形状である必要はない。したがって,ピン抜けの課題の解決 手段の一つであるという事情は,本件発明における「楕円形」の語が,曲率に差の ある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ,曲率に差のある 形状とした場合,具体的な形状次第では,的やダブル突入の場合の前の矢のフィル ムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ,ピン抜\nけの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点,本件明細書に は,先端部の形状について,「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン 抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は,何ら記載さ れていない。
他方,本件明細書上,重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端 部の形状との関係は明確ではないが,重心の課題の原因の一つとして,矢の先端部 の頭部と円柱部との位置のずれが挙げられていることのほか,本件発明の効果等に 関し,請求項1の発明に係る実施例についてのものではあるものの,「ピンを従来 の丸釘から先端球形に変更することによって矢の長手方向の重心位置を矢の先端方 向に寄せることができた」ことが記載され,その変形例が本件発明に係るもので, 上記実施例と同様に従来の矢の丸釘と比較した丸ピンの重量等について具体的な記 載がされていることも考慮すると,「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状 は,円柱部との位置のずれを解消しやすく,また,上下方向の重心に偏りがなく, かつ,従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重 くなるといった観点から,重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理 解することもあり得る。しかし,そのような観点からも,先端部の形状は,幾何学 上の楕円の形状で足り,曲率に差のある形状である必要はない。むしろ,曲率に差 のある形状とした場合,具体的な形状次第では,円柱部との位置の調整が困難にな ったり,上下方向の重心に偏りがなく,かつ,先端部が相対的に重くなるといった 特徴が十分に発揮できなくなり,重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえると\nころである。この点,本件明細書には,先端部の形状について,「楕円形」としてど のような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料とな り得るデータ等は,何ら記載されていない。
ウ 本件発明の実施例は,本件明細書の【0065】〜【0069】及び【図3】 のとおりであり,先端部の長手方向の断面は,請求項1の発明の実施例(同【図2】) の先端部の形状である「球形」の長手方向の断面である円を左右(矢の進行方向か らすると前後)に二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形(換言する と,「円」を左右に引き伸ばしたような形)であって,「小判型」や「俵型の断面」 などというべきものであり,幾何学上の楕円の形状とは異なるものの,長手方向の 両端の曲率を同じくするものである。上記の形については,本件明細書に実験結果 が記載されており,また,前記イ(イ)で指摘したような,ピン抜けの課題の解決や重 心の課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いものといえる。
(3) 構成要件B及びDの「楕円形」の意味及び文言侵害の成否について\n
ア 前記(1)及び(2)の点を踏まえると,構成要件B及びDの「楕円形」は,幾何\n学上の楕円の形状や,本件発明の実施例の形のような,楕円に近い形状であって長 手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で,曲率に差のあ る形状は含まないものと解するのが相当である。なお,これと異なる技術常識を認 めるべき証拠もない。
イ 被告製品のピンの先端部は,「長手方向断面が,前部が曲率の緩い曲線形状, 後部が略円錐形となるように円弧を描き,後部の円柱部との接合面が上下に角を有 し,前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」(構成要件b)であり,\n曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものである から,構成要件B及びDの「楕円形」には含まれない。\nしたがって,被告製品が,文言上,本件発明の技術的範囲に属するとは認められ ない。
ウ 被控訴人は,曲率に差のある形状のピンの先端についても,1)「かえし」が ないため矢が抜きやすいこと,2)上下方向の重心が均等であり,また,3)従来技術 の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり,矢全体の長手方向の重心を前寄りに 寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件B及びD\nの「楕円形」に含まれると主張するが,前記(1)及び(2)で認定説示した点に照らし, 上記1)〜3)を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできな い(なお,被控訴人の上記主張によると,請求項1の発明に係る「球形」が,同時 に本件発明に係る「楕円形」に含まれることとなり得,この観点からも上記主張は 相当といい難い。)。 また,被控訴人は,本件で問題になっているのは,一般的に楕円形といえばどの ような形を最初に思い浮かべるかではなく,卵形や涙滴型のような,長手方向の端 の一方が他方よりも緩い曲率の形状を「楕円形」と表現するのか否かであると主張\nするが,被告製品の先端部の形状が本件発明の構成要件B及びDの「楕円形」に含\nまれるかという判断に先立って,まず,本件発明の構成要件の解釈として構\成要件 B及びDの「楕円形」の意味が問題となるのであるから,被控訴人の上記主張は, その前提を誤るものといえ,前記ア及びイの判断を左右するものではない。
4 争点1−2(均等侵害の成否)について
・・・・
(エ) 本件発明の構成要件A〜Eに加え,前記(ア)ないし(ウ)を踏まえると,本件発 明について,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは,\nピンと巻いたフィルムによって構成される吹矢において,構\成要件B〜Dのうち, 特に「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とか らなるピン」,「先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ・・・たフィルム」 及び「前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続さ れた」という構成を採用することにより,ピン抜けの課題と重心の課題をともに解\n決するという点にあると解される。
(オ) 前記3で認定判断した構成要件B及びDの「楕円形」の意味及び弁論の全趣\n旨によると,本件発明の先端部の形状と被告製品の先端部の形状について,1)本件 発明では「楕円形」であるのに対し,被告製品では,曲率に差のある形状を基礎と して,「長手方向断面が,前部が曲率の緩い曲線形状,後部が略円錐形となるよう に円弧を描」く形状となっていること(なお,別紙乙第1号証のとおり,後部の略 円錐形となるような円弧について,一定の曲率が選択されているものである。乙3 の1・2,乙15参照)と,2)根元段差部分があることとにおいて,異なっている ということができる。 上記のうち1)について,前記3(2)イで指摘したところからすると,本件発明は, 少なくともピン抜けの課題の解決方法として,「長手方向断面が楕円形である先端 部」という構成を採用したものと解される。そして,同イ(イ)で指摘したとおり,「長 手方向断面が楕円形」という形状を曲率に差のある形状に変更した場合,ピン抜け の課題の解決や重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところ,「楕円形」と してどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断 の資料となり得るデータ等は本件明細書に記載されていない。 そうすると,本件発明における前記3(3)で認定判断した意味での「長手方向断面 が楕円形」という先端部の形状の特定は,本件発明の本質的部分に含まれるものと いうべきであり,それを被告製品の先端部の形状に置き換えることは,本件発明の 本質的部分を変更するものというべきである。 ウ したがって,本件発明の構成中に,被告製品と異なる部分が存在するところ,\n異なる部分は本件発明の本質部分であるから,第1要件を満たさない。
(2) 第3要件について
また,本件全証拠をもってしても,本件発明の「長手方向断面が楕円形」という 形状を被告製品の先端部の形状に置き換えることについて,前記3(2)イ(イ)で指摘 したとおり,曲率に差のある形状への変更によりピン抜けの課題の解決や重心の課 題の解決に支障を生じ得るともいえる一方で,どのような範囲内の変更であればそ れらの課題がなお適切に解決されるかの判断の資料となり得る記載が本件明細書に ないにもかかわらず,当業者が被告製品の製造等の時点において上記置換えを容易 に想到することができたというべき技術常識等は認められない。 したがって,第3要件も満たさない。
(3) まとめ
したがって,その余の点について判断するまでもなく,均等侵害は成立しない。
(4) 被控訴人の主張について
ア(ア) 被控訴人は,第1要件について,「かえし」部分が存在せず,矢が的や前の 矢から引き抜きやすい滑らかな曲線状の長手方向断面形状を有する先端部と,当該 先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンを備えているという点が本件発明の本 質的部分であると主張するが,前記(1)ア及びイで認定説示したとおりであって,被 控訴人の上記主張は採用できない。それゆえ,上記主張を前提とする本件発明と被 告製品との一致点・相違点に係る被控訴人の主張も採用できない。 (イ) 被控訴人は,第1要件について,ピンの先端部の後方部の形状に着目したと いう点で本件発明は技術的思想として新しいなどとも主張するが,そのような着眼 点に本件発明の一つの特徴があるとしても,その上で,本件発明においては,課題 解決の方法として,「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたとい う事情を均等侵害の成否の検討においても無視することはできず,また,ピンの先 端部の後方部の形状に係る構成は,本件発明による複数の課題の解決のうちのいま\nだ一つにとどまるというべきものであるから,被控訴人の上記主張は,前記(1)イ及 びウの認定判断を左右するものではない。
イ 被控訴人は,第3要件について,本件発明は,矢が的や前の矢から引き抜き やすいピンの先端部を提供するものであり,そのためにはピンの先端部の形状は球 形や楕円形に限られず,「かえし」部分が存在せず,かつ,引き抜く際の抵抗がよ り小さくなるような滑らかな曲線状で形成されていればよいことは,当業者におい て容易に想到できるなどと主張するが,前記ア(ア)のとおり,本件発明の本質的部分 についての被控訴人の主張は採用できないから,当業者において容易に想到できる という被控訴人の上記主張は,その前提を欠くものであり,第3要件を満たさない というべきことは,前記(2)のとおりである。その余の被控訴人の主張も,本件発明 の本質的部分についての被控訴人の主張を前提とするものか,本件発明において課 題解決の方法として「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたと いう事情を無視するもので相当でないものであって,いずれも採用できない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.04. 4
令和2(ワ)11834 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年1月27日 大阪地方裁判所
・・・
前提事実(第2の2(2))によれば,原告は,本件イラストの著作者とし て,その著作権及び著作者人格権を有する者と認められる。 にもかかわらず,被告が,本件応募行為等に際し,本件データを原告に無断で 複製していまじんに提供し,また,いまじんに対し本件イラストの著作者が「X 2」である旨を伝えたことにより,本件番組の放送に際してはその旨の表示がさ\nれ,原告の実名又は原告筆名は著作者として表示されなかった。\n
イ 被告の故意又は過失の有無(争点1)
被告は,本件イラストの著作者ではなく,また,その主張を前提としても, SNS を通じて知り合っただけの人物から同人の作品としてデータの提供を受けた にとどまる。 本件応募フォーム,とりわけ本件注意書の記載内容(前記1(1))に鑑みれば, 本件番組がオリジナル作品の制作者本人による応募を前提とするものであること は容易に理解される。また,この趣旨を踏まえれば,仮に制作者本人以外の者が 応募する場合であっても,応募者が制作者本人の承諾等を得た上で応募すべきこ とが求められることも,やはり容易に理解し得る。さらに,日テレ及びその系列 局で本件番組が放送されること及び放送日時等も踏まえれば,本件番組が多くの 視聴者により視聴されることも容易に予想される。\n他方,昨今のインターネットをめぐる状況を踏まえると,SNS その他ウェブサ イト等を通じて,他人が作成したイラスト等の画像データを入手することは事実 上容易であり,また,検索サイトによる画像検索等の方法により特定の画像の制 作者等を特定することは,特別の専門的知識等がなくとも比較的容易である。
以上のような事情を踏まえれば,被告は,本件応募行為等に際し,本件イラス トに係る他人の著作権及び著作者人格権を侵害することのないよう,インターネ ット上の画像検索等の客観性を有する適切な方法により,その著作者ないし著作 権者を確認すべき注意義務を負っていたことが認められる。にもかかわらず,被 告は,その主張を前提としても,単に被告に本件データを提供した人物(P3) に本件イラストが同人の作品であることなどを直接電話等で確認したにとどま る。そうである以上,被告には,本件イラストに係る著作権(複製権)及び著作 者人格権(氏名表示権)の各侵害行為について,少なくとも過失が認められる\n(なお,原告は,複製権侵害につき,明示的には被告の故意を主張するにとどま るが,その主張全体の趣旨から,過失の主張も包むものと理解される。)。これ に反する被告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.04. 1
令和1(ワ)25550 設計図面の複製の差止め等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月30日 東京地方裁判所
原告は、本件企画書の作成に際して本件土地の開発計画を立案し、つくば 建設設計事務所等から提出された検討結果を総合的に取りまとめ、本件企画 書に落とし込む作業を行ったこと、建築計画等の制作において設計図面等の 著作権は発注者である取りまとめ会社に帰属する慣例があることから、原告 は本件企画書の著作者であると主張する。 しかし、単に計画を立案したというのみではアイデアの提供にとどまるし、 他社による検討結果を取りまとめ、本件企画書に落とし込む作業をしたとし ても、当該他社の創作的表現を本件企画書に記載したのみでは、当該作業を\n通じて、本件企画書に原告の思想又は感情を創作的に表現したことにはなら\nないというべきである。そして、本件全証拠によっても、原告が本件企画書 等の作成にどのように関与したのかは明らかではないから、本件企画書等が 「著作物」に該当するとしても、原告がこれを「創作」したと認めることは できない。したがって、原告が本件企画書等の「著作者」(著作権法2条1 項2号)であるとは認められない。 また、原告が主張するような慣例が存在することを認めるに足りる証拠も ないから、そのような慣例に基づいて原告が本件企画書等の著作者になると 認めることもできない。 以上の次第で、仮に本件企画書等に著作物性が認められるとしても、原告 は本件企画書等の著作者であると認めることはできない。
2022.04. 1
令和2(ワ)32121 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月30日 東京地方裁判所
著作権法が、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、\n文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(同法2条1項1号)をいい、 複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製 することをいう旨規定していること(同項15号)からすると、著作物の複 製(同法21条)とは、当該著作物に依拠して、その創作的表現を有形的に\n再製する行為をいうものと解される。 また、著作物の翻案(同法27条)とは、既存の著作物に依拠し、かつ、 その表現上の本質的な特徴である創作的表\現の同一性を維持しつつ、具体的 表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表\現す ることにより、これに接する者が既存の著作物の創作的表現を直接感得する\nことのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される。 そうすると、被告写真3が原告写真を複製又は翻案したものに当たるとい うためには、原告写真と被告写真3との間で表現が共通し、その表\現が創作 性のある表現であること、すなわち、創作的表\現が共通することが必要であ るものと解するのが相当である。
一方で、原告写真と被告写真3において、アイデアなど表現それ自体では\nない部分が共通するにすぎない場合には、被告写真3が原告写真を複製又は 翻案したものに当たらないと解される。そして、共通する表現がありふれた\nものであるような場合には、そのような表現に独占権を認めると、後進の創\n作者の自由かつ多様な表現の妨げとなり、文化の発展に寄与するという著作\n権法の目的(同法1条)に反する結果となりかねないため、当該表現に創作\n性を肯定して保護することは許容されない。したがって、この場合も、複製 又は翻案したものに当たらないと解される。
(2) 原告は、原告写真と被告写真3において共通する部分である共通点aない しfは創作性のある表現であるから、被告写真3は原告写真を複製又は翻案\nしたものに当たる旨主張するので、以下において判断する。
ア 共通点aについて
原告写真と被告写真3とは、被写体であるスティック春巻を2本ない し3本ずつ両側から交差させている点において共通する。 しかし、証拠(乙9)によれば、角度や向きを変えながら料理を順に 重ねて盛る「重ね盛り」という方法が存在することが認められるところ、 原告写真と被告写真3の被写体であるスティック春巻はいずれも細長い 形状を有するから、スティック春巻を盛り付ける場合に、上記の「重ね 盛り」の方法によってスティック春巻を数本ずつ交差させて配置するこ とは、スティック春巻の撮影する場合に一般的に行われるものであると いうことができる。加えて、証拠(甲25、26、乙2、6ないし8) によれば、共通点aと同様に、棒状の春巻を配置して撮影された写真が 複数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現は、\nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点aは創作的表現であるとはいえないから、被告写\n真3の共通点aの部分が、原告写真の共通点aの部分を複製又は翻案した ものに当たると認めることはできない。
イ 共通点bについて
原告写真と被告写真3とは、2本のスティック春巻を斜めにカットして、 断面を視覚的に認識しやすいように見せ、さらに、チーズも主役でない程 度に見えるようにしている点において共通する。 しかし、具が衣に包まれているという春巻の形状に照らすと、春巻の 具を撮影するためには春巻をカットしなければならないし、その際、具 を強調するために、断面積が大きくなるよう、斜めにカットすることは、 スティック春巻を撮影する際に一般的に採用され得る手法ということが できる。加えて、証拠(甲25、26、乙2、6ないし8)によれば、 共通点bと同様に春巻を斜めにカットした断面を配置して撮影された写 真が複数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表\n現は、ありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点bは創作的表現であるとはいえないから、被告\n写真3の共通点bの部分が原告写真の共通点bの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
ウ 共通点cについて
原告写真と被告写真3とは、端に角度がついた、白色で模様がなく、被 写体である複数本のスティック春巻とフィットする大きさの皿を使用して いる点において共通する。 しかし、証拠(乙10、11)によれば、白い器は料理の色を引き立て る効果があり、選択肢として基本的な色であること、料理の写真を撮影す る際には盛り付ける料理にぴったり合う大きさの皿を選択することが重要 であることが認められる。そうすると、白色で模様がなく、黄土色のステ ィック春巻とフィットする大きさの皿を使用することは、スティック春巻 の写真を撮影する上で一般的に行われ得るということができる。加えて、 証拠(甲25、26、乙2、8)によれば、共通点cと同様に、白色で模 様がなく、被写体である複数本のスティック春巻とフィットする大きさの 皿を使用して撮影された写真が複数存在すると認められることに照らすと、 上記の共通点に係る表現はありふれたものといわざるを得ない。\n以上によれば、共通点cは創作的表現であるとはいえないから、被告\n写真3の共通点cの部分が原告写真の共通点cの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
エ 共通点dについて
原告写真と被告写真3とは、皿に並べた春巻を、正面からでなく、角度 をつけて撮影している点において共通する。 しかし、証拠(乙12)によれば、料理写真の構図として、料理を正面\nから撮影するのではなく、左右に回転させて左右向きに配置して、斜めの 方向から撮影する手法が存在することが認められる。そうすると、皿に並 べた春巻を、角度をつけて撮影することは、一般的に行われ得るというこ とができる。加えて、証拠(甲25、26、乙7、8)によれば、共通点 dと同様に、皿に並べた春巻を、角度をつけて撮影した写真が複数存在す ると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現はありふれたも\nのといわざるを得ない。 以上によれば、共通点dは創作的表現であるとはいえないから、被告\n写真3の共通点dの部分が原告写真の共通点dの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
オ 共通点eについて
原告写真と被告写真3とは、撮影時に光を真上から当てるのではなく、 斜め上から当てることで、被写体の影を付けている点において共通する。 しかし、証拠(乙13)によれば、料理写真の撮影方法として、料理の 斜め後ろから料理に光を当て、料理上部を明るく照らすとともに手前側を 暗くして立体感を生じさせる斜め逆光という手法が存在すること、斜め逆 光は料理写真で最もよく使われるライティングであることが認められる。 したがって、被写体に影を付け、立体感を醸成するという撮影方法は、春 巻を含む料理の写真を撮影する上で一般的に用いられ得る手法であるとい うことができる。加えて、証拠(甲25、26、乙2、6ないし8)によ れば、共通点eと同様に、斜め逆光の手法を用いて撮影された春巻の写真 が多数存在すると認められることに照らすと、上記の共通点に係る表現は\nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点eは創作的表現であるとはいえないから、被告\n写真3の共通点eの部分が原告写真の共通点eの部分を複製又は翻案し たものに当たると認めることはできない。
カ 共通点fについて
原告写真と被告写真3とは、葉物を含む野菜を皿の左上のスペースに置 いている点において共通する。 しかし、揚げ物である春巻に、野菜が付け合わせとして盛り付けられ ることは、一般的に行われることであるといえるから、春巻の写真を撮 影する際に野菜が皿の隅のスペースに置かれることもまた、一般的に行 われることということができる。現に、証拠(甲25、26、乙2、6 ないし8)によれば、上記の共通点と同様に配置された春巻の写真が複 数存在することが認められる。そうすると、上記の共通点に係る表現は\nありふれたものといわざるを得ない。 以上によれば、共通点fは創作的表現であるとはいえないから、被告写\n真3の共通点fの部分が原告写真の共通点fの部分を複製又は翻案したも のに当たると認めることはできない。
キ 全体的観察
前記アないしカのとおり、共通点aないしfはいずれも創作的表現であ\nるとは認められないから、これらの共通点を全体として観察しても、原告 写真と被告写真3との間で創作的表現が共通するとは認められない。\n
ク 小括
以上の次第で、原告写真と被告写真3は、ありふれた表現が共通するに\nすぎず、原告写真と被告写真3との間で創作的表現が共通するとは認めら\nれないから、被告写真3が原告写真を複製又は翻案したものに当たるとは 認められない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2022.03.31
令和3(ネ)10075 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和4年3月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,ダイセン又はWuxi社が本件出願前意匠の存在について悪意 であったから,本件出願前意匠に類似する原告意匠についても悪意であった といえ,原告意匠と類似する被告製品の意匠についてダイセンに先使用権は 成立しない旨主張する。 しかしながら,当時ダイセンの営業部長であったCの陳述書(乙38)に よれば,ダイセン及びWuxi社は,被告製品の開発に当たって,本件出願 前意匠に接する機会はなく,既に市販されていた洗面台用ごみ受けの構成\n(原判決別紙公知意匠目録1ないし3)を参考としつつ,打合せの最中に, つまみ部分があったほうが取り外しやすいという意見が出たことから,取り 外しの便宜のためにつまみ部を付加することにしたことが認められる。かか る開発の経緯は,排水口のごみ受けの分野全般において,円状のフィルタの 周囲につまみ部を設ける構成が珍しくなかったこと(同目録4〜13)に照\nらしても,何ら不自然ではない。 他方,前記第3の2(1)の控訴人の主張が事実であったとしても,被告製品 の開発の過程でWuxi社が本件出願前意匠に接し得たことをうかがわせる 事情(例えば,Wuxi社と控訴人の中国の協力会社との間に人的つながり や地理的近接性があったこと等)は,本件証拠上全くうかがわれない。控訴 人の主張は,ほぼ同じ時期に,同じ中国で製品の開発が行われていたという だけの事実に基づいて,Wuxi社は本件出願前意匠の存在を知ったはずだ とするものであり,到底採用することができない。
(2) 以上によれば,本件出願前意匠と原告意匠との同一性や,原告意匠と被告 製品の意匠との類似性を問うまでもなく,ダイセン又はWuxi社は,意匠 登録出願に係る意匠(原告意匠)「を知らないで」被告製品の意匠を創作し たと認められるから,この点において先使用権の成立要件は充足されている。
◆判決本文
1審はこちら。
2022.03.31
令和3(行ケ)10087 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年3月22日 知的財産高等裁判所
2 登録商標を使用すべき商品について
(1) 商標法50条2項によれば,本件の場合,商標権者たる原告が本件商標の 登録取消しを免れるためには,本件指定商品のいずれかについての本件登録 商標の使用の事実を証明しなければならない。そして,使用の事実は本件指 定商品と同一の商品に限られるのであって,指定商品に類似する商品につい ての使用の事実を証明しても,登録取消しを免れ得ないことは,同条項の文 理上明らかである。商標権のうち禁止権に係る部分すなわち類似部分の使用 は,権利としての使用でなく事実上の使用であるため,商標法50条の意図 する登録商標の使用義務の履行とは認められないからである。 なお,商標法50条2項の適用に当たり,使用する商標については商標法 38条5項かっこ書きが適用されるため,「登録商標と社会通念上同一と認 められる商標」の使用であっても登録取消しを免れ得るが,いかなる商品に ついての使用であるかに関しては商標法に同旨の定めはないから,上記「社 会通念上同一」とは登録商標に関する記述であって,「指定商品と社会通念 上同一と認められる商品」について使用の事実を証明しても,商標の登録取 消しを免れることはできないと解される。
(2) そして,本件指定商品は,「フランス製の被服」であり,「フランス製」 とは,フランス国内で製造された物を意味すると解されるところ,前記認定 のとおり,本件使用商品は,フランス国以外の国で製造された物であるから, 本件使用商品の使用によっては本件指定商品について本件登録商標を使用し たものと認めることはできないというべきである。
3 原告の個別の主張について
(1) 原告は,本件使用商品がフランス国以外の国で製造されたことを自認しつ つも,フランス国で企画,デザイン及び品質管理が行われていることを理由 に,「フランス製の」被服等に当たると認められるべきであるとして,前記 第3の1及び2のとおり種々の主張をする。 しかしながら,同主張に係る事実関係を前提としても,原告の主張は,結 局のところ,本件使用商品(フランスで企画等が行われた被服等)は本件指 定商品(「フランス製の」被服等)と類似すること,あるいは社会通念上同 一と認められることを理由に,本件商標の登録取消しを免れ得ると主張する に等しいものであり,上記のとおり,商標法50条2項の文理に反するから, 採用できない。そして,このことは,商品の原産地表示に関する不正競争防\n止法,関税法並びに不当景品類及び不当表示防止法の一般的な運用(乙2,\n3,5〜8,11)に照らしても明らかである。
(2) 商標審査便覧に係る主張(前記第3の3)につき
原告は,商標審査便覧において,商標法4条1項16号の拒絶理由を解消 するための補正として指定商品に「○○製の」との限定を付すことが示され ているところ,この限定が「製造された」の趣旨であるとは明記されていな いことを指摘する。 しかしながら,商標審査便覧の内容が当裁判所における商標法の解釈適用 を左右しないことは当然である。また,原告の指摘箇所において,「○○製 の」との限定を付す補正は一例として教示されているにすぎないと解され, 現に,「イタリア製の」との限定を付す補正を教示する拒絶理由通知書(甲 21の2)に対して「イタリアにてデザインされイタリア国法人としての出 願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産され た」等の限定を付す補正を行い登録査定に至った登録第6430949号 (甲21の3)のような例もみられるのであるから,商標出願の実務におい て,「○○製の」と「〇〇国でデザインされた」等とは区別されているとい うべきである。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3) 商標法50条の趣旨に係る主張(前記第3の4)につき 確かに,上記認定の事実関係を前提とすれば,本件使用商品はフランス国 で企画等がされた被服等であって「フランス製の」被服等と著しく類似する から,商標の使用を通じた信用の蓄積がない商標を整理しようとする商標法 50条の趣旨に照らして,本件商標の登録を取り消すことはいささか酷であ るともいえる。また,本件商標の場合,出願人(原告)が「フランス製の」 との限定を付す補正をしたのは商標法4条1項16号の拒絶理由を解消する ためやむなく行ったことにすぎず,例えば「フランスで製造,企画,デザイ ン又は品質管理された」のような限定を付す補正が拒絶理由通知書や商標審 査便覧等において教示されていたとすればそれに従った可能性が高い,とい\nう事情もある。 しかしながら,そのような事情があるとしても,前記2のとおり,商標法 50条2項の文理からすれば,「指定商品」を「指定商品と社会通念上同一 と認められる商品」に拡張解釈することは認められないのであるから,かか る拡張解釈を排した本件審決の判断に誤りはない。 なお,原告は,商標法2条1項1号における「商標」と「標章」との使い 分けを根拠に,「社会通念上同一と認められる商標」とは「『社会通念上同 一と認められる標章』が,『社会通念上同一と認められる商品』について使 用されている」と解釈されるべきとも主張するが,独自の解釈であって採用 することができない。
(4) 特許庁における審査実務の一貫性に係る主張(前記第3の5)につき 原告は,外国の地名を含む商標の出願に対して商標法4条1項16号該当 の拒絶理由通知がされた後,「○○製の」ではなく「○○でデザインされ た」等の限定を付す補正によって登録査定に至った例があると主張する。 しかしながら,そのことは,当該補正によって商標法4条1項16号該当 の拒絶理由が解消したと判断されたことを示すにすぎず,「○○でデザイン された」等と「○○製の」とが同義であると判断されたことを示すわけでは ない。したがって,原告の上記主張は,上記2の判断を何ら左右しない。
2022.03.31
令和3(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年3月28日 知的財産高等裁判所
公然実施発明と甲3発明1は、技術分野や作用機能を共通にし、甲3文献に接した当業者であれば、公然実施発明には、スリープ状態にお\nいてホームボタンを押してから認証を経てデバイスにアクセスできるま での一連の動作に関して、デバイスのホームスクリーン又はメニューを 表示する前に、本人認証のためにパスコードの入力を要求することは、パスコードが知られたり、パスワードを忘れたりするという、甲3発明\n1と共通の技術課題が存在することを想起するものといえ、公然実施発 明において、許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセスし、 閲覧することを防ぐため、デバイス機能を有効にする前又はデバイスリソ\ースにアクセスする前の起動時に、デバイスが迅速にユーザを認証することを目的とした甲3発明1を適用する動機付けがあるといえる。
(イ) 原告は、前記第3の1(1)イ(イ)のとおり、公然実施発明では、本件 発明1のように、使用者識別機能を、使用者の操作以外の追加の操作をすることなく、実行するという技術思想は全くない旨主張するが、前記\n(ア)のとおり、甲3発明1に接した当業者であれば、公然実施発明が有 する技術課題及び甲3発明1の適用を想起するものといえ、原告の主張 する当初の技術思想の相違は、その後の技術適用の動機付けの有無と直 接関係するものとはいえないから、原告の上記主張は当を得ないという べきである。
また、原告は、公然実施発明において、ディスプレイがオンにされた 後に、更にディスプレイ上のスライダをドラッグすることで初めて認証 を実行することには、ユーザの誤操作(意図せざる操作等)による誤動 作を防止するという意義があるから、これを改変して本件発明1のよう に構成することは、公然実施発明の技術的意義・機能\を損なう旨の主張 もするが、甲3発明1の使用者識別機能を採用し、指紋によるユーザ認証をしても、認証に係る誤操作は防止できるから、公然実施発明の技術\n的意義・機能を損なうことにはならない。なお、仮に、原告がホーム画面の誤作動防止に係る機能\をも指摘しているとしても、そもそも本件発明1においては、ロック画面からホーム画面への移行の仕方については 何ら規定していないから、操作入力を行った使用者が正当な使用者と認 証された場合に、ディスプレイ上のスライダをドラッグすることで初め てホーム画面に移行する構成も本件発明1の構\成に含まれることにな り(現に本件明細書の図1等においてもスライダが表示されているところである。)、スライダを取り除く改変をしなければ本件発明 1 の構成に至らないわけではないから、原告の主張は前提を誤るものといえる。\nしたがって、原告の主張は、いずれにしても採用できない。
エ 公然実施発明に甲3発明1を適用した場合に、本件発明1の構成に容易に想到するかについて\n
(ア) 甲3発明1において、指紋による認証の結果を得るには一定の時間 を要することは、明らかである。また、公然実施発明に甲3発明1を適 用することで、ホームボタンを押下すると、起動によりディスプレイが オンになり、それと同時に指紋認証を行い(別紙4のA図右及びB図1 左)、認証が成功すれば、追加の操作を要することなく、更にホーム画面 に移行するという構成を得ることが可能\である(別紙4のB図1右)。 そして、本件発明1で特定されるロック画面は、「前記非活性状態の際 になされた前記活性化ボタンに対する使用者の操作に基づいて」「表示され」るものであって、ロックが解除されていない状態を表\示する機能以\n外は特定されていない。そうすると、公然実施発明に甲3発明1を適用 したものにおいて、ホームボタンの押下後、オンになったディスプレイ にホーム画面に移行する前に表示される画面も、客観的にロックが解除されていない状態を表\示するものであり、これを「ロック画面」ということができる。したがって、公然実施発明に甲3発明1を適用した場合、使用者によ る追加の操作なしに、指紋認識による使用者識別機能が、非活性状態からロック画面が表\示された活性状態への切り替えのための操作入力により行われるという、本件発明1の構成に容易に想到するということができる。\n
(イ) 原告は、前記第3の1(1)イ(ウ)aのとおり、甲3発明1においても、 ロックを解除するために画面上のスライダのドラッグ操作を受け付け る構成となっているから、公然実施発明に甲3発明1を組み合わせた場合には、当業者は、公然実施発明と甲3発明1の共通の技術思想をなす\n上記構成を残しつつ甲3発明1の指紋認証を行うことを想到することになり、ディスプレイが活性化された後にスライダのドラッグという追\n加の操作を要することになるから、本件発明1の構成とはならない旨主張する。しかし、前記イ(ア)aのとおり、甲3文献からは、ホームボタンの背 後にセンサを配置し、ユーザが当該ホームボタンを押下した時に、ユー ザからの明示的な入力を要求することなく、指紋による認証を行う構成も、甲3発明1として認定することができるのであるから、原告の主張\nは採用できない。
(ウ) 原告は、前記第3の1(1)イ(ウ)bのとおり、公然実施発明の構成においては、ロック状態の画面を表\示させ、その画面上に表示されるスラ\nイダがドラッグされたときに初めて、次のパスコードの入力画面に移行 し、パスコードを入力させて認証を行う、という一連の認証操作を行わ せるものであるから、公然実施発明の使用者識別機能に係る手順のうちロック状態の画面上でのスライダをドラッグする処理を排除するので\nあれば、ロック画面も用いない構成しか想到できない旨主張する。しかし、前記(ア)のとおり、「ロック画面」自体は、ロックが解除さ れていない状態を示す画面であり、スライダのドラッグ操作とロック画 面の表示を不可分一体のものとして捉えなければならない理由はないから、原告の主張は採用できない。\n
(エ) 原告は、前記第3の1(1)イ(ウ)cのとおり、公然実施発明のロック 画面は、パスコードの入力における意図せぬ誤操作を防止する意義・機 能があるとした上で、甲3発明1の「シームレス」に使用者識別機能\を 行う構成とは両立しない旨主張する。しかし、公然実施発明において、甲3発明1の使用者識別機能\を採用し、ロック解除する時に指紋によるユーザ認証をしても、偶発的な誤操作等は防止できることは前記ウ(イ) のとおりであって、原告の主張は採用できない。
(オ) 原告は、前記第3の1(1)イ(ウ)dのとおり、別紙4のB図1左には スライダが表示されているところ、指紋認証に成功した場合に「当該成功後に直ちにホーム画面に遷移する構\成」であるとされる以上、スライダの機能は利用されず、当業者がそのように何ら機能\を発揮しないスラ イダをあえて表示させる構\成を考え付くとすれば、本件発明1を見た上 での後知恵である旨主張する。
原告の主張の真意は判然としないが、そもそも本件発明1においては、 ロック画面からホーム画面への移行の仕方については何ら規定してい ない(したがって、この場面におけるスライダの表示の有無やその利用の有無等についても何も限定はない)ことは前記ウ(イ)において説示し たとおりであるところ、被告の主張如何にかかわらず、公然実施発明に 甲3発明1を組み合わせた場合に、正当な使用者と認証されたときに、 スライダを利用しようとしなかろうと、どちらにしてもロック画面から ホーム画面へ移行させることが可能であること自体は明らかであるから、原告の主張は失当というほかない。\n
(4) 小括
その他原告がるる主張する点は、いずれもその前提に誤りがある、あるい は理由がないものであり、採用できない。 以上によれば、相違点1についての容易想到性を認めた本件審決の判断に 誤りはないから、原告主張の取消事由1は理由がない。
◆判決本文
関連事件です。
◆令和3(行ケ)10054
本件の侵害事件です。
◆令和3(ネ)10081
上記控訴審の1審です。104条の3で権利行使不能と判断されています。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.03.30
平成31(ワ)11108 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年3月11日 東京地方裁判所
不競法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示(人の業務に係る氏名、\n商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示す\nるものをいう。以下同じ。)と同一又は類似の商品等表示を使用等すること\nをもって、不正競争に該当する旨規定している。この規定は、周知な商品等 表示の有する出所表\示機能を保護するという観点から、周知な商品等表\示に 化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得す る行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保するものと解される。そし て、商品の形態(色彩を含むものをいう。以下同じ。)は、特定の出所を表\n示する二次的意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的に は商品の出所表示機能\を有するものではないから、上記規定の趣旨に鑑みる と、その形態が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能\を 発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないというべ\nきである。そうすると、商品の形態は、1)客観的に他の同種商品とは異なる 顕著な特徴(以下「特別顕著性」という。)を有しており、かつ、2)特定の 事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極 めて強力な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の 出所を表示するものとして周知(以下、「周知性」といい、特別顕著性と併\nせて「出所表示要件」という。)であると認められる特段の事情がない限り、\n不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。\n
そして、商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一\n部の商品形態が商品等表示に該当しないときであっても、上記商品に関する\n表示が全体として商品等表\示に該当するとして、その一部の商品を販売等す る行為まで不正競争に該当するとすれば、出所表示機能\を発揮しない商品の 形態までをも保護することになるから、上記規定の趣旨に照らし、かえって 事業者間の公正な競争を阻害するというべきである。のみならず、不競法2 条1項1号により使用等が禁止される商品等表示は、登録商標とは異なり、\n公報等によって公開されるものではないから、その要件の該当性が不明確な ものとなれば、表現、創作活動等の自由を大きく萎縮させるなど、社会経済\nの健全な発展を損なうおそれがあるというべきである。そうすると、商品に 関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商\n品等表示に該当しないときは、上記商品に関する表\示は、全体として不競法 2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。\n
これを本件についてみると、原告表示は、別紙原告表\示目録記載のとおり、 原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定されるにとどまり、女 性用ハイヒールの形状(靴底を含む。)、その形状に結合した模様、光沢、 質感及び靴底以外の色彩その他の特徴については何ら限定がなく、靴底に付 された唯一の色彩である原告赤色も、それ自体特別な色彩であるとはいえな いため、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含むものである。
そして、前記認定事実及び第2回口頭弁論期日における検証の結果(第2 回口頭弁論調書及び検証調書各参照)によれば、原告商品の靴底は革製であ り、これに赤色のラッカー塗装をしているため、靴底の色は、いわばマニュ キュアのような光沢がある赤色(以下「ラッカーレッド」という。)であっ て、原告商品の形態は、この点において特徴があるのに対し、被告商品の靴 底はゴム製であり、これに特段塗装はされていないため、靴底の色は光沢が ない赤色であることが認められる。そうすると、原告商品の形態と被告商品 の形態とは、材質等から生ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を 異にするものであるから、少なくとも被告商品の形態は、原告商品が提供す る高級ブランド品としての価値に鑑みると、原告らの出所を表示するものと\nして周知であると認めることはできない。そして、靴底の光沢及び質感にお ける上記の顕著な相違に鑑みると、この理は、赤色ゴム底のハイヒール一般 についても異なるところはないというべきである。
したがって、原告表示に含まれる赤色ゴム底のハイヒールは明らかに商品\n等表示に該当しないことからすると、原告表\示は、全体として不競法2条1 項1号にいう商品等表示に該当しないものと認めるのが相当である。\n
のみならず、前記認定事実によれば、そもそも靴という商品において使用 される赤色は、伝統的にも、商品の美感等の観点から採用される典型的な色 彩の一つであり、靴底に赤色を付すことも通常の創作能力の発揮において行\nい得るものであって、このことはハイヒールの靴底であっても異なるところ はない。そして、原告赤色と似た赤色は、ファッション関係においては国内 外を問わず古くから採用されている色であり、現に、前記認定事実によれば、 女性用ハイヒールにおいても、原告商品が日本で販売される前から靴底の色 彩として継続して使用され、現在、一般的なデザインとなっているものとい える。そうすると、原告表示は、それ自体、特別顕著性を有するものとはい\nえない。また、前記認定事実によれば、日本における原告商品の販売期間は、 約20年にとどまり、それほど長期間にわたり販売したものとはいえず、原 告会社は、いわゆるサンプルトラフィッキング(雑誌編集者、スタイリスト、 著名人等からの要望又は依頼に応じて、これらの者が雑誌の記事、メディア での撮影等で使用するため原告商品を貸し出すという広告宣伝方法をいう。) を行うにとどまり、自ら広告宣伝費用を払ってテレビ、雑誌、ネット等によ る広告宣伝を行っていない事情等を踏まえても、極めて強力な宣伝広告が行 われているとまではいえず、原告表示は、周知性の要件を充足しないという\nべきである。したがって、原告表示は、そもそも出所表\示要件を充足するも のとはいえず、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当するものとはい\nえない。
(3) また、前記認定事実によれば、原告商品は、最低でも8万円を超える高価 格帯のハイヒールであって、靴底のラッカーレッド及びその曲線的な形状に 加え、靴の形状、ヒールの高さその他の形態上の顕著なデザイン性を有する 商品であるのに対し、被告商品は、手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒール であることからすると、ハイヒールの需要者は、両商品の出所の違いをそれ 自体で十分に識別し得るものと認めるのが相当である。さらに、いわゆる高\n級ブランドである原告商品のような靴を購入しようとする需要者は、その価 格帯を踏まえても、商品の形態自体ではなく、商標等によってもその商品の 出所を確認するのが通常であって、原告商品、被告商品とも、中敷や靴底に ブランド名のロゴが付されているのであるから、需要者は当該ロゴにより出 所の違いを十分に確認することができる。しかも、原告商品のような高級ブ\nランド品を購入しようとする需要者は、自らの好みに合った商品を厳選して 購入しているといえるから、旧知の靴であれば格別、現物の印象や履き心地 などを確認した上で購入するのが通常であるといえ、上記の事情を踏まえて も、このような場合に誤認混同が生じないことは明らかである。 このような取引の実情に加え、原告商品と被告商品の各形態における靴底 の光沢及び質感における顕著な相違に鑑みると、原告商品と被告商品とは、 需要者において出所の混同を生じさせるものと認めることはできない。 そうすると、被告商品の販売は、不競法2条1項1号にいう不正競争に明 らかに該当しないものと認められる。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2022.03.30
令和1(ワ)10829 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和4年2月10日 大阪地方裁判所
(イ) 本件意匠1の実施品である原告製品1は、使用者がその柄を握り、枝部の先 端の涙滴状部を頭部(頭皮)に当てた状態で、枝部から涙滴状部にかけて力を加え て動かしながら、頭部をマッサージするものである。
(ウ) このような頭部マッサージ具の購入に当たり、需要者は、通常、店舗であれ ば店頭に置かれた商品そのものないし商品パッケージに付された商品画像等を、イ ンターネット上であれば EC サイト等に掲載された商品画像等を視認する。 原告製品1のパッケージ(以下「本件パッケージ1」という。)は、台紙上に製 品を正面側から視認できる状態で設置し、これを透明なプラスチックケースで覆う ものである。台紙の表面(商品側)には、「頭のラインに沿って/頭皮をかき上げ\n/キュっと引き締め」(「/」は改行部分を示す。以下同じ。)という説明文と、 使用者が原告製品1の柄を持ち、その涙滴状部を頭皮に当てている画像(以下「本 件画像1−1」という。)及び人物の頭部を他者が両手の手指を広げてマッサージ するイメージ画像と、涙滴状部を頭皮に当て枝部の先端方向に動かしてマッサージ することをうかがわせるイラスト(以下「本件イラスト1」という。)等が掲載さ れている。本件画像1−1及び本件イラスト1に掲載された原告製品1の画像等は、 いずれも、正面側を斜め上方向から見たものである。また、台紙の裏側には、「使 用方法」として「突起部分をヘッドラインに沿って頭皮に当て、押しながらかき上 げてください。」との説明文(以下「本件説明文1」という。)や、本件画像1− 1と同様のイラスト及び本件イラスト1が掲載されている。(乙1) 他方、原告サイトの原告製品1の紹介ページ(乙12)には、上部に商品画像と して本件パッケージ1の画像及び以下の画像から説明文や矢印等を除いた商品自体 のみの画像の2つの画像のうち1画像が拡大表示可能\とされているほか、「ヘッド ラインタイプ/頭のラインに沿って/頭皮をかき上げてキュッ」という説明文、本 件画像1−1と同様の画像に人物の頭部に使用方向を示す矢印が三本描かれている 画像、本件イラスト1及び本件説明文1が掲載されているほか、次の画像(以下 「本件画像1−2」という。)が掲載されている。
(エ) 需要者が注意を惹かれる部分
上記各事情に照らせば、需要者は、原告製品1の使用に当たり、頭部マッサージ の効果に直截的に影響を与える部分である枝部の本数、頭皮に直接当たる部分であ る枝部の先端の形状、柄から涙滴状部に力を伝える部分である枝部の形状に主に注 目すると考えられる。他方、各涙滴状部間の距離については、さほど注意を惹かれ ないと思われる。 また、性質上頭部マッサージを現に実施している間に原告製品1を直接視認する ことは困難と思われるものの、事前ないし事後の時点では、これを正面側ないし正 面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多いものと考 えられる。他方、原告製品1の購入に当たっては、需要者は、これを正面側ないし 正面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多く、左右 各側面側、平面側及び背面側から視認する機会は乏しいと考えられる。
イ 本件公知意匠1について
(ア) 証拠(乙2、3)によれば、本件公知意匠1は、いずれも本件出願日1 (平成20年3月6日)前に公知となった意匠と認められる。
(イ) 乙2意匠
証拠(甲17、乙2、15、24)及び弁論の全趣旨によれば、乙2意匠は、次 のとおりのものと認められる。 乙2意匠は、いわゆる「孫の手」であり、背中を掻いたり、身体を叩いたりする 目的で使用される物品に係る意匠である。この種の商品は、頭部を掻いたり叩いた りする方法で頭部に刺激を与える目的で使用される場合もある。そのため、乙2意 匠は、本件意匠1の属する分野と同一の分野に属しないものとはいえない。 もっとも、乙2意匠は、正面視において、柄の先端に接続された板状の部材が、 接続部側と先端側との間の中央付近で湾曲し、湾曲した先の先端側部分が平行な5 本の枝部に枝分かれしているものである。乙2意匠における「基端」を柄の先端と の接続部と捉えるならば、枝部は、熊手状に湾曲させて形成されてはいるものの、 基端からは分岐しておらず、また、各枝部は丸棒状ではなく板状に形成されている。 他方、板状の部材の接続部側と先端側との間の中央付近の湾曲部付近を「基端」と 捉えるならば、乙2意匠の枝部は、基端から5本に分岐し、熊手状に湾曲させて形 成されたものとはいえるものの、各枝部が丸棒状ではなく板状に形成されているこ とは、同様である。 さらに、「基端」をいずれと捉えるかにかかわらず、各枝部の先端部は、丸みの ある形状とされてはいるものの厚みに変化はなく、涙滴状部に相当するものはない。 各枝部間の距離も、各枝部の先端部の幅に比してかなり狭い。
(ウ) 乙3意匠
証拠(乙3)及び弁論の全趣旨によれば、乙3意匠は次のとおりのものであると 認められる。 乙3意匠は、人やペット等の背中や腹部を掻いたり、マッサージするためなどに 使用される物品に係る意匠である。これも、乙2意匠と同様に、本件意匠1の属す る分野と同一の分野に属しないものとはいえない。 乙3意匠は、人の手をそのまま模した形状であり、その指部をもって「基端から 5本に分岐した丸棒状の枝部」と捉えることは、一応可能である。もっとも、乙3\n文献を見る限り、指部(枝部)は、基端から先端まで熊手状に湾曲しているとはい えず、また、その先端に涙滴状部が形成されていない。さらに、乙3意匠が本件意 匠1の具体的構成要件 C1-3〜E1-3 に相当する構成を有するとも認められない。\n
(エ) 以上のとおり、本件公知意匠1のうち、乙2意匠は、5本に分岐した枝部が 形成されている点及び枝部が熊手状に湾曲させて形成されている点で、また、乙3 意匠は、「基端から5本に分岐した丸棒状の枝部」と捉えることが可能な部分があ\nる点で、それぞれ本件意匠1と共通する部分があるといえるにとどまる。もっとも、 その共通するといえる部分の具体的形状は、本件意匠1とは大きく異なる。 そうである以上、本件公知意匠1は、本件意匠1の基本的構成態様及び具体的構\ 成態様いずれとの関係でも、本件意匠1に先行する公知意匠ということはできない。 その他本件意匠1の要部を判断するにあたり参考とすべき公知意匠は、証拠上見当 たらない。
ウ 本件後願意匠
登録意匠の要部認定に当たっては、先行する公知意匠を考慮すべきではあっても、 登録意匠の出願に後れる後願意匠を考慮することは、原則として相当でない。また、 この点を措くとしても、証拠(乙4)によれば、乙4意匠は、涙滴状部に金属球を 有する点で本件意匠1の形状と明確に異なること、証拠(乙5)によれば、乙5意 匠は、基端から5本に分岐した丸棒状の枝部が全体として人の手指の指部を想起さ せる形状となっており、その先端に涙滴状部がない点で本件意匠1の形状と明確に 異なることなどから、本件後願意匠は、翻って本件意匠1の要部を判断するものと して参考となり得るものではない。
エ 小括
以上の事情を総合的に考慮すれば、本件意匠1の要部は、基本的構成態様 A1-3 及び B1-3 並びに具体的構成態様 D1-3 であると見るのが相当である。
・・・
イ 差異点について
(ア) 差異点 A について
差異点 A は、平面視における枝部の湾曲の程度と、これによる左右各側面視にお ける涙滴状部の配置に係るものである。需要者が原告製品1及び被告製品1を平面 側及び左右の側面側から視認する機会が乏しいこと等を踏まえれば、差異点 A は、 本件意匠1と被告意匠1とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異とはいえない。
(イ) 差異点 B 及び C について
差異点 B は、正面視における一番外側の枝部の湾曲の形状に係るもの、差異点 C は、等間隔に配置された涙滴状部間の距離に係るものである。 これらの差異点は、いずれも、原告製品1及び被告製品1を正面側から視認する ことにより認識し得るものであり、需要者はこれを目にする機会が多いといえる。 もっとも、上記各差異点は、中央の枝部がほぼ直線状に伸び、外側にいくにつれて 枝部の湾曲の程度が大きくなるという共通点 B や、枝部の先端の涙滴状部が等間隔 に配置されているという共通点 C がある中で、一番外側の枝部の先端近くの形状や、 涙滴状部間の距離がいささか異なるというにとどまり、顕著に特徴的なものとまで はいえず、本件意匠1と被告意匠1とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異で はない。
ウ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると、本件意匠1と被告意匠1は、その骨格的な構\n成態様において共通し、両意匠の差異点は、それ自体も、また、これらを組み合わ せたとしても、そのもたらす印象をもって共通点により需要者に生じる美感の共通 性を凌駕するほどのものということはできない。
・・・・
) 法39条2項による損害額の推定覆滅に係る部分については、同項に基づく 推定が覆滅されるとはいえ、無許諾で実施されたことに違いはない以上、当該部分 に係る損害評価が尽くされたとはいえない。したがって、当該部分については、同 条3項が重畳的に適用されると解するのが相当である。この点に関する被告の主張 は採用できない。
・・・
b 検討
被告製品1と原告製品1は、共に頭部マッサージ具である。原告製品1は枝部の 先端に形成された涙滴状部を頭部の形状に沿って押し当て、押しながらかき上げる といった使用方法が想定されている(乙1)のに対し、被告製品1は、枝部の先端 に形成された涙滴状部を頭皮に押し当て、微細な振動を与えるといった使用方法が 想定されている(甲3、4、乙29)。このように、両製品は、具体的な使用方法 は異にするものの、枝部の先端に形成された涙滴状部を頭皮等のマッサージ対象部 位に押し当ててマッサージを行うものである点で、その基本的な用途を同じくす る。両製品の販売価格には2倍以上の差があるものの、具体的な価格差は610円 (税抜)であり、「プチプラ」のもともとの意義はともかく、市場において「プチ プラ」と呼ばれる廉価な生活雑貨品のカテゴリーにいずれも分類されることがある 以上、両製品は、その価格差を踏まえても、市場において競合するものといえる。 また、被告は、被告各製品を被告店舗等のみで販売しているものの、被告店舗の 出店先の商業施設に原告の製品を取り扱う店舗も出店している例が多数ある。こう した商業施設では、需要者は、商業施設内の各店舗を巡って目的に適う同種製品を 比較検討して購入することが可能であり、実際上も、このような行動はしばしば見\n受けられる。さらに、被告製品1が販売されている EC サイトは被告サイトのみで あるとしても、被告店舗等で被告製品1に触れた需要者が、他の EC サイトで頭部 マッサージ具を検索することは容易であり、これもしばしば見受けられる行動とい えるのであって、その結果、複数の EC サイトにおいて販売されている原告製品1 が検索結果として表示されることも容易に推察される。\nこのような事情を踏まえれば、業務態様ないし販売チャンネルのあり方における 原告と被告との違いや被告製品1と原告製品1との価格差は、損害額の推定を覆滅 すべき事情とはいえないか、いえるとしてもその程度は限られる。 これに対し、被告は、被告店舗での取扱商品の多様さや、商品ラインナップにお ける被告製品1の位置付けなどから、需要者は、被告店舗を訪れて被告製品1に触 れた際に始めて被告製品1の存在を知り、そのまま衝動的に購入する場合が多く、 被告製品1が存在しなければそもそも頭部マッサージ具の需要が発生しないか、需 要者が当初より被告製品1を購入する意思をもって被告サイトで被告製品1を購入 しているため、被告製品1が販売されなくともその分の需要が原告製品1に吸収さ れるとはいえないなどと主張する。しかし、そのような需要者の購買行動等があり 得るとしても、被告製品1の需要者の全てないし多くがそのように行動すると考え るべき根拠はない。被告製品1が廉価なことを踏まえても、価格のみならずその機 能やデザイン等を含む総合的な評価に基づいて、同種製品と比較検討の上で購入に\n至る需要者も一定数存在すると考えるのが、むしろ経験則に合致する。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 できない。
(ウ) 競合品の存在
本件意匠1及び被告意匠1の各構成態様並びに原告製品1及び被告製品1の具体\n的な使用態様等を踏まえると、乙28の各ウェブサイト掲載商品に係る別紙「被告 主張の競合品一覧(本件意匠1)」のうち、少なくとも1)、2)、4)〜6)、9)、10)、 15)、20)、21)は、原告製品1及び被告製品1の競合品と認められる。 そうすると、被告製品1が市場に存在しない場合、被告製品1に係る需要の全て が原告製品1に吸収されるとは限らないから、これらの競合品の存在は、被告が得 た利益と原告が受けた損害との間との相当因果関係を阻害するものとして、損害額 の推定を一定程度覆滅させる事情として考慮すべきである。
(エ) 被告の営業努力等
証拠(甲41、乙45〜49)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、約6年の間 に全国的に被告店舗を多数展開し(令和3年5月時点で62店舗)、複数のウェブ サイトで人気の生活雑貨店として取り上げられていることが認められることなどを 踏まえると、被告ブランドは一定程度需要者に認知されているとうかがわれる。 もっとも、被告自身、被告製品1につき被告の主力商品として販売されていたも のではないと主張していることに加え、被告製品1に特化した宣伝広告等がされた ことを認めるに足りる証拠もないこと、廉価な生活雑貨品という被告製品1の性格 等を踏まえると、被告製品1を購入する需要者にとって、被告ブランドの取扱商品 であることが主な購入の理由ないし動機となっているとは考え難い。 その他被告の格別な営業努力が被告製品1の売上増加に貢献していると見るべき 具体的な事情はない。 したがって、被告の営業努力等は、損害額の推定を覆滅すべき事情とはいえない か、いえるとしてもその程度は限られる。
(オ) 侵害品の性能\n
前記((イ)b)のとおり、被告製品1は、枝部の先端に形成された涙滴状部を頭 皮に押し当て、微細な振動を与えることにより頭皮をマッサージする効果を奏する 商品であり、涙滴状部を頭部の形状に沿って押し当て、押しながらかき上げるとい った使用方法が想定されている原告製品1とは、その具体的な使用方法において異 なる。この使用方法の相違は、実用品である頭部マッサージ具の機能に関わるもの\nである。実用品である以上、商品の機能性は、デザインと同等かそれ以上に需要者\nの商品選択において重要な要因として位置付けられる。このことは、被告が商品デ ザインを重視した商品開発を行い、需要者に対してこれを訴求していることがうか がわれること(甲81〜83)などを考慮しても異ならない。 したがって、原告製品1と被告製品1の具体的な使用方法の相違すなわち機能面\nの相違は、損害額の推定を相当程度覆滅すべき事情といえる。
(カ) 覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すると、本件では、被告製品1に係る原告の損害額の 推定につき、4割の限度で覆滅されるとするのが相当である。これに反する原告及 び被告の各主張はいずれも採用できない。 そうすると、被告の本件意匠権1侵害による原告の損害額は、●(省略)●円 (=●(省略)●*(1-0.4))となる。
オ 法39条2項及び3項の重畳適用、実施料率
(ア) 法39条2項による損害額の推定覆滅に係る部分については、同項に基づく 推定が覆滅されるとはいえ、無許諾で実施されたことに違いはない以上、当該部分 に係る損害評価が尽くされたとはいえない。したがって、当該部分については、同 条3項が重畳的に適用されると解するのが相当である。この点に関する被告の主張 は採用できない。
(イ) 実施に対し受けるべき金銭の額
「意匠の実施に対し受けるべき金銭の額」(法39条3項)すなわち意匠の実施 に対し受けるべき料率は、当該意匠の実際の実施許諾契約における実施料率や、そ れが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、当該意 匠自体の価値、当該意匠を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の 態様、意匠権者と侵害者との競業関係や意匠権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合的に考慮して、合理的な料率を定めるべきである。また、その際、必ずしも 当該意匠権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必 然性はなく、意匠権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受 けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと を考慮すべきである。 また、不当利得返還請求に関し、当該「受けるべき金銭の額に相当する額」は、 本来、意匠権者がその登録意匠の実施に当たり意匠権者に対して支払うべきであっ た実施料相当額であるから、侵害者がこれを支払うことなく登録意匠を実施した場 合は、その実施により、侵害者は同額の利得を得、意匠権者は同額の損失を受けた ものと評価することができる。したがって、法39条3項の「受けるべき金銭の額 に相当する額」が不当利得における受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の損 失の額に相当すると認めるのが相当である。
(ウ) まず、本件意匠権1に係る実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる 証拠はなく、その他原告が本件意匠権1に係る実施許諾契約を締結する場合に定め る実施料率をうかがわせる事情はない。 また、「実施料率〔第5版〕技術契約のためのデータブック」(甲59)によれ ば、「プラスチック製品」の技術分野(その対象には、「プラスチック板・棒・管 ・継手・異形押出製品製造技術、・・・その他のプラスチック製品製造技術」であり、 「その他のプラスチック製品」とは「プラスチック製台所用品・浴室用品等」であ るが、「プラスチック製の家具(29)・ブラシ(31)・履物(27)等」は含まれ ない。)における外国技術導入契約の実施料(許諾製品の出来高にリンクした料率 表示であったもの)につき、平成4年度〜平成10年度の外国技術導入契約(イニ\nシャルロイヤリティがないもの。63件)の場合、平均値は3.9%、中央値は3 %であった(なお、甲59には、このほかに技術分野を「ゴム製品」とする項も存 するが、その対象は、タイヤ・チューブ製造技術、ゴム製・プラスチック製履物・ 同付属品製造技術等であり、被告製品1の分野と類似するものがないから、これを 参考とするのは相当でない。)。また、「ロイヤルティ料率データハンドブック〜 特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」(甲60)によれば、「個 人用品または家庭用品」の技術分類における実施料率(13件)は、平均が3.5 %、標準偏差1.6%、最大値7.5%、最小値0.5%であり、「健康;人命救 助;娯楽」の技術分類(54件)では、平均5.3%、標準偏差3.2%、最大値 14.5%、最小値0.5%である。
さらに、前記(エ(イ)b、エ(オ))のとおり、被告製品1の需要者は、製品の機能\nを中心に、デザイン及び価格性を総合的に考慮した上で商品選択を行うものと見ら れることから、本件意匠1ないしこれに類似する被告意匠1を用いた場合の売上及 び利益への貢献の程度の評価にあたっても、これを踏まえる必要がある。 加えて、原告製品1と被告製品1はいずれも頭部マッサージ具であることに加 え、原告と被告は、取扱い商品や販売店舗の出店先が相当程度に重複していること から、高い程度で競合関係にあるといえる。このため、仮に原告が被告に対し本件 意匠権1に係る実施許諾契約を締結するならば、その実施料は高めに設定されるの が通常であると考えられる。しかも、証拠(甲64〜69)及び弁論の全趣旨によ れば、原告は、自己の保有する登録意匠に係る侵害品の防止に積極的に努めている ことがうかがわれる。
以上の事情に加え、意匠権侵害に基づく損害賠償請求の場面での仮想実施料率の 考察であることを総合的に考慮すると、本件意匠権1を侵害した者に対して事後的 に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は5%を下らないというべきであ る。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。 そうすると、法39条3項により認められる損害賠償請求の額は、●(省略)● 円(≒●(省略)●*0.4*0.05)となる。
2022.03.30
令和2(ワ)19931等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月16日 東京地方裁判所
いわゆる医薬用途発明においては,一般に,当業者にとって,物質名, 化学構造等が示されることのみによっては,当該用途の有用性及びそのた\nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり,当該発明に係る医薬\nを当該用途に使用することができないから,そのような発明において実施 可能要件を満たすためには,明細書の発明の詳細な説明に,薬理データの\n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより,当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明1及び2の特許請求の範囲においては,本件化合物が「痛みの 処置における」(構成要件1B)「鎮痛剤」(構\成要件1C)及び「鎮痛 剤」(構成要件2C)として作用することが記載されているところ,いず\nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし, 本件明細書には,本件化合物について,「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛,術後疼痛,転移癌に伴う骨関節炎の痛み, 三叉神経痛,急性疱疹性および治療後神経痛,糖尿病性神経障害,カウザ ルギー,上腕神経叢捻除,後頭部神経痛,反射交感神経ジストロフィー, 線維筋痛症,痛風,幻想肢痛,火傷痛ならびに他の形態の神経痛,神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」(前記1(1)イ)と記載されて いることに照らすと,本件発明1及び2は,本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって,本件発明1及び2について実施可能要件を満たすというた\nめには,本件明細書の発明の詳細な説明に,薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより,上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ア)の各文献の記載によれば,本件出願当時,術後疼痛試験は,ラ ットの皮膚,筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより,痛 覚過敏を引き起こし,これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが,技術常識であったと認められる。 そして,本件明細書には,「S−(+)−3−イソブチルギャバ」\n(弁論の全趣旨によれば,構成要件3Aを充足する本件化合物の一種で\nあると認められる。)が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており,さらに,「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後1時間以内にピークに達 し,3日間維持された。実験期間中,動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」(前記1(1)キ(キ)),「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも3時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は,ギャバペンチンおよびS− (+)−3−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して\nも等しく有効なことである。」(同(コ))との記載がある。 以上によれば,本件出願当時,本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は,本件化合物について,侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し,その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明3の構成と均等なものであるかについて\n
(ア) 原告は,本件発明3は,慢性疼痛に対する画期的処方薬として,抗て んかん作用を有するGABA類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり,その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから,対象となる痛みが侵害受容性疼痛か,神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく,効能・効果を神経障害性疼痛や\n線維筋痛症に伴う疼痛とし,慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は,均等侵害の第1要件を満たすと主張する。
しかし,前記1(1)アのとおり,本件特許に係る発明は,てんかん,ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が,痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し,反復使用により耐性を生じず,モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ,前記2(1)イのとおり,本件 出願当時,痛みには種々のものがあり,その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると,いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは,本件発明 3において本質的部分というべきであり,その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は,本件発明3の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって,本件発明3に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明3の本質的部分でない\nということはできないから,被告医薬品は均等の第1要件を満たさない。
(イ) また,前記(1)アによれば,原告は,本件訂正前発明3においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ,本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると,本件発明3との関係においては,被告医薬品の効能・効果\nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって,被告医薬品は均等の第5要件も満たさない。
(ウ) 以上によれば,被告医薬品は,本件発明3の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。\n
イ 被告医薬品が本件発明4の構成と均等なものであるかについて\n
前記アと同様に,いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは,本件発 明4の本質的部分というべきであり,被告医薬品は均等の第1要件を満た さず,また,本件発明4との関係においては,被告医薬品の効能・効果で\nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から,均等の第5要件も満たさない。 したがって,被告医薬品は,本件発明4の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。\n
◆判決本文
関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.03.29
令和3(ネ)10083 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和4年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人は,控訴人表示画面と被控訴人表\示画面との一致箇所をひとまとまり として捉えて創作性を判断すべきこと,ビジネスソフトウェアのディスプレイ(表\ 示画面をいう趣旨と解される。)における表現の創作性については丁寧な検討が必\n要であること,控訴人表示画面について表\現上主要な箇所は2)データ分析等画面(単 品詳細情報画面,日別画面,他店舗在庫表示画面,定期改正入力画面,リクエスト\n管理画面)であり,そこには表現上の工夫が多数散りばめられていることなどを主\n張する。
しかし,被控訴人製品の各表示画面から控訴人製品の各表\示画面の本質的な特徴 を感得することはできず,被控訴人表示画面に接する者が全体として控訴人表\示画 面の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるとは認められないことは,\n訂正して引用した原判決の第4の1で認定判断したとおりである。 控訴人表示画面と被控訴人表\示画面の対比に係る判断は,同1(3)のとおりであ って,控訴人表示画面と被控訴人表\示画面の共通する部分をひとまとまりにして検 討することによって,上記判断が左右されるものではない。ビジネスソフトウェア\nのディスプレイ(表示画面)における表\現の創作性について丁寧な検討が必要であ るという一般論の主張も,上記判断に影響しない。控訴人が2)データ分析等画面に 多数散りばめられていると主張する表現上の工夫のうち,発注操作を行う欄の配色\nについては,創作者の思想又は感情が創作的に表現されているといえる程度の特徴\nを有するものとは認められず,同欄の位置や詳細情報を画面の下方に配置すること は,書店業務を効率的に行うという観点から通常想定される範囲内のものである。 控訴人の主張する2)データ分析等画面における素材の選択及び配列における選択の 幅についても,訂正して引用した原判決の第4の1(4)で判断したとおりである。
イ 控訴人は,控訴人製品の表示画面と被控訴人製品の表\示画面に共通性が多数 認められること,操作ガイダンスの文字列に一致が何か所もあることなどを主張す るが,それらの主張は,訂正して引用した原判決の第4の1の認定判断を左右する ものではない。
(2) 争点4(不正競争防止法違反の有無)に関する控訴人の補充主張について
ア 控訴人は,控訴人表示画面の特別顕著性に関し,需要者を書店ユーザーに限\n定すべきこと,控訴人製品がその表示画面に顕著な特徴を有することを主張するが,\n控訴人表示画面の特徴に関しては訂正して引用した原判決の第4の1(3)及び(4)で 認定判断したとおりであり,控訴人表示画面に特別顕著性が認められないことは,\n同3で判断したとおりである。控訴人の主張するように控訴人製品の需要者を書店 に限定したとしても,上記の認定判断は左右されない。
イ 控訴人は,周知性についても主張するところ,控訴人製品のシェアについて 控訴人が当審で追加提出した証拠(甲83の1・2,甲84)を含む本件全証拠を もってしても,控訴人の主張するシェアを認めるに足りない。なお,仮に,控訴人 製品が相応のシェアを占めているとしても,そのことから直ちに,控訴人表示画面\nの周知性が認められるものともいえない。 また,控訴人は,控訴人製品の宣伝・広報活動について主張するが,当該活動に ついて控訴人が追加提出した証拠(甲85〜91)を含む本件全証拠をもってして も,当該活動は一定の期間及び範囲に限定して認められるにすぎず,また,その内 容をみても,当該活動において控訴人表示画面が媒体に表\示されていたものではな いから,控訴人表示画面の周知性を裏付けるものとはいえない。\n控訴人のその他の主張も,訂正して引用した原判決の第4の3(2)における控訴 人表示画面の周知性が認められない旨の判断を左右するものではない。\n
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2022.03.29
令和3(行ケ)10112 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年3月23日 知的財産高等裁判所
(2) 本件指定商品は、本件商標について書換登録申請がされた日(平成13年\n3月15日(甲7、8)。以下「本件申請日」という。)に施行されていた商標法\n施行規則別表(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの。以下「省\n令別表」という。)第9類15に定める「電子応用機械器具及びその部品」を意味\nするものと解されるので、同類15に定める「電子応用機械器具及びその部品」の 意義について検討する。
ア 本件申請日に施行されていた商標法施行令別表\(平成13年政令第265号 による改正前のもの)には、「第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、 映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械 器具及び電気式又は光学式の機械器具」との定めがある。
イ 省令別表には、次の定めがある。\n
(ア) 「第9類3 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクト ル」
(イ) 「第9類15 電子応用機械器具及びその部品
(1) 電子応用機械器具
ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用 ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震 探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測探器 超音波応用探傷器 超音波 応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機(中央処 理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テ ープその他の周辺機器を含む。) 電子顕微鏡 電子式卓上計算機 ワードプロセ ッサ
・・・
ウ なお、弁論の全趣旨により本件申請日の後に発行されたものと認められる類\n似商品・役務審査基準(乙1、2)においても、「配電用又は制御用の機械器具」 として「開閉器」及び「点滅器」が掲げられているが、「電子応用機械器具及びそ の部品」としては、「開閉器」も「点滅器」も掲げられていない。
エ 上記ア及びイによると、本件指定商品(「電子応用機械器具及びその部品」) は、上記イ(イ)のとおり省令別表第9類15に定める「電子応用機械器具及びその\n部品」に該当するものとして掲げられた「電子計算機」、「X線管」、「ダイオー ド」、「集積回路」等の商品を含み、上記イ(ア)のとおり同類3に定める「配電用 又は制御用の機械器具」に該当するものとして掲げられた「開閉器」及び「点滅器」 を含まないと解するのが相当である。そして、証拠(甲13〜15)及び弁論の全 趣旨によると、ここでいう「開閉器」ないし「点滅器」とは、電気回路を開閉する 装置、すなわち、スイッチを意味するものと認められる。
(3) これを本件各商品についてみるに、証拠(甲5、9〜12、16の1、甲 17〜19、23、24)及び弁論の全趣旨によると、本件各商品は、いずれも照 明器具の点滅を制御したり、その色を調節したりするICスイッチであると認めら れるから、本件各商品は、少なくとも省令別表第9類3に定める「制御用の機械器\n具」としての「開閉器」ないし「点滅器」に該当するというべきである。したがっ て、本件各商品は、同類15に定める「電子応用機械器具及びその部品」、すなわ ち、本件指定商品には該当しないといわざるを得ない。
(4) 原告は、本件各商品の部品(CPU、IC等)はいずれも本件指定商品に 該当するから、本件各商品も本件指定商品に該当する旨主張する。しかしながら、 本件において本件指定商品に該当するか否かが問題とされるのは、完成品たる本件 各商品であり、その部品ではないから、仮に原告が主張するとおり本件各商品の全 ての部品が本件指定商品に該当するとしても、そのことは、本件各商品が本件指定 商品に該当しないとの上記判断を左右しない。 また、原告は、「配電」は変電所から需要端までの屋外の電力輸送を意味し、家 庭内等において使用する照明器具の内部に配設される本件商品1は「配電用の機械 器具」の範ちゅうに属しないとして、本件商品1が「配電用の機械器具」の範ちゅ うに属し、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属しないとした本件審 決の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、上記(3)において説示したとお り、本件商品1は、少なくとも「制御用の機械器具」としての「開閉器」ないし 「点滅器」に該当するものであるから、仮に「配電」の意義が原告の主張するとお りであったとしても、そのことは、本件商品1が本件指定商品に該当しないとの上 記判断を左右しない。
2022.03.29
令和3(行ケ)10058 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年3月23日 知的財産高等裁判所
甲5技術は、コンテンツの映像(主映像)及び主映像を補足するなどの理由で表\n示される字幕等の映像(副映像)を表示することができるようにした復号装置に係\nる技術である。甲5技術においては、主映像及び副映像は、表示装置の画面(甲5\nの第19図参照)上に設けられた各画枠の内部に表示されるところ、主映像の画枠\nのサイズは、表示装置のアスペクト比及び主映像のアスペクト比に基づいて変換さ\nれ、副映像の画枠のサイズも、表示装置のアスペクト比及び副映像のアスペクト比\nに基づいて変換される。このようにしてサイズが変換された主映像及び副映像の各 画枠は、表示装置の画面上に配置されるが、その際、例えば表\示装置のアスペクト 比が16:9であり、主映像のアスペクト比が4:3であるなどの条件を満たす場 合、副映像の画枠の一部は、主映像の画枠と重なり合い、副映像の一部は、主映像 の画枠の内側に表示されるが、その余の部分は、主映像の画枠の外側に表\示される という事象が生じるものである。
そして、甲5技術によると、主映像の画枠は、主映像が表示される領域であると\n解されるから、これが本件発明1の構成1E及び1Fにいう「第1の表\示欄」(動 画を表示する領域)に相当するものであることは明らかである。\nしかしながら、甲5技術によると、副映像の画枠に表示される副映像の例として\n挙げられているのは字幕であり、甲4技術の「データコンテンツ」と同様、主映像 の配信時に既に存在するものである(なお、甲5によると、甲5技術の副映像に当 たる字幕は、映像データであることがうかがわれる。甲5には、字幕がテキストデ ータであるとの開示又は示唆はない。)。これに対し、本件発明1のコメントは、 前記のとおり、動画に対し任意の時間にユーザが付与するものである。 また、甲5の記載(明細書1頁5行目〜2頁11行目)によると、従来、副映像 のアスペクト比は、主映像のアスペクト比に関連付けられており、例えば、表示装\n置のアスペクト比が16:9であり、主映像のアスペクト比が4:3であるとき、 副映像(字幕)のアスペクト比は必ず4:3となるため、小型の電子機器において は字幕が見えづらくなってしまうという問題があったところ、甲5技術は、主映像 のアスペクト比から独立したアスペクト比で副映像を表示することにより、副映像\nを見やすくすることを目的とするものであると認められる。これに対し、本件発明 1は、前記のとおり、動画と重なって表示されたコメントが動画に含まれるもので\nはないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユーザが把握 できるようにすることを目的とするものである。 以上のとおり、甲5技術の「副映像の画枠」は、本件発明1の「コメント」を表\n示する領域ではないから、これが本件発明1の構成1E及び1Fにいう「第2の表\ 示欄」に相当するということはできない。また、甲5技術において、副映像の画枠 の一部が主映像の画枠と重なり、副映像の一部が主映像の画枠の内側に表示され、\nその余の部分が主映像の画枠の外側に表示されるという事象を生じさせるのは、副\n映像のアスペクト比が主映像のアスペクト比と関連付けられていたことから来る副 映像の見づらさを解消するためであり、本件発明1のようにコメントが動画に含ま れるものではないこと及びこれがユーザによって書き込まれたものであることをユ ーザが把握できるようにすることを目的とするものではなく、この点からも、甲5 技術の上記内容が本件発明1の構成1E及び1Fに相当するということはできない。\nしたがって、甲5技術も、本件発明1の構成1E及び1Fに相当する構\成を有する ものではない。
エ 原告の主張について
原告は、甲5技術の「字幕」はユーザが入力するものでないものの、これを端末 に表示させる局面においては本件発明1と同様に文字列データとして処理されるも\nのであるし、本件原出願日当時にWEB2.0が技術常識であったことからしても、 甲5に接した当業者にとって、甲5技術の「字幕」を本件発明1の「コメント」に 置換することは容易であったと主張する。 しかしながら、甲5技術の「字幕」と本件発明1の「コメント」の技術的意義の 相違は、前記ウにおいて説示したとおりであるところ、仮に、甲5技術及び本件発 明1において「字幕」及び「コメント」が文字列データとして処理される場面があ るとしても(ただし、甲5に甲5技術の字幕がテキストデータであるとの開示又は 示唆がないことは、前記ウにおいて説示したとおりである。)、そのことにより上 記相違の本質が解消されるものではない。また、前記(2)エ(ア)において説示した ところに照らすと、仮に、本件原出願日当時、原告が主張するような内容のWEB 2.0という社会現象が生じていたとしても、そのことから直ちに、甲5技術にい う「字幕」(副映像)と本件発明1にいう「コメント」につき、これらが相互に置 換可能であると認めることはできない。よって、原告の上記主張は失当である。\n
(4) 前記(2)及び(3)のとおり、甲4技術及び甲5技術は、いずれも本件発明1 の構成1E及び1Fに相当する構\成を有するものではないから、甲1発明に甲4技 術及び甲5技術を適用しても、相違点1−1に係る本件発明1の構成を得ることは\nできない。
(5) なお、原告は、相違点1−1に係る本件発明1の構成は甲1発明において\nふきだしの大きさ並びにふきだし中のコメント(テキスト注釈)の文字長、フォン トの大きさ及び表示位置を適宜変更することにより得られるものであるから、設計\n的事項にすぎないと主張する。 しかしながら、甲1の図18によると、甲1発明においては、ふきだしが映像表\n示部の枠の外側にはみ出すこととされる一方、テキスト注釈については、それが3 行にわたる場合を含め、ふきだし中の上側、下側、左側及び右側にあえて十分な余\n白を設けて、テキスト注釈が映像表示部の枠の外側にはみ出さないようにしている\nと認められるから、ふきだしの大きさ並びにふきだし中のテキスト注釈の文字長及 びフォントの大きさをどのようにするかが設計的事項であるとしても、ふきだしと 映像表示部との位置関係及びテキスト注釈の表\示位置につき、これを相違点1−1 に係る本件発明1の構成(構\成1E及び1F)とすることについてまで設計的事項 であるということはできない。よって、原告の上記主張を採用することはできない。
(6) 小括
以上のとおりであるから、相違点1−1についての本件審決の判断に誤りはない。 そして、前記2(4)のとおり、本件発明9と甲1プログラム発明との間にも、相違 点1−1と同様の相違点が存在するといえるところ、上記説示したところに照らす と、この相違点についての本件審決の判断にも誤りはない。取消事由5は理由がな い。よって、無効理由2−1は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.03.17
令和2(ワ)31138等 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年1月28日 東京地方裁判所
被告主張表示1について\n
被告主張表示1は,「IIBESA」,「いいべさー」,「ホワイトライ\nスパワー」の3段の文字列からなり,「ホワイトライスパワー」の部分 は,黒字の背景に白文字の表示となっており,「いいべさー」,「いいべ\nさー」,「ほわいとらいすぱわー」との称呼が生じる。そして,「いいべ さー」とは,東北地方の方言で「いいでしょう」という意味を持ち, 「いいでしょう」,「いいでしょう」,「白い米の力」との観念が生じるも のといえる。
このように,被告主張表示1の外観において,「IIBESA」,「い\nいべさー」,「ホワイトライスパワー」の部分は3段に分かれて表示され\nており,「ホワイトライスパワー」の部分は黒字の背景に白文字の表示\nになっており,他とは区別されている。そして,その観念については, 「いいでしょう」,「いいでしょう」,「白い米の力」というものであり, 「いいでしょう」は「白い米の力」(ホワイトライスパワーの文字部分) を修飾しており,「白い米の力」の部分が需要者の注意を引きつけるも のといえる。また,その称呼についても「いいべさー」,「いいべさー」, 「ほわいとらいすぱわー」というものであり,これを一連のものと一読 するのは冗長であり,各部分について格別に称呼が生じるといえる。 加えて,被告主張表示1の「ホワイトライスパワー」のうち「ライス\nパワー」部分は,需要者である化粧品に関心のある一般の消費者に原告 勇心酒造の出所を示すものとして周知の表示であった(前記3(1))。そ して,原告商品及び被告各商品は,ともに化粧品の部類に属するものと いえるところ,化粧品類の取引においては,一般に,「ホワイト」とは, その商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効果を謳う品質や効能\表示\nに用いられるものとして,広く使用されているといえ,このような化粧 品類の取引の実情に鑑みれば,「ホワイト」の部分は,その商品の品質, 効能,色彩を表\示するものと理解し得るものといえる。これらによれば, 本件においては,「ホワイトライスパワー」のうち,「ライスパワー」の 部分が周知の表示として需要者に強い印象を与え,このこととの関係に\nおいて,「ホワイト」の部分は,その「ライスパワー」の品質,効能,\n色彩を示すものと理解し得て,その場合には識別力を有しないか,又は 識別力の弱い部分であるというべきであり,一般の消費者は,「ライス パワー」部分に着目するといえる。
このように,被告主張表示1の外観や観念,称呼に加えて,「ライス\nパワー」部分が需要者に周知の表示といえることや化粧品類の取引の実\n情に照らせば,被告主張表示1において強く支配的な印象を与えるのは,\n「ホワイトライスパワー」の文字部分のうちの「ライスパワー」部分で あるというべきである。 したがって,被告主張表示1については,原告各表\示と被告主張表示\n1の「ライスパワー」部分の類似性を検討するのが相当である。 そうすると,原告表示1と,被告主張表\示1の「ライスパワー」部分 は,外観,称呼,観念において同一であり,原告表示2及び3と被告主\n張表示1の「ライスパワー」部分は,称呼,観念において同一であると\nいえるから,原告各表示と被告主張表\示1は,両者を全体的に類似のも のとして受け取るおそれがあるといえ,類似しているといえる。
・・・
原告各表示と被告各表\示が類似していることに加えて,原告商品及び被告各 商品はいずれ化粧品の部類に属し,取引者及び需要者は共通のものといえる ことなどに照らせば,被告が原告各表示と類似する被告各表\示を付して被告 各商品の販売等することは,需要者に他人である原告の商品と混同を生じさ せる行為といえる。 したがって,被告が被告各表示を使用した商品を販売等する行為は,不競法\n2条1項1号の不正競争に該当する行為といえる。
・・・
被告主張標章1について
被告主張標章1は,被告主張表示1と同一の構\成であり,「IBESA」,「いいべさー」,「ホワイトライスパワー」の3段の文字列からなり, 「ホワイトライスパワー」の部分は,黒字の背景に白文字の表示となっ\nており,「いいべさー」,「いいべさー」,「ほわいとらいすぱわー」との 称呼が生じる。そして,「いいべさー」とは,東北地方の方言で「いい でしょう」という意味を持ち,「いいでしょう」,「いいでしょう」,「白 い米の力」との観念が生じるものといえる。 このように,被告主張標章1の外観において,「IIBESA」,「い いべさー」,「ホワイトライスパワー」の部分は3段に分かれて表示され\nており,「ホワイトライスパワー」の部分は黒字の背景に白文字の表示\nになっており,他とは区別されている。そして,その観念については, 「いいでしょう」,「いいでしょう」,「白い米の力」というものであり, 「いいでしょう」は「白い米の力」(ホワイトライスパワーの文字部分) を修飾しており,「ホワイトライスパワー」の文字部分が需要者の注意 を引きつけるものといえる。また,その称呼についても「いいべさー」, 「いいべさー」,「ほわいとらいすぱわー」というものであり,これを一 連のものと一読するのは冗長であり,各部分について格別に称呼が生じ るといえる。
加えて,被告主張標章1の「ホワイトライスパワー」のうち「ライス パワー」部分は,化粧品に関心のある一般の消費者に,原告勇心酒造の 出所を示す表示として周知の表\示といえ,需要者に強い印象を与えると いえる(前記3(1))。また,原告商品及び被告各商品は,ともに化粧品 の部類に属するものといえるところ,化粧品類の取引においては,「ホ ワイト」とは,一般に,その商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効\n果を謳う品質や効能表\示に用いられるものとして,広く使用されている といえ,このような化粧品類の取引の実情に鑑みれば,「ホワイト」の 部分は,その商品の品質,効能,色彩を表\示するものと理解し得るもの といえる。これらによれば,本件においては,「ホワイトライスパワー」 のうち,「ライスパワー」の部分が周知の表示として需要者に強い印象\nを与え,このこととの関係において,「ホワイト」の部分は,その「ラ イスパワー」の品質,効能,色彩を示すものと理解し得て,その場合に\nは識別力を有しないか,又は識別力の弱い部分であるというべきであり, 一般の消費者は,「ライスパワー」部分に着目するといえる。
このように,被告主張標章1の外観や観念,称呼に加えて,「ライス パワー」の部分が需要者に周知の表示といえることや化粧品類の取引の\n実情に照らせば,被告主張標章1で強く支配的な印象を与える部分は, 「ホワイトライスパワー」の文字部分のうちの「ライスパワー」部分で あるというべきである。 したがって,被告主張標章1については,原告各表示と,被告主張標\n章1の「ライスパワー」部分との類否を検討するのが相当である。そう すると,原告商標1と,被告主張標章1の「ライスパワー」部分は,外 観,称呼,観念において同一であり,原告商標2と被告主張標章1の 「ライスパワー」部分は,称呼,観念において同一であるといえる。そ して,原告勇心酒造と原告創研は,原告各商標の持つ出所識別機能等を\n保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価する ことができ(前記認定事実(4)),実質的には同一の表示による商品化事\n業を一体として営む関係にあるといえることに鑑みれば,上記「ライス パワー」部分が同一である場合,原告各商標と被告主張標章1は,類似 しているということが相当である。
・・・
カ 被告は,1)被告主張標章1ないし4が全体としてまとまりよく表示され\nており,称呼も冗長ではなく,よどみなく一連に称呼できることから,全 体を一体として理解すべきである,2)「ホワイトライスパワー」のうち 「ホワイトライス」とは白米を指すことから,「ホワイト」の部分だけを 分離して判断することはできないなどと主張するが,これらの被告の主張 を採用することができないのは,前記4(3)キのとおりである。
キ 以上のとおり,原告各商標と被告主張標章1ないし4及び被告標章5な いし8は類似しているといえる。そして,被告主張標章1ないし4は, 「ホワイトライスパワー」又は「White Rice Power」と いう被告標章1ないし4の文字列を含むことからすれば,原告各商標と被 告標章1ないし4は類似しているといえる。したがって,原告各商標と被 告各標章は類似しているといえる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2022.03.16
令和2(ワ)22071 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月18日 東京地方裁判所
2 争点2−3(サポート要件違反)について
事案にかんがみ,サポート要件に関する争点2−3から判断する。
(1) 判断枠組み
特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特 許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲 に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な 説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術 常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきであり,明細書のサポート要件の存在は特許権者 が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2) 本件発明の課題
ア 【0006】には,本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供すること」と記載されているにとどまり,界面活性剤の含有の 有無や含有量,界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載 はない。 しかし,本件明細書において,【0006】は,【0005】とともに 「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ ろ,【0005】には,「界面活性剤は,皮膚に負担をかけ,荒れ等を生 じさせ得るため,界面活性剤を使用していないか,又は,界面活性剤の 使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ うすると,【0006】に記載された本件発明の目的は,【0005】に 記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的 である。 加えて,【0011】には,本件発明に係る液状化粧品は,「有効成分を 所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である との記載がある。そして,本件発明に対応する「第2のタンパク質抽出 剤」の「有効成分」について,【0037】では,「第2の高級アルコー ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方,界面活性剤は挙げられて おらず,かえって,【0038】には,「本発明の第2のタンパク質抽出 剤は,界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また,上記の 「所定量」について,【0060】には,「第2のタンパク質抽出剤を液 状化粧品として使用する場合,「炭化水素」の含量としては,タンパク質 抽出剤(液状化粧品)の「全量」に対して3体積%以上含まれているこ とが好適である。」,「炭化水素の濃度が低い場合には,タンパク質抽出剤 (液状化粧品)をより多く使用することにより,タンパク質の抽出は可 能である。しかし,炭化水素の含有量が全量に対して3体積%を下回る\nと,化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな るため,好適ではない。」,「第2のタンパク質抽出剤を液状化粧品として 使用する場合,「第2の高級アルコール」の含量としては,「炭化水素」 の体積に対して1体積%以上含まれていることが好適である。」,「第2の 高級アルコールの濃度が低い場合には,タンパク質抽出剤(液状化粧品) をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし,\n第2の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して1体積%を下回ると, 化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた め,好適ではない。」との記載がある。 さらに,【0044】には,「第2の高級アルコール」を「炭化水素」と 組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい るほか,【0065】には,本件発明の「タンパク質抽出剤は,界面活性 剤等を含まなくとも,優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって, 本発明のタンパク質抽出剤によれば,皮膚への負担を低減しつつ,所望 の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方,界面活性剤がタンパ ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 以上によれば,本件発明の課題は,単にタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することと解することはできず,界面活性剤を使用していな いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。
イ 原告は,本件発明の課題は,【0006】記載のとおり,タンパク質を 抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが, 前記アで説示したところに照らし,採用することができず,このことは, 本件特許の出願経過において,原告が【0006】にあった「上記課題を 解決するためになされたものであり,」との記載を削除する補正をした事 実によっても左右されるものではない。
・・・
ウ 本件明細書に記載された実施例のうち,実施例13(【0149】)は, 角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり,第2のタンパク質 抽出剤Aとして,約30体積%のオクチルドデカノールと,約60体積% のスクアラン(スクワラン)を含むものが用いられている(【0141】)。 なお,実施例13の結果として,実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた ことに関する記載や示唆はない。 また,本件明細書に記載されたその余の実施例は,いずれも,角栓のあ る皮膚に関するものではない。
エ 本件明細書には,炭化水素の含有量が全量に対して3体積%を下回る場 合及び第2の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して1体積%を下回 る場合において,角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記 載や示唆はない。
(5) 検討
前記(2)のとおり,本件発明の課題は,界面活性剤を使用していないか又 は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することにあると認められるところ,前記(2)のとおり,本件明 細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関 する記載がないから,特許請求の範囲の記載上,上記課題を解決するために 必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は ないと理解できる。
しかるに,前記(4)のとおり,本件明細書においては,タンパク質を抽出 する効果を奏する有効成分として,第2の高級アルコールであるオクチルド デカノールと,リモネン,スクアレン,及びスクアランからなる群から選ば れる1種類以上の炭化水素が特定されているところ,炭化水素の含有量がタ ンパク質抽出剤の全量に対して3体積%を下回る場合及び第2の高級アルコ ールの含有量が炭化水素に対して1体積%を下回る場合には,化粧品として 実用的なものではないことが記載されており,かつ,炭化水素及び第2の高 級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を 奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 また,本件明細書には,本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに 加えて,角栓のある皮膚を対象とする実施例13において用いられた,角栓 除去用液状クレンジング剤に相当する「第2のタンパク質抽出剤A」に含ま れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は,それぞれ,全量の3 体積%及び炭化水素(スクアラン)に対する1体積%を大きく上回るもので ある。
以上によれば,本件発明の特許請求の範囲の記載は,本件明細書の発明の 詳細な説明の記載により,当業者が,本件発明に係る角栓除去用液状クレン ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の3体積%未満又はオクチルドデカ ノールの配合量が炭化水素の1体積%未満の範囲であっても,角栓除去作用 があり,前記(2)の課題を解決できることについて,認識することはできな いというべきであり,本件全証拠によっても,本件明細書の発明の詳細な説 明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな い。
(6) 原告の主張について
ア 原告は,【0002】ないし【0005】の記載は,本件発明をするに 至った契機を記載したものにすぎず,【0006】は,こうした認識に端 を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」 してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す る。 しかし,前記(2)アで説示したところによれば,本件発明の課題が単に タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す ることはできない。
イ 原告は,【0061】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール 及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから,本 件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 しかし,【0061】には,第2のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」 に使用した場合の各成分の含有量について,実際の使用態様において 「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて いるにすぎず,オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含 有しない濃度において,タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を 奏することができるかについては,何ら記載も示唆もされていない。し たがって,【0061】の記載をもって,本件発明が本件明細書の発明の 詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。
ウ 原告は,【0061】には,水を含有する態様の第2のタンパク質抽出 剤(液状化粧品)において,炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で あり,第2の高級アルコールの配合量は,炭化水素の体積に比し,1体 積%以上から200体積%以下の範囲内の量であると記載されているとこ ろ,炭化水素であるスクアランは水に溶けないから,スクアランがわずか でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ている旨を主張する。
しかし,【0061】の直前の段落である【0060】には,第2のタ ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に,水を含有する態様 と含有しない態様とを区別することなく,炭化水素の配合量を定めるこ とが記載されている。そして,これに続く【0061】も,【0060】 と同様,第2のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ いて説明したものであり,かつ,【0060】の記載内容を排斥する記載 はない。そうすると,【0061】は,【0060】の記載のとおり,炭 化水素が全量の3体積%以上含まれていることを前提とした記載と解釈 するのが相当である。
エ 原告は,本件明細書の実施例13には,スクワランとオクチルドデカノ ールが含まれる第2のタンパク質抽出剤Aは,角栓のある皮膚に対する洗 浄効果,すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか にされているから,その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる ことを認識できる旨を主張する。 しかし,実施例13には,角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ いての記載が存在するにとどまり,実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ れたことについては記載されていない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和3(行コ)10003 手続却下処分取消請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
法184条の4第4項は,外国語特許出願の翻訳文の提出について,手続 期間を遵守しなかったことによって出願又は特許に係る権利の喪失を引き起 こしたときの権利の回復について定めた特許法条約(PLT)12条に整合し た救済手続を導入するために,平成23年の特許法改正により新設されたも のであり,こうした規定新設の経緯からすると,外国語特許出願人について, 期限の徒過があった場合でも,柔軟な救済を図ることを目的としたものであ ると解される。しかし,他方で,1)特許協力条約(PCT)に基づく国際特許 出願の制度は,国内書面提出期間内に翻訳文を提出することによって,我が 国において,当該外国語特許出願が国際出願日にされた特許出願とみなされ るというものであるから,同制度を利用しようとする外国語特許出願の出願 人には,自己責任の下で,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出する ことが求められる。また,2)取り下げられたものとみなされた国際特許出願 に係る権利の回復を無制限に認めると,国内書面提出期間経過後も,当該国 際特許出願が取り下げられたものとみなされたか否かについて,第三者に過 大な監視負担をかけることになる。そうすると,法184条の4第4項にい う「正当な理由があるとき」とは,特段の事情がない限り,国際特許出願を 行う出願人が相当の注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて国内 書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいう ものと解すべきである。控訴人は,法184条の4第4項の「正当な理由」 の解釈は,期限管理システムが通常の状態で有効に機能しているのであれば,\n人は間違えることもあるのだからそれは救済するという立場に近づける方向 で緩やかにすべきであると主張するが,その解釈に当たって上記1),2)の点 も考慮しなければならないことからすると,「正当な理由」の解釈を一概に緩 やかにすべきであるということはできず,控訴人の上記主張は,採用するこ とができない。
(2) 相当な注意を尽くしていたか否かについて
控訴人は,本件担当パラリーガルが控訴人に送付した本件メールに,日本 の国内移行手続の期限として誤った記載がされたのは,本件代理人事務所に おいてダブルチェック体制による期限管理システムが有効に機能していたに\nもかかわらず,偶発的でかつ予期し得ない人為的ミスが重なって生じたもの\nであり,偶発的に生じた予期し難いものであったとした上で,法184条の\n4第4項の「正当な理由」の解釈を控訴人主張のとおりに緩やかにすれば, 本件においては,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて 国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったもので あり,法184条の4第4項の「正当な理由」があると主張する。 しかし,法184条の4第4項の「正当な理由」の解釈を控訴人主張のと おりに緩やかにすることができないことは,前記(1)に述べたとおりである。 また,本件代理人事務所では,国際出願の出願人に,国内移行手続の期限と して,国・地域にかかわらず,国内移行手続の期間が30か月である場合の 期限を報告するのが標準の実務であり,また,費用見積りは,クライアント から要望があった場合に行う手続であった(甲23和訳3〜4頁)。そうする と,費用見積りを,クライアントの要望がないにもかかわらず,本件担当弁 護士が選択した国について,国内移行手続の期間が30か月の国と31か月 の国に分けて用意し,それに伴って国内移行手続の期限も,国内移行手続の 期間が30か月の国と31か月の国に分けて表示するというのであれば,そ\nれは通常の取扱いと異なるのであるから,通常の取扱いと異なる部分につい て,誤りが生じないように,通常の取扱い以上にチェックすることが必要と なるというべきである。そして,本件の取扱いにおいては,国内移行手続の 期限を,国内移行手続の期間が30か月の国と31か月の国に分けて表示す\nるという点が,同期間が30か月である場合の期限のみを報告するという通 常の場合と異なっており,同期限は,国際特許出願の出願人であるクライア ントの権利の得喪に非常に重要な意味を有するから,通常と異なる取扱いを する以上は,同期限の表示の誤りの有無は,入念に点検すべきであるといえ\nる。そして,本件メール案には,国内移行手続の期限及び同手続に要する費 用の見積額が記入された一覧表(本件一覧表\)が記載され,国によって異な る期限が表示されていたのであるから,これらの国ごとの期限に誤りがない\nかを点検すべきであり,これをすることは容易にできたものと認められる。 しかしながら,本件一覧表に示された期限が正しいかどうかについてダブル\nチェック等により入念な点検が行われたことはうかがわれない。 本件一覧表に記載されていたのと同じ誤った期限は,本件担当パラリーガ\nルが日本の特許事務所に送付した,見積額を問い合わせるメール(甲19の 英文2頁目)にも表示されていたが,それは,本文の上の「Re:」という欄に 表示されていたにとどまり,そのメールの本文の問い合わせ事項に含まれて\nいたものではなかった。そのため,これに返信した日本の特許事務所がこの 表示の誤りを指摘しなかったとしても,日本の特許事務所がその表\示に誤り がないことを確認したと考えることは必ずしもできないようなものであった。 そうすると,上記メールに対する日本の特許事務所の返信メールに誤りの指 摘がなかったことをもって,その表示が正しいことについて確認がされたと\n認めることはできない。 したがって,控訴人は,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観 的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかっ たものであるとは認められず,法184条の4第4項の「正当な理由」があ るとは認められない。
◆判決本文
1審はこちら
2022.03.15
令和2(ワ)7486 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月28日 大阪地方裁判所
ア 特徴的部分1)について
前記各認定によれば、被告は、少なくとも平成29年8月10日頃までは、魚の 神経抜き及び血抜きにあたってはあえて少し血を残す方が良く、魚の熟成等の観点 からは血の回りだけでなく神経絞めに意味があると考えており、このような考えに 基づき、脳髄や神経を抜くことで血抜きをするという発想を持っていたことがうか がわれる。また、被告は、この頃、「明石浦漁港のやり方」すなわち背骨上側に沿う 脊髄神経に針金を通し神経を破壊する方法に加えて水圧を使うことを提案している ことに鑑みると、尾部を切断することやそれによって血液弓門を露出させ、血液弓 門から水圧を掛けて血抜きをすることは、必ずしも想到していなかったものと推察 される。他方、原告は、早く確実に作業することが可能なことや骨全体まで完全に血抜きをすることを重視し、神経抜きはすればよいがしなくてもよく、血を回さな\nいための神経抜きであると考えていた。原告は、当時実施していた方法はエラに水 圧を掛けて血抜きをするものであったが、この方法では鬱血を広げてしまうという 欠点があるとしていたところ、足踏み式試作品を見て、水が噴出されるノズルの先 端部分の形状をより細くすれば十分に加圧することが可能\\となり、「全て切った尾 びれの付け根から処理でき」る、すなわち、尾部を切断して血液弓門を露出させ、 そこに先端を細くしたノズルを刺して水圧を掛け、神経抜きと血抜きを行う方法を 着想したことがうかがわれる。 その後の原告と被告とのやり取りは、原告が着想した上記方法を念頭に、ノズル の形状や流量調節器具に関する具体的検討を進めたものと理解される。 したがって、本件各発明の特徴的部分1)は、被告が製作した足踏み式試作品に接 したことを契機とするものの、長年の水産会社勤務、とりわけ魚の生き締めに関す る実地での経験等を背景とした原告の着想及び具体化に基づくものといってよい。 したがって、本件各発明の特徴的部分1)の完成については、被告のみならず原告も 創作的に寄与したものというべきである。 イ 特徴的部分2)について
前記各認定によれば、本件各発明の特徴的部分2)に関する原告と被告とのやり取 りは、以下のような経過をたどったものと理解される。 すなわち、被告は、原告とのやり取りを開始した平成29年7月11日までには 既にノズルの先端の形状がテーパ状である足踏み式試作品を試作していたが、同月 12日には、ノズルの形状が針状のエアダスターにつき、十分に用途を果たすこと、\nエアガンでないと極細ノズルが付けられないこと、魚によっては極細ノズルは要ら ないかもしれないが、特に血管の方までやるなら極細ノズルは必要と考えることな どの意見を述べた。また、原告は、同年8月1日、被告に対し、足踏み式試作品に ついて、先端部分をもっと細くすることができるかを尋ね、被告が簡単にできる旨 を回答すると、それであれば神経まで潰せるし、逆から骨の血も抜ける、全て切っ た尾ヒレの付け根から処理できるとの考えを示した。さらに、同日、原告は、針状 試作品について、これを用いれば簡単に後ろから処理できる、水圧で神経が出せる なら、スーパーでも使えるなどと感想を述べた。その後の同年9月の間のやり取り においても、原告と被告は、ノズルの形状については針状の極細ノズルとすること を念頭に検討を進めていたことがうかがわれる。 もっとも、原告は、針状試作品では魚が暴れた際等にノズルが変形等してしまう\nなどの不具合があると結論付け、同年11月1日、被告に対し、ノズルの形状をテー パ状にすることを提案した。これに対し、被告は、当初、テーパ状とすると製造に あたって精密さが求められ、コストが掛かることなどを指摘し、消極的な態度を示 したが、原告が製造業者からテーパ状のノズルの製作は比較的簡単である旨の回答 を得たこともあって、ノズルの形状をテーパ状とすることも検討することとした。 しかるに、原告は、その後、ノズルの形状をテーパ状とするだけでは十分ではな\nく、せめて先端の1cm程度を針状にして魚の骨の中で固定することが必要であると し、当該針状の部位からそのままテーパ状の部位につながるノズルの形状を提案し た。これに対し、被告は、スプレー式に噴出するテーパ状のノズルであっても、圧 力の逃げ場がないように神経弓門や血液弓門に刺すなどすることができるのではな いか、との意見を述べたが、原告は、これに否定的な態度を示した。 このような経緯を経て、本件各発明は、あらゆる大きさの魚に対応するための血 液弓門の密着封止構造を実現すると共に、ノズル先端部の破損を抑制するため、ノ\nズルの先端部分の形状をテーパ状にすること(特徴的部分2))をその特徴的部分の 1つとするものとして完成するに至ったものといえる。このことに鑑みると、特徴 的部分2)につき、最終的には被告の考えに基づき発明として完成したものの、課題 を解決するための着想及びその具体化の過程においては、被告のみならず原告も創 作的に寄与したものというべきである。
ウ したがって、原告と被告は、共に本件各発明の特徴的部分1)及び2)の完成に 創作的に寄与したものといえ、原告と被告は、本件各発明の共同発明者と認められ る。これに反する原告の主張は採用できない。
エ 被告の主張について
被告は、原告の助言を受ける前に既に本件各発明を完成させていた旨を主張し、 これに沿う供述等をする。 しかし、着想としてであれ被告が原告とのやり取りとかかわりなく単独で本件各 発明を完成させていたことをうかがわせる検討メモその他の客観的な資料は見当た らない。その点を措くとしても、前記認定に係る本件各発明に至る経緯を見る限り、 被告は、とりわけ本件各発明の特徴的部分2)について、原告の意見を踏まえて方針 を変更したことがうかがわれる。この方針変更は、特徴的部分2)に関わるものであ る以上、単に本件各発明を商品化する上で必要となったという程度にとどまるもの とはいえない。また、本件各発明を商品化した商品の販売促進につき原告の協力を 得るという被告の意図の存在は、前記認定に係る本件各発明に至る経緯からもうか がわれるものの、本件各発明の構成を具体的に示すなどして原告との議論を誘導す\nるなどした形跡はうかがわれず、むしろ上記のとおり原告の意見を踏まえて方針変 更をしたことなどを踏まえると、そのような意図のみに基づくものとまでは認めら れない。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 できない。
(5) 小括
以上より、本件特許は、特許法38条に違反してされたものであるから、同法1 23条1項2号所定の要件に該当すると共に、原告は本件特許に係る発明である本 件各発明について特許を受ける権利を有する者であることから、原告は、特許権者 である被告に対し、同法74条1項に基づき、その持分の移転請求権を有する。
2 本件出願の不法行為該当性等(争点2)について
不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、 訴訟追行を弁護士に委任した場合、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容 された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、 不法行為と相当因果関係に立つものというべきである(最高裁昭和44年2月27 日第一小法廷判決・民集23巻2号441頁参照)。 しかし、本件において、原告は、冒認出願又は共同出願違反による損害として、 本件訴訟追行に要した弁護士費用以外の損害の主張をしていないことから、弁護士 費用以外の損害を認めることはできない。そうである以上、原告が、冒認出願等の 被害者として、本件出願により生じた損害につき本件訴えを提起することを余儀な くされたとは認められない。そうすると、原告が本件訴訟追行に要した弁護士費用 は、冒認出願等と相当因果関係のある損害とはいえない。 したがって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の成立は認め られない。これに反する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和3(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月21日 知的財産高等裁判所
(1) 特許出願における特許請求の範囲の記載については,「特許を受けようとす る発明が明確であること」という要件に適合することが求められるが(特許法36 条6項2号),これは,特許制度が,発明を公開した者に独占的な権利である特許権 を付与することによって,特許権者についてはその発明を保護し,一方で第三者に ついては特許に係る発明の内容を把握させることにより,その発明の利用を図るこ とを通じて発明を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的とするものであ ることを踏まえたものである(最高裁平成24年(受)第1204号同27年6月 5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁)。同要件については,同目的の見地 を踏まえ,請求項の記載のほか,明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識 を考慮して判断されることになる。 これを本願発明についてみると,前記第2の2の本願の請求項1の記載及び本願 明細書の図1の内容に加え,本願明細書中,本願発明の特徴について説明する段落 において,「増幅器の出力回路」(又は「アナログ増幅器の出力回路」)という表現が\nひとまとまりの語として用いられていること(本願明細書の段落[0001],[0002], [0007]〜[0009],[0012]。同[0017],[0020]も参照。なお,本願明細書[甲11]中に,本願発明の内容に関して,「出力回路」の語が単体で用いられている個所 はない。),前記1(2)の本願発明の概要からすると,本願発明の技術的特徴の最たる 部分は,出力電流に相関した消費電流の変化がないという点にあり,その旨が本願 の請求項1にも明記されているところ,本願明細書の段落[0009]の記載からする と,本願発明が上記の技術的特徴を回路の構成によって実現するものであることは\n明らかであることのほか,実施例についても,「信号に相関した電流を電源回路に流 さない出力部」という記載がある(本願明細書の段落[0015]。同[0018],[0023] も参照)一方で,前段の増幅部については図示されていない旨の記載があること(同 [0016]。同[0019]も参照)を踏まえると,本願の請求項1中,「・・・を特徴と するオーディオ用増幅器の出力回路」という記載において,「・・・を特徴とする」 という部分は,「オーディオ用増幅器の出力回路」,すなわち,「オーディオ用増幅器」におけるものであるという特定の付加された「出力回路」を修飾するものであるこ とが,明確であるというべきである。 そうすると,本願の請求項1の記載は,第三者が特許に係る発明の内容を把握す ることを困難にするものとはいえず,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確 なものであるとは認められず,本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,特許法3 6条6項2号に規定する要件を満たしている。
(2) 前記(1)の判断に反する被告の主張は,いずれも採用することができない。被 告の主張は,本願の請求項1の記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明 確なものであることを根拠づけるものとはいえない。
(3) したがって,取消事由1には理由がある。
もっとも,前記第2の3(2)の本件審決の進歩性についての判断は,本願の請求項 1の記載の明確性についての前記(1)の判断を前提としても,なお問題となるもの であって,前記進歩性についての判断に誤りがない場合には,本件審決の結論に誤 りはないこととなるから,次に,取消事由2について検討する。
5 取消事由2(進歩性について)について
・・・
以上を踏まえると,相違点アを認定しなかった点で本件審決に誤りがあるとはい えない。なお,仮に,形式的に引用発明と本願発明を対比して,相違点アを認定し たとしても,引用発明におけるショットキーバリアダイオードが高抵抗素子として 機能するものであることを含めて既に述べた点のほか,本願発明についても3端子\n増幅素子の入力端子より信号SIG側にバイアス回路として抵抗R1及びR2を設け ることが示されていること(本願明細書の段落[0015],図1)に照らし,相違点ア が本願発明の進歩性を基礎付けるものとはいえない。
c 前記bは,あくまで本願発明がショットキーバリアダイオードの構成を付加\nすることを排除していない旨をいうものにすぎず,同構成を本願発明の構\成要素と して追加するものではない。後者の理解を前提とする原告の主張(それゆえにそれ が前者の理解と矛盾しているという主張を含む。)は,採用することができない。 また,特に入出力電圧の点で引用発明と本願発明が異なるという原告の主張は, 本願発明の発明特定事項に含まれていない構成を前提に本願発明についていうもの\nであって,その前提を欠き,採用することができない。引用発明との対比のために, 本願発明の入出力電圧の範囲を具体的に検討する必要がある旨をいう原告の主張も, 同様に,本願発明の発明特定事項に含まれていない構成をいうもので,採用するこ\nとができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和2(ネ)10059 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟__全文__ 令和4年2月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上によると,基礎出願A,Bの上記記載に接した当業者は,上記本件優先日当 時の技術常識とを考え併せ,「大豆胚軸」以外の「ダイゼイン類を含む原料」を発酵 原料とした場合でも,ラクトコッカス20-92株のようなエクオール及びオルニ チンの産生能力を有する微生物によって,発酵原料中の「ダイゼイン類」がアルギ\nニンと共に代謝されるようにすることにより,発酵物の乾燥重量1g当たり,8m g以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールを含有する,食品素材として用い られる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたという\nべきであるから,本件訂正発明を基礎出願A,Bから読み取ることができるものと 認められる。 したがって,本件訂正発明は,少なくとも基礎出願A,Bに記載されていたか, 記載されていたに等しい発明であると認められ,本件訂正発明は,基礎出願A,B に基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。 そうすると,本件特許は,特許法104条の規定の適用については,本件優先日 である平成19年6月13日に出願されたものとみなされるから,本件訂正発明生 産物が同条の特許出願前に日本国内において「公然知られた物でない」か否かを検 討するに当たり,本件優先日以降に公開された乙B3(国際公開第2007/06 6655号。国際公開日2007(平成19)年6月14日)を考慮することはで きない。
ウ 「公然知られた物でない」に当たるか
その物が特許法104条の「公然知られた」物に当たるといえるには,基準時に おいて,少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた 事実が存することを有するというべきところ,本件訂正発明生産物が,本件優先日 当時に公知であった乙B16,乙B24に記載されていたとはいえず,また,乙B 16又は乙B24から本件訂正発明を容易に想到することができないことは後記3 (4),(6)のとおりである。そうすると,本件優先日時点において,乙B16又は乙 B24に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたという ことはできない。 また,被控訴人らは,本件訂正発明生産物は,乙B16の「実施例1」の「乾燥 重量1g当たり,1mg−3mgのエクオールが生成」している発酵物「992m g」に栄養強化添加物である「97.48%」の純度のオルニチン(乙B67の国 際公開公報(WO2006/051940))を「8mg」加えたものであるにすぎ ないから,「公然知られた物」であると主張するが,前記アのとおり,本件訂正発明 生産物は,「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって,前記発 酵物の乾燥重量1g当たり,8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオール が生成され,食品素材として用いられる物」であるから,乙B16に乙B67を組 み合わせたとしても,「発酵物の乾燥重量1g当たり,8mg以上のオルニチン及び 1mg以上のエクオールが生成された」物に当たらないから,上記被控訴人らの主 張は採用できない。
なお,被控訴人らは,本件発明による生産物について,乙B4により公然知られ た物に当たる旨の主張をしていたので念のため検討するに,乙B4に本件訂正発明 が記載されていたとはいえず,また,乙B4から本件訂正発明を容易に想到できた ものではないことは後記3(3)のとおりであり,乙B4によっても当業者が本件訂 正発明生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。 したがって,本件訂正発明生産物は,本件優先日当時,「公然知られた物でない」 といえる。
エ 被控訴人方法の構成について\n
被控訴人らは,被控訴人原料の生産方法が原判決別紙「被告方法目録」記載の被 控訴人方法であることについて自白が成立しているから,特許法104条の推定は 働かないと主張する。そして,令和元年6月7日の原審第4回弁論準備手続期日に おいて,当事者双方が,被控訴人方法の構成について原判決別紙「被告方法目録」\n記載のとおりである旨陳述している(当裁判所に顕著)。 原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴人方法と,当審で控訴人 が主張する被控訴人方法とでは,前者における「α3 前記酵素処理工程を経て得 られたダイゼインを含む処理液と,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●をアルギニンを含む培養液と共に混合して発酵処理をし,」との構成部\n分を,後者では「α3−1 前記酵素処理工程を経て得られたダイゼインを,アル ギニンを含むその他の成分と混合して培地とした上,これを滅菌処理して滅菌済培 地とし,」と「α3−2 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●を同滅菌済培地に植菌して発酵処理をし,」との構成に変更するというものであ\nるところ,同α3−1及びα3−2の内容は,α3の内容を更に具体化・詳細化し ようとするものであり,また,控訴人は,原判決における本件訂正発明に係るクレ ーム解釈に基づく場合の構成としてα3−1及びα3−2とすべきと主張している\nものであるから,まずは,原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴 人方法(α1〜6によるものであって,α3をα3−1及びα3−2に変更しない もの)の構成について検討を進めることとする。\n
オ 推定の覆滅について
被控訴人らは,被控訴人原料の生産方法が被控訴人方法であり,これが本件訂正 発明の方法とは異なるから,本件訂正発明の方法を使用していないとの主張立証を しているものと解されるから,以下,被控訴人方法(まずは,α1〜6によるもの であって,α3をα3−1及びα3−2に変更しないもの)が本件訂正発明の方法 とは異なるものであるか検討する。
・・・
c 原判決は,構成α3の「アルギニンを含む培養液」は,本件発明の構\成要件 A−2,A−3の「アルギニンを含む発酵原料」に当たらず,被控訴人方法は本件 発明のA−2,A−3を充足しないと判断したが,本件訂正発明においても,構成\n要件B’−1に「アルギニンを含む発酵原料」とあるので,α3の「アルギニンを 含む培養液」が構成要件B’−1の「アルギニンを含む発酵原料」に当たるか検討\nする。 構成要件B’−1は,「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を」と\nいうものであるが,これは,構成要件A’においてダイゼイン類にアルギニンを添\n加したものを指すと解するのが自然である。そして,上記bのとおり,被控訴人方 法の構成α3においては,「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養\n液を,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と共に混合して発 酵処理をしているところ,「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養 液の混合物を,「オルニチン産生能力及びエクオール産生能\力を有する微生物」であ る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●で「発酵処理」してい るから,上記混合物は発酵原料に当たるというべきである。そうすると,同混合物 は,「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料」に当たるから,被控訴人 らの主張する被控訴人方法を前提としても,被控訴人原料の生産方法は,本件訂正 発明の構成要件B’−1を充足し,構\成要件B’−1の発酵原料を微生物で発酵処 理することを内容とする構成要件B’−2も充足する。\n
この点,原判決は,本件発明について,アルギニンは,発酵処理をする前の発酵 原料の調製をする段階において発酵原料に含まれているものであり,構成α3の「ダ\nイゼインを含む処理液」が発酵原料に当たり,「アルギニンを含む培養液」は発酵原 料ではなく,発酵効率の促進等を目的とする栄養成分に当たるものと解した上で, 被控訴人方法は発酵処理段階においてアルギニンが初めて現れるから本件発明の構\n成要件を充足しないと判断した。
しかしながら,本件特許請求の範囲及び本件明細書をみても,ダイゼイン類にア ルギニンを添加した後に微生物を加えることと,ダイゼイン類とアルギニンと微生 物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はな い。また,本件明細書をみると,【0091】に「発酵原料(発酵に供される原料)」 との記載があるものの,【0093】には「ダイゼイン類を含む発酵原料としては, ダイゼイン類を含む限り,特に制限されるものではない」と発酵原料に特段の制限 がないものとされており,そのほかには発酵原料を定義付ける記載はない。前記1 (2)のとおり,本件訂正発明においてオルニチン産生能力及びエクオール産生能\力 を有する微生物による発酵に供されるのは,「ダイゼイン類」と「アルギニン」であ り,ダイゼイン類にアルギニンが添加されたのちに微生物が添加されたとしても, ダイゼイン類に,アルギニンと微生物が同時に添加されたとしても,アルギニンが 発酵に供されることに変わりがない。そうすると,被控訴人方法におけるアルギニ ンが,発酵原料ではないというべき理由がない。
原判決は,本件明細書の【0033】の「当該エクオール含有大豆胚軸発酵物は, 発酵原料として大豆胚軸を用いて製造される」との記載及び【0036】の「大豆 胚軸の発酵において,発酵原料となる大豆胚軸には,必要に応じて,発酵効率の促 進や発酵物の風味向上等を目的として,酵母エキス,ポリペプトン,肉エキス等の 窒素源;グルコース,シュクロース等の炭素源;リン酸塩,炭酸塩,硫酸塩等の無 機塩;ビタミン類;アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に,エクオール産 生微生物として,アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの(中略)を\n使用する場合には,大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって,得 られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合,アルギニンの 添加量については,例えば,大豆胚軸(乾燥重量換算)100重量部に対して,ア ルギニンが0.5〜3重量部程度が例示される。」と発酵原料となる大豆胚軸には, 必要に応じて,発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を添加してもよいと記載さ れていることから,発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は,発酵原料とは別の 成分として扱われていると認定したが,ダイゼイン類を含む「大豆胚軸」が発酵原 料に当たることと,ダイゼイン類を含む処理液とアルギニンを含む培養液のいずれ もが発酵原料に当たると考えることは何ら矛盾するものではない。また,【0036】 の記載も,大豆胚軸にアルギニンを添加したものを発酵原料とみなすことと矛盾す るものではない。したがって,原判決の判断には誤りがあるというほかない。 そうすると,α3の「アルギニンを含む培養液」は,構成要件B’−1の「アル\nギニンを含む発酵原料」に当たると認めるのが相当であるから,被控訴人方法が構\n成要件A’,B’−1,B’−2を充足しないことが立証されているとはいえない。
・・・
(ウ) 以上のとおり,被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していない ことが立証されているとはいえないから,特許法104条の推定が覆滅されたと認 めることはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和2(ワ)22290等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月19日 東京地方裁判所
ア 実施可能要件違反の判断基準について
いわゆる医薬用途発明においては,一般に,当業者にとって,物質名, 化学構造等が示されることのみによっては,当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予\測することは困難であり,当該発明に係る医薬を当該用途に使用することができないから,そのような発明において実施 可能要件を満たすためには,明細書の発明の詳細な説明に,薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより,当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解\nするのが相当である。 本件発明1及び2の特許請求の範囲においては,本件化合物が「痛みの 処置における」(構成要件1B)「鎮痛剤」(構\成要件1C)及び「鎮痛 剤」(構成要件2C)として作用することが記載されているところ,いずれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし,本件明細書には,本件化合物について,「痛みの処置とくに慢性の疼痛性\n障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛,術後疼痛,転移癌に伴う骨関節炎の痛み, 三叉神経痛,急性疱疹性および治療後神経痛,糖尿病性神経障害,カウザ ルギー,上腕神経叢捻除,後頭部神経痛,反射交感神経ジストロフィー, 線維筋痛症,痛風,幻想肢痛,火傷痛ならびに他の形態の神経痛,神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」(前記1(1)イ)と記載されて いることに照らすと,本件発明1及び2は,本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって,本件発明1及び2について実施可能要件を満たすというためには,本件明細書の発明の詳細な説明に,薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより,上記各痛みに対して鎮痛効\n果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
イ 痛みの分類及び機序について
(ア) 痛みの分類及び機序について,証拠(甲15の1,甲26,39,4 1,42,46,55,59,77ないし84,86,88)によれば, 本件出願当時,以下の文献が存在したことが認められる。
・・・
(イ) 前記(ア)aないしgの文献の記載によれば,痛みは,その機序により大 きく分けると,1)炎症や組織損傷による侵害レセプターへの刺激により 生じる侵害受容性疼痛,2)末梢神経又は中枢神経が圧迫されたり,絞扼 されたり,遮断されたりすることにより生じる神経障害性疼痛,3)直接 末梢からの侵害刺激がないにもかかわらず存在し,心因性のもので,特 発性疼痛とも呼ばれる心因性疼痛の三つに分類することができること, 線維筋痛症は,上記3)の心因性疼痛に分類されること,上記のとおりに 分類された痛みの中にも様々なものがあり,それぞれの痛みについて機 序や症状,治療方法が存在することが,本件出願当時,技術常識であっ たと認めるのが相当である。
(ウ) これに対して,原告は,痛覚過敏及び接触異痛は,通常の痛みとは異 なり,末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常で生じる痛みであると主張し,その根拠として,本件出願当時に前記(ア)hないしlのとお りの文献が存在したことを指摘する。 しかし,前記(ア)h,i,k及びlの各文献は,マスタードオイル,カ プサイシン及び切開による侵害刺激を与える実験の結果に基づくもので あるから,これらの実験により,痛覚過敏及び接触異痛が,その原因に かかわらず,末梢性感作や中枢性感作による神経の機能異常により生じると,直ちにいうことはできない。
また,前記(ア)jの文献では,「NメチルDアスパラギン酸(NMDA) 受容体の過剰活性は,神経障害性疼痛の発生における要因の1つである 可能性がある。」,「動物の神経障害性疼痛モデルにおいて示唆されるように…,痛覚過敏は NMDA 受容体によって介在される「ワインドアップ 現象」の提示である可能性がある。」などと記載されているところ,これらの記載は,NMDA受容体の過剰活性が神経障害性疼痛の要因となること,あるいは痛覚過敏がNMDA受容体によって介在されるワイン\nドアップ現象(神経細胞の感作)によるものであることの可能性を指摘したにすぎず,これをもって,上記文献の記載内容が本件出願当時の技術常識であったということはできない。そして,他に,本件出願当時,痛覚過敏及び接触異痛がその原因にかかわらず末梢性感作や中枢性感作による神経の機能\異常で生じる痛みであることが技術常識であったと認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
・・・
以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明においては,ホルマリン 試験,カラゲニン試験及び術後疼痛試験の各薬理データの記載により,本 件化合物が侵害受容性疼痛に分類される痛みに対して鎮痛効果があること 及びそのための当該医薬の有効量は裏付けられているといえる。しかし, 本件発明1及び2がその内容とする「痛み」,すなわち,少なくとも「炎 症性疼痛,術後疼痛,転移癌に伴う骨関節炎の痛み,三叉神経痛,急性疱 疹性および治療後神経痛,糖尿病性神経障害,カウザルギー,上腕神経叢 捻除,後頭部神経痛,反射交感神経ジストロフィー,線維筋痛症,痛風, 幻想肢痛,火傷痛ならびに他の形態の神経痛,神経障害および特発性疼痛 症候群」(前記1(1)イ)の各痛みに対して鎮痛効果があること及びそのた めの当該医薬の有効量を裏付ける記載はない。したがって,本件発明1及 び2は,実施可能要件に違反するものと認められる。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和3(行ケ)10101 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年2月22日 知的財産高等裁判所
商標法4条1項15号を無効理由とする本件審判の請求について
ア 本件審判の請求は,本件商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経 過した後にされたものであるから,本件審判の請求中,商標法4条1項1 5号を理由とする請求は,本件商標が「不正の目的で商標登録を受けた場 合」(商標法47条1項括弧書き)に限りする
原告は,1)本件商標の動物図形と原告の業務に係る周知著名な引用商標に は高い類似性があり,本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用され た場合,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあること,2)被告によ る被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグ ッズへの被告標章の使用の事実があること,3)本件審判において,被告の自 白をもとに,被告の不正の目的を推認させる事情を原告が具体的かつ詳細に 立証した後,被告がこれに争わない意向を表明した経緯があることを総合考\n慮すれば,被告は,周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし, その出所表示機能\を希釈化させ,又はその名声を毀損させる「不正の目的」 で本件商標の登録出願をし,その商標登録を受けたものである旨主張する。
ア そこで検討するに,1)については,引用商標は原告の業務に係る周知著 名な商標ではあるが,前記(1)ウ(イ)認定のとおり,本件商標と引用商標と は,外観,称呼,観念のいずれにおいても異なり,本件商標と引用商標は, 類似しない。 また,本件商標の動物図形と引用商標は,四足動物が右から左に向けて 跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿 でシルエット風に描かれている点で共通し,その基本的姿勢等に似通った 点があることから,本件商標に接した需要者は,本件商標の動物図形は引 用商標を模倣したものと連想,想起するものと一応いい得るが,「JUM PING SHI−SA」の文字部分があることによって,本件商標の動 物図形からは,引用商標から生じる「PUMA」ブランドの観念や「プー マ」の称呼は生じないものと認められること(前記(1)ウ(ア)a)に照らす と,本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想,想起するから といって,被告が本件商標の登録出願をし,その商標登録を受けたことに ついて,周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし,その出 所表示機能\を希釈化させる「不正の目的」があったものと認めることはで きない。
イ 2)については,証拠(甲61ないし63)によれば,知的財産高等裁判 所は,別紙3のとおりの構成からなる被告標章についての商標登録無効審\n判請求を不成立とした審決(無効2016−890014号事件)の審決 を取り消す旨の判決をした後,特許庁が被告標章が商標法4条1項15号 に該当することを理由に被告標章の商標登録を無効とする別件無効審決 をし,別件無効審決は,令和元年9月2日,確定したことが認められる。 しかしながら,本件商標と被告標章の外観は,四足動物が右から左に向 けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見 た姿でシルエット風に描かれている点で共通し,その基本的姿勢等に似通 った点があるものの,被告標章には本件商標において大きな構成部分であ\nる文字部分を有していないという顕著な相違があり,両商標は,外観,称 呼及び観念において異なり,類似しないことに照らすと,原告が主張する 被告による被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及 びアダルトグッズへの被告標章の使用の事実があるからといって,被告が 本件商標の登録出願をし,その商標登録を受けたことについて,周知著名 な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし,その出所表示機能\を希釈 化させ,又はその名声を毀損させる「不正の目的」があったものと認める ことはできない。
ウ 3)については,商標登録無効審判の審判手続においては,職権で証拠調 べをすることができ,当事者が申し立てない理由についても審理すること\nができるなどの職権探知主義が採用され(商標法56条において準用する 特許法150条1項,153条1項),自白法則は適用されないから(商 標法56条において準用する特許法151条が準用する民事訴訟法17 9条の規定から「当事者が自白した事実は証明することを要しない」とし た部分の準用が除かれている。),商標登録無効審判の請求人は被請求人 が商標登録の無効理由を基礎づける事実について自白した場合であって も,当該事実を証拠によって証明する必要がある。また,被請求人には特 許庁がした審決を取り消す権限がなく,商標登録無効審判に処分権主義の 適用はないから,被請求人は,請求人の請求を認諾することはできないも のと解される。
しかるところ,原告が3)の根拠として挙げる被告作成の令和2年9月2 8日付け上申書(甲104)には,「被請求人は,請求人の主張を認め,\n請求の趣旨に対し,請求人が主張するとおりの審決がなされ,本件商標権 が遡及消滅することを争わない。」との記載があるが,上記記載中の「請 求人の主張を認め」にいう「請求人の主張」を基礎づける具体的な事実が 特定されていないから,上記記載をもって被告が具体的事実について自白 したものと認めることはできないのみならず,具体的事実を証明する供述 証拠として評価することもできない。また,上記記載中の「請求の趣旨に 対し,請求人が主張するとおりの審決がなされ…争わない。」との部分は 請求の認諾の趣旨のものとうかがわれるが,商標登録無効審判においては 請求の認諾はできないから,上記部分を斟酌することはできない。 次に,原告が3)の根拠として挙げる被告作成の平成19年9月12日付 け「商標登録第5040036号について1)」と題する書面(甲41)に は,商標の制作経緯等に関し,「2003年(平成15年)年末ごろ,弊 社も新アイテムとして『シーサー』を分かりやすく,そして現代の若者に も受け入れられるデザインをコンセプトにしようと改めてデザインを構\n想しました。2004年(平成16年)3月ごろ,コンセプトであげた『分 かりやすく・シンプルに』と言うことでデザインに当時では珍しいピクト グラム(道路標識や公共施設,非常口など図柄だけで意味を表現するデザ\nイン)を取り入れてはどうか?と,社内で議論しました。そこで,(スポ ーツブランド)にはシンプルなデザイン(ロゴ)が多数使用されていたこ とから世界的に有名な『ラコステ』『ポロ・ラルフローレン』『マンシン グウェア』『プーマ』など,動物(生物)をモチーフにしたデザインを参 考にして図3)のように大まかなデザインができあがりました。空想上の生 物なので,伝統工芸の焼き物や民芸雑貨などをシルエット(影)にしてみ たものの形状はまだ複雑でシンプルを追求すると(プーマ)風なデザイン になっていました。しかし,デザイン(ロゴ)だけでは『シーサー』を表\n現していると誰も気づかないのでは?等の意見もあり,前述で述べた『獅 子面T-シャツ』のように文字(読み方・言い方)をデザインに組み合わせ てはどうか?ということで図4)になりました」,「その後,何度かデザイ ンを変更して図5)〜7)を経て現在は図8)(平成17年から発売)になって います。」との記載がある。しかし,上記記載中の「『プーマ』など,動 物(生物)をモチーフにしたデザインを参考にし」た,「(プーマ)風な デザインになっていました」旨の部分は,これに引き続きく「デザイン(ロ ゴ)だけでは『シーサー』を表現していると誰も気づかないのでは?等の\n意見もあり,前述で述べた『獅子面T-シャツ』のように文字(読み方・言 い方)をデザインに組み合わせてはどうか?ということで図4)になりまし た」との部分と併せて読めば,本件商標(図6))は,『プーマ』など,動 物(生物)をモチーフにしたデザインを参考にして『シーサー』を表現す\nる意図で作成されたものとうかがわれるから,被告が周知著名な引用商標 に化体した顧客吸引力にただ乗りし,その出所表示機能\を希釈化させる 「不正の目的」で本件商標(図6))の登録出願をし,その商標登録を受け たことを認め,あるいはこれを裏付ける趣旨の記載であると評価すること はできない。 したがって,上記書面から,被告に上記「不正の目的」があったものと 認めることはできない。
(3) 小括
以上によれば,本件商標は「不正の目的」で商標登録を受けたものに該当 しないとした本件審決の判断に誤りはないから, 原告主張の取消事由1は, 理由がない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和3(行ケ)10041 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年3月8日 知的財産高等裁判所
ア 本件商標に係る主張について
(ア) 原告は,本件商標につき,「BREZ」部分を要部として分離観察す ることが可能である旨主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(1))。 (イ) しかしながら,前記のとおり,本件商標は,「BREZTRI」の欧 文字を標準文字で書してなるものであり,いずれかの部分が目立つ態様 で記載されているものではない。また,本件商標の構成文字数は7文字\nと少なく,全体を「ブレズトリ」と自然に発音することが可能である。\nさらに,「BREZ」は,辞書等に掲載されていない語であり,後記のと おり,この部分が取引者,需要者に格別の造語として認識されている事 実も認められないことからすれば,独立した単語として認識されるもの とはいえない。加えて,「TRI」は,接頭辞として用いられた場合に「三, 三重の」等を意味する旨が辞書等に掲載されてはいるものの(甲22), 本件商標の「TRI」部分は語尾に位置することからすれば,直ちに「三, 三重の」や「triple」を意味する単語として認識されるものとは いえない。 これらの事情によれば,本件商標は,各構成部分がそれを分離して観\n察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してい る商標というべきであるから,全体を一連一体のものとして観察するの が相当であり,「BREZ」部分と「TRI」部分とを分離して観察する ことはできないというべきである。
(ウ) 上記の点に関して原告は,「TRI」部分につき,薬剤の名称とし 末尾に「tri」を付すことが多い実情が存するから,識別力が弱い旨 主張する。 確かに,証拠(甲38,39)によれば,原告が主張するような使用 例が複数あることが認められる。しかしながら,本件商標の構成文字数\nが少ないこと,「BREZ」は独立した単語として認識されるものとはい えないことからすれば,「TRI」部分について,単に薬剤の名称の末尾 に付された語であり,「BREZ」部分とは区別すべきものであると直ち に認識されるものとはいい難い。そうすると,原告が主張するような実 情があるからといって,「TRI」部分の識別力が弱いということはでき ない。
(エ) また,原告は,「BREZ」部分につき,需要者の間で広く認識され た引用商標1の「BREZ」部分と同様に,特徴的で識別力の強い部分 である旨主張する。 しかしながら,後記のとおり,引用商標1それ自体はある程度の周知 性を有しているといえるものの,だからといって同商標の「BREZ」 部分も周知であるということはできないから,本件商標の「BREZ」 部分につき,特徴的で識別力の強い部分であるということはできない。
(オ) 以上によれば,本件商標につき,「BREZ」部分を要部として分離 観察することはできないというべきである。 したがって,原告の上記主張は採用することができない
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.03.15
令和2(ワ)3481 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和4年1月20日 大阪地方裁判所
ア 「営業秘密」(法2条6項)といえるためには,当該情報が秘密として管理 されていることを要するところ,秘密として管理されているといえるためには,秘 密としての管理方法が適切であって,管理の意思が客観的に認識可能であることを\n要すると解される。 これを本件見積書記載の情報について見るに,前記各認定事実のとおり,本件見 積書には営業秘密である旨の表示がなく,そのデータにはパスワード等のアクセス\n制限措置が施されていなかった。また,原告において,業務上の秘密保持に関する 就業規則の規定はなく,被告P1との間で見積書の内容に関する秘密保持契約等も 締結等していなかった。原告は,発注者との間においても見積書の内容に関する秘 密保持契約を締結していなかった。さらに,原告は,見積書記載の情報が営業秘密 であることなどの注意喚起も,その取扱いに関する研修等の教育的措置も行ってい なかった。本件見積書のデータ管理の点でも,原告は,見積書の使用後にデータを 西脇支社のコンピュータから削除するよう指示しなかった。 このような本件顧客情報及び本件価格情報その他本件見積書記載の情報の管理状 況に鑑みると,当該情報は,原告の企業規模等の具体的状況を考慮しても,原告に おいて,特別な費用を要さずに容易に採り得る最低限の秘密管理措置すら採られて おらず,適切に秘密として管理されていたとはいえず,また,秘密として管理され ていると客観的に認識可能な状態にあったとはいえない。\nしたがって,本件見積書記載の情報は秘密として管理されていたとはいえない。
イ 原告は,本件見積書記載の情報につき,原告代表者が一元的に管理し,その\n了承がなければ従業員や外部業者に対して明らかにされないから,秘密として管理 されていたと主張する。 しかし,前記認定のとおり,本件見積書の各データは,パスワードによる保護等 の措置のないままに,発注者に交付されるべきもの又は参考として被告P1にメー ルにより送信されたものであり,その使用後も,情報漏洩を防止する何らの措置も 採られなかったことなどに鑑みると,これらの情報は,いずれも秘密として適切に 管理されているとはいえず,秘密として管理されていると客観的に認識可能な状態\nであったともいえない。 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても,この点に関する原告の主張は採用 できない。
ウ そうすると,その余の点について検討するまでもなく,本件顧客情報及び本 件価格情報は,「営業秘密」に該当しない。
2022.02.23
令和2(行ケ)10114 商標権 行政訴訟 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所
原告らとブランデッドボースト社が平成27年(2015年)11月4日 に締結した本件和解契約には,1)原告らは,「BOAST」の商号で「BO AST」商標を付した商品を米国外で自由に販売することができることを確 認する旨の条項(12項),2)ブランデッドボースト社は,世界中でボース ト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標 権を妨害しない旨の条項(14項)が存在することは,前記1(4)認定のとお りである。
前記1認定の本件和解契約締結に至る経緯,本件和解条項12項及び14 項の文言に鑑みると,本件和解条項14項の「世界中でボースト社又は原告 によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標権を妨害しな い」にいう「妨害しない」との文言は,ブランデッドボースト社が,原告ら が有する米国外で商標登録された「BOAST」ブランドに係る商号権及び 商標権の有効性を争わない義務(いわゆる不争義務)を負うことを定めた趣 旨を含むものと解される。 そうすると,ブランデッドボースト社は,本件和解契約に基づき,原告に 対し,本件商標の商標権について不争義務を負うものと認められる。 そして,前記1(5)認定のとおり,被告は,平成29年(2017年)10 月3日,ブランデッドボースト社から,米国内の「BOAST」ブランドに 係る事業を買収し,同社が保有する「BOAST」ブランドに係る米国登録 商標の移転を受け,これに伴い,ブランデッドボースト社の本件和解契約に 基づく契約上の地位を承継したのであるから,被告は,原告に対し,本件和 解契約に基づいて,本件商標の商標権について不争義務を負うものと認めら れる。
(2) 商標法50条1項が,「何人も」,同項所定の商標登録取消審判を請求す ることができる旨を規定し,請求人適格について制限を設けていないのは, 不使用商標の累積により他人の商標選択の幅を狭くする事態を抑制するとと もに,請求人を「利害関係人」に限ると定めた場合に必要とされる利害関係 の有無の審理のための時間を削減し,審理の迅速を図るという公益的観点に よるものと解される。 一方で,商標権に関する紛争の解決を目的として和解契約が締結され,そ の和解契約において当事者の一方が他方(商標権者)に対して当該商標権に ついて不争義務を負うことが合意された場合には,そのような当事者間の合意の効力を尊重することは,当該商標権の利用を促進するという効果をもた らすものである。また,このように当事者間の合意の効力を尊重するとして も,第三者が当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審 判を請求することは可能であるから,上記公益的観点による利益を損なうも\nのとはいえない。 したがって,和解契約に基づいて商標権について不争義務を負う者が,当 該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求するこ とは,信義則に反し許されないと解するのが相当である。 しかるところ,前記(1)認定のとおり,被告は,原告に対し,本件和解契約 に基づいて,本件商標の商標権について不争義務を負うものであるから,被 告による本件審判の請求は,信義則に反し,許されないというべきである。 これと異なる本件審決の判断は誤りであある。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.02.23
令和3(行ケ)10056 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月10日 知的財産高等裁判所
(1) 発明の要旨認定
特許出願に係る発明の要旨の認定は,特段の事情がない限り,願書に添付 した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるが,特許請 求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか, あるいは,一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に 照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合は,明細書の発明の詳細 な説明の記載を参酌することが許される(最高裁平成3年3月8日第二小法 廷判決・民集45巻3号123頁参照)。 これを本件補正後発明について検討するに,前記1(3)のとおり,本件補正 後発明は,二つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し,組み 合わされる各装置の発明(サブコンビネーション発明)であって,特許請求 の範囲請求項1の記載から,第1ユーザによって操作される情報処理装置に 関する発明であることが理解されるが,特許請求の範囲請求項1の記載中に, 情報処理装置とは別の,他の装置であるサーバにおける処理の内容が記載さ れているため,特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解す ることができない特段の事情がある。 したがって,本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して,本件補正 後発明の要旨を認定することとする。
ところで,サブコンビネーション発明においては,特許請求の範囲の請求 項中に記載された「他の装置」に関する事項が,形状,構造,構\成要素,組 成,作用,機能,性質,特性,行為又は動作,用途等(以下「構\造,機能\n等」という。)の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を 有するかを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ,「他の装 置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特定する事項であって,当該請 求項に係る発明の構造,機能\等を何ら特定してない場合は,「他の装置」に 関する事項は,当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないこと になるから,これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定することが 相当であるというべきである。 以上の観点から,以下,本件補正後発明を検討する。
(2) 構成要件(A)及び(E)について\n
本件補正後発明の構成要件(A)及び(E)は,発明の対象が「第1ユー\nザによって操作される情報処理装置」であることを特定する記載事項である から,これによって,本件補正後発明は「情報処理装置」の発明であること が画定される。
(3) 構成要件(B)について\n
特許請求の範囲請求項1の記載によれば,構成要件(B)における「事業\nに使用されていないが前記第1ユーザが活用を希望する知的財産権を,前記 第1ユーザが保有する1以上の知的財産権の中から特定し,当該知的財産権 に関する公報の情報を,前記サーバに通知する公報通知手段と」の記載は, 情報処理装置が有する公報通知手段を直接的に特定する構成であるといえる。\n一方,「(公報の情報を,)サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の 根拠となる情報を含む第1情報として(,前記サーバに通知する)」との記 載は,サーバに通知する公報の情報を更に限定する記載であると認めること はできるが,サーバによって抽出処理を行うことを前提とした限定であって 直接的に情報処理装置を限定する特定事項ではない。 上記第2情報及び第3情報の抽出処理について,請求項の記載をみると 「(C1)前記公報通知手段により通知された前記第1情報により特定される 前記公報に含まれ得る第1書類の内容のうち,所定の文字,図形,記号,又 はそれらの結合が,前記第2情報として抽出され, (C2)当該公報に含まれ得る第2書類の内容のうち,抽出された前記第2 情報と関連する文字,図形,記号又はそれらの結合が,前記第3情報として 抽出され,」 と特定されている。 上記特定事項に対応する発明の詳細な説明の記載を参照すると,構成要件\n(C1)は,特に段落【0023】のクレーム内単語として抽出する構成に,\n構成要件(C2)は段落【0024】の明細書内関連単語として抽出する構成\nに対応すると認められる。 一方,本願明細書等の段落【0021】には,上記「第1情報」に関して, 「特許権者は,活用を希望する特許権の情報(例えば特許番号等)を予めサ\nーバ1に通知しているものとする。即ち,当該特許権の公報(特許掲載公報 若しくは出願公開公報)の内容が公報情報DB61にデータとして記憶され ているものとする。」と記載され,段落【0022】には,「ここで,公報 の内容のデータは,必ずしも公報の謄本のデータである必要は特になく,そ の名称のごとく,公報の内容さえ特定できれば足り,任意の形態のデータで よい。」と記載されていることから,これらの抽出処理に用いられる公報の 情報は,普通に公開されている特許公報の内容であれば足りるといえ,第1 情報としてサーバに通知される知的財産権に関する公報の情報は,普通に公 開されている特許権の公報の内容を表す情報(すなわち,知的財産権に関す\nる公報の情報)以上に格別の内容を含むものではないことは明白である。 すなわち,構成要件(B)における,公報通知手段が「第1情報」としてサ\nーバに通知する公報の情報とは,通常の特許公報又は公開特許公報を示すに すぎないと認められる。そして,本願明細書等を精査しても,当該情報を通 知するに先立って,情報処理装置において,サーバにおける処理(第2情報 及び第3情報の抽出等)に資するため何らかの処理がされること等を開示又 は示唆する記載は,何ら見出すことができない。 そうすると,構成要件(B)の「サーバによる第2情報及び第3情報の抽\n出の根拠となる情報を含む第1情報として」との記載事項は,第1情報の通 知を受けたサーバが当該第1情報から第2情報及び第3情報を抽出するとい う,サーバにおける処理(構成要件(C1)及び(C2))を特定しているにす ぎない。すなわち,上記記載事項は,第1情報自体が,第2情報及び第3情 報を抽出するため通常の公報とは異なる格別の情報を含むことを特定してい るものではない。 このように,本件補正後発明の構成要件(B)のうち「サーバによる第2\n情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む第1情報として」の記載事 項は,サーバの処理を特定したものであり,情報処理装置が備える公報通知 手段の内容を特定するものではないから,構成要件(B)によって特定され\nる発明特定事項の認定に当たっては,上記記載事項を除外するのが相当であり,本件審決が(B')のとおり認定したことに誤りはない。
(4) 構成要件(C)及び(C1)ないし(C7)について
本件補正後発明の構成要件(C)及び(C1)ないし(C7)は,情報処理装 置から知的財産権に関する公報の情報(第1情報)の通知(送信)を受けた サーバが,第1情報から第2情報を抽出し,さらに第3情報を抽出し,第3 情報と第4情報とから通知対象を決定して当該公報の情報を第5情報として 通知対象者の端末に通知し,その後,通知対象者の端末から第6情報を受信 し第7情報を生成して情報処理装置に送信するという,サーバが行う処理を 特定したものであって,情報処理装置が行う処理を特定するものではない。 すなわち,情報処理装置から通知された情報に対して,どのような処理を行 い,どのような情報を生成して情報処理装置に送信するかという処理は,サ ーバが独自に行う処理であって,情報処理装置が行う処理に影響を及ぼすものではない。 一方,情報処理装置は,第1情報をサーバに送信し,第7情報をサーバか ら受信するものであるところ,かかる情報処置装置の機能は,サーバに所定\nの情報を送信してサーバから所定の情報を受信するという機能に留まり,当\n該機能は,上記構\成要件(C)及び(C1)ないし(C7)によって影響を受け たり制約されるものではない。このように,構成要件(C)及び(C1)ない し(C7)は,情報処理装置の機能,作用を何ら特定するものではない。\nよって,本件補正後発明の認定に当たっては,構成要件(C)及び(C1) ないし(C7)を発明特定事項とはみなさずに本件補正後発明の要旨を認定す べきであり,これと同旨の本件審決に誤りはない。
(5) 構成要件(D)について\n
本件補正後発明の構成要件(D)は,情報処理装置が備える「受付手段」\nが,サーバから送信される「第7情報」を受け付けることを特定するもので ある。 そして,本件補正後発明の構成要件(C)及び(C1)ないし(C7)の記載 によれば,「第7情報」は,「知的財産権に興味を有する者が存在すること を少なくとも示す情報」であって,「情報処理装置により前記第1情報が (サーバに)通知された結果として生成され」,「(サーバから)情報処理 装置に送信された」情報である。また,同(B)の記載によれば,「前記第 1情報」は「知的財産権に関する公報の情報」である。そして,構成要件\n(C6)及び(C7)に対応する発明の詳細な説明の記載(段落【0029】, 【0040】及び【0041】)も参酌すると,「第7情報」は,サーバの 通知部が特許権者端末に通知する情報であって,特許権者がサーバに登録し た特許掲載公報を見て興味応答を示した事業者のリスト(匿名事業者リス ト)を少なくとも含む情報であるということができ,これは,上記特許請求 の範囲の記載から特定した「第7情報」と格別の相違はない。そうすると, 結局,「第7情報」は,「知的財産権に興味を有する者が存在することを少 なくとも示す情報であって,情報処理装置により知的財産権に関する公報の 情報がサーバに通知された結果として生成され,サーバから情報処理装置に 送信された情報」ということができる。 よって,本件補正後発明の構成要件(D)により特定される事項の認定に\n当たっては,「第7情報」を上記のとおり言い換えるのが相当であり,本件 審決が(D')のとおり認定したことに誤りはない。
(6) 原告の主張に対する判断
ア 原告は,知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提 示するという本件補正後発明の課題からして,本件補正後発明はサーバと 情報処理装置とを組み合わせたシステムを前提にしたものであって,構成\n要件(C)及び(C1)ないし(C7)によって,情報処理装置の発明の機能\nを特定している旨主張する。 しかしながら,本願明細書等には発明の課題としてそのような記載があ るとしても,親出願についてはともかく,分割出願としての本件補正後発 明は,上記(1)ないし(5)で説示したとおり,システムの発明ではなくあくまで情報処理装置の発明である。そして,上記(4)で説示したとおり,構成要\n件(C)及び(C1)ないし(C7)はサーバの処理を特定するものであって 情報処理装置の機能を特定するものではないから,本件補正後発明を特定\nする事項には含まれない。 よって,原告の前記主張は採用することができない。
イ 原告は,知財高裁平成22年(行ケ)第10056号事件の判決を援用 し,本件補正後発明はサーバと情報処理装置とを組み合わせたシステムを 前提にしたものであってサーバを除外して検討するのは誤りであるとも主 張する。 しかしながら,原告が援用する上記事件は本件とは無関係の全く別の事 件であって,事案も異なるから,上記事件の判決の判断を根拠とする原告 の上記主張はそもそも採用することができない。 なお,付言するに,原告が援用する上記事件に係る発明は,発光部を有 する液体インク収納容器と,前記液体インク収納容器を搭載し前記発光部 の発光を受光する受光手段を備えた記録装置とを組み合わせたシステムに おける液体インク収納容器に関する発明であって,上記システムに専用さ れる特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組の\nものとして発明を構成するものであることから,容易想到性を検討するに\nあたり,記録装置の存在を除外して検討することはできないとした裁判例 であるところ,原告は,これに関連して,本件補正後発明の情報処理装置 は,第7情報として認識された場合において当該第7情報を受け付ける専 用端末である旨主張する。 しかしながら,本件補正後発明における情報処理装置とサーバからなる システムでは,情報処理装置の機能は,単に,サーバに「公報の情報」\n(第1情報)を送信し,サーバから「知的財産権に興味を有する者が存在 することを少なくとも示す情報」(第7情報)を受信するという機能に留\nまるものであって,サーバに対して情報を送受信する機能を有する情報処\n理装置であればどのような情報処理装置であってもよいから,サーバに対 して専用される特定の情報処理装置とみなすことはできない。また,本願 明細書等には,情報処理装置が種々の情報の中から第7情報を選択して認 識する等の技術事項は開示されておらず,情報処理装置はサーバから送信 された情報を単に第7情報として受け付けるものにすぎないと解されるか ら,原告の上記主張は本願明細書等に開示された技術事項に基づくもので はなく,採用することができない。
ウ 原告は,情報処理装置とサーバが別個のものとしても,本件審決は,発 明の実施形態に強みを有する事業者を選択できるという本件補正後発明の 意義を無視し,「公報通知手段」がサーバに通知する情報について,単に 「当該知的財産に関する公報の情報」と矮小化し,また「受付手段」が受 け付ける情報についても,「知的財産権に興味を有する者が存在すること を少なくとも示す情報」と矮小化して認定しており,本件審決の認定は誤 りである旨主張する。 しかしながら,第1情報を送信するという送信処理自体は,かかる第1 情報からどのようにして第2情報及び第3情報を抽出するのか,その抽出 方法を規定するものではないから,情報処理装置の「公報通知手段」は, 技術的には,知的財産権に関する公報の情報をサーバに送信するものにす ぎないというべきである。また,第7情報は知的財産権に興味を有する者 の情報であるところ,本件補正後発明の構成要件(C5)及び(C6)によれ ば,事業者による選択結果という事業者の自由な意思に基づいた人為的な 情報にすぎないものであって,第1情報と関連するものの第1情報から 「生成された」情報ではない。さらに,情報処理装置の「受付手段」は, サーバから上記第7情報を受け付けるものの,これは単に情報の受信にす ぎないものであって,情報処理装置の側に,当該第7情報を受け付けるた めの特別の構成を有するものでもない。\nしてみると,上記(2)ないし(5)で検討したとおり,本件補正後発明の「公 報通知手段」は,単に「知的財産に関する公報の情報」をサーバに通知す るものにすぎず,本件補正後発明の「受付手段」は「知的財産権に興味を 有する者が存在することを少なくとも示す情報」を受け付けるものにすぎ ないというべきであり,本件審決が「公報通知手段」及び「受付手段」に つき,それぞれ(B')及び(D')のとおり認定したことに誤りはない。
関連カテゴリー
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> リパーゼ認定
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.02.22
令和3(行ケ)10076 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年2月9日 知的財産高等裁判所
商標法上,商標の本質的機能は,自他商品又は役務の識別機能\にあると解するの が相当であるから(同法3条参照),同法50条にいう「登録商標の使用」という ためには,当該登録商標が商品又は役務の出所を表示し,自他商品又は役務を識別\nするものと取引者及び需要者において認識し得る態様で使用されることを要すると 解するのが相当である。 この点に関し,原告は,上記「登録商標の使用」といえるためには,当該登録商 標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足りる旨 主張するが,上記のとおりの商標の本質的機能に照らし,採用することができない。\n
(2) 本件各書籍について
証拠(甲8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,36の 1及び2)によれば,本件各書籍(表紙,裏表\紙,書籍に付された帯等も含む。) には,「知本主義の時代を生きろ」,「私は資本主義ではなく「知本主義」時代が 到来すると思う。」,「資本主義に代わる知本主義」,「「資本主義」から「知本 主義」へ」など,「知本主義」の文字を用いた表現が一定程度記載されているもの\nと認められる。 しかしながら,原告が「知本」の語につき辞書にも記載がないと主張するとおり, 「知本主義」の語の観念は不明確であり,「主義」との語尾から何らかの主義主張 を指すことがうかがわれるのみである。そうすると,上記のとおり本件各書籍にお いて「知本主義」の文字を用いた表現が一定程度記載されていることや,本件各書\n籍が通信販売サイト等において宣伝されていること(甲9,11,13,15,1 7,19,21,23,25,27,37)を考慮しても,「知本主義」の文字又 はこれを含む表現に触れた取引者及び需要者は,これらの文字等を書籍の副題の一\n部,記載内容,宣伝文句,著者の主張等であると認識するにとどまり,これらの文 字等が当該書籍に係る自他商品識別機能を果たすと認識するとは考え難い(これは,\n「知本主義」の文字が鍵括弧でくくられている場合であっても変わるところではな い。)。なお,この点に関し,原告も,「知本主義」の文字等が書籍に付された場 合,「知本」の主義主張に関する分野ないし事項の書籍であることを取引者及び需 要者に想起させる旨主張しているところである。 したがって,本件各書籍における「知本主義」の文字の記載は,商標法50条に いう「登録商標の使用」に該当しない。
(3) 甲28会報について
ア 証拠(甲28)によれば,甲28会報には,「賢主主義と知本主義」との表\n題が付され,「X会のうた」として,「いっぱい 知本主義」との記載がされ, 「「知本主義」を実践するX会12月例会」なる会合の告知がされているものと認 められるが,甲28の記載やその他の証拠によっても,甲28会報が市場における 独立した商取引の対象たる商品であると認めることはできないから,甲28会報に おける上記表題等の記載をもって,本件商標が商品について使用されたということ\nはできない。
イ 証拠(甲28)によれば,甲28会報には,「令和元年12月23日」との 日付の記載があるものと認められ,その他,甲28会報が本件要証期間内に発行さ れたものと認めるに足りる証拠はない。
ウ 以上のとおりであるから,甲28会報における上記アの記載をもって,原告 又は本件商標の専用使用権者若しくは通常使用権者(以下「原告ら」という。)が 本件要証期間内に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできな い。
(4) 甲29の選挙公報について
証拠(甲29)によれば,甲29は,東京都選挙管理委員会が平成11年4月1 1日執行の東京都知事選挙に際して発行した選挙公報(原告に係るもの)であり, 「資本主義(拝金主義)から知本主義へ」との記載がされているものと認められる。 しかしながら,一般に選挙公報が「新聞」,「雑誌」若しくは「書籍」又はこれ らに係る広告等に該当しないことは明らかである。また,上記認定のとおりの選挙 の執行期日にも照らすと,同選挙公報が本件要証期間内に発行されたと認めること もできない。 そうすると,甲29の選挙公報における上記記載をもって,原告らが本件要証期 間内に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできない。
(5) 甲30の社歌について
証拠(甲30)及び弁論の全趣旨によれば,甲30の書面には,「知本主義・知 財企業「B 勤務心得の歌」」と題する歌の歌詞が記載され,その歌詞の中に「知 本主義」の語が用いられているものと認められる。 しかしながら,本件全証拠によっても,甲30の書面が「新聞」,「雑誌」若し くは「書籍」又はこれらに係る広告等に該当すると認めることはできないし,同書 面の作成時期も不明である(同書面には,「SINCE1957」との記載がみられるのみ である。)。 そうすると,甲30の書面における上記記載をもって,原告らが本件要証期間内 に本件指定商品について本件商標を使用したと認めることはできない。
(6) 甲34のウェブサイトについて
証拠(甲34)及び弁論の全趣旨によれば,甲34は,原告の著書を宣伝するウ ェブサイトであって,原告が代表取締役を務める株式会社Bが運営するものの画面\nを印刷した書面であると認められる。 しかし,甲34をみても,本件商標又は社会通念上これと同一の商標が当該ウェ ブサイトに表示されているということはできない。\nしたがって,原告らが甲34のウェブサイトにおいて本件商標を使用したとは認 められない。
(7) 甲37のウェブサイトについて
証拠(甲37)及び弁論の全趣旨によれば,甲37は,原告の著書(甲36の1 及び2)を宣伝するウェブサイトであって,上記株式会社Bが運営するものの画面 を印刷した書面であり,同画面には,同著書を宣伝する文言として,「資本主義社 会は「知本主義」へ」との記載がされているものと認められる。 しかしながら,前記(2)において説示したとおり,「知本主義」の文字を含む上 記記載に触れた取引者及び需要者は,これを同著書の記載内容,宣伝文句,著者の 主張等であると認識するにとどまり,これが同著書に係る自他商品識別機能を果た\nすと認識するとは考え難い。 したがって,甲37のウェブサイトにおける上記記載は,商標法50条にいう 「登録商標の使用」に該当しない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2022.02.22
令和3(ネ)10066 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 前記のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり(原判決46頁 23行目ないし49頁1行目),本件各発明の特許請求の範囲の記載内容 に加え,本件明細書の段落【0012】の記載内容及び【図7】に記載さ れた本件各発明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容か\nらすれば,本件各発明の「操作メニュー情報」とは,「ポインタの座標位置 によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段 に表示するため」の「画像データ」であり,出力手段に表\示され,利用者 がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構\ 成されていることを要するものというべきである。
イ そして,被告製品のページ一部表示が,縮小された中央ページの右端又\nは左端あるいは両端に,幅が細く縦長の白みがかった長方形として表示さ\nれること,そこには何の文字,図形,記号,アイコン等は表示されないこ\nとからすれば,当該長方形部分のみを見た利用者は,それがどのような命 令を実行する表示であるのかを理解することはできないというべきであ\nり,したがって,被告製品のページ一部表示の画像は本件各発明の「操作\nメニュー情報」には当たらず,本件ホームアプリが構成要件Bの「操作メ\nニュー情報」を有するとは認められないことは,前記のとおり補正して引 用する原判決が説示するとおりである(原判決49頁2行目ないし50頁 6行目)。
控訴人は,1)被告製品においては構成e又は構\成e’によってそれまで 表示されていなかったページ一部表\示の画像が液晶画面に表示されるよ\nうになること,2)ページ一部表示の画像と壁紙画像との境界が明確である\nことを指摘するが,これらの点は,いずれも利用者がページ一部表示の画\n像自体から「実行される命令結果」の内容を理解することができるか否か に関わるものではないから,上記の判断を左右するものではないというべ きである。また,控訴人は,3)被告製品のページ一部表示の画像が表\現し ている表示内容は,実行されるスクロール命令の結果を小さな絵で表\現し た画像であるとも指摘するが,上記のとおり,ページ一部表示の画像は,\nその表示内容等からすれば,利用者がその表\示自体から「実行される命令 結果」の内容を理解できるように構成された画像データであるということ\nはできない。 なお,上記の判断に照らすと,控訴人が上記第2の3(1)アにおいて主張 する判断基準によったとしても,被告製品のページ一部表示の画像は,少\nなくとも同主張における3)の要件を満たすものとはいえないから,本件ホ ームアプリが構成要件Bの「操作メニュー情報」を有するとは認められな\nい。
ウ したがって,控訴人の主張(1)アは採用することができない。
(2) 控訴人の主張(1)イについて
ア 控訴人が主張(1)イにおいて指摘する各点は,いずれも上記(1)で検討し たところと同様の事情であるといえるから,いずれも前記の判断を左右す るものではないというべきである。そして,このことは,本件ホームアプ リに係るソースコードの記載内容を基に検討した場合であっても同様で\nある。
イ したがって,控訴人の主張(1)イは採用することができない。
(3) 小括
ア 控訴人は,上記のほかにも,争点1−3について縷々主張するが,いず れも前記の判断を左右するものではないというべきである。 イ 以上によれば,本件ホームアプリは,構成要件Bにいう「操作メニュー\n情報」を有するとは認められず,被告製品が構成要件Bを充足するものと\nは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,被告製品 が本件各発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.02.22
令和2(ワ)1160 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和4年1月31日 東京地方裁判所
ア 被告標章1の分離観察の可否
被告標章1の外観は別紙被告標章目録記載1のとおりである。すなわち, 上段に横書きの「KENT」,中段に横書きの「MARINE SPIR IT」,下段に横書きの「BROS.」を,いずれもほぼ同じ列幅で,か つ,上段と中段との行間及び中段と下段との行間をほとんど空けること なく三段に配して成る結合商標であって,全体としてまとまりよく構成\nされている。 もっとも,欧文字は左から右に順次目線を移して読解するものであるか ら,二段以上にまたがって欧文字が配された場合には,横一列に配され た場合と比較して結合の度合いは相当弱くなるといえる。特に,上段と 下段でそれぞれ独立した単語となり得る場合には,なおさらである。さ らに,上段と下段を構成する欧文字はいずれもおおむね同じ大きさであ\nる上,黒地に白抜きで記載されている点及び手書き風の字体である点に おいても共通するのに対し,中段を構成する欧文字の大きさは上段及び\n下段の欧文字より相当小さく,その行の高さは上段及び下段の行の高さ の3分の1程度にすぎない上,白地に黒い字で記載されている。しかも, 中段を構成する欧文字は,水平方向に平行に延びる2本の直線と垂直方\n向の弦を有する2つの半円とを組み合わせた横長の角丸長方形様の図形 によって囲まれ,当該図形部分は白く着色されており(そのため,中段 を構成する欧文字は,上段及び下段とは異なり,黒字で記載されてい\nる。),中段の全体が一本の白い横棒のような外観を呈している。このよ うに,中段の外観は上段及び下段と大きく異なる上,横棒のような外観 を有しているから,中段を境に,上段と下段が分離されたような外観を 有しているということができる。
そして,前記(2)アのとおり,イトーヨーカドーは,平成21年度以降, 約10年という相当長期間にわたって,168回もの多数回,チラシに 「Kent」ブランドのシャツ,パーカー,パンツ,靴下,コート,セ ーター,下着,手袋等の広告を掲載しており,前記(2)ウのとおり,「K ent」ブランドの商品については,イトーヨーカドーにおいて,平成 21年度から平成30年度までの間に●(省略)●もの売上げがあった もので,年によって増減はあるものの,平均すれば年間約50億円を売 り上げてきたこと,前記(2)イのとおり,限られた期間及び回数ながら, 著名人を起用した「Kent」ブランドのテレビCMが全国に放映され たことに照らせば,「Kent」ブランドは,令和元年当時,被服の分野 において,相応の周知性を有しており,取引者及び需要者に対し,商品 の出所識別標識として相当強い印象を与えていたものと認めるのが相当 である。そうすると,被告標章1の上段の「KENT」は,上記「Ke nt」の二文字目以降を大文字で記載したほかは,つづりが同一である ことから,「KENT」の標章が被服に用いられた場合には,取引者及び 需要者において「Kent」ブランドを想起するものと認めることがで きる。
他方,「BROS.」についてみれば,25類・被服を指定商品とする 「BROS ブロス」との登録商標が存在すると認められるものの(乙 3),本件全証拠によっても,被服に関する「BROS」の実際の使用例 としては,男性用下着のサブブランドとしてのものが認められるのみで あって,「BROS」がどの程度の周知性を有するのかは明らかではない。 そうすると,上記の登録商標の存在を根拠に「BROS.」から出所識別 標識としての称呼,観念が生ずると認めることはできず,その点につい ては,本件証拠上,明らかではないというべきである。以上の事情を総 合すれば,被告標章1の構成部分のうち,「BROS.」から出所識別標\n識としての称呼,観念が生じないとまでは認められないものの,上段の 「KENT」と下段の「BROS.」は,二段以上にまたがって配され, かつ,それぞれが独立した単語となり得ることにより,横一列に配され た場合と比較して結合の度合いは相当弱くなることに加え,一本の白い 横棒のような外観を有する中段の「MARINE SPIRIT」によ り上下に分離されている上,「KENT」に対応する「Kent」ブラン ドが,被服の分野において,相応の周知性を有しており,取引者及び需 要者に対し,商品の出所識別標識として相当強い印象を与え得ることか らすれば,上段の「KENT」と下段の「BROS.」とを分離して観察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している とまではいえない。したがって,被告標章1については,上段の「KE NT」のみを分離して観察することができると認めるのが相当である。 その結果,被告標章1については,「ケント」との称呼が生じ,かつ,原 告が使用権を設定し,イトーヨーカドーが使用する「Kent」ブラン ドの商品であるとの観念が生じるものと認められる。
イ 被告標章2の分離観察の可否
被告標章2の外観は別紙被告標章目録記載2のとおりである。すなわち, 上段に横書きの「KENT」,下段に横書きの「BROS.」を,いずれ もほぼ同じ列幅で,かつ,上段と下段との行間をほとんど空けることな く二段に配して成る結合商標であって,全体としてまとまりよく構成さ\nれている。 もっとも,欧文字は左から右に順次目線を移して読解するものであるか ら,上記の「KENT」と「BROS.」のように,二段以上にまたがっ て欧文字が配された場合には,横一列に配された場合と比較して結合の 度合いは弱くなり,上段と下段でそれぞれ独立した単語となり得る場合, その結合の度合いがより弱くなることは,被告標章1の場合と同様であ る。
そして,前記アのとおり,「BROS.」から出所識別標識としての称呼, 観念が生じないとは認められないものの,他方で,「Kent」は商品の 出所識別標識として取引者及び需要者に相当強い印象を与えていたもの と認められ,かつ,「KENT」の標章が被服に用いられた場合には,取 引者及び需要者において「Kent」ブランドを想起するものと認めら れる。 そうすると,被告標章2においては,被告標章1の中段に相当する部分 が存在しないものの,そもそも「KENT」と「BROS.」の結合の度 合いが弱い上,「KENT」に対応する「Kent」ブランドが商品の出 所識別標識として相当強い印象を与え得ることからして,被告標章2の 各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思わ\nれるほど不可分的に結合しているものとは認められないというべきであ り,上段の「KENT」を分離観察することができるというべきである。 その結果,被告標章2についても,被告標章1と同様,「ケント」との称 呼及び「Kent」ブランドの商品の観念が生じるものと認められる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.02.14
令和2(ワ)19927 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年12月24日 東京地方裁判所
原告は,本件発明3は,慢性疼痛に対する画期的処方薬として,抗て んかん作用を有するGABA類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり,その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから,対象となる痛みが侵害受容性疼痛か,神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく,効能・効果を神経障害性疼痛や\n線維筋痛症に伴う疼痛とし,慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は,均等侵害の第1要件を満たすと主張する。 しかし,前記1(1)アのとおり,本件特許に係る発明は,てんかん,ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が,痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し,反復使用により耐性を生じず,モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ,前記2(1)イのとおり,本件 出願当時,痛みには種々のものがあり,その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。 そうすると,いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは,本件発明 3において本質的部分というべきであり,その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は,本件発明3の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって,本件発明3に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明3の本質的部分でない\nということはできないから,被告医薬品は均等の第1要件を満たさない。
(イ) また,前記(1)アによれば,原告は,本件訂正前発明3においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ,本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると,本件発明3との関係においては,被告医薬品の効能・効果\nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって,被告医薬品は均等の第5要件も満たさない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2022.02.14
令和2(ワ)19927 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年12月24日 東京地方裁判所
(1) 言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,か つ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表\現に修正, 増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,\nこれに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること\nのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして,著作権法は,思想又は 感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),既\n存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア, 事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表\現上の創作性がない部 分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には 当たらないと解するのが相当である(最高裁平成11年(受)第922号同 13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁)。 そうすると,本件社史部分が原告書籍を翻案したものに当たるというため には,原告書籍と本件社史部分とが,創作的表現において同一性を有するこ\nとが必要であるものと解される。
したがって,原告書籍と本件社史部分との間で,事実など表現それ自体で\nない部分でのみ同一性が認められる場合には,本件社史部分は原告書籍を翻 案したものに当たらない。 また,原告書籍と本件社史部分との間に,表現において同一性が認められ\nる場合であっても,同一性を有する表現がありふれたものである場合には,\nその表現に創作性が認められず,本件社史部分は原告書籍を翻案したものに\n当たらないと解すべきである。すなわち,著作者等の権利の保護を図り,も って文化の発展に寄与するという著作権法の目的(同法1条)に照らせば, 著作物に作成者の何らかの個性が現れており,その権利を保護する必要性が あるといえる場合には,上記の創作性が肯定され得るが,一方で,表現があ\nりふれたものである場合には,そのような表現に独占権を認めると,後進の\n創作者の自由かつ多様な表現の妨げとなり,かえって上記の著作権法の目的\nに反する結果となりかねないため,当該表現に創作性を肯定して保護を与え\nることは許容されないというべきであり,そのため,原告書籍と本件社史部 分との間で同一性を有する表現がありふれたものである場合には,その表\現 に創作性を認めることができない。
(2) まず,別紙2記述対比表の原告書籍及び本件社史部分の各記述について,\nそれぞれの間での創作性を有する表現の同一性が認められるか否かについて\n検討する。
ア 番号1の各記述について
(ア) 原告書籍の番号1の記述は,原告書籍における当該記述の前後の文脈 を踏まえると,被告従業員であったBが被告の二輪世界選手権への再挑 戦の担当者になるとの内示を受ける前日に出身地を尋ねられた際のやり とりを記述したものであり,本件社史部分の番号1の記述は,本件社史 部分における当該記述の前後の文脈を踏まえると,Bが上記内示の際に 出身地を尋ねられたことを記述したものであると認められる。 これらの記述は,Bが上記内示を受ける際に出身地を尋ねられたこと を内容とする点で共通しているが,このようなやりとりがあったことは 事実にすぎないというべきであり,表現それ自体でない部分で同一性が\n認められるに留まる。また,出身地を尋ねるやりとりがあったことにつ いて,原告書籍の番号1の記述では,「おいB,おまえ家は東京だよな」 と記述されているのに対し,本件社史部分の番号1の記述では,「世間話 の中で出身地を聞かれました。『東京です』と答えたのを覚えていますよ」 と記述されており,それらの具体的な記述における描写の手法が異なる ものとなっており,表現それ自体において同一性を有するとは認められ\nない。
(イ) 原告は,原告書籍と本件社史部分に同じ事実が記述されていることに ついて,社史編纂委員会の担当者は原告書籍に記述された事実を原告書 籍に依拠して知ったものであるから,翻案該当性が認められるべき旨を 主張する。 しかしながら,前記(1)のとおり,本件社史部分に記述された事実が原 告書籍に依拠したものであったとしても,原告書籍と本件社史部分の各 記述が事実といった表現それ自体でない部分において同一性を有するに\n留まる場合には,原告書籍の翻案には当たらないと解するのが相当であ るから,原告の上記主張は採用することができない。 (ウ) したがって,番号1の各記述について,創作的表現において同一性を\n有するものと認めることはできない。
・・・
(ウ) 小活 前記(ア)及び(イ)の対比の結果に照らせば,原告書籍の番号20−1及 び20−2の記述と本件社史部分の番号20の記述が創作的表現におい\nて同一性を有するものと認めることはできず,これは,原告書籍の番号 20の記述全体と本件社史部分の番号20の記述とを対比した場合でも 同様である。
(3) 前記(2)のとおり,番号1ないし20の各記述において,本件社史部分が 原告書籍と創作的表現において同一性を有するとは認められないから,依拠\n性について検討するまでもなく,被告社史中の本件社史部分は原告書籍の翻 案に該当するものではない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2022.02.14
平成30(ワ)866 職務発明の対価 特許権 民事訴訟 令和3年12月27日 大阪地方裁判所
ウ コスト面について
(ア) 本件工場の建設に係る設備投資について,実行予算●(省略)●に対し,実\n際には●(省略)●の建設費用を要し,本件増設工事に更に●(省略)●の費用を 要したことで,合計●(省略)●を要したこと(前記(3)ウ(イ)a)に加え,被告に とって,本件工場は本件乾式分別法による設備を導入した初めての事例であるのに 対し,溶剤分別法による設備を設置した事例は既に FOJ 等において存在し,FVO 建設当初における溶剤分別設備に係る投資額の見積もりは本件設備の見積もりに比 して比較的正確になされたと考えられること等を踏まえると,本件工場建設に係る 設備投資額が溶剤分別法による設備を導入する場合と比して安価であったとは考え 難く,少なくともその点は不明と見るほかない。
(イ) 比例費については,平成27年〜平成29年の FVO 等の各 SOS パーツの加 工費に係る試算結果を比較した場合,FVO は FOJ 等に比して大幅に低額である。 また,分別設備に係る最終製品の比例費を見ても,FVO は,●(省略)●FOJ 等 に比して幾分低額である(以上につき,前記(3)ウ(イ)b)。もっとも,具体的な金 額は不明ながら,本件工場の稼働開始から平成26年までは FVO において●(省 略)●ことも考慮に入れる必要がある。
(ウ) 歩留まりについては,当初より乾式分別法による歩留まりが溶剤分別法より も低いことが前提とはされていたものの,本件増設工事を経て更に設計上の分別収 率は●(省略)●に引き下げられ,実際の歩留まりも●(省略)●という状況にあ る(前記(3)ウ(イ)c)。
(エ) これらの事情を総合的に考慮すると,本件乾式分別法は,必ずしも溶剤分別 法に比してコスト面で明確に有利とはいえない。
エ 採算性について
FVO パーツ品の採算性については,販売限利率を見る限り,FVO パーツ品は, CBE として販売されたもの及び SOS パーツ単体で販売されたもののいずれも,総 じて FOJ パーツ品よりも低い(前記(3)ウ(イ)d)。すなわち,FVO 品は,SOS パ ーツ製造の比例費を溶剤分別法により製造された FOJ 品に比して抑えられている にもかかわらず,FOJ 品よりも利益への貢献の程度は低いといえる。 なお,販売限利率は,分別方法による利益率の相違等をそれ自体として表すもの\nでは必ずしもないが,販売限利は,その算出に当たってその時々の相場と過去の実 績等が考慮され,変動費に相当する見込額として位置付けられるものであることな どに鑑みると,販売限利率に基づき収支採算性を評価することには一定程度の合理 性があると考えられる。
オ CBE 販売市場の状況について
CBE の国際的な需要は,平成12年〜平成20年にかけて急激に拡大し,それ 以降も,平成28年まで,緩やかな拡大傾向を示しているところ(前記(3)エ(ア)), 被告グループのシェアが本件工場の稼働によって増大したことを裏付けるに足りる 客観的な資料はない。むしろ,平成19年〜平成28年における被告グループのシ ェアは●(省略)●で増減していると見られると共に,この変動はココアバターと の価格変動との関連性がうかがわれる(前記(3)エ(イ))。これを見る限り,本件各 発明の実施は,被告による競合他社からのシェア奪取にはつながっていないと考え られる。 また,被告との合計で CBE 市場の約8割のシェアを占める AKK 及び LC は, CBE 製造にあたり,いずれもシア脂から SOS パーツを製造・精製する工程におい て,溶剤分別法によっている。本件各発明はシア脂を原料とする分別にも利用でき るとされているものの,実際には,各設備の規模等のほか,本件工場の稼働による 被告のシェア増大といった事情もないことをも踏まえれば,競合他社にとって,多 額の設備投資を行って本件乾式分別法による設備を導入するメリットは乏しいと思 われ,本件各特許権の存在いかんにかかわりなく本件乾式分別法による設備の導入 は容易ではないと考えられるのであって,本件各特許権の存在が競合他社による本 件各発明の実施を回避させているとまではいえない。 このことは,原告との係争が表面化した後とはいえ,被告が特許料不納付により\n本件各特許権を消滅させ,又はその方向で対応する旨の判断を示していることとも 平仄が合うといえる。
なお,油脂分別技術の開発の方向性としては,安全性及びコスト面での問題を抱 える溶剤分別法から,最も持続可能性の高い方法とされる乾式分別法に向かうとし\nても,現状においては乾式分別法もなお問題点を抱えており,溶剤分別法も依然と して選ばれる場面があるとされていることなどに鑑みると,少なくとも本件各特許 権の存続期間においては,油脂分別法として溶剤分別法と乾式分別法はなお選択的 な関係にあるものと見るべきであって,その意味で,溶剤分別法は本件各発明の代 替技術として位置付けられる。
カ 小括
以上の事情を総合的に考慮すると,本件において,本件各特許権に係る通常実施 権の実施によって得られる利益の額を超えて被告が利益を得たと認めるに足りる証 拠はないというべきである。すなわち,被告は,本件各特許権により独占の利益を 得たとはいえない。
キ 原告の主張について
原告は,被告が本件各特許権により独占の利益を得ているとして,縷々主張する。 しかし,FVO パーツ品及び FVO 品の品質については,原告は主にパイロットレ ベルでの乾式分別法による SOS パーツの数値を根拠とするにとどまり,また,実 際に本件設備を用いて製造した FVO パーツ品を用いた分析結果等の信用性につき 疑義を抱くべき事情は見当たらない。また,コスト及び採算性については,前記の とおりである。
さらに,溶剤分別法に係る各種規制の存在も,溶剤分別法による設備の導入の障 害になり得るものではあっても,その新設が不可能ないし著しく困難であるとまで\n見るべき事情はない。このため,前記のとおり,油脂分別法として溶剤分別法はな お乾式分別法の代替技術といえる。 本件発明賞や本件経営賞の受賞等も,FVO における本件乾式分別法による設備 の導入に対する肯定的な評価を裏付けるものではあるものの,必ずしも被告に独占 の利益が生じたことを前提とするものではない。 被告の有価証券報告書に FVO から被告への特許料支払が記載されていること (甲74)についても,その支払が本件各特許権の実施に係るものであるかが明ら かではない上,本件各特許権の特許権者が被告であること,グループ会社とはいえ 被告と FVO とは法人格を異にすることなどに鑑みると,これをもって,被告に本 件各特許権による独占の利益が生じていることを示すものとは必ずしも見られない。 その他原告が縷々指摘する事情を踏まえても,この点に関する原告の主張は採用 できない。
2022.02.14
令和3(ワ)1333 著作権 令和3年12月21日 東京地方裁判所
前記認定のとおり,原告漫画1の累計発行部数(紙媒体による書籍,電子書籍及 び複数巻を一つにまとめた新装版を含む。以下同じ。)は約2000万部,原告漫画 2の累計発行部数は約370万部であり,原告漫画の1冊当たりの販売価格は46 2円であって,原告漫画の売上額は,およそ109億4940万円となるところ, 原告漫画の著作権者であると認められる原告が受けるべき使用料相当額は,原告漫 画の上記のような発行部数等に照らし,同売上額の10パーセントと認めるのが相 当である。 ところで,本件ウェブサイトによる原告漫画が無断掲載されたことにより,原告 漫画の正規品の売上が減少することが容易に推察され,原告漫画においても,発売 日翌日に本件ウェブサイト上にその新作が掲載されていたことによれば,新作が無 料で閲覧できることにより,読者の原告漫画の購買意欲は大きく減退するというべ きである一方,被告らの行為は,本件ウェブサイトによる原告漫画の違法な無断掲 載を,広告の出稿や広告料支払という行為によって幇助したものにとどまること, 原告漫画2の上記累計発行部数は令和2年1月頃までのものであって,本件ウェブ サイトが閉鎖された平成30年4月より後の期間における原告漫画2の売上げに関 して被告らの行為との間の関連性を認めることができないことその他本件に顕れた 一切の事情に照らして検討すれば,被告らの本件における行為が原告漫画の売上減 少に寄与した割合は,約1パーセントと認めるのが相当である。 これらの事情に鑑みると,本件ウェブサイトによる原告漫画に係る著作権(公衆 送信権)侵害行為を被告らが幇助したことと相当因果関係が認められる原告の損害 額は,1000万円(≒109億4940万円×0.1×0.01)と認めるのが 相当である。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.02.13
令和1(ワ)25121 特許権 令和3年12月9日 東京地方裁判所
このように,乙8発明は,ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し,そのリンク情報を取得して記憶し, ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして,かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は,ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ,当該リンクを出力することは,ユーザに対する提案を行うも のということができ,また,当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから, ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると,乙8発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は,構成要件1Eの「前記第1又は第2受付手段によって受け\n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し, また,乙8発明の,アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は,構\成要件5Eの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに,乙8発明における,ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は,構成要件1Fの「前記個人情報に基づいてウェブサ\nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し,上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は,構\成要件5Fの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他,構成要件E及びFと乙8発明の間に,相違する点は認められない。\n以上によれば,構成要件E及びFは,乙8発明の構\成と同一のものといえる。
エ 構成要件G(「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と,を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと,を更に有する」)につき,\n乙8発明と対比する。 構成要件Gに関し,本件明細書の記載をみると,「飲みすぎないように!」などの\nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり(【0119】),かかる記載内容 からすると,構成要件Gにおける「注意を促す」とは,気を付けるように仕向ける,\n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして,乙8発明は,スケジュールが未完了であることが確認すると,アバタ ーから,「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な,スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する(【0\n043】)。そして,乙8発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている(【0024】等)ところ,上記機能は,ユ\nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け,又は, スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると,乙8発明の,アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は, 構成要件1Gの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し,ま\nた,乙8発明の,ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は,構\成要件5Gの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他,構成要件Gと乙8発明の間に,相違する点は認められない。\n以上によれば,構成要件Gは,乙8発明の構\成と同一のものといえる。
オ 構成要件H(「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ\nグラム。」につき,乙8発明と対比する。 乙8発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は,情報の提供に当た るため,この点をもって既に,アバター管理部を有する乙8発明の学習・生活支援 サーバは,情報を提供する装置(「情報提供装置」)であるということができる。 また,上記サーバは,アバター管理部のほかに,ユーザ情報管理部,テキスト分 析部,情報収集部,コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており,制御部は,\n少なくとも一つのCPU等を備え,ROM等に予め記憶されたプログラムを読み込\nんで実行することにより,上記各部の機能を事項することが可能\となるものである (【0021】等)ことから,乙8発明の学習・生活支援サーバは,情報提供装置で あって,各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ,乙8発明\nは,構成要件1Hの「情報提供装置」,構\成要件5Hの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他,構成要件Hと乙8発明の間に,実質的に相違する点は認められない。\n以上によれば,構成要件Hは,乙8発明の構\成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって,本件各発明は,その全ての構成要件が,乙8発明の構\成と実質 的に同一のものであるから,本件各発明は,乙8発明との関係で,新規性を欠くも のといわざるを得ず,いずれも,特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる(特許法29条1項3号,123条1項2号)。
(5) 原告らの主張について
原告らは,1)乙8公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは, 構成要件Eにおける,議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す\nる,2)乙8公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは,ウェブサイトの 所在を示す情報であって,この所在を示す情報が,「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく,乙8発明は構成要件Eと相違し,また,ウェブサイトのリ\nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Fの「情報」とも相\n違する,3)乙8発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは,構成要件Gの,気を付けるよう仕\n向けることとは相違する,4)乙8発明のユーザ端末は,情報提供をするものではな いから,構成要件Hと相違する,などとして,本件各発明が乙8発明の構\成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら,原告らの上記各主張は,次のとおり,いずれも理由がないという べきである。 まず,上記1)及び3)の点については,乙8発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは,スケジュールが完了していないことを知り,新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって,「スケジュールの 修正の依頼」も,ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから,構成要件Eの「提案を行う」と実質的に同一の構\ 成であるといえる。また,乙8発明の上記のような働きは,まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け,又は,気を配るよう に仕向けることであるといえるから,乙8発明は,構成要件Gの「注意を促す手段」\nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。\nまた,上記2)の点については,構成要件Eの「提案を行う」との文言について,\n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に,ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく,ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上,前記説示のとおり,キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは,当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し,まさに,この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると,乙8発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは, 構成要件Eが規定するユーザに対する「提案を行う」との構\成と,同一であるとい わなければならない。また,構成要件Fの「情報」との相違を指摘する原告の主張\nも,結局,リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず,これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが,前記のと おり,ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは,ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において,ユーザに提案すべき情報を表示するものであり,乙8発明\nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは,構成要件Fの「情報」と異なるもので\nはないというべきである。 さらに,上記4)の点は,前記説示のとおり,乙8発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは,構成要件1Hの「情報提供装置」,構\成要件5Hの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば,原告らの主張はいずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.02. 8
令和3(行ケ)10113 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月25日 知的財産高等裁判所
(3) 上記認定事実によれば,「睡眠コンサルタント」が,「睡眠の事柄につい て相談・助言・指導を行う専門家」の意味合いを容易に認識させることは, その構成から明らかである。そして,上記認定事実によれば,「睡眠コンサ\nルタント」と称する資格又は「睡眠コンサルタント」の文字を含む名称を冠 する資格を与える団体が存在し,当該団体が睡眠に関する専門的な知識の教 授等を行っている例が複数あること(上記ア〜エ),これらの団体により認 定資格を得た者が「睡眠コンサルタント」と名乗り,睡眠に関する知識の教 授,及び睡眠に関するセミナーの企画・運営又は開催を行っている例が複数 あること(上記オ〜ク),それ以外にも,睡眠に関する専門的な知識を有す る「睡眠コンサルタント」と称する者が,睡眠に関する知識の教授,及び睡 眠に関するセミナーの企画・運営又は開催等を行っている例が複数あること (上記ケ〜タ)が認められる。また,知識の教授及びセミナーの企画・運営 又は開催を行う業界において,講義及びセミナー等の内容に関する書籍(テ キスト,問題集等)及びビデオ等が制作されている実情があることは,顕著 な事実である。
以上からすると,本願商標は,本願指定役務である「技芸・スポーツ又は 知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制 作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用 のものを除く。)」との関係で,本件審決がされた令和3年7月26日の時 点において,「睡眠に関する専門的な知識を有する者による,睡眠に関する 役務である」という役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切\nな表示であり,本願商標の取引者,需要者によって本願商標が本願指定役務\nに使用された場合に,役務の質を表示したものと一般に認識されるものであ\nるから,本願商標は,本願指定役務について役務の質を普通に用いられる方 法で表示する標章のみからなる商標であると認めるのが相当である。\nしたがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。これと同旨の 本件審決の認定判断に誤りはない。 ・・・ 原告は,「○○〇コンサルタント」という商標の登録例が多数あること,専門分野を表す「〇〇〇」の次に「専門家」を意味する言葉を付加した商標の登録例も多数あることを挙げて,これらの登録例と構\成を同じくする本願商標は登録されて然るべきである旨主張する。しかしながら,商標登録の可否は,商標の構成,指定役務,取引の実情等を踏まえて,具体的な実情に基づき商標ごとに個別に判断すべきものであって,原告が指摘するような他の商標登録事例が多数あるからといって本願商標の登録の可否が影響を受けるものではないから,本願商標が本願指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表\示する標章のみからなる商標であることを否定する理由にはならない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2022.02. 8
令和3(行ケ)10092 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月27日 知的財産高等裁判所
ア 上記(1)ないし(3)のとおり,本件商標及び引用商標は,観念において類 似するものではないものの,外観及び称呼が互いに相紛らわしいものであ るというべきである。 そして,前記3で検討したとおり,本件商標及び引用商標に係る需要者 には一般消費者が含まれるものであるところ,一般消費者が通常有する注 意力を踏まえると,外観及び称呼が互いに相紛らわしい両商標を取り違え ることは十分にあり得るといえることからすれば,両商標の類似性の程度\nは,相当程度高いというべきである。
イ 原告は,引用商標の取引の実情に関して,商標中の大文字のアルファベ ットを小文字表記に変えて使用することなどは全く行われておらず,この\nことは引用商標においても同様である旨主張する。 しかしながら,上記(1)イのとおり,アルファベットからなる商標の使用 においては,その構成文字について,大文字と小文字とを相互に変換して\n表記することが一般に行われているといえる。また,商標法においても,\n商標登録の取消しの審判について,登録商標と社会通念上同一と認められ る商標(例えば,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更\nするものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標)の使用を証明するこ とによって商標登録の取消しを免れることができる旨が規定されている が(商標法50条1項,2項,38条5項),これは,商標の使用において は,同一の称呼及び観念が生じる範囲内で商標の構成文字の文字種を相互\nに変換して表記したり,デザイン化したりすることが一般によく行われる\nことを前提とした規定であるといえる。これらの事情を考慮すると,商標 中の大文字のアルファベットを小文字表記に変えて使用することが全く\n行われていないということはできない。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
5 出所混同が生ずるおそれの有無
本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基 準として,前記2ないし4において検討した事情を総合的に考慮すると,注意 力がそれほど高いとはいえない一般消費者が,被告補助参加人及びそのグルー プ会社の業務に係る商品及び役務を表示するものとして極めて高い周知著名性\nを有する引用商標に相当程度類似し,取り扱う商品も密接に関連する本件商標 が付された商品に接した場合には,当該商品が被告補助参加人及びそのグルー プ会社の業務に係る商品であると混同するおそれがあるというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.02. 4
令和2(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月2日 知的財産高等裁判所
(イ) 前記(ア)の各記載によると,本件基準日当時の骨粗鬆症に関する技術 常識は,次のとおりである。すなわち,1)骨粗鬆症は,骨強度の低下を特徴とし,骨折の危険性が増大した骨疾患であり,その治療の目的は,骨折を予防し,QOL(qu\nality of life)の維持改善を図ることである,2)骨粗鬆症は,加齢とと もに発生が増加する,3)骨粗鬆症による骨折の複数の危険因子の中で, わが国では,低骨密度,既存骨折,年齢に関するエビデンスがある,4) 骨粗鬆症の診断基準に関して,1990年当時,厚生省シルバーサイエ ンスプロジェクト「老人性骨粗鬆症の予防および治療に関する総合的研\n究班」により提唱された診断基準(1989年診断基準)があったが, 1996年に診断基準が改訂され(1996年診断基準),その後,20 00年に更に改訂された(2000年診断基準),5)骨強度は骨密度と骨 質の2つの要因からなり,骨密度が骨強度のほぼ70%を,骨質が残り の30%を説明することが知られていたといえる。
イ 本件3条件について
(ア) 甲7発明と本件発明1とは,「1回当たり200単位のPTH(1− 34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする」との用量の点 において一致するが,その投与の対象となる骨粗鬆症患者の範囲を一応 異にする。
(イ) 甲7発明で投与対象とされた患者は,前記(1)のとおり,1989年診 断基準で骨粗鬆症と診断された患者であるところ,より新しい基準を参 酌しながらその患者を選別することは,当業者がごく普通に行うことで あるから,甲7発明に接した当業者が,甲7発明のPTH200単位週 1回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する対象患者を選択するのであれば, 1989年診断基準とともに,より新しい,1996年診断基準又は2 000年診断基準を参酌するといえる。 そして,前記ア(ア)b及びcのとおり,1996年診断基準で骨粗鬆 症と診断される者は,1)骨萎縮度I度以上又は骨密度値がYAMの8 0%以下の低骨量で非外傷性椎体骨折を有する者か,2)X線上椎体骨折 を認めないが,骨萎縮度II)度以上,又は,骨密度値がYAMの70%未 満である者であり,2000年診断基準で骨粗鬆症と診断される者は, 3)骨萎縮度II)度以上又は骨密度がYAMの80%未満の低骨量が原因で, 軽微な外力による非外傷性椎体骨折等(脆弱性骨折)を有する者か,4) 脆弱性骨折がないものの,骨萎縮度II)度以上,又は,骨密度値がYAM の70%未満の者である。
本件条件(2)及び本件条件(3)は,上記1)と同じであるから(「既 存椎体骨折」は「非外傷性椎体骨折」を含む。),当業者が甲7発明の2 00単位週1回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する骨粗鬆症患者を本件条 件(2)及び本件条件(3)で選別するのには何ら困難を要しない。 また,前記ア(イ)のとおり,骨粗鬆症は,加齢とともに発生が増加す るとの技術常識があり,高齢者は加齢を重ねた者であるのは明らかであ るところ,高齢者として65歳以上の者を選択するのは常識的なことで あり,高齢者の医療の確保に関する法律32条でも65歳以上が高齢者 とされている。したがって,これらを参酌し,骨粗鬆症による骨折の複 数の危険因子として,低骨密度及び既存骨折に並んで年齢が掲げられて いることに着目して投与する骨粗鬆症患者を65歳以上として,本件条 件(2)及び本件条件(3)に加えて本件条件(1)のように設定する ことはごく自然な選択であって,何ら困難を要しない。 そうすると,甲7発明に接した当業者が,投与対象患者を本件3条件 を全て満たす患者と特定することは,当業者に格別の困難を要すること ではない。
ウ 被告の主張について
(ア) 被告は,前記第3の3(2)ア(イ)a及びbのとおり,本件3条件は, 層別解析により初めて,本件条件(1)ないし本件条件(3)を組み合 わせるとPTHの骨折抑制効果が高いという新規な知見を得たことに基 づくものであり,本件3条件は一般的な指標ではなく,甲7文献の開示 事項からは導かれず,むしろ甲7文献にはサブグループ間で薬物に対す る応答は同程度であった旨の記載があり,甲7発明から本件3条件を選 択する動機付けは否定される旨主張する。
しかしながら,前記イにおいて判示したように,本件基準日における 技術常識に照らせば,甲7発明に接した当業者が投与対象患者を本件3 条件を全て満たす患者とすることに格別の困難はない。また,本件3条 件の組合せについても,客観的観点からその選択において格別なもので ある,あるいは,他の骨折リスク因子等も含めた様々な組合せが想定さ れる中で本件3条件を組み合わせること自体に特別の意味合いがあると 認めるに足りる証拠はない(被告が主張する層別解析は,後述するよう に,あくまで本件3条件の全てを満たす患者(高リスク患者)のグルー プと,本件3条件の全部又は一部を満たさない患者(低リスク患者)の グループのうちごく一部のグループとを比較するものにすぎず,また, その結果自体も被告主張の顕著な効果が認められると即断できるもので はない。)。 そして,確かに甲7文献には,別紙2のとおり,「年齢が64歳以下と 65歳以上,体重が49kg以下と50kg以上,閉経後10年未満,10 から20年,20年以上,および脊椎骨折が0,1および2箇所以上を 有するサブグループに被験者を分類して比較したところ,サブグループ 間で薬物に対する応答は同程度であった。」との記載があることは認めら れるものの(300頁左欄11行ないし右欄6行目),当該記載は,上記 記載中の条件によってサブグループ化されたサブグループ間の薬物効果 の比較について述べているにすぎず,当該記載により,甲7発明の投与 対象患者をサブグループ化すること全般が阻害されるとはいえない。 したがって,被告の上記主張は,いずれも採用することができない。
(イ) また,被告は,前記第3の3(2)ア(イ)cのとおり,甲7発明におけ る200単位投与群には,副作用が多発しており,200単位は副作用 脱落率が高い用量と認識されているから,当業者はこれを試みない旨主 張する。
確かに,別紙2のとおり,甲7文献には,PTH200単位週1回投 与のH群の副作用発生率は42%であり,72人のうち16人(約22%) が副作用により脱落していて,副作用発生率及び副作用による脱落率は, 50単位を投与したL群(副作用発生率19%)及び100単位を投与 したM群(副作用発生率19%)のいずれと比べても高いことが記載さ れており(表6),骨粗鬆症の治療は長期間にわたるため,臨床使用にお\nいて患者の症状や治療継続意思に直接に影響する副作用が起こることは 望ましくはないから(甲70ないし72,100),甲7文献の上記記載 に接した当業者は,この点に限っていえば,200単位の投与よりも1 00単位の投与の方がより適当であると認識することが考えられる。 しかしながら,他方,甲7文献には,重篤な有害事象は認められない と記載されており(301頁左欄1行ないし右欄4行目),さらに,20 0単位の投与が腰椎骨密度を48週間後に8.1%増加させたこと,及び, その増加の程度は,100単位投与の3.6%,及び,50単位投与の0. 6%のいずれよりも高いことが記載され,PTHは腰椎骨密度を48週 という比較的短期間で用量に依存して増加させる極めて有望なものと評 価されている(300頁左欄11行ないし右欄6行目,301頁右欄5 行ないし303頁右欄23行目。有望とされた対象から200単位の投 与のみが排除されているとは理解し難い。)。そして,前記ア(イ)のとお り,骨粗鬆症の治療の目的は骨折を予防することであるところ,骨密度\nが低いことは,既存骨折,年齢とともに,わが国でエビデンスがある骨 折危険因子であり,骨密度は骨強度のほぼ70%を説明するとの技術常 識がある。
以上によれば,甲7文献に接した当業者は,200単位週1回投与と 100単位週1回投与とを対比した場合に,副作用の面と効果の面を総 合考慮して,いずれを選択するか判断するものと考えられ,200単位 週1回投与がその選択が排除されるほど劣位したものと見られるとはい えず,これを選択することもまた十分に動機付けられているというべき\nである。したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
(ウ) さらに,被告は,前記第3の3(2)ア(イ)dのとおり,PTH製剤が 高齢者には効きにくいということは技術常識であったから,PTH製剤 を高齢者に特に使用しようとする積極的な動機付けは生じない旨主張す る。
被告は,関係文献(乙29)を挙げて,PTH製剤が高齢者には効き にくいということは技術常識であるとするが,「フォルテオ皮下注キット 600μg フォルテオ皮下注カート600μg「2.7.3臨床的有 効性の概要」」(乙29)における記載(213頁)として,プラセボ投 与群,テリパラチド20μg投与群(連日投与)及びテリパラチド40 μg投与群(連日投与)に分けてフォルテオを投与をした際の新規椎体 骨折発生率の結果が示されているところ,65歳以上75歳未満の患者, 及び,75歳以上の患者いずれに対しても,テリパラチド投与群におけ る椎体骨折発生率は,プラセボ投与群の椎体骨折発生率より低くなって いるから,これらの記載をもって,フォルテオが高齢者,すなわち65 歳以上の患者に効きにくいなどとはいえない。また,被告は,20μg投与群又は40μg投与群のプラセボ投与群に対する骨折相対リスク減少率は,患者が75歳以上の場合には,65歳以上75歳未満の場合よりも低くなっている旨を指摘するが,75歳 以上の患者群の骨折相対リスク減少率が65歳以上75歳未満の患者群 の骨折相対リスク減少率よりも低いとしても,それは,投与対象を75 歳以上の高齢者とすることの動機付けの有無の問題にはなるとしても, 投与対象を65歳以上の高齢者とすることの動機付けには何らの影響を 与えない。したがって,上記各文献をもって,200単位のPTH製剤を65歳 以上の高齢者に投与することが妨げられ,動機付けが生じないとはいえ ない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2022.02. 4
令和3(行ケ)10037 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月2日 知的財産高等裁判所
以上の訂正前明細書の記載を全体的に総合して観察すると、訂正前 発明における「固定」には、摩擦力やチルト機構等を用い所定量以上の\n力を加えることによって状態の変更が可能な「半固定」と、ストッパ等\nを用い回動を停止させる「一時的に固定」の2種類が存在し、時に「半 固定」と「一時的に固定」とを混然と使用する箇所もないではないが、 これらを使い分けていることが理解できるし、これらが概念的に異なる ものであることはその性質上も明らかである。このことを考慮して、訂正前発明1の構成をみてみると、2つの表\示板を約120度から約170度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成eの中間左右見開き固定手段は、「一時的\nに固定」する手段であり、2つの表示板を「摩擦力により」「保持する」\n構成Cの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らか\nであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理 解できる。したがって、構成eの中間左右見開き固定手段の構\成を基に して、任意角度保持手段について「任意の角度」を約120度から約1 70度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈 する根拠はないこととなり、任意角度保持手段の「任意の角度」は通常 の語義に従い、0度から360度の範囲が含まれると理解すべきもので ある。
(オ) 以上からすると、訂正事項1−4は、訂正前発明に、2つの表示板を\n0度から最大見開き角度までの任意の角度とすることができ、最大見開 き角度が約180度を超えるものを包含するよう訂正するものとなる ところ、このような構成は訂正前明細書には記載されていない。\nしたがって、訂正事項1−4は、訂正前の明細書の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事 項を導入しないものであるとはいえない。
イ 原告の主張について
原告は、前記第3の1(1)イのとおり、1)「ユーザーの任意の角度」とは、 ユーザが装置の構造上の制約の下に自由意思により変化・回動させること\nができる角度である、2)180度を超えてから360度まで回動させても 2つの表示板の各画面を容易に見ることができず実用的な意味は全くな\nい、3)0度から360度まで回動させるためにはヒンジ部の1つの回転軸 を2つの表示板の厚さ寸法を合計した長さ以上の巨大な直径を有する回\n転軸としなければならないが、訂正前明細書【図2】からみると訂正前発 明の表示装置はそのような構\造を有していない旨主張する。 しかしながら、「あらかじめ定められた角度にユーザが任意に変化させ られること」と「ユーザが任意の角度に変化させられること」とは、固定 方法を異にすれば両立する機能であるところ、どちらも角度の変化はユー\nザがその自由意思によりするものであるから、訂正前明細書にユーザが自 在に枠体を折り曲げられるとの記載等、角度の変化がユーザの自由意思に よるとの記載があったからといって、「任意の角度」が前者に限定されると する根拠にはならず、上記1)の主張は採用することができない。 また、引用文献1には第1のパネル12と第2のパネル14が背中合わ せで並置され、片手で装置を運び、もう片方の手でデータを入力する状態 が記載されていることからしても(9頁32行ないし10頁13行目、図 3)、表示装置の2つの表\示板の回動角度を270度ないし360度の範 囲にまで設定可能にする使用方法も十\分に実用的なものといえるから、上 記2)の主張も採用することができない。 また、上記3)の主張は、単なる実施例に関する図面に基づく主張にすぎ ず、訂正前発明は、ヒンジ軸の構造も、回転軸の直径も、表\示板の厚さも 何ら特定するものではないから、前提を欠くものとして失当である。 したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。その ほか、原告はるる主張するが、いずれも、前記アの認定判断を左右しない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項1−4は新規事項を追加する訂正で ある。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2022.02. 1
令和3(行コ)10001 手続却下処分取消等請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和4年1月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
エ 控訴人は,1)法184条の4第4項の立法趣旨や立法経緯,特許庁の ガイドラインに鑑みると,期間徒過の原因となった事象が予測可能\であ るといえない場合は,当該事象により期間徒過に至ることのないように 事前に措置を講じておくことを出願人等に求めるのは酷であることから すると,期間徒過の原因となった事象が出願人等の補助者の人為的ミス に起因するときは,ガイドラインの「相応の措置」(状況に応じて必要と されるしかるべき措置)が採られたかどうか,すなわち,期間内に手続 をすることができなかったことについて「正当な理由」があるかどうか は,監督者が個々具体的な人為的ミスを防ぐための措置を採っていたか ではなく,当該補助者を使用する出願人等がガイドライン3.1.5(5) に規定するaからcの3要件を満たしているか否かによって判断される べきである,2)本件特許事務所では,特許期限管理システム「IPマネ ージャー」を使用し,経験豊富な補助者(A,B及びC)を起用するな ど期間徒過が生じることがないようにするための期限管理体制が採用さ れていたが,本件期間徒過は,本件国際出願の期限前日である平成28 年9月21日,本件国際出願の出願書類の準備と本件国際出願用の新た な期限管理ファイル(本件期限管理ファイル)作成の作業が並行して行 われるという緊急事態の状況下で,Aが錯誤により本件期限管理ファイ ルに本件国際出願の基礎出願の優先日を誤入力し,優先日の入力に対す るB及びCによるダブルチェックが働かず,Aの誤入力が見過ごされた 結果,IPマネージャーによって誤った優先日に基づいて誤った国内移 行の移行期限が自動作成され,それに気づかなかったことが重なって偶 発的に起きた事象であり,このような特殊な事態に起因する複数の補助 者による偶発的な確認ミス等は予測可能\であるといえないから,上記期 限管理体制は,「相応の措置」に該当し,本件期間徒過を回避することが できなかったことについて「正当な理由」があるというべきである旨主 張する。 しかしながら,1)については,ガイドラインは,期間徒過後の救済規 定に関し,救済要件の内容,救済に係る判断の指針及び救済規定の適用 を受けるために必要な手続を例示することによって,救済が認められる か否かについて出願人等の予見可能\性を確保することを目的として,特 許庁が作成したものであり(乙4の表紙から4枚目の「期間徒過後の救\n済規定に係るガイドラインの利用に当たって」),法令等の法規範性を有 するものではなく,裁判所の法令の解釈やその判断を拘束するものでは ない。
次に,2)については,前記(2)及び(3)によれば,IPマネージャーの期 限管理ファイルの「基礎出願」欄に優先日として優先権を主張する基礎 出願の出願日を正確に入力することは,控訴人から本件国際出願の委任 を受けた本件特許事務所の基本的な業務であり,これを正確に入力する 必要性が高いことは明らかであること,本件においては,国際出願手続 及び各国への国内移行手続を担当するCから,ドケット管理部署に所属 するAへの連絡が適切ではなかったこと,本件期限管理ファイルを作成 したAは本件国際出願に係る優先日として米国特許仮出願1及び2のい ずれの出願日を入力すべきであるかを十分に確認することなく誤った優\n先日を入力(本件誤入力)したこと,本件国際出願の際のD弁護士等に よるチェック,本件国際出願後のBによるチェック及び本件国内移行期 限管理ファイル作成の際のドケット管理部署による優先日の事後的なチ ェックがいずれも行われなかったか,不十分であったことによって本件\n期間徒過が発生したことが認められる。 また,本件国際出願の期限の前日に,本件国際出願の出願書類の準備 と本件国際出願用の新たな期限管理ファイル(本件期限管理ファイル) 作成の作業を並行して行うことが,緊急事態であるということも,特殊 な事態であるということもできないし,本件国際出願を期限に余裕をも って行えば,このような事態に至ることを回避することも可能であった\nものである。
さらに,Aの本件誤入力は,本件期限管理ファイルへ優先日として米 国特許仮出願1の出願日である「2015年9月22日」と入力すべき であったのに,米国特許仮出願2の出願日である「2015年12月1 6日」と入力したという単純なミスであり,D弁護士等,B又はドケッ ト管理部署が,通常の注意力をもって,他の資料等と照合してダブルチ ェックを行えば,容易に発見することができたものと認められる そうすると,控訴人から委任を受けた本件特許事務所の担当弁護士や 補助者事務員が本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしたも のと認められないから,控訴人において,本件期間徒過を回避すること ができなかったことについて「正当な理由」(法184条の4第4項)が あるものと認めることはできない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
◆判決本文
同様の人為ミスの事件です。
知財高裁2部は、正当理由についてかなり踏み込んで判断しています。
◆令和3(行コ)10002
(ア) 控訴人は,本件技術担当補助者は特許庁における7年以上の職歴を有する弁
理士であり,担当弁理士においては,本件案件について相当な注意を払って本件技
術担当補助者を選任したものである旨を主張するが,一般的に,本件技術担当補助
者が特許庁において担当していた業務と,その後担当弁理士の事務所において担当
するに至った業務とを同視することはできないものであるところ,本件全証拠によ
っても,これらを同視することができる事情を認めることはできない。補正して引
用した原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」(以下,単に「原
判決の第4」という。)の1(3)イ(ア)で認定したとおり,本件技術担当補助者は,
平成30年4月に担当弁理士の事務所に採用され,本件案件について指示を受けた
当時,同事務所における勤務経験は2か月程度にすぎなかったものであって,そも
そも「業務の進め方」に記載された通常の業務の流れについてすら,必ずしも習熟
していたといえるか疑問が残るところである。
上記に関し,同じく原判決の第4の1(2)で指摘した本件回復理由書の記載によ
ると,本件期間徒過に至った当時,本件技術担当補助者に対する指導・教育等のた
めに担当弁理士の業務負担は一時的に更に増大していたなどというのであるが,そ
のことは,本件技術担当補助者の特許庁における経験や弁理士という資格をもって,
直ちに担当弁理士の事務所における技術担当補助者としての業務の遂行能力を評価\nすることができないことを裏付けているといえる。なお,控訴人が提出する世界知
的所有権機関のPCT受理官庁ガイドライン(甲35)の166Mの(f)においても,
出願人又は代理人が説明すべき事情の一つとして,当該補助者が「その特定の業務」
を任されていた年数が指摘されているところである。
したがって,控訴人の上記主張は,本件期間徒過について正当な理由が認められ
ないとの前記認定判断を左右するものではない。
(イ) 控訴人は,本件技術担当補助者の誤認や思い込みは,担当弁理士の想定外の
人為的ミスというほかない旨を主張するが,本件期間徒過の原因について,専ら本
件技術担当補助者の単独の人為的過誤であると評価することが相当でないことは,
補正して引用した原判決の第4の1(3)アで説示したとおりである。
(ウ) 控訴人は,補助者の選任について相当な注意を払っていた以上,担当弁理士
においては,補助者を信頼することが許されるという旨を主張するが,補正して引
用した原判決の第4の1(3)アで説示したとおり,本件期間徒過に関しては,担当弁
理士の指示の方法が本件技術担当補助者の誤認に無視できない影響を与えたものと
みるのが相当であって,そのことや,前記(ア)で指摘した点を考慮すると,控訴人の
上記主張は,その前提を欠くものというべきである。
(エ) 控訴人は,来客対応や外出等が重なれば,担当弁理士において,期限管理シ
ステムにアクセスする余裕がないことが生じ得ることや,補助者への指示が万事円
滑に行われているという認識の下において担当弁理士に期限管理システムにアクセ
スする義務があるとはいえない旨を主張するが,前者の点は,何ら正当な理由を基
礎付ける事情に当たらず,後者の点は,前記(ウ)で説示したところからして,本件期
間徒過についてはその前提を欠くものというべきである。
(オ) その他の控訴人の主張する点も,本件期間徒過について正当な理由が認めら
れないとの前記認定判断を左右するものではない。
以上に関し,本件技術担当補助者の誤認についての主張からすると,控訴人は,
要するに,弁理士であって国内書面の提出期限の重要性を認識していた本件技術担
当補助者においては,少なくとも事務担当補助者から国内書面の印刷物を渡された
以上,担当弁理士が直接に事務担当補助者に国内書面の作成を指示したといった事
情にかかわらず,自らの経験も踏まえ,国内書面提出期間の徒過に至らないよう対
応すべきであったものであり,そのような対応をしなかった本件技術担当補助者に
本件期間徒過のほぼ全面的な責任があるとの捉え方を前提として,担当弁理士には
正当な理由があったことを主張するものとみられるが,本件技術担当補助者に対す
るそのような要求ないし期待は,「業務の進め方」に記載された通常の業務の流れ
における技術担当補助者の責任の範囲すらも一定程度超えるものとみ得るものであ
り,ましてや,担当弁理士が通常の業務の流れから逸脱した形で指示を行った本件
において,担当弁理士が相当な注意を尽くしていたことを基礎付ける事情とは到底
なり得ないものである。
2022.02. 1
令和3(ネ)10025 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和4年1月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア(ア) 本件アマゾンサイトのウェブページ(本件切替え画像)において, 別紙3(2)のとおり,交換用カートリッジのイメージ画像の左上部に被告 表示2が,その下の中央部に「待望の」,「交換用カートリッジ」,「つい に発売!!」との本件三段書き表\示が,被告表 示2の左上部に小さく表\ 示された複数の画像が,その上に青色の文字で「【ノーブランド品】タカ ギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カートリッジ...」 との表示が掲載されていた。
本件切替え画像は,交換用カートリッジのイメージ画像及び本件三段 書き表示の「交換用カートリッジ」,「ついに発売!!」の文字部分から, イメージ画像に表\示された交換用カートリッジの商品の販売広告である ことを理解できる。
また,被告表示2は,
「タカギ社製
浄水蛇口の交換用カートリッジを
お探しの皆様へ」
と青色の文字で3段書きに表示してなるものである。
被告表示2の上段の「タカギ社製」の文字部分(被告標章)及び中段 の「浄水蛇口の交換用カートリッジ」の文字部分の2段の記載部分は,\n販売広告の対象商品と関連付けたものとして理解できる。そして,2段 の上記記載部は,その構成態様から,「タカギ」が製造した「交換用カー トリッジ」を表\示したものと読み取ることが可能 であり,また,「タカギ」\nが製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」を表示した ものと読み取ることも可能\であると一応考えられる。 一方で,被告表示2の左上部に小さく表\ 示された複数の画像の上に青 色の文字で「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互 換性のある交換用カートリッジ...」との表示は,販売広告の対象商品が 「ノーブランド品」であって,「タカギ」が製造した「浄水器」に使用で\nきる「交換用カートリッジ」であることを説明したものと理解できる。 そして,1)「ノーブランド品」とは,ブランドを掲げずに一般名称の みを記した商品を意味するものと解されること,2)原告表示(黒色のゴ シック体の「タカギ」の表\示)は,家庭用浄水器及びその関連商品を購 入しようとする需要者の間において,控訴人の業務に係る商品を表示す るものとして周知となっており(前記1(1)イ),家庭用浄水器及びその 関連商品のブランド名として理解されていたことに鑑みると,控訴人製 の純正品の交換用カートリッジについて「ノーブランド品」と表示する ことは通常考えられないというべきであるから,本件切替え画像に接し\nた需要者は,「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け 互換性のある交換用カートリッジ...」との表示は,販売広告の対象商品 が控訴人製の純正品とは異なる商品であることを示したものと理解する\nものと認められる。 そうすると,「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付 け互換性のある交換用カートリッジ...」との表示は,被告表\ 示2の上段 の「タカギ社製」の文字部分(被告標章)及び中段の「浄水蛇口の交換 用カートリッジ」の文字部分の2段の記載部分が「タカギ」が製造した 「交換用カートリッジ」(控訴人製の純正品)を表示したものと読み取る ことを否定する打ち消し表\示としての機能 を有するものと認められる。\nしたがって,本件アマゾンサイトの本件切替え画像の被告表示2に接 した需要者は,被告表\示2の上段の「タカギ社製」の文字部分(被告標 章)及び中段の「浄水蛇口の交換用カートリッジ」の文字部分の2段の 記載部分は,「タカギ」が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カー トリッジ」を表示したものと理解するものと認められる。
(イ) 以上によれば,被告表示2における被告標章の使用によって,被告 商品が控訴人製の純正品であると需要者に誤認させて,被告商品の出所\nが控訴人又は控訴人の関連会社であるとの混同を生じさせるおそれが あるものと認めることはできないし,また,その営業主体が控訴人又は 控訴人の関連会社であるとの混同を生じさせるおそれがあるものと認 めることはできない。
イ(ア) これに対し控訴人は,本件アマゾンサイトアンケート調査の結果に よれば,「ノーブランド品」と掲げ,かつ,「タカギの浄水器に使用でき る、取付け互換性のある交換用カートリッジ」と表示されていたとして も,「タカギ」が製造・販売元であると認識する回答者の数は,「タカギ」\nが製造・販売元ではないと認識する回答者の数を上回っており,また, 原告製浄水器を使用したことがある需要者に着目すると,3分の1を超 える需要者は「タカギ」が製造元であると認識していることに照らすと, 「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある 交換用カートリッジ」との表示が,被告商品が「タカギ」が製造・販売 する商品ではないと需要者が認識する表\示(打ち消し表 示)であるとい\nうことはできないなどとして,上記調査結果から,本件切替え画像に接 した大多数の需要者は,被告標章を含む被告表示2から,「タカギ」 が被告商品の製造・販売元であると認識する旨主張する。\nそこで検討するに,証拠(甲23ないし25)によれば,本件アマゾ ンサイトアンケート調査は,本件アマゾンサイトに掲載された被告表示 2についての需要者の認識を確認することを目的とし,控訴人がGMO\nリサーチに委託し,2021年(令和3年)4月27日,20歳以上9 9歳以下のオンラインショッピング利用経験者を調査対象者とし,別紙 4(3)の本件アマゾンサイトの商品ページに掲載されている商品の画像及 びその説明文(本件アマゾンサイト画像1)),別紙4(4)の本件アマゾンサ イトの商品ページに掲載されている商品の画像(本件アマゾンサイト画 像2))を提示して,調査対象者が,画像を見ながら質問に回答するオン ラインリサーチを実施し,それぞれの画像につき各500名の回答(回 答者の重複はない。)を得て,その回答結果を集計したものであることが 認められる。
しかるところ,前記1(3)ア(ア)認定のとおり,原告商品の需要者は,家 庭用浄水器及びその関連商品を購入しようとする者であり,原告製浄水 器の交換用カートリッジである被告商品の需要者も,これと同様である ところ,本件アマゾンサイトアンケート調査の調査対象者は,20歳以 上99歳以下のオンラインショッピング利用経験者であって,その中に は,家庭用浄水器及びその関連商品を購入しようとする者以外の者が含 まれている点において,本件アマゾンサイトアンケート調査の結果は, 需要者の認識を正確に反映したものとはいえない。 また,本件アマゾンサイトアンケート調査で調査対象者に提示された 画像は,本件切替え画像全体ではなく,そのうちの被告表示2のみの画 像(本件アマゾンサイト画像2))であり,交換用カートリッジの購入を 検討する需要者が実際に接する画像と異なることに照らすと,本件アマ ゾンサイトアンケート調査の結果から,需要者の認識を確認すること は困難であるというべきである。 したがって,その余の点について検討するまでもなく,控訴人の上記 主張は,採用することができない。
(イ) また,控訴人は,甲18の報告書記載のとおり,本件アマゾンサイト の被告標章に接した複数の顧客から被告商品を控訴人製の純正品である と勘違いして購入した旨のクレームを受けたことを根拠として挙げて, 被告標章の使用によって,被告商品が控訴人製の純正品であると需要者 に誤認させた旨主張する。 しかしながら,甲18の報告書に記載されている「顧客」が本件アマ ゾンサイトで被告商品を購入した者であるかどうかは不明であり,その 数も僅かであることに照らすと,甲18の報告書の記載から,被告標章 の使用によって,被告商品が控訴人製の純正品であると需要者に誤認さ せたものと認めることはできない。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 前記ア及びイによれば,被控訴人グレイスランドが本件アマゾンサイト で被告商品の広告に被告表示2を掲載した行為による被告標章(「タカギ 社製」の表\示)の使用が,控訴人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 に該当するものと認めることはできないから,控訴人の前記主張は,理由 がない。
(3) 小括
以上のとおり,被控訴人グレイスランドが本件アマゾンサイトで被告商品 の広告に被告表示2を掲載した行為による被告標章の使用は,控訴人の商品 又は営業と混同を生じさせる行為に該当するものと認められないから,不競\n法2条1項1号の不正競争行為に該当しない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2022.02. 1
令和2(行ケ)10080等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月27日 知的財産高等裁判所
(3) 本件出願当時の5−HT1A 受容体部分作動薬の双極性障害のうつ病エピ ソードに対する治療効果に関する技術常識について\n
ア 前記(1)イの記載事項を総合すると,本件出願当時,1)大うつ病(単極性 うつ病)の症状の一つである「大うつ病エピソード」(うつ病エピソ\ード) と双極性障害(双極性障害I)型及びII)型)の症状の一つである「大うつ病 エピソード」(うつ病エピソ\ード)の定義及び診断基準は同一であったこと, 2)大うつ病性障害の患者に有効であることが立証されているすべての抗う つ薬は双極性障害のうつ病エピソードの患者にも有効であると考えられて\nいたこと,3)一方で,双極性障害の患者に対する抗うつ薬の投与によって, 躁病エピソードを誘発し,躁転や急速交代化を引き起こす可能\性があるが, このような可能性がある場合には,抗うつ薬の投与量の調整,気分安定薬\nとの併用等により対応していたことが認められる。 上記認定事実と5−HT1A 受容体部分作動薬が,脳内のシナプス後5− HT1A 受容体に結合することによって発現する5−HT1A 受容体部分作 動作用に基づいて抗うつ作用を有することは,本件出願当時の技術常識で あったこと(前記(2))によれば,本件出願当時,5−HT1A 受容体部分 作動薬一般がその抗うつ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対\nして治療効果を有することは技術常識であったことが認められる。
イ この点に関し本件審決は,本件出願時において,各種の抗うつ薬を双極 性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用することができることは,技\n術常識であるが,一方で,双極性障害の患者に抗うつ薬を使用した場合, 躁病エピソードの誘発,軽躁エピソ\ードの誘発,急速交代化の誘発,及び 混合状態の悪化等の様々な有害事象が生じる危険性があることを考慮する と,全ての抗うつ薬が双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用す\nることができるという技術常識があるとは言い難く,5−HT1A 部分作動 薬を双極性障害の「うつ病エピソード」の治療に使用できることが技術常\n識であるとはいえないなどとして,5−HT1A 部分作動薬を双極性障害の 治療に使用することができることは,本件出願時の技術常識であるとはい えない旨判断した。
(ア) ところで,医薬品の開発は,基礎研究として対象疾患の治療の標的 分子(受容体等)を探索し,標的分子(受容体等)に対する薬理作用及び 当該薬理作用を有する化合物を探索する薬理試験(in vitro 試験,動物実 験)が実施され,このような薬理試験の結果として,化合物が有する薬 理作用が疾患に対する治療効果を有すること(「医薬の有効性」)につい て合理的な期待が得られた段階で医薬用途発明の特許出願がされるのが 一般的であるものと認められる。 一方で,薬機法は,医薬品の製造販売をしようとする者は,その品目 ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければなら ない旨規定し(14条1項),その承認審査においては,申請に係る医薬\n品の名称,成分,分量,用法,用量,効能,効果,副作用その他の品質,\n有効性及び安全性に関する事項を審査し,その審査の結果,申請に係る\n医薬品又は医薬部外品が,その申請に係る効能\又は効果を有すると認め られないとき,申請に係る医薬品が,その効能\又は効果に比して著しく 有害な作用を有することにより,医薬品又は医薬部外品として使用価値 がないと認められるときは,承認を与えない旨規定し(同条2項3号), 厚生労働省令で定める医薬品の承認を受けようとする者は,申請書に,\n厚生労働省令で定める基準に従って収集され,かつ,作成された臨床試 験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければなら\nない旨規定している(同条3項)。この臨床試験は,臨床試験第1相(少 数の健常人に対する投与であり,副作用などの有無をみる。),臨床試験 第2相(少数の患者に対する投与であり,効果などが見込まれるかをみ る。),臨床試験第3相(多数の患者に対する投与であり,効果などがあ ることを確認する。)の3段階の試験で実施される。このように医薬品の 承認審査では,申請に係る化合物の薬効及び安全性(副作用,有害事象\nの有無及び程度等)を総合的に考慮し,「医薬の有用性」について審査し ている。
以上のような医薬品の開発の実情,医薬品の承認審査制度の内容,特 許法の記載要件(実施可能要件,サポート要件)の審査は,先願主義の下\nで,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業 の発達に寄与するとの特許法の目的を踏まえてされるべきものであるこ とに鑑みると,物の発明である医薬用途発明について「その物の使用す る行為」としての「実施」をすることができるというためには,当該医薬 をその医薬用途の対象疾患に罹患した患者に対して投与した場合に,著 しい副作用又は有害事象の危険が生ずるため投与を避けるべきことが明 白であるなどの特段の事由がない限り,明細書の発明の詳細な説明の記 載及び特許出願時の技術常識に基づいて,当該医薬が当該対象疾患に対 して治療効果を有することを当業者が理解できるものであれば足りるも のと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,本件審決が述べる「双極性障害の患者に 抗うつ薬を使用した場合,躁病エピソードの誘発,軽躁エピソ\ードの誘 発,急速交代化の誘発,及び混合状態の悪化等」の「様々な有害事象が生 じる危険性」については,本件出願当時,抗うつ薬と気分安定薬とを併 用することにより,躁転のリスクコントロールが可能であり,躁転発生\n時には抗うつ薬の中止又は漸減により対応可能であると考えられていた\nこと(前記ア3))に照らすと,上記特段の事由に当たるものと認められない。 そして,本件出願当時,5−HT1A 受容体部分作動薬一般がその抗う つ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を有する\nことが技術常識であったことは,前記ア認定のとおりである。
(イ) 以上によれば,本件審決の前記判断は誤りである。
ウ この点に関し被告らは,双極性障害については,鬱病相と躁病相があり, 双極性障害の鬱病相を治療するために抗鬱薬を投与すると,躁転の可能性\nを有意に高め,双極性障害の症状を悪化させる可能性が高いという固有の\n事情が存在し(甲A1,2,31の1,乙A98,106,),臨床上も,双 極性障害の鬱病相の治療において抗鬱薬の使用は慎重に行うべきとされて いることからすれば,全ての抗鬱薬を双極性障害の鬱病相(うつ病エピソ\nード)の治療に用いることができるなどという技術常識は存在しない旨主 張する。 しかしながら,前記イで説示したところに照らすと,被告ら主張の上記 固有の事情があるとしても,本件出願当時,5−HT1A 受容体部分作動薬 一般がその抗うつ作用により双極性障害のうつ病エピソードに対して治療\n効果を有することが技術常識であったことを否定する根拠にならない。 したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
◆判決本文
関連事件です。
令和2(行ケ)10079等
◆判決本文
令和2(行ケ)10078等
◆判決本文
令和2(行ケ)10077
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2022.02. 1
令和2(行ケ)10128 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年1月11日 知的財産高等裁判所
(2) 引用発明における「検出部ID」の技術的意義
上記認定に係る引用発明の「検出部ID」が,「電源タップ4」の住居内 での設置箇所を識別するものであるか否かについて検討する。 引用発明の「検出部ID」は,住居内で「電源タップ4」を一意に識別す る符号であるものの,引用文献1には,前記「検出部ID」が「電源タップ 4」の設置箇所を表す情報と関連するものであることは一切記載されていな\nい。また,電源タップの一般的な使用形態を参酌すると,電源タップを住居 内のどこに設置してどのような電気機器に接続するかは,当該電源タップを 利用する者が任意に決められるものと解される。 引用文献1では,「電源タップ4」に照明器具が接続される態様も開示さ れているものの(【図6】),照明器具は,居間,トイレ,寝室等,住居内 のあらゆる箇所で用いられるものであり,よって,当該照明器具に接続され る電源タップの設置箇所も住居内のあらゆる場所が想定されるものであるか ら,「検出部ID」により「電源タップ4」を一意に識別しても,それは 「電源タップ4」の識別にとどまるものであって,当該「電源タップ4」の 設置箇所も識別できるとする根拠は見出せない。 すなわち,「電源タップ4」の「検出部ID」から住居内の設置箇所を識 別するためには,「検出部ID」と当該「電源タップ4」の住居内での設置 箇所とを対応付けた何らかの付加的情報が必要である。「電源タップ4」の 「検出部ID」という,電源タップを一意に識別する符号から,当該「電源 タップ4」の設置箇所を識別することができる,と認めることはできない。
(3) 被告の主張について
ア 被告は,本願明細書等の段落【0024】において,照明装置から発信 されるID番号としては「位置ID番号」のみが開示されているところ, 位置ID番号に紐づけられる位置情報に設置箇所(個々の部屋)が含まれ るか否かが明らかでないと指摘する。 しかしながら,次の(ア)ないし(ウ)に照らすと,本願発明の「位置ID 番号」には,居宅内の各部屋を特定する「内部管理ID番号」が含まれる, と理解されるから,被告の上記指摘は上記認定を覆すものではない。
(ア) 段落【0026】及び【0027】においては,情報を受信するク ラウドサーバの側のデータベース内に,居宅内の各部屋を特定する「内 部管理ID番号」が登録されることが記載されており,段落【002 9】以下では,安否確認システムの動作によって,居宅内のどの部屋 (設置箇所)において異常が生じているのかを判定する仕組みが詳細に 説明されている。そうすると,発信装置から発信される「位置ID番 号」が,クラウドサーバの保有する「内部管理ID番号」を含むものと 解しないと,本願明細書等の記載全体を合理的に理解することができな い。
(イ) 段落【0035】,【0040】及び【0042】には,段落【0 024】と異なり,「位置ID番号」が照明装置の設置箇所(居間,ト イレ,寝室等の各部屋)を特定することが明示されている。
(ウ) 段落【0024】において,「位置ID番号」に紐づけられる「位 置情報」は,「設置箇所が存在する施設の住所,並びに設置箇所の緯度 経度及び施設の設置する階数等」(下線付加)である。この「等」に, 設置箇所となる各部屋の名称(居間,トイレ,寝室等)を含めることに よって,位置ID番号が,設置箇所を特定する情報(クラウドサーバの 「内部管理ID番号」に対応する情報)を含むものと解釈することが許 されないとはいえない。 また,設置箇所となる各部屋の名称を「等」に含めることが許されな い,あるいは位置情報をクラウドサーバへ登録する旨について述べたも のにとどまる,と解釈し,当該施設の中での「設置箇所」(各部屋)の 位置情報は,利用者が照明装置の設置後にアプリを用いてクラウドサー バに登録する,と理解することも可能である。段落【0019】の「利\n用者は,取得したアプリにしたがい,・・・照明装置の設置箇所・・・ の設定登録を行う」との記載も参酌すると,むしろ,かかる理解が本筋 であるともいえる。 前記(1)のとおり,照明装置から発信される「ID番号」とクラウドサ ーバに登録される「ID番号」とを相互に対照することができて初めて 本願発明は所期の作用効果を奏することができるのであるから,本願明 細書等に接する当業者の理解は,上記のいずれかであると考えられる。
イ 被告は,電源タップに接続される電気機器の設置箇所(部屋)は,電気 機器の種別によって通常定まるから,引用発明の「検出部ID」は,単に 「電源タップ4を一意に識別する符号」,すなわち,住居内の「どれ」か ということを識別する符号にとどまるものでもなく,住居内で「どこ」に 設置されているのかを識別する符号であって,位置情報として意味を有し, 本願発明の「内部管理ID番号」と同じ役割を有している旨主張する。
たしかに,被告がその主張の根拠とする引用文献1の【図5】において, 「住居ID」,「検出部ID」(図5の「計測部ID」との記載は「検出 部ID」の誤記と認められる。),「機器種類」,「稼働状況」などから なる機器稼働データが例示されており,たとえば,「検出部ID」が“i d13”の場合は,「住居ID」が“hid7”の場合も“hid2”の 場合も「機器種類」が“電気炊飯器”であること,「検出部ID」が“i d17”の場合は,「機器種類」が“PC”,“アイロン”,あるいは “ポット”であることが例示されており,「検出部ID」と電気機器の種 類,ひいては「電源タップ4」の設置箇所との間に何らかの相関関係があ ることも推測される。 しかしながら,引用文献1の【図5】におけるこれらの例示は,利用者 が住居内に各電源タップを任意に設置して電気機器に接続した結果として 生じる,「検出部ID」と接続されている電気機器との対応関係を示して いるにすぎないというべきであって,たとえば,前記ポットは,台所,居 間,ダイニング,寝室のいずれでも利用されることに鑑みると,【図5】 の記載をもってして,「電源タップ4」の「検出部ID」と当該「電源タ ップ4」の設置箇所との間に何らかの対応関係が定められているとするこ とはできない。
また,引用文献1の段落【0075】ないし【0078】には,実施の 形態3に係る生活状況監視システムにおいて,「電源タップ4」に機器種 類を設定する「スライドスイッチ20a」を設けることが記載されており, 【図16】には,機器種類として,「冷蔵庫」,「炊飯器」,「テレビ」, 「アイロン」,「レンジ」,「その他」が例示されており,「スライドス イッチ20a」がこれらの機器種類の中から任意に機器種類を選択するこ とが示されている。 してみると,引用文献1に記載の「電源タップ4」は,「冷蔵庫」, 「炊飯器」,「テレビ」等を含め,種々の電気機器に接続されることを前 提としたものであり,当該「電源タップ4」が設置される箇所も,台所, 居間等,住居内の様々な箇所が想定されるものであるから,「電源タップ 4」の「検出部ID」と当該「電源タップ4」の設置箇所との間には,元 来関連性はない。
以上によれば,引用文献1に,「電源タップ4」を一意に識別するため の「検出部ID」に基づいて,当該「電源タップ4」の設置箇所を識別す るという技術思想が開示されているとは認められず,被告の上記主張は採 用することができない。
ウ 被告は,住居内の電源タップ及びそれに接続される家電機器は,いった ん設置されれば移動しないのが通常であること,引用発明においては「電 源タップ4」の設置箇所が判明しているからこそ警戒すべき状況か否かの 判定ができること,を考慮すれば,「電源タップ4」の「検出部ID」は 設置箇所を識別し得る情報であり,本願発明の位置情報(設置箇所の情報 を含む。)と相違しない旨主張する。 しかしながら,以下のとおり,被告の上記主張は採用することができな い。
(ア) 引用文献1の【図13】には,警戒すべき状況か否かを判定するた めの条件の例が記載されている。この記載からは,電気機器の種別(テ レビ,炊飯器,アイロン等)と稼働状況(稼働中か停止中か)に応じて 警戒状況を判定するという技術思想は読み取れるものの,電気機器の種 別が同一である場合に,当該電気機器の設置箇所に応じて判定する条件 を異ならせる(例えば,居間と寝室のテレビとで判定条件を異ならせ る)という技術思想を読み取ることはできない。 例えば,【図13】に記載された判定条件のうち,「3日以上,『電 気炊飯器』の『停止』が続いた場合」は,住人が食事をとっていないと いう事態をうかがわせるから,かかる場合をもって段落【0057】等 にいう「警戒すべき稼働状況」として登録する,というのが引用発明の 技術思想であると解される。電気炊飯器の設置箇所は,通常,「台所」 という住居内の特定の部屋であるが,その間に住人が台所に立ち入った か否かが,警戒状況か否かを判定するための条件とされているものでは ない。 このように,引用発明においては,警戒すべき状況か否かを判定する ための情報として,特定の電源タップに接続された電気機器の種別を用 いているが,当該電源タップ及びそれに接続された電気機器の設置箇所 と関連する情報を用いることの開示又は示唆はない。
(イ) 引用文献1の【図6】には,二つの部屋のそれぞれにおいて,同一 の種別の電気機器である照明装置が「電源タップ4」に接続される態様 が開示されており,二つの部屋にそれぞれ設けられた「電源タップ4」 が,「検出部ID」を「遠隔監視装置1」に送信するものと認められる が,この場合であっても,上記(ア)に示したとおり,「検出部ID」は, 各々の電源タップ及びこれに接続された電気機器を一意に識別するため の符号であるにとどまり,「電源タップ4」の設置箇所を示す情報では ないから,「検出部ID」により各部屋を識別できるとする技術的根拠 は見出せない。
(4) 以上によれば,引用発明の「検出部ID」は,「電源タップ4」の住居内 での設置箇所を識別するものではないから,本願発明の位置情報のうち,住 居内における設置箇所を特定する「内部管理ID番号」(具体的には居間, トイレ,寝室等の各部屋)とは技術的意義を異にする。 それにもかかわらず,本件審決は,引用発明の「検出部ID」は本願発明 の「内部管理ID番号」に相当するとして,「施設内での設置箇所に係るI D番号」が安否確認に用いられることを一致点の認定に含めており,この認 定には誤りがあるといわざるを得ない。その結果,本件審決は,原告の主張 に係る相違点5を看過しており,上記一致点の認定誤りは本件審決の結論に 影響を及ぼす誤りである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.01.26
令和3(ネ)10031 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 控訴人の主張ア(イ)(本件発明の課題解決原理に基づく検討について)に つき
本件発明の技術的意義(前記1(2))に鑑みれば,本件明細書に開示され た発明は,半導体チップ上の領域ごとのゲート電極周縁長の合計が異なる 半導体集積回路装置(具体的にはシステムLSI)において,このような 領域ごとのゲート電極周縁長の合計のばらつきが,従来知られていたマイ クロローディング効果による局所的なパターン寸法の変動などとは異な り,半導体チップ全体にわたるCDロスに許容できないほどの変動をもた らすという,本件特許の出願時においては新規な課題を見い出し,これを, ダミーパターンを挿入してゲート電極周縁長のばらつきを抑えることに より解決したものである。したがって,本件発明の課題とその解決原理に 照らすと,本件発明の「半導体集積回路装置」は,システムLSIを意味 するものと解される。
本件特許の出願時に既に慣用されていたDRAMにおいて,メモリセル アレイを構成するビットラインやワードラインが,DRAMにおける他の\n回路と比較して周縁長が密な回路パターンであり,メモリセルアレイ領域 とそれ以外の回路領域とではゲート電極周縁長の合計がばらつくという 技術常識があったとしても,それが,DRAMを構成する半導体チップ全\n体にわたるCDロスに許容できないほどの変動をもたらすものであるこ とは,本件明細書に何ら言及されておらず,また,上記の新規な課題が, システムLSI中の一部の領域にすぎないDRAM単体においても同様 に生じるものであると認めるに足りる証拠はない。 そうすると,本件発明の課題とその解決原理に照らして,本件発明の「半 導体集積回路装置」は,システムLSIを意味するものと解され,DRA Mを含むと解することはできない。
ウ 控訴人の主張ア(ウ)(審査経過に基づく検討について)につき
控訴人は,審査経過に関し,第1回目及び第2回目の拒絶理由通知につ いて,審査官は,本件特許の発明がシステムLSIの発明であるとは認識 しておらず,また,出願人の意見書においても,本願発明と引用発明の相 違点について,本願発明はシステムLSIであるのに対して引用発明はシ ステムLSIではないという説明はしていないと主張する。 しかし,そもそも特許発明の技術的範囲の画定は,特許請求の範囲の記 載に基づいて定められるが,特許請求の範囲に記載された用語の意義の解 釈は明細書及び図面を考慮して行われるのであって(特許法70条1項及 び2項参照),特許出願の審査過程において,審査官がその特許発明をどの ように理解していたかということは,裁判所の特許発明の技術的範囲の画 定の判断を拘束するものではない。
また,出願人は,第1回目の拒絶理由通知に対する意見書(平成15年 11月28日提出,乙2)において,特許法29条1項3号及び同条2項 の規定に該当しない理由として,「言い換えると,ダミーパターンを挿入す ることによって,異なるマスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の 程度を小さくします。このため,ライン状パターンに品種に依存した寸法 変動が生じることを防止できるので,DRAM等の搭載率が用途又は仕様 により異なるシステムLSIにおいても,ゲート電極又はメタル配線等の 加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に一定にできます。従って, 請求項4の発明によると,動作マージンのバラツキが解消された半導体集 積回路装置を実現できるという格別の効果が得られます。」(乙2〔2〜3 頁〕)と記載し,第2回目の拒絶理由通知に対する意見書(平成16年3月 25日提出,乙4)において,特許法29条2項の規定に該当しない理由 として,「言い換えると,ダミーパターンを挿入することによって,異なる マスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の程度を小さくします。こ のため,本願明細書の段落番号[0132]に記載されておりますように, 『半導体集積回路装置の品種によりマスクパターンレイアウトが大きく 異なる場合にも,マスクパターンレイアウトの違いに起因してライン状パ ターンに寸法ばらつきが生じることを防止できる。従って,DRAM等の 搭載率が用途又は仕様により異なるシステムLSIにおいても,ゲート電 極又はメタル配線等の加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に 一定にできるので,動作マージンのバラツキが解消された半導体集積回路 装置を実現できる』という格別の効果・・・が得られます。」(乙4〔4頁〕) と記載し,いずれの意見書においても,本願発明がシステムLSIに用い られて効果を生ずることを明確に述べており,このような段階を踏まえて 本件特許が登録されたものである。 したがって,仮に,審査官が,拒絶理由通知を発出する際に,特許請求 の範囲に記載された発明の要旨認定において,「半導体集積回路装置」を, その一般的な字義どおりに,DRAMを含む半導体集積回路装置全般と解 釈しており,また,出願人の意見書において,本願発明と引用発明の相違 点として,本願発明はシステムLSIであるのに対して引用発明はシステ ムLSIではないことが明示されていなかったとしても,それに基づいて, 本件発明の「半導体集積回路装置」にシステムLSIではないDRAM自 体が含まれるということはできない。
(3) そうすると,本件発明における「半導体集積回路装置」(構成要件1A,1\nE,5B,5E等)という語は,システムLSIを意味するものとして用い られており,DRAMはこれに含まれないというべきであり,DRAMであ ることに争いのない被控訴人製品(前記第2,2による引用のうちの原判決 「事実及び理由」第2,2⑽(原判決8頁20〜23行目))は,本件発明1 の構成要件1A,1E,本件発明5の構\成要件5B,5Eをいずれも充足せ ず,本件発明1及び本件発明5の技術的範囲のいずれにも属さないものと認 められる。 控訴人は種々主張するが,その主張は,いずれも採用することができない。
◆判決本文
原審はアップされていません。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.01.24
令和2(行ケ)10113 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月19日 知的財産高等裁判所
上記各事実によれば,被告は,ブランデッドボースト社を買収した後,本 件審判請求に及ぶ直前まで,原告との間で,原告が保有する本件商標を含む 日本及びその他の国のBOASTブランドに係る登録商標の買取りについて 協議をしていたが,協議中断の数か月後に本件審判請求に及んだものである。 こうした経緯に加え,被告は,本件審判請求における手続において,原告 が,「2017年10月3日,請求人は,ブランドボースト社(当審注:ブ ランデッドボースト社のこと)より,同社の「BOAST」ブランド事業を 買収し,同社が保有する米国「BOAST」登録商標の移転を受けた(乙1)。 したがって,請求人は,被請求人が保有する日本「BOAST」登録商標に 干渉しない義務を含む,本件和解契約に基づく義務を履行する責任を負う」, 「また,請求人は,本件和解契約に基づき,日本「BOAST」登録商標に 係る被請求人の権利に対する干渉を行ってはならない義務を負う」旨主張し たのに対して,具体的に弁駁していないことは記録上明らかであり,また, 本訴における原告による同旨の主張についても反論していないことからする と,被告は,ブランデッドボースト社から米国内における「BOAST」事 業を買収するに際して,原告らと同社との間では,同社が,世界中でボース ト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標 権を妨害しない旨の本件和解契約に基づく義務を負担しており,上記買収に より被告も同義務を履行する責任を負うことを認識しながら,これを前提と して,原告との間で,原告が保有する本件商標を含む日本及びその他の国の BOASTブランドに係る登録商標の買取り交渉をしていたものと認められ る。
そうすると,被告は,原告との間で,原告が保有する本件商標を含む日本 及びその他の国のBOASTブランドに係る登録商標の買取り交渉が頓挫す るや否や,原告が保有する商標権を妨害してはならない旨の上記義務に反す ることを知りながら,本件商標の取消しを求めて本件審判請求に及んだもの と認めるのが相当である。したがって,本件審判請求は,金銭的負担をすることなく本件商標を使用することを企図し,取消審判制度が何人も申し立てることができることに藉\n口して,専ら原告を害する目的でしたものと認められるから,権利の濫用に 当たるものというべきである。
◆判決本文
審決(取消2018−300722)は、下記のように、権利濫用とまではいえないとして、不使用であるので登録を取り消すと判断していました。
イ 判断
上記事実によれば、被請求人らとブランドボースト社との間で、互いの商号及び商標に係る権利について妨害しないことを含む本件和解契約が結ばれていたことは窺えるものの、そのような当事者間の合意が、本件商標に対する不使用取消審判の請求までも禁止するものであるかは、証拠上明らかでなく、当該契約違反か否かは措くとしても、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる事情を見いだすこともできない。また、前記(1)の不使用取消制度の趣旨からすれば、登録商標は使用をしているからこそ、保護を受けられるのであって、一定期間登録商標が使用されていない場合には、保護すべき信用が存しないのであるから、取り消されてもやむを得ないものである。
そして、後述するとおり、被請求人は本件商標の使用について、何らの主張、立証もしていないものである。なお、請求人と被請求人との登録商標買取り交渉が合意に至らなかった状況において、本件商標の不使用を理由として、請求人が本件審判請求を行ったとしても、そのこと自体は格別不自然とはいえない。その他、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情は見いだせず、本件審判請求が権利の濫用であるとはいえないし、信義則違反であるとして本件審判請求が成り立たないとすべきともいえない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.01.24
令和3(行ケ)10107 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和4年1月19日 知的財産高等裁判所
また,仮に,引用商標の中国における周知性が認められると仮定しても,前 記認定事実によれば,被告は,中国人であるものの,来日してから長らく我が 国に居住し,本件商標の登録出願に先立って「旅程管理業務を行う主任(国内)」 の資格を取得し,本件商標の商標登録後,引用商標が登録出願されるまでに, 実際に本件商標を構成する「花間堂」の文字を含む名称のツアーを主催したこ\nとが認められることからすると,本件商標の指定役務である「宿泊施設の提供, 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」等のために本件商標を登録出願して 登録を受けたものと推認されるところであり,また,本件商標を構成する文字\nを選択した理由についても具体的に陳述しているところである。このような事 実関係からすれば,被告が本件商標の登録出願をした経緯に,不正の利益を得 る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的があったとは認め難く, 本件全証拠を検討してみても,被告に上記のような目的があったと認めるに足 りる証拠はない(なお,引用商標の中国における周知性についても,原告提出 の書証中には,原告が運営する「花間堂」を「中国大陸で有名な高級チェーン ホテル」(前記1(3)イ(ウ)),「中国の有名な民宿ブランド」(同(エ)),「中 国大陸の有名な高級ホテルブランド」(同(オ)),「中国国内の有名な優れた リゾートホテルブランド花間堂」(同(カ))として紹介するものがあるものの, 該当部分の抄訳であり,当該記事内容やその記事がどういった媒体からによる ものであるのかの詳細が不明であるし,その他のものを併せても,これらの記 事等のみから,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において, 中国の需要者の間で原告の業務に係る役務を表示するものとして周知であると\n認定することはできず,また,「花間堂」の中国国内における売上高,利用者 数,旅行業界におけるシェア等に関する証拠もないから,上記中国における周 知性を認めることはできないことを念のため付言する。)。 そうすると,本件商標は,商標法4条1項19号に該当するものとはいえず, これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2022.01.18
令和3(行ケ)10067 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和4年1月12日 知的財産高等裁判所
1 本件審決は,本願意匠が引用意匠に類似し,意匠法3条1項3号に該当する から意匠登録を受けることができないと判断した。
そこで検討するに,意匠は物品と一体をなすものであるから,登録出願前に日本 国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外 国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを 理由として,意匠法3条1項により登録を拒絶するためには,まずその意匠にかか る物品が同一又は類似であることを必要とし,更に,意匠自体においても同一又は 類似と認められるものでなければならない(最高裁判所昭和45年(行ツ)第45 号同49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁参照)。 そうすると,物品の同一性又は類似性の認定に誤りがある場合には,意匠法3条 1項該当性の判断に誤りがあるというべきである。 2(1) 原告は,本件審決が,本願意匠に係る物品について「医療用注射器の外筒」 と認定したことが誤りであると主張し,これに対し被告は,1)本件審決は,本件願 書等の記載から本願意匠に係る物品を「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有す\nるもの」と認定したところ,この判断に誤りはなく,2)原告が,本件意見書や本件 審判請求書で本願意匠と引用意匠の物品が「注射器等に用いられるカートリッジ」 であって「物品が共通する」などと主張していたことは上記1)の認定を裏付けるも のであり,原告が,本訴において,本件審決以前にしていた主張と異なる主張をす ることは禁反言により許されないなどと主張している。
(2) そこで検討するに,本件意見書や本件審判請求書において,原告は,本願意 匠と引用意匠の物品が「注射器等に用いられるカートリッジ」であって「物品が共 通する」などと主張していたことが認められるが(乙5,7),意匠登録出願につい ての拒絶理由の存否は,審査官が職権により判断すべきものであって(旧法17条), 出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くも のではない上,権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟 である本件において,被告は行政庁として対応しているものであって,本願意匠の 意匠に係る物品につき,査定及び審判の各段階における原告の主張が本訴における 主張と異なるものであったことにより被告の利益が不当に害されるとの関係もない ことからすると,本件意見書や本件審判請求書における上記の原告の主張をもって, 禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張 と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。 また,被告以外の第三者との関係において,禁反言の法理が適用されることによ り,原告が本願意匠に係る意匠権を行使する場面に制限を受けるおそれがあるとし ても,特定の当事者間における権利行使の制限の当否と権利の付与の適否とは,お よそ場面が異なるのであるから,直ちに本願意匠について,意匠権登録による保護 を与えるべきではないなどということはできない。
(3) さらに,審決取消訴訟の審理対象は,当該審決の判断の違法であり,その範 囲は当該審判手続において具体的に争われた拒絶理由に限定されるものであるから (最高裁判所昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集3 0巻2号79頁参照),各当事者は,審判手続において具体的に争われていない拒絶 理由を主張することは許されないものの,審判手続において具体的に争われた拒絶 理由に係る判断の当否に係る主張やそれを裏付ける証拠の提出についてまで制限を 受けるものではない。そして,原告の,本願意匠の意匠に係る物品が「自動注射器 等の内部に挿入される,交換可能な薬液溶液」であり,引用意匠に係る物品である\n「注射器用シリンジ」とは異なる旨の主張は,本件の審判手続について争われた拒 絶理由である「引用意匠との類似」に関する主張であって,審理対象に含まれない 事項に係るものではないから,この観点からも原告の主張を制限する理由はない。
(4) そこで,以下,原告が,本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品が異なると主 張していることを前提として,本願意匠に係る物品について検討する。 3(1) 意匠法24条1項は「登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した 図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意 匠に基いて定めなければならない。」と規定する。 また,旧法6条1項3号は,意匠登録出願の際に提出すべき書類に,「意匠に係る 物品」を記載すべき旨規定し,意匠法施行規則別表第一には意匠に係る物品の欄に\n記載すべき区分が定められているが,同表には「インジェクターカートリッジ」と\nの区分の記載はない(乙2,3,15。なお,同表には,「インジェクター」を含む\n区分の記載もなく,「カートリッジ」を含むものとしては「レコードプレーヤー用カ ートリッジ」の区分の記載があるのみである。)。同表の備考二には,「この表\の下欄 に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは, その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係 る物品」の欄に記載しなければならない。」と記載されている。そして,同規則様式 第2備考39には「別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品\nについて意匠登録出願をするときは,「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の 使用の目的,使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載する。」 と記載されている。
(2) 前記(1)の各規定を踏まえ,本件願書等の記載から,本願意匠の意匠に係る物 品が何であるか検討する。本件願書等(乙1)の記載をみると,【意匠に係る物品】 として「インジェクターカートリッジ」とあるほか,【意匠の説明】及び図面はいず れも別紙第1記載のとおりであって,本件願書等には【意匠に係る物品の説明】の 欄はなく,その余の欄にも意匠に係る物品の説明は記載されていない。本件願書等 における物品を示唆する記載は「インジェクターカートリッジ」との文言及び図面 のみである。
(3) そこで,「インジェクターカートリッジ」との文言について検討すると,これ は,「インジェクター」と「カードリッジ」という2つの単語が組み合わされたもの と認められる。
ア 「インジェクター」についてみると,新英和大辞典第六版(乙9)には,外 来語である「インジェクター」のもとの英単語である「injector」について,「注射 する人,注入器,注射器」という意味が記載されており,証拠(甲7,15)によ ると,本件優先日より前に,糖尿病の注射治療に用いる注射薬として「オートイン ジェクター」と呼ばれる,ボタンを押すだけであらかじめ充填されている1回分の 薬液が自動的に注入されるGLP−1受容体作動薬の注入器及び「アポカインイン ジェクター」との名称の電動式医療品注入器(原告の主張する自動注射器を意味す るものと推認される。)が既に存在していたことが認められる。加えて,原告及び被 告ともに,インジェクターが「注射器」を意味するものと認識している。そうする と,本件において,「インジェクター」は注射器を意味すると推察される。
イ 「カートリッジ」についてみると,外来語である「カートリッジ」のもとの 英単語である「cartridge」について,新英和大辞典第六版(乙9)には,「弾薬筒, 薬筒,薬包,実包」「(機械・器具などの一部に取換えのできるように工夫された液 体・ガスなどの)小容器」,ウィズダム英和辞典(甲8)には「交換[詰め替え]用容 器」,New Oxford American Dictionary(甲9)には「巻かれた写真用フィルム,イ ンク,その他の物又は物質を内包する容器であり,装置の中に挿入するべくデザイ ンされたもの」との意味がそれぞれ記載されている。そして,証拠(甲13)によ ると,本件優先日より前に,専用注入器に装着して使用する「カートリッジ製剤」 と呼ばれるインスリン製剤が存在していたことが認められる。また,本件優先日よ り前に公開されていた特許公報(甲12,28〜32)には,自動注射器,注射器 装置,ばね駆動式の注射装置,ペン型注射器及び医療用自動注射装置に用いられる, 薬を充填した小容器を意味する「カートリッジ」に関する記載(その中には,薬剤 カートリッジ,薬物充填カートリッジなどと記載されている部分もある。)があるこ とが認められる。そうすると,「カートリッジ」は交換用の液体・ガスなどを充填し た小容器を意味するものと推測される。なお,上記各証拠に照らす限り,「カートリ ッジ」が文言上,「外筒」を意味するものと認めることはできない。
ウ 次に,「インジェクターカートリッジ」の語句について検討するに,被告は, 本件願書の【意匠に係る物品】の記載は「インジェクターカートリッジ」であり, 「インジェクター用カートリッジ」ではないなどとも主張するが,証拠(甲17〜 20,22,23)によると,「カートリッジ」の文言は,「トナーカートリッジ」 「インクカートリッジ」のようにカートリッジ自体についてその内容物を意味する 文言とともに用いられる場合がある一方で,浄水器に用いられるカートリッジにつ いて「浄水器用カートリッジ」とする登録意匠と「浄水器カートリッジ」とする登 録意匠とが存在し,「浄水器カートリッジ」が浄水器用のカートリッジを意味する場 合があることが認められ,「インジェクターカートリッジ」という文言をもって,イ ンジェクター用のカートリッジを意味するものと理解することも不自然ではない。 そして,本願意匠の意匠に係る物品として,出願人である原告が,注射器を意味す る「インジェクター」のみにとどめず,あえて「インジェクターカートリッジ」と したものであることを併せ考慮すると,「インジェクターカートリッジ」は,「注射 器用のカートリッジ」を意味すると認めるのが相当である。
エ 前記ア〜ウを総合すると,「インジェクターカートリッジ」は,「注射器用の 交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」を意味すると認めるのが相当である。\n
(4) そうすると,本願意匠の意匠に係る物品を「医療用注射器の外筒の用途及び 機能を有するもの」とした本件審決の認定には誤りがあるというほかない。もっと\nも,本件願書等には,「インジェクター」(注射器)が「自動注射器」を意味するこ とまでを示唆する記載はなく,本件優先日当時において,一般に,「インジェクター カートリッジ」が自動注射器用のカートリッジを意味していたと認めるに足りる証 拠もないから,本願意匠の意匠に係る物品は,自動注射器に限ることなく,「『注射 器』用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」であると認めるのが相当で\nある。
(5) 被告は,本件審決は「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有するインジェ\nクターカートリッジ」であると認定したのであって「医療用注射器の外筒」と認定 したものではないから原告の主張は前提を欠くなどと主張するが,物品の同一性及 び類似性は,物品の用途及び機能等を比較して実質的に判断すべきところ,本件審\n決の認定は「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有するもの」というものであっ\nて実質的に上記原告の主張のとおり「医療用注射器の外筒」と認定したものといえ る。被告の上記主張は形式にすぎ,本質を看過したもので相当ではない。 また,被告は, 本件願書に【意匠に係る物品の説明】の欄を設けて物品の理解を 助ける説明を記載し,参考図を提出する必要があったと主張しているところ,前記 3(1)のとおり,意匠法施行規則別表第一には「インジェクターカートリッジ」との\n区分の記載はなく,また,「インジェクターカートリッジ」が一般用語とはいえない ことからすれば,被告の主張するように【意匠に係る物品の説明】を記載するのが 適当であったとはいえるものの,このことから,本願意匠に係る物品が「医療用注 射器の外筒の用途及び機能を有するもの」であると直ちに認定できるものではなく,\n上記被告の主張は,本願意匠に係る物品についての上記認定に影響しない。
4 他方,本件審決は,別紙第2記載の注射器の意匠のうち,「注射器用シリンジ」 の意匠を引用意匠としているところ,当該部分に係る物品は,注射器用外筒の用途 及び機能を有するものと認められる。\nそうすると,本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は共通しない。
5 したがって,本件審決の本願意匠に係る物品の認定及び本願意匠と引用意匠 の同一性の認定には誤りがあるから,取消事由1(本願意匠に係る物品の認定及び 本願意匠と引用意匠の物品の同一性(類似性)の認定の誤り)には理由がある。
2022.01.18
令和3(行ケ)10050 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月22日 知的財産高等裁判所
ア 原告の主張(1)について
(ア) 前記1(3)で検討したとおり,従来の撮像装置においては,ヒンジユ ニットを本体に連結する第1ヒンジに係る軸Aが,ディスプレイをヒン ジユニットに支持する第2ヒンジの外側で第2ヒンジに係る軸Bと交 差し,軸A上の一対の第1ヒンジがディスプレイの外側に突出して配置 されているために,ヒンジユニットがディスプレイよりも大きくなって しまうという課題があったところ,本件発明1は,この課題を解決する ために,一対の第1ヒンジの一方が一対の第2ヒンジの間に配置される 構成(構\成要件1Fの構成)を採ったものであり,この点に技術的意義\nがあるということができる。 他方で,前記2(1)及び(2)によれば,甲1発明においては,軸受44 の孔44bを有する支持部44eが,孔44aを有する支持部44dよ りも液晶表示ディスプレイ3に近い側にあり,軸受44の支持部44d\n及び第1回転軸41の他方端が貫通するガイド45が,基台43におけ る第2回転軸42の他方端を軸支するサイドフレーム46と反対側のカ メラ縦方向の一辺に配置されている(構成要件1gの構\成。甲1公報の 段落【0028】ないし【0030】及び図1ないし3)。そうすると, 甲1発明においては,本件発明1における「一対の第1ヒンジ」に相当 する支持部44d及びガイド45の一方が,本件発明1における「一対 の第2ヒンジの間」に相当する支持部44eとサイドフレーム46との 間に配置されているものではないから,甲1発明は,構成要件1Fの構\ 成を備えるものではない。 以上によれば,本件発明1及び甲1発明は,甲1発明が構成要件1F\nの構成を備えていない点に実質的な相違があるといえ,両発明を対比し\nた場合には,この点を相違点として認定するのが相当であるから,両発 明について,ディスプレイ及び中間に位置するプレートが共に動く方向 とディスプレイのみが動く方向とが,縦方向又は水平方向のいずれであ るのかの違いしかないということはできない。 (イ) また,前記2(1)及び(2)によれば,甲1発明2は,甲1発明と構成\n要件1c及び1f以外の構成を共通にするものであるところ,上記(ア) で検討したとおりの構成要件1gの構\成の内容からすれば,甲1発明2 も,構成要件1Fの構\成を備えていないものといえる。 そうすると,甲1公報の段落【0074】において開示されている構\n成どおりの図を描けば,本件発明1及び甲1発明は同じものになるとい うことはできない。
(ウ) 以上によれば,原告の主張(1)は採用することができない。
イ 原告の主張(2)について
(ア) 原告の主張(2)は,善解するに,甲1発明において軸受の方向を90 度ずらして取り付けることにより,構成要件1Fの構\成と同様の構成を\n採ることができること,このことは甲1公報の段落【0074】に開示 されていることを主張するものと解される。 (イ) しかしながら,甲1公報の段落【0074】には,甲1発明におい て,カメラ縦方向回りに左右に回動させるヒンジユニット及びカメラ横 方向回りに上下に回動させる液晶ディスプレイのそれぞれの回動の向 きを,ヒンジユニットをカメラ横方向回りに,液晶ディスプレイをカメ ラ縦方向回りとしてもよいことが記載されているにすぎず,軸受の方向 を90度ずらして取り付けることが開示され,又は示唆されているもの とはいえない。また,上記アで検討したとおり,甲1公報の段落【00 74】には,構成要件1Fの構\成が開示されているものではないという べきである。
(ウ) 以上によれば,原告の主張(2)は採用することができない。
ウ 原告の主張(3)について
(ア) 本件明細書の図3について検討するに,第2ヒンジ24に係るヒン ジブラケット33が支持部21に接している部分の位置を基準とすれば, 第1ヒンジ23の軸B寄りに位置する方のヒンジブラケット31は,一 対の第2ヒンジ24の間に配置されているといえる。ただし,図3にお いては,上記ヒンジブラケット33の先端は,原告が主張するように, 支持部の外側に向かって水平方向に延びており,同ヒンジブラケット3 3に設けられた軸B回りにディスプレイを回動可能に支持する孔が上記\n第1ヒンジ23の外側に位置する形となっているようにもみえる。その ようにみると,本件明細書の図3における軸A及び軸Bは,図6Aと同 様の位置関係となるといえるところ,図6Aは,ヒンジユニットが大き くなってしまうという課題を有する従来技術が「参考例」として記載さ れているものであると解されることからすれば,図3は,本件発明1の 実施形態を説明するための図1Aの分解斜視図であると説明されてはい るものの,本件発明1の実施例を示す図面としては,適切なものではな いといわざるを得ない。 しかしながら,本件明細書においては,本件発明1の実施形態を示す 図面として図4Aが記載されているところ,図4Aは,一対の第1ヒン ジの一方が一対の第2ヒンジの間に配置されるという構成要件1Fの構\ 成を適切に示した図面であるといえる。そして,図4Aは,図3のヒン ジユニットの一対の第1ヒンジ及び一対の第2ヒンジの配置を示す模式 図として説明されているから,図3を上記原告の主張するようにしか読 み取ることができないというものではない。
(イ) そうすると,本件明細書の図3は,原告の主張するようにしか読み 取ることができないというものではないから,図3の記載内容を根拠と して,本件発明1が甲1発明と同じであるなどということはできない。
(ウ) 以上によれば,原告の主張(3)は採用することができない。
エ 原告の主張(4)について
(ア) 前記1(2)によれば,本件明細書の図6A及び図6Bは,ヒンジユニ ットが大きくなってしまうという課題を有する従来技術が「参考例」と して記載されているものである。そうすると,図6A及び図6Bの記載 内容を根拠として,本件発明1が甲1発明と同じであるなどということ はできない。
(イ) 以上によれば,原告の主張(4)は採用することができない。
オ その他 このほか,原告は,本件発明1は甲1発明に対する新規性を欠くとして 種々の主張をするが,これまで検討したところに照らすと,原告の主張は 採用することができない。
(4) 小括
以上によれば,本件発明1ないし5は甲1発明に対する新規性を欠くもの ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2022.01.18
令和3(ネ)10008 謝罪広告等請求控訴事件 その他 民事訴訟 令和3年12月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は,原審裁判所と同じく,一審被告の主張に係る違法性阻却事由は 認められないと判断する。その理由は,次のとおりである。
(1) 民事上の不法行為である名誉毀損については,その行為が公共の利害に関 する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実が真実 であることが証明されたときは,右行為には違法性がなく,不法行為は成立 しないものと解するのが相当であり,もし,右事実が真実であることが証明 されなくても,その行為者においてその事実を真実と信じるについて相当の 理由があるときには,右行為には故意もしくは過失がなく,結局,不法行為 は成立しないものと解するのが相当である(最高裁昭和41年6月23日第 一小法廷判決・民集20巻5号1118頁)。 この点について一審被告は,「一審原告の父親が,一審原告を日大に裏口 入学させた」という事実が真実であり,又は真実であると信じるにつき相当 の理由があること,当該事実の摘示が公共の利害に関する事実に係ること, 当該事実の摘示が専ら公益を図る目的でされたことを主張して,名誉毀損に よる不法行為責任を否定する。 以下,検討する。
(2)事実の公共性及び目的の公益性について
この点に関して,一審原告は,単に一審原告が著名人であるという理由だ けで「公共性」を満たすことには全くならないから,本件各記事は,そもそ も公共の利害に関する事実には当たらず,公益を図る目的がないことも明ら かである旨主張する。 しかしながら,一審原告は,もともとは「B」の一員として世に出たが, 本件各証拠によれば,本件各記事等の掲載の時点までには,テレビ番組の司 会者を務めたり,雑誌等のインタビュー記事や自らの著書等において政治や 社会に関する発言を公にしたりしていることが認められるから,一審原告の 経歴や人柄にかかわる事実は,一定程度,不特定多数人が関心を寄せてしか るべき公共の利害に関する事実に当たるというべきである。また,そのよう な人物につき,社会一般では非難の対象となる裏口入学という事実が存在し ていたのであれば,それを広く報道することは,経歴に関する不正を正そう とする行為と認められるから,一定程度,公益を図る目的に出たものという べきである。 したがって,本件各記事等の掲載は,公共の利害に関する事実に係るもの であり,専ら公益を図る目的でされたものと認められる。 もっとも,一審原告が現実に公職に就いたことはない上に,公職への応募 や立候補を企図していることをうかがわせる証拠もないのであるから,公共 の利害に関する程度はさして高いものではない。また,大学への裏口入学と いう事実が仮にあったとしても,未成年の当時のことである上に,一審原告 の現在の活動に対する評価は学歴によって左右される性質のものでもないか ら,公益にかかわる程度は高いものではないというべきである。
(3) 真実性又は真実と信ずるについての相当の理由の存否について
本件各記事等に記載された内容は,本件経営コンサルタントから聴き取っ た内容として編集スタッフがまとめた乙17録取書に依存しているものであ る。しかるに,本件経営コンサルタントについてはその特定は必ずしも十分\nであるとはいえず,また,後述のとおり,乙17録取書に同人の供述内容が 正確に録取されていることの担保はなく,乙17録取書の内容の真実性を基 礎付けるに足りる証拠は乏しく,かえって,乙17録取書の内容には客観的 事実及び証拠に矛盾する点が多い上に,一般的な経験則に照らして不自然な 内容も多い。これらの点に照らすと,乙17録取書の内容に依存している本 件各記事等の内容,特に,「一審原告の父親が,一審原告を日大に裏口入学 させた」という事実が真実であることの証明があったとはいえない。 また,乙17録取書に依存した内容の本件各記事等を公にすることによる 影響(一審原告の社会的評価の低下等)の大きさに比して,実際に一審被告 において行った取材の期間・経過やその内容等は前記1のとおりであって, 後述のとおり,編集スタッフにおいて,本件経営コンサルタントの陳述につ き十分な検討や裏付け取材を行ったとはいえない。そうすると,一審被告に\nおいて,本件各記事等の内容を真実と信じるについての相当な理由があった (以下,このことを「相当性」という。)とは認められない。 以下,当審における一審原告の主張も踏まえて,詳述する。
・・・
オ 小括
上記イないしエに説示したことを考慮すると,一審被告は本件経営コン サルタントの供述(乙17録取書)と矛盾せず積極的にその信用性を基礎 付けるには足りない取材結果のみを積み重ね,それに基づいて本件経営コ ンサルタントの供述が信用できるものと軽信したものといわざるを得ない から,編集スタッフが得た取材結果等は本件各記事等の内容の真実性を裏 付けるものではなく,また,真実と信じるについて相当の理由があると認 めることもできないというべきである。なお,このことは,真実性の証明 の対象事実として,一審被告が主張する事実(すなわち,亡父が本件経営 コンサルタントを通じて裏口入学のための手段を尽くした結果として一審 原告を日芸演劇学科に入学させたという事実)を前提としても,その内容 に照らし,左右されるものではない。
◆判決本文
原審はこちら
2022.01.11
平成31(ワ)647 債務不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月26日 東京地方裁判所
ウ そこで,以上の説示を前提として,以下,公然実施発明1への甲5−1発 明の組合せの可否について検討する。 まず,公然実施発明1は,スリープ状態とスリープ解除状態とを有し,スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス\nマートフォンというものであり,他方,甲5−1発明の技術分野は,生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると,両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また,公然実施発明1は,スリープ状態において,ホームボタンを押すことによ り,デバイス機能を有効にするときに,起動して認証を行うというものであるか\nら,ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに,パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。\nこの点,公然実施発明1においては,ホームボタンの押下の後,パスコード認証の 前に,ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ\nるが,この構成については,タッチパネル入力による誤作動防止(パスコードによ\nる認証の設定がされている場合は,パスコードやホーム画面の誤作動防止であり, パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても,ホーム画面の誤作動 防止)という,ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ,パスコード 認証という構成は,これとは別の,ユーザ識別のための構\成として把握することが できるものであって,上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構\ 成であるというべきである。そして,甲5−1発明における「ユーザがデバイスを オンにする,ロックを解除する,または,起動する」ことは,デバイスの機能を有\n効にすることであるといえ,また,デバイス機能を有効にする前に,生体情報の提\n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると,公然\n実施発明1と甲5−1発明とは,デバイスの機能を有効にするときに,ユーザ識別\nのための認証動作を行う点に関して,その作用機能が共通するものと認められる。\n以上によれば,公然実施発明1と甲5−1発明においては,技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって,当業者(その発明の属する技術の\n分野における通常の知識を有する者)において,両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり,その他,本件全証拠をみても,両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると,公然実施発明1のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として,甲5−1発明におけるデバイス\nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため\nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構\n成を組み合わせることは,当業者が容易に想到できたことである。また,公然実施 発明1はパスコードの入力による認証に関して,誤ったパスコードが入力されると, ロック状態が維持され,ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ\nれる構成を有するし,甲5−1発明も,特定されたユーザが許可されていないと判\n断した場合,認証を行うようユーザに指示する構成を有し(甲5文献【0080】),\nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること,及びユーザ認\n証のための操作が行われると,認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは,当該技術の性質・内容に照らし,周知慣用技術といえる。そして,公然実 施発明1は,使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な使用者と認証され\nなければロック状態を維持するものであるところ,公然実施発明1に甲5−1発明 を組み合わせる際に,かかる構成をあえて排除又は変更する理由は,本件全証拠を\nみても見当たらない。 以上からすると,当業者は,相違点1に係る構成を容易に想到することができた\nものといえ,本件発明1−1を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ア) 被告は,公然実施発明1は,パスコードの入力という使用者識別機能を有\nするものの,指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく,こ れを有する甲5発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし,前記認定のとおり,両発明においては,いずれも,デバイスの機能を有\n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって, パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの,両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると,被告の上記主張は,採用することができない。
(イ) また,被告は,公然実施発明1は,ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ,これ\nは,デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ\ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲5発明の課題と共通しないから,公然実施発明1に甲5発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら,前記説示のとおり,公然実施発明1に係るパスコード認証という 構成については,ユーザ識別のための構\成として,上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構\成として把握することができるというべきである。 そうすると,公然実施発明1におけるパスコードによる認証という構成と,甲5−\n1発明におけるシームレスな認証処理という構成とは,ユーザにおいて許可されて\nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり,両発明において,デバイス機能を有効に\nするときのユーザ認証の動作に関して,その作用機能が共通するものと認められる\nことに変わりはない。すなわち,ユーザによる誤作動の防止と,スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは,その性質内容に 照らし,互いに別個のものということができ,公然実施発明1がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって,これに甲5−1発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると,被告の上記主張は,採用することができない。
(ウ) さらに,被告は,本件発明1−1は,1) 指紋認証による使用者識別機能が,\n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により,かつ,使用者による 追加操作なしに行われる,2) 使用者識別機能による認証の結果,使用者が正当な\n使用者と認証されなければ,移動通信端末機のロック状態を維持するとともに,デ ィスプレイ部にメッセージを表示する,3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると,使用者識別機能による認証の結果にかかわらず,\nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが,公然実\n施発明1にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ,甲5発明 には,上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため,両者を組み合わせても,\n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし,被告主張の上記1)については,上記ウで説示したとおり,公然実施発明 1のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として,甲5−1発明における\nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証\nするための構成を,公然実施発明1のスライダを備えたロック画面を残したまま組\nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また,公然実施発明1は,パスコードを入力することによる使用者識別機能によ\nる認証の結果,認証されなければロックを維持するものといえるところ,公然実施 発明1に甲5−1発明を組み合わせる際に,かかる構成をあえて排除又は変更する\n理由が認められないこと,ユーザ認証がされなかった場合には,ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること,及びユーザ認証のための操\n作が行われると,認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは,前記説示のとおりである。そうすると,被告主張の上記2)及 び3)について,実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば,本件発明1―1は,当業者が公然実施発明1に甲5−1発明を組\nみ合わせることにより,容易に想到することができたものといえ(特許法29条2 項),本件発明1−1は,特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある(同法123条1項2号)。
・・・
7 争点3−3(無効理由2の解消の有無)
(1) 本件訂正事項2−1,2−2に係る訂正による無効理由2の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項2−1は,本件発明2−1の構成要件2−1Cの活性状態をロック\n画面が表示されたものに限定するものであり,本件訂正事項2−2は,本件発明2\n−2の構成要件2−2Aに,「前記ロック画面には,現在の時間を表\示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項2−1,2−2に係る訂正による無効理由2の解消の有無 しかしながら,本件訂正発明2−1及び本件訂正発明2−2と公然実施発明2と を対比してみたとしても,前記5(2)で認定した公然実施発明2の構成からすれば,\nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点,同画面に\n現在の時間を表示することができる点について,相違するものではない。\n以上によれば,本件訂正事項2−1,2−2に係る訂正によっても,無効理由2 を解消することはできないといわなければならない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.01.11
令和2(ワ)1573 債務不存在確認請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年8月27日 東京地方裁判所
ア 以上のとおり,原告X1,原告X2及び原告X3は本件ファイル1を, 原 告X4,原告X6,原告X7及び原告X8は本件ファイル2を,原告X9及 び原告X10は本件ファイル3を,それぞれ,BitTorrentを通じ てダウンロードしたものと認められる(以下,ダウンロードを行ったと認め られる上記各原告を「原告X1ら」という。)。 そして,前記前提事実2(3)のとおり,BitTorrentは,リーチャ ーが,目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても,既に所 持しているファイルの一部(ピース)を,他のリーチャーと共有するために アップロード可能な状態に置く仕組みとなっていることに照らすと,原告X\n1らは,ダウンロードしたファイルを同時にアップロード可能な状態に置い\nたものと認められる。
イ 前記前提事実のとおり,BitTorrentは,特定のファイルをピー スに細分化し,これをBitTorrentネットワーク上のユーザー間で 相互に共有及び授受することを通じ,分割された全てのファイル(ピース) をダウンロードし,完全なファイルに復元して,当該ファイルを取得するこ とを可能にする仕組みであるということができる。\n これを本件に即していうと,原告X1らが個々の送受信によりダウンロー ドし又はアップロード可能な状態に置いたのは本件著作物の動画ファイル\nの一部(ピース)であったとしても,BitTorrentに参加する他の ユーザーからその余のピースをダウンロードすることにより完全なファイ ルを取得し,また,自己がアップロード可能な状態に置いた動画ファイルの\n一部(ピース)と,他のユーザーがアップロード可能な状態に置いたその余\nのピースとが相まって,原告X1ら以外のユーザーが完全なファイルをダウ ンロードすることにより取得することを可能にしたものということができ\nる。そして,原告X1らは,BitTorrentを利用するに際し,その 仕組みを当然認識・理解して,これを利用したものと認めるのが相当である。
以上によれば,原告X1らは,BitTorrentの本質的な特徴,す なわち動画ファイルを分割したピースをユーザー間で共有し,これをインタ ーネットを通じて相互にアップロード可能な状態に置くことにより,ネット\nワークを通じて一体的かつ継続的に完全なファイルを取得することが可能\nになることを十分に理解した上で,これを利用し,他のユーザーと共同して,\n本件著作物の完全なファイルを送信可能化したと評価することができる。\n したがって,原告X1らは,いずれも,他のユーザーとの共同不法行為に より,本件著作物に係る被告の送信可能化権を侵害したものと認められる。\nウ(ア) これに対し,原告らは,アップロード可能な状態に置いたファイルが全\n体のごく一部であり,個々のピースは著作物として価値があるものではな いから,原告らの行為は著作権侵害に当たらないと主張するが,上記イで 判示したとおり,原告X1らによる行為は,他のユーザーと共同して本件 著作物を送信可能化したものと評価できるから,原告らの主張は採用する\nことができない。
(イ) 原告らは,ファイルを送信する側は,自らがファイルをアップロード可 能な状態に置いていることを認識していないことも多いと指摘するが,原\n告X1らは,BitTorrentを利用するに当たって,前記前提事実 (3)イ記載のような手続を踏み,各種ファイルやソフトウェアを入手して\nいる以上,BitTorrentの基本的な仕組みを理解していると推認 されるのであって,とりわけ,BitTorrentにおいて,ユーザー がダウンロードしたファイル(ピース)について同時にアップロード可能\nな状態に置かれることは,その特徴的な点であるから,これを利用した原 告X1らがこの点を認識していなかったとは考え難い。
(ウ) 原告らは,送信可能化権侵害の主張に関し,ユーザー間における本件著\n作物に係るファイルの一部(ピース)の授受を中継した可能性やダウンロ\nードを開始した直後に何らかの事情でダウンロードが停止した可能性が\nあり,原告らが本件著作物を送信可能な状態に置いたと評価することはで\nきないと主張する。 しかし,BitTorrentにおいて,ユーザーがダウンロードした ファイル(ピース)について同時にアップロード可能な状態に置かれるこ\nとは,前記判示のとおりであり,原告X1らがこれを中継したにすぎない ということはできず,また,本件各ファイルのダウンロードの開始直後に ダウンロードが停止したことをうかがわせる証拠もない。
(エ) 原告らは,シーダーとして本件著作物の動画ファイルの配布を行ったも のではなく,原告X6や原告X10の共有比に照らしても,被告の主張す るダウンロード総数の全部や主要な部分を惹起したということはできな いので,民法719条1項前段を適用する前提を欠くと主張する。 しかしながら,そもそも,民法719条1項前段は,個々の行為者が結 果の一部しか惹起していない場合であっても,個々の行為を全体としてみ た場合に一つの加害行為が存在していると評価される場合に,個々の行為 者につき結果の全部につき賠償責任を負わせる規定であるから,仮に個々 の原告がアップロード可能な状態に置いたデータの量が少なく,結果に対\nする寄与が少なかったとしても,そのことは,原告X1らの共同不法行為 責任を否定する事情にはならないというべきである。
エ 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告X1らが本件各フ ァイルをアップロード可能な状態に置いた行為は,本件著作物に係る被告の\n送信可能化権を侵害することになる。\n
2 争点2−1(共同不法行為に基づく損害の範囲)について
(1) 被告は,本件著作物の侵害は,本件各ファイルの最初のアップロード以降継 続しており,社会的にも実質的にも密接な関連を持つ一体の行為であることな どを理由として,原告らがBitTorrentを利用する以前に生じた損害 も含め,令和2年4月2日当時のダウンロード回数について,原告らは賠償義 務を負う旨主張する。しかしながら,民法719条1項前段に基づき共同不法行為責任を負う場合であっても,自らが本件各ファイルをダウンロードし又はアップロード可能な\n状態に置く前に他の参加者が行い,既に損害が発生しているダウンロード行為 についてまで責任を負うと解すべき根拠は存在しないから,被告の上記主張は 採用することはできない。
また,被告は,BitTorrentにアップロードされたファイルは,サ ーバからの削除という概念がないため,永遠に違法なダウンロードが可能であ\nるとして,現在に至るまで損害は拡大している旨主張する。 しかし,前記前提事実(3)ウのとおり,BitTorrentは,ソフトウェ\nアを起動していなければアップロードは行われないほか,BitTorren t上や端末の記録媒体からファイルを削除すれば,以後,当該ファイルがアッ プロードされることはないものと認められる。 そうすると,原告X1らがBitTorrentを通じて自ら本件各ファイ ルを他のユーザーに送信することができる間に限り,不法行為が継続している と解すべきであり,その間に行われた本件各ファイルのダウンロードにより生 じた損害については,原告X1らの送信可能化権侵害と相当因果関係のある損\n害に当たるというべきである。他方,端末の記録媒体から本件各ファイルを削 除するなどして,BitTorrentを通じて本件各ファイルの送受信がで きなくなった場合には,原告X1らがそれ以降に行われた本件各ファイルのダ ウンロード行為について責任を負うことはないというべきである。
(2) アップロードの始期について
ア 以上を前提に検討するに,証拠(甲6)によれば,原告X6については, 遅くとも平成30年6月4日までには本件ファイル2をアップロード可能\nな状態に置いていたことが認められる。
イ 原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X7,原告X8,原告X 9及び原告X10については,BitTorrentを通じて本件各ファイ ルのダウンロードを開始した時期は明らかではないものの,証拠(乙11)に よれば,遅くとも,それぞれ次の各年月日において本件各ファイルをアップ ロード可能な状態に置いていたことが認められる。\n
(ア) 原告X1 平成30年6月12日
(イ) 原告X2 平成30年6月4日
(ウ) 原告X3 平成30年6月2日
(エ) 原告X4 平成30年6月4日
(オ) 原告X7 平成30年6月12日
(カ) 原告X8 平成30年6月13日
(キ) 原告X9 平成30年6月2日
(ク) 原告X10 平成30年6月9日
(3) アップロードの終期について
ア 乙14及び弁論の全趣旨によれば,原告X1らは,それぞれ,別紙「損害 額一覧表」の「終期」欄記載の各年月日に原告ら代理人に相談をしたことが\n認められるところ,同原告らは既にプロバイダ各社からの意見照会を受け, 著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があることを認識していた上,上\n記相談の際に,原告ら代理人からBitTorrentの利用を直ちに停止 すべき旨の助言を受けたものと推認することができるから,同原告らは,そ れぞれ,遅くとも同日にはBitTorrentの利用を停止し,もって, 本件各ファイルにつきアップロード可能な状態を終了したものと認めるの\nが相当である。
イ これに対し,原告らは,プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点で, 直感的にBitTorrentの利用を停止した旨主張するが,プロバイダ 各社から意見照会を受けたからといって,直ちにBitTorrentの利 用停止という行動に及ぶとは限らず,実際のところ,原告X6は,平成30 年10月19日に受領したものの,少なくとも同年11月頃までBitTo rrentソフトウェアを端末にインストールしていたことがうかがわれ\nる(甲6)。そうすると,プロバイダ各社からの意見照会を受けた時点でB itTorrentの利用を停止したと認めることはできない。
ウ 以上によれば,原告X1らは,それぞれ,別紙「損害額一覧表」の「期間」\n欄記載の期間中に他のユーザーが本件各ファイルをダウンロードしたこと により生じた損害の限度で,賠償義務を負うことになる。
(4) ダウンロード数
ア 本件全証拠によっても,上記各期間中に本件各ファイルがダウンロードさ れた正確な回数は明らかではない。他方で,証拠(乙2〜4,8〜10)に よれば,令和元年10月1日から令和3年5月18日までの595日間にお いて,本件ファイル1については501,本件ファイル2については232, 本件ファイル3については910,それぞれダウンロード数が増加している ことが認められるところ,各原告につき,同期間の本件各ファイルのダウン ロード数の増加率に,前記(2)・(3)において認定したダウンロードの始期か ら終期までの日数(別紙「損害額一覧表」の「日数」欄記載のとおり)を乗\nじる方法によりダウンロード数を算定するのが相当である。この計算方法に基づき算定されたダウンロード数は,別紙「損害額一覧表」の「期間中のダウンロード数」欄記載のとおりである。\n
なお,原告らは,乙2〜4記載のコンプリート数(ダウンロード数)と甲 10記載のコンプリート数が大幅に異なることを根拠に,乙2〜4記載のコ ンプリート数に依拠することは相当ではないと主張するが,コンプリート数 が一致しないのは,参照するトラッカーサーバーが異なることが原因である と考えられ,上記乙2〜4のコンプリート数に特に不自然・不合理な点はな い以上,上記各証拠に記載されたコンプリート数に基づいてダウンロード数 を計算することが相当である。
(5) 基礎とすべき販売価格
ア 原告X1らが本件各ファイルをBitTorrentにアップロード可 能な状態に置いたことにより,BitTorrentのユーザーにおいて,\n本件著作物を購入することなく,無料でダウンロードすることが可能となっ\nたことが認められる。これにより,被告は,本件各ファイルが1回ダウンロ ードされるごとに,本件著作物を1回ダウンロード・ストリーミング販売す る機会を失ったということができるから,本件著作物ダウンロード及びスト リーミング形式の販売価格(通常版980円,HD版1270円)を基礎に 損害を算定するのが相当である。
そして,被告は,DMMのウェブサイトにおいて本件著作物のダウンロー ド・ストリーミング販売を行っているところ,被告の売上げは上記の販売価 格の38%であると認められるので(弁論の全趣旨),本件各ファイルが1回 ダウンロードされる都度,被告は,通常版につき372円(=980×0. 38),HD版につき482円(=1270×0.38)の損害を被ったも のということができる。
イ 本件ファイル3は通常版の動画ファイルのピースであるのに対し,本件フ ァイル1及び2はHD版の動画ファイルのピースであることが認められる ので(弁論の全趣旨),別紙「損害額一覧表」の「価格」欄記載のとおり,\n原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X6,原告X7及び原告X 8については482円,原告X9及び原告X10については372円を基礎 として,損害額を計算することが相当である。
ウ 本件各ファイルをダウンロードしたユーザーの中には有料であれば本件 著作物を購入しなかったものも存在するという原告らの指摘や,BitTo rrentのユーザーと本件著作物の需要者等が異なるという原告らの指 摘も,前記認定を左右するものということはできない。 (6) 以上によれば,原告X1らが被告に対して負うべき損害賠償の額は,それぞ れ,別紙「損害額一覧表」の「損害額」欄記載のとおりとなる(なお,同別紙\n「5)期間中のダウンロード数」は計算結果を小数第2位まで表示したものであ\nり,「損害額」欄は小数第1位で切り捨てたものである。)。
3 争点2−2(減免責の可否)について
原告らは,原告らにおいて複製物を作成しようという意思が希薄であり,客観 的にも本件著作物の流通に軽微な寄与をしたにすぎないことや,原告らとユーザ ーとの間の主観的・経済的な結び付きが存在しないことからすれば,関連共同性 は微弱であるとして,損害額につき大幅な減免責が認められるべきである旨主張 するが,原告らの指摘するような事情をもって,前記認定の損害額を減免責すべ き事情に当たるということはできない。
関連カテゴリー
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.01.11
令和1(ワ)27053 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月31日 東京地方裁判所
争点1−1(被告製品の小径部側壁部は,係止片は大径部側に一体形成される一方 小径部側には設けられていないという文言を充足するか−構成要件1E4),2E4), 3E5)充足性)について
構成要件1E4),2E4),3E5)によれば,「係止片は」「大径部側に」「一体形成 される一方」「小径部側には設けられておらず」というのであり,上記のとおり,本 件発明は,従来よりも安全性などの向上を図るというその目的をより良く達成する という上記の技術的見地から,針先再露出防止を担う係止片の構成を工夫して,拡\n開部の大径部側に一体形成し小径部側には設けないという構成を採用したものとい\nうことができる。これによれば,本件発明において,拡開部に設ける「係止片」に ついては,大径部側に一体形成されている必要があるとともに,小径部側には設け られていない構成である必要があるものであって,「係止片」が小径部側に設けられ\nている構成は排除されているものといわなければならない。\n
そして,この「係止片」は,使用後の針先再露出を防止する部材であるといえる が,当該部材が針先の先端側への移動を阻止して針先再露出を防止する態様につい ては,構成要件1Dに「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた\n所定位置において,該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止 される」とある以上には何ら具体的な限定がなされていない。また,本件明細書の 発明の詳細な説明を見ても,当該部材が,針先の先端側への移動を阻止する具体的 態様を限定する根拠となり得るような記載は見当たらない。加えて,本件特許の出 願経過を見ると,証拠(乙14,15)によれば,原告は,令和元年5月15日頃, 特許庁から進歩性欠如等を理由とする拒絶理由通知を受け,その際,構成要件1D\nに関し,「針先プロテクタの断面形状を,周知の形状である小径部と大径部とを備え た楕円形とし,大径部の周壁に針ハブ係合部を設け,大径部の周壁で覆われた内部 に係止部を設けた構成とすることは,当業者が容易になし得たことである。」などと\n指摘されたことを踏まえて,同年6月19日,従前の請求項で「前記拡開部の前記 大径部に対応する位置に,前記筒状の周壁に一体形成された前記係止部が設けられ て」と記載していた部分を,「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方, 前記小径部側には設けられておらず,」と補正したものであることが認められる。そ の上で原告は,同日特許庁に提出した意見書において,本件発明の進歩性を基礎付 ける事情として,拒絶理由通知書で審査官が指摘した引用文献(乙27,29)に ついては,いずれも針先プロテクタの小径部側に係止部が設けられており本件発明 とは異なる旨主張し,その際,当該係止部が針先の先端側への移動を阻止する具体 的態様には言及していなかったことが認められる。そして,本件特許は,その上で 登録されている。
そうすると,本件特許請求の範囲の記載文言をみても,本件明細書の発明の詳細 な説明をみても,小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」が針先 の先端側への移動を阻止する具体的態様を限定する根拠となり得るような記載がな く,加えて,原告自身,本件特許の出願手続においては,その特許請求の範囲を前 記のように「前記小径部側には設けられておらず,」と補正した上で,意見書におい て,具体的態様については何ら限定しないまま,小径部側に「係止片」が設けられ ていない点を本件発明の進歩性を基礎付ける事情として主張し,その上で本件特許 が登録されたものである。 以上によれば,本件発明において小径部側に設けられてはならない「係止片」は, 針先の先端側への移動を阻止する具体的態様が限定されているものではなく,他の 部材と協働して針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものであるといわなけ\nればならない。
そこで,被告製品をみるに,前記前提事実によれば,被告製品においては,針基 に設けられた針リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが,小径部側壁部の 突端面により縦リブの側面を挟持することで互いに係合することにより,針基が針 先保護部に対して回動することを防止する構成になっており,仮にこのような回動\nが発生して針基の受部が大径部係止手段のない小径部側まで移動した場合には,針 基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前進することになる。すなわ ち,小径部側壁部がなければ,大径部係止手段が無効化されて,針基が前進し,留 置針の針先が針先保護部の先端側から再露出することになるのであるから,被告製 品においては,小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段による針基の 受け部の係止が協働して機能することによって,針先の再露出を防止していると認\nめられる。
そうすると,被告製品の小径部側壁部は,他の部材と協働して,針先の先端側へ の移動を阻止する構成であるといえ,当該小径部側壁部は,本件発明において小径\n部側に設けられることが排除されている「係止片」に当たるといわなければならな い。これによれば,「係止片」が針先抜出防止機構を含むものであるか否かに関わら\nず,被告製品は,小径部側に「係止片」が設けられているものとして,本件発明に おいて排除されている構成を有しているから,本件発明の構\成要件1E4),2E4), 3E5)をいずれも充足しないといわなければならない。 したがって,被告製品は,本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,本件発明の構成要件1Dの「係止片」が,針ハブ(に設けられた受部)\nと「係止」されることによって「再露出を防止する(つまり,留置針が前進しな いように止める)」ものであるのに対し,被告製品の小径部側壁部は,針基の縦リ ブの側面を挟持して針基の回動を防止しているだけで,針基の前進を防止してい るわけではないから,「係止片」に該当しないなどと主張する。 しかし,前記説示のとおり,本件発明にいう「係止片」は,他の部材と協働し て針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものといわなければならない。そ\nして,被告製品において,小径部側壁部がそれ単体として針先の再露出を防止す るものでないとしても,小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段に よる針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再露出を防止し\nているものである以上,本件発明にいう「係止片」に該当しないということはで きない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ また,原告は,被告製品の小径部側壁部が針基の縦リブの側面を挟持する場所 は,針基と針先保護部の位置関係にかかわらないのであって,留置針の針先側へ 針先プロテクタが移動せしめられた「所定位置」において係止するものでないた め,被告製品の小径部側壁部は「係止片」に当たらないとも主張する。 しかしながら,前記のとおり,被告製品は,小径部側壁部がそれ単体として針 先の再露出を防止するものではなく,小径部側壁部による針基の回動防止と大径 部係止手段による針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再\n露出を防止するものであり,その機能が発揮される場所は,前記前提事実のとお\nり,針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる位置に限定されている。 このことからすれば,被告製品の小径部側壁部は,「留置針の針先側へ針先プロテ クタが移動せしめられた所定位置において」,大径部係止手段と協働して針先の再 露出を防止しているといえる。被告製品の小径部側壁部が,針先と針先保護部の 位置関係にかかわらず針基の縦リブの側面を挟持しているという事情は,この説 示を左右するものではない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ さらに,原告は,本件発明の構成要件1E4),2E4),3E5)が「前記係止片 は,前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し,」と規定していることをもって, 本件発明で小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」は「前記針 ハブに向かって傾斜した内側面」を有しているものに限られているなどと主張す る。
しかし,構成要件1E4),2E4),3E5)の「前記係止片は,前記針ハブに向 かって傾斜した内側面を有し」との文言は,本件明細書の段落【0061】の記 載(「・・・垂直面79a,79aの外周側に位置する傾斜面79b,79bが,外周 側になるにつれて先端側に傾斜していることから,垂直面79a,79aと基端 側規制面40とが傾斜面79b,79bに干渉されることなく当接することがで きて,針ユニット20と針先プロテクタ10の軸方向における相対移動防止効果 がより確実に発揮され得る。」との記載)も併せると,そのような大径部側に一体 形成される係止片の構成について,規定した針ユニットと針先プロテクタの軸方\n向における相対移動防止効果がより確実に発揮されるという効果を奏させるべく 規定されたものであると認められる。そうすると,当該文言は,大径部側に円筒 状部と一体形成される係止片について特定したものにすぎず,設けられていては ならない位置にある「係止片」の形状を限定するものではないというべきである。 したがって,被告製品の小径部側壁部が「傾斜した内側面」を有しないことは, 被告製品の小径部側壁部が本件発明において小径部側に設けられてはならないと されている「係止片」に当たることを否定する理由にはならない。原告の上記主 張は,採用することができない。
エ 以上によれば,原告の上記主張はいずれも採用できない。原告は,その他も縷々 主張するが,それらの主張内容を慎重に精査しても,上記説示を左右するに足り るものはない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2022.01. 7
平成30(ワ)1130 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月31日 東京地方裁判所
ア 前記前提事実によれば,本件発明の構成要件1Eは,「該印刷層は,白色の有機\n顔料,白色または黄色の無機顔料,蛍光染料,および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成1eは,「印刷層\nは,●(省略)●と●(省略)●を含有する●(省略)●印刷インキにより形成 されるが,」である。そして,被告製品の印刷層の●(省略)●印刷インキに含有 される●(省略)●は,「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは,本件発明については,印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば,それだけで構成要件1Eを充足するのではなく,これにより「色相を明\nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件1Eには,印刷層が「白色の有機顔料,および蛍光増白剤」\nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり,「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また,前記1のとおり,本件発明は,再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ,本件明細書の段落【0004】には,三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち,反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては,その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの,それ以外の再帰反射シートについては,外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また,本件明細書の【0014】,【0015】には,本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され,段落【0021】,【0 030】,【0032】には,印刷層の目的は「色相を調節」,「色相の調整」と記 載され,段落【0036】には,「本発明に用いられる着色剤は,特に限定される ものではないが,・・・色相を明るくすることができ,且つ,隠蔽性が得られるもの が良く,シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく,・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料,並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ,中でも, 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており,「色相を明るくすること」 は,「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで, あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため,本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は,色相の調節ないし調整を意味するも のであり,「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方, 本件明細書の実施例では,白色顔料が用いられているものの,その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく,比較例でも, 実施例とは印刷の模様のみを変えて,「Y値」すなわち「色相(明るさ)」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば,本件発明の構成要件1Eの「着色剤」が「色相を\n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば,本件発明の構成要件1Eの「着色剤」が「色相を明るくするこ\nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し,被告らは,本件特許の出願経過において,原告が,補正により本 件発明に構成要件1Eを追加し(乙21),本件発明の効果は,「色相,特に昼光\n下での色相(Y値=明るさ)が改善されて」いることであり,同構成要件の着色\n剤を用いることにより色相(Y値=明るさ)を改善したと主張しており(乙3), 同構成要件の「白色」,「黄色」,「蛍光」を用いて「色相(Y値=明るさ)」を改善\nする技術的意義を強調しているから,上記着色剤の意義は,色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし,原告が提出した乙21の内容を見ても,本件発明の構成要件1Eの技\n術的意義が,「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ,乙3には,本件発明の効果は,「十分な再帰反射性能\を有し,かつ色相, 特に昼光下での色相(Y値=明るさ)が改善されており,耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され,Y値と同義である「色相(Y値=明るさ)」 と,それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため,明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに,乙3には, 一般に用いられている着色剤は,再帰反射性の確保のために光透過性を有するが, 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して,本件 発明の構成要件1Eの着色剤は,光透過性を有するものではないこと,本件発明\nは,構成要件1Eの着色剤を用いることにより,再帰反射シートの昼光下での色\n相(Y値=明るさ)を更に改善したこと,本件発明では,印刷領域が構成要件1\nB〜1Dを具備する独立印刷領域であるため,印刷層が光透過性を有しない構成\n要件1Eの着色剤を含有しても,それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能\を 有することが記載されている。以上によれば,原告は,本件特許の出願経過にお いて,本件発明の構成要件1Eの着色剤について,明るさの改善だけでなく,そ\nれ以外の効果も主張していると解されるから,そのような主張をもって,本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他,被告らの主張を検討しても,採用すべきものはない。
エ したがって,被告製品(1)の構成1eは,それぞれ本件発明の構\成要件1E及び これを引用する構成要件2Bを充足する(なお,仮に同構\成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても,これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り,必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ,証拠(甲17)及び 弁論の全趣旨によれば,被告製品では,「白色」の「無機顔料」に当たる●(省略) ●を含有しない領域よりも,これを含有する領域の方が色相も改善●(省略)● による色相改善の効果を享受)していることがうかがわれ,被告製品の●(省略) ●印刷インキの色相が暗くなっているのは,●(省略)●で色相が明るくなった 一方で,●(省略)●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり,これに よって本件発明の構成要件1Eの充足性が否定されることにはならないというべ\nきである。)。
・・・
推定覆滅の事情
a 特許法102条2項における推定の覆滅については,同条1項ただし書の 事情と同様に,侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば,1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること (市場の非同一性),2)市場における競合品の存在,3)侵害者の営業努力(ブ ランド力,宣伝広告),4)侵害品の性能(機能\,デザイン等特許発明以外の特 徴)などの事情について,特許法102条1項ただし書の事情と同様,同条 2項についても,これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
b そこで,被告らが特許法102条1項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに,次のとおり,2割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは,本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は,顧客吸引には全く寄与しておらず,被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり,被告旧製品のカ タログでも,印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし, 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり,本件発明 は,被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし,前記1(9)で説示したとおり,本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は,再帰反射シートの印刷層について,「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており,連続層を形成せず」,「独 立印刷領域の面積が0.15mm2〜30mm2」,かつ,「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより,印刷層周辺の密着\n性を向上させ,耐水性・耐候性を向上させるとともに,色相の改善を図る ことにあるのであるから,その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は,その前提を欠くものである。また,被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果(乙45〜49)についても,その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから,これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして,証拠(甲3,4,9,10,23,67〜70)及び弁論の 全趣旨によれば,被告旧製品のカタログやウェブサイトには,本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記\n載が多数存在することも認められる。 したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に,被告は,本件発明は,被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず,むしろ,3Mブランドに裏付けられた被告らの信用,実績及び知名度 等こそが,被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり,現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし,仮に被告らが3Mグループとしてのブランド力を有するとして も,これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また,仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても,顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上,従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから,これをもって直ちに本件発明が顧客への販売\nに貢献していないということはできない。 したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また,被告らは,主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については,再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく,原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり,実際に,被告らの販売\nする被告製品並びにその他の製品(Diamondグレード及びEngi neeringグレードの再帰反射シート)の売上比がそれぞれ●(省略) ●であり,原告製品の売上比が10%であるから,仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば,そのうちの●(省略)●(=10/(10+● (省略)●))のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし,そもそも,競合品といえるためには,市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは,被告ら が販売するDiamondグレード及びEngineeringグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが,弁論の全趣旨 によれば,前者の価格は被告旧製品の●(省略)●以上であり,後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから,これらの製品の\n価格や性能等を捨象して,同様の用途に用いられる再帰反射シートである\nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると,被告 らが主張するDiamondグレード及びEngineeringグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず,それゆえに被告旧製品の需要がDiamondグレー ド及びEngineeringグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって,被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに,被告らは,仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても,原告の逸失利益は,被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ,原告製品の販売単価は被告旧製品の●(省 略)●程度の価格帯であり,原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●(省略)●程度であるはずであり,原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●(省略)●程度にすぎないことが推認されるから,特許法10 2条2項によって推定される損害額は,原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点,弁論の全趣旨によれば,原告製品の販売単価は,被告旧製品の ●(省略)●程度の価格帯であることが認められるところ,仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても,原告において,被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く,この点については,一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが,他方で,原告製品の販売単 価が低価格であることにより,その販売数量が,被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから,大幅な推定覆滅を認めるのが相\n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると,被告らが主張する推定覆滅事由のうち, 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ,推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり,その覆滅割合は2割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に,原告は,予備的主張として,特許法102条3項の適用を前提とする損\n害額の支払を求めているため,以下検討する。
・・・
a 特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については,平成10年法律第51号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ,「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して,同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で,被許諾者が最低保証額 を支払い,当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し,技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には,侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして,上記 のような特許法改正の経緯に照らせば,同項に基づく損害の算定に当たって は,必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく,特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき,実施に対し受けるべき料率は,むしろ,通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって,実施に対し受けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て,合理的な料率を定めるべきである。
b そこで検討するに,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,1)原告は,本 件訴訟の提起前に,被告らを含む3Mグループに対し,本件特許のライセン ス料率5%を提案していたこと(乙41),他方で,米国3Mは,過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において,再帰反射シートに関する特許の実施 料率は9%であると主張していたこと(甲71),米国3Mらは,過去に第三 者に提起した訴訟において,ロイヤルティ料率20%での合意をしたこと(甲 72,乙66),株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産(資産)価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」(平成22年3月)において,再 帰反射シート(樹脂シート)が該当する「化学」の最小値が0.5%,最大 値が32.5%,平均が4.3%であるとされていること(甲73,乙67), 被告3Mジャパンらは,原告に提起した特許権侵害訴訟において,実施料率 を10%と主張していること等が認められる。 また,2)本件発明は,前記のとおり,再帰反射シートの構成全体に関わる\n発明であり,相応の重要性を有しているといえ,これらの構成を備えた従来\n技術は存在せず,この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして,3)本件発明は,被告旧製品の全体について実施されており,これ によって向上される耐水性・耐候性は,需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから,本件発明を被告旧製品に用いることにより,被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに,原告と被告らは,いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり, 競業関係にある。
c 上記bの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると,本件特許\n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき,本件での実施に対し受ける べき料率は,10%を下らないものと認めるのが相当である。 したがって,本件特許権侵害について,特許法102条3項により算定さ れる損害額は,前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の10%になる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.01. 7
平成18(行ケ)10043 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成18年6月29日 知的財産高等裁判所
標章「速脳速聴基本プログラム」の使用が、登録「速脳速聴」の使用と認定されました。指定商品は「中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・ 磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」です。
本件関連標章1は,「速脳速聴」(本件商標)と「基本プログラム」と が結合した語から成るものである。この構成中の「速脳速聴」の部分は,\n高速で聴くことによって脳の回転を高めるといった程度の意味を有するも のと理解されないこともないが,明確な意味を有するとまではいえず,取 引者・需要者において,既存の明確な観念を伴わない新たな造語であると 認識するものと認められる。一方,「プログラム」の語は,本件商標の指 定商品である電子応用機械器具の分野において,その一種である電子計算 機のためのプログラムを示す普通名称であり,これに冠して付加されてい る「基本」の語は,「物事が成り立つためのよりどころとなるおおもと。 基礎。」(甲27の2,ウェブサイトの「 辞書」),「物事がそれに goo 基づいて成り立つような根本。」(甲28,株式会社岩波書店平成3年1 1月15日発行「広辞苑第4版」)を意味し,後に「応用」若しくは「発 展」など次の段階へと続くことを想起,連想させる一般的な記載にすぎな いから,本件関連標章1に接した取引者・需要者は,通常,その構成中の\n「基本プログラム」の部分は,商品の特定のために当該商品の用途等を表\n示したものと理解して,それ自体を自他商品の識別力を有する部分とは考 えないと認めるのが相当である。
そして,「速脳速聴」と「基本プログラム」とは,一体不可分の密接な 関係にあるとはいえないし,「速脳速聴基本プログラム」の称呼は,「ソ\nクノウソクチョウキホンプログラム」と著しく冗長であって,この一連一\n体の称呼によることが取引の実情に即したものであるとは言いがたく,む しろ,取引の実際においては,冒頭の「速脳速聴」の部分に即して「ソク\nノウソクチョウ」との称呼を生ずるのが通常であるということができる。\nそうすると,本件関連標章1の「速脳速聴基本プログラム」の語は, 「速脳速聴」の部分において,取引者・需要者の注意を引くものであり, その部分が自他商品の識別力を有するものというべきである。 もっとも,本件関連標章1の「速脳速聴」の部分について,高速で聴く ことによって脳の回転を高めるといった程度の意味のものととらえ,本件 関連標章1について,一体として「速脳速聴の基本的なプログラム」,あ るいは,「速脳速聴に関する基本的なプログラム」との観念を生ずること もあり得ないものではない。しかし,一般には,「速脳速聴」の観念が必 ずしも明確でないことに照らしても,「速脳速聴の基本的なプログラム」 等の観念が生ずる可能性がないわけではないことによって,「速脳速聴」\nの部分の自他商品識別力が否定されるものではないというべきである。 そして,この「速脳速聴」は,本件商標と同一なのであるから,本件関 連標章1は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみるのが相当 であり,上記1及び2・・・ に照らせば,プランニングラボは,本件予\n告登録前3年以内に,本件関連標章1により,本件商標の指定商品である 本件商品1につき,商標法2条3項1号及び8号にいう本件商標の「使 用」をしていたというべきである。
ウ ところで,被告は,本件CDに付されている商標は,「速脳速聴基本プ ログラム」であるから,本件商標「速脳速聴」とは,同一の商標ではない し,「速脳速聴基本プログラム」は,一体として「速脳速聴の基本プログ ラム」の観念が生じ,当然,一連一体として観察,称呼しなければならず, 本件商標とは,称呼,外観,観念のすべてを異にするものであり,識別力 を異にすることが明らかであるから,本件関連標章1は,本件商標と社会 通念上同一と認められる商標でないと主張する。 しかし,「速脳速聴基本プログラム」がそれ自体一つの商標であるとし ても,上記のとおり,取引の実際においては,「速脳速聴」の部分,すな わち,本件商標に相当する部分が商標として自他商品識別力を有している ものというべきである。また,「速脳速聴基本プログラム」から,一体と して「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることは,\n上記のとおりであるが,そのことから,このような結合語を,直ちに一連 一体として観察,称呼しなければならないものとはいえず,一体として 「速脳速聴の基本プログラム」の観念が生ずる可能性があることによって,\n「速脳速聴」の部分の自他商品識別力が否定されるものではないことも, 上記のとおりである。
(4) 次に,本件取扱説明書の表紙に記載されている「速脳速聴<R>基本プログ ラム」(以下「本件関連標章2」という。)について検討する。 ア 本件関連標章2が,本件商標と社会通念上同一といえるかについてみる と,本件関連標章2は,「速脳速聴」と「基本プログラム」とが<R>マー クで区分された語であるところ,この<R>マークは,米国における連邦登 録商標の商標表示の方法(米国連邦商標法1111条〔ランナム法29\n条〕)であって,商標法73条,同法施行規則17条にいう商標登録表示\nではないが,我が国でも登録商標に簡明な<R>マークを付すことが慣行的 に行われていることは,当裁判所に顕著である。そして,本件関連標章2 においては,<R>マークによって,「速脳速聴」と「基本プログラム」と が明確に分離されており,また,上記のとおり,本件取扱説明書の裏表紙\nには,「『速脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会(X 〔注,原告〕)が保有する商標です。」等の記載があることから,取引者 ・需要者は,「速脳速聴」が商標であると容易に理解することができるも のである。 そうすると,本件関連標章2は,本件関連標章1以上に,「速脳速聴」 の部分に自他商品識別力があるということができるから,本件商標と社会 通念上同一と認められる商標であり,プランニングラボは,本件関連標章 2によっても,本件関連標章1と同様,本件商標の使用をしていたといわ なければならない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2022.01. 6
平成30(ワ)28215 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年9月17日 東京地方裁判所
以上のとおり,原告表示画面と被告表\示画面の共通する部分は,いずれも アイデアに属する事項であるか,又は,書店業務を効率的に行うに当たり必 要な一般的な指標や情報にすぎず,各表示項目の名称の選択,配列順序及びそのレイアウトといった具体的な表\現においても,創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない上,両製品の配色の差違等により,利用者が画面全体から受ける印象も相当異なるというべきである。そ\nして,被告表示画面について,他に原告表\示画面の本質的特徴を直接感得し 得ると認めるに足りる証拠はない。
(4) 表示画面の選択や相互の牽連関係における創作性の有無・程度
ア 原告は,表示画面の牽連性に関し,原告製品は,画面の最上部にメニュータグを常時表\示し,どの画面からも次の業務に移行できるようにしている点や,画面の中央にサブメニュー画面を用意し,画面遷移なしに表示することを可能\にしている点などに独自性があると主張する。 しかし,画面の最上部にメニュータグを常時表示し,そのいずれの画面からも次の業務に移行できるようにすることや,画面の中央にサブメニュー画\n面を用意し,画面遷移なしに表示することを可能\にすることは,利用者の操 作性や一覧性あるいは業務の効率性を重視するビジネスソフトウェアにおいては,ありふれた構\成又は工夫にすぎないというべきであり,原告製品における表示画面相互の牽連性に特段の創作性があるということはできない。
イ また,原告は,原告製品が補充発注画面や自動計算機能を備えていることをもって他社にはない独自性があると主張するが,在庫の変動に伴い商品を\n補充して発注することや,定期改正数を自動計算することなどは,一般的な 書店業務の一部であり,原告製品の補充発注(条件設定)画面及び補充発注 (入力)画面に表示された項目の名称の選択,配列順序及びそのレイアウトなどの具体的な表\現において,創作者の思想又は感情が創作的に表現されて\nいるということはできないことは,前記(3)ケ及びコで判示のとおりである。
ウ したがって,原告製品は,表示画面の選択や画面相互の牽連性において独自性又は創作性があるとの原告主張は採用し得ない。\n
・・・
(1) 原告は,被告製品の表示画面が不競法2条1項1号の規定する不正競争行為に該当すると主張するところ,ビジネスソ\フトウェアの表示画面は,商品の形\n態と同様,1)当該表示画面が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,2)その表示画面が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な広告宣伝や爆発的な販売実績等により,\n需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている場合に不競法2条1項1号の「商品等表\示」に該当すると解するのが相当である。
(2) 周知性について
原告は,原告表示画面が,遅くとも平成25年末までには,出版業界及び書店業界において広く認識されていたと主張するが,以下のとおり,理由がない。\nア 原告製品の販売数や市場占有率に関し,原告は,原告のシステム製品は出 版社市場でトップシェアを占めており,原告製品は既に全国の小売書店10 00店舗に向けて販売・採用されていると主張するが,原告商品の導入件数, 市場規模,原告製品の市場占有率を客観的に示す証拠は提出されていない。
イ また,原告は,業界新聞である「文化通信BB」において原告製品が紹介 されたことを指摘するが,「文化通信BB」の発行部数等は明らかではなく, その記事の内容は原告製品を紹介する内容を含むものの,原告製品の表示画面は一切掲載されていない(甲18)。\n同様に,原告は,日販が平成25年8月1日付け業界新聞において書店向 けPOSレジと原告製品を連携させることを発表し,系列の書店1000店に合計1300台を販売することを表\明したと主張するが,同記事で導入が表明されているのはPOSレジであり,原告製品が書店に導入されたことを裏付けるものではない上,同記事には原告製品の表\示画面は一切表示されて\nいない(乙23)。
ウ さらに,原告は,「文化通信」及び「新文化」のウェブサイトの上段に,バ ナー広告を掲載したことや,「BOOK EXPO」や「書店大商談会」に出 展し,広報を行っていることを根拠に,原告表示画面には周知性がある旨主張する。\n しかし,証拠(乙22)によれば,文化通信社のウェブサイト上に掲載さ れたバナー広告は,「BOOK ANSWERシリーズ」という製品名を表示するものにすぎず,原告製品の表\示画面は一切示されていない。また,「BOOK EX PO」や「書店大商談会」への出展についても,その規模や具体的な出展・ 宣伝態様などは一切明らかではない。
エ 以上によれば,原告画面表示が,遅くとも平成25年末までに,出版業界及び書店業界において広く認識されていたと認めることはできない。\n
(3) 特別顕著性について
原告は,原告表示画面には特別顕著性が認められる旨主張し,その根拠として,1)業務統合型のシステムを構築するという設計思想に基づき,仕入部門で使用するメニューと店売部門で使用するメニューが統合されている点や,2)発 注に当たって,商品分析の画面から一旦発注画面に移行することなく,商品分 析の画面から即発注することができる点,3)帳票を作成するという発想がなく, 画面上に表示して見るということを基本にしている点,4)独自の用語を用いて いる点に,他社製品にはない原告製品の独創的な特徴がある旨主張する。
しかし,上記1)〜3)の点は,いずれも,原告製品の設計思想や機能としての独自性を指摘するものにすぎず,表\示画面自体の顕著な特徴を基礎付けるものということはできない。また,上記4)の点についても,原告製品の表示画面に用いられた用語は,一般的な書店業務に用いられているものがほとんどであり,\n画面全体の特別顕著性を基礎付けるに足りる独創的を有すると認めることは できない。
したがって,原告表示画面が同種製品と異なる顕著な特徴を有しているということはできない。\n
(4) 以上のとおり,原告表示画面には,周知性及び特別顕著性のいずれも認められないから,原告表\示画面が「商品等表示」に該当するということはできない。\nしたがって,その余の点を判断するまでもなく,不正競争防止法に関する原 告の主張についても理由がない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2022.01. 6
令和3(ネ)10026 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月30日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(2) 控訴人の当審における補充主張に対する判断
控訴人は,請求1−1に関し,前記第2の3(1)アのとおり,別件評決ない し別件米国判決は,被控訴人の元従業員であるAの認識や記憶に基づかない 意図的な偽証に基づきされたのであり,被控訴人自身も,そのことを認識し たはずであるにもかかわらず,Aの供述や証言を援用して,自らに有利な架 空のストーリーを主張していたことになり,別件評決及び別件米国判決には, 民事訴訟法338条1項7号の再審事由が存するといえ,我が国の法秩序の 基礎をなす公序,適正手続という観点に照らして到底容認されるべきもので はなく,同法118条3号の要件を欠くほどに重大な瑕疵があると主張する。 しかし,民事訴訟法338条1項7号の再審事由は,証人の虚偽の陳述が 判決の証拠となった場合でなければならず,同号を理由に再審を求める場合 には,まず刑事手続で有罪の判決が確定した後等でなければならないところ (同条2項),本件においてはこのような事情は認められない。したがって, Aの供述・証言に係る事情をもって同号の再審事由が認められるとする控訴 人の主張は失当というほかない。証人の供述の信用性等は,本来,別件米国 訴訟の中で攻撃防御を尽くした上,誤った判断がされたのであれば,最終的 には上告や再審といった手続の中で是正されるべきものであるところ,別件 米国訴訟においては,そのような機会を経た上で,控訴人の敗訴が確定し, 現在に至っているのであるから,請求1−1に係る控訴人の訴えは,別件米 国訴訟の蒸し返しに当たるといわざるを得ない。 なお,念のために付言すれば,Aは,2015年(平成27年)2月15 日付けの宣誓供述書(甲32)で,参加人が宇部興産に本件発明の実施品を 販売するために本件特許のライセンスを被控訴人に要求し,被控訴人は宇部 興産が非競合者であるためライセンスを与えることを許諾したと供述してい るものの,別件米国訴訟における証人尋問においては,A自身はライセンス の交渉自体には関与していないこと,Cから,本件特許により設備を販売で きなくなり参加人としては困るとの話があったので購買部門に話をつないだ こと,参加人が販売対象として考えているのが非競合他社であるかどうかに ついては明確な議論はなく,ただ,その後上級管理者からは,非競合他社で ある宇部興産に販売しようとしているので問題はないだろうと言われたこと を証言し(甲35),別件関連訴訟における陳述書(甲50)では,Cから ライセンスの打診は受けたが上司に話をつないだだけであるとし,別件関連 訴訟の証人尋問では,Cから本件特許が製品の販売に支障をきたすので何と かならないかという話があったので,上司に話をつないだこと,宇部興産と いう具体名は出なかったが,被控訴人の競合相手ではない同社のことだろう と推測したものであることを証言している(甲51)。このような経緯に照 らせば,別件米国訴訟においてAが意図的な偽証をしていたとまで認めるこ とは困難であり,また,その偽証に基づき被控訴人が別件米国訴訟を追行し ていたともいい難い。 その他,控訴人がるる主張する点を考慮しても,日本の裁判所が審理及び 裁判をすることが当事者間の衡平を害する特別の事情(民事訴訟法3条の9) があるとの判断を覆すに足りるものではない。
2 確認の利益の有無(請求1−2について。争点3)
確認の利益が認められるためには,原告の権利又は法律的地位に危険又は不 安が存在し,これを除去するために,原告と被告の間で,その訴訟物である権 利あるいは法律関係の存否を確認することが必要かつ適切であることを要する。 被控訴人は,令和3年7月20日の当審第1回口頭弁論期日において,仮に, 本件日本特許権の侵害に基づく被控訴人の控訴人に対する損害賠償請求権が存 在するとしても,請求権自体放棄すると陳述した。 そうすると,請求1−2の対象となる権利については,被控訴人による権利 行使の意思がないことはもちろん,本件口頭弁論終結時におけるその存在自体 が認められないことになり,権利の存否を巡る法律上の紛争は解決されたとい えるから,現に控訴人の法律的地位に危険又は不安が存在し,これを除去する ため被控訴人に対し確認判決を得ることが必要かつ適切であると認めることは できない。 したがって,その他の点について判断するまでもなく,請求1−2に係る訴 えには確認の利益が認められないから,不適法というべきである。
3 訴訟物の特定の有無(請求2について。争点4)
当裁判所も,請求2に係る訴訟物の特定に欠けるところはないものと判断す る。その理由は,原判決の第3の3の説示のとおりであるから,これを引用す る。
4 請求2−1に係る訴えの準拠法(争点2)並びに別件米国訴訟の提起及び追 行の違法性等(争点6)
(1) 日本法に基づく不法行為の成否
ア 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は,原則として加害行為の 結果発生地の法による(通則法17条本文)。もっとも,不法行為につい て外国法によるべき場合において,当該外国法を適用すべき事実が日本法 によれば不法とならないときは,当該外国法に基づく損害賠償その他の処 分の請求は,することができない(同法22条1項)。このため,請求2 −1に係る訴えの準拠法をいずれの地の法と考えるとしても,被控訴人に よる別件米国訴訟の提起及び追行につき日本法により不法行為といえる 必要があることになる。そこで,以下,この点につきまず検討する。
イ 別件米国訴訟は,被控訴人が勝訴して確定するに至っており,このよう な場合に,訴えの提起や追行が不法行為となるためには,確定判決の騙取 が不法行為となる要件,すなわち判決の成立過程において,被控訴人が控 訴人の権利を害する意図のもとに,作為又は不作為によって控訴人の訴訟 手続に対する関与を妨げ,あるいは虚偽の事実を主張して裁判所を欺罔す\nる等の不正な行為を行い,その結果,本来あり得べからざる内容の確定判 決を取得したこと(最高裁判所昭和43年(オ)第906号同44年7月 8日第三小法廷判決・民集23巻8号1407頁),ないしはこれに準ず る特段の事情を要すると考えるのが相当である。そもそも,法的紛争の当 事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求め得ることは,法治国家の根幹 に関わる重要な事柄であるから,訴えの提起や追行が不法行為を構成する\nか否かを判断するに当たっては,裁判制度の利用を不当に制限する結果と ならないような慎重な配慮が必要とされるのであり,民事訴訟を提起した 者が敗訴の確定判決を受けた場合ですら,当該訴えの提起が相手方に対す る違法な行為となるには,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法 律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを 知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに あえて訴えを提起し,又はそれを維持したなど,訴えの提起・追行が裁判 制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められることを要す ると理解されている(63年判決)のであるから,民事訴訟を提起した者 が勝訴の確定判決を受けている場合には,前示のとおり,より高次の特段 の事情を要するというべきである。
これを前提にして本件を見れば,引用に係る原判決第2の1(補正後の もの)及び第3の1(2)イで認定された事実関係に照らせば,本件が,確定 判決の騙取が不法行為となる要件ないしはこれに準ずる特段の事情どこ ろか,民事訴訟を提起した者が敗訴した場合の要件すら満たし得ないもの であることは明らかというべきである(なお,別件米国訴訟においてAが 意図的な偽証をしていたとまで認めることは困難であり,また,その偽証 に基づき被控訴人が別件米国訴訟を追行していたともいい難いことは,前 記1(2)において判示したとおりである。)。 以上のとおりであるから,被控訴人による別件米国訴訟の提起・追行が 不法行為となるとはいえない。
(2) 小括
以上によれば,請求2−1に係る訴えの準拠法をいずれの地とした場合 でも,日本法によれば,被控訴人による別件米国訴訟の提起及び追行につ き,控訴人に対する不法行為は成立しない以上,損害賠償その他の処分の 請求をすることはできない。 したがって,その他の点について判断するまでもなく,請求2−1は理 由がない。
5 請求2−2に係る訴えの準拠法(争点2)及び本件許諾契約に基づく被控訴 人の控訴人に対する本件各特許権不行使債務の不履行の有無(争点7)につい て
(1)準拠法について
本件許諾契約には,その成立及び効力に係る準拠法を明示的に定めた規定 はない。もっとも,本件許諾契約により参加人に対する独占的通常実施権の 許諾を行う被控訴人は,日本に主たる事務所を有する日本法人であること等 を踏まえれば,本件許諾契約の効力の準拠法は,その最密接関係地である日 本法とするのが相当である(通則法8条2項,1項)。
(2) 債務不履行の有無について
控訴人は,前記第2の3(4)アのとおり,参加人と被控訴人との間で締結さ れた第三者のためにする契約の効果又は参加人が本件各特許発明について再 実施許諾する権限に基づき控訴人に本件各特許権の再実施を許諾したことに より,控訴人は本件各発明について実施権を有し,被控訴人は控訴人に対し 本件各特許権を行使しない義務を負っているところ,これに反して被控訴人 が別件米国訴訟を提起したことが控訴人に対する債務不履行となると主張す る(なお,控訴人のこの点に係る請求は,被控訴人が別件米国訴訟を提起, 追行したことにより生じた弁護士費用相当額の損害賠償である。)。 しかし,控訴人の特許権者の実施権者に対する提訴が債務不履行となると すれば,それは実質的には訴権の放棄に等しい効果をもたらすものであるか ら,特許権者が実施権者に不提訴義務を負うことが前提となるというべきで ある。仮に参加人からの機械装置の購入者が,本件許諾契約に基づき,本件 各特許発明について実施権を取得し,それが被控訴人に主張できるものであ るとしても,そのことは,被控訴人が購入者に対し差止請求権や損害賠償請 求権を行使して訴えを提起しても,抗弁が成立して請求が棄却されることを 意味するだけで,当然に被控訴人に参加人からの機械装置の購入者に対する 訴えの提起をしない義務を負わせるものとはいえない。 本件許諾契約には,参加人から機械装置を購入して本件各特許発明(製法 特許)を実施した者に対する不提訴義務が規定されていないことはもちろん, 参加人に対する不提訴義務についても規定されていない。事情が変更する可 能性があり,様々な形態をとり得る特許権者と実施権者ないし実施権者から\nの機械装置の購入者の将来の紛争について,明文の規定もなく不提訴の合意 があったと軽々に認めることはできない。控訴人は本件許諾契約の当事者で はなく,当時存在もしていなかったのであるから(控訴人の成立は,原判決 第2の1(1)アのとおり,2008年〔平成20年〕4月頃である。),なお さら,本件許諾契約が控訴人に対する不提訴義務を定めていると認めること はできない。その他に,本件において,不提訴の合意があったことを裏付け るに足りる事情は見当たらない。 したがって,その他の点について判断するまでもなく,本件において被控 訴人の控訴人に対する不提訴義務は認められず,被控訴人が別件米国訴訟の 提起をしたことについて,債務不履行が成立する余地はないというべきであ る。
(3) 小括
以上のとおり,被控訴人が別件米国訴訟を提起したことについて債務不履 行は認められず,請求2−2は理由がない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 裁判手続
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2022.01. 6
令和3(ワ)12332 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年10月15日 東京地方裁判所
上記認定事実によれば,本件アカウントにログインした者が本件各投稿をす ることによって,下記2において説示するとおり,原告の権利を侵害したもの と認めるのが相当である。そうすると,ログインに関する本件発信者情報は, 上記侵害の行為をした発信者を特定する情報であるといえるから,「権利の侵 害に係る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。 これに対し,被告は,本件発信者情報が本件アカウントにログインした者の 情報にすぎず,本件各投稿を行った本件発信者の情報ではないことからすると, 本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと主張する。 しかしながら,本件発信者情報は本件各投稿を行った本件発信者の情報であ るといえることは,上記において説示したとおりであり,被告の主張は,その 前提を欠く。のみならず,プロバイダ責任制限法4条の趣旨は,特定電気通信 による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバ シー,表現の自由,通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通\n信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し て発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより,加害者の 特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにある(最高裁平成21年\n(受)第1049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676 頁参照)。そうすると,アカウントにログインした者が,権利の侵害に係る情 報を送信したものと認められる場合には,侵害情報の送信時点ではなく,アカ ウントにログインした時点における発信者情報であっても,「権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。そうすると,被告の 主張は,上記判断を左右するに至らない。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2022.01. 6
令和1(ワ)15716等 競業行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年10月29日 東京地方裁判所
証拠(乙4,75)及び弁論の全趣旨によれば,原告商標は被告ら標章1 と同一であること,Bは,遅くとも,母であるDが亡くなった平成19年以 降,本件商号を用いて貸画廊を運営しており,平成21年以降は,被告ら標 章1を使用していたこと,原告において本件営業譲渡契約が締結されたと主 張する平成27年2月当時,本件商号及び被告ら標章1には原告独自の信用 が化体しておらず,むしろ,それらが正当に帰属すべきはBであったと認め られる。
これに対し,原告は,本件営業譲渡によって,Bから本件商号を含め本件 画廊に関する全ての権利を譲り受けていると主張するが,前記1のとおり, 本件営業譲渡契約の成立は認められないから,平成30年1月30日の原告 商標の登録出願がされた時点においても,本件商号及び被告ら標章1に原告 独自の信用が化体していたとは認められず,これらが正当に帰属すべきはB であったと認めるのが相当である。 そうすると,原告が,Bに対して,原告商標権に基づく差止及び廃棄請求 並びに商標権侵害による損害賠償請求を行うことは,権利の濫用に該当して 許されないというべきである。また,弁論の全趣旨によれば,被告会社は, Bが代表者を務め,Bと一体になって被告ら標章1を使用しているものと認\nめられるから,原告が,被告会社に対して,原告商標権に基づく差止及び廃 棄請求を行うことも,同様に権利の濫用に該当するというべきである。
2022.01. 5
平成31(ネ)10008 不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和3年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記第2の2で判示したとおり被告サイト1には本件表示1〜6が記載されているほか,前記1(2)アで認定した記載がされている。 不妊治療において,治療用の器具を使用する際は,当該器具の使用方法に従うこ とは当然であることを考慮すると,被告サイト1の上記記載を閲覧した医療関係者 は,被告サイト1に記載された本件表示1〜6は,医療関係者が,クライオテック法のプロトコールを遵守して,被告製品を使用して正常な卵子,胚及び胚盤胞,す\nなわち,臨床において使用可能な卵子,胚及び胚盤胞(以下「正常な卵子」などという。)の凍結保存をした場合,融解後の生存率は100%となるという意味であ\nると認識するものと認められる。
・・・
ア 控訴人は,令和2年9月7日,法7条に基づき,平成30年7月26日 から令和2年7月31日までの間の1)貸借対照表・損益計算書・法人事業概況説明書を含む決算報告書,2)営業報告書,3)確定申告書控え(添付書類を含む),4)総 勘定元帳,5)売上元帳,6)仕入元帳を提出対象の書類とし,上記期間の被告製品に よって乳児が出生される年間の件数は2万8333件であること,乳児一人の出生 に必要な被告製品一式の販売価格は7733円であること及び被告製品の利益率は 70%であることを証すべき事実として,書類提出命令の申立てをしたところ,当裁判所は,同年10月9日,送達日から14日以内に上記申\立てに係る書類の提出を命じる旨の決定をしたが,被控訴人は,提出期限までに上記の各書類を提出しな かった。 そして,上記の各書類の記載に関して具体的な主張をすること及び上記の各書類 によって証明すべき事実を他の証拠によって証明することは,著しく困難であると 認められる。
したがって,民訴法224条3項により,控訴人が,被告広告によって受けた損 害の賠償請求期間として主張している平成27年7月26日から令和2年7月31 日までの間における被告製品によって乳児が出生される年間の件数は2万8333 件であること,乳児一人の出生に必要な被告製品一式の販売価格は7733円であ ること及び被告製品の利益率は70%であることは真実と認められる。 なお,前記2〜4のとおり,被告広告に本件記載部分を含む本件各表示を表\示す る行為は,法2条1項20号の不正競争に当たり,被控訴人は,同不正競争につい て,控訴人に対し損害賠償責任を負うものと認められるところ,上記の書類提出命 令に係る書類は,いずれも,被控訴人の上記不正競争によって控訴人の受けた損害 を算定するために必要であること,被控訴人は,上記書類の提出によって受ける損 害について特段の主張をしていないことからすると,上記の書類提出命令について, 被控訴人において,書類の提出を拒む正当な理由があるとは認められない。 イ 被控訴人は,被告製品を購入した者は,被告製品を実際に使用してみて 購入したのであり,被告広告に接したことによって被告製品を購入したのではない こと,被告製品の性能,品質は原告製品よりも優れていること,控訴人の売上げ,利益は減少していないことを理由に,被控訴人は,被告広告によって利益を受けた\n事実は認められないと主張する。 しかし,前記アのとおり,法5条2項の「侵害の行為により・・・受けてい る・・・利益の額」は,侵害行為と相当因果関係のある利益を意味するのではなく, 侵害者が得た利益の全額を意味するのであり,本件においては,上記「利益の額」 は,本件記載部分を含む本件各表示を掲載した被告広告を表\示している期間中に, 本件各表示によってその品質等が示されている被告製品を販売したことによって被控訴人が受けた利益の全額であるというべきであるから,被控訴人の上記主張は理\n由がない。
(3) 推定の覆滅について
ア 前記1(3)のとおり,被控訴人の営業活動は,主に,営業担当者が被告 製品の購入が見込まれる不妊治療施設を訪問して行うというものであるから,その ような営業活動において,被告広告が利用されることがあるとしても,被控訴人の 営業活動にとって,広告の占める程度は小さいといえる。 しかし,そうであるとしても,被告広告に記載された本件各表示に接することにより,被告製品の購入を検討するようになり,前記1(3)のとおり,所属の培養士 を技術講習会(ワークショップ)に参加させ,その結果,被告製品を購入する不妊 医療施設が存在するものと推認され,このような意味において,本件各表示は,被告製品の購入動機に影響を与えている場合があるというべきである。もっとも,そ\nの場合であっても,技術講習会(ワークショップ)における被告製品の使用感等が 被告製品を購入しようとの意思決定をするに当たって重視されるものと考えられる から,本件各表示の影響は相当程度限定的であるというべきである。また,本件製品は継続的に使用されるものであるから,原告製品や被告製品の販\n売の多くは,既に,同製品を購入して,同製品を使用している不妊医療施設に対す るものであると認められるところ,「生存率100%」が実現できるかは,客観的 に判明し,被告製品を使用している者にとっては,その真偽を比較的容易に認識し 得るといえることからすると,被告製品を継続的に購入し,使用している不妊医療 施設が購入の更なる継続をしようとの意思決定をするに当たっては,「生存率10 0%」などの本件記載部分に影響を受けることはないというべきである。 以上の事情を総合考慮すると,被告製品の売上げに対する被告広告の貢献の程度 は,かなり小さいといわざるを得ない。
また,前記1(9)のとおり,日本において販売されている本件製品のほとんどは, 原告製品又は被告製品であるが,海外においては,原告製品と被告製品が競合して いるインドのシェアは,被告製品が18%,原告製品が54%であり,原告製品と 被告製品が競合しているロシアのシェアは,被告製品が15%,原告製品が60% である。そうすると,法5条2項の推定が一部覆滅され,その割合は95%であると解するのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成30(ワ)22646
以上によれば,研究報告1ないし5によっては,手順を厳密に遵守して被
告製品を用いて卵子を凍結保存し融解したとしても100%の生存率を達成
することができないとは認めるに足りず,他にこれを認めるに足りる証拠も
ないから,被告から提出された証拠(乙4ないし10)の内容も考慮すれば,
本件記載部分を含む本件各表示が被告製品の需要者である医療関係者や研究者をしてその品質等を誤認させるおそれがあるとは認めるに足りない(なお,\n本件記載部分の表現については,紛争予\防の観点から,研究報告1ないし5
の内容も踏まえ,より慎重に検討することが望まれる。)。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2022.01. 5
平成31(ワ)2534 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年11月11日 大阪地方裁判所
ア 著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,\n美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(法2条1項1号)。したがって,著作 物といえるためには,思想又は感情を表現したものであること,その表\現に創作性 があること,文学,学術,美術又は音楽の範囲に属するものであることを要する。
イ 前提事実及び前記認定に係る各事実によれば,原告は,旧展示システムから の移行として本件展示システムを構築するに当たり,本件購入契約及び本件構\築契 約に基づき,本件展示システムの機能を実現するために必要な機能\を選定し,性能,\nセキュリティ対策ないし費用等の面から必要かつ最適と考えるサーバ機器及びネッ トワーク機器等を,その組合せも踏まえた上で選定し,各機能等を分担させて本件\n展示システムを構築することとして,本件サーバ設計書を改訂し,これに基づき,\n本件展示システムを構築したことが認められる。\nもっとも,本件サーバ設計書と本件展示システム自体とはその表現形式を異にす\nることから,本件展示システムの著作物性の有無は,本件サーバ設計書の著作物性 とは別個に検討する必要がある。すなわち,本件展示システム自体につき著作物性 が認められるためには,本件サーバ設計書を離れてなお固有の創作性が認められる 必要がある。 しかるに,本件展示システム自体は,いわば本件サーバ設計書の記載 を技術的・機械的に具体化したものにとどまるものというべきであって,固有の創 作性があると見るべき部分に関する具体的な主張立証はない。そうである以上,本 件展示システム自体をもって創作的な表現と見ることはできない。\nしたがって,本件サーバ設計書の表現の創作性すなわち著作物性の有無に関わり\nなく,本件展示システム自体をもって著作物ということはできない。
ウ これに対し,原告は,本件展示システムは本件サーバ設計書とは独立して外 部に表出された著作物である旨などを主張する。\nしかし,本件展示システムが本件サーバ設計書の記載のとおりに構築されたもの\nであることは,原告自身も認めるところである。原告が本件展示システム自体の創 作性の表現として縷々主張するものも,本件サーバ設計書の記載に基づき実現され\nているものと理解されるのであって,前記のとおり,これを離れて本件展示システ ムに固有の創作性があると見るべき部分についての具体的な主張立証はない。また, 本件保守管理仕様書には「生物情報データベースフォーマット,及び,WebGIS」 の著作権が原告に帰属する旨の記載があるものの,著作物性の有無は当事者間の契 約条項の記載によって決定されるものではない。そもそも,上記記載が示すものと 本件展示システム自体との関係性に関する具体的な主張立証はなく,両者の異同そ の他の関係性は不明というほかない。 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても,この点に関する原告の主張は採用 できない。
(3) 小括
以上のとおり,本件展示システム自体の著作物性は認められない。したがって, 原告は,本件展示システム自体に係る著作者人格権(同一性保持権)を有しないか ら,その余の点を論ずるまでもなく,被告に対する著作者人格権に基づく差止及び 廃棄請求権を有しない。
ア 本件サーバ設計書1頁にはネットワーク構成図等が記載されているところ\n(前記1(1)エ(イ)),本件展示システムが ADSL 回線と本件ルータを接続すること により外部ネットワークと接続することは,本件購入仕様書及び本件構築仕様書に\nも,システム構成として記載されている。また,同頁記載の各端末に割り当てられ\nたグローバル IP アドレスは,本件サーバ設計書を見ずとも,所定の手順を履践す ることにより確認可能なものである。また,本件サーバ設計書15頁には,「項目\n名設計」の項に本件ルータの初期パスワード及び変更後パスワードが記載されてい るところ(前同),このうち,初期パスワードは本件説明書にも記載がある。さら に,本件サーバ設計書17頁には,「ルータ・ファイアウォール設定コマンド」の 項の「パケットフィルタリング」に関する記載があるところ(前同),本件展示シ ステムにおいてファイアウォール機能がパケットフィルタリングにより行われるこ\nとは,本件購入仕様書及び本件構築仕様書にも記載されている。加えて,本件ルー\nタがファイアウォール機能を有することやそのファイアウォールポリシーの詳細な\n設定情報,ルータの設定コマンド等は一般に公開されている(乙1,3〜5)。し かも,「パケットフィルタリング」記載の設定方法は,メーカーが一般に公開して いる設定例集(乙5)記載の設定例と,サーバの IP アドレスを異にするに過ぎな い。
そうすると,本件展示システムにつき外部との接続を遮断するために必要な情報 のうち,本件サーバ設計書を参照しなければ被告及び外部業者が把握し得ないもの は,本件ルータの変更後パスワード及び開放されているポート番号である。これに, 確認に所定の手順を要するIPアドレスをも含むとしても,サーバのIPアドレス及 び本件ルータの変更後パスワードは,本件展示システムに固有のものと思われるこ とから,これらの情報が第三者との関係で秘密として保持されることにつき,原告 にとっての有用性ないし固有の利益があるとは考え難く,少なくともこれがあるこ との具体的な主張立証はない。また,本件サーバ設計書17頁には,開放済みポー ト番号として本件閉鎖行為により閉鎖された80,25及び53のほか,110, 143,123も記載されているが,これらも含め,いずれも代表的なポート番号\nとされるものであるから(乙14),これらの情報についても,秘密として保持さ れることにつき原告にとっての有用性ないし固有の利益があるとは考え難い。 そうすると,被告の外部業者に対する本件開示行為(本件サーバ設計書1頁,1 5頁及び17頁の開示)につき,原告の法的に保護すべき権利ないし利益を侵害す るものとはいえない。 したがって,本件開示行為をもって,被告による国家賠償法上の違法行為と認め ることはできない。
イ これに対し,原告は,本件開示行為により,本件サーバ設計書記載の原告の 秘密情報を保持する権利ないし利益が侵害された旨及びこれにより本件展示システ ムの基となっている基礎システムを使用する他の顧客のシステムについてセキュリ ティ対策を施す必要が生じ,損害を受けた旨などを主張する。 しかし,前記のとおり,本件開示行為により開示された情報は,いずれも公開さ れたものであるか,原告にとって有用性ないし固有の利益がある情報とはいえない。 また,損害の点についても,他の顧客に対する連絡・周知文書や対策として調達し たとする機器の購入の裏付資料といった客観的な証拠はない。 その他原告が縷々主張する事情を考慮しても,この点に関する原告の主張は採用 できない。
2022.01. 5
令和3(ネ)10057 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月17日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
控訴人は,1)平成22年6月24日,3本スリットフィンの風上側 のスリットをなくすことにより座屈強度の向上を図ることができること を着想し,同日,Eに対し,フラットフィンの強度計算をFにしてもら うように指示し,その後,2本スリットフィンの座屈強度計算もFにし てもらうように指示したこと,2)その結果,2本スリットフィンの座屈 強度は当初フィンの2.5倍で,フラットフィンとほぼ同一であったが, Eは,2本スリットでは伝熱性能が低下するとして,3本のスリットを\n風下側に押し込めることを提案し,控訴人はこれを承諾したこと,3)そ の後,控訴人及びEによる試験を経て,同年7月下旬頃,本件発明が完 成したことを主張する(本判決による補正後の原判決4頁21行目から 5頁20行目まで)。
(イ) そこで,前記(ア)の控訴人の主張について検討する。
控訴人は,控訴人メール1において,Eに対し,フラットフィンの座 屈強度の解析を指示し,Eは,Eメールにより,●(省略)●を報告し た。しかし,それらの●(省略)●に記載されていたものであり(前記 (3)ケ(イ)),このうち●(省略)●に提出されたものであり(前記キ),E らが住環研において●(省略)●を示すものであった。
また,控訴人は,Eメールに対して返信した控訴人メール2において, ●(省略)●と記述したが,これは,Eメールに示された●●を見て, 控訴人がその時に,●(省略)●と認識したというにとどまるものと認 められ,それをもって,控訴人が,Eらに先んじて,当初フィンを2本 スリットフィンに変えることを着想したとはいえない。 さらに,控訴人がEに対して2本スリットフィンの座屈強度計算を指 示したことを認めるに足りる証拠はなく,Eが3本のスリットを風下側 に押し込めることを提案し,控訴人がこれを承諾したこと,その後,控 訴人及びEによる試験を経て,平成22年7月下旬頃,本件発明が完成 したことなどの控訴人の主張に係る事実を認めるに足りる証拠もない。 そうすると,仮に,伝熱性能を確保しつつ座屈強度を向上させるため\nに2本スリットフィンとすることが本件発明の特徴的部分に係る着想で あるとしても,控訴人がそれを着想したとは認められず,控訴人は,本 件発明の発明者とは認められない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> 職務発明
>> ピックアップ対象
2022.01. 5
令和2(ワ)10386 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和3年11月25日 大阪地方裁判所
ウ 原告商品1−1と被告商品との共通点及び差異点
原告商品1−1と被告商品の各形態を対比すると,原告商品1−1の基本的形態 の全て及び具体的形態 T1-1-3 と,被告意匠の基本的形態の全て及び具体的形態 t3 が 共通点であり,それ以外の形態が差異点であると認められる。 すなわち,原告商品1−1と被告商品の各形態とは,差異点2)’,3)’,5)’〜12)’の ほか,具体的形態 S1-1-3 と s3 につき,原告商品1−1では,中空部中央に位置する 円形板から細い48本の直線状のファンガードが放射状に円筒状中空部下面とほぼ 面一に形成されている(S1-1-3)のに対し,被告商品では,中空部中央に位置する円 形板から細い36本の湾曲線状のファンガードが放射状に円筒状中空部下面とほぼ 面一に形成されている(s3)点で相違する(差異点 C)。
エ 検討
原告商品1−1と被告商品の各形態の差異点のうち,差異点2)’,3)’,6)’〜10)'及 び C は,原告意匠と被告意匠の差異点2),3),6)〜10)及び A と同じである。そうで ある以上,少なくとも差異点3)’,6)’,8)’,9)’及び C については,原告意匠と被告意匠とが差異点3),6),8),9)及び A により異なる美感を生じるのと同様に,原告 商品1−1と被告商品の各形態につき,需要者に異なる美感を生じさせるものとい える。また,これらの差異点の存在にもかかわらずなお両商品の形態が酷似し,実 質的に同一というべき事情は見当たらない。 したがって,原告商品1−1と被告商品の各形態は実質的に同一であるとは認められないから,被告商品は,原告商品1−1の形態を模倣したものということはできない。これに反する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2022.01. 4
令和2(ネ)10029 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 原告は,1)本件発明1の「該平均重合度が,該セルロース粉末を塩酸2. 5N,15分間煮沸して加水分解させた後,粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より5〜300高いこと」との要件(差分要件)は,「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず, 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は,いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって,実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること,BATTIST A論文の記載に照らすと,「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると,本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から,差分要件の数値範囲において,本件発明の 1の課題を解決できると当業者が認識することはできない,2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は,「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より100低いと仮定した場合,実施例2ない し6において示されている差分の範囲は150〜255であり,その下限 値は150であること,差分5ないし10という数値は,粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり,実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと,当業者は,差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると,本件明細 書記載の差分が150以上の実施例のデータのみをもって,測定誤差のレ ベルである差分5ないし10を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明1の課題を解決できると認識することはできないとして, 本件発明1はサポート要件に適合しない旨主張するので,以下において判 断する。
(ア) 本件発明1の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,本件発明1の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが,本件明細書の【0 015】に,「本発明でいうレベルオフ重合度とは2.5N塩酸,沸騰温 度,15分の条件で加水分解した後,粘度法(銅エチレンジアミン法) により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は,本件発明1の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから(前記6(1)イ),本件発明1の「レベルオフ重合度」とは,2. 5N塩酸,沸騰温度,15分の条件で加水分解した後,粘度法(銅エチ レンジアミン法)により測定される重合度」をいうものと解される。 なお,本件明細書の【0015】には,レベルオフ重合度に関し,「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると,酸が浸透しうる結晶 以外の領域,いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため,レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており(I NDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMIST RY,Vol.42,No.3,p.502−507(1950)),その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を2.5N塩酸,沸騰温度,15分 の条件で加水分解した時,重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき,重合度の低下が起きれば,レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を2.5N塩酸,沸騰温度,15分の条件で加水分解した時, 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき, 重合度の低下が起きれば,レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は,本件出願当時,「レベルオフ重合度」とは,セルロースを 酸加水分解すると,その重合度は,酸加水分解初期に急激に200−3 00に低下した後ほぼ一定になり,このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと(前記(1)イ(ア))に照らすと,レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
a 本件明細書には,実施例2ないし7及び比較例1ないし11のセル ロース粉末について,それぞれの原料パルプ(市販SPパルプ,市販 KPパルプ等)のレベルオフ重合度が記載されている(【0039】な いし【0047】)。 前記(1)イ(ア)のとおり,本件出願当時,酸加水分解時に,非結晶部 分は酸で分解されやすいが,結晶部分は分解されず残り,残った部分 の化学構造と結晶構\造は,原料セルロースのままであって,分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると,本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は,原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和2年9月11日付け意見書(乙72) 中には,「3桁のLODPを報告するときの有効数字は2桁とするのが 一般的であるが,実際のところ,2桁目,3桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので,LODPについて十の桁,一の桁を議\n論することは技術的に意味がない。そして,同一のセルロースでもL ODPは酸加水分解条件等によって変化することも常識である,その ため,例えば,市販の木材パルプのLODPを測定したとしても,そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のLODP については,やはり実際に測定してみなければわからず,原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか,具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら,他方で,上記意見書中には,「LODPとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間(・・・)経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や,「BATTI STA論文でも同様であるが,「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に,例えば,「平均重合度が下がりきっている(これ以上全く低下し ない)」という含意はない。」,「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも2時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」,「こうした変化も含めて200 〜300程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると,上記意見書の上記記載部分は,市販の木材パ ルプのLODPとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のLODPとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で,木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のLODPについては,原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから,上記記 載部分によって,本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
b 加えて,本件明細書の表4には,実施例2ないし7及び比較例1な\nいし11のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると, 本件明細書に接した当業者は,上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また,本件明細書の表4には,「平均重合度」,「粒子の平均L/D(長\n径短径比)」,「平均粒子径」,「見掛け比容積」,「見掛けタッピング比容 積」,「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」(差分 要件)のいずれもが本件発明1の数値範囲内にある実施例2ないし7 のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明1の数値 範囲外である比較例1ないし11とのセルロース粉末の円柱状成形体 について,平均降伏圧[MPa],錠剤の水蒸気吸着速度Ka,硬度[N] 及び崩壊時間[秒]が示されている。 そして,実施例2ないし7のセルロース粉末は,いずれも,安息角 が55°以下,錠剤硬度が170N以上,崩壊時間が130秒以下で あり,ここで,安息角は,55°を超えると,流動性が著しく悪くな り(【0018】),錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり,1 70N以上が好ましく(【0019】),崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり,130秒以下が好ましい(【0019】)のであるか ら,実施例2ないし7のセルロース粉末は,成形性,流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ\nができる。
したがって,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から,実施例2ないし7のセルロース粉末は, 本件発明1の課題を解決できると認識できるものと認められるから, 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には,「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子L/Dが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」(【0015】),「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては,5〜300程度であることが 好ましい。さらに好ましくは10〜250程度である。5未満では粒子 L/Dを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。300を超えると繊維性が増して崩壊性,流動性が悪くなって 好ましくない。」(【0016】),「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと,製造工程における攪拌操作で粒子L/D が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し,L/Dが小さくなるので,乾燥前の粒子 の平均L/Dを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」(【0021】)との記載がある。 これらの記載から,セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと,乾燥前のセルロース粒子のL/Dが低下しやすく,そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して,得られるセルロース粉末 のL/Dが小さくなり,L/Dが小さくなると,成形性が低下すること を理解できる。 そして,本件発明1の差分要件は,レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを,セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分(差分要件)で表し,その下限を「5」としたこ\nとを理解できるから,当業者は,本件発明1の差分要件の数値範囲の全 体にわたり,本件発明1の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって,2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から,当業者は,本件発明1の差分要件の数値範囲の全体に わたり,本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また,これと同様の理由により,本件発明2も,発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。
◆判決本文
1審はこちら
◆東京地裁平成29年(ワ)24598号
キ 以上によれば,本件差分要件は,粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるところ,明細書の発明の詳細な説明には,実施例について,粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく,また,優先日当時の技術常識によっても,それが記載されているに等しい とはいえない。したがって,本件明細書の発明な詳細には,本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。そうすると,本件明細書の発明な詳細において,特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2022.01. 4
令和1(ワ)30282 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年11月29日 東京地方裁判所
前記1(1)イ(ア)のとおり,原告は,従前から使用していたブランド である「Attractions」に係る原告標章を商標登録しよう と考え,本件弁理士に対し相談したところ,本件登録商標の存在が判 明したため,その取消請求をすることとした。こうした経緯に照らす と,原告は,今後「Attractions」のブランドを事業展開 するに当たり,原告標章の使用が本件商標権を侵害するおそれがあっ たことから,それを避けることを目的として上記取消請求をすること としたものと認められる。
また,証拠(原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,I\nBEX社との和解交渉が難航していたことや,原告代理人から,IB EX社が原告に対し保全命令を申し立て,原告の商品が差し押さえら\nれるなどする可能性があるとの説明を受けたことなどを契機として,\n平成29年7月末頃から「Attractions」のブランドの使 用を取り止めることを選択肢の一つとして検討し始めたこと,同年8 月8日頃にIBEX社から本件連絡書の送付を受けたため,「Att ractions」のブランドの使用を取り止め,別ブランドに変更 することを決定したこと,さらに,同年9月1日以降,実際に「At tractions」の商標を切り替える対応を採り,商標を切り替 えることができない本件在庫商品については販売の停止を決定したこ とが認められる。
さらに,前記(1)ア(ア)のとおり,平成28年9月1日から平成29 年8月31日までの会計年度における原告の売上高は1億0794万 2353円であると認められるのに対し,前記(1)ア(イ)のとおり,平 成29年8月31日の時点において原告が保有していた本件在庫商品 の販売価額は合計2875万7760円であると認められるから,こ れらの数値を基礎とすれば,本件在庫商品が原告の総売上高に占める 割合は26%余りであることになる。 以上のように,原告は,そもそも本件商標権を侵害するリスクを避 けるために本件審判請求事件に係る請求をしたところ,IBEX社が これを争い,同社の主張に沿う外観の証拠が提出され,その一方でI BEX社との手続外での和解交渉が難航していたことからすると,遅 くとも平成29年7月頃には,本件在庫商品を販売することにより本 件商標権を侵害し,原告の商品が差し押さえられるなどするリスクを 相当程度具体的に認識していたと認められる。そして,本件在庫商品 が原告の総売上高に占める割合が26%余りであったことからすると, これが差し押さえられた場合には原告の経営に大きな影響を及ぼす可 能性があったと認められる。こうした中で,本件連絡書を送付され,\nIBEX社から同年8月18日までの回答を迫られたという経緯に照 らせば,原告において,同年9月1日以降に「Attraction s」のブランドの使用を取り止めるという判断をするのはやむを得な いものであったというべきである。
以上によれば,IBEX社の前記1(2)の不法行為と原告の損害と の間に相当因果関係が認められることはもとより,被告に認められる 善管注意義務違反が,IBEX社の代表取締役としての権限を行使す\nることなく,Bらに業務を任せきりにし,IBEX社による上記不法 行為を惹起したというものであることに照らすと,被告の任務懈怠と 原告の損害との間にも相当因果関係があると認めるのが相当である。 b これに対し,被告は,原告が商標を切り替える対応を採り,本件在 庫商品の販売を取り止めるという行為に及んだのは,原告自身の経営 判断によるものであるとして,被告の任務懈怠と原告の損害との相当 因果関係は認められないと主張する。 しかし,原告の上記行為が経営判断に基づくものであるとしても, 前記 a で説示したとおり,それはやむを得ないものであったというこ とができ,むしろ,経営判断として合理的かつ自然なものであるとい うべきであるから,原告の経営判断が介在したことをもって,被告の 任務懈怠と原告の損害との間の相当因果関係を否定することはできな い。したがって,被告の上記主張を採用することはできない。 c また,被告は,IBEX社の経営を実質的に支配していたのはBで あり,被告がBの判断を翻意させることはできなかったから,被告の 任務懈怠と原告の損害との間には相当因果関係は認められないと主張 する。 しかし,前記1(1)アのとおり,被告は,Bの大学の同級生であり, IBEX社の経営会議やBとF弁護士との打ち合わせに同席するなど, 代表取締役として一応の役割を果たしていた。また,被告は同社の代\n表取締役であり,被告の他に同社には役員が選任されていなかったの\nであるから,法的には同社の業務に関する一切の権限を被告のみが有 しており,同社の代表取締役として,主体的に行動することは可能\で あったというべきである。したがって,被告は,IBEX社の一連の 不法行為により原告が損害を被ることについても,これを阻止するこ とができなかったとまではいえない。
以上によれば,被告が代表取締役としての任務を懈怠することなく,\n原告に不法行為による損害を与えないようにする善管注意義務を果た し,本件審判請求事件や本件仮処分命令申立て等について適切に対処\nしていれば,原告が主張する損害が発生していなかったということが できる。 してみると,IBEX社の経営をBが実質的に支配していたことか ら直ちに被告の任務懈怠と原告の損害との間の相当因果関係が否定さ れるものではなく,被告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.01. 4
平成27(ワ)547 不正競争行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成29年1月19日 大阪地方裁判所
被告のウェブサイトの html ファイル上の前記前提事実(4)ウ記載のコードのう ち,「<meta name=″keywords″content=″バイクリフター″>」との記載は,い わゆるキーワードメタタグであり,ユーザーが,ヤフー等の検索サイトにおいて, 検索ワードとして「バイクリフター」を入力して検索を実行した際に,被告のウェ ブサイトを検索結果としてヒットさせて,上記(1)のディスクリプションメタタグ 及びキーワードタグの内容を検索結果画面に表示させる機能\を有するものであると 認められる。このようにキーワードメタタグは,被告のウェブサイトを検索結果と してヒットさせる機能を有するにすぎず,ブラウザの表\示からソース機能\をクリッ クするなど,需要者が意識的に所定の操作をして初めて視認されるものであり,こ れら操作がない場合には,検索結果の表示画面の被告のウェブサイトの欄にそのキ\nーワードが表示されることはない。(弁論の全趣旨)\n
ところで,商標法は,商標の出所識別機能に基づき,その保護により商標の使用\nをする者の業務上の信用の維持を図ることを目的の一つとしている(商標法1条) ところ,商標による出所識別は,需要者が当該商標を知覚によって認識することを 通じて行われるものである。したがって,その保護・禁止の対象とする商標法2条 3項所定の「使用」も,このような知覚による認識が行われる態様での使用行為を 規定したものと解するのが相当であり,同項8号所定の「商品…に関する広告…を 内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」というのも,同号 の「広告…に標章を付して展示し,若しくは頒布し」と同様に,広告の内容自体に おいてその標章が知覚により認識し得ることを要すると解するのが相当である。 そうすると,本件でのキーワードメタタグにおける原告商標の使用は,表示され\nる検索結果たる被告のウェブサイトの広告の内容自体において,原告商標が知覚に より認識される態様で使用されているものではないから,商標法2条3項8号所定 の使用行為に当たらないというべきである。
これに対し,原告は,インターネットの検索サイトの利用者がサーチエンジンに キーワードとして原告商標を入力した際にサーチエンジンを通じて被告ホームペー ジでのメタタグ表記を視認しているといえることから,被告による原告商標のメタ\nタグ使用は,商標的使用に当たると主張する。しかし,検索サイトにおける検索キ ーワードと検索結果との関係にさまざまな濃淡があることは周知のことであること からすると,検索結果画面に接した需要者において,検索キーワードをもって,検 索結果として表示された各ウェブサイトの広告の内容となっていると認識するとは\n認め難いから,検索キーワードの入力や表示をもって,キーワードメタタグが,被\n告のウェブサイトの広告の内容として知覚により認識される態様で使用されている と認めることはできない。
(3) よって,被告標章1のディスクリプションメタタグないしタイトルタグへの 記載は商標的使用に当たり,侵害行為であると認められるが,原告商標のキーワー ドメタタグへの使用については,これを商標的使用に当たると認めることはできな いから,侵害行為であるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和3(ネ)10046 著作者人格権等侵害行為差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年12月22日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件懲戒請求書は,一審原告が,弁護士会に対し,一審被告Yに対する 懲戒請求をすること,及び懲戒請求に理由があること等を示すために,本 件懲戒請求の趣旨・理由等を記載したものであって,利用者に鑑賞しても らうことを意図して創作されたものではないから,それによって財産的利 益を得ることを目的とするものとは認められず,その表現も,懲戒請求の\n内容を事務的に伝えるものにすぎないから,全体として,著作物であるこ とを基礎づける創作性があることは否定できないとしても,独創性の高い 表現による高度の創作性を備えるものではない。\n
イ 一審原告自身の行動及びその影響
本件産経記事は,一審原告による本件懲戒請求の後,産経新聞のニュー スサイトに掲載されたものであって,本件懲戒請求書の「懲戒請求の理由」 の第3段落全体(4行)を,その用語や文末を若干変えるなどした上で, かぎ括弧付きで引用していることに加え,証拠(甲2,乙2,6)及び弁 論の全趣旨を総合すれば,一審原告は,産経新聞社に対し,一審被告Yの 氏名に関する情報を含め,本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を自 ら提供したものと推認される。 そうすると,一審原告は,産経新聞社に対し,本件懲戒請求書又はその 内容に関する情報を提供し,それに基づいて,本件懲戒請求書の一部を引 用した本件産経記事が産経新聞のニュースサイトに掲載され,その結果, 後記(2)のとおり,一審被告Yが,ブログにより,本件懲戒請求書に記載さ れた懲戒請求の理由及び本件産経記事の内容に対して反論しなければな らない状況を自ら生じさせたものということができる。
ウ 保護されるべき一審原告の利益
前記2のとおり,本件懲戒請求書は公表されたものとは認められないか\nら,一審原告は,本件懲戒請求書に関して,公衆送信権により保護される べき利益として,公衆送信されないことに対する財産的利益を有しており, 公表権により保護されるべき利益として,公表\されないことに対する人格 的利益を有していたものと認められる。 しかし,本件懲戒請求書の性質・内容(前記ア)を考慮すると,一審原 告が本件懲戒請求書に関して有する財産的利益及び人格的利益は,もとも とそれほど大きなものとはいえない上,一審原告自身の行動及びその影響 (前記イ)を考慮すると,保護されるべき一審原告の上記利益は,一審原 告自身の自発的な行動により,少なくとも産経新聞のニュースサイトに本 件産経記事が掲載された時以降は,相当程度減少していたものと認めるの が相当である。
(2) 一審被告Yによる本件記事1と本件リンクの目的について 前記第2の2(前提事実)によれば,本件記事1の目的は,本件産経記事 により,一審被告Yに対する本件懲戒請求の事実が報道され,一審被告Yに 対する批判的な論評がされたことから,一審被告Yが,自らの信用・名誉を 回復するため,本件懲戒請求の理由及びそれを踏まえた本件産経記事の報道 内容に対して反論することにあったものと認められる。 ところで,弁護士に対する懲戒請求は,最終的に弁護士会が懲戒処分をす ることが確定するか否かを問わず,懲戒請求がされたという事実が第三者に 知られるだけで請求を受けた弁護士の業務上又は社会上の信用や名誉を低下 させるものと認められるから,懲戒請求が弁護士会によって審理・判断され る前に懲戒請求の事実が第三者に公表された場合には,最終的に懲戒をしな\nい旨の決定が確定した場合に,そのときになってその事実を公にするだけで は,懲戒請求を受けた弁護士の信用や名誉を回復することが困難であること は容易に推認されるところである。したがって,弁護士が懲戒請求を受け, それが新聞報道等によって弁護士の実名で公表された場合には,懲戒請求に\n対する反論を公にし,懲戒請求に理由のないことを示すなどの手段により, 弁護士としての信用や名誉の低下を防ぐ機会を与えられることが必要である と解すべきである。
本件においては,前記(1)イのとおり,一審原告が一審被告Yに対する懲戒 請求をしたことに加え,一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情 報を自ら産経新聞社に提供したため,一審被告Yに対して本件懲戒請求がさ れたことが報道され,広く公衆の知るところになったのであるから,一審被 告Yが,公衆によるアクセスが可能なブログに反論文である本件記事1を掲\n載し,本件懲戒請求に理由のないことを示し,弁護士としての信用や名誉の 低下を防ぐ手段を講じることは当然に必要であったというべきである。した がって,本件記事1を作成,公表し,本件リンクを張ることについて,その\n目的は正当であったものと認められる。
(3) 本件リンクによる引用の態様の相当性について
ア 上記(1)及び(2)のとおり,一審被告Yは,本件リンクにより,本件懲戒請 求書の全文(ただし,本件懲戒請求書のうち,一審原告の住所の「丁目」 以下及び電話番号が墨塗りされているもの。)を本件記事1に引用したも のであるが,本件においては,一審原告が自ら産経新聞社に本件懲戒請求 書又はその内容を提供し,産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲 載されたため,一審被告Yは,弁護士としての信用及び名誉の低下を防ぐ ために,ブログに反論文である本件記事1を掲載し,懲戒請求に理由のな いことを示すことが必要となった。 確かに,本件懲戒請求書は未公表の著作物であり,本件産経記事には本\n件懲戒請求書の一部が引用されていたものの,その全体が公開されていた ものではないが,懲戒請求書の理由の欄には,その全体にわたって,懲戒 請求を正当とする理由の主張が記載されていたから(甲2),一審被告Yと しては,本件記事1において本件懲戒請求書の要旨を摘示して反論しただ けでは,自分に都合のよい部分のみを摘示したのではないかという疑念を 抱かれるおそれもあったため,その疑念を払拭し,本件懲戒請求の全ての 点について理由がないことを示す必要があり,そのためには,本件懲戒請 求書の全部を引用して開示し,一審被告Yによる要旨の摘示が恣意的でな いことを確認することができるようにする必要があったものと認められ る。 また,一審被告Yは,本件記事1に本件懲戒請求書自体を直接掲載する のではなく,本件懲戒請求書のPDFファイルに本件リンクを張ることに よって本件懲戒請求書を引用しており,本件懲戒請求書が,本件記事1を 見る者全ての目に直ちに触れるものでなく,本件懲戒請求書の全文を確認 することを望む者が本件懲戒請求書を閲覧できるように工夫しており,本 件懲戒請求書が必要な限りで開示されるような方策をとっているという ことができる。 さらに,本件記事 1 は,本件懲戒請求書とは明確に区別されており,本 件懲戒請求に理由のないことを詳細に論じるものであって,その反論の前 提として本件懲戒請求書が引用されていることは明らかであり,仮に主従 関係を考えるとすれば,本件記事1が主であり,本件懲戒請求書はその前 提として従たる位置づけを有するにとどまる。 そして,前記(1)のとおり,一審原告が本件懲戒請求書に関して有する, 公衆送信権により保護されるべき財産的利益,公表権により保護されるべ\nき人格的利益は,もともとそれほど大きなものとはいえない上,一審原告 自らの行動により,相当程度減少していたから,本件懲戒請求書の全部が 引用されることにより一審原告の被る不利益も相当程度減少していたと 認められるばかりか,一審原告は,自らの行為により,本件懲戒請求書又 はその内容を産経新聞社に提供し,本件産経記事の産経新聞のニュースサ イトへの掲載を招来したものであり,一審原告の上記行為は,本件懲戒請 求があったこと及び本件懲戒請求書の内容を世間に公にするという点に おいて,一審被告Yの弁護士としての信用及び名誉に関して非常に大きな 影響を与えるものであったと認められる。 イ 以上の点を考慮するならば,一審被告Yが,本件リンクを張ることによ って本件懲戒請求書の全文を引用したことは,一審原告が自ら産経新聞社 に本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供して本件産経記事が産 経新聞のニュースサイトに掲載されたことなどの本件事案における個別的 な事情のもとにおいては,本件懲戒請求に対する反論を公にする方法とし て相当なものであったと認められる。
(4) 権利濫用の成否
前記(1)のとおり,一審原告が本件懲戒請求書に関して有する,公衆送信権 により保護されるべき財産的利益,公表権により保護されるべき人格的利益\nは,もともとそれほど大きなものとはいえない上,一審原告自身の行動によ り,相当程度減少していたこと,前記(2)のとおり,本件記事1を作成,公表\nし,本件リンクを張ることについて,その目的は正当であったこと,前記(3) のとおり,本件リンクによる引用の態様は,本件事案における個別的な事情 のもとにおいては,本件懲戒請求に対する反論を公にする方法として相当な ものであったことを総合考慮すると,一審原告の一審被告Yに対する公衆送 信権及び公表権に基づく権利行使は,権利濫用に当たり,許されないものと\n認めるのが相当である。
(5)当事者の主張に対する判断
ア 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は,一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情報 を産経新聞社に提供し,本件懲戒請求書の一部が本件産経記事に引用さ れたとしても,一審原告の公表権を保護すべき必要性が全くなくなった\nわけではなく,他方,一審被告Yは,本件懲戒請求書の要旨又はその一 部を引用することにより一審原告の懲戒請求に対して反論することが可 能であり,本件懲戒請求書の全部を引用する必要がなかったにもかかわ\nらず,これを全部引用して公表したのであるから,一審原告の一審被告\nYに対する公表権の行使は権利濫用に当たらないと主張する。\n しかし,前記(1)ウのとおり,一審原告が本件懲戒請求書に関して公衆 送信権により保護されるべき財産的利益,公表権により保護されるべき\n人格的利益は,もともとそれほど大きなものとはいえない上,一審原告 自身の行動により相当程度減少していたものと認められる。他方,前記 (3)のとおり,一審被告Yは,一審原告が産経新聞社に本件懲戒請求書又 はその内容を提供し,産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲載 されたため,弁護士としての信用及び名誉の低下を防ぐために,本件懲 戒請求書の全文を引用して開示した上で反論する必要があったものであ るから,それらを比較衡量すれば,後者の必要性が前者の必要性をはる かに凌駕するというべきであるから,たとえ一審原告の公表権を保護す\nべき必要性が全くなくなったわけではないとしても,一審原告の一審被 告Yに対する公表権の行使は権利濫用に該当するというべきである。\nしたがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 一審原告は,本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞 社に提供するという一審原告の行為と,本件リンクを張るという一審被 告Yの行為とは,行為の性質やそれによって閲覧可能となる範囲・程度\nが異なり,本件懲戒請求書の内容が拡散する規模は,本件リンクを張る 行為の方が,本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に 提供する行為よりも圧倒的に大きいから,一審原告による公衆送信権及 び公表権の行使は権利濫用に当たらないと主張する。\n しかし,本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提 供するという一審原告の行為は,産経新聞又はそのニュースサイトによ って本件懲戒請求に関する情報が報道されることを意図してされたもの と容易に推認され,実際,産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が 掲載されたものであり,産経新聞が大手の一般紙であって,法律に興味 を有する者に限らず広く公衆がその新聞又はニュースサイトを閲読する ものであることからすると,一審原告の上記行為は,一審被告Yに対す る本件懲戒請求があったこと及び本件懲戒請求書の内容を世間に公にす るという点において,一審被告Yの弁護士としての信用及び名誉に関し て非常に大きな影響を与えるものであったと認められるから,本件懲戒 請求書の内容が拡散する規模において,本件リンクを張る行為の方が, 本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提供するとい う一審原告の行為よりも大きいということはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和2(行ケ)10069 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月9日 知的財産高等裁判所
(ア) 検討
a 甲7発明と本件発明1とは,「1回当たり200単位のPTH(1− 34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする」との用量の 点において一致するが,その投与の対象となる骨粗鬆症患者の範囲を 一応異にする。
b 甲7発明で投与対象とされた患者は,前記(1)のとおり,1989年 診断基準で骨粗鬆症と診断された患者であるところ,甲7発明に接し た当業者が,甲7発明のPTH200単位週1回投与の骨粗鬆症治療 剤を投与する対象患者を選択するのであれば,より新しい基準を参酌 しながらその患者を選別することは,当業者がごく普通に行うことで あるから,1989年診断基準とともに,より新しい,1996年診 断基準又は2000年診断基準を参酌するといえる。 そして,前記ア(ア)b及びcのとおり,1996年診断基準で骨粗 鬆症と診断される者は,1)骨萎縮度I度以上又は骨密度値がYAMの 80%以下の低骨量で非外傷性椎体骨折を有する者か,2)X線上椎体 骨折を認めないが,骨萎縮度II)度以上,又は,骨密度値がYAMの7 0%未満である者であり,2000年診断基準で骨粗鬆症と診断され る者は,3)骨萎縮度II)度以上又は骨密度がYAMの80%未満の低骨 量で,軽微な外力による非外傷性椎体骨折等(脆弱性骨折)を有する 者か,4)脆弱性骨折がないものの,骨萎縮度II)度以上,又は,骨密度 値がYAMの70%未満の者である。
本件条件(2)及び本件条件(3)は,上記1)と同じであるから(「既 存の骨折」は「非外傷性椎体骨折」を含む。),当業者が甲7発明の2 00単位週1回投与の骨粗鬆症治療剤を投与する骨粗鬆症患者を本件 条件(2)及び本件条件(3)で選別するのには何ら困難を要しない。 また,前記ア(イ)のとおり,骨粗鬆症は,加齢とともに発生が増加 するとの技術常識があり,高齢者は加齢を重ねた者であるのは明らか であるところ,高齢者として65歳以上の者を選択するのは常識的な ことであり,高齢者の医療の確保に関する法律32条でも65歳以上 が高齢者とされている。したがって,これらを参酌し,骨粗鬆症によ る骨折の複数の危険因子として,低骨密度及び既存骨折に並んで年齢 が掲げられていることに着目して投与する骨粗鬆症患者を65歳以上 として,本件条件(2)及び本件条件(3)に加えて本件条件(1) のように設定することはごく自然な選択であって,何ら困難を要しな い。
そうすると,甲7発明に接した当業者が,投与対象患者を本件3条 件を全て満たす患者と特定することは,当業者に格別の困難を要する ことではない
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和1(ワ)8905 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月18日 大阪地方裁判所
(ア) 本件明細書の記載によれば,本件明細書においては,「針先の再露出」ない しこれと同旨の意味を含む表現(「針先再露出阻止機構\」等)と「針抜出し」ない しこれと同旨の意味を含む表現(「針抜出阻止機構\」等)がそれぞれ用いられてい る。その上で,「針先の再露出」等の表現は,針先プロテクタが留置針の針先側へ\nの移動位置において針ハブに係止された後に,針先プロテクタが留置針の基端側へ 後退(移動)すること(【0013】,【0027】,【0070】,【0073】)又は留置針 が針先側(先端側)へ前進(移動)すること(【0028】,【0029】,【0034】〜 【0036】)により針先が外部に露出することを意味する場合に用いられている。 他方,「針抜出し」等の表現は,留置針が基端側へ移動し,針先プロテクタの基端\n側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを意味する場合に用いられ るものと理解される(【0022】,【0028】,【0029】,【0034】,【0035】, 【0071】)。
このように,本件明細書では,「針先の再露出」等と「針抜出し」等の表現が明\n確に使い分けられていることを踏まえると,「留置針の針先の再露出」(構成要件\n1D 等)とは,針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において針ハブに係 止された後に,針先プロテクタが留置針の基端側へ後退(移動)すること又は留置 針が針先側(先端側)へ前進(移動)することにより針先が外部に露出することを 意味するものであって,留置針が基端側へ移動し,針先プロテクタの基端側から抜 け落ちることにより針先が外部に露出する場合はこれに含まれないと解される。こ れに反する被告の主張は採用できない。 したがって,「係止片」(構成要件 1D 等)は,上記の意味における「留置針の 針先の再露出」を防止する機構を構\成するものと理解される。構成要件 1E4)等の 「係止片」も,「前記係止片」として構成要件 1D 等を受けたものであることか ら,同様である。
(イ) 「係止片」(構成要件 1E4)等)につき,本件明細書には,針先プロテクタの 大径部側に形成されるものの形状及び機能等に関しては,それが「針ハブに向かっ\nて傾斜した内側面を有し」,「円筒状部と一体形成される」ことを含めて具体的に 記載されている(【0028】,【0034】,【0036】,【0058】,【0059】, 【0061】,【0065】,【0067】〜【0070】,図 9)。これに対し,「小径部側に 設けられ」ない「係止片」に関しては,その形状はもとより,係止片を小径部側に 設けないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害等につい て,本件明細書には何ら記載されていない。
また,本件特許の出願経過を見ると,本件意見書によれば,小径部に設けられて いない係止片の形状につき,原告は「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有」 するものを念頭に置いていると理解する余地もあるものの,本件各発明の進歩性を 主張するに当たり,本件通知書の引用文献2及び4に各記載の「針先プロテクタの 小径部側」に設けられている「係止部」の具体的な形状に言及してはおらず,小径 部に設けられていない係止片の形状についてはもとより,係止片を小径部側に設け ないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害についての言及 もない。そうすると,本件意見書の記載については,原告は,公知の発明と構成が\n異なることを示す趣旨で「係止片」が「小径部側には設けられて」いないことに言 及したに過ぎず,「係止片」の形状に関しては,拡開部の大径部側に設けられた係 止片Sが針ハブに向かって傾斜した内側面を有することを説明するにとどまり,小径 部側に設けられていない係止片に関しては何ら述べていないものと理解される。 このような本件明細書の記載及び本件特許に係る出願経過を参酌すると,「係止 片」(構成要件 1E4)等)につき,「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有 し」とは,「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」「係止片」の形状を 特定したものであって,「前記小径部側には設けられて」いない「係止片」の形状 を特定するものではないと理解される。これに反する原告の主張は採用できない。
(ウ) 小括
以上より,本件各発明の「係止部」とは,「該針先プロテクタに設けられた」も のであり,これが「該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が 防止される」,すなわち,針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において 針ハブに係止された後に,針先プロテクタが留置針の基端側へ後退(移動)するこ と又は留置針が針先側(先端側)へ前進(移動)することにより針先が外部に露出 することを防止するものであって(以上につき,構成要件 1D 等),針先プロテク タの有する「前記円筒状部の基端側に」設けられるものであり(構成要件 1E2) 等),かつ,「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し,前記大径部側に前記 円筒状部と一体形成される」が,その形状のいかんを問わず「前記小径部側には設 けられ」ない(以上につき,構成要件 1E4)等)ものであると解される。
(2) 構成要件の充足性\n
ア 被告各製品の小径部の側壁部の構成等\n
(ア) 被告各製品の小径部側壁部につき,針先保護部(針先プロテクタ)の基端側 に設けられていること,針抜出防止機構(針先プロテクタが留置針の針先側への移\n動位置において針ハブに係止された後に,更に留置針が基端側へ移動し,針先プロ テクタの基端側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを防止する機 構)として機能\すること,及び,少なくとも針管と針先保護部が相対移動してクリ ック感が生じる位置において,小径部側壁部の突端面により針基に設けられた縦リ ブの側面を挟持することで,針基が針先保護部に対して回動を防止する状態となる ことについては,当事者間に争いがない。
(イ) 証拠(甲3〜6,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製品において は,小径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持することで針基の回動を 防止しつつ,針先保護部が初期状態の配置位置から留置針の針先方向へ移動し,小 径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持した状態のまま,クリック感が 生じる位置(「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位 置」(構成要件 1D 等)に相当する。)である針基の受け部において大径部係止手 段が針基に対して係止されることによって,針管の針先が再度,針先保護部の先端 側から露出することが防止されることとなる。 また,証拠(乙63)及び弁論の全趣旨によれば,仮に被告各製品の小径部側壁 部が存在しない場合,針基の受け部においても針基は回動可能な状態にある。この\n場合,針基が回動したとしても,針先保護部の大径部係止手段に針基の縦リブが接 触することにより針基の回動がいったん停止することとなる。この状態ではなお大 径部係止手段と針基の受け部が接触しているため,直ちに針先保護部が基端側に移 動可能となるものではない。もっとも,この状態において一定の外力が加えられる\nと,縦リブが大径部係止手段を乗り越えて再び回動するなどして,針基の受け部と 大径部係止手段の係止が解除され,針先保護部が基端側に再度移動し,留置針の針 先が再露出する状態となり得ることが認められる。 しかも,被告各製品の添付文書(甲5)には,次のような記載がある。
「・針を収納する際は,ロックが外れたことを確認し,真っ直ぐ引くこと。(針 基が曲がったり,折れるおそれがある。)
・針が収納,固定された状態でグリップ部を強く引っ張る,回転させる操作をし ないこと。(針基が曲がったり,折れるおそれがある。)
・針が収納,固定された状態で針先が飛び出す方向に力を加えないこと。(針刺 し及び感染のおそれがある。)」 これらの記載によれば,被告各製品においては,留置針を収納する際や収納・固 定された状態において日常的な使用時に作用し得る程度の外力により,針基の屈曲 や針先再露出といった状態が生じ得ることがうかがわれる。まして,被告各製品の 小径部側壁部が存在しない場合は,更に小さい外力によりこのような状態が生じ得 ると考えられる。
(ウ) そうすると,被告各製品においては,針先保護部に大径部係止手段及び小径 部側壁部が設けられており,針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる 位置において,針先保護部に設けられた大径部係止手段が針基に対して係止される ことと,針基に設けられた縦リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが相互 に係合することにより針基が針先保護部に対して回動することが防止される状態に あることとが相まって,針基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前 進することができなくなっているものと認められる。すなわち,被告各製品は,大 径部係止手段のみならず小径部側壁部が針先保護部に設けられていることにより針 先の再露出が防止される構成となっている。\n以上のとおり,被告各製品の小径部側壁部は,針先再露出防止機構としての機能\ をも有するものと認められる。したがって,被告各製品の小径部側壁部は,「係止 片」(構成要件 1D 等)に該当し,これが小径部に設けられている以上,被告各製 品は,「前記係止片は,…前記小径部側には設けられておらず」(構成要件 1E 4))を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
平成30(ワ)35263 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和3年9月29日 東京地方裁判所
(1) 秘密管理性
ア 本件データは,気圧の上限・下限,加圧(減圧)に要する時間,チャン バー内を一定の気圧に保っている時間,排気時間及び動作の繰返しの回数 等を内容とし,これらの数値に基づいて酸素チャンバー内の気圧を昇降さ せるためのものであり,本件酸素チャンバーの制御装置内に設置された媒 体に記録されているものであると認められる(原告代表者〔10,11頁〕),\n弁論の全趣旨)。
イ 本件データの上記内容に照らすと,同データは酸素チャンバーの作動を 制御する上で中核をなすものであり,その秘密性は高いと考えられるとこ ろ,証拠(甲2,3,9,11,15,原告代表者〔2,6,23頁〕)\nによれば,1)原告製の酸素チャンバーは,その出荷前に,制御装置内の特 定の箇所をジャンパー線で接続し導通させることにより,本件データ等を 読み出せないようロックがかけられており,それ以降,原告社内でこれに アクセスできるのは,原告代表者のほか限られた人数の役員等であったこ\nと,2)原告の従業員には就業規則第5条(5)により守秘義務を課せられて いたこと,3)原告は,本件データを含む制御装置一式の製作を委託してい た協立電機との間で機密保持契約を締結しており,本件データは同契約第 1条の「秘密情報」に該当すると考えられること,4)原告製の酸素チャン バーの販売代理店であった被告会社も本件データの変更は自由にできな かったこと,5)原告製の酸素チャンバーを購入した顧客も本件データにア クセスすることはできなかったことの各事実が認められ,これを覆すに足 りる証拠はない。 このように,原告社内においても本件データにアクセスすることのでき る者は限られており,取引先等についても秘密保持義務が課せられ,ある いは本件データへのアクセスができない状態とされていたことに照らす と,本件データは原告において秘密として管理されていたというべきであ る。
ウ(ア) これに対し,被告らは,原告が主張するロックの内容は明らかではな く,また,全国的に販売されている原告製の酸素チャンバーの納品や修 理の作業を支障なく行うには本件データの内容を原告の従業員等が知っ ていることが必要であったと主張する。 しかし,原告の主張するロックの内容は上記イ1)のとおり十分に具体\n的であり,かかる措置を講じてもなお本件データへのアクセスが可能で\nあることをうかがわせる証拠はない。また,原告の従業員が,原告製の 酸素チャンバーの納品を行い,あるいは同製品の修理を行うために本件 データにアクセスすることが必要な事例が日常的に生じていたことをう かがわせる証拠はなく,原告製の酸素チャンバーが全国に販売されてい たとしても,そのことから,原告従業員が本件データにアクセスするこ とができたとの事実を推認することはできない。
(イ) また,被告らは,原告との間で,本件データを対象とする秘密保持契 約を締結したことはなく,本件販売代理店契約の契約書(甲3)をみて も,原告製の酸素チャンバー全てについて原告又は原告が委託した者が 修理をする旨の規定はないと主張する。 しかし,上記イ4)のとおり,被告会社が本件データを自由にアクセス し,これを変更し得たことを示す証拠はないことに照らすと,被告会社 との間で本件データは秘密として保護されていたというべきである。ま た,被告会社又は原告の委託者が原告製酸素チャンバーを修理すること があったとしても,これらの業者が本件データにアクセスすることがで きたことをうかがわせる証拠はない。 そうすると,本件データは,被告会社及び原告製酸素チャンバーの修 理を行う業者との間においても,秘密として管理されていたというべき である。
(ウ) さらに,被告らは,本件クラブに納品された本件酸素チャンバーには 本件データのロックがかけられていなかったので,本件データは秘密と して管理されていなかったと主張する。 しかし,本件クラブに納品された本件酸素チャンバーに本件データの ロックがかけられなかったのは,前記前提事実(3)イのとおり例外的な 措置であって,このことは,本件データが秘密として管理されていたと の上記判断を左右しないというべきである。
・・・
本件においては,以下のとおり,被告らが本件データを実際に読 み出して取得し,また,被告会社が取得した本件データを使用して酸素チャ ンバーを製造したことを客観的に示す証拠は存在しない。 ア 被告らが本件制御装置等を保管していた間,本件制御装置に対していか なる作業又は操作を行ったかは証拠上明らかではない。
原告は,本件制御装置等の持ち出し前と返還後とでは,同装置等の側面 にテープ付けしていた鍵の位置が異なっており,明らかに鍵を使用した痕 跡があったことや,原告が本件酸素チャンバーの復旧作業を行った際,本 件制御装置に対する原告のPC以外のPCからのアクセスを確認したこ となどを指摘するが,これを裏付ける客観的な証拠は何ら提出されていな い。 また,原告代表者は,本件クラブには本件データを読み出し,パラメー\nタの設定や変更を行い得る設備や人材等を有していたため,ロックの解除 の方法を伝えたものであり,本件クラブにおいて同ロックを解除したかど うか,また,パラメータ等の変更後のロックをかけたかどうかは承知して いない旨の供述をしているところ(原告代表者〔24,28〜29頁〕),\n同供述を前提にすると,仮に被告らが持ち出した本件制御装置等を使用し て本件データへのアクセスを試みたとしても,奏功したかどうかは明らか ではない。
さらに,原告は,制御装置等の取外しや取付けをしたのみでは酸素チャ ンバーの機能が動作しなくなることはないので,本件制御装置等の返還後\nに本件酸素チャンバーの低圧モードに支障が生じたのは,本件データの複 製等が行われた現れであると主張するが,低圧モードに支障が生じたこと から,直ちに本件データの複製等が行われたと推認することはできない。 そして,他に,被告らが本件制御装置等を保管していた間に本件制御装 置に対して行った具体的な操作や作業の内容を特定し得る証拠はない。 イ 原告は,被告会社が本件データを使用して,酸素チャンバーを製造した と主張するが,被告会社製の酸素チャンバーの開発・製造に当たり,本件 データが使用されたことを客観的に示す証拠はない。
かえって,被告会社の製造した酸素チャンバーの制御装置マニュアル(乙 8)及びW証言〔1,2頁〕によれば,被告会社製の酸素チャンバーにお いては,制御装置のモード選択画面に表示される圧力や運転時間について,\n納品時に所定の設定はされているものの,顧客がこれを変更することも可 能な仕様となっており,顧客がこれらの数値を自由に変更することができ\nない原告製の酸素チャンバーとは仕様が異なるものであると認められる。 なお,原告は,本件酸素チャンバーのラダープログラムと被告会社製の 酸素チャンバーのラダープログラムを対比することにより,被告会社によ る本件データの使用の有無を解析できると主張し,被告らに対し,同プロ グラムの任意提出を求めていたが,その後,被告らが同プログラムを改ざ んしているおそれが高いとして,被告会社の保有するラダープログラムの 提出を求めない旨の意思を表明した(原告第6準備書面)。原告は,被告\nらがラダープログラムを証拠として任意提出しないことから本件データ の使用を推認し得ると主張するが,ラダープログラムを実際に対比するこ となく,そのような推認をすることはできない。
ウ 以上によれば,被告らが本件データを取得し,また,被告会社が取得し た本件データを使用して酸素チャンバーを製造したとの事実を認めるに 足りる証拠はないので,本件持出し行為が不競法2条1項4号の不正競争 行為に該当するとの原告主張は理由がない。
2022.01. 3
令和2(ワ)4023 特許権 民事訴訟 令和3年10月7日 大阪地方裁判所
(3) 推定覆滅について
ア 本件発明の効果
本件発明の効果は,各種タイプのチャイルドシートの背面側に装着することがで きること(【0022】),カバーの天部の高さ位置を適宜設定・変更することがで き,カバーの内部空間で,幼児の頭頂部がカバー天部に接触しないか,接触しても カバーの重みがもろに幼児の頭部に掛ることが少なくなり,居住環境が向上するこ と(【0023】)である。 要するに,本件発明の作用効果は,1)各種のチャイルドシートに装着できるこ と,2)幼児の頭部に合わせてカバーの天部高さ位置を適宜調整できることにあると いえる。 もっとも,様々な形状のチャイルドシートに対応してその略全体を被覆するチャ イルドシートカバーは従来技術として各種存在し(【0002】〜【0010】),これら は本件発明以外の適宜の方法で装着されていたのであるから,上記効果のうち1) は,本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。 また,前記1ないし3のとおり,ハ号物件等,ホ号物件等及びト号物件等のよう に本件発明の技術的範囲に属しない部品によっても,装着方法によってはチャイル ドシートカバーを適宜高さ位置に装着できると考えられるから,本件発明の効果2) も,本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ア) 本件発明は,チャイルドシートのほぼ全体を被覆するチャイルドシートカ バーを自転車のチャイルドシートに装着する際に使用される部品である装着補助プ レートの発明である。チャイルドシートカバーを選択するのは,主に幼児の保護者 等である自転車所有者と考えられるが,装着補助プレートは,チャイルドシートカ バーそのものではなく装着に用いる補助的な部品であって,使用時にはチャイルド シートカバーの内部に隠れ,雨避け等のチャイルドシートカバーの機能そのものを\n発揮する部分ではないから,装着補助プレート自体が需要者の関心を惹き,製品選 択の直接の動機となるとはいえない。 また,本件発明の効果は,前記アのとおり,いずれも本件発明によるのでなけれ ば実現し得ない効果ではなく,本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たって は,必ずしも重視できるものではないが,本件発明に係る装着補助プレートを使用 したチャイルドシートカバーの広告において前記の効果1)及び2)を謳っている場合 は,需要者に当該チャイルドシートカバーの利点,優位性を認識させるものである から,製品選択の動機となり得る事情といえる。
(イ) 証拠(甲4,5)によれば,被告は,イ号物件の特徴として,「背もたれ の高いタイプのチャイルドシートなら装着 OK」などと効果1)については謳ってい るものの,効果2)については特に宣伝していない。 また,証拠(甲6)によれば,被告は,ロ号物件の特徴としても,「各種後付け シートに対応しています」などと効果1)については謳っているものの,効果2)に関 しては,取付方法の説明において「6)最後にファスナーを閉じたら,装着完了。突 っ張る部分がある場合は,カバーの高さを調節してください。背面部分を高くセッ トしすぎるとカバーにシワが寄ったり,突っ張ったりするので適宜調節ください」 との記載があるにすぎず,カバーの高さ位置を調整できる旨を記載しているが,特 段の利点としては記載していない。 さらに,証拠(甲4,18)によれば,イ号物件及びロ号物件の購入者のレビュ ーにおいても,効果2)について記載したものはなく,単にカバーがワイヤーにより 自立して天井が高いことに係る記載があるにとどまり,証拠(甲3,16)によれ ば,原告においても,効果1)及び2)を宣伝していないことが認められる。
(ウ) 原告は,チャイルドシートカバーが自転車に常時装着されているものでは なく,使用,不使用時に取り外しを行うものであるので,需要者にとってカバーが 簡単に取り付けられるかどうかが重要であるところ,原告製品の補助プレートを用 いることでカバーの取付が従来より容易となり,需要者から支持を得ていると主張 する。
しかしながら,本件明細書によれば,「カバーを装着したままで使用するという ことが常態」(【0009】)であるというのであり,「本発明においても,上記従来 のチャイルドシートカバーと同様に,これを装着したままの状態で,自転車の不使 用時は勿論のこと,…どのような天候の際にも,幼児を乗せて使用することができ るカバーに適用可能なものである」(【0012】)とされているから,本件発明は, チャイルドシートカバーを常時装着した状態で使用することを前提としたものであ る。また,本件発明にチャイルドシートカバーの取付を容易にする効果があること は本件明細書に記載がなく,【発明が解決しようとする課題】や【課題を解決する ための手段】にも取付を容易にすることに関する記載はないから,チャイルドシー トカバーの取付が容易になることは本件発明の効果とは関係がない。
(エ) 以上によれば,本件発明は,効果1)及び2)を有し,これを実施する製品の 販売等に一応貢献し得るものであるが,効果1)については需要者に重視されず,効 果2)については,イ号物件及びロ号物件において需要者にほとんどその効果が認識 されないものであって,顧客誘引力は極めて低く,イ号物件及びロ号物件の他の利 点を考慮して,これを購入した需要者が多かったものと考えられる。
ウ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば,本件においては,8割の損害額の推定が覆滅 されるとすべきである。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和1(ワ)9113 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月16日 大阪地方裁判所
ウ 推定覆滅について
(ア) 本件各発明の効果
本件発明1の効果は,発明に係るケーシングのコンセント部に対する設置形態を 採用することにより,設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなり,設置箇所\nの美観が向上されると共に,歩行の妨げになることが抑制されること,上記設置形 態を採用することで大きさ等に制限が生じるケーシング内に複数のアンテナ素子を 配置するにあたり,複数のアンテナ素子がケーシングの内壁面に沿う板状に形成さ れ,内挿部の内壁面において表示面部の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分\n配配置されることで,アンテナ素子間の離間距離を十分に大きくとって,送受信波\nの相互干渉を良好に抑制することができること(【0009】)である。 本件発明2の効果は,本件発明1の効果に加えて,ケーシングの内挿部における 四方の内壁面において,表示面部の両側縁部から後方に延出し互いに対向する一対\nの平面状側壁部が存在し,これらの平面状側壁部のそれぞれに複数のアンテナ素子 を分配配置するという合理的な構成により,これら複数のアンテナ素子を表\示面部 の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分配配置できると共に,一対の平面状側 壁部は互いに平行な平面となるので,その平面状側壁部に沿った姿勢で配置される 複数のアンテナ素子のそれぞれにおいて,指向性を決定する延出方向が設定しやす くなること(【0019】),複数のアンテナ素子が表示面部の後方側内部空間を挟ん\nで対角位置に配置されているので,それぞれのアンテナ素子間の離間距離を一層大 きくとって,それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉を一層良好に抑 制することができること(【0021】)である。 本件発明3の効果は,本件発明1及び2の効果に加えて,無線 LAN に加えて有 線 LAN や電話回線が利用可能になること,表\示面部の後方側にモジュラーアダプ タが配置されているので,複数のアンテナ素子をモジュラーアダプタを間に挟んだ 状態で配置することができ,それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉 が一層良好に抑制されること(【0017】)である。 要するに,本件各発明の作用効果は,1)ケーシングをコンセント部に埋設状態で 設置でき,設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなることによる美観の向上\n及び歩行の妨げとなることの防止,2)複数のアンテナ素子間の送受信波の相互干渉 の抑制,3)アンテナ素子の指向性を決定する延出方向設定の容易化(本件発明1を 除く)にあるといえる。
(イ) 本件各発明の貢献の程度等について
本件各発明は,コンセント部に埋設状態で設置される情報コンセントに係る発明 であり,主として集合住宅やホテル,オフィス等に一括して設置することが想定さ れる(甲4,54,55,弁論の全趣旨)。そうすると,それらの設置を扱うイン ターネットサービスプロバイダーが原告製品及び各被告製品の主要な取引者と解さ れると共に,最終的な需要者である情報コンセントが設置される建築物の施主の意 向も,製品選択に影響することが考えられる。これらの者にとって,本件各発明の 前記の効果1)〜3)は,いずれも選択の動機となり得る事情といえる。 また,証拠(甲52)によれば,被告は,各被告製品について,「標準の情報コ ンセント内に埋込み,省スペースで快適な無線 LAN 環境」,「美観重視のお客様 に適した,見た目がスマートな埋込み型」,「JIS 規格のコンセントであればメー カを問わず設置可能」などと宣伝しており,効果1)を謳っている上,「もっと電波 を強くしてほしい」という要望に応じて導入された事例や,「確実に無線が使用で きる環境でありながら,部屋に設置しても存在を意識しないデザイン」が評価され たという事例等を紹介して宣伝してもおり,効果2)を取り上げた宣伝も行っている と認められる。 そうすると,本件各発明は,少なくとも効果1)及び2)により,これを実施する製 品の販売に貢献するものというべきであって,顧客誘引力がない又は乏しいものと はいえない。
これに対し,被告は,本件各発明の特徴は従来から存在したケーシングに対して 技術常識に基づく配置を併せた点に限定されること,原告が商品の訴求ポイントと して挙げる事情は本件各発明と無関係であること,乙26文献及び乙27文献記載 の公知技術の存在を指摘して,本件各発明は売上や利益に対して寄与せず,又はそ の寄与は無視できる程度に小さいなどと主張する。 しかし,被告がその主張の前提とする本件各発明の特徴に関する理解は,本件各 発明に係る技術的思想や効果を正しく理解したものとはいえず,被告の上記主張は その前提を欠く。また,乙26文献及び乙27文献には,いずれも複数のアンテナ を配置することの記載も示唆もないから,これらの文献記載の公知技術の存在は, 本件各発明の貢献の程度を失わせるものとはいえない。 このほか,被告において,他に顧客誘引力を有すべき製品の特徴等についての主 張立証はない。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
(ウ) 競合品の存在について
証拠(甲1,49〜52,55,56)によれば,原告製品及び各被告製品は, JIS 規格のコンセントプレートに対応した情報コンセント型無線 LAN アクセスポイ ントの製品であるところ,エレコム株式会社の製品(WAB-S733IW-PD。以下「甲 56製品」という。)も,1つの電子チップ型アンテナ及び1つの基板アンテナの 2つのアンテナ素子を有し,JIS 規格のコンセントプレートに対応した製品である から,原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品であることが認められ る。もっとも,その販売開始時期,販売価格,販売実績,市場占有率その他具体的 な事情について,被告による主張立証はなく,証拠上明らかでない。また,甲56 製品のほかに,原告製品及び各被告製品と市場において競合するものと認められる 製品の存在等に関する具体的な主張立証はない。 そうすると,原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品として甲56 製品が存在する以上,その存在をもって特許法102条2項に基づく損害額の推定 の覆滅事由として考慮すべきではあるものの,その覆滅の程度は極めて限定的であ り,本件においては,5%の限度で推定が覆滅されるにとどまると考えるのが相当 である。
これに対し,被告は,原告製品及び各被告製品と同種の製品を販売している競合 企業が多数存在するなどと主張する。しかし,一般論として技術的に同一の製品で はなくとも市場において競合することがあり得るとしても,他社製品との競合の状 況に関する具体的な主張立証がない以上,特許法102条2項に基づく損害額の推 定を覆滅すべき事情としてこれを考慮することはできない。また,原告製品の失注 といった個別の取引事例に基づく主張については,その具体的な事情が明らかでは ないから,失注の点をもって直ちに原告製品の競争力の乏しさを示すものとは必ず しもいえない。したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
(3) 損害額(特許法102条3項に基づくもの)並びに特許法102条2項及 び3項の重畳適用について
原告は,損害額につき,選択的に特許法102条3項に基づく推定をも主張す る。しかし,その主張する額は特許法102条2項に基づき推定される損害額(前 記(2)エ)より少ない。したがって,同条3項に基づく損害額について論ずる必要 はない。 特許法102条2項及び3項の重畳適用については,前記(2)ウのとおり,本件 において同条2項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは 競合製品の存在のみであるところ,被告による各被告製品の販売実績等と直接の関 わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては,同条3項適用の基礎 を欠く。したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和2(ワ)3646 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年11月9日 大阪地方裁判所
原告は,原告標章(標準文字)が商標登録され,これに係る公報が発行された後 は,原告標章を使用せず,被告ら標章により本件商品を販売した行為は,登録商標 の出所表示機能\を毀損するものとして,商標権侵害が成立する旨を主張する。
しかしながら,商標権侵害は,指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で,商 標権者以外の者が,登録商標を同一又は類似の商標を使用する場合に成立すること がその基本であり(商標法25条,37条),原告が原告標章を付した本件商標を 被告らに譲渡した際に,原告標章と同一又は類似の商標を使用する競業者が存在し なかったことをもって,本件商標権はその役割を終えたと見ることができるのであ り,原告から本件商品を譲り受けた被告らが,これを原告標章以外の商品名で販売 することができるかは,商標権の問題ではなく,前記検討したとおり,原告と被告 らとの合意の存否の問題と考えざるを得ない。 したがって,後半期間において,被告フジホームが本件商品を被告ら標章により, また取扱説明書を差し替えて自社のオンラインストアで販売したこと(被告ら行為 2)),あるいは被告サンリビングが,原告より直接入手した本件商品を,被告ら標 章によりダイワに譲渡したことは(被告ら行為3)),いずれも商標権侵害にはあた らないといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和3(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年11月30日 知的財産高等裁判所
特許権の存続期間の延長登録の制度は,政令処分を受けることが必要であったた めに特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とする ものであるから,本件医薬品の製造販売が,本件各発明の実施に当たらないのであ れば,本件処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることがで きなかったということはできない。 ところで,本件処分は,オキサリプラチンを有効成分とする「エルプラット点滴 静注液50mg」(本件医薬品)に係る本件処分に係る医薬品製造販売承認事項一部 変更承認申請当時(平成26年10月3日。甲2・参考資料7参照)の法14条9\n項に規定する医薬品の製造販売についての承認である。原告は,本件医薬品はオキ サリプラチンと注射用水からなり,本件医薬品中でオキサリプラチンが水と反応し て遊離したシュウ酸を緩衝剤とする旨主張している。 そこで,以下,本件医薬品の製造販売行為が,本件各発明の実施に当たるか検討 する。
3 本件各発明の「緩衝剤の量」について
(1) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は,前記第2の1(2)のとおりであり,本 件発明1〜9及び15〜17については,1)オキサリプラチン,2)有効安定化量の 緩衝剤であるシュウ酸又はそのアルカリ金属塩及び3)製薬上許容可能な担体である\n水,を包含する「安定オキサリプラチン溶液組成物」に係るものであり,本件発明 10は,1)オキサリプラチン,2)有効安定化量の緩衝剤であるシュウ酸又はそのア ルカリ金属塩及び3)製薬上許容可能な担体,を包含する水性溶液である「オキサリ\nプラチン溶液組成物」に関して,緩衝剤を溶液に付加することを含む安定化方法に 係る発明,本件発明11〜14は,本件発明1〜9のいずれかの組成物についての 担体(水)と緩衝剤を混合することを含む製造方法に係る発明である。
(2) 原告は本件審決における「緩衝剤の量」の認定に誤りがあると主張するので 検討するに,上記(1)の特許請求の範囲の記載からすると,「緩衝剤」は,溶液に添 加したり,混合することを前提とするものと解するのが自然である。また,上記の 通り,本件発明1〜9及び15〜17が,オキサリプラチン,緩衝剤及び担体を含 む溶液組成物に係るものであるところ,オキサリプラチンを水に溶解させたときに 生じるシュウ酸を緩衝剤と称し,オキサリプラチンや水とは別個の要素として把握 するのは不自然である。さらに,「緩衝剤」の「剤」は,「各種の薬を調合すること。 また,その薬」(広辞苑〔第6版〕)を意味するから,この一般的な意義に従うと, 「緩衝剤」は,「緩衝作用を有する薬」を意味すると解される。そうすると,特許請 求の範囲の記載からは,本件各発明における「緩衝剤」に,オキサリプラチンから 遊離したシュウ酸は含まれないと解するのが相当である。
(3) 次に,特許請求の範囲に記載された用語の意義は,明細書の記載を考慮して 解釈するものとされる(特許法70条2項)ので,本件明細書(甲1)の記載をみ ると,前記1(1)のとおり,「緩衝剤という用語」について,「オキサリプラチン溶液 を安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオDACHプラチンお よびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあら ゆる酸性または塩基性剤を意味する。」(【0022】)として,これを定義付ける記 載があり,上記の「剤」の一般的意義に照らしても,「緩衝剤」について,「緩衝作 用を有する薬」を意味するものと理解することは,本件明細書の記載にも整合する。 なお,原告は,本件において,本件明細書の記載を考慮すべきではない旨主張し ているが,特許法70条2項は一般的に特許発明の技術的範囲を定める場面に適用 され,特許侵害訴訟における充足性を検討する場面にのみ適用されるものではない から,原告の上記主張は採用できない。また,原告は,オキサリプラチンから遊離 したシュウ酸が緩衝剤としての役割を果たすと主張するが,同主張は本件特許の特 許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に整合していないし,一般に,有効成分 である化合物が水溶液中で分解した場合に,当該分解物を「緩衝剤」と称するとい うような技術常識があると認めるべき証拠もない。
(4) そして,前記1(2)のとおり,本件各発明が,オキサリプラチンと水からなる 従来技術よりも安定したオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とする ものであることに加え,本件明細書には,緩衝剤としてシュウ酸が二水和物として 付加される実施例1〜17が記載され,オキサリプラチン及び水のみからなる実施 例18は従来技術である比較例とされていることなどの本件明細書のその余の記載 を考慮しても,「緩衝剤」にオキサリプラチンから遊離したシュウ酸を含むと認める ことはできない。そうすると,「緩衝剤の量」に,オキサリプラチンから遊離したシ ュウ酸の量を含めるべきであるという原告の主張を採用することはできず,本件発 明1の「緩衝剤の量」について,「オキサリプラチン溶液組成物の作製時に,オキサ リプラチン及び担体に添加,混合された緩衝剤の量を意味し,オキサリプラチン溶 液組成物中のオキサリプラチンが経時的に分解することで生じたシュウ酸の量は, 当該『緩衝剤の量』に含まれない」とする本件審決の認定に誤りはない。
4 本件医薬品を製造販売する行為が本件各発明の実施行為に該当するか否かに ついて
(1) 証拠(甲9)によると,本件医薬品中のシュウ酸モル濃度は,製造直後にお いて5×10-5M,36箇月保存後において8×10-5Mであることが認められる ものの,前記3のとおり,オキサリプラチン溶液組成物中のオキサリプラチンが経 時的に分解することで生じたシュウ酸の量は,本件各発明における「緩衝剤の量」 に含まれないから,本件医薬品のシュウ酸モル濃度から直ちに,本件医薬品が本件 各発明の「緩衝剤の量」の範囲の緩衝剤を含有するということはできない。そして, 証拠(甲3,10)によると,本件医薬品は,オキサリプラチンと注射用水のみを 成分とし,その他の添加物はないことが認められるから,本件各発明における「緩 衝剤」すなわち「オキサリプラチン溶液組成物の作製時に,オキサリプラチン及び 担体に添加,混合された緩衝剤」を含有しないというほかないから,本件医薬品は, 本件各発明における「緩衝剤の量」の範囲を満たす量の「緩衝剤」を含有しない。
(2) そうすると,本件医薬品を製造・販売することは,本件各発明の実施に当た らないから,本件医薬品には緩衝剤が外から添加されていないとして,特許発明の 実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められないとした本件審決の判 断に誤りはない。
◆判決本文
延長対象の特許が同じ事件です。
2022.01. 3
令和2(ワ)11491 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和3年9月15日 東京地方裁判所
ア 原告意匠の出願日は令和元年8月20日であるところ,上記(2)におい て判示した被告製品の開発経緯によれば,被告製品を開発・製造して被告 に販売したダイセンは,Wuxi社及びCNTA社との間で洗面台用排水 口フィルターの新製品の開発を進め,平成31年4月にWuxi社から抜 き型図面(乙20)を受け取り,これに基づき試作品を作成した上で,被 告に対して新製品販売の提案を行い,被告製品の意匠は令和元年7月に被 告に採用されて,被告製品の製造・販売に至ったものと認められる。
イ ダイセンがWuxi社から受領した上記抜き型図面の構成は,上記(1) イの被告製品の意匠の基本的構成態様及び具体的構\成態様をいずれも備 えたものであり,被告製品の意匠と同一又は類似するということができる。 そして,同図面に基づいて作成されたと推認される被告製品の試作品(乙 23の2の1の下段,乙23の2の2,乙23の4)も同様に被告製品の 意匠の基本的構成態様及び具体的構\成態様をいずれも備え,被告製品の意 匠が被告に採用された後に,ダイセンの担当課長がCNTA社の担当者に 送信した電子メール(乙27)の本文に挿入された試作品の画像も同各態 様を備えていたものと認められる。 そうすると,原告意匠と同一又は類似する意匠は,平成31年4月にダ イセンがWuxi社から知得し,仮にそうではないとしても,ダイセンが 被告と打合せを重ねる中で原告意匠の出願日までの間に創作したもので あり,その意匠は平成31年4月から被告製品の意匠の採用時まで,一貫 して,上記(1)イの基本的構成態様及び具体的構\成態様を備えていたもの というべきである。
ウ 意匠法29条は「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意 匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,そ の実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意 匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する」と規定するところ, 上記(2)のとおり,ダイセンは,令和元年8月2日には被告から2万個の被 告製品の製造を受注していたことに照らすと,原告意匠の出願日(同月2 0日)には原告意匠又はこれに類する意匠の実施である事業を開始してい たというべきである。 加えて,ダイセンが,原告意匠の出願日当時,原告意匠について知って いたことを示す証拠はない。
エ 以上によれば,原告意匠と被告製品の意匠が類似しているとしても,ダ イセンは,原告意匠を知らないで自ら原告意匠又はこれに類似する意匠を 創作し,又は同意匠の創作をした者から知得して,原告意匠登録出願の際, 現に日本国内において原告意匠又はこれに類似する意匠の実施である事 業をしていたということができるので,意匠法29条に基づき,原告意匠 権について通常実施権を有するものというべきである。そうすると,被告 が,原告意匠権について通常実施権を有するダイセンから被告製品を仕入 れて販売等する行為が原告意匠権を侵害するということはできない。
(4) 原告の主張について
ア 抜き型図面(乙20)について
(ア) 原告は,抜き型図面は,作成日付が印字されておらず,手書き部分は 後日追記された可能性があるため,同図面が原告意匠の登録出願前に作\n成されたかどうか不明であると主張する。 しかし,ダイセンが平成31年4月11日にWuxi社及びCNTA 社と打合せを行った際の商談記録表(乙21)には,「シートサイズ:\nφ40mm(穴/12mm)×厚さ5mm,取っ手/8mm(45゜C))」, 「抜き型の形状は4月13日までに協議した上で決定させる。」,「別 紙参照:抜き型図面データ」との記載がある。同記録表はその内容,形\n式等に照らして,その「作成日」(同月17日)に作成されたものと信 用し得るところ,同記録表の上記記載に加えて,令和元年6月5日付け\nの電子メールに添付されていた乙23の2の1上段の画像データが乙 20の抜き型図面と同一であり,同図面にはその寸法が記載されている ことなども考慮すると,平成31年4月11日の上記打合せにおいて同 抜き型図面が配布されたと認めるのが相当である。 原告は,同抜き型画面には「4/13 最終案」との手書きの書込み があるのに対し,乙23の2の1上段の画像データには同様の書込みが ないと主張するが,同画像データは,乙20の抜き型図面の図面部分の みを画像データとしたものとも考えられることからすると,同画像デー タに書込みがないことをもって,「4/13 最終案」との上記書込み が原告と被告間の紛争が生じてからされたものであるということはで きない。
(イ) また,原告は,Wuxi社が,抜き型図面のCADファイルをわざわ ざ印刷した上で,紙媒体を日本まで郵送したというのは不自然であると 主張する。 この点,Wuxi社が抜き型図面の元データを印刷して紙媒体として 配布した経緯は明らかではないが,データの流用,改変の防止などの観 点から,CADデータを印刷し,精度を落とした上で,取引先との打合 せにおいて配布したとしても不自然ということはできない。
(ウ) さらに,原告は,乙20の抜き型図面の元データに作為が加わる可能\n性は否定できないと主張するが,乙20の画像データに作為が加えられ たことを具体的に示す証拠は存在しない。
イ 令和元年6月5日付け電子メール(乙23の1)に添付された図面及び 写真データ(乙23の2の1)について
(ア) 原告は,乙23の2の1の画像データ及び製品比較表(乙23の4)\nの画像データのプロパティ(乙34,36の2)は容易に変更すること ができるので,その信用性には疑問があると主張するが,同プロパティ が変更されたことを具体的に示す証拠は存在しない。
(イ) 原告は,被告の主張によると乙23の2の1上段の画像データが作成 されたのは抜き型図面の作成後ということになるが,通常,データを作 成してから印刷するはずであるから,被告の主張は不自然であると主張 する。 しかし,被告の主張するとおり,本件では,Wuxi社が,自らの保 有するデータに基づき,紙媒体の抜き型図面を作成してダイセンに交付 し,その後にダイセンが紙媒体の同図面から必要な部分をデータ化して 乙23の2の1上段の画像データを作成したものと認めるのが相当であ る。そうすると,抜き型図面の作成時期が乙23の2の1上段の画像デ ータの作成時期より早いのは当然であるというべきである。
ウ 製品比較表(乙23の4)について\n
(ア) 原告は,乙36の2のプロパティの作成日時は「2014/12/1 7」と本件よりはるかに過去のものになっており,また,最終更新日も 記載されておらず,同プロパティにある「最終印刷日」もいずれの画面 を印刷したのか不明であると主張する。 しかし,同プロパティの「作成日時」の記載は,同表の元になったフ\nォーマットの作成日時を示すものであると考えられ,製品比較表の作成\n日を示すものということはできない。 また,同プロパティによれば,その最終更新日は令和元年6月5日午 前9時41分であり,最終印刷日は同日午前9時40分であると認めら れ,印刷対象は同表であると認められる。そうすると,同プロパティの\n最終更新日や印刷対象が不明であるということはできない。 同プロパティに表示された最終更新日や最終印刷日は,令和元年5月\n27日の商談記録表(乙22)に「類似商品が販売されていないか,確\n認の依頼を受ける。比較資料を作成し,提出するとした。」との記載が あり,その次の打合せが同年6月12日に行われていること(乙24) とも整合するものであり,信用することができるというべきである。
(イ) 原告は,製品比較表の表\示と乙36の1のデータファイルの画像とは 異なると主張するが,乙36の1は画面の一部をスクロールしたために その一部が表示されていないものにすぎず,製品比較表\(乙23の4) と乙36の1のデータファイルとは同一のものであると認められる。
(ウ) 原告は,製品比較表は乙23の2の1下段の画像データを利用してい\nるので製品比較表のデータファイルの最終印刷日(令和元年6月5日午\n前9時40分)が乙23の2の1の画像データの作成日時(同日午前1 1時14分。乙34)より早いのは不自然であると主張する。 しかし,被告の主張する「乙23の2の1の画像データの作成日時」 は,乙23の2の1の画像データを貼り付けたエクセルファイルをPD\nFファイルに変換した日時にすぎないものと認められる(乙34)から, 被告が,試作品の画像データを作成した上で,これを利用して製品比較 表を作成し,その後同データと抜き型図面の画像データを併せて乙23\nの2の1のPDFファイルを作成したとも考えられる。そうすると,製 品比較表のデータファイルの最終印刷日が被告製品の試作品の写真の\n画像データを貼り付けたPDFファイルの作成日時より早いとしても\n不自然ということはできない。
エ 令和元年7月31日付け電子メール(乙27)について
原告は,電子メールの改ざんや編集は容易であって,ダイセンにも乙2 7の電子メールを改ざんする動機があったと主張するが,同メールの記載 やその本文に挿入された試作品の画像データが改ざんされたことを具体 的に示す証拠は存在しない。
オ 被告製品の意匠の完成時期について
原告は,令和元年8月2日の打合せに係る商談記録表(乙29)に「デ\nザイン案を提出したが,NGとのことであった。」と記載されていること をもって,この時点においてデザインが完成していなかったと主張する。 しかし,1)同年7月22日に行われた被告とダイセンの商談記録表には\n「当初の提案形状のままで,商品化を依頼した」との記載があること,2) 同月30日付けでキャンドゥから採用通知書がダイセンに送付されてい ること(乙26),3)ダイセンの担当課長のCNTA社の担当者宛の電子 メール(乙27)に「下記のフィルターで,採用決定しました。」と記載 され,その直下に被告製品の試作品の画像が挿入されていることによれば, 乙29の商談記録表における「デザイン」とは被告商品の形状に関するデ\nザインではなく,上記電子メールに「作成中」であると記載されている被 告製品の化粧袋のデザインであると解するのが相当である。 そうすると,同年8月2日時点において被告製品のデザインが完成して いなかったとの原告の主張は採用し得ない。
2022.01. 3
平成31(ワ)7038等 特許権侵害行為差止等請求事件,損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年10月29日 東京地方裁判所
29条1項2号にいう「公然実施」とは,発明の内容を不特定多数の 者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい,本件各発明のよう な物の発明の場合には,商品が不特定多数の者に販売され,かつ,当業者 がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろ ん,外部からそれを知ることができなくても,当業者がその商品を通常の 方法で分解,分析することによって知ることができる場合も公然実施とな ると解するのが相当である。
・・・
エ 日本黒鉛らについて
(ア) 日本黒鉛各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか
a 日本黒鉛製品2,4及び5に係る日本黒鉛製品結果及び乙A18結 果は近接していること,日本黒鉛製品4及び5に係る乙A18結果の 回折プロファイルにおいて,菱面晶系黒鉛層(3R)の(101)面 及び六方晶系黒鉛層(2H)の(101)面の各ピークが出現すると される回折線の角度43ないし44°付近のピークは比較的明瞭であ り,前記2(1)ウ(イ)のとおり,PDXLの自動解析機能を使用しても\n適切な解が得られると考えられること,日本黒鉛製品2に係る乙A1 8結果の回折プロファイルにおける回折線の角度43ないし44°付 近のピークは明瞭とはいい難いが,このような場合に,PDXLの自 動解析機能を使用して得られた解が常に誤っていることを認めるに足\nりる証拠はないことからすると,日本黒鉛製品2,4及び5のRat e(3R)については,日本黒鉛製品結果及び乙A18結果のいずれ も採用することができるというべきである。
他方で,日本黒鉛製品1及び3に係る乙A18結果については,同 じ製品であるにもかかわらず,算出されたRate(3R)にかなり のばらつきがあること,日本黒鉛製品1及び3に係る乙A18結果の 各回折プロファイルにおける回折線の角度43ないし44°付近のピ ークは必ずしも明瞭ではないこと,前記2(1)ウ(イ)のとおり,PDX Lは,ピークが不明瞭な場合,自動解析機能によっては不合理な解に\n収束したり,解が発散したりすることがあり,このような場合,試料 を考慮した解析条件を手動で入力する必要があること,前記(1)ウ(イ) aのとおり,原告は,自動解析機能によっては不合理な解に収束した\nり,解が発散したりする場合には適宜の解析条件を手動で入力するこ とにより,PDXLを用いて解析を行い,日本黒鉛製品結果を得たこ とからすると,日本黒鉛製品1及び3のRate(3R)については, 日本黒鉛製品結果を採用することができ,乙A18結果は採用するこ とができないというべきである。
b 日本黒鉛製品結果及び乙A18結果によれば,日本黒鉛製品2は本 件各発明の構成要件1B及び2Bを,日本黒鉛製品4及び5は構\成要 件1Bをそれぞれ充足し,日本黒鉛製品結果によれば,日本黒鉛製品 1及び3は構成要件1B及び2Bを充足することとなり,前記2の本\n件各発明の解釈を前提とすると,日本黒鉛製品1ないし3は本件各発 明の,日本黒鉛製品4及び5は本件発明1の各技術的範囲に属すると 認めるのが相当である。
(イ) サンプルのRate(3R)
a 次に,前記(1)ウ(イ)bのとおり,日本黒鉛工業が保管していた日本 黒鉛製品1,2,4及び5の各サンプルのRate(3R)は,サン プル結果3)のとおりである。
そして,日本黒鉛工業の証人Zは,日本黒鉛工業においては,平成 13年10月頃からおおむね10年に1回,製品のサンプルを保管す るようになり,平成20年6月12日に採取した日本黒鉛製品1のサ ンプル,平成13年10月5日に採取した日本黒鉛製品2のサンプル, 平成20年7月30日に採取した日本黒鉛製品4のサンプル及び同年 12月16日に採取した日本黒鉛製品5のサンプルを保管している旨 証言し,Z証人作成の陳述書(乙A120)にも同旨の記載があると ころ,証拠(乙A86,94,95)による裏付けがあることからす ると,Z証人の上記証言は採用することができるというべきである。 したがって,上記日本黒鉛製品1,2,4及び5の各サンプルは上 記各日に採取したものと認めるのが相当である。
b 日本黒鉛製品1に係るサンプル結果3)については,同じ製品である にもかかわらず,算出されたRate(3R)にかなりのばらつきが あること,サンプル結果3)の回折プロファイルにおいて,菱面晶系黒 鉛層(3R)の(101)面及び六方晶系黒鉛層(2H)の(101) 面の各ピークが出現するとされる回折線の角度43ないし44°付近 のピークは必ずしも明瞭ではないこと,前記2(1)ウ(イ)のとおり,P DXLは,ピークが不明瞭な場合,自動解析機能によっては不合理な\n解に収束したり,解が発散したりすることがあり,このような場合, 試料を考慮した解析条件を手動で入力する必要があることからすると, 日本黒鉛製品1のサンプルのRate(3R)について,サンプル結 果3)は採用することができないというべきである。 他方で,日本黒鉛製品4及び5の各サンプルに係るサンプル結果3) については,複数回算出したRate(3R)にばらつきはほとんど なく,サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度43 ないし44°付近のピークは比較的明瞭であり,前記2(1)ウ(イ)のと おり,PDXLの自動解析機能を使用しても適切な解が得られると考\nえられることからすると,日本黒鉛製品4及び5の各サンプルのRa te(3R)について,サンプル結果3)を採用することができるとい うべきである。 日本黒鉛製品2のサンプルに係るサンプル結果3)については,複数 回算出したRate(3R)にばらつきはほとんどないこと,そして, サンプル結果3)の回折プロファイルにおける回折線の角度43ないし 44°付近のピークは必ずしも明瞭ではないものの,本件証拠上,こ のような場合に,PDXLの自動解析機能を使用して得られた解が常\nに誤っているとまでは認められないことからすると,日本黒鉛製品2 のサンプルのRate(3R)について,サンプル結果3)を一応採用 することができるというべきである。
(ウ) 日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する日 本黒鉛各製品を製造販売していたか
前記イ(イ)のとおり,菱面晶系黒鉛層の増加に影響を及ぼすと考えられ る要素のほとんどは,黒鉛製品の製造工程及び製造された製品が満たす べき規格に関わるといえるが,具体的に,どのような条件の下,どのよ うな操作をすることにより,単に菱面晶系黒鉛層が増加するだけでなく, 六方晶系黒鉛層との総和における菱面晶系黒鉛層の割合であるRate (3R)がどの程度変動するかは,本件訴訟に現れた全証拠によっても 確定することができない。 そして,前記(1)ウ(ア)のとおり,日本黒鉛工業は,本件特許出願前か ら日本黒鉛各製品を製造しており,本件特許出願前から現在に至るまで, その製造工程及び出荷の基準となる規格値に大きな変更はない。 また,前記前提事実(2)及び(7)アのとおり,原告が日本黒鉛製品結果 をもって日本黒鉛らに対して提訴したのは平成31年3月であり,平成 26年9月9日の本件特許出願からそれほど長い年月が経過しているも のとはいえない。
以上によれば,日本黒鉛らは,本件特許出願前から現在に至るまで, 日本黒鉛各製品の各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており,この間, 菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造 工程及び規格値に変更はないことから,この間に製造販売された日本黒 鉛各製品は,同じ製造工程を経て,同じ規格を満たすものであると認め られる。そして,他にこれらの製品に対してRate(3R)の増減に 影響を及ぼす事情が存したとは認められず,前記(ア)のとおり,現時点に おいて,日本黒鉛製品1ないし3は本件各発明の,日本黒鉛製品4及び 5は本件発明1の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば,日 本黒鉛らは,本件特許出願前から,このような日本黒鉛各製品を製造販 売していたと認めるのが相当であり,前記(イ)bのとおり,本件特許出願 前の平成20年に採取した日本黒鉛製品4及び5のRate(3R)が 31%以上であることも,この結論を裏付けるというべきである。
なお,日本黒鉛製品2に係るサンプル結果3)は,乙A18結果と相違 しているが,日本黒鉛製品2は土状黒鉛であり,菱面晶系黒鉛層(3R) の(101)面及び六方晶系黒鉛層(2H)の(101)面の各ピーク が出現するとされる回折線の角度43ないし44°付近のピークが必ず しも明瞭ではなく,前記2(1)ウ(イ)のとおり,PDXLは,ピークが不 明瞭な場合,自動解析機能によっては不合理な解に収束したり,解が発\n散したりすることがあり,同じく土状黒鉛である日本黒鉛製品1に係る サンプル結果3)及び乙A18結果を見てもばらつきがあることからする と,日本黒鉛製品2に係るサンプル結果3)と乙A18結果が相違するこ とは,日本黒鉛らが本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属す る日本黒鉛製品2を製造販売していたという上記認定を左右するとはい えない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 0030 新規性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和3(ネ)10044 著作権侵害請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年12月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「イ 前記ア認定のとおり,本件原告滑り台は,遊具としての実用に供 されることを目的として製作されたことが認められる。 ところで,著作権法2条1項1号は,「著作物」とは,「思想又は 感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の\n範囲に属するもの」をいうと規定し,同法10条1項4号は,同法に いう著作物の例示として,「絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物」 を規定しているところ,同法2条1項1号の「美術」の「範囲に属す るもの」とは,美的鑑賞の対象となり得るものをいうと解される。そ して,実用に供されることを目的とした作品であって,専ら美的鑑賞 を目的とする純粋美術とはいえないものであっても,美的鑑賞の対象 となり得るものは,応用美術として,「美術」の「範囲に属するもの」 と解される。 次に,応用美術には,一品製作の美術工芸品と量産される量産品 が含まれるところ,著作権法は,同法にいう「美術の著作物」には, 美術工芸品を含むものとする(同法2条2項)と定めているが,美術 工芸品以外の応用美術については特段の規定は存在しない。 上記同条1項1号の著作物の定義規定に鑑みれば,美的鑑賞の対 象となり得るものであって,思想又は感情を創作的に表現したもので\nあれば,美術の著作物に含まれると解するのが自然であるから,同条 2項は,美術工芸品が美術の著作物として保護されることを例示した 規定であると解される。他方で,応用美術のうち,美術工芸品以外の 量産品について,美的鑑賞の対象となり得るというだけで一律に美術 の著作物として保護されることになると,実用的な物品の機能を実現\nするために必要な形状等の構成についても著作権で保護されることに\nなり,当該物品の形状等の利用を過度に制約し,将来の創作活動を阻 害することになって,妥当でない。もっとも,このような物品の形状 等であっても,視覚を通じて美感を起こさせるものについては,意匠 として意匠法によって保護されることが否定されるものではない。 これらを踏まえると,応用美術のうち,美術工芸品以外のもので あっても,実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離し て,美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えてい\nる部分を把握できるものについては,当該部分を含む作品全体が美術 の著作物として,保護され得ると解するのが相当である。 以上を前提に,本件原告滑り台が美術の著作物に該当するかどう かについて判断する。
ウ 控訴人は,本件原告滑り台は,一品製作品というべきものであり, 「美術工芸品」(著作権法2条2項)に当たり,創作性を有するから, 美術の著作物に該当する旨主張する。
そこで検討するに,1)「タコの滑り台,北欧に」との見出しの平 成23年7月7日の朝日新聞の記事(甲4)には,控訴人のB会長の 発言として「タコの滑り台は一つ一つデザインが違い,その都度設計 する。」,2)「タコの滑り台の話」と題するC作成の令和2年7月11 日の毎日新聞の記事(甲25)には,タコの滑り台について「一つ一 つが手作りで,全く同形の作品はないという。」,3)株式会社パークフ ル作成のウェブサイトに掲載された「日本縦断!タコすべり台がある 公園特集」と題する2018年(平成30年)1月3日付けの記事 (乙24)には,タコの滑り台について「どのタコも手作りで作られ ていて,二つとして同じ形のタコはいないんだそう!」との記載があ る。
しかしながら,上記各証拠の記載は,いずれも,B会長の発言又 は伝聞を掲載したものであって,客観的な裏付けに欠けるものである。 他方で,前記前提事実(2)及び(3)のとおり,前田商事が全国各地から発 注を受けて製作したタコの滑り台は260基以上にわたること,前田 商事が製作したタコの滑り台は,基本的な構造が定まっており,大き\nさや構造等から複数の種類に分類され,本件原告滑り台は,その一種\nである「ミニタコ」に属するものであったことからすれば,本件原告 滑り台と同様の「ミニタコ」の形状を有する滑り台が他にも製作され ていたことがうかがわれる。そうすると,上記各証拠から直ちに本件 原告滑り台が一品製作品であったものと認めることはできない。他に これを認めるに足りる証拠はない。
よって,本件原告滑り台は,「美術工芸品」に該当するものと認め られないから,控訴人の上記主張は,その前提を欠くものであって, 理由がない。
エ 控訴人は,本件原告滑り台が「美術工芸品」に当たらないとしても, 美術の著作物として保護される応用美術である旨主張する。 そこで,まず,本件原告滑り台において,実用目的を達成するた めに必要な機能に係る構\成と分離して,美的鑑賞の対象となり得る美 的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるかどうかを検\n討し,その上で,全体として美術の著作物に該当するかどうかについ て判断する。
・・・
このように,タコの頭部を模した部分は,本件原告滑り台の中でも最 も高い箇所に設置されており,同部分に設置された上記各開口部は,滑 り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不可欠な構造で\nあって,滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成であると\nいえる。また,上記空洞は,同部分に上った利用者が,上記各開口部及 びスライダーに移動するために必要な構造である上,開口部を除く周囲\nが囲まれた構造であることによって,高い箇所にある踊り場様の床から\n利用者が落下することを防止する機能を有するといえる。他方で,上記\n空洞のうち,スライダーが接続された開口部の上部に,これを覆うよう に配置された略半球状の天蓋部分については,利用者の落下を防止する などの滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成とまではい\nえない。 そうすると,本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち,上記 天蓋部分については,滑り台としての実用目的を達成するために必要な 機能に係る構\成と分離して把握できるものであるといえる。 しかるところ,上記天蓋部分の形状は,別紙1のとおり,頭頂部から 後部に向かってやや傾いた略半球状であり,タコの頭部をも連想させる ものではあるが,その形状自体は単純なものであり,タコの頭部の形状 としても,ありふれたものである。 したがって,上記天蓋部分は,美的特性である創作的表現を備えてい\nるものとは認められない。 そして,本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち,上記天蓋 部分を除いた部分については,上記のとおり,滑り台としての実用目的 を達成するために必要な機能に係る構\成であるといえるから,これを分 離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えてい\nるものと把握することはできないというべきである。 以上によれば,本件原告滑り台のうち,タコの頭部を模した部分は, 実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して,美的鑑賞 の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握で\nきるものとは認められない。
・・・
そうすると,本件原告滑り台のうち,タコの足を模した部分は,座っ て滑走する遊具としての利用のために必要な構成であるといえるから,\n同部分は,実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して, 美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分\nを把握できるものとは認められない。
・・・
前記(ア)ないし(ウ)のとおり,本件原告滑り台を構成する各部分にお\nいて,実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して, 美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部\n分を把握することはできない。 そして,上記各部分の組合せからなる本件原告滑り台の全体の形状に ついても,美的鑑賞の対象となり得るものと認めることはできないし, また,美的特性である創作的表現を備えるものと認めることもできない。\nしたがって,本件原告滑り台が美術の著作物に該当するとの控訴人の 主張は,採用することができない。
・・・
「(カ) また,控訴人は,応用美術であっても「実用目的を達成するため に必要な機能に係る構\成と分離して,美術鑑賞の対象となり得る美的 特性を備えている部分を把握できるもの」については「美術の著作物」 として保護され得るという判断基準によるとしても,「実用目的を達 成するために必要な機能に係る構\成と分離して」とは,その構成部分\nを物理的に取り除くというのではなく,実用品として必要な機能を果\nたす構成を観念的に捨象して,創作物をみることを意味すると解すべ\nきであり,本件原告滑り台を滑り台としての機能を取り去ってみたと\nき,その形状は,Aが彫刻家としての思想又は感情を創作的に表現し\nたものであり,抽象芸術として十分に鑑賞の対象になり得るものであ\nるから,美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとして,美 術の著作物に該当する旨主張する。 しかしながら,本件原告滑り台は,遊具としての実用に供されるこ とを目的として製作された作品である以上,これが美術の著作物に該 当するか否かを判断するに当たっては,実用品である滑り台としての 機能を果たす構\成を観念的に捨象して検討することはできないから, 控訴人の上記主張は,採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
2022.01. 3
令和3(ワ)15819 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年12月10日 東京地方裁判所
前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ る。
ア ツイッターの利用者がツイート等の投稿を行うには,事前にアカウントを 登録した上,ユーザー名,パスワード等を入力し,当該アカウントにログイ ンすることが必要である。そのため,アカウントの使用者は,ツイッターの 仕組み上,当該アカウントにログインした者とされている。
イ ツイッター社により開示された本件IPアドレス等の使用期間(令和3年 3月15日から同年5月7日まで)においても,本件各アカウントは,いず れも,昼夜を問わず頻繁にログインされるなど,継続的に使用されている。 (甲2ないし6,12)。
「権利の侵害に係る発信者情報」該当性
上記認定事実によれば,ツイッターの上記仕組み及び本件各アカウントの使 用状況を踏まえると,本件各アカウントにログインした者が本件各投稿をする ことによって,下記2において説示するとおり,原告の権利を侵害したものと 認めるのが相当であり,これを覆すに足りる的確な証拠はない。そうすると, ログインに関する本件発信者情報は,上記侵害の行為をした発信者を特定する 情報であるといえるから,「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するものと いえる。 これに対し,被告は,本件発信者情報が本件アカウントにログインした者の 情報にすぎず,本件各投稿を行った本件発信者の情報そのものではないことか らすると,本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない旨 主張する。 しかしながら,本件発信者情報は本件各投稿を行った本件発信者の情報であ るといえることは,上記において説示したとおりであり,被告の主張は,その 前提を欠く。のみならず,プロバイダ責任制限法4条の趣旨は,特定電気通信 による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバ シー,表現の自由,通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通\n信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し て発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより,加害者の 特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにある(最高裁平成21年\n(受)第1049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676 頁参照)。そうすると,アカウントにログインした者が,権利の侵害に係る情 報を送信したものと認められる場合には,侵害情報の送信時点ではなく,アカ ウントにログインした時点における発信者情報であっても,「権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和2(行ケ)10089 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月15日 知的財産高等裁判所
発明の要旨認定は,特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであ り,発明が属する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通 常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈するのが相当である。 もっとも,特許請求の範囲の記載の意味内容が,明細書又は図面にお いて,通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されていれ ば,通常の意味内容とは異なるものとして解される余地はあるものの, そのような定義又は説明がない場合には,上記のとおり解釈するのが 相当である。
・・・
f 本件審決の解釈の適否
(a) 本件審決の説示
本件審決は,シートシェルについて次のように説示する。 (i) 「ア.本件発明1の『シートシェル』で特定される事項」に おいて「本件発明1の『シートシェル』は,・・・『支持部』と は別個の部材であると解するのが相当である。そうすると, 『シートシェル』の定義は,『シート』の『シェル』であって,『子 供又は乳児を支持する支持部』とは別個の部材であって,『前 記支持部は前記シートシェルの内側にあ』るから,支持部が 内側にある『支持部のための構造要素』である『シェル』とい\nうことができる。」とする(本件審決第5,2(1)(1−2)ア 〔本件審決49頁9〜17行目〕)。 (ii) 前記(i)の「『シートシェル』の定義からみて,甲1発明1の 『側方支持部6を備えた背もたれ5,座部4,ヘッドレスト 10』は子供を支持する部材であるから本件発明1の『支持 部』に相当するものであり」とする(本件審決第5,2(1)(1 −2)イ〔本件審決49頁19〜21行目〕)。 (iii) 「シートシェルが,従来技術とは異なり,子供を支持する 支持部材とは別な部材であることは,以下の明細書の記載か らも明白である。」(本件審決第5,2(1)(1−2)オ(ア)〔本 件審決53頁20〜21行目〕)として,本件明細書の段落【0 008】及び【0019】を挙げる。
(b)本件審決の解釈
前記(a)の本件審決の説示を総合すると,本件審決は,本件発明の 「支持部」が,シートシェルに係る技術常識の(a)ないし(c)(前記c (a)ないし(c)により理解される「シートシェル」及び「子供を支え る柔軟性のある素材」に相当し,本件発明の「シートシェル」は, 「支持部」を内側に配置する,従来技術(技術常識)における「シ ートシェル」及び「子供を支える柔軟性のある素材」とは別異の, それらに更に追加される構造要素と解釈しているものと認められ\nる。
(c) 本件審決の解釈の適否
本件審決は,本件発明の「シートシェルが,従来技術とは異なり, 子供を支持する支持部材とは別な部材である」と解する根拠として, 本件明細書の段落【0008】や【0019】を引用するが(前記 (a) (iii)),これらの段落は,「側面衝突保護部」の配置とその作用又 は効果についての説明にとどまるものであって,「シートシェル」が 従来技術とは別異なものであるとの記載はないし,支持部について は何らの記載もないことからすると,上記段落が本件審決の上記解 釈を裏付けるものとはいえない。そして,本件発明の特許請求の範 囲の記載や本件明細書の発明の詳細な説明の記載において,前記(b) の本件審決の解釈を採用すべき根拠を見出すことはできない。した がって,前記(b)の本件審決の解釈を採用することはできない。
(d)被告の主張の検討
被告は,本件発明の「シートシェル」の解釈について,「背部側か ら支持部を構造的に保持するシェル(外殻)的構\造要素である」,「支 持部とは別個のシェル形状の一構成要素であり,子供を前部側で支\n持する支持部の背部側を外側から構造的に保持する,支持部のため\nのシェル(外殻)的構造要素であって,車両の側部から伝わる横か\nらの力がシートシェルに導かれるように側面衝突保護部を配置し たシェルである」,「シートシェルは,シートシェルの内側にある支 持部の背部側を外側から構造的に保持し,かつ側面衝突保護部を取\nり付けるのに必要とされる程度に剛性(段落【0022】)を備える シェル形状部材である」,「シートシェルはその背部側が露出してお り,シェルの名のとおり曲面形状である」などと主張する(前記第 3,1(1)ア〔被告の主張〕)。確かに,本件図面の図2,5及び6に, シートの背部に曲面形状の構造が示されているようにも見え,実施\n例において,それがシートシェルに該当するとされている。しかし, 本件明細書には,本件発明のシートシェルを,被告が主張するよう な外殻的構造の意味に限定して解釈すべき根拠となるような記載\nはなく,シートシェルという用語の解釈に当たって,本件発明が属 する技術分野における優先日前の技術常識を考慮した通常の意味 内容とは異なるように解釈すべきことを裏付ける根拠もないから, 被告の上記主張は採用することができない。
(イ) 側面衝突保護部の配置について
a 請求項1(本件発明1)により示される側面衝突保護部の配置 本件発明1は「前記シートシェルの外側で前記シートシェルに取り 付けられる側面衝突保護部」(構成要件1D)という構\成を備えるから, 本件発明1の側面衝突保護部は,シートシェルの外側でシートシェル に取り付けられるものである。そして,前記(ア)dのとおり,「シート シェル」は,剛性のある素材から成るチャイルドセーフティシートの 基本構造体であると解されることからすると,このような基本構\造体 である「シートシェル」の側面の外側に取り付けられた「側面衝突保 護部」が受けた力は,自ずと「シートシェル」に伝達されることにな る。
本件発明1は,「前記側面衝突保護部は,前記チャイルドセーフティ シートが前記車両の前記シートに取付けられた状態において,前記車 両の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力が 前記シートシェルに導かれるように,配置される」(構成要件1G)と\nいう構成を備えるところ,上記のとおり,側面衝突保護部がシートシ\nェルの外側で前記シートシェルに取り付けられること(構成要件1D),\nシートシェルは剛性のある素材から成るチャイルドセーフティシート の基本構造体であり(前記(ア)d),側面衝突保護部が受けた力は自ず とシートシェルに伝達されることに照らすと,上記の構成(構\成要件 1G)は,シートシェルの外側に取り付けた側面衝突保護部の配置(換 言すれば「取付位置」)が,シートシェルの側面の外側であることを示 すのみであり,その配置について,それ以上に何ら具体的な特定をす るものではないと認められる。
b 被告の主張の検討
被告は,請求項1(本件発明1)の「側面衝突保護部は,・・・横か らの力が前記シートシェルに導かれるように,配置される」(構成要件\n1G)という文言は,機能的限定であるから,本件明細書に記載され\nた具体的構成に基づいて限定的に解釈し,「側面衝突保護部が,チャイ\nルドセーフティシートの座部領域より上方であって,チャイルドセー フティシートの背部に配置される」ことによって,「横からの力が,支 持部(子供)には導かれず,シートシェルにのみ導かれる」ことを意 味するものと解釈すべきであると主張する(前記第3,1(1)イ〔被告 の主張〕)。
しかし,発明の要旨認定は,特許請求の範囲の記載に基づいて行わ れるべきであり,それは,特許請求の範囲の記載の中に作用又は機能\nを用いて物を特定しようとする記載がある場合であっても同様である。 本件発明1の「前記側面衝突保護部は,前記チャイルドセーフティシ ートが前記車両の前記シートに取付けられた状態において,前記車両 の側部から前記チャイルドセーフティシートに伝わる横からの力が前 記シートシェルに導かれるように,配置される」(構成要件1G)とい\nう構成には,「車両の側部からチャイルドセーフティシートに伝わる横\nからの力がシートシェルに導かれる」ということしか記載されておら ず,「横からの力が,支持部(子供)には導かれず,シートシェルにの み導かれる」とは記載されていないから,被告主張のような限定的な 解釈をとることはできない。請求項6(本件発明6)には,側面衝突 保護部の側部要素がチャイルドセーフティシートの座部領域より上に 配置されるチャイルドセーフティシートが記載され,請求項7(本件 発明7)には,側部要素がチャイルドセーフティシートの背部に配置 されるチャイルドセーフティシートが記載されており,また,本件明 細書の段落【0008】及び【0019】には,衝突による横からの 力が子供の体に直接伝わらず,子供の体を迂回してシートシェルに導 かれるように取り付けられる側面衝突保護部材に関する記載があるが, 請求項1(本件発明1)の文言を,従属請求項である請求項6及び7 の記載並びに本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0008】及び 【0019】の記載によって限定して解釈する理由はないから,被告 の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和2(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月16日 知的財産高等裁判所
特許法36条4項1号の委任する特許法施行規則24条の2は,発明の詳細な説 明の記載について,「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発 明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解 するために必要な事項を記載することによりしなければならない」と規定するとこ ろ,原告は,本件明細書からはオルニチンを用いた本件訂正発明が,どのような課 題をどのように解決したか明らかでないこと,「発酵物の乾燥重量1g当たり」「8 mg 以上のオルチニン」という数値限定に対応する課題も効果も,本件明細書に記載 がなく,当業者において本件訂正発明の課題やその解決手段を認識することはでき ないから,上記委任省令要件違反である旨主張する。
(2) 本件明細書の記載について
そこで検討するに,前記1(1)のとおり,本件明細書の段落【0226】には,「ア ルギニンについては,発酵処理によりオルニチンに変換されることが確認された。 従って,大豆胚軸にアルギニンを添加してラクトコッカス 20-92 株で発酵処理する ことにより,エクオールのみならず,オルニチンをも生成させ得ることが明らかと なった。」との記載があり,本件明細書の段落【0228】【表3】にも,発酵によ\nり,アルギニンからオルニチンが生成することが示されている。また,本件明細書 の段落【0050】には,「ダイゼイン類を含む原料」の一例である「大豆胚軸」を 用いた場合のオルニチンの含有量について,「エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥 重量1g当たりオルニチンが5〜20mg,好ましくは8〜15mg,更に好ましくは 9〜12mg 程度が例示される。」と記載されており,当業者は,本件訂正発明は,こ の好ましい量の下限を採用したものであると理解できる(前記5(5)参照)。
これらからすると,当業者は,本件訂正発明の技術上の意義は,ラクトコッカス 20-92 株で発酵処理することにより,エクオールのみならず,オルニチンをも生成さ せ得ることを明らかにし,エクオール及びオルニチンを含有する発酵物(オルニチ ンの含有量は乾燥重量1g当たり8mg 以上)の製造方法を提供したことにあること 及び発酵処理によりこれを解決することが理解できるから,本件明細書の発明の詳 細な説明の記載には,当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が 記載されているということができる。
(3) 原告の主張について
原告は,本件明細書の【発明が解決しようとする課題】段落【0010】におい てオルニチンに係る記載がないことを指摘するが,上記のとおり,特許法施行規則 24条の2は,「発明の詳細な説明の記載」に係る規定であるから,本件明細書全 体の記載から理解できれば足り,必ずしも,発明の技術上の意義を理解するために 必要な事項が「発明が解決しようとする課題」の項目に記載されている必要はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和3(行ケ)10052 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月20日 知的財産高等裁判所
以上によれば,本願補正発明の第1のステップないし第4のステップは, 全体として考察すると,分析者が,頭髪の知識等を利用して自然乾燥ヘア スタイルを推定し(第1のステップ),分析の対象となる頭部の領域を選択 し(第2のステップ),セクションに適した分類項目の中から分析者が推定 した分析対象者のヘアスタイルを分類し(第3のステップ),この分類に対 応するカット手法の分析を導出する(第4のステップ)ことを,頭の中で すべて行うことが含まれるものである以上,仮に,分析者が頭の中で行う 分析の過程で利用する頭髪の知識や経験に自然法則が含まれているとして も,専ら人の精神的活動によって前記1(1)で認定した課題の解決すること を発明特定事項に含むものであって,「自然法則を利用した技術的思想の創 作」であるとはいえないから,特許法2条1項に規定する「発明」に該当 するものとはいえない。
2022.01. 3
令和3(行ケ)10060 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月20日 知的財産高等裁判所
進歩性無しとされた請求項1は以下です。
請求項1(本件補正発明)
管理主体が存在しないパブリック型ネットワークにおいて台帳を分散して記録する複数のノードの少なくとも1つに対し,トランザクションのリクエストを送信する複数のプロセスであって,設定されるプロセス多重度に応じた複数のプロセスを生成する生成部と,
トランザクションの指示を受け付け,前記複数のプロセスのいずれかに当該トランザクションのリクエスト送信を割り当てる割当部と,を備えるシステム。
これらの記載によると,引用文献1の実験においては,スレッド当たり のリクエスト数をセキュリティ機能のOFF又はONの相違に従って固\n定し,並列スレッド数を変化させてスループット(1秒当たりのリクエス ト処理量)を測定しているのであり,「全スレッドによる合計リクエスト件 数」は並列スレッド数にのみ左右されるから,引用文献1は,専ら並列ス レッド数とスループットとの関係を測定したものであり,その測定結果と して,並列スレッド数の増加に対するスループットは,ある程度までは増 加し,一定程度で頭打ちとなり,その後は挙動不安定になるというものが 得られたとするものである。そうすると,引用文献1は,並列スレッド数 を増加させていけばスループットは増加するが,ある程度以降は挙動が安 定しなくなるので,その場合には並列スレッド数の増加による効果がなく なり,「リクエストの流量制限」で対応しなければならないと理解すべきも のであるから,その記載内容は,スレッド数の増加による効果には一定の 最大限度があることを含意するものというべきである。 以上のとおりであるから 原告の前記第3の1(1)アの主張は採用する ことができない。なお,原告は,引用文献1においては,「負荷が大きすぎ ること」,すなわち「単位時間当たりのリクエスト数が大きすぎること」を 認識するための手段としてスレッドの数を増加させてみた測定結果が記 載されているのにすぎず,このような記載をもって,「スレッド数(並列度) の制御」を,「リクエストの流量制御」における課題解決手段として読み取 ることはできないない旨主張するが,前述のとおり,引用文献1の該当部 分の記載は,単に課題認識手段としての測定結果を表示したものとはいえ\nず,スレッドの数を増加させた場合の結果に応じて,課題解決に向けた対 応策の示唆等にも及ぶものであるから,原告の前記主張は前提を欠くもの というべきである。 したがって,引用文献1には,引用発明がスレッド数を制御すること, 少なくとも,スレッドの多重度を設定し,これより,設定されるスレッド 多重度に応じた複数のスレッドを生成するものであるとの記載があると 認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和2(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年11月16日 知的財産高等裁判所
ア 特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載さ れた発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載によ り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,ま た,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当で ある。
イ 本件訂正発明の課題について
(ア) 前記1(2)によると,本件訂正発明は,連通可能な隔壁手段で区画された複数\nの室を有する輸液容器が病院で使用されているところ,輸液中には通常微量金属元 素が含まれていないことから投与が長期になると微量金属元素欠乏症を発症するが, 微量金属元素は輸液と混合した状態で保存すると品質劣化が問題となるため,依然 として輸液の投与直前に混合されているという現状に鑑み,外部からの押圧によっ て連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用い,用時に細菌\n汚染の可能性なく微量金属元素を混入することができ,かつ,保存安定性にも優れ\nた輸液製剤の創製研究が開始されたものの,含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一 室に充填して微量金属元素収容容器を同室に収容すると,当該アミノ酸輸液と微量 金属元素が隔離してあっても微量金属元素を含む溶液が不安定であるという問題が 生じることを知見し,その上で,微量金属元素が安定に存在していることを特徴と する含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを目的とするものであ る。
(イ) 上記(ア)からすると,本件訂正発明1及び2は,微量金属元素が安定に存在し ていることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを 課題とするものであるが,より具体的には,外部からの押圧によって連通可能な隔\n壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用いて,あらかじめ微量金属元素 を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤であって,含硫化合物を含む溶液を\n一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を提供 することを課題とするものと解される。同様に,本件訂正発明10及び11の課題 は,そのような輸液製剤の保存安定化方法を提供することを課題とするものである。
ウ 本件訂正発明1について
(ア) 本件訂正発明の請求項1は,前記イの課題に関し,「外部からの押圧によって 連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において」,「室\nに・・・微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されて」 いるとして,あらかじめ微量金属元素を用時に混入可能な形で保存することを特定\nしつつ,「一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも 1種を含有する溶液が充填され,他の室に・・・微量金属元素を含む液が収容され た微量金属元素収容容器が収納されており,微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂 フィルム製の袋であ」り,「前記溶液は,アセチルシステインを含むアミノ酸輸液で あり」,「前記輸液容器は,ガスバリヤー性外袋に収納されており」,「前記外袋内の 酸素を取り除いた」ものであるとして,含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場 合であっても微量金属元素が安定に存在している構成を特定しているものといえる。\n
(イ) 本件明細書の発明の詳細な説明をみると,段落【0006】及び【0007】 で輸液製剤の大枠が示された上で,輸液容器の構造や材料(同【0012】,【00\n13】),微量金属元素,特に銅イオンを安定化することができるという効果(同【0 014】),硫黄原子を含む化合物及びこれを含む溶液の例示(同【0015】,【0 016】),微量金属元素を含有する液を収容する容器の具体的な収納方法や態様(同 【0020】),微量金属元素の例示(同【0021】)や,微量金属元素の組成(同 【0022】),微量金属元素収容容器を収納している室の態様(同【0024】)や 当該室に充填され得る輸液やその組成等(同【0025】〜【0030】)が,それ ぞれ具体的に記載されている。 そして,本件訂正発明1に係る構造や材質に対応した輸液製剤の好ましい態様で\nある本件明細書の【図1】について,その構造(段落【0031】)や,微量金属元\n素を用時に混入可能とする構\成(同【0032】),輸液の充填の態様(同【003 3】),ガスバリヤー性外袋や脱酸素剤の封入とそれらの材質等(同【0035】〜 【0039】),投与時の混合の態様(同【0046】)がそれぞれ詳細に記載されて いる。
(ウ) その上で,本件訂正発明1に該当する実施例1(同【0052】,【図1】)と, これに該当せず,含硫アミノ酸を含む溶液を充填した室に微量金属元素収容容器を 収納した比較例(同【0060】,【図4】)について,具体的な製造方法や溶液(A)〜(C)の具体的な成分組成(同【0062】【表1】,【0063】【表\2】,【0064】【表3】)が示され,実施例1と比較例の重要な差異が微量金属元素収容容器\nを収納する室の差異であることが示された上で,「安定性試験」として,60゜C)で2 週間保存した後の容器の外観を肉眼で観察したところ,比較例の輸液製剤において のみ微量金属元素収容容器に着色がみられたこと(同【0065】),「銅の安定性」 について,開始時を「100.0%」とした場合,実施例1では,60゜C)で2週間 保存した場合が「100.8%」,60゜C)で4週間保存した場合が「102.6%」 であったのに対し,比較例では,60゜C)で2週間保存した場合が「88.8%」,6 0゜C)で4週間保存した場合が「69.8%」であったことが示されて(【表5】),最後に,発明の効果が記載されている(同【0066】)ところである。\nなお,上記「安定性試験」に関し,輸液製剤の保存時において含硫アミノ酸であ るシステインやその誘導体であるアセチルシステイン等が分解することにより硫化 水素ガスが発生すること,硫化水素ガスが熱可塑性樹脂フィルムを透過すること及 び硫化水素ガスが銅や鉄などの金属と反応して硫化物を生成する(水溶液中におい ては黒色の沈殿を生成する)ことは,技術常識である(甲7〜9,弁論の全趣旨)。 また,微量金属の定量分析法としては,ICP発光分光分析法が慣用技術であって, その測定法等は技術常識であると解される(甲34,35,弁論の全趣旨)。
(エ) 前記(ア)〜(ウ)によると,当業者は,本件訂正発明1の構成を採ることによって,\n同【0065】や【表5】に記載されているように,含硫アミノ酸を含む溶液を充\n填した室に微量金属元素収容容器を収納した場合と比較して,微量金属元素が安定 に存在している輸液製剤を得ることができると認識することができると解され,本 件訂正発明1は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細 な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るといえる。 したがって,本件訂正発明1がサポート要件を欠くものとはいえない。
(オ) 原告の主張について
a 原告は,本件明細書の実施例1において,アセチルシステインから発生した 硫化水素ガスが溶液(C)を充填した小袋に到達することを妨げることのできる実 施例1の構成は,小袋を収納する「第1室4」にブドウ糖を含む溶液(A)が充填\nされているとの構成1)及び外袋に「脱酸素剤9」が封入されているとの構成2)のみ であり,当業者も構成1)及び構成2)によるものであると当然に理解すると主張する。 しかし,本件訂正発明1の構成に係る本件明細書の実施例1では,アセチルシス\nテインを含む溶液(B)が「第2室5」に充填された一方で,溶液(C)を充填し た小袋は,それとは異なる室である「第1室4」に挟着されているのであって,同 小袋を「第2室5」に収納した比較例の場合と比較すると,同小袋の外面が直接溶 液(B)に触れることがないという点と,溶液(B)と溶液(C)との間に,同小 袋の構成素材に加え,「第2室5」の構\成素材及び「第1室4」の構成素材とを介す\nる状態となっている(被告のいう「三重の壁」となっている。)という点で,差異が あることが明らかである。 そして,上記の差異が,アセチルシステインから発生する硫化水素ガスが溶液(C) を充填した小袋に到達することを妨げるに当たり,何らの作用を果たさないという べき技術常識その他の事情は認められないから(なお,被告の実験報告書[甲21, 36,乙1]を排斥して専ら原告の実験報告書[甲19,20,23]の結果の信 用性を認めるべき事情は見当たらない。),当業者の理解に係る原告の上記主張は採 用することができない。 したがって,当業者において,本件明細書の実施例について専ら構成1)及び構成\n2)により微量金属元素の安定が図れたと理解することを前提とする原告の主張は, 本件訂正発明1における「他の室」が空室である場合についての主張も含め,いず れも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和3(ワ)3208 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年11月9日 大阪地方裁判所
(1) 著作権法114条3項に基づく使用許諾料相当の損害について
ア 証拠(甲1,2,4〜9,18,乙2,3[各枝番を含む。])及び弁論の全 趣旨によれば,原告製品は,オンラインストア等で顧客に対し販売されていること, 原告製品には,永久ライセンス版と,使用期間を1か月,1年,3年に制限したサ ブスクリプション版が存在するところ,これらの動作種別は,ライセンス認証時に 原告から送付される認証コードの種別により決せられることが認められるが,被告 は,前記認定のとおり,本件海賊版製品の落札者に対し,本件海賊版製品と共に, ライセンス認証を回避する不正なプログラム,及びインターネットに接続せずにイ ンストールをすること等を指示するマニュアル等を添付して,落札者をして前記ラ イセンス認証システムを無効化させ,これによって,落札者は,使用期間の制限な く本件海賊版製品を使用することが可能になったことが認められる。\nこれらの事実関係に照らすと,原告製品の永久ライセンス版の定価をもって,原 告が原告製品の著作権の行使につき受けるべき価額であると認めるのが相当である。
イ これに対し,被告は,原告製品の定価をもって著作権法114条3項の使用 料相当額とすることは,最低限の賠償額を保障した同3項の趣旨及び文理に反する 旨を主張する。しかし,被告販売行為により,落札者は,もともとの原告製品の使 用期間制限の有無や期間にかかわらず,使用期間の制限なく本件海賊版製品を使用 することが可能となるのであり,これによって,原告は,被告販売行為がなければ\n得られたであろう永久ライセンス版の定価の額に相当する額を得られなかったこと になるし,被告販売行為の態様は,本件海賊版製品をライセンス認証を回避しつつ インストールすることができるよう販売するという悪質なものであり,その違法性 は高く,市場への影響も大きい。 被告は,原告製品の定価と原告製品の使用料相当額として受けるべき金銭の額と は別である旨を主張するが,原告製品のようなアプリケーションプログラムの販売 価格は,その本質において著作物の使用許諾に対する対価というべきであるから, 前述のとおり,原告製品の定価をもって,著作権法114条3項が定める著作権の 行使につき受けるべき金銭の額と見ることができるのであり,被告の主張は理由が ない。
また,被告は,原告製品と動作環境との適合性や進化するセキュリティソフトと\nの相性の問題等があるため,本件海賊版製品を期間の制限なく使用できることはあ り得ないことから,原告製品の永久ライセンス版の価格を使用許諾料の基準とする のは相当でないこと,あるいは,原告製品の期間契約には,1か月,1年及び3年 の各期間設定があるところ,契約期間が長くなれば割安になることから,原告製品 のうち永久ライセンス版が設定されていないものについて1年ライセンス版の価格 を使用許諾料の基準とするのは相当でないことを主張する。しかし,前述したとお り,被告販売行為により,落札者は,もともとの原告製品の使用期間制限の有無や 期間にかかわらず,使用期間の制限なく本件海賊版製品を使用することが可能とな\nるのであり,その時点で原告には原告製品の永久ライセンス版の定価相当額の損害 が発生したというべきであって,その後,動作環境等により本件海賊版製品を使用 できなくなる可能性があることやもともとの原告製品には期間制限があることなど\nの事情は,損害額の算定には影響しないと解するのが相当である。
ウ 証拠(甲2の1〜2の18)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品の永久ラ イセンス版の定価は,別紙2−1「原告損害一覧表1」及び同2−2「原告損害一\n覧表2」の各「原告製品価格」欄記載の価格をくだらないことが認められ,被告販\n売行為による原告の損害は,同各「原告損害」欄記載の合計10億5509万67 50円をくだらない。
(2) 弁護士費用相当の損害について
被告販売行為と相当因果関係のある弁護士費用は,原告が主張する弁護士費用1 億0550万円をもって相当と認める。
関連カテゴリー
>> プログラムの著作物
>> 複製
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2022.01. 3
令和3(ネ)10043 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上からすると,当業者によって,当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは,低地球温暖化係数の化合物である HFO−1234yfを調整する際に,不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや,低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが,当初明細書中には,沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては,記載も示唆もされていないから,その主張は前提を欠く し,このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば,それは新たな技術的事項を導入するものであり,まさしく新規 事項の追加にほかならない。
◆判決本文
1審はこちら
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新たな技術的事項の導入
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.11.30
令和3(ネ)10058 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお,事案に鑑み,念のため,被告製品の均等論の第1要件の充足につい て判断する。
本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書の開示事 項を総合すれば,本件発明1は,従来の遠隔監視システムでは,施設の侵入 者があったり,施設において異常が発生した場合に,当該施設の所有者や管 理責任者が一次的に当該侵入や異常発生を知ることができず,また,警備会 社からの二次的な通報により上記所有者や責任者が侵入や異常発生を知るこ とは可能であるが,これらの者が外出している場合等には警備会社が通報を\nすることができないといった課題があり,こうした課題を解決するために, 構成要件1Bないし1Gの構\成を採用し,施設の監視対象領域を監視する監 視装置からのメッセージと監視装置によって得られた画像の情報が当該施設 の所有者や管理責任者に対応する顧客の携帯端末に通知又は伝達されること により,顧客が何れの場所においても施設の異常等を適切に把握することが できるとともに,監視装置から受理された画像の略中央部分の画像からなる コンテンツを携帯端末に伝達することにより,表示装置が小さい携帯端末で\nも顧客により十分に認識可能\な画像を表示することができ,さらに,カメラ\nの「パンニング」を含む携帯端末からの遠隔操作命令により「パンニング」 に従った領域を特定し,その領域の画像を携帯端末に伝達するステップを備 え,顧客が参照したい領域を特定して携帯端末に提示することができるよう にしたことにより,施設の所有者や管理責任者が外部からの侵入や異常の発 生を知り,その内容を確認することができるという効果を奏するようにした ことに技術的意義があるものと認められる(【0004】ないし【0007】)。 このような技術的意義に鑑みると,本件発明1の本質的部分は,1)何れの 場所においても顧客が携帯し得るものとして,監視装置からの異常検出によ って監視装置により撮影された画像データの伝達を受ける端末を「携帯端末」 とし,2)「携帯端末」に伝達する画像は,略中央部分の画像領域から構成さ\nれ,3)携帯端末からの「パンニング」を含む遠隔操作命令を受理し,その領 域の画像を携帯端末に伝達するステップを含むことにより,4)表示装置が小\nさい携帯端末でも,顧客により十分に認識可能\な画像を表示することができ,\nさらに,携帯端末からの遠隔操作命令により,顧客が参照したい領域を特定 して携帯端末に提示することができるようにした点にあるものと認められる。 すなわち,単にセンサの情報伝達の宛先を警備会社の中央コンピュータから 施設の所有者等の携帯端末に切り替えたことのみに重きがあるわけではなく, 何れの場所においても顧客にとって携帯が容易で,操作等が迅速かつ簡便で あるためには表示装置が小さい端末とならざるを得ない面があるところ,そ\nうであっても,外部からの侵入や異常の発生を知り,その内容を確認するこ とが十分に可能\な構成を有することが本件発明1の本質的部分であるという\nべきである。なお,本件発明2及び3は本件発明1(請求項1)の従属項で あり,また,本件発明5は,本件発明1の遠隔監視方法の発明を監視制御サ ーバに関する発明としたものであるから,これらの発明の本質的部分もこれ に同様である。
これに対し,被告製品は,監視装置からの異常検出によって監視装置によ り撮影された画像データを伝達する端末は,携帯電話のような表示装置が小\nさい端末ではなく,また,端末からの遠隔操作命令により受理された画像の うち他の領域の画像を参照すること示す命令である「パンニング」を含む遠 隔操作命令を受理し,その領域の画像を携帯端末に伝達するステップを含ま ないため,顧客が何れの場所においても施設の異常等を適切に把握すること ができ,表示装置が小さい「携帯端末」でも顧客は十\分に認識可能な画像を\n表示することができ,顧客が参照したい領域を特定して「携帯端末」に提示\nすることができるようにしたことにより,施設の所有者や管理責任者が外部 からの侵入や異常の発生を知り,その内容を確認することができるという本 件各発明の効果を奏するものと認めることはできない。 したがって,被告製品は, 本件各発明の本質的部分を備えているものと認 めることはできず,被告製品の相違部分は,本件各発明の本質的部分でない ということはできないから,均等論の第1要件を充足しない。 よって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品は,本件各発 明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められない。\n
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.11.22
令和3(ワ)2526 発信者情報開示請求事件 令和3年9月6日 大阪地方裁判所
本件テロップと本件記事の各内容を比較すると,本件記事には本件テロップと完全に一致する表現が多数含まれる。他方,相違する部分は,句読点の有無や助詞の違い,文言の一部省略等の僅かな相違のほか,例えば,次のような相違部分が存在する。これらの相違部分は,表\現の手法等に若干の違いが見られるものの,内容的には,本件テロップの表現を若干修正したり,要約又は省略したり,前後の表\現を入れ替えるなどしているにとどまり,実質的にほぼ同一の内容を表現したものといえる。\n
1) 本件テロップ:「ドイツ出身のヴァレンティンさんは幼い頃からずっと動物 を大切に思ってきました。」
本件記事:「この感動のストーリーは2人の人間から始まります。その1人がヴァ レンティンさん。ヴァレンティンさんはドイツ出身。幼い頃よりずっと動物を大切 に思ってきました。」
2) 本件テロップ:「2人はボツワナで自然保護プロジェクトを立ち上げました。 野生動物の保護を目的とするプロジェクトです。」
本件記事:「2人はボツワナで野生動物の保護を目的とする自然保護プロジェクト を立ち上げました。」
3) 本件テロップ:「メスのライオンで非常に弱っており,瀕死の状態です。」
本件記事:「そのメスの幼いライオンで非常に弱っており,瀕死の状態です。」
4) 本件テロップ:「けれどシルガにとって,人間に慣れてしまう事は危険な事で す。」
本件記事:「しかし,人間に慣れてしまってはいけません。」
5) 本件テロップ:「そう決めた2人は決して他の人間をシルガと交流させたりし ませんでした。」
本件記事:「他の人間とは交流させませんでした。」
6) 本件テロップ:「2人は本当にシルガの為を思い,幸せを願っていたのです。」
本件記事:「2人はシルガの幸せ,野生に戻る事を1番に考えていました。」
7) 本件テロップ:「ヴァレンティンさんとミッケルさんは,シルガの世話をする だけでなく狩りの仕方も教えます。」
本件記事:「2人は世話だけでなく,狩りの仕方も教えます。」
8) 本件テロップ:「何度も何度も練習を重ね,ようやくシルガが獲物を狩る事が 出来るようになった頃,2人は複雑な気持ちに襲われはじめていました。」
本件記事:「狩りの練習を何度も練習を重ね,ようやくシルガは獲物を狩る事が出 来る様になった頃,2人は複雑な気持ちになりました。」
9) 本件テロップ:「そしてシルガは予想を上回る反応を示します。」
本件記事:「そこで予想を超える事に。」
10) 本件テロップ:「ずっとヴァレンティンさんに会えずに寂しく思っていた事が, その表情から伝わります。」
本件記事:「ずっとヴァレンティンさんに会えず,さみしかった事が分かります。」
(2) 複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製 することをいうところ(著作権法2条1項15号),著作物の複製とは,既存の著作 物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表\現することなく,その表現上の本質\n的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうものと解される。また,\n翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表\現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表\現上の本質的な特徴 を直接感得することができる別の著作物を創作する行為をいうものと解される(最 高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻 4号837頁参照)。
本件記事は,記事中に本件動画が埋め込まれていること(甲5)や,上記のとお り,本件テロップと完全に一致する表現を多数含み,相違する部分も,句読点の有無等の僅かな形式的な相違のほか,本件テロップの表\現の僅かな修正,要約,前後の入れ替え等にとどまり,実質的にほぼ同一の内容を表現したものであることに鑑みると,本件テロップに依拠したものと認められると共に,著作物である本件テロッ\nプの表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者がその特徴を直接感得できるものと認められる。\n
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2021.11.22
令和3(ネ)10007 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「室」という語は,一般的には,「へや」すなわち「物を入れる所」などを 意味する語であるところ(甲27),構成要件1A及び2Aの文言のほか,前記2(2)の本件各訂正発明の概要及び前記(1)の本件各訂正発明の課題を踏まえると,構成要件1A及び2Aの「複数の室を有する輸液容器」の要件は,複数の輸液を混合\nするのに用いられる従来技術であるそのような輸液容器を用いる輸液製剤であるこ とを示すことによって,本件訂正発明1及び2の対象となる範囲を明らかにするも のである。本件各訂正発明の課題は,そのような輸液容器を用いて,あらかじめ微 量金属元素を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤で,含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を\n提供することにあるから,本件各訂正発明における「室」の意義の解釈に当たって は,上記の一般的な意義のほか,輸液容器における「室」の意義も考慮するのが相 当である。
そこで検討すると,本件特許の出願当時には,輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構\成される空間であって,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた空間を「室」と呼んだ上で(乙31),その「室」の中に 収納される,薬剤を収容する構成部材を「容器」と呼んだり(甲25,乙17),その「室」の外側に付加して空間を構\成する部材を「被覆部材」と呼んだり(乙16),その「室」に連通される「ポート部材」が薬剤を収容し得る機能を備えるものとしたり(乙12),その「室」を分割したものを「区画室」と呼んだり(乙5)すると\nいった例があった。本件特許の出願後も,上記基礎となる一連の部材によって構成される「室」の中に収納される,薬液を収容する構\成部材を「容器」や「袋」などと呼ぶ例が複数みられるが(甲14,15,乙19),そのように,輸液等を収容す るという機能を有する部分を指す語として「室」以外の語が加えられている中においても,「室」という語は,基本的に,輸液容器全体の構\成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって,輸液を他の輸液と分離して収容しておくために仕切られた相対的に大きな空間を指すものとして用いられ,「容器」や「袋」の\n付加の有無にかかわらず,そのような「室」が複数あるものが「複室輸液容器」な どと呼ばれていたことがうかがわれる(なお,上記のうち,甲15は,大きな「隔 室」の中に「内袋」があり,その「内袋」が更に複数の「薬剤収容室」で構成されているというものであり,「室」の中に「室」があるという点では,やや珍しいもの\nともみられるが,各「隔室」と各「薬剤収容室」は,あくまでそれぞれ一連の部材 によって構成されている。)。そして,上記のような「室」の理解は,本件明細書の記載とも整合的である。\n
(イ) 上記(ア)の点を踏まえると,構成要件1A及び2Aにいう「室」についても,輸液容器全体の構\成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって,\n輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間をい うものと解するのが相当である。
イ 「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器」について\n
もっとも,本件訂正発明1の構成要件1A及び本件訂正発明2の構\成要件2Aに おいては,「複数の室を有する輸液容器」の前に,「外部からの押圧によって連通可 能な隔壁手段で区画されている」との特定が付加されている。そうすると,上記特定により,「室」が「連通可能\な」ものであることが明確にされているというべきであるから,構成要件1A及び2Aにおける「室」については,「外部からの押圧によって連通可能\な」ものであることを要するものである。
ウ 被控訴人製品について
(ア) 「室」について
a 先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第2の1(7)ア及び弁論の全趣旨 によると,被控訴人製品に係る輸液容器について,その構成の中で基礎となる一連の部材によって構\成される空間は,大室及び中室を直接構成するとともに小室T及\nび小室Vの外側を構成する一連の部材によって構\成される空間であるといえる。
b もっとも,小室Tに関しては,外側の樹脂フィルムによって構成される空間が,上記のとおり輸液容器全体の構\成の中で基礎となる一連の部材によって構成さ\nれる空間である一方で,連通時にも,内側の樹脂フィルムによって構成される空間(本件袋)にのみ輸液が通じることとされており,小室Tの外側の樹脂フィルムに\nよって構成される空間に輸液が直接触れることがない。そのため,小室Tの外側の樹脂フィルムによって構\成される空間が,前記の「室」の理解のうち,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間に当たるかどう かが問題となり得る。 しかし,輸液容器全体の構成を踏まえると,被控訴人製品における小室Tは,外側の樹脂フィルムによって構\成される空間の中に,内側の樹脂フィルムによって構\n成される空間(本件袋)を内包するという二重の構造になっているにすぎず,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための空間としての構\成において,外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間に機能の優劣等があるとはみられない。この点,小室Tと中室との間の接着部について,内側の樹脂フィルムの接着を剥離した\n場合のみならず,外側の樹脂フィルムの接着のみを剥離した場合であっても小室T の外側のフィルムの内側の空間に中室に収容された輸液が流入してこれが本件袋の 外面に直接触れることとなり,中室内の輸液と本件袋の中の液との分離の態様に少 なからず差異が生じるのであり,輸液同士の混合という点では専ら小室Tの内側の 樹脂フィルムの接着部分が意味を持つとしても,隣接する中室内の輸液からの分離 という観点からは,外側の樹脂フィルムにも重要な意義があることは明らかである。 そして,内側の樹脂フィルムによって構成される空間(本件袋)は,被控訴人製品に係る輸液容器において基礎となる一連の部材とは別の部材により構\成され,上記基礎となる一連の部材に構成を追加する部分である(このことは,小室Vの内側の樹脂フィルムによって構\成される空間と対比しても,明らかである。)。以上の諸点を踏まえると,小室Tについても,被控訴人製品に係る輸液容器の構成の中で基礎となる一連の部材である外側の樹脂フィルムによって構\成される空間(本件小室T)をもって,「室」に当たるとみるのが相当である。
c ところで,被控訴人製品の小室Tの外側の樹脂フィルムによって区画される 空間のように,輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構\成され る空間が,輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大き な空間であるといえるか疑問があり得るような場合に,本件各訂正発明の「室」を どのように理解すべきかについて,本件訂正発明1及び2に係る請求項の文言上は, 必ずしも明らかであるといえないから,そのような場合における「室」の理解につ いて,本件明細書の内容を踏まえた検討も行うと,本件明細書の段落【0024】 は,「微量金属元素収容容器を収納している室」には,溶液が充填されていてもよ いし,充填されていなくてもよい旨を明記しており,同【0033】は,「本態様 の輸液製剤では,図1に示す輸液容器の第1室4に,溶液が充填されていてもよい し,充填されていなくてもよい」と明記しているところであるから,本件各訂正発 明においては,輸液が充填される空間であるか否かという点は,「室」であるか否か を決定する不可欠の要素ではないと解される。 それゆえ,前記bのような理解は,本件明細書における「室」の理解にも沿うも のであるといえる。
d 以上に対し,被控訴人らは,被控訴人製品において,小室Tの外側の樹脂フ ィルムによって構成される空間(本件小室T)は存在しないと主張するが,2枚の樹脂フィルムの間に空間が構\成されている(その空間中には,2枚の内側の樹脂フィルムの間の空間(本件袋)が包摂されている。)こと自体は,明らかであり,被控 訴人らの主張は採用することができない。
(イ) 「連通可能」について
a 前記(ア)のとおり,「室」については理解すべきものであるとしても,前記イ のとおり,構成要件1A及び2Aにおいては,「室」が「連通可能\」であることが要 件とされているところ,前記(ア)bで既に指摘したとおり,小室Tに関しては,連通 時にも,内側の樹脂フィルムによって構成される空間(本件袋)にのみ輸液が通じることとされており,「室」である外側の樹脂フィルムによって構\成される空間(本件小室T)に輸液が通じることはない。 そうすると,結局,被控訴人製品は,「室」が「連通可能」という要件を充足しないから,構\成要件1A及び2Aを充足しないというべきである。
b これに対し,控訴人は,本件小室Tに収納された本件袋に輸液が通じること は,本件小室Tに輸液が通じることといえる旨を主張する。この点,前記(ア)dのと おり,本件小室Tという空間が本件袋という空間を包摂していることは確かに認め られるが,そのことと,本件袋との連通をもって本件小室Tとの連通と評価し得る かは,別の問題である。本件訂正発明1及び2に係る請求項1及び2が「室」と「容 器」を明確に分けていることや,前記ア(ア)で指摘した「室」と「容器」についての 技術的な関係のほか,本件明細書の段落【0020】の「微量金属元素収容容器は, それを収納している室と連通可能であることが望ましい。」という記載は,容器の連通が室の連通とは異なるものとみる見方に沿うものであることからすると,控訴人\nの上記主張を採用することはできない。
(3) 争点(4)について
構成要件10A及び11Aの「複室輸液製剤」にいう「室」についても,前記(2) アと同様に解するのが相当である。 そして,構成要件1A及び2Aと異なり,構\成要件10A及び11Aについては, 「室」が「連通可能」であることは要件とされていない。したがって,先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第2の1(7)イ及び弁論 の全趣旨により,被控訴人方法は,構成要件10A及び11Aを充足するというべきである。\n
4 争点(2)(構成要件10C及び11Cに係る点に限る。)について
前記3(2)及び(3)で指摘した点を踏まえ,先に引用した原判決の「事実及び理由」 中の第2の1(7)イ及び弁論の全趣旨によると,被控訴人方法においては,「含硫ア ミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する溶液を収 容している室」である中室とは「別室」である小室Tの外側の樹脂フィルムによっ て構成される「室」(本件小室T)に,構\成要件10C又は11Cで特定された微 量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器である,小室Tの内側の樹 脂フィルムによって構成される本件袋が収納されていると認められる。したがって,被控訴人方法は,構\成要件10C及び11Cを充足する。
◆判決本文
1審は、構成要件1C、10Cを具備しないので、技術的範囲に属しないと判断していました。
◆平成30(ワ)29802
以上の記載によれば,本件各発明については,次のとおりのものである旨
認めることができる。
すなわち,まず本件各発明の技術分野は,経口・経腸管栄養補給が不能又は不十\分な患者に対して,経静脈からの各種輸液(糖製剤,アミノ酸製剤,電解質製剤,混合ビタミン製剤,脂肪乳剤等)の投与を行うための輸液製剤
に関するものである。この点,当該輸液製剤は,経時変化を受けることなく
保存し,その使用時に細菌による汚染なく混合するため,連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器に収容される。\nしかして,輸液中には,通常,銅等の微量金属元素が含まれていないこと
から,患者は,輸液の投与が長期になるときにはいわゆる微量金属元素欠乏
症を発症することとなる。しかるところ,これを予防するために必要な微量金属元素を輸液と混合した状態で保存すると,化学反応によって品質劣化の\n原因になり,これを防ぐべく含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填
し,微量金属元素収容容器を同室に収容すると,当該アミノ酸輸液と微量金
属元素とを隔離していても,微量金属元素を含む溶液が不安定となるという
技術的課題が生じていた。
本件各発明は,このような技術的な課題に対して,連通可能な隔壁手段で区画されている複室の一室に含硫アミノ酸を含有する溶液を充填し,これと\nは他の室に,微量金属元素を収容した容器を収納するという構成を採用することにより,上記技術的な課題を解決し,微量金属元素が安定に存在してい\nることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供するとい
う効果を奏するようにしたものであるというべきである。
そうである以上,本件各発明の課題解決の点における特徴的な技術的構成は,微量金属元素収容容器を,含硫アミノ酸を含有する溶液と同じ室ではな\nく,同室と連通可能な他の室に収納するという構\成を採用したところにある
ものというべきである。そして,これは,連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として,その複数の各「室」に\nついては,それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造となっており,上記の微量金属元素収容容器を収納する「室」は,含硫アミノ酸を含有する\n溶液とは異なる輸液の充填・保存のための構造となっている「室」であるという技術的構\成が採用されたものということができる。すなわち,本件各発明において,構成要件1Aの「複数の室」及び構\成要
件10Aの「複室」は,各種輸液を充填して保存するための構造となっている各空間を意味すると解されることから,輸液容器に設けられた空間がその\n一室である構成要件1C及び10Cの「室」に当たるためには,当該空間が輸液を充填して保存し得る構\造を備えていることを要すると解するのが相当であり,これに反する原告の前記主張は採用できない。
この点,証拠(甲2)によれば,本件明細書には,発明の詳細な説明とし
て,「(略)また,微量金属元素収容容器は,それを収納している室と連通
可能であることが好ましい。(以下,略)」(段落【0020】)との記載や,「上記『微量金属元素収容容器を収納している室』には,溶液が充填さ\nれていてもよいし,充填されていなくてもよい。(以下,略)」(段落【0
024】)との記載のあることが認められる。しかしながら,前者の記載に
ついては,前記で説示した本件各発明の技術的意義に照らせば,微量金属元
素収容容器が上記のような意味の「室」に収納されていることを前提とする
記載であり,同容器が輸液を充填して保存し得る構造を備えていない構\成の
ものに収納されている場合をも許容する趣旨であるとは解されない。また,
後者の記載についても,同様に,「微量金属元素収容容器を収納している
室」には,輸液が充填されていない構成のものも含まれることを述べたものにすぎず,そもそも輸液を充填して保存するための構\造となっていない構成\nのものまで含まれることを意味したものと解することはできない。
したがって,これらの記載によっては,前記判断は左右されず,その他,
本件明細書の記載内容を詳細に検討しても,前記判断を左右し得る記載は見
当たらない。
そこで,これを被告製品ないし被告方法について見ると,
及び弁論の全趣旨によれば,小室Tの内側の樹脂フィルムで形成された袋を
覆っている外側の樹脂フィルム2枚は,中室側及び小室V側の両端部におい
て内側の樹脂フィルムと溶着されており,使用時にも当該溶着部分は剥離し
ないと認められる。
そうすると,小室Tの外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の
空間は,使用時に中室及び小室Vと連通するものではなく,これに照らすと,
同空間が,輸液を充填して保存し得る構造を備えているものとは認められないといわざるを得ず,同空間が「室」に当たるということはできない。\nしたがって,被告製品及び被告方法は構成要件1C及び10Cの「室に・・・微量金属元素収容容器が収納」されている構成を具備するとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 間接侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.11.16
令和3(ネ)10047 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年10月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(ア) 控訴人X1は,被控訴人は形式的な権利者にすぎないから,利用申\n込みを拒否するに当たり,実質的な権利者である委託者や受益者の意思 を確認すべき義務があり,本件利用申込み1の対象楽曲には控訴人X1\nの作詞及び作曲に係る本件3曲が含まれていたから,通常の委託者であ れば許諾を望むと考えられるにもかかわらず,控訴人X1及びブラステ ィーの意思の確認を怠った旨主張する。
しかし,まず,引用する原判決の第2の2(6)エ(補正後のもの)のと おり,被控訴人は,本件著作権契約によりその権限を得たブラスティー から本件3曲の楽曲の著作権の信託譲渡を受けており,形式的にも実質 的にも本件3曲の著作権者であることから,被控訴人が「形式的な権利 者」であるとする控訴人X1の上記主張はそもそも当を得ない。 また,この点を措くとしても,被控訴人は,著作者等から委託を受け て多数の楽曲の著作権等を集中的に管理しており,委託者もこうした管 理の実態を前提として楽曲の委託をしているから,利用者からの申込み\nを拒絶することについて「正当な理由」があるか否かは,個々の委託者 の利害や実情にとどまらず,著作権等に関する適正な管理と管理団体業 務への信頼の維持の必要性等についても勘案した上で,利用者からの演 奏利用許諾の申込みを許諾することが通常の委託者の合理的意思に反す\nるか否かの観点から判断されるべきことは前記アで説示したとおりであ る。そして,本件においては,通常の委託者の合理的意思に照らし,同 申込みを拒絶することについて「正当な理由」があると認められること\nは,前記イで説示したとおりであり,その結論は,本件利用申込み1に\n本件3曲が含まれているか否かによって左右されるものではないから, 受託者である被控訴人が本件3曲に関して委託者兼受益者であるブラス ティーの意向を確認すべき義務があったとはいえず,まして本件3曲に 関する本件約款上の受益者でもない控訴人X1の意向を確認すべき義務 があったとは到底いえない。
(イ) 控訴人X1は,本件利用申込み1は別件訴訟を有利にするためにA\nらの呼びかけに応じたものではなく,Aらとも親しい関係にはないし, 本件店舗は控訴人X1がライブ演奏を行う1つの店にすぎず,平成28 年4月6日に本件店舗で被控訴人管理楽曲を演奏した際は1曲140円 を供託した上で演奏しており,著作権侵害に加担していないなどと主張 する。 しかし,前示のとおり,本件利用申込み1は,著作権の管理に係る被\n控訴人の方針や別件一審判決を不服とし,ライブ演奏の予約済みの出演\n者等に被控訴人管理楽曲を演奏する場合には出演者が被控訴人に利用申\n込みをするようホームページで公表された後にされたものであり,また,\n控訴人X1は,本件店舗に21回の出演歴があり,別件一審判決直後も 無許諾で被控訴人管理楽曲を演奏していたこと等を踏まえると,控訴人 X1の主観的意図はともかく,外形的,客観的に見れば,同申込みは,\n無許諾で長期間にわたって被控訴人管理楽曲を使用してきた本件店舗の 運営に賛同し,支援するものと受け止められてもやむを得ないものであ る。なお,本件全証拠を精査しても,平成28年4月6日に開催された 本件店舗のライブ演奏に当たって,控訴人X1が被控訴人管理楽曲の演 奏使用料を供託したとの事実を認めることはできない(本件店舗の経営 者らに被控訴人管理楽曲の使用料を手渡したとしても,それが供託に当 たるものではないことはいうまでもない。)。
エ また,控訴人X1は,当審においてそれぞれ以下のとおり主張するが, いずれも理由がない(なお,前記イ及びウと重複する部分は説示しない。)。
(ア) 控訴人X1は,前記第2の4(1)ア(ア)のとおり,被控訴人は,係争 中の店舗における演奏を予定する第三者からの演奏利用許諾の申\込み については一切受け付けない方針の下,本件利用申込み1について「正\n当な理由」の審査を行うことなく,本件店舗が使用料未清算であるとい った理由のみで拒否したものであり,こうした拒否は,使用料を徴収す るための私的制裁措置であって独占禁止法19条で禁止される優越的 地位の濫用に当たる旨主張する。
確かに,被控訴人は,被控訴人管理楽曲の利用許諾を得ることなく営 業の一環として演奏した店舗との間では,その店舗が過去の楽曲の使用 料を清算しなければ,新たに被控訴人管理楽曲に係る演奏の利用許諾を しないこととしており,また,その店舗において無許諾の利用があり, 楽曲の使用料の清算が未了であれば,第三者からその店舗における被控 訴人管理楽曲の利用の申込みがあっても,その楽曲の利用がその店舗の\n営業の一環として行われるものである限り,利用の許諾をしない取扱い をしている(前記認定事実1(4)イ)が,楽曲の演奏の利用許諾の申込み\nについて拒否したことに「正当な理由」があるか否かは,演奏利用許諾 の申込みの時点における事情を踏まえた事後的な法律判断というべきで\nあり,演奏利用許諾の申込みを拒否した際に示した理由に拘束されるも\nのではない。そして,本件においては,上記申込みの時点でAらと被控\n訴人間には著作権侵害等に係る裁判が係属しており,被控訴人は,平成 22年9月24日以降,職員を本件店舗のライブに客として派遣し,ラ イブ名,演奏曲目や演奏時間等の実態調査等をしており,また,本件店 舗のホームページ等を調査することを通じて,控訴人X1の本件店舗の 出演歴や本件申込みがされた経緯等を把握していたことが認められるの\nであり(前記認定事実1(2),(3)ア,イ,(4)ア),このような事情を踏 まえると,本件利用申込み拒否1に「正当な理由」があることは,現に\n拒否時に示された理由等にかかわらず,揺らぎ得ない。そして,本件利 用申込み拒否1に「正当な理由」がある以上,それが私的制裁措置であ\nって優越的地位の濫用に当たるなどという控訴人X1の上記主張も当を 得ないというほかない。
なお,控訴人X1は,前記第2の4(1)ア(イ)のとおり,被控訴人が控 訴人X1による本件利用申込み1を拒否した当時,別件訴訟の判決は確\n定していなかったにもかかわらず,被控訴人は,本件店舗の経営者らが 被控訴人管理楽曲の使用料相当額を清算していないものと決めつけて控 訴人X1による被控訴人管理楽曲の演奏利用許諾の申込みを拒否してお\nり,こうした被控訴人による拒否は優越的地位の濫用であり,本件約款 における受託者としての忠実義務にも反するとも主張する。しかし,債 権者は,事実的,法律的根拠があれば,判決の確定を待つことなく,債 務者との間の権利義務関係があることを前提とした措置を執ることはで きる(判決の確定により債権が存在しないことが明らかとなったときは, その措置により生じた損害を賠償すべきことは無論である。)ところ, 被控訴人による措置が事実的,法律的根拠を明らかに欠いているといっ た事情は見当たらない(後に別件訴訟はAらの敗訴で確定している。)。 したがって,被控訴人が講じた措置は優越的地位の濫用に当たらず,受 益者との関係で忠実義務に反するものでもない。
(イ) また,控訴人X1は,前記第2の4(1)イのとおり,控訴人X1が被 控訴人管理楽曲の利用料の支払を申し出て音楽著作物の演奏利用許諾を\n求めているのであるから,受託者である被控訴人がこれを拒否すること は信託法上の忠実義務に反する旨主張する。
しかし,前記アで説示したとおり,被控訴人が多数の委託者からの委 託を受けて楽曲に係る著作権等を集中的に管理しており,委託者も広く 楽曲の利用がされることを期待して被控訴人による楽曲の集中管理を前 提とした委託をしている以上,被控訴人による楽曲全体の著作権等に関 する適正な管理と管理団体としての業務全般の信頼の維持という観点を 軽視することは相当でない。そして,本件利用申込み1がされた経緯や\n時期等を踏まえると,控訴人X1が使用料の支払を申し出て被控訴人管\n理楽曲の演奏利用の許諾を求めたとしても,これに許諾を与えることは, 本件店舗の運営姿勢を是認し,安定的な著作権の管理,使用料の徴収に 支障を生じさせることにつながりかねないものであるといわざるを得ず, 通常の委託者の合理的意思に反するものであって,被控訴人の管理団体 としての業務の信頼を損ねかねないものである(なお,本件のような状 況下においては,支払がされる確実性についての信頼関係も希薄になら ざるを得ないと解される。)。控訴人X1の上記主張は,個別の委託者 兼受益者の実情を重視して本件利用申込み1を拒否することが特定の楽\n曲の委託者兼受益者の信託法上の忠実義務に反するというものであって, 被控訴人による多数の楽曲に係る著作権等の集中管理の実態を見ないも のというほかなく,当を得ない。
2021.11.16
令和3(ネ)10048 著作権侵害行為差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年10月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
著作権法は,著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであっ\nて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの(同法2条1項1号) をいい,複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有 形的に再製することをいう旨規定していること(同項15号)からすると, 著作物の複製(同法21条)とは,当該著作物に依拠して,その創作的表\n現を有形的に再製する行為をいうものと解される。 また,著作物の翻案(同法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ, その表現上の本質的な特徴である創作的表\現の同一性を維持しつつ,具体 的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表\ 現することにより,これに接する者が既存の著作物の創作的表現を直接感\n得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される。 そうすると,被告レジュメが原告ワークブックに係る著作物を複製又は 翻案したものに当たるというためには,原告ワークブックと被告レジュメ との間で表現が共通し,その表\現が創作性のある表現であること,すなわ\nち,創作的表現が共通することが必要であるものと解するのが相当である。\n一方で,原告ワークブックと被告レジュメにおいて,アイデアなど表現そ\nれ自体ではない部分が共通するにすぎない場合や共通する表現がありふ\nれた表現である場合には,被告レジュメが原告ワークブックを複製又は翻\n案したものに当たらないと解される。
イ 控訴人会社は,原告ワークブックと被告レジュメは,全体の構成が実質\n的に同一であり,しかも,原判決別紙2レジュメ対比表及び原判決別紙5\n原告ワークブックに関する主張対比表の「原告らの主張」欄記載のとおり,\n具体的な記述部分における同一性を有する表現は創作性のある表\現であ るから,被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものに当た る旨主張するので,以下において判断する。
(ア) 原告記述部分1ないし24及び被告記述部分1ないし24に係る複 製又は翻案について
a 原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5について
(a) 原判決別紙2レジュメ対比表の番号1ないし5のとおり,原告ワ\nークブックの当該部分と被告レジュメの当該部分とは,それぞれ, 会議において,会議での約束事として,そのまま「やってみる」こ と(番号1),「携帯」電話を切っておくこと(番号2),「問題」 を見つけたら,「問題を指摘する」のではなく,「解決策を提示す る」こと(番号3),「わかりません」という回答はしないこと(番 号4),「発言」は,「短く」,「簡潔に」,「直接的な表現で」\n行うこと(番号5)を内容とする記述である点で共通する。 しかしながら,原告記述部分1は「まずは本書の手順どおりその ままやってみる。」であるのに対し,被告記述部分1は「とりあえず 身を預けてやってみる。」,原告記述部分3は「問題を見つけたら問 題を指摘するのではなく,解決できる人に解決策を提示する(自分 自身かもしれない)。」であるのに対し,被告記述部分3は「問題を 発見したとき,解決策を提示する。問題を指摘するだけは無し」,原 告記述部分4は「このワークブックが質問してくる質問に「わかり ません」という回答はなし。」であるのに対し,被告記述部分4は「侍 会議中,「わかりません」「ありません」という答えは無しでやっ てみる」,原告記述部分5は「発言は3Sにやる。(スリーエス:Short 短く,Simple 簡潔に,Straight 直接的な表現で)」であるのに対し, 被告記述部分5は「発言は短く,簡潔に,直接的な表現でやる。」で あり,具体的記述における表現は異なり,共通性は認められない。\nそうすると,被告記述部分1ないし5と原告記述部分1ないし5 は,会議の約束事を説明した記述であるという点において共通して いるものの,その共通する部分は,会議における約束事をどのよう に取り決めるかというアイデアであって,表現それ自体ではない。\n
(b) 控訴人会社は,1)原告記述部分1ないし5及び被告記述部分1な いし5について,会議における約束事の表現の仕方にはいくつかの\n選択肢がある中で,一見当たり前と思われるような内容も約束事と してあらかじめ記載するという表現形式をとっている点で同一性\nを有しており,その同一性を有する部分は創作的な表現である,2) また,会議における約束事は多数あり,どの約束事を選択するか, その組合せ,約束事の表現の仕方については,その選択の幅は広く,\nアイデアの表現方法がただ1つしか存在しない場合,あるいは,1\nつでなくとも相当程度に限定されている場合には該当しないので あるから,原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5の同 一性を有する部分はアイデアそのものではない旨主張する。
しかしながら,会議の冒頭で約束事を決めることや,当たり前の ことをあえてワークブックないしレジュメに記載するということ 自体は,アイデアにすぎないから,仮に,そうしたアイデアそのも のに個性の表れが認められるとしても,そのことをもって直ちに創\n作的表現部分に共通性があるとはいえない。また,アイデアの表\現 方法がただ1つしか存在しない場合,あるいは,1つでなくとも相 当程度に限定されている場合かどうかは,具体的表現を前提にその\n表現に創作性があるかどうかの考慮要素になり得るとしても,前記\n(a)認定の原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5の共 通する部分がそもそも表現であるか,アイデアであるかの判断を左\n右するものではない。 したがって,控訴人会社の上記主張は,採用することができない。
(c)また,控訴人会社は,1)原告記述部分1ないし5と被告記述部分 1ないし5の5つの約束事が同一であり,約束事の1つ1つは短い 表現であるが,約束事は一体として意味を成すものであることから,\n原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5の表現を一体\nとしてみた場合には,相当程度の文章になるのであって,短い表現\nではない,2)これらの5つの約束事を全て記載した他の書籍やウェ ブページは見当たらず,約束事の1つ目に,手順どおりそのまま「や ってみる」という表現を選択していることには作成者の創意工夫が\n表れているなど,これらの5つの約束事の配置や文字列には作成者\nの創意工夫が表れており,ありふれた表\現とはいえないから,創作 的表現が共通する旨主張する。\nしかしながら,前記(a)認定のとおり,原告記述部分1ないし5と 被告記述部分1ないし5は,具体的記述における表現の共通性は認\nめられない。
また,原告記述部分1中の「まずは・・・そのままやってみる。」との 表現部分は,ウェブページ(乙16)において「素直にそのままや\nる」との記載が,書籍(乙20)において「おやくそく」,「まず はやってみよう」との記載が,それぞれ存在していること,会議中 の「発言」に関するものとして,原告記述部分5中の「発言は3S にやる。(スリーエス:Short 短く,Simple 簡潔に,Straight 直接的 な表現で)」との表現部分は,ウェブページ(乙15)において「会\n議での発言は「3S」(Short=短く,Simple=簡潔で, Straight=直接的に)のルールでおこないましょう。」と の記載が存在することに照らすと,上記各表現部分は,いずれもあ\nりふれた表現であり,創作性があるとはいえない。\nしたがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
(d)以上によれば,被告記述部分1ないし5が原告記述部分1ないし 5と共通する部分は,表現それ自体ではないから,被告記述部分1\nないし5は,原告記述部分1ないし5を複製又は翻案したものに当 たるものと認めることはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成31(ワ)4521
原告・被告物件などはこちら
2021.11. 5
令和2(ワ)3474 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年10月19日 大阪地方裁判所
ア 本件発明1〜3の効果
本件発明の効果は,センサ保持具の回動を保持するための機械的な連結構造がコンパクトになること(【0014】),接続器を引掛型配線器具に掛着する作業に際して引掛型配線器具の掛着面を視認しやすく,作業が容易になると共に,作業の安全性も向上すること(【0016】),本体カバーを天井面に密着させることが可能になり,美観に優れた取付状態が得られること(【0017】)である。 要するに,本件発明の作用効果は,1)センサの回動構造のコンパクト化,2)引掛型配線器具の掛着面の視認性の向上,3)本体カバーの天井面への密着にあるといえる。
イ 本件発明の貢献の程度等について
本件発明は,センサを用いてランプを自動的に点灯・消灯する天井取付タイプの照明器具に係る発明であるから,主として屋内のトイレ灯などとして使用されることが想定される。そして,本件発明の実施品である照明器具の需要者は,新築建物に照明器具を設置する総合住宅メーカー等の業者と既存の照明器具を交換しようとする個人が想定されるところ,前記の効果1)〜3)は,いずれも選択の動機となり得る事情といえる。 もっとも,本件発明の効果1)については,センサを回動させることが前提となっているところ,屋内のトイレ灯等を想定すると,一度センサの検知範囲を確認して照明器具を設置してしまえば,後にセンサを回動させて検知範囲を変更する必要が生じることはそれほどないものと考えられるから,センサが取付後も回動可能であることの顧客誘引力は低いものと解される。また,本件発明の効果2)及び3)は,接続器等を引掛型配線器具に掛着した後,別体に形成された本体カバー及びセードを後付けすることによる効果であるため,本件発明によるのでなければ実現し得ない効果ではなく,例えば,周知技術1によっても実現することができる。そうすると,効果2)及び3)については,本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たっては,必ずしも重視できるものではない。 さらに,被告は,そのカタログ(乙14)において,被告製品1の特徴として,人感センサ付,クイック点灯,引掛シーリング取付式,本体可動式,点灯照度調節機能付,点灯保持時間調節機能\付などを挙げているものの,掛着面の視認性や本体カバーが後付けであることについては触れていない。 以上によれば,本件発明は,センサの回動構造がコンパクトであるという効果(効果1))によりこれを実施する製品の販売等に貢献するものであって,相応の顧客誘引力を有するといえるものの,その程度は限られているというべきである。また,効果2)及び3)に関しては,本件発明は,本体カバーが後付けであり,外観上の体裁が同程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ア) 効果1)について
本件発明の効果1)は,センサが回動可能であることを前提として,構\造をコンパクトにするものであるが,センサを回動可能としたのは照明器具本体(本体カバー,セード等)により検知範囲が制約されることに対処したものであるから,本体がコンパクトであることによってセンサの検知範囲に制約がなく,センサを回動させる必要がない製品も,本件発明の効果1)と同様の効果を奏しているものといえ,被告製品の競合品に該当するといえる。
証拠(乙11の1〜6,乙20の1〜3,乙21の1〜5,乙22の1〜7,乙23の1〜3,乙24の1,2,乙25〜28)によれば,原告及び被告以外のセンサ付シーリングライト製品のうち,乙11の1の型番 LBC56975,乙11の4の型番 OL 013 180,OL 013 120,乙11の5の型番 IG20026C,乙11の6の型番 LE-3837 については,センサ保持具が大きく,本体がコンパクトではないが,その余のセンサ付シーリングライト製品は,いずれも被告製品と同等以下のコンパクトな形状を有しているものと認められる。これにより,これらの製品は,本件発明の効果1)と同様の効果を奏するものといえる。
(イ) 効果2)について
本件発明の効果2)は,引掛型配線器具に掛着する照明器具であることを前提とするが,照明器具が一般的な引掛型配線器具に掛着する形式であるか,電気設備工事を要するものであるかは,照明器具を交換しようとする個人の需要者にとっては大きな違いである。また,総合住宅メーカー等の事業者においても,引掛型配線器具を設置するか否かや施工の際の視認性は相応に商品選択に影響があると考えられる。そうすると,各被告製品の競合品といえる前提として,引掛型配線器具に掛着する照明器具であることが必要である。 証拠(乙20の1〜3,乙21の1〜5,乙22の1〜7,乙23の1〜3,乙24の1,2,乙25〜28)によれば,乙20の1〜3,乙21の1〜5,乙22の1〜7,乙23の1〜3,乙24の1,2,乙25〜28の被告指摘に係る製品は,いずれも引掛型配線器具に掛着する照明器具であり,被告製品と同等程度には掛着面が視認しやすく,効果2)と同様の効果を奏するものといえる。
(ウ) 効果3)について
証拠(乙20の1〜3,乙21の1〜5,乙22の1〜7,乙23の1〜3,乙24の1,2,乙25〜28)によれば,原告及び被告以外のセンサ付引掛シーリングライト製品のうち,乙21の1〜5の型番 IG20042C(以下「乙21製品」という。),乙23の1の型番 TGS-6119(以下「乙23の1製品」という。),乙23の2の型番 TZGS-6099(以下「乙23の2製品」という。),乙24の1の型番 SCL9NMS-HL(以下「乙24製品」という。),乙28の型番 TN-CLLS-L(以下「乙28製品」という。また,以上を併せて,「乙21製品等」という。)は,いずれも,本体カバーが天井面に密着した外観を有しており,効果3)を奏するものといえる。
(エ) その他
原告は,ランプ交換ができない LED 内蔵型照明器具は,ランプ交換を望む顧客の需要を満たすことができないので,競合品に当たらないと主張する。しかしながら,そのような需要者が存在するのか明らかではなく,そもそも,ランプ交換が可能であるか否かは本件発明の作用効果とは無関係である。したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。\n
(オ) 以上より,乙21製品等は,いずれも,本件発明の効果と同様の効果を有する製品として,原告製品及び各被告製品と市場において競合するものとみるのが相当である。 また,証拠(乙21の1,乙22の1,乙23の1,2,乙24の1,乙28)によれば,乙21製品等の販売開始時期は,乙21製品が平成16年4月,乙23の1製品が平成20年6月,乙23の2製品が平成22年2月,乙24製品が平成29年10月,乙28製品が平成28年7月であることが認められる。原告は,乙21製品について,平成16年〜平成20年のカタログに掲載された製品であり,平成21年9月1日に生産を終了したと主張するが,一般的にカタログに掲載された製品は特段回収等がされない限り数年程度は流通していると考えられ,被告製品の競合品に当たらないとはいえない。
もっとも,原告製品,各被告製品及び乙21製品等のセンサ付引掛シーリングライトの市場におけるシェアは明らかではなく,原告において,平成27年当時の住宅用照明のうち直付け型の居室外用の照明器具市場における原告のシェアが●(省略)●%であったことを自認するにとどまる。被告は,照明器具市場全体の売上のシェアや住宅用照明市場におけるシェア,LED シーリングライト市場におけるシェアを主張するが,原告製品,被告製品及び乙21製品等のセンサ付引掛シーリングライトは,そのごく一部であって,他の多数の照明器具が含まれるシェアから被告製品の競合品のシェアを推認することは困難である。 これらの事情を総合的に考慮すると,センサ付引掛シーリングライトの市場において原告製品及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば,特許法102条2項に基づく損害額の推定に係る覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの,その程度は限定的と考えるのが相当である。
エ 推定覆滅の程度 以上の事情を総合的に考慮すれば,本件においては,2割の限度で損害額の推定が覆滅されるにとどまるとすべきである。
・・・
ア 証拠(乙10の1〜3)によれば,平成22年10月21日から同年11月5日にかけて,大手家電量販店チェーンの3店舗において,原告製品と被告製品3及び4が隣り合った状態で陳列され販売されたことが認められる。 一般に店舗において商品の陳列場所等は商品の売上に影響を及ぼす重要な要素であって,原告においても,営業担当者等を通じて,当然に自社製品や競合他社製品が家電量販店においてどのように陳列・販売されているかを逐次把握していたものと考えられるから,遅くとも平成22年11月5日には,原告において,被告製品3及び4の存在を知ったものと認められる。 そして,原告製品と各被告製品は同種の用途の競合品であって,大手家電量販店チェーンにおいては概ね統一的な商品陳列を行っているものと考えられることからすれば,各被告製品は,家電量販店において基本的に原告製品と隣接して陳列されていたと考えられ,被告製品3及び4以外の各被告製品についても,その販売開始から間もなく,原告は,各被告製品の存在を知ったものと認められる。
イ 本件発明は,前記のとおり,効果1)〜3)を奏するものであり,これらの効果は外観上明らかであって,各被告製品の外観から,各被告製品が本件特許権の侵害品であることの疑いを持つことは十分に可能\である。 原告は,本件発明の構成要件 A〜D は,内部構造に係るものであるから,被告製品の外観からは判明しないと主張するが,被告製品の外観からして本体カバーに被覆された接続器やセンサ保持具が存在することは明らかであり,センサ保持具が天井面と略平行な面内で回動可能\に構成されていることは推測することができる。そして,証拠(乙10の1〜3)によれば,家電量販店の陳列棚において,天井を模した造作があり,引掛型配線器具が設けられ,各被告製品を現実に組み立て,取り付けることができるようになっていたものと認められ,原告において,各被告製品の取付状態を確認することもできたものと考えられる。また,証拠(甲5の1〜3,甲7,乙14)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,各被告製品を毎年発行する被告のカタログに掲載すると共に,各被告製品の仕様や構\造を記載した「施工・取扱説明書」をインターネット上等で公開していたことが認められ,カタログには引掛シーリングに取り付けるタイプであること,人感センサがあり,本体可動式であること等が記載され,施工・取扱説明書には,購入者又は工事店が各被告製品を取り付けることができるよう,各部を分解した構造図とセンサの可動範囲等が記載されているのであるから,被告はこれらの情報を秘匿せず,一般に公開していたのであって,原告は,各被告製品の存在を知り,その外観から本件特許権侵害の疑いを持った時点で,各被告製品の構\造等を容易に検討することができたといえる。
ウ 原告は,遅くとも平成22年11月5日までに被告製品3及び4の発売を知り,その余の各被告製品についても,発売後まもなくその事実を知ったものと認められ,各被告製品の構造等を知ることもできたのであるから,製品が競合する関係にある原告としては,その時点で,損害賠償請求をすることが可能\な程度に,損害及び加害者を知ったと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2021.11. 5
令和3(行ケ)10061 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年11月4日 知的財産高等裁判所
ア 原告は,本件商標の使用が特定乳化技術を用いて製造した化粧品ではない化 粧品についてのものであることまで被告が主張立証しなければならないと主張する が,既に判示したとおり,同主張を採用することはできない。
イ 原告は,その主張の根拠として商標法50条2項を挙げるところ,同項は, 「その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をし ていることを被請求人が証明しない限り」と定めるが,上記のうち「その請求に係 る指定商品又は指定役務」という文言から,直ちに,本件商標の使用が特定乳化技 術を用いて製造した化粧品ではない化粧品についてのものであることまで被告が主 張立証しなければならないとはいえない。
商標法50条が定める取消審判請求の審理の対象となる指定商品の範囲は,設定 登録において表示された指定商品の記載に基づいて決められるのではなく,審判請求人において取消しを求めた審判請求書の「請求の趣旨」の記載に基づいて決めら\nれるものではあるが,審判請求書の「請求の趣旨」は,審判における審理の対象・ 範囲を画し,取消審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品の範 囲を決定づけるという意味のほか,被請求人における防御の要否の判断・防御の準 備の機会を保障するという意味でも重要なものというべきである。
しかるに,本件のように,要証期間における本件商標の指定商品のうち関連部分が第3類「化粧品」であったにもかかわらず,専ら審判請求人において,本件商標の登録の日の後に認知されてきたものとみられる一方で要証期間を通じて周知のものであるとも認めら れない商品の製造方法である特定乳化技術に基づいて,本件審判請求と対の審判請 求とに取消審判請求を分けた上で,被告に対し,対の審判請求においては化粧品が 特定乳化技術に基づいて製造したものであることも含めた本件商標の使用の主張立 証を求め,本件審判請求においては特定乳化技術を用いて製造した化粧品でないこ とをも含めた本件商標の使用の主張立証を求めることは,被告の防御の準備の機会 を著しく損なうものであって,前記のとおり,被請求人において,審判請求に係る 指定商品又は指定役務の「いずれかについて」の登録商標の使用を証明すれば足り ると定める商標法50条2項が,上記のような要請まで含むものとは解されないと ころである。
特に,本件のように,製造方法に係る特定を審判請求人が任意に付し た場合に,商標権者において,自らの商品の製造方法を開示して立証しない限り, 商標登録の取消しを免れないとみることは,商標権者に過度の負担を課すものであ って不合理であることが明らかであり,そのような立証を求めるに帰する原告の主 張は,信義誠実の原則に照らしても採用することができない。
2021.10.29
令和3(行ケ)10006 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年10月26日 知的財産高等裁判所
ア 前記1(3)によれば,引用文献2技術事項は,物質に特有な高吸収X線を 利用することにより,荷物や人体内に隠匿した麻薬,あるいは爆薬や象牙 などの禁制品の有無を検査できるものであるから,人体用だけでなく,荷 物の中の見えない物体の有無を検査するX線荷物検査装置でもあるとい える。そうすると,食品等の異物検査を行うX線検出装置である引用発明 1の技術分野と,医療検査や荷物検査を行う引用文献2技術事項の技術分 野は,X線検査装置が用いられる技術分野として関連するものであるとい える。 また,引用発明1においては,判定部24において「各ライン走査ごと のデータ中の最大画素濃度のデータを所定の閾値と比較してX線吸収率 が大きい金属異物等の混入の有無が検出濃度レベルと閾値との比較によ り判定される」(M)ものであり,ワークWのX線画像の検出濃度レベルと 所定の閾値とを比較することにより,金属異物等の混入が有る場合の濃度 レベルと混入が無い場合の濃度レベルとを判定する必要があるから,ワー クWのX線画像における金属異物等の混入の有無の濃度レベルの間の差 異を明確にしなければならず,X線画像において目的とする物体を透過し たX線の検出出力と前記目的とする物体以外の部分を透過したX線の検 出出力との間に明確な差異を有するX線画像を生成するという課題を有 している。一方,引用文献2においては,従来のX線撮影装置では「目的 とする臓器などを明瞭に表示するようにしたコントラストの高いX線像\nを得ることが難しい」(【0002】)という課題を有し,また,異なる波長 の単色X線を用いて得られたX線像の差分から目的とする部分を際立た せて表示する方法を用いる場合,「異なる時刻に撮影したX線像の差分を\n取ると,位置がずれてしまい明瞭な動脈像を生成することができない」 (【0004】)という課題を有しているところ,引用文献2技術事項によ り「それぞれピクセルへの入射X線量をカウントしカウント値の差分を取 ると,軟部組織や骨に吸収されたX線が相殺され血管部分のみに差が現れ て冠状動脈のコントラストの大きな鮮明な映像を得ることができる」(【0 021】)としている。コントラストが大きなX線画像は,物体を透過した X線の検出出力と目的とする物体以外の部分を透過したX線の検出出力 との間に明確な差異を有するものであるから,引用発明1と引用文献2技 術事項とは課題を共通するといえる。 さらに,引用発明1と引用文献2技術事項は,いずれも被測定物の中の 外から見えない物体を検出するために用いられるX線画像を形成し,当該 X線画像に基づいて検査を行うという作用・機能が共通するといえ,加え\nて,引用文献2には,「X線検出部11に1次元のリニアアレイを用いて1 次元走査して測定することもできる」【0014】ことが記載され,被測定 物を1次元走査してX線画像を得ることも示唆されており,引用発明1の X線ラインセンサにより搬送される被測定物のX線画像とは,X線画像を 被測定物を1次元走査して生成するという点においても共通する。 以上のように,引用発明1と引用文献2技術事項との間に,技術分野, 解決課題及び作用機能に密接な関連性・共通性があることからすると,引\n用発明1に引用文献2技術事項を組み合わせることに強い動機付けがあ るといえる。
イ 前記第3の1(1)イ(ア)bのとおり,原告は,引用発明1のX線検査装置 は異物の有無を低コストで検査する分野の装置であり,簡易な検査作業の 実現を目的とするのに対し,引用文献2技術事項のX線検査装置は,コス トを度外視して検査する分野の装置であり,被曝防止を目的とするもので あるから,当業者は,異物検出の精度向上のためにわざわざ引用発明1に 引用文献2技術事項とを組み合わせたりする動機付けない旨主張する。 まず,引用文献2には,「撮影は1度で済み」(【0010】),「エネルギ ーを変えて検査するときにも1度の撮影で済むので検査時間が短縮する 利点がある。」(【0022】)との記載があるが,それは副次的なものにす ぎず,引用文献2技術事項の課題は,複雑で高価な装置を用いずにコント ラストの高いX線像を得ることである(【0003】ないし【0007】, 【0010】,【0022】,【0024】)。したがって,引用文献2技術事 項のX線検査装置は,コストを度外視して検査する分野の装置であると認 めることはそもそも相当でない。また,引用発明1が,コンベア搬送路上 のワークの金属異物等の混入の有無を検査する異物検査装置であること からして,引用発明1が製品製造現場用の装置であり,引用文献2の記載 上は,引用文献2技術事項が直接には医療用検査装置に用いることを想定 しているとしても,コストをどの程度かけるかということと技術分野とは 直結しないところ,製品の性質,製造現場の規模,製品の販路等も度外視 して,製品製造現場用の装置であれば,おしなべて性能の低い製品で足り,\n当業者は性能の向上には意を払わず,医療検査装置用の技術には関知しな\nいなどとは当然にいえることではなく,そのようにいえる証拠は提出され ていない。
異物検査装置の異物検査の性能を向上させることは自明の要請ともいう\nべきところであり,前記アのとおり,引用発明1の異物検査装置に,技術 分野,課題・解決手段,作用・機能,効果とも密接に関連ないし共通する\n引用文献2技術事項を適用する強い動機付けがあるというべきである。
ウ 前記第3の1(1)イ(イ)aのとおり,原告は,1つの「設定時X線画像」 を基準とする引用発明1に,複数個の画像を基準とし,その基礎とする技 術的思想を異にする引用文献2技術事項を適用することには阻害要因が ある旨主張する。 ここで,「設定時X線画像」とは,実検査前にサンプルを使用した検査に おいて得られたX線画像データとして設定情報記憶部23に保持された 初期設定データの1つであり(引用文献1の【0052】ないし【005 5】),当該品種に設定された各種パラメータや検出条件及び判定条件にお ける検査における代表画像とされ(【0042】),実検査時に実検査時のX\n線画像Wiと共に表示器26に表\示され,実検査中に両者を照合すること により,検査の条件に実検査品が適合したものか否かを判定することや (【0046】,【0059】ないし【0061】),品種選択操作を視覚的に 容易に把握することに役立てるものである(【0062】,【0063】)。 したがって,検査の目的に合わせたX線画像を得られるならば「設定時 X線画像」も同時に得られる関係にあるところ,引用文献2技術事項によ ると複数のX線画像を生成することができ得るが,特に感度のよいエネル ギー領域を選択して目的部位の像を鮮明化したり,異なるX線エネルギー 領域における出力信号の差分に基づいて画像化するなどして,最適な条件 で選んだ画像を1つ生成できることも明らかである。そして,当業者が, 異物検査の目的に応じて最適な画像を選択してそれを代表画像とするこ\nとができないとする理由もない。 そうすると,引用発明1のX線画像を得る手段として引用文献2技術事 項を適用することには,阻害要因はない。
エ 前記第3の1(1)イ(イ)bのとおり,原告は,低コストでの簡便・容易化 を目指す引用発明1に,高精度で複雑・高度な引用文献2技術事項を適用 することには,甲1発明の目的から乖離・矛盾するから阻害要因がある旨 主張する。 しかしながら,前記イにて説示したとおり,技術分野としての観点から 見た場合に,あたかもX線検査装置が低コストでの簡便・容易化を目指す 装置の分野の技術と複雑・高精度で複雑・高度な装置の分野の技術に二極 化していて,両者の技術が相容れないとは認められない。その上,引用文 献2技術事項の課題は,前記イのとおり,複雑で高価な装置を用いずにコ ントラストの高いX線像を得ることであり,前記アのように,被測定物を 1次元走査して測定するような簡易な方法も示唆されている。また,引用 文献2に禁制品の有無を検査することもできるとの示唆があるからとい って,引用文献2技術事項が空港や税関等で用いる検査装置のみに用いら れる技術ととらえることは,同技術の正しい理解とはいい難い。 したがって,原告の上記主張は前提を欠くものであって,採用すること ができない。
オ 以上のとおり,引用発明1に引用文献2技術事項を組み合わせる動機付 けがあり,阻害要因があることもうかがわれないところ,引用発明1にお いて,引用文献2技術事項に基づき,相違点1に係る本件発明1の発明特 定事項を得ることが容易であることは,本件決定が引用する取消理由通知 書が説示するとおりであり,誤りは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2021.10.28
令和3(ワ)2322 著作権 民事訴訟 令和3年8月20日 東京地方裁判所
事案に鑑み,まず,争点1−4について検討する。
(1)ア 前記前提事実によれば,原告X1は,令和元年7月6日,プロレスラーと してのデビューに当たって必要となるコスチュームの制作について被告か ら相談を受け,衣装制作会社及びデザイナーを紹介するとともに,被告から 送信を受けた本件デザイン画のデータについて,「アイドルらしくて,いい よ。」,「コスチューム代,俺が出そうか?」,「絶対にクオリティは下げ ないで。」などのコメントをしているとの事実が認められる。これによれば, 原告X1は,本件コスチュームの制作に積極的に協力し,その代金の負担ま で申し出ているのであり,完成したデザイン画及びそれに基づいて制作され\nる本件コスチュームの著作権の使用について特段の制限や条件を付したこ とをうかがわせる事実は存在しない。
イ 同様に,原告X1は,令和元年8月8日,被告から,完成した本件コスチ ュームを着用した写真の送付を受けたが,これ対して特段の異議を述べるこ とはなく,被告のデビュー後も,被告とLINEを通じてやり取りを行って いるが,その際に,本件デザイン画や本件コスチュームの使用について特段 の異議を述べたとの事実も認められない。
ウ このように,原告X1は,被告が令和元年8月10日にプロレスラーとし てデビューすることを認識した上で,本件デザイン画や同デザイン画をベー スとしてコスチュームを制作することを認識し,同日の前に実際に制作され たコスチュームのデザインを確認していながら,その使用についてデビュー の前後を通じ何ら異議を述べていないのであるから,仮に原告会社が本件デ ザイン画及び本件コスチュームの著作権を有するとしても,被告に対してそ の使用を許諾していたものというべきである。
(2)ア これに対し,原告会社は,本件デザイン画につき,著作権法30条の3に いう「検討の過程における利用」において必要と認められる限度で使用する ことは承諾していたが,当該限度を超えて,本件デザイン画と同一又は類似 のコスチュームを使用することは承諾していなかった旨主張する。 しかし,原告X1は,被告が完成した本件デザイン画を使用して本件コス チュームを制作し,これを着用して活動することを認識した上で,同デザイ ン画の使用に関して何らの制限や条件を付していなかったと認められるこ とは前記判示のとおりである。 したがって,「検討の過程における利用」のみを許諾していたとの原告会 社の主張は採用し得ない。
イ 原告会社は,原告X1が令和元年8月8日に本件コスチュームの写真を確 認した際に異議を述べなかったのは,2日後に被告のデビューが控えていた ためである旨主張する。 しかし,原告X1は,令和元年8月8日より以前の段階から,本件デザイ ン画に基づいて本件コスチュームを制作していることを認識していたと認 められ,デビュー後の被告とのやりとりにおいても,本件デザイン画及び本 件コスチュームの使用について何ら異議を述べていないのであるから,原告 X1が本件コスチュームの写真を確認したのが被告のデビューの2日前で あったとしても,同事実は,原告会社が本件デザイン画及び本件コスチュー ムの使用について承諾していたとの結論を左右しない。 したがって,原告会社の上記主張は採用し得ない。
2021.10.28
平成29(ワ)1390 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月16日 大阪地方裁判所
本件訂正発明1−1に係る特許請求の範囲の記載によれば,同発明に係るランプ は,「基板を保持する金属製の基台」(構成要件 1-1F’)をその構成要素の1つとして備えるところ,「前記基台は,前記長尺状の底部と,前記底部の短手方向の一\n方の端部に設けられた第1壁部と,前記底部の短手方向の他方の端部に設けられた 第2壁部とを有し」(構成要件 1-1I’),「前記第1壁部及び前記第2壁部は,前 記底部の前記基板側に衝立状に形成されて」(構成要件 1-1J’)いることが特定さ れている。 これによれば,基台の底部の短手方向の両端部にそれぞれ設けられた第1壁部と 第2壁部は,底部に対し基板側に形成されるものであり,その形状ないし状態が 「衝立状」であることが示されている。もっとも,いかなる形状等をもって「衝立 状」とするかについては記載がなく,その意味が一義的に明らかとはいえない。
イ 本件明細書1の記載等
「第1壁部」及び「第2壁部」について,本件明細書1【0055】には,第1基 台 50 が,長尺状の底部(底板部)と,底部における第1基台 50 の短手方向(基板 11 の幅方向)の両端部に形成された第1壁部 51 及び第2壁部 52 とを有すること, これらの壁部は,第1基台 50 を構成する金属板を折り曲げ加工することによって衝立状に形成されていることが記載されている。また,同段落には,同明細書図\n3B と合わせ,LED モジュール の基板 11 は第1壁部 51 と第2壁部 52 とによっ て挟持されており,LED モジュール は,第1壁部 51 と第2壁部 52 とによって 基板 11 の短手方向の動きが規制された状態で第1基台 50 に配置されることも記載 されている。本件訂正における本件訂正発明1−1の構成要件 1-1J'の追加は,こ の記載等を含む本件明細書1の記載による開示に基づいて行われたものである(甲 83)。 さらに,広辞苑(乙291)においては,「衝立」とは「衝立障子の略」であり, 「衝立障子」とは「屏障具の一。一枚の襖障子または板障子に台をとりつけ,移動 便ならしめたもの。・・・玄関・座敷などに立てて隔てとする。」と説明されている。 加えて,「衝立障子」は,一般に,それが設置される面に対して略直立するものと 把握される。他方,「状」とは,物事の形,姿,有り様,様子を意味し,「○○状」 とは,ある物事の形等を「○○」に例える際に用いられる表現である。以上の本件明細書1の記載等を踏まえると,第1壁部及び第2壁部は,基台の底\n部の基板側に衝立状に形成されることにより基板11を挟持し,短手方向の動きが 規制する機能を果たすものであるところ,その形状等は上記意味での「衝立障子」に例えられるものである必要があることが理解できる。\n
ウ 小括
以上より,本件訂正発明1−1に係る特許請求の範囲及び本件明細書1の記載等 並びに「衝立」の一般的な意味等に鑑みると,第1壁部及び第2壁部が「衝立状」 に形成されるとは,これらの壁部が基台の底部の基板側に,同底部に対して略直立 した形状に形成されていることを意味するものと解される。これに反する原告の主 張は採用できない。
(2) 被告製品1〜5,7〜10及び12の構成要件充足性
被告製品1〜5,7〜10及び12の断面図は,別添「被告製品断面図」のとお りである。 このうち,被告製品4及び5については,第1壁部及び第2壁部に相当すると見 られる部位は,基台の底部から基板側に形成された基台の一部が内側に向けて鋭角 に傾斜した形状に形成されており,底部に対して略直立した形状とはいえない。 次に,被告製品1〜3,7〜10及び12については,第1壁部及び第2壁部に 相当すると見られる部位には,基台の底部から基板側に略直立といってよい形状に 延出している部分もあるものの,これと一体のものとして,基板とほぼ同じ高さで 基台の底部に平行に形成された部分もあるため,全体としては「コの字」又は「T 字」と表現すべき形状に形成されているものというべきであって,底部に対して略直立した形状に形成されているとはいえない。\nしたがって,被告製品1〜5,7〜10及び12は,いずれも,第1壁部及び第 2壁部に相当すると見られる部位が底部の基板側に「衝立状」に形成されておらず, 本件訂正発明1−1の構成要件 1-1J’を充足しない。
(3) 小括
以上により,被告製品1〜5,7〜10及び12は,いずれも,本件訂正発明1 −1の技術的範囲に属しない。
4 充足論のまとめ
本件発明1−1,1−3,1−16及び1−17及び並びに本件訂正発明1−1 7につき,対象となる各被告製品が各発明の構成要件を充足し,その技術的範囲に属することは,前記(第1の5)のとおりである。\nまた,本件発明1−14並びに本件訂正発明1−18及び1−20については, 前記2のとおり,被告製品1〜5,7〜16は,対応する各発明の構成要件を充足し,その技術的範囲に属すると認められる。\n他方,本件訂正発明1−1については,被告製品1〜5,7〜10及び12は, いずれもその構成要件 1-1J'を充足せず,その技術的範囲に属しない。したがって, 本件訂正発明1−1については,その余の点を論ずるまでもなく,訂正の再抗弁は 認められない。
5 403W 製品に基づく先使用権の成否(争点10) 事案に鑑み,まず,403W 製品に基づく先使用権の成否(争点10)について検 討する。
(1) 403W 製品の先使用について
ア 証拠(以下に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら れる。
(ア) 被告は,平成24年4月23日頃,韓国で製造された 403W 製品480セッ トを輸入した(乙143,315)。
(イ) 被告は,同月25日,ミツワ電機株式会社関西支社に対し,403W 製品24 台を含む商品の見積書を作成,送付し,同月26日,同社関西特機営業所から受注 して,同月28日,これを井づつやに納品した(乙167,168)。 その後,井づつやに納品された上記 403W 製品24台は,同所のエントランスロ ビー等において使用されていたところ,被告は,平成30年7月23日までに,井 づつやからこれを入手した。この被告 403W 製品には,製造ロット番号として 「120416」が表示されているところ,これは,当該製品の製造年月日が平成24年4月16日であることを意味する。(乙166,弁論の全趣旨)\n
(ウ) 被告は,本件チラシ(平成24年1月発行)に,平成24年3月初旬発売予定の商品として 403W 製品を掲載した(乙138)。また,被告は,本件カタログ (同年2月発行)にも 403W 製品を掲載したところ,他の掲載商品には発売予定時期を明記したものが見られるが,403W 製品にはそのような記載はない(乙35)。
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば,被告は,遅くとも本件優先日である 平成24年4月25日以前に,403W 発明の実施である事業をしていたことが認め られる。
(2) 403W 発明の構成等
ア 403W 発明の構成のうち,上記第2「10」(被告の主張)(3)における構成 1- 3a10〜c及び e並びに 1-14a10〜f及び hについては,原告 PIPM も明ら かには争わないから,これを認める。 上記構成 1-3a10〜c及び eは,本件発明1−1の構成要件 1-1A〜C 及び E, 本件発明1−3の構成要件 1-3A〜C 及び E,本件発明1−16の構成要件 1-16A〜 C 及び F,本件発明1−17の構成要件 1-17A〜C 及び E 並びに本件訂正発明1− 17の構成要件 1-17B’〜D’にそれぞれ相当するものといえる。また,構成 1-14a10 〜f及び hは,本件発明1−14の構成要件 1-14A〜E,G 及び本件訂正発明 1−18の構成要件 1-18B’〜F’,I’にそれぞれ相当するものといえる。 さらに,403W 製品は,直管形 LED ユニットであり,樹脂(ポリカーボネート) 製カバー(筐体)の長手方向の両端に口金が設けられているところ,その一方には 電源内蔵ユニット用専用口金を備え,この口金のみが,電源内蔵用専用ソケット(給電側)を通じて交流電力を受けるものである(乙35,299)。そうすると,\n403W 発明は,本件発明1−16の構成要件 1-16E 並びに本件訂正発明1−17の 構成要件 1-17E’及び本件訂正発明1−18の構成要件 1-18G’,H’に相当する構成を備えていることが認められる。\n加えて,403W 製品は,既存の器具本体をそのまま残し,専用ソケット及び直管形LED ユニットをリニューアルして照明装置として使用する製品シリーズに含まれる製 品である(乙35)。したがって,ランプである 403W 製品に係る発明(403W 発明) は,そのランプが取り付けられた照明装置に係る発明に含まれるといえる。このため, 403W 発明は,本件発明1−17の構成要件 1-17F,本件訂正発明1−17の構成要件 1-17A’及び G’並びに本件訂正発明1−18の構成要件 1-18A’及び K’に相当する構成を備えていることが認められる。
イ 403W 製品の輝度均斉度等
(ア) 証拠(以下に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら れる。
a LED モジュールの寿命は,製造業者等が指定する条件下で点灯したとき, LED モジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間,又は全光束が点灯初期に測 定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間とされているとこ ろ,高光束 LED を1万時間連続通電してその光出力の変化を調査した実験データ によれば,1チップ方式の白色 LED の寿命(光出力が70%になる時間)は4万 5000時間と推定されるとの実験データがある。なお,原告パナソニックのカタログ(乙34)には,直管形 LED ランプについて,4万時間経過後の光束維持率 が95%であることが示されている。 また,LED を連続的に点灯し続けると,LED チップを封止する樹脂(以下 「LED 樹脂部」という。)が黄変し,光量の低下を招くことがある。さらに,LED 照明は,使用する場所の環境温度が高くなるほど劣化が加速されると共に,使用環 境下に硫化ガス等の発生要因がある場合,LED 樹脂部及び接合部にダメージを与 えることなどによっても,劣化が加速する場合がある。 (以上につき,上記のほか,甲37〜39)
b 被告 403W 製品は,平成24年4月28日の井づつやへの納品後,被告が平 成30年7月に入手するまで,6年以上の間継続的に使用されていたものと見られ るところ,その LED 素子の中央部分はやや黄変しており(乙217,218), カタログに記載された初期値を100%とした場合の被告 403W 製品の全光束(全 ての方向に放出する光束の総和)は89.0%,光効率は92.6%に減少してい る(乙216)。もっとも,被告 403W 製品の LED1個あたりの配光データは, 新品の LED の配光データが概ね120度(ランバーシアン配光の場合)であるの に対し,114度及び115度である(乙214,215の3,215の4)。 また,403W 製品のカバーと 402W 製品のカバーは,共通の部材(ポリカーボネ ート)を使用した同じ仕様のものであると認められるところ(乙35,298,2 99,315),被告 403W 製品と未使用の 402W 製品について,それぞれカバー を交換して全光束及び y/x 値を測定した結果,いずれも交換せずに測定した結果と の差は,1%以下(全光束)及び0.01(y/x 値)であった(乙316〜318, 弁論の全趣旨)。
(イ) 以上の事情を踏まえると,被告 403W 製品の LED 素子は,6年以上使用を 継続されているものであり,LED 樹脂部の黄変及び全光束や光効率の減少は生じ ているものの,その配光特性は,初期値(ランバーシアン配光)と大きく異ならず, 著しい経時変化は見られないものといってよい。403W 製品の光拡散性を有するカ バー部分についても,被告 403W 製品には,上記継続使用期間にもかかわらず,全 光束や y/x 値の測定値に影響を与えるような劣化等が生じているとはいえない。 そうすると,被告 403W 製品について,被告が平成30年7月23日に測定した y 値=15.7mm,x 値=11.7mm,y=1.34x との測定結果(乙166)及び令和2年1 月29日に測定した y 値=15.6mm,x 値=11.7mm,y=1.33x との測定結果(乙29 7)は,いずれも 403W 製品の初期値とほぼ同等のものと見るのが相当である。
(ウ) そうすると,403W 発明は,「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y(mm)とし,隣り合 う前記 LED チップの発光中心間隔を x(mm)とすると,y=15.7mm,x=11.7mm であり,y=1.34x」との構成すなわち構\成 1-3d及び 1-14g10)を有するといえる。 したがって,403w 発明は,本件発明1−1の構成要件 1-1D,本件発明1−3の 構成要件 1-3D,本件発明1−14の構成要件 1-14F,本件発明1−16の構成要素 1-16D 及び本件発明1−17の構成要件 1-17D 並びに本件訂正発明1−17の 構成要件 1-17F’及び本件訂正発明1−18の構成要件 1-18J’に相当する構成を有していると認められる。\n
ウ 以上より,403W 発明は,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及び1 −18の構成要件を充足する構\成を備えたものであり,これらの各発明と同一性が 認められる。
エ 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は,被告 403W 製品について,長時間の使用による経年変化,LED 素子の樹脂やせや黄変,使用環境の影響等により,被告測定時点での被告 403W 製 品の y/x 値等が初期値のものと同等とはいえない旨を主張する。 しかし,上記のとおり,被告 403W 製品については,長時間の使用による経年変 化等により,LED 素子の中央部に黄変が見られ,また,カタログ値と比較して全 光束や光効率が10%程度減少しているという事実は認められるものの,それ以上 に,LED 素子の劣化(凹み)をはじめ,配光特性に影響を及ぼし得るような LED 素子の劣化等を裏付ける具体的な事情は見当たらず,カバー部材についても,y/x 値等に影響を与えるような劣化が生じているといった事実の存在を具体的にうかが わせる事情は見当たらない。本件交換実験の結果に関しても,上記のとおり,交換 に係る製品が共通の部材を使用した同じ仕様のものであると認められることに鑑み ると,原告 PIPM が指摘する事情を考慮しても,その結果の信用性を直ちに疑うべ きものとまではいえない。 その他原告 PIPM が縷々指摘する事情を踏まえても,この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
(3) 先使用権の範囲
上記(1)及び(2)によれば,被告は,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及 び1−18の内容を知らないで自らこれらに含まれる 403W 発明をし,本件優先日 の際に,日本国内において,その発明の実施である事業をしている者と認められる。 したがって,被告は,403W 発明及び上記事業の範囲内において,本件各発明1並 びに本件訂正発明1−17及び1−18に係る特許権について,通常実施権を有す る。 また,403W 製品は,x 値及び y 値の関係性を特定する技術的思想が明示的ない し具体的にうかがわれるものではないものの,実際にはその x 値及び y 値の関係性 により,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及び1−18に係る構成要件に相当する構\成を有し,その作用効果を生じさせている。加えて,403W 発明につき, 照明器具としての機能を維持したまま,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17及び1−18の特定する x 値及び y 値の関係性を充たす数値範囲に設計変更するこ とは可能と思われる。このため,被告製品1〜5及び7〜16は,いずれも,403W 発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式であるにとどまる ものといえる。 そうすると,被告による被告製品1〜5及び7〜16の製造販売は,被告の上記 通常実施権の及ぶ範囲内に含まれる。
(4) 小括
以上のとおり,被告は,403W 発明に基づく上記通常実施権により,業として被 告製品1〜5及び7〜16を製造販売し得ることから,その余の点につき論ずるま でもなく,原告 PIPM は,被告に対し,本件各発明1並びに本件訂正発明1−17 及び1−18に係る本件特許権1を行使し得ない。
6 無効理由9(クラーテ製品2)の公然実施による新規性欠如)の有無(争点12)
(1) 公然実施の有無
ア 証拠(以下に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら れる。
(ア) リコーは,平成23年7月7日,直管形 LED ランプである「クラーテ P シ リーズ40形」を同月末発売予定である旨をプレスリリースした。また,同社は,平成24年1月現在の製品を掲載したカタログ「<クラーテ>P シリーズ」(乙1 71の1)にクラーテ製品2)を掲載しているところ,同カタログ掲載の仕様は,上 記プレスリリースに係る製品の仕様と概ね同一である。さらに,同社は,遅くとも 同月には,クラーテ製品2)を含むシリーズ製品を販売していた。(上記のほか,乙 170,172,173,368)
(イ) 被告は,令和元年9月12日終了のオークションにより,クラーテ製品2)1 4本(被告クラーテ製品2))を入手したところ,これらの被告クラーテ製品2)には, いずれも,製造ロット番号として「1203」が表示されている。これは,当該製品の製造年月が平成24年3月であることを意味する。(乙172,174,186,\n288)
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば,クラーテ製品2)は,遅くとも平成2 4年1月頃には,リコーから販売されたことによりその構造が解析可能\な状態に至 ったものと認められる。 これに対し,原告 PIPM は,クラーテ製品2)の上市時期が明らかでないこと,仮 に被告クラーテ製品2)の製造日が平成24年3月であっても,製品製造後すぐ出回 るとは考えがたいことなどを主張する。 しかし,上記のとおり,リコーがクラーテ製品2)を平成24年1月には販売して いたことが認められるのであって,それから約3か月が経過した本件優先日時点で は,クラーテ製品2)が実際に市場に出回っていたものと見るのが合理的かつ相当で ある。したがって,この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
ウ 小括
以上より,クラーテ発明2)は,本件優先日より前に日本国内において公然実施を された発明といえる。
(2) クラーテ発明2)の構成等
ア クラーテ発明2)が構成 1-20a’12〜f’12 及び h’12 を有すること,これらの構成がそれぞれ本件訂正発明1−20の構\成要件 1-20A’〜F’及び H’に相当すること については,原告は明らかに争わないことから,これを認める。なお,本件訂正発 明1−20の構成要件 1-20D’の「「基台の上に実装された」の意義について, LED チップが実装された容器が基板を介して間接的に実装された構成を含むことは上記2のとおりである。\nイ 被告クラーテ製品2)14本の構成 1-20g’12 に係るパラメータ(y/x)の被告 測定値は,1.208〜1.278 であった(乙289)。また,関連無効審判における検 証手続の結果によれば,被告クラーテ製品2)は,x 値は 8.6mm,y 値は 10.39mm であり,y≒1.208x であった(乙346,365,弁論の全趣旨)。 そうすると,クラーテ発明2)は,「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y(mm)とし,隣り合う 前記 LED チップの発光中心間隔を x(mm)とすると,y≒1.208x の関係である」(構成 1-20g’12)の構成を有するものと認められる。この構\成は,本件訂正発明1−20 の構成要件 1-20G’に相当する。
(3) したがって,本件訂正発明1−20は,本件優先日より前に日本国内におい て公然実施をされた発明であるクラーテ製品2)に係る発明と同一の発明であるから, 法29条1項2号に違反し,無効にされるべきものと認められる。すなわち,本件 訂正発明1−20に係る本件訂正によっては無効理由が解消されないことから,本 件訂正発明1−20に係る訂正の再抗弁は認められない。
(4) 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は,被告測定値のばらつきや経年変化等の事情を指摘して,被告測定 値が初期値と等しいとはいえない旨を主張する。 この点,被告クラーテ製品2)については,オークションの出品者による説明とし て,中古品であること,商品の状態として「やや傷や汚れ」があること,使用期間 が2年弱であること,電気工事業者による取り外し作業の際に「ざっくりと中性洗 剤で管だけ拭きあげた状態」で丁寧な梱包により発送すること,「RICOH ロゴマ ークあたり」が黒ずんで見えるものの,LED は使用が進んでも黒ずむことはない ため元々の仕様であることなどが記載されている(乙288)。 もっとも,クラーテ製品2)は,光束が70%まで低下するまでの定格寿命が4万 時間とされている(乙170の3,171の1)。このため,被告クラーテ製品2) につき,仮に25%に相当する1万時間使用された事実があったとしても,配光特 性に影響を与えるとは必ずしもいえず,現に,被告クラーテ製品2)のうち2本の配 光特性はいずれも117度である(乙320)。口金ピンやランプマーク側の管端 部の黒ずみについても,その存在から直ちに他の部位にも同様の黒ずみが存在し, 配光特性に影響を与えるとは必ずしも推認し得ないことから,同様である。また, クラーテ製品2)については,光触媒の膜が剥がれて本来の効果が得られなくなる場 合があるとして,製品の表面を強く擦らないようにとの注意喚起がされているものの(乙170の3),「ざっくりと中性洗剤で」「拭き上げ」るといった態様がこ\nれに含まれるとは考えられない。むしろ,LED ランプの手入れ方法としてこのよ うな方法が奨励されているとも見られる(乙35)。さらに,被告クラーテ製品1) (乙169,214,215によれば,未使用品と認められる。)と被告クラーテ 製品2)のカバー部材を交換した測定によっても,両者の半値幅等に有意な差異はな い(乙370)。 これらの事情等を踏まえると,被告クラーテ製品2)につき,経年変化等によりパ ラメータの値に変化が生じているとは考えられず,上記(2)での認定に係る被告ク ラーテ製品2)の被告測定値及び関連無効審判の検証手続における測定値は,初期値 と概ね等しいものと見られる。 したがって,この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
7 まとめ
以上のとおり,本件各発明1(並びに本件訂正発明1−17及び1−18)に係 る本件特許権1に基づく原告 PIPM の請求については,被告に 403W 発明に基づく 先使用権が成立することにより,原告 PIPM は,被告に対し,本件特許権1を行使 し得ない。他方,本件訂正発明1−1に係る訂正の再抗弁は,被告製品1〜5,7 〜16がその技術的範囲に属さないことにより,また,本件訂正発明1−20に係 る訂正の再抗弁は,クラーテ発明2)の公然実施を理由とする新規性欠如の無効理由 があり,本件訂正によって無効理由が解消されないことにより,いずれも再抗弁の 成立が認められない。 以上より,その余の点について論ずるまでもなく,被告による本件特許権1の侵 害は認められないから,原告 PIPM の本件特許権1の侵害に基づく請求は,いずれ も理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.10.26
令和2(ワ)26567 著作権 民事訴訟 令和3年8月18日 東京地方裁判所
「この水虫(白癬)爪専用クリアーネイル&ヤスリセットは100年以上の歴史を誇るDrスコール社が科学的に研究を重ねて作られた独自技術の集大成です。解決法として従来製品よりも簡単に優しく治療できます。
水虫(白癬)菌の発育を妨げ菌の発生を防ぎます。
水虫(白癬)菌の成長と始発を予防し清潔な爪に貢献をします。」\n
被告説明文の「ア」部分は,本件商品がドクターショール社の製品であるこ とや,本件製品が従来製品よりも簡単かつ優しく治療できること,水虫菌の発 生・発育を防止することなどを記載するものである。このような製品の出所, 特性や効能については,その性質上,消費者が過大な期待を抱くことのないよ\nうに,客観的な事実をできる限り正確かつ明確に説明することが求められてお り,思想又は感情を創作的に表現する幅は狭く,表\現の選択肢は限られたもの となると考えられる。このため,上記「ア」部分の記載に創作性があるとは認 められない。
(2) 被告説明文の「イ〜エ」部分は,本件商品が適合する症状や,本件商品の使 用方法,爪白癬(爪水虫)が生じる原因について記載したものである。これら についても,利用者が誤った場面や方法で本件商品を使用すること等を避ける ために,前記ア同様,その性質上,客観的な事実をできる限り正確かつ明確に 説明することが求められており,思想又は感情を創作的に表現する幅は狭く,\n表現の選択肢は限られたものとなると考えられる。このため,上記「イ〜エ」\n部分の記載についても創作性があるとは認められない。
2021.10.26
令和3(ネ)10005 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 特許法102条3項による損害額として,侵害品の売上高を基準とし, そこに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定する場合,実施に対し受 けるべき金銭の料率の算定に当たっては,1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界におけ る実施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわ ち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,3)当該特 許発明を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の態様,
4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた 諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。以下,順に 検討する。
1) 当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それが明 らかでない場合には業界における実施料の相場等 本件訂正発明について実際に実施許諾契約が締結されたことを示 す証拠はない。
・・・
本件訴訟において,本件特許権の技術分野については実際の実施許 諾契約の実施料率を示す証拠はない。 本件特許権の技術分野に近似する分野(「機関またはポンプ」) の実施料率についてのアンケート調査結果によれば,実施料率3〜 4%未満の例が最も多く(37.5%),実施料率5〜6%未満の例 や実施料率2〜3%未満の例は同数(12.5%),実施料率1〜 2%未満は3件(18.8%)とされており,また,他の調査結果や データベースには,実施料率3%又は6%の例や実施料率5〜8%又 は3%の例もあったとされていることからすれば,圧縮機の分野でも, 実施料率を3%から4%程度とする例を中心としつつ,その前後の実 施料率とする例も相当程度あることがうかがわれる。 なお,一審被告は,前記第2の3 本件訴訟の 事案と本件ライセンス契約はいずれも圧縮機を販売するための特許権 の実施許諾を対象とするものであって,実施許諾の対象は同じと評価 すべきであるから,本件ライセンス契約を重視すべきであると主張す るが,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●このようなライセンス契約の事例を他の事例より 特に重視すべき理由があるとはいえず,圧縮機分野の実施料率の一例 としてみるのが相当である。
また,一審被告は,甲19ないし21に掲げられた事例は,いず れも,一審被告や一審原告とは何ら関係がない一般的なものであって, 具体的な点において,本件と共通性や類似性はないとか,本件特許権 は,圧縮機の分野に係る日本の特許権1件であるから,特許法102 条3項の実施に対し受けるべき料率を検討するに当たっては,日本の 特許権1件の非独占的な実施許諾による料率と対比すべきであるとこ ろ,甲20は日本の特許権に関するものではなく,また,独占的実施 許諾の事例であるなどと主張するが,実施料率を定める事例として, 具体的な点において完全に合致する事例がなければ,同分野の他の事 例(他の国の特許権に関するものを含む。)を参酌することは当然で あるし,甲20で独占的とされるのは製造のみであり,販売について ライセンシーが独占権を得ていることはうかがわれない。したがって, 一審被告の主張は採用できない。
2) 本件訂正発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性\n
本件優先日前である平成9年3月25日に発行された書籍「カーエ アコン」(甲11)には,ピストン式圧縮機の斜板形のものでロータ リバルブを使用したものは記載されておらず,113頁の図6.5で 吸入弁(リードバルブ)が図示されている。 従来技術であるリードバルブ方式は,シリンダ室と吸入室の圧力 差が必要であること,流路断面積が小さいこと,弁による吸入抵抗が 発生するという難点があることから,シャフトの回転によって冷媒を 提供するロータリバルブ方式が提案されてはいたものの(乙18,2 2,23,28,30等),回転軸の外周面と軸孔の内周面のクリア ランスによって,吐出行程時の圧縮室から冷媒が漏れるという問題が あったこと,クリアランス管理が非常に難しいこと(本件明細書【0 004】)から実用化には至っていなかったのであり,本件訂正発明 において,ロータリバルブを備えた回転軸に伝達される圧縮反力を利 用して,吐出行程にあるシリンダボアに連通する吸入通路の入口に向 けてロータリバルブを付勢させて,体積効率を向上させていること (本件明細書【0015】),クリアランスに関する厳密な管理が不 要となること(本件明細書【0043】)は,コスト面も含め,ロー タリバルブ方式を実用化するのに寄与したものと認められ,一審原告 が,本件優先日後に,ロータリバルブ方式のピストン式圧縮機を販売 していることは争いがない。
もっとも,実用化当初の一審原告の製品(10SR15C)は, 本件訂正前の構成であるから,ロータリバルブが円筒状でなく凹部や\n溝が設けられており,本件訂正発明そのものの実施品ではないと考え られる。しかし,同製品も,圧縮反力で冷媒漏れを防止するという本 件訂正発明の技術思想を利用するものであり,この点については本件 訂正の前後で変更はない。 そうすると,本件訂正発明はロータリバルブ方式のピストン式圧 縮機の実用化に寄与したものというべきで,相応の顧客吸引力がある ということができる。
一審被告は,被告各製品の販売先であるマツダに対し,設計変更 品を継続して販売しているが,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●少なくとも,侵害時(平成24年12月から平成 29年6月)の大部分において,本件訂正発明の効果を奏する代替 技術はなかったということになる。
3) 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害 の態様
本件訂正発明がロータリバルブ方式を実用化するのに貢献したこ とは前記2)のとおりである。 一方,どの程度の体積効率の向上がもたらされるかは具体的数値 をもっては明らかではなく,本件訂正発明の作用効果についての顧客 吸引力等は一定程度限定される。 被告各製品はクラッチ部分と組み合わされて販売されている。 乙62によれば,被告各製品に該当する部品番号に相当するコン プレッサー(クラッチ部分及び圧縮機部分)の販売価格は468.1 5ドル,クラッチ部分のみの販売価格は231.82ドルとする事例 があることが認められるが,これはアフターマーケット(商品販売後 の需要に対する正規ディーラーではない業者の市場)における販売価 格であり,直ちに一審被告とJCSないしマツダとの間の被告各製品 の取引にあてはめることはできない。また,一審被告は,被告各製品 と別にクラッチを販売しているものではない。 しかし,クラッチ部分と圧縮機部分は観念的には区別することが でき,特許法102条3項の適用に当たっては,被告各製品の売上高 は,クラッチ部分を含むものであるという事情も考慮する必要がある。 一審被告は,前記第2の3 被告各製品は,本 件訂正発明とは無関係に,厳密なクリアランス管理により,冷媒漏 れ防止の効果を達成していると主張する。 一審被告のいう被告各製品における「厳密なクリアランス管理」 は,シャフトとシャフト用孔を極めて高精度に仕上げ,クリアラン スを30μmに設定する構造を採用し,ラジアル軸受は,斜板取付\nけ部とスラスト軸受を除く全領域でシャフトを支持する軸受とし, さらに,軸受がシリンダブロックの外側に突き出る長い構造を採用\nすることによって,シャフトの動きを伴うことなく,冷媒が吸入通 路の入口から漏出するのを防止するというものである(引用に係る 原判決12頁5行目ないし13行目)。
しかし,一審被告の主張のとおり厳密なクリアランス管理により冷 媒漏れを防止しているというのであれば,乙3報告書(被告製品1 〔クリアランスが30μm〕と,クリアランスを50μm,70μm, 90μm,110μmに変更した圧縮機の体積効率を比較したもの) において,クリアランスが30μmである被告製品1よりも50μm のものの方が体積効率は落ちることになるはずであるが,30μmと 50μmとで体積効率はほとんど変わらなかったとされているのであ るから,一審被告の主張は十分な裏付けを欠くものというべきである。\nまた,仮に,被告各製品が,一審被告主張の厳密なクリアランスを 採用し,その構成が冷媒漏れの防止に対する効果を奏することがある\nとしても,一方で,被告各製品は,原判決別紙イ号物件説明書及びロ 号物件説明書記載のとおりの構造を有しており,ピストン60に作用\nした圧縮反力Fが斜板やスラスト荷重吸収機能が付与されたフロント\n側スラスト軸受70に伝達され,このスラスト荷重吸収により斜板5 1の動きを許容することで斜板51の径中心部を中心としてシャフト 50を傾かせようと作用し,これによって,シャフト50(回転弁) は,吐出行程中のシリンダボア22に連通するフロント側通路23の 入口に向けて付勢され,この際シャフト50が変位しているのであっ て,この本件訂正発明の構成要件C,Fを充足する構\成によっても, 冷媒漏れが防止されるものといえることは,原判決が第4の3で説示 するとおりであるから,本件訂正発明とは無関係に冷媒漏れを防止し ているという一審被告の主張は採用できない。
4) 特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針
一審原告は,ロータリバルブ方式のピストン式圧縮機を製造・販 売しており,一審被告は,平成24年12月以降,ロータリバルブ 方式のピストン式圧縮機である被告各製品を輸入・販売しているの であるから,両者は競合関係にある。一審被告は,前記第2の3⑵ のとおり,被告各製品が組み込まれていたマツダ製の自動車 においては,圧縮機について,「被告親会社→一審被告→JCS→ マツダの商流」という系列関係が確立しているとして競業関係を否 定するが,ここでは,特許権者と侵害者の間の料率を定める上で競 業関係が問題とされているのであるから,一審原告がマツダに直接 販売することができるかどうかの問題ではなく,一審被告の主張は 採用できない。 ロータリバルブ方式のピストン式圧縮機の市場は寡占状態にあり, 相互に実施許諾を行っていない閉ざされた市場傾向にある(弁論の 全趣旨)。
イ 以上の検討を踏まえると,圧縮機の分野では,実施料率を3%から 4%程度とする例を中心としつつ,その前後の実施料率とする例も相当 程度あることがうかがわれること,本件訂正発明が相応の技術的価値を 有し,代替品もなかったこと,一審原告と一審被告が競業関係にあり, 相互に実施許諾を行うことが考えにくいこと,他方,本件訂正発明の作 用効果に対する顧客吸引力等は一定程度限定されること,被告各製品の 売上高はクラッチ部分を含むものであること等の本件諸事情を考慮すれ ば,特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,本件での実 施に対し受けるべき料率は,3%と認めるのが相当である。 なお,一審被告は,第2の3 本件訂正発明の作用 効果や侵害の成否等について,前件侵害訴訟における知財高裁判決や本件 無効審決,ソウル高等法院等,判断主体によって判断が分かれていること\nを理由に,本件訂正発明の価値が低いと主張するが,事前の実施許諾契約 の料率については特許権が無効となる可能性等も考慮して算定されるのと\n異なり,特許法102条3項の損害は,特許権が有効であり,特許権侵害 があることを前提に算定されるものであるから,別個の手続の状況を考慮 に入れるのは相当でない。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2021.10.21
令和3(ネ)10029 特許侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年10月13日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
足場が不要になることが本件発明の唯一の効果であるとはいえないことは,上記2のとおりである。また,同業他社の製品(乙60の各枝番)の施工方法は,証拠上は必ずしも明らかではなく,本件発明及び被告方法のように,倹鈍式によるガラス板の嵌め込み,ガラス板及び目地枠を摺動させることによる取付け,係止爪と被係止爪との係止,といった工程を可能にするものか否かは定かでない。また,控訴人が引用する裁判例は,本件とは事案を異にし,本件における損害額の算定において参考となるものではない。そうすると,控訴人の当審における上記主張は,原判決を引用して説示したとおり推定覆滅率2割を相当とするとの判断を左右するものではなく,採用することができない。\n
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成29(ワ)10716
以上によれば,本件発明は,施工コスト低減という効果(3))によりこれを
実施する製品の販売等に貢献するものであって,相応の顧客誘引力を有するといえ
るものの,その程度は限られているというべきである。また,効果1)及び2)に関し
ては,本件発明は,手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同
程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ア) 外観上の体裁の良さ等(1))について
証拠(乙27,29〜31,39,42。各枝番を含む。以下同じ。)によれ
ば,乙27製品等は,いずれも,手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数
のガラス板が取り付けられ,ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認
められる。これにより,これらの製品は,本件発明の効果1)と同様の効果を奏する
ものといえる。
(イ) 取付強度の高さ等(2))について
証拠(乙27,29〜31,39,42)によれば,乙27製品等は,いずれ
も,ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠(縦枠,竪枠)を用い,ガラス取付
枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる
(乙31製品については,「2辺支持タイプ」との記載もあるが(甲18),「4
辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある(乙31)。)。これにより,こ
れらの製品は,本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。
これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製
目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指
摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的
にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件明細書によれば,取付
強度及び耐久性に係る本件発明の効果は,「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係
合保持され,隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し
て」(【0013】)の強度に関するものに過ぎない。このほか,原告製品(証拠(甲
14,15)及び弁論の全趣旨より,本件発明に係る取付方法により取り付けられ
るものと認められる。)と同様に,これらの製品の施工例として高層マンション等
の複数階層を有する建築物が示されていること(乙30,31,42)に鑑みて
も,乙30製品,乙31製品及び乙42製品は,少なくとも,原告製品と競合し得
る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。
したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(ウ) 施工コストの低減(3))について
証拠(乙37〜42)によれば,乙27製品等は,いずれも,ガラス板とアルミ
製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり,ガラス板とアルミ製目地枠を\n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに
より,これらの製品は,本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。
これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製
目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指
摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程
度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件発明の効果の1つである施工コ
ストの低減は,足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって,
アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること(乙30製品,乙31製品)や手摺
笠木部分の取付方法が回転式であること(乙42製品)による製造コストとは無関
係である。
したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(エ) その他
原告は,乙27製品及び乙29製品につき,本件特許権を侵害する製品である可
能性が高い旨を指摘する。しかし,原告も可能\性を指摘するにとどまるし,これら
の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから,本件に
おいては,この点は考慮に含めないこととする。
(オ) 以上より,乙27製品等は,いずれも,本件発明の効果と同様の効果を有す
る製品として,原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当
である。
もっとも,原告は,原告製品を遅くとも平成24年3月までには販売していると
認められる(甲14,15,弁論の全趣旨)。他方,証拠(乙55)及び弁論の全
趣旨によれば,乙27製品等の販売開始時期は,乙31製品が平成24年,乙27
製品が平成26年,乙30製品が平成27年,乙29製品が平成28年3月,乙3
9製品が平成29年10月であることが認められる。
また,原告製品,被告製品及び乙27製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ
ットレール製品市場におけるシェアは,いずれも証拠上明らかでない。
これらの事情を総合的に考慮すると,アルミ製手摺製品の市場において原告製品
及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば,特許法102条2
項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの,被告に
よる主張立証の程度に鑑みれば,その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば,被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程
度は限られるものの,他方で,競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的
であり,他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから,本件におい
ては,2割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに
反する原告及び被告の各主張は,いずれも採用できない。
そうすると,特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額は,以下のと
おりとなる。
・・・
したがって,原告の損害額は合計5481万9267円となり(内訳は以下のと
おり),原告は,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づき,同額の損害賠
償請求権を有する。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.10.19
令和3(ネ)10036 著作権等の侵害に基づく削除等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年9月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
既存の著作物に依拠して創作された著作物が思想,感情若しくはアイデア, 事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表\現上の創作性がない部 分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案に当 たらないことは引用する原判決が説示するとおりである。
本件についてみると,被告イラストは,原告文章と同じく,原作である「O NE PIECE」に登場するキャラクターの設定に依拠して,身長差のあ る同性の2人が,壁に掴まりながら特定の体位で性交渉を行うという描写に おいて,原告文章と同一性を有するにとどまるものであり,こうした描写自 体は,アイデアないし着想にすぎないか,表現上の創作性がない部分である。\nそうすると,原告文章を全体として見た場合に一定の創作性が認められる余 地があるとしても,前述のとおり,被告イラストは,原告文章のうちアイデ アないし着想にすぎないか,表現上の創作性がない部分において同一性を有\nするにすぎないのであるから,原告文章の翻案に当たるものでないことは明 らかというべきである。 控訴人は,原告文章の創作性につき前記第2の3(1)のとおり指摘し,被告 イラストは,これらの創作部分が全て描写されているので,原告文章の翻案 に当たる旨主張するが,控訴人の指摘する部分は,いずれも,アイデアない し表現上の創作性のない部分であるにすぎないし(「ONE PIECE」 に登場するキャラクターの設定については,当然のことながら創作性を認め ることができない。),その具体的な表現ぶりも,性表\現として平凡かつあ りふれたものであり,そもそも被告イラストが当該表現部分に依拠して作成\nされたと特定することもできないものといわざるを得ない。 したがって,控訴人の主張は失当というほかない。
(2) 被告文章が原告イラストの翻案に当たるとの点について
被告文章は,原作である「ONE PIECE」に登場するキャラクター の設定に依拠して,原作に登場する2人の人物が性交渉後に,身長の低く若 い人物(ルフィ)が失禁したと勘違いし,動揺をしている描写設定において, 原告イラストと同一性を有するに止まり,こうした描写設定は,同性間の性 交渉を描写するに当たってのアイデアないし着想にすぎないか,表現上の創\n作性があるとはいえない部分である。そうすると,原告イラストを全体とし て見た場合に一定の創作性が認められる余地があるとしても,前述のとおり, 被告文章は,原告イラストのうちアイデアないし着想にすぎないか,表現上\nの創作性がない部分において同一性を有するにすぎないのであるから,原告 イラストの翻案に当たるものでないことは明らかというべきである。 控訴人は,前記第2の3(2)のとおり,被告文章は,原告イラストの最後の コマの「ルフィ」のセリフを受けて,あたかも連歌のように,直前の状況や 内容を参看し,その背景や情趣,心境を踏まえて,そのポエジーを受け継い で記載されたものである旨主張するが,独自の見解というほかないものであ り,控訴人主張のセリフ自体に表現上の創作性を認めることはできないし,\nましてやそのセリフから連歌性やポエジーの存在を認め,被告文章が原告イ ラストに依拠した翻案に当たるなどと認めることは到底できない。
◆判決本文
原審はこちら
◆令和1(ワ)30833
以下のように判断されています。
まず,原告文章と被告イラストについては,原告文章が言語の著作物で
あるのに対し,被告イラストは基本的には美術の著作物であって,表現の\n形式が異なり,これらを対比すると,両者は,描写対象の設定(身長差の
ある設定の2人の登場人物が,一般的には困難と思われている体位で性行
為を行っている点,性器の状態,及び登場人物の一方が壁につかまろうと
しているという点)につき同一性を有するにとどまるといえる。しかして,
上記描写対象の設定は,その内容自体や,原告文章の性質・内容に照らし,
内面的思想たるアイデアにすぎず,表現それ自体でない部分であるという\nべきである。また,仮に表現自体と捉えられる部分があったとしても,本\n件各証拠を見ても,上記設定による表現に幅があると認められ制作者の個\n性の表れとして著作物性を肯定することを基礎付けるに足りるものは見当\nたらず,原告文章の性質・内容に照らせば,上記設定を前提とする限り,
これを表現したものとしては平凡かつありふれたものであり,表\現上の創
作性がない部分であるといわざるを得ない。
イ 次に,原告イラストと被告文章については,原告イラストが基本的には
美術の著作物であるのに対し,被告文章は言語の著作物であって,表現の\n形式が異なり,これらを対比すると,両者は,描写対象の設定(2人いる
登場人物の一方が性的行為の際に勘違いをした状況で,他方の登場人物に
対する言動・働きかけに及んでいる点)につき同一性を有するにとどまる
といえる。しかして,これについても,上記説示が同様に当てはまるもの
である。すなわち,上記描写対象の設定は,その内容自体や,原告イラス
トの性質・内容に照らし,内面的思想たるアイデアにすぎず,表現それ自\n体でない部分であるというべきである。また,仮に表現自体と捉えられる\n部分があったとしても,本件各証拠を見ても,上記設定による表現に幅が\nあると認められ制作者の個性の表れとして著作物性を肯定できることを基\n礎付けるに足りるものは見当たらず,原告イラストの性質・内容に照らせ
ば,上記設定を前提とする限り,これを表現したものとしては平凡かつあ\nりふれたものであり,表現上の創作性がない部分であるといわざるを得な\nい。
ウ 以上によれば,被告イラストは原告文章を翻案したものには当たらず,
また,被告文章は原告イラストを翻案したものには当たらないというべき
である。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2021.10.19
令和2(行ケ)10103 特許権 行政訴訟 令和3年10月6日 知的財産高等裁判所
ア 甲1発明の課題の認定について
(ア) 黄色の発色
甲1には,「イエロー系」,「イエローとライトイエローの違いが分かり づらいです。」(4頁の上から5枚目の写真の上下)と記載されていると ころ,この記載からは,甲1製品において,「イエロー」と「ライトイエ ロー」の色の相違が判別し難いという問題があることは認められる。し かし,上記の記載の前提として,「イエロー」は,色票等ではなくペンラ イトの「ライトイエロー」との比較がされているにとどまる上(上記写 真),色の相対的な判別の問題と,一般的に各色の基準とされている色(色 票の該当色)にどれだけ近い色を出しているかという発色の問題は異な るから,「イエロー」と「ライトイエロー」の色の相違が判別し難いとい う上記の問題は,「イエロー」が一般的に黄色の基準とされている色にど れだけ近い色を出しているかという発色の問題とは異なる。 本件審決は,「それら『イエロー』及び『ライトイエロー』の各発色に ついて検討するに,p.4-写真には,写真中央に位置する4本のペンライ トの他に,その左側に2本(『亜美・真美』及び『小鳥』),右側に2本(『ル ミスティック』及び『大電光改』)の計4本の他のペンライトが色比較の ために配置されているところ,上記写真中央の4本(甲1発明)の『イ エロー』の発色は,上記他の4本のペンライトの黄色の発色とは異なり, むしろ p.4-6 写真((摘示(1q))示されるオレンジ系の色に近い発色 となっている。」(本件審決第6,2,2−1(2)(2−1)ア(ア) 〔本件 審決47頁〕)と述べ,甲1の写真を根拠として,甲1製品の「イエロー」 とされる黄色の発色自体に問題があるという認定をしている。本件審決 が,甲1サイトのアドレスにアクセスの上,ディスプレイ上に表示され\nた写真(画像)に基づいて上記認定をしたのか,又は用紙に印刷された 写真に基づいて上記認定をしたのかは,本件審決の記載からは直ちには 明らかでないが,仮に,前者であるとした場合,ディスプレイに表示さ\nれる色の発色は,ディスプレイ自体の性能や調整に依存するものである\nし,また,後者であるとした場合でも,紙に印刷される色の発色は,紙 の品質やプリンタの性能や調整に依存するものであり,さらにいえば,\n写真を撮影したカメラの性能や調整によっても発色は相違するものであ\nるから,いずれにしても,実際の甲1製品の発色とディスプレイ上の表\n示又は印刷されたものの発色は,必ずしも同じとは限らない。また,甲 1製品と対比された他社のペンライトが,甲1製品よりも,一般的に黄 色の基準とされている色に近いことを裏付ける客観的な証拠はない。そ のため,甲1の写真に基づいて,「イエロー」が一般的に黄色の基準とさ れている色にどれだけ近い色を出しているかを判断することはできず, 甲1の写真を根拠に,「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題がある と認定することはできない。
その他の甲1の記載によっても,甲1に,「イエロー」とされる黄色の 発色自体に問題が内在しているという課題が示されていると認めること はできない。 そうすると,「イエロー」と「ライトイエロー」の各発色の色の違いを 明確に識別することができないという問題は,「イエロー」とされる黄色 の発色自体に問題が内在しているということもできるとする本件審決の 判断(前記(3)ア(ア))は誤りである。
(イ) 演色性
本件審決が甲1発明の課題に関して認定する「演色性」は,発色のバ ランスを崩れないようにすることや,全体が綺麗に光るようにすること (前記(3)ア(イ)),多くの色彩の選択肢を提供すること(前記(3)(ウ)。 本件審決は,第6,2,2−1(2)(2−1)ア(ウ)〔本件審決48頁〕で, 甲10に記載されているように周知の課題といえると認定する。)であり, 甲2に記載された技術事項として認定された「演色性」,すなわち,照明 された物体の色が自然光で見た場合に近いか否かという,一般的な意味 での「演色性」(前記(3)イ(イ))とは異なる。
イ 甲2に記載された技術事項の認定
前記(3)イ(イ)のとおり,甲2に記載された技術事項として認定された「演 色性」は,照明された物体の色が自然光で見た場合に近いか否かという, 一般的な意味での「演色性」であるものと認められる。
ウ 相違点1に係る本件発明1の構成のうちの「黄色発光ダイオード」及び\nその「発光色」の容易想到性
前記(2)のとおり,甲1発明と甲2に記載された技術事項は,技術分野が 完全に一致しているとまではいえず,近接しているにとどまるから,甲1 発明に甲2に記載された技術事項を採用して本件発明1を想到すること が容易であるというためには,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採 用するについて,相応の動機付けが必要であるというべきである。
本件審決は,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付け があり,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して本件発明1を容 易に想到することができたと判断する前提として,甲1発明に,「イエロー」 とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があり(前記(3) ア(ア)),甲1発明に,演色性を向上させるという,甲2と共通の課題があ ると認定した(前記(3)ア(イ),(ウ))。しかし,前記ア(ア)のとおり,甲1発 明に,「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課 題があるとする本件審決の認定は誤りであるし,また,本件審決が甲1発 明の課題に関して認定する「演色性」(本件審決が第6,2,2−1(2)(2 −1)ア(ウ)〔本件審決48頁〕で,甲10に記載されているように周知の 課題といえると認定する事項を含む。)は,甲2に記載された技術事項とし て認定された「演色性」,すなわち,照明された物体の色が自然光で見た場 合に近いか否かという,一般的な意味での「演色性」とは異なる(前記ア (イ))。
そうすると,本件審決は,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用 する動機を基礎づける甲1発明の課題の認定を誤っているものであり,ま た,甲2に記載された技術事項の内容(前記(1)),甲1発明と甲2に記載さ れた技術事項の技術分野相互の関係(前記(2))を考慮すると,甲1発明に は,甲2に記載された技術事項と共通する課題があるとは認められず,そ のため,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付けがある とは認められない。 したがって,甲1発明に甲2に記載された技術事項及び周知の課題(甲 10)を採用して,黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到するこ とができたとは認められず,これを容易に想到することができたとする本 件審決の判断(前記(3)ウ(ア))は誤りである。
本件審決は,甲1発明に甲2に記載された技術事項及び周知の課題(甲 10)を採用して,黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到するこ とができた(前記(3)ウ(ア))という判断を前提として,甲1発明に甲2に記 載された技術事項及び周知の課題(甲10)を採用し,本件発明1の構成\nのうちの「黄色発光ダイオード」及びその「発光色」を容易に想到するこ とができた(本件審決第6,2,2−1(2)(2−1)イ(ア)〔本件審決48 〜50頁〕)と判断するところ,その前提とする判断が誤っているから,本 件発明1の構成のうちの「黄色発光ダイオード」及びその「発光色」を容\n易に想到することができたという判断も誤りである。
エ 黄色発光ダイオードの単独発光色及び混合発光色の容易想到性
前記ウのとおり,甲1発明と甲2に記載された技術事項との間には課題 の共通性がなく,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付 けがあるとは認められないが,念のため,仮にそのような動機付けがある として,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用することにより,黄 色発光ダイオードが単独で発光することにより得られる黄色の発光色,及 び前記黄色発光ダイオードとそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオード から発せられる光が混合することにより得られる発光色という,相違点1 に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたかについて検討\nする。
甲2には,前記(1)認定のとおり,カード型LED照明光源10に実装さ れるLEDを,相関色温度が低い光色用又は相関色温度が高い光色用や青, 赤,緑,黄など個別の光色を有するものとすることができること(段落【0 080】)が記載されているが,当該事項に係る実施の形態1に関連する段 落【0076】ないし【0080】の記載全体をみても,青,赤,緑,黄 など個別の光色のうちからいずれか1色の単色LEDのみを搭載したLE D光源により青,赤,緑,黄などいずれかの個別の光色を発光するという 意味なのか,複数色のLED光源を搭載して青,赤,緑,黄などの個別の 光色となるように制御するという意味なのか必ずしも判然としない。段落 【0080】に続いて,段落【0081】の前半において「更に,多発光 色(2種以上の光色)のLEDをカード型LED照明光源10に実装する ことにより,・・・この場合,2種の光色を用いた2波長タイプのときには」 との記載が続くことに照らせば,段落【0080】の上記記載は,前者の 意味,すなわち,1種の光色を用いた1波長タイプを意味し,黄色の単色 LEDを搭載したLED光源により黄色の光色を有するという意味と解す ることはできる。しかし,本件発明1は,赤色発光ダイオード,緑色発光 ダイオード,青色発光ダイオード,黄色発光ダイオード及び白色発光ダイ オードを備え,複数得られる特定の発光色として,少なくとも,黄色発光 ダイオードから単独で発せられる光により得られる発光色の他に,黄色発 光ダイオードから発せられる光とそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオー ドから発せられる光とを混合して得られる発光色が得られなければならな いところ(相違点1),前者の意味であるとすれば,上記の混合して得られ る発光色が容易想到であるとはいえない。他方,仮に後者の意味だとして も,甲2には,複数色のLED光源に黄色のLEDを含んでいるとの直接 的な記載はないから,黄色以外のLED光源によって黄色の光色を得てい る可能性も否定できず,黄色のLEDの単独発光が容易想到であるとはい\nえない。 さらに,前記(1)イで認定したとおり,甲2には,3種の光色を用いた3 波長タイプの場合は青と青緑(緑)と赤発光の組合せ,4種の光色を用い た4波長タイプの場合は青と青緑(緑)と黄(橙)と赤発光の組合せが望 ましく,特に4波長タイプのときには平均演色評価数が90を超える高演 色な光源を実現できること(段落【0081】)が記載されており,演色性 を向上させるためにRGBY(赤,緑,青,黄)4種類のLEDを用いる ことが記載されているが,これらの記載は,一般的な意味での演色性の向 上に関するものであるから,これらの記載からは,RGBY4種類のLE Dを用いた照明装置において,黄色のLEDを単独発光させることが客観 的かつ具体的に把握できるものとは認められない。 また,甲2には,RGBWY(赤,緑,青,白,黄)の5種類のLED を用いることが,段落【0065】や【0189】に記載されているが, 具体的な記載としては電源に関する説明があるのみで,これらの記載から は,RGBWYの5種類のLEDを用いた照明装置において,黄色LED を単独で発光させることやその他の色と混ぜて発光色を制御することは, 客観的かつ具体的に把握することはできない。 そうすると,仮に甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機 付けがあり,甲2に記載された技術事項を甲1発明において採用し,甲1 発明において黄色発光ダイオードを備えたとしても,黄色発光ダイオード が単独で発光することにより得られる黄色の発光色,及び,前記黄色発光 ダイオードとそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオードから発せられる 光が混合することにより得られる発光色という,相違点1に係る本件発明 1の構成を容易に想到することができたとは認められない。\n
なお,本件発明1は,黄色LEDを追加した上で,白色LEDとそれ以 外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して発光色を得,黄色 LEDとそれ以外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して 発光色を得るとの構成をとることによって,電圧が低下した状態において\nも発色のバランスを保つことができるもの(本件特許の明細書の段落【0 007】,【0009】,【0010】,【0013】〜【0017】,【002 1】,【0033】,【0034】)であり,このような発明の効果は,甲1発 明及び甲2に記載された技術事項から予測できるものとはいえないから,\nこの点からしても,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用すること によって本件発明1を容易に想到することができたとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2021.10.19
令和3(行ケ)10036 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年10月6日 知的財産高等裁判所
ア 国語辞典の記載
本件商標と引用商標(スイートパーティー)は,「スイーツ」という部分 と「スイート」という部分が異なる。 国語辞典には,「スイーツ」という語については,「【sweets】甘いもの。 ケーキ・菓子など。」を意味するものと記載されている(広辞苑第7版,乙 2)。 他方,「スイート」という語については,「【sweet】1)甘いこと,甘口。 2)甘美なこと。快いこと。気持ちよいさま。」を意味するものと記載され, 「スイート」という語を用いた語として,「−・コーン【〜corn】トウモロ コシの一品種。糖分を多く含む。−・スポット【〜spot】ゴルフのクラブ・ フェースやテニスのラケットなどの,球を最も効果的に打つことができる 点。−・ハート【〜heart】恋人(特に女性)。愛人。−・ピー【〜pea】マ メ科の蔓性観賞用一年草。シチリア島原産で,江戸時代末に渡来。葉はエ ンドウに似,先端は巻ひげとなる。桃色・白色・紫色・斑などの蝶形花を つけ,花後に莢を生じる。園芸品種が多い。ジャコウエンドウ。ジャコウ レンリソウ。−・ホーム【〜home】(特に新婚の)楽しい家庭。愛の巣。−・ ポテト【〜potato】1)サツマイモのこと。2)サツマイモで作った洋風菓子。 サツマイモを蒸して裏漉しし,砂糖・卵黄・バターなどを加えて練り,オ ーブンで焼く。」が挙げられている(広辞苑第7版,乙2)。 上記の国語辞典の記載によれば,「スイーツ」と「スイート」は別の語と して一般的に認識されており,また,「スイート」という語は,「1)甘いこ と,甘口。」の他に,「2)甘美なこと。快いこと。気持ちよいさま。」などの 意味を有し,「スイートハート」,「スイートホーム」など,「甘いこと」以 外の,「愛しい」,「楽しい」の意味で用いられる例があることが一般的に認 識されているものと認められる。
イ 実際の使用例
(ア) 「スイーツ」という語の使用例
インターネット上で検索結果の多い「スイーツ」という語を含む用語 の例として「人気スイーツ」があり(検索結果:約 2,060,000 件,乙1 2),「絶対おすすめ!人気スイーツベスト 20!」,「人気スイーツをお取 り寄せ」のように使用されている(乙13,14)。また,「スイーツレ シピ」という用語(検索結果:約 1,780,000 件,乙15)は,「お手軽ス イーツレシピをご紹介」,「『本格チョコ』のスイーツレシピ特集」のよう に使用されている(乙16,17)。「スイーツ食べ放題」(検索結果:約 1,440,000 件,乙18)という用語は,「種類以上のスイーツ食べ放 題!」,「平日限定スイーツ食べ放題プラン」のように使用されている(乙 19,20)。これらの用語において,「スイーツ」という語は,「ケーキ・ 菓子など」の意味で使用されている。
(イ) 「スイート」という語の使用例
「スイート」という語が食料品との関係で使用される例としては,「ス イートワイン」,「スイートチョコレート」,「スイートチリソース」など\nがあり(乙21〜乙23),「スイート」という語は「甘い,甘口」の意 味で使用されている。
(ウ) 「スイーツ」という語と「スイート」という語が同一作成者のウェ ブページで使い分けられている例
・・・
(エ) 「スイーツパーティー」という語の使用例
・・・
(キ) 以上によれば,実際の使用例において,「スイーツ」という語と「ス イート」という語は,それらが他の語と結びつく場合も含めて区別して 使用されており,「スイーツ」という語は,「甘いもの,ケーキ・菓子な ど」の意味で使用され,他方,「スイート」という語は,「甘い,甘口」 の他,「甘美な,快い,愛しい,楽しい」という意味で用いられているも のと認められる。そして,「スイーツパーティー」という語は,スイーツ (甘いもの,ケーキ,菓子など)が提供され,それらを食べるパーティ ーの意味で用いられている。
ウ そうすると,本件商標は,「スイーツ」と「パーティー」を二段書きにし たものであるから,「スイーツ」(甘いもの,ケーキ・菓子など)という名 詞が強調された上で,その全体から,「スイーツパーティー」という語とし て認識され,スイーツ(甘いもの,ケーキ,菓子など)が提供され,それ らを食べるパーティーという観念を生じるものと認められる。 他方,引用商標は,「スイートパーティー」又は「SWEET PART Y」という語として認識され形容詞である「スイート」「SWEET」が必 然的に名詞の「パーティー」を修飾する関係にあるから「スイート」なパ ーティーを意味し,「スイート」という語の意味のうち,パーティーを修飾 する場合に当てはまる意味は,「甘美な,快い,愛しい,楽しい」という意 味であるから,「甘美な,快い,愛しい,楽しいパーティー」という観念を 生じるものと認められる。
・・・・
(5) 類否の判断
以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観上明確に区別できるものであ ること,本件商標と引用商標は観念において明確な差異があること,本件商 標と引用商標とは称呼において類似しているものの,その類似性の程度は高 くないことを考慮すると,本件商標と引用商標は,外観,観念,称呼等によ って取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察する場合に は,同一又は類似の商品に使用された場合に,その商品の出所につき誤認混 同を生ずるおそれはないものと認められる。 したがって,本件商標を引用商標の類似商標と解することはできないとい うべきである。
3 原告の主張の検討
(1)ア 原告は,「スイーツパーティー」という語が一般的になればなるほど「ス イートパーティー」,「SWEET PARTY」は,「スイーツパーティー」 と同じような,「甘いものを対象としたパーティー」という類似する観念で 捉えられ,観念としても非常に近い,紛らわしいものとして認識されるお それは十分に生じる旨主張する(前記第3,2(3)イ(ア))。 しかし,前記2(3)のとおり,「スイーツ」という語と「スイート」という 語は,区別して観念されており,それらが他の語と結びつく場合も含めて 区別して使用されているから,「スイーツパーティー」という語が一般的に なっても,「スイートパーティー」,「SWEET PARTY」から類似す る観念が生ずるとはいえず,原告の上記主張は,採用することができない。
イ(ア) 原告は,「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」とが混同 を生じるか否かが問題であって,「スイーツ」という語と「スイート」と いう語の違いを強調して商標の類否を判断することは重大な誤りである 旨主張する(前記第3,2(3)イ(イ))。 しかし,前記のとおり,本件商標は,「スイーツ」と「パーティー」を 二段書きにしたものであり,しかも名詞と名詞が結合した商標であるか ら,上段の「スイーツ」を分離して観察することが可能であること,「ス\nイーツ」,「スイート」及び「パーティー」はそれぞれ独立した意味のあ る単語であって,「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」は, 「パーティー」の部分において共通し,「スイーツ」,「スイート」は,「パ ーティー」という語を修飾して,どのようなパーティーであるかを示す 部分であるから,「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」とが 混同を生じるか否かを明らかにする上で,「スイーツ」という語と「スイ ート」という語の観念等の違いの有無を検討することは必要である。
(イ) また,原告は,「スイート」という語が「すてきな」,「楽しい」,「か わいらしい」といった意味で使用されている例は乙27以外にない旨, 食品,とりわけ菓子について「スイート」という語が用いられた場合, 味覚を表す「甘い」という意味以外の理解をし,わざわざ「甘美な」,「快\nい」という意味を認識する者はいない旨主張する(前記第3,2(3)イ(イ))。 しかし,「スイート」という語が,甘美な,愛しい,楽しいという意味 で使用された例は,乙27(前記2(3)イ(カ))の他,乙8(前記2(3)イ(ウ) d),乙24,乙26(前記2(3)イ(エ)a),乙65(前記2(3)イ(オ))に ある。また,食品,とりわけ菓子について用いられる場合でも,「スイー ト」という語により修飾される語が味覚を生ずるものでない場合は,「ス イート」という語は,甘美な,愛しい,楽しいの意味で使用されるもの と推認され,前記2(3)イ(ウ)dのとおり,菓子について,「スイートなビ ジュアルが本命チョコにお勧め!」(乙8〔2頁〕)として,「スイート」 という語が,甘美な,愛しい,楽しいの意味で用いられている例もある。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(2)ア 原告は,本件商標及び引用商標の指定商品の需要者は,幼児,老人を含 む大衆であり,本件商標と引用商標のカタカナ表記(外観)及び称呼は,\n同行音の近似音とされる「ツ」と「ト」の一字(一音)が相違するだけで あり,本件商標を英語表記して引用商標の英語表\記と比較しても,「S」一 文字の有無が相違するだけであるから,需要者の通常の注意力を基準とす ると,本件商標と引用商標は相紛らわしく,混同のおそれがあると主張す る(前記第3,2(4)ア)。
しかし,「スイート」,「パーティー」という語は,子供を含めて一般に広 く知られた平易な語であると認められ(弁論の全趣旨),「スイーツ」,「ス イーツパーティー」という語も,子供を対象とするゲーム,玩具,絵本に ついて用いられていることからすれば(乙62〜乙64),広く知られた平 易な語であると認められるから,難解で聞き慣れない語の中の一字(一音) が相違する場合と異なり,本件商標と引用商標は,外観及び称呼において, 「ツ」と「ト」の一字(一音)が相違するだけであっても,その区別は可 能であるものと認められる。そして,本件商標と引用商標とで観念が明確\nに異なることは,前記2(3)ウのとおりである。したがって,需要者を考慮 しても,本件商標と引用商標は混同のおそれがあるとは認められず,原告 の上記主張は,採用することができない。
イ 原告は,菓子等を製造販売する訴外会社の申し入れにより商標使用許諾\n契約を締結し,訴外会社から指摘されて本件無効審判を請求したことから, 本件商標と引用商標とが相紛らわしいことは,菓子等の製造販売業者にお いて認識されていたと主張する(前記第3,2(4)イ)。 しかし,原告と訴外会社との一契約をもって,菓子等の製造業者すべて における認識を判断することは相当ではなく,また,原告が訴外会社と商 標使用許諾契約を締結するに至った経緯や訴外会社の意図は明らかでない から,菓子等の製造販売業者において,一般に,引用商標と「スイーツパ ーティー」という商品名が商標として類似していると認識していたと認め るに足りないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.10.19
令和2(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年10月7日 知的財産高等裁判所
(3) 本願発明の「制御装置」と引用発明の「短絡制御回路」の対比
ア(ア) 本願発明の制御装置は,「燃料電池スタックの水和レベルを増加させる再 水和間隔を提供するために」,「燃料電池スタックを通る空気流動を調節するように 構成される」ものである。\n
(イ) 本願発明の特許請求の範囲の請求項1の文言や本願発明が燃料電池に係るも のであることのほか,前記1(2)の本願発明の概要からして,上記のうち「燃料電池 スタックの水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するために」については,燃 料電池の良好な動作のために,膜/電極接合体(MEA)が好適に水和された状態 とすべく,MEA内の水分量を積極的に増加させるという目的をいうものと解され る。この点,本願明細書の段落【0036】及び【0037】には,「再水和間隔」 が,燃料電池カソードにおいて過剰な水を産生して燃料電池における膜の水分量を\n増加させる短い期間であって,燃料電池上の外部電気負荷及び温度などのその環境 動作条件に基づき有効であるレベルを超えて,水和レベルを増加させるために,燃 料電池アセンブリがその動作環境を能動的に制御する期間である旨が記載されてい\nるところである。 そして,「燃料電池スタックを通る空気流動を調節する」については,上記目的の ために,膜の含水量の低下等をもたらし得る空気流動を調節することをいうものと 解される。
イ 引用発明の短絡制御回路は,「燃料電池の負の水和降下現象を防止するため に」,「燃料電池への燃料ガスの供給を停止する」ものであるところ,このうち「負 の水和降下現象」の意味内容については,前記2(3)イで検討したとおりである。そ して,その意味内容を踏まえると,「負の水和降下現象を防止する」とは,基本的に, MEAにおける水和の損失が,熱の発生につながり,それが薄膜電極アセンブリの 乾燥につながるといった状態を停止させる,又は抑制することをいうものと解され る。 そして,「燃料電池への燃料ガスの供給を停止する」については,上記目的のため に,燃料電池の発熱につながる燃料ガスの供給を停止することをいうものと解され る。
ウ(ア) 上記ア及びイによると,本願発明の「制御装置」と引用発明の「短絡制御 回路」は,MEA内の水分量を積極的に増加させることを目的とするか,MEAに おける水和の損失等を停止させる,又は抑制することを目的とするにとどまるかと いった点において異なるとともに,燃料電池のカソード側で水分の低下につながり\n得る空気流動を調節するか,アノード側で熱の発生につながる燃料ガスの供給を停 止するかといった点においても異なっている。
(イ) もっとも,上記のうち後者の点については,本件審決は,「空気流動を調節す る」ことと「燃料ガスの供給を停止する」ことを「気体流動を調節する」とした上 で,相違点2を認定しており,その認定判断に誤りがあるとはいえない。
エ 他方で,本願発明の制御装置と引用発明の短絡制御回路について,「所定条件 で,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して」,気体流動を調節するよ うに構成される「制御装置」であるという点で一致するとした本件審決の判断に誤\nりがあるとは認められない。
オ 以上によると,本願発明の制御装置と引用発明の短絡制御回路が,「水和レベ ルを増加させる再水和間隔を提供するために」という点で一致しているとした点に おいて,本件審決には誤りがある。
カ 原告は,本願発明の制御装置が短絡制御を行うものではない旨を主張するが, 短絡制御の点は一致点として認定されておらず,原告の上記主張は当を得ないもの である。また,原告は,引用発明における燃料ガスの供給の停止が「流動を調節す る」に当たらないと主張するが,甲3の段落【0023】には,燃料電池10への 燃料ガス105の供給を停止するような位置にバルブ104をすると同時に,電気 的スイッチ124を閉鎖電気状態にする旨の記載がある一方,本願明細書の段落【0 010】には空気流動をゼロまで減少させることについて記載があり,これらの記 載も踏まえると,両者は,対象となる気体以外の点で実質的に相違するものとは認 められず,いずれも気体流動の調整を行うとの概念の範囲で一致するものといえる。 さらに,原告は,「所定条件」の内容が本願発明と引用発明とで全く異なる旨を主張 するが,本件審決が認定した相違点1及び2のほか,前記ウ(ア)で指摘した本願発明 の制御装置と引用発明の短絡制御回路の目的の相違があることに加え,別途,それ らの動作に係る所定条件に関して相違点を認定すべきものとは認められない。
キ(ア) 被告は,燃料電池においてイオン交換膜の含水量が減少する一般的な原因 について主張した上で,引用発明においても,薄膜電極アセンブリの水和レベルが 増加することは明らかであると主張する。 しかし,被告の上記の主張のうち,単に薄膜電極アセンブリの含水量の減少量が 小さくなることをいうにすぎないもの(含水量の積極的な増加を意図した制御を行 っているものではない。)は,前記ウ(ア)の判断を左右するものではない。この点, 被告は,燃料電池内の発熱が収まることで,それまでの発電で生じた水や空気中に 含まれる水蒸気によって水和レベルが増加することも主張するが,当該主張を裏付 ける証拠や,そのような技術常識を直ちに認めるに足りる証拠は見当たらない。
(イ) 被告は,本願発明における水和レベルの増加のメカニズムが明確でなく,本 願の実施例で実行される制御で水和レベルが増加するのであれば,引用発明でも同 様であるという旨を主張するが,本願発明における「燃料電池スタックの水和レベ ルを増加させる再水和間隔を提供するために」の意味内容については,前記ア(イ)で 認定判断したとおりであって,そのメカニズムが明確か否かという点は,直ちに本 願発明と引用発明の一致点及び相違点の判断に影響を与えるものではない。
(4) まとめ
ア 以上によると,本願発明と引用発明は,次の一致点で一致し,本件審決が認 定した相違点1及び2のほか,次の相違点3及び4で相違するというべきである。
(一致点)
「燃料電池システムであって,
第1の燃料電池スタックと,
前記第1の燃料電池スタックと直列の,第2の燃料電池スタックと,
前記第1の燃料電池スタックと並列の,第1の電子部品と,
前記第1の燃料電池スタックの水和状態を調整するために,所定条件で,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して,前記第1の燃料電池スタックを通る気体流動を調節するように構成される,制御装置と,
を備える,前記燃料電池システム。」
(相違点1)
所定条件に関し,本願発明は,「定期的に」であるのに対し,引用発明は,「燃料 電池の出力電圧が約0.4Vより低くなる場合」である点。
(相違点2)
気体流動の調節に関し,本願発明は,気体は空気であるのに対し,引用発明は, 気体は燃料ガスである点。
(相違点3)
第1の電子部品に関し,本願発明は,電子部品は整流器であるのに対し,引用発 明は,電子部品は電界効果トランジスタである点。
(相違点4)
燃料電池スタックの水和状態を調整するために関し,本願発明は,水和レベルを 増加させる再水和間隔を提供するためであるのに対し,引用発明は,負の水和降下 現象を防止するためである点。
イ その上で,後記5の点も踏まえると,少なくとも相違点4の看過は,本件審 決の取消事由に当たるというべきである。
5 容易想到性の判断について
(1) 相違点1,2及び4は,いずれも本願発明の「制御装置」又は引用発明の「短 絡制御回路」に関するもので,技術的構成として相互に関連するものといえるから,\n以下,一括して検討する。
(2)ア 前記4(3)イからすると,引用発明が「燃料電池の出力電圧が0.4Vよ り低くなる場合」に「燃料ガス」を調節する目的は,主として熱の発生を抑えるこ とで「負の水和降下現象を防止する」ためであり,これは,甲3にいう「第1の動 作条件」(甲3の段落【0024】)に係るものである。 他方で,甲3には,「第2の動作条件」として,燃料電池の特性パラメータを回復 させる構成が記載されている(甲3の段落【0025】〜【0027】)。\nこのように,二つの条件に係る構成があることに加え,甲3の段落【0001】,\n【0009】,【0023】,【0029】及び【0030】の記載並びに【図4】に 照らし,上記「第1の動作条件」が,基本的に,「燃料電池が故障した際」(同【0 001】。【図4】にいう「欠陥は重大」である場合である。)に係るものとみられる ことからすると,相違点1,2及び4に係る引用発明の構成は,燃料電池の故障を\n示すものとみ得る状態を具体的に検知し,負の水和降下現象を防止するために,燃 料ガスの供給を停止して熱の発生を抑えるためのものと解するのが相当である。 イ 上記のような燃料電池の故障を示すものとみ得る状態を具体的に検知したと の引用発明に係る「燃料電池の出力電圧が0.4Vより低くなる場合」の動作につ いて,実際の出力が閾値以上に変化しているか否かにかかわらず,これを「定期的 に」行うことを想到することが,当業者において容易であるとはいい難いというべ きである。甲3に,引用発明に係る燃料ガスの供給の停止を定期的に行うこととす る動機付けや示唆があるとは認められない。甲3の段落【0024】には,第1の 動作条件について,「約0.4Vより低い範囲に低下する場合」以外の記載があるが, そこで挙げられている他の特性パラメータも,燃料電池の故障を示すものとみ得る 状態の検知の範疇に止まるものである。燃料電池の保湿レベルを周期的に増加させ ることに係る周知の事項(甲4[前記3(1)],甲5[前記3(2)])を参照しても, 上記判断は左右されない。 上記判断に反する被告の主張は,いずれも採用することができない。
ウ また,引用発明が,上記アのように,主として熱の発生を抑えることを目的 としたものであることを考慮すると,「気体流動を調節する」ことについて,引用発 明から,燃料電池の乾燥につながり得る一方で冷却効果をも有する空気の流動(本 願明細書の段落【0006】参照)を停止することを,当業者が容易に想到し得た ということも困難である。甲3に,空気の流動を調節することの動機付けや示唆が あるとは認められない。 上記判断に反する被告の主張は,いずれも採用することができない。
(3) 以上によると,相違点1,2及び4に係る本願発明の構成が引用発明に基づ\nいて容易に想到できたものとは認められないから,相違点1及び2について容易想 到と判断した点において,本件審決には誤りがあるというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.10.19
令和3(行ケ)10071 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年10月14日 知的財産高等裁判所
(1) 本件商標と引用商標の類否判断について
ア 外観
(ア) 本件商標は,「pum’s」の文字を太字の斜体の書体で表し,末尾\nの「s」の文字の下端を語頭の「p」の文字の下部まで横一直線に延伸 し,下線のように表されて構\成されている。原告は,本件商標の1文字 目と4文字目は,大文字「P」「S」と認識されると主張するが,1文 字目の左側の縦棒が下に突き出しているのは小文字であるからなのは明 らかであり,4文字目も上端が他の小文字と同じ高さに位置しているか ら,大文字とは認識されない。また,原告は,本件商標の2文字目は, 右側の縦棒がないため,大文字「U」と捉えられると主張するが,2文 字目は他の小文字と同じ大きさであって,直ちに採用できない。 一方,引用商標は,「PUmA」の文字を縦線を太く垂直に,横線を 細く描く書体で表し,各文字は,小文字である「m」も含めて,同じ高\nさで構成されている。\n両者は,語頭を含めた「pum(PUm)」の文字を共通にするが, 末尾において本件商標が小文字の「s」であるのに引用商標が大文字の 「A」であるという文字の相違,アポストロフィの有無,下線のように 表されたものの有無,書体が斜体であるか否か及び文字の横線が細いか\n否かといった点において明らかに異なり,外観においては,相紛れるお それはない。
(イ) 原告は,第3の1(1)ア(ア)cのとおり,るる主張するが,前記(ア)で 認定したとおり,本件商標と引用商標の外観上の相違は明白であり,仮 に,原告が主張する個別の点につき一定の類似が認められるとしても, そのことから,外観において相紛れるおそれがあるということはできな い。 なお,念のために判断すれば,上記c(a)については,引用商標は文字 の横線が細いことが明確であるのに対し,本件商標では縦線と横線の太 さの違いは子細に見なければ看取できず,逆に,本件商標では角部の丸 みは明確であるが,引用商標では明らかでないし,同(b)については,本 件商標が斜体であるのに対し,引用商標は各文字が垂直かつ同じ高さで, 長方形の範囲に収まって全体として整然とした印象を与えるものであっ て,両者の印象が異なることは明らかであるし,同(c)については,いず れにしても本件商標における「s」の文字の下端の延伸された部分が引 用商標との相違点として着目されないということにはならないし,同? については,相違する最後の「A」と「S」の文字が相似た文字に看取 される場合があるとは認め難いし,同(e)については,特段の意味内容を 想起させない「pum」の欧文字部分が本件商標の要部であるとは到底 いえず,原告の各主張は個別にみても採用し得ない。 そうすると,本件商標と引用商標の外観は大きく異なるものであって, 前記1の引用商標の周知著名性を勘案しても,両者の外観が類似すると の原告の主張は採用できない。
イ 称呼
(ア) 本件商標からは「パムズ」,「パムス」,「プムズ」又は「プムス」 の称呼が生じるのに対し,引用商標からは「プーマ」又は「ピューマ」 の称呼が生じ,語頭の「pu」ないし「PU」を「プ」と読んだ場合に 音を共通にする場合があるとしても,いずれも3音という短い音数にお いては,2音目及び3音目における音の相違,特に,3音目の「ズ」な いし「ス」(本件商標)と「マ」(引用商標)の相違は大きいものであ って,相紛れるおそれはない。
(イ) 原告は,前記第3の1(1)ア(イ)のとおり,本件審決が,本件商標の要 部である「PUm」の欧文字部分から生ずる「プム」の称呼と引用商標 から生ずる称呼とを対比していないと主張するが,本件商標における 「pum」の欧文字部分が要部であるという主張が到底採用できないこ とは前記アのとおりである上,仮に同部分を本件商標の要部とし,これ を「プム」と称呼し,引用商標を「プーマ」と称呼したとしても,短音 と長音の違い,「ム」と「マ」の違いは,短い標章の中では大きな差異 として認識されるものというべきである。
ウ 観念
本件商標が造語であることから,特定の観念を生じないのに対し,引用 商標が周知著名であることから,「原告のブランド」との観念を生じ,両 者は明確に区別することができ,相紛れるおそれがない。
エ その他
原告は,前記第3の1(1)ア(エ)のとおり,本件商標と引用商標の需要者 である一般消費者は,衣類や靴等に商標をワンポイントマークとして小さ く表示された場合,些細な相違点に気付かないことも多いと主張する。\nしかし,商標が小さく表示された場合をことさら取り上げることの当否\nは措くとしても,そもそも本件商標と引用商標は全体的な印象においても 明らかに異なることは前記アのとおりであり,小さく表示された場合でも,\nその相違は明白であるから,原告の主張は採用できない。 また,原告は,前記第3の1(1)ア(オ)のとおり,本件消費者調査の結果を 理由に,本件商標と引用商標の類似性を主張する。 しかし,本件消費者調査は,本件商標の登録査定時よりも後に実施され たものであること,本件商標について助成想起(本件商標の指定商品〔ス ポーツ関連用品〕の出所標識という前提〔ヒント〕を与えて自由回答形式 で聴取するもの)による質問について原告を連想した15%という数値は 大きいとはいえない上,スポーツ関連用品というヒントを与えられれば, 多少とも本件商標と共通点のあるブランドを想起しようと努めると考え られることを考慮すると,この数値すらそのまま受け取ることはできない こと,本件商標と引用商標を並べた場合に両商標が類似するという回答も, このような限界のある質問の後にされたものであることを考慮すれば,本 件商標と引用商標の類似性を裏付ける資料とはいえない。したがって,こ の点に係る原告の主張も採用し得ない。
(2) 小括
以上によれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれに おいても相紛れるおそれがなく,類似しないものと認められる。 そうすると,本件商標の指定商品と同一又は類似する商品が引用商標7, 8及び10の指定商品中に含まれているとしても,本件商標は,商標法4条 1項11号に該当せず,本件審決の判断に誤りはない。
3 取消事由2(本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)につい て
(1) 混同のおそれについて
「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程\n度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度,当該商標の指定商品等と他\n人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並 びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし,当該 商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準 として,総合的に判断すべきである。 これを本件につき検討するに,前記2において判断したとおり,本件商標 と引用商標とは,引用商標の周知著名性を勘案しても,外観,称呼及び観念 のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,その類似 性は極めて低いというべきであるから,本件商標の指定商品には「運動用特 殊衣服,運動用特殊靴」が含まれており,原告の業務に係る商品との間の関 連性や,取引者や需要者の共通性が高く,また,そのような商品はいずれも 注意力が高いとはいえない一般消費者も需要者とするものであることを考慮 しても,本件商標に接する取引者及び需要者が,原告又は引用商標を連想又 は想起することはないというべきである。これに反する原告の主張は,前記 2において判断したのと同様の理由によりいずれも採用し得ない。そうする と,本件商標は,これをその指定商品に使用をしても,その取引者及び需要 者をして,当該商品が原告の商品に係るものであると誤信させるおそれがあ るものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2021.10.18
令和3(ネ)10040 差止請求権不存在確認請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年10月14日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
控訴人は,前記第2の3(2)エ(ア)のとおり,本件特許の出願過程の経 緯から客観的,外形的に見るならば,物又は方法の発明として特許出願 している被控訴人が,その補正として「逐次又は一斉に表示」という構\ 成を削除したのであるから,画像選択手段を含むコンピューターにより 出力されるという構成においても「逐次又は一斉に表\示」という構成を\n意識的に除外したと主張する。
しかし,当該出願経過によれば,被控訴人は,明確性要件違反の拒絶 理由(甲8)に対し,本件補正により,コンピューターを構成に含む学\n習用具と記載し,また,被控訴人が甲第10号証と併せて提出した意見 書(甲9)3頁の「(4)記載不備の拒絶への対処」では「作業の主体を 「手段」とし,人が行う作業を示す部分を削除致しました。」としている のであり,他の部分も削除したことを外形的に示す説明はない。 また,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」との構成を付\n加した点について,客観的には,組画を構成する複数の画のうち任意の\n1つの画像データ(ユニット画)を選択すること(例えば第一の関連画 のみを選択すること)が意識的に除外されているとはいい得るとしても, 二以上の組画の画像データを選択することが意識的に除外されたとは いえない。また,「逐次」の文言が用いられている本件明細書【0037】, 【0038】及び【0052】 において,「逐次」及び「一斉」の両方 が用いられているのは特定の組画を構成するユニット画について記載\nしている【0038】に「特定の組画を構成するユニット画は,全て一\n斉に表示してもよいが,前述のように逐次表\示するほうが,学習効果が 増して好ましい。」とあるのみであるから,本件補正前の「それぞれの前 記記憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対\n象を記憶する」との記載は,特定の組画を構成するユニット画を逐次又\nは一斉に表示することを指していると解するべきであり,「逐次又は一\n斉に表示」という構\成を削除したからといって,複数の組画を選択する 構成を除外する意図であったと認めることはできない。\n
さらに,被控訴人が,上記意見書で進歩性に関して主張したところは, 本件発明が,1)対応する語句が存在する原画の形態を,その形態に対応 する語句と結びつけて記憶することを目的すること,2)関連画の輪郭が, 原画に類似等しており,一定の意味内容を有することから,学習対象者 が,意味内容と原画との関連付けにより,記憶することに苦痛を感じる ことなく楽しみを感じながら,原画を記憶することができること,3)関 連画及び原画に対応する語句の音声データを再生し,関連画及び原画の 表示は対応する語句の再生と同期して行うこと,4)原画又は原画に対応 する語句を思い出すことを目的とするため,関連画の表示及び関連画に\n対応する語句の再生を行った後に,原画の表示及び原画に対応する語句\nの再生を行うこと,5)第一の関連画,第二の関連画,及び原画の順に表\n示し,しかも,前記第一の関連画,前記第二の関連画,及び前記原画を, 対応する語句の再生と同期して表示することにより,4通りのルートに\nよって原画及び対応する語句を思い出すことができることを挙げるもの であるが(甲9),これらの特徴は,複数の組画を選択する構成と矛盾す\nるものではなく,これを意識的に除外する旨を表示したものとはいえな\nい。
(イ) 控訴人は,前記第2の3(2)エ(イ)のとおり,被控訴人が補正において, 構成要件B2の画像選択手段の構\成を加えた点について,複数の組画を 選択する構成を除外しない意図であるならば「一又は複数の組画」や単\nに「組画」等といった記載にすることは極めて容易であり,本件特許の 出願経過を客観的,外形的に見るならば,「一の組画の画像データを選択 する画像選択手段」を付加したことは,複数の組画を選択する構成を意\n識的に除外したことになると主張する。 しかし,仮に,他により容易な記載方法があったとしても,出願人が, 補正時に,これを特許請求の範囲に記載しなかったからといって,それ だけでは,第三者に,対象製品等が特許請求の範囲から除外されるとの 信頼を生じさせるとはいえない。客観的にみて,「一の組画の画像データ を選択する」との記載が,組画を構成する画が維持された状態で選択す\nる限りにおいては,二以上の組画の画像データを選択することを意識的 に除外するものとまでは認められないことは,前記(ア)のとおりである。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.10.14
令和3(行ケ)10032 商標権 行政訴訟 令和3年10月6日 知的財産高等裁判所
上記事実(ア)ないし(エ)によれば,本件商標の登録出願当時,原告使用商標 は,処方薬としての原告薬剤を表示する商標として,処方薬の需要者であ\nる皮膚科の医師等の医療関係者の間において,広く知られていたものと認 められる。これに対し,化粧品としての用途が,雑誌記事に取り上げられ るなどして一般に知られるようになったのは,証拠上は平成26年以降で ある上(事実(オ)),その紹介記事の内容(別紙2)をみても,「知る人ぞ 知る」という取り上げ方をされており,その時点において既に周知著名で あったとはいえない。そして,これらの記事においては原告薬剤は処方薬 であることへの注意喚起がなされていること(事実(オ)),原告が医師等に 対して美容目的での処方をしないように啓発していること(事実(カ))も踏 まえると,本件商標の登録出願(平成30年1月29日)の時点において, 化粧品の需要者である一般消費者の間で,原告使用商標が周知著名であっ たとまではいえない。
また,事実(キ)ないし(ケ)のとおり,これらの記事が出た後に,複数の事業 者からヘパリン類似物質含有商品が相次いで販売された事実,その広報宣 伝において原告薬剤を引き合いに出すものや,名称に「ヒル」又は「ヒル ド」を含むものが多くみられる事実は,化粧品の分野におけるヘパリン類 似物質含有商品という市場自体が,原告薬剤の美容目的への流用という事 態によって成立したという経緯を反映するものではあるが(例えば甲26 の1(2018(平成30)年12月6日付け「日経doors」記事)の 「『ヒルドイド』で知られる医療用保湿剤の成分,ヘパリン類似物質を配 合した市販薬とコスメが,18年秋に相次いで登場した。背景には,化粧 品代わりに求める女性が増え,健康保険財政を圧迫するまでになったとい う事情がある。」との記載),そのような経緯があるからといって,医療 用医薬品である原告薬剤の名称としての原告使用商標が,化粧品の分野に おいて周知著名性を獲得していたことになるものではない。
なお,本件アンケートにおいてヒルドイドの「認知度」が5割ないし6 割にのぼっていた(事実(コ))としても,これらの「認知度」は,皮膚の乾 燥に起因すると考えられるトラブルを抱えて何らかの皮膚薬を最近になっ て使用していた者の間でのものであるから(事実(コ)のa),原告薬剤が処 方薬の分野で5割以上の高い市場占有率を得ていること(事実(ウ))に照ら して,本件アンケートにおける「認知度」が高くなることはある程度必然 的であり,化粧品の分野における一般消費者の間での周知著名性を明らか にするものではない。
ウ 原告の主張について
原告は,上記アの各事実に基づき,原告使用商標が化粧品の分野におい ても本件商標の登録出願当時に周知著名性を獲得していた旨主張するが, これらの事実を前提としても周知著名性を認定するに足りないことは,上 記イで説示したとおりであるから,原告の主張は採用することができない。 また,原告は,ヘパリン類似物質を含有する一般用医薬品「ヒルマイル ド」につき,原告薬剤を想起している需要者が多数いること(別紙4)や, 「あのヒルドイドが店頭で新発売!」といううたい文句で販売されている ことからも,原告使用商標が広く知られている実態を見て取れる旨主張す るが,そもそも「ヒルマイルド」は被告の販売する商品ではないばかりか, 「ヒルマイルド」は「ヒル」の文字の後に「イ」の文字を含み,「ド」の 文字で終始する点において,原告使用商標との類似性は本件商標よりも更 に高いから需要者に原告薬剤を想起させたとも考えられるところであるし, 「あのヒルドイドが店頭で新発売」という文言は,医療用医薬品であって 店頭では販売されない原告薬剤の代わりとなる商品が発売されたという趣 旨に理解されるから,原告の主張は,上記イの判断を左右しない。
◆判決本文
関連事件です。こちらは医薬品について周知著名と認定されています。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.10.14
令和2(行ケ)10103 特許権 行政訴訟 令和3年10月6日 知的財産高等裁判所
ウ 相違点1に係る本件発明1の構成のうちの「黄色発光ダイオード」及びその「発光色」の容易想到性\n
前記(2)のとおり,甲1発明と甲2に記載された技術事項は,技術分野が 完全に一致しているとまではいえず,近接しているにとどまるから,甲1 発明に甲2に記載された技術事項を採用して本件発明1を想到すること が容易であるというためには,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採 用するについて,相応の動機付けが必要であるというべきである。
本件審決は,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付け があり,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して本件発明1を容 易に想到することができたと判断する前提として,甲1発明に,「イエロー」 とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があり(前記(3) ア(ア)),甲1発明に,演色性を向上させるという,甲2と共通の課題があ ると認定した(前記(3)ア(イ),(ウ))。
しかし,前記ア(ア)のとおり,甲1発 明に,「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課 題があるとする本件審決の認定は誤りであるし,また,本件審決が甲1発 明の課題に関して認定する「演色性」(本件審決が第6,2,2−1(2)(2 −1)ア(ウ)〔本件審決48頁〕で,甲10に記載されているように周知の 課題といえると認定する事項を含む。)は,甲2に記載された技術事項とし て認定された「演色性」,すなわち,照明された物体の色が自然光で見た場 合に近いか否かという,一般的な意味での「演色性」とは異なる(前記ア (イ))。
そうすると,本件審決は,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用 する動機を基礎づける甲1発明の課題の認定を誤っているものであり,ま た,甲2に記載された技術事項の内容(前記(1)),甲1発明と甲2に記載さ れた技術事項の技術分野相互の関係(前記(2))を考慮すると,甲1発明に は,甲2に記載された技術事項と共通する課題があるとは認められず,そ のため,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付けがある とは認められない。 したがって,甲1発明に甲2に記載された技術事項及び周知の課題(甲 10)を採用して,黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到するこ とができたとは認められず,これを容易に想到することができたとする本 件審決の判断(前記(3)ウ(ア))は誤りである。 本件審決は,甲1発明に甲2に記載された技術事項及び周知の課題(甲 10)を採用して,黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到するこ とができた(前記(3)ウ(ア))という判断を前提として,甲1発明に甲2に記 載された技術事項及び周知の課題(甲10)を採用し,本件発明1の構成\nのうちの「黄色発光ダイオード」及びその「発光色」を容易に想到するこ とができた(本件審決第6,2,2−1(2)(2−1)イ(ア)〔本件審決48 〜50頁〕)と判断するところ,その前提とする判断が誤っているから,本 件発明1の構成のうちの「黄色発光ダイオード」及びその「発光色」を容\n易に想到することができたという判断も誤りである。
エ 黄色発光ダイオードの単独発光色及び混合発光色の容易想到性
前記ウのとおり,甲1発明と甲2に記載された技術事項との間には課題 の共通性がなく,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付 けがあるとは認められないが,念のため,仮にそのような動機付けがある として,甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用することにより,黄 色発光ダイオードが単独で発光することにより得られる黄色の発光色,及 び前記黄色発光ダイオードとそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオード から発せられる光が混合することにより得られる発光色という,相違点1 に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたかについて検討\nする。
甲2には,前記(1)認定のとおり,カード型LED照明光源10に実装さ れるLEDを,相関色温度が低い光色用又は相関色温度が高い光色用や青, 赤,緑,黄など個別の光色を有するものとすることができること(段落【0 080】)が記載されているが,当該事項に係る実施の形態1に関連する段 落【0076】ないし【0080】の記載全体をみても,青,赤,緑,黄 など個別の光色のうちからいずれか1色の単色LEDのみを搭載したLE D光源により青,赤,緑,黄などいずれかの個別の光色を発光するという 意味なのか,複数色のLED光源を搭載して青,赤,緑,黄などの個別の 光色となるように制御するという意味なのか必ずしも判然としない。段落 【0080】に続いて,段落【0081】の前半において「更に,多発光 色(2種以上の光色)のLEDをカード型LED照明光源10に実装する ことにより,・・・この場合,2種の光色を用いた2波長タイプのときには」 との記載が続くことに照らせば,段落【0080】の上記記載は,前者の 意味,すなわち,1種の光色を用いた1波長タイプを意味し,黄色の単色 LEDを搭載したLED光源により黄色の光色を有するという意味と解す ることはできる。しかし,本件発明1は,赤色発光ダイオード,緑色発光 ダイオード,青色発光ダイオード,黄色発光ダイオード及び白色発光ダイ オードを備え,複数得られる特定の発光色として,少なくとも,黄色発光 ダイオードから単独で発せられる光により得られる発光色の他に,黄色発 光ダイオードから発せられる光とそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオー ドから発せられる光とを混合して得られる発光色が得られなければならな いところ(相違点1),前者の意味であるとすれば,上記の混合して得られ る発光色が容易想到であるとはいえない。他方,仮に後者の意味だとして も,甲2には,複数色のLED光源に黄色のLEDを含んでいるとの直接 的な記載はないから,黄色以外のLED光源によって黄色の光色を得てい る可能性も否定できず,黄色のLEDの単独発光が容易想到であるとはい\nえない。
さらに,前記(1)イで認定したとおり,甲2には,3種の光色を用いた3 波長タイプの場合は青と青緑(緑)と赤発光の組合せ,4種の光色を用い た4波長タイプの場合は青と青緑(緑)と黄(橙)と赤発光の組合せが望 ましく,特に4波長タイプのときには平均演色評価数が90を超える高演 色な光源を実現できること(段落【0081】)が記載されており,演色性 を向上させるためにRGBY(赤,緑,青,黄)4種類のLEDを用いる ことが記載されているが,これらの記載は,一般的な意味での演色性の向 上に関するものであるから,これらの記載からは,RGBY4種類のLE Dを用いた照明装置において,黄色のLEDを単独発光させることが客観 的かつ具体的に把握できるものとは認められない。 また,甲2には,RGBWY(赤,緑,青,白,黄)の5種類のLED を用いることが,段落【0065】や【0189】に記載されているが, 具体的な記載としては電源に関する説明があるのみで,これらの記載から は,RGBWYの5種類のLEDを用いた照明装置において,黄色LED を単独で発光させることやその他の色と混ぜて発光色を制御することは, 客観的かつ具体的に把握することはできない。 そうすると,仮に甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機 付けがあり,甲2に記載された技術事項を甲1発明において採用し,甲1 発明において黄色発光ダイオードを備えたとしても,黄色発光ダイオード が単独で発光することにより得られる黄色の発光色,及び,前記黄色発光 ダイオードとそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオードから発せられる 光が混合することにより得られる発光色という,相違点1に係る本件発明 1の構成を容易に想到することができたとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2021.10.14
令和2(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年10月7日 知的財産高等裁判所
イ 引用発明の「電界効果トランジスタ」は,甲3における「第1の条件」にお いて,「不良燃料セルのアノードとカソードの間の電流を短絡し,よってその不良燃料電池のための電流側路を設ける」もの(甲3の段落【0009】)であり,甲3の\n【図3】において,電気的なスイッチ124(nチャネルMOSFET)として示 されているもので,開放電気状態と閉鎖電気状態とを有する(同【0020】〜【0 022】)。そして,引用発明においては,燃料電池の出力電圧が約0.4Vより低 くなるような場合に,電界効果トランジスタが閉鎖電気状態とされる(同【002 3】)。 この点,電界効果トランジスタが閉鎖電気状態とされた場合,ドレインからソース,ソ\ースからドレインのいずれの方向にも電流が流れ得ることは,技術常識であるから,直ちに引用発明の電界効果トランジスタが整流器に相当するものとはいえ ない。 そこで,上記のように,引用発明の電界効果トランジスタが閉鎖電気状態とされ た場合の電流の流れについて検討すると,燃料電池の出力電圧が約0.4Vより低 くなるような状態となって電界効果トランジスタが閉鎖電気状態とされた時点では, 燃料電池のアノード,カソード間の電位差により,電界効果トランジスタでは,カソ\ード53側からアノード52側へ電流が流れ,その後,燃料電池の電位差が低下することによって,アノード52側からカソード53側へ電流が流れるに至るものと解するのが相当である。そうすると,甲3において,好適実施例として記載され\nている【図3】の構成においても,電界効果トランジスタを流れる電流は一方向に限定されているものではない。\n
ウ 以上によると,本願発明における第1の整流器が飽くまで一方向にのみ電流 を流すものであるのに対し,引用発明における電界効果トランジスタは,双方向に 電流を流すものであるから,引用発明の電界効果トランジスタが本願発明の第1の 整流器に相当するとはいえず,この点において,本件審決には誤りがある。
エ(ア) これに対し,被告は,引用発明においては,電界効果トランジスタが閉鎖 電気状態とされた場合であっても,電流は電界効果トランジスタをアノード52側 からカソード53側に流れると主張し,その根拠として,甲3の段落【0023】の記載を指摘する。\n
しかし,上記イのように,電界効果トランジスタが閉鎖電気状態とされた時点で は,カソード53側からアノード52側へ電流が流れるとしても,その後,アノード52側からカソ\ード53側へ電流が流れるに至るのであって,同段落の記載はそのような理解と矛盾するものとはいえない。甲3の段落【0001】,【0005】, 【0008】及び【0009】の記載や,【図4】(上記各段落の記載内容に照らし, 引用発明に係る甲3の「第1の条件」の際の動作は,同図の「欠陥は重大か?」に 対する答えが肯定(Y)の場合の動作,すなわち同図の「燃料電池への水素供給遮 断及び燃料電池の両端を永久的に短絡」という動作に当たるものと認められる。)を 踏まえると,段落【0023】は,引用発明において電界効果トランジスタが閉鎖 電気状態とされた場合に最終的に至る,引用発明の構成においてより重要な電流の流れについてのみ記載したものと理解することができ,そこに至るまでに一旦電流\nが反対方向に流れることを否定するものとは解されない。 したがって,甲3の段落【0023】の記載は被告の上記主張の根拠とはならず, 乙13(前記3(5))の記載や,燃料電池を迂回する経路をMOSFETで形成する ことに係る周知技術(乙13[前記3(5)],乙14[同(6)]参照)など,その他被 告の主張する点は,いずれも上記認定判断を左右する事情ではない。 なお,被告は,本件第1回口頭弁論期日における技術説明会のための資料におい て,甲3の【図3】における電界効果トランジスタについて,ドレインとソースの表\記が逆である旨を指摘するが(乙15の10頁),上記認定判断のとおり,同図の記載と段落【0023】の記載が直ちに矛盾しているとはいえず,相当とはいえな い。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2021.10.13
令和1(ワ)11874 商標権 民事訴訟 令和3年6月23日 東京地方裁判所
ア 証拠(乙112,113)によれば,平成22年10月1日から平成3 1年4月30日までの期間における本件各店舗の総売上高は,652億5 439万2382円であると認められる。
イ 使用料率について
(ア) 商標法38条3項による損害は,原則として,侵害に係る役務の売上 高を基準とし,これに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきで あり,実施に対し受けるべき料率は,1)実際の実施許諾契約における実 施料率や,業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該商標 権の顧客吸引力,3)当該商標を使用した場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様,4)商標権者と侵害者との競業関係や商標権者の営業方針 等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきであ る(知財高裁特別部平成30年(ネ)第10063号・令和元年6月7日 判決(最高裁HP)参照)。
(イ) 被告らは,パチンコホールの売上げを計上する場合,貸玉の対価をも って売上高とするグロス方式と,貸玉の対価から客に提供した景品原価 を控除した金額をもって売上高とするネット方式があるところ,パチン コ店について商標法38条3項の損害額を算定するに当たっては,ネッ ト方式により貸玉の対価から景品原価を控除した金額を基に計算するべ きであると主張する。 しかし,本件において,損害を算定する基準となる売上高は,当該役 務によって得られる収入,すなわち,貸玉の対価と解するのが自然であ り,店舗運営に係る諸費用のうち景品原価のみを控除した額を売上げと みなすべき合理的な理由はない。被告らが主張するような,パチンコ業 界における利益率は使用料率の算定において考慮すれば足りるというべ きである。
(ウ) そこで,原告各商標についての相当な使用料率について以下検討する。
a 本件においては,原告が実際に原告各商標の使用を許諾したことを うかがわせる証拠はなく,業界における実施料の一般的な相場等も明 らかではない。
b 原告各商標は,上記(1)イで摘示した事情,すなわち,パチンコ業界 における店舗数ランキング,「ベガスベガス」という名称の需要者へ の訴求力,原告の店舗情報に関するウェブサイトへのアクセス状況, 原告の会員数などを考慮すると,相応の顧客吸引力を有するものと認 められる。
他方で,全日本遊技事業協同組合連合会が実施したアンケート結果 (乙40・15頁)によると,パチンコホールを選ぶ上でのポイント として需要者が重視するのは,1)遊戯機種,2)アクセスの容易さ,3) 出玉感,4)ホールの雰囲気,5)店員の接客態度などであり,店舗の名 称が売上げ又は利益に貢献する程度は限定的であるというべきである。
c さらに,原告と被告らはその事業分野で競合しているが,営業地域 をみると,原告の店舗は,北海道,東北地方及び関東地方が中心であ り,本件各店舗の所在する広島県及び山口県においては店舗展開及び 営業活動をしていない。他方,被告らは,原告各商標の出願前から本 件各店舗を同地域に出店し,地元の需要者に対して,新聞の折込みチ ラシ(乙55,56,78,85〜87,90,91,96,97), 新聞紙面広告(乙53,54,77),テレビCM(乙57,59〜 66,86〜88,91〜93,97〜101)などによる宣伝広告 活動を継続してきたものと認められ,被告らによるかかる営業活動が その売上げに貢献する割合は大きかったと推察される。
d 本件各店舗の月当たりの営業利益をみると,売上高の概ね●(省略) ●前後で推移しているものと認められ(乙112,113),売上高 に対する営業利益の比率は必ずしも高くないことからすると,通常想 定される使用料率は上記の割合より相当程度低くなると考えられるが, 本件においては,さらに,店舗の名称が売上げに貢献する程度は限定 的であり,原告と被告らは本件各店舗の所在地で競合していないこと, 被告の営業努力の寄与が大きいなどの事情が認められる。
e 以上の事情も含め,本件に現れた事情を総合考慮すると,原告各商 標に関する使用料率は0.15%であると認めるのが相当である。
◆判決本文
関連事件です。不使用であるとした審決の取消請求事件です。
2021.10. 8
令和3(行ケ)10029 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年9月21日 知的財産高等裁判所
ア 本件商標は,「HIRUDOMILD」の10文字の標準文字で表してなるものであり,「ヒルドマイルド」の称呼が生じるものである。\nところで,本件商標が10文字からなるものでその一部のみを観察することも想 定可能な程度の長さを有していること,その構\成中の「MILD」の文字部分は, 前記1(5)のとおり,「物事の程度や人の性質・態度などが穏やかなさま。」「刺激の 少ないさま。」などを意味する英単語として広く知られ,また,会話中においても日 常的に使用されており,ひとまとまりの語句として強く認識され得るものであるこ とからすると,本件商標は,「HIRUDO」の構成部分と「MILD」の構\成部分 からなる結合商標であるとみることができる。 そして,「HIRUDO」の構成部分は,我が国において周知されているものではないから一種の造語と理解され,同構\成部分に対応する和名の「ヒルド」は,前記1(1)のとおり長期間にわたって原告商品の他には薬剤の名称には使用されておら ず,薬剤の名称としてありふれたものではないことからしても,需要者に対し,商 品の出所識別標識として強い印象を与えるといえる。これに対し,「MILD」の構成部分は,前記1(5)のとおり,薬剤の分野においては,薬の効果や刺激が弱いこと を意味するものとして理解され,その和名である「マイルド」は薬のブランド名等 とともに商品名に用いられることが相当程度にあるから,指定商品である薬剤との 関係において,自他識別機能は極めて弱いというべきであり,「MILD」の構\成部 分から出所識別標識としての称呼,観念が生じるとはいえない。 そうすると,本件商標については,「HIRUDO」の文字のみを抽出し,この部 分だけを引用商標と比較して類否を判断することも許されるというべきである。
イ したがって,本件商標については,「HIRUDOMILD」の外観及び「ヒ ルドマイルド」の称呼のほか,「HIRUDO」の外観及び「ヒルド」の称呼が生じ るものとして引用商標と比較することが相当である。なお,「HIRUDO」は特定 の意味合いを有しない一種の造語と理解され,本件商標からは特定の観念を生じな いというべきである。もっとも,上記1(5)からすれば,「HIRUDOMILD」 が薬剤に使用された場合には,「薬効又は刺激が弱い『HIRUDO』」という観念 が生じ得ると認めるのが相当である。
(2) 引用商標について
ア 引用商標1は,「Hirudoid」の8文字のアルファベットからなるもの であり,「ヒルドイド」の称呼を生じる。辞書等に採録された既成語ではなく,特定 の意味合いを有しない一種の造語と理解され,特定の観念を生じない。
イ 引用商標2は,「ヒルドイド」の5文字の片仮名からなるもので,「ヒルドイ ド」の称呼を生じる。辞書等に採録された既成語ではなく,特定の意味合いを有し ない一種の造語と理解され,特定の観念を生じない。
4 本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1の類否について検討する。
(1) 本件商標の指定商品は「薬剤」であり,引用商標1の指定商品は「薬剤(蚊 取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。)」を 含むものであって,その指定商品は同一又は類似である。
(2)ア 本件商標は,その10文字中,7文字目の「M」,9文字目の「L」を除 く「HIRUDO(Hirudo)」「I(i)」「D(d)」の8文字が,引用商標1と大文字と小文字の差はあるものの共通し,その並び順も同じである。次に,称呼 についてみると,本件商標と引用商標1は,「ヒルド」「イ」「ド」の5つの構成音が共通し,その並び順も同じであり,本件商標の方が引用商標1よりも「マ」と「ル」\nの2音多いものの,印象の強い語頭の3音と語尾の1音が同じである。そして,前 記3(1)のとおり,本件商標は,薬剤に使用された場合,「薬効又は刺激が弱いHI RUDO」を連想させるものである。 イ 本件商標の「HIRUDO」の構成部分と引用商標1を比較すると,大文字と小文字の差はあるものの,その6文字全てが引用商標1の冒頭6文字と共通し,\nその3つの構成音全てと引用商標1の語頭の3つの構\成音が共通する。「HIRU DO」及び引用商標1はいずれも特定の意味を有しない造語であり,それ自体から 特定の観念は生じない。
(3) 原告商品は医療用医薬品であるものの,その需要者は医療関係者に限られる ものではなく,その最終需要者は患者である上に,前記1(2)のように,記事やオン ラインショップ等で,市販品であるヘパリン類似物質含有製剤について「『ヒルドイ ド』で知られる医療用保湿剤の成分」を配合している旨の説明がされるほどに「ヒ ルドイド」が市販品である保湿剤の購入者に知られていたと推認されることからし ても,原告使用商標が表示された原告商品の需要者には,医師等医療関係者のみならず患者も含まれるというべきである。本件商標の付された商品は存在しないもの\nの,仮に被告が主張するように医療用医薬品のみに使用されるものであったとして も上記需要者の認定を左右しない。 その上で,取引の実情について検討するに,前記1(1)及び(2)のとおり,引用商 標1を表示した原告商品が60年以上にわたり販売されていること,原告が原告商品について一定の宣伝活動を継続していること,平成29年度には原告商品が医療\n用医薬品の年間売上げで19位となるなど非常に高い売上げを有していること,平 成26年度から平成30年度までの間のヘパリン類似物質含有製剤又は血液凝固阻 止剤の分野における原告商品の売上占有率は,徐々に減少しているものの全期間を 通じて金額にして7割,数量にしても5割を超えていたこと,平成29年頃には, アンチエイジングの効果がある又は肌荒れ・乾燥に効果のある保湿クリームとして 女性誌等でも取り上げられ,美容目的で処方を受ける例があることが疑われるなど として問題視されるまでになっていたこと,原告が適正な処方をするよう注意喚起 した後に,原告商品と同じヘパリン類似物質を配合した市販品(医薬品又は医薬部 外品)が複数販売されるようになり,製造者や販売店が,「ヒルドイドで有名な『ヘ パリン類似物質』を配合」などと説明するなどしていたこと及び令和3年2月から 同年3月に実施されたアンケートによると乾燥肌等に対する皮膚薬を使用又は1年 以内に使用した者の44%が「ヒルドイド」を保湿剤であると認識していたことか らすると,平成29年頃までには,需要者の相当割合の者が,「ヒルドイド」という 造語及びこれに対応する欧文字の「Hirudoid」から,「ヘパリン類似物質を 配合した保湿剤」である原告商品を想起するものと認められ,長期間をかけて形成 されたこの状況は,本件商標の出願日及び本件査定日においても継続していたもの と認めるのが相当である。 また,昭和51年から平成11年まで販売されていた「ヒルドシン」を除けば, 語頭に「ヒルド」や「HIRUDO(Hirudo)」が付された薬剤は原告商品の みであったこと,原告が原告商品について適正な処方をするよう注意喚起した後に, 原告商品と同じヘパリン類似物質を配合した市販品(医薬品又は医薬部外品)が複 数販売されるようになり,そのうち医薬部外品の一つは語頭に「ヒルド」を用いて おり,一部の購入者が原告商品の市販品であると誤解して購入するなどしていたこ と等に照らすと,本件商標の出願日及び本件査定日時点において,需要者の間では, 「ヒルド」やこれに対応する欧文字の「HIRUDO」は,「ヒルドイド」及び「H IRUDOID」を意味する単語として認識されており,「ヒルド」に対応する欧文 字の「Hirudo」は「Hirudoid」を意味するものと認識されていたと 認めるのが相当であるから,「HIRUDO」と引用商標1は,いずれも「ヘパリン 類似物質を配合した保湿剤であるヒルドイド」を想起させるということができ,観 念を共通とするものと認められる。
(4) 被告の主張について
被告は,「○○」と「○○MILD」の両方が商標登録されている例が複数ある旨 指摘するが,これらの登録例は,同一権利者による商標出願に係るものか,指定商 品が異なるか,「○○」の部分が「PRECIOUS」など特定の意味を有する単語 であるなどしていて,本件とは事案が異なる(乙1)。また,「ウフェナ」の文字を 標準文字で表してなる商標が,「ウフェナマイルド」の文字と「UFENAMILD」の文字を上下二段に表\してなる構成の引用商標と類似しないと判断した審決例(乙\n2)があるが,当該引用商標の構成が本件商標及び本件の引用商標とは異なる上,同審決においては取引の実情が考慮されていないなど本件とは事案が異なるもので\nある。 次に,被告は,語頭に「ヒルド」を付す名称の薬剤は原告商品のみではない旨主 張するが,「ヒルド」を語頭に付した名称の商品が原告商品の他に複数販売されてい る状況が長期間にわたり継続するなどして「HIRUDO」の構成部分の出所識別機能\が失われたとまで認めるべき事情はないから,これらの商品の存在は,本件商標と引用商標1の類否の判断に影響しない。
(5) 上記を総合すると,本件商標と引用商標1は,指定商品が同一で,外観,観 念,称呼に共通している部分があり,同一又は類似の商品に使用された場合に,商 品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるというほかないから,両商標は類似 すると認めるのが相当である。
◆判決本文
関連事件です。商標がカタカナ表記です。
◆令和3(行ケ)10028
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.10. 8
令和2(ワ)8061 商標権侵害差止請求 商標権 民事訴訟 令和3年9月27日 大阪地方裁判所
被告は,被告標章1につき,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるこ とを認識することができる態様により使用されていない,すなわち商標的使用がさ れていない旨を主張する。 しかし,前記のとおり,オンラインフリーマーケットサービスであるメルカリに おける具体的な取引状況をも考慮すると,記号部分「#」は,商品等に係る情報の検 索の便に供する目的で,当該記号に引き続く文字列等に関する情報の所在場所であ ることを示す記号として理解される。このため,被告サイトにおける被告標章1の 表示行為は,メルカリ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマン\nトサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情報を検索する便に供する ことにより,被告サイトへ当該利用者を誘導し,当該サイトに掲載された商品等の 販売を促進する目的で行われるものといえる。このことは,メルカリにおけるハッ シュタグの利用につき,「より広範囲なメルカリユーザーへ検索ヒットさせること ができる」,「ハッシュタグ機能をメルカリ上で使うと使わないでは,商品閲覧数\nや売り上げに大きく差が出ます」などとされていること(いずれも甲7)からもう かがわれる。
また,被告サイトにおける被告標章1の表示は,メルカリ利用者が検索等を通じ\nて被告サイトの閲覧に至った段階で,当該利用者に認識されるものである。そうす ると,当該利用者にとって,被告標章1の表示は,それが表\示される被告サイト中 に「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する情報が所 在することを認識することとなる。これには,「被告サイトに掲載されている商品 が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものである」との認識も当 然に含まれ得る。
他方,被告サイトにおいては,掲載商品がハンドメイド品であることが示されて いる。また,被告標章1が同じくハッシュタグによりタグ付けされた「ドットバッ グ」等の文字列と並列的に上下に並べられ,かつ,一連のハッシュタグ付き表示の\n末尾に「好きの方にも・・・」などと付されて表示されている。これらの表\示は,掲載 商品が被告自ら製造するものであること,「シャルマントサック」,「ドットバッ グ」等のタグ付けされた文字列により示される商品そのものではなくとも,これに 関心を持つ利用者に推奨される商品であることを示すものとも理解し得る。しかし, これらの表示は,それ自体として被告標章1の表\示により生じ得る「被告サイトに 掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名である」 との認識を失わせるに足りるものではなく,これと両立し得る。 これらの事情を踏まえると,被告サイトにおける被告標章1の表示は,需要者に\nとって,出所識別標識及び自他商品識別標識としての機能を果たしているものと見\nられる。すなわち,被告標章1は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であ ることを認識することができる態様による使用すなわち商標的使用がされているも のと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2021.10. 8
令和1(ワ)5444 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月28日 大阪地方裁判所
法人の代表者等が,法人の業務として第三者の特許権を侵害する行為を行った場\n合,第三者の排他的権利を侵害する不法行為を行ったものとして,法人は第三者に 対し損害賠償債務を負担すると共に,当該行為者が罰せられるほか,法人自身も刑 罰の対象となる(特許法196条,196条の2,201条)。 したがって,会社の取締役は,その善管注意義務の内容として,会社が第三者の 特許権侵害となる行為に及ぶことを主導してはならず,また他の取締役の業務執行 を監視して,会社がそのような行為に及ぶことのないよう注意すべき義務を負うと いうことができる。 他方,特許権者と被疑侵害者との間で特許権侵害の成否や特許の有効無効につい て厳しく意見が対立し,双方が一定の論拠をもって自説を主張する場合には,特許 庁あるいは裁判所の手続を経て,侵害の成否又は特許の有効性についての公権的判 断が確定するまでに,一定の時間を要することがある。 このような場合に,特許権者が被疑侵害者に特許権侵害を通告したからといっ て,被疑侵害者の立場で,いかなる場合であっても,その一事をもって当然に実施 行為を停止すべきであるということはできないし,逆に,被疑侵害者の側に,非侵 害又は特許の無効を主張する一定の論拠があるからといって,実施行為を継続する ことが当然に許容されることにもならない。 自社の行為が第三者の特許権侵害となる可能性のあることを指摘された取締役と\nしては,侵害の成否又は権利の有効性についての自社の論拠及び相手方の論拠を慎 重に検討した上で,前述のとおり,侵害の成否または権利の有効性については,公 権的判断が確定するまではいずれとも決しない場合があること,その判断が自社に 有利に確定するとは限らないこと,正常な経済活動を理由なく停止すべきではない が,第三者の権利を侵害して損害賠償債務を負担する事態は可及的に回避すべきで あり,仮に侵害となる場合であっても,負担する損害賠償債務は可及的に抑制すべ きこと等を総合的に考慮しつつ,当該事案において最も適切な経営判断を行うべき こととなり,それが取締役としての善管注意義務の内容をなすと考えられる。
具体的には,1)非侵害又は無効の判断が得られる蓋然性を考慮して,実施行為を 停止し,あるいは製品の構造,構\成等を変更する,2)相手方との間で,非侵害又は 無効についての自社の主張を反映した料率を定め,使用料を支払って実施行為を継 続する,3)暫定的合意により実施行為を停止し,非侵害又は無効の判断が確定すれ ば,その間の補償が得られるようにする,4)実施行為を継続しつつ,損害賠償相当 額を利益より留保するなどして,侵害かつ有効の判断が確定した場合には直ちに補 償を行い,自社が損害賠償債務を実質的には負担しないようにするなど,いくつか の方法が考えられるのであって,それぞれの事案の特質に応じ,取締役の行った経 営判断が適切であったかを検討すべきことになる。
・・・
(コ) 別件判決は,ネオケミアに対し,金1億1107万7895円及びこれに 対する遅延損害金を原告に支払うこと等を命じるものであり,令和元年6月7日に これに対する控訴棄却判決がなされたが,原告において供託金の差押え等の方法に より計700万円を回収した以外に,ネオケミアより原告に対する前記損害賠償債 務の弁済はなされていない。 被告P1は,令和2年9月24日付けで,二酸化炭素経皮吸収技術の開発等を目 的とする新会社を設立した。また被告P1は,ネオケミアについて破産手続開始の 申立てを行い,同年12月7日,同手続開始決定を得た。\n破産者ネオケミアについては,令和3年2月28日の時点で,回収済みとして破 産管財人が保管している資産の額は124万9370円,届出のあった一般破産債 権の総額は1億6969万3683円とされた。
・・・
ウ 判断
前記アで認定した事実,及び前記イで被告P1の主張について判断したところを 総合すると,被告P1が,各被告製品の製造販売が本件各特許権の侵害にならな い,あるいは本件各特許は無効であると主張した点について十分な論拠があったと\nいうことはできず,むしろ特許制度の基本的な内容に対する無理解の故に,ネオケ ミア特許の実施品であれば本件各特許権の侵害にはならないと誤解して各被告製品 の製造販売を続け,取引先にもそのように説明したものである。 前述のとおり,特許権侵害の成否,権利の有効無効については,公権力のある判 断が確定するまでは軽々に決し得ない場合があり,自社に不利な判断が確定する場 合もあるのであるから,取締役にはそれを前提とした経営判断をすべきことが求め られ,前記(1)の1)ないし4)で述べたような方法をとることで,特許権侵害に及 び,自社に損害賠償債務を負担させることを可及的に回避することは可能であるに\nも関わらず,被告P1はそのいずれの方法をとることもせず,各被告製品の製造販 売を継続している。さらに,別件判決(甲5)によれば,ネオケミアは各被告製品 の販売により相応の利益を得ていたのであるから,特許権侵害となった場合の賠償 相当額を留保するなどして,別件判決確定後に損害を遅滞なく填補すれば,ネオケ ミアに損害賠償債務を確定的に負担させないようにすることも可能であったのに,\n被告P1は任意での賠償を行わず,ネオケミアを債務超過の状態としたまま,破産 手続開始の申立てを行ったものである。\n
以上を総合すると,被告P1が,本件各特許が登録されたことを知りながら,特 段の方法をとることなく各被告製品の製造販売を継続したことは,ネオケミアの取 締役としての善管注意義務に違反するものであり,被告P1は,その前提となる事 情をすべて認識しながら,ネオケミアの業務としてこれを行ったのであるから,そ の善管注意義務違反は,悪意によるものと評価するのが相当である。
(3) 被告P2の悪意重過失について
ア 会社法上,取締役として選任されている以上は,個々の能力,知識,報酬等\nの有無にかかわらず,取締役として一般に要求される善管注意義務を尽くして代表\n取締役の業務執行を監視,監督すべきものである。 被告P2は,自身が名目上の取締役であり,ネオケミアの業務に全く関与せず, 本件各特許の内容を知らず,各被告製品が本件各特許権を侵害するかを判断する機 会もなかったので,被告P1の経営判断が特許権侵害であるとしても,それを発見 し,抑止することはできなかったと主張するが,このような理由で,取締役として の善管注意義務が存在しない,あるいは免除されていると解することはできない。
イ 既に認定したとおり,原告とネオケミアとの間で各被告製品に係る明らかな 紛争が発生していたのであるから,被告P2において,これを把握することは容易 であり,前記(2)で検討したとおり,被告P1に対し,ネオケミアに不利となる公 権的判断が確定する可能性をも考慮した適切な経営判断を行っているかを確認し,\n被告P1の判断に不十分な点があれば,再考を求めることは可能\であったと解され る。 被告P2が,上述したような監視,監督を尽くしても,被告P1の行為を抑止で きなかったとすべき具体的な事情は認められないし,被告P2がネオケミアの業務 に関心を持たず,本件各特許すら知らず,各被告製品に係る紛争を知らなかったと いうことを被告P2に有利な事情と解することはできず,むしろ,取締役としての 義務に違反する程度は大きいといわざるを得ない。
以上を総合すると,被告P2には,取締役である被告P1の業務執行に対する適 切な監視,監督を怠ったことについて,重大な過失があったということができる。
(4) 被告P3の悪意重過失について
ア 前記前提事実,証拠(甲31の1,60の1及び2,乙82の1,丙1, 2,4,被告P3本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (ア) 被告P3は,エステティシャンとして活動していたところ,原告ら10数 社から発売されていた炭酸ガスパックを試した結果,ネオケミアの製品が効果的で あったため,被告P1に面会して炭酸ガス療法及び炭酸ガス美容について説明を受 け,炭酸ガスパック剤の特許はネオケミアのみが有しているので,安心して販売で きると聞いた。 被告P3は,ネオケミアの製品には特許使用料が上乗せされて他の商品より高額 であったが,ネオケミアの製品が最も良いと考え,これを仕入れて販売することに した。
(イ) 被告P3は,ネオケミアの製品が人気を博した後,琉球粘土を配合した炭 酸ガスパック剤を作りたいと考え,被告P1に相談した。 被告P3は,事業を法人化して製品の開発・販売を進めることし,平成23年1 1月18日,自らを代表取締役とするクリアノワールを設立し,平成24年頃,ネ\nオケミアの協力を得て被告製品14を開発した。
(ウ) 被告P3は,平成25年7月22日,原告から被告製品14が本件各特許 の技術的範囲に属するとして,その製造販売の中止等を求める通告書を受領し,ま た,取引先からも,原告から同様の通告を受けたと聞いた。 被告P3は,原告からの通告書を確認してもその内容を理解することができなか ったため,被告P1に面会して説明を求めたところ,被告P1から,原告は本件各 特許権を有しているが,大阪の大手の事務所である北浜法律事務所の弁護士と青山 特許事務所の弁理士に相談しており,弁護士及び弁理士が特許権の侵害はないから 心配はないと言っていると聞いた。また,被告P1は,弁護士を代理人として原告 と交渉しているので心配ない,任せてほしいなどとも言ったことから,被告P3 は,これを信用し,被告製品14の販売を継続することとした。 被告P3は,同月29日頃,被告P1から,前記(2)ア(キ)の書面(丙4)を受領 した。
(エ) 被告P3は,別件訴訟の提起を受けて,改めて被告P1に説明を求めたと ころ,被告P1から,北浜法律事務所の弁護士と青山特許事務所の弁理士が原告の 特許権を侵害していることはないと言っている旨を再び告げられ,別件訴訟の裁判 費用をネオケミアが負担し,万一敗訴した場合は,賠償金もネオケミアが負担する と言われた。また,被告P3は,その頃,被告P1から,被告製品2について,本 件発明2−1の技術的範囲に属さない旨の青山特許事務所の弁理士作成の鑑定書の 写しの交付を受けた。 被告P3は,炭酸ガスパックの専門家である被告P1が自信を持っており,原告 製品よりもネオケミアの製品の方が品質・性能が良く,悪い製品の特許が優先する\nことはあり得ないと考え,被告製品14の販売を継続した。 その後,被告P3は,ネオケミアの代理人弁護士や弁理士から直接説明を受ける 機会があり,その際も,大丈夫だ,心配ないと言われた。
(オ) 被告P3は,平成28年12月16日,別件訴訟において裁判所から心証 開示を受けた後も,被告製品14の販売が本件各特許権の侵害に当たることに疑問 を持っていたが,裁判所の判断である以上やむを得ないと考え,被告製品14の販 売を止めた。
(カ) 令和元年6月7日の控訴棄却判決により,クリアノワールに対し1223 万6265円及び遅延損害金を支払うよう命じた別件判決は確定したが,原告にお いて供託金の差押えにより150万円を回収した以外に,クリアノワールが原告に 対し前記債務を弁済することはなく,被告P3は,同年6月,琉球粘土と炭酸ガス パックからなるスキンケア商品その他を販売することを目的とする新会社を設立し た。
イ 判断
前記認定したところによれば,被告P3は,原告から被告製品14の販売が本件 各特許権の侵害に当たるとの警告を受けたものの,本件各特許の発明者であって炭 酸ガスパックの専門家であった被告P1から,ネオケミアが委任した弁護士や弁理 士が特許権侵害ではないと言っているなどと聞き,どのような根拠で特許権侵害に 当たらないということになるのか理解できないまま,ネオケミアも特許権を有して いて,原告製品よりネオケミアの製品の方が品質・性能が良いので,原告の特許権\nが優先することはないなどと考え,被告製品14の販売を継続する意思決定をした というのであるから,主として,被告製品14の製造元であるネオケミアからの説 明に依拠してその判断を行ったことになる。 しかしながら,特許権侵害が成立しないとするネオケミア側の説明に十分な論拠\nがなく,むしろ被告P1の特許制度に対する誤解が前提となっていたことは,前記 (2)で検討したとおりであるし,品質・性能において上回っていることは,特許権侵\n害を否定する理由とはなり得ない。
被告P3は,特許権侵害の判断は素人には難しく,警告を受ければすべからく製 造販売等を停止しなければならないとすることは不当であると主張するが,前記 (1)で述べたとおり,クリアノワールの代表取締役として,被告P3には,特許権\n侵害の成否や権利の有効性についての公権的判断が,自己に有利にも不利にも確定 する可能性があることを前提に,そのいずれの場合であっても第三者の権利を侵害\nし損害を生じさせることを可及的に回避しつつ,自社の利益を図るような経営判断 をすべき注意義務があったということができる。 この点について被告P3は,特許権侵害の警告を受けた後も,主として被告製品 14の製造元であるネオケミア側からの説明に依拠し,前記(1)の1)ないし4)で検 討したような方法をとることもなく,裁判所からの心証開示があるまでの間,被告 製品の14の販売をして特許権侵害の不法行為を継続し,原告に損害を生じさせた のであるから,取締役としての善管注意義務に違反したというべきであり,少なく とも重過失によると認めるのが相当である。
(5) 被告P4の悪意過失について
会社法上,取締役として選任されている以上は,個々の能力,知識,報酬等の有\n無にかかわらず,取締役として一般に要求される善管注意義務を尽くして代表取締\n役の業務執行の監督を行うべきものである。 前記(4)のとおり,原告から警告書の送付を受けるなど,クリアノワールについ て被告製品14に係る明らかな紛争が発生していたのであるから,その取締役であ った被告P4においてこれを把握することは容易であった。また,前記(4)で認定 したとおり,被告P3に確認すれば,特許権侵害が成立しないことの十分な論拠は\nなく,仮に特許権侵害が確定した場合の対応も想定しないままに,クリアノワール が被告製品14の販売を継続しようとしていることを知り得たのであるから,被告 P4には,取締役である被告P3の監視・監督を怠る義務違反があったというべき であり,その過失の程度は重大というべきである。
4 原告の損害額(争点4)について
(1) 訴外2社の行為に係る原告の損害額
ア ネオケミアの行為に係る原告の損害額
(ア) 証拠(甲45〜49,51〜57)及び弁論の全趣旨によれば,各被告製 品とその顆粒の販売によるネオケミアの売上の額は別紙「ネオケミアの売上の推 移」(ただし,平成22年12月6日の被告製品6の売上を除く)のとおりと認め られる。 そして,当該売上額から,原告において経費として控除することを自認する額を 差し引き,その1割に相当する金額を弁護士費用として加算した金額は,1億08 29万1485円である。 証拠(甲5,6)によれば,別件訴訟において原告が弁護士及び弁理士に委任し て訴訟追行していたことが認められ,ネオケミアの行為と相当因果関係のある弁護 士費用等は,ネオケミアの利益の額の1割とするのが相当であるから,ネオケミア の行為と相当因果関係のある損害として特許法102条2項により推定される損害 額及び弁護士費用は,1億0829万1485円であると認められる。 また,原告は,700万円を回収した等として控除することを自認しているか ら,ネオケミアの行為と相当因果関係のある損害額として現存するのは,1億01 29万1485円であると認められる。
(イ) 上記1億0829万1485円という金額は,別件判決が特許法102条 2項を適用して算出したネオケミアの損害賠償債務の元金部分(1億1107万7 895円)から,被告製品6の売上にかかる部分と原告が差押え等により回収した 700万円を控除した金額に一致するところ,被告らは,会社法429条1項に基 づく責任に特許法102条2項を適用または類推適用すべきではない旨主張する。 しかしながら,特許法102条2項は,推定を用いるとはいえ,特許権者が受け た損害賠償額を算定する方法を定めたものであり,別件判決の確定により,原告が ネオケミアの特許権侵害により上記損害を受けたことは確定しているのであるか ら,取締役の善管注意義務違反によりネオケミアが特許権侵害を行ったことによる 損害も,これと同じものであると解するのが相当であり,法的性質は異なるとし て,別途の算定をしなければならないと解すべき理由はない。
イ クリアノワールの行為に係る原告の損害額
(ア) 弁論の全趣旨によれば,被告製品14の販売に係る別紙「ダイヤモンドス キンジェルパック売上一覧表(クリアノワール)」の内容は,クリアノワールが自\nら原告に開示したものであると認められ,被告製品14の販売によるクリアノワー ルの売上の額は当該別紙記載のとおりと認められる。 そして,当該売上額から,原告において経費として控除することを自認する額を 差し引き,その1割に相当する金額を弁護士費用として加算した金額は,1223 万6265円であり,被告P4がクリアノワールの取締役であった平成26年11 月30日までの期間の利益額は896万8027円である。 証拠(甲5,6)によれば,別件訴訟において原告が弁護士及び弁理士に委任し て訴訟追行していたことが認められ,クリアノワールの行為と相当因果関係のある 弁護士費用等は,クリアノワールの利益の額の1割とするのが相当であるから,ク リアノワールの行為と相当因果関係のある損害として特許法102条2項により推 定される損害額及び弁護士費用は,1223万6265円であると認められる。 また,原告は,150万円を回収したとして控除することを自認しているから, 現存するクリアノワールの行為と相当因果関係のある損害額は,1073万626 5円であると認められる。
(イ) 上記1223万6265円という金額は,別件判決が特許法102条2項 を適用して算出したクリアノワールの損害賠償債務の元金部分に一致するが,前記 アで述べたとおり,取締役の善管注意義務違反によりクリアノワールが特許権侵害 を行ったことによる損害も,同様に解するのが相当である。 被告P3及び被告P4は,会社法429条1項は悪意又は重過失を要件としてお り,成立要件を厳格にしておきながら,損害額の立証については立証を容易にする 推定規定を適用することは立法趣旨に反すると主張するが,会社法429条1項の 責任は不法行為責任とは別個の責任を定めるものであるところ,第三者の生じた損 害をどう認定するかについては何も定めておらず,特許権侵害があった場合の損害 の算定について,特許法の規定を用いることを禁じるものとは解されない。
(2) 損害の発生について
被告P3及び被告P4は,クリアノワールが沖縄県内でのみ被告製品14を販売 しており,原告は沖縄県内で原告製品を販売していなかったから,クリアノワール の行為によって原告は損害を被っていないと主張する。 しかしながら,証拠(甲7,8)によれば,原告製品は販売地域を限定した製品 とは認められないものであり,原告製品の性質上,沖縄県内での販売が困難である とか,原告において沖縄県において原告製品を販売することができない事情があっ たとは認められないから,仮に原告製品が沖縄県において販売されていなかったと しても,被告製品14が販売されていることが原告製品の沖縄県への進出を妨げる 等の損害が生じ得たのであり,特許法102条2項の適用を否定すべき理由とはな らない。
(3) 被告らの任務懈怠行為との因果関係について
ア 被告P1について
前記3(2)のとおり,被告P1は,本件各特許が登録されたことを知ってなお, ネオケミアにおいて各被告製品やその顆粒剤を製造販売するに際し,被告P1の当 該意思決定によってネオケミアが本件各特許権の侵害行為をしたのであるから,ネ オケミアが本件各特許権の侵害行為により原告に与えた前記(1)アの損害は,被告 P1の任務懈怠行為と相当因果関係のある損害と認められる。
イ 被告P2について
前記3(3)のとおり,被告P2は,被告P1にネオケミアの業務執行を一任して 監視・監督義務を怠ったものであり,これは重過失による任務懈怠行為に当たると ころ,前記アのとおり,原告がネオケミアから受けた前記(1)アの損害が被告P1 の悪意の任務懈怠によって生じたものであって,被告P1の任務懈怠行為と同損害 に相当因果関係があるのであるから,被告P2の任務懈怠行為と同損害にも相当因 果関係があると認められる。
ウ 被告P3について
前記3(4)のとおり,被告P3は,原告から被告製品14の販売が本件各特許権 の侵害となるとの通知を受けてなお,クリアノワールにおいて被告製品14を販売 するに際し,調査・検討を怠って,漫然と被告製品14の販売を継続する意思決定 をしたものであり,この善管注意義務違反は重過失による任務懈怠に当たるとこ ろ,クリアノワールが本件各特許権の侵害行為により原告に与えた前記(1)イの損 害は,被告P3の任務懈怠行為と相当因果関係のある損害と認められる。
エ 被告P4について
前記3(5)のとおり,被告P4は,被告P3にクリアノワールの業務執行を一任 して監視・監督義務を怠ったものであり,これが任務懈怠行為に当たるところ,前 記ウのとおり,原告がクリアノワールから受けた前記(1)イの損害が被告P3の重 過失による任務懈怠によって生じたものであって,被告P3の任務懈怠行為と同損 害に相当因果関係があるのであるから,被告P4の任務懈怠行為と被告P4がクリ アノワールの取締役在任中にクリアノワールから原告が受けた損害にも相当因果関 係があると認められる。 そして,前記(1)イのとおり,被告P4がクリアノワールの取締役であった期間 にクリアノワールが本件各特許権を侵害して被告製品14を販売したことにより得 た利益は,896万8027円であり,原告は,これから回収済みの150万円を 控除した746万8027円についてのみ被告P4に対して請求しているから,こ の全額について,被告P4の任務懈怠行為との間に相当因果関係があるものと認め られる。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 賠償額認定
>> ピックアップ対象
2021.10. 8
令和3(行ケ)10046 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年9月29日 知的財産高等裁判所
本件商標は,「Nクール」の文字を標準文字で表してなるものである。\n次に,本件使用商標は,別紙1のとおり,「Nクール(R)ベストII」の緑色 の文字を表してなるものである。そして,本件使用商標の構\成中の「ベス ト」の文字部分は,本件使用商品(「メッシュベスト」)との関係では, 商品の種類を表すものであり,「(R)」の文字部分は登録商標を意味する記 号及び「II」の文字部分はローマ数字の2を表するものであって,いずれ\nも自他商品識別標識としての機能を有するものと認められないから,本件\n使用商標の要部は,「Nクール」の文字部分であると認めるのが相当である。 そこで,本件商標と本件使用商標の要部の「Nクール」の文字部分を対 比すると,外観は異なるが,構成文字が共通であり,「エヌクール」とい\nう同一の称呼が生じることからすると,本件使用商標は,全体として本件 商標と社会通念上同一の商標であると認められる。
ウ 以上によれば,被告は,要証期間内の令和2年1月23日から同年4月 2日までの間,日本国内において,本件使用商品に関する広告(本件カタ ログデータ)に本件商標と社会通念上同一の商標である本件使用商標を付 して電磁的方法により提供したものと認められるから,かかる被告の行為 は,本件商標の使用(商標法2条3項8号)に該当するものと認められる。
2 本件使用商品の本件商標の指定商品該当性について
(1) 本件使用商品が本件審判の請求に係る指定商品である第25類「ベスト」 に該当するかについて検討する。
ア(ア) 本件商標の登録出願時(登録出願日平成28年6月20日)に施行 されていた商標法施行令別表(以下「政令別表\」という。)には,第25 類の名称として「被服及び履物」が挙げられている。 また,本件商標の登録出願時に施行されていた商標法施行規則別表(平\n成28年経済産業省令第109号による改正前のもの。以下「省令別表」\nという。)には,第25類に属する商品として「一 被服」を掲げ,その 細分類として定められた「(一) 洋服」から「(十一) ナイトキャップ 帽子」までに商品が例示列挙されているが,「ベスト」については掲げら れていない。
(イ) 次に,本件商標の登録出願時に用いられていた国際分類(第10− 2016版)を構成する類別表\(以下「国際分類類別表」という。)の第\n25類の「注釈」(Explanatory Note)には,「この類 には,特に,次の商品は含まない:特殊な用途に供する被服及び履物(商 品のアルファベット順一覧表参照).」と記載されている。一方で,国際\n分類類別表の「商品のアルファベット順一覧表\」には,「ベスト」(「ve sts」,「waistcoats」)は,第25類に属する商品として掲 げられている。
(ウ) 「ベスト」(「vests」,「waistcoats」)とは,一般に, 「丈が短く,体にぴったりつく,袖のない胴着の一種」を意味するもの と認められる(甲3,4)。
イ 前記ア認定の政令別表第25類の名称,省令別表\に第25類に属するも のとされた商品の内容,国際分類類別表の第25類の「注釈」において示\nされた商品の説明及び国際分類類別表の「商品のアルファベット順一覧表\」 の記載,「ベスト」の用語の意義を総合考慮すると,本件審判の請求に係る 指定商品である第25類「ベスト」とは,省令別表第25類に属する商品\nとして掲げられた「被服」に含まれる「丈が短く,体にぴったりつく,袖 のない胴着の一種」であって,「特殊な用途に供するものではないもの」と 解するのが相当である。
これを本件使用商品についてみるに,証拠(甲7,8,13の2,14 の3,15の3)によれば,本件使用商品は,メッシュ生地で作られた, 丈が短く,体にぴったりつく,袖のない胴着であると認められる。 また,前記1(1)ウの認定事実によれば,本件使用商品は,被告が販売す る「空調服」(電動ファンを内蔵した上着)(甲9)の下に着用する「専用 メッシュベスト」であるが,「空調服」自体,その有する機能から暑さ対策\nが必要となる場面で着用されることが想定された商品であり,実際に,業 界を問わず,様々な場面で利用されており(本件カタログデータの2頁に 「建設,建築業界を始め,土木・自動車・流通・運輸・金属・農業など・・・ 業界を問わず,あらゆるシーンで採用されています。」との記載(前記1(1) ウ(イ))がある。),その用途が限定されていないことからすれば,本件使 用商品も,同様にその用途が限定されていないものと認められるから,「特 殊な用途に供するものではないもの」と認められる。 したがって,本件使用商品は,「丈が短く,体にぴったりつく,袖のない 胴着の一種」であって,「特殊な用途に供するものではないもの」であるか ら,本件商標の指定商品第25類「ベスト」に含まれるものと認められる。
(2) これに対し原告は,1)類似商品・役務審査基準によれば,第25類は,細 分類として「被服」を含み,更にこの「被服」は「洋服,コート,セーター 類,ワイシャツ類」を含み,このうちの「セーター類」には「3 セーター 類 カーディガン,セーター,チョッキ」が含まれるところ,「ベスト」(「v ests and waistcoats)」は,「1 洋服」とは別の「3 セーター類 カーディガン,セーター,チョッキ」の中に分類されており, これに準じるものでなければならないから,洋装ファッションとしての「機 能又は用途」と,それにふさわしい「材料」を有するものでなければならな\nい,2)「メッシュベスト」(本件使用商品)は,保冷剤を保持するための装着 具であり,洋装ファッションとしての「機能又は用途」を有せず,また,単\n純にメッシュ(網)を,保冷剤を保持するように縫製したものにすぎず,保 冷剤を装着せずに使用することは実用性がなく実際上も考えられない特別な 「材料」からなり,保冷具の一部材にすぎないから,洋装ファッションとし てのベストではなく,第25類の一般的な被服に属する「ベスト」(類似群コ ード17A01)の範疇に属する商品であるとはいえない旨主張する。 しかしながら,1)については,本件審判の請求に係る指定商品である第2 5類「ベスト」は,省令別表第25類に属する商品として掲げられた「被服」\nに含まれる「丈が短く,体にぴったりつく,袖のない胴着の一種」であって, 「特殊な用途に供するものではないもの」と解すべきであることは,前記(1) イ認定のとおりである。また,省令別表には,第25類に属する商品として\n掲げた「一 被服」の細分類の「(一) 洋服」から「(十一) ナイトキャップ 帽子」までに「ベスト」は掲げられていないが,上記細分類に掲げられた商 品は,第25類に属する商品の例示列挙であるから,第25類「ベスト」は, 上記細分類中の「(三) セーター類 カーディガン セーター チョッキ」 に準じるものでなければならないと解すべき理由はない。また,国際分類類 別表の第25類の「注釈」において示された商品の説明(前記(1)ア(イ))に 照らしても,第25類「ベスト」は,洋装ファッションとしての「機能又は\n用途」とそれにふさわしい「材料」を有するものでなければならないと解す べき合理的な根拠はない。
2)については,本件使用商品は,メッシュ生地で作られた,丈が短く,体 にぴったりつく,袖のない胴着であるが(前記(1)イ),その材料は特殊なもの であるとはいえず,保冷剤を装着することができるという機能を有するとし\nても,そのことによって本件使用商品が保冷具の一部材にすぎないものであ るともいえない。また,上記のとおり,第25類「ベスト」は,洋装ファッシ ョンとしてのベストに限られるものではない。 したがって,原告の上記主張は,理由がない。
2021.10. 8
令和3(ネ)10028 損害賠償等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年9月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
また,控訴人は,当審において,原判決は,全体として一つのゲーム を一画面一画面に分断し,分断した画面ごとに共通する部分(アイコン 等の配置等)について,個別に創作性を判断し,その結果として,共通 する部分全体の創作性を否定したものであり,一連の流れのあるゲーム の著作権侵害を判断しているのではなく,画面の著作権侵害を判断して いるにすぎないから,このような原判決の判断手法によると,他社のゲ ームをデッドコピーしても,キャラクターやアイコンのデザイン等を多 少変更さえしてしまえば,著作権侵害を免れることになり,不合理であ るとして,被告ゲームは原告ゲームを複製又は翻案したものに当たらな いとした原判決の判断手法は誤りである旨主張する。 しかしながら,原告ゲーム全体と被告ゲーム全体の共通部分が創作的 表現といえるか否かを判断する際に,その構\成要素を分析し,それぞれ について表現といえるか否か,表\現上の創作性を有するか否かを検討す ることは,有益かつ必要なことであり,その上で,ゲーム全体又は侵害 が主張されている部分全体について表現といえるか否か,表\現上の創作 性を有するか否かを判断することは,合理的な判断手法であると解され る。 そして,前記(イ)のとおり,原判決は,被告ゲームと原告ゲームの共 通点はアイデアや創作性のないものにとどまり,また,具体的表現にお\nいて相違し,デッドコピーであるとは評価できないから,被告ゲーム全 体が,原告ゲーム全体を複製又は翻案したものに当たるということはで きないと判断したものであり,その判断手法に誤りはない。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。」
(2) 原判決42頁6行目の「原告は,」を「ア 控訴人は,」と改め,同43頁 20行目から44頁20行目までを次のとおり改める。
「 イ ところで,著作権法上の「プログラム」は,「電子計算機を機能させ\nて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせ たものとして表現したもの」をいい(同法2条1項10号の2),プロ\nグラムをプログラム著作物(同法10条1項9号)として保護するた めには,プログラムの具体的記述に作成者の思想又は感情が創作的に 表現され,その作成者の個性が表\れていることが必要であると解され る。すなわち,プログラムの具体的記述において,指令の表現自体,そ\nの指令の表現の組合せ,その表\現順序からなるプログラムの全体に選 択の幅があり,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性が表\れ ていることが必要であると解される。 これを原告ソースコードについてみるに,前記ア認定のとおり,原\n告ソースコードは,原告ゲームの473個のLuaファイルのうちの\n1個である「MissionMainPage.lua」であり,原告 ソースコードに係るプログラムは,「任務(ミッション)」に係る画面\n(メインミッション画面,デイリーミッション画面,功績画面)の切 り替えに関する処理及び表示内容の更新処理を行うプログラムである。\nそして,原告ソースコードの記述は,原判決別紙「ソ\ースコード対比 表」の「原告ソ\ースコード」欄記載のとおりであり,個々の記述の意味 は,同表の「裁判所の認定」欄記載のとおりである。\n原告ソースコードの記述は,いずれも単純な作業を行うfunct\nion(ローカル変数やテーブルの宣言及びモジュールの呼び出し等) が複数記述されたものであり,ソースコードによって記述される機能\ が上記のとおりローカル変数やテーブルの宣言及びモジュールの呼び 出し等の単純な作業を行うことである以上,表現の選択の幅は狭く,\nその具体的記述の表現も,定型的なものであり,ありふれたものであ\nると言わざるを得ない。 また,個々の記述の順序や組合せについても,ゲームの機能に対応\nさせたにすぎないものであり,ありふれたものである。 そうすると,原告ソースコードの具体的記述に控訴人の思想又は感\n情が創作的に表現され,控訴人の個性が表\れていると認めることはで きないから,原告ソースコードに係るプログラムは,プログラムの著\n作物に該当するものと認めることはできない。 したがって,被告ソースコードの大部分が原告ソ\ースコードと共通 しているとしても,原告ソースコードに係るプログラムの著作物性は\n認められないから,被告ソースコードの制作は,原告ソ\ースコードに 係るプログラム著作権(複製権又は翻案権)の侵害に当たらない。
(4) 編集著作権の侵害について 控訴人は,当審において,1)原告ゲームは,素材である個々の画面(8 4画面)の選択,その画面遷移等の配列,素材である各画面内における アイコン,ボタン,キャラクター等の選択又は配列に作成者の個性が発 揮されているから,素材の選択又は配列によって創作性を有する編集著 作物である,2)原告ソースコードも,個々のソ\ースコードの書き方,各 ソースコードの順序,変数の名称等の素材を選択して組み合わせたこと\nに作成者の個性が発揮されているから,素材の選択又は配列によって創 作性を有する編集著作物である,3)被告ゲームは,編集著作物である原 告ゲーム(原告ソースコードを含む。)を複製又は翻案して制作されたも\nのであるから,被告ゲームの制作及び配信行為は,原告ゲームについて 控訴人が有する編集著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)の侵害に 当たる旨主張する。 しかしながら,控訴人の上記主張は,原告ゲーム又は原告ソースコー\nドにおける個々の素材の選択又は配列にいかなる創作的表現がされてい\nるのか,その創作的表現が被告ゲーム又は被告ソ\ースコードにおいてど のように利用されているのかについて具体的に主張するものではないか ら,その主張自体理由がない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2021.10. 8
令和2(ワ)14629 意匠権侵害差止等請求事 意匠権 民事訴訟 令和3年9月7日 東京地方裁判所
ア 本件意匠と被告意匠は,基本的構成態様において共通し,また,具体的構\ 成態様のうち,共通点1から5において共通する。 このうち,本件意匠の基本的構成態様は,需要者の注意を引くべき形状等\nとはいえず,類否判断に当たって,それが共通することを大きく取り扱うこ とは相当ではない。 具体的構成態様の共通点のうち,共通点1及び2は,需要者の注意を引く\nべき形状等に係るものであり,これらが共通することは,類否判断に影響を 与える。もっとも,渦流生成部において,捕捉部を中心とする等角度位置に 配置された複数の斜面体を設ける構成を有する公知意匠があり(前記\n),この点を特に大きく取り扱うことは相当とはいえない。 共通点3から4は,フランジ部の形状等であり,需要者が注意を引くべき 部分の形状等ではなく,また,フランジ部においてその形状等が占める割合 も大きくなく,類否判断に与える影響は小さいといえる。
イ 本件意匠と被告意匠の具体的構成態様は,差異点1から6において異なる。\n差異点1から4は,渦流生成部の形状であり,注意を引くべき形状等に関 するものである。そして,本件意匠においては,渦流生成部を形成する4個 の斜面体が,段差構造によって境界を形成するものであり,渦流生成部を形\n成する斜面体が,段差構造によって境界を形成し,斜面体を区切る構\造体が ないという形状等が,注意を引くべき形状等に含まれるといえるところ,差 異点1は,その形状等に係るものである。本件意匠が上記の形状等であるの に対し,被告意匠においては,本件意匠と異なり,斜面体の外周部には,堰 部が設けられている。斜面体の段差構造によって境界を形成するか,別に堰\n部を設けるかは,その形状等自体が明確に異なるものである。ヘアキャッチ ャーの需要者は,それが排水口の上に設置された際等も含めてその真上から だけでなく,やや斜め上から見る場合も多いといえるところ,斜視図等(別 紙本件意匠,本件意匠説明図,被告意匠目録,被告意匠説明図,本件意匠・ 被告意匠対照表)に特に明らかなとおり,需要者は,本件意匠の渦流生成部\nは平面状の斜面体のみで構成されるやや平板な段差構\造であることを認識 するのに対し,被告意匠では,斜面体の外周部に斜面体に対し垂直方向に突 出する堰部があることを認識し,斜面体から堰部が突出していること及び堰 部によってもたらされる別の斜面体との段差が強く印象付けられる。また, 本件意匠では,斜面体のみで渦状模様を生じさせるものであり,渦流生成部 が平面状の斜面体のみからなり,渦状模様もあっさりした印象を与える。こ れに対し,被告意匠では,堰部によって各斜面体が明確に区別され,堰部自 体も斜面体と独立して渦状模様を顕出させるものであって,このことにより 斜面体と堰部それぞれによって二重の明確な渦状模様を生じさせるという 印象を与えるものである。したがって,差異点1は,本件意匠と被告意匠の 類否判断に大きく影響を与える。 差異点2(斜面体の個数)及び3(斜面体の形状)も,需要者の注意を引 くと考えられる渦流生成部の形状に係る差異であり,類否判断に影響を与え るといえる。もっとも,本件意匠と被告意匠において,斜面体の形状は,い ずれも最も長い曲線が内側に湾曲する3つの線で囲まれるものであり,その 形状の差は大きなものとはいえない。そして,本件意匠と被告意匠では,こ のような形状の斜面体がいずれも捕捉部を中心として等角度位置に配置さ れていて,斜面体の形状に大きな差がないことからも,その個数が6個であ っても4個であっても,数個の斜面体で構成されているとの印象を与える側\n面があり,個数の差が美感に与える影響は必ずしも大きなものであるとはい えない。差異点4(捕捉部の形状)は,需要者の注意を引くと考えられる捕 捉部の形状に係る差異であり,本件意匠の捕捉部には整流体がないのに対し, 被告意匠には,本件意匠にはない整流体があり,それが膨出していることか らも,類否判断に一定の影響を与えるといえる。 差異点4から6は,いずれも,需要者の注意を引くとはいえない,フラン ジ部における差異であり,その差異も大きくなく,類否判断に与える影響は 大きくないといえる。
ウ 以上によれば,本件意匠と被告意匠は,基本的構成態様で共通し,具体的\n構成態様においても,注意を引くべき形状等に係る共通点1及び2において\n共通する。もっとも,本件意匠の基本的構成態様は,注意を引くべき形状等\nとはいえず,また,具体的構成態様の共通点も類否判断に与える影響を特に\n大きく取り扱うことは相当ではない。 他方,本件意匠と被告意匠の具体的構成態様の差異のうち,差異点1は,\n本件意匠において特に注意を引くべき形状等に関する差異であり,被告意匠 には本件意匠には見られない堰部があるのであり,前記のとおり,それが類 否判断に与える影響は大きい。また,差異点4も類否判断に一定の影響を及 ぼす。 これらからすると,本件意匠と被告意匠の差異点から受ける印象は,本件 意匠と被告意匠の共通点から受ける印象を凌駕するものであるといえる。よ って,被告意匠は,本件意匠に類似していないというべきである。
(7) 原告は,本件意匠も被告意匠も,堰部の有無にかかわらず,内側に向かう渦 の流れという美感が共通するので,堰部の有無は美感判断に影響をしないと主 張する。既に説示したとおり,内側に向かう渦の流れという美感自体は,公知 意匠にも共通するありふれた意匠であり(公知意匠1から4),この点を共通 にすることを類否判断で大きく扱うことは相当ではない。 また,原告は,公知意匠1から4のヘアキャッチャーに係る意匠はいずれも, 正面視において渦流壁がフランジ部よりも上方に張り出していたところ,本件 意匠も被告意匠もこれがなく,全体的に平面的な美感を共通にしていると主張 する。上記公知意匠における渦流壁は,フランジ部よりも上部に張り出し,ま た,平面視において占める面積は大きく,被告意匠の堰部は,公知意匠の渦流 壁に比べれば,その存在感は大きくない。しかし,渦流生成部を区分けする構\n造体がフランジ部よりも上部に張り出していない意匠自体は公知であったと いえる上(公知意匠5),本件意匠は渦流壁,堰部に相当する部位を全く有して いないのに対し,被告意匠は堰部を有しているのであって,堰部の存在の有無 自体が類否判断に大きな影響を与えるというべきである。原告の指摘は前記判 断を覆すに足りるものではない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2021.10. 8
令和2(行ケ)10038 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年9月28日 知的財産高等裁判所
前示のとおり,本件訂正発明の構成は容易想到であるが,これに対し,\n被告は,前記第3の5(2)イのとおり,本件訂正発明は,本件3条件を全て 満たす患者に対する顕著な骨折抑制効果(以下「効果1)」という。),2)本 件条件(4)の服薬歴がある患者に投与すると,本件条件(4)の服薬歴 のない患者に対するよりも骨折抑制効果がより増強される効果(以下「効 果2)」という。)を奏し,これらの効果は,当業者が予測をすることができ\nなかった顕著な効果を奏するものである旨主張する。 以下,これらの効果について検討する。
(ア) 効果1)について
a 前記イ(イ)のとおり,骨粗鬆症は,骨強度の低下を特徴とし,骨折 の危険性が増大した骨疾患であり,骨粗鬆症の治療の目的は骨折を予\n防することであり,「骨強度」は骨密度と骨質の2つの要因からなり, 骨密度は骨強度のほぼ70%を説明するとの技術常識があったから, 当業者は,骨密度の増加は,骨折の予防に寄与すると理解するところ,\n甲7文献には,「ここに挙げた薬剤を投与することによって骨密度(B MD)が増加するため,骨折予防は飛躍的に進歩した」(296頁右欄\n10行ないし297頁左欄25行目)と骨密度の増加が骨折予防に寄\n与することが記載され,その上で,48週で骨密度を8.1%増大させ たことが開示されている(300頁左欄11行ないし右欄6行目)。そ うすると,甲7発明の骨粗鬆症治療剤が骨折を抑制する効果を奏して いることは,当業者において容易に理解できる。
b 効果1)の骨折抑制効果とは,単なる骨折発生率の低減ではなく,プ ラセボ投与群の骨折発生率と対比した場合の骨折発生率の低下割合を 指すものであるが,本件明細書の記載からでは,本件3条件を全て満 たす患者と定義付けられる高リスク患者に対する骨折抑制効果が,本 件3条件の全部又は一部を欠く者と定義付けられる低リスク患者に対 する骨折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。 すなわち,効果1)を確認するためには,高リスク患者に対する骨折 抑制効果と低リスク患者に対する骨折抑制効果とを対比する必要があ るが,前記1のとおり,本件明細書には,実施例1において,高リス ク患者では,100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体 以外の部位の骨折発生率は,いずれも実質的なプラセボである5単位 週1回投与群における発生率に対して有意差が認められるが,低リス ク患者では,100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体 以外の部位の骨折の発生率は,いずれも,5単位週1回投与群におけ る発生率に対して有意差が認められなかったと記載されているのにと どまる(【0086】ないし【0096】,【表6】ないし【表\11】)。 そして,低リスク患者の新規椎体骨折についていえば,100単位週 1回投与群11人と5単位週1回投与群10人(令和3年1月15日 付け被告第1準備書面33頁における再解析の数値による。)について, それぞれ,ただ1人の骨折例数があったというものであり,また,椎 体以外の部位の骨折は,上記5単位週1回投与群について,ただ1人 の骨折例数があったというものであって,有意差がなかったことが, 症例数が不足していることによることを否定できない。このように, 低リスク患者において,100単位週1回投与群の新規椎体骨折及び 椎体以外の部位の骨折の発生率が5単位週1回投与群のそれらの発生 率に対して有意差がなかったとの結論が,上記のような少ない症例数 を基に導かれたことからすると,高リスク患者における骨折発生の抑 制の程度を低リスク患者における骨折発生の抑制の程度と比較して, 前者が後者よりも優れていると結論付けることはできない。 したがって,実施例1をみても,高リスク患者に対するPTHの骨 折抑制効果が,低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高 いということを理解することはできず,さらに,本件明細書のその他 の部分をみても,高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が,低 リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理 解することはできない。 以上によれば,効果1)は,本件明細書の記載に基づかないものとい うべきである。
c 被告は,効果1)を明らかにするものとして,別紙4の実験成績証明 書(甲79)を提出する。
しかしながら,本件明細書の記載から,高リスク患者に対するPT Hの骨折抑制効果が,低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よ りも高いということを理解することができず,また,これを推認する こともできない以上,効果1)は対外的に開示されていないものである から,上記実験成績証明書を採用して,効果1)を認めることは相当で ない。 仮に,上記実験成績証明書を参酌するにしても,本件3条件の全て を満たす患者(高リスク患者)のグループと,本件3条件の全部又は 一部を満たさない患者(低リスク患者)のグループのうちごく一部の グループとを比較しているものにすぎないから,本件3条件の効果が 明らかになっているとはいえない。また,上記実験成績証明書には, 本件条件(1)を満たし,本件条件(2)又は本件条件(3)のいず れかを満たさない患者とされる「非3条件充足患者」につき,「非3条 件充足患者においてもPTH投与群ではコントロール群よりも骨折の 発生が抑制されたが,3条件充足患者においては,PTH投与群では コントロール群よりも骨折の発生が『有意に』抑制された。」旨が記載 されているだけである。すなわち,本件3条件を満たさない患者につ いては,PTH投与群においてコントロール群よりも骨折発生が抑制 されたものの有意差がなかったことが理解できるのみであり,それら 有意差がなかったとの結論も症例数が少ないことによるものと推認さ れることからすると,本件3条件の全てを満たす患者の骨折発生の抑 制の程度が本件3条件を満たさない患者に対する骨折発生の抑制の程 度より優れていると結論付けることはできない。そうすると,上記実 験成績証明書をみても,本件3条件を全て満たす患者に対するPTH の骨折抑制効果が,本件3条件を満たさない患者に対するPTHの骨 折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。 d 以上によれば,いずれにしても効果1)を認めることはできないから, その他の点について判断するまでもなく,効果1)を予測することので\nきない顕著な効果という余地はない。
(イ) 効果2)について
前記ア(ウ)のとおり,効果2)は本件明細書からうかがうことのできな い効果である。
被告は,骨粗鬆症治療薬の服薬歴が本件3薬剤のいずれか1剤のみの 場合における新規椎体骨折発生数が記載された甲86証明書により本件 訂正発明の顕著な効果が裏付けられると主張する。仮に,上記実験成績 証明書を参酌するにしても,甲86証明書は,本件3薬剤それぞれにつ いて,服薬歴のある患者につき被験薬(PTH)を投与された場合と対 照薬(プラセボ)を投与された場合との骨密度変化率や新規椎体骨折発 生数を対比しているにすぎず,本件3薬剤のいずれかの服薬歴がある患 者と当該薬剤の服薬歴がない患者との間で,被験薬を投与された場合の 骨密度変化率や新規椎体骨折発生数を対比したものではないから,プラ セボ投与との対比による被験薬の骨粗鬆症治療に対する効果しか示され ていない。しかも,各薬剤についての評価例数があまりにも僅少で,そ のようなデータから算出される骨折相対リスク減少率は,骨折例数が1 件増減するだけで大きくその値を変えることは明らかであり,骨折相対 リスク減少率を対比してその効果を論じることも相当ではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2021.09.24
令和1(ワ)23407 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月10日 東京地方裁判所
本件発明の技術的意義や本件発明における調整手段の位置付けについて みると,従来の吊張り装置としては,略円弧状の天井部に沿って設けら れたウインチワイヤーと吊り上げワイヤーとを連結する連結体が,天頂 部との距離に応じてウインチワイヤーに沿って移動するよう構成されて\nいる装置が考えられたが,複数の停止体の設置等の調整作業を天井側で 行わなければならず費用がかかり煩雑である等の問題点があった(段落 【0006】【0008】)ところ,本件発明は,略円弧状の屋内の天 井部に沿ってウインチワイヤーを設け,吊り上げワイヤーを一端側でウ インチワイヤーに連結しその他端側に吊張体を設けるなどの構成をとる\nとともに,天頂部,又は天頂部に最も近接している基準となる吊り上げ ワイヤーのウインチワイヤーとの取付位置と,任意の吊り上げワイヤー のウインチワイヤーとの取付位置との「高さ方向の距離に対応した長さ」 (構成要件C),すなわち,取付位置の高さの差の長さ(以下「本件差\n分」という。)に基づく吊り上げワイヤー等の長さの変更,すなわち調 整を,ネット等の吊張体若しくは吊り上げワイヤーの下端(床面)側又 はその両方に調整手段を設け,あらかじめ行うことにより,上記問題点 を解決するものである(段落【0010】【0025】【0026】 【0045】。前記1(2))。
また,「調整」とは,「1)調子の悪いものに手を加えてととのえること。 2)ある基準に合わせてととのえること。過不足なくすること。3)釣り合 いのとれた状態にすること。折り合いをつけること。」(大辞林第4版) などとされる。 上記のとおりの本件発明の技術的意義,調整手段の意義や,「調整」の 一般的意味からすると,本件発明に係る吊張り装置において吊張体を過 不足なく適切に吊り張りするためには,本件差分が認識された上で,本 件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあら かじめ変更する必要があり,本件発明の「調整手段」は,そのためのも のであって,本件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー 等の長さをあらかじめ変更する構成であり,その調整を行うことにより,\n吊張体を過不足なく適切に吊り張りするための手段であると理解するこ とができる。 本件明細書の具体的な実施例についてみても,ネット吊張り装置におい て,天頂部の吊り上げワイヤー(9b)の取付位置と,他の吊り上げワ イヤー(9a)の取付位置との「距離に対応した長さ」であるL1等の長 さ(L)が認識された上で,一対の筒状体(15)を吊り上げワイヤー に挿通し,その一対(2個)の筒状体の間の距離を「距離に対応した長 さ」(L 本件差分)とすることによって,調整を行う調整手段が記載 されており(段落【0036】【0037】【図1】【図4】【図5】 等)ここでは,ネット体を過不足なく適切に吊り張りするため,吊り上 げワイヤーに挿通する一対の筒状体が設けられ,その筒状体の間の距離 を認識された差(L 本件差分)と同じにすることができることが記載 されており,本件差分(L)を基準としてこれに合うように筒状体の間 の距離の長さをあらかじめ変更する構成が調整手段として記載されてい\nる。以上のとおり,本件発明の「調整手段」(構成要件C)とは,吊張体を\n過不足なく適切に吊り張りするため,認識された本件差分を基準として これに合うように長さをあらかじめ変更するための手段であると解され る。
なお,吊張体の吊張り装置は,複数の部材を組み合わせて構成され,そ\nこには当然に連結部材や係止部材が含まれ,それらの連結部材や係止部 材において,何らかの長さの変更を行うことができる場合もあり得る。 しかし,本件発明の「調整手段」等の技術的意義は,上記のとおりのも のであり,吊張り装置に何らかの長さ変更を行う構成があったとしても,\n本件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあ らかじめ変更するための手段であると認められないものは,本件発明の 「調整手段」とはいえないと解される。仮に,本件発明において,単に 長さを変更する手段のみをもって調整手段に該当すると解するとすれば, 吊張体の施工やメンテナンスに際して吊り上げワイヤー等の長さを変更 するに当たり,他の手段によって,本件差分を基準としてこれに合うよ うにしなければならないことになるが,そのような作業を床面側のみで 行うことが可能であることは本件明細書の記載等によっても明らかでは\nなく,このような構成によっては本件発明の課題を解決することができ\nない。ここで,本件明細書には,吊り上げワイヤーにネット体への係止 体を設けることで,又は,ネット体に吊り上げワイヤーの係止体を設け ることで,吊り上げワイヤーの長さの調整を行うこともできることが記 載されている(段落【0058】)。これまで述べてきたところから, そのような係止体が,認識された本件差分を基準としてこれに合うよう に吊り上げワイヤー等の長さをあらかじめ変更するための手段といえる 場合には,本件発明の「調整手段」といえ,上記記載はその趣旨のもの と理解することができる。それに対し,そのような手段とはいえず,通 常の係止体としての構成,機能\を超える構成,機能\等を有しないものは, これまで述べたところに照らせば,本件発明と関係なく用いられている 係止体であり,本件発明の「調整手段」が有する効果を奏するものでは なく,本件発明の「調整手段」に該当するとは認められない。 他方,被告らは,本件発明の「調整手段」が筒状体など本件明細書に記 載された具体的な実施例に限られる趣旨の主張もするが,本件発明の技 術的範囲が上記の範囲に限定される理由はなく,前記のとおり,本件差 分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあらかじ め変更する構成を備えたものであれば,本件発明の「調整手段」といえ\nる。
・・・・
(3) 被告製品1が本件発明の技術的範囲に属するかについて
原告は,被告製品1において,各吊り上げワイヤーと各バトンを連結する シャックル,リングキャッチ,チェーン(以下,これらを「本件連結材」と いう。)が本件発明の調整手段であると主張する。 ここで,本件発明の「調整手段」(構成要件C)とは,吊張体を過不足な\nく適切に吊り張りするため,認識された本件差分を基準としてこれに合うよ うに長さをあらかじめ変更するための手段である(前記(1)イ)。 本件連結材は,ワイヤーとバトンを連結する際に通常用いられる連結材と 認められるところ,それは,単に連結のために通常用いられる複数の構成部\n品から成っているものにすぎず,認識された本件差分を基準としてこれに合 うように長さをあらかじめ変更する構成を有するものであるとは認められず,\nそのような調整作業をするための手段とはいえない。 また,被告製品1において,もともと各吊り上げワイヤーのウインチワイ ヤーへの連結位置から連結材の下端までの長さはほぼ同程度であり(前記(2) イ),天頂部に最も近接した吊り上げワイヤーが取り付けられたバトンが床 面に到達した状態においては,他の各吊り上げワイヤーはたわんだ状態とな るのであって(同エ),本件連結材によって吊り上げワイヤー等の長さの変 更は行っていない(同ウ)。本件連結材による長さの変更が想定されている ことを認めるに足りる証拠もなく,本件連結材は,そもそも長さの変更を行 うための手段ではないともいえる。 したがって,被告製品1の連結材は,構成要件Cの調整手段には該当しな\nい。 以上から,被告製品1は,構成要件Cを充足せず,本件発明の技術的範囲\nに属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2021.09.23
令和3(行ケ)10047 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年9月15日 知的財産高等裁判所
これに対し被告は,1)本件各写真(甲28)の撮影日が2018年11月 14日であることについては,客観的な裏付けがなく,撮影日が同日である ことは疑わしい,2)発行名義を桂ヶ丘開発とする「精算書控」及び「御精算書」 (甲46の1ないし9)は,本件審判段階では提出されず,本件訴訟に至って 初めて提出されたものであること,桂ヶ丘開発は原告が代表取締役を務める会\n社であり,発行名義を桂ヶ丘開発とする精算書をいつでも作成できること,令 和3年6月20日に本件ゴルフ場のクラブハウス内の物販コーナーで「福米」 を表示した米が販売された際に発行された「御精算書」(乙1)には,「福米」\nの文字の記載がなく,甲46の1ないし9記載の発行日付当時に実際に発行さ れていた精算書に「福米」の文字が表示されていたものとは,にわかに信用し\n難いことに照らすと,甲46の1ないし9の証明力は低い,3)桂ヶ丘開発が本 件ゴルフ場の利用者に対して福米2018を販売したとの原告の主張は,原 告が本件審判段階で本件ゴルフ場のクラブハウス内で一般客に対して自ら商 品「米」の販売を行ったと主張していたこと及びその立証のために提出され た桂ヶ丘開発の取締役会議事録(甲45)の記載と矛盾する旨主張する。 しかしながら,1)については,本件各写真(甲28の2枚の写真)の画像デ ータ(甲56)の「プロパティ」の「詳細」の「撮影日時」欄にそれぞれ「2 018/11/14 13:24」(甲28の「下」の写真に係る画像データ) 及び「2018/11/14 13:25」(甲28の「上」の写真に係る画 像データ)と表示されていること,本件各写真に写された本件価格表\には「期 間限定」,「福米2018」及び「2018年11月末日までの限定価格。」と の表示があり,その表\示内容は,本件各写真の撮影日時が「2018/11 /14 13:24」及び「2018/11/14 13:25」であるこ とと矛盾しないことに照らすと,本件各写真の撮影日は2018年11月1 4日であると認められる。被告が1)について指摘する原告提出の他の写真(甲 15,29ないし31)に日付が入っていない点,本件ゴルフ場のクラブハウ スのフロント付近で日常的に販売されている商品を写真撮影する理由も考え難 い点,同日以外の日に他の客の少ない時間にフロント前に商品を陳列し,写真 撮影することは容易であるとの点は,上記認定を覆すものではない。
次に,2)については,甲46の1ないし3,5ないし7は,桂ヶ丘開発が 運営する「桂ヶ丘カントリークラブ」作成名義の「精算書控」,甲46の8は, 甲46の3の「精算書控」に対応する「桂ヶ丘カントリークラブ」作成名義 の「御精算書」であり,それぞれ利用者の氏名,「お客様番号」,発行日時, 「精算金額」のほか,「精算項目」欄にプレーフィ,利用税等とともに,「福 米(5kg)」,「数量」欄に「1」又は「2」,「単価」欄に「2,200」, 「金額」欄に「2,200」又は「4,400」との記載があり,その体裁に 特段不自然な点は認められないから,甲46の1ないし3,5ないし8の記載 内容は信用できるものといえる。この点に関し被告が提出する「桂ヶ丘カント リークラブ」作成名義の「御精算書」(乙1)には,「2021年6月20日 1 3:29」,「精算項目」欄に「〈軽〉新米(2kg)」,「数量」欄に「1」,「単 価」欄に「800」,「金額」欄に「800」と記載され,「福米」の記載はな いことが認められる。しかし,乙1は,要証期間経過後の令和3年6月20 日に単価800円で販売された「新米(2kg)」の精算書であり,甲46の 1ないし3,5ないし8に係る「福米」とは販売時期が異なること,本件各 写真に撮影された本件価格表に表\示された「福米2018」の「2kg」の 販売価格「700円」と単価が異なることに照らすと,乙1に係る「新米(2 kg)」は,甲46の1ないし3,5ないし8に係る「福米」と異なる商品で あると認められるから,乙1に「福米」の記載がないことは,甲46の1な いし3,5ないし8の記載内容の信用性を揺るがすものではない。また,原告 は,本件審決において本件審判段階で主張した本件商標の使用の事実が認め られなかったため,本件訴訟において,本件商標の使用の事実を改めて整理 して主張し,その立証のため,甲46の1ないし9を新たに提出したものであ るから,甲46の1ないし9が本件審判段階では提出されなかったことや桂 ヶ丘開発は原告が代表取締役を務める会社であることは,甲46の1ないし3,\n5ないし8の信用性を左右する事情には当たらない。 さらに,3)については,本件審決は,原告による「桂ヶ丘カントリークラ ブ」(本件ゴルフ場)のクラブハウス内の物販コーナーにおける「米」の販売 に係る本件商標の使用の主張について,平成30年10月1日に開催された 桂ヶ丘開発の取締役会議事録(審判乙34・本訴甲45)には,「第1号議案 として,本件商標権者が個人事業主として生産している米(福米2018) を桂ケ丘カントリークラブのロビー内の物販コーナーで販売することについ て承認された旨の記載があるが,当該米についての販売期間の記載はない。」 (審決書13頁36行〜14頁1行)として,上記主張は認められない旨判 断した。原告は,本件審決の上記判断を踏まえて,本件訴訟において,上記 物販コーナーにおける「米」の販売に係る本件商標の使用の主体を,原告か ら原告が代表取締役を務める桂ヶ丘開発に構\成し直して,桂ヶ丘開発が本件 ゴルフ場の利用者に対して本件ステッカーが米袋に貼付された福米2018\nを販売したとの主張をするに至ったものと認められるから,原告の主張の変 遷が不自然であるということはできないし,上記取締役会議事録の記載と矛 盾するということもできない。
2021.09.23
令和2(ワ)3247等 損害賠償請求 特許権 民事訴訟 令和3年9月6日 大阪地方裁判所
(1) 前提事実,争いのない事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば, 次の事実が認められる。 ア 被告は,原告退職後の平成22年9月から漏水探査等を目的とする事業を行 うようになったところ,平成23年頃実施の門川町上水道漏水調査委託業務の入札 に参加し,これを落札した。これについて,原告は,その後,門川町に対し,被告の 指名競争入札参加申請書及び被告が納品した漏水調査結果報告書等を求めて公文書\n公開請求を行った(甲15,16)。
イ 被告は,平成26年10月1日,原告から,平成23年4月26日付け「情 報窃盗に関する記述」と題する部分及び平成25年9月26日付け「情報窃盗及び 機密保持違反に関する刑事告訴に至る記述」と題する部分からなる書面(乙7)を 受領した。同書面のうち,前者の部分には,被告が,原告が「業務を通じ考案した 「エアー加圧工法」を実用新案特許出願中 平成2年6月 その工法さえも盗み出 した」との旨や,書類(結果報告書及び作業計画書等)の無断使用による著作権侵 害,原告の固定客や取引先の横取り等による原告の被害額が推定1500万円以上 に上ること,被告を刑事告訴する旨等が記載されている。後者の部分には,前者の 部分と同趣旨の記載のほか,「虚偽申請による不当なる資格取得」との記載があり,\n原告の被害額が推定3000万円以上に上ること,被告を刑事告訴する旨等が記載 されている。
ウ 原告は,全国漏水調査協会会長に宛て,平成27年4月1日付け「質問書」 (乙9)を送付した。同書面には,同協会発行の有資格者認定名簿における被告の 記載に関する質問等が記載されている。
エ 原告は,同月6日,被告に対し,「「漏水調査技術者認定証等」に関する件」 と題する書面(乙8の1)を送付した。同書面には,被告につき,「不正に全国漏 水調査協会の民間資格者として,再登録を行っています。」,「貴殿が行った行為 は,「業務上横領」や「詐欺」に匹敵する許し難い行為だと思います。」,「まず貴\n殿が,「弊社の技術」を盗む目的を持って入社し弊社が長年の研究や試行錯誤の上 で開発した「エア加圧工法」と言う独自工法を盗み」などと記載されていると共に, 「期日までに,何らかのご連絡,若しくは,「漏水調査技術者証の返還」が,無き 場合は,「刑事告訴」及び「法的手段」を取りますので,ご了承下さい。」とも記載 されている。
オ 原告は,全国漏水調査協会会長に宛て,同年5月6日付け「勧告書」(甲3 2,乙10)を送付した。同書面は,上記「質問書」に対する回答が得られていな いとして送付されたものであり,ここには,有資格者の調査技師の欄に被告が記載 されているが,その記載内容は虚偽である旨の指摘等が記載されている。また,同 書面(乙10)の余白には,「この書面を提出した事で,彼は責任を取り自から会 長職を辞職した!!」との原告代表者の手書きによる記載がある。\n
カ 原告は,同年6月11日,被告に対し,同日付け「通知書」(甲29,乙11 の1)を送付した。同書面には,「その盗んだ技術の中身には,長年研究開発した 「エア加圧工法」が含まれており,弊社が開発した技術を無断で利用して,平然と 営業利益を上げています。」などとして,原告の損害金総額1億円の支払を求める 旨等が記載されている。 これに対し,被告は,同年9月14日,原告に対し,同日付け「回答書」(甲9, 31,乙12の1)を送付した(同月15日に原告に到達。乙12の2)。同書面に は,「調査内容の「エア加圧工法」は他社企業でも行われている工法で,特許侵害 等の法を犯す工法ではありません」などと記載されていると共に,1億円の支払請 求については,内容が事実に反していることなどから応じられない旨が記載されて いる。
キ 被告は,平成31年2月7日頃,原告から,平成30年2月7日付け「最後 通告書」(乙13の1。なお,同書面の作成日付は,書面全体の記載の趣旨から, 「平成31年」の誤記と思われる。)を受領した(乙13の2)。同書面には,「貴 殿は,…私文書偽造詐欺行為を平然と行って置きながら,…全国漏水調査協会に私\n文書偽造の行為にあたる事を長年繰り返し申請をして,不正に漏水調査士の資格を\n取得しています。」,「弊社の「報告書書式や漏水調査カルテ書式等」を退職時に 何らかの形で持ち出しましたね。」,「「工具は持ち出して居ない」とは思います が,どの様な方法でエアを注入していますか?」,「漏水調査工法のエア加圧工法 は,弊社が開発したものです。…弊社は,昨年5月11日付で,エア加圧工法で, 「特許権」を取得しています。このままだと仕事を失う事になりますよ。速やかに, なんらかの行動を起して下さい。」,「弊社が取得した「エア加圧工法」は,…何人 たりとも勝手に利用して,使用が出来ないのです。それを犯して使用する場合は, 「知的財産権の侵害行為」となり,そこには,処罰の対象になります。…独自の工 法を考えださない限りは,特許権侵害行為になり,この仕事は,出来ません。」な どと記載されていると共に,改めて,総額1億円の技術使用料の支払を求める旨等 が記載されている。 なお,同書面には,被告の使用する工法が原告の「特許権」の侵害にあたると原 告が考える理由等に関する記載はない。
ク 原告は,本件の証拠として提出した令和2年8月22日付け「上申書(5)認否 事項についての反論」(甲21)において,「裁判を提訴するまで,被告の行って居 る工法につては,知る由は無かった。」としている。
ケ 原告は,全国漏水調査協会会長に宛て,本訴の提起後である令和2年9月1 1日付けで,同協会の漏水調査技術資格認定者名簿における被告の記載に関して質 問をし,同月28日付けで回答を得たものの,これを不十分として,同年10月1\n日付け「公開質問書」(甲32)を送付して再度質問をし,同月16日付けで回答 を得た。
(2) 法的紛争の当事者が紛争の解決を求めて訴えを提起することは,原則として 正当な行為であり,訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴 訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くもので ある上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知 り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的 に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当 である(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・ 民集42巻1号1頁参照)。 前記(1)認定のとおり,原告は,被告が原告を退職して独立開業した後,本訴の提 起に至るまでの間,被告が門川町の業務を落札したことを契機に,被告の事業活動 を問題視するようになり,被告の使用する工法が原告の「エア加圧工法」を無断で 使用するものであるなどとして,刑事告訴の可能性にも言及するなどしつつ,被告\nに対して直接非難する趣旨を含む書面を送付した。他方で,原告は,漏水調査協会 に対しても,有資格者名簿に被告が記載されていることにつき,質問の形式を取り ながら,これを問題視していることをうかがわせる内容の書面を送付した(しかも, 原告は,本訴提起後も改めてこのような行為に及んでいる。)。さらに,本件特許 権の設定登録後には,「エア加圧工法」につき特許権を取得したとの前提ではある ものの,被告の行為は特許権侵害にあたるとして,技術使用料の支払を重ねて求め たものである。 こうした経過を経て本件の本訴が提起されたことを踏まえると,本訴の提起も, 被告がその事業上実施する工法を原告が問題視して行った一連の行動の一環として 行われたものと理解される。
他方,原告と被告との一連のやり取りにおいて,原告は,被告から「特許侵害等 の法を犯す工法ではありません」などと反論されたこともあるにもかかわらず,被 告の使用する工法等が原告の特許権を侵害するものと考える理由に言及したことは なく,また,被告が使用する漏水探査方法の具体的内容やこれに使用する装置につ いて質問等をしたのも,平成30年2月7日付け「最後通告書」におけるものが初 めてである。加えて,本件における原告の主張立証活動,就中,原告自身が「裁判 を提訴するまで,被告の行って居る工法につては,知る由は無かった。」とし,実 際,被告が主張する被告装置の構成等を前提として主張立証を行っていることに鑑\nみると,原告は,本訴の提起に先立ち,被告の使用する漏水探査方法やこれに使用 する装置に関する調査等を自ら積極的には必ずしも行っていなかったことがうかが われる。 このような本訴の提起に至る経緯や訴訟の経過等に加え,前記のとおり,被告装 置につき本件各発明の技術的範囲に属さないことに照らすと,原告は,本訴で主張 する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであることにつき,少なく とも通常人であれば容易にそのことを知り得たのに,被告による事業展開を妨げる ことすなわち営業を妨害することを目的として,敢えて本訴を提起したものと見る のが相当である。 そうすると,原告による本訴の提起は,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相 当性を欠くものと認められるから,被告に対する不法行為を構成する。これに反す\nる原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.09.22
令和1(ワ)11673 差止請求等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和3年9月3日 東京地方裁判所
原告は,原告商品は形態1)ないし7)を組み合わせたものであり,原告 商品全体の形態と同一又は類似の商品は見当たらないから,他の同種商 品と識別し得る特徴を有すると主張する。 しかし,原告商品の販売が開始された当時,原告商品が備える形態1) ないし7)の全てを備えるブラジャー又はナイトブラが販売されていたこ とを認めるに足りる証拠はないものの,前記(1)ウ(ア)のとおり,形態1) ないし7)のうちの3つ又は4つを備える商品AないしGが存在していた。 そうすると,原告商品の販売開始時点では,既に,原告商品の形態に似 通った商品が複数販売されていたということができる。しかも,前記(ア) のとおり,原告商品の形態1)ないし7)は,いずれも他の商品とは異なる 顕著な特徴とは認められないから,当該商品には認められないが原告商 品には認められる形態上の特徴により,需要者であるブラジャー又はナ イトブラの購入に関心がある一般消費者が出所の違いを識別することが できるとはいえない。そして,形態1)ないし7)を組み合わせることによ り上記需要者の注意を特に惹くことになる事情も見当たらないことから すると,形態1)ないし7)を組み合わせた原告商品の形態が他の同種の商 品とは異なる顕著な特徴を有していると認めることはできない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 周知性について
前記(1)イ(ア)のとおり,原告商品は平成28年9月12日に販売が開始 されたところ,原告商品の形態につき周知性が確立したと原告が主張する 平成29年12月までに約1年4か月,被告商品1の販売が開始された平 成30年10月まででも約2年1か月しか経過していない。そして,前記 (1)ウ(ア)のとおり,原告商品の販売が開始される前から,原告商品が備え る形態1)ないし7)のうち複数を有するブラジャー又はナイトブラが販売さ れており,原告商品の形態が原告によって長期間独占的に利用されたとは 認められない。
・・・
商品の形態を比較した場合,問題とされている商品の形態に他 人の商品の形態と相違する部分があるとしても,当該相違部分についての 改変の内容・程度,改変の着想の難易,改変が商品全体の形態に与える効 果等を総合的に判断した上で,その相違がわずかな改変に基づくものであ って,商品の全体的形態に与える変化が乏しく,商品全体から見て些細な 相違にとどまると評価されるときには,当該商品は他人の商品と実質的に 同一の形態というべきである。
イ 被告商品1について
(ア) 前記(1)アのとおり,被告商品1は,原告商品が備える形態1)ないし7) を全て備え,別紙3比較写真目録記載の写真のとおり,全体的なデザイ ンはほぼ同一であるといえる。 被告商品1と原告商品の間には相違点1)が認められるが,別紙2原告 商品目録記載の写真のとおり,原告商品のカップ部の中央に付けられた リボンはごく小さな装飾にすぎず,そのようなリボンを取り外すという 改変については,その程度はわずかであり,着想することが困難である とはいえず,商品全体の形態に与える効果もほとんどないといえる。 また,被告商品1と原告商品の間には相違点2)が認められるが,別紙 1被告商品目録記載1の写真のとおり,左右の前身頃を構成する3枚の\n生地のうち最下部にある生地が被告商品全体に占める面積はそれほど大 きいものではなく,他の部分の布地と同系色であってレース生地の存在 が際立つものではない上,別紙3比較写真目録記載の写真のとおり,原 告商品と被告商品1とで,ナイトブラとしての機能を成り立たせるパー\nツの形状及び構成は同一といってよいことからすると,相違点2)は,需 要者であるブラジャー又はナイトブラの購入に関心がある一般消費者に 対し,原告商品よりもレース生地が比較的多いという印象を与えるにと どまるから,被告商品1の上記部分をレース生地とすることが商品全体 の形態に与える効果は小さいといえる。さらに,前記1(2)イのとおり, ブラジャーにレース生地を用いること自体ありふれた形態であり,上記 部分を無地の生地からレース生地に置き換える着想が困難であるともい えない。
そうすると,相違点1)及び2)は,いずれもわずかな改変に基づくもの であり,商品の全体的形態に与える変化は乏しく,商品全体から見て些 細な相違にとどまるといえるから,被告商品1は原告商品と実質的に同 一の形態であると認めるのが相当である。 (イ) 前記(ア)のとおり,被告商品1と原告商品は実質的に同一の形態であり, 前記前提事実(2)及び(3)アのとおり,被告商品1の販売が開始された平 成30年10月頃に先立つ平成28年9月12日に原告商品の販売が開 始されているところ,本件全証拠によっても,被告が被告商品1を独自 に開発したことをうかがわせる事情は認められないことからすると,被 告は原告商品の形態に依拠して被告商品1を作り出したと推認するのが 相当である。
(ウ) 以上によれば,被告商品1は,原告商品の「商品の形態」を「模倣し た商品」であると認められる。
・・・
また,被告商品2と原告商品の間には相違点5)が認められるが,別紙 1被告商品目録記載2の写真のとおり,被告商品2も,被告商品1と同 様,レース生地の色合いが他の部分の布地と同系色であって,レース生 地の存在が際立つものではなく,被告商品2では,被告商品1よりレー ス生地が多く用いられているものの,そのレース生地が肩紐部や背部と いった比較的注目することが多くないと考えられる部分に用いられてお り,一方で,同写真と別紙2原告商品目録記載の写真を見比べると,原 告商品と被告商品2とで,ナイトブラとしての機能を成り立たせるパー\nツの形状及び構成はほぼ同一であるといえることからすると,この改変\nが商品全体の形態に与える効果は大きくないというべきである。さらに, 前記1(2)イのとおり,ブラジャーにレース生地を用いること自体ありふ れた形態であり,被告商品2の相違点5)に係る部分を無地の生地からレ ース生地に置き換える着想が困難であるとはいえない。 被告商品2と原告商品の間には相違点6)が認められるが,ホックが4 段階であるか3段階であるかの違いにすぎず,ホックを連結する段階数 を増やすという改変を着想することは容易であり,そのような改変が商 品全体の形態に与える効果は小さいといえる。 そうすると,相違点3)ないし6)は,いずれもわずかな改変に基づくも のであり,商品の全体的形態に与える変化は大きくなく,商品全体から 見て些細な相違にとどまるといえるから,被告商品2は原告商品と実質 的に同一の形態であると認めるのが相当である。
(イ) 前記(ア)のとおり,被告商品2と原告商品は実質的に同一の形態であり, 前記前提事実(2)及び(3)イのとおり,被告商品2の販売が開始された平 成31年2月頃に先立つ平成28年9月12日に原告商品の販売が開始 されているところ,本件全証拠によっても,被告が被告商品2を独自に 開発したことをうかがわせる事情は認められないことからすると,被告 は原告商品の形態に依拠して被告商品2を作り出したと推認するのが相 当である。
・・・
不競法5条2項の侵害者が侵害行為により受けた利益の額は,侵害者の侵 害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりその製 造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額で あると解するのが相当である。 辞任前の被告訴訟代理人が作成した一覧表(甲54)によれば,被告が被\n告商品1を販売したことにより,1億5794万円の売上げがあり,商品原 価として2650万円,カード決済料金として552万7900円及び送料 原価として2650万円を要したこと,被告が被告商品2を販売したことに より,1億4254万5320円の売上げがあり,商品原価として2873 万7640円,カード決済料金として498万9086円及び送料原価とし て2391万7000円を要したことが認められる。
そして,弁論の全趣旨 によれば,上記の商品原価,カード決済料金及び送料原価は,いずれも被告 各商品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と認められる。 他方で,上記一覧表(甲54)には,被告商品1につき広告費として73\n20万5070円,人件費420万円及び販売システム費用789万700 0円,被告商品2につき広告費として7063万0834円,人件費630 万円及び販売システム費用712万7266円を要したかのような記載があ る。しかし,被告が上記広告費を支出してどのような内容の広告をしたのか, それが被告各商品に係るものであったかは,証拠上明らかではないし,上記 人件費及び販売システム費用がいかなる目的で支出されたかも証拠上明らか でないから,これらの費用は,被告各商品の製造販売に直接関連して追加的 に必要となった経費とは認められない。
したがって,被告が被告商品1を販売したことによる利益の額は9941 万2100円(=1億5794万円−2650万円−552万7900円− 2650万円)であると,被告商品2を販売したことによる利益の額は84 90万1594円(=1億4254万5320円−2873万7640円− 498万9086円−2391万7000円)であると,それぞれ認められ る。
(2) 本件訴訟に現れた全ての事情を勘案すると,本件訴訟の弁護士費用相当の 損害額は,被告商品1につき994万1210円,被告商品2につき849 万0159円と認めるのが相当である。
(3) したがって,被告が被告各商品を販売したことにより原告が被った損害額 は,合計2億0274万5063円である。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> 商品形態
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2021.09.20
令和2(行ケ)10044 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年8月30日 知的財産高等裁判所
原告は,相違点2に関し,本件審決が,1)刊行物5の記載及び脂質の大量 の摂取を控えることが健康上の技術常識であることを考慮すると,1回の「用 量」でω−6脂肪酸を40gを超えた脂質含有配合物として用いることは考 えられないから,「ω−6脂肪酸の用量は,40g以下」であること(相違点 2に係る本願発明の構成)は,刊行物5に記載自体がなくとも記載されてい\nるに等しい事項であるから,相違点2は,実質的な相違点ではないか,刊行 物5発明において,「ω−6脂肪酸の用量は,40g以下」とすることは,「用 量」の意味が,1回の「用量」や1日の「用量」であるかにかかわらず当業 者が容易になし得る技術的事項である旨判断したのは誤りである旨主張する ので,以下において判断する。
ア(ア) 刊行物5(甲24)には,1)「従来の技術」として「最近の日本人の 食生活は欧米型化が進み,肉類を中心とした食事の機会が大幅に増え, 脂肪の摂取量については一日当り40gと増加し,それに伴い,疾病の 種類も変化し,高血圧,心臓病の循環器系疾患や乳癌,大腸癌などが増 加して,こちらも欧米型化になり,大きな社会問題になっている。これ らの疾病の原因は,脂肪酸の摂取過多と考えられていた。しかし,研究 が進むにつれて,脂肪を構成する不飽和脂肪酸の種類の摂取アンバラン\nスによることが判明した。これは肉類に多く含まれるω−6脂肪酸であ るアラキドン酸から産生される2型のプロスタグランジンやロイコトリ エンなどが過剰になり,ω−3脂肪酸によって産出される3型のプロス タグランジンやロイコトリエンとのバランスがくずれる事による。」(前 記(1)エ),2)「発明が解決しようとする課題」として,「ω−6脂肪酸の 過剰摂取は,PGF2α,TXA2などの2型プロスタグランジンやロイ コトリエンの産生を促し,血小板凝集や血管収縮を起こし動脈硬化や血 栓症を誘発する。しかしω−3脂肪酸は逆に,これらの疾患を抑制した り,更に,乳癌や大腸癌の発癌率を抑えたり(・・・),癌細胞の転移能を低\n下させる(・・・)ことが報告されている。・・・気をつけなければならないの は,ω−3脂肪酸ばかりを摂取するのではなく,ω−3脂肪酸とω−6 脂肪酸をバランス良く摂取することである。しかし,前述のように現在 の日本人の食事はω−6脂肪酸の摂取に偏っている。この状態を改善す るためにω−3脂肪酸などを高濃度に濃縮して添加した食品や栄養補助 剤などが開発された。しかしこれらの製品を過度に摂取した場合,逆に ω−3脂肪酸の過剰摂取につながり新たな疾病の原因となる。そこでω −3,ω−6脂肪酸の適正な比率での摂取が必要である。」,「本発明は, ω−3脂肪酸とω−6脂肪酸をバランス良く摂取することができ,前述 の疾病の予防や改善に効果が期待されるように,脂質の脂肪酸組成を適\n正比率に調整した食品を提供することを目的とする。」(以上,前記(1)オ), 3)「課題を解決するための手段」として,「本発明の食品は,脂肪酸組成 をω−3脂肪酸とω−6脂肪酸との比が1:1〜1:5になるように調 整した高度不飽和脂肪酸を含むことを特徴とする。」,「本発明の食品の脂 肪酸組成は,ω−3脂肪酸とω−6脂肪酸との比が1:1〜1:5にな るように調整する。この範囲よりも小さいときは,ω−3脂肪酸が過剰 になり,この範囲よりも大きいときはω−6脂肪酸が過剰になってしま い,いずれの場合もω−3脂肪酸とω−6脂肪酸との摂取バランスが崩 れてしまうので好ましくない。」(以上,前記(1)カ),4)「発明の効果」 として,「本発明によれば,食品に含有される脂質のω−3,ω−6脂肪 酸の比率を適正比率である1:1〜1:5に保つように調製された食品 を提供することができるので,ω−3脂肪酸とω−6脂肪酸をバランス 良く摂取することができ,高血圧,心臓病の循環器系疾患や乳癌,大腸 癌などの疾病の予防や改善に効果が期待される。」(以上,前記(1)キ)と の記載がある。
これらの記載によれば,刊行物5には,刊行物5記載の高度不飽和脂 肪酸を含む食品(「本発明」)の技術的意義に関し,従来は,高血圧,心 臓病の循環器系疾患や乳癌,大腸癌などの疾病の原因は,脂肪酸の「摂 取過多」と考えられていたが,研究が進むにつれて,脂肪を構成する不\n飽和脂肪酸の種類の摂取アンバランスによることが判明したこと,現在 の日本人の食事はω−6脂肪酸の摂取に偏っており,この状態(ω−6 脂肪酸の「過剰摂取」)を改善するためにω−3脂肪酸などを高濃度に濃 縮して添加した食品や栄養補助剤などが開発されたが,これらの製品を 過度に摂取した場合,逆にω−3脂肪酸の「過剰摂取」につながり新た な疾病の原因となるため,ω−3,ω−6脂肪酸の適正な比率での摂取 が必要であることから,「本発明」は,ω−3脂肪酸とω−6脂肪酸をバ ランス良く摂取することができ,前述の疾病の予防や改善に効果が期待\nされるように,脂質の脂肪酸組成を適正比率に調整した食品を提供する ことを目的とし,その課題を解決するための手段として,脂肪酸組成を ω−3脂肪酸とω−6脂肪酸との比が1:1〜1:5になるように調整 した高度不飽和脂肪酸を含む構成を採用し,これによりω−3脂肪酸と\nω−6脂肪酸をバランス良く摂取することができ,高血圧,心臓病の循 環器系疾患や乳癌,大腸癌などの疾病の予防や改善の効果が期待される\nことについての開示があることが認められる。また,前記(1)の刊行物5 の記載によれば,刊行物5において,「過剰摂取」の用語は,ω−3脂肪 酸,ω−6脂肪酸が適正比率(1:1〜1:5)の範囲を基準として, 「この範囲よりも小さいときは,ω−3脂肪酸が過剰になり,この範囲 よりも大きいときはω−6脂肪酸が過剰にな」ると述べていること(前 記(1)カ)に照らすと,ω−3脂肪酸とω−6脂肪酸との摂取バランス(比 率)が崩れた状態を表現するために用いており,一方で,「摂取量」が多\nい状態を表現するときは「摂取過多」の用語を用い,「摂取量」との関係\nでは,「過剰摂取」の用語を用いていないことが認められる。 以上を前提に検討すると,刊行物5における「最近の日本人の食生活 は欧米型化が進み,肉類を中心とした食事の機会が大幅に増え,脂肪の 摂取量については一日当り40gと増加し,それに伴い,疾病の種類も 変化し,高血圧,心臓病の循環器系疾患や乳癌,大腸癌などが増加して, こちらも欧米型化になり,大きな社会問題になっている。」との記載は, それに引き続き「しかし,研究が進むにつれて,脂肪を構成する不飽和\n脂肪酸の種類の摂取アンバランスによることが判明した。」などの記載が あることに照らすと,「脂肪の摂取量」が「一日当り40g」に増加した こと自体が問題であることを述べたり,それを改善すべきことを示唆す るものではないと理解するのが自然である。 また,刊行物5の記載全体をみても,刊行物5において,脂肪の摂取 量を1日当たり40gに差し控えるべきことや,「ω−6脂肪酸の用量」 は,1日又は1回当たり「40g以下」とすべきことについての記載や 示唆はない。
(イ) 次に,本件審決が述べるように「脂質の大量の摂取を控えること」 自体が健康上の技術常識であるといえるとしても,脂質の適正な摂取量 は,年齢,性別,エネルギー摂取量等の要素によって変わり得るものと 考えられるから,そのことから直ちに「脂肪の摂取量」を1日当り40 g以下とすることが技術常識であることを導出することはできないし, それが技術常識であることを前提に「ω−6脂肪酸の用量」は,1日又 は1回当たり「40g以下」とすることが技術常識であるということは できない。本件においては,他に「ω−6脂肪酸の用量は,40g以下」 とすることが技術常識であることを認めるに足りる証拠はない。 イ(ア) 前記アの認定を総合すると,刊行物5には,本件審決のいう技術常 識を踏まえても,刊行物載5発明に含有する「ω−6脂肪酸の用量は, 40g以下であること」についての実質的な開示があるものと認めるこ とはできない。 そうすると,刊行物5発明が「ω−6脂肪酸の用量は,40g以下」 であるとの構成(相違点2に係る本願発明の構\成)を有することは認め られないから,相違点2は実質的な相違点であるものと認められる。 これと異なる本件審決の判断は誤りである。
(イ) 次に,前記ア認定のとおり,刊行物5には,脂肪の摂取量を1日当 たり40gに差し控えるべきことや,「ω−6脂肪酸の用量」は,1日又 は1回当たり「40g以下」とすべきことについての記載や示唆はなく, また,「ω−6脂肪酸の用量は,40g以下」とすることが技術常識であ ることを認めるに足りる証拠がないことに照らすと,刊行物5に接した 当業者が,刊行物5発明において,相違点2に係る本願発明の構成を採\n用することの動機付けがあるものと認めることはできないから,上記構\n成とすることを容易に想到することができたものと認められない。 これと異なる本件審決の判断は誤りである。
ウ これに対し被告は,1)刊行物5には,脂肪の摂取量については1日当た り40gと増加しているとの記載及びそれを問題であると認識している ことの記載があり,刊行物5発明は,脂質(脂肪)の取り過ぎの抑制を前 提に,ω−6脂肪酸とω−3脂肪酸をバランス良く摂取することを技術思 想とする発明であるから,脂質の一部である不飽和脂肪酸のさらに一部で あるω−6脂肪酸を一定以下に抑えることは当然であり,脂質全体として 取り過ぎであるとの認識である40gという値以下と特定することには 強い動機付けがある,2)しかも,1日の脂質摂取は,刊行物5発明のドリ ンク剤組成物以外の食品からも生じるのであるから,1日又は1回当たり ω−6脂肪酸40g以下との上限を設定することは,当業者が容易になし 得る技術的事項であるから,当業者は,刊行物5発明において,相違点2 に係る本願発明の構成とすることを容易に想到することができた旨主張\nする。
しかしながら,前記ア(ア)で説示したとおり,刊行物5における「最近の 日本人の食生活は欧米型化が進み,肉類を中心とした食事の機会が大幅に 増え,脂肪の摂取量については一日当り40gと増加し,それに伴い,疾 病の種類も変化し,高血圧,心臓病の循環器系疾患や乳癌,大腸癌などが 増加して,こちらも欧米型化になり,大きな社会問題になっている。」との 記載は,「脂肪の摂取量」が「一日当り40g」に増加したこと自体が問題 であることを述べたり,それを改善すべきことを示唆するものではない。 また,刊行物5の記載全体をみても,刊行物5において,脂肪の摂取量 を1日当たり40gに差し控えるべきことや,「ω−6脂肪酸の用量」は, 1日又は1回当たり「40g以下」とすべきことについての記載や示唆は ない。 加えて,本件においては,他に「ω−6脂肪酸の用量は,40g以下」 とすることが技術常識であることを認めるに足りる証拠はない。 したがって,刊行物5に接した当業者が刊行物5発明において相違点2 に係る本願発明の構成を採用することの動機付けがあるものと認めるこ\nとはできないから,被告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.09.18
令和2(ワ)4332 特許権侵害行為差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年8月20日 東京地方裁判所
上記認定事実のとおり,被告ジョウズ及び被告アンカーは,いずれもAn kerグループに属する法人であり,被告ジョウズの設立時の代表者と被告\nアンカーの代表者は同一である上,被告ジョウズの令和元年9月時点での従\n業員数は2名であり,そのうちの1名であるZは令和元年5月に被告アンカ ーから被告ジョウズに移籍しているとの事実が認められる。また,被告ジョ ウズの本店所在地のオフィスの利用契約上の地位は被告アンカーから譲り受 けたものであるなど,両社には密接な人的及び物的な関係があるということ ができる。
また,被告ジョウズは被告製品1及び2の販売に関する記者発表が行われ\nる約4か月前に設立されているが,その人的態勢は,代表者であるYのほか\n従業員が2名にすぎず,その2名についても,令和元年9月1日から同月3 0日までの1人当たりの勤務日数及び勤務時間は通常の事業活動をしている とは考え難いほど短い。また,被告ジョウズのオフィスはシェアオフィスで あり,平成30年10月時点において,同オフィスの入居するビル1階の受 付には被告ジョウズの表示はなかったことなどによれば,被告ジョウズが被\n告製品に関する実質的な事業活動を行っていたとは考え難い。 さらに,上記のとおり,楽天における被告製品の販売サイトにおける商品 の返送先住所は被告アンカーの所在地と同じビルであると認められるところ, 被告ジョウズが被告アンカーに対して返品された商品の取扱いを委託すると ともに,マーケティング業務などを委託していたことについては当事者間に 争いがない。被告らは,被告アンカーが受託したのは上記業務に限定される と主張するが,マーケティング業務も行いながら,商品については返品取扱 い業務のみを取り扱っていたとは考え難く,上記の被告ジョウズの物的・人 的態勢も考慮すると,被告アンカーは被告製品の販売等に関する業務を被告 ジョウズと共同して行っていたと推認することが相当である。
加えて,被告製品1及び2の記者発表に関する記事等には,「Anker\nグループが技術的にサポートしたことから,アンカー・ジャパンのY社長が ジョウズ・ジャパンの代表取締役を兼任する」などと記載されていること,\n被告製品3の記者発表は当時まだ被告アンカーの在籍していたZが行ってい\nること,被告商品に関するウェブページには,同製品がAnkerグループ ないし中国アンカー社のサポートを受けて作られたものである旨の説明がさ れていること,Ankerグループのオフィシャルストアの海外のウェブサ イトにおいて被告製品が「Anker Jouz 20」などとして販売さ れていることなどの事実によれば,被告製品に関する事業には,被告アンカ ーを含むAnkerグループや中国アンカー社が関与していることがうかが われる。 以上を総合すると,被告アンカーが被告ジョウズと共同して被告製品の販 売等をしていたと認めるのが相当である。
(3) 被告らの主張について
ア これに対し,被告らは,被告製品に関する業務の委託先の一つにすぎず, 被告製品の返品及びマーケティング業務等の委託を受けていただけであ り,業務委託の対価も固定額であり,被告製品の販売実績によって金額が 左右されるものではないと主張する。
しかし,被告らからは,被告アンカーから被告ジョウズに宛てた業務委 託料の請求書や担当者名等が黒塗りされた請求書や電子メール等が提出 されているにとどまり,被告ジョウズと被告アンカーとの間の業務委託契 約書,被告製品に関する費用や利益の帰属を示す客観的な証拠,被告アン カーが行っていた業務の実態やこれに関与した者の氏名や具体的な役割 等を客観的かつ具体的に明らかにする証拠は提出されていない。 前記判示のとおり,被告ジョウズと被告アンカーの人的・物的関係や被 告ジョウズの実態などを考慮すると,被告アンカーは被告ジョウズから一 部の業務を受託していたにとどまらず,被告製品の販売等に関する業務を 同被告と共同して行っていたと推認することが相当であり,これを覆すに 足りる的確な証拠は存在しない。したがって,被告らの上記主張は理由がない。
イ 被告らは,被告ジョウズと被告アンカーには資本関係がなく,取扱製品 も異なる上,代表取締役自らが営業等を行っている会社は多数存在し,商\n品開発において他社と協力することも通常の事業活動にすぎないので,被 告らに相互に相手方の役割等を認識し,これを利用する意思はなかったと 主張する。
しかし,両社はいずれもAnkerグループに属する法人であり,被告 ジョウズの設立時の代表者と被告アンカーの代表\者は同一である上,被告 ジョウズは本店所在地のオフィスの利用契約上の地位を被告アンカーか ら譲り受けるなど,両社には密接な人的及び物的な関係があることは前記 判示のとおりである。また,被告ジョウズの実態などを考慮すると,被告 アンカーが返品処理業務やマーケティングなど一部の業務を受託してい たにとどまらず,被告製品の販売等に関する業務を被告ジョウズと共同し て行っていたと評価し得ることも上記のとおりである。 したがって,被告らの上記主張は理由がない。
(4) 以上によれば,被告アンカーは,被告ジョウズと共同して,被告製品の販 売,輸入及び販売の申出をしてきたと認められる。\n
◆判決本文
関連事件です。
◆令和1(行ケ)10174
下記はアップされていません。
令和1年(ワ)20075特許権侵害差止請求事件
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.09.18
令和2(行ケ)10132 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年8月31日 知的財産高等裁判所
発明の効果が予測できない顕著なものであるかについては,当該発明の\n特許要件判断の基準日当時,当該発明の構成が奏するものとして当業者が\n予測することのできなかったものか否か,当該構\成から当業者が予測する\nことのできた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点か ら検討する必要がある(最高裁判所平成30年(行ヒ)第69号令和元年 8月27日第三小法廷判決・集民262号51頁参照)。もっとも,当該発 明の構成のみから予\測できない顕著な効果が認められるか否かを判断す ることは困難であるから,当該発明の構成に近い構\成を有するものとして 選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同 種の効果を参酌することは許されると解される。 前示のとおり,本件発明の構成は容易想到であるが,これに対し,被告\nは,前記第3の3(2)イのとおり,本件発明は,本件3条件を全て満たす患 者に対する顕著な骨折抑制効果(以下「効果1)」という。),2)本件条件(4) を満たす患者に対する副作用発現率と血清カルシウムに関する安全性が 腎機能が正常である患者に対する安全性と同等であるという効果(以下\n「効果2)」という。)及び3)BMD増加率が低くてもより低い骨折相対リス クが得られるとの効果(以下「効果3)」という。)を奏し,これらの効果は, 当業者が予測をすることができなかった顕著な効果を奏するものである\n旨主張する。 以下,これらの効果について検討する。
(ア) 効果1)について
a 前記イ(イ)のとおり,骨粗鬆症は,骨強度の低下を特徴とし,骨折 の危険性が増大した骨疾患であり,骨粗鬆症の治療の目的は骨折を予\n防することであり,「骨強度」は骨密度と骨質の2つの要因からなり, 骨密度は骨強度のほぼ70%を説明するとの技術常識があったから, 当業者は,骨密度の増加は,骨折の予防に寄与すると理解するところ,\n甲7文献には,「ここに挙げた薬剤を投与することによって骨密度(B MD)が増加するため,骨折予防は飛躍的に進歩した」(296頁右欄\n10行ないし297頁左欄25行目)と骨密度の増加が骨折予防に寄\n与することが記載され,その上で,48週で骨密度を8.1%増大させ たことが開示されている(300頁左欄11行ないし右欄6行目)。そ うすると,甲7発明の骨粗鬆症治療剤が骨折を抑制する効果を奏して いることは,当業者において容易に理解できる。 b 効果1)の骨折抑制効果とは,単なる骨折発生率の低減ではなく,プ ラセボの骨折発生率と対比した場合の骨折発生率の低下割合を指すも のであるが,本件明細書の記載からでは,本件3条件を全て満たす患 者と定義付けられる高リスク患者に対する骨折抑制効果が,本件3条 件の全部又は一部を欠く者と定義付けられる低リスク患者に対する骨 折抑制効果よりも高いということを理解することはできない。 すなわち,効果1)を確認するためには,高リスク患者に対する骨折 抑制効果と低リスク患者に対する骨折抑制効果とを対比する必要があ るが,前記1のとおり,本件明細書には,実施例1において,高リス ク患者では,100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体 以外の部位の骨折発生率は,いずれも実質的なプラセボである5単位 週1回投与群における発生率に対して有意差が認められるが,低リス ク患者では,100単位週1回投与群における新規椎体骨折及び椎体 以外の部位の骨折の発生率は,いずれも,5単位週1回投与群におけ る発生率に対して有意差が認められなかったと記載されているのにと どまる(【0086】ないし【0096】,【表6】ないし【表\11】)。
ここで,低リスク患者の新規椎体骨折についていえば,100単位 週1回投与群11人と5単位週1回投与群10人(令和3年2月15 日付け被告第1準備書面32頁における再解析の数値による。)につい て,それぞれ,ただ1人の骨折例数があったというものであり,また, 椎体以外の部位の骨折は,上記5単位週1回投与群について,ただ1 人の骨折例数があったというものであって,有意差がなかったことが, 症例数が不足していることによることを否定できない。このように, 低リスク患者において,100単位週1回投与群の新規椎体骨折及び 椎体以外の部位の骨折の発生率が5単位週1回投与群のそれらの発生 率に対して有意差がなかったとの結論が,上記のような少ない症例数 を基に導かれたことからすると,高リスク患者における骨折発生の抑 制の程度を低リスク患者における骨折発生の抑制の程度と比較して, 前者が後者よりも優れていると結論付けることはできない。 したがって,実施例 1 をみても,高リスク患者に対するPTHの骨 折抑制効果が,低リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高 いということを理解することはできず,さらに,本件明細書のその他 の部分をみても,高リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果が,低 リスク患者に対するPTHの骨折抑制効果よりも高いということを理 解することはできず,ましてや,200単位週1回投与群に関し,高 リスク患者における骨折発生抑制が,低リスク患者における骨折発生 抑制よりも優れていると結論付けることはできない。 以上によれば,効果1)は,本件明細書の記載に基づかないものとい うべきである。
◆判決本文
当事者が同じ分割出願についての関連事件です。審決取り消しです。
◆令和2(行ケ)10056
こちらは審決維持です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2021.09. 8
平成28(行ケ)10257 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月19日 知的財産高等裁判所
原告は,本件発明特定事項の機能Aは,当業者によって,本件明細書の\n段落【0117】,段落【0118】,段落【0120】及び段落【0143】な どの記載を総合することにより導かれると主張する。
しかし,段落【0117】は,ウェブサーバから画像データファイル をダウンロードすることについての記載ではなく,ウェブページを閲覧する場合 についての記載であり,同段落の「ページ画像」とは,ウェブページをブラウザで 表示した画像であって,画像データをデータファイルとしてダウンロードする場合\nに関する記載ということはできない。 また,同段落には,閲覧しているウェブページがLCDパネル15Aの画面水平 解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用する場合に,中央演算回路1_10A1 が,その固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成し,VRA M1_10Cに書き込むとともに,グラフィックコントローラ1_10Bが,LCD パネル15Aの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを切 り出してLCDドライバ15Bに送信することが記載されているが,「その結果と して,LCDパネル15Aにおいてページ画像がスクロール表示される。」のであ\nり,LCDドライバ15Bに送信される信号は,画像の一部分に対応するビットマ ップデータの信号であるから,この場合には,本来解像度がディスプレイパネルの 画面解像度より大きい画像から,ディスプレイパネルの画面解像度と同じ画像への 解像度の変更が行われているということはできない。 次に,段落【0118】に記載されている事項は,携帯電話機1がテレビ番組の 視聴用に使用される場合のグラフィックコントローラ1_10BやVRAM1_10 C等の機能であり,携帯電話機1により表\示される「画像」は,テレビ受信用アン テナ112Aで受信した「テレビ番組の画像」であるから,画像データをデータフ ァイルとしてダウンロードする場合とは異なるというべきである。 そして,段落【0143】には,段落【0117】,【0118】に記載されてい るような,ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記\n載はない上,段落【0143】の記載は前記のとおりであって,画像データファイ ルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから,段落【014\n3】の記載に接した当業者が,その記載を段落【0117】,段落【0118】の記 載と関連付けて,ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を 表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解する\nとは考えられない。
(イ) 段落【0120】には,「デジタル音声信号及び/又はデジタル動画 信号をデータファイルに変換して保存したり,該保存したデータファイルを読み出 して必要な処理を行う」,「画像データファイル及び/又は音声データファイルは, ウェブサイトにアクセスし,・・・受信・変換されたデジタル信号を,バス19経由で 中央演算回路1_10A1が受信し,必要な変換を行ってフラッシュメモリ14A に書き込むことによっても保存することができる。」との記載があるが,段落【01 20】には,受信した「デジタル音声信号及び/又はデジタル動画信号」を携帯電 話1においてデータファイルに変換して保存したり,それを読み出して再生する ことが記載されているにすぎず,この記載と前記のような内容の段落【0143】 の記載を併せて見たとしても,当業者が,ウェブサーバから本来解像度が携帯電話 機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロー ドして画像を表示する場合に,VRAMからディスプレイパネルの画面解像度と同\nじ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し,読み出したビットマップ データを伝達するデジタル表示信号を生成し,これをディスプレイ制御手段に送信\nする機能を想起するとは考えられない。\n
(ウ) そうすると,原告の主張する本件明細書の各記載を総合しても,訂 正事項7に係る「前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプレイパネルの画面 解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像を表示する場合\nに,前記VRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有す る画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出されたビットマップデータ を伝達するデジタル表示信号」を生成し,該デジタル表\示信号を前記ディスプレイ 制御手段に送信する機能」が導かれるとは認められず,本件明細書には他に同機能\ の実現についての記載又は示唆は存在しない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2021.09. 8
平成25(行ケ)10346 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年10月9日 知的財産高等裁判所
本件特許明細書には,【0041】に,中立線 を残して,その両側に溝を形成し,音叉腕の中立線を含めた部分幅W7は 0.05mmより小さく,また,各々の溝の幅は0.04mmより小さくな るように構成する態様,及び,このような構\成により,M1をMnより大きく することができることが記載されている。また,【0043】には,溝が中 立線を挟む(含む)ように音叉腕に設けられている第1実施例〜第4実施例 の水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動で の容量比r1が2次高調波モード振動の容量比r2より小さくなるように構成\nされていること,及び,このような構成により,同じ負荷容量CLの変化に\n対して,基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が2次高調波 モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記載さ れている。 しかし,上記【0041】と【0043】の各記載に係る構成の態様は,\nそれぞれ独立したものであるから,そこに記載されているのは,各々独立し た技術的事項であって,これらの記載を併せて,本件追加事項,すなわち, 「中立線を残してその両側に,前記中立線を含めた部分幅が0.05mmよ り小さく,各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝が形成され た場合において,基本波モード振動の容量比r1が2次高調波モード振動の 容量比r2より小さく,かつ,基本波モードのフイガーオブメリットM1が高 調波モード振動のフイガーオブメリットMnより大きい」という事項が記載 されているということはできない。また,その他,本件特許明細書等の全て においても,本件追加事項について記載はないし,本件追加事項が自明の技 術的事項であるということもできない。 そうすると,本件追加事項の追加は,本件特許明細書等の全ての記載を総 合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項 を導入するものというべきである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2021.09. 8
令和1(ワ)30991 特許権侵害差止等請求事件 令和3年3月30日 東京地方裁判所
なお、原告の査証命令申立てについては却下されました。\n
前記(2)に説示したとおり,前記第2の1(4)アの出願当初の請求項1及び 2の記載からすれば,本件特許に係る特許出願当初の請求項1及び2の記載 は,HFO−1234yfに対する「追加の化合物」を多数列挙し,あるい は当該「追加の化合物」に「約1重量パーセント未満」という限定を付すに とどまり,上記のとおり多数列挙された化合物の中から,特定の化合物の組 合せ(HFO−1234yfに,HFO−1243zfとHFC−245c bとを組み合わせること)を具体的に記載するものではなかったというべき である。
しかして,上記(3)の当初明細書の各記載について見ても,特許出願の当 初の請求項1と同一の内容が記載され(【0004】),新たな低地球温暖化 係数(GWP)の化合物であるHFO−1234yf等を調製する際に,H FO−1234yf又はその原料(HCFC−243db,HCFO−12 33xf,及びHCFC−244bb)に含まれる不純物や副生成物が特定 の「追加の化合物」として少量存在することが記載されており(【0003】, 【0016】,【0019】,【0022】),具体的には,HFO−1234y fを作製するプロセスにおいて,有用な組成物(原料)がHCFC−243 db,HCFO−1233xfおよび/またはHCFC−244bbである ことが記載され(【0005】),HCFC−243db,HCFO−123 3xf及びHCFC−244bbに追加的に含まれ得る化合物が多数列挙さ れてはいる(【0006】ないし【0008】)ものの,そのような記載にと どまっているものである。
そして他方,当初明細書においては,そもそもHFO−1234yfに対 する「追加の化合物」として,多数列挙された化合物の中から特に,HFO −1243zfとHFC−245cbという特定の組合せを選択することは 何ら記載されていない。この点,当初明細書においては,HFO−1234 yf,HFO−1243zf,HFC−245cbは,それぞれ個別に記載 されてはいるが,特定の3種類の化合物の組合せとして記載されているもの ではなく,当該特定の3種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載され ているものでもない。また,表6(実施例16)については,8種類の化合\n物及び「未知」の成分が記載されているが,そのうちの「245cb」と 「1234yf」に着目する理由は,当初明細書には記載されていない。さ らに,当初明細書には,特許出願当初の請求項1に列記されているように, 表6に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず,\nその中から特にHFO−1243zfだけを選び出し,HFC−245cb 及びHFO−1234yfと組み合わせて,3種類の化合物を組み合わせた 構成とすることについては,当業者においてそのような構\成を導き出す動機 付けとなる記載が必要と考えられるところ,そのような記載は存するとは認 められない(なお,本件特許につき,優先権主張がされた日から特許出願時 までの間に,上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足 りる証拠はない。)。
これらに照らせば,当業者によって,当初明細書,特許請求の範囲又は図 面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては,低地球 温暖化係数(GWP)の化合物であるHFO−1234yfを調製する際に, HFO−1234yf又はその原料(HCFC−243db,HCFO−1 233xf,及びHCFC−244bb)に含まれる不純物や副反応物が特 定の「追加の化合物」として少量存在する,という点にとどまるものという ほかなく,その開示は,発明というよりはいわば発見に等しいような性質の ものとみざるを得ないものである。そして,当初明細書等の記載から導かれ る技術的事項が,このような性質のものにすぎない場合において,多数の化 合物が列記されている中から特定の3種類の化合物の組合せに限定した構成\nに補正(本件補正)することは,前記のとおり,そのような特定の組合せを 導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たら ないことに鑑み,当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するもの と評価せざるを得ない。したがって,本件補正は,当初明細書等の記載から 導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したもので あるというほかない。
以上によれば,本件補正は「願書に最初に添付した明細書,特許請求の範 囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしたものということはできず, 特許法17条の2第3項の補正要件に違反してされたものというほかなく, 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められ(特許法 123条1項1号),同法104条の3第1項により,特許権者たる原告は, 被告に対しその権利を行使することができないこととなる。
・・・
原告は,令和2年10月19日,原告主張製品のうち,被告から原告に対 し販売された最終製品以外のものに含まれるHFO−1234yf,HFO −1243zf,HFC−245cb及びHFO1234zeの含有量を立 証すべき事項として,査証命令の申立てをした(当庁令和2年(モ)第267 4号)。
(2) しかしながら,前記のとおり,本件特許は特許無効審判により無効にされ るべきものと認められるのであって,原告主張製品であれ,被告主張製品で あれ,対象製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かを問わず,原告は被 告に対し,本件特許権を行使することができないものである。そうすると, 当裁判所としては,本件訴訟において,原告の請求に理由があるかを判断す るために,上記の立証すべき事項たる事実を判断する必要がないものといわ ざるを得ず,ひいては,同事実を判断するため,上記査証命令申立てにより\n得られる証拠を取り調べることが必要であるとも認められない。 以上によれば,上記査証命令の申立ては,必要でない証拠の収集を求める\nものであり,その必要性を欠くものというべきであるから,原告の上記査証 命令申立ては,これを却下することとする。\n
関連カテゴリー
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.09. 2
令和2(行ケ)10126 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年8月30日 知的財産高等裁判所
本願商標の商標法4条1項8号該当性について
原告は,1)本願商標の出願当時,本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」\nという言語的要素からなる音から,通常,容易に連想,想起するのは,ドラ ッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」又は企業名としての株式会社 マツモトキヨシ,株式会社マツモトキヨシホールディングス(原告)であっ て,「マツモトキヨシ」と読まれる人の氏名であるとはいえないから,本願 商標を構成する「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音は,「マツ\nモトキヨシ」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものではない, 2)したがって,本願商標は,「他人の氏名」を含む商標であるとはいえない から,本願商標が商標法4条1項8号に該当するとした本件審決の判断は誤 りである旨主張するので,以下において判断する。
(1)商標法4条1項8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称 等を含む商標は,その承諾を得ているものを除き,商標登録を受けること ができないと規定した趣旨は,人は,自らの承諾なしに,その氏名,名称 等を商標に使われることがないという人格的利益を保護することにある ものと解される(最高裁平成15年(行ヒ)第265号同16年6月8日 第三小法廷判決・裁判集民事214号373頁,最高裁平成16年(行ヒ) 第343号同17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号59 5頁参照)。 このような同号の趣旨に照らせば,音商標を構成する音が,一般に人の\n氏名を指し示すものとして認識される場合には,当該音商標は,「他人の 氏名」を含む商標として,その承諾を得ているものを除き,同号により商 標登録を受けることができないと解される。 また,同号は,出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名,名称等に 係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり,音商標を構成する音と同\n一の称呼の氏名の者が存在するとしても,当該音が一般に人の氏名を指し 示すものとして認識されない場合にまで,他人の氏名に係る人格的利益を 常に優先させることを規定したものと解することはできない。 そうすると,音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在すると\nしても,取引の実情に照らし,商標登録出願時において,音商標に接した 者が,普通は,音商標を構成する音から人の氏名を連想,想起するものと\n認められないときは,当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識 されるものといえないから,当該音商標は,同号の「他人の氏名」を含む 商標に当たるものと認めることはできないというべきである。
(2)ア これを本願商標についてみるに,前記2の認定事実によれば,1)株式 会社マツモトキヨシが昭和62年にドラッグストア「マツモトキヨシ」 の店舗展開を開始した後,平成29年1月30日に本願の出願がされる までの約30年以上にわたり,株式会社マツモトキヨシ,原告及び原告 のグループ会社が,「マツモトキヨシ」の表示をドラッグストアの店名\n又は自己の企業名として継続して使用したこと,2)同年3月31日現在 で,ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店舗数は,全国45都道府県 で1555店舗,原告のグループ会社のメンバーズカード(ポイントカ ード)の会員数は約2440万人に達しており,また,「マツモトキヨ シ」のブランドは,インターブランド社による2016年度及び201 7年度のブランド価値評価ランキングでドラッグストアとして日本で ナンバーワンブランドの評価を獲得したこと,3)平成8年から開始され たドラッグストア「マツモトキヨシ」のテレビコマーシャルでは,女性 又は男性の声の音色,複数の声の斉唱で本願商標と同一又は類似の音を フレーズに含むコマーシャルソングが相当数使用され,テレビコマーシ\nャルが放映された以降においても,本願商標と同一又は類似の音がドラ ッグストア「マツモトキヨシ」の各小売店の店舗内において使用されて いたことが認められる。 これらの認定事実によれば,本願商標に関する取引の実情として,「マ ツモトキヨシ」の表示は,本願商標の出願当時(出願日平成29年1月\n30日),ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店名や株式会社マツモ トキヨシ,原告又は原告のグループ会社を示すものとして全国的に著名 であったこと,「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む本願商標と 同一又は類似の音は,テレビコマーシャル及びドラッグストア「マツモ トキヨシ」の各小売店の店舗内において使用された結果,ドラッグスト ア「マツモトキヨシ」の広告宣伝(CMソングのフレーズ)として広く\n知られていたことが認められる。
イ 前記アの取引の実情の下においては,本願商標の登録出願当時(出願 日平成29年1月30日),本願商標に接した者が,本願商標の構成中\nの「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から,通常,容易に 連想,想起するのは,ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」, 企業名としての株式会社マツモトキヨシ,原告又は原告のグループ会社 であって,普通は,「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」,「松本 潔」,「松本清司」等の人の氏名を連想,想起するものと認められない から,当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものと はいえない。 したがって,本願商標は,商標法4条1項8号の「他人の氏名」を含 む商標に当たるものと認めることはできないというべきである。
(3)ア これに対し被告は,1)ウェブサイト(乙4ないし7)には,原告とは 他人の「松本清」,「松本潔」,「松本清司」等の氏名表示のひとつと\nして,「マツモトキヨシ」の片仮名が表記されており,かつ,これらの\n者は,現存していると推認できること,各地域のハローページ(乙8な いし19)には,「マツモトキヨシ」と読まれる人の氏名として,原告 とは他人の「松本清」,「松本潔」等が掲載されており,かつ,これら の者は,いずれも本願商標の登録出願時から現在まで存在している者で あると推認できること,氏名を片仮名表記することは,各種の商取引に\nおいて,社会一般に行われていること(乙20ないし28)からすると, 本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音は,\n「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」,「松本潔」,「松本清司」 等の人の氏名を容易に連想,想起させるものであり,「マツモトキヨシ」 と読まれる人の氏名として客観的に把握されるものである,2)原告の提 出に係るテレビコマーシャルに関する証拠からは,当該テレビコマーシ ャルの規模が明らかでなく,平成19年以降の放映も確認できないから, 当該テレビコマーシャルが本願商標の音を聞いた者の認識に与える影 響は限定的であること,当該テレビコマーシャルを視聴した者は,視覚 的要素とともに「マツモトキヨシ」の言語的要素からなる音を聴取,把 握し,記憶するものといえるので,当該テレビコマーシャルは,本願商 標に接した者が,「マツモトキヨシ」の言語的要素からなる音を,マツ モトを姓とし,キヨシを名とする人の氏名であると認識することなく, 店舗名又は企業名としてのみ認識することの根拠たり得ないこと,原告 の挙げるブランド価値ランキングは,本願商標の音を聞いた者の認識を 直接反映したものとはいい難く,このほか,「マツモトキヨシ」という 言語的要素からなる音がドラッグストアの店名又は企業名としてのみ 認識されることを裏付ける証拠はないことからすると,1)のとおり,上 記言語的要素からなる音が,「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」, 「松本潔」,「松本清司」等の人の氏名として客観的に把握されること を否定することはできないとして,本願商標は,商標法4条1項8号の 「他人の氏名」を含む商標に当たる旨主張する。 しかしながら,前記(2)ア認定のとおり,「マツモトキヨシ」の表\n示は,本願商標の出願当時,ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店名 や株式会社マツモトキヨシ,原告又は原告のグループ会社を示すものと して全国的に著名であり,「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む 本願商標と同一又は類似の音は,テレビコマーシャル及びドラッグスト ア「マツモトキヨシ」の各小売店の店舗内において使用された結果,ド ラッグストア「マツモトキヨシ」の広告宣伝(CMソングのフレーズ)\nとして広く知られていたという取引の実情を踏まえると,本願商標に接 した者が,本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素か\nらなる音から,通常,容易に連想,想起するのは,ドラッグストアの店 名としての「マツモトキヨシ」,企業名としての株式会社マツモトキヨ シ又は原告のグループ企業であって,普通は,「マツモトキヨシ」と読 まれる「松本清」,「松本潔」,「松本清司」等の人の氏名を連想,想 起するものと認められない。
また,甲43によれば,上記テレビコマーシャルの規模は首都圏を中心 にドラッグストア「マツモトキヨシ」の出店のある全国の地域に及んでい たことが認められる上,上記テレビコマーシャルの放映後も,上記テレビ コマーシャルで使用された本願商標と同一又は類似の音がドラッグスト ア「マツモトキヨシ」の各小売店の店舗内で使用されていたものと認めら れるから,当該テレビコマーシャルが本願商標を聞いた者の認識に与える 影響が限定的であるということはできないし,上記テレビコマーシャルが 視覚的要素を伴うことも,上記認定を左右するものではない。 さらに,前記(1)で説示したとおり,同号は,出願人の商標登録を受 ける利益と他人の氏名,名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定 であり,当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合 にまで,他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したも のと解することはできないことに鑑みると,本願商標に接した者が,「マツ モトキヨシ」の言語的要素からなる音をドラッグストアの店名又は企業名 としてのみ認識することがない以上は,本願商標が同号の「他人の氏名」 を含む商標に該当するとの解釈は妥当とはいえない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
イ 次に,被告は,本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要\n素からなる音が,「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」,「松本潔」,「松 本清司」等の人の氏名として客観的に把握され,本願商標は「他人の氏名」 を含む商標である以上,商標法4条1項8号の趣旨に照らせば,上記言語 的要素からなる音が,原告又は株式会社マツモトキヨシが経営するドラッ グストアを指し示すものとして一定程度知られていることや,特定の者の 略称として一定の著名性を有することは,本願商標の同号該当性を左右す るものではない旨主張する。 しかしながら,前記アで説示したとおり,本願商標は「他人の氏名」を 含む商標であるとはいえないから,被告の上記主張は,その前提を欠くも のであり,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2021.08.30
令和3(行ケ)10031 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年8月19日 知的財産高等裁判所
前記2(1)のとおり,本件商標と引用商標1及び2は,外観及び称呼にお いて明らかに相違するものであるから,引用商標と同一又は類似である原 告使用商標も,本件商標とは非類似の商標であるといえる。
もっとも,本件商標が原告商標と非類似の商標であっても,その商品の 出所について混同を生じるおそれがある商標については,商標法4条1項 15号に規定する商標に当たる余地もあり得るので,以下,念のためこの 点についても検討する。
イ 前記2(1)アのとおり,本件商標の取引者及び需要者は,先発医薬品につ いては,医師,薬剤師等の医療関係者であり,一般用医薬品及び医薬部外 品については,薬剤師等のほか,一般消費者も含まれることになる。 そして,仮に原告使用商標が周知著名であるとしても,原告使用商標は 「Hirudoid」又は「ヒルドイド」として認知されているのであっ て,「Hirudo」又は「ヒルド」として認知されているわけではなく, また,本件全証拠を精査しても,薬剤の取引の分野において,販売名の語 頭3文字に略して取引されているといった取引の実情を認めるに足りる 証拠はないことからすると,一般消費者を含む取引者及び需要者において 普通に払われる注意力を基準としても,本件商標を付した一般用医薬品又 医薬部外品について,原告が製造販売したものであり,又は原告と経済的 若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの ようにその商品の出所について混同を生じる恐れがあるものと認めるこ とはできない。 なお,前示のとおり,本件商標は先発医薬品にも使用されることもあり 得るところ,その取引者及び需要者は,医療関係従事者であり,薬効も原 告使用商標に付される原告商品と異なるものであるから,その商品の出所 について混同を生じるおそれがあるといえないことはなおさら明らかで ある。
◆判決本文
こちらは関連事件です。「ヒルドソフト」(標準文字)と仮名表\示となった商標です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.08.21
令和2(行ケ)10115 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年6月24日 知的財産高等裁判所
甲1には,請求項1に「任意の形状の中央ハンドル」との記載があり,発 明の詳細な説明中に,ユーザが握る中央ハンドルは「球,あるいは他のあら ゆる任意の形状とすることが可能である。」と記載があることから,長尺状の\nハンドルを排除するものではないと理解することはできる。しかし,「球,あ るいは他のあらゆる任意の形状とすることが可能である。」との記載ぶりか\nらすれば,まずは「球」が念頭に置かれていると理解するのが自然であり, しかも甲1の添付図(FIG.1,FIG.2)は,いずれも器具の正面図 であり,実施例を表すとされているが,そこに描かれたハンドルの形状や全\n体のバランスに照らして,球状のハンドルが開示されているとしか理解でき ないものである。 また,甲1には,甲1発明のマッサージ器具は,ユーザがハンドル(1)を握 り,これを傾けて,ハンドルに2つの軸で固定された2つの回転可能な球を\n皮膚に当てて回転させると,球が進行方向に対して非垂直な軸で回転するこ とにより,球の対称な滑りが生じ,球の間に拘束されて挟まれた皮膚を集め て皮膚に沿って動き,引っ張る代わりに押圧すると,球の滑りと皮膚に沿っ た動きによって皮膚が引き伸ばされることが開示されているところ,こうし た2つの球がハンドルに2つの軸に固定され,2つの軸が70〜100度を なす角度で調整された甲1発明において,球が進行方向に対して非垂直な軸 で回転し,球の間に拘束されて挟まれた皮膚を集めて皮膚に沿った動きをさ せるためには,ハンドルを進行方向に向かって倒す方向に傾けることが前提 となる。
ハンドルが球状のものであれば,後述するハンドルの周囲に軸で4個の球 を固定した場合を含めて,把持したハンドル(1)の角度を適宜調整して進行方 向に向かって倒す方向に傾けることが可能である。しかし,ハンドルを長尺\n状のものとし,その先端部に2つの球を支持する構成とすると,球状のハン\nドルと比較して傾けられる角度に制約があるために進行方向に傾けて引っ張 る際にハンドルの把持部と肌が干渉して操作性に支障が生じかねず,こうし た操作性を解消するために長尺状の形状を改良する(例えば,本件発明のよ うに,ボールの軸線をハンドルの中心軸に対して前傾させて構成させる(相\n違点3の構成)。)必要が更に生じることになる。そうすると,甲1の中央ハ\nンドルを球に限らず「任意の形状」とすることが可能であるとの開示がある\nといっても,甲1発明の中央ハンドルをあえて長尺状のものとする動機付け があるとはいえない。 また,甲1においては,「マッサージする面に適合させるために,より大き な直径を持つ1つまたは2つの追加球をハンドルが受容可能である」形態も\n開示されており,FIG.2には,小さい直径の球(2)を2つ,大きな直径球
(3)を2つそれぞれハンドル(1)に軸によって固定された図が開示されている。 このような実施例において,ハンドル(1)を球状から長尺状とすると,前記の とおり,甲1発明のマッサージ器具は,ユーザがハンドル(1)を握り,これを 傾けて,ハンドルに2つの軸で固定された2つの回転可能な球を皮膚に当て\nて回転させると,球が進行方向に対して非垂直な軸で回転することにより, 球の対称な滑りが生じ,球の間に拘束されて挟まれた皮膚を集めて皮膚に沿 って動き,引っ張る代わりに押圧すると,球の滑りと皮膚に沿った動きによ って皮膚が引き伸ばされるとの作用効果を生じるところ,例えば,大きい球 (3)を皮膚に当てることを想定し,長尺状のハンドルを中心軸に前傾させて構\n成させると,小さい球(2)を皮膚に当てるときには,ハンドルを進行方向に対 して傾けて小さい球(2)の球を引っ張ることができなくなる。したがって,こ うした点からすると,甲1のハンドル(1)を長尺状のものとすることには,む しろ阻害要因があるといえる。
(2) これに対し,被告は,1)甲1のFIG.1の正面図は,ハンドルが円形で 図示されているが,ハンドルが円柱状(長尺状)の形状であるとしても整合 する,2)同FIG.2においては,4つの球をハンドルに取り付けて,皮膚 が吸引される使用方法が記載されており,こうした使用方法を前提とすると, ハンドルが長尺状であればローラ(球)と接触することなくハンドルを握る ことができるから,ハンドルの形状は,球体と理解するよりも長尺状(円柱 状)のハンドルと理解するのが自然である旨主張する。 しかし,正面図であるFIG.1やFIG.2において図示されている円 形が球状ではなく円柱状(長尺状)の形状を示すものと理解することが困難 なことは,前記(1)において判示したところから明らかである。また,4つの 球をハンドルに取り付けて使用する形態であっても,FIG.2の実施例の 記載によると,使用されるのは2つの球であり,ハンドルを把持する際には 軸を避けて指でハンドルを把持すれば足り,ハンドルを長尺状(円柱状)の ハンドルと解するのが自然であるともいえず,かえって,上記のとおりハン ドルを長尺状とすることについては阻害要因があるというべきである。そう すると,甲1の実施例(FIG.1,FIG.2)には球状のものしか開示 されていないと認められ,被告の上記主張は採用し得ない。 また,被告は,甲1において,ハンドル(1)は,握って引っ張るものである という使用方法が明記され,ハンドルの形状としてあらゆる任意の形状とす ることができると記載されているのであるから,当然ながら握りやすい長尺 状の形状が想定された形状であり,甲1発明のハンドルは,握って傾けなが ら引っ張るものであるから,ハンドルの先端部に球を設けることは当業者で あれば容易に想到するものであるから,本件審決の判断に誤りはない旨主張 する。
しかし,たとえハンドルを球に限らず任意の形状とすることは可能である\nとしても,甲1発明の球状のハンドルを長尺状のものとした場合における操 作性の問題があることから,球状の実施形態しか開示されていない甲1発明 の中央ハンドルを長尺状のものとする動機付けがあるとはいえないことは前 記(1)のとおりであり,一般的に長尺状のハンドルが握りやすいものであると いえたとしても,そのことは結論を左右し得ない。また,小さい球(2)を2つ, 大きい球(3)を2つそれぞれハンドル(1)に軸によって固定された場合に,ハン ドル(1)を長尺状とすると,甲1発明の作用効果との関係でその操作に支障が 生じることから,甲1発明のハンドル(1)を長尺状のものとすることにはむし ろ阻害要因があることも前記(1)のとおりである。したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(3) そうすると,甲1発明のハンドルが長尺状のハンドルを排除するものでは ないとして,当業者が長尺状のハンドルを容易に想起し得るものとはいえな いし,ましてや,長尺状のハンドルが甲1に記載されたに等しい事項である と認めることはできないから,甲1発明のハンドルには長尺状のものが含ま れ,長尺状のハンドルが甲1の1に記載されたに等しい事項であることを前 提として,相違点1については,ハンドルを長尺状のものとした場合には, 一対の回転可能な球を先端部に配置することは甲1発明,又は甲1発明及び\n周知技術1に基づいて当業者であれば容易に想到し得たものであり,また, 相違点3については実質的な相違点にならないとした本件審決の判断は誤り というほかない。
◆判決本文
こちらは審決の判断維持ですが無効理由なしとの審決が維持されています。
原告・被告が入れ替わってます
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2021.08.21
令和2(行ケ)10148 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年6月16日 知的財産高等裁判所
ア 本願商標
(ア) 本願商標は,カンガルーをモチーフとしたと思われる図形部分と, その下に「KANGOL」と横書きされた欧文字部分からなる。
(イ) 上記の図形は,その形状からすれば,カンガルーをモチーフとした 図形であると認識され得るものといえるが,やや抽象化された図形であ ることからすれば,同図形部分から特定の称呼や観念が生じるものとま ではいえない。また,上記の欧文字は,一般的な辞書等に掲載されてい る語ではなく,特段の図案化もされていないことからすれば,同欧文字 部分から特定の観念が生じるものとはいえない。 そうすると,上記の図形部分及び欧文字部分には観念上のつながりが あるとはいえないところ,本願商標全体の構成からすると,同各部分は,\n視覚上分離して看取されるものであって,分離して観察することが取引 上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないか ら,それぞれが要部として認識されるものといえる。
(ウ) そして,上記の欧文字部分についてみるに,同部分からは「KAN GOL」の欧文字に相応して「カンゴール」の称呼が生じるが,特定の 観念は生じないといえる。
イ 引用商標
引用商標は,「KANGOL」の欧文字を標準文字で表したものであると\nころ,本願商標の欧文字部分と同様に,引用商標からは「カンゴール」の 称呼が生じるが,特定の観念は生じないといえる。
ウ 類否判断 上記ア及びイを基に,本願商標の要部である「KANGOL」の欧文字 部分と引用商標とを比較すると,両者は,観念を比較することはできない ものの,欧文字のつづりが同じである上,本願商標の欧文字部分について 特段の図案化はされていないから,外観が極めて類似するものといえる。 また,両者からはいずれも「カンゴール」の称呼が生じるから,両者は称 呼を共通にするものといえる。 以上の事情を総合して全体的に考察すれば,本願商標の要部である「K ANGOL」の欧文字部分及び引用商標については,これらが同一又は類 似の商品又は役務に使用された場合には,その商品又は役務の出所につき 誤認混同を生ずるおそれがあるといえる。
・・・・
上記ア及びイで検討したとおり,本願指定役務及び引用指定役務は,い ずれも衣類を中心とするファッション商品を取扱商品とするものである 上,これらの取扱商品が通信販売ウェブサイトにおいて販売されるなどし ている実情があることからすれば,いずれも一般需要者を広く対象とする ものといえる。また,上記イ(ア)ないし(エ)及び(コ)によれば,特定のブ ランドが付された両役務の取扱商品を,同一の小売業者から購入する需要 者は少なくないと考えられる。 これらの事情を考慮すると,本願指定役務及び引用指定役務は,需要者 の範囲が一致するものといえる。
エ 類否判断
上記アないしウで検討したところによれば,本願指定役務及び引用指定 役務は,具体的な取扱商品は異なるものの,いずれも衣類を中心とするフ ァッション商品を取扱商品とする点において共通するほか,役務を提供す る手段,目的及び業種が共通するものといえる。また,両役務は,役務を 提供する場所が共通する場合があるほか,需要者の範囲が一致するものと いえる。 これらの事情を考慮すると,本願指定役務及び引用指定役務については, これらの役務に同一又は類似の商標を使用する場合には,同一営業主の提 供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるといえ る。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.08.21
令和2(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年7月8日 知的財産高等裁判所
前記(1)のとおり,相違点2は,相違点21)及び相違点23)により構成さ\nれるべきものである。本件審決は,相違点21)は容易に想到できるとして おり(当裁判所としてもその結論を是認できる。),原告は,相違点23)の 容易想到性を否定した本件審決の判断を争っている。
イ 相違点23)の容易想到性
(ア) 相違点23)は,「『フレームと床との間に介護者又は患者の足が存在 しても,挟み込みが生じないように』,下降スイッチが押し状態であって もフレームをいったん停止させ,『ブザーを鳴らして警報』すること」で ある。
原告は,前記第3の2(1)イ(イ)のとおり,「フレームと床との間に,介 護者又は患者の足が存在しても,挟み込みが生じないように」との点が 用途による限定を付すものであり発明の構成とはならないから,相違点\nを構成することもない旨主張するが,上記特定事項は,フレームが停止\nする高さを何に基づいて決定するかを特定するものであるから,発明を 構成する部分であり,その主張は失当である。したがって,本件訂正発\n明1が用途発明になることもない。 そうすると,同(2)イ(ア)の被告の主張につき判断するまでもなく,原 告の上記主張はいずれにせよ採用することができない。 (イ)a 前記第2の3(2)アのとおり,甲1発明における下方中間位置は患 者支持面が床から約14インチ(約356mm)の高さであり,同最 下位置は患者支持面が床から約8インチ(約203mm)の高さであ るところ,下方中間位置から最下位置に153mm下降できるという ことは,少なくともフレームの下端が床から153mm以上離れてい なければならないから,下方中間位置でのメインフレーム12の床か らの高さは153mmよりは高いことになる。 ここで,甲2技術事項に係る別紙3の記載によると,足が届く範囲 の可動部と床面との間に120mm以上の寸法があれば,足を挟み込 む危険がないものと理解される。 そうすると,甲1発明における下方中間位置でのメインフレーム1 2の床からの高さは,本件訂正発明1の「介護者又は患者の足が存在 しても,挟み込み等が生じないような高さ」(本件訂正明細書【002 1】)であるといえ,また,甲1発明の最下位置は「床に近接して配置 される」ものであり(甲1[0011],FIG−4),足が挟み込まれ る高さであることは明らかであるから,最下位置に向けて下降する下 方中間位置は「これ以上フレーム1が下降すると,足を挟み込んでし まうような高さ」(本件訂正明細書【0021】)である。 そして,甲1には,「磁石112のホール効果センサ118に隣接し た配置までの移動は,下方中間位置でのベッド10の位置付けに相当 し,磁石112のホール効果センサ116に隣接した配置までの移動 は,上方中間位置でのベッド10の位置付けに相当する。」([0036]) との記載があり,そして,甲1発明の管部110は,軸受部材108 に摺動接触して支持された状態でねじ式リニアアクチュータ98のね じ120に対して直線移動で駆動できるよう構成されており,磁石1\n12は,水平移動に当たり必ずホール効果センサ118及び116に 隣接した位置を通るから,甲1発明のベッドは,必ずフレームが下降 する際に上方中間位置及び下方中間位置で自動的に下降を停止するベ ッドである。
b ここで,昇降機能を有するベッドにおいて,フレームと床との間に,\n人体の侵入を防止し,人体が挟み込まれないよう下降を停止させるこ とは当業者にとって極めて馴染みの深い周知技術であると認められる (甲4の【請求項1】,【0003】,甲21の【請求項1】,【0003】, 【0005】参照)。 そして,昇降機能を有するベッドにおいて,フレームと床との間に\n人体が挟み込まれないよう警告音で周囲に異常を知らせることも当業 者にとって極めて馴染みの深い周知技術であると認められる(甲4の 【0014】,【0010】,甲21の【0014】,【0010】参照)。 c そうすると,上記aのように,介護者又は患者の足が存在しても, 足の挟み込みが生じないような下方中間位置においてフレームの下降 は停止するが,それ以上フレームが下降すれば介護者又は患者の足が 挟み込まれてしまうことになる甲1発明に接した場合,昇降機能を有\nするベッドにおいて,人体の侵入を防止し,人体が挟み込まれないよ うにベッドの下降を停止するとの周知技術に従い,その下降を停止す る高さを「前記フレームと床との間に,介護者又は患者の足が存在し ても,挟み込みが生じないよう」な意図で設定し,この際,警告音で フレームと床との間に人体が挟み込まれないよう知らせるとの周知技 術に従い,警告音を発するようにすることは,当業者には格別困難な ことではないといえる。
(ウ) 被告の主張について
被告は,前記第3の2(2)イ(ウ)のとおり,足を挟んでしまうことの防 止という課題は甲1発明に内在する課題とはいえない旨主張する。しか しながら,「特開2002−125808号公報」(甲4)及び「特開2 002−125807号公報」(甲21)においては,各【発明の詳細な 説明】の中に,子供が入り込むことの防止に係る記載がされているとこ ろ,各請求項1には,それぞれ「床部下への人体の侵入を監視して,人 体の侵入ありとした際に」又は「人体が存在する旨の検知信号により」 と記載されているのであり,子供が入り込むことのみに限定されるもの と解すべき事情も見当たらないことに照らしても,これらの発明の技術 的思想としては,人体が挟み込まれるのを防止するということが抽出で きるのであり,人体の対象には介護者又は患者も含まれるから,当業者 であれば,甲1に介護者又は患者の足を挟んでしまうことを防止すると の課題の記載や示唆がなくとも,甲1発明のベッドを介護者又は患者の 足を挟んでしまうことを防止するとの意図の下に設定することは容易と いうほかない。したがって,上記主張は,採用することができない。 さらに,被告は,同(エ)のとおり,「ブザーを鳴らして警報」すること は容易想到ではない旨主張するが,上記(イ)cのとおり,昇降機能を有\nするベッドにおいてフレームと床との間に人体が挟み込まれないよう警 告音で周囲に異常を知らせることは周知技術であるところ,人体の挟み 込みの防止のために警報音を鳴らすということの目的は,人体の挟み込 みの防止のためにフレームの下降を停止して実際に挟み込みを防止する こととは異なり,人体が挟み込まれる前の所定の段階であらかじめ操作 者を含む周囲の者に注意確認を促すことにある(警報音を鳴らすものの フレームの下降を人体の接触を感知するまで停止しないという選択もあ り得るから,警報音を鳴らすこととフレームの下降停止とは独立に置換 可能な独立の技術的事項である。)。したがって,フレームと床との間に\n人体があって実際に挟み込みの危険があるか否かは,人体の挟み込みの 防止のために警報音を鳴らすという技術的事項を導入するに際して直接 の関係を有するものではない。そうすると,警告音を発する場面を,異 物を検出した段階とするのか,あるいは,フレームがそれより下降すれ ば人体の挟み込みの危険が生じ得る高さとするかは,設計的事項にすぎ ず,「特開2002−125808号公報」(甲4)及び「特開2002 −125807号公報」(甲21)に記載の発明から認められる周知技術 と甲1発明とは,むしろ警報音を鳴らす局面,対象又は目的を共通とす るといえる。したがって,下方中間停止位置で常に自動的に下降を停止 する甲1発明において,上記周知技術に基づいて下方中間停止位置で停 止した際に「ブザーを鳴らして警報」することは容易に想到できるとい え,上記周知技術が異常を検知した際に警報音を発するものである点が 甲1発明に同技術を適用することを妨げるものではない。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。。 そのほか,被告がるる主張するところも,前記イの判断を左右するも のではない。
(エ) まとめ
以上によれば,相違点21)に加えて,相違点23)についても容易に想 到できるというべきであるから,本件審決の相違点2の容易想到性判断 には,誤りがある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.08.21
平成30(ワ)21900 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月20日 東京地方裁判所
(1) 推定される損害額
ア 前記前提事実(5)のとおり,被告は,本件特許権の登録日である平成29 年6月16日から令和元年10月31日までの間,被告各製品合計●省略 ●個を販売し,これにより●省略●円の売上げがあり,少なくとも●省略 ●円の経費を要した。 したがって,法102条2項の利益の額は,5652万1465円(消 費税込み)と認めるのが相当である。 イ 被告は,被告による被告各製品の販売がなかったならば原告が利益を得 られたであろうという事情は存在しないので,法102条2項の適用はな いと主張する。
しかし,証拠(甲12,35ないし38,乙17,33,107,10 8)及び弁論の全趣旨によれば,1) 電動ファン付きウエアの市場において, 平成29年当時,原告グループ(原告,株式会社空調服等。以下同じ。) は約30%,被告グループ(被告,株式会社サンエス等。以下同じ。)は 約40%,平成30年当時,原告グループは約33%,被告グループは約 33%,令和元年当時,原告グループは約40%,被告グループは約2 0%,令和2年当時,原告グループは約35%,被告グループは約20% の各シェアを占めていたこと,2) 原告は,首後部からの空気の排出口の大 きさを調整することができるように,空調服の販売を開始した当初は調整 紐型空調服を製造販売し,その後,2段階調整型空調服を製造販売してい るが,本件各発明を実施する空調服は製造販売していないことが認められ る。 上記認定事実によれば,原告グループは電動ファン付きウエアの市場に おいて大きなシェアを占め,原告は,首後部からの空気の排出口の大きさ を調整するために,調整紐型空調服又は2段階調整型空調服を販売してい たものと認められる。他方で,被告各製品のように複数段階で調整できる 空調服が多数販売され,他の電動ファン付きウエアの市場とは異なる独自 の市場を形成していたことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,原告製品は被告各製品の競合品であると認めるのが相当で あるから,被告が被告各製品を販売して本件特許権を侵害しなければ,原 告は原告製品をさらに販売して利益を得られたであろうという事情が認め られる。 したがって,本件には法102条2項が適用されるので,被告の上記主 張は採用することができない。
ウ 被告は,商品の運用及び管理を●省略●に委託しており,平均すると商 品1点当たり●省略●円の経費を要したから,売上げから合計●省略●円 (●省略●円×●省略●個)を控除すべきであると主張する。 法102条2項の利益の額とは,侵害者の売上高から,侵害者において 侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必 要となった経費を控除した限界利益の額をいうところ,証拠(乙62)及 び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成28年6月21日以降,●省略● に対し,被告の物流センターにおける衣料用繊維製品等の入出荷業務その 他これに付随する業務全般を,製品の点数にかかわらず一律の月額委託料 (平成29年8月1日以降は●省略●円)を支払うことを約して委託した ことが認められる。 そうすると,●省略●に対する委託料は,被告が被告各製品を製造販売 することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と は認められないから,前記アの被告各製品の売上げからこれを控除するの は相当でない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(2) 推定の覆滅事由
ア 本件各発明が被告各製品の部分のみに実施されていること
(ア) 前記1(2)のとおり,空調服は,送風手段を用いて外部から服内に空気 を取り込み,当該空気が服内を流通し,その間に人体から出た汗を蒸発 させ,気化熱により体表面の温度を下げようとするものであるところ,\n本件発明1は,空調服の襟後部又はその周辺に二つの調整ベルトを設け, 一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数ある取付部のうち いずれか一つを取り付けることによって,襟後部と首後部との間に形成 される開口部を広げたり,狭めたりすることを可能にし,より適切な空\n調服の冷却効果を,より簡単に得ることを目指したものである。 しかし,本件特許の出願当時,既に,空調服の襟後部の内表面に一組\nの調整紐を設け,これらを結ぶことによって上記開口部の大きさを調整 する技術があったところ(本件明細書【0004】),本件発明1は, 一組の調整紐を任意の長さに結ぶことが難しく,上記開口部の大きさを 求める冷却効果に応じた適正なものにすることが困難であったことを解 決しようとしたものであり(同【0006】及び【0009】),上記 開口部からの空気の排出の効率化という点では,従来技術の延長線上に 位置付けられるものである。そして,本件発明1は,主として,従来技 術における調整紐を「取付部」を有する「調整ベルト」に置き換えたも のであるが,前記5(2)のとおり,本件特許の出願当時,ボタン及びボタ ンホール等を使用し,衣服におけるサイズを複数段階で調整することが できる周知慣用の技術が存在したものである。 以上からすると,従来技術と比較したときの本件発明1の技術的意義 は,必ずしも大きいものではなかったといわざるを得ない。 なお,本件発明2は,本件発明1の空気排出口調整機構を備える空調\n服の服本体の発明であって,本件発明2につき本件発明1とは異なる独 自の技術的意義は認められない。
(イ) 従来技術に係る調整紐型空調服において,送風手段を作動させたとき の襟後部と首後部との間に形成される開口部の形状は,電動ファンの風 力,前部ファスナーの締め具合,着用者の姿勢や体格,服の布地や布ベ ルト,ゴムベルト等の素材,襟部の形状等の影響を受けると考えられる ところ,この点については,本件発明1を実施した空調服であっても異 なるところはない。そして,上記従来技術又は本件発明1に係る空気排 出口調整機構が,上記の諸要素と比較して,上記開口部の形状決定にど\nの程度の影響を与えるのか,ひいては当該空調服の冷却性能にどの程度\nの作用効果があるのかを確定するに足りる証拠はない。 また,調整紐型空調服の場合,結び目付近に調整紐の先端部分が集ま り,空気排出の障害となることが指摘されるが(本件明細書【000 8】),紐という形状から考えて障害の程度がさほど大きいものとはい えず,本件発明1により特に有意な作用効果が得られるとはいえない。 さらに,従来技術に係る調整紐型空調服においても,一定の技量があ れば調整紐を任意の長さに結ぶことは可能であり,本件発明はこの点に\nついて特段の技量を要しないこととしたところに発明の作用効果がある といえるものの,実際に空調服を使用するに際し,上記の調整紐の長さ につき,どれほどの頻度で,どの程度細かく調整することが必要とされ ていたのかは明らかではない。 そうすると,本件発明1は,容易に襟後部と首後部との間に空気排出 口を形成し,これを調整することができるものの,従来技術に比して大 きな作用効果があるものとは認められない。
(ウ) 証拠(乙34,35)及び弁論の全趣旨によれば,顧客が空調服を選 択する際,空調服の価格,デザイン,服の素材並びに電動ファン及びバ ッテリーの性能に着目することが多いと認められ,空調服の襟後部と人\n体の首後部との間の空気排出口を調整する機構の有無が特に着目された\nことを認めるに足りる証拠はない。 また,被告各製品のうちの本件各発明を実施する部分は,ボタン,ボ タンホール,ゴムベルト及び布ベルトで構成され,その製造がさほど困\n難であったとは認められず,証拠(乙19)及び弁論の全趣旨によれば, 被告各製品に上記部分を設けるのに要する費用は1着当たり41ないし 42円であり,被告各製品の販売価格の1ないし2%にすぎなかったと 認められる。 さらに,証拠(甲3,乙57ないし59)及び弁論の全趣旨によれば, 平成29年から令和元年までの被告の商品のパンフレット及びウェブサ イトにおいて,空調服の構造を紹介するページに,本件発明1に係るゴ\nムベルト及び布ベルトが取り付けられた部分の写真が掲載され,その機 能を紹介する記載があるが,同写真は,ファンの写真よりは小さく,フ\nァンの取り付け位置及び着脱方法並びにバッテリーの各写真と同程度の 大きさであったこと,個々の空調服を紹介するページに,空調服が備え る機能として,ペンを差すポケット,バッテリー用ポケット,袖口の複\n数のボタン,保冷剤用ポケット等の各写真と並んで,上記部分の写真が 掲載されていることが認められる。 そうすると,被告各製品が備える機能のうち本件発明1を実施した部\n分が占める割合は小さかったといえ,また,同部分の顧客誘引力が特に 高かったとはいえない。
(エ) 以上によれば,本件発明1の技術的意義や作用効果,被告各製品のう ち本件発明1が実施された部分の顧客誘引力等に照らすと,本件特許権 を侵害する同部分が被告各製品の販売に貢献したところは小さいといわ ざるを得ないから,この事情に基づき,法102条2項により推定され る損害額の80%について推定の覆滅を認めるのが相当である。
イ 市場における競合品の存在
(ア) 前記(1)イのとおり,平成29年から令和元年までの電動ファン付きウ エアの市場において,原告グループのシェアは約30ないし40%,被 告グループのシェアは約20ないし40%であり,原告は,襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することができるように, 2段階調整型空調服を製造販売している。 また,前記ア(ウ)のとおり,被告は,その商品のパンフレット等におい て,ペンを差すポケット,バッテリー用ポケット等の機能と並んで本件\n発明1に係る部分を紹介しており,購入者が本件発明1が実施された部 分のみに着目して被告各製品を選択したとはいい難い。 一方で,証拠(乙39ないし45)及び弁論の全趣旨によれば,原告 及び被告以外の業者も,首後部からの空気の排出をより効率的に行うた めの機能を備えた空調服や,その他種々の機能\を備えた空調服を販売し ていることが認められる。 そうすると,空調服のうちの特定のものだけが被告各製品の競合品と なるとは認められず,競合品に係るシェアは上記の原告,被告及びその 他の競業他社のシェアのとおりと認めるのが相当であり,これを踏まえ ると,被告が被告各製品を販売することがなかったとしてもその購入者 の全てが原告製品を購入したとはいえないから,この事情に基づき,法 102条2項により推定される損害額の50%について推定の覆滅を認 めるのが相当である。
(イ) 被告は,被告各製品を製造販売しなかったとしても,被告各製品を購 入しようとしていた顧客は,本件各発明の技術的範囲に属しない被告の 代替製品を購入するはずであるから,被告各製品の販売と原告の損害と の間には因果関係は認められず,仮に法102条2項が適用されるとし ても,この点は推定の覆滅事由になると主張する。 しかし,被告が被告各製品を製造販売しなかったとして,被告が他に いかなる空調服を製造販売したかは証拠上明らかではないから,被告の 上記主張は採用することができない。
ウ 被告の営業努力
被告は,独自のブランドである「空調風神服」の名称で被告各製品を販 売しており,「空調風神服」には強い出所識別力があるから,被告各製品 の販売には上記ブランドによる力が貢献していると主張する。 しかし,前記(1)イのとおり,遅くとも平成29年以降,電動ファン付き ウエアの市場において,原告グループのシェアと被告グループのシェアは 拮抗し,むしろ原告グループのシェアの方が伸びていることからすると, 原告製品の顧客吸引力と比較して「空調風神服」の名称に特に強い顧客吸 引力があるとは認められないというべきであり,他にこれを認めるに足り る証拠はない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
エ その他
被告は,1) 原告製品は本件発明1を実施しておらず,被告が被告各製品 を販売したことにより原告が損害を受けることはない,2) 原告製品はイン ターネットショッピングサイトにおいて酷評されていると主張する。 しかし,上記1)について,前記(1)イのとおり,原告は,電動ファン付き ウエアの市場において,被告各製品の競合品を製造販売していたから,原 告製品において本件各特許が実施されていなかったからといって,被告が 被告各製品を製造販売したことにより,原告が損害を被ったことを否定す ることはできない。 また,上記2)について,原告(原告グループ)が電動ファン付きウエア の市場において相当程度のシェアを占めていることは前記(1)イのとおりで あり,インターネットショッピングサイトにおけるごく一部の評価(乙4 6)をもって,被告各製品が販売されなかったとしても原告製品が売れる ことはなかったということはできない。 したがって,被告の上記各主張はいずれも採用することができない。 (3) 小括 ア 以上によれば,本件各発明の被告各製品の売上げに対する貢献の程度に より80%(前記(1)ア),電動ファン付きウエアの市場に競合品が存在す ることにより50%(前記(1)イ)の推定の覆滅を認めるべきであるから, 被告による本件特許権の侵害により,原告が被った逸失利益に係る損害額 は,565万2147円(5652万1465円×(1−0.8)×(1 −0.5))と認められる。 イ 被告の上記不法行為と相当因果関係の認められる弁護士費用相当額は6 0万円と認めるのが相当である。
ウ よって,原告が被った損害額は合計625万2147円である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2021.08.17
令和2(行ケ)10033 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年6月28日 知的財産高等裁判所
(3) 相違点10−2の容易想到性
ア 本件発明7のステップ(b)について
(ア) 相違点10−2においては,本件発明7のステップ(b)に係る構\n成の容易想到性が問題となるところ,上記1(4)のとおり,本件発明7の ステップ(b)は,原油組成物を実質的に塩基なしで水性流体処理ステ ップにかけるステップであり,かつ,相分離を改善するために無機塩を 水性流体に添加するものである。
(イ) そして,上記(2)アのとおり,本件優先日当時,油の精製において, アルカリ精製による脱酸処理の前に脱ガム処理を経ること,一般的な脱 ガム処理の方法の1つとして,水や水蒸気等の水性流体を油組成物と接 触させ,水和したガム質を含む親水性の不純物を油から分離して除去す る方法があったことは,いずれも周知の技術であったと認められる。ま た,証拠(甲3,4,6〔693,700,701頁〕)によれば,本件 優先日当時,蒸留(物理的精製)による脱酸処理の前に脱ガム処理又は 水洗の処理を経ることは,周知であったと認められる上,証拠(甲5〔4 75頁の表2〕,6〔693頁右欄の表\1〕,13〔571頁の右欄〕,1 4〔98頁の図2〕,24〔185頁〕)によれば,水や水蒸気等の水性 流体を油組成物と接触させた後に分離する処理によってタンパク質性化 合物が除去されることも,周知であったと認められる。
(ウ) そうすると,本件発明7のステップ(b)は,タンパク質性化合物 を含む親水性の不純物の少なくとも一部を油から分離させて除去し得る 点において,上記の水や水蒸気等の水性流体を用いた脱ガム処理又は水 洗の処理と異なるところはないというべきである。
イ 甲2文献における開示
(ア) 上記(1)のとおり,甲2文献においては,油をストリッピング工程の 前に前処理してもよいと記載されている(【0057】)。
(イ) そして,上記アのとおり,ストリッピング処理を行う前に水や水蒸 気等の水性流体を用いた脱ガム処理又は水洗の処理を経ることが周知 であったことからすれば,甲2発明のストリッピング処理の前に,水や 水蒸気等の水性流体を用いた脱ガム処理又は水洗の処理を行い,親水性 の不純物の少なくとも一部を油から分離させて除去することを,当業者 は当然に動機付けられるものといえる。
ウ 解乳化剤としての無機塩の添加が周知技術であったか否か
(ア) 水や水蒸気等の水性流体を用いた脱ガム処理又は水洗の処理におい ては,水相と油相との界面が十分に解乳化され,水性流体を油から容易\nに分離することが可能な状態となることが好ましいことは明らかである。\n
(イ) そして,証拠(甲30,31,44ないし46)によれば,一般科 学においては,従来から,塩化ナトリウム等の塩を解乳化剤として用い ることが広く知られていたと認められることからすれば,水や水蒸気等 の水性流体を用いた脱ガム処理又は水洗の処理においても,水相と油相 との界面を解乳化し,水性流体を油から容易に分離することが可能な状\n態とするために,塩化ナトリウム等の塩を用いることを,当業者は当然 に動機付けられるものといえる。
エ 容易想到性
(ア) 上記アないしウで検討したところによれば,甲2文献に接した本件 優先日当時の当業者は,甲2発明のストリッピング処理の前に,水や水 蒸気等の水性流体を用いた脱ガム処理又は水洗の処理を行い,親水性の 不純物の少なくとも一部を油から分離させて除去すること,その際に, 水相と油相との界面を解乳化し,水性流体を油から容易に分離すること が可能な状態とするために,塩化ナトリウム等の塩を用いることを,容\n易に想到することが可能であったといえる。\n
(イ) また,本件発明7のステップ(b)に係るその他の構成について検\n討するに,証拠(甲5,24)によれば,魚油には炭素数16から22 の遊離脂肪酸が必ず含まれていることが認められる。 さらに,粗魚油の一般的な遊離脂肪酸濃度は2重量%ないし5重量% であると認められる(甲5〔475頁の表1〕)ところ,水や水蒸気等の\n水性流体を用いた脱ガム処理又は水洗の処理においては,油組成物中の 遊離脂肪酸は中和されず,その量が変化しないことは明らかであるから, 上記処理後の魚油の遊離脂肪酸濃度が,0.5重量%ないし5重量%の 範囲内となることも明らかである。
(ウ) 以上によれば,甲2文献に接した本件優先日当時の当業者は,本件 発明7のステップ(b)に係る構成を,容易に想到することができたも\nのといえる。
オ 被告の主張について
(ア) 被告は,甲2文献には,ストリッピング処理前の前処理過程の一例 として脱臭工程のみが挙げられている上,脱ガム処理のほか,本件発明 7のステップ(b)に係る構成について何らの記載等もされていないか\nら,当業者は同構成を採ることを動機付けられるものではない旨主張す\nる。 しかしながら,甲2文献の段落【0057】には,ストリッピング工 程の前処理の一例として脱臭工程が挙げられているものの,これに限る 旨の記載は存しない上,前記のとおり,水や水蒸気等の水性流体を用い た脱ガム処理等が周知の技術であり,これをストリッピング処理の前に 行うこともまた周知であったことからすれば,当業者は,ストリッピン グ工程の前処理として,水や水蒸気等の水性流体を用いた脱ガム処理等 を行うことを動機付けられるものといえる。 したがって,被告の主張は,採用することができない。
(イ) 被告は,原告が主張する脱ガム処理には様々な方法によるものが含 まれるから,相違点10−2に係る本件発明7の構成には至らない旨主\n張する。 しかしながら,前記のとおり,水や水蒸気等の水性流体を用いた脱ガ ム処理が,一般的な脱ガム処理の方法の1つとして周知の技術であった と認められることからすれば,甲2文献に接した当業者は,これを甲2 発明に適用することを動機付けられるものといえるから,被告が指摘す るとおり,脱ガム処理に様々な方法によるものが存在するとしても,前 記の結論を左右するものではないというべきである。 したがって,被告の主張は,採用することができない。
(ウ) 被告は,エマルジョン形成の解消が容易ではないことは技術常識で あったこと,甲44文献に記載された有機相及び本件発明7のステップ (b)における有機相は全く異なるものであること,魚油の精製工程に おいて無機塩を解乳化剤として用いることに関する文献が本件訴訟にお いて提出されていないことから,当業者が無機塩を添加して有機相と水 相とを分離させる技術を甲2発明に適用することを動機付けられるもの ではない旨主張する。 しかしながら,欧州の特許公開公報である甲44文献に対応する日本 の公開特許公報である乙C6文献には,海産動物油等の天然源からEP A及びDHA混合物等を抽出する方法に関して,脂肪酸混合物を含む相 と水相との分離を高めるために,塩化ナトリウム等の塩類を少量加える ことが記載されている。また,甲30文献には,魚鯨油を2%程度の塩 化ナトリウム等の塩類水溶液で洗浄する方法が記載されており,脱ガム 処理として魚鯨油を塩類水溶液で洗浄する方法が行われているものと認 められる。このように,魚油の精製工程において,無機塩を添加するこ とによって相分離を図る方法が記載されている文献が存在するのに対し, 本件各証拠上,このような方法の採用を妨げるような内容の文献は見当 たらない。 そうすると,一般科学において実施されている相分離を改善するため の無機塩の添加を,魚油の精製工程において実施することが妨げられる ものではないというべきである。 したがって,被告の主張は,採用することができない。
(エ) 被告は,本件発明7は当業者には予測し得ない顕著な効果を奏する\n旨主張する。
しかしながら,これまで検討したとおり,本件発明7のステップ(b) に係る構成は,周知技術である水や水蒸気等の水性流体を用いた脱ガム\n処理等に,同じく周知技術である相分離を改善するために無機塩を添加 する方法を組み合わせたものであることからすれば,当業者は,同構成\nが塩基を使用しないものであることや,相分離の改善によりトリグリセ リド油の回収率を高めることができることを当然に予測し得るものとい\nえるから,本件発明7は,予測し得ない顕著な効果を奏するものとは認\nめられない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.08.17
令和2(ワ)9992 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年6月24日 大阪地方裁判所
1 本件原画の著作物性(争点1)について
(1)前記(第2の2(1))のとおり,本件原画は,一般向けの販売を目的とする時計のデザインを記載した原画であり,それ自体の鑑賞を目的としたものではなく,現に,原告は,本件原画に基づき商品化された原告製品を量産して販売している。すなわち,本件原画は,実用に供する目的で制作されたものであり,いわゆる応用美術に当たる。
( 2 )「著作物」とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいい,このうち「美術の著作物」には美術工芸品が含まれる(同条2項)。他方,応用美術のうち,美術工芸品に当たらないものが「美術の著作物」に該当するかどうかについては,明文の規定はない。しかし,「著作物」の上記定義によれば,「美術の著作物」は,実用目的を有しない純粋美術及び美術工芸品に限定されるべきものではない。すなわち,実用目的で量産される応用美術であっても,実用目的に必要な構\成と分離して,美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては,純粋美術の著作物と客観的に同一なものとみることができる。そうである以上,当該部分は美術の著作物として保護されるべきである。他方で,実用目的の応用美術のうち,実用目的に必要な構成と分離して,美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握することができないものについては,純粋美術の著作物と客観的に同一なものとみることはできないから,美術の著作物として保護されないと解される。\n
(3)本件原画について
ア 本件原画は,別紙写真目録記載のとおりであるところ,本件形態1及び2の観点を踏まえると,これには,以下のとおりの形態の時計が表現されているものと認められる。\n
(ア)長針,短針,秒針の三種の針を有する壁掛け型アナログ時計であり,各針はいずれも白色である。各針は,いずれも黒色の円盤状部の中心にその回転軸を固定されている。
(イ)上記円盤状部の頂部上部に数字の「12」を配置し,これを起点として,上記円盤状部の外周に沿って右回りに,黒色太字ゴシック体様の算用数字「1」〜「11」を概ね均一の大きさで順に円環状に配置している。これらの数字のうち,「1」,「2」,「5」,「6」,「7」,「11」及び「12」は,上記円盤状部に接着している。また,「6」及び「7」を除く数字は,隣接する別の数字のいずれか又は両者と接着している。
(ウ)前記数字のうち「12」を構成する「2」の頂部から「1」〜「8」を経て「9」の下部まで,円環状に配置された各数字の外周側に,これらに沿うと共にそれぞれの数字に接着する形で,黒色の円弧状の枠が配置されている。
イ 本件原画のうち,本件形態1に係る部分(前記ア(ア))について,時計の針が本体の色彩との関係で視認しやすいこと自体は,針の位置により時間を表示するアナログ時計の実用目的に必要な構\成といえる。配色に係るデザイン性(本体の黒色と針の白色のコントラスト)も,このような構成を実現するために採用されているものといえるのであって,当該構\成と分離して美的鑑賞の対象となるような美的特性を備えている部分として把握することはできない。
ウ 本件形態2に係る部分(前記ア(イ),(ウ))については,まず,アナログ時計において,「1」〜「12」の各数字及びこれを「12」を頂部として配置して右回りに円環状に配置することは,時間の表示という実用目的に必要な構\成といえる。また,これらの数字により形成された円環の内側にある円盤状部及び外側に形成された円弧状の枠は,円環状に配置された数字と互いに接着することにより,全体として時計本体を構成し,その形状を維持している部分と見られるから,これらも実用目的に必要な構\成といえる。使用されている数字のフォントや円盤状部の大きさの点も,数字の見易さ及び時計としての使用に耐える一定の強度の実現という時計としての実用目的に必要な構成である。さらに,数字の字体そのものは,何ら特徴的なものではない。\n
他方,各数字の外周側に円弧状の枠が設けられていない部分は,デザインの観点から目を引く部分と見ることも可能である。もっとも,当該部分は,下部に上記枠の終端部が接する「9」を除くと,2桁の数字(「10」〜「12」)が配置された部分であるところ,全ての数字の外側を円弧上の枠により囲んだ製品においては「10」及び「11」の数字のサイズが他の数字に比して明らかに小さいこと(乙3)にも鑑みると,上記枠の設けられていない部分に他の部分と同様に枠を設けた場合,10の桁を示す「1」の部分がそれぞれ円弧状の枠と干渉して数字を読み取り難くなり,時間の把握という時計の実用目的を部分的にであれ損なうことになると考えられる。\n
そうすると,当該部分のデザインについても,時計の実用目的に必要な構成と分離して美的鑑賞の対象となるような美的特性を備えている部分として把握することはできない。エしたがって,本件原画は,実用目的に必要な構\成と分離して,美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握することができないものであるから,これを純粋美術の著作物と客観的に同一なものと見ることはできず,著作物とは認められない。
2021.08.17
令和2(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年7月29日 知的財産高等裁判所
本件審決は,引用発明の構成b1の「コンテンツ」及び構\成f1の「OTTデバイス」が,それぞれ本願発明8の「デジタル・コンテンツ・アイテム」及び「ディスプレイ装置」に相当するという判断を前提として,クライアントに対してファイルを配信する方法において配信の効率化を図ることは一般的課題であるから,引用発明に甲2技術を適用することは,当業者が容易に想到し得たことであるとし,引用発明に甲2技術を適用した発明は,OTTデバイスの「ファイルの受信品質および受信性能の指標を含む品質情報を取得する」構\成を備える方法ということができ,同構成は,構\成Hの「1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータをサービス管理システムにより収集する」構\成に相当すると判断した。
(2) しかし,前記3(1)アの甲2の記載(段落【0002】,【0005】,【0012】,【0014】〜【0018】,【0072】〜【0079】,【0116】〜【0123】等。特に,品質情報を具体的に記載した段落【0073】〜【0078】)からすると,甲2技術は,ファイルの効率的な配信のための技術であって,そこで取得される品質情報は,クライアント計算機の性能や動作状態,あるいは回線状態などに関するものと認められる。なお,甲2の段落【0049】,【0050】,【0053】及び【図3】からすると,甲2において,サーバ201と同様の概略構\成であり得るクライアント211がディスプレイ装置と接続されることは示唆されているが,他方で,ディスプレイ110は,あくまで,サーバ201に備わる表示コントローラ105と接続される外部装置として取り扱われており,そのような外部装置であるディスプレイ110から何らかの情報を取得することについての記載は見当たらない。したがって,甲2技術における「受信品質の指標・・・および受信性能\の指標を含む品質情報」に,ディスプレイ装置の品質等の情報が含まれているとまでは認められず,その点に係る技術常識等を認めるべき他の証拠もない。
(3) そうすると,仮に,引用発明の構成b1の「コンテンツ」及び構\成f1の「OTTデバイス」が,それぞれ本願発明8の「デジタル・コンテンツ・アイテム」及び「ディスプレイ装置」に相当するという判断を前提とし,クライアントに対してファイルを配信する方法において配信の効率化を図ることが一般的課題であると解して,引用発明に甲2技術を適用し,OTTデバイスの「ファイルの受信品質および受信性能の指標を含む品質情報を取得する」構\成を備えるものとしたとしても,直ちに「ディスプレイ装置」の「品質情報を取得する」ことまでをも含む構成になるということはできず,本願発明8の構\成Hの「1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータをサービス管理システムにより収集する」構\成に相当するものになるとはいえない。よって,本件審決における相違点1に係る容易想到性の判断には,誤りがある。以上の認定判断に反する被告の主張は,採用することができない。
5 相違点2に係る構成の容易想到性について\n
(1)本件審決は,引用発明と甲3技術は,送信クライアント,受信クライアント及びサーバとの間でデータ送受信を行う方法である点において共通することから,引用発明に甲3技術を適用することは,当業者が容易に想到し得たことであるとし,引用発明に甲3技術を適用した発明は,OTTデバイス(ピア1A)から他のOTTデバイス(ピア1B)に対して,「ピア1Bは,ピア1Aに該当のデータの送信を要求する」構成を備える方法ということができ,当該構\成は,構成Jの「外部の創作地点から,インターネットを介して,前記1つまたは複数のディスプレイ装置へと,前記サービス・クラウドの外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送する」構\成に相当すると判断した。
(2) しかし,甲3技術がピアツーピアシステムに係るものである(構成i)のに対し,引用発明は,コンテンツの取込み,自動パブリッシング,配信及び格納並びに収益化等の複合的なタスクが実行可能\であるもので,それ自体が主体的にコンテンツの取込みや配信等を行う方法であるものと解されるから,甲3技術と引用発明とは,少なからず技術分野を異にするものというべきである。この点,「送信クライアント,受信クライアント及びサーバとの間でデータ送受信を行う方法」という広い技術分野に属することから直ちに,それらの関係性等を一切考慮することなく,引用発明に甲3技術を適用することを容易に想到することができるものとは認め難い。そして,甲3に,他に,甲3技術を引用発明に適用する動機付けや示唆となる記載があるとも認め難い。 よって,本件審決における相違点2に係る容易想到性の判断には,誤りがある。
(3) 被告は,本願明細書(甲6)の段落【0130】の記載を踏まえて,本願発明8の構成Jにいう「外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送する」という文言の意味について,「デジタル・コンテンツ・アイテム」が「外部コンテンツ・ゲートウェイ」を経由するか否かにかかわらず,「外部コンテンツ・ゲートウェイ」の機能\「により転送する」ことをいうと主張するが,上記(2)の判断は,本願発明8の構成Jにいう「外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送する」を上記の被告が主張するように理解したとしても左右されるものではない。\n
6 相違点3に係る構成の容易想到性について\n
(1)本願発明8の構成Kの「ライブ・データ・フィード・ゲートウェイ」については,構\成Kの文言によると,サービス・クラウドに備えられ,コンテンツをサービス・クラウドの外部の供給源からディスプレイ装置に提供する機能を有するものと認められ(前記1(2)ウ(ク)),また,「ライブ・データ・フィード」という用語からすると,外部の供給源から供給されるデータには「ライブ」の要素が含まれるものと解される。しかるに,甲4技術が,上記の「ライブ」の要素が含まれるデータの供給に関する構成を含むものであるかは明らかでない。したがって,引用発明に甲4技術を適用しても,直ちに本願発明8の構\成Kに至るものかは,明らかでない。
(2) 本件審決は,甲4技術の構成kの「オンラインサービスコンピューティング装置108」が,本願発明8の「ライブ・データ・フィード・ゲートウェイ」に相当すると判断したが,上記(1)の点に関し,この判断の根拠が明確にされているとはいえない。また,被告は,甲4技術の「オンラインサービスコンピューティング装置108」は,コンテンツアイテムを外部供給源(「オンラインソーシャルネットワーキングサービス」)から受信してユーザ装置310に送信するから,データを一方から他方へ転送する制御機能\を有する「ゲートウェイ」に相当するとした上で,データは「多数のユーザにより投稿され共有された種々のメディアコンテンツアイテム」や「コンテンツを共有しているユーザ又は『友達』により供給されたニュースフィード」を含むから,上記ゲートウェイは「サービス・クラウドのライブ・データ・フィード・ゲートウェイ」といえると主張するが,上記(1)の点に関し,その根拠が明確にされているとはいえない。
(3) 以上の点は,原告が取消事由として主張するものではないが,特許庁において更なる審理判断がされることを考慮して判示するものである。7相違点4に係る構成の容易想到性について(1) 引用発明と甲5技術は,いずれもサーバにコンテンツを取り込む方法に係るものであるという点で技術的な共通性を有するといえ,引用発明に甲5技術を適用することは,当業者が容易に想到し得たことであるといえる。そして,引用発明に甲5技術を適用した発明は,OTTデバイスに表示するための「画像データが表\す画像の被写体種類(シーン)を解析して,画像の色を,被写体種類ごとに予め記憶された目標濃度に補正する」構\成を備える方法ということができ,この構成は,本願発明8の構\成F2の「前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを,前記デジタル・メディア・コンテンツ取込エンジンにより解析する」構成に相当するということができる。よって,相違点4に係る構\成を採用することは,当業者が容易に想到し得たことである。(2)ア原告は,本願発明における解析は,ユーザが視聴するための,映画やテレビ番組等のコンテンツをディスプレイ装置に送信するために行われるものであるところ,ユーザにおいてそれらの画像の特定の部分(顔等)を調整したいという要求はないから,甲5技術に係る「画像データが表す画像の被写体種類(シーン)を解析して,画像の色を,被写体種類ごとに予\め記憶された目標濃度に補正する」構成は,本願発明8の構\成F2には相当しないと主張する。
しかし,本願発明8の構成F2は,「ディスプレイ装置上に表\示するための」「デジタル・コンテンツ・アイテムを,前記デジタル・メディア・コンテンツ取込エンジンにより解析する」というもので,「解析」の具体的な内容については記載されていない。そして,本願発明8の構成中に,「デジタル・コンテンツ・アイテム」について,原告の主張するような内容のものに特定する旨の記載もなく,他に本願発明8の構\成F2の「解析」を原告の主張するように限定して解釈すべき理由はない。したがって,原告の上記主張は,その前提を欠くものであって,採用することができない。イ原告は,本願明細書の段落【0119】の記載から,本願発明8の構成F2の「解析」は,ビジュアル及び音響コンテンツの両方に対して行われ得るもので,甲5技術の「解析」とは異なる旨を主張するが,本願の特許請求の範囲の請求項8には,「音」について何ら記載がなく,上記アのような記載があるのみであるから,本願発明8の構\成F2の「解析」が音響に対しても行われるものと解することはできない。したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ原告は,引用発明と甲5技術とを組み合わせる動機付けはなく,シーンごとに画像の特定の部分を調整するために,オペレータの好みに従って事前に手動で入力される「目標濃度」を用い,オートセットアップ機能を介して,画像を調整するという甲5技術の「解析」の特徴は,特定の装置の技術的仕様に画像をより良好に適合させるために画像の調整を行う本願発明の「解析」とは対照的であって,甲5技術の「解析」を本願発明に組み込むことは,無意味であり,逆効果であると主張するが,上記アで指摘したのと同様,本願発明8における「解析」について,特定の装置の技術的仕様に画像をより良好に適合させるために画像の調整を行うためのものと限定して解釈すべき理由はないから,原告の上記主張も,前提を欠くものであって採用することができない。\n
8まとめ
以上によると,原告主張の取消事由のうち,相違点の認定の誤り及び相違点4に係る容易想到性の判断の誤りは,いずれも理由がないが,相違点1に係る容易想到性の判断の誤り及び相違点2に係る容易想到性の判断の誤りは,いずれも理由がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.08.10
令和3(行ケ)10026 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年7月29日 知的財産高等裁判所
結合商標の類否判断の方法について
(1) 商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,かつ,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,各構\成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合は,一つの称呼,観念が他人の商標の称呼,観念と同一又は類似であるといえないとしても,他の称呼,観念が他人の商標のそれと類似するときは,両商標はなお類似するものと解するのが相当である(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁参照)。
(2) この点について,原告は,結合商標の一部を分離,抽出して商標の類否を判断することは,「商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合」や,「それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合」などの場合に限られるべきであると主張する。しかし,原告が挙げる上記の場合以外にも,「各構\成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合」には,分離して観察することが許されると解するのが相当である。原告が引用する最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁も,このことを否定するものとは解されない。
(3) そして,以上の(2)で述べた事情などを総合的に考慮して,結合商標の一部を分離,抽出して商標の類否を判断することが許されるかどうかを判断することが相当であると解される。
2本願商標について
(1)本願商標は,朱色の半楕円と同色縞模様の半楕円を斜めに接するように組み合わせてなる図形を配した本願図形部分と,その右にやや図案化された「SANKO」の欧文字を本願図形部分と同様の朱色で横書きした本願文字部分からなるところ,図形と文字という構成要素の性質の違いや,本願図形部分の上部が本願文字部分の上部よりも少なからず上にはみ出す形となっていることのほか,本願文字部分については容易に「サンコ」又は「サンコー」という称呼を有する部分として理解されることからすると,本願図形部分と本願文字部分とは,外観上,明確に分離して看取されるものであるといえる。そうすると,本願図形部分及び本願文字部分について,それらの部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえない。
(2) 上記のとおり容易に特定の称呼を有する部分として理解される本願文字部分は,本願商標の構成の大きな部分(7割以上)を占めている。そして,「SANKO」の文字は,辞書等に載録のない語であるから,特定の観念を生じないものである。そうすると,本願文字部分は,需要者の印象に残りやすく,強い印象を与えるということができる。
(3) これに対し,本願図形部分については,その形状に照らし,称呼を有しない図形であるのか,一定の文字を図案化したものであるのか,一見して直ちに明確なものであるとはいい難いが,商標において,企業等の名称の文字の一部が図案化される例は少なからずあると解されることや,本願文字部分の冒頭の文字が「S」であることからすると,本願図形部分は,「S」を図案化したものであると理解することも可能であるといえ,その場合には本願図形部分から「エス」の称呼が生じ得る。もっとも,本願文字部分の冒頭の文字が「S」であることからすると,本願図形部分が「S」を図案化したものと理解される場合においては,本願文字部分の冒頭の「S」を取り出して特に図案化して配置したものにすぎず,本願文字部分と独立した意味を有するものではないとの理解がされることも多いものとみることができる。\n
(4)上記(1)〜(3)からすると,本願商標については,本願文字部分のみによって商標の類否を判断することも許されるということができる。したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「サンコー」又は「サンコ」の称呼が生じ,特定の観念を生じないものである。
3 引用商標1,2及び4について
(1) 証拠(乙3,5,6)によると,引用商標1,2及び4について,本件審決が認定した前記第2の3(2)ア(ア),(イ)及び(エ)のとおりに認められる。
(2)引用商標1は,やや図案化された「SANCO」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して,「サンコー」又は「サンコ」の称呼を生じる。「SANCO」の文字は,辞書等に載録のない語であり,特定の観念を生じない。
(3)引用商標2及び4は,水色の雫を重ねたような図形を配し,その下にやや図案化された「SANCO」の欧文字を青色で横書きしてなるところ,引用商標2及び4を構成する図形部分と,「SANCO」の文字部分は,視覚上,明確に分離して看取されるものであり,それらが常に一体となって特定の観念を生じるものともいえないから,文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能\を果たすものといえる。したがって,引用商標2及び4は,その構成文字に相応して「サンコー」又は「サンコ」の称呼を生じる。「SANCO」の文字は,辞書等に載録のない語であり,特定の観念を生じない。4本願商標と引用商標1,2及び4の類否引用商標1,2及び4の「SANCO」の欧文字は,本願文字部分である「SANKO」と,外観の全体的な印象において近似するものであるといえる。そうすると,本願商標と引用商標1,2及び4は,文字部分の比較において,観念を比較できないとしても,その外観は近似し,いずれも「サンコー」又は「サンーコ」の称呼を共通にするものであるから,これらを総合的に勘案すると,両商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
5 以上のとおり,本願商標は,引用商標1,2及び4と類似する商標であるところ,本願商標が引用商標1,2及び4の指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものであることについては,当事者間に争いがない。よって,本願商標は,商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断に誤りはなく,原告主張の審決取消事由は認められない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.08.10
令和2(行ケ)10151等 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年7月29日 知的財産高等裁判所
1 取引に係る認定事実
(1) 証拠(甲6の2,甲12の2,甲20,23,24)によると,1)原告が,愛知県在住の特定人(以下「A」という。)から,令和2年1月10日,PayPalで1万7940円の支払を受けたこと及び2)同支払を原告に連絡するPayPalからのメールには,同支払金額について,「エクス:バイアージュ6個(送料無料)」,「¥17,940JPY」が,数量「1」であるとの記載があることが認められる。また,証拠(甲13の2)によると,3)問い合わせ番号「6271−4993−2452」のレターパックプラスについて,令和2年1月12日に福岡県で引受けがされ,同月13日に愛知県の届け先に届けられたことが認められる。さらに,証拠(甲7の2,甲28の3)及び弁論の全趣旨によると,4)原告が「6271−4993−2452」と記載されたレターパックプラスの追跡番号シールを所持しており,同シールは,本件納品書写し(甲7の2)と同一内容の納品書の控え(甲28の3)の裏面に貼付されていることが認められる。\n
(2) 本件チラシ(甲4)には,「送料無料」,「美容クリーム(エクスバイアージュ)¥2,990」との記載がある。また,原告が提出する別のチラシ(甲3)には,「特別販売(2,990円&送料無料)」,「感謝を込めて【1個2,990円&送料無料】の特別販売続行中」との記載がある。なお,同チラシには,「EX:biargue(エクスバイアージュ)」について「40,000円(税込)」との記載もある。さらに,本件サイト(甲5)には,「EX:biargue」との表示がされたクリームの瓶の写真及び本件使用商標1−2の表\\示(別紙3の2)の右側に,「特別販売キャンペーン」,「1個(送料無料)2,990円」,「6個(送料無料)17,940円」などの記載がある。以上の各チラシ及び本件サイトの各記載は,上記(1)2)の事実と整合するもので,上記(1)2)の事実と合わせると,上記(1)1)のAからの支払が,本件チラシに記載された「美容クリーム(エクスバイアージュ)」(本件使用商品1)6個の代金の支 払であることを推認させるものである。
(3)ア本件納品書写し(甲7の2)及びこれと同一内容で上記(1)4)のとおり裏にレターパックプラスの追跡番号シールが貼付された納品書の控え(甲28の3)の記載内容をみると,「今回の商品配送詳細【無料】」,「【商品名】日本郵便・レターパックプラス(対面でのお受取)」,「【追跡番号(商品番号)】627149932452」との記載のほか,「商品」として「美容クリーム」,「単価」として「¥2,990」,「個数」として「6」,「計」として「¥17,940」,「備考」として「送料無料」の記載があり,宛名欄にはAの氏名の記載がある。そして,本件納品書写し及び上記納品書の控えには,上部に,「DOLGES」の文字の下に「D」及び「S」を重ねるように組み合わせて円で囲んだ図形を配置した商標(以下「本件使用商標1−3」という。)が表\\示され,右下部に本件使用商標2−2が表示されている。\n
イ上記アの事実に,上記(1)1)〜4)の事実及び上記(2)のとおり推認される事実を併せ考慮すると,原告が,上記(1)1)の令和2年1月10日のAからの支払を受けて,本件チラシに記載された「美容クリーム(エクスバイアージュ)」(本件使用商品1)6個を発送し,それが同月13日に愛知県在住のAに届けられたという事実が推認され,この推認を覆す事情は認められない。
(4) 原告の本人尋問における供述及び陳述書(甲25)の記載(以下,併せて「原告供述等」という。)によると,原告が,上記(1)1)の令和2年1月10日のAからの支払を受けて,本件使用商品1(6個)に,本件納品書の写し(甲7の2)の原本及び本件チラシ(甲4)を同封したレターパックプラスを発送し,それが同月13日にAに届けられたという取引(以下「本件取引」という。)の事実が認められる。原告供述等は,上記(1)〜(3)で指摘した各事実と整合しており,本件取引について述べる部分について,その信用性を否定すべき事情は見受けられない。2本件商標1及び2の使用について(1)ア本件チラシ(甲4)には,本件使用商標1−1を紙製の外装箱に表示し\nた美容クリームである本件使用商品1の写真(別紙3の1)が掲載されているとともに,本件使用商標2−1を容器側面に表示した美容ミストである本件使用商品2の写真が掲載されている。本件チラシは,原告が作成したものである(原告供述等,弁論の全趣旨)。
イ本件納品書写し(甲7の2)には,前記1(3)アのとおり,本件使用商標1−3が表示されている。本件納品書写しの原本は,原告が作成したものである(原告供述等,弁論の全趣旨)ウ本件使用商標1−1及び1−3は,本件商標1と,本件使用商標2−1は,本件商標2と,それぞれ社会通念上同一であると認められる。\n
(2) 上記(1)の事実及び前記1(4)のとおり認められる本件取引の事実からすると,本件商標1及び2の商標権者である原告が,要証期間内である令和2年1月10日から同月13日までの間に,本件商標1の指定商品のうち「化粧品」に含まれる本件使用商品1について,本件商標1の使用(商標法2条3項2号[商品の包装に標章を付したものの譲渡],8号[広告に標章を付して頒布])をするとともに,本件商標2の指定商品のうち「化粧品」に含まれる本件使用商品2について,本件商標2の使用(同項8号[広告に標章を付して頒布])をしたものと認められる。
2021.07.29
令和3(行ケ)10003 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年7月19日 知的財産高等裁判所
被告は,平成28年頃,本件サービスの有料会員のみが閲覧可能な本件ウェ\nブサイトの本件トップページ(甲15)に本件使用商標が表示された本件バナ\nーを,本件バナーのリンク先の「美少女図鑑 作品一覧」の見出しがある本件 ウェブページ(甲17)に本件バナーの画像をそれぞれアップロードして,本 件バナー及びその画像を掲載したこと,ファンプラス社が,令和2年4月1月 以降,本件トップページ及び本件ウェブページにそれぞれ本件バナー及びその 画像を継続的に掲載したことにより,被告又はファンプラス社が要証期間内に 本件使用商標を使用した旨を主張するので,以下において判断する。
(1) 甲15は,本件トップページを印刷した書証であり,甲15には,「Fの ぶらり商店街」の見出しの下に,別紙記載の本件バナーを含む複数のバナー が表示されている。また,甲17は,本件ウェブページを印刷した書証であ\nり,甲17には,「美少女図鑑 作品一覧」の見出しの下に,本件バナーの 画像が表示され,その画像の下には,複数の電子写真集のサムネイルが表\示 されている。本件バナーには,別紙記載のとおり,女性を被写体とする3枚 の写真(本件写真1ないし3)を背景に,白く縁取りされたピンク色の書体 の「美少女図鑑」の文字からなる本件使用商標が表示されている。\nそして,証拠(甲15,17,32)及び弁論の全趣旨によれば,本件ト ップページに表示された本件バナーのリンク先が本件ウェブページであるこ\nと,本件ウェブページに表示された各サムネイルの横には,例えば,「女子\n校生 先輩は僕のいいなり A 2018−09−01」,「女子校生 純 白 B 2018−09−01」等の記載があることが認められる。 しかしながら,甲15及び17は,いずれも要証期間経過後の本件審判請 求後に印刷されたものであるから,甲15及び17が存在するからといって, 要証期間(平成29年6月18日から令和2年6月17日までの間)に,本 件トップページ及び本件ウェブページに本件バナー及びその画像が表示され\nていたものと直ちに認めることはできない。 また,本件バナーのアップロード時のログ等の電子記録は提出されておら ず,平成28年頃,本件トップページ及び本件ウェブページに本件バナー及 びその画像がアップロードされて掲載されたことを客観的に裏付ける証拠は 存在しない。
もっとも,甲17には,本件ウェブページに表示された各サムネイルに係\nる「2018−09−01」等の日付の記載があるが,これらの日付は,当 該サムネイルに係る電子写真集の販売開始日等を示したものとうかがわれ, また,本件バナーのアップロード時期とサムネイルのアップロード時期が当 然に同じ時期になるものとはいえないから,これらの日付から,本件バナー が平成28年頃にアップロードされたものと認めることはできない。
(2)次に,C作成の令和3年4月14日付け陳述書(乙3)中には,1)Cが代 表取締役を務める友ミュージック社は,およそ5,6年前に,被告の依頼を\n受け,本件ウェブサイトの会員限定ページに本件バナーをアップロードした, 2)同ページの本件バナーとリンクさせる形で,美少女図鑑のコンテンツ用ペ ージをアップロードした,3)その後,本件バナーはアップロード時と同じ状 態で会員限定ページに掲載され続けており,現在に至るまで本件バナーに変 更を加えていない旨の記載部分がある。 しかし,上記記載部分によっても,本件バナーのアップロードの時期は, およそ5,6年前とあいまいであるのみならず,上記記載部分は,本件使用 商標を表示する本件トップページ及び本件ウェブページをアップロードした\n時期が「2015年3月25日」であることを証明する旨のC作成の令和2 年9月23日付け証明書(甲20)の記載部分と齟齬するものであるから, 措信することができない。
また,G(以下「G」という。)作成の令和3年6月11日付け陳述書(乙 8)には,1)Gは,被告に在籍していた,今から5,6年前,被告が保有す るコンテンツ(乙5ないし7)から女性3名の写真と本件使用商標を使用し て,本件バナーを作成し,友ミュージック社に依頼して,本件ウェブサイト の有料会員のみが閲覧できる本件トップページに本件バナーを掲載し,本件 バナーのリンク先において,年齢の若い女性を被写体とするコンテンツを一 覧化した本件ウェブページを作成した,2)本件バナーに表示された女性3名\nの写真は,直近1,2年前に出版された,女子高生シリーズの中で比較的新 しい3冊の写真集から選んだものである,3)その後,本件バナーはアップロ ード時と同じ状態で会員限定ページに掲載され続けており,現在に至るまで 本件バナーに変更を加えていない旨の記載部分がある。 しかし,上記記載部分によっても,本件バナーのアップロードの時期は, およそ5,6年前とあいまいであるのみならず,本件バナーの背景の本件写 真1ないし3は,Cが挙げる乙5ないし7(電子写真集1ないし3)記載の 写真と異なる構図の写真であるから,乙5ないし7は,本件バナーのアップ\nロードが平成28年頃にされたことを直ちに裏付けるものでないことからす ると,上記記載部分は措信することができない。 したがって,乙3及び8から,本件トップページ及び本件ウェブページに それぞれ本件バナー及びその画像が掲載されたことを認めることはできない。 他に本件使用商標が表示された本件バナー及びその画像が要証期間内に\n本件トップページ及び本件ウェブページに掲載されていたことを認めるに足 りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2021.07.27
令和2(ネ)10044 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年6月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 非侵害論主張5)について
ア 自白の成否及び時機に後れた攻撃防御方法該当性
一審原告は,非侵害論主張5)は,原審の答弁書記載の認否によって成立 した自白の撤回に当たり,また,時機に後れた主張でもあるから,許され ない旨主張する。 たしかに,一審被告は,原審答弁書における構成要件1A等の認否に際\nし,被告給油装置の電子マネー媒体が本件発明の「記憶媒体」に当たると の対比を明確に争っていたわけではないが,従前から,被告給油装置が本 件発明の技術的思想を具現化したものでないことを主張しており,非侵害 論主張5)は,これを,使用される決済手段の差異(プリペイドカードと非 接触式ICカード)という観点から論じたものであるといえるから,一審 被告が充足論全体について単純に認めるとの認否をしていない以上,自白 を撤回して新たな主張をしているとはいえないし,この主張を時機に後れ たものとして扱うのも相当ではない。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
イ 非接触式ICカードの「記憶媒体」該当性
本件明細書において,本件発明の「記憶媒体」の具体的態様としては, 磁気プリペイドカード(【0033】)のほか,「金額データを記憶する ためのICメモリが内蔵された電子マネーカード」(【0070】)や 「カード以外の形態のもの,例えば,ディスク状のものやテープ状のもの や板状のもの」(【0071】)も開示されている。このように,本件発 明の「記憶媒体」は必ずしも磁気プリペイドカードには限定されない。 しかしながら,本件発明の技術的意義が上記1のとおりであることに照 らして,「媒体預かり」と「後引落し」との組合せによる決済を想定でき る記憶媒体でなければ,本件3課題が生じることはなく,したがって,本 件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことになら\nないから,上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は,本件発明 の「記憶媒体」には当たらない。 かかる見地にたって検討するに,被告給油装置で用いられる電子マネー 媒体は非接触式ICカードであるから,その性質上,これを用いた決済等 に当たっては,顧客がこれを必要に応じて瞬間的にR/Wにかざすことが あるだけで,基本的には常に顧客によって保持されることが予定されてい\nるといえる。そのため,電子マネー媒体に対応したセルフ式GSの給油装 置を開発するに当たって,物としての電子マネー媒体を給油装置が「預か る」構成は想定し難く,電子マネー媒体に対応する給油装置を開発しよう\nとする当業者が本件従来技術を採用することは,それが「媒体預かり」を 必須の構成とする以上,不可能\である。 そうすると,被告給油装置において用いられている電子マネー媒体は, 本件発明が解決の対象としている本件3課題を有するものではなく,した がって,本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから,本件 発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきである。むしろ,電子 マネー媒体を用いる被告給油装置は,現金決済を行う給油装置において, 顧客が所持金の中から一定額の現金を窓口の係員に手渡すか又は給油装置 の現金受入口に投入し,その金額の範囲内で給油を行い,残額(釣銭)が あればそれを受け取る,という決済手順(これは乙4公報の【0002】 に従来技術として紹介されており,周知技術であったといえる。)をベー スにした上,これに電子マネー媒体の特質に応じた変更を加えた決済手順 としたものにすぎず,本件発明の技術的思想とは無関係に成立した技術で あるというべきである。一審被告の非侵害論主張5)は,このことを,被告 給油装置の電子マネー媒体は本件発明の「記憶媒体」に含まれないという 形で論じるものと解され,理由がある。
ウ 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は,本件発明の「記憶媒体」は,構成要件1C及び1Fの動\n作に適した「記憶媒体」であれば足りる旨主張する。 しかしながら,発明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであ るから,発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義を解\n釈するに当たっては,発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果 に関する明細書の記載を参酌し,当該構成によって当該作用効果を奏し\n当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべ きである。しかるに,一審原告の上記主張は,かかる観点からの検討を せず,形式的な文言をとらえるにすぎないものであって,失当である。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 一審原告は,本件明細書の【0070】に「記憶媒体」として「金額 データを記憶するためのICメモリが内蔵された電子マネーカード」を 例示する記載があり,非接触式ICカードもこれに含まれる旨主張する。 しかしながら,上記記載は,【0033】の「プリペイドカード71 は,磁気カードからなり」等の記載を受けて,カードの記憶素子が磁性 材ではなくICメモリであっても良い旨を示すにとどまり,そのカード が非接触で動作することを示す記載ではない。また,上記記載において, ICメモリは「金額データを記憶するための」ものであって,非接触式 ICカードのように演算・通信の機能を有することは開示も示唆もされ\nていないから,上記記載を根拠に非接触式ICカードが本件発明の「記 憶媒体」に当たるとはいえない。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 一審原告は,非接触式ICカードが券売機に取り込まれて使用され得 ることは周知であり,本件明細書には設定器内部にカードを取り込んだ ままとしない記憶媒体を用い得ることが示されているから,非接触式I Cカードが本件発明の「記憶媒体」に当たらないとはいえない旨主張す る。 しかしながら,前掲前提事実のとおり,被告給油装置において電子マ ネー媒体を使用する際には,電子マネー媒体(非接触式ICカード)は R/Wにかざされるだけであって装置に「取り込まれ」ることはない。 非接触式ICカード一般に一審原告主張のような使用態様はあり得るも のの,被告給油装置ではそのような使用態様によらずに非接触式ICカ ードが「電子マネー媒体」として用いられているので,被告給油装置に おける「電子マネー媒体」の技術的意義は,本件発明における「記憶媒 体」のそれとは異なる。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(3) 充足論についての小括
以上によれば,一審被告の非侵害論主張4)及び5)は理由があるから,その 余の非侵害論主張の成否について判断するまでもなく,被告給油装置及び被 告プログラムは本件特許を侵害しない。
4 争点4(無効論)について
念のため,仮に,本件発明1の「先引落し」金額は顧客が指定する場合を含 み(上記3(1)イ(イ)参照),また,非接触式ICカードも本件特許の「記憶媒 体」に含まれる(上記3(2)イ参照)とした前提で,無効論につき検討する。 なお,本件において,無効論は,本件発明1及び本件発明3(本件訂正後の もの)について検討すれば足りる。このことは,上記「第3」4の冒頭に説示 したとおりである。
(1) 「時機に後れた攻撃防御方法」該当性について
無効主張A,B,Dは,原審における侵害論の心証開示後に主張されたも のであり,そのため,原審においては時機に後れたものとして取り扱われた わけであるが,既に充足論に関する項で指摘したとおり,構成要件1C1充\n足性(非侵害論主張4))及び構成要件1A,1C,1F3,1F4充足性\n(非侵害論主張5))に関する原審の主張整理には,本来は,争いがあるもの として扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったとい わざるを得ない。そして,無効論に関する主張の要否や主張の時期等は,充 足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるか ら,充足論について,本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えら れる本件においては,無効主張が原審による心証開示後にされたという一事 をもって,時機に後れたものと評価するのは相当ではない。 また,上記無効事由に関する当審における無効主張は,控訴後速やかに行 われたといえる。 以上によると,一審被告による上記無効主張は,原審及び当審の手続を全 体的に見た観点からも,また,当審における手続に着目した観点からも,時 機に後れたものと評価することはできない。 したがって,いずれの無効主張も,時機に後れた攻撃防御方法として却下 すべきものではない。
・・・
ウ 相違点の容易想到性
上記の表において一致点とされていない本件発明1の構\成は,相違点と なる。 しかしながら,いずれの構成も,セルフ式GSの給油装置において,審\n判甲B1装置の現金による支払を,電子マネー媒体による支払に置き換え る際には,当然に備わる構成である。すなわち,上記の各相違点をまとめ\nると,本件発明1においては装置がR/Wを備えること,電子マネーの金 額データはR/Wにより電子的に書き換えられること,の2点となるが, いずれの構成も,現金の場合は貨幣という有体物に化体されている金銭的\n価値を,電子的情報という無体物に化体させたことによって必然的に生じ る帰結である。 また,現金による支払を電子マネー媒体による支払に置き換えること自 体は,電子「マネー」という名称自体からも容易に着想することができる し,例えば乙16の12(電子商取引推進協議会「モバイルECに関わる 決済標準モデルの研究中間報告書」平成13年3月発行)には,非接触式 ICカードが「電子マネー」として利用されること,FeliCa内蔵の携帯電 話は「電子財布」になること等が記載されており,これらの記載は,現金 による支払いを電子マネー媒体に置き換えることを動機付ける。 そうすると,当業者にとって,上記各相違点にかかる本件発明1の構成\nに想到することは,通常の創作能力の発揮にすぎず,容易であったといえ\nる。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.07.27
令和3(行ケ)10013 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年7月20日 知的財産高等裁判所
事案の性質に鑑み,まず本件商標の使用の有無の点から検討,判断する。 商標法は,50条において,「日本国内」において「商標権者,専用使用権 者又は通常使用権者」のいずれかが「不使用取消審判請求に係る指定役務」 のいずれかについての登録商標の「使用」をしていることを商標権者が証明 しない限り,当該指定役務について当該商標の登録が取り消されると定め, また,2条において,商標とは「業として」使用するものであり,その「使 用」とは,同条3項各号に列記されているのものに限ることを定めている。 したがって,本件において,商標権者である原告は,本件サービス又は本 件チャンネルにおける本件商標の使用が,日本国内において原告又はリンガ フランカ社によって,本件指定役務について,業務に係る標章として同条3 項各号に列記されている態様で行われていることを立証することを要する。
(2)本件サービスにおける本件商標の使用について
ア 前記1(8)のとおり,本件サービスに係る会員認証ページ(甲8)には, 本件商標と同一の商標が表示されており,また,同(1)ウ及び(3)のとおり, 本件サービスは日本国内における日本人も対象としていることが明らか であるから,本件商標は,日本国内において使用されているといえる。 しかしながら,上記ページは,要証期間経過後で本件審判請求がされた 後の平成31年4月16日に印刷されたものにすぎず,要証期間に同ペー ジに本件商標が表示されていたことを直ちに明らかにするものではない\nし,自己のウェブサイトの表示を変えることは容易であるから,この証拠\nだけから要証期間に本件商標が表示されていたことを推認できるもので\nもない。 したがって,要証期間に本件サービスで本件商標が使用されていること を認めるに足りる証拠はないというべきである。
イ 仮に,要証期間に本件サービスに係る会員認証ページに本件商標が表示\nされていたとしても,本件商標は本件指定役務の範囲に含まれる役務につ いて使用されているとはいえない。 すなわち,本件指定役務のうち,「語学に関する知識の教授」,「国際文化 に関する知識の教授」又は「教育研修のための施設の提供」は,人に対す る教育又は知能を開発するための役務であるが,本件サービスは,会員が\nSNSを利用して会員同士で情報発信,情報交換をするものであり,その 際に使用できる言葉をグロービッシュの基本単語1500語又はその派 生語に限定したというにすぎず,実態としては個人間の交流の場を提供し ているだけのサービスである。したがって,本件サービスが主体的に知識 の教授や教育研修を行っているとはいえず,本件サービスを利用すること でグロービッシュについての能力が向上することがあるとしても,それは,\n単なる副次的な作用,効果にすぎない。 そうすると,本件サービスの提供は,「語学に関する知識の教授」,「国際 文化に関する知識の教授」又は「教育研修のための施設の提供」のいずれ にも該当しないというべきである。
ウ したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件サービスに おいて,要証期間に上記各指定役務について本件商標の使用がされていた とは認められない。
(3) 本件チャンネルにおける本件商標の使用について
ア 前記1(4)のとおり,本件動画1)ないし4)には,その冒頭に本件商標と同 一の商標が使用されており,また,本件サービスやグロービッシュ・ラー ニング・センターの案内を内容とするなど日本国内における日本人を対象 としていることが明らかであるから,当該商標は日本国内において使用さ れているといえる。 また,前記1(4)のとおり,本件動画1)ないし4)の投稿日は要証期間開始 前の平成25年3月9日から同年7月9日にかけてであるところ,要証期 間経過後である令和2年10月9日時点においても本件動画1)ないし4) を視聴することが可能であり,同日時点の本件動画1)の視聴回数が750 回,本件動画2)の視聴回数が1125回,本件動画3)の視聴回数が431 回,本件動画4)の視聴回数が437回となっているから(甲10),要証期 間に本件動画1)ないし4)が視聴され得る状態であったことは十分に推認\nすることができる。したがって,要証期間に本件商標が本件チャンネルに おいて使用されたことが認められる(なお,被告は,要証期間に本件チャ ンネルが閉鎖されていた可能性を否定することはできない旨主張するが,\n閉鎖されていたことを疑うに足りる事情は見当たらない。)。
イ しかしながら,本件サービスの提供は,前記(2)イで判示したとおり,「語 学に関する知識の教授」又は「国際文化に関する知識の教授」,さらには「語 学教育に携わる教師の育成のための教育又は研修」のいずれの役務にも当 たらないというべきであるから,本件動画1)ないし4)が本件サービスの案 内を内容とするとしても,それが上記各指定役務に関する「広告」(商標法 2条3項8号)に該当する余地はない。 また,本件動画1)及び2)は,専らグロービッシュそのものの紹介を内容 とするものと把握される動画であって,具体的な役務との関連性が明確に されているとはいえず,この点からも「役務に関する広告」(商標法2条3 項8号)とはいい難いものである。したがって,本件動画1)及び2)におけ る本件商標の使用が,商標法2条3項所定の「使用」に該当するとは認め られない。 さらに,本件動画3)は,専らリンガフランカ社の前記1(1)ウ2)のサービ スの紹介を,本件動画4)は,専ら前記1(1)ウ3)のサービスの紹介を内容と するとものとそれぞれ把握される動画であるところ,前記1(6)及び(7)のと おり,リンガフランカ社は,要証期間前の平成25年9月30日には上記 両サービスを終了させており,原告は,同サービスの運営を引き継いでい ないから,本件動画3)及び4)を「役務に関する広告」(商標法2条3項8号) と捉えるとしても,その内容は,事業として行われていない実態のサービ スに関するものにすぎない。そうすると,本件動画3)及び本件動画4)は, 業として行われている役務について使用されているものではないから,そ こに本件商標が表示されているとしても,その本件商標の使用を商標とし\nての使用と解することはできない。
ウ 以上によれば,本件チャンネルで公開されている動画である本件動画1) ないし4)における本件商標の使用は,いずれにしても商標法2条3項所定 の「使用」とはいえない,あるいは商標的使用とはいえないことになる。
(4) 小括
以上の次第で,本件商標が,要証期間中,本件指定役務のうち,「語学に関 する知識の教授」,「国際文化に関する知識の教授」,「教育研修のための施設 の提供」又は「語学教育に携わる教師の育成のための教育又は研修」の役務 について使用されていたと認めることはできず,また,原告は,本件指定役 務のうち,上記役務を除く役務について要証期間に本件商標が使用されてい る点について具体的に主張立証をしておらず,本件証拠からもその使用をう かがうことはできない。 したがって,要証期間に本件商標が本件指定役務について使用された旨の 立証はないというべきであるから,本件商標の使用者に係る点について判断 するまでもなく,いずれにしても本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2021.07.27
令和2(行ケ)10147 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年6月29日 知的財産高等裁判所
これらによると,「アイテムボックス」は,アイテムを収納するものとしてゲーム 分野で慣用されている語であるとはいえるものの,「アイテムボックス」という記載 をもって,アイテムボックスに収納できるアイテムの数に所定の上限が設けられて いるか否か,アイテムボックスが必ずすべてのアイテムを収納するものであるか否 か,といった特定の仕様が一義的に決まるものではない。 当初明細書に記載の「アイテムボックス」の解釈に当たっては,当初明細書に記 載の「アイテムボックス」が収納上限を設けているという仕様を有していることを 前提としているものといえ,甲12〜14の記載は,当初明細書等に記載の「アイ テムボックス」が収納上限を設けているという前提に対して何らの影響を与えるも のとはいえない。
ウ 原告は,本願発明1は「アイテムボックスに特定アイテムの収納上限が 設けられ」ることを特定しているわけではないから,「アイテムボックスに特定アイ テムの収納上限が設けられている」ことが当初明細書に記載されているか否かは, 本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である旨主張する。 しかし,当初明細書において唯一アイテムボックスに関して記載されている段落 【0051】における「アイテムボックス」に関する記載からは,当該「アイテム ボックス」に収納上限が設けられているものであることが読み取れるのみであるか ら,「アイテムボックス」に特定アイテムを収納するとした場合には,特定アイテム の収納上限が設けられることになるとの解釈が,新たな技術的事項を導入するもの であるか否かを判断する際に考慮すべき事項である。 なお,新規事項の追加の判断は,補正により追加された事項が,当初明細書に記 載された事項から導き出される全ての技術的事項との関係から,新たな技術的事項 が導入されたものであるか否かであるから,本願発明1において「アイテムボック スに特定アイテムの収納上限が設けられ」ることを特定しているか否かは,新たな 技術的事項を導入するものであるか否かの判断に影響するものではない。
エ 原告は,令和2年4月1日付け意見書(甲8)と当初明細書等の記載が 整合するか否かは,本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である 旨主張する。 しかし,原告は,同意見書(甲8)において,当初明細書に記載の「アイテムボ ックス」には収納上限が設けられているということを前提とした主張をしているた め,同意見書の主張と,当初明細書との記載とが整合しているか否かは,新たな技 術的事項を導入するものであるか否かを判断する際に検討すべき事項であって,無 関係というべきではない。
(3) 「特定のアイテム」について
ア 当初明細書の段落【0051】には,「・・・具体的には,ユーザは,付 与される様々な種類の不要なアイテムを,1つの特定のアイテムに変換して所持す ることができるため,・・・」として,「付与される様々な種類の不要なアイテム」 を「1つの」「特定アイテム」に変換して所持することが記載されているところ,「1 つの」特定のアイテムが,「1個の」特定のアイテムのことを意味するのか,「1種 類の」特定のアイテムのことを意味するのかは当初明細書には記載されていない。 しかし,当初明細書の【図3】において,レアリティが「R」のカードが3個の 「特定のアイテム」に変換され,レアリティが「N」のカードが2個の「特定のア イテム」に変換されることが看取でき,すべてのカードが「『1個の』特定のアイテ ム」に変換されるものではないことを踏まえると,当初明細書の段落【0051】 に記載の「1つの」特定のアイテムは,「1種類の」特定のアイテムのことを意味す ると解することができる。 本件審決は,「1つの」特定のアイテムについて,直接的に言及していないものの, 「特定のアイテム」が「1種類」であることを当然の前提とした上で,判断してい る。
イ 当初明細書には,「特定のアイテム」が「上限なくユーザが所持可能とす\nることができる」ものであることが記載されているとともに,当初明細書には「特 定のアイテム」を上限なくユーザが所持可能とするという構\成をとることによって, ユーザは,付与される様々な種類の不要なアイテムを,一つの特定のアイテムに変 換して所持することができるため,不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができることが記載されている。 これらの記載によると,本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定 のアイテムに変換する」ことの技術的意義は,不要なアイテムを,上限なくユーザ が所持可能とすることができる「特定のアイテム」に変換することによって,収納\nすることができるアイテムの数に上限が設けられている「ユーザのアイテムボック ス」が満杯になることを防ぐことであると理解される。
ウ 上記イのような「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換 する」ことの技術的意義に照らすと,当初明細書等に記載の「アイテムボックス」 は,収納上限が設けられているものであるのに対し,当初明細書に記載の「特定の アイテム」は,「上限なくユーザが所持可能とすることができる」ものであるから,\n「アイテムボックス」に収納される「アイテム」と,「特定のアイテム」とでは,所 持可能な数に上限があるかないかという点で,アイテムの性質が異なるといえる。\nまた,当初明細書には,「特定のアイテム」が「他アイテム」とは異なる種類のアイ テムであることが説明されている。 当初明細書の記載に接した当業者は,そこに記載された収納上限が設けられてい る「アイテムボックス」に,上限なくユーザが所持可能とするようにされた「特定\nのアイテム」が収納されると認識することはなく,上限なくユーザが所持可能とす\nるようにされた「特定のアイテム」は,収納上限のある「アイテムボックス」とは 別に管理するものであると認識するというべきである。 また,「特定のアイテム」と,「ユーザに付与される」「他のアイテム」とは異なる 種類のアイテムであることが説明されており,「特定のアイテム」とユーザに付与さ れるアイテムとでは,所持可能な数に上限があるかないかという点で,アイテムの\n性質が異なるものと理解されることからしても,「ユーザ」に付与される「他のアイ テム」がアイテムボックスに収納されるものであるからといって,「特定のアイテム」 がアイテムボックスに収納されるものであると当然に理解するものとはいえない。 以上によると,当初明細書の記載は,上限なくユーザが所持可能とすることがで\nきる「特定のアイテム」を収納上限のある「アイテムボックス」に所持する(アイ テムボックスに収納する)ことを排除していると評価できる。
エ 原告が主張するように,本願発明において,「特定のアイテム」が「アイ テムボックス」に収納されるものであると解した場合には,当初明細書の段落【0 051】にのみ記載されているところの「アイテムボックス」には収納上限が設け られているのであるから,不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換したとして も,(複数個の)1種類の「特定のアイテム」が不要なアイテムとして変換されたア イテムの代わりにアイテムボックスに収納されることとなる以上,(複数個の)「特 定のアイテム」によりアイテムボックスが占有されることになるのであるから,ア イテムボックスが満杯になることを防ぐことができなくなってしまうこととなり, 不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換することにより,ユーザのアイテムボ ックスが満杯になることを防ぐという「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイ テムに変換する」ことの技術的意義を損なうものといえる。
オ 原告は,アイテムの所持とアイテムボックスへの収納とが関連すると主 張する。 しかし,上記(2)の「アイテムボックス」に関する前提や上記イの本願発明におけ る「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義 を踏まえると,当初明細書の段落【0051】の記載は,ユーザに付与された不要 なアイテムを特定のアイテムに変換して,変換した特定のアイテムをアイテムボッ クスに入れることなく上限なしに所持できるようにすることにより,ユーザのアイ テムボックスが満杯になることを防ぐという,原因と結果の関係を示しているとい うべきである。 本件審決は,「1つの特定のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによ りユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる」ことを,当初明 細書の記載を踏まえて,両者を関連付けた上で判断を行っているから,「1つの特定 のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができる」ことを別個独立したものとして捉えている との原告の主張は誤りである。
カ 原告は,当初明細書の段落【0052】は,段落【0051】の記載に 加え,更に「上限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」という構\成を付 加的に採用してもよいこと,その付加的な構成によって「特定アイテムを貯蓄する\n事が可能となり,ユーザの好きなタイミングで特定アイテムを使用する事ができる」\nという効果があることを述べたにすぎないから,新たな発明特定事項が当初明細書 に明確に記載されているか否かは,段落【0052】の記載に左右されるものでは ない旨主張する。
しかし,新規事項の追加の判断は,補正により追加された事項が,当初明細書の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技 術的事項を導入するものであるか否かである以上,本件審決において,当初明細書 の段落【0051】だけでなく,段落【0052】を含めた当初明細書のすべての 記載を総合的に判断して,「アイテムボックス」及び「特定のアイテム」,並びに, 本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」こ との技術的意義を解釈して,新規事項の追加の判断を行ったことに,誤りはない。 なお,本件審決は,本願発明において,「特定のアイテム」が「アイテムボックス」 に収納されるものであると解した場合には,不要なアイテムを「特定のアイテム」 に変換することにより,ユーザのアイテムボックスが満杯になることを防ぐという 「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義を 損なうものであると判断しており,当該判断においては,「特定のアイテム」が「上 限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」ものであるか否かに関係なく,\n「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事項が新規事項 であると判断している。
(4) 以上のとおり,当初明細書には,「特定のアイテム」が「アイテムボック ス」に収納されることが記載されているとはいえず,また,当初明細書の記載から, 「特定のアイテム」が「アイテムボックス」に収納されることが自明であったとも いえないから,「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事 項を追加する補正が,当業者によって当初明細書の全ての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであると した本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.07.26
平成31(ワ)11130 商標権侵害差止請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年6月17日 東京地方裁判所
被告標章2と本件商標を比較すると,これらは外観において明らかに異 なる。他方,被告標章2と本件商標は,「フフフ」の称呼を共通にする場 合がある。もっとも,被告標章2は特定の観念を生じないのに対し,本件 商標は軽く笑う声等の観念を生じ,これらは観念において異なる。
そうすると,被告標章2と本件商標は,称呼において類似する場合があ るとしても,外観,観念において相違しており,その出所について誤認混 同を生じさせるような取引の実情があるとは認められず,同一又は類似の 商品等に使用された場合に,商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれ があるとは認められない。
したがって,被告標章2は本件商標と同一又は類似のものではない。 なお,「富富富」は,被告富山県によって育成された本件米の品種名で あり(前記1(1),(6)),被告富山県は,特に,平成30年秋頃以降,本 件米について積極的に広告,宣伝しており(同(5)),「富富富」が米の 品種名であることは相当程度知られていたと認められる。被告標章2は, この品種名を普通に用いられる方法で表示したものである。\n
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2021.07.16
平成29(ワ)36506 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月19日 東京地方裁判所
原告は,被告に対し,特許法102条3項に基づく損害賠償を請求していると ころ,同項は,「特許権者・・・は,故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を, 自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨規定してい るから,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準とし,そこに, 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 そして,かかる実施に対し受けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施許 諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の 相場等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内 容や重要性,他のものによる代替可能性,3)当該特許発明を当該製品に用いた場 合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,4)特許権者と侵害者との競業関係や 特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定め るべきである(知財高裁平成30年(ネ)第10063号令和元年6月7日大合 議判決参照)。
本件においては,被告アプリが無償で配信されており,被告アプリのユーザが 友だち登録をし,友だち等との間で被告システム等によるメッセージの送受信等 のサービスを享受すること自体により被告に売上げは発生しない(甲73)から, 「侵害品の売上高」をどのように確定すべきかがまず問題となり,次いで,実施 に対し受けるべき料率(相当実施料率)の算定が問題となる。 そこで,それぞれにつき,以下,検討する。
(1) 売上高について
ア 当事者の主張
原告は,被告の事業のうち,本件特許権侵害の対象となる事業は,コア事 業中の「アカウント広告」と「コミュニケーション」の売上げであり,本件 特許登録日である平成29年9月15日から被告が「ふるふる」の提供を終 了した日の前の日である令和2年5月10日までの間(以下「本件損害算定 期間」という。)の売上高(アカウント広告につき合計1519億5800 万円,コミュニケーションにつき767億2800万円)に基づいて損害額 を算定すべきであると主張する。 一方,被告は,主に被告アプリ上でアカウントを有する企業等からの売上 げであるアカウント広告の売上げは損害賠償額算定の対象とならず,仮に, コミュニケーションの売上げが損害賠償額算定の対象となり得るとしても, 対象となるのは本件機能と関係のある部分に限られると主張する。\n
イ 認定事実
そこで検討するに,前記前提事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると, 以下の事実を認めることができる。
・・・
(ウ) 企業等のアカウントとの間の「ふるふる」による友だち登録(被告シス テム等図面【図38】,甲61) LINE@等のサービスを導入している企業等が住所の位置情報をあ らかじめ登録している場合,一般ユーザが被告アプリの友だち追加画面で 「ふるふる」を選択して手元のスマートフォンを振ると,半径1km圏内 の上記企業等も友だち登録の候補として表示され,同ユーザが同企業等に\nつき友だち追加処理をすると,同企業等が同ユーザの友だちとして追加登 録される。
ウ 「ふるふる」以外の友だち登録及び海外企業への輸出に係る売上げ等につ いて
原告は,損害賠償の対象は,「ふるふる」による友だち登録及びこれによ り友だちとなったユーザとの交流等に限定されず,QRコードやID検索等 の他の友だち登録も含み,また,海外企業を含む連結売上高を対象とすべき であると主張する。 (ア) しかし,原告は,本訴提起当初から,一貫して「ふるふる」による友だ ち登録及びその後の交流が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張を していたのであり(前記前提事実(5),被告システム等図面【図2】〜【図 4】,【図34】〜【図44】),その余の友だち登録手段による友だち 登録等が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張立証は侵害論の対象 とされていないので,損害賠償の対象となるのは,「ふるふる」による友 だち登録と相当因果関係のある範囲の売上高に限定されるというべきで ある。
(イ) また,海外企業を含む連結売上高を対象とすべきとの点については,被 告から海外企業への実施品の輸出に係る売上高を対象とする趣旨と考え られるが,原告が侵害論において対象としていた被告の実施行為は,被告 システムの使用と,被告アプリの生産,譲渡及び譲渡の申出にとどまって\nおり,仮に被告システム等が輸出されているとしても,当該被告システム 等に本件機能が搭載されているかどうかといった点も本件の証拠上明ら\nかではないから,この点の原告の主張も採用し難い。
エ 損害賠償の対象となる売上高の範囲について そこで,前記イ(ア)〜(ウ)で認定した事実に基づき,本件において損害賠償 の対象となる売上高の範囲につき検討する。
(ア) アカウント広告の売上げについて
アカウント広告の売上げは,企業等からの売上げに関するものであると ころ,一般ユーザは,かかる企業等との間でも「ふるふる」による友だち 登録をなし得るものの,この場合は,企業等が住所の位置情報をあらかじ め登録している必要があり,また,その際,企業等はスマートフォンを操 作するとは考え難いから,そもそも,この場合に,「近くにいるユーザ同 士がスマートフォン(2)を操作して友だち登録することによりコンピュ ータ(14)を利用してコミュニケーションによる交流」(構成a等)を\n具備するとは認め難く,他にこの場合の被告システム等が本件各発明の技 術的範囲に属するという的確な主張立証はない。 また,前記イ(ア)aに記載されたアカウント広告を構成する各売上げの\n内容に照らすと,これらの売上げは,いずれも,一般のユーザ同士の本件 機能による友だち登録との関係がないか,関係があっても希薄であるとい\nうべきである。 そうすると,アカウント広告の売上げは,本件の損害賠償の対象となら ないと解するのが相当である。
・・・
b 前記aで認定した売上高は,「ふるふる」以外の友だち登録に関する 分も含まれているところ,被告の侵害行為は,「ふるふる」による友だ ち登録に関するものであるから,被告の侵害行為と相当因果関係にある 売上高は,上記売上高に,本件損害算定期間中の「ふるふる」による友 だち登録割合を乗じて算出するのが相当である。そして,前記イ(イ)の とおり,同割合は,●(省略)●であるから,被告の侵害行為と相当因果 関係にある売上高は,●(省略)●となる。 ●(省略)●
(ウ) 以上のとおり,被告の侵害行為と相当因果関係にある売上高は,●(省 略)●となる。
・・・
(2) 相当実施料率について
ア 本件各発明の実施許諾契約における実施料率やその相場等
原告は,原告代表者から専用実施権の設定を受けているが,その設定契約\nの詳細は本件の証拠上明らかでなく,また,原告が他人に本件各発明の実施 を許諾したことをうかがわせる証拠はない。 そこで,相場等につきみるに,証拠(甲157〜159,乙82)によれ ば,電子計算機に係るロイヤルティ(件数719件)は,平均値が33.2%, 最頻値が50.0%,中央値が40.0%とされている一方,「技術分類 コ ンピュータテクノロジー」,「対象となる製品・技術例 計算;係数,チェ ック装置等」におけるロイヤルティ料率の相場は,1%未満,1〜2%未満, 2〜3%未満,3〜4%未満がいずれも16.7%であり,4〜5%未満が 25.0%であるとされている。 しかし,本件においては,被告アプリは無償で配信され,被告アプリのユ ーザが「ふるふる」を使用して友だち登録をし,その後の交流を行うといっ た行為自体による被告の売上げは発生しないという特殊性があることから すれば,上記の相場等を重視することはできない。
イ 本件各発明の価値や代替可能性等\n
本件各発明は,前記1(2)に記載のとおり,初対面の人物同士が出会った 後互いにコンタクトを取ることができるようにする際に,極力個人情報を明 かすことなくコンタクトが取れるようにするためのコンピュータシステム 及びプログラムに関する発明であって,相手方に互いの個人情報を通知する ことなく後々コンタクトを取ることができ,かつ,相手方以外の他人がその 相手方に成りすましてコンタクトしてくる不都合をも防止できる理想的な 連絡可能状態を構\築する手段を提供することを目的として,現実世界で出会 ったユーザ同士がユーザ端末を操作し,コンピュータを利用して交流を行う に当たり,コンピュータ(サーバ)が各ユーザ端末の位置情報を取得し,該 位置情報に基づいて所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索 されたことを必要条件として,該検索されたユーザ端末を新たな交流先とし て交流先のリストに追加して表示させ,ユーザが表\示された複数の交流先の 内からコミュニケーションを取りたい相手を選択指定し,指定された相手と の間でメッセージを送受信できるようにするという手段を採用することで, 互いにコミュニケーションによる交流に同意したユーザ同士が連絡先の個 人情報を知らせ合うことなく交流できるという効果が得られるようにした ことを特徴とする発明である。 このような発明には一定のニーズが存在するものと考えられるから,本件 各発明には相応の価値があるものと認められる。 もっとも,前提事実(6)のとおり,本件特許に関する無効審判請求におい て,特許庁は,本件特許が進歩性を欠く旨の職権審理結果通知をしていると ころ,このことは,実際に本件特許が無効となるか否かはともかく,類似の 技術が存在することを示すものということができる。
ウ 本件各発明の被告の売上げや利益への貢献等
証拠(甲41・3丁)によれば,「ふるふる」を利用する場合の最大の特 長は,複数人と一度に友だちになれることであり,サークルや部活,仕事の チーム,パーティーなど,複数の人が集まる場で活躍しそうであるとされて いることが認められ,これらの事実に加え,前記(1)イ(イ)記載の事実関係に よると,既に友人等であるユーザ同士が友だち登録する方法が多く,実際に もそのようなユーザ同士により友だち登録がされることが多いことがうか がわれることからすると,被告システム等においては「ふるふる」による友 だち登録がされる場合であっても,それ以前に相互の個人情報を交換してい る場合も少なくないものと考えられる。
●(省略)●
被告による企業努力が大きく貢献しているとうかがわれるとこ ろである。 そうすると,被告システム等に係る売上げや利益についての本件各発明の 貢献の度合いは,かなり限定的なものであると認められる。 エ 以上の諸事情,とりわけ,本件各発明には相応の価値があると認められる ものの,これと類似の技術が存在することがうかがわれることや,被告シス テム等に係る売上げや利益についての本件各発明の貢献の程度は限定的な ものであることなどを総合的に考慮すると,本件における相当実施料率は● (省略)●と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.07.15
令和3(行ケ)10010 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年6月30日 知的財産高等裁判所
ア 「パールアパタイト」の語が,一般の辞書等に掲載されていることを認 めるに足りる証拠はない。 一方で,本件商標を構成する「パール」の文字部分は,「真珠」の意味\nを有するものと認められる(甲3,11,12)。
イ 原告は,本件商標の登録査定時において,「アパタイト」の語が,取引 者,需要者の間で,歯の再石灰化を促し美白効果のある「ハイドロキシア パタイト」又は光触媒応用製品に適用可能な「アパタイト」を意味する語\nとして,一般的に広く認識されていた旨主張するので,以下において判断 する。
(ア) 証拠(甲23ないし205(枝番のあるものは枝番を含む。特に断 りのない限り,以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認 められる。
a 株式会社サンギ(以下「サンギ」という。)は,平成5年2月,歯 を白くする美白効果のある歯磨き剤として,「薬用ハイドロキシアパ タイト」を含有する「アパガードM」を発売した。 「アパガードM」は,1995年(平成7年)に放映を開始した「芸 能人は歯が命」のキャッチコピーのテレビCMの効果等によって,ヒ\nット商品となり,1996年(平成8年)には,年間売上げが140 億円を記録した。 「アパガードM」の発売後,同年中には,歯磨き業界大手の他の事 業者(サンスター,ライオン)も,美白効果のある歯磨き剤として, 「ハイドロキシアパタイト」又は「フルオロアパタイト」を配合する 歯磨き剤を製造,販売するようになった(甲146ないし155)。 また,「アパガードM」は,FRIDAY,プレジデント,WED GE等の雑誌(甲175ないし181)において,「薬用ハイドロキ シアパタイト」配合のヒット商品として,取り上げられた。 このほか,「アパガードM」及びその後発品に関する記事が,平成 17年6月14日付けの読売新聞(甲160),平成21年9月14 日付け及び平成22年5月3日付けの日経流通新聞(甲169,17 0),同年6月5日付けの朝日新聞(甲171)や,週刊東洋経済, 日経ヘルス等の雑誌(甲182,183等)に掲載された。
b 「ハイドロキシアパタイト」の語の意義に関し,平成21年7月2 7日付けの朝日新聞(甲27)に,「ハイドロキシアパタイト」は, 「骨や歯,貝殻などの成分。人体への害が少なく,なじみやすいこと から,人工骨や人工歯根などの医用材料に使われている。」,平成2 2年5月29日付けの加藤歯科医院のウェブサイト(甲29)に,「ハ イドロキシアパタイトとはリン酸カルシウムでできた歯や骨を構成す\nる成分のことで,エナメル質は97%,象牙質の70%がハイドロキ シアパタイトで構成されています。」などと掲載された。\nまた,香粧品科学研究開発専門誌フレグランスジャーナル2008 年(平成20年)6月号(甲204)に,「ハイドロキシアパタイト (Ca10(PO4)6(OH) 2)は,リン酸カルシウムの一種であり,歯牙 や骨といった硬組織の主成分であって,化学合成品においても生体に 対する安全性の高い化合物である。・・・工業的には,・・・広範囲な用途に 利用されている。化学合成したハイドロキシアパタイトがそのような 用途に利用されるのは,生体硬組織と直接結合するといった高い生体 親和性やタンパク質,核酸および配糖体との吸着特性を有するためで ある。」(20頁右欄)などと掲載された。 さらに,日本化粧品工業連合会作成の医薬部外品の成分表示名称リ\nストにおいて,「成分名 ヒドロキシアパタイト」,「別名 ハイド ロキシアパタイト」,「本品は,主としてヒドロキシアパタイト(・・・)」 と記載されている(甲139,140)。
c 「アパタイト」の語の意義に関し,材料開発・応用専門誌「ニュー セラミックス」1990年(平成2年)7月号(甲59)に,「アパ タイトはアパタイト構造(六方晶系・・・)をもつ結晶群の総称であるか,\n単にアパタイトといった場合は最も代表的なリン酸カルシウムを意味\nすることが多い。水酸アパタイト(以下,単にアパタイトと略称する。) といえば,Ca10(PO4)6(OH)2 であり,生体アパタイトのモデル物 質である。フッ素アパタイトはCa10(PO4)6(PO4)F2 となる。」 (96頁左欄),「PHOSPHORUS LETTER 2000 年6月第38号」(甲135)に,「アパタイトはM10(ZO4)6X2 の組 成を持つ結晶鉱物の総称であり,次の各元素が単独あるいは複数M, ZO4,Xの位置に入る。M:Ca,Ba,Sr,Mg,Na・・・,ZO4: PO4,AsO4・・・,X:F,OH,Cl・・・このようにアパタイト構造に\nは多くの種類の元素が入り得るために,さまざまな固溶体が生成する。」 (8頁左欄),「PHOSPHORUS LETTER 2010年 2月第67号」(甲138)に,「アパタイトはカルシウムヒドロキ シアパタイト(Ca10(PO4)6(OH)2 :Hap)に代表される塩基性\n金属リン酸塩の一種である。」(22頁左欄)などと掲載されている。
d 応用化学,環境化学,触媒化学,生化学等の各種化学分野の文献等 において,「アパタイト」を含む用語が,ハイドロキシアパタイト(ヒ ドロキシアパタイト)のほかに,フッ化アパタイト二酸化チタン光触 媒(甲35),可視光応答型アパタイト被覆二酸化チタンハーフメタ ル(甲39),水酸アパタイト(甲47,58,64,71,111), フッ素アパタイト(甲50),ハロゲン固溶アパタイト(甲53), Pb2+〜Ag+交換水酸アパタイト(甲56),フッ素アパタイト結 晶(甲60),チタンアパタイト(甲86),カルシウムヒドロキシ アパタイト粒子(甲88)などと使用されている。
(イ) 前記(ア)の認定事実によれば,1)歯を白くする美白効果のある歯磨 き剤として広告宣伝された,「薬用ハイドロキシアパタイト」を含有す る「アパガードM」がヒット商品となり,新聞,雑誌等で取り上げられた 結果,「薬用ハイドロキシアパタイト」又は「ハイドロキシアパタイト」 の語は,一般消費者の間でも,歯や骨を構成する成分であることはある\n程度知られるようになったこと,2)「ハイドロキシアパタイト」は,Ca 10(PO4)6(OH)2 の化学式で表される,リン酸カルシウムの一種である\nこと,3)「アパタイト」は,M10(ZO4)6X2 の組成をもつ結晶鉱物の総称 であり,M,Z及びXには複数の種類の元素が入り得るため,特定の化 合物を指すものではなく,「ハイドロキシアパタイト」は,アパタイトの 一種(Mがカルシウム(Ca),Zがリン(P),Xが水酸基(OH)の もの)ではあるが,アパタイトそのものを意味するものではないことが 認められる。 加えて,「アパタイト」の文字は,その称呼から,英単語「appet ite」(「本能的欲望,(特に)食欲」)(甲17)又は「apati\nte」(「燐灰石。ハイドロキシアパタイト」)(甲16)に通じるもの である。
以上の認定事実に照らすと,前記(ア)の冒頭掲記の証拠(甲23ない し205)から,「アパタイト」の語が,本件商標の登録査定時におい て,取引者,需要者の間で,歯の再石灰化を促し美白効果のある「ハイド ロキシアパタイト」又は光触媒応用製品に適用可能な「アパタイト」を\n意味する語として,一般的に広く認識されていたものと認めることはで きず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。かえって,「アパタイト」 は,M10(ZO4)6X2 の組成をもつ結晶鉱物の総称であって,具体的な特定 の物質を表するものではなく,このことからしても「アパタイト」が特\n定の意味合いを理解させるものとはいえない。 したがって,原告の前記主張は,採用することができない。
ウ 前記ア及びイによれば,本件商標は,「真珠」の意味を有する「パール」 の文字と,特定の意味合いを理解させるものとはいえない「アパタイト」 の文字とからなる結合商標であり,その構成全体から,特定の意味合いを\n認識することはできないから,特定の商品の品質を直接的に表示するもの\nと認めることはできない。 したがって,これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
エ これに対し原告は,本件商標の登録査定時において,「アパタイト」の 語が,取引者,需要者の間で,歯の再石灰化を促し美白効果のある「ハイ ドロキシアパタイト」又は光触媒応用製品に適用可能な「アパタイト」を\n意味する語として,一般的に広く認識されており,「アパタイト」という 成分に着目して商品の購入に及ぶといった取引の実情があったことを考 慮すると,「パール」と「アパタイト」とが結合した「パールアパタイト」 の語から構成される本件商標は,「真珠」及び「アパタイト(ハイドロキ\nシアパタイト)」という物質(化学物質)を想起させるものであるから, 「真珠」及び「アパタイト(ハイドロキシアパタイト)」を含有するとい う商品の品質を表示する旨主張する。\nしかしながら,前記イで説示したとおり,「アパタイト」の語が,取引 者,需要者の間で,歯の再石灰化を促し美白効果のある「ハイドロキシア パタイト」又は光触媒応用製品に適用可能な「アパタイト」を意味する語\nとして,一般的に広く認識されていたものと認めることはできない。 また,「パールアパタイト」の語は,一般の辞書等に掲載されていない 造語であって,具体的な特定の商品を示すことを認めるに足りる証拠はな いのみならず,「パールアパタイト」の語から,「真珠」そのものと「ア パタイト(ハイドロキシアパタイト)」とを成分に含有する具体的な商品 を一般に想起することを認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.07.15
平成31(ワ)8117 損害賠償等請求(商標権侵害)事件 商標権 民事訴訟 令和3年6月28日 東京地方裁判所
(1) 法38条2項に基づく請求について
原告は,原告商標を自ら使用していないものの,市島酒造社らに対して原 告商標の通常使用権を許諾し,市島酒造社らが原告商標を継続して使用して いるから,法38条2項に基づく請求が認められると主張する。 この点,前記2(1)ア(ア)のとおり,原告は,原告商標を自ら使用したこと はないところ,商標権者が当該商標を使用していることは,法38条2項を 適用するための要件とはいえず,商標権者において,侵害者による商標権侵 害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合 には,同項の適用が認められると解すべきである。 しかし,前記2(1)ア(オ)のとおり,原告は,日本酒を生産等する市島酒造 社らに対して原告商標の通常使用権を許諾したにすぎず,自らは日本酒の生 産等を行っていないから,被告が被告各標章を付した被告商品を販売するこ とがなかったならば,原告が日本酒の販売等によって利益を得たであろうと は直ちには認められない。また,本件全証拠によっても,被告による被告商 品の販売が,原告が上記許諾の対価として受ける原告商標を付する商品の容 器に貼付するラベルその他の関連印刷物の注文に影響を与えるといった事情\nは認められず,他に,被告による商標権侵害行為がなければ,原告が利益を 得たであろうという事情を認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告に法38条2項に基づく請求は認められない。
(2) 法38条3項に基づく請求について
ア 法38条3項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準とし, そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 そして,実施に対し受けるべき料率については,当該商標の実際の実施 許諾契約における実施料率,業界における実施料の相場,当該商標を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様等訴訟に現れた 諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。
イ 前記5のとおり,被告は,平成31年4月19日以降,被告標章1が印 刷されたラベルを瓶に貼付せず,被告標章2が印刷されていない外箱に入\nれた被告商品を販売するようになったから,原告が被告に対して原告商標 権侵害に基づく損害賠償を請求することができるのは,被告が設立された 平成20年5月21日から平成31年4月18日までの間のものと認める のが相当である。 そして,証拠(甲21,乙10)及び弁論の全趣旨によれば,被告は, 上記期間に,被告商品のうち,720ml瓶入りのものを1万5456本, 1800ml瓶入りのものを2171本,それぞれ販売し,これにより, 2783万0092円と905万7659円の各売上げ(合計3688万 7751円)があったと認められる。
ウ 以上を前提に,まず,原告がこれまでに原告商標の通常使用権を許諾し たことにより得られた利益について検討する。
(ア) 前記2(1)ア(オ)のとおり,原告は,市島酒造社らに対して原告商標の 通常使用権を許諾し,その対価として,市島酒造社らから原告商標を付 する商品の容器に貼付するラベルその他の関連印刷物を受注する契約を\n締結していた。 上記受注による原告の利益には,原告が印刷を受注したことそのもの による利益も含まれているといえるから,原告商標の使用の対価に相当 する金額は,上記受注による利益の額から,原告が印刷を受注したこと そのものによる利益の額を控除した額と考えるべきである。
(イ) 証拠(甲24ないし26)及び弁論の全趣旨によれば,原告の事業全 体における平成29年から令和元年までの平均の粗利率は約27.5% であり,原告の市島酒造社からの受注に係る平均の粗利率は約45. 7%,原告の大関社からの受注に係る平均の粗利率は約47.8%であ ると認められる。 そうすると,原告商標の使用の対価に相当する金額の割合は,市島酒 造社らからの受注に係る代金額の算定方法や販売費及び一般管理費の取 扱い等について更に厳密な検討をする余地はあるものの,原告の市島酒 造社らからの受注に係る平均の粗利率から原告の事業全体における平均 の粗利率を控除することによって,約18.2%ないし20.3%と一 応計算することができる。
(ウ) 被告商品の容器に貼付するラベルその他の関連印刷物の発注額につい\nては,以下のとおり認定することができる。 被告商品の容器に貼付するラベルその他の関連印刷物の発注額の単価\nについて,証拠(乙9)及び弁論の全趣旨によれば,1) 720ml瓶入 りのもの1本当たりの単価の合計は99.5円(本件ラベル:5円,商 品名等ラベル:18円,本件瓶の背面のラベル:2.5円,本件外箱: 74円),2) 1800ml瓶入りのもの1本当たりの単価の合計は36 1.5円(本件ラベル:5円,商品名等ラベル:45円,本件瓶の背面 のラベル:21.5円,本件外箱:290円)と認められる。
前記イのとおり,原告が被告に対して損害賠償を請求することができ る平成20年5月21日から平成31年4月18日までの間に販売され た被告商品のうち720ml瓶入りのものは1万5456本,1800 ml瓶入りのものは2171本であるから,被告商品の容器に貼付する\nラベルその他の関連印刷物の発注額は,720ml瓶入りのものについ て153万7872円(99.5円×1万5456本),1800ml 瓶入りのものについて78万4817円(361.5円×2171本) と認められ,合計で232万2689円となる。
(エ) 前記(イ)のとおり,原告商標の使用の対価に相当する金額の割合が受注 額の約18.2%ないし20.3%であるとすると,被告商品における 原告商標の使用の対価に相当する金額は,42万2729円(232万 2689円×0.182)ないし47万1506円(232万2689 円×0.203)と一応計算することができる。 そして,この金額は,平成20年5月21日から平成31年4月18 日までの間の被告商品の売上げの合計3688万7751円の約1.1 5%ないし1.28%に相当する。
エ 次に,原告商標を被告商品に用いた場合の売上げ等への貢献について検 討する。
原告商標は,「夢」の標準文字からなり,これ自体は,比較的頻繁に目 にする文字であるから,本来的に高い顧客吸引力があるとまではいえない。 また,前記前提事実(3)のとおり,被告商品の商品名は「夢とまぼろしの物 語」であり,被告各標章はこの商品名の一部を切り出したものであること, 本件瓶の正面には本件ラベルよりも大きい商品名等ラベルが貼付され,本\n件外箱の正面には特徴的な武者の絵が大きく描かれていることからすると, 被告各標章が独自に有する顧客吸引力は限定的というべきであり,被告商 品の売上げに対する貢献もそこまで大きなものであったとは認め難い。
オ 以上の諸事情に加え,前記ウのとおり,原告が原告商標の通常使用権を 許諾したことにより得られた利益の実績を基に,被告商品について計算し た原告商標の使用の対価に相当する金額の割合や,広告業等における商標 権のロイヤルティ料率の相場は概ね3ないし6%であり,1%未満の例も あると認められること(甲23)を考慮すると,原告商標の使用に対し受 けるべき金銭の額に相当する額は,被告商品の売上げの2%に相当する額 と認めるのが相当である。
したがって,原告の損害は,73万7755円(3688万7751円 ×0.02)と認められる。
カ 原告は,市島酒造社らから原告商標のラベルその他の印刷物を受注して おり,これによる利益が原告商標のライセンス料に相当するところ,原告 にはこの受注により1社当たり年232万2514円の売上げがあり,原 告における粗利率25%を乗ずると,年58万0628円がライセンス料 相当額となり,被告は原告商標権を11年間にわたり侵害したので,ライ センス料相当額の損害は638万円となると主張する。 しかし,前記ウ(ア)のとおり,原告商標の使用の対価に相当する金額は, 市島酒造社らからの受注による利益の額から,原告が印刷を受注したこと そのものによる利益の額を控除した額と考えるべきであるから,原告にお ける粗利率をそのまま採用することは相当ではない。 また,前記2(1)ア(オ)のとおり,原告は,原告商標の通常使用権を許諾 する対価として,原告商標を付する商品の容器に貼付するラベルその他の\n関連印刷物を受注する旨の契約を締結していたところ,このような契約内 容からすると,原告の受注額は原告商標を付する商品の数量に比例するこ とになり,その数量は市島酒造社らと被告とでは異なるものと考えられる から,市島酒造社らからの平均の受注額は直ちに被告に当てはまるもので はない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 さらに,原告は,原告商標のライセンス料率は,少なくとも5%と認め るべきであるとも主張するが,前記イないしオで説示したとおり,上記ラ イセンス料率は2%と認めるのが相当であるから,同主張も採用すること ができない。
キ なお,前記2(1)ア(ウ),(エ)のとおり,原告は,旧原告商標権を侵害する 標章を使用した酒造会社との間で,年150万円以上の印刷物の受注又は 300万円の損害賠償金の支払を合意している。 しかし,いかなる標章が付された日本酒が,どのくらいの期間に,何本 販売され,どのくらいの売上げがあったのかなど,上記酒造会社が旧原告 商標権を侵害した態様が明らかではないから,本件と比較することは困難 である。 また,上記合意は,原告商標に関するものではない上,比較的古いもの であり,原告商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を算定す るに当たっては,原告商標に関する直近の許諾契約である原告と市島酒造 社らとの間の契約(前記2(1)ア(オ))を参考にするのが相当である。 したがって,原告が上記の合意をしていたことは,前記オの認定判断を 左右するものではない。
(3) 小括
以上のとおり,原告は,被告による原告商標権の侵害により,原告商標の 使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額として,73万7755円の損 害を被ったと認められる(法38条3項)。 また,原告が本件訴訟を遂行するのに要した弁護士費用相当額の損害は, 本件に現れた一切の事情を考慮すると,10万円と認めるのが相当である。 したがって,原告は,被告に対し,83万7755円の損害賠償を請求す ることができる。 なお,原告は,法39条,特許法105条の3に基づき相当な損害額を認 定すべきであると主張するが,本件においては,原告に生じた損害額は上記 のとおり算定することができるので,「損害額を立証するために必要な事実 を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるとき」に該当せず,同 主張についての判断は要しない。
2021.07. 2
令和2(行ケ)10136 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和3年6月16日 知的財産高等裁判所
意匠法3条1項3号における類否の判断は,出願された意 匠と類似する意匠とが,出願意匠に係る物品と同一又は類似の物品につき一 般需要者に対して出願意匠と類似の美感を生じさせるかどうかを基準として なされるべきであるのに対し,同法3条2項は,物品との関係を離れた抽象 的なモチーフとして日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若し くは色彩又はこれらの結合(公然知られた形態)を基準として,それからそ の意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作 することができた意匠でないことを登録要件としたものであり,上記公然知 られた形態を基準として,当業者の立場から見た意匠の着想の新しさないし 独創性を問題とするから(平成10年法律第51号による改正前の法3条2 項につき,最高裁昭和49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号3 08頁,最高裁昭和50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号 287頁参照),意匠の類似性と創作容易性とは判断主体や判断手法を全く 異にしている。 したがって,原告の上記主張は,両者の違いを無視した独自の見解といわ ざるを得ないものであって,採用することができない。
(2) 原告は,本願分野の登録意匠について自ら作成した別掲4を用いるなどし て,原告の挙げる7要素のうち少なくとも一つの「意匠が非類似になる意匠 上の要素」があれば,形状のわずかな相違であっても創作非容易と認められ るべき旨主張する。 しかしながら,まず,別掲4の多数の登録意匠のうち,出願人及び登録日 を同じくする複数の意匠は,互いに部分意匠や関連意匠の関係にある可能性\nが高く,その場合は形状の差異がわずかであっても登録されているのは当然 のことにすぎないから,原告の分析は,その前提に問題があるといわざるを 得ない。 そして,既に述べたとおり,本願意匠は,引用意匠1の凹陥の数と位置を 引用意匠2のそれに置き換えたのにすぎず,何ら意匠としての着想の新しさ や独創性を認めることはできないのであるから,原告のいう登録済意匠の存 在を考慮したとしても,本願意匠は創作容易であるとの結論が左右されるも のではない。
2021.07. 2
令和2(行ケ)10148 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年6月16日 知的財産高等裁判所
ア 役務の内容及び取扱商品等
(ア) 本願指定役務及び引用指定役務は,いずれも小売等役務であるから, 商品の品揃え,陳列,接客サービス等といった役務の提供の手段や,小 売又は卸売といった役務の提供の目的が共通するものといえる。 (イ) また,本願指定役務及び引用指定役務は,本願指定役務が主に織物, 衣服,身の回り品等を取扱商品とするのに対し,引用指定役務は帽子を 取扱商品とする点において異なるものの,いずれの取扱商品も衣類を中 心とするファッション商品であるといえるから,この範囲において取扱 商品が共通するものといえる。
(ウ) さらに,本願指定役務及び引用指定役務は,いずれも衣類を中心と するファッション商品を取り扱う卸売業者又は小売業者が提供する役 務であるから,役務を提供する業種が共通するものといえる。 イ 役務の提供の場所 次の各事情によれば,本願指定役務及び引用指定役務は,それぞれの取 扱商品が,同一事業者の通信販売ウェブサイトにおいて,同一の事業者が 提供する一連の商品の一環として,あるいは同一のカテゴリーに属する一 連の商品の一環として販売されるなどしている実情があることが認めら れる。
(ア) 「ZOZOTOWN」の通信販売ウェブサイトにおいて,「NIKE」 ブランドの取扱商品として,パーカー,ティーシャツ,靴,バッグ等が, 帽子と共に掲載されている(乙1)。
・・・
(コ) 「ZOZOTOWN」の通信販売ウェブサイトにおいて,「mari mekko」ブランドの取扱商品として,クッション,靴下,ティーシ ャツ,エプロン,バッグ,財布,タオル等が,帽子と共に掲載されてい る(乙10)。
ウ 需要者の範囲
上記ア及びイで検討したとおり,本願指定役務及び引用指定役務は,い ずれも衣類を中心とするファッション商品を取扱商品とするものである 上,これらの取扱商品が通信販売ウェブサイトにおいて販売されるなどし ている実情があることからすれば,いずれも一般需要者を広く対象とする ものといえる。また,上記イ(ア)ないし(エ)及び(コ)によれば,特定のブ ランドが付された両役務の取扱商品を,同一の小売業者から購入する需要 者は少なくないと考えられる。 これらの事情を考慮すると,本願指定役務及び引用指定役務は,需要者 の範囲が一致するものといえる。
エ 類否判断
上記アないしウで検討したところによれば,本願指定役務及び引用指定 役務は,具体的な取扱商品は異なるものの,いずれも衣類を中心とするフ ァッション商品を取扱商品とする点において共通するほか,役務を提供す る手段,目的及び業種が共通するものといえる。また,両役務は,役務を 提供する場所が共通する場合があるほか,需要者の範囲が一致するものと いえる。 これらの事情を考慮すると,本願指定役務及び引用指定役務については, これらの役務に同一又は類似の商標を使用する場合には,同一営業主の提 供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるといえ る。
(3) 小括 以上によれば,本願指定役務と引用指定役務は,役務が類似するものと認 められる。
3 原告の主張について
(1) 原告は,原告とカンゴール社との間で本件契約が締結され,その後,原告 とカンゴール社との間で取扱商品及び役務に係る棲み分けがされてきたこと を,現実的かつ具体的な取引の実情として重視すべきである旨主張する。 しかしながら,本件契約それ自体は,原告とカンゴール社との間における 個別の合意にすぎないから,同契約を締結した事実や,同契約に基づいて原 告が本願商標を継続的に使用している事実は,商標の類否判断において考慮 し得る一般的,恒常的な取引の実情(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同 49年4月25日第一小法廷判決・審決取消訴訟判決集昭和49年443 頁参照)には当たらないというべきである。 また,原告が提出する証拠(甲30ないし49)は,原告が,本願商標を 用いて衣類等を提供してきたことを裏付けるものであるとはいえても,帽 子(及びそれに係る役務)とそれ以外の衣類(及びそれに係る役務)とで, 原告が主張するような棲み分けがされ,それが需要者に認識されているこ とを認めるに足りるものではなく,むしろ,原告が,本願商標を用いて帽子 を販売している例さえ存在することが認められる。 したがって,原告の主張は,採用することができない。
(2) 原告は,原告とカンゴール社との間においては,カンゴール社が所有す る複数の登録商標につき,帽子類以外の指定商品に係る商標権が原告に分 割移転された例等がある旨主張するが,たとえそうであるとしても,このよ うな個別的な事情によって商標法4条1項11号の適用が排除されるもの ではないと解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 役務
>> 類似
>> ピックアップ対象
2021.06.29
令和1(行ケ)10132 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年11月5日 知的財産高等裁判所
本件発明の器具は下記に動画があります。 https://www.youtube.com/watch?v=RTerQy8M-BI
・・・この点に関する原告の主張を正確に記載すると,本件発明は,1)ピンが 複数の溝を有する構成を含むこと,2)ピンバーとベースが一体成型になって いる構成を含むこと,3)ピンバーをベースの溝ではなく,ベース上の凸部に 嵌め込む方式の構成を含むこと,4)ピンに,溝ではなく,ピンを貫く間隙を 有する構成を含むこと,の4点において,本件米国仮出願にはない構\成を含 むからパリ優先権が否定され,その結果,甲1動画との関係で新規性,進歩 性を欠き,無効であるというものである。
しかしながら,本件発明が,その請求項の文言に照らし,原告が新たな構\n成であると主張する1)ないし4)の点を含まない構成,すなわち,本件米国仮\n出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであると\nころ(この点は,原告も否定していないものと考えられる。),この構成は,\n1まとまりの完成した発明を構成しているのであって,1)ないし4)の構成が\n補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような 場合,パリ条約4条Fによれば,パリ優先権を主張して行った特許出願が優 先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由とし\nて,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすること はできず,ただ,基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパ\nリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから,当該特許出願に係る特許 を無効とするためには,単に,その特許が,パリ優先権の基礎となる出願に 含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず,当該\n構成部分が,引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必\n要があるというべきである。このように解することがパリ条約4条Fの文言 に沿うばかりではなく,このように解しないと,例えば,特許権者がAとい う構成の発明について外国出願をし,その後,その構\成を含む発明Bが公知 となった後に,わが国において,パリ優先権を主張し,構成Aと,前記外国\n出願には含まれないが,発明Bに対して新規性,進歩性が認められる構成C\nを合わせた構成A+Cという発明について特許出願をした場合,当該発明は,\n構成Aの部分は,発明Bよりも外国出願が先行しており,優先権も主張され\nており,かつ,構成Cは,発明Bに対し新規性,進歩性が認められるにも関\nわらず,前記外国出願に含まれない構成Cを含んでいることのみを理由とし\nて構成Aについての優先権までが否定され,特許出願が拒絶されるという結\n論にならざるを得ないが,そのような結論は,パリ条約4条Fが到底容認す るものではないと考えられるからである。
なお,1)ないし4)も,それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから,引用発明に対する新規性,進歩性は,それぞれの構\成について,別個に問題とする必要がある。この観点から検討すると,甲1によれば,甲1動画に係るツールは,前記 3)の構成を有していることが認められる。そして,本件発明の請求項は,「\nベース上にサポートされた複数のピン」と定めているのみであって,前記3) の構成を含むことは明らかであるから,この点において,本件発明は,甲1\n動画との関係で新規性を欠くものといわなければならない。したがって,パ リ優先権が認められるかどうかを判断するため,さらに,構成3)が,本件米 国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。\n
これに対し,甲1動画に係るツールは,前記1),2),4)の構成を含むものとは認めら\nれないから,新規性が問題となる余地はなく,また,これらの構成が,甲1\n動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。 そうであるとすると,これらの構成が,本件米国仮出願に含まれない構\成で あるかどうかを判断するまでもなく,原告の主張は失当というべきである。
(3) そこでさらに,構成3)が,本件米国仮出願に含まれない構成であるかど\nうかについて判断するに,たしかに,米国仮出願書類には,ベースに設けた 溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていないが,これは実施例の記載 にすぎないし,米国仮出願書類全体を検討しても,ベースにピンバーを固定 する態様を,この実施例に係る構成に限定する旨が記載されていると理解す\nることはできない。そして,ベースに凹部を設け,その凹部にピンバーを嵌 め込む態様の構成(米国仮出願書類の実施例の記載)と,ベースに凸部を設\nけ,この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成(3)の構成)とは,まさに裏\n腹の関係にあるものであって,一方を想起すれば他方も当然に想起するのが 技術常識であるといえるから,たとえ明示的な記載がないとしても,ベース に凹部を設ける構成が記載されている以上,ベースに凸部を設ける構\成も, その記載の想定の内に含まれているというべきである。 そうすると,3)に係る構成が,本件米国仮出願に含まれない構\成であると はいえないから,この点に関する原告の主張も失当ということになる。
2021.06.28
令和2(ワ)25127 「オーサグラフ世界地図」の共同著作権確認請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年6月4日 東京地方裁判所
確認の訴えは,即時確定の利益がある場合,すなわち,現に,原告の有する 権利又は法的地位に危険又は不安が存在し,これを除去するため,被告に対し て確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に限り許される。したがって,そ れが許されるためには,仮に原告の権利又は法的地位に危険又は不安が存在す るとしても,その危険又は不安が被告に起因し,かつ,対象となる権利又は法 的地位について確認判決をすることでその危険又は不安が解消されなければな らないというべきである。
しかし,本件においては,Bによる講義の内容が「オーサグラフ世界地図は Bが発明したものである」というものとなったこと,上記講義と同内容の論文 が学術論文誌に掲載されたこと,本件ウェブサイト内に本件地図とともに本件 地図はBが発明したものである旨の説明文が掲載されたことについて,それら が被告に起因するものであることを認めるに足りる証拠はない。また,被告は, 本件地図に係る著作権又は著作者人格権が自らにあるとは主張しておらず,今 後,被告がこのような主張をすることをうかがわせる事情も認められない。そ うすると,原告の有する権利又は法的地位に存在する危険又は不安が被告に起 因するものであるとはいえない。
さらに,被告が,自らは本件地図の作成に関与しておらず,本件地図に関し て原告及びBのいずれかにいかなる権利が帰属するかを判断し得ないとも主張 していることに照らせば,そのような被告に対して確認判決を得ることにより, 原告の有する権利又は法的地位への危険又は不安を取り除くことができるとは 考え難い。そして,前記前提事実(3)のとおり,原告は,別件訴訟において,B に対し,本件地図と同じくオーサグラフ図法により作成された別件各地図が原 告及びBを発明者とする共同著作物であることの確認を求め(本件と同様に, 原告及びBが別件各地図に係る著作権及び著作者人格権を有することの確認を 求めるものと解される。),これに対して,Bは,別件各地図はBが単独で作 成したものであると主張して争っているが,原告と被告との間で本件地図に係 る著作権及び著作者人格権の帰属を確定したところで,原告とBとの間におい て別件各地図に係る著作権及び著作者人格権の帰属を確定することはできない。 このことは,Bが被告の設置する慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科准 教授であり(前記前提事実(1)イ),被告とBは雇用関係にあると認められるこ とを考慮しても変わりはない。さらに,前記前提事実(2)のとおり,本件ウェブ サイトはBが管理運営しており,被告が本件ウェブサイトの内容を変更するこ とができるとは認められないから,被告に対して確認判決を得たとしても,本 件ウェブサイト内において,本件地図につき当該判決に従った取扱いがされる ことが期待できるとはいえない。そうすると,本件において原告の権利又は法 的地位について確認判決をすることにより,原告の権利又は法的地位に存在す る危険又は不安が解消されるとは認められないというべきである。 そのほかに,原告と被告との間で,本件地図に係る原告の権利又は法的地位 に危険又は不安が存在し,これを除去するために被告に対して確認判決を得る ことが必要かつ適切であることをうかがわせる事情は認められない。 したがって,原告と被告との間で原告及びBが本件地図に係る著作権及び著 作者人格権を有することを確認することについては即時確定の利益が認められ ないから,本件においては確認の利益が認められない。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.06.23
令和2(ネ)10048 職務発明対価等請求控訴事件,同附帯控訴事件 その他 民事訴訟 令和3年5月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所も,原審と同様に,本件ノウハウに係る控訴人の被控訴人に対する 対価請求権が存するということはできないと判断する。 その理由は,次のとおりである。
(1) 本件ノウハウは,特許登録がされていない職務発明として主張されてい るものであるところ,特許性を有する発明でなければ,これを実施すること によって独占の利益が生じたものということはできず,特許法35条3項に 基づく相当の対価を請求することはできないと解される。 そこで,以下,控訴人が主張する内容に基づき,本件ノウハウが特許性を 有する発明といえるか否かについて検討する。
(2) 原審及び当審における控訴人の主張によれば,控訴人が主張する本件ノ ウハウの特徴は,次のとおり理解することができる。
ア 完全確率抽選方式の下で,何らの工夫もせずに予想ゲームと馬主ゲーム\nとを組み合わせた競馬ゲームを設計すると,馬主ゲームにおいて購入する 馬の能力値によって馬ごとのメダル獲得の期待値に不公平が生じるため,\nプレイヤーが能力値の高い馬ばかりを購入するようになり,馬主ゲームの\nゲーム性が損なわれてしまう。他方で,各馬の能力値を同一にすることに\nよってこの問題を解消しようとすると,今度は予想ゲームのゲーム性が損\nなわれてしまう。このように,上記のような競馬ゲームの設計においては, 馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値の不公平さを解消して 公平性を確保しつつ,現実の競馬同様のゲーム性を持たせる工夫をする必 要があるという課題があった。
イ 本件ノウハウは,上記の課題を解決するために,1)プレイヤー馬につい て,能力値とは別に,一定の割合でメダル数と相互に換算される活力値と\n呼ばれる指標を導入した上で,2)馬主ゲームにおいて,レースに出走する ために消費する活力値(以下「消費活力値」という。)とレース結果に応じ て増加する活力値(以下「増加活力値」という。)の期待値とを等しくする ことにより,馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値の不公平さ が生じないようにするものである。 また,消費活力値及び増加活力値の算出においては,3)同じレースに複 数のプレイヤー馬が出走する場合もあるところ,プレイヤー馬の能力値が\n当初は未確定であることから,各プレイヤー馬の増加活力値,消費活力値 及び能力値について,一旦暫定値を用いて計算し,必要に応じて数値を再\n調整する計算方法が採られている。 さらに,4)活力値は,メダルとして目に見える賞金や出走料とは異なり, プレイヤーに認識されない形で増減され,次回以降の競馬ゲームに影響を 与えるように導入されており,これにより,ゲーム性が醸成されている。 (以下,上記1)ないし4)の点を,順に「特徴1)」などという。) (3) 以下,控訴人が主張する本件ノウハウが特許性を有する発明といえるか 否かにつき,特徴1)ないし4)を基に検討する。
ア 特徴1)について
(ア) 予想ゲームのみの競馬ゲームを設計する場合であれば,各馬の能\力 値を定めた上で,能力値に応じた適切なオッズを定めることにより,公\n平性及びゲーム性を確保することができるといえるが,これにゲーム内 容が全く異なる馬主ゲームを組み合わせて新たな競馬ゲームを設計し ようとするのであれば,能力値とは別の指標を導入する必要が生じるこ\nとは,いわば必然のことであるといえる。
(イ) また,上記(2)アによれば,完全確率抽選方式の下で予想ゲームと馬\n主ゲームとを組み合わせた競馬ゲームを設計する場合,馬主ゲームで購 入する馬の能力値に差があることが原因となって馬ごとのメダル獲得\nの期待値に不公平さが生じることにより,馬主ゲームのゲーム性が損な わる事態が生じ得るが,他方で,馬の能力値の差をなくすことによって\nこの問題を解消しようとすると,今度は予想ゲームのゲーム性が損なわ\nれてしまうというのであるから,これらの問題を解決するためには,能\n力値を調整するのみでは足りず,能力値とは別の指標を導入する必要が\nあることは明らかである。
(ウ) 以上によれば,特徴1)における活力値の導入は,完全確率抽選方式 の下で予想ゲームと馬主ゲームとを組み合わせた競馬ゲームを設計す\nる場合において,必然的に必要となる指標を導入したものにすぎないと いうべきである。
・・・・
オ 小括
以上検討したところによれば,本件ノウハウにおける活力値の導入につ いては,必然的に導入すべき指標を用いたものにすぎないというべきであ る上,活力値を用いた期待値の算出等についても,課題解決のために当然 に採られ得る手段であるか,又は通常よく採られる方法を超えるものでは ないというべきである。
(4) なお,控訴人は,本件ノウハウにおいては,ペイアウト率90%のメイン ゲームと同100%のサブゲームとが組み合わされ,ゲームセンターと顧客 との間の利害のバランスがとられている点が画期的であるとも主張する。 しかしながら,ペイアウト率をいくらに設定するかという問題は,それ自 体としては,技術の問題ではなく,取極めの問題にすぎないから,控訴人主 張の点は,本件ノウハウの特許性を根拠付ける事情には当たらない。
(5) 以上検討したところによれば,本件ノウハウは,特許性を有する発明であ るとは認められず,これを実施することによって被控訴人に独占の利益が生 じたということはできないから,本件ノウハウが控訴人によって職務発明と して開発され,被告製品2において実施されたものであったとしても,控訴 人は,被控訴人に対し,本件ノウハウにつき,特許法35条3項に基づく相 当の対価を請求することはできない。
関連カテゴリー
>> 職務発明
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2021.06.21
令和2(ワ)27196 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年4月23日 東京地方裁判所
前記アないしウの事情を踏まえて,著作権法114条3項の損害額を検 討すると,前記ア及びイのとおり,本件料金表における使用料を一応の参\n考としつつ,一般紙と機関紙としての性質の違いに加え,原告における有 償での使用許諾の実績や使用料規定の存在が認められないことからは,聖 教新聞の記事や写真等の使用については本件料金表よりも低額の使用料が\n想定され,他方で,前記ウのとおり,本件掲載行為については使用料の増 額要素があることも考慮すれば,前記1の自動公衆送信権侵害についての 著作権法114条3項の損害額は,それぞれ以下のとおり認定するのが相 当であり,その合計額は32万円と認められる。
・・・
原告は,被告による著作権侵害の態様が悪質であるとして,著作権法114条3項の損害を算定にするに当たっては,本件料金表における使用料相当額のさらに1.5倍した額を基準とすべきであると主張する。\nしかし,前記エの損害額の認定は,原告に有償での使用許諾実績等がないこと,本件料金表の金額,本件各画像の使用点数や使用期間,被告による本件各画像の掲載態様等,本件訴訟に現れた一切の事情を総合考慮した上で,著作権法114条3項を適用したものであるところ,この認定を超えて,本件料金表\における使用料を1.5倍した額を基準とすべき合理的な理由は見当たらない。
2021.06.18
平成30(ワ)38504 特許権侵害差止等請求事件 令和3年3月30日 東京地方裁判所
これらの記載によれば,本件発明の目的は,各種の痒みを伴う疾患にお ける痒みの治療のために止痒作用が極めて速くて強いオピオイドκ受容体 作動薬を有効成分とする止痒剤を提供することにあるところ,本件明細書 には,まさしくその有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として,本 件発明に記載された本件化合物のほかに,その薬理学的に許容される酸付 加塩が挙げられることが,「オピオイドκ受容体作動性化合物またはその 薬理学的に許容される酸付加塩」というように明記されているほか,同化 合物に対する薬理学的に好ましい酸付加塩の具体的態様(塩酸塩,硫酸塩, 硝酸塩等)も明示的に記載されている。
そうすると,出願人たる原告は,本件明細書の記載に照らし,本件特許出 願時に,その有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として,本件化合物 を有効成分とする構成のほかに,その薬理学的に許容される酸付加塩を有効\n成分とする構成につき容易に想到することができたものと認められ,それに\nもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというべきである。 そして,本件発明につき,出願人たる原告の主観的意図いかんにかかわらず, 第三者たる当業者の立場から客観的にその内容を把握できる徴表である本件\n明細書においては,本件化合物の薬理学的に許容される酸付加塩という構成\nは,まさしく,各種の痒みを伴う疾患における痒みの治療のために止痒作用 が極めて速くて強いオピオイドκ受容体作動薬を有効成分とする止痒剤を提 供するという本件発明の目的を達成する構成として,当該目的と関連する文\n脈において,特許請求の範囲に記載された本件化合物と並んで,明示的,具 体的に記載されているものである。
これらによれば,出願人たる原告は,本件特許出願時に,本件化合物の薬 理学的に許容される酸付加塩を有効成分とする構成を容易に想到することが\nできたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったものである といえ,しかも,客観的,外形的にみて,上記構成が本件発明に記載された\n構成(本件化合物を有効成分とする構\成)を代替すると認識しながらあえて 特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるものというべき\nである。
そうすると,本件発明については,本件化合物の酸付加塩であるナルフラ フィン塩酸塩を有効成分とする被告ら製剤が,本件特許出願の手続において 特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの,被告ら製剤と 本件発明に記載された構成(本件化合物を有効成分とする構\成)とが均等な ものといえない特段の事情が存するというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2021.06.17
令和3(行ケ)10022 商標登録維持決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年4月28日 知的財産高等裁判所
一審原告の商品と被告商品との価格差及び限界利益額の差,需要者 層の相違,販売態様の相違について 一審被告は,1)被告商品の価格は,一審原告の商品の価格の約2倍 から4倍であり,一審原告の商品と被告商品とでは大きな価格差があ り,安価のスニーカーを求める一審原告の需要者と高級志向のスニー カーを求める被告商品の需要者とでは,需要者層が異なること,一審 原告の商品はインターネット上で販売されるのに対し,被告商品は高 級デパートの店頭で販売され,販売態様においても差があることに照 らすと,被告商品が販売されなかったとしても,被告商品の需要者が, 安価で大衆向けの一審原告の商品を購入することはあり得ないこと, 2)仮に一審被告による被告商品の販売に係る限界利益率を一審原告が 訴状で主張していた販売価格の10パーセントとすると,一審原告の 商品の1足当たりの限界利益は300円となるのに対し,被告商品の 1足当たりの限界利益は,560円から1155円となり,限界利益 の額に差があることから,これらの事情は本件推定を覆す事情に該当 する旨主張する。
(ア) そこで検討するに,証拠(甲68ないし77,183ないし18 6)及び弁論の全趣旨によれば,一審原告は,自社の商品を,主に 靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売し, その小売価格は2000円から6000円程度の商品が中心であ り,一審原告が対象期間中に原告各商標と類似する商標を付したス ニーカーを販売した際の販売価格は1足当たり3000円程度で あったことが認められる。
一方で,証拠(乙19)及び弁論の全趣旨によれば,被告商品は 主に百貨店等の店頭で販売されたものであり,原判決別紙3被告商 品販売一覧表記載のとおり,その小売価格は1万5000円から2\n万1000円,被告が百貨店等に販売する際の卸売価格は5600 円から1万1550円であったことが認められる。 上記認定事実によれば,一審原告の商品と被告商品の販売価格は, 1足当たりの小売価格で5倍から7倍程度の差があり,被告商品が 高額であることが認められる。
そして,商標権が,特許権等の他の工業所有権とは異なり,それ 自体に創作的価値があるものではなく,商品又は役務の出所である 事業者の営業上の信用等と結びつくことによってはじめて一定の 価値が生ずるという性質を有するため,商標権が侵害された場合に, 侵害者の得た利益が当該商標権に係る登録商標の顧客誘引力のみ によって得られたものとはいえない場合が多く,スニーカーにおい ても,価格,全体のデザイン,アッパー及びソールの素材,履き心\n地等も考慮されて購買動機が形成されることに照らすと,一審原告 の商品と被告商品との販売価格の上記違いは,原告各商標と類似す る被告各標章が購買動機の形成に寄与した程度を低く評価すべき 事情に当たるものと認めるのが相当である。 したがって,一審原告の商品と被告商品との販売価格の上記違い は,本件推定を覆す事情に該当するものと認められる。 一方で,一審被告が主張する一審原告の商品と被告商品との1足 当たりの限界利益の額の差については,一般に,需要者が限界利益 の額を認識し得るものではなく,限界利益の額の差が購買動機の形 成に直接影響するものとはいえなから,本件推定を覆す事情に該当 するものと認めることはできない。また,一審被告が主張する一審 原告の商品と被告商品との販売態様の差についても,被告商品がデ パート等でのみ限定販売されていたとする事情は認められないか ら,本件推定を覆す事情に該当するものと認めることはできない。
(イ) これに対し一審原告は,スニーカーなどのファッションアイテ ムにおいては,需要者は,価格帯が多少異なっても気に入ったもの を購入するものであり,例えば,同じブランドでも1500円〜1 万7280円という10倍以上の幅広い価格の商品が販売されて いる例(甲195)があるように,この程度の価格差をもって需要 者層が異なるとはいえないこと,一審原告が被告商品の価格帯であ る1万5000円〜2万1000円のスニーカーを現実には販売 していないとしても,このようなスニーカーを販売する潜在的な能\n力を保有していることからすると,一審原告の商品と被告商品との 販売価格の違いは,本件推定を覆滅すべき事情に該当しない旨主張 する。 しかしながら,一審原告の上記主張は,前記(ア)で説示したとこ ろに照らし,採用することができない。
イ 一審原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことにつ いて
一審被告は,原告が販売していた商品の多くに,原告各商標と同一 又は類似の標章が付されていなかったから,被告商品の販売によって 一審原告の売上げが減少したという関係にないことは,本件推定を覆 す事情に該当する旨主張する。 しかしながら,一審被告による被告商品の輸入販売行為がなかった ならば利益が得られたであろうという事情が一審原告に認められる ことは,前記(1)イ認定のとおりであり,一審原告が原告各商標と類似 する標章が付されていないスニーカーも販売していたことを指摘す るのみでは,本件推定を覆滅すべき事情があるものということはでき ない。 したがって,一審被告の上記主張は,採用することができない。
ウ 競合品の存在について
一審被告は,側面に「X」型十字が付された大人用スニーカーは,\n被告商品の他にも市場に多数存在していることは,本件推定を覆す事 情に該当する旨主張する。 しかしながら,乙1によれば,一審被告が他のスニーカーに付され ていると指摘する「X」型十字は,その形状が被告各標章や原告各商\n標とは大きく異なるものであり,このほか,原告各商標と同一又は類 似の標章が付された他社のスニーカーの存在及びそのシェアについて の具体的な主張立証はされていないから,一審被告の上記主張は採用 することができない。
エ 一審被告の営業努力,ブランド力の差等について
一審被告は,被告商品を販売するための営業努力,一審原告と一審 被告とのブランド力の差,原告各商標の訴求力の程度等からすれば, 原告各商標の被告商品の売上げへの寄与は著しく低いから,かかる事 情は本件推定を覆す事情に該当する旨主張する。 しかしながら,一審被告が作成した展示会の資料においてミュニッ ク社商品については「2014年日本デビュー」との記載がされ,一 審被告が広告宣伝活動を行ったこと(前記(2)イ(キ))を考慮しても, 対象期間中の日本国内におけるミュニック社商品に係るブランドの知 名度の程度を裏付ける証拠はない。 他方で,証拠(甲170ないし176,180ないし182)及び 弁論の全趣旨によれば,原告各商標に関する販売,広告宣伝状況につ いては,平成14年頃から原告各商標と類似の標章が付されたスニー カーが,原告が許諾した業者によって販売されており,歌手のBがこ れを着用した雑誌広告が掲載されたこともあったとの事情も認められ, これらの点からすれば,一審被告の主張する上記各点をもって,本件 推定を覆滅すべき事情に該当するものと認めることはできない。 したがって,一審被告の上記主張は,採用することができない。
オ まとめ
以上を前提に検討するに,1)前記ア(ア)認定の本件推定を覆す事情 の内容,2)前記ア(ア)認定のとおり,商標権が侵害された場合に,侵 害者の得た利益が当該商標権に係る登録商標の顧客誘引力のみによっ て得られたものとはいえない場合が多く,スニーカーにおいても,価 格,全体のデザイン,アッパー及びソールの素材,履き心地等も考慮\nされて購買動機が形成されること等を総合考慮すると,被告商品の限 界利益の額に対する原告各商標の寄与割合は,8割と認めるのが相当 であり,上記寄与割合を超える部分については被告商品の限界利益の 額と一審原告の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認め られる。
したがって,本件推定は上記限度で覆滅されるから,商標法38条 2項に基づく一審原告の損害額は,被告商品の限界利益の額(前記(2) ウ(ウ)の244万5001円)の8割に相当する195万6000円 と認められる。」
◆判決本文
1審はこちら。
2021.06.17
令和1(ワ)21993 著作権侵害訴訟事件 著作権 民事訴訟 令和3年4月28日 東京地方裁判所
(1) 争点1−1(本件原告滑り台が美術の著作物に該当するか)について
ア 前記前提事実(2)及び(3)によれば,本件原告滑り台は,自治体(兵庫県 赤穂市)から公園に設置する遊具の発注を受けて,小型のタコの滑り台と して製作されたものであり,その形状は,別紙1原告滑り台目録記載のと おり,上部にタコの頭部を模した部分を備え,正面に1本,右側面に2本, 左側面に1本の計4本のタコの足を有するというものである。そして,こ れらのタコの足は,いずれも,子どもたちなどの利用者が滑り降りること ができるスライダーとなっており,また,利用者がスライダーの上部に昇 るための取っ手が取り付けられているなど,遊具である滑り台として通常 有する構造を備えている。そうすると,本件原告滑り台は,利用者が滑り\n台として遊ぶなど,公園に設置され,遊具として用いられることを前提に 製作されたものであると認められる。したがって,本件原告滑り台は,一 般的な芸術作品等と同様の展示等を目的とするものではなく,遊具として の実用に供されることを目的とするものであるというべきである。 そして,実用に供され,あるいは産業上利用されることが予定されてい\nる美的創作物(いわゆる応用美術)が,著作権法2条1項1号の「美術」 「の範囲に属するもの」として著作物性を有するかについては,同法上, 「美術工芸品」が「美術の著作物」に含まれることは明らかであるもの の(著作権法2条2項),それ以外の応用美術に関しては,明文の規定が 存在しない。
この点については,応用美術と同様に実用に供されるという性質を有す る印刷用書体に関し,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を 備えることを要件の一つとして挙げた上で,同法2条1項1号の著作物 に該当し得るとした最高裁判決(最高裁平成10年(受)第332号同 12年9月7日第一小法廷判決・民集54巻7号2481頁)の判示に 照らし,同条2項は,単なる例示規定と解すべきである。 さらに,上記の最高裁判決の判示に加え,同判決が,実用的機能の観点\nから見た美しさがあれば足りるとすると,文化の発展に寄与しようとす る著作権法の目的に反することになる旨説示していることに照らせば, 応用美術のうち,「美術工芸品」以外のものであっても,実用目的を達成 するために必要な機能に係る構\成と分離して,美術鑑賞の対象となり得 る美的特性を備えている部分を把握できるものについては,「美術」「の 範囲に属するもの」(同法2条1項1号)である「美術の著作物」(同法 10条1項4号)として,保護され得ると解するのが相当である。 以上を前提に,本件原告滑り台が「美術の著作物」として保護される応 用美術に該当するかを検討する。 イ 原告は,本件原告滑り台が,一品製作品というべきものであり,「美術 工芸品」(著作権法2条2項)に当たるから,「美術の著作物」(同法10 条1項4号)に含まれる旨主張する。 そこで検討するに,著作権法10条1項4号が「美術の著作物」の典型 例として「絵画,版画,彫刻」を掲げていることに照らすと,同法2条 2項の「美術工芸品」とは,同法10条1項4号所定の「絵画,版画, 彫刻」と同様に,主として鑑賞を目的とする工芸品を指すものと解すべ きであり,仮に一品製作的な物であったとしても,そのことをもって直 ちに「美術工芸品」に該当するものではないというべきである。
本件においてこれをみると,前記アのとおり,本件原告滑り台は,自治 体の発注に基づき,遊具として製作されたものであり,主として,遊具 として利用者である子どもたちに遊びの場を提供するという目的を有す る物品であって,「絵画,版画,彫刻」のように主として鑑賞を目的とす るものであるとまでは認められない。 したがって,本件原告滑り台が「美術工芸品」に該当すると認めること はできず,原告の上記主張は採用することができない。 ウ 原告は,本件原告滑り台が「美術工芸品」に当たらないとしても「美術 の著作物」として保護される応用美術であると主張する。そこで,本件原 告滑り台が,実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して, 美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるもので あるか否かについて,以下検討する。
(ア) タコの頭部を模した部分について
別紙1原告滑り台目録記載1(2)の各写真によれば,本件原告滑り台 のうちタコの頭部を模した部分の構成は,次のとおりであると認められ\nる。すなわち,タコの頭部を模した部分は,本件原告滑り台を正面から 見て,その最も高い箇所のほぼ中央部に存在しており,タコの足を模し たスライダーによって形作られるなだらかな稜線から上に突き出るよう な格好で配置されている。そして,その形状は,本件原告滑り台のうち 最も高い箇所に存在する頭頂部から,正面向かって後方にやや傾いた略 鐘形をなしており,全体として曲線的な印象を与える形状であって,そ うした形状と,上記のような配置等から,当該部位を見た者をして,タ コの頭部を連想させるような外観となっている。さらに,その構造をみ\nると,内部は空洞をなし,頭部に上った利用者が立てるような踊り場様 の床が設置されている。また,正面,左側面及び背面にそれぞれ1か所, 右側面に2か所の開口部を有しており,そのうち正面,右側面及び左側 面の開口部からは後述のタコの足を模したスライダーが延びているほか, 背面の開口部付近には,手でつかんだり,足を掛けたりして上り下りす るための取っ手が8個取り付けられている。 このように,タコの頭部を模した部分は,本件原告滑り台の中でも最 も高い箇所に設置されているのであるから,同部分に設置された上記各 開口部は,滑り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不 可欠な構造であって,滑り台としての実用目的に必要な構\成そのもので あるといえる。また,上記空洞は,同部分に上った利用者が,上記各開 口部及びスライダーに移動するために不可欠な構造である上,開口部を\n除く周囲が囲まれた構造であることによって,最も高い箇所にある踊り\n場様の床から利用者が落下することを防止する機能を有するといえるし,\nそれのみならず,周囲が囲まれているという構造を利用して,隠れん坊\nの要領で遊ぶことなどを可能にしているとも考えられる。\nそうすると,本件原告滑り台のうち,タコの頭部を模した部分は,総 じて,滑り台の遊具としての利用と強く結びついているものというべき であるから,実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離し て,美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できる ものとは認められない。
(イ) タコの足を模した部分について
別紙1原告滑り台目録記載1(2)の各写真によれば,本件原告滑り台 には,タコの頭部を模した部分から4本のスライダーが延びており,こ れらはいずれもタコの足を模したものであって,その形状は,直線状か 曲線状かの相違はあるものの,いずれについても,なだらかな斜度をな しつつ,地面に向かって延びているほか,滑らかな板状のすべり面を有 し,かつ,その左右には手すり様の構造物が付されていると認められる。\nこの点,滑り台は,高い箇所から低い箇所に滑り降りる用途の遊具で あるから,スライダーは滑り台にとって不可欠な構成要素であることは\n明らかであるところ,タコの足を模した部分は,いずれもスライダーと して利用者に用いられる部分であるから,滑り台としての機能を果たす\nに当たって欠くことのできない構成部分といえる。\nそうすると,本件原告滑り台のうち,タコの足を模した部分は,遊具 としての利用のために必要不可欠な構成であるというべきであるから,\n実用目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して,美術鑑賞 の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認め られない。
(ウ) 空洞(トンネル)部分について
別紙1原告滑り台目録記載1(2)の各写真によれば,本件原告滑り台 には,正面から見て左右に 1 か所ずつ,スライダーの下部に,通り抜け 可能なトンネル状の空洞が配置されていると認められる。\nこの構成は,滑り台としての機能\には必ずしも直結しないものではあ るが,前記アのとおり,本件原告滑り台は,公園の遊具として製作され, 設置された物であり,その公園内で遊ぶ本件原告滑り台の利用者は,こ れを滑り台として利用するのみならず,上記空洞において,隠れん坊な どの遊びをすることもできると考えられる。 そうすると,本件原告滑り台に設けられた上記各空洞部分は,遊具と しての利用と不可分に結びついた構成部分というべきであるから,実用\n目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して,美術鑑賞の対 象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められ ない。
(エ) 本件原告滑り台全体の形状等について
別紙1原告滑り台目録記載1(2)の各写真によれば,本件原告滑り台 は,頭部(前記(ア)),足(前記(イ))及び空洞(前記(ウ))等によって形 成されており,その全体を見ると,本件原告滑り台は,見る者をしてタ コの体を模しているとの印象を与えるものであると認められる。また, とりわけ本件原告滑り台の正面からその全体を見ると,空洞のある頭部 を頂点に,左右へ広がる緩やかな2本の足によって均整の取れた三角形 を見て取ることができ,見栄えのよい外観を有するものということがで きる。 この点,本件原告滑り台のようにタコを模した外観を有することは, 滑り台として不可欠の要素であるとまでは認められないが,そのような 外観は,子どもたちなどの本件原告滑り台の利用者に興味や関心を与え たり,親しみやすさを感じさせたりして,遊びたいという気持ちを生じ させ得る,遊具のデザインとしての性質を有することは否定できず,遊 具としての利用と関連性があるといえる。また,本件原告滑り台の正面 が均整の取れた外観を有するとしても,そうした外観は,前記(ア)及び
(イ)でみたとおり,滑り台の遊具としての利用と必要不可欠ないし強く 結びついた頭部及び足の組み合わせにより形成されているものであるか ら,遊具である滑り台としての機能と分離して把握することはできず,\n遊具のデザインとしての性質の域を出るものではないというべきである。 そうすると,本件原告滑り台の外観は,遊具のデザインとしての実用 目的を達成するために必要な機能に係る構\成と分離して,美術鑑賞の対 象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められ ない。
(オ) 以上のとおり,本件原告滑り台は,その構成部分についてみても,\n全体の形状からみても,実用目的を達するために必要な機能に係る構\成 と分離して,美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把 握できるものとは認められないから,「美術の著作物」として保護され る応用美術とは認められない。
(カ) これに対し,原告は,本件原告滑り台の実用目的は滑り台自体とし ての機能を前提に把握すべきであり,高所に上がるための手段と,滑り\n降りるためのスライダーがあればその機能を果たすことができるので,\n表現の選択の幅は広いとした上で,本件原告滑り台のタコの頭部を模し\nた部分,タコの足を模した部分及び空洞(トンネル)部分は,滑り台の 機能から必然的に創作できるものではなく,滑り台の機能\とは独立して 存在する特徴であって,製作者であるBの個性が表われた部分といえる\nから,そのような部分を有する本件原告滑り台は「美術の著作物」に該 当する応用美術であると主張する。 しかしながら,ある製作物が「美術の著作物」たる応用美術に該当す るか否かに当たって考慮すべき実用目的及び機能は,当該製作物が現に\n実用に供されている具体的な用途を前提として把握すべきであって,製 作物の種類により形式的にその目的及び機能を把握するべきではない。\n原告の主張は,滑り台には様々な形状や用途のものがあるにもかかわら ず,本件原告滑り台が滑り台として製作されたものであるという点を過 度に重視するものであり,子どもたちなどの利用者が本件原告滑り台に おいて具体的にどのような遊び方をするかを捨象している点で相当では ない。
また,原告の上記主張は,本件原告滑り台の表現の選択の幅が広く,\n製作者であるBの個性が表われていることを根拠とするものであるが,\nその点は,著作物性(著作権法2条1項1号)の要件のうち,「思想又 は感情を創作的に表現したもの」との要件に係るものであって,「美術」\n「の範囲に属するもの」との要件に係るものではないというべきである。 したがって,原告の上記主張はいずれも採用することができない。 エ 以上によれば,本件原告滑り台は,著作権法10条1項4号の「美術の 著作物」に該当せず,同法2条1項1号所定の著作物としての保護は認め られないというべきである。
2021.06.16
令和2(行ケ)10092 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年5月31日 知的財産高等裁判所
上記(1)の記載によれば,引用技術2の「油性ゲル状」「粘着シート製剤」 は,上記(1)イの従来技術である「架橋アクリル系粘着剤」の組成を調整する ことによって,粘着性を維持しつつ薬剤の溶解性を高めたシートであって, 皮膚への粘着性は,従来技術と同様に,専らアクリル系粘着剤に依存してい ることが認められる。
3 相違点についての審決の判断の当否
上記1(3)のとおり,本願発明の技術的意義に照らすと,本願発明の「オイル ゲル」は,アクリル系粘着剤等の粘着性ではなく,ゲル化したオイルの粘着性 によって,皮膚に対して粘着するものである。これに対し,引用技術2の「油 性ゲル状粘着製剤」は,上記2(2)のとおり,アクリル系粘着剤の粘着性によっ て,皮膚に対して粘着するものである。 このように,引用技術2の「油性ゲル状粘着製剤」は,本願発明の「オイル ゲル」とは技術的意義を異にするから,引用発明に引用技術2を適用しても, 相違点に係る本願発明の構成には至らない。\nしたがって,容易想到性に関する審決の判断には誤りがある。
4 被告の主張について
被告は,「オイルゲル」は有機溶剤を溶媒とするゲルの総称であるとの技術 常識が存在し,本願発明の「オイルゲル」の意義や組成について本件明細書に は記載がないから上記技術常識に沿って解釈すべきであり,上記技術常識によ れば引用技術2の「油性ゲル」は「オイルゲル」に含まれる旨主張する。 たしかに,乙1(特許庁「周知・慣用技術集(香料)第I部香料一般」1999 年1月29日発行)等によれば,「ゲル」を流体(溶媒)の違いという観点から 「ヒドロゲル」「オイルゲル」「キセロゲル」の3種類に分類することが一般 的に承認されている事実は認められ,また,乙6(権英淑ほか「実効感を発現 するためのスキンケア製剤設計」FRAGRANCE JOURNAL Vol.34 No.1 pp.52-55 (2006))等には,この分類を前提として,アクリル系材料を基剤とした「オイ ルゲル」の粘着剤に言及する記載も見られる。しかしながら,他方,甲7(柴 田雅史「化粧品におけるオイルの固化技術」J.Jpn. Soc. Colour Mater., 85 [8] 339-342 (2012))では,冒頭に「有機溶剤(オイル)を少量の固化剤を用 いて固形もしくは半固形状にしたものは一般に油性ゲルと呼ばれ,・・・・・・メイク アップ化粧品を中心に幅広い製品の基剤として用いられている」と記載されて おり,化粧品の分野において,「オイルゲル」の用語をこのような意味で用い ることも一般的であったと認められるから,「オイルゲル」という用語が,当 然に被告主張のような意味に用いられると断定することはできない。
そうすると,本願発明の「オイルゲル」の技術的意義は,特許請求の範囲の 記載だけからは一義的に明確ではない。そこで,明細書の発明の詳細な説明の うち,従来技術に関する記載及び解決課題に関する記載を参酌し,上記1のと おり,「オイルゲルシート」を「アクリル系粘着剤等の粘着性ではなく,ゲル 化したオイルの粘着性によって,皮膚に対して粘着するシート」と解釈すべき である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2021.06.16
令和2(ネ)10010 損害賠償等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年5月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
4 争点4(ツイート直前ログイン時IPアドレス等が発信者情報に該当するか)について
(1) 被控訴人は,本件アカウント1及び6につき,ツイート1並びに6及び6’ の直前のログイン時IPアドレス等の開示を求めるのに対し,控訴人は,ロ グイン時のIPアドレス及びタイムスタンプは,侵害情報の発信行為とは全 く別個の行為であるアカウントへのログイン行為に関する情報であるから, 「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法4条1項柱書) に該当しないと主張する。
(2) プロバイダ責任制限法4条1項は,開示請求の対象となるべき情報につい て,「権利の侵害に係る発信者情報」と規定し,その具体的な内容を総務省 令(発信者情報省令)に委任しているところ,権利の侵害に「係る」という ように,やや幅をもって規定していることからすれば,権利の侵害そのもの から把握される発信者情報だけでなく,権利の侵害に関連して把握される発 信者情報であり,発信者情報省令により定められているものであれば,開示 請求の対象となると解すべきである。 そして,新発信者情報省令5号が「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」 と規定し,侵害情報に「係る」というように,やや幅をもって規定している ことからすれば,侵害情報の発信そのもののIPアドレスだけでなく,侵害 情報の発信と密接に関連し,同一人物のものである確度が高い情報のIPア ドレスであれば,開示請求の対象となると解すべきである。 これを本件についてみるに,上記3(2)で述べたとおり,ツイート行為1並 びに6及び6’によって送信されたテキストデータ等は本件写真1及び2に 係る被控訴人の同一性保持権の侵害を発生させた侵害情報と評価することが できる。そして,ツイッターに投稿(ツイート)するためには特定のアカウ ントにログインしなければならず,ツイート1又は6若しくは6’は直前に おける本件アカウント1又は6へのログイン行為によるログイン状態を利用 してされたと合理的に考えられる。これらのことからすれば,ツイート1並 びに6及び6’の直前のログインに係る情報は,侵害情報の送信と密接に関 連する情報であって,同一人物のものである確度が高いから,侵害情報の発 信に関連して把握される発信者情報であると認められ,したがって,被控訴 人は,控訴人に対し,新発信者情報省令5号に基づき,本件アカウント1に ついてツイート1の直前に同アカウントにログインした際のIPアドレスの 開示を請求することができ(原判決主文第2項(1)のうちIPアドレスの開示 を認めた部分),本件アカウント6についてツイート6の直前に同アカウン トにログインした際のIPアドレスの開示を請求することができるとともに (原判決主文第2項(2)のうちIPアドレスの開示を認めた部分),ツイート 6’の直前に同アカウントにログインした際のIPアドレスの開示を請求す ることができる(本判決主文第2項(2))ものと認められる。
他方,新発信者情報省令8号は,「第五号のアイ・ピー・アドレスを割り 当てられた電気通信設備,第六号の携帯電話端末等からのインターネット接 続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識 別番号(中略)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定 電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻」として,開示の対象 となる「侵害情報が送信された年月日及び時刻」は,「侵害情報が送信され た」ときのものであることをと定めている。上記のとおり,ツイート1並び に6及び6’に係るテキストデータ等は侵害情報に当たると解されるところ, ツイート1並びに6及び6’自体とは異なるツイート1並びに6及び6’の 直前のログインに係る送信の年月日及び時刻は,「侵害情報が送信された年 月日及び時刻」という文言に該当するとは認められない。したがって,本件 アカウント1について,ツイート1の直前のログインに係る送信の年月日及 び時刻の開示を請求することはできず,本件アカウント6について,ツイー ト6の直前のログインに係る送信の年月日及び時刻の開示,並びにツイート 6’の直前のログインに係る送信の年月日及び時刻の開示を請求することは できない(そのため,原判決主文第2項(1)のうち,本件アカウント1につい てツイート1の直前のログインに係る送信の年月日及び時刻の開示を命じた 部分を取り消し(本判決主文第1項(1)),原判決主文第2項(2)のうち,本件 アカウント6についてツイート6の直前のログインに係る送信の年月日及び 時刻の開示を命じた部分を取り消し(本判決主文第1項(2)),当審における 追加請求のうち,本件アカウント6についてツイート6’の直前のログイン に係る送信の年月日及び時刻の開示を請求する部分を棄却する(本判決主文 第2項(3))。)。
(3) これに対し,控訴人は,ツイッターのシステム上,一つのアカウントに対 して,複数のログイン状態が競合することは頻繁に発生しており,ツイート 行為がその直前のログイン行為によるログイン状態を利用して行われたもの であるかどうかは明らかではないから,ツイート行為と直前のログイン行為 の関連性は明らかとはいえない旨主張する。 しかしながら,ツイッターのシステム上,一つのアカウントに対して複数 のログイン状態が競合することがあるとの一般的な可能性を考慮しても,ツ\nイート行為がその直前のログイン行為によるログイン状態を利用して行われ たと考えることには合理性があるものと認められ,控訴人の指摘は,ツイー ト行為1並びに6及び6’の直前のログイン時におけるIPアドレスが,侵 害情報の送信と密接に関連する情報であって,同一人物によるものである確 度が高く,侵害情報の発信に関連して把握される発信者情報であるとの上記 認定を左右しない。したがって,控訴人の上記主張には理由がない。
また,控訴人は,発信者情報の開示は,通信の秘密や表現の自由という重\n大な権利権益に関する問題である以上,ひとたび開示されてしまうと原状回 復は不可能であるという性質を有していることから,開示請求の対象となる\n発信者情報は,訴訟による権利回復を可能にするという制度の趣旨に照らし\nて必要最小限度の範囲に予め限定するのが相当であり,ログイン時IPアド\nレス等のような情報を開示の対象に含めるべきではなく,現に,ログイン時 情報を発信者情報として開示することは立法時には必ずしも想定されてい なかったと主張する。 しかし,通信の秘密や表現の自由を保護しつつ,情報の発信により著作権\n法上の権利を侵害された者の救済を図ることも必要であり,プロバイダ責任 制限法及び発信者情報省令の解釈により認められる範囲において発信者情報 を開示することは許容されるべきであるから,控訴人の上記主張を採用する ことはできない。
関連カテゴリー
>> ピックアップ対象
2021.06.15
令和1(行ケ)12020 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年5月19日 知的財産高等裁判所
(イ) 加圧ポンプ140や空所134を経由しない経路を設ける手段(手 段1)の採用と甲1発明の技術思想について
a 空所134への液体の集約
被告は,甲1は,甲1発明が,「改良された液体分布機構」として,ポンプ140によって液体を加圧し,さらに,この加圧した液体をい\nったん空所134に集約した上で「コンプレツサ内の必要な全ての個 所」(スラストピストン室60を含む。)に供給するという構成を採用したことを明らかにしており,甲1発明の「改良された液体分布機構\」においては,ポンプ140により加圧された液体が,中間ハウジング 30に形成された空所134を介することなく供給される個所は,コ ンプレツサ内に存在しないとし,したがって,スラストピストン室6 0についてのみ,ポンプ140によって加圧されない液体を空所13 4を介することなく供給するなどという構成は,甲1発明の技術思想に反するものであって,適用が排斥されていると主張する(前記第3,\n1(2)イ(イ)c(a))。
甲1には,空所134に関し,「中間ハウジング30はまた,圧力の かかつた液体を分布する空所あるいはマニフオールド134を有して いる。」(9欄35〜37行),「空所134は,コンプレツサベアリン グおよびシール,スラストピストン,交叉する穴18と20により形 成された作動室,および容量制御バルブ42に対する駆動体の室70 に圧力のかかつた液体を分布せしめるためのマニフオールドとして働 く。圧力のかかつた液体は,パイプ148,150通路152および パイプ154を介して空所134から室70に供給される。」(10欄 6〜13行)と記載され,ポンプ140によって加圧した液体の供給 について,いったん空所134に集約した上で「コンプレツサ内の必 要な全ての個所」(スラストピストン室60を含む。)に供給するとい う構成を採用することが記載されているにとどまる。そうすると,ポンプ140により加圧された液体を供給する経路の一部を,あえて空\n所134を経由しない別の経路として設けるように変更することは, 甲1の技術思想に反するものとして,その適用が排斥されているとい う余地があるとしても,ポンプにより圧力が加えられない液体をスラ ストピストン室60に供給する非加圧の経路を設ける場合に,これを, ポンプ140及び空所134を経由しないように設けることまでもが 排斥されていると解することはできない。したがって,被告の上記主 張を採用することはできない。
被告は,加圧ポンプ140や空所134を経由しない経路を設ける と,スラストピストン室60に供給される液体がフイルタ146を迂 回することになるので,異物(ロータ同士の接触により生ずる金属く ず・鉄粉,液体の化学反応により生ずる不物等)がスラストピストン 室60に到達して詰まり等が生じることなどの不都合があり,ひいて はコンプレツサ10が機能不全に陥るとし,甲1発明において,スラストピストン室60に液体を供給する構\成を,ポンプ140・フイルタ146・空所134を迂回するものの他のフイルタを通過してスラ ストピストン室60に至る構成に改変しようとすると,フイルタ146とは別個のフイルタの追加が必要となり,更にはそれに応じた液体\nパイプ・液体パイプ接合の追加等が必要となるため,甲1発明がコン プレツサ外部の液体パイプ接合の数を最少としようとしている趣旨等 に反し,そのような構成を採用することには,やはり阻害要因があると主張する(前記第3,1(2)イ(イ)d(b))。
しかし,スラストピストン室60に供給される液体がフイルタ14 6を迂回したとしても,圧縮機全体での液体の循環が繰り返される中 で,大部分の異物はいずれはフイルタ146を通って除去されること になるし,必要であれば,ポンプの前にフイルタを経由するように構成を変更し,ポンプにより圧力を加えられる液体も,圧力を加えられ\nない液体もフイルタを通過するようにするなどの対応を取ることもで きるから,コンプレツサ10が機能しなくなるとは認められない。また,このように構\成を変更するとしても,それによってコンプレツサ外部の液体パイプ接合の数が著しく増えるとする根拠はない。したが って,被告の上記主張を採用することはできない。
・・・
。このように,甲1発明に ついても,逆スラスト力(逆スラスト荷重状態)の発生という課題を 認識できることから,そのような課題を解決するために,逆スラスト 荷重解消のために非加圧の経路を設けるという動機付けも生じるもの と認められる。そうすると,逆スラスト力(逆スラスト荷重状態)が 発生するという技術的課題やその課題の解消について甲1に直接の言 及がないとしても,そのような課題を解決するために甲1発明に非加 圧の経路を設けるという動機付けが生じるものと認められる。したが って,被告の上記主張を採用することはできない。
3 以上によれば,本件特許発明は,甲1発明に,甲2ないし甲5に記載された 周知技術を適用して当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許 法29条2項の規定により特許を受けることができず,本件特許は特許法12 3条1項2号の規定により無効とすべきものであると認められ,取消事由1(無 効理由1に関する進歩性の判断の誤り)は理由がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2021.06.15
令和2(ネ)10062 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和3年5月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
最高裁平成15年判決について
同判決は,いわゆる真正商品の並行輸入について,それが1)当該商標が外 国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に 付されたものであり(以下「第1要件」という。),2)当該外国における商 標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に 同一人と同視し得るような関係にあることにより,当該商標が我が国の登録 商標と同一の出所を表示するものであって(以下「第2要件」という。),\n3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る 立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品 とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される 場合(以下「第3要件」という。)には,商標権侵害としての実質的違法性 を欠くと判断した。
この判決は,商標権者から商標の使用許諾を受けた上で,当該商標を付し た商品を製造販売した者から,当該事件の被告が商品を輸入したという事案 に関するものであった。これに対し,本件の事案は,商標権者が自ら商品を 製造してこれを販売代理店に売却し,その販売代理店から被控訴人ブライト が商品を輸入したという事案であり,製品が商標権者自らの手によって製造 されていたかどうかという点において,重大な違いがある。このため,後述 のとおり,上記の3要件を事案の違いに応じて変容させる必要がないのかと いう点が問題になり得るものの,基本的には,上記の3要件をベースとして 被控訴人ブライトによる輸入行為が実質的に違法性を欠くものであるかどう かを判断すべきであると解されるので,以下,各要件について判断する。
(3) 第1要件について
ア 上記のとおり,第1要件は,当該商標が当該商標権者等によって適法に 付されたものであるかどうかを問題とするのに止まるから,この要件をそ のまま適用する限り,商標権者が製造した本件商品の輸入が問題になって いる本件においては(控訴人らは,本件商品の全てが,ランピョン社がM ゴルフ社に販売した商品であることは立証されていない旨主張するが,既 に認定したとおり,Mゴルフ社は,かつてはランピョン社の販売代理店で あり,同社から正規の2UNDR商品を購入し,保有していたことが認め られ,また,被控訴人ブライトがMゴルフ社から輸入した商品の点数(2 387点)は,Mゴルフ社が,ランピョン社から購入し,上記輸入直前の 時点において保有していたとしてもおかしくない商品の点数(2448 点)の範囲内であるのに対し,被控訴人ブライトが輸入した商品が,上記 とは他のルートで入手されたものであったことを疑わせるような証拠は全 くないのであるから,本件商品が真正商品であることを否定することはで きないものというべきである。),第1要件が満たされることは明らかで あるし,本件代理店契約の解除や,地域制限条項の存在などといった控訴 人ら主張の事情は,この判断に何ら影響を及ぼすものではないということ になる。そして,これが被控訴人らの主張するところでもある。
イ これに対し,控訴人らは,本件事案においては,第1要件は,単に適法 に商標が付されたことだけではなく,適法に商標が付された商品が,商標 権者の意思に基づいて流通に置かれたことまで要求するものとして理解す べきであると主張する。 たしかに,最高裁平成15年判決の事案は,商標が,商標権者自身では なく,商標権者から使用許諾を受けた者によって付された事案であったた め,使用許諾権者がその権原に基づいて商標を付したのかどうかという意 味において,商標が適法に付されたのかどうかが問題となる余地があった のに対し,本件事案のように,商標権者自身が商品を製造販売している事 案では,この要件が問題になることはほとんど考えられず,果たして,商 標が適法に付されたかどうかのみを単独の要件とする意味があるのかとい う点が問題となり得る。この点や,最高裁平成15年判決以前には,本件 事案のような事案に関し,「商標権者が当該商標を適法に付して流通に置 いたこと」を要件とする見解が有力であり,このように「適法に流通に置 いたこと」を要件とすることは,非正規のルートで入手された商品が並行 輸入された場合を排除するという意味を持ち得るものであることを併せ考 えると,最高裁平成15年判決とは事案が異なる本件においては,商標が 適法に付されたかどうかだけではなく,それが適法に流通に置かれた(あ るいは,商標権者の意思に基づいて流通に置かれた。以下,同じ。)かど うかも問題とする必要があるという見解もあり得るものと考えられる。そ の意味で,控訴人らの主張にはもっともなところがあるといえる。 しかし,仮にそのように考えるとしても,本件において,Mゴルフ社は, ランピョン社から正規に本件商品を購入したのであるから,この時点にお いて,本件商品が「適法に流通に置かれた」ことは明らかである。そして, 本件代理店契約の解除や地域制限条項の存在といった控訴人ら主張の事情 は,上記の判断を左右するに足りるものではないと考えられる。その理由 は,次のとおりである。
ウ すなわち,まず,本件代理店契約解除との関係について検討すると,前 認定のとおり,Mゴルフ社は,上記解除によって本件商品を販売してはな らない義務を負うと解する余地はある。しかし,このような条項があるか らといって,Mゴルフ社が本件商品の処分権限を失うわけではない(本件 代理店契約解除によって,直ちにMゴルフ社の本件商品に対する所有権が 失われるものではないことは控訴人ら自身が自認しているところであるし, ランピョン社が買戻権を行使した事実が存在しないことも既に指摘したと おりである。)。そうであるとすると,Mゴルフ社が,本件代理店契約解 除後に本件商品を売却したとしても,それは,ランピョン社との間で債務 不履行という問題を生じさせるだけで,本件商品が「適法に流通に置かれ た」という評価を覆すまでのものではないというべきである。実質的に見 ても,Mゴルフ社が正規に購入した商品を,本件代理店契約解除後に他に 売却したからといって,直ちに商標の出所表示機能\が害されるとはいえな いのであって,この点からしても,第1要件該当性を否定する理由はない。 この点は,地域制限条項との関係についても同様であり,地域制限条項 は,あくまでも債権的な効力を有するにすぎず,Mゴルフ社による本件商 品の処分権限を奪うものではないのであるから,これに違反した処分がさ れたからといって直ちに,本件商品が「適法に流通に置かれた」という評 価が覆るものではないというべきである。実質的にみても,Mゴルフ社が 正規に購入した商品を制限地域外で販売したからといって直ちに商標の出 所表示機能\が害されるとはいえないのであって,この点からしても,第1 要件該当性を否定する理由はない(なお,最高裁平成15年判決は,地域 制限条項違反を理由の一つとして第1要件該当性を否定しているので,こ の判断との関係についても念のため触れておく。同判決の事案は,商標の 使用許諾契約において地域制限がされていたという事案であったため,使 用権者は,そもそも,制限地域外において商品に商標を付す権限を有して いなかった。このため,制限地域外で商標を付したとしても,それは「適 法に」商標を付したことにならないとの評価を免れなかった。これに対し, 本件事案において,Mゴルフ社の商品処分権限は何ら制約されていないこ とは既に説示したとおりであり,この点において,本件と最高裁平成15 年判決の事案とは事案を異にするというべきである。)。
エ 以上の次第で,第1要件の内容を最高裁平成15年判決の判断どおりと みた場合でも,それに「適法に流通に置かれたこと」との要件を加えたも のとして理解したとしても,いずれにせよ,同要件は満たされているとい うべきである。
(4) 第2要件について
本件においては,控訴人ハリスが我が国における商標権者であると同時に 外国における商標権者でもあるから,本件商品に付された商標と我が国の登 録商標(原告商標)とが同一の出所を表示するものであることは明らかであ\nる。 なお,被控訴人ブライトは,我が国において被告各標章を利用した宣伝広 告活動を行っているが,これは本件商品の輸入後の行為であることからする と,そもそも,かかる事情が第2要件該当性の判断に影響を及ぼすものであ るのかは疑問である。また仮に,これらの事情を考慮に入れる必要があると しても,原告商標と被告各標章が類似のものであることは上記1で原判決を 引用して説示したとおりであるから,出所表示の同一性に影響を及ぼすもの\nではなく,いずれにせよ第2要件該当性は肯定されるべきである。
(5) 第3要件について
ア 最高裁平成15年判決における第3要件は,「我が国の商標権者が直接 的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当 該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保 証する品質において実質的に差異がないと評価される場合」であることと いうものである。 ところで,最高裁平成15年判決の事案は,商標権者自身ではなく,商 標の使用許諾権者が商品を製造したという事案であった。そこで,商標に 係る商品の品質保証のため,商標権者が,商標使用許諾権者(あるいは, その下請等の立場にあった者)の行為に対して,直接的に又は間接的に品 質管理を行い得る立場にあったかどうかが重要な問題になり得たものであ る。これに対し,本件のように,商標権者自身が商品を製造している場合 には,商品の品質は,商標権者自身が商品を製造したという事実によって 保証されており,後は,その品質が維持されていれば品質保持機能に欠け\nるところはないといえる。そして,本件商品は男性用下着であって,常識 的な期間内で流通している限り,その過程で経年劣化等をきたす恐れはな いし,商標権者自身が品質管理のために施した工夫(商品のパッケージ 等)がそのまま維持されていれば,商品そのものに対する汚損等が生じる おそれもないといえる。 そうであるとすると,少なくとも,本件のように商標権者自身が商品を 製造している事案であって,その商品自体の性質からして,経年劣化のお それ等,品質管理に特段の配慮をしなければ商標の品質保証機能に疑念が\n生じるおそれもないような場合には,商標権者自身が品質管理のために施 した工夫(商品のパッケージ等)がそのまま維持されていれば,商標権者 による直接的又は間接的な品質管理が及んでいると解するのが相当である。
イ そこで,以上の観点から,第3要件が満たされているかどうかを検討す るに,本件商品と2UNDR商品の日本における販売代理店が販売する商 品とが,登録商標の保証する品質において実質的に差異がないといえるこ とは,原判決「事実及び理由」第3,2⑷オ(原判決31頁24行目から 32頁17行目まで)に記載のとおりである。そして,商品のパッケージ 等はそのまま維持されていたものと推認できるから,「我が国の商標権者 が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあること」 との要件も,満たされているものといってよい。
ウ 控訴人らは,地域制限条項は,商品が最終消費者に販売されるまでの間 の品質を商標権者がコントロールするために重要な条項であるから,同条 項の違反は商標の品質保証機能を害する旨主張するが,販売地域の制限に\n係る取決めは,通常,商標権者の販売政策上の理由でされるにすぎず,商 品に対する品質を管理して品質を保持する目的と何らかの関係があるとは 解されないから,上記主張は失当である(なお,最高裁平成15年判決の 事案における地域制限条項は,商品を製造する地域を制限する条項という 意味も持っていたため,どこで商品を製造するかは品質の保持に影響する と解する余地があった。これに対し,本件事案においては,商品自体は商 標権者によって製造済みであり,それをどの地域で販売するかが問題にな るのにすぎないのであるから,両者が全く事情を異にすることは明らかで ある。)。また,本件代理店契約が解除されたという事実も,第3要件の 充足性に影響を及ぼす事情とはいい難い。
エ 控訴人らは,本件商品の包装箱にシールを剥がした跡があることや,広 告に「訳あり/パッケージ汚れ」との記載があることは,商標の品質保証 機能を害する旨主張する。\nしかし,包装箱(パッケージ)の汚れ等の不具合は,商品(男性用下 着)自体の品質とは直接の関係がなく(パッケージの汚れが,単に表面に\nとどまらず,内部にまで影響を及ぼしていたことを認めるに足りる証拠は ない。),本件商品の品質が控訴人らの扱う2UNDR商品の品質よりも 実際に劣っていたことをうかがわせる証拠もない。また,「訳あり/パッ ケージ汚れ」との記載は,商品そのものではなく,そのパッケージに汚れ があることを「訳あり」と称しているのにすぎないものと理解できるから, これによって,2UNDR商品そのものの品質に疑念が生じるおそれはな いものといえる。 したがって,この点に関する控訴人らの主張は失当である。
オ さらに,控訴人らは,控訴人ハリスは,正規代理店を経由して日本に輸 入された商品については交換に応じる等の保証をしており,品質について 独自の信用を構築しているところ,本件商品は保証の対象外であり,本件\n商品の購入者は,商品に欠陥があった場合も交換等を受けられないのであ るから,控訴人ハリスの保証を受けられないことは,品質保証機能を害す\nるとも主張する。 しかし,控訴人ハリスが,顧客からの要請に基づいて,商品の交換に応 じることがあるというだけで,独自の品質管理体制が構築されていたとま\nでいうことはできないし,そのほかに,控訴人らが,商品の品質について, 並行輸入を排除するのに足りるような独自の信用を構築していることを認\nめるに足りる証拠はない。 したがって,この点に関する控訴人らの主張も失当である。
(6)まとめ
以上の次第で,本件において,第1要件ないし第3要件は,いずれも満た されているというべきであるから,被控訴人ブライトによる本件商品の輸入 行為は,実質的な違法性を欠くというべきである。
3 並行輸入の違法性阻却と販売行為の態様との関係について
控訴人らは,被控訴人ブライトの輸入行為が違法性を阻却されるとしても, 商標権者が許容しない方法で広告宣伝及び販売をする行為は違法性を阻却され ない旨主張する。 しかしながら,その理由として控訴人らが挙げる事情は,いずれも並行輸入 の違法性阻却の場面で検討ずみのものであって,むしろ,上記2のとおり,商 標の品質保証機能が害されていないことの理由ともなり得るものである。また,\n被控訴人ブライトは,被告各標章を利用して本件商品の宣伝,広告を行ってい るところ,被告各標章の中には,本件商標と完全に同一であるとはいい難いも のも含まれているが,本件商標と類似するものであることは上記1で原判決を 引用して説示したとおりであり,このような標章を使用することによって本件 商標の機能を害しているとまではいえないから,この点も違法性阻却を否定す\nるに足りる事情であるとはいい難い。
◆判決本文
1審はこちら。
2021.06. 6
令和2(ネ)1006 不当利得返還等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年5月17日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,平成25年9月以降のやり取りにおいて被控訴人学園か ら提案された120万円には著作権に対する対価は含まれていなかった ものであり,控訴人と被控訴人学園との間で本件システムの開発に係る 委託費用は月額約32万円と合意されていたことからすれば,著作権侵 害行為によって生じた控訴人の損失は160万円を下らない旨主張し, また,著作権法114条1項又は同条3項に基づいて算定しても,同損 失は160万円を下らない旨主張する。 (イ) まず,控訴人と被控訴人学園との間のやり取り又は合意に関する主 張について検討するに,仮に,上記やり取りにおける被控訴人学園の提 案が,本件システムに係るプログラムの著作権を取得する対価を含む趣 旨ではなかったとしても,前記認定事実のとおり,平成24年12月か ら平成25年3月までの本件システムの開発費用は105万円であっ たこと,この支払がされた時点において,本件プログラムは本件システ ムの半分程度を完成させたものであったことに加え,上記提案のほかに 控訴人及び被控訴人学園が本件プログラムの対価について具体的な金 額を協議したと認めるに足りる証拠はないことや,本件における被控訴 人学園による本件プログラムの著作権等侵害行為の態様等,本件に現れ た一切の事情を考慮すると,被控訴人学園による著作権侵害行為につい て,本件プログラムの著作権の利用料相当額としての利益を受け,控訴 人に損失を及ぼした金額は,20万円と認めるのが相当であり,これを 超える利益及び損失が生じたものと認めるに足りる的確な証拠は存し ない。また,控訴人と被控訴人学園との間において,本件システムの開発に 係る委託費用を月額約32万円とする合意が成立したと認めるに足りる 証拠は存しない。そうすると,控訴人と被控訴人学園との間のやり取り又は合意を根拠 として,控訴人に160万円の損失が生じたと認めることはできない。
(ウ) 次に,著作権法114条に基づく控訴人の主張について検討するに, 同条1項に基づく主張については本件プログラムの譲渡等に係る控訴 人の利益の額につき,同条3項に基づく主張については本件システムと は異なるシステムであるWebClassのライセンス料を基に利用 料相当額を算定することにつき,それぞれ具体的な根拠を欠くというべ きである。 そうすると,著作権法114条1項又は同条3項を根拠として,控訴 人に160万円の損失が生じたと認めることはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
◆平成30(ワ)36168
被告学園は,前記4の著作権侵害行為につき,本来原告に支払うべき金
銭を支払っていないから,その金銭の額に相当する額の利益を受け,原告
に同額の損失を及ぼしたと認められる。そこで,以下,上記の額(利用料
相当額)がいくらであるのかについて検討する。
原告は,被告学園から,平成24年12月から平成25年3月までの本
件システムの開発費用として,105万円を受け取った(前記1(4))。こ
れは,前記3のとおり,著作権の対価ではなく,それまでの労務の対価と
して支払われたものであったが,原告が上記の金銭を受け取った時点で,
本件プログラムは,本件システムの半分程度を完成させたにとどまるもの
であった(前記1(5))。Cは,同年10月頃,原告に対し,本件システム
の残りの開発に係る開発費用として,120万円を支払うことを提案して
おり(前記1(14)),当該提案がされた経緯や提案された金額からすれば,
これは,残り半分程度の本件システム開発に係る労務の対価に加えて,被
告学園が原告から本件システムに係るプログラムの著作権を取得する対価
を含む趣旨での提案であったものと推認することができる。
以上に加え,上記提案のほかに原告と被告学園が本件プログラムの対価
の具体的な金額について協議したと認めるに足りる証拠はないこと,前記
4の被告学園の本件プログラムの著作権等侵害の態様等,本件に現れた一
切の事情を考慮すると,被告学園が前記4の著作権侵害行為について,本
件プログラムの著作権の利用料相当額としての利益を受け,原告に損失を
及ぼした金額は20万円と認めるのが相当である。
イ 原告は,平成25年4月1日から同年10月15日までの本件システム
の開発に係る委託費用相当額の損失をも被ったと主張して,被告らに対し
同額の不当利得の返還を請求するので,以下検討する。
前記1(4)ないし(6),(11)ないし(14)の経緯に照らせば,被告らは上記
期間に対応する本件システムの開発の成果物を受領していないし,原告と
被告らとの間において,上記期間に係る本件システムの開発の委託費用の
支払を合意したとも認められない(むしろ原告は,被告学園に対し,Bへ
の本件圧縮ファイルの送付以降の開発費用等の支払は不要であると伝えて
いる。)。そうすると,被告らにおいて,原告による平成25年4月1日
から同年10月15日までの対応する本件システムの開発に係る利益を受
けたと認めることはできない。
また,前記2,3のとおり,本件プログラムの著作権は原告に帰属して
おり,被告らは,本件プログラムの著作権を取得しておらず,本件全証拠
によってもこれを利用する権原を取得したとも認められないから,被告ら
は原告の許諾なく本件プログラムを利用することはできない。そうすると,
被告らにおいて,原告に本件プログラムを作成させた対価を支払う必要は
ないというべきであり,その支払を免れたことによる利益を受けたとは認
められない。
したがって,原告が被告らに対して委託費用相当額の不当利得返還請求
権を有しているとは認められず,原告の上記主張は理由がない。
2021.06. 6
令和2(ワ)2956 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月20日 大阪地方裁判所
本件各発明に係る特許請求の範囲及び本件訂正明細書の各記載によれば,本件各 発明の本質的部分については,以下のとおりと認められる。 すなわち,従来,硬貨の表面に描かれた模様は,硬貨を製造するプレス機に設置\nされるプレス金型に予め彫り込まれ,硬貨をプレス及び打ち抜きする際,硬貨の表\ 面に金型の凹凸が反転して表現されていたところ,プレス金型に対して硬貨の表\面 に浮き出る部分は,平面彫刻機で彫り込んで行われていた。しかし,平面彫刻機の ように厚み方向のみ切削する切削工具では,切削した部分及び切削を行わなかった 部分は平面仕上げであり,金属の地肌のままの色合いであるため,放電加工機で不 規則かつ微細に地金を削り取りいわゆるナシ地仕上げを行ったり,切削した部分を 細かく研磨して鏡面仕上げを行ったりし,また,立体彫刻機で人物や動物等立体的 な図形を彫り込み,得られた硬貨の表面の凸部に人物等を立体的に表\現して,硬貨 の装飾効果を高めていた。しかし,これらの方法によっても,図形等の部分を除い た硬貨の地模様に対応する部分は,平面仕上げ,鏡面仕上げ,ナシ地仕上げのいず れかであり変化に乏しく,また,メダル遊戯機で使用される硬貨は,コスト等の兼 ね合いがあり,高価な金属の使用が難しく,表面の輝きが鈍いものが多いという課\n題があった。本件各発明は,こうした課題に対し,硬貨の表面の地模様に立体彫り\nによる変化を起こし,硬貨の輝きを増し,硬貨の装飾価値等を高めることを目的と するものである。具体的には,本件発明1は,切削深さを任意に変えられる同時三 軸制御 NC フライス機を,硬貨表面に描かれる人物や動植物等の図形に用いるので\nはなく,金型の表面に対して一定パターンで切削を繰り返すことにより硬貨の地金\n部分に立体的な幾何学的模様からなる新たな地模様を描き出し,硬貨の装飾価値を 高めるものである。本件発明2は,本件発明1と同様の方法で硬貨の地模様を描き 出すことに加え,同じく同時三軸制御 NC フライス機により地模様以外の模様に対 応する部分をV溝状に切削することで,当該模様部分の表面積の増加等により硬貨\nの表面の輝きを増加させ,硬貨の装飾価値等を高めるものである。\n以上を踏まえると,本件各発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,少なくとも 「金型の厚み方向へ切削可能な」切削工具「を用い,金型に対して一定のパターン\nで切削深さと,水平面に対する金型の切削角度と,を変えながら金型表面上を移動\nさせ,傾斜面を含む特定のパターンを金型上に描き,これを金型表面全体に繰り返\nすことにより繰り返し模様からなる地模様を形成すること」は,従来技術には見ら れない特有の技術的思想を有する本件各発明の特徴的部分すなわち本質的部分であ るといえる。さらに,本件発明2においては,これに加え,上記工具「により硬貨 の表面に浮き出る文字,図形等の模様に対応する部分をV溝状に切削すること」も,\n特徴的部分すなわち本質的部分ということができる。
(3) 前記のとおり,本件各発明における「金型」(構成要件B,C,E及びF)は\nプレス金型を意味し,また,被告製造方法の構成については当事者間に争いがある\nものの,被告製造方法が原金型に関する工程とプレス金型に関する工程という2つ の工程を含むこと,被告機械を用いて原金型の表面に地模様及び地模様以外の模様\nに対応する部分を切削加工により作製することは,当事者間に争いがない。これを 踏まえると,本件各発明においては,プレス金型の厚み方向へ切削可能な切削工具\nを用い,プレス金型に対して一定のパターンで切削深さと,水平面に対するプレス 金型の切削角度と,を変えながらプレス金型表面全体に繰り返すことにより繰り返\nし模様からなる地模様を形成し,本件発明2においては,これに加えて,上記工具 により硬貨の表面に浮き出る地模様以外の模様に対応する部分をV溝上に切削して\nプレス金型を得るのに対し,被告製造方法においては,被告機械を用いて原金型の 表面に地模様及び地模様以外の模様に対応する部分を切削加工により作製し,こう\nして得られた原金型から(特定されない加工方法(被告方法1)又は放電加工(被 告方法2)により)プレス金型を得る点で相違する。そうすると,被告製造方法は, 本件各発明の本質的部分を共通に備えているとはいえない。 したがって,本件各発明と被告製造方法の相違部分は,本件各発明の本質的部分 に当たる。
(4) 原告らの主張について
これに対し,原告らは,本件各発明の本質的部分は,金型に対して一定のパター ンで切削の深さと,水平面に対する金型の切削角度と,を変えながら金型表面上を\n移動させ,傾斜面を含む特定のパターンを金型上に描くことと,地模様以外の模様 に対応する部分をV溝状に切削することであり,原金型とプレス金型の2つの金型 を用いるか否かは本件各発明の本質的部分ではないなどと主張する。 しかし,前記のとおり,原金型からプレス金型に対する転写等の工程につき,そ の構成を特定しなくても,本件各発明の作用効果を奏し得るものが行われることが\n当業者にとって技術常識であるとは認められないことをも踏まえると,金型につき 原金型とプレス金型の2つを用いるか否かは,本件各発明の本質的部分に係る相違 部分というべきである。 したがって,この点に関する原告らの主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2021.06. 4
令和2(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年5月17日 知的財産高等裁判所
イ シリコーン誘発凝集阻害という課題の発見の容易性について 原告は,タンパク質製剤におけるシリコーン誘発凝集は知られており, タンパク質の凝集が多糖類−タンパク質コンジュゲート凝集の原動力であ ることを当業者は理解していたから,公知発明1に6種の肺炎球菌CRM コンジュゲートを追加することによりタンパク質含量が増える13価の肺 炎球菌CRMコンジュゲート製剤でシリコーン誘発凝集が生じることは予\n見可能であった旨主張する。\nしかし,原告がその主張の根拠とする公知文献(甲25,26,71) は,キャリアタンパク質がCRM又は破傷風毒素(TT)である多糖類− タンパク質コンジュゲートの構造的不安定性に関連する凝集について記載\nするのみであるから,これらの公知文献からは,多糖類−タンパク質コン ジュゲートのシリコーン誘発凝集が本件優先日当時に課題として当業者に 認識されていたとはいえない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 課題の解決手段の適用の容易性について
上記イで述べたとおり,当業者は本件発明の課題を認識できないから, 既にこの点において容易想到性は否定されることになるが,念のため,課 題解決手段適用の容易想到性に関する原告の主張についても検討しておく。
(ア) タンパク質製剤のシリコーン誘発凝集の解決手段に関する知見につき
原告は,当該課題の解決のために,当業者は,タンパク質製剤におけ るシリコーン誘発凝集の解決手段に関する知見を採用し得た旨主張する。 しかしながら,原告がその主張の根拠とする公知文献(甲3,69) には,タンパク質医薬品のシリコーン誘発凝集についての記載はあるが, 多糖類−タンパク質コンジュゲートのシリコーン誘発凝集についての記 載はない。他方,多糖類−タンパク質コンジュゲートの構造的不安定性\nや凝集は,タンパク質部分のみでなく多糖類部分の影響も受けることが 知られていたところ(甲25,50),多糖類とタンパク質は構造や性\n質が異なるから,両者の挙動は異なることが当然に予想される。そうす\nると上記公知文献(甲3,69)に記載されたタンパク質医薬品のシリ コーン誘発凝集についての知見が,多糖類−タンパク質コンジュゲート のシリコーン誘発凝集にも直ちに妥当するものとは認められない。また, 上記公知文献は,タンパク質医薬品のシリコーン誘発凝集の問題を解決 する手段として,それぞれ,界面活性剤の添加又はシリコーン含有量の 低減を開示するのみであって,本件発明の構成であるアルミニウム塩の\n添加には触れていないから,公知発明1にタンパク質製剤のシリコーン 誘発凝集の解決手段に関する上記公知文献記載の知見を適用しても,本 件発明の構成には至らない。\nしたがって,原告の上記主張は採用できない。
(イ) アルミニウム塩の発揮する効果に関する知見につき
原告は,凝集体の発生に関連するタンパク質の疎水性表面への吸着は\nアルミニウム粒子で防ぐことができるとの知見(甲81の3,76)が あったから,疎水性界面を示すシリコーンによるワクチンの凝集も,ア ルミニウム塩をアジュバントとすることにより防ぐことができると当業 者は理解したと主張する。
しかし,上記知見においては,容器の疎水性表面へのタンパク質の吸\n着は,液体(製剤)と固体(容器)との界面における容器表面とタンパ\nク質分子との相互作用に関連すると理解されていたのに対し(甲81の 3),タンパク質医薬品のシリコーン誘発凝集は,微量のシリコーンの 存在と空気−液体界面におけるタンパク質の変性や(甲3),タンパク 質結合に関与する分子間相互作用へのシリコーンの影響(甲69)に関 連すると考えられており,シリコーン誘発凝集がタンパク質のシリコー ンへの吸着によって生じると考えられていたとは認められないから,疎 水性表面へのタンパク質の吸着をアルミニウム粒子により阻害する旨の\n上記知見を,直ちに肺炎球菌CRMコンジュゲートのシリコーン誘発凝 集の阻害のために適用することは困難であったといえる。 したがって,原告の上記主張は採用できない。
エ 単なる「発見」にすぎないとの予備的主張について\n
原告は,相違点4に係る発明特定事項は,ワクチン製剤のアジュバント としてアルミニウム塩を選択するという周知慣用技術を採用したとき,ア ルミニウム塩が肺炎球菌CRMコンジュゲートワクチン製剤においてはシ リコーン凝集阻害という効果を示すという,公知発明1(7価プレベナー )でも生じていたメカニズムを「発見」したにすぎないから,相違点4を 根拠に本件発明の進歩性を認めることは,自由技術に独占権を与えること になって不当である旨主張する。 しかし,この主張は,本件発明と公知発明1とは実質的には同一である という前記の主張と本質を同じくするものであるといえるところ(すなわ ち,本件発明と公知発明1とは実質的には同一であって,発明の構成にお\nいて違いはないという前提があって初めて,本件発明の独自性は,凝集の メカニズムを「発見」したにすぎないという議論が成り立ち得ることにな るはずである。),この主張を採用することができないことは既に説示し たとおりである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2021.06. 4
平成31(ワ)784 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年4月26日 大阪地方裁判所
「需要者の間に広く認識されている」(商標法32条1項)といえるため には,全国的に知られている必要はないものの,商品又は役務の性質等を踏まえつ つ,取引の実情を考慮して,一定の地理的範囲において広く知られているものとい えることを要すると解される。本件においては,たこ焼きの需要者はたこ焼きを購 入しようとする一般の消費者であると見られること,たこ焼きは,通常,加熱調理 されて温かい状態で食べられる食品であることなどを考慮すると,被告標章が「需 要者の間に広く認識されている」といえるためには,被告店舗が多数存在する愛知 県及びその近隣県の需要者の多くに認識されていることを要するといえる。
(イ) 前記認定事実((1)ア)によれば,被告は,本件商標の登録出願まで15年 以上にわたって被告標章を使用し,店舗を展開してきたものであり,また,被告の 売上,愛知県内の店舗数,各店舗の総来店者数のいずれも,決して少ないとはいえ ない。 しかし,本件商標の登録出願当時における愛知県を除く隣接県の店舗数は,各県 とも数店舗にとどまる(前記(1)ア)。愛知県においても,本件商標の登録出願後 の数ではあるものの愛知県内に500店舗を超えるたこ焼き店が存在すること(前 記(1)ア)に鑑みれば,被告店舗数は,それ自体をもって被告標章が需要者の多く に認識されていることを裏付けるに足りるほど多数であるとまではいえない。しか も,基本的には SC 内,しかも多くは地域密着型の総合スーパーマーケットに出店 し,単独で又は他のファーストフード店その他の飲食店と共に,専門店として1階 に位置し,店舗出入り口付近又はフードコートに配置され,たこ焼き,お好み焼 き,たい焼き,焼きそば,フライドポテト,杵つき団子,ソフトクリーム等を主要\nな取扱商品とするという被告店舗の出店態様等(前記(1)イ)を考慮すると,その 来店客は,基本的にはスーパーマーケットを中心とする SC 内の他店での買い物を 目的とする買い物客のうち,買い物の合間の食事や持ち帰りの軽食として手軽に食 べられる飲食物を購入するために来店する者が多数を占め,被告店舗での購入を主 要な目的として来店する者は必ずしも多くないものと推察される。さらに,被告店 舗において,被告標章は来店客により容易に認識され得る態様で表示されていると\nいえるものの,こうした来店客が被告標章に払う注意の程度は必ずしも高くないと 思われる。
また,上記出店態様等に鑑みると,出店先の SC がその商圏内で配布する広告宣 伝用の折込チラシ等に被告店舗の広告も掲載される例が多いことが推察され,現に その例も認められるものの(前記(1)ウ(オ)),そのような折込チラシの性質上,被 告の店舗に関する広告は,SC 内に出店する専門店の1つとして掲載されるにとど まり,その掲載スペースも大きくはないものと推察される(乙23添付の資料3及 び4では,被告店舗に割り当てられているスペースは全体の 1/16 程度である。)。 求人広告においても被告標章が表示されていることが認められるものの,これに触\nれる者は求職中の者に自ずと限定されることに鑑みると,これをもって需要者に広 く認識されていることを裏付ける事情としては必ずしも考慮し得ない。広告宣伝費 としての支出額(前記(1)ウ(ア))も,売上及び店舗数を踏まえると,被告と同じ業 種ないし業態の事業者に比して顕著な額を投下していることが明らかとまではいい 難い。
本件商標の登録出願までに被告店舗がマスコミ等に取り上げられた状況(前記 (1)ウ(イ)〜(エ))を見ても,その回数はむしろ少なく,かつ,その影響が及ぶ範囲も 限定的である。他方,上記時期に限らず,その後も含めた被告のウェブサイトの総 閲覧者数,口コミサイトや第三者のブログ等での掲載状況(前記(1)ウ(カ),エ(ア)) を見ても,その掲載数等が多いとはいえない。 これらの事情を総合的に考慮すると,被告標章は,本件商標の登録出願の際,被 告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,愛知県及びその隣接県の需要\n者の多くに認識されていた,すなわち「需要者の間に広く認識されて」いたとは認 められない。これに反する被告の主張は採用できない。
・・・
被告は,本件訴訟における原告の本件商標権の行使につき,原告は,被告 に対し損害賠償請求をするという不当な目的で本件商標の登録出願を行い,本件訴 訟を提起したものであるから,原告の被告に対する本件商標権の行使は権利濫用に 当たると主張する。 確かに,本件商標の登録出願は,被告が売上額及び店舗数とも大きく伸ばした段 階でされたものであり(前記1(1)ア),また,被告による被告標章の使用を理由 として本件商標の登録出願に関する早期審査を求めながら,その商標登録後被告に 対する最初の警告書送付まで1年半近くの期間を要した(前記(1)エ,オ)といっ た経緯は認められる。
しかし,前記(1)ア〜ウのとおり,原告は,「たこ焼工房」に「43」,「Sea & Sun」等を結合させた標章をその屋号として主に使用しているところ,「たこ焼工 房」と組み合わせる表示が複数存在することに鑑みると,原告としては,「たこ焼\n工房」の表示それ自体も自己を示すものとして使用しているものとうかがわれる。\nまた,原告は,「たこ焼工房/Sea & Sun/ シーアンドサン」の商標につき登録 出願し,商標登録を得ている。原告によるこうした営業表示の使用状況等を踏まえ\nると,原告が,既に商標登録を受けた商標「たこ焼工房/Sea & Sun/シーアンド サン」の一部である「たこ焼工房」につき商標権として権利化を図ったこと自体を 不当ということはできない。このことは,原告が被告ないし被告標章の存在等を知 って本件商標権を取得したといった事情があったとしても異ならない。さらに,本 件商標の登録から最初の警告書送付までの期間,更には本件訴訟提起までの期間の 点も,原告が賠償請求し得る損害額をより多額とする意図を有していたと認めるべ き具体的な事情はない。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても,本件における原告の被告に対する 本件商標権の行使をもって権利の濫用というべき事情があるとはいえない。
2021.06. 4
平成30(ワ)8708 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月13日 大阪地方裁判所
本件発明の構成要件B1,B2及びB3は,「支持面」について規定するもので\nあり,その文言によれば,1)支持面は,水平支持部材の上面の略中央にある開口部 の端部にあり,2)支持面は,側溝蓋の当接部の曲面(断面凸状)と略相似の断面凹 状の曲面からなり,3)当接部の下端部とせぎり部との間に所定の隙間を形成するた め,4)支持面の下端に沿って連続的にせぎり部が形成されるというものである。 前記1のとおり,従来製品においては,側溝蓋の平面の当接部が,側溝本体の平 面の支持面によって支持されていたところ,本件発明においては,断面凸状の当接 部が,略相似の関係にある断面凹状の支持面で支持されることによって,側溝蓋に より受ける荷重が分散されるとともに密着性がよくなり,支持面に平面がないため に小石,砂利,土等が堆積しにくくなり,側溝蓋のガタツキや騒音の発生を抑制し, かつ,せぎり部により当接部の下端部と支持面の下端部との間に所定の隙間が形成 されるため,砂利,土等がその隙間に集まり,当接部と支持面との間の面接触状態 が維持され,堆積した小石,砂利,土等も除去しやすい,という効果があるとされ る。
そうすると,せぎり部は,本来であれば略相似の関係にある曲面が当接する関係 にあった当接部と支持面のうち,支持面の下端の形状を変更することによって,当 接部の下端部との間に隙間を設けるものであるから,せぎり部は,それが設けられ ていなければ支持面の一部として当接部と当接した部分に存することになるし,せ ぎり部と対応する位置には,断面凸状の曲面からなる当接部の下端部が存すること になる。逆に言うと,側溝蓋と側溝本体との間に隙間が存したとしても,その隙間 が,断面凸状の曲面からなる当接部の下端部に対応するのでなければ,それは本件 発明のせぎり部にはあたらないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2021.06. 4
令和2(行ケ)10102等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年5月20日 知的財産高等裁判所
ウ また,甲1の「読取り/書込みデバイス102」は単独で機能するもの\nである。
(ア) 甲1発明は,RFIDタグの読取り/書込みを行うデバイスと,この デバイスを利用する会計端末に関するものである(甲1の訳文3頁4行〜6行)が, 一般に,RFID読取りデバイスにより情報が読み取られる対象物には,液体を含 む物や水分量が多い物もあるが,そうでない物もある。こうした液体を含む物や水 分量が多い物を取り扱わない店舗も多々あるが,甲1発明の発明者は,スーパーマ ーケットのように,液体を含む物や水分量が多い物も販売する店舗に着目し,その ような店舗においては,「FR 2 966 954 A1号」として公開されてい る特許公開公報(乙30)の図に示された装置では,効率的な読取りを実施するこ とができないと考えており(甲1の訳文3頁10行〜26行),甲1発明は,「液体 を含む物や水分量の多い物についてもRFIDタグが効率的に読みとれること」, 「対象物のタイプにかかわらず,RFIDタグが効率的に読みとれること」を目的 とするものであることを,当業者は理解する。
そして,当業者は,甲1の具体的構成(甲1の訳文3頁35行〜47行)により,\n「本発明によるデバイスによって,載置キャビティ内において,端末の近傍に置か れた製品,特に端末に隣接する棚に置かれた製品に貼付されたRFIDタグが通電\nされ,したがって読み取られるリスクを伴わずに,読取り/書込み動作を実施する のに使用される電波の出力を増加させることが可能になり,またしたがって,キャ\nビティ内に載置されたタグを,液体を含む対象物に貼付されたタグであっても,よ\nり良好に読み取ることが可能になる。」という効果を有すること(甲1の訳文4頁1\n4〜19行)を理解する。
甲1の具体的構成と,乙30に記載されているRFID読取りデバイスの相違は,\n1)「前記挿入アパーチャの周りに配置され,前記挿入アパーチャから上方に延在し, 前記載置キャビティと外部との間の電波を減衰することができる,防壁と呼ばれる 少なくとも1つの壁」(「防壁」)と,2)「前記少なくとも1つの防壁を通して前記挿 入アパーチャにアクセスするための,アクセス開口部と呼ばれる少なくとも1つの 開口部」(「アクセス開口部」)のみである。 2)の「アクセス開口部」は,1)の「防壁」がある場合に,載置キャビティに物を 入れるため(「防壁を通して前記挿入アパーチャにアクセスするため」)の開口部で あるから,防壁があれば必然的に存在することになるものであり,水分を含む物で も情報が効率的に読み取れることとは関係しない。甲1の具体的構成が,乙30に\n係る発明と異なり,水分を含む物でも情報が効率的に読み取れるのは,「防壁」があ るからであると当業者は理解する。 したがって,当業者は,水分を含まない物や対象物が軽い物を読み取るのであれ ば,電波を低量にするから,「防壁」のない装置で十分であると理解する。\nそして,甲1では,「防壁」のないものとして,「読取り/書込みモジュール20 0」が,[図2]に示され,甲1の訳文10頁1〜19行に具体的な構成が記載され\nており,当業者は,「読取り/書込みモジュール200」は,「防壁」を備えるもの ではなく,よりシンプルな構成であるが,読取装置に必要な要素をすべて備えるも\nのであり,水分を含まない対象物については,問題なく動作することを理解する。 このように,甲1には[図1]に示されている読取装置と,[図2]に示されてい る読取装置の二つが開示されており,[図1]の読取装置は,水分を含む物も含まな い物も,効率よく読み取ることができるものであり,[図2]の読取装置は,水分を 含まない物に使用することができると,当業者は理解する。 甲1発明2のように,読取装置を独立した発明として把握する公知文献,公知技 術は枚挙に暇がない(甲2,乙28〜37)。
(イ) 原告らは,水分を含まない物を読み取るものとして,甲1発明2を単 体で利用することについては甲1に何ら記載がないと主張している。 しかし,被告は,読取対象物が水分の少ない場合については従来技術と同様に甲 1発明2が単体の読取装置として機能することを説明しているのであるから,これ\nに対する反論となっていない。当業者が甲1文献の記載を読めば,読取対象物が水 分の少ない物を取り扱う店舗においては,水分の多い物を読み取るために創作され た甲1発明1全体を実施するのは無駄であり,従来技術に近い甲1発明2を実施す べきであると考えるのが当然である。 また,原告らは,電波の出力を下げると金属に貼られたタグも読み取りできなく\nなると主張する。 しかし,そのような事実があるかは不明であるし,仮にそうであるとしても,読 取対象物が金属製でない場合は,従来技術と同様に,甲1発明2が単体の読取装置 として機能し,使用可能\である。本件明細書には,電波強度や金属に貼られたタグ\nを読み取る点について記載がなく,本件発明が金属に貼られたタグが読めるものと\nは解釈できないから,甲1発明2と対比できるものではない。
エ 原告らは,防壁及びアクセス開口部は,甲1に記載される目的を達成す るために必須の構成であると主張する。\nしかし,上記ウのとおり,甲1の[図2]の読取装置は,水分を含まない物につ いては読取装置として十分に使用することができると,当業者は理解する。本件審\n決は,甲1に記載されたこれらの発明のうち,水分を含まない物に使用することが できる[図2]の読取装置を「甲1発明2」と認定したものであるから,誤りはな い。
オ 原告らは,甲1の実施例に重量計が使われていることを指摘するが,読 取対象物が水分の少ない場合については,重量計が存在しても,従来技術と同様に, 甲1発明2が単体の読取装置として機能することに変わりはない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.05.31
平成31(ワ)2675 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月18日 東京地方裁判所
以上によれば,被告製品は,そのほとんどが吹矢協会と関係がある需要 者により購入されたと認めることが相当である。そして,被告製品は,吹 矢協会の関係者において吹矢協会の公認用具であることを理由として購 入された割合が相当に高いと認められる。原告の製造販売する吹矢用具は 令和2年12月1日以降は吹矢協会の公認用具でなかったから上記の理 由で購入された被告製品の需要の全てが原告の製造販売する吹矢の矢に 向かうとは認められない。他方,原告の製造する吹矢の矢については,吹 矢協会の公認がなくとも購入するとする者もいたことがうかがわれ,被告 製品の需要が全く原告の製造販売する吹矢用具に向かわないとはいえな い。
被告は,原告の吹矢用具が吹矢協会の公認用具でないことを理由として 令和2年12月1日以降の被告の売上げについての推定覆滅を主張する ところ,上記事情に照らせば,同日以降の利益については,65%の割合 で損害額の推定が覆滅すると認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.05.22
令和1(行ケ)10108 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年5月13日 知的財産高等裁判所
上記の本件明細書の記載等からすると,本件明細書には,図4で示 された24のコントロールチャネルエレメントについて,最高レベルの 集合レベル1ではそれぞれが1つのコントロールチャネル(24個)を 形成し,比較的低いレベルである集合レベル2では2つのコントロール チャネルエレメントが1つのコントロールチャネル(12個)に,集合 レベル4では4つのコントロールチャネルエレメントが1つのコント ロールチャネル(6個)に,集合レベル8では8つのコントロールチャ ネルエレメントが1つのコントロールチャネル(3個)に,それぞれま とめられた上で,スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補 は,集合レベル1は4つ,集合レベル2は4つ,集合レベル4は4つ,\n集合レベル8は3つに制限され,この制限によってデコーディング試行 の数は15に低減されること,このような制限をツリー構造に課すこと により,図4の例では,集合レベル1では4つのコントロールチャネル\nを,集合レベル2では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4で は2つのコントロールチャネルを,集合レベル8では1つのコントロー ルチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。 また,本件明細書の上記記載に加えて,図4を総合すると,スケジュ ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構\ 造によ って課される割合は,図4の実施例では,最高レベルの集合レベル1で は,24個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合6分の 1),比較的低いレベルの集合レベル2では12個のコントロールチャ ネルを4つの候補に(候補の割合3分の1),集合レベル4では6個のコ ントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の2)それぞれ制 限し,集合レベル8の3個のコントロールチャネルを制限しない(候補 の割合1分の1)ことが開示されているに等しい事項といえる。
そうすると,本件明細書及び図面には,ユーザイクイップメントに対 するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の各レベルにおける割合に着目し,最高レベルよりも低い2,4,8の各レベル\nにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は,最高レベルにおける,ユーザイ\nクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対する\nアロケーションを含むスケジュールをすることが開示され,又は開示さ れているに等しい事項であるということができる。また,【0025】の 記載からすると,最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネ ルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表\されていることが開示されていることから,この開示事項に上記 事項と合わせると,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能\なコントロール チャネル候補の割合がより大きくされることも開示され,又は開示され ているに等しい事項であるといえる。
したがって,訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る技術 的事項は,いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を 導入するものであるとはいえないから,訂正事項2及び3は,新規事項 の追加に当たるものとはいえない。
イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき は,訂正の効果は出願時まで遡及する(特許法128条)ところ,特許請 求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の 効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば,同法126条6項の「実 質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの」であるかは,訂正の前 後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり,こうした 解釈によって,特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利 益を与えることを防止することができる。以下,これを前提にして判断す る。
(ア) 本件訂正前の請求項1は,「前記アロケーションは,最高レベルのコ ントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され, 前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構\造のノードによって表 され,それにより,比較的低いレベ\nルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構\造の比較的低いレベルにあ るツリー構造のノードによって表\ される,方法」との発明特定事項を含 むものであり,この発明特定事項からは,ツリー構造のノードによって表\されるコントロールチャネルのアロケーションは,最高レベルにある コントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行さ れ,それにより比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーシ ョンが可能となることと理解される。
これに対し,本件訂正後の請求項1は,訂正事項1ないし3によって, 「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは,前記最高レベル における,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,前記最高レ\nベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツ リー構\造のノードによって表 され,それにより,前記最高レベルよりも\n低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルに おける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\な コントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップ メントに対するアロケーションを実行することが可能となり,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構\造の前 記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表\ さ れ,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメン トに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の割 合がより大きくされる,方法」との発明特定事項を含むものであり,こ の発明特定事項からは,ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンは,最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ ョンに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,それにより,最高レベルよりも低い各レベルのユーザイクイップメ\nントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ\nョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することを可能\と し,かつ,ツリー構造におけるより低いレベルほどユーザイクイップメ ントに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の 割合がより大きくされる方法が含まれるものと理解することができる。 このように,訂正後の請求項1は,訂正前の請求項にはない,「ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ ャネル候補」という概念を追加した上で,「前記最高レベルよりも低い各\nレベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使 用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける, ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに 対するアロケーションを実行する」,「ツリー構造における,より低いレ ベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\ なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追 加し,これによって,訂正前の方法では,ツリー構造で表\ される比較的 低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかっ た,ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の割合 を大きくすることが発明特定事項に含まれることになったといえる。 そうすると,訂正事項1ないし3は,特許請求の範囲を実質上変更す るものであるから,特許法126条5項に適合するものとはいえない。
(イ) これに対し,原告は,前記第3の1(1)ア(イ)及びイ(イ)のとおり,1) 訂正事項2及び3は,新たな技術的事項を導入するものではなく,2)訂 正事項2は,訂正前は,無条件で比較的低いレベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを可能としていたのを,訂正後は,使用可能\ なコ ントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実 行することを可能とするものであるから,本件訂正は,特許請求の範囲 の減縮に該当する旨主張する。\n
しかし,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかに ついては,特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前 記のとおりであるところ,発明の詳細な説明に記載された事項からどの 事項を発明特定事項とし,上位概念とするかについては,出願者がその 技術的意義に鑑みて適宜選択して特許請求の範囲とするものであって, 明細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的事項との関係 において,新たな技術的事項を導入するものではないからといって,訂 正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有す るものとはいえない。
そして,前記(ア)のとおり,請求項1は,訂正事項2及び3によって, 訂正前の方法では,ツリー構造で表\ される比較的低い各レベルのアロケ ーションについては特に規定するところがなかった,ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーショ\nンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくするとの事項が発明特定事項に含まれることになったものであり,こうした発明特定\n事項は,「統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的 に低減される」という課題((【0004】)を解決する発明の構成そのも のに関する事項であるから,単に条件付けをしたのにすぎないとはいえ\nず,特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。 したがって,原告の上記主張は採用できない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2021.05.22
平成30(ワ)16422等 商標使用差止等請求事件 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年4月23日 東京地方裁判所
ア 商標法38条2項は,商標権者は,故意又は過失により自己の商標権を 侵害した者に対してその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場 合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,そ の利益の額は,商標権者が受けた損害の額と推定すると規定しているとこ ろ,同項が損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定である ことに照らせば,商標権者に,侵害者による商標権侵害行為がなかったな らば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,商標法38 条2項の適用が認められると解すべきである。
イ 本件において,被告は,本件商標1と類似する被告各使用標章を本件商 標1と同一の指定役務である飲食物の提供に使用している。しかしながら, 原告が本件商標1を用いて経営する原告店舗は長崎県島原市に所在してい るところ,しゃぶしゃぶ料理の提供という原告の業務に係る顧客は,飲食 店の一般的な顧客の範囲からすると,同市及びその周辺に在住の者である と推認され,本件において,これと異なる事実を認めるに足りる証拠はな い。他方,被告が経営していた本件店舗は東京都台東区に所在しており, 本件店舗の業務に係る顧客は,東京都内及びその周辺に在住の者であると 推認され,本件において,これと異なる事実を認めるに足りる証拠はない。 原告店舗における事業との関係で被告による商標権侵害行為がなければ原 告が利益を得られたといえるためには,それらが競合関係にある必要があ ると解されるところ,原告店舗及び本件店舗の事業の性質から,原告店舗 に対する需要者と本件店舗に対する需要者とは重ならず,原告店舗と本件 店舗が競合関係にあるとは認められない。
ウ 原告は,本件に商標法38条2項が適用されると主張するに当たり,オ ンラインショップや東京都中央区所在のアンテナショップ(以下,これら を併せて「原告オンラインショップ等」という。)において,本件各商標 を付して本件豚肉等を販売しているところ,被告が本件店舗において被告 各標章を使用して飲食物を提供しなければ,豚肉舞豚を食べたいという顧 客の需要は,原告オンラインショップ等に向かうというべきであり,これ により原告は利益を得られたなどと主張する。 ここで,被告による商標権侵害行為がなければ,原告オンラインショッ プ等において原告が利益を得られたというためには,少なくとも本件店舗 における業務と原告オンラインショップ等における業務が競合関係にある といえる必要があるとするのが相当である。そして,原告オンラインショ ップ等においては,本件豚肉等が販売されているのに対し,本件店舗では 豚肉のしゃぶしゃぶ料理が提供されており,これらの事業の形態は大きく 異なる。また,顧客についてみても,本件店舗においては,店舗において 豚肉舞豚を用いたしゃぶしゃぶ料理の提供を受けたいという顧客が主であ るのに対し,原告オンラインショップ等においては,本件豚肉等を購入し 自宅で食べたいという顧客が主である。本件店舗における業務と原告オン ラインショップ等における業務にはこのような相違があるところ,本件に おいて,店舗において豚肉舞豚を用いた料理を食べたいと考える顧客の需 要が原告オンラインショップ等に向かうことを裏付ける的確な証拠はない。 そうすると,本件店舗と原告オンラインショップ等とでは,類型的に事業 の形態が相違しており,本件でその顧客等が重なる事情も認められず,本 件店舗における業務と原告オンラインショップ等における業務が競合関係 にあるとはいえないと認めるのが相当である。原告の上記主張を採用する ことはできない。
なお,原告は,被告が本件店舗を閉店したと主張する平成30年8月を 基準に,閉店後の平成30年9月から平成31年2月までとその前年同期 (平成29年9月から平成30年2月まで)の原告オンラインショップ等 の売上げを比較し,本件店舗閉店後の前者の売上げが閉店前年同期の後者 の売上げから約125%増額しており,被告による商標権侵害行為により 原告は得られる利益を逸していたなどと主張する。しかしながら,証拠 (甲38,39)及び弁論の全趣旨によれば,原告オンラインショッピン グ等の平成30年9月から平成31年2月までの売上げが974万074 3円(内訳:ふるさと納税に係る売上げ964万6895円,それ以外の 売上げ9万3848円)であり,平成29年9月から平成30年2月まで の売上げが776万8833円(内訳:ふるさと納税に係る売上げ757 万6000円,それ以外の売上げ19万2833円)であることが認めら れ,本件店舗の閉店前と閉店後の同時期の売上げを比較すると,本件店舗 の閉店後の期間の売上げが増加しているとはいえるものの,それはふるさ と納税による売上げが増加したことに伴うものといえる。そして,ふるさ と納税制度を利用して商品を購入する動機は,ふるさとへの貢献や返礼品 を受領することなど多種多様であることに鑑みれば,上記の売上額の増加 をもって,原告の主張を裏付けるものということはできず,他に原告の上 記主張を認めるに足りる証拠もない。
エ 以上によれば,原告の業務と被告各使用標章の使用に係る被告の業務と の間で市場における競合関係があるとはいえず,被告による商標権侵害行 為がなかったならば,原告が利益を得られたであろうと認めることはでき ない。したがって,原告の本件商標権1の侵害による損害額の算定に当た って,商標法38条2項を適用する前提を欠き,同項の適用は認められな い。
(2)商標法38条3項の損害額について
ア 本件店舗は,「舞豚」というブランドの豚肉のしゃぶしゃぶ料理を提供 することを特徴とする飲食店であるところ,被告は,被告各使用標章を本 件店舗の名称,店舗の外観や料理のメニュー表などに広く用いていたこと(前記前提事実(3)アイ)からすれば,商標法38条3項による損害額の算 定に当たっては,本件店舗の売上げに対して,本件商標1の使用に対し受 けるべき料率を乗じて算定するのが相当である。
イ 次に,本件商標1の使用に対し受けるべき金銭の料率について検討する。 証拠(甲36)によれば,株式会社帝国データバンク作成の「知的財産 の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査報告書」におい て,「商標権に関する分類別ロイヤルティ料率の平均値」について全体 (205件)では2.6%であり,「商標の分類」が「第43類 飲食物 の提供及び宿泊施設の提供」については3件の例があり,最大値5.5%, 最小値1.5%,平均値3.8%であるとの記載が認められ,飲食物の提 供についての商標権のロイヤルティ料率は,全体の平均値より相当程度高 いといえる。 また,証拠(後掲)及び弁論の全趣旨によれば,豚肉舞豚は平成7年1 0月19日の第39回長崎県種豚共進会において農林水産大臣賞を受賞し たこと(甲37),本件店舗の開店時に長崎新聞には「島原産ブランド豚 提供「舞豚」」という見出しの記事が,島原新聞には「「舞豚」が東京進出」 という見出しの記事がそれぞれ掲載されたこと(乙4)が認められる。こ れらの事実に照らせば,豚肉舞豚に対して一定の評価が与えられていたこ とがうかがえる。 そして,本件店舗は,豚肉舞豚をしゃぶしゃぶ料理として提供すること を大きな特徴とする店舗であるところ,被告は,店舗の名称や看板,メニ ュー表等に被告各使用標章を使用していた。他方,本件店舗には,他に顧客を特に引き付けるような標章等が使用されていたともいえない。そうす\nると,被告は,一定の評価が与えられていた豚肉舞豚と同じ呼称等を有す る被告各使用標章を,店舗の名称も含めて積極的に活用して本件店舗を営 業していたといえ,被告各使用標章の使用は被告の売上げにも貢献するも のであったといえる。
これらの事情に加えて,被告は,本件各商標の使用許諾契約が被告によ る信頼関係を破壊する行為により解除された後も,被告各使用標章の使用 を継続していたなど本件訴訟に現れた一切の事情を併せて考えれば,商標 権を侵害した者に対して事後的に定められるべき商標の使用に対し受ける べき料率は,8%と認めるのが相当である。
ウ 以上によれば,被告による商標権侵害について,商標法38条3項によ り算定される損害額は,本件店舗の売上高(平成29年12月から平成3 0年8月)1189万7246円(争いのない事実)に8%を乗じた金額 である95万1779円となる。
(3) 損害不発生の抗弁について
被告は,原告に使用料相当額の損害は発生しておらず,商標法38条3項 は適用されないと主張する。 しかし,被告は,店舗の名称や看板,メニュー表等に被告各使用標章を使用した一方,本件店舗において他に強く顧客を誘引する標章等が使用されて\nいたものではない。被告各使用標章の使用が被告の売上げに貢献していたと いえることは前記(2)のとおりであるから,被告が被告各使用標章を使用した ことにより原告に使用料相当額の損害が生じないとは認められない。被告の 損害不発生の抗弁についての主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2021.05.12
平成30(ワ)38486 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年3月24日 東京地方裁判所
イ 被告会社による著作権侵害について
本件プログラムをパソコンにインストールすることは,本件プログラムを\n有形的に再製するものとして,本件プログラムの複製に該当するところ(著 作権法2条1項15号),前記1(1)ないし(3)によれば,本件平成20年契約 においては,平成20年9月の一時期を除き,パソコン1台分についてのみ\n本件プログラムのインストールすることが許諾されていたと認められるから, 前記アのとおり,被告会社において,本件平成20年契約の締結当初から本 件旧プログラムをインストールしていた1台に加え,平成26年3月以降, 合計10台のパソコンに本件旧プログラムをインストールしたことは,本件\n旧プログラムの著作権(複製権)の侵害に該当する。なお,被告会社は,平 成20年の契約の内容として,1つのライセンスの契約で,インストールす るパソコン台数を問わずに本件プログラムが使用できるとの合意が成立して\nいたと主張するが,前記2(3)イのとおり,当該主張は採用することができな い。 また,被告会社は,自ら複製権侵害行為を行っているから,上記10台に 複製された本件旧プログラムについて,その使用する権原を取得した時に著 作権侵害の事実について知っていたものと認められ,これを使用する行為は, 著作権法113条2項により,本件旧プログラムの著作権を侵害する行為と みなされる。
(2) 争点2−2(著作権侵害による損害額)について
ア 前記(1)の著作権侵害の態様と,本件平成20年契約においてライセンス 数に応じた本件旧プログラムの複製,すなわちライセンス数に応じた台数 のパソコンへのインストールが許諾されていたことからすれば,前記(1)の 著作権侵害による損害額は,本件旧プログラムが違法に複製されたパソコ\nンごとに,その使用期間に応じたライセンス料相当額と認めるのが相当で ある。 本件旧プログラムの平成30年3月までの使用期間は,平成26年3月 にインストールされた2台につき各49か月,平成28年9月にインスト ールされた1台につき19か月,同年10月にインストールされた5台に つき各18か月,平成29年12月にインストールされた1台につき4か 月,平成30年1月にインストールされた1台につき3か月の累計214 か月となる。 そして,このうち,平成26年3月分については,当時の消費税率に基 づいた1台当たり月額4万4100円(4万2000円×1.05)とし て,平成26年4月分ないし平成30年3月分については,当時の消費税 率に基づいた1台当たり月額4万5360円(4万2000円×1.08) として,それぞれ算定すると,次のとおり,損害額合計は970万452 0円と認められる。
4万4100円×2か月+4万5360円×212か月=970万4520円
イ(ア) 原告は,著作権侵害の不法行為に基づく損害額の算定に当たっても, 債務不履行に基づく場合と同様に,本件プログラムが複製されたパソコ\nンの台数ではなく,本件プログラムを使用した医師会数を基準としてラ イセンス料相当額を算定すべきと主張する。 しかしながら,前記1(4)のとおり,被告会社は,本件旧プログラムを 使用するに当たり,医師会ごとにバックアップデータを作成し,作業し たい医師会に合わせて,その都度使用するバックアップデータを切り替 えることにより,本件旧プログラムをインストールした1台のパソコン\nで複数の医師会に係る作業を行っていたところ,このような被告会社の 行為が本件旧プログラムを有形的に再製するもの,すなわち複製とは認 められないし,違法な複製がされたことを前提とする著作権法113条 2項のみなし侵害に該当するともいえない。 そうすると,前記(1)の著作権侵害行為と相当因果関係のある損害とし て,医師会数を基準としたライセンス料相当額の損害が発生したとは認 められないから,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告らは,原告のホームページに記載された料金表(乙7)に基づい\nて,前記アのライセンス料相当額を算定すべきと主張する。 しかしながら,前記2(4)イで検討したとおり,本件平成20年契約に おけるライセンス料相当額を算定にするに当たって,原告のホームペー ジに記載された通常の料金表(乙7)が適用されるとは認められないから, 同料金表に基づいて算定するのは相当ではなく,被告らの上記主張は採\n用することができない。
関連カテゴリー
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2021.05.11
平成30(ワ)19441 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月28日 東京地方裁判所
本件発明は,端部開口を含む「空気導入口」(構成要件D)から空気\nが導入されてその空気が「排出部」(構成要件E)から排出され,その\n空気の流れによってガス容器収容部,ガス容器を冷却するという空冷機 構を備え,ガス容器収容部,ガス容器に対する熱害の発生を防ぐという\nものである(前記(1))。 原告は,各被告製品の側面開口と底面穴が「空気導入口」であり,カ バー穴が「排出部」であると主張する。 原告は,原告実験1−1から1−3,2−1から2−3,3−1,3 −2,3−3(前記(2)オ,キ,ケ)を,被告は被告実験1−1,1−2, 2(同カ,ク)を行った(このうち,原告実験1−1,2−1,3−1, 被告実験1−1,2が標準ガス容器に関する実験であり,原告実験1− 2,1−3,2−2,2−3,3−2,3−3,被告実験1−2が小型 ガス容器に関する実験である。)。そして,これらの実験において,燃 焼中のガス容器上側側面,下側側面等の温度が測定されるほか,スモー ク粒子を用いて,器具周辺の空気の流れを示すことが試された。 ここで以下の(ウ)ないし(オ)のとおり本件に提出された証拠によって は,各被告製品について,ガス容器収容部,ガス容器を冷却するよう, 側面開口及び底面穴から器具本体内へ空気が導入され,その導入された 空気がカバー穴から排出されていることを認めるに足りない。
被告製品1については,スモーク粒子を用いた原告実験1−3(前 記(2)オ(ウ) において,カバー穴から空気がガス容器収容部外に流出して いるように見えるときが多いものの,そうでないときがあるほか,側面 開口においては,基本的にガス容器収容部から空気が流出しているよう に見え,側面開口から空気がガス容器収容部内部に流入する動きは観察 できるとしても,少しの間しか観察できない。また,被告製品1には, 作動部とガス容器収容部の間には仕切板が一部に設けられているにすぎ ない。作動部においては,空気が取り込まれて燃焼炎等の影響を受けて 熱せられるところ,本件各証拠によっても,作動部で燃焼炎の影響を受 けて熱せられた空気がどのような動きをするかを認めるに足りず,作動 部において燃焼炎等の影響を受けて熱せられた空気がガス容器収容部側 のカバー穴,側面開口から流出することがないことを認めるに足りる証 拠はない。 他方,燃焼の際には,ガス容器内の液化石油ガスの気化に伴い,ガ ス容器は気化冷却され,ガス容器内のガスの温度は低下する(前記(2)ア(イ) そして,気化冷却により液化石油ガスの気化が妨げられることか ら,ガス器具にはガス容器の加温機構を備える必要があり(同前),被\n告製品1においても,燃焼炎の熱や輻射熱を作動部からガス容器収容部 に伝達してガス容器を加温するための加温機構が備えられている(同\nイ)。したがって,ガス容器の気化冷却の程度や,燃焼熱や輻射熱の影 響は,ガス容器収容部及びガス容器の温度に影響を与え得る要因である と認められる。このうち,気化冷却に関して,原告が行った各実験のう ちガス容器内のガスを使い切るまで燃焼したものにおいて,いずれも, ガス容器上側側面及び下側側面の温度がガスを使い切る直前から急激に 上昇しており(同オ ,(ア)(イ))帰化冷却はガス容器を用いた燃焼の最 終段階まで継続しており,かつ,ガス容器下側側面の温度は,開口等の 一部を塞ぐ作為の有無にかかわらず,概ね室温以下で推移しているので あって(同前),その燃焼中のガス容器ひいてはガス容器収容部の冷却 に及ぼす影響は相当に大きいものと認められる。
以上のとおりの原告実験1−3における側面開口付近の空気の流れ, 被告製品1の構造に照らしてカバー穴等から流出する空気と燃焼炎の影\n響を受けた作動部側の空気との関係が不明なこと,燃焼中のガス容器, ガス容器収容部に影響を与え得る諸要因を考慮すると,ガス容器収容部, ガス容器を冷却するよう,側面開口及び底面穴から器具本体内へ空気が 導入され,その導入された空気がカバー穴から排出されていることを認 めるに足りない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2021.05.10
令和2(行ケ)10041 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月25日 知的財産高等裁判所
(ア) ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動に関する本件優先日当時 の知見について
前記ア(ウ),(エ),(カ),(ケ)の各記載からすると,本件優先日当時までに,Co wanらは,ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動と痒みの間には関連性が あることを提唱していたものと認められる。 しかし,これらの証拠によっても,本件優先日当時,Cowanらが,ボンベシ ン誘発グルーミング・引っ掻き行動と痒みには関連性があることを実験等により実 証していたとは認められないし,また,その作用機序等も説明していない。さらに, 甲4には,「この行動,及びその行動の発生におけるボンベシンの考え得る役割に ついては,更に研究する必要がある。」と記載されており,ボンベシン誘発グルー ミング・引っ掻き行動と痒みには関連性があると断定まではされていない。 加えて,前記ア(ア)のとおり,昭和35年に発表された甲25では,そもそもラッ\nトのグルーミングの実施形態,目的,又は,これを支配する状況等は,ほとんど何 も知られていないとされており,前記ア(キ)のとおり,平成4年に発表された甲27\nでも,ボンベシンにより誘発される行動が,痛み等の侵害刺激に基づく可能性があ\nるとの指摘がされており,前記(2)ア(オ)のとおり,平成7年に発表された甲9にお\nいても,信頼性のある痒みの動物モデルは存在しない,マウスは起痒剤Compo und48/80を皮下注射されても引っ掻き行動をせず,マウスがグルーミング 中に耳及び体の引っ掻き行動するのが痒みに関連した行動とは考えられないなどと されており,Cowanら以外の研究者は,ボンベシンやそれ以外の原因により誘 発されるグルーミング・引っ掻き行動が,痒み以外の要因によって生じているとの 見解を有していたと認められる。 そして,前記(2)ア(オ)のとおり,甲9は,Compound48/80やサブス タンスPを起痒剤として取り扱っており,本件明細書の実施例12でも起痒剤とし てボンベシンではなく,Compound48/80が使用されている一方,ボン ベシンは,本件優先日当時,起痒剤として当業者に広く認識されて用いられていた ものであるとは,本件における証拠上認められない。 以上からすると,本件優先日当時,ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動 と痒みの間に関連性があるということは,技術的な裏付けがない,Cowanらの 提唱する一つの仮説にすぎないものであったと認められる。
(イ) オピオイドκ受容体作動性化合物とボンベシン誘発グルーミング・引 っ掻き行動との関係について
前記ア(イ)〜(カ),(ケ),(コ)の記載を総合すると,本件優先日当時までに,ベンゾモ ルファン,エチルケタゾシン,チフルアドム,U−50488,エナドリンといっ たオピオイドκ受容体作動性化合物が,ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行 動を減弱すること,他方で,同じオピオイドκ受容体作動性化合物であっても,S KF10047,ナロルフィン,ICI204448といったものは,ボンベシン 誘発グルーミング・引っ掻き行動を減弱しないこと,さらに,オピオイドμ受容体 作動性化合物であるフェナゾシン,オピオイドκ受容体作動作用を有することにつ いて報告がされていない化合物(乙6〜11)であるメトジラジン,トリメプラジ ン,クロルプロマジン,ジアゼパムのようなものであっても,ボンベシン誘発グル ーミング行動が減弱されることが,Cowanらによって明らかにされていたとい える。
また,前記ア(エ),(カ)の記載及び弁論の全趣旨を総合すると,上記のボンベシン 誘発グルーミング・引っ掻き行動を減弱するオピオイドκ受容体作動性化合物の基 本構造は,それぞれ異なっており,エチルケタゾシンはベンゾモルファン骨格,チ\nフルアドムはベンゾジアゼピン骨格,U−50488及びエナドリンはアリールア セトアミド構造をそれぞれ有しており,甲1発明の化合物Aとはそれぞれ化学構\造 (骨格)を異にするものであった。そして,前記ア(ク)のとおり,化学構造の僅かな\n違いは,薬理学的特性に重大な影響を及ぼし得るものである。 以上からすると,本件優先日当時,オピオイドκ受容体作動性化合物が,ボンベ シン誘発グルーミング・引っ掻き行動を抑制する可能性が,Cowanらによって\n提唱されていたものの,甲1の化合物Aがボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き 行動を減弱するかどうかについては,実験によって明らかにしてみないと分からな い状態であったと認められる上,上記(ア)のとおり,ボンベシンが誘発するグルーミ ング・引っ掻き行動の作用機序が不明であったことも踏まえると,なお研究の余地 が大いに残されている状況であったと認められる。
(ウ) 上記(ア),(イ)を踏まえて判断するに,前記ア(イ)〜(カ),(ケ)のとおり, 本件優先日当時,Cowanらは,1)ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動 が,痒みによって引き起こされているものであるという前提に立った上で,2)オピ オイドκ受容体作動性化合物のうちのいくつかのものが,ボンベシン誘発グルーミ ング・引っ掻き行動を減弱することを明らかにしていた。 しかし,上記1)の点については,上記(ア)のとおり,技術的裏付けの乏しい一つの 仮説にすぎないものであった。 上記2)の点についても,上記(イ)のとおり,本件優先日当時において研究の余地が 大いに残されていた。 そうすると,本件優先日当時,当業者が,Cowanらの研究に基づいて,オピ オイドκ受容体作動性化合物が止痒剤として使用できる可能性があることから,甲\n1発明の化合物Aを止痒剤として用いることを動機付られると認めることはできな いというべきである。
(エ) 小括
以上からすると,当業者が,甲1発明に甲2〜9,12などから認定できる一連 のボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動とオピオイドκ受容体作動性化合物 に関する知見を適用し,本件発明1を想到することが容易であったということはで きないというべきであり,取消事由1は理由がない。
ウ 原告の主張について
原告は,これまで認定判断してきたところに加え,1)本件審決は,技術常識が存 在しないことから直ちに動機付けを否定してしまっており,公知文献から認められ る仮説や推論からの動機付けについて検討しておらず,裁判例に照らしても誤りで ある,2)甲63によると,ダイノルフィンAと同じオピオイドκ作動作用を持つ化 合物は,痒みや痛みを抑制することが容易に予測でき,甲1の化合物Aを使用して\n止痒剤としての効果を奏するかを確認してみようという動機付けも肯定できると主 張する。 しかし,上記1)について,仮説や推論であっても,それらが動機付けを基礎付け るものとなる場合があるといえるが,本件においては,Cowanらの研究に基づ いて,甲1発明の化合物Aを止痒剤として用いることが動機付けられるとは認めら れないことは,前記イで認定判断したとおりであり,原告が指摘する各裁判例もこ の判断を左右するものとはいえず,原告の上記1)の主張は採用することができない。 上記2)について,本件明細書には,前記1(1)イのとおり,甲63にダイノルフィ ンと共に挙げられているエンドルフィン,エンケファリン(前記ア(サ))が,痒みを 惹起することが記載されている上,前記ア(サ)のとおり,甲63が,痒みと痛みの関 係は明確ではなく,研究を更に行わなければならないと結論付けているところから すると,甲63の記載が,ダイノルフィン,エンドルフィン,エンケファリン等の 内因性オピオイドが,止痒剤の用途を有することを示唆するものであるとは認めら れず,甲63の記載から,当業者が,甲1の化合物Aについて,止痒剤としての効 果を奏するかを確認することを動機付けられるとは認められない。 そして,その他,原告が主張するところを考慮しても,前記イの認定判断は左右 されないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2021.05. 7
令和2(行ケ)10030 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年4月28日 知的財産高等裁判所
原告は,本件審決は,「水槽の底部に,円筒状陥没部を形成し,該円筒状陥 没部の底部に内向きフランジ部を形成し,該内向きフランジ部を排水口金具 と接続管とで挟持取付けること」(本件周知技術)は,本件出願前の周知技術 にすぎないから,取付けの強固さや水密性等を考慮して,甲1発明の「縁部 2」の構成を,本件周知技術のように,円筒状陥没部を形成し,該円筒状陥\n没部の底部に形成された内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取 付けることによって,相違点1に係る本件発明の構成とすることは,当業者\nが容易になし得たことである旨判断したが,甲1発明に本件周知技術を適用 する動機付けはないから,本件審決の判断は,誤りである旨主張するので, 以下において判断する。
ア 甲1発明は,「浴槽の底部1は,開口部を有し,その縁部2は,貫通する 方法で湾曲しながら徐々に下側に向かって成形され,この開口部の中には, 排水装置が挿入されており,この排水装置は,おおよそ筒状を呈した排水 ケーシング3を有しており,排水ケーシング3の上端部にはパッキン5を 保持し固定するフランジ4が配置されて,上記縁部2の下端が該パッキン 5に接しており,上側からは,排水カップ6が,排水ケーシング3の中へ ネジ固定により挿入されて,上部外側の縁部分で浴槽の底部に接しており, 排水カップ6の内側には,排水カップ6の上端の径と略同径の閉塞板7が 挿入されており,タペット8を用いることにより上昇させたり,下降させ たりすることができ,閉塞板7は,開口部に接触せず,閉鎖時には,浴槽 の底部1に概ね面一とされ,閉塞板7の裏側には,径内方向に凹んだ断面 コ字状の環状の溝部が設けられ,該溝部にパッキンが保持されている,排 水装置」(前記第2の3(2)ア)である。
甲1の図面(別紙2参照)は,排水ケーシング3の円形断面の中心線に おける断面図であること(前記2(2)イ(イ)),甲1の「ここでは,唯一の図 面が,本発明に基づく排水装置の横断面の形状を示している。ここに示さ れた一つの浴槽の底部1は,一つの開口部を有しており,その縁部2は, 貫通する方法で下側に向かって成形されている。この開口部の中には,排 水装置が挿入されており,この排水装置は,排水ケーシング3を有してい る。・・・排水カップ6の内側には,閉塞板7が挿入されており,一本のタペ ット8を用いることにより上昇させたり,下降させたりすることができる。」 (前記(1)ウ)との記載に照らすと,甲1の図面は,閉塞板7が下降し,開 口部を閉鎖した状態を示した図面であることを理解できる。 そして,甲1の図面から,甲1発明の縁部2は,断面形状が内側に湾曲 しながら徐々に下側に向かって縮径する構成を有し,縁部2の湾曲面に上\n部外側の縁部分が当接する排水カップ6と,縁部2の下端に接するパッキ ン5を保持し,固定するフランジ4を含む排水ケーシング3とで挟持取り 付けられていることを理解できる。
他方で,甲1には,縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持 取付けられていることやその作用等について明示的に述べた記載はない。 また,甲1の記載事項全体(図面を含む。)をみても,縁部2が排水カップ 6と排水ケーシング3とで挟持取付けられている構成について,取付けの\n強固さや水密性等の観点から,改良すべき課題があることを示唆する記載 もない。
イ 次に,「水槽の底部に,円筒状陥没部を形成し,該円筒状陥没部の底部に 内向きフランジ部を形成し,該内向きフランジ部を排水口金具と接続管と で挟持取付けること」(本件周知技術)が,本件出願当時,周知であったこ とは,前記(1)イのとおりである。 他方で,本件周知技術に係る甲3,5及び8には,円筒状陥没部の底部 に形成した内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付ける構\n成の作用等について述べた記載はない。 また,甲3,5及び8には,取付けの強固さや水密性等の観点から,内 向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付ける構成が,甲1の図\n面記載の縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持取付けられ る構成よりも優れていることを示唆する記載はない。\n
ウ 前記ア及びイによれば,甲1に接した当業者は,甲1発明の縁部2の構\n成について,取付けの強固さや水密性の点において課題があることを認識 するとはいえないから,甲1発明の縁部2に本件周知技術の構成を適用す\nる動機付けがあるものと認めることはできない。 したがって,当業者は,甲1及び本件周知技術に基づいて,甲1発明に おいて,相違点1に係る本件発明の構成とすることを容易に想到すること\nができたものと認めることはできない。 これと異なる本件審決の判断は誤りである。
(3) 被告の主張について
ア 被告は,1)本件発明の「内向きフランジ部」は,円筒状陥没部の底部か ら縮径するように延出させることで排水口金具と接続管とで挟持取付ける ものである必要があり,かつ,それで足りるところ,甲1発明の縁部2は, 断面形状が内側に凸となる円弧状を呈し,下方向だけでなく内側方向にも 延出することで,開口部を下側に向かって縮径しており,このように開口 部を縮径することによって「排水カップ6」と「排水ケーシング3」とで 挟持取付けられるものである点において,本件発明の「内向きフランジ部」 と甲1発明の縁部2は,構造的に共通する,2)本件明細書の【0013】 の記載に照らすと,本件発明の「内向きフランジ部」は,「円筒状陥没部」 の底部に位置することで排水口金具が「水槽の底部1」に露出しない状態 で排水口金具と接続管とで挟持取付けられるものであるところ,甲1発明 の縁部2も,「開口部」の底部に位置することで排水口金具が「浴槽の底部 1」に露出しない状態で排水口金具と接続管とで挟持取付けられる点にお いて,本件発明の「内向きフランジ部」と機能及び作用が共通するとして,\n甲1発明の縁部2は,フランジ形状を呈していないとしても,構造,機能\ 及び作用が共通しているから,本件発明の「内向きフランジ部」と実質的 に同一であり,相違点1は実質的な相違点ではない旨主張する。 しかしながら,被告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)には,本件発明の「内向き フランジ部」に関し,「水槽の底部に,円筒状陥没部を形成し,該円筒状 陥没部の底部に形成された内向きフランジ部が排水口金具と接続管と で挟持取付けられて排水口部を形成」されること,「その円筒状陥没部内 を上下動するカバーが,前記排水口金具のフランジ部とほぼ同径である」 ことの記載はあるが,本件発明の「内向きフランジ部」の形状や構造を\n規定する記載はない。また,本件明細書においても,本件発明の「内向 きフランジ部」の用語を定義する記載はない。 一般に,「フランジ」とは,「管を他の管または機械部分と結合する際 に用いる鍔型の部品。」(広辞苑第七版)を意味することからすると,本 件発明の「内向きフランジ部」とは,円筒状陥没部において内側に向け て形成された鍔状の部分を意味するものと解される。そして,上記結合 の際には鍔状の形状であることに即した作用を奏するものといえる。 しかるところ,甲1発明の縁部2は,湾曲しながら徐々に下側に向か って形成され,下端部に至るまでなだらかな弧状であり,内側に向けて 形成された鍔状の部分は存在しないから,本件発明の「内向きフランジ 部」に相当するものと認めることはできない。 このように甲1発明の縁部2は,鍔状の部分を備えていない点におい て,本件発明の「内向きフランジ部」と構造が明らかに異なり,その作\n用にも差異があるといえるから,本件発明の「円筒状陥没部の底部に形 成された内向きフランジ部が排水口金具と接続管とで挟持取付けられて」 いる構成と,甲1発明の縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで\n挟持取付けられている構成とが実質的に同一であるものと認めることは\nできない。
(イ) したがって,相違点1は実質的な相違点でないとの被告の主張は, 理由がない。
イ また,被告は,水槽の底部に,円筒状陥没部を形成し,該円筒状陥没部 の底部に内向きフランジ部を形成し,該内向きフランジ部を排水口金具と 接続管とで挟持取付けること(本件周知技術)は,本件出願当時,周知で あったことからすると,甲1に接した当業者は,取付けの強固さや水密性 等を考慮し,甲1発明の「縁部2」に本件周知技術を適用することによっ て,相違点1に係る本件発明の構成とすることを容易に想到することがで\nきた旨主張する。 しかしながら,被告の上記主張は,前記⑵で説示したとおり,採用する ことができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.05. 4
令和2(ネ)10060 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和3年4月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 十字部分の色彩等に基づく類否の主張について\n
控訴人は,標章において色彩が類否に大きく影響すること,十字部分を有\nする標章は特に十字部分の色彩が類否に大きく影響することを前提として,\n被控訴人商標と控訴人標章1,3は外観,称呼,観念が異なり,類似しない と主張するが,控訴人の主張を採用することはできない。以下,詳述する。
ア 標章において色彩が類否に大きく影響するという控訴人の主張について 控訴人は,例えば,国旗において色彩が重要な要素であるように,標章 は,同一の文字や図形の結合等であっても,色彩の相違によって印象が異 なるものであり,現に,商標法70条1項は,色彩を登録商標と同一にす れば登録商標と同一の商標となる場合であっても,色彩が異なれば登録商 標に類似しない商標があることを前提としており,このことは,色彩以外 が同一であり色彩だけが異なっている商標が非類似になることを示して いるとし,そのため,商標の類否判断に色彩が大きく影響すると主張する。 しかし,国旗において色彩が重要な要素であるとしても,国旗の例が直 ちに商標に当てはまるものではない。また,標章において,文字や図形は 色彩に劣らず重要な要素であり,商標法70条1項が,色彩を登録商標と 同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの を,登録商標に類似の商標にとどまるとするのではなく,登録商標に含ま れるとしていることからすれば,文字や図形が同一であって色彩のみが異 なる商標は,登録商標と同一の商標と認められる場合が多いといえる。そ のため,控訴人の上記条項の理解は不適切であり,同条項に基づき,標章 において色彩のみが類否に大きく影響するということはできない。なお, 色彩が識別性等の観点から大きな意味を有しており,色彩のみが異なるこ とにより全く違う商標となってしまうような例外的な場合について商標 法70条1項が適用されないとする余地があるとしても,上記の認定は左 右されない。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 十字部分を有する標章は特に十\字部分の色彩が類否に大きく影響すると いう控訴人の主張について 控訴人は,商標法4条1項4号は,赤十字の標章と同一又は類似の商標\nについて商標登録を受けることができないと定めており,赤十字の標章及\nび名称等の使用の制限に関する法律1条は,白地に赤十字の標章若しくは\n赤十字の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称をみだりに用いる\nことを禁じていること,緑と白で構成された十\字の標章は,安全標識とし て定められていることから,十字部分を有する標章においては特に十\字部 分の色彩が類否に大きく影響すると主張する。 しかし,赤十字の標章や安全標識について上記の事実があるとしても,\n赤十字の標章と同一又は類似の商標でなければ,十\字部分を含む商標の登 録は認められる余地があり,十字部分を含む商標において十\字部分の色彩 が識別性等の観点からどのような意味を有するかは,その商標の具体的な 構成等に照らして判断されるべき事柄であって,一概に,十\字部分を有す る標章において特に十字部分の色彩が類否に大きく影響するということ\nはできず,控訴人の上記主張は,採用することができない。
ウ 被控訴人商標と控訴人標章1,3の類否について 控訴人は,被控訴人商標と控訴人標章1,3は,外観,称呼,観念が異 なり,類似しないと主張する。 しかし,原判決の説示するとおり(原判決9頁6行目ないし10頁10 行目),被控訴人商標と控訴人標章1は,外観が類似しており,いずれも 「ジュウジ」「クロス」などの同一の称呼及び「十字」「クロス」などの\n同一の観念が生じ,取引の実情を踏まえると,被控訴人商標と控訴人標章 1は,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあり,両者は類似する と認められる。また,原判決の説示するとおり(原判決11頁5行目ない し12頁14行目),被控訴人商標と控訴人標章3は,外観が類似してお り,同一の称呼及び観念が生じ,取引の実情を踏まえると,被控訴人商標 と控訴人標章3は,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあり,両 者は類似すると認められる。したがって,控訴人の上記主張は採用するこ とができない。
(2) 十字以外の部分等に基づく類否の主張について\n
控訴人は,商標法4条1項1号が,国旗と同一又は類似の商標は商標登録 を受けることができないと定めていることからすると,被控訴人商標が登録 されているのは,スイス国旗と類似していないからであり,そうであるとす ると,被控訴人商標のうち,スイス国旗と似ている十字部分は要部ではなく,\n円弧からなるループ状図形が要部であるとした上で,被控訴人商標の円弧か らなるループ状図形の外周と控訴人各標章の正方形部分の外周は,形状,色 彩,観念が異なるとし,被控訴人商標の指定商品と同一又は類似の商品に使 用された控訴人各標章が外観,観念等によって取引者,需要者に与える印象, 記憶,連想等は,被控訴人商標とは全く異なるものであるから,被控訴人商 標と控訴人各標章は類似しないと主張する。 しかしながら,被控訴人商標が登録されているのは,スイス国旗と類似し ていないからであるとしても,そのことから直ちに,被控訴人商標のうち, 十字部分以外の円弧からなるループ状図形が要部であるとして,その部分の\n比較に基づいて商標の類否を判断すべきであるとはいえない。商標の類否は, 外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を 総合して,その商品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきもの であるところ,被控訴人商標と控訴人各標章は,いずれも十字部分と外周部\n分からなり,十字部分は被控訴人商標及び控訴人各標章の中心にあって目立\nつ位置にあるから,類否判断に当たっては,十字部分も含めて被控訴人商標\nと控訴人各標章のそれぞれの全体を比較考察すべきである。そのため,十字\n部分以外の周囲の部分の比較により被控訴人商標と控訴人各標章は非類似で あるとする控訴人の上記主張を採用することはできない。
◆判決本文
1審は東京地裁ですがなぜかアップされていません。
こちらは同商標権に対する不使用審決取消訴訟です。審決は不使用と認定しましたが、知財高裁はこれを取り消しています。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2021.04.30
令和2(行ケ)10125 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年4月27日 知的財産高等裁判所
本願商標は,「六本木通り特許事務所」の文字を標準文字で表してなり,指定役務を第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」と\nするものである。 本願商標の構成中の「六本木通り」の文字は,昭和59年(1984年)に,起点を東京都千代田区霞が関2丁目,終点を渋谷区渋谷2丁目とする道\n路に東京都が設定した通称名を意味する語である(乙1)。また,本願商標 の構成中の「特許事務所」の文字は,弁理士等が業務を行う事務所を意味する語であり(弁理士法76条1項参照),弁理士は,特許,実用新案,意匠,\n商標等に関する特許庁における手続等の代理又はこれらの手続に係る事項に 関する鑑定その他の事務を行うこと等をする者であり(弁理士法4条参照), 事務を行う者が所在する事務所があたかも事務を行う主体と呼ばれることは 慣用の表現であるから,「特許事務所」は,特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称と認識されるものである。\nそうすると,本願商標は,道路の通称名である「六本木通り」の文字と, 特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称である「特許事務所」の文 字とを結合したものと認識,理解されるものである。
(2) 本願商標の指定役務である「スタートアップに対する特許に関する手続の 代理」は,「特許に関する手続の代理」の範囲を「スタートアップ」に係る ものに限定したものであり,語義からして「特許に関する手続の代理」に含 まれることは明らかであるから,本願商標の構成中の「特許事務所」の文字は,本願商標の指定役務を提供する者の一般的名称を意味すると理解される。\nまた,本願商標の構成中の「六本木通り」は,本件審決時である令和2年(2020年)9月時点で35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれてい\nる道路の通称名であるから,本願商標の指定役務の提供の場所を意味すると 理解される。
そうすると,本願商標に係る「六本木通り特許事務所」との文字は,本願 商標の指定役務との関係で,役務の提供場所と理解される「六本木通り」と の文字と,役務を提供する者の一般的な名称と理解される「特許事務所」の 文字とを結合させたものであるから,本願商標の指定役務の需要者は,これ を「通称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手 続の代理等を行う者」を意味するものと認識するというべきである。 以上からすると,「六本木通り特許事務所」との文字は,六本木通りに近 接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明し ているにすぎず,本願商標の指定役務の需要者において,他人の同種役務と 識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであって,その 構成自体からして,本願商標の指定役務に使用されるときには,自他役務の出所識別機能\を有しないものと認められる。 したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当するものというべき であり,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本願商標の指定役務の分野において「〇〇通り□□事務所」の 文字が広く採択,使用されているとの本件審決の認定は誤りである,ある いは本願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」 という名称の法律事務所が多数あるとしても,「〇〇通り法律事務所」と の名称に自他役務の出所識別機能がないと根拠付けることはできない旨主張する。\n
確かに,これらの主張については,当裁判所としても首肯し得る面もあ る。しかしながら,そもそも本願商標の指定役務の分野において「〇〇通 り□□事務所」の文字が広く採択,使用されているとの事実の有無や,本 願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」という 名称の法律事務所が多数あるとの事実の有無等が,本願商標の自他役務の 出所識別機能の有無の判断に当たって必要な前提事実となるものではないから,これらの点に関する本件審決の認定に誤りがあるとしても,その\n認定の誤りが結論を左右するものではなく,本願商標に自他役務の出所識 別機能を認めることができないことについては,前記⑵において認定判断 したとおりである。したがって,原告の上記主張は,結論を左右しない点に関する誤りを主張するにすぎず,採用し得ない。
イ 原告は,「〇〇通り□□事務所」の語は,単に各構成要素の辞書的な意味を足し合わせた意味だけを有するものではないから,本願商標も,その\n全体において造語として需要者に印象付けられる旨主張する。 一般的に,複数の語を組み合わせてなる語がそれを構成する各語の意味を結合したものを超える意味を有し得るとはいえるものの,原告は,「通\n称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手続 の代理等を行う者」と認識される本願商標が,その組合せ自体によりこれ とは異なる新たな意味を生じさせること,あるいは,使用された結果,何 人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っている ことを何ら具体的に主張立証していないから,原告の上記主張は,その前 提を欠くものというべきであって,採用することができない。
ウ 原告は,本願商標は,新規で意外性のある造語である旨主張する。 しかしながら,商標の構成についていえば,「○○通り」と「法律事務所」とを組み合わせた構\成をとる商標は多数の例が認められ(乙7ないし 51),法律事務所は特許事務所と同様に本願商標の指定役務を提供し得 る事務所であるから(弁護士法74条1項,3条2項参照),「法律事務 所」を「特許事務所」と言い換えて「○○通り」と「特許事務所」との組 合せとしたとしても,格別,新規なものとは認識し得ないといえ,その構成に意外性もない。また,前記のとおり,本願商標の構\成中の「六本木 通り」の文字は,35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれている 道路の通称名であり,本願商標の構成中の「特許事務所」は,本願商標の指定役務を提供する者を意味する一般的な名称であるから,この両語の組\n合せから新規な意外性を生じるということもできない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2021.04.29
平成30(ワ)5041 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月21日 大阪地方裁判所
被告の主たる事務所は日本国内にあることから,本件各請求に係る訴えのい ずれについても,日本の裁判所が管轄権を有する(民訴法3条の2第3項)。 もっとも,その場合でも,事案の性質,応訴による被告の負担の程度,証拠の所 在地その他の事情を考慮して,日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間 の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があ ると認めるときは,裁判所は,その訴えの全部又は一部を却下することができる (同法3条の9)。そこで,本件各請求に係る訴えにおいて,それぞれ,上記「特 別の事情」があると認められるかについて,以下検討する。
(ア) 前記イ(ア)のとおり,請求1−1は,別件米国訴訟と同一の訴訟物に関するも のである。 また,本件において,本件各装置が本件米国特許に係る発明の実施品であること, 本件各装置が参加人から SKC 等に販売されたこと及び原告が本件各装置を使用し て本件各製品を製造したことについては,当事者間に争いはない。本件での主要な 争点は,本件許諾契約により参加人が許諾された本件実施権の範囲,すなわち,参 加人の販売先に関する制限の存否といった本件許諾契約の解釈である。他方,別件 米国訴訟においても,その経過(前記イ(イ))から,消尽及び黙示のライセンスの抗 弁は主要な争点として位置付けられ,本件許諾契約の解釈につき,日本法の専門家 の各意見書及び関係者の供述書並びにそれを踏まえた主張の提出,陪審公判での証 人尋問といった形で,原告等と被告とが主張立証を重ね,陪審及び加州裁判所の判 断の対象となっている。その意味で,本件と別件米国訴訟とは,争点を共通にする ものといえる。 しかも,別件米国訴訟の提起は平成22年7月であり,本件の訴え提起までの約 8年間,こうした主張立証が行われ,その結果として,別件評決及び加州裁判所の 別件米国判決に至ったものである。なお,この間,原告が日本において請求1−1 に係る訴えのような訴訟を提起することを妨げる具体的事情があったことはうかが われない。
これらの事情を総合的に考慮すると,別件米国訴訟につき加州裁判所の別件米国 判決がされるまでは,原告は,日本において請求1−1に係る訴えのような訴訟を 提起する考えはなく,別件米国判決を受けたことを契機に,その結論を覆すべく請 求1−1に係る訴えを提起したものと理解される(別件米国判決の基礎となった証 拠方法の重大な瑕疵等を度々指摘する原告の主張からも,原告のこのような意図が うかがわれる。)。他方,請求1−1に係る本件の訴えに応訴すべきものとした場 合,被告は,時期を異にして別件米国訴訟と共通する主張立証活動を重ねて強いら れることとなるのみならず,別件米国判決の結論を本件において覆そうとする以上, 原告は別件米国訴訟では行わなかった主張立証を追加的に行う蓋然性が高いと見ら れるところ,これに対する対応を強いられることで,被告にとっては,更なる応訴 の負担を新たに生じる蓋然性も高いといえる。 そうすると,本件許諾契約はいずれも日本法人である被告と参加人との間で締結 されたものであり,関連する証拠も,多くは日本語で作成されていること又は日本 語を解する者である蓋然性が高く,その所在も多くは日本国内にあると見られるこ とを考慮しても,請求1−1に係る訴えについては,日本の裁判所が審理及び裁判 をすることが当事者間の衡平を害する特別の事情(民訴法3条の9)があると認め られる。
(イ) これに対し,原告は,日本の裁判所で審理をすることが必要かつ適切である こと,別件米国訴訟の重複・蒸し返しに当たらないこと,別件米国判決は日本にお いて承認されないことなどを指摘して,特別の事情があるとはいえない旨主張する。 しかし,請求1−1に係る訴えに関する限り,日本の裁判所で審理をすることが 必要かつ適切であるとは必ずしもいえないこと,別件米国訴訟の蒸し返しに当たる と見られることは,上記のとおりである。別件関連訴訟が係属しているといっても, 請求1−1に係る訴えとは当事者及び訴訟物を異にする別の事件である以上,その 主張立証の負担をもって本件における主張立証の負担を無視ないし軽視し得ること にはならない。
また,別件米国判決が日本において承認されないとする根拠として,原告は,別 件米国判決が重大な瑕疵のある証拠に依拠するものであることを指摘する。しかし, そのような誤りは本来的には米国の訴訟手続を通じて是正されるべきものであると ころ,かえって,別件米国判決は,CAFC においても承認され,確定している。こ のことと,再審事由(民訴法338条)に該当するような具体的な事情もないこと に鑑みると,日本法に照らしても,原告の上記指摘は別件評決及び別件米国判決の 依拠する証拠評価に対する不満をいうにすぎず,これをもって外国の確定判決の効 力が認められる要件である「判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は 善良の風俗に反しないこと」(民訴法118条3号)を欠くとはいえない。 さらに,原告は,別件米国判決が承認された場合に,別件関連訴訟につき参加人 の被告に対する損害賠償請求等の判決が確定すると両者に矛盾が生じることなどを 指摘して,その点からも別件米国判決は承認されるべきものではないとする。しか し,別件関連訴訟が原告の主張するとおりに帰結するか否かは,請求1−1に係る 訴えの提起の時点では不明というほかない。この点を措くとしても,別件関連訴訟 は,本件とも別件米国訴訟とも当事者及び訴訟物を異にするものであるから,その 判決の効力は原告と被告との関係に及ぶものではない。 その他原告が縷々指摘する点を考慮しても,この点に関する原告の主張は採用で きない。
(ウ) 以上のとおり,請求1−1に係る訴えについては,日本の裁判所が審理及び 裁判をすることが当事者間の衡平を害する特別の事情があると認められるから,こ れに係る訴えを却下することとする。
関連カテゴリー
>> 裁判手続
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2021.04.27
令和2(行ケ)10118 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年3月11日 知的財産高等裁判所
前記2〜4のとおり,本件商標及び引用商標の類否判断においては,それぞれ, 「SMS」の文字部分を抽出し,これらを対比することになり,称呼は同一となる。 また,本件商標の「SMS」と引用商標の各「SMS」からは,特定の観念を生 じない。そして,各「SMS」の文字の外観については,本件商標と引用商標とでは,書体が異なるが,特段書体に特徴があるとはいえないから,この差異によって,両文 字の外観に異なる印象が生じるとはいえない。また,本件商標の色彩は黒色である のに対し,引用商標3の色彩は青色を基調にして白色が混入している点で差異があ るが,このような差異は些細な差異であるから,この差異によって,両文字の外観 に異なる印象が生じるとはいえない。したがって,本件商標の「SMS」と引用商 標の各「SMS」とでは,外観も類似しているといえる。
・・・・
原告は,本件商標全体と引用商標全体を対比して,それらの類否判断をす べきであると主張するが,前記2〜4のとおり,本件商標及び引用商標は,いずれ も,外観上,「SMS」の文字部分と他の部分は明確に区別され,これらを分離して 観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合していると認めら れないから,本件商標及び引用商標から「SMS」の文字部分を抽出して,類否判 断をすることは相当であり,原告の上記主張は理由がない。
(2) 原告は,「SMS」とは,携帯電話でのメッセージ送受信サービスである 「Short Message Service(ショートメッセージサービス)」の 略語であり,本件審決がされた令和2年の時点で,「ショートメッセージサービス」 の略語としての「SMS」は,通信分野に限らず,一般に周知されていると主張し, その証拠として,甲25,26を提出する。 甲25によると,「SMS」が「ショートメッセージサービス」の略語であること を説明したウェブサイトが存在することが認められるが,前記2(2)のとおり,「S MS」の語が一般的な辞書に掲載されている例があるとは認められないことからす ると,上記ウェブサイトの存在から,「SMS」が「ショートメッセージサービス」 の略語を意味することが一般的に認識されていたということはできないというべき である。 また,甲26のアンケートは,「SMSという言葉を聞いたことがありますか?」, 「SMSとは何か知っていますか?」,「いつごろからSMSについて知っています か?」の三つの質問について,それぞれ「ある,ない」,「知っている,知らない」, 「 年ごろから」との回答を求めるというアンケートであることが認められるとこ ろ,上記の質問内容からすると,同アンケートにおいて,SMSを知っているとの 回答があったとしても,その回答者が,「SMS」がどのような意味を有するものと 認識していたかは明らかではないから,同アンケートから,「SMS」が「ショート メッセージサービス」の略語を意味することが一般的に認識されていたと認めるこ とはできない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3) 原告は,商標の登録例を考慮すると,本件図形部分は,十分な出所識別力\nを有し,また,本件商標も十分な出所識別力を有すると主張する。\nしかし,本件図形部分や本件商標が十分な出所識別力を有することから直ちに,\n他の商標との類否判断において,本件文字部分を抽出することができないことには ならないから,原告の上記主張は理由がない。
(4) 原告は,「SMS」の文字を含む商標が商標登録された事例を挙げて,「S MS」の文字を含む商標の他の商標との類否判断においては,「SMS」の文字 と他の文字又は図形は一体不可分に判断されるべきであるなどと主張する。 しかし,前記1のとおり,商標の類否判断は,外観,観念,称呼等によって取引 者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合し,かつ,具体的な取引状況に基づ いて行うものであり,事案ごとの具体的な事実に基づく判断となるものであって, 「SMS」の文字を含む他の商標についての特許庁における類否判断の結果によっ て,本件訴訟における本件商標と引用商標の類否判断が左右されることはない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.04.23
平成31(ワ)2597等 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和3年1月26日 東京地方裁判所
原告は,本件文書1を一部改変したおみくじを寺院に対して販売しており (甲10,乙7の1,2,弁論の全趣旨),その販売価格は1枚当たり120 円である(甲11の1,2)。そのおみくじについて,印刷,用紙及び折り畳 みを印刷業者に依頼した場合に要する費用が1枚当たり約41円以下であ って(甲12),その他の販売に要する経費を考慮してもその販売により追 加的に必要となった経費は1枚当たり50円を上回ることはないと認めら れるから,原告における本件文書1を一部改変したおみくじの1枚当たりの 利益額は70円を下回ることはないと認められる。
・・・
以上によれば,著作権法114条1項に基づく原告の損害額は,以下の計 算式のとおり,572万8590円となる。
(計算式)
70円(単位数量当たりの原告利益)×(81117枚+720枚+0枚)(被告の譲渡数量)=572万8590円
原告は,著作権侵害について,予備的に著作権法114条2項に基づく額\nを主張するが,原告の主張するおみくじ1枚当たりの被告の利益額が同条1 項に基づく主張における原告の利益額よりも小さいことなどから,予備的な\n主張が著作権法114条1項に基づく損害額よりも大きくなるとは認めら れない。
カ 著作者人格権侵害による損害額
本件文書1において,その内容が真逆になるような内容の改変がされるこ とは,おみくじについての表現の本質的部分についての改変であるといえる\nことに加え,その他,本件にあらわれた の著作者人格権侵害について原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は5 0万円をもって相当であると認める。
2021.04.23
平成30(ワ)5948 損害賠償請求事件 著作権 令和3年1月21日 大阪地方裁判所
プログラムに著作物性があるというためには,指令の表現自体,そ\nの指令の表現の組合せ,その表\現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があ り,かつ,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性,すなわち,表\現上の創 作性が表れていることを要するといわなければならない(知財高裁平成21年\n(ネ)第10024号同24年1月25日判決・判例時報2163号88頁)。
イ そこで検討するに,前記1(5)で認定したところによれば,原告プログラム は,市販のプログラム開発支援ソフトウェアである Microsoft Visual Studio を使用 して Microsoft Visual Basic 言語で記述されているから,ソースコードを個別の行\nについてみれば,標準的な構文やありふれた指令の表\現が多用されており,独創的 な関数等は用いられていない。 しかしながら,前記(5)イについては,一定の画面表示を得るために複数の記述\n方法が考えられるところ,一定の意図のもとに特定の指令を組み合わせ,独自のメ ソッドを作成して独自の構\成で記述しており,同ウ及びエについては,一定の処理 方式を選択すること自体はアイデアにすぎないが,やはり,一定の結果を得るため にどのように指令を組み合せ,どの範囲で構造体を設定し,配列・構\造化するかに は様々な選択肢が考えられるところ,その具体的な記述は,一定の意図のもとに特 定の指令を組み合わせ,多数の構造体を設定し,配列・構\造化した独自のものにな っている。
また,同オについては,HTML データから一定の情報を抽出する指令の記述は 選択の幅があるところ,メンテナンス性を考慮して独自の記述をしていることが認 められ,同カについても,人間が情報を入力してログインや舟券購入の操作をする ことを想定して作成されている投票サイトのサーバーに,人間の操作を介さずに必 要なデータを送信してログインや舟券の購入を完了するための指令の表現方法は複\n数考えられるところ,複数の方式を適宜使い分けて記述し,一連の舟券購入動作を 構成していることが認められる。\nそうすると,前記イないしカのソースコードには表\現上の創作性があるといえ, これらを組み合わせて構成されている原告プログラムにも,表\現上の創作性が認め られるというべきである。
ウ 被告ら(被告エーワンを除く。以下同じ。)は,原告プログラムの機能は,\n原告プログラムを利用せずに競艇公式ウェブサイト等により実行できると主張する が,競艇公式ウェブサイト等で人間の動作として情報を得たり舟券の購入をしたり することと,原告プログラムにより情報を得たり自動的に舟券を購入したりするこ とは異なるから,原告プログラムに創作性がないとする理由にはならない。 また,被告らは,原告プログラムが利用しているデータが競艇公式ウェブサイト で公知であると主張するが,プログラムに入力される変数であるレース情報等のデ ータが公知であるか否かはプログラムの著作物性とは関係がなく,失当である。 さらに,被告らは,原告プログラムのうち自動運転機能の部分は,既存のソ\ース コードを単純作業により組み合わせたものであり,「Boat Advisor」等の類似のソ\nフトウェアが多数存在すると主張する。しかしながら,前記のとおり,原告プログ ラムは,独自の指令の組合せ,構造体等の設定,構\成によって記述されており,あ りふれたものとはいえず,証拠(乙2)をみても,「Boat Advisor」はレース予\n想,データ分析を主たる機能とするソ\フトウェアであり,原告プログラムのように 舟券を自動購入するものであるとは認められず,原告プログラムがありふれたソー\nスコードによって構成されているものとはいえない。\n原告プログラムに著作物性がないとの被告らの主張は,採用できない。
(2) 争点2(被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案したものか) について
ア 前記1(3)で認定したところによれば,被告プログラムは,被告P4がP7 より入手した原告プログラムについて,被告P3において逆コンパイルを行うと共 に難読化を解除し,期待値と称する機能を追加した以外は,逆コンパイルによって\n得られた原告プログラムの機能をそのまま利用したものであるから,少なくともそ\nのまま利用した部分において,被告プログラムは,原告プログラムを複製したもの ということができる。
イ また,前記1(6)で認定したところによれば,被告プログラムは,少なくと も,原告プログラムの BoatRaceCom.DLL 及び Kcommon.DLL を複製して作成され たことが明らかである。 さらに,被告プログラムは,原告プログラムと画面表示やモジュール名がほぼ同\nじであること,マニュアルに記載された機能が原告プログラムとほぼ同一であるこ\nとも,上記アの結論と合致する。
ウ 被告らは,被告プログラムは,被告プログラム独自のアルゴリズムで算出さ れた期待値(人気指数)に基づく予想をユーザーに提供するものであって,その部\n分に創作性があり,原告プログラムとは全く異なるものであると主張する。 被告らが主張する期待値の機能については,本件の証拠によっても判然とはしな\nいが,仮に,より勝率が高くなることが期待される買目を計算して推奨し,舟券を 自動購入する機能を追加した点で,被告プログラムは原告プログラムと異なる旨を\nいう趣旨であるとしても,原告プログラムが元々有する買目設定の機能を強化,発\n展させたものと理解し得るものであると共に,既に認定したとおり,被告プログラ ムは,期待値の機能を追加した以外の部分については,原告プログラムを複製した\nものをそのまま利用しているとされるのであり,全体として,被告プログラムは, 原告プログラムの本質的特徴を直接感得し得るものであるから,少なくとも翻案に あたることは明らかというべきであり,被告プログラムの作成は,原告プログラム についての原告らの著作権を侵害するものである。 なお,被告らは,被告プログラムに「買目切捨」や「保険買目」など,原告プロ グラムにはない機能があると主張するが,被告P3において,期待値の機能\以外は 原告プログラムと異なる機能はないと供述していること,前記のとおり,マニュア\nルや画面が同じであること,原告プログラムにも同一の機能があることから,当該\n主張は上記結論を左右するものではない。
・・・
前記1の(2)ないし(4)によれば,P7は1本20万円を原告らに支払って取 得した原告ソフトウェアを1本50万円から80万円で約30本販売したこと,被\n告P5は,被告エーワンの名義で,被告ソフトウェア約70本を1本60万円から\n100万円で販売し,その中に,平成28年5月2日のP8に対する100万円の 売買が含まれること,以上の事実が認められる。なお,被告ガルヒが被告ソフトウ\nェアを販売するためのセキュリティ認証キーを140個用意したことは前記1の (4)で認定したとおりであるが,これに対応する140本の被告ソフトウェアが販\n売されたと認めるに足りる証拠はない。
イ 以上によれば,被告らは,被告ソフトウェアを少なくとも70本販売し,う\nち少なくとも1本は平成28年5月2日に100万円で販売し,その余は少なくと も1本60万円で販売したと認めるのが相当であり,ここから控除すべき経費等の 主張はないから,被告ソフトウェアの販売により被告らが受けた利益は,少なくと\nも4240万円であると認められる。 そうすると,著作権法114条2項により,原告らの受けた損害額は4240万 円,著作権を共有する原告各人について2120万円ずつと推定される。 また,損害のうち100万円(各50万円)は,平成28年5月2日に被告ソフ\nトウェアが販売されたことによるものであり,被告エーワンを含む被告らは,同日 から遅滞の責を負う。その余については販売時期が不明であり,前記のとおり,被 告ソフトウェアが3から4か月間販売されていたことからすれば,遅くとも同年9\n月2日までには,その余の損害すべてに係る侵害行為が行われたと認められるか ら,原告らのその余の損害について,被告らは,同日から遅滞の責を負うものと認 められる。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> 複製
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2021.04.23
平成30(ワ)37847 共同著作権に基づく利得分配請求等事件 令和3年1月21日 東京地方裁判所
2人以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離 して個別的に利用することができないものを共同著作物というところ(著作 権法2条1項12号),共同著作者に当たるというためには,当該著作物の制 作に際し,創作と評価されるに足りる程度の精神的活動をしている必要があ るというべきである。 そこで,原告において本件各作品の制作に際し,かかる創作的関与が認め られるか否かにつき見るに,上記1(1)イ及びウで認定したとおり,原告は, 本件各作品の制作を企図した被告Aから,制作への協力を依頼され,台詞を 読み上げる声優の候補者を数人紹介し,被告Aが制作したシナリオや指示に 沿う形で,効果音の収録や編集の作業を担当したにとどまっているものであ り,これらの原告の関与の性質・内容に照らせば,ボイスドラマであるとい う本件各作品の性質に照らしてもなお,原告が,本件各作品の制作に際し, 創作行為を行ったものとみることは困難というほかない。そうすると,本件 各作品の制作に際するこれらの関与について,原告が,創作と評価されるに 足りる程度の精神的活動をしたものとまで認めるに足りないというべきであ り,原告が本件各作品の共同著作者に当たるものとは認められない。
(2) これに対し,原告は,本件各作品の制作に際し,1)声優を選択した点,2) セリフや表現方法につきアドバイスをした点,3)効果音を選択・収録した点, 4)全体の長さを一定時間内におさめるよう編集した点において,創作的に関 与した旨を主張する。 しかしながら,1)の点については,上記のとおり声優の候補者を紹介した にとどまるものであり,2)の点については,その具体的内容は判然としない が,いずれにしてもアドバイスをしたにとどまるものであり,3)及び4)の点 については,具体的な作業を担当したとしても,上記のとおり,被告Aが制 作したシナリオや指示に沿う形で作業を行い,被告Aのチェックを受けてい たものである。これらからすれば,たとえ原告において上記1)ないし4)の点 において尽力した旨の認識であったとしても,そのいずれも,原告の創作的 な精神活動がなされたことを具体的に基礎付けるものとまでは言い難い。そ うすると,原告の上記主張は,原告の創作的関与を否定した上記認定を左右 するものではなく,同主張は採用することができない。
2021.04.23
令和2(行ケ)10110 決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月18日 知的財産高等裁判所
これに対して,原告は,前記第3の1(1)のとおり,甲1に引用された実 施例と本件発明3の実施例は,全く同一であり,自然締付け力を付与され ていない状態とする効果を生じさせるための新たな構成要素が付加されて\nいるわけでもないし,仮に,本件優先日当時,自然締付け力を皆無にする 施術が広く実施されていなかったとしても,加圧力の範囲は,身体に対す る負担や得られる効果を勘案しつつ適宜決定し得る程度の事項である旨主 張する。 原告の主張は,本件明細書と甲1の明細書を対比すれば,本件明細書の 図1ないし図7が甲1の明細書の図1ないし図7と同一であること,すな わち,本件発明3と甲1−3発明でそれぞれ用いられる緊締具,加除圧制 御装置及び加除圧制御システムが同一であることを指摘するものと解さ れるが,そうであるとしても,甲1−3発明には,加圧工程と除圧工程を 交互に繰り返す圧力調整手段を制御する制御手段の「下ピーク」のときに 緊締具が所定の部位に与える締付け力について,特定部分を締付ける加圧 力を付与しない状態,すなわち,自然締付け力による加圧力も付与しない 状態に制御することについての記載も示唆もないことは前記(1)のとおり である。
また,甲1−3発明は,四肢の所定の部位の締付け力の上げ下げを行い ながら,その所定の部位よりも下流側に流れる血流を阻害し,それによっ て筋肉に疲労を生じさせ,筋肉の効率的な増強を図ることを目的とするも のである(【0003】,【0004】,【0009】,【0010】)から,甲 1に接した当業者が,加圧工程と除圧工程を交互に繰り返す圧力調整手段 を制御する制御手段の「下ピーク」のときに,緊締具が所定の部位に与え る締付け力について,自然締付け力による加圧力も付与しない状態にして 血流を阻害しないようにする構成とする動機付けがあるとはいえない。\nなお,原告は,甲2発明は,筋肉トレーニングの方法を応用することに よって動脈硬化,つまり,血管のメタボリック症候群状態を改善すること を目的としており,血管を強化する方法の1つを示している旨主張してい るところ,上記主張の趣旨は明らかではないが,要するに,甲2発明にお いて筋肉トレーニング方法を応用することで血管強化も実現できること が示されている以上,本件発明3と同じ緊締具,加除圧制御装置及び加除 圧制御システムが用いられている甲1−3発明において,血管強化も実現 するために,除圧工程により加圧動作によって付与された加圧力が完全に 除去された状態において特定部分を締め付ける加圧力が付与されていな い構成にすることは,設計的事項であると主張するものと解される。\nしかし,甲2の発明の詳細な説明には,「メタボリック症候群は,・・・動 脈硬化,心筋梗塞,或いは脳卒中を起こしやすい状態である」(【0005】) との記載があるのみで,メタボリック症候群が動脈硬化の状態にあると記 載されているわけではなく,また,「加圧トレーニング方法は,四肢の少な くとも1つで流れる血流を阻害することによりその効果を生じさせるも のである・・・加圧トレーニング方法を,メタボリック症候群の治療に用い ようとした場合には,・・一般的には中高年であるメタボリック症候群の患 者は血管の強度,柔軟性が低下していることが多いため,四肢の付根付近 の締付けを行うことにより四肢に与える圧力の制御に最大限の注意が必 要である」(【0007】),「加圧トレーニングは,・・・四肢の付根付近の所 定の部位を締付けて加圧することにより,四肢に血流の阻害を生じさせ, それにより運動したのと同様の効果を生じさせるものである。・・・しかし ながら,メタボリック症候群の患者のような,血管の強度,柔軟性が低下 している者の四肢を締付ける場合には,動脈まで閉じさせるような大きな 圧力を与えることは適切ではない。他方,静脈をある程度閉じさせるよう な圧力で締付けを行わなければ,メタボリック症候群の患者の治療を十分\nには行うことができない。そこで,本願発明における治療システムでは, 四肢の付け根付近の締付けを本格的に行う通常処理に先立って前処理を 行い,その前処理で,四肢の付根付近を締付ける際に与える適切な圧力と しての最大脈波圧を特定することとしている。・・・本願発明の治療システ ムは,メタボリック症候群の患者を含む血管の弱い者の治療に適したもの となる。」(【0009】)との記載がある。そうすると,甲2発明は,加圧 トレーニング方法の機序を応用した,血管の弱いメタボリック症候群の患 者に対する治療装置等に関する発明であって,血管強化方法に関するもの ではないというべきであるから,甲2に血管強化方法が開示されていると の原告の上記主張は,その前提を欠くものであり,その他の点につき判断 するまでもなく,この点に関する原告の主張は理由がない。
イ また,原告は,甲6には,ベルト(あるいはカフ)を外すことにより締 付け力を皆無にする方法が記載されているところ,本件発明3においては, 「自然締付け力」を皆無にするための付加的な構成要素は示されておらず,\n具体的な方法すら示されていないから,ベルトを単に緩める,あるいは外 すという方法もその「自然締付け力」を皆無にする方法として本件発明3 に包含されている旨主張する。 上記主張の趣旨は明らかではないが,甲6に記載されたベルトを外すこ とにより締め付け力を皆無にするという技術事項を,自然締め付け力によ る加圧力を付与しない方法として甲1−3発明に適用すれば,本件発明3 の相違点2の構成に容易に想到するというものと解される。\n しかし,そもそも甲1に接した当業者が,加圧工程と除圧工程を交互に 繰り返す圧力調整手段を制御する制御手段の「下ピーク」のときに,緊締 具が所定の部位に与える締付け力について,自然締付け力による加圧力も 付与しない状態として血流を阻害しない状態とする構成にする動機付け\nがあるとはいえないことは前記アのとおりである。 また,甲6には,1)「(バラコンバンドの効能)・・・2.血管内を清掃し 血管にも弾力がでる。バンドを強く締めると,そこで血流が止まる。心臓 からは絶え間なく血液は送られてくる。血液は,バンドの所で滞留し,血 量はその部で倍加される。バンドをはずすと,血は倍の速力で血管内を流 れる。その時血管壁を掃除し,動脈硬化を治し,血管そのものも弾力がで る。」(74頁7行目〜75頁5行目),2)「足裏指巻き ●まず親指と第2 指の間を通してかかとにひっかけ,次に第2指と第3指を通して,またか かとへ巻き,指の間を通した余りで足の甲をこの停止部分にバンドを巻く。 一つでも関節を越したほうがよく効くので,手の場合なら肘の下の二つの 腕にバンドを巻くといい。(肘の上から巻き込んでいてもかまわない)きつ めに巻いて我慢できなくなったらはずそう。すると,ダムの水門を開いた ように,血液がどっと流れ込み,これまで充分にいきわたっていなかった ところまで勢いよく入り込む。」(120頁上段8行目〜121頁2行目) との記載があるが,これらは,血流を一時的に止めた後にバンドを外した 場合の効果が記載されているに止まる。したがって,これらの記載に基づ き,緊締具を付けたままの状態で,「ガス袋120へ空気を送って締付け部 位を加圧する上ピークと,ガス袋120へ送った空気を抜いて締付け部位 への加圧を行わない下ピークと,を繰り返す加除圧方法」を採用する甲1 −3発明に,下ピークにする度に緊締具(甲6でいえば「バンド」)を外し, 上ピークにする前にこれを付け直すような変更を施すことは想定できず, この点からも,甲1−3発明に甲6に記載された事項を適用する動機付け はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.04.23
令和1(行ケ)10140 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月16日 知的財産高等裁判所
ア 本件発明1の「利用者データベース」について
(ア) 前記第2の2の特許請求の範囲の記載のとおり,構成要件1Bの「利\n用者データベース」は,管理コンピュータ側に備えられるものであり, 「監視端末側に対して付与されたIPアドレスを含む監視端末情報」が, 「利用者ID」に「対応付けられて登録」されているものと規定されて いる。 また,管理コンピュータ側は,「利用者の電話番号,ID番号,アド レスデータ,パスワード,さらには暗号などの認証データの内少なくと も一つからなる利用者IDである特定情報」を入手し(構成要件1Di),\n「この入手した特定情報が,前記利用者データベースに予め登録された\n監視端末情報に対応するか否かの検索を行」い(構成要件1Dii),「前 記特定情報に対応する監視端末情報が存在する場合,…この抽出された 監視端末情報に基づいて監視端末側の制御部に働きかけていく」(構成\n要件1Diii)と規定されている。 そうすると,特許請求の範囲の記載からは,「利用者データベース」 は,記憶媒体の種類や構成等の限定は付されていないものの,入手する\n特定情報から,あらかじめ登録された監視端末情報を検索することがで き,入手した特定情報に対応する監視端末情報が存在する場合に当該監 視端末情報に含まれるIPアドレスを抽出し得る程度に,IPアドレス を含む監視端末情報が利用者IDに「対応付けられて登録されている」 ものと理解することが相当である。
(イ) そこで,次に,本件明細書の記載をみると,前記1のとおり,本件発 明の実施例において,「利用者データベース」は,磁気ディスクや光磁 気ディスクからなる記憶装置35に記憶され,利用者の電話番号,ID 番号,アドレスデータ,パスワード,暗号,指紋等を基にした利用者を 識別可能な符号である利用者IDに,該利用者の暗証番号並びに該利用\n者が監視したい場所に設置されている監視端末に付与されているIPア ドレスを対応付けているものであり(【0020】,【0021】,【図 5】),利用者の認証の際に参照されるとともに,利用者がアクセス可 能な監視端末のグローバルIPアドレスを検索抽出するために参照され\nるものとされている(【0026】,【0029】,【0030】,【図 7】)。 本件明細書の記載によっても,「利用者データベース」は,利用者を 識別できる情報(「利用者ID」)に,当該利用者が監視したい場所に 設置されている監視端末に付与されたグローバルIPアドレス(「監視 端末情報」)が検索できる程度に対応付けられることを要するものと理 解される(なお,実施例における記憶媒体の種類は単なる例示であるこ とが明らかであるから,やはり,本件発明1において,「利用者データ ベース」の記憶媒体の種類や構成等に限定が付されたものと理解するこ\nとはできない。)。
(ウ) 以上からすると,本件発明1の「利用者データべース」は,利用者を 識別できる情報に監視端末側に付与されたIPアドレス等の情報が,検 索できる程度に対応付けられて登録されていることを要するものの,そ れで足り,記憶媒体の種類や構成等が具体的に限定されているものでは\nないと解されるが,利用者を識別できる情報とIPアドレスが関連性な く記憶され,両者がシステム動作中に単にあい続いて利用されているだ けの関連性しか有しない場合には,前記(ア)において説示した意味合い において,当該監視端末情報に含まれるIPアドレスを抽出し得る程度 に,IPアドレスを含む監視端末情報が利用者IDに「対応付けられて 登録されている」ものということはできないから,「利用者データベー ス」が構成されているとはいえないと解するのが相当である。\n
◆判決本文
こちらは原告被告の同じ関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.04.22
令和2(行ケ)10073 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月24日 知的財産高等裁判所
(1) 一致点及び相違点
上記1及び2によれば,本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は, 本件審決が認定したとおり(前記第2の3(2)イ)であると認められる(なお, 以下において,「医療情報取得情報」とは,患者の医療情報を取得するため に,端末装置から取得され,又は情報処理装置の記憶部にあらかじめ記憶さ れた情報をいう。)。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,甲1発明の「ベッドサイド端末識別子」は患者名を取得するた めの識別情報であり,本件発明1の「第1識別情報」に相当するから,相 違点1−1は存在しない旨主張する。 しかしながら,本件明細書1及び甲1公報の記載内容からすれば,本件 発明1の「第1識別情報」は,患者ごとに付された患者ID等であるのに 対し,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」は,ベッドサ イド端末ごとに付されたIPアドレス等であり,両者が識別する対象は異 なるというべきである。また,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端 末識別子」は,患者IDと関連付けられて記憶されることによって初めて 患者を識別する情報として用いることが可能となるにすぎないものであ\nり,それのみによって直接に患者が識別されるものではない。 これらの事情を考慮すると,本件発明1の「第1識別情報」と甲1電子 カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」とは,異なる概念であるとい うべきであるから,相違点1−1を認定することができる。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ なお,原告が主張する相違点は,上記相違点1−2と実質的に同じ内容 である(原告が指摘するとおり,相違点1−2の第2段落及び第3段落は, 第1段落に伴って形式的に生じる相違点にすぎない。)。
◆判決本文
こちらは関連発明です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 相違点認定
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.04.22
令和2(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月22日 知的財産高等裁判所
前記のとおり,相違点1は,切削ローラの路面に対する高さを調節する ための機構に関するものであるところ,相違点2は,切削ローラの移動方\n向を踏まえた切削ローラ及びこれを支持する切削ローラハウジングとフ レームとの支持構造に関するものであり,また,相違点3は,切削ローラ\nに一体化された切削ローラ駆動ユニットの可動方向を踏まえた同ユニッ トの支持構造に関するものである。\nそうすると,これらは相互に密接に関連するものといえるから,相違点 1ないし3の容易想到性については,併せて判断するのが相当である。
イ そこで検討するに,上記2(1)のとおり,検甲1発明においては,切削ロ ーラ及び切削ローラと一体化した駆動部がハウジング部に支持され,ハウ ジング部は,上下方向変位用の油圧シリンダが取り付けられた2つの棒状 ガイド及び4本の連結棒を介してフレーム部に支持されているところ,切 削ローラの路面に対する高さの調節に関しては,切削ローラを油圧シリン ダ等の駆動機構によって垂直方向に移動させる構\成が採られている。 これに対し,本件発明1においては,上記1(3)のとおり,切削ローラ及 び切削ローラハウジングが上下方向及び進行方向に機械フレームに強固 に支持されているところ,切削ローラの路面に対する高さの調節に関して は,切削ローラを車体の上下動によって垂直方向に移動させる構成が採ら\nれている。
そして,本件優先日時点において,これらの方法以外に,自走式道路切 削機における切削ローラの路面に対する高さを調節する方法があったこ とをうかがわせる証拠は存しないから,当業者としては,上記2つの方法 のいずれかを採るほかなかったものといえる。そうすると,これらの方法 のいずれを採るかは,当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎないという べきである(なお,切削ローラを上下させるために,油圧シリンダ等によ り切削ローラそのものを垂直方向に移動させることは誰しも思いつくと ころであるといえるし,また,上記3(1)ないし(3)によれば,甲6文献な いし甲8文献には,いずれも,自走式道路切削機における切削ローラの路 面に対する高さを調節する方法として,車体の上下動を用いる構成を採る\nことが記載されていることからすれば,本件優先日当時の自走式道路切削 機の技術分野において,同構成は,周知の技術であったといえる。したが\nって,これらの2つの方法のうちいずれかを採用することには技術的創意 を要するから設計事項には当たらないなどといった議論は成り立たな い。)。 これらの事情を考慮すると,検甲1発明において,相違点1に係る本件 発明1の構成を採ることは,容易に想到し得るものであったといえる。\n
ウ また,検甲1発明において,切削ローラの路面に対する高さを調節する 方法として,上下方向変位用の油圧シリンダを用いる構成に代えて,車体\nの上下動を用いる構成を採る場合には,ハウジング部を垂直方向に移動さ\nせるための機構であった同油圧シリンダが不要となるところ,同油圧シリ\nンダが設置されていた棒状ガイドとフレーム部との間に,敢えて新たな別 の部材を設置する必要はない。そうすると,当業者としては,棒状ガイド をフレーム部で直接支持するような構造を採ろうとするのが自然な技術\n的発想であるといえる。
そして,上記のように,検甲1発明において,棒状ガイドをフレーム部 で直接支持するような構造を採る場合には,切削ローラ及びハウジング部\nは,横断方向にのみ移動することができるようにすればよいのであって, 敢えてこれらを垂直方向又は進行方向にも移動することができるように する必要はない。そうすると,当業者としては,切削ローラ,ハウジング 部及び切削ローラと一体化した駆動部を,垂直方向及び進行方向に移動し ないように,垂直方向及び進行方向にフレーム部で強固に支持し,進行方 向に対して横断方向にのみ変位可能に支持する構\造を採ろうとするのが 自然な技術的発想であるといえる。
エ 以上によれば,検甲1発明において,相違点1に係る本件発明1の構成\nを採った場合には,必然的に,相違点2及び3に係る本件発明1の構成を\n採ることとなるというべきである。 したがって,検甲1発明において,相違点2及び3に係る本件発明1の 構成を採ることは,相違点1と同様に,容易に想到し得るものであったと\nいえる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2021.04.22
令和2(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年4月20日 知的財産高等裁判所
本件補正によって,当初明細書等の段落【0002】,【0008】及び【0 010】に追加された事項並びに図3〜8には,本願発明の原理に関する事項が記 載されているところ(甲9),これらの事項は,当初明細書等には記載されておらず (甲4,16),また,自明な事項ということもできないから,新規事項を追加する ものといえる。 したがって,本件補正は,当初明細書等に記載された範囲内においてするものと はいえず,特許法17条の2第3項に違反するものである。
(2) 原告は,本件補正は,先行技術文献に記載された内容を「発明の詳細な説 明」の【背景技術】の欄に追加する補正であると主張する。 しかし,本件補正は,「高周波超伝導電磁エンジンは,磁石となるループと超伝導 磁石を重ね合わせたものである。二つの磁石は離れないように固定する。その二つ の磁石の中の一つは,常伝導の磁石である。但し,この常伝導の磁石は一回巻きで 芯が無く,高周波数かつ低電圧の脈流を流す。脈流の周波数は,その波長がループ の一周の長さと一致する程度の高周波数とする。もう一つの磁石は,超伝導磁石で あり,超伝導状態となるので永久電流が流れる。磁石と磁石を重ねたので,磁石と 磁石の間には,図3で上下方向の矢印で表した反発力もしくは吸引力(どちらも磁\n力)が生じる。しかし,この特殊な構造ゆえに生じる打消しの力により,図4のよ\nうに,超伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力は打ち消される。従って,常伝導磁 石に働く反発力もしくは吸引力のみが残り,これを推進力として利用する」,「図8 のように,脈流の周波数は,その波長がループの一周の長さと一致する程度の高周 波数としているので,高周波超伝導電磁エンジンの超伝導磁石には,各瞬間におい て,脈流により生じるローレンツ力がゼロの部分がある。これにより,電磁力の偏 りが生じる。よって,この電磁力の偏りのために,運動量秩序に従った動きを電子 対はすることができない。ローレンツ力の力積は電子対の重心運動を動かすことが できないので,重心運動の運動量に変化せずに,各超電子の散乱を通じて,最終的 には熱エネルギーとして外部に放出される。超伝導磁石の超電流を構成する電子対\nの重心運動が生じないので,超伝導磁石に働く電磁力(ローレンツ力)は磁力となら ず,超伝導磁石の磁力は打ち消された形となる。その結果,常伝導のループに働く 電磁力,即,磁力だけが残り,これを直線的運動エネルギーとして利用できる。」と の記載及び図4,8(以下「本件追加部分」という。)を加えるものであるところ, 本件追加部分は,特許文献1の記載の一部及び甲2文献の記載の一部から成るもの である。当初明細書等には,特許文献1及び甲2文献が先行技術文献として記載さ れているものの,それのどの部分を引用するかは記載されておらず,上記各文献を 見ても,それから直ちに本件追加部分を把握できないことからすると,本件補正は, 新規事項を追加するものということができる。
(3) 原告は,本願発明の原理は,甲2文献に記載されているところ,甲2文献は 出版されてから年数が経過しているため,上記原理は技術常識となっていると主張 する。 しかし,本願発明の原理が甲2文献に記載されており,甲2文献が出版されてか ら相当の年数が経過していたとしても,それだけで,本願発明の原理が技術常識と なっていたと認めることはできない。
(4) したがって,本件補正が,特許法17条の2第3項に違反するとした本件 審決の判断に誤りはない。
3 実施可能要件違反について\n
(1) 本願発明は,磁気シールドで半分程度を覆った「超伝導磁石」に対して固 定された位置にあるループに直流電流を流して,同ループに電磁力を発生させ,「超 伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより,ループに発生する電 磁力を推進力,制動力,浮力として利用するというものであるところ,当初明細書 等には,「超伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより,ループに 発生する電磁力を推進力,制動力,浮力として利用する原理についての説明が記載 されておらず,また,このような原理が技術常識であるということもできない。 なお,本件補正によって追加された事項では,上記の原理について説明されてい るが,磁石となるループと超伝導磁石を固定した場合,仮に,超伝導磁石に働く磁 力が常伝導ループに働く磁力より小さいとしても,互いに固定された超伝導磁石と ループ間の力は,作用・反作用の法則によって釣り合うことになり,結局,本願発 明の装置を動かす力は発生しないと考えるのが自然であるから,本件補正後の明細 書及び図面を前提としても,本願発明の原理について,当業者が理解し実施できる 程度に裏付けがされているとはいえない。この点について,原告は,作用・反作用 の法則が保障するのは,超伝導磁石に働く電磁力と常伝導ループに働く電磁力が釣 り合うことまでであり,発生した電磁力がそのまま磁力となって,釣り合うことま では保障しないと主張するが,上記のとおり,作用・反作用の法則により,超伝導 磁石に働く力と常伝導ループに働く力は釣り合うと解されるから,原告の上記主張 は理由がない。 また,原告は,本願発明の原理を利用して製造されたストレンジクラフトが存在 すると主張して,その証拠として写真集「ストレンジクラフトの写真」(甲3)を提 出するところ,甲3には,飛行する物体を撮影した写真が掲載されているものの, 同物体が,本願発明の原理を利用したものであると認めるに足りる証拠はないから, 原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2021.04.22
令和2(行ケ)10032 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月30日 知的財産高等裁判所
これに対し,被告は,前記第3の1(2)ア(ア)のとおり,甲1発明におい ては,撮像装置を光軸まわりに回転させる方向が「ロール方向」の傾きで あることは技術常識であるから,表示部の回転した角度である「天地方向\nの向き」,すなわち「天地方向の情報を示す矢印の角度」が「ロール方向の 傾き」であると主張する。 しかし,「画像撮像装置1000が,右に30度傾いた状態である場合の, 報知画像600Aを示す図」である図13の「矢印512」は,「天地方向 の情報を示す」(【0112】)ものであるところ,「天地方向算出手段22 2は,傾斜測定部250が算出した重力加速度の方向と大きさに基づいて」 天地方向を判定し(【0079】,【0087】,【0088】,【0107】), 「傾斜測定部250」は,直交する2軸の重力加速度センサーが,【007 2】の式(3)で求められる,「方向D303と水平面P302とが成す角度」 (【0069】)であるθの値を算出し,平面P302の傾斜度を測定する (【0073】,【0074】)ものである。そして,前記(1)ア(イ)のとおり, こうした直交する2軸の重力加速度センサーと水平面との角度がなす傾 斜度により判定される角度は,光軸が水平面と平行である場合を除き,撮 像装置を光軸まわりに回転させる方向の傾きの角度とは異なるから,「矢 印512」で示される「天地方向の情報を示す矢印の角度」が「ロール方 向の傾き」であるということはできない。
イ また,被告は,前記第3の1(2)ア(イ)のとおり,甲1発明は,第1傾斜 度及び第2傾斜度の両方に基づいて画像撮像装置の前後方向の傾き,すな わち,ピッチ方向の傾きを検出するものといえる旨主張する。
確かに,甲1には,1)天地方向算出手段222は,第1傾斜度及び第2 傾斜度のいずれかが所定値A(例えば,30〜60の範囲の値)以上であ るか否かを判定(ステップS120)し(【0105】),所定値A以上であ れば,天地方向算出手段222が,傾斜測定部250が測定した第1傾斜 度及び第2傾斜度に基づいて画像撮像装置1000の天地方向の算出を 行い(【0107】),制御部が画像撮像装置1000の天地方向の算出結果 に基づく情報を表示した報知画像を生成し,表\示部150に表示する(【0\n108】),2)ステップS120において,所定値A未満であれば,天地方 向算出手段222が傾斜測定部250が測定した第1傾斜度及び第2傾 斜度に基づいて,画像撮像装置1000の天地方向の算出を行う(【011 8】)ところ,図14のように画像撮像装置1000が水平面に対して平行 である場合,天地方向算出手段222は,傾斜測定部250が測定した第 1傾斜度及び第2傾斜度に基づいて画像撮像装置の天地方向の判定はで きない(【0119】)が,画像撮像装置が図14の状態になる前に必ず第 1傾斜度及び第2傾斜度のいずれかが所定値A以上(ステップS120に おいてYESの場合)の状態にあり,天地方向が判定できる状態にあって (【0121】),傾斜度及び天地方向が記憶(ステップS126)する処理 が行われており(【0122】),こうした場合,天地方向算出手段222は, 記憶されている傾斜度データ及び天地方向のデータの少なくとも一方に 基づいて画像撮像装置1000の天地方向の判定を行い(【0123】),こ の算出結果に基づく情報を報知した報知画像を表示部150に表\示させ る(【0124】),3)【図16】は,画像撮像装置1000が水平面P30 2に対し平行である場合の報知画像を示す図である(【0126】)ことが それぞれ開示されている。
しかし,天地方向算出手段222は,傾斜測定部250が算出した重力 加速度の方向を大きさに基づいて天地方向を判定し(【0079】,【008 7】,【0088】,【0107】),画像撮像装置に内蔵された2軸の重力加 速度センサーである傾斜測定部250は,【0072】の式(3)により求め られる重力加速度センサーと水平面とが成す角度θ(D301,303と 同じ軸上にある重力加速度センサーと水平面P302とが成す角度)の値 を算出することによって傾斜度を測定するものであるから,甲1で測定さ れる第1傾斜度及び第2傾斜度は,撮像装置の水平軸が水平面と平行であ る場合を除き,撮像装置を水平軸周りの傾き度合いであるピッチ方向の傾 きを算出するものではないことは前記(1)イ(イ)のとおりである。また,【図16】について,画像撮像装置の水平軸が水平面と平行であることを前提として,画像撮像装置を水平軸周りに前後に回転(変位)させて画像撮像装置が水平面P302に平行になった状態であると仮定したとしても,上記の開示事項からは,「画像撮像装置が水平面に対し平行である場合」かどうかの判定に際し,第1傾斜度及び第2傾斜度が用いられる ことは読み取ることができるものの,ピッチ方向の傾きを検出し,判定に 用いることを開示しているとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2021.04.22
平成30(ワ)3461 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟
ア これまで検討したところによれば,原告製の使用済み紙管を保有する者は, 被告製品と合わせることで一体化製品を生産できること,一体化製品は本件特許の 技術的範囲に属すること,被告製品は,一体化製品の生産にのみ用いられる物であ ることが認められるから,業として被告製品を製造,販売することは,特許法10 1条1号の間接侵害に当たるというべきである。 この点について被告らは,原告製品の購入者は,紙管に分包紙を合わせて買い受 けたものであるところ,本件発明の本質は紙管部分にあるから,分包紙を費消した としても原告製品の効用は終了せず,分包紙の交換は,製品としての同一性を保っ たまま,通常の用法における消耗部材を交換することにすぎないから,原告は,原 告製品の購入者に対し,本件特許権に基づく権利行使をすることができない旨を主 張する(消尽の法理)。 これに対し原告は,使用済み紙管については原告が所有権を留保しており,一体 化製品の生産は特許製品の新たな製造に当たるとして,消尽を否定し,間接侵害の 成立を主張する。
イ そこで検討するに,本件発明の実施品である原告製品を原告より取得した利 用者がこれに何らかの加工を加えて利用した場合に,当初製品の同一性の範囲内で の利用にとどまり,改めて本件特許権行使の対象にはならないとすべきか,特許製 品の新たな製造にあたり,本件特許権行使の対象となるとすべきかは,当該特許製 品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総 合考慮して判断すべきものである(最高裁判所平成19年11月8日第一小法廷判 決・民集61巻8号2989頁参照)。 本件発明は,分包紙ロールの発明であって,紙管と,紙管に巻き回される分包紙 から成るものであり,紙管についてはこれに設ける磁石の取付方法に限定があるの に対し,分包紙については,紙管に巻き回す以上の限定がないことは,既に述べた ところから明らかである。
しかしながら,証拠(甲5の1,2,甲23,乙11,12)及び弁論の全趣旨 によれば,分包紙ロールの価格は分包紙の種類によって決められていること,原告 製の使用済み紙管については,相当数が回収されていることが認められるのである から,本件特許の特徴は紙管の構造にあるとしても,原告製品を購入する利用者が\n原告に支払う対価は,基本的に分包紙に対するものであると解されるし,調剤薬局 や医院等で薬剤を分包するために使用されるという性質上,当初の分包紙を費消し た場合に,利用者自らが分包紙を巻き回すなどして使用済み紙管を繰り返し利用す るといったことは通常予定されておらず,被告製品を利用するといった特別な場合\nを除けば,原告より新たな分包紙ロールを購入するというのが,一般的な取引のあ り方であると解される。 また,一体化製品を利用するためには,利用者は,使用済み紙管の外周に輪ゴム を巻いた上で,これを被告製品の芯材内に挿入しなければならないが,これは,使 用済み紙管を一体化製品として使用し得るよう,一部改造することにほかならない。 そうすると,分包紙ロールは,分包紙を費消した時点で,製品としての効用をい ったん喪失すると解するのが相当であり,使用済み紙管を被告製品と合わせ一体化 製品を作出する行為は,当初製品とは同一性を欠く新たな特許製品の製造に当たる というべきであり,消尽の法理を適用すべき場合には当たらない。
ウ なお, 原告は,利用者との合意により,使用済み紙管の所有権は原告に留保 されていると主張するところ,証拠(甲3,17ないし21,23,25)によっ ても,使用済み紙管を原告に返還すべきこととされている取引の実情が認めるにと どまり,利用者との間で所有権留保についての明確な合意が存在するとまでは認め られないが,前記イで検討したところによれば,使用済み紙管の所有権の所在は, 上記結論を左右するものではない。
エ 以上検討したところによれば,使用済み紙管と被告製品を合わせて一体化製 品を作出すれば,新たな特許製品の製造に当たり,一体化製品の生産にのみ用いる 被告製品を業として製造,販売することは,特許法101条1号の間接侵害に当た るというべきである。
・・・・
原告は,前記認定した被告日進の利益率が約27%であることから,被告O HUと被告セイエーの利益率も同程度と推認されること,被告日進の原価率が約7 0%(被告OHUより4203万8700円で仕入れ,5952万4536円で販 売。)であることから,被告OHUの原価率も同程度と推認されること(被告日進 に4203万8700円で売った物は,被告セイエーより2942万7090円で 仕入れた。その27%が被告セイエーの利益。)と主張する。 しかしながら,原告において共同不法行為が成立すると主張する被告らの関係に おいて,被告セイエー,被告OHU,被告日進,顧客と被告製品が流通する過程に おいて,各段階で高い利益を確保することができる場合もあれば,最終の被告日進 から顧客に至る段階で利益を確保しようとする場合もあり得るところ,本件におい て,前者の取引形態であったことを示す証拠,あるいはそれを示唆するような事実 は何ら示されていない。
原告が推認する利益率,原価率をあてはめた場合,被告日進の販売額の約6割の 金額を,グループとしての被告らは利益として確保したことになり,高額に過ぎる と解されると同時に,被告セイエーが負担した製造原価以外には,被告OHUも被 告日進も,控除すべき費用をほとんど負担していないことになる。 以上によれば,被告らの利益率がすべて27%であり,被告OHUの原価率は被 告日進と同様に70%と推認される旨の原告の主張は採用できないというべきであ る。 本件において,被告セイエーが負担した製造原価等の経費,被告OHUの被 告セイエーからの仕入額,被告OHUが負担した経費については,主張,証拠共に 開示されていないが,これは被告らが開示するよう求められつつこれを拒んだので はなく,原告が,訴状(平成30年4月20日付け)の段階では,被告セイエー及 び被告OHUは,いずれも被告日進の売上高の3%の利益を有する旨を主張し,損 害論の審理に入る際の訴えの変更申立書(令和2年1月27日付け)においても,\n被告セイエー及び被告OHUは,いずれも被告日進の売上高の3%相当の利益を有 していると主張したため,被告らにおいてこれを争わず,被告セイエーらの経費等 に関する主張,証拠を提出しないままに終わったという審理の経緯によるものであ る。
原告は,被告らが被告日進の売上及び経費に関する主張,証拠を提出した後の訴 えの変更申立書(2)(同年11月13日付け)に の推認を主張したところ,被告らは,被告セイエー及び被告OHUの利益が被告日 進の売上の3%であることについては,裁判上の自白が成立している旨を主張した ものである。
以上の経緯を前提に検討すると,原告の訴状,訴えの変更申立書の主張は,\n被告日進の売上高が確定する前になしたものであるから,具体的な金額についての ものではなく,裁判上の自白が成立するとはいい難い。 他方,被告らの利益率をいずれも27%,被告セイエーの原価率を70%と推認 することについては,具体的な根拠に乏しく,被告セイエー及び被告OHUが負担 した経費等が開示されておらず,これに基づいて被告らの利益を算定できないこと について,被告らを責めるべき事情は存しない。 以上の審理の経過を踏まえ,原告が訴状の段階から訴訟の最終の段階に至るまで, 被告セイエー及び被告OHUの利益は被告日進の売上の3%とする主張を維持し, 被告らもこれを争わずに来たこと,他に依拠すべき算定方法がないことを考慮し, 弁論の全趣旨により,被告セイエー及び被告OHUが被告製品の製造,販売によっ て得た利益は,被告OHUにつき被告日進の売上の3%である178万5736円, 被告セイエーにつき,同金額から, のとおり,返品等分の製造原価とし て11万3925円を控除した167万1811円と認めるのが相当である。
(3) 推定の覆滅
これまで検討したところによれば,薬剤分包装置を業務上使用するためには薬剤 分包紙が必須であるから,同装置の利用者は,定期的に自己の保有する薬剤分包装 置に適合した分包紙ロールを購入することとなる。そして,被告製品は,使用済み 紙管の外径とほぼ一致する内径を持つ分包紙ロールであり,被告らが一体化製品を 作出して原告装置において使用できることを明示していたこと,市場に存在する原 告製品又は被告製品以外の主な分包紙ロールがこれと異なる寸法の内径を持つもの であることは前記3(1)ウのとおりであるから,需要者は,原告製の分包紙の代替と して被告製品を購入していたものと考えられる。 原告は,本件発明の技術的範囲に属する原告製品の製造,販売を独占できる立場 にあり,被告製品が市場に存在しない場合には,需要者は値段にかかわらず原告製 品を購入したものと考えられるから,被告製品の価格がこれに比べて有利であるこ とは,特許法102条2項に基づく前記(1)の推定を覆滅するものではない。
関連カテゴリー
>> 消尽
>> 間接侵害
>> のみ要件
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2021.04.21
平成30(ワ)36690 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月15日 東京地方裁判所
(1) 消滅時効の成否
前記前提事実(2),(6)ないし(8)のとおり,本件特許の登録は平成22年7 月30日にされており,被告各製品の製造,販売は同年12月から平成23 年9月の期間に行われたものであったところ,原告は,平成24年1月9日 頃,被告による被告各製品の製造,販売が別件特許権の侵害に当たる等とし て,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求を求める別件訴訟を提起し, 平成25年8月2日に別件判決が言い渡された。 そして,証拠(甲4,5,乙1,5)及び弁論の全趣旨によれば,原告は, 別件訴訟の審理を通じて,遅くとも別件判決の言渡日である平成25年8月 2日までには,被告各製品の具体的な構成について本件の訴状で記載した程\n度には認識していたものと認められる。 したがって,本件の主位的請求に係る不法行為に基づく損害賠償請求権に ついては,原告が遅くとも同日までにその損害及び加害者を知ったものと認 められるから,改正前民法724条前段の3年の時効期間は同日から進行し, 平成28年8月2日の経過をもって,本件訴訟提起前に消滅時効が完成した ものと認められる。
・・・
ウ 実施料率の認定
(ア) 前記イ(ア)ないし(ウ)によれば,1)実際の実施許諾契約における実施料 率,業界における実施料の相場等について,次の点を指摘することがで きる。 本件発明を含め,原告による特許発明の実施許諾の実績はない。また, 業界における実施料の相場等として,本件報告書及び前記「実施料率 〔第5版〕」における平均値等の記載を採用することも相当ではない。こ のような状況に照らせば,本件発明に関し,業界における実施料の相場 等を示すものとしては,被告が締結した被告製品に関する特許の実施許 諾契約の内容を参考とするのが相当である。 そして,被告従業員の前記陳述書においては,被告各製品に関連する 標準必須特許以外のライセンス契約において,パテントファミリー単位 での特許権1件あたりのライセンス料率が●(省略)●%であり,その うち,ランニング方式での契約をとるC社との契約においてはライセン ス料率の平均が約●(省略)●%であったこと,また,被告が,平成2 2年頃,被告各製品の販売に関連し,画像処理・外部出力関連の標準規 格の特許ライセンス料を含む使用許諾料として支払っていた額は1台当 たり合計●(省略)●米ドルであったことが説明されている(別紙5 「被告各製品の販売状況」記載の売上合計を販売台数合計で除して算出 した,被告各製品1台当たりの売上高は約●(省略)●円である。)。 なお,上記陳述書における被告従業員の説明によれば,これらのライ センス契約のうち,C社を含む一部の会社との間の契約においてはクロ スライセンスの条項が設けられていたところ,前記イ(イ)a(a)によれば, クロスライセンスの存在はライセンス料率を引き下げる要因と考えられ るから,上記の被告従業員の説明に係るライセンス料率についても,ク ロスライセンスによる減額がされていた可能性は否定されない。\n(イ) 前記(ア)の点に加え,前記イ(エ)のとおり,2)本件発明が被告各製品に とって代替不可能なものとは認められず,3)本件発明を実施することに よる被告の利益の程度も明らかではないこと,前記イ(ア)のとおり,4)原 告と被告との間に競業関係がなく,原告は,特許発明について自社での 実施はしておらず,他社に実施許諾をして実施料を得ることを営業方針 としているものの,これまで保有する特許発明について,実施許諾契約 の締結に至ったことはないことといった事情を総合考慮すれば,本件発 明について,被告各製品の製造,販売に対して受けるべき実施料率は0. 01%と認めるのが相当である。
エ 被告が返還すべき利得の額
以上によれば,被告が返還すべき利得額は,別紙5「被告各製品の販売 状況」記載の被告各製品の売上高合計980億1770万4000円に実 施料率0.01%を乗じた980万1770円と認められる。
◆判決本文
別件訴訟はこちらです(請求棄却)。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> その他
>> ピックアップ対象
2021.04.21
令和2(行ケ)10063 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月25日 知的財産高等裁判所
前記(1)で認定した事実関係をもとにして,本件発明の実施に本件処分を受ける ことが必要であったかどうかについて検討する。 ア 特許権の存続期間の延長登録の制度は,政令処分を受けることが必要で あったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的 とするものであるから,本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったか どうかは,このような特許法の存続期間延長の制度が設けられている趣旨に照らし て判断されるべきであり,その場合における本件処分の内容の認定についても,こ のような観点から実質的に判断されるべきであって,本件承認書の「有効成分」の 記載内容のみから形式的に判断すべきではない。このように解することは,最高裁 平成26年(行ヒ)第356号同27年11月17日第三小法廷判決・民集69巻 7号1912頁の趣旨にも沿うものということができる。
イ 前記(1)エで認定した事実からすると,医薬品について,良好な物性と安 定性の観点からフリー体に酸等が付加されて,フリー体とは異なる化合物(付加塩) が医薬品とされる場合があること,そのような医薬品が人体に取り込まれたときに は,付加塩からフリー体が解離し,フリー体が薬効及び薬理作用を奏すること,ナ ルフラフィンとナルフラフィン塩酸塩についても同様の関係にあり,ナルフラフィ ンとナルフラフィン塩酸塩で薬効及び薬理作用に違いがないことは,本件医薬品の 製造販売の承認申請がされた平成28年3月31日までに,当業者に広く知られて\nいたものと認められる。
ウ 上記イで述べたところに,前記(1)オ,カ,キで認定した事実や前記(1) クの専門家の意見書の内容を総合すると,医薬品分野の当業者は,医薬品の目的た る効能,効果を生ぜしめる作用に着目して,医薬品に配合される付加塩だけでなく,\nそのフリー体も「有効成分」と捉えることがあるものと認められる。
エ 前記(1)ア〜ウのとおり,本件承認書には,「有効成分」として「ナルフ ラフィン塩酸塩」と記載されており,本件添付文書にも「有効成分に関する理化学 的知見」として,「ナルフラフィン塩酸塩」と記載され,その構造式や性状などが\n記載されているが,これは,賦形剤などの製剤補助剤と区別する観点から,実際に 医薬品に配合されている原薬(付加塩)を有効成分として捉えていることに基づく 記載であると解される。これに対し,本件添付文書の「有効成分・含量(1錠中)」 の欄に,「ナルフラフィン塩酸塩2.5μg(ナルフラフィンとして2.32μg)」 と記載されており,本件インタビューフォームには,和名は「ナルフラフィン塩酸 塩」と記載されているものの,洋名については「ナルフラフィン塩酸塩」と「ナル フラフィン」が併記されているし,「有効成分(活性成分)の含量」として カプ セル:1カプセル中ナルフラフィン塩酸塩2.5μg(ナルフラフィンとして2. 32μg)含有 OD錠:1錠中ナルフラフィン塩酸塩2.5μg(ナルフラフィ ンとして2.32μg)含有」と記載されている。そして,前記(1)アのとおり,本 件承認書における●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●同じ く,前記(1)イ,ウのとおり,本件添付文書や本件インタビューフォームにおける, 本件医薬品の「薬物動態」の血漿中濃度や薬物動態パラメータもナルフラフィン塩 酸塩ではなく,ナルフラフィンを測定して得られたものとなっている。
オ 以上のことを考え併せると,本件処分の対象となった本件医薬品の有効 成分は,本件承認書に記載された「ナルフラフィン塩酸塩」と形式的に決するので はなく,実質的には,本件医薬品の承認審査において,効能,効果を生ぜしめる成\n分として着目されていたフリー体の「ナルフラフィン」と,本件医薬品に配合され ている,その原薬形態の「ナルフラフィン塩酸塩」の双方であると認めるのが相当 である。 したがって,「ナルフラフィン塩酸塩」のみを本件医薬品の有効成分と解し,「ナ ルフラフィン」は,本件医薬品の有効成分ではないと認定して,本件発明の実施に 本件処分を受けることが必要であったとはいえないと判断した本件審決の認定判断 は誤りであり,取消事由1は理由がある。
(3) 被告の主張について
被告は,原告が本件延長登録出願に当たって,本件医薬品の「有効成分」を「ナ ルフラフィン塩酸塩」と主張していたことや原告が作成した書類(甲83,88, 90)で有効成分をナルフラフィン塩酸塩としていたと主張する。 しかし,本件延長登録出願の経緯は,前記(1)ケ認定のとおりであって,この経緯 に照らして,原告が取消事由1の主張をすることや裁判所が同取消事由1に理由が あると判断することを妨げられる理由はなく,前記(2)の上記判断を左右するもの ではない。また,被告が主張する文書(甲83,88,90)は,本件医薬品の製 造販売の承認申請に向けて作成された文書であるところ、本件医薬品の有効成分は,\n本件医薬品の承認審査の経緯や内容等を踏まえると,実質的にはナルフラフィン塩 酸塩とナルフラフィンの双方と解するのが妥当であるから、本件承認書(甲4,9 6,148)の記載が前記(2)の認定判断を左右しないことと同様に,上記の文書も、 前記(2)の認定判断を左右するものではない。
2021.04.21
平成31(ワ)2034 損害賠償請求事件 その他 民事訴訟 令和3年1月8日 東京地方裁判所
(1) 本件事業譲渡の対象について
本件事業譲渡の対象について,原告は,関東地方に所在する食品加工業者 及び食品工場向けの食品用機械の開発,製造,加工,販売又はメンテナンス の事業等が包括的に含まれると主張するのに対し,被告は,本件事業譲渡の 対象は,旧関東事業部の行っていた食品用機械のメンテナンス及び付属部品, 資材の販売等の事業に限られると主張するので,以下,検討する。 ア 本件事業譲渡契約書第1条には,被告は原告に「関東事業部」を譲渡す る旨の記載があるところ,前記前提事実(第2の1(1)),証拠(甲11, 12)及び弁論の全趣旨によれば,1)被告は,平成23年11月,海外メ ーカー製の食品用機械の輸入及び販売事業等を行うことを目的として,関 東産機事業部を被告所沢事務所内に立ち上げたこと,2)その後,関東産機 事業部の責任者であるAが平成27年に被告を退社したことから,被告所 沢事務所内に同事業部の担当者が不在になり,関東産機事業部が行ってい た事業は,原告代表者を含む旧関東事業部の従業員等が引き継いで行うよ\nうになったこと,3)平成28年から平成29年頃にかけての被告の受注予\n定表は「札幌」と「関東」とで別々に作成されており,関東地方の受注予\ 定表には関東産機事業部と旧関東事業部の区別なく,受注案件の進捗状況\n等が記載されていること,の各事実が認められる。 上記各事実によれば,本件事業譲渡当時,関東産機事業部の活動は事実 上休止状態にあり,被告の関東地方における事業やその営業は,そのほと んどを旧関東事業部が行っていたものと認められ,本件事業譲渡契約書第 1条の「関東事業部」とは,同契約締結当時に旧関東事業部が行っていた 事業,すなわち,被告の関東地方における食品加工業者及び食品工場向け の食品用機械の開発,製造,加工,販売又はメンテナンスの事業を包括的 に含むものと解するのが相当である。
イ また,前記前提事実(第2の1(2))のとおり,本件事業譲渡契約書には, 関東産機事業部に残される資産や契約等についての記載は存在せず,かえ って,同契約書第2条は,被告は,原告に対し,建物付属設備,機械装置, 器具備品等の全てを含む資産,旧関東事業部の敷地及び建物(工場・事務 所)の物品の全てに関する契約,並びに旧関東事業部の行う事業に関する 営業上の秘密,ノウハウ,顧客情報等を含む必要又は有益な全ての情報を 譲渡すると規定されている。 被告は,原告に譲渡した事業には関東産機事業部の事業は含まれないと 主張するが,本件事業譲渡契約書の草案を作成したのが被告であることに ついては当事者間に争いないところ,仮に被告の主張するように関東産機 事業部を事業譲渡の対象としないのであれば,本件事業譲渡契約書におい て旧関東事業部に譲渡する食品用機械や資材等の資産,契約,顧客等と被 告の関東産機事業部に残す資産,契約,顧客等とが区別して規定されてし かるべきであるが,本件事業譲渡契約書においては,関東産機事業部に一 部の資産,契約,顧客情報等を残すことを前提とする記載は存在しない。 そうすると,本件事業譲渡契約書第2条の規定は,被告が,原告に対し, 被告の関東における食品加工業者及び食品工場向けの食品用機械の開発, 製造,加工,販売又はメンテナンスの事業等に関する資産,顧客情報を包 括的に譲渡する趣旨であると解するのが相当である。
ウ さらに,平成28年10月21日に開催された役員会議の議事録(乙1 2)には,本件事業譲渡に関し,被告代表者が「(関東事業部の)事業譲\n渡を考えています。・・・関東事業部の資産価値1,000万円,営業権1,000万円 くらい。Xさんが関東事業部の頭でもあるため,Xさんが関東事業部を買 う形が望ましい。」と発言した旨の記載があると認められるが,同議事録 には,関東産機事業部の事業を譲渡対象としないことやその資産価値につ いての記載は存在しない。 このことに照らしても,本件事業譲渡契約の対象には,被告の関東にお ける食品加工業者及び食品工場向けの食品用機械の開発,製造,加工,販 売又はメンテナンスの事業等が包括的に含まれると解するのが相当であ る。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> その他
>> ピックアップ対象
2021.04.21
令和2(行ケ)10107 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年4月14日 知的財産高等裁判所
本件商標は,別紙1記載のとおり,「ざんまい」の文字を横書きに書 してなる商標である。本件商標から「ザンマイ」の称呼が生じる。 「ざんまい」の語は,「一心不乱に事をするさま。」(広辞苑第七版)の 意味を有するから,本件商標から,このような意味合いの観念を生じる。 また,前記2(2)ア認定のとおり,「すしざんまい」の表示は,本件商標 の登録出願時及び登録査定時において,被告が店舗展開する「すしざん\nまい」チェーン店の名称として,需要者である一般消費者の間に広く認 識され,被告の業務に係る「すしを主とする飲食物の提供」を表示する ものとして,著名であったこと,「すし」に関連する登録商標の使用にお\nいては,「すし」又は「寿司」の表示を登録商標の前後に付加して使用す ることが普通に行われており,現に,原告においても,本件商標の「ざ\nんまい」の前に「寿司」の文字を付加した「寿司ざんまい」の商標を使 用していること(前記1(4))に鑑みると,本件商標が指定商品「すし」 に使用されたときは,被告が店舗展開する「すしざんまい」チェーン店 を想起し,その名称としての「すしざんまい」の観念をも生じるものと 認めるのが相当である。
(イ) 引用商標1は,別紙2記載のとおり,上段に筆文字風で記載された 「つきじ喜代村」の文字を,中段に大きく筆文字風で記載された「すし ざんまい」の文字を,下段に小さくゴシック体で記載された「SUSH IZANMAI」の文字を3段に配した構成からなる結合商標であり, このうち,「すしざんまい」の文字は,引用商標1の中央に他の文字より\nも大きく,かつ,太く記載されており,「すし」の部分は,「し」が「す」 の左下に位置し,縦書きのように記載されている。 そうすると,引用商標1を構成する「つきじ喜代村」の文字部分,「すしざんまい」の文字部分及び「SUSHIZANMAI」の文字部分は,\n外観上,それぞれが分離して観察することが取引上不自然と思われるほ ど不可分的に結合しているものとはいえない。 そして,「すしざんまい」の文字部分の上記構成態様に照らすと,引用 商標1の構\成中の「すしざんまい」の文字部分は,取引者,需要者に対 し,「すしを主とする飲食物の提供」の役務の出所識別標識として強く支 配的な印象を与えるものと認められるから,要部として抽出できるもの と認めるのが相当である。 しかるところ,引用商標1の要部である「すしざんまい」の文字部分 及び「すしざんまい」の標準文字からなる引用商標2から,いずれも「ス シザンマイ」の称呼が生じる。 また,前記2(2)ア認定のとおり,「すしざんまい」の表示は,本件商標の登録出願時及び登録査定時においては,被告が店舗展開する「すしざ\nんまい」チェーン店の名称として,需要者である一般消費者の間に広く 認識され,被告の業務に係る「すしを主とする飲食物の提供」を表示す るものとして,著名であったことに鑑みると, 引用商標1の要部である 「すしざんまい」の文字部分及び引用商標2から,被告が店舗展開する 「すしざんまい」チェーン店を想起し,その名称としての「すしざんま い」の観念を生じるものと認めるのが相当である。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば,本件商標と引用商標1及び2は,外観 及び称呼が異なるが,観念においては,本件商標が指定商品「すし」に 使用されたときは,本件商標から被告が店舗展開する「すしざんまい」 チェーン店を想起し,その名称としての「すしざんまい」の観念をも生 じるのに対し,引用商標1の要部である「すしざんまい」の文字部分及 び引用商標2からも,被告が店舗展開する「すしざんまい」チェーン店 を想起し,その名称としての「すしざんまい」の観念を生じる点で共通 するものと認められる。
イ 以上のとおり,1)「すしざんまい」の表示は,本件商標の登録出願時及 び登録査定時において,被告が店舗展開する「すしざんまい」チェーン店\nの名称として,需要者である一般消費者の間に広く認識され,被告の業務 に係る「すしを主とする飲食物の提供」を表示するものとして,著名であ ったこと(前記2(2)ア),2)本件商標と引用商標1の要部である「すしざ んまい」の文字部分及び引用商標2から,いずれも被告が店舗展開する「す しざんまい」チェーン店を想起し,その名称としての「すしざんまい」の 観念を生じる点で共通すること(前記ア(ウ)),3)本件商標の指定商品であ る「すし」と被告の業務に係る役務である「すしを主とする飲食物の提供」 は,需要者が一般消費者である点で共通し(前記2(1)ア),販売の対象とな る商品又は提供の対象となる商品がいずれも「すし」である点で共通する ことを総合考慮すると,本件商標をその指定商品の「すし」に使用すると きは,その取引者,需要者において,被告が店舗展開する「すしざんまい」 チェーン店の名称として著名な「すしざんまい」の表示を想起し,当該商 品を被告又は被告と緊密な営業上の関係又は同一の表\示による商品化事業 を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であるかのよ うに,その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。 したがって,本件商標は,引用商標1及び2との関係において,商標法 4条1項15号に該当するものと認められる。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(2) 原告の主張について
原告は,1)引用商標1及び2の指定役務「すしを主とする飲食物の提供」 にいう「すし」と本件商標の指定商品「すし」とは,握り寿司等3種類を除 き,「すし」の内容が一致せず,需要者が異なる,2)「すし」の販売にいう「す し」は,弁当と同じような用途であるのに対し,「すしを主とする飲食物の提 供」にいう「すし」の提供は,すし職人と会話を楽しむといった別の要素が あり,極めて人間的であり,しかも,魚の鮮度が勝負であり,鮮度が比較的 短時間で落ちる商品を鮮度の良い状態で提供していること,回転ずしや着席 スタイルのすし店等でも,テイクアウトは行われているが,全体のごく一部 であり,特に着席スタイルのすし店は鮮度にこだわり,テイクアウトは拒否 されるのは周知の事実であることからすると,「すし」と「すしを主とする飲 食物の提供」とは,その性質,用途又は目的において密接な関連性を有する とはいえない,3)原告の業態は,宅配寿司であり,ウェブサイト又は電話に よる注文を受けてから寿司を盛り,スピーディな配達をするというものであ るのに対し,被告の業態は,カウンター方式及び個室方式をとり,会食・接 待・結納などにも利用できる料亭をイメージした落ち着いた雰囲気の個室を 用意しており,テイクアウトはあくまで「お持ち帰り」としての利用であり, 原告の業態と被告の業態が相違するなどとして,本件商標の登録出願時及び 登録査定時において,本件商標をその指定商品「すし」に使用した場合,こ れに接する需要者が引用商標を想起,連想し,当該商品を被告あるいは被告 と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの ように,その出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないから,本 件商標が商標法4条1項15号に該当するものとはいえない旨主張する。 しかしながら,1)については,前記2(1)イで説示したとおり,本件商標の 指定商品「すし」と引用商標1及び2の指定役務「すしを主とする飲食物の 提供」とは,需要者が異なるものと認めることはできない。 2)については,「すしを主とする飲食物の提供」の提供の場所を原告が主張 するような着席スタイルのすし店に限定すべき合理性はない。 3)については,原告が主張する原告の業態と被告の業態の相違は,本件商 標をその指定商品「すし」に使用した場合,これに接する需要者が,当該商 品を被告又は被告と緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を 営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であるかのように,\nその出所について混同を生ずるおそれがあるとの前記(1)の判断を左右するも のではない。
◆判決本文
こちらは関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2021.04.21
令和1(行ケ)10159 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年4月15日 知的財産高等裁判所
前記2(1)イのとおり,引用発明は,医師等が観察して診断を行う診断用 画像モニタ装置と離れて,操作者が被検者に対してX線装置のコリメータ やTVカメラの調整等を行う際の被検者及び操作者のX線被爆を避ける ために,X線曝射しない状態でコリメータやカメラの操作ができ,簡単か つ安価で操作者の手元で表示することができるX線映像装置を提供することを目的とするものである。\nそして,引用文献1は,こうした課題を解決するために,医師等が観察 する診断用画像モニタ装置とは別に,1対の平行コリメータ位置マーカ2 4,24や円形コリメータ位置マーカ25,カメラ画像正立位置マーカ2 6の画像を,制御ユニット18の制御の下で,X線照射停止直前に撮像さ れ画像メモリ19に格納されたX線透視像を画像と重ねて操作用液晶デ ィスプレイ装置21に表示し,マーカ24,25,26上を指などで触れてドラッグすると,その位置情報が制御ユニット18に取り込まれて演算\nされて新たな表示位置が求められ,その位置へ各マーカが動いていくような表\示がされ,この入力情報に応じて制御ユニット18が指令をコリメータ12及びTVカメラ15へ出し,コリメータ12の遮蔽板の位置や方向 が変更され,TVカメラ15の回転角度が調整され,現実に動いた位置・ 方向の情報が制御ユニット18に返され,これに応じて制御ユニット18 が平行コリメータ位置マーカ24,24又は円形コリメータ位置マーカ2 5の表示位置を固定するとともに,表\示されたX線透視像23及びカメラ 画像正立位置マーカ26を回転させる(【0018】,【0019】)という 構成を開示している。このように,引用発明は,あくまで,医師等が観察して診断を行う診断用画像モニタ装置とは別に,X線被爆を避けるために,X線曝射しない状\n態で操作ができ,画像を操作者の手元で表示することができるX線映像装置を提供することを目的とするものであって,こうした技術的意義を有す\nる引用発明において,引用文献1には,操作者が医師等の術者が被検者を 見る方向と異なる方向から被検者を見ることにより,操作者が被検者を見 る方向と操作用画像表示装置に表\示される患部の方向とが一致しないと いう課題(課題B2)があるといった記載や示唆は一切ない。
イ この点につき,被告は,前記第3の2(1)のとおり,当業者であれば,課 題B2の存在を理解し,手術中に被検者の患部を表示する画像表\示装置に おいて,「操作者」が異なる方向から被検者に対向する場合,各々の被検者 を見る向き(視認方向)に一致させるという周知の課題(乙3,4)を参 照し,異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプ レイ21の画像の向きを,操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致 させるという課題を当然に把握し,引用発明に技術事項2を適用する動機 づけがある旨主張する。
しかし,当業者であれば,課題B2の存在を当然に理解するという点に ついては,これを裏付けるに足りる証拠の提出はなく,むしろ,原告が主 張するように,術者と操作者との力関係や役割の違いに照らせば,操作者 は,従前は,このような課題を具体的に意識することもなく,術者の指示 に基づきその所望する方向に画像を調整することに注力していたもので あるのに対して,本願発明は,その操作者の便宜に着目して,操作者の観 点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上 げたことに意義があるとの評価も十分に可能\である。
また,乙3には,「本発明の手術用顕微鏡システムでは,前記画像表示手段を複数備え,少なくとも一つの画像表\示手段で表示される画像の向きが\n変更可能であることが望ましい。このような構\成では,術者と助手とが向 き合って手術する時のように,撮像部分を異なる方向から見る場合におい ても,それぞれの見る方向に応じて画像の向きを変えることにより,撮像 部分を見るのと同じ向きの画像を表示することが可能\となり,より手際の よい手術が行えるようになる。」(【0007】),「本発明の手術用顕微鏡シ ステムは,・・・前記画像処理装置は,各電気光学撮像手段からの撮像信号に 基づいて,基準画像信号を生成して,基準画像を前記画像表示手段に表\示 させる基準画像生成部と,前記各撮像信号に基づいて,基準画像と上下ま たは左右が反転した反転画像信号を生成して,前記画像表示手段に表\示さ せる反転画像生成部とを備えることを特徴とする。」(【0008】)との記 載があるように,術者とそれを補助する術者が向き合って手術をするとき のように撮像部分を異なる方向から見る場合でも,画像表示手段で表\示さ れる画像の向きをそれぞれの見る方向に応じて変更する構成により,撮像部分を見るのと同じ向きの画像を表\示することが可能となり,より手際の\nよい手術が行えるようになるとの課題が示されているにとどまり,術者と X線撮影装置の操作者についてそのような課題があると開示するもので はない。
さらに,乙4には,「本実施例の装置の動作について,図を参照して説明 する。まず,図1において術者Aは第1モニタ4を見て,術者Bは第2モ ニタ7を見て手技を行っている。ここで術者Bは内視鏡2に対向している ので,内視鏡2の原画像をそのまま第2のモニタ7に表示すると,上下左右が逆の感覚で見えてしまう。このため,画像処理装置8にて,第2モニ\nタ7の画面のみを上下左右反転させた倒立像を映し出す。」(【0022】), 「本実施例では,第2モニタ7を倒立像にすることで,術者Bが上下左右 逆の感覚で手技を行うことがないので,スムーズに手技を行うことができ る。また,第1モニタ4及び第2モニタ7のいずれでも倒立像にできるの で,内視鏡2の向きや術者の位置が変わっても,容易に対応できる。」(【0 025】)との記載があるように,術者Aと術者Bがそれぞれ異なるモニタ を見て手技を行う場合において,術者Bが見ている第2のモニタ7に内視 鏡2の原画像を見てそのまま表示すると,上下左右が逆の感覚で見えてしまうという課題が示されているにとどまり,術者とX線撮影装置の操作者\nについてそのような課題があると開示するものではない。
そうすると,上記の乙3,4の各文献に記載された課題は,あくまで術 者と助手又は術者と術者がそれぞれ異なるモニタを見ることによって生 じる課題を指摘するにとどまり,術者とは異なる操作者が操作を行うとい う引用発明の場合において,操作者の便宜のために,操作者が見る患部の 向きの方向と,操作者が見る操作用液晶ディスプレイの患部の向きとを一 致させるという課題を示唆するものとはいえないから,当業者がこのよう な課題を当然に把握するともいえない。
(2) また,仮に,引用発明について,前記課題B2の存在を認識し,異なる方 向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ21の画像の 向きを,操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという課題を 把握して,操作用液晶ディスプレイ装置21に表示されるX線画像のみを回転させるという相違点の構\成とする動機づけがあると仮定しても,前記2(2) のとおり,技術事項2’は,HMDを装着し操作者を兼ねた術者が見るHM Dの画像表示部に表\示されるX線画像と実際の患者の患部の位置把握を容易 にするために,上記術者の床面上の位置情報に基づいて上記X線画像の回転 処理を行うものであるから,回転処理がされるX線画像はHMDの画像表示部であり(引用文献2の【0014】,【0020】,図14等),また,画像\n回転処理の基になる位置情報は,床面に設けられた感圧センサによるもので ある(引用文献2の【0022】)。
こうした技術事項2’の構成は,キャビネット43に設置された診断用画像モニタ17は術者である医師が使用し,台車41に設けられた操作用液晶\nディスプレイ装置21は撮像装置のセッティング等のために操作者が状況に 応じて自由に移動し,また台車41に様々な立ち位置を取ることができる引 用発明の具体的な構成と大きく異なるものであるから,引用発明と引用文献2に記載されたX線装置は同一の技術分野に属し,X線画像を表\示する装置を有する点で共通するとしても,HMDに表示されるX線画像の回転処理が行われるという技術事項のみを抽出して引用発明に適用する動機づけがある\nとはいえない。 さらに,技術事項2’は,操作者を兼ねた術者が装着したHMDに表示されるX線透視像を床面の位置情報に基づいて回転させるという構\成を有するものであるから,こうした構成を無視して,表\示されたX線画像のみを回転させるという技術事項のみを適用し,本願発明の相違点の構成に想到するとはいえない。\n
(3) 以上によれば,本願発明と引用発明との相違点は,本願発明は「前記X線 画像のうち,前記表示部に表\示されるX線画像のみを回転させる画像回転機 構を備え」ているのに対し,引用発明は,そのような特定がない点に尽きるが(本願発明における画像回転機構\自体については目新しいものとはいえない。),引用文献1には,「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見て操作する「操作者」の視認方向が「診断用画像モニタ装置17」を見る「術者」の「被検者」の視認方向と一致しないという課題(課題B2)について記載も示唆もなく,被告が提出した文献からは,手術中に被検者の患部を表示する画像表\示装置において,異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ21の画像の向きを,操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという課題があると認めるに足りないから,こうした課題があることを前提として,引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえず,また,本件審決の技術事項2の認定に誤りがあり,引用文献2に記載された事項(技術事項2’)から引用発明との相違点の構\成に想到するともいえないから,結局のところ,本願発明は,引用発明及び引用文献2に記載された技術事項2’に基づいて当業者であれば容易に想到し得たものとはいえず,これと異なる本件審決の判断は,その余の点につき判断するまでもな く,誤りである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.04.20
平成30(ワ)3789 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和3年2月9日 東京地方裁判所
ア 被告商品の売上高について
前記期間の被告商品の売上金額は,11億0573万1572円(消費 税相当額抜き)であった(乙34,弁論の全趣旨)。 もっとも,このうち2251万6179円は未収であり(乙35),結 局,被告商品が販売されて被告が利益を受けたものとはいえないから, 上記売上金額から控除すべきである。また,被告は被告商品の売上げに 係る消費税を納税しなければならないから,税抜金額を売上金額とする。 以上から,前記期間の被告商品の売上高は,別紙損害額の売上高欄記載 のとおり,10億8321万5393円であったと認められる。
・・・
エ 被告が受けた利益の額について
以上から,被告が前記期間に被告商品の販売により受けた利益の額は, 別紙損害額の限界利益欄記載のとおり,合計6億1192万6912円 となる。
(3) 推定覆滅事由について
ア 不正競争防止法5条2項による推定は,侵害者による侵害行為がなかっ たとしても侵害者が受けた利益を被侵害者が受けたとはいえない事情が 認められる場合には,覆滅されると解される。
イ 掲記の証拠によれば,次の各事実が認められる。 被告は,被告商品について,電子商取引サイト等において,本件品質 誤認表示によるオリゴ糖の純度に係る特徴のほか,オリゴ糖が1種類で\nはなく,複数の種類のオリゴ糖を配合していることを強調し,また,被 告商品の原材料が全て動植物に由来するものであり添加物がないことな どの特徴をも大きく取り上げ,妊婦や乳幼児等が摂取しても安全,安心 であるなどと広告宣伝していた。さらに,「実感力」などの言葉を使っ て,584人のアンケート結果によれば,「『毎日すっきり!』実感で きました!」というモニターが76.1%であるなど,多くの者が何ら かの形で便通の効果を実感しているとして,「満足率97.2%」であ るという記載をするなどしていた。(甲10〜16)
被告は,被告商品の購入者に対して,商品を使用した感想,被告の客 対応,他社との違い等を自由に記載する欄を設けたアンケートの葉書を 交付していたところ,それらを記載して被告に返送した回答者928人 のうち,被告商品が「オリゴ糖100%」であることについて言及した ものは6人であった。回答者には,多くの者が便通が改善したことを述 べていた。(乙41,42) オリゴ糖類食品は,オリゴ糖などを組み合わせ,配合することによっ て製造されており,主力製造業者及びその販売する商品としては,原告 商品及び被告商品のほか,塩水港精糖の「オリゴのおかげ」,加藤美蜂 園本舗の「北海道てんさいオリゴ」,日本オリゴの「日本オリゴのフラ クトオリゴ糖」,株式会社明治フードマテリアの「メイオリゴ」,Hプ ラスBライフサイエンスの「オリゴワン」,伊藤忠製糖の「クルルのお いしいオリゴ糖オリゴDEクッキング」,井藤漢方製薬の「乳酸菌オリ ゴ糖」,梅屋ハネーの「梅屋イソマルトオリゴ糖」,正栄の「スッキリ\nオリゴ糖」,ユウキ製薬の「活き活きオリゴ糖」,オリヒロの「オリゴ 糖シロップ」,ビオネの「ビオネ・ビートオリゴ」,日本甜菜製糖の 「ラフィノース100」などがある。これらのオリゴ糖類食品市場にお ける平成25年度から平成28年度及び平成30年度の原告商品の占有 率は,22.8%から26.9%であり,平均約24.4%であった。 上記のオリゴ糖類食品には,その内容や形態,販売態様において様々 なものがあり,例えば,塩水港精糖の販売する「オリゴのおかげ」は, 個包装された顆粒状のもの,シロップ形態のものなどがあり,加藤美蜂 園本舗の販売する「北海道てんさいオリゴ」は天然の甘味料であること をうたった商品であるが,同社は他にシロップ形態の商品も販売してお り,株式会社明治フードマテリアの販売する「メイオリゴ」には,液体, 粉末,顆粒等の各形態が存在する。もっとも,いずれについても,需要 者である一般消費者が,日常の食生活の中で健康に有用な効果作用を発 揮するオリゴ糖を簡便に摂取できる点に商品の意義が認められており, 需要者は,これらの多数の各商品の中から,各商品の上記の点以外の様 々な特徴を勘案して選択,購入しているといえる。 (本項につき,甲34,41,乙54,59,61(なお,乙59の5 によれば,平成29年度の原告商品の市場占有率42.3%であるとさ れているが,その前後の年度の市場占有率と大きな差があること,平成 29年度の市場規模が47億4000万円である一方,同年前後の原告 商品の売上高は概ね年9億7000万円から10億9000万円程度で あること等に照らすと,上記の同年度の市場占有率を直ちに信用するこ とはできない。))
ウ 被告は,被告商品について,本件品質誤認表示によるオリゴ糖の純度に\n係る特徴のほか,複数の種類のオリゴ糖を配合していること,被告商品の 原材料が全て動植物に由来するものであり添加物がないことなどの特徴を も大きく取り上げ,妊婦や乳幼児等が摂取しても安全,安心であるなど, 被告商品の魅力を掲げて広告宣伝していた。そして,被告商品の購入者が 自由に記載したアンケート結果によっても,オリゴ糖の純度に特に着目し て被告商品を購入した需要者が多かったことが直ちに認められるものとま ではいえない(前記イ )。また,オリゴ糖類食品には様々な形態のもの が存在し,原告商品と被告商品が似た形態であるのに対し,これらと異な る形態のものが多数あるのであるが,形態にかかわらず,これらの商品は, 基本的に需要者である一般消費者が,オリゴ糖を簡便に摂取できる点に商 品の意義が認められている。そうすると,需要者は,多数の各商品の中か ら,各商品の様々な特徴を勘案して選択,購入することもあるといえ原告 商品以外のオリゴ糖類商品も原告商品及び被告商品と市場において競合す るといえるものである。このようなオリゴ糖類食品市場における原告商品 )。
そして,本件では品質を誤認させるような表示が問題となっていて,被\n告商品の出所を原告と誤認するおそれが問題となっているわけではない ところ,被告商品を販売するウェブサイトには,被告が強く関与するも の(前記第2の1(2)ケ)に加えて,アマゾン,楽天,ヤフーなどが運営 するサイトもあり,これらにおいて原告商品について触れられていると は認められない(甲10,15,32)。 さらに,被告は,平成28年11月までは自社の電子商取引サイト等も 含めて本件品質誤認表示をしていたが,同月以降,自社の電子商取引サイ\nトからはその表示を削除し,平成30年2月には,アフィリエーターらに\n対し,「オリゴ糖100%使用」等の表示をしないように求めた(前記1\n(2)エ)。
これらを考慮すると,被告の本件品質誤認表示による被告商品の販売数\n量の増加と,他のオリゴ糖類食品の販売数量の低下,さらには,原告商 品の販売数量の低下との間には,それほど強い相関関係が成り立つとは いえず,上記の各事情を総合考慮すれば,被告の本件品質誤認表示がな\nかったとしても被告が受けた利益を原告が受けたとはいえない事情が相 当程度認められ,被告が受けた利益の額の97%について,原告が受け た損害の額であるとの推定が覆滅されるとするのが相当である。 以上から,上記推定覆滅後の額は,別紙損害額の推定覆滅後の金額欄記 載のとおり,1835万7803円となる。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2021.04.20
令和2(行ケ)10035 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月29日 知的財産高等裁判所
原告は,本件審決が,相違点1ないし3について,「再変動」(本願発明の 「単位演出」に相当。)の契機となる前回の「変動(再変動)」に基づく仮停 止について,初回の変動においてチャンス目Aが仮停止し,2回目の変動(再 変動)においてチャンス目Bが仮停止するというように,仮停止させるチャ ンス目を,段階的に大当り信頼度が高いものとしていく引用発明において, 「再変動」の契機となる,前回の「変動(再変動)」に基づく所定のチャンス 目により仮停止させることを節目として,引用文献2に記載の技術である, 遊技図柄の確変図柄の割合を変化させるという演出である「図柄群変化演出」 を適用することにより,所定のチャンス目が仮停止した後の「再変動」にお いて,当該「図柄群変化演出」により遊技図柄の確変図柄の割合が変化した 後の遊技図柄を用いた変動を実行するとともに,当該「図柄群変化演出」に おいて,遊技の興趣を向上させるために,遊技図柄の確変図柄の割合を変化 させる態様として,上記周知技術の態様を採用して,非確変図柄を確変図柄 に変更することにより,相違点1ないし3に係る本願発明の構成とすること\nは,当業者が容易になし得たものである旨判断したが,引用発明から出発し て,相違点1ないし3に係る本願発明の構成に想到することは,当業者にと\nって容易であったということはできない旨主張するので,以下において判断 する。
ア(ア) 引用文献1には,所定の入賞領域(始動入賞口)に遊技媒体が入賞す る(始動条件が成立する)と識別情報を可変表示(「変動」)可能\な可変 表示装置が設けられ,識別情報の可変表\示の表示結果が特定表\示結果(大 当り図柄)となった場合に遊技者にとって有利な特定遊技状態(大当り 遊技状態)に制御可能に構\成された従来の遊技機において,可変表示が\n実行されるより前に複数回の可変表示に渡って予\告演出を実行し,連続 した予告演出の態様の組合せにより,表\示結果を予告するものも提案さ\nれているが,遊技に有利状態となる可能性が低い予\告演出が実行された 場合には,遊技者が落胆してしまい,遊技の興趣が低下してしまうおそ れがあったという問題があったため,「本発明」の課題は,上記実情に鑑 み,遊技の興趣を向上させた遊技機を提供することを目的とすることに ある旨の開示がある(【0002】,【0003】,【0005】,【0006】)。
(イ) 次に,引用発明の遊技機は,1)「特図ゲームの第1開始条件と第2開 始条件のいずれか一方が1回成立したことに対応して,飾り図柄の可変 表示が開始されてから可変表\示結果となる確定飾り図柄が導出表示さ\nれるまでに,「左」,「中」,「右」の飾り図柄表示エリア5L,5C,5R\nにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後,全部の飾り図柄\n表示エリア5L,5C,5Rにて飾り図柄を再び変動させる擬似連の可\n変表示演出であって,擬似連の可変表\示演出(「再変動」)は1回の変動 において最大3回まで実行可能になっていて,再変動の回数が多ければ\n多いほど,大当り信頼度が高くなるように変動パターンが決定され,決 定された変動パターンなどに基づいて演出制御パターンとしての特図 変動時演出制御パターンをセットし,演出制御パターンに含まれる,演 出装置における演出動作の制御内容を示し,演出制御の実行を指定する 表示制御データ#1〜表\示制御データ#n(nは任意の整数)の内容に 従って,画像表示装置5の制御を進行させる演出制御用CPU120と\nを備え」(構成b),2)「可変表示結果が「リーチハズレ」,「大当り」の\nいずれであるかによって擬似連予告演出が実行される割合,擬似連予\告 パターンの決定割合が異なり,具体的には,可変表示結果が「大当り」\nである場合には,「リーチハズレ」である場合よりも,擬似連予告演出が\n実行される割合が高くなっていて,チャンス目Aが停止する擬似連予告\nパターンYP1−1の擬似連予告演出が実行された場合よりも,チャン\nス目Bが停止する擬似連予告パターンYP1−2の擬似連予\告演出が 実行された場合の方が,可変表示結果が「大当り」となる割合である大\n当り信頼度が高くなっていて,チャンス目の種別により大当り信頼度が 異なるものとされ,4回の変動及び再変動(擬似連3回の変動パターン) に渡って実行される擬似連予告演出の擬似連予\告パターンとして,初回 の変動においてチャンス目Aが仮停止し,2回目の変動(再変動)にお いてチャンス目Bが仮停止し,3回目の変動(再変動)において,背景 画像が特殊な背景画像に変化し,4回目の変動(再変動)においては継 続して特殊な背景画像において変動が実行される擬似連予告パターン\nを設けることで,大当り信頼度が段階的にステップアップしていくよう な演出を行」い(構成c),3)「所定の通常大当り組合せとなる確定飾り 図柄が停止表示されると,通常開放大当り状態に制御され,その終了後\nには,時短制御が行われる一方,所定の確変大当り組合せとなる確定飾 り図柄が停止表示されると,通常開放大当り状態に制御され,その終了\n後には,時短制御とともに確変制御が行われ,確変制御が行われると, 各回の特図ゲームにおいて可変表示結果が「大当り」となる確率は,通\n常状態に比べて高くなり,確変制御は,大当り遊技状態の終了後に可変 表示結果が「大当り」となって再び大当り遊技状態に制御されるという\n条件が成立したときに終了する」(構成e)との構\成を有している。 引用発明は,構成cのとおり,疑似連予\告演出で仮停止するチャンス 目の種別(チャンス目A又はB)及び疑似連予告演出の回数と背景画像\nの変化とからなる擬似連予告パターンを設けることによって,大当り信\n頼度が段階的にステップアップしていくような演出を行う構成のもの\nであることが認められる。
そして,引用文献1には,チャンス目に関し,「チャンス目Aは,図2 1(A)に示すように,左図柄と中図柄が同じ数字であり,右図柄のみ が1つずれた数字の組合せとなっている。また,先読み予告パターンS\nYP1−2に基づく停止図柄予告では,連続演出用のチャンス目として,\n図21(B)に示すチャンス目CB1〜CB6(チャンス目B)のいず れかが停止する。チャンス目Bは,図21(B)に示すように,並び数 字の組合せとなっている。この実施の形態では,後述するように,チャ ンス目Aが停止する停止図柄予告が実行された場合よりも,チャンス目\nBが停止する停止図柄予告が実行された場合の方が,大当りとなる可能\ 性(大当り信頼度)が高くなっている。このようにすることで,停止図 柄予告が実行されるときに,いずれのチャンス目が停止したかに遊技者\nを注目させることができ,遊技の興趣が向上する。」(【0247】),「ま た,図35(B)に示す決定割合では,チャンス目Aが停止する擬似連 予告パターンYP1−1の擬似連予\告演出が実行された場合よりも,チ ャンス目Bが停止する擬似連予告パターンYP1−2の擬似連予\告演出 が実行された場合の方が,可変表示結果が「大当り」となる割合(大当\nり信頼度)が高くなっている。このように,チャンス目の種別により大 当り信頼度が異なるので,遊技者が停止図柄に注目するようになり,遊 技の興趣が向上する。」(【0370】)との記載がある。上記記載から, 「チャンス目」(チャンス目A及びB)は,「飾り図柄」を構成する個々\nの数字ではなく,「数字の組合せ」であり,「数字の組合せ」に着目して 可変表示結果が「大当り」となる割合(大当り信頼度)に差を設けてい\nることを理解できる。
・・・
イ(ア) 引用文献2には,1)複数種類の遊技図柄を変動表示装置において変\n動表示させることで変動表\示遊技を行う従来の遊技機においては,「リー チ状態」が発生した場合,例えば,遊技者の大当たり状態の発生に対す る期待感を高めて,遊技の興趣を盛り上げるために,最後に停止状態と なる変動表示部における遊技図柄の変動表\示速度を変化させたり,変動 表示部に表\示される遊技図柄の背景領域を利用してキャラクタ等による 演出表示を行ったりするのが一般的であるが,既に在り来たりのもので\nあり,それらの演出表示だけでは遊技者は遊技の興趣を得難くなってお\nり,また,未だ変動表示中の変動表\示部において変動表示される遊技図\n柄の中で特定の組合せ態様を成立し得ない遊技図柄の数を減少させて, 特定の組合せ態様が成立し易いような状態を演出表示することにより,\n遊技者の大当たり状態の発生に対する期待感を高めている遊技機もある が,遊技図柄の数を減少させた状態で行われる変動表示の速度が高速で\nあると,遊技者が遊技図柄の数が減少していることを把握できないまま 遊技を終了してしまうおそれがあるため,変動表示の速度を低速にする\nのが一般的であるが,その場合には,遊技自体にスピード感がなくなり, 変化に乏しい面白みのないものとなり,遊技の興趣を得難いという問題 点があったことから,遊技者の遊技に対する興趣を高める上で斬新な変 動表示を行う遊技機が求められており,2)「本発明」の課題は,上記実 情に鑑み,遊技者の遊技に対する興趣を高めることが可能な遊技機を提\n供することを目的とすることにある旨の開示がある(【0002】ないし 【0004】)。
・・・
ウ 以上を前提に検討するに,前記ア及びイの認定事実によれば,引用発明と 引用文献2に記載の技術は,遊技の興趣の向上という課題が共通し,1回の 変動中に複数段階で演出態様を変化させるという共通の機能を有している\nものと認められるが,一方で,引用発明と引用文献2に記載の技術は,遊技 の興趣の向上のために着目する観点が相違すること(前記イ(イ)),引用発 明の「飾り図柄」は,「基本的態様を示す基本要素部」と「第一属性および 第二属性のいずれが設定されているかを示す属性要素部」の二つの要素部 を有する「識別図柄」であるとはいえず,引用発明の「飾り図柄」のうち の「確変図柄」は,本願発明の「第一属性が設定された識別図柄」に相当 するものではなく,引用発明の「飾り図柄」のうちの「非確変図柄」は, 本願発明の「第二属性が設定された識別図柄」に相当するものではないこ と(前記(3)イ)に鑑みると,引用文献1及び2に接した当業者が,数字の 組合せからなるチャンス目の種別(チャンス目A又はB)及び疑似連予告\n演出の回数と背景画像の変化に着目し,この観点から,大当り信頼度が段 階的にステップアップしていくような演出を行う引用発明において,遊技 の興趣の向上のために,「一連の遊技図柄」に含まれる確変図柄の割合の大 きさに着目する引用文献2に記載の技術を適用して遊技図柄の確変図柄の 割合を変化させる構成とする動機付けがあるものと認めることはできな\nいし,引用発明に引用文献2に記載の技術及び本件周知技術を適用する動 機付けがあるものと認めることもできない。
また,仮に引用発明に引用文献2に記載の技術及び本件周知技術を適用 しようとした場合に,引用発明において相違点1ないし3に係る本願発明 の各構成をそれぞれどのように備えることになるのかを具体的に想到す\nることは,当業者にとって容易であるということはできない。 そうすると,本件審決の相違点1ないし3の容易想到性に関する前記判 断のうち,「当該「図柄群変化演出」において,遊技の興趣を向上させるた めに,遊技図柄の確変図柄の割合を変化させる態様として,上記周知技術 の態様を採用して,非確変図柄を確変図柄に変更することにより,相違点 1ないし3に係る本願発明の構成とすることは,当業者が容易になし得た」\nとの部分は,論理付けが不十分であって,採用することができないから,\n本件審決における相違点1ないし3の容易想到性の判断には誤りがある。
エ これに対し被告は,1)引用発明と引用文献2に記載の技術は,遊技者に 段階的に有利となる期待感を高めることで興趣を向上させるという点で 課題が共通し,1回の変動中に複数段階に演出態様を変化させるという点 で作用・機能も共通すること,2)擬似連変動を行うパチンコ機において, 図柄や画像の段階的な変化を仮停止後の再変動を契機に行うことは,広く 一般に周知の技術であること,3)引用文献2の【0074】の「前記一連 の遊技図柄に含まれる確変図柄の割合を変更させることが可能であれば\n如何なる方法であっても良い。」との記載は,引用文献2に記載の技術にお いて,「図柄群変化演出」により遊技図柄(識別図柄)の確変図柄の割合を 変化させる方法について,実施例に例示した形態以外の他の周知の態様に 置換することを許容していることを示唆するものであり,当該他の周知の 方法の具体例として,本件周知技術である「通常図柄を確変図柄扱いにし ていく図柄変化演出」が存在することに鑑みると,引用文献1及び2に接 した当業者は,引用発明における「1回の変動」における「擬似連」とし てその各「仮停止」した後の「再変動」において,「図柄群変化演出」によ り遊技図柄の確変図柄の割合が変化した後の遊技図柄を用いた変動を実 行する構成とし,当該「図柄群変化演出」において,遊技の興趣を向上さ\nせるために,遊技図柄の確変図柄の割合を変化させる態様として,本件周 知技術の態様(「変化前に表示装置において変動表\示されていた識別図柄 群には含まれていなかった新規の識別図柄となるように設定された図柄 群変化演出を,変化前の非確変図柄を消して替わりに新たな確変図柄を出 現させること」)を適用して,相違点1ないし3に係る本願発明の構成とす\nることを容易になし得たものである旨主張する。
しかしながら,前記ウで説示したとおり,引用発明と引用文献2に記載の 技術は,遊技の興趣の向上のために着目する観点が,引用発明においては, 数字の組合せからなるチャンス目の種別(チャンス目A又はB)及び疑似 連予告演出の回数と背景画像の変化であるのに対し,引用文献2に記載の\n技術は,「一連の遊技図柄」に含まれる「確変図柄の割合」の大きさである点 において相違すること,引用発明の「飾り図柄」は,「基本的態様を示す基 本要素部」と「第一属性および第二属性のいずれが設定されているかを示 す属性要素部」の二つの要素部を有する「識別図柄」であるとはいえず, 引用発明の「飾り図柄」のうちの「確変図柄」は,本願発明の「第一属性 が設定された識別図柄」に相当するものではなく,引用発明の「飾り図柄」 のうちの「非確変図柄」は,本願発明の「第二属性が設定された識別図柄」 に相当するものではないことに照らすと,上記1)及び2)の点を考慮しても, 引用文献1及び2に接した当業者が,引用発明において,遊技の興趣の向 上のために,引用文献2に記載の技術及び本件周知技術を適用して遊技図柄 の確変図柄の割合を変化させる構成とする動機付けがあるものと認める\nことはできない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.04.20
令和2(行ケ)10133 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年3月30日 知的財産高等裁判所
ア 原告は,漢字表記の「宇治茶」は,「京都府宇治地方から産出する茶」\nという意味を持つほか,本件地域団体商標の存在により,商品に付された 場合,原告の業務に係る商品であることを示す出所識別機能を有すると主\n張する。 しかし,商標法7条の2は,地域名と商品名からなる商標は自他識別力 を有しないため,原則として同法3条1項3号又は6号に該当すると解さ れることから,一定の要件を備えた場合に,「第3条の規定(同条第1項 1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず,」地域団体商標の商 標登録を受けることができるとしているものであり,地域団体商標の登録 を受けたからといって,当然に同法3条1項3号に該当しない(出所識別 機能を有する)ことになるわけではないことは明らかである。\n
イ 原告は,欧文字表記の「Ujicha」は商品の産地等を「普通に用い\nられる方法で表示するもの」でないと主張する。\n しかし,前記のとおり,多数のウェブサイトにおいて,本願の指定商品 又は関連する商品に関して,「UJICHA」,「Ujicha」,「U ji cha」,「UJI−CHA」,「Uji」,「“Uji”」,「U JI」といった文字が包装に使用されていることが認められるし,さらに, 国際化の進展による外国人需要者の増加や,我が国におけるローマ字の普 及状況も考慮すれば,欧文字表記は,取引者において一般的に使用する範\n囲に属するものであって「普通に用いられる方法」に当たるというべきで あるから,原告の主張は採用することができない。
ウ 原告は,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとすれば,同法26 条1項2号により,本件地域団体商標に係る商標権の効力(同法37条1 号に規定する排他権)は,「Ujicha」の商標に及ばないこととなり, 地域団体商標制度を設けた趣旨が没却されると主張する。 しかし,地域団体商標の登録を受けたからといって,当然に当該商標が 同法3条1項3号に該当しないことになるわけではないことは前記アのと おりであるし,本件地域団体商標に係る効力がそれとは異なる「Ujic ha」の商標に及ばないからといって,地域団体商標制度を設けた趣旨が 没却されるとは到底いえないから,原告の主張は採用することができない。
ア 原告は,本願商標の使用の事実を立証するものとして,原告の組合員(甲 4)である株式会社伊藤久右衛門(以下「伊藤久右衛門」という。)の使 用に係る甲1,2と,矢野園の使用に係る甲5,6を提出する。 イ まず伊藤久右衛門の使用について判断すると,同社は,かぶせ茶,煎茶, ほうじ茶についてそれぞれティーバッグを販売しているところ(甲1), 甲2は,そのうちかぶせ茶の包装について,中央上部に大きく「かぶせ茶」 の横書きの記載があり,その下に「急須用ティーバッグ」,さらにその下 に「UJICHA TEA BAG」と横書きで記載されており,煎茶や ほうじ茶についても中央上部にそれぞれ茶の種類が記載されているもの と推認される。 そうすると,本願商標「Ujicha」と甲2の表示は,その文字数や\n記載ぶりが大きく異なるものというべきであるから,両者が実質的に同一 であると認めることはできない。 よって,伊藤久右衛門による甲2の表示については,商標法3条2項に\nいう使用がされたものとは認められない。
ウ 次に,矢野園の使用については,同社は,その商品の包装の中央部に, 煎茶については「産地直送 宇治蔵出し煎茶」の,玉露については「産地 直送 宇治蔵出し玉露」の大きな縦書きの記載をし,その下部に横書きで 「UJICHA」の記載をしているが,同包装には,原告との関連性を示 す記載はない(甲5,6)。 このような記載では,原告固有の商標として表示しているのか,単なる\n産地表示や品質表\示として表示しているのかが明らかとはいえず,当該表\ 示に接する需要者が,本願商標について,原告又はその構成員固有の出所\n識別標識であると直ちに認識,理解するとはいえない。
エ 甲7,8によれば,矢野園が包装に「UJICHA」の記載をした煎茶 について,平成20年に東京に1万本,平成21年に金沢に1万本売り上 げたことが認められるが,販売期間,累計の販売数量,売上金額,販売地 域を裏付ける証拠はなく,原告の他の組合員に関しては,本願商標を付し た指定商品の売上に関する証拠は提出されていないし,原告又はその組合 員による本願商標を付した指定商品の市場占有率を裏付ける証拠もない。 他方で,本願の指定商品又は関連する商品に関して,原告の組合員以外の ウェブサイトにおいて,「UJICHA」(乙7,8,12,13),「U jicha」(乙14),「Uji cha」(乙9),「UJI−CH A」(乙10,11)といった「宇治茶」の欧文字表記を包装に表\示した 商品が掲載されている。
オ 以上を前提に検討すると,本願商標に通じる「宇治茶」は,前記1の とおり,「京都府宇治地方で産出する茶」を指称する語として広く受け入 れられ,もともと特定の主体と結びつき難いものである一方,原告の組合 員である伊藤久右衛門による甲2の表示については,そもそも商標法3条\n2項にいう使用がされたものとは認められないし,矢野園による本願商標 の使用態様も,原告固有の商標として表示しているのか,単なる産地表\示 や品質表示として表\示しているのかが明らかとはいえない態様のもので ある。また,原告の組合員による本願商標を付した指定商品の販売期間, 販売数量,累計の売上金額,販売地域,市場占有率等については,矢野園 による平成20年及び平成21年の散発的な販売実績を除き,これを裏付 ける証拠はなく,結局,原告又はその構成員による本願商標の使用状況は\n明らかでない。さらに,原告の組合員以外の者が,「UJICHA」,「U jicha」,「Uji cha」,「UJI−CHA」といった「宇治 茶」の欧文字表記を包装に表\示した商品を販売しているという実情があ る。
これらを総合すると,本願商標が,原告又はその構成員により使用をさ\nれた結果,需要者が原告又はその構成員の業務に係る商品であると全国的\nに認識されているとはいえず,本願商標は商標法3条2項の要件を具備し ないというべきことは明らかである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2021.04.16
令和2(行ケ)10085 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月9日 知的財産高等裁判所
前記第2の4のとおり,平成24年10月1日より前の国際特許出願 である本願には,特許協力条約の「引用による補充」に関する規定は適用されない から,本願について「引用による補充」によって本件欠落部分を含んだ出願の出願 日が本願の国際出願日である平成23年8月25日になることはなく,本件欠落部 分を受理官庁に提出した同年9月29日となるが,本件欠落部分を含まない場合に は,本願の出願日が同年8月25日となる。 そして,本願に本件欠落部分を含まないようにする手段として施行規則38条の 2の2第4項の手続が定められているのであるから,同手続によることなく本件欠 落部分を含まないようにすることはできないものと解される。 前記1のとおり,原告は,施行規則38条の2の2第1項に基づいて本件通知を 受けたにもかかわらず,本件指定期間内に本件欠落部分が本願に含まれないものと する旨の同条4項の請求をしなかったのであるから,本願の出願日が平成23年9 月29日となることは明らかである。
イ 前記1のとおり,本願発明と同一の発明である引用発明が掲載された本 件学術誌が,本願の出願日の前の平成23年9月11日に公開されたのであるから, 本願発明には,新規性が認められない。
(2) 原告は,1)出願日が発明の公知日よりも後になることを知らずに,論文発 表等により発明を公知にしてしまった場合は,錯誤に陥って発明を公知にしてしまったのであるから,改正前特許法30条2項の「意に反して」に該当する,2)改正 前特許法30条2項の「意に反して」とは,権利者が発明を公開した後に,権利者 の意に反して出願日が繰り下がり,当該発明が遡及的に出願日よりも前の公知発明 となってしまった場合も含むとして,本願においては,同項が適用されるべきであ ると主張する。 しかし,本件において,原告は,引用発明が掲載された本件学術誌が公開された ことを認識していたことは明らかである。原告は,当初の出願後に「引用による補 充」を求めた行為によって出願日が繰り下がることを認識し得たのであり,また, 改正前特許法30条4項に規定する手続を,特許法184条の14に規定する期間 内に行うことも可能であったといえる。したがって,本件においては,改正前特許法30条2項の「意に反して」には当たらず,同項は適用されないというべきである。\nこの点について,原告は,出願日が繰り下がることがあることを知らなかったと 主張するが,それは日本の特許法についての知識が乏しかったということにすぎず, 上記判断を左右するものではない。
(3) 原告は,本件通知によって出願日が繰り下がる認定がされた日は平成25 年9月24日であり,この時点では既に「国内処理基準時」から30日が経過して いるから,原告が改正前特許法30条4項に規定する手続を行うことは不可能であると主張する。\nしかし,原告は,米国特許商標庁に対し,平成23年9月29日に,本件欠落部 分につき「引用により補充」を求める書面を提出しているのであるから,この時点 で,将来,施行規則38条の2の2第4項の請求をしない限り,本願の国際出願日 が平成23年9月29日となり,本件論文が本願の国際出願日前に公開されたこと になることを認識し得たものである。したがって,原告は,国内処理基準時(特許 法184条の4第6項)から30日以内(特許法184条の14,特許法施行規則 38条の6の3)に,改正前特許法30条1項の適用を受けることができる発明で あることを証明する書面を特許庁長官に提出することができたものということがで きる。 よって,原告の上記主張は理由がない。
(4) 以上より,取消事由1は認められない。
3 取消事由2(本願の出願日の認定の誤り)について
(1) 前記2(1)アのとおり,本願の国際出願日は,平成23年9月29日であ る。
(2) 原告は,特許庁長官に提出した翻訳文には,本件欠落部分が含まれていな かったから,本願の明細書には本件欠落部分が含まれていないとみなされ,また, 特許法184条の6第2項により,本件翻訳文は,願書に添付して提出した明細書 とみなされるから,本件欠落部分は本願の明細書の範囲外となっていると主張する。 しかし,前記2(1)アのとおり,本願の国際出願日は平成23年9月29日であり, このことは,特許法184条の4第1項に基づき指定官庁である特許庁長官に提出 した本件翻訳文に本件欠陥部分の翻訳が含まれていたか否かや,本件翻訳文が特許 法36条2項の明細書とみなされ(特許法184条の6第2項),外国語特許出願に 係る明細書等について補正できる範囲は,翻訳文の範囲に限定されている(特許法 184条の12第2項)ことで影響を受けるものではない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3) 原告は,本件通知には,本願について「引用による補充」がなかったとする 場合には,本件指定期間内に条約規則に基づく請求書に所定の事項を記載して提出 するとともに,「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提 出してほしいことが記載されているが,本件通知の発送よりも前に,手続補正によ り削除すべき本件欠落部分が明細書に存在しないことになるから,本件通知に応答 して,「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出するこ とは不可能であり,「引用による補充」がされる前の明細書の全文を手続補正書により提出することを求める本件通知は法律に基づいた処分ではなく,重大かつ明白な瑕疵があると主張する。\nしかし,本件通知の文書に上記の記載があるからといって,本願の国際出願日の 認定が左右される理由はない。
(4) 原告は,翻訳文からあえて膨大な量の本件欠落部分を除いているのである から,本件翻訳文の提出をしたことにより,本件欠落部分が本願に含まれないもの とする旨の請求をする意思を持っていることが客観的に明らかであるところ,原告 は,本件翻訳文の提出により,本願に「引用による補充」がなかったとする黙示的 な意思表示をしており,同意思表\示は,施行規則38条の2の2第4項の請求に当 たるから,本件通知には重大かつ明白な瑕疵があるとともに,本件通知に対する応 答があったとみなされるべきであると主張する。 しかし,施行規則38条の2の2第4項は,特許庁長官が,認定された国際出願 日を通知する際に指定した期間内に,条約規則20.5(c)の規定によりその国際特 許出願に含まれることとなった明細書等が当該国際特許出願に含まれないものとす る旨の請求をすることができる旨を規定しており,本件通知前にした本件翻訳文の 提出行為が,上記の請求に当たらないことは明らかである。このことは,本件欠落 部分の分量が70頁であり,一方,本願の当初の明細書の分量が22頁であること によって左右されるものではない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2021.04.16
令和2(行ケ)10127 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年3月25日 知的財産高等裁判所
(ア) 本件指定商品における「工楽松右衛門の創製した帆布」の意義につい て,まず検討する。
前記(1)エで認定した各文献の記載によると,播州高砂の船頭であった工樂松右 衛門は,江戸時代後期の天明年間に,従来使われていた刺し帆より耐久性や強度な どに優れる織り帆を発明し,それが「松右衛門帆」として全国に伝播し,明治時代 頃まで帆船の帆などとして広く利用されていたものと認められる。 もっとも,前記(1)エの各文献の記載にあるとおり,現代において帆船が用いられ なくなったことに伴い,「松右衛門帆」は急速に姿を消していったものと認められ, B論文(甲7)の表にあるとおり,現代においては,残存する「松右衛門帆」も限\nられたものとなっていたと認められる。そして,前記(1)エの各文献等の記載や前記 (1)ウ(ア)のとおり,被告による「松右衛門帆」の復元に当たって,D教授が改めて 調査を行っていることも考え併せると,被告が,平成22年頃から「松右衛門帆」 を復元したとする本件布地を用いた商品の製造販売を始めるまでの間,「松右衛門 帆」が,具体的にどのようなものであるのかについて,B教授のような一部の専門 家以外の者には,その詳細は不明なものとなっていて,本件指定商品の取引者,需 要者たる一般人が,容易に調査できる範囲の資料から得られる「松右衛門帆」につ いての情報は,前記(1)エ(ア)の各辞典に記載されていた「太い綿糸で織られた幅広 の厚手の帆布」程度のものになっていたと認められる。 このような状況において,前記(1)ウ(ア),(イ)のとおり,被告は,D教授の協力を 得て,神戸大学海事博物館に所蔵されていた,原告らの実父で,帆船について研究 をしていたCによって寄贈された「松右ヱ門帆」という資料名の布の調査に基づい て,1)現在,一般に流通している帆布と異なり,2本の単糸を引き揃えにしている 点や2)緯糸が経糸より3倍太くなっていて,極端に太い点などの特徴を有する布地 (本件布地)による,かばん等の商品の製造販売を始めた。 そして,前記(1)ウ(ウ)認定の被告や御影屋による広告宣伝活動や同エ(イ)f以降 及び同(ウ)の第三者による文献等の記載から分かるとおり,平成22年頃以降から 要証期間中にかけて,被告や御影屋が「松右衛門帆」を復元したとする本件布地を 用いた商品の製造販売を開始して広告宣伝活動を行うことで,「松右衛門帆」とは, 被告が復元した上記1),2)のような特徴を持つ本件布地を指すものであるという認 識が,取引者,需要者の間に広まっていたものと認められる。
そうすると,遅くとも,本件商標を付した本件かばん2が,一般消費者に販売さ れ,平成30年2月5日に納品された時点で,本件指定商品の取引者,需要者は, 「松右衛門帆」,すなわち,「工楽松右衛門の創製した帆布」とは,本件布地のよう な「太い木綿糸を用い,太さの違う経糸と緯糸を2本引き揃えて織った厚く丈夫な 布地」(前記(1)ウ(ア))であると認識していたものと認められる。
(イ) 原告らは,1)本件指定商品中の「工楽松右衛門の創製した帆布」とは,
「天明年間に播州高砂に実在した船頭である工樂松右衛門がはじめてつくりだした 帆布」を意味しており,「松右衛門帆」は,「工楽松右衛門の創製した帆布」の上位 概念であるから,「松右衛門帆」から「工楽松右衛門の創製した帆布」の意義を解釈・ 認定するのは誤りである,2)布の耳部(両端)1寸ほどについては縦糸1本横糸2 本で織り,それ以外の部分については縦糸2本横糸2本で織っている(特徴1)),幅 の長さは2尺5寸(約75センチ)ほどのものである(特徴2))という二つの特徴 を備えないと,「工楽松右衛門の創製した帆布」とはいえない,3)神戸大学海事博物 館所蔵の帆布はその出自が不明である上,耳部が失われているから,「工楽松右衛門 の創製した帆布」とはいえない,4)工樂松右衛門が創製した当時の「松右衛門帆」 に使われていた糸は2.2番手相当であり(甲68),神戸大学海事博物館に所蔵さ れていた帆布や本件布地とは糸の太さが異なるし,織布の密度も異なる上,本件布 地の織り方は他の織り方においても認められる構造である,5)本件指定商品の意義 は,登録事項に基づき客観的に認定判断されるべきであり,商標権者である被告自 身の広告宣伝によって定まるとするのは不当であるなどと主張する。
a 上記1)について
前記(1)エの文献の記載を見るに,各辞典(甲46〜48)では,「工楽松右衛門 の創製した帆布」と「松右衛門帆」を同じものとして扱っており,また,各文献(甲 3〜7)においても,「この松右衛門が開発した,いわゆる『松右衛門帆』」(甲4),「松右衛門帆は,高砂在住の松右衛門帆が天明(1785)に創製した」(甲7)な どと,各辞典と同様に「工楽松右衛門の創製した帆布」と「松右衛門帆」を同じも のとして扱っているから,「工楽松右衛門の創製した帆布」と「松右衛門帆」は同じ ものであると認められ,原告らが主張するように両者が異なるものであるとは認め られず,上記(ア)の認定判断は左右されない。
b 上記2)について
前記(1)エ(イ)a,dのとおり,甲3には「工楽家に現存する帆」として幅3尺の ものが存在する旨の記載がある上,B論文(甲7)の表の中にも,幅が2尺5寸と\nは大きく異なる1尺9寸5分のものが記載されているし,同論文には,「現在の工業 製品と違って,織り幅を規格化していたかどうか疑問で,また,織り手によって多 少差があったのではないだろうか。」と記載されている。そして,前記(1)エ(イ)a, eのとおり,「松右衛門帆」は,人伝いに各地に伝播していったもので,中には地方 において見様見真似で織ったものも存在していた(甲3,4)とされている。そう すると,「松右衛門帆」とされるものの幅やその他の性状といったものについては, 「松右衛門帆」が船の帆として使用されていた当時から既に相当にバラつきがあっ たものと推認できるところである。 また,前記(1)ウ(イ)で認定したように,被告の商品のかばん類に耳部が用いられ ておらず,裁断されるなどして,織り上げられた時点とは幅も異なるものとなって いることからすると,布地の耳部は,一般的に布地から製品を作る際に必ずしも使 用されるものではなく,また,布地の幅も,それぞれの製品に応じて裁断されるな どして異なったものとなると認められるところ,前記(1)エ(イ)d,e のとおり,「松 右衛門帆」は,船の帆として利用されただけでなく,前垂れや覆い,敷物などの他 の用途にも利用されていた(甲4,7)のであるから,そのような中で,「松右衛門 帆」が,幅二尺五寸以外の大きさに加工されたり,耳部がない形で利用されたりす ることもあったものと推認できる。 さらに,現代において,帆船の減少に伴い,「松右衛門帆」の意義が不明確なもの となっていたのは,上記(ア)で認定したとおりである。
以上からすると,「松右衛門帆」が船の帆として使用されていた当時から,特徴1), 2)が,「松右衛門帆」の特徴として広く認識されていたとは認められないし,まして, 「松右衛門帆」の意義が一旦不明確となった以降で,かつ,前記(1)エ(イ)aのとお り,一般に帆布が船の帆に限られず幅広く様々な製品で使われるようになった本件 査定日や要証期間の時点において,特徴1),2)が,「工楽松右衛門の創製した帆布」 の特徴として,本件指定商品の取引者,需要者に認識されていたとは認められず, 原告らの上記主張は,上記(ア)の認定判断を左右するものではない。 なお,原告らは,被告も,耳部が「松右衛門帆」の特徴であるとして宣伝してい る(甲9)から,特徴1)が「松右衛門帆」の特徴である旨主張するが,甲9にも記 載されているように,被告や御影屋が製造販売するかばんには,耳部は使われてい ないのであるから,原告らの上記主張は採用できない。
c 上記3)について
前記(1)ウ(ア)のとおり,神戸大学海事博物館所蔵の帆布は,帆船の研究をしてい た原告らの実父によって寄贈され,同博物館で「松右ヱ門帆」として保管されてき たものであるから,前記(1)ウ(イ)のとおり同帆布の調査に基づいて復元された本件 布地が「松右衛門帆」とはいえないということはできない。原告らが主張する耳部 に関する特徴1)が,現代において,「松右衛門帆」の特徴として,本件指定商品の取 引者,需要者に認識されていたとはいえないことは,上記bで認定判断したとおり であり,原告らの主張はその前提を欠いている。
d 上記4)について 上記bのとおり,「松右衛門帆」が船の帆として使われていた当時から,その規格 にはバラつきがあったものと認められるところ,神戸大学海事博物館に所蔵されて いた「松右ヱ門帆」は,上記cのとおりのものであって,これとは異なる「松右衛 門帆」が存在するからといって,神戸大学海事博物館に所蔵されていた「松右ヱ門 帆」が「松右衛門帆」であることを否定することはできない。 また,神戸大学海事博物館に所蔵されていた「松右ヱ門帆」や本件布地の織り方 が他にも認められる構造のものであったとしても,それが「松右衛門帆」であるこ\nとを否定することにはならない。
e 上記5)について
上記(ア)で認定判断したように,現代において「松右衛門帆」の意義が不確かなも のとなっていたところ,被告や御影屋による広告宣伝活動の結果として,要証期間 までの間にその意義が再度認識されるようになってきているのであり,取引の実情 として,「松右衛門帆」,すなわち,「工楽松右衛門の創製した帆布」の意義を認定す るに当たり,被告や御影屋の広告宣伝活動の結果を考慮に入れることは何ら不当で はないし,上記(ア)で認定判断した事実経過からすると,第三者の地位を著しく不安 定にするということはない。 また,前記(1)ウ(ア),(イ)のとおり,被告は,神戸大学海事博物館において「松右 ヱ門帆」として所蔵されていた,帆船の研究家である原告らの実父が寄贈した帆布 を調査し,これを復元することを試みて,本件布地を完成させている上,本件布地 の特徴が,前記(1)エ(ア)の各辞典に記載されている「松右衛門帆」の特徴と合致す るのみならず,同(イ)の文献に記載されている「松右衛門帆」の特徴とも耳部以外の 点で概ね合致するものであることからすると,被告や御影屋が,本件布地を「松右 衛門帆」,すなわち,「工楽松右衛門の創製した帆布」として販売することは,本件 指定商品の品質について誤認を生じさせて公益を害するものとはいえず,本件にお いて,被告や御影屋の広告宣伝の結果を考慮に入れることは,このような観点から も相当なものといえる。 したがって,原告らの上記5)の主張は採用することができない。
f 小括 以上から,原告らの上記1)〜5)の主張はいずれも採用することができないし,そ の他原告らが主張するところも,いずれも上記(ア)の認定判断を左右するものでは ない。
イ 本件かばんが,「工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類」である のかについて
前記アで認定した本件指定商品における「工楽松右衛門の創製した帆布」の意義 に基づいて,本件かばん2が,「工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類」に 該当するかについて検討する。 前記(1)ウ(ア),(イ)のとおり,被告は,D教授が神戸大学海事博物館において「松 右ヱ門帆」として所蔵されていた帆布についてした調査に基づき復元した本件布地 を使用して,本件かばん2を製作したところ,本件布地は,太い木綿糸を用いて, 2本の単糸を引き揃えにして平織りにし,かつ,緯糸の太さが,経糸より約3倍太 くなっていた厚手の帆布なのであるから,本件布地は,取引者,需要者が観念し得 る「工楽松右衛門の創製した帆布」としての要件を満たすものであったといえる。 したがって,本件布地を使用した本件かばん2は,「工楽松右衛門の創製した帆布 を用いたかばん類」に該当するものであったと認めるのが相当である。 以上のとおり,本件商標の通常使用権者である御影屋は,要証期間内である平成 30年2月頃に本件商標を付した「工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類」 に該当する本件かばん2を一般消費者に販売していたのであるから,本件商標は, 要証期間中に,日本国内において,通常使用権者により,本件指定商品中,「工楽松 右衛門の創製した帆布を用いたかばん類」について使用されていた(商標法2条3 項1,2号)ということができる。
2021.04.13
令和2(行ケ)10084 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年2月25日 知的財産高等裁判所
しかし,「空調」という語と「服」という語の親和性の程度が本来的には高いと いい難いことを考慮しても,「空調服」の語が特定の意味合いを有すると理解でき ることは,上記(1)のとおりである。また,上記(1)で指摘した,「服」が末尾に来 る一般的な名詞の例に照らしても,漢字3文字から構成される短い用語であること\n等から,「空調」の語と「服」の語を分離できないということはできない。そして, 「空調服」という文字構成を原告各社が生み出したという事情は,「空調服」とい\nう語を分離して解釈できるか否かを左右するものではない。 イ 原告らは,「空調服」を「空調」と「服」とに分離して解釈したとして も,「空調」の意味からすると,「空調服」が通気機能を備えた作業服の品質を表\ すものとはいえないと主張するが,「空調」の語の意義を考慮すると,「通気機能\nを備えることにより,空気の温度等を調節する機能を有する服」を認識させるもの\nと解されることは,上記(1)のとおりである。電気機械器具品質表示規程の定めは,\nこの認定を左右するものではない。
ウ 原告らは,「空調服」の語の一般的な使用例について,1)原告各社等以 外のEFウェアのメーカーによっては一切使用されておらず,「EFウェア」等の 語が定着していること,2)ネット通販サイトにおける「空調服」の使用例について は,EFウェアにおける原告商品の認知度の高さゆえに「空調服」の表記が用いら\nれたものにすぎず,同表記が原告商品以外の商品の自他商品識別表\示として用いら れているわけではないこと,3)EFウェアの取引のごく一部に係るものにすぎない ネット通販サイトにおける記載(誤用例)をもって需要者,取引者の認識を判断す ることはできないこと,4)当該「空調服」が原告商品を指しているものが含まれて いること,5)「日本経済新聞」などのメディアについては,順次,「空調服」が原 告各社の商標であることについての訂正がされていること,6)特許出願明細書や実 用新案登録出願の明細書については,出願人がファン付き作業服の需要者や取引者 であるとは限らず,需要者,取引者の認識を表すとはいえないことなどを主張する。\nしかし,他に「EFウェア」等の語が存在することから直ちに,「空調服」の語 が「EFウェア」等の語とは異なる意義を有するということはできないし,作業服 メーカーによる用語法をもって直ちに本願指定商品の需要者の認識を表すものとい\nうことはできない。また,他に原告らが主張する事情は,商標法3条2項に該当す るかどうかについて考慮することができる事情とはいえても,上記(1)の認定判断 を左右するものとはいえない。
3 商標法3条2項該当性について
(1) 特別顕著性について
ア 原告商品「空調服」は,原告ら代表者の発案により原告セフト研究所が\n開発したもので,原告空調服が「空調服」の販売を本格的に開始した平成17年当 時,「空調服」のほかにEFウェアは存在せず,「空調服」は,極めて独自性の強 いものであった(前記1(2)イ)。そして,ファンが衣服に取り付けられているとい う「空調服」は,平成17年当時,他に例のない形態で,これを目にした者に強い 印象を与えるものであったと解される。 また,前記2(1)で指摘したように,本願商標「空調服」の語の意味内容を,本来 の字義から直ちに理解することには一定の困難があり,上記のように,EFウェア という商品分野がいまだ存在しなかった当時においては,「空調服」という語の構\n成も,強い独自性を有していたということができる。 そうすると,「空調服」という商品やその「空調服」という名称は,強い訴求力 を有していたといえる。
イ 上記アの事情に加えて,EFウェアという商品分野において,平成27 年頃まで約10年間は,原告各社等によって市場は独占されていたこと(前記1(3) ア)及び前記1(2)イ〜カで認定した諸事情,特に,「空調服」が原告らの商品を指 すものとして,全国紙を含む新聞や雑誌で多数回にわたって取り上げられたこと, 全国放送の番組を含むテレビ番組でも多数回にわたって同様に取り上げられたこと, 建設会社等の企業に導入されたことなどを踏まえると,平成27年頃までには,「空 調服」は,「通気機能を備えた作業服・ワイシャツ・ブルゾン」という商品分野に\nおいて,原告らの商品として,需要者,取引者に全国的に広く知られるに至ってい たものと認めるのが相当である。
ウ その後,平成27年頃から他社がEFウェアの市場に参入するようにな り(前記1(3)ア),新聞記事やネットショッピングサイト等においてEFウェアを 示す語として「空調服」の語が用いられること(前記1(5)ア(イ))もあったが,原 告商品「空調服」が上記のとおり広く知られていたために同種の商品を「空調服」 と呼ぶ例が生じたと認められる。そして,1)前記1(3)ア〜クで認定した諸事情,特 に,平成28年以降においても,「空調服」が原告商品を指すものとして,又はE Fウェアの元祖が原告空調服の「空調服」であるとして,全国紙を含む新聞や雑誌 で多数回にわたり取り上げられ,また,全国放送を含むテレビ番組等においても同 様に取り上げられ,原告空調服による広告もいろいろな形態で行われ,企業におけ る「空調服」の導入例も拡大してきたことなどの事情,2)「空調服」以外にEFウ ェアを指す一般的な用語が用いられていること(前記1(5)ア(ア)),3)EFウェア の他のメーカーにおいては,「空調服」とは異なる商品名やブランド名で販売活動 を行っていること(前記1(5)イ),4)多くの他業者の参入があっても,なお,平成 30年及び令和元年(平成31年)の時点において,原告各社等による「空調服」 はEFウェアの3分の1程度のシェアを占めていること(前記1(4)イ)を考慮する と,「空調服」は,原告らの商品の出所を示すという機能を失うことなく,その認\n知度を高めていったものと認めることができる。
エ したがって,本件審決時である令和2年4月30日の時点において,本 願商標「空調服」は,使用をされた結果,本願指定商品の需要者,取引者が,原告 各社の業務に係る商品であることを認識することができるものであるから,商標法 3条2項に該当するというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2021.04. 9
令和2(行ケ)10043 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月30日 知的財産高等裁判所
引用発明c−1は,粒子径分布が好適範囲に管理されていても,平均粒 子径から大きく逸脱する粗大粒子が存在する場合には,表示品位の低下や,光学フ\nィルムに欠点が生じる(段落[0005])ため,好適な粒子径を逸脱する粗大な 粒子の含有量が低レベルに低減された微粒子,及び,このような微粒子の製造方法, 並びにこの微粒子を含む樹脂組成物を提供するものであり(段落[0006]), 湿式分級と乾式分級とを組み合わせた方法により処理することで,粒径の好適範囲 から逸脱する粗大粒子や微小粒子を一層効率よく低減するものである(段落〔00 09〕)。
本件発明は,前記(1)アのとおり,架橋アクリル酸系樹脂粒子の揮発分が塗膜表\n面にムラなどを生じさせる結果,塗膜表面の傷付き性能\の低下が生じてしまうこと を解決することを課題としているところ,甲2−3には,このような本件発明の課 題は現れていない。
また,前記(2)によると,合成樹脂粒子の製造については,水分量を低減させ, 残存モノマーを低減させることにより,その品質を向上させることが知られていた ことは認められるが,前記(2)の各証拠から,本件発明のように,粒子中の揮発分 が表面ムラの発生や,塗膜表\面の傷付き性低下などを生じさせていたこと(本件明 細書の段落【0005】)という課題や,この課題を解決するために,加熱減量を 減ずるという構成を採用することが,本件優先日当時,当業者に知られていたと認\nめることはできないし,まして,本件発明の「加熱減量のす.5%」が当業 者に知られていたと認めることはできない。
そして,他に,上記の点について動機付けとなる証拠が存するとは認められない から,甲2−3によって,相違点c−1を容易に想到することができたと認めるこ とはできず,本件発明1は,当業者が容易に発明をすることができたものではない。 被告は,合成樹脂粒子の技術分野において,粒子の残存モノマー,水分などの揮 発分が存在することに起因して,何らかの問題が発生する場合に,当該揮発分の量 を一定量以下に低減化させることは,一般的な共通課題であるから,本件発明1は, 引用発明c−1から容易想到であると主張するが,被告の上記主張を採用すること ができる証拠がないことは,既に説示したところから明らかである。
(4) 以上によると,本件発明1が,当業者が容易に発明をすることができたも のであるとする本件決定の判断に誤りがある。
そして,本件発明1は,当業者が容易に発明をすることができたものでないから, 本件発明4,8も,当業者が容易に発明をすることができたものではないし,さら に,本件発明9及び本件発明10も,当業者が容易に発明をすることができたもの ではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.04. 9
平成31(ワ)3273 差止請求権不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月25日 大阪地方裁判所
イ 原告は,組画の逐次又は一斉の表示をして記憶する人の「作業」となる部分\nを削除しつつ,組画の表示を構\成要件 B2 の選択手段に限定して,明確性の欠如に 係る拒絶理由を補正すると共に,「組画を逐次又は一斉に表示して」とする構\成を 削除し,かつ,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を付加したとい う本件補正の経緯から,被告は,特許請求の範囲につき,「一の組画の画像データ を選択する画像選択手段」に客観的,外形的に限定し,これを備えない発明を本件 発明の技術的範囲から意識的に除外したなどと主張する。 しかし,本件通知書及び本件意見書の各記載を踏まえると,「それぞれの前記記 憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対象を記憶する」の\nは人間が行う作業であって,物の発明としての「学習用具」の構成をなしていない\nなどといった明確性要件に係る本件通知書の指摘に対し,被告は,本件補正におい て,作業の主体につき,画像選択手段,画像表示手段,音声選択手段,音声再生手\n段といった「手段」とし,人が行う作業を示す部分を削除することで,これらの手 段を含むコンピューターであることを明確にしたものと理解される。それと共に, 進歩性に係る本件通知書の指摘に対しては,上記のように作業の主体を明確にした ことに加え,組画記録媒体に記録される画像データを,「1又は複数種の記憶対象 から成る記憶対象群に含まれる個別の記憶対象を表現する原画及び該原画に関連す\nる関連事項又は関連像を表現する1又は複数種の関連画から成る組画の画像」(当\n初の請求項1)から「原画,該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭 を有し対応する語句が存在する第一の関連画,並びに,該原画及び第一の関連画に 似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在 する第二の関連画,から成る組画の画像データ」に限定すると共に,画像表示手段\nが第一の関連画,第二の関連画,及び原画をその順に表示することとし,さらに,\nその表示を,これらに対応する語句の再生と同期させることとして,情報の提示方\n法を限定したものである。
このような出願経過を客観的,外形的に見ると,被告は,本件補正により,人為 的作業を示す部分としての「逐次又は一斉に表示」という行為態様は意識的に除外\nしているものの,物及び方法の構成として,逐次又は一斉に表\示する構成を一般的\nに除外する旨を表示したとはいえない。また,「一の組画の画像データを選択する\n画像選択手段」との構成を付加した点は,本件明細書に「一の組画」の画像データ\nの選択,表示を念頭に置いた記載があることを踏まえたものと理解されるものの\n(例えば【0057】),これをもって直ちに,客観的,外形的に見て,複数の組画を 選択する構成を意識的に除外する旨を表\示したものとは見られない。 そうすると,原告指摘に係る本件補正の経緯をもって,被告は,特許請求の範囲 につき,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」に客観的,外形的に限 定し,これを備えない発明を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したと見るこ とはできない。この点に関する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.04. 8
令和2(ネ)10022 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年3月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(ウ) 本件について
前記(ア)及び(イ)によると,演奏権の行使となるのは,演奏者が,1) 面前にいる個人的な人的結合関係のない者に対して,又は,面前にいる 個人的な結合関係のある多数の者に対して,2)演奏が行われる外形的・ 客観的な状況に照らして演奏者に上記1)の者に演奏を聞かせる目的意思 があったと認められる状況で演奏をした場合と解される。 本件使用態様1ないし4のとおり,控訴人らの音楽教室で行われた演 奏は,教師並びに生徒及びその保護者以外の者の入室が許されない教室 か,生徒の居宅であるから,演奏を聞かせる相手方の範囲として想定さ れるのは,ある特定の演奏行為が行われた時に在室していた教師及び生 徒のみである。すなわち,本件においては,一つの教室における演奏行 為があった時点の教師又は生徒をとらえて「公衆」であるか否かを論じ なければならない。 オ 以下,前記の基本的考え方を前提に,教師による演奏行為及び生徒によ る演奏行為がそれぞれ「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」 行われたものに当たるかについて検討する。
(2) 教師による演奏行為について
ア 教師による演奏行為の本質について
引用に係る原判決の第2の3(1)アのとおり,控訴人らは,音楽を教授す る契約及び楽器の演奏技術等を教授する契約である本件受講契約を締結 した生徒に対して,音楽及び演奏技術等を教授することを目的として,雇 用契約又は準委任契約を締結した教師をして,その教授を行うレッスンを 実施している。 そうすると,音楽教室における教師の演奏行為の本質は,音楽教室事業 者との関係においては雇用契約又は準委任契約に基づく義務の履行とし て,生徒との関係においては本件受講契約に基づき音楽教室事業者が負担 する義務の履行として,生徒に聞かせるために行われるものと解するのが 相当である。
・・・
(ウ) これに対して,控訴人らは,前記第2の5(1)ア(ア)のとおり,教師 がレッスンで演奏(録音物の再生を含む。)するかどうか,どのような演 奏をどの程度するかについて教師の裁量に任されているから,控訴人ら は教師の演奏を管理・支配していないし,音楽教室における教師の楽曲 の演奏は,未完成又は不完全な演奏であり,また,1回1回全て異なる ものであるから,音楽教室事業者が管理・支配できるものではない旨主 張する。 しかしながら,教師は,控訴人らとの雇用契約又は準委任契約に基づ き,その義務の履行として演奏技術等を生徒に教授するのであって,履 行方法に選択肢を有するとしても,履行しない自由を有してはおらず, その履行に当たって一定の裁量があるとしても,本件受講契約において 控訴人らが生徒に対し負担する義務を履行するために必要なレッスンを 行う義務を負うこと自体には何ら変わりはないのであるから,教師がレ ッスンの進行について裁量を有することは,教師がした演奏の主体が控 訴人らであるとする前記判断を左右するものではない。
また,教師が未完成又は不完全な形で毎回異なるように演奏するのは, その技量が不足するためではなく,生徒への演奏技術等の教授のために 敢えてしていることであって,まさしく控訴人らとの間の雇用契約又は 準委任契約に基づく義務の履行に適ったことをしているにほかならない。 したがって,演奏内容の完成度若しくは完全度又は再現性は,教師が, 控訴人らとの雇用契約又は準委任契約に基づく義務の具体的履行方法と してどのような演奏手法を用いたかということを意味するにすぎず,教 師のした演奏の主体が控訴人らであるとする前記判断を左右するもので はない。 そのほかに控訴人らが教師の演奏行為に係る演奏主体について主張す る点は,いずれもその前提を異にする,あるいは理由がないものである から,前記判断を左右し得ない。
エ 「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」について
(ア) 前記(1)エ(ア)のとおり,演奏権の行使に当たるか否かの判断は,演 奏者と演奏を聞かせる目的の相手方との個人的な結合関係の有無又は 相手方の数において決せられるところ,この演奏者とは,著作権者の保 護と著作物利用者の便宜を調整して著作権の及ぶ範囲を合目的な領域 に設定しようとする著作権法22条の趣旨からみると,演奏権の行使に ついて責任を負うべき立場の者,すなわち演奏の主体にほかならない。 そうすると,前記ウ(イ)のとおり,音楽教室における演奏の主体は,教 師の演奏については控訴人ら音楽教室事業者であり,教師の演奏行為に ついて教師が「公衆」に該当しないことは当事者間に争いがなく,生徒 に聞かせるために演奏していることは明らかであるから,実際の演奏者 である教師の演奏行為が「公衆」に直接聞かせることを目的として演奏 されたものであるといえるかは,規範的観点から演奏の主体とされた音 楽教室事業者からみて,その顧客である生徒が「特定かつ少数」の者に 当たらないといえるか否かにより決せられるべきこととなる。
(イ) そこで検討するに,引用に係る原判決の第2の3(1)アによると,生 徒が控訴人らに対して受講の申込みをして控訴人らとの間で受講契約を締結すれば,誰でもそのレッスンを受講することができ,このような音\n楽教室事業が反復継続して行われており,この受講契約締結に際しては, 生徒の個人的特性には何ら着目されていないから,控訴人らと当該生徒 が本件受講契約を締結する時点では,控訴人らと生徒との間に個人的な 結合関係はなく,かつ,音楽教室事業者としての立場での控訴人らと生 徒とは,音楽教室における授業に関する限り,その受講契約のみを介し て関係性を持つにすぎない。そうすると,控訴人らと生徒の当該契約か ら個人的結合関係が生じることはなく,生徒は,控訴人ら音楽事業者と の関係において,不特定の者との性質を保有し続けると理解するのが相 当である。
したがって,音楽教室事業者である控訴人らからみて,その生徒は, その人数に関わりなく,いずれも「不特定」の者に当たり,「公衆」にな るというべきである。音楽教室事業者が教師を兼ねている場合や個人教 室の場合においても,事業として音楽教室を運営している以上は,受講 契約締結の状況は上記と異ならないから,やはり,生徒は「不特定」の 者というべきである。
・・・・
オ 小活
以上によれば,教師による演奏については,その行為の本質に照らし, 本件受講契約に基づき教授義務を負う音楽行為事業者が行為主体となり, 不特定の者として「公衆」に該当する生徒に対し,「聞かせることを目的」 として行われるものというべきである。
(3) 生徒による演奏行為について
ア 生徒による演奏行為の本質について 引用に係る原判決の第2の3(1)ア及び前記(2)アに照らせば,控訴人らは, 音楽を教授する契約及び楽器の演奏技術等を教授する契約である本件受 講契約を締結した生徒に対して,音楽及び演奏技術等を教授することを目 的として,雇用契約又は準委任契約を締結した教師をして,その教授を行 うレッスンを実施している。 そうすると,音楽教室における生徒の演奏行為の本質は,本件受講契約 に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため,教師に聞かせようとし て行われるものと解するのが相当である。なお,個別具体の受講契約にお いては,充実した設備環境や,音楽教室事業者が提供する楽器等の下で演 奏することがその内容に含まれることもあり得るが,これらは音楽及び演 奏技術等の教授を受けるために必須のものとはいえず,個別の取決めに基 づく副次的な準備行為や環境整備にすぎないというべきであるから,音楽 教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を 受けることにあるというべきである。 また,音楽教室においては,生徒の演奏は,教師の指導を仰ぐために専 ら教師に向けてされているのであり,他の生徒に向けてされているとはい えないから,当該演奏をする生徒は他の生徒に「聞かせる目的」で演奏し ているのではないというべきであるし,自らに「聞かせる目的」のものと もいえないことは明らかである(自らに聞かせるためであれば,ことさら 音楽教室で演奏する必要はない。)。被控訴人は,生徒の演奏技術の向上の ために生徒自身が自らの又は他の生徒の演奏を注意深く聞く必要がある とし,書証(乙57の58頁)や証言(原審証人Q15頁)を援用するが, 自らの又は他の生徒の演奏を聴くことの必要性,有用性と,誰に「聞かせ る目的」で演奏するかという点を混同するものといわざるを得ず,採用し 得ない。
・・・
ウ 演奏主体について
(ア) 前述したところによれば,生徒は,控訴人らとの間で締結した本件 受講契約に基づく給付としての楽器の演奏技術等の教授を受けるためレ ッスンに参加しているのであるから,教授を受ける権利を有し,これに 対して受講料を支払う義務はあるが,所定水準以上の演奏を行う義務や 演奏技術等を向上させる義務を教師又は控訴人らのいずれに対しても負 ってはおらず,その演奏は,専ら,自らの演奏技術等の向上を目的とし て自らのために行うものであるし,また,生徒の任意かつ自主的な姿勢 に任されているものであって,音楽教室事業者である控訴人らが,任意 の促しを超えて,その演奏を法律上も事実上も強制することはできない。 確かに,生徒の演奏する課題曲は生徒に事前に購入させた楽譜の中か ら選定され,当該楽譜に被告管理楽曲が含まれるからこそ生徒によって 被告管理楽曲が演奏されることとなり,また,生徒の演奏は,本件使用 態様4の場合を除けば,控訴人らが設営した教室で行われ,教室には, 通常は,控訴人らの費用負担の下に設置されて,控訴人らが占有管理す るピアノ,エレクトーン等の持ち運び可能ではない楽器のほかに,音響設備,録音物の再生装置等の設備がある。しかしながら,前記アにおい\nて判示したとおり,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教 師に演奏を聞かせ,指導を受けること自体にあるというべきであり,控 訴人らによる楽曲の選定,楽器,設備等の提供,設置は,個別の取決め に基づく副次的な準備行為,環境整備にすぎず,教師が控訴人らの管理 支配下にあることの考慮事情の一つにはなるとしても,控訴人らの顧客 たる生徒が控訴人らの管理支配下にあることを示すものではなく,いわ んや生徒の演奏それ自体に対する直接的な関与を示す事情とはいえない。 このことは,現に音楽教室における生徒の演奏が,本件使用態様4の場 合のように,生徒の居宅でも実施可能であることからも裏付けられるものである。以上によれば,生徒は,専ら自らの演奏技術等の向上のために任意か\nつ自主的に演奏を行っており,控訴人らは,その演奏の対象,方法につ いて一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても,教授を受ける ための演奏行為の本質からみて,生徒がした演奏を控訴人らがした演奏 とみることは困難といわざるを得ず,生徒がした演奏の主体は,生徒で あるというべきである。
(イ) これに対して,被控訴人は,引用に係る原判決の第3の2〔被告の 主張〕(1)エ(イ)及び(ウ)並びに前記第2の5(2)ア(ウ)のとおり,音楽教 室における生徒の演奏は,1)控訴人らとの間で締結した本件受講契約に おけるレッスンの一環としてされるものであり,レッスンの受講と無関 係に演奏するものではないこと,2)教師の指導の下,教育効果の観点か ら必要と考えられる場合にその限度でされること,3)本件受講契約によ って特定されたレッスンで使用される楽譜において課題曲として指定 された音楽著作物を,教師の指導・指示の下で演奏することを原則とす るものであること,4)控訴人らが費用を負担して設営した教室において, 控訴人らの管理下にある音響設備,録音物の再生装置等,録音物,楽器 等を利用してされるものであること,5)音楽教室事業が音楽著作物を利 用せずに楽器の演奏技術を教授することは不可能であることに照らすと,本件受講契約に基づき支払う受講料の中に,音楽著作物の利用の対\n価部分が含まれていることに照らせば,生徒の演奏についても音楽教室 事業者である控訴人らによる管理・支配及び利益の帰属が認められ,演 奏の主体は控訴人らである旨主張する。
しかしながら,上記1)ないし4)において控訴人が主張する事情から直 ちに,生徒が任意にする演奏の主体を音楽教室事業者であると評価する ことができないことは,前記説示から明らかである。なお,被控訴人は, 前記第2の5(2)ア(イ)のとおり,カラオケ店における客の歌唱の場合と 同一視すべきである旨主張するが,その法的位置付けについてはさてお くにしても,カラオケ店における客の歌唱においては,同店によるカラ オケ室の設営やカラオケ設備の設置は,一般的な歌唱のための単なる準 備行為や環境整備にとどまらず,カラオケ歌唱という行為の本質からみ て,これなくしてはカラオケ店における歌唱自体が成り立ち得ないもの であるから,本件とはその性質を大きく異にするものというべきである。 さらに,上記5)において被控訴人が主張する事情については,レッス ンにおける生徒の演奏についての音楽著作物の利用対価が本件受講契 約に基づき支払われる受講料の中に含まれていることを認めるに足り る証拠はないし,また,いずれにしても音楽教室事業者が生徒を勧誘し 利益を得ているのは,専らその教授方法や内容によるものであるという べきであり,生徒による音楽著作物の演奏によって直接的に利益を得て いるとはいい難い。 したがって,被控訴人の上記主張はいずれも採用できない。
(ウ) そのほかに被控訴人らが生徒の演奏行為に係る演奏主体について 主張する点は,いずれもその前提を異にする,あるいは理由がないもの であるから,前記判断を左右し得ない。
エ 小括
以上のとおり,音楽教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるか ら,その余の点について判断するまでもなく,生徒の演奏によっては,控 訴人らは,被控訴人に対し,演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利 得返還債務のいずれも負わない(生徒の演奏は,本件受講契約に基づき特 定の音楽教室事業者の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行わ れるものであるから,「公衆に直接(中略)聞かせることを目的」とするも のとはいえず,生徒に演奏権侵害が成立する余地もないと解される。)。 なお,念のために付言すると,仮に,音楽教室における生徒の演奏の主 体は音楽事業者であると仮定しても,この場合には,前記アのとおり,音 楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導 を受けることにある以上,演奏行為の相手方は教師ということになり,演 奏主体である音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを 目的として演奏することになるから,「公衆に直接(中略)聞かせる目的」 で演奏されたものとはいえないというべきである(生徒の演奏について教 師が「公衆」に該当しないことは当事者間に争いがない。また,他の生徒 や自らに聞かせる目的で演奏されたものといえないことについては前記 アで説示したとおりであり,同じく事業者を演奏の主体としつつも,他の 同室者や客自らに聞かせる目的で歌唱がされるカラオケ店(ボックス)に おける歌唱等とは,この点において大きく異なる。)。
◆判決本文
1審はこちら。
2021.03.30
平成30(ワ)60 不当利得返還請求事件 その他 民事訴訟 令和3年3月11日 大阪地方裁判所
(1) 以上より,被告が特許料不納付により本件特許権5〜8を消滅させたこと は,本件許諾契約上の特許維持義務(本件許諾契約書8条2項)の不履行に当た る。したがって,本件許諾契約は,原告の解除の意思表示(前記第2の1(10))に より解除されたこととなるから,被告は,原告に対し,原状回復義務(民法545 条)として,本件許諾契約に基づき原告が支払った実施料の返還義務及び利息支払 義務を負う。
(2) 本件許諾契約書において,実施料の額は本件プラントの処理能力に基づき算\n定されており(5条1項。前記第2の1(4)),本件各特許権の実施料を個別に算 定し,これを合算した額をもって実施料とするといった定め方はされていない。本 件各特許権の存続期間終了に応じて実施料を減額するといった規定も存在しない。 また,本件仕様書において,本件プラントにおいて本件各発明が実施される設備な いし方法及びそこで実施される発明を特定しているわけでもない。 これらの事情に鑑みると,本件許諾契約は,本件プラントの建設,操業及びリサ イクル品の製造,販売等において,本件各発明に係る技術のどれがどのように使用 されるかを具体的に特定して実施料を算定したものではなく,本件各特許権を一体 的なものとして取り扱い,本件許諾契約書記載のとおり,本件プラントの処理能力\nに基づき実施料を算定したものと理解される。 そうすると,本件許諾契約は,出願日の最も遅い本件特許権8(出願日平成10 年4月11日)の存続期間が終了する平成30年4月11日までは,契約として意 義を有していた可能性が高く,同契約に基づく本件実施料は,平成18年4月1日\n〜平成30年4月11日の期間中,本件各特許権のいずれかの通常実施権を許諾さ れることの対価として一体的に定められたものと見られる。 もっとも,本件各特許権のうち最もその消滅が遅かったのは本件特許権6(平成 23年7月6日)であり,それまでは,原告は,本件許諾契約に基づく通常実施権 者としての地位を享受していた。このため,本件許諾契約の解除により,原告も, その間に享受した利益を返還すべき地位にある。 そこで,本件実施料として支払われた1億5750万円から,原告が実際に通常 実施権者としての地位を享受していた期間に相当する部分を控除すると,8857 万1347円となる。
\157,500,000-(\157,500,000*1923 日/4394 日)=\88,571,347
(日数は実日数,小数点以下切捨て)
(3) 被告の主張について
被告は,本件実施料はそもそも実質的には本件各特許権の実施に係る許諾料では ない,本件許諾契約の目的は本件プラントが本稼働を開始した平成18年4月時点 で既に達成されている,本件プラントにおいて本件各特許権が実施されていないこ とから,被告が本件特許5〜8を消滅させたことによって原告に損害が発生してお らず,債務不履行となるべき事実自体がないなどと主張する。 しかし,本件許諾契約に至る経緯等(前記1(1))に鑑みれば,本件実施料が実 質的に本件各特許権の実施に係る許諾料でないと見るべき事情はない。また,本件 許諾契約は,本件プラントの操業を埼玉ヤマゼンが担うことを前提としたものであ ることから(前記第2の1(2),第3の1(1)ケ,(2)),その目的が本件プラントの 本稼働開始により既に達成されたと見ることもできない。 さらに,そもそも,本件では本件許諾契約の債務不履行による解除に基づく原状 回復請求がされているのであって,損害賠償請求はされていないことから,損害の 発生の有無は問題とならない。その点は措くとしても,本件プラントにおける本件 各発明の実施の有無は必ずしも判然とせず(前記1(5)),また,本件許諾契約に より原告が認められるのは通常実施権にとどまるものの,本件許諾契約には,JRT が原告以外の者にも本件各発明の実施を許諾する場合は,事前に原告との協議を要 することが定められていること(本件許諾契約書3条。前記第2の1(4)ア)など に鑑みると,なお本件特許権5〜8が権利として維持されることには意味があった ものといえる。しかも,前記(2)のとおり,本件許諾契約においては,本件実施料 を定めるに当たり本件各特許権は個別にではなく一体的に取り扱われていることか ら,本件特許権1〜4が本件譲渡契約の時点で既に消滅していたことは,原状回復 が認められる範囲を定めるに当たり考慮すべき事情とはいえない。その他被告が 縷々指摘する事情を考慮しても,この点に関する被告の主張は採用できない。
2021.03.30
令和2(ネ)10051 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年2月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1)控訴人は,新薬の製造販売承認を得るための必要な試験は,平成11年最 判の射程外であるところ,特許法69条1項の「試験又は研究」に該当するかにつ いては特許権者の利益と第三者の利益を綿密に検討する必要があり,本件治験は, 同項の「試験又は研究」に該当しないと主張する。 しかし,新薬の製造販売承認を得るために必要な本件治験が,特許法69条1項 の「試験又は研究」に該当することは,原判決「事実及び理由」の第4の1(2)のと おりである。 控訴人は,新薬の製造販売承認のためにする試験と後発薬の製造販売承認のため の試験の内容が異なる旨主張するが,平成11年最判の趣旨が本件治験についても 該当することは,原判決の「事実及び理由」の第4の1(2)のとおりであって,この ことは,製造販売承認のための試験の内容によって左右されるとは解されない。
(2) 控訴人は,特許権者ではない第三者が特許権の存続期間中に新薬の製造 販売承認を得た場合,当該第三者は,特許権の存続期間満了までは,当該新薬を製 造販売することができないから,その間,当該新薬の再審査期間中に製造販売でき ないという空白期間が生じると主張するが,実地医療での使用における安全性情報 の調査は,特許期間満了後に開始すればよいのであり,実地医療での使用における 安全性情報等の調査という目的が十分に果たされないというものではない。\n
(3) 控訴人は,特許権者でない第三者が特許発明について新薬としての治験 を行うことに特許権の効力が及ばないとすると,この第三者が特許権者に先行して 製造販売承認を得ることも可能になり,特許権者は,特許権の存続期間中であるに\nもかかわらず,事実上自らの特許発明に係る実施品について治験を実施することす らできなくなることとなるから,特許出願をするメリットがなくなり,発明の公開 というデメリットばかりが大きいことになるため,薬剤の発明者は,特許出願をた めらうことになり,医薬品産業の発達を著しく阻害することになり,特許法の目的 に反すると主張する。
しかし,特許法は,当該特許権の存続期間中に特許発明を独占的に実施し,それ により利益を得る機会を確保しているものであるが,特許権者が現実に利益を得る ことまでをも保障するものではないから,第三者が特許権者に先行して製造販売承 認を得たり,特許権者が,事実上,自らの特許発明の実施品について治験を実施す ることが難しくなることがあるとしても,これが特許法の趣旨に反すると認めるこ とはできず,控訴人の上記主張は,本件治験が特許法69条1項の試験に該当する との判断を左右するものではない。
(4) 控訴人は,再生医療等製品のうち特にバイオ医薬品については,通常の医 薬品とは異なる規制や制約があるのであり,その開発には,長期の開発期間を要す ることから,製造承認販売を得て販売されるタイミングが当該特許権の存続期間満 了間近とならざるを得ず,特許権の存続期間中に第三者が承認申請のための治験(臨\n床試験)を実施することを許容すると,特許権者の不利益は甚大なものとなる旨主 張する。 しかし,この点についての控訴人の主張を採用することができないことは,原判 決の「事実及び理由」の第4の1(3)ウのとおりである。 また,控訴人は,特許権の存続期間中に第三者が承認申請のための治験(臨床試\n験)を実施することを許容すると,革新的な医薬品の研究開発に悪影響を与えると か国内外において製薬業界に大きな混乱を与えると主張するが,控訴人の陳述書(甲 32)のみで,そのような事情を認めることはできず,他に,そのような事情を認 めるに足りる証拠はない。
(5) 控訴人は,新薬の承認申請のための治験を特許権の存続期間中に何らラ\nイセンスもなく実施可能ということにすると,諸外国の取扱いに反する旨主張する。\nしかし,我が国と諸外国では,法制度を異にしているから,我が国において諸外 国と同様の取扱いをしなければならないとはいえない。また,欧州においては,証 拠(甲41)及び弁論の全趣旨によると,欧州各国の中で,それぞれの国内法にお いて,医薬品の承認を得るための手続が特許権侵害とならないとする,いわゆるB olar条項の適用の範囲を定めており,フランス,イタリア,スペイン及び英国 は,同条項の適用を,後発医薬品の承認を得るための試験に限定していないことが 認められる。 控訴人は,Amgen が米国及び欧州で Massachusetts General Hospital の特許(本 件特許に対応する米国特許と欧州特許)についてライセンス契約を締結した上で TVEC の臨床試験を実施していることを主張するが,新薬に係る治験が特許権侵害に 該当しないとされていたとしても,新薬に係る治験を行うために特許権者とライセ ンス契約を締結することはあり得ることであるから,控訴人の上記主張から諸外国 の制度に関する認定をすることはできない。 控訴人は,陳述書(甲32)において,後発薬と異なり,新薬に係る治験につい ては,当該新薬に係る特許が存在している場合に,当該特許の所有者からライセン スを受けることなく当該治験を実施することが当該特許の侵害に該当するという考 え方が定着していると記載するが,諸外国の制度に関する上記認定によると,控訴 人の陳述書の上記記載を採用することはできない。 上記のとおり,新薬に係る治験が特許権侵害とならないとする国が複数存在する ことからすると,そうでない制度を有する国があるとしても,我が国において,本 件治験が特許法69条1項の「試験又は研究」に該当すると判断することが,諸外 国の制度と異なるものであるとはいえない。
(6) 控訴人は,本件治験は本件特許権の存続期間満了「前」の販売を目的とし たものであると主張する。 しかし,本件治験は,本件特許権の存続期間中の製造販売を目的としたものであ るといえないことは,原判決の「事実及び理由」の第4の1(3)イのとおりであって, 被控訴人が,本件特許権の存続期間満了日より前に T-VEC の承認を得られる可能性\nがあるかどうかやそのような可能性がある時点で本件治験を開始したかどうかによ\nって,この判断が左右されることはない。 控訴人は,原判決が判示する論理が認められるとすると,特許権の存続期間中に 行われるすべての治験について特許権の存続期間中の製造販売を目的としていると 認定されることはおよそないこととなるから,平成11年最判が目的要件を提示し た趣旨を完全に逸脱していると主張するが,原判決の判示する論理によったからと いって,特許権の存続期間中に行われるすべての治験について特許権の存続期間中 の製造販売を目的としていると認定されることはおよそないこととなるとはいえな いことが明らかである。
◆判決本文
1審はこちらです。
2021.03.30
令和3(行ケ)10118 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年3月11日 知的財産高等裁判所
(1) 本件商標は,別紙1のとおりであり(甲1),三つのハート形の図形を横に 重なるように並べた本件図形部分と,その下に配置された横書きにした「SMS」 のありふれた書体の欧文字(本件文字部分)とからなる商標である。 本件図形部分は,ハートの形を縁取った線を横に二つ描き,その二つのハートの 形の内側の二つの半円部分を用いて,中央部分に三つ目のハートの形を描いたもの で,一筆書きによって描くことができるようになっている。 本件図形部分及び本件文字部分のいずれにも色彩はなく,本件図形部分の高さは, 本件文字部分の高さの3倍弱であり,本件図形部分の横幅は,本件文字部分の横幅 の2倍弱である。
(2) 本件商標の上記(1)の外観からすると,本件商標においては,本件図形部分 と本件文字部分とを明確に区別することができ,それらの各部分を分離して観察す ることが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとは認められな いから,本件商標から,本件文字部分を抽出し,同部分を他人の商標と比較して商 標の類否を判断することができるというべきである。 そして,本件文字部分からは,「エスエムエス」との称呼が生じるが,「SMS」 の語は,「広辞苑 第六版」には掲載されておらず(甲19),他に一般的な辞書に 掲載されている例があるとも認められないから,造語であると認められ,特定の観 念は生じないというべきである。
3 引用商標1及び2について
(1) 引用商標1及び2は,別紙2,3のとおりであり(甲2,3),オレンジ色 の小さな円をL字型に並べた形状と,同様の黄色のL字型の形状とを組み合わせた 正方形を45度傾けた形状の図形部分(引用1及び引用2図形部分)と,その右側 に配置された,横書きにした「SMS」の欧文字と横書きにした「Best ma tching Best value」の欧文字を上下二段に配置した部分(引用 1及び引用2文字部分)からなる商標である。 引用1及び引用2図形部分の高さは,「SMS」の文字部分の高さの2倍程度であ り,引用1及び引用2図形部分の横幅は,「SMS」の文字部分の横幅の6割程度で ある。また,「Best matching Best value」の文字部分は, 「SMS」の文字部分と同じ横幅で,「SMS」の文字部分に比較して,極めて小さ く書かれている。
(2) 引用商標1及び2の上記(1)の外観からすると,引用商標1及び2において は,引用1及び引用2図形部分と引用1及び引用2文字部分とを明確に区別するこ とができる。また,引用1及び引用2文字部分については,「SMS」の文字部分と, 「Best matching Best value」の文字部分は2段に分か れていて,大きさも顕著に異なるのであるから,両者を明確に区別することができ る。 したがって,引用商標1及び2において,「SMS」の文字部分が他の部分と分離 して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとは 認められないから,「SMS」の文字部分を抽出し,同部分を他人の商標と比較して 商標の類否を判断することができるというべきである。 そして,前記2(2)のとおり,「SMS」の文字部分からは,「エスエムエス」との 称呼が生じるが,特定の観念は生じないというべきである。
・・・・
原告は,「SMS」とは,携帯電話でのメッセージ送受信サービスである 「Short Message Service(ショートメッセージサービス)」の 略語であり,本件審決がされた令和2年の時点で,「ショートメッセージサービス」 の略語としての「SMS」は,通信分野に限らず,一般に周知されていると主張し, その証拠として,甲25,26を提出する。 甲25によると,「SMS」が「ショートメッセージサービス」の略語であること を説明したウェブサイトが存在することが認められるが,前記2(2)のとおり,「S MS」の語が一般的な辞書に掲載されている例があるとは認められないことからす ると,上記ウェブサイトの存在から,「SMS」が「ショートメッセージサービス」 の略語を意味することが一般的に認識されていたということはできないというべき である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2021.03.26
令和1(ネ)1735 著作権に基づく差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年1月14日 大阪高等裁判所
同一性又は類似性について
ア 共通点
原告作品と被告作品の共通点は次のとおり(以下「共通点1)」などと いう。)である。
1) 公衆電話ボックス様の造作水槽(側面は4面とも全面がアクリルガ ラス)に水が入れられ(ただし,後記イ6)を参照),水中に主に赤色の 金魚が50匹から150匹程度,泳いでいる。
2) 公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で 固定され,その受話部から気泡が発生している。
・・・・
著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知 させるに足りるものを有形的に再製すること(著作権法2条1項15号) をいい,著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上\nの本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更\n等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これ\nに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること\nのできる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁昭和53年9月7日 第一小法廷判決・民集32巻6号1145頁,最高裁平成13年6月2 8日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。 依拠については後記(3)において検討することとし,ここではそれ以外 の要件について検討する。 共通点1)及び2)は,原告作品のうち表現上の創作性のある部分と重な\nる。なお,被告作品は,平成26年2月22日に展示を開始した当初は, アクリルガラスのうちの1面に,縦長の蝶番を模した部材を貼り付けて\nいた(相違点6))。しかし,前記のとおり,この蝶番は目立つものでは なく,公衆電話を利用する者にとっても,鑑賞者にとっても,注意をひ かれる部位とはいえないから,この点の相違が,共通点1)として表れて\nいる原告作品と被告作品の共通性を減殺するものではない。
一方,他の相違点はいずれも,原告作品のうち表現上の創作性のない\n部分に関係する。原告作品も被告作品も,本物の公衆電話ボックスを模 したものであり,いずれにおいても,公衆電話機の機種と色,屋根の色 (相違点1)〜3))は,本物の公衆電話ボックスにおいても見られるもの である。公衆電話機の下の棚(相違点4))は,公衆電話を利用する者に しても鑑賞者にしても,注意を向ける部位ではなく,水の量(相違点5)) についても同様であることは前記のとおりである。すなわち,これらの 相違点はいずれもありふれた表現であるか,鑑賞者が注意を向けない表\ 現にすぎないというべきである。 そうすると,被告作品は,原告作品のうち表現上の創作性のある部分\nの全てを有形的に再製しているといえる一方で,それ以外の部位や細部 の具体的な表現において相違があるものの,被告作品が新たに思想又は\n感情を創作的に表現した作品であるとはいえない。そして,後記(3)のと おり,被告作品は,原告作品に依拠していると認めるべきであり,被告 作品は原告作品を複製したものということができる。 仮に,公衆電話機の種類と色,屋根の色(相違点1)〜3))の選択に創 作性を認めることができ,被告作品が,原告作品と別の著作物というこ とができるとしても,被告作品は,上記相違点1)から3)について変更を 加えながらも,後記(3)のとおり原告作品に依拠し,かつ,上記共通点1) 及び2)に基づく表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,原告作品にお\nける表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから,原告作品\nを翻案したものということができる。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2021.03.26
令和2(ネ)10052 特許権持分一部移転登録手続等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月17日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,1)抗PD−L1抗体がPD−1分子とPD−L1分子の相 互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」な いし「着想」は,本件出願当時,公知であったから,本件発明の技術的 思想の特徴的部分は,上記公知の課題について具体的な免疫細胞と標的 となるがん細胞を用いて抗PD−L1抗体がPD−1分子とPD−L1 分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の賦活化の効果を実証し た点にあること,2)控訴人は,抗PD−L1抗体の作製に貢献し,指導 教官であるA教授から指導を受けながら,試行錯誤を重ねて本件発明を 構成する個々の実験系を構\\築し,主要な実験のほぼすべてを単独で行い, 特に2C細胞とP815細胞の組合せ実験に関しては,A教授から指示 を受けることなく着想して,遂行し,この点に関する控訴人の貢献の程 度は大きいこと,3)控訴人が本件発明と同内容のPNAS論文の筆頭著 者(共同第一著者)であること等からすると,控訴人は,本件発明の具 体化に創作的に関与したものといえるから,本件発明の発明者であると いうべきである旨主張する。 しかしながら,以下のとおり,控訴人の主張は,理由がない。
ア 1)について
控訴人は,抗PD−L1抗体がPD−1分子とPD−L1分子の相 互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」 ないし「着想」が,本件出願当時(原出願1の優先日平成14年7月 3日及び平成15年2月6日),公知であったことについて,JEM論 文及び1999(平成11)年9月に出願されたダナ・ファーバー癌 研究所等の特許出願の優先権主張の基礎出願に係る明細書の記載を根 拠として挙げる。 しかしながら,JEM論文(甲66)は,「新しいB7ファミリーメ ンバーによるPD−1免疫抑制性受容体の関与が,リンパ球活性化の 負の制御を導く」ことに関する論文であり,JEM論文中には,「ヒト 卵巣腫瘍から3つのESTがみられるように,PD−L1は,いくつ かの癌において発現されている。このことは,腫瘍が,抗腫瘍免疫応 答を阻害するために,PD−L1を使用している可能性を提起する。」との記載部分があるが,一方で,JEM論文には,腫瘍に発現したP\nD−L1が抗腫瘍免疫応答を阻害することを実際に実証する実験デー タやその分析結果等の記載がないことに照らすと,JEM論文の上記 記載部分は,腫瘍が抗腫瘍免疫応答を阻害するためにPD−L1を使 用している可能性があることの仮説を述べたものにとどまるというべきである。\n
次に,控訴人提出の甲60は,ダナ・ファーバー癌研究所等を出願 人,2000年(平成12年)8月23日を国際出願日,2001年 (平成13年)3月1日を国際公開日とする国際出願((PCT/US /23347)の国際公開公報,甲61は,その公表特許公報であって,本件においては,上記国際出願の優先権主張の基礎出願に係る明\n細書の提出はないし,また,控訴人の指摘する甲61の「PD−1を 介するシグナリングを阻害する作用剤を対象の免疫細胞に投与して, 免疫応答のアップレギュレーションから利益を受けるであろう症状を 治療することを特徴とする・・・1の具体例において,該症状は,腫瘍・・・ からなる群より選択される。」(段落【0009】)との記載から直ちに 抗PD−L1抗体がPD−1分子とPD−L1分子の相互作用を阻害 することによりがん免疫の賦活をもたらすとの「知見」を導出するこ とはできない。 したがって,控訴人の1)の主張のうち,抗PD−L1抗体がPD− 1分子とPD−L1分子の相互作用を阻害することによるがん免疫の 賦活化の効果が,本件出願当時,公知であったとの点は,採用するこ とはできない。 そして,前記1(2)認定のとおり,本件発明の技術的思想は,PD− 1,PD−L1による抑制シグナルを阻害して,免疫賦活させる組成 物及びこの機構を介した癌治療のための組成物を提供するという課題を解決するための手段として,抗PD−L1抗体がPD−1分子とP\nD−L1分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもた らすことを見出した点にあるものと認められ,本件発明の発明者であ るというために,上記技術的思想を着想し,又は,その着想を具体化 することに創作的に関与したことを要するものと解されるところ(前 記(1)),控訴人が上記技術的思想の着想に関与していないことは,前 記(2)オで説示したとおりである。
・・・・
エ まとめ
以上によれば,控訴人は,A教授の指導,助言を受けながら,自ら の研究として本件発明を具体化する個々の実験を現実に行ったものと 認められるから,A教授の単なる補助者にとどまるものとはいえない が,一方で,上記実験の遂行に係る控訴人の関与は,本件発明の技術 的思想との関係において,創作的な関与に当たるものと認めることは できないから,控訴人は,本件発明の発明者に該当するものと認める ことはできない。 したがって,控訴人の前記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2021.03.19
令和2(ネ)10035 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明の技術的思想(課題解決原理)は,前記2(1)ア(イ)のとおり,二 股の美容器において,ハンドルを,凹部を有するハンドル本体と,その凹部 を覆うハンドルカバーで構成することにより,ハンドルが上下又は左右に分\n割された従来の構成よりも,ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとと\nもに,美容器の組み立て作業性が向上するようにしたというものである。そ して,本件発明に係る美容器は,美容器のハンドルを持ち,ローラを肌に押 し当ててこれを使用するから,本件発明の技術的思想(課題解決原理)によ って達成されるハンドルの成形精度や強度の維持は,美容器を使用する需要 者一般が関心を有する美容器の基本構造に関するものであり,二股美容器の\n使用やマッサージの施行に影響する事項であって,美容器全体に貢献してい るものと認められる。本件発明が需要者の商品選択に特段寄与しないとする 根拠はなく,被告各製品の販売に対する本件発明の寄与が限定的であるとす る根拠もない。したがって,本件において,本件発明の寄与率を考慮して推 定を覆滅すべき理由はない。
控訴人は,被告各製品は特許第5840320号の技術的範囲には属しな いが,同特許に係る発明の効果を有しており,そのような効果のあることが 被告各製品購入の主な動機になっていることは,本件における損害額算定に 当たっての推定覆滅事由として考慮されなければならないと主張する(前記 第2の5(4)ア(イ))。しかし,被告各製品が特許第5840320号に係る 発明の効果を有しているかどうかは明らかでなく,また,そのような効果の 存在が被告各製品購入の主な動機になっていることを認めるに足りる証拠は ない。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
◆平成29(ワ)32839
当事者が同じ関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。
◆平成31(行ケ)10032
当事者が同じ審決取消訴訟はこちらです。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.03.19
令和2(行ケ)10075 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年3月11日 知的財産高等裁判所
甲1発明及び甲3記載事項は,共に,弁当包装体という技術分野に属す るものであると認められる(甲1の段落【0001】,甲3の段落【0017】)。 しかし,甲1発明は,熱収縮性チューブを使用した弁当包装体について,煩雑な 加熱収縮の制御を実行することなく,包装時の容器の変形やチューブの歪みを防ぎ, また,店頭で,電子レンジによる再加熱をした際にも弁当容器の変形が生じること を防ぐことを課題とするものである(甲1の段落【0003】,【0004】)のに対 し,甲3に記載された発明は,ラベルを構成する熱収縮性フィルムについて,主収\n縮方向である長手方向への収縮性が良好で,主収縮方向と直交する幅方向における 機械的強度が高いのみならず,フィルムロールから直接ボトルの周囲に胴巻きした 後に熱収縮させた際の収縮仕上がり性が良好で,後加工時の作業性の良好なものと するとともに,引き裂き具合をよくすることを課題とするもの(甲3の段落【00 07】,【0008】)である。 そして,上記課題を解決するために,甲1発明は,非熱収縮性フィルム(21) と熱収縮性フィルム(22)とでチューブ(20)を形成し,熱収縮性フィルム(2 2)の周方向幅はチューブ全周長の1/2以下である筒状体であり,熱収縮性フィ ルム(22)の熱収縮により,弁当容器の外周長さにほぼ等しいチューブ周長に収 縮して弁当容器に締着されてなるものとしたのに対し,甲3に記載された発明の熱 収縮性フィルムは,甲3の特許請求の範囲記載のとおり,各数値を特定したもので ある。 これらのことからすると,甲1発明と甲3に記載された発明は,課題においても その解決手段においても共通性は乏しいから,甲3記載事項を甲1発明に適用する ことが動機付けられているとは認められない。
イ これに対し,被告は,甲1発明と甲3記載事項は,熱収縮という作用, 機能が共通する旨主張するが,熱収縮は,通常,弁当包装体が持つ基本的な作用,\n機能の一つにすぎないことを考慮すると,被告の上記主張は,実質的に技術分野の\n共通性のみを根拠として動機付けがあるとしているに等しく,動機付けの根拠とし ては不十分である。\nまた,被告は,甲1発明と甲3記載事項とでは,ポリエステルフィルムを用いて いる点が共通する旨主張するが,包装体用の熱収縮性フィルムを,ポリエステルと することは,本件特許の出願前の周知技術(甲1の段落【0010】,甲3の【請求 項7】,段落【0003】,甲6〔特開2008−280371号公報〕の段落【0 001】)であると認められ,ポリエステルは極めて多くの種類があること(乙5) からすると,材料としてポリエステルという共通性があるというだけでは,甲1発 明において,熱収縮性フィルムとして,甲3記載事項で示される熱収縮性フィルム を適用することに動機付けがあるということはできない。
ウ 以上によると,甲1発明において,熱収縮性フィルムとして,甲3記載 事項で示される熱収縮性フィルムを適用する動機付けがあると認めることはできな い。 したがって,甲1発明及び甲3記載事項に基づいて,相違点2に係る本件発明2 の構成とすることは,当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.03.14
令和2(ネ)1492 意匠権 民事訴訟 令和3年2月18日 大阪高等裁判所
ア 推定覆滅の割合について
前記引用に係る原判決において説示されているとおり(原判決43頁 14行目から51頁13行目まで)け,本件においては,意匠法39条2 項による損害額の推定は,7割の限度で覆滅されるというべきである。 控訴人は,控訴人の製品が被控訴人の製品より安価であることを理由 に,覆滅の割合を9割とすべきであると主張する。しかし,証拠(乙1 9)によれば,ここで控訴人が比較しているのは,外付け型 HDD につい ての控訴人の製品全体の平均単価と被控訴人の製品全体の平均単価で あって,原告製品の価格と被告製品の価格がどれだけ違うのかは明らか でない。被告製品が一般に原告製品より安価であるといえるとしても, 前記の7割という推定覆滅の程度は,このことをも考慮の対象とした上 でのものである。したがって,控訴人の主張を採用することはできない。
イ 実施料率について
前記引用に係る原判決において説示されているとおり(原判決52頁 5行目から53頁21行目まで),本件においては,意匠法39条3項 を適用して損害額を認定するに当たり(同条2項による損害額の推定が 覆滅される部分について同条3項を適用する場合を含む。),被控訴人 が本件意匠の実施に対し受けるべき料率(実施料率)は,5%を下らな いというべきである。 控訴人は,アンケート調査結果(乙45)を根拠として,本件におけ る実施料率は3%程度とすべきであると主張する。このアンケート調査 結果には,特許権のみの場合のロイヤルティ料率と特許権と意匠権を組 み合わせた場合のロイヤルティ料率が示されており,前者は,平均値が 約3.5%,中央値が約3.3%であり,後者は,平均値が約3.1%,中 央値が約2.9%であるから,確かに控訴人の指摘するとおり,後者の数 字の方が若干低くなっている。しかし,このアンケート調査の回答数は 必ずしも多くなく,特許権と意匠権を組み合わせた場合のロイヤルティ 料率についての回答数は全部で25にすぎないし,意匠権のみの場合の ロイヤルティ料率についての調査結果は存在しない。また,特許権,意 匠権それぞれ単独でロイヤルティ料率を設定する場合と,これを組み合 わせてロイヤルティ料率を設定する場合を比較すると,単純に,単独の 場合の料率を足したものが組み合わせた場合の料率になるとは考え難く, むしろ,組み合わせた場合の料率は,単独の場合の料率を足したものよ り低くなるのが一般的ではないかと考えられる。したがって,このアン ケート調査結果は,本件における実施料率を認定するに当たっては,あ くまでも参考資料の一つにとどまるといわざるを得ない。これに加え, 本件意匠自体の価値,被告製品の需要者がデザイン性を考慮する程度, 原告製品と被告製品とが競合品の関係にあることといった事情を総合的 に考慮すれば,本件における実施料率は5%を下らないというべきであ り,控訴人の主張を採用することはできない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2021.03.14
平成29(ワ)10716 特許権侵害差止等請求事件 特許権 令和3年2月18日 大阪地方裁判所
消費税は,国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されるものであるとこ ろ(消費税法4条1項),「例えば,次に掲げる損害賠償金のように,その実質が 資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当する ことに留意する。・・・(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財 産権の権利者が収受する損害賠償金」(消費税法基本通達 5-2-5)とされているこ とに鑑みると,特許権を侵害された者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金 を侵害者から受領した場合,その損害賠償金も消費税の課税対象となるものと推察 される。そうすると,特許権者が特許権侵害による損害のてん補を受けるために は,課税されるであろう消費税額相当分についても損害として受領し得る必要があ るというべきであるから,「利益」には消費税額相当分も含まれ得ると解される。 適用されるべき消費税率について,原告は,損害賠償支払時点の税率(10%) によるべきと主張する。
しかし,上記のとおり,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金に対する消費 税が課せられるのは,損害賠償金の実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認めら れることによる。ここで,資産の譲渡等に相当する行為と見られるのは,特許権侵 害行為である。また,消費税基本通達 9-1-21 では,「工業所有権等又はノウハウを 他の者に使用させたことにより支払いを受ける使用料の額を対価とする資産の譲渡 等の時期は,その額が確定した日とする。」とされている。これらのことに鑑みる と,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金は,特許権侵害行為時に直ちに損害 が発生して金額が確定するものであるから,資産の譲渡等の時期は,特許権侵害行 為時であると解される。 そうすると,本件においては,第1期間〜第4期間のいずれにおいても,本件特 許権侵害行為時の消費税率8%が適用されることとなる。
・・・・
本件明細書の記載によれば,本件発明の効果は,前記4(1)のとおりである。要 するに,本件発明の効果は,1)外観上の体裁の良さ及び室内側への風雨の進入防止 並びに2)取付強度の高さ及び風圧に対する耐久性の良さと,3)取付作業時に足場等 が不要となることによる施工コストの低減にあるといえる。もっとも,上記効果の うち1)及び2)は,手摺本体取付け後の効果であるため,取付方法に係る発明である 本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とは必ずしもいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ア) 本件発明は,手摺の取付方法に係る発明である。手摺を選択するのは,最終 的にはこれを取り付ける建築物の施主であるものの,手摺の取付方法そのものが施 主の関心を惹くとは考え難い。その意味で,本件発明に係る手摺の取付方法を実施 することは,製品選択の直接の動機となるとはいえない。 しかし,本件発明の効果1)〜3)は,いずれも建築物に取り付けるべき手摺製品の 選択の動機となり得る事情ということはできる。
(イ) もっとも,前記アのとおり,効果1)及び2)は,いずれも手摺本体取付け後の 効果であるため,取付方法に係る発明である本件発明によるのでなければ実現し得 ない効果とは必ずしもいえない。例えば,本件特許出願後に公開されたものである ものの,特開 2009-2283号公報(乙16。平成21年10月8日公開)には,手 摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数のガラス板等のパネルが取り付けら れ,パネル間にはパネル支持枠(アルミニウム系金属で構成されるものであり\n(【0012】),アルミ製目地枠に相当する。)を用い,パネルの上下左右全ての側 部が支持固定される手摺の構成が開示されている。そうすると,効果1)及び2)につ いては,本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たっては,必ずしも重視し得 るものではない。
(ウ) 他方,効果3)については,最終的な需要者(ないしこれに対して建築物に取 り付けるべき手摺を提案する手摺取付業者や建築物の開発業者等)にとって,顧客 誘引力を生じ得るものといってよく,本件発明の貢献の程度を評価するに当たって はこれを考慮に入れるべきである。 もっとも,複数階層の建築物の建築現場においては,手摺取付工事のための足場 は不要であっても,別工程のために足場の設置が必要となることは,当然あり得る (乙50〜54参照)。このため,このような場合は,結局は足場等設置に要する コストが発生し,施工コスト低減の効果がないか,あるとしても,設置期間短縮等 による限られた効果しか生じないものと合理的に推察される。 他方,このような事情は主として建築物の新築時や大規模修繕時のものであり, それ以外のメンテナンス時には,足場等を不要とすることによる施工コストの低減 という効果が発揮されることは考えられる。現に,乙42製品のカタログ(乙4 2)には,「パネルは室内側から取り付けられ,メンテナンス性に優れていま す。」と記載されている。また,原告製品のカタログ(甲15)においても,「ガ ラス嵌め込み工事における,外部足場が不要になります。」との記載があり,これ もメンテナンス性における優位性を指摘するものと理解される。ただし,建築物の 新築時及び大規模修繕時に比較すると,それ以外の機会にメンテナンスを実際に要 する例は,規模的にかなり少ないと推察される。 さらに,被告は,そのウェブサイト(甲3の1)において,被告製品の特徴とし て,ガラスの連続した意匠となること,4辺支持とすることでガラス厚を薄く設計 できるとともに,手すりの高耐風圧仕様となること,ガラスの縦枠への掛かり寸法 をガラス厚とし,安心な製品仕様としていることを挙げるものの,足場を組む必要 がないこと(その結果として施工費が安価になること)については触れていない。 加えて,本件発明に係る手摺取付方法によれば,ガラス取付業者においてガラス 板と目地枠を取り付けることができるとしても,それがどの程度施工コストの低減 に貢献する効果を有しているのかは明らかではない。
(エ) 以上によれば,本件発明は,施工コスト低減という効果(3))によりこれを 実施する製品の販売等に貢献するものであって,相応の顧客誘引力を有するといえ るものの,その程度は限られているというべきである。また,効果1)及び2)に関し ては,本件発明は,手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同 程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ア) 外観上の体裁の良さ等(1))について 証拠(乙27,29〜31,39,42。各枝番を含む。以下同じ。)によれ ば,乙27製品等は,いずれも,手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数 のガラス板が取り付けられ,ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認 められる。これにより,これらの製品は,本件発明の効果1)と同様の効果を奏する ものといえる。
(イ) 取付強度の高さ等(2))について 証拠(乙27,29〜31,39,42)によれば,乙27製品等は,いずれ も,ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠(縦枠,竪枠)を用い,ガラス取付 枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる (乙31製品については,「2辺支持タイプ」との記載もあるが(甲18),「4 辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある(乙31)。)。これにより,こ れらの製品は,本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指 摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的 にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件明細書によれば,取付 強度及び耐久性に係る本件発明の効果は,「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係 合保持され,隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し て」(【0013】)の強度に関するものに過ぎない。このほか,原告製品(証拠(甲 14,15)及び弁論の全趣旨より,本件発明に係る取付方法により取り付けられ るものと認められる。)と同様に,これらの製品の施工例として高層マンション等 の複数階層を有する建築物が示されていること(乙30,31,42)に鑑みて も,乙30製品,乙31製品及び乙42製品は,少なくとも,原告製品と競合し得 る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。 したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(ウ) 施工コストの低減(3))について 証拠(乙37〜42)によれば,乙27製品等は,いずれも,ガラス板とアルミ 製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり,ガラス板とアルミ製目地枠を\n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに より,これらの製品は,本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し,原告は,乙30製品,乙31製品及び乙42製品につき,アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指 摘する。しかし,上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程 度のものであるかは明らかでない。そもそも,本件発明の効果の1つである施工コ ストの低減は,足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって, アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること(乙30製品,乙31製品)や手摺 笠木部分の取付方法が回転式であること(乙42製品)による製造コストとは無関 係である。 したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(エ) その他 原告は,乙27製品及び乙29製品につき,本件特許権を侵害する製品である可 能性が高い旨を指摘する。しかし,原告も可能\性を指摘するにとどまるし,これら の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから,本件に おいては,この点は考慮に含めないこととする。
(オ) 以上より,乙27製品等は,いずれも,本件発明の効果と同様の効果を有す る製品として,原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当 である。 もっとも,原告は,原告製品を遅くとも平成24年3月までには販売していると 認められる(甲14,15,弁論の全趣旨)。他方,証拠(乙55)及び弁論の全 趣旨によれば,乙27製品等の販売開始時期は,乙31製品が平成24年,乙27 製品が平成26年,乙30製品が平成27年,乙29製品が平成28年3月,乙3 9製品が平成29年10月であることが認められる。 また,原告製品,被告製品及び乙27製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ ットレール製品市場におけるシェアは,いずれも証拠上明らかでない。
これらの事情を総合的に考慮すると,アルミ製手摺製品の市場において原告製品 及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば,特許法102条2 項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの,被告に よる主張立証の程度に鑑みれば,その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば,被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程 度は限られるものの,他方で,競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的 であり,他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから,本件におい ては,2割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに 反する原告及び被告の各主張は,いずれも採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2021.03.14
令和2(行ケ)10042 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月25日 知的財産高等裁判所
(ア) 原告は,本件明細書の段落【0111】の記載及び【図8】を指摘し, 本件決定が,訂正1イにおける「第3部材とは反対側」と本件明細書に記載された 「回転中心C3とは反対側」とは別意であると判断したことは誤りであり,訂正1 イ及び訂正2イにおける「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」は,第 1線分に対して第3部材の回転中心とは反対側をいうものと解釈すべきであると主 張する。 しかし,本件明細書の段落【0111】における「回転中心C3」は,「伝達軸8 2」の中心として特定されており(本件明細書の段落【0016】,【0056】), クランクシャフトの軸方向から見たときの径の大きさによって定義される「第3部 材」とは異なる概念であるから,「回転中心C3とは反対側」との記載を根拠として, 「前記第3部材とは反対側」の語をもって,第3部材の回転中心とは反対側と同義 ということができないことは,明らかである。 この点,原告は,訂正1イ及び訂正2イについて,誤記であることが明らかであ るとも主張するが,上記の点及び前記イで指摘した諸点に照らし,採用できない。
(イ) 原告は,本件明細書等には,上記「第3部材とは反対側」を「第3部 材の全体とは反対側」と解釈することの記載又は示唆はないと主張するが,前記イ で判示したところに照らし,原告の上記主張は採用できない。 また,原告は,そのように解釈した場合,【図8】の図示内容を始めとする本件明 細書等に記載された内容と整合しないことになるとも主張するが,そのような事情 があるからといって,前記イの判断が左右されるものでもない。
(ウ) 原告は,訂正1イ及び訂正2イの「前記第1線分に対して前記第3部 材とは反対側」からは,その技術的意義が一義的に明確にできないから,本件明細 書等を参酌して,訂正1イ及び訂正2イにおける「前記第1線分に対して前記第3 部材とは反対側」は,第1線分に対して第3部材の回転中心とは反対側をいうもの と解釈すべきであると主張する。 しかし,前記イのとおり,「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」の意 義(意味内容)自体は,一義的に明確であって,前記イのように解することができ るというべきである。
(2) 訂正1イ及び訂正2イが本件明細書等に記載した事項の範囲内のものであ るかどうか
ア 上記(1)のとおり,訂正1イ及び訂正2イにおける「前記第1線分に対し て前記第3部材とは反対側」は,第1線分によって区切られる領域の片側に第3部 材の全体が存在することを前提とし,それが存在する側と第1線分を挟んで反対側 をいうものと解すべきところ,そのような構成は,本件明細書には,「基板」を図示\nしている【図8】,【図9】及び【図11】を含め,全く記載されていない。 そして,「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」を上記のとおり解する と,訂正1イ及び訂正2イは,第3部材について,第1線分に重ならないという構\n成に限定するものとなるが,そのように限定する技術的意義については,本件明細 書等には記載がない。他方で,「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」を 上記のとおり解すると,訂正1イ及び訂正2イは,同時に,本件訂正前の請求項1 及び9では,第1部材〜第3部材の各定義に照らし,モータか第1伝達歯車のいず れかという限度にまでしか特定されていなかった「第3部材」について,モータで はない(すなわち第1伝達歯車である)という限定を加える結果をもたらすもので あるが,それは,応用例に係る本件明細書の段落【0157】及び【図15】で, 「第3部材」と解される「クランクシャフト54の軸方向から見たときの径が最も 小さい部材」が「モータ60」とされていることと相容れないものである(なお, 上記段落及び図では,そもそも請求項1及び9における「第1線分」すなわち第1 部材の回転中心と第2部材の回転中心とを結ぶ線分が「線分S1」ではなく「線分 S3」 と記載されており,上記「第1線分」の定義との関係自体も必ずしも明らか でない。)。 そして,その他,本件明細書に,第1線分によって区切られる領域の片側に第3 部材の全体が存在することを前提とし,それが存在する側と第1線分を挟んで反対 側における基板の位置について記載されていないにもかかわらず,訂正1イ及び訂 正2イが本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたというべき事情は認 められない。 そうすると,訂正1イ及び訂正2イは,いずれも,本件明細書等に記載した事項 の範囲内においてしたものということはできない。
イ(ア) 仮に,原告の主張するとおり,訂正1イ及び訂正2イにおける「前記 第1線分に対して前記第3部材とは反対側」について,第1線分に対して「第3部 材の回転中心」とは反対側をいうものであると解したとしても,以下のとおり,訂 正1イ及び訂正2イは,本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたもの ということはできない。
a 本件明細書の段落【0111】,【0113】及び【0118】の記 載並びに【図8】,【図9】及び【図11】によると,本件明細書には,訂正1イ及 び訂正2イに含まれる「前記基板は,前記クランクシャフトの軸方向から見た場合 に,前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側において前記被駆動歯車に重な る領域及び前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側において前記モータと重 なる領域を有する,駆動ユニット」の構成のうち,第1部材が被駆動歯車,第2部\n材がモータ,第3部材が第1伝達歯車である場合の実施例が記載されていると認め られる。 しかし,本件訂正後の請求項1及び9においては,基板の構成について,上記の\n特定がされているのみであるので,被告が主張する五つの態様のもの(前記第4の 1(2)イ(イ),(ウ)。以下,併せて「被告主張の別態様」という。)も含まれることに なるが,これらは本件明細書等には記載されていない。
b また,前記1(2)オのとおり,本件明細書には,「基板」の位置を上 記のとおり特定したこと,殊に,基板が被駆動歯車及びモータと重なる領域が第1 線分に対して「第3部材とは反対側」の領域であることについて,本件発明の課題 との関係でいかなる技術的意義を有するかの記載はなく,それを認めるに足りる技 術常識があるとも認められない。したがって,訂正1イ及び訂正2イの上記構成が\nいかなる技術的意義を有するかは不明というほかない。
c そうすると,本件訂正後の請求項1及び9は,その技術的意義が明 らかでない,本件明細書等に記載のない被告主張の別態様を含むこととなるところ, 被告主張の別態様中には,本件明細書に記載された上記aの実施例と比較して「基 板」の技術的意義が共通するものと直ちにみ難いものが含まれているといえるから, このような訂正は,本件明細書等に記載した事項の範囲内でされたものということ はできない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2021.03.14
令和2(行ケ)10058 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月25日 知的財産高等裁判所
ア 周知技術について (ア) 昭和53年に出願され,昭和54年に公開された実用新案登録願(甲 64)には,前記4(3)のとおり,小児用手術台は,患者の身長の長短によって,長 すぎたり,短かすぎて,医師が適切な診療処置を行うのに不便であったこと,この ことから,医師が適切な診療処置を行うためには,手術台の長さを,患者の身長に 応じたものにする必要があったこと,そのために,小児用手術台の患者受板部を, 中央受板部の前後に連結される頭受板及び足受板の他に,複数の補助受板で構成し,\n小児から中年の患者の身長に応じて各受板を適宜組み合わせ連結して手術台を形成 することが記載されていると認められる。
・・・
(ウ) 前記4(5)のとおり,昭和53年〜昭和55年に,日本において,小児 外科用手術台であるMOC−1800が販売されていたが,そのカタログ(甲76) によると,前記4(5)のとおり,同手術台は,主枠の両側に,腰板,背板,脚板,枕 板(頭部受板)及び補助板を取り付けることができ,その組合せにより,様々な長 さのテーブルトップを形成することができることが認められ,また,同カタログに は,「全長60〜187cmの間で幼少児の身長に応じて全長が選べる」,「21種類 の組合せの中より小児の身長に応じて,テーブルトップの全長を選択してください。」 などの記載がある。この事実からすると,患者の身長に応じて,長さの異なるテー ブルトップを備える手術台の需要があったこと,この需要に対応するために,主枠 の両側に,腰板,背板,脚板,枕板(頭部受板)及び補助板を組み合わせて,様々 な長さのテーブルトップを形成できる手術台が販売されていたことが認められる。
・・・
(オ) 以上の事実からすると,本件特許の出願時には,手術台のテーブルトッ プは,患者の身長に応じた長さとすることが望まれており,医療機関において,テ ーブルトップの長さを調整できる手術台の要望があったこと,その要望に応えるた めに,各種の大きさのコンポーネントを組み合わせて,適宜の長さのテーブルトッ プとする手術台が販売されており,また,小児外科においては,長さが可変の手術 台が一定程度普及していたことが認められる。
・・・
前記5(3)イのとおり,製品1発明3)においては,患者の頭部側から順に,1)背板, 座板,足板の組合せ,2)背板(短),座板,背板の組合せ,3)背板(短),座板,足 板の組合せを適宜選択し,各組合せによるテーブルトップとし,また,4)各種頭板, 背板,座板,足板の組合せ,5)各種頭板,背板(短),座板,背板の組合せ,6)各種 頭板,背板(短),座板,足板の組合せを適宜選択し,各組合せによるテーブルトッ プとすることが可能であり,上記1)の組合せを上記2)の組合せに変更することや上 記2)の組合せを上記3)の組合せに変更すること,上記4)の組合せを上記5)の組合せ に変更することや上記5)の組合せを上記6)の組合せに変更することも可能であると\nころ,甲1,2,4及び5には,これらの組合せを禁止したり,推奨しない旨の記 載もなく,かえって,前記3のとおり,甲2には,「マッケ手術台システム1120 は,モジュール方式でデザインされ」(2頁),「広く世界的に採用されている非常に フレキシブルなモジュール方式の手術台システムです。」との記載がある。
そして,前記イのとおり,製品1において,患者の背が高い場合には,足側の背 板の先に頭板を付け加える使用方法が行われていたことからすると,前記アのとお り,手術台のテーブルトップを患者の身長に応じた長さとすることが望まれており, その要望に応えるために各種のコンポーネントを組み合わせることなどが行われて いることを知る当業者は,製品1発明3)において,患者の身長に対応させるために 各種モジュールを取り換えて手術台を患者の身長に対応したものとすることを容易 に想到することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ア) 被告は,背板(短)は頭部手術という特定の用途のためにのみ頭板と 共に使用されると主張する。 しかし,甲5の20頁には,背板(短)に頭板「1002.62」と取り付けら れた写真が載っているが,同頁の表題は「眼科,ENT,一般外科,麻酔科」と表\ 記されていることから,背板(短)は,必ずしも,特定の用途のために頭板と共に 使用されるとは認められない。 また,患者の頭側に頭板を取り付けた背板(短)を配置した場合,前記5(3)イの とおり,足側は背板又は足板を配置することが可能であり,足側の背板を足板に交\n換すれば,テーブルトップの全長も変わるから,被告の主張を前提としても,使用 者の体格に対応して,床板を支えるフレームを交換したことになる。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
(イ) 被告は,製品1の具体的な構成は,それぞれが独立した構\成であり,そ れらの構成を組み合わせることにより相違点を解消することはできないと主張する。\nしかし,製品1発明3)の構成は,前記5(2)のとおりであるところ,同構成は,背\n板,座板及び足板の各コンポーネント並びに背板(短)及び各種頭板のアクセサリ ーを含めて,一つの製品である製品1から認定できる技術的構成であるから,一つ\nの発明の構成である。そして,前記イの実施態様も製品1の実施態様であるから,\nこれを考え併せて,製品1発明3)から本件発明を容易に想到することができるとい うべきである。
(ウ) 被告は,原告の主張は,「設計事項」という名目の下,甲61以下の証 拠に基づく異なる構成(公知事実)を組み合わせることにより相違点を解消できる\nという新たな進歩性欠如の主張をするものであり,本件訴訟の審理事項から排除さ れるべきものであると主張するが,前記アの周知技術を本件発明の進歩性を判断す るに当たっての当事者の技術水準を示すものとして考慮することはできるのであり, 前記ウの判断はそのような趣旨で考慮したものであるから,本件訴訟の審理範囲外 ではない。
(3) 以上より,取消事由2は理由がある。
7 そうすると,その余の取消事由について判断するまでもなく,原告の主張し た無効理由は認められないとした本件審決の判断は誤りであるから,本件審決は取 り消されるべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2021.03.14
令和2(ネ)10045 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(ア) 図105ドットパターンにおいては,情報ドットは,四隅を格子ドッ トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ,本件補正1 1)部分に当たる構成要件B1の情報ドットは,「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。\n図105には,水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引 かれているが,当初明細書1に,「格子状に配置されたドットで構成されている。」(【0185】),「格子ブロックの四隅(格子線の交点\n(格子点)上)には格子ドットLDが配置されている」(【0186】), 「4個の格子ドットLDの正中心に配置したドットである(図106(a) 参照)」(【0197】)と記載されているとおり,格子ドットは等間 隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり,格子線は格子ドットを結ぶラインであるから,図105に示さ\nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を 示すために参考として引かれた補助線にすぎず,格子線とは認められな い(図106(a)のように,格子ドット同士を対角線で結べば,その 交点は「格子線の交点」となるが,その線は構成要件B1に規定する「縦横方向」のラインではない。)。\n そうすると,「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格 子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正11)部分は,図105のドットパターンとは似て非なる ものであり,そもそも図105ドットパターンに基づく補正であるとは 認められない。
(イ) 図5ドットパターンにおいては, 情報を表現するドットは,格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ,構\成要件B1の情報ドットは「格子点の中心から等距離で45°ずつずらし た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから,本件補正 11)部分は,図5ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか,当初明細書1に本件補正11)部分に対応する記載は認め られないから,本件補正前発明1の本件補正11)部分に対応する部分と 構成要件B1とを対比するまでもなく,本件補正11)部分は新たな技術 的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明3の特許請求の範囲の記載(分説後のもの)は,次のとおり である(引用に係る原判決の「事実及び理由」第2の2(5)ウ参照)。
A3 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと,
B3 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから 等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと,
C3 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ ンと,前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ れた水平ラインとの交点を格子点とし,該格子点からのずれ方でデータ 内容が定義された情報ドットと,からなるドットパターンであって,
D3 前記垂直方向に配置されたドットの1つは,当該ドット本来の位置 からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している E3 ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件B3の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と,\n構成要件C3の「前記垂直方向に配置されたドット」と,構\成要件D3 の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される から,この一つの「垂直方向に配置されたドット」は,垂直方向に「等 間隔」に配置される一方で(構成要件B3),「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており,その「ず\nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが,これを合 理的に解釈するならば,「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され たドット」以外のドットに係り,この一つの「垂直方向に配置されたド ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので あり,そのずらされる方向,距離とも何ら限定はないと解するほかない。 また,本件発明3は,「ずらし方によって前記ドットパターンの向き を意味している」(構成要件D3)としているから,「ずらし方」,すなわち,本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直\n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され, 本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図105ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書3には,図103ないし106のほか,次の記載がある。
「【0239】 また,本発明のドットパターンでは,キードットのずらし方を変更す ることにより,同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる ことができる。つまり,キードットKDは格子点からずらすことでキー ドットKDとして機能するものであるが,このずらし方を格子点から等距離で45度ずつずらすことにより8パターンのキードットを定義でき\nる。
【0240】 ここで,ドットパターン部をC−MOS等の撮像手段で撮像した場合, 当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが,こ のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸(撮影軸)を中心に回動され た位置,すなわち撮影軸を中心にして回動した位置(ずれた位置)にあ る場合には,撮像された格子ドットとキードットKDとの位置関係から 撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ(カメラの角度)がわかることにな る。この原理を応用すれば,カメラで同じ領域を撮影しても角度という 別次元のパラメータを持たせることができる。そのため,同じ位置の同 じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【0241】 いわば,同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき ることになる。
【0242】 この原理を応用したものが図74,図76,図78に示すような例で ある。図74では,ミニフィギュア1101の底面に設けられたスキャ ナ部1105でこのミニフィギュア1101を台座上で45度ずつ回転 させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を 得ることできるため,8通りの音声内容を出力させることができる。」 (図74,76及び78については本判決への添付を省略する。)
(イ) 上記(ア)の記載は,構成要件D3との関係においては,確かに,格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味\nすることを記載するものといえる。 しかしながら,構成要件C3との関係について見れば,本件発明3は,「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構\成を有するところ,前記2(1)ウのとおり(引用に係る原判決の「事実及び 理由」第3の1(補正後のもの)のとおり,当初明細書1と本件明細書 3の関連部分の記載はいずれも同じである。),図105ドットパター ンにおいては,情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か らずらすことによってデータ内容を定義するものであって,格子ドット からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない(構成要件C3は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから,構成要件 C3が図105ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな い。)。 そうすると,本件発明3は,図105ドットパターンに関する記載に 係るものとはいえない。
ウ 図5ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書3には,図2,5ないし8のほか,次の記載がある。 「【0069】 ・・・図5から図8は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【0070】 上述したようにカメラ602で取り込んだ画像データは,画像処理ア ルゴリズムで処理してドット605を抽出し,歪率補正のアルゴリズム により,カメラ602が原因する歪とカメラ602の傾きによる歪を補 正するので,ドットパターン601の画像データを取り込むときに正確 に認識することができる。
【0071】 このドットパターンの認識では,先ず連続する等間隔のドット605 により構成されたラインを抽出し,その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ\nンを抽出する。
【0072】 次に,抽出したラインの1つを水平ラインとする。この水平ラインを 基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは,水 平ラインを構成するドットからスタートし,次の点もしくは3つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。\n
【0073】 最後に,情報領域を抽出してその情報を数値化し,この数値情報を再 生する。」 (イ) また,引用に係る原判決の「事実及び理由」第3の4(2)(補正後のも の)とおり,図5及び図7では,左端の垂直ラインに配置されたドット の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ ンに沿って左側に配置され,「x,y座標フラグ」とされていることが 示され,図6及び図8では,左端の垂直ラインに配置されたドットの一 つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに 沿って右側に配置され,「一般コードフラグ」とされていることが示さ れている。
(ウ) 本件発明3は,「前記垂直方向に配置されたドットの1つは,当該ド ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意 味している」(構成要件D3)ことを特徴とするドットパターンであるところ,図5ドットパターンに関し,本件明細書3には,前記(ア)のとお り,「垂直ラインは,水平ラインを構成するドットからスタートし,次の点もしくは3つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す\nる。」(【0072】)との記載がある。しかしながら,これは,垂直 ライン上の特定位置(本来の位置)にドットがないことによってドット パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって,「ドット本来 の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載 とはいえない。 また,前記(イ)のとおり,図5ないし8には,他のドットから形成され る垂直ラインから左右にずれたドットが示され,それらドットが「x, y座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ であることが記載されている。しかしながら,引用に係る原判決の「事 実及び理由」第3の4(2)(補正後のもの)によれば,「x,y座標フラ グ」(図5及び7)がある場合には,情報を表現する部分のドットパターンはXY平面上の特定の座標値を示し,「一般コードフラグ」(図6\n及び8)がある場合には,情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード(番号)を示すものと認められる。そうすると,「x,y\n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは,情報を 表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず,フラグとしてその位置を認\n識され,ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって ドットパターンのデータの内容を定義しているが,ドットパターンの向 きを意味しているものではない。そして,そのほか,図5ないし8には, ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし,データ の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット を兼ねるとの記載もない。
さらに,「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき,その本来の 位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特 徴とする本件発明3の実施形態について,上記ドットがどのような方向, 距離において配置されるのかについては,本件明細書3にはその記載は ない。 以上によると,図5ドットパターンは,「ずらし方によって前記ドッ トパターンの向きを意味している」(構成要件D3)との構\成を有しな い。 そうすると,本件発明3は,図5ドットパターンに関する記載に係る ものともいえない。
エ 控訴人は,1)図5ないし8において,「x,y座標フラグ」又は「一 般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され ている,2)本件明細書3の段落【0239】ないし【0241】,【図 105】,【図106】の(d)の記載を参酌すれば,キードットにデータ 内容を定義する機能とドットパターンの向き(角度)を意味するという機能\を持たせ得ることが示されている,3)本件明細書の段落【0230】 の記載から,「x,y座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード ットと同様の機能が備わると理解できる,4)本件明細書3の【0072】 では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように しているし,本件明細書3の図5ないし8には「x,y座標フラグ」又 は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実 際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている,5)「x,y座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」 がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。\n
しかしながら,前記ウで認定したとおり,図5ないし8においては, ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず,控訴人 主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから,上 記1)の主張は採用することができない。 また,【0239】ないし【0241】,【図105】,【図106】 の(d)の記載は,図105ドットパターンに関する記載であり,図105 ドットパターンと図5ドットパターンを組み合わせることは新規事項の 追加となることは前記2にて判断したとおりであるから,そのような組 み合わせをしたのであれば,それ自体からしてサポート要件を欠くこと になり,上記2)の主張は失当である。
次に,図105ドットパターンに関する記載である段落【0230】 (引用に係る原判決の「事実及び理由」第3の2の【0230】III)部分 参照)には「本発明におけるドットパターンの仕様について図103〜 図106を用いて説明する。」との記載があるだけであり,これにより 「x,y座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図105ドット パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから,上記3)の主張は採用することができない。 さらに,控訴人の上記4)及び5)の主張については,確かに,ドットパ ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対 称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ り,また,図5ないし8に記載された「x,y座標フラグ」又は「一般 コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから, これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可 能である。しかしながら,本件明細書3は,そのような構\成としたもの と理解すべき記載となっておらず,「本来の位置からのずらし方」とし てどのような選択に従い本件発明3を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは,前記ウで示したとおりである。したがって,\n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり,技術常識を踏まえても,当業者において,本件発明3 が本件明細書3の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで きないというべきであるから,本件発明3に係る本件特許3は,特許法 36条6項1号に違反し,特許無効審判により無効とされるべきもので ある。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.03.12
令和2(行ケ)10088 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年2月22日 知的財産高等裁判所
原告は,1)原告キャラクターと本願商標との密接不可分的なつながり,2) 原告キャラクター及び原告ウェブサイトの周知著名性,3)不動産業界の取引 の実情を考慮すると,本願商標からは,原告キャラクターの観念,さらには 原告による各種不動産情報の提供の役務という観念が生じる旨主張する。こ の主張は,取引の実情を考慮すると,本願商標から,上記の各観念が生じる と主張しているものと解される。 しかしながら,証拠(甲34〜39,41)によれば,原告が,原告キャ ラクターを利用した宣伝広告活動や営業活動を展開しており,原告キャラク ターやその愛称である「ホームズくん」がそれなりの知名度を有するに至っ ていることは認められるものの,他方で,参加人も,引用商標1やそれに類 似した標章,「ホームズ君」という名称等を利用して宣伝広告活動や営業活 動を行っており,相応の知名度を得るに至っていること(丙20〜323) 等の事情に照らしてみると,本願商標の指定役務に係る取引分野において, 「ホームズくん」といえば原告キャラクター,ひいては原告の営業を表すと\n取引者,需要者の誰もが理解するといえるほどの一般的,普遍的な観念が成 立するに至っているとまで認めることはできない。そして,単に,原告が「 ホームズくん」という愛称の原告キャラクターを利用しており,それが,一 定程度の知名度を有しているという程度のことであれば,それは,せいぜい 本願商標に係る個別的な事情であるにとどまり,取引の実情として考慮する ことが許される,指定商品・役務全般についての一般的・恒常的事情(最高 裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日第一小法廷判決・審決取消 訴訟判決集昭和49年443頁参照)には当たらない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
3 引用商標1の外観・観念・称呼について
(1) 引用商標1は,別紙審決書写しの別掲2のとおり,「ホームズ君」部分, 「耐震フォーラム」部分,引用図形部分から成る結合商標である。 ア 引用商標1は,外観上,「ホームズ君」部分,「耐震フォーラム」部分 及び引用図形部分の三つが分離されないような態様で構成されているもの\nではない。そして,「ホームズ君」部分及び「耐震フォーラム」部分と引 用図形部分とは,文字と図形との違いに加え,色彩においても大きく異な っており,外観上密接不可分な関係にないことは明らかである。他方,「 ホームズ君」部分と「耐震フォーラム」部分とは,色彩が青色で統一され ており,字体も共通するようにみられるものの,改行により二列になって いて一体性に乏しい上,前者は文字が青であるのに対し,後者は,青の背 景に白抜きで文字が表されている点でも異なり,更に文字の大きさも異な\nるため,やはり外観上密接不可分な関係にあるとはいい難い。 また,「ホームズ君」部分,「耐震フォーラム」部分,引用図形部分の 三者が,称呼,観念において密接不可分の関係性を有していると認めるだ けの根拠を見出すこともできない(なお,後のイで述べるとおり,「ホー ムズ君」部分と引用図形部分には,観念において一定の関係があると理解 することも可能であるが,そうであるとしても,「ホームズ君」部分を要\n部として抽出し得るという結論に変わりがないことは,後に述べるとおり である。)。 したがって,引用商標1は,各構成部分を分離して観察することが,取\n引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないか ら,各部分を分離して観察することも許されるものというべきである。
イ そして,「ホームズ君」の文字は,それ自体としてみれば,商品・役務 の出所識別標識としての機能を十\分に果たし得るものであるといえること, 「ホームズ君」部分は,引用商標1の他の部分に比べると小さいとはいえ, 十分に認識可能\な形で記載されており,出所識別標識としての機能を果た\nし得ないほどに他の部分に埋没してしまっているとはいえないこと等の事 情に照らしてみると,「ホームズ君」部分を,引用商標1の要部として抽 出することは十分に可能\であるということができる。 他方「耐震フォーラム」部分を構成する「耐震」及び「フォーラム」は\nいずれも普通名詞であって(乙7・8(大辞林第三版)),これらを結合 した「耐震フォーラム」の語は,建築物等の耐震性に関する講演会・討論 会を指称するためしばしば使用されていること(乙9〜19(各種の専門 新聞・一般日刊新聞))に照らすと,引用商標1が例えば「不動産に関す るセミナーの企画・運営」に用いられた場合には,「耐震フォーラム」部 分は,「建物の耐震性に関する講演会・討論会」程度の意味合いを認識さ せるにすぎず,出所識別標識としての称呼・観念を生じさせるとはいえな い。
また,引用図形部分は,全体としてみると,探偵風の装束をした人物が 家を観察している場面を描いたものと受け取れ,横にある「ホームズ君」 部分を併せ見ることにより,家を観察する名探偵ホームズといった観念を 生ずる余地があるが,仮にそうであるとしても,それは,「ホームズ君」 のイメージを視覚的に描き出したものであって,「ホームズ君」部分を補 完するものにすぎないと理解すべきであるから,独立して出所識別機能を\n果たすとまで見ることはできない。 以上によれば,本件においては,引用商標1から抽出した「ホームズ君 」部分と本願商標との比較によって類否を判断すべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2021.03.11
令和2(行ケ)10104 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年2月22日 知的財産高等裁判所
商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された 場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否か によって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外観,観念,称 呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべ く,しかも,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その 具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行 ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁, 最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集5 1巻3号1055頁参照)。
また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構\成部 分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分 的に結合していると認められる場合においては,その構成部分の一部を抽出し,\nこの部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは,原則として許さ れないが,その場合であっても,商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に\n対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や, それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じない場合などには, 商標の構成部分の一部だけを取り出して,他人の商標と比較し,その類否を判\n断することが許されるものと解される(最高裁昭和37年(オ)第953号同 38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成 3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5 009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷 判決・裁判集民事228号561頁参照)。 以下,上記の判断枠組みに沿って,本願商標及び引用商標の類否について検 討する。
2 原告の主張1(分離観察の可否)について
(1) 本願商標について
ア 商標の構成\n
(ア) 本願商標は,黒色の長方形図形を背景として,左側から順に,本願 漢字部分及び本願欧文字部分が配置された結合商標であり,両部分は, ほぼ同じ高さで横一列に,重なり合うことなく配置されている。
(イ) 本願漢字部分は,「旬」の漢字1文字からなる。この文字は,赤色の 毛筆体で描かれており,本願欧文字部分の各文字の4倍程度の大きさで ある。また,本願漢字部分は,やや図案化されているものの,その程度 は低いといえる。
(ウ) 本願欧文字部分は,同じ幅で上下2段に配置された「JAPAN」 及び「SHuN」の欧文字からなり,これらの文字は,いずれも白色の 毛筆体で描かれている。また,本願欧文字部分は,本願商標のうち2分 の1程度の幅を占めている。
イ 分離観察の可否
(ア) 本願漢字部分は,漢字1文字が赤色で大きく描かれているのに対し, 本願欧文字部分は,上下2段に配置された複数の欧文字が白色で描かれ ており,両部分の文字の大きさや色彩,文字種,構成等は,明らかに異\nなるといえる。また,本願漢字部分及び本願欧文字部分は,ほぼ同じ高 さで横一列に配置されてはいるものの,重なり合うことなく配置されて いる。そうすると,本願漢字部分及び本願欧文字部分は,それぞれが独 立したものであるとの印象を与え,視覚上分離して認識されるものとい える。 また,本願欧文字部分は,本願商標のうち2分の1程度の幅を占めて おり,看者の目を引きやすいとはいえるものの,他方で,本願漢字部分 は,その色彩や大きさからすれば,相応に目立つ態様で表示されている\nといえるから,本願商標に接した者は,本願欧文字部分のみならず,本 願漢字部分にも注意を引かれるものといえる。なお,黒色の背景部分は, 視覚上,特段の印象を与えるようなものではない。
(イ) また,本願漢字部分は,平易な漢字である「旬」の文字を表したも\nのであるから,同部分からは,「シュン」との称呼が生じるとともに,日 常用語として「魚介・野菜・果物などがよくとれて味の最もよい時」等 (乙2)を意味する「旬」の観念が生じるものといえる。 他方で,本願欧文字部分は,上下2段に配置された「JAPAN」及 び「SHuN」の欧文字からなるものであるところ,平易な英語である 「JAPAN」の文字からは,「ジャパン」との称呼が生じるとともに, 「日本」の観念が生じるが,「SHuN」の文字は,外国語の成語である とは認められず,特定の意味合いを表す語であるとも認められないから,\n同文字からは,いわゆるローマ字読みによって「シュン」との称呼が生 じ得るとはいえるものの,特定の観念は生じないというべきである。そ うすると,本願欧文字部分からは,特定の観念が生じるものではないと いうべきである。
以上のとおり,本願漢字部分は,本願欧文字部分との間において,「S HuN」の文字部分と称呼が共通し得るのみであり,これ以外の部分と は,称呼の面からみても,観念の面からみても,共通するところはない から,本願漢字部分及び本願欧文字部分は,統一性のある称呼又は観念 によって結び付けられているものではないというべきである。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)で検討したところによれば,本願漢字部分及び本 願欧文字部分は,それぞれが独立したものであるとの印象を与え,視覚 上分離して認識されるものといえる上,称呼又は観念上の関連性がある ものとはいえない。 そうすると,本願漢字部分及び本願欧文字部分は,本願漢字部分のみ を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的 に結合しているものとは認められない。そして,前記のとおり,本願漢 字部分は,相応に目立つ態様で表示されているといえることからすれば,\n本件においては,本願商標から本願漢字部分を抽出し,同部分のみを他 人の商標と比較して類否を判断することが許されるというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2021.03.11
令和2(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月24日 知的財産高等裁判所
本件審決は,前記2(1)イ〔本判決22頁〕のとおり,原告が主張する式及 び説明に基づいて本件発明を実施するとしても,当業者に過度の試行錯誤を 要するものと判断した。
(2) 判断の誤りの有無とその理由
ア しかし,本件審決の前記(1)の判断は誤りである。その理由は,次のイの とおりである。
イ(ア) 前記2(3)イ(エ) 〔本判決27頁〕のとおり,前記2(3)イ(ウ) 〔本判 決27頁〕の式中の各項目のうち,θ以外の項目を適宜設定し,Fsが, θが増加する所定角度範囲内において徐々に減少するような構成を実\n現することにより,構成要件Gにおける「エプロンを跳ね上げるのに要\nする力は,エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」 するとの構成は実現されるものと認められるところ,前記2(3)イ(ウ〔本) 判決27頁〕の式中の各項目のうち,θ以外の項は複数存在することか ら,それらについて適切な数値の組合せを見出して本件発明に係る作業 機を作成して本件発明を実施するために過度な試行錯誤を要するかを 検討することが必要となる。
この点に関し,原告は,【図2】に記載された各支点の基本的な位置関 係に基づき,構成要件Gの「エプロンを跳ね上げるのに要する力」と「エ\nプロン角度」の変化曲線をシミュレーションし,甲60(審判乙14) の7頁のグラフ(別紙図4)の結果を得た。そして,同グラフによれば, 【図2】に記載された作業機の位置関係を基礎にして,第3の支点15 2の位置を,第1の支点140を中心として25°下方に移動させた「第 1の作業機」において,「第1の姿勢」(作業機が水平より33°前傾し た状態)の場合(同グラフの青色線)には,エプロンを跳ね上げるのに 要する力は,エプロン角度が0°から60°に変化する間に,250N から0Nに徐々に減少したことが認められ,「第2の姿勢」(作業機が水 平より18°前傾した状態)の場合(同グラフの黄色線)には,エプロ ンを跳ね上げるのに要する力は,エプロン角度が0°から60°に変化 する間に,約230Nから約75Nまで徐々に減少したことが認められ る。また,甲64(審判乙18)の6頁のグラフ(別紙図5)によれば, 「第1の作業機」において,「最上姿勢」(トラクタ油圧機構で作業機を\n最も持ち上げた位置,入力軸が水平より30.5°前傾した状態)の場 合,エプロンを跳ね上げるのに要する力は,エプロン角度が0°から6 0°に変化する間に,約230Nから約20Nまで徐々に減少したこと が認められる。そして,前記4(2)イ(ア)〔本判決43頁〕のとおり,これ らの場合は,エプロンを跳ね上げるのに要する力が,一般的な作業者が 感じることができる程度に徐々に減少したものと認められる。そうする と,これらのシミュレーションにより,構成要件Gの実施が可能\である ことが立証されたものと認められる。 これらのシミュレーションは,コンピュータを用いたものと推認され るが,その実施が特に困難であったとは認められず,上記の結果を得る ために過度の試行錯誤が必要であったことを窺わせる事情はない。 したがって,前記2(3)イ(ウ)〔本判決27頁〕の式中の各項目のうち, θ以外の項目について適切な数値の組合せを見出して本件発明に係る作 業機を作成して構成要件Gの「エプロンを跳ね上げるのに要する力は,\nエプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」するとの 構成を実施するために,当業者は過度の試行錯誤を要しないものと認め\nられる。
(イ)a 被告は,本件明細書の【0028】には「上記実施例の各支点の位 置関係からこのような荷重の傾向が観察される。」と記載されており, 【図2】の作業機の支点の位置により【図7】のグラフが得られたこ とが明らかにされているとした上,原告が,力学的なシミュレーショ ンにより「エプロンを跳ね上げるのに要する力」が「エプロン角度が 増加する所定角度範囲内において徐々に減少」する変化曲線を得たと する「第1の作業機」(別紙図2の青色で記載された構造)は,【図2】\nの作業機とは第3の支点(152)の位置が異なり,本件明細書,本 件特許の特許出願の願書に添付された図面に記載されていないもの であるから,「第1の作業機」を用いて得た甲60(審判乙14)の7 頁のグラフ及び甲64(審判乙18)の6頁のグラフに基づいて,本 件発明の構成要件Gが実施可能\であるとする原告の主張は誤りであ ると主張する。
しかし,【図2】の作業機は,本件発明の構成を説明するための作業\n機の一例であるところ(【0016】),本件発明の特許請求の範囲にお いて,支点の位置に関しては,第2の支点及び第3の支点の位置につ いて,アシスト機構が両支点を通る同一軸上で移動可能\であること (構成要件E)が定められているのみであることからすると,その定\nめを充たしていれば,本件発明の作業機における第2の支点及び第3 の支点の位置は,【図2】に示される具体的な位置と同じである必要は ない。そして,特許出願の願書に添付される図面は,設計図のように 寸法等が正確なものが求められるものではなく,発明の技術内容を理 解できる程度の精度で表現されていれば足りるものであり,【図2】も,\n本件発明の構成を説明するために示されたものであって,設計図のよ\nうに厳密な形状や寸法等を具体的に示したものとは認められないか ら,【図2】の作業機とは第3の支点(152)の位置が異なるのみで 全体の構成が同じであり,構\成要件Eも満たしている「第1の作業機」 において,構成要件Gの「エプロンを跳ね上げるのに要する力は,エ\nプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」するとい う構成が実施可能\であることが示されていれば,本件発明の構成要件\nGは実施可能であると認められる。本件明細書の【0028】には「上\n記実施例の各支点の位置関係からこのような荷重の傾向が観察され る。」と記載されているが,本件発明の構成が特許請求の範囲により特\n定されていることからしても,上記の【0028】の記載は,本件発 明の作業機における第2の支点及び第3の支点の位置が【図2】に示 される具体的な位置と同じであることまでを要求するものとは認め られない。したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
b 被告は,「第1の作業機」の計算に用いたガススプリング(甲65(審 判乙19))は,直径をφ16mmにした「オールガスタイプ」のもの であり,【図5】及び【図6】に記載された「フリーピストンタイプ」 のものでないところ,【図5】及び【図6】に記載された「フリーピス トンタイプ」のピストンでは【図7】のグラフが得られないことは明 らかであると主張する。
しかし,本件発明におけるアシスト機構で用いるガススプリングに\nついて,本件訂正後の請求項1には,「ガススプリング」と記載されて いるのみであり,「オールガスタイプ」であるか「フリーピストンタイ プ」であるかについての特定がない。また,本件明細書の【0029】 には,「上記実施例においては,ガススプリングとして,フリーピスト ンを有するものを用いたが,フリーピストンを用いない従来型のガス スプリングを用いることも可能である。」と記載されており,本件発明\nのガススプリングが「フリーピストンタイプ」のものに限られない旨 記載されている。そうすると,「オールガスタイプ」のガススプリング (甲65(審判乙19))を計算に用いて,前記(ア)のとおり,「第1の 作業機」により構成要件Gが実施可能\であることが示されていること (甲60(審判乙14)1〜2頁,甲64(審判乙18)1頁,甲6 5(審判乙19))からすれば,構成要件Gは実施可能\であると認めら れる。そして,「オールガスタイプ」のガススプリング(甲65(審判 乙19))は,その構造に照らし,本件特許の原出願時に実施可能\であ ったものと推認され,本件特許の原出願時に実施できなかったことを 裏付ける具体的な証拠はない。したがって,被告の上記主張は,採用 することができない。
c 被告は,本件発明に係る作業機を自ら開発した原告ですら,【図7】 のグラフのデータを得た日に存在していた「当時の作業機」を再現で きないのであるから,構成要件Gが実施不可能\であることは明らかで あると主張する。 しかし,特許発明が実施可能性であるか否かは,実施例に示された\n例をそのまま具体的に再現することができるか否かによって判断され るものではないから,本件特許の原出願時に当業者が本件明細書の記 載に基づいて本件発明を実施することができたか否かは,【図7】のグ ラフのデータを得た「当時の作業機」自体を再現できるか否かによっ て判断されるものではない。前記(ア)のとおり,甲60(審判乙14), 甲64(審判乙18)によれば,構成要件Gが実施可能\であることが 認められる。したがって,被告の上記主張は,採用することができな い。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2021.03.10
令和2(ネ)10050 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年2月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお,控訴人は,当審において,乙第18号証に記載された発明を主引例 とする無効の抗弁を新たに主張した。
しかしながら,この新たな無効の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当た るかどうかは,原審及び当審における審理の経過を総合的に踏まえて検討す べきものであるところ,一件記録によれば,原審においては,平成31年3 月12日に第1回口頭弁論期日が開かれた後,審理が弁論準備手続に付され たこと,充足論及び無効論について当事者双方の主張立証が行われた後,令 和元年12月20日の第5回弁論準備手続期日において,当事者双方の主張 立証が尽くされたことが確認された上で,裁判所の心証開示が行われたこと が認められる。そして,裁判所の心証開示が行われた上記第5回弁論準備手 続期日までに,乙第18号証に記載された発明を主引例とする無効の抗弁を 主張することが困難であったことをうかがわせるに足りる証拠はない。そう であるとすれば,控訴人としては,上記第5回弁論準備手続期日までに新た な無効の抗弁を主張すること(あるいは,少なくとも,速やかにその主張を する予定である旨を告知すること)が可能\\\であったし,そうすべきものであ ったといえるから,それをしなかったことは時機に後れたものであり,また, 時機に後れたことについて重大な過失があったものといわざるを得ない。そ して,そのような評価は,控訴人が控訴をし,審級が変わったからといって 変わるものではないところ,当審において新たな無効の抗弁の成否を審理す ることになれば,訴訟の完結が遅延することは明らかである。
以上の次第で,当審としては,新たな無効の抗弁を時機に後れた攻撃防御 方法であるとして却下したものである。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2021.02.25
令和2(ネ)10053 意匠権侵害行為差止請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和3年2月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件意匠の具体的構成態様は前記(2)のとおりであるところ,タッチパネ ルの縦横比や後傾角度をどのように構成するかによっては,ありふれた範\n囲内の差しか生じないのであり,また,ディスプレイの枠を等幅に構成す\nるのはありふれた手法であるから,具体的構成態様1)及び3)が美感に与え る影響は微弱である。したがって,前記(4)イの共通点に係る具体的構成態\n様1)及び2)並びに前記(5)イの差異点が類否判断に与える影響はほとんど ない。
ウ また,本件意匠の基本的構成態様に関して,次のような公知意匠がある。\n 公知意匠A(意匠に係る物品「クレジットカードのポイント照会による 商品券販売」)は,傾斜面から下方に向かって側面視「く」字状に形成さ れた基台上にディスプレイ部が筐体より一段高く形成され,薄板状のディ スプレイ部の相当程度が筐体の上端部から突出しているディスプレイ部 について,上方を後方に傾斜させたディスプレイが縦長長方形状であり, ディスプレイを収容するケーシングが縦長略直方形状であるものと認め られる。
また,公知意匠B(意匠に係る物品「無人発券機」)は,傾斜面から下 方に向かって側面視「く」字状に形成された基台上にディスプレイ部が筐 体より一段高く形成され,薄板状のディスプレイ部の相当程度が筐体の上 端部から突出しているディスプレイ部について,上方を後方に傾斜させた ディスプレイが縦長長方形状であり,ディスプレイを収容するケーシング が縦長略長方形状であるものと認められる。 さらに,公知意匠C(意匠に係る物品「金融自動化機器」)は,筐体上 部においてアーム状の部品で接続されて正面視で筐体の上端部から突出 しているような外観を呈するディスプレイ部について,上方を後方に傾斜 させたディスプレイが縦長略長方形状であり,ディスプレイを収容するケ ーシングが右上に突出部分があるほか縦長略長方形状であるものと認め られる。
これらによると,本件意匠登録出願前に,自動精算機又はそれに類似す る物品の分野において,筐体の上端部から一定程度突出するディスプレイ 部について,上方を後方に傾斜させたディスプレイが縦長長方形状であ り,ディスプレイを収容するケーシングが縦長略直方形状である意匠が知 られていたものといえるし,より一般的に考えても,自動精算機又はそれ に類似する物品のディスプレイ部において利用者が見やすくタッチしや すい形状を得るためには,本件意匠のような基本的構成態様とすることが\n社会通念上も極めて自然かつ合理性を有するものと考えられる。
そうすると,本件意匠の基本的構成態様は,新規な創作部分ではなく,\n自動精算機又はこれに類似する物品に係る需要者にとり,特に注意を惹き やすい部分であるとはいえず,需要者は,筐体の上端部から一定程度突出 し上方を後方に傾斜させたディスプレイ部であること自体に注意を惹か れるのではなく,これを前提に,更なる細部の構成から生じる美感にこそ\n着目するものといえるから,本件意匠の基本的構成態様が美感に与える影\n響は微弱である。したがって,共通点に係る基本的構成態様が類否判断に\n与える影響はほとんどないし,また,タッチパネル部を本体正面上部の右 側に設けるか左側に設けるかによっては,ありふれた範囲内の差しか生じ ないから,前記(5)アの差異点も類否判断に与える影響はほとんどない。
エ 以上からすると,本件意匠については,前記(2)イの具体的構成態様2), 4)及び5)が需要者の注意を惹きやすい部分となるから,前記(4)イの共通点 に係る具体的構成態様3)並びに前記(5)ウ及びエの各差異点が類否判断に 与える影響が大きい。
そこで検討するに,本件意匠と被告意匠とは傾斜面部を有する点におい て共通するといっても,下側部分も含めて,被告意匠の傾斜面部の幅,あ るいはこれにその下側縁と接する周側面の幅を合わせた合計幅は極めて わずかな広さしかないのに対し,本件意匠は,傾斜面部の上側及び左右側 部分の幅(傾斜面部の上側部分の外縁上側から傾斜面部の下側部分の外縁 下側までの直線長さを仮に50cmとすると,0.75cm前後となる。) に対する傾斜面部の下側部分の幅(上記の仮定によれば,3cm前後とな る。)に極端に差を設けることによって,下側部分が顕著に目立つように 設定されており,しかも,傾斜面部の下側部分に本体側から正面側に向け た高さを確保することにより,タッチパネル部が本体の正面から前方に突 出する態様を構成させているというべきである。そして,需要者は,様々\nな離れた位置から自動精算機を確認し,これに接近していくものであり, 正面視のみならず,斜視,側面視から生じる美感がより重要であるといえ るところ,本件意匠の傾斜面部の下側部分の目立たつように突出させられ た構成は需要者に大きく着目されるといえ,この構\成態様により,本件意 匠はディスプレイ部全体が浮き出すような視覚的効果を生じさせている と認められる。他方,被告意匠は,傾斜面部と周側面がわずかな幅にすぎ ず(上記の仮定によれば,合計しても1.2cm前後にすぎない。),ディ スプレイ部がただ単に本体と一体化しているような視覚的効果しか生じ ないと認められる。したがって,差異点から生じる印象は,共通点から受 ける印象を凌駕するものであり,本件意匠と被告意匠とは,たとえディス プレイ部の位置等に共通する部分があるとしても,全体として,異なった 美感を有するものと評価できるのであり,類似しないものというべきであ る。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 部分意匠
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2021.02.25
令和1(ネ)10078 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年2月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ A邸工事が「公然」実施されたものではないとの主張について 控訴人は,A邸は塀や草木に囲まれており,容易に外部からA邸をのぞ き見ることはできないこと,山に囲まれており,近隣の住民もわずかであ ること,作業が屋根上で行われるものであり,外部から容易にその作業の 内容を確認することができないことから,A邸工事は,公然と行われたも のとはいえないと主張する。 しかし,被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務を負わない不特 定の者によって技術的に理解されるか,そのおそれのある状況で実施され たのであれば,工事は公然と行われたと評価するのが相当であるところ, 本件においては,まず,A邸の屋根からストーブの煙突が突出している側 (煙突の正面側)の隣地は,本件工事の当時には駐車場であり(乙14の 10),同駐車場には10台を優に超える駐車スペースがあり,敷地もA邸 より高いことが認められるのであって(乙24の2),同駐車場からは煙突 についても十分視認が可能\であるし,当該工事が第三者から視認されるこ と等を拒むような態様で行われていたことはうかがえない。
また,乙12の資料4は,前記ア(イ)認定のとおり平成19年7月2日 に被告から住友林業に提出されたものであるところ,同図面にはインナー フラッシングが明記されており,これが,住友林業からニシカネにファッ クスで転送されている(乙32)。そして,前記ア(イ)において認定したと おり,住友林業の下請業者であるニシカネがA邸の煙突について不燃材の 装着を行うことになっていたが,その時点では,煙突の屋内からの引き出 し及び立ち上げ部分はまだ設置されておらず,住友林業又はニシカネにお いて煙突の屋根貫通部の構造を認識することは十\分可能であったといえ\nるところ,A邸工事の施工方法及び防水構造は,引用に係る原判決の「事\n実及び理由」第4の2(3)ア及びイ(ア)記載のとおりであって,いずれも複 雑なものではなく,当業者であれば,乙12の資料4や,II)期工事時の煙 突の屋根貫通部の構造から,これらの発明を技術的に理解できるものと認\nめられる。
以上によれば,A邸工事は,本件特許出願前に,被控訴人のために発明 の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者(少なくとも上記住友林業 やニシカネ等の下請業者等)によって技術的に理解されるか,そのおそれ のある状況で実施されたもので,公然実施された発明に当たるというべき であるから,控訴人の主張は採用できない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.02.23
令和2(行ケ)10011 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月17日 知的財産高等裁判所
上記記載から,隔壁の遠位部に備えたスリットは,隔壁の遠位部を通る イントロデューサ針の位置決めをし,その挿入を簡単にするために設けら れたものであることを理解できる。 さらに,図1,23,25ないし27から,延長チューブの遠位端が, カテーテル・アダプタの近位端と遠位端との間で,かつ,隔壁の遠位部の 遠位端よりも更に遠位側に開口した中空部分に接続していることを看取 できるから,引用文献1記載のカテーテル及びイントロデューサ針アセン ブリにおいては,患者への流体の注入及び患者の循環系からの流体の除去 は,延長チューブを通じてカテーテル・アダプタの上記中空部分を介して 行うものであることを理解できる。 ウ 以上によれば,引用文献1記載の隔壁は,針の保管及び使用中に針の周 りにシールを提供し,針が引き出された場合に密閉されるように隔壁アセ ンブリ内に設けられたものであって,隔壁の遠位部に備えたスリットは, そこを通るイントロデューサ針の挿入を簡単にするために設けられたも のであるから,隔壁の遠位部は,流体の「該流入及び流出を可能とするよ\nうに開口可能なスリットを有して」いると認めることはできない。\nそうすると,引用文献1記載の「隔壁」の遠位部は,本願発明の「前記 第2弁部材は,二方弁であり,流体が,前記カテーテルハブの前記内室を 通って近位方向及び遠位方向の両方向に流れることが可能となるように\n開口可能であ」るとの構\成(本件構成)に相当するものといえず,引用文\n献1記載のカテーテル及びイントロデューサ針アセンブリは,本件構成を\n有しない点で本願発明と相違するから,この点において,本件審決には, 一致点の認定の誤り及び相違点の看過があるものと認められる。
(2) これに対し被告は,1)引用文献1には,カテーテル及びイントロデューサ 針アセンブリについて,従来より,流体を患者に注入することができるとと もに,患者の循環系からの流体の除去を可能にするものであることが述べら\nれていること(【0002】),2)流体の患者への注入及び患者の循環系からの 流体の除去は,カテーテルハブの中空部に配置された,「二方弁」として機能\nする「スリットを備えた隔壁」を介してされることが技術常識であること(例 えば,甲3,乙6)からすれば,当業者は,引用文献1記載のカテーテル及 びイントロデューサ針アセンブリの「隔壁」の遠位部は,本件構成に相当す\nると当然把握するから,本件審決における一致点の認定に誤りはない旨主張 する。
ア 1)について
引用文献1の【0002】には,「医療では,このようなカテーテル及び ントロデューサ針アセンブリは,患者の脈管系内に適切にカテーテルを配 置するのに使用される。定位置になると,静脈(すなわち,「IV」)カテ ーテルなどのカテーテルを使用して,生理食塩水,医療化合物,及び/ま たは栄養組成(完全非経口栄養,すなわち「TPN」を含む)を含む流体 をこのような治療を必要とする患者に注入することができる。カテーテル は加えて,循環系からの流体の除去,及び患者の脈管系内の状態の監視を 可能にする。」との記載がある。\n上記記載から,カテーテル及びイントロデューサ針アセンブリのカテー テルは,「循環系からの流体の除去,及び患者の脈管系内の状態の監視」を 可能にすることを理解できるが,上記記載は,隔壁の遠位部又はその遠位\n部に設けられたスリットが流体の「流入及び流出を可能とするように開口\n可能」な構\成であることを示唆するものとはいえない。
イ 2)について
乙6(国際公開第2008/052791号)には,バルブ組立体の具 体的構造として,側部のポートに沿って配置され,ポートを閉じる弁であ\nって,ポート内の加圧された流体の作用により開口可能となる第1バルブ\n要素(チューブ要素5),流体が遠位方向又は近位方向のいずれかに流れる ことを可能にする二方向バルブとして形成されるスロット6aを備えたバ\nルブディスク6(原文4枚目7行〜5枚目3行(訳文5枚目),原文5枚目 17行〜20行(訳文6枚目),図1,2等)の記載がある。 引用文献3(甲3・訳文乙5)には,1)スリットを有する隔壁と隔壁作動 体とを含み,使用中は,隔壁作動体が隔壁のスリットを通って前進し,隔 壁を通る流体経路を形成する血液制御バルブと,カテーテルアセンブリ内 の流体がサイドポートから漏れることを防止できるポートバルブ(【000 2】,【0003】),2)「カテーテルアダプタは,隔壁作動体と隔壁とを含 む血液制御バルブを収容する。隔壁は,管腔の一部を封止する。1つ以上 のスリットが隔壁を貫通して延在することで,隔壁を通る選択的なアクセ スを提供できる。よって,ポートバルブは,ポートを介してカテーテルア ダプタの内部管腔に対する一方向の選択的なアクセスを提供し得る。」(【0 005】)との記載がある。 上記記載から,カテーテル組立体において,流体の患者への注入及び患 者の循環系からの流体の除去は,カテーテルハブの中空部に配置された「二 方弁」として機能する「スリットを備えた隔壁」を介してされ得る技術が,\n本願優先日当時,一般に知られていたことが認められる。 一方で,上記記載から,カテーテルハブの中空部に配置された「スリッ トを備えた隔壁」が常に「二方弁」として機能するとまで認めることはで\nきないから,上記技術が一般に知られていたことを踏まえても,前記⑴ウ の認定を左右するものではなく,当業者は,引用文献1記載のカテーテル 及びイントロデューサ針アセンブリの「隔壁」の遠位部は,本件構成に相\n当すると当然把握するものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2021.02.19
令和2(ネ)10036 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 控訴人は,原判決は,特許法70条1項,2項等に反し,本件特許請求の 範囲に記載のある「問題のある実施例」を本件各発明の実施例とせず,「最善の実施 例」のみを本件各発明であるとした点に誤りがある旨主張する。
ア 本件特許請求の範囲の【請求項1】には,「ホストコンピュータが,前記 券情報と前記発券情報とを入力する入力手段と,該入力手段によって入力された前 記券情報と前記発券情報とに基づき,かつ,前記座席管理地に設置される指定座席 のレイアウトに基づいて表示する座席表\示情報を作成する作成手段と,該作成手段 によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と,該記憶手段によって\n記憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段と,」と記載されており,「券情報」\nと「発券情報」とを統合して「座席表示情報」を作成し,これを記憶手段に記憶さ\nせることが記載されていると認められるから,控訴人の主張する「最善の実施例」 が本件特許請求の範囲に記載されていると認められ,控訴人の主張する「問題のあ る実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認めることはできない。 また,本件特許請求の範囲の【請求項2】には,「ホストコンピュータが,前記券 情報と前記発券情報とを入力する手段と,該入力手段によって入力された前記券情 報と前記発券情報とを,複数の前記座席管理地又は前記端末機を識別する座席管理 地識別情報又は端末機識別情報別に集計する集計手段と,該集計手段によって集計 された前記券情報と前記発券情報とに基づき,かつ,前記座席管理地に設置される 指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表\示情報を作成する作成手段と,該 作成手段によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と,該記憶手段\nによって記憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段と,」と記載されており,\n「券情報」と「発券情報」とを統合して「座席表示情報」を作成し,これを記憶手\n段に記憶させることが記載されていると認められるから,控訴人の主張する「最善 の実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認められ,控訴人の主張する 「問題のある実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認めることはでき ない。
イ 上記のことは,本件明細書(甲2)の記載からも明らかである。 本件明細書の「発明の詳細な説明」は,補正して引用した原判決「事実及び理由」 の第3,1(1)のとおりであり,段落【0002】には,【従来の技術】として,「従 来,指定座席を管理する座席管理システムとしては,カードリーダで読取られた座 席指定券の券情報及び券売機等で発券された座席指定券の発券(座席予約)情報等\nを,例えば列車車内において,端末機(コンピュータ)で受けて記憶し表示して,\n指定座席の利用状況を車掌が目視できるようにして車内検札を自動化する座席指定 席利用状況監視装置(特公H5−47880号公報)が発明されている。」との記載 があり,段落【0004】において,「券情報」及び「発券情報」を地上の管理セン ターから受ける場合について,「伝送される情報は2種になるために通信回線の負 担を1種の場合と比べて2倍にするなどの問題がある。」ことが記載されている。 そして,本件明細書の段落【0005】には,【発明が解決しようとする課題】と して,「上記発明の座席指定席利用状況監視装置は上記券情報と上記発券情報とに 基づいて各座席指定席の利用状況を表示するにはこれ等の両情報を地上の管理セン\nターから受ける場合,伝送される情報量が2倍になるために,該情報を伝送する通 信回線の負担を2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度をともに2倍にす るなどの点にある。」として,控訴人の主張する「問題のある実施例」の問題点が指 摘されており,段落【0006】には,【課題を解決するための手段】として「本発 明は,上記管理センターに備えられるホストコンピュータが,カードリーダで読取 られた座席指定券の券情報と券売機等で発券された座席指定券の発券情報とを入力 して,これ等の両情報に基づいて表示する座席表\示情報を作成して,作成された前 記座席表示情報を,前記ホストコンピュータと通信回線で結ばれて,指定座席を設\n置管理する座席管理地に備えられる端末機へ伝送して,該端末機が,前記座席表示\n情報を入力して表示してするように構\成したことを主要な特徴とする。」と記載さ れており,段落【0007】に,【作用】として,「上記ホストコンピュータから上 記端末機へ伝送される情報量が上記券情報と上記発券情報との両表示情報から1つ\nの表示情報となる上記座席表\示情報にすることで半減され,これによって通信回線 の負担と端末機の記憶容量と処理速度とを半減する。」と記載され,段落【0008】 〜【0019】に,【実施例】として,控訴人が主張する「最善の実施例」(「座席表\n示情報」は,券情報と発券情報という二つの情報を一つに統合した実施例)が記載 されていることが認められる。さらに,段落【0020】に,【発明の効果】として, 「該端末機がする各指定座席の利用状況の表示を前記券情報と前記発券情報との両\n表示情報から1つの表\示情報となる前記座席表示情報で実現できるようになり,こ\nれによって前記ホストコンピュータから前記端末機へ伝送する情報量が半減され, 通信回線の負担と端末機の記憶容量と処理速度等を軽減するとともに,端末機のコ ストダウンが計られて,本発明のシステムの構築を容易にする。」と記載されている\nことが認められる。 これらの本件明細書の記載によると,本件各発明は,指定座席を管理する座席管 理システムに関して,地上の管理センターから券情報と発券情報の両情報を端末機 で受ける場合,伝送される情報が2種になることから,伝送される情報が1種の場 合と比べて,通信回線の負担が2倍となり,端末機の記憶容量と処理速度を2倍に するなどの技術的課題があることに鑑み,地上の管理センターに備えられるコンピ ュータが,カードリーダで読み取られた券情報と,券売機等で読み取られた発券情 報等を入力して,これらの情報から一つの座席表示情報を作成し,作成された座席\n表示情報を,コンピュータと通信回線で結ばれて,指定座席を設置管理する座席管\n理地に備えられた端末機に伝送して,端末機が座席レイアウトに基づき各指定座席 の利用状況を表示するという構\成を採用したものであって,この点に,本件各発明 の技術的意義があると認められる。 このような本件明細書の記載によると,控訴人の主張する「問題のある実施例」 は,本件各発明が解決すべき課題を示したものであり,その課題を解決したのが本 件各発明であるから,これが本件各発明の実施例であると認めることはできない。
・・・
また,控訴人は,被控訴人は,被告システム1の「OD情報」,「改札通過情報」 が,それぞれ,本件明細書の図2の「発券情報」,「券情報」に,被告システム1の 「マルスサーバ」及び「セキュリティサーバ」が,「地上の管理センター」に該当す ることを認めているから,被告システム1は,本件明細書の図2の構成を備えるも\nのであり,本件特許権を侵害するものであると主張するが,本件明細書の図2は, 控訴人の主張する「問題のある実施例」に関するものであり,被告システム1が, 上記図2の構成を備えるからといって,本件各発明の構\成を備えるということには ならない。
原判決(15頁〜24頁)が判示するとおり,被告システム 1 は,本件発明 1 の構\n成要件1−B及び1−C並びに本件発明2の構成要件2−B及び2−Cの文言を充\n足せず,被告システム2は,本件発明1の構成要件1−A,1−B及び1−C並び\nに本件発明2の構成要件2―\A,2−B及び2−Cの文言を充足しないから,被告 各システムが本件各発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
(4) 控訴人は,被告システム1と本件各発明との間の本件相違点(被告システ ム1は,本件各発明における,ホストコンピュータにおいて券情報と発券情報から 一つの「座席表示情報」を作成し,これを,指定座席を設置管理する座席管理地に\n備えられる端末機に伝送し,端末機において「座席表示情報」を表\示するという構\n成を有していないこと)は,本件各発明の本質的部分ではないと主張するが,控訴 人のこの主張を採用することができないことは,原判決(25頁〜26頁)が判示 するとおりである。 本件相違点は,本件各発明の本質的部分に係るものであるから,被告システム1 は,均等の第1要件を充足しない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2021.02.18
令和2(ネ)597 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和3年1月21日 大阪高等裁判所
原告制作物1を含む原告レシピブック1に係るデザイン制作委託契約 においては,契約書は作成されておらず,成果物の著作権の帰属や利用 に関する明示的な合意は存在しない。また,原告レシピブック1の発注 から納品に至る交渉経過等の詳細は明らかでない。
控訴人代表者は,同種の夏用レシピブックにつき,次の夏まで常識的な範囲で増刷することを許諾すると伝えたことがあったとか,レシピ\nブックに掲載された素材等を別の媒体で使うときは連絡があればほぼ快 諾しており,追加料金を生じるとは限らないなどと供述している(控訴 人代表者本人)。また,控訴人は,播磨喜水の依頼を受けて,シェフコラボレシピブック等に掲載した写真及びレシピ情報等を用いてレシピ\nカードを制作するなど,一旦納品した成果物の一部を他の制作物に用い ることもあったことが認められる(甲43〜50,控訴人代表者本人)。このように,レシピブック等に掲載した写真や情報が,レシピブック\n以外の媒体において控訴人に制作を依頼せずに使用されることもありう ると解されていたことが窺われるものの,新たな制作物において使用す る場合の具体的な権利関係が明確に決められていたとは認め難く,控訴 人と播磨喜水との間の個別のデザイン制作委託契約の趣旨,内容等から, 控訴人の著作物である原告制作物1に関する利用許諾についての当事者 の合理的意思を解釈する必要がある。
原告レシピブック1は,播磨喜水の取扱商品をレシピ情報の提供と組 み合わせて紹介することによって,宣伝広告,販売促進に役立て,さら にはブランドイメージの向上を図るものとして,播磨喜水が制作を依頼 し,控訴人が制作したものと解される。そして,播磨喜水の事業遂行に おいて,原告レシピブック1の内容と整合する範囲で,その成果物の一 部をそのまま使用する場合については,播磨喜水のブランドイメージの 形成,向上を企図した宣伝広告や販売促進活動における使用として,播 磨喜水はもちろん,控訴人も想定していたとみるのが合理的である。 しかし,被告制作物1は,原告制作物1(成果物である原告レシピ ブック1の出来上がった料理の写真である。)を「2017 SUMMER」と 明記された平成29年夏期用のチラシの背景に使用したものであり,そ の制作目的は同じとはいえない。 また,控訴人のデザイナーであるP2は,被告制作物1を発見し,平 成29年6月6日,P1に対し,LINEを通じて抗議をしており(甲 19:「事前にご相談がありましたら問題になりませんでしたが,この 件は著作物の無断使用になります。困りましたね。」という内容),控 訴人は,本件提訴後,これが被控訴人による最初の著作権侵害であると 主張し,控訴人代表者もその旨供述している(甲39,控訴人代表\者本 人21頁)。 これに対し,当時,被控訴人代表者のP1は,控訴人から原告制作物1の使用について,許諾があったという反論をしておらず,むしろ,播\n磨喜水がチラシ等を作成しようとする都度,ブランディング名目で常に 事前相談を求められることについて,不満を有していたことが認められ る(甲19,乙34)。
以上によると,前述したとおり,播磨喜水において,その事業活動の 一環として,控訴人が制作した成果物又はその一部をその作成目的に 従って,そのまま別の機会に利用する場合はともかく,成果物を構成する素材である原告制作物1(写真)を,事前の許諾を得ずにこれを異な\nる目的で利用することまで許諾していたと認めることはできない。
エ 抗弁1についてのまとめ
被控訴人による被告制作物1の制作は,控訴人の利用許諾を得ずに原 告制作物1をそのまま,制作目的の異なる制作物(原判決別紙被告制作 物目録記載2のチラシ)の背景に印刷し,これを複製するものであって, 原告制作物1の著作権を侵害する行為であると認められる。
・・・・
原告制作物5−2の著作物性については,いずれも,3種類の商品(播 磨喜水の白,黒,赤)を右下角斜め上方から撮影した写真であり,その撮影 方法は,商品を紹介する写真としてありふれた表現である。
・・・・
(イ) 損害額について
証拠(甲7の8,甲44の1〜44の5,甲45の1,甲50)及び 弁論の全趣旨によれば,原告制作物1を含む原告レシピブック1(12 頁から成り,5種類の料理写真及びそのレシピ情報,表紙写真,及びその料理写真,商品写真,商品の値段その他の情報,通信販売案内等を掲\n載するもの)の制作に係るオリジナルレシピブランディング料及び撮 影・スタイリング・フードコーディネイト料が100万円であったこと, 控訴人においては,同種のレシピブックに掲載した料理の1つのレシピ 情報と写真を1枚のレシピカードとして基づいてレシピカードを制作す る費用が1枚2万5000円とされていたことが認められ,控訴人は, レシピカードの上記制作費用が複製の使用料であると主張する。 これらを踏まえ,原告制作物1(写真1枚)に対する使用料としては, 2万5000円と認めるのが相当である。 また,事案の内容,認容額その他諸般の事情を考慮し,控訴人が負担 した弁護士費用のうち2500円につき,本件による損害として相当と 認める。
(ウ) 以上によれば,原告制作物1に係る著作権侵害による損害賠償請求は, 2万7500円(及び遅延損害金)の支払を求める限度で理由があるが, その余は理由がない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2021.02.16
平成31(行ケ)10041 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月4日 知的財産高等裁判所
本件発明6は,貫通孔に関し,開孔率が3.07%以上であって,深さが 100〜2000μmであり,50個〜400個/cm2の密度で存在し,開 口面積が直径280〜1400μmの円形であるとの発明特定事項(相違点 6B)を有するところ,前記1(2)のとおり,第1表面のシート材のこの貫通\n孔は,創傷から滲み出した滲出液を貯留し,創傷面との間や上記の貫通孔内 などに滲出液を保持して湿潤環境を良好に維持するものでありながら,その 貫通孔は上記の第1表面側から第2表\面側への液体の透過を許容して,創傷 部位に過剰の滲出液を保持することがないという技術的意義を有するものと 認められる。
これに対し,甲1の発明の詳細な説明には,「被覆層下面側の少なくとも傷 接触表面は疎水性を有する。」(【0028】), 「 次に,液体の移動について 述べる。被覆層のこの疎水性の表面は,吸収層へ体液などの液体が移動し得\nるように形成される。被覆層の下面側を液体透過性とするためには,メッシ ュ,穿孔フィルム等のプラスチックシートや,編布,織布,不織布等の液体 透過性の繊維状シートを使用することができる。被覆層に疎水性樹脂層を形 成する場合は,被覆層の液体が移動し得る孔を塞がないように疎水性樹脂層 を塗工するか,疎水性樹脂層を塗工した後に疎水性樹脂層ごと被覆層を打ち 抜けば良い。」(【0029】),「 次に,吸収層について述べる。吸収層は,セ ルロース系繊維,パルプ,高分子吸水ポリマー等の吸水性の高い材料を単独 又は併用して使用することができ,必要とされる吸収量にあわせてこれらの 量を調整すればよい。特に,水吸収時にゲルを形成する物質を含ませること が好ましく,このようにすることで,創傷を湿潤状態に保ち,傷の治癒を促 進することができる。」(【0034】)との記載がある。これらの記載によれ ば,甲1発明においては,被覆層を貫通する孔60は,傷からの体液を吸収 層へ移動させるようにする機能を有するものであり,創傷を湿潤状態に保ち,\n傷の治癒を促進することができるのは,必要とされる吸収量にあわせて材料 を調整し,特に水吸収時にゲルを形成する物質を含ませることが好ましい吸 収層によってであり,被覆層を貫通する孔の機能によるものではないと理解\nすることが相当であり,甲1の発明の詳細な説明には,被覆層20に設けら れた孔60に創傷部位からの滲出液を保持し,創傷面の湿潤状態を保つこと についての記載や示唆はない。
また,甲7には,甲1発明の被覆層に相当するところの,多数の凸部及び その周囲に形成される凹部を有し,凸部には厚さ方向に貫通する孔を有する 樹脂製のシート材からなる第1層と水を吸収保持可能な第2層の順に積層さ\nれてなる創傷被覆材が開示されており(【0010】,【0014】),この創傷 被覆材は,創傷部と第1層の凹部との間に滲出液を貯留する空間が形成され ることにより,創傷部から流出する滲出液を保持し,創傷部の湿潤状態を保 持し,滲出液が多くなると,第1層の凸部に形成された孔を通して第2層の 吸収層に吸収されることが開示されている(【0012】,【0024】)。しか し,甲7の創傷被覆材は,「 第1シート材は,創傷部と凹部(6)との間に滲 出液の貯留空間を形成する。これは,創傷面と第1層との間における前記貯 留空間に,創傷部からの滲出液を保持することにより創傷部の湿潤状態を保 持できるという点で優れている。また,第1シート材は滲出液が多くなると, 凸部(5)に形成された貫通孔(4)を通して吸収層(2)に吸収させるこ とができるため,滲出液が面内方向に広がるのを防止するという点でも優れ ている。」(【0024】)との記載があるように,創傷部と凹部(6)との間 に滲出液の貯留空間を形成し,創傷部の湿潤状態を保持するものであり,貫 通孔(4)については,「滲出液が多くなると,凸部(5)に形成された貫通 孔(4)を通して吸収層(2)に吸収させることができる」という機能を果\nたすものである。
そうすると,甲7の貫通孔は,そもそも創傷面からの滲出液を貯留する機 能を有しないから,甲7に記載された貫通孔の開孔率,深さ,密度,直径に\n関する技術的事項を甲1発明に適用しても,第1表面のシート材に創傷から\n滲み出した滲出液を貯留するための貫通孔を設ける本件発明6に想到するこ とができないし,また,創傷を湿潤状態に保ち,傷の治癒を促進することが できるのが孔の機能によるものではない甲1発明に甲7に記載された発明を\n適用する動機付けもない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.02.16
令和2(行ケ)10001 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月8日 知的財産高等裁判所
(ア) 相違点1は,引用例1発明の共重合体が,本件発明とは異なり,d 成分を構成モノマーとして含まないというものであるところ,上記(1) ア(イ)bのとおり,甲7文献には,第1成分(a成分)及び第2成分(b 成分)又はそのいずれか(特に第1成分)と共重合させる第3成分とし て,「架橋性の官能基(エポキシ基,水酸基,アミド基及びN−メチロー\nルアミド基の少なくとも1種)を有するもの」が挙げられている。 そこで,引用例1発明における第3成分として,エポキシ基を有する モノマー(c成分)及び水酸基を有するモノマー(d成分)の2種を併 用することを,当業者が容易に想到し得たか否かについて検討する。
(イ) まず,上記(1)ア(ア),(イ)a及びdのとおり,引用例1発明は,可 塑化ポリ塩化ビニルシート上に積層して使用するのに好適な接着剤組成 物に関する発明であり,共重合体中のカルボキシル基の10%以上をア ルカリ金属と反応(中和)させることにより,耐ガソリン性及び耐油性\nを向上させることを目的とするものである。 そうすると,化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物 の発明である本件発明と引用例1発明とでは,技術分野や発明が解決し ようとする課題が必ずしも一致するものではないから,もともと引用例 1発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏し いというべきである。
(ウ) また,上記(1)ア(イ)bのとおり,甲7文献には,第3成分として選 択し得る4種のモノマーの例示として8つのモノマーが挙げられてい るほか,4種のモノマーの1種のみ又は2種以上を併用して第1成分と 共重合させることができる旨が記載されている。そうすると,引用例1 発明における第3成分は,上記の各モノマーのうち1種のみを選択する 場合のほか,2種ないし4種のモノマーを併用する場合もあり得るとい うことになるから,その組合せは,異なる官能基に属するモノマーを併\n用する場合に限ったとしても,被告が主張する6通りにとどまるもので はない。
そして,証拠(甲7)によれば,甲7文献には,エポキシ基を有する モノマー(c成分)と水酸基を有するモノマー(d成分)を組み合わせ た合成例は記載されておらず,また,d成分を構成モノマーとして含む\nことによる効果等に関する具体的な記載もされていないものと認められ る。そうすると,甲7文献には,引用例1発明の技術思想として,複数 の組合せの中からエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノ マーの2種を選択すべきである旨や,水酸基を有するモノマーを選択す ることによって特定の効果が得られる旨が開示されているものとはいえ ない。 これらの事情を併せ考慮すると,甲7文献に接した当業者が,引用例 1発明の第3成分として,複数の組合せの中から敢えてエポキシ基を有 するモノマー及び水酸基を有するモノマーの2種を選択する理由に乏し いというべきである。
(エ) 以上のとおり,本件発明と引用例1発明とでは技術分野や発明が解 決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから,もともと引 用例1発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付け が乏しいことに加え,甲7文献の記載内容からすると当業者が複数の組 合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有する モノマーの2種を選択する理由に乏しいことからすれば,甲7文献に接 した当業者において,相違点1に係る本件発明の構成に至る動機付けが\nあったということはできない。 したがって,引用例1発明において,構成モノマーとしてd成分を含\nませることを,本件出願時における当業者が容易に想到し得たというこ とはできない。
・・・
(3) 相違点2の容易想到性 上記(2)のとおり,相違点1について容易想到であるということはできな いが,事案に鑑み,相違点2の容易想到性についても検討する。
ア 検討
(ア) 相違点2は,(メタ)アクリル酸エステル共重合体を構成するモノマ\nーの全量を100質量%としたときのb成分の配合量b及びc成分の配 合量cの値が,本件発明は「10≦b+40c≦26(但し0.05≦ c≦0.45)」であるのに対し,引用例1発明の共重合体においてはc が0.5,b+40cが26.8であるというものである。 そこで,引用例1発明における上記b及びcの値を変更し,本件発明 における数値範囲内に調整することを,当業者が容易に想到し得たか否 か否かについて検討する。
(イ) まず,上記(2)ア(イ)のとおり,本件発明と引用例1発明とでは技術 分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではない というべきである。
(ウ) また,上記(1)ア(イ)fのとおり,引用例1発明の実施例には,引用 例1発明における第3成分を,N−メチロールアクリルアミドからアク リルアミドに量比を変えることなく置き換えた場合に,ピール(g/2 cm)が「1025FA」から「675AF」になり(なお,「ピール」 とは,剥離に要する力をいう(甲7)。),凝集力が「ずれ0.6mm」か ら「ずれ16mm」になった例が示されている(表−8の実施例6,7)。\nこのことからすれば,架橋性官能基であるエポキシ基,水酸基,アミド\n基及びN−メチロールアミド基は,その種類に応じて異なる粘着力や凝 集力を示すものと考えられるから,各モノマーは,粘着力や凝集力の点 で等価であるとはいえないというべきである(なお,表−8の実施例7\nにおける凝集力の数値(「ずれ16mm」)については,他の実施例にお ける数値と比較すると,「ずれ1.6mm」の誤記である可能性もあると\nいえるが,誤記であったとしても,実施例6とは3倍弱の違いが生じて いるのであるから,結論を左右しない。)。 そうすると,当業者において,各モノマーを同量の別のモノマーに置 き換えたり,水酸基を有するモノマー(d成分)を導入した分だけグリ シジルメタクリレート(c成分)の配合量を減少させて第3成分全体の 配合量を維持したりすることが,自然なことであるとか,容易なことで あるなどということはできない。
(エ) さらに,上記(1)ア(ア)によれば,引用例1発明においては,第3成 分(グリシジルメタクリレートはこれに当たる。)を第1成分及び第2成 分の合計量100重量部に対して0.5〜15重量部とするとされてい るから,第1成分ないし第3成分の合計量を100質量%としたときの 第3成分の配合量は,0.5〜13.0質量%となる(0.5/(10 0+0.5)×100〜15/(100+15)×100)。 そうすると,引用例1発明において,グリシジルメタクリレートの配 合量を本件発明における数値範囲内である0.45質量%以下とするた めには,第3成分の配合量の下限値とされている値である0.5質量% を下回る量まで減少させる必要があるところ,甲7文献の記載をみても, このような調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.02. 8
令和2(ネ)10003 特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年1月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許請求の範囲の記載によれば,本件訂正発明の「アクセス制御手段」は, 携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し,保護することを希望 する被保護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段であって, RFIDインターフェースを有するRバッジを一意に識別できる識別情報を 受け取って,該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別\n情報との比較を行う比較手段で,前記アクセス要求を許可するという比較結 果が得られた場合は,前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過す るまでは前記被保護情報へのアクセスを許可するものである。
一方,被告製品の「画面ロック解除制御手段」は,上記1のとおり,画面 ロックを解除し,または画面ロックを継続する手段であって,背面にかざさ れたICカードの固有IDを受信し,その固有IDを用いて,当該ICカー ドが登録済ICカードであるか否かの比較を行う比較手段で,画面ロックを 解除するという比較結果が得られた場合(登録済ICカードであると判定さ れた場合)は,画面ロックが解除された後,無操作状態が一定期間継続しな い限り,画面を介して操作することができるものである。
ここで,被告製品の「背面にかざされたICカードの固有ID」が,本件 訂正発明の「RFIDインターフェースを有するRバッジを一意に識別でき る識別情報」に相当することに争いはないから,被告製品の「画面ロック解 除制御手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に係る構成要件を充\n足するというためには,1)被告製品の「画面ロックを解除し,または画面ロ ックを継続する手段」が,本件訂正発明の「携帯電話の所有者が第三者によ る閲覧や使用を制限し,保護することを希望する被保護情報(以下,単に 「被保護情報」という。)に対するアクセス要求を許可または禁止する手 段」に当たるとともに,2)被告製品において「画面ロックを解除するという 比較結果が得られた場合(登録済ICカードであると判定された場合)は, 画面ロックが解除された後,無操作状態が一定期間継続しない限り,画面を 介して操作することができる」ことが,本件訂正発明の「アクセス要求を許 可するという比較結果が得られた場合は,前記アクセス要求が許可されてか ら所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」こと に当たることを要するといえる。
(2) そこで,上記1)及び2)の2点に分けて,被告製品の「画面ロック解除制御 手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するか否かについて 検討する。
ア 上記1)の点につき
(ア) 証拠(甲4など)によれば,被告製品の「画面ロック機能」とは,ス\nマートフォンの画面をロックすることによって画面を介した操作が行え ないようにするためのものであり,画面ロックの解除とは,スマートフ ォンの操作(画面を介した操作)が可能な状態にするためのものであっ\nて,これらは被保護情報へのアクセスを許可するとか禁止するといった ことそのものを意味するわけではないし,それと同視すべき事柄である ということもできない。このことは,画面を介した操作が可能となった\nからといって,常に被保護情報へのアクセスが行われるわけではなく, 公開された地図の検索等,被保護情報には当たらない情報へのアクセス に終始する場合もあり得ることや,逆に,被保護情報そのものにパスワ ードが付されている場合等を想定すると,画面ロックを解除したからと いって直ちに当該被保護情報にアクセスできるようになるわけではない ことなどからも明らかである。 もちろん,被保護情報そのものにパスワード等が付されていない場合 には,画面ロックを解除した後,ユーザが画面を介して所定の操作を行 うことにより,スマートフォンに格納された被保護情報へのアクセスが 可能になるし,壁紙として,第三者に見られたくない写真を設定してい\nるような状況の下では,画面ロックの解除と同時に,被保護情報へのア クセスが起こり得ることとなる。しかしながら,これらは,画面が開か れたことそのものや,それによって画面を介した操作が可能になったこ\nとに付随して生じた結果というべきものであって,画面ロックやその解 除の直接の目的や効果といえるものではない(なお,1)の構成における\n違いが,2)の構成における違いにも反映していると考えられることにつ\nいては,後述のイ参照。)。
(イ) また,証拠(乙2)によれば,被告製品は,「画面ロック」状態にお いても,画面を介した操作によらないアクセス要求(例えば,自動改札 機の通過のために乗車券の情報にアクセスすること,電話着信があった ときに発信者の名前を画面に表示するために電話帳の情報にアクセスす\nること等)に対しては,アクセスを禁止していないことが認められ,こ の場合には,画面ロックの解除を経ないで被保護情報へのアクセスが可 能になることとなる。このことも,画面ロックやその解除が,被保護情\n報へのアクセスの禁止や許可そのものではないことを裏付ける一事情と いうべきである。なお,控訴人は,上記の例は,被告製品の構成を認定\nするための対象にはなっていない事例であるから考慮すべきではないと いう趣旨の主張をするが,画面ロックやその解除の意義を認定するため の事情として考慮することには何ら妨げはないものというべきである。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)に検討したところによれば,被告製品の「画面ロックを 解除し,または画面ロックを継続する手段」が,本件訂正発明の「被保 護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段」に当たるとい うことはできない。
イ 上記2)の点につき
本件訂正発明の「アクセス制御手段」の「前記アクセス要求が許可され てから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可す る」構成は,その記載のみからは,所定期間が経過した後の状態が明らか\nでない。しかしながら,本件明細書の【0009】に,本件訂正発明の目 的は,「個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該 情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを 提供することにある。」と記載されていることや,【0039】に,「タ イマを設けて一定のタイムラグを許容することで,ICアセンブリ130 とICアセンブリ140とを実際に使用するときの距離が比較的長い場合 であっても,通信可能距離の短い通信方式を採用することが可能\にな る。」と記載されていることからすると,上記の構成の意義は,所定時間\nに限ってアクセスを許容する構成を付加することで,第三者による被保護\n情報の不正使用を確実に防止しつつ,Rバッジと携帯電話とが離間してい ても,自動改札機等による被保護情報に対するアクセス要求を適切に処理 できるようにしたことにあると解される。そうすると,所定時間経過後に は,被保護情報の保護のために,再度アクセスを禁止することが必須とさ れているというべきであり,「前記アクセス要求が許可され」たときを起 点とし,それから所定の時間が経過した後は,たとえ被保護情報へのアク セスが継続している最中であっても,被保護情報へのアクセスは禁止され ることになるものと解される。
これに対し,被告製品の構成は,前述のとおり,「画面ロックを解除す\nるという比較結果が得られた場合は,画面ロックが解除された後,無操作 状態が一定期間継続しない限り,画面を介して操作をすることができる」 というものである。その一定期間の起点は,画面ロックが解除された後, 何の操作もしないという例外的な場合には,画面ロックが解除されたとき となるが,何らかの操作がされる多くの場合には,その操作が終了したと きとなるのであって,常にアクセス許可がされたときが一定期間の起点と なる本件訂正発明とは異なる。また,本件訂正発明においては,アクセス 許可がされた後,一定期間が経過すれば,被保護情報へのアクセスが継続 してDいたとしてもアクセスが禁止されることになるのに対し,被告製品に おいては,画面を介した操作が継続している限り,一定期間がカウントさ れることはなく,したがって,画面がロックされることはあり得ないので あり,この点においても違いが存するものというべきである。 そして,両者にこのような違いが生じているのは,本件訂正発明におい ては,アクセス許可が被保護情報へのアクセスという意味を有するため, 被保護情報の保護という観点から時間制限が設けられているのに対し,被 告製品の画面ロック解除は,単に,画面を介した操作を可能にするという\n意味しか持たないため,被保護情報の保護という観点から時間制限をする 必要はなく,無駄な電力消費を防ぐという観点から時間制限が設けられて いるのにすぎないからであり,両者の時間制限が持つ技術的意義が全く異 なるからであると解される(このように本件訂正発明におけるアクセス許 可と被告製品における画面ロック解除が持つ技術的意義に違いがあること は,被告製品が1)の構成要件をも充足しないことをも裏付けるものである\nといえる。)。
ウ 上記ア及びイに検討したところによれば,被告製品の「画面ロック解除 制御手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するとはいえ ない。
(3) 控訴人は,本件訂正発明の「アクセス」とは,携帯電話の正当なユーザと して被保護情報を閲覧・利用・更新することを意味しており,被告製品にお いては,画面ロック状態では,正当なユーザであることを確認できていない ため,被保護情報(電子マネー,電話帳,写真などのデータ)の閲覧・使 用・更新は禁止されているとして,被告製品が,本件訂正発明の構成要件を\n充足する旨主張する。 しかしながら,被告製品の画面ロック状態においては,被保護情報の閲 覧・利用・更新に制限があるとはいえ,それが全面的に禁止されているもの ではなく(上記(2)ア(イ)),画面ロック状態の解除後においても,それだけで 被保護情報へのアクセスが全面的に可能になるものでもない(上記・・・(2)ア(ア))。 被告製品の「画面ロック解除制御手段」は,まさに文字どおり,画面ロック 解除を制御しているにとどまり,被保護情報へのアクセスの制御との関連は 限定的なものにとどまる。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2021.02. 8
令和2(行ケ)10007 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年1月25日 知的財産高等裁判所
上記の甲11,甲22,甲24,甲25の記載によれば,これらの文 献には,チェーンケースの下側部分が耕耘地面よりも下部に位置するよ うな深い位置で耕耘すると,前記チェーンケースによって前記耕耘地面 にチェーンケース跡の溝が形成されてしまい,次工程の播種作業の障害 になることから,飛散土を一部遮蔽しないようにして前記チェーンケー ス跡の溝に土を供給して前記チェーンケース跡の溝を埋め戻すという技 術事項が記載されていたことが認められる。
(ウ) そこで,甲14発明に,飛散土を一部遮蔽しないようにしてチェー ンケース跡の溝に土を供給してチェーンケース跡の溝を埋め戻すという 甲11,甲22,甲24,甲25に記載された技術事項を適用して,相 違点d(開口部について,本件発明1は,耕耘された土砂を外側方に流 し出し前記チェーンケース跡の溝に供給して前記チェーンケース跡の溝 を埋め戻すためのものであるのに対し,甲14発明は,そのような特定 がない点。)に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたかが\n問題となる。しかし,前記(ア)のとおり,甲14の補助側板は,耕耘具 により泥土が飛散するのを防ぐことによって隣接する既耕地の境界部分 の均平性を高めるものであり,耕耘具により泥土が飛散するのを防ぐも のであるのに対し,甲11,甲22,甲24,甲25に記載された技術 事項は,一部といえども泥土の飛散を遮断せずに,かえって泥土の飛散 によって溝に土を供給するというものであり,両者は,泥土の飛散を防 ぐのかそれともそれを利用するのかという点で対極の技術思想に基づく ものであり,したがって,甲14の補助側板に,甲11,甲22,甲2 4,甲25に記載された技術事項を適用することについては阻害事由が あるものと認められる。そうすると,甲14発明に甲11,甲22,甲 24,甲25に記載された技術事項を適用して相違点dに係る本件発明 1の構成を容易に想到することはできなかったものと認められる。\nウ(ア) 原告は,本件審決は,補助側板の「新たな取付位置」を設定してい るが(判断1)),「新たな取付位置」は不要であると主張する(前記第3 の1(4)イ)。
しかし,前記イ(ア)のとおり,甲14の補助側板は,どのような耕耘 深さで作業するかにかかわらず,畑で作業する場合には畑用の取付け位 置に,水田で作業する場合には水田用の取付け位置に取り付けて作業す るものであり,耕耘具により泥土が飛散するのを防ぐことによって隣接 する既耕地の境界部分の均平性を高めるものであるから,チェーンケー ス跡の溝を埋め戻すための開口部を設置するためには,耕耘深さに応じ て補助側板の取付位置を設定する必要があり,本件審決の上記判断(判 断1))に誤りがあるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2021.02. 4
平成30(ワ)11672 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和3年1月12日 大阪地方裁判所
前記のとおり,本件商標は,欧文字2文字と漢字2文字からなっており, カタカナ3文字と漢字1文字からなる被告標章1とは,語尾の「活」の一文字のみ が共通しているに過ぎず,欧文字とカタカナから受ける印象も相応に異なるから, 外観は同一ではなく,類似するものとも認め難い。 また,被告標章1からは特定の観念を生じないため,観念の点において,両者が 同一又は類似ということはできない。 しかしながら,称呼においては,両者は長音の有無が異なるに過ぎず,長音は他 の明確な発音と比べて比較的印象に残りにくいことから,離隔的に観察した場合, 同一のものと誤認しやすく,極めて類似しているといえる。被告は,アクセントが 異なると主張するが,本件商標も被告標章1も造語であるため,固定したアクセン トがあるわけではなく,時と場所を異にしてもアクセントの違いで区別できるほ ど,印象が異なるものとは認め難い。
(イ) 取引の実情を踏まえて検討するに,需要者である求人企業においては,前 記認定のとおり,本件商標に係る役務についても,被告役務についても,役務利用 に当たっては文書による申込みを要し,役務のプランを選択し,相応の料金を支払\nうものであり,新規に正社員を採用するという企業にとって日常の営業活動とは異 なる重要な活動の一環として行われる取引であるから,求人に係る媒体の事業者が 多数ある中で(乙17,33),どの程度の経費を投じていかなる媒体でいかなる 広告や勧誘を行うかは,各事業者の役務内容等を考慮して慎重に検討するものと考 えられ,外観や観念が類似しない本件商標と被告標章1について,需要者である求 人企業が,称呼の類似性により誤認混同するおそれがあるとは認め難い。 しかしながら,求職者についてみると,前記認定のとおり,本件商標に係る役務 も被告役務も,利用のための会員登録は簡易であり,無料で利用できる上,証拠 (乙13,18ないし27,34。各枝番を含む。)によれば,多数の他の求人情 報ウェブサイトでも会員登録無料をうたっており,気軽に利用できるように簡単に 会員登録ができることを宣伝しているところ,情報を得て就職先の選択肢を広げる 意味で複数のサイトに会員登録する動機がある一方で,複数のサイトに会員登録す ることに何らの制約もなく,現実に多数の大学生が複数の就職情報サイトに登録し ていることが認められる。そうすると,求職者については,必ずしも役務内容を事 前に精査して比較検討するのではなく,会員登録が無料で簡易であるため,役務の 名称を見てとりあえず会員登録してみることがあるものと考えられる。 そして,本件商標も被告標章1も短く平易な文字列であり,発音も容易であるこ と,本件商標に係る役務や被告役務はインターネット上で提供されているところ, インターネット上のウェブサイトやアプリケーションにアクセスする方法として は,検索エンジン等を利用した文字列による検索が一般的であり,正確な表記では\nなく,称呼に基づくひらがなやカタカナでの検索も一般に行われており,ウェブサ イトや検索エンジン側においてもあいまいな表記による検索にも対応できるように\nしていることが広く知られていることからすれば,需要者である求職者は,外観よ りも称呼をより強く記憶し,称呼によって役務の利用に至ることが多いものという べきである。
そうすると,求職者が需要者に含まれるという取引の実情にかんがみれば,需要 者に与える印象や記憶においては,本件商標と被告標章1とでは,前記外観の差異 よりも,称呼の類似性の影響が大きく,被告標章1は特定の観念を生じず,観念の 点から称呼の類似性の影響を覆すほどの印象を受けるものではないから,前述のと おり必ずしも事前に精査の上会員登録するわけではない学生等の求職者において, 被告標章1を本件商標に係る役務の名称と誤認混同したり,本件商標に係る役務と 被告役務とが,同一の主体により提供されるものと誤信するおそれがあると認めら れる。
(ウ) 被告は,ウェブサイトでの役務の提供においては,役務主体の識別はウェ ブサイトの上部等の目立つところに付されたロゴにより行われるのが通常であると 主張するが,前記のとおり,インターネット上においても,文字列で構成された商\n標については,称呼で記憶してアクセスすることが多いのであり,称呼の重要性が 低いものとはいえない。また,被告は,求職者がサービス内容を確認して会員規約 に同意し,所定の情報を入力して会員登録するまでの過程で多くの画面に接するこ とにより視覚で役務の内容や運営主体を理解すると主張するが,証拠(乙3,36 の1,2)によれば,被告は,ウェブサイト上で,被告役務につき「まずは会員登 録してください。メールアドレスと属性の登録のみで約1分で完了します。」など と記載し,会員登録フォームのページには被告役務の内容を説明する特段の記載は なく,メールアドレスや学校名等の登録のみで会員登録が完了し,会員規約はスク ロールしなければ内容を確認できないものであることが認められる。他方,被告役 務の会員登録に当たって,学生に役務の内容や運営主体を理解させ,本件商標に係 る役務との誤認混同を生じさせないようにする識別表示については,存するとは認\nめられない。
2021.02. 3
令和1(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年1月21日 知的財産高等裁判所
本件クレーム1は下記です。
我国地熱エネルギ活用の地熱発電を促進するため,地熱発電発電反対を抑止 する目的のため,第一に地熱発電用の井戸を掘らないこと,第二に既存のd温泉 の源泉からのお湯で発電すること,第三に発電により源泉の温度を下げ,第四 に入浴に適する温度に下げた温泉を温泉業者に提供し,第五に温泉業者の源泉 低温化のコストを不用にしてメリットを与えるという五つの組み合わせの方法 により温泉業界の地熱発電反対を抑止し,地熱発電を促進し,我国地熱エネル ギ活用を増大し得ることを特徴とする我国地熱発電促進方法。
引用発明は下記です。
地熱発電の普及が実現されるため,源泉の権利者への不具合を生じさせず 熱水蒸気発電装置1を設置するモチベーションを高くするため,温泉利用設 備30用の源泉を吸い上げる機構に熱水蒸気発電装置1を接続するだけで,\n自らが使用する電力をまかなうことができ,発電に使用した熱水を,本来の 温泉水としても利用でき,温泉利用設備30の所有者にとっても利益になり, 源泉の権利者への不具合を生じさせず温泉利用設備30の所有者にとって熱 水蒸気発電装置1を設置するモチベーションを高くし,熱水蒸気発電装置1 の普及を進みやすくする,地熱発電の普及が実現される方法。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2021.02. 3
令和2(行ケ)10065 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年1月21日 知的財産高等裁判所
原告は,本件商標の登録出願時及び登録査定時までに,原告使用商標1が付された,別紙4の「モンスターエナジー」及び「モンスターエナジーアブソリュートリーゼロ」,原告使用商標4が付された「モンスターカオス」の3商品(原告商品)を発\n売したこと,原告から独占販売権を得たアサヒ飲料は,原告商品について 「モンスターエナジー」ブランドとニュースリリースで紹介していたこと, 原告商品は好調な売上げを記録し,本件商標の登録出願時までに先に我が 国においてエナジードリンクとして認知を得ていたレッドブルに次いで2 位の認知度を獲得したこと,原告及びアサヒ飲料は,新商品の発売,イベン ト等の開催に合わせて原告使用商標を付し,「モンスターエナジー」又は 「MONSTER ENERGY」の名称を付した賞品が当たる様々なキ ャンペーン活動を行ったほか,著名なアスリートを支援して,原告使用商 標が付された競技用スーツを着たアスリートが原告使用商標を付した競技 道具や車両で競技する姿を見てもらい,また,これらの動画をソーシャルメディアにアップするなどしたほか,イベントのスポンサーとなり,会場\n内に原告使用商標を付したブースを設けて,原告使用商標を付したスタッ フ等が来場者に原告使用商標を付した「モンスターエナジー」ドリンクを 無償で配布し,原告使用商標を付した車両を展示し,原告使用商標を付し た車両等を走行させるなどすることを通じて,キャンペーンの応募者,視 聴者や来場者に原告使用商標の浸透を図ったことが認められ,原告使用商 標は,原告商品を愛飲し,また,原告が支援する特定のアスリートに関心を 持ち,あるいは原告がスポンサーとなったイベント会場等に来場した一定 の需用者層には知られていたということはできる。
しかしながら,そもそも上記の認識の対象となったのは,あくまで原告 使用商標である。原告は,「MONSTER」及びその音訳「モンスター」 は,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,原告の業務に係る商品を 表示するものとして需要者の間で広く認識されていた旨主張するが,原告及び原告から我が国において独占販売権を得たアサヒ飲料が本件商標の登\n録出願時及び登録査定時までに販売した「エナジードリンク」に付した商 標,エナジードリンクの販売のための広告及び販売促進活動において使用 した商標は,いずれも原告使用商標であり,少なくとも,「MONSTER」 の標準文字からなる引用商標1のみをその業務において使用したと認める に足りる証拠はない。また,前記認定事実によれば,原告(モンスターエナ ジージャパン合同会社)及びアサヒ飲料は,「MONSTER」あるいはそ の音訳「モンスター」ではなく,原告使用商標と「モンスターエナジー」又 は「MONSTER ENERGY」の名称を用いて,新商品の発売,販売 のための広告及び販売促進活動等を行っているのであり(なお,モンスタ ーエナジージャパン合同会社のウェブページには,一部「モンスターガー ル」,「モンスターファミリー」といった表記も見られるが,「モンスターエナジー ガール」,「モンスターエナジー ファミリー」の略称であると 容易に理解されるものでもあるし,いずれにしても「モンスター」ないし 「MONSTER」の文字を用いてこれらの活動を行ってきたとは認めら れない。),この点からも,「MONSTER」及びその音訳「モンスター」 が本件商標の登録出願時及び登録査定時には,原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間で広く認識されていたといえないことが裏付\nけられる。したがって,この点に関する原告の主張は採用し得ない。 また,前記認定事実(1(4))によれば,エナジードリンクの主要な需要 者層は,30代から50代の男性が中心であり,10代から20代の男女 にも広がりつつあるが,1)エナジードリンクが何か分からないと回答した 人が16.1%,57.0%の人がエナジードリンクを購入して飲んだこと がないと回答し,2)エナジードリンクは,「飲んでいる人と飲んでいない人 と飲んでいない者の二極分化」しており,月に1日以上飲んでいる人で6 割を占め,「好調なエナジードリンクを支えているのは強烈なロイヤルカ スタマーに依るもの」と分析され,3)「61.9%がエナジードリンクの飲 用経験があり,5人に1人は「それを月に1回以上」飲用していることが分 かった」との調査結果があるように,エナジードリンクは,通常の清涼飲料 水のような幅広い需要者層が購入するものではないから,原告商品が,エ ナジードリンクとしてレッドブルに次いで2位の認知度を獲得し,当初の 目標を超える売上げを記録しているとしても,限られた需要者層が繰り返 し愛飲していることがうかがわれる。したがって,原告使用商標は,無効請 求商品の需要者である一般消費者に周知著名であったということはできな い。
以上によれば,「MONSTER」及びその音訳「モンスター」は,上記 のいずれの点においても周知著名性を認めることはできないし,原告使用 商標も,一般消費者に周知著名であったと認めることはできない。
・・・・
原告は,前記第3の2(1)のとおり,本件商標と引用商標の類似性の程度は高 く,本件商標に接した取引者及び需要者が原告及びその「MONSTER」ブラ ンドを直ちに想起,連想することは明らかであり,本件商標の使用は,原告が 「MONSTER」ブランドについて獲得した信用力,顧客吸引力にフリーラ イドするものといわざるを得ず,その経済的な価値を低下させるものであると して,本件商標は,公正な取引秩序の維持を目指す商標法の目的,国際信義の精 神に反するものであり,社会一般の道徳観念に反するものであるから,本件商 標は公の秩序を害するおそれがある商標というべきであり,商標法4条1項7 号に該当する旨主張する。
しかし,1)本件商標と原告使用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいて も類似するものではないこと,2)原告使用商標はいずれも一般消費者に周知著 名とはいい難いこと,3)無効請求商品に本件商標が使用されたとしても,需要 者において,本件商標から原告使用商標を連想し,原告の業務に係る商品,原告 と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると,そ の商品の出所の混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできないことは, 前記2のとおりであるから,原告の上記主張は,その前提を欠くものというほ かない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.02. 3
令和2(行ケ)10062 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年1月21日 知的財産高等裁判所
本件商標は,前記第2の1(1)のとおり,「久保田メソッド(AKANON)」\nの文字を標準文字で表してなるところ,その構\成中前半部の「久保田メソッ\nド」の文字部分中,「久保田」については,ありふれた姓氏である久保田が まず想起され,「メソッド」が「方法,方式」の意味を有する英語「met\nhod」の片仮名表記であることはよく知られたことであるから,「久保田\nメソッド」の文字部分からは,「(ありふれた姓氏である)久保田という者\nによる方法,方式」といった意味合いを想起させる。また,構成中後半部の\n「(AKANON)」中の欧文字部分の「AKANON」は,辞書等に載録 されていない造語と認められ,ローマ字読みで「アカノン」と称呼されるも のの,これに類する語は想起されず,特定の観念を生じさせないものであり, 「久保田メソッド」の語と括弧内の「AKANON」の語との間に観念上の\n結び付きはない。また,文法上,「( )」(括弧)は,他の部分と区別し その中に他の部分の補充,注釈等を記入するための記号であり,通常,括弧 外の文字が主として,括弧内の文字が従として扱われることに照らせば,本 願商標が,「久保田メソッド」と括弧内の「AKANON」の語とに分離さ\nれて観察され,「久保田メソッド」が主として認識されることは明らかであ\nる。これに加えて,「久保田メソッド」が日本語表\記で先に配置されていて より目立ち,構成文字全体から生ずる「クボタメソ\ッドアカノン」の称呼が やや冗長であって,本件商標は「クボタメソッド」と略して称呼され得るこ\nと,「久保田メソッド」が明確な意味を有するのに対し,「AKANON」\nは造語であって特定の意味を有するものではないことから一般人にはなじみ にくいことも併せて考慮すると,本件商標中,「久保田メソッド」の部分が\n役務の出所識別標識として支配的な印象を与えていることは否定し難いとい うべきである。
そうすると,本件商標の構成中,その前半部に位置する「久保田メソ\ッド」 の部分は独立して自他役務の出所識別機能を果たし得るものと認められ,こ\nの部分を要部として抽出でき,本件商標は,その要部である「久保田メソッ\nド」の文字部分に相応して,「クボタメソッド」の称呼を生じ,「(ありふ\nれた姓氏である)久保田という者による方法,方式」といった観念を生ずる ものである。
・・・・
(3) 対比
本件商標と引用商標とをそれぞれ対比すると,本件商標の要部である「久 保田メソッド」の文字部分と引用商標1の要部である「久保田メソ\ード」及 び「KUBOTA METHOD」並びに引用商標2の要部である「クボタ メソッド」の文字部分とは,表\記方法が異なるのみであり,当該文字部分か ら生じる「クボタメソッド」又は「クボタメソ\ード」との称呼が共通し,又 は聞き誤りのおそれがあり,「(ありふれた姓氏である)久保田(クボタ) という者による方法,方式」の観念をいずれも共通にするものであるから, 本件商標と引用商標とは,互いに相紛れるおそれのある類似の商標であると 認められる。
そうすると,本件商標と引用商標1が本件商標の指定役務中,引用商標1 の指定役務とも類似する「乳幼児のための技芸・スポーツ又は知識の教授, 電子出版物の提供」に使用された場合には,その役務の出所について混同が 生ずるおそれがあり,本件商標と引用商標2が本件商標の指定役務中,引用 商標2の指定役務とも類似する「乳幼児のためのセミナーの企画・運営又は 開催」に使用された場合には,その役務の出所について誤認混同が生じるお それがあるから,本件商標は,「乳幼児のための技芸・スポーツ又は知識の 教授,乳幼児のためのセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」 (本件指定役務)ついて,商標法4条1項11号に該当する。
2 原告の主張について
原告は,1)姓氏と方法,方式を意味する「メソッド」又は「メソ\ード」の文 字とを結び付けた商標は「役務の質」を表示するものであるから,「久保田」\nが「(ありふれた姓氏である)久保田」を示すものであろうと幼児教育の分野 における「A」を示すものであろうと,本件商標中の「久保田メソッド」の文\n字部分は,その指定役務との関係において独立して自他役務の出所識別機能を\n有しない,2)同様に引用商標1中の「久保田メソード」及び「KUBOTA M ETHOD」並びに引用商標2中の「クボタメソッド」の部分も,それら指定\n役務との関係において独立して自他役務の出所識別機能を有しない,3)本件商 標も,引用商標1及び引用商標2も,全体が不可分一体のものであるから要部 抽出はできない,仮に要部抽出をするとしても,要部は「久保田メソッド」,\n「久保田メソード」,「KUBOTA METHOD」又は「クボタメソッド」\nのいずれの文字部分でもない,4)そうすると,上記各部分を要部として抽出し て商標を対比し,本件商標と引用商標とが類似すると判断した本件審決の判断 は誤りである旨主張する。
しかしながら,姓氏と「メソッド」とを結び付けた商標が「ある者が発案し\nた方法,方式」の意味をも含む場合があるとしても,当該商標が「ある者によ る(実施される)方法,方式」の意味をも有すること自体は否定し難いから, 当該商標を直ちに「役務の質」のみを表示する商標であるなどということはで\nきない。そして,姓氏又は名称と「メソッド」の文字を繋げた構\成を有する相 当数の商標登録例が現に認められていること(甲97)からも明らかなとおり, たとえありふれた姓氏であるとしても,姓氏と「メソッド」とを結合した商標\nは,その構成から直ちに出所識別機能\を有さない商標といえるものでもない。 そして,本件において,「久保田メソッド」が,その姓氏を有する発案者及び\nその関係者以外の者にも広く用いられるなどした結果,需要者,取引者に,特 定の幼児教育方法としての役務の質を表示するものとのみ認識されるようにな\nっており,特定の役務の出所先を表示するものではないことをうかがわせる証\n拠もない。
したがって,「久保田メソッド」に自他役務の出所識別機能\がないとはいえ ないから,原告の上記主張は,前提を欠くものであって,その余の点について 論じるまでもなく採用することができないものである。 なお,原告は,Aが自らの育児法を幼児教育現場の指導者の間で積極的に採 用させ,これを幼児教育の現場において広く実践させているから,「久保田メ ソッド」の商標的使用を制限することは不当であり,「久保田メソ\ッド」は独 占適応性に乏しい商標であるなど,るる主張する。しかしながら,その主張を 裏付けるに足りる証拠は提出されていない上,そもそも仮に,「久保田メソッ\nド」がAの考案に係る久保田メソッドの名称であるとすれば,原告に本件商標\nの商標権者の地位を保有させ,その名称の独占を認めることは,かえって不当 というべきであるから,いずれにせよ,上記主張を採用する余地はない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.02. 2
令和2(行ケ)10095 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年1月26日 知的財産高等裁判所
ア 原告は,新聞や書籍といった情報伝達媒体に属する商品において,取 引の対象となっているのは,その物理的な性状である紙ではなく,実質的には,そ の内容(コンテンツ)であり,この種の商品の流通とは,情報の流通のことを指し, インターネットを通じて流通できるため,新聞等は紙である必要性はなくなったし, 電子版も含まなければならないから,「紙媒体」に限定した本件審決の判断には誤り がある旨主張する。
商標法における商品に,電子情報財等の無体物が含まれることを否定するもので はないが,たとえ,新聞や書籍などの情報伝達媒体に属する商品が,原告がいうと ころの「その内容(コンテンツ)」に価値を見いだして購入する需要者がいるとして も,いわゆる収集家の如く,紙媒体としての新聞や書籍について,「その内容(コン テンツ)」以外の点に価値を見いだす需要者も存在する。また,インターネットが普 及し,「内容(コンテンツ)」がインターネットを通じて流通することが可能であるとしても,これにより紙媒体としての「新聞」の存在自体が完全に否定されるもの\nではないし,実際に,紙媒体としての「新聞」は依然として流通している。そうす ると,紙媒体としての「新聞」の流通とは,紙媒体としての「新聞」という物品そ のものの流通として捉えられるべきものである。
イ 原告は,本件アンケート(甲28)の結果をもとに,本件商標が指定商 品である「新聞」に実質的に使用されていると主張する。 しかし,本件アンケート調査は,その対象者がどのような条件・方法により抽出 されたものであり,どのような方法によりインターネットを通じて実施されたもの であるかは明らかでなく,本件アンケート調査によって得られた結果が,「電子版の 新聞及び本件ウェブサイトを一般購読者がどのように捉えているか」を示すものと して参酌することはできない。
また,本件アンケートは,ウェブサイト上におけるアーカイブの提供が,「電子化 された新聞の内容を提供(供覧)する役務」に該当するものであるか否かに関する ものであるから,これによって得られた結果を,本件商標が指定商品である紙媒体 である新聞に使用されているか否かを検討するに当たり,参酌することはできない。 さらに,本件アンケートの回答について,原告は,「どちらとも言えない,わから ない」という回答を,「新聞かもしれない,と消極的に感じている」と恣意的に認定 しているから,本件アンケート調査が,「需要者の約75%が本件ウェブサイトを 『新聞』と認識している。」ことを示すものでもない。
2021.01.29
令和2(行ケ)10066 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年1月14日 知的財産高等裁判所
本件審決は,甲1文献には甲1文献記載技術的事項2,すなわち,「2軸式ヒンジ において,第1回転軸11と第2回転軸12とを平行状態で互いに回転可能となる\nように連結する,一対の支持片511,512の間に,第1位置制限カム521, 第2位置制限カム522及び一対の支持片511,512に対し,両側の短軸53 4により揺動可能である切換片53を設けることにより,第1回転軸11と第2回\n転軸12を交互に回転させるようにする」という技術事項が記載されているところ, 甲2発明において,「接続部材3」を一対とすれば,第1回転軸11及び第2回転軸 21をより安定して平行状態で互いに回転可能に支持できることになるとして,甲\n2発明に甲1文献記載技術的事項2を適用して,甲2発明の相違点Aに係る構成を\n本件発明1の構成とすることは容易であると判断し,被告も同様の主張をする。\n
しかし,前記2(2)のとおり,甲2文献には,「本考案で開示されている開閉が安定 した2軸ヒンジは,軸スリーブ4及び当該軸スリーブ4を収容するハウジング5を 更に含む。当該軸スリーブ4は,当該接続部材3に接続される接続板41と,当該 接続板41に設置され,それぞれ当該第1回転軸11と当該第2回転軸21とが設 置される第1嵌接部42及び第2嵌接部43とを有する。当該ハウジング5は,収 容空間51及び当該収容空間51に連通する開口52が設けられ,当該軸スリーブ 4と当該接続部材3とを収容し,当該接続板41と当該ハウジング5とに,相互に 対応してガイド凸条411とガイド凹溝53とが設けられ,当該ハウジング5の収 容空間51に配置されるように当該軸スリーブ4をガイドする。」(段落【0016】)との記載があり,同記載と甲2文献の【図2】からすると,甲2発明に係るヒンジ は,接続部材3に接続される接続板41と,同接続板41に設置され,それぞれ第 1回転軸11及び第2回転軸21とが設置される第1嵌接部42及び第2嵌接部4 3とを有する軸スリーブ4並びに同軸スリーブ4を収容するハウジング5を備えて いることが認められ,同部材により,第1回転軸11及び第2回転軸21を安定し て平行状態で回転可能に支持できるから,甲2発明においては,甲1文献記載技術\n的事項2を適用する必要はない。
また,前記3(1)のとおり,甲1発明における支持片512は,第1自動閉合輪2 13・第2自動閉合輪223と共に自動閉合機能を発揮する部材を構\成すること, 第1位置制限ブロック531・第2位置制限ブロック532に突設された第1ガイ ドブロック531a・第2ガイドブロック532aを伸入させるガイド溝512c を備えて,切換片53の揺動範囲を制限する機能を有していること,第1トルク装\n置21及び第2トルク装置22は,第1自動閉合輪213・第2自動閉合輪223 に接して設けられ,第1自動閉合輪213・第2自動閉合輪223を圧迫しており, この作用により,上記の自動閉合機能が発揮されることが認められるから,これら\nの部材(第1自動閉合輪213・第2自動閉合輪223,支持片512,切換片5 3)は,機能的に連動しており,一体的に構\成されているといえる。また,甲1発 明における支持片511は,第1ストッパ輪411及び第2ストッパ輪412と一 体となってストッパ機構を構\成すること,第1ストッパ輪411と第1ストッパ凸 点511aとが互いに干渉すると,切換え片53が揺動し,第1位置制限ブロック 531が第1位置制限口521a内に嵌入して,第1回転軸11が回動不能となり,\n第2回転軸12のみが回動可能となるように制限し,第2ストッパ輪412と当該\n第2ストッパ凸点511bとが互いに干渉すると,切換え片53が揺動し,第2位 置制限ブロック532が第2位置制限口522a内に嵌入して,第2回転軸12が 回動不能となり,第1回転軸11のみが回動可能\となるように制限すること,第1 位置制限ブロック531・第2位置制限ブロック532に突設された第1ガイドブ ロック531a・第2ガイドブロック532aを伸入させるガイド溝511cを備 えて,切換片53の揺動範囲を制限する機能を有していることが認められるから,\nこれらの部材(切換片53,第1位置制限カム521・第2位置制限カム522, 支持片511,第1ストッパ輪412・第2ストッパ輪411)も,機能的に連動\nしており,一体的に構成されているといえ,さらに,これらの部材と上記の第1自\n動閉合輪213・第2自動閉合輪223,支持片512も一体的に構成されている\nといえる。そして,上記のとおり,甲2発明は,軸スリーブ4及びハウジング5を 備えることにより,第1回転軸11及び第2回転軸21を安定して平行状態で回転 可能に支持できる構\成を有しており,甲1文献記載技術事項2を適用する必要がな いことを考慮すると,上記の一体的に構成された部材から,支持片511及び支持\n片512のみを取り出して,一対の支持片を有するという構成を甲2発明に適用す\nる動機付けはないというべきである。
また,前記(1)のとおり,甲2発明の接続部材3は,第1位置制限部113に当接 して第1回転軸11の回転を制限する第1位置決め部35と,第2位置制限部21 3に当接して第2回転軸21の回転を制限する第2位置決め部36とを有するので あるから,甲2発明は,甲1発明のストッパ機構に相当する部材を備えていると認\nめられ,また,前記(2)のとおり,甲2発明は,選択的回転規制手段を有していると ころ,甲1発明の上記の一体的に構成された部材は,ストッパ機構\と選択的回転規 制手段を含むものであるから,甲1発明の上記の一体的に構成された部材を甲2発\n明に適用しようする動機付けもないというべきである。 したがって,甲2発明に甲1文献記載技術的事項2を適用する動機付けはないと いうべきであり,甲2発明の相違点Aに係る構成を本件発明2の構\成とすることが 甲1文献により動機付けられているということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2021.01.29
令和2(ネ)10047 特許実費等請求控訴事件 その他 民事訴訟 令和3年1月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「(1)ア 特許実費の支払義務を負う対象となる権利の範囲について,本件契約 書5条1項は,「専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許権等」と 規定していることから,控訴人は,専用実施権の設定登録がされた特許権について のみ,それらの特許実費を負担することになるのかが問題となる。
(ア) 出願中の特許について
本件契約書1条1号は,「本件特許権等」について,出願中の特許も含まれるも のと定義していること,本件契約書5条1項は,「当該特許権又は出願中の特許に 係る出願,登録及び維持に要する実費(以下「特許実費」という。)を負担する」 と規定していること,本件契約書5条2項は「2条3項に基づく非独占的通常実施 権への変更通知をしたときは,当該変更通知がなされた対象特許権及び/又は出願 中の特許については,前項の費用負担義務を免れるものとし」と規定していること からすると,本件契約書5条1項により控訴人が負担することになる特許実費には, 出願中の特許についての特許実費も含まれることは明らかである。 そして,出願中の特許については,専用実施権の設定や独占的通常実施権の許諾 はできないから,それが特許権の設定登録がされた後に本件契約上専用実施権や独 占的通常実施権の対象となるのであれば,特許実費の支払義務を負う対象となると いうべきである。なお,出願中の特許については,仮専用実施権の設定や仮通常実 施権の許諾をすることができる(特許法34条の2,34条の3)が,本件契約書 には,仮専用実施権の設定や独占的仮通常実施権の許諾がされたものに限り,控訴 人がその特許実費を負担する旨の規定はないから,控訴人がその特許実費を支払う 義務がある出願中の特許がこれらのものに限られると解することはできない。 したがって,出願中の特許についても,本件契約書2条3項に基づく非独占的通 常実施権への変更がされていないものであれば,控訴人がその特許実費を支払う義 務があるというべきである。
(イ) 特許権の設定登録がされた特許権について
本件契約書2条1項,2項は,本件特許権等につき,当初は,専用実施権の設定 合意をするが,本件契約締結日から3年経過したときに,その専用実施権が独占的 通常実施権に変更される旨規定しており,本件契約においては,専用実施権の設定 合意がされ,その設定登録がされていなくても,その専用実施権は,3年経過後に 独占的通常実施権に変更されるものとされているのであるから,本件特許権等のう ち特許権の設定登録がされた特許権については,「専用実施権又は独占的通常実施 権を有している本件特許権等」とは,本件契約書2条1項により専用実施権の設定 の合意がされた特許権及び本件契約書2条2項により同専用実施権が独占的通常実 施権に変更された特許権を意味し,控訴人は,そのような特許権であり,本件契約 書2条3項に基づく非独占的通常実施権への変更をしていないものであれば,専用 実施権の設定登録がされているかどうかにかかわらず,それらの特許実費を支払う 義務があるというべきである。
イ 次に,本件契約書1条1号において,「本件特許権等」が「本件製品を 技術的範囲に含む」ものと定義されていることから,その意味が問題となる。 本件契約書1条3号は,「本件製品」について,「(1)圧電型加速度センサ(L字 タイプ),(2)触覚センサ(薄型力覚センサ),(3)トルクセンサ,(4)マイクロ発電 機,及び(5)MEMSミラーを意味する。」と定めており,そこに控訴人が製造,販 売するあるいは製造,販売する予定の製品といった限定はないから,本件契約上,\n「本件製品」とは,これらの技術分野の製品一般を意味するものである。 したがって,「本件製品を技術的範囲に含む」とは,これらの技術分野を技術的 範囲に含むことを意味し,「本件特許権等」は,これらの技術分野に関する特許権 又は出願中の特許を意味すると解するのが相当である。
ウ そして,本件契約についての以上の解釈は,前記1(2)で認定した本件 契約締結に至る経緯,前記1(3)で認定した本件契約締結後の当事者のやり取りの 状況等及び前記1(5)アで認定した控訴人による本件契約に基づく特許実費の支払 状況とも矛盾なく整合するものであって,これ以外の解釈をすることはできない。
(2) 以上のとおり,控訴人は,被控訴人に対して,本件製品(圧電型加速度セ ンサ(L字タイプ),触覚センサ(薄型力覚センサ),トルクセンサ,マイクロ発電 機,及びMEMSミラーの技術分野)に関する出願中の特許,専用実施権の設定の 合意がされた特許権及び同特許権から独占的通常実施権の許諾のある特許権に変更 された特許権のうち,上記の専用実施権又は独占的通常実施権が非独占的通常実施 権に変更されていないものについての特許実費を支払う義務を負うが,前記1(7) アのとおり,平成29年度第2半期における上記範囲の特許実費は,4512万6 043円である。
◆判決本文
1審はこちら。
◆平成31(ワ)3197
被告は,本件変更通知以降は,被告が本件特許権等につき何らの専用実施権を
有しないことが明確となった以上,それ以降に発生した本件変更通知後特許実費につ
いては,本件契約上,被告が負担すべきものと解釈されるべきではないし,仮にその
ように解釈されたとしても,本件変更通知後特許実費の発生原因となった原告による
特許出願等が被告にとって必要性がなく,また,早期に行われる必要もないものであ
ったことも踏まえると,原告の本件変更通知後特許実費の請求は権利の濫用に該当す
る旨主張する。
しかしながら,前記(1)のとおり,本件契約上,原,被告間に本件特許権等について
の専用実施権の設定合意が存在する間は,被告が本件特許権等の特許実費を負担すべ
きであると解されるところ,前記1(6)のとおり,本件変更通知によって上記の合意
が解消されるのは平成30年3月31日である上に,本件変更通知の対象には本件特
許権等に含まれる出願中の特許は含まれておらず,前記(1)アの本件特許権等の文言の解釈を前提とすると,本件変更通知の対象とされたのは本件契約の対象となる本件特
許権等のうちの一部にとどまることとなるから,本件変更通知により被告が本件特許
権等につき何らの専用実施権を有しないことが明確になったともいえない。
また,証拠(甲2,43)及び弁論の全趣旨によれば,原告の請求に係る平成29
年度第2半期における特許実費のうち,原告において平成29年11月10日以前に
特許事務所に対して出願等の依頼をしたにもかかわらず,特許事務所からの実際の請
求が平成30年2月23日以降にされたにすぎないものも相当額含まれていること
が認められるし,また,これに当たらないものに関し,原告において,同日以降に殊
更同年3月31日までに特許出願等の特許実費を発生させる行為をしたと認めるに
足りる証拠もないこと,本件契約上,被告における実施の必要性がないこと等を理由
として被告において特許実費の負担を免れることができる旨の定めも存在しないこ
とに照らすと,原告の本件変更通知後特許実費の請求が権利の濫用に該当するともい
えない。
エ 被告は,過去に原告の有する本件製品に関する特許権及び出願中の特許を対象
としてその特許実費全額を支払っていた点について,後に精算することを前提に仮払
したにすぎない旨主張する。
しかしながら,本件契約書上,支払対象とならない特許実費に関する仮払やその精
算に関する定めは存在しない上に,証拠(甲6〜15,24〜28)及び弁論の全趣
旨によれば,被告が,原告の特許実費の請求に応じてその支払をするに当たり,仮払
であることや後に精算する必要があることを示すことなく支払をしたことが認めら
れるほか,前記1(7)カのとおり,Bは,過去の特許実費の支払につき,仮払という説
明ではなく,支払当時将来的に独占的な実施権を得られるであろうとの期待から自発
的に支払ったなどと説明していたのであって,他に被告が原告に対して仮払であるこ
とや精算の必要性があることを支払の際に示していたことをうかがわせる証拠もな
いことに照らすと,被告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2021.01.28
令和2(行ケ)10101 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年1月19日 知的財産高等裁判所
前記1に認定した事実によると,「庵治石」との文字は,「香川県高松市 庵治町・牟礼町産の花崗岩」を意味するものであり,これを用いた石材又は この石材を加工した石製品は,「庵治石(あじいし)」と呼ばれ,古くから 我が国において品質の高い石製品として広く知られており,香川県の伝統工 芸品となっていることが認められる。 一方,引用商標権者及びその構成員を含む高松市庵治町及び牟礼町内の採\n掘業者や石材業者らは,昭和20年から40年代にかけて組合を結成し,昭 和45年(1970)からは毎年,庵治石を用いた石製品の展示即売会を行 ってきており,平成19年3月9日には,地域団体商標として引用商標の設 定登録を受け,庵治石を用いた石製品に「庵治石(R)登録証」や「庵治石(R)プ レート」を発行したり,「庵治石(R)」のシールを付したりして,ブランドの 維持に努め,さらに,庵治石の知名度向上や庵治石を用いた石製品の販路拡 大等を目的とした様々な展示会やイベントを開催し,引用商標の普及活動の ための各種事業を長年継続して現在まで実施しているところ,その模様が相 当数の来場者や新聞,雑誌等への記事掲載を通じて,相応の程度に広告され ている。加えて,引用商標は,地域団体商標の登録を受けていることから, 経済産業省特許庁が年1回発行する冊子及び同庁のホームページに毎回掲載 され,地域団体商標の普及事業において紹介されている。 これらの事情を考慮すると,引用商標は,本願商標の登録出願時及び本件 審判時において,「香川県高松市庵治町・牟礼町で採掘され加工された製品 に係る引用商標権者の伝統的工芸品ないし地域ブランド」との引用商標権者 又はその構成員の業務を示すものとして,需要者の間に広く認識されており,\n相当程度高い周知性を有していたものと認めるのが相当である。
(2) 原告の主張について
原告は,「庵治石」の文字は「香川県庵治町産の石」及び「香川県庵治町 産の石を加工して製作された石塔・墓石等」を表示するものとして我が国に\nおいて広く知られていたものであり,全体として石材の一種を示す普通名称 であって石材関連の商品及び役務との関係において自他商品役務識別機能及\nび出所表示機能\を有しない語であり,そうであれば,「庵治石」を標準文字 で表してなる引用商標が引用商標権者の業務を想起させるものとして周知性\nを有することはない旨を主張する。 しかしながら,「庵治石」の文字が「香川県高松市庵治町・牟礼町産の花 崗岩」を意味すると認められることは,前記のとおりであり,原告も自認し ているところ,「庵治石」がその本来の産地以外の産地から産出される同種 同等の石材の呼称にも用いられるなど,石材の種類を示す普通名称になった ことを示す証拠はなく,また,庵治地方以外の業者が「庵治石」を産地を示 すためではなく自己の商標として使用していたことを認めるに足りる証拠も ない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
3 出所の混同のおそれに係る判断の誤りの存否について
(1) 検討
前記2(1)のとおり,「庵治石」の文字は,「香川県高松市庵治町・牟礼町 産の花崗岩」を意味するが,同時に,広く知られた「香川県高松市庵治町・ 牟礼町で採掘され加工された製品に係る引用商標権者の伝統的工芸品ないし 地域ブランド」をも意味し,その文字部分のみで特定の意味合いを有するよ く知られた語であるから,本願商標の「庵治石工衆」は,「庵治石」の文字 部分と「工衆」の文字部分とを分離して観察することが取引上不自然である と思われるほど両者が不可分的に結合しているものとはいい難いといえる。 そして,本願商標の構成から「庵治石」の文字を除いた「工衆」の文字部分\nは,辞書等に載録された成語ではなく,「ものを作ることを職とする人々」 程の意味合いを連想させるにとどまるから,本願商標の指定役務との関係で は出所識別標識としての機能は必ずしも強くなく,本願商標の構\成中の「庵 治石」の文字部分が出所識別標識を果たし得る要部として看取されるという べきである。
本願商標の要部である「庵治石」の文字部分と引用商標とを対比すると, いずれも標準文字で「庵治石」の文字を書してなる点で外観が同一であり, また,「アジイシ」の称呼が生じる点で,称呼が同一である。そして,本願 商標をその指定役務に使用した場合は,本願商標の要部から「香川県高松市 庵治町・牟礼町産の花崗岩」という観念だけでなく,「香川県高松市庵治町・ 牟礼町で採掘され加工された製品に係る引用商標権者の伝統的工芸品ないし 地域ブランド」という観念も生じるものであり,本願商標の観念は,引用商 標から生じる観念と同一である。そうすると,本願商標と引用商標の類似性 は極めて高いというべきである。
また,本願商標の指定役務は,その加工又は情報提供の対象物を,引用商 標の指定商品を含む墓用石材や墓石等とするものであるから,本願商標の指 定役務と引用商標の指定商品とは,密接な関連性を有するとともに,取引 者,需要者も相当程度で共通にするものといえる。そして,本願商標の指定 役務の需要者に含まれる一般需要者は,必ずしも石材等について専門的な知 識や経験を有するものではない者も含まれており,高度の注意力をもって役 務の提供を受けるとは限らない。
以上を考慮すると,本願商標をその指定役務に使用した場合には,これに 接する取引者,需要者は,出所識別標識としての機能を果たし得る要部であ\nる「庵治石」の文字部分に着目して,地域ブランド名として周知である引用 商標を連想,想起し,当該役務が引用商標権者又はその構成員との間に緊密\nな営業上の関係又は同一の表示による商品役務化事業を営むグループに属す\nる関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信し,役務の出所につき誤 認を生じさせるおそれがあるものというべきである。 そうすると,本願商標は,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる おそれがある商標であるから,商標法4条1項15号に該当する。
(2)原告の主張について
原告は,1)取引者,需要者は,本願商標を「庵治石」の産地である庵治地 域を表す「庵治」と「石工」及び「衆」からなるものであると認識し,取引\n者,需要者に対して「香川県庵治地域において,石を切り出したり,それを 細工したりする職人の集団」ほどの観念を想起させ「アジイシクシュウ」又 は「アジセッコウシュウ」の称呼を生じさせるから,引用商標と混同のおそ れはない,2)仮に,取引者,需要者が本願商標を「庵治石」と「工衆」とか らなる商標であると認識するとしても,「庵治石」の文字には自他商品役務 識別機能及び出所表\示機能がないから,本願商標は,引用商標と識別力のな\nい部分で共通するにすぎず,引用商標権者の業務と何らかの関係性があると 認識させるものでない旨主張する。 しかしながら,上記1)の主張については,本願商標を「庵治」と「石工」 及び「衆」からなるものであると認識するのが通常であるとはいい難く,ま た,仮に,そのような認識が生じるとしても,それと並んで,庵治石を要部 とした前記(1)記載の観念が生じることは明らかであるし,上記2)の主張の 前提が成り立たないことは,前記(1)に認定判断したとおりであるから,原 告の上記主張は,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2021.01.28
令和2(行ケ)10047 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和3年1月20日 知的財産高等裁判所
以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観及び称呼において明らかに 相違することに照らすならば,本件商標から「今からだ」ほどの意味合い を連想,想起させ,引用商標から「ここ(この時点)からだ」ほどの意味 合いを連想,想起させる点で観念において類似する面があることを勘案し ても,本件商標と引用商標を本件商標の指定商品「サプリメント」に使用 したときに,その出所について誤認混同を生じるおそれがあるものと認め ることはできないから,本件商標は,引用商標に類似する商標であるとい うことはできない。 したがって,本件商標は,商標法4条1項11号に該当するものとは認 められない。
エ これに対し,原告は,本件商標と引用商標は,外観は相違するが,称呼 が類似し,観念が同一であること,引用商標は,原告の業務に係る商品を 表示するものとして,需要者であるスポーツ愛好家の間に広く認識されて\nいるという取引の実情があることをも考慮して全体的に考察すれば,本件 商標と引用商標が本件商標の指定商品「サプリメント」に使用された場合f には,その商品の出所について誤認混同が生ずるおそれがあるから,本件 商標と引用商標は全体として類似している旨主張する。 しかしながら,前記(1)認定のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願 時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品を表示するものとして,\n需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。 また,前記ウ認定のとおり,本件商標と引用商標は,外観及び称呼にお いて明らかに相違することに照らすならば,観念において類似する面があ ることを勘案しても,本件商標と引用商標を本件商標の指定商品「サプリ メント」に使用したときに,その出所について誤認混同を生じるおそれが あるものと認めることはできない。 したがって,原告の上記主張は採用することはできない。
・・・・
2 取消事由2(商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)について
(1) 本件商標の商標法4条1項15号該当性について
原告は,1)引用商標は,「ここからだ」,「まだまだ諦めない」という意味 も含有した造語であり,独創性があること,2)引用商標は,本件商標の登録 出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品を表示するものとし\nて,需要者であるスポーツ愛好家の間に周知であったこと,3)本件商標と引 用商標は,少なくとも称呼や観念において類似する面があること,4)引用商 標を付した原告の商品と本件商標を付した被告の商品は,商品の用途や目的, 成分,用法,販売方法等において共通し,同一又は密接な関連性を有するも のであり,需要者が共通すること,5)本件商標を付した被告の商品のパッケ ージは,原告の商品のパッケージと比べて,形状,図柄,キャッチコピーな どその外観において類似点が多く,広報プロモーション活動の方法も似通っ ていること,6)本件商標の指定商品「サプリメント」は,スポーツ愛好家が 日常的に摂取する性質の商品であり,その需要者が特別の専門的知識経験を 有する者ではないから,これを購入するに際して払われる注意力は,さほど 高いものではないことを総合的に考慮すると,本件商標を上記指定商品に使 用したときは,その商品が原告の商品と誤認混同する可能性があり,本件商\n標は,原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であり,商標 法4条1項15号に該当するから,これを否定した本件審決の判断は誤りで ある旨主張する。
しかしながら,前記1(1)認定のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願 時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品を表示するものとして,\n需要者の間に広く認識されていたものとは認められず,また,前記1(2)ウ認 定のとおり,本件商標と引用商標は,観念において類似する面があるといえ るものの,外観及び称呼において明らかに相違する。 そうすると,その余の点について判断するまでもなく,本件商標をその指 定商品「サプリメント」について使用したときに,これに接する需要者がそ の商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の 業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるお それがあるものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2021.01. 7
令和2(行ケ)10050 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年12月23日 知的財産高等裁判所
原告は被告の下で杜氏として2年働き、その後、袂を分かったんですね。原告の目的は、被告の商標の使用禁止なのでしょう。51条で取り消しができれば、混同するとしてやめさせるつもりだったのかもしれませんね。
原告は,「農口尚彦研究所」の日本酒は,日本酒評価サイトである「S AKETIME」の石川の日本酒ランキング2020において,第1位を 獲得したこと,ANAの国際線ファーストクラスにおいて,2018年(平 成30年)から継続して「農口尚彦研究所」の日本酒が提供されているこ と,このほか,様々な著名雑誌や全国放送のテレビ等においても,原告の みでなく,「農口尚彦研究所」も,北陸を代表する酒蔵として紹介されて\nいることなどからすると,原告自身の名はもちろん,原告の手による「農 口尚彦研究所」の日本酒及びその日本酒を販売する「農口尚彦研究所」の 名称も,需要者の間で広く認識されており,引用商標は,本件審決時にお いて,原告の業務に係る商品「日本酒」を表示するものとして,周知又は\n著名であったといえるから,これを否定した本件審決の認定は誤りである 旨主張するので,以下において判断する。
(ア) 引用商標は,別紙2に示すとおり,「農口尚彦研究所」の文字を縦 書きの楷書体で書してなるものである。 商品「日本酒」は,嗜好品であり,その需要者は,一般消費者である から,引用商標が周知であるというためには,需要者である一般消費者 の間で,引用商標が原告の業務に係る「日本酒」を表示するものとして\n広く認識されている必要がある。
(イ) そこで検討するに,前記アの認定事実によれば,原告が杜氏を務め る株式会社農口尚彦研究所は,平成29年12月頃から,引用商標を付 した日本酒(「農口尚彦研究所」の日本酒)を継続して販売し,本件審 決時(審決日令和2年3月27日)までの販売期間は約1年5か月であ ることが認められる。一方で,引用商標を付した日本酒の販売数量,売 上金額,市場占有率等についての立証はなく,引用商標を付した日本酒 の販売実績を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) 次に,前記ア(エ)の雑誌,新聞,ウェブサイト等には,原告について, 「酒造りの神様・X杜氏の復活!」,「酒造りの神,Xの酒が復活!」, 「日本酒の神様,ふたたび始動!」,「「酒造りの神様」「伝説の杜氏」 と称されるX氏」などと掲載され,原告が平成29年から酒蔵「農口尚 彦研究所」で杜氏として酒造りを再開したことが紹介されていること, 引用商標を付した日本酒が,2018年(平成30年)から,ANAの 国際線ファーストクラスの機内で提供される「日本酒セレクション」に 採用されていること,令和2年にもANAのウェブサイトで人気の銘柄 として紹介されていることが認められる。 もっとも,上記雑誌,新聞,ウェブサイト等においては,「農口尚彦 研究所」は,原告が杜氏を務める酒蔵として紹介されており,上記AN Aのウェブサイトを除き,日本酒の銘柄又はブランド名として,「農口 尚彦研究所」が用いられることを明確に示す記載はない。また,日本酒 が掲載された写真についても,当該写真から「農口尚彦研究所」と表示\nされていることを判読することは困難である。 加えて,前記ア(エ)の雑誌,新聞,ウェブサイト等における原告の紹 介記事等によれば,原告の氏名である「X」は,日本酒の銘柄等に関心 の高い日本酒愛好家の間では知名度が高かったものといえるが,嗜好や こだわり等も様々な一般消費者の間において,広く知られていたとまで 認めることはできない。 以上によれば,前記ア(エ)の雑誌,新聞,ウェブサイト等の掲載状況 から,本件審決時において,酒蔵「農口尚彦研究所」及び「農口尚彦研 究所」の日本酒は,日本酒の銘柄等に関心の高い日本酒愛好家の間では, 相当程度認識されていたものと認められるものの,一般消費者の間で広 く認識されていたものと認めることはできず,ましてや,引用商標が原 告の業務に係る商品「日本酒」を表示するものとして,広く認識されて\nいたものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はな い。
(エ) 以上によれば,引用商標は,本件審決時において,原告の業務に係 る商品「日本酒」を表示するものとして,需要者の間で広く認識されて\nいたものと認めることはできないから,原告の前記主張は採用すること ができない。
2021.01. 5
令和2(ワ)2403 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年12月23日 東京地方裁判所
本件写真は,原告が,天候の良好な平成23年3月2日の日中に,インドの世界遺産であるエローラ石窟群のカイラーサ寺院を被写体として選択し,日陰となる箇所が極力少なくなるように配慮しつつ,同寺院の正面を斜め上方から,同寺院の主要な建物を 中心に据え,その全体がおおむね収まるように撮影したものであることが認め られる。 そうすると,本件写真は,原告が撮影時期及び時間帯,撮影時の天候,撮影 場所等の条件を選択し,被写体の選択及び配置,構図並びに撮影方法を工夫し,\nシャッターチャンスを捉えて撮影したものであるから,原告の個性が表現され\nたものということができる。したがって,本件写真は原告の思想又は感情を創 作的に表現した「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当し,本件写真を創\n作した原告は「著作者」(同項2号)に該当するので,本件写真に係る著作権 及び著作者人格権を有する。
・・・
前記2(3),3のとおり,本件画像は,飲食店業等を目的とする会社である 被告がその事業のために本件サイトに掲載したものであり,本件画像の掲載 期間は,約5年に及ぶ。また,証拠(甲6ないし8)によれば,原告は,自 身の写真のライセンスに当たっては,通常,「fotoQuote」の料金 表(甲7)を使用していること,同料金表\によれば,世界市場のウェブ広告 にハーフページ(300×600ピクセル)の大きさの写真を5年間使用さ せる内容のライセンス料は,地域をアジアに限定しても,1989米ドルを 下らないこと,令和2年8月20日(本件の訴え提起の前日)時点における 米ドル・円相場の仲値が1ドル106.10円であることが認められる。さ らに,証拠(甲3の1)によれば,本件画像は,400×300ピクセルの 大きさで使用されていたことが認められる。そうすると,本件写真を営利目 的で使用する場合,原告は,21万1032円でその利用を許諾することと していたものと認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 以上に加え,本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件写真に係る原告 の著作権(複製権,自動公衆送信権)の行使につき受けるべき金銭の額に相 当する額(著作権法114条3項)は,21万1032円と認めるのが相当 である。 また,上記の諸事情に鑑みれば,本件写真に係る原告の著作者人格権(氏 名表示権)が侵害されたことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料\nは5万円,弁護士費用相当額の損害は5万円とそれぞれ認めるのが相当であ る。
(2) これに対し,被告は,原告が損害の算定根拠とする「fotoQuote」 の料金表は,あくまで営利目的の広告等として写真が使用された場合に適用\nされるものであり,被告は非営利公益目的で本件写真を使用したものである から,これを算定根拠とすることはできないと主張する。 しかし,前記2(3)のとおり,本件画像は,飲食店業等を目的とする会社で ある被告がその事業のために本件サイトに掲載したものであり,被告が本件 画像を利用したのは営利目的であったというべきであるから,被告の上記主 張は前提を欠く。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2021.01. 5
令和2(行ケ)10086 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年12月23日 知的財産高等裁判所
(1) 本願商標は,「AZURE」の欧文字を表してなる。「azure」は,\n「空色,青空」の意味を有し,「アジュア」と発音される英単語として辞書 (乙2。ジーニアス英和辞典 第5版,2014年12月25日発行。)に掲 載されているが,中学生向け(乙2ないし6)や高校生向け(乙7)の学習書 で覚えておくべき単語として挙げられていないことはもちろん,TOEIC の制作機関が提供するボキャブラリーブック(乙8。国際的なビジネスの場 で一般的に使われる語彙を集めている。)でも取り扱われておらず,我が国に おいてその意味が広く一般に知られている語とは認められず,また,本願商 標の指定商品・指定役務の分野において,特定の意味合いを有する語として 知られているとの事情も見いだせない。そうすると,需要者から,一種の造語 として看取されることもあるものといえる。 それ自体あまり知られていない欧文字からなる商標は,一般的には,我が 国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼 されるとみるのが自然であるから,本願商標は,英語風の読み方に倣って「ア ジュア」の称呼を生ずるほか,ローマ字風の読み方に倣って「アズレ」の称呼 をも生ずると認めるのが相当である。
(2) 原告は,本願商標は,「pure」,「cure」,「secure」等 の語尾に「ure」を有する英単語と同様に,英語として自然な文字の並びで あることに加え,広く知られているマイクロソフト社のクラウドプラットフ\nォーム「Microsoft Azure」に使用されているように,我が国 において認知されている語といえるため,英語の読み方に倣って称呼される とみるのが自然であると主張する。 しかし,前記(1)で判断したところに照らせば,「azure」は,「pu re」,「cure」,「secure」等の英単語のように一般に知られて いるとは認められない。そして,マイクロソフト社のクラウドプラットフォ\nーム「Microsoft Azure」については,一般のビジネスにおい て幅広く使われていると認めるに足りる証拠はない上,「Azure」の称呼 も,「アジュア」のほか「アズレ」とされる場合,「アズール」とされる場合 もあり(乙9ないし14,26),大手企業が上記クラウドプラットフォーム を採用する場合に「アズール」と呼んでいる場合もある(乙10,11)。 また,イギリスの自動車のブランド「AZURE」も「アズール」と称呼さ れ(乙15ないし19),ステッドマン医学大辞典第5版(乙21,2002 年2月20日)では一群の異染性塩基性青色メチルチオニン又はフェノチア ジン色素を示す用語「azure」を「アズール」と称呼し,南山堂医学大辞 典第20版(乙22,2015年4月1日)は,「アズール」の語を,英語a zureに由来し,アズール顆粒やギムザ染色を示すものとして挙げている。 したがって,引用商標から「アジュア」の称呼のみが生じるとはいえず,原 告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.12.31
令和2(行ケ)10055 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年11月4日 知的財産高等裁判所
以上によると,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標は,本 件不成立役務のうち「図書及び記録の供覧」,「図書の貸与」及び「書籍の制作」 についての原告の業務に係る役務を表示するものとして周知であり,また,「セミ\nナーの企画・運営又は開催」は,引用商標に係る原告の「茶道の教授」の役務と類 似の役務,「興行の企画・運営又は開催」は,引用商標に係る原告の「茶会の企画・ 運営又は開催」の役務と同一又は類似の役務,「電子出版物の提供」は,引用商標 に係る原告の「図書及び記録の供覧」及び「図書の貸与」の役務と類似の役務であ ると認められるから,本件商標の本件不成立役務のうち上記各役務についても,商 標法4条1項10号に該当するものとして,登録を無効とすべきである。 なお,被告は,類似群コードについて主張するが,類似群コードは,それ自体類 似との推定に係るものにすぎない上,審査官の審査の基準であって,裁判所がこれ に拘束されることはないから,上記判断を左右するものではない。
3 商標法4条1項7号該当性について
(1) 商標法4条1項各号は,商標登録を受けることができない商標として,相 当数の類型を規定しているのであって,同項7号において,「公の秩序又は善良の 風俗を害するおそれがある商標」がその一類型として規定されているのは,他の号 に当てはまらなくてもなお商標登録を受けることができないとすべき商標が存在し 得ることを前提に,一般条項をもって,そのような商標の商標登録を認めないこと としたものであると解されるから,同号の適用は,その商標の登録を社会が許容す べきではないといえるだけの反社会性が認められる場合に限られるべきである。
(2) 既に認定判断したとおり,本件商標は,多くの指定役務について,商標法 4条1項10号に該当するものである。また,証拠(甲7,27,28)及び弁論 の全趣旨によると,被告代表者Bは,原告が家元である織部流に入門したことがあ\nると認められるから,被告代表者Bは,本件商標について商標法4条1項10号に\n該当する事由があることを認識していたものと認められる。 しかし,本件商標は,これら商標法4条1項10号に該当するものについては, そのことを理由に無効とされるのであり,その余の指定役務である「美術品の展示」 について,本件商標の登録を許容すべきでないといえるだけの反社会性があるとい うべき事情を認めるに足りる証拠はない。
(3) これに対し,原告は,被告及び被告代表者Bが,古田家や古田織部と何の\n関係もないにもかかわらず,茶道織部流の何百年にもわたる伝統を承継する正当な 根拠も理由もなく,あたかも自己が創設した茶道の流派であるかのように,これを 独占しようとしているなどと主張するが,上記のとおり,「美術品の展示」を除く 役務について本件商標は無効であるので,被告が茶道について織部流を独占するこ とにはならない。 上記に関し,原告は,Lが織部流の茶会を開催しようとした際に織部流の名称の 使用の中止を求める平成30年10月26日付け「お知らせ」と題する書面(甲2 1)が届いたと主張するが,同書面の差出名義人である「A13」が被告又は被告 の意を受けた者であるとは直ちには認め難い。 また,原告は,被告代表者Bが関係した展示会や催し,同人の講演,同人の経歴\nや「織部賞」について主張するが,これらの主張は上記(2)の判断を左右するもので はない。さらに,本件審判請求の際の被告代表者Bの陳述書(甲28)についても,\n審判において被告代表者Bが自己の言い分を記載したものにすぎず,上記(2)の判 断を左右するものではないし,原告が提出する被告代表者Bにだまされていた旨の\n記載のあるKの陳述書(甲40)や,本件審判請求において提出された同人名義の 陳述書(甲29)のほか,被告代表者Bを発行者とする「茶湯手帳」の記載(前記\n1(1)エ)も,上記(2)の判断を左右するに足りるものではなく,その他,本件商標 の登録を許容すべきでないといえるだけの反社会性があるというべき事情を認める に足りる証拠はない。
4 小括
以上によると,本件審決のうち,「セミナーの企画・運営及び開催」,「電子出 版物の提供」,「図書及び記録の供覧」,「図書の貸与」,「書籍の制作」及び「興 行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競 馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」の役務について 商標法4条1項10号に該当しないとした範囲で,原告の主張する取消事由には理 由があると認められる。その余の原告の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.12.31
令和1(ワ)26106 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年10月14日 東京地方裁判所
(2) 原告作品全体の創作性及び被告作品全体との対比について
ア 証拠(甲1,2,5〜7)によれば,原告の原著作物(別紙2)に描かれ た原告キャラクターは,頭部は髪がなく半楕円形であり,目は小さい黒点で 顔の外側に広く離して配され,上下に分かれたくちばし部分はいずれも厚く オレンジ色であり,上下のくちばしから構成される口は横に大きく広がり,\n体は黄色く,顔部分と下半身部分との明確な区別はなく寸胴であり,手足は 先細の棒状であるとの特徴を有しており,原告作品においては,原告キャラ クターのこれらの特徴の全部又は一部が表現されているものと認められる。\n
イ 証拠(乙1)及び別紙6「対比キャラクター」を含む弁論の全趣旨によれ ば,原告作品に描かれた原告キャラクターの上記特徴のうち,キャラクター の髪を描かず,頭部を半楕円形で描く点は同別紙の「エリザベス」及び「タ キシードサム」と,目を小さい黒点のみで描く点は同別紙の「タキシードサ ム」,「アフロ犬」,「ハローキティ」,「にゃんにゃんにゃんこ」及び「ラ イトン」と,口唇部分を全体的に厚く,口を横に大きく描く点は同別紙の「お ばけのQ太郎」と,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに寸胴に描き, 手足は手首・足首を描かずに先細の棒状に描く点は同別紙の「おばけのQ太 郎」及び「エリザベス」(ただし,いずれも手の部分)と共通し,いずれも, 擬人化したキャラクターの漫画・イラスト等においては,ありふれた表現で\nあると認められる。
ウ そうすると,原告作品は,上記の特徴を組み合わせて表現した点にその創\n作性があるものと認められるものの,原告作品に描かれているような単純化 されたキャラクターが,人が日常的にする表情をし,又はポーズをとる様子\nを描く場合,その表現の幅が限定されることからすると,原告作品が著作物\nとして保護される範囲も,このような原告作品の内容・性質等に照らし,狭 い範囲にとどまるものというべきである。
(3) 被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか否かについて 上記(2)を踏まえ,被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか否かにつ いて,作品ごとに以下検討する。
ア 被告作品1について
(ア) 被告作品1−1について
a 原告作品1−1と被告作品1−1との対比
原告作品1−1と被告作品1−1とを対比すると,両作品は,ほぼ正 面を向いて立つキャラクターにつき,目を黒点のみで描いている点,く ちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半 身部分とを明確に区別せずに描いている点,胴体部分に比して手足を短 く描いている点のほか,黒色パーマ様の髪が描かれている点において共 通するが,黒色パーマ様の髪型を描くこと自体はアイデアにすぎない上, その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはあり ふれた表現であると認められる。\n 他方,両作品については,原告作品1−1では,キャラクターの体色 が黄色で,両目が小さめの黒点のみで顔の外側付近に広く離して描かれ, 上下のくちばしはオレンジ色で,たらこのように厚く描かれているのに 対し,被告作品1−1では,キャラクターの体色は白色で,両目がより 顔の中心に近い位置に,多少大きめの黒点で描かれ,上下のくちばしは 黄色で原告キャラクターに比べると厚みが薄く,横幅も狭く描かれてい るなどの相違点がある(以下,これを「作品に共通する相違点」という。)。 加えて,原告作品1−1では,キャラクターが,いわゆるおばさんパ ーマ状の髪型(毛量は体の約5分の1程度で,への字型の形状をし,眉 毛も見えている。)をして,口を開け,左手を上下に大きく振りながら, 表情豊かに相手に話しかけているかのような様子が表\現されているの に対し,被告作品1−1では,いわゆるアフロヘアー風のこんもりとし た髪がキャラクターの体全体の半分程度を占めるなど,その髪型が強調 され,キャラクターの表情や手足の描写にはさしたる特徴がないなどの\n相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。\n 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通\nするにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があるこ\nとにも照らすと,被告作品1−1から原告作品1−1の本質的特徴を感 得することはできないというべきである。 したがって,被告作品1−1は,原告作品1−1の複製にも翻案にも 当たらない。
◆判決本文
原告作品、被告作品、参考著作物はこちらです。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2020.12.31
平成29(ワ)40337 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年7月22日 東京地方裁判所
独占禁止法21条は,「この法律の規定は,・・・特許法・・・による権利の行使 と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定しているが,特許権の行 使が,その目的,態様,競争に与える影響の大きさなどに照らし,「発明を 奨励し,産業の発達に寄与する」との特許法の目的(特許法1条)に反し, 又は特許制度の趣旨を逸脱する場合については,独占禁止法21条の「権利 の行使と認められる行為」には該当しないものとして,同法が適用されると 解される
。 同法21条の上記趣旨などにも照らすと,特許権に基づく侵害訴訟におい ても,特許権者の権利行使その他の行為の目的,必要性及び合理性,態様, 当該行為による競争制限の程度などの諸事情に照らし,特許権者による特許 権の行使が,特許権者の他の行為とあいまって,競争関係にある他の事業者 とその相手方との取引を不当に妨害する行為(一般指定14項)に該当する など,公正な競争を阻害するおそれがある場合には,当該事案に現れた諸事 情を総合して,その権利行使が,特許法の目的である「産業の発達」を阻害 し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして,権利の濫用(民法1条3項) に当たる場合があり得るというべきである。 ところで,一般指定14項(競争者に対する取引妨害)は,「自己・・・と国 内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について, 契約の成立の阻止,契約の不履行の誘因その他いかなる方法をもってするか を問わず,その取引を不当に妨害すること」を不公正な取引方法に当たると 規定しているところ,乙3先例において,公正取引委員会が,プリンタのメ ーカーが,技術上の必要性等の合理的理由がなく又はその必要性等の範囲を 超えてICチップの書換えを困難にし,カートリッジを再生利用できないよ うにした場合や,ICチップにカートリッジのトナーがなくなったなどのデ ータを記録し,再生品が装着されたときにレーザープリンタの機能の一部が\n作動しないようにした場合には同項に違反するおそれがあるとの見解を示し ていることは,上記(1)コ(イ)のとおりである。
以上を踏まえると,本件において,本件各特許権の権利者である原告が, 使用済みの原告製品についてトナー残量が「?」と表示されるように設定し\nた上で,その実施品である原告電子部品のメモリについて,十分な必要性及\nび合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより, リサイクル事業者が原告電子部品のメモリの書換えにより同各特許の侵害を 回避しつつトナー残量の表示される再生品を製造,販売等することを制限し,\nその結果,当該リサイクル事業者が同各特許権を侵害する行為に及ばない限 りトナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出 した上で,同各特許権に基づき権利行使に及んだと認められる場合には,当 該権利行使は権利の濫用として許容されないものと解すべきである。 以下,本件各特許権の行使が権利の濫用に該当するかどうかについて,検 討する。
(3) トナーの残量表示を「?」とすることによる競争制限の程度について\n
ア 原告プリンタにおいては,前記第2の2(7)のとおり,純正品であるトナ ーカートリッジが装着された場合には,トナー残量が段階的に表示される\nのに対し,使用済みの原告製品にトナーを補充した再生品が装着された場 合には,印刷動作には支障がないものの,トナーの残量表示が「?」と表\ 示されるとともに,トナーがもうすぐなくなる旨の予告表\示はされず,ト ナーを使い切ると,トナーがなくなった旨のメッセージが出て,赤色ラン プが点灯するとの事実が認められる。
イ 原告は,トナーの残量の表示が「?」であるトナーカートリッジであっ\nても印刷は可能であり,ユーザーは価格を重視するので,純正品に比較し\nて廉価な再生品が競争上の不利益を被ることはないと主張する。
(ア) しかし,市場で競合する他の製品の場合と異なり,トナーカートリッ ジの再生品の場合には,再生品の価格の方が純正品の価格よりある程度 安いことはそのユーザーにとって当然の前提であり,再生品がユーザー に対して訴求力を有するのは,再生品と純正品の価格差のみならず,当 該再生品が純正品との価格差にもかかわらず,純正品と同等の品質を備 えているという点にあると考えられる。
(イ) このことは,被告DSジャパンのウェブサイト(甲7の2)において, 被告製品が「高品質で低価格」,「高品質で安全なリサイクルトナーを 安価で販売」などと記載され,その品質が優れていることが強調され, 更に「当社リサイクルトナーの品質」として,E&Qマークを取得して いる旨が記載されていることからもうかがわれるところである。 また,原告のウェブサイトには,前記(1)オ記載のとおり,「プリンタ の性能を安定した状態でご使用いただくために,リコー純正品のご使用\nをおすすめします。リコー純正品以外のご使用は,印字品質の低下やプ リンタ本体の故障など,製品に悪影響を及ぼすことがあります。」と記 載されており,同記載に接したユーザーは,プリンタメーカーは品質上 の理由から純正品の使用を勧めており,廉価な再生品の購入に当たって は,その品質に十分に留意する必要があることを容易に理解し得るもの\nと考えられる。
(ウ) さらに,再生品トナーカートリッジの市場シェアをみると,前記(1)ク のとおり,トナーカートリッジにおける平成21年から平成29年まで のリユース率は,モノクロ・カラー合計で23.1〜26.4%で推移 しているものと認められる。再生品の価格が純正品に比べて廉価であり, 価格面においては競争上優位に立っているにもかかわらず,その市場シ ェアが上記の程度にとどまっているとの事実は,ユーザーにとってトナ ーカートリッジ再生品の品質が非常に重要であり,再生品がユーザーの 信頼を得ることが難しいことを示しているものということができる。
(エ) 以上のとおり,ユーザーは,再生品を購入するかどうかを決めるに当 たり,純正品との価格差に勝るとも劣らず,その品質が純正品と同等か どうかを重視しているということができる。
ウ 本件において,原告プリンタに純正品であるトナーカートリッジを装着 した場合には,トナー残量が段階的に表示されるのに対し,再生品を装着\nした場合には,トナーの残量表示が「?」と表\示され,予告表\示もされな いことは,上記アのとおりである。 プリンタにとってトナー残量表示は一般的に備わっている機能\であると 認められるところ(弁論の全趣旨),トナー残量が「?」と表示されると,\nユーザーとしてはいつトナーが切れるかの予測がつかないことから,トナ\nーが切れたときに備えて予備のトナーカートリッジを常時用意しておか\nなければならず,トナー残量の表示がされる場合に比べ,本来不必要な保\n守・管理上の負担をユーザーに課すこととなる。 また,プリンタに純正トナーカートリッジを装着した場合にトナー残量 が「?」と表示されることは通常あり得ないことから,同表\示に接したユ ーザーは,トナーカートリッジの再生品の品質にはやはり問題があって, プリンタのトナー残量表示機能\が正常に作動していないのではないか,あ るいは,トナーカートリッジが純正品ではないことからプリンタがトナー カートリッジに記録された情報を適正に読み取ることができないのではな いかなどの不安感を抱き,再生品の使用を躊躇すると考えられる。 前記のとおり,プリンタメーカーである原告自身が品質上の理由から純 正品の使用を勧奨していることや,価格差にもかかわらず再生品の市場占 有率が一定にとどまっていることなどに照らすと,我が国において再生品 の品質に対するユーザーの信頼を獲得するのは容易ではないものと考えら れる。このような状況下において,トナーの残量が「?」と表示される再\n生品を販売しても,その品質に対する不安や保守・管理上の負担等から, 我が国のトナーカートリッジ市場においてユーザーに広く受け入れられる とは考え難い。
エ 実際のところ,我が国のトナーカートリッジ市場において,トナー残量 を「?」と表示する再生品が製造,販売等されていることを示す証拠は存\n在しない。このことは,原告製のプリンタのうち,対応するトナーカット リッジの電子部品のメモリの書換えが可能な機種はもとより,本件書換制\n限措置がされている機種(C830及びC840シリーズ)についても同 様である。被告らを含むリサイクル事業者が,わざわざ費用を費やして原 告電子部品のメモリの書換え又は同部品の取替えを行い,トナー残量が表\n示されるようにした上で再生品を販売しているとの事実も,トナー残量を 「?」と表示するトナーカートリッジを市場で販売したとしても,ユーザ\nーから広く受け入れられる可能性が低いことを示しているというべきであ\nる。
オ 加えて,前記(1)ケのとおり,公的機関によるカラーレーザープリンタ用 トナーカートリッジ等の入札においては,メーカーによる再生品以外の再 生品について,トナーカートリッジに装着するチップの情報を,リサイク ルの都度確実に書き換えることや,純正品と同等の機能を有することなど\nが条件とされているものがあるとの事実が認められる。これによれば,本 件書換制限措置がされている原告電子部品について,被告電子部品と取り 替えることなく,トナー残量が「?」と表示される再生品を製造,販売等\nした場合,このような条件を課す公的機関による入札において当該再生品 が入札条件を満たす可能性は低いというべきである。\n この点について,原告は,上記の入札条件は,あらゆる点で純正品と同 等の機能を有することまで求める趣旨ではなく,又は定型的な条件にすぎ\nずメモリの書換えが制限されていることを想定したものではないと主張 する。しかし,トナー残量が正確に表示されない再生品が「純正品と同等\nの機能」を有するということはできず,また,電子部品のメモリの情報を\n確実に書き換えるという条件が定型的なものであるとしても,他の手段に より電子部品のメモリの情報を書き換えた場合と同様のトナー残量表示\nをすることが求められる可能性が高いと考えるのが自然である。\n したがって,本件書換制限措置により,被告らが官公庁等との取引を継 続し得なくなることはあり得ないとの原告の主張は採用し得ない。
カ 以上のとおり,本件書換制限措置により,被告らがトナーの残量の表示\nが「?」であるトナーカートリッジを市場で販売した場合,被告らは,競 争上著しく不利益を被ることとなるというべきである。
(4) 本件各特許権の侵害を回避しつつ,競争上の不利益を被らない方策の存否 について
ア 上記(3)のとおり,被告らは,原告製プリンタのうち,本件書換制限措置 がされていない機種に適合するトナーカートリッジについて,トナー残量 が「?」と表示される製品を販売するのではなく,電子部品のメモリを書\nき換え,トナー残量の表示をすることができるようにした上で販売してお\nり,本件書換制限措置がされているC830及びC840シリーズ機種に ついても,同措置がとられていなければ,同様にメモリを書き換えること により再生品を製造,販売していたものと推認される。 本件書換制限措置は,原告製プリンタのうち,同各シリーズについて, 被告らによるこうした従前の対応を採り得なくするものであるが,被告ら は,これにより競争上の不利益を被ることなく特許権侵害を回避すること が困難な状況に置かれたと主張するのに対し,原告は,被告電子部品の構\n造を工夫するなどして,本件各特許権の侵害を回避することは可能である\nと主張する。
イ そこで,まず,前提として,被告らが従来行っていた原告電子部品のメ モリの書換行為が本件各特許権を侵害するかどうかについて検討する。
(ア) インクタンク事件最高裁判決は,譲渡済みの特許製品について加工等 がされた場合の特許権侵害の成否について,「特許権の消尽により特許 権の行使が制限される対象となるのは,飽くまで特許権者等が我が国に おいて譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから,特許権者 等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ, それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造された ものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権 を行使することが許されるというべきである。そして,上記にいう特許 製品の新たな製造に当たるかどうかについては,当該特許製品の属性, 特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総 合考慮して判断するのが相当であり,当該特許製品の属性としては,製 品の機能,構\造及び材質,用途,耐用期間,使用態様が,加工及び部材 の交換の態様としては,加工等がされた際の当該特許製品の状態,加工 の内容及び程度,交換された部材の耐用期間,当該部材の特許製品中に おける技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきであ\nる。」と判示する。
(イ) これを本件についてみると,本件各発明のうち,例えば,本件各発明 1は,前記第4の1のとおり,情報記憶装置の基板に形成された穴部に, 画像形成装置本体の突起部に形成された設置用の本体側端子に係合す るアース端子を形成した上,当該穴部を複数の金属板のうち2つの金属 板の間に挟まれる位置に配設することにより,情報記憶装置に電気的な 破損が生じにくくなるとともに,端子の本体側端子に対する平行度のず れを最低限に抑えるようにするものであり,画像形成装置本体(プリン タ)に対して着脱可能に構\成された着脱可能装置(トナーカートリッジ)\nに設置される情報記憶装置(電子部品)の物理的な構造や部品の配置に\n関する発明であるということができる。また,本件各発明2及び3も, 同様に情報記憶装置の物理的構造や部品の配置に関する発明である。\n
これに対し,被告らが行っている原告電子部品のメモリの書換えは, 情報記憶装置の物理的構造等に改変を加え,又は部材の交換等をするも\nのではなく,情報記憶装置の物理的な構造はそのまま利用した上で,同\n装置に記録された情報の書換えを行うにすぎないので,当該書換えによ り原告電子部品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと評 価することはできない。
(ウ) そうすると,原告電子部品のメモリを書き換える行為は本件各特許権 を侵害するものではないというべきである。 ウ 原告は,原告プリンタに使用可能な電子部品の製造等に当たっては,原\n告プリンタ側の形状に合う構造であれば足りるので,被告電子部品の構\成 を工夫するなどの他の手段により本件各特許権への抵触を回避することが 可能であると主張する。\n
しかし,本件各発明に係る情報記憶装置は,画像形成装置本体(プリン タ)に対して着脱可能に構\成された着脱可能装置(トナーカートリッジ)\nに搭載されるものであり,当該情報記憶装置に形成された穴部を介して, 画像形成装置本体の突起部と係合するものであるから,被告製品の構成や\n形状は,適合させる原告プリンタの構成や形状に合わさざるを得ず,その\n設計上の自由度は相当程度制限されると考えられる。 実際のところ,原告プリンタに関し,リサイクル事業者によって販売さ れている再生品は,いずれも電子部品を交換しており(乙2,37),そ の構造自体を本件各特許権の侵害を回避するような態様で変更している製\n品が存在することを示す証拠は存在しない。被告らは,本件各特許権の侵 害を回避するため,被告電子部品の設計を変更したが,設計変更後の被告 電子部品がなお本件各発明の技術的範囲に属することは前記判示のとおり であり,その他の方法により本件各特許の侵害を回避することが可能であ\nることをうかがわせる証拠は存在しない。
エ 以上によれば,被告らをはじめとするリサイクル事業者が,現状におい て,本件書換制限措置のされた原告製プリンタについて,トナー残量表示\nがされるトナーカートリッジを製造,販売するには,原告電子部品を被告 電子部品に取り替えるほかに手段はないと認められる。そして,本件各特 許権に基づき電子部品を取り替えた被告製品の販売等が差し止められるこ とになると,被告らはトナー残量が「?」と表示される再生品を製造,販\n売するほかないが,そうすると,前記(3)のとおり,被告らはトナーカート リッジ市場において競争上著しく不利益を受けることとなるというべきで ある。
(5) 本件書換制限措置の必要性及び合理性について
原告は,本件書換制限措置について,1)トナーの残量表示の正確性の担保,\n2)電子部品のメモリに書き込まれたデータの製品開発及び品質管理・改善へ の活用,3)●(省略)●の観点から行っており,このような措置を行うこと は必要かつ合理的であると主張するので,以下,検討する。 ア 本件書換制限措置の必要性及び合理性全般について 原告の主張する上記1)〜3)の各点について検討するに当たり,本件書換 制限措置の必要性及び合理性全般に関し,以下の点を指摘することができ る。 (ア) 本件書換制限措置がされた原告製プリンタ(C830及びC840シ リーズ)のうち,先行して販売されたのはC830シリーズであるが, その開発時点においては,既に原告製プリンタの他機種に適合するトナ ーカートリッジの電子部品のメモリを書き換えた再生品が市場に流通 していたものと推認される。 ところが,上記C830シリーズの原告製プリンタの開発時点におい て,メモリの書換えをした再生品による具体的な弊害が生じており,そ の対応が必要とされていたことや,この点が同プリンタの開発に当たっ て考慮されていたことをうかがわせる証拠は存在しない。原告の主張す る上記1)〜3)の各点については後に検討するが,これらの点とC830 シリーズの開発を具体的に結びつける証拠は本件において提出されてい ない。
(イ) また,本件書換制限措置が,本件各特許権に係る技術の保護やその侵 害防止等と関連性を有しないことは当事者間に積極的な争いはない。そ うすると,本件書換制限措置を講じる必要性及び合理性は,本件各特許 の実施品であるC830及びC840シリーズ用トナーカートリッジ にとどまらず,C830及びC840シリーズ以外の機種用トナーカー トリッジについても同様に妥当すると考えられるが,同各シリーズ以外 の機種については同様の措置は講じられていない。 原告は,その理由について,●(省略)●と主張するが,その説明は 抽象的であり,本件各特許の権利行使の可能性を考慮して上記各シリー\nズの機種についてのみ本件書換制限措置がされたのではないかとの疑 念を払拭することはできない。
なお,この点に関し,原告は,C830及びC840シリーズ以外の 原告製プリンタ用カートリッジのメモリについても書換えに一定の制約 を付してきたと主張するが,本件書換制限措置と同様の措置がされ,ト ナー残量表示が制限されている他の原告製プリンタが存在すると認める\nに足りる証拠はない。
(ウ) 加えて,本件書換制限措置は,純正トナーカートリッジを原告製プリ ンタに装着して印刷をする上で直接的に必要となる措置ではなく,使用 済みとなったトナーカートリッジについて,リサイクル事業者が再生品 を製造,販売するために電子部品のメモリを書き換える段階でその効果 を奏するものである。すなわち,本件書換制限措置は,特許実施品であ る電子部品が組み込まれたトナーカートリッジについて,譲渡等により 対価をひとたび回収した後の自由な流通や利用を制限するものである ということができる。
この点に関し,被告らは,トナーカートリッジの譲渡後の流通を妨げ ることはできないとして,本件各特許権について消尽が成立すると主張 するが,「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるの は,飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに 限られる」(インクタンク事件最高裁判決)と解されるので,特許製品 である「情報記憶装置」そのものを取り替える行為については,消尽は 成立しないと解される。 しかし,譲渡等により対価をひとたび回収した特許製品が市場におい て円滑に流通することを保護する必要性があることに照らすと,特許製 品を搭載した使用済みのトナーカートリッジの円滑な流通や利用を特 許権者自身が制限する措置については,その必要性及び合理性の程度が, 当該措置により発生する競争制限の程度や製品の自由な流通等の制限 を肯認するに足りるものであることを要するというべきである。 以上を踏まえ,原告が本件書換制限措置の必要性及び合理性の根拠と して挙げる上記1)〜3)の各点について,順次検討する。
イ トナーの残量表示の正確性担保について\n
原告は,本件書換制限措置をした理由として,●(省略)●からである と主張する。
(ア) しかし,●(省略)●であることから,使用済みの原告製品にトナー を再充填して原告製プリンタにそのまま装着した場合に,そのトナー残 量を「?」と表示することに合理性があるとしても,そのことは,その\nメモリの書換えを制限する措置を講じることにより,当該第三者が自ら の責任でトナーの残量を表示するのを妨げることまでも正当化するもの\nではない。 本件書換制限措置は,リサイクル事業者がメモリの書換えにより,自 らの責任でトナー残量を表示することを制限するものであるから,その\n必要性及び合理性を是認するには,そのような措置をとらないと,トナ ー残量が不正確なトナーカートリッジが市場に流通してユーザーの利益 を害し,ひいては,原告製品への信頼が損なわれる具体的なおそれが存 在することを要するというべきである。
(イ) 原告は,再生品を含む第三者のトナーカートリッジには,製品ごとに 印刷枚数に大きなばらつきがあるので,再生事業者が「?」以外のトナ ー残量表示をできないようにしないと,トナー残量が不正確なトナーカ\nートリッジが市場に流通してユーザーの利益を害すると主張し,再生品 の印刷可能枚数が純正品と大きく違うことを示す具体例として,1)同一 顧客から回収した特定の第三者メーカー(E&Qマーク付きのもの)の 同一種類の再生品2つを分析したところ,一方の製品は純正品の73. 9%しか印刷できなかったのに対し,他方の製品は純正品の141.8% も印刷できたこと(甲39の添付資料1),2)同一メーカーのカラート ナーカートリッジの印刷枚数は,純正品の約75%〜88%しか印刷で きなかったこと(同添付資料2),3)他のメーカー(E&Qマークのな いもの)の再生品の中には,純正品の60%しか印刷できないものもあ ったこと(同添付資料3)などを指摘する。
a しかし,上記1)〜3)の調査は,対象となるメーカーの数は2つにす ぎず,調査の対象となった再生品の数も少数であるので,その分析結 果から,当該メーカーの再生品のトナー充填量が純正品と大きく異な り,その残量表示が一般的に不正確であると推認することはできず,\nまして,市場に流通する他のメーカーも含めた再生品のトナーカート リッジ全般について,そのトナーの充填量が純正品の充填量と大きく 異なり,その残量表示が不正確であると推認することはできない。\n
b また,トナーカートリッジの再生品については,E&Qマーク等の 認証基準が設定され,このうち,E&Qマークについては,前記(1)キ のとおり,第三者審査機関が再生品の製造工場に出向き,所定の環境 管理基準及び品質管理基準に基づく審査を行い,これに適合すると判 定された製品に付されるものであり,品質関連基準には,印刷枚数が 純正比90%以上であるという項目が含まれると認められる(乙28)。 このように,トナーカートリッジの再生品については,認証基準の 設定により品質の確保が図られているところ,本件証拠を総合しても, かかる認証を得たトナーカートリッジの再生品について,トナー残量 表示が不正確な製品が多く流通しており,メモリの書換制限により同\n表示を行うことができないようにしないと原告製品に対する信頼を維\n持することが困難であるなどの事情が存在するとは認められない。
c さらに,E&Qマーク等を得ている再生品については,同マークが 製品に貼付されているので(乙28),当該再生品を使用するユーザ\nーは,通常,それが再生品であることを認識して購入,使用するもの と考えられる。このため,仮に,E&Qマーク等を得ている再生品の トナー残量表示が不正確であるとしても,それによりユーザーの信頼\nを失うのは,当該再生品を製造,販売したリサイクル事業者自身であ って,それによって,本件書換制限措置を必要とするほどに原告製品 の信頼が損なわれるとは認め難い。
d もとより,市場で流通しているトナーカートリッジの再生品の中に は,認証を得たもののみならず,認証マークを貼付していないものも\n存在し,こうした製品については,ユーザーが純正品と誤認すること も考えられなくはない。しかし,こうした認証を得ていない再生品に ついて,トナー残量表示が不適切なトナーカートリッジが現に市場に\nおいて多数流通するなどして,原告製品の信頼性に対して影響を及ぼ していると認めるに足りる証拠は存在しない。
e なお,前記(1)イのとおり,●(省略)●ところ,純正品である原告 製品においても,印刷可能枚数と実際の印刷枚数に一定の乖離が生じ\nることは,前記(1)ウのとおりである。このようなトナー残量の算出方 法等に照らすと,リサイクル事業者が,原告製品に充填されるトナー の規定量と同量のトナーを再充填すれば,印刷可能枚数の残量を純正\n品と同程度の正確性をもって表示することは可能\であると認められる。
(ウ) 以上によれば,本件書換制限措置がされた当時はもとより,本訴提起 時点においても,トナーカートリッジの再生品市場にトナー残量表示が\n不正確な製品が多く流通しており,そのメモリの書換えを制限すること により「?」以外の残量表示を行うことができないようにしないと原告\n製品に対する信頼を維持することが困難であるなど,本件書換制限措置 を行うことを正当化するに足りる具体的な必要性があったと認めるこ とはできない。 したがって,本件書換制限措置は,トナーの残量表示の正確性担保の\nための装置としては,その必要性の範囲を超え,合理性を欠くものであ るというべきである。
・・・
ア 差止請求について
上記(1)ないし(5)によれば,本件各特許権の権利者である原告は,使用 済みの原告製品についてトナー残量が「?」と表示されるように設定した\n上で,本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて,十分な\n必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じ ることにより,リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの 書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ,トナー残量の表示される再\n生品を製造,販売等することを制限し,その結果,被告らが当該特許権を 侵害する行為に及ばない限り,トナーカートリッジ市場において競争上著 しく不利益を受ける状況を作出した上で,当該各特許権の権利侵害行為に 対して権利行使に及んだものと認められる。 このような原告の一連の行為は,これを全体としてみれば,トナーカー トリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をし\nた製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり,トナーカートリ ッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告ら とそのユーザーの取引を不当に妨害し,公正な競争を阻害するものとして, 独占禁止法(独占禁止法19条,2条9項6号,一般指定14項)と抵触 するものというべきである。 そして,本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと,同措置 を行う必要性や合理性の程度が低いこと,同措置は使用済みの製品の自由 な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると, 本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは,特許法 の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するもの として,権利の濫用(民法1条3項)に当たるというべきである。
イ 損害賠償請求について
差止請求が権利の濫用として許されないとしても,損害賠償請求につい ては別異に検討することが必要となるが,上記ア記載の事情に加え,原告 は,本件各特許の実施品である電子部品が組み込まれたトナーカートリッ ジを譲渡等することにより既に対価を回収していることや,本件書換制限 措置がなければ,被告らは,本件各特許を侵害することなく,トナーカー トリッジの電子部品のメモリを書き換えることにより再生品を販売して いたと推認されることなども考慮すると,本件においては,差止請求と同 様,損害賠償請求についても権利の濫用に当たると解するのが相当である。 ウ したがって,本訴において,原告が,被告らに対して,本件各特許権に 基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び損害賠償等の請求をするこ とは,いずれも権利の濫用に当たり許されないものというべきである。
2020.12.28
令和1(ワ)5462 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和2年12月3日 大阪地方裁判所
不競法2条1項3号が,他人の商品形態を模倣した商品の販売行為等を不正 競争とする趣旨は,先行者の商品形態を模倣した後行者は,先行者が商品開発に要 した時間,費用及び労力等を節約できる上,商品開発に伴うリスクを回避ないし軽 減することができる一方で,先行者の市場先行のメリットが著しく損なわれること により,後行者と先行者との間に競業上著しい不公平が生じると共に,個性的な商 品開発や市場開拓への意欲が阻害されることになるため,このような行為を競争上 不正な行為として位置付け,先行者の開発利益を模倣者から保護することにあると 解される。 そうすると,同号所定の不正競争につき差止ないし損害賠償を請求することがで きる者は,模倣されたとされる形態に係る商品を先行的に自ら開発・商品化して市 場に置いた者に限られるというべきである。 また,原告商品及び被告商品のような女性向け衣類は,欧米での新作商品や流行 等の影響を受けると共に,中国及び韓国の製造業者ないし仲介業者と日本の販売業 者等との間で多くの取引が行われていると認められる(甲18,19,弁論の全趣 旨)。これらの事情に鑑みると,上記「市場」は,本件の場合,日本国内に限定さ れず,少なくとも欧米,中国及び韓国の市場を含むものと解される。
(2) 検討
ア 本件カタログ商品は,原告商品と同様の特徴(原告商品特徴)を有する(当 事者間に争いのない事実)。
また,本件カタログ(乙12)は,表裏の各表\紙のほか21頁からなる商品カタ ログとして製本されたものであるところ,その表紙右下部に「2015年春季新\n品」との記載があるとともに,本件カタログ商品がその14頁に掲載されている。 さらに,本件カタログ1頁には,その作成者である「广州琼林服饰」(本件中国メ ーカー)が例年韓国,日本,欧米等に輸出していることも記載されている。これら の記載によれば,本件カタログは,本件中国メーカーが,遅くとも平成27年春頃 までに,韓国,日本,欧米等を市場とする2015年(平成27年)春季向けの新 製品として,本件カタログ商品を含む本件カタログ掲載商品を紹介する趣旨で作成 され,頒布されたものであることがうかがわれる。 そうすると,原告商品と同様に原告商品特徴の全てを備えるものである本件カタ ログ商品は,平成27年春頃,本件中国メーカーにより市場に置かれたものといえ るから,原告は,模倣されたとされる形態に係る商品を先行的に自ら開発・商品化 して市場に置いた者ということはできない。
2020.12.25
令和2(ワ)3594 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年12月17日 東京地方裁判所
(1) 前記1(1)のとおり,原告は,本件ソフトの配布を原告コミュニティへの入\n会の特典とし,原告コミュニティに入会した者から入会費用を受け取ること によって,本件ソフトを独占的に利用することができる地位による利益を享\n受していた。ここで,被告が本件各行為により本件ソフトを配布した本件各\n参加者は,いずれも原告コミュニティの紹介,勧誘を受けたが入会しなかっ たこと(前記1(2))を踏まえると,被告の本件各行為がなかったならば本件 各参加者全員が入会費用を支払って原告コミュニティに入会したことを認め ることはできない。もっとも,本件各参加者のうちAは,原告コミュニティ に参加した被告と情報交換をして,被告から本件ソフトの交付を受け,また,\n本件ソフトの配布のために必要な処理等を率先して行うなどしていて,本件\nソフトの価値に強く着目していた者であり,被告の行為がなければ,本件ソ\ フトを入手するために本件ソフトが入会特典である原告コミュニティに参加\nしたと認めることが相当である。そうすると,被告の本件各行為により,原 告は少なくとも本件ソフトが入会特典である原告コミュニティに参加した者\nを1名失ったと認められる。
そして,本件ソフトが入会特典であり本件ソ\フトの再許諾料を含むといえ る原告コミュニティの入会費用は24万9900円であり,また,本件契約 において,原告がBANANAに対して支払う1回の利用許諾代金が同額で あり,再利用許諾の代金を含む原告コミュニティの参加費用はその利用許諾 代金を下回らない範囲で設定するとされていたこと(前記第2の1(2)イ)等 に照らすと,原告は,少なくとも同額の損害を被ったものと認められる。
また,原告は,BANANAに対して本件各参加者7人分の利用許諾代金 174万9300円を支払う義務を負っているなどとも主張する。しかし, 被告の本件各行為によって原告に上記の支払義務が発生したことを認めるに は足りず,原告が被告の本件各行為により同額の損害を被ったとは認められ ない。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2020.12.23
令和2(ネ)10040 損害賠償請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和2年12月17日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
c 取引の実情
控訴人は,被控訴人商標が付された被控訴人商品と,控訴人商品等 は,価格,品質,商品名及びロゴ等の点で異なるので,取引の実情に 照らして,控訴人商品等と被控訴人商標は誤認混同を生ずることはな く,類似しない旨主張する。 しかし,被控訴人商標が付された被控訴人商品と,控訴人商品等が, 価格,品質,商品名及びロゴ等の点で異なるとしても,そのことから 直ちに,取引の実情に照らして,控訴人商品等の形状と被控訴人商標 が誤認混同を生ずることがないとはいえないし,類似性が否定される ことはない。被控訴人商品の新品は,被控訴人の直営店舗や専門店等 を通じて店舗又はインターネット上で販売されており,それらの販路 の数は比較的限定されているものの(弁論の全趣旨),高級ブランド バッグである被控訴人商品の中古品については,中古市場が成立して おり,店舗及びインターネット上で活発に取引がされている一方で(公 知の事実),控訴人商品等も新品は店舗(甲1,2,弁論の全趣旨) 及びインターネット上で販売され(原判決第2の2(1)イ(原判決3頁 14行目ないし19行目)),中古品もインターネット上で取引され ており(甲51〜61),このように,被控訴人商品と控訴人商品等 は,新品及び中古品のいずれについても市場に共通性があると認めら れる。また,中古品については,被控訴人商品であっても品質は新品 に比べて劣化しており,価格も新品よりは低廉である上,一般に中古 品は,ある期間使用された後に譲渡されるため,出所や商品名が新品 のように明確にされていない場合や,品質,商品名及びロゴの有無等 を十分に確認することなく取引が行われている場合(特にインターネ\nット上の取引の場合)が少なくないから(弁論の全趣旨),価格,品 質,商品名及びロゴによって被控訴人商品と控訴人商品等が明確に区 別されるとはいい難く,被控訴人商品の中古品が市場において活発に 取引されていることからすると,被控訴人商品と控訴人商品等の混同 の可能性が具体的に存在すると認められる。そうすると,前記a,b\nのとおり,控訴人商品等(控訴人商品及びバーキンタイプのバッグ) は被控訴人商標と外観上類似するから,価格,品質,商品名及びロゴ に相違があることを考慮しても,被控訴人商標を付した被控訴人商品 と控訴人商品等は具体的な取引において誤認混同のおそれがあるもの と認められる。したがって,取引の実情に照らして,控訴人商品等の 形状は被控訴人商標と誤認混同を生ずるおそれがあり,類似するもの と認められる。
・・・
(4) 争点4(被控訴人の損害)について
ア 控訴人商品等の販売個数について
(ア) 控訴人は,遅くとも平成22年8月11日以降,バーキンタイプの バッグを販売しており(甲41,弁論の全趣旨),平成30年2月14 日には,控訴人の店舗を訪問した被控訴人関係者に対して,控訴人商品 を販売した(甲1,乙34)ことからすると,控訴人は,対象期間(平 成22年8月11日から平成30年2月14日までの期間)において控 訴人商品等を販売していたものと認められる。そして,控訴人は,バー キンタイプのバッグを平成22年夏か秋頃に中国の業者から100個仕 入れ,それがバーキンタイプのバッグの最後の仕入れであったこと,そ の100個のバーキンタイプのバッグについて,被控訴人商標権の登録 がされた直後の平成23年10月頃の在庫は30個程度であったが,控 訴人はその頃からバザーに出品するなどして在庫処分を開始しており, 平成25年4月には在庫処分をほぼ終了し,平成26年1月か2月頃に, 最後の1点を販売したことを主張しており(本判決による補正後の原判 決第2の4(4)【被告の主張】ア(イ)(原判決13頁6行目ないし12行 目)),これらの控訴人の主張は,バーキンタイプのバッグの販売及び その前提としての仕入れという,控訴人に不利益な事実に関する主張で あるから,その主張に係る事実があったものと認めることができる。そ うすると,控訴人は,対象期間中に,少なくとも100個の控訴人商品 等を販売したものと認めるのが相当である。
(イ) これに対し,控訴人は,平成22年8月11日の時点においてバー キンタイプのハンドバッグが100個存在したという証拠はなく,平成 30年2月14日に誤って被控訴人関係者に有償譲渡したバッグは平 成22年頃に仕入れたバッグではなく,控訴人商品等をチャリティーバ ザーで販売したのは販売利益を寄付するためであったから,対象期間中 に少なくとも100個の控訴人商品等を販売したことはないと主張す る。 しかし,前記(ア)のとおり,控訴人は,バーキンタイプのバッグを平 成22年夏か秋頃に100個仕入れたことが認められ,仮に平成30年 2月14日に被控訴人関係者に有償譲渡した控訴人商品が平成22年 頃に仕入れたバッグではないとしても,控訴人が平成30年2月14日 時点において被控訴人商品に形態の類似した控訴人商品を譲渡してい たことからすると,控訴人が対象期間(平成22年8月11日から平成 30年2月14日までの期間)において,平成22年に仕入れたバーキ ンタイプのバッグや控訴人商品を含めて,控訴人商品等を,実際には1 00個を超えて販売した可能性があるとしても,少なくとも100個販\n売したことは,これを認めることができる。また,控訴人が控訴人商品 等の一部をチャリティーバザーで販売し,その利益の一部を寄付したと しても,それは控訴人が利益を得たことを否定する事情にはならず(寄 付は,利益の処分と評価すべきものであって,利益そのものを否定する 事情には当たらない。),控訴人が販売利益を寄付したことを裏付ける 客観的な証拠もないから,いずれにせよ,控訴人は控訴人商品等を10 0個販売したことにより利益を得たものと推認される。
イ 控訴人商品等の販売に係る限界利益率について
控訴人は,控訴人商品はサンプル品であって仕入処理が行われておらず, 購入した際の領収証等の資料はないと主張し,また,バーキンタイプのバ ッグの仕入れに関する資料は保管期間経過によって全て廃棄処分済みで あると主張して,これを提出しない。さらに,控訴人は,バーキンタイプ と同程度の販売価格のハンドバッグの仕入価格は販売価格の55%程度 であったから,バーキンタイプのバッグの仕入価格も販売価格の55%程 度であったと主張し,販売価格の55%の価格でハンドバッグの仕入れを 行ったことを裏付ける証拠として乙31(平成29年1月の取引の納品書) を提出する。しかし,乙31は,どのような態様の商品の仕入れに係るも のか明らかでなく,平成22年に中国の業者から100個仕入れたと認め られるバーキンタイプのバッグとは,仕入の時期,取引先,仕入数が異な るから,乙31により,バーキンタイプのバッグの仕入価格が販売価格の 55%程度であったことは認められず,その他に,これを裏付ける証拠は ない。控訴人がその他の経費として主張する梱包費用,送料については, 具体的な支出の有無や額を裏付ける的確な証拠はない。
そこで限界利益率について検討すると,上記のとおり,控訴人の主張に よっても,仕入価格が販売価格の55%を上回ることはない。また,控訴 人は,バッグ等の販売を業として行っており,控訴人商品等の仕入れ,販 売,経費等に関する資料を所持し,その内容を把握しているのが自然であ ると解されるにもかかわらず,これらを提出せず,その内容を明らかにせ ず,そのため,経費等も具体的に立証されていない。このように,控訴人 が,被控訴人主張の利益率(60%)を否認しながら,関連性の乏しい証 拠のほかは,本来提出されてもおかしくない証拠を含め,何ら証拠を提出 していないことからすると,控訴人は控訴人商品等の販売により相当高率 の利益を得たと疑われてもやむを得ない側面があること,及び60%とい う利益率が有名ブランドを模したバッグの販売による利益率として不当 に高いとは考えられないことなどの事情を併せ考えると,控訴人商品等の 販売による限界利益率を60%と認定することについて,これが高率に過 ぎるとして不当とする根拠はない。これらの事情を考慮すると,控訴人商 品等の販売による控訴人の限界利益は,平均して販売価格の60%であっ たものと認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.12.22
令和2(行ケ)10096 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年12月2日 知的財産高等裁判所
審判便覧(丙1)によると,1項参加人も3項参加人と同様,被参加人が審判請 求を取り下げない限り,被請求人が答弁書を提出した後でも,被請求人の同意なく 参加を取り下げることができるとされている。また,1項参加の申請に際して,特\n許法施行規則様式第65によると,参加申請書に「請求」を記載することは求めら\nれていない。
しかし,審判便覧の上記取扱いについては,被参加人が取下げをしない限り,特 許法155条2項が保護しようとしている被請求人の利益,すなわち,審決を得て, 審判請求の理由がないことを確定するという利益の保護は図られているのであるか ら,その段階で1項参加人の取下げについて被請求人の同意を要する実益は乏しい ことから,上記のように取り扱われていると解され,上記の取扱いが,1項参加人 が「請求」を定立していないことに基づくものとはいえず,1項参加人が特許法1 79条1項の「請求人」に当たらないことの理由とはならない。 また,特許法施行規則様式65についても,1項参加人の請求は,被参加人の請 求と同一のものであるとの理解の下に上記のような様式が定められていると解され, そのことから1項参加人が「請求」を定立していないということはできず,1項参 加人が,特許法179条の「請求人」に当たらないことの理由とはならない。
(3) 上記4),5)について
特許法148条1項は,被参加人が請求を取り下げた場合に限り,1項参加人が 「請求人」となるとは規定しておらず,1項参加人が同項に基づいて「請求人」と なるのは,被参加人が審判請求を取り下げ,1項参加人が審判手続を続行した場合 に限られると解することはできない。 また,1項参加人に審決取消訴訟の被告適格を認めることが1項参加人の意思に 反する事態を招来するとは認められない。1項参加人が多数いるからといって,そ のことにより,訴訟手続がいたずらに煩雑化したり,遅延を招いたりして,訴訟経 済に反するとは認められない。 さらに,被告ニプロは,審決取消訴訟の係属中に被参加人が無効審判請求を取り 下げた場合,「請求人」として1項参加人が審決取消訴訟を受継することができると 主張するが,いかなる法的根拠に基づいてそのような「受継」ができるのか明らか ではない。また,仮に,このような「受継」をすることができたとしても,1項参 加人が受継した時点での訴訟の進行状況によっては,主張立証が制限されることも あり得るといえ,1項参加人の手続保障に欠けるところがないとはいえない。
◆判決本文
こちらは関連事件です。
2020.12.22
平成30(ワ)22338 特許法74条1項を原因とする特許権移転登録請求事件 民事訴訟 令和2年12月1日 東京地方裁判所
(1) 本件発明1及び本件発明11の特徴的部分について
ア 原告は,本件発明1及び本件発明11の特徴的部分の完成への関与につ いて,その大部分を担ったのは,原告代表者及びAiであると主張する。
イ 前記1(16)によれば,従前の技術的課題を解決する,本件発明1の特徴的 部分は,ラップネットにおいて従前,技術的課題であるとされていた作 業性,家畜の安全性を確保するために,ラップネットの経糸及び緯糸の いずれにもセルロース系繊維を用いたというものであると認められる。 この特徴的部分は,本件出願において優先権の主張がされた先の出願2 (平成25年7月22日出願)の請求項1に含まれるものであった。そ して,本件明細書の発明の実施の形態における,本件発明1のラップネ ットに関する経糸及び緯糸に使用する糸の種類や引張強度等の数値を含 めた記載は,先の出願2の明細書の記載とほぼ同様のものである。 これらによれば,本件発明1の特徴的部分は,平成25年7月22日ま でには完成されていた。
ウ 前記1(16)によれば,本件発明1のように,ラップネットの経糸及び緯糸 のいずれにもセルロース系繊維を用いると,特に緯糸に比べて強度が要求 される経糸が太くなり,それによって1本のロールに巻き取れるラップネ ットの長さが短くなるという課題があった。本件発明11は,その課題を 解決するため,本件発明1等のラップネットの製造方法において,巻上げ ローラを回転軸方向に所定の振幅で往復運動させて巻き取るというあや振 り機構を適用したものであり,本件発明11の特徴的部分は,本件発明1\nから10に係るラップネットの製造方法において上記のようなあや振り機 構を適用した部分であると認められる。\n
この特徴的部分は,本件出願において優先権の主張がされた先の出願2 (平成25年7月22日出願)の請求項6に含まれるものであった。そ して,本件明細書の実施の形態における,巻上げローラを回転軸方向に 所定の振幅で往復運動させて巻き取るというあや振り機構を用いた場合\nの往復運動の振幅,その場合の巻き取ったラップトップの長さや直径の 数値を含めた記載は,先の出願2の明細書の記載と同じものである。 これらによれば,本件発明11の特徴的部分は,平成25年7月22日 までには完成されていた。
(2) 本件発明1の特徴的部分の完成に対する原告代表者及びAiの現実の関与 について
ア 被告は,平成25年3月中旬頃,原告に対し,糸を提供して,緯糸に綿糸 を使用したラップネットの編布を依頼し,同年5月にタカキタ,原告,被告 の関係者が集まった場において,Biが全部を綿糸で製造した方が安全でな いかとの発言をして,その後,被告は,他の業者に対して依頼して製造して いた複数の種類の綿糸を原告に提供して,経糸及び緯糸に綿糸を使用するラ ップネットの編布を依頼し,原告は経糸にこれらの綿糸を使用してラップネ ットを試作した。 ここで,ラップネットの緯糸,経糸に綿糸を用いることについて,原告代 表者又はAiが着想して,これを被告に提案したと認めることはできない (前記1(19)ア,イ)。
イ 原告は,平成25年5月,被告から提供を受けた複数の種類の綿糸を経糸 及び緯糸に使用して,ラップネットの試作を行い,タカキタは,その試作品 の強度が十分であることを確認した。\nもっとも,経糸に使用した綿糸は,被告が平成25年3月頃からラップネ ットの経糸に使用することを想定して他社に依頼して製造していたものであ り,それを原告に提供したものであった。また,ラップネットの編組織は一 般的なものであり,その製造には一般的なラッシェル編機を用いることが可 能であり(前記1(2)),原告は,従前から保有していたラッシェル編機を用 いて編布をした。
ウ 原告は,平成25年7月22日,先の出願2をした。その請求項1に記載 された発明は,ラップネットにおける経糸及び緯糸がセルロース系繊維であ るというものであったところ,その明細書の実施例には,経糸,緯糸に用い る具体的な綿糸の種類や,それを用いて,ラッシェル編機を使用してラップ ネットを製造した場合の編地の長さ方向に連なるチェーンステッチ1本当た りの具体的な強度(引っ張り強さ)が記載されていた。この強度等の数値は, 被告代表者が,その知識,経験に基づき計算したもので,原告から提供され\nたものはなかった。 また,原告は,先の出願2等を優先権の基礎として,平成26年4月23 日に本件出願をしたところ,その明細書の実施例には,先の出願2とほぼ同 様の,経糸,緯糸に用いる具体的な綿糸の種類や,それを用いて,ラッシェ ル編機を使用してラップネットを製造した場合の編地の長さ方向に連なるチ ェーンステッチ1本当たりの具体的な強度(引っ張り強さ)が記載されてい た。この強度等の数値は,被告代表者が,その知識,経験に基づき計算した\nもので,原告から提供されたものはなかった。また,上記の計算や本件明細 書の記載に当たり,原告から提供を受けた試験結果等が参考等されたことを 認めるに足りる証拠はない。
エ 前記アによれば,本件発明1の特徴的部分について,原告代表者又はAi が着想したと認めることはできない。また,前記イのとおり,原告が綿糸を 使用したラップネットの編布を行ったことは認められるものの,それは被告 が製造して原告に提供した綿糸を使用してされたものであって,ラップネッ トの編組織が一般的なものであり,上記編布において一般的な編布に必要な 技術以外の技術が用いられたことを認めるに足りる証拠はないことなどから すると,そのような編布をしたことのみをもって,原告代表者及びAiが直 ちに本件発明1の特徴的部分の完成に現実に関与したと認めるには足りない。 そして,前記ウのとおりの明細書の記載やその記載に至る経緯に照らせば, 原告が編布を行ったり,その後,その試作品の強度試験を行ったりしたこと があったとしても,原告代表者及びAiが,本件発明1の特徴的部分の完成 に現実に関与したと認めるには足りない。 したがって,本件発明1の特徴的部分の完成に原告代表者又はAiが具体 的に関与したとはいえず,原告代表者又はAiが本件発明1を発明したとい うことはできない。
オ 原告,被告及びタカキタは,平成25年12月,本件開発契約を締結した (前記1(14))。しかし,本件開発契約において,有効期間は同年9月からと 定められているのに対し,本件発明1の特徴的部分が同年7月22日までに 完成されていたことから,そもそも,本件発明1は,本件開発契約に基づい て開発,発明されたものとはいえない。また,原告もその当事者である本件 開発契約においては,その有効期間前の被告の活動等として,被告が,平成 25年5月に綿ベールネットの編布を原告に依頼したこと,原告に複数の綿 糸を納入したこと,タカキタに綿ネットの試験巻きを依頼したことが特に記 載されており,「綿ベールネット」自体は被告が開発したことが前提とされ ていたともいえる。 また,被告が平成24年に原告に対しラップネットの編布を依頼した後, 被告及び原告は,共同で特許出願をしたり,畜産試験場を訪れたり,試作品 についての評価をタカキタで受けたり,どのような試作品を製造するかを確 認したり,補助金の交付の申請をしたりした(前記1(3),(5),(7)ないし(9))。 また,原告は,新たに編機を購入するなどした上でラップネットの製造につ いての開発を行った(同(15))。
しかし,上記各事実は,それ自体は本件発明1の特徴的部分の完成に直接 関係するとはいえないものであって,それらの事実をもって直ちに本件発明 1の特徴的部分の完成に原告代表者又はAiが現実に関与したと認めるに足 りるものではない。上記各事実は,前記アないしウに記載した事実に照らす と,本件発明1の特徴的部分の完成に原告代表者又はAiが具体的に関与し たとはいえないという上記認定を左右するものではない。
なお,被告が,ラップネットに関し,平成25年1月に原告と共同で別件 出願1をしたことや,同年12月に原告及びタカキタと本件開発契約を締結 したことについて,被告代表者は,別件出願1は,原告からラップネットを\n量産化するに当たり,生分解性ポリエチレンフィルムのスリット加工等も原 告において行った上で編布をしたい旨の申出を受けたことから,経編機の改\n良における原告の役割を期待して,共同で行うこととしたものであり,また, 本件開発契約は,被告において綿製ラップネットの基本的な開発が完了した 段階で量産化や生産効率化を図るに当たり,原告及びタカキタにおいて積極 的な役割を果たすことが期待されたことから締結したものである等と陳述す る(乙34)。この説明は,原告が平成26年1月頃から新しく購入したラ ッシェル編機を用いてラップネットの製造を行う(前記1(15))など,ラップ ネットの量産化,生産効率化における役割を果たしたことや,原告と被告は 被告が原告に糸代及び加工賃を支払うという態様で継続的に取引を行うよう になっていて(同(18)),ラップネットの生産効率化等は被告の利益でもあっ たことなどを含めた前記認定に係る事実経過にも矛盾せず,相応の合理性が あるものである。
カ 以上によれば,本件発明1について,原告代表者及びAiが発明者である ことを認めるに足りず,同人らが本件発明1に係る特許を受ける権利を有し ていたとはいえない。
(3) 本件発明11の特徴的部分の完成に対する原告代表者及びAiの現実の関 与について
ア 原告代表者,Ai及び被告代表者は,平成25年5月31日,タカキタ\nにおいてラップネットの試作品の評価を受け,以後の予定として,巻取り\nの際にあや振りをするなどの仕様で試作品を製造することが確認された (前記1(8))。 ここで,原告代表者又はAiが,綿糸を用いるラップネットの編布におい てあや振りの技術を適用することを着想し,被告に提案したとは認められな い(前記1(19)エ)。
イ 原告は,平成25年6月以降,巻上げローラを回転軸方向に所定の振幅で 往復運動させるのではなく,巻上げローラの前にあや振り装置を設置すると いう方法により,あや振りを施すことを試みていた(前記1(10))。なお,そ れ以前,原告は,巻上げローラを左右に往復運動させる方法を試みたが,所 望の結果が得られず,また,上記方法について,被告にその機械の動作等を 見せたことはなく(同(2)),同動作等に関する情報を被告に対して提供した ことを認めるに足りる証拠はない。
ウ 巻取りに際してあや振りをすること自体は,繊維業界において広く用いら れている基本的な技術であり,被告が昭和60年頃に導入した整経機にもあ や振り機構が備わっており,被告代表\者は,従前からあや振りの技術を認識 し,日常的に用いていた。 被告は,平成25年7月22日,先の出願2をした。その請求項6に記載 された発明は,経糸及び緯糸がセルロース系繊維からなるラップネットの製 造方法において,巻上げローラを回転軸方向に所定の振幅で往復運動させる というものであった。そして,明細書の実施例には,巻上げローラを回転軸 方向に往復運動させる振幅の数値や,1本のロールに巻き取ったラップネッ トの長さ,その直径の数値が記載されているところ,この数値等は被告代表\n者が知識と経験に基づいて計算したものであり,原告から提供されたもので はなかった。そして,原告は,先の出願2等を優先権の基礎として,平成2 6年4月23日に本件出願をしたところ,本件明細書の実施例には,あや振 りに関して,先の出願2の実施例と同じ記載がされていて,この数値等は被 告代表者が知識と経験に基づき計算したものであった。上記の計算や本件明\n細書の記載に当たり,原告から提供を受けた何らかの情報が参考等されたこ とを認めるに足りる証拠はない。
エ 上記アによれば,本件発明11の特徴的部分について,原告代表者又はA\niが着想したと認めることはできない。また,原告が巻上げローラの前にあ や振り装置を設置するという方法によりあや振りを施すことを試みていたこ とは認められるが,本件発明11は,巻上げローラを回転軸方向に所定の振 幅で往復運動させるというものである。そして,前記ウのとおりの明細書の 記載やその記載に至る経緯に照らしても,原告代表者やAiが本件発明11 の特徴的部分の完成に現実に関与したと認めるには足りない。 したがって,本件発明11の特徴的部分の完成に原告代表者又はAiが現 実に関与したとはいえない以上,原告代表者又はAiが本件発明11を発明 したということはできない。
オ 原告は,ラップネットの試作を行い,平成25年6月以降は,巻上げロー ラの前にあや振り装置を設置する方法によりあや振りを施すことを試みるよ うになり(前記1(10)),平成30年7月には,ネット生地を鎖編組織の間隔 の範囲内で幅方向に一定の大きさで振りながら巻き取ることなどの構成を有\nする製造方法についての特許出願をする(同(18))など,ラップネットの製造 においてあや振りに関する開発を行っていたことはうかがえる。しかし,上 記各事実は,その内容及び時期から,平成25年7月22日までに完成され ていた,本件発明1等のラップネットの製造方法において巻上げローラを回 転軸方向に所定の振幅で往復運動させて巻き取るというあや振り機構を適用\nするという,本件発明11の特徴的部分の完成に対し,原告代表者及びAi が具体的に関与したことの根拠となるものではない。
(4) 以上によれば,原告代表者又はAiが本件発明1及び本件発明11を発明し, ひいては本件各発明の大部分を担ったとの原告の主張には理由がない。 なお,本件各発明のうち,本件発明1及び本件発明11以外の発明について, その特徴的部分の完成に対する,原告代表者又はAiの具体的な関与を認める に足りる証拠もない。原告の主張中には,本件各発明の中には本件開発契約の 期間中の発明がある旨述べる部分もあるが,その期間中にされた発明であるこ とによって,直ちに特定の発明の特徴的部分の完成に原告代表者及びAiが具 体的に寄与したと認められることになるものではない(本件開発契約でも発明 に係る権利は発明をした当事者に帰属することが定められていた。)。 したがって,原告代表者及びAiが被告代表者と共同で本件各発明をしたと\nは認めるに足りない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2020.12.21
令和2(行ケ)10076 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年12月15日 知的財産高等裁判所
同号掲記の標章のうち商品等の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり,商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって,その反面として,商品・役務の出所を表\示し自他商品・役務を識別する標識として用いられるものは少なく,需要者としても,商品等の形状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは異なり,商品の機能\や美観を際立たせるために選択されたものと認識するものであり,出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。また,商品等の機能\又は美観に資することを目的とする形状は,同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを必要とし,その使用を欲するものであるから,先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは,公益上の観点から適切でないといえる。したがって,商品等の形状は,同種の商品が,そ の機能又は美観上の理由から採用すると予\測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り,普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,3条1項3号に該当すると解するのが相当である。
(2) 包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形形状\n
ア 液体状の商品の包装容器に付された形状
飲食料品を取り扱う業界において,液体状の商品を封入する包装容器は, 持ちやすさ,注ぎやすさ,飲みやすさ等の観点から,細口で縦長のものが 採択,使用されることが多い。しかし,このような商品の性質から要求さ れる一定の制約の下においても,様々な形状の包装容器が存在し(乙1〜 乙5),これらの包装容器の表面に立体的形状による装飾を付したもの,中\nでも連続する菱形形状(ダイヤカット)を付したものが,次のとおり認め られる。
・・・・
そうすると,液体状の商品の包装容器の上部又は下部に,連続する菱形 形状を付すことは,取引上普通に採択,使用されているものと認められる。 そして,そのいずれの場合においても,その包装容器の連続する菱形形状 の上又は下に,商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼\付され又は商 品名が目立つ態様で表示されているものと認められることや,1),2)の各 記載等に照らしてみると,菱形形状は,持ちやすさなどの機能や美観の観\n点から採用されているものと考えられる。
・・・
(イ) 焼肉のたれに係る包装容器に付された菱形形状
焼肉のたれの包装容器の表面に付す立体的装飾の一類型として連続す\nる立体的な菱形形状を用いるものが,次のとおり認められる。
1) 「コスモ食品株式会社」のウェブサイト(乙17)において,「北の 方から 焼肉のたれ 中辛350g」(1枚目),「北の方から 焼肉の たれ 薬膳 中辛350g」(3枚目)の見出しの下,連続する縦長の 菱形の立体的形状が下部に付され,その上に商品名等を目立つ態様で 表示したラベルが貼\付された容器の写真が掲載されている。
2) 「フードレーベル」のウェブサイト(乙18)において,「焼肉トラ ジ 焼肉のたれ 240g」の見出しの下,連続する縦長の菱形の立 体的形状が下部に付され,その上に商品名等を目立つ態様で表示した\nラベルが貼付された容器の写真が掲載されている。\n
3) 「Amazon」のウェブサイト(乙19)において,「成城石井 焼 肉のたれ 350g」(1枚目)の見出しの下,連続する縦長の菱形の 立体的形状が包装容器の下部に付され,その上に商品名等を目立つ態 様で表示したラベルが貼\付された容器の写真が掲載されている。
4) 「Amazon」のウェブサイト(乙20)において,「焼肉チャン ピオン 焼肉のたれ 240g」(1枚目)の見出しの下,連続する縦 長の菱形の立体的形状が蓋部及び下部に付され,その間の中央部分に 商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼\付された容器の写真が掲 載されている。 そうすると,焼肉のたれの包装容器の上部又は下部の表面に,連続す\nる縦長の菱形形状を付すことは,取引上普通に採択,使用されているも のと認められる。そして,そのいずれの場合においても,その包装容器 の表面の連続する縦長の菱形形状の上又は下に,商品名等を目立つ態様\nで表示したラベルが貼\付されているものと認められること等からすれば, これらの菱形形状も,機能や美観の観点から採用されているものと推認\nされる。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 立体商標
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.12.21
令和2(ネ)10039 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年12月1日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記(ア)の発明の詳細な説明の記載によれば,発明の詳細な説明に記 載された実施例(第1実施例,第2実施例)は,いずれもアンテナ素子 の下に平面アンテナユニットを配置し,アンテナ素子の下縁と平面アン テナユニットの上面の間隔を約0.25λ 以上としたものであり,それ により,アンテナ素子と平面アンテナユニットについて,相互に影響を 及ぼすことが低減され,それぞれ単独で存在する場合の各アンテナと同 等の電気的特性を示すことを具体的に示すものである。発明の詳細な説 明には,第1実施例のアンテナ装置を用いた実験結果が記載されている ところ(【0018】〜【0026】,図7〜図12,図15〜図19), これらは,アンテナ素子と平面アンテナユニットの相互干渉がアンテナ の電気的特性に及ぼす影響を検証したものであると認められ,実施例が, 発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するという効果を生ず るかどうかを確かめるものと認められる。 そうすると,発明の詳細な説明に記載された実施例は,前記認定の発 明の詳細な説明に記載された発明(前記イ(イ))の実施の形態を具体的 に示し,その発明の課題(前記ア(イ))を解決するという効果を生ずる ことを示すものであると認められる。
(3) 請求1に記載された発明は,発明の詳細な説明に記載された発明か ア 請求項1に記載された発明は,前記第2,3(2)のとおりであり,1)アン テナ素子に加えて別のアンテナである平面アンテナユニットを組み込むこ とは構成要件とされてはおらず,また,2)仮にアンテナ素子に加えて平面 アンテナユニットを組み込んだ場合に,アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔が約0.25λ以上であることも構成要件とさ\nれていない。そのため,請求項1に記載された発明は,アンテナ素子に加 えて平面アンテナユニットを組み込み,アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔を約0.25λ以上とするアンテナ装置以外に も,1)そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニットが組み込まれて いないアンテナ装置の発明を含み,また,2)アンテナ素子に加えて平面ア ンテナユニットが組み込まれてはいるものの,アンテナ素子の下縁と平面 アンテナユニットの上面との間隔が約0.25λ未満であるアンテナ装置 の発明を含むものである。
イ これに対し,発明の詳細な説明に記載された発明は,前記(2)イ(イ)のと おりであり,アンテナ素子と,アンテナ素子の直下であって,前記アンテ ナ素子の面とほぼ直交するよう配置されている平面アンテナユニットとを 備えるアンテナにおいて,平面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の 下端との間隔を約0.25λ以上とするものであると認められる。
ウ そうすると,請求項1に記載された発明のうち,1)アンテナ素子以外に 平面アンテナユニットが組み込まれていないアンテナ装置の発明,及び2) アンテナ素子に加えて平面アンテナユニットが組み込まれてはいるもの の,アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔が約0. 25λ未満であるアンテナ装置の発明は,発明の詳細な説明に記載された 発明ではない。 したがって,請求項1に記載された発明は,発明の詳細な説明に記載さ れた発明以外の発明を含むものであり,発明の詳細な説明に記載された発 明であるとは認められない。
(4)請求項1に記載された発明は,発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は 出願時の技術常識に照らし,当業者が課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか発明の詳細な説明に記載された発明の課題は,限られた空間しか有してい ないアンテナケースを備えるアンテナ装置に既設の立設されたアンテナ素子 に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込むと相互に他のアンテナの影 響を受けて良好な電気的特性を得ることができないという課題であり(前記 (2)ア(イ)),このような課題を当業者が認識するためには,限られた空間し か有しないアンテナ装置において,既設の立設されたアンテナ素子に加えて 新たに平面アンテナユニットを組み込むことが前提となる。しかし,請求項 1に記載された発明は,そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニット が組み込まれていないアンテナ装置の発明を含み(前記(3)ア),そのような 構成の発明の課題は,発明の詳細な説明には記載されていない。そのため,\n請求項1に記載された発明は,当業者が発明の詳細な説明の記載によって課 題を認識できない発明を含むものであり,当業者が課題を解決できると認識 できる範囲を超えたものである。
また,請求項1に記載された発明は,アンテナ素子に加えて平面アンテナ ユニットが組み込まれてはいるものの,アンテナ素子の下縁と平面アンテナ ユニットの上面との間隔が約0.25λ未満であるアンテナ装置の発明を含 むが(前記(3)ア),発明の詳細な説明には,課題を解決する方法として,平 面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の下端との間隔を約0.25λ 以 上とすることが記載されており,アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニッ トの上面との間隔を約0.25λ未満とするならば,発明の詳細な説明に記 載された課題を解決することはできない。そのため,請求項1に記載された 発明は,この点においても当業者が発明の詳細な説明に記載された解決手段 によって課題を解決できると認識できない発明を含むものであり,当業者が 課題を解決できると認識できる範囲を超えたものである。 その他,請求項1に記載された発明が,発明の詳細な説明の記載若しくは 示唆又は出願時の技術常識に照らし,当業者が課題を解決できると認識でき る範囲のものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって,請求項1に記載された発明は,発明の詳細な説明の記載若し くは示唆又は出願時の技術常識に照らし,当業者が課題を解決できると認識 できる範囲のものであるとは認められない。
◆判決本文
関連訴訟(原告被告が同じ)はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.12.21
令和1(行ケ)10136 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年12月15日 知的財産高等裁判所
上記(1)イ(イ)・(ウ)のとおり,本件明細書においては,パロノセトロン又はそ の塩を含む溶液は,pH及び/又は賦形剤濃度の調整並びにマンニトール及び キレート剤の適切な濃度での添加によって,安定性が向上することが記載さ れ,実施例1〜3において,製剤が最も安定するpHの値,クエン酸緩衝液及 びEDTAの好適な濃度範囲,マンニトールの最適レベルが示され,実施例 4,5に代表的な医薬製剤が示されているが,実施例4,5においては,実\n際に安定性試験が行われていないため,そこに記載された医薬製剤が少なく とも24ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されているとはいえない。ま た,その他の箇所をみても,安定化に資する要素は挙げられてはいるものの, それらが24ケ月の貯蔵安定性を実現するものであることについての直接的 な言及はないし,どのような要素があればどの程度の貯蔵安定性を実現する ことができるのかを推論する根拠となるような具体的な指摘もなく,結局, 具体的な裏付けをもって,具体的な医薬製剤が少なくとも24ケ月の貯蔵安 定性を有することが記載されているとはいえない。
なお,上記(1)イ(イ)のとおり,本件明細書の一連の実施例は,薬剤の安定化 のための合理的な条件を見出すための要因を探求するものであって,特に, 実施例1〜3は,個々の要因を探求するプレフォーミュレーション(予備処\n方設計,前処方化)に該当し,実施例4,5の代表的な医薬製剤は処方化研\n究(製剤設計)に該当するといえるとしても,上記のとおり,本件明細書に は,pH,賦形剤,マンニトール及びキレート剤の濃度を調整することで,安 定性向上に関し,どのような作用・機序があるのか,どの程度の安定性の向 上,安定性への貢献が見込めるのかが記載されていないため,実施例4,5 の医薬製剤が少なくとも24ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されてい るとはいえないし,その他の箇所をみても,合理的な説明をもって,具体的 な医薬製剤が少なくとも24ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されてい るとはいえない。 そうすると,本件明細書には,24ケ月要件を備えたパロノセトロン製剤 が記載されているとはいえないし,本件出願時の技術常識に照らしても,当 業者が,本件各発明につき,医薬安定性が向上し,24ケ月以上の保存を可 能にするパロノセトロン製剤とその製剤を安定化する許容される濃度範囲を\n提供するという本件各発明の課題(上記(1)ア)を解決できると認識できる範 囲のものであるとはいえない。 なお,実施例6,7の記載は,(1)イ(エ)のとおり,パロノセトロン塩酸塩以 外の成分(賦形剤,等張剤など)の有無及び濃度についての記載や,pHの 値についての記載を欠くため,本件各発明に該当する製剤に関する実施例で あるとはいえないし,これによって安定性が確認されたのは,最長でも16 日間にすぎないのであるから,上記(2)イの技術常識に照らしてみても,24 ケ月要件を備えたパロノセトロン製剤を提供する等の本件各発明の課題(上 記(1)ア)を解決し得ることの根拠にはなり得ない。
(4) 原告の主張について
ア 上記第4の1(1)及び(2)の主張について
上記(3)のとおり,本件明細書には,pH,賦形剤,マンニトール及びキレ ート剤の濃度を調整することで,安定性向上に関し,どのような作用・機 序があるのか,どの程度の安定性の向上,安定性への貢献が見込めるのか が記載されていないため,本件出願時の技術常識を踏まえても,実施例4, 5の医薬製剤が24ケ月要件を備えたものであることが記載されていると はいえないし,その他の箇所をみても,具体的な医薬製剤が少なくとも2 4ケ月の貯蔵安定性を有することを,具体的な根拠に基づいて合理的に説 明しているとはいえない。そして,24ケ月という期間に直接言及する【 0017】【0037】の記載も,上記(1)イ(ア)のとおり,当該製剤ないし 容器を24ケ月以上保存できることをいかなる方法で確認したか等につい ての具体的な言及を欠くから,これらの段落の記載をもって,24ケ月要 件が本件明細書に実質的に記載されているということもできない。 したがって,原告の上記第4の1(1)及び(2)の主張は採用することができ ない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2020.12.15
令和2(行ケ)10028 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年12月9日 知的財産高等裁判所
上記認定事実によれば,ローズ・オニールが創作したキューピー人形及び その名称の「キューピー」が大正2年(1913年)に我が国に紹介された 後,「キューピー人形」及びその名称の「キューピー」は,本件出願前(出 願日大正11年4月1日)に,日本国内の全国にわたり,広く知られるよう になったことが認められる。原告の挙げる甲6,9ないし14,18ないし 21の記述(前記第3の1(1)ア(イ))は,これを裏付けるものといえる。 しかしながら,一方で,上記認定のとおり,大正5年(1916年)以降, ローズ・オニールが創作に関与したキューピー人形とは異なる「日本なりの キューピー」人形や,日本文化と関わりを持たせて描かれた絵葉書,年賀状 などが発売され,また,日本的な,日本でデザインされたキューピーは,様々 な商品のブランド名,広告類のイラスト等や商品の容器等に広く使用されて きたこと,加えて,甲6には,「その代表たるキューピーちゃんも,最初は\nドイツで作られたものだそうだが,それが日本でも作られるようになり,い つの間にか日本的キューピーとして生れかわった。そのルーツもあまり知ら れずに,そのくせ,最近まで,子供の頃に一度もキューピーを手にしていな い人はなかったというぐらい大衆性が続いたのは,キューピーが子供ばかり でなく大人にも可愛がられる何かを,強力にもっていたからだろう。」,「遠 く太平洋をへだてた島国の日本のこと,生みの親のローズさんのことも,オ リジナルの可愛らしいイラストのキューピーもあまり知られないまま,どん どん日本なりのキューピーが作られ,ますます広く愛されたのである。」(前 記1(3)ア(イ))との記載があることに鑑みると,キューピー人形は,本件出 願当時,キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識され ることなく,西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に 使用できるものと理解され,全国において,キューピー人形やそれを模した 絵柄や図形等が多数作成され,商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用さ れる状況にあったものと認められる。
以上によれば,原告の挙げる甲6,9ないし14,18ないし21の記述 から,キューピー人形及びその名称の「キューピー」が,本件出願前に自他 商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めるこ\nとはできず,他人の業務に係る商品を表示するものとして,日本国内におけ\nる需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。他にこれ を認めるに足りる証拠はない。
・・・
(2) 不正の目的について
原告は,被告の創業者のAは,本件出願前の1915年(大正4年)3月 から同年12月9日までの間米国に滞在中に,米国においてキューピー人形 及びその名称「キューピー」が広く知られていたことを了知したところ,1) 本件商標は,ローズ・オニール創作に係る人形の絵図及び人形の題号「KE WPIE」,「キューピー」のみからなること,2)本件出願以前において, ローズ・オニールの創作したキューピー人形の特徴を備えたキューピー人形 とその名称は,日本国内において,老若男女を問わず,全国津々浦々まで人 気があり,周知著名であったこと,3)被告は,本件商標を指定商品に使用し た実績がないこと(甲65,66),4)被告のウェブページ(甲27の1, 2)には,Aが他人の著名標章を自己のものとして商標登録した経緯が記載 されていること,5)被告は,本件出願後に,本件商標と同様のローズ・オニ ール創作に係る人形の絵図とローズ・オニール創作に係る人形の題号「KE WPIE」,「キューピー」から構成されるキューピー関連商標470件に\nついて広範な指定商品において出願及び登録し,あるいは商標を譲り受けて, 他人の知的創作である「キューピー人形の絵図」,「キューピーの名称」か らなる商標の独占を図ったことからすると,Aは,他人の標章の著名性にた だ乗りし,あるいは他人の知的財産を自己のものとして,権利化を図るとい う「不正の目的」をもって,本件出願を行ったものである旨主張する。
そこで検討するに,本件商標の出願時及び商標登録時において,ローズ・ オニールの創作に由来するキューピー人形及びその名称の「キューピー」は, 日本国内の全国にわたり,広く知られるようになったことは認められるもの の,キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ない\nし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず,他人 の業務に係る商品を表示するものとして,日本国内における需要者の間に広\nく認識されていたものと認めることはできないことは,前記(1)で説示したと おりである。
こうした状況のもとで,Aは,大正11年4月1日,本件商標の出願をし, 商標登録を受けたものであるから,その余の点について判断するまでもなく, Aが本件出願に当たり,他人の標章の著名性にただ乗りし,あるいは他人の 知的財産を自己のものとして,権利化を図るという「不正の目的」を有して いたものと認めることはできない。
・・・・
(3) 国際信義違反について
原告は,1)被告の創業者のAによる本件商標の出願及び登録は,外国の著 名標章を自己のものとすることを目的とするものであり,不正の目的をもっ てされたものである,2)A及び本件商標を承継した被告は,ローズ・オニー ルの創作に係る人形の絵図と類似し,かつ,その創作に係る人形の名称「キ ューピー」の創作者の母国であり,「キューピー人形」の著作物の第1発表\n国であり,意匠登録された米国において,多数のキューピー関連商標を出願, 登録し(甲36),「KEWPIE DOLL」なる商標に対して権利行使 をした(甲37),3)のみならず,被告は,米国を含めた全世界において, 本件商標と同じく,キューピー人形の絵図,「KEWPIE」,「キューピ ー」等の文字商標を多数出願及び登録し,他人の知的創作であるキューピー 人形及びその名称の権利化を図っており,A及び被告による他人の知的創作 の剽窃行為は全世界に及んでいる,4)したがって,本件商標の出願及び登録 は,国際信義に反する旨主張する。 そこで検討するに,証拠(甲30,37,38)によれば,本件商標を承 継した被告は,「KEWPIE(kewpie)」の文字からなり,又は当 該文字を構成中に含む登録商標を米国において合計7件(2018年10月\n13日時点)保有しているほか,既に消滅したもの又は保留中のものを含め て,「KEWPIE(kewpie)」の文字やキューピーの絵図等を含む 商標について,ドイツ,シンガポール,カナダ,フィリピン,オーストラリ ア,マレーシア,フランス,デンマーク,ベトナム,インドネシア,ブルネ イ,メキシコ,カンボジア,モンゴル,イスラエル,ラオス,チリ,アイス ランド,ニュージーランド,欧州連合に出願等をしたこと,被告は,201 6年(平成28年)5月26日,「KEWPIE DOLL」の商標に係る 出願に対して異議の申立てをしたことが認められる。\n
しかしながら,一方で,前記(2)認定のとおり,Aが本件出願に当たり,他 人の標章の著名性にただ乗りし,あるいは他人の知的財産を自己のものとし て,権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはで きないのみならず,被告が「KEWPIE(kewpie)」の文字からな り,当該文字等を含む商標を米国のみならず多数の国に出願し,登録を受け たことは,被告が我が国のみならず世界中で様々な事業を展開する上で,本 件商標と類似する商標の出願及び登録が必要であったことによるものと認め られ,また,被告が「KEWPIE DOLL」の商標に係る出願に対して 異議の申立てをしたことも,米国で保有する「KEWPIE」の文字からな\nる商標と類似する文字が含まれているために権利行使をしたものであり,い ずれも国際信義に照らし,不当であるということはできない。 したがって,本件商標の出願及び登録が国際信義に反するとの原告の上記 主張は理由がない。
(4) 本件商標の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」該当性について
以上によれば,Aが,他人の標章の著名性にただ乗りし,あるいは他人の 知的財産を自己のものとして,権利化を図るという「不正の目的」をもって, 本件出願を行ったものと認めることはできず,また,本件商標の出願及び登 録が国際信義に反するものと認めることはできないから,本件商標権をAか ら承継した被告が保有することが,社会公共の利益に反し,又は社会の一般 道徳観念に反するものと認めることはできない。 したがって,本件商標が旧商標法2条1項4号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ 虞アルモノ」に該当するとの原告の主張は採用することができない。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由1は 理由がない。
3 取消事由2(本件商標の旧商標法2条1項11号該当性の判断の誤り)につ いて
(1) 原告は,本件商標は,ローズ・オニールが創作したキューピー人形の絵図 と「KEWPIE」の欧文字とその片仮名から構成されるものであって,本\n件商標を付した商品について,需要者は,著名な「キューピー人形」,「K EWPIE」の名称と関係があるという特定の出所を認識することにより混 同を生じさせるものであるから,旧商標法2条1項11号の「商品ノ混同ヲ 生セシムルノ虞アルモノ」に該当する旨主張する。
しかしながら,前記1(1)で説示したとおり,キューピー人形は,本件出 願当時,キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識され ることなく,西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に 使用できるものと理解され,全国において,キューピー人形やそれを模した 絵柄や図形等が多数作成され,商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用さ れる状況にあったものであり,本件商標の出願時及び商標登録時において, ローズ・オニールの創作に由来するキューピー人形及びその名称の「キュー ピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたも\nのと認めることはできず,他人の業務に係る商品を表示するものとして,日\n本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできな いことに照らすと,本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する需 要者において,特定の他人(当該他人と緊密な営業上の関係等にある営業主 を含む。)の商品の出所との同一性の誤認を生じるおそれがあったものと認 めることはできない。 したがって,本件商標は,旧商標法2条1項11号の「商品ノ混同ヲ生セ シムルノ虞アルモノ」に該当するものと認められないから,原告の上記主張 は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.12.15
令和1(ワ)21183 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和2年12月3日 東京地方裁判所
以上によれば,前件仮差押申立事件において500万円を超えて仮に差し\n押さえられた部分について,被告米国法人には過失が推定される。 これに対し,被告米国法人は,前件仮差押申立事件において,商標法38\n条1項において被告米国法人が販売することができた商品には,規範的に被 告米国法人と同視できる者が販売することができた商品も含むという理解を 前提として被保全債権額の主張をしたところ,事実関係や裁判例等から,そ のような主張をしたことには相当な理由があるから被告米国法人には過失が ない旨主張し,上記の事由から過失の推定が覆滅する旨主張する。 前件仮差押申立事件の申\立書において,被告米国法人は,被告米国法人が 被告商品を直販しているから,日本における推定小売価格の全額が被告米国 法人の利益となる旨主張していた(前記1(3))。
被告商品は,実際には,被告米国法人から,順に,MSオペレーション, MSリージョナルセイルズ,被告日本法人に販売され,日本国内において, 被告日本法人により販売されていたのであるが,前件仮差押申立事件の申\立 書において,被告米国法人は,前記のとおりの主張をしており,被告商品を 日本において販売しているのが被告日本法人であることや,被告日本法人が 被告米国法人と同視することができることなどの主張はしていなかった。そ して,取引の流れについて上記の主張をしていないだけでなく,被告米国法 人の販売後日本における販売までの間に独立の法人格を有する複数の法人が 介在している以上,前件仮差押申立事件の申\立人である被告米国法人の利益 はMSオペレーションに販売することによる利益であるのが原則であるのに, 特段の説明も一切なく,「直販」していることを挙げて日本における推定小 売価格の全額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていた。この主張は, 被告米国法人が自ら日本国内で販売していることを前提として主張していた と解するほかはない。
これらからすると,前件仮差押申立事件の仮差押申\立書における被告米国 法人の主張は,実際の取引の流れを踏まえつつ,商標法38条1項において 被告米国法人が販売することができた商品には,規範的に被告米国法人と同 視できる者が販売することができた商品も含むという理解を前提にしてされ たものとは認められない(なお,仮に,実際の取引の流れを踏まえて,上記 のような理解から仮差押申立書を記載したとすると,被告日本法人と被告米\n国法人の関係や被告日本法人が被告米国法人と同視できるなどの主張を明示 的にせずに仮差押申立書において上記のように主張することが適切であるか\nは疑問の余地があるほか,特に,被告米国法人の利益について,特段の説明 もなく,直販を理由として日本国内の推定小売価格の全額が被告米国法人の 利益となるとの主張をすることは不適切といえる。債務者の審尋等を経ない 仮差押えの申立てにおける主張については,特にこのことがいえる。)。\n被告米国法人は,本件において,過失の推定を覆す事情として上記理解を していたことを前提とする主張をするのであるが,その主張は前提を欠くと いえる。被告らの主張中には,前件訴訟等における被告米国法人の原告に対する損 害賠償額が前記の額となったことに関係して,原告が前件訴訟等において侵 害行為の詳細を明らかにしなかったことを指摘する部分がある。
しかし,上記が本件における過失の推定を覆す事情になるかは措くとして も,原告が販売した原告商品に対応する被告商品の種類等が明らかにならな かったことによって前件訴訟等における損害賠償額が本来の損害賠償額より も少額となったことを認めるに足りる証拠はない。前件訴訟等の裁判所は, 上記詳細が明らかにならなかったことから証拠がないことを理由に損害が認 められないとしたりはせず,同状況も含み得る種々の事情を考慮した上で商 標法39条において準用する特許法105条の3を適用して,相当な損害額 を認定したものである。なお,被告米国法人は,前件仮差押申立事件の申\立 書において,商標法38条2項に基づき損害が算定され,直販を理由として 日本の推定小売価格の全額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていた が,被告米国法人から独立した法人格を有する複数の企業を介して日本国内 において被告商品が販売される以上,仮に介在する企業が完全子会社であっ たとしても,被告米国法人の利益は,被告米国法人がMSオペレーションに 販売したことによって得られた利益であり,その額は,通常は,日本におけ る推定小売価格の全額とはならないといえる。また,被告米国法人は,前件 仮差押申立事件の申\立書において,上記のとおり,日本の推定小売価格の全 額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていたが,その後の前件訴訟等 においては,利益率は42%であると主張し,前件訴訟等の裁判所は,原告 主張の利益率を逸失利益の算定の根拠とすることは相当でないとしてその利 益率を採用しなかった。
以上によれば,前件仮差押申立事件において500万円を超えて仮に差し\n押さえられた部分について,被告米国法人に過失が推定され,被告米国法人 は,その推定が覆ると主張するが,本件において,被告米国法人が過失の推 定が覆るとしている事由はその前提を欠くといえる 。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.12.10
令和1(行ケ)10117 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年12月3日 知的財産高等裁判所
1 取消事由1(新規事項の追加についての判断の誤り)について
本件決定が,本件訂正は新規事項の追加に当たるとする理由は,本件明細書 等においては,駐車装置の利用者(以下「確認者」という。)が乗降室内の安 全等を確認する位置(訂正後請求項1の「安全確認実施位置」)及びその近傍 に位置する安全確認終了入力手段は,原則として乗降室内にあるものとされ, 例外的に,確認者がカメラとモニタを介して安全確認を行う場合にのみ,乗降 室外とすることができるものとされているにもかかわらず,訂正後請求項1に おいては,確認者が直接の目視によって安全確認を行う場合にも,安全確認実 施位置と安全確認終了入力手段を乗降室外とする(以下,これを「乗降室外目 視構成」という。)ことができることとなり,この点において,本件明細書等\nには記載のない事項を導入することになるというものであり,本訴における被 告の主張もこれと同旨である。
ところで,訂正後請求項1の構成Bは,「前記車両の運転席側の領域の安全\nを人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の 反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれに配置 され,人による安全確認の終了が入力される複数の入力手段と,」と定めるの みであって,安全確認実施位置や安全確認終了入力手段の位置を乗降室の内と するか外とするかについては何ら定めていないから,乗降室外目視構成も含み\n得ることは明らかである。
そこで,本件明細書等の記載を検討してみると,たしかに,確認者が目視で 安全確認を行う場合に関する実施例1,2,4においては,安全確認終了入力 手段は乗降室内に設けるものとされ,確認者がカメラとモニタによって安全確 認を行う実施例3においてのみ,安全確認終了入力手段を乗降室の内,外に複 数設けてもよいと記載されている(【0090】)のであって,乗降室外目視 構成を前提とした実施例の記載はない。しかしながら,これらはあくまでも実\n施例の記載であるから,一般的にいえば,発明の構成を実施例記載の構\成に限 定するものとはいえないし,本件明細書等全体を見ても,発明の構成を,実施\n例1〜4記載の構成に限定する旨を定めたと解し得るような記載は存在しない。\n他方,発明の目的・意義という観点から検討すると,安全確認実施位置や安 全確認終了入力手段は,乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば,安全確 認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり,その位 置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない(被告は,このような解釈は, 本件明細書【0055】【0064】を不当に拡大解釈するものであるという 趣旨の主張をするが,この解釈は,本件明細書等全体を考慮することによって 導き得るものである。)。
この点につき,被告は,乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認するこ とは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから,本件明\n細書等において,乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をす\nる。しかしながら,乗降室に壁のない駐車装置や,壁が透明のパネル等によっ て構成されている駐車装置等であれば,乗降室の外からでも自由に安全確認が\nできるはずであるし(その1つの例が,別紙2の駐車装置である。なお,被告 は,本発明は,「格納庫」へ車両が搬送される機械式駐車装置の発明であるこ とや,本件明細書等の図1の記載から,乗降室の外から乗降室内を目視するこ とはできないと主張するが,「格納庫」が外からの目視が不可能な壁によって\n構成されていなければならない理由はないし,上記図1は,実施例1の構\成を 示したものにすぎず,駐車装置の構成が図1の構\成に限定されるものではな い。),仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構\成されている場合 でも,出入口付近の適切な位置に立てば(したがって,そのような位置やその 近傍を安全確認実施位置として安全確認終了入力手段を配置すれば),乗降室 外からであっても,目視により乗降室内の安全確認が可能であることは,甲1\n9の報告書が示すとおりであり,いずれにせよ被告の主張は失当である。また, 仮に被告の主張が,訂正後請求項1は,安全確認実施位置や安全確認終了入力 手段が,目視による安全確認が不可能な位置にある場合までも含むものである\nという意味において,本件明細書等に記載のない事項を導入するものであると いうものであるとしても,「安全確認実施位置」とは,安全確認の実施が可能\nな位置を指すのであって,およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むもの\nではないと解されるから,やはり,その主張は失当である。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2020.12. 7
令和2(行ケ)10072 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年12月2日 知的財産高等裁判所
1 本件商標のうち,「奥西木工」の文字部分が,出所表示機能\を有する要部に当 たるかについて
本件商標は,前記第2の1のとおり,全体が一様に朱色の家具の催事についての 広告チラシを縮小した構成からなり,その上部には,上が欠けた円図形の内側に大\nきな赤い文字で「大処分」と記載され,その右側に「キズ物 半ぱ物 山積」と記 載された白抜きの将棋の駒様の図形を配し,さらに,上記円図形の右内側に大きく 「家具」の文字が記載され,内側に家具の絵が配されており,上記円図形の左上に 「京都最大の家具専門店奥西木工の魅力あるキズもの」と大きく記載され,同図形 の上に「キズ物市」とより大きく記載され,同図形の左には「大放出」と大きく記 載されており,その下部には,矢印と共に「うら面へつづく」と記載され,最下部 には赤色の長方形の中に白抜き文字で「奥西木工」等の文字が記載されているもの である。
上記のような本件商標の構成からすると,本件商標に接した需要者,取引者は,\n本件商標が,「キズ物市」という家具の催事についてのチラシであると認識すると認 められるところ,「大処分」,「家具」,「キズ物市」,「大放出」といった記載や家具の絵は,販売される商品や催事の内容などを表すものと認識されるのであって,本件\n商標には,「奥西木工」の文字部分以外に,本件商標に記載された各商品(家具)の 出所を示すような表示はない。そうすると,本件商標に接した需要者,取引者は,\n「奥西木工」の記載をもって,指定商品である家具の出所を表示するものとして認\n識するものと認められ,「奥西木工」の文字部分は,要部であるというべきである。
・・・
そうすると,本件チラシ1は,その全体のレイアウトは,本件商標と共通する部 分があるものの,本件チラシ1のいずれにも本件商標の要部である「奥西木工」と いう文字部分がなく,「タキソウパルクス刈谷店」,「タキソ\ウ家具」,「タキソウ家具本店」,「タキソ\ウパルクス吉原店」などとの記載があるのみであるから,本件チラ シ1に記載された本件使用商標1は,本件商標とは外観が大きく異なる上,本件商 標から生じる「オクニシモッコウ」などの称呼や「奥西木工の主催するキズ物市」 といった観念も本件使用商標1からは生じない。以上からすると,本件使用商標1が,本件商標と社会通念上同一ということはできない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2020.12. 2
令和1(ネ)10081 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上の本件発明3の特許請求の範囲(請求項3)の記載及び本件明細書 の記載によれば,構成要件Bの「操作メニュー情報」は,「ポインタの座\n標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力 手段に表示するため」の「画像データ」であり,出力手段に表\示され,利 用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるよう\nに構成されていることを要するものと解される。\n
イ これに対し控訴人は,構成要件Bの「操作メニュー情報」は,命令の「対\n象」や「内容」のいずれかを,小さな絵で表現したものが,「実行される\n命令結果を利用者が理解できるという動作・作用を目的・目標として構成\nされている画像データ」であって,「画面上のどの座標位置・範囲に表示\nするかという表示位置・範囲に関する情報」を含むものである旨主張する。\n しかしながら,本件発明3の特許請求の範囲(請求項3)の記載中には, 「操作メニュー情報」が「実行される命令結果を利用者が理解できるとい う動作・作用を目的・目標として構成されている画像データ」であること\nの根拠となる記載は存在せず,控訴人の上記主張は,特許請求の範囲の記 載に基づかないものであるから,採用することができない。
(3) 被告製品における「操作メニュー情報」(構成要件B)の具備の有無につ\nいて
控訴人は,1)被告製品の本件ホームアプリにおける「上ページ一部表示」\n及び「下ページ一部表示」は,その内容や表\示位置からすれば,これを見た 利用者は上ページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえる から,利用者が,その表示の有無を視覚的に認識でき,その表\示内容から, 所望の命令を実行した結果についても理解できるような,画像データに当た り,「操作メニュー情報」に該当する,2)被告製品における「左上領域」(別 紙参考図の図1記載の左側の赤色の点線枠内),「右上領域」(同図1記載 の右側の赤色の点線枠内),「左下領域」(同図2記載の左側の赤色の点線 枠内,同図3のB記載の左側の画像)及び「右下領域」(同図2記載の右側 の赤色の点線枠内,同図3のB記載の右側の画像)は,「操作メニュー情報」 に該当する旨主張する。
ア そこで検討するに,被告製品の構成エ(ウ),(エ),オ(ウ)及び(エ)及び 別紙「乙2の2の説明図」によれば,被告製品においては,1)利用者が, 移動させたいショートカットアイコンをロングタッチし,ドラッグ操作を することにより当該ショートカットアイコンを移動させ,ロングタッチし た位置と当該ショートカットアイコンをドラッグしている指等のタッチパ ネル上の位置が約110ピクセル離れた場合に,その際のページ画面が縮 小表示されるとともに,そのページ画面のページ番号に応じて,当該ペー\nジが上端ページであれば1つ下のページの一部の画像である「下ページ一 部表示」のみが,下端ページであれば1つ上のページの一部の画像である\n「上ページ一部表示」のみが,それ以外のページであればこれらがいずれ\nもIGZO液晶ディスプレイに表示される「縮小モード」となること,2) 「縮小モード」の状態で,「上ページ一部表示」が表\示されているとき, 利用者が当該ショートカットアイコンをドラッグしている指等及びマウス カーソルの先端の座標位置を「左上領域」又は「右上領域」のいずれかの\n範囲に入れたときは,上ページスクロール1又は上ページスクロール2を 生じさせる命令が実行され,また,「縮小モード」の状態で,「下ページ 一部表示」が表\示されているとき,利用者が当該ショートカットアイコン をドラッグしている指等及びマウスカーソルの先端の座標位置を「左下領\n域」又は「右下領域」のいずれかの範囲に入れたときは,下ページスクロ ール1又は下ページスクロール2を生じさせる命令が実行されることが認 められる。
イ しかるところ,被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表\ 示」は,別紙「乙2の2の説明図」の図6等に示すように,「縮小モード」 の状態で,IGZO液晶表示ディスプレイの画面上に表\示される長方形状 上の画像データであるが,その表示には「実行される命令結果」の内容を\n表現し,又は連想させる文字や記号等は存在せず,利用者がその表\示自体 から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構成されているも\nのと認めることはできない。
また,利用者が,縮小モードの状態で,1つ上のページ又は1つ下のペ ージの一部を表示した画像である「上ページ一部表\示」又は「下ページ一 部表示」を見て,「上ページ一部表\示」又は「下ページ一部表示」までド\nラッグすれば,上ページ又は下ページに画面をスクロールさせることがで きるものと考え,実際にそのように画面をスクロールさせる操作をしたと しても,それは,「上ページ一部表示」又は「下ページ一部表\示」の表示\n自体から「実行される命令結果」の内容を理解するのではなく,操作の経 験を通じて,画面をスクロールさせることができることを認識するにすぎ ないものといえる。 したがって,被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表\示」 は,利用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解でき\nるように構成された画像データであるものと認めることはできないから,\n構成要件Bの「操作メニュー情報」に該当しない。\n
ウ 次に,前記アの認定事実によれば,被告製品における「左上領域」,「右 上領域」,「左下領域」及び「右下領域」は,いずれも,被告製品の出力 手段であるIGZO液晶表示ディスプレイの画面上の特定の座標位置で囲\nまれた領域であり,その領域は,画面上に画像データとして表示されてい\nるものではなく,利用者が画面上で認識できるものではない。 したがって,被告製品における「左上領域」,「右上領域」,「左下領 域」及び「右下領域」は,出力手段に表示され,利用者が「実行される命\n令結果」を理解できるように構成されている「画像データ」であるものと\n認めることはできないから,構成要件Bの「操作メニュー情報」に該当し\nない。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.11.30
平成31(ワ)10672等 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 令和2年11月17日 東京地方裁判所
原告は,被告Aが原告で勤務していた平成28年頃から,顧客カルテをファ イリングしているバインダーの背面下部にマル秘シールが貼られていたと主\n張し,その主張の根拠として甲6号証を提出し,証人Gは上記主張に沿う供述 をする。これに対し,被告らは,マル秘シールは被告Aが原告を退職した後に 貼られたものであると主張し,被告Aはそれに沿う供述をする。\n甲6号証のマル秘シールの写真は,本件訴訟の準備のために平成31年3月 27日に撮影されたものであり,これによって,いつからマル秘シールが貼ら\nれていたかが客観的に明らかになるものではない。また,証人Gの供述と整合 する客観的証拠は存在しない。かえって,甲6号証には顧客カルテがファイリ ングされているバインダーが10冊以上写っているところ,そのバインダーの 形や顧客番号を示すと考えられる番号の記載方法などは相互に異なっている ものも多いのに対し,マル秘シールは大きさが同じで,最後の一冊を除き文字 も同じであり,写真撮影時に比較的近接した時期に一斉に貼付されたことと矛\n盾しないことを窺わせるものである。
以上によれば,被告Aが原告で勤務していた平成28年頃から顧客カルテを ファイリングしているバインダーの背面下部にマル秘シールが貼られていた\nという事実を認めるには足りず,被告Aが原告で勤務していた平成28年頃か ら顧客カルテをファイリングしているバインダーの背面下部にマル秘シール が貼られていたという事実は認定できない。\n
顧客カルテとその管理について
ア イのとおり,原告店舗において,施術履歴等を記載した紙である顧 客カルテは,バインダーにつづられ,バックルームに設置された棚にバイン ダーが並べて保管されていた。バックルームは,原告の従業員であれば自由 に入退室することができ,従業員が一人で休憩することもあり,従業員であ れば,顧客カルテは,バックルームで自由に見ることができたものであった。 顧客カルテは,ファスナーがついたファイルに入れて他の店舗に持ち運び することがあった。また,顧客カルテを共有する目的で,原告従業員全員を メンバーとするLINEのカルテ共有用グループが作成されていて,カルテ 共有用グループを使用して顧客カルテを従業員が共有する場合,原告従業員 が私用のスマートフォン等で顧客カルテを撮影し,それをカルテ共有用グル ープの全メンバーに送信していて,撮影した従業員の私用のスマートフォン にその画像が保存されるほか,全従業員のスマートフォン等にも,その画像 が送信され,保存されることとなっていた。このような送信は,原告代表者\nや店長の許可などの特別な手続は必要なく,通常業務として行われていた。 すなわち,原告の従業員は,全ての顧客カルテを少なくとも就業時間中は 誰でも自由に見ることができ,また,その画像は,通常業務の中で,特に上 司の決裁等もなく,私用のスマートフォン等で撮影され,当該カルテを必要 としない者を含む全従業員の私用のスマートフォン等に送信され,保存され ていたといえる。
イ ここで,顧客カルテ自体には,秘密であることを示す記載はなく,また, 本件送信行為の当時,顧客カルテをつづったバインダーに秘密であることを 示す記載等があったとは認められない。
他方,原告は,顧客情報の管理については注意喚起を行っているなどと主 張し,証人Gは,原告店舗では,店長が月に1,2回の頻度で全ての原告従 業員に対して顧客カルテの画像を削除するように口頭で伝え,店長は原告従 業員が私用のスマートフォンを操作して顧客カルテの画像を削除している 姿を見たこともあった旨供述する(甲39,証人G)。しかし,その供述を裏 付ける客観的証拠はないほか,同供述によっても,口頭で削除の指示を述べ ただけであり,前記アのとおり全従業員の私用のスマートフォン等に画像が 送信,保存されているとの状況にもかかわらず,口頭の指示を超えて,同グ ループ上で顧客カルテの画像を削除するようメッセージを送信したりする ことなどもなかった。
原告の顧客カルテの管理マニュアル(前記 )は,顧客カルテについ ての一定の取扱いを定めているが,これは顧客カルテ等の一般的な取扱い等 を定めるものであり,カルテ共有用グループの扱いなど顧客カルテに関する 重要な事項に触れるものでもなかった。また,就業規則や入社時合意では, 職務上知り得た情報の取扱いなどが定められていたが,その対象となる情報 の定義は一般的なものであって,これらによって顧客カルテやその施術利益 が秘密であることが示されているとはいえないものであった。 その他,監視カメラはレジや店舗の入口付近を映すものであって,それが バックルームの棚付近も映していたとしても,一般的な防犯対策や不審者に 対する対策を超えて,それによって,顧客カルテそのものを直ちに秘密とし て管理していたことになるものとはいえない。
ウ 上記のとおりの,顧客カルテの客観的な利用,保存等を含めた管理の状況, 顧客カルテが秘密であることを直接示す記載の欠如やそれが秘密であると 認識させる事情の少なさ等の事情を総合的に考慮すると,原告店舗の顧客カ ルテの施術履歴は,「秘密として管理されている」(不競法2条6項)という ことはできない。
エ 原告は,原告の顧客カルテの管理状況,就業規則や入社時合意の存在等を 挙げて,顧客カルテが秘密として管理されている旨主張するが,上記に照ら し,理由がない。
また,原告は,被告Aが,Dに対し,平成29年12月9日日にLINE で,「Eっていう私の友達のカルテ,もらえたりしないかな?誰にもバレず に」などと送信し,平成30年1月20日日に,LINEで「私に友達のカ ルテ送ったことだけは内緒でお願いします!」「それがバレるかどうかで左 右されるっぽい!」などと送信したことを挙げて,被告Aも顧客カルテを秘 密として認識していた旨主張する。
しかし,平成29年12月9日のLINEは,被告Aが原告を退職する時 点で原告代表者と被告Aの関係が相当悪化していたこと(乙21,弁論の全\n趣旨)や被告Aが原告との間で作成した入社時誓約書などの文言に抵触し得 る形で原告の店舗の近くの被告ら店舗での就業を退職後早々に開始したこ となどから,本件施術履歴が秘密情報であるか否かにかかわらず,被告Aが, 自身のための行為を原告代表者等に知られたくないと思う背景があった状\n況でされたものであり,かえって,Dがそれに対して逡巡する形跡なく程な く本件送信行為を行っていることからも,同日のやり取りは,直ちに,被告 AやDを含む原告の従業員において,顧客カルテを秘密として認識していた ことの根拠となるものではない。また,平成30年1月20日のLINEは, 前日に原告から顧客情報の不正使用等を指摘する通告書が送付され,これに ついて被告Bから顧客情報を持ち出していなければ大丈夫であるとアドバ イスされたものの,被告Bや被告Cには本件送信行為についての報告をして いなかったために本件送信行為を隠そうとしたものとも解され,また,顧客 カルテが当時言及されていた「顧客情報」に含まれることが明らかな一方, それが「営業秘密」など「秘密」であるか否かが当時話題とされていたかは 明らかでなく,上記のLINEにより,被告Aにおいて顧客カルテの情報が 秘密として管理されている情報であるとの認識を有していたことが直ちに 裏付けられるものではない。
以上によれば,顧客カルテの情報の一部である本件施術履歴も秘密管理性を 欠くから,その余を判断するまでもなく,本件施術履歴が営業秘密であるとは 認められない。したがって,本件送信行為は不正競争に該当しないから,本件 送信行為についての原告の被告Aに対する請求は認められない。
2020.11.27
令和1(ネ)2739 意匠権 民事訴訟 令和2年10月30日 大阪高等裁判所
当裁判所も,控訴人及び一審被告静岡産業社の共同不法行為により被控訴人が受けた損害につき,意匠法39条1項により推定される損害額は5348万7589円であって,上記共同不法行為と相当因果関係にある弁護士費用及び弁理士費用は540万円とするのが相当であり,その合計額は5888万7589円であるが,他方で,値下げによる損害についての賠償は認められないと判断する。その理由は,次のとおり補正し,後記4(3)及び5のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」第4の8(ただし,一審被告静岡産業社のみの主張に対する判断部分を除く。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
そして,被控訴人は,原判決言渡しの後,一審被告静岡産業社との間で任意の和解をし,これに基づき,一審被告静岡産業社から,2944万3795円及びこれに対する平成30年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を受けたので,上記損害賠償残金は2944万3794円及びこれに対する平成30年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員となった。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成30(ワ)2439
イ号および本件意匠は以下です。
2020.11.27
令和2(ネ)10025 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年11月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
4 損害発生の有無及びその額(争点8)について(当審における当事者の補充主張に対する判断を含む。)
(1)特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」について
特許法102条3項は,特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であり,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準とし,そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして,同項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については,技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で,被許諾者が最低保証額を支払い,当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定される特許発明の実施許諾契約の場合と異なり,技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には,侵害者が上記のような契約上の制約を負わないことや,平成10年法律第51号による同項の改正の経緯に照らし,同項に基づく損害の算定に当たっては,必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はない。特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,実施に対し受けるべき料率は,通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきであり,1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な実施料率を定めるべきである。
(2) 実施料率の算定に当たり考慮すべき事情括弧内に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によると,次の各事実が認められる。ア実施料率に関する数値等(ア)社団法人発明協会発行の「実施料率〔第5版〕」(平成15年9月30日発行。甲79)には,「電子・通信用部品」分野の実施料率について,次の旨の記載がある。aイニシャル・ペイメント条件がない場合の実施料率の平均値は,昭和63年度〜平成3年度は4.9%,平成4年度〜10年度は3.3%である。平均値が下降した結果,全技術分野中実施料が最も低い技術分野の一つとなった。
bこの技術分野は,契約件数が全技術分野の中でも多い方であるが,他の契約件数上位の技術分野と比較して,実施料率が低く抑えられている。その理由としては,1)この技術分野では,高額のライセンス収入を得ることとともに,技術を普及させ,対象技術の標準化を目指すことが重要視されるケースが他の技術分野と比較して多いことや,2)半導体産業は設備投資が大きく,ライセンシーの危険負担が大きいことが考えられる。c平成4年度〜10年度の実施料率8%以上の契約(イニシャル・ペイメント条件の有無を問わない。)合計21件を技術内容的に細分すると,電子管が1件,半導体が18件,その他の電子・通信用部品が2件であり,半導体が大半を占めている。
(イ)平成22年8月31日に発行された「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」によると,本件発明1〜3に関連する「電気」の分野の実施料率について,平均値は2.9%,最大値は9.5%,最小値は0.5%であった(乙89)。
(ウ)一審原告が訴訟等で相手方と和解をする際には,相手方において侵害品から一審原告の製造するLEDへの置換えが可能な場合には,当該LEDを相手方が購入することを条件として,侵害品の売上高に5%前後の実施料率を乗じた損害賠償額で和解をすることがあるが,そのような置換えが難しい場合には,製品の製造販売の中止を条件に,侵害品の売上高に上記より高い実施料率を乗じた損害賠償額で和解をすることがある(甲84の1)。一審原告は,平成28年5月,本件特許1を含む二つの特許を侵害するLED電球の販売に係る事案に関し,相手方と,総売上高に10%の実施料率を乗じた額に8%の消費税相当額を加算した金額で裁判上の和解を成立させた(甲84の1・3)。\n
(エ)一審原告の競合メーカーであるフィリップス社は,平成28年6月21日,LED照明及びLEDレトロフィット電球のライセンスプログラムを公表したが,そこでは,LED照明の総収入に基づく実施料率は,単色照明(白色又は有色の固定色)については3%であることが示されている(乙102)。\n
イ本件発明1〜3の価値・重要性等に関する事情
(ア)一審原告による青色LEDの開発後,赤,緑,青の三種類のLEDを用いるのではなく,青色LEDと蛍光体を用いて一審原告が白色LEDの開発を実現したことは,非常に重要な産業上の意味を持つもので,その後のLED市場の急速な拡大に大きく寄与し(甲24,26),一審原告による白色LEDの開発については,文部科学省発行の「令和元年版科学技術白書」(甲86)においても取り上げられている。
(イ)白色LEDを構成するために青色LEDチップと組み合わせる蛍光体の材料としては,YAG系のほか,TAG(テルビウム・アルミニウム・ガーネット)系,サイアロン系,BOS(バリウム・オルソ\シリケート)系などがある(乙105)。この点,ドイツのOSRAM Opto社は,平成15年〜平成16年頃に,複数の会社に対し,TAG蛍光体による白色LEDのライセンスを供与しており(乙108),平成20年には,アメリカのVishayIntertechnology社は,カメラのフラッシュ・ライト,自動車のブレーキ・ランプや方向指示器やインスツルメント・パネルのバックライトや非常灯などに向けたものとして,TAG蛍光体を用いた白色LEDを発売した(乙109の1・2)。平成18年には,TAG系蛍光体材料などを用いた白色LEDが続々登場しているとの報道があり(乙106),平成24年には,YAG,TAG及びシリケートが,世界三大の蛍光体であると評価されていた(乙107)。
(ウ)平成27年に発表された「LED製品開発の現状と最新動向」と題する論文(豊田合成技報57号。乙91)には,次の旨の記載がある。\n
a青色LEDを光源とし蛍光体を励起させる方式の白色LEDの開発により,小型・省電力の白色光源が実用化され,更なる用途拡大が進んだ。代表例としては,液晶ディスプレイが挙げられる。白色LEDの高効率化により,急速にバックライト用光源の置き換えが進んだ。LED化によるメリットは,主に,発光効率が高いことと,薄型化ができることである。LEDは光源自体のエネルギー効率が高いことに加え,配光指向性によりバックライトへの入射効率が高くなるため,機器としての省エネが図りやすいことも大きなメリットとなっている。LEDが当たり前になった現在においても,パネル画質向上(高精細化・広色域化)に伴うパネル透過率低下(画面が暗くなること)を補うため,LEDへの効率向上への期待・ニーズは依然として高い。\n
b最近,従来の青色LEDと黄色蛍光体の組み合わせから,光の三原色である青色LEDと緑色蛍光体・赤色蛍光体の組み合わせによる色品質の向上が図られている。従来の青色LEDに黄色蛍光体を加えた疑似白色光は,液晶に用いられる場合,色の純度が低く,液晶パネル上の色域が狭いのが一般的である。色域を拡げるためには,液晶パネルのカラーフィルタの濃度を上げる方法があるが,光の損失が大きくなるため望ましくない。そこで,色域を向上させるため,青色LEDに緑色蛍光体と赤色蛍光体を組み合わせた,新規白色光が開発されている。
ウ一審被告製品の売上げ及び本件LEDの位置付け等
(ア)一審被告製品の売上げ(乙87)
a一審被告製品1一審被告製品1の販売期間は平成26年1月から平成28年3月までであり,総販売台数は43万3971台で,1台当たりの平均販売価格は3万3902円,総売上高は147億1230万5518円であった。売上高の内訳は,平成26年1月から平成27年9月までが147億0404万7272円,同年10月が293万6815円,同年11月から平成28年3月までが532万1431円であった。
b一審被告製品2一審被告製品2の販売期間は平成27年5月から平成28年12月までであり,総販売台数は29万6608台,1台当たりの平均販売価格は3万4461円,総売上高は102億2138万1519円であった。売上高の内訳は,平成27年5月から平成27年9月までが24億1436万1080円,同年10月が9億3268万0350円,同年11月から平成28年11月までが68億4922万2715円,同年12月が2511万7374円であった。
(イ)一審被告製品における本件LEDの位置付け等
a一審被告製品は,いずれもデジタルハイビジョン液晶テレビであり,一審被告製品1及び2のバックライトには,いずれも1台につき24個のイ号LED又はロ号LEDが搭載されていた。液晶テレビの方式は,バックライトの種類によって,直下型とエッジ型とに区分されるところ,一審被告製品は,直下型である(甲85)。
bテレビに用いられるLEDについては,テレビ一台に複数のLEDが用いられることから安価であることが望ましい一方で,テレビ内部に設けられたLEDを交換することはできないから,耐久性が極めて重要な特性として求められる。
c東芝のテレビ事業部の担当者は,平成21年4月に,液晶テレビのバックライトは白色LEDがトレンドになると主張し,RGB三色のLED光源よりも白色LEDの方がより高画質を実現できるという認識を明らかにしていた(甲32)。そして,一審被告は,一審被告製品を含む液晶テレビのシリーズ商品を販売するに当たり,映像美を一つのセールスポイントとしており,また,一審被告製品は,「おまかせオートピクチャー」という,周囲の明るさに適した画質に自動で調整するとの機能を有していたところ,それは,リニアに発光するというLEDの特性を利用したものであった(甲77,78,92)。一審被告製品1を購入したユーザーのレビューには,画質の良さやコストパフォーマンスの良さを指摘するものがある(甲93)。\n
d一審被告製品は,平成27年7月から11月までの売れ筋ランキングの上位(第3位)を占めていた(甲94)。
e直下型バックライトが採用される液晶テレビ用の一般的なサイズのLEDにおいては,本件発明2及び3に関連した技術を用いたLEDが多用されている(甲87〜89)。
f一審被告製品はOEM製品であり,一審被告は,本件LEDの単価も知らず,本件LEDがどこのメーカーの製品であるのかも知らなかった。
エLEDに関する市場等
(ア)テレビのバックライト用の白色LEDの世界的な平均価格は,平成26年は0.1ドル,平成27年は0.08ドル,平成28年は0.068ドルであった(乙85の1〜3,乙104)。なお,年間平均為替レート(TTS)は,平成26年は106.85円/1ドル,平成27年は122.05円/1ドル,平成28年は109.84円/1ドルであった(乙90)。(イ)株式会社富士キメラ総研発行の「2017LED関連市場総調査」(平成29年1月25日発行。甲84の2)には,次の旨の記載がある。
aテレビ用バックライトユニットについてテレビ用バックライトユニットでは,直下型の白色LEDパッケージが採用されている。テレビ向けのLEDは,高出力かつ広色域,長寿命が要求されるケースが多く,他のバックライトユニット向けLEDと比較してハイエンドな商品となる。平成28年第4四半期時点において,32型テレビ用の直下型バックライトユニットの主要な価格帯は,1台当たり1400円〜1700円である。ただし,光学シート構成やLEDパッケージの仕様,搭載個数によって大きく価格が変動する。また,テレビメーカー各社が独自設計を行うハイエンドテレビ用バックライトユニットは,より高価格になる。\nなお,光学シートの機能複合による搭載枚数削減,LEDパッケージの性能\向上による搭載数量削減により,今後も低価格化が続く見通しである。b白色LEDパッケージについて白色LEDパッケージとは,疑似白色に発光するLEDパッケージである。主に可視光(GaN系)LEDチップに蛍光体を使用することで,疑似的に白色光を実現している。白色LEDパッケージについて,日本では発光効率を高める開発が続けられている。一方で,演色性(色再現性)も必要であるが,演色性と発光効率はトレードオフの関係にある。なお,中国では,コストの圧縮を目的として,LEDパッケージメーカーによるリードフレームを始めとする各種部材の内製化が進んでいる。世界的にみると,白色LEDパッケージ市場は,数量ベースで引き続き好調な伸びとなっている。ただし,従来大きなウェイトを占めてきたバックライト向けは,出荷数量が大きく減少している。セット機器の減少に加え,中小型バックライト向けでは搭載工数の減少やOLEDへの移行,テレビ用バックライト向けではパッケージ当たりの光束量の増加に伴う搭載個数の減少が主な市場縮小の要因となっている。白色LEDパッケージについて平成28年第4四半期時点で,バックライト向けの直下型の白色LEDパッケージの価格は,1個当たり,18円〜24円である。
c白色LEDパッケージに採用される蛍光体について高発光効率・低価格が要求される製品には,黄色の蛍光体が単体で採用されるケースが多い。演色性や広い色域が要求される場合には,黄色と赤色や,赤色と緑色の組み合わせが採用されている。LED用蛍光体については,中国において,地域別生産数量に占めるウェイトが高まっている。平成27年の出荷数量実績では,黄色の蛍光体について,YAG蛍光体が83.5%を占めており,シリケート系が10.2%,その他が6.3%を占めている。この点,シリケート系は,近年減少傾向にある。YAGなどに比べ高温高湿条件下での信頼性に劣るためである。平成29年に一審原告のYAG主要保有特許が失効するのを受けて,特に電球など色温度3000K程度の照明向けLEDパッケージでは,効率の良さを背景にYAGへの移行が進む可能性がある。\n
(ウ)総合技研株式会社発行の「2017年度白色LED・応用市場の現状と将来性」(乙86)には,次の旨の記載がある。a白色LEDメーカーシェア動向について,メーカーは一審原告のほかに合計10社以上あるところ,平成24年〜平成28年において,一審原告は継続してシェア第1位を占めている。この点,シェアは,平成24年は23.7%,平成25年は24.2%,平成26年度は25.4%,平成27年度は19.6%,平成28年度は19.1%である。b分野別・用途別白色LED応用市場分析に関し,分野別市場規模について,平成24年〜平成29年で,液晶バックライトを用途とするものは,61.2%から44.4%に減少し,一般照明を用途とするものが34.5%から50.8%に増加してきた。他方,液晶バックライトの数量ベースでみると,平成24〜平成28年で,液晶テレビを用途とするものは,40%前後で推移しており,他の用途(ノートパソコン,液晶モニター,タブレット端末,スマートフォン等)を大きく引き離している。\n
(エ)直下型バックライトについては,商流として,LEDメーカーとは別に直下型バックライトを製造するバックライトメーカーが存在し,テレビの製造メーカーに対しては,当該バックライトメーカーが直下型バックライトを部材として供給している。オ一審原告のライセンス方針等(ア)一審原告は,平成28年においても,バックライト用LED(テレビ,モニター,ノートパソコン及びタブレットを含む。)収入で,世界第2位,14.1%のシュアを占めている(乙84)。(イ)一審原告は,後発メーカーとの間で,平成8年頃から,各国で特許訴訟の提起や交渉を繰り返してきたところ,平成14年には,後発メーカーのLEDの技術水準も向上したため,互いに補完し合える技術を保有しているメーカーとはクロスライセンス契約を結んで和解をするようになったが,その際,クロスライセンス以外の形態でLEDメーカーにライセンスを供与することは,一部の例外を除いてなかった。それは,ライセンス収入には頼らず,特許はあくまでも自社の技術を保護する手段と考え,自社製品の販売によって利益を得るという経営方針によるものである(甲84の1)。
(3) 実施料率の算定
訂正して引用した原判決第3で判示した本件発明1〜3の意義等に加え,上記(2)で認定した諸事情を踏まえ,以下,実施料相当額について検討する。
ア実施料率を乗じる基礎(ロイヤルティベース)について
(ア)前記(1)で特許法102条3項について指摘した点に加え,1)本件LEDは直下型バックライトに搭載されて一審被告製品に使用されていたところ,直下型バックライトは,液晶テレビである一審被告製品の内部に搭載された基幹的な部品の一つというべきであり,一審被告製品から容易に分離することが可能なものとはいえないこと,2)LEDの性能は,液晶テレビの画質に大きく影響するとともに,どのようなLEDを用い,どのようにして製造するかは製造コストにも影響するものであること,3)一審被告は,後記イのとおり,本件LEDの特性を活かした完成品として一審被告製品を販売していたもので,一審被告製品の販売によって収益を得ていたこと等に照らすと,一審被告製品の売上げを基礎として,特許法102条3項の実施料相当額を算定するのが相当である。
(イ)これに対し,一審被告は,本件特許1〜3の貢献が,LEDチップに限定される旨を主張するが,採用することができない。また,一審被告は,LEDチップが独立して客観的な市場価値を有して流通していると主張するが,そうであるとしても,上記(ア)1)〜3)の事情からすると,本件においてLEDの価格をロイヤリティのベースとすることは相当ではない。なお,直下型バックライトについても,独立の市場価値を有するものと認められるが,上記(ア)1)〜3)の事情からすると,直下型バックライトの価格をロイヤリティのベースとすることも相当ではない。
さらに,一審被告は,最終製品を実施料算定の基礎とすると,本件LEDがより高価な最終製品に搭載されるほど実施料が高額になると主張するが,本件LEDがより高額な製品に搭載されてより高額な収入をもたらしたのであれば,その製品の売上げに対する本件LEDの貢献度に応じて実施料を請求することができるとしても不合理ではない。
イ実施料率について
(ア)a一審原告は,クロスライセンス以外の形態でLEDメーカーにライセンスを供与することは,一部の例外を除いてはなく(前記(2)オ(イ)),特許権が侵害された場合,一審原告の製造するLEDへの置換えが可能な場合にはそれを前提に5%前後の実施料率を用いて,置換えが難しい場合にはより高い実施料率を用いて和解をしており,平成28年に,本件特許1を含む二つの特許権を侵害するLED電球の販売に係る事案において,10%の実施料率を想定し,それに8%の消費税相当額を付加して,裁判上の和解をした(前記(2)ア(ウ))。 b平成10年度までにおいて,電子・通信用部品分野のうち,半導体については,実施料率8%以上の契約が少なからず存する(前記2ア(ア)c)。
c本件特許1は,長時間の使用に対する特性劣化が少なく,色ずれや輝度低下の極めて少ない発光装置に係る特許であり,本件特許2及び3は,ダイシングの際の剥離の防止や廃棄される樹脂の低減を図るとともに,生産効率を大幅に向上させ,安価な発光装置を提供する方法及び当該装置に係る特許である。これらの特性は,液晶テレビのバックモニタ用の白色LEDとして,大きく活かされるものであったといえ,殊に,本件特許1は,非常に重要な産業上の意味を持つものとして,その後のLED市場の急速な拡大に大きく寄与した(前記(2)イ(ア),(ウ)a,同ウ(イ)b,c,e,同エ(イ)a)。この点,YAG系の蛍光体以外の蛍光体を用いた白色LEDも存在していたことが認められる(同イ(イ),(ウ))が,一審原告は,白色LEDメーカーとして,平成24年〜平成28年において継続してシェア第1位を占めており,平成28年にバックライト用LED収入でも世界第2位のシェアを占めていること(同エ(ウ)a,同オ(ア))や,平成27年の出荷数量実績において黄色の蛍光体につきYAG系の蛍光体が大部分を占めていること(同エ(イ)c)に照らすと,一審被告製品の販売期間である平成26年1月から平成28年12月までの期間において,液晶テレビのバックライト用の白色LEDについて,一審原告の製品は他の製品に比べてかなり優位な地位にあったものと認められる。
d以上のa〜cで述べたところに,前記(1)で特許法102条3項の実施料率について述べたところや,前記(2)で認定した関連技術分野における実施料率の特徴や幅,YAG系蛍光体を用いた白色LEDの価値等に係る他の事情を総合すると,平成26年1月から平成28年12月までの期間(ただし,本件特許3については平成27年10月23日以後,本件特許2については平成28年12月16日以後)における本件発明1〜3の実施料率は,10%を下回ることのない相当に高い数値となるものと認められる。なお,1)フィリップス社は平成28年に単色のLED照明の実施料率について3%と公表しており(前記(2)ア(エ)),2)LEDの属する技術分野における実施料率の平均値は,3.3%,2.9%といった数値である(同ア(ア)a,(イ))。しかし,上記1)の数値は,フィリップス社の特許についてこれからライセンスする場合の数値であり,また,上記2)は,広汎な分野における実施料率の平均値であり,いずれも上記認定を左右するものではない。
(イ)液晶テレビである一審被告製品は,本件LED以外の多数の部品から成り立っており,上記(ア)の実施料率をそのまま適用することは相当ではないが,前記(ア)cのとおり,本件発明1〜3の技術は,液晶テレビのバックモニタ用の白色LEDとして,大きく活かされるものであったということができる上,一審被告製品は,映像美を一つのセールスポイントとするなどして,売れ行きは好調であった(前記(2)ウ(イ)c,d)のであるから,一審被告製品の売上げに対する本件発明1〜3の技術の貢献は相当に大きいものであり,前記(2)で認定した白色LEDの価格等に係る事情を考慮しても,平成26年1月から平成28年1月までの間(ただし,本件特許3については平成27年10月23日以後,本件特許2については平成28年12月16日以後)において,一審被告製品の売上げを基礎とした場合の実施料率は,0.5%を下回るものではないと認めるのが相当である。
ウ一審被告の主張について一審被告は,一審被告製品2には一審原告が主張立証するLEDチップとは異なるチップが使用されているため,一審原告が主張立証するロ号LEDが使用されている一審被告製品2の販売数量は不明であるから一審被告製品2に係る損害賠償請求は認められないと主張するが,訂正して引用した原判決第3の1(5)(原判決93頁)で判示したことからすると,一審被告製品2には,その販売期間を通じて,本件特許1〜3を侵害するロ号LEDが使用されていたと推認されるというべきであり,一審被告の上記主張やその裏付けとしての証拠(乙66,70)は,この推認を覆すに足りるものではない。その他,一審被告の主張は,前記イの認定を左右するに足りるものではない。
(4) 一審原告が一審被告に請求し得る額の算定以上を踏まえると,一審原告が一審被告に請求し得る額は,次のとおりとなる。ア実施料相当額について,一審被告製品の総売上高は,一審被告製品1が147億1230万5518円,一審被告製品2が102億2138万1519円で,合計249億3368万7037円であり,同額に,上記(3)の実施料率0.5%を乗じると,1億2466万8435円(1円未満四捨五入)となる。
イ弁護士費用相当額については,原告の主張額である1200万円を認めるのが相当である。
ウしたがって,一審原告は,一審被告に対し,少なくとも損害賠償として,合計1億3666万8435円を請求することができるところ,この金額は,一審原告の請求額を超えているので,消費税相当額の加算について判断するまでもなく,一審原告の損害賠償請求は,全部について理由がある。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2020.11.21
令和2(ネ)10004 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年9月30日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ウ 推定覆滅事由について
一審被告は,1)本件期間1ないし4に係る販売分につき,一審被告が販 売した被告各製品中,順方向電圧の異なるLEDを搭載した製品の販売実 績が乏しいこと等,被告各製品の競合品の存在,2)本件期間1及び2に係 る販売分につき,本件特許権が一審原告と三菱化学との共有であったこと は,いずれも本件推定を覆す事情に該当し,かかる事情を考慮すると,本 件推定は覆滅される旨主張するので,以下において判断する。 (ア) 本件期間1ないし4に係る販売分につき,一審被告が販売した被告 各製品中,順方向電圧の異なるLEDを搭載した製品の販売実績が乏し いこと等,被告各製品の競合品の存在 a 一審被告は,1)LED基板のサイズを同一にして,部品点数及び製 造コストを削減できるとともに,LED基板の大きさを可及的に小さ くして,汎用性を向上させることができるという本件再訂正発明の作 用効果は,順方向電圧の異なるLED搭載製品を作製することを前提 とするものであり,被告各製品において,白色LEDと青色LEDと は,いずれも順方向電圧は同じであり,順方向電圧が異なるのは赤色 LEDであるから,本件再訂正発明の作用効果を奏するのは赤色LE Dを搭載する製品であるところ,本件期間1ないし4の期間中に一審 被告が販売した被告各製品中,赤色LED搭載製品(被告製品2及び 5)の販売実績が乏しいこと,2)需要者の立場からは,LED基板の 設計において,本件再訂正発明の実施品であるLED単位数の「最小 公倍数」の単位基板が長さ方向に連設されている製品と最小公倍数で はない「公倍数」の単位基板が連設されている製品とでは,購入意欲 に有意な差異を生じるものではなく,また,本件再訂正発明において 複数のLED基板が直列させてある点は,基板の接続箇所で不具合が 起こる可能性が高いとして,製品としての評価を低下させ得る事情で\nあることは,被告各製品に実施された本件再訂正発明に顧客吸引力が ないことなどを示すものといえるから,本件推定を覆す事情に該当す る旨主張する。
(a) 1)について
本件再訂正により,本件再訂正前の第1次訂正発明(請求項1) の「LED基板」の枚数及び配置が「複数の前記LED基板を前記 ライン方向に沿って直列させてある」構成に特定されたこと,第1\n次訂正発明の技術的意義は,前記2(1)ア,イ(イ)及びウで説示した とおりである。また,本件明細書の【0009】及び【0041】 の記載から,順方向電圧の異なるLED毎に定まるLEDの個数を LED単位数の「最小公倍数」にすることにより可及的に小さくし たLED基板の直列させる数を変えることで,このLED基板を 様々な長さの光照射装置に用いることができるようになることを理 解できる。
これらを総合考慮すると,本件再訂正発明の技術的意義は,順方 向電圧の異なる種類のLEDを用いたライン状の光を照射する光照 射装置において,LED基板の大きさを同一にして,部品の共通化 により部品点数の削減,製造コストの削減を実現することを主たる 課題とし,電源電圧とLEDを直列に接続したときの順方向電圧の 合計との差が所定の許容範囲となるLEDの個数をLED単位数と し,LED基板に搭載するLEDの個数を順方向電圧の異なるLE D毎に定まるLED単位数の「最小公倍数」とする構成を採用した\nことにより,順方向電圧の異なるLED同士でLED基板に搭載さ れるLEDの個数を同一にし,順方向電圧の異なるLEDが搭載さ れるLED基板同士の大きさを同じにすることができ,また,LE D基板を収容する筐体として同一のものを用いることができること から,LED基板及び筐体などの部品を共通化し,部品点数を削減 することができるとともに,製造コストを削減するという効果を奏 し,さらに,LED基板の大きさを可及的に小さくして,汎用性を 向上させるという効果を奏し,加えて,「複数の前記LED基板を 前記ライン方向に沿って直列させてある」構成を採用したことによ\nり,可及的に小さくしたLED基板の直列させる数を変えることで, このLED基板を様々な長さの光照射装置に用いることができると いう効果を奏することにあるものと認められる。
そして,被告各製品のうち,白色LED搭載製品と青色LED搭 載製品は,順方向電圧が同じであり(白色LED搭載製品である被 告製品1と青色LED搭載製品である被告製品3,白色LED搭載 製品である被告製品4と青色LED搭載製品である被告製品6は, 順方向電圧が同じであることは,争いがない。),LED基板は共 通のサイズのものを利用することができるので,被告各製品におい ては,本件再訂正発明は,白色LED搭載製品及び青色LED搭載 製品と順方向電圧が異なる赤色LED搭載製品(被告製品2及び5) 及び赤外LED搭載製品(被告製品7)について,専用のLED基 板及びこれを収容する筐体を用意する必要はなく,白色LED搭載 製品及び青色LED搭載製品と共通のサイズのLED基板及び同一 の筐体を用いることができる点において主たる効果を発揮するもの と認められる。
しかるところ,本件期間1ないし4における被告各製品の販売個 数は,合計●●●個であり,このうち,被告製品2及び5は●個, 被告製品7は●個であるから(前記イ(ア)),被告製品2,5及び 9の販売個数(合計●●個)が占める割合は,全体の約●●●●で ある。
一方で,被告各製品のうち,白色LED搭載製品又は青色LED 搭載製品を購入した者においても,その購入時に赤色LED搭載製 品一緒に購入している場合や,既に赤色LED搭載製品を有し,又 は将来赤色LED搭載製品を購入する予定である場合もあり得るか\nら,白色LED搭載製品及び青色LED搭載製品においては本件再 訂正発明の主たる効果が発揮されていないとまではいえないが,こ のような点を考慮してもなお,被告製品2,5及び7の販売個数(合 計●●個)が全体の約●●●●であることは,本件期間1ないし4 における被告各製品の売上げに対する本件再訂正発明の寄与ないし 貢献の程度が相当低いことを示すものといえる。
したがって,被告製品2,5及び7の販売個数(合計●●個)が 全体の約●●●●であることは,本件推定を覆す事情に該当するも のと認められる。これに反する一審原告の主張は採用することができない。
(b) 2)について
一審被告は,需要者の立場からは,LED基板の設計において, 本件再訂正発明の実施品であるLED単位数の「最小公倍数」の単 位基板が長さ方向に連設されている製品と最小公倍数ではない「公 倍数」の単位基板が連設されている製品とでは,購入意欲に有意な 差異を生じるものではなく,また,本件再訂正発明において複数の LED基板が直列させてある点は,基板の接続箇所で不具合が起こ る可能性が高いとして,製品としての評価を低下させ得る事情であ\nることは,被告各製品に実施された本件再訂正発明に顧客吸引力が ないことを示すものといえるから,これらの事情は,本件推定を覆 す事情に該当する旨主張する。 しかしながら,一審被告の上記主張の根拠とする事情を裏付ける に足りる証拠はないから,一審被告の上記主張は採用することがで きない。
b 次に,一審被告は,本件再訂正発明の実施品であるライン光照射装 置と実施品ではないライン光照射装置とは,照明器具としての性能に\n変わりがなく,ライン光照射装置であれば全て被告各製品及び原告が 販売する原告各製品の競合品となることに鑑みると,仮に被告各製品 が販売されなかったとしても,被告各製品の販売数量に対応する需要 が,原判決別紙競合品(被告主張)一覧表記載の他社のライン光照射\n装置にも向かったであろうといえるから,このような被告各製品の競 合品の存在は,本件推定を覆す事情に該当する旨主張する。 そこで検討するに,原判決別紙競合品(被告主張)一覧表記載の原\n判決別紙競合品(被告主張)一覧表記載の他社のライン光照射装置は,\n被告各製品の競合品に該当し,このような被告各製品の競合品の存在 は,本件推定を覆す事情に該当するものと認められる。その理由は, 次のとおり訂正するほか,原判決60頁2行目から61頁8行目まで に記載のとおりであるから,これを引用する。
・・・・
(c) 原判決61頁8行目末尾に次のとおり加える。
「また,被告各製品のカタログ(甲3)及びウェブページ(甲4, 13)には,被告各製品において本件再訂正発明を実施している ことやその実施により光照射装置としての性能が向上し,部品点\n数及び製造コストの削減を図ることができることなどをうかがわ せる記載は見当たらず,他方で,「業界最高クラスの光量を実現」, 「驚異の明るさを実現」など被告各製品の光量の大きさに関する 機能を宣伝文言としていることに照らすと,被告各製品において\n本件再訂正発明が実施されていることが大きな顧客吸引力となっ ていたということはできない。」
c 以上を前提に検討するに,前記a(a)及びbの本件推定を覆す事情の 内容,本件再訂正発明の技術的意義等を総合的に考慮すると,被告各 製品の限界利益の形成に対する本件再訂正発明の寄与は●●と認め るのが相当であり,前記寄与割合を超える部分については被告各製品 の限界利益の額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がな いものと認められる。したがって,本件推定は上記a(a)及びbの本件推定を覆す事情により上記限度で覆滅されるものと認められる。 そうすると,上記推定覆滅後の被告各製品の限界利益の額は,別紙 認容額算定表の3)欄記載の562万2270円となる。
d これに対し一審原告は,1)被告各製品のうち,白色LED搭載製品 及び青色LED搭載製品においても,本件再訂正発明は大きな顧客吸 引力を有すること,2)画像処理LED照明の国内シェア(数量ベース) については,平成26年から平成30年まで一貫して,一審原告が1 位,一審被告が2位であり,一審原告のシェアは2割を超えており(甲 18ないし22),このように画像処理LED照明のシェアを2割以 上一審原告が有している以上,被告各製品の販売がなかった場合には, そのうちの少なくとも2割は原告各製品に向かうことは明らかである し,シェア上位の会社の信頼性という面からは,2位のシェアを占め る被告各製品を購入した需要者は,被告各製品の販売がなかった場合 には1位のシェアを占める原告各製品を購入する蓋然性が高いこと, 3)原判決別紙競合品(被告主張)一覧表記載の各製品のうち,原告各\n製品の種類の多さを考えても,被告各製品の販売がなかった場合には これに対応する需要は原告各製品に向かう割合は極めて高いことを勘 案すると,本件推定は5割を超えては覆滅しない旨主張する。 しかしながら,1)については,前記bで説示したとおり(原判決引 用部分),本件再訂正発明の顧客吸引力は大きいとはいえない。 また,2)については,原告各製品及び被告各製品は,ライン状の光 を照射する光照射装置(ライン光照射装置)であるところ,仮に画像 処理LED照明一般という,ライン光照射装置よりも広いカテゴリの シェアで一審原告が1位であり,そのシェアが2割を超えていたとし ても,被告各製品の販売がなかった場合に,これに対応する2割の需 要が原告各製品に向かい,原告各製品を購入する蓋然性が高いという ことはできない。 さらに,3)については,原告各製品の種類が多いからといって,被 告各製品の販売がなかった場合にはこれに対応する需要は原告各製品 に向かう割合は極めて高いということはできない。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
・・・
b 原判決61頁16行目から62頁12行目までを次のとおり改める。 「b(a) 特許法73条2項は,特許権が共有に係るときは,各共有者 は,契約で別段の定めをした場合を除き,他の共有者の同意を 得ないでその特許発明の実施をすることができる旨規定してい るから,各共有者は,上記の場合を除き,自己の持分割合にか かわらず,無制限に特許発明を実施することができる。 そうすると,特許権の共有者は,自己の共有持分権の侵害に よる損害を被った場合には,侵害者に対し,特許発明の実施の 程度に応じて特許法102条2項に基づく損害額の損害賠償を 請求できるものと解される。また,同条3項は特許権侵害の際 に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であ ると解されることに鑑みると,特許権の共有者に侵害者による 侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情 が存在しないため,同条2項の適用が認められない場合であっ ても,自己の共有持分割合に応じて,同条3項に基づく実施料 相当額の損害額の損害賠償を請求できるものと解される。 しかるところ,例えば,2名の共有者の一方が単独で同条2 項に基づく損害額の損害賠償請求をする場合,侵害者が侵害行 為により受けた利益は,一方の共有者の共有持分権の侵害のみ ならず,他方の共有者の共有者持分権の侵害によるものである といえるから,上記利益の額のうち,他方の共有者の共有持分 権の侵害に係る損害額に相当する部分については,一方の共有 者の受けた損害額との間に相当因果関係はないものと認められ, この限度で同条2項による推定は覆滅されるものと解するのが 相当である。
以上を総合すると,特許権が他の共有者との共有であること 及び他の共有者が特許発明の実施により利益を受けていること は,同項による推定の覆滅事由となり得るものであり,侵害者 が,特許権が他の共有者との共有であることを主張立証したと きは,同項による推定は他の共有者の共有持分割合による同条 3項に基づく実施料相当額の損害額の限度で覆滅され,また, 侵害者が,他の共有者が特許発明を実施していることを主張立 証したときは,同条2項による推定は他の共有者の実施の程度 (共有者間の実施による利益額の比)に応じて按分した損害額 の限度で覆滅されるものと解するのが相当である。 これを本件についてみるに,一審原告と三菱化学は,本件期 間1及び2において,本件特許権を持分2分の1の割合で共有 していたことは,前記aのとおりであるが,一方で,その期間 中に,三菱化学が本件再訂正発明を実施したことについての立 証はない。 そうすると,本件期間1及び2に係る販売分についての本件 推定は,三菱化学の共有持分割合による同条3項に基づく実施 料相当額の損害額の限度で覆滅されるというべきある。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2020.11.21
平成28(ワ)4029 不正競争行為に基づく損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和2年10月1日 大阪地方裁判所
(ア) 前記(1)ウ(エ)のとおり,被告P1は,被告会社において,パッケージリフォー ム商品の商品開発や仕入交渉等を単独で担当するとともに,原告の標準構成明細を\n使用して本件比較表及びこれに添付された標準構\成明細を作成し,これをP4等に 示した。また,被告P1は,原告の標準構成明細の書式を使用して被告会社の標準\n構成明細のテンプレート(別紙2「営業秘密目録」資料1−1−2)を作成した\n(前記ウ(オ))。当該テンプレートは,原告の標準構成明細の書式とかなりの程度類\n似する上,その備考欄上部の記載は,これが原告の標準構成明細の書式をもとに作\n成されたことをうかがわせる。 被告P1も,当該テンプレート作成に当たり表としては原告の標準構\成明細を使 用したことを認めている(被告P1本人)。 これらの事情に加え,被告P1がP1HDD に原告の標準構成明細のデータを保\n存していること(前記ア(イ))に鑑みると,被告P1は,被告会社のパッケージリフ ォーム商品の開発に当たり,その仕入価格,粗利率,粗利金額の設定のため原告の 標準構成明細記載の原告の仕入価格等の情報を参考にしていたことが合理的に推認\nされる。また,被告P1は,被告会社の標準構成明細の書式作成に当たり,原告の\n標準構成明細の書式を使用したことが認められる。\nしたがって,被告P1による上記原告の標準構成明細の使用は,別紙2「営業秘\n密目録」資料1−1の情報の使用といえる。
また,資料1−1の情報は,被告P1が原告在職中に取得したものであるところ, その当時被告P1がこれにアクセスすることは原告においても許容されていたこと から,その取得に不正の手段は使用されていない。もっとも,被告P1が,被告会 社への転職に向けた就職活動と時期を同じくして,複雑な手順を経て原告データサ ーバの情報をP1私物パソコンやP1HDD に保存したこと,被告会社で現に上記 のとおりその情報を使用したことに鑑みると,被告P1による原告データサーバ上 の情報の取得は,転職後に転職先でリフォーム事業に使用する意図を少なくとも含 んでいたことがうかがわれる。そうすると,被告P1による上記使用行為は,被告 会社のリフォーム事業にこれを使用することで被告会社の利益を増大させ,ひいて は自己の評価を高める等の目的があったものと見られるのであって,不正の利益を 得る目的での使用といえる。 以上より,被告P1による資料1−1の情報の使用及び同情報に基づき作成され た資料1−1−2の情報の使用は,不正競争(不競法2条1項7号)に当たる。
(イ) 前記(1)ウ(エ)及び(1)エのとおり,被告会社共有フォルダ内に原告の標準構成\n明細のデータが保存されており,同フォルダを通じてP4及びP8がこれに含まれ るデータを業務上使用する USB メモリに保存している。しかも,そのフォルダ名 から,当該データが,本来は被告会社にあるはずのない原告のデータであることは 容易に理解し得る。 これらの事情を総合的に考慮すると,被告会社は,資料1−1の情報につき,営 業秘密不正開示行為があることを知り又は少なくとも重大な過失によって知らずに, これを取得したものと認められる。すなわち,被告会社による資料1−1の情報の 取得は,不正競争(不競法2条1項8号)に当たる。 他方,被告P1は,被告会社において,その在籍中は被告会社のパッケージリフ ォーム商品の開発等を単独で担当していたものであり,その際に使用する標準構成\n明細も,原告の標準構成明細のデータ及び原告在籍中の被告P1の経験に基づき,\n他の被告会社従業員の関与のないままに作成されたものとうかがわれる。そうする と,被告会社における標準構成明細(甲86,87)について,被告会社が,被告\nP1の営業秘密不正開示行為により作成されたものと知っていたこと又は知らない ことにつき重大な過失があると認めるに足りる証拠はない。 したがって,資料1−1−2の情報については,被告会社の行為は,不正競争 (2条1項8号)に当たらない。これに反する原告の主張は採用できない。
(ウ) 被告らの主張について 被告らは,被告会社共有フォルダに保存されていた情報であっても,それをもっ て被告P1の被告会社に対する開示行為とはいえない,被告P1が自ら作成又は取 得した情報については,同人による不正取得ではなく,また,原告又はサンキュー から示された情報ともいえない,資料1−1の情報につき,被告P1のそれまでの 知識や経験に鑑みれば原告の標準構成明細やそこに記載された仕入価格等の具体的\n数値に係る情報を使用する必要がないなどと主張する。 しかし,被告P1の被告会社に対する開示が認められることは前記認定のとおり である。また,被告P1が自ら作成した情報が仮にあるとしても,原告及びサンキ ューの企業規模をも考えた場合,被告P1がその作成及び改訂を全て単独で行って いたとは考え難く,これを裏付けるに足りる証拠もない(被告会社の標準構成明細\nの作成等被告会社における商品開発等に関するものは除く。)。被告P1がサンキ ュー在籍時に取得した情報についても,サンキュー等が原告の完全子会社となりそ のグループに属するに至ったことにより原告の情報管理体制の下に置かれた以上, 被告P1もこれに基づく情報管理を行わなければならないことになる。さらに,被 告P1の経験等を考慮するとしても,原告の標準構成明細と被告会社の標準構\成明 細テンプレート(甲86)の類似性は相当に高い。加えて,本件比較表の作成に当\nたっては,そもそも被告P1による原告データサーバからの各種情報の取得は転職 後に被告会社で使用する意図の下に行われたと見られる上,いかに被告P1の経験 等を考慮しても,対応する原告の標準構成明細を実際に確認しなければ正確な数値\nまでは再現できないと思われることから,被告P1は,これを確認したものとうか がわれる。そのような被告P1が,被告会社の標準構成明細の書式作成に当たり原\n告の標準構成明細を敢えて参考にしないと考えることは不合理である。\nその他被告らが縷々主張する点を踏まえても,この点に関する被告らの主張は採 用できない。
2020.11.21
平成31(ワ)2210 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年8月11日 東京地方裁判所
本件発明1−1の特許請求の範囲の記載をみると,本件発明1−1は, 「患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1 取得部と」(構成要件1−1A),「前記第1患者識別情報と,患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否\nかを判定する第1判定部と」(構成要件1−1B)を有するものであり,第1判定部において第1判定をする。また,「前記第1判定部で一致すると\n判定された場合に,看護師または医師を識別するための第1医師等識別情 報を前記端末装置から取得する第2取得部と」(構成要件1−1D),「前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識別する情報としてあらか\nじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判 定部と」(構成要件1−1E)を有するものであり,第2判定部において第2判定をする。\n
ここで,第1判定と第2判定の関係について,特許請求の範囲には,「前 記第1判定部で一致すると判定された場合に」(構成要件1−1D),第1医師等識別情報が取得されて第2判定がされることが記載されている。こ\nのことから,第1判定で一致すると判定されることが,第2判定がされる ことの前提であることが記載されているといえる。もっとも,第1判定と 第2判定との時間的な接着性の有無等についての記載はない。 そこで,本件明細書1をみると,本件明細書1には,実施の形態1ない し4が記載されている。実施の形態1では,第1判定や,第1判定で一致 するとの判定がされて患者の医療情報を出力することについての実施の 形態(構成要件1−1Aないし1−1C)が記載されているが,第1判定で一致するとの判定がされた直後に第2判定がされるとか,第1判定は,\n第2判定がされる都度にされるものであるなど,第1判定と第2判定の時 間的関係やその機会についての記載はない。そして,実施の形態1では, 患者が,患者の手に巻いており識別情報を含むリストバンドのバーコード を端末装置の撮像部で撮像することによって第1判定がされる(段落【0 045】)。そして,第1判定で一致するとの判定がされた場合には,「患者 用画面」が生成,表示され(段落【0047】ないし【0050】),患者用画面には検査の予\定や患者への注意事項が表示されるなどし(【004\n3】【図7】,患者はその画面を確認することで患者に対して行われる医療 行為等を知ることができ(段落【0019】),その患者用画面に対し,患 者が,例えば,検査ボタンをタッチすると検査名欄や検査説明欄が表示された検査表\示画面が生成,表示されることが記載されている(段落【00\n51】等)。また,第1判定で一致するとの判定がされて患者用画面が表示(ステップS21)されると検査ボタンや手術ボタンの入力を受け付ける\nようになり,その入力がされた場合には対応する画面の表示処理がされるが,入力がされなかったり,上記対応する画面の表\示処理がされたりした後には,患者用画面の表示に戻ることが記載されている(段落【0065】ないし【0068】,【図12】)。\n
実施の形態2は,看護師が患者の医療情報を確認するための看護師専用 画面を表示部に表\示する実施の形態であり,主に構成要件1−1Dないし1−1Fに対応する実施の形態が記載され,特に説明する構\成等以外は実施の形態1と同じであることが記載されている(段落【0088】)。そこ では,患者用画面が表示部に表\示された後,看護師が,自身のリストバン ドに記載されたバーコードを撮像部で撮像し,第2判定がされることが記 載されている(段落【0091】)。また,第2判定が一致した場合には医 療スタッフ用画面が表示されるところ,医療スタッフ用画面である看護師専用画面,バイタル画面等の表\示後に終了処理(ステップS120)がされると,患者用画面の処理(ステップS23)に移ることが記載されてい る(段落【0122】【図26】【図12】)。そこには,上記の他に,第1 判定と第2判定との関係についての記載はない。 また,実施の形態3は主に第1判定に関係する記載であり(ただし,請 求項2に関する形態),実施の形態4は,第2判定に関係する記載である が,それらの記載も含めて,本件明細書1に,第1判定と第2判定との時 間的接着性についての記載はない。 本件明細書1における背景技術や発明が解決しようとする課題の記載 によれば,医療情報を医療用サーバから取得し,取得した医療情報に基づ いてピクトグラムを表示する端末装置という従来技術ではセキュリティを確保することが難しかったところ,本件発明1−1は,セキュリティを\n従来技術より向上させることができるというものである(段落【0003】 ないし【0006】)。本件明細書1には,本件発明1−1について,上記 のとおり,従来技術よりセキュリティを向上させることが記載されている が,その記載のほかには従来技術と比較した優れた効果についての記載は ない。
以上の特許請求の範囲の記載や本件明細書1の記載に照らせば,第2判 定は,第1判定で一致すると判定された場合にされるものである。しかし, 本件明細書1には,実施の形態として,患者がその手に巻いているリスト バンドのバーコードを端末装置の撮像部で撮像することによって第1判 定がされ,一致すると判定された場合に患者用画面が表示され,それに対して患者が一定の操作をする形態が記載されている。そして,患者用画面\nの表示後に,医療スタッフがそのリストバンドのバーコードを撮像部で撮像することで第2判定がされ,そこで一致すると判定されると医療スタッ\nフ用画面が表示されるが,その終了処理後は,患者の医療情報を表\示する 患者用画面の表示に戻ることも記載されている。これらに照らすと,本件発明1−1において,第2判定がされるのは,第1判定で一致すると判定\nされた場合ではあるが,第1判定で一致するとされた後に患者による一定 の操作がされ,その後に第2判定がされることや,第1判定で一致すると 判定されて第2判定がされて第2判定で一致するとされて看護師等が必 要とする医療情報を含む表示画面が出力された後に,第1判定で一致すると判定された後と同じ,患者の医療情報を表\示する患者用画面に戻り,その状態から再び第2判定がされることがあり得ることが記載されている といい得る。
以上によれば,本件発明1−1において,第2判定がされるのは第1判 定で一致すると判定された場合であるが,第1判定がされるのは第2判定 がされる直前に限られるとか,第2判定がされる前にその都度第1判定が されるとは限られないと解するのが相当である。このように解したとして も,第1判定がされてそこで一致すると判定されない限り第2判定はされ ず,第2判定において一致すると判定されない限り看護師等が必要とする 医療情報を含む表示画面が表\示されることはないから,本件明細書1に記 載されたセキュリティの向上という効果を奏するといえる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.11.21
令和1(行ウ)527 手続却下処分取消等 その他 行政訴訟 令和2年8月20日 東京地方裁判所 棄却
2 争点1(原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったこ とにつき,特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか否か)に ついて
(1) 法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときとは,特段の事情 のない限り,国際特許出願を行う出願人(代理人を含む。以下同じ。)として, 相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて国内書面提出期間 内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいうものと解する のが相当である(知財高裁平成28年(行コ)第10002号同29年3月7 日判決・判例タイムズ1445号135頁参照。)。
(2) これを本件について見るに,本件事務員は,本件日本事務所に対し,本件 メールを送信後,数分後に送信の不奏功を告知する本件送信エラー通知を受 けていたにもかかわらず,また,ほぼ同時刻に送信した他の5箇所の代理人 事務所からは送信と同日中に受信確認メールの送信を受けた一方で,本件日 本事務所からは受信確認メールの送信を受けていなかったにもかかわらず, 国内提出期間が徒過するまで,本件日本事務所に対して,本件指示メールの 受信確認等を一切行わなかったものである。さらに,本件事務員を監督する 立場にあった本件現地事務所代理人は,本件指示メールのカーボンコピーの 送信先となっており,同メールを受信できなかった事情が特段見当たらない 以上は同メールを受信していたものと認められるが,その後,国内書面提出 期間の徒過を回避するための具体的な役割を果たした形跡が見当たらない。 これらによれば,本件事務員及び本件現地事務所代理人が相当な注意を尽く していたとは認められないし,本件において「正当な理由」の有無の判断を 左右するに足りる特段の事情があったとも認められない。
(3) これに対し,原告は,法184条の4第4項の「正当な理由」の有無は, 当事者の規範意識を基準とすべきであり,本件においては米国の基準ないし 実務に基づいて判断すべきであるとした上で,本件事務員が,長年の経験を 有し,これまで一度も同様の問題を起こしたことのない者であったこと,本 件現地事務所の期限管理システムの下,本件現地事務所代理人が業務規則に 従い,本件事務員に対し的確な指導及び指示をしていたこと,国内書面提出 期間の終期の徒過を知った直後から,最善を尽くしたことなどを縷々主張す る。
しかしながら,法184条の4第4項の適用の有無は,国内移行手続にお いて判断されるものであるから,同項の「正当な理由」の有無については, 日本における規範・社会通念等を基準に判断されるべきである。また,本件 現地事務所が期限管理システムや業務規則により期限徒過を防止する態勢を 企図していたとしても,本件の事実経過のとおり,本件事務員が本件送信エ ラー通知を受信していたにもかかわらず,本件日本事務所に対して本件指示 メールの受信確認等を一切行わず,期限徒過を生じさせたことからすれば, 結局のところ,本件事務員が業務を適切に行っている限りは問題が生じない が,見落としや錯誤など何らかの過誤を発生させた場合,何らの監督機能や\n是正機能が働くこともなく,問題の発生を抑止できない態勢にとどまってい\nたと言わざるを得ない。また,その余の主張について慎重に検討しても,本 件において,正当な理由の有無の判断に影響を与えるものとはいえない。 以上からすれば,原告の前記主張は,いずれも前記判断を左右するもので はない。
(4) したがって,本件において,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文 を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の 「正当な理由」があるということはできない。
2020.11.21
平成31(ワ)1409 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年7月22日 東京地方裁判所
1 争点1(本件治験が特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明 の実施」に当たるか)について
(1) 特許法69条1項は「試験又は研究のためにする特許発明の実施」について 特許権の効力が及ばないと規定しているが,その趣旨は,特許法1条に規定さ れた「発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発 達に寄与する」ためには,当該発明をした特許権者の利益を保護することが必 要である一方,特許権の効力を試験又は研究のためにする特許発明の実施にま で及ぼすと,かえって産業の発達を損なう結果となることから,産業政策上の 見地から,試験又は研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及ば ないこととし,もって,特許権者と一般公共の利益との調和を図ったものと解 される。
本件治験が同項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当た るかどうかは,特許法1条の目的,同法69条1項の上記立法趣旨,医薬品医 療機器等法上の目的及び規律,本件治験の目的・内容,治験に係る医薬品等の 性質,特許権の存続期間の延長制度との整合性なども考慮しつつ,保護すべき 特許権者の利益と一般公共の利益との調整を図るという観点から決すること が相当である。
(2) 前記第2の2(8)のとおり,平成11年最判は,後発医薬品について,第三 者が,特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じく する後発医薬品を製造して販売することを目的として,その製造につき薬事法 (当時)14条所定の承認申請をするため,特許権の存続期間中に,特許発明\nの技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し,これを使用して同申請書\nに添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは,特許法69条1項にい う「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり,特許権の侵害とは ならないと判示している。 本件治験の対象とされているT-VECは,前記第2の2(5)のとおり,外国の医 薬品規制当局の製造承認を受け,我が国でブリッジング試験を行っている先発 医薬品であるが,以下のとおり,本件治験についても,平成11年最判の趣旨 が妥当するものと解される。
ア 平成11年最判は,後発医薬品が特許法69条1項にいう「試験又は研究 のためにする特許発明の実施」に当たる理由として,後発医薬品についても, 他の医薬品と同様,その製造の承認を申請するためには,あらかじめ一定の\n期間をかけて所定の試験を行うことを要し,その試験のためには,特許権者 の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産し,使用する 必要がある点を指摘する。 本件治験は,外国の医薬品規制当局の製造承認を受け,我が国でブリッジ ング試験を行うものであるが,証拠(乙15)によれば,ブリッジング試験 とは,外国臨床データを新地域の住民集団に外挿するために新地域で実施さ れる臨床試験であり,新地域における有効性,安全性及び用法・用量に関す る臨床データ又は薬力学的データを得ることを目的として行われるもので あって,同試験に当たり,一定の条件に適合する外国臨床データは医薬品の 製造等承認申請書に添付される資料として受け入れられるものの,日本人に\nおける当該医薬品の有効性及び安全性の評価を行うため,原則として,国内 で実施された臨床試験成績に関する資料を併せて提出することが必要であ ると認められる。
そして,本件治験は,T-VECの「日本人被験者における安全性及び有効性を 評価するための試験」(甲8の1・2頁「Official Title」欄)であり,修 正版WHO応答基準を用いたDRR(持続性奏効率)によって評価されるT-VECの 抗腫瘍活性が主要評価項目となっているものと認められる(甲8の1・4頁 「Primary Outcome Measures」欄の2)。このDRRとは,乙14の論文によれ ば,最初の12か月以内に開始する完全奏功(CR:腫瘍が完全に消失するこ と)及び部分奏功(PR:腫瘍が一定の割合以上小さくなること)が6か月連 続して継続した割合として定義されるものであるから,T-VECの製造販売の 承認申請には,日本人被験者にT-VECを投与して,一定の期間をかけて臨床 試験を行うことが必要となる。
そうすると,先発医薬品等に当たるT-VECについても,後発医薬品と同様, その製造販売の承認を申請するためには,あらかじめ一定の期間をかけて所\n定の試験を行うことを要し,その試験のためには,本件発明の技術的範囲に 属する医薬品等を生産し,使用する必要があるということができる。
イ 平成11年最判は,特許権存続期間中に,特許発明の技術的範囲に属する 化学物質ないし医薬品の生産等を行えないとすると,特許権の存続期間が終 了した後も,なお相当の期間,第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果 となるが,この結果は,特許権の存続期間が終了した後は,何人でも自由に その発明を利用することができ,それによって社会一般が広く益されるよう にするという特許制度の根幹に反するとしている。
T-VECについても,前記判示のとおり,その製造販売の承認を申請するた\nめには,あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要するので, 本件特許権の存続期間中に,本件発明の技術的範囲に属する医薬品の生産等 を行えないとすると,特許権の存続期間が終了した後も,なお相当の期間, 本件発明を自由に利用し得ない結果となるが,この結果が特許制度の根幹に 反するものであることは,平成11年最判の判示するとおりである。
ウ 平成11年最判は,第三者が,特許権存続期間中に,薬事法(当時)に基 づく製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて,同期間終了後に譲渡\nする後発医薬品を生産し,又はその成分とするため特許発明に係る化学物質 を生産・使用することは,特許権を侵害するものとして許されないと判示す る。本件治験については,前記のとおり,医薬品医療機器等法の規定に基づい て第I)相臨床試験を行っているところであり,被告が,本件特許権の存続期 間中に,本件特許権の存続期間満了後の譲渡等を見据え,同法に基づく製造 販売承認のための試験に必要な範囲を超えてT-VECを生産等し,又はそのお それがあることをうかがわせる証拠は存在しない。
そうすると,特許権者である原告が本件特許権の存続期間中にその独占的 実施により利益を得る機会は確保されるのであって,それにもかかわらず, 本件特許権の存続期間中にT-VECの製造承認申請に必要な試験のための生産\n等をも排除し得るものと解すると,本件特許権の存続期間を相当期間延長す るのと同様の結果となるが,それは,平成11年最判も判示するとおり,特 許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものとい うべきである。
エ 以上のとおり,平成11年最判の趣旨は本件治験についても妥当するので, 本件治験は,特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実 施」に当たる。
2020.11.21
平成30(ワ)21448 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年7月9日 東京地方裁判所
イ 本件発明の技術思想(課題解決手段)について
前記(1)によれば,本件発明は,鋼管等を回転して圧入する立坑構築機に\n関し,輸送する際に幅を狭くする必要があったところ,従来技術において は,円弧状歯車片同士の端部が当接されず,その隙間から内部の転動体が こぼれ落ちてしまうため,標準的なベアリングを使用することができない という課題が生じていたので,これを解決するため,構成要件Eに係る構\ 成を採用し,円弧状ベアリング片が隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成し,もって,分割して幅方向の寸法を狭くすることができると\n共に,転動体がこぼれ落ちなくなり回転を安定させることができ,標準的 なベアリングを使用して装置を安価に構成することができるようにした\nという技術的思想であるものと認められる。すなわち,本件発明において, 円弧状ベアリング片は,それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付 ベアリングを構成するという技術的意義を有しているものというべきで\nあり,このことは,前記のとおり,課題解決手段の欄(段落【0011】) において,「円弧状ベアリングは隙間なく接続して環状の歯車付ベアリン グを構成し,内輪及び外輪の間に配置された球やころ等の転動体がこぼれ\n落ちない構造になっている。かかる構\成によって,分割して幅方向の寸法 を狭くすることができると共に,標準的なベアリングを使用して回転を安 定させることができる。」と記載されていることからも根拠付けられるも のである。
ウ 構成要件Eへの被告製品の充足性について\n
しかして,構成要件Eには,円弧状ベアリング片が「それぞれの両端部\nを各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成する」との文言が記載され\nているところ,「接続」とは「つなぐこと。つながること。続けること。続 くこと。」を意味するものである(広辞苑第7版)。そうすると,その文言 の一般的意義,上記の本件発明の技術的思想(本件発明において,円弧状 ベアリング片は,それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成するという技術的意義を有しているものであること)に照らせ\nば,環状の歯車付ベアリングを構成するために隙間なく接続する部品,す\nなわち,つなぐ部品が円弧状ベアリング片であって初めて,円弧状ベアリ ング片が「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構\n成する」といえるものであると解するのが相当である。そうすると,環状 の歯車付ベアリングを構成した際に,円弧状ベアリング片の両端部に隙間\nが有るならば,「接続」とは評価し難いものというべきである。 しかるに,前記アによれば,被告製品においては,環状の歯車付ベアリ ングは,2つある分割フレーム14に設けられた内外輪部ケースそれぞ れの両端部及び回転リング部材51−3,51−4それぞれの両端部を 隙間なく接続して構成するものであって,分割内輪部23や分割外輪部\n24それぞれの両端部を隙間なく接続するものでも,つなぐものでもな く,円弧状ベアリング片である円弧状部材36,37それぞれの両端部 には,客観的に隙間があるから,被告製品の円弧状部材36,37は 「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成す\nる」ものであるとはいえず,被告製品は,構成要件Eを充足しないもの\nというほかない。
・・・
以上によれば,本件特許は当業者が乙2発明に基づいて容易に発明するこ とができたもの(特許法29条2項)であるから,特許無効審判により無効 にされるべきもの(同法123条1項2号)である。 なお,本件特許については,知的財産高等裁判所令和2年(行ケ)第10 102号事件同2年3月24日判決(裁判所ホームページ)が,特許無効審 判請求の不成立審決に対する取消請求を棄却しているところ,原告は,これ を理由として,口頭弁論再開の申立てをしているが,同判決は,乙2発明を\n主引用発明とし,乙20発明を副引用発明として適用することに基づく進歩 性の欠如については判断しておらず,上記判断は同判決と矛盾するものでは ないから,再開の必要性は認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2020.11.21
令和1(行ケ)10165 特許権 行政訴訟 令和2年11月5日 知的財産高等裁判所
2 本件補正の適否について
(1) 前記第2の2のとおり,本願発明に係る特許請求の範囲については,本件 出願時には「通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体」と記載 されていたものが,本件補正後には「通気性及び通水性が確保され且つ透光 性を有する不織布又は織布からなるカバー体」へと記載が変更されたもので あり,本件カバー体につき,「通水性」及び「透光性」を有する旨の記載が追 加されたものといえる。 そして,上記1のとおり,本件当初明細書等には,本件カバー体が通水性 を有する旨の記載(【0035】)は存するものの,「透光性を有する」との事 項に対応する明示的な記載は存しない。 そこで,本件カバー体が「透光性を有する」との事項が,本件当初明細書 等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて,以下,検討する。
(2) 工業分野一般において,透光性とは,物質を光が透過して他面から出るこ とをいう(JIS工業用語大辞典第5版(乙1))ところ,本願発明の技術分 野における「透光性」の用語が,これと異なる意味を有するものとみるべき 事情は存しない。 そうすると,本件カバー体が「透光性を有する」とは,本件カバー体が光 を透過させて他面から出す性質を有することを意味するものといえる。
(3) 次に,上記1のとおり,本件カバー体は織布又は不織布から構成されると\nころ,本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識につい て検討する。 証拠(甲23,24)及び弁論の全趣旨によれば,本件出願よりも前の時 点において,遮光カーテンの生地に遮光性能を付与するために,有彩色の生\n地に黒色の生地を重ねて二重にする,有彩色の糸と共に黒色の糸を使用して 生地を製造する,黒色顔料を配合した塗料を生地に塗布積層する,黒色顔料 を配合したプラスチックフイルムを生地に張り合わせるなどの方法が採られ ていたことが認められる。また,証拠(乙4,10)及び弁論の全趣旨によ れば,本件出願よりも前の時点において,織布である樹木の萌芽抑制シート の遮光性を高めるために,糸材にカーボン粉末が練り込まれた黒色糸を使用 する方法が採られたり,織布又は不織布である野生動物侵入防止用資材の遮 光率を高めるために,繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくく する方法が採られたりしていたことが認められる。 このように,本件出願よりも前の時点において,織布又は不織布に遮光性 能を付与するために,特殊な製法又は素材を用いたり,特殊な加工を施した\nりするなどの方法が採られていたことからすれば,本件出願時において,織 布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採る必要 があるということは技術常識であったといえる。そうすると,このような特 別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないということ\nもまた,技術常識であったとみるのが相当である。 そして,繊維分野において,遮光性能とは,入射する光を遮る性能\をいう (「JISハンドブック 31 繊維」(乙8))から,遮光性能を有しないと\nいうことは,入射する光を遮らずに透過させること,すなわち上記(2)の意味 における「透光性」を有することを意味することとなる。 以上検討したところによれば,織布又は不織布について遮光性能を付与す\nるための特別な方法が採られていなければ,当該織布又は不織布は透光性を 有するということが,本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する 技術常識であったとみるのが相当である。
(4) 以上を前提として,本件カバー体が「透光性を有する」との事項が,本件 当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて検討する。 上記(3)によれば,本件出願時における当業者は,織布又は不織布について 遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ,当該織布又は\n不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。 そして,上記1のとおり,本件当初明細書等には,織布又は不織布から構\n成される本件カバー体につき,遮光性能を有する旨や遮光性能\を付与するた めの特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず,かえって,本件 カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載(【0035】)や,本件カバー 体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構\成する材料がそのまま露出し, 通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載(【0 036】)が存するところである。 このような本件当初明細書等の記載内容からすれば,当業者は,本件カバ ー体を構成する織布又は不織布について,特殊な製法又は素材を用いたり,\n特殊な加工が施されたりするなど,遮光性能を付与するための特別な方法は\n採られていないと理解するのが通常であるというべきである。 そうすると,本件当初明細書等に接した当業者は,本件カバー体は透光性 を有するものであると当然に理解するものといえるから,本件カバー体が「透 光性を有する」という事項は,本件当初明細書等の記載内容から自明な事項 であるというべきである。
(5) 以上によれば,本件補正は,本件当初明細書等の全ての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入す るものではなく,本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたも のといえるから,特許法17条の2第3項の要件を満たすものと認められる。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 当業者自明
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2020.11.21
令和2(行ケ)10005 特許権 行政訴訟 令和2年11月10日 知的財産高等裁判所
ア 原告は,当業者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度に まで具体的・客観的なものとして構成されていないいわゆる「未完成発明」は,特\n許法29条の2における「他の特許出願‥の発明」に当たらず,後願排除効を有さ ないとし,甲1明細書に記載された発明は発明として未完成であると主張する。
イ そこで判断するに,特許法184条の13により読み替える同法29条の2 は,特許出願に係る発明が,当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録 出願であって,当該特許出願後に特許掲載公報,実用新案掲載公報の発行がされた ものの願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「先願明細書等」という。)に記 載された発明又は考案と同一であるときは,その発明について特許を受けることが できないと規定する。 同条の趣旨は,先願明細書等に記載されている発明は,特許請求の範囲以外の記 載であっても,出願公開等により一般にその内容は公表されるので,たとえ先願が\n出願公開等をされる前に出願された後願であっても,その内容が先願と同一内容の 発明である以上,さらに出願公開等をしても,新しい技術をなんら公開するもので はなく,このような発明に特許権を与えることは,新しい発明の公表の代償として\n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない,というものである。 このような趣旨からすれば,同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは, 先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握され る発明をいい,記載されているに等しい事項とは,出願時における技術常識を参酌 することにより,記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。 したがって,特に先願明細書等に記載がなくても,先願発明を理解するに当たっ て,当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方, 抽象的であり,あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示 が不十分であるような発明は,ここでいう「発明」には該当せず,同条の定める後願\nを排除する効果を有しない。また,創作された技術内容がその技術分野における通 常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術 効果をあげることができる程度に構成されていないものは,「発明」としては未完成\nであり,特許法29条の2にいう「発明」に該当しないものというべきである。
ウ これを本件についてみると,・・・・
エ 以上によれば,ガラス合紙の,シリコーンのポリジメチルシロキサンであ る有機ケイ素化合物の含有量を3ppm以下,好ましくは1ppm以下で,0. 05ppm以上とした先願発明は,ガラス合紙からガラス板に転写された有機ケ イ素化合物に起因する配線の不良等を大幅に低減でき,特にポリジメチルシロキ サンがガラス板に転写され,より配線や電極の不良等が発生し易くなることを抑 制できるものであって,先願発明の目的とする効果を奏するものであること,そ のようなガラス合紙は,ポリジメチルシロキサンを含有する消泡剤を使用しない で製造したパルプを原料として用い,ガラス合紙の製造工程において,パルプの 洗浄,紙のシャワー洗浄,水槽を用いる洗浄や,これらを2種以上行う方法によ り製造できること,以上のことが理解できる。
そうすると,先願発明は,創作された技術内容がその技術分野における通常の知 識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果を あげることができる程度に構成されたものというべきである。\nよって,先願発明は,特許法29条の2にいう「発明」に該当し,未完成とは いえないから,同条により,これと同一の後願を排除する効果を有する。
関連カテゴリー
>> 発明該当性
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2020.11.20
令和1(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年11月11日 知的財産高等裁判所
1) 以上によれば,本願発明1の特許請求の範囲(請求項1)及び本願 明細書には,本願発明1の「臀部の頂上部よりも上側」は,「下方窄ま\nり」の状態の設定の開始位置(起点)を規定したものであることの開示 はあるが,その用語の意義や技術的意義について述べた記載はない。 しかるところ,「頂上」の用語は,一般に,「いただき,てっぺん」 などを意味すること(広辞苑(第七版)),ヒップサイズの寸法は,人 体を側方から見て臀部が最も後方に突き出している位置(最も高い位置)\nをメジャーで測定するのが一般的であることに鑑みると,本願発明1の 「臀部の頂上部よりも上側」にいう「臀\部の頂上部」の用語は,臀部が\n最も後方に突き出している位置(最も高い位置)を意味するものと理解 することができ,身頃の展開状態(展開平面図)においては,その位置 は,「臀部における点」として観念できるものと解される。\n
そうすると,本願発明1の「臀部の頂上部よりも上側」は,臀\部が最 も後方に突き出している位置(最も高い位置)よりも,上方であれば, それが多少の上方であっても,「臀部の頂上部よりも上側」に含まれる\nものと解される。
イ これに対し原告は,本願明細書の記載(【0010】,【0013】等) によれば,相違点1に係る本願発明1の構成は,下方窄まりにする領域の\n開始位置(臀部の形状と不整合にする領域の開始位置)を「臀\部の頂上部 よりも上側」に設定(相違点1に係る本願発明1の構成)し,この設定に\nより,生地が「臀部の頂上部」に対して「下方窄まり」の形状で接するこ\nとになるため,「臀部の頂上部」を押圧する力には上向きの成分(上向き\nのベクトル)が含まれることになり,これが臀部の頂上部をも上方に持ち\n上げる作用を果たすので,「ショーツ等衣料のヒップ下部該当部位周りを ヒップ下部体形にフィットすべく絞ることができ」,「背面覆い部分の下 部がヒップ下部の膨らみ体形にぴったり合って該下半分を絞り込むように 深く包み込むことができる」という作用効果を奏する旨主張する。 しかしながら,前記ア認定のとおり,本願明細書の【0010】及び【0 013】の記載は,「下方窄まり」の状態に設定した構成によれば,ヒッ\nプ下部体形の半球形状の下半分を深く立体的に包み込むことができるので, ヒップ下部へのフィット性に優れ,ヒップ裾ラインのずり上がりを確実に 防止できるとともに,直立姿勢時にショーツ等衣料のヒップ下部や臀溝部\nに相当する個所に弛み皺やだぶつきが発生することが無くなり,美しいヒ ップ裾ラインを出すことことができるという効果を奏する旨を開示するも のであるが,本願明細書には,この効果が「下方窄まり」の状態の設定の 開始位置(起点)を「臀部の頂上部よりも上側」としたことによるもので\nあることについての記載はない。
また,前記ア認定のとおり,本願明細書には,本願発明1の「臀部の頂\n上部よりも上側」の具体的な位置を示した記載はないし,「下方窄まり」 の状態の設定の開始位置(起点)を「臀部の頂上部よりも上側」とするこ\nとの技術的意義について述べた記載もない。ましてや,「下方窄まり」の 状態の設定の開始位置(起点)を「臀部の頂上部よりも上側」とすること\nによって,生地が「臀部の頂上部」に対して「下方窄まり」の形状で接す\nることになるため,「臀部の頂上部」を押圧する力には上向きの成分(上\n向きのベクトル)が含まれることになり,これが臀部の頂上部をも上方に\n持ち上げる作用を果たすことについては,記載も示唆もない。 したがって,原告の上記主張は,本願明細書の記載に基づかないもので あるから,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2020.11.11
平成29(ワ)11462 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和2年7月29日 東京地方裁判所
◆イ号および本件商標
原告各商標と被告各標章の外観を比較すると,上記のとおり,それぞれ1)英
文字の「X」型十字が左側(反時計回り方向)に傾いた形で組み合わされた2本の帯からなり,2)帯状線の輪郭が鋸歯状であるという点において共通しており,被告
各標章の外観は,原告各商標の外観と,その識別力の強い部分において共通する特
徴を有しているといえる。
他方で,被告各標章は,3)右上から左下に伸びる帯が左上から右下に伸びる帯の
上に重なっており,4)各帯の輪郭線に沿って,その内側にステッチがそれぞれ2本
施されているとの点で原告各商標とは異なる特徴を有しているが,同色の帯の重な
りであって,ステッチも輪郭線の近くに施されているものであるから,いずれも一
見して目立つ特徴であるとまではいえない。また,被告各標章の色彩についても,
商品識別力の強い点とはいえない。
被告は,その他に別紙4被告が主張する原告各商標と被告各標章の外観相違点の
とおり,原告各商標と被告各標章との間に,中心点から右下及び左下に伸びる部分
の長さの比,2つの帯のなす角度,帯の端部の形状,帯の太さ等において,相違点
があると主張するが,いずれも,上記1),2)の共通点を前提にすれば,需要者に対
して原告各商標と異なる印象を与えるようなものであるとまではいえない。
これらの争点について,被告は,靴という商品の性質や,被告商品の価格帯・販
売場所からすれば,需要者はそのデザインを細部まで入念に検討する等として,「X」
型十字の標章の細部に相違点がある場合には外観上類似性がないと判断されるべきと主張するが,上記に説示した内容に照らせば,この主張は採用することができな\nい。
したがって,被告各標章は,いずれも,原告各商標とその外観において類似する
というべきである。
イ 前記(2)及び(3)のとおり,原告各商標と被告各標章は,いずれも特定の称
呼・観念が生じるものではなく,これらが著しく相違するとは認められない。
また,本件証拠上,原告各商標と被告各標章につき,上記の外観の類似性にかか
わらず,商品の出所を誤認混同するおそれがないとするような取引の実情等がある
とも認められない。被告商品の価格帯・販売場所などの被告の指摘する前記事情に
ついて,商品の出所の誤認混同の有無を判断する上で考慮すべき取引の実情として
検討しても,本件について,上記判断を左右するとはいえない。
ウ したがって,被告各標章は,いずれも,原告各商標とそれぞれ類似するとい
うべきである。
2 争点2(非商標的使用(商標法26条1項6号)該当性)について
(1) 被告各標章は,別紙2被告標章目録のとおりであり,前記第2の2(3)イで
示したとおり,いずれも靴の甲の側面において,側方から見て概ね中央の位置に付
されている。
上記の位置は,靴の外観において特に目立つ部分ということができ,証拠(乙1,
2,4,5,6,7,12)によれば,靴において,当該部分に商標を付すことは
一般的に行われていることが認められる。また,証拠(甲26,27)及び弁論の
全趣旨によれば,被告商品を製造したミュニック社においては,スニーカー様の靴
の側面の中央の位置に傾いた「X」型十字を表\\示した平面図状の標章について国際
商標登録をしていたことも認められる。
そうすると,上記の位置に目立つ大きさで付されている被告各標章については,
商品識別機能を果たすものとして使用されていると認めるのが相当である。
(2) 被告は,被告商品においては,被告各標章の他にも,ミュニック社が商標登
録した別の標章の一部が,商品そのもの,包装箱及びタグに記されており,被告各
標章は単なるデザインとして使用されているにすぎない等と主張するが,他の登録
商標が付されていることによって,当然に被告各標章が商品識別機能を有しないということはできない上,証拠(乙13)によっても,被告商品に付されている他の\n登録商標(乙14)は,その位置や大きさからして被告各標章よりも際だって目立
つものであるとは認められず,そうであれば,被告商品に付されている他の登録商
標の使用は,被告各標章が商品識別機能を果たすものとして使用されている旨の前記判断を左右するものではなく,被告の上記主張は採用することができない。また,\nミュニック社商品において,被告各標章を使用していないスニーカーがあること
(乙15,16)によっても,被告商品に付された被告各標章に出所識別機能がないということはできない。\n被告は,ミュニック社以外の靴について,「X」型十字が単なるデザインとして付されているものがあると主張するが,証拠(乙1)によれば,被告が他の靴に付さ\nれていると指摘する「X」型十字は,その形状や位置において,被告各標章とは大きく異なるものであり,この点の指摘も上記(1)の結論を左右するものとはいえない。
(3) 以上によれば,被告商品に付された被告各標章が,需要者が何人かの業務に
係る商品である認識することができる態様により使用されていない商標(商
標法26条1項6号)に該当するとはいえない。
3 商標権侵害の有無についてのまとめ
以上によれば,被告商品は原告各商標権の指定商品に含まれるところ,被告各標
章はいずれも原告各商標とそれぞれ類似し,被告各標章の使用について商標法26
条1項6号によって原告各商標権の効力が及ばないとはいえないから,被告が,被
告各標章を付した被告商品を輸入し,販売することは,原告各商標権を侵害するも
のとみなされる(商標法37条1項1号)。
4 争点3(原告の損害)について
(1) 商標法38条2項の適用の有無について
被告は,原告は対象期間のうち,少なくとも平成27年10月25日までの期間
については,原告各商標を使用したスニーカーを販売していなかったとして,同期
間の損害については,商標法38条2項は適用されないと主張する。
しかしながら,証拠(甲183)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,対象期間
を通じて,英文字の「X」型十字が左側(反時計回り方向)に傾いた形で組み合わされた2本の帯状線からなり,帯状線の輪郭が鋸歯状であるという特徴を持つ,原\n告各商標と同一又は類似する標章を甲の側面部分に付したスニーカーを販売してい
たものと認められる。
このように対象期間において原告が被告商品と競合する商品を販売していたこと
からすれば,原告には,被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益
が得られたであろうという事情が存在すると認められ,対象期間中の原告の損害額
の算定については商標法38条2項の適用があるというべきである。
(2) 被告が侵害の行為により受けた利益について
ア 利益の意義
被告商品の輸入販売について,商標法38条2項所定の侵害行為により被告が受
けた利益の額は,被告商品の売上高から,被告において被告商品を輸入販売するこ
とによりその輸入販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利
益の額である。
イ 事実認定
前記の前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告商品の輸入販売状
況及び売上高,経費等について,以下の事実が認められる。
(ア) 被告商品を含むミュニック社商品の輸入及び販売
被告は,遅くとも平成26年2月3日以降,被告商品を含むミュニック社商品を,
ベルネダ社から輸入し,靴流通問屋や百貨店等に卸売していた(乙19,25,2
6)。
被告における対象期間中のミュニック社商品全体の販売額は,総額●(省略)●
円であった(乙20,21)。
(イ) 被告によるミュニック社商品の費用に関する管理
被告は,平成26年11月1日にミュニック社商品のみを扱うミュニック事業部
を設立し,同日以降はミュニック事業部において輸入販売の管理を行っていた。被
告は,ミュニック社商品について,同事業部の設立の前後を通じて商品別又は品番
別の経費の管理はしていなかった(乙19)。
(ウ) 被告商品の販売数量
被告商品については,別紙3被告商品販売一覧表記載のとおり,被告各標章のうち「標章番号」欄記載の番号の標章が付された「商品名」,「品番」欄記載の商品名,品番を有するスニーカーを,それぞれ同別紙記載の数量輸入していた(弁論の全趣\n旨)。
また,平成29年4月7日時点の被告商品の在庫は別紙3被告商品販売一覧表の「在庫数量(4/7)」欄の記載のとおりであり(合計●(省略)●足),この在庫\nとは別に,被告は,同年9月ころに,輸入した被告商品のうち同別紙の「2017
/9/15返品」との記載の下に記載された数量(合計●(省略)●足)を仕入先
に返品した。
そうすると,対象期間中の被告商品の販売数は,輸入数量から上記の在庫数量及
び返品数量を控除した同別紙の「販売数量」欄記載の数量(その合計は●(省略)
●足)である(弁論の全趣旨)。
(エ) 被告商品の販売価格
被告商品それぞれの消費者への販売価格については,別紙3被告商品販売一覧表の「上代」価格のとおりである(被告商品の消費者への販売価格が1万5000円\nないし2万1000円程度であったとの当事者間に争いのない事実,弁論の全趣旨)。
そして,被告は,被告商品を靴流通卸問屋や百貨店に,上記の「上代」価格に別
紙3被告商品販売一覧表の「掛率」欄記載の割合を乗じた「販売価格」欄記載の価格で販売していた(乙19,25,26,弁論の全趣旨)。\n
(オ) 被告商品の仕入額
被告商品の1個当たりの仕入価格は別紙3被告商品販売一覧表の「輸入平均単価」欄に記載の金額であり,前記(ウ)の被告商品の販売数に対応する仕入額は同別紙の
「仕入額」欄記載のとおりとなり,合計額は●(省略)●円である(弁論の全趣旨)。
(カ) 諸掛(外注費)について
被告は,対象期間中に,ミュニック社商品の輸入販売に関して,被告での会計処
理において「諸掛(外注費)」の勘定科目において,「加工料」,「運賃」,「付属代」,
「関税」と「雑費」に分類した費用を次のとおり支出し,その合計は●(省略)●
円である(乙19,53,93,弁論の全趣旨)。
a 加工料について
加工料に分類された費用は●(省略)●円であり,これは主に輸入したミュニッ
ク社商品を販売するための納品,入出庫,梱包等の作業のために被告が支払った費
用である(乙53,79,93,弁論の全趣旨)。このうち,商品値引き費用につい
ては,ミュニック社商品を百貨店が値引販売した際に,被告が値引額を負担したも
のである(乙19,弁論の全趣旨)。
b 運賃について
運賃に分類された費用の合計額は●(省略)●円であり,これは主に輸入の際の
運送費,海上運賃,航空運賃等として被告が支払った費用である(乙53,81〜
85,93,弁論の全趣旨)。
また,このうちTQ使用料については,革製品の輸入の際にその数量に応じて必
要となるものである(乙85,弁論の全趣旨)。
c 付属代について
付属代に分類された費用の合計額は●(省略)●円であり,これはミュニック社
商品の販売に当たって被告が付していたタグや袋等の購入費用である(乙53,8
0,93,弁論の全趣旨)。
d 関税について
関税に分類された費用の合計額は●(省略)●円であり,これはミュニック社商
品の輸入の際に支払った関税である(乙53,81〜83,86,87,93,弁
論の全趣旨)。
e 雑費について
雑費に分類された費用の合計額は●(省略)●円であり,これは,主にミュニッ
ク社商品の輸入手続を依頼した業者に支払った通関料や手数料(取扱料)等の費用,
前記c及びdに計上されなかったTQ使用料や袋代,ミュニック社商品に付した輸
入保険料である(乙53,81,86〜88,93,弁論の全趣旨)。
(キ) 広告費について
被告は,対象期間中に,「広告費」の勘定科目において,ミュニック社商品の宣伝
のためのダイレクトメール作成費用,展示会や百貨店での催事に要した費用として
合計●(省略)●円を支出した(乙19,22〜24,54,63〜72,94,
弁論の全趣旨)。このうち,被告商品の写真のみを大きく扱ったダイレクトメールが
作成されていたことがある(乙22)。
(ク) 運賃について
被告は,対象期間中に,ミュニック社商品に関し,「運賃」の勘定科目において,
運送費,倉庫における入庫・梱包等に係る倉庫費用・出荷作業料,検品検査代その
他の国内での運送及び保管の費用として●(省略)●円の出費をした(乙19,5
5,89〜92,95,弁論の全趣旨)。
(ケ) 販売手数料について
被告は,対象期間中に,「販売手数料」の勘定科目において,ミュニック社商品の
販売に関して販売業務及び営業業務を委託した業務委託費用として,合計●(省略)
●円を支出した(乙56,96,弁論の全趣旨)。また,被告はミュニック社商品の
販売活動等に関してAとの間で業務委託契約を締結していた(乙27,弁論の全趣
旨)。
(コ) 荷造包装費について
被告は,対象期間中に,「荷造包装費」の勘定科目において,段ボール代,梱包テ
ープ等のミュニック社商品の梱包資材費用として●(省略)●円の上記支出をした
(乙57,97,弁論の全趣旨)。
(サ) 保険料について
被告は,対象期間中に,「保険料」の勘定科目において,ミュニック社商品の販売
に関して,火災保険料,損害保険料及び輸入保険料(ただし前記(カ)eで計上されな
かったもの)として合計●(省略)●円を支出し,また,海外出張の際の傷害保険
料として●(省略)●円を支出した(乙19,58,98,弁論の全趣旨)。
このうち,火災保険料,損害保険料,輸入保険料として支出された合計●(省略)
●円については,毎回の保険料が定額でなく,補助元帳上,摘要欄に対象となる商
品数が記載されているものがある(乙58)。
(シ) 旅費交通費について
被告は,対象期間中に,「旅費交通費」の勘定科目において,ミュニック社商品の
営業等に要した交通費,国内出張費及び海外出張費として合計●(省略)●円を支
出した(乙59,99,弁論の全趣旨)。
(ス) 見本費について
被告は,対象期間中に,「見本費」の勘定科目において,ミュニック社商品販売の
ためのサンプル購入費用や,スニーカーに関する書籍の購入費用として合計●(省
略)●円を支出した(乙60,100,弁論の全趣旨)。
(セ) 雑損失について
被告は,対象期間中に,「雑損失」の勘定科目において,為替予約を解約した際に発生した費用として,「為替予\約解約損」●(省略)●円を計上している(乙61,弁論の全趣旨)。
(ソ) 特別損失について
被告は,対象期間中に,「特別損失」の勘定科目において,ミュニック社商品を販
売していた恵比寿三越伊勢丹に支払った費用(広告費用,撤退費用,撤退違約金,
B氏特別退職金)合計●(省略)●円を「恵比寿店舗撤退違約金」,「恵比寿店舗費
用等」,「恵比寿店舗撤退費用」及び「特別退職金」として計上している(乙32,
弁論の全趣旨)。
ウ 事実認定の補足
(ア) 輸入数量について,原告は,被告から,被告各標章が付された商品のインボ
イスとして,被告商品の品番についてマスキングをした上で開示を受けたものの,
開示資料に裏付けられる前記イ(ウ)認定の数量以外にも,被告商品の輸入数量がある
旨を主張するが,原告が被告商品に関するインボイス等を対象として行った文書提
出命令の申立ては,後記5のとおり必要性がなく,その他,原告の主張を認めるに足りる証拠はない。\nまた,被告標章19を付した商品については,原告がその商品の商品名及び品番
として特定する「MASSANA」及び「862015」と,被告標章3の2を付
した商品の商品名及び品番とが同一であり,外観も,被告標章3の2を付した商品
とソールの色を除いて類似していると認められる(甲11,198,弁論の全趣旨)踏まえると,被告標章3の2を付した商品の輸入に関して被告から原告に開\n示され,それに沿うものとして認められる前記イ(ウ)の数量とは別に,輸入された事
実やその数量はないと考えることが自然であって,これを認めるに足りる証拠はな
い。
(イ) 前記イ(カ)ないし(ソ)認定の費用を超えて,ミュニック社商品に関する費用を
認めるに足りる証拠はない。
エ 検討
前記イの認定事実を基に,限界利益の額を検討する。
(ア) 被告商品の売上高
前記イ(ウ)及び(エ)によれば,対象期間における被告商品の売上高は,別紙3被告
商品販売一覧表の「売上高」欄のとおりであり,合計●(省略)●円である。
(イ) 売上高から控除すべき経費
a 売上高から控除すべき経費として,まず,被告商品の仕入額があり,前記イ
(オ)のとおり,●(省略)●円である。
b その他,売上高から控除すべき経費としては,前記イ(カ)の外注費,前記イ
(キ)の広告費,前記イ(ク)の運賃,前記イ(コ)の荷造包装費及び前記イ(サ)の保険料
(傷害保険料を除く。)のうち,それぞれ被告商品に係る部分が,前記認定した各費
用の性質上,被告商品の輸入販売に直接関連して追加的に必要となったものとして,
該当すると認められる。そして,前記イ(イ)のとおり,被告は,ミュニック社商品の
経費について商品別又は品番別に管理しておらず,上記各費用の被告商品に係る部
分を直接的に示す資料はないことから,ミュニック社商品の販売総額に占める被告
商品の割合,被告商品の輸入数量に占める販売数量の割合などを考慮して,被告商
品に係る費用の額を算出するのが相当であり,これは,次のとおり,合計●(省略)
●円であると認められる。
(a) 外注費については,対象期間中の被告におけるミュニック社商品全体の販売
総額●(省略)●円に占める被告商品の販売総額●(省略)●円の割合(以下,こ
の割合を「被告商品の販売総額の割合」ともいう。)が約●(省略)●%であること,
被告商品の輸入数量●(省略)●足のうち対象期間中に販売された数量●(省略)
●足の占める割合が約●(省略)●%である踏まえ,被告商品に係る費用の
額は,全体の●(省略)●円の15%に当たる●(省略)●円と認められる。
(b) 広告費については,上記の被告商品の販売総額の割合が約●(省略)●%で
あることに加え,ミュニック社商品の広告宣伝活動の中で,被告商品が取り上げら
れた程度や被告商品の広告宣伝のみに要した額を確定し得る証拠はない考慮
し,被告商品に係る費用の額は,全体の●(省略)●円の15%に当たる●(省略)
●円と認められる。
(c) 運賃については,前記(a)において考慮したものと同様の事情のほか,輸入
に要した費用の場合と比較して,国内の運送保管費の場合には,販売されなかった
商品に係る費用の占める割合が少ないと考えられることも考慮し,被告商品に係る
費用の額は,全体の●(省略)●円の20%に当たる●(省略)●円と認められる。
(d) 荷造包装費については,前記(c)において考慮したものと同様の事情を考慮
し,全体の●(省略)●円の20%に当たる●(省略)●円と認められる。
(e) 保険料のうち,火災保険料,損害保険料,輸入保険料として支出された●
(省略)●円については,前記イ(サ)において認定した,毎回の保険料が定額でない
ことや対象となる商品数の記載が帳簿に示されていることなどの事情を踏まえれば,
輸入販売数量によって変動するものとして控除すべき経費と考えられ,被告商品に
係る費用の額は,前記(a)において考慮したものと同様の事情を考慮し,上記金額の
15%に当たる●(省略)●円と認められる。
c その他の費用については,次のとおり,被告商品の輸入販売に直接関連して
追加的に必要となった経費とはいえず,売上高から控除すべき経費には当たらない。
(a) 前記イ(ケ)の販売手数料は,百貨店のミュニック社商品の売り場へのミュニ
ック社商品販売員派遣に関する人件費や交通費といった費用(乙78,弁論の全趣
旨),ミュニック社商品の販売活動等に関する業務委託先への報酬額(乙27,弁論
の全趣旨)であるが,これらの費用と被告商品の販売との関連性などは明らかでは
なく,いずれも,被告商品の輸入販売に直接関連する経費とはいえない。
(b) 前記イ(サ)の保険料のうち,前記b(e)でその一部を控除すべき経費と認めた
火災保険料等を除くもの,すなわち傷害保険料は,海外出張費に付随する費用であ
り,後記(c)のとおり,海外出張費は控除すべき経費に該当しないことからすれば,
同様に控除すべき経費には該当しないものというべきである。
(c) 前記イ(シ)の旅費交通費のうち,交通費及び国内出張費は,その支出と被告
商品の販売との関連性について具体的な主張立証はなく,控除すべき経費には該当
しない。海外出張費については,被告が提出する出張報告書等(乙28)によって
も,これらの海外出張が特に被告商品の輸入販売のために必要となった認め
るに足りず,被告商品の輸入販売に直接関連して追加的に必要となった経費とはい
えない。
(d) 前記イ(ス)の見本費については,サンプル商品や書籍の購入が被告商品に関
するものであることの具体的な主張立証はなく,被告商品の輸入販売に直接関連す
る経費とはいえない。
(e) 前記イ(セ)の雑損失は,為替予約を解約した際に発生した費用であり,その性質からしても,被告商品の輸入販売に直接関連する経費とはいえない。\n
(f) 前記イ(ソ)の特別損失のうち,恵比寿三越伊勢丹に支払った撤退違約金,撤
退費用,営業担当者の特別退職金については,販売不振からミュニック社商品の恵
比寿三越伊勢丹での販売を終了したことによって発生したものにすぎないし,恵比
寿店舗費用等についてはこの発生原因や被告商品との関連性について具体的な裏付
けはないのであって,いずれも,被告商品の輸入販売に直接関連する経費とはいえ
ない。
(ウ) 限界利益の額
以上によれば,対象期間における被告商品の輸入販売により,被告が受けた限界
利益の額は,前記(ア)の被告商品の売上高●(省略)●円から,前記(イ)aの被告商
品の仕入額●(省略)●円及び同bのその他の控除すべき経費●(省略)●円を控
除した583万0211円である。
(3) 推定覆滅事由について
ア 証拠(甲68〜77,183〜186)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,
自社の商品を,主に靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売
し,その小売価格は2000円から6000円程度の商品が中心であり,原告が,
対象期間中に原告各商標と同一ないし類似する商標を付したスニーカー(甲183)
を販売した際の売上げは一足当たり3000円程度であったと認められる。
他方で,証拠(乙19)及び弁論の全趣旨によれば,被告商品は主に百貨店等の
店頭で販売されたものであり,別紙3被告商品販売一覧表記載のとおり,その小売価格は1万5000円から2万1000円,被告が百貨店等に販売する際の卸売価\n格は●(省略)●円から●(省略)●円であったと認められる。
被告商品の販売による一足平均の限界利益は前記(2)エ(ウ)で認定した583万0
211円を,前記(2)イ(ウ)で認定した販売数量である●(省略)●足で除した●
(省略)●円であり,原告が販売した競合品の一足当たりの限界利益を裏付ける証
拠はないが,上記の原告が販売した競合品の価格自体や,被告商品における一足当
たりの売上額が原告による競合品よりも大幅に高かったことからすれば,販売され
た商品一足当たりの限界利益についても,被告商品の方が原告の商品よりも大きか
ったものと推認される。
このような販売態様や販売価格の違い及び一足当たりの限界利益の違いは,被告
の限界利益額の一部について,商標法38条2項の推定を覆滅すべき事情として考
慮すべきである。
イ 他方で,被告が主張するその他の事情については,以下のとおり,いずれも
商標法38条2項の推定覆滅事情として考慮すべき事情とはいえない。
(ア) 原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことについて
被告は,原告が販売していた商品の多くには,原告各商標と同一又は類似の標章
が付されておらず,被告商品の販売によって,原告の売上げが減少したという関係
にないと主張する。
原告は,原告各商標と同一又は類似する標章を使用したスニーカーを販売してお
り,被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益が得られたであろう
という事情が原告に認められることは前記(1)のとおりであり,原告が上記のスニー
カー以外に原告各商標と類似する標章が付されていない靴を販売していたとの事情
は,損害額の推定を覆滅すべき事情に当たるとも認められない。
(イ) 競合品の存在について
被告は,側面に「X」型十字が付された大人用スニーカーは,被告商品の他にも市場に多数存在していると主張するが,証拠(乙1)によれば,被告が他のスニー\nカーに付されていると指摘する「X」型十字は,その形状が被告各標章や原告各商標とは大きく異なるものであり,その他,原告各商標と同一又は類似の標章が付さ\nれた原告又は被告以外によるスニーカーの存在とそのシェアについての具体的な主
張立証はないから,この点も損害額の推定を覆滅すべき事情には当たらない。
(ウ) 被告の営業努力,ブランド力の差等について
被告は,被告商品を販売するための営業努力,原告と被告とのブランド力の差,
原告各商標の訴求力の程度等からすれば,原告各商標の被告商品の売上げへの寄与
率は著しく低いとも主張するが,被告が作成した展示会の資料においてもミュニッ
ク社商品については「2014年日本デビュー」との記載がされており,被告が前
記(2)イ(キ)のように被告が広告宣伝活動を行った考慮しても,対象期間中に
おける日本においてのブランドの知名度の程度を裏付ける証拠はなく,他方で,証
拠(甲170〜176,180〜182)及び弁論の全趣旨によれば,原告各商標
に関する販売,広告宣伝状況については,平成14年頃から原告各商標と同一又は
類似の標章が付されたスニーカーが原告が許諾した業者によって販売されており,
有名歌手がこれを着用した雑誌広告が掲載されたこともあったとの事情も認められ,
これらの点からすれば,上記の被告の主張する各点をもって,推定覆滅事情に当た
るとは認められない。
ウ 前記ア及びイで検討した事情によれば,被告商品の輸入販売による原告の損
害については,商標法38条2項の推定を覆滅すべき事情が認められ,その覆滅割
合は2割と認めるのが相当である。
(4) 損害額についてのまとめ
以上によれば,被告商品の輸入販売による原告各商標権侵害について,商標法3
8条2項に基づく原告の損害額は,被告の限界利益である583万0211円の8
割に相当する466万4168円であると認められる。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.11.11
平成28(ワ)35157 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月24日 東京地方裁判所
しかして,前記第2のとおり,原告は,特許第5177317号(本件特 許権1)に基づく請求と,同第5610056号(本件特許権2)に基づく 請求をするところ,両請求の関係は,選択的併合の関係にあるものと解され る。そして,原告は,いずれの請求についても,損害額として,特許法10 2条2項により算定される損害額,弁護士費用相当額及びこれらに対する遅 延損害金を主張するものであるから,仮に本件特許権2の侵害が認められる 場合であっても,本件特許権1の侵害により算定される損害額と,本件特許 権2の侵害により算定される損害額とは,同一の額となるというべきである。 そうすると,本件特許権1の侵害による損害額の算定を行ったものが,原 告の請求の一部認容となる場合も,上記損害額が,仮に被告らの輸入販売等 の行為が本件特許権2を侵害するものであった場合の同侵害による損害額を 下回るものとは認められないものと考えられるから,本件特許権2の侵害や 損害額について判断するまでもなく,本件特許権1の侵害による損害額を, 原告の被った損害としてそのまま認容すべきこととなる。 そこで,原告の損害額として,本件特許権1の侵害による損害額について 検討する。
特許法102条2項により算定される損害額
ア 前記前提条件(4)(5)のとおり ,被告LEDは被告製品に搭載されて販 売されたものであるところ,被告LEDの主な用途は写真撮影時のフラッ シュライトであるが,被告らが販売している被告製品以外の機種にはかか るフラッシュライトの性能を特長にしたスマートフォンもあること(甲5),被告製品はデザインを重視し,機能\をシンプルなものにした製品として紹介・宣伝されており,被告製品の紹介や宣伝の中ではLEDライト の性能等について一切触れられておらず,被告製品の基本スペックとしてもLEDライトは挙げられていないこと(甲5,6の1,7)などの各事\n実がそれぞれ認められる。これらによれば,被告LEDについては,被告 製品の主要な特長として位置付けられているとは認められず,このような 被告LEDにつき被告製品の主要部として特に強い顧客吸引力があるとい うことは困難というべきである。 そして,前記前提条件(4)のとおり被告製品の販売による利益額は、被 告HTCについては●(省略)●円,被告兼松については●(省略)●円 であるところ,被告製品の市場想定価格は●(省略)●円(税別)である こと(甲7),被告製品自体の製造コストは明らかでないものの,被告製 品が発売された平成27年10月時点で既に販売されていた他のメーカー のスマートフォンについては,利益率は60%前後であるとされているこ と(乙52),他方,HTC台湾に被告製品を納入したメーカーが被告L EDを仕入れた価格は1個●(省略)●米ドルであったこと(乙47)が それぞれ認められる。
これらの事実からすれば,被告製品の製造コストは約●(省略)●円 (≒●(省略)●円×〔1−0.6〕)となり,これを被告製品が発売さ れた平成27年10月の平均の為替レート120.16円/米ドルで換算 すると,約●(省略)●米ドル(≒●(省略)●円÷120.16円/米 ドル)となるから,被告製品の製造コストに占める被告LEDの仕入価格 の割合は,約●(省略)●%(≒●(省略)●×100)となる。なお, 証拠(甲50)によると,50種類の単色LEDが1個約700円ないし 900円でインターネット販売されていることが認められるが,これらの 単色LEDは,砲弾型のものや複数のLEDチップが実装されたものであ るなど,被告LEDと同じ構成のものであるか明らかでないから,損害額を算定するに当たって事情として考慮するのは相当とはいえない。\n以上を総合すれば,被告LEDの販売による利益額は,被告HTCにつ いては●(省略)●円(≒●(省略)●円×0.25%),被告兼松につ いては●(省略)●円(≒●(省略)●円×0.25%)と認めるのが相 当である。
イ これに対し,原告は,被告製品1台当たりにおける被告LEDによる利 益額は100円を下回らない旨主張する。 しかしながら,前記前提条件(4)によれば 被告製品の販売による利益額 は,被告HTCについては1台当たり約●(省略)●円(≒●(省略)● 円÷●(省略)●台),被告兼松については1台当たり約●(省略)●円 (≒●(省略)●円÷●(省略)●台)となるところ,被告LEDによる 利益額を1台当たり100円とすれば,その割合は,前者との関係では約 ●(省略)●%,後者との関係では約●(省略)●%となるのであって, 上記アに説示した被告製品における被告LEDの位置付けや顧客誘引力に 照らすと,いずれの割合も相当とは認め難いから,原告の上記主張は採用 できない。
ウ 以上によれば,被告HTCに対する特許法102条2項による損害金の 額は,●(省略)●円と,被告兼松に対する特許法102条2項による損 害金の額は,●(省略)●円とそれぞれ認められる。
・・・
(3) 推定覆滅事由について
ア 証拠(甲68〜77,183〜186)及び弁論の全趣旨によれば,原告は, 自社の商品を,主に靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売 し,その小売価格は2000円から6000円程度の商品が中心であり,原告が, 対象期間中に原告各商標と同一ないし類似する商標を付したスニーカー(甲183) を販売した際の売上げは一足当たり3000円程度であったと認められる。 他方で,証拠(乙19)及び弁論の全趣旨によれば,被告商品は主に百貨店等の 店頭で販売されたものであり,別紙3被告商品販売一覧表記載のとおり,その小売\n価格は1万5000円から2万1000円,被告が百貨店等に販売する際の卸売価 格は●(省略)●円から●(省略)●円であったと認められる。 被告商品の販売による一足平均の限界利益は前記(2)エ(ウ)で認定した583万0 211円を,前記(2)イ(ウ)で認定した販売数量である●(省略)●足で除した● (省略)●円であり,原告が販売した競合品の一足当たりの限界利益を裏付ける証 拠はないが,上記の原告が販売した競合品の価格自体や,被告商品における一足当 たりの売上額が原告による競合品よりも大幅に高かったことからすれば,販売され た商品一足当たりの限界利益についても,被告商品の方が原告の商品よりも大きか ったものと推認される。 このような販売態様や販売価格の違い及び一足当たりの限界利益の違いは,被告 の限界利益額の一部について,商標法38条2項の推定を覆滅すべき事情として考 慮すべきである。
イ 他方で,被告が主張するその他の事情については,以下のとおり,いずれも 商標法38条2項の推定覆滅事情として考慮すべき事情とはいえない。 (ア) 原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことについて 被告は,原告が販売していた商品の多くには,原告各商標と同一又は類似の標章 が付されておらず,被告商品の販売によって,原告の売上げが減少したという関係 にないと主張する。
原告は,原告各商標と同一又は類似する標章を使用したスニーカーを販売してお り,被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益が得られたであろう という事情が原告に認められることは前記(1)のとおりであり,原告が上記のスニー カー以外に原告各商標と類似する標章が付されていない靴を販売していたとの事情 は,損害額の推定を覆滅すべき事情に当たるとも認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.11.10
令和2(ネ)10034 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和2年11月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
2 争点1(控訴人表示が,控訴人の商品等表\示として需要者の間に広く認識 されているか)について
(1)ア 前記1のとおり,控訴人は,中小企業等協同組合法に基づいて設立さ れた事業協同組合であり,その組合員の資格は,前記1(1)アで認定した控訴人の 地区内の中小規模の事業者に限られ,一方,被控訴人も中小企業等協同組合法に基 づいて設立された事業協同組合であり,その組合員の資格は,前記1(2)で認定し た被控訴人の地区内の中小規模の事業者に限られる。 また,控訴人の事業内容は,前記1(1)アのとおり,高速道路割引ETCカード 事業,各種備品や消耗品,車両燃料等の共同購買事業,外国人実習生受入事業等で あるから,控訴人に加入する可能性のある事業者は,これらの事業に関心のある事\n業者であると認められ,一方,被控訴人の事業は,前記1(2)のとおり,高速道路 割引ETCカード事業,車両燃料等の共同購買事業,情報提供事業等であるから, 被控訴人に加入する可能性のある事業者は,これらの事業に関心のある事業者であ\nると認められる。 したがって,控訴人に加入する可能性のある事業者のうち被控訴人のそれと重な\nる事業者は,前記1(1)アで認定した控訴人の地区のうち北海道を除く25の都府 県内の中小規模の事業者であると認められる。
イ 不正競争防止法2条1項1号にいう「営業」は,取引社会における事 業活動と評価できるものを指す(最高裁平成17年(受)第575号同18年1月 20日第二小法廷判決・民集60巻1号137頁)ところ,本件においては,控訴 人及び被控訴人が行う上記1(1),(2)の各事業は,上記「営業」ということができ るものである。そして,控訴人の事業の需要者には,控訴人の組合員となって控訴 人の上記1(1)アの事業を行う可能性のある上記アの事業者及び同事業の取引の相\n手方となる可能性のある者を含むというべきであり,その範囲は,かなり広く,被\n控訴人の事業者と重なる範囲もかなり広いということができる。
ウ 前記1(1)アのとおり,控訴人の組合員数は342事業者あるいは2 94事業者であるが,この数は,上記の需要者の範囲からすると極めて僅かなもの であるといえる。また,控訴人の事業に関する取引高等の控訴人の事業規模を示す 証拠は提出されていないが,控訴人の上記の組合員数からすると,その規模も小さ いものと推認される。
また,前記1(1)イのとおり,控訴人が行っている宣伝,広告は,ホームページ の開設,パンフレットの交付によっており,上記の方法のほか,千葉信用金庫及び 商工中金に紹介してもらう方法も用いているが,これら以外の方法で宣伝,広告を していることを認めるに足る的確な証拠はないことからすると,控訴人の宣伝,広 告の規模,程度は極めて小さなものであり,また,その効果も極めて小さいもので あるというべきである。 以上からすると,控訴人が,平成6年3月から,自己の名称として,控訴人表示\n又は「関東ビジネスサポート」の表示を使用していることを考慮しても,控訴人表\ 示が控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていると認めることはで\nきない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,組合員が多種多様な業種で構成されていることから,控訴人\n表示は多様な業界で周知となっていると主張するが,前記1(1)アのとおり,控訴 人の組合員数は342事業者あるいは294事業者であり,この数は多種多様な業 種の事業者の数からすると極めて僅かな数であるから,控訴人表示が多様な業界で\n周知となっているとは認められない。
イ 控訴人は,同業の事業協同組合で構成された互助団体に加入し,中心的\nな活動を行っていること(甲20)から,控訴人表示は周知となっていると主張す\nる。 しかし,控訴人が上記の互助団体においていかなる活動を行っているのか,また, どのような成果を挙げたか等についての証拠はないことを考慮すると,控訴人の上 記主張事実から,控訴人表示が周知となったと認めることはできない。\n
ウ 控訴人は,控訴人表示の需要者は,高速道路を業に伴って頻繁に利用し,\n長距離移動を日常的に行い,利用料金の割引を受けようとする事業者に限定される と主張する。 しかし,控訴人の事業の需要者は,前記(1)イ認定のとおりであって,高速道路 割引ETCカード事業にのみ関心のある事業者だけであると認めることはできない。
エ 控訴人は,商工中金等の金融機関がその顧客に控訴人を紹介していると ころ,このことは,控訴人の信用度が高く,控訴人の名称が浸透していることを示 していると主張する。 しかし,仮に,控訴人の商工中金等に対する信用度が高いとしても,そのことか ら直ちに控訴人表示が周知であると認めることはできず,控訴人の上記主張は理由\nがない。
オ 控訴人は,控訴人と被控訴人との間で混同が生じていると主張し,その 具体例として,1)控訴人の顧客会社に被控訴人から電話勧誘があり,同顧客会社は, 被控訴人を控訴人と勘違いしたこと,2)控訴人の同業の事業協同組合から,その組 合員に控訴人から執拗な電話勧誘があったとの苦情が申し立てられたが,上記の電\n話勧誘は被控訴人によるものであるのに控訴人によるものと勘違いをしていたこと, 3)被控訴人に対する苦情を控訴人に申し立ててきた事業者がいたこと,4)控訴人を 被控訴人であると間違えて,控訴人に電話がかかってきたこと(以上につき,甲 8),5)被控訴人にすべき振込みを間違えて控訴人にしてきたこと(甲32),6)被 控訴人の組合員から,控訴人を被控訴人と間違えて,問合せの電話がかかってきた こと,7)控訴人が依頼している業者が,被控訴人のホームページを控訴人のものと 混同したこと(甲33)などを指摘する。 しかし,5),6)については,被控訴人の取引先や組合員が相手を間違えたという にすぎず,また,1),7)については,控訴人の取引先が相手を間違えたというにす ぎず,いずれも,控訴人表示が周知であることの根拠になるものということはでき\nない。 また,2)〜4)については,これらの事実があるとしても,そのことから,直ちに 控訴人表示の周知性を推認させるということはできない。\nしたがって,控訴人の上記主張は理由がない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和1(ワ)14303
1審は下記のように前置きをして、判断しています。
「法人の名称は,法人の事業又は営業全体を表す点で,個別の商品\nや役務を表す商標と区別されるものであって,当該事業又は営業との関係で\nみて一般的名称といえる性質を有するものもあり得るところ,そのような法
人の名称は,自他識別力を欠くか,自他識別力が極めて弱いものというべき
20 であるから,当該名称の使用の時期が相当程度に長くその浸透度も極めて大
きいことなどから商品等表示該当性を獲得したといえるなどの事情がない限\nり,それが法人の営業等を表示するものとして需要者の間に広く認識される\nに至っているものと認めて周知性を肯定することは,極めて困難といわなけ
ればならない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.11. 4
令和1(行ケ)10137 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年10月28日 知的財産高等裁判所
原告らは,本件審判において,主引用例である甲1に記載された発明と して「シクロオキシゲナーゼ−2阻害剤としてヒトに経口投与される,3 00mgのセレコキシブを含む経口投与用カプセル」の発明を主張し,当 事者双方は,発明の目的を発明特定事項に含めることについて議論してい なかったが,審判合議体は,本件審決において,審理の過程で当事者が一 切主張しなかった目的を発明特定事項に含む甲1発明を認定し,この認定 について原告らに反論の機会を与えることなく,本件発明1と甲1発明と の相違点に係る容易想到性の判断をし,甲1発明を主引用例とする進歩性 欠如の無効理由は理由がないと判断したものであり,このような審理は, 原告らにとって不意打ちであり,原告らの手続保障を著しく欠くものであ るから,本件審決には審理不尽の手続違背がある旨主張する。
しかしながら,審判合議体が審決で認定する主引用例記載の引用発明の 内容と請求人の主張する引用発明の内容とが異なる場合において,当事者 対し,事前に審決で認定する引用発明の内容を通知し,これに対する意見 を申し立てる機会を与えるかどうかは,審判合議体の審判指揮の裁量に委\nねられていると解されるから,このような機会を与えなかったからといっ て直ちに審判手続に手続違背の違法があるということはできない。 また,原告らの主張する甲1に記載された発明と本件発明1との相違点 は,本件審決が認定した甲1発明と本件発明1との相違点1−1及び1− 2と異なるものではないから,審判合議体が本件審決認定の甲1発明を引 用発明として認定した上で,本件発明1の進歩性について判断をしたこと が,原告らにとって不意打ちであるとはいえず,上記裁量の範囲を逸脱し たということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2020.10.29
令和1(行ケ)10126 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年10月22日 知的財産高等裁判所
正規状態での施工の利点(上記(2)ア)及び2枚目クランプ状態での施工の 問題点(同イ)にかんがみると,甲1発明において,400mmの場合に2 枚目クランプ状態で施工すると,地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には施 工不能となるおそれがあるから,正規状態での施工が可能\になるように構成\nすることを当業者は動機付けられるといえる。 ここで,600mm用のチャック装置のままで400mmの鋼矢板を正規 状態で施工すると,チャック装置が大きすぎるために干渉問題が生じる(上 記(2)ウ)。この干渉問題を解決するために,上記(3)の周知事項を適用して, 必要に応じて圧入機に仕様変更を加えつつ,600mm用のチャック装置よ りも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm用のチャック装置を備え\nる一体型チャックフレームに交換することにより,あるいは,600mm用 の着脱式チャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm\n用の着脱式チャック装置に交換することにより,400mmの場合でも正規 状態での施工が可能になるように構\成することは,当業者が容易に想到し得 たことといえる。
なお,本件特許の明細書の【0027】には,従来技術の説明として,溶 接事項記載に相当する記載があるが,溶接の工程にはそれなりの手間や費用 を要する上に,溶接した鋼矢板は,その再利用にも支障が生じ得ることなど を踏まえると,鋼矢板の溶接は,あくまでも次善の策にすぎず,当業者とし ては,より抜本的な解決策の採用に向けて動機付けられるであろうことは否 定できない。そうすると,溶接事項記載の存在により,相違点に係る本件発 明1の構成を採用することが阻害されるとはいえない。\n
2 第2次審決(甲7−1)との関係について
なお,甲7の1,2によれば,本件審判手続と第2次審決に係る無効審判手 続とでは,類似の無効理由が主張されていたことが認められるので,第2次審 決との抵触等が問題にならないではないが,同証拠によれば,両者で主張され た無効理由は,主引例が異なる上に,その根拠として提出された証拠にも違い があることが認められるから,本件において,原告が,甲1発明に基づく進歩 性欠如を主張することが,第2次審決の効力に違反するものではないし,また, その主張が既に決着済みの問題を蒸し返すものであって信義則に違反するとま で認めるに足りる証拠もない。
◆判決本文
1次判決はこちら
◆平成28(行ケ)10161
2次判決はこちら
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2020.10.29
令和1(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年10月22日 知的財産高等裁判所(3部)
本件訂正発明1と甲1発明の相違点の認定の誤りについて
ア 甲1の【0016】には,「図1にホットプレスにより作製したターゲッ トの断面組織写真を示す。これによれば,微細な黒い点(SiO2)が均質 に分布しているのが観察され,・・・以上の結果より,このターゲット組織は SiO2がCo−Cr−Ta合金中に分散した微細混合相からなっている ことがわかった。」との記載があるから,甲1の図1の黒い点はSiO2と 認められる。そして,甲1の図1によれば,SiO2の黒い点は粒子状をな しており,いずれも半径2µmの仮想円よりも小さいと認められる。したが って,甲1の図1のSiO2粒子はいずれも,SiO2粒子内の任意の点を 中心に形成した半径2µmの全ての仮想円よりも小さいと認められ,形状2 の粒子の存在を確認することはできないから,本件訂正発明1が必ず形状 2を含むのに対し,甲1発明においては,形状2の粒子を含むのか否かが 一見して明らかではないと認められる。
前訴判決は,審決を取り消す前提として,甲1発明の図1の全ての粒子 は形状1であると認定しており(甲30,61頁),この点について拘束力 が生じているものと認められ,この点からしても,本件訂正発明1が必ず 形状2を含むのに対し,甲1発明においては,形状2の粒子を含むのか否 かが一見して明らかではないということができる。 そうすると,本件訂正発明1が形状2の粒子を含むのに対し甲1発明に おいて形状2の粒子を含むのか否かが一見して明らかでないとの本件審 決の相違点(相違点2)の認定に誤りはないものと認められる。 イ(ア) この点につき,原告は,甲3に記載された再現実験は,甲1の実施 例1の再現実験であり,甲3で確認される非磁性材料粒子の組織は,甲 1の実施例1の組織と同じであるとして,甲3の断面組織写真である図 6の画面右下には形状2の粒子が存在するから(甲47),本件訂正発明 1と同じく,甲1発明にも形状2の粒子が存在するということができ, 形状2の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点をもって,本件 訂正発明1と甲1発明の相違点ということはできないと主張する。
(イ) 前記2(2)アのとおり,メカニカルアロイングは,高エネルギー型ボ ールミルを用いて,異種粉末混合物と硬質ボールを密閉容器に挿入し, 機械的エネルギーを与えて,金属,セラミックス,ポリマー中に金属や, セラミックスなどを超微細分散化,混合化,合金化,アモルファス化さ せる手法で,セラミックス粒子を金属マトリクス内に微細に分散させる ことを可能とするものであり,このようなメカニカルアロイングの仕組\nみに照らすと,メカニカルアロイングにおいては,ボールミルのボール の衝突により異種粉末混合物にどのような力が加えられるかにより,生 成物の組織が異なってくるものと認められる。また,甲52に「一般に 粉末のミリング時には衝撃,剪断,摩擦,圧縮あるいはそれらの混合し たきわめて多様な力が作用するがメカニカルアロイングにおいて最も重 要なものはミリング媒体の硬質球の衝突における衝撃力とされている。 衝撃圧縮により粉末粒子は鍛造変形を受け加工硬化し,破砕され薄片化 する。・・・薄片化および新生金属面の形成に加え,新生面の冷間圧接およ びたたみ込みが重なるいわゆる Kneading 効果により,次第に微細に混 じり合い,ついには光学顕微鏡程度では成分の見分けがつかないほどに なってしまう。」(前記2(1)オ)との記載があることからすると,メカニ カルアロイングにおいて最も重要なものはミリング媒体の硬質球の衝突 における衝撃力であると認められる。そうすると,ボールミルのボール の材質や大きさ,ボールミルの回転速度等の条件が異なれば,メカニカ ルアロイングによって得られる粉末の物性は異なり,そのような粉末か ら得られるスパッタリングターゲットの研磨面で観察される組織の形態 も異なると認められる。 そうであるとすれば,少なくともボールミルのボールの材質や大きさ, ボールミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件が明らかにされな ければ,どのような組織の生成物ができるかが明らかにならないものと いうべきである。 そこで本件についてみると,甲1には,甲1発明のスパッタリングタ ーゲットを製造する際の,ボールミルのボールの材質や大きさ,ボール ミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件についての記載はなく, 甲3のメカニカルアロイングの条件が,甲1発明のスパッタリングター ゲットを製造する際のメカニカルアロイングの条件と同じであったとい う根拠はない。そうすると,甲3に記載されたスパッタリングターゲッ トが形状2の粒子を含んでいたとしても,このことのみから,甲1発明 のスパッタリングターゲットも形状2の粒子を含むということはできな い。そして,その他に,甲1発明のスパッタリングターゲットが形状2 の粒子を含むことを認めるに足りる証拠はない。
・・・
(2) 本件訂正発明1〜6の進歩性についての判断の誤りについて
ア 本件訂正発明1と甲1発明の相違点2,本件訂正発明2と甲1発明の相 違点2’の容易想到性について検討する。 甲1発明は,ハードディスク用の酸化物分散型 Co 系合金スパッタリン グターゲット及びその製造方法に関する発明であり(【0001】【産業上 の利用分野】),発明の目的は,保磁力に優れ,媒体ノイズの少ない Co 系合 金磁性膜をスパッタリング法によって形成するために,結晶組織が合金相 とセラミックス相が均質に分散した微細混合相であるスパッタリングタ ーゲット及びその製造方法を提供することにある(【0009】【発明が解 決しようとする課題】)。そして,発明者らは,Co 系合金磁性膜の結晶粒界 に非磁性相を均質に分散させれば,保磁力の向上とノイズの低減が改善さ れた Co 系合金磁性膜が得られることから,そのような磁性膜を得るため には,使用されるスパッタリングターゲットの結晶組織が合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相であればよいことに着目し,セラミ ックス相として酸化物が均質に分散した Co 系合金磁性膜を製造する方法 について研究し,甲1記載の発明を発明した(【0010】【課題を解決す るための手段】)。そして,甲1には,急冷凝固法で作製した Co 系合金粉末 と酸化物とをメカニカルアロイングすると,酸化物が Co 系合金粉末中に 均質に分散した組織を有する複合合金粉末が得られ,この粉末をモールド に入れてホットプレスすると非常に均質な酸化物分散型 Co 系合金ターゲ ットが製造できる(【0013】(課題を解決するための手段))と記載され ており,甲1発明のスパッタリングターゲットは,アトマイズ粉末とSi O2粉末を混合した後メカニカルアロイングを行い,その後のホットプレ スにより製造されたものであり,SiO2が Co−Cr−Ta 合金中に分散した 微細混合相からなる組織を有する(【0015】,【0016】(実施例1))。 他方,メカニカルアロイングについては,本件特許の優先日当時,前記 2(2)記載の技術常識が存在したと認められ,当業者は,甲1発明のスパッ タリングターゲットを製造する際も,原料粉末粒子が圧縮,圧延により扁 平化する段階(第一段階),ニーディングが繰り返され,ラメラ組織が発達 する段階(第二段階),結晶粒が微細化され,酸化物などの分散粒子を含む 場合は,酸化物粒子が取り込まれ,均一微細分散が達成される段階(第三 段階)の三段階で,メカニカルアロイングが進行すること自体は理解して いたものと解される。
そして,メカニカルアロイングが上記第一ないし第三の段階を踏んで進 行することからすると,メカニカルアロイングが途中の段階,例えば,第 二段階では,ラメラ組織が発達し,形状2の粒子も存在するものと考えら れ,甲49(実験成績報告書「甲3の混合過程で形状2の非磁性材料粒子 が存在すること(1)」)及び甲50(実験成績報告書「甲3の混合過程で 形状2の非磁性材料粒子が存在すること(2)」)も,メカニカルアロイン グの途中の段階においては,形状2の粒子が存在することを示している。 しかし,甲1には,形状2のSiO2粒子について,記載も示唆もされて いない。むしろ,本件特許の優先日当時のメカニカルアロイングについて の前記技術常識(前記2(2))に照らすと,メカニカルアロイングは,セラ ミックス粒子等を金属マトリクス内に微細に分散させるための技術であ り,第二段階は進行の過程にとどまり,均一微細分散が達成される第三段 階に至ってメカニカルアロイングが完了すると認識されていたものと推 認されるところであり,前記2(1)の技術文献の記載に照らして,メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることが想定されていたとは 認められない。メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階までで終 了することについて,甲1には何ら記載も示唆もされておらず,その他に, これを示唆するものは認められない。むしろ,甲1には,合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相である結晶組織を得ることが,課題 を解決するための手段として書かれており,セラミックス相が均質に分散 した微細混合相を得るためには,均一微細分散が達成される第三段階まで メカニカルアロイングを進めることが必要であるから,甲1は,メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることを阻害するものと認め られる。
そうすると,当業者は,メカニカルアロイングについて前記2(2)記載の 技術常識を有していたものではあるが,甲1発明のスパッタリングターゲ ットを製造する際に,メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階ま でで終了することにより,SiO2粒子の形状を形状2(形状2’)の粒子 を含むようにすることを動機付けられることはなかったというべきであ る。 したがって,相違点2及び相違点2’に係る事項は,当業者が容易に想 到し得たものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2020.10.29
令和2(ワ)1667 著作権侵害損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年10月23日 東京地方裁判所
証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば,本件サイトには本件各写真を含 め多数の写真が掲載されており,これらの写真は,「写真の著作物」(著作権 法10条1項8号)又はそれに該当し得るものであったと認めることができ る。そして,被告は,本件各写真を含めた写真をインターネット上で公開す る以上,その著作権又は著作者人格権を侵害していないことについて調査, 確認する義務があったといえる。ところが被告は,本件各写真が著作権,著 作者人格権を侵害していないかについて調査,確認をせずに本件各写真をイ ンターネット上に公開して公衆送信等しており,被告には,少なくとも過失 があったといえる。
(2) 被告は,本件サイト売買を行ったウェブサイトには,「買い手は基本的に 著作権に触れているかどうか把握することは難しい」,「一般的には損害賠償 請求等は,サイトを売った人と著作権違反の警告を出した人の間で行われる」 との記載があり,サイト売買の通例では買い手である被告には損害賠償の支 払義務がなく,また,被告が本件サイトを購入した平成28年2月1日時点 で,掲載されている画像は3万8000点以上にも及び,これらの著作権の 有無を確認するのは実質的に不可能であり,被告には調査義務はないと主張\nする。 しかし,他人の写真を利用する場合にはその著作権又は著作者人格権を侵 害する可能性があるから,被告は,本件各写真を公衆送信等する以上,前記\nの調査,確認をする義務があったといえる。被告が指摘する記載等がウェブ サイトにあったことや本件サイトに多数の写真が掲載されていたことなど被 告が指摘する事情によってこのことは左右されず,被告の上記主張は採用す ることはできない。なお,被告が本件サイト売買を行ったウェブサイトには, 「サイト購入時,著作権には注意すること」,「サイトを購入する時あるいは 売却する時もそうですが,著作権が問題となってトラブルになることがあり ます。使用されている文章や画像,イラスト,アイディアが他の人のマネを していることがあります。」などと記載され(乙1),サイト売買の対象とな るウェブサイトには著作権法上の問題があるものが含まれ得ることが明記さ れていた。
3 争点(5)(損害額)について
(1) 公衆送信権侵害について
ア 証拠(甲7)によれば,協同組合日本写真家ユニオン作成の使用料規程 である本件規程は,同組合が管理の委託を受けた写真の著作物の利用にか かわる使用料を定めるものであり,一般利用目的(宣伝広告を目的とせず, 記事と共に,事柄を説明するために写真の著作物を利用する場合)でウェ ブページの最初のページ以降のページに写真を掲載する使用料は,12か 月以内で2万5000円,1年を超える場合の次年度以降の使用料は1年 当たり1万円とされている。 原告は結婚式における写真撮影を業とするカメラマンであり,本件各写 真は,原告が,依頼を受けて結婚式場において撮影したものであり(前記 前提事実(1)ア,同(2)),カメラマンである原告が業務により作成したもの といえる。そうすると,原告が本件各写真の著作権の行使につき受けるべ き金銭の額に相当する額(著作権法114条3項)の算定に当たっては, 本件規程の内容を参酌するのが相当である。そして,本件規程の内容に加 えて,被告が遅くとも平成30年12月5日頃までには本件各写真の原告 の公衆送信権(著作権法23条1項)を侵害したこと,本件各写真は令和 2年2月17日に本件各ページから削除されたことその他の本件各写真の 使用態様等に鑑みれば,原告が本件各写真の公衆送信につき受けるべき金 銭の額(著作権法114条3項)は,本件各写真1枚当たり4万円と認め るのが相当である。
イ この点について,原告は,1)撮影した写真1枚当たり8万円で売却して おり(甲6),本件のような長期間の無断使用はその4倍が相当であるこ と,2)本件規程の商用広告目的の写真の使用料が12か月以内で5万円で あることを考慮して損害額を算定すべきであるなどと主張する。 しかしながら,「ご請求書」と題する甲6号証には,「広告写真使用料」 として8万円と記載されているが,当該写真がどのような写真か明らかで はない上に,この1件の利用許諾例の外に原告の写真の使用料を裏付ける 証拠は見当たらないことなどからすれば,本件各写真の使用料が1枚当た り8万円であると認めることはできず,他に原告の上記1)の主張を認める に足りる証拠はない。
また,本件規程の「商用広告目的」とは,「写真に写された物品等を宣 伝するために広告として利用する場合」をいうとされている(本件規程の 第3条)ところ,本件各写真は,結婚式に関係する文章が記載されるなど した本件各ページに掲載されたものであり(前記前提事実 ア,イ),い ずれも本件各写真に写された物品等を宣伝するために広告として本件各ペ ージに掲載されたものとはいえず,本件各写真の使用は,上記「商用広告 目的」には当たらず,原告の上記2)の主張も採用することはできない。したがって,原告の上記主張はいずれも採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2020.10.27
令和1(行ケ)10161 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年10月21日 知的財産高等裁判所
本件審決は,相違点の認定において,本件補正発明が,「ダンパを囲繞す る空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連である」点と,「想定される入力方向に 対して機能する向きに設置され」,「上記想定される入力方向に対し,二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部が設置され」る点とを分けて認定して\nいる。 しかし,本件補正発明は物の発明であること及び前記1で認定した本件明細書の 記載からすると,本件補正発明の,「想定される入力方向に対して機能する向きに設置され」,「上記想定される入力方向に対し,二つの上記剪断部の面内方向が傾斜す\nるように上記剪断部が設置され」との構成は,「端部の連結部を介して一連に設けられ」,「ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連である」二つの\n剪断部の形状について,いずれの剪断部も,想定される方向からの入力に対して機 能し,想定される入力方向に対し面内方向に傾斜するように設置できる形状であることを特定したものと解するのが相当であるから,本件補正発明の,「二つの剪断部\nが,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一連に設けられ」との構成,弾塑性履歴型ダンパが「想定される入力方向に対して機能\する向きに設置され」,「上記想定される入力方向に対し,二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部 が設置され」との構成及び「ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連である」との構\成は,いずれも,ダンパの形状を特定するものである。そして,これらの形状の構成は相互に関連して,ダンパが振動エネルギーを吸収する機序に影響を与えるものであるから,上記の各構\成を別個の相違点として,それぞれ独立に容易想到性の判断をするのは相当ではないというべきである。これに反する 被告の主張は理由がない。
(2) 相違点4’の容易想到性について
ア 前記2(1)で認定した引用文献1の記載からすると,引用発明1は,水平 方向の全方向からの震動エネルギを,X)成分とY成分に分担して極低降伏点鋼製パ ネルが塑性変形して吸収する制震パネルダンパであること,従来は,水平方向の全 方向からの震動エネルギを吸収するために,極低降伏点鋼製パネルの向きが直角と なるように二つのダンパをL字状やT字状に並べて配置していたところ,そのよう なダンパの配置方法では,それぞれのパネル毎に一対のエンドプレートを設置する ため,取り付けのためのスペースが大きくなり,また,取り付けのための手間がか かるという課題があり,同課題を解決するために,引用発明1−2は,ダンパの形 状を,平面視した場合に断面が中空の矩形になる四角柱状とし,これを一対のエン ドプレートの間に設置する構成にしたもの,引用発明1−1は,ダンパの形状を,平面視した場合に断面が互いに直交する十\字状としたものであり,それぞれこれを一対のエンドプレートの間に設置する構成にしたものであることが認められる。一方,本件補正発明の特許請求の範囲の「想定される入力方向に対して機能\する向きに設置される弾塑性履歴型ダンパであって」,「上記想定される入力方向に対し, 二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部が設置され」との記載及 び前記1で認定した本件明細書の記載によると,本件補正発明は,振動エネルギー の入力方向を想定し,特定の入力方向からの振動に対応するダンパであること,本 件補正発明の従来技術であるダンパは,剪断部を一つしか有していないために,地 震の際にいずれの方向から水平力の入力があるかは予測困難であるのに,一方向からの水平力に対してしか機能\せず,また,想定される入力方向に対して高精度にダンパの剪断変形方向を合わせる設置角度設定が必要であるという課題があったこと, 本件補正発明は,剪断部を二つ設け,これらを端部で連結させたことにより大きな 振動エネルギーを吸収できるようにし,また,向きの異なる二つの剪断部を想定さ れる入力方向に対し面内方向に傾斜するように設置できる形状とすることにより, 入力の許容範囲及び許容角度が広くなり,据付誤差を吸収することができるように したことが認められる。 このように,引用発明1は,水平方向の全方向からの震動エネルギーを吸収する ためのダンパであるのに対し,本件補正発明は,振動エネルギーの入力方向を想定 し,その想定される方向及びその方向に近い一定の範囲の方向からの振動エネルギ ーを吸収するためのダンパであり,両発明の技術的思想は大きく異なる。これに反 する被告の主張は理由がない。 そして,相違点4’に係る本件補正発明の構成は,上記のような技術的思想に基づくものであるから,引用発明1−2との実質的な相違点であり,それが設計事項\nにすぎないということはできない。
イ(ア) 前記2(2)で認定した引用文献2の記載からすると,引用文献2には, 本件審決が認定した引用発明2(前記第2の3(1)イ)が記載されているが,引用発 明2の略L字状に配置された二つの剪断パネル型ダンパー90の各パネル部は,端 部で連結されていないことが認められる。 引用発明1−2においては,各側面のパネルはすべて端部で隣接するパネルと連 結されているが,引用発明1−2のこの構成に代えて,引用発明1−2に,二つの剪断パネル型ダンパー90のパネル部を,端部を連結することなく,略L字状に配\n置するという引用発明2の上記構成を適用して,ダンパの断面形状をL字状とするなど2枚のパネルを端部で連結する構\成とすることの動機付けは認められない。
(イ) 前記2(3),(4)で認定した引用文献3,4の記載によると,塑性変形す る部材を用いて震動を吸収するダンパー部材において,塑性変形する部材の降伏強 度を調整するなどの目的で,穴又はスリットを設けることは,周知技術であること が認められるが,引用発明1−2にこの周知技術を適用したとしても,ダンパを囲 繞する空間と一連とはなるが,ダンパの断面形状をL字状とするなど2枚のパネル を端部で連結する構成となるものではない。
(ウ) その他,相違点4’に係る本件補正発明の構成を引用発明1−2に基づいて容易に想到することができたというべき事情は認められない。\n
(エ) 以上からすると,その余の点について判断するまでもなく,引用発明 1−2に基づいて本件補正発明を容易に発明することができたとは認められない。
(オ) なお,本件審決は,引用文献1には,断面が十字状や中空の矩形の形状の引用発明1のほか,断面が円状のダンパも記載されていることから,引用文献1\nにおける極低降伏点鋼パネルの数や配置及び交点の接合形態については,異なる方 向成分の震動を分担して塑性変形により吸収する機能が維持される範囲で,自由度がある,引用文献1は,断面が略L字状となるダンパを排除していないと判断する。\nしかし,本件補正発明を引用発明1−2に基づいて容易に発明することができた ということができないことは,既に判示したとおりであって,引用文献1において, 極低降伏点鋼パネルの数や配置及び交点の接合形態については自由度があり,また, 断面が略L字状となるダンパを排除していないとしても,そのことから直ちに本件 補正発明を発明する動機付けがあるということができないことは明らかである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2020.10.27
平成30(ワ)35053 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和2年10月22日 東京地方裁判所
(3)事実認定の補足説明
原告らは,被告らがMゴルフ社から本件商品を購入した当時,本件代理店契 約は解除されていてMゴルフ社は2UNDR商品の販売代理店ではなかった と主張するのに対し,被告らはそのような事実はないと主張する。
上記(2)イ(ウ)のとおり,原告ハリス及びランピョン社の代表者は平成28年5\n月上旬にMゴルフ社に本件代理店契約を解除する旨のメールを送信した。そし て同ウのとおり,同月6日を最後に,各国の販売代理店に送信されていた原告 ハリスの商品に関する一斉送信メールがMゴルフ社に送信されなくなってお り,その後,令和元年5月3日まで両社の間で連絡が取られた形跡がないこと に照らせば,本件代理店契約は平成28年5月上旬に解除され,被告ブライト がMゴルフ社から初めて本件商品を購入した同月27日には,本件代理店契約 は解除されていたと認めるのが相当である(上記(2)イ(ウ)) 。
(4) 本件輸入行為の違法性について
ア 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につ き,その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為は,許 諾を受けない限り,商標権を侵害する。しかし,そのような商品の輸入であ っても,1)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾 を受けた者により適法に付されたものであり(以下「第1要件」という。), 2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は 法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより, 当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって(以下\n「第2要件」という。),3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商 品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者 が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的 に差異がないと評価される場合(以下「第3要件」という。)には,いわゆる 真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠く(最高 裁平成14年(受)第1100号同15年2月27日第一小法廷判決・民集 57巻2号125頁)。
イ 本件商品は,ランピョン社から2UNDR商品の販売代理店であったMゴ ルフ社に販売されたものであった。 上記(2)イ、ウによれば、本件代理店契約 において,代理店契約の解除後の販売代理店における販売や在庫の処分等に ついての定めはなく,また,本件代理店契約の解除後,ランピョン社又は原 告ハリスがMゴルフ社に対して在庫の処分等について指示をしたことはな かった。他方,各国の販売代理店に対して同じ2UNDR商品のカタログや 注文のための商品のリストが送付されていたこと(同ウ)から,我が国で販 売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別 の品質等を有していたとは認められず,2UNDR商品の販売代理店の販売 地域の制限が,販売政策上の合意を超えて,2UNDR商品の品質の維持や 管理等と関係することをうかがわせる事情は見当たらない。また,本件商品 は箱型のパッケージに包装された男性用下着であり,通常は流通の過程でパ ッケージ内の商品自体の品質が劣化するものではなく,また,本件で,流通 の過程で商品の品質を変化させるおそれが存在したことを認めるに足りる 証拠はない。 そして前提事実(1)、上記(2)イ(ア)および弁論の全趣旨によれば、ランピョン 社と原告ハリスとは実質的には一体であるともいえる。
ウ 第1要件について
本件標章が付されていた本件商品は,ランピョン社が代理店契約に基づい てMゴルフ社に販売したものであった。 本件商品を被告ブライトがMゴルフ社から購入したのは,上記(2)、(3)のと おり本件代理店契約の解除後であるが,ランピョン社がMゴルフ社に販売し た2UNDR商品に対する上記イのとおりのランピョン社の管理内容等に 照らし,このことによって,原告商標の出所表示機能\が害されることになる とはいえない。また,本件代理店契約では,Mゴルフ社の販売地域はシンガ ポールに限定されていたが,上記イのとおり,そもそも我が国で販売される 2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等 を有していたとは認められず,販売地域の制限が本件商品の品質の維持や管 理等と関係していたとも認められないから,Mゴルフ社の販売地域が限定さ れていたことによって原告商標の出所表示機能\が害されることになるとは いえない。 これらによれば,本件商品に付された本件標章は,外国における商標権者 である原告ハリスから使用許諾を受けたランピョン社又はランピョン社と 実質的には一体ともいえる原告ハリスによって,適法に付されたものである ということが相当である。 したがって,本件輸入行為は第1要件を具備するものと認められる。
エ 第2要件について
前提事実(1)のとおり、原告商標についてのカナダなどの海外における商標権者と日本における商標権者はいずれも原告ハリスであり,本件標章は原告 商標と同一又は類似のものであるから(上記1),それらは同一の出所を表\n示するものであるといえる。 したがって,本件輸入行為は第2要件を具備するものと認められる。
オ 第3要件について
本件標章が付された本件商品は,本件代理店契約に基づきランピョン社に よってMゴルフ社に販売されたものである。そして,ランピョン社と原告ハ リスは実質的には一体ともいえた。 本件商品が被告ブライトによりMゴルフ社から購入されたのは,本件代理 店契約の解除後であるが,ランピョン社がMゴルフ社に販売した2UNDR 商品に対する上記イのとおりのランピョン社の管理内容等に照らし,このこ とによって,原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。\nまた,本件代理店契約では,Mゴルフ社の販売地域はシンガポールに限定さ れていたが,上記イのとおり,そもそも我が国で販売される2UNDR商品 が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたと は認められないこと,Mゴルフ社の販売地域の制限が本件商品の品質の維持 や管理等と関係するとも認められないこと,本件商品が運送中に品質が直ち に劣化するものではない男性用下着であることなどから,そのことによって 原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。\nこれらによれば,我が国の商標権者である原告ハリスは,直接的に又は少 なくともランピョン社を通じて本件商品の品質管理を行い得る立場にあっ て,本件商品と2UNDR商品の日本における販売代理店が販売する商品と は登録商標の保証する品質において実質的に差異がないといえる。 したがって,本件輸入行為は,第3要件を具備するものと認められる。
カ 原告らは,被告ブライトが本件商品を購入したのが本件代理店契約の解除 後であること,本件代理店契約には販売地をシンガポールとする販売地制限 条項があることを挙げて,本件輸入行為が違法性を欠くことにはならない旨 主張するが,上記ウ,オに照らし理由がない。 また,原告らは,被告ブライトの広告に「訳あり/パッケージ汚れ」など という表示があり,本件商品の包装が汚れており,シールをはがしたような\n跡があり,本件商品は原告アイインザスカイが販売する2UNDR商品に比 して著しく安価であることから,本件輸入行為は原告商標や本件標章の出所 表示機能\及び品質保証機能を害すると主張する。しかし,本件商品の需要者\nは,本件標章が付されることによる通常期待される品質を前提として,安価 になっているのは上記事情によるものであると認識すると考えられ,上記事 情によって原告商標の出所表示機能\や品質保証機能が害されるとはいえず,\n上記主張は採用できない。
さらに,原告らは,Mゴルフ社は本件代理店契約の解除により正規の販売 代理店ではなくなったため,本件商品は欠陥等があっても原告ハリスから保 証を受けられないから,原告商標の出所表示機能\や品質保証機能が害される\nと主張する。しかし,商標権者から保証を受けられるか否かが並行輸入の場 面における商標の出所表示機能\や品質保証機能に直ちに影響するとはいえ\nないし,本件において,特定の商品について欠陥等の保証をすることについ て原告ハリスが日本国内で独自の信用を構築していたと認めるに足りる証\n拠もない。原告ら主張の事情によって原告商標の出所表示機能\や品質保証機 能が害されるとはいえず,原告らの主張は採用できない。\n
キ 小括
以上によれば,被告ブライトの本件輸入行為は,いわゆる真正商品の並行 輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠く適法なものであると認 められる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.10.23
令和2(行ケ)10017 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年10月13日 知的財産高等裁判所
オ 引用商標の周知著名性及び独創性
原告のカタログにおいて,「空調服」の文字は多くが記述的に用いられている上, その頒布部数を認めるに足りる的確な証拠はない(前記ア(ア))。また,原告のウェブ サイト(同(イ))の閲覧者数も不明であるし,原告商品のシェアや売上げを認めるに 足りる的確な証拠はない。 前記イのとおり,原告商品は,平成14年から本件使用時点までの間に,暑さ対 策に有効な作業服等として,「空調服」との語と共に複数のメディアで取り上げられ, そのメディアに全国紙や全国ネットの著名なテレビ番組が含まれてはいるものの, 大部分は全国紙,全国ネットではなく,頒布部数や視聴者数が不明のものであり(同 イに掲記した証拠参照),その回数もその期間に比して多いとまではいえない。 加えて,「空調服」との語は,ファンを備えた作業服等一般を示すものとして記述 的に用いられ(前記エ(ア),(イ)),あるいは,原告を出所とするものと解し得ない商品 に関するカタログでも用いられている(前記ウ)。 以上によれば,原告の親会社であるセフト研究所の登録商標が表示されたCMが\nウェブサイト上で多数回閲覧されたこと(前記ア(ウ))を考慮しても,引用商標が, 原告の出所に係る商品を示すものとして周知著名であったと認めることはできない。 また,引用商標は,「空調」と「服」という日常的に用いられる平易な言葉を組み 合わせ,同一の書体及び大きさで等間隔に配置した構成であり,独創性の程度が高\nいとまではいえない。
カ 原告の主張について
(ア) 原告は,前記ア(ウ)のCMに関し,152件のウェブサイト上の記事が掲載 されたと主張するが,原告の提出した証拠(甲156)からは,記事において引用商 標に言及されているか否か不明であり,当該記事の閲覧者数も不明であるから,引 用商標の周知性を裏付けるものではない。 原告は,原告がこれまでに支払った原告商品の広告宣伝費用の総額が,少なくと も5211万円であること並びに原告商品の売上高及び原告商品のシェアについて 主張するが,原告の主張を裏付ける的確な証拠はない。
(イ) 原告は,法人等の需要者や取引者の間で,「空調服」との語は原告の会社名 又は商品名と認識されていることや,原告商品についての記事や番組においても, ファンを備えた被服一般を表す用語として「電動ファン付きウェア」とか,「ファン\n付き作業服」とか,「EFウェア」等の用語が区別して用いられている例があり,引 用商標には自他識別機能が認められると主張するが,このことから直ちに,引用商\n標が原告商品の出所を示すものとして周知であったということにはならないから, 上記認定を左右するものではない。
(ウ) 原告は,ウェブサイト上の「テレビ紹介情報」における「空調服」の検索結 果299件(甲164)を提出するが,本件使用時点後のものも多く含まれる上に, 検索結果からは原告商品の出所を示すものとして「空調服」が紹介されたのかが必 ずしも明らかではないものも多いから,上記認定を左右するものではない。
(4) 被告商品と原告商品との間の関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者 の共通性その他取引の実情等
ア 商品の関連性並びに取引者及び需要者の共通性
前記1のとおり,被告が本件使用商標を使用する被告商品と,原告が引用商標を 使用する原告商品は,いずれも電動のファンを備えた作業服であり,取引者及び需 要者は共通するものと推認される。
イ 取引の実情等
原告商品の包装には,「空調服」の文字が付されており(甲71),原告商品が掲載 されたカタログには「空調服」の文字が付されている(甲7の13)。 これに対し,被告商品のタグ及び包装には,「THE」の文字と組み合わせて本件 使用商標が付され(甲17の3・4。ただし,包装においては色彩が反転している。),被告商品が掲載されたカタログ(甲17の2)及び被告のウェブサイト(甲17の 1・14)には本件使用商標が表示されている。これらには,本件使用商標の末尾に\n「(R)」が組み合わされたものもあり,取引者及び需要者において,本件使用商標が全 体として商品の出所を示すことを理解するということができる。
(5)出所の混同の有無
ア 上記(4)アのとおり,本件使用行為に係る商標が使用された被告商品と引用商 標が使用された原告商品は,ファンを備えた作業服等であって同一の商品であるも のの,本件使用商標と引用商標は類似せず,かえって,前記(2)のとおり相違するも のである。そして,前記(3)のとおり引用商標は原告を示すものとして周知著名とは いえず,独創性の程度が高いといえない上,証拠からは,本件使用商標が使用され た被告商品と引用商標が使用された原告商品について,混同を生ずるおそれがある ような取引の実情は認められない。 そうすると,両商標を同一の商品に使用した場合に,取引者及び需要者において 普通に払われる注意力を基準として,出所の混同を生ずるとはいい難い。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は,本件使用商標が使用された被告商品と引用商標が使用された原告商 品の形態等が酷似し,両商品について需要者の間で取り違えが生じるほどである旨 を主張する。
本件使用商標が使用された被告商品と,引用商標が使用された原告商品の一部に おいて,基本的構成(襟付きの長袖であり,服胴部の前方中央に縦に帯状の袷部を\n形成し,その内側にファスナーを取り付け,両脇腹部,両胸部及び左腕部にポケッ トを設け,背面左右両腰部に開口部を形成し,その使用態様において,需要者が当 該開口部にファンを設置して使用できる態様のものである)が同一であるほか,具 体的構成(比翼仕立ての正面部分,前面のポケットの数及び位置,左袖のペン差し\nの構成,電池ボックスポケット及びバッテリー用ポケットの位置,袖口のマジック\nテープ等)の点からみても類似し,カラーラインナップも類似する3色のものがあ ることは認められる(甲8,甲17の14及び弁論の全趣旨)。しかし,前記(4)イの とおり,それぞれの商品やその包装及び広告ないし価格表には異なる商標が付され\nていることが認められ,その商標は前記(2)のとおり相違しているのであるから,上 記のとおり商品の形態が類似しているからといって,取引者及び需要者において普 通に払われる注意力を基準として,出所の混同を生ずるとはいい難いし,また,需 要者の間で頻繁に取り違えが生じていることを認めるに足りる証拠もない。
(イ) 原告は,被告は,ファンを備えた作業服の販売について原告に10年以上後 れる後行者でありながら,原告の周知の商標を組み込んだ本件使用商標を使用し, 商品の形態等も酷似させ,原告の商品の名声にフリーライドして自らの商品を販売 するものであるから,これを取引の実情として考慮すべきであると主張する。 しかし,引用商標と本件使用商標が相違することは前記(2)のとおりであるし,形 態が類似しているからといって,出所の混同を生ずるとはいえないのは上記(ア)のと おりである。また,証拠(甲8,12,13,甲17の14,乙16の1〜11及び 弁論の全趣旨)によれば,1)セフト研究所と被告が,平成15年頃,ファンを備えた 被服に関係するセフト研究所の出願中の特許について,セフト研究所が被告に実施 許諾(非独占的通常実施権)することなどを内容とする契約を締結したこと(甲1 2),2)セフト研究所と被告が,平成24年11月20日,i)セフト研究所が保有 する特許権に係る特許を用いたファン付き作業服等の被服の部分を被告が製造し, これにファン部材を組み付けた製品を被告が販売することを許諾し,ii)セフト研 究所が販売する製品の被服の部分の製造を優先的に被告に委託し,被告は優先的に 受託することなどを内容とする契約を締結したこと(甲13),3)平成27年頃に両 者の関係が悪化してほどなく上記契約関係が終了したことは認められるものの,原 告ないしセフト研究所が,その保有する特許権の技術的範囲を超える,ファンを備 えた作業服全体の独占権を有するものでもないことは明らかである。以上によれば, 被告が,ファンを備えた作業服の販売について,原告の後行者であるのに,原告の 名声にフリーライドしたものと評価することはできず,原告の主張は前提を欠く。
(ウ) 原告は,被告が,平成29年のカタログ(甲160)に虚偽の記載をし,意 図的に混同を生じさせていることを取引の実情として主張する。しかし,株式会社 中電工が平成17年から使用している「空調服」の出所が原告であることを裏付け るに足りる証拠はなく,原告の主張は前提を欠く。
2020.10.19
令和2(ワ)910 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年9月25日 東京地方裁判所
前記前提事実,証拠(甲1,6,8,乙1)及び弁論の全趣旨によれば, 本件写真は,原告が,空気の透明度が高い冬季において,天候が良好な日 の夜間に,約180度の眺望を有する本件展望台から見ることができる夜 景のうち,大阪府内所在のりんくうゲートタワー及びその周辺の建造物の 組合せを被写体として選択し,中でも目を引く建造物であるりんくうゲー トタワーを構図のほぼ中心に据え,その左右に複数の建造物がそれぞれ配\n置されるようにして,カメラについては,「70−200mm」のレンズを 選択し,レンズ焦点距離を「200.00mm」,シャッター速度を「16. 0秒」,絞り値を「f/9」とするなどの設定をした上で,ストロボ発光な しで撮影したものと認められる。 そうすると,本件写真は,原告において,撮影時期及び時間帯,撮影時 の天候,撮影場所等の条件を選択し,被写体の組合せ,選択及び配置,構\n図並びに撮影方法を工夫し,シャッターチャンスを捉えて撮影したもので あり,原告の個性が表現されているものと認められる。\nしたがって,原告が撮影した本件写真及びこれに本件文字を付加して作 成した本件写真画像は,いずれも,原告の思想又は感情を創作的に表現し\nたものということができるから,「著作物」(著作権法2条1項1号)に該 当する。
イ 被告は,本件写真の被写体であるりんくうゲートタワー及びその周辺の 建造物は,屋外に恒常的に設置されているものであるから,これを被写体 として撮影しようとすれば,焦点距離や撮影位置,構図等の表\現の選択の 幅は必然的に限定され,本件写真の構図自体ありふれたものであるから,\n撮影者の個性が現れたものとはいえず,本件写真には創作性がない旨主張 する。
しかしながら,別紙4写真画像目録記載の本件写真画像から明らかなよ うに,本件展望台からの眺望は広く,撮影することができる建造物は多数 あり,それらから発せられる光も様々であるから,どのような位置から, どのような構図で撮影するか,どの建物に焦点を合わせるかといった選択\nの幅が限定的であるということはできない。 そして,前記アのとおり,原告は,上記の幅の中から1つの撮影位置, 構図及び焦点距離を選択した上,さらに,撮影時期及び時間帯,撮影時の\n天候等の条件についても選択して,撮影方法を工夫し,シャッターチャン スを捉えて撮影したものであるから,本件写真には,原告の個性が現れて いるものと認められる。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2020.10.15
令和1(ネ)10062 商標権移転登録手続等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和2年10月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
甲と乙は,業務提携について合意し,その際,乙は,甲に対し,諸外 国で乙が保有し登録された「ROCCA」商標(本件商標)の使用を認め, 甲は,本件商標権を,日本において登録した。乙は,本件商標について・・・ 無効審判を請求したが,特許庁は,請求が成り立たない旨の審決(本件審 決)を下し,本件審決は確定した。甲と乙は,本件審決の解釈に関して見 解の相違を生じたことなどから,業務提携が事実上中断し,かつ,本件商 標権の帰属について,長年にわたり,合意に至らなかった。そこで,甲と 乙は,上記法解釈に係る見解の相違があることを認めつつ,本件を将来に 向けて解決し,業務提携を再開・発展させることにより,相互に共存共栄 することとした。」(前文),2)「甲は,乙に対し,本契約書別紙商標権目録 1記載の本件商標権について,移転登録手続を執ることを合意し,乙は, 甲に対し,「ROCCA SINCE 1947」商標を,日本において, 乙の使用に係る同商標と異なる字体で使用することにつき,通常使用権を 許諾する。上記移転登録手続に要する費用は,乙が負担し,上記許諾は無 償とする。」(1条3項)などの記載があることが認められる。本件和解契 約書案の上記1)中の「甲と乙は,本件審決の解釈に関して見解の相違を生 じたことなどから,業務提携が事実上中断し,かつ,本件商標権の帰属に ついて,長年にわたり,合意に至らなかった。」との記載は,2017年(平 成29年)2月25日付け書面の添付書面として本件和解契約書案を送付 した時点では,控訴人と被控訴人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標 権を移転することの合意が成立していないことを示すものであり,平成2 6年4月23日に控訴人と被控訴人間で本件合意が成立していたことと矛 盾する記載であり,また,本件和解契約書案の上記2)の内容は,本件合意 の内容と必ずしも一致するものではない。
・・・
そこで検討するに,上記1)の記載部分は,控訴人代表者のAが,2\n014年(平成26年)4月23日,レストランの席上で,被控訴人 代表者のCに対し,控訴人が使用し管理する「ROCCA」が国際著\n名商標であることは,Cもよく知っているはずであり,鈴屋(被控訴 人)は「ROCCA」商標を返還すべきであると明確に述べ,最終的 に,Cも,これを認めるに至った,Cは,控訴人との商標を巡る紛争 を直ちに解決するため,「ROCCA」商標を控訴人に移転する代わり に,控訴人との取引を継続し,ダミアーニ・グループに支援を要請し たいと述べ,Aの提案に同意した旨を供述するものであるところ,A がレストランの席上で「ROCCA」商標の返還を求める旨の提案を してから,Cが「最終的にこれを認めるに至った」具体的な経緯につ いての説明がない上,当時,被控訴人がダミアーニ・グループに支援 を要請すべき事情があったことを認めるに足りる証拠はなく,さらに は,ダミアーニ・グループのダミアーニB.V.社が請求した本件商 標1の商標登録無効審判(別件無効審判)を不成立とする別件審決が 既に確定している状況下において,CがAの提案に応じるべき合理的 な理由はないことに照らすと,Aの上記供述内容はそれ自体不自然で あって,説得力を欠くものである。 かえって,前記(1)アのとおり,控訴人が被控訴人に送付した201 7年(平成29年)2月25日付け書面(甲8の1)添付の本件和解 契約書案中には,被控訴人と「Damiani Internati onal S.A.」は,「業務提携が事実上中断し,かつ,本件商標 権の帰属について,長年にわたり,合意に至らなかった。」との記載部 分があり,この記載部分は,AとCが平成26年4月23日に面談し た後の本件和解契約書案が送付された時点において,控訴人と被控訴 人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標権を移転することについて の合意が成立していないことを示すものであり,上記1)の記載部分と 矛盾するものである。 次に,上記2)及び3)の記載部分は,A個人の内心の思いや考えを述 べたものであり,Aが,Cに対し,言葉として発して,その内容を確 認したというものではないから,控訴人主張の本件合意の成立を裏付 けるものではない。 以上によれば,甲22の上記1)ないし3)の記載部分は措信すること はできず,甲22の他の記載を勘案しても,甲22から控訴人主張の 本件合意が成立したことを認めることはできない。
◆判決本文
1審はこちら
2020.10.12
令和1(ワ)19889 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和2年3月18日 東京地方裁判所
原告ブランドに係る商品の需要者は,衣料品を中心とするファッション全 般に関心を有する一般消費者であると解されるところ,前記認定のとおり, 1)原告の店舗数及びその展開地域,2)オンラインショップも運営しているこ となど,その販売態様,3)原告の商品の売上高及び来店者数,4)セレクトシ ョップ分野における原告の地位(三大ブランドの一つ),5)雑誌,カタログ, フリーペーパー等における宣伝・広告の状況,6)フェイスブック,ツイッタ ー,インスタグラムにおけるフォロワー数などの事情を総合すると,原告表\n示は,被告表示の使用が開始された平成31年4月時点において,需要者等\nの間において,原告の商品等表示に当たるものとして,周知であったと認め\nられる。
(2) これに対し,被告は,原告商品の売上高や店舗数,UNITED ARR OWS,BEAMS,ユニクロ,しまむらなどの同業他社に比して少ないこ とを指摘する。 しかし,原告商品の売上高や店舗数が,原告より更に規模が大きい同業他 社と比較して小さいとしても,そのことは原告ブランドが需要者等の間で周 知であるとの認定を妨げるものではない。前記認定のとおり,原告は,アパ レルの一つの分野として確立しているセレクトショップ分野において,BE AMS及びUNITED ARROWSとともに,三大セレクトショップの 一つと評価されており,その店舗は,著名百貨店,主要ターミナル駅の駅ビ ル,大型路面店などを中心に,全国に展開され,売上高(平成31年2月期) も245億7502万円に上ることなどを考慮すると,原告表示が周知であ\nると認められることは前記判示のとおりである。
(3) 被告は,「知恵蔵」の出版が10年以上前であることなどを指摘し,原告 が挙げる書籍は周知性を基礎付けるものではないと主張するが,前記1(2) のとおり,アパレル業界に関する書籍及び「知恵蔵」などの一般書籍は,出 版時期を問わず,いずれも,原告がセレクトショップの大手であるとの認識 を示している上,上記1で認定した原告ブランドの宣伝・広告状況などにも 照らすと,原告がセレクトショップとして需要者等によく知られているとい う「知恵蔵」に記載された状況は,平成31年4月時点においても変わりが ないというべきである。
(4) 被告は,原告による広告宣伝について,他社の広告費との比較や実際の広 告効果の定量的な主張・立証がないと主張するが,前記1(3)(4)記載のとお り,原告ブランドの雑誌等における紹介の状況,SNSにおけるフォロワー の数,創業40周年の際の宣伝・広告状況(全国主要駅におけるポスター広 告,新聞における全面広告等),プロサッカーにおけるスポンサー企業とし ての宣伝・広告状況など,原告による広告・宣伝の内容,量等に照らすと, 他企業の広告費との比較を要することなく,原告表示は需要者等の間で周知\nであると認めることができる。
(5) 被告は,被告サイトの利用者向けに実施したアンケート調査の結果によれ ば,回答者341名のうち,原告表示を知らなかった者は297名に及ぶこ\nとを理由として,原告表示が周知ということはできないと主張する。\n しかし,被告の行ったアンケート調査調査は,その対象者が被告サイトの 利用者であり,被告サイトにより提供されるサービスの性質,内容等に照ら すと,その利用者層は一定の限定された範囲にとどまるものと考えられ,そ の調査結果が必ずしも原告ブランドに係る商品の需要者の認識を反映してい るとはいい難い。そうすると,上記調査結果は,原告表示が需要者等の間で\n周知であるとの結論を左右しないというべきである。
(6) 以上のとおり,原告表示は,少なくとも周知性を有するものであって,不\n正競争防止法2条1項1号の「需要者の間に広く認識されているもの」に当 たるというべきである。
3 争点2(混同のおそれの有無)について
(1) 不正競争防止法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」には,他人の周 知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と当該他人とを同一\n営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会 社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業\nを営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含すると解さ れる(最高裁平成7年(オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判 決・集民189号857頁,最高裁昭和56年(オ)第1166号同59年 5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号920頁参照)。
(2) これを本件についてみるに,前記認定(5)及び(6)のとおり,1)原告は,原 告表示を含むブランド名を用いて,アパレル分野に限らず,自動車のメンテ\nナンスやカスタム,生活雑貨の販売などの事業も手掛けていること,2)原告 は,原告表示を用いて,異業種の他企業との間で,多数のコラボレーション\n企画を実施しており,そのことは需要者等に相応に認識されていたものと推 認されること,3)原告は,原告表示を用いて,福祉分野を始めとする社会的\nな活動にも参加しており,公式サイトにおいて,「コンプライアンス,LG BT,ダイバーシティなどについての啓蒙」に取り組んでいる旨を表明して\nいることが認められる。 これによれば,被告サイトに原告表示と類似する被告表\示を使用すること は,原告と被告との間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊 密な営業上の関係があり,又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属\nする関係が存すると需要者等に誤信させる行為であって,原告の商品又は営 業と「混同を生じさせる行為」というべきである。
(3) これに対し,被告は,原告の属するアパレル分野と被告の属するマッチン グサイトの分野とは,全くの異業種であり,業種の隔たりが大きいと主張す るが,原告自身が,障害者を始めとするマイノリティや福祉に対する支援活 動を積極的に行っていることは前記判示のとおりであり,また,アパレルメ ーカーがマッチングアプリとの協業プロジェクトを実施した事例や,セクシ ャルマイノリティの間で人気の出会い系アプリがアパレルラインを発表した\n事例があると認められること(甲65)に照らすと,アパレル分野とマッチ ングサイトの分野とが全くの異業種であるということはできない。
(4) また,被告は,原告は他の企業の知名度を借りたコラボレーションをして いるにすぎないと主張するが,原告が他の分野で事業自体を展開していない としても,他業種の企業とコラボレーションをし,原告表示の付された商品\n等を提供することとなれば,需要者等は,原告と被告との間に子会社等の関 係があるなどの誤信をするおそれがあることに変わりはないというべきであ る。
(5) 被告は,被告の実施したアンケート調査結果も根拠として,被告サイトが 原告によって運営されていると誤信することはないと主張するが,前記判示 のとおり,被告の行ったアンケート調査結果が原告ブランドの需要者等の認 識を反映しているとは必ずしもいうことはできないので,同アンケート調査 結果を根拠にして混同のおそれがないということはできないが,同調査結果 によっても,セレクトショップ「SHIPS」を知っている者の2割以上に 混同が生じていることによれば,被告表示に接した需要者等が上記の混同を\nする可能性は高いというべきである。\n
(6) したがって,被告の行為は,原告の商品又は営業と「混同を生じさせる行 為」に当たる。
4 争点3(営業上の利益の侵害の有無)について
原告は,昭和52年に「SHIPS 銀座店」を開設して以来,その店舗を 拡大し,平成31年3月頃までに,全国19都道府県に約70店舗を展開する に至っており,原告ブランドには長年にわたる使用により信用力が形成されて いると解されるところ,被告による被告表示の使用は,原告ブランドの信用力\nに依拠し,その意に反してこれと類似の被告表示を使用するものであり,原告\nブランドの信用力を希釈化若しくは毀損するものであるということができる。 したがって,被告の行為は,原告の営業上の利益を侵害し,これを侵害する おそれのある行為であると認められる。
5 争点4(故意・過失の有無及び損害額)について
(1) 被告は,被告以外にも「シップス」又は「SHIPS」の名称を用いる事 業者が存在することなどを理由として,被告には過失がなかったと主張する が,「SHIP」等の名称を用いる業者が他に存在するとしても,そのこと をもって過失の存在が否定されるものではない。被告は,原告表示の存在を\n知りつつ,被告サイトに被告表示を使用したものであり,原告表\示の周知性 や原告表示との類似性を容易に認識し得たものと認められるので,被告には\n少なくとも過失が存在したものというべきである。
(2) そして,本件訴訟の難易度,審理の経過,認容する請求の内容その他本件 において認められる諸般の事情を考慮すると,被告による不正競争行為と相 当因果関係にある弁護士費用相当額は20万円とするのが相当である。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2020.10.12
平成30(ネ)10016 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年5月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(イ) これに対し被控訴人は,1)イ号製品においては,供給口(5)から 供給された液体は,空気口(10)から噴出された外部傾斜領域(7A ')に平行な方向に沿って流動する空気流の強い剪断応力と液体の自重で 下流側へ引っ張られて傾斜面(外部傾斜領域(7A'))に沿って流れ, 空気流によって傾斜面に液体を押し付ける力は作用しておらず,乙23 の鑑定書記載のとおり,流体力学の一般原理においては,傾斜面に対し て平行な高速気流によっては,傾斜面に供給された液体に対し,傾斜面 に押し付ける力は生じないから,イ号製品は,構成要件オの「液体を,\n高速流動する空気流で平滑面に押し付けて」の構成を備えていない,2) 構成要件オの「薄膜流を空気流で空気中に微粒子として噴射する」とは,\n「高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾 斜面から離れるとき」に「10μm以下の液滴の微粒子」になることを いうが,イ号製品は,気液体が混じった高速噴流が衝突することによっ て,微粒子を得られるものであり,この衝突前に微粒子を得られるもの ではないとして,イ号製品は,構成要件オを充足しない旨主張する。\n しかしながら,被控訴人の主張は,以下のとおり理由がない。
a 上記1)について
乙23の鑑定書には,1)液体が傾斜面に供給された場合,液体を傾 斜面側に押す力がなくても,液体は,その粘性による剪断応力と自重 とで傾斜面に沿って流れること,2)気体が傾斜面に平行に流れる場合, 気体は,傾斜面を押す力を発揮し得ないこと,3)液体には,高速の気 流との速度差によって傾斜面に平行な方向の剪断応力が作用し,液滴 の飛散を伴う流れとなるが,このような傾斜面に平行な気流では,該 傾斜面に液体を押し付けるような力は作用しないことは,流体力学の 一般原理である旨の記載がある。 しかしながら,乙23は,空気の直線流れの方向と平行に平板を設 置した場合における流体力学の一般原理について述べるものであって, イ号製品においては,「供給口(5)」から供給されたノズルの軸方 向(垂直方向)に直進する液体流が,空気口(10)から噴射する高 速流動する空気流によって,空気流と合流する時点で,外側傾斜領域 (7A')に沿って平行に進むように進行方向が曲げられており(前記 (ア)a),傾斜面(外側傾斜領域(7A'))に液体流を押し付ける力 が作用しているものといえるから,イ号製品には妥当しない。 したがって,被控訴人の上記1)の主張は理由がない。
b 上記2)について
本件発明4の特許請求の範囲(請求項4)には,「微粒子」の粒子 径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 次に,本件明細書には,微粒子の粒子径に関し,「図1に示すノズ ル」について「この構造のノズルは,液体を10μm以下の微細な粒\n子に噴射できる。」(【0003】),「図3に示すノズル」につい て「粒子径を5μmとする微粒子を得ることに成功した。しかしなが ら,この構造のノズルは,液体を噴射する供給口5の調整が極めて難\nしく,調整がずれると微粒子の粒子径は20〜30μm以上に急激に 大きくなった。」(【0011】),「図4に示すノズル」について 「この構造のノズルは,アトマイズエアーとスプレッディングエアー\nの衝突角を25度に設計すると,10μm以下の微粒子が得られる。」 (【0012】),「図11の拡大図に示すノズル」について「この 構造のノズルは,液体を極めて微細な,たとえば1〜5μmの微粒子\nとして噴射できる特長がある。」(【0052】),「ちなみに,本 発明者が試作したノズルは,1分間に1000gの液体を噴射して, 粒子径を10μm以下の微粒子の液滴を噴射することに成功した」(【0 072】)との記載があるが,これらの記載から,本件発明4の「微 粒子」の粒子径を「10μm以下」に限定する趣旨を読み取ることは できず,また,本件明細書には,本件発明4の「微粒子」の粒子径を 「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 さらに,本件意見書には,「内部混合タイプのノズルは,閉鎖され た空間内で液体の微粒子として噴霧します。このため,ノズルの内部 で極めて目詰まりしやすい欠点があります。・・・にもかかわらず,内部 混合タイプの噴霧ノズルが多用されますのは,外部混合タイプでは, 安定して液体を極めて小さい微粒子に噴霧できないからです。外部混 合タイプの噴霧ノズルであって,液体を微粒子として安定して噴霧で きます優れたノズルは実用化が困難です。」,「本願発明は,外部混 合タイプのノズルを改良したものです。本願発明の噴射方法とノズル は,前述の独特の構成で,液体を極めて小さい微粒子に安定して噴射\nできる特長があります。本発明の噴射方法とノズルは,液体を,10 μm以下の極めて小さい微粒子として,安定して噴射することが可能\nです。・・・それは,本発明の噴射ノズルが,液体を極めて小さい孔や, 極めて小さいスリットから噴射して微粒子に噴射するのではなく,平 滑面を極めて速い速度で高速流動する空気流で,液体を薄く引き伸ば して微粒子にして噴射するからです。」(以上,6頁16行〜7頁2 行)との記載がある。上記記載中には,「液体を,10μm以下の極 めて小さい微粒子として,安定して噴射することが可能です。」との\n記載があるが,上記記載全体として読めば,「本発明」は,「平滑面 を極めて速い速度で高速流動する空気流で,液体を薄く引き伸ばして 微粒子にして噴射する」構成により,液体を微粒子として安定して噴\n霧でることを説明したものであって,「本発明」が「10μm以下」 の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述 べたものではない。
以上によれば,構成要件オの「微粒子」とは,小さな粒子径の粒子\nを意味するものであって,粒子径の数値範囲に限定はなく,「10μ m以下」の粒子径のものに限定されるものでもない。そして,イ号製品においては,外側傾斜領域(7A')に沿って進む,液滴を含む薄膜流は,外側傾斜領域(7A')から離れるときに小さな粒子径の液滴(微粒子)となっていることは,前記(ア)b認定のとお りである。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2020.10.12
平成29(ワ)19073 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年3月4日 東京地方裁判所
イ そこで検討すると,前記1(1),(3)イ認定のとおり,本件プログラムは,ED INETにおける取扱いに変更があったことを踏まえ,ユーザーが作成した会計に 関するエクセルファイル等をX−Smartに取り込み,会計科目を開示科目に組 み替え,編集作業等を経て,宝XBRLの形式に変換することを簡易に行うことな どを目的として開発されたものであり,相応の分量のソースコードから成るもので\nある。 しかしながら,前記1(2)に照らすと,DI社が原告に本件プログラムの開発を委託した際に提供された本件各資料のうち,少なくとも本件資料4ないし6には,本 件プログラムに要求される機能及びそれを実現する処理,画面の構\成要素等を別紙 3本件プログラム説明書と同様のものとすることが概ね示されていたと認められる。 また,前記1(3)認定のとおり,本件プログラムは,ユーザーからのフィードバッ クの結果を踏まえ,順次,DI社からの発注を受けて修正及び追加等をしながら開 発されたものであり,その過程で,そのソースコードの一部については,DI社か\nら元となるデータやそのサンプルが提供され,その作成方法を指示されるなどして 作成されたものであること,その他,ソースコード中にNetAdvantageに含まれるフ ァイル,VisualStudioで自動生成されるファイル,オープンソースからダウンロー\nドしたファイルから作成された部分や,一般的な設定ファイル等である部分も相応 に含まれていることにも照らせば,ソースコードの分量等をもって,本件プログラ\nムに係る表現の選択の幅が広いと直ちにはいえない。\n
(2)原告が創作的表現であると主張している部分についての検討\n
以上を前提として,本件プログラムのうち,原告が創作的表現であると主張して\nいる部分について検討する。 ア ドロップダウンリストの生成に係る部分 前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード1には,画面1の「ファイル形式」を\n選択するドロップダウンリストを生成する処理が記述されているところ,原告は, 本件ソースコード1では,ドロップダウンリストを「asp:DropDownList」を利用し て別の箇所で生成しているが,他の表現1のように,ドロップダウンリストを直接\n生成することもできるから,選択の幅があり,ここに原告の個性が表れている旨主\n張する。 しかしながら,前記1(3)ウ認定のとおり,本件プログラムの開発はASP.NE T環境下で行われているところ,証拠(乙227)及び弁論の全趣旨によれば, 「asp:DropDownList」は,ドロップダウンリストを生成するためのツールとしてA SP.NET環境で用意されているものであり,これを利用する方法は一般的なこ とであると認められるから,他の表現1があるとしても,「asp:DropDownList」を 利用することに作成者の個性が表れているということはできない。\nまた,本件ソースコード1の具体的な記述も,ASP.NET環境で利用可能\な 宣言構文のとおりのものであると認められる(乙227)のであって,作成者の個\n性が表れていると認めるに足りず,創作的表\現であるとはいえない。
イ サブルーチンに係る部分
原告は,本件ソースコード2ないし4について,サブルーチン化するか否か,サ\nブルーチン化するとしてどのようにサブルーチン化するかについて選択の幅がある と主張する。 しかしながら,前記第2の2(5)ア認定のとおり,サブルーチンは,高等学校工業 科用の文部科学省検定済教科書である乙232文献にも記載されているような基本 的なプログラミング技術の一つであり,証拠(乙238,240)及び弁論の全趣 旨によれば,プログラム中で繰り返し表れる作業につきサブルーチンに設定するこ\nとで可読性及び保守性を向上させることができ,そのような観点からサブルーチン を設定することは一般的な手法であると認められるから,本件ソースコード2ない\nし4にサブルーチンが設定されているというだけでは,作成者の個性が表れている\nとはいえない。
また,本件ソースコード3において,更にサブルーチンを設定しないことに何ら\nかの目的,意図があるともいい難いから,サブルーチンを更に分割することができ るというだけでは,作成者の個性が表れていると認めるに足りないというべきであ\nる。 以上に加えて,原告は,上記の各点以外に,本件ソースコード2ないし4の記述\nに選択の幅があることを具体的に主張立証しておらず,これらを創作的表現である\nと認めるに足りない。
ウ 条件分岐及びループに係る部分
(ア) 本件ソースコード5\n
前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード5には,画面1から画面2に遷移する\n際に呼び出されるサブルーチンのうち,アップロードしたファイルの種類を判別し, 対応する画面を生成する処理が記述されているところ,原告は,本件ソースコード\n5では,switch文で条件分岐を行っているが,他の表現5のように,els\ne−ifで条件分岐を行うこともできるから,選択の幅があり,ここに原告の個性 が表れている旨主張する。\nしかしながら,証拠(乙223ないし226,232,233)及び弁論の全趣 旨によれば,switch文は,複数の選択肢の中から式の値に合うものを選び, その処理を行うものであり,else‐ifは,複数の条件のどれに当てはまるか によって異なる処理を行うものであって,いずれも高等学校工業科用の文部科学省 検定済教科書である乙232文献その他複数の文献(乙223ないし226,23 3)に記載されている条件分岐の基本的な制御文であり,3種類以上の場合に分け て条件を指定するときに使用されるものであると認められるから,本件ソースコー\nド5のように,アップロードしたファイルの種類によって場合を分けて条件を指定 する必要がある場合に,switch文を使用すること自体は一般的なことである と認められ,そのことに作成者の個性が表れているということはできない。\n
(イ) 本件ソースコード6\n
前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード6には,ファイルの何列目からデータ\nを取り込むかを取得し,取り込み開始が20列目を超えているか否かを判別し,超 えている場合にはエラーを発生させる処理が記述されているところ,原告は,本件 ソースコード6では,for文でループを行っているが,他の表\現6のように,w hile文でループを行うこともできるから,選択の幅があり,ここに原告の個性 が表れている旨主張する。\nしかしながら,証拠(乙223ないし226,232,233)及び弁論の全趣 旨によれば,for文は,繰り返す回数を指定して反復処理を行うものであり,w hile文は,指定した条件を満たす限り反復処理を行うものであって,いずれも, 高等学校工業科用の文部科学省検定済教科書である乙232文献その他複数の文献 (乙223ないし226,233)に記載されているループの基本的な制御文であ り,for文で記述できるものはwhile文でも記述可能であると認められるか\nら,本件ソースコード6のように,取り込み開始が20列目を超えているか否かを\nループ処理によって判別するに当たり,for文を使用すること自体は一般的なこ とであると認められ,そのことに作成者の個性が表れているということはできない。\n
(ウ) 本件ソースコード7\n前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード7には,ファイルの最大列数や項目名\nの開始列を取得する処理が記述されているところ,原告は,本件ソースコード7で\nは,全てのデータに対してforeach文でループを行っているが,他の表現7\n(1)のように,あらかじめ決められた条件で抽出されたデータに対してのみループを 行うことも可能であり,他の表\現7(2)のように,for文でループを行うこともで きるから,選択の幅があり,ここに原告の個性が表れている旨主張する。\n
しかしながら,証拠(乙223ないし226,233)及び弁論の全趣旨によれ ば,C#において,foreach文は,複数のデータの集まりの各要素を最初か ら最後まで1回ずつ呼び出して処理するものであり,for文等と共に複数の文献 (乙223ないし226,233)に記載されているループの基本的な制御文であ って,for文等で記述された処理を代替し得るものであると認められるから,本 件ソースコード7のように,ファイルの最大列数や項目名の開始列を判別するに当\nたり,foreach文を使用すること自体は一般的なことであると認められ,そ のことに作成者の個性が表れているということはできない。\nまた,他の表現7(1)及び(2)は,ループを行う範囲を限定するものであると認めら れるが,同等の処理を行うものと認められる本件ソースコード7と比べて記述が長\nく,可読性が低下していると認められるところ,あえてそのような記述をする必要 があると認めるに足る証拠はないから,これを選択可能な他の表\現であるとは認め 難い。
(エ) 本件ソースコード8\n
前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード8には,金額の単位を選択するために\n画面3に表示されるドロップダウンリストを生成するための判別処理等が記述され\nているところ,原告は,本件ソースコード8では,foreach文によるループ\nの中で,求める条件が正しい場合に次の条件に進むように記述しているが,他の表\n現8のように,求める条件が正しくない場合にループをやり直すように記述するこ ともできるから,選択の幅があり,ここに原告の個性が表れている旨主張する。\nしかしながら,前記(ウ)のとおり,foreach文は,ループの基本的な制御 文であるから,本件ソースコード8のように,ドロップダウンリストを生成するた\nめの判別処理として,foreach文を使用すること自体は一般的なことである と認められ,そのことに作成者の個性が表れているということはできない。\nまた,証拠(乙232ないし234)及び弁論の全趣旨によれば,他の表現8に\n用いられているcontinue文は,ループの中で使用され,その前のif文が 真になった場合にcontinue以降の処理をスキップして,次のループ処理の 最初に戻るものであると認められるものの,if文を用いた本件ソースコード8と\n比べてソースコードが長く,可読性が低下していると認められ,あえてそのような\n記述をする必要があると認めるに足る証拠はないから,これを選択可能な他の表\現 であるとは認め難い。
(オ) 本件ソースコード9\n
前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード9には,画面2で選択された列の種別\nを判別して対応する処理が記述されているところ,原告は,本件ソースコード9で\nは,else−ifで条件分岐を行っているが,他の表現9(1)のように,swit ch文で条件分岐を行うこともでき,他の表現9(2)のように,switch文に加 えて,foreach文によるループの対象として,条件分岐の判別に必要な変数 を直接取得することもできるから,選択の幅があり,ここに原告の個性が表れてい\nる旨主張する。 しかしながら,前記(ア)のとおり,else−if及びswitch文は,いず れも条件分岐の基本的な制御文であるから,本件ソースコード9のように,画面2\nで選択された列の種別を判別して対応する処理を行うに当たり,else−ifで 条件分岐を行うこと自体は一般的なことであると認められ,そのことに作成者の個 性が表れているということはできない。\nまた,証拠(乙222)及び弁論の全趣旨によれば,他の表現9(2)は,他の表現\n9(1)と同様のswitch文の中に統合言語クエリ(LINQ)を実行する処理に 係る記述を挿入したものであると認められるものの,ソースコードが長く,可読性\nが低下していると認められ,あえてそのような記述をする必要があると認めるに足 る証拠はないから,これを選択可能な他の表\現であるとは認め難い。
(カ) 小括(本件ソースコード5ないし9)\n
原告は,上記(ア)ないし(オ)の各点以外に,本件ソースコード5ないし9の記述に\n選択の幅があることを具体的に主張立証しておらず,これらを創作的表現であると\n認めるに足りない。
エ 変数への設定に係る部分
前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード10には,画面4に表\示される会計科 目のデータの判別及び設定を行う処理が記述されているところ,原告は,本件ソー\nスコード10では,変数に対して判別結果を直接設定し,条件演算子「?」,「:」 を使用しているが,他の表現10のように,if文によって変数に設定する値を変\nえることもできる,実際の表現の方が簡潔に表\現されているが,他の表現10にも,\nデバッグやログの出力をしやすいといった利点があるのであって,選択の幅があり, ここに原告の個性が表れている旨主張する。\nしかしながら,証拠(甲48,乙236,237)及び弁論の全趣旨によれば, 条件演算子は,条件に基づいて複数の処理を選択する演算子であると認められ,i f文等の条件分岐の制御文と同様の処理を行い得るものであって,両者は代替され 得るものとして認識されていると認められるから,本件ソースコード10のように,\n会計科目のデータの判別及び設定を行うに当たり,条件演算子を使用すること自体 は一般的なことであると認められ,変数に対して判別結果が直接設定されることが 特殊なことであると認めるに足る証拠もないから,それらに作成者の個性が表れて\nいるということはできない。 また,原告は,上記の点以外に,本件ソースコード10の記述に選択の幅がある\nことを具体的に主張立証していないから,これを創作的表現であると認めるに足り\nない。
オ チェック処理に係る部分
前記1(4)認定のとおり,本件ソースコード11には,組替操作時に画面4でドロ\nップされた行番号の取得及び変換を行う処理が記述されているところ,原告は,本 件ソースコード11では,TryParseメソ\ッドの戻り値でドロップされた行 番号のチェック結果を判別しているが,他の表現11のように,Parseメソ\ッ ドを用いて,まず行番号の取得を試みて,エラーが発生するかどうかでチェック結 果を判別することもできるから,選択の幅があり,ここに原告の個性が表れている\n旨主張する。 しかしながら,証拠(乙226,227)によれば,TryParseメソッド\n及びParseメソッドは,いずれもC#ライブラリに標準機能\として搭載された, 文字列を数値に変換する手法であるところ,TryParseメソッドは,変換に\n失敗したときに,例外として情報を取得し,それを精査することにより失敗の原因 を究明することができるとされるParseメソッドとは異なり,戻り値として,\n失敗したという情報だけを取得し,ソースコードはParseメソ\ッドより短くな ると認められ,本件ソースコード11のように,ドロップされた行番号の取得及び\n変換を行うに当たり,TryParseメソッドを用いること自体は一般的なこと\nであると認められ,そのことに作成者の個性が表れているということはできない。\nまた,原告は,上記の点以外に,本件ソースコード11の記述に選択の幅がある\nことを具体的に主張立証していないから,これを創作的表現であると認めるに足り\nない。
カ デバッグログを出力するコードに係る部分
(ア) 本件ソースコード12\n
原告は,本件ソースコード12にデバッグログを出力するコードが挿入されてい\nることにプログラム作成者の個性が表れると主張する。\nしかしながら,弁論の全趣旨によれば,プログラムの開発過程において,プログ ラムの保守及び変更等の必要から,不具合があり得ると考えられるソースコード上\nにデバッグログを出力するコードを挿入することは一般的に行われていることであ ると認められるから,デバッグログを出力するコードが挿入されているというだけ で,そのことに作成者の個性が表れているということはできない。\nまた,本件ソースコード12のデバッグログを出力するコードの記述に作成者の\n個性が表れていることについて原告は具体的に主張立証していないから,これを創\n作的表現であると認めるに足りない。\n
(イ) 本件ソースコード13\n
原告は,デバッグログを出力するコードが挿入されていない本件ソースコード1\n3に対し,他の表現12(1)及び(2)のように,デバッグログを出力するコードを挿入 することも選択し得るとも主張するが,納品されるプログラムにデバッグログを出 力するコードが挿入されていないこと自体は一般的なことであると考えられるから, そのことに作成者の個性が表れているということはできない。\n
キ コメントに係る部分
原告は,本件ソースコード14等におけるコメントの有無及びその内容にプログ\nラム作成者の個性が表れる旨主張する。\nしかしながら,前記(1)アのとおり,プログラムは,電子計算機を機能させて一の\n結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現し\nたもの(著作権法2条1項10号の2)であるところ,コメントは,コンピュータ ーの処理の結果に影響するものではなく,コンピューターに対する指令を構成する\nものであるとはいえないから,上記のプログラムに当たらない。 また,原告は,本件ソースコード14のコメントの内容に作成者の個性が表\れて いることを具体的に主張立証しておらず,これを創作的表現であると認めるに足り\nない。
ク 小括(本件ソースコード)\n
以上のとおり,原告が創作的表現であると主張している本件ソ\ースコードについ て,作成者の個性が表れているということはできず,著作権法で保護されるべき著\n作物であると認めることはできない。
(3) 原告の主張について
原告は,本件プログラムはプログラムの著作物に当たるとし,その理由として, 1)本件プログラムは,原告が創作した部分に限っても,合計4万0381ステップ という膨大な量のソースコードから成り,指令の組み合せ方,その順序,関数化の\n方法等には無限に近い選択肢があること,2)本件プログラムにおけるエクセル取込 機能及び簡易組替機能\は,一般的な用途に使用されるものではないから,これらの 機能を実現するためのプログラムがありふれたものであるとはいえないこと,3)原 告は,NetAdvantageやVisualStudio等の開発ツールを用いながらも,ライブラリ群 の中からどのライブラリを用いるべきか,どの順番でライブラリを呼び出させるべ きか,どのように加工すべきか,どのようにパラメータを設定すべきかなどに工夫 を凝らしており,それらに個性が表れていること,4)本件各資料は,いずれも要求 定義又は外部設計に関するものにすぎず,DI社が要求している機能を実現するた\nめの指令の組合せは記載されていないから,本件プログラムに係る選択の幅を狭め るものではないことを主張する。 しかしながら,上記1)について,前記(1)アのとおり,プログラムに著作物性があ るというためには,プログラムの全体に選択の幅があり,かつ,それがありふれた 表現ではなく,作成者の個性,すなわち,表\現上の創作性が表れていることを要す\nると解されるところ,本件プログラムに表現上の創作性があることについて具体的\nに主張立証されない以上,前記(1)イで認定,説示したとおり,多くのステップ数に より記述されていることをもって,直ちに表現上の創作性を認めることはできない。\nまた,上記2)について,原告の主張は,本件プログラムの機能の特殊性を指摘す\nるにとどまっているところ,プログラムの機能そのものは著作権法によって保護さ\nれるものではなく,特定の機能を実現するためのプログラムであるというだけで,\n直ちに表現上の創作性を認めることはできない。\nさらに,上記3)について,原告は,ライブラリの使用等にどのような工夫をした かについて具体的に主張立証しておらず,その点に選択の幅があり,作成者の個性 が表れていると認めるに足りない。\nまた,上記4)について,本件各資料にソースコードが具体的に記述されていない\nとしても,要求されている機能及び処理を実現するための表\現に選択の幅があると 当然にはいえないから,この点を考慮しても,本件プログラムに表現上の創作性を\n認めるに足りないというべきである。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2020.10.12
令和2(ネ)10018 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和2年10月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審原告の主張は,原判決が法114条1項ただし書に基づき,本件各漫 画のPV数に本件各同人誌の利益額を乗じた額から9割を控除したことにつ いて,原判決の認定判断の不当を種々の観点からいうものである。 しかしながら,一審原告の主張は採用することができない。その理由は, 次のとおりである。
ア 公衆送信行為による著作権侵害の事案において,法114条1項本文に 基づく損害額の推定は,「受信複製物」の数量に,単位数量当たりの利益 の額を乗じて行うものとされている。そして,本件のように,著作権侵害 行為を組成する公衆送信がインターネット経由でなされた事案の場合, 「受信複製物の数量」とは,公衆送信が公衆によって受信されることによ り作成された複製物の数量を意味するのであるから(法114条1項本 文),単に公衆送信された電磁データを受信者が閲覧した数量ではなく, ダウンロードして作成された複製物の数量を意味するものと解される。と ころが,本件においては,公衆が閲覧した数量であるPV数しか認定する ことができないのであるから,法114条1項本文にいう「受信複製物の 数量」は,上記PV数よりも一定程度少ないと考えなければならない。 また,本件において,一審被告会社は,本件各ウェブサイトに本件各漫 画の複製物をアップロードし,無料でこれを閲覧させていたのに対し,一 審原告は,有体物である本件各同人誌(書籍)を有料で販売していたもの であり,一審被告会社の行為と一審原告の行為との間には,本件各漫画を 無料で閲覧させるか,有料で購入させるかという点において決定的な違い がある。そして,無料であれば閲覧するが,書籍を購入してまで本件各漫 画を閲覧しようとは考えないという需要者が多数存在するであろうことは 容易に推認し得るところである(原判決27頁において認定されていると おり,本件各同人誌の販売総数は,本件各ウェブサイトにおけるPV数の 約9分の1程度にとどまっているが,これも,本件各漫画の顧客がウェブ サイトに奪われていることを示すというよりは,無料であれば閲覧するが, 有料であれば閲覧しないという需要者が非常に多いことを裏付けていると 評価すべきである。)。
イ そうすると,本件各漫画をダウンロードして作成された複製物の数(法 114条1項の計算の前提となる数量)は,PV数よりも相当程度少ない ものと予想される上に,ダウンロードして作成された複製物の数の中にも,\n一審原告が販売することができなかったと認められる数量(法114条1 項ただし書に相当する数量)が相当程度含まれることになるのであるから, これらの事情を総合考慮した上,法114条1項の適用対象となる複製物 の数量は,PV数の1割にとどまるとした原判決の判断は相当である。こ の点につき,一審原告は種々主張しているが,上記の点に照らし,その主 張を採用することはできない。
(2) 一審被告らの主張は,法114条1項に基づく損害額の認定を行うこと自 体の不当をいうものであるが,PV数と受信複製物数の違いを念頭に置いた 上で,更に一審原告が販売できないとする事情を考慮して損害額算定の基礎 となる数量を算定し,これに一審原告の利益額を乗じる手法が不合理である とすべき事情は見当たらないから,法114条1項に基づく損害額の認定は 相当であり,「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事 実の性質上極めて困難であるとき」として法114条の5を適用する必要は ない。
◆判決本文
原審はこちらです。
2020.10.12
令和1(行ケ)10148 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年10月7日 知的財産高等裁判所
(3) 原告の主張に対する判断
ア 原告は,「医薬品」の語は,販売名(商品名),一般名あるいは,薬効, 有効成分及び投与経路を特定できるコードを意味するとの本件審決の認定は,リパ ーゼ事件判決に反していると主張する(前記第3の1(2)ア)。 特許請求の範囲から発明を認定するに当たり,特許請求の範囲に記載された発明 特定事項の意味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に,技術常識を斟 酌することは妨げられないというべきであり,リパーゼ事件判決もこのことを禁じ るものであるとは解されない。 そして,本件発明1における「相互マスタ」に登録される「一の医薬品」と「他 の一の医薬品」が,いずれも,販売名(商品名)又は一般名,薬価基準収載用薬品 コードであれば薬効,投与経路・有効成分(7桁のコード)以下の下位の番号によ って特定されるものなど,具体的に当該医薬品の薬効,投与経路及び有効成分が特 定できるレベルのものを意味すると認められることは,前記(2)ウ(ア)のとおりであ り,特許請求の範囲の記載や技術常識からこのように判断できるものであることは, 前記(2)ウ(ア)で判断したとおりである。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
イ 原告は,本件審決の要旨認定は,「医薬品」の概念と,「医薬品」を表現\nするデータ(本件明細書の【0040】)を区別する本件明細書の記載と矛盾すると 主張する(前記第3の1(2)イ(ア))。 しかし,「相互マスタ」に登録される「一の医薬品」と「他の一の医薬品」につい て,具体的に当該医薬品の薬効,投与経路及び有効成分が特定できるレベルのもの を意味すると判断することは,データの格納の構成について判断しているものであ\nり,本件明細書の【0040】の記載にも沿うものであるから,本件明細書の記載 と矛盾するものではない。
原告は,本件審決の「医薬品」の認定は,「相互作用が発生する医薬品の組み合わ せ」の概念と,その表現方法,すなわち医薬品の組み合わせを表\現するためのデー タの概念・種類(薬効コード)を区別している本件特許の請求項2の記載に反する ものであるとも主張する(前記第3の1(2)イ(ウ))が,同様に,「相互マスタ」に登 録される「一の医薬品」と「他の一の医薬品」について,具体的に当該医薬品の薬 効及び有効成分が特定できるレベルのものを意味すると判断することは,データの 格納の構成について判断しているものであり,本件特許の請求項2の記載にも沿う\nものであるから,本件特許の請求項2の記載と矛盾するものではない。
ウ 原告は,本件審決は,特許請求の範囲に記載のない構成要素を付加して\n「医薬品」の文言を殊更狭く要旨認定をしており,サポート要件違反,実施可能要\n件違反,明確性要件違反の無効理由が存在することを示すものである旨の主張をす る(前記第3の1(2)イ(オ))が,本件発明1における「相互マスタ」に登録される「一 の医薬品」と「他の一の医薬品」が,いずれも,販売名(商品名)又は一般名,薬 価基準収載用薬品コードであれば薬効,投与経路・有効成分(7桁のコード)以下 の下位の番号によって特定されるものなど,具体的に当該医薬品の薬効,投与経路 及び有効成分が特定できるレベルのものを意味すると認められることは,前記(2) ウ(ア)のとおりであり,そのように解することから,本件発明1にサポート要件違反, 実施可能要件違反,明確性要件違反があるとは認められないから,原告の上記主張\nを採用することはできない。
エ 原告は,本件審決の理論で相互作用マスタに格納されるデータの概念の レベルについて解釈を行うと,結局どの概念のレベルまで特定すれば本件発明1の 範囲に含まれ,どの概念のレベルでは当該範囲に含まれないのか判然とせず,発明 の外縁が不明確となると主張する(前記第3の1(3)エ(ウ))。 しかし,既に判示したとおり,本件発明1において,「相互マスタ」に登録される 「一の医薬品」と「他の一の医薬品」について,具体的に当該医薬品の薬効,投与 経路及び有効成分が特定できるレベルのものを意味すると認められるのであり,そ のように解することが,本件発明1の外縁を不明確にするということはできない。 また,原告は,本件明細書の【0040】が「薬効コード」は「何でもよい」と していることを指摘するが,この段落の記載は,本件特許の特許請求の範囲の記載 を超えたものを意味していると認めることはできないから,「何でもよい」というの も,具体的に当該医薬品の薬効,投与経路及び有効成分が特定できるレベルであれ ば「何でもよい」と述べているにすぎないと認められる。 オ その他の原告の主張を採用することができないことは,既に判示したと ころから明らかである。
(4) 以上によると,本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りはなく,それに 基づく相違点1,2についての容易想到性の判断(前記第2の4(1)ウ)も誤りはな いから,取消事由1は理由がない。
3 取消理由2(本件発明9の容易想到性の判断の誤り)について
(1) 原告は,本件審決は,本件発明1の要旨認定を誤った結果,請求項1の従 属項である請求項9に係る本件発明9の要旨認定をも誤り,引用例との一致点,相 違点の認定を誤ったと主張する。 しかし,前記2で判示したところによると,本件発明9と甲1発明には,少なく とも前記第2の4(1)イの相違点1〜4が認められることになる。そして,相違点1 及び2についての容易想到性の判断(前記第2の4(1)ウ)にも誤りがないから,そ の余の点を判断するまでもなく,本件発明9は,当業者が容易に発明をすることが できたものとは認められない。 したがって,取消事由2は理由がない。
(2) なお,原告は,本件発明9は,個別マスタを共通マスタと別に設け,個別 マスタを優先して処理する点において,甲1発明と相違するが,本件審決は,この 点の容易想到性の判断を誤ったものであると主張する。 原告の上記主張は,令和元年12月10日付けの原告準備書面(1)において主張さ れたものではなく,この準備書面に対し,被告らから令和2年2月10日付け被告 ら第1準備書面で反論がされた後の同年3月27日付け原告準備書面(2)において 初めて主張されたものであるから,時機に後れた攻撃防御方法の提出であるが,取 消事由2については,前記(1)のとおり,原告の上記主張について判断するまでもな く判断することができるので,上記主張は,訴訟の完結を遅延させるものではない。 したがって,上記主張を却下することはしないこととする。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.10.12
令和2(行ケ)10021 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年10月8日 知的財産高等裁判所
ウ そして,本願指定商品である翻訳支援ツールも,コンピュータプログラ ムである以上,引用指定商品である「電子計算機用プログラム」に含まれ るから(原告は,この点を争っているようであるが,引用指定商品の「電 子計算機用プログラム」は,特に限定がない以上,コンピュータプログラ ム一般を含むものと解される。そして,翻訳支援ツールも,用途がやや特 殊であるとはいえ,コンピュータを動作させて一定の作業を行うためのプ ログラムである以上,コンピュータプログラムにほかならないのであるか ら,引用指定商品に含まれることを否定することはできない。),本願指定 商品と引用指定商品とは同一であるということになる。 したがって,原告の主張は,既にこの点において失当というべきである が,当事者双方が,本願指定商品である翻訳支援ツールと引用指定商品で ある翻訳ソフトとが類似するかどうかについて争っていることにかんが\nみ,念のため,この点についても判断することとする。
(2) 生産部門及び販売部門について
ア 上記(1)アによれば,翻訳支援ツールは,主に翻訳事業者又は翻訳者が使 用することが想定されている商品であるといえるところ,実際の取引例を みても,翻訳事業者が生産,販売をしている例が多く見受けられる(乙2, 3,7,14)。
イ また,翻訳ソフトは,自動翻訳をすることを主な機能\とするコンピュー タソフトウェアであること(乙6)からすれば,翻訳事業者又は翻訳者の\nみならず,他の事業者や一般の消費者も使用することが想定されている商 品であるといえるところ,実際の取引例をみても,翻訳事業者ではない一 般のソフトウェアメーカーが生産している例や,当該ソ\フトウェアメーカ ー又は家電量販店が販売している例が多く見受けられる(乙8ないし10, 15,16)。
ウ そうすると,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは,生産部門及び販売部門\nが異なることが多いものといえる。 しかしながら,他方で,上記ア及びイで挙げた取引例とは異なり,一般 のソフトウェアメーカーが翻訳支援ツールを生産,販売している例や,翻\n訳事業者が翻訳ソフトを生産,販売している例も見受けられる(乙11な\nいし13)。また,翻訳支援ツールと類似した機能を含む翻訳ソ\フトが,家 電量販店又はそのウェブサイトにおいて販売されている例も見受けられ る(乙13,15,16)。 これらの事情を考慮すると,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの生産部門\n及び販売部門は,必ずしも明確に区別されるものではないというべきであ る。
エ 以上によれば,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは,生産部門及び販売部\n門を共通にする場合があるといえる。
(3) 用途及び機能について\n
ア 上記(1)及び(2)によれば,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは,翻訳者に\nよる翻訳作業を効率化等するためのものであるか,それとも自動翻訳をす るものであるかという点で,主たる用途や機能が異なるものといえる。\n
イ しかしながら,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは,いずれも翻訳作業を\n行うことを目的とし,コンピュータを動作させるためのプログラムである という点においては,用途及び機能を共通にするものといえる。また,翻\n訳支援ツールは,その多くが自動翻訳の機能も有していると認められ(乙\n7,11),他方で,翻訳ソフトには,翻訳支援ツールと類似した機能\や翻 訳支援ツールと連携する機能を含むものがあると認められる(乙8,13)。\nこれらの事情を考慮すると,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの用途や機\n能を厳密に区別するのは困難であるというべきである。\n
ウ 以上によれば,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの用途及び機能\には,共 通する部分があるといえる。
(4) 需要者について
ア 上記(1)アによれば,翻訳支援ツールは,主に翻訳事業者又は翻訳者が使 用することが想定されている商品であるといえるから,その主な需要者は, 翻訳事業者又は翻訳者であるといえる。
イ また,上記(2)イのとおり,翻訳ソフトは,自動翻訳をすることを主な機\n能とするコンピュータソ\フトウェアであることからすれば,翻訳事業者又 は翻訳者のみならず,他の事業者や一般の消費者も使用することが想定さ れている商品であるといえるから,その主な需要者には,広く一般の事業 者及び消費者が含まれるものといえる。
ウ そうすると,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは,主な需要者が異なるこ\nとが多いものといえる。 しかしながら,上記(2)及び(3)で検討したとおり,翻訳支援ツール及び 翻訳ソフトは生産部門及び販売部門を共通にする場合があり,また,用途\n及び機能に共通する部分があるといえることからすれば,翻訳事業者又は\n翻訳者ではない一般の事業者又は消費者が翻訳支援ツールを購入するこ ともあり得るし,これとは逆に翻訳事業者又は翻訳者が翻訳ソフトを購入\nすることもあり得るといえる。そうすると,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの需要者については,上記の範囲で共通することがあるというべきである。\n
エ 以上によれば,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは,需要者の範囲が一致\nすることがあるといえる。
(5) 小括
ア 上記(2)ないし(4)で検討したとおり,翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは,\n生産部門及び販売部門を共通にする場合があるといえること,用途及び機 能に共通する部分があるといえること,需要者の範囲が一致することがあ\nるといえることからすれば,両者に同一又は類似の商標が使用された場合 には,同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認されるおそれ があるというべきである。
イ したがって,翻訳支援ツールである本願指定商品と翻訳ソフトを含む引\n用指定商品は,商標法4条1項11号にいう「類似する商品」に当たるも のと認められる。
(6) 原告の主張について
ア 原告は,翻訳支援ツールである本願指定商品は汎用性のある「電子計算 機用プログラム」ではなく,翻訳ソフトとは根本的に異なるものである旨\n主張する。
イ しかしながら,これまで検討したところに照らすと,翻訳支援ツールが, 自動翻訳を主な機能とするものではなく,翻訳者による翻訳作業を支援す\nるためのものであり,主に翻訳事業者又は翻訳者が使用することが想定さ れている商品であるからといって,直ちに翻訳ソフトとの類似性が否定さ\nれるものではないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2020.10. 7
平成31(ワ)9997 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和2年6月3日 東京地方裁判所
原告は,被告において,対象期間中に,被告商品等を少なくとも100個販売し たと主張するところ,前記第2の2(5)のとおり,被告は平成22年8月11日には バーキンタイプのバッグを販売し,平成30年2月14日には被告商品を販売した ことのほか,被告において,バーキンタイプのバッグは一度に100個単位で仕入 れ,最後の仕入れは平成22年夏ないし秋頃に100個仕入れたものであった,最 後に仕入れた商品は全て販売した旨主張していることからすれば,原告の主張する とおり,被告は,対象期間中に,少なくとも100個の被告商品等を販売したもの と認めるのが相当である。
イ 被告商品等の販売価格
前記第2の2(5)のとおり,被告商品は,平成30年2月に2万8080円(税抜 価格2万6000円)で販売されたものであることに加え,バーキンタイプのバッ グの販売価格に関する当事者双方の主張,被告が保管期間の経過により廃棄済みと してバーキンタイプのバッグの販売に関する資料を提出していないことなどの本件 の審理に現れた事情を総合すれば,被告商品等の1個当たりの販売価格は,平均す ると,被告商品の販売価格と同じく税抜価格2万6000円程度であったものと認 めるのが相当である。
ウ 被告商品等の総販売額
被告は前記イの税抜価格に消費税を付して被告商品等を販売していたところ(甲 1,弁論の全趣旨),被告の総販売額を算定するに当たって適用すべき消費税率につ いては,被告がバーキンタイプのバッグの販売を平成26年2月頃までに終了した と主張していることや平成30年2月14日に販売された被告商品のほかに平成2 6年3月以降に被告商品等が販売されたことを示す証拠がないことを踏まえ,販売 に係る100個のうち99個については平成26年2月までの5%とし,1個につ いては8%とすることが相当である。 そして,前記ア及びイによれば,対象期間中の被告商品等の販売によって,被告 は,以下のとおり,合計273万0780円の売上を上げたものと認めるのが相当 である。
2万7300円(税抜価格2万6000円+5%の消費税分)×99個+2万8 080円(税抜価格2万6000円+8%の消費税分)×1個=273万0780 円
エ 被告商品等の販売に係る限界利益率
(ア) 仕入費用
被告は,被告商品はサンプル品であって仕入処理が行われておらず,購入した際 の領収証等の資料もないと主張し,また,バーキンタイプのバッグの仕入れに関す る資料は保管期間経過によって全て廃棄処分済みであるとして,これを提出してい ない。 被告は,バーキンタイプのバッグの仕入価格について,同程度の価格のハンドバ ッグの仕入価格が販売価格の55%程度であったから,バーキンタイプのバッグの 仕入価格も同様であったと主張し,販売価格の55%の価格で仕入れを行った平成 29年1月の取引の納品書(乙31)を提出するが,被告が平成22年に中国のハ ンドバッグ製造業者から100個単位で仕入れたと主張するバーキンタイプのバッ グとは,仕入の時期,取引先,仕入数が異なり,どのような商品の仕入れであった かも明らかではないから,上記の納品書に係る取引は,バーキンタイプのバッグの 仕入価格が販売価格の55%であったことを裏付けるものとはいえず,その他,被 告が主張する仕入価格を裏付ける的確な証拠はない。
(イ) その他の経費 被告が,その他の経費として主張するバザーへの寄付金,梱包費用,送料につい ては,具体的な支出の有無や額を裏付ける的確な資料はない。
(ウ) 限界利益率
このような被告の主張立証の状況を含めた弁論の全趣旨によれば,被告商品等の 販売による被告の限界利益は,原告の主張するように,平均して販売価格の60% 程度であったものと認めるのが相当である。
オ 被告が賠償すべき利益の額
以上によれば,対象期間中の被告商品等の販売によって,被告には,以下のとお り,少なくとも163万8468円の限界利益が発生したものと認めるのが相当で あり,同額が,不競法5条2項により被告が賠償すべき損害額となる。 273万0780円×60%=163万8468円
(2) 信用毀損による無形損害について
前記2及び前記(1)で検討したところからすれば,原告商品は,高級ブランドであ る原告を代表する高級バッグとして著名なものであり,そのほとんどが1個100万円を超える価格で販売される高級品であったところ,被告は,原告商品と類似す\nる形態を持ちながら,原告商品には使用されない合成皮革等の安価な素材が使用さ れた被告商品等を,原告商品と比べて著しい廉価の1個2万7300円程度で,平 成22年8月から平成30年2月までの期間に少なくとも100個販売したもので ある。
したがって,被告商品等の販売という不正競争によって,原告は原告商品に係る 信用を毀損されたものというべきであり,原告商品の形態と類似する外見のハンド バッグが被告以外の業者によっても販売されていること(乙1〜17)といった被 告の主張する事情を考慮しても,被告商品等の販売に係る,信用毀損による無形損 害の額は100万円を下らないというべきである。
関連カテゴリー
>> 立体商標
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.10. 7
平成30(ワ)34729 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年2月26日 東京地方裁判所
ア 特許法101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」の判断基準
特許法101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは,従来技術の 問題点を解決するための方法として当該発明が新たに開示する従来技術にみられな い特徴的技術手段について,当該手段を特徴付けている特有の構成を直接もたらす特\n徴的な部材等を意味すると解するのが相当である。
イ 本件発明が開示する特徴的技術手段 前記(1)の本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,従来技術の問題点及びそ れを解決するための方法として本件発明が開示する特徴的技術手段は次のとおりで ある。すなわち,従来技術において,裏面を上向きにして載置された半導体基板にレ ーザを照射して基板内部に改質領域を形成し,1)その後,基板を研削して薄くし,半 導体基板の裏面にエキスパンドテープを装着し,エキスパンドテープを伸張させるこ とで改質領域を基点として基板を割ることや,2)改質領域を形成することにより半導 体基板の厚さ方向に割れを発生させ,基板の裏面を研削及びケミカルエッチングする ことで割れを裏面に露出させることで,半導体基板をチップに切断することが行われ ていたが,これらの従来技術においては,チップ断面の改質領域の部分から発塵する 場合やチップが破断する場合があり,チップの抗折強度が小さくなるという問題点が あるほか(段落【0010】),上記2)の従来技術においては,改質領域から必ずしも 自然に割れが発生しない場合もあるといった問題点や,熱応力を利用する場合の問題 点(段落【0011】,【0012】),ケミカルエッチングを行うことに伴う問題点(段 落【0013】〜【0020】)及び基板の裏面を研削して改質領域から割れを発生さ せる際に,基板の固定方法が開示されていないという問題点(段落【0021】)があ る。そして,上記問題点を解決し,割断を確実に効率よく行って,安定した品質のチ ップを効率よく得るという効果を奏する(段落【0026】)ものとして,レーザ光に より形成された改質領域内のクラックを研削により進展させて改質領域がウェーハ の断面に残らないようにする実施形態(段落【0155】)や,研削中に亀裂が進展す るものの研削後完全に基板が分割されていない状態が保たれ,その後割断工程を経て ウェーハを効率よく割断することができる実施形態(段落【0181】,【0182】)がそれぞれ開示されている。
そうすると,本件発明は,ウェーハを割断する技術において,レーザ光により既に 内部に改質領域の形成されているウェーハの割断に当たり,従来技術における上記の 各問題点を解決するために,ウェーハの裏面を研削することにより,改質領域から延 びた微小亀裂をウェーハの表面に到達させずに進展させるようにコントロールしつ\nつ,改質領域を除去する点にその技術的意義を有するものであるということできる。
以上によれば,従来技術の問題点を解決するために本件発明が開示する特徴的技術 手段は,構成要件Bに係る改質領域が形成されたウェーハの「裏面を研削することに\nより,前記改質領域から延びた微小亀裂を前記ウェーハの表面に到達しない位置まで\n進展させつつ前記改質領域を取り除く研削手段」の構成であるということができる。\n
ウ 被告各製品が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するかについて 前記第2の1(5)のとおり,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,あくまでウ\nェーハの内部にレーザ光で改質領域を形成するための装置であって,前記イの本件発 明の特徴的技術手段の構成を直接実現する装置ではない。そうすると,被告各製品は,\n本件発明による課題の解決に不可欠なものに該当するとはいえない。
◆判決本文
原告被告か同じ事件は以下です。こちらは本件特許が異なり、また、東京地裁47部の判断です。
◆平成30(ワ)34728
控訴審でも同様の判断がなされています。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> 不可欠性
>> ピックアップ対象
2020.10. 7
平成30(ワ)39343 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年2月14日 東京地方裁判所
被告会社の運営する本件各ウェブサイトは,本件各漫画のような同人誌に 限らず,アニメ,ゲーム,小説など多様なジャンルの作品を掲載し,甲9の 1に「1万冊以上全部無料で読めちゃう」と記載されているように,多量の 作品を無料で閲覧し得ることを特徴とするサイトであると認められる(甲9, 42)。このため,本件各漫画のような同人誌の愛好者にとどまらず,多数 の者が同サイトを訪問し,その際に,購入する意図なく掲載作品を閲覧する ことも少なくないものと推測される。
他方,本件各漫画は,その内容等にも照らし,その需要者の範囲は限定さ れている上,その販売形態は即売会による販売と同人誌の通信販売を手がけ る出版社による委託販売によるものであり,即売会による販売が全体の約3 分の1を占める(甲56)。また,その販売数は,作品の発売後数か月間の 販売数が多く,その後の月間販売数は急激に減少するという傾向が看取され, 一定数の販売が継続するものではない(甲52〜55)。 そして,本件各漫画のPV数と同各漫画の販売実績(甲56)を比較する と,本件各漫画のPV数の合計が11万7318(上記認定に係る1冊分の PV数の合計は7万6738)であるのに対し,本件各漫画の販売総数は8 513冊であり,1冊分のPV数をとってみても,その販売総数はPV数の 約9分の1程度であると認められる。 以上のとおり,本件各ウェブサイトによる閲覧と原告による本件各漫画の 販売とでは,その需要者の範囲,閲覧又は販売する作品の数及び種類等が大 きく異なるほか,本件各漫画は販売直後に多くが販売される傾向にあること や,本件各ウェブサイトは無料で閲覧を可能にするものであり,作品を購入\nする意図なくその内容を閲覧する需要者は少なくないものと考えられ,実際 のところ,同一の漫画についてPV数と販売実績には大きな差があることな どに照らすと,本件各漫画のPV数のうち,原告が販売し得たと認め得る数 量は,その1割であると認めるのが相当である。 638/089638
2020.10. 7
令和1(ワ)8916 商標権 令和2年9月17日 大阪地方裁判所
以上によれば,「ジルコニアバー」という名称は,平成27年の時点において, 材質を表す「ジルコニア」と,ハンドピースの先に用いる先端部品であることを指\nす「バー」という2つの単語を組み合わせた名称であって,そのいずれの意味も一 般的に知られていたところ,特に歯科技工用切削,研磨用品の需要者,取引者にと っては,この名称から,ジルコニアを研磨剤として使用する先端部品であることを 容易に認識,理解することができるものであったと認められる。
(3) 被告による被告標章の使用態様について
被告は,前記認定のとおり,歯科医院向け技工用器材その他を販売する被告のウ ェブサイトにおいて,ハンドピース用の器材であるとして,被告商品のカテゴリー 名,各商品の名称の一部及び販売名として,被告標章を表示していたものであって,\n他のカテゴリーに属する被告の商品として,「ダイヤモンドバー」,「カーバイド バー」,「スチールバー」その他があることを前提に,普通の字体で表示していた\nにすぎない。
以上によれば,被告標章の記載は,平成27年の時点において,被告商品の原材 料及び用途又は形状を「普通に用いられる方法で表示する」にすぎないものであっ\nたと認めることができる。
2020.09.29
令和1(行ケ)10171 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年9月24日 知的財産高等裁判所
商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された 場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否か によって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外観,観念,称 呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべ く,しかも,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その 具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行 ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁, 最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集5 1巻3号1055頁参照)。 また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構\成部 分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分 的に結合していると認められる場合においては,その構成部分の一部を抽出し,\nこの部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは,原則として許さ れないが,その場合であっても,商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に\n対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や, それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じない場合などには, 商標の構成部分の一部だけを取り出して,他人の商標と比較し,その類否を判\n断することが許されるものと解される(最高裁昭和37年(オ)第953号同 38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成 3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5 009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷 判決・裁判集民事228号561頁参照)。 なお,出所識別標識としての印象を与える機能を,以下「識別力」という。\n
3 本願商標の要部
原告は,本願商標の構成は,不可分一体のものであって分離観察をすること\nは許されないと主張する。 そこで検討するに,まず本願商標の外観を見ると,同一の色の「甘味」の文 字部分と「おかめ」の文字部分とが,間隔を空けながらも一列に配置され,そ の背景に,上記各文字部分と一部重なるような形で,より淡色ではあるものの, 同系統の色で表された家紋様の図形部分が配置され,一体としてまとまりのあ\nる外観を呈しているといえなくもない。しかし,その一体性はさほど強いもの ではなく,むしろ,「甘味」の文字部分と「おかめ」の文字部分とは,字の大 きさも太さも全く異なっている上,かなり広い間隔を置いて配置されているた め,それほど統一感があるとはいえないし,図形部分も各文字部分を有機的に 結合させるほどの機能を果たしているとは見えず,むしろ,背景の装飾といっ\nた程度の機能を果たしているのにすぎないと見える。そうであるとすると,本\n願商標の外観の構成は,分離観察を不可能\とするほどの一体性を有していると は認められない。
原告は,「おかめ」という屋号の甘味処を経営しているところ,本願商標の 文字部分は「甘味おかめ」という屋号を示し,図形部分は,その家紋を示して いるから,本願商標は,全体として,おかめという屋号の甘味処という観念を 有すると主張し,この主張は,本願商標が上記のような観念において不可分一 体性を有するという趣旨にも受け取れる。しかし,甘味を提供する飲食店にお いて,屋号と家紋を一体的に組み合わせた商標を用いることが一般的に行われ ていると認めるに足りる証拠はないし,本願商標が,原告の屋号と家紋を表し\nた商標として著名であると認めるに足りる証拠もない。そうすると,本願商標 に接した需要者が,本願商標を甘味処の屋号とその家紋を一体として表した商\n標であると観念するとはいえないから,原告の主張は失当である。そして,他 に,本願商標が,分離観察を許さないほど不可分一体であると認めるに足りる 証拠はない。
そうすると,本願商標は分離観察をすることも許されるものというべきとこ ろ,本願商標のうち,「おかめ」の文字部分は,大きな字体の太字で書かれて おり,目立つものである上,自他商品識別力も有するといえるから,この部分 を要部として抽出することも許されるものというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.09.29
平成27(ネ)10069 売買代金請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年12月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 本件基本契約18条2項に基づく義務
ア 本件基本契約は,控訴人と被控訴人との間の物品の売買取引に関する基本的 事項を定めるものであるところ,18条1項は「被控訴人は,控訴人に納入する物 品並びにその製造方法及び使用方法が,第三者の工業所有権,著作権,その他の権 利(総称して「知的財産権」という。)を侵害しないことを保証する。」旨,同条 2項は「被控訴人は,物品に関して知的財産権侵害を理由として第三者との間で紛 争が生じた場合,自己の費用と責任においてこれを解決し,または控訴人に協力し, 控訴人に一切迷惑をかけないものとする。万一控訴人に損害が生じた場合,被控訴 人はその損害を賠償する。」旨規定する。そして,本件基本契約には,他に知的財 産権侵害を理由とする第三者との間の紛争に対する解決手段・解決方法等について の具体的な定めがないことからすれば,同条2項は,同条1項により,被控訴人は, 控訴人に対し,その納品した物品に関しては第三者の知的財産権を侵害しないこと を保証することを前提としつつ,第三者が有する知的財産権の侵害が問題となった 場合の,被控訴人がとるべき包括的な義務を規定したものと解するのが相当である。
イ この点,被控訴人は,本件基本契約18条2項は「自己の費用と責任におい てこれを解決」する債務と,「控訴人に協力し,控訴人に一切の迷惑をかけない」 債務を選択的に規定したものであり,選択権を有する被控訴人は,前者の債務を選 択したから,本件紛争の解決権は被控訴人に留保されていたものであると主張する。 しかし,本件紛争の解決権が被控訴人に留保されていたことを認めるに足りる証 拠はなく,同項の文言から被控訴人が選択権を有すると解することはできない。 ウ 一方,控訴人は,被控訴人が,本件基本契約18条2項に基づき,少なくと も1)第三者が保有する特許権を侵害しないこと,具体的には納入した物品が特許請 求の範囲記載の発明の技術的範囲に含まれないことや,当該特許が無効であること などの抗弁があることを明確にし,また,2)当該第三者から特許権の実施許諾を得 て,当該第三者に対してライセンス料を支払うなどして,当該第三者からの差止め 及び損害賠償請求により控訴人が被る不利益を回避する義務を負っていたと主張す る。 しかし,同項の文言のみから,直ちに被控訴人の負うべき具体的な義務が発生す るものと認めることはできず,上記のとおり,同項は,被控訴人がとるべき包括的 な義務を定めたものであって,被控訴人が負う具体的な義務の内容は,当該第三者 による侵害の主張の態様やその内容,控訴人との協議等の具体的事情により定まる ものと解するのが相当である。
(3) 本件基本契約18条2項に基づく被控訴人の具体的義務について
ア 前記のとおり,控訴人はWi−LAN社から,本件各特許権のライセンスの 申出を受けていたこと(前記前提事実等(8)及び前記(1)イ。なお,Wi−LAN社 のライセンスの申出が,本件チップセットあるいは本件製品を問題としていたのか,\n控訴人のサービスを問題としていたのかは,証拠上,明らかでない。),控訴人は, 被控訴人に対し協力を依頼した当初から,本件チップセットが本件各特許権を侵害 するか否かについての回答を求めていたこと(前記(1)ア),被控訴人,控訴人及び イカノス社の間において,ライセンス料,その算定根拠等の検討が必要であること が確認され,イカノス社において,必要な情報を提示する旨を回答していたこと(前 記(1)タ)に鑑みれば,被控訴人は,本件基本契約18条2項に基づく具体的な義務 として,1)控訴人においてWi−LAN社との間でライセンス契約を締結すること が必要か否かを判断するため,本件各特許の技術分析を行い,本件各特許の有効性, 本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否か等についての見解を,裏付けと なる資料と共に提示し,また,2)控訴人においてWi−LAN社とライセンス契約 を締結する場合に備えて,合理的なライセンス料を算定するために必要な資料等を 収集,提供しなければならない義務を負っていたものと認めるのが相当である。
イ 控訴人は,この点について,被控訴人が自ら又はイカノス社をして,Wi− LAN社から特許権の実施許諾を得てライセンス料を支払うことにより,控訴人が 被る不利益を回避する義務をも負っていたと主張する。しかし,前記(1)で認定した 被控訴人と控訴人との間の交渉の経緯及び内容,並びに前記1説示のとおり,本件 ライセンス契約が締結される以前はおろか,現段階に至っても,本件チップセット が本件各特許権を侵害するか否かは明らかではないことに鑑みても,本件基本契約 18条2項に基づく具体的な義務として,被控訴人において,自ら又はイカノス社 をして,Wi−LAN社との間でライセンス契約を締結すべきであったとまで認め ることはできない。
(4) 被控訴人の義務違反について
ア 技術分析の結果を提供すべき義務について
(ア) イカノス社は,平成23年8月及び同年11月,控訴人に対し,技術分析 の結果を報告している。しかし,まず,同年8月の報告(乙20)の内容は,前記 (1)トで認定したとおり,別件特許については,これらの技術を使用していないとの 報告がされたものの,本件特許1,2,4,6及び9については,これらの特許が DSLAMに関連する特許であり,イカノス社が提供したCPEの機能に必要な技\n術とは無関係であるとの報告がされたのみで,これらの技術を使用しているのか否 かについての報告がなく,本件特許3,5,7及び8については何らの報告もなかっ た。また,同年11月の報告(乙21)の内容も,前記(1)ノで認定したとおり,別 件特許については,これらの技術を使用していないとの報告がされたものの,本件 各特許については,DSLAM送信機の請求項である,CPEの請求項と思われる, DSLAMの実装に固有の要素であり,CPEの実装には見られない要素であるな どという程度の,簡単な意見を付したものにすぎず,およそ本件各特許の有効性や 充足性を判断できる程度の内容とはいえないものであった。そして,被控訴人自ら は,詳細な技術分析を行ったものとはいえないし,本件証拠上,上記イカノス社の 意見を客観的に裏付ける資料の存在も認めることはできない。
(イ) 被控訴人の主張について
a 被控訴人は,この点について,イカノス社において詳細な分析ができなかっ たのは,控訴人が部品表等の必要な資料を提供しなかったことが原因であると主張\nする。 確かに,イカノス社は,被控訴人を介して,控訴人に対し,控訴人の部品表等の\n資料の開示を求めていたものの(前記(1)ケ),本件各特許の有効性,本件チップセッ トが本件各特許権を侵害するか否か等を調査するに当たっての上記資料の必要性は 必ずしも明らかではない。そして,前記(1)ケのとおり,開示を求められた控訴人に おいても,上記資料の必要性に疑問を呈し,イカノス社に対してその意図を確認す るよう被控訴人に求めているところ,イカノス社から上記資料の必要性について回 答がされたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると,単にイカノス社が上記 資料の開示を求めていたというだけでは,技術分析における上記資料の必要性を認 めることはできない。
b また,被控訴人は,平成23年10月12日の三者間協議において,Wi− LAN社が,本件チップセットではなく,控訴人の提供するシステムがAnnex. C関連の特許を侵害する旨の主張をしているとの報告がされ,本件チップセット以 外の部分が本件各特許権を侵害しているか否かを検討する必要が生じていたことを 受けて,イカノス社は,控訴人に対し,Wi−LAN社の特許が控訴人のサービス に関連するか否かについての控訴人の解析を共有することを求めたが,控訴人はこ れを拒否したのであって,このように,イカノス社において詳細な技術分析を行う 前提として,回路図等の資料が必要であった旨主張する。 しかし,イカノス社が,被控訴人を介して,控訴人に対し,控訴人の回路図等の 資料の開示を求めたのは,同年2月22日であり(前記(1)ケ),被控訴人から,W i−LAN社が,本件チップセットではなく,控訴人の提供するシステムがAnn ex.C関連の特許を侵害する旨の主張をしているとの報告がされた同年10月1 2日(前記(1)ヌ)よりも前であって,上記資料の開示を求めた時点においては,被 控訴人からは,本件各特許の有効性,本件チップセットが本件各特許権を侵害する か否か等を調査するに当たっての上記資料の必要性が何ら示されていない。そして, 控訴人が,被控訴人及びイカノス社との協議開始当初から,イカノス社に要請して いたのは,本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否かについての技術分析 であって(前記(1)ウ),本件チップセット以外の控訴人の提供するシステムが本件 各特許権を侵害するか否かについての技術分析ではないのであるから,イカノス社 が,同年10月26日に,本件各特許が控訴人のサービスに関連するか否かについ ての控訴人の分析の共有を求めたのに対して,控訴人がこれを拒否しているからと いって(前記(1)ネ),本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否かについて のイカノス社による技術分析が不可能になるということはできない。\n
c さらに,被控訴人は,イカノス社製のDSLAM用チップセットが初めて控 訴人に納入されたのは平成23年12月以降のことであるから,イカノス社が技術 分析の結果を提示した同年7月ないし11月の時点において,本件各特許がDSL AMに関連するものであることが分かれば,本件チップセットが本件各特許権を侵 害するか否かに関する見解をそれ以上示す必要はなかった旨主張する。 しかし,イカノス社の報告(乙20,21)自体が客観的な資料により裏付けら れたものとはいえないことは,前記(ア)のとおりである。そして,前記前提事実等 (3)及び(5)のとおり,ADSLサービスにおいてはADSLモデム用及びDSLA M用のいずれのチップセットも使用されるところ,控訴人と被控訴人は,平成22 年12月から控訴人のADSLサービスに係るWi−LAN社との間の本件紛争に ついて協議を重ねていたこと(前記(1)ア),控訴人が,平成23年5月の時点で, 被控訴人に対してDSLAM用チップセットを発注していることに鑑みれば,被控 訴人及びイカノス社は,遅くとも,平成23年11月に行った技術分析結果の報告 の際には,本件DSLAM用チップセットに関してもその見解を示す必要があった ものと認めるのが相当である。
d 被控訴人は,この点について,控訴人作成に係る平成23年5月12日付け DSLAM用チップセットの注文書(甲2)に記載されているように,DSLAM 用チップセットについては,別途協議の上で対応するとして,本件基本契約18条 2項とは別の枠組みで解決されることが,控訴人及び被控訴人の間で合意されてい たのであるから,本件基本契約18条2項を根拠に,本件DSLAM用チップセッ トについても見解を示す義務を負うとすることはできない旨主張する。 確かに,控訴人作成に係る平成23年5月12日付けDSLAM用チップセット の注文書(甲2)の「その他の条件」欄には,「※本注文(Last Time B uy)に対する附帯条件」として,「4:注文日現在,Wi−LAN社と協議中の ライセンス費用は含まれていない。同費用が発生する場合は別途協議の上対応。」 と記載されている。しかし,同日の時点においては,控訴人及び被控訴人間で,W i−LAN社とのライセンス交渉に対する協議が継続しており,Wi−LAN社と の間でライセンス契約を締結してライセンス料を負担することとなった場合には, 本件基本契約18条2項に基づいて,被控訴人にも費用負担が生じ得ることとなる。 甲2の上記記載は,この点を明らかにするために,DSLAM用チップセットの販 売価格にはWi−LAN社と協議中のライセンス費用は含まれていないこと,同費 用が発生した場合には別途協議の上対応することを確認したものにすぎないという べきであって,上記DSLAM用チップセットの注文について,本件基本契約18 条2項の適用がないことを規定したものということはできない。
e 以上によれば,被控訴人の前記各主張は,いずれも採用することができない。
(ウ) 以上のとおりであるから,イカノス社において報告された技術分析の結果 は十分なものであるとはいえず,その他,本件証拠上,被控訴人又はイカノス社が,\n本件各特許の有効性や本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否か等につい ての見解を,裏付けとなる資料と共に提示したものと認めることはできないから, 被控訴人はこれを提供する義務を怠ったものというべきである。
イ ライセンス料の算定に関する情報を提供すべき義務について
(ア) 控訴人が,ライセンス料の算定に関する情報を必要としていたことは,前 記(1)タ,チ及びテで認定したとおりであるところ,これに対し,イカノス社は,本 件各特許に対する標準的な料率に関する情報を提示することを述べたものの,結局, 合理的なロイヤルティ率については,具体的な数字を提示することは困難であると して,提示することができず,次に,コネクサント社製のチップセットに適用され るロイヤルティ率に基づく検討を提案し,同ロイヤルティ率を突き止めようとした が,これについても新たな情報を発見することができなかったと報告するにとど まっている(前記(1)テ)。また,被控訴人自身は,ライセンス料の算定に関する情 報の提供をしていない。 そうすると,被控訴人又はイカノス社から,控訴人に対し,ライセンス料の算定 に関する情報が提供されたと認めることはできない。
(イ) これに対し,被控訴人は,本件各特許についてはITUにFRAND宣言 がされており,Wi−LAN社において,控訴人に対しライセンス料を算定するた めの情報を提供すべき義務があるから,Wi−LAN社から合理的なロイヤルティ の情報が得られれば,もはや被控訴人においてかかる情報を提供する必要はなかっ たし,被控訴人は,平成23年8月の時点で,合理的なロイヤルティが1000万 円程度であることを認識した上で,既にWi−LAN社に伝えているのであるから, 被控訴人においてライセンス料の算定根拠となる資料を提供する義務が生じること はない旨主張する。 しかし,被控訴人が,本件基本契約18条2項に基づき,上記情報を提供する義 務を負うことと,Wi−LAN社に上記情報を提供する義務があるか否かとは無関 係であるから,この点に関する被控訴人の主張は失当である上,Wi−LAN社か らかかる情報が提供されていない以上,被控訴人から情報を取得する必要があった ことは明らかである。そして,控訴人が,Wi−LAN社に対し,合理的なロイヤ ルティは例えば11万USドルから12万USドルの範囲内にあるべきことを主張 したこと(前記(1)ト)に対して,Wi−LAN社からは,本件紛争の解決に対する 見解には大きな隔たりがあるとして,早期解決をする場合にはどの程度の金額の提 示が可能かを2週間以内に連絡するよう,2週間以内に回答がない場合には自動的\nに早期ライセンス交渉は終了するなどと,更なる要請を受けるなどしていること(前 記(1)ナ)からすれば,控訴人には,被控訴人からの合理的なライセンス料の算定根 拠となる資料の提供が必要であったというべきである。 したがって,被控訴人の上記主張は,採用することができない。
(ウ) 被控訴人は,仮に,被控訴人にライセンス料を算定するための情報を提供 する義務があったとしても,継続的にコネクサント社やイカノス社へ情報提供を要 求していたから,この義務を果たしていたと主張する。
しかし,本件基本契約18条2項に基づく被控訴人の義務は,単なる努力義務で はない。また,控訴人は,本件訴訟において,ライセンス料の算定に関する資料と して,1)Wi−LAN社の提示した特許のロイヤルティ料率に関する実例,2)イカ ノス社が第三者と締結しているライセンス契約におけるロイヤルティ料率の実例, 3)Wi−LAN社が提示した特許と同様の特許権に関する標準的なロイヤルティ料 率を示す実例その他の資料を挙げているところ(これらがおよそ不合理なものとは いえない。),イカノス社が第三者と締結しているライセンス契約におけるライセ ンス料率の実例はイカノス社に回答を委ねるとしても,例えば,本件各特許のライ センス料に関する実例や,本件各特許と同様の特許権に関する標準的なライセンス 料率の資料などは,被控訴人において,自ら,又はコネクサント社及びイカノス社 以外の他社の協力を仰ぎ,資料の収集,調査等を行うことが不可能なものとはいえ\nないから,コネクサント社やイカノス社に対して継続的に情報提供を要求しただけ ではおよそ最善を尽くしたとはいえない。 被控訴人は,この点について,特許ライセンス契約においては守秘義務条項が設 けられており,特に対価や実施料率に関する事項については第三者に開示すること が許容されていないのが一般的であるから,他社の協力を仰いだとしても,資料の 収集を行うことは事実上不可能である旨主張する。しかし,被控訴人において,自\nら,又はコネクサント社及びイカノス社以外の他社の協力を仰いだ事実があること についての具体的な主張立証もない以上,合理的なライセンス料を算定するための 資料の提供義務を負う被控訴人として,およそ義務を果たしたものということはで きない。
(エ) 以上によれば,被控訴人は,控訴人においてWi−LAN社とライセンス 契約を締結する場合に備えて,合理的なライセンス料を算定するための資料を提供 すべき義務を怠ったものといえる。
ウ 小括 以上のとおり,被控訴人は,前記(3)アの1)及び2)の義務をいずれも怠ったもので あり,被控訴人には本件基本契約18条2項の違反がある。
3 争点3(相殺の成否)について
(1) 被控訴人による本件基本契約18条2項違反と控訴人がWi−LAN社に 支払ったライセンス料2億円相当額の損害との間の相当因果関係の成否 ア 控訴人は,平成24年2月23日,Wi−LAN社との間で,本件ライセン ス契約を締結し,同年3月16日,同社に対してライセンス料として2億円を支払っ た。
確かに,前記1のとおり,本件口頭弁論終結時においても,本件チップセットが 本件各特許権を侵害するものであると認めるに足りる証拠がない以上,結果的に見 れば,本件ライセンス契約が締結された時点において,控訴人がWi−LAN社と の間でライセンス契約を締結し,ライセンス料として2億円を支払う必要性があっ たということはできない。 イ しかし,以下の事情を総合すれば,被控訴人による本件基本契約18条2項 違反と,控訴人のライセンス料相当額の損害との間には,相当因果関係を認めるこ とができる。
・・・
(オ) そうすると,控訴人は,未だWi−LAN社による違反調査等が行われる 第2ラウンドに移行しておらず,直ちに差止請求を含む訴訟提起がされる危険性が あるとはいえない状況において,Wi−LAN社からは,本件チップセットが本件 各特許権を侵害していることについて,技術分析の結果等の客観的資料に基づく具 体的根拠が示されているわけではなく,控訴人において,本件チップセットの構成・\n動作と本件各特許発明の各構成要件を逐一吟味した資料等に基づいて,その充足性\nを検討することなく,イカノス社による技術分析への対応等から本件チップセット が本件各特許権を侵害する又は侵害する可能性が高いと考え,算定根拠が明らかで\nはないWi−LAN社のライセンス料の提示に対して,その内容を質すこともなく, また,本件ライセンス契約直前にされた被控訴人による制止を顧慮することなく, 本件ライセンス契約を締結し,ライセンス料2億円を支払ったことになる。この点 については,拙速との評価を免れず,控訴人にも,損害の発生について,過失があ るといわざるを得ない。
イ そして,上記アにおいて説示した事情,前記(1)イ(ア)のとおり,本件ライセ ンス契約の対象には,本件各特許以外の特許が含まれていること,その他本件訴訟 に顕れた一切の事情及び弁論の全趣旨を勘案すれば,損害の発生に対する過失割合 は,控訴人が7割,被控訴人が3割と認めるのが相当である。 ウ したがって,控訴人の被控訴人に対する本件基本契約18条2項の債務不履 行に基づく損害賠償債権を自働債権とし,被控訴人の控訴人に対する本件各物品の 売買契約の代金債権を受働債権とする相殺の意思表示は,2億円の3割である60\n00万円の限度でその効力が生じるものというべきである。
◆判決本文
原審はこちらです。
2020.09.26
平成29(ワ)22010 実用新案権侵害差止等請求事件 実用新案権 民事訴訟 令和2年2月5日 東京地方裁判所
ア 構成要件Dは,取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け,「口紐により取出し筒から引き出した命綱の周囲を緊縛して,取出し筒の開口部を密閉する」というも\nのであり,それによって,取出し筒から空気が漏れるのを防止し,冷却効率を損な わないという作用効果を奏するものであるところ(前記1(1)ア(イ)),上記の「緊 縛」については,「きつくしばること」という一般的な字義(乙1)のとおり,口 紐により命綱の周囲をきつく縛ることを意味すると解するのが相当である。
イ 被告は,「緊縛」は,口紐を取出し筒の先端部に巻き付け,その両端を絡ま せてつなぎ合わせることを意味すると解すべきであるとし,その理由として,1) 「縛る」に「ひもや縄などを巻き付けて結び,離れたり,動いたりしないようにす る」という字義があり,「結ぶ」に「ひも・帯などの両端をからませてつなぎ合わ せる」という字義があること,2)本件明細書の図4に,口紐を筒部先端部に巻き付 け,その両端を絡ませてきつく縛り,筒部の開口部を密閉する態様の実施例が示さ れていることなどを主張する。 しかしながら,被告が主張するような態様によらなくとも,筒部の開口部を密閉 することによって,取出し筒から空気が漏れるのを防止し,冷却効率を損なわない という作用効果を奏することは可能であると考えられるところ,上記1)については, 「緊縛」の一般的な字義を離れて,その意味を過度に限定するものであり,上記2) についても,実施例にすぎず,本件明細書の考案の詳細な説明において,口紐を筒 部先端部に巻き付け,その両端を絡ませてきつく縛る態様のものでなければならな いとする説明もみられないことなどに照らせば,いずれの主張も採用することはで きず,「緊縛」がそのような態様のものに限定されると認めることはできない。
(2) 被告製品
これを被告製品についてみると,前記第2の2(6)のとおり,被告製品は,ランヤ ード取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け,「口紐をランヤード取出し筒から引き 出したランヤードの周囲に巡らせ,コードストッパーを用いて筒部先端部分を収縮 させることにより,ランヤードを固定して,ランヤード取出し筒の開口部を密閉す る」という構成(構\成d)を有するところ,コードストッパーを用いるものであっ たとしても,口紐により命綱の周囲をきつく縛ることにより,筒部の開口部を密閉 するものである認められるから,構成要件Dを充足する。したがって,被告製品は,文言上,本件考案の技術的範囲に属する。\n 3 争点3(被告製品3及び6は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物か)について
前記第2の2(6)イ認定のとおり,被告製品3及び6は,服本体のみで販売されて いる製品であり,ファン等を取り付け又は収納することによって,本件考案の技術 的範囲に属する被告製品と同様の構成を備えるものとなると認められるから,被告製品と同様に,構\成要件Dを充足する。
そして,被告製品3及び6は,ハーネス型安全帯を着用できるようにするために 空調服の背中部分にランヤード取出し筒を設けたものであり,そのような構成を有しない通常の空調服と比べて販売単価が高いものであること,具体的には,前記1\n(1)カ(イ)認定のとおり,被告各製品の販売単価とこれらに対応するものとして被告 が販売している通常の空調服の販売単価を対比すると,被告製品1及び4は約1 5%,被告製品2及び5は約23%,被告製品3及び6は約48%割高であること, 同(ウ)認定のとおり,被告の空調服のカタログに,「ウェアのみ」の製品は「洗い 替え用やファン・バッテリーなどをお持ちの方向けのウェアのみです。」と記載さ れ,被告製品3及び6は「フルハーネス安全帯着用者専用空調服です。背中部分か らランヤードを取り出すことができます。もちろん空気は逃がしません。・・・」など と記載されていることなどからすると,被告製品3及び6は,ハーネス型安全帯を 着用するために販売されている製品であると認めるのが相当であり,ハーネス型安 全帯を全く利用しない使用形態は,経済的,商業的,実用的な用途として想定され ていないというべきであるから,本件登録実用新案に係る物品である被告製品の製 造のみに用いるものと認めるのが相当である。 したがって,被告製品3及び6は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物(実用新案法28条1号)に当たる。
・・・
5 争点5(被告は先使用による通常実施権を有するか,又はセフト社の先使用 による通常実施権を援用することができるか)について
(1) 被告各製品の製造等に関し,被告らが先使用による通常実施権を有するとい うためには,被告らにおいて考案の実施である「事業の準備」(実用新案法26条, 特許法79条)をしていたこと,すなわち,その考案につき,いまだ事業の実施の 段階には至らないものの,即時実施の意図を有しており,かつ,その即時実施の意 図が客観的に認識される態様,程度において表明されていることを要するものと解される(特許法79条に関する最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日\n第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照)。
(2) これを本件についてみると,本件出願日までの被告らにおけるフルハーネス 対応空調服の開発状況等は前記1(1)エ認定のとおりである。すなわち,1)被告ら代 表者は,平成27年3月3日頃,背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け,その先端部分を紐様のものなどを用いて縛る構\成を有する空調服に係る着想を得て,その構成を手書きで図示した乙11図面を作成し,同月4日,そのデータをゼハロスに送信して,試作品の作成を依頼したこと,2)ゼハロスは,同月31日までに, 背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け,その先端部分を紐及びコードストッ パーを用いて縛る構成を有しており,被告各製品と同様の構\成を有する本件試作品 を作成したこと,3)被告らは,同年4月7日,被告において購入したハーネス型安 全帯を用いて本件試着品の試着をしたことが認められる。 しかしながら,フルハーネス対応空調服の構成に係る手書き図面が作成され,その試作品を作成して,社内でその試着をしたからといって,被告らにおいて,即時\n実施が可能な状況にあったかは必ずしも明らかとはいえないところ,前記第2の2(5)認定のとおり,被告らが被告各製品の製造,販売等を開始したのは平成28年5 月であり,本件試作品が作成され,試着された平成27年3月及び同年4月から1 年以上を要したことにも照らせば,本件出願日の時点では,少なくとも,本件考案 の実施に当たる被告各製品の事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識さ れる態様,程度に表明されていたということはできないというべきである。\n
(3) 被告は,1)被告ら代表者は,平成27年3月4日,本件考案の構\成が記載さ れた乙11図面のデータをゼハロスに送信し,試作品の作成を依頼しているところ, フルハーネス対応空調服が顧客のニーズ等を背景として作れば売れる製品であった こと,その開発又は販売の障害となるような事情は存在しなかったこと,被告らの 社内体制として,被告ら代表者の意思決定が重要な意味を持っていたことなどに照らせば,被告ら代表\者の上記の行為は,フルハーネス対応空調服の事業化を決定する旨の被告らの意思表示であるということができること,2)ゼハロスは,被告ら代 表者の上記の依頼を受け,他社に委託するなどして,平成27年3月31日までに,本件試作品を作成しているところ,被告らが,莫大な時間,労力,資金を投下して,\n既存の空調服を研究,開発し,商品化してきたこと,本件考案は,既存の空調服に 筒を取り付けるだけで完成するシンプルな構成であることなどに照らすと,被告らは,本件試作品の作成によって,フルハーネス対応空調服に係る事業活動のほとん\nどを完了しており,被告らによる即時実施の意図が客観的に表明されていること,3)被告ら代表者は,平成27年3月26日の空調服の会において,必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供する旨発言しており,被告らが同空調服\nを販売する意思を有していたことが示されていること,4)被告らは,平成27年4 月7日,本件試作品の試着を行い,被告ら代表者においてフルハーネス対応空調服は完成したと強い手応えを感じ,同空調服の販売の意思はより強固なものになった\nから,遅くともその時点で,被告らによる販売の意思は確定的なものとなったこと などを主張する。
しかしながら,上記1)について,乙11図面は,手書きの比較的簡略な図面であ り,そのデータを他社に送信して試作品の作成を依頼したというだけで,即時実施 が可能な状況にあったといえないことは明らかである。被告ら代表\者の意思決定が 重要であったというのは被告らの内部的な事情にすぎないことにも照らせば,ゼハ ロスへの乙11図面の送信等をもって,被告各製品の実施に係る被告らの即時実施 の意図が客観的に認識される態様,程度に表明されたということはできない。また,上記2),4)について,本件考案は既存の空調服の背中部分の構成を変更するにとどまるものであり,被告らは既存の空調服の研究,開発実績を有していると\n認められたとしても,試作品が一度作成され,社内でその試着がされただけでは, 製品化に耐えるものであるか未だ明らでなく,試着の結果を踏まえて設計の見直し 等の作業が必要になるであろうことは十分に考えられるところである。被告らが被告各製品の製造,販売等を開始したのはその後1年以上が経過した平成28年5月\nであったことなどにも照らせば,本件試作品が作成されたことや試着されたことを もって,被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態 様,程度に表明されたということはできない。さらに,上記3)について,被告が指摘する空調服の会における被告ら代表者の発言は,必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供するというもので\nあり,これをもって,被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に 認識される態様,程度に表明されたということはできない。
(4) 以上によれば,本件出願日である平成27年5月11日当時,本件考案の実 施に当たる事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度に 表明されていたと認めることはできないから,被告らにおいて,その「事業の準備」をしていたということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.09.26
平成30(ワ)40314 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和2年1月22日 東京地方裁判所
原告らは,被告標章においては,被告標章図形部分が最も目を引く部分であり, これと相まって,その直後に記載された文字部分の冒頭部分であり,かつ被告標章 図形部分と観念を共通にする「SAKURA」の文字部分が目に入りやすくなるこ と,被告標章の「SKY」の文字部分も,高層建物の宿泊施設の名称に一般に用い られているものであって,被告標章の「HOTEL」及び被告標章4の「KASH IWA」の各文字部分と同様に提供される役務の性質,場所を示すものであり,自 他識別力が低いこと,被告標章2では,最も目を引く上記図形部分の真横に「SA KURA」の文字部分が配されており,被告標章3及び4では,最も目を引く上記 図形部分の真下に「SAKURA」の文字部分が配され,それ以外の文字部分が改 行して配されていることからして,「SAKURA」の文字部分が一層目を引くこと になることなどを指摘して,被告標章の要部は,「SAKURA」の文字部分,被告 標章図形部分又は「SAKURA」の文字部分及び被告標章図形部分である旨主張 する。
しかしながら,証拠(甲25)によっても,比較的高層の建物の宿泊施設のみな らず,建物の階数が数階程度にとどまる低層の宿泊施設においても「スカイ」の文 字を含む名称が用いられていることが認められる上に,他に高層建物の宿泊施設の 名称において「スカイ」ないしは「SKY」の文字が用いられることが一般的であ ることを裏付ける的確な証拠もないから,「SKY」の文字が,高層建物の宿泊施設 の名称に一般に用いられる,宿泊施設の建物の高さという提供される役務の性質を 表示するとは直ちには認め難く,被告標章の「SKY」の文字部分から出所識別標\n識としての称呼,観念が生じないということはできない。 上記の点に加え,前記 において判示したとおり, 被告標章2ないし4の要部の「SAKURA」の文字部分と「SKY」の文字部分 とが一体のものとして認識し得るものであることのほか,「SAKURA」の文字部 分と「SKY」の文字部分につき,共にほぼ同一の大きさの文字により構成され,\nかつ全体の大きさにもさほど差はないことにも照らすと,被告標章図形部分が目を 引く部分であり,「SAKURA」の文字部分が被告標章2ないし4において被告標 章図形部分の真横又は真下に配されていることをもって,「SKY」の文字部分が被 告標章2ないし4の要部に含まれないということはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.09.26
令和1(ワ)231 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年1月31日 東京地方裁判所
(1) 証拠(甲2,4,10〜12)によれば,1)本件サイトの「再生数」は 「9896」との表示がされていること,2)本件著作物の収録時間は120 分であるが,甲4の2には,アップロードされた動画の再生時間が21分0 5秒であるかのような記載があり,被告が自認する限度でも,その再生時間 は50分にすぎないこと,3)本件著作物は,原告のグループ会社が運営する ウェブサイトにおいて有料でインターネット配信されており,これをストリ ーミングで視聴する際の料金が300円(平成28年6月21日時点)とさ れていること,4)原告は,第三者に対し,著作物のストリーミング配信を 「売上総額(消費税抜き)」の38%で許諾した例があることの各事実を認 めることができる。
(2) 原告は,被告がアップロードした動画の再生回数が9896回であること から,これに前記のストリーミング料金である300円の38%を乗じた1 12万8144円が使用料相当損害額であると主張するが,本件サイトに表\n示された「再生数」が,無料会員によるごく短い時間のサンプル動画の視聴 も含まれるのかどうかも含め,どのような方法に基づいて計測されたかは明 らかではない。 また,上記のとおり,本件著作物の収録時間は120分であるのに対し, 被告がアップロードした動画の再生時間は,被告の自認する限りでも50分 であり,その再生時間は本件著作物の収録時間より相当程度短かったものと 認められる。 さらに,原告が使用料率の証拠として提出する契約書等は,平成15年4 月のコンテンツ提供基本契約書に基づき平成21年3月に交わされた覚書で あり,その契約時期は本件著作物のアップロードより相当程度以前のもので あり,その数も1例にすぎないので,これを基礎として本件著作物の利用料 率を定めることは相当ではなく,加えて,上記のストリーミング料金が消費 税を含む金額かどうかも明らかではない。 以上によれば,原告が主張する再生回数,ストリーミング料金及び利用料 率を基礎とし,その計算式に基づいて算定された損害が原告に生じたと直ち に認めることはできないが,他方,上記(1)の認定事実(本件サイトに表示\nされた再生回数,被告がアップロードした動画の再生時間,ストリーミング 料金の額,過去の契約例など)に加え,本件に現れた諸事情を全て総合する と,その損害額は40万円と認めるのが相当である。 なお,被告は,本件著作物は他サイトからの引用であり,著作権侵害の故 意・過失がなかったようにも主張するが,被告は他人の著作物を自らアップ ロードしたのであるから,被告に少なくとも過失があると認められることは 明らかである。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2020.09.26
令和1(ワ)30272 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年6月25日 東京地方裁判所
被告が本件発信者情報1(氏名又は名称)を保有しているかを検討するため, 本件サービスに係る会員登録の情報内容についてみるに,証拠(甲11)によ れば,本件サービスの利用規約には,本件サービスの会員登録希望者は,本件 サービスの利用規約の全てに同意した上,同利用規約及び被告が定める方法に より会員登録をする旨の定めがある(同利用規約第4条1.)ことが認められ るにとどまり,同利用規約(甲11)の内容を全て精査しても,会員登録時に 登録すべき情報内容についての定めはなく,本件サービスを利用するためには 会員登録希望者ないし利用者がその氏名又は名称を登録する必要があることを うかがわせる定めも見当たらない。そうすると,本件登録者において,本件サ ービスの利用規約の定めに従い,本件発信者情報1(氏名又は名称)を登録し て被告に提供したと認めることはできず,その他,被告が本件発信者情報1 (氏名又は名称)を保有していると的確に認めるに足りる証拠はない。 したがって,被告が本件発信者情報1(氏名又は名称)を保有しているとは 認められない。 この点,原告は,本件サービスを利用してホームページ等を作成するために は,電子メールアドレス等のほかに,氏名又は名称を登録することが必要であ る旨主張する。しかし,本件の具体的事案に即して本件サービスの利用規約の 定めについて具体的に検討しても,本件登録者において,本件発信者情報1を 登録して被告に提供したと認めることができないことは,上記説示のとおりで ある。原告の上記主張は,推測の域を出るものではないというほかなく,採用 することができない
2 争点(2)本件発信者情報は法4条1項の「発信者情報」に当たるか)につい て
(1) 前記1で判示したとおり,本件発信者情報のうち本件発信者情報1(氏 名又は名称)については,被告がこれを保有しているとは認められないから, 本件発信者情報1の開示を求める原告の請求は,争点(2)について判断する までもなく,既に理由がない。 そこで,争点(2)に関しては,本件発信者情報2(電子メールアドレス) の開示を求める原告の請求について判断する。
(2) 法4条1項は,開示請求の対象となる「当該権利の侵害に係る発信者情 報」とは,「氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であ って総務省令で定めるものをいう。」と規定し,これを受けて省令は,その ような情報の一つとして「発信者の電子メールアドレス」と規定する(省令 3号)ところ,法2条4号は,「発信者」とは,「特定電気通信役務提供者 の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不 特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し,又は当該特定電気通 信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信され るものに限る。)に情報を入力した者をいう。」と規定する。 しかして,法が,2条4号により「発信者」を上記のように文言上明記し た趣旨は,法において,他人の権利を侵害する情報を流通過程に置いた者を 明確に定義することにより,それ以外の者であって当該情報の流通に関与し た者である特定電気通信役務提供者の私法上の責任が制限される場合を明確 にするところにある。そうすると,法4条1項を受けた省令3号の「発信者 の電子メールアドレス」の「発信者」についても,法2条4号の規定文言の とおりに,特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体 (当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。) に情報を記録し,又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入 力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した本 人に限られると解するのが相当である。
(3) そこで,これを前提に,本件について検討する。 前記のとおり,被告が,本件発信者情報2(本件登録者の電子メールア ドレス)を保有していることから,本件登録者は,本件サイトを開設した 際に,被告に対し,電子メールアドレスを提供したといえるものの,前記 1の説示に照らせば,氏名又は名称の提供をしたものとは認められない。 このように,本件サイトの開設に当たり本人情報として氏名又は名称が 提供されず電子メールアドレス等が提供されているような場合,本件登録 者が,真に本件登録者本人の電子メールアドレスを被告に提供したことに は合理的疑いが残るところである。 この点,証拠(甲11)をみても,本件サービスの利用規約には,本件サ ービスの会員は,本件サービスを利用する際に設定する登録情報に虚偽の情 報を掲載してはならない旨定められている(同利用規約第3条2.)ことが 認められるものの,他方,同利用規約(甲11)の内容を全て精査しても, 登録情報の内容が当該会員本人の情報であることを確認するための方法を定 めた定めはなく,かえって,登録情報に虚偽等がある場合や登録された電子 メールアドレスが機能していないと判断される場合には,被告において,本\n件サービスの利用停止等の措置を講じることができる旨の定めが存する(同 録希望者が他人の情報や架空の情報を登録するおそれのあることがうかがわ れるところである。特に,本件の場合,本件サイトは平成13年頃開設され たものである(甲1)ところ,本件サイトには,原告がその頃以降に創作し たほぼ全てのメールマガジンが原告に無断で転載されている(甲2)ことに 照らせば,本件サイトはそのような違法な行為のために開設されたものであ ることがうかがわれるから,本件登録者が本件サイトを開設する際に他人の 電子メールアドレスや架空の電子メールアドレスを登録した可能性を否定し\n難いといわざるを得ない。 そして,その他,本件登録者が本件サービスを利用して本件サイトを開設 する際に登録した電子メールアドレスが本件登録者本人のものであると認め るに足りる証拠はなく,本件登録者が本件サイトを開設する際に登録した電 子メールアドレスが本件登録者本人のものであると認めることは困難という べきである。 そうすると,被告の保有する電子メールアドレス(本件発信者情報2)は, 法2条4項にいう「特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記 録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限 る。)に情報を記録し,又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装 置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力 した者」の電子メールアドレスであるとはいえず,ひいては,省令3号の
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2020.09.26
平成30(ワ)18151 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年6月25日 東京地方裁判所
かかる事実経過に鑑みれば,そもそも原告は,本件原告ライセンス契約に 基づいて,本件キャラクターを付すなどにより本件キャラクターを利用した 商品を日本において独占的に販売するなど,自ら当該商品化権を専有してい るという事実状態を生じさせているものではない上,本件原告ライセンス契 約に至る状況等をみても,被告が本件TXBB契約等を通じ日本における当 該キャラクター商品の販売を継続していたという状態であるのに,権利者と されるSMFにおいて,本件原告ライセンス契約により原告の利用権の専有 を確保したと評価される行為がされたとはいえず(SMFは,被告ないしT XBB等に対し,権利侵害に係る警告,利用行為の差止請求や損害賠償請求, 原告からサブライセンスを受けるよう求める通告等をいずれも行っておらず (前記(2)ケ),また,本件訴訟提起の前後を通じても,原告が被告とサブラ イセンス契約の締結交渉を企図する中で,原告から求めがあったにもかかわ らず,原告が本件キャラクターの独占的利用権を有することを書面などによ り明確にする等の具体的な対応を一切とらず,さらに,被告に対し,利用権 を被告と原告の双方に設定した,いわば二重譲渡の状態にあることを認めつ つ被告の利用権を優先させるかのような姿勢を見せていた(前記(2)コ,サ)。), かえって,SMFは,上記契約の更新期前の時期には,被告との間で被告へ の利用権設定に向けての交渉や被告映画の販売交渉等に係る合意を行い,ま た,訴外香港法人に対し本件キャラクターの利用権を付与するなどの状態と なっていたものである。
そうすると,このような本件事案における事実状態をもってしては,権利 者とされるSMFによって,利用権者たる原告の利用権の専有を確保したと 評価されるに足りる行為が行われたとはいえず,SMFによって,原告が, 現にSMFから唯一許諾を受けた者として当該キャラクター商品を市場にお いて販売している状況に準じるような客観的状況が創出されているなど,原 告が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が 存在しているということはできないというべきである。 したがって,原告は,被告に対し,独占的利用権が侵害されたとして損害 賠償請求をすることはできないというほかない。
(4) これに対し,原告は,SMFの代表者であったCが,その陳述書(甲7)\nにおいて,原告に独占的利用権を与えたこと,及び本件TXBB契約に基づ いて被告が本件キャラクターを利用する権利はないことを言明していること などから,原告の独占的利用権の侵害による被告の不法行為が成立する旨を 主張する。
しかしながら,前記のとおり,原告において本件TXBB契約が終了した 旨を主張する平成26年12月31日以降,現時点に至るまで,SMFから 被告に対し,本件キャラクターの利用につき警告や法的措置が何ら取られて いないこと,本件訴訟提訴後の平成30年において,被告の組合員の職務執 行者であるDに対し,本件TXBB契約が終了した旨を明確に主張していな いこと,上記Cの陳述書(甲7)以外に,原告に対する本件キャラクターの 独占的利用権の付与を積極的に認める姿勢を明らかにした形跡が全く見当た らないことなどからすれば,権利者とされるSMFにおいて,原告への利用 権設定に当たりその専有を確保したと評価されるに足りる行為を行い上記に 準じる客観的状況を創出しているといえないことに変わりはなく,同人が契 約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が存在し ているということはできないとの前記判断を左右するものではない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない(なお,本件の経 緯に鑑みれば,仮に,SMFが,被告に対し,本件TXBB契約の存続を否 定する趣旨の主張に及ぶことがあったとしても,そのことから,SMFにお いて,原告への利用権設定に当たりその専有を確保したと評価されるに足り る行為を行い上記に準じる客観的状況を創出しているといえることになるも のではなく,原告が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有していると いう事実状態が存在しているということができない本件事案の下において, 原告の被告に対する,独占的利用権が侵害されたことを理由とする損害賠償 請求が肯定されることにはならない。)。
2020.09.26
令和2(行ケ)10014 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年9月23日 知的財産高等裁判所
上記(1)〜(3)によると,本件商標と引用商標は,外観において著しく異なってお り,また,称呼や観念を共通にする場合があるものの,それは,本件商標を「フフ フ」と称呼した限られた場合のみである。そして,上記のような差異があるにもか かわらず,本件商標と引用商標が類似しているものと認めるべき取引の実情その他 の事情は認められない。 したがって,本件商標は,引用商標と類似するものとは認められない。
3 原告の主張について
(1) 原告は,本件商標と引用商標からいずれも「おいしさ」や「満足感」に関 する観念を生ずる旨主張するが,以下のとおり,この主張を採用することはできな い。
ア 「ふふふ」の語について
原告は,人が食品を食べたときに軽く笑うのは,その食品に「おいしさ」や「満 足感」を感じたときであるということを,誰もが容易に想像できるから,食品分野 においては,「ふふふ」の語が,「おいしさ」や「満足感」に関する観念をも生ず ると主張する。 しかし,食品分野において,「ふふふ」の語が,特定の態様の笑い声や笑う様子 といった観念を生ずることを前提として,食品について「おいしさ」といった肯定 的な評価を示す直接的な表現として用いられている例(「食卓にふふふな時間を」\n(甲4の5),「ふふふ〜なオヤツ」(甲4の7),「ふふふなモノたち」(甲4 の8),「ふふふなレアチーズ」(甲4の9),「ふふふな食べ比べ」(甲4の1 0)といった用例)があることは認められるものの,それを超えて,「ふふふ」の 語が,食品について,「おいしさ」や「満足感」を示すものとして一般的に用いら れているものというべき事情を認めるに足りる証拠はない。「ふふふ」の語が,食 品について,必ずしも「おいしさ」や「満足感」に関する観念を示すものと直ちに 認められない形で用いられている例(甲28〜33,36,37,42,43,4 5)や,一定の態様の「笑い声」や「笑う様子」を示すものとして用いられている にとどまるというべき例(甲4の1〜4・11,甲12の2・4・11)も認めら れるところである。この点,原告が証拠として提出する辞典(甲3の4・5)にお いても,「ふふふ」の語については,「いたずらっぽく,少々ふざけて,含み笑い をする時などの様子」(甲3の4)を示すものとされたり,「いたずらっぽい笑い, または不敵な笑いを示すことが多い。」(甲3の5)とされたりしているのであっ て,一般的に,必ずしも常に肯定的な意味合いを示すものとはみられない。 上記のように,食品分野においては,「ふふふ」の語が肯定的な意味合いで用い られることが相応にあるということは認められるものの,それを超えて,「おいし さ」や「満足感」に関する観念が一般的に生ずるとまでいうことはできない。
イ 本件商標から生ずる観念について
(ア) 原告は,本件商標の使用態様(甲5の2・3,甲6の1〜4,甲7〜 9,甲10の1・2,甲11の1・2)や被告が策定したマニュアルの記載(甲1 6)から,本件商標が「おいしさ」や「満足感」に関する観念を生ずるものである ことを被告が自認している旨を主張する。 しかし,食品分野において,「ふふふ」の語が「おいしさ」や「満足感」に関す る観念を生ずるという一般的な事情が認められないことは,上記アのとおりである。 証拠(甲5の2・3,甲6の1〜4,甲7〜9,甲10の1・2,甲11の1・2) から認められる本件商標の使用態様や被告の「富富富デザインマニュアル」(甲1 6)の記載を考慮しても,被告が本件商標に係る「フフフ」という称呼を,そこか ら生ずる特定の態様の「笑い」という観念を積極的な評価と結びつける形で用いる ことを超えて,本件商標から「おいしさ」や「満足感」に関する観念を生ずるよう な形で用いているとは認められない。
(イ) 原告は,本件商標に接した需要者の認識についても主張するが,証拠 (甲11の2,甲12の1〜11)から認めることができる事実は,本件商標が「フ フフ」の称呼を生ずることがあることと,「フフフ」の称呼を生じた場合には,本 件商標が特定の態様の「笑い」という観念を生じることがあることの各事実にとど まり,本件商標から「おいしさ」や「満足感」に関する観念を生ずると認めること はできない。
ウ 引用商標から生ずる観念について
原告は,引用商標が「おいしさ」や「満足感」に関する観念を生ずる旨を主張す るが,食品分野において,「ふふふ」の語が「おいしさ」や「満足感」に関する観 念を生ずるという一般的な事情が認められないことは,上記アのとおりである。原 告が指摘する原告のカタログの記載(甲15)についても,あくまで「ふふふ」の 語を笑い声や笑う様子を示すものとして用いるものにすぎないということができ, 引用商標から上記観念が生ずることを上記記載が裏付けるものとはいえない。
エ したがって,本件商標と引用商標とからいずれも「おいしさ」や「満足 感」に関する観念が生ずるとの原告の主張を採用することはできない。
(2) 原告は,本件商標は,引用商標に富山県の「富」で当て字をしたものにす ぎないと主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。原告の主張は, 引用商標と一般的な擬音語・擬態語である「ふふふ」の語を同一視するものであっ て相当でない。一般的な擬音語・擬態語である「ふふふ」の語が有する意味を踏ま えて被告がそのような称呼を有する商標を登録することが,引用商標が存すること で直ちに妨げられるものではない。 また,本件商標と引用商標が「平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互\nに変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」(商標法38条5項括 弧書き)に当たらないことも明らかである。
(3) 原告は,需要者は,本件商標と引用商標を同一のものと認識していると主 張し,事例(甲11の2,甲12の2・5・7〜9)を指摘するが,これらの事例 は,本件商標が「フフフ」という称呼又は笑い声や笑う様子と結びつけられている ことを示すものにとどまり,本件商標と引用商標とが同一のものであるのと誤認等 がされた事実があることを示すものではなく,需要者が本件商標と引用商標を同一 のものと認識していると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.09.24
令和1(行ケ)10170 審決取消請求 商標権 行政訴訟 令和2年9月16日 知的財産高等裁判所
しかるところ,1)引用商標の構成中の本件円環部分と本件図形部分と\nは分離観察し得るものであること,2)本件円環部分のうち,緑色の太い 帯状の円環内に白抜きで表された「STARBUCKS」及び「COF\nFEE」の文字部分全体から「スターバックスコーヒー」の称呼が生じ, また,本件円環部分は外側の緑色の細い円環と内側の白色の細い円環と によって全体の領域が明確に画されており,本件円環部分の外観は全体 として記憶に残りやすいものと認められることからすると,引用商標の 構成中の本件円環部分は全体として需要者に対して強い印象を与えるも\nのといえる。
しかしながら,他方で,原告が主張する引用商標における本件緑色円 環配置構成は,引用商標中の具体的な構\成部分そのものではなく,本件 円環部分から抽出した上位概念化した要素としての構成及び配置の態様\nをいうものであり,緑色の帯状の円環内における白抜きの文字が「ST ARBUCKS」及び「COFFEE」の文字とは異なる文字である場 合や白抜きの図形が星印以外の図形であっても,本件緑色円環配置構成\nに含まれることになるが,引用商標に接した需要者において,このよう な上位概念化した要素としての構成及び配置の態様をイメージし,それ\nが記憶に残るものと認めることは困難である。
(イ) そうすると,引用商標が平成23年3月末当時に著名であったから といってそのことから直ちに引用商標における本件緑色円環配置構成が\n原告の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く\n認識されていたものと認めることはできない。ましてや,上記時点から約4年後の本件商標の登録出願時(登録出願 日平成28年3月9日)及び登録査定時(登録査定日同年11月1日) において,本件緑色円環配置構成が原告の業務に係る商品及び役務を表\ 示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることは できない。
ウ 本件アンケート調査について
(ア) 原告は,1)本件アンケート調査の調査対象者の抽出方法が適切であ ること,2)本件アンケート調査は,週末の2日間にインターネットを通 じて行われたものであり,調査期間は特段短いものではないこと,3)本 件アンケート調査における552名というサンプル数は,アンケート調 査の信頼性を確保するのに合理的であること,4)仮に緑色の二重円環を 示して調査を行ったとしても,そこから得られる結果は引用商標を含む 原告の商標を日常生活で目にする需要者の実際の認識を反映するもので はないから,本件緑色円環配置構成に関する需要者の認識を適切に測る\nためには,本件標章を対象に質問を行うべきであり,かつ上記注意事項 を示さなければならないから,本件アンケート調査の質問内容は適切で あること,5)本件アンケート調査は,本件商標の登録出願時及び登録査 定時から1年後の平成29年に実施されたものであり,本件アンケート 調査の結果は,上記各時点における需要者の認識を反映したものといえ ることからすると,本件アンケート調査は適切に実施されたものであり, 本件アンケート調査の結果は,上記各時点における本件緑色円環配置構\n成の周知著名性を示すものである旨主張する。
(イ) そこで検討するに,前記(1)イの認定事実によれば,本件アンケート 調査は,引用商標の「緑色の円環部分(ただし,文字・記号は判読不能\nに加工したもの)」である本件標章の著名性を検証することを目的とし て,調査対象者に対し,本件標章の画像について,「ある会社」,「外 食産業に属する会社」又は「あるコーヒーショップの会社」が運営する お店の設備やお店で販売する商品の図柄の一部を抜き出して加工したも のである旨,元々の図柄では,円の中心部に絵があり,緑色の輪の部分 には会社名が特定できる白い文字が表示されていたが,本件標章の画像\nでは,絵の部分を白く塗りつぶし,文字部分にはモザイク処理を施し, 会社名が読み取れないようにしてある旨の説明を付して示した上で,「こ の画像を見て,何と言う会社またはお店の名前を思い浮かべましたか。 以下の回答欄に思い浮かべた会社またはお店の名前をお書きください。 わからない場合は「わからない」とお書きください。」との質問に対す る回答を求めたものであることが認められる。
しかるところ,前記イ(ア)のとおり,原告が主張する引用商標におけ る本件緑色円環配置構成は,本件円環部分から抽出した上位概念化した\n要素としての構成及び配置の態様をいうものであるが,引用商標に接し\nた需要者において,このような上位概念化した要素としての構成及び配\n置の態様をイメージし,それが記憶に残るものと認めることは困難であ ることに照らすと,本件緑色円環配置構成の認識度ひいては著名性を適\n切に調査することは,その性質上困難を伴うものといえる。 そして,本件標章は,別紙3のとおり,外側から順に緑色の細い円環, 白色の細い円環,白色のモザイク模様が付された緑色の太い帯状の円環 から構成されるドーナツ形状の図形からなるものであり,本件標章と引\n用商標における本件円環部分は,緑色の細い円環,白色の細い円環,緑 色の太い帯状の円環を有するドーナツ形状である点では共通するが,緑 色の太い帯状の円環内の構成態様及び内側の白色の細い円環の有無の点\nにおいて異なる態様の標章であることに照らすと,本件標章から本件円 環部分を想起するものと認めることはできないし,ましてや,本件標章 から本件緑色円環配置構成を認識できるものと認めることはできない。\nこの点に関し,本件アンケート調査には,本件標章について,元々の図 柄では,円の中心部に絵があり,緑色の輪の部分には会社名が特定でき る白い文字が表示されていたが,本件標章の画像では,絵の部分を白く\n塗りつぶし,文字部分にはモザイク処理を施し,会社名が読み取れない ようにしてある旨の説明が付されているところ,上記説明は,本件標章 に接した需要者が視覚によって認識し,又は想起することができない内 容を文章によって誘導するものであって適切なものではない。 そうすると,本件アンケート調査は,本件緑色円環配置構成の認識度\nひいては著名性を調査することを目的とする調査方法として適切である と認めることはできないから,原告の前記主張は,理由がない。
エ まとめ
以上によれば,引用商標が,平成23年3月末当時において原告の業務 に係る商品及び役務を表示するものとして著名であり,引用商標の構\成中 の本件円環部分は全体として需要者に対して強い印象を与えるものであっ たことは認められるが,このことと本件アンケート調査の結果から,引用 商標における本件緑色円環配置構成が,本件商標の登録出願時及び登録査\n定時において,原告の業務に係る商品及び役務を表示するものとして,需\n要者の間に広く認識されており,周知著名であったものと認めることはで きない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2020.09.21
令和2(ネ)10002 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年9月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 特許法101条2号の「その物の生産に用いる物」該当性について
ア 訂正の上で引用した原判決の第3の1(2)アで説示したとおり,本件発明 において,特許法101条2号の「その物」は,本件発明に係る「分割起点形成装 置」を意味するのであって,SDBGプロセス実行システムBが上記の「その物」 に当たる余地はない。
イ 控訴人は,1)本件明細書の段落【0162】〜【0202】及び図15 においては七つの工程が記載されているところ,レーザによる改質層の形成(2番 目の工程)及び改質層の研削除去(3番目の工程)によって,分割するための起点 である改質領域から延びる微小亀裂が形成されていること,2)構成要件Aの「内部\nにレーザ光で改質領域を形成したウェーハを分割するための分割起点形成装置」と いう表現からは,「分割起点形成装置」が分割に用いられる装置であること及び当\n該分割とは内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハの分割であることしか読 み取れないこと,3)本件発明は,クラックの進展の程度を制御しようとする技術思 想のものであるところ,チップ断面の改質領域の部分からのチップの破断等を防ぐ という課題からは,本件発明が,改質領域が形成されたウェーハを対象とするとは 断定できないこと,4)本件明細書には,既に改質領域が形成されたウェーハを入手 すればよい,改質領域はどのように形成されても構わないといった表\現はどこにも 記載も示唆もされておらず,特に本件明細書の段落【0167】では,チップの厚 さと改質領域を形成する位置について言及がされていることを理由に,本件発明に おいては,適切な位置,形状等で改質領域を形成することも,必須のものと考えら れているのであり,本件発明における分割起点形成装置にはレーザ照射装置が含ま れるなどと主張する。
しかし,本件明細書の記載が研削除去工程だけでなくレーザ改質工程についても 触れたものとなっており,本件明細書の段落【0167】では,チップの厚さと改 質領域を形成する位置について言及がされているとしても,本件特許請求の範囲の 記載からすると,本件発明がレーザ改質工程を含むものといえないことは,訂正の 上で引用した原判決の第3の1(3)アで説示したとおりである。また,構成要件Aの\n文言や本件発明の課題等からすると,本件発明が,既にその内部にレーザ光で改質 領域が形成されたウェーハを加工対象物として,その割断のための分割の起点を形 成する装置であることは,訂正の上で引用した原判決の第3の1(2)アで判示した とおりであり,このような解釈が日本語の通常の語法に反するということはできな い。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
ウ 控訴人は,訂正の用意がある旨主張するが,訂正の上引用した原判決の 第3の1(2)で判示したところによると,控訴人が主張する訂正は,特許法126条 1項ただし書が規定するいずれのものにも当たらないのみならず,実質上特許請求 の範囲を拡張し,又は変更するもの(特許法126条6項)であるから,その要件 を欠くものである。
(2) 特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」につ いて
ア 控訴人は,本件発明は,研削が終了した段階で亀裂が表面に到達してい\nない点に,従来技術と対比した場合の進歩性を根拠づける差があるのであって,本 件発明に係る技術思想を特定するに当たり,改質領域形成手段も研削手段と同様に 重視されるべきであると主張するが,この主張については,訂正の上で引用した原 判決の第3の1(3)イで説示したとおり採用することができない。 この点について,控訴人は,本件明細書の段落【0167】の記載が研削工程と 有意な関連性を有する改質領域形成手段が備えるべき具体的な構成,条件等につい\nての説明であると主張するが,本件明細書の段落【0167】には,「ウェーハW の表面(デバイス面)を効率的に破断するため」のレーザ光の照射方法が記載され\nているにすぎず,研削工程と有意な関連性を有する改質領域手段が備えるべき具体 的な構成,条件等について説明されているものではない。\n
イ 控訴人は,甲第6号証及び乙第3号証を指摘し,SDBGプロセス実行 システムBに被控訴人各製品が不可欠であると主張するが,被控訴人各製品がSD BGプロセス実行システムBを構成するに当たって不可欠なものであるか否かが本\n件における特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の 認定を何ら左右するものでないことは,訂正の上で引用した原判決の第3の1(2) イで説示したところから明らかである。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> 不可欠性
>> ピックアップ対象
2020.09.17
令和1(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年9月15日 知的財産高等裁判所
イ 本件審決は,引用発明1を前記第2の3(2)アのとおり,低純度酸素の生成に 関し,「高純度酸素が側塔から抜き取られる位置よりも15〜25平衡段高い位置で 側塔から液体として抜き出され,液体ポンプを通過することにより高い圧力に圧送 され,主熱交換器を通過することによって気化され」るものと認定した。 原告は,上記認定を争い,引用発明1は,低純度酸素を専ら液体として抜き出す ものではないと主張し,その根拠として記載Aを指摘する。
ウ 記載Aは,「Either or both of the lower purity oxygen and the higher purity oxygen may be withdrawn from side column 11 as liquid or vapor for recovery.」というものである(甲1の1。5欄8行〜10行)。引用例1の他の箇所 (例えば,5欄11行〜22行,23行〜32行,33行〜39行)において, “recover”の用語が最終的な製品を得ることという意味で用いられていることから すると,記載A文末の“recovery”も最終製品の回収のことを意味し,他方で文中の “withdrawn”は,中間的な生成物の抜き出しのことを意味するものと解される(4 欄40行の“withdrawn”,5欄43行の“withdrawal”も同様である。)。そうすると,記載Aは,前記ア gのとおり,低純度酸素及び高純度酸素のいずれか又は両方は, 回収のために,液体又は気化ガスとして側塔11から抜き出されてもよいと訳すの が相当である。 そうだとすると,記載Aからは,引用発明1が低純度酸素を専ら液体として抜き 出すもので,気体としての抜き出しは排除されている,と理解するのは困難である。 しかも,引用例1の全体をみると,引用発明1が解決しようとする課題は,低純 度酸素及び高純度酸素の両方を高回収率で効果的に精製することができる極低温精 留システムを提供することであり ,課題を解決する手段は,空気成分の 沸点の差,すなわち低沸点の成分は気化ガス相に濃縮する傾向があり,高沸点の成 分は液相に濃縮する傾向があることを利用したものである(同 と認められ,図 1に示されたのは,あくまで,好ましい実施形態にすぎない 。図1の説明 においては,低純度酸素を液体として抜き出し,それにより大量の高純度酸素を得 られるとしても,それは,最も好ましい実施形態を示したものであって,引用例1 に側塔11から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえ ない。
エ また,証拠(甲2,3の1,4,7の1,8)によれば,本件発明1の出願当 時,空気分離装置又は方法において,高純度酸素と区別して低純度酸素を回収する ことができ,その際に,精留塔から,低純度酸素を気体として抜き出す方法も液体 として抜き出す方法もあることは,技術常識であったと認められる。上記認定の技 術常識に照らしても,引用例1には,低純度酸素を液体として抜き出すことのみな らず,気体として抜き出すことが記載されているに等しいというべきである。
オ そうすると,本件審決が,引用発明1を,低純度酸素を専ら液体として抜き 出すものと認定し,これを一致点とせずに相違点1と認定したことは,誤りといわ ざるを得ない。 本件審決は,その余の相違点及び本件発明2〜4と引用発明1との相違点につい て判断せず,原告被告ともにこれを主張立証していないから,これらの点に係る新 規性及び進歩性については,再度の審判により審理判断が尽くされるべきである。
・・・
事案に鑑み,取消事由3についても判断する。
(1) 実施可能要件適合性\n
ア 本件各発明に係る「空気分離方法」のための「空気分離装置」は,2種以上の 純度の酸素を取り出すものであり,そのうち1種を低純度のガス酸素で取り出すこ とによって,低圧精留塔内の主凝縮器に必要な酸素の純度を低減でき,その結果, 空気圧縮機の吐出圧の低減を図り,該圧縮機の消費動力を低減し,「空気分離装置」 の稼動コストを従来よりも小さくすることができるものである。 イ 本件各発明において用いられる装置は,「空気圧縮機」,「吸着器」,「主熱 交換器」,「高圧精留塔」,「低圧精留塔」,「低圧精留塔」内に設けられた「主凝 縮器」,「昇圧圧縮機」,「液酸ポンプ」,「空気凝縮器容器」及び「空気凝縮器容 器」内に設けられた「空気凝縮器」を主として備える「空気分離装置」であり,それ ぞれの意味するところは,図面をもって具体的に示されている(【0023】,図 1)。
工程についても,1)「低圧精留塔」内で精留分離された液体酸素が,「空気凝縮器 容器」内に供給され,「空気凝縮器容器」内で気化したガス酸素(低純度酸素)が, 供給ライン(ガス酸素供給ライン)により「主熱交換器」に送られて常温に戻された 後,必要に応じて空気が混合されて酸素富化燃焼用酸素として外部(酸素富化炉) に供給されること(【0027】〜【0029】),2)「空気凝縮器容器」内の液体 酸素は,供給ラインにより「液酸ポンプ」に送られて必要圧に昇圧された後,「主熱 交換器」で蒸発及び昇温されることによりガス酸素(高純度酸素)となり,酸化用酸 素として外部(酸化炉)に供給されること(【0030】),3)「空気凝縮器容器」 内の液体酸素(高純度酸素)の抜き出し量は,例えば10%〜80%の間とするこ と(【0059】,【表3〜5】),以上のことが,具体的に示されている。\nそして,以上のような「空気分離装置」によれば,必要とされる高純度酸素が全体 の酸素の一部である場合に,必要とされる高純度酸素の純度を確保しつつ,「低圧 精留塔」の「主凝縮器」から取り出す液体酸素の純度を低減し,低減分の酸素の沸点 を下げることが可能となり,また,「低圧精留塔」内で液体酸素とガス窒素との間で\n行われる熱交換の温度差を大きくすることにより,「高圧精留塔」内の必要圧力を 下げることができ,これにより,「空気圧縮機」の吐圧力を低減し,ひいては該圧縮 機の消費動力の低減が可能となるので,「空気分離装置」の稼動コストを従来より\nも抑えることができるとして,効果及びその機序の説明もされている(【0018】, 【0035】,【0036】)。
ウ 本件明細書の発明の詳細な説明には,前記ア,イのことがその具体的な実施 の形態も含めて記載されており,当業者は,これをみれば,過度の試行錯誤を要す ることなく,本件各発明を実施することができる。 よって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,実施可能要件に適合する。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 引用文献
>> 相違点認定
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.09.17
令和1(ワ)16017 意匠権侵害行為差止請求事件 意匠権 民事訴 令和2年8月27日 東京地方裁判所
上記イによれば,本件登録出願前に,自動精算機又はそれに類似する物品 において,筐体の上端部から一定程度突出するディスプレイ部について,上 方を後方に傾斜させたディスプレイが縦長長方形状であり,ディスプレイを 収容するケース部分が縦長略直方形状である意匠,ディスプレイ部の縦と横 の比が概ね1.5対1である意匠,ディスプレイ部のケース部分がディスプ レイと略相似形の内枠部と,内枠部の外周を囲む外枠部からなる2段の枠部 で構成されている意匠は知られていたといえる。これらによれば,自動精算機を購入する需要者にとり,本件意匠の基本的\n構成態様や具体的構\成態様A,Bが,特に注意を惹きやすい部分であるとは いえない。そして,このことを考慮すれば,具体的構成態様C,Dは,本件意匠においては,本件図面において実線で示されている部分の中では一定の\n大きさを占めているといえるものでもあり,注意を惹きやすい部分であると いうべきである。
本件意匠と被告意匠の差異点(前記(2)ウ(イ)のうち3)本件意匠はディスプレイ周囲のケース部分の外枠部が正面視及び斜視において内枠部の外縁 から外輪部の外縁に向かって傾斜する傾斜面になっているのに対し,被告意 匠はディスプレイ周囲のケース部分が扁平となっていて,本件意匠のような 傾斜面を全く有していない点,4)本件意匠はケース部分の外枠部の下側部分 の幅が,外枠部の上側部分の幅,左側部分の幅及び右側部分の幅よりも略4 倍の幅広に形成されているのに対し,被告意匠はケース部分の上下左右の幅 がすべて等しくなっている点は,本件意匠の具体的構成態様C,Dに係る部分の違いであり,2)本件意匠はディスプレイ周囲のケース部分はディスプレ イと略相似形の内枠部と,内枠部の外周を囲む外枠部とからなる2段の枠部 から構成されているのに対し,被告意匠はディスプレイ周囲のケース部分はディスプレイと略相似形の扁平な枠部で構\成されており,本件意匠のような内枠部と外枠部という構成を有していない点は,具体的構\成態様Dの前提と なる構成自体が異なるというものである。それらの違いは,特に注意を惹きやすい部分であるとはいえない基本的構\成態様が共通することから受ける印象を凌駕するものであり,本件意匠と被告意匠は,全体として,異なった 美感を有するものであり,類似しないと認められる。
エ 原告は,本件意匠の基本的構成態様と具体的構\成態様について,前記第2, のとおり主張し,本件意匠の要部は,自動精算機全体との関係で位置, 大きさ,範囲を考慮したタッチパネル部であって,原告が主張する上記構成態様を前提として,本件意匠と被告意匠の構\成態様の共通点は,本件意匠の要部についての共通点であるのに対し,具体的構成態様の差異点については,いずれも両意匠の共通性を凌駕するものではなく,本件意匠と被告意匠が類\n似する旨主張する。
しかし,原告が本件意匠の基本的構成態様,具体的構\成態様であると主張 する構成態様は,本件図面において破線で示された筐体の形状を部分意匠である本件意匠の形状そのものとして主張しているものである。部分意匠の趣\n旨からも,本件において,タッチパネル部の幅と筐体の幅との具体的な比率 やタッチパネル部の筐体からの突出の具体的な比率そのものなどの原告主 張の上記構成態様が,本件意匠の具体的な形状であるとは解されない。なお,登録意匠と対象となる意匠の位置等の違いが類否判断に影響を及ぼす場合\nがあるとしても,本件においては,本件意匠と被告意匠に類否判断に影響を 及ぼすような位置等の差異はない(前記(3))。 また,原告は,類否判断において本件意匠と被告意匠について,上記の位 置等が共通することを重視すべき旨を主張する。 しかし,本件においては,少なくとも,筐体の上端部から突出するディス プレイ部について,前記イで掲載した意匠が知られており,このことを考慮 すると,前記のとおり,本件意匠と被告意匠は類似しないというべきである。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2020.09.17
令和1(行ケ)10070 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年9月10日 知的財産高等裁判所
エ 進歩性の判断について
原告は,原告甲1発明は,シールド工法により発生する泥土の処理方法 に関する発明であるから,仮に,その泥土に気泡シールド工法により発生 する泥土が含まれないとしても,気泡シールド工法がシールド工法の典型 例であることなどを考慮すれば,気泡シールド工法によって発生した泥土 を原告甲1発明の対象とすることは容易に想到することができると主張す る。 しかしながら,原告甲1発明に開示された発明は,「推進工事,シール ド工事,基礎工事,浚渫工事のような建設工事等で発生する泥土」であっ て,高い含水比により流動性が高い反面,気泡の存在は想定されていない ものを対象とし,これに凝集剤を適切に供給することよって「凝集された 無数の土粒子間に自由水を満遍なく抱合して,粒状化した状態に処理」 【0049】するという発明である。これに対し,気泡シールド工法によ って発生する泥土は,含水比が低く,気泡を有している点において,原告 甲1発明が想定する泥土とは性質が異なるのであるから,当業者には,こ のように性質の異なる泥土を,原告甲1発明の対象とすることの動機付け はないというべきである。このことは,気泡シールド工法がシールド工法 の典型例であるとしても,それによって左右されるものではない(問題は, 泥土の性質であるからである。)。
原告は,気泡シールド工法とその他の泥土圧シールド工法とは技術分野 に親近性があり適宜の互換性があること,両工法には発生する泥土の流動 性という課題の共通性があることなども指摘している。しかし,前者に関 していえば,問題は,泥土の性質であって,工法の種類ではないことは既 に指摘したとおりである。また,後者についていえば,気泡を有する泥土 の場合には,流動性をなくすために気泡を消滅させなければならないとい う固有の課題が存在するのであるから,流動性という表面的な現象面にお\nいて共通性があるからといって,直ちに,気泡を有する泥土を原告甲1発 明の対象とすることが容易であるということはできない。 よって,原告甲1発明において,相違点1に係る本件発明1の構成とす\nることは,当業者が容易に想到できたものとはいえない。したがって,本 件発明1が進歩性を欠くとはいえず,審決の同旨の判断には結論において 誤りはない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.09.17
令和1(行ケ)10166 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年9月2日 知的財産高等裁判所
このように防護標章登録制度は,原登録商標の禁止権の及ぶ範囲を非類 似の商品又は役務について拡張する制度であり,一方で,第三者による商 標の選択,使用を制約するおそれがあることに鑑みると,同法64条 1 項 の「需要者の間に広く認識されている」とは,原登録商標の指定商品の全 部又は一部の需要者の間において,原登録商標がその商標権者の業務に係 る指定商品を表示するものとして,全国的に認識されており,その認識の\n程度が著名の程度に至っていることをいうものと解するのが相当である。
イ この点に関し原告は,本件においては,原登録商標(「Tuche'」)が, 本願の指定商品「生理用パンティ,生理用ショーツ」の需要者と需要者層 が重なる原登録商標の指定商品「ストッキング」,「婦人用ソックス・タ\nイツ」,「女性用下着」の需要者(10代から40代の女性)の間に周知 著名性があれば,「需要者の間に広く認識されている」ことの要件を具備 する旨主張する。 そこで検討するに,原登録商標の指定商品は,第25類「被服,履物, 運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であるところ,「ストッキング」,「婦 人用ソックス・タイツ」及び「女性用下着」は,「被服」に含まれるから,\nこれらの商品の需要者は,原登録商標の指定商品の需要者に該当する。 一方で,例えば,「ストッキング」についてみると,2012年(平成 24年)11月5日付け日経産業新聞(乙39)には,「靴下各社,若年 層に照準―ストッキングおしゃれに,アツギ,グンゼ(市場リポート)」\nの見出しの下に,「ナイガイ」に関し,「同社のストックングはライセン スブランド「ランバン」が中心で,顧客層も60代以上が多い。」などの 記事が,2013年(平成25年)7月15日付け日経MJ(流通新聞) (乙40)には,「美脚効果をねらって10〜20代の女性を中心にここ 数年ブームとなっているストッキング」,「アツギが20〜60代に調査 したところ「日常ストッキングをはく人」は平均66.8%。トップは2 0代前半(76%)で,2位が50代(72.5%)。透け感の好みなど も20代と50代は似る。」などの記事が掲載されていることに照らすと, 「ストッキング」の需要者は,10代から40代に限らず,幅広い年齢層 の女性が需要者であるものと認められる。
また,商標法64条1項の「商品に係る登録商標が自己の業務に係る指 定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合」との\n文言及び同項の趣旨(前記ア)に鑑みると,同項の「需要者の間に広く認 識されている」にいう「需要者」は,「商品に係る登録商標」(原登録商 標)の需要者をいうものと解されるから,この「需要者」の範囲を防護標 章登録出願である本願の指定商品の需要者と重なる範囲に限定すべき理由 はない。したがって,原告の上記主張のうち,需要者の年齢層を「10代から4 0代」に限定する部分については採用することができない。 そこで,以下においては,「ストッキング」,「婦人用ソックス・タイ\nツ」及び「女性用下着」の需要者を前提に,原登録商標が「需要者の間に 広く認識されている」ことの要件を具備しているかどうかを判断する。
・・・・
上記認定事実によれば,原登録商標を使用した商品のうち,原告使用 商品は,19年以上にわたり継続して全国的に販売され,2010年か ら2017年までの売上高及びその市場シェアに照らすと,本件審決時 (審決日令和元年9月19日)においては,相当数の需要者が原登録商 標を原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識してい\nたものと認められる。
(イ) 他方で,前記(ア)の認定事実によれば,原告使用商品の売上高は, 毎年減少傾向にあり,2017年度(平成29年度)の売上高は,20 10年度(平成22年度)の売上高の3分の1程度であり,その市場シ ェアも減少傾向にあり,2017年は3.0%にとどまっている。また, 原告使用商品のパッケージに表示された原登録商標は,記憶や印象に強\nく残りやすいものとは直ちには認められないことは,前記ア(ア)認定の とおりである。 次に,原登録商標を使用した商品の広告宣伝については,前記(1)ウ(ア) 認定のとおり,2008年(平成20年)9月から2019年(令和元 年)12月までの間に,「Tuche’」ブランドのストッキング,婦人ソ\nックス,タイツ,インナーウェアの紹介記事が,「STORY」,「n on−no」,「MORE」,「With」,「CanCam」,「A neCan」,「CLASSY」,「Domani」,「女性セブン」, 「女性自身」等のファッション雑誌,女性雑誌,ウェブサイト(「We b Domani」,「ELLE ONLINE」,「ALL Abo ut」)等に掲載されたが(甲39,40の1ないし184),これら のうち,2017年ないし2019年に発行された雑誌における「Tu che’」ブランドのストッキングに関する掲載態様は,他のブランドのス トッキング等と共に紹介されているものが多く,紹介記事の中でブラン ド名が欧文字表記されているものは3誌のみであり,他の雑誌では片仮\n名で「トゥシェ」と掲載されており,原登録商標(「Tuche’」)が印 象に残る掲載態様であるとはいえない。また,前記(1)ウ(イ)認定のとお り,広告宣伝費は,2014年度(平成26年度)が3213万868 8円,2015年度(平成27年度)が6510万6184円,201 6年度(平成28年度)が5340万0587円,2017年度(平成 29年度)が4259万0674円であるが,このうち,雑誌広告費は, 2015年度は241万5000円,2016年度は973万5515 円にとどまっていることに照らすと,広告宣伝の規模は大規模であると はいえない。
・・・
エ まとめ
以上によれば,原告使用商品は,2000年(平成12年)から19年 以上にわたり,全国的に継続的に販売され,その売上高及び市場シェアか ら,原登録商標は相当数の需要者において原告の業務に係るストッキング を表示するものとして認識されていたものと認められるものの,一方で,\n原告使用商品の売上高は,毎年減少傾向にあり,2017年度(平成29 年度)の売上高は2010年度(平成22年度)の売上高の3分の1程度 であり,その市場シェアも減少傾向にあること,原告使用商品のパッケー ジに表示された原登録商標は,記憶や印象に強く残りやすいものとは直ち\nには認められないこと,原告使用商品の広告宣伝は,大規模なものとはい えず,その広告宣伝効果は限定的であること,本件アンケートは,実施時 期が古く,アンケートの調査対象者もストッキングの需要者の一部にとど まっているため,本件審決時における原登録商標に係る需要者の認識の程 度を判断する資料としては,適切なものではないのみならず,本件アンケ ートの結果においても,大半の需要者が原登録商標を認識していることを 示すものとはいえないことを併せ考慮すると,本件審決時において,大半 の需要者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示するものと\nして認識しているものとはいえず,原登録商標に係る需要者の認識の程度 は,著名の程度に至っているものと認めることはできない。
また,本件においては,ストッキング以外の婦人用ソックス・タイツ及\nび婦人用下着の商品の関係においても,本件審決時において,原登録商標 が需要者の間で原告の業務に係るこれらの商品を表示するものとして認識\nされ,その認識の程度が著名の程度に至っていることを認めるに足りる証 拠はない。したがって,原登録商標は,本件審決時(審決日令和元年10月29日) において,原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間\nに広く認識されている」ものと認めることはできない。 これに反する原告の主張は採用することができない。
2020.09.17
令和1(行ケ)10091 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年9月10日 知的財産高等裁判所
ア 原告は,審決が事項1)(ボルトの本数)及び事項2)(三角部材)を構成\nに含めずに引用発明を認定したことは誤りである旨主張するので,検討す る。
(ア) 引用発明の認定に際しては,ひとまとまりの技術的思想を構成する要\n素のうち,本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない 限度で認定すれば足り,特段の事情がない限り,本件補正発明の発明特 定事項との対応関係を離れて,引用発明を必要以上に限定して認定する 必要はないと解される。 審決の認定した引用発明は,「操作コントロールとバランス感覚を養 う上で支援となる自転車を提供すること」及び「走行練習の期間を短縮 させる自転車を提供すること」という考案の課題(引用文献1の【00 03】)に照らし,「接続部品を車体上の接続部の収納空間内から取り 外し,前記ペダルユニットを車体上から分離させる」こと(同【000 7】)及び「ペダルユニットが枢設されている接続部品を車体上の接続 部の収納空間内に固設する」こと(同【0008】)に対応する構成を\n含めて「走行練習用の自転車」の構成要素を特定したものであるから,\n課題を解決するために必須の構成を,ひとまとまりの技術的思想として\n把握できるように特定したものということができる。
(イ) 事項1)(ボルトの本数)を捨象したことについて
a ボルトの本数について,引用文献1の実施例を示した【図1】【図 2】【0006】では2本とされているものの,【実用新案登録請求 の範囲】においてボルトの本数は特定されていない上に,【考案の詳 細な説明】においても,実施例においてボルトを2本としたことの理 由やその作用効果,自転車の機能との関係等についての記載や示唆は\nみられない。そうすると,引用発明において,ボルトの本数(それが 2本であること)は,発明の本質的要素には当たらないというべきで あるから,事項1)を欠くことによって,引用文献1に開示された考案 の技術的思想を把握できなくなるものではない。 したがって,引用文献1において,ボルトの本数には特段の技術的 意義はないと解するのが当業者の通常の理解であると考えられるから, 「ひとまとまりの技術的事項」としての引用発明を認定するに当たっ て,ボルトの本数に関する事項1)を捨象することは妨げられないとい える。
b なお,本件補正発明は,ボルトの本数を,発明特定事項として何ら 限定するものでないから,引用発明の認定に当たって事項1)を捨象し ても,本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限 度で認定しているといえ,この点からしても,原告の主張は失当であ る。 また,原告の主張中には,本件補正発明の意義の中には,組立てを 容易にすることが含まれているとする部分があり,この主張は,本件 補正発明は,組立てを容易にするという観点から,ボルトの本数(1 本)を本質的な要素とするという趣旨であると考えられないでもない。 しかしながら,本件補正発明の請求項の範囲には,ボルトの本数は含 まれていないし,本件明細書を検討しても,ボルトの本数が1本であ ることが,本件補正発明の本質的要素であることが記載されていると 理解することはできないから,上記のような理解は成り立たない。
(ウ) 事項2)(三角部材)を捨象したことについて
a 引用文献1の【図1】〜【図3】には三角部材らしき図示がなされ ているものの,考案の詳細な説明では言及がないし,同種の形状を有 する自転車車体において三角部材が必須の部材であるとの技術常識が あるとも認めがたい。そうすると,引用文献1に接した当業者が三角 部材に特段の技術的意義があると理解することは想定し難いから,ひ とまとまりの技術的事項としての引用発明を認定するに当たって事項 2)を捨象することは妨げられない。
b 他方,本件補正発明は,三角部材に相当する部材を備えることを発 明の構成要素とするものではなく(本件明細書において発明の一実施\n形態として【0018】で言及され,本願図1ないし3に図示されて いるにとどまる。),それを除外することを構成要素とするものでも\nない。したがって,引用発明の認定に当たって事項2)を捨象しても, 本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認 定しているといえ,この点からしても原告の主張は失当である。
(エ) 以上によれば,事項1)及び2)を捨象した審決の引用発明の認定は,引 用文献1に開示された考案の有するひとまとまりの技術的思想につき, 本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定 したものということができる。かかる認定が,引用文献1に記載された 技術内容から必須の一部構成を捨象したとも,不当に抽象化・一般化・\n上位概念化したともいえない。 したがって,引用発明の認定に誤りがあるとの原告の主張は採用する ことができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2020.09.17
令和2(行ケ)10040 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年9月10日 知的財産高等裁判所
ア 本願商標は,左側から順に,本件図形部分,THANKS部分及びAI 部分からなる結合商標であり,各構成部分は,同じ高さで横一列に,重なり合うことなく配置されている。\n
イ 本件図形部分は,太さが均一でない赤色の線で描かれており,下方の1 点で交差する縦長ループを横に2つ並べたような図形である。また,本件 図形部分は,全体としてハート型様の形状となるように,2つの縦長ルー プを一筆書きしたような図形であるとみることも可能である。
ウ THANKS部分は,「T」の欧文字,その右側に配置された同文字より もやや高さが低い「HANKS」の欧文字,その上部に配置された小さめ の「Related to Heart」の欧文字からなり,これらの文 字は,いずれも黒色の線で描かれている。また,THANKS部分は,本 願商標のうち3分の2程度の幅を占めている。
エ AI部分は,赤色の線で描かれた「AI」の欧文字であり,本件図形部 分とほぼ同じ幅である。また,AI部分の「A」の文字の中央の横線は, 横長の楕円形に図案化され,「AI」の文字の中段に同文字を取り巻くよう に描かれている。もっとも,上記図案化の程度は低く,AI部分は,図形 ではなく文字として認識されるものといえる。
(3) 分離観察の可否について
ア 外観からの検討
(ア) 上記(2)のとおり,本願商標においては,左側から順に,赤色の図形 である本件図形部分,黒色の文字であるTHANKS部分及び赤色で多 少図案化された文字であるAI部分が,重なり合うことなく配置されて いるところ,このような色彩や構成の違いからすれば,各構\成部分は, 同じ高さで横一列に配置されてはいるものの,それぞれが独立したもの であるとの印象も与え,視覚上分離して認識され得るものといえる。
(イ) また,上記(2)のとおり,THANKS部分は,目につきやすい中央 部に相当程度の幅で表されており,看者の目を引きやすいとはいえるものの,他方で,一般に,赤色は黒色よりも注意を引きやすい色彩である\nといえることからすれば,本願商標に接した者は,THANKS部分の みならず,赤色の本件図形部分及びAI部分にも注意を引かれるものと いえる。
(ウ) さらに,上記(ア)及び上記(2)エのとおり,AI部分は,他の構成部分と視覚上分離して認識され得るものといえるが,他方で,図形ではな\nく文字として認識されるものといえることからすれば,THANKS部 分と併せて一連の欧文字の列として認識されることもあるといえる。
(エ) 以上の各事情を併せ考慮すると,本願商標に接した者は,各構成部分がそれぞれ独立したものと認識するか,又は図形である本件図形部分\nと文字であるTHANKSAI部分とに分けられるものと認識すると いえる。
イ 称呼及び観念からの検討
(ア) 上記(2)イのとおり,本件図形部分は,2つの縦長ループを横に2つ 並べたか,又は全体としてハート型様の形状となるように一筆書きした 図形であるとみることができるところ,その形状や色彩を見ても,大き な特徴がある図形であるとはいい難く,何らかの意味合いを表すものとして認識されるものとはいえないから,同部分からは,特定の観念は生\nじず,何らの称呼も生じない。
(イ) THANKS部分についてみるに,同部分のうち「THANKS」 の欧文字は,平易な英語である「thank」の複数形であり,「サンク ス」との称呼が生じる上,その訳に従って「感謝」等の観念が生じると いえるものの,それ以上の特定の観念が生じるものとはいえない。 また,「Related to Heart」の欧文字は,比較的平易 な英語であるといえるところ,「リレイテッドトゥーハート」との称呼が 生じる上,その訳に従って「心に関連する」といった観念が生じるとい えるものの,それ以上の特定の観念が生じるものとはいえない。
(ウ) AI部分についてみるに,「AI」の欧文字は,人工知能を意味する略語として広く知られていることからすれば,「エーアイ」との称呼が生\nじる上,「人工知能」の観念が生じるといえるものの,それ以上の特定の観念が生じるものとはいえない。\n
(エ) 以上のとおり,本件図形部分,THANKS部分及びAI部分は, 称呼の面からみても,観念の面からみてもばらばらであり,統一性のあ る称呼ないし観念によって結び付けられているとはいえないから,本願 商標は,称呼,観念の観点から不可分であるということもできない。
ウ まとめ
(ア) 上記ア及びイで検討したとおり,本願商標の各構成部分は,それぞれが独立したものであるとの印象を与え,視覚上分離して認識されるも\nのといえる上,称呼,観念の観点から不可分であるともいえず,他に, その不可分一体性を認めるべき事情も見当たらない。 そうすると,本件図形部分とその他の構成部分とは,本件図形部分のみを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分\n的に結合しているものとは認められない。
(イ) したがって,本件図形部分を分離して観察することは可能であるというべきところ,本件図形部分は,相応の特徴を備えている上,それが,\n看者の注意を引きやすい赤色で描かれた図形であることや,最も左側に 配置されていることなども併せ考慮すると,本願商標に接した者は,本 件図形部分を,単なる装飾ではなく,THANKS部分及びAI部分と は独立したシンボルマークのようなものと認識するものといえるから, これを要部として観察することも許されるというべきである。
(ウ) 以上検討したところによれば,本件においては,本願商標から本件 図形部分を抽出し,同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断する ことが許されるというべきである。 したがって,取消事由1及び2は,いずれも理由がない。
2 原告の主張について
(1) 原告は,本願商標は会社名とシンボルマークとを組み合わせた企業ロゴ であり,需要者等はその全体を企業ロゴとして認識するか,又は会社名の表記部分に着目するのが通常であるから,全体を一体的に観察すべきである旨\n主張する。 しかしながら,いわゆる企業ロゴに接した需要者等が,図形やマーク部分 のみに注意を引かれることも当然にあり得るというべきであるから,企業ロ ゴについて,常に全体を一体的に観察すべきであるとはいえない。また,上 記1で検討したとおり,本件図形部分は,本願商標の外観上,他の構成部分と一体のものと認識されるものではなく,また,相応に目立つ態様で表\示されているといえるのであるから,本願商標に接した者が,本件図形部分のみ に注意を引かれることは十分にあり得るというべきである。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 原告は,THANKSAI部分の称呼及び観念に関して,同部分は原告の グループ名「THANKSAI(サンクスアイ)」を表すものであり,同部分からは「サンクスアイ」等の称呼が生じ,また,原告グループのモットーで\nある「感謝愛」等の観念が生じる上,これに伴って,他の構成部分からも共通する観念が生じる旨主張する。\n そこで検討するに,証拠(甲3ないし7,9の1及び2,甲10,11) 及び弁論の全趣旨によれば,原告が,サンクスアイ株式会社との名称のグル ープ会社を有し,指定商品に係る同社の事業において本願商標を使用してい ることが認められる上,原告は,グループ全体で,「感謝」,「愛」等を企業イ メージとして事業活動を行ってきたことがうかがわれる。 しかしながら,この点が,取引の実情として主張されているのだとすれば, 上記事情は,原告の現状の取引状況に基づく個別的な事情であって,取引状 況として考慮することが許される,その指定商品全般についての一般的,恒 常的事情(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日第一小法 廷判決・審決取消訴訟判決集昭和49年443頁参照)といえるかどうかは 疑問である。また,この点を措くとしても,THANKS部分及びAI部分 は,いずれも比較的平易な英語や広く知られた略語であるところ,本件各証 拠をもっても,本願商標の指定商品の取引者や需要者の間において,原告の グループ名や企業イメージが広く知られていたものとまでは認められないこ とからすれば,THANKSAI部分から直ちに原告のグループ名や企業イ メージを表すような特定の称呼や観念が生じるものとはいえない。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(3) 原告は,原告のグループ名を表すTHANKSAI部分の自他商品識別標識としての機能\は極めて強いのに対して,本件図形部分は,よくあるリボンモチーフを重ねてハート型様にするなどの単純な構成からなる上,同部分から特定の称呼や観念が生じないというのであれば,同部分には自他商品識\n別標識としての機能はないか,極めて弱い識別力しかない旨主張する。 しかしながら,上記(2)で検討したとおり,THANKSAI部分から直ち に原告のグループ名や企業イメージを表すような特定の称呼や観念が生じるものとはいえないことからすれば,同部分が,本願商標の指定商品との関係\nにおいて,殊更に強い出所識別機能を有するものとはいえない。 他方で,上記1で検討したとおり,本件図形部分は,本願商標において相 応に目立つ態様で表示されているといえる上,相応の特徴を備えており,看者の注意を全く引かないほど単純な構\成であるとまではいえないことからすれば,同部分は,本願商標の指定商品との関係において,一定程度の出所識 別機能を有するものというべきである。 そうすると,他の構成部分と比較しても,本件図形部分は,本願商標の指定商品との関係において,これを要部として抽出して同部分のみを他人の商\n標と比較して類否を判断することが許される程度の出所識別機能を有するものといえる。\n
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.09.11
平成29(ワ)27378 特許権持分一部移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年8月21日 東京地方裁判所
原告は,本件発明の発明者であることの確認を求める利益を有すると主張す る。しかし,確認の利益は,原告の権利又は法律的地位に危険や不安定が現存し, かつ,その危険や不安定を除去する方法として,当事者間に当該請求について 判決をもって法律関係の存否を確定することが必要かつ適切な場合に認められ ると解されるところ,本件発明の発明者であることの確認請求は,原告が本件 発明の発明者にあるという事実関係についての確認を求めるものにすぎず,給 付の訴えである不法行為に基づく損害賠償請求をすれば足りるのであるから, 原告には本件発明の発明者であることの確認を求める利益があるということは できない。 したがって,本件訴えのうち,原告が本件発明の発明者であることの確認を 求める部分は確認の利益を欠き,不適法である。
・・・
上記(2)ないし(4)によれば,1)本件発明の技術的思想を着想したのは,被 告Y及びZ教授であり,2)抗PD−L1抗体の作製に貢献した主体は,Z教 授及びW助手であり,3)本件発明を構成する個々の実験の設計及び構\築をし たのはZ教授であったものと認められ,原告は,本件発明において,実験の 実施を含め一定の貢献をしたと認められるものの,その貢献の度合いは限ら れたものであり,本件発明の発明者として認定するに十分のものであったと\nいうことはできない。 したがって,原告を本件発明の発明者であると認めることはできない。
(6) 原告の主張について
ア 発明者の認定基準について
(ア) 本件実験のほぼ全てを原告が行ったことについては,当事者間に争い がないところ,原告は,化学の分野においては,発明の基礎となる実験 を現に行い,その検討を行った者が発明者と認められるべきであると主 張する。 しかし,前記判示のとおり,発明者と認められるためには,当該特許 請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分を着 想し,それを具体化することに現実に加担したことが必要であり,仮に, 発明者のために実際に実験を行い,データの収集・分析を行ったとして も,その役割が発明者の補助をしたにすぎない場合には,発明者という ことができないと解すべきである。 原告が本件発明に係る技術的思想に関与せず,抗PD−L1抗体の作 製・選択及び本件発明を構成する実験の設計・構\築に対する貢献もごく 限られたものであったことは,前記判示のとおりであり,これによれば, 原告の本件発明における役割は補助的なものであったというべきであ る。
(イ) また,原告は,特許発明に係る情報を記載した各種文書を作成し,こ れを管理している場合には,いわば発明を占有するものとして発明者性 が推認されるべきであると主張するが,研究の補助者が特許発明に係る 情報を記載した各種文書を作成・保管することもあり得ることに照らす と,特許発明に関する文書の作成・保管主体をもって直ちに発明者であ ると推認することはできない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> その他特許
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2020.09.10
平成29(ワ)28189 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年1月17日 東京地方裁判所
上記記載によれば,本件発明等の課題は,1)包装体の大きさを従来と同様 に維持しつつ,より大きなサイズのシート状物を積層できる構造を提供する\nこと,2)包装体同士を積み重ねた際の安定感のあるシート状物の積層体を提 供することにあり,本件発明等の効果は,3)従来と比較して第2の折片の面 積分だけ大きいサイズのシート状物によって,従来と変わらないサイズの積 層体を形成することができ,また,第2の折片が設けられた大きさ分だけ肉 厚部分が形成され,積層体同士を重ね合わせた際の安定感を向上することが できるという効果を得られることにあると認められ,本件発明等においては, 上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得るために第2の折片を設けてい るが,本件発明等に係るシート状物のサイズを従来のものより大きくするた めには,その前提として,第2の折片以外の部分を可能な限り大きくするこ\nとが必要となるものと解される。
すなわち,本件発明等の第1の中間片の幅は積層体の幅と略同じ長さと規 定されているところ,第2の中間片及びこれと略同じ幅の第1の折片の長さ を第1の中間片の幅の2分の1より小さくすると,第2の折片を設けたとし ても,シート状物全体のサイズがその分だけ従来のものよりも小さくなって しまい,上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得ることができなくなる一 方,第2の中間片の幅を第1の中間片の2分の1よりも長くすると,第2の 中間片同士が中央部で重なり合い,全体の嵩高状態が不安定なものになって しまい,上記2)の課題解決に支障が生じることとなる。そうすると,本件発 明等の上記課題1)及び2)を解決し,所期の効果を奏するには,第2の中間片 の幅を,第1の中間片の1/2を超えない範囲でこれに限りなく近づけるこ とが望ましいものと認められる。
エ 前記のとおりの「略」という語の通常の意義及び構成要件Cにおいて第2\nの中間片の幅寸法が規定されている技術的意義に照らすと,同構成要件にい\nう「略1/2」とは,正確に2分の1であることは要しないとしても,可能\nな限りこれに近似する数値とすることが想定されているものというべきで あり,各種誤差,シート状物の伸縮性等を考慮しても,第1の中間片の2分 の1との乖離の幅が1割程度の範囲内にない場合は「略1/2」に該当しな いと解するのが相当である。
オ これに対し,原告は,本件発明等は,容易に伸縮する素材を用いることを 前提とし,第2の中間片及び第1の折片の幅に誤差が生じた場合にも,第2 の折片によりその誤差を吸収して,積層体が所望とする幅寸法になるように 調整することに主眼があるのであって,本件発明等における「略1/2」の 語は,1/2を超える場合は含まないが,1/2より短いものは広く許容す る意味と解釈すべきであると主張する。
しかし,本件明細書等には,第2の中間片が第1の中間片の幅の1/2よ り小さい幅となったときに第2の折片がその誤差を吸収することにより積 層体の幅寸法を維持することが本件発明等の課題である旨の記載は存在し ない。むしろ,前記判示のとおり,本件明細書等には,積層体の幅を従来と 同様とした上で,第2の折片を設けることにより「第2の折片の面積分だけ 従来と比較して大きいサイズのシート状物」(段落【0011】)を形成す ることが本件発明等の課題である旨が記載されているのであって,その課題 解決のためには,前記のとおり,第2の中間片の幅を,可能な限り第1の中\n間片の1/2を超えない範囲でこれに近づけることが望ましいものという べきである。
・・・
3 相違点1の認定の誤りについて
(1) 前記2(1)の甲6の記載事項(図2ないし4を含む。)を総合すれば,甲 6には,本件審決が認定するとおり,甲6(審判甲1)発明が記載されてい ることが認められる。そして,本件訂正発明と甲6(審判甲1)発明を対比すると,本件訂正発明の第2の折片の幅と甲6(審判甲1)発明における「腰折ウェットテシュ ー11f,12f」(第2の折片に相当)の幅について,本件訂正発明は, 「上記第1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整する とともに,上記第1の中間片の幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の 幅より短い幅となる」のに対し,甲6(審判甲1)発明は,「腰折ウェット テシュー11,12の展開長の略五分の一の長さ,又は腰折ウェットテシュ ー11,12の幅方向の中心線Yを越えず且つこれに接近した長さ」である 点で相違すること(本件審決認定の相違点1)が認められる。したがって,本件審決における相違点1の認定に誤りはない。
(2) これに対し原告は,1)特許法施行規則24条の2は,特許発明の技術上の 意義ある部分は,「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」 により特定される旨規定していることからすると,発明は,解決課題(目的 あるいは作用・効果)と解決手段(構成)とで特定しなければならない,2) 本件訂正発明と甲6に記載された発明の相違点を捉えるには,第2の折片と 他の片との関係性をシート全体の折構造で把握する必要があるなどとして,\n本件審決における甲6(審判甲1)発明の認定は適切ではなく,本件審決認 定の相違点1は,原告主張の相違点1(前記第3の1(1))のとおり認定すべ きである旨主張する。
しかしながら,特許出願に係る発明の要旨の認定は,特許出願の願書に添 付した特許請求の範囲の記載に基づいてすべきものであるところ,原告主張 の相違点1は,本件訂正発明の特許請求の範囲(請求項1)記載の発明特定 事項以外の事項(本件明細書記載の「背景技術」,「発明が解決しようとす る課題」等)をも含めて本件訂正発明の要旨を認定することを前提として, 本件訂正発明と甲6に記載された発明とを対比するものであるから,その前 提において,採用することができない。また,特許法施行規則24条の2は, 特許法36条4項1号の経済産業省令の定めるところによる記載は,発明が 解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分 野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必 要な事項によりしなければならない旨規定し,明細書の発明の詳細な説明の 記載要件を定めた規定であるから,原告主張の相違点1が適切であることの 根拠となるものではない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
4 相違点1の判断の誤りについて
(1) 本件訂正発明の「上記第1の中間片から積層方向上側に折り返され上記第 1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとともに, 上記第1の中間片の幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の幅より短い 幅となる第2の折片」にいう「調整」の意義について ア 本件訂正発明の「上記第1の中間片から積層方向上側に折り返され上記 第1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとと もに,上記第1の中間片の幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の幅 より短い幅となる第2の折片とを有するように折り畳まれ」との記載から, 本件訂正発明の「第2の折片」は,「第1の中間片の幅の1/2未満で, かつ,上記第1の折片の幅より短い幅」であって,「第1の中間片から積 層方向上側に折り返され」,「第2の折片」によって「第1の中間片の幅 が所望とする積層体の幅寸法となるように調整」することができることを 理解できる。 一方で,本件訂正発明の特許請求の範囲(請求項1)には,「上記第1 の中間片から積層方向上側に折り返され上記第1の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように調整する」にいう「調整」について,具体 的な調整方法等について規定した記載はない。
イ 次に,本件明細書には,「調整」に関し,「調整」の語について定義し た記載はなく,「図1に示すように,シート状物10は,所望とする積層 体の幅寸法と略同じ長さに形成された第1の中間片11と,積層方向下側 に折られ,第1の中間片11の略1/2の幅に第1の中間片11に隣接し て形成された第2の中間片12と,第2の中間片12から積層方向下側に 折り返され第2の中間片12と略同じ幅に形成された第1の折片13と, 第1の中間片11から積層方向上側に折り返され第1の中間片11の幅が 所望とする積層体の幅寸法となるように調整する第2の折片14とから構\n成されている。」(【0014】)との記載がある。また,本件明細書に は,「第2の折片」に関し,「第2の折片14は,第1の中間片11と隣 接し,シート状物10の長さ方向に平行な長辺10a,10bと,第3の 折れ線17と短辺10cとによって囲まれる部分である。シート状物10 の長辺10a,10bの第2の折片14の長さにあたる部分,つまり第3 の折れ線17と短辺10cとの距離Dは,D<Cの関係を有する。つまり, 距離Dは,距離Aの半分より小さい値である。」(【0020】),「以 上のように構成されたシート状物積層体1は,従来の積層構\造においては ない第2の折片14を有することで,従来と変わらない積層体の幅として も,第2の折片14の面積分だけ従来よりもサイズの大きいシート状物1 0を積層させることができる。具体的には,シート状物10は,従来使用 されるシート状物の大きさと比較して,第2の折片14の面積分,つまり 上述のD<Cの関係を有する範囲内で大きさを変更することができ,約2 5%まで大きいサイズのシート状物を使用することができる。」(【00 26】)との記載がある。
ウ 以上の本件訂正発明の特許請求の範囲の記載,本件明細書の記載及び図 1によれば,本件訂正発明の「上記第1の中間片から積層方向上側に折り 返され上記第1の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調 整する」にいう「調整」とは,シート状物の第1の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように,「第2の折片」の幅を「第1の中間片の 幅の1/2未満で,かつ,上記第1の折片の幅より短い幅」となるように 設定することを意味するものと解される。
・・・
被告製品2)については,上記アの審理経過に照らし,信用性が高いと認め られる甲25及び乙A39に基づいて検討することが相当であるところ,原 告が被告製品2)(YRC24/3FM13:59)について測定した結果(甲25:別紙6 −2)によれば,同製品の各シート状物の第1の中間片の幅の2分の1に対 する第2の中間片の幅の比率(以下,単に「第2の中間片の比率」というこ とがある。)が90%〜100%の範囲内にあるものは,全80枚のうち3 枚にすぎず,その平均値(「平均値(1,80枚目除く)」欄のもの。以下 同じ。)も83%にとどまるものと認められる。また,被告PPJが被告製品2)(YRC24/3FM16:40)について測定した結果(乙A39:別紙6−4)によれば,第2の中間片の比率が90%〜100%の範囲内にあるものは,全80枚のうち30枚であるものの,同比率がその範囲内にあるものは,いずれも偶数番目のシート状物であって,奇数番目の シート状物にはこれが存在しない上,全体の平均値も84%にとどまるもの と認められる。
上記の被告製品2)全体における第1の中間片の幅の2分の1に対する第2の中間片の幅の平均比率,その比率が90%〜100%の範囲内にあるものの割合及びその分布等に照らすと,被告製品2)の第2の中間片が構成要件C「第1の中間片の略1/2の幅」との要件を充足するとは認められない。\n
◆判決本文
対応する審決取消訴訟はこちらです。こちらは、無効審決が維持されています。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.09. 9
平成31(受)619 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件 令和2年9月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 知的財産高等裁判所
本件確認請求に係る訴えは,被上告人が,第三者である参加人の上告人に対する 債務の不存在の確認を求める訴えであって,被上告人自身の権利義務又は法的地位 を確認の対象とするものではなく,たとえ本件確認請求を認容する判決が確定した としても,その判決の効力は参加人と上告人との間には及ばず,上告人が参加人に 対して本件損害賠償請求権を行使することは妨げられない。
そして,上告人の参加人に対する本件損害賠償請求権の行使により参加人が損害 を被った場合に,被上告人が参加人に対し本件補償合意に基づきその損害を補償 し,その補償額について上告人に対し本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害 賠償請求をすることがあるとしても,実際に参加人の損害に対する補償を通じて被 上告人に損害が発生するか否かは不確実であるし,被上告人は,現実に同損害が発 生したときに,上告人に対して本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請 求訴訟を提起することができるのであるから,本件損害賠償請求権が存在しない旨 の確認判決を得ることが,被上告人の権利又は法的地位への危険又は不安を除去す るために必要かつ適切であるということはできない。
なお,上記債務不履行に基づく損害賠償請求と本件確認請求の主要事実に係る認定判断が一部重なるからといって,同損害賠償請求訴訟に先立ち,その認定判断を本件訴訟においてあらかじめしておくことが必要かつ適切であるということもできない。 以上によれば,本件確認請求に係る訴えは,確認の利益を欠くものというべきで ある。
◆判決本文
原審(知財高裁)は下記です。
◆平成30(ネ)10059
1審はこちらです。
◆平成29(ワ)28060
本件についての参考サイト(20200909時点では控訴審まで)
https://innoventier.com/archives/2019/03/8058
関連カテゴリー
>> 実施権
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2020.09. 7
令和1(ワ)7786 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 令和2年8月27日 大阪地方裁判所
ア 原告表示1について\n
前記(第2の2(1),第3の1)認定の各事実に加え,証拠(甲3,5,9の2 及び9の3,21,22,29,36)及び弁論の全趣旨によれば,原告大学は, その母体の設立からは140年,現在の名称となってからでも50年以上という長 期にわたり,京都市に所在して芸術教育を実施し,文化勲章受章者を含む多数の芸 術家を輩出している。また,原告大学は,京都市内にギャラリー(@KCUA)を設 置し,同所にて展覧会等の催事を繰り返し実施するとともに,京都市内において, 案内チラシ等に原告表示1を付すなどして展覧会や演奏会を主催し,また,地下鉄\n駅構内その他京都市内の人目に付きやすい場所に,原告表\示1を付して作品を展示 し,さらに,京都市内において児童その他市民向けの芸術教育活動等を行ってきた ことが認められる。 これらの事情のほか,京都府及びその近隣府県の範囲における交通や新聞等によ る報道の実情等に鑑みると,京都府及びその近隣府県に居住する一般の者が,原告 大学を表示するものとして原告表\示1を目にする機会は,相当に多いものと合理的 に推認される。 そうすると,原告表示1は,原告大学を表\示するものとして需要者に広く認識さ れており,周知のものといってよい。これに反する被告の主張は採用できない。
イ 原告表示2〜4について\n
(ア) 前記1認定の各事実によれば,原告表示2〜4については,例えば原告大\n学の卒業生や受験指導組織といった特定の属性を有する層で原告表示3又は4が比\n較的多数使用されているといった例もあるものの,程度の差こそあれ,原告表示1\nと比較してその使用頻度はいずれも少ないといえる。 しかも,原告大学を示す略称又は通称として,原告表示2〜4のほか,「京都市\n立芸大」,「市立芸大」,「市芸」その他様々なものが使用されている。原告大学 の正式名称(原告表示1と同一のもの)のうち,「京都」(又は「京」),「芸\n術」(又は「芸」)及び「大学」(又は「大」)は,大学の名称としては,所在 地,中核となる研究教育内容及び高等教育機関としての種類を示すものとして,い ずれもありふれたものである。加えて,原告大学の中心的な活動場所等が京都市で あること,このため,原告大学の略称等が使用される地域的範囲としても,京都市 又は京都府であることが必然的に多くなり,「京都」(又は「京」)は敢えて明示 せずとも文脈上暗黙の了解事項となりやすいと推察されることなどに鑑みると,略 称等に「市立」(又は「市」)が含まれ,「京都」(又は「京」)が省略されるこ とも,当然起こり得ることといってよい。原告の設置主体である京都市及び京都市 長や原告大学関係者が,原告大学を示すものとして,自ら「市立」(又は「市」) を含む略称等を使用する例が少なからず見られること,インターネット上又は書籍 としての地図においても,原告大学については「市立」が含まれる表示が使用され\nていることも,この文脈において合理的に理解し得る。 そもそも,このように多種多様な略称等を生じ,それぞれが一定程度使用されて いること自体,原告大学の略称等として各表示それ自体が有する通用力がいずれも\nさほど高くないことをうかがわせる。同一の文書等の中で,原告表示1と共に使用\nされる例が多いことも,同様に,原告表示2〜4の略称等としての通用力の低さを\nうかがわせる。 しかも,原告表示2〜4と同一の表\示が,原告大学ではなく被告大学を示す表示\nとして使用される例も,相応に見受けられる。 他方,原告表示2〜4が,それぞれ,原告表\示1を想起させることを介して,又 はこれを介さずに,原告大学を想起させるものとして広く知られていることをうか がわせるに足る具体的な証拠はない。
(イ) これに対し,原告は,原告表示2〜4についても原告大学の表\示として周 知であり,また,これらと同一の表示が被告大学を指すものとして使用される例は\n誤記であるなどと主張する。 しかし,上記(ア)の事情のほか,仮に原告表示2〜4が原告大学の略称等として\n周知であるとすれば,そのような誤記が多数生ずるはずはないし,そもそも,作成 主体を異にする者の間で同様の誤記が頻発すると考えることは合理性に乏しい。そ の他原告が縷々指摘する事情を考慮しても,この点に関する原告の主張は採用でき ない。
(ウ) 以上より,原告表示2〜4については,原告の商品等表\示として需要者の 間に広く知られたもの,すなわち周知のものということはできない。
・・・
イ 前記(3)イ(ア)のとおり,原告表示1のうち,「京都」,「芸術」及び「大\n学」の各部分は,大学の名称としては,所在地,中核となる研究教育内容及び高等 教育機関としての種類を示すものとして,いずれもありふれたものである。このた め,これらの部分の自他識別機能又は出所表\示機能はいずれも乏しい。他方,\n「(京都)市立」の部分は,大学の設置主体を示すものであるところ,日本国内の 大学のうちその名称に「市立」を冠するものは原告大学を含め11大学,「市立」 ではなく「市」が含まれるものを含めても13大学にすぎず,しかも,京都市を設 置主体とする大学は原告大学のみである(乙2)。このような実情に鑑みると,原 告表示1のうち「(京都)市立」の部分の自他識別機能\又は出所表示機能\は高いと いうべきである。 また,その名称に所在地名を冠する大学は多数あり,かつ,正式名称を構成する\n所在地名,設置主体,中核となる研究教育内容及び高等教育機関としての種類等の うち一部のみが相違する大学も多い(乙1)。このため,需要者は,複数の大学の 名称が一部でも異なる場合,これらを異なる大学として識別するために,当該相違 部分を特徴的な部分と捉えてこれを軽視しないのが取引の実情と見られる。 そうすると,原告表示1の要部は,その全体である「京都市立芸術大学」と把握\nするのが相当であり,殊更に「京都」と「芸術」の間にある「市立」の文言を無視 して「京都芸術大学」部分を要部とすることは相当ではない。この点に関する原告 の主張は採用できない。 また,本件表示の要部については,上記のとおり「京都」,「芸術」及び「大\n学」のいずれの部分も自他識別機能又は出所表\示機能が乏しいことから,これらを\n組み合わせた全体をもって要部と把握するのが適当である。
ウ 原告表示1と本件表\示とは,その要部を中心に離隔的に観察すると,「市 立」の有無によりその外観及び称呼を異にすることは明らかである。観念について も,「市立」の部分により設置主体が京都市であることを想起させるか否かという 点で,原告表示1と本件表\示とは異なる。取引の実情としても,前記イのとおり, 需要者は,複数の大学の名称が一部でも異なる場合,これらを異なる大学として識 別するために,当該相違部分を特徴的な部分と捉えてこれを軽視しない。 そうすると,原告表示1と本件表\示とは,取引の実情のもとにおいて,取引者又 は需要者が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から全体的に 類似のものとして受け取るおそれがあるとはいえない。そうである以上,原告表示\n1と本件表示とは,類似するものということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.09. 7
令和2(ネ)10023 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年8月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「(1) 構成要件A等の「ホワイトカード」及び「使用限度額」の意義\nア 前記1(1)のとおり,本件明細書等では,段落【0002】〜【000 5】において本件発明の課題が説明されているところ,同課題は,クレジットカー ドについてのものであり,プリペイドカードサービスやデビットカードサービスに ついてのものではない。そして,段落【0006】において,「以上の課題を解決 するために,本発明は,・・・ホワイトカード使用限度額引き上げシステムを提供 する。」と記載され,さらに,段落【0007】〜【0009】において,上記課 題を解決するための具体的構成が記載されている。これらの記載に,「ホワイト\nカード」の用語は,クレジットカードに関して使用された場合は,「カード会社が 個人向けに発行する最もベーシックなクレジットカード」を意味するものと認めら れること(乙6,7)を併せ考慮すると,段落【0006】〜【0009】の「ホ ワイトカード」は,段落【0002】〜【0005】に記載されたカードであるク レジットカードを意味するものと認められる。 一方で,本件明細書等には「ホワイトカード」がプリペイドカードやデビット カードを含む旨の記載は存在しないから,本件明細書等の「ホワイトカード」には, プリペイドカードやデビットカードは含まれないものと解される。
イ 前記1(1)のとおり,本件明細書等には,段落【0002】〜【000 5】で,従来技術として,クレジットカードについて,ユーザの支払能力などに応\nじて所定期間内で使用可能な金額である「使用限度額」が契約時にある程度固定さ\nれ,使用限度額の引上げなどの変更がなかなかできない,あるいは煩雑な手続が必 要となるという課題があること,先行技術であるクレジットカード管理システムに 関する発明の乙8発明は,ユーザの利用実績により使用限度額を変更できるという ものであるが,同発明によっても,ユーザが他者から送金を受けた場合に使用限度 額を変更することはできないという課題があることが記載され,段落【0006】 で,上記の課題を解決するために,本件発明は,ユーザが他者から送金を受けたこ とにより使用限度額を引き上げることができるシステムを提供することが記載され ており,これらの記載からすると,本件発明における「使用限度額」は,従来技術 における「使用限度額」と同様に,クレジットカードの使用限度額を意味するが, ユーザに対する入金があると所定の手続を経ずに引き上げられるものであると解す るのが相当である。 したがって,本件発明における「使用限度額」は,ユーザが所定期間内に使用 することのできる金額の上限額を意味し,その額は,ユーザとの契約時には,その 支払能力(信用力)に応じて設定され,「ある程度固定される」ものであるが,そ\nの後,ユーザに対する入金があった場合,所定の手続を経ずに引き上げられるもの であると認められる。
ウ 以上のとおり,本件発明における「ホワイトカード」はクレジット カードを意味し,「使用限度額」は,「契約時に設定され,契約時には,ある程度固 定される,所定期間内で使用可能な金額」を意味するものというべきである。\n
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,本件発明の課題について「使用限度額に関しては契約時に ある程度固定されるため,限度額の引上げなどの変更がなかなかできない,あるい は煩雑な手続きが必要となる」という従来技術の課題(段落【0003】)は乙8 発明により解決済みであり,本件発明の課題は,他者からの送金の受金等による ユーザの所持金の増加を速やかに使用限度額に反映させることにある(段落【00 05】)と主張する。 しかし,本件明細書等の段落【0003】と段落【0005】の記載によると, 乙8公報に記載された従来技術は,「予め定められた使用限度額内での利用実績に\n応じて算出変更」することにより使用限度額を変更することを可能にするものであ\nるが,それでは「他者からの送金を受金することなどでユーザの所持金が当該クレ ジットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても,カード会社に逐一連絡など して所定の手続きを経なければそれが使用限度額に反映され」ないという課題を解 決し得ないことから,本件発明は,本件特許請求の範囲に規定された構成を採用す\nることにより,入金を受け付けた旨の情報に基づいて,所定の手続(煩雑な手続) を経ることなく,ホワイトカードの使用限度額を引き上げることを可能としたもの\nと認められる。
このように,乙8発明は,「使用限度額に関しては契約時にある程度固定される ため,限度額の引上げなどの変更がなかなかできない,あるいは煩雑な手続きが必 要となる」という従来技術の課題のうちの一部を「クレジットカードの使用限度額 を利用実績に応じて算出変更する技術」によって解決したにすぎず,本件発明は, 乙8発明により解決できなかった従来技術の「他者からの送金を受金することなど でユーザの所持金が当該クレジットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても, カード会社に逐一連絡などして所定の手続きを経なければそれが使用限度額に反映 されることは無い」という課題を解決したものであるから,控訴人の上記主張は理 由がない。
◆判決本文
原審はこちらです
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.09. 7
令和1(行ケ)10146 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年8月19日 知的財産高等裁判所
,商品の色彩は,商品の特性であるといえるから,同号所定 の「その他の特徴」に該当するものと解される。そして,商品の色彩は,古 来存在し,通常は商品のイメージや美観を高めるために適宜選択されるも のであり,また,商品の色彩には自然発生的な色彩や商品の機能を確保す\nるために必要とされるものもあることからすると,取引に際し必要適切な 表示として何人もその使用を欲するものであるから,原則として何人も自\n由に選択して使用できるものとすべきであり,特に,単一の色彩のみから なる商標については,同号の上記趣旨が妥当するものと解される。
イ 次に,商標法3条2項は,同条1項3号から5号までに該当する商標で あっても,「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務 であることを認識することができるもの」については,商標登録を受ける ことができる旨を規定している。同条2項の趣旨は,同条1項3号から5 号までに該当する商標であっても,特定の者が長年その業務に係る商品又 は役務について使用した結果,その商標がその商品又は役務と密接に結び ついて出所表示機能\をもつに至ることが経験的に認められるので,このよ うな場合には商標登録を受けることができるとしたものと解される。 そうすると,同条1項3号に該当する単一の色彩のみからなる商標が同 条2項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で あることを認識することができるもの」に当たるというためには,当該商 標が使用をされた結果,特定人の業務に係る商品又は役務であることを表\n示するものとして需要者の間に広く認識されるに至り,その使用により自 他商品識別力又は自他役務識別力を獲得していることが必要であり,さら に,同条1項3号の前記趣旨に鑑みると,特定人による当該商標の独占使 用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要 すると解するのが相当である。 以上を前提に,本願商標が同条2項の「使用をされた結果需要者が何人 かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当する かどうかについて判断する。
・・・
本願商標は,別紙1(1)及び(2)イ記載のとおり,油圧ショベルのブー ム,アーム,バケット,シリンダチューブ,建屋カバー及びカウンタウエ イトの部分をオレンジ色(マンセル値:0.5YR5.6/11.2)と する構成からなる,色彩のみからなる商標であるところ,本願商標の色\n彩は,単一の色彩であり,本願商標の色彩を付する位置は,上記部分に特 定されているが,上記部分の形状は,別紙1(1)に着色して示された図形 の形状や輪郭のものに限定されるものではない。 本願商標の色彩名の「オレンジ色」は,一般に「赤みがかった黄色」と 定義され(乙1),基本色の一つであること(乙37の4頁),JISの色 彩規格に,慣用色名として「オレンジ色」(マンセル値:5YR6.5/ 13)が挙げられていること(乙2),本願商標の色彩と同じ色相が色相 環に挙げられ,近似した色見本が挙げられていること(乙3)からする と,本願商標の色彩のオレンジ色は,ありふれた色彩であって,特異な色 彩であるとはいえない。
また,本願商標の色彩と同系色の「橙」色(マンセル値:5YR6.5 /14)は,人への危害及び財物への損害を与える事故防止・防火,健康 上有害な情報並びに緊急避難を目的として規格化された「JIS安全色」 の一つであり(乙10ないし12),ヘルメット(乙4),レインスーツ (乙5),サイトウェア(乙9),ガードフェンス(乙6),特殊車両(乙 7),タワークレーン(乙8)にオレンジ色が使用されているように,オ レンジ色は,工事現場で一般に使用されている色彩である。 さらに,オレンジ色は,黄色と赤色の中間色であって,基本色の一つで あることから,オレンジ色の色彩名から観念される色の幅は広いもので ある上,人の視覚によって,マンセル値で特定された本願商標のオレン ジ色とマンセル値の異なる同系色のオレンジ色を厳密に識別することに は限界がある(乙37,38)。
(イ) 油圧ショベルは,前記2(1)アの構造を有するところ,本願商標で特定\nされた色彩を付する位置は,油圧ショベルのブーム,アーム,バケット, シリンダチューブ,建屋カバー及びカウンタウエイトの部分であり,車 体色として色彩が通常施される箇所をほぼ網羅しており,色彩を付する 位置としては,ありふれたものである。
(ウ) 以上によれば,本願商標の色彩及び色彩を付する位置は,いずれもあ りふれたものであり,本願商標の構成態様に特異性はない。\n
イ 原告による本願商標の使用態様,油圧ショベルの販売実績及び広告宣伝
(ア) 前記2(2)及び(3)の認定事実によれば,原告は,1970年(昭和4 5年)10月1日に設立されて以来,50年以上にわたり,本願商標又は 本願商標と同一の色彩が使用された油圧ショベルを全国の事業者に対し て継続して販売してきたこと,原告の油圧ショベルの1974年(昭和 49年)から2018年(平成30年)までの年度別販売台数は,●●● ●●●●●●台であり,1981年以降のシェア(市場占有率)は概ね2 0%台であって,油圧ショベルのシェアは,原告を含む主要5社がほぼ 独占し,2005年(平成17年)から2011年(平成23年)までの 国内出荷台数のシェアでは,原告は毎年3位以内に入っていることが認 められる。
上記認定事実によれば,全国の建設工事,土木工事等の工事現場では, 多くの工事関係者等が本願商標又は本願商標の色彩が使用された原告の 油圧ショベルを頻繁に目にしていたものと認められ,これらの工事関係 者等は,原告の油圧ショベルにオレンジ色が使用されていることを認識 したものと認められる。 他方で,前記2(2)イのとおり,原告の油圧ショベルの多くには,アーム 部や車体後部に白抜き又は黒文字で著名商標である「HITACHI」 又は「日立」の文字が付されており,カタログにも原告の社名や「HIT ACHI」又は「日立」の文字の記載があることが認められ,これらの文 字の表示から,原告の油圧ショベルの出所が現に認識され,又は認識さ\nれ得ることも否定することはできない。
(イ) 前記2(4)の認定事実によれば,原告は,1993年(平成5年)以降, 本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を, 少なくとも47種類以上作成し,これらを合計26種類の新聞及び雑誌 に継続的に掲載したこと,原告は,大手建設機械レンタル会社のカタロ グ,書籍・小冊子に本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画 像を用いた広告を継続的に出稿したほか,本願商標の色彩を使用した油 圧ショベルのカラー画像を用いたウェブ広告をGoogle等の4種類 のオンライン媒体に出稿し,このウェブ広告は,合計300万回以上表\n示されたこと,原告は,1990年(平成2年)9月から2016年(平 成28年)1月までの間にわたり,本願商標の色彩を使用した油圧ショ ベル,積込み機,ホイールローダ,鉱山用ダンプトラックなどの建設機械 を含めて,その映像が表示されるテレビCMを放映したこと,1990\n年(平成2年)から2014年(平成26年)までの期間の原告の広告宣 伝費は,多いときで年間15億円を超え,2010年(平成22年)から 2014年(平成26年)においても年間約4億円に及んでいることが 認められる。
他方で,これらの広告(テレビCMを含む。)には,いずれも原告の社 名や「HITACHI」又は「日立」の文字が表示されていること(甲6,\n7の1,50等),原告の油圧ショベルのほか,原告の積込み機,ホイー ルローダ,鉱山用ダンプトラックなどに本願商標の色彩を使用した建設 機械が表示されるもの(甲6の1,6の13,50の3,50の4の2,\n50の5ないし7,50の10,50の47ないし52,50の62ない し66,50の100,50の103ないし108,50の112ないし 118,50の121,50の122,54の5),油圧ショベルのモチ ーフがオレンジ色をした五線譜の音符として表示されるもの(甲50の\n2の2,50の14,50の15,50の34,50の35,50の36), 原告の油圧ショベルその他の建設機械が将棋の駒として表示されるもの\n(甲50の9の2,50の29,50の30,53,54の1),オレン ジを背景にしたキリンのシルエットと同じシルエットの一つに油圧ショ ベルが表示されるもの(甲50の8の2,50の28,50の41,50\nの111)があることに鑑みると,これらの広告は,需要者に対して,本 願商標の色彩が原告のコーポレートカラーであることを印象付けるもの であるとしても,本願商標と原告の油圧ショベルとの間に強い結びつき があることまで印象付けるものとはいえない。
(ウ) さらに,前記2(6)のとおり,本願商標の色彩と同系色であるオレンジ 色をその車体の一部に使用した油圧ショベルとして,住友建機のハイブ リッドショベル,ボブキャット社のDXシリーズ,イワフジの林業ベー スマシン及びその後継機,クボタの「ミニバックホー」等が販売されてい たことに照らすと,本件審決時において,原告が油圧ショベル(ミニショ ベルを含む。)についてオレンジ色の色彩を独占的に使用していたものと 認めることはできない。
(エ) 以上によれば,本願商標が使用された原告の油圧ショベルの販売実績, シェア及び広告宣伝から,本願商標又は本願商標の色彩が原告の油圧シ ョベルに使用されていることは,相当多くの需要者に認識されているこ とは認められるものの,他方で,本願商標は,色彩及び色彩の付する位置 がありふれたものであって,その構成態様は特異なものとはいえないこ\nと,原告の油圧ショベルの多くには,アーム部や車体後部等に著名商標 である「HITACHI」又は「日立」の文字が付されており,これらの 文字の表示から,原告の油圧ショベルの出所が現に認識され,又は認識\nされ得ることも否定することはできないこと,原告による広告宣伝は, これに接した需要者に対し,本願商標と原告の油圧ショベルとの間に強 い結びつきがあることまで印象付けるものとはいえないこと,原告以外 の複数の事業者が本願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体 の一部に使用した油圧ショベルを販売していたことを総合考慮すると, 本件審決時(審決日令和元年9月19日)において,原告によって本願商 標が使用をされた結果,本願商標のみが独立して,原告の業務に係る油 圧ショベルを表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとま\nで認めることはできない。
ウ 本件アンケートの調査結果について
前記(1)認定のとおり,油圧ショベルの需要者は,建設業者,建設機械を 取り扱う販売業者及びリース業者のみならず,農業従事者及び林業従事者, 農機及び林業機械を取り扱う販売業者等が含まれるものであるが,本件ア ンケートは,土木建設業以外の業種等の需要者が調査対象者から除外され, 農業従事者及び林業従事者等が調査対象者に含まれていないから,本件ア ンケートの調査結果は,油圧ショベルの需要者の一部の認識を反映したも のにとどまっている。
また,前記2(5)アの認定事実によれば,本件アンケートのうち,本願商 標に係るアンケートの設問は,別紙1(1)アの本願商標の画像を示した上で, 「以下の画像の色彩を見て,どのメーカーの油圧ショベルかをお答えくだ さい。」というものであり,「回答するメーカー名は,選択式ではなく,自由 記入式」としているが,「回答するメーカー名」は複数であってもよいこと の明記はない。他方で,前記イ(エ)のとおり,原告以外の複数の事業者が本 願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体の一部に使用した油圧 ショベルを販売していたことに照らすならば,「回答するメーカー名」は複 数であってもよいことが明記されていないことは,本願商標に係るアンケ ートの調査結果(有効回答数168通(回収率33.9%),認知率97. 0%)にも,影響を及ぼすものといえる。 そうすると,本件アンケートの調査結果から認定できる需要者における 本願商標の認知度は限定的であるものといわざるを得ない。
エ まとめ
前記アないしウによれば,本件商標が使用された原告の油圧ショベルの 販売期間,販売実績,シェア及び広告宣伝から,本願商標又は本願商標の色 彩が原告の油圧ショベルに使用されていることは,相当多くの需要者に認 識されていることは認められるものの,本願商標の色彩のみが独立して, 原告の販売する油圧ショベルを表示するものとして需要者の間に広く認識\nされていたものとまで認めることはできず,また,本件アンケートは,農業 従事者及び林業従事者等の認識が反映されておらず,油圧ショベルの需要 者の一部の認識を反映したものにとどまっており,本件アンケートの調査 結果から認定できる需要者における本件商標の認知度は限定的であるもの といわざる得ないことからすれば,本件アンケートの調査結果を併せ考慮 しても,本件審決時(審決日令和元年9月19日)において,本願商標は, 原告によって使用をされた結果,原告の業務に係る油圧ショベルを表示す\nるものとして需要者の間に広く認識されていたものとまで認めることはで きないから,本願商標は,その使用により自他商品識別機能ないし自他商\n品識別力を獲得したものと認めることはできない。 これに反する原告の主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.09. 7
令和1(行ケ)10173 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年9月3日 知的財産高等裁判所
本件特許請求の範囲には,複数のピークが生じる場合に,特定のピークを選択す る旨の記載や,全てのピークが140゜C)以上であることの記載が存在しないところ, 上記のとおり,実施例1〜7の発泡体は,比較例2,3と同じ直鎖状低密度ポリエ チレンを20〜60重量%で含有するから,【表1】に記載された141.5〜14\n7.4゜C)(140゜C)以上)の結晶融解温度ピーク以外に,140゜C)未満の結晶融解温度ピークを含むであろうことは,当業者であれば,上記イの技術常識により,容易に理解することができる。このことは,原告による実施例2の追試結果の図(甲8) や甲10の図4とも符合する。 そうすると,本件明細書(【表1】)の実施例1〜7についての結晶融解温度ピー\nクは,複数の結晶融解温度ピークのうち,ポリプロピレン系樹脂を含有させたこと に基づく140゜C)以上のピークを1個記載したものであることが理解できるから, 「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140゜C)以上」は,複数 の結晶融解温度ピークが測定される場合があることを前提として,140゜C)以上に ピークが存在することを意味するものと解され,このような解釈は,上記アの解釈 に沿うものである。
また,本件発明1は,ポリプロピレン系樹脂の含有量を規定するものではないか ら,ポリプロピレン系樹脂の含有量が,140゜C)未満のピークを示す直鎖状低密度 ポリエチレンの含有量を下回る場合を含むことは,実施例7の記載から明らかであ る。そして,このような場合に,当業者であれば,140゜C)未満に一番大きいピーク (最大ピーク)が生じ得ることを理解することができるのであり,「示差走査熱量計 により測定される結晶融解温度ピークが140゜C)以上である」について,複数のピ ークがある場合のピークの大小は問わないものと解するのが合理的である。
エ 以上のとおり,本件発明1の「示差走査熱量計により測定される結晶融解温 度ピークが140゜C)以上である」とは,示差走査熱量計による測定結果のグラフの ピーク(頂点)が140゜C)以上に存在することを意味し,複数のピークがある場合 のピークの大小は問わないものと解され,その記載について,第三者の利益が不当 に害されるほどに不明確であるということはできない。
(3) 被告の主張について
被告は,「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140゜C)以上で あり」について,1)結晶融解温度ピークといえるものは140゜C)以上であるという 解釈,2)最も高温側の結晶融解温度ピークが140゜C)以上であるという解釈,3)最 大ピークを示す温度が140゜C)以上である,又は,最大面積の吸熱ピークの頂点温 度が140゜C)以上であるという解釈,4)最も低い結晶融解ピーク温度が140゜C)以上であるという解釈,5)わずかなピークであっても,そのピークが140゜C)以上に 存在すればよいという解釈等複数の解釈が考えられるところ,いずれを示すものか が不明であると主張する。しかし,3)4)の解釈を採るべき場合にはその旨が明記さ れているところ(乙2・【0032】,乙3・【0056】,乙4・【0024】,乙5・[0025],乙6・【0018】,甲5・【0014】,乙7・【0008】,乙8・【0091】,乙9・【0027】),本件明細書にはこのような記載はなく,複数あるピークの大小を問わず,1つのピークが140゜C)以上にあれば「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140゜C)以上であり」を充足すると解すべきであることは,前記(2)において説示したとおりである。また,5)について,特許請求の範 囲の記載及び本件明細書にピークの大きさを特定する記載はないから,ピークの大 きさを問わず「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140゜C)以 上であり」に該当するというべきであり,「示差走査熱量計により測定される結晶融 解温度ピークが140゜C)以上であり」との記載が不明確であるという被告の主張は 採用できない。 また,被告は,本件発明1において結晶融解温度ピークが複数ある場合は想定さ れていないと主張する。しかし,本件発明1において,結晶融解温度ピークが複数 ある場合が想定されていることは,前記(2)ウに説示したところから明らかである。
・・・
被告は,本件発明はいわゆるパラメータ発明であり,サポート要件に適合す るためには,発明の詳細な説明は,その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との\n関係の技術的な意味が,特許出願時において,具体例の開示がなくとも当業者に理 解できる程度に記載するか,又は,特許出願時の技術常識を参酌して,当該数式が 示す範囲内であれば所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程\n度に,具体例を開示して記載することを要する(知財高裁平成17年(行ケ)100 42号同年11月11日判決)と主張する。しかし,本件発明は,特性値を表す技術\n的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した 物を構成要件とする発明ではなく,被告が指摘する上記裁判例にいうパラメータ発\n明には当たらないから,被告の主張は前提を欠く。
イ 被告は,本件発明の特許請求の範囲の記載が明確ではなく,また,実施可能\n要件を欠き本件発明1は製造することができない態様を含むものであるから,本件 発明はサポート要件に適合しないと主張する。しかし,明確性要件及び実施可能要\n件についての判断は前記2及び3のとおりであり,被告の主張は採用できない。
ウ 被告は,本件明細書の記載(【0020】)から,厚さ,結晶融解温度ピーク, 発泡倍率及び気泡のアスペクト比の4つの条件のうち耐熱性と関連があるのは結晶 融解温度ピークのみであり,これが高いほど耐熱性が優れている旨説明されている と理解できると主張する。 しかし,本件明細書には,厚さ,結晶融解温度ピーク,発泡倍率及び気泡のアスペ クト比の4つの条件のうち耐熱性と関連があるのは結晶融解温度ピークのみであり, これが高いほど耐熱性が優れている旨の説明は存在しない。かえって,結晶融解温 度ピークが143.9゜C)であっても,気泡のアスペクト比が0.5と0.9〜3の範 囲外である比較例1において,耐熱性に劣る結果となっている(【表1】)ことから\nすれば,4つの条件のうち耐熱性と関連があるのが結晶融解温度ピークのみとは理 解されない。
エ また,被告は,4つの条件のうち耐反発性と関連があるのは結晶融解温度ピ ークを除く3つであり,発泡倍率が15cm3/gに近いほど,気泡のアスペクト比 が0.9あるいは3に近いほど,また,厚さが1500μmに近いほど耐反発性が 劣る旨説明されていることを前提に,実施例1及び5の構成の一部を本件発明1の\n範囲内の境界に近い数値に変更した場合に,本件発明1の課題を解決できると認識 することができないと主張する。 しかし,本件明細書には,発泡倍率が15cm3/gに近いほど,気泡のアスペク ト比が0.9あるいは3に近いほど,また,厚さが1500μmに近いほど耐反発 性が劣ることの記載はない。また,被告の主張する構成の変更により耐反発性が低\n下するとしても,所定の評価方法に基づき耐反発性が◎と評価された実施例1及び 5(【0074】,【表1】)について,本件課題を解決できないほどの耐反発性の低下をもたらすとする根拠は不明であり,被告の主張は採用できない。\nオ 被告は,実施例に記載された「AD571」以外のポリプロピレン系樹脂を 使用した場合や,実施例とは異なる条件で発泡体を製造した場合に,本件発明1の 課題を解決できることが実施例によって裏付けられていないと主張する。
しかし,ポリプロピレン系樹脂が,耐熱性や機械的強度(耐衝撃性)に優れた樹脂 であることは,本件特許の出願時の技術常識であり(甲10の「はじめに」の項,乙 11[0002],乙12[0002],乙14[0002]),これによれば,当業者は, 「AD571」以外のポリプロピレン系樹脂を使用した場合や実施例と異なる条件 で発泡体を製造した場合についての実施例及び比較例がなくても,本件明細書の記 載や本件特許の出願時の技術常識に照らし,本件発明1の両面粘着テープが,本件 課題を解決できると認識できるというべきである。
カ 被告は,「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140゜C)以 上であり」について,140゜C)以上の部分にごく小さな結晶融解温度ピークでも存 在しさえすれば良いとすると,そのような,ピークを発現する材料がごく少量の場 合に本件発明1の課題を解決できると認識することはできないと主張する。 しかし,前記ウのとおり,比較例1によれば,耐熱性には結晶融解温度ピークの みならず気泡のアスペクト比が関係していることを理解することができる。そして, 上記オのとおり,ポリプロピレン系樹脂は,耐熱性や機械的強度(耐衝撃性)に優れ た樹脂であるところ,融点が140゜C)よりも低いポリプロピレン系樹脂も本件特許 の出願時の当業者に知られていた(乙11[0008],[0009],乙12[0080],[0097],乙14[0078])。そうすると,ポリプロピレン系樹脂を含有させたこ とに基づく140゜C)以上のピークがごく小さいものであったとしても,ポリプロピ レン系樹脂の含有量を調整すること及び気泡のアスペクト比を調整することにより, 本件課題を解決することができると認識することができるというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.09. 1
令和1(行ケ)10155 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年8月26日 知的財産高等裁判所
「袋」の辞書的な意味は,「中に物を入れて,口をとじるようにした入れ物。」 とされている(広辞苑第七版)。そして,本件発明においても「袋」の語がそのよ うなものとして扱われている(本件明細書の段落【0052】,【0055】,【0 058】,【0059】参照)と認められ,「袋」について上記辞書的意味を超え て,それを限定する記載はない。 他方,甲1の段落【0053】の「・・・複数の区画室28には,少なくとも2 種以上のビタミンが,少なくとも一部のビタミンを他のビタミンと隔離するように, 別々に収容されている・・・」,「・・・壁材39の内壁面同士を剥離可能に熱溶\n着した弱シールからなる隔離部43により下端部が収容室24と隔離され・・・」 との記載,段落【0054】の「・・・収容容器30の隔離部43は,区画室28 の壁材39を押圧することにより,剥離して開放できる・・・」との記載及び【図 6】からすると,甲1発明の区画室28は,内部にビタミン等を収容することが予\n定されたものであり,隔離部43が閉じたり,開いたりして「口」としての役割を 果たすものであると認められるし,【図6】に表れた区画室28の形状からしても\n区画室28は「袋」と呼んで差し支えないものである。 そうすると,甲1発明の区画室28の形態は,本件発明1にいう「袋」に相当す るものであり,この点を否定した審決の認定は相当ではない。
・・・
本件発明1では,輸液製剤は,輸液容器が,ガスバリヤー性外袋に収納されてお り,上記外袋内の酸素を取り除いたものであるのに対して,甲1輸液製剤発明では, そのような特定のない点。 イ 前記(1)イ(エ)bのとおり,当業者は,甲1から,収容室23にシステイ ン,またはその塩,エステルもしくはN−アシル体を収容し,区画室28に微量金 属元素を収容するという構成を認識することができないところ,本件発明1の「ア\nセチルシステイン」は,システインのN−アシル体であるから,相違点1−1及び 相違点1−2は,実質的な相違点ということができる。
(3) 小括
以上からすると,その余の点について判断するまでもなく,本件発明1が甲1輸 液製剤発明と同一ではないとした審決は結論において相当であり,原告が主張する 取消事由1は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2020.09. 1
令和1(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年8月26日 知的財産高等裁判所
(イ) 前記ア(イ)〜(エ)の本件明細書の記載からすると,特許請求の範囲の請求 項1及び15にある第1,第2及び第3段階と第1,第2及び第3の温度の技術的 意義は,次のとおりであると認められる。
1) 第1段階として,加熱要素の温度をエアロゾル形成基材からエアロゾルが発 生する温度であるが許容温度(「エアロゾル形成基材から所望の物質の揮発が開始さ れる温度」から「エアロゾル形成基材から望ましくない物質の揮発が開始される温 度」未満又は「エアロゾル形成基材が燃焼する温度」未満)の範囲内の第1の温度 まで上昇させ,装置及び基材が温まり,凝縮が抑えられてエアロゾルの送達が増加 することに伴い,2)第2段階として,エアロゾルの送達を抑えるため,第1の温度 より低いが,エアロゾル形成基材のエアロゾル揮発温度よりは低くならない,エア ロゾルの送達を軽減する温度である第2の温度へと加熱要素の温度を低下させ,そ の後,エアロゾル形成基材の枯渇及び熱拡散の低下に起因するエアロゾル送達の減 少が生じるため,それを補償するため,3)第3段階として,加熱要素の温度を第2 の温度より高いが許容温度内にある第3の温度に上昇させる。4)これらの構成を採\n用することにより,「ユーザによる複数回の吸煙を含む期間にわたって特性がより一 貫したエアロゾルを提供するエアロゾル発生装置及びシステムを提供すること」と いう本件発明の課題が解決される。
(ウ) 以上の本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして,本件特 許の特許請求の範囲の請求項1及び15を見ると,原告が主張する特性がより一貫 したエアロゾルを提供できない態様の時間や温度のもの(前記第3の1(原告の主 張)(1)で原告が例として挙げているようなもの)までが本件特許の特許請求の範囲 に含まれるとは解されない。
(エ) そうすると,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び15は,発明の 詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。
(2) 原告は,1)本件特許の特許請求の範囲には,第1,第2及び第3の温度の技 術的意義や持続時間又は切替タイミングについて何も規定されていないから,特許 請求の範囲を本件明細書の記載に基づいて限定解釈することは許されない,2)「第 3の温度」に関して,加熱要素の温度を上げることで,エアロゾル送達の減少を抑 制できるという技術常識が存在せず,当業者はそのことを理解できないし,「第2段 階」についても,エアロゾルの送達を抑制するために加熱要素の温度を下げるとい うことは当業者には理解できないと主張する。
ア 上記1)について
(ア) 前記のとおり,サポート要件の判断は,特許請求の範囲の記載と発明 の詳細な説明の記載とを対比して行うものであるが,対比の前提として特許請求の 範囲から発明を認定するに当たり,特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意 味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に,必要に応じて明細書や図面 の記載を斟酌することは妨げられないというべきであり,当事者が引用するリパー ゼ判決は,そのことを禁じるものと解することはできない。 そして,本件においては,本件明細書の記載に照らすと,特許請求の範囲の請求 項1及び15について,前記(1)で認定したとおりのものであると理解できるのであ り,それを基に特許請求の範囲と発明の詳細な説明を対比すると,特許請求の範囲 に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の 記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると いえる。
(イ) 原告は,この点について,サポート要件の判断に当たって,発明の詳 細な説明に基づく特許請求の範囲の限定解釈が許されるとすると,特許請求の範囲 が文言上どれだけ広くてもサポート要件違反になることがなくなり,その趣旨が没 却されるし,侵害の場面で広範な特許請求の範囲に基づき充足を主張でき,二重の 利得を得ることになるから不当であると主張する。 しかし,サポート要件の判断に当たって,発明の詳細な説明を参酌するからとい って,特許請求の範囲に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明の内容が,発 明の詳細な説明によってサポートされていないときは,サポート要件違反になるこ と(例えば,特許請求の範囲の文言に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明 の内容が,AとBの両方を含むものであるが,実施例等としては,Bしかないとき にAはサポートされていないと判断する場合があることなど)はあり得るのであっ て,常にサポート要件違反を免れるということにはならない。 また,特許発明の技術的範囲を定めるに当たり,明細書及び図面を考慮するとさ れていること(特許法70条2項)からすると,原告のいう二重の利得が発生する とはいえない。したがって,原告の上記主張は,前記(1)の判断を左右するものではない。
イ 上記2)について
「第3の温度」について,本件明細書では,段落【0056】において,【図4】 を示しつつ,成分の送達は,ピークを迎えた後に,「基材の枯渇」及び「熱拡散効果 が弱まること」によって,時間と共に低下すると説明しているところ,同説明は一 般的な科学法則に合致した合理的なものであり,当業者は,ここから吸い終わりに 近い頃に,より高い熱量を加えて,熱拡散効果を高めてエアロゾル形成基材全体の 温度を上げ,エアロゾルの発生量を増やすことで,エアロゾル送達の減少を抑制で きると理解することができると認められる。
また,「第2段階」について,本件明細書では,段落【0019】において,装置 及びエアロゾル形成基材が温まることによって凝縮が抑えられてエアロゾルの送達 が増加するため,第2段階で加熱要素の温度を第2の温度へと低下させると記載さ れている。【図4】は,上記段落【0019】に記載されている一定時間経過後のエ アロゾル送達の増加に沿うものとなっている。これらの本件明細書の記載も一般的 な科学法則に合致した合理的なものであり,これらの記載に接した当業者は,「第2 段階」において,加熱要素の温度を下げることにより,エアロゾル発生基材からの エアロゾルの発生を抑えることで,エアロゾルの送達の増加を抑制することができ ると理解することができると認められる。 そして,このような第3段階におけるエアロゾル送達の減少の抑制や第2段階に おけるエアロゾル送達の増加の抑制が,「特性がより一貫したエアロゾルを提供する エアロゾル発生装置及びシステムを提供する」という本件発明の課題を解決するも のであることも,本件明細書の記載から明らかである。 なお,原告は,「第3段階」の開始タイミングと「第3の温度」についても主張す るが,それらが本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして解釈される べきことは,前記(1)のとおりである。 以上のとおり,当業者は,本件明細書の記載から「第3の温度」や「第2段階」 について理解することができると認められ,これらが理解できないとする原告の主 張は採用することができない。
(3) よって,原告が主張する取消事由1は理由がない。
3 取消事由3(実施可能要件違反についての判断の誤り)について\n
(1) 本件発明は物及び方法の発明であるところ,物の発明における発明の実施と は,その物の生産,使用等をいい(特許法2条3項1号),方法の発明における発明 の実施とは,その方法の使用をする行為をいうから(同項2号),物及び方法の発明 について実施可能要件を充足するか否かについては,当業者が明細書の記載及び出\n願当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,その物を生産, 使用等することができるか,その方法の使用をすることができるか否かによるとい うべきである。
前記2で認定,判断したとおり,特許請求の範囲の請求項1及び15についての 技術的な意義は明らかであり,また,本件明細書には,設定されるべき許容温度の 範囲の例や三つの具体例を含む発明を実施するための形態が記載されている。また, 従来技術について記載した本件明細書の段落【0002】,【0003】や後述する 甲1の段落【0045】,【0046】,【0048】〜【0050】,甲2の段落[0003],[0027],[0037],[0039]などからすると,加熱式エアロゾル発生装置において,各種のエアロゾル形成基材の種類,香味などを考慮して,加熱温度や時間を適宜設 定することは,本件出願日当時における周知技術であったと認められる。 以上によると,当業者は,本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基 づいて,過度の試行錯誤を経ることなく,使用するエアロゾル形成基材に応じて, 「第1の温度」・「第1段階」,「第2の温度」・「第2段階」及び「第3の温度」・「第3段階」を設定し,本件発明を実施することができるものと認められるから,実施 可能要件は充足されていると認められる。\n
(2) 原告は,任意のエアロゾル形成基材に対して最適な温度プロファイルと時 間的プロファイルを実験的に求めるのは過度の試行錯誤に当たり,エアロゾル形成 基材の材料が明らかにならないと本件明細書に開示された三つの実施例すら実施で きないと主張するが,上記(1)で判示したところに照らし,採用することはできない。
(3) よって,原告が主張する取消事由3は理由がない。
4 取消事由2(明確性要件違反についての判断の誤り)について 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載のみな らず,明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願時における技術常識を 基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明 確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は,本件特許の請求項1及び15の「少なくとも1つの加熱要素」が複数の 加熱要素である場合,請求項1及び15に記載された各「前記加熱要素」が1)複数 の加熱要素のうち一つの加熱要素を意味するのか,2)複数の加熱要素のうちのいく つかを意味するのか,3)全ての複数の加熱要素を意味するのかが不明であると主張 する。
しかし,前記2で認定,判断した特許請求の範囲の請求項1及び15の技術的意 義からすると,これらの発明においては,複数の加熱要素がある場合には,最終的 に複数の加熱要素が協働することにより,「第1の温度」・「第1段階」,「第2の温度」・ 「第2段階」及び「第3の温度」・「第3段階」が実現できるように各加熱要素を適 宜制御するものであることは明らかである。 そうすると,請求項1及び15の「少なくとも 1 つの加熱要素」は,加熱要素が 一つある場合には,その加熱要素を,加熱要素が複数ある場合には,適宜制御され る複数の加熱要素を意味するのであって,原告が主張する1)〜3)のいずれかが特定 されていなくても,請求項1及び15の記載は明確であるといえる。 この点について,原告は,請求項1に5回登場する「前記加熱要素」がどのよう なものを指すか不明であると主張するが,これらの「前記加熱要素」も,上記のと おり,加熱要素が複数ある場合は,適宜制御される複数の加熱要素を意味するので あって,不明確であるということはできない。 よって,原告が主張する取消事由2は理由がない。
・・・
他方,甲2発明は,前記ア,イのとおり,加熱が開始された後,天火の温度が2 40゜C)に達すると,制御部の制御により,電気加熱片による加熱が停止され,天火 の温度が180゜C)を下回ると加熱が再開されることが繰り返され,吸い始めから吸 い終わりまでの間,天火の動作温度が180゜C)〜240゜C)に維持されるように制御 されるというものであり,本件明細書の段落【0056】や【図3】,【図4】にあ るような,動作中に一定の温度をもたらすように構成され,エアロゾル成分の送達\nがピークを迎えた後,エアロゾル形成基材が枯渇して熱拡散効果が弱まるにつれ, 時間と共にエアロゾル成分の送達が低下する従来技術に相当するものといえる。甲 2には,ユーザによる複数回の喫煙を含む期間にわたって,エアロゾルの送達量を 一貫とするために,凝縮が抑えられてエアロゾルの送達量が増加することに応じて 第1の温度から第2の温度へと温度を低下させたり,逆にエアロゾル形成基材の枯 渇及び熱拡散の低下に応じて第2の温度から第3の温度へと温度を上昇させたりす るという技術思想については,記載も示唆もされていない。 以上からすると,甲2発明と本件発明1及び15では,加熱要素の制御方法やそ のための電気回路の構成が異なっているというべきであり,甲2発明と本件発明1\n及び15との間には,本件審決が認定した前記第2の3(5)エ(ア)a及び(ウ)a記載の 相違点1B及び相違点15Bが存在すると認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.09. 1
令和1(行ケ)10143 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年8月27日 知的財産高等裁判所
整髪又は調髪に用いる櫛は,理美容道具としての性格上,その機能性が重\n視されるものと考えられるところ,取引の実情においても,櫛の背骨部の位 置に一定間隔で模様,窪み又は貫通孔等を設けることにより,それらを目盛 り代わりに用いる,指のすべり止めとしての機能を果たさせる,しなりを生\nみ出し,使いやすさを向上させるなどといった,機能向上のための工夫がさ\nれ,それらの工夫が宣伝されている実情があることが認められる(乙5〜1 7)。したがって,カットコームの背面部の貫通孔も,一般的には,機能向\n上のための工夫として認識されるのが通常であり,自他商品の識別標識とし ての特徴であると理解されるものではないといえる。 また,このことは本願商標に係る貫通孔が設けられたカットコームについ ても同様であり,商品の紹介で強調されているのは,「硬さとしなやかさを 両立するための『エアーサスペンション機能(1センチ間隔で空いた背面の\n穴)』」などといった機能面での工夫であって,貫通孔に自他商品識別標識\nとしての機能があることは,何ら言及されていない(乙23〜25)。そう\nすると,これらの記述に接した需要者は,一般的には,上記貫通孔は,機能\n向上のための工夫として設けられているものと認識するのが通常であって, これを自他商品の識別標識と認識するとは考え難いところである。
(4) 以上に検討したところによれば,本願商標の構成は,指定商品の需要者と\nして想定される一般消費者の注意力に照らしてみたとき,構成自体として,\n識別力を備えたものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.09. 1
令和1(行ケ)10139 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年8月27日 知的財産高等裁判所(3部)
前記2(1)のとおり,甲1発明は,プリント配線板との位置合わせ用 のマークであるアライメントマーク(認識マーク)を備えた金属製の印 刷用マスクに関する発明である(甲1【0001】ないし【0003】)。 また,アライメントマークは,印刷用マスクをプリント配線板に対して 正しい位置に配置するためのものであり,カメラで読み取られるなどし てその位置座標が正確に認識されることによって位置合わせ用のマーク としての機能を果たすものといえる(甲1【0003】,【0004】)か\nら,形成されるアライメントマークには,その形状や記載内容に係る精 度よりも,マークの位置や輪郭の寸法に係る精度が強く求められるもの ということができる。 他方で,上記(1)のとおり,甲3文献には,高速度鋼や超鋼合金製の工 具類に文字や数字等のパターンをマーキングする方法として,甲3記載 技術が従来の技術として挙げられるとともに,その課題を解決する手段 として湿式鍍金法を用いたマーキング方法が記載されている。そして, 甲3文献に記載されたこれらの技術は,高精度を要求されるドリル等の 工具類に識別情報としての文字や数字等を表示するためのものであるか\nら,マーキングされる文字や数字等には,その位置や大きさに係る精度 よりも,文字や数字等としての明瞭さや高い解像度が強く求められるも のということができる。 これらの事情を考慮すると,甲1発明及び甲3記載技術は,各技術が 属する分野が異なるものである上,技術の適用対象や要求される機能も\n異なるというべきである。 これに加え,前記2(1)のとおり,甲1発明における被加工品は,金属 製の印刷用マスクであるところ,その材料としてはニッケル合金やニッ ケル−コバルト合金等が好ましいとされている(甲1【0012】)のに 対し,上記(1)によれば,甲3文献における被加工品は,高速度鋼や超硬 合金性の工具類であるから,甲1発明及び甲3記載技術は,被加工品の 材料も異なる。 以上によれば,甲1発明及び甲3記載技術は,技術分野や技術の適用 対象,要求される機能,材料がいずれも異なるというべきである。\n
・・・
オ 原告は,欠点(1)ないし(4)につき,甲3記載技術を甲1発明に適用する ことの阻害要因とはなり得ないなどと主張する。 しかしながら,上記(1)のとおりの甲3文献の記載内容によれば,欠点 (1)ないし(4)は,電解マーキング法一般を念頭に置いた欠点を列挙したも のと読むことができるのであって,そうであれば,同文献に接した当業者 が,電解めっき法に劣るマーキング方法であると否定的に評価されている 甲3記載技術を,電解めっき法を採用するのが好ましいとされている甲1 発明に敢えて適用しようとすることは考え難いというべきである。また, 欠点(1)ないし(4)につき,本件出願時の時点において既に克服された欠点 であることが技術常識又は周知の事項であったと認めるに足りる証拠は 存しない。
したがって,欠点(1)ないし(4)は,甲3記載技術を甲1発明に適用する ことについての阻害要因となり得るというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2020.08.24
令和1(行ケ)10167 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年8月20日 知的財産高等裁判所
商標権は,原告がした令和元年12月12日受付の申請により,\n次の(1)(2)のとおりに分割され,その登録がされた。 (1)指定商品を第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用機械 器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置但し,パワーショベル用の破砕機・切断機・ 掴み機・穿孔機等のアタッチメントを除く」とするもの(登録第5490432号 の1。甲294。以下,分割後の商標を「本件商標1」という。) (2)指定商品を第7類「パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等の アタッチメント」とするもの(登録第5490432号の2。甲295。以下,この 商標を「本件商標2」という。)。
・・・・
商標権の分割は,登録しなければ,その効力を生じない(商標法35条,特許 法98条1項1号)。そして,登録によって生じる分割の効果が遡及することを定 めた規定はないから,分割の効果は,登録の時点から将来に向かって生じるものと 解するのが相当である。 この点に関し,原告は,商標法は,商標登録が無効にされるのを回避するために, その24条2項で,商標権の消滅後においてもその分割をすることができると規定 しており,この趣旨を全うするためには,分割の効果が商標登録時まで遡及するか, 遡及したのと同等の利益が維持されるものと解さざるを得ないと主張する。 しかしながら,既に消滅し,存在しない権利関係を分割するということは,本来, 実体としてはあり得ないものである。商標法24条2項がこのようなものを認めた のは,商標権が存続していた当時の権利行使の当否を判断する前提として,必要な 限りにおいて,分割された商標権の存在を擬制するにすぎないというべきである。 このように解したとしても,商標法24条2項の趣旨に反するものとは解されない。
3 原告の主張について
(1) 商標権の分割の効果は,前記2のとおり,登録の時点から将来に向かって生 じること,また,複数の指定商品についてされた1件の審決は,分割後のそれぞれ の指定商品についてされたものと解すべきこと(商標法69条,46条の2参照) からすれば,原告が商標権の分割をしたことそれ自体は,本件審決の効力を左右す るものではなく,その登録以前にされた本件審決の判断の当否に影響することはな いというべきである。
(2) この点を措くとしても,以下に述べるとおり,原告が本件訴訟において商標 権の分割の効果を主張して,審決の取消しを求めることは,原被告間の手続上の信 義則に反し,又は権利を濫用するものとして許されないというべきである。 なるほど商標法24条によれば,商標権の分割は,その商標権が存続している間 は当然行うことができるものと解され,その時期を制限する旨の定めはない。しか しながら,商標法が,商標権の移転を伴わない場合も含めて,商標権を分割するこ とを認めている趣旨は,前記2(2)のとおり,異議申立てや無効審判の請求がされた\n場合に,問題のない商品又は役務に関する商標権を分離して,権利行使を容易にす ることができるというメリットを生かすことにある。そうであるとすれば,商標権 の無効が主張され,異議申立てや無効審判の請求がされたときは,商標権者におい\nて商標権の分割を遅滞なく行うことを期待しても,商標権者に酷であるとは解され ない。他方で,商標権者において商標権の分割がされないまま,異議申立てや無効\n審判の手続が進行すればするほど,商標登録の無効を主張した相手方には,商標権 の分割がされることはないものとの信頼が生じることになる。 また,商標登録無効審決後に商標権が分割された場合に,分割後の指定商品ごと に無効理由を判断し,審決の違法性を判断すべきものとすると,商標権を分割すれ ば実質的に特許庁や裁判所の判断を繰り返し求めることが可能になり,分割の回数\nを増やすことにより,紛争解決を引き延ばすことになる。
商標権の分割をめぐるこのような当事者間の基本的な利害関係に加え,特に本件 においては,本件商標の商標権者である原告において商標権の分割がされることな く,無効審判の手続が進行して請求不成立審決がされ,これを取り消す旨の第1次 判決がされ,原告の上訴を経て第1次判決が確定し,無効審判の審理が更にされて 本件商標の登録を無効とする旨の本件審決がされたという事実経過を経た後に,商 標権の分割がされている。また,原告は,第1次判決後に本件商標2と商標及び指 定商品を同じくする別件商標の出願をして,既にその商標登録を得ていることに照 らせば,遅くとも別件商標の出願時には本件商標の分割をすることができたもので ある。さらに,本件商標2の指定商品は,本件商標の指定商品である商標法施行規 則別表第7類2「鉱山機械器具」,同7類3「土木機械器具」,同7類4「荷役機械\n器具」,同7類18「農業用機械器具」及び同7類27「廃棄物圧縮装置,廃棄物破 砕装置」のうち,同7類3「土木機械器具」に含まれるとされる「パワーショベル」 を用途とするアタッチメントと解されるが,同7類5「化学機械器具」に含まれる とされる「破砕機」や同7類1「金属加工機械器具」に含まれるとされる「切断機」 等も例示するものであって,このように細分化され,本件商標の指定商品に含まれ るか否かが直ちに明らかとはいえないものを含む商品への分割は,予測し難いもの\nである。これらの事情に鑑みると,本件商標について上記のような商標権の分割が されることはないとの被告の信頼の程度は大きいものということができる。 よって,原告が本件訴訟において商標権の分割の効果を主張して,本件審決の取 消しを求めることは,原被告間の手続上の信義則に反し,又は権利を濫用するもの として許されない。
◆判決本文
審決を取り消した審決取消訴訟の判決はこちら。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.08.24
平成30(ワ)2715 名称使用差止請求事件 不正競争 民事訴訟 令和2年3月25日 東京地方裁判所
原告の事業活動が営業に該当するか
前記・・・アの認定事実によれば,原告を含む太左衛門が 行う事業活動は,長唄囃子の演奏や指導等の文化芸術活動としての性格を有するもの ではあるが,他方において,これらの活動から出演料,名取料等の一定の対価を収受 するなどしていることからすれば,経済上の収支計算の上に立って経済秩序の一環と して行われる事業活動としての性格をも有するものといえる。したがって,原告を含 む太左衛門が行う事業活動は,法2条1項1号の「営業」に該当すると認められる。
(2)「望月」の表示が被告らにとって他人の周知な営業表\示に該当するか
ア 太左衛門は,代々,望月流の家元を称し,古くは芝居囃子において活躍し,その後は自ら演奏会等に出演して長唄囃子を演奏する活動,その門弟等に技芸を伝授し,指導する活動,門弟に対して「望月」の姓を冠した名取名を認許して免状を発行する活動,長唄囃子の保存,普及活動等を行い,出演料,授業料, 名取料といったこれらに対する対価を得てきたものである。 そして, エのとおり,昭和41年9月25日発行の本件名鑑においては, 長唄の流派の一つとして望月家の項目が設けられ,十世家元として太左衛門の名が冒\n頭に挙げられ,望月流の説明内容として,初世左吉や初世太左吉が太左衛門の門弟な いしは門弟筋の人物であることや,「浪花町派」,「森下派」及び「田圃派」が望月流内の3大支流であることなどが記載されていることからすれば,本件名鑑においては, 太左衛門が望月流一門全体を代表する家元として紹介されているということができ\nる。実際に, 十代目太左衛門は,昭和48年及びそれ以降,左武\n郎,左太郎,左喜三郎,左之助及び左喜蔵ら,本件名鑑において「森下派」に属する とされたものか又は現在「森下派」に属すると主張している者らについても名取名の 認許をするなど,望月流一門全体を代表することを示す行動をとっている。\n
さらに,前記・・・は,平成5年6月27日,尾上梅幸 や市村羽左衛門らの歌舞伎役者,芳村五郎治ら他流派の長唄演奏者らの出演の下,十\n一代目家元として九代目望月太左衛門追善囃子演奏会を2回にわたり歌舞伎座で開 催したが,その際の松竹株式会社の会長の挨拶に,十一代目太左衛門につき「流祖こ\nのかた二百数十年の歴史と伝統をうけつぐ望月流の家元太左衛門」と,九代目太左衛\n門につき「九世家元」との記載があり,・・・襲名を紹介する平成5年7月9日付けの東京新聞夕刊の記事には,「望月流は・・・,初代太左衛門以来,太左衛門の名で家元が引き継がれてきた。」との記載があり,同年8月の歌舞伎座での歌舞伎公演の筋書における松竹株式会社会長の挨拶には「太左衛門 の名跡は望月流の家元として二百数十年にわたり囃子方の世界で重きをなしてまい\nりました」などとの記載が,七代目尾上梅幸の挨拶には「望月流の家元太左衛門の名 跡を,この度長左久さんが継承し,十二代目望月太左衛門を名乗ることとなりました。」との記載がそれぞれあり,原告が,平成6年6月に,宗家家元十\二代目望月太左衛門 として,尾上梅幸や市村羽左衛門らの歌舞伎役者,杵屋喜三郎ら他流派の長唄演奏者 らの出演の下,十代目望月太左衛門追善襲名披露演奏会を歌舞伎座で開催した際には,\nそのプログラムに掲載された松竹株式会社会長,日本芸術文化振興会理事長及び仙台 市長のお祝いには,太左衛門について望月流の家元である旨言及する記載がそれぞれ ある。北國新聞も,同月8日,原告につき望月流の家元と記載した記事を掲載してい る。
・・・のとおり,平成9年1月には伝統芸能紙及び関西芸能\紙が,平成15年4月には北國新聞が2回,それぞれ,原告につき望月流の家元と記載した記事を掲載したり,歌舞 伎音楽専従者協議会のウェブサイトにおいて,原告につき「望月流十二代目家元」と\n紹介しているほか,前記1 ア及びイのとおり,平成16年には,四世左吉の襲名の 際に,「十二代目家元望月太左衛門」名義での原告の挨拶を含む挨拶状が送付された\nほか,原告が四世左吉や左之助の門弟らに対し,名取名を認許し,前記1 エのとお り,長唄協会が,平成28年頃に,原告を望月流の代表者として取り扱っている。\n
以上によれば,太左衛門は,代々,望月流の家元を称し,演奏会等に出演して長唄 囃子を演奏する活動等を行い,昭和41年頃には,本件名鑑において,望月流一門全 体を代表する家元として紹介されるに至り,かつ,実際に昭和48年及びそれ以降に\n太左衛門が望月流一門全体を代表する家元であることを示す行動をとってきたほか,\n平成5年6月ないし8月及び平成6年6月には,太左衛門が望月流の家元である旨が 新聞記事において紹介され,上記の各演奏会において,太左衛門が望月流の家元であ る旨を含む上記の各挨拶がプログラム等に掲載される状況にあったということがで きる。さらに,それ以降も,原告は,自らが望月流一門全体を代表する家元であるこ\nとを示す行動をとり,新聞記事等においても同様の紹介がされたほか,長唄協会も同 様の認識を有しているということができる。
以上に加え 流派の運営を統括する地位にある者を指すことに照らすと,遅くとも原告が十二代目太左衛門を襲名した後である平成6年6月までには,太左衛門が,望月流一門全体の家元として本件需要者の間で広く認識されるに至り,それ以降も現在に至るまで,本件需要者の間で広く同様に認識されていたと認めるのが相当である。\n
イ ・・・おいては,家元が門弟に対して名取名を認許するところ,名取名は「望月」の姓を冠したものであ り,名取に取り立てられた者は,以後自らの活動を行うにつきこの「望月」の姓を冠 した名取名を表示し使用することが許されることに照らすと,望月流の名取名におけ\nる「望月」姓は,名取に取り立てられた個人の芸名としての性格を有するだけではな く,同時に,家元による望月流の営業活動を示すものであるということができるから, 「望月」の表示は,望月流の家元としての原告の営業表\示に該当するというべきであ る。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.08.18
令和1(行ケ)10084 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年8月5日 知的財産高等裁判所
上記記載によれば,甲1発明のパック剤は,皮膚に塗布し,乾燥後に 皮膜となったものを剥離して使用するものであって,使用時に皮膚上で 皮膜を形成して作用するものと理解できるから,甲1には,甲1発明の A剤に含まれる「ポリビニルアルコール」及び「カルボキシメチルセル ロースナトリウム」は,皮膚上の皮膜形成に寄与する「増粘剤」である ことの開示があるものと認められる。 他方で,甲1には,「本発明のパック剤には上記必須成分のほかに, 通常のパック剤に使用される・・・増粘剤・・・などを適宜配合することができ る。」(前記2(1)カ)との記載はあるが,「アルギン酸ナトリウム」に ついての記載はなく,「アルギン酸ナトリウム」が皮膚上の皮膜形成に 寄与する「増粘剤」であることを示唆する記載もない。 (イ) 原告は,甲87ないし89を根拠として挙げて,本件優先日当時, アルギン酸ナトリウムが,皮膚上の皮膜形成に寄与する「増粘剤」とし て周知であった旨主張する。
そこで検討するに,甲87(特開平成9−278926号公報)には, 「【発明の属する技術分野】本発明は,主として,青果物や加工食品等 を高品質な状態に保存するのに使用されるガス透過性フィルムに関す る。」(【0001】),「【課題を解決するための手段】本発明のガ ス透過性フィルムは,アルギン酸と水溶性化合物とを含む水溶液で皮膜 を形成し,この皮膜をカルシウ塩等の多価金属塩の水溶液に接触させて アルギン酸を不溶化させアルギン酸凝固フィルムとし,不溶化したアル ギン凝固フィルムを水洗して水溶性化合物を溶解し,溶解される水溶性 化合物でガス透気度を調整することを特徴とする。」(【0010】), 「皮膜を形成するアルギン酸を含む水溶液は,アルギン酸を酸やアルカ リに溶解させた水溶液,水にアルギン酸ナトリウムやアルギン酸カリウ ムやアルギン酸アンモニウム等のアルギン酸塩を溶解させた水溶液が使 用できる。」(【0011】),「本発明のガス透過性フィルムは,ア ルギン酸と水溶性化合物を含む水溶液で皮膜を形成し,この皮膜をカル シウム塩等の多価金属塩で凝固させて,不溶化されたアルギン酸凝固フ ィルムを水洗してガス透気度を調整する。アルギン酸と水溶性化合物と を含む水溶液は,たとえば,段ボール箱や食品等の被コーティング物の 表面に塗布して皮膜とし,あるいは,スリットから多価金属塩の水溶液中に押し出して皮膜とする。」(【0015】),「被コーティング物\nに塗布される皮膜は,アルギン酸ナトリウムの濃度で調整できる。アル ギン酸を含む水溶液は,アルギン酸の濃度を高くすると粘土も高くなる。 粘土の高いアルギン酸水溶液を含む水溶液を使用すると,被コーティン グ物の表面に付着される膜厚が厚くなる。たとえば,アルギン酸ナトリウムの水溶液は,濃度を高くすると粘度も高くなるので,被コーティン\nグ物を濃度の高いアルギン酸ナトリウムの水溶液に浸漬して,厚い皮膜 を形成し,あるいは,アルギン酸を含む水溶液を噴霧して,被コーティ ング物の表面に厚い皮膜を形成する。」(【0016】),「[実施例1]下記の工程でガス透過性フィルムを製造する。」,「1) 1wt% のアルギン酸と,1wt%のプルランを含む水溶液を,5×5cmの段 ボールライナーの片面にに塗布し,段ボールライナーの表面にアルギン酸とプルランを含む水溶液の皮膜,膜厚500μmを形成する。」(【0\n019】)との記載がある。上記記載から,アルギン酸を含む水溶液を 段ボール箱や食品等の被コーティング物の表面に塗布することにより皮膜が形成されることを理解できるが,他方で,甲87には,アルギン酸\n又はアルギン酸を含む水溶液が人体の皮膚上の皮膜形成に寄与すること についての記載も示唆もない。
また,甲88及び89(「機能性包装資材の開発技術の形成−機能\性 段ボール箱の開発」徳島県立工業技術センター研究報告Vol.4)に おいても,アルギン酸又はアルギン酸を含む水溶液が人体の皮膚上の皮 膜形成に寄与することについての記載も示唆もない。 そうすると,原告の上記主張は採用することができない。他に本件優 先日当時,アルギン酸ナトリウムが,皮膚上の皮膜形成に寄与する「増 粘剤」として周知であったことを認めるに足りる証拠はない。
(ウ) 以上によれば,甲1に接した当業者において,甲1発明のA剤に含 まれる,皮膚上の皮膜形成に寄与する「増粘剤」であるポリビニルアル コール又はカルボキシメチルセルロースを,このような機能を有する「増粘剤」であるとはいえないアルギン酸ナトリウムに置換する動機付けが\nあるものと認めることはできないから,原告の前記主張は採用すること ができない。
◆判決本文
関連事件です。
◆令和1(行ケ)10082
本件特許の侵害訴訟事件です。特別部の判断です。
◆平成30(ネ)10063
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.08.18
令和1(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年8月12日 知的財産高等裁判所
本願の請求項1は,「前記切削切断部は,この根菜類の表面から切削対象\n部位を削り出す切削手段,及び根菜類の切削対象部位を二片,又は多片の形状に切 断するための切断手段の根菜類切削切断装置」としており,「切削手段」は,「根菜 類の表面から切削対象部位を削り出す」ものであり,「切断手段」は,「根菜類の切\n削対象部位を二片,又は多片の形状に切断するためのもの」である。このような請 求項1の文言によると,「切削対象部位」は,切削手段により根菜類の表面から削り\n出されるものであるとともに,切断手段により二片,又は多片の形状に切断される ものであることは理解できるが,「切断手段」が,切削手段によって切り出された後 の切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断することまでが記載されているとい うことはできない。
また,上記請求項1の記載によると,本願発明の「切断手段」は,「根菜類の切削 対象部位を二片,又は多片の形状に切断するためのもの」であるから,先に根菜類 の表面から切削対象部位を削り出し,その後,その切削対象部位を切断するものは\nもとより,先に根菜類の切削対象部位に縦溝を入れ,その後,「切削手段」によって, 根菜類の表面から切削対象部位が削り出され,根菜類の切削対象部位が二片,又は\n多片の形状に切断される状態になるものについても,請求項1の文言上,「根菜類の 切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断するためのもの」ということができる。 原告は,本願発明において,根菜類から「切削手段」によって削り出す前の「根 菜類の切削対象部位」に対しては,縦溝を入れることは可能であっても,物を断ち\n切ること,切り離すことを意味する「切断」を行うことはできないと主張するが, 原告の上記主張は,上記で判断したとおり採用することはできない。
イ また,本願明細書を見ると,段落【0048】には,実施例1として, 切削手段1Aで切削切断片KSを形成し,切削手段1Aで切削切断片KSを形成す る直前に,その部分を切断手段1aで切削切断片KS1,KS2,KS3となるよ うに切断するが,工程的には切削と切断が順次,又は略同時に行われることが示さ れているものの,切断工程の切断手段1aが先で,切断線を備えた人参に,切削工 程の切削手段1Aが切断すると他の例もあり得ることも示されており,さらに,段 落【0052】は,実施例1の根菜類切削切断装置Nにおいて,切削片KS(切削 対象部位)が切断手段1aで完全でない切断がされた後に(「根菜類の表面から分離\nしていない状態で」を意味すると解される。)切削手段1Aで切削されて切削切断片 KS1,KS2,KS3となることが記載されているから,本願発明においては, 「切削対象部位」である切削片KSは,「切削手段」による切削の後に又は略同時に 「切断手段」により切断される態様のみならず,根菜類から切断手段により完全で ない切断がされた後に切削手段により切り取られる態様のものも含まれているとい える。
ウ そうすると,本願発明において,「切削手段」による切削と「切断部分」 による切断の前後関係は特定されておらず,前後関係がいずれであっても本願発明 に含まれるということができる。 なお,原告は,本願明細書の【図16】の(a),(b),(d)は,先に切削部分 から切削され,その後切断部分により切断される態様を示していることを指摘する が,本願明細書の段落【0047】によると,【図16】の(a),(b),(d)は一実施例を示したものにすぎないと認められるから,上記判断を左右するものではな い。
エ 以上によると,本願発明の「根菜類の切削対象部位」は,先に根菜類の 表面から切削手段によって削り出された後のものに限定されるものではなく,先に\n切断手段によって切断された後に,切削手段によって根菜類の表面から切削される\nものも含まれているといえるから,切断部分が切断するのは,根菜類の表面(外周)\nである場合も含まれることになる。 したがって,甲1発明の「ごぼう60の外周」は,本願発明の切断手段によって 切断される「根菜類の切削対象部位」に相当しないとの原告の主張を採用すること はできない。
(3) 原告は,甲1発明の「2つ割り刃11」は,本願発明の「切削手段」によ って根菜類の表面から削り出された「切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断\nするための」「切断手段」に相当しない旨主張する。 まず,本願発明は,先に根菜類の表面から切削手段によって切削対象部位を削り\n出し,その後,その切削対象部位を切断手段によって二片又は多片に切断するもの に限られることはなく,先に切削対象部位を切断手段によって完全でない切断がさ れ,その後,根菜類の表面から切削手段によって切削対象部位を削り出すものも含\nまれることは,前記(2)のとおりである。 また,甲1発明において,「2つ割り刃11」は,ごぼう60の外周に縦溝を入れ, その後,「ささがき刃10」がごぼうの外周の表面をささがきし,その結果,2つ割\nりになるささがきを生成するものであることは,前記2のとおりである。 そうすると,甲1発明の「2つ割り刃11」は,本願発明における「切断手段」 に相当すると認められるから,この点に相違点があるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2020.08.18
令和2(ラ)10004 訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告事件 その他 令和2年8月3日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 前記(1)イのとおり,C弁護士は,平成20年1月11日から令和元年1 2月31日までの間,抗告人塩野義に社内弁護士として在籍し,抗告人塩 野義の知的財産部情報戦略グループのサブグループ長として,他の抗告人 塩野義の従業員とともに,平成29年4月1日以降,抗告人らが有する本 件特許権に対応する外国の特許権侵害を理由とする相手方の親会社に対す る米国及びカナダでの訴訟提起の準備,米国訴訟提起後のディスカバリー 手続への対応,米国訴訟における特許の請求項の解釈の検討,カナダ訴訟 における訴訟戦略の検討等を行い,平成30年2月15日から令和元年1 0月15日までの間,基本事件の追行を委任する弁護士の選定,基本事件 の実体的な内容を含む抗告人ら代理人や関係者との訴訟準備に係る協議, 抗告人ら代理人に対する相談資料の作成等,基本事件の訴訟提起のための 準備を担当していたことが認められる。 上記認定事実によれば,C弁護士は,基本事件の内容について,抗告人 塩野義から法律的な解釈及び解決を求める相談を受けて,具体的な法律的 な見解を示し,法律的手段を教示又は助言をしたものと認められるから, 基本事件は,C弁護士にとって,抗告人塩野義の「協議を受けて,賛助し た事件」(弁護士法25条1号及び本件基本規程27条1号)に該当する。 そうすると,C弁護士は,弁護士法25条1号及び本件基本規程27条 1号により,基本事件について,被告である相手方の訴訟代理人としての 職務を行うことはできないものと認められる。
イ そして,前記(1)ウ,オ,カ及びキ(イ)の認定事実によれば,C弁護士は, 抗告人らが令和元年11月20日に基本事件の訴訟を提起した後の令和2 年1月1日,本件事務所に入所し,同日から同年2月10日までの間本件 事務所に在籍したこと,その間の同年1月16日,相手方は,本件事務所 に所属するA弁護士らに基本事件の訴訟追行を委任する旨の同月8日付け の訴訟委任状を原審裁判所に提出し,A弁護士らは,相手方の訴訟代理人 となったことが認められる。 上記認定事実によれば,基本事件は,本件事務所の所属弁護士のA弁護 士らにとって,所属弁護士であったC弁護士が本件基本規程27条1号に より職務を行い得ない事件であるといえるから,本件基本規程57条本文 に定める「他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が本件基 本規程27条1号の規定により職務を行い得ない事件」に該当するものと 認められる。
(3) A弁護士らの「職務の公正を保ち得る事由」の有無について 相手方は,本件基本規程57条ただし書の「職務の公正を保ち得る事由」 の有無は,職務の公正らしさ,すなわち職務の公正な外観の保護という一律 の基準をもって判断すべきではなく,諸事情を総合考慮して具体的事案に即 して実質的に判断されるべきであるところ,1)A弁護士は,基本事件の受任 後直ちに,C弁護士とA弁護士らを含む本件事務所の弁護士らとの間での基 本事件に関する情報の共有や漏えいを防止するための情報遮断措置を講じた こと,2)C弁護士が本件事務所において勤務した期間は1か月余りの短期間 にとどまり,その間に基本事件の情報の共有や漏えいをしたことはなく,C 弁護士の退職(退所)により基本事件に関する情報の共有や漏えいのおそれ も存在しないこと,3)仮にC弁護士及びA弁護士らが基本事件に関する秘密 保持義務違反行為やそれを唆すような行為に及べば,弁護士として懲戒処分 を受けるのみならず,巨額の損害賠償責任や刑事責任を負う可能性すらあるから,そのような行為に及ぶことはあり得ないこと,4)相手方が基本事件の 訴訟代理人を変更したのは,いったんは相手方の特許出願に主に携わってい るD弁護士の所属する特許法律事務所に相談して委任したが,その後,製薬 特許専門訴訟に特化し,その分野での経験が豊かな訴訟専門弁護士に依頼す べきと考えるに至り,2年前に依頼したことがある本件事務所に訴訟遂行を 委任することにしたからであり,その経緯に特段不自然な点はないこと,5) 基本事件は,医薬品に関する特許関係訴訟であって高度に専門特化された分 野の訴訟であり,かつ,渉外案件である基本事件を取り扱うことができる弁 護士は限られており,抗告人ら及びその関係会社のいずれをも顧客としない 法律事務所を探すことは極めて困難であるという実情があり,本件基本規程 57条によってA弁護士らについて訴訟行為の排除が認められるとすると, 相手方において憲法32条が保障する裁判を受ける権利が十分に満足されない事態に発展することからすると,基本事件について抗告人らと相手方との\n利害対立の程度は小さいとはいえない点を踏まえても,基本事件の情報漏え いとそれによる依頼人の利益の侵害の危険性がなく,また,そのような情報 漏えい及び利益の侵害も現に発生していないから,A弁護士らには「職務の 公正を保ち得る事由」がある旨主張する。
ア 「職務の公正を保ち得る事由」の意義について
前記3(2)ウで説示したとおり,本件基本規程57条が,本件基本規程2 7条1号との関係において,他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を 含む。)が同号により職務を行い得ない事件について,所属弁護士が,「職 務の公正を保ち得る事由」があるときを除き,その職務を行うことを禁止 しているのは,所属弁護士がその事件について職務を行うことは,依頼者 に所属弁護士の職務の公正に対する疑念と不安を生じさせるものであり, 他方で,先に他の所属弁護士又は共同事務所を離脱した他の所属弁護士を 信頼して協議又は依頼をした当事者においても,所属弁護士の職務の公正 に対する疑念を生じさせるものであることから,依頼者の信頼を確保し, 依頼者及び上記当事者の利益を保護するとともに,弁護士の職務執行の公 正を確保し,弁護士の品位を保持することを目的とするものであり,この ような本件基本規程57条の規定の趣旨に照らすと,同条ただし書の「職 務の公正を保ち得る事由」とは,所属弁護士が,他の所属弁護士(所属弁 護士であった場合を含む。)が本件基本規程27条1号により職務を行い 得ない事件について職務を行ったとしても,客観的及び実質的にみて,依 頼者の信頼が損なわれるおそれがなく,かつ,先に他の所属弁護士(所属 弁護士であった場合を含む。)を信頼して協議又は依頼をした当事者にと って所属弁護士の職務の公正らしさが保持されているものと認められる事 由をいうものと解するのが相当である。 以上を前提に,A弁護士らの「職務の公正を保ち得る事由」の有無につ いて判断する。
イ 相手方の1)ないし4)の主張について
(ア) 前記(1)の事実関係を前提に検討するに,1)基本事件は,医薬品に関 する本件特許権に基づく特許侵害訴訟であり,抗告人ら又はその関連会 社は,米国及びカナダにおいて本件特許権に対応する外国の特許権に基 づく特許侵害訴訟を相手方の親会社に対して提起し,これらの訴訟が基 本事件と並行して審理されていることからすると,基本事件は,抗告人 らと相手方との間の利害の対立が大きい事件であると認められること, 2)基本事件において,現時点では,相手方から訴状記載の請求原因に対 する認否及び反論が提出されていないが,訴状の記載内容から,基本事 件の審理では,被告製品及び被告成分が本件発明の構成要件を充足するかどうか,均等論の各要件を満たすかどうかなどが主要な争点となるこ\nとが予想され,更には,相手方が本件特許に関する無効の抗弁を提出し,それが争点となり得ることも予\想されるところ,C弁護士は,本件事務所に入所する前に,抗告人塩野義において,知的財産部情報戦略グルー プのサブグループ長として,基本事件の訴訟提起のための準備に中心的 に関与するとともに,本件特許権に対応する外国の特許権侵害を理由と する相手方の親会社に対する米国及びカナダの特許侵害訴訟に係るディ スカバリー手続への対応,請求項の解釈,訴訟戦略の検討等について深 く関与していたことからすると,本件特許に係る薬剤の開発及び特許出 願の経緯,上記開発過程における薬理試験の結果,薬理試験に供された 候補化合物,インテグラ―ゼ阻害作用を奏する化学構\\造等に関する様々 な情報を知り得る立場にあったものと推認され,これらの情報は,基本 事件の訴訟追行において重要な意味を有するものと解されること,3)相 手方は,基本事件の訴訟が提起された当初の段階では,本件事務所とは 異なる法律事務所に所属するD弁護士らに基本事件の訴訟追行を委任し, 令和元年12月23日の基本事件の第 1 回口頭弁論期日にはD弁護士が 相手方の訴訟代理人として原審裁判所に出頭したが,C弁護士が令和2 年1月1日に本件事務所に入所した後,同月16日,A弁護士らに基本 事件の訴訟追行を委任する旨の訴訟委任状を原審裁判所に提出し,一方 で,D弁護士らは同月18日に相手方の訴訟代理人を辞任する旨の辞任 届を原審裁判所に提出したことに照らすと,C弁護士が本件事務所に入 所した時期と近接する時期に,基本事件の被告である相手方の訴訟代理 人が,本件事務所とは異なる法律事務所に所属するD弁護士らから本件 事務所に所属するA弁護士らに切り替わったものといえること,以上の 1)ないし3)の事情は,抗告人らにとって,A弁護士らが基本事件の相手 方の訴訟代理人として職務を行うことについて,その職務の公正らしさ に対する強い疑念を生じさせるものであるものと認められる。
(イ)a これに対し相手方は,A弁護士は,基本事件の受任後直ちに,C 弁護士とA弁護士らを含む本件事務所の弁護士らとの間での基本事件 に関する情報の共有や漏えいを防止するための情報遮断措置を講じた 旨主張(相手方の1)の主張)する。
そこで検討するに,前記(1)の事実関係によれば,1)A弁護士は,令 和2年1月1日にC弁護士が本件事務所に入所することが内定してい た状況下で,令和元年12月27日,相手方との間で,基本事件を受 任することについて合意をした後,同日,C弁護士と面談した際,C 弁護士が基本事件に担当者として関わっていた旨を述べたことから, C弁護士に対し,それ以上の発言をしないように伝え,C弁護士から 抗告人塩野義で担当した基本事件を含む一切の秘密情報を本件事務所 に漏らさないことを誓約する旨記載された誓約書の提出を受けたこと, 2)同日,A弁護士は,本件事務所に所属するB弁護士及び弁理士及び 事務局の職員に対し,C弁護士から基本事件の情報を一切受け取らず, C弁護士にも漏えいしないようにすること等を指示した上,基本事件 に関するメールでのやり取りはC弁護士以外の本件事務所の所員全員 (本件メンバー)間のみで行い,その際のメールの宛先は本件メンバ ー全員とし,宛先の追加又は削除をしないこと,勤務時間の内外を問 わず,基本事件についてC弁護士からは一切聞かず,C弁護士に一切 伝えないこと,基本事件に関するファイルを本件事務所のサーバコン ピュータ内のC弁護士がアクセスできないように設定された本件フォ ルダにのみ入れるものとし,誤ってC弁護士がアクセスできるように 設定されたフォルダに入れた場合には,直ちに削除するとともに,A 弁護士に報告すること,基本事件に関する打合せ及び会話は,C弁護 士が執務室に不在でも本件事務所の第2会議室のみで行うこと等の指 示をしたこと,3)C弁護士が本件事務所での勤務を開始してからは, A弁護士は,基本事件に関する紙媒体の管理の徹底や基本事件に関す る書類をスキャンしたデータの管理の徹底などをC弁護士が不在の場 で弁護士,弁理士及び事務局に指示をし,また,基本事件の訴訟記録 を弁護士及び弁理士の執務室から離れた事務局の執務室の鍵付きのキ ャビネットに保管させ,A弁護士と事務局のみがその鍵を管理するよ うにしたことが認められ,これらの1)ないし3)の措置は,基本事件に 関する情報の共有や漏えいを防止することを目的とする情報遮断措置 に相当するものと認められる。
しかしながら,他方で,C弁護士が本件事務所での勤務を開始した 令和2年1月2日当時,本件事務所には,A弁護士,B弁護士及びC 弁護士を含む合計8名の弁護士及び弁理士が所属し,同じ執務室で執 務を行っていたが,執務室内の構造としては,各弁護士及び弁理士個人の執務スペースの周囲三方がノートパソ\コンの画面の2倍程度の高さの仕切りが設けられていたにとどまること,本件事務所では,本件 事務所の各弁護士及び弁理士の間で,補助する事務局の職員を別にす るといった態勢は執られていなかったことに照らすと,上記1)ないし 3)の措置は,本件事務所において,C弁護士とA弁護士らを含む本件 事務所の他の弁護士及び弁理士らとの間における口頭による基本事件 に関する情報の伝達,交換,共有等を遮断するには一定の限界があり, 基本事件に関する情報遮断措置として十分なものであったものと認めることはできない。\nそうすると,A弁護士が講じた上記情報遮断措置は,抗告人らにお けるA弁護士らが基本事件の相手方の訴訟代理人として職務を行うこ とについての職務の公正らしさに対する疑念を払拭させるものである ということはできない。
b 次に,相手方は,C弁護士が本件事務所において勤務した期間は1 か月余りの短期間にとどまり,その間に基本事件の情報の共有や漏え いをしたことはなく,C弁護士の退職(退所)により基本事件に関す る情報の共有や漏えいのおそれも存在しない旨,仮にC弁護士及びA 弁護士らが基本事件に関する秘密保持義務違反行為やそれを唆すよう な行為に及べば,弁護士として懲戒処分を受けるのみならず,巨額の 損害賠償責任や刑事責任を負う可能性すらあるから,そのような行為に及ぶことはあり得ない旨主張(相手方の2)及び3)の主張)する。 そこで検討するに,C弁護士が本件事務所に在籍した期間は令和2 年1月1日から同年2月10日までの1か月余りであるが,前記aの とおり,A弁護士が講じた本件事務所内の情報遮断措置は,C弁護士 とA弁護士らを含む本件事務所の他の弁護士及び弁理士らとの間にお ける口頭による基本事件に関する情報の伝達,交換,共有等を遮断す るには一定の限界があり,基本事件に関する情報遮断措置として十分なものであったものといえないことに照らすと,C弁護士が本件事務\n所に在籍した期間が1か月余りの短期間であったことを考慮してもな お,客観的及び実質的にみて,C弁護士の在籍中に,C弁護士とA弁 護士らとの間で基本事件に関する情報の伝達,交換,共有等が行われ たのではないかという抗告人らの疑念は解消されるものではない。 また,C弁護士の本件事務所の退所は,A弁護士とC弁護士の合意 によるものであり,しかも,相手方から,C弁護士作成の令和2年2 月12日付け陳述書(疎乙12)が本件の疎明資料として提出されて いることに照らすと,A弁護士らとC弁護士は,C弁護士が本件事務 所を退所した後も,互いに連絡を取り合うことのできる関係にあると いえるから,C弁護士の上記退所の事実から直ちに,C弁護士とA弁 護士らとの間で基本事件に関する情報の伝達,交換,共有等が行われ るおそれがあるのではないかという抗告人らの疑念を払拭させるもの ではない。 さらに,口頭による基本事件に関する情報の伝達,交換,共有等が 内部的に行われた場合,その事実を外部から把握することは事実上困 難であることに照らすと,弁護士が受任事件に関し秘密保持義務違反 行為やそれを唆すような行為に及べば,懲戒処分を受けるのみならず, 損害賠償責任や刑事責任を負うおそれがあることは,抗告人らにおけ るA弁護士らが基本事件の相手方の訴訟代理人として職務を行うこと についての職務の公正らしさに対する疑念を払拭させるものであると いうこともできない。
c 相手方は,相手方が基本事件の訴訟代理人を変更したのは,いった んは相手方の特許出願に主に携わっているD弁護士の所属する特許法 律事務所に相談して委任したが,その後,製薬特許専門訴訟に特化し, その分野での経験が豊かな訴訟専門弁護士に依頼すべきと考えるに至 り,2年前に依頼したことがある本件事務所に訴訟遂行を委任するこ とにしたからであり,その経緯に特段不自然な点はない旨主張(相手 方の主張4))する。
しかしながら,本件においては,相手方が,2年前に依頼したこと のある本件事務所に対して当初から基本事件の訴訟遂行を委任せずに, 本件事務所とは異なる法律事務所に所属するD弁護士らに委任するに 至った具体的な経緯,その後,製薬特許専門訴訟に特化し,その分野 での経験が豊かな訴訟専門弁護士である本件事務所のA弁護士らに依 頼すべきであると考えるに至った時期及びその具体的理由等について の疎明がないことに照らすと,相手方の4)の主張は,C弁護士が本件 事務所に入所した時期と近接する時期に,基本事件の被告である相手 方の訴訟代理人が,本件事務所とは異なる法律事務所に所属するD弁 護士らから本件事務所に所属するA弁護士らに切り替わったことから 生じる,抗告人らにおけるA弁護士らが基本事件の相手方の訴訟代理 人として職務を行うことについての職務の公正らしさに対する疑念を 払拭させるものであるということはできない。
ウ 相手方の5)の主張について
相手方は,基本事件は,医薬品に関する特許関係訴訟であって高度に専 門特化された分野の訴訟であり,かつ,渉外案件である基本事件を取り扱 うことができる弁護士は限られており,抗告人ら及びその関係会社のいず れも顧客としない法律事務所を探すことは極めて困難であるという実情が あり,本件基本規程57条によってA弁護士らについて訴訟行為の排除が 認められるとすると,相手方において憲法32条が保障する裁判を受ける 権利が十分に満足されない事態に発展する旨主張(相手方の5)の主張)す る。
しかしながら,基本事件が医薬品に関する特許関係訴訟であって高度に 専門特化された分野の訴訟であり,かつ,渉外案件であるとしても,我が 国において,本件事務所に所属する弁護士以外に,基本事件の相手方の訴 訟代理人として訴訟追行を行うことのできる弁護士が存在しないというこ とはおよそ考えられないから,相手方の上記主張は,採用することができ ない。
エ まとめ
以上によれば,相手方主張の1)ないし5)に係る事情は,本件事務所に所 属するA弁護士らが,本件事務所の所属弁護士であったC弁護士が本件基 本規程27条1号により職務を行い得ない事件である基本事件について, 相手方の訴訟代理人として職務を行ったとしても,客観的及び実質的にみ て,先にC弁護士を信頼して協議し,賛助を受けた抗告人塩野義にとって, A弁護士らの職務の公正らしさが保持されているものと認められる事由に 当たるものということはできないから,A弁護士らに本件基本規程57条 ただし書の「職務の公正を保ち得る事由」があるものと認めることはでき ない。
2020.08.17
平成30(ワ)31428 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月30日 東京地方裁判所
(3)ア 第1要件にいう特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請 求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する\n特徴的部分であり,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明 の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲 の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部\n分が何であるかを確定することによって認定される(知的財産高等裁判所平 成27年(ネ)第10014号同28年3月25日判決)。
ここで,本件明細書をみると,従来の技術においては,券情報と発券情報 の2つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送していたため情報量が2倍に なり通信回線の負担が2倍になっていた。本件発明は,このような従来の技 術と異なり,「ホストコンピュータ」において,券情報と発券情報という2つ の情報に基づいて1つの座席表示情報を作成するものであり,それによって,\n端末機へ伝送される情報量が半減されて通信回線の負担が軽減されるとい う効果を奏するものである(【0002】〜【0007】,【0020】)。
このような本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らせば,本件発明に おいて,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であ\nる本質的部分は,「ホストコンピュータ」が券情報と発券情報との2つの情 報に基づいて1つの「座席表示情報」を作成する作成手段を有し,そのよう\nにして作成された「座席表示情報」が「ホストコンピュータ」から端末機に\n伝送される点にあるといえる。 被告システムにおいては,券情報と発券情報との2つの情報に基づいて1 つの情報が作成されるサーバーはなく,したがって,それらの2つの情報に 基づいて作成された1つの情報を端末機に伝送するサーバーもない。そうす ると,本件発明の本質的部分において,本件発明の構成と被告システムの構\ 成は異なる。したがって,被告システムが均等侵害の第1要件を充足するこ とはない。
また,被告システムは,端末機に対して券情報と発券情報という2つの情 報に基づいて作成された1つの情報が伝送されるものではないから,券情報 と発券情報がそれぞれ端末機に伝送されるシステムに比べて通信回線の負 担と端末機の記憶容量及び処理速度を半減するものではない。したがって, 本件発明と同一の作用効果を奏するものではなく,第2要件を満たさない。
イ 原告は,第1要件について,本件発明の特許請求の範囲に記載された構成\nと被告システムの構成の異なる部分は,サーバーと通信回線の個数に関する\n相違であって,本件発明の本質的部分に関係するものとはいえない旨主張す る。
しかし,上記アのとおり,券情報と発券情報とに基づく情報が作成され, そのようにして作成された情報が伝送されるサーバーがあることは,均等侵 害の第1要件にいう本件発明の本質的部分であるといえ,被告システムは, その本質的部分において,本件発明と異なる。
また,原告は,本件発明の作用効果は,車掌が携帯する端末機に表示され\nる各指定座席の利用状況(自動改札通過情報及び発売実績情報の有無)を車 掌が目視で確認できるようにして,車内改札を本来空席であるはずの座席に 座っている乗客に対して従来のように切符の提示を求めるだけで足りるよ うにしたものであり,これにより車内改札の省略化を図るというものであり, 被告システムの作用効果と同じである旨主張する。
しかし,前記3(1)のとおり,本件明細書の記載に照らせば,従来技術と比較した本件発明の効果は,券情報と発券情報がそれぞれ端末機に伝送されるシステムに比べて通信回 線の負担と端末機の記憶容量及び処理速度を半減するところにある。したが って,被告システムが本件発明と同じ作用効果を有するとはいえない。 (4)上記(3)のとおり,被告システムは,少なくとも均等侵害の第1要件,第2要 件を充足せず,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明\nの技術的範囲に属するものであるということはできない。
◆判決本文
本件特許の訂正審判についての審決取消訴訟事件です。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.08.14
平成30(ネ)10085 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
争点2−1(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)
控訴人は,本件明細書の発明の詳細な説明には,構成要件Hに対応する「シ\nフト機能」に係る構\成について,「いったんスルー注文」及び「決済トレー ル注文」と組み合わせた,複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ1回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず,構成要件Hに含まれる「シフト機\n能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたも\nの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば,構\成要件 Hは,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから,特許 法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)に適合する とはいえない旨主張する。
ア そこで検討するに,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載中に は,構成要件Hの「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記\n複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ とを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において,「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから,当該「売り注文情報」は,複数の場合に限らず,一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,1)「シフト機能」につ\nいて,「金融商品取引管理装置1や金融商品取引管理システム1Aにお いて,既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち,「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能\である。この「シ フト機能」による注文は,上述した,「いったんスルー注文」や「決済\nトレール注文」や,各種のイフダン注文(例えば後述する「リピートイ フダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)等に基づいて,新 規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文 や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと(【0078】),2)「シフト機能」は,「相\n場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場 価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」(【0018】)という効果を奏すること,3)「発明の 実施の形態3」は,「この実施の形態3の金融商品取引管理システムに おいては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,「ら くトラ」による注文と組み合わせ,さらに「シフト機能」を行わせる状\n態を示す。」(【0138】)ものであるが,「上記の「シフト機能」\nは,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態2の構成において適\n用することもできる。」こと(【0151】)及び「上記各実施の形態 は本発明の例示であり,本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは,いうまでもない。」こと(【016 4】)の記載がある。
上記1)の記載から,「シフト機能」は,「新規注文と決済注文が少な\nくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文や決済注文が発注される 際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり,シ フトされる先に発注済の注文には,「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構\成が含まれること,先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価\n格帯」をシフトさせる構成のものが含まれることを理解できる。\nまた,上記1)ないし3)の記載から,「シフト機能」は,「相場価格を\n反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し,「いった んスルー注文」,「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文(例え ば・・・「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)」 等の注文方法とは別個の処理であること,「シフト機能」にこれらの各\n種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。 ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には,図35に示す「実施の形態 3」(【0144】ないし【0148】)として,シフト機能に決済\nトレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ, 決済注文S5,S4が約定した後に,元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文B5,B4及び元の売り注文S5,S4と同じ注文価格の売 り注文S5,S4が再度生成されるが,この時点ではシフトは発生せ ず,通常のリピートイフダン注文が繰り返され,その後相場価格が変 動して,S1ないしS3の売り注文価格がトレールし,S1ないしS 3が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると,再度生成 された売り注文S5,S4は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして,S1ないしS5のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は,構成要件Hに含まれる,「シフト機能\」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一\nつであることが認められる。
また,シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には,\n図35において,S2及びS3の売り注文価格がトレールしないため, それぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり,それぞ れ別々に約定し,その場合,実施の形態3の取引例でS5,S4が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に,S3,S2が約定 した段階ではシフトが生じず,その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのS1が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると,複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Hに係る構\成は,本 件明細書の上記記載から認識できるから,本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.08.14
平成29(ワ)20502等 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認事件 著作権 民事訴訟 令和2年2月28日 東京地方裁判所(40部)
不存在確認訴訟ですので、原告は場合分けをして判断を求めました。東京地裁はすべて、否定しました。主な論点は、「公衆」「聞かせることを目的」「2小節以内の演奏について演奏権が及ぶか」「演奏権の消尽」、「録音物の再生に係る実質的違法性阻却事由」「権利濫用」です。
上記(ア)ないし(オ)のとおり,原告らの音楽教室で演奏される課題曲の 選定方法,同教室における生徒及び教師の演奏態様,音楽著作物の利用 への原告らの関与の内容・程度,著作物の利用に必要な施設・設備の提 供の主体,音楽著作物の利用による利益の帰属等の諸要素を考慮すると, 原告らの経営する音楽教室における音楽著作物の利用主体は原告らで あると認めるのが相当である(なお,原告ら(別紙C)の経営する個人 教室は,生徒の居宅においてレッスンを行っているので,著作物の利用 に必要な施設・設備についての管理・支配は認められないが,原告ら(別 紙C)は原告ら自身が教師として課題曲の選定,レッスンにおける演奏 等をしているので,同原告らが利用する音楽著作物の利用主体は同原告 らであると認められる。)。
・・・
このように,原告らの音楽教室におけるレッスンは,教師が演奏を行って 生徒に聞かせることと,生徒が演奏を行って教師に聞いてもらうことを繰り 返す中で,演奏技術の教授が行われるが,このような演奏態様に照らすと, そのレッスンにおいて,原告ら音楽教室事業者と同視し得る立場にある教師 が,公衆である生徒に対して,自らの演奏を注意深く聞かせるため,すなわ ち「聞かせることを目的」として演奏していることは明らかである。
2020.08.14
令和1(ワ)22576 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年2月12日 東京地方裁判所
被告は,法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」とは,侵害情報の 発信者についての情報に限られるとの解釈を前提とした上で,本件発信者情 報は,本件アカウントにログインした者についての情報にすぎず,本件各投 稿を行った本件発信者についての情報ではないので,本件発信者情報は「権 利の侵害に係る発信者情報」に当たらないと主張する。
ア 前記第2の2(2)及び(3)記載のとおり,本件各投稿は,平成31年2月 10日及び15日の2日間に合計7回にわたり投稿されたものであり,原 告が同月1日正午(日本標準時)から仮処分決定が相手方に送達された日 の正午時点までの期間に係るものについて,仮の開示を求める仮処分決定 を得てツイッター社に発信者情報の開示を求めたところ,同社は,その保 有している発信者情報として,同年4月11日から令和元年6月4日まで の間に本件アカウントにログインされた際のIPアドレス及びタイムス タンプ(本件IPアドレス等)を開示している。このことから明らかなよ うに,本件IPアドレス等は,本件各投稿の際に使用されたIPアドレス そのものではない。
イ しかし,法4条1項は,「権利侵害時の発信者情報」あるいは「権利が 侵害された際の発信者情報」など,権利を侵害する行為(本件では本件各 投稿)の際に使用された発信者情報に限定する旨の規定をすることなく, 「権利の侵害に係る発信者情報」と規定しており,「係る」という語は「関 係する」又は「かかわる」との意味を有することに照らすと,法4条1項 の「権利の侵害に係る発信者情報」とは,侵害情報が発信された際に割り 当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報に限定されること なく,権利侵害との結びつきがあり,権利侵害者の特定に資する通信から 把握される発信者情報を含むと解するのが相当である。
ウ また,法4条の趣旨は,特定電気通信による情報の流通によって権利の 侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘 密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通信の用に供される特定電\n気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を 請求することができるものとすることにより,加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解されるところ(最高裁平成21年(受)第1049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676頁),侵害情報そのものの送信時点ではなく,その前後に割り当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報であっても,それが当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には,当該発信者のプライバシ\nー,通信の秘密等の保護の必要性の程度に比べ,被害者の権利の救済を図 る必要性がより高いというべきである。
エ さらに,本件において,ツイッター社は,個々の投稿に係るIPアドレ ス等のログを保存しておらず,ログインに係る情報についても直近2か月 分程度のログしか保存していないことがうかがわれるが,侵害情報そのも のの送信を媒介した特定電気通信を媒介した者でなければ開示関係役務提 供者に該当しないとすると,権利を侵害されたことは明白であるにもかか わらず,サイト運営者のログイン情報の保存方法・期間等により発信者情 報開示請求の成否が左右され,侵害情報が発信された時点のIPアドレス 等又は侵害情報を投稿するためのログイン時のIPアドレス等が保存され ていない場合には,被害者は権利行使を断念せざるを得なくなる。法4条 が,このような事態,すなわちサイト運営者のログイン情報の保存状況に より被害者の権利救済の可否が左右されることを想定し,これを容認して いたとは考え難い。
オ 以上によれば,侵害情報の送信の後に割り当てられたIPアドレスから 把握される発信者情報であっても,それが侵害情報の発信者のものと認め られるのであれば,法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に 当たると解するのが相当である。
(2) 上記(1)の解釈を前提として,本件IPアドレス等によって本件アカウン トにログインした者と,本件各投稿を行った本件発信者が同一と認められる かどうかについて検討する。
ア 証拠(甲19)によれば,ツイッターを利用するためには,氏名,電話 番号又はメールアドレスを登録するとともに,パスワードを設定してアカ ウント登録をすることが必要であり,その上で,作成したアカウントを実 際に利用し,ツイート等の投稿を行うためには,電話番号,メールアドレ ス又はユーザー名に加え,パスワードを入力してアカウントにログインを することが必要であると認められる(前記第2の2(4))。 このように,ツイッターは,利用者がアカウント及びパスワードを入力 することによりログインをしなければ利用できないサービスであること に照らすと,当該アカウントにログインをするのは,そのアカウント使用 者である蓋然性が高いというべきである。
イ また,本件アカウントは,ユーザー名が「B」であり,その投稿内容等 に照らすと,本件各投稿は,特定の個人が継続的に投稿したものであると 認められ(甲1〜6),ツイッター社により開示された本件IPアドレス 等の使用期間(平成31年4月11日から令和元年6月4日まで)におい ても,昼夜を問わず,毎日本件アカウントにログインされており,本件ア カウントが継続的に使用されていたことがうかがわれる(甲8)。そして,本件訴訟提起後である令和元年9月5日及び6日にされた本件 アカウントのツイート(甲20)には,「どれだけ嫌なことがあっても ど れだけ辛いことがあっても …頑張ってこのアカウントを育ててきたの ですが この度 悪質な嫌がらせに合いまして 暫くの間 別アカウン ト…で過ごすことになりました」,「赤子を抱えて身動きが取りづらい状 況を狙って私を潰しに来たのであれば 義理も人情もない方なのでしょ う」,などの投稿がされていることが認められる。これらのツイート内容 等によると,令和元年9月の上記各投稿の投稿者は,特定の個人であり, 原告の行為を非難する旨の本件各投稿をした者と同一であることが推認 される。
ウ 上記アのとおり,ツイッターのアカウントにログインをするのは,その サービスの仕組みに照らし,当該アカウントの使用者である蓋然性が高い ところ,上記イのとおり,本件アカウントは,本件各投稿がされた平成3 1年2月頃から令和元年9月頃の間,特定かつ同一の個人が継続して利用 していたものと認めるのが相当であり,法人が営業用に用いるなど複数名 でアカウントを共有し,又はアカウント使用者がその間に変更されたこと をうかがわせるような事情は存在しない。 そうすると,本件IPアドレスによって本件アカウントにログインした 者と,本件各投稿を行った本件発信者は同一ということができるので,本 件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるというべきであ る。
エ これに対し,被告は,ツイッターの仕組み上,ユーザーがアカウントを 他人と共有することが禁止されていないことや,本件アカウントには,本 件IPアドレス以外のIPアドレスを用いた被告以外の経由プロバイダ を利用したログインが複数回行われていることから,本件アカウントは複 数人で共有されている可能性が高く,本件IPアドレスで本件アカウント にログインした者と本件各投稿をした者が同一であるとはいえないと主\n張する。
しかしながら,ツイッターの仕組み上,アカウントの共有が禁止されて いないとしても,通常は,特定の個人が自分用のアカウントとして継続的 に一つのアカウントを使用することが多く,本件アカウントについても, その投稿内容等に照らし,個人用のアカウントと認められることは,前記 判示のとおりである。
また,被告以外の異なる経由プロバイダを介して本件アカウントにログ インされているとの点についても,個人であっても,例えば携帯電話とパ ソコンのそれぞれについて異なる経由プロバイダと契約することもあり 得るのであるから,そのことから直ちに複数人が本件アカウントを共有し\nている可能性が高いということはできない。 \n
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2020.08.14
令和1(ワ)32646 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 令和2年3月25日 東京地方裁判所
指定商品の類似性の有無については,それらの商品が通常同一営業主に より製造又は販売されている等の事情により,それらの商品に同一又は類 似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認さ れるおそれがあると認められるか否かにより判断すべきと解される。
本件商標権の指定商品は,「モーターを組み込んだ小型模型,モーター を組み込んだ小型模型の部品及び付属品,ラジオコントロール式模型おも ちゃ,ラジオコントロール式模型の部品及び付属品,乗物模型おもちゃ」 であり,モーターそのものではないが,モーターと,これを動力として組 み込み動く小型模型は密接な関係があり,被告自身,モーターを組み込ん だ車の小型模型のキットである「Arduino用UCTRONICS IRスマートロボットカーキット」(甲20)をはじめとする商品を複数 販売していることが認められる(甲12〜19,21〜25)。そうする と,モーター及びこれを動力として組み込んで動く小型模型は,通常同一 営業主により製造又は販売されていると推認できる。 本件商品1,2,5〜7,9〜15は,いずれもマイクロサーボモータ ーであり,これと指定商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営 業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる から,本件商標権の指定商品と類似する。
・・・
原告は,原告のライセンス料に係る規定(甲30,31)に基づき,販売 等の数量の算定が困難な場合,あるいは,SG9系列の商品1個の販売につ き,250円又は侵害品の売価(税込単価)から250円を控除した金額の うち,いずれか多い金額で計算した場合の合計が11万2000円に満たな い場合の11万2000円の使用許諾料相当額を請求するものと解される。 しかし,原告が同規定に基づき実際にライセンスを行った実績があること を認めるに足りる証拠はないから,同規定に基づき使用料相当額を算定する ことは相当ではない。本件に係る諸般の事情を総合考慮すると,本件商標の使用料率は10%と するのが相当であるから,上記の10万2087円に10%を乗じた1万0 208円(小数点以下切り捨て)が,本件商標権の権利者が本件商標の使用 に対し受けるべき金銭の額に相当する価額と認められる。
(5) 上記第2の2請求原因(2)のとおり,本件商標権は,原告及び外国法人2社 によって共有されていることが認められ,具体的な共有持分を認めるに足り る証拠はないから,それぞれの持分は3分の1と推定される(民法250条)。 原告は,日本国内における原告商標の管理,使用許諾等のライセンスは専 ら原告が行っていると主張するが,それを認めるに足りる証拠はない。 上記(4)の損害賠償請求権は,可分債権であるから,原告に帰属する損害賠 償請求権は,1万0208円を三分した3402円(小数点以下切り捨て) と認められる。なお,本件商品1に係る損害額は2907円であり,その余 の商品に係る損害額は495円となる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.08.14
平成30(ワ)4851 特許権侵害差止等請求事件 特許権 令和2年5月28日 大阪地方裁判所
本件拒絶理由通知記載の拒絶理由は明確性要件違反であり,具体的には,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1の記載につき,「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか,その外縁が明確に特定できない」こと,「「第2油路」が具体的に想定できない」こと及び「「流量調整弁」が具体的に想定できない」ことが挙げられている。換言すれば,スイングクランプ,リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載となっていることによって新規性又は進歩性が欠如するとの無効理由は指摘されていないことから,本件第2補正は,こうした無効理由を回避するためにされたものではない。また,明確性要件違反の指摘においても,スイングクランプ,リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載であるが故に不明確とされているわけでもない。 もっとも,上記拒絶理由のうち「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか,その外縁が明確に特定できない」とは,より具体的には,油圧シリンダの具体的な規定がなく,その油室の数が不明であり,そのために,第1油路,第2油路及び流量調整弁の機能ないし役割が不明であるといった問題点を指摘するものである。これは,当業者にとって,クランプ装置のタイプを含む装置の前提的な構\成の不明確さを指摘する趣旨のものと理解されると思われる。
(オ) 原告は,本件第2補正の際に提出した意見書(乙2の2)で,請求項1 に係る補正につき,本件拒絶理由通知での審査官の指摘に対して,「補正後の請求項 1では,「前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダ」と規定し ております。…補正後の請求項1に係る本願発明において,「第1油路」及び「第2 油路」や,両流路の接続部にある「流量調整弁」が,何のために在って何をしてい るのかという点については明確であると思料いたします。よって,ご指摘の記載不 備は解消し得たものと思料致します。」との補足説明をしている。
(カ) 以上の事情を踏まえて本件第1補正から本件第2補正に至る経緯を見る と,客観的,外形的には,原告は,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1の記 載によれば,その構成はスイングクランプとリンククランプいずれのタイプのクラ\nンプ装置も含むものであることを認識しながら,本件拒絶理由通知を受けて行った 本件第2補正により,敢えて補正後の特許請求の範囲にリンククランプのタイプの クランプ装置を含むものとして記載しなかった旨を表示したものと理解される。\nそうである以上,本件においては,本件第2補正においてリンククランプのタイ プのクランプ装置が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特 段の事情が存する。 したがって,被告製品群4〜6は,本件発明との関係で,均等の第5要件を充足 しない。この点に関する原告の主位的主張は採用できない。
ウ 原告の予備的主張について\n
原告は,予備的主張として,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1記載\nの「クランプ用の油圧シリンダ」は「アンクランプ用の油圧シリンダ」(本件第2補 正後の特許請求の範囲請求項3)を含まないとの理解を前提として,本件第2補正 後の特許請求の範囲請求項3は補正前の特許請求の範囲に含まれないものを手続補 正により追加したものであり,請求項3については意識的に除外されたものとはい えないなどと主張する。 しかし,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1記載のクランプ装置は,「クラ ンプ本体に進退可能に装着された出力ロッド」及び「出力ロッドを駆動するクラン\nプ用の油圧シリンダ」等を備えることは記載されているものの,「出力ロッド」が退 入側・進出側いずれに駆動することによってワークをクランプするものであるかを うかがわせる記載はない(なお,この時点での請求項2〜4にも,クランプのタイ プに関係する記載はない。)。このことと,従来技術としてはスイングクランプ及び リンククランプの両タイプが挙げられていることに鑑みれば,本件特許に係る明細 書においては出願当初よりリンククランプのタイプのクランプ装置も除外されてい ないといえることを併せ考えると,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1は, スイングクランプのみならずリンククランプのタイプのクランプ装置をも含むもの と理解される。本件第2補正後の特許請求の範囲請求項1において「クランプ用の 油圧シリンダ」とし,請求項3において「アンクランプ用の油圧シリンダ」とされ たのは,本件拒絶理由通知を受けた対応として,クランプ装置の構成をより具体的\nに特定したことに伴うものと理解することができるから,本件第2補正の前後で 「クランプ用の油圧シリンダ」を異なる意味に解することはなお合理的である。 したがって,原告の予備的主張はその前提を欠くから,これを採用することはで\nきない。
エ 小括
以上より,均等侵害として,被告製品群4及び6は本件発明1の技術的範囲 に属するとはいえず,また,被告製品群5は本件発明3の技術的範囲に属するとは いえない。そうである以上,被告らによる被告製品群4〜6の製造,販売等は,本 件特許権を侵害するものとはいえない。 したがって,被告製品群4〜6に係る原告の被告らに対する製造等の差止請求, 廃棄請求及び損害賠償請求は,いずれも理由がない。
3 争点3(被告製品群7及び8の製造,販売等に係る間接侵害の成否)につい て
(1) 前記(第2の2(4)オ)のとおり,被告製品群7及び8は,被告製品群1〜 3のクランプに取り付けて使用される場合にクランプ装置の生産に用いるものであ る。また,特許法101条2号の趣旨によれば,「発明による課題の解決に不可欠なも の」とは,それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決 されるような部品等,換言すれば,従来技術の問題点を解決するための方法として, 当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について,当該手段を特徴付けている特 有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が,これに該当するものと解される。\n本件発明において,作動油の流量の微調整を容易かつ確実に可能とすることなど\nの課題を解決する直接的な手段となるものは,相対移動可能な弁体部を有する弁部\n材をその構成に含む「流量調整弁」である。このため,「流量調整弁」は,本件発明\nが新たに開示する特徴的技術手段における特徴的な部品等ということができる。被 告製品群7及び8(スピードコントロールバルブ)は,この「流量調整弁」に相当 するものであるから,「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101 条2号)に該当する。
これに対し,被告らは,被告製品群1及び3が本件発明1の構成要件1K及び1Xを 充足せず,被告製品群2が本件発明3の構成要件3K及び3Xを充足しないことから, 被告製品群7及び8は本件発明の課題の解決に不可欠なものではないと主張する。 しかし,前記1のとおり,被告製品群1〜3は本件発明の上記各構成要件を充足す\nる。そうである以上,この点に関する被告らの主張はその前提を欠き,採用できな い。
(2) 被告らが,本件発明が特許発明であることを知っていたことについては,当 事者間に争いがない。 また,被告らは,被告製品群7を被告製品群1及び3の,被告製品群8を被告製 品群2のアクセサリとしてそれぞれ製造,販売していること(甲6,10,11, 乙9,10)に鑑みると,被告製品群7及び8が本件発明の実施品である被告製品 群1〜3に用いられることを知っていたことが認められる。 なお,被告製品群7及び8は,スイングクランプのほか,リンククランプ,リフ トシリンダ,ワークサポートにも使用可能なものである(甲6,10,乙4,5,\n9,10)。
しかし,特許法101条2号の趣旨に鑑みれば,発明に係る特許権の侵害品「の 生産に用いる物…がその発明の実施に用いられること」とは,当該部品等の性質, その客観的利用状況,提供方法等に照らし,当該部品等を購入等する者のうち例外 的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現 に存在し,部品等の生産,譲渡等をする者において,そのことを認識,認容してい ることを要し,またそれで足りると解される。 本件においては,後記6のとおり,被告製品群7及び8に属する製品がスイング クランプと組み合わせて販売される割合が大きいことに鑑みると,これを購入等す る者のうち例外的とはいえない範囲の者が被告製品群7及び8を特許権侵害に利用 する蓋然性が高い状況が現に存在するとともに,被告らはそのことを認識,認容し ていたものといえる。そうである以上,上記事情は本件における間接侵害の成立を 妨げるものではない。 これに対し,被告らは,被告製品群7が本件発明1の実施に,被告製品群8が本 件発明3の実施にそれぞれ用いられることを認識していないなどと主張する。しか し,被告らは,当然に被告製品群1〜3の構成を認識していると考えられるところ,\n被告製品群1〜3が本件特許権侵害を構成する以上,被告製品群7及び8について\nも,本件発明の実施に用いられるものであることを知っていたといえる。この点に 関する被告らの主張は採用できない。
(3) 小括
以上より,被告らが被告製品群7及び8を製造,販売する行為は,本件特許権 の間接侵害(特許法101条2号)を構成する。\n
◆判決本文
関連の審決取消事件です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> ピックアップ対象
2020.08.14
平成30(ワ)22428 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和2年7月10日 東京地方裁判所
争点1(本件申告が虚偽事実の告知に当たるか)について\n
(1) 本件申告の趣旨\n
本件申告の内容は,第2の2(5)ウ記載のとおりであるが,1)本件サービス の利用に当たり,被告は,被告各商標権を登録していること,2)被告は本件 申告に当たって被告各商標を入力した上で申\告内容について記載しているこ と,3)アマゾン社からバルジャノ社へのメール(甲8,9,12)にも「商 標権を侵害しているとの主張が権利者から届きました」と記載され,更に同 各メールには「侵害の種類」として「商標権」と記載されるとともに,被告 各商標権等の登録番号が記載されていることなどの事実によれば,本件申告\nは原告商品が被告各商標権を侵害していることを趣旨とするものであると認 めるのが相当である。 これに対し,被告は,本件申告の申\告内容は「偽造品であること」である ので,本件申告は被告各商標権の侵害を趣旨とするものではないと主張する\nが,偽造品であるということには,他人の信用が化体した標章を商標権等の 正当な法的権原なく商品に付すことが含まれるのであり,上記のとおり,被 告が本件サービスの利用に当たり被告各商標を登録し,本件申告に際しても\n同各商標を入力していることを併せ考えると,被告が本件申告の申\告内容と して「偽造品であること」と入力したとしても,そのことは,本件申告の趣\n旨が被告各商標権の侵害を趣旨にあるとの上記判断を左右しないというべき である。
(2) 原告が被告各商標権を侵害している旨の摘示について
原告各商標は,別紙原告商標目録記載のとおり,標準文字の「COMAX」 から構成されるものなどであり,いずれも「第20類 マットレス,まくら, クッション,座布団,家具」を商品区分とするものであるところ,原告商品 は,いずれも第20類に属する枕,マットレス等であって,原告各商標を付 したものである。これに対し,被告各商標は,いずれも,商品区分を「第1 7類 天然ゴム ゴム」とするものであるから,原告商品は被告各商標権を 侵害するものではない。 なお,本件申告内容の「偽造品であること」という入力内容が,被告各商\n標権の侵害を意味するものではなく,他の商標権等の侵害を意味するもので あるとしても,原告は,原告商品に自らの商標を表示して販売しているので\nあり,シンガポール・コマックス等の他人の使用する標章等を使用し,その 真正品と偽って表示しているものではないので,被告の入力した上記申\告内 容はいずれにしても虚偽であるということができる。 そうすると,本件申告の内容は,被告と競争関係にある原告の営業上の信\n用を害する虚偽の事実であるということができる。
(3) 原告が被告の独占販売権を侵害している旨の摘示について
ア 被告は,1)シンガポール・コマックスとの間で特約販売店契約(乙1) を締結し,本件申告当時,同社から「COMAX Natural La tex」の商標を付した枕等の独占的販売権を得ていた,2)原告は,シン ガポール・コマックスの子会社であるラテックスシステムズから「COM AX」商標等に関する使用許諾を受けたが(乙2),同使用許諾契約は平 成27年11月10日をもって解除されたので(乙3),本件申告当時,\n原告商品を販売すべき正当な権原を有していなかったと主張する。 しかし,原告は,原告各商標権を取得した上で,同各商標を付した原告 商品を我が国において販売しているのであるから,原告商品を販売するに 当たり,シンガポール・コマックス等から「COMAX」商標の使用許諾 を得る必要はなく,そもそもシンガポール・コマックスがいかなる権利を 有しているかも証拠上明らかではない。 また,原告は,乙2書面及び乙3通知書の作成に関与したことを否定す るところ,乙2書面及び乙3通知書は,いずれもラテックスシステムズが 作成した書面であり,原告がその内容に同意していたことを示す証拠は存 在しない。そうすると,「COMAX」商標の使用許諾契約が原告とラテ ックスシステムズ間で締結され,これが解除されたとの事実を認めること もできない。 このように,原告は,原告各商標を使用して,原告商品を販売すべき権 原を有しているので,被告がシンガポール・コマックスの「COMAX N atural Latexの枕及びマットレス」の独占的販売権を有して いるとしても,原告商品の販売は被告の独占販売権を侵害するものではな い。 なお,被告は,原告が「COMAX」商標の正当な使用権原がないこと を前提として,原告が原告各商標権を被告に行使することは権利の濫用に 当たると主張するが,同主張は,その前提を欠くものであって失当である。
イ そうすると,本件申告が,被告がシンガポール・コマックスから許諾さ\nれた独占販売権を侵害するという趣旨である場合においても,その申告内\n容は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であ るということができる。
(4) 原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間の混同に関する主張に ついて
被告は,原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間に混同が生じ ていたことから,その是正を求めるために本件申告に及んだと主張するが,\n原告による原告商品の販売が正当な商標権に基づくものであることは前記判 示のとおりであり,仮に,需要者の間において,海外で販売されているシン ガポール・コマックスの商品と原告商品との混同が生じているとしても,そ のことについて,原告が法的責任を負うべき理由はなく,被告が虚偽の告知 をすることを正当化するものでもない。
(5) 小括
以上のとおり,本件申告は,原告商品が本件各商標権を侵害していること を趣旨とするものであり,その内容は,被告と競争関係にある原告の営業上 の信用を害する虚偽の事実であり,不競法2条1項21号の不正競争行為に 該当するので,原告は,被告に対し,原告商品の販売が被告の有する商標権 を侵害するとの虚偽の事実を第三者に告知又は流布することの差止めを求め ることができる。 なお,被告が本件申告において権利が侵害されているとして通知した商品\nは,原告商品の全てではないが,同通知に係る商品以外の原告商品にも原告 各商標が使用され,本件サイトに出品されていたことに照らすと,被告が, 需要者及び原告の取引関係者その他の第三者に対し,これらの原告商品が被 告各商標権を侵害する旨を告知・流布するおそれはあるというべきであるの で,これらの商品についても虚偽の告知を差し止めるべき必要性があると認 められる。 また,前記判示の本件申告の内容及び態様に照らせば,被告が本件申\告を するにつき,少なくとも過失が認められる。
2 争点2(原告の損害の有無及びその額)について
(1) 不競法5条2項に基づく損害
ア 原告は,本件サイトにおける原告商品の出品が停止された令和元年8月 までの15か月間に,被告は,被告商品の販売により,少なくとも月間8 万5000円程度の利益を得ていたはずであるから,不競法5条2項に基 づき,被告に対し,8万5000円に15月を乗じた127万5000円 の損害賠償を求めることができると主張する。 しかし,被告は,本件申告の前後を通じて,特に販売態様等を変えるこ\nとなく被告商品を販売していたと認められるところ,証拠(乙22〜24) によれば,被告商品の売上全体(別紙1)及び本件サイトに限定した被告 商品の売上げ(別紙2)のいずれについても,本件申告後の売上げは,む\nしろ減少しているものと認められる。 そうすると,被告は,本件申告に係る不正競争行為により,営業上の利\n益を得たということはできず,本件申告とその後の被告商品の販売による\n利益との間に相当因果関係があると認めることはできない。
イ これに対し,原告は,不競法5条2項は,損害額のみならず,侵害行為 と損害との間の因果関係も推定する規定であると主張するが,同項は損害 額の推定に関する規定であり,損害の発生や相当因果関係の存在までも推 定するものではなく,これらの点については原告に立証責任があると解さ れる。本件においては,本件申告と本件申\告後に被告が得た販売利益との 間に相当因果関係が存在すると認めるに足りる証拠はない。 ウ したがって,原告の不競法5条2項に基づく損害賠償の主張には理由が ない。
(2) 無形損害
前記判示のとおり,被告による本件申告は,原告が被告の商標権等を侵害\nしているというものであり,その内容は,原告及び原告商品の信頼を低下さ せるものであり,本件申告の申\告先であるアマゾン社は全世界的なインター ネット通販サイトを運営する企業である。加えて,本件申告は,原告が自ら\nの商標を商品に付していることを容易に知り得たにもかかわらず,これを「偽 造品」と称するものであって,その態様は悪質であることにも照らすと,原 告の営業上の信用を毀損する程度は小さくないというべきである。 しかし,他方で,本件申告は,アマゾン社に対するもののみであり,イン\nターネットなどを通じて,不特定の需要者,取引者に対して告知したもので はないことなどの事情も認められ,こうした事情も含め,本件に現れた諸事 情を総合的に考慮すると,原告に生じた無形損害は,50万円であると認め るのが相当である。
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2020.08.14
令和1(ネ)10059 特許権 民事訴訟 令和2年3月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「ア 均等侵害が成立するための第1要件にいう本質的部分とは,当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成\nする特徴的部分であり,このような特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備 えていると認められる場合には,相違部分は本質的部分ではないと解される。 そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特 許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲 の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何\nであるかを確定することによって認定されるべきである。 ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているとこ ろが,出願時の従来技術に照らして客観的に不十分な場合には,明細書に記載され\nていない従来技術も参酌して,当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。\n
イ 本件特許出願の審査において,特許庁は,本件各発明は,平成15年 8 月 22日に公開された特開2003−234608号公報(甲30。以下「引用文献 1」という。)等の文献に基づき,当業者が容易に発明し得た旨の拒絶理由通知書 を送付した(乙6)ことから,引用文献1に記載された技術について検討する。
・・・
まず,引用発明1と比較して,本件発明1の本質的部分を検討する。
(ア) 本件発明1の内容は,前記1(2)で判示したとおりであり,その技術 的思想を構成する部分は,仮固定用ホルダの構\成を,可撓性樹脂で成形し,前記給 電用筒状部の外壁面に沿って下方に延びる複数のメインアーム部と,同メインアー ム部に対して下端部にて繋がったサブアーム部とを有し,同サブアーム部の下端部 は,同サブアーム部が外側に拡がるための支点となり,同サブアーム部の上端部は 前記メインアーム部の外側面よりも外方向に突出した係止爪をなし,かつ同係止爪 は上端に向かって肉厚が増加しているものとし,同構成を採用することにより,ア\nンテナ挿入時には,メインアーム部及びサブアーム部の両部材が内側に動くため, より小さい挿入力で取付孔への挿入が可能となり,また,抜け方向に荷重が加わっ\nたときは,車体パネルの内側面に係止爪の上端が当接し,サブアーム部が外側に拡 がるため,抜け力を増大させることができ,仮固定用ホルダの挿入力は小さいまま で,抜け力を大きくすることを可能としたことである。\n一方,本件特許の出願前に公開された引用文献1に記載された引用発明1の内容 は,前記イ(イ)で判示したとおり,固定板付き基板ブラケット9の構成を,円筒状\n突出部の外周面に沿って下方に伸びる複数の側板4を有し,側板4にコ字状の切溝 4eを設け,切溝4eに囲まれた矩形状のバネ片4aの上端が側板4から外側に向 かって離れるものとしたものであり,このうち,側板4は本件発明1のメインアー ム部に,バネ片4aは本件発明1のサブアーム部にそれぞれ相当するものであり, アンテナの挿入時には,側板4及びバネ片4aが内側に撓み,抜け方向に荷重が加 わったときは,ルーフパネル20にバネ片4aの上端部が当接し,バネ片4aが外 側に撓んで仮止めすることになると認められる。
(イ) そこで,本件発明1のうち,引用発明1に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分を検討すると,引用発明1は,抜け方向に荷重が加わった\nときに,サブアーム部に相当するバネ片4a全体が撓むため,十分な抜け力を確保\nできなかったことから,本件発明1は,仮固定用ホルダを可撓性樹脂で成形し,サ ブアーム部の上端部は上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとするこ とにより,抜け方向に荷重が加わったときに,サブアーム部の下端部を回転の支点 として,サブアーム部が外側に拡がるようにし,同下端部でサブアーム部の回転を 受け止めることにより,抜け力を増加させたものと認められる。そして,本件発明 1が,サブアーム部の上端部は上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるもの としたのは,上記のとおりサブアーム部の強度を増すためであると認められる。 以上からすると,本件発明1のうち,引用発明1に見られない特有の技術的思想 を構成する特徴的部分とは,可撓性樹脂で成形されたサブアーム部の上端部は上端\nに向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとし,これにより,抜け方向に荷重 が加わったときに,サブアーム部は,下端部を支点として回転するように外側に拡 がり,下端部において,サブアーム部の上記回転を受け止めて,抜けを防止すると いう部分であると認められる。そして,この部分が本件発明1の本質的部分に当た ることになる。
(ウ) 控訴人は,本件発明6の本質的部分は,「アンテナに抜け方向の荷重 が加わった際に,下端部を支点とした外向きの回転力がサブアーム部に発生するこ とにより,サブアーム部が内側に向かって変位することが防止されるため,サブ アーム部に設けられた係止爪が車体パネルから外れて抜けてしまう(すっぽ抜ける) ことがない」という構成にあると主張する。\nしかし,控訴人が主張する上記の構成は,引用発明1にも見られるから,同構\成 が本件発明1や本件発明6の本質的部分ということはできない。
エ 次に,被控訴人製品が,前記ウで認定した本件発明1の本質的部分を共 通に備えているかについて検討する。 被控訴人製品においては,サブアーム部は,可撓性樹脂で成形されており,車体 パネルに係止するための爪部を備えるが,同爪部は,サブアーム部の中間付近に位 置している(乙1,2,13)ため,その上部のサブアーム部であるフック部が, 抜け方向に荷重が加わったときに,サブアーム部がその下端部を支点として外側に 拡がることを阻止し,そのため,サブアーム部は,その下端部を回転の支点として 外側に拡がることはなく,したがって,同下端部で,サブアーム部の回転を受け止 めることによって抜け力を増大させるものではない。 そうすると,被控訴人製品は,本件発明1の本質的部分を備えているとは認めら れない。
オ 控訴人は,被控訴人製品において,抜け方向の荷重が加わると,サブ アーム部の下端部を支点とした外向きの回転力が発生することにより,サブアーム 部に設けられた爪部が内向きに変位して車体パネルから外れるという事象が防止さ れているから,被控訴人製品は,本件発明6の本質的部分を備えていると主張する。 しかし,前記エのとおり,被控訴人製品においては,抜け方向の荷重が加わり, サブアーム部が外側に拡がろうとしても,同動きはフック部によって阻止されるた め,サブアーム部は,その下端部を回転の支点として外側に拡がることはないから, 被控訴人製品は,本件発明1や本件発明6の本質的部分を備えておらず,控訴人の 上記主張は理由がない。
カ したがって,本件発明1と被控訴人製品との前記の相違点は,本件発明 の本質的部分ではないということはできないから,被控訴人製品は,均等の第1要 件を充足しない。」
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2020.08.14
平成30(ネ)10062 職務発明対価請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
超過売上げの割合
(ア) 超過売上げの割合は40%と認めるのが相当である。その理由は,原判決100頁6行目から102頁19行目までの記載のとおりであるからこれを引用する。
(イ) 一審原告は,70ないし100%を主張し,一審被告は10%を主張 する。具体的には,一審原告は,本件各製品のいずれについても,これ らを独自に製造販売し得る技術力を有する著名な大企業が多数存在する から,仮にこれらの競合他社に本件各発明をライセンスした事態を想定 した場合,一審被告が得たであろう仮想の売上高は実際の売上高からい くら少なく見積もっても7割程度は喪失していたことが明らかである旨 主張し,他方,一審被告は,FeliCa事業は,一審被告及びJR東日本の 主導により構築されたインフラストラクチャーの市場影響力及び策定さ\nれた標準規格の通用力等に基づき,特許権の排他的効力を利用すること なく,事業が拡大・維持されてきたのであるから,独占の利益は極めて 小さく1割を超えることはない旨主張する。 そして,これらの主張が前提とする,強力な競合他社の存在や,一審 被告とJR東日本等が構築した強力な市場影響力の存在や標準規格の通\n用力等については,それぞれに裏付けとなる証拠が存在するといえるか ら,本件においては,これらの事情を総合的に考慮した上で,超過売上 げの割合を決定する必要がある。すなわち,双方が主張する事情の一方 のみに基づいて,極端に高い,あるいは極端に低い超過売上げの割合を 決定することはできないのであって,全体としてみれば,原判決が指摘 するとおり,半分をやや下回る40%を超過売上げの割合と認定するの が相当である。
ウ なお,一審被告は,本件各特許の特許権登録前の実施等に関しては,独 占の利益は極めて小さいから,このことを考慮すべきであると主張する。 たしかに,出願公開前の段階においては,特許法上何ら特別な保護は認 められていないのであるから,この段階における特許発明の実施について 独占の利益を肯定することは困難というべきである。しかし,出願公開後 においては,一定の条件の下に補償金支払請求権が認められ,この限度で 特許法上の保護が与えられているのであるから,特許権登録後の2分の1 の限度では独占の利益が認められるというべきである。一審被告は,特許 権登録前の段階では,特許が成立しているかどうかも定かではないと主張 するが,現実に特許が成立している以上,この点を重視するのは相当では ない。
以上を前提に考えると,特許1〜3,5〜7は,対価支払請求権の計算 対象前である平成12年以前に出願公開がされているから(甲1〜3,5 〜7),平成13年以降出願登録までの全期間について2分の1の限度で 独占の利益が認められることになるが,特許4は平成16年12月2日, 特許8は平成20年7月17日,特許9は平成13年7月19日,特許1 0は平成13年10月18日,特許11は平成17年1月27日に出願公 開されているので(甲4,8〜11),出願公開日の翌月である特許4に ついては平成17年1月,特許8については平成20年8月,特許9につ いては平成13年8月,特許10については平成13年11月,特許11 については平成17年2月から各特許権登録までの期間について2分の1 の限度で独占の利益を認めるのが相当である。
エ 仮想実施料率
(ア) 本件実施発明の意義は,原判決102頁21行目から103頁11行 目までに記載のとおりであるからこれを引用する。
(イ) 本件実施発明の実施に係る諸事情を考慮すると,本件実施発明に係る 各発明についてそれぞれ仮想実施料率を定め,その仮想実施料率をいず れも0.3%と認めるのが相当である。この認定に当たって考慮した事 情については,原判決102頁21行目から104頁15行目まで及び 104頁19行目から105頁3行目までの各記載を引用するほか,本 件各証拠(当審で新たに提出された多数の証拠を含む。)に基づき認定 できる事情とそれに基づく判断を次のa以下のとおり補足する。 なお,一審原告は,本件においては仮想実施料率ではなく限界利益率 を用いるべき旨主張するが,限界利益率を用いるべき理由は見当たらず, その主張は採用することができない。
a 当事者双方が提出した資料から認定できる実施料率等のうち,本件 において参考になると思われるものとしては,次のようなものがある。
(a) 経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブ ック」(甲98)によれば「器械」分野のロイヤルティ料率の平均 値は3.5%,最大値は9.5%,最小値は0.5%,標準偏差は 1.9%であり,「電気」分野の平均値は2.9%,最大値は9. 5%,最小値は0.5%,標準偏差は1.5%であり,「コンピュ ータテクノロジー」分野の平均値は3.1%,最大値は7.5%, 最小値は0.5%,標準偏差は2.0%であり,「精密機器」分野 の平均値は3.5%,最大値は9.5%,最小値は0.5%,標準 偏差は1.9%である。
(b) IT業界のライセンスの実務においては,必須特許の累積ロイヤ ルティ料率は最大限5%とされていることが多い(乙381,38 2)。
(c) 標準規格であるMPEG(動画圧縮)やデジタルテレビチューナ ーのパテントプールにおいて,きわめて多数の対象特許(ARIB ではピーク時に600件)についてのライセンス料は,最終製品の エンドユーザーに対する販売価格の●●とされた(乙390)。
(d)FeliCa開発の過程で一審被告がフランステレコムから同社保有特 許のライセンスを持ち掛けられた際の同社の当初の申出額は,1件\n当たり●●●●●●●●であった(乙396)。
b 上記aの(b)〜(d)掲記の各証拠はいずれも一審被告が提出したもので あるところ,一審原告は,(b)及び(c)については,FRAND宣言の有 無等の点で本件とは事情が異なること,算定の基礎となる製品価格が 最終製品の価格であるからICチップの価格を基礎とする本件には適 用できないこと等を主張し,(d)については,フランステレコムの有し ていた特許は本件各特許に比してFeliCa事業の実現のための重要性が 格段に劣ること等を主張する。 しかしながら,類似の実施料率に基づいて仮想実施料率を算定しよ うとする場合,仮想実施料率を算定すべき事例と類似事例との間には, 多かれ少なかれ違いが存することは免れないのであるから,違いの存 在を考慮しつつ,仮想実施料率を算定せざるを得ないところ,一審原 告主張の事情が,このような観点から参考資料とするのにも適さない といえるほど決定的な事情であるとは認められない。一審原告の主張 は,採用することができない。
c 両当事者は,aで掲げたもののほかにも,参考とすべき実施料率例 が存在すると主張するが,以下のとおり,その主張を採用することは できない。
(a) 一審原告は,一審被告の内部資料(乙329)においてICチッ プのライセンス単価は2004年度で●●●,2010年度で●● ●とされており,各年度のICチップの単価はそれぞれ●●●●, ●●●●であるから,料率としてみるとそれぞれ25%,20%に なる旨主張する。 しかしながら,上記内部資料は,FN社の設立に先立つ一審被告 内部の会議の資料として同社の事業計画を記載したものであって (乙389),不確実な予測にとどまる。そして,同資料にいう\n「ICチップ」は,携帯電話用に新たに開発されるものであるから 本件各製品とは別の製品であり(乙389),しかも,携帯電話特 有の技術(その多くは共同出資者のNTTドコモが保有するものと 推認される。)も多数用いられるので,本件各特許がどの程度重要 性を持つか定かでない(なお,携帯電話はそれ自体に電源を有する から,少なくとも,リーダライタ等からICチップへ無線で給電す ることに関連する技術である本件特許2及び8が実施されないこと は確かである。)。 よって,上記資料は,本件の仮想実施料率を認定するための資料 として用いるのは適切でない。
(b) 一審原告は,発明協会研究センター編「実施料率(副題)技術契 約のためのデータブック」第5版(甲99)によれば,「電子計算 機・その他の電子応用装置」の実施料率の平均は33%であるから, これも参考にすべき旨主張する。 しかしながら,上記データブックによれば,実施料率は,契約の 件数的に見れば,1%から10%程度の範囲に相当数が集中してい るが,例えば,実施料率40%の契約件数が50件以上あるなど, 高率の実施料率の範囲内で契約件数が突出しているところが数か所 あり,その結果,平均実施料率が高率化していることが認められる ところ(甲99,172頁の図2−20−2参照),高率の実施料 率による契約件数が突出している部分については,特殊な事情が存 在している可能性を否定することができない。そうであるとすると,\n特殊事情を考慮しない単純平均としての平均実施料率にどれだけの 意味があるのかは疑問といわざるを得ず,この数値を参考にするこ とはできない。
(c) 一審被告は,デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー 合同会社作成の報告書(乙53)を根拠として,FeliCa関連事業の 累積利益率は●●●●であるから,これを前提に25%ルール(利 益のうち,知的財産権が貢献している部分はその25%であるとし て,その価値を計算する方法)又は利益三分法(営業利益は,資本 力,営業力,技術力の3つから構成されるとして,営業利益の3分\nの1が技術力=知的財産権の価値であるとする方法)を適用すると, FeliCa関連の知的財産全体の適正実施料率は0.42%(25%ル ール)〜0.56%(三分法)であるところ,FeliCaに用いられた 知的財産権には特許権以外にノウハウもあること,特許権は本件各 特許のほかに少なくとも20件は存在すること(当審における補充 立証により裏付けられる事実)からすれば,本件各特許の適正実施 料率は更に低い旨主張する。 しかしながら,このように仮想実施料率を算定するベースとなる 利率を利益率とする必然性はないし,この方法によった場合,例え ば,何らかの事情によって事業の利益率がマイナスになってしまっ た場合には,事業に用いられた技術の知的財産権の価値がいくら高 くても仮想実施料率を算定し得ないこととなるという不都合が生ず ることも考慮する必要がある。以上の点を考慮すると,FeliCa関連 特許権の価値が営業利益に適正に反映されているかどうかについて 深刻な争いがある本件においては,営業利益率をベースとして仮想 実施料率を算定することは相当ではないというべきである(なお, aで取り上げた実施料率に基づいて検討する場合に比べると,利益 率をベースとした場合には,それだけで実施料率が一桁小さくなる ことになるが,このような大きな違いを正当化するような事情が存 するかどうかは疑問である。)。
d そこで,aで指摘した料率を前提として,本件における適切な仮想 実施料率を検討する。
aで掲げた各料率のうち,(c)のパテントプールに関する事例は,最 終製品の価格に対する実施料率が問題とされている点で,料率が低め に設定されている可能性があり,また,(d)のフランステレコムが申し\n出たライセンス料率は,その対象となる発明の意義等が本件実施発明 と比べてどの程度なのかが明らかではなく,いずれも参考資料として の重要性は高くないものといわざるを得ない。したがって,(a)と(b)を 中心に検討するのが相当である。
まず,(a)を見ると,本件実施発明が関連すると考えられる「器械」 「電気」「コンピュータテクノロジー」「精密機器」の分野における 平均実施料率は,2.9%〜3.5%である。また,(b)によれば,I T業界におけるライセンスの実務においては,必須特許の累積ロイヤ ルティ料率は最大限5%であるというのであるから,平均累積ロイヤ ルティ料率は,上記の平均実施料率とそれほど異ならないであろうこ とが予想される。そして,FeliCa技術は,Suicaを初めとする交通系 カードに採用されたほか,電子マネーカードにも採用されるなど,そ の技術的意義は高いと認められるから,この点は,仮想実施料率を高 める方向に働くと考えられる一方,本件実施発明は,その内容やその 技術的意義に照らし,FeliCa技術の中核的技術に当たると考えられる ものの,FeliCaには本件特許発明以外の技術も用いられており,それ らも相応の意義を有すると考えられるから(一審原告は,他の発明に はほとんど価値がないと主張し,一審被告は,本件実施発明の技術的 意義は極めて低いと主張するが,いずれも極端な主張であって,採用 することはできない。),FeliCa技術に対して支払われるべき実施料 のすべてを本件実施発明に帰属させるべきであると考えることはでき ず,この点は,本件実施発明に対する仮想実施料率を下げる方向に働 く要素であると考えざるを得ない。 これらの点を総合考慮すると,本件実施発明に対して支払われるべ き仮想実施料の料率は,11件の特許発明全体で3.3%,1件当た り0.3%程度と認めるのが相当である。
e 一審原告は,上記a(a)の実施料率を参考にするとしても,本件実施 発明の価値は極めて高いのであるから,「器械」分野における実施料 率の最大値である9.5%を採用すべきであると主張するが,9. 5%という実施料率は,平均実施料率(3.5%)を3標準偏差分 (標準偏差1.9%×3=5.7%)を超えて上回るものであり,こ のような実施料率の主張は非現実的といわざるを得ない(平均値+3 標準偏差=3.5%+5.7%=9.2%であるから,9.5%は, 3標準偏差分を上回る数値である。なお,統計学上,データの99. 7%は平均値の3標準偏差の範囲内に収まるはずであるから,一審原 告の主張は,その範囲をはずれた,通常では考えられないような例外 的な実施料率を主張していると評価せざるを得ない。)。 他方,一審被告は,被告各製品においては,本件実施特許のほかに も一審被告保有の特許及びノウハウ等が実施されているから,被告各 製品の価格に対するライセンス料が高額となりすぎる「スタッキン グ」の問題が生じ得る旨主張するが,上記の計算は,スタッキングの 問題も考慮した上での計算であるから,一審被告の主張は,上記の結 論を左右するものではない。
(3) FN社に対する実施権の現物出資に伴う利益
ア この点に関する認定判断は,原判決106頁17行目の「また,」から 22行目末尾までを次のとおり改めるほか,原判決の認定判断(105頁 14行目から107頁16行目までの記載)のとおりであるからこれを引 用する。 「そして,乙48その他の本件の証拠上,上記の出資に当たり,出資の目 的となった特許出願に係る発明のそれぞれにつきその軽重が考慮された とは認められないものの,これまで認定した諸事情を踏まえると,本件 対象実施権に係る発明の技術的意義は高いと認められる一方,他の出資 の対象となった特許発明は,件数は非常に多いものの,その中に本件対 象実施権に係る発明に匹敵するような技術的価値を有するものが存在し たことを裏付ける的確な証拠は存在しない。そうであるとすると,本件 対象実施権の価値を算出するのに当たり,単純に,件数に応じた計算を するのは相当ではなく,むしろ,本件対象実施権は,現物出資の対象と なった実施権の半分の価値を有するものとみて,その価値は●●●●● ●●●●(●●●●●●●●●×2/3×1/2)であると認めるのが 相当である。」
イ 一審原告は,現物出資後にFN社から一審被告に間接的に還元される利 益の額も考慮に入れるべきであり,具体的には,FN社の売上額のうち本 件各製品の売上げに係るものを抽出した上で,この売上げについて一審被 告がFN社から受領すべき相当なライセンス料を,現物出資に当たっての 評価に基づき計算された価値に加算すべきである旨主張する。 しかしながら,現物出資の後にFN社から一審被告へ利益の還元がなさ れたとしても,それは,一審被告が,FN社へ特許権等の独占実施権を出 資した対価として得たFN社の株式を保有し続け,FN社がその営業努力 により事業利益を上げ,かつその利益の一部を株主である一審被告に還元 することによるものである。かかる利益還元は,あくまで見込みとしてで はあるが,FN社への現物出資の評価に当たって評価され尽くしているも のであるから,これを一審原告の主張のように,現物出資の対価としての 評価額に更に加算するのは相当でない。 したがって,一審原告の上記主張は採用することができない。
(4) 第三者に対する実施許諾に伴う利益
両当事者の当審における主張も踏まえて,次のとおり認定判断する。
ア 証拠(乙334,342,425)及び弁論の全趣旨によれば,次の事 実を認定することができる。
(ア) 2008年(平成20年)以降,JR東日本が販売するSuicaカード のうちには,ICチップを一審被告以外の他社(以下「A社」とい う。)が製造し,最終製品としてのカードのJR東日本への納入までの 商流に一審被告が介在していないものがある。
(イ) そのICチップの製造個数は,2019年(平成31年)3月までの 累計で●●●●●●●●●●である。
(ウ) これらのICチップには,一審被告が開発したFeliCaOSが搭載され ている。
(エ) 一審被告はこれらのICチップ1個当たり●●●●●●●●●●●● ●●をA社から受領している。 イ 一審原告は,FeliCaOSでは本件各発明が実施されていること,OSラ イセンスには本件各発明の実施を許諾する趣旨が含まれていることが明ら かであるから,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そのまま独占の 利益として算定されるべきものである旨主張する。 しかしながら,●●●●●●●●●●●を本件各特許の実施許諾料と同 視して独占の利益に加算するのは相当でない。なぜなら,弁論の全趣旨に よれば,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●,本件各発明を実施するステップも含まれ てはいるが,ICチップの動作に関連するそれ以外のステップも多数含ま れており,本件各発明を実施するステップに対応する部分は極めて少ない と考えられるからである(一審原告は,これに対して的確な反論反証をし ていない。)。 そして,一審被告が●●●●●●●●●●●●●●,本件各発明を実施 するステップが占める割合を具体的に算定するに足りる資料はないが,そ の割合は極めて少ないと考えられることを考慮し,次のとおり,●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●を第三者に対する実施許諾に伴う独 占の利益と考えることとする。
(計算式)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
4 争点(3)(本件発明について一審被告が貢献した程度)について
(1) 本件全証拠を総合すると,本件発明について一審被告が貢献した程度を9 5%(発明者らの貢献度を5%)と評価するのが相当である。その理由は, 原判決の108頁5行目から114頁19行目までの記載のとおりであるか らこれを引用する。
(2) 当審において,両当事者はそれぞれ,自己に有利な事実を原判決が適切に 認定し考慮していないと主張する。 しかしながら,例えば,一審原告は,FeliCa事業が一審被告の社内で断念 されかかった時期においても一審原告は開発の継続を進言するとともに独力 で研究を続けたこと等を一審原告の貢献として主張するが,これを一審被告 の側から見れば,一審原告の人件費及び研究費用等の負担を甘受して,実用 化・事業化の目途の立たないFeliCaの研究に注力するのを容認していた,と いうことになる。このように,長期継続的な雇用関係のもとでの従業者の職 務発明においては,従業者が独力で成し遂げた発明に見えるものであっても, 使用者による有形無形の貢献が大きく寄与しているのが常態であり,本件各 発明もその例に漏れない。また,逆に,使用者による貢献がいかに大きくて も,個々の従業者の創意工夫なくしては発明は生まれないのであり,このこ とに対する評価を欠いては職務発明制度そのものが成り立ちえない。 以上の点を踏まえ,当事者双方の主張について更に補足すると以下のとお りである。
まず,一審原告は,1)非接触式ICカードに関し,一審被告の技術的蓄積 は皆無であったから,本件各発明は,一審原告がほぼ独力で行ったものであ る,2)一審原告は,本件各発明を行ったばかりではなく,その事業化につい ても大きな貢献(例えば,香港の主要交通機関におけるFeliCa採用の実現に 当たっては,一審原告は一人で関係者に対する説明等を行ったし,JR東日 本におけるFeliCaの採用に当たっても,一審原告が,関係者に対する説明等 必要な交渉に積極的に関与した。)を行った,3)一審被告は,FeliCaの事業 化に関する経営判断を誤るなど,本件各発明から収益を上げるについて大き なマイナスをもたらしており,その貢献は極めて低いなどといった主張をし ている。しかしながら,1)についていえば,本件各発明は,仮に直接それに 関わる技術は開発されていなかったとしても,原判決が認定するとおり,そ れまでの関連技術や知識の蓄積があって初めて行われたものと認められるの であって,一審原告の主張は,このような技術や知識の継承の重要性を無視 するものであるといわざるを得ない。また,2)についていえば,香港の主要 交通機関におけるFeliCaの採用に当たっては,一審被告の企業規模や財務の 安定性も大きな要素となっていたこと,JR東日本におけるFeliCaの採用に ついても,一審被告とJR東日本との密接な関係が大きな要素となっていた ことは既に指摘したとおりであるし,一審原告の活動に関しても,その背後 には,一審被告の支援やバックアップ等があったことは容易に推認できると ころである。さらに,3)については,経営判断は,表面に出ない事情も含め\nた諸般の事情に基づいて行われるものであって,その当否を軽々に論ずるこ とはできないのであって,一審原告の主張は,これら様々な事情を考慮しな い結果論の嫌いを免れないものといわざるを得ない。以上の点を考慮すると, 一審原告の主張をそのまま採用することは困難である。 他方,本件各発明の重要性も既に指摘したとおりであるし,一審原告が, 関係者に対する技術説明等,単なる技術開発にとどまらない貢献を行ったこ とも事実であると認められる。一審被告の主張は,このような一審原告の貢 献を軽視しているといわざるを得ず,やはり,そのままその主張を採用する ことはできない。 以上の次第であって,両当事者の当審における補充主張は,上記(1)の判断 を左右しない。
5 争点(4)(発明者間における一審原告の貢献の程度)について
本件全証拠を総合すると,各本件実施発明の共同発明者間における一審原告 の貢献の程度は,共同発明者各自の貢献の程度を均等として評価するのが相当 である。その理由及び具体的な割合は,原判決の114頁21行目から115 頁18行目までの記載のとおりであるからこれを引用する。 一審原告は,本件各発明に係る技術的創作を行ったのは一審原告であり,他 の者は,一審原告の指示に基づいてプログラミングをするなど,技術的創作に 該当しない関与を行ったにすぎないという趣旨の主張をし,その陳述書(甲9 0〜92)にもこれに沿う部分があるが,F(乙162),A(乙163)は, これに反する陳述をしており,いずれの陳述が正当であるかは,にわかに決し 難いところがある上に,発明報告書(乙27〜36)等の客観的証拠にも一審 原告の主張を裏付けるに足りる記述は存在しない。したがって,一審原告の主 張は,そのまま採用することは困難であるといわざるを得ない。
◆判決本文
原審はこちらです。
2020.08.14
平成30(ワ)10126 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月30日 東京地方裁判所
図103〜106のドットパターンに関係して,前記2のとおり,段落 【0184】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)の記載があ る。これらによれば,そのドットパターンは,格子状に配置されたドット で構成される。そして,格子ドットLDと呼ばれるドットを四隅に配置し,その4つの格子ドットLDで囲まれた領域の中心からどの程度ずらすかに\nよってテータ内容が定義され,例えば,同領域の中心から等距離の位置で 45度ずつずらした点を8個定義することで,8通りのデータを表現でき,このずらす距離を変更した点を8個定義することで16通りのデータを表\現できる。また,格子ドットLDは,本来,縦横方向の格子線の交点上で ある格子点上に配置されるが,その位置をずらしたドットをキードットK Dとして,このキードットKDに囲まれた領域,又は,キードットKDを 中心にした領域が一つのデータを示している。また,キードットKDを格 子点から等距離で45°ずつずらすことにより,その角度ごとに別の情報 を定義することができることなどが記載されている。(以下,図103〜1 06や上記発明の詳細な説明に記載されている技術思想のドットパターン を「図105ドットパターン」ということがある。) 図105について,垂直方向のラインについて,LV1,LV2などの 符号を付し,水平方向のラインについて,LH1,LH2などの符号を付 し,ドットにD1,D2などの番号を付したものが別紙図105その2で ある。
図105においては,例えば,垂直方向の格子線であるLV1,LV3, LV5と,水平方向の格子線であるLH1,LH3,LH5の交点に格子 ドットが配置され,格子ドットが四隅に配置されている領域が示されてい る(例えば,D1,D2,D13,D12(ただし後述)を四隅とするも の,D2,D3,D14,D13を四隅とするもの)。そして,その4個の 格子ドットで囲まれる領域の中心から等距離の位置でいずれかの位置に 1個のドットが配置されていることが示され(例えば,D7,D8),図 105全体では,上記領域の中心から等距離の位置で,45°ずつずれた 位置のいずれか1つの位置にドットが配置されることが記載されている。 また,図103には,交点から45°ずつずれた位置にドットを配置する 構成が記載されている。そして,D12やD56は,垂直方向の格子線であるLV3又はLV11上にあるが,水平方向の格子線であるLH1上に\nはなく,これらは,格子線の交点からずれたキードットKDであることが 示されている。
ア 本件補正1及び2による補正後の構成要件B1・G2は「(前記ドットパターンは,)縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中\n心に,前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした 方向のうちいずれかの方向に,どの程度ずらすかによってデータ内容を定義 し」である。
当初明細書1及び2の記載や図における図105ドットパターンにおい て,4個の格子ドットで囲まれる領域の中心は,それらの格子ドットが配置 されている格子線の中間にそれらと並行して存在するといえる格子線の交 点ともいえるから(例えば,格子点D1,D2,D13,D12で囲まれる 領域の中心は,垂直方向の格子線であるLV1,LV3の間のLV2と,水 平方向の格子線であるLH1,LH3の間のLH2の交点といえ,また,L V2,LV4,LV6,LH2,LH4,LH6は,縦横方向に等間隔に設 けられた格子線ともいえる。),上記構成要件B1・G2に係る構\成は,【01 84】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)及び図105に記載 されているといえる。
他方,図5ドットパターンにおいて,図5〜図8では,縦横方向に等間隔 で設けられた格子線(例えばLV4,LV7,LV10,LH4,LH7, LH10)の交点から等距離に,水平方向及び(又は)垂直方向にずらした 位置に各1〜3個のドットが記載されて情報を示している。これらでは,縦 横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に,情報内容 を定義するドットが格子点の中心からずれることで情報が示されていると いえるが,情報内容を定義するドットは,水平方向及び(又は)垂直方向に ずらされるのであり,等距離で90°ずつずらしているとはいえるとしても, 等距離で45°ずつずらしているものではない。図5〜図8では,格子線の 間に設けられた垂直方向及び水平方向のライン(例えば,LV3,LV5, LH3,LH5)が示された上で,それらのラインや格子線の交点に情報を 示すドットが示されていて(例えば,D9,D14),これは情報を示すド ットを格子点の中心から等距離で90°ずつずらすことを前提としている ものであり,このように交点に情報を示すドットを配置するこの図では情報 を示すドットを等距離で45°ずつずらすことは想定されていない。そうす ると,上記構成要件B1・G2に係る構\成は,【0023】〜【0027】 I),【0067】〜【0071】II)及び図5〜図8に記載されているもので はない。
イ 本件補正1及び2による補正後の構成要件C1・H2は「前記情報ドットが配置されて情報を表\現する部分を囲むように,前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と,該第一方向ラインと交差 するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方 向ライン上とにおいて,該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置さ れた(ドットパターンである)」である。
前記アのとおり,当初明細書I),II)には,図105ドットパターンに関す る記載において,本件補正1及び2による補正後の構成要件B1・G2に係る構\成が記載されていた。しかし,図105ドットパターンにおいては,縦横方向の格子線の交点上である格子点上に格子ドットLDが配置され,その 位置をずらしたドットをキードットKDとして,このキードットKDに囲ま れた領域,又は,キードットKDを中心にした領域が一つのデータを示すも のとされている。このようなキードットKDに囲まれた領域又はキードット KDを中心にした領域が一つのデータを示すものであり,「前記情報ドット が配置されて情報を表現する部分」(C1・H2)であるといえるところ,図105ドットパターンでは,前記のようにキードットKDによって,それ\nに囲まれた領域,又はそれを中心にした領域が情報を表現する部分とされているのであり,また,図105では,情報を表\現する部分はキードットKDにより囲まれていることが示されているのであって,そうである以上,「第 一方向ライン」及び「第二方向ライン」(C1・H2)として特定される水 平方向及び垂直方向のラインによって,情報を表現する部分を囲んでいると直ちにいえるものではない。したがって,「第一方向ライン」,「第二方向ラ\nイン」がない以上,情報を示すドットが配置されて情報を表現する部分を囲むような「第一方向ライン」及び「第二方向ライン」上にドットが配置され\nているということもできない。以上によれば,上記構成要件C1・H2に係る構\成は,【0184】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)及 び図105に記載されているとは認められない。 なお,図5ドットパターンについて,補正後の構成要件B1・G2に係る構\成の記載はないのであるが,図5ドットパターンには,情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように,縦方向の所定のドットの間隔ごとに水平方向に引いた水平ラインと,水平ラインと交差するように横方向の所\n定のドットの間隔ごとに垂直方向に引いた垂直ラインが存在し,また,それ らのライン上において,複数の格子点上に格子ドットが配置されているとい える。したがって,上記構成要件C1・H2に係る構\成は,【0023】〜 【0027】I),【0067】〜【0071】II)及び図5〜図8に記載され ているとはいえる。
ア 前記(3)によれば,当初明細書1及び2において,構成要件B1・G2に係る構\成は,【0184】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)及 び図105には記載されているとはいえるが,そこで記載されているドッ トパターンである図105ドットパターンは構成要件C1・H2の構\成を 有するものではない。また,当初明細書1及び2において,構成要件C1・H2に係る構\成は,【0023】〜【0027】I),【0067】〜【007 1】II)及び図5〜図8には記載されているとはいえるが,そこで記載されて いるドットパターンである図5ドットパターンは構成要件B1・G2の構\ 成を有するものではない。
そして,図5ドットパターンと図105ドットパターンは,情報ドットの ずらし方,1つの交点に対する情報ドットの個数,情報ドット以外のドット の配置,格子線又はラインのうち特定のものを「第一方向ライン」等として 特定するか否か,垂直ライン上のドットが本来の位置からのずれ方によって データの種類を表すか否か,1つのデータを区画するキードットKDが存在するか否か等,多くの点で相違しており,これらの相違は,各実施例が開示\nする技術的事項,すなわちドットパターンによる情報の定義方法が相当に異 なることに起因する。当初明細書1及び2は,極小領域であってもコード情 報やXY座標情報が定義可能なドットパターンを提供するとし(【0013】I),【0008】II)),複数のドットパターンを記載しているのであるが,そ こに記載されたドットパターンである図5ドットパターンと図105ドッ トパターンの情報の定義方法は上記のとおり相当に異なるのであり,また, 当初明細書1及び2に,これらの異なる情報定義方法を採用した各ドットパ ターンが採用する情報定義方法を相互に入れ替えたり,重ねて採用したりす ることについては何ら記載されていない。したがって,当初明細書1及び2 に,これらのドットパターンを組み合わせたものについての記載があるとは いえないし,それが当業者に自明であるともいえない。 以上によれば,当初明細書1及び2には,いずれも,本件補正1及び2に よって変更された構成要件B1・G2及び構\成要件C1・H2の構成をいずれも備えるドットパターンについての記載があるとはいえない。\nそうすると,当初明細書1又は2において,全ての記載を総合したとして も,当初明細書1又は2には,本件補正1及び2で補正後のドットパターン が記載されているとはいえず,本件補正は,当初明細書1又は2に開示され ていない新たな技術的事項を導入するものである。 したがって,本件補正1及び2は,当初明細書1又は2の記載等から導か れる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものである から,特許法17条の2第3項の補正要件に違反する。
イ これに対し,原告は,図103〜図106の実施例と図5〜図8の実施例 は,極小領域であってもコード情報やXY座標情報が定義可能なドットパターンを提案するという共通の課題を解決するための異なる実施例であり,こ\nれらを組み合わせることは当業者には自明の範囲のものであるから,構成要件B1・G2及び構\成要件C1・H2の構成は,いずれも当初明細書1及び\n2に記載されていると主張する。しかしながら,図5〜図8の実施例で示される図5ドットパターンと図103〜図106の実施例で示される図105ドットパターンでは,上記のとおり,情報の定義方法が相当に異なり,それを組み合わせることが当業者に 自明とはいえないし,当初明細書1及び2にそのような組み合わせを前提と した記載も存在しない。原告の上記主張には理由がない。
4 争点4−3(サポート要件に違反しているか)について
事案に鑑み,続いて,争点4−3のうち,本件発明3〜5についてのサポート 要件違反について判断する。
本件発明3の構成要件D3及び本件発明4の構\成要件E4の特許請求の範 囲の記載は「前記垂直方向に配置されたドットの1つは,当該ドット本来の位 置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」との記 載を含み,本件発明5の構成要件D5の特許請求の範囲の記載は,「前記垂直 方向に配置されたドットの1つにおける当該ドット本来の位置からのずれ方 によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」との記載を含むもので ある。 これらには,垂直方向に配置されたドットの1つについて,本来の位置に配 置せず別の位置に配置すること,そして,「ずらし方によって」「ずれ方によっ て」ドットパターンの向きを示すとしていることからも,本来の位置と実際に 配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているといえる。\n
(2)ア 本件明細書3及び4には,前記1の記載があり,また,ドットパターンに 関係して前記2の記載がある。 ここで,本件明細書3及び4には,ドットを本来の位置とは違う位置に配 置し,本来の位置と実際に配置された位置のずれ方によってドットパターン の向きを表現することに関係し得るものとして,本件明細書3の【0009】III)に特許請求の範囲と同じ記載があり,後記イのキードットKDのずらし方 に関係する記載があることを除いて,何ら記載がない。 イ 【0240】〜【0242】III),【0234】〜【0236】IV)には,キー ドットKDにつき,撮像された格子ドットとキードットKDとの位置関係か らカメラの角度が分かり,カメラで同じ領域を撮影しても角度という別次元 のパラメータを持たせることができる旨の記載がある。このようにキードッ トKDの配置のずらし方によってドットパターンを撮像するカメラの角度 が分かることが記載されているところ,その角度が分かるためには配置のず らし方があらかじめ定められていることを前提としているはずであり,ドッ トパターンについていうと,キードットKDの配置のずらし方によって,ド ットパターンの向きを示すことが記載されているともいえる。 しかしながら,上記記載は,図105ドットパターンに関するものである (ドットパターンに関する明細書の記載及び図面は,当初明細書1及び2, 本件明細書1〜4では,いずれも同じであり,本件明細書3,4にも,図1 05ドッパターンと図5ドットパターンが記載されているといえる。)。前記 のとおり,図105ドットパターンにおいて,情報を示すドットは4 個の格子ドットLDに囲まれた領域の中心から等距離の位置で45°ずつ ずらしたいずれかの位置に配置されている。しかし,その中心点を交点とす るような垂直ラインと水平ラインを仮想的に想定したとして,それらは水平 方向あるいは垂直方向に配置されたドットから設定されたものではない。す なわち,図105ドットパターンにおいては,4個の格子ドットLDに囲ま れた領域の中心について,そこを交点とする垂直ラインと水平ラインを仮想 的に想定するとしても,それらの垂直ラインと水平ラインを設定するドット はない。そうすると,図105ドットパターンは,少なくとも,「前記水平 方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ラインと,前記垂直方 向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの 交点」である「格子点…からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」 (構成要件C3・D4・C5)に係る構\成を有するものではない。また,図 105,図106においては,キードットKDは,垂直方向の格子線上にあ るが水平方向の格子線上にはないという態様で格子点からずれていて,これ らのキードットKDは「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドット」(A 3・B4・A5)の1つであり,「前記水平方向に配置されたドットの端点 に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」 (A3・C4・A5)ではないから,「前記垂直方向に配置されたドットの 1つは,当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターン の向きを意味している」(構成要件D3・E4・D5)ものには当たらないといえる。\n以上によれば,図105ドットパターンは,少なくとも,構成要件C3・D4・C5に対応する構\成を有するものではない。また,図105,図10 6のキードットKDは,構成要件D3・E4・D5の情報ドットではないともいえる。\n
そうすると,図105ドットパターンは,本件発明3〜5に係るドットパ ターンと異なるドットパターンである。そのような図105ドットパターン に関してキードットKDについて上記記載があるとしても,その記載をもっ て,本件発明3〜5について,「ずらし方によって前記ドットパターンの向 きを意味している」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」(構\成要件D5)についての記載があるといえるものではないし,また,当業者にとって,その記載があると理解する ことはできない。
ウ 図5ドットパターンについては,水平ライン(図5その2のLH1,LH 13等)上に等間隔に配置されたドット(図5その2のLH1上ではD1, D8,D20,D30等)は「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドッ ト」(構成要件A3・B4)「等間隔に所定個数,所定方向に配置されたドットを水平方向に配置されたドット」(構\成要件C5)であるといえ,垂直ライン(図5その2のLV1,LV13等)上に等間隔で配置されたドット(例 えば,図5その2のD2,D3等)は「前記水平方向に配置されたドットの 端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたド ット」(構成要件B3・C4),「前記所定方向に対して垂直方向に等間隔に所定個数配置されたドットを垂直方向に配置されたドットとして抽出し」(構\成要件C5)であるといえる。また,水平ライン及び垂直ライン上に設置さ れた上記各ドットを通過する縦横の格子線の交点から,90°ずつずれたい ずれかの方向にずれた情報ドットは,「前記水平方向に配置されたドットか ら仮想的に設定された垂直ラインと,前記垂直方向に配置されたドットから 水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの交点を格子点とし,該格子点 からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」(構成要件C3・D4・ C5)であるといえる。 しかしながら,「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味して いる」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する」(構\成要件D5)については,本件明細書3及び4には,関係する記載はないといえる。図5ドットパターンの図5〜8において垂直ライン 上にドットがないところがあり,そこにはドットが本来の位置と比べて,図 5では左(図5その2のD2),図6では左又は右,図7では左,図8では右 にずれた位置にドットが配置されているが,【0069】〜【0073】III), 【0063】〜【0067】IV)には,これらのドットについて,その本来の 位置と実際に配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きを 意味することを示す記載は全く存在しない。かえって,上記のドットについ て,図5及び図7では,左にずれたドットについて「x,y座標フラグ」と 記載され,そのドットパターンがx座標,y座標を示すことが記載され,図 6及び図8では,右にずれたドットについて「一般コードフラグ」と記載さ れ,そのドットパターンが「一般コード」を示すことが記載されている。そ うすると,これらのドットは,ドットの本来の位置と実際に配置された位置 との関係によってドットパターンのデータの種類を定義していることがう かがえる。 また,図5ドットパターンについて,【0072】III),【0066】IV)には, 水平ラインから垂直ラインを抽出した後,「垂直ラインは,水平ラインを構成するドットからスタートし,次の点もしくは3つ目の点がライン上にない\nことから上下方向を認識する。」という記載があり,垂直ライン上のドット の有無によってドットパターンの上下方向を認識することが記載されてい る。しかし,ここでは,ライン上にドットがあるかないかだけを認識して上 下方向を判断することが記載されているのであって,構成要件D3・E4・D5に係る構\成である,本来のドットの位置と実際に配置されたドットの位 置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているとはいえない。\n
これらによれば,図5ドットパターンについても,本件明細書3及び4は, 「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」\n(構成要件D5)の構\成について,何ら記載はないといえることとなる。そ の他,本件明細書3及び4に,本件発明3〜5における上記構成について説明していると解される記載は存在しない。\n
エ 以上によれば,本件明細書3及び4には,「ずらし方によって前記ドット パターンの向きを意味している」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」(構\成要件D5)の構成につい\nて,具体的に何ら記載がないといえるし,具体的な記載がないにもかかわら ず,当業者が,技術常識に照らして上記構成を理解したことを認めるに足りる証拠もない。\n したがって,本件発明3の構成要件D3,本件発明4の構\成要件E4,本 件発明5の構成要件D5は,本件明細書3及び4の発明の詳細な説明に記載したものとは認められない。\n ア 原告は,図5〜図8において,「ドットパターンの向きを意味している」ド ットは,「x,y座標フラグ」又は「一般コードフラグ」と兼用されている と主張する。 しかしながら,図5〜図8の記載は上記のようなものであって,そこでは ドットが「x,y座標フラグ」又は「一般コードフラグ」として記載されて いるが,それ以外に,ドットパターンの向きに関する記載はない。そして, 明細書の発明の詳細な説明においても,【0071】〜【0073】III),【0 065】〜【0067】IV)においては,ドットの本来の位置と実際に配置さ れた位置との関係によってドットパターンの向いている方向を認識するこ とについては何ら説明されておらず,また本件明細書3及び4のどこにも, ずれ方によってドットパターンの向きを意味するドットと,データ内容を定 義するドットとを兼用するとの説明は記載されていない。原告の上記主張に は理由がない。
イ 原告は,【0239】〜【0241】III),【0233】〜【0235】IV)に は,キードット(KD)につき,データ領域の範囲を定義する第1の機能と,ずらし方を変更することによりドットパターンの向き(角度)を意味すると\nいう第2の機能を有することが示されており,図105及び図106(d)では全てのキードット(KD)を一定の方向にずらすことによってドットパ\nターンの向きを表すことが開示されていると主張する。 しかしながら,これらは,図105ドットパターンに関する記載である。 前記(2)イのとおり,図105ドットパターンの情報の定義方法は本件発明3 〜5の構成要件C3・D4・C5に係る構\成の情報の定義方法と異なる。当 業者において,本件発明3〜5の情報の定義方法と異なる情報の定義方法を 採用する図105ドットパターンに開示された構成をもって,本件発明3〜5の構\成要件D3・E4・D5の各構成が開示されていると理解することは\nできない。原告の上記主張には理由がない。
5 小括
以上によれば,本件発明1及び2に係る本件特許1及び2は特許法17条の2 第3項に違反し,本件発明3〜5に係る本件特許3及び4は同法36条6項1号 に違反し,いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである(同法12 3条1項1号,4号)。そうすると,その余を判断するまでもなく,原告は,同法 104条の3第1項により,被告各製品が本件発明1〜5の技術的範囲に属する ことを主張して本件各特許権を行使することはできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.08.13
平成30(受)1412 発信者情報開示請求事件 令和2年7月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所
発信者情報開示事件です。1審では、リツイートはインラインリンクであるので、著作権侵害、人格権侵害に該当しないと判断され、請求は棄却されました。知財高裁(2部)は、著作者人格権侵害があったとして、一部の発信者情報について開示を認めました。最高裁(第3小)も人格権侵害は認めましたが、著作権侵害は否定しました。
自動公衆送信の主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ,情報 を自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者と解されるところ(最高裁平成 23年1月18日判決・民集65巻1号121頁参照),本件写真のデータは,流 通情報2(2)のデータのみが送信されていることからすると,その自動公衆送信の 主体は,流通情報2(2)の URL の開設者であって,本件リツイート者らではないと いうべきである。著作権侵害行為の主体が誰であるかは,行為の対象,方法,行為 への関与の内容,程度等の諸般の事情を総合的に考慮して,規範的に解釈すべきで あり,カラオケ法理と呼ばれるものも,その適用の一場面であると解される(最高 裁平成23年1月20日判決・民集65巻1号399頁参照)が,本件において, 本件リツイート者らを自動公衆送信の主体というべき事情は認め難い。控訴人は, 本件アカウント3〜5の管理者は,そのホーム画面を支配している上,ホーム画面 閲覧の社会的経済的利益を得ていると主張するが,そのような事情は,あくまでも 本件アカウント3〜5のホーム画面に関する事情であって,流通情報2(2)のデー タのみが送信されている本件写真について,本件リツイート者らを自動公衆送信の 主体と認めることができる事情とはいえない。また,本件リツイート行為によって, 本件写真の画像が,より広い範囲にユーザーのパソコン等の端末に表\示されること となるが,我が国の著作権法の解釈として,このような受け手の範囲が拡大するこ とをもって,自動公衆送信の主体は,本件リツイート者らであるということはでき ない。さらに,本件リツイート行為が上記の自動公衆送信行為自体を容易にしたと はいい難いから,本件リツイート者らを幇助者と認めることはできず,その他,本 件リツイート者らを幇助者というべき事情は認められない。
(ウ) 控訴人は,自動公衆送信にも放送にも有線放送にも当たらない公衆 送信権侵害も主張するが,前記(ア)のとおり自動公衆送信に当たることからすると, 自動公衆送信以外の公衆送信権侵害が成立するとは認められない。
(3) 複製権侵害(著作権法21条)について
前記(2)イのとおり,著作物である本件写真は,流通情報2(2)のデータのみが送 信されているから,本件リツイート行為により著作物のデータが複製されていると いうことはできない。したがって,複製権侵害との関係でも,控訴人が主張する「 ブラウザ用レンダリングデータ」あるいは HTML データ等を「侵害情報」と捉える ことはできず,「ブラウザ用レンダリングデータ」あるいは HTML データ等が「侵 害情報」であることを前提とする控訴人の複製権侵害に関する主張は,採用するこ とができない。
(4) 公衆伝達権侵害(著作権法23条2項)について
著作権法23条2項は,「著作者は,公衆送信されるその著作物を受信装置を用 いて公に伝達する権利を専有する。」と規定する。 控訴人は,本件リツイート者らをもって,著作物をクライアントコンピュータに 表示させた主体と評価すべきであるから,本件リツイート者らが受信装置であるク\nライアントコンピュータを用いて公に伝達していると主張する。しかし,著作権法 23条2項は,公衆送信された後に公衆送信された著作物を,受信装置を用いて公 に伝達する権利を規定しているものであり,ここでいう受信装置がクライアントコ ンピュータであるとすると,その装置を用いて伝達している主体は,そのコンピュ ータのユーザーであると解され,本件リツイート者らを伝達主体と評価することは できない。控訴人が主張する事情は,本件写真等の公衆送信に関する事情や本件ア カウント3〜5のホーム画面に関する事情であって,この判断を左右するものでは ない。そして,その主体であるクライアントコンピュータのユーザーが公に伝達し ているというべき事情も認め難いから,公衆伝達権の侵害行為自体が認められない。 このように公衆伝達権の侵害行為自体が認められないから,その幇助が認められる 余地もない。
(5) 著作者人格権侵害について
ア 同一性保持権(著作権法20条1項) 侵害
前記(1)のとおり,本件アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている\n画像は,流通情報2(2)の画像とは異なるものである。この表示されている画像は,\n表示するに際して,本件リツイート行為の結果として送信された HTML プログラム や CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,上記のとおり 画像が異なっているものであり,流通情報2(2)の画像データ自体に改変が加えら れているものではない。 しかし,表示される画像は,思想又は感情を創作的に表\現したものであって,文 芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものとして,著作権法2条1項1号にいう 著作物ということができるところ,上記のとおり,表示するに際して,HTML プロ グラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどを指定されたために,本件ア カウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3〜5のよ\nうな画像となったものと認められるから,本件リツイート者らによって改変された もので,同一性保持権が侵害されているということができる。 この点について,被控訴人らは,仮に改変されたとしても,その改変の主体は, インターネットユーザーであると主張するが,上記のとおり,本件リツイート行為 の結果として送信された HTML プログラムや CSS プログラム等により位置や大きさ などが指定されたために,改変されたということができるから,改変の主体は本件 リツイート者らであると評価することができるのであって,インターネットユーザ ーを改変の主体と評価することはできない(著作権法47条の8は,電子計算機に おける著作物の利用に伴う複製に関する規定であって,同規定によってこの判断が 左右されることはない。)。また,被控訴人らは,本件アカウント3〜5のタイム ラインにおいて表示されている画像は,流通情報2(1)の画像と同じ画像であるから, 改変を行ったのは,本件アカウント2の保有者であると主張するが,本件アカウン ト3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は,控訴人の著作物である本\n件写真と比較して改変されたものであって,上記のとおり本件リツイート者らによ って改変されたと評価することができるから,本件リツイート者らによって同一性 保持権が侵害されたということができる。さらに,被控訴人らは,著作権法20条 2項4号の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は, 本件アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイート が行われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむ を得ない」改変に当たると認めることはできない。
イ 氏名表示権(著作権法19条1項)侵害\n
本件アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像には,控訴人\nの氏名は表示されていない。そして,前記(1)のとおり,表示するに際して HTML プ ログラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,本件 アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3〜5の\nような画像となり,控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから,控\n訴人は,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆 への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができ\nる。
ウ 名誉声望保持権(著作権法113条6項)侵害
本件アカウント3〜5において,サンリオのキャラクターやディズニーのキャラ クターとともに本件写真が表示されているからといって,そのことから直ちに,「\n無断利用してもかまわない価値の低い著作物」,「安っぽい著作物」であるかのよ うな誤った印象を与えるということはできず,著作者である控訴人の名誉又は声望 を害する方法で著作物を利用したということはできない。そして,他に,控訴人の 名誉又は声望を害する方法で著作物を利用したものというべき事情は認められない から,本件リツイート者らは,控訴人の名誉声望保持権(著作権法113条6項 )を侵害したとは認められない。
(6) なお,控訴人は,本件アカウント2,4及び5の各保有者が自然人として は同一人物であり,又はこれらの者が共同して公衆送信権を侵害した旨主張するが, そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
(7)「侵害情報の流通によって」(プロバイダ責任制限法4条1項1号)及び 「発信者」(同法2条4号)について
前記(5)ア,イのとおり,本件リツイート行為は,控訴人の著作者人格権を侵害す る行為であるところ,前記(5)ア,イ認定の侵害態様に照らすと,この場合には,本 件写真の画像データのみならず,HTML プログラムや CSS プログラム等のデータを 含めて,プロバイダ責任制限法上の「侵害情報」ということができ,本件リツイー ト行為は,その侵害情報の流通によって控訴人の権利を侵害したことが明らかであ る。そして,この場合の「発信者」は,本件リツイート者らであるということがで きる。
(8) 争点(2)について
本件アカウント2の流通情報2(3)及び(4)については,流通情報3〜5と同様に, 流通情報2(2)の画像が改変され,控訴人の氏名が表示されていないということが\nできるから,著作者人格権の侵害があるということができる。しかし,本件アカウ ント1の流通情報1(6)及び(7)については,流通情報1(3)の画像と同じものが表示\nされているから,著作者人格権の侵害があると認めることはできない。これらにつ いて著作権の侵害を認めることができないことは,流通情報3〜5と同様である。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成28(ネ)10101
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2020.08.12
平成31(行ケ)10047 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月22日 知的財産高等裁判所
相違点4の容易想到性の判断(1)の誤りの有無について
原告は,1)甲1発明の「分岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」は, 予め一体とされた後,一体となった状態のまま,ベース2に取り付けられ,\n「回路遮断器の取り付け構造」における「回路遮断器」として用いられるも\nのであり,本件訂正発明の「回路遮断器」とその機能及び用途において相違\nするものではないから,本件審決における相違点2の認定には誤りがある,
2)本件審決における相違点4の容易想到性の判断(1)は,本件訂正発明と甲1 発明との間に相違点2が存在することを前提とするから,その前提において 誤りがある旨主張する。
ア(ア) そこで検討するに,本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線 とねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグ インタイプの回路遮断器」,「取付用板」と「回路遮断機の取付構造」\nとの文言からすると,本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線と ねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグイ ンタイプの回路遮断器」における「回路遮断器」は,取付用板に取り付 けられる取付機構を有するものと理解できる。\nそして,「回路遮断器」の構成の一部である取付機構\は,回路遮断機 能を有する機器そのものと予\め一体不可分に作製する場合のほかに,回 路遮断機能を有する機器と別部材の取り付け部材とを一体化して作製す\nる場合などが考えられる。 しかるところ,本件訂正発明の特許請求の範囲(請求項2)には,「回 路遮断器」の取り付け機構について,回路遮断機能\を有する機器そのも のと予め一体不可分に作製されたものに限定する記載はない。また,本\n件明細書においても,そのような限定をする趣旨の記載はない。 そうすると,別部材の取付部材を有する回路遮断器は,本件訂正発明 の「回路遮断器」に含まれるものと解すべきである。
(イ) これに対し被告は,本件訂正発明の特許請求の範囲(請求項2)に は,「回路遮断器を分電盤などの母線が設けられた取付板に取り付ける ための前記回路遮断器と取付板の構造」,「前記回路遮断器の前記母線\nとは反対側の負荷側には…ロックレバーを設け」,「前記取付板と前記 回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部」との記載が あること,本件訂正明細書には,本件発明の実施形態として,凹部やロ ックレバーを含む1つの部材として回路遮断器が構成されている実施形\n態のみが記載されていることからすると,本件訂正発明は,回路遮断器 を取付板に直接取り付けることを前提にした発明であるといえる旨主張 する。 しかしながら,前記(ア)認定のとおり,本件発明1の「回路遮断器」 は,取付板に取り付けられる取付機構を有するものであるところ,本件\n訂正発明2の特許請求の範囲(請求項2)には,「回路遮断器」の取り 付け機構について,回路遮断機能\を有する機器そのものと予め一体不可\n分に作製されたものに限定する記載はなく,また,本件訂正明細書にお いても,そのような限定をする趣旨の記載はないから,被告の上記主張 は採用することができない。
イ(ア) 次に,甲1には,取り付け部材5に関し,「各分岐開閉器4の下に は夫々取り付け部材5を配置してあり,この取り付け部材5を介して分 岐開閉器4をベース2を取り付けるようになっている。取り付け部材5 は図6に示すように上片5aと両側の側片5bとで略コ字状に形成され ている。取り付け部材5の長手方向の両端には上記引っ掛け凹所8に引 っ掛け係止する引っ掛け爪9を設けてある。両端の引っ掛け爪9のうち 導電バー3側の引っ掛け爪9は変位可能な形状にした係脱用引っ掛け爪\n9aとなっており,他方の引っ掛け爪9は略剛体になっている。取り付 け部材5の上には分岐開閉器4が配置され,両端の引っ掛け爪9を分岐 開閉器4の引っ掛け凹所8に引っ掛け係止することで取り付け部材5の 上に分岐開閉器4を取り付けてある。」(【0013】),「そして分 岐開閉器4を取り付け部材5に取り付けた状態で取り付け部材5と一緒 に分岐開閉器4が次のように装着される。取り付け部材5をベース2の 上に配置して係止爪23が長孔23に挿入され,分岐開閉器4と一緒に 取り付け部材5が導電バー3の方にスライドさせられる。分岐開閉器4 と取り付け部材5をスライドさせると,接続端子16が導電バー3に差 し込まれて電気的に接続される。…このとき板ばね25の先端部25a が係止孔24に係止して取り付け部材5が動かないように止められる。 このように分岐開閉器4を取り付けたとき,係脱用引っ掛け爪9aが導 電バー3側に位置するため,導電バー3と接続端子16の係止にて係脱 用引っ掛け爪9aと引っ掛け凹所8との係止が外れにくくなり,分岐開 閉器4が外れにくいように取り付けることができる。また板ばね25の 先端部25aの係止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉 器4と一緒に取り付け部材5を取り外すことができる。」(【0014】) との記載がある。この記載によれば,甲1発明の取り付け部材5と分岐 開閉器4は,別部材ではあるが,分岐開閉器4を取り付け部材5に取り 付けた状態で,ベース2の上に配置し,取り付け部材5と一緒に分岐開 閉器4を導電バー3の方向にスライドさせていくと前記導電バー3が接 続端子16に差し込まれていき,ベース2に分岐開閉器4を取り付けた 取り付け部材5が取り付けられること,板ばね25の先端部25aの係 止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉器4と一緒に取り 付け部材5を取り外すことができることからすると,「分岐開閉器4を 取り付けた取り付け部材5」は,予め一体とされた後一体となった状態\nのまま,ベース2に取り付けられ,また,一体となった状態のままベー スから取り外されるのであるから,「分岐開閉器4を取り付けた取り付 け部材5」における取り付け部材5は,分岐開閉器4と一体化された分 岐開閉器4の取付機構としての機能\を有するものと認められる。 そうすると,甲1発明の「分岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」 は,本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線とねじ無しで接続を 行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグインタイプの回路遮 断器」における「回路遮断器」に相当するものと認められる。 したがって,甲1発明の「分岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」 は,本件発明の「回路遮断器」に相当するものでないとした本件審決の 認定は誤りであるから,本件審決における相違点4の容易想到性の判断 (1)も誤りである。
(イ) これに対し被告は,1)甲1の記載によれば,甲1発明は,取り付け 部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り付ける場合に生じる問題 (【0003】)を課題とし,取り付け部材を介在させて分岐開閉器を ベースに取り付けることを前提にした発明である,2)甲1には分岐開閉 器が同じ構成で取り付け部材の高さが違う実施形態が記載されており,\n取り付け部材は,分岐開閉器をベースに取り付けるためのスペーサとし て機能する別部材であるから,取り付け部材は,回路遮断器の一部を構\ 成するものではない,3)甲1発明において,分岐開閉器は協約形ブレー カであり,取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であるから,「分 岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」を本件発明の回路遮断器とみ なすことはできないなどとして,甲1発明の「分岐開閉器4を取り付け た取り付け部材5」は,本件発明の「回路遮断器」に相当するものとい えない旨主張する。
しかしながら,前記(1)イ認定の甲1の開示事項によれば,甲1には, 「本発明」は,差し込み式の分岐開閉器の取り付けがしやすく,しかも 取り付けた後の分岐開閉器が外れにくい分電盤を提供することを課題と し,本件審決認定の甲1発明は,「請求項4の分電盤」に係る構成を採\n用することにより,分岐開閉器の接続端子が導電バーから外れる方向に 取り付け部材が移動するのを抑えることができ,分岐開閉器を強固に固 定できるという効果を奏するとともに,「請求項5の分電盤」に係る構\n成を採用することにより,弾性体を変形させることにより取り付け部材 をベースから外すことができ,分岐開閉器の交換作業が容易にできると いう効果を奏することが開示されているものと認められることに照らす と,甲1発明は,取り付け部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り 付ける場合に生じる問題のみを課題としたものとはいえない。 次に,甲1には,分岐開閉器の一定の寸法に限定することを示す記載 や導電バーを分岐開閉器の寸法に合わせた位置に配置することができな いことを示す記載はなく,取り付け部材が,所定形状の分岐開閉器を導 電バーの異なる高さに合わせるためのスペーサとして機能することを示\nす記載はない。また,前記(ア)認定のとおり,「分岐開閉器4を取り付 けた取り付け部材5」における取り付け部材5は,分岐開閉器4と別部 材であるが,分岐開閉器4と一体化された分岐開閉器4の取付機構とし\nての機能を有するものであるから,取り付け部材5が別部材であること\nは,「分岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」が本件発明の「回路 遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 さらに,甲1には,甲1発明において分岐開閉器は協約形ブレーカで あり,取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であることについて の記載はないし,また,仮に分岐開閉器と取り付け部材がそのような関 係にあるからといって,「分岐開閉器4を取り付けた取り付け部材5」 が本件発明の「回路遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ 以上のとおり,本件審決における相違点4の容易想到性の判断(1)には誤 りがある。
(4) 相違点4の容易想到性の判断(2)の誤りの有無について
原告は,1)甲1及び2に接した当業者においては,甲1発明及び甲2発明 は技術分野,課題及び作用・機能において共通すること,甲1発明において\nは,プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際 においては,板ばねの先端部25aが底面から突出しない状態に維持(ロッ クを外した状態に維持)させなければならないという課題があることを認識 するといえるから,甲1発明において,この課題を解決し,分岐開閉器の取 り外しを容易にするために,甲1発明の板ばねに係る構成部分に甲2発明の\n係止アーム及び操作用取手(ロックを外した状態を維持できる構造)を適用\nすることを試みる動機付けがあるといえる,2)甲1発明に甲2発明を適用す るに当たっては,甲2に記載された機器の底面から突出することによって機 器のスライドを防止するための部材を,突出する状態と突出しない状態のそ れぞれにおいて択一的に選択「保持」可能な構\成とするという技術的思想を 甲1発明に適用すれば足りるものであり,例えば,別紙原告主張書面記載の 図1ないし図5に示した構成が考えられ,甲2に記載された選択保持可能\と いう技術的思想を甲1発明に適用することは可能であり,かつ,その適用に\nおいて特段の技術的困難はない,3)そうすると,甲1及び甲2に接した当業 者は,甲1発明において,プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉 器をスライドさせる際に,板ばねの先端部25aが底面から突出しない状態 に維持(ロックを外した状態に維持)させなければならないという課題があ ることを認識し,この課題を解決し,分岐開閉器の取り外しを容易にするた めに,甲1発明の板ばねに係る構成部分に甲2発明の係止アーム及び操作用\n取手(ロックを外した状態を維持できる構造)を適用し,相違点4に係る本\n件訂正発明の構成(本件訂正発明におけるレバーは,「前記突出部が回路遮\n断器の取付面から突出しない状態で保持されるように構成され」る構\成)と することを容易に想到することができたものである旨主張する。
ア しかしながら,甲1には,甲1発明の板ばねの係止が解除された状態(上 方に撓んだ状態)で保持されることについての記載や示唆はない。また, 甲1の【0014】の記載によれば,甲1発明においては,取り付け部材 5の側片5bの下面から板ばね25が自動的に突出してベース2の係止 孔24に係止することにより取り外し方向の規制が行われるから,取り外 し方向の規制を行う際に,規制部材を突出した位置に保持する必要もない。 そうすると,甲1発明において,甲2発明の構造を適用して,機器の底\n面から突出して機器のスライドを防止するための部材を,操作用取手を用 いることで突出する状態と突出しない状態のそれぞれにおいて択一的に 選択保持可能な構\成とするという動機付けがあるものと認めることはで きない。
イ また,仮に原告が主張するように甲1発明において,プラグコネクタの 接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際においては,板ばね の先端部25aが底面から突出しない状態に維持(ロックを外した状態に 維持)させなければならないという課題があることを認識し,当業者が, 甲1発明において,甲2発明の係止アーム及び操作用取手(ロックを外し た状態を維持できる構造)の構\成を適用することを検討しようとしたとし ても,具体的にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできない というべきであるから,結局,甲1発明に甲2発明の上記構成を適用する\n動機付けがあるものと認めることはできない。 この点に関し,原告は,甲1発明に甲2発明の上記構成を適用する具体\n例として,別紙原告主張図面の図1ないし5で示した構成が考えられる旨\n主張するが,板ばねや分岐開閉器のような小さな部材にさらに操作用取手 や突起等を設け,その精度を保つ構造とすることを想起することが容易で\nあったものとは考え難い。
ウ 以上によれば,甲1発明における板ばねに係る構成部分に,甲2に記載\nされた発明の係止アーム及び操作用取手(ロックを外した状態を維持でき る構造)を適用する動機付けがあるものと認めることはできないから,本\n件審決における相違点3の容易想到性(2)の判断に誤りはない。 したがって,原告の前記主張は理由がない。
(5) 小括
以上のとおり,本件審決における相違点4の容易想到性(1)の判断に誤りは あるが,相違点4の容易相当性(2)の判断について誤りはないから,その余の 点について判断するまでもなく,本件訂正発明は,甲1発明及び甲2発明に 基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはでき ない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2020.08.12
令和2(行コ)10002 特許権 行政訴訟 令和2年7月22日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許権者はA弁理士に無効審判の代理と、年金管理を委任していましたが、途中で前者は別の弁理士に変更されました。無効審判は請求人との間で取り下げられましたが、年金を納めていなかったため、特許が消滅したという案件です。
控訴人らは,1)特許庁は,年金管理事務を年金管理サービス会社などに外 部委託することを推奨し,特許権者は,年金管理サービス会社に年金管理を 委託し,相応の対価を支払うことで,自社で年金管理を行うことから解放さ れ,年金管理サービス会社からの期限通知に対し,権利維持の意思表示を行\nうのみで年金納付手続がされているという年金管理の運用実態に鑑みれば, 特許権者は,年金管理サービス会社に年金管理を委任した時点で,特許料の 納付期限の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたと解すべきである, 2)控訴人中井紙器は,A弁理士に対し,本件特許権を含む多くの特許権の年 金管理を委任し,本件特許権の第4年分の特許料についても,A弁理士から の「年金通知のご案内」という納付期限が近付いている旨の通知を受け, 納付手数料,印書代,電子化情報処理料といった年金管理費用をA弁理士に 支払うことが予定されており,本件特許権の第4年分の特許料の納付期限で\nある平成28年1月18日及び本件追納期間の末日である同年7月19日の 時点において,本件年金管理はA弁理士に委任されたままの状態であったか ら,控訴人中井紙器は,A弁理士に本件年金管理を委任したことにより,相 当な注意を尽くしたものといえるとして,控訴人中井紙器が本件追納期間内 に本件特許料等を納付することができなかったことについて「正当な理由」 (法112条の2第 1 項)がある旨主張する。
ア そこで検討するに,前記第2の2の前提事実によれば,1)控訴人中井紙 器は,本件特許権の設定登録がされた平成25年1月18日ころまでに, A弁理士に対し,本件特許権の第4年分以降の特許料の納付管理(本件年 金管理)を委任したこと,2)A弁理士は,平成27年6月1日,控訴人中 井紙器のX1会長から,口頭で,本件無効審判に係る手続の代理人を解任 する趣旨の告知を受けた後,控訴人中井紙器に対し,同日付けで本件無効 審判に係る手続の委任を解除した旨の書面の提出を求める旨の甲3の書面 を送付し,控訴人中井紙器は,A弁理士に対し,同日付けで本件無効審判 に係る委任を解除したことに相違ない旨の甲2の書面を送付したこと,3) A弁理士は,X1会長から上記告知を受けたころ,A弁理士の事務所で特 許料の納付管理事務に従事していた担当者に対し,本件年金管理の事務を しなくてよい旨の指示をするとともに,控訴人中井紙器の本件特許権以外 の権利については今後も特許料の納付管理事務を行うよう指示をしたこと, 4)本件特許権の第4年分の特許料の納付期限の平成28年1月18日及び 本件追納期間の末日の同年7月19日が経過するまでの間,A弁理士は, 控訴人中井紙器に対し,上記納付期限の案内や本件追納期間に関する連絡 を行わなかったことが認められる。上記認定事実によれば,控訴人中井紙 器から本件年金管理に係る事務の委任により,その代理人となったA弁理 士は,控訴人中井紙器から本件無効審判に係る手続の委任の解除の告知を 受けた際に,本件年金管理に係る委任も解除されたものと認識したことが 認められる。
しかるところ,先に説示したとおり,特許権者が特許料の納付管理又は 納付手続を代理人に委任している場合は,法律関係の形成に影響を及ぼす べき主観的態様は原則として代理人の主観的態様に従って判断されるべき であり(民法101条参照),法112条の2第1項に規定する「正当な 理由」の有無についても,原則として原特許権者の代理人について決する のが相当であると解されるから,控訴人ら主張の年金管理の運用実態を勘 案しても,特許権者が年金管理サービス会社に年金管理を委任した時点で, 特許料の納付期限の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたというこ とはできない。
したがって,控訴人中井紙器がA弁理士に本件年金管理を委任した時点 で控訴人中井紙器が本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽 くしたものと認めることはできない。
イ 次に,A弁理士は,控訴人中井紙器の代理人として,本件特許権の第4 年分の特許料の不納付及び本件追納期間の徒過により本件特許権が遡って 消滅したものとみなされる効果が生じることを認識し,又は認識すべきで あったことに照らすと,前記アのとおり本件年金管理に係る委任が解除さ れたものと認識したとしても,控訴人中井紙器に対し,自らの認識と控訴 人中井紙器の認識に齟齬がないかどうかを確認し,あるいは控訴人中井紙 器が本件特許権の第4年分の特許料の納付期限を明確に把握しているかど うかを控訴人中井紙器に確認するなど本件追納期間の徒過を回避するため に必要な措置をとるべきであったものと解される。そして,本件において は,A弁理士がかかる措置をとったことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,控訴人らが主張するように控訴人中井紙器とA弁理士との 間の本件年金管理の事務の委任契約が本件追納期間中も存続していたとし ても,A弁理士は控訴人中井紙器の代理人として本件追納期間の徒過を回 避するために相当な注意を尽くしたものと認めることはできない。 加えて,前記認定(原判決15頁9行目から21行目まで)のとおり, 控訴人中井紙器においては,本件追納期間内に締結した本件和解契約によ り,本件特許権の一部(持分)を控訴人グラセルに譲渡するに当たり,本 件特許権の第4年分の特許料が納付期限までに納付されているかどうかを 確認し,その納付が未了である場合には本件追納期間内に本件特許料等を 納付すべき取引上の注意義務を負っていたのであるから,自ら又はA弁理 士を通じて上記納付の有無について必要な調査・確認を行うべきであった にもかかわらず,かかる調査・確認を行っていないことに照らすと,控訴 人中井紙器自らも本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽く したものと認めることはできない。
ウ 以上によれば,本件特許権を共有していた原特許権者である控訴人中井 紙器が本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたにもか かわらず,客観的な事情により本件追納期間内に本件特許料等を納付する ことができなかったものと認めることはできないから,控訴人中井紙器が 本件追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについ て「正当な理由」(法112条の2第1項)があるということはできない。 したがって,控訴人らの前記主張は理由がない。
◆判決本文
原審はこちら
2020.08.12
令和1(行ケ)10129 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月29日 知的財産高等裁判所
原告は,甲1発明には,隙間1,2が存在し,隙間1,2は,甲1発明 において,本件発明1にいう「開口」に相当する部分(ボンベ装填部8の背面部の 開放された部分)の一部をなしているから,甲1発明は,「専用小型ガスボンベ2 A」を器具本体にセットしたときに「上記開口を含む空気導入口」を備えており, 仮に,隙間1,2が本件発明1いう「開口」に含まれないものであるとしても,隙 間1,2は,外部からボンベ装填部8の内部に空気を導入する機能を有するから,\n本件発明1と甲1発明が同一である旨主張する(原告の主張1)ので,まず,この 点について判断する。
a 前記1(2)で認定したとおり,本件発明は,小型ガス容器を器具本体 にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を,空気導入口 として活用し,そのような開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入する空冷機構を備えることで,ガス器具の小型化に伴う発熱の問題を解決し,標準型ガ\nス容器によるガス器具とほぼ同等の熱量を発生可能で,熱害の心配のない安全性の\n高い小型ガス器具を提供するというものである。 また,本件明細書の【発明の実施の形態】には「・・・上記の開口27を,器具 本体10内へ空気を導入する空気導入口28としても利用し,冷却性能を向上させ\nるための空冷機構を構\成する。・・・小型ガス器具では,その分冷却性能の向上を図\nることが好ましいのに対して,前記の開口27を空冷機構の一部として活用するこ\nとができるという特徴を発揮する。」(段落【0017】),「・・・後部開口27や小開口29よりなる空気導入口28から流入する多量の空気が排出部32へ抜け る・・・」(段落【0023】)との記載がある。 以上からすると,標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口を,小型 ガス容器を器具本体にセットしたときには,空気導入口として活用し,器具本体内 に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能\の向上を図るというのが本件発明の技術 思想であると認められる。そうすると,本件発明にいう「開口」とは,小型ガス容 器を器具本体にセットしたときに,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷\n却性能を向上させるような「空気導入口」として機能\し得る程度のものである必要 があるというべきである。
b 上記aを踏まえて,甲1について検討するに,確かに甲1の【図6】 や【図8】には,原告の主張する隙間1,2らしきものが記載されている。しかし, 特許公報に添付された図面は,発明の技術内容を理解しやすくするためのものにす ぎず,部材の大きさや位置関係が正確に記載されているとは限らないものであると ころ,甲1の【発明の詳細な説明】には,カバー部材5・仕切板9と背面カバー材6又は背面カバー部材31との間に隙間1,2を設けることを明示又は示唆する記載は,全く存在しない。 特に,隙間2に関しては,甲1の段落【0037】の「・・・背面カバー部材3 1には,その両側縁に係合凸部32が形成されており,この係合凸部32が仕切板 9及びシャーシ3に立設した図示しない支持柱部材とに形成した高さ方向の係合溝 に相対係合される。」との記載及び【図8】からすると,被告が主張するように係合 凸部32と図示されていない支持柱部材に形成された係合溝により,ボンベ装填部 8の背面部が閉塞され,隙間2は生じないとも考えられる。 そうすると,甲1の【図6】及び【図8】から直ちに原告が主張するような隙間 1,2の存在を認めることはできないというべきであるから,原告の主張1はその 点からして採用することができない。
c 仮に,甲1の【図6】や【図8】から隙間1,2の存在が認められ るとしても,甲1には,隙間1,2から空気を導入して冷却性能の向上を図るとい\nう技術思想については全く記載も示唆もない上,【図6】や【図8】に描かれた隙間 1,2はいずれもごく小さいものであるから,それらに接した当業者が,隙間1, 2から空気を導入することで,器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性\n能の向上を図ることができると認識すると認めることはできない。したがって,隙\n間1,2が,原告が主張する本件発明1にいう「開口」に相当する部分(甲1発明 におけるボンベ装填部8の背面部における開放された部分)に含まれるかどうかに かかわらず,原告の主張1を採用することはできない。
(イ) 原告は,甲1発明は,ボンベ装填部8の背面側を開放するという使用形態が可能な機械的構\成を備えているから,本件発明1と甲1発明は同一又は実質的に同一であると主張する(原告の主張2)。 しかし,前記アの甲1の記載事項からすると,甲1発明には,標準型ガス容器を 器具本体にセットするときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口 を,小型ガス容器を器具本体にセットした際に空気導入口として活用し,器具本体 内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能\の向上を図るという技術思想は存在せ ず,かえって,甲1発明では,専用小型ガスボンベ2Aの使用中にボンベ装填部8 の背面部を閉塞するために,敢えて部品点数を増やしてまで背面カバー部材6又は 背面カバー部材31を設けている(甲1の段落【0019】,【0025】〜【00 28】,【0034】,【0037】,【0038】)のであり,甲1には,専用小型ガスボンベ2Aの使用中に背面カバー部材を開放することについては何ら記載されてお らず,そのことは全く想定されていないというべきである。このことは,甲1にお いて,背面カバー部材6にトーションスプリング等を使わない態様が記載されてい るとしても変わるものではない。 また,甲1発明のうち,背面カバー部材6がシャーシ3に取り付けられている実 施形態の場合,背面カバー部材6を開放すると,背面カバー部材6分だけガスコン ロ装置の設置スペースが増大することになり,大きな設置スペースを必要としない 小型のガスコンロ装置を提供するという甲1発明の目的(甲1の段落【0005】 〜【0008】)とも反することになる。 そうすると,甲1発明が,ボンベ装填部8の背面側を開放するという使用形態が 可能な機械的構\成を備えているとしても,そのことをもって,本件発明1と甲1発 明が同一又は実質的に同一であるということはできず,原告の主張2は採用するこ とができない。このことは,ボンベ装填部8の背面側を開放するという使用形態が 周知・慣用技術であったとしても変わるものではない。
(ウ) 以上の検討及び弁論の全趣旨からすると,本件発明1と甲1発明と の間には,審決が認定した前記第2の3(2)イ記載の一致点及び相違点1があるこ とが認められる上,相違点1は実質的な相違点であって,本件発明1と甲1発明は 同一又は実質的に同一とはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.08. 7
令和1(行ケ)10068 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月15日 知的財産高等裁判所
前記(ア)からすると,甲3発明は,「マウント1及びLEDユニット2からなり, マウント1はLEDユニット2を収容する凹部10aを備えるLED照明装置A1 において,LEDユニット2が複数のLEDモジュール20,支持部材3及び電力 変換部5を備え,コの字状とされた支持部材3に電力変換部5を収容する照明器具」 というもので,天井からの突出量を低減することによって室内がスマートであると の印象を与え得るLED照明装置を提供するものであると認められる。
イ 甲2発明に甲3発明を適用して,点灯装置を器具本体側ではなく,光源 ユニット側へと配置するように変更する動機付けがあるかどうかについて判断する。 前記(1)イのとおり,甲2発明は,器具本体に設けられた収容凹部に点灯装置を配 置することで,点灯装置を効率的に配置するという課題を解決したことに技術的意 義がある発明であるが,点灯装置を光源ユニット側に配置することは,配置可能な\n点灯装置のサイズ(幅方向の長さ)が取付部材21の取付面21a の長さ程度のも のとなってしまい,収容凹部の収容スペースを有効に活用できなくなるから,甲2 発明の課題解決手段と相容れないものである。 また,甲2の段落【0024】の「・・・点灯装置3は,箱状のケース内に回路 基板及びこの基板に実装された回路部品を収容して構成されており,商用交流電源\nACに接続されていて,この交流電源ACを受けて直流出力を生成するものである。 点灯装置3は,例えば,全波整流回路の出力端子間に平滑コンデンサを接続し,こ の平滑コンデンサに直流電圧変換回路及び電流検出手段を接続して構成されてい\nる。・・・」との記載からすると,甲2発明の点灯装置は,複数の部品から構成され\nる一定の重量のある部材であると認められ,甲2発明では,器具本体側にそのよう な重量のある点灯装置を配置することを前提として,光源ユニットは,簡易な係止 部材で取り付けられているが,仮に点灯装置を光源ユニット側に配置するとした場 合,器具本体と光源ユニットの係止機構を中心として甲2発明全体の構\造を再検討 する必要がある。 したがって,甲3発明を甲2発明に適用する動機付けがあるとは認められない。
ウ 原告は,1)甲2発明と甲3発明が課題や課題解決手段を共通にしている, 2)器具本体と光源ユニットが分離されるLED照明器具にあって,光源ユニット側 に甲2発明の点灯装置のような電源装置を配置することは周知慣用技術であり,点 灯装置を光源ユニットに配置することに伴う設計変更は当業者にとって通常の創作 力の範囲内の設計事項であると主張する。
(ア) 上記1)について
前記ア(ア)のとおり,甲3発明は,本件発明1と同様に天井からの突出量の低減を 課題としているものと認められる。他方,甲2発明の課題は,前記(1)イのとおり, 施工作業の省力化と点灯装置等の部品の効率的な配置である上,甲2からは甲3発 明にあるような天井からの突出量の低減という技術思想を読み取ることはできず, 甲2発明と甲3発明とが課題を共通にしているとはいえず,原告の主張はその前提 を欠くものである。 この点について,原告は,かさばる部材である点灯装置(甲3発明の電力変換部) の効率的な配置という限度で甲2発明と甲3発明が課題を共通にしている旨主張す るが,発明の課題をあまりに抽象化して捉えており,相当ではないので,採用する ことができない。
(イ) 上記2)について
証拠(甲1の12・13,甲3〜5)によると,審決が認定したとおり,「光源 としてLEDを用いた照明器具において,光源ユニット側に電源装置を配置する」 ことは本件出願日当時,周知慣用技術(周知慣用技術1)であったと認められる。 しかし,前記イのとおり,甲2発明において,点灯装置を光源ユニット側に配置 することは甲2発明の技術的意義を没却するものである上,甲2発明の構造を大き\nく変える必要があるから,当業者の通常の創作力の範囲内の設計事項であるという ことはできない。
この点について,原告は,甲2発明の「収容凹部」において,電源装置を光源ユ ニット側に取付配置した場合でも,器具本体側に取付配置した場合でも,発明の目 的とした照明器具全体での高さ寸法,天井からの突出量は変わらないと主張するが, 直ちにそのように認めることはできないのみならず,仮にそうであるとしても,上 記で述べた理由により,甲2発明において,点灯装置を光源ユニット側に配置する ことが当業者の通常の創作力の範囲内の設計事項であるとはいえない。 また,原告は甲2発明の係止部材の構造等は特定されておらず,甲3発明の係止\n機構は,甲2発明の係止部材と同様に簡易なものであると主張するが,甲2発明に\nおいて,「係止部材4」は,「取付部材21」,「発光素子22」,「基板23」及び「カバー部材24」からなる光源部を係合保持するものである(甲2の段落【0023】,【0027】,【0028】,【図3】,【図4】)が,甲3発明の係止機構であるホルダ11は,LEDモジュール20,支持部材3,カバー4及び重量のある電力変換部\n5からなるLEDユニット2を保持するもの(甲3の段落【0026】,【0027】,【図2】,【図4】)であり,甲2発明の係止部材の方が,甲4発明のホルダより簡易 なものであれば足りることはその役割から明らかであるから,甲2発明において, 点灯装置を光源ユニット側に配置することが当業者の通常の創作力の範囲内の設計 事項であるとはいえない。
(4) 小括
以上のとおり,相違点について,甲2発明に甲3発明を適用する動機付けがある とは認められないから,阻害事由の点について判断するまでもなく,本件発明1は, 甲2発明及び甲3発明又は周知慣用技術1から容易想到なものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.08. 7
令和2(行ケ)10006 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年7月29日 知的財産高等裁判所
(1) 証拠(乙13〜28)によると,1) 「宮下孝洋」という者が2018年 12月版(掲載情報は同年9月5日現在)及び2016年12月版(掲載情報は同 年9月7日現在)の「ハローページ(新潟県上越版)」に,2) 「宮下隆寛」という 者が2019年3月版(掲載情報は2018年11月28日現在)及び2017年 3月版(掲載情報は2016年12月1日現在)の「ハローページ(長野県飯田版)」 に,3) 「宮下貴博」という者が2019年3月版(掲載情報は2018年11月 28日現在)及び2017年3月版(掲載情報は2016年12月1日現在)の「ハ ローページ(長野県松本版)」に,4) 「宮下孝弘」という者が2019年3月版(掲 載情報は2018年11月28日現在)及び2017年3月版(掲載情報は201 6年12月1日現在)の「ハローページ(長野県木曽版)」に,5) 「宮下高広」と いう者が2019年9月版(掲載情報は同年6月3日現在)及び2017年9月版 (掲載情報は同年6月5日現在)の「ハローページ(長野県長野版)」に,6) 「宮 下高弘」という者と「宮下貴浩」という者がそれぞれ2019年9月版(掲載情報 は同年6月3日現在)及び2017年9月版(掲載情報は同年6月5日現在)の「ハ ローページ(長野県上田版)」に,7) 「宮下孝弘」という者が2019年2月版(掲 載情報は2018年11月1日現在)及び2017年2月版(掲載情報は2016 年11月1日現在)の「ハローページ(小平・西東京・東村山市版)」に,8) 「宮 下貴博」という者が2018年11月版(掲載情報は同年7月26日現在)及び2 016年11月版(掲載情報は同年8月3日現在)の「ハローページ(川崎市川崎・ 幸・中原区版)」に,それぞれ掲載されていることが認められ,上記各事実からする と,上記の者は,いずれも本願商標の登録出願時から本件審決時まで現存している ものと推認できる。そして,上記の者は,いずれもその氏名の読みを「ミヤシタタ カヒロ」とすると考えられる。その他,ウェブページ(乙7,8,10,11,2 9〜32)からも,氏名の読みを「ミヤシタタカヒロ」とする「宮下貴博」,「宮 下敬宏」,「宮下孝洋」,「宮下孝広」又は「宮下貴浩」という者及び氏名の読み を「ミヤシタタカヒロ」とすると考えられる「宮下隆裕」又は「宮下隆博」という 者が存することが認められ,これらの者も,本願商標の登録出願時から本件審決時 まで現存しているものと推認できる。 弁論の全趣旨によると,上記の者は,いずれも原告とは他人であると認められる から,本願商標は,その構成のうちに「他人の氏名」を含む商標であって,かつ,\n上記他人の承諾を得ているとは認められない。 したがって,本願商標は,商標法4条1項8号に該当する。
(2)ア これに対し,原告は,商標法4条1項8号の「他人」については,承諾 を得ないことにより人格権の毀損が客観的に認められるに足りる程度の著名性・希 少性等を必要とすると解すべきであると主張する。 しかし,商標法4条1項8号は,自らの承諾なしに,その氏名,名称等を商標に 使われることがないという人格的利益を保護するものである(最高裁平成15年(行 ヒ)第265号同16年6月8日第三小法廷判決・裁判集民事214号373頁, 最高裁平成16年(行ヒ)第343号同17年7月22日第二小法廷判決・裁判集 民事217号595頁参照)ところ,その規定上,「雅号」,「芸名」,「筆名」 及び「略称」については,「著名な」という限定が付されている一方で,「他人の 氏名」及び「名称」についてはそのような限定が付されていない。同号は,氏名及 び名称については著名でなくとも当然にその主体である他人を指すと認識されるこ とから,当該他人の氏名や名称の著名性や希少性等を要件とすることなく,当該他 人の人格的利益を保護したものと解される。したがって,原告の上記主張は採用す ることができない。
イ また,原告は,ファッションの分野においては,周知,著名なブランド の使用者に独占排他的権利が認められてしかるべきであると主張し,1) 同程度に 周知,著名性を獲得したブランドであるにもかかわらず,他人の現存の有無といっ た出願人(ブランド使用者)の関与し得ない要素によって承諾の要否や承諾が必要 な数が異なり,登録可能性に差異が生じる旨,2) 氏名をローマ字表記する場合は,\n承諾の対象者が広く,他人の承諾を得ることが困難であるから,氏名のローマ字表\n記が相当珍しいものでない限り,商標登録が事実上不可能となる旨,3) 上記のよ うなブランドに係る商標は,それがファッション分野の商品に使用されると,当該 デザイナーのブランド表示として客観的に把握されるから,同じ読みの氏名の他の\n者を想起,連想させるものではなく,当該他人の人格的利益が毀損されるおそれは ない旨を主張する。 しかし,「他人の氏名」を含む商標について原則として商標登録を受けることが できないとし,「その他人の承諾」を得ている場合をその例外と定める商標法4条 1項8号においては,上記1)及び2)のようなことが一定程度生じることは,予定さ\nれているというほかなく,そのことを直ちに公平でないとか商標法1条の目的に反 するということはできない。また,同号が具体的な人格的利益の侵害又はそのおそ れを要件として定めるものではないことからすると,上記3)のような場合には同号 に該当しないと解することはできない。したがって,原告の上記主張は,前記(1)の 判断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.08. 7
平成31(行ケ)10040 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月2日 知的財産高等裁判所
(ア) 甲1又は甲2の内容中の示唆について
a 甲1及び甲2には,次の(a)及び(b)の事項が開示されているので,以 下,これらが,引用発明において,単層カーボンナノチューブとして 甲2実施例1CNTを適用することの示唆となるか否かについて検討 する。
(a) 引用発明における導電剤としての単層カーボンナノチューブは, 「直径が0.5〜10nmであり,長さが10μm以上であり,炭 素純度が重量基準で99.9%以上である」単層カーボンナノチュ ーブである。一方,上記(2)ア(ア)及び(オ)によれば,甲2実施例1CN Tは引用発明の単層カーボンナノチューブの純度,直径,長さの規 定を満たすものといえる。(以下「事項(a)」という。)
(b)甲2には,上記(2)ア(イ)〜(エ)より,単層カーボンナノチューブの用 途として,導電体,電極材料が挙げられ,甲2の単層カーボンナノ チューブが優れた電子・電気特性を有すること,単層カーボンナノ チューブ・バルク構造体を導電体として使用することも記載されて\nいる。(以下「事項(b)」という。)
b 事項(a)について
甲20,21,23には以下の記載がある(引用に当たり,文意に 影響しない範囲で記載の一部を省略又は変更した。)。 [甲20](ドージンニュース新連載「新しいナノ材料としてのカー ボンナノチューブ−最近の展開(バイオからエネルギーまで)1)」 URL省略,令和元年6月6日検索)
「2.カーボンナノチューブの構造,特性\n
CNTはグラフェンシートを円筒状に丸めた構造をしている。\n円筒が一本のみからなるCNTをSWNTと呼ぶ。SWNTは直 径0.5〜数nmとかなり細いが・・・CNTの合成後の長さは 数十nmから,長いものでは数mmに及ぶものがあり,合成法に\nより様々な長さ分布を持つ混合物として得られる。」(2頁) 「2012年現在,30社以上のメーカーがCNTを製造販売して いる。それぞれ製造法,直径分布,純度,結晶化度等に差があり, 一口にCNTと言っても多様性があることを認識して使わなけれ ばならない。表1に代表\的なCNTメーカー(2012年1月現 在)を挙げた。」(4頁。表1には代表\的なCNTメーカーとし て8社が列挙されている。) [甲21](「雑科学ノート−カーボンナノチューブの話−」URL 省略,令和元年6月6日検索) 「CNTの直径は,これまで書いてきた巻きの強さや層の数によっ ていろいろですが,SWCNTの場合は1〜3nm,MWCNT の場合は10〜20nmぐらいのものが一般的です。髪の毛が5 0〜100μmぐらいですから,その数千分の一から数万分の一, ということですね。長さは,一般的な大量生産品では0.1〜数 十μm程度ですが,基板の上に垂直に成長させる方法では数百μ\nm以上のものも作られています。」(4頁) [甲23](末金皇ら「ブラシ状カーボンナノチューブの高速成長技 術の開発」大陽日酸技報 No.23(2004),URL省略 ) 「CNTは,直径が数nm程度,長さが数μmから数百μmと極め て高いアスペクト比を持つ構造物である。」(8頁左欄13〜1\n5行) 甲20,21,23の上記各記載によれば,本願特許出願当時,単 層カーボンナノチューブの直径や長さは製品によって様々であり,そ の中で,0.5〜10nmの直径,10μm以上の長さは,単層カー ボンナノチューブの直径や長さとしてごく一般的であったと認められ る。そうすると,事項(a)のとおり,甲2実施例1CNTが引用発明の 単層カーボンナノチューブの純度,直径,長さの規定を満たすことが 開示されているからといって,そのことが,多数存在する単層カーボ ンナノチューブから甲2実施例1CNTを選択し,引用発明のカーボ ンナノチューブとして使用することを示唆するものとはいえない。
c 事項(b)について
甲2は,甲2に記載された発明の単層カーボンナノチューブが種々 の技術分野や用途へ応用できることを開示しているが(上記(2)ア(イ)), 電池の電極材料への応用としては,負極の材料として用いることが挙 げられているのみであり(同(エ)),正極の導電助剤として用いること の記載又は示唆はない。また,導電性を生かした応用としては,電子 部品の銅配線に代えて用いることの記載はあるものの(同(ウ)),これ が電池の正極の導電助剤としての応用を示唆するものとはいえない。
d 以上によれば,事項(a)又は事項(b)が,引用発明の導電助剤の単層カ ーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを適用することの示唆 となるとはいえない。そして,他に,甲1又は甲2に,引用発明の導 電助剤の単層カーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを使用 することの示唆となる記載も見当たらない。 以上によれば,甲1及び2のいずれにも,引用発明の導電助剤の単 層カーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを使用することの 示唆はない。
(イ) 技術分野の関連性について
引用発明は,リチウムイオン二次電池正極用導電剤を用いたリチウム イオン二次電池の技術分野に属するものである【0001】。一方,甲 2に開示された発明は,導電体,電極材料,電池等の技術分野に属する ものである(上記(2)ア(イ)〜(エ))。 そうすると,両発明は,導電体,電極材料または電池という限りにお いて,関連する技術分野に属するといえるにとどまる。
(ウ) 課題の共通性について
引用発明は,正極に混合する導電剤の量を低減して,リチウムイオン 二次電池を大容量化し,かつ,高出力におけるリチウムイオン二次電池 容量の劣化を抑制することを課題とする【0012】。一方,甲2に開 示された発明は,従来にみられない高純度,高比表面積のカーボンナノ\nチューブ(特に配向した単層カーボンナノチューブ・バルク構造体)を\n提供することを課題とする(上記(2)ア(ア))。 よって,両発明の課題は共通しない。
(エ) 作用・機能の共通性について\n
引用発明において,単層カーボンナノチューブは,リチウムイオン二 次電池正極用の導電剤として用いられ,ここで,導電剤は,導電性の低 い正極活物質に混合することにより電池の容量を大きくすることができ るという作用・機能を有する【0003】。一方,甲2に開示された発\n明の単層カーボンナノチューブは,導電体,電極材料,電池等の用途に 用いられるものであるところ(上記(2)ア(イ)及び(エ)),導電体として使用 される際には,配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として,\n電子部品の縦配線,横配線に代えることにより微細化,安定化を図ると いう作用・機能を有し(同(ウ)),電極材料として使用される際には,配 向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として,リチウム二次電池\nの電極材料,燃料電池や空気電池等の電極(負極)材料という作用・機 能を有するが(同(エ)),いずれの作用・機能も,導電性の低い正極活物\n質に混合することにより電池の容量を大きくすることができるという作 用・機能には当たらない。\nよって,両発明の作用・機能が共通しているとはいえない。\n
(オ) 以上のとおり,甲1及び甲2には,引用発明において,導電助剤とし て用いるカーボンナノチューブとして甲2実施例1CNTを適用するこ とを動機付ける記載又は示唆を見出すことができない。 ウ 上記イのとおり,主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に想到す ることを動機付ける記載又は示唆を見出せない以上,上記アに説示したと ころに照らして,かかる想到を阻害する事由の有無や,本願発明の効果の 顕著性・格別性について検討するまでもなく,その想到が容易であるとし た審決の判断には誤りがある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.08. 7
令和1(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月2日 知的財産高等裁判所
原告は,アンチローリングタンクが,「浸水防止部屋」に相当する旨主 張するのに対し,被告は,「浸水防止部屋」とは,損傷を受けた場合に浸 水する「空間」であって,主として「浸水防止」を企図した「空間」であ ると解すべきところ,アンチローリングタンクは,主として「浸水防止」 を企図した「空間」ではないから,本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該 当しない旨主張する。また,本件審決は,「浸水防止部屋」は,損傷を受 けた場合に浸水する「空間」であり,専ら「浸水防止」を企図した「空間」 であると解すべきであるところ,甲4発明のアンチローリングタンクは, 専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから,本件訂正 発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして,本件訂正発明と甲4発明 との対比等を行うことなく,進歩性違反の無効理由は成立しないと判断し た。
ウ 「浸水防止部屋」の意義
(ア) 特許請求の範囲の記載によれば,本件訂正発明1の「浸水防止部屋」 は,側壁及び隔壁に接すること,仕切板により形成されること,機関区 域に設けられること,側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり側壁が 損傷した場合浸水することなどが特定されているものの,「専ら」ある いは「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。な お,当業者の技術常識として,「空間」とは,「空所」や「ボイド」と は異なり,必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ, このことは「下層空間13の船尾側に推進用エンジン14が配置されて いる」(段落【0022】)などの本件明細書の記載とも整合する。し たがって,「空間」であることから,直ちに「専ら」あるいは「主に」 浸水防止を企図していることは導けない。また,SOLAS条約によれ ば,浸水率の計算において,タンクは,0または0.95のいずれかよ りリスクが高くなるケースを用いて計算すべきとされており,タンクで あってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることとな るから,「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が,必ずし もタンクを排除するものとはいえない。
次に,本件発明の課題及び解決手段は,前記のとおり,浸水防止部屋 を設けて,側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても,浸水防止部屋が 浸水するだけで,浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないよう にすることで,浸水区画が過大となることを防止し,設計の自由度を拡 大することを目的とするものである。そうだとすれば,「浸水防止部屋」 は,それに面する側壁が損傷し浸水しても,それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密構造となっていれば,浸水区画が過大となることを防止するという本件発明の目的にかなうのであって,タンク等の他\nの機能を兼ねることが,当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない(被告は,タンクが浸水すると,タンク本来の機能\を果たせなくなったり,環境汚染につながったりするから,タンクと「浸水防止部屋」は 両立しえないと主張するが,本件発明は,「浸水防止部屋」を意図的に 浸水(損傷)しやすくするわけではないから,上記認定は左右されない。)。 かえって,実願昭49−19748号(実開昭50−111892号) のマイクロフィルム(甲17)には,別紙5に示す第1図及び「本考案 は,横置隔壁2の船側部両端に,船側外板1を一面とした高さ方向に細 長い浸水阻止用の区画7を備えているから,横隔壁数を増加しなくても, 船側外板1の損傷による船内への浸水を該区画7内に,または該区画7 と隣接する1つの船内区画内にとどめることができ」(4頁下から7〜 1行)との記載があり,本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する「空間7」を有する船舶の発明が開示されているところ,同文献には,\n「該区画7を小槽として利用することもできる。」(5頁7行)とも記 載されているから,浸水防止を目的とした区画を,小槽(タンク)とし て利用することは,公知であったと認められる。また,「浸水防止部屋」 が他の機能を兼ねることを許容する方が,設計の自由度が拡大し,その意味で本件発明の目的に資するものである。\n以上によれば,「浸水防止部屋」とは,それに面する側壁が損傷し浸 水しても,それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当である。\n
(イ) 被告は,本件明細書の段落【0004】を根拠に,本件明細書では, タンクと浸水防止部屋は区別されている旨主張する。 しかし,段落【0004】は,ボイドスペースを海水バラストタンク として機能させるという従来技術が記載されているにとどまり,タンクと浸水防止部屋を比較して記載しているものではないから,前記「浸水\n防止部屋」の解釈を左右するものではない。
エ アンチローリングタンクについて
甲4発明のアンチローリングタンクは,タンクであって液体を貯留する ものであるから,それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の 構造となっている可能\性がある。 しかるに,本件審決は,アンチローリングタンクが,専ら浸水防止を企 図した空間ではないとの理由のみから,これが浸水防止部屋に該当せず, 無効理由2−2は成立しないと判断したものであるから,本件審決の判断 には誤りがあり,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。 なお,原告は,本件訂正発明3,4については,無効理由2−2が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
(2) 甲6発明を主引例とする無効理由(無効理由2−3)について
ア 甲6文献の記載
甲6文献の55頁から61頁は,「2基2軸CPP装備・船尾双胴型旅 客船兼自動車航送船“3号はやぶさ”の概要」と題する文章であり,57 頁19〜28行の下記の記載のほか,「共栄運輸向け旅客船兼自動車航送 船“3号はやぶさ”」の一般配置図(別紙3【甲6図面】参照)が示され ている。
「(9)トリム及びヒール調整装置
本装置は車輌乗降時の岸壁と舷外ランプの高さを保つため,船首トリミ ングタンク(F.P.T.,No.1W.B.T.(C),No.2W.B.T.(C),No.3W.B.T.(C)) 及び船尾トリミングタンク(No.4W.B.T.(C)&No.4W.B.T.(P/S))を利用し て船体のトリムを調整し易いように配管されており,船橋操縦盤に組み 込みのタッチパネル式監視制御コンソールによりポンプ,弁の遠隔操作が出来るようになっている。」\n
イ 本件審決は,船尾トリミングタンクが,専ら「浸水防止」を企図した「空 間」であるとはいえず,「浸水防止部屋」に相当しないと判断したが,か かる浸水防止部屋の解釈が誤りであることは,前記(1)と同様である。 よって,本件審決の判断には誤りがあり,その誤りは審決の結論に影響 を及ぼすものである。 なお,原告は,本件訂正発明3,4については,無効理由2−3が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2020.08. 7
平成30(行ケ)10159等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月2日 知的財産高等裁判所
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に 記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説 明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出 願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるか否かを検討して判断すべきである。 そして,サポート要件を充足するには,明細書に接した当業者が,特許請 求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り,また, 課題の解決についても,当業者において,技術常識も踏まえて課題が解決で きるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであ って,厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。 なぜなら,まず,サポート要件は,発明の公開の代償として独占権を与える という特許制度の本質に由来するものであるから,明細書に接した当業者が 当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することが できれば,サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり, また,明細書が,先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものである ことも考慮すれば,その記載内容が,科学論文において要求されるほどの厳 密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。
(2) 本件化合物発明の課題について
本件明細書の記載によれば,本件化合物発明が解決しようとする課題は, 製剤化したときに安定な医薬となり得て,また,水性媒体への溶解でボロン 酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物(凍結乾燥粉末の形 態のBME)を提供することである。そして,この課題が解決されたといえ るためには,凍結乾燥粉末の状態のBMEが相当量生成したこと,並びに当 該BMEが保存安定性,溶解容易性及び加水分解容易性を有することが必要 であると解されるから,これらの点が,上記(1)で説示したような意味におい て本件明細書に記載又は示唆されているといえるかについて検討することと する。なお,ここでいう「相当量」とは,医薬として上記課題の解決手段に なり得る程度の量,という意味である。
(3) 凍結乾燥粉末の状態のBMEが相当量生成したことについて
ア 本件明細書の【0084】には,実施例1として,ボルテゾミブとD− マンニトールとの凍結乾燥製剤の調製方法が開示されている。そして,本 件出願日当時の技術常識に照らすと,同調製方法のように,tert−ブ タノールの比率が高く(相対的に水の比率が低く),過剰のマンニトール を含む混合溶液中で,周辺温度より高い温度で攪拌するという条件の下で は,ボルテゾミブとマンニトールとのエステル化反応が進行し,相当量の BMEが生成すると理解し得る。 また,本件明細書の【0086】には,【0084】記載の方法によっ て調製された実施例1FD製剤は,FAB質量分析により,BMEの形成 を示すm/z=531の強いシグナルを示したこと,このシグナルはボル テゾミブとグリセロール(分析時のマトリックス)付加物のシグナルであ るm/z=441とは異なっており,しかも,m/z=531のシグナル の強度は,m/z=441のシグナルと区別されるほど大きいことが開示 されている。これらの事項からすれば,実施例1FD製剤は,相当量のB MEを含むといえる。 したがって,本件明細書には,凍結乾燥粉末の状態のBMEが相当量生 成したことが記載されていると認められる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは,FAB質量分析においては,ピークの大小をもっ て試料に含まれる物質の存在量の大小を評価できないのであるから,実施 例1の記載から凍結乾燥製剤に相当量のBMEが含まれていることを認識 できない旨主張する。 しかしながら,上記(1)に説示したとおり,サポート要件を充足するため には,厳密な科学的な証明までは必要としないと解されるところ,上記ア の凍結乾燥製剤の調製方法に関する知見(相当量のBMEが生成されてい ると考えられるとする甲60(丙教授の鑑定意見書)及び甲61(丁教授 の意見書)の記載を含む。)や,FAB質量分析により,m/z=531 の強いシグナルが確認されていることに照らせば,当業者は本件化合物発 明の対象物質(凍結乾燥粉末の状態のBME)が相当量生成したと合理的 に認識し得るというべきである。 したがって,請求人ホスピーラの上記主張は,上記アの判断を左右しな い。
(4) 保存安定性について
ア 本件明細書の【0094】〜【0096】には,固体や液体のボルテゾ ミブは,2〜8℃の低温で保存しても,3〜6ヶ月超,6ヶ月超は安定で はなかったのに対して,実施例1FD製剤(上記(3)のとおり相当量のBM Eを含む。)は,5℃,周辺温度,37℃,50℃で,いずれの温度でも, 約18ヶ月間にわたって,薬物の喪失は無く,分解産物も産生しなかった との試験結果が開示されている。この記載によれば,本件明細書には,本 件化合物が,ボルテゾミブに比較して優れた保存安定性を有していること を当業者が認識し得る程度に記載されているといえる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは,本件明細書の【0094】〜【0096】に記載 された保存安定性の向上は,マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾燥 という周知技術の適用により奏されたものと認識することが自然である旨 主張する。
この点,確かに,実施例1FD製剤において,調製に供したボルテゾミ ブの全量がBMEとなっているとは限らず,マンニトールを賦形剤として 凍結乾燥されたボルテゾミブも含まれていると考えられるから,凍結乾燥 されたボルテゾミブの存在が,保存安定性の向上に寄与しているとも考え られるところである。しかしながら,相当量のBMEを含む製剤が保存安 定性を示している以上,BMEも保存安定性の向上に寄与していると考え るのが通常人の認識であるといえるし,これに反して,凍結乾燥されたボ ルテゾミブのみが保存安定性に寄与していると認めるべき事情は見当たら ない。
そうすると,サポート要件の充足のために必要とされる当業者の認識が 上記(1)のようなもので足りる以上,請求人ホスピーラの上記主張は,上記 アの判断を左右しない。
◆判決本文
こちらは同一特許に関する関連事件です。
原告は同じで被告が異なります。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2020.08. 7
令和2(行ケ)10022 商標権 行政訴訟 令和2年7月8日 知的財産高等裁判所
原告は,1)原告の調査結果によれば,インド料理等を提供する店舗におい て,「マハラジャ」の片仮名又は「Maharaja」の英文字を構成に含\nみ,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が14店舗存在したこと(甲9 ないし17,21ないし25),2)2019年に開催されたさいたま市内の 複数のカレー店舗を食べ歩き,各店舗でスタンプを集めて競い合うスタンプ ラリーのイベントの名称は,「さいたマハラジャ2019」であり(甲18), このようなイベントの名称中に「マハラジャ 」の語が採用されたことは,「マ ハラジャ 」の語がインド料理と強い関連性を有する単語であることが広く認 識されていることを示すものといえることからすると,インド料理等を提供 する店舗において,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あ り,「マハラジャ」と称呼され,それによって「大王」の観念が生じる商標 が店名として一般的に使用されているという取引の実情があり,このため需 要者は,かかる商標の外観によって店舗を識別していることに鑑みれば,本 願商標と引用商標1なしい3の類否判断においては,称呼及び観念が共通し ているとしても,外観上の相違が重要であるというべきであり,両者を本願 商標の指定役務「インド料理の提供」等に使用した場合に当該役務の出所混 同のおそれはないから,本願商標が引用商標1なしい3に類似する商標であ るということはできない旨主張する。
ア そこで検討するに,原告提出のインド料理店のウェブページ(甲9ない し17,21ないし25)によれば,大阪市内の「インド料理 マハラジ ャ(Maharaja)」の店名の店舗(甲9),群馬県高崎市内の「イ ンド料理 NEWマハラジャ」の店名の店舗(甲10),静岡県富士市内 の「インド料理 マハラジャダイニング 富士店」の店名の店舗(甲11), 東京都武蔵野市内の「マハラジャ(MAHARAJA)」の店名の店舗(甲 12),山梨県都留市内の「インドレストラン マハラジャ」の店名の店 舗(甲13),京都市内の「マハラジャ」,「MAHARAJA」の店名 の店舗(甲14,19),札幌市内の「スープカレー Maharaja 〜マハラジャ〜」の店名の店舗(甲15),静岡市内の「マハラジャダイ ニング」「MAHARAJA」の店名の店舗(甲16),埼玉県川越市内 の「NEW MAHARAJA KAWAGOE ニューマハラジャ川越」 の店名の店舗(甲17)等「マハラジャ」と称呼される文字を店名に含む 店舗が14店舗存在することが認められる。 しかしながら,他方で,NTTタウンページにおける業種分類「インド 料理店」の2017年(平成29年)の登録件数は2162件であったこ と(乙9)に照らすと,本件審決時において,インド料理店のウェブペー ジに「マハラジャ」と称呼される文字を店名に含む店舗が14店舗存在す るからといってインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称 呼される店名の店舗が全国に多数あり,「マハラジャ」と称呼される商標 が店名として一般的に使用されているという取引の実情があるものと認め ることはできない。 また,2019年(令和元年)9月から11月にかけてさいたま市内で 「さいたマハラジャ2019」との名称の複数のカレー店舗を食べ歩き, 各店舗でスタンプを集めて競い合うスタンプラリーのイベントが開催され たことが認められるが(甲18),このことからインド料理等を提供する 店舗において「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あるこ とを裏付けることはできない。他に原告主張の取引の実情が存在すること を認めるに足りる証拠はない。
イ さらに,仮に原告の主張するようにインド料理等を提供する店舗におい て「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数存在するとしても, 商標の構成文字は絶えず同じ態様で固定して用いるのではなく,使用場面\nに応じて書体や色彩を変更することが普通に行われていることに照らすと, 「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数存在するからいって, 需要者がインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称呼され る店名に係る商標の外観によって店舗を識別している実情があるものとい うことはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.08. 7
令和1(行ケ)10124 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年8月4日 知的財産高等裁判所
以上によれば,甲2文献には,プローブ装置において,1)プローブ装置筺体 内から外に向かってガイドレールを設け,プローブカードを交換する際に,プロー ブカードをガイドレールに沿って引き出すこと,2)プローブ装置本体の上面に被検 査体に対向して載置されたテストヘッドのメンテナンスやパフォーマンスボードの 交換については,テストヘッドをプローブ装置本体から分離して上昇させて別の場 所に移動することが記載され,検査室の内部から整備空間側にテストヘッドを引き 出すことの記載はない。
・・・・
被告は,甲2文献や乙1〜3の記載によれば,メンテナンスの対象物を引き 出してメンテナンスをすること,また,その際に,スライドレールにより引き出す 構成とすることは周知技術であると主張する。\n前記(1)ア及び上記ア(ア)のとおり,引用例及び甲2文献には,プローブ装置におい て,メンテナンスの際に検査室からプローブカードを引き出すこと及びその際ガイ ドレールに沿って引き出す構成とすることの記載がある。しかし,本件原出願の当\n時,テストヘッドの重量は25kgから300kgを超えるものが知られ(本件明 細書【0022】,甲5【0003】・【0043】,甲6【0014】,甲7,乙3【0005】),テストヘッドとプローブカードとは重量や大きさにおいて相違すること は明らかである。したがって,プローブカードに関する上記記載から,テストヘッ ドを含むメンテナンスの対象物一般について,メンテナンスの対象物を引き出して メンテナンスをすること,また,その際に,スライドレールにより引き出す構成と\nすることが周知技術であったということはできない。 また,乙1〜3には,検査室に収容されたテストヘッドの構成は開示されておら\nず,テストヘッドを引き出すものではないから,被告の主張する周知技術を裏付け るものではない。 以上によれば,被告の主張する各文献の記載から,メンテナンスの対象物を引き 出してメンテナンスをすること,また,その際に,スライドレールにより引き出す 構成とすることが周知技術であったということはできず,ほかにこれを認めるに足\nりる証拠はない。
(イ) 被告は,乙3(【0024】)にも記載があるとおり,テストヘッドを引き出 した方が作業性に優れることは自明であるから,メンテナンスの対象物をスライド レールにより引き出してメンテナンスを行う方が,作業が容易であることを動機付 けとして,引用発明において,相違点1に係る構成を想到することは容易であると\n主張する。 しかし,前記ア(イ)cのとおり,乙3はテストヘッドが検査室に収容されたプロー ブ装置を開示するものではなく,同段落の「超重量級のテストヘッドであってもテ ストヘッド4を安全且つ円滑に反転させ,前後,上下に移動させることができ,テ ストヘッド4をメンテナンス等の作業性に優れた位置へ移動させることができる。」 との記載から,テストヘッドを引き出した方が作業性に優れていることを読み取る ことはできない。
また,引用例には,1)試験対象の仕様及び試験内容に応じて行うピンエレクトロ ニクスの交換や,その他のテストヘッドのメンテナンスは収容室の背面扉を開けて 行うこと(【0029】,【0036】,【0063】,【0080】,【0085】),2)レイアウトの異なるウエハに対応するためのプローブカードの交換や,その他のプローブカードのメンテナンスは収容室のメンテナンスカバーを開けて行い,プローブ カードは収容室の外部に引き出すことができること(【0028】,【0029】,【0030】,【0037】,【0080】,【0085】),3)背面扉はテストヘッドのメンテナンスが容易な位置に配置され,メンテナンスカバーはプローブカードのメンテ ナンスが容易な位置に配されていること(【0029】)が記載されている。 このように,引用発明においては,テストヘッドのメンテナンスは背面扉を開け て行うものとされ,背面扉はメンテナンスを行うのに容易な位置に配置されている のであるから,検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備 え,テストヘッドを引き出す構成を採用することの動機付けは見いだせない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.07.21
平成30(ワ)6183等 不当利得返還請求事件,損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月26日 大阪地方裁判所
被告は,本件OEM契約に基づく独占販売権の付与(1条)により,「空 気触媒TioTio」等のブランド価値を高め,その販売拡大に努めるなどして,繊維関 連市場においてセルフィールないし「空気触媒TioTio」を積極的に販売すると共に, 競合する類似品の販売を行わないこと,ブランド価値を低める行為を行わないこと といった,これと矛盾する行為を行わない債務を負うなどと主張する。
イ しかし,本件OEM契約1条は,原告との関係では,被告から商品の提供 を受けて販売を行い,被告の販売方針を尊重して「甲商品」(セルフィール)の販売 拡大に努めるものとすることを定めたものであり,内容的な具体性には乏しい。こ のため,同条は,「目的」という表題とも相まって,契約当事者としての原告の一般\n的抽象的な責務ないし努力義務を示したものにとどまり,具体的な債務を定めたも のではないと理解される。 また,前記3のとおり,本件OEM契約においては,「空気触媒TioTio」の表示を\n付した商品の販売は,原告を主体として行われることとされ,被告は,そのような 原告に対し,商品の製造に使用される水性組成物を販売する立場にあるにすぎない。 すなわち,原告は,本件OEM契約において,被告の商品の販売等を取り扱う販売代 理店や特約店といった立場ではなく,被告から買い受けた商品を用いて加工した商 品を自己のブランドの商品として販売する主体として位置付けられているのである から,明示的な契約条項なしに,競合する類似品の販売を禁止されるとは必ずしも 考えられない。しかるに,本件OEM契約には,被告との関係で,原告による「空気 触媒TioTio」に係る商品と競合・類似する商品の販売行為を禁止する旨の条項は, 明示的には設けられていない。そうすると,原告は,本件OEM契約に基づき,「空 気触媒TioTio」に係る商品と競合・類似する商品の販売を行わないという債務を負 うとはいえない。このことは,商取引における忠実義務ないし信義則上の義務とい う見地から考えても,同様である。 なお,被告は,本件OEM契約につき,販売独占権の付与を伴う販売委託契約であ り,法的性質は委任契約であるとも主張するけれども,本件OEM契約の内容に鑑み ると,被告が被告製造に係る商品の販売を原告に委託するという内容のものとはお よそいえないから,これを前提とする主張は採用できない。
ウ 他方,「空気触媒TioTio」等のブランド価値を低める行為を行わない債務 については,本件OEM契約9条その他の内容をも考慮すると,信義則に基づき,原 告がそのような債務を負うと解する余地もないではない。 しかし,証拠(乙4,6)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品ないしこれを使 用して製造された繊維製品は,「ハイブリッド触媒」というその名称のとおり,酸化 機構の異なる2種類の触媒を組み合わせたものと認められ,セルフィールや「空気\n触媒TioTio」のように空気触媒のみを用いた商品とは異なる。前記イのとおり,原 告は「空気触媒TioTio」と競合・類似する商品の販売を行わない義務を負わないか ら,少なくとも,「空気触媒TioTio」に係る商品とは異なる触媒に係る商品について 研究・開発し,販売することは,本件OEM契約との関係で許容される。そうして販 売することとなった商品について,その商品特性に応じた商品名にすることは普通 に行われることであって,原告が「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表示を\n使用したとしても,これをもって直ちに「空気触媒TioTio」のブランド価値を低め る行為ということはできない。そもそも,「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の 表示が,これを付された商品等につき,「空気触媒TioTio」との比較において相対的 に品質,内容面で優れたものであると需要者に認識させるものといえないことは, 前記2のとおりであるから,「空気触媒TioTio」のブランド価値の低下をもたらすと もいえない。 したがって,仮に,被告主張のとおり,信義則上,原告が「空気触媒TioTio」等 のブランド価値を低める行為を行わないという債務を負うとしても,原告による原 告製品の販売行為は,これに違反するものということはできない。 エ さらに,原告が原告製品に「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表\n示を付していることについては,本件OEM契約上,「空気触媒TioTio」はOEMブラ ンドとされ(8条),原告の商品の表示と位置付けられること,被告の商標とされて\nいるのは「空気触媒」であること(9条),原告による「空気触媒TioTio」の競合・ 類似品の販売は必ずしも禁止されないこと(前記イ)に加え,「空気触媒TioTio」, 「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」のいずれも原告が商品等表示の主体と理解\nされることなどから,本件OEM契約上の債務ないし忠実義務に違反するものとはい えない。
オ なお,被告は,競合・類似品の販売禁止及びブランド価値低下行為の禁 止という債務を包摂するものとして,「空気触媒TioTio」等の積極的な販売拡大義務 に矛盾する行為を行わないという債務を措定し,原告によるその不履行を主張する 趣旨とも理解し得る。しかし,その債務(義務)の具体的内容が特定されておらず, 一般的抽象的なものにとどまることから,少なくとも,それ自体として原告に対す る法的拘束力を持つものと考えることはできない。また,被告が販売拡大義務と矛 盾する原告の悪質な行為と主張するもののうち,セルフィールの分析結果を東洋紡 に提供したことを認めるに足りる証拠はないし,大阪大学との共同研究や別件特許 出願等も,そもそも,原告の販売拡大の責務ないし義務と矛盾するものではない。
2020.07.21
平成30(ワ)6029 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和2年5月28日 大阪地方裁判所
意匠法39条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,侵 害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造,販売することによりそ の製造,販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額で あり,その主張立証責任は意匠権者側にあるものと解される。
(イ) 被告が平成29年6月〜令和元年6月の間に被告製品を5万2708台 販売したことは,当事者間に争いがない。
また,証拠(乙15)及び弁論の全趣旨によれば,上記期間における被告製品の 合計売上額(税抜)は,合計4億5514万1899円と認められる(内訳は別紙 「損害一覧表(裁判所の認定)」の「売上額(税抜)」欄のとおり)。\nこの点,被告は,上記期間における被告製品の合計売上額につき,乙15の1の 「売単価」欄記載の額の合計額であると主張する。 しかし,「売単価」欄は,その名称から,売却単価を記載したものと理解される。 子細に見ても,型番及びJANコードを同じくする製品で,「受注数」欄記載の受注 数が異なるものであっても,「売単価」欄記載の額は原則として同一である。すな わち,例えば,型番及びJANコードが同一の伝票番号167017及び167018の各製品を 見ると,受注数は前者が1個,後者が2個とされているが,「売単価」欄記載の額 はいずれも8800円とされている(受注数が1個の場合と5個の場合でも,同様 に「売単価」欄記載の額が同額という例もある。伝票番号374934及び374935)。同 一型番の製品であっても,伝票番号168810(2万6900円)と169855(2万85 00円)のように,「売単価」欄記載の額が異なる例はあるものの,2倍以上の開 きがある例は見当たらない。 そうすると,乙15の1の「売単価」欄記載の額は,売却単価を意味するにとど まるものと理解されるのであって,その合計額をもって被告製品の合計売上額と見 ることに合理性はない。すなわち,「売単価」欄記載の額に「受注数」欄記載の受 注数を乗じた額をもって売上額と理解すべきである。この点に関する被告の主張は 採用できない。
(ウ) また,消費税法基本通達5−2−5(「例えば,次に掲げる損害賠償金 のように,その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲 渡等の対価に該当することに留意する。…(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害 者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金」)に鑑みると,意匠法39 条2項の「利益の額」は,消費税(8%。以下同じ)込の売上額をもとに算定すべ きである。これに反する被告の主張は採用できない。
イ 被告製品に係る経費の額
(ア) 被告製品の製造原価(仕入額)
証拠(乙15)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品の仕入額は,売上額 の算定の場合と同様に,乙15の1の「実原価」欄記載の額に「受注数」欄記載の 受注数を乗じたものの合計4億1013万5936円(税抜)と認められる。また, これに消費税を加算することとなる。これに反する被告の主張は採用できない。
(イ) 被告主張の販売手数料等
被告は,「利益の額」(意匠法39条2項)算定に当たり控除すべき経費 として,さらに,販売手数料(乙15の1の「販売手数料」欄記載のもの)を主張 する。
しかし,乙15の1の「販売手数料」欄記載の額は,いずれも「売単価」欄記載 の額の9%程度と見られ,そのような計算方法によること自体,これをもって被告 製品の製造,販売に直接関連して追加的に必要になった費用とは考え難いことをう かがわせる。また,被告が「販売手数料」の内訳として挙げるものは,システム利 用料,出店料,成約手数料,ポイント付与原資,オプション料,広告掲載料,支払 システム利用料,広告宣伝メール配信手数料,保険料,口座決済手数料,ポイント 費用,代金引換回収費用,月額登録料,カスタマーサポート費用,クレジットカー ド決済店舗管理費用,トランザクション従量課金費用,キャッシュバックキャンペ ーン費用,クーポン広告料,クリック単位課金費用等であるところ,証拠(乙22 〜33)を子細に見ると,定額のもの(例えば,乙23の「プラン共通_楽天ペイ 利用料」,「プラン共通_商品一括登録サービス」等,乙28の1の「請求書」の 「固定費用」欄記載の各項目,乙31の「出店料」,乙33の「GOODA情報掲 載」)が見受けられる。額が変動しているものも,一部に,商品カテゴリのレベル で売上と手数料率が示されているものがあるものの(乙31),これも含め,被告 製品との具体的な関係は証拠上全く不明というほかない。そうである以上,これら の費用は,いずれも,被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となったものと はいえない。 したがって,被告主張に係る「販売手数料」を「利益の額」算定に当たって控除 すべき経費とすることはできない。この点に関する被告の主張は採用できない。
ウ 被告製品についての小計
以上より,被告製品に係る利益の額(税込)は4860万6441円と認め られる。
・・・
キ 推定覆滅事由の有無等
(ア) 「利益の額」(意匠法39条2項)とは,原則として,侵害者が得た利 益全額であり,これについて「損害の額」として推定が及ぶものの,侵害者の側で, 侵害者が得た利益の一部又は全部について,意匠権者が受けた損害との相当因果関 係が欠けることを主張立証した場合には,その限度で上記推定は覆滅されるものと 解される。推定を覆滅させる事情としては,侵害者が得た利益と意匠権者が受けた 損害との相当因果関係を阻害する事情,例えば,意匠権者と侵害者の業務態様等の 相違(市場の非同一性),市場における競合品の存在,侵害者の営業努力(ブラン ド力,宣伝広告),侵害品の性能(機能\,性能等意匠以外の特徴)等が挙げられる。\n以下では,このような観点から,推定覆滅の有無及び程度について検討する。
(イ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
・・・
(ウ) 検討
a まず,前記1のとおり,本件意匠は,意匠登録出願前の公知意匠に はない特徴的な構成態様(基本的構\成態様(A3)〜(C3))をその要部として有するも のであり,相応な程度の顧客吸引力を有するといってよい。このことは,本件意匠 の実施品である原告製品がグッドデザイン賞を受賞し,「造形的には,シンプルで あるが一つのコーナーを大きなアールとすることで,このシリーズの特徴となり, バランスのよいデザインとしてまとまっている。また,同社の他のシリーズとのア イデンティを感じさせるデザインである。」と評価されていること(乙11)から もうかがわれる。また,前記((イ)a,b)のとおり,被告製品及び原告製品のパッ ケージ等には,製品自体の画像が掲載されており,これに接した需要者は,自ずと 本件意匠の要部に相当する製品の正面及び平面を形成するプレートに着目すること になると推察される。
そうである以上,本件意匠は,具体的な製品イメージの形成に直接関わるもので あり,被告製品の売上に相応に貢献していると見るのが相当である。 もっとも,原告製品及び被告製品が属する商品カテゴリであるデータ記憶機 (HDD製品)においては,需要者がこれを購入するに当たり,意匠のみならずその 機能面,具体的には,用途との関連におけるデータ容量,接続予\定の機器との接続 可能性,データ転送速度,耐久性や静音性等も,重要な商品選択の要因となる(乙\n41〜43参照)。このことは,前記((イ)a及びb)認定に係る被告製品や原告製 品のパッケージ等の記載内容からもうかがわれ,むしろ,機能面での特徴がこれら\nの宣伝媒体における中心的な内容となっているといえる。顧客の商品レビュー(甲 7,23,乙18の2,18の3)の内容を見ても,製品のデザイン性に言及する ものもあるものの,機能に言及するものの方が相当多い。こうした事情に鑑みると,\n需要者は,HDDの購入に際し,デザイン性と機能とでは,第一次的には機能\を,第 二次的にデザイン性を考慮するものと見るのが適当である。 もとより,販売価格も重要な商品選択の要因であることには多言を要しないとこ ろ,需要者は,製品購入に当たり,当然,販売価格と自己の求める機能及びデザイ\nン性とのバランスを考慮することとなる。 したがって,被告製品の需要者は,第一次的には製品の機能を,第二次的にデザ\nイン性を,販売価格をも考慮に入れつつ評価し,その購入動機を形成するものと考 えられる。そうすると,被告製品やそのケースに係る被告の利益の全てが,本件意 匠と類似する意匠である被告意匠に起因するものということはできない。すなわち, 上記事情は,侵害者である被告が得た利益と意匠権者である原告が受けた損害との 相当因果関係を阻害する事情として,相当程度考慮すべきである。これに反する原 告の主張は採用できない。
b これに対し,被告は,原告製品と被告製品とでは美感及び印象が全 く異なり,代替可能性がないと主張する。\nしかし,前記1のとおり,本件意匠と被告意匠とは類似するものであり,需要者 にとって美感及び印象が全く異なるということはできないから,この主張はそもそ も前提を欠く。なお,被告は,被告製品には,原告製品と異なり白色のものもある ことを指摘するけれども,複数色で商品展開していることの販売実績への影響は具 体的に明らかでない。その点を措くとしても,前記のとおり,商品選択におけるデ ザイン性の考慮は第二次的なものと位置付けられることに鑑みると,仮に影響があ るとしても,その程度は限定的なものにとどまると思われる。 また,被告は,競合品ないし代替品となる同種のデータ記憶機が数多く販売され ていることを指摘する。
もとより,前記のとおり,第一次的には製品の機能が購入動機の形成要因となる\nことを考えると,機能面で原告製品及び被告製品と競合する他社のHDD製品が市場 に存在することは,被告製品の販売がなくなった場合に,必ずしもその売上に相当 する需要の全てが原告製品に向かうものではないことを意味する。そうである以上, この点は推定覆滅事由として考慮する必要がある。もっとも, 証拠(乙19)及び 弁論の全趣旨によれば,令和元年5月のベンダー販売実績において,原告は34社 中1位(販売数量シェア40.76%,販売金額シェア41.03%,平均単価1 万0417円)であるのに対し,被告は11位(販売数量シェア0.66%,販売 金額シェア0.62%,平均単価9841円)とされる。これを踏まえると,被告 製品に対する需要は,その販売がなくなった場合,むしろ相当程度原告製品に向か うものと考えるのが適当である。 さらに,被告は,原告製品のうち「HD-LXU3D」シリーズについて,その自動暗 号化機能の点で被告製品と需要者が異なると指摘する。しかし,当該機能\は,HDD であることを前提としたいわば付加的な機能にすぎないから,当該機能\の存在ゆえ に需要者を異にするということはおよそできない。
c 以上の事情を総合的に考慮すると,本件では,被告製品とそのケー スに係る被告の利益について,7割の限度で意匠法39条2項による推定が覆滅さ れるとするのが相当である。これに反する原告及び被告の各主張はいずれも採用で きない。
ク 意匠法39条2項及び3項に基づく原告の損害額
以上によれば,意匠法39条2項に基づく原告の損害額は,1469万47 17円と認められる(詳細は別紙「損害一覧表(裁判所の認定)」参照。以下同\nじ。)。 他方,推定覆滅に係る部分については,同条2項に基づく推定が覆滅されるとは いえ無許諾で実施されたことに違いはない以上,同条3項が適用されると解するの が相当である。後記((2)イ(エ))のとおり,実施料率は5%として算定すべきと考え られることから,当該覆滅部分につき,意匠の実施に対し原告が受けるべき金銭の 額(税込)は1737万9277円となる。そうすると,両者を合わせた額は,合 計3207万3994円となる。
(2) 意匠法39条3項に基づく損害について
ア 被告製品の売上額
前記((1)ア)のとおり,被告製品の売上額(税抜)は4億5514万189 9円であり,これに消費税を加算すると4億9155万3250円となる。なお, 意匠権実施許諾契約に基づき支払われる実施料も「資産の譲渡等」の対価に当たる ことを踏まえると,意匠法39条3項に基づく損害の額の算定に当たっても,消費 税を加算して算定するのが相当である。
イ 実施に対し受けるべき金銭の額
(ア) 意匠法39条3項の実施に対し受けるべき料率は,当該意匠の実際の実 施許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料 の相場等も考慮に入れつつ,当該意匠自体の価値,当該意匠を当該製品に用いた場 合の売上及び利益への貢献や侵害の態様,意匠権者と侵害者との競業関係や意匠権 者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合的に考慮して,合理的な料率を定めるべ きである。また,その際,必ずしも当該意匠権についての実施許諾契約における実 施料率に基づかなければならない必然性はなく,意匠権侵害をした者に対して事後 的に定められるべき,実施に対し受けるべき料率は,むしろ,通常の実施料率に比 べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
(イ) 本件意匠に係る実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる証拠は ない。
また,証拠(乙45)及び弁論の全趣旨によれば,「特許権」の技術分類を器械 とする項目(対象となる製品・技術例には「情報記憶」が含まれている。)の「ロ イヤルティ料率アンケート調査結果」として,特許の場合のロイヤルティ料率(全 体の件数は64件)は,料率4〜5%未満及び2〜3%未満がそれぞれ23.4% と最も多く,料率3〜4%未満が18.8%,料率1〜2%未満が14.1%など となっている。平均値は約3.5%,中央値は約3.3%程度と見られる。意匠権 と組み合わせた場合のロイヤルティ料率(全体の件数は25件)は,料率1〜2% 未満,2〜3%未満,4〜5%未満がそれぞれ6社と最も多く,料率3〜4%未満 が3社,5〜6%が2社,〜1%未満,6〜7%未満がそれぞれ1社であり,平均 値は約3.1%,中央値は約2.9%程度と見られる。
(ウ) 前記((1)キ(ウ)a)のとおり,被告製品の需要者は,第一次的には製品 の機能を,第二次的にデザイン性を,販売価格をも考慮に入れつつ評価し,その購\n入動機を形成するものと見られることから,本件意匠ないしこれに類似する被告意 匠を用いた場合の売上及び利益への貢献の程度についても,これを踏まえて考察す る必要がある。他方,原告製品と被告製品はいずれもHDD製品であり,原告と被告 とは直接的な競業関係にあるから,仮に原告が被告に対し本件意匠に係る実施許諾 契約を締結するならば,その実施料率は高めに設定されるのが通常と思われる。
(エ) 実施に対し受けるべき料率
上記(イ)及び(ウ)の事情に加え,意匠権侵害に基づく損害賠償請求の場面での 仮想実施料率の考察であることを総合的に考慮すると,本件において,意匠権侵害 をした者に対して事後的に定められるべき,実施に対し受けるべき料率は5%を下 らないというべきである。
(オ) 被告の主張について
被告は,被告製品は原告製品を模倣したものではなく,これらが混同され るものでもないこと,原告製品と異なり開口部を備えないことを指摘して,損害の 発生はなく,仮に発生したとしても1%を上回らないなどと主張する。 しかし,開口部の有無が本件意匠と被告意匠の差異点であることを踏まえても, 本件意匠と被告意匠が類似すること(前記1)に鑑みれば,損害が発生していない ということはできず,また,開口部の有無という差異をもって,実施に対し受ける べき料率を低く見るべき事情になるともいえない。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
(カ) 意匠法39条3項に基づく原告の損害額
以上によれば,意匠法39条3項に基づき原告が請求し得る「受けるべき 金銭の額に相当する額」すなわち損害額は,2457万7662円と認められる。
2020.07.21
令和1(ネ)10064 職務発明対価請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審被告は,本件各発明は,●●●●●●●●●●●●●●●●● ●「最たる会社主導事業」であるFAMプロジェクトの中でされたも のであり,本件各発明の1審原告を含む共同発明者らは,かかるプロ ジェクトのメンバーとして,1審被告の業務命令に従って各研究開発 に従事したにすぎないこと,発明者は,給与及び身分等を保障され, 研究開発に係るリスクを負わないのに対し,使用者は事業の失敗のリ スクを負っていることを斟酌すれば,本件各発明により1審被告が受 けるべき利益についての1審被告の貢献度は,原判決認定の95%を 優に超えるものであり,99%と認められてしかるべきである旨主張 する。 しかしながら,前記認定のとおり,1審被告の指摘する諸事情を踏 まえても,本件各発明の内容及びその技術的意義,本件各発明の完成 に至る経過に照らすと,本件各発明は1審原告を含む本件各発明の発 明者らの創意工夫がなければ,発明の完成に至らなかったものであり, 1審被告の貢献度は,95%と認定するのが相当であるから,1審被 告の上記主張は採用することができない。」
・・・
「カ 当審における1審原告の補充主張について
1審原告は,(1)1審原告は,生分解性ポリマーの研究を行っていた こともあり,環境負荷低減に対する意識が高くFAMの実験過程にお いて大量の廃水を生み出す状況を危惧し,FAM生産において廃水リ サイクルを行うことを想起し,廃水リサイクルの方法について具体的 な実験計画を策定し,平成9年12月8日,●●●●技術会議におい て,廃水リサイクルを行うことや,廃水リサイクルの具体的な実験を 今後行っていくことについてプレゼンテーションをし,平成10年1 月頃,オープンセル構造のFAMを調製することに成功し,遅くとも\n同年4月頃までには,1審原告一人による創作活動の結果,3回の廃 水リサイクルを実現し,この時点で,144号特許の請求項1ないし 6,12ないし15,17記載の発明は完成したこと,(2)共同発明者 のBは,1審原告の補助者にすぎず,Bが同年4月から同年8月末頃 まで行った中和技術に関する実験は,1審原告の具体的な指導の下で 行われたものであり,また,Nは,Bの行う実験を一部担当したにす ぎないし,C及びBは,遠心分離に関する実験を行ったものの,実際 の廃液を使用していないため,144号発明等とは無関係であること, (3)1審原告は,144号特許の出願の願書に筆頭発明者として記載さ れ,明細書原案を作成したことからすると,144号発明等の共同発 明者間における1審原告の貢献度は,低く見積もっても90%以上で ある旨主張する。 しかしながら,上記(1)については,前記認定事実に照らすと,1審 原告一人による創作活動の結果,3回の廃水リサイクルを実現した時 点で,144号特許の請求項1ないし6,12ないし15,17記載 の発明が完成したものと認めることはできない。 次に,上記(2)については,前記認定のとおり,1審原告が挙げる共 同発明者のB,N及びCに関する諸事情は認めることはできない。 さらに,上記(3)については,1審原告が明細書原案を作成したこと を裏付ける的確な証拠はないし,また,144号発明等に係る特許出 願において1審原告が筆頭者に記載されたからといって,そのことか ら直ちに1審原告の貢献度が客観的にみて高いことが根拠付けられる ものでもない。
2020.07.17
平成29(ワ)22922 著作権に基づく差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年11月15日 東京地方裁判所
(1) 出版権者は,設定行為で定めるところにより,頒布の目的をもって,その 出版権の目的である著作物を,原作のまま印刷その他の機械的又は科学的方 法により文書又は図画として複製する権利を専有し(著作権法80条1項1 号),被告が,原告の出版権を侵害したというためには,被告が,頒布の目 的をもって,その出版権の目的である著作物を複製したことが必要である。 また,原告が出版権を有する著作物について,被告が本件出版物において複 製したというためには,本件出版物が,被告によって,原告が出版権を有す る著作物に依拠して作成されたことを要する。 原告は,本件においてAを著作者とする著作物の出版権侵害を主張すると ころ,本件出版物の質問票における質問の表現と新日本版の質問票における\n質問の表現とを比較し,その類似性に基づいて上記出版権侵害を主張してお\nり,本件出版物の質問票に記載された質問が,新日本版の質問票に記載され た質問に依拠して作成され,本件出版物の質問票が,原告が出版権を有する 新日本版の質問票を複製していると主張していると解され の主張),まず,この点について判断する。
(2) 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実を認めることができ る。
ア Bらは,昭和63年10月10日,日本心理学会第52回大会におい て,「MMPI自動診断システム(1)翻訳,標準化,および,実施プロ グラム」と題する発表を行った。\nこの発表において,Bらは,旧三京房版におけるMMPIの質問の翻\n訳には多数の誤訳などの問題が存在し,これが日本においてMMPIが 活用されていない原因であるから,MMPIの質問の翻訳と標準化をや り直すべきであると考え,Bがまず翻訳の下訳を作成し,それにEとC がそれぞれ手を加えた2種類の訂正原稿を比較しながら,3名で最終原 稿をまとめたと発表した(以下,この翻訳を「Bら新訳」という。)。ま\nた,Bらは,Bら新訳につき,標準化作業を継続中であると発表した。\n(乙2の1,乙4,10) なお,心理検査は測定値(得点)によって特定の性格特性を測定する が,その測定値(得点)に基づいて測定事項を正しく判断するためには, 個人が所属する準拠集団ごとに,当該心理検査を相当数の被験者に対し て実施したデータを集積し,得点の分布を調べ,当該心理検査の測定値 (得点)を解析する基準(尺度)を明らかにする作業が必要であり,こ れを標準化という。(甲3)
イ Bらは,昭和63年12月15日発行の「なぞときロールシャッハ ロールシャッハ・システムの案内と展望」において,昭和62年11月 7日当時には,Bら新訳は完成していなかったこと,昭和63年6月当 時にはBら新訳に基づく検査を実施したことを記載した(乙9)。
ウ Bらは,平成元年11月30日の同学会第53回大会において「MM PI自動診断システム(2)暫定的標準化と自動解釈について」と題す る発表を行った。この発表\において,Bらは,Bら新訳は翻訳の誤りが 多い旧三京房版とはほとんど一致しないこと,及びBら新訳について標 準化作業を継続中であることを発表した。(乙2の2)\n
エ Bらは,平成2年11月30日の同学会第53回大会において「MM PI自動診断システム(3)新版,三京房版,メイヨウ新基準との比較」 と題する発表を行った。この発表\において,Bらは,Bら新訳につき標 準化作業を行い,「現在までに参加した被験者は男性113名,女性15 6名である。」と発表した。(乙2の3)\n
オ Bらは,平成4年3月25日,Bら新訳を付録として付した「コンピ ュータ心理診断法 MINI,MMPI-1自動診断システムへの招待」 と題する書籍を出版した(乙4)。
カ 平成13年1月1日発行のF編著「国際的質問紙法心理テストMMP I-2とMMPI-Aの研究 Minnesota Multiphasic Personality Invent ory 2 & A Study(北里大学看護学部精神保健学教授平成12年3月退任 記念論集)」には,MMPIには旧三京房版も含めて15種類の翻訳があ ったが,それらには誤訳があるほか恣意的な意訳などの疑問点があった 旨の記載があり,また,「1992年(判決注:平成4年):富山大学の Bらが,これ等の疑問点を訂正する形のMMPI-1新訳版を作成。」と の記載があり,また,「1993年(判決注:平成5年):Dらがこれま での翻訳を修正し,再標準化しMMPI−1新日本版を作成。」との記載 がある(乙1)。
キ Bらは,平成18年,Bら新訳の質問項目92の「看護婦」との訳語 について,「看護師」と変更した(乙7,10〔17頁〕)。
ク 被告は,平成29年,Bら新訳のうち上記キの部分を変更した質問が 掲載された本件出版物を出版した(前提事実 オ)。
ケ 新日本版について,以下の事実が認められる。(乙13)
新日本版は,平成5年10月1日,MMPI新日本版研究会を編者と して原告から出版された(前記前提事実(2)エ)。同研究会の代表はDであ\nり,同研究会のメンバーにAは含まれていない。 新日本版の前書きには,旧三京房版は改訂の必要性が痛感されていた こと,Aらは改訂に着手したが完成しなかったこと,Aから依頼を受け て平成2年にMMPI新日本版研究会が旧三京房版の改定作業を引き受 けたこと,MMPI新日本版研究会は,より適切な日本語版を作成する という目的からMMPI原版を最も適切と思われる日本語に移して適切 な標準化作業を行うという条件の下でこの作業に取り組み,項目の配列 順序は旧三京房版を踏襲するがそれ以外の点では全く独自の観点から作 業を進め,新日本版を作成したことなどが記載されている。
(3) 以上の事実によれば,Bらは,昭和62年11月7日から昭和63年6月 までに間にBら新訳を完成させ,これを前提として,学会での発表を行うと\n共に標準化作業を進め,平成4年3月25日にBら新訳を掲載した書籍を出 版したと認められる。前記前提事実(2)エのとおり,新日本版は平成5年10 月1日に出版されたものであるから,Bらが,Bら新訳を作成した昭和62 年から昭和63年当時,新日本版に接し,これを用いてBら新訳を作成する ことは不可能であったといえる。\n
これに対し,原告は,昭和63年には既に新日本版の第一段階の質問票は 完成しており,Bらがこれを参照した可能性がある旨主張するが,MMPI\n新日本版研究会が旧三共房版の改訂作業を引き受けたのは平成2年であり, 同研究会が「MMPI原版を最も適切と思われる日本語に移」す作業を行っ たこと(前記(2)ケ)からすれば,昭和63年の段階で新日本版の質問票の質 問と同内容の翻訳が完成していたと認めることは困難であるし,また同翻訳 が公表され,Bら一般の研究者が参照し得たと認めるに足りる証拠もない。\n そして,本件出版物の質問票の質問は,Bら新訳の質問92が「看護婦に なりたいと思います。」から「看護師になりたいと思います。」へと変更され た以外は,Bら新訳の質問と同一であるから(甲4の1,乙10,前記(2) ク),本件出版物の質問票の質問が,新日本版の質問票の質問に依拠して作 成されたと認めることはできない。なお,本件出版物の質問票の質問と新日 本版の質問票の質問は,その内容においてほぼ重なるが,これらはいずれも MMPIを翻訳したものでその内容が共通することは当然であり,その重な りによって,本件出版物の質問票が新日本版の質問票に依拠して作成された と認めることはできない。 したがって,本件出版物は新日本版を複製したものであるとは認められず, 原告主張の出版権侵害は理由がない。
(4) 原告は,原告が旧三京房版の出版権を有するとも主張するため,本件出版 物の質問票が,旧三京房版の質問票を複製したものであるか否かについても 検討する。
本件出版物の質問票の質問は,その内容において,旧三京房版の質問票の 質問と重なるものもあるが(甲3,乙6,10),これらもいずれもMMP Iを翻訳したものであるから,このことをもって直ちに本件出版物の質問票 が旧三京房版の質問票に依拠してこれを再製したものとはいえない。前記(2) で認定したとおり,Bらは,旧三京房版における質問の翻訳に疑問を持ち, 独自にMMPIの英文の翻訳等を行ってBら新訳を完成させたものと認めら れること,上記各質問票の質問の日本語の表現は同じ英文に対応するものと\nしてはいずれも相当に違うこと(甲3,乙6,10)などから,本件出版物 の質問票の質問が旧三京房版の質問票の質問を複製したものであると認める ことはできず,その他,本件出版物が旧三京房版を複製したことを認めるに 足りる証拠はない。したがって,本件出版物が旧三京房版を複製したもので あるとは認められない。
2020.07.17
令和1(ネ)10069 商標権 民事訴訟 令和2年6月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(ア) 被告各標章は,「MMPI−1」の部分と「性格検査」,「回答用 紙」又は「自動診断システム」の部分とを結合した標章である。 平成29年4月1日当時において,需要者の間で,「MMPI」の表\n示は,ハサウェイとマッキンレーが開発した心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」(ミネソタ多面的人格目録)(本\n件心理検査)又はその略称を表すものであることが広く認識されていた\nこと(前記(2)ア),ハイフン記号と数字を組み合わせてバージョンを示 すことが一般的に行われていること(甲4,87,乙5)を踏まえると, 被告標章1(「MMPI−1 性格検査」)に接した需要者は,被告標 章1は,「MMPI−1」という名称の「性格検査」を示したものと理 解し,被告標章1における「−1」のハイフン記号及び数字部分は,「M MPI」のバージョンを,「MMPI」の文字部分は,ハサウェイとマ ッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するものと認め られる。また,被告標章3又は被告標章5に接した需要者は,上記と同 様に,被告標章3又は被告標章5は,「MMPI−1」という名称の「性 格検査」を示したものと理解し,「MMPI」の文字部分は,ハサウェ イとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するもの と認められる。 次に,被告標章2(「MMPI−1 回答用紙」)に接した需要者は, 被告標章2における「MMPI」の文字部分は,ハサウェイとマッキン レーが開発した本件心理検査を示したものと認識し,被告標章2は,本 件心理検査に用いられる「回答用紙」であることを示したものと理解す るものと認められる。 さらに,被告標章4(「MMPI−1自動診断システム」)に接した 需要者は,被告標章4における「MMPI」の文字部分は,ハサウェイ とマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識し,被告標 章4は,本件心理検査の診断結果を作成する自動診断システムであるこ とを示したものと理解するものと認められる。
(イ) 前記(ア)のとおり,被告各標章に接した需要者は,被告各標章にお ける「MMPI」の文字部分をハサウェイとマッキンレーが開発した本 件心理検査を示したものと認識するものと認められるから,「MMPI」 の文字部分は,心理検査の内容を示したものと認められる。 そして,法26条1項3号の役務の「質」には役務の「内容」が含ま れるから,被告各標章における「MMPI」の文字部分は,本件商標の 指定役務である「心理検査」の質を示したものと認められる。 次に,前記ア認定の被告各商品及び被告広告における被告各標章の表\n示態様によれば,被告各標章における「MMPI」の文字部分は,いず れも,その文字の大きさ,フォント及び表示位置等に顕著な特徴がある\nとはいえず,取引上一般に用いられている方法で表示したものと認めら\nれるから,本件商標の指定役務「心理検査」の質を「普通に用いられる 方法」で表示したものと認められる。\n
ウ まとめ
以上によれば,「MMPI」の文字部分を含む被告各標章は,本件商標 の指定役務「心理検査」の「質」又は当該指定役務に類似する商品の「品 質」を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するものと認めら\nれるから,法26条1項3号に該当する。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成29(ワ)38481
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.07.17
令和1(行ケ)10147 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年6月23日 知的財産高等裁判所
本願商標が商標法3条1項3号に該当することは,当事者間に争いがないと ころ,同条2項は,同条1項3号ないし5号に対する例外として,「使用をされた結 果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるも の」は商標登録を受けることができる旨規定している。その趣旨は,特定人が当該 商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独 占排他的に継続使用した実績を有する場合には,当該商標は例外的に自他商品識別 力を獲得したものということができる上に,当該商品の取引界において当該特定人 の独占使用が事実上容認されている以上,他の事業者に対してその使用の機会を開 放しておかなければならない公益上の要請は薄いということができるから,当該商 標の登録を認めようというものと解される。 そして,使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは,当該商標が使用され た期間及び地域,商品の販売数量及び営業規模,広告宣伝がされた期間及び規模等 の使用の事情,当該商標やこれに類似した商標を採用した他の事業者の商品の存在, 商品を識別し選択する際に当該商標が果たす役割の大きさ等を総合して判断すべき である。また,輪郭のない単一の色彩それ自体が使用により自他商品識別力を獲得 したかどうかを判断するに当たっては,指定商品を提供する事業者に対して,色彩 の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべきである。
(2) 認定事実
ア 本願商標の使用態様
原告の前身である日立製作所は,昭和40年,油圧ショベル「UH03」の外 面の塗装の色彩として,本願商標の色彩を採用した(甲46)。 原告は,昭和45年10月,日立製作所の建設機械製造部門が独立し,旧日立建 機株式会社と合併して設立された株式会社であり,遅くとも昭和49年以降,本願 商標の色彩を,油圧ショベルを始めとする各種建設機械の外面の塗装の色彩として, 現在まで継続して使用してきた(甲1の1〜44,8の1〜15,弁論の全趣旨)。 原告の販売する油圧ショベルには,オレンジ色を車体の全体に使用したもの もあるが(甲1の13・14・17・18・20・21・36・37,7の1・4〜 7・9〜12),アーム部及び車台後部はオレンジ色であるものの,操縦席近辺や駆 動部は黒色ないし鼠色のもの(甲1の1〜12・15・16・19・22〜35・3 8〜44,5の1・5〜18,7の2・3・8・13,8の1〜15),操縦席近辺 はオレンジ色で,アーム部は黒いもの(甲2の2),アーム部はオレンジ色で,操縦 席や車台後部に緑色のラインが入ったもの(甲5の2〜4)もある。また,その多く には,アーム部や車台後部等に白抜き又は黒文字で著名商標である「HITACH I」又は「日立」の文字が付されている(甲1の1〜42・44,2の2,8の1・ 3・4・6〜8・10・12・13)。 原告のカタログにも,上記のとおり,オレンジ色を車体の全体に使用した油圧シ ョベルの写真のみならず,車体の一部にのみオレンジ色を使用した油圧ショベルの 写真も掲載されており,原告の社名や,「HITACHI」又は「日立」の文字が記 載されている(甲1の1〜44,2の2,8の1〜15)。
イ 本願商標の使用期間,使用地域及び販売数量
原告は,車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用された油圧ショベル を,北海道・東北,関東,中部,関西及び西日本(九州を含む。)の各地域に所在す る事業者に対して販売し,本願商標の色彩が使用された油圧ショベルは,日本全国 で使用されている(甲4の2・4,21の1〜6)。 原告は,車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用されたミニショベル を除く油圧ショベル(6トン以上のもの。甲40)を昭和49年から平成30年ま での間に合計●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●,ミニショベル(6 トン未満のもの。甲40)を平成3年から平成30年までの間に合計●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●,それぞれ販売した(甲52の1・2)。 ミニショベルを除く油圧ショベルは,主に,原告,株式会社小松製作所,コベルコ 建機株式会社,キャタピラージャパン合同会社及び住友建機株式会社の5社が製造 販売しているところ,昭和49年から平成30年までの間の原告の油圧ショベルの シェアは概ね20%である(甲44の1〜8,52の1)。また,ミニショベルにつ いては,平成3年から平成30年までの間の原告のシェアは概ね10%前後である (甲52の2)。
ウ 広告宣伝の方法,期間,規模
雑誌・新聞広告,ウェブ広告等の掲載
原告は,少なくとも平成5年以降,車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使 用された油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を,少なくとも72種類以上作成 し(甲57),これらを「日本経済新聞」,「朝日新聞」,「産経新聞」,「日刊工業新聞」,「建通新聞」,「北海道新聞」等の新聞や,「日経ビジネス」,「投資経済」,「東洋経済」,「週刊ダイヤモンド」,「週刊エコノミスト」,「日経コンストラクション」,「建設機械」,「月刊廃棄物」等の雑誌等,少なくとも29種類以上の媒体に,継続的に掲載した(甲5の1〜18,58の1,59の1・2・4〜6・8〜153)。
また,原告は,少なくとも平成20年以降,大手建設機械レンタル会社のカタロ グや,書籍・小冊子にも,車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用された油 圧ショベルのカラー画像を用いた広告を継続的に出稿したほか(甲59の154〜 162),平成30年6月以降,本願商標の色彩が使用された油圧ショベルのカラー 画像を用いたウェブ広告を3種類作成して(甲56,57,59の164・165), 8種類のサービスに出稿しており(甲61),これらのウェブ広告は,合計で,少な くとも4000万回以上表示された(甲56,61)。\nこの他,車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用された原告の油圧ショベ ルのうち,実際に市場で販売されたものの画像が,昭和54年以降,建設機械分野 の専門誌の表紙にも取り上げられた(甲7の1〜13)。\nこれらの広告においては,いずれも原告の社名や,「HITACHI」又は「日立」 の文字が記載されている。
テレビCM
原告は,少なくとも平成2年9月から平成28年1月までの間(ただし,平成1 3年下期から平成19年上期は除く。)に,車体の少なくとも一部に本願商標の色彩 が使用された原告の油圧ショベル,積込み機,ホイールローダ,鉱山用ダンプトラ ック等が映像の一部に登場するテレビCMを,繰り返し放映した。もっとも,これ らのテレビCMには,油圧ショベル以外の建設機械に係るものが含まれ,全体の映 像も,明らかでない。
エ アンケートの結果
マーケティングリサーチ事業を専門とする楽天リサーチ株式会社(現在の名称は, 「楽天インサイト株式会社」)が原告からの依頼により,全国502か所の建設業界 の事業者を対象として,平成29年1月に実施したアンケートの結果(以下「本件 アンケート」という。)によれば,有効回答数は193件であり(回収率38.6%),
本願商標の色彩の画像を見せた上で,「どのメーカーの油圧ショベルかをお答えくだ さい」との質問に対し,185件が原告と回答した(認知率95.9%)との結果と なっている(甲19)。 本件アンケートは,原告が製造する建設機械の販売会社が顧客開拓のために独自 に調査してリストアップしている日本全国の需要者に係るデータ約●●●件から, ホイールローダ,ダンプトラック,道路機械及び環境機械等の需要者や,農業や酪 農など土木建設業者以外の業種の者を除いた約●●●件のうち,10台以上油圧シ ョベルを保有している者を調査対象としたものである。対象者の業種は,主に土木 建設業,解体業,産業廃棄物処理業,建設機械レンタル業であるとされる(甲54)。
オ 原告以外の者による本願商標と類似する標章の使用
以下のとおり,原告以外の事業者により,本願商標と類似する標章が使用されて いたことが認められる。なお,以下の証拠には,令和2年1月頃印刷したウェブサ イト等もあるが,これらの証拠に弁論の全趣旨を総合すれば,本件審決時(令和元 年9月19日)においても,同様に,原告以外の事業者により,本願商標と類似する 標章が使用されていたことが推認できる。 「住友建機株式会社」のウェブサイト(令和2年1月23日印刷)には,「油 圧ショベル」の商品紹介のページに,アーム部がオレンジ色の油圧ショベルの写真 が掲載されている(甲77,乙13)。 「株式会社ボブキャット」の発行する「DOOSAN」のチラシ(令和2年1 月27日印刷)には,アーム部及び車体後部がオレンジ色の油圧ショベルの写真及 びアーム部及び車体上部をオレンジ色にした油圧ショベルの写真が掲載されている (乙14)。 「イワフジ工業株式会社」のウェブサイト(令和2年1月29日印刷)及びカ タログ(平成30年6月発行)には,「製品情報」中の「林業ベースマシン」のペー ジに,アーム部及び車体下部がオレンジ色の「CT−500C/CS 林業ベース マシン」の写真が掲載されている(乙15,16)。
「神野農機」のウェブサイト(令和2年1月23日印刷)には,「商品一覧」 の頁に,アーム部及び車体下部がオレンジ色の「フルカワ ミニバックホー FX −007」の写真が掲載されている(乙17)。
「農機新聞」(平成29年3月7日発行)には,「イベロジャパンがトラクター 用バックホー3機種発売」の見出しの記事情報において,バケット部,アーム部及 び本体がオレンジ色のバックホーの部分の写真が掲載されている(乙18)。
「DiESEL TRADiNG」のウェブサイト(令和2年1月23日印 刷)には,「建設機械在庫一覧」のページに,アーム及び車体がオレンジ色の「IH I建機 ミニショベル」の写真が掲載されている(乙20)。 「株式会社クボタ」のウェブサイト(令和2年1月27日印刷)には,「開発 中の電動トラクタと小型建機を公開〜脱ディーゼルの進む欧州で事業性を検証し, 製品化を目指す〜」の見出しの下,「小型建機(ミニバックホー)」の試作機の写真と して,アーム部,車体及び脚部駆動部の中心部がオレンジ色の油圧ショベルの写真 が掲載されている(乙21)。
また,「製品情報」中の「建設機械」のうち,「ミニバックホー」のページ(令和2 年1月23日印刷)に,アーム部,車体下部がオレンジ色の「林業モデル」のバック ホーの写真(乙22)が,「ホイールローダ」のページ(令和2年2月3日印刷)に アーム部,車体,ホイールがオレンジ色のホイールローダの写真(乙23)が,「キ ャリア」のページ(令和2年1月23日印刷)に荷台部などがオレンジ色のキャリ アの写真(乙24)が,「農業ソリューション製品」のページ(令和2年1月23日\n印刷)に,車体の前部,泥よけ部及び天井部がオレンジ色のトラクタの写真(乙3 3)が,それぞれ掲載されている。
「WINBULL/YAMAGUCHI」のウェブサイト(令和2年1月2 3日印刷)には,「YX−21X」の商品紹介の項に,荷台部がオレンジ色のキャリ アの写真(乙25),「YXS−121HX」の商品紹介の項に,アーム部及び車体部 がオレンジ色の除雪機の写真(乙26)が,それぞれ掲載されている。 「トヨタL&F」のウェブサイト(令和2年1月23日印刷)には,「製品情 報」ページに,ショベル部及び車体下部がオレンジ色のショベルローダの写真(乙 27),フォーク部及び車体下部がオレンジ色のフォークリフトの写真(乙28)が, それぞれ掲載されている。
「サオリエクスポート」のウェブサイト(令和2年1月23日印刷)には, 「H7年 コベルコ ラフタークレーン RK160−2」の商品紹介の項に,ア ーム部及び車体がオレンジ色のクレーン車の写真(乙29),「H17 イスズジャ ストン」の商品紹介の項に,アーム部及び車体をオレンジ色の高所作業車の写真(乙 32)が,それぞれ掲載されている。
「オークフリー」のウェブサイト(令和2年1月23日印刷)には,「H7年 TADANO タダノ 4.9t ラフタークレーン」の商品紹介の項に,車体上 部がオレンジ色のクレーン車の写真が掲載されている(乙30)。 「エイハンジャパン」のウェブサイト(令和2年1月23日印刷)には,「高 所作業車製品案内」のページに,乗車部及び下部の車体をオレンジ色にしたマスト 式高所作業車の写真が掲載されている(乙31)。
カ 油圧ショベルの取引の実情
油圧ショベルは,ユンボ,パワーショベル,バックホー,ドラグショベル,シ ョベルカーなど様々な名称で呼ばれる掘削機械の一種であり,日本国内で建設業に おいて広く用いられているほか,その用途に汎用性があることから農業や林業にも 利用されている(甲38〜40,乙15〜18,22)。 油圧ショベルを製造販売する原告,株式会社小松製作所,コベルコ建機株式 会社,キャタピラージャパン合同会社及び住友建機株式会社は,油圧ショベルのほ かにも,ブルドーザー,クレーン,ホイールローダー等も製造販売しており,また, ミニショベルを製造販売する株式会社クボタ,ヤンマーホールディングス株式会社, 株式会社竹内製作所等は,農機も製造販売しているのであって,同一の事業者が, 油圧ショベルのほか,それ以外の建設機械や農機を製造販売している(甲42,4 4の1〜8,45)。 市場分析においても,油圧ショベルは,ブルドーザー,クレーン,ロードローラ等 とまとめて,建設機械に係る業界として扱われている(甲42)。 建設機械等の取引においては,製品の機能や信頼性を検討し,メーカー名や\n商品名等を明記した注文書や物品受領書などを介して取引が行われている(甲21 の1〜6)。
(3) 使用による自他商品識別力について
ア 本願商標の色彩を付した油圧ショベルの販売について 前記(2)ア,イのとおり,原告は,約50年にわたり,本願商標の色彩を車体の少 なくとも一部に使用した油圧ショベルを販売しており,その販売台数及びシェアは, ミニショベルを除く油圧ショベルが合計約●●●台で概ね20%,ミニショベルが 合計約●●台で概ね10%前後であって,それぞれ年間数千台の販売実績を上げて いることが認められる。 しかしながら,本願商標の色彩であるオレンジ色は,「赤みを帯びた黄色」(乙1) であり,JISの色彩規格に,慣用色名としてオレンジ色が挙げられ(乙2),本願 商標の色彩と同じ色相が色相環に挙げられ,近似した色見本が挙げられるなど(乙 3),ありふれた色である。そして,本願商標の色彩と類似した色彩である橙(マン セル値:5YR 6.5/14)は,人への危害及び財物への損害を与える事故防止 などを目的として公表されているJIS安全色にも採用され(乙10,11),ヘル\nメット(乙4),レインスーツ(乙5),ガードフェンス(乙6),特殊車両(乙7),タワークレーン(乙8),現場作業着(乙9)等に利用されていることが認められ, 建設工事の現場において,一般的に使用される色彩である。 また,前記(2)アのとおり,原告の販売する油圧ショベルの多くには,本願商標の 色彩のほか,アーム部や車体等に白抜き又は黒文字で著名商標である「HITAC HI」又は「日立」の文字が付されており,カタログにも原告の社名や「HITAC HI」又は「日立」の文字の記載があること,本願商標が,単色でなく他の色彩と組 み合わせて車体の一部にのみ使用されている商品も少なくないことに照らせば,本 願商標の色彩は,これらの文字や色彩と合わせて原告の商品である油圧ショベルを 表示しているというべきである。\n以上によれば,原告が本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧シ ョベルを販売したことにより,本願商標の色彩のみが独立して,原告の油圧ショベ ルの出所識別標識として,日本国内における需要者の間に広く認識されていたとま では認められない。
イ 広告宣伝について
前記(2)ウのとおり,原告は,本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した 油圧ショベル等の建設機械の画像を用いた宣伝広告を,新聞,雑誌等の各種広告媒 体によって,少なくとも20年以上にわたり行っていることが認められる。 しかしながら,これらの広告等には,いずれも,原告の社名が表示されている上,\nその多くに「HITACHI」又は「日立」の文字が併せて記載されており,本願商 標の色彩のみが独立して,原告の商品である油圧ショベルの出所を表示していると\nはいえない。 また,これらの広告等の中には,油圧ショベルのモチーフが,オレンジ色をした 五線譜上の音符や将棋の駒として表示されたり,オレンジを背景にしたキリンのシ\nルエットとして表示されたりするなど,デザインの一環として用いられ,広告内容\nが油圧ショベルと関連付けられたものではないものも存在し(甲59の2・8・9 等),このような広告は,視聴者に対し,オレンジ色が原告のコーポレートカラーで あると印象付け,本願商標の色彩を一定程度認知させるものとはいえても,色彩と 商品の結び付きは弱く,このことから直ちに,本願商標の色彩が,原告の油圧ショ ベルの出所識別標識として,広く認識されたとまで認めることは困難である。 以上によれば,本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧ショベル の画像を用いた宣伝広告により,本願商標の色彩が,原告の油圧ショベルの出所識 別標識として,需要者の間に広く認識されたとまではいえない。
ウ 本件アンケートの結果
本件アンケートの調査対象は,全国の油圧ショベルの取引者及び需要者とされる ものの,ホイールローダ,ダンプトラック,道路機械,環境機械等の需要者や,農業 や酪農など土木建設業者以外の業種の者が除かれている上,油圧ショベルを10台 以上保有している者のみに絞られているから,対象者は油圧ショベルの需要者の一 部に限定されている。また,対象者数は,約●●●件の需要者のうちの502件で あり,有効回答数はその38.6%である193件にとどまる。そして,認知率9 5.9%という高い数字は,有効回答数193件に対する数字であり,対象者数5 02件に対しては36.8%にとどまる。 本件アンケートの質問方法は,本願商標の色彩の画像を見せた上で,「どのメーカ ーの油圧ショベルかをお答えください」と尋ねるものであるところ,かかる質問は, 本願商標が出所識別標識と認識されることを前提とするものであるから,その回答 によって,本願商標が原告のみの出所識別標識と認識されていることを示している のか,単に原告の油圧ショベルの車体色と認識するにとどまるのかを区別すること はできない。 以上によれば,本件アンケートの結果のみから直ちに,本願商標の色彩が出所識 別標識として認識され,本願商標が付された油圧ショベルの出所が原告のみである ことが広く認知されていたものと認めることはできない。
エ 原告以外の者による本願商標に類似する色彩の使用 前記(2)オのとおり,本件審決時(令和元年9月19日)までに,住友建機株式会 社,DOOSAN等が,車体色がオレンジ色の油圧ショベルを販売し,株式会社ク ボタやイワフジ工業株式会社等が,車体色がオレンジ色の農機や林業用機械を販売 していたこと,また,株式会社クボタ等が,車体色がオレンジ色のホイールローダ, ショベルローダ,キャリア,フォークリフト,クレーン車,高所作業車等の建設機械 を販売していたことが認められ,農機等を含む油圧ショベルや各種建設機械の車体 色として,複数の事業者によりオレンジ色が広く採択されていた。 そうすると,原告が本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧ショ ベルを長期間にわたり相当程度販売していたとしても,油圧ショベルと需要者が共 通する建設機械や,油圧ショベルの用途とされる農機,林業用機械の分野において, 車体色としてオレンジ色を採用する事業者が原告以外にも相当数存在していたので あるから,原告が,他者の使用を排除して,油圧ショベルについて本願商標の色彩 を独占的に使用していたとまでは認められない。
オ 油圧ショベルの取引の実情
前記(2)カのとおり,油圧ショベルは,建設機械の一種であり,建設業のほか農業 や林業にも利用され,同一の事業者が油圧ショベルのほか,それ以外の建設機械や 農機を製造販売している。また,油圧ショベルを含む建設機械は,製品の機能や信\n頼性を重視し,メーカーを確認して製品の選択が行われ,価格も安価なものではな いことから,製品を識別し購入する際に,車体色の色彩が果たす役割が大きいとは いえない。
カ 以上のとおり,原告は,本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した 油圧ショベルを長期間にわたり相当程度販売するとともに,継続的に宣伝広告を行 っており,本願商標の色彩は一定の認知度を有しているとはいえるものの,その使 用や宣伝広告の態様に照らすなら,本願商標の色彩が,需要者において独立した出 所識別標識として周知されているとまではいえない。そして,本願商標は,輪郭の ない単一の色彩で,建設現場等において一般的に採択される色彩であること,油圧 ショベル及びこれと需要者が共通する建設機械や,油圧ショベルの用途とされる農 機,林業用機械の分野において,本願商標に類似する色彩を使用する原告以外の事 業者が相当数存在していること,油圧ショベルなど建設機械の取引においては,製 品の機能や信頼性が検討され,製品を選択し購入する際に車体色の色彩が果たす役\n割が大きいとはいえないこと,色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべ き公益的要請もあること等も総合すれば,本願商標は,使用をされた結果自他商品 識別力を獲得し,商標法3条2項により商標登録が認められるべきものとはいえな い。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2020.07.17
平成31(ネ)10015 特許権 民事訴訟 令和2年6月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
このように本件明細書には,「発酵原料」として「大豆胚軸」を使用 した場合の発酵処理及び実施例の記載はあるが,一方で,「発酵原料」 として「大豆胚軸抽出物」を使用した場合の発酵処理及び実施例に関す る記載はない。
(エ) 前記(ア)ないし(ウ)によれば,本件明細書には,「本発明」(「大 豆胚軸発酵物」)の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」 とを明確に区別した上で,発酵原料として使用される「大豆胚軸」は, 「含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として,大 豆の産地や加工の有無について制限され」ず,「脱脂処理や脱タンパク 処理に供したもの」も使用することができ,発酵原料にイソフラボンを\n別途添加しておくことにより,得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール 含量をより高めることが可能となることを開示し,他方で,コストが高\nく,エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大 豆胚軸抽出物」は,「本発明」(「大豆胚軸発酵物」)の発酵原料に適 さないことの開示があることが認められる。
ウ 検討
以上の本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書 の記載を前提に検討するに,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)に は,本件発明1の「大豆胚軸発酵物」(構成要件1−C)を定義した記載\nはなく,その発酵原料となる「大豆胚軸」を特定の成分のものに限定する 記載もないが,一方で,本件明細書では,「大豆胚軸発酵物」の発酵原料 として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で,コス トが高く,エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる 「大豆胚軸抽出物」は,発酵原料に適さないことの開示があることに照ら すと,かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は,本件発明1 の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当である。 もっとも,本件明細書には,発酵原料に適さない「大豆胚軸抽出物」の 成分やイソフラボン含量等についての開示はないことは,前記イ(イ)aの とおりである。 しかるところ,大豆胚軸からイソフラボンを含有する成分の抽出処理は,\n一般に,水,アルコール(エタノール等)又は含水アルコールなどの溶媒 を用いた抽出によって行われるが,大豆胚軸から高濃度のイソフラボンを\n含有する「大豆胚軸抽出物」を得るには,このような抽出処理に加え,合 成吸着樹脂を用いた濃縮操作等の精製処理が必要であることは,本件特許 の優先日当時の技術常識であったことが認められる(例えば,甲43の【0 011】,【0012】,甲46の【0002】ないし【0005】,甲 49の【0013】ないし【0015】)。 そして,高濃度のイソフラボンを含有する「大豆胚軸抽出物」は,コス\nトが高く,エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる ことは自明であるから, かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発 酵物は,本件発明1の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと認めるのが 相当である。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2020.07.14
令和1(ネ)10044 損害賠償等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和2年1月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これに対し,控訴人は,本件技術情報1ないし6,8ないし17及び 26には,乙11記載の公知文献等に記載された情報が含まれており, 非公知性は認められない旨主張する(乙11)。 しかしながら,本件技術情報は,電磁鋼板の生産現場で採用されてい る具体的条件を含むものであり,乙11記載の公知文献等に記載されて いる研究開発段階の製造条件とは,技術的位置付けが異なる。また,乙 11記載の公知文献等に記載されている製造条件は,文献毎にばらつき があったり,一定の数値範囲を記載するにとどまるものである。そして, 電磁鋼板は多段階工程で製造され,高品質の電磁鋼板を製造するために は,各工程の最適条件の組合せが必要とされるのであって,一工程の一 条件のみでは高品質の電磁鋼板を製造することはできない。 したがって,乙11記載の公知文献等に本件技術情報の具体的な条件 を含む記載があるというだけでは,生産現場で実際に採用されている具 体的な条件を推知することはできず,非公知性は失われていないという べきである。 そして,以下に述べるとおり,本件技術情報1ないし6,8ないし1 7及び26には,乙11記載の公知文献等に記載された情報が含まれて おり,非公知性は認められない旨の控訴人の主張は理由がない。
(ア) 本件技術情報1について
控訴人は,本件技術情報1は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等に記載された情報 とは性質を異にするものであるから,大量の情報の中に本件技術情報 1に近い情報が存在しているからといって,非公知性は否定されない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
◆判決本文
原審はこちら
2020.07.14
令和1(行ケ)10096 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年6月3日 知的財産高等裁判所
甲2において,シランカップリング剤は,金属アルコキシドやその他の物質のポ リイミド系重合体の前駆体であるポリアミック酸系重合体への分散性,混合性を向 上させ,熱膨張率などの特性にもとづく寸法安定性を改善することを目的とするも のであり,本件発明2のように,「支持体と十分な密着性」を有し,かつ,「物理的\nな方法で綺麗に剥離する」というものではないから,本件発明2とは異なる目的の ために配合されている。
甲3において,アルコキシシラン化合物は,透明性を損なわずに,寸法安定性に 優れ,かつ無機化合物基板との密着性が高いシリカ粒子が分散してなる新規なポリ イミド組成物及びその製造方法を提供するために,ポリイミド溶液に添加し,ポリ イミド溶液において水の存在下で反応させるものであり,本件発明2において,ア ルコキシシランが,ポリイミド前駆体であるポリアミド酸の組成物に配合されるの とは,配合対象が異なっている上,本件発明2のように,「支持体と十分な密着性」\nを有し,かつ,「物理的な方法で綺麗に剥離する」というものではないから,本件発 明2とは異なる目的のために配合されている。
甲4は,ポリイミド銅張積層板のポリイミド層と銅箔との間の接着性を高めるた めに,ポリイミド前駆体コーティング溶液中に,アルコキシシランを組み込むとい うもので,本件発明2のように,「支持体と十分な密着性」を有し,かつ,「物理的\nな方法で綺麗に剥離する」というものではないから,本件発明2とは異なる目的の ために配合されている。
甲5は,良好な熱伝導性と接着性を有し,さらに,良好な耐熱性を有する樹脂組 成物を提供することを目的とするものであるが,(C)成分の例として,3−ウレイ ドプロピルトリエトキシシランを含む組成物が,ポリイミド樹脂と無機フィラーの 相溶性を高め,ボイド(空隙)を抑制し,少ない無機フィラー含量でも高い熱伝導 性が得られると記載されており,本件発明2のように,「支持体と十分な密着性」を\n有し,かつ,「物理的な方法で綺麗に剥離する」というものではないから,本件発明 2とは異なる目的のために配合されている。
甲6は,電子部品の絶縁膜又は表面保護膜用樹脂組成物,パターン硬化膜の製造\n方法及び電子部品に関するものであり,最終加熱時においてメルトを起こすことな く,最終加熱以降の加熱においても架橋成分等の昇華及びガス成分の発生が少ない 層間絶縁膜又は表面保護膜を製造するために,3−ウレイドプロピルトリエトキシ\nシランを添加することができる(段落【0057】)というものであり,シリコン基 板に対する接着性増強剤として3−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン,ビ ス(2−ヒドロキシエチル)−3−アミノプロピルトリエトキシシランなどのアル コキシシラン化合物を含むことができる(段落【0069】)との記載があるが,「支 持体と十分な密着性」を有し,かつ,「物理的な方法で綺麗に剥離すること」が可能\ なポリイミド樹脂膜を形成することが可能な樹脂組成物を提供するという本件発明\n2とは添加目的が異なっている。
g 以上によると,甲2〜6によって,甲2〜6にされたアルコキシシ ラン化合物を本件発明2のために用いるという動機付けがあるとは認められないか ら,相違点3が容易想到であると認めることはできない。 なお,甲2〜6には,ポリイミド前駆体に添加するシランカップリング剤として, 本件発明2における4種のアルコキシシラン化合物のうちの少なくとも1種と甲1 記載の他種のものが並列的に列挙されているとしても,甲2〜6は,アルコキシシ ラン化合物を使用する目的や対象が本件発明2とは異なるから,本件発明2におい て,甲2〜6に記載するアルコキシシラン化合物を用いることが容易想到であると は認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.07.14
平成31(ネ)10024 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和2年6月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,原告ウェブページに,原告商標が付された原告腕時計 4本の画像を掲載した旨主張する。 しかしながら,原告ウェブページの写真である甲62は,そこに 表示された4本の腕時計の画像が不鮮明であるため,同画像からは,\nこれらの腕時計の文字盤にいかなる標章が付されているのかを認識 することはできず,その他に,原告ウェブページに原告商標を付し た腕時計が表示されていることを認めるに足りる証拠はない。\nこれに対し控訴人は,仮に上記画像のみから「moto」の文字をは っきり認識できないとしても,同画像の右横に原告商標が大きく表\n示され,更に「moto」が控訴人の登録商標である旨の記載もあるこ と,腕時計の文字盤に商標が付されることは極めて多いことに鑑み れば,画像の文字盤に付された欧文字が「moto」であることを十分\nに認識できる旨主張する。 しかしながら,そもそも,原告ウェブページに表示された腕時計\nの画像は不鮮明であって,文字盤に欧文字が付されていると認識す ることは困難であるし,腕時計の文字盤に常に商標が付されるもの であるとも認められない。また,前記(1)ア(ア)で認定した原告ウェ ブページにおける画像等の配置や全体の構成に照らしても,「moto」 が登録商標である旨の説明文は,その上方に近接して表示された原\n告商標について説明する文章と理解するのが自然であるから,これ らの表示から,腕時計の画像に「moto」の標章が付されていること を認識するものではないといえる。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。 以上によれば,要証期間内に,原告商標が付された腕時計の画像 が原告ウェブページに表示されたと認めることはできない。\n
(イ) 原告商標の表示\n
a 前記(1)ア(ア)のとおり,原告ウェブページには,腕時計の品名, 品番,値段,商品説明等についての記載や,控訴人の腕時計が将 来発売予定であること,個別の商談により購入が可能\であること を説明する記載はない。 そして,かかる原告ウェブページの体裁,記載からは,少なく とも平成30年3月6日頃に原告更新ウェブページが作成され, 腕時計の品名,品番,値段,商品説明等についての具体的な記載 が掲載されるまでの間は,控訴人において,同ウェブページに画 像が表示された腕時計が実際に製造され,商品として購入できる\n実態があったことを推認することはできないというべきである。 以上によれば,原告ウェブページに表示された原告商標や「moto 時計」のウェブページである旨の表示は,商品である「腕時計」\nについて使用されたものとは認められない。
b これに対し控訴人は,(1)原告ウェブページに原告腕時計の商品 名等を表示しなかったのは,原告腕時計の画像を原告ウェブペー\nジに掲載した当時は,原告腕時計の販売や取引先に対する営業活 動の開始前だったからである,(2)原告ウェブページに掲載された 原告腕時計の画像は,控訴人が君園に発注して納品を受けた腕時 計につき,中華撮影が広告用に撮影したものを使用して,原告ウ ェブページ掲載用に作成したものであって,甲121ないし12 3は君園から受領した原告腕時計の見積書及びデザイン画像,甲 126は中華撮影から受領した原告腕時計の写真の納品書,甲1 27は原告ウェブページ用に作成した写真である旨主張し,Fの 第2次審判における証人尋問録音の反訳(乙226)及び同人の 陳述書(甲80。上記反訳と併せて,以下「Fの陳述書等」とい う。),君園の社長の陳述書(甲194)及び中華撮影の写真家の 陳述書(甲195)中には,これに沿う部分がある。 しかしながら,(1)についていえば,控訴人主張の事情は,原告 更新ウェブページが作成されるまでの 1 年以上にわたり,原告ウ ェブページに原告腕時計の品目,品番,商品説明等の一切が表示\nされていないことの説明になるものではない。また,(2)も,以下 の点に照らせば,採用できるものではない。 すなわち,甲122のデザイン画像は,腕時計本体の写真がや や不鮮明であるのと対照的に,文字盤上の「moto」の文字又は文 字盤全体が不自然なほど鮮明で浮き上がっているように見えるも のであり,画像データを加工等して作成された画像であることが うかがえる。また,同画像が添付された電子メール(甲122) には本文がなく,これらの画像の作成目的,作成方法等も証拠上 明らかでない。 そして,甲121の見積書には,「製品明細」(「ステンレス サ ファイアガラス 日本製ムーブメント 手作箱及び説明書」),「注 意事項」(「腕時計サンプル製作」),「数量」(合計16個)等の記 載があるものの,商品の単価やサンプル製作納期の記載がないな ど,不自然な点も少なくなく,「製品明細」に記載されたとおりの 製品が製造されたことを示す写真等の客観的な証拠もない。また, 控訴人は,甲123の見積書は,納品書兼領収書の役割を果たす ものであって,甲121の見積書に対応するものである旨主張す るが,甲123の見積書にも製品の単価等の記載はない。 さらに,甲126の納品書には,中華撮影が控訴人に対して単 価400台湾ドルの写真19枚を納入し,控訴人からその代金を 受領した旨の記載があるものの,納品する写真の画像等は添付さ れていないため,これらの証拠からは,納入された写真が原告腕 時計のものであるかは明らかでない。 加えて,文字盤に「moto」の標章が付されていることが認識で きる4本の腕時計の写真(甲127)も,その作成時期,作成経 緯は明らかでなく,これが原告ウェブページ上の腕時計の画像と 同一のものであることを裏付ける客観的な証拠はない。 以上によれば,控訴人の上記主張を採用することはできないと いうべきである。
(ウ) 原告商標の使用の有無
前記(ア)及び(イ)によれば,控訴人が,原告ウェブページに腕時 計の画像及び原告商標の表示等を表\示したことをもって,原告商標 の使用(商標法2条3項8号)に該当すると認めることはできない。
イ A社との取引について
(ア) 控訴人は,取引先であるA社に対し,原告腕時計の写真及びサ ンプルを送るので,同商品の販売を検討してほしい旨依頼し,平成 29年5月15日頃,原告腕時計を譲渡して,引き渡したものであ り,同月12日付のA社宛メールには,原告商標が付された原告腕 時計1本の画像が添付されており,伝票の品名欄に「moto 腕手時 ×1点 サンプル」と記載されている同日付のA社宛宅配伝票によ り,A社宛に原告腕時計を発送したものである旨を主張し,A氏の 供述,調査嘱託の結果及びFの陳述書等中には,これに沿う部分が ある。 しかしながら,A社宛メールに添付された腕時計の写真(甲20 2)は,文字盤部分の画像が,他の部分(時計のバンド,時計の背 景等)と比べて不鮮明であって,文字盤上の「moto」の文字及び針 のみが浮き上がるように見えるなど不自然なものであって,文字盤 部分について加工が行われたのではないかとの疑いを払拭すること ができない。また,A社宛宅配伝票(甲203)の品名欄に「moto 腕手時×1点サンプル」の記載があるとの事実は,同宅配便によっ て原告腕時計が配送されたことを客観的に裏付けるものではない。 加えて,A社の取扱商品,控訴人とA社との取引実績,控訴人と A社代表者との人的関係等,控訴人とA社との関係に関する認定事\n実(前記(1)イ)に照らすと,控訴人が,控訴人との取引実績も,腕 時計の販売実績も全くないA社に対して,腕時計を販売してもらう ためのサンプルとして原告商標を付した原告腕時計を譲渡したとの 主張には,不自然かつ不合理な点があるといわざるを得ず,せいぜ い,控訴人と親しい関係にあるA社(又はA氏個人)に対し,腕時 計を参考送付して,商品化の可能性等について意見を求める程度の\nことがあったにすぎないものと考えられる。 以上によれば,控訴人がA社に対して原告商標を付した原告腕時 計の譲渡及び引渡しをした事実を認めることはできないし,仮に控 訴人からA社に腕時計が送付された事実があったとしても,それが 「商品」としての腕時計の送付であったと認めることは困難である。 また,上記のとおり,控訴人とA社の間で,原告商標を付した原告 腕時計に係る取引がされたものと認めることはできないことから, A社宛メール及びA社宛宅配伝票に「moto」の表記をしたことは,\n取引書類に原告商標を付したものとはいえない。 したがって,控訴人とA社との連絡に関し,原告商標の使用(商 標法2条3項8号)を認めることはできない。
(イ) なお,控訴人は,前記(ア)のA社との取引以外にも,B社,C 社及びD社に対して原告腕時計の販売を検討してほしい旨依頼し, 原告腕時計のサンプルを送付したり,ギフト・ショーに原告商標を 付した原告腕時計を展示し,同腕時計の写真を掲載したカタログを 頒布したりしたものであり,これらの事実はいずれも要証期間後の ものではあるが,控訴人が要証期間内に腕時計について原告商標を 使用した事実を補強するものである旨主張する。 しかしながら,控訴人の主張する上記事実は,そもそも要証期間 後の事実である上,B社,C社及びD社の実在性や控訴人との関係 も明らかでないこと等に照らし,これらの事実から,要証期間内の 控訴人による原告商標の使用の事実を推認することは到底困難であ る。
・・・
以上によれば,要証期間内において,原告商標が腕時計について使用 されたとは認められず,原告商標の指定商品中「腕時計」は,商標登録 取消審判により取り消されるべきものということができ,実際にも,本 判決前記第2の2のとおり,第2次審判の請求に基づき,商標登録の取 消審判がされている(ただし,審決取消訴訟が係属中)状況にある。 なお,控訴人は,仮に商標登録取消審判が成立したとしても,被告商 品は,「卓上時計(置き時計)」としても使用され,また,携帯型の時計 である点において「懐中時計」と同じであるから,腕時計を除く「時計」 と同一又は類似するものといえ,差止請求が認められることに変わりは ない旨主張する。 しかしながら,前記(引用に係る原判決第4の2(1))のとおり,被告 商品の内容や性質に照らすと,被告商品は,その指定商品の区分として は,第9類の「情報処理用の機械器具」に該当し,第14類の「時計」 には該当しないと解するのが相当である。 また,被告商品はスマートウォッチと呼ばれる商品であるところ,前 記認定(引用に係る原判決第4の2(2)イ)の被告商品の生産,販売,原 材料,品質,用途,需要者等に関する諸事情に照らすと,被告商品が, 原告商標の指定商品「時計」のうち,「腕時計」と類似の商品であるとい うことができるのは格別,その他の指定商品(「腕時計」を除く「時計」) とも類似の商品であるとは認められない(なお,被告商品のユーザーガ イドには,「卓上時計としても使えます」との記載があることは前認定の とおりであるが,これは,卓上に置けば,事実上卓上時計としての機能\nも果たすということを述べているのにすぎないと認められるから,これ によって卓上時計との商品としての類似性が肯定されることになるもの ではない。)。 したがって,控訴人の上記主張は理由がなく,控訴人による差止請求 は,権利の濫用として許されないというべきである。
(4) 一方,商標法54条2項により原告商標権の指定商品中「腕時計」が 消滅する効果が発生するのは,平成29年6月23日(第2次審判の審 判請求登録日)であるところ,控訴人が損害賠償を求めている期間は, 平成28年7月から平成29年2月までであるので,損害賠償請求との 関係では,権利濫用の抗弁は失当である。」
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.07.14
令和1(行ケ)10094 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年6月4日 知的財産高等裁判所
原告ウェブページについて
ア 腕時計の画像の表示\n
原告は,原告ウェブページに,本件商標が付された原告腕時計4本の画 像(甲23の1〜3)を掲載した旨主張する。 しかしながら,原告ウェブページの写真である甲23の1〜3は,そこ に表示された4本の腕時計の画像が不鮮明であるため,同画像からは,こ\nれらの腕時計の文字盤にいかなる標章が付されているのかを認識すること はできず,その他に,原告ウェブページに本件商標を付した腕時計が表示\nされていることを認めるに足りる証拠はない。
これに対し原告は,仮に上記画像のみから「moto」の文字をはっきり認 識できないとしても,同画像の右横に本件商標が大きく表示され,更に\n「moto」が原告の登録商標である旨の記載もあること,腕時計の文字盤に 商標が付されることは極めて多いことに鑑みれば,画像の文字盤に付され た欧文字が「moto」であることを十分に認識できる旨主張する。\nしかしながら,そもそも,原告ウェブページに表示された腕時計の画像\nは不鮮明であって,文字盤に欧文字が付されていると認識することは困難 であるし,腕時計の文字盤に常に商標が付されるものであるとも認められ ない。また,前記1(2)で認定した原告ウェブページにおける画像等の配置 や全体の構成に照らしても,「moto」が登録商標である旨の説明文は,その 上方に近接して表示された本件商標について説明する文章と理解するのが\n自然であるから,これらの表示から,腕時計の画像に「moto」の標章が付 されていることを認識するものではないといえる。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 以上によれば,要証期間内に,本件商標が付された腕時計の画像が原告 ウェブページに表示されたと認めることはできない。\n
イ 本件商標の表示\n
(ア) 前記1(2)のとおり,原告ウェブページには,腕時計の品名,品番, 値段,商品説明等についての記載や,原告の腕時計が将来発売予定であ\nること,個別の商談により購入が可能であることを説明する記載はない。\nそして,かかる原告ウェブページの体裁,記載からは,少なくとも平 成30年3月6日頃に原告更新ウェブページが作成され,腕時計の品名, 品番,値段,商品説明等についての具体的な記載が掲載されるまでの間 は,原告において,同ウェブページに画像が表示された腕時計が実際に\n製造され,商品として購入できる実態があったことを推認することはで きないというべきである。 以上によれば,原告ウェブページに表示された本件商標や「moto 時計」 のウェブページである旨の表示は,商品である「腕時計」について使用\nされたものとは認められない。
(イ) これに対し原告は,(1)原告ウェブページに原告腕時計の商品名等を 表示しなかったのは,原告腕時計の画像を原告ウェブページに掲載した\n当時は,原告腕時計の販売や取引先に対する営業活動の開始前だったか らである,(2)原告ウェブページに掲載された原告腕時計の画像は,原告 が君園に発注して納品を受けた腕時計につき,中華撮影が広告用に撮影 したものを使用して,原告ウェブページ掲載用に作成したものであって, 甲44ないし46は君園から受領した原告腕時計の見積書及びデザイン 画像,甲49は中華撮影から受領した原告腕時計の写真の納品書,甲5 0は原告ウェブページ用に作成した写真である旨主張し,原告の従業員 であるEの本件審判における証人尋問録音の反訳(甲20,80)及び 同人の陳述書(甲28。上記反訳と併せて,以下「Eの陳述書等」とい う。),君園の社長の陳述書(甲94)及び中華撮影の写真家の陳述書(甲 95)中には,これに沿う部分がある。 しかしながら,(1)についていえば,原告主張の事情は,原告更新ウェ ブページが作成されるまでの1 年以上にわたり,原告ウェブページに原 告腕時計の品目,品番,商品説明等の一切が表示されていないことの説\n明になるものではない。また,(2)も,以下の点に照らせば,採用できる ものではない。
すなわち,甲45のデザイン画像は,腕時計本体の写真がやや不鮮明 であるのと対照的に,文字盤上の「moto」の文字又は文字盤全体が不自 然なほど鮮明で浮き上がっているように見えるものであり,画像データ を加工等して作成された画像であることがうかがえる。また,同画像が 添付された電子メール(甲45)には本文がなく,これらの画像の作成 目的,作成方法等も証拠上明らかでない。 そして,甲44の見積書には,「製品明細」(「ステンレス サファイア ガラス 日本製ムーブメント 手作箱及び説明書」),「注意事項」(「腕時 計サンプル製作」),「数量」(合計16個)等の記載があるものの,商品 の単価やサンプル製作納期の記載がないなど,不自然な点も少なくなく, 「製品明細」に記載されたとおりの製品が製造されたことを示す写真等 の客観的な証拠もない。また,原告は,甲46の見積書は,納品書兼領 収書の役割を果たすものであって,甲44の見積書に対応するものであ る旨主張するが,甲46の見積書にも製品の単価等の記載はない。 さらに,甲49の納品書には,中華撮影が原告に対して単価400台 湾ドルの写真19枚を納入し,原告からその代金を受領した旨の記載が あるものの,納品する写真の画像等は添付されていないため,これらの 証拠からは,納入された写真が原告腕時計のものであるかは明らかでな い。 加えて,文字盤に「moto」の標章が付されていることが認識できる4 本の腕時計の写真(甲50)も,その作成時期,作成経緯は明らかでな く,これが原告ウェブページ上の腕時計の画像と同一のものであること を裏付ける客観的な証拠はない。 以上によれば,原告の上記主張を採用することはできないというべき である。
ウ 本件商標の使用の有無
前記ア及びイによれば,原告が,原告ウェブページに腕時計の画像及び 本件商標の表示等を表\示したことをもって,本件商標の使用(商標法2条 3項8号)に該当すると認めることはできない。
◆判決本文
同一商標権の侵害訴訟の控訴審です。
◆平成31(ネ)10024
上記控訴審の1審判決です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2020.07.14
平成29(ワ)15776 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成31年2月22日 東京地方裁判所
そこで検討するに,本件においては,以下の事実を認めることができる。
(ア) 時計としての機能\nスマートウォッチ及び被告商品が時計としての機能を有することにつ\nいては,当事者間に争いがない。
(イ) 製造業者
いわゆるスマートウォッチと呼ばれる商品は,アップル社,韓国LG 電子,サムスンなどのIT企業に限らず,セイコーウォッチ,フォッシ ル,タグ・ホイヤー,シチズン,スカーゲン,フレデリック・コンスタ ント,カシオ計算機などの時計メーカーによっても製造,販売されてい る(甲30,43,47,52,乙173)。 そして,スマートウォッチ市場には,平成28年頃から時計メーカー の参入が続き(甲43〜46),平成28年9月21日付け東京読売新 聞(甲52)は,「時計メーカー 参入続々 スマートウォッチ IT 企業と差別化」との表題の下,「米アップルなどのIT企業だけでなく,\n腕時計メーカーが相次いで参入している」と報じている。
(ウ) 販売状況
a 小売店における商品の展示状況
平成29年7月から10月の時点において,ビックカメラ有楽町店 の3階健康家電売場にウェアラブルウォッチのコーナーが,6階に時 計売場がそれぞれ設けられているが,シチズン,カシオ,タグ・ホイ ヤー,フォッシルなどのブランドの商品が展示された6階時計売場の ショーケースでは,同ブランドのスマートウォッチとそれ以外の腕時 計が並べて陳列されている(甲53,109,乙19)。他方,同年 6月の時点において,被告店舗では,被告商品は8階の携帯電話用品 売場で販売され,腕時計は10階の腕時計売場で販売されていた(乙 2)。 原告及び被告の行った調査を総合すると,平成29年9月及び10 月の時点において,東京,神奈川,千葉,埼玉,大阪,京都に所在す る28の時計店のうち,スマートウォッチと通常の腕時計の両方を取 り扱っている店舗は17店であった(甲109,乙19。なお,タイ ムステーションNEOの堺鉄砲町店とトレッサ横浜店は同一店舗とし て計算している。)。
b ネットショッピングにおける商品の区分
平成29年7月の時点において,ビックカメラのインターネット通 販サイトでは,カシオのスマートウォッチが「国内メーカー腕時計(男 性向け)」のカテゴリーで,通常の腕時計とともに販売されている(甲 54)。また,アマゾンのウェブサイトにおいて,被告商品は「家電・ カメラ・AV機器」というカテゴリーで扱われている(なお,腕時計 は「Amazon Fashion」というカテゴリーで扱われてい る。)が,「moto 腕時計」で検索すると被告商品が表示される\n(甲11〜13,81〜88,乙21)。さらに,ヤフーショッピン グのウェブサイトでは,被告商品は「腕時計・アクセサリー」カテゴ リーの中の「スマートウォッチ」に分類され(甲89〜93),楽天 市場のウェブサイトには被告商品を「腕時計」と分類している店舗が ある(甲96)。上記の3つのウェブサイトには,被告商品を「スマ ートウォッチ 腕時計」と表示しているものがある(甲82,83,\n89〜95)。
(エ) 被告商品の説明,使途等
a 被告商品を製造したモトローラ・モビリティのウェブサイト(平成 28年当時)には,時計表示の被告商品の写真が掲載されるとともに,\n「あなたの時間を刻む時計を選ぶ」などと表記されている(甲7,1\n0,11)。
b モトローラ・モビリティが作成した被告商品のユーザーガイドの表\n紙には時計表示がされた被告商品の写真が掲載されるとともに,その\n「概要」ページには,被告商品を「新型の時計Moto360(第2世 代)」と紹介した上で,その初期画面が時計表示であることが説明さ\nれ,さらに,「卓上時計としても使えます」,「お客様の時計は」,「時 計にどのような機能があるのか探索してみてください」,「1台の時\n計にさまざまな表情」などの記載が存在する(甲15)。\n
c シネックスインフォテック,Amazon,楽天ブックス等の正規 販売店及び正規販売店以外の販売業者による被告商品の広告には,全 て時計表示の被告商品の写真が掲載されている(甲8〜13,81〜\n96)。また,シネックスインフォテックは,被告商品について,「ス マートフォンに対応しており,腕に付けた時計に必要な情報をタイム リーにお知らせします」,「ウォッチフェイスを自由に変更して時計 の雰囲気を変え」などと紹介している(甲8)。
(オ) 原材料及び品質
被告商品は,1.56インチLCDゴリラガラス3採用のディスプレ イ,筐体(本体ステンレススチール,裏面プラスチック),心拍センサ ー,光センサー,バッテリーと,Android WearというOS, CPU,RAM,ROMなどから構成される(乙22)。\n通常のアナログ時計は,地板,歯車,電池,コイルブロック,巻真等 で構成され,デジタル時計は地板,液晶パネル,反射板,回路スペーサ\nー回路ブロック,電池絶縁版等から構成される(乙23)。\n
(カ) 需要者の範囲
a 雑誌における取扱い
スマートウォッチの雑誌における取扱いについてみると,スマート ウォッチは,「Men’s JOKER WATCH」,「時計 F INEBOYS」,「WATCH NAVI」といった腕時計専門雑 誌,「Men‘s NON−NO」,「AERA STYLE MA GAZINE」などのファッション雑誌や,「mono(モノ・マガ ジン)」,「MonoMax(モノマックス)」,「日経TREND Y」などの雑誌における腕時計特集において,通常の腕時計とともに 紹介されている(甲30〜42,44〜49)。 また,「時計 FINEBOYS VOL.12」(平成29年5 月発行)の「ゼロからわかる!腕時計の100識」という小冊子の「時 計のタイプを知る。」という項目において,スマートウォッチは,デ ジタルウォッチ,デザインウォッチ等と並び,腕時計のタイプの一つ として紹介されている(甲31)ほか,「AERA STYLE M AGAZINE Vol.35」(平成29年7月発行)の腕時計に 関するアンケートでは,「どの種類の時計が欲しい?」という質問の 選択肢として,機械式時計,クォーツ等と並び,スマートウォッチが 挙げられている(甲33)。
b 価格
被告商品は,アマゾンのウェブサイトで3万8000円から4万4 000円程度の価格帯で販売されているが(甲10〜13),スマー トウォッチ一般の値段は商品によって様々であり(甲32,37,4 3,45,51,105),高価格のものは30万円を超えている(甲 51)。他方,通常の腕時計の価格も,数千円台のもの(甲31)か ら100万円を超えるもの(甲33)まで様々である。
ウ 上記認定事実によれば,スマートウォッチの市場には時計メーカーも参 入し,IT企業のみならず,時計メーカーも腕時計等の時計に加えてスマ ートウォッチを製造,販売しているとの事実が認められる。このように, 腕時計とスマートウォッチでは製造業者が共通し,時計メーカーが時計製 造で培った技術を活かし,スマートウォッチ市場に参入している状況が看 取される。 また,販売状況を見ても,ビックカメラ有楽町店の例に見られるように, スマートウォッチと時計の売り場が共通している店舗もあり,原告及び被 告の行った調査結果によれば,時計店の中にはスマートウォッチと腕時計 の両方を取り扱っている店が相当程度あることがうかがわれ,ネットショ ッピングにおいても,スマートウォッチと腕時計のカテゴリーの区別は截 然とせず,スマートウォッチを「腕時計・アクセサリー」の一つに分類し ているショッピングサイトも存在する。そうすると,スマートウォッチと 腕時計は,その販売分野においても共通若しくは近接しており,同一のウ ェブサイトや売り場で一緒に販売されていることも少なくないというこ とができる。
さらに,上記のとおり,スマートウォッチが時計としての機能を備えて\nいることは争いがないところ,証拠に現れているスマートウォッチの初期 画面はいずれも時計であり,被告商品を製造したモトローラ・モビリティ のウェブサイト及び同商品の取扱説明書においても,時計表示の被告商品\nの写真が掲載されるとともに,同商品が「時計」である旨の記載がされ, 同商品を販売するインターネットサイトにおいても同様の説明がされて いると認められる。そうすると,スマートウォッチは,時計表示が付随的\nな機能にすぎない他の家電製品とは異なり,その主たる用途・使途は時計\nとして使用することにあるというべきである。 加えて,上記イ(カ)によれば,スマートウォッチの購入者は特定の層では なく,時計に関心を有する一般消費者であり,ネットショッピングや小売 店などで腕時計を購入しようとする一般の消費者にとって,スマートウォ ッチは,通常の腕時計等と並んで購入対象となるものであると認められる。 また,スマートウォッチと時計とで販売価格が大きく異なるとは認められ ないことも考え併せると,スマートウォッチと腕時計の需要者層は重複し ているということができる。
エ 以上のとおり,スマートウォッチと腕時計の製造業者の同一性,商品の 広告・販売状況,商品の用途,需要者の範囲等の事情を総合的に考慮する と,原告商標の指定商品である腕時計及び被告商品に同一又は類似の商標 を使用した場合には,同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認される おそれがあるというべきである。 したがって,被告商品は,原告商標の指定商品のうち「腕時計」と類似 の商品であるということができる。
3 争点(3)(モトローラ商標使用の抗弁の成否)について
前記1及び2で判示したとおり,原告商標と被告各標章は類似し,かつ,原 告商標の指定商品である腕時計と,モトローラ商標の指定商品である第9類に 属する被告商品とは類似する。そして,前記前提事実のとおり,モトローラ商 標の出願日又は優先日は,いずれも原告商標の出願日に後れているから,モト ローラ商標は,商標法4条1項11号,46条1項1号により,いずれも無効 にされるべきものである。このような無効事由のある登録商標に基づく専有権 の主張は,権利の濫用であって理由がなく,被告が主張するモトローラ商標使 用の抗弁は,成立しない。
4 争点(4)(権利濫用の抗弁の成否)について
原告は,被告が第二次不使用取消審判請求の登録日(平成29年6月23日) 前3年以内の要証期間内に原告商標を腕時計について使用していないので,原 告商標の指定商品のうち「腕時計」は不使用取消審判によって取り消されるべ きものであり,そのような原告商標権に基づく権利行使は権利の濫用として許 されないと主張するので,以下,検討する。
(1) 認定事実
ア 原告は,平成29年1月23日から6月23日までの間,自社のウェブ サイト内の「moto時計」のページ上部に,左側から中央にかけて縦に 並ぶような形で4本の腕時計の写真を掲載し,その右端に原告商標等を表\n示した。同ウェブサイトには,写真が掲載された腕時計の商品名,商品番 号,値段等の情報は表示されておらず,これらの時計の広告や商品説明,\n
同各商品を購入するための表示等も存在しない(甲62,120,乙17)。\nイ モトローラ・モビリティは,平成29年3月17日付け「ご回答」(乙 15)を原告代理人に送付し,同書面において,「当職らは,モトデザイ ン株式会社が商標「MOTO」を用いて腕時計の販売を行っていることに ついて疑いがあると考えています。モトデザイン株式会社のウェブサイト では腕時計の画像と共に「moto」の語が使用されていますが,当該使 用は本件対応のみを目的とする不自然かつ名目的なものに見受けられ…」 などと主張した。モトローラ・トレードマークは,同年6月8日,特許庁 審判官に対し,第二次不使用取消審判請求をした。
ウ 原告は,平成29年5月12日,A社宛てに,「見積及び腕時計サンプ ル発送致します」との件名のメール(甲63の1)を送信した。同メール には,「moto腕時計について,本日サンプルを送付致しますので,併 せてご確認のうえご検討下さい。」,「添付ファイルにて,先に商品写真 を送付致します。」と記載され,文字盤に「moto」の表記がある腕時\n計の写真及び腕時計とは別の商品についての見積書が添付されていた。ま た,同日受付で,品名に「moto腕手時×1点サンプル」と記載された 宅配伝票(甲63の2)が作成されている。
エ 原告の従業員であるFは,平成29年5月19日,自己の個人IDを用 いて,商品名が「moto時計 腕時計」であり,腕時計の画像が付され た商品を5000円でヤフーオークションに出品したところ,同年6月2 1日,氏名不詳者が同金額で落札し,同月22日,同人から支払がなされ た(甲64)。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.07.13
令和1(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年6月18日 知的財産高等裁判所
【請求項1】 電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込 信号を送信すること, 前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債 務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること, 前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落 信号を送信することを含む,電子記録債権の決済方法。
本願発明の発明該当性について
前記(2)の観点から,本願発明の発明該当性について検討する。 ア(ア) 前記(1)イ(イ)のとおり,本願発明は,従来から利用されている電子 記録債権による取引決済における割引について,債権者をより手厚く保 護するため,割引料の負担を債務者に求めるよう改訂された下請法の運 用基準に適合し,かつ,債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大 させることなく,債務者によって割引料の負担が可能な電子記録債権の決済方法を提供するという課題を解決するための構\成として,本願発明に係る構成を採用したものである。一方,本願発明の構\成のうち,「(所定の)金額を(電子記録債権の)債権者の口座に振り込むための振込信号を送信すること」,及び「(所定 の)金額を電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための引落信号 を送信すること」は,電子記録債権による取引決済において,従前から 採用されていたものであり,また,「電子記録債権の額を(電子記録債権 の)債務者の口座から引き落とす」ことは,下請法の運用基準の改訂前 後で,取扱いに変更はないものである。 そうすると,本願発明は,「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の 口座に振り込む」ことと,「前記電子記録債権の割引料に相当する割引料 相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とす」こととを, 前記課題を解決するための技術的手段の構成とするものであると理解できる。\n
(イ) また,本願明細書には,「本発明」の効果として,「電子記録債権の 割引が行われる場合,債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大さ せることなく,割引料を負担する主体を債務者とすることで,割引困難 な債権の発生を効果的に抑制することが可能となるという効果を奏する」ことが記載されている(前記(1)イ)。 一方,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)には,電子記録債権の 決済方法として,「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振 り込むための第1の振込信号を送信すること」,「前記電子記録債権の割 引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から 引き落とすための第1の引落信号を送信すること」,「前記電子記録債権 の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信 すること」が記載されているに過ぎないため,かかる構成を採用することにより,「自然法則を利用した」如何なる技術的手段によって,債務者\nや債権者の事務負担や管理コストを増大させないという効果を奏する のかは明確でなく,本願明細書にもこの点を説明する記載はない。 なお,本願明細書には,「本発明」の実施形態1及び2の決裁方法は, 割引料の負担主体が債権者と債務者のいずれの場合にも対応すること ができるため,債権者と債務者は,従来利用してきた電子決済サービス を引き続き利用することができ,支払業務等の負担の軽減と人的資源を 引き続き有効に活用することができる旨の記載があるが(前記(1)イ(カ)),これは,従来から利用されている電子記録債権による取引決済における割引を対象とする発明であることによって,当然に奏する効果であるものと理解できる。
また,本願明細書に記載された本願発明の効果のうち,「割引困難な債 権の発生を効果的に抑制することが可能となる」という点については,「本発明」の実施形態1及び2に関する本願明細書の【0051】及び\n【0082】の記載(「また,電子記録債権を割引した際の割引料を債務 者が負担する場合,債権者は割引の際に一時的に負担した割引料を債務 者から回収することができる。さらに,割引料相当料の負担を軽減する ための方策を構築するための動機づけを債務者に対して与えることができるため,支払遅延や割引困難な債権の発生を効果的に抑制すること\nが可能となる。」)に照らすと,かかる効果は,電子記録債権の割引料を債務者が負担する方式に改めたことによる効果であることを理解でき\nる。
(ウ) 以上によれば,本願発明は,電子記録債権を用いた決済方法におい て,電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに, 割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを,課題を解決するた めの技術的手段の構成とし,これにより,割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改訂に対応し,割引料を負担する主体を債務\n者とすることで,割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができ るという効果を奏するとするものであるから,本願発明の技術的意義は, 電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きると いうべきである。
イ 前記アで認定した技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の 構成及びその構\成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれ ば,本願発明の技術的意義は,電子記録債権を用いた決済に関して,電子 記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえる から,本願発明の本質は,専ら取引決済についての人為的な取り決めその ものに向けられたものであると認められる。 したがって,本願発明は,その本質が専ら人為的な取り決めそのものに 向けられているものであり,自然界の現象や秩序について成立している科 学的法則を利用するものではないから,全体として「自然法則を利用した」 技術的思想の創作には該当しない。 以上によれば,本願発明は,特許法2条1項に規定する「発明」に該当 しないものである。
ウ これに対し原告は,(1)請求項に係る発明が自然法則を利用しているかど うかは,本願発明の構成要件全体を単位として判断すべきものであるから,本件審決のように,本願発明の一部の構\成要件を単位とした判断には意味がなく,本件審決の判断には誤りがある,(2)仮に,本願発明の一部の構成要件を単位とした判断をする場合であっても,本願発明の各処理の実行は,\n全て信号の送受信によって達成されるところ,信号の送受信は,金融取引 上の業務手順そのものを特定するだけで達成できるものではなく,自然法 則を利用することで初めて達成できるものである,(3)本願発明を全体とし てみれば,「第1の引落信号」の送信と「第2の引落信号」の送信とを別々 に行うことができる構成を有していることから,「債務者の口座から割引料相当額を引き落とす時期」と「債務者の口座から電子記録債権の額を引き\n落とす時期」とを分けることができ,その結果,債務者が「割引料」と「電 子記録債権の額」とを区別して管理することが容易になり,例えば,「債務 者は,事務的な負担の増大を伴うことなく,一定期間に支払わなければな らない割引料相当料を容易に,かつ正確に把握することができる。」(本願 明細書【0017】)という効果を奏することができ,また,「第1の引落 信号を送信する」という構成は,債務者が割引料を負担するに当たって,実際の現金を用いなくても電子的な情報のやり取りによって,手続的負担\nを抑制するという効果を奏するから,全体として特許法2条1項の「自然 法則を利用した技術的思想の創作」に該当する,(4)本願発明を「コンピュ ータソフトウエア関連発明」であるとみても,「第1の引落信号」及び「第2の引落信号」を区別して送信する構\成は,コンピュータ同士の間で行われる必然的な技術的事項を越えた技術的特徴であるから,自然法則を利用 した技術的思想の創作である旨主張する。 まず,上記(1)の点について,本願発明を全体として考察した結果,「自然 法則を利用した」技術的思想の創作には該当しないと判断されることにつ いては,前記イのとおりである。 上記(2)の点については,前記アのとおり,本願発明において,「信号」を 「送信」することを構成として含む意義は,電子記録債権による取引決済において,従前から採用されていた方法を利用することにあるのに過ぎな\nい。すなわち,前述のとおり,本願発明の意義は,電子記録債権の割引の 際の手数料を債務者の負担としたところにあるのであって,原告のいう「信 号」と「送信」は,それ自体については何ら技術的工夫が加えられること なく,通常の用法に基づいて,上記の意義を実現するための単なる手段と して用いられているのに過ぎないのである。そして,このような場合には, 「信号」や「送信」という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても,本願発明は,全体として「自然法則を利用した」技術的思\n想の創作には該当しないものというべきである。 上記(3)の点について,本願明細書の記載(【0017】)によれば,原告 が主張する「債務者は,事務的な負担の増大を伴うことなく,一定期間に 支払わなければならない割引料相当料を容易に,かつ正確に把握すること ができる。」との効果は,「金融機関」が,「電子的通信手段を用い,割引料 に相当する金額・・・を定期的・・・に算出し,各債務者に対して割引料相当料が 確定したことを定期的に通知する」ことにより奏するものであることを理 解できるところ,上記の構成は,本願発明の構\成に含まれないものである。 また,「債務者の口座から割引料相当額を引き落とす時期」と「債務者の口 座から電子記録債権の額を引き落とす時期」とを分けることにより,債務 者が「割引料」と「電子記録債権の額」を区別して管理することが容易に なるとの効果については,本願明細書に記載されていないし,本願発明の 特許請求の範囲(請求項1)には,「第1の引落信号を送信すること」と「第 2の引落信号を送信すること」が記載されているに過ぎず,その構成に上記信号を送信する時期や,上記信号に基づきいつどのように引落しが行わ\nれるかを含むものではない。
そして,実際の現金を用いなくても電子的な情報のやり取りによって, 手続的負担を抑制するという効果は,前記ア(イ)で説示したように,電子 記録債権による取引決済における割引を対象とする発明であることによっ て,当然に奏する効果である。
上記(4)の点については,請求項1には,3つの信号を送信することが記 載されるにとどまり,ソフトウエアによる情報処理が記載されているものではない。したがって,本願発明は,コンピュータソ\フトウエアを利用するものという観点からも,自然法則を利用した技術的思想の創作であると はいえない。 以上のとおり,原告の上記主張は,いずれも採用することができない。
(3) 小括
以上によれば,本件審決が,本願発明は,特許法2条1項の「自然法則 を利用した技術的思想の創作」とはいえないから,同法29条1項柱書に 規定する要件を満たしておらず,特許を受けることができないものである 旨判断した点に誤りはなく,原告主張の取消事由1は理由がない。
関連カテゴリー
>> 発明該当性
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.07.13
令和1(ネ)10067 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月18日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(2) 推定の覆滅について
ア 当裁判所も,特許法102条2項による損害額の推定(上記(1))は,7 割の限度で覆滅され,さらに,第2及び第3特許を一審原告及びミサワホ ームが共有していることから,同社が有する損害賠償請求権の相当額14 63万7125円についても推定が覆滅され,この結果,一審原告の損害 額は,原判決と同様に4867万8376円であると認定する。その理由 は,次のとおりである。
イ 第2及び第3特許の技術的意義とその位置付け
第2及び第3特許の技術的意義についての検討は,原判決39頁18行 目から42頁11行目までの記載のとおりなので(ただし,原判決42頁 同10行目の「幅方向へ」から11行目末尾までを「幅方向へ移動しない ようにする点,及び,台輪の接続部の嵌合部と被嵌合部が,台輪本体の長 手方向の向きを逆にしても接続するように構成されている点(効果4)であると認められる。」と改める。),これを引用する。これによると,第2特許の技術的意義は,台輪本体の延在方向に沿って\nテーパ部を設けることによって,布基礎の凸部に干渉されることなく台輪 本体を略水平な状態で布基礎の天端面に設置することができること(効果 2)であり,第3特許の技術的意義は,台輪の両端部に設けられた接続部 を嵌合可能な構\成とすることにより,台輪が幅方向に移動しないようにす ることができること(効果3)と,当該接続部の嵌合部と被嵌合部が,台 輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続するように構成されていること(効果4)であると認められる。そうすると,第2特許,第3特許は,いずれも台輪全体に関する特許という形になってはいるものの,第2特許は\n台輪本体の側面縁部(延在方向),第3特許は台輪両端部に設けられた接 続部という,台輪のごく一部に技術的特徴が存するのにすぎないのである から,実質的には,特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合に 当たるものと解される。したがって,推定覆滅が認められるかどうかは, 特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け,当該特許発 明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮して判断すべきものである。
ウ 推定覆滅に関する判断(その1:第2及び第3特許の顧客誘引力等) 推定覆滅に関する判断の前提となる基礎的事情は,原判決42頁12行 目から45頁13行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 以上に基づいて,まず,第2特許の顧客誘引力等について判断するに, 第2特許の技術的特徴であるテーパ部は,本件被告カタログで挙げられた 6点の特徴の中には挙げられておらず(テーパ部に関しては,「素手で持 っても痛くありません」という,第2特許の技術的特徴とは異なる特徴と の関係で挙げられているのにすぎない。),また,一審原告のカタログ等 においても,甲20の1,2のカタログには「両端に天端モルタルのバリ 逃げ」との説明が付された一審原告の製品の図が小さく掲載されているの みであるし,最も詳しい説明のある甲21のパンフレットには,「バリ逃 げ」が項目として取り上げられている(第2発明の技術的特徴に関する具 体的言及も存在する。)ものの,11点の特徴のうちの1点として位置付 けられているのにすぎず,大きな特徴という取扱いはされていない。しか も,被告第2製品におけるテーパ部は,高さ1mm,幅2mmという極めて小 さなものであるため,布基礎の凸部による干渉を避ける効果も極めて限定 されたものであり,第2特許の技術的特徴が十分に発揮されているとは到底いえないものといわざるを得ないから,仮に第2特許そのものには相応の顧客誘引力があるとしても,被告第2製品のテーパ部は,その顧客誘引\n力を十分に発揮しているとはいい難い。このように考えると,被告第2製品における第2特許の顧客誘引力は,極めて限定されたものであるというべきである。\n
次に,第3特許の顧客誘引力等について判断すると,この点についても, 本件被告カタログが挙げる6点の特徴には,明示的な言及はされていない (「スピード施工」との記載はあるが,「スピード施工」が可能となる理由は様々あり得るのであるから,これによって,第3特許の技術的特徴について言及されたとはいえない。また,説明写真の中には,「連結構\造」についての言及はあるものの,連結構造そのものが第3特許の技術的特徴とはいえないことは既に指摘したとおりであるし,第3特許の技術的特徴\nである嵌合部に関しては全く言及がない。)。また,一審原告のカタログ 等においても,甲20の1,2のカタログには何ら言及はなく,最も詳し い説明のある甲21のパンフレットにも,「7 継手嵌合 キソパッキンロングを連結するための,凹凸の形状です。」という記載があるのみで,嵌合部については説明があるものの,第3特許の技術的特徴に関連する記\n載は全くない。このように考えると,第3特許の技術的特徴は,被告第2 製品においてはもとより,一審原告の製品においても,大きな意味がある ものとしては取り扱われていないと判断せざるを得ない。したがって,被 告第2製品における第3特許の顧客誘引力も非常に限定されたものにとど まるというべきである。
以上の点に,前述のとおり,第2特許の技術的特徴である側面縁部のテ ーパ部,及び第3特許の技術的特徴である接続部は,いずれも,台輪本体 のごく一部を占めるにすぎないこと等を総合的に考慮すると,本件におい ては,特許法102条2項による推定が,7割の限度で覆滅されるという べきである。 一審被告は,推定覆滅が少なくとも8割の限度で認められるべきである として種々主張するが,第2,第3特許の顧客誘引力に関していう点につ いては既に判示したとおりであって,採用することができない。また,被 告第2製品に競合品が存するとはいえないことは原判決37頁16行目か ら39頁1行目までに記載されたとおりであり,被告第2製品に易切断領 域が設けられていることが推定覆滅に影響を及ぼすものではないことは原 判決39頁2行目から17行目までに説示されたとおりであって,これら に関する主張も採用することはできない。 他方,一審原告は,7割の推定覆滅には根拠がないとして種々主張する が,この点に関しては,既に説示したとおりであって,やはりその主張は 採用することができない。
エ 推定覆滅に関する判断(その2:ミサワホームに生じた損害)
この点に関する判断は,原判決47頁1行目から17行目までに記載の とおりであって,ミサワホームに生じた損害1463万7125円の限度 で,推定が覆滅されるべきであると認められる。
オ 一審原告の損害額
この点に関する判断は,原判決47頁18行目から23行目までに記載 のとおりであって,一審原告の損害額は,一審被告の利益額2億1105 万1670円に,推定が覆滅されない割合3割を乗じ,その結果からミサ ワホームに生じた損害額1463万7125円を控除した残額である48 67万8376円であると認められる。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.07.13
令和1(ネ)10063 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所も,電子メールに設定された複数の電子メールアドレスを個々の 電子メールアドレスに分割し,記憶手段に記憶されている制御ルール等に従 って,電子メールの送出に係る制御内容を決定し,決定された制御内容に従 って電子メールの送信制御を行うとの構成は,本件発明1における本質的部分に該当し,同様に,複数の送信先が設定された電子メールから電子メール\nアドレス単位で個別メールを生成することは,本件発明2における本質的部 分に該当するところ,被告装置はドメインごとに分割するものであるため, かかる構成を有さず,均等の第1要件を充足しないと判断する。その理由は,後記(2)のとおり控訴人の当審における補充主張に対する判 断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第4の3及び6(原判決72 頁20行目から74頁25行目まで,77頁25行目から78頁13行目) 記載のとおりであるから,これを引用する。
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア 控訴人は,本件発明1において,複数の送信先を分割する単位が, 個々の電子メールアドレス単位であることは,本件発明1の課題の解決 をするのにあたり不可欠ではなく,「メッセージ単位」より小さい単位 でかつ,制御ルールに従って送出を制御し得る単位で,複数の送信先を 個々に分割した上で,分割した電子メールの送出に係る制御内容を決定 及び送信制御を行い,上記単位に応じた電子メールの送出制御を行うこ とが,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的な部分であると主張する。\nしかし,本件明細書等1には,「特許文献1に記載の技術においては, 送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断 することができない。そのため,複数の送信先が記載された電子メール に対しては,誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば,その他の送信先に対するメール送信までもが保留,取り消しがされるこ\nととなる。」(段落【0004】),「本発明は上述の問題点に鑑みなさ れたものであり,ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に,宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電\n子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とする。」(段落 【0005】)と記載されている。 「送信先」及び「宛先」はいずれも電子メールアドレスを意味するこ とは前記1のとおりであるから,これらの記載によれば,本件発明1は, 誤送信の可能性がある電子メールアドレスが1つでも含まれていれば,その他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留,取消し\nされることとなることを課題として認識し,その課題に鑑みて,電子メ ールアドレスに応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく 電子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とするものと解さ れる。
このように,本件明細書等1には,誤送信の可能性がないその他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留,取消しされてしま\nうという従来技術である特許文献1の課題に対し,電子メールアドレス に応じた電子メールの送出制御を行うことによって課題を解決しようと することが記載されているのであるから,そのために必須の構成である電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割\nする構成が,本件発明1の本質的部分に含まれないとはいえない。
イ 控訴人は,本件発明1の課題は,従来技術では,本来保留される必要の ない「その他の電子メールアドレス」に対するメール送信が全て保留さ れてしまうことであって,それに比べれば,ドメインに応じた送出制御 を行った場合であっても,少なくとも一部の電子メールアドレスに対す る電子メールの送信が保留されない場合,「電子メールアドレスに応じ た電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出さ せる」効果を得ることができる旨主張する。 しかし,前記1(3)ウ(イ)のとおり,「誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば,その他の送信先に対するメール送信までもが\n保留,取り消しがされることとなる。」(段落【0004】(1))とは, 本来保留される必要のないその他の送信先(すなわち電子メールアドレ ス)に対するメール送信は全てなされるべきであるとの趣旨と解するの が自然である。 また,前記アのとおり,「効率よく電子メールを送出させる」ことは, 電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制御によってもたらされ るものとされている。電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制 御によれば,保留の必要がないその他の電子メールアドレスに対する送 信は全てなされるのであるから,本件発明の効果も同様と解すべきであ って,保留の必要がないその他の電子メールアドレスのうちの一部の電 子メールアドレスに対する電子メールの送信が保留されなくなることで は足りないというべきである。
ウ 控訴人は,文言侵害が否定された場合に,本件明細書等1の課題に記載 された「送信先」を「電子メールアドレス」と読み替えて,課題を認定 し,当該課題から直接的に本質的部分を認定することは,均等侵害の成 否の場面において,文言侵害が否定されることを理由に,均等侵害の成 立が直ちに否定され,均等侵害がその機能を果たさない結果となることから,かかる結果が著しく妥当性を欠く旨主張する。\nしかし,本質的部分の認定は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基 づいて,特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許 発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(大合議判決)。よって,本件明細書等1の記載に基\nづいて,本件発明1が,従来技術である特許文献1のどのような点を課 題として把握し,どのような解決手段を提示し,どのような効果をもた らすものなのかを把握することは,当然なされるべきことであるから, 控訴人の主張は理由がない。
エ 被告装置は,電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレ スごとに分割するという,本件発明1の本質的部分に含まれる構成を有していないから,均等の第1要件を充足しない。\n
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2020.06.26
令和1(行ケ)10164 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年6月17日 知的財産高等裁判所
1 取消事由1(商標法3条1項6号該当性の判断の誤り)について
(1) 本願商標の構成について\n
ア 本願商標は,別紙1に記載のとおり,Iハート図形とその下に「JAP AN」の欧文字を書してなるものであり,別紙1に記載の商品を指定商品とするも のであるところ,本願商標の構成のうち,Iハート図形が全体として,「私は〜が大\n好きです。」との意味合いを表す英語の「I LOVE 〜」を端的に表意するもの\nであること,Iハート図形とその横に又は下に何らかの文字を結合した表示が,何\nらかの文字が表すものに対して愛着の気持ち等を表\すものとして理解されることは 当事者間に争いがない。 そうすると,Iハート図形の横又は下に「地名」を結合した表示は,当該地名(国\n名や都市名等)が表す場所に対する愛着の気持ち等を表\すものとして理解されると 認められる。
イ(ア) 別紙2に掲げた証拠及び弁論の全趣旨によると,別紙2のとおり,本 件審決前に,日本において,インターネットのウェブサイトのIハート図形が使用 されている表示が30件(別紙2(1)〜(10),(12)〜(19),(21)〜(32))存したもの と認められる。 また,証拠(乙42)によると,本件審決前に,「オスミツキ商店街」のウェブサ イトにおいて,商品「ステッカー」の表面に「I」及び「ハートマーク図形」とその下に「TOYA」の文字を表\示した画像(以下,「TOYA表示」という。)とともに,「オスミツ\nキ商店街は,支笏洞爺国立公園内・洞爺湖温泉街にある雑貨屋,HORIDAY MARKET TOYAの公式オンラインショップです。」,「I LOVE TO YA STICKER」,「ぜひいろんな場所にバシバシ貼って,洞爺好きをアピー\nルしてください!」との記載があったことが認められる。
(イ) 上記(ア)の各表示のうちIハート図形の横又は下に「地名」を結合し\nた表示(別紙2の(1)〜(10),(12)〜(19),(21)〜(29),(31)及びTOYA表示)は,\n結合した当該地名が表す場所に対する愛着の気持ち等を表\す表示として,又は,当\n該地名が表す場所の土産物などとして客の関心をひくための表\示として,被服を取 り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって使用されているも のと認められる。 また,Iハート図形の横又は下に「日本」を意味する英語である「JAPAN」 の欧文字を結合した表示(別紙2の(1)〜(10),(13)〜(19))は,日本又はスポーツ の日本代表チームなど日本に属するものに対する応援の気持ちを表\す表示として,\n被服を取り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって,使用さ れていることがあると認められる。
(ウ) 証拠(甲10,21,22,乙10)及び弁論の全趣旨によると,次 の事実が認められる。
a I ハート図形の下に「NY」を結合した表示は,1970年代後半\nから,ニューヨークの観光キャンペーンに用いるために「アイラブニューヨーク」 というスローガンと共に使用され,Iハート図形の下に「NY」を結合した表示が\n付されたマグカップ,Tシャツなどのライセンス商品が販売されている。それらの ライセンス契約による収入は年30億円にのぼるといわれている。
b Iハート図形の下に「JAPAN」を結合した表示が付されたTシ\nャツ(別紙2の(7))や,Iハート図形の下に栃木を表す「TG」を結合した表\示が 付されたTシャツ(別紙2の(31))は,Iハート図形の下に「NY」を結合した表\n示を意識して作られた商品である。
(エ) なお,被告の提出する証拠のうち,乙1,22〜28,37〜41, 43は,いずれも本件審決後に作成された書証であり,本件審決前にこれらの書証 の表示が存在していたと認めるに足りる証拠はないから,これらの証拠を認定に用\nいることはできない。また,乙2,3は,書証上,作成日が明らかでなく,本件審 決前の事情を示す表示であると認めることはできないから,これらを認定に用いる\nことはできない。
(2) 本願商標の商標法3条1項6号該当性について
前記(1)によると,本願商標は,「私は,日本が大好きです。」の意味合いとして容 易に理解されるものであり,日本においては,Iハート図形の横又は下に「地名」 を結合した表示は,結合した当該地名が表\す場所に対する愛着の気持ち等を表す表\ 示又は当該地名が表す場所の土産物などとして客の関心をひくための表\示として, また,Iハート図形の横又は下に「JAPAN」を結合した表示は,日本又はスポ\nーツの日本代表チームなど日本に属するものに対する応援の気持ちを表\す表示とし\nて,被服を取り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって使用 されていることが認められるから,本願商標をその指定商品に使用した場合,本願 商標に接する取引者,需要者は,これを,日本に対する愛着の気持ちや日本に属す るものに対する応援の気持ちを表現したものあるいは日本の土産物を示すものと認\n識するにすぎないと認められる。そうすると,本願商標は,自他商品の識別力を有 さないというほかない。 したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識す ることができない商標であるから,商標法3条1項6号に該当することになる。
(3)ア これに対し,原告は,商品販売サイトが存在することは,当該商品が一 般消費者の目に触れ,取引されていることを意味するものではない,既に商品の取 扱いが終了している商品販売サイトは「広く用いられていること」の証拠とはなら ないと主張する。 証拠(甲25,26,40,41)及び弁論の全趣旨によると,電子商取引サイ トである Amazon.co.jp の日本における取扱品目数は,平成27年当時で2億点(公 表値),売上高は1兆円と算出され,Yahoo!ショッピングの取扱品目数は,平成29 年当時で2億8000万点を超え,楽天市場の取扱品目数は,令和元年12月時点 で2億7000万点を超えていること,日本国内の消費者向けの電子商取引の市場 規模は,平成30年には約18兆円に達していることが認められる。 しかし,前記(1)イ(ウ)のとおり,本願商標と同様に「Iハート図形+地名」の形 をとる「Iハート図形+NY」の表示が,既に40年以上使用されている上に,日\n本国内においても,前記(1)イ(イ)のような使用例が29件存在していたことからす ると,これらのウェブサイトにおける閲覧実績や販売実績を検討するまでもなく, 本願商標は,前記(2)のとおり,自他商品識別力を有しないものと認められる。 前記(1)イ(ア)のウェブサイトの中に,既に商品の取扱いが終了している商品販売 サイトが存するとしても,インターネットのウェブサイトにおいて,Iハート図形 の横又は下に「地名」が結合した表示が存し,その表\示が前記(1)イ(イ)で記載した ようなものと理解されるのであるから,既に商品の取扱いが終了している商品販売 サイトがあることは,前記(2)の判断を左右するものではない。 イ 原告は,本願商標に接した需要者が,本願商標が日本代表チームなどに\n対して愛着の気持ちを表すデザインあるいは日本の土産物において客の関心をひく\nためのデザインとして認識,理解することはない旨主張する。 しかし,本願商標は,「私は,日本が大好きです」の意味合いを容易に理解させる ものであるところ,本願商標と同様に,Iハート図形の横又は下に「JAPAN」 を結合した表示が,「応援」,「応援グッズ」,「代表\チーム」,「サッカー」,「Wカップ」, 「侍ジャパン」,「サムライジャパン」,「サッカー 野球」,「オリンピック2020」, 「日本代表を応援しよう」などと共に商品販売サイトにおいて用いられていること\n(別紙2の(1)〜(3),(12),(15)〜(17))からすると,本願商標に接した取引者, 需要者は,当該表示は日本代表\チームなどに対して愛着の気持ちを表す表\示と理解 することがあると認められる。また,本願商標と同様に,Iハート図形の横又は下 に「地名」を結合した表示が,「日本のお土産に最適」,「グアムの定番お土産」,「JTBのお土産通販サイト」,「松島お土産」,「江ノ電公認みやげ」,「栃木 お土産」 などと共に商品販売サイトにおいて用いられていること(別紙2の(6),(21),(23), (26),(27),(31))からすると,本願商標に接した取引者,需要者は,当該表示は,\n日本の土産物として客の関心をひくための表示と理解することがあるものと認めら\nれる。 したがって,原告の主張を採用することはできない。
ウ 原告は,本願商標は,赤色のハート図形を用い,Iハート図形が標章の 半分以上を占めるデザインとすることで,一見して日本に対する愛着の気持ちが瞬 時に伝わる特徴的なデザインとなっているから,本願商標を需要者が何人かの業務 に係る商品であることを認識することができない商標と評価することはできないと 主張する。 しかし,本願商標に自他商品識別力がないことは既に判示したとおりであって, 原告の主張を採用することはできない。
エ 原告は,本願商標と同種の商標が商標登録されていることから,本願商 標には自他商品識別力があると主張する。
証拠(甲36,37,39)によると,(1)指定商品を第25類(被服,ガーター, 靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運 動用特殊靴)とし,本願商標と同じ構成を有する商標が,原告を商標権者として,\n平成27年3月27日に商標登録されていること,(2)指定役務を第30類(菓子, パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドックなど) とし,本願商標と同じ構成を有する商標が,原告を商標権者として,平成30年6\n月15日に商標登録されていること,(3)指定役務を第35類(広告業,トレーディ ングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言など)とし,I ハート図形 の下に「TOKYO」と記載した商標が,米国の企業を商標権者として,令和元年 7月5日に商標登録されていることが認められる。 しかし,本願商標に自他商品識別力が認められないことは既に判示したとおりで あるところ,商標法3条1項6号該当性の判断は,個別具体的に検討,判断される ものであるから,上記(1)〜(3)の商標登録がされているからといって,本願商標に自 他商品識別力があると認めることはできない。
オ 原告は,本願商標と同一のデザインを表示した商品を多数生産,販売し\nた実績があり,今後も生産していく予定であると主張し,原告代表\者の陳述書(甲 27)には,平成27年3月以降,原告は,本願商標と同一のデザインを施したT シャツ,靴下,トートバック,キーホルダー等のアパレル雑貨や,土産用の菓子な ど約10万点を生産し,実店舗を中心に販売したこと,原告は,平成30年以降, 「I love JAPANプロジェクト」を始めること,本願商標と同一のデザインの商標 について商標登録を受けており,これらの商標については,他社に対して使用を許 諾し,使用許諾先では本願商標と同一のデザインの商品を6万点ほど生産中で,今 後は20万点以上の規模で生産することを計画していることなどの記載がある。 しかし,本願商標に自他商品識別力が認められないことは,既に判示したとおり であって,上記の陳述書の記載によってもこの判断は左右されない。
(4) 以上によると,取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(裁量権の逸脱,濫用)について 原告は本件拒絶査定及び本件審決は平等原則に反し,裁量権の範囲を逸脱,濫用 している旨主張する。 しかし,本願商標に自他商品識別力が認められないことは既に判示したとおりで あり,本願商標と同種の商標が登録されている点についても,前記1(3)エのとおり であるから,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした本件審決の判断に違 法な点はない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2020.06.26
令和1(行ケ)10077 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年6月11日 知的財産高等裁判所(1部)
もっとも,発明の進歩性の判断に際し,本件発明と対比すべき主引用発明は, 当業者が,出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができた かどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そし て,本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり,主引用発 明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたか どうかを判断する場合には,主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆,技術分野 の関連性,課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して,主引用発明に副引用\n発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに,適用 を阻害する要因の有無,予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断する\nこととなる。 このような進歩性の判断構造からすれば,本件発明と主引用発明との間の相違点\nを認定するに当たっては,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構\n成を単位として認定するのが相当であり,かかる観点を考慮することなく,相違点 をことさらに細かく分けて認定し,各相違点の容易想到性を個々に判断することは, 進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり,適切でない。
ウ 前記アのとおり,本件発明1と引用発明の一致点及び相違点が本件審決の認 定したとおりのものであることについては,当事者間に争いがない。 しかし,前記イで述べたところに照らせば,本件審決が認定した相違点のうち, 少なくとも相違点4ないし6に係る構成は,グラブバケット自体の水中での抵抗を\n減少させて降下時間を短縮し,グラブバケットが掴み物を所定の容量以上に掴んだ 場合でも該グラブバケットの内圧上昇に起因する変形,破損を引き起こすことがな いようにするという技術的課題の解決に向けられたまとまりのある構成であるから,\n本件において,相違点4ないし6は,本来,次のとおりに認定すべきものであった。
(相違点A)
本件発明1においては,シェルカバーの一部に形成された空気抜き孔に取り付け られた「開閉式のゴム蓋を有する蓋体」が,「シェルを左右に広げたまま水中を降下 する際には上方に開いて水が上方に抜け」るとともに,「シェルが掴み物を所定容 量以上に掴んだ場合にも,内圧の上昇に伴って上方に開」き,「グラブバケットの水 中での移動時には,外圧によって閉じられる」ものであるのに対し,引用発明にお いては,掩蓋の一部に形成された空気抜きのための開口に取り付けられた「開閉式 の逆止弁」が,「シエルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて空 気が上方に抜けるとともに,バケットを海上に引き上げる場合に閉じられる」が, 「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開」 くか否かは明らかでない点。
エ 本件発明1と引用発明との相違点は,本来,前記ウのとおりに認定すべきも のであった。しかしながら,この点を措き,本件審決の認定したところ及び当事者 の主張に従い,相違点6の判断の当否として検討してみても,後記(3)のとおり,本 件審決の判断に誤りがあるとはいえない。
・・・
3 特許法167条又は信義則の違反をいう被告の主張について
(1) 被告は,本件無効審判における事実及び証拠は,別件無効審判のそれと実質 的に同一であるから,本件無効審判の請求は,特許法167条の規定に違反し,「紛 争の蒸し返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請に反し,許されない旨主張す るので,事案に鑑み,以下,判断する。
(2) 別件無効審判の経緯は,前記第2の1(2)認定のとおりであり,本件特許につ いて,平成22年12月14日付け別件無効審判の請求以来,約7年4月間の長期 間にわたり,4回の審決と3回の判決,1回の決定がされたことが認められる。 現行特許法が,同一の請求人についても,同法167条の場合を除いて,何回で も,かつ,時期的制限もなく(同法123条3項),無効審判を請求することのでき る制度を採用していることについては,特許権の安定や紛争の一回的解決の見地か ら再検討の余地があるが,特許法167条は,「特許無効審判‥の審決が確定したと きは,当事者‥は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができない。」と規定している。そして,同条の趣旨は,(1)同一争点による紛争の蒸 し返しを許さないことにより無効審判請求等の濫用を防止すること,(2)権利者の被 る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること,(3)紛争の一回的な解決を図る こと等にあると解され,無効審判請求において,「同一の事実」とは,同一の無効理 由に係る主張事実を指し,「同一の証拠」とは,当該主張事実を根拠づけるための実 質的に同一の証拠を指すものと解される。 ところで,無効理由として進歩性の欠如が主張される場合において,特許発明が 出願時における公知技術から容易に想到できたというためには,(1)当該特許発明と, 引用例(主引用例)に記載された発明(主引用発明)とを対比して,当該特許発明と 主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で,(2)当業者が主引用発明に他の公 知技術又は周知技術とを組み合わせることによって,主引用発明と相違点に係る他 の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが当業者において容易に想到で\nきたことを示す必要がある。そうすると,主引用発明が異なれば,特許発明との一 致点及び相違点の認定が異なり,これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容 も異なってくるから,無効理由としても異なることになる。 したがって,進歩性の欠如という無効理由について,主引用発明が異なるときは, 「同一の事実」に当たらないことになる。
(3) これを本件についてみると,別件無効審判において,主引用発明とされたの は,甲8及び甲9に記載された各発明であり,本件の主引用例(甲7)は,別件無効 審判では提出されていない。主引用例から認定される発明(主引用発明)が別件無 効審判で主張された主引用発明と異ならなければ,無効理由としても同一と評価で きるが,本件審決は,別件無効審判のそれとは異なる発明(掩蓋に逆止弁が取り付 けられた構成を含むもの)を甲7の記載から認定している。浚渫用グラブバケット\nにおいて逆止弁に技術的意義があることは明らかであるから,本件無効審判の主引 用発明が別件無効審判のそれと異ならないということはできない。 したがって,現行法下の無効審判請求及び審決取消訴訟においても,「紛争の蒸し 返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請を満たすような主張立証がされるべ きことは,被告の主張するとおりであるものの,本件においては,理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2020.06.26
令和1(行ケ)10115 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年6月11日 知的財産高等裁判所
ア 特許請求の範囲の記載については,特許を受けようとする発明が明確である ことを要する(特許法36条6項2号。明確性要件)。 明確性要件の適否は,特許請求の範囲の記載,明細書の記載及び図面並びに出願 時の当業者の技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不 利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断するのが相当である。
イ 特許請求の範囲請求項1及び2にいう「同一面」の意義は,前記(1)のとおり であり,その意義は明確であり,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不利益 を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。
ウ 原告は,本件明細書の発明の詳細な説明において,「略同一面」という文言に ついて「樹脂部とリードとは略同一面に形成されている。この略同一面とは同じ切 断工程で形成されたことを意味する。」との特別な定義付けがされていることを指摘 し,これと「同一面」という文言が同義であると直ちには理解できないとして,明確 性要件の適合性を争う。 しかし,特許請求の範囲請求項1及び2にいう「同一面」とは,樹脂パッケージの 外側面において樹脂部とリードとが同一面に形成されることを意味するものと解釈 することができることは,前記(1)のとおりである。他方,本件明細書の発明の詳細 な説明の「略同一面」については,「樹脂部とリードとは略同一面に形成されている。 この略同一面とは同じ切断工程で形成されたことを意味する。」(【0042】)とい うものであり,前記「同一面」と同義のものである。よって,特許請求の範囲に記載 された「同一面」という用語と,発明の詳細な説明に記載された「略同一面」という 用語とが,異なる意味で用いられていると解すべき根拠は見当たらず,そうすると, 発明の詳細な説明において専ら「略同一面」という文言が用いられているからとい って,発明の詳細な説明に記載された製造方法により,樹脂パッケージの外側面に おいて樹脂部とリードとが「同一面」に形成されるという当業者の理解が妨げられ るものではない。原告の主張は理由がないというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2020.06.25
平成31(行ケ)10019等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所
ア 特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記 載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か, また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。
イ(ア) 本件発明の課題は,「コリネ型細菌を用いたL−グルタミン酸の製造 において,L−グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」で\nあり,本件発明11の中には,誘導条件下のみならず,非誘導条件下においても生 産能力の向上を図るものが含まれているところ,誘導条件下において,19型変異\nを導入した株であるATCC13869−19株の生産能力が野生株に比して向上\nしていることは,本件明細書の実施例10(段落【0125】〜【0128】,【表\n9】,【表10】)に開示されているといえるから,当業者は,19型変異について,\n誘導条件下でグルタミン酸の生産能力向上がみられるものであることを認識できる\nといえる。
(イ) 次に,非誘導条件下における19型変異の生産能力の向上について検\n討するに,本件明細書の実施例8の培養は,実施例2と同様の方法で実施されたと されていて,その培地には,請求項6などにいう「過剰量のビオチン」に該当する 300μg/lのビオチンが存在していた上,界面活性剤等は添加されていなかっ たと認められるから,実施例8は,非誘導条件下での19型変異株の生産能力向上\nについてした実験である(本件明細書の段落【0120】,【0097】,【0032】)。 そして,実施例8の【表7】には,以下のとおり,19型変異株であるATCC\n13869−19株が,野生株に比して0.2g/L多くのL−グルタミン酸を生 産したことが示されている。そして,それを受けて本件明細書の段落【0120】 には,「ATCC13869−19株は親株のATCC13869株と比べてL−グ ルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。」と記載されているから,それらの記載から, 当業者は,19型変異について,非誘導条件下でも本件発明の課題を解決できるも のであることを認識するといえる。
ウ 原告らは,実施例8に関して,(1)実施例2における野生株のグルタミン 酸生産量の値及びブランク値,実施例3におけるブランク値並びに実施例2,3, 5,7,9の値からみて,実施例8における野生株と19型変異株のグルタミン酸 生産量の違いは誤差の範囲内にすぎず,当業者は,実施例8からグルタミン酸の生 産能力が向上したとは認識できない,(2)ブランク値と変異株及び親株の結果とを対 比しないと,実施例8の信用性を評価することはできない,(3)甲28の実験や甲3 4の実験の結果からも19型変異株が非誘導条件下でグルタミン酸を生成しないこ とが裏付けられていると主張する。
(ア) 上記(1)について
本件明細書上,実施例3,6〜9は,いずれも実施例2記載の方法又は同様の方 法で,培地中に300μg/lのビオチンが存在するなどの非誘導条件下で実施さ れたものである(本件明細書の段落【0097】,【0100】,【0109】,【0112】,【0117】,【0120】,【0123】)。そして,実施例2,3,6の【表\n1】,【表2】,【表\4】,【表5】に記載されているブランク値について,本件明細書に明示的な説明はされていないものの,菌体量を示すOD620値がいずれも0.\n002と極めて低い値になっていることからすると,被告が主張するとおり,グル タミン酸生産菌を接種しない培養開始時の培地(初発培地)でのグルタミン酸の濃 度を表すものであると認められる。また,甲36,乙6によると,非誘導条件下で\nの野生株(ATCC13869)のグルタミン酸生産量の値は,培養が進むにつれ てグルタミン酸が分解された後の値であると認められる。 上記四つのブランク値が,それぞれ異なっていること(【表1】が0.4g/L,\n【表2】と【表\4】が0.6g/L,【表5】が0.7g/L)からすると,実施例\n3,6〜9について,実施例2記載の方法又は同様の方法で実施されたと記載され ているものの,初発培地におけるグルタミン酸の濃度などの培養条件は実施例又は 各培養ごとに異なるものであったと認められる。本件明細書の段落【0097】の 記載及び甲36,乙6の記載からすると,上記のような各実施例におけるブランク 値の違いは,天然物を起源とする大豆加水分解物に由来するものであると認められ る。 そもそも,本件明細書のブランク値及び野生株のグルタミン酸生産量の値は,上 記認定のとおりのものであって,これらの値を根拠に,これらの値とは異なる実施 例8における野生株と19型変異株とのグルタミン酸生産量の違いが誤差に基づく ものということはできない。その上,上記認定のとおり,培養条件は,実施例又は 各培養ごとに異なるから,なおさら,実施例2や実施例3に表れた数値を根拠に,\n実施例8における野生株と19型変異株におけるグルタミン生産量の0.2g/L の違いが誤差に基づくものであるということはできない。 さらに,実施例2,3,5,7,9のその他の数値からみても,実施例8の野生 株と19型変異株のグルタミン酸生産量の0.2g/Lの違いが誤差に基づくもの ということはできない。 以上からすると,上記(1)は,前記イの判断を左右するものとはいえない。
(イ) 上記(2)について
本件発明の課題は,「コリネ型細菌を用いたL−グルタミン酸の製造において,L −グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」であるところ,\nここでいう「生産能力の向上」とは,「野生株などの非改変株と比較して,L−グル\nタミン酸生産能が上昇したこと」を意味する(【請求項1】,【請求項4】,【請求項5】\n及び本件明細書の段落【0015】,【0031】)から,実施例8において,19型 変異株が,野生株に比してより多くのグルタミン酸を生産することが示されている 以上,ブランク値が記載されていないとしても,実施例8の結果が信用できないも のということはできない。
・・・・
(4) 小括
以上からすると,19型変異に関して,本件発明11にサポート要件違反や実施 可能要件違反があるとはいえないから,原告らが主張する取消事由1は理由がない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2020.06.19
令和1(行ケ)10116 審決(拒絶)取消 令和2年5月20日判決 審決取消(2部) 特許権 (回転ドラム型磁気分離装置) 新規性,進歩性,相違点の判断
本件補正発明では,第1の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を 形成するのに対し,引用発明は,上記のような流路を形成しているか否かが不明な 点
ウ これに対し,被告は,引用文献1においては,タンク17の底部が底部 材に相当し,マグネットドラム27とタンク17の底部との間に混濁液の流路が形 成されるとして,相違点3は存在しないと主張する。
(ア) しかし,本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は,「・・・前記使 用済みクーラント液は,第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流 れ,・・・前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと,前記第 1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え,前記スクレパーにより掻き 取られた磁性体が大きくなった状態のまま,前記使用済みクーラント液の流れに沿 って前記第1の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装 置。」というものであり,同記載からすると,第2の回転ドラムから第1の回転ドラ ムに向かうクーラント液は,第 1 の回転ドラム下部に第 1 の回転ドラムと底部材と の間に形成された流路を流れるものであって,スクレパーによって掻き取られた磁 性体を第1の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして,このことは, 本件明細書に,「スクレパー27は,第1の回転ドラム13の下部の流路を形成する 底部材30に連結されており,掻き取られた不要物(磁性体)は第1の回転ドラム 13へと誘導される。」(段落【0041】),「スクレパー27は,第1の回転ドラム13の下部の流路を形成する底部材に連結されていれば足りるので,第2の回転ド ラム21側から第1の回転ドラム13に向かって下降するよう傾斜していても良 い。」(段落【0053】),「図7に示すように,本実施の形態に係る回転ドラム型磁気分離装置は,第2の回転ドラム21の外筒29に当接するスクレパー27が,第 2の回転ドラム21側から第1の回転ドラム13側へ傾斜するよう設けられてい る。」(段落【0054】),「これにより,スクレパー27で書き取られた第2の回転ドラム21に付着した不要物が,傾斜に沿って第1の回転ドラム13側へと流れに 乗って移動しやすく,第1の回転ドラム13により確実に回収することが可能とな\nる。」(段落【0055】)と記載されていることからも,裏付けられているというこ とができる。 したがって,本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは,第2の 回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解 すべきである。
(イ) 引用文献1には,マグネットドラム27(第1の回転ドラムに相当) とタンク17の底部との間にマグネットドラム25(第2の回転ドラムに相当)か らマグネットドラム27に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていな い(甲1)から,相違点3’は存在し,被告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2020.06.19
令和1(行ケ)10151 審決(拒絶)取消 令和2年5月20日判決 審決取消(2部) 商標権 ((掲載省略)) 類似性(4条1項11号),商標の類似性
前記(2)アのとおり,「CORE」の語には,「ものの中心部,中核,核心」,「建 物の中央部で,共用施設・設備スペース・構造用耐力壁などが集められたところ」,\n「地球の核」,「試錐(ボーリング)によって採取した円柱状の土壌や岩石の試料」, 「一部のオペレーションシステムでプログラムが不正に終了したとき,メモリの内 容をまるごと保存したファイル(コアファイル,コアダンプ)」,「マイクロプロ セッサのコア」,「Intel社の商品であるCOREシリーズ」等の多様な意味 があるが,前記(2)アのとおり,多くのコンピュータ関連の用語辞典等には,「CO RE」や「コア」の項目が掲載されていない。
上記の意味のうち,「コアファイル」,「コアダンプ」,「マイクロプロセッサ のコア」,「Intel社の商品であるCOREシリーズ」は,コンピュータ関連 の用語であるが,「CORE」の語がコンピュータソフトウェアである本件指定商\n品に使用された場合は,コンピュータハードウェアを意味する「マイクロプロセッ サのコア」やコンピュータハードウェアの商品名である「Intel社の商品であ るCOREシリーズ」を意味するものとは認識されないというべきであるし,「コ アファイル」や「コアダンプ」も一部のオペレーションシステムで用いられている 用語にすぎず,「コアファイル」や「コアダンプ」と認識されるとも認められない。 また,「CORE」の語が本件指定商品に使用された場合,「中心部,中核,核 心」などの一般の辞書に掲載されている意味のどれとも認識されないか,認識され るとしても,せいぜい「中心部,中核,核心」という意味と認識されるにすぎない というべきである。
イ 「ML」について
(ア) 前記(2)イの認定からすると,「ML」の語には,「マシーンラーニン グ(Machine Learning)」,「メーリングリスト(mailin g list)」,「マークアップ言語(MarkupLanguage)」の略語 の意味があることが認められる。 しかし,(1)本件において,一般的な辞書に,「ML」の項目が存在することの証 拠は提出されていないこと,(2)前記(2)イのとおり,「ML」の語が「マシーンラー ニング(Machine Learning)」の略語として使用された例は一定 数存するが,それらの使用例においては,必ず,「機械学習」という語と共に使用 されていること,(3)コンピュータ関連の用語辞典の中には,「ML」の項目が存在 するものがあるものの,同項目が存在しないものもあり(「ウィキペディア」のウ ェブサイトの「コンピュータ略語一覧」),同項目を設けている用語辞典(「IT 用語辞典e−Words」)では,「ML」は「メーリングリスト」の意味である と説明されていることからすると,「ML」の語が何らの説明もなく使用された場 合,「マシーンラーニング(Machine Learning)」の略語を意味 すると認識されるとはいえないというべきである。また,ブランド名と「ML」を 結合し,「ML」を「Machine Learning」として用いる例がある としても,「CORE」のみでは,本件指定商品との関係ではブランド名とは認めら れないから,そのことを根拠に本願商標の「ML」が「Machine Lear ning」と認識されると認めることもできない。 また,上記のとおり,コンピュータ関連の用語辞典には,「ML」を「マークア ップ言語」を意味するものと説明しているものはないこと,本件証拠上,「ML」 の語が「マークアップ言語」の略語の意味として使用されていると認められる例は, 「SGML」,「XML」,「HTML」のみであることからすると,「CORE」の語の次に一文字開けて「ML」の語を配置した場合に,「ML」の語が「マークアップ 言語」と認識されるとはいえないというべきである。 さらに,上記のとおり,「ML」の語が「メーリングリスト(mailing l ist)」の略語の意味を有することは「IT用語辞典e−Words」に記載さ れているが,他に,「ML」の語が「メーリングリスト」の意味で使用されている例 を示す証拠は提出されていないことからすると,「ML」の語が「メーリングリス ト(mailing list)」の略語の意味として認識されるということもで きない。
(イ) 以上からすると,本件指定商品に,「CORE」の語の末尾に1文字開 けて「ML」を配した語が使用された場合,「ML」から,何らかの観念が生じると 認めることはできない。
ウ 以上のア,イで判示したところからすると,本願商標が本件指定商品に 使用された場合,「CORE」の語からは,せいぜい「中心部,中核,核心」とい った一般的な意味が認識されるにすぎず,「CORE」の部分が出所識別標識とし て強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し,「ML」の語からは 特定の観念を生じることはなく,「ML」の部分が「CORE」の部分に比べて特 段出所識別標識としての機能が弱いということはできない。\nまた,本願商標の外観上も,「CORE」と「ML」は,いずれも,同じ大きさの 標準文字で構成されており,その間に1文字開いているだけであるから,別個独立\nの商標と認識されるものではない。 さらに,称呼においても,本願商標は,一連に発音されるものと認められる。 したがって,本願商標と引用商標との類否を判断するに当たっては,本願商標全 体と引用商標を対比すべきであり,本願商標から「CORE」の部分を抽出し,こ れを引用商標と対比してその類否を判断することは許されないというべきである。 したがって,原告の主張する取消事由1は理由がある。
2 取消事由2(本願商標と引用商標の類否判断の誤り)について
本願商標からは,「コアエムエル」の称呼が生じ,引用商標1,2からは,「コア」 の称呼が生じるところ,その音数は大きく異なっていることからすると,その差異 は大きいというべきである。 また,本願商標の「CORE ML」と引用商標1の「CORE」及び引用商標 2の「コア」とは,その外観が異なる。 本願商標の「CORE ML」の「CORE」の部分と,引用商標1の「COR E」及び引用商標2の「コア」では,「中心部,中核,核心」といった観念が生じ る点で,観念が共通することがあるものの,上記のとおり,本願商標と引用商標1, 2とは,称呼と外観において異なっており,称呼における差異は大きいことからす ると,本願商標は,引用商標のいずれとも類似していないというべきであり,原告 の主張する取消事由2は理由がある。
◆判決本文
令和1(行ケ)10116 審決(拒絶)取消 令和2年5月20日判決 審決取消(2部)
特許権 (回転ドラム型磁気分離装置) 新規性,進歩性,相違点の判断
相違点の認定誤りを理由として、拒絶審決が取り消されました。
本件補正発明では,第1の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を
形成するのに対し,引用発明は,上記のような流路を形成しているか否かが不明な
点
ウ これに対し,被告は,引用文献1においては,タンク17の底部が底部
材に相当し,マグネットドラム27とタンク17の底部との間に混濁液の流路が形
成されるとして,相違点3は存在しないと主張する。
(ア) しかし,本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は,「・・・前記使
用済みクーラント液は,第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流
れ,・・・前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと,前記第
1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え,前記スクレパーにより掻き
取られた磁性体が大きくなった状態のまま,前記使用済みクーラント液の流れに沿
って前記第1の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装
置。」というものであり,同記載からすると,第2の回転ドラムから第1の回転ドラ
ムに向かうクーラント液は,第 1 の回転ドラム下部に第 1 の回転ドラムと底部材と
の間に形成された流路を流れるものであって,スクレパーによって掻き取られた磁
性体を第1の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして,このことは,
本件明細書に,「スクレパー27は,第1の回転ドラム13の下部の流路を形成する
底部材30に連結されており,掻き取られた不要物(磁性体)は第1の回転ドラム
13へと誘導される。」(段落【0041】),「スクレパー27は,第1の回転ドラム13の下部の流路を形成する底部材に連結されていれば足りるので,第2の回転ド
ラム21側から第1の回転ドラム13に向かって下降するよう傾斜していても良
い。」(段落【0053】),「図7に示すように,本実施の形態に係る回転ドラム型磁気分離装置は,第2の回転ドラム21の外筒29に当接するスクレパー27が,第
2の回転ドラム21側から第1の回転ドラム13側へ傾斜するよう設けられてい
る。」(段落【0054】),「これにより,スクレパー27で書き取られた第2の回転ドラム21に付着した不要物が,傾斜に沿って第1の回転ドラム13側へと流れに
乗って移動しやすく,第1の回転ドラム13により確実に回収することが可能とな\nる。」(段落【0055】)と記載されていることからも,裏付けられているというこ
とができる。
したがって,本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは,第2の
回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解
すべきである。
(イ) 引用文献1には,マグネットドラム27(第1の回転ドラムに相当)
とタンク17の底部との間にマグネットドラム25(第2の回転ドラムに相当)か
らマグネットドラム27に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていな
い(甲1)から,相違点3’は存在し,被告の上記主張は理由がない。
515/089515
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.06.19
令和1(行ケ)10118 審決(無効・不成立)取消 令和2年6月17日判決 請求棄却(2部)特許権 (アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン訪導体を含有する局所的眼科用処方物)進歩性,顕著な効果の有無,判決の拘束力
(イ)次に,ケトチフェンの効果から,本件化合物の効果を予測することができたかどうかについて判断する。\n
a 甲1によると,Ketotifen(ケトチフェン)とKW−4679(本件化合物のシス異性体の塩酸塩)は,いずれも,モルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果については有意でないと評価がされているが,甲32には,Ketotifen(HC)(ケトチフェン)点眼液のヒスタミンの遊離抑制効果をスギ花粉症患者の眼球への投与実験によって検討したところ,アレルギー反応の誘発後,5分及び10分後の涙液中ヒスタミン量は,対照眼と比べて,有意なヒスタミン遊離抑制効果がみられ,ヒスタミン遊離抑制率は,誘発5分後で67.5%,誘発10分後で67.2%であったことが記載されている。これらによると,ケトチフェンは,ヒトの場合においては,モルモットの実験結果(甲1)とは異なり,ヒト結膜肥満細胞安定化剤としての用途を備えており,ヒスタミン遊離抑制率は,誘発5分後で67.5%,誘発10分後で67.2%であることが認められる。
もっとも,本件優先日当時,ケトチフェンがヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制率について30μM〜2000Mの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであったと認めることができる証拠はない。なお,甲39は,本件優先日後に公刊された刊行物であって,その記載を参酌してケトチフェンが上記で認定したものを超える効果を有していると認めることはできない。b甲1において,Ketotifen(ケトチフェン)及び本件化合物と同様に,モルモットの結膜におけるヒスタミンの遊離抑制効果を有しないとされているChlorpheniramine(クロルフェニラミン)については,本件優先日当時,ヒト結膜肥満細胞の安定化効果を備えることが当業者に知られていたと認めることができる証拠はない。また,本件化合物やケトチフェンと同様に三環式骨格を有する抗アレルギー剤には,アンレキサクノス(甲1のAmelexanox),ネドクロミルナトリウムが存在する(甲1,11,19,31,弁論の全趣旨)ところ,アンレキサクノスは有意なモルモットの結膜からのヒスタミン遊離抑制効果を有している(甲1)が,本件化合物は有意な効果を示さないこと(甲1),ネドクロミルナトリウムは,ヒト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に対する実験においてヒトの結膜肥満細胞をほとんど安定化しない(本件明細書の表1)が,本件化合物は同実験においてヒトの結膜肥満細胞に対して有意の安定化作用を有することからすると,三環式化合物という程度の共通性では,ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果につき,当業者が同種同程度の薬効を期待する根拠とはならない。さらに,ケトチフェンは各種実験において本件化合物(又はその上位概念の化合物)との比較に用いられており(甲208〜210。ただし,甲210は,本件優先日後の文献である。),甲1では,ケトチフェンは本件化合物と並べて記載されているが,ケトチフェンと本件化合物の環構\造や置換基は異なるから,上記のとおり比較に用いられていたり,並べて記載されているからといって,当業者が,ケトチフェンのヒスタミン遊離抑制効果に基づいて,本件化合物がそれと同種同程度のヒスタミン遊離抑制効果を有するであろうことを期待するとはいえない。
原告は,ケトチフェンが,三環式骨格を有する抗アレルギー剤である点で本件化合物に共通し,本件化合物の上位概念の化合物やKW−4679などの効果において,比較対象とされている(甲208〜210)ことから,ケトチフェンの効果の程度から,KW−4679(本件化合物)の効果の程度を推認することは可能であったと主張するが,原告の主張を採用することはできない。したがって,甲1の記載に接した当業者が,ケトチフェンの効果から,本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する効果について,前記アのような効果を有することを予\測することができたということはできない。
(ウ)さらに,本件優先日当時,甲20,34及び37の文献があったことから,本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果をこれらの文献から予測できたかについて判断する。a甲20には,スギ花粉症患者の眼球への投与実験における塩酸プロカテロ−ル点眼液のヒスタミン遊離抑制率が,誘発5分後で0.003%点眼液が平均81.7%,0.001%点眼液が平均81.6%,0.0003%点眼液が平均79.0%,誘発10分後で0.003%点眼液が平均90.7%,0.001%点眼液が平均89.5%,0.0003%点眼液が平均82.5%であることが記載されている。また,甲34には,スギ花粉症患者の眼球への投与実験におけるDSCG(クロモグリク酸二ナトリウム)2%点眼液のヒスタミン遊離抑制率が,誘発5分後で平均73.8%,誘発10分後で平均67.5%であることが記載されている。\nさらに,甲37には,スギ花粉症患者への眼球の投与実験におけるペミロラストカリウム点眼液のヒスタミン遊離抑制率が,誘発5分後で0.25%点眼液が平均71.8%,0.1%点眼液が平均69.6%,誘発10分後で0.25%点眼液が平均61.3%,0.1%点眼液が平均69%であることが記載されている。
b しかし,本件化合物と,塩酸プロカテロ−ル(甲20),クロモグリク酸二ナトリウム(甲34),ペミロラストカリウム(甲37)は,化学構造を顕著に異にするものであり,前記(イ)bのとおり,三環式骨格を同じくするアンレキサクノスと本件化合物のモルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果が異なり,ネドクロミルナトリウムと本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果が異なることからすると,ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果も,その化学構造に応じて相違することは,当業者が知り得たことであるから,前記aの実験結果に基づいて,当業者が,本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果を,前記a記載の化合物と同様の程度であると予\測し得たということはできない。また,前記aの各記載から,塩酸プロカテロ−ル(甲20),クロモグリク酸二ナトリウム(甲34),ペミロラストカリウム(甲37)がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について30μM〜2000Mの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることはできず,他に,これらの薬剤がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について30μM〜2000Mの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることができる証拠はない。 したがって,前記aの各記載から,本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害について前記アのような効果を有することを予測することができたということはできない。\n
ウ 原告は,本件発明1の顕著な効果が認められるためには,本件化合物が0.0001〜5w/v%の濃度の全範囲で,かつ,本件明細書の表1に記載された29.6%〜92.6%というヒスタミン放出阻害率の全範囲でヒスタミン放出阻害率が顕著な効果を有しなければならないと主張する。しかし,本件発明1の効果は,30μM〜2000μMの間でヒスタミン放出阻害率が濃度依存的に上昇し,最大値92.6%となり,この濃度の間では,阻害率が最大値に達した用量(濃度)より高用量(濃度)にすると,阻害率がかえって低下するという現象が生じていないことにあるから,0.0001〜5w/v%の濃度の全範囲で,かつ,本件明細書の表\1に記載された29.6%〜92.6%というヒスタミン放出阻害率の全範囲で,他の薬物のヒスタミン放出阻害率を上回るなどの効果を有することが必要とされるものではない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
エ 以上によると,本件発明1の効果は,当該発明の構成が奏するものとして当業者が予\測することができた範囲の効果を超える顕著なものであると認められるから,当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。
◆判決本文
最高裁判決はこちら
平成30(行ヒ)69 審決取消請求事件 令和元年8月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 知的財産高等裁判所
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2020.06.12
令和元年(ネ)10044 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年1月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所(原審・東京地方裁判所平成29年(ワ)第29604号)
これに対し,控訴人は,本件技術情報1ないし6,8ないし17及び 26には,乙11記載の公知文献等に記載された情報が含まれており, 非公知性は認められない旨主張する(乙11)。 しかしながら,本件技術情報は,電磁鋼板の生産現場で採用されてい る具体的条件を含むものであり,乙11記載の公知文献等に記載されて いる研究開発段階の製造条件とは,技術的位置付けが異なる。また,乙 11記載の公知文献等に記載されている製造条件は,文献毎にばらつき があったり,一定の数値範囲を記載するにとどまるものである。そして, 電磁鋼板は多段階工程で製造され,高品質の電磁鋼板を製造するために は,各工程の最適条件の組合せが必要とされるのであって,一工程の一 条件のみでは高品質の電磁鋼板を製造することはできない。 したがって,乙11記載の公知文献等に本件技術情報の具体的な条件 を含む記載があるというだけでは,生産現場で実際に採用されている具 体的な条件を推知することはできず,非公知性は失われていないという べきである。
そして,以下に述べるとおり,本件技術情報1ないし6,8ないし1 7及び26には,乙11記載の公知文献等に記載された情報が含まれて おり,非公知性は認められない旨の控訴人の主張は理由がない。
(ア) 本件技術情報1について
控訴人は,本件技術情報1は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等に記載された情報 とは性質を異にするものであるから,大量の情報の中に本件技術情報 1に近い情報が存在しているからといって,非公知性は否定されない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(イ) 本件技術情報2について
控訴人は,本件技術情報2は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●本件技術情報2が開示されている旨主張する。 しかしながら,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●本件技術情報2の非公知性は失われないから,控訴 人の上記主張は理由がない。
(ウ) 本件技術情報3について
控訴人は,本件技術情報3は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●このことは多くの乙11記載 の公知文献等(甲99ないし108)に記載されている旨主張する。 しかしながら,前記(ア)のとおり,●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等に記載され た情報とは性質を異にするものであるから,大量の情報の中に本件技 術情報3に近い情報が存在しているからといって,非公知性は否定さ れない。また,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●が開示されているとはいえない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(エ) 本件技術情報4について
控訴人は,本件技術情報4は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● しかしながら,前記(ア)のとおり,本件技術情報4の操業条件は, ●●●●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等に記載され た情報とは性質を異にするものであり,各特許文献において「実施例」 として記載されているからといって,直ちに被控訴人における●●● ●●●●を示すものではない。 したがって,本件技術情報4は,依然として非公知であるというべ きであるから,控訴人の上記主張は理由がない。
(オ) 本件技術情報5について
控訴人は,本件技術情報5は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● したがって,本件技術情報5は非公知であるというべきであるから, 控訴人の上記主張は理由がない。
(カ) 本件技術情報6について
控訴人は,本件技術情報6は●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●本件技術情報6が開示されているとはいえない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(キ) 本件技術情報8について 控訴人は,本件技術情報8は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●乙11記載の公知文献等には ●●●●●●●●●●●技術が多く開示されている旨主張する。 しかしながら,本件技術情報8においては,●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙11記載の公知文献等に 開示されていない。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●かかる技術情報も乙11記載の公知 文献等に開示されていない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(ク) 本件技術情報9について
控訴人は,本件技術情報9は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙11記載の 公知文献等に記載されていないから,控訴人の上記主張は理由がない。
(ケ) 本件技術情報10ないし14について
控訴人は,本件技術情報10ないし14は,●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●は,乙11記載の公知文 献等に開示されている旨主張する。 しかしながら,本件技術情報10ないし14を構成する●●●●●\n●●●●●●●●●●●は,控訴人の指摘する乙11記載の公知文献 等に記載されていないから,控訴人の上記主張は理由がない。
(コ) 本件技術情報15ないし17について
控訴人は,本件技術情報15ないし17は,●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙11記載の公知文献等に開 示されている旨主張する。 しかしながら,控訴人の指摘する乙11記載の公知文献等に本件技 術情報15ないし17は記載されていないから,控訴人の上記主張は 理由がない。
(サ) 本件技術情報26について
控訴人は,本件技術情報26は,●●●●●●●●●に関するもの であるところ,乙11記載の公知文献等に開示されている旨主張する。 しかしながら,本件技術情報26の●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●は,控訴人の指摘する乙11 記載の公知文献等に開示されていないから,控訴人の上記主張は理由 がない。」
3 争点2(控訴人による不競法2条1項4号又は7号の不正競争の成否)につ いて
次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第4の3記載のとお りであるから,これを引用する。 原判決28頁5行目から8行目の「開示した。」までを次のとおり改める。 「前記1(5)で認定のとおり,控訴人は,●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●被控訴人の電磁鋼板に関する本件 技術情報を開示したことが認められる。」
4 争点3(被控訴人の損害額)について
次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第4の4記載のとお りであるから,これを引用する。
(1) 原判決30頁23行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「(4) 控訴人は,控訴人が●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●が,HGOの品質改善に大きく寄与した旨主張するが, これを認めるに足りる証拠はない。控訴人は,そのほかにもるる主張す るが,いずれも,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●との上記認定判断を左右するものではな い。」
(2) 原判決30頁24行目の「(4)」を「(5)」と改める。
5 争点4(弁済の抗弁の成否)について
次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第4の5記載のとお りであるから,これを引用する。
原判決31頁6行目から7行目までを次のとおり改める。
「しかしながら,POSCOと控訴人の負う債務は不真正連帯債務であるか ら,POSCOと被控訴人との間でPOSCOの負う債務の額について何らか の合意がされたとしても,合意の効果は控訴人に及ぶものではない。また,P OSCOと被控訴人との間の訴訟は,POSCOらによる営業秘密侵害行為等 を理由として986億円の損害賠償等を求める訴えであるところ,POSCO の支払った和解金300億円がいかなる債務のいかなる額の弁済に充てられた かを認めるに足りる証拠はない。 この点に関し控訴人は,弁済の事実の証明軽減が図られるべきである旨主張 するが,採用することはできない。 したがって,控訴人の弁済の抗弁は認められない。」
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2020.06.12
令和1(ネ)10072 販売差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和2年3月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
不正競争防止法にいう「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方 法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と 知られていないもの(同法2条6項)をいう。 ところで,争点1−2との関係で先に述べたところによれば,本件ノウハウ(2)の 完成前から存在する機械において同ノウハウに係る方法を使用することができたと きは,当該機械やそれと同じ性能・機能\を有する機械を販売することが甲5協定書 による規制を受けることはないものと解されるところ,前記認定(引用に係る原判 決第3の1(8))のとおり,被控訴人において,控訴人のいう本件ノウハウ(2)の完成 する前から,型式「WB」の製氷機を用いてマイナス50度程度の条件で冷媒を用 いて濃塩水氷を製氷することが可能であったことや,冷媒蒸発温度がマイナス65度になる冷凍機が一般に流通していたことなどの事情に照らせば,技術的には,本\n件ノウハウ(2)の完成前から同ノウハウに係る方法を用いて濃塩水氷を製氷すること ができたことが認められる。加えて,控訴人が被控訴人に本件ノウハウ(2)を伝えた とする平成29年4月28日時点で,両者の間に有効な秘密保持契約が存在してい たことを認めるに足りる証拠がないなどの事情にも照らせば,本件ノウハウ(2)は, そもそも非公知性及び有用性の要件を欠き,「営業秘密」にも当たらないというべき である。
ウ よって,本件ノウハウ(2)について,被控訴人の不正競争行為を認めることは できない。
2020.06.12
令和1(ネ)10049 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 令和2年3月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
商標法38条2項における推定の覆滅については,侵害者が得た利益と商標権 者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例 えば,商標権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性), 市場における競合品・競合サービスの存在,侵害者の営業努力(ブランド力,宣 伝広告),侵害品・侵害サービスの性能(機能\,デザイン,サービス内容等商標 以外の特徴)などの事情について,推定覆滅の事情として考慮することができる ものと解される。
これを本件についてみると,ドワンゴが提供するブロマガの配信サ ービスとFC2が提供するブロマガの配信サービスとは,いずれもブ ログ記事を配信するサービスであるという点で共通する。 一方,各サービスの具体的内容は,前記認定のとおりであり(引用 に係る原判決第2の2(3),(4),同第3の1(1),9(1),例えば,FC2 におけるブロマガの配信サービスは,ユーザーが,作成したブログ記 事に一定の設定をして投稿することで,購読料を支払ったユーザーの みがブログを閲覧することができる機能があり,ブログ記事の投稿者は,ブログ記事の年月ごとに価格を設定する方法又はブログ記事単体\nに価格を設定する方法を選択した上で,所定の範囲からその価格を設 定するという特徴を有するなど(引用に係る原判決第3の9(1)),両者 のサービス態様には少なからず相違が存在するものである。 また,前記のとおり,ニコニコのCHブロマガのサービス開始日(平 成24年8月1日)において,FC2が提供するFC2ブログには4 00万人を超えるユーザーが存在したものであり,FC2が「ブロマ ガ」の名称を付して提供するサービスは,FC2ブログの機能の一つであって,「ブロマガ」を開設し記事を投稿しようとする者,その記事\nを購入しようとする者は,いずれもFC2ブログのためのIDを有す ることが必要で,このIDにログインした上で,「ブロマガ」を利用す るものである(引用に係る原判決第3の9(1),乙139,148)。そ うすると,FC2ブログの機能の一つであることを主な理由として,「ブロマガ」の配信の役務を利用した者も多いと認められる。\n加えて,上記のとおり,FC2におけるブロマガの配信サービスは, ユーザーがブログ記事に課金設定をして投稿することで,購読料を支 払ったユーザーのみが閲覧できるというサービスであることからする と,同サービスの売上げは,ブログ記事の投稿者の知名度や記事の内 容の貢献度が高いものと考えられる。 これらの事情からすると,甲標章が,FC2におけるブロマガの配 信サービスによる利益の全てに貢献しているとはいえないから,同サ ービスによる利益の全額をドワンゴの逸失利益と認めるのは相当でな く,同サービスにおいては,商標法38条2項における事実上の推定 が一部覆滅されるというべきである。 そして,上記で判示した事情など本件に現れた事情を総合考慮する と,同覆滅がされる程度は,全体の約96%であると認めるのが相当 である。
2020.06.12
令和1(行ケ)10145 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年6月4日 知的財産高等裁判所(3部)
上記ウ(ア)によれば,味噌の製造工程においては,「天地返し」とは,味 噌の発酵・熟成の過程で味噌の上下方向の位置を入れ替えることを意味し, 味噌の熟成ムラを防いで全体の品質を均一にするなどの効果があることが 理解でき,同(5)〜(8)のとおり,「天地返し」を商品の品質を示すものとし て表示した味噌が複数販売されている。また,上記ウ(ア)(1)(4)(5)及び(イ)に照らせば,味噌を取り扱う業界におい ては,「仕込(み)」の語は,必ずしも,前記イ記載の辞書的意味である 「酒や味噌・醤油などの醸造で,原料を混ぜて桶などにつめること。」と して使用されているものではなく,味噌の製造工程における作業や手間等 を表示するものとしても使用され,また,「仕込(み)」の語の前に,味噌の品質等に関する文字や原材料等を表\示する文字が結合された場合には,「仕込(み)」の部分は,「醸造された商品(味噌)」と同旨の意味合い でも使用されているといえる。 そうすると,「天地返し仕込」の文字を指定商品である味噌に使用した 場合,取引者,需要者をして,「製造工程において上下方向の位置の入れ 替えがされた味噌」という商品の品質を表したものと認識されるものであると認められる。\n
(2) 以上に加え,上記(1)アのとおりの本願商標の構成に照らせば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表\示する標章のみからなる商標であり,商標法3条1項3号に該当するということができる。
(3) 原告の主張について
原告は,味噌の製造工程において,天地返しをして仕込むという工程は存 在しないから,「天地返し仕込」は一種の造語であり,自他識別性を有して いるから,品質を表したものとは認識されないと主張する。しかし,「仕込」の語が味噌を取り扱う業界において,必ずしも「原料を混ぜて桶などにつめ\nること。」の意味で使用されているものではないのは上記(1)エに説示したと おりである。また,本願商標の指定商品である味噌の需要者には一般消費者 が含まれるところ,一般消費者が,味噌の製造工程において,天地返しをす る対象が醸造された味噌なのかその原料なのかといった点に着目するとは解 し得ない。これによれば,味噌の製造工程において,天地返しをして仕込む という工程が存在するか否かは,上記判断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2020.06.12
令和1(行ケ)10085 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年6月4日 知的財産高等裁判所(3部)
相違点6に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構\成は,次のとおりである。(1)「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減 じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって,どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の\n取決めにすぎない。 (2) よって,第7領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を,第3領域(敵ヒーローへの攻撃を行うための領域)への移動を補充の\n契機とする本願発明の構成に変更することは,ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。\n(3) よって,引用発明の構成を本願発明における構\成とすることも,ゲーム 上の取決めの変更にすぎず,当業者が容易に想到し得た。
(2) しかしながら,審決の上記論理構成は,次のとおり不相当である。ア 審決は,引用発明の認定に当たって「カード」の種類に言及していない が,CARTEによれば,第10領域から第11領域へのカードの補充の 契機となるのは,「シャードカード」(深緑の地色に白抜きで円形と三日 月形が表示されているカード)の第11領域から第7領域への移動及び第7領域から第6領域への移動である(00分39秒〜40秒,00分49\n秒〜50秒等)。 そして,「シャードカード」は,専ら「マナ」(カードのセッティング やスキルの発動に必要不可欠なエネルギー<00分42秒>)を増やすため に用いられるカードであり,その移動先はシャードゾーン(第7領域)又 はマナゾーン(第6領域)に限られ,敵との直接の攻防のためにアタック ゾーン(第3領域)又はディフェンスゾーン(第4領域)に移動させられ ることはない。これに対し,「クリーチャーカード」は,敵のクリーチャ ーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって,第11領域から適 宜アタックゾーン(第3領域)又はディフェンスゾーン(第4領域)に移 動させられ,攻防の能力を表\す「APの値」及び「HPの値」を有してい る。
イ このように,引用発明におけるカードの補充は,本願発明におけるそれ との対比において,補充の契機となるカードの移動先の点において異なる ほか,移動されるカードの種類や機能においても異なっており,相違点6は小さな相違ではない。そして,かかる相違点6の存在によって,引用発\n明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。し たがって,相違点6に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として,他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断すること\nは,相当でない。
(3) 被告の主張について
被告は,手持ちのカードの数が減じたときにこれを補充する構成(乙7,乙8)とするかこれを補充しない構\成(乙9,乙10)とするかは,ゲーム制作者がゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計的な事項にすぎな いから,引用発明において,第3領域(アタックゾーン)にカードを配置し た場合でも第11領域の手持ちカードが補充されるようにすることは,何ら 技術的な困難性があることではなく,まさに,提供しようとするゲーム性に 応じたゲーム上の取決めにすぎない旨主張する。 しかしながら,相違点6は,ゲームの性格に関わる重要な相違点であって, 単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはで きないことは,(2)において説示したとおりである。。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.06.12
令和1(行ケ)10075 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年5月28日 知的財産高等裁判所
イ 相違点2−4について
本件明細書には,「樹脂層40の原料は,低温接着性樹脂(低融点樹脂)であって, 熱ラミネート(熱融着)が可能なものであれば制限されない」(【0043】)との記載があるところ,かかる記載によれば,本件発明7の「熱ラミネート」との用途は,\n「熱封着樹脂層」に基づくものである。 一方,引用例2の「接着層となる…エチレン・メタクリル酸共重合体の金属塩な どの,融点が85〜135℃のヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」との記載 によれば,引用発明2Bの「融点が90℃のエチレン・メタクリル酸共重合体(C) からなるC層」は,「ヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」であり,熱封着樹脂 層である。 そうすると,本件発明7の「熱封着樹脂層」と引用発明2Bの「融点が90℃のエ チレン・メタクリル酸共重合体(C)からなるC層」とは,ともに熱封着樹脂層であ るから,「熱ラミネート」用であるとの点において,相違はないものと認められる。 したがって,相違点2−4は,実質的な相違点ではない。
ウ 小括
以上によれば,本件発明7は,当業者が引用発明2Bに基づいて容易に発明をす ることができたものである。
(4) 本件発明8の容易想到性について
本件発明8は,本件発明7の「第1のスキン外層」をポリエチレン系樹脂,「コア 層」をポリプロピレン系樹脂,「第2のスキン内層」をポリプロピレン樹脂及びポリ エチレン系樹脂から選択された1種以上,「熱封着樹脂層」をエチレンビニルアセテ ート,エチレンメチルアセテート,エチレンメタクリル酸,エチレングリコール,エ チレン酸ターポリマー,及びエチレン/プロピレン/ブタジエンターポリマーより なる群から選択された1種以上に,それぞれ限定したものである。 引用発明2Bの「融点が90℃のエチレン・メタクリル酸共重合体(C)からなる C層」は,「ヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」,すなわち,「熱封着樹脂層」 であるから,「エチレンメタクリル酸」を原料とする「熱封着樹脂層」が開示されて いる。 また,引用発明2の基材層として,従来技術(甲33)に開示された構成を採用する動機付けがあることは,前記(2)アのとおりであるところ,甲33に開示された複 合フィルムは,ポリプロピレン,ポリプロピレン,ポリエチレンからなるから,「第 1のスキン外層」をポリエチレン系樹脂,「コア層」をポリプロピレン系樹脂,「第2 のスキン内層」をポリプロピレン樹脂及びポリエチレン系樹脂から選択された1種 以上にすることも容易に想到できる。 他方,阻害事由の主張はない。 したがって,引用発明2Bの層構成を本件発明8のものとすることは,当業者が容易に想到することであるから,本件発明8は,当業者が引用発明2Bに基づいて\n容易に発明をすることができたものである。
(5) まとめ
本件発明6は,引用例2に記載された発明から容易に発明できたものではないが, 本件発明7,8は,いずれも,引用例2に記載された発明から容易に発明できたも のであり,取消事由2は,本件発明7,8に係る部分に限り,理由がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.05.11
平成29(ワ)24598 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月26日 東京地方裁判所
原告による測定結果
株式会社東洋環境分析センターが,平成30年2月,原告の依頼によ り,宮崎県食品開発センターが保有するPT−Rを用いて,前記イの記載 に従って,同じロットナンバーの被告製品2について,3回測定した結果 によれば,被告製品2(1ロット)の見掛けタッピング比容積は,いずれ も2.4cm3/g(2.45cm3/g,2.46cm3/g,2.46cm3/g)で あった(甲20の1,20の2)。
オ 被告による測定結果
株式会社住化分析センターが,平成30年2月,被告の依頼により, PT−Xを用いて,前記イの記載に従って,製造時期が異なりロットナ ンバーが異なる5つの被告製品についてそれぞれ1回ずつ測定した結果 によれば,被告製品2(製造時期の異なる5ロット)の見掛けタッピン グ比容積は2.2〜2.3cm3/g(2つの製品について2.2cm3/g, 3つの製品について2.3cm3/g)であった(乙11)。 被告が,平成30年10月頃,宮崎食品開発センターが保有するPT −Rを用いて,前記イの記載に従って,製造時期が異なりロットナンバ ーが異なる5つの被告製品2について,それぞれ3回ずつ測定した結果 によれば,その見掛けタッピング比容積は2.2〜2.3cm3/g(3つ の製品について3回とも2.3cm3/g,1つの製品について2.2cm3/ g,2.2cm3/g,2.3cm3/g),1つの製品について,2.2cm3/ g,2.3cm3/g,2.3cm3/g)であった(乙34)。
(2)本件明細書の特許請求の範囲には見掛けタッピング比容積の測定方法は記 載されていないが,発明の詳細な説明には,前記(1)イのとおり,実施例・比 較例における見掛けタッピング比容積はPT−Rを用いて測定された値であ る旨の記載がある。
原告は,PT−Rを用いて測定した結果(前記(1)エ)によれば,被告製品 2の見掛けタッピング比容積は2.4cm3/gであるから,構成要件1F及び2Fをいずれも充足すると主張する。\nて測定した結果によれば,製造時期の異なる5ロットの被告製品2につき, いずれも見掛けタッピング比容積が2.4cm3/gに達していなかった。その 実験の信用性が否定されることを裏付ける客観的な証拠はない。上記のとお り,5ロットという複数の被告製品2について,それぞれ3回ずつ検査した 結果,いずれも見かけタッピング比容積が構成要件1F・2Fの下限である2.4cm3/gに達していなかったというのであるから,被告製品2は構成要定対象,測定方法による測定結果に照らして,原告の同エの測定結果によっ\nて被告製品2の見掛けタッピング比容積が2.4cm3/gであることを認める に足りない。
・・・
本件発明1及び2は,前記のとおり,2.5N塩酸,15分,沸騰温 度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度(平均重合度) をレベルオフ重合度とするものである(そのような具体的な本件加水分 解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。)。したがって,本件では,本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解さ\nれた後に測定されるレベルオフ重合度について,優先日当時,当業者 が,技術常識に基づいて,発明の詳細な説明に記載された原料パルプの レベルオフ重合度と,原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉 末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題 となるといえる(なお,本件加水分解条件は,レベルオフ重合度を求め るものとして,当該酸濃度温度条件では比較的短時間といえる時間の加 水分解を定めたものであることがうかがえる。)。
ここで,優先日当時,本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合 度について,天然セルロースとそれを加水分解して生成されたセルロー ス粉末とが同じレベルオフ重合度となることを直接的に述べた文献があ ったことを認めるに足りる証拠はない。他方,本件明細書においてレベ ルオフ重合度の説明において現に引用されている文献であり,種々の対 象について本件加水分解条件を含む条件で加水分解をした上で本件加水 分解条件(2.5N塩酸,沸騰温度,15分)を提唱したBATTIS TA論文は,(1)木材パプルについて,温和な加水分解条件での加水分解 を経た後に2.5N塩酸,沸騰という過酷な条件で加水分解した重合度 と,温和な加水分解条件での加水分解を経ずに2.5N塩酸,沸騰温度 という条件で加水分解した重合度を実際に測定して,前者の値が後者の 値より低かったこと,(2)セルロースを加水分解した際には結晶化がされ るという他の複数の研究者による研究成果を紹介した上で,上記(1)等の 実験結果は温和な加水分解は重量減少を伴わない結晶化を誘導すること を示しているようであること,(3)温和な加水分解や過酷な加水分解で起 こるメカニズムを提唱した上で,温和な加水分解を経た後に過酷な加水 分解がされた場合には結晶化された短いセルロース鎖の残渣が保持され るため,温和な加水分解を経ずに過酷な加水分解がされた場合よりもレ ベルオフ重合度が低下すると予想されることなどを述べていた。なお,セルロースの加水分解において再結晶化が起こることは他の文献でも紹\n発明の詳細な説明の実施例2ないし7のセルロース粉末は,前記 のとおり,原料パルプを4N塩酸,40°C,48時間という条件,3N 塩酸,40°C,40時間という条件,3N塩酸,40°C,24時間とい う条件などで加水分解したものであり,天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。 前記のとおり,本件では本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が問 題となるところ,本件加水分解条件を提唱し,本件明細書でも引用してい るBATTISTA論文は,上記のとおり,他の複数の研究者による研究 成果を紹介した上で,本件加水分解条件によるレベルオフ重合度について は,温和な加水分解を経た場合にはその過程を経ていないものに比べて, 値が低下することが予想されると述べていた。その内容とは異なり,本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合度について,天然セルロースと,\nそれを温和な条件で加水分解して生成されたセルロース粉末とが同じレ ベルオフ重合度であるという技術常識があったことを認めるに足りる証 拠はない。 に述べられるレベルオフ重合度は本件加水分解 条件により測定されたものではないし,同文献の著者は,優先日頃におい ても,著者が考える「レベルオフ」するためには本件加水分解条件の時間 では足りないと考えられていた旨述べる(同 )。 また,本件明細書に記載された実施例のセルロース粉末は,原料パル プを加水分解した後,攪拌,噴霧乾燥(液供給速度6L/hr、入口温 度180〜220°C、出口温度50〜70°C)して得られたものであ る。当該セルロース粉末の本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度 の明示的な記載が明細書にない以上は,上記加水分解,攪拌,噴霧乾燥 の工程を経た当該セルロース粉末について,本件加水分解条件下でのレ ベルオフ重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識がある 場合に,当該セルロース粉末のレベルオフ重合度が本件明細書に記載さ れているに等しいといえる。上記の加水分解,攪拌や噴霧乾燥を経たセ ルロース粉末の本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度が原料パルプ のそれとの関係でどのような値になるかについての技術常識を認めるに 足りる証拠はない。 これらを考慮すれば,優先日当時,当業者が,本件明細書に記載され た原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセ ルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じである と認識したと認めることはできない。また,発明の詳細な説明の実施例 は,具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解,攪 拌,噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が,優先日 当時,技術常識に基づいて,記載されている当該原料パルプのレベルオ フ重合度に基づいて,上記具体的な条件で得られたセルロース粉末につ いて,本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することが できたとも認められない。
以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,セルロース粉末 について,本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度の記載があるの に等しいとは認められない。 カ 原告は,非晶質領域が分解されて結晶領域のみが残った状態に達したと きの重合度であるレベルオフ重合度は,途中に原料パルプから本件セルロ ース粉末という加水分解過程を経ると否とに関わらず同じ値となるのであ り,当業者であれば,原料パルプとそこから温和な加水分解によって得ら れる本件セルロース粉末のレベルオフ重合度は等しくなると当然に理解す ることができる旨主張し,また,BATTISTA論文における上記実験 結果における温和な加水分解の条件が,本件の実施例における原料パルプ からセルロース粉末を生成する温和な加水分解の条件と同じものではない ことを指摘する。
しかし,本件においては具体的な本件加水分解条件による加水分解がさ れたセルロースの重合度(平均重合度)が問題となる。本件加水分解条件 を提唱し,発明の詳細な説明でも引用されるBATTISTA論文が,本 件加水分解条件によるレベルオフ重合度について前記のように述べていた ところ,優先日当時,そこに記載されているのと異なる内容の技術常識が あったことを認めるに足りる証拠はない。また,BATTISTA論文 は,セルロースを加水分解した際には結晶化がされるという他の複数の研 究者による研究成果を紹介した上で,前記の予想をしているのであり,そこに記載されているのと異なる技術常識があったことを認めるに足りる証\n拠がない本件で,BATTISTA論文においてされた実験での温和な加 水分解の条件が,本件の実施例における原料パルプから粉末セルロースを 作成する加水分解の条件と全く同じものではないことは上記の結論を直ち に左右するものではない。
なお,原告は,実験をした結果,原料パルプを本件加水分解条件で加水 分解したときの平均重合度と,当該原料パルプを実施例2と同じ加水分解 条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解し たときの平均重合度は実質的に同じであったとして,平成30年8月頃に 測定された結果を記載した平成31年3月20日付け報告書(甲56の 1)を提出し,また,上記でセルロース粉末を得る際の写真やセルロース 粉末を得た際に80°Cの熱風を当てる工程を含む24時間の乾燥処理をし たことなどが記載された同年4月9日付け報告書(甲57)を提出する。 しかし,本件では,優先日当時,本件明細書に記載された加水分解,攪 拌,噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について,本件加水分解条 件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が 問題となるところ,上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認める ことはできない。
キ 以上によれば,本件差分要件は,粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるとこ ろ,明細書の発明の詳細な説明には,実施例について,粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく, また,優先日当時の技術常識によっても,それが記載されているに等しい とはいえない。したがって,本件明細書の発明な詳細には,本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。
そうすると,本件明細書の発明な詳細において,特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえ\nない。 以上によれば,本件発明1及び2は,発明の詳細な説明の記載により当業 者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないから,特 許法36条6項1号に違反する。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.04. 2
令和1(ネ)10058 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
前記認定のとおり,本件地盤特許についてはecoリーフ の下請けであるはなみずきの担当者のFが,本件ナビ特許については リーフの担当者であるE又は代表取締役であるAが,被控訴人に対し,本件各特許権の共有持分を購入すれば,近日中に大幅に価値が上がり,\n高額なロイヤリティを受け取れるなどと虚偽の説明をして購入を勧誘 し,被控訴人から,本件各特許権の共有持分の購入代金名下に合計8 295万円を騙取したものと認められ,これらの行為は被控訴人に対 する不法行為を構成するものと認められる。加えて,(1)このように本件各特許権の持分を細分化して高額で譲渡 するという基本的枠組みは,控訴人X2,日本知財開発及びジンムの 関与がなければ成立し得ないものであるから,Fらが控訴人X2,日 本知財開発及びジンムと無関係に被控訴人に対する上記虚偽の説明を して勧誘を行ったものとは考えられないこと,(2)本件地盤特許譲受申込書(甲3)には,本件地盤特許の共有持分を1口60万円で譲渡す\nることが,本件ナビ特許の特許権譲受申込書(甲5)には,本件ナビ特許の共有持分を1口20万円で譲渡することが記載されているとこ\nろ,いずれの書面にも特許権者及び譲渡者として控訴人X2の氏名及 び日本知財開発の名称が記載されていること,(3)控訴人X2及び日本 知財開発が作成した別件侵害訴訟に関する報告書(甲22ないし24 の2)及び本件ナビ特許に関する報告書(甲27の1ないし3)の各 内容に照らすと,控訴人X2,日本知財開発及びジンムは,Fらが上 記虚偽の説明をして,被控訴人に本件各特許権の共有持分を購入させ たことを認識し,これに積極的に加担したものと認められる。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば,ecoリーフ,はなみずき,リーフ, 控訴人X2,日本知財開発及びジンムは,被控訴人から本件各特許権 の共有持分の購入代金名下に合計8295万円を騙取したことの全体 について,共同不法行為責任を負うものと認めるのが相当である。 したがって,控訴人らの前記主張は採用することができない。 イ 控訴人X3は,本件については何も知らず,控訴人X2は監督すべき 要注意の人物ではないから,控訴人X3が控訴人X2に対する強い監督 責任を問われるべきものではない旨主張する。 しかしながら,控訴人X3は,ジンムの取締役であり,代表取締役である控訴人X2の業務執行が適正に行われるよう監視すべき義務がある。\nしかるところ,控訴人X3作成の平成29年11月4日付け答弁書(原 審)には,5年前に,控訴人X2から,特許の一部を譲ってその代金が もらえると聞いていたが,訴外鹿島建設との裁判に負けた後は控訴人X 3への説明はなくなった旨の記載がある。上記記載によれば,控訴人X 3は控訴人X2が特許権の共有持分権を譲渡していることを認識してい たことが認められるから,控訴人X2の業務執行について監視を行うこ とが可能であったものと認められる。もっとも,上記答弁書中には,控訴人X3は控訴人X2と別居中である旨の記載があるが,別居が開始し\nた時期やその態様についての記載はないことに照らすと,上記記載から 直ちに控訴人X2の業務執行についての監視が困難であったものと認め ることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,控訴人X3は,控訴人X2及びジンムが関与した本件各 特許権の共有持分の不正な販売行為に関し,ジンムの取締役としての控 訴人X2に対する監視義務の履行を怠ったことについて重大な過失があ ったものと認められるから,被控訴人に対し,会社法429条1項に基 づく損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。 したがって,控訴人X3の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
原審はこちら。
2020.04. 2
令和1(ネ)10082 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
控訴人は,本件発明1における構成要件E及びFの「フリップフロップ現象発生用軸体」について,「フリップフロップ現象を発生させる軸体を意味する。」との原判決の判断には誤りがあると主張する。\nしかし,本件発明1における構成要件E及びFの「フリップフロップ現象発生用軸体」は,その文言からフリップフロップ現象を発生させる軸体を意味することは\n明らかである。また,本件明細書を見ても,本件発明1はクーランド液が「フリッ プフロップ現象発生用軸体」を通過することによってフリップフロップ現象を発生 させるなどして,その課題を解決するものである(本件明細書の【0006】, 【0007】,【0041】〜【0045】)から,「フリップフロップ現象発生 用軸体」がフリップフロップ現象を発生させる軸体であることは明らかである。 したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 控訴人は,本件明細書の【0037】は,電子回路の用語を参考に記載 しているだけであるのに,原判決は,本件発明1が「フリップフロップ現象」を解 決原理としていると誤解していると主張する。 しかし,本件明細書の【0037】の記載が,電子回路の用語に基づく参考記載 にすぎないと認めることができないことは,原判決の「事実及び理由」の第4の2(1)イ(カ)bの通りである。
(1) また,上記アのとおり,本件発明1は,「フリップフ ロップ現象」を解決原理としているものである。 したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 「フリップフロップ現象」の意味について
ア 控訴人は,本件明細書の【0011】,【0043】及び【0007】 の記載によると,フリップフロップ現象とは,「フリップフロップ現象発生用軸体 を通過することにより当該現象の結果として『クーラント液等』が『乱流となり無 数の微小な渦を発生』した状態」を指すことを基本としていると主張する。 しかし,本件明細書の【0037】に,「フリップフロップ現象(フリップフロ ップ現象とは,流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象)」と 記載されている上,本件各発明と共通する技術分野において,本件特許出願前に 「フリップフロップ現象」の語が,おおむね,流体の流れの周期的な振動ないし方 向変換を意味するものとして使用されていること(原判決の「事実及び理由」の第 4の2(1)イ(ウ))からすると,本件発明1におけるフリップフロップ現象は,基本 的には,(1)「流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象」を意味 すると解釈することができ,(2)「クーラント液等」が「乱流となり無数の微小な渦 を発生」した状態を指す語としての使用は,上記(1)の意味におけるフリップフロッ プ現象の発生を前提とした,派生的な使用と位置づけられるべきである。控訴人が 指摘する本件明細書の【0011】,【0043】及び【0007】の記載は,こ の判断を左右するものではない。
イ 控訴人は,本件特許の出願当時の当業者の理解について主張する。 まず,乙14〜20は,いずれも公開特許公報であるが,これらの特許において は,A及びBのほか,C(乙16),D(乙17),E(乙18,20),F(乙 19)も共同発明者とされていることが認められるから,単に,A及びBの2名の 研究者,発明者がフリップフロップ現象を「流体の流れの周期的な振動ないし方向 転換を意味するもの」として使用しているとは認められない。 また,控訴人は,本件発明1の構成要件Dの記載によると,当業者は,本件明細書の【0037】の括弧内の記載の流れ(流体の流れる方向が周期的に交互に方向\n変換して流れること)が生じないことを理解すると主張する。 しかし,本件発明1の構成において,ひし形凸部がフリップフロップ現象発生用軸体の軸心に対してどのような傾きをもって設置されているかは特定されておらず,\n上記軸心に対してひし形凸部が傾きを持っていて非対称となっているかは明らかで はないから,当業者が,本件明細書の記載や,「フリップフロップ現象」の語につ いての当業者の一般的な理解に反して,本件明細書の【0037】の括弧内記載の 流れ(流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象)が生じないこ とを理解すると認めることはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2020.04. 2
令和1(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月19日 知的財産高等裁判所
本件審決は,引用発明1及び甲4発明の装身具は,いずれも,装身 具を簡単にシャツの第一ボタンに装着できるようにするという共通の課 題を有し,また,これを着用するに当たり,切欠き状の部分にボタンが はまり込むことで装着するという共通の機能を有するから,引用発明1のボタン係合部19における切欠き状の部分の具体的な形状として,甲\n4発明の係止導孔を有する円形の釦挿通孔の態様を採用し,相違点2に 係る本件補正発明の構成とすることは,当業者であれば容易になし得たことである旨判断した。\nしかしながら,前記(2)イのとおり,引用発明1は,簡易型のネクタイ 本体を取付ける着用具を改良することによって,着用状態における位置 ずれや傾きを生じ難く,低コストで生産でき,そして着用操作も容易で ある簡易着用具付きネクタイを提供することを課題とするものである。 一方,前記ア(イ)のとおり,甲4に記載された考案は,襟飾り,生花 等の種々の装飾小物,殊に襟前に止着する装身具について,着脱が簡単 であり,かつ,衣服の損傷がほとんどない装身具取付台を提供すること を課題とするものであるが,かかる装身具として,蝶ネクタイやネクタ イを例示するものではなく,蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有 の問題があることを指摘するものでもない。 したがって,引用発明1と甲4発明は,その具体的な課題において, 大きく異なるものといえる。 また,発明の作用・機能をみても,引用発明1は,基板部,ネクタイ取付部及び一対の突出片から成る簡易着用具を備え,ネクタイ取付部の\n裏側に位置する基板部に,その下縁を凹状に切り欠いたボタン係合部を 設け,その切欠きにシャツの第一ボタンを係合させるとともに,一対の 突片を襟下へ挿入することで,簡易蝶ネクタイの良好な着用状態及び簡 単な着用操作を実現するものである(前記(2)ア(オ))。 そして,甲1には,引用発明1に関し,(1)「ボタン係合部19」の奥 部は,ボタン取付け糸の部分を丁度跨ぐことができる程度の小円弧状を なすものとし,その幅は,ボタンとの係合状態において横方向にほとん ど移動しない程度のものとすること,(2)着用時にボタンとの係合を容易 にするとともに,着用時に基板部2の片側がボタン穴に入り込むことを 防ぐために,「ボタン係合部19」の下方を,ラッパ状に下方へ拡大し て基板部2の下縁に達するものとすることの記載(前記(2)ア(エ)a)が ある。これは,結び目の陰に隠れて見えない状態のボタン係合部を,上 方から探りながらも容易に装着できるようにするための工夫といえるか ら,簡易着用具1の基板部2における,ボタン係合部19の配置位置及 びその形状を引用発明1の構成とすることは,引用発明1の課題を解決するために,重要な技術的意義を有するものであることを理解できる。\n他方,甲4発明は,取付台主板に対して上方に係止導孔を連続形成し た釦挿通孔を穿設すると共に,他の一部に背面方向に突出するピンを突 設し,ピン先端にピン挟持機構を有するピン挿入キャップを冠着することで,釦の確実な止着と,各種装身用小物の衣類への簡単な着脱を実現\nするものであって(前記ア(イ)b),第1ボタンへの係合方法,衣類への 確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において,引用発明1と大きく異 なるものであるから,発明の具体的な作用・機能も,引用発明1とは大きく異なるものといえる。\n
加えて,甲4の記載事項(前記ア(ア)c)によれば,甲4発明の装身 具取付台は,衣類に装着する際に,第1ボタンの前部からアプローチし て,釦挿通孔(2)に挿入した後,装身具取付台を鉛直方向の下部に移 動させ,係止導孔(3)を第1ボタンの取付糸に係合するものであるか ら,当業者であれば,第1ボタンを釦挿通孔(2)に挿入する際に,こ れらを視認できる状態でないと,ボタンの着脱動作が困難となることを 理解できる。
そうすると,仮に,引用発明1のボタン係合部19における切欠き状 の部分の具体的な形状として,甲4発明の「細幅の係止導孔(3)を有する 円形の釦挿通孔(2)」の態様を採用した場合には,ボタン係合部19の前 側に位置し,その前側にネクタイが取り付けられるネクタイ取付部3が 存在するため,簡易蝶ネクタイを着用する際に,簡易蝶ネクタイ及びネ クタイ取付部に隠されて,第1ボタン及びボタン穴を視認することがで きないことになる。そのため,ボタン係合部を切欠き状にする場合より も,着用具へのボタンの係合が困難となることは明らかであるといえる。
(イ) 以上によれば,引用発明1と甲4発明とは,発明の課題や作用・機 能が大きく異なるものであるから,甲1に接した当業者が,甲4の存在を認識していたとしても,甲4に記載された装身具取付台の構\成から,「細幅の係止導孔(3)を有する円形の釦挿通孔(2)」の形状のみを取り出し, これを引用発明1のボタン係合部19における切欠き状の部分の具体的 な形状として採用することは,当業者が容易に想到できたものであると は認め難く,むしろ阻害要因があるといえる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2020.04. 2
令和1(行ケ)10095 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月12日 知的財産高等裁判所
請求項1には,「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」との 記載があるところ,請求項1の記載自体から,この炭化タングステン粒子は,「少な くとも二個の粉砕工具」の「工具表面」に「含有」されるものであることを理解することができ,また,上記炭化タングステン粒子は,第1の粉砕工具の表\面には95重量%以下含有され,その粒径が1.3μm以上であること,第2の粉砕工具の表面には80重量%以上含有され,その粒径が0.5μm以下であること,粒径はメ\nジアン粒径であること,炭化タングステン粒子のメジアン粒径が1.3μm以上あ るいは0.5μm以下であることは,炭化タングステン粒子を「質量により秤量」し て測定するものであることが理解できる。 しかしながら,請求項1の記載からは,粉砕工具の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義が明らかであ\nるとはいえない。 また,本件特許の出願当時において,炭化タングステンを含んでなる表面を有する粉砕工具の工具表\面に含有される炭化タングステン粒子につき,質量により秤量したメジアン粒径を得ることができたとする当業者の技術常識を認めるに足りる証 拠はない。
イ 本件明細書の記載
本件明細書には,「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表\面」のタングステン含有量が95%以下であり,工具表面の材料における\n100%に対する残りは,好ましくはコバルト結合剤であり,好ましくは1%未満 の程度に追加の炭化物が存在する(【0026】〜【0028】),焼結の結果は,炭 素の添加によっても影響を受ける(【0029】)との記載があり,「炭化タングステ ンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表\面」の炭化タングステン粒子 が,コバルトである結合剤と焼結により一体化していることが開示されている。そ して,本件明細書には,コバルト結合剤と焼結により一体化した「粉砕工具」の「工 具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径について,定義や測定方法の記載はない。\nウ 以上によれば,本件明細書の記載を考慮し,出願当時の技術常識を基礎とし ても,本件発明の「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表\面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義を理解することはできず,本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを 得ないから,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,明確性要件を充足しないと いうべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義 は,沈降法により測定されるストークス径について,質量を基準に粒子径を表した質量分布におけるメジアン粒径ということで,一義的に明確であり,ストークス径\nはストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。 そこで検討するに,甲18(神保元二ら編「微粒子ハンドブック」初版第1刷,1 991年9月1日)には,ストークス径は,最も広く用いられる代表径であり,静止流体中を重力で落下する粒子の沈降速度v1と同じ沈降速度をもち,また同じ密度を\nもつ球形粒子の直径であり,流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な 代表径であることの記載があり,本件出願当時,粒子の大きさを測定する方法として,ストークス径を得る沈降法があることは,周知であったことが認められる。\nまた,ウェブページ「粒度分布測定の基礎知識」(甲19)には,「主な粒度分布測 定原理」の表の「遠心沈降法」の欄に,「測定粒子径の定義」を「ストークス径」,「基本粒度分布」を「重量基準」との記載があり,「遠心沈降法 液相中の粒子群の沈降 状態を吸光度などから計測して,球と仮定して導かれたストークスの式などと照合 し,有効径(ストークス径)を求める。」との記載がある。ウェブページ「粒径分布 測定[重力/遠心沈降式]」(甲22)には,「[測定原理/測定法]微粒子を水または不溶溶媒中に懸濁させ,重力場にそのまま静置するか遠心場に粒子懸濁液を置くと, 大きな粒子ほど速い速度で沈降していきます。その様子を粒子懸濁液に照射したレ ーザー光の透過光強度によって検出します。粒子サイズは重力沈降の場合,次のS tokesの式から得られます。」との記載があり, とのストークスの式が記載されている。これらによれば,沈降法は,重量(質量)基 準に基づく粒度分布が得られるものであること,液相中の粒子の沈降速度から粒径 を求めるものであり,分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認められる。\nしかし,前記(2)イのとおり,本件明細書には,「炭化タングステンを含んでなる 表面を有する」「粉砕工具」の「工具表\面」の炭化タングステン粒子が,コバルトで ある結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方,炭化タングス テン粒子が工具表面から分離可能\であることの記載や示唆はない。また,ストーク スの式によりストークス径を算出するためには,ストークスの式に沈降距離h,沈 降時間t等のパラメータを代入することが必要であるところ,本件明細書を見ても, ストークスの式のパラメータの値としてどのような値を採用するかについての記載 はない。 そうすると,粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があ ることが周知であり,沈降法により重量(質量)基準に基づく粒度分布が得られる としても,「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が,コバルトである結合剤と焼結により一体化している以上,沈降法により炭化タング\nステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから,本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が,沈降法に基づいて得\nられるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。
イ 原告は,焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か,変化 するとしてどの程度変化するかは,焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも 十分に予\測が可能であり,その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径を調整し,必要に応じて焼結条件を調整すればよく,また,焼結の前後それぞれの\n炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し,その変化の有無や程度を確認するこ とで,ストークス径の粒度分布の変化を予測することは可能\であるから,工具表面に存在する炭化タングステン粒子自体を測定するまでもない,また,本件発明にお\nけるメジアン粒径は,「1.3μm以上」ないし「0.5μm以下」という広い範囲 を規定するものであるから,焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性にほとんど影 響を及ぼさないと考えられる旨主張する。 しかし,本件明細書には,焼結条件との兼ね合いで焼結による粒径の変化を予測して炭化タングステン粒子の粒径を調整することや,焼結の前後それぞれの炭化タ\nングステン粒子の粒径を画像で確認し,その変化の有無や程度を確認してストーク ス径の粒度分布の変化を予測することの記載や示唆はないから,本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が,かかる予\測や調整等を行うことを前提として沈降法により測定されるストークス径のメジアン粒径である とは解されない。また,本件発明におけるメジアン粒径が,広い範囲を規定するも のであるとしても,焼結の有無が数値範囲の充足性に影響を及ぼさないと解すべき 根拠はないから,上記の判断を左右するものではない。
ウ 原告は,焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要がある としても,コバルトの融点は1495℃,炭化タングステンの融点は2870℃で あるから,バインダーであるコバルトを溶かすなどして除去し,炭化タングステン 粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である旨主張する。しかし,本件明細書には,一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン\n粒子とを加熱し,バインダーであるコバルトを除去し,炭化タングステン粒子を取 り出して沈降法で測定することについては,記載も示唆もないから,本件発明の「炭 化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が,コバルトを除去して 取り出した炭化タングステン粒子を沈降法により測定したストークス径であるメジ アン粒径であるとは解されない。 仮に,上記測定方法により炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定する ことができたとしても,一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン粒子 とを加熱し,バインダーであるコバルトを除去し,炭化タングステン粒子を取り出 すという過程において,炭化タングステン粒子の密度や形状が一切変化しないとい う根拠はないから,そのように取り出して測定した炭化タングステン粒子のストー クス径が,そのまま,コバルトマトリックスと一体化した工具表面の炭化タングステン粒子のストークス径であるということもできない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2020.04. 2
令和1(行ケ)10135 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所
前記(3)のとおり,「AI」の語は,多くの新聞やウェブサイト等におい て,「人工知能」を意味する言葉として使用されていること,その中には,「AI」の語の意味を説明せずに「AI」とのみ表\記されているものもある(甲3,4)ことからすると,「AI」の語は,人工知能を意味する言葉として一般的に知られているものと認められる。\nそして,前記(3)のとおり,介護の分野において人工知能である「AI」を活用することに関する新聞やウェブサイトの記載が多数あると認められるが,一方で,証\n拠上,介護の分野において,「AI」という語を人工知能以外の意味で使用している例があるとは認められないことからすると,介護の分野において「AI」の語を使\n用した場合は,その「AI」は,人工知能を意味するものと認識されるというべきである。\n前記(3)のとおり,新聞やウェブサイト等においては,「AI介護」の語が,AI を活用した介護という意味で,「AI介護ソフト」の語が,AIを活用した介護のためのソ\フトウェアという意味で,「AI介護事業」の語が,AIを活用した介護事業という意味で,「AI介護ロボ」及び「AI介護ロボット」の語が,AIを活用した 介護用ロボットという意味でそれぞれ使用されていることからすると,「AI」の語 に名詞が続いた場合は,当該「AI」は,「AIを活用した」との趣旨で使用され, また,そのような使用法が一般的に受け入れられているものと認められる。 以上からすると,本願商標の「AI介護」からは,AIを活用した介護という意 味合いが生じ,本願商標に接した取引者,需要者は,通常,本願商標は,本願の指 定役務である「介護」の質を示すものと認識するため,本願商標は,自他役務識別 力を欠くというべきである。 したがって,本願商標は,商標法3条1項3号の商標に該当するというべきであ る。
(5) 原告の主張について
ア 原告は,本願商標の「AI」の語は「愛」のローマ字読みであり,本願 商標からは,「愛の介護」というような意味合いを生じると主張する。 しかし,前記(4)のとおり,「AI」の語は,人工知能を意味する言葉として一般的に知られていること,「愛」をローマ字読みで表\記する場合に,「I」の文字を大文字で表記することは不自然であることからすると,「AI」の語は,通常,「エーアイ」と発音され,人工知能\を意味するものと認識されるというべきであり,「愛」と認識されるとは認められない。このことは,本願の商標出願・登録情報表示において,「AI介護」の称呼を,第1に「アイカイゴ」としていることによって左右され\nない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。 イ 原告は,(1)「AI介護ロボ」,「AI介護ロボット」,「AI介護活用」,「A I介護ソフト」及び「AI介護のウェルモ」の各語は,「AI介護」の文字を分離抽出して観察すべきではない,(2)前記(3)の新聞やウェブサイト等に記載された役務 は,商標法上の役務ではないか,本願の指定役務である「介護」には当たらず,非 類似の役務である,(3)上記新聞やウェブサイト等の記載内容は,目標を記載したも のや開発段階のものであり,AIが介護現場で現実に使用されたことの記載ではな い,(4)甲4,乙20〜22の見出しは,本文の記事にふさわしくないと主張する。 しかし,「AI介護ソフト」の語がAIを活用した介護のためのソ\フトウェアを 意味し,「AI介護ロボ」及び「AI介護ロボット」の語がAIを活用した介護用 ロボットを意味することは,前記(4)イ認定のとおりである。また,「AI介護活用」 は文字どおりAIを介護に活用するという意味である。取引者,需要者は,これら について,「AI介護」とそれに続く「ソフト」,「ロボ」,「ロボット」又は「活用」とを分離して認識するというべきである。\nまた,「AI介護のウェルモ」の語について,取引者,需要者が,「AI介護」 と「ウェルモ」を分離して認識することは明らかである。また,商標法3条1項3 号の商標に該当するというためには,当該商標が,取引者,需要者において同号が 規定する商標に当たると認識されることで足り,当該商標が,その指定役務又は類 似する役務において実際に使用されている必要はないところ,前記(4)のとおり,「A I介護」という語からは,AIを活用した介護という意味合いが生じ,「AI介護」 という語は,取引者,需要者において,本願の指定役務である「介護」の質を示す ものと認識されるのであり,新聞やウェブサイト等の記載内容が,目標を記載した ものや開発段階のものであるとしても,この認定が左右されることはない。 さらに,甲4,乙20〜22の見出しの「AI介護」の語がAIを活用した介護 という意味で用いられていることは明らかであって,そのことは本文の記載によっ て左右されるものではない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
ウ 原告は,「AI」と「介護」の語は,共に,多義的であり,漠然とした 意味合いにとどまっているから,取引者,需要者である介護事業者・介護サービス の利用者が「AI介護」の文字に接して,「AIを活用した介護」であると認識する ことはないと主張する。 しかし,前記(4)のとおり,「AI」の語は,種々の意味を有するが,通常は,「人 工知能」を意味し,しかも,「AI」の語が「人工知能\」を意味することは一般的に 知られているといえるから,「AI」の語が漠然とした意味合いにとどまり,「AI 介護」の語を「AIを活用した介護」であると認識できないということはない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は,乙13〜17,22は,本件審決後に作成されたから,証拠と することはできないと主張するが,乙13〜17,22の記載が公表された日は,前記(3)のとおりであり,いずれも本件審決の前であると認められるから,原告の上 記主張は理由がない。 オ 原告は,「AI」を「アイ」と称呼している出願例もあると主張する(甲 14,15)。 甲14の登録商標は,その一部に「ai」の語を,甲15の登録商標は,その一 部に「AI」の語をそれぞれ含むものであるが,本願とは異なる登録例であり,商 標の構成も本願とは大きく異なるから,本願について,「AI」は,通常「エーアイ」と発音され,人工知能\を意味するものと認識されるとの前記(4)の認定を左右し ない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2020.04. 2
平成31(行ケ)10019等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所(2部)
1997年(平成9年)に執筆された甲8の共同執筆者の一人は,クラマー博士 であるところ,甲8は,上記乙39,40を引用し,後述のとおり,甲8の実験で 観察されたグルタミン酸の排出が担体によるものであるとの結論を導いている(甲 8,乙39,40,42)。 イ 上記アに関連し,原告らは,証拠(甲47〜50)からすると,本件優 先日当時,コリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,グルタミン酸が,浸透圧 に応じて浸透圧調節チャネルから排出されることが周知となっていたと主張する。 しかし,甲47には,「特別な条件下で,大腸菌がトレハロースを排出した観察結 果(StyrvoldとStrem 1991)およびコリネバクテリウム・グル タミカムがグルタミン酸を排出した観察結果(Shiioら 1962)は我々の 研究と関連している。」との記載があるにすぎず,これだけで,原告らが主張するよ うな技術常識があったと認めるには足りない。 また,甲48,49はいずれも大腸菌に関する文献であって,そこからコリネバ クテリウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌におけるグルタミン酸排出 の技術常識の存在を認めることはできない。 甲50には,その5頁の図に関して,コリネバクテリウム・グルタミカムの低浸 透圧における相溶性溶質の排出が,少なくとも3種類の機械受容チャネル(浸透圧 調節チャネル)を通じて起こる旨の記載がある。しかし,後述する甲8の記載から すると,浸透圧調節チャネルを通じた排出は全ての溶質について等しく行われるも のではなく,特定の溶質について選択的に行われるのであると認められるから,上 記排出されるべき「相溶性の溶質」の中にグルタミン酸が含まれるのかは,上記図 だけからでは必ずしも明らかになっているとはいえず,甲50から原告らの主張す る技術常識の存在を認めることはできない。 以上からすると,原告らの上記主張を認めるに足りる証拠はない。
(2) 甲8発明の認定の誤りについて(取消事由2)
前記(1)の事実関係を踏まえて,甲8において,原告らが主張するように,グルタ ミン酸が浸透圧調節チャネルから排出されたと認定できるかについて検討する。
・・・
甲8のTable 1.には,上記のとおり,低浸透圧の状態になった際にグルタ ミン酸が排出されていることが記載されているが,beforeの値を基準にその 排出量を検討すべきとする原告らの主張を前提としても,グルタミン酸は,浸透圧 が540mOsmになるまでほとんど排出されず,540mOsmになって20% が排出されているにすぎないところ,これは,全部で11種類検討されている溶質 の中でATPに次いで小さな値である。そして,上記のようなTable 1.の 結果を受けて,クラマー博士をはじめとする甲8の執筆者らは,グリシンベタイン など多くが排出されている溶質については浸透圧調節チャネルから排出されたとし つつ,グルタミン酸の排出については,浸透圧調節チャネルではなく,担体による 排出であるとの結論を導いている。 Table 1.でグルタミン酸に次いで排出が制限されていることが観察された リジンについては,前記(1)アで認定したとおり,本件優先日当時までに,その輸 送を担う担体がクラマー博士らによって発見されており,グルタミン酸の排出につ いてもリジンなどと同様に担体によるものであるとの説がクラマー博士らによって 提唱されていた。そのクラマー博士が,自ら実験をした上でTable 1.の結果 を分析し,甲8の共同執筆者の一人として上記のような結論を導いていることから すると,甲8に接した当業者が,それと異なる結論を敢えて着想するとは通常は考 え難いところである。
以上からすると,原告らが主張するように,当業者が,Table 1.の結果を 受けて,甲8に記載された浸透圧調節チャネルをグルタミン酸の排出と関連付けて 認識すると認めることはできないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.03.30
令和1(行ケ)10119 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年3月11日 知的財産高等裁判所
前記(ア)及び(イ)認定のとおり,(1)本願商標は,橙色の単色の色彩 のみからなる商標であり,本願商標の橙色が特異な色彩であるとはいえ ないこと,(2)橙色は,広告やウェブサイトのデザインにおいて,前向き で活力のある印象を与える色彩として一般に利用されており,不動産の 売買,賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイトにおいても,ロゴマー ク,その他の文字,枠,アイコン等の図形,背景等を装飾する色彩とし て普通に使用されていること,(3)原告ウェブサイトのトップページにお いても,別紙2のとおり,最上部左に位置する図形と「LIFULL H OME’S」の文字によって構成されたロゴマーク,その他の文字,白\n抜きの文字及びクリックするボタンの背景や図形,キャラクターの絵, バナー等の色彩として,本願商標の橙色が使用されているが,これらの 文字,図形等から分離して本願商標の橙色のみが使用されているとはい えないことを総合すると,原告ウェブサイトに接した需要者においては, 本願商標の橙色は,ウェブサイトの文字,アイコンの図形,背景等を装 飾する色彩として使用されているものと認識するにとどまり,本願商標 の橙色のみが独立して,原告の業務に係る「ポータルサイトにおける建 物又は土地の情報の提供」の役務を表示するものとして認識するものと\n認めることはできない。 したがって,本願商標は,本願の指定役務との関係において,本来的 に自他役務の識別機能ないし自他役務識別力を有しているものと認める\nことはできない。
イ これに対し原告は,原告ウェブサイトは,不動産総合ポータルサイトの トップブランドとしての確固たる地位を築いており,本願の指定役務の分 野においては,周知著名であること,我が国において,全国規模で種々の 取引形態の不動産物件を掲載する一定規模以上(掲載物件数が常時100 万件以上)の不動産総合ポータルサイトとしては,原告のほか,リクルー トグループが提供する「SUUMO(スーモ)」,大東建託が提供する「い い部屋ネット」,オウチーノが提供する「O−uccino」,ヤフーが 提供する「ヤフー不動産」,アパマンが提供する「アパマンショップ」, アットホームが提供する「athome(アットホーム)」があるが,各 不動産総合ポータルサイトは,それぞれイメージカラーを施しており,例 えば,原告は橙色,「SUUMO(スーモ)」は緑色,「いい部屋ネット」 は赤色,「O−uccino」はピンク色,「ヤフー不動産」は赤色,「ア パマンショップ」は濃青色,「athome(アットホーム)」は紅赤色 といった棲み分けがされているため,不動産総合ポータルサイトに接する 取引者,需要者は,色によるポータルサイトの識別が可能な状況ができて\nおり,本願商標の橙色は,原告ウェブサイトと即座に認識,理解をすると いう取引の実情があることを考慮すると,本願商標は,その指定役務との 関係において,本願商標の橙色が独立して,本来的に自他役務の識別機能\nないし自他役務識別力を有する旨主張する。 しかしながら,ポータルサイトとは,一般に,「インターネットを利用 する際,まず最初に閲覧されるような,利便性の高いウェブサイトの総称」 (「大辞林」第三版)であるところ,前記(1)ア認定のとおり,本願の指定 役務の需要者は,住宅やマンションなどの不動産物件の購入,賃借等を検 討している一般の消費者であり,このような需要者は,ポータルサイトで, 必要な情報に関する検索を行い,その検索結果に基づいて,不動産業者等 に対し,掲載物件についての問合せをしたり,不動産業者等から紹介を受 けるなどして,不動産取引を行うのが通常であることからすると,このよ うな需要者は,不動産の売買,賃貸の仲介等を行う不動産取引業の需要者 と同一であるか,又は重複するものと認められる。 そして,原告が主張するように掲載物件数が常時100万件以上の不動 産総合ポータルサイトが日本全国の不動産情報を網羅しているとしても, 不動産総合ポータルサイトと他の不動産業者が開設するウェブサイトとは, インターネット上で不動産情報を入手するための入口であるという点で共 通し,不動産関連の情報を提供するというサービスの内容が密接に関連し ていることに照らすと,上記需要者において,これらが質的に異なるもの と認識するものと認めることはできない。 また,不動産物件を探す者は,まず,不動産総合ポータルサイトを介し て不動産情報にアクセスするのが取引の実情であることを認めるに足りる 証拠はない。 そうすると,仮に原告が主張するように原告ウェブサイが不動産総合ポ ータルサイトのトップブランドとして周知著名であり,各不動産総合ポー タルサイトがそれぞれイメージカラーを施しており,それらの色による棲 み分けがされているとしても,不動産総合ポータルサイトに接する需要者 が,色彩のみによってポータルサイトを識別可能な状況にあるものと認め\nることはできない。 したがって,原告の上記主張は,その前提において採用することができ ない。
(2) 使用による識別力の獲得について
ア 原告ウェブサイトにおける使用について
前記1(1)の認定事実によれば,原告は,平成18年から13年間にわた り,原告ウェブサイトにおいて継続して本願商標の橙色を使用してきたこ とが認められる。 しかしながら,他方で,前記(1)ア(ウ)(1)ないし(3)のとおり,本願商標の 橙色は特異な色彩であるとはいえないこと,橙色は,広告やウェブサイト のデザインにおいて,前向きで活力のある印象を与える色彩として一般に 利用されており,不動産の売買,賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイ トにおいても,ロゴマーク,その他の文字,枠,アイコン等の図形,背景 等を装飾する色彩として普通に使用されていること,原告ウェブサイトの トップページにおける本願商標の橙色の使用態様は,上記不動産業者のウ ェブサイトと同様に,ロゴマーク,その他の文字,白抜きの文字及びクリ ックするボタンの背景や図形,キャラクターの絵,バナー等の色彩として 本願商標の橙色が使用されているが,これらの文字,図形等から分離して 使用されていたものといえないことに鑑みると,原告による原告ウェブサ イトにおける本願商標の使用の結果,本件審決時(審決日令和元年7月3 1日)において,本願商標の橙色のみが独立して,原告の業務に係る「ポ ータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表示するもの\nとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認める ことはできない。
イ 原告のテレビCMにおける使用について
前記1(2)のとおり,原告のテレビCMが,平成26年5月から同年10 月までの間,平成27年1月から9月までの間,平成30年4月及び5月 に,全国各地の放送局で放送されたことが認められるが,一方で,甲27 に係るテレビCM以外には,それらの各放送において本願商標の橙色が具 体的にどのような態様で使用されていたのかを認めるに足りる証拠はない。 また,甲27に係るテレビCMは,キャラクターの絵,「LIFULL HOME’S」の文字や図柄等に橙色が使用されているものであって,原 告ウェブサイトのトップページの画像自体が映し出されたものではないか ら,上記テレビCMを視聴者が本願商標の橙色と原告ウェブサイトに係る 役務とを関連付けて理解するものとは認めることはできない。
ウ 原告の売上高について
原告は,本願商標の橙色と原告が展開する不動産情報の提供に関する事 業との間には密接かつ直接的な関係が存在するものといえるから,本願商 標の橙色の存在が原告の事業の売上げに多大な貢献をしている旨主張する。 しかしながら,本願商標の橙色と原告の事業との間には密接かつ直接的 な関係が存在することを認めるに足りる証拠はなく,原告の事業の売上高 が高額であるからいって,本願商標の橙色のみが独立して,原告の業務に 係る役務を表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識\nされていたことの根拠になるものではない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
エ アンケート調査結果について
(ア) 原告が提出するアンケート調査結果について検討するに,第1次調 査(甲30)は,「不動産・情報サイト」の名称として「LIFULL HOME’S」や「HOME’S」と記載した228人を対象として, 本願商標の橙色を見せ,思い浮かべた不動産・住宅情報サイトの名称を 記載させるという方法によるものであるから(前記1(3)ア),その対象 者は,調査前から原告ウェブサイトの名称を認識していた者に限定され ており,しかも,本願商標の橙色を示す前の段階で,原告ウェブサイト の名称を示され,いわば正解をほのめかされた状態で回答しているとい えることから,原告ウェブサイトの名称を記載する回答する者が高い確 率で現れるのは当然であるというべきである。 したがって,第1次調査の結果を採用することはできない。
(イ) 次に,第2次調査(甲33)では,回答方法として,本願商標の橙 色の画像を示して,「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」, 「HOME’S(ホームズ)」,「SUUMO(スーモ)」,「at h ome(アットホーム)」,「マイナビ賃貸」,「CHINTAI(チ ンタイ)」,「この中にはない・わからない」の選択肢の中から,「不 動産・住宅情報サイト・アプリ」を1つ選択させるという方法によって おり,理由を示すことなく選択する形式のため,偶然,「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」又は「HOME’S(ホームズ)」 を選択する可能性を排除できず,かつ,原告ウェブサイトの選択肢とし\nて「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」及び「HOM E’S(ホームズ)」の2つが掲げられている以上,偶然に原告ウェブ サイトを選択する確率は,必然的に高くなるというべきである。にもか かわらず,「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」と回 答した者が13.2%,「HOME’S(ホームズ)」と回答した者が 41.8%と,その合計は55%とさほど高くなく,むしろ,「SUU MO(スーモ)」と回答した者が16.3%,「at home(アッ トホーム)」と回答した者が10.9%,「この中にはない・わからな い」と回答した者が14.5%と,一定の割合を占めており,「SUU MO(スーモ)」と回答した者及び「この中にはない・わからない」と 回答した者の割合は,「LIFULL HOME’S(ライフルホーム ズ)」と回答した者の割合を上回っている。このような事情に照らせば, 第2次調査の結果を採用することはできない。
オ まとめ
以上によれば,原告は,平成18年から13年間にわたり,原告ウェブ サイトにおいて継続して本願商標の橙色を使用してきたこと,原告のテレ ビCMの実績及び原告の売上実績を勘案しても,本件審決時(審決日令和 元年7月31日)において,本願商標の橙色のみが独立して,原告の業務 に係る「ポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表\n示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたも のと認めることはできないから,本願商標は,その使用により自他役務の 識別機能ないし自他役務識別力を獲得したものと認めることできない。\nこれに反する原告の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2020.03.30
平成31(行ケ)10032 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所(4部)
原告は,(1)甲7の1には,甲7の1記載のマッサージ器の開き角度の 構成により,一対のローラを用いて,マッサージ器をある一方向に移動\nさせることで,一対のローラが,皮膚をひだよせしたり,押し曲げたり, 引っ張ったりし,逆方向にマッサージ器を移動させることで,皮膚が弛 緩したり,ほぐしたりする効果を奏することの開示があること,(2)甲7 の1記載のマッサージ器のローラによって,筋肉が引っ張られ,押して ほぐされるのであれば,それと並行して毛穴が収縮し,毛穴の中の汚れ が押し出される効果も認められるから,甲1−1発明の油分の浮き上が らせ効果及びゲルマニウムの浸透効果がより促進されることに照らすと, 当業者は,甲1−1発明において,甲7の1記載のマッサージ器の前記 (ア)bの構成を適用する動機付けがあるといえるから,「ローラの回転\n軸が,柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,一対のローラ の回転軸のなす角が鈍角に設けられ」た構成(相違点2に係る本件特許\n発明1の構成)とすることを容易に想到することができたものである旨\n主張する。
そこで検討するに,前記ア(イ)a認定のとおり,甲1−1発明のロー ラ支持部200は,別紙2の図1に示すとおり,横軸部210と縦軸部 220とで形成された「T字形状」であり,2つのローラ100,10 0が単一の横軸部210の両端に取り付けられているから,2つのロー ラの回転軸が共通する一軸の構成であり,これにより2つのローラ10\n0,100は平行な位置関係にあることを理解できる。 他方で,甲7の1記載のマッサージ器は,別紙5の正面図及び背面図 に示すように,「一対のローラの回転軸が,柄の長軸方向の中心線とそ れぞれ鋭角に設けられ,一対のローラの回転軸のなす角が鈍角」に設け られており,一対のローラの回転軸は,別異の軸で構成された2軸の構\ 成であり,これにより2つのローラは,甲1−1発明と比べて接近した 位置関係にあることを理解できる。
このように甲1−1発明と甲7の1記載のマッサージ器は,2つのロ ーラの回転軸の構成が異なるところ,甲1には,2つのローラ100,\n100の回転軸を1軸から2軸とすることについての記載も示唆もない。 かえって,甲1には,「前記ローラ支持部は二股になっており,2つの ローラが離れて支持されていると,皮膚に与える機械的な刺激が大きく なるというメリットがある。」(【0015】)との記載があり,2つ のローラが離れていることが望ましいことを示唆する記載がある。 また,甲7の1の「意匠の創作内容の要点」欄には,「本願マッサー ジ器は,人体の部位を引っ張り,押して筋肉をほぐすマッサージ器であ って,安定感と立体感を強調し,新しい美感を生じさせるようにしたこ とを創作内容の要点とする。」との記載があるが,一方で,甲7の1に は,ローラの材質,表面の構\成等についての記載はなく,「人体の部位 を引っ張り,押して筋肉をほぐす」ことによって皮膚に対していかなる 効果が生じるかについての具体的な開示はない。 そうすると,甲1及び甲7の1に接した当業者において,甲1−1発 明において,2つのローラの回転軸が1軸より複雑な構造である2軸の\n甲7の1記載のマッサージ装置の上記構成を適用する動機付けがあるも\nのと認めることはできない。
以上によれば,当業者が甲1−1発明と甲7の1に記載された発明に 基づいて,相違点2に係る本件特許発明1の構成を容易に想到すること\nができたものと認めることはできない。
◆判決本文
関連する審決取消訴訟はこちらです。
◆平成30(行ケ)10160
関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.03.26
令和1(行ケ)10111 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年3月11日 知的財産高等裁判所
ア 引用商標1及び2は,別紙記載1及び2のとおり,「駿河屋」の漢字3 文字を横書きに書してなり,その構成文字に相応して,「スルガヤ」の称\n呼が生じる。 しかるところ,前記1の認定事実を総合すると,(1)旧駿河屋は,昭和1 9年3月に設立以来,平成26年5月29日に事業を停止するまでの約7 0年間にわたり継続して,「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」を販売し, 平成24年3月期時点では,和歌山県に15店舗,京都府に1店舗,大阪 府に3店舗の直営店,百貨店11店舗に販売店を出店し,このほか,百貨 店72店舗及び量販店等532店舗の銘店コーナ等に「駿河屋」の商標を 使用し,同3月期における直営店での売上高は約7億6568万円,百貨 店での売上高は約4億8955万円であったこと,(2)旧駿河屋が販売する 「羊羹」については,「徳川家ゆかりの伝統の味「煉羊羹」」,「駿河屋 は,紀州家御用御菓子司として和歌山に御用本店を置くようになった(現 在でも駿河屋は和歌山と伏見に総本家を置いている。)。」,「駿河屋の 「煉羊羹」は,秀吉の聚楽第茶会に諸侯の引き出ものに用いられ絶賛され たという「伏見羊羹」を発展させたもので,試作に成功したのが慶長4年 (1599)のことである。」,「淡紅色をした「極上本煉煉羊羹」は, みかけとちがいその歯ざわりはずっしり重く,深く厚みのある味が伝わっ てくる。」などと刊行物(甲42の1(「日本の名菓 《和菓子》」)で 紹介されていたこと,(3)旧駿河屋は,昭和32年4月24日,旧駿河屋の 前身の個人営業の「総本家駿河屋」の分家又は「総本家駿河屋」等から暖 簾分けを受けた「別家」等とともに,会員相互の親睦を図るとともに老舗 駿河屋の伝統を守り,商号及び商標権の確保に協力し,共存共栄を図るこ とを目的として,「駿河屋」の商号,商標の保全に必要な協定及びその他 の措置等の事業を行う「駿河屋会」を発足し,「駿河屋会」の会員は,「駿 河屋」の商標を使用した「羊羹」等の和菓子を販売し,平成27年6月2 5日に旧駿河屋の破産手続廃止決定が確定した前後を通じて,ウェブサイ トや取扱商品の「羊羹」の包装等に「駿河屋」の商標の使用を継続してい ること,(4)旧駿河屋の事業停止(平成26年5月29日)から約10か月 後の平成27年3月24日,原告は,旧駿河屋の旧本店店舗において営業 を再開し,「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」等の和菓子を販売するよ うになり,旧本店店舗における営業再開時には「駿河屋」の再建として新 聞各誌で大きく報道されたことが認められる。 上記認定事実によれば,本件商標の登録査定時(登録査定日平成29年 4月12日)において,「駿河屋」の商標は,羊羹等の和菓子の取引者, 需要者の間において,近畿地方を中心に, 旧駿河屋又はその分家等が取り 扱う和菓子(特に,羊羹)を表示するブランド名として広く認識され,全\n国的にも相当程度認識されていたものと認められる。 そして,このような「駿河屋」の商標の周知性等に照らすと,「駿河屋」 の文字を横書きに書してなる引用商標1及び2から,「羊羹」等の和菓子 のブランド名としての「駿河屋」の観念が生じるものと認めるのが相当で ある。
イ これに対し被告は,(1)旧駿河屋は,「駿河屋」を単独では使用せず,「総 本家」の文字を付して「総本家駿河屋」を使用し,又は「総本家駿河屋」の 商標と同時に「駿河屋」を使用し,駿河屋会所属の分家との区別を明確に して,出所の混同を防止してきたから,引用商標1及び2が,旧駿河屋が 取り扱う和菓子(特に「羊羹」)を表示するものとして周知著名性を獲得\nしたとはいえない,(2)仮に旧駿河屋が引用商標1及び2について周知著名 性を獲得したとしても,旧駿河屋は,破産手続廃止決定の確定により,そ の法人格が消滅していること,駿河屋会所属の分家は,地名に「駿河屋」 の文字を付して,旧駿河屋との出所の混同を防止してきたこと,原告は, 旧駿河屋から事業譲渡を受けておらず,旧駿河屋が営業していた地で「株 式会社総本家駿河屋」の商号を使用して営業しているだけであり,旧駿河 屋の有していた引用商標1及び2についての周知著名性を引き継いでいる わけではないことからすれば, 旧駿河屋が獲得した引用商標1及び2につ いての周知著名性は,旧駿河屋の法人格の消滅とともに断絶している旨主 張する。 しかしながら,上記(1)の点については,前記1(4)アの認定事実によれば, 旧駿河屋がそのウェブサイトで使用していた「総本家駿河屋」の表示は,旧\n駿河屋が営業主体であることを表示したものと認識することができるが,\n一方で,旧駿河屋の販売する「羊羹」の包装資材,包装紙及び紙袋におい ては,「駿河屋」の文字部分が,同文字部分の右肩等に小さな文字で記載 された「総本家」文字部分と外観上明確に区別される態様で示されている から,「駿河屋」の文字部分は独立した商標として使用されているものと 認められる。 次に,上記(2)の点については,前記ア認定のとおり,「駿河屋」の商標 は,旧駿河屋のみならず,駿河屋会の会員の分家及び別家の経営する店舗 の営業活動を通じて,取引者,需要者の間において,近畿地方を中心に, 旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子(特に,羊羹)を表示するブラ\nンド名として広く認識され,全国的にも相当程度認識されていたものと認 められるものであり,このような「駿河屋」の商標のブランド名としての 周知性等は旧駿河屋の破産手続廃止決定の確定による法人格の消滅により 直ちに失われるものとはいえない。
また,前記1(2)イのとおり,駿河屋会は,「駿河屋」の商号,商標を使 用し,煉羊羹,菓子の製造又は販売に従事する個人及びその主宰する会社 等を会員とし,会員相互の親睦を図るとともに老舗駿河屋の伝統を守り, 商号及び商標権の確保に協力し,共存共栄を図ることを目的として,「駿 河屋」の商号,商標の保全に必要な協定及びその他の措置等の事業を行う ために発足したものである上,前記1(4)の認定事実によれば,駿河屋会の 会員の分家及び別家等の取扱商品の羊羹の包装等においては,「駿河屋」 の文字部分が,同文字部分の右肩等に小さな文字で記載された「大阪」, 「伏見」,「京都駅前」又は「宇治」の文字部分と外観上明確に区別され る態様で示されているから,「駿河屋」の文字部分は独立した商標として 使用されているものと認められる。加えて,株式会社大阪の駿河屋のウェ ブサイトでは,「駿河屋のお菓子」の見出しの下に,「伝統の製法で作ら れた羊羹に昔ながらの味わいが楽しめるお菓子。お菓子の老舗,駿河屋の ラインナップです。」,「古来より受け継がれた,駿河屋羊羹の「こころ」」 などと表示していること(前記1(4)イ),株式会社京都駅前駿河屋は,そ の店舗に「駿河屋」と記載された看板及び「SURUGAYA」と記載さ れた看板を掲げていること(前記1(4)オ)に照らすと,駿河屋会の会員の 分家及び別家は,旧駿河屋の破産手続廃止決定の確定後も,「駿河屋」の 商標を取扱商品の羊羹等の和菓子のブランド名として継続して使用してい たことが認められる。
さらには,旧駿河屋の事業停止から約10か月後の平成27年3月24 日,原告は,旧駿河屋の旧本店店舗において営業を再開し,「駿河屋」の 商標を使用した「羊羹」等の和菓子の販売を行っていることに鑑みると, 和菓子のブランド名としての「駿河屋」の周知性等は,本件商標の登録査 定時においても維持されていたものと認められる。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(2) 本件商標の要部抽出の可否について
ア 本件商標は,「総本家駿河屋」の標準文字から構成された,「総本家」\nの文字部分と「駿河屋」の文字部分とからなる結合商標である。 本件商標の構成文字は,外観上,同書,同大,同間隔で表\示されており, 「ソウホンケスルガヤ」の称呼も生じるが,一方で,前記(1)認定のとおり, 「駿河屋」の商標は,本件商標の登録査定日当時,羊羹等の和菓子の取引 者,需要者の間において,近畿地方を中心に, 旧駿河屋又はその分家等が 取り扱う和菓子(特に,羊羹)を表示するブランド名として広く認識され,\n全国的にも相当程度認識されていたものと認められるのに対し,「総本家」 の語は,「多くの分家の分かれ出たもとの家。おおもとの本家。」を意味 する普通名詞であること(甲6)に照らすと,「総本家」の文字部分と「駿 河屋」の文字部分とは,それを分離して観察することが取引上不自然であ ると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 そして,本件商標がその指定商品の「最中」に使用された場合には,本 件商標の構成中の「駿河屋」の文字部分が和菓子のブランド名として周知\nであったことから,取引者,需要者に対し,上記商品の出所識別標識とし て強く支配的な印象を与えるものと認められる。 そうすると,本件商標の構成中「駿河屋」の文字部分を要部として抽出\nし,これと引用商標1及び2とを比較して商標そのものの類否を判断する ことも,許されるというべきである。
イ これに対し被告は,(1)引用商標1及び2の商標登録がされた後に,指定 商品を「煉羊羹」,「菓子」等とする「駿河屋」の文字を含む9件の商標 (乙5ないし13)が商標登録されていること,(2)商品「菓子」又は「羊 羹」について,主に,地名に「駿河屋」の文字を加えた商標を多数の者が 使用しており,これらの使用者には,「京阪宇治駅前駿河屋」(乙16), 「京三条駿河屋」(乙17),「河内駿河屋」(乙18),「美濃国駿河 屋」(乙25),「京都駅前駿河屋」(乙26)のように,駿河屋会の会 員でない者も含まれていること,(3)引用商標1 及び2の商標権者である株 式会社大阪の駿河屋は「大阪の駿河屋」の商標を,有限会社伏見駿河屋は 「伏見駿河屋」の商標を,株式会社京都駅前駿河屋は「京都駅前駿河屋」 の商標を使用し,互いに出所の混同が生じないようにしていること,(4)引 用商標1及び2の商標権者は,駿河屋会以外の者による「駿河屋」の商標 の使用に対して,商標権侵害を主張することなく,長年放置してきたこと 等の取引の実情によれば,本件商標の登録査定時には,「駿河屋」という 商標だけでは,商品「和菓子」や「羊羹」について,何人の商品の出所を 示すものであるのか,需要者は,認識できない状態になっていたから,本 件商標から「駿河屋」の文字部分を要部として抽出することはできない旨 主張する。
しかしながら,前記(1)認定のとおり,「駿河屋」の商標は,本件商標の 査定日当時,羊羹等の和菓子の取引者,需要者の間において,近畿地方を 中心に, 旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子(特に,羊羹)を表示\nするブランド名として広く認識され,全国的にも相当程度認識されていた ものと認められる。 このことは,指定商品を「煉羊羹」,「菓子」等とする「駿河屋」の文 字を含む9件の商標が商標登録されていること(上記(1))や,株式会社大 阪の駿河屋は「大阪の駿河屋」の商標を,有限会社伏見駿河屋は「伏見駿 河屋」の商標を,株式会社京都駅前駿河屋は「京都駅前駿河屋」の商標を, それぞれの営業を表示するものとして使用していること(上記(3))によっ て左右されるものではない。 また,前記1(5)認定のとおり,駿河屋会の会員以外の者が「駿河屋」の 文字を使用している例もみられるが,それが多数であるとはいえない上, 羊羹等の和菓子についての具体的な使用態様も明らかでないから,上記(2) 及び(4)をもって,「駿河屋」の商標が,何人の商品の出所を示すものであ るのか,需要者が認識できない状態になっていたということはできない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(3) 本件商標と引用商標1及び2の類否について
本件商標の要部である「駿河屋」の文字部分(標準文字)と別紙記載1及 び2の引用商標1及び2を対比すると,字体は異なるが,「駿河屋」の文字 を書してなる点で外観が共通し,いずれも「スルガヤ」の称呼及び羊羹等の 和菓子のブランド名としての「駿河屋」の観念が生じる点で,称呼及び観念 が同一である。 そうすると,本件商標と引用商標1又は引用商標2が本件商標の指定商品 「最中」に使用された場合には,その商品の出所について誤認混同が生ずる おそれがあるものと認められるから,本件商標と引用商標1及び2は,それ ぞれ全体として類似しているものと認められる。 したがって,本件商標は,引用商標1及び2に類似する商標であるものと 認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.03.26
平成31(行ケ)10018等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月19日 知的財産高等裁判所
前記(1)イのとおり,甲2には,C.グルタミカムプロモーターの核酸 配列(図1)が記載されており,コリネ型細菌の染色体上の,GDH 遺伝子のプロモーター配列の−35領域に「TGGTCA」配列及び−10 領域に「CATAAT」配列を有し,CS遺伝子のプロモーター配列の−3 5領域に「TGGCTA」配列及び−10領域に「TAGCGT」配列を有するこ とが示されている。また,甲2には,C.グルタミカムプロモーターの セットにおいて,最もよく保存されている配列は-35 領域の「ttGcca.a」 及び-10 領域の「ggTA.aaT」であることが記載されている(図5)。 一方,甲2には,コリネ型細菌を用いた発酵法によるグルタミン酸 の製造方法において,グルタミン酸生合成系遺伝子であり,コリネ型 細菌の染色体上の特定の遺伝子であるGDH遺伝子及びCS遺伝子の プロモーター配列について,その−35領域及び−10領域の塩基配 列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に改変することの動機付けとな るような記載はない。 したがって,甲2発明に接した当業者は,甲2の原告ら指摘箇所を 認識していたとしても,甲2発明において,GDH遺伝子のプロモー ター配列の−35領域及び−10領域の配列と目的遺伝子の発現量の 強化の程度及びそれによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目\nし,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を得るため\nに,GDH遺伝子のプロモーター配列の−35領域及び−10領域の 配列を本件発明1−1の配列に置換する動機付けはないから,当業者 は上記構成を容易に想到できたものとは認められない。\nb これに対し原告らは,(1)L−グルタミン酸の生産を増強するために は,L−グルタミン酸に至るまでの各反応に関与する酵素(CS,G DH,ICDH等)の発現を強化することが望ましいことは,本件優 先日前において技術常識であったこと,(2)E.coli において,プロモー ターの−10領域及び−35領域をコンセンサス配列に変更ないし近 づけることによって,目的遺伝子の発現を強化できることも,本件優 先日前において技術常識であったこと,(3)甲2には,コリネ型細菌と E.coli のコンセンサス配列が同等であることや,コリネ型細菌のプロ モーターの−10領域のコンセンサス配列が「TA.aaT」であり,この 3番目の塩基「.」として,相対的に「T」が最も頻度が高いことが記 載されていることからすると,甲2の記載は,当業者に対し,甲2発 明のGDH遺伝子のプロモーター配列の−10領域(CATAAT)の1番 目の塩基「C」を「T」に変異して,コンセンサス配列,すなわち本件 発明1−1の構成(「TATAAT」)とし,同−35領域(「TGGTCA」) の1番目〜3番目の塩基を保存性の高い「TTG」にするために,2番目 の塩基「G」を「T」に変異して,本件発明1−1の構成(「TTGTCA」) とすることを示唆するものである旨主張する。
しかしながら,仮に,本件優先日前において,L−グルタミン酸の 生産を増強するために,L−グルタミン酸の生成反応に関与する酵素 (CS,GDH,ICDH等)の発現を強化することが望ましいこと が知られていたとしても,当該酵素の遺伝子を増強する具体的な方法 は,相当多数のものが想定し得たものと考えられるのであって,かか る方法として,本件発明1のように,目的遺伝子のプロモーターの特 定の領域に変異を導入する方法が知られていたことは認められない。 また,E.coli において,プロモーターの−10領域及び−35領域 をコンセンサス配列に変更ないし近づけることによって,目的遺伝子 の発現を強化できる場合があることが,本件優先日前において知られ ていたとしても,コリネ型細菌について,これと同様の知見が存在し ていたことを認めるに足りる証拠はない。かえって,前記(1)イのとお り,甲2には,C.グルタミカムにおけるプロモーターの活性と-35 及 び-10 のコンセンサス配列との類似性の間には,E.coliと異なり,相 関は確認できなかった旨が記載されている。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.03.26
令和1(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月19日 知的財産高等裁判所
本件審決は,引用発明1及び甲4発明の装身具は,いずれも,装身 具を簡単にシャツの第一ボタンに装着できるようにするという共通の課 題を有し,また,これを着用するに当たり,切欠き状の部分にボタンが はまり込むことで装着するという共通の機能を有するから,引用発明1\nのボタン係合部19における切欠き状の部分の具体的な形状として,甲 4発明の係止導孔を有する円形の釦挿通孔の態様を採用し,相違点2に 係る本件補正発明の構成とすることは,当業者であれば容易になし得た\nことである旨判断した。 しかしながら,前記(2)イのとおり,引用発明1は,簡易型のネクタイ 本体を取付ける着用具を改良することによって,着用状態における位置 ずれや傾きを生じ難く,低コストで生産でき,そして着用操作も容易で ある簡易着用具付きネクタイを提供することを課題とするものである。 一方,前記ア(イ)のとおり,甲4に記載された考案は,襟飾り,生花 等の種々の装飾小物,殊に襟前に止着する装身具について,着脱が簡単 であり,かつ,衣服の損傷がほとんどない装身具取付台を提供すること を課題とするものであるが,かかる装身具として,蝶ネクタイやネクタ イを例示するものではなく,蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有 の問題があることを指摘するものでもない。 したがって,引用発明1と甲4発明は,その具体的な課題において, 大きく異なるものといえる。
また,発明の作用・機能をみても,引用発明1は,基板部,ネクタイ\n取付部及び一対の突出片から成る簡易着用具を備え,ネクタイ取付部の 裏側に位置する基板部に,その下縁を凹状に切り欠いたボタン係合部を 設け,その切欠きにシャツの第一ボタンを係合させるとともに,一対の 突片を襟下へ挿入することで,簡易蝶ネクタイの良好な着用状態及び簡 単な着用操作を実現するものである(前記(2)ア(オ))。 そして,甲1には,引用発明1に関し,(1)「ボタン係合部19」の奥 部は,ボタン取付け糸の部分を丁度跨ぐことができる程度の小円弧状を なすものとし,その幅は,ボタンとの係合状態において横方向にほとん ど移動しない程度のものとすること,(2)着用時にボタンとの係合を容易 にするとともに,着用時に基板部2の片側がボタン穴に入り込むことを 防ぐために,「ボタン係合部19」の下方を,ラッパ状に下方へ拡大し て基板部2の下縁に達するものとすることの記載(前記(2)ア(エ)a)が ある。これは,結び目の陰に隠れて見えない状態のボタン係合部を,上 方から探りながらも容易に装着できるようにするための工夫といえるか ら,簡易着用具1の基板部2における,ボタン係合部19の配置位置及 びその形状を引用発明1の構成とすることは,引用発明1の課題を解決\nするために,重要な技術的意義を有するものであることを理解できる。 他方,甲4発明は,取付台主板に対して上方に係止導孔を連続形成し た釦挿通孔を穿設すると共に,他の一部に背面方向に突出するピンを突 設し,ピン先端にピン挟持機構を有するピン挿入キャップを冠着するこ\nとで,釦の確実な止着と,各種装身用小物の衣類への簡単な着脱を実現 するものであって(前記ア(イ)b),第1ボタンへの係合方法,衣類への 確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において,引用発明1と大きく異 なるものであるから,発明の具体的な作用・機能も,引用発明1とは大\nきく異なるものといえる。
加えて,甲4の記載事項(前記ア(ア)c)によれば,甲4発明の装身 具取付台は,衣類に装着する際に,第1ボタンの前部からアプローチし て,釦挿通孔(2)に挿入した後,装身具取付台を鉛直方向の下部に移 動させ,係止導孔(3)を第1ボタンの取付糸に係合するものであるか ら,当業者であれば,第1ボタンを釦挿通孔(2)に挿入する際に,こ れらを視認できる状態でないと,ボタンの着脱動作が困難となることを 理解できる。 そうすると,仮に,引用発明1のボタン係合部19における切欠き状 の部分の具体的な形状として,甲4発明の「細幅の係止導孔(3)を有する 円形の釦挿通孔(2)」の態様を採用した場合には,ボタン係合部19の前 側に位置し,その前側にネクタイが取り付けられるネクタイ取付部3が 存在するため,簡易蝶ネクタイを着用する際に,簡易蝶ネクタイ及びネ クタイ取付部に隠されて,第1ボタン及びボタン穴を視認することがで きないことになる。そのため,ボタン係合部を切欠き状にする場合より も,着用具へのボタンの係合が困難となることは明らかであるといえる。
(イ) 以上によれば,引用発明1と甲4発明とは,発明の課題や作用・機 能が大きく異なるものであるから,甲1に接した当業者が,甲4の存在\nを認識していたとしても,甲4に記載された装身具取付台の構成から,\n「細幅の係止導孔(3)を有する円形の釦挿通孔(2)」の形状のみを取り出し, これを引用発明1のボタン係合部19における切欠き状の部分の具体的 な形状として採用することは,当業者が容易に想到できたものであると は認め難く,むしろ阻害要因があるといえる。 したがって,本件補正発明は,引用発明1に基づいて当業者が容易に 発明をすることができたものであるとはいえないから,これに反する本 件審決の判断には誤りがあり,同判断を前提とする本件審決の補正却下 の決定にも誤りがある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2020.03.26
令和1(行ケ)10100 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月19日 知的財産高等裁判所
以上のとおり,引用文献4から6に記載された発光素子は,いずれもA lGaN層又はAlGaAs層を組成傾斜層とするものであるが,引用 文献4では緩衝層及び活性層における結晶格子歪の緩和を目的として緩 衝層に隣接するガイド層を組成傾斜層とし,引用文献5では,隣接する 2つの層(コンタクト層及びクラッド層)の間のヘテロギャップの低減 を目的として当該2つの層自体を組成傾斜層とし,引用文献6では,隣 接する2つの半導体層の間のヘテロギャップの低減を目的として2つの 層の間に新たに組成傾斜層を設けるものである。このように,被告が指 摘する引用文献4から6において,組成傾斜層の技術は,それぞれの素 子を構成する特定の半導体積層体構\造の一部として,異なる技術的意義 のもとに採用されているといえるから,各引用文献に記載された事項か ら,半導体積層体構造や技術的意義を捨象し上位概念化して,半導体発\n光素子の技術分野において,その駆動電圧を低くするという課題を解決 するために,AlGaN層のAlの比率を傾斜させた組成傾斜層を採用 すること(本件技術)を導くことは,後知恵に基づく議論といわざるを 得ず,これを周知の技術的事項であると認めることはできない。 よって,本件技術が周知の技術的事項であるとして,相違点1,2に係 る構成に想到することが容易であるとした本件取消決定の判断には誤りが\nある。
イ なお,乙6の3及び引用文献5から,AlGaN半導体積層体において, 隣接する2つの層の間のヘテロギャップを低減させることで駆動電圧を 低減させること目的として,当該層を組成傾斜層とするという限度では, 周知の技術的事項を認める余地はある。 しかし,引用発明Aにおいて,アンドープ層とドーピング層は,いずれ もAl0.6Ga0.4Nから構成されており,両者の間にヘテロギャップは\n存在しないと考えられる。また,超格子バッファとアンドープ層との間の ヘテロギャップに着目するとしても,引用発明Aにおいて,n側電極はコ ンタクト層であるドーピング層又はアンドープ層に形成されるから,それ より下層(p側電極とは反対側)にある超格子バッファとの間のヘテロギ ャップは,駆動電圧にほとんど影響しないと考えられる。 よって,引用発明Aのアンドープ層について,隣接するドーピング層と の関係においても,超格子バッファとの関係においても,駆動電圧の低下 を目的としてヘテロギャップの低減を図るために,組成傾斜層とする動機 付けがあるとは認められない。そのため,上記技術が周知であるとしても, 少なくとも相違点1に係る構成に想到することは容易とはいえない。\nこの点について,被告は,アンドープ層及びドーピング層はいずれもコ ンタクト層であるから一体として考えるべきである旨主張する。しかし, 両層はドーピングの有無が異なることに加え,引用文献1の本文において, 両層それぞれについて膜厚が記載されていることや,図1でも2つの層は 区別して記載されていることからすれば,両層は別個の層として取り扱わ れていることは明らかであり,いずれもコンタクト層であるとの一事をも って,当業者が両者をともに組成変更するとの動機を持つとは考え難いか ら,被告の主張は採用できない。
4 格子不整合との主張について
被告は,半導体積層体の格子不整合を緩和するために組成傾斜層を用いるこ とが周知の技術事項であり,また,当業者であれば,引用発明Aの半導体積層 体に格子不整合が生じていることを認識し得るから,引用発明Aにおいて,か かる格子不整合を緩和するために,アンドープ層及びドーピング層を組成傾斜 層にする動機付けがある旨主張する。 しかし,半導体積層体では,通常,組成の異なる半導体層を積層した構造を\n採るため,格子定数差がない半導体層だけで素子を構成することができないこ\nとは技術常識であるところ,かかる半導体積層体に組成傾斜層を採用すること が常に行われていると認めるに足る証拠はなく,かえって引用文献4及び5で は,組成傾斜層は付加的な構成とされているにすぎず,これが設けられていな\nい実施例が大半を占める。また,弁論の全趣旨によれば,組成傾斜層を設ける ことには成膜が難しいといった弊害もあり,膜厚の厚薄及び格子定数差の大小 を踏まえ,格子定数差を許容した設計とすることや,応力緩和層を設けるなど 組成傾斜層以外の手段を採ることもあると認められる。そうだとすれば,半導 体積層体において,組成傾斜層を用いることにより半導体層間の格子定数差を 緩和すること自体は周知の技術事項であるとしても,当業者にとって,半導体 層間の格子定数差はおよそ許容できないものであり,これがあれば組成傾斜層 の適用が当然に試みられるとまでは認められず,組成傾斜層の適用が容易想到 というためには,引用発明Aにおいて格子定数差に基づく問題が発生している ことなど,そのための契機が必要というべきである。 引用文献1には,超格子バッファが,「応力を緩和する」ために採用されて いることは記載されているものの,かかる超格子バッファを備えた半導体積層 体において,さらに各半導体層間の格子定数差を課題として認識するような記 載は見当たらない。また,そうであるのに,被告が主張するように,各半導体 層の組成比を仮定しさらに場合分けをしてまで半導体層間の格子定数の差を顕 在化させることを当業者が行うとは考え難いし,仮に被告が主張するとおりの 格子定数差を当業者が認識したとしても,それが,組成傾斜層を用いて格子不 整合を緩和する必要があると考えるほどの差であるのかも明らかではない。さ らに,被告は,超格子バッファとアンドープ層の間に格子定数差がない可能性\nがあるとしているところ,かかる場合に,ドーピング層を電子供給層との格子 整合のために組成傾斜層とするにしても,前記3(4)イに記載のとおり,ドー ピング層とは別の層であるアンドープ層まで組成傾斜層とする動機付けはない。 以上によれば,引用発明Aに接した当業者が,格子定数差の緩和を目的とし て,アンドープ層及びドーピング層の双方を組成傾斜層とする動機付けがある とは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.03.26
令和1(行ケ)10152 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年3月19日 知的財産高等裁判所
本願商標は,「ベジバリア」の文字及び「塩・糖・脂」の文字を,いずれ も標準的な書体で2段にして成る商標であり,分離して観察することが取引 上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないか ら,「ベジバリア」の部分と「塩・糖・脂」の部分を分離して観察すること 自体は不可能とはいえない。\nしかし,「ベジバリア」の部分は,自他識別力を有すると考えられるのに 対し,「塩・糖・脂」の部分は,「・」が存在することもあって3つの文字 がそれぞれ独立し,「塩」は塩分を,「糖」は糖分を,「脂」は脂肪分を意 味する一般的,普遍的な意味を有する文字として認識されるものであるとい える。そして,これらの文字は,それが,指定商品であるサプリメント,栄 養補助食品に用いられた場合には,当該商品が塩分,糖分及び脂肪分のコン トロールに良い影響を与えるなどといった記述的,説明的意味を表すのにと\nどまり,取引者,需要者に特定的,限定的な印象を与える自他識別力を有す るものではない(引用商標の「塩糖脂」は,3つの文字が一体となっている ところから,それらが一体の文字として自他識別力を有するという余地が生 ずるが,「塩・糖・脂」の場合には,「・」により分離されているため, 「塩糖脂」と同列に論じることはできないものである。)。このことと, 「塩・糖・脂」の部分は,「ベジバリア」の部分と比べ,明らかに小さい文 字で構成されており,その分目立たなくなっていることを併せ考えれば,こ\nの部分は,自他識別標識としての称呼,観念は生じないものであるというべ きである。 したがって,本願商標は,「ベジバリア塩・糖・脂」全体として,又は 「ベジバリア」の部分としてのみ自他識別標識としての称呼,観念が生じる ということになる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.03.25
平成30(ワ)18573 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月4日 東京地方裁判所
3 争点1−2(均等侵害の成否)について
原告は,本件無線ユニットの信号伝送方法が,構成要件1Cにおける「2〜\n3cmの距離」との構成を充足しないとしても,この相違点は本件各発明に係\nる方法と均等なものということができるので,均等侵害が成立すると主張する ので,以下検討する。
(1) 第1要件(非本質的部分)について
ア 前記判示のとおり,本件各発明は,埋設した測定装置と地表の測定装置\nを接続する信号線等のケーブルが長くなると,誘導電圧の影響によって測 定結果が乱れ,また,落雷によって生じる高い誘導電圧によって埋設した 測定装置の電子回路が故障するなどの課題を解決するため,測定装置近傍 に2〜3cmの距離でカップリングさせたアンテナを設け,電波を介して 同軸ケーブルで信号を伝送する構成を採ることにより,上記課題の解決を\n図るものであると認められる。 そして,カップリングさせたアンテナの距離については,その距離が大 きくなりすぎると十分な電界強度が確保できず,信号の伝送に支障が生じ\nる可能性がある一方(本件明細書等の【発明の実施の形態】),その距離\nが小さくなりすぎると,落雷に伴う誘導電圧から測定装置内部の電子回路 を保護する能力が低下することから,上記課題の解決が困難になるものと\n考えられる。本件各発明において,カップリングさせたアンテナ間の距離 を「2〜3cm」としたのは,この距離が相反する上記の要請をいずれも 満たすからであると解するのが相当である。 このことは,前記前提事実(5)記載のとおり,カップリングの距離を 2〜3cmとすることによる臨界的意義は認められないから,当業者 が行う単なる設計事項にすぎないとした平成17年2月2日付け拒絶 理由通知書(乙15の4)に対し,原告が,同年3月16日付け意見書 (乙15の6)において,「ボアホール内で使用する歪計や傾斜計は, 直径約10cm程度で,気密性が高い空域に収納しなければなりませ ん.…多数の回路を収容する必要があり,アンテナ部分の空域は小さく することが望まれます.しかし,測定装置を小さくする目的で,アンテ ナ部分をあまり密結合構造にすると,本来の目的である落雷に伴う誘\n導電圧から,測定装置内部の電子回路を保護する能力が低下します.こ\nれらの相反する条件を参酌し,2〜3cm離すことが最も適した距離 であるといたしました.」と説明していることからも明らかである。 以上の事実によれば,カップリングされたアンテナ間の距離は,上記の 相反する2つの要請を調和させ,本件各発明の効果を奏する上で本質的な 部分というべきである。
イ これに対し,原告は,本件明細書等の段落【発明の実施の形態】に「カ ップリングの距離を短くすれば電界強度はより大きくなって,信号の伝送 距離を長くできる」との記載があり,これはカップリングの距離を2〜3 cmよりも短くすることを示唆しているから,上記相違点は,本件各発明 の本質的部分に当たらないと主張する。 しかし,原告の指摘する上記記載は,カップリングしたアンテナ間の距 離を2〜3cmまで短くすることの技術的意義を説明する記載にすぎず, 本件各発明において,上記距離を2cmより更に短くすると,平成17年 3月16日付け意見書(乙15の6)にも記載されているとおり,落雷に 伴う誘導電圧から測定装置内部の電子回路を保護する能力が低下するので\nあるから,本件明細書等の上記記載が,上記距離を2cmより更に短くす ることを示唆しているということはできない。 ウ したがって,本件無線ユニットの信号伝送方法は,均等の第1要件を充 足しない。
・・・
(2) 第5要件について
前記前提事実(5)記載のとおり,原告は,平成16年11月11日付け手続 補正書(乙15の2)により,「2〜3cmの距離で」との構成を付加し,\nその理由について,平成17年3月16日付け意見書において,「ボアホー ル内で使用する歪計や傾斜計は,直径約10cm程度で,気密性が高い空域 に収納しなければなりません.…多数の回路を収容する必要があり,アンテ ナ部分の空域は小さくすることが望まれます.しかし,測定装置を小さくす る目的で,アンテナ部分をあまり密結合構造にすると,本来の目的である落\n雷に伴う誘導電圧から,測定装置内部の電子回路を保護する能力が低下しま\nす.これらの相反する条件を参酌し,2〜3cm離すことが最も適した距離 であるといたしました.」と説明していることによれば,原告が,カップリ ングさせたアンテナ間の距離を2〜3cmに限定し,それ以外の距離を意識 的に除外したものというべきである。 したがって,本件無線ユニットの信号伝送方法は,均等の第5要件を充足 しない。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2020.03.25
平成29(ワ)3428 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年12月24日 東京地方裁判所
前記認定事実によれば,本件電子掲示板は,(1)平成11年に開設され,平 成12年に西鉄バスジャック事件の犯人とされる少年が同掲示板に犯行予告\nを書き込むなどの出来事もあって社会的に注目を集めるようになり,平成1 4年頃には利用者が急激に増加し(前記2(2)ア,ウ,エ),(2)平成16年及 び平成17年には本件電子掲示板に掲載された投稿をほぼそのまま出版した 「電車男」が話題となり,インターネットに係る複数の賞を受賞し,これが ネットニュースで報道され(前記2(2)カ),(3)平成18年頃には,本件電子 掲示板の名称である「2ちゃんねる」という言葉がマスコミにおいて頻繁に 登場したり,本件電子掲示板内において使用される用語が一般の雑誌におい ても使われたり,電子掲示板を利用しない一般人の間でも本件電子掲示板が 話題に上ったりするようになった(前記2(2)キ)。 これらによれば,本件電子掲示板のトップページ等に表示されていた被告\n標章1及び2は,遅くとも,平成18年には,本件電子掲示板に係る役務を 表示するものとして,全国の需要者の間に広く認識されるに至ったと認める\nことができる。そして,平成25年3月当時,本件電子掲示板の月間の閲覧 数が29億にのぼるとして「日本語圏最大級のネットコミュニティ」などと 宣伝されていたことに照らせば(前記2(2)ス),原告商標1及び2が出願さ れた平成25年1月25日及び平成26年3月27日においても,上記周知 性が維持,継続していたものと認められる。
(4)ア
本件電子掲示板に係る役務を誰が提供していたかについてみると,原告 は,本件電子掲示板を開設した者であり,管理人と呼ばれたこともあり, 平成26年3月まで,本件電子掲示板の広告収入を間接又は直接に受領し ていた(前記2(2)ア,カ,キ,セ)。また,そのように受領した広告収入 の一部をNTテクノロジー社に渡していた(前記2(2)エ)。他方,原告は, 平成21年以降,ブログや「僕が2ちゃんねるを捨てた理由」と題する書 籍等において,自ら積極的に,本件電子掲示板を第三者に譲渡したとか, 本件電子掲示板の管理人を退き,アドバイザーか1ユーザーであるなどと 公言していた(前記2(2)ク,コ,シ)。また,平成21年1月2日以降, 本件ドメイン名に係るWhois 情報において,本件証拠上,原告に特に関係 が深いと考えられる会社(東京プラス社やブラジル社)や原告は,登録者 や運営名に関する連絡先,登録サービス提供者等のいずれにも登録されて いない(前記2(3))。 NTテクノロジー社は,平成11年頃から本件電子掲示板のサーバの提 供や関係する掲示板の開設を新たに行うなどしており,その後も,利用者 が増大した本件電子掲示板のサーバの管理や関係するソフトウェアのプロ\nグラミング等を単独で又は被告と共にしていた(前記2(2)イ,エ,オ)。 また,NTテクノロジー社は,平成14年頃には本件電子掲示板の閲覧の 利便性を向上させるソフトウェアを開発してこれを本件電子掲示板の利用\n者に販売し,その多額の売上げを原告を介さずに自ら取得していた(前記 2(2)イ,エ)。NTテクノロジー社は東京プラス社を介して原告から本件 電子掲示板の広告料の一部の送金を受けていて,その送金額は平成14年 頃は少なくとも当面は月額2万ドルとされていたところ,それに関する契 約書はなく,送金額は変動し,実際に送金された総額は相当の多額であり, また,NTテクノロジー社が求めた増額に任意に応じてその送金がされた こともうかがわれる(前記2(2)エ,テ)。そして,少なくとも平成17年 5月以降,本件ドメイン名に係るWhois 情報において,NTテクノロジー 社(NTテクノロジー社の設立者のジムを含む。)は,単に技術面に関す る連絡先としてだけでなく,継続して,運営面に関する連絡先や登録サー ビス提供者として登録されていた(前記2(3))。被告は,平成16年頃よ り,本件電子掲示板の管理に直接携わるソフトウェアのプログラミング等\nの業務を担うようになり(前記2(2)オ),平成24年5月3日に本件ドメ イン名を取得して本件ドメイン名の登録者となり,遅くとも平成26年2 月19日から本件電子掲示板のトップページ等に被告標章1及び2を表示\nして使用し,その使用は平成29年9月30日まで継続し(前提事実(5), 前記2(3)カ),本件証拠上,平成26年3月5日には,本件電子掲示板の トップページの下に会社名,所在地等が表示され,平成30年4月当時の\n「5ちゃんねる」と題する電子掲示板のトップページには,本件電子掲示 板を被告から譲り受けたと解される記載が表示されていた(前記2(2)タ, ツ)。
本件電子掲示板は,多種の掲示板から構成された巨大掲示板サイトであ\nり,その性質上,サーバの管理,新たな掲示板や機能の導入,それらの維\n持,改善等の運営は極めて重要である。また,平成14年頃には利用者が 急激に増加していたのであり,遅くともその頃以降,それらの管理,運営 等が占める役割には非常に大きいものがあった。そして,それらの管理, 運営等は,平成11年以降,NTテクノロジー社が単独で又は被告と共に 担っていた。この点について,原告が前記2(2)テ記載の別件訴訟において 提出した陳述書中には,NTテクノロジー社は東京プラス社からサーバの 管理業務を受託したにすぎない旨の記載があるが(甲21),上記の事実 関係に照らせば,NTテクノロジー社が単に原告等の委託を受けてその指 示等に基づいて管理業務を行っていたのみであるというのは不合理という ほかない。原告が平成26年2月19日まで本件電子掲示板の役務の提供 を行っていたといえるかは措くとして,少なくとも,NTテクノロジー社 は,遅くとも平成14年以降は,自ら主体的に本件電子掲示板に係る役務 の提供を行っており,本件電子掲示板に係る役務を自己の役務として提供 していたと認めるのが相当である。そして,被告も,平成16年以降,N Tテクノロジー社とともに本件電子掲示板の役務の提供をしており,少な くとも平成26年2月19日から平成29年9月30日までの間,本件電 子掲示板に係る役務を自己の役務として提供しており,遅くとも被告が本 件ドメイン名を取得した平成24年5月3日頃に,NTテクノロジー社か ら,本件電子掲示板の運営に係る事業の譲渡等を受けるなどして,その地 位を承継したと認めるのが相当である。
イ 商標法32条の先使用権は,識別性を備えるに至った商標の先使用者に よる使用状態を保護し,もって,先使用者が当該商標に蓄積した信用を同 人において享受することを可能にするものである。前記先使用権の趣旨に\n照らせば,当該商標を主体的に自己の業務として提供する役務を表示する\nものとして使用してその商標の持つ出所,品質等について信用を蓄積した 者やその者から当該事業の承継を受けた者は,先使用権の他の要件を満た せば先使用権を有するといえる。 被告標章1及び2は,遅くとも平成14年頃以降は,少なくとも,NT テクノロジー社において主体的に自己の業務として提供していたといえる 本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして使用され,遅くとも平成\n18年頃には周知性を獲得し,その後も,NTテクノロジー社は被告標章 1及び2を表示して同役務の提供を継続したため,上記周知性が維持・継\n続されたといえる。被告は,遅くとも平成24年5月3日頃に,NTテク ノロジー社から本件電子掲示板の運営に係る事業の承継を受けるなどして その地位を承継し,本件商標1及び2の登録出願当時(本件商標1につき 平成25年1月25日,本件商標2につき平成26年3月27日),継続 して被告標章1及び2を使用して本件電子掲示板に係る役務を自己の業務 として提供していたから,被告標章1及び2は,上記時点において,被告 の業務である本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして周知であっ\nたと認められる。また,被告は,平成29年9月30日まで,自己の業務 を行う意図で被告標章1及び2を表示した本件電子掲示板に係る役務を提\n供したと認めることが相当である。
ウ 不正競争の目的なくある特定の標章を表示する役務を複数の者が共同し\nて提供していた場合,その複数の者の間で紛争が生じた後であっても,少 なくとも,主体的に自己の役務として自ら役務を提供して当該表示の持つ\n出所,品質等について信用を蓄積するために果たした役割が主要といえる 者が,紛争後も提供した当該役務が従前と同様のものであった場合,その 者による当該標章の使用は,前記の先使用権の制度趣旨に照らし,不正競 争の目的なくされているとするのが相当である。そして,前記に照らせば, NTテクノロジー社は,不正競争の目的なく本件電子掲示板に係る役務を 主体的に自らの役務として提供して,当該表示の持つ出所,品質等につい\nて信用を蓄積するために主要な役割を果たしたといえる。平成26年2月 19日にはそれまで本件電子掲示板に関与していた東京プラス社及び原告 が本件電子版のサーバにアクセスできなくなったところ,東京プラス社及 び原告の同時点までの本件電子掲示板への関与の内容には不明な部分もあ るが,NTテクノロジー社と共に上記提供を行ったか,NTテクノロジー 社から本件電子掲示板に係る事業の承継を受けるなどしてその地位を承継 した被告は,平成26年2月19日以降も本件電子掲示板に係る役務をそ れまでと同様に提供していたことがうかがえ,NTテクノロジー社の果た した上記の役割に照らせば,同日以降平成29年9月30日までの間,被 告標章1及び2を本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして,不正\n競争の目的なく使用したと認めることが相当である。
エ 以上によれば,平成26年2月19日から平成29年9月30日までの 間,被告は,本件商標1及び2を本件電子掲示板に係る役務を表示するも\nのとして使用することについて,先使用権を主張することができる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.03.25
平成28(ワ)4815 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年1月20日 大阪地方裁判所
特許法102条2項は,民法の原則の下では,特許権侵害によって特許権者 が被った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発生及び額,こ れと特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなければならないところ,そ の立証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の填補がされないという不都合が 生じ得ることに照らして,侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは,そ の利益の額を特許権者の損害額と推定するとして,立証の困難性の軽減を図った規 定である。このような趣旨に鑑みると,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為 がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在する場合には,同項の 適用が認められると解すべきであるとともに,同項所定の侵害行為により侵害者が 受けた利益の額とは,原則として,侵害者が得た利益全額であると解するのが相当 であって,このような利益全額について同項による推定が及ぶと解される。
(イ) 証拠(甲13)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,被告による本件特許権 侵害行為の期間(平成20年〜平成28年)において,スクリュ圧縮機に相当する 圧縮機ユニット又はスクリュ圧縮機に凝縮器を備えたものに相当するコンデンシン グユニットである原告各製品を製造し,プラント業者等に販売していたことが認め られる。 他方,証拠(乙39,78,81,82,85,93,99,110)及び弁論 の全趣旨によれば,被告は,平成20年〜平成28年にかけて,油冷式スクリュ圧 縮機である被告製品2−2及び2−3が組み込まれたスクリュ式ガス圧縮システム であるNewTonシステムを使用した冷凍・冷蔵プラントである被告製プラントを販 売した一方,NewTonシステムや被告製品2−2及び2−3を,国内においては別 個独立に販売することはなかったこと(なお,国外向けには,被告のグループ会社 に単体又は単独で販売し,当該グループ会社がシステムを完成させて顧客に販売す ることはあった。)が認められる。 このように,被告は,基本的には,油冷式スクリュ圧縮機である被告製品2−2 及び2−3が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントを販売する という形で本件特許権侵害行為を行っているから,本件特許権侵害行為における侵 害品は,上記NewTonシステムとするのが相当である。 そして,NewTonシステムと原告各製品が組み込まれたシステムとは,上記のと おり,冷凍・冷蔵プラントの需要者を需要者とする点で共通する以上,NewTonシ ステムと原告各製品の需要者も,その面では共通する部分があるといえる。 したがって,本件においては,原告に,被告による本件特許権侵害行為がなかっ たならば利益が得られたであろうという事情が存在するといえることから,特許法 102条2項の適用が認められる。
(ウ) これに対し,被告は,原告各製品がスクリュ圧縮機等であるのに対し,被告 が販売するのは被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステムを使用し た被告製プラントであることを指摘して,特許法102条2項の適用は認められな いと主張する。 しかし,被告指摘に係る事情は,要するに特許権者である原告と侵害者である被 告との間の業務態様の相違(ひいては市場の非同一性)を指摘するものであるとこ ろ,このような事情を考慮しても,原告各製品と被告製品2−2及び2−3とは, 上記(ア)のような形で市場においてなお競合関係にあると見るのが相当であるから, 特許法102条2項の適用を否定すべき事情とはいえない。被告指摘に係る当該事 情は,同項に基づく損害額の推定を覆滅する事情として考慮すれば足りる。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額
(ア) 侵害者がその侵害の行為により受けた「利益の額」(特許法102条2項)は, 侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりそ の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ り,その主張立証責任は特許権者側にあると解される。 前記アのとおり,本件における侵害品は被告製品2−2及び2−3が組み込まれ たNewTonシステムであるから,本件特許権侵害行為により被告が受けた「利益の 額」は,その売上高から,被告においてNewTonシステムの製造販売に直接関連して 追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額を算定するのが相当である。 これに対し,被告は,本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であること, 原告自身が侵害品を圧縮機として特定していること,NewTonシステムから圧縮機だ けを分離可能であることなどを指摘して,本件の侵害品は,NewTonシステムではな く,圧縮機本体を中核とする被告製品2−2及び2−3であると主張する。 しかし,前記アのとおり,本件の侵害品はNewTonシステムとすることが相当であ り,このことは,本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であることなどに より左右されない。NewTonシステムから圧縮機を物理的に分離可能であるとしても,\n前記アのとおり,被告においては基本的にこれを別個独立に販売しておらず,この 部分の譲渡による利益を直接的に観念し得ない以上,同様であり,被告製品2−2 及び2−3がNewTonシステムの一部分であることは,損害額の推定を覆滅する事情 として考慮すれば足りる。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
(イ) NewTonシステムの販売台数
証拠(乙85,93,110)及び弁論の全趣旨によれば,被告が販売した NewTonシステムの販売台数は,別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜 「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「NewTon台数」欄に各記載のとおりであ ることが認められる。
b これに対し,被告は,被告が販売したNewTonシステムのうち,本件特許権の 存続期間中に受注し,存続期間満了後に製造を終えて納入したものについては,本 件特許権の存続期間中に,存続期間満了後に行われた適法な譲渡についての申出が\n行われたにすぎないから,本件特許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にすべ きではないと主張する。 しかし,被告は,本件特許権の存続期間中に「譲渡の申出」を行った上で受注し\nており,この時点で顧客との間の請負契約が成立している以上,製造及び納入の完 了が本件特許権の存続期間満了後であったとしても,これによる原告の損害は,な お本件特許権の存続期間中の侵害行為である「譲渡の申出」と相当因果関係にある\n損害というべきである。そうすると,これに係る「譲渡」による販売分も,本件特 許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にするのが相当である。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
(ウ) NewTonシステム1台ごとの売上額
a NewTonシステムは,前記ア(イ)のとおり,基本的に冷凍・冷蔵プラントとは 別個独立のものとして販売されていないものの,証拠(乙39,92,110)及 び弁論の全趣旨によれば,被告は,被告製品2−2及び2−3が組み込まれた NewTonシステムの「定価」を設定し,そのNewTonシステムを使用した被告製プラ ントを販売するに当たって,当該「定価」を見積書に記載するなどして顧客に対し 見積りを示した上で,被告製プラントを販売していることが認められる。 そうすると,NewTonシステム1台ごとの売上額を算定するに当たり,当該「定 価」に依拠することには合理性がある。
他方,証拠(甲23,乙100,119)及び弁論の全趣旨によれば,被告は, NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売に当たり,「出精値引」などと して,冷凍・冷蔵プラントを構成する部品価格の合計額から値引きして販売する例\nがあったことが認められる。もっとも,全ての取引において値引きが行われたこと を認めるに足りる事情はなく,また,プラントを構成するいずれの部品が値引き対\n象とされたかも不明であるから,上記売上額の算定に当たり値引き分を考慮するこ とは合理的でない。 以上を踏まえると,証拠(乙39)及び弁論の全趣旨によれば,NewTonシステ ム1台ごとの売上額は,別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTon システムの利益額算定表(4)」の「定価(単価)」欄に各記載のとおりであると認め られる。 これに対し,被告は,NewTonシステム1台ごとの売上額は,その実質的な販売 価格に相当する●(省略)●により算定すべきであると主張する。 しかし,証拠(乙39,92,93)及び弁論の全趣旨によれば,NewTonシス テムの●(省略)●は,被告の製造部門が販売部門に販売処理手続を行う際の設定 される価格にすぎず,被告は,この●(省略)●を上回る価格を「定価」として設 定した上で,NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売していることが認 められる。すなわち,●(省略)●「定価」においてこれが反映されているものと 理解される。そうすると,顧客に対する関係では,●(省略)●は実質的な販売価 格とはいえない。 したがって,NewTonシステム1台ごとの売上額の算定に当たりその●(省略) ●を基礎とすることは合理性を欠き,相当でない。この点に関する被告の主張は採 用できない。
b 593番代替機及び6048番転用機について
証拠(乙99)及び弁論の全趣旨によれば,別紙「NewTonシステムの利益額算 定表(5)」の対象となっている593番代替機は,106番機の代替機として,顧客 に無償で譲渡されたことが認められる。そうすると,106番機と593番代替機 の販売は一連の取引によるものといえる。このような経緯を踏まえると,106番 機と593番代替機の販売については,106番機1台分の売上額●(省略)●円 をもって2台合計の売上額として算定するのが相当である。 また,証拠(乙99)及び弁論の全趣旨によれば,別紙「NewTonシステムの利 益額算定表(6)」の対象となっている6048番転用機は,同一の顧客に対して61 8番機2台と共に合計3台として納品されたこと,この取引におけるNewTonシステ ムの代金は2台分の代金とされたことが認められる。このような経緯を踏まえると, 2台分の売上額である●(省略)●円(●(省略)●円×2)をもってこれら3台合 計の売上額として算定するのが相当である。 以上に反する原告の主張は採用できない。
(エ) NewTonシステム1台ごとの経費
a 前記(ア)のとおり,控除すべき経費は,侵害品の製造販売に直接関連して追加 的に必要となったものをいい,例えば,侵害品についての原材料費,仕入費用,運 送費等がこれに当たる。これに対し,例えば,管理部門の人件費や交通・通信費等 は,通常,侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たら ない。
b 控除すべき経費
(a) 製造原価
証拠(乙39,93,110)及び弁論の全趣旨によれば,NewTonシステム1 台ごとの製造原価は,別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTonシ ステムの利益額算定表(4)」の「製造原価(単価)」欄に各記載のとおりであること が認められる。
(b) その余の経費
被告は,上記製造原価のほかに,被告製品2−2及び2−3が組み込まれた NewTonシステムの製造工場に係る間接人件費並びに販売費及び一般管理費を控除 すべき旨を指摘する。 まず,間接人件費についてみると,間接人件費は,正に管理部門の人件費である ところ,被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステムの製品の製造 販売に直接関連して,間接人件費に相当する費用が追加的に発生したと見るべき事 情は見当たらない。そうすると,被告製品2−2及び2−3が組み込まれた NewTonシステムの製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず, 控除すべき経費に当たらない。 次に,販売費及び一般管理費についてみると,証拠(乙75,84,109)及 び弁論の全趣旨によれば,上記(a)の製造原価には,社内加工費及び艤装作業費が含 まれていることが認められるところ,これを除くと,証拠(乙78,101)及び 弁論の全趣旨によっても,被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシス テムの製品の製造販売に直接関連して,販売費又は一般管理費に相当する費用が追 加的に発生したと見るべき事情は見当たらない。そうすると,被告指摘に係る販売 費及び一般管理費は,被告製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステム の製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず,控除すべ き経費に当たらない。 したがって,被告の上記指摘は当たらない。
(c) 被告の主張について
そもそも被告は,最小二乗法を用いて限界利益率を算定するのが管理会計学上確 立した方法であるとして,本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額を算定 するに当たっても,最小二乗法を用いるのが合理的であると主張する。 しかし,前記(ア)のとおり,特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受 けた利益の額として算定すべき額は,侵害者の侵害品の売上高から,侵害者におい て侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要とな った経費を控除した限界利益の額であり,被告主張に係る管理会計学上の限界利益 の額とは必ずしも一致しない。また,算定の目的を異にする以上,侵害者が受けた 「利益の額」(特許法102条2項)の算定に当たり,管理会計学上の限界利益の 額の算定方法である最小二乗法を用いないとしても,不合理であることにはならな い。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
ウ 推定の覆滅について
(ア) 基礎となる事情
a NewTonシステム及び被告製品2−2及び2−3等について
(a) NewTonシステムの特徴及び販売促進活動
NewTonシステムは,平成19年にNewTon3000が商品化され,平成20年以降, 被告製プラントに使用される形で販売されており(甲8の3,乙45),基本的に, 冷凍・冷蔵プラントとは別個独立のものとしては販売されていない。被告製品2− 2及び2−3のみならず,被告製品2は,いずれもNewTonシステム専用の圧縮機で あり(甲3),NewTonシステムを使用した被告製プラントを購入する際には,必然 的に購入することになるところ,これらも,NewTonシステムと同様に,基本的に別 個独立のものとして販売されていない。また,NewTon3000は,IPMモーターを 搭載することなどにより,従来式に比べて20%の省エネを実現するとされ,発売 開始当初は年間200台,10年後には年間800台の販売を目標にしていた(乙 45,116)。 被告は,その後もNewTonシステムの開発を継続し,平成24年にはチルド専用の NewTonC,フリーザー専用のNewTonF等のシリーズ展開が行われ,平成28年ま でに累計●(省略)●台以上を販売した。さらに,被告は,平成28年7月,省エ ネ性を保ちつつ,冷媒充填量の削減,メンテナンス性の向上及び小型・軽量化を達 成したフリーザー専用の機種として,F-300,F-600等の販売を開始した(甲8の3, 乙45)。
NewTonシステムは,被告自ら開発したIPMモーターを搭載することなどによっ て,より高度な経済性と省エネルギー性を実現する点,令和2年に全廃されるフロ ン冷媒対策として,自然冷媒であるアンモニアで二酸化炭素を冷却するという間接 冷却方式を採用するとともに,アンモニアを機械室に閉じ込める構造によりその安\n全な利用を可能とし,さらに,漏洩センサー等を装備するなどしてアンモニアが漏\n洩しても素早い対応が取れるようにしている点,コンパクトなユニット設計を採用 することで導入を容易としている点,遠方監視システム及び保全診断システムなど 24時間365日のサポート体制を設けている点等に特徴があるとされ,これらの 点が強調された形で販売促進活動が行われていた(甲8の3,乙38,45)。 なお,NewTonシステムや被告製品2−2及び2−3の宣伝広告物には,本件明細 書記載の本件発明の作用効果に直接言及し,又はこれを具体的にうかがわせる記載 は見られない(甲3,8の3,乙38,66の1)。
(b) NewTonシステムを導入した業者によるNewTonシステムについての評価 被告は,その作成に係る「Customer’s Point of View」と題する記事において, NewTonシステムを導入した顧客の導入の動機,導入後の成果等を紹介していると ころ,これには,以下のような記載がある。
・・・
(b) 原告各製品の取扱業者による販売促進活動
・・・・
(イ) 検討
a 前記認定のとおり,被告は,基本的には,油冷式スクリュ圧縮機である被告 製品2−2及び2−3を独立して販売しておらず,また,これらを組み込んだ NewTonシステムについても同様であり,被告製品2−2及び2−3を組み込んだ NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売している。他方,原告は,スク リュ圧縮機又はこれに凝縮器を付加した原告各製品を販売しているにとどまり,プ ラントという単位でみると,「セットメーカ」などといわれる別の業者が需要者に 対して提案するパッケージに組み込まれて販売されるという関係にある。このよう に両者の業務形態が大幅に異なることは,本件の侵害品であるNewTonシステムへ の需要と原告各製品への需要とが質的に異なる面があることをうかがわせる。この ため,仮に被告製品2−2ないし2−3を組み込んだNewTonシステムが販売され なかったとしても,原告各製品のいずれかが被告製品2−2又は2−3に直接代替 されることは考え難い。他方,そのような場合に,被告製品2−2及び2−3の譲 渡数量に対応する需要の全部又は一部が原告各製品の組み込まれたシステムを使用 したプラントに向かうことはあり得ることから,その場合は,結果的に,上記需要 が原告各製品に向かったことになる。もっとも,原告は,プラントを構成する圧縮\n機を販売するにとどまり,プラント全体の構成及び価格の決定や需要者に対する販\n売促進活動において及ぼし得る影響力には限りがあると思われる。 以下では,このような観点も踏まえて,推定覆滅の有無及び程度を検討する。
b 被告製品2−2及び2−3は,本件発明の技術的範囲に属するものである以 上,基本的には本件発明の作用効果を奏すると考えられるところ,被告製品2−2 及び2−3において,本件発明の作用効果を奏していないという事情はうかがわれ ない。この点,被告は,被告製品2−2及び2−3が本件発明の作用効果を奏する ものではない旨主張するが,採用できない。 もっとも,本件発明の作用効果は,スラスト軸受の負荷容量を大きくすること, バランスピストンの受圧面積を大きくすること,逆スラスト荷重状態の発生をなく すことなど,単純かつコンパクトな構造で,振動,騒音を低減させることができる\nというものであり,技術的にはさておき,本件発明の実施品ないしこれを組み込ん だシステムの経済的価値に強いインパクトを及ぼすような性質のものとは必ずしも いえない。このことは,被告製品2−2及び2−3につき,被告がその販売促進活 動において本件発明の作用効果に直接的に言及していないこと,NewTonシステム に対する外部的な評価においても,本件発明の作用効果に直接的に関わるものは見 当たらず,これを示唆するものもないこと,特許権者である原告自身も,スクリュ 圧縮機等である原告各製品において本件発明を実施していないことによっても裏付 けられる。そうすると,本件発明の作用効果それ自体には,それほど強い顧客吸引 力はないと見るのが相当である。
また,弁論の全趣旨によれば,NewTonシステムは被告製プラントの顧客吸引力 の中核を成す部分であり,被告製品2−2及び2−3は,NewTonシステムを稼働 させるために不可欠な部品であることが認められる。そこで,NewTonシステムの 顧客吸引力を検討すると,被告は,NewTonシステムの販売促進活動において,省 エネ,安全性,サポート体制等を特徴とするものであるとの点を強調している。し かも,被告が強調するNewTonシステムのこれらの特徴は,表彰の受賞理由とされ,\nまた,その導入の動機となり,現にその実績も上がっているとされるなど,第三者 からも積極的に評価されていることがうかがわれる(なお,原告は,省エネや安全 性が本件発明の作用効果であるとも主張するけれども,NewTonシステムにおける 省エネや安全性はIPMモーターや間接冷却方式を採用するなどしたことによるも のであり,本件発明の作用効果とは無関係と見られることから,この点に関する原 告の主張は採用できない。)。
c 被告製品2−2及び2−3の製造原価がNewTonシステムの製造原価に占め る割合は,被告製品2−2及び2−3の技術的・商業的価値を直接的に反映したも のではないが,これを推し測る一事情とはなるところ,被告製品2−2及び2−3 がNewTonシステムを可動させるために不可欠な部分であるといっても,NewTonシ ステムの製造原価における被告製品2−2又は2−3の製造原価の割合は,●(省 略)●にとどまる。
d NewTonシステムを使用した被告製プラントとそれ以外の同様のプラントの 販売実績は,アンモニア/二酸化炭素冷媒・冷凍設備の冷凍機用途の油冷式スクリ ュ圧縮機市場が事実上被告と原告の二社寡占状態であることに鑑みると,原告及び 被告の各製造に係る圧縮機の納入実績におおむね対応するものと推察されることか ら,NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売実績の方が右肩上がりであ る●(省略)●。また,被告製プラントで使用されるNewTonシステムに組み込ま れる圧縮機として被告の製造に係るもの以外のもの(おのずと,原告の製造に係る 製品がその候補となる。)が組み込まれるという事態は考え難い。そうすると,被 告が非侵害品を販売していたり,販売することが容易であったりすれば,仮に被告 製品2−2及び2−3が組み込まれたNewTonシステムが販売されなかったとして も,需要の多くは被告の製造に係る非侵害品等を組み込んだNewTonシステムを使 用したプラントに向かったであろうと考えるのが合理的である。 そして,被告は,被告製品2−2及び2−3以外にも,本件発明を侵害しない NewTonシステム専用品として,被告製品2−1を製造しており,これによって被 告製品2−2及び2−3に代替することが考えられる。なお,原告は,被告製品2 −1が組み込まれたNewTonシステムの販売実績が少なかったことを指摘するけれ ども,現に納入実績がある以上,需要者の需要を満たすものである限り,被告製品 2−1による代替に需要が向かう可能性を否定することはできない。\nまた,被告は,本件特許権侵害行為当時,被告製品2以外にはNewTonシステム 専用の油冷式スクリュ圧縮機を製造していなかったものの,弁論の全趣旨によれば, NewTonシステムにおいて,本件特許権の侵害を回避するために,例えば油ポンプ を加えて加圧流路を設けることについての物理的な制約はさほどなく,また,コス ト的にも問題とすべき程度に至るとは見られない。そうすると,被告製プラントを 欲する需要者の要望に対し,既存機種をベースとしたカスタマイズ等の形で対応し, 本件特許権侵害を回避することは比較的容易であったとうかがわれる。実際には, 本件特許権の非侵害品であるNewTonシステム専用の圧縮機としては被告製品2− 1しかなく,また,上記カスタマイズといった対応も取られなかったとはいえ,推 定を覆滅すべき事情としては,この点も考慮するのが合理的である。この点につき, 原告は,競合品として考慮できるのは現実に市場に存在した製品に限られると主張 するが,上記のとおり,これを採用することはできない。
e 被告は,被告のNewTon事業の限界利益率が,原告の圧縮機事業の限界利益 率を上回ることを前提に,特許法102条2項により算定された利益の額が,特許 権者である原告がその実施能力に基づき得られたであろう利益の額を上回る場合は,\nその限度で覆滅されると主張する。 しかし,仮に被告のNewTon事業の限界利益率が原告の圧縮機事業の限界利益率 を上回るとしても,それをもって原告の圧縮機事業の実施能力が被告のNewTon事 業の実施能力に劣ることを意味するものではないから,被告の上記主張は,その前\n提を欠く。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
f 以上の事情を総合的に考慮すると,本件においては,被告製品2−2及び2 −3が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントの販売がなかった 場合に,これに対応する需要の全てが原告各製品やこれを組み込んだスクリュ圧縮 機,更にはこれを使用したプラントに向かったであろうと見ることに合理性はなく, むしろ,そのような需要はごく限られると考えられる。そうすると,本件では,9 割の限度で,特許法102条2項による推定を覆滅するのが相当である。 この点に関する原告及び被告の各主張は,いずれも採用できない。
エ 以上によれば,原告の逸失利益の額は,別紙「損害額算定表(裁判所認定)」\nの(3)欄のとおり,合計12億5428万1900円であると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.03.25
令和1(行ケ)10102 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月24日 知的財産高等裁判所
(ア) 引用発明1は,大口径の鋼管杭(ケーシング)の圧入,引抜きを行うための 回転式ケーシングドライバに関し,引用発明2’は,種々の径のケーシングに対応す ることができ,現場打杭に使用される回転式ボーリングマシンに関するから,両発 明の技術分野は共通する。 しかし,引用発明1では,小さく分割することでその輸送を容易にしながら,ケ ーシングドライバの大型化を図ることのできる構造の,昇降フレームを提供するこ\nとを目的とするのに対し,引用発明2’では,種々のケーシングチユーブに適用し, 掘削排土及びケーシングチユーブの回転の両操作を同時に行うことのできる回転式 ボーリングマシンを提供することを目的とするので,両発明の目的は異なる。 また,引用例1には,引用発明1の把持機構(旋回ベアリング6,回転リング7,\n及びバンド装置14)に代えて,引用発明2’の把持機構(クランプ部2)を採用す\nることに関する記載も示唆も認められない。 そうすると,引用発明1に引用発明2’を適用することについて,直ちに動機付け があると評価することはできない。
(イ) そこで,更に両発明の構成をみると,引用発明1の「旋回ベアリング6,回\n転リング7,及びバンド装置14」と引用発明2’の「クランプ部2」は,いずれも ケーシングの回転及び把持の機能を有する点において共通する。\nしかし,上記の目的の相違に対応して,引用発明1の「昇降フレーム4」は,旋回 ベアリング6を取り付ける「取付座4a」を分断するように分割する構成を有し,\nその「取付座4a」のサイズは一定であり,種々の径の旋回ベアリング6を固定で きるよう拡大や縮小が可能なものではないのに対し,引用発明2’の割ライナー4及\nび割クランプ3は,種々の径のケーシングチユーブをクランプするために締付拡大 可能なものであり,回転駆動される割ライナー4,及び割ライナー4を回転可能\に 支承する側の割クランプ3の両者が,締付ジヤツキ5の動作によってその径を変更 することのできるものである。このような引用発明2’の割ライナー4及び割クラン プ3を,旋回ベアリング6の径の変更に対応するための構成を有しない引用発明1\nの「昇降フレーム4」上の「取付座4a」にそのまま取り付けることはできないか ら,引用発明1に引用発明2’を組み合わせるためには,分割可能な「昇降フレーム\n4」及び「取付座4a」という引用発明1の構成自体を変更する必要が生じる。\nそうすると,引用発明1に引用発明2’を組み合わせることについては,これを阻 害する要因があるというべきである。
イ 原告らの主張について
原告らは,(1)旋回ベアリングを分割することは周知の技術であり,また,土木機 械である立杭構築機について,その運搬時の作業性を勘案して各種構\成部材を分割 することも引用例2から容易に発想できるから,引用発明1に引用発明2’を適用す る動機付けがある,(2)引用発明1に引用発明2’を適用するに際しては,引用発明1 の「取付座4a」に所定の径の旋回ベアリング6が固定できるように,サイズの合 う部材を現場において選択すれば足り,阻害要因はないと主張する。 しかし,(1)については,前記アで述べたとおりの理由により適用の動機付けがな いし,(2)についても,引用発明1に引用発明2’を適用する場合には,「取付座4a」 のサイズに応じた部材のほかに,「旋回ベアリング6の外歯歯車6cに噛合する出力 歯車11」のサイズや配置の変更も必要となることからすれば,適用することに阻 害要因があると評価すべきである。原告らの主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2020.03.25
平成30(ワ)15781 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和2年2月20日 東京地方裁判所
需要者について
原告は,外国人をターゲットとしてホテル事業を展開していることから, 本件商標と被告の標章の類否を判断するに当たり,需要者は都内近郊の宿泊 施設を利用しようとする外国人観光客であると主張する。しかし,前記1(5) で認定したとおり,平成29年の原告宿泊施設の宿泊客の国籍をみると,日 本が最も多かったものであり,その他本件全証拠に照らしても,原告宿泊施 設が外国人観光客のみを対象としているものとは認められず,本件の需要者 は,外国人観光客に限定されるものではなく,およそ宿泊施設を利用しよう とする者であるというべきである。
(2) 類否について
ア 被告使用標章
(ア) 別紙被告標章目録1記載(1),(7)及び(8)の標章 別紙被告標章目録1記載(1),(7)及び(8)の標章は,桜の花びらのマーク 及び「桜」の漢字,横書きの「SAKURA」,横書きの「HOTEL」 の各文字をこの順番に縦に並べた外観を有し,「サクラホテル」との称呼, 及び桜の花をそのイメージとする宿泊施設という観念が生ずる。 ・・・ イ 本件商標と被告使用標章の対比
本件商標は,カタカナの「サクラホテル」との外観を有し,「サクラホテル」との称呼,及び桜の花をそのイメージとする宿泊施設という観念が生 ずるところ,被告使用標章の各標章から生ずる称呼及び観念は上記アで説 示したとおりであるから,本件商標と被告使用標章の各標章は,称呼及び 観念が同一ないし極めて類似しているといえる。一方で,本件商標と被告 使用標章の各標章はいずれも外観において異なるものの,被告使用標章は 「サクラホテル」を漢字やローマ字などで表記したものの組合せであるか,\nそれらに加えて桜の花びらのマークなどを組み合わせたものにすぎないか ら,その取引の実情に照らし,日本人を始めとする需要者にとって,両者 の外観の差異は大きいものとはいえないというべきであり,両者が称呼及 び観念において同一ないし極めて類似していることに照らせば,本件商標 と被告使用標章は類似しているというべきである。 ・・・ ア 商標法38条2項の適用
原告は,商標法38条2項に基づき,本件商標権侵害により原告に生じ た損害を主張するところ,被告は,原告宿泊施設と被告宿泊施設は競合関 係にない,第三者の競業が存在する,被告の営業努力が著しい,ホームペ ージの記載から運営主体が異なることは明らかであるなどとして,原告に 損害が発生していないから,商標法38条2項の適用がないと主張する。 しかし,被告は,本件商標に類似する被告使用標章を,本件商標の指定 役務である宿泊施設の提供に使用しているところ,原告宿泊施設と被告宿 泊施設はいずれも東京23区内に存在しており,提供するサービスの価格 に差はあるものの,需要者が全く異なるとまではいえないから,被告によ る被告使用標章の使用により原告に損害が発生していないと認めることは できない。また,被告は,「第三者」の競業や被告の著しい営業努力,ホー ムページの記載なども主張するが,これらに関し,上記認定を左右するに 足りるような具体的事情を客観的に認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,被告の上記主張は採用することはできず,商標法38条 2項の適用があるというべきである。
イ 被告の利益
(ア) 被告使用標章の使用により被告の得た利益は,被告が被告使用標章を 使用していた平成29年9月15日の営業開始から平成30年3月5日 までの被告宿泊施設の売上げから,いわゆる変動費を控除した限界利益 がこれに当たると解すべきである。そして,宿泊業という被告の業種に 鑑みれば,水道光熱費及び消耗品費が変動費に当たることが認められる ところ,本件全証拠を精査しても,その他控除すべき費用は認められな い。
(イ) 証拠(乙27)によれば,上記期間の被告宿泊施設の売上げ,水道光 熱費,消耗品費は次のとおりであると認められる(ただし,平成30年 3月分はいずれも5日間の日割り計算である。1000円未満切捨て。)。
i 売上げ
平成29年9月分 251万9000円
平成29年10月分 645万7000円
平成29年11月分 600万3000円
平成29年12月分 684万9000円
平成30年1月分 587万円
平成30年2月分 760万9000円
平成30年3月分 138万3000円
合計 3669万円
ii 水道光熱費
平成29年9月分 7万3000円
平成29年10月分 23万9000円
平成29年11月分 27万7000円
平成29年12月分 30万9000円
平成30年1月分 38万円
平成30年2月分 26万4000円
平成30年3月分 10万8000円
合計 165万円
iii消耗品費
平成29年8月分 138万9000円
平成29年9月分 236万1000円
平成29年10月分 10万6000円
平成29年11月分 37万4000円
平成29年12月分 2万2000円
平成30年1月分 1万円
平成30年2月分 4万9000円
平成30年3月分 5000円
合計 431万6000円
(ウ) 以上によれば,上記期間の被告の限界利益は3072万4000円で あると認められる。
ウ 推定覆滅
原告は,平成11年頃から「サクラホテル」との名称を用いて宿泊施設 を提供している旨主張する。しかし,本件商標である「サクラホテル」は, 普通名詞である2つの単語を単純に組み合わせたものであり,そのうちの 1つは提供する役務の内容である「ホテル」であること,証拠(乙17) によれば,日本において「桜」,「さくら」,「Sakura」又は「サクラ」 を名称に使用した宿泊施設は多数存在することが認められ,宿泊施設の名 称に桜という単語を使用すること自体,強い自他識別力を付与するものと は言い難い。これらによれば,本件商標の顧客吸引力は強いものであると はいえず,これに類似する被告使用標章が,被告の売上げに寄与した程度 は極めて限定的であるというほかない。そして,前記1(6)及び(7)で認定 したとおり,原告宿泊施設と被告宿泊施設において提供するサービスに相 応の価格差があることも併せ考慮すれば,被告の限界利益額の相当大きな 部分について,損害の推定が覆滅されるというほかなく,その覆滅割合は, 上記のほか,本件に顕れた諸般の事情に照らし,9割と認めるのが相当で ある。
エ 損害額
以上によれば,被告の本件商標権の侵害につき,商標法38条2項によ って推定される原告の損害は,被告の限界利益である3072万4000 円の1割に相当する307万2400円であると認められる。
(2) 対応費用
原告は,本事案に係る被告の不誠実な対応により,原告に法律家による対 応の費用等の損害が発生したと主張する。 しかし,本件全証拠に照らしても,本訴訟提起前の交渉経緯における被告 の対応が殊更に不誠実であったとは認められず,本訴訟における和解協議に 係る原告の主張も,客観的にみれば,原告の期待が裏切られたというにとど まるものといわざるを得ない。 もっとも,原告が請求する対応費用の趣旨に鑑みれば,この費用には本訴 訟に係る弁護士費用も含まれていると解されることから,弁護士費用相当額 については,原告の損害として認めるのが相当であるが,その他については, 本件商標権の侵害により,被告が賠償すべき原告の損害を認めることはでき ないというべきである。しかして,本訴訟に係る弁護士費用については,上 記(1)の損害額に照らし,30万円が相当であると認められる。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.03.25
令和1(ワ)19689 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年2月25日 東京地方裁判所
(1) 争点2−1(本件発信者情報1は法4条1項1号の「当該権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するか)について
原告は,本件投稿動画が投稿されたことにより原告動画に係る原告の公衆 送信権又は送信可能化権が侵害されたと主張しているところ,本件発信者情\n報1は,本件投稿行為から約1年8か月が経過した,平成31年4月28日 午後0時00分34秒(協定世界時)に本件サイトにログインした者の情報 であり,このログイン時に本件投稿行為が行われたものではないから,法4 条1項1号の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないことは明ら かである。 この点について,原告は,最終ログイン者が本件投稿動画の投稿者である 可能性が高いと主張するが,同人が,本件投稿動画が投稿された本件サイト\nに,ユーザ名とパスワードを用いてログインした者であるとしても,本件投 稿動画を投稿した者であると直ちに認定することはできず,本件投稿行為か ら同人のログインまで約1年8か月もの期間が経過していることも考慮すれ ば,同人と本件投稿動画を投稿した者が同一人物ではない可能性が相当程度\n残っており,その他,本件全証拠を精査しても,最終ログイン者が本件投稿 動画の投稿者であるとは認め難いというほかない。 また,原告は,仮に最終ログイン者が本件投稿動画を投稿した者ではない としても,投稿した者と密接に関連する者であり,省令が「発信者その他侵 害情報の送信に係る者」の情報も発信者情報に該当することを規定している ことからすれば,本件発信者情報1は開示の対象になると主張する。しかし, 本件において,最終ログイン者と本件投稿動画の投稿者がどのような関係に あるのかを的確に認めるに足る証拠はなく,また,法4条1項1号の「当該 権利の侵害に係る発信者情報」との文言,及び省令の「発信者その他侵害情 報の送信に係る者」という文言からは,その文言内容や規定振りに照らして, 本件投稿行為を行った者以外の者である最終ログイン者の情報が,原告が指 摘するような理由によって直ちに,開示の対象となる発信者情報に当たると いうことはできないというべきである。 以上によれば,原告の主張はいずれも採用することができず,本件発信者 情報1は,法4条1項1号の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当し ない。
(2) 争点2−2(本件発信者情報2又は同3は法4条1項1号の「当該権利の 侵害に係る発信者情報」に該当するか)について
前記第2の1の前提事実によれば,本件発信者情報2及び同3は,平成3 1年4月28日午後00時00分34秒(協定世界時・最終ログイン時)に 本件サイトにログインがされた際の割当てに係るIPアドレスを,約1年8 か月前である本件投稿行為が行われた日時頃に割り当てられていた者に関す る情報である。 そして,原告は,このような本件発信者情報2又は同3に関し,本件投稿 行為が行われた日時頃に上記IPアドレスを割り当てられていた者は,本件 投稿行為をした者である可能性が高いものであるから,同人の情報に係る本\n件発信者情報2又は同3は,法4条1項1号の発信者情報に該当する旨主張 する。 しかし,前記(1)で説示したとおり,本件投稿行為から最終ログイン時まで は約1年8か月の期間があることなどを考慮すれば,最終ログイン者が本件 投稿動画の投稿者であると認め難いというほかなく,ひいては,最終ログイ ン時から約1年8か月も前である本件投稿行為が行われた日時頃に,本件サ イトへの最終ログインの際の割当てに係るIPアドレスを割り当てられてい た者が,本件投稿行為を行った者であるとも認め難いというほかない。 以上によれば,原告の主張はいずれも採用することができず,本件発信者 情報2及び同3は,いずれも法4条1項1号の「当該権利の侵害に係る発信 者情報」に該当しない。
関連カテゴリー
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2020.03.24
令和1(行ウ)278 特許料納付書却下処分取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月22日 東京地方裁判所
法112条の2第1項所定の「正当な理由」があるときとは,原特許権者(代 理人を含む。以下同じ。)として,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず, 客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかったときをいう ものと解するのが相当であるところ(知財高裁平成30年(行コ)第10006 号令和元年6月17日判決参照),以下のとおり,本件においては,本件追納期 間内に原告らが第4年分の特許料等を納付することができなかったことについ て,同項の「正当な理由」があったとは認められない。
1 正当な理由の有無について
(1) 原告中井紙器について
ア 原告らは,本件追納期間の徒過は,A弁理士が,原告中井紙器から本件年 金管理に係る委任についても解任されたと誤認したという人為的なミスに 起因するものであることを前提とした上で,本件年金管理につきA弁理士と いう適切な代理人を選任した時点で原告中井紙器としては本件追納期間の 徒過を回避するために必要な注意義務を尽くしており,A弁理士から甲3の 書面を受け取っていた以上,原告中井紙器が本件誤認に気付くことは困難で あったなどと主張する。 イ しかし,特許料の納付をするかどうかの判断,その支払期限の管理,特許 料の支出の確認を含め,自らの特許権に関する管理を行うのは,特許料納付 の手続を代理人に依頼していたとしても,特許権者の基本的な業務であり, かつ,容易になし得ることである。原告中井紙器は,本件特許の原特許権者 であり,しかも,原告グラセルとの間で本件特許の有効性をめぐり係争中で あったのであるから,本件特許の第4年分の特許料の納付期限が平成28年 1月18日であり,本件追納期間の末日が平成28年7月19日であること を認識し,同各期限までに特許料等が支払われているかどうかを容易に確認 し得たというべきである。 しかるに,原告中井紙器は,支払期限の管理,確認など特許権者として行 うべき基本的な管理を行うことなく,上記各期限を徒過させたものであって, 特許権者としての相当な注意を尽くしていたということはできない。 ウ これに対し,原告らは,本件追納期間の徒過は,本件年金管理事務を受任 していたA弁理士が,本件無効審判に係る手続のみならず,本件年金管理事 務についても委任を解除されたと誤認したという人為的なミスに起因する ものであると主張する。
しかし,前記第2の2(7)記載のとおり,原告中井紙器は,平成27年6月 1日付けの書面をもって,A弁理士に対し,当時係属中であった本件無効審 判に係る手続の委任を解除した旨の告知をしたところ,本件年金管理事務が 特許出願等の手続代理に付随する事務としての性質を有し,出願,無効審判 など各種の手続代理と年金管理事務とを異なる代理人に依頼するとは通常 考え難いことに照らすと,同原告により解除された委任事務は,本件無効審 判に係る手続のみにとどまらず,本件特許に係る全ての事務を包括するもの であったと解するのが自然である。仮に,原告らの主張するように,A弁理 士に対して委任していた事務の一部のみを解除するのであれば,その旨の説 明があってしかるべきであるが,原告中井紙器からA弁理士に対してそのよ うな説明がされたことをうかがわせる証拠は存在しない。 そうすると,本件特許の管理業務も解除された委任事務に含まれるとのA 弁理士の認識が誤信であるということはできず,本件追納期間の徒過がA弁 理士の人為的ミスに基づくものであったということもできない。 エ 仮に,原告中井紙器が本件特許の年金管理業務はA弁理士に引き続き委任 していたものと誤信し,あるいは,原告中井紙器により解除された委任事務 の中に本件特許に係る年金管理事務が含まれていなかったとしても,前記判 示のとおり,自らの特許権に関する管理を行うのは特許権者の基本的な業務 であり,しかも,A弁理士に対しては,特許無効審判に係る手続の代理の委 任を解除しているのであるから,同原告としては,同弁理士からの納付期限 の連絡を漫然と待つのではなく,自ら調査・確認し,又は同弁理士に自ら連 絡をするなどして,特許料等の納付期限の管理を行うべきことは当然であり, それが困難であったとも考えられない。 したがって,原告中井紙器がA弁理士に本件年金管理事務を委任したこと をもって必要な注意を尽くしたなどということはできないのであり,同原告 が特許権者として相当の措置を講じたということはできない。
オ さらに,前記第2の2(11)記載のとおり,原告らは,本件追納期間内であ る同年3月9日に,原告中井紙器が本件特許権の持分1%を原告グラセルに 譲渡する一方で,原告グラセルが無効審判請求を取り下げることなどを内容 とする本件和解契約を締結したと認められるが,原告中井紙器としては,本 件特許権の一部を原告グラセルに譲渡するに当たり,同特許権の特許料が期 限までに支払済みであることを確認し,その支払が未了である場合には本件 追納期間内に第4年分の特許料等を納付すべき取引上の注意義務を負って いたというべきである。 しかるに,原告中井紙器は,同契約に当たり,本件特許の第4年分の支払 の有無を調査すれば,その支払が未了であることを容易に確認し得たにもか かわらず,自ら又はA弁理士に確認するなどして,必要な調査・確認を行わ ないまま,漫然と,本件追納期間の末日を経過したのであるから,特許権者 として,相当な注意を尽くしたということはできない。
(2) 原告グラセルについて
ア 原告らは,本件和解契約において本件年金管理の義務が原告中井紙器にあ って原告グラセルにはないことを合意するなどして本件年金管理の義務が 原告グラセルにないことを明確にしているから,原告グラセルは,本件追納 期間の徒過を回避するために必要な注意義務を尽くしたと主張する。 しかし,本件特許権の持分1%を取得する原告グラセルとしては,本件和 解契約を締結するに当たり,自らの取得する本件特許権が有効に存続するも のであることを確認するのが通常であると考えられる。原告グラセルは,無 効審判手続の当事者であったのであるから,本件特許に係る第4年分の特許 料の納付期限が平成28年1月18日であることは認識していたものと考 えられ,本件和解契約に当たり,同特許料が支払済みであるかどうかを原告 中井紙器に確認し,これが未払である場合には,本件追納期間中に特許料等 の納付を求めることは容易であったというべきである。 しかるに,原告グラセルが原告中井紙器に第4年分の特許料の支払に関し て照会し,あるいは,その点について自ら調査したことをうかがわせる証拠 は存在しない。
イ そうすると,原告グラセルは,自ら特許料の納付の時期について適切に管 理すべき立場にありながら,原告中井紙器が本件年金管理を行うものと軽信 し,本件追納期間中にも自らの不注意によって本件追納期間内に特許料等の 納付をすべきことを認識しないまま,漫然と,本件追納期間の末日を経過し たのであるから,同原告が相当な注意を尽くしたにもかかわらず,客観的に みて追納期間内に特許料等を納付することができなかったということはで きない。 なお,原告らは,本件和解における本件特許権の持分の譲渡は実質的には 実施許諾契約の性質を有するものであったと主張するが,仮にそのとおりで あったとしても,上記結論を左右するものではない。
(3) 特殊な事情の有無について
原告らは,本件追納期間の徒過は,(1)A弁理士が本件年金管理に係る事務の 委任についても解任されたと誤認したことと,(2)A弁理士が自己の認識と異な る内容の書面を送付したことという2つの特殊な事情が重なって生じたもの であるので,正当な理由があると認められるべきであると主張する。 しかし,本件年金管理事務も解除された委任事務に含まれると解すべきであ り,この点について,A弁理士に誤認があったとは認められないことは前記判 示のとおりである。また,甲3の書面の内容は前記2(7)に記載のとおりである ところ,同書面に記載された内容とA弁理士の内心の認識に齟齬があると認め ることはできない。 また,仮に,原告の主張する上記事情が認められるとしても,本件追納期間 の徒過は,原告らが特許権者としての通常の注意を払っていれば容易に避ける ことができたものであり,これらの事情をもって通常起こりえない特殊な事情 であるということはできない。
2020.03.24
令和1(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月17日 知的財産高等裁判所
本件審決は,本件明細書の【0022】, 【0024】〜【0027】が新たな技術 的事項を導入するものであることを理由に,本件補正は,本件当初明細書に記載さi れた事項の範囲内においてするものとはいえないと判断した。 しかし,本件補正は,特許請求の範囲についてのみするものであり(乙18),本 件明細書の【0022】, 【0024】〜【0027】 に係る補正は,本件第1 補正に おいてなされたものであって,本件補正においてされたものではない。本件補正が 新規事項を追加するものであるか否かは,本件当初明細書の配載に基づいてなされ るべきものであり,本件審決が,新たな技術的事項を導入するものであることを理 由に本件補正を却下したことには,誤りがあるというべきである。 もっとも,本件補正発明1が,特許出願の際独立して特許を受けることができる ものでない場合には,本件補正は部められないので,以下,独立特許要件について 検討する。
・・・
引用例1には,先端部32は,支持構造体42内に埋め込まれ,支持構造体42 は,超伝導単層金属タイプカーボンナノチュープ、44に対する排熱装置及び超高真 空密閉体としても働き,超伝導単層金属タイプカーボンナノチューブ44は,電場 放出引出し電極として及び微小超高真空室としても機能することの開示があり(【0054】図2).放出先端部は,微小超高真空室にまって固まれていることが示唆 されている。 かかる記載によれば,引用発明1において,放出先端部の近傍に熱を加えられる 部位を具備しないようにすることは,当業者が容易に想到できることである。 よって,相違点2は,引用発明1から容易に想到することができるものである。
エ原告の主張について
原告は,引用発明1は,先端のだんだん半径の小さくなる先端の大きさとS/N 比値とを問題としており,略閉じサイズである移動部が続く構成である本件補正発\n明1とは異なる旨主張する。 しかし,本件補正後の請求項1は,略同じサイズで粒子移動部が続く旨を特定し ていないため,粒子移動部が略同じサイズで続かない構成を含むものである。\nまた,本件補正発明1の粒子移動部に相当する引用発明1の放出先端部32は, rO. 3ナノメートルから10ナノメートルまでの範囲の,比較的小さい直径を有 する」とともにチューブ形状である(乙21 【0053】)から,放出先端部は,そ のいかなる断面もナノサイズであると解される。 よって,原告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば,本件補正発明1は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明を することができたものであるから,特許出願の際独立して特許を受けることができ たものではない。 よって,本件審決が本件補正を却下したことは,結論において相当である。
・・・
以上によれば,本件第1補正は,本件当初明細書に「ナノオーダの構造物」と\nしか記載のなかった本願発明の素子について,極めて高純度で無欠陥の超周期を含 む結晶性の良い金属材質の三次元系のワイヤ形状であることを特定した上,ナノワ イヤ形状の断面上での金属電子の量子状態を決定するに当たっては,一定の前提を 置いた運動方程式,角運動量保存則, B0nrの量子論を用いること等の説明を加 えている。 その上で,電気伝導を持つ使用ナノワイヤ内の熱による誤差が少ない伝導電子が 擬一次元的パリステック(弾道的)運動するためには,式(20) を満たし,ナノワ イヤの直径がおよそ30nni以下の太さとなることが条件であり,また,ナノオー ダの構造物を絶縁体で被覆すれば,その断面空間内にある粒子流の許されるエネル\nギー状態は量子力学で決まる最低エネルギー準位近くでは断面中心部での存在確率 が大きく断面の周囲での構成原子・分子による乱れの影響が少ないとして,ナノオ\nーダの構造物の断面積の大きさを特定したり,絶縁体で被覆するなどの技術的事項\nを追加している。 そうすると,本件第1補正に係る事項は,本件当初明細書には記載がなく,本件 当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。 よってa 本件第1補正は,本件当初明細書等のすべての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであっ て,新規事項に該当するというべきである。
(5) 原告の主張について
原告は,本件第1補正について,既知である科学的なことを書き加えたものであ る,新しいことを追加したが,それは説明を加えたものである,ナノワイヤと書い てなかったが,より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており,ただ例\n示しただけである,例えば,材質については,電流を流すときに金属材料であると いうことを記載したにすぎないなどと主張する。 しかし,公知のものや本願発明についての説明であっても,出願時の明細書に記 載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ,ナノオーダ の構造物の具体的な物質,形状,寸法等がそのようなものとはいえないことは,前\n記のとおりである。よって,原告の主張は理由がない。 (6) 小括
以上によれば,本件第1補正は,本件当初明細書に記載された事項の範囲内にお いてするものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2020.03.18
令和1(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月17日 知的財産高等裁判所
引用発明の販売促進の対象を「ホストクラブ」のサービスとし,ホストクラブへ の「来店」の「勧誘」の目的で使用した場合,「仮想現実動画」は,潜在顧客を対象 とした,ホストクラブで提供するサービスを疑似体験する動画となり得ると解され る。しかしながら,引用例1には,「仮想現実動画」について,「メンタルケア」を行うものとすることや,「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応 じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」仮想現実動画ファイルとすることに ついて,記載も示唆もない。また,かかる事項が周知であったと認めるに足りる証拠もない。そうすると,引用発明に基づき,相違点2’に係る「潜在顧客の心理状態に応じて 選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホス トクラブ仮想現実動画ファイル」の構成を当業者が容易に想到し得たとはいえない。\nよって,相違点2’に係る本件補正発明の構成は,当業者が容易に想到し得たもの\nではない。
ウ 相違点4’の容易想到性について
前記イのとおり,相違点2’に係る「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧 客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現 実動画ファイル」の構成を当業者が容易に想到することができたとはいえない以上,\n「異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選\n択される複数のコマンドボタン」を「各ホストクラブ仮想現実動画ファイル」に「対 応」させることを,当業者が容易に想到することができたとはいえない。 よって,相違点4’に係る本件補正発明の構成は,当業者が容易に想到し得たも\nのではない。
エ 被告の主張について
被告は,(1)引用発明におけるサービスの販促活動の内容は,広告代理店と広告主 であるサービス提供者との間の取決めに即したものとならざるを得ず,「仮想現実動 画」を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」となる内容として「心理状態に応じ て選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う」ものとするこ とは,引用発明の販促活動を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」とすることに 伴って生ずることにすぎず,また,(2)コマンドボタンに動画の内容を表記すること\nは周知技術であるところ,かかる動画の内容としてサービスの「メンタルケア的な 側面」を捉えた表示を行うことも,周知技術の採用に当たって,広告代理店とサー\nビスの提供者との間の取決めに即して,適宜決定すべきことである旨主張する。 しかし,引用例1には,テーマパークへの来場を勧誘したいサービスの提供者が, テーマパークの魅力を潜在顧客に伝える目的で,来場すると体験できるアトラクシ ョンを疑似体験するための仮想現実動画を提供することの記載はあるものの,その 際に,当該サービスのメンタルケア的な側面に応じた複数の異なる仮想現実動画を サーバーに記憶させておき,潜在顧客が疑似体験したいサービスを自由に選択でき るようにすることや,当該サービスのメンタルケア的な側面を仮想現実動画のタイ トル等として表記した複数のボタンを設けることの記載はなく,かかる示唆もない。\nそして,引用発明を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」に適用した場合に, 販促支援の内容は,販促支援をする広告代理店とこれを受ける広告主との間の取決 めに即したものとなるとしても,「仮想現実動画」を,「心理状態に応じて選択され 潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」ものにする ことが必然とはいえない。 また,コマンドボタンに動画の内容を表記することが周知技術であるとしても,\n取決めの下でなされる販促活動がかかる周知技術を踏まえたものになることが,必 然とはいえない上,仮にかかる周知技術を適用したとしても,前記ウのとおり,「潜 在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケ アを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」の構成を当業者が容易\nに想到することができたとはいえない以上,「異なる心理状態の表記が各々されてい\nるとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタン」を「各 ホストクラブ仮想現実動画ファイル」に「対応」させるとの構成を,当業者が容易に\n想到することができたとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.03.18
令和1(行ケ)10095 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月12日 知的財産高等裁判所
ア 原告は,「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義 は,沈降法により測定されるストークス径について,質量を基準に粒子径を表した\n質量分布におけるメジアン粒径ということで,一義的に明確であり,ストークス径 はストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。 そこで検討するに,甲18(神保元二ら編「微粒子ハンドブック」初版第1刷,1 991年9月1日)には,ストークス径は,最も広く用いられる代表径であり,静止\n流体中を重力で落下する粒子の沈降速度v1と同じ沈降速度をもち,また同じ密度を もつ球形粒子の直径であり,流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な 代表径であることの記載があり,本件出願当時,粒子の大きさを測定する方法とし\nて,ストークス径を得る沈降法があることは,周知であったことが認められる。 また,ウェブページ「粒度分布測定の基礎知識」(甲19)には,「主な粒度分布測 定原理」の表の「遠心沈降法」の欄に,「測定粒子径の定義」を「ストークス径」,「基本粒度分布」を「重量基準」との記載があり,「遠心沈降法 液相中の粒子群の沈降 状態を吸光度などから計測して,球と仮定して導かれたストークスの式などと照合 し,有効径(ストークス径)を求める。」との記載がある。ウェブページ「粒径分布 測定[重力/遠心沈降式]」(甲22)には,「[測定原理/測定法]微粒子を水または不溶溶媒中に懸濁させ,重力場にそのまま静置するか遠心場に粒子懸濁液を置くと, 大きな粒子ほど速い速度で沈降していきます。その様子を粒子懸濁液に照射したレ ーザー光の透過光強度によって検出します。粒子サイズは重力沈降の場合,次のS tokesの式から得られます。」との記載があり,
・・・
とのストークスの式が記載されている。これらによれば,沈降法は,重量(質量)基 準に基づく粒度分布が得られるものであること,液相中の粒子の沈降速度から粒径 を求めるものであり,分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認めら\nれる。 しかし,前記(2)イのとおり,本件明細書には,「炭化タングステンを含んでなる 表面を有する」「粉砕工具」の「工具表\面」の炭化タングステン粒子が,コバルトで ある結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方,炭化タングス テン粒子が工具表面から分離可能\であることの記載や示唆はない。また,ストーク スの式によりストークス径を算出するためには,ストークスの式に沈降距離h,沈 降時間t等のパラメータを代入することが必要であるところ,本件明細書を見ても, ストークスの式のパラメータの値としてどのような値を採用するかについての記載 はない。
そうすると,粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があ ることが周知であり,沈降法により重量(質量)基準に基づく粒度分布が得られる としても,「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が,\nコバルトである結合剤と焼結により一体化している以上,沈降法により炭化タング ステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから,本件発明の「炭化\nタングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が,沈降法に基づいて得 られるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。 イ 原告は,焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か,変化 するとしてどの程度変化するかは,焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも 十分に予\測が可能であり,その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径\nを調整し,必要に応じて焼結条件を調整すればよく,また,焼結の前後それぞれの 炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し,その変化の有無や程度を確認するこ とで,ストークス径の粒度分布の変化を予測することは可能\であるから,工具表面\nに存在する炭化タングステン粒子自体を測定するまでもない,また,本件発明にお けるメジアン粒径は,「1.3μm以上」ないし「0.5μm以下」という広い範囲 を規定するものであるから,焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性にほとんど影 響を及ぼさないと考えられる旨主張する。 しかし,本件明細書には,焼結条件との兼ね合いで焼結による粒径の変化を予測\nして炭化タングステン粒子の粒径を調整することや,焼結の前後それぞれの炭化タ ングステン粒子の粒径を画像で確認し,その変化の有無や程度を確認してストーク ス径の粒度分布の変化を予測することの記載や示唆はないから,本件発明の「炭化\nタングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が,かかる予測や調整等を\n行うことを前提として沈降法により測定されるストークス径のメジアン粒径である とは解されない。また,本件発明におけるメジアン粒径が,広い範囲を規定するも のであるとしても,焼結の有無が数値範囲の充足性に影響を及ぼさないと解すべき 根拠はないから,上記の判断を左右するものではない。
ウ 原告は,焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要がある としても,コバルトの融点は1495℃,炭化タングステンの融点は2870℃で あるから,バインダーであるコバルトを溶かすなどして除去し,炭化タングステン 粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である旨主張する。\nしかし,本件明細書には,一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン 粒子とを加熱し,バインダーであるコバルトを除去し,炭化タングステン粒子を取 り出して沈降法で測定することについては,記載も示唆もないから,本件発明の「炭 化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が,コバルトを除去して 取り出した炭化タングステン粒子を沈降法により測定したストークス径であるメジ アン粒径であるとは解されない。 仮に,上記測定方法により炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定する ことができたとしても,一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン粒子 とを加熱し,バインダーであるコバルトを除去し,炭化タングステン粒子を取り出 すという過程において,炭化タングステン粒子の密度や形状が一切変化しないとい う根拠はないから,そのように取り出して測定した炭化タングステン粒子のストー クス径が,そのまま,コバルトマトリックスと一体化した工具表面の炭化タングス\nテン粒子のストークス径であるということもできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2020.03.13
令和1(行ケ)10095 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月12日 知的財産高等裁判所
特許法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載に関し,特許を受けようとする 発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は,仮 に,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許が付与された発 明の技術的範囲が不明確となり,第三者の利益が不当に害されることがあり得るの で,そのような不都合な結果を防止することにある。そして,特許を受けようとす る発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だけではなく,願書に添付し た明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願当時における技術常識を基 礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確 であるか否かという観点から判断されるべきである。
・・・・
請求項1には,「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」との 記載があるところ,請求項1の記載自体から,この炭化タングステン粒子は,「少な くとも二個の粉砕工具」の「工具表面」に「含有」されるものであることを理解する\nことができ,また,上記炭化タングステン粒子は,第1の粉砕工具の表面には95\n重量%以下含有され,その粒径が1.3μm以上であること,第2の粉砕工具の表\n面には80重量%以上含有され,その粒径が0.5μm以下であること,粒径はメ ジアン粒径であること,炭化タングステン粒子のメジアン粒径が1.3μm以上あ るいは0.5μm以下であることは,炭化タングステン粒子を「質量により秤量」し て測定するものであることが理解できる。 しかしながら,請求項1の記載からは,粉砕工具の「工具表面」に「含有」される\n炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義が明らかであ るとはいえない。 また,本件特許の出願当時において,炭化タングステンを含んでなる表面を有す\nる粉砕工具の工具表面に含有される炭化タングステン粒子につき,質量により秤量\nしたメジアン粒径を得ることができたとする当業者の技術常識を認めるに足りる証 拠はない。
イ 本件明細書の記載
本件明細書には,「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の\n「工具表面」のタングステン含有量が95%以下であり,工具表\面の材料における 100%に対する残りは,好ましくはコバルト結合剤であり,好ましくは1%未満 の程度に追加の炭化物が存在する(【0026】〜【0028】),焼結の結果は,炭 素の添加によっても影響を受ける(【0029】)との記載があり,「炭化タングステ ンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表\面」の炭化タングステン粒子 が,コバルトである結合剤と焼結により一体化していることが開示されている。そ して,本件明細書には,コバルト結合剤と焼結により一体化した「粉砕工具」の「工 具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン\n粒径について,定義や測定方法の記載はない。
ウ 以上によれば,本件明細書の記載を考慮し,出願当時の技術常識を基礎とし ても,本件発明の「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工\n具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン\n粒径の意義を理解することはできず,本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを 得ないから,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,明確性要件を充足しないと いうべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義 は,沈降法により測定されるストークス径について,質量を基準に粒子径を表した\n質量分布におけるメジアン粒径ということで,一義的に明確であり,ストークス径 はストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。 そこで検討するに,甲18(神保元二ら編「微粒子ハンドブック」初版第1刷,1 991年9月1日)には,ストークス径は,最も広く用いられる代表径であり,静止\n流体中を重力で落下する粒子の沈降速度v1と同じ沈降速度をもち,また同じ密度を もつ球形粒子の直径であり,流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な 代表径であることの記載があり,本件出願当時,粒子の大きさを測定する方法とし\nて,ストークス径を得る沈降法があることは,周知であったことが認められる。 また,ウェブページ「粒度分布測定の基礎知識」(甲19)には,「主な粒度分布測 定原理」の表の「遠心沈降法」の欄に,「測定粒子径の定義」を「ストークス径」,「基本粒度分布」を「重量基準」との記載があり,「遠心沈降法 液相中の粒子群の沈降 状態を吸光度などから計測して,球と仮定して導かれたストークスの式などと照合 し,有効径(ストークス径)を求める。」との記載がある。ウェブページ「粒径分布 測定[重力/遠心沈降式]」(甲22)には,「[測定原理/測定法]微粒子を水または
・・・
不溶溶媒中に懸濁させ,重力場にそのまま静置するか遠心場に粒子懸濁液を置くと, 大きな粒子ほど速い速度で沈降していきます。その様子を粒子懸濁液に照射したレ ーザー光の透過光強度によって検出します。粒子サイズは重力沈降の場合,次のS tokesの式から得られます。」との記載があり, とのストークスの式が記載されている。これらによれば,沈降法は,重量(質量)基 準に基づく粒度分布が得られるものであること,液相中の粒子の沈降速度から粒径 を求めるものであり,分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認めら\nれる。
しかし,前記(2)イのとおり,本件明細書には,「炭化タングステンを含んでなる 表面を有する」「粉砕工具」の「工具表\面」の炭化タングステン粒子が,コバルトで ある結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方,炭化タングス テン粒子が工具表面から分離可能\であることの記載や示唆はない。また,ストーク スの式によりストークス径を算出するためには,ストークスの式に沈降距離h,沈 降時間t等のパラメータを代入することが必要であるところ,本件明細書を見ても, ストークスの式のパラメータの値としてどのような値を採用するかについての記載 はない。 そうすると,粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があ ることが周知であり,沈降法により重量(質量)基準に基づく粒度分布が得られる としても,「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が,\nコバルトである結合剤と焼結により一体化している以上,沈降法により炭化タング ステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから,本件発明の「炭化\nタングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が,沈降法に基づいて得 られるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。
イ 原告は,焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か,変化 するとしてどの程度変化するかは,焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも 十分に予\測が可能であり,その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径\nを調整し,必要に応じて焼結条件を調整すればよく,また,焼結の前後それぞれの 炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し,その変化の有無や程度を確認するこ とで,ストークス径の粒度分布の変化を予測することは可能\であるから,工具表面\nに存在する炭化タングステン粒子自体を測定するまでもない,また,本件発明にお けるメジアン粒径は,「1.3μm以上」ないし「0.5μm以下」という広い範囲 を規定するものであるから,焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性にほとんど影 響を及ぼさないと考えられる旨主張する。 しかし,本件明細書には,焼結条件との兼ね合いで焼結による粒径の変化を予測\nして炭化タングステン粒子の粒径を調整することや,焼結の前後それぞれの炭化タ ングステン粒子の粒径を画像で確認し,その変化の有無や程度を確認してストーク ス径の粒度分布の変化を予測することの記載や示唆はないから,本件発明の「炭化\nタングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が,かかる予測や調整等を\n行うことを前提として沈降法により測定されるストークス径のメジアン粒径である とは解されない。また,本件発明におけるメジアン粒径が,広い範囲を規定するも のであるとしても,焼結の有無が数値範囲の充足性に影響を及ぼさないと解すべき 根拠はないから,上記の判断を左右するものではない。
ウ 原告は,焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要がある としても,コバルトの融点は1495℃,炭化タングステンの融点は2870℃で あるから,バインダーであるコバルトを溶かすなどして除去し,炭化タングステン 粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である旨主張する。\nしかし,本件明細書には,一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン 粒子とを加熱し,バインダーであるコバルトを除去し,炭化タングステン粒子を取 り出して沈降法で測定することについては,記載も示唆もないから,本件発明の「炭 化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が,コバルトを除去して 取り出した炭化タングステン粒子を沈降法により測定したストークス径であるメジ アン粒径であるとは解されない。 仮に,上記測定方法により炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定する ことができたとしても,一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン粒子 とを加熱し,バインダーであるコバルトを除去し,炭化タングステン粒子を取り出 すという過程において,炭化タングステン粒子の密度や形状が一切変化しないとい う根拠はないから,そのように取り出して測定した炭化タングステン粒子のストー クス径が,そのまま,コバルトマトリックスと一体化した工具表面の炭化タングス\nテン粒子のストークス径であるということもできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2020.03.13
平成29(ワ)27238 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年2月28日 東京地方裁判所
本件では,本件LED又はその製造方法が特許発明の技術的範囲に属するということだけでなく,白色LEDはそれのみで販売の対象となるものであり,原告は白色LEDの製造,販売を行っていることなどから,特許法102条3項の金額の算定に当たって,まず,上記の平均的な価格の24個分の価格に,主として本件特許権1の侵害が問題 となる平成27年10月までの期間については5パーセントを乗じ,本件特許 権1に加えて本件特許権3(登録日平成27年10月23日)の侵害も問題と なる平成27年11月以降の期間(なお,本件発明2と本件訂正後発明3の内 容に照らし,損害の算定に当たり本件特許権2(登録日平成28年12月16 日)の侵害については特に期間を分けて考慮することをしない。)については 8パーセントを乗じると,それぞれ,10.80円及び17.28円となる(2 16円×5パーセント=10.80円 216円×8パーセント=17.28 円)。
そして,本件で特許権の侵害となるのは本件LEDを使用した被告製品の販 売であること,本件LEDはデジタルハイビジョンテレビである被告製品にと り不可欠のものであり,その機能,性能\において重要な役割を果たしていると いえること,原告の白色LEDの市場におけるシェア,原告が主張するライセ ンスについての方針,その他本件に現れた諸事情を考慮し,本件において,被 告製品1及び2を通じ,特許法102条3項の実施に対し受けるべき金銭の額 は,被告製品1台当たり,消費税相当額を含めて,平成27年10月までの期 間については,20円をもって相当であると認め,平成27年11月以降の期 間については,30円をもって相当であると認める。
以上のとおり,本件において,原告が実施に対し受けるべき実施料として被 告製品1台当たり,20円又は30円とするのが相当であるところ,これらは, それぞれ,被告製品の平均的な販売価格の0.058パーセント又は0.08 7パーセントである(20円÷3万4129円≒0.00058 30円÷3 万4129円≒0.00087)。これらに基づき,特許法102条3項に基づ く損害額は,以下のとおり,1645万6641円とするのが相当と認める。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.03.12
平成30(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月21日 知的財産高等裁判所
引用発明1は,薄肉の鋼管を梁鉄骨のウェブに設けた貫通孔に挿入して溶接によ り固着し,貫通孔の周辺のウェブ両面に補強プレートを溶接により固着する従来技 術において,溶接量と部品点数を少なくし,加工や品質管理をしやすくすることを 目的として,貫通孔を貫通する厚肉鋼管2の外周部の中央部をウェブ1aに溶接固 着する際に,その片面からリング状の裏当て体3aを一体形成して当接する構成を\n採用したものである。したがって,引用発明1の裏当て体3a(フランジ部)が厚肉 鋼管2と一体に形成される部位は,溶接部位である厚肉鋼管2のほぼ中央部であり, 引用例1には,これを端部に設けることについて記載も示唆もない。そうすると, 引用発明1には,裏当て体3aを外周部の軸方向の片面側の端部に設ける構成を採\n用する動機付けがないというべきである。 また,甲2,3,6〜10,23〜25の記載及び後記甲5(引用例2)の記載に よれば,フランジと呼ばれる部分が種々の分野で用いられていること自体は周知技 術であるとしても,相違点2に係る構成は,甲2,3,5〜10,23〜25のいず\nれにも開示も示唆もない。甲2,3は,梁補強金具の外周にフランジを設ける構成\nであるが,フランジを端部に設けることの記載はなく,甲5には,スリーブ管にフ ランジを設けることの記載はない。甲6,7には,フランジを端部に形成すること が記載されているが,甲6に記載されたフランジはボルト締め用の管フランジであ り,甲7に記載されたものは一般的なH形鋼のフランジであって,梁貫通孔構造用\nの厚肉鋼管である引用発明1とは技術分野が異なる。甲23〜25は,いずれも, 梁に配管を通すための構造において,それぞれ対となる2つの部材を用いた梁の補\n強やスリーブ材の固定に関する技術を開示したものであって,一体的な構成を有す\nる1つの金具を用いて梁の補強等を行う引用発明1とは,技術分野が異なる。した がって,これらの文献の記載によって,引用発明1の技術分野において,フランジ 部を端部に形成することが周知技術であったとは認められない。 以上によれば,引用発明1について,相違点2に係る構成を容易に想到すること\nはできない。
ウ 原告の主張について
原告は,引用例1は,貫通孔1bより外径が大きい裏当て体3aが,厚肉鋼管2 の外周部の軸方向の中央より軸方向の片側にて厚肉鋼管2と一体に形成されること を開示しているのであるから,引用発明1において,裏当て体3aの形成箇所を, 厚肉鋼管2の外周部の軸方向の中央より軸方向の片側に位置する領域のうち片側の 端部とすることも設計事項として選択し得るものであるところ,フランジ部を相違 点2の構成とすることで,引用発明1と比較して優れた作用効果をもたらすもので\nはないから,甲6,7のように端部に形成された「フランジ」を引用発明1の裏当て 体3a(フランジ部)に適用できない理由はないなどと主張する。 しかし,引用発明1において,裏当て体3aを設ける位置は,厚肉鋼管2の外周 部のほぼ中央部であるから,軸方向の片側に形成されることが開示されているから といって,片側の端部に設けることの動機付けがあるとはいえないこと,また,甲 6,7は,引用発明1とは技術分野を異にし,これらの文献の記載によって,引用発 明1の技術分野において,フランジを端部に形成することが周知技術であったとは 認められないことは,前記イのとおりであるから,引用発明1に甲6,7のように 端部に形成された「フランジ」を適用し,裏当て体3aの位置を,梁補強金具の軸方 向の片側の端部とすることが設計事項として選択し得るものとはいえない。
・・・
(2) 相違点3の容易想到性
ア 容易想到性の判断
引用発明2は,スリーブ管の幅・肉厚を変えた試験体を用いて,そのせん断及び せん断+曲げ耐力を実験的に調査した結果等を開示するものであり,そもそも梁補 強金具の外周にフランジ部がないことを前提とした技術であって,そのスリーブ管 にフランジ部を設けることの記載も示唆もない。したがって,引用発明2において は,甲1〜3に記載された,梁補強金具の外周にフランジ部を設ける構成を適用し\nて,フランジ部を設ける動機付けはない。 また,仮に,引用発明2に甲1〜3に記載された事項を適用してフランジ部を設 けたとしても,甲1〜3に記載されたフランジ部は,いずれも,梁補強金具の中央 部に設けられたものであり,フランジを設けた方面側が面一に形成されるものでは ないから,相違点3に係る構成には至らない。\nさらに,甲1〜3,6〜10,23〜25の記載によれば,フランジと呼ばれる部 分が種々の分野で用いられていること自体は周知技術であるとしても,相違点3に 係る構成は,いずれの文献にも開示も示唆もない。前記のとおり,甲1〜3には,フ\nランジを設けた片面側を面一にすることの記載はなく,甲6,7には,フランジを 設けた片側面が面一になることが記載されているとしても,甲6に記載されたフラ ンジはボルト締め用の管フランジであり,甲7に記載されたものは一般的なH形鋼 のフランジであって,梁補強用のスリーブ管についての引用発明2とは技術分野が 異なる。また,甲23〜25は,いずれも梁に配管を通すための構造において,それ\nぞれ対となる2つの部材を用いて梁の補強やスリーブ材の固定に関する技術を開示 したものであって,梁補強金具の外側にフランジを設けない引用発明2とは,技術 分野が異なる。したがって,これらの文献の記載によって,引用発明2の技術分野 において,フランジ部を外周部の軸方向の片面側の端部に形成し,当該面を梁補強 金具の内周から外周部の一部であるフランジ部の外周まで平面である構成とするこ\nとが周知技術であったとは認められない。 よって,引用発明2について,甲1〜3のフランジ部を適用し,周知技術(甲1〜 3,6〜10,23〜25)を適用して,相違点3に係る構成を容易に想到すること\nはできない。
イ 原告の主張について
原告は,引用発明2と甲1〜3に記載された発明とは,梁のウェブの貫通孔に挿 入され,かつ,かかる梁を補強するための梁補強金具であるという点で共通してい るので,適用の動機付けがないとはいえないと主張する。しかし,前記のとおり,引 用発明2にフランジ部を設ける理由がない以上,適用の動機付けがないことは明ら かであり,原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.03.11
令和1(行ケ)10083 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月18日 知的財産高等裁判所
ア アルギン酸ナトリウムに置換する動機付けについて
(ア) 原告は,気泡状の二酸化炭素を効率的に発生・保持するとの本件発明1の課 題は,周知の課題であったところ,アルギン酸ナトリウムが起泡剤としても利用す ることができるもので,発生した気泡状の二酸化炭素を閉じ込める効果を有するこ とは周知であり,粘性を高めることにより気泡の安定性が増すこと,界面活性剤が 気泡の発生・保持に効果的に作用することも技術常識であったから,増粘剤として アルギン酸ナトリウムを選択することは容易である旨主張する。 しかし,気泡状の二酸化炭素の持続性が周知の課題であることの根拠として原告 が挙げる文献のうち,特開平9−206001(甲5)には,「このゲル状食品は, 製造時に,膠質水溶液と炭酸ガスとを混合した後に加熱する。この加熱によって炭 酸ガスは激しく発泡すると同時に膠質水溶液から逃散してしまう」(【0002】), 「その目的とするところは,発泡成分の発泡によって生成した気泡が,ゼリー中に 多数内包され,しかもこの気泡中の炭酸ガスが長時間保持され,喫食時に口中で強 い発泡感が感じられる発泡性ゼリーを,家庭で簡単に手作りできる発泡性ゼリー用 粉末およびこれを用いた発泡性ゼリーの製法を提供するにある」(【0004】)との 記載があるものの,同文献に記載されているのは,ゲル状食品であって,引用発明 のパック剤とは異なる技術分野に関するものである。 また,特開昭63−310807号公報(甲18)は,炭酸ガスのガス保留性につ いて,特開平3−161415号公報(甲63)は,炭酸ガスを高濃度で長時間保持 することについて,特開昭63−280799号公報(甲64)及び特開昭62− 294604号公報(甲65)は,炭酸ガスの発生による発泡の持続性について,特 開昭61−43102号公報(甲66)は,化粧料の炭酸ガスの滞留時間について, 特開昭61−43101号公報(甲67)及び特開昭61−40205号公報(甲 68)は,炭酸ガスが化粧料に溶けて配合されていることについて,それぞれ記載 したものであるが,これらの文献のいずれにも,気泡状の二酸化炭素を保持するこ とが周知の課題であると読み取れる記載はない。 したがって,本件優先日当時において,パック剤の技術分野において気泡状の二 酸化炭素を保持するとの本件発明1の課題が周知であったとは認められず,引用発 明の増粘剤としてアルギン酸ナトリウムを適用する動機付けがあるとはいえないか ら,原告の主張は採用できない。
(イ) 原告は,アルギン酸ナトリウムを含む水溶液が皮膜を形成するから,引用 発明の増粘剤をアルギン酸ナトリウムに置換しても,皮膜形成作用を維持すること はでき,引用発明におけるポリビニルアルコール及びカルボキシメチルセルロース ナトリウムをアルギン酸ナトリウムに置き換えることは可能である旨主張する。\n特開平9−278926号公報(甲86)には, アルギン酸を含む水溶液は,皮 膜を形成すること(【0011】,【0015】),被コーティング物に塗布される皮膜は,アルギン酸の濃度で調整できること(【0016】)が,「機能性包装資材の開発\n技術の形成 −機能性段ボール箱の開発−」と題する文献(1995年。甲87)に\nは,アルギン酸ナトリウム(G−I)と天然多糖類プルラン(PI−20)を(1: 1)で混合した5wt%溶液を,秤量220g/m2の段ボールライナー表面に塗工\nし,5wt%塩化カルシウム水溶液を噴霧し凝固させ,フィルムを形成させたこと が,「機能性包装資材の開発技術の形成 −機能性無機粉体の開発−」と題する文献\n(1995年。甲88)には,アルギン酸ナトリウムとプルランを混合してフィル ムを形成した場合,両者の混合比を変化させると酸素透過量と炭酸ガス透過量が変 化することが,それぞれ記載されていることが認められる。 しかし,これらの文献に開示されているのは,内容物を保護する目的で使用され る包装材料としてのフィルムやコーティング被膜をアルギン酸ナトリウムによって 形成することであるところ,引用発明のパック剤の膜は,その造膜過程において皮 膚に刺激を与えて血行を促進すると共に,皮膚表面の汚れを吸着して清浄するもの\nであって,造膜後には皮膚から剥がして除去されるものであって,その適用対象や, 使用目的・作用効果が異なる。 したがって,甲86〜88を考慮しても,引用発明におけるポリビニルアルコー ル及びカルボキシメチルセルロースナトリウムをアルギン酸ナトリウムに置き換え 可能であるということはできず,原告の主張は採用できない。\n
イ 酸を「顆粒(細粒,粉末)剤」に含ませる点について
原告は,二酸化炭素を適切に発生させるための徐放化技術として,炭酸塩と酸を 一つの固形物に含有させることは慣用技術であるところ,どのような剤型を選択す るかは,化粧品についての一般的な課題であり,美容目的の化粧品については,当 該化粧品の効能や作用機序等が異なっていても同一の剤型のものが存在していたの\nであるから,剤型の選択の局面においては,技術分野を狭く解することは誤りであ り,慣用技術を適用できる旨主張する。 特開平6−179614号公報(甲6)には,アルギン酸水溶性塩類を含有する ゲル状パーツからなる第一剤と,前記アルギン酸水溶性塩類と反応しうる二価以上 の金属塩類および前記反応の遅延剤を含有する粉末パーツからなる第二剤との二剤 からなることを特徴とする,剥がすタイプのパック剤が,化粧品製造製品届書(香 椎化学工業株式会社,平成13年1月11日。甲7)に係る化粧品製造品目追加許 可書(厚生大臣,平成3年11月12日。甲8)には,2剤を使用前に混合して肌に 塗布し,膜が乾燥したら剥がすパック剤が,特開平7−53324号公報(甲9) には,美白や保湿を目的として,粉末あるいは顆粒状の組成物を,使用する直前に 化粧水や乳液に分散せしめ,皮膚に塗布する用時混合タイプのものが,「化粧品成分 ガイド」第5版(フレグランスジャーナル社,2009年2月25日。甲10)に は,化粧品の剤形タイプとして,溶液タイプ,ジェルタイプ,乳化タイプ,固体タイ プ,液体タイプ,ペーストタイプ,皮膜タイプ,エアゾールタイプがあることが,そ れぞれ記載されていることが認められる。 しかしながら,甲6ないし8に記載されているのは,剥がすタイプのパック剤, 甲9に記載されているのは,化粧水や乳液など肌に塗布する化粧品であり,甲10 には,剤型タイプの分類が記載されているにすぎず,これらの文献のいずれも,炭 酸ガスを発生させ,発生する炭酸ガスによる血行促進作用により,皮膚の血流を良 くし皮膚にしっとり感を与えるパック剤に関するものではないから,これらによっ て,引用発明の技術分野において炭酸塩と酸を一つの固形物に含有させることが慣 用技術であったとは認められない。そして,化粧品の剤型は,その効能や使用目的\nに応じて個別に検討されるものであることは当然であり,分野の異なる技術を引用 発明に適用できるとはいえないから,原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.03.11
平成30(行ケ)10165 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
(ア) 甲3には,引用発明2−2−1’(実施例4記載の用時混合型の医療 溶液)が「血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。 一方で,甲3には,前記(1)イ(イ)認定のとおり,「本発明」の目的の1 つは,滅菌されかつ沈殿物を含まず,保存及び使用の間に渡り良好な安 定性を保証する「医療溶液」(血液透析,血液透析濾過,血液濾過及び腹 膜透析用の透析液,腎疾患集中治療室内での透析用の溶液,通常は緩衝 物質を含む置換液又は輸液,並びに栄養目的のための溶液)を提供する ことにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療 室内での透析用の溶液」とは,救急・集中治療領域において,急性腎不 全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むこ とは自明である。
また,甲3には,前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり,(1)急性腎不全に 罹患している患者に適応となる治療法は,数週間を通しての持続的腎機 能代替療法(CRRT)であり,血液濾過が用いられるが,血清リンレ\nベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果,定期的な週 3回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で,低リン血症が 起こり得るものであること,(2)低リン血症は,リンの投与によって予防,\n治療されるが,医療溶液にリンを導入する場合,沈殿する様々なリン酸 カルシウムの形成の問題があり,生理的pHに等しいpH値を有する生 理溶液では,リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題が あること,(3)「本発明」の発明者らは,特定のpH範囲等の如き一定の 条件下では,カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及び リン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ,滅菌の安定なリン酸塩 含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからす ると,「本発明」の実施例である引用発明2−2−1’の「医療溶液」は, 急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。 以上の点に照らすと,甲3に接した当業者においては,甲3記載の実 施例4(引用発明2−2−1’)において,当該「医療溶液」を「血液浄 化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。 したがって,当業者は,引用発明2−2−1’において,相違点(甲 3−3−b”)に係る本件訂正発明12の構成とすることを容易に想到す\nることができたものと認められる。 これと異なる本件審決の判断は,誤りである。
(イ) これに対し被告らは,引用発明2−2−1’は,単なる「医療溶液」 にすぎず,これを「血液浄化用薬液」として使用することができると解 すべき技術常識は存在しないことなどからすると,甲3に「医療溶液」 として記載された引用発明2−2−1’を「血液浄化用薬液」とするこ とは,当業者が容易に想到し得たことではない旨主張する。 しかしながら,前記(ア)のとおり,甲3の記載事項に照らすと,当業 者は,引用発明2−2−1’において,相違点(甲3−3−b’’)に係る 本件訂正発明12の構成とすることを容易に想到することができたもの\nと認められるから,被告らの上記主張は採用することができない。
イ 相違点(甲3−3−d”)について
(ア) 引用発明2−2−1’(実施例4記載の用時混合型の医療溶液)にお ける第一単一溶液と第二単一溶液を混合した即時使用溶液の各成分の イオン濃度は,「K+」(カリウムイオン濃度)が「4.0mM」(4.0 mEq/L),「HPO4 2-」(リン酸イオン濃度)が「1.20mM」(無 機リン濃度3.72mg/dL),「Ca2+」(カルシウムイオン濃度) が「1.25mM」(2.50mEq/L),「Mg2+」(マグネシウムイ オン濃度)が「0.6mM」(1.2mEq/L),「HCO₃⁻」(炭酸水 素イオン濃度)が「30.0mM」(30.0mEq/L)である。 一方,前記(1)イ(イ)の認定事実によれば,甲3には,(1)「本発明」の 目的の1つは,滅菌されかつ沈殿物を含まず,保存及び使用の間に渡り 良好な安定性を保証する「医療溶液」を提供することにあること,(2)「本 発明」の発明者らは,カルシウムイオン及びマグネシウムイオンは,特 定のpH範囲等の如き一定の条件下では,重炭酸塩と共に保持し得るも のであり,一定の条件下では,リン酸塩とも一緒に保持することができ, 特定の環境,濃度,pH範囲及びパッケージングにおいて,滅菌の安定 なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したこと,(3)「本発明」 は,上記課題を解決するため,「即時使用溶液」が,1.0〜2.8mM の濃度(無機リン濃度に換算すると「3.1〜8.7mg/dL」)のリ ン酸塩を含み,滅菌され,かつ6.5〜7.6のpHを有するという構\n成を採用したことの開示があることが認められる。
加えて,甲3には,(4)「本明細書で述べる現在好ましい実施形態への 様々な変更および修正は当業者に明らかであることが理解されるべきで ある。そのような変更および修正は,本発明の精神および範囲から逸脱 することなくおよびその付随する利点を減じることなく実施することが できる。」(前記(1)ア(ケ))との記載があることに照らすと,甲3に接し た当業者は,引用発明2−2−1’における上記即時使用溶液の各成分 のイオン濃度を最適なものに変更し得るものと理解するものといえる。 しかるところ,前記(2)イ認定のとおり,本件優先日当時,「急性血液 浄化」のための血液濾過(透析)用に使用され得る,市販されている透 析液及び補充液において,カルシウムイオン濃度を「2.5〜3.5m Eq/L」,マグネシウムイオン濃度を「1.0〜1.5mEq/L」, 炭酸水素イオン濃度を「30mEq/L」前後の範囲の中で調整するこ とは,技術常識又は周知であったものである。 そして,上記技術常識又は周知技術を踏まえると,引用発明2−2− 1’における上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度(「1.2mE q/L」)を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整する ことは,当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると,甲3に接した当業者は,引用発明2−2−1’における 上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度を市販されている透析液及 び補充液の上記数値範囲内の「1.0mEq/L」(相違点(甲3−3− d”)に係る本件訂正発明12の構成)にすることを容易に想到すること\nができたものと認められる。 したがって,これと異なる本件審決の判断は,誤りである。
(イ) これに対し被告らは,(1)不溶性微粒子の形成を抑制する溶液を実現 するためには,リン酸塩の濃度のみならず,溶液に含まれる他の成分及 び各イオン濃度の組合せが調整される必要があるから,これらの組合せ が1個の不可分のまとまりのある技術事項となるところ,本件訂正発明 12は,配合及び混合液の各成分の濃度が所定の組合せであることによ って,混合後長時間が経過してpHが上昇しても,不溶性炭酸塩の生成 を抑制することができる用時混合型急性血液浄化用薬液を実現したも のであるから,混合液の各成分の濃度は,成分ごとに区々別々に対比す るのではなく,各成分の濃度の組合せを一つの単位として認定して,引 用発明2−2−1’と対比するのが相当である,(2)引用発明2−2−1’ は,「所定のリン酸塩の濃度に対し,粒子の形成が24時間内抑制され る,混合時の即時使用溶液のpHの範囲を特定した発明」であり,本件 訂正発明12とは,技術的意義を異にする発明であるから,各成分の濃 度の相違は,設計事項となるものではなく,また,引用発明2−2−1’ に基づき,その各成分の濃度を変更して本件訂正発明12に到達しよう とする動機付けは,そもそも観念できない,(3)引用発明2−2−1’は, 低リン血症を防止するとともに粒子の形成を抑制する旨の課題に対し, 所定の配合及び各成分の濃度を定めるとともに,「溶液混合時のpHの 範囲を定めることにより」既に上記課題を解決しているものであるから, 引用発明2−2−1’に接した当業者が,上記課題を解決するために引 用発明2−2−1’の各成分の濃度を変更する動機付けもない,(4)一定 の濃度の範囲内で各成分の濃度を適宜に変動することができるのは,あ くまで,「一般の透析液・補充液」限りのものであって,これは,リン 酸塩を含む溶液に妥当するものではないなどとして,当業者は,引用発 明2−2−1’において,相違点(甲3−3−d”)に係る本件訂正発 明12の構成(マグネシウムイオン濃度を「1.0mEq/L」)とす\nることを容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら,前記(ア)のとおり,甲3に接した当業者においては, 甲3記載の実施例4(引用発明2−2−1’)において,マグネシウム イオン濃度を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整 することは,当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると,当業者は,引用発明2において,相違点(甲3−3−d”) に係る本件訂正発明12の構成とすることを容易に想到することができ\nたものと認められる。このことは,混合液の各成分の濃度の組合せをひ とまとまりの相違点と認定した場合であっても同様である。 したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 相違点(甲3−3−a”)について
(ア) 本件訂正発明12の特許請求の範囲(請求項12)の記載中には, 本件訂正発明12の「当該薬液調製後少なくとも27時間にわたって不 溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」との構成の意義を規定し\nた記載はない。 次に,本件明細書(甲11)には,「時間の経過と共に補充液中のカル シウムイオンおよびマグネシウムイオンと炭酸水素イオンが反応し,不 溶性の炭酸塩の微粒子や沈殿が生じる」こと(【0007】),「当該薬液 中には,カルシウムイオンやマグネシウムイオンが存在するにも拘わら ず,リン酸イオンを含有させても不溶性のリン酸塩を生じない。また, リン酸イオンの存在により,炭酸水素イオンとカルシウムイオンやマグ ネシウムイオンが共存し,pHが7.5を超えるような長時間後であっ ても,不溶性炭酸塩の生成が抑制される」こと(【0023】),「不溶性 微粒子や沈澱の生成が長時間にわたって抑制される」とは,投与対象に 適用すべき最終薬液の調製後,たとえば上記A液とB液の混合後,少な くとも27時間にわたり不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されること, またはpHが7.5以上になっても不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制さ れること」を意味すること(【0057】)の記載がある。 また,本件明細書には,本件訂正発明12に規定するオルトリン酸の 濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が4.0mg/dL」の薬液と 「リン酸イオンを含有しない薬液」との対比実験を行ったところ,「7日 間でpHが7.23〜7.29から7.89〜7.94までほぼ直線的 に上昇し,その間にリン酸イオン不含有薬液では不溶性微粒子の粒径も 数も顕著に増加したが,リン酸イオン含有薬液ではpHの上昇にもかか わらず,不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった。」(【008 8】)との記載があり,この記載は,本件訂正発明12に規定するオルト リン酸の濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が4.0mg/dL」 の薬液では,「7日間」にわたって「リン酸イオン含有薬液ではpHの上 昇にもかかわらず,不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった」 ことを示すものである。もっとも,本件明細書には,本件訂正発明12 の「用時混合型血液浄化用薬液」が「27時間」にわたって不溶性微粒 子や沈殿の形成が実質的に抑制されたことを明示した記載はない。 以上の本件訂正発明12の特許請求の範囲(請求項12)の記載及び 本件明細書の記載を総合すると,本件訂正発明12の「そして当該薬液 調製後少なくとも27時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質 的に抑制され」との構成は,本件訂正発明12のA液及びB液の成分組\n成及びそれらのイオン濃度を請求項12に記載されたものに特定するこ とによって実現されるものと理解できる。
(イ) そして,前記ア及びイのとおり,甲3に接した当業者は,引用発明 2−2−1’において,「血液浄化用薬液」として使用すること(相違点 (甲3−3−b”)に係る本件訂正発明12の構成)及びマグネシウムイ\nオン濃度を本件訂正発明12の濃度とすること(相違点(甲3−3−d”) に係る本件訂正発明12の構成)を容易に想到することができたもので\nある。 加えて,引用発明2−2−1’のカリウムイオン濃度と本件訂正発明 12のカリウムイオン濃度は「4.0mM」(4.0mEq/L),引用 発明2−2−1’の炭酸水素イオン濃度と本件訂正発明12の炭酸水素 イオン濃度は「30.0mEq/L」であって,いずれも一致する。 以上によれば,本件訂正発明12の「少なくとも27時間にわたって 不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は,引用\n発明2−2−1’において,相違点(甲3−3−b”)及び(甲3−3− d”)に係る本件訂正発明12の構成とした場合に,自ずと備えるものと\n認められる。 したがって,引用発明2−2−1’において,相違点(甲3−3−a”) に係る本件訂正発明12の構成とすることは,当業者が容易に想到する\nことができたものと認められる。 したがって,これと異なる本件審決の判断は,誤りである。
(ウ) これに対し被告らは,引用発明2−2−1’は,「所定のリン酸塩 の濃度に対し,粒子の形成が24時間内抑制される,混合時の即時使用 溶液のpHの範囲を特定した発明」にすぎず,24時間を超える長時間 の経過によるpHの上昇は,全く想定されていないこと,粒子の形成が 24時間抑制されれば,pHの上昇にかかわらず,少なくとも27時間 にわたって,不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されるとする技術常識は ないことからすると,引用発明2−2−1’には,同発明から,混合後 長時間が経過してpHが上昇しても,不溶性微粒子や沈澱の生成を抑制 することができる血液浄化用薬液を想到する基礎がないから,相違点(甲 3−3−a”)に係る本件訂正発明12の構成は,引用発明2−2−1’\nに基づいて容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら,前記(ア)及び(イ)で説示したとおり,引用発明2−2− 1’において,相違点(甲3−3−a”)に係る本件訂正発明12の構成\nとすることは容易に想到することができたものと認められるから,被告 らの上記主張は採用することができない。
(4) 本件訂正発明12の顕著な効果について
被告らは,(1)本件訂正発明12は,「混合後長時間が経過してpHが上昇し ても,不溶性微粒子や沈殿の生成が抑制することができる用時混合型急性血 液浄化用薬液」を実現した発明であるのに対し,引用発明2−2−1’は, 「所定のリン酸塩の濃度に対し,粒子の形成が24時間内抑制される,混合 時の即時使用溶液のpHの範囲を特定した発明」にすぎず,また,用時混合 型急性血液浄化用薬液の技術分野では,本件優先日当時,所定の配合により, 混合後長時間が経過してpHが上昇しても,不溶性微粒子や沈殿の生成を抑 制することができる旨の技術常識はなかったことからすると,本件明細書の 【0088】に係る「混合後長時間が経過してpHが上昇しても,不溶性微 粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件訂正発明12の効果 は,引用発明2−2−1’に比して,質的に差のある当業者が予測できない\n格別の効果である,(2)被告らが,本件明細書記載の実施例2の検体と甲3記 載の実施例4(表9)の検体について行った不溶性微粒子の形成の対比試験\nの結果(甲20の参考資料3)によると,両検体のpHは,混合後,同様の 上昇推移を経て,54時間経過後に約8.7まで上昇したところ,本件明細 書記載の実施例2の検体では,10μmの微粒子が,混合後27時間経過時 に8個,54時間経過時に12個形成されるにとどまり,25μmの微粒子 が,混合後54時間経過時でも1個形成されるにとどまったのに対し,甲3 の実施例4(表9)の検体では,10μmの微粒子が,混合後27時間経過\n時に17個,54時間経過時に78個も形成され,25μmの微粒子が,混 合後54時間経過時には5個も形成されていたことからすると,「混合後長時 間が経過してpHが上昇しても,不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制すること ができる」という本件訂正発明12の効果は,甲3の記載から予測できない\n格別の効果であるのみならず,引用発明2−2−1’の配合や各成分の濃度 では実現することができない,当業者の予測を超えた顕著な効果である旨主\n張する。
そこで検討するに,被告らが主張する「混合後長時間が経過してpHが上 昇しても,不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件 訂正発明12の効果は,「当該薬液調整後少なくとも27時間にわたってpH 7.5以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」ること(【0 057】)に相当する効果であるものと認められる。一方で,本件明細書には, 本件訂正発明12の成分組成及びイオン濃度を有する用時混合型急性血液浄 化用薬液において,「混合後27時間経過時」及び「54時間経過時」のpH の推移,微粒子の形成状況について明示した記載はないから,上記対比試験 の結果(甲20の参考資料3)に基づく効果は,本件明細書に記載された本 件訂正発明12の効果であるとは認められない。 そして,上記「当該薬液調整後少なくとも27時間にわたってpH7.5 以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」るという効果は, 前記(3)ウで説示したところと同様に,引用発明2−2−1’において,相違 点(甲3−3−b”)及び(甲3−3−d”)に係る構成とした場合に,自ず\nと備えるものと認められるから,当業者の予測を超えた顕著な効果であると\nいうことはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2020.03. 6
令和1(行ケ)10103 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月26日 知的財産高等裁判所
前記(1)アで認定したとおり,甲3文献は,PHC杭のフーチングへの埋 込み長さと接合部の補強方法が異なる場合における杭頭固定度,接合方法及び終局 耐力を把握することを主目的として,5種類の試験体((1)杭をフーチング内へ単に 埋込む方式で,埋込み長さを10cmとした試験体,(2)杭をフーチング内へ単に埋 込む方式で,埋込み長さを35cmとした試験体,(3)フーチング内で立ち上げ筋と スパイラルフープ筋により補強し,埋込み長さを20cmとした試験体,(4)内径3 5.4cm,長さ35cm,厚さ0.6cmの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によっ て杭体と一体化し,定着長35cmのアンカー鉄筋(D10−8本)を鋼管に溶接 して接合部を補強し,埋込み長さを10cmとした試験体,(5)内径35.4cm, 長さ35cm,厚さ0.6cmの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によって杭体と一体 化し,定着長35cmのアンカー鉄筋(D10−8本)を鋼管に溶接して接合部を 補強し,埋込み長さを20cmとした試験体)について曲げせん断試験実験を行っ たこと,及び同実験の条件を開示したものであるから,甲3文献は,PHC杭を用 いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構\造における杭頭固定度及び終局 耐力を把握する実験であると認められる。そして,甲3発明は,PHC杭を用いた 剛接合構造による支持構\造であることを前提とした上記の実験において,杭をフー チング内へ単に埋込む方式で,埋込み長さを10cmとした試験体について,フー チングのコンクリートの圧縮強度を228kg/cm2,杭体のコンクリートの圧 縮強度を895kg/cm2とするとの条件を設定したものである。 したがって,PHC杭を用いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構\造 における杭頭固定度及び終局耐力を把握する実験において,PHC杭を用いた剛接 合構造によるコンクリート造基礎の支持構\造という実験の前提自体を変更すること の動機付けはないというべきである。
イ 前記2(3)ウ(キ)のとおり,剛接合構造と半剛接合構\造とでは,杭の移動 に対する拘束の有無,杭頭部に生じる曲げモーメントの大きさが異なるなどの点で 差異がある。 また,甲37には,「充填コンクリートは,鋼管の拘束度に応じてその圧縮強度が 著しく増大し,プレーンコンクリートの約6〜10倍になる」との記載があること からすると,PHC杭と場所打ちコンクリート杭とでは,求められるコンクリート の強度も異なるというべきである。 このように,剛接合構造と半剛接合構\造とでは,杭頭部に生じる曲げモーメント の大きさが異なる上に,PHC杭と場所打ちコンクリート杭とでは,求められるコ ンクリートの強度も異なるのであるから,甲3発明における杭体とフーチングの圧 縮強度の関係をそのままにして,甲3発明の実験の前提となるPHC杭を用いた剛 接合構造を場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合構\造に置換することを,当業 者が容易に想到するとは認められない。
ウ そして,上記ア,イで判示したところは,杭に基礎を「載置」する構成\nがありふれた構成であり,PHC杭と場所打ち杭は相互に代替的な構\成であり,甲 3文献に,「地震力に対する建築物の基礎の設計指針・・・が示され,実務に供され つつあるが,杭頭接合部の固定度・・・と接合方法および構造耐力の問題が,研究\n課題の一つとして残されている。」と記載されているとしても,左右されることはな い。
また,原告は,PHC杭と場所打ちコンクリート杭の相違が重要であるとすれば, 本件明細書には,鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭の相違を前提としても,な お同様の作用効果が生じることにつき説明がないから,当業者が,課題を解決する ものと理解できず,この点でもサポート要件違反となると主張するが,本件明細書 には,鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭のそれぞれについて本件発明の作用効 果を生じることが記載されており,サポート要件に違反するものではない。
エ したがって,甲3発明に,場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合に よるコンクリート造基礎の支持構造という技術を適用して,本件発明2の相違点ア\n〜ウに係る構成とすることを当業者が容易に想到すると認めることはできない。\nまた,本件発明3は,本件発明2の構成に「コンクリート造基礎と前記杭頭部と\nの間に芯鋼材を配筋したこと」を付加したものであるところ,甲3発明に基づき本 件発明2を容易に発明することができない以上,甲3発明に基づき本件発明3も容 易に発明することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.03. 6
平成31(行ケ)10059 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年2月26日 知的財産高等裁判所
ア(ア) 原告は,平成19年9月3日に設立された,衣料品及び服飾雑貨の 卸,小売販売,製造及び輸出入等を目的とする株式会社である。 (イ) ダンエンタープライズは,要証期間(平成24年4月23日から平 成27年4月22日までの間)において,本件商標権の商標権者であっ た。
(ウ) ジーティーオーは,ダンエンタープライズの有する商標権(本件商 標権を含む。)の使用許諾の窓口として,ダンエンタープライズから購 入した使用許諾を証明する「証紙」を使用許諾先に販売する業務を行っ ていた。一方,ダンエンタープライズは,ジーティーオーから,「商品 化申請管理表\」及び「証紙申請書」の提出を受けて,商標を付する予\定 の商品を確認して,商標の使用を承認した上で,商品化権使用料名義で 商標の使用料を受け取り,「証紙」をジーティーオーに引き渡していた。 イ(ア) 原告は,平成25年9月3日及び4日,ジーティーオーに対し,原 告が商品化を企画している「COCO」の欧文字を付した4種類のトー トバッグの商品(「COC−COB01」,「COC−COB02」, 「COC−CV01」,「COC−CV02」)のデザイン及び12種 類のカラーのデータ画像を添付したメール(甲89の1,2,90の1, 2,134の1,2,135の1,2)を送信し,本件商標の使用許諾 を求める旨の申請をした。\nその後,原告とダンエンタープライズは,同月30日,期間同年10 月1日から3年間,指定商品第14類,第18類,第25類及び第26 類「身飾品他か」,使用許諾地域日本国内の約定で,ダンエンタープラ イズが原告に対し,本件商標権の使用権を独占的に許諾し,原告が本件 商標を付した「かばん・小物類」の商品を製造及び販売することを許諾 する旨の本件使用許諾契約(甲24)を締結した。
(イ) 原告は,平成25年10月29日,韓国のミラクル社(甲124の 2,3)に対し,「2013.10」,「COC−BGT01」,「C OC−CV01」,「COC−BGT02」,「COC−CV02」と の表示の下に,「COCO」の欧文字が付されたトートバッグのデザイ\nン及び寸法等を記載した画像データ(甲91の2,3,136の1,2) を添付した,「COCOバッグサンプル作成のお願いになります。」, 「指示書添付致します。」,「大,中2サイズでWHITE(生成り) とBLACKで作成お願いします。」などと記載したメール(甲91の 1)を送信した。
(ウ) 原告は,平成25年12月4日,ミラクル社に対し,「Re:商品 発注になります:COCOバッグ発注」との件名で,「商品発注の件」 と題する書面2通(甲93の2,3,137の1,2)を添付した,「発 注書2件添付しております。」,「COC−BGT」,「COC−CV」, 「納期が確定しましたら教えて下さい。」などと記載したメール(甲9 3の1)を送信した。上記添付書面中には,「(COC−BGTビッグ トート)1st」として品番「COC−BGT01」のカラー5色を3 500枚,品番「COC−BGT02」のカラー5色を3500枚の合 計7000枚を単価US4.8ドルで発注(甲93の2,137の1) し,「(COC−CVキャンバストート)1st」として品番「COC −CV01」の5色を2500枚,「COC−CV02」の5色を25 00枚の合計5000枚を単価US4.0ドルで発注(甲93の3,1 37の2)する旨の記載がある。
(エ) 原告は,平成25年12月27日,ミラクル社に対し,「付属指示: COCOビッグトート修正」との件名で,(1)作成日「2012.12. 25」,品番「COC−BGT01,02/COC−CV01,02」, ブランド「COCO」と記載した「付属仕様書」(甲116の2,13 9の1),(2)「2013.12.25」,「COC−BGT02」,「C OC−CV02」,「COC−BGT01」,「COC−CV01」と の表示の下に,「COCO」の欧文字が付されたトートバッグのデザイ\nン等を記載した画像データ(甲116の3,4,139の2,3)を添 付した,「COCO付属の指示になります。」,「混率修正致しました。」 などの記載のあるメール(甲116の1)を送信した。上記「付属仕様 書」には,「COCO」の欧文字,品番,素材等を記載したステッカー の仕様が記載されていた。
(オ) ジーティーオ―は,原告の依頼を受けて,平成26年1月17日付\nけの証紙申請書(甲3)を作成し,ダンエンタープライズに対し提出し\nた。上記申請書には,「株式会社ダンエンタープライズの許諾により「C\nOCO」の商品化権を下記掲載の商品に使用致しますので証紙の発行を 依頼いたします。」との記載に続き,以下の記載がある。
「商品名 承認NO. 製造数量
COCOトートバック(中) 44516 1900
COCOトートバック(中) 42832 1900
COCOトートバック(大) 44515 1900
COCOトートバック(大) 42831 1900
COCOエコバッグ 43015 15000
(合計) 22600」
(カ) ジーティーオ―は,平成26年1月20日,ダンエンタープライズ\nから,甲3の証紙申請に係る証紙合計2万2600枚の納品(甲4)を\n受け,そのころ,原告に対し,上記証紙を引き渡した。
ウ(ア) 原告は,平成26年3月25日,日本PMSに対し,「※再送です 【COCO 商品のご案内】【E−COME】」との件名で,「Coc oバッグ BIGトートNo.1」のファイル名及び「Cocoバッグ キャンバストートNo.1」のファイル名のPDFデータ(甲127の 2)等を添付した,「再送致します。現状では,圧倒的にトート・ミニ トートの方が予約段階での付きは良い状況です。」,「早速ではござい\nますが【COCO絵型】を添付しております。何卒よろしくお願い致し ます。」などと記載したメール(甲127の1)を送信した。 「Cocoバッグ BIGトートNo.1」のファイル名のPDFデ ータ(甲127の2の1枚目)には,「Coco ビッグトートNo. 1」,「Coco ビッグトートNo.2」との表題の下に表\が記載さ れ,表の枠内には,「STYLENO」欄に「COC−BGT01」,\n「COC−BGT02」,「納期」欄に「4月上旬頃〜随時発送予定 下 代@990−」とする「COCO」の欧文字が表示されたそれぞれカラ\nー5色のトートバッグの写真が掲載され,表の枠外にはトートバッグを\n持った女性の写真とともに,「商標:COCO 商標登録番号:第14 93277号」,「この商品は,(株)イーカムが(株)ダンエンター プライズの所有する,商標:COCOの使用,販売許諾を独占契約した 正規国内ライセンス商品です。」との表示があった。\nまた,「Cocoバッグ キャンバストートNo.1」のファイル名 のPDFデータ(甲127の2の2枚目)には,「Coco キャンバ ストートNo.1」,「Coco キャンバストートNo.2」との表\n題の下に表が記載され,表\の枠内には,「STYLENO」欄に「CO C−CV01」,「COC−CV02」,「納期」欄に「4月上旬頃〜 随時発送予定 下代@930−」とする「COCO」の欧文字が表示さ\nれたそれぞれカラー5色のトートバッグの写真が掲載され,表の枠外に\nはトートバッグを持った女性の写真とともに,「商標:COCO 商標 登録番号:第1493277号」,「この商品は,(株)イーカムが(株) ダンエンタープライズの所有する,商標:COCOの使用,販売許諾を 独占契約した正規国内ライセンス商品です。」との表示があった。\n
(イ) 原告は,平成26年4月23日,埼京三喜に対し,「【COCO絵 型】【イーカム】」との件名で,「Cocoバッグ BIGトートNo. 1」のファイル名及び「Cocoバッグ キャンバストートNo.1」 のファイル名のPDFデータ(甲128の2)等を添付した,「早速で はございますが【COCO絵型】を添付しております。」,「こちらの 商品の中の,トート2アイテムに関しましては5月GW明け納期商品と なっております。」などと記載したメール(甲128の1)を送信した。 「Cocoバッグ BIGトートNo.1」のファイル名のPDFデ ータ(甲128の2の1枚目)には,「Coco ビッグトートNo. 1」,「Coco ビッグトートNo.2」との表題の下に表\が記載さ れ,表の枠内には,「STYLENO」欄に「COC−BGT01」,\n「COC−BGT02」,「納期」欄に「5月中旬頃〜随時発送予定 下 代@1134−」とする「COCO」の欧文字が表示されたそれぞれカ\nラー5色のトートバッグの写真が掲載され,表の枠外にはトートバッグ\nを持った女性の写真とともに,「商標:COCO 商標登録番号:第1 493277号」,「この商品は,(株)イーカムが(株)ダンエンタ ープライズの所有する,商標:COCOの使用,販売許諾を独占契約し た正規国内ライセンス商品です。販売許諾地域:日本国内限定 商品可 能化アイテム:かばん,小物類」との表\示があった。 また,「Cocoバッグ キャンバストートNo.1」のファイル名 のPDFデータ(甲128の2の2枚目)には,「Coco キャンバ ストートNo.1」,「Coco キャンバストートNo.2」との表\n題の下に表が記載され,表\の枠内には,「STYLENO」欄に「CO C−CV01」,「COC−CV02」,「納期」欄に「5月中旬頃〜 随時発送予定 下代@1026」とする「COCO」の欧文字が表示さ\nれたそれぞれカラー5色のトートバッグの写真が掲載され,表の枠外に\nはトートバッグを持った女性の写真とともに,「商標:COCO 商標 登録番号:第1493277号」,「この商品は,(株)イーカムが(株) ダンエンタープライズの所有する,商標:COCOの使用,販売許諾を 独占契約した正規国内ライセンス商品です。販売許諾地域:日本国内限 定 商品可能化アイテム:かばん,小物類」との表\示があった。
エ ミラクル社は,(1)「荷送人/輸出者」欄にミラクル社,「買い手名」欄 に原告,「積荷港」欄に「中国,上海」,「最終仕向港」欄に「日本,博 多」,「出港予定日」欄に「2014年4月19日」,「インボイスNo. 作成日」欄に「MC140417 2014年4月17日」,「L/C No.日付」欄に「L/C:211−612−14457」,「品名の詳細」 欄に「鞄 COC−BGT01 424枚 USD2,035.20」, 「鞄 COC−BGT02 390枚 USD1,872.00」,「鞄 COC−CV01 131枚 USD524.00」,「鞄 COC−C V02 195枚 USD780.00」などと記載された「コマーシャ ルインボイス」(甲130の2,4),(2)「パッキングリスト詳細」欄に 「COC−BGT01」,「COC−BGT02」,「COC−CV01」, 「COC−CV02」の「カラー」が「ホワイト」である旨の記載のある 「パッキングリスト」(甲130の2,4)を発行した。 原告は,平成26年4月28日,輸入者を原告,ミラクル社を輸入取引 者,積出地を上海,船卸港を博多,仕入書番号を「MC140417」と する貨物の輸入について,博多税関支署長から,輸入許可(甲130の1, 3)を受けた。 原告は,同日,乙仲業者のSGHグローバルジャパン株式会社(以下「S GH社」という。)に対し,輸入関税,費用等(甲130の1)を支払い, 上記貨物の引渡しを受けた。
オ 原告は,平成26年10月14日,ユニーから,「ディズニー,COC O,スクールの発注明細を添付します。確認をお願いします。本日,伝票 発行しました。」,「10/19までに納品をお願いします。」などと記 載したメール(甲107の1)を受信した。上記メールの添付ファイル(甲 107の2)には「COCOキャンバストート COC−CV01 各色 20」,「COCOキャンバストート COC−CV02 各色20」と の記載があった。 原告は,同月15日,ユニーに対し,上記発注の内容を確認し,商品確 保が完了した旨のメール(甲108)を送信し,同月18日,ユニーに対 し,「COCOキャンバストート COC−CV01 各色」及び「CO COキャンバストート COC−CV02 各色」を納品(甲110の1 ないし20,111の1ないし20)した。
(2) これに対し被告は,前記(1)掲記の証拠に関し,(1)甲91の1ないし93, 107の1,2,110の1ないし20,111の1ないし20,112, 127の1,2,128の1,2等は,原告が所持し,その提出も極めて容 易であったにもかかわらず,4年の審理がされた本件審判の段階では提出さ れずに,本件訴訟に至って初めて提出されたのは極めて不自然であるから, そもそも信用することができない,(2)甲91の1,116の1,117の1, 127の1,128の1の各メール等に添付されていたファイルであるとし て,当該メールと合わせて提出された書面(甲91の2,3,116の2な いし4,117の2,127の2,128の2等)について,実際に当該メ ールに添付されたファイルの中身と同一のものであることについての立証が ない,(3)原告提出のUSBメモリ(甲148)に保存されたメールデータに ついては,メールの作成日について,インターネットヘッダーの「Received from」の表示時刻は容易に変更可能\であり,当該変更を反映する形で,メー ル自体の送受信日時も同様に変更されることになるから,上記メールデータ によっても,各メールが表示されたとおりの日時に送受信されたとは限らな\nい,(4)甲148に保存された甲127の1,128の1のメールデータのイ ンターネットヘッダーには「Received from」の項目が存在しておらず,この ことは,当該メールが実際に送信された形跡が存在しないことを意味するな どと主張する。
しかしながら,上記(1)の点については,本件審判の経過及び本件訴訟の審 理経過に照らすと,原告は,本件審決を踏まえて,本件訴訟において,本件 審判段階では主張していなかった本件商標の使用の事実を新たに主張し又は 主張を補充し,新たな証拠を提出したものと認められ,被告主張の上記甲各 号が本件審判段階で提出されていなかったことから直ちにその信用性がない ということはできない。 次に,上記(2)の点については,甲89ないし91,93,107,116, 117,120ないし122,124,126ないし128,132(いず れも枝番を含む。)の各メールのメールデータを保存したUSBメモリ(甲 148)によれば,印刷された各メールの本文(甲89ないし91,93, 107,116,117,120ないし122,124,126ないし12 8,132の各1)にそれぞれの添付ファイルを印刷した書面(甲89の2, 3,90の2,3,91の2,3,93の2,3,107の2,116の2 ないし4,117の2,120の2,121の2,122の2,124の2, 3,126の2ないし5,127の2,128の2,132の2)が添付さ れていた事実を確認することができるから,上記(2)の点は理由がない。 さらに,上記(3)の点については,アプリケーションを用いて電子メールデ ータ自体を編集することで,各メールの送受信日時を変更することが可能で\nあるとしても(乙37,38),甲148から,上記のとおり各メールに記 載された添付ファイルが添付されていることを確認することができ,これら のメールが送受信されたことが認められることに照らすと,原告において各 メールの送受信日時のみの変更を行ったものと認めることは困難である。 また,上記(4)の点については,「Received from」の項目は,メールを受信 した際の項目であるから,原告が送信した甲127の1,128の1のメー ルに上記項目が存在しないことは何ら不自然なことではない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 他に前記(1)の認定を左右するに足りる証拠はない。
2 原告による本件4商品の輸入及び販売の事実の有無等について
(1)ア 前記1の認定事実を総合すれば,(1)原告は,平成25年9月30日,ダ ンエンタープライズとの間で,期間同年10月1日から3年間,使用許諾 地域日本国内の約定で,ダンエンタープライズが原告に対し,ダンエンタ ープライズが有する本件商標権の使用権を独占的に許諾し,原告が本件商 標を付した「かばん・小物類」の商品を製造及び販売することを許諾する 旨の本件使用許諾契約(甲24)を締結した後,同月29日,韓国のミラ クル社に対し,「COC−BGT01」,「COC−BGT02」,「C OC−CV01」,「COC−CV02」との表示の下に,「COCO」\nの欧文字が付されたトートバッグのデザイン及び寸法等を記載した画像デ ータ添付したメール(甲91の1ないし3)で,「COCOバッグ」のサ ンプル品の作成を依頼したこと,(2)原告は,同年12月4日,ミラクル社 に対し,品番「COC−BGT01」のカラー5色を3500枚,品番「C OC−BGT02」のカラー5色を3500枚,品番「COC−CV01」 のカラー5色を2500枚,「COC−CV02」のカラー5色を250 0枚の合計1万2000枚のトートバッグ(「COCOバッグ」)をメー ル(甲93の1ないし3)で発注し,同月27日,ミラクル社に対し,「付 属仕様書」と「COCO」の欧文字が付されたトートバッグのデザイン等 を記載した画像データを添付したメール(甲116の1ないし4)で,品 番「COC−BGT01」,「COC−BGT02」,「COC−CV0 1」及び「COC−CV02」の仕様,デザイン等について指示をしたこ と,(3)原告は,平成26年3月25日,日本PMSに対し,「Cocoバ ッグ BIGトートNo.1」のファイル名及び「Cocoバッグ キャ ンバストートNo.1」のファイル名のPDFデータを添付したメール(甲 127の1,2)で,品番「COC−BGT01」,「COC−BGT0 2」,「COC−CV01」及び「COC−CV02」のトートバッグの 商品の案内をし,また,原告は,同年4月23日,埼京三喜に対し,「C ocoバッグ BIGトートNo.1」のファイル名及び「Cocoバッ グ キャンバストートNo.1」のファイル名のPDFデータを添付した メール(甲128の1,2)で品番「COC−BGT01」,「COC− BGT02」,「COC−CV01」及び「COC−CV02」のトート バッグの商品の案内をしたこと,(4)上記(3)の各PDFデータには,「CO CO」の欧文字がそれぞれ表示されたカラー5色のトートバッグの写真が\n掲載され,そのうちの一つには,別紙2の「COCO」の欧文字の標章が 付されていたこと,(5)ミラクル社は,「荷送人/輸出者」欄にミラクル社, 「買い手名」欄に原告,「積荷港」欄に「中国,上海」,「最終仕向港」 欄に「日本,博多」,「出港予定日」欄に「2014年4月19日」,「イ\nンボイスNo.作成日」欄に「MC140417 2014年4月17日」, 「品名の詳細」欄に「鞄 COC−BGT01 424枚 USD2,0 35.20」,「鞄 COC−BGT02 390枚 USD1,872. 00」,「鞄 COC−CV01 131枚 USD524.00」,「鞄 COC−CV02 195枚 USD780.00」などと記載された「コ マーシャルインボイス」(甲130の2,4)及び「COC−BGT01」, 「COC−BGT02」,「COC−CV01」,「COC−CV02」 の「カラー」が「ホワイト」である旨の記載のある「パッキングリスト」 (甲130の2,4)を発行した後,原告は,平成26年4月28日,輸 入者を原告,ミラクル社を輸入取引者,積出地を上海,船卸港を博多,仕 入書番号を「MC140417」とする貨物の輸入について,博多税関支 署長から,輸入許可を受け,同日,上記貨物の引渡しを受けたこと,(6)原 告が輸入許可を受けた品番「COC−BGT01」,「COC−BGT0 2」,「COC−CV01」及び「COC−CV02」の「ホワイト」の 「鞄」は,上記(3)の各PDFデータに掲載された「COCO」の欧文字を 付した白色のトートバッグの画像の商品と同一の商品であることが認めら れる。 以上によれば,原告は,平成26年4月28日,ミラクル社から,「C OCO」の欧文字からなる標章(別紙2)を付したトートバッグである本 件4商品(品番「COC−BGT01」,「COC−BGT02」,「C OC−CV01」及び「COC−CV02」)を輸入したことが認められ る。
イ これに対し被告は,(1)「ミラクルチームコーポレーション(英語表記:\nMIRACLE. TEAM CORPORATION)」なる会社は,イン ターネット上で検索しても関連する情報を確認することができず(乙10, 11),ミラクル社が発行する輸入関係資料に同社の住所として表示され\nた住所(「(省略)」)も実在しないこと(乙12),原告は,「Whi te(生成り)」及び「Black」の2色のサンプル品を受領しただけ で,その直後に同サンプル品とは全く色合いの異なる商品6000枚を含 む合計1万2000枚の本件4商品をミラクル社に発注する取引を行った というのは経営判断として明らかに合理性を欠いていることからすると, そもそもミラクル社の存在自体が疑わしく,原告がミラクル社を通じて中 国の工場において本件4商品を製造した事実は存在しないから,原告が本 件4商品をミラクル社から輸入した事実も存在しない,(2)原告がミラクル 社から輸入したとする「COMMERCIAL INVOICE」(イン ボイス)及び「PACKING LIST」(梱包明細書)記載の「CO C−BGT01」,「COC−BGT02」,「COC−CV01」及び 「COC−CV02」の商品が「COCO」の欧文字からなる標章(本件 使用商標)を付した本件4商品を指すことを示す証拠はなく,一方で,原 告が「COCO」ないし「ココ」との名称のキャラクター等を用いた「キ ャンバストート」等を取り扱っていた可能性も十\分にあり,このような商 品について,「COC−BGT01」,「COC−BGT02」,「CO C−CV01」及び「COC−CV02」との品番が付けられていたとし ても何ら不思議ではないなどとして,原告がミラクル社から本件使用商標 を付した本件4商品を輸入した事実は存在しない旨主張する。 しかしながら,上記(1)の点については,原告は,平成26年4月28日, 輸入者を原告,ミラクル社を輸入取引者,積出地を上海,船卸港を博多, 仕入書番号を「MC140417」とする貨物の輸入について,博多税関 支署長から,輸入許可を受け,同日,上記貨物の引渡しを受けたこと(前 記1(1)エ),上記輸入許可に係る輸入許可通知書(甲130の3)記載の ミラクル社の「住所」は,韓国の税務署長作成の2013年4月25日付 け事業者登録証(甲124の2,3)記載のミラクル社の「事業場所所在 地」と一致することに照らすと,ミラクル社は実在する事業者であるもの と認められ,被告が主張するようにインターネット上の検索サイトで「M IRACLE.TEAM CORPORATION」を検索してもミラク ル社の情報が表示されず,ミラクル社が発行する輸入関係資料に同社の住\n所として表示された住所が表\示されなかったとしても,そのことから直ち にミラクル社が存在(実在)しないということはできないし,ひいては原 告が本件4商品をミラクル社から輸入した事実も存在しないということは できない。また,原告が「White(生成り)」及び「Black」の 2色のサンプル品を確認しただけで,他の色の商品を含む本件4商品の発 注を行ったことが特段不合理であるということはできない。
次に,上記(2)の点については,前記ア認定のとおり,原告が輸入した品 番「COC−BGT01」,「COC−BGT02」,「COC−CV0 1」及び「COC−CV02」の「ホワイト」の「鞄」は,甲127の2, 128の2の各PDFデータに掲載された「COCO」の欧文字を付した 白色のトートバッグの画像の商品と同一の商品であることが認められる。 また,原告が上記輸入の当時,上記画像の商品とは異なる他の商品につい て,「COC−BGT01」,「COC−BGT02」,「COC−CV 01」及び「COC−CV02」の品番を付していたことを認めるに足り る証拠はない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
(2)ア 次に,前記1の認定事実及び前記(1)アの認定事実を総合すれば,(1)原 告は,平成26年10月14日,ユニーに対し,「COC−CV01」及 び「COC−CV02」の商品を販売し,同月18日,これを納品したこ と,(2)上記「COC−CV01」及び「COC−CV02」の商品は,甲 127の2,128の2のPDFデータに掲載された「COCO」の欧文 字を付した各トートバッグの画像の商品と同一の商品であることが認めら れる。 上記認定事実によれば,原告は,平成26年10月14日,ユニーに対 し,「COCO」の欧文字からなる標章(別紙2)を付した「COC−C V01」及び「COC−CV02」の商品を販売したことが認められる。
イ これに対し被告は,(1)原告がユニーに納品した品番「COC−CV01」 及び「COC−CV02」の商品にどのような商標が付されていたかは不 明である,(2)原告のユニーあての請求書は,伝票番号や明細事項が物品受 領書及び納品書(控)と一致しない上,上記請求書記載の請求額及び支払 明細書の合計金額がいずれも異なることからすると,ユニーがそのような 取引をしたとは考えられない,(3)原告ホームページの平成27年(201 5年)9月7日時点の「ブランド紹介」ページ(乙18)及び同月8日時 点での「お知らせ」ページ(乙19)には,本件商標に係るブランドの掲 載はないことに照らすと,要証期間において,原告が本件商標に係るブラ ンドを展開していなかったことが強く推認されるなどとして,原告がユニ ーに対し本件使用商標を付した「COC−CV01」及び「COC−CV 02」を販売した事実は存在しない旨主張する。 しかしながら,上記(1)の点については,前記ア認定のとおり,原告が平 成26年10月18日にユニーに納品した「COC−CV01」及び「C OC−CV02」の商品は,甲127の2,128の2のPDFデータに 掲載された「COCO」の欧文字を付した各トートバッグの画像の商品と 同一の商品であることが認められる。 また,被告主張の上記(2)及び(3)の事情があったとしても,上記認定を左 右するものではない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
(3) 前記(1)及び(2)の認定事実によれば,原告は,平成26年4月28日,ミ ラクル社から,「COCO」の欧文字からなる標章(別紙2)を付したトー トバッグである本件4商品(品番「COC−BGT01」,「COC−BG T02」,「COC−CV01」及び「COC−CV02」)を輸入したこ と,原告は,同年10月14日,ユニーに対し,本件4商品のうち,「CO C−CV01」及び「COC−CV02」の商品を販売したことが認められ る。 そして,原告による「COCO」の欧文字からなる標章(別紙2)を付し た本件4商品の輸入及び本件4商品のうちの「COC−CV01」及び「C OC−CV02」の商品の販売は,商標法2条3項1号の「商品に標章を付 したもの」の輸入及び譲渡に該当するものと認められる。 また,本件4商品に付された「COCO」の欧文字からなる標章(別紙2 参照)は,「COCO」の欧文字から構成され,本件商標(別紙1)とは書\n体が異なるが,本件商標と社会通念上同一の商標であることが認められる。 そうすると,原告は,本件商標の通常使用権者であった原告が,要証期間 内に,日本国内において,本件審判請求に係る指定商品である第18類「か ばん」を輸入及び販売することによって,本件商標と社会通念上同一の商標 の使用をしていることを証明したものと認められる。 したがって,原告主張の取消事由は理由がある。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2020.03. 5
令和1(行ケ)10105 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年1月29日 知的財産高等裁判所
原告は,被告及び被告と密接な関連性を有するサクラグループは,原告及び その取引先の業務を妨害し,本件商標の商標権を譲渡することにより不正の利 益を得る目的で,本件商標の登録出願をしたものであり,本件商標の出願経緯 等には,適正な商道徳に反し,社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠く 事情があるから,本件商標は,商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風 俗を害するおそれがある商標」に該当する旨主張するので,以下において判断 する。
(1) 業務妨害等の目的について
原告は,被告又はサクラグループは,原告がした繊研新聞の記事に係るハ ワード社に対する抗議行為に対する報復措置の一環として,原告のロゴとほ ぼ同一のロゴをあえて使用して,原告及びその取引先の業務を妨害するとと もに,原告のブランドにフリーライドするという不正の目的で,本件商標の 登録出願をしたものといえる,原告の上記抗議行為は正当なものであり,被 告らから報復措置を受けるいわれがないにもかかわらず,被告らが本件商標 を利用して,業務妨害行為及びフリーライド行為を行ったから,その不当性 は強度である旨主張する。 そこで検討するに,前記1の認定事実によれば,(1)原告と被告は,199 7年(平成9年)から,被告が,高島USAを通じて,「Goodwear」 の商標を付したティーシャツ(原告商品)を輸入し,日本国内で販売すると いう取引関係にあったところ,被告が1999年(平成11年)に原告商品 に係る商標権について調査した結果,原告が日本において「Goodwea r」の商標の商標登録を有しておらず,一方で,ビーグッド社が「good wear」又は「Good Wear」の欧文字を含むビーグッド社商標の 商標権を有していることが判明したことを契機として,原告及び被告がそれ ぞれビーグッド社との間でビーグッド社商標の譲渡交渉を行うようになった 後,被告がビーグッド社からビーグッド社商標の商標権の譲渡を受け,平成 12年1月6日にその移転登録が経由された後,被告が被告の販売する商品 にビーグッド社商標を使用するようになり,原告と被告との取引関係が解消 されたこと,(2)原告は,ビーグッド社商標の譲渡交渉中の平成11年7月2 日,「GoodwearUSA」の欧文字からなる商標について商標登録出願 をし,平成14年3月28日付けで,当該商標が商標法3条1項3号に該当 することを理由に拒絶査定を受けた後,平成15年4月4日,別紙2の構成\nからなる金色で縁取りをした赤色の「Goodwear」の欧文字,図形等 を含む原告登録商標の商標登録を受けたが,原告商品に使用されていた「G oodwear」の欧文字からなる商標(甲3の1)については,商標登録 出願をしなかったこと,(3)被告の関連会社のサクラグループが本件商標の商 標登録出願をしたのは,原告と被告の上記取引関係の解消から約12年を経 過した後の平成24年3月12日であること,(4)サクラグループ及びそのラ イセンシー又は被告は,本件商標の商標登録後,本件商標のうち,「Goo dwear」の欧文字部分を黒色から赤色とした商標をティーシャツ等に使 用するようになったものであり,上記商標は本件商標と社会通念上同一の商 標であると認められることからすると,被告及びサクラグループは,サクラ グループによる本件商標の登録出願時,原告との関係で,「Goodwea r」の欧文字を含む商標の商標登録出願を差し控えるべき信義則上の義務等 を負っていたものとまで認めることはできないし,一方で,サクラグループ 及びそのライセンシー又は被告は,本件商標の商標登録後,本件商標と社会 通念上同一の商標を実際に使用しているのであるから,サクラグループによ る本件商標の商標登録出願が原告及びその取引先の業務を妨害する目的や原 告のブランドにフリーライドする目的をもって行ったものと認めることはで きない。
もっとも,前記1の認定事実によれば,平成22年11月18日付けの繊 研新聞において,サクラグループの取引先のハワード社が米国のカジュアル ブランド「グッドウェア」のライセンス製造販売を始める旨の記事が掲載さ れたことについて,原告は,上記記事中の「米国のカジュアルブランド「グ ッドウェア」」は原告を意味するが,原告とハワード社とは取引も取引交渉 もなかったため,上記記事に誤りがあると考え,繊研新聞社に対して上記記 事の訂正を求めるとともに,原告の代理人弁護士を通じて,ハワード社に対 し,原告とサクラグループとの間には何らの契約関係もないことから,サク ラグループの商標権に基づくライセンスを受けても,原告商品との誤認,混 同を生ずるような商品の販売は許されない旨を通知したことに端を発し,被 告の代表取締役のAが原告代表\者に対して原告と被告との交渉が決裂した場 合には原告の代理人弁護士のハワード社への通知に対する「報復措置」を行 うこと及びその「報復措置」の具体例について言及したメールを送信した後, 被告が原告登録商標について商標法53条1項に基づく不正使用取消審判 (取消2011−300044号事件)及び同法51条1項に基づく不正使 用取消審判(取消2011−300162号事件)を請求するとともに,原 告の取引先に対し,原告登録商標を取り消す旨の審決が確定すれば,現在取 り扱っている商品の法的拠り所を喪失することになるなどと警告する旨の通 知をし,さらに,サクラグループは,赤色の「Goodwear」の欧文字 と「Massachusetts」の欧文字を含む商標,赤色の「Good wear」の欧文字と「Essex」の欧文字を含む商標及び本件商標の商 標登録出願をしたことが認められる。上記認定事実によれば,サクラグルー プによる本件商標の商標登録出願は,原告の代理人弁護士のハワード社への 通知に対する対抗措置の一環として行われた側面があるものと認められる。 しかしながら,上記(1)ないし(4)の事情に照らすと,このような側面がある からといって直ちにサクラグループによる本件商標の商標登録出願が原告及 びその取引先の業務の妨害や原告のブランドにフリーライドする目的をもっ て行ったものと認めることはできない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(2) 不正の利益を得る目的について
原告は,原告が平成28年12月に本件商標について別件無効審判を請求 した後,被告らは,平成29年1月,原告に対し,本件商標を含むグッドウ ェア関連商標を譲渡する意向がある旨を告げるとともに,もし譲渡交渉が成 功すれば,訴訟や刑事告訴などといった原告と被告らとの間の将来の紛争を 回避できるであろうなどと述べた上で,120万米ドルの譲渡対価を要求し たことは,被告らが,原告が他社による保有を望まない商標(本件商標を含 む。)をあえて選択して商標登録出願をし,商標登録を受けた上で,自己に 有利な交渉材料として本件商標等を利用し,120万米ドルもの極めて高額 な譲渡対価を要求したことを示すこと,本件商標の出願時に原告と被告らと の間では鋭い対立関係があった事情にも鑑みると,被告らは,不正の利益を 得る目的で,本件商標の登録出願をしたものであり,その不当性は強度であ る旨主張する。
そこで検討するに,前記1(4)イ及びウ認定のとおり,被告の代表取締役の\nAは,原告が平成28年12月5日に本件商標について別件無効審判を請求 した後の平成29年1月31日,原告代表者に対し,「私たちは再び衝突し\nそうです。こちらとしては今回でこの一連の紛争を終結させたいと真に望ん でいるので,いったん衝突に至れば,こちらは勝つためにありとあらゆる手 段(訴訟,刑事告訴等を含みます。)をとらざるを得ません。一方で,紛争 には辟易しています。最近,私は,条件が満たされるならばこちらの商標を 誰かに近々譲渡しようかと考えています。そちらはこの譲渡の件に興味をお 持ちではないでしょうか? うまくいけば,私たちは衝突の繰り返しを回避 することができます。…私たちは円満な解決を望んでおります。」などと記 載したメールを送信し,さらに,同年2月6日,原告代表者に対し,「現段\n階での私の考える解決に関してですが,過去のことについては話し合う必要 はありません。話し合うべきことは,譲渡額のみです。私たちの提示額は, 私たちの5年間の利益に基づいて算出された120万米ドルです。あなたの お考えを聞かせてください。」などと記載したメールを送信したことが認め られる。
上記認定事実によれば,被告は,原告に対し,被告又はサクラグループが 保有する本件商標を含む「Goodwear」の欧文字を含む商標の商標権 を120万米ドルで譲渡する旨の提案をしたことが認められるが,一方で, (1)Aの上記各メールの文面によれば,120万米ドルの譲渡対価はあくまで も被告側の希望額の提示であるにすぎないこと,(2)本件においては,Aが上 記提案をした後,原告に対し,本件商標を含む「Goodwear」の欧文 字を含む商標の買取りを求める更なる要求をしたことをうかがわせる証拠は ないこと,(3)サクラグループ及びそのライセンシー又は被告は,本件商標の 商標登録後,本件商標と社会通念上同一の商標を実際に使用していること(前 記1(4)ア)に照らすと,Aが原告に対し上記提案をしたことから直ちにサク ラグループによる本件商標の商標登録出願が不正の利益を得る目的をもって 行ったものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり,被告及びサクラグループは,原告及びその取引先の業務を 妨害し,本件商標の商標権を譲渡することにより不正の利益を得る目的で, 本件商標の登録出願をしたものと認めることはできないから,本件商標の出 願経緯等に,適正な商道徳に反し,社会通念に照らして著しく社会的相当性 を欠く事情があるとの原告の前記主張は,その前提を欠くものである。 したがって,本件商標は商標法4条1項7号に該当するものと認めること はできないから,これと同旨の本件審決の判断はその結論において誤りはな く,原告主張の取消事由1は理由がない。
3 取消事由2(理由不備の違法)について
(1) 原告は,本件審決は,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その 他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くもの があったものと認めることはできないとの結論を示すにとどまり,本件商標 の出願経緯等や出願目的に関する事実認定,法律を事実に適用した判断過程 を示しておらず,重要な争点について実質的な理由を欠いているから,本件 審決には,理由不備(商標法56条,特許法157条2項)の違法がある旨 主張する。
そこで検討するに,本件審決の審決書によれば,本件審決は,(1)原告提出 の全証拠によっても,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他 不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものが あったものと認めることはできないし,本件商標の登録後,被告が原告に対 して,何らの実質的損害がないにもかかわらず不当な要求をする警告書等を 送付したというような事実も見いだせず,原告主張のビーグッド社とのビー グッド社商標の譲渡交渉経緯や原告登録商標に対する被告による異議申立て\nや取消審判(商標法53条1項,同法51条1項,同法50条1項)等につ いては,いずれの商標も本件商標とは構成態様を異にするものであり,かつ,\n「Goodwear」の文字部分の識別力が弱いことも併せ考慮すれば,当 該経緯等が,本件の審理判断に影響を及ぼすものではないから,本件商標が 同法4条1項7号に該当するということはできない,(2)原告提出の証拠及び 主張を前提とすると,原告は,平成2年(1990年)頃の我が国への進出 にあたって,「Goodwear」の欧文字からなる商標を自ら登録出願す る機会は十分にあったというべきであり,また,平成11年(1999年)\n6月後半の時期においても,原告は,速やかに「Goodwear」の欧文 字からなる商標を登録出願することができたものであるところ,被告が,そ の時期に「Goodwear」の欧文字からなる商標の存在を認識していた ものであるとしても,商標権の帰属等をめぐる問題は,あくまでも,当事者 同士の私的な問題として解決すべきであり,しかも,原告は,この時期にお いても被告に対し,原告の「Goodwear」関連の商標登録出願をしな いことや,出願をした場合には原告へ帰属させる旨の契約や交渉等ができた にもかかわらず,そのような措置を講じた事実は見いだせず,かつ,自ら登 録出願しなかった責めを被告に求めるべき格別な事情を見いだすこともでき ないことからすると,本件商標について,商標法の先願登録主義を上回るよ うな,その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあるというこ とはできないし,そのような場合には,あくまでも,当事者間の私的な問題 として解決すべきであるから,公の秩序又は善良の風俗を害するというよう な事情があるということはできず,本件商標は,同号に該当しない旨判断し たことが認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.03. 4
平成31(ネ)10003 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年2月28日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
「本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して,原 告製品の限界利益の全額から6割を控除し,また,被告製品の販売数量に上記の原 告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から,特 許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。」
知財高裁は、最近、寄与度という用語を使用しないという傾向を打ち出しています。特別部として明確化したということでしょうか。
特許法102条1項は,民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損 害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり,特許法102条 1項本文において,侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は専用実施権者(以下 「特許権者等」という。)がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位 数量当たりの利益額を乗じた額を,特許権者等の実施の能力の限度で損害額とし,同項ただし書において,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは,当該事情に相当する\n数量に応じた額を控除するものと規定して,侵害行為と相当因果関係のある販売減 少数量の立証責任の転換を図ることにより,より柔軟な販売減少数量の認定を目的 とする規定である。 特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば,特許権者等が「侵害行為が なければ販売することができた物」とは,侵害行為によってその販売数量に影響を 受ける特許権者等の製品,すなわち,侵害品と市場において競合関係に立つ特許権 者等の製品であれば足りると解すべきである。 また,「単位数量当たりの利益の額」は,特許権者等の製品の売上高から特許権者 等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的 に必要となった経費を控除した額(限界利益の額)であり,その主張立証責任は, 特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。さらに,特許法102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については,侵害\n者が主張立証責任を負い,このような事情の存在が主張立証されたときに,当該事 情に相当する数量に応じた額を控除するものである。
(2) 侵害の行為を組成した物の譲渡数量
ア 前記3ないし5のとおり,被告製品の譲渡行為は,本件特許権2を侵害 するものであり,被告製品は「侵害の行為を組成した物」に該当する。 イ 一審原告が本件訴訟において損害賠償請求をしている不法行為の期間で ある平成27年12月4日から平成29年5月8日までの期間(以下「本件侵害期 間」という。)の被告製品の譲渡数量は下記のとおりであり,被告は総計35万17 24個,月平均2万0690個程度の被告製品を譲渡したことになる(争いがない。)。
被告製品1(DR−250A) 7万1077個
被告製品2(DR−250C) 14万1135個
被告製品3(FS−800) 1万5114個
被告製品4(DR−250P) 8万2584個
被告製品5(DR−250G) 1万8526個
被告製品6(DR―250SW) 8263個
被告製品7(JDR−300) 416個
被告製品8(DR−260BK) 6088個
被告製品9(DR−260C) 8521個
ウ 被告製品は,ディスカウントストアや雑貨店に卸売販売されることが中 心であり,一審被告作成の文書では1万5000円(税抜)の価格表示がされているものが多いが(甲7〜13),実際には,3000円ないし5000円程度の価格で販売されている(乙85〜93)。\n被告製品は,ゲルマニウムの粒を使用したゲルマミラーボールと説明されている が,後記の原告製品のように微弱電流(マイクロカレント)を発生する機構は有していない(甲7〜13)。
(3) 侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額
ア 侵害行為がなければ販売することができた物
前記(1)のとおり,「侵害行為がなければ販売することができた物」とは,侵害行 為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品,すなわち,侵害品と市 場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる。一審原告は,本件発 明2の実施品として,「ReFa CARAT(リファ カラット)」という名称の 美容器(以下「原告製品」という。)を,平成21年2月以降販売しており(甲23, 24,弁論の全趣旨),原告製品は,「侵害行為がなければ販売することができた物」 に当たることは明らかである。 原告製品は,ローラの表面にプラチナムコートが施され,支持軸に回転可能\に支 持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより,肌を摘み上 げ,肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器(弁論の全趣旨)であり,搭 載されたソーラーパネルにより,微弱電流(マイクロカレント)を発生する機構\を 有している(甲23)。 原告製品は,原告の店舗,大手通販業者,百貨店,家電量販店で販売され,希望 小売価格である2万3800円(税抜)又はこれに近い価格で販売されている(甲 23,乙94〜108)。 一審原告は,平成27年10月から平成29年8月までの間に,125万641 0個の原告製品を販売しており(月平均5万4626個〔1個未満切り捨て〕),最 も少ない月(平成28年1月)でも1万8770個,最も多い月(平成28年12 月)には8万5492個を販売した(甲38)。
イ 単位数量当たりの利益の額の意義
前記(1)のとおり,特許法102条1項所定の「単位数量当たりの利益の額」は, 特許権者等の製品の売上高から,特許権者等において上記製品を製造販売すること によりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益 の額であり,その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。
ウ 原告製品の限界利益の額
(ア) 売上高及び製造原価
平成27年10月から平成29年8月までの間の原告製品の販売数量は125万 6410個,売上高は合計132億4606万1089円であり,製造原価は●● ●●●●●●●●●●●である(甲38,39)。
(イ) 製造原価以外の控除すべき費用
a 前記(ア)の期間における一審原告の全製品の売上高は合計671億0 968万1552円であり(甲40),一審原告の全製品に対する原告製品の売上比 率は19.74%となる(132億4606万1089円÷671億0968万1 552円≒0.1974)。
b また,前記(ア)の期間における原告製品が含まれる「ReFa」ブラ ンドの製品全体の売上高が342億0958万6196円であり(甲28),同売上 に占める原告製品の売上比率は38.72%となる(132億4606万1089 円÷342億0958万6196円≒0.3872)。
c 前記(ア)の期間における原告製品の製造販売に直接関連して追加的に 必要となった費用は,前記(ア)の製造原価のほか,後記(1)〜(9)のとおりであり,その 額は,(1),(3),(4),(6)〜(9)については,一審原告の全製品について生じた各費用(甲 40)に前記aの比率を乗じた額であり,(2)及び(5)については,「ReFa」ブラン ドの製品について生じた各費用(甲32,33)に前記bの比率を乗じた額である
(1円未満切り捨て)。
(1) 販売手数料 ●●●●●●●●●●●●
(2) 販売促進費 2億5798万4777円
(3) ポイント引当金 741万7870円
(4) 見本品費 5343万9379円
(5) 宣伝広告費 5億2075万3024円
(6) 荷造運賃 4億5578万0084円
(7) クレーム処理費 6548万5934円
(8) 製品保証引当金繰入 590万2260円
(9) 市場調査費 1038万5182円
(1)から(9)までの合計額 ●●●●●●●●●●●●●
d 一審被告は,原告製品の売上高から,一審原告の全ての費用を,原 告製品の売上比率に従って控除すべきであると主張する。
しかし,前記(1)のとおり,特許法102条1項は,民法709条に基づき販売数 量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規 定であり,侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売 することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を上記の損害額としたも のである。このように,同項の損害額は,侵害行為がなければ特許権者等が販売で きた特許権者等の製品についての逸失利益であるから,同項の「単位数量当たりの 利益の額」を算定するに当たっては,特許権者等の製品の製造販売のために直接関 連しない費用を売上高から控除するのは相当ではなく,管理部門の人件費や交通・ 通信費などが,通常,これに当たる。また,一審原告は,既に,原告製品を製造販 売しており,そのために必要な既に支出した費用(例えば,当該製品を製造するた めに必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの)も,売上高から控除する のは相当ではないというべきである。 一審被告が,売上高から控除すべきであると主張する上記費用のうち,前記cの (1)〜(9)の費用以外の費用は,全て上記の売上高から控除するのが相当ではない費用 に当たるというべきであるから,一審被告の上記主張は理由がない。
(ウ) 原告製品の限界利益の額は,原告製品の前記(ア)の売上高から前記(ア) の製造原価と前記(イ)cの各費用の合計額を控除した69億6809万2706円で あり,これを,前記(ア)の期間における原告製品の販売数量125万6410個で除 すると5546円(69億6809万2706円÷125万6410個≒5546. 03円。1円未満切り捨て)となる。
(エ) 前記第2の2で認定した本件発明2の特許請求の範囲の記載及び前記 1で認定した本件明細書2の記載からすると,本件発明2は,回転体,支持軸,軸 受け部材,ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが,軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる(以下,この部分を「本件特徴部分」という。)。\n原告製品は,前記アのとおり,支持軸に回転可能に支持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより,肌を摘み上げ,肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから,本件特徴部分は,原告製品の一部分である\nにすぎない。 ところで,本件のように,特許発明を実施した特許権者の製品において,特許発 明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても,特許権者の製品の販売によ って得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される というべきである。 そして,原告製品にとっては,ローリング部の良好な回転を実現することも重要 であり,そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の 内周面の形状も,原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。 しかし,上記のとおり,原告製品は,一対のローリング部を皮膚に押し付けて回 転させることにより,皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器である から,原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は,ローリング部の構成であるものと認められ,また,前記アのとおり,原告製品は,ソ\ーラーパネルを備え,微弱電流を発生させており,これにより,顧客誘引力を高めているものと認められ る。これらの事情からすると,本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに 貢献しているとはいえないから,原告製品の販売によって得られる限界利益の全額 を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく,したがって,原告製品においては,上 記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。 そして,上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け,原告製品が 本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合 考慮すると,同覆滅がされる程度は,全体の約6割であると認めるのが相当である。 この点に関し,一審被告は,原告製品全体の製造費用に占める軸受けの製造費用 の割合を貢献の程度とすべき旨主張するが,上記の推定覆滅は,原告製品の販売に よる利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり,当該部 分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない。また,一審被告は,原 告製品においては,ローラの抜落の防止機能が不十\分であるから,軸受けの貢献度 は低い旨主張するが,一審被告が根拠とする乙138(原告製品に関するブログの 記載)から,原告製品においてローラの抜落の防止機能が不十\分であると認めるこ とはできず,他に同事実を認めるに足りる証拠はない。よって,上記主張はいずれ も採用できない。 以上より,原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たっては,原告 製品全体の限界利益の額である5546円から,その約6割を控除するのが相当で あり,原告製品の単位数量当たりの利益の額は,2218円(5546円×0.4 ≒2218円)となる。
(4) 実施の能力に応じた額
特許法102条1項は,前記(1)のとおり,侵害者の譲渡数量に特許権者等の製品 の単位数量当たりの利益の額を乗じた額の全額を特許権者等の受けた損害の額とす るのではなく,特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度という制約を設けているところ,この「実施の能\力」は,潜在的な能力で足り,生産委託等の方法により,侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能\な場合も実施の能力があるものと解すべきであり,その主張立証責任は特許権者側にある。そして,前記(3)アのとおり,一審原告は,毎月の平均販売個数に対し,約3万個 の余剰製品供給能力を有していたと推認できるのであるから,この余剰能\力の範囲 内で月に平均2万個程度の数量の原告製品を追加して販売する能力を有していたと認めるのが相当である。したがって,一審原告は,一審被告が本件侵害期間中に販売した被告製品の数量\nの原告製品を販売する能力を有していたと認められる。
(5) 一審原告が販売することができないとする事情
ア 前記(1)のとおり,特許法102条1項ただし書は,侵害品の譲渡数量の 全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情(以 下「販売できない事情」という。)があるときは,販売できない事情に相当する数量 に応じた額を控除するものとすると規定しており,侵害者が,販売できない事情と して認められる各種の事情及び同事情に相当する数量に応じた額を主張立証した場 合には,同項本文により認定された損害額から上記数量に応じた額が控除される。 そして,「販売することができないとする事情」は,侵害行為と特許権者等の製品 の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい,例えば,(1)特許権者と侵害者 の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性),(2)市場における競合 品の存在,(3)侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),(4)侵害品及び特許権者の 製品の性能(機能\,デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの 事情がこれに該当するというべきである。
イ 以下,一審被告が販売できない事情として主張する事情について検討す る。
(ア) 一審被告は,原告製品と被告製品の価格の差異や販売店舗の差異を, 販売できない事情として主張する。
a 本件においては,前記(2)ウ,(3)アのとおり,原告製品は,大手通 販業者や百貨店において,2万3800円又はこれに近い価格で販売されているの に対し,被告製品はディスカウントストアや雑貨店において,3000円ないし5 000円程度の価格で販売されているが,このように,原告製品は,比較的高額な 美容器であるのに対し,被告製品は,原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程 度の廉価で販売されていることからすると,被告製品を購入した者は,被告製品が 存在しなかった場合には,原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきで ある。したがって,上記の販売価格の差異は,販売できない事情と認めることがで きる。 そして,原告製品及び被告製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからす ると,同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと 認められる。 一方で,上記両製品は美容器であるところ,美容器という商品の性質からすると, その需要者の中には,価格を重視せず,安価な商品がある場合は同商品を購入する が,安価な商品がない場合は,高価な商品を購入するという者も少なからず存在す るものと推認できるというべきである。また,前記(3)アのとおり,原告製品は,ロ ーラの表面にプラチナムコートが施され,ソ\ーラーパネルが搭載されて,微弱電流 を発生させるものであるから,これらの装備のない被告製品に比べてその品質は高 いということができ,したがって,原告製品は,その販売価格が約2万4000円 であるとしても,3000円ないし5000円程度の販売価格の被告製品の需要者 の一定数を取り込むことは可能であるというべきである。以上からすると,原告製品及び被告製品の上記価格差の存在による販売できない事情に相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。\n
b このように,原告製品と被告製品との価格の差異は,需要者の購入 動機に影響を与えているといえるが,大手通販業者や百貨店において商品を購入す る者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないというような経験 則があるとは認め難いから,価格の差を離れて,原告製品と被告製品の上記販売態 様の差異が,需要者の購入動機に影響を与えているとは認められず,販売態様の差 異は,販売できない事情として認めることはできないというべきである。
(イ) 一審被告は,競合品が多数存在することを,販売できない事情として 主張する。
平成31年4月の時点で,原告製品と被告製品の同種の製品として,少なくとも 29種類の製品が販売されていることが認められる(乙176,弁論の全趣旨)が, 本件証拠上,本件侵害期間(平成27年12月4日ないし平成29年5月8日)に, 市場において,原告製品と競合関係に立つ製品が販売されていたと認めるに足りな いから,この点を,販売できない事情と認めることはできない。
(ウ) 一審被告は,本件発明2は軸受けについての発明であるところ,被告 製品における軸受けの製造費用は全体の製造費用の僅かな部分を占めるにすぎず, 軸受けは付属品に類するものであることを販売できない事情として主張する。 しかし,本件発明2が美容器の一部に特徴のある発明であるという事情は,既に 原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たって考慮しているのであるから, 重ねて,これを販売できない事情として考慮する必要はないというべきである。
(エ) 一審被告は,軸受けの部分は外見上認識することができず,代替技術 が存することなどを販売できない事情として主張する。 しかし,一審被告の主張する上記の事情は,被告製品及び原告製品のいずれにも 当てはまるものであるから,同事情の存在によって,被告製品がなかった場合に, 被告製品に対する需要が原告製品に向かわなくなるということはできず,したがっ て,これらの事情を販売できない事情と認めることはできない。
(オ) 一審被告は,原告製品は,微弱電流を発生する機構を有しているが,被告製品はそのような機構\を有していないことを販売できない事情として主張する。確かに,前記(3)アのとおり,原告製品は,微弱電流を発生する機構を有しており,一方で,被告製品はそのような機構\を有していないが,このことは,被告製品は,原告製品に比べ顧客誘引力が劣ることを意味するから,被告製品が存在しなかった 場合に,その需要が原告製品に向かうことを妨げる事情とはいい難い。したがって, 上記の点は,販売できない事情と認めることはできない。
(カ) 一審被告は,一審被告の営業努力を,販売できない事情として主張す るが,本件証拠上,一審被告に,販売できない事情と認めるに足りる程度の営業努 力があったとは認められない。
ウ 以上によれば,本件においては,前記イ(ア)aで判示した事情を考慮する と,この販売できない事情に相当する数量は,全体の約5割であると認めるのが相 当である。
(6) 本件発明2の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について 前記(3)及び(5)のとおり,原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっ ては,本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して,原 告製品の限界利益の全額から6割を控除し,また,被告製品の販売数量に上記の原 告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から,特 許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。仮に,一審被告 の主張が,これらの控除とは別に,本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を 考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても,これを認める規定は なく,また,これを認める根拠はないから,そのような寄与度の考慮による減額を 認めることはできない。
(7) 損害額の算定
以上からすると,特許法102条1項による一審原告の損害額は,被告製品の譲 渡数量35万1724個のうち,約5割については販売することができないとする 事情があるからその分を控除し,控除後の販売数量を原告製品の単位数量当たりの 利益額2218円に乗じることで,3億9006万円(2218円×35万172 4個×0.5≒3億9006万円)となる。 また,一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用 は,認容額,本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考 慮して,5000万円と認めるのが相当である。 したがって,一審原告の損害額は,合計で4億4006万円となる。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成28(ワ)5345
本件発明2の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく,上記事情を総合すると,その寄与率は10%と認めるのが相当である。
・・・
上記アないしオで検討したところによれば,特許法102条1項による原告の損
害額は,被告製品の譲渡数量35万1724個のうち,5割については販売するこ
とができないとする事情があるから控除し,これに原告製品の単位数量当たりの利
益額●(省略)●円及び本件特許2の寄与率10%を乗じることで,・・・
関連する審決取消訴訟はこちらです。
◆平成30(行ケ)10160
関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> ピックアップ対象
2020.03. 4
平成31(行ケ)10025 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
本件審決は,本件明細書の記載から,本件特許発明1ないし4の課題は「気 体を過飽和の状態に液体へ溶解させ,かかる過飽和の状態を安定に維持」する ことであり,当該課題を「降圧移送手段を設け,かつ液体にかかる圧力を調整 す」ることにより,解決できることが理解できるが,一方で,0.8mより長 い細管には,水素水を過飽和の状態とし,かつ,これを安定に維持することが できない例が含まれることは当業者であれば十分に認識しうる事項であるから,過飽和の状態が安定に維持できると認めることができない数値範囲が含まれて\nいる本件特許発明1ないし4は,発明の詳細な説明に記載された,発明の課題 を解決するための手段が反映されていないため,発明の詳細な説明に記載した 範囲を超えて特許を請求するものであり,サポート要件に適合しない旨判断し たが,原告は,本件審決の上記判断は誤りである旨主張するので,以下におい て判断する。
・・・
前記1の本件明細書の記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明に は,(1)「本発明」の気体溶解装置1は,気体を発生させる気体発生手段2 と,この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段3と,気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽4と,この液体が細管5a を流れることで降圧する降圧移送手段5とを備えること(【0029】, 図1),「本発明の気体溶解方法は,水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって,生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と,前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と, を少なくとも含む気体溶解装置において,前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと(【0023】),(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し,「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで,液体吸入口7から吸入した水に加圧溶解」され, 「水素を加圧溶解した水」は,「加圧型気体溶解手段」の吐出口9から吐 出され,溶存槽4に「過飽和の状態」で溶存されること(【0034】), 「20度Cにおける加圧型気体溶解手段3の圧力Yとしては,0.10〜1. 0MPaであることが好ましく,0.15〜0.65MPaであることが より好ましく,0.20〜0.55MPaであることがさらにより好まし く,0.23〜0.50MPaであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで,気体を液体中に容易に溶解できる」こと(【0036】), (3)「降圧移送手段」に関し,「降圧移送手段5は,溶存槽4及び取出口1 0を接続する管状路5aにおいて,取出口10からの水素水の吐出動作に よる管状路5a内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば, 降圧移送手段5の管状路5aは,内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと(【0030】),「溶存 槽4に溶存された液体は,降圧移送手段5である細管5a内で層流状態を 維持して流れることで降圧され(S6),水素水吐出口10から外部へ吐 出される(S7)」こと(【0034】),「降圧移送手段5である細管 5aの内径Xが,1.0mm以上5.0mm以下であることが好ましく, 1.0mmより大きく3.0mm以下であることがより好ましく,2.0 mm以上3.0mm以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで, 特開平8−89771号公報記載の技術のように,降圧するために10本 以上の細管を設置する必要が無く,細管5aを1本有することで降圧する ことができるとともに,管内に層流を形成し得る」こと(【0035】), (4)「細管」の内径X及び長さL,「加圧型気体溶解手段」の圧力Yと「層 流」との関係に関し,「細管5aの内径をXmmとし,加圧型気体溶解手 段3により加えられる圧力をYMPaとしたときに,細管5a内に層流を 形成させるようなものであって,X/Yの値が,1.00〜12.00で あることを特徴とするものであり,さらに,X/Yの値が,3.30〜1 0.0であることが好ましく,4.00〜6.67であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が,かかる条件で細管5a中を 層流状態で流れて降圧移送されることで,気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ,さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと (【0031】),「上記発明において,前記管状路の内径及び長さをそ れぞれX,Lとし,前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をYと したときに,前記管状路内の水素水に層流を形成させるようX,Y及びL の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと(【0020】)の 記載がある。上記記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,「本 発明」の気体溶解装置は,「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し,この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され,「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口10に移送する構成を採用し,これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ,かかる過飽和の状態を安定\nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるもの と認められる。
ここに「過飽和」とは,「気体の液体への溶解度は温度により異なるが, ある温度A(度C)における気体の液体への溶解量が,その温度A(℃)に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと(本件明細書の【0 031】),「層流」とは,一般に,速度の方向がそろった規則的な流れ であって,流速が十分遅いときに実現するものであること(甲39の1)をいう。また,細管の内径X及び長さL,加圧型気体溶解手段の圧力Yと\nいう変数に関し,L及びYの2つの変数の値が同じであれば,細管の内径 Xの値が大きいほど,細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること,加 圧型気体溶解手段の圧力Yの値が大きければ,気体を液体に多く溶解させ ることができるが,細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること,細管 の長さLの値が大きければ,細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは,技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり,本件明細書には,「上記発明において,前記管状路の 内径及び長さをそれぞれX,Lとし,前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をYとしたときに,前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようX,Y及びLの値が選択されていることを特徴としてもよい」(【0 020】)との記載があるが,水素水に層流を形成させるようにするには X,Y及びLの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載は ない。 そこで,本件明細書記載の実施例1ないし13及び比較例1及び2に基 づいて,以下において検討する。なお,別紙2は,実施例1ないし13及 び比較例1及び2を一覧表にまとめたものである。
(ア) まず,実施例1ないし3(【0053】ないし【0055】)を比 較すると,別紙2のとおり,3つの実施例で細管の内径Xの値は2mm, 長さLの値は1.6m及び水素水の流量の値は730cm3/minと同 じであるところ,加圧型気体溶解手段の圧力Yの値は,実施例1は0. 41Mpa,実施例2は0.25Mpa,実施例3は0.30Mpaで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Yの値が最も大きい実施例1の水素濃 度は6.5ppmと最も大きく,圧力Yの値が最も小さい実施例2の水 素濃度の値は2.6ppmと最も小さく,両実施例の差は3.9ppm である。 このような実施例1ないし3の比較の結果は,前記アの技術常識に照 らすと,細管の内径X及び長さLと水素水の流量の各値が同じであれば, 加圧型気体溶解手段の圧力Yの値が大きいほど,水素が水に多く溶け込 むため,生成時における水素濃度の値が大きくなる結果,測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に,実施例5(【0057】)と実施例7(【0059】)を比 較すると,別紙2のとおり,両実施例で細管の内径Xの値は2mm及び 水素水の流量の値は560cm3/minと同じであるが,加圧型気体溶 解手段の圧力Yの値は,実施例5が0.38Mpa,実施例7が0.4 5Mpaで,実施例7は実施例5の約1.18倍であり,また,細管の 長さLの値は,実施例5が1.6m,実施例7が1.8mで,実施例7 は実施例5の約1.13倍である。水素濃度の値は,実施例5が3.8 ppm,実施例7が4.5ppmであり,両実施例の水素濃度の差は0. 7ppmであり,実施例2と実施例3との水素濃度の差3.9ppmと 比べると,その差はわずかである。このような実施例5と実施例7の比 較の結果は,細管の内径X及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて,加圧型気体溶解手段の圧力Yの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは,増加の前後で,水素濃度はおお むね同じであり,水素濃度が高まらないことを示している。 また,実施例10(【0062】)と実施例11(【0063】)を 比較すると,別紙2のとおり,両実施例で細管の内径Xの値は2mm, 水素水の流量の値は550cm3/minと同じであるが,加圧型気体溶 解手段の圧力Yの値は,実施例10が0.20Mpa,実施例11が0. 50Mpaで,実施例11が実施例10の2.5倍であり,細管の長さ Lの値は,実施例10が1.4m,実施例11が3mで,実施例11は 実施例10の約2.14倍である。水素濃度の値は,実施例10が2. 7ppm,実施例11が2.4ppmであり,実施例10が実施例11 よりも0.3ppm高いが,実施例2と実施例3との水素濃度の差3. 9ppmと比べると,その差はわずかである。このような実施例10と 実施例11の比較の結果は,実施例5と実施例7の比較の結果と同様に, 細管の内径X及び水素水の流量の各値が同じである場合において,加圧 型気体溶解手段の圧力Yの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは,増加の前後で,水素濃度はおおむね同じであ り,水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例1ないし3の比較 の結果と前記アの技術常識から,細管の内径X及び水素水の流量の各値 が同じである場合に,水素濃度の値を高めるには,加圧型気体溶解手段 の圧力Yの値の増加割合が細管の長さLの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方,比較例1及び2については,別紙2のとおり,比較例1は, 細管の内径Xの値が2mm,細管の長さLの値が0.4m,加圧型気体 溶解手段の圧力Yの値が0.05MPa,水素水の流量の値が960c m3/min,水素濃度の値が1.6ppm,比較例2は,細管の内径 Xの値が3mm,細管の長さLの値が0.8m,加圧型気体溶解手段の 圧力Yの値が0.08MPa,水素水の流量の値が900cm3/mi n,水素濃度の値が1.8ppmであって,いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ(【0066】,【0067】),比 較例1及び2は,圧力Yの値が0.05又は0.08MPaであって, 実施例1ないし13における圧力Yの値(0.20ないし0.60MP a)と比べて相当小さかったため,そもそも,加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から,本件特許発明1の気体溶解装置は,水に水素を 溶解させて水素水を生成し,取出口から吐出させる装置であって,気体を 発生させる気体発生手段と,この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と,気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と,この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え,降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し,管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり,一方,必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し,例えば,細管の内径(X)が1.0mmより大 きく3.0mm以下で,かつ,細管の長さ(L)の値が0.8mより大き く1.4mより小さい数値範囲のときであっても,「細管の内径X及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには,加圧型 気体溶解手段の圧力Yの値を大きくすればよく,この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Y及び細管の長さLの値をいずれも大きくして,水素濃度の 値を高めるには,加圧型気体溶解手段の圧力Yの値の増加割合が細管の長 さLの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 (前記イ)を勘案し,細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようX,Y及びLの値を選択することにより,「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ,かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明1の課題を解決できると認識できるものと認められる。
エ これに対し被告は,(1)当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から,細管の長さの値が0.8mより大きく1.4mより小 さい場合に,過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから,本件特許発明1は,サポート要件に適合 しない,(2)過飽和の状態が維持される条件として,降圧移送手段の管状路 (細管5a)の内径や長さのみならず,細管5aの材料,加圧型気体溶解 手段3により加えられる圧力,水素発生量,水の流量等の条件は,過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明1の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1にはそれらの 条件が記載されていないため,当業者は,細管の内径X及び長さがそれぞ れ本件特許発明1に規定された範囲内であれば,本件特許発明1の上記課 題を解決できると認識することはできないから,この点からも,本件特許 発明1は,サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら,前記ウ認定のとおり,本件特許発明1において細管の長 さの値が0.8mより大きく1.4mより小さい場合においても,本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて,当業者が,本件 特許発明1の課題を解決できると認識できるものと認められるから,被告 の上記主張は,いずれも理由がない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2020.02.28
平成31(行ケ)10038 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
以上によると,甲2及び3から共通して把握できる技術は,「テレビ放 送の受像機において,メインのテレビ放送の映像とともに,文字放送を受信して文 字放送の文字をプログラム制御によりスクロール表示する際に,メインのテレビ放\n送の映像に文字が含まれている場合,メインのテレビ放送の映像の文字と重ならな いように文字放送の文字の表示位置を変更してスクロール表\示する技術」であり, 甲19及び25から共通して把握できる技術は,「FlashのActionSc riptのhitTestを用いることにより,ムービークリップの領域判定を行 う技術」である。 このように,甲2及び3から把握できる技術と,甲19及び25から把握できる 技術は共通するものではないから,甲2,3,19及び25に共通する慣用技術を 把握することはできない。
カ 原告は,甲1発明と甲2等技術は,プログラミングという技術分野に属 するとともに,動画と文字情報とを配信するという技術分野に属することで共通す るため,甲1発明に甲2等技術を適用する動機付けがあると主張する。 甲1発明は,ライブ映像とライブ閲覧者からのコミュニケーション情報(例えば, チャット〔テキスト文による情報〕)とを一つの画面でリアルタイムで同期表示する\n機能を有するライブ配信サーバ(構\成1a)と,クライアントであるライブ閲覧者 の複数のライブ閲覧者端末(構成1b)とが,通信ネットワークを介して接続され\nて構成されるライブ配信システム(構\成1c)に関する発明である。そして,甲1 発明の前記ライブ閲覧者端末が再生するマルチメディアコンテンツは,「ライブ映 像データ」であり(構成1a,構\成1a2,構成1a5,構\成1b4),前記ライブ 閲覧者端末が表示する複数のチャット文は,ライブ閲覧者が入力した「テキスト文\nによる情報」(構成1a,構\成1a5,構成1b5)である。\n他方,甲2及び3に記載された技術事項は,上記オ(オ)のとおり,テレビ放送の受 像機において,メインのテレビ放送の映像とともに,文字放送を受信して文字放送 の文字をプログラム制御によりスクロール表示する際に,メインのテレビ放送の映\n像に文字が含まれている場合,メインのテレビ放送の映像の文字と重ならないよう に文字放送の文字の表示位置を変更してスクロール表\示する技術である。 そうすると,甲1発明は,ライブ配信サーバとライブ閲覧者端末とが通信ネット ワークを介して接続されて構成されるライブ配信システムに関する発明であるのに\n対して,甲2及び3に記載された技術事項は,テレビの文字放送の受信機の技術で あるから,両者は,その前提となるシステムが異なる。 また,甲1発明と甲2及び3に記載された技術事項とは,文字を表示する点では\n共通するものの,表示される文字は,甲1発明では,ライブ閲覧者が入力するチャ\nット文であるのに対し,甲2及び3に記載された技術事項は,メインのテレビ放送 の映像に含まれる文字と文字放送の文字であるから,対象とする文字が異なる。 したがって,甲1発明と甲2及び3に記載された技術とは,技術が大きく異なる といえるのであり,プログラミングに関するものであることや動画と文字情報を配 信するものであるということ,文字と文字の重なり合いが生じないようにする技術 であることだけでは,甲1発明に甲2及び3に記載された技術を適用する動機付け があると認めることはできないから甲1発明に甲2及び3に記載された技術を適用 して本件特許発明1を容易に発明することができたとはいえない。 また,甲19及び25には,文字列情報の表示位置の制御については何ら開示さ\nれていないから,甲1発明に甲19及び25に記載された技術を適用して本件特許 発明1を容易に発明することができたとはいえない。
キ 原告は,甲1発明と甲2等技術は,視認性の低下という課題が共通する と主張するが,前記のとおり,甲1発明は視認性の低下という課題を有しないため, 甲1発明と甲2等技術が課題において共通するとは認められない。
ク 以上によると,その余の点を判断するまでもなく,甲1発明に甲2等技 術を適用して本件特許発明1を容易に発明をすることができたと認められないから, 本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.02.28
平成31(行ケ)10039 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
上記(1)によると,本件特許発明は,「放送されたテレビ番組などの動画に 対してユーザが発言したコメントをその動画と併せて表示するシステム」という背\n景技術を前提とし(段落【0002】),「コメントの読みにくさを低減させる」とい う課題を解決するための発明であり(段落【0005】),動画を再生するとともに, 前記動画上にコメントを表示する表\示装置であって,前記コメントと,当該コメン トが付与された時点における,動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画\n再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記 憶部と,前記動画を表示する領域である第1の表\示欄に当該動画を再生して表示す\nる動画再生部と,前記再生される動画の動画再生時間に基づいて,前記コメント情 報記憶部に記憶されたコメント情報のうち,前記動画の動画再生時間に対応するコ メント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し,当該 読み出されたコメントを,前記コメントを表示する領域である第2の表\示欄に表示\nするコメント表示部とを有し,前記第2の表\示欄のうち,一部の領域が前記第1の 表示欄の少なくとも一部と重なっており,他の領域が前記第1の表\示欄の外側にあ り,前記コメント表示部は,前記読み出したコメントの少なくとも一部を,前記第\n2の表示欄のうち,前記第1の表\示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表\ 示することを特徴とするものであり(段落【0006】),本件特許発明により,「オ ーバーレイ表示されたコメント等が,動画の画面の外側でトリミングするようにし\nて,コメントそのものが動画に含まれているものではなく,動画に対してユーザに よって書き込まれたものであることが把握可能となり,コメントの読みにくさを低\n減させることができる」(段落【0012】)という効果を奏するものであることが 認められる。
(3) 本件特許発明における「コメント」について検討すると,本件特許発明1 は,「(1A)動画を再生するとともに,前記動画上にコメントを表示する表\示装置 であって,(1B)前記コメントと,当該コメントが付与された時点における,動画 の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と\nを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と,」を構成要件としている。\n構成要件1Bによると,「コメント」が付与された時点で,「動画の最初を基準と\nした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間」が記憶されるこ\nとになるから,「コメント」は,それが表示される表\示装置において,動画を再生す る時に付与され,付与された時点の動画再生時間が,コメント付与時間としてコメ ント情報記憶部に記憶されるものであると解される。そして,「コメント」は,「動 画を再生するとともに,前記動画上にコメントを表示する表\示装置」(1A)におい て,動画を再生する時に付与されるものであるから,コメントを付与する者は,表\n示装置において,動画を再生して閲覧するユーザであることを読み取ることができ る。 そうすると,本件特許発明における「コメント」とは,表示装置において,動画\nを閲覧するユーザが,動画の再生開始後の任意の時点に,動画に対して付与するも のと解することができる。
・・・・
これに対し,原告は,相違点1について,甲1の「テキスト」は,ユ ーザが発言するものが排除されることはなく,「コメント」を含むから,本件審決の 相違点1の認定には誤りがあると主張する。 甲1には,ユーザとの双方向の情報伝達が行える環境が整ってきたとの記載はあ る(段落【0002】)ものの,甲1発明は,前記ア認定のとおりのものであって, 動画コンテンツ作製者側が「動画コンテンツ」の個々の動画に応じて,または1つ の動画内でも個々の場面に応じて表示されるように予\め作成した「データコンテン ツ」が,「動画コンテンツ」とともに「コンテンツ」を構成し,その「データコンテ\nンツ」はインターネットのホームページのデータに対応するものであり,代表的に\nはテキストや静止画を含み,場合によっては音声などのデータを含むものであるか ら,甲1発明の「テキスト」とは,コンテンツ作製者側が「動画コンテンツ」の個々 の動画に応じて,または1つの動画内でも個々の場面に応じて指定した「テキスト」 であり,ユーザの投稿したテキストデータをその構成に含むとは認められない。\n原告は,甲1について,ユーザからのコメントが付与されたデータコメントを配 信することも予定されているというべきであると主張するが,甲1発明の「データ\nコンテンツ」は上記認定のとおりのものであって,そこにユーザからのコメントが 含まれると認めることはできない。 また,原告は,インターネットで公開されるインタラクティブなサービスではテ キスト情報の送受信を行う場合,ユーザが投稿したコメントの送受信に容易に拡張 可能であることは当業者の常識であるとも主張するが,甲1発明が前記のような内\n容であり,甲1には,ユーザがコメントを投稿することについての記載があるとは 認められないことからすると,甲1発明がユーザが送信したコメントをその構成に\n含むものであると認めることはできない。 さらに,原告は,甲22,24及び25はユーザが送信したデータをテキストデ ータと表記しているから,「テキスト」であることをもって「コメント」を排除する\nと解することはできないと主張するが,上記のとおり,甲1発明は,ユーザが送信 したデータをその構成に含むものではなく,原告の指摘することは,上記判断を左\n右するものではない。 したがって,本件特許発明1と甲1発明の相違点として,相違点1を認めること ができる。
・・・
本件特許発明1における「コメント」は,表示装置において,ユーザ\nが動画を再生している時に付与され,表示装置から,ユーザによりいつでも付与可\n能であるのに対し,甲1発明の「データコンテンツ」の「テキスト」は,コンテン\nツ作製者側で「データコンテンツ」として予め作成されたものであって,ユーザに\nより表示装置で付与されるものではないし,表\示装置において再生している時に付 与されるものでもない。 したがって,本件特許発明1における「コメント」と,甲1発明における「デー タコンテンツ」の「テキスト」とは,ユーザによる付与が可能か否か,付与を行う\n装置,付与を行う時において異なり,このように異なる「データコンテンツ」の「テ キスト」を「コメント」に置き換えることは,甲1発明の前提となる装置構成の変\n更を必要とするものであって,甲1発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を ユーザが付与する「コメント」に容易に置き換えることができるものとは認められ ない。 よって,甲1発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を「コメント」に置き 換えることは,当業者が容易に想到し得た事項とはいえない。 (イ) これに対し,原告は,甲1の段落【0002】の記載や,WEB2. 0という技術常識によると,「テキスト」を利用者からの情報伝達を可能とする「コ\nメント」に置換することができる旨主張する。 しかし,甲1には,ユーザがコメントを投稿することについての記載は全くなく, 段落【0002】の記載があり,誰もがウェブサイトを通して自由に情報を発信で きるように変化したウェブの利用状態であるWeb2.0が知られていたとしても, 甲1発明の「データコンテンツ」をユーザが付与する「コメント」に置き換えるこ とが容易であるとは認められない。
(ウ)a 原告は,甲22に基づき,動画配信において,その魅力を高めるた めに,コンテンツ作製側で,個々の動画に応じて,または,1つの動画内でも個々 の場面において指定される「テキスト」を利用者からの情報伝達を可能とする「コ\nメント」に置換することには十分な動機付けがあると主張する。\n甲22は,発明の名称を「ストリーミング配信方法」とする発明の公開特許公報 であり,「動画コンテンツをネットワークを介して利用者端末にストリーミング配 信するストリーミングサーバと,ストリーミング配信中の動画コンテンツに関連付 けられたウェブ掲示板又はチャット領域をネットワークを介して利用者端末に提供 するウェブサーバと,動画コンテンツの配信を受け,ウェブ掲示板又はチャット領 域のテキスト書込部にテキストデータからなるメッセージを書き込む利用者端末と からなるストリーミング配信システムにおいて,ストリーミングサーバは,ウェブ サーバの書込ログファイルに格納されたテキストデータを収集し,収集されたテキ ストデータをストリーミング配信中の動画コンテンツに重畳し,テキストデータの 重畳された動画コンテンツを利用端末に配信するストリーミング配信システム」を 採用することにより,「利用者は,非常に便利であり,会場の客席の様な雰囲気を味 わうことができる」技術(以下,「甲22技術」という。)が記載されていることが 認められる。 他方,甲1発明は,「ネットワーク環境」をユーザへのデータコンテンツの配信に 用いたものであり,「データコンテンツ」を双方向に情報伝達するものではないから, 甲22技術があることをもって,甲1発明の「データコンテンツ」の「テキスト」 をユーザが付与する「コメント」に置換する動機付けがあるということはできない。
b 原告は,動画とユーザが入力した文字データ(コメント)を同期表\n示させることは,本件原出願日の時点において慣用技術であった(甲26〜34) から,甲1発明に当該慣用技術を適用して甲1の「テキスト」を「コメント」に置 換することは容易であると主張する。 甲26〜34には,映像を見ながらユーザがリアルタイムでテキストによるコミ ュニケーションを行う技術(以下,「甲26等技術」という。)が開示されているこ とが認められる。 しかし,甲1発明は,「ネットワーク環境」をユーザへのデータコンテンツの配信 に用いたものであり,「データコンテンツ」を双方向に情報伝達するものではないか ら,原告の主張する甲26等技術が慣用技術であるとしても,甲1発明の「データ コンテンツ」の「テキスト」をユーザが付与する「コメント」に置換する動機付け があるとは認められない。
c 原告は,動画と同時に表示するデータコンテンツはユーザが指定す\nるのでなければ,コンテンツ作製者側で指定するのが通常であり,甲22や甲26 〜34には,甲 1 発明における「コンテンツ作製者側で,個々の動画に応じて,ま たは,1つの動画内でも個々の場面に応じて相応しいデータコンテンツおよび表示\n態様が指定される」ことの記載も示唆もないということはできないと主張する。 しかし,甲26〜34は,ユーザがデータコンテンツを指定することを前提とし たものであるから,原告の主張は失当である。原告は,甲33「コメントを表示す\nる際には,入力する際に指定された場所を指し示すように,指定された場所毎にコ メントを表示する,映像コメント入力・表\示方法を提案する。」(段落【0008】),甲34「提供された増補は,配置の命令と,持続時間の命令とを有してもよい」(段 落【0006】)の記載も指摘するが,いずれもユーザ側が指定する場合に関する記 載であるから,甲1発明における「コンテンツ作製者側で,個々の動画に応じて, または,1つの動画内でも個々の場面に応じて相応しいデータコンテンツおよび表\n示態様が指定される」が記載又は示唆されていると読み取ることはできない。 なお,甲22技術の内容は,コンテンツ作製者側が,利用者端末から収集したテ キストデータを,ストリーミング配信中の動画コンテンツに重畳し,テキストデー タの重畳された動画を利用者端末に配信するものであるが,このような甲22技術 があるからといって,甲1発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を「コメン ト」に置換する動機付けがあるとはいえないことは,前記(1)イ(ウ)aのとおりであ る。
◆判決本文
原告被告の異なる別特許の審取事件です。
こちらも無効理由無しとした審決が維持されています。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.02.27
令和1(ネ)10046 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当審における補充主張に対する判断
控訴人は,本件明細書等の記載によれば,本件各発明の効果は, ドラ イパビットの翼部の屈曲部l乙ネジの翼係合部の屈曲部が接触することに よるものであるとし,これを前提に,被告製品は本件各発明の効果を奏 しないと主張する。 本件明細書等の段落【0003), 【0004】, 【0008】, 【図1】の記載からは,従来技術においては,食い付き部分を有する ネジを含む従来のネジにおいて,翼係合部とドライパピットの翼部と の引っ掛かりが悪いことやドライパピットがネジに対して傾いた状態 であることにより更ネジを回転させようとするとき,カムアウト現象 が生じ易いという課題が存するところ,本件各発明の「側壁面」の構\n成を採用すると,対応する形状の翼部を有するピットを用いれば,ネ ジに対してドライパピットが傾きにくくなり,また,翼部の屈曲した 側面に,対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので, 前記側面が前記側壁面を確実に把握し,翼部と翼係合部との引っ掛か りがよくなるため, ドライバピットがカムアウトしにくくなり,上記 課題が解決されることが理解できる。 そして「食い込む」とは「他の領域へ入りこんで侵す。侵入す る。」 (乙10 1) ことであるから,本件明細書等の段落【0008】 の「翼部の屈曲した側面に,対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面 が食い込むJとは,回転力を加えることにより, ドライパピットの翼部 とネジの翼係合部が接触する箇所において, ドライパピットの翼部の側 面がネジの翼係合部の側壁面を確実に把握し,引っ掛かりがよくなるこ とを意味するものと解され,本件各発明の効果を奏するために, ドライ パピットの翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することが必須で あるということはできない。また,控訴人の指摘する本件明細書等の段 落【0014], 【0017]及び【0022]にも, ドライバピット の翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することの記載はない。 控訴人は,本件意見書2の図A,B等は, ドライパピットの翼部の屈 曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触することを裏付けると主張するが, 本件明細書等の上記記載に照らせば,本件意見書2の各図は上記判断を 左右するものではない。
(イ) 控訴人の主張によっても,専用ピットの翼部の先端が被告製品の 「先端部内側面Jに点状に接触するというのであるから,被告製品に おいても, ドライパピットに回転力を加えた際に当該接触した箇所で 食い込みが生じ,翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなり, ドライ パビットがカムアウトしにくくなるという効果を奏すると解され,被 告製品において本件各発明の効果を奏しないということはできない。
本件特許に係る無効理由の有無(争点2) について
(1) 本件特許に係る無効理由の有無(争点2) についての判断は,次のとお り補正し,後記のとおり当審における補充主張に対する判断を付加するほか は,原判決第4の・・・記載のとおりであるから,これを引用する。
ア原判決56頁24行目「動機」を「動機付け」と改める。
イ原判決57頁19行目冒頭から25行目末尾までを次のとおり改める。
「しかし,前記判示のとおり,ネジ及びドライパピットの食い付き部分は 周知技術であり,出願当初の明細書等の実施例に当該周知技術について記 載がされていないとしても,それは本件各発明が当該周知技術を備えるこ とを排除する趣旨であるとは解し得ない。そうすると,本件各発明の技術 的範囲に当該周知技術の構成を備えたネジが含まれるとしても,構\成要件 1D及び2Aの「ネジの中心側から外方に向かつて延びる平面状の基端側 部分」との発明特定事項を追加する本件手続補正が新規事項の追加となる ものではない。 また,本件明細書等の段落【0003], 【0004】, 【0008], 【図1】の記載からは,本件各発明の「側壁面」の構成を備えることによ\nり,対応する形状の翼部を有するピットを用いれば,ネジに対してドライ パピットが傾きにくくなり,また,翼部の屈曲した側面に,対応する形状 に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので,前記側面が前記側壁面を確 実に把握し,翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなるため, ドライパピ ットがカムアウトしにくくなるという本件各発明の効果が得られることが 理解でき(本判決第3の2(3)ウ(7)参照。), 「食い付き部分」の有無は 本件各発明の課題の解決に影響する構成とはいえない。したがって,控訴\n人主張の点は,サポート要件適合性を否定するものではないというべきで ある」
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア 乙13考案及び乙5-8公報に開示された周知技術による進歩性の欠如 (争点2- 1) について
控訴人は,食い付き部分に関し,屈曲した二平面とR面を相互に代替す ることは当業者の技術常識であると主張するo しかし,食い付き部分と本 件各発明の「側壁面」は,目的も機能も異なり,食い付き部分の構\成に関 する技術常識を側壁面に適用することはできなし、から,控訴人の主張は採 用できない。
イ 乙13考案並びに乙12考案及び乙5〜8公報に開示された周知技術に よる進歩性の欠知(争点2-2) について
控訴人は,乙12考案の効果は本件各発明の「食い込む」ことにより 「カムアウトがしにくくなる」効果と実質的に同質の効果であるから, 乙13考案と乙12考案とは,実質的な目的・課題及び作用・機能にお\nいて共通し,両者を組み合わせる動機付けがあると主張する。しかし, 乙12考案の「切込溝3Jは錆びついたピスを容易に抜くために設けた ものであるのに対し,乙13考案の「円弧E-Fからなる溝」は, ドラ イパーのねじ込み力を完全に受け止めるために設けられたものであって, これらの考案の課題は全く異なることは,上記引用に係る補正された原 判決第4の5に説示したとおりであり,乙13考案に乙12考案を組み 合わせる動機付けがあるということはできない。
ウ補正要件違反又はサポート要件違反の有無について(争点2-3) につ いて
控訴人は,本件各発明の「屈曲」について,翼部の屈曲した側面に,対 応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むことが可能な「屈曲J, すなわち, ドライパピットの翼部の屈曲部に,対応する形状に屈曲したネ ジの翼係合部の屈曲部が深く内部に入り込むほど接触することを要すると 限定解釈しないとすると,本件各発明の課題である「ドライパピットがカ ムアウトしにくい(回動部から外れにくい)ネジおよびドライパピットを 提供するJ (【0004】)を解決し得ると当業者が認識し得ないものを 特許請求の範囲に含むことになると主張する。しかし, ドライパビットが カムアウトしにくい(回動部から外れにくし、)ネジとの課題を解決するに つき, ドライパピットの翼部の屈曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触す る(食い込む)ことが必須であるといえないのは前記2(1)イ及び(2)に説 示したとおりでありこれを前提とする控訴人の主張は採用できない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成28(ワ)14753
被告は,本件意見書1における,「引用文献2〜4」のネジと本件各発
明のネジ穴とは構成が異なる旨の記載は,本件各発明の特許請求の範囲か\nら,ネジ穴の中心部に食い付き部分(円弧面状の部分)を有する構成を意\n識的に除外する趣旨であって,食い付き部分を有する構成が本件各発明の\n技術的範囲に属すると主張することは,禁反言の法理に照らして許されな
いと主張する。
イ しかし,本件意見書1には,以下の内容の記載がある。
(ア) 本件手続補正は,請求項1について「引用文献2〜4記載の発明との
相違が明確になるように締付側側壁面(10)の形状をより細かく限定
した」ものであり,請求項2について「引用文献2〜4記載の発明との
相違が明確になるようにネジの翼係合部(2)の緩め側側壁面(9)の
形状をより細かく限定したもの」である。(乙10の2頁)
(イ) 「引用文献2」(乙6)記載の発明は,「本来の意味においては,各
翼係合部は屈曲部を有していない。具体的には,引用文献2記載の発明
の場合,各翼係合部の両側壁面は,それぞれ全体が1つの平面状をなし
ており,全く屈曲されていない」点で本件各発明と異なる。
引用文献2記載の発明において「強いて回動部の中心部の円弧面状の
部分を翼係合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」,本願発
明のような優れた作用効果を全く果たさない。(乙10の4頁)
(ウ) 「引用文献3」(乙7),「同4」(乙8)記載の発明においても,
「本来の意味においては,各翼係合部は屈曲部を有していない。具体的
には,引用文献3,4記載の発明の場合,本来の意味での各翼係合部の
両側壁面は,軸方向から見ると扇形の両辺(直線状部)をなす平面状の
部分のみである」点で本件各発明と異なる。
引用文献3,4記載の発明における「ネジの中央部分において翼係合
部の基端側部分間をつなぐR部分は,円弧面状をなす部分であって,ネ
ジへのドライバビットの食い付きをよくするために設けられる所謂食い
付き部を構成する部分」であって,「前記R部分(食い付き部分)は,\nネジの締め付けおよび緩め動作自体には直接関係のない部分」にすぎな
い。
「引用文献3,4」記載の発明において,「強いて前記R部分を翼係
合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても,これらの部分は,平
面状ではなく,円弧面状の部分であり,かつネジの中心側から外方に向
かって延びていない」ので,本件各発明とは構成が異なる。\n 引用文献3,4記載の発明において,「強いて前記R部分を翼係合部
の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」,本件各発明の作用効果
は生じない。(乙10の5頁)
ウ 本件意見書1の上記記載によれば,原告は同意見書において,「引用文
献2〜4」記載の発明に係る構成と本件各発明に係る構\成が異なることを
説明するとともに,仮に同各文献の構成が対応する本件各発明の構\成に相
当するとしても,同各文献記載の発明が本件各発明の効果を奏しないとい
うことを説明しているにすぎないのであって,上記記載をもって,本件各
発明の特許請求の範囲から,ネジ穴の中心部に食い付き部分(円弧面状の
部分)を有する構成を意識的に除外しているということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> ピックアップ対象
2020.02.27
平成30(ワ)8414 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和元年12月18日 東京地方裁判所
事案に鑑み,争点(2)から検討するに,原告製品形態が,不競法2条1項1 号に該当するには,(1)商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特 徴を有しており(特別顕著性),かつ,(2)その形態が特定の事業者によって長 期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等によ り,需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するも\nのとして周知になっていること(周知性)を要すると解されるが,以下の理由 から,原告製品形態は上記要件を満たすものというべきである。
(1) 特別顕著性
ア 原告製品が以下の形態を備えていることは,当事者間に争いがない。
(1) 「持ち手部分」と,光を発する「ライト部分」と,その間の「リング 部分」とで構成され,「リング部分」はメッキが施されている。\n
(2) ライト部分の先端にメッキの外カバーを付けており,リング部分のメ ッキと合わせて同一色,統一感のあるデザインとしている。
(3) 全体のフォルムは円柱状のシンプルな形態とし,ライト部分及び持ち 手部分の側面は,どの角度から見ても,平らな直線又はなだらかな曲線 によりそれぞれ外縁が形成され、突起物や階段状又は鋭角な部分が存在 しない。ただし,メッキ仕様のリング部分だけは,ライト部分,持ち手 部分を外側から覆う外観となり,一回り径が太くなっている。
(4) 持ち手部分は,真ん中でなだらかに凹型となる曲線を描き,底面部の 角は丸みを帯びており,正面視,背面視において瓢箪型である。\n
(5) ライト部分先端の外カバーも,凸状に丸みを帯びており,正面視,背 面視において円弧を描く球状である。
(6) 全体の長さが約25センチメートルで,そのうちライト部分は約15 センチメートル,持ち手部分とリング部分を合わせて約10センチメー トル,ライト部分の太さは直径約3センチメートルである。
(7) 持ち手部分の底面部に,発光・消灯及び発光色の切替えを行うスイッ チボタンが設置され,側面部にはスイッチを設置していないか,あるい は,スイッチを設置する場合でも,外観上その存在がわからないような スイッチとする。
イ 原告製品1が発売された平成24年4月当時に存在した同種製品は,上 記1(6)ア記載のとおりであるが,甲18の写真撮影報告書,甲17等に よれば,このうち,「大電光改」及び「CHEER LIGHT」は,原 告製品に比べて細くて小さいペンライトであり,いずれもリング部分が太 くなっている形態をしている点などにおいて,原告製品の形態と異なる。 また,「大電光煌」は持ち手部分が太くて,製品全体の長さにおけるラ イト部分の割合が原告製品より小さく,ライト部分の先端は半円球状であ る点などにおいて,原告製品の形態と異なる。 さらに,「ネオンスティック」は製品全体の長さにおける持ち手部分の 割合が原告製品より小さく,持ち手部分に設けられたボタンが特徴的であ る点で,「カラフルビーム」はライト部分が先端に向けて細くなっており, 持ち手部分に円形のダイヤルが取り付けられている点において,原告製品 の形態と異なる。 加えて,これらの同種製品は,いずれも,リング部分及びライト部分の 先端に同一色のメッキが施されておらず,持ち手部分にスイッチ等が設け られているなど,全体的に凹凸があって統一感のない印象を与えるもので ある。
ウ これに対して,原告製品は,全体的に丸みの帯びた円柱状のシンプルな 形態であり,ライト部分からリング部分、持ち手部分を通じて、全体とし て凸凹感のない直線又は曲線により外縁が形成されている点(形態(3))に 特徴がある。 また,原告製品のリング部分にはメッキが施されるとともに,ライト部 分の先端にも同一色のメッキの外カバーが付けられており,リング部分の メッキとライト部分先端のメッキの金属的な光沢は,原告製品に他社の製 品にはないデザイン上のアクセントを与えているということができる(形 態(1),(2))。さらに,原告製品の持ち手部分は,その真ん中がなだらかな曲線から形 成される凹型となっており,底面部の角は丸みを帯びている上,ライト 部分先端の外カバーも,凸状に丸みを帯びて円弧を描く球状であり,更 に側面部にスイッチボタンもないことが,全体として,柔らかくシンプ ルな印象を与えているということができる(形態(4),(7))。加えて,原告製品の全体の長さは約25センチメートルと他社の多くの製品より長く,ライト部分と持ち手部分の長さのバランスも良く,全体の長さとライト部分の太さの割合も均衡がとれているとの印象を与えるものである(形態(6))。
以上のとおり,原告製品形態(1)〜(7)は,平成24年4月当時の同種製品 にはない形態上の特徴であるということができ,更に,これらの特徴があ いまって,製品全体として,同種製品とは異なる顕著な特徴を備えている ということができる。
エ これに対し,被告は,形態(1)〜(7)は,いずれもありふれたものであると 主張する。
(ア) しかし,形態(1),(2)については,上記のとおり,平成24年4月当時 のペンライトのリング部分及びライト部分の先端に同一色のメッキを 施しているものはなく,また,ペンライトを使用する上で,その構成\n部分に金属的な装飾を加える必然性はないのであるから,同各形態は 原告製品に特徴的なものというべきである。
(イ) 被告は,形態(3)に関し,ペンライトのライト部分が円柱状であるのは 特別なことではなく,平成24年4月当時の同種製品も,丸みを帯び た円柱状のシンプルな形態であったと主張する。 しかし,原告製品は,単にライト部分が円柱状であるのみならず,全 体的に丸みの帯びた円柱状のシンプルな形状をしており,ライト部分 からリング部分、持ち手部分を通じて、全体として凸凹感のない直線 又は曲線により外縁が形成されている点に特徴があり,かかる特徴は 同種製品には見られないものである。
(ウ) 被告は,形態(4)に関し,持ち手部分の中央付近をなだらかにへこませ るデザインは公知であったこと,形態(5)に関し,ペンライトの先端に 外カバーを設けたり,その先端を球状にすることは,特別なことでは ないこと,形態(6)に関し,原告製品の長さはコンサート等のイベント における規制に従ったものにすぎず,その太さも特別なものではない こと,形態(7)に関し,底面部のスイッチは,底から見ない限り視認で きないので,識別力を生じさせないことなどを指摘する。しかし,原告製品は,持ち手部分の中央部分をなだらかにへこませるとともに,ペンライトの先端の外カバーを球状にし,更に持ち手部分の側面にスイッチを側面に設けないことにより,全体として,なだら かな曲線と直線から形成されるすっきりとして統一感のある輪郭が形 成され,全体として柔らかくシンプルな印象を与えるのであり,こう した特徴は同種製品には見られないものである。そうすると,上記の 個々の形態が公知であることなどを理由として,原告製品形態があり ふれたものであるということはできない。
(エ) 被告は,平成24年10月に発売されたルミエースや同年12月に発 売されたカラフルサンダー110などに原告製品形態と共通する特徴 が見られると主張するが,これらの製品は,原告製品1及び2の後に 発売されたものであるから,同各製品の発売時点では原告製品の形態 は同業者の間では知られていたのであり,原告製品形態も参考にしな がらデザインされた可能性が高い。これらの製品が原告製品形態と同\n様の特徴を有するとしても,そのことをもって原告製品形態の特別顕 著性は否定されるものではないというべきである。
(オ) 被告は,ペンライトという製品は,その性質上,外見を重視するので はなく,輝度や色などの機能を重視して選択される製品であるから,\nこの観点からしても,原告製品形態には特別顕著性はないと主張する。 しかし,ペンライトは,その用途・性状に一定の制限があるとしても, 種々のデザインを工夫し得ることは同種製品のデザインとの対比から も明らかであり,また,ペンライトの需要者が,趣味・嗜好に強い興 味・関心を示すいわゆる「オタク」を中心とする者であることに鑑み ても,これらの需要者は,機能のみならずデザインにもこだわりを持\nって購入するペンライトの選択をすると考えるのが自然である。
オ 以上によれば,原告製品形態は特別顕著性を有するということができる。
(2) 周知性
ア 前記1(2)のとおり,原告製品1(キングブレードMAX)及び同2 (キングブレードX10)は,平成24年4月に原告製品1の販売が開始 されて以降,同年10月までに,両製品で累計●(省略)●本,●(省略) ●円を売り上げたとの事実を認めることができる。 平成25年ころにおいて,国民的アイドルとされるアイドルグループの CDの売上が,複数枚購入を含め合計56万枚程度であり(甲38),平 成26年8月に開催された日本最大級とされるアニメソングのライブの3\n日間の延べ来場者数が8万人程度であったと認められること(甲37)を 考慮すると,わずか6か月という短期間のうちに●(省略)●本の売上げ があったことは,趣味嗜好に強い関心を有するいわゆる「オタク」を需要 者とするこの種の製品としては「爆発的」と評価し得る売れ行きであった ということができる。
イ また,前記1(3)のとおり,原告製品は,平成24年10月,テレビ番 組に使用され,それを見た視聴者が,同番組において使用されたペンライ トの商品名については紹介がされていなかったにもかかわらず,原告製品 であると認識し,ツイッター上で,「みんなキンブレ振ってる」などとツ イートしたとの事実によれば,そのころには,需要者において,原告製品 形態を有する商品は原告製品であって,原告を出所とすることを表示する\nものとして,広く知られていたと認めるのが相当である。
ウ さらに,前記1(4)のとおり,原告製品2(キングブレードX10)は, 平成25年2月,アマゾンのおもちゃのベストセラーの3位にランクイン したとの事実が認められるが,このランキングは,ペンライト又はそれに 類する商品間のランキングではなく,おもちゃ全体におけるランキングで あることに照らすと,原告製品は同時点において既に需要者に広く知られ していたものと認められる(甲21の4)。 以上によれば,原告製品形態は,平成24年10月時点において,また, 遅くとも平成25年1月までに,原告の出所を表示するものとして,周知\n性を獲得していたというべきである。
エ これに対し,被告は,原告製品が,平成24年10月以後も売れ行きを 伸ばしている事実を指摘し,そのことから逆に,平成24年時点の市場占 有率はそれほど高くなかったと主張するが,平成24年4月から10月ま での売上本数や売上高等に照らし,同月時点において原告製品形態が需要 者に広く知られていたと認められることは前記判示のとおりであり,平成 25年以降に更に売上げが増加したことは,上記認定を左右するものでは ない。また,被告は,原告製品が多く売れたのは,原告製品形態のデザイン性 が着目されたからではなく,高輝度という機能に需要があったためである\nと主張するが,原告製品の需要者が機能のみならず,デザインも重視して\nペンライトを購入したと考えるのが自然であることは前記判示のとおりで ある。さらに,被告は,原告の製品の中には原告製品目録に掲げられていない ものもあり,また,原告製品の中にも原告製品形態の一部を満たさない種 類のものがあると主張するが,原告製品の主力は原告製品目録記載の製品 であり,その他の製品が原告製品形態の一部を満たしていなかったとして も,原告製品形態の周知性が否定されるものではない。加えて,被告は,需要者は,原告製品をその形態によって識別しているのではなく,キングブレードという名称とともに,そのロゴ及びマークによって原告製品と識別していたものであると主張するが,テレビ番組の視聴者が,同番組において使用されたペンライトの形態を見て原告製品であ ると認識したことは前記判示のとおりであり,需要者はその形態により原 告製品と識別し得たというべきである。
オ 以上によれば,原告製品形態は,平成24年10月時点において,また, 遅くとも平成25年1月までに,周知性を獲得したものと認められる。
3 争点(3)(原告製品と被告製品との混同のおそれの有無)
(1) 被告製品は,原告製品形態の全てを備えるのみならず,原告製品のX10 シリーズのバージョン2以降のものと基本的に同一の形状及び大きさを有す るのであるから,需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれがあるもの と認められる。
(2) これに対し,被告は,原告製品と被告製品の名称が異なることなどを理由 に,混同のおそれを否定するが,需要者は,インターネットに掲載された商 品の形態を見てその出所を識別することも少なくないと考えられ,また,商 品名は新商品が発売されるたびに異なった名称が付されることもあるのであ るから,製品の名称が異なることから直ちに混同のおそれがないということ はできない。
(3) また,被告は,需要者は,知識が豊富な「オタク」であるから,ロゴやマ ーク,機能や価格帯などから製品を原告製品から被告製品を識別すると主張\nするが,一口に「オタク」といっても,その知識や経験は様々であり,需要 者にはコンサートなどの各種イベントへの参加者なども含まれるのであるか ら,需要者の性質から,当然に,製品の機能や価格帯により出所を識別する\nことができるということはできない。
(4) 以上のとおり,需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれはあるとい うべきである。 したがって,被告製品は,需要者の間に広く認識された原告の商品等表示\n(原告製品形態)と類似するものであり,原告製品と混同を生じさせるもの であるということができるので,被告製品を販売する行為は,不競法2条1 項1号の不正競争行為に該当する。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.02.27
平成30(ワ)39914 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月25日 東京地方裁判所
上記(ア)によれば,乙12公報には,情報ユニット及び識別ユニット のそれぞれが有する2個のデータの比較によって,情報ユニットの認証 処理をするという技術的事項が開示されているということができる。そ して,乙12発明は,乙11発明と技術分野及び課題が共通しているの であるから,当業者にとって,乙11発明に前記の技術的事項を適用し, 使用者が入力するパスワードを含む3つのデータの演算による認証処理 に代え,本件発明のように,2個のデータの比較による認証処理を採用 することは,容易に想到し得たというべきである。 ウ これに対し,原告は,乙11発明において,パスワードを含む3つのデ ータを用いた複雑な構成にすることは,その課題解決にとって不可欠なも\nのであるので,乙11発明に乙12発明を組み合わせる動機付けは存在し ないと主張する。 しかし,乙11発明は,携帯電話等にパスワードを設定するのみでは不 正使用の防止としては十分ではないという課題を解決するため,IDカー\nド等の携帯電話以外の物体に記憶されたデータを利用し,携帯電話等に予\nめ記憶されたデータとの間で比較・照合することにより,不正使用を防止 しようとするものであって,この点において,本件発明及び乙12発明と その技術的な思想を共通にしているということができる。 もとより,乙11発明は,携帯電話等に記憶されたデータとICカード に記憶されたデータという二種類のデータを使用するにとどまらず,使用 者が入力したパスワードも加えて比較・照合を行う点で本件発明と異なる が,これは,比較・照合に使用するデータを更に一種類増やすことにより 安全性を高めようとしたものであって,上記技術思想と基本的に異なるも のではなく,また,乙11公報には,IDカード6と携帯電話1との間で データの授受がある限りパスワードの再入力をする必要がないようにする など(乙11公報の段落【0014】),パスワードの入力作業により生 じる操作の煩瑣性の軽減という課題も示唆されているということができる。 そして,本件明細書等の段落【0028】に記載されているように,3 つのデータを利用する代わりに2つのデータを利用したとしても,一意な データを複数組み合わせたものやこれを暗号化したものを照合用データと して利用するなど,様々な工夫をすることにより不正使用の防止という課 題を解決することは可能であるから,乙11公報に接した当業者は,操作\nの煩瑣性を軽減するため,3つのデータを利用する代わりに,乙12公報 に開示されているような2つのデータによる比較・照合する構成を容易に\n想到し得たというべきであり,かかる構成を採用したとしても,上記のと\nおり,不正使用の防止という効果を奏することが可能であることを十\分に 認識し得たものと考えられる。 したがって,相違点Cに係る構成は,乙11発明に乙12発明を適用す\nることにより,当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(8) 相違点Dについて
相違点Dに関し,乙11公報には,「携帯電話1の電源を投入した時ある いは通話のためにキー5を押したときに携帯電話1より第1の電波信号送受 信装置3を介して電波信号Aを送信する。IDカード6は電波信号Aを受信 するとIDカード6にあらかじめ記憶されたデータ9を,電波信号Bを介し て自動的に送信する。・・・IDカード6より受信したデータ9と,パスワード として入力されたデータ10と,第1のデータ読み取り装置2内にあらかじ め記憶されたデータ11とを比較し,データ9とデータ11との和がデータ 10になる場合にのみ携帯電話1が使用可能である。」(段落【001\n2】),「携帯電話1の電源が投入されている状態のとき,計時装置4は電 源が投入されてからの時間を計時する。計時装置4の計時時間をもとに,… 一定時間…ごとに第1のデータ読み取り装置2内にてデータ11を書き換え, 同時にIDカード6に電波信号Aを送信し,IDカード6内のデータ9を書 き換える。携帯電話1とIDカード6との間でデータのやりとりが行われ, データ9とデータ11の和がデータ10になるときは常に携帯電話1を使用 可能にする。・・・携帯電話1とIDカード6の距離が離れていると,IDカー\nド6からデータ9が送信されることはない。ここでデータ9の送信がなけれ ば自動的に電源が切れ,携帯電話1の使用を不可能にする。」(段落【00\n13】)との記載がある。 上記記載によれば,乙11発明においては,最初に携帯電話の電源を投入 した際の演算結果を満たせば,少なくとも一定時間,携帯電話の使用が可能\nになるものと認められる。そして,携帯電話1の電源の投入は本件発明の 「アクセス要求」に相当するから,乙11発明は,「アクセス要求が許可さ れてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」 構成を備えるということができる。\nしたがって,相違点Dは,実質的な相違点には当たらない。
・・・・
3 争点3−3(乙16に基づく拡大先願違反) また,念のため,争点3−3も検討するに,以下のとおり,本件発明は,い わゆる拡大された先願と同一の発明にも当たるということができる。
・・・・
原告は,「本件発明は,被保護情報に対するアクセス要求を許可する という比較結果が得られた場合は,アクセス要求が許可されてから所定 時間が経過するまでは被保護情報へのアクセスを許可するものであるの に対し,乙16発明は,動作処理要求に伴った一連の操作が前記携帯電 話機に対して行われると個人認証を行い,個人認証が完了すると当該一 連の操作のみが可能になるのであって,当該処理中に他の処理を行うこ\nとも,当該処理が終了後に他の処理を行うこともできず,また,所定時 間を計時することもなく,所定時間が経過するまで携帯電話機内の情報 に対するアクセスを含む何らかの操作を許可するものではない点」にお いて相違すると主張する。
(イ) そこで,検討するに,乙16公報の段落【0035】には,「制御部 11は,比較認証の結果が一致していた場合,前記ステップST4にお けるキー入力は,特定の使用者(使用が許可されている携帯電話機使用 者)によるキー入力であるものと判断し,ロック解除状態とし,前記ス テップST4にて入力装置14から入力された発信操作及びメモリダイ ヤル等の操作を有効として(ステップST9),発信処理等を継続する (一連のキー入力による処理が完了するまでの処理の継続を可能とす\nる)。」との記載がある。これによれば,乙16発明においては,被保 護情報へのアクセスが許可されると,「一連の処理が完了するまでの」 時間,アクセスが許可されるものということができる。 他方,本件発明の構成要件Fは,「前記アクセス制御手段は,当該比\n較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は, 前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保 護情報へのアクセスを許可する」というものであり,「所定期間」に関 する限定は付されていない。 また,本件明細書等の段落【0120】及び【0121】には,アク セスが許可されると,タイマに所定の時間t2を設定し,時間t2が経 過するまでに開始した処理が終了した場合には,時間t3をタイマに設 定し,時間t3が経過するまでに次の作業を開始した場合には,レッド バッジの読み込みをすることなく,引き続き次の作業を行うことができ, 更に一つの作業が終了するたびにt3が起動されることが記載されてい るものと認められる。これによれば,本件発明においても,アクセスが 許可された後,一連の作業が継続している間は,アクセスが許可されて いるということができる。 以上によれば,乙16発明における「一連の処理が完了するまでの」 時間も,構成要件Fの「所定時間」に当たるというべきである。\n
(ウ) これに対し,原告は,乙16発明は,一連の処理中に他の処理を行う ことも,当該処理が終了後に他の処理を行うこともできず,また,所定 時間を計時することもなく,所定時間が経過するまで携帯電話機内の情 報に対するアクセスを含む何らかの操作を許可するものではないので, 本件発明と異なると主張する。 しかし,前記判示のとおり,乙16発明においては,「一連の処理が 完了するまでの」時間は,被保護情報へのアクセスが許可されているの であるから,仮にその間に他の処理を行うことができないとしても,構\n成要件Fの「前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するま では前記被保護情報へのアクセスを許可する」との構成を満たすとの結\n論を左右するものではない。 また,構成要件Fの「所定期間」には特段の限定は付されていないの\nで,これを計時された一定の長さの時間に限定されると解することもで きない。
2020.02.27
平成31(行ケ)10010 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月25日 知的財産高等裁判所
特許法29条の2は,特許出願に係る発明が,当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって,当該特許出願後に特許掲載公報,実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「先願 明細書等」という。)に記載された発明又は考案と同一であるときは,その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は,先願明細書等に記載されている発明は,特許請求の範囲以外の記 載であっても,出願公開等により一般にその内容は公表されるので,たとえ先願が\n出願公開等をされる前に出願された後願であっても,その内容が先願と同一内容の 発明である以上,さらに出願公開等をしても,新しい技術をなんら公開するもので はなく,このような発明に特許権を与えることは,新しい発明の公表の代償として\n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない,というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは,先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい,記載されて いるに等しい事項とは,出願時における技術常識を参酌することにより,記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。 したがって,特に先願明細書等に記載がなくても,先願発明を理解するに当たっ て,当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方, 抽象的であり,あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示 が不十分であるような発明は,ここでいう「発明」には該当せず,同条の定める後願\nを排除する効果を有しない。そして,ここで求められる技術内容の開示の程度は, 当業者が,先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理\n解し得る程度に記載されていれば足りるというべきである。
(イ) これを本件についてみると,引用発明1の実施例1〜3には,引用発明1 の(i)〜(iii)の各ベクターを製造する方法が詳細に記載されており,実施例4に は,ドナー配列(GFP遺伝子)が標的配列又はその近傍に組み込まれていること を確認するための具体的な試験方法も明記されている。 また,前記のとおり,実施例4の実験結果から,核局在化シグナルを含むRNA 誘導型エンドヌクレアーゼ,ガイドRNA,ドナーポリヌクレオチドの組合せが, 真核細胞に組み込まれ,標的部位にて二本鎖の切断及び修復が生じていると理解す ることができ,実施例5の実験結果も上記の理解の妨げになるものとは解されない。 さらに,上記(i)〜(iii)のベクターを含むベクター系は,真核細胞内で適切に 転写,翻訳,核移行等がなされるに必要な技術手段,及び,真核細胞内で適切に標的 配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであるから,ベクター系にし た場合でも,真核細胞中の標的配列を開裂し,標的配列の改変を行う機能を有する\nものと理解できることも,上記のとおりである。 そうすると,引用例1には,当業者が,先願発明がそこに示されていること及び それが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるといえるから,「ガイドR\nNAが,II型Cas9タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導 し,そこで該II型Cas9タンパク質が,該標的部位にて染色体DNA二本鎖の 切断を誘導し,該二本鎖の切断が,染色体配列が修飾されるようにDNA修復過程 により修復される」機能の部分も含めて,後願を排除するに足りる程度の技術が公\n開されていたものと認めるのが相当である。
エ 原告らのその他の主張について
(ア) 原告らは,引用例1の優先基礎明細書(甲105)によれば,実施例4に「ド ナー配列の挿入および融合タンパク質の発現が確認された」という文言がなく,実 施例4で採用されたFACSだけでは,検出された蛍光が標的部位への組込み以外 の他の要因によるものでないことが示されているとはいえず,また,対象と比較し て約10倍以上の蛍光が検出されなければ,標的部位への組込みが生じていないと 理解すべきであるとして,これに沿う研究者の意見書(甲103)を提出する。しか し,引用例1に記載された実験結果について,技術内容の開示が不十分であるとま\nではいえない。 原告らは,実施例5のPCR実験の結果で,処理DにおいてPCR産物が確認さ れなかったことから,標的部位にはドナー配列の遺伝子が組み込まれなかったこと が示されていると主張するが,実施例5の処理Dにおいては,前記イ(ウ)のとおり, ガイドRNAや標的配列などの違いにより,ゲノム改変効率が不足していた結果と して,所定のゲル上のバンドが検出されなかった可能性があるから,実施例5の処\n理Dの結果から,引用発明1のベクター系が,標的配列にドナー配列(GFP遺伝 子など)を組み込む機能を有することまで否定されないと解すべきである。\n
(イ) 原告らは,当業者であれば,引用例1のFACS実験とPCR実験により得 られた矛盾する結果を検討し,CRISPR−Cas9システムが真核細胞におい て作動するか否かの疑問は未解決であると結論したはずである,あるいは,他の科 学者らが他の技術又は構築物を用いて真核細胞で成功を収めることができたことに\n基づいて引用例1の実験が成功したと推論することもできないとも主張する。 しかし,実施例4の実験結果は,核局在化シグナルを含むRNA誘導型エンドヌ クレアーゼ,ガイドRNA,ドナーポリヌクレオチドが,真核細胞に組み込まれ,標 的部位において二本鎖の切断及び修復が生じていることを理解するに足りるもので あるし,実施例5の実験結果も上記の理解の妨げになるものとまでは解されない。 また,引用発明1の(i)〜(iii)のベクターを含むベクター系は,前記イ(オ)の とおり,真核細胞内で適切に転写,翻訳,核移行等がなされるに必要な技術手段,及 び,真核細胞内で適切に標的配列の改変がされるに必要な技術手段を備えるから, 引用発明1のベクター系が,真核細胞中の標的配列を開裂し,当該標的配列の改変 を行う機能を有するものと理解することができ,引用例1には,引用発明1の実施\nが可能であることを理解するに足りる記載がある。\nそうすると,引用発明1において,CRISPR−Cas9システムが真核細胞 でも作動するか否かが解決していないとはいえない。
(ウ) 原告らは,本願発明は,CRISPR−Cas9システムを真核細胞内環境 において真核生物のゲノムDNAに適合させるガイダンスを開示しているとして, 引用例1のCRISPR−Cas9系との機能の相違を強調するが,本願発明は,\n請求項1の記載から判断して,Cas9に複数のNLSを付加する,tracrR NAを長くする,キメラRNAの3’末端にターミネーターとして例えばポリTを 挿入する等の選択を行ったものではなく,むしろ,本願発明と引用発明1は,発明 の構成上,共通のベクターを含むベクター系を使用するものである。\n両者の相違を強調する原告らの主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2020.02.27
平成31(行ケ)10011 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月25日 知的財産高等裁判所
(相違点)
本願発明は「tracr配列が,30以上のヌクレオチドの長さを有」するもの であると下限値が特定されているのに対して,引用発明1では,本願発明の「tr acr配列」に相当する部分の長さについて明確な特定はなく,「第二及び第三領域」 の合わせた長さが「約30から約120ヌクレオチド長の範囲」である点。
(5)相違点の検討
ア 特許法29条の2は,特許出願に係る発明が,当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって,当該特許出願後に特許掲載公報,実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「先願 明細書等」という。)に記載された発明又は考案と同一であるときは,その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は,先願明細書等に記載されている発明は,特許請求の範囲以外の記 載であっても,出願公開等により一般にその内容は公表されるので,たとえ先願が\n出願公開等をされる前に出願された後願であっても,その内容が先願と同一内容の 発明である以上,さらに出願公開等をしても,新しい技術をなんら公開するもので はなく,このような発明に特許権を与えることは,新しい発明の公表の代償として\n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない,というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは,先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい,記載されて いるに等しい事項とは,出願時における技術常識を参酌することにより,記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。
イ 本願明細書の【0162】には,tracr配列の長さとゲノム改変効率の 関係について,「EMX1およびPVALB遺伝子座中の5つ全ての標的について, tracr配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察された」と の一般的な説明がなされ,特に,ゲノム改変効率の増加が優れるものとして,nが 67,85,すなわちtracr配列の長さが45,63のキメラRNAをとりあ げて,「野生型tracrRNAのより長い断片を含有するキメラRNA(chiR NA(+67)及びchiRNA(+85))は,3つ全てのEMX1標的部位にお けるDNA開裂を媒介し,特にchiRNA(+85)は,ガイド及びtracr配 列を別個の転写物中で発現する対応するcrRNA/tracrRNAハイブリッ ドよりも顕著に高いレベルのDNA開裂を実証した(図16b及び17a)。ハイブ リッド系(別個の転写物として発現されるガイド配列及びtracr配列)を検出 可能な開裂を生じなかったPVALB遺伝子座中の2つの部位も,chiRNAを\n使用してターゲティングした。chiRNA(+67)及びchiRNA(+85) は,2つのPVALBプロトスペーサーにおける顕著な開裂を媒介し得た(図16 c及び17b)。」との説明が加えられている。 そして,本願明細書の図16や図17を参照すると,プロトスペーサー1やプロ トスペーサー3を標的とした場合については,nが+67,+85である場合のみ ならず,nが+54,すなわちtracr配列の長さが32のキメラRNAである 場合も,nが+48,すなわちtracr配列の長さが26のキメラRNAを上回 る改変効率が得られていることを見て取ることができ,本願発明がtracr配列 につき30以上のヌクレオチドの長さに設定したことによって引用発明1とは異な る新たな効果を奏していることも理解できる。 このように,本願発明は,「tracr配列の長さ」に着目し,「tracr配列 が,30以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによ\nって,ゲノム改変効率が増加することを特徴とするものである。 他方,引用例1には,ガイドRNAが第一領域から第三領域までの3つの領域を 含むこと(【0067】),ステムの長さは約6から約20塩基対長であってよいこと (【0069】),一般的に,第三の領域は,約4ヌクレオチド長以上であり,例えば,第三の領域の長さは,約5から約60ヌクレオチド長の範囲であるとすること(【0 070】),ガイドRNAの第二及び第三領域の合わせた長さは,約30から約12 0ヌクレオチド長の範囲であり得ること(【0071】)が記載されているにすぎな い。
ウ また,本願明細書【0063】の「ループの3’側の配列の部分は,trac r配列に対応する」の記載によれば,本願発明のtracr配列は,引用発明1の 第二領域の片方のステムと第三領域を合わせたものに相当すると認められる。しか し,引用例1には,tracr配列(第二領域の片方のステムと第三領域を合わせ たもの)の長さそれ自体を規定するという技術思想が表れてはいない。\nさらに,本願優先日当時,tracr配列の長さを30以上のヌクレオチドの長 さとするとの当業者の技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。 エ よって,引用例1に「tracr配列が,30以上のヌクレオチドの長さを 有」するものという構成を採用したことが記載されているといえないし,技術常識\nを参酌することにより記載されているに等しいともいえない。
(6) 被告の主張について
被告は,26ヌクレオチド長のtracr配列を有するガイドRNA(+48) と,32ヌクレオチド長のtracr配列を有するガイドRNA(+54)とで,プ ロトスペーサー2,4及び5を標的としたものでは差異を見出せない(図16,図 17)とした上,30以上のヌクレオチド長と特定する本願発明においては,標的 配列に依存することなく,改変効率が向上するとの効果を有しているとはいえない として,本願発明は,引用発明1と異なる新たな効果を奏すると認めることはでき ないと主張する。 しかし,前記のとおり,本願明細書によれば,プロトスペーサー1やプロトスペ ーサー3という異なる標的配列に対して,32ヌクレオチド長のtracr配列を 有するキメラRNAが,26ヌクレオチド長のtracr配列を有するキメラRN Aよりも,ゲノム改変効率が増加していることが記載されており,tracr配列 について30以上のヌクレオチド長であることを特定する本願発明は,プロトスペ ーサー1やプロトスペーサー3以外においても真核細胞のゲノム改変効率が向上す る可能性がないということはできない。\nしたがって,被告の主張は,理由がない。
(7) 小括
以上のとおり,本件審決において本願発明と引用発明1との一応の相違点として 挙げられた「tracr配列が,30以上のヌクレオチドの長さを有」することは, 実質的な相違点であり,本願発明と引用発明1とが同一の発明であるとは認められ ないから,本願発明につき特許法29条の2の規定により特許を受けることができ ないとした本件審決の判断には誤りがある。
・・・
(4)相違点4の判断について ア 引用例2には,全長成熟(42ヌクレオチド)crRNAと,5’又は3’末 端で配列が欠如した様々な切断型のtracrRNAを組み合わせて再構成された\n二本鎖のCas9−tracrRNA:crRNA複合体を用いた試験において, 天然配列のヌクレオチド23〜48(tracr配列のヌクレオチド長は26)を 保持しているtracrRNAがCas9によるDNA切断に有効であることが示 されている(前記(1)ウ,ク,図3A)。 また,tracrRNA:crRNAは一本鎖のキメラRNAに設計でき(前記 (1)ア),ヌクレオチド23〜48を保持した長いキメラA(tracr配列のヌクレ オチド長は26)が,二本鎖のtracrRNA:crRNA複合体を用いた場合 と同じような挙動でCas9によるDNA切断を誘導したこと,他方,短いキメラ B(tracr配列のヌクレオチド長は18)の場合には,DNA切断を誘導でき なかったこと(前記(1)エ,オ,図5B)が示されている。 以上の引用例2の実験結果に接した本願優先日の当業者は,26ヌクレオチド長 よりも短いtracr配列は,Cas9の開裂効果が劣ることから,Cas9タン パク質による標的配列の開裂には,少なくとも,天然配列の23〜48を保持した 26ヌクレオチド長のtracr配列を含む必要があることを理解する。 ところが,tracr配列の長さについては,26ヌクレオチドより短い場合と の比較では,長い26ヌクレオチドの方が好ましいことは理解できるものの,引用 例2には,26ヌクレオチドより長い場合で比較した場合に,より長さの大きいt racr配列の方が好ましいことを示す記載は,見当たらない。 加えて,本件全証拠によっても,本願優先日当時,tracr配列の長さが大き ければ大きいほど好ましいことを示す技術常識が存在したことを認めるに足りない。
(イ) 一方,本願明細書の【0162】によると,tracr配列の長さとゲノム 改変効率の関係について,「EMX1およびPVALB遺伝子座中の5つ全ての標的 について,tracr配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察 された」との一般的な説明がされ,本願明細書の図16や図17から,プロトスペ ーサー1やプロトスペーサー3を標的とした場合に,tracr配列の長さが32 のキメラRNAの方が,tracr配列の長さが26のキメラRNAよりも,ゲノ ム改変効率に優れていると理解することができる。 そうすると,引用例2の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても,ゲノムの改 変効率を向上させる観点で,引用発明2のtracrRNAの長さについて,引用 例2に具体的に開示されている26から30以上に変更することを,当業者が動機 付けられていたということはできない。
(ウ) また,本願優先日当時,引用例2の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免 疫に由来するCRISPR/Cas系(前記(1)ア)を,緩衝液中での混合(試験管レ ベル)でなく,真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献 は存在しておらず,tracr配列の長さを30以上に設定するという技術手段を 採用することで,真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は,当業 者の期待や予測を超える効果と評価することができる。\n
(エ) したがって,相違点4として挙げた本願発明の発明特定事項,すなわち「t racr配列」について,「30以上のヌクレオチドの長さ」とすることは,引用例 2の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても,当業者が容易に想到し得たとはい えないものである。
イ 被告の主張について
被告は,引用例2の記載から,23〜48の26ヌクレオチド長を含むtrac rRNAであれば,その5’末端側や3’末端側にさらにヌクレオチドが存在して も,Cas9によるDNA切断を誘導できると理解することができるとした上,引 用例2には5’末端側や3’末端側にヌクレオチドを付加してさらに長くすること を妨げる記載はなく,図3Aには,上記最小領域のほか,「15−53」,「23− 89」,「15−89」の領域からなるさらに長いtracrRNAも,crRNA と共に用いることでCas9によるDNA切断を誘導できることが示されていると して,引用発明2のうち「tracrRNA」を多少長くして30ヌクレオチド長 程度のものとすることは,当業者が適宜なし得たことであると主張する。 しかし,図3Aには,長いtracrRNAをcrRNAと組み合わせて二本鎖 として用いた実験結果が示されるものの,特に長いtracrRNAの方が標的配 列の開裂に優れることは開示されていない。また,引用発明2のtracr配列の 長さを26から30にするには,15%以上長くする必要があるから,これが多少 長くした程度のものであるとはいえない。さらに,上記のとおり,本願優先日当 時,tracr配列の長さが大きければ大きいほど,好ましいことを示す技術常識 は存在せず,真核細胞にCRISPR/Cas系を適用したことを報告する技術論 文,特許文献も存在しなかったことからすれば,tracr配列の長さを30以上 に設定することに伴い真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は, 当業者の期待や予測を超えるものと評価されるというべきである。\n
◆判決本文
下記は出願人の一部が一致するCrispr-Casの関連事件ですが、こちらは拒絶審決が維持されています。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2020.02.25
平成31(ネ)10033 パブリシティ権侵害等差止等・著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和2年2月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1)原判決を引用して認定した事実経過によれば,本件事案には,次のような 事情がある。
(2) 両当事者は,平成9年から平成25年までの間,本件ブランドを用いた日 本での婦人服販売事業のための契約関係にあり,本件ブランドの知名度の向 上について共通の利益を有していた。被告各表示の素材となった一審原告X\nの肖像写真及び紹介文並びに被告写真に複製された原告写真は,上記事業に おける本件ブランドの宣伝広告の目的のために,一審原告側から提供された 素材である。そして,その提供に当たっては,当時の両当事者は協力関係に あったという背景から,使用の目的,態様及び期間等について,文書等によ る明確な取極めはなされていなかった。 平成25年の修正サービス契約の解除(本件解除)により両当事者間の契 約関係が解消された時点において,これらの素材は,被告ウェブサイト上及 び店舗内の被告各表示及び被告写真として現に用いられていた。そのことは,\n一審原告側においても了知していた可能性が高いし,仮に了知していなかっ\nたとしても,被告ウェブサイトの閲覧及び店舗の訪問によって容易に知りう る状態にあった。
契約関係の解消後も,一審被告は,日本国内のJS商標を既に譲り受けて いた以上,本件ブランドの下での婦人服販売事業をそれ以前とほぼ同じ態様 で継続することが可能であり,そのことは一審原告側も了知していた。また,\n乙7の終了合意書が締結された平成14年以降,同事業における商品のデザ インや宣伝広告の手法等について,一審原告側は具体的に関与する権利を失 っていたから,本件解除によりすべての契約関係が解消されたからといって, 一審被告が被告ウェブサイトを改修するなどして宣伝広告の内容を改めるべ き事業上の必然性はなかった。そうすると,契約関係の解消後も,被告各表\n示及び被告写真をそれまでと同様に使用し続けることを,一審被告は予定し\nており,一審原告側も,これを予想していたか少なくとも予\想し得たといえ る。
また,JS商標は一審原告Xの氏名と同一であるから,JS商標及び各商 標に関連するグッドウィルを商標権譲渡契約によって譲り受けた上で行う一 審被告の事業活動は,その需要者層に,一審原告X個人がこれに関与してい るとの認識又は印象を必然的に生じさせるものであったといえる。このよう な状況は,契約関係の終了後においても直ちに変わるものではない。
(3) このように,本件事案は,長期間にわたり契約関係にあった当事者が,必 ずしも明確に定めてこなかった事柄が問題となり,それが原因となってパブ リシティ侵害行為,著作権侵害行為及び不正競争行為(いずれも法的性質と しては不法行為)として損害賠償等が請求されている,というものである。 そうすると,権利侵害の成否や損害額の算定の判断に当たっても,契約関係 にない権利者と侵害被疑者との間の訴訟におけるものとは異なり,契約関係 にあった当時の事情を踏まえた合理的な意思解釈が必要とされる。 (4) そして,当裁判所は,上記(3)のような観点に立った上で,原審の判断は是 認し得ると考え,原判決を引用して上記1のとおり判断するものである。
3 両当事者の当審における主張に対する判断
・・・
ア パブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害について
原判決の認定した100万円という損害額につき,一審原告会社は高額 に過ぎる旨主張し,一審被告は低額に過ぎる旨主張する。 そこで検討するに,本件においては,以下のような事情を考慮する必要 があると考えられる。すなわち,
(ア) 本件証拠中,例えば甲28には,一審原告Xについて,「世界12ヶ 国に進出。どの国でも高い人気を獲得している。」という記載がある一 方で,「日本は世界最大のマーケット」という記載もある(前者につい ては甲27,後者については甲27,29,30にも同旨の記載があ る。)。 そして,後掲各証拠(いずれも枝番含む)によれば,「世界12ヶ国 に進出」というその実態は,一審原告Xの生地である米国ニューヨーク 市のソーホー地区に平成5年ころから直営の実店舗を有している(乙1\n0)ほかは,米国を含む各国のデパート等に断続的に商品を卸したり (甲134),ネットショップに商品が掲載されたり(甲117〜12 1,133)しているにとどまる。一審原告側が運営するウェブサイト には,店舗の所在場所として18か国のデパート等が挙げられているが (甲122),その中には商品の実際の取扱いを確認できないものが多 い上(乙39ないし45),取扱いがある場合でもデパートの店内に本 件ブランドを冠した売場を確保してはいない(乙11,48)。そして, 一審原告側が主要国の大都市の目抜き通りに独自の路面店を構えている\nこと等を示す証拠は見当たらない。 なお,一審原告Xの日本国外での活動に関する証拠(甲2〜7,10 1〜116)はいずれもウェブサイトへの掲載であるところ,ウェブサ イトは,紙媒体と異なり,掲載可能な記事数が極めて多い媒体である。\nまた,一審原告Xが出展したファッションショー(甲103〜109, 111〜115)は,いわば「地元」であるニューヨーク市でのもので ある上に,出展料を支払えば参加資格に制限はない(一審被告前代表者\n本人尋問)。
(イ) 一審原告Xの世界的な名声については上記(ア)のとおり一定の留保を付 けざるを得ないのに比して,日本国内での名声(特に被告商品の需要者 層におけるもの)は,それなりに高いと認められる。 もっとも,本件ブランドの日本での立上げ以前から一審原告Xが日本 の需要者層に広く知られていたことを示す証拠は見当たらないのに対し, それ以降は一審被告を先駆けとする各ライセンシーが本件ブランドのビ ジネスに深く関わってきたことからすれば,日本における一審原告Xの 名声には,各ライセンシーによるマーケティングの成果という側面が多 分にある。一審原告Xの日本国内での名声を示すものとして一審原告側 から提出されている証拠(甲8〜10,27〜34,83,84,16 2,214〜470等)も,各ライセンシーによる上記と同様のマーケ ティングに影響されたものである可能性がある(例えば,外見上は出版\n社が編集したムックである甲8にも,Editorial cooperatorとして,複 数名の一審被告の関係者が関与している(5頁)。) そして,各ライセンシーがそのマーケティングに当たり,一貫して, 一審原告Xを被告表示2〜4のとおりの容貌・経歴・信条を有する人物\nとして需要者層に印象付けようと努めてきたことは本件各証拠から明ら かであるから,一審原告Xが「世界的に有名な」ファッションデザイナ ーであるとの名声が日本において形成されるについては,各ライセンシ ーの寄与,中でもその先駆けである一審被告の寄与が相当程度に大きか ったと認められる。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)の事情によれば,一審原告Xの肖像等が顧客誘引力を有 し同人にはパブリシティ権が認められるとしても,それらは,いわゆる 超一流のファッションデザイナー(例えばB,C,Dにつき甲44,5 4,56)のものと同列ではないし,パブリシティ権の形成に当たって 一審被告がライセンシーとして寄与してきたという経緯を考慮すべきで ある。
(エ) 一審原告らは,一審原告Xのパブリシティ権の価値が高く,その侵害 による損害が大きい旨の主張を裏付けるため,過去の裁判例及び文献の 記載を多数援用する(甲85,131,166〜169,194〜20 0,473等)。しかしながら,過去においてパブリシティ権の価値が 検討された事案の多くは,きわめて知名度が高い権利者(その多くは, 知名度の高さが「公知の事実」に近いような芸能人,運動選手等であ\nる。)の名称及び肖像等が有する顧客誘引力を,その知名度の形成に寄 与していない他者が利用した事案であるから,これらの事案を通じて形 成された法理論及びマーケティング理論並びに個別の事案における裁判 所の判断は,本件にそのまま適用できるものではない。もっとも,一審 原告Xの我が国における認知度は,それなりに高いことからすると,そ の形成に当たって一審被告の貢献が大きいことを考慮しても,パブリシ ティ権侵害に対する損害賠償の額を余りに少額とすることもまた相当で はないというべきである。 上記(ア)〜(エ)で検討した点を踏まえると,一審原告Xのパブリシティ侵害 によって生じた使用料相当損害の額は,原判決が説示するとおり,100 万円と評価するのが相当であって,これに反する一審原告会社及び一審被 告の主張は,いずれも採用することができない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 肖像権等
>> その他
>> ピックアップ対象
2020.02.25
平成30(ワ)12609 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月9日 東京地方裁判所
被告は,(1)乙2公報は,音響IDとインターネットを用いて,放音装置から放音 された音響IDによって識別される識別対象の情報に対し,これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙2技術を開示しているところ,本件 発明1も乙2技術を採用するものであり,相違点1−1ないし同1−4は,識別対 象,複数の関連情報の選択条件,関連情報の内容に係る相違にすぎず,当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに,(2)当業者は,乙2技術を乙4課題の 解決に応用して,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成を容易に想到し得た旨主張する。\n
しかしながら,まず,被告の上記(1)の主張については,前記1(2)認定のとおり, 本件発明1は,コンピュータを,(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段,(ii)サーバに対し,抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段,(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し,情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求\nの言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段,(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明であり,乙2公報等に音響IDとインターネットを利用するという点で本件発明1と\n同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても,その手順や方法を具体的に特定し,使用言語が相違する多様な利用者が理解可能\な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。\nまた,被告の上記(2)の主張については,前記イのとおり,乙4公報に,発明が解 決しようとする課題の一つとして,システムを複数の言語に対応させること(以下, 単に「乙4発明の課題」という。)が記載されているものの,以下のとおり,乙2 発明1を乙4発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず,仮に,乙4発明の 課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなどして乙2発明1の構\成に変更を加え たとしても相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成に到達しないから,採用することができない。\n
(ア) 乙2発明1を乙4発明の課題を組み合わせる動機付け
a 前記のとおり,乙2発明1は,放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり,放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響IDを用い,ID解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し,前記イ(イ)のとおり,乙 4発明は,利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり,展示物に固有のIDを赤外線 等の無線通信波によって発信し,携帯受信器が発信域に入ると上記IDを受信し, 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり,サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから,両発明は,想定される使用場面や発明の基本的な構\成が異なっており,乙2発明1を乙4発明の課題に組み合わせる動機付けは認められない。
b 被告は,(1)乙4発明は,放音装置を利用した情報提供技術という乙2技術と 同じ技術分野に属するものであること,(2)乙2技術は汎用性の高い技術であり, 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと(乙11ないし13),(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と(乙2,5,6,8,11ないし13等)などによれば,当業者において,乙2 技術を乙4課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら,乙2発明1と乙4発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ,また,本件優先日1当時,音 響IDとインターネットを利用し,又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙2公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても,いず れも乙4発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記のとおりであり,乙4発明の課題の解決のみを取り上げて乙2発明1を適用する動機\n付けがあると認めるに足りない。
(イ) 乙2発明1に対する乙4発明等の適用
また,以下のとおり,乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなどして乙2発明1の構\成に変更を加えたとしても,本件発明1の構成に到達しない。\n前記第2の2(2)ア(ウ)認定の特許請求の範囲,前記(1)認定の本件明細書1の発明 の詳細な説明,図面,弁論の全趣旨に照らすと,本件発明1は,概要,以下のとお りのものであると認められる。
ア 本件発明1は,端末装置の利用者に情報を提供する技術に関する(【0001】)。
イ 従来から,美術館や博物館等の展示施設において利用者を案内する各種の技 術が提案されていたが,各展示物の識別符号が電波や赤外線で発信装置から送信さ れるものであったため,電波や赤外線を利用した無線通信のための専用の通信機器 を設置する必要があった。本件発明1は,そのような問題を踏まえてされたもので あり,無線通信のための専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供 することを目的とする(【0002】,【0004】)。
ウ 本件発明1は,(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ\nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段,(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段,(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段,(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより,赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに,案内音声である再生対象音の識別情報に対\n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする(【0005】)。
エ 以上に加えて,本件発明1は,前記送信手段が,当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し,前記受信手段が,情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用するこ\nとにより,相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指 定された言語に対応する関連情報を受信することができ,使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである(【0\n006】等)。
2 本件アプリの広告等について
証拠(甲6,7)によれば,次の事実が認められる。
(1) 被告作成の「Sound Insight(サウンドインサイト)」と題す る本件アプリを用いたシステムに関する広告(甲6。以下「本件広告」という。) には,次のとおり記載されていた。
ア (1)「映像・音声にのせて,情報配信」,(2)「動画・音楽などの音に人間には 聞こえない音波信号(音波ID)を埋め込み,テレビ・サイネージ・スピーカー等 から再生し,スマートフォンアプリで音波信号(音波ID)を受信する事により, 紐づいた情報をスマートフォン上に自動表示」,(3)(音波信号に紐づく情報を表示\nする手順の一つとして)「映像・音声に重畳した音波信号を発する」
イ (1)「音で情報を配信」,(2)「『Sound Insight』は,人には聞 こえない音波信号(音波ID)を使い,映像や音に合わせてアプリを連動できます。 利用者が信号音を意識することなくスマートフォン上に情報を表示します。」\n
ウ 「多言語で配信可能 日本語のほか,英語,中国語,台湾語,韓国語,ロシ ア語など多言語で情報配信できます。」
エ (使用例の一つとして)「バスの車内案内では 多国語で停留所情報や地域 の情報を案内できます。」
(2) 本件アプリのダウンロード用のウェブサイト(甲7。「本件ダウンロードサ イト」という。)には,次のとおり記載されていた。 「『サウンドインサイト』は,空港,駅,電車,バスなどの様々な場所に設置さ れた各種スピーカーから送信された音波を,専用アプリをインストールしたスマー トフォンで受信することで,関連する情報を自動で表示させることのできるサービ\nスです。・・・『サウンドインサイト』の活用により,・・・外国人観光客へ空港・駅などのアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する『言語支援用途』・・・などで活 用いただくことができます。」
3 争点1(本件アプリは本件発明1の技術的範囲に属するか)について
(1)争点1−1(本件アプリは構成要件1Bを充足するか)について\n
ア 構成要件1Bに対応する本件アプリの構\成に係る事実認定
(ア) 前記第2の2(5)ア(ア)のとおり,本件アプリは,スピーカー等の放音装置か ら,識別情報であるIDコードを表す音響IDを含む音響が放音されると,これを\n収音し,当該音響IDからIDコードを検出するものとしてスマートフォンを機能\nさせるものであるところ,前記2(1)のとおり,本件広告には,「映像・音声にのせ て」,「動画・音楽などの音」に埋め込んで,「映像・音声に重畳」させて音響I Dを放音することが記載されているほか,使用例の一つとして,バスの車内案内で は多言語で停留所情報等を提供することができることが記載されていること,同(2) のとおり,本件ダウンロードサイトには,本件アプリは,空港,駅,電車,バス等 に設置された放音装置から送信された音波を,スマートフォンで受信することで, 関連する情報を自動で表示させることのできるサービスを提供するものであること\nが記載されていることなどからすると,被告から音響IDの提供を受けた顧客にお いて,案内音声を識別するものとしてIDコードを使用し,これを案内音声ととも に放音装置から放音することは,本件アプリにつき想定されていた使用形態の一つ であるというべきである。そうすると,本件アプリは「案内音声と当該案内音声を 識別するIDコードを含む音響IDとを含有する音響を収音し,当該音響からID コードを抽出する情報抽出手段」(構成1b)を備えていると認めるのが相当であ\nる。
(イ) 被告は,本件アプリが構成1bを備えていることを否認し,その理由として,\n(1)被告サービスにおいて,被告は,放音される音響やIDコードの識別対象を決定 しておらず,これらを選択,決定しているのは顧客であって,いずれも「案内音声」 に限られるものではないこと,(2)本件アプリの利用場面の中で,最も多くの需要が 見込まれているのは商品説明の場合であるが,商品説明において,放音装置から音 声が発せられることは必須ではなく,かえって,音声が放音されるとスマートフォ ンに表示される情報を理解する妨げになることを主張する。\nしかしながら,被告の上記(1)の主張は,構成要件1B所定の音響が放音されない\n場合があることを指摘するにとどまるものであり,前記(ア)のとおり,本件広告に おいても,案内音声を収音する使用形態を回避させるような記述はなく,むしろ, そのような使用形態を想定したものとなっていたというべきであるから,前記認定 を覆すに足りないというべきである。 また,被告の上記(2)の主張について,本件アプリにつき最も多くの需要が見込ま れていたのが商品説明の場面であったとしても,被告において,そのような使用形 態に特化したものとして本件アプリを広告宣伝していたものでもなく,前記認定を 覆すに足りない。
イ 構成要件1Bに係るあてはめ\n
以上の認定を踏まえて検討すると,構成1bの「案内音声」は,本件発明1の\n「案内音声である再生対象音を表す音響信号」に対応し,構\成1bの「案内音声を 識別するIDコードを含む音響ID」は,本件発明1の「案内音声である再生対象 音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号」に対応する。 そして,本件発明1は,コンピュータを所定の手段として機能させるプログラム\nに係る発明であり,構成要件1Bは,放音された所定の音響を収音した収音信号か\nら識別情報を抽出する情報抽出手段を規定するものであるから,構成要件1B所定\nの音響が放音された場合に,これを収音し,識別信号を抽出する手段としてコンピ ュータを機能させるプログラムであれば,これと異なる用途でコンピュータを機能\ させ得るとしても,又は音響が放音されない場面があるとしても,同構成要件を充\n足すると解すべきところ,本件アプリは,同所定の音響を収音し,当該音響からI Dコードを抽出するものとしてスマートフォンを機能させるものであるから,放音\nされる音響やIDコードの識別対象を選択しているのが顧客であり,音響が放音さ れない使用方法が選択され得るとしても,構成要件1Bを充足する。\n
(2)争点1−2(本件アプリは構成要件1Dを充足するか)について\n
ア 構成要件1Dの「関連情報」の言語の解釈\n
(ア) 構成要件1Dは,「関連情報」について,「前記案内音声である再生対象音\nの発音内容を表す関連情報であって,前記情報要求に含まれる識別情報に対応する\nとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求の言語情報 で指定された言語に対応する関連情報」と規定しているから,「関連情報」の言語 は,相異なる言語に対応するものの中から情報要求の言語情報で指定された言語に 対応するものと解すべきである。
(イ) 被告は,「関連情報」は,第1言語で発音される案内音声の発音内容を第1 言語で表した文字列であると解すべきであるとし,その理由として,原告が本件訂\n正審判請求1の際に訂正事項が明細書の記載事項の範囲内であることを示す根拠と して本件明細書1の【0041】を挙げていたことを指摘するが,構成要件1Dは\n上記のとおりのものであるから,「関連情報」が案内音声の言語と同一のものであ ると解するのは文言上無理がある。また,同段落には,第2言語に翻訳することな く,第1言語の指定文字列のまま関連情報Qとする実施例が開示されているが,こ れは第1実施形態の変形例の一つ(態様1)にすぎず,原告が本件訂正審判請求1 の際に同段落を指摘したからといって,当該実施例の態様に限定して「関連情報」 の言語について解釈するのは相当でない。
イ 構成要件1Dに対応する本件アプリの構\成に係る事実認定
(ア) 前記第2の2(5)ア(ウ)及び同イのとおり,本件アプリは,管理サーバから, リクエスト情報に含まれるIDコード及びアプリ使用言語の情報に対応する情報の 所在を示すものとして送信されるアクセス先URLを受信するものとしてスマート フォンを機能させるものであり,管理サーバには,1個のIDコードに対応させて,\n6個までのアプリ使用言語に対応するURLを記憶することができるところ,前記 2(1)のとおり,本件広告には,日本語のほか,英語,中国語,台湾語,韓国語,ロ シア語など多言語で情報配信できることが記載されており,使用例の一つとして, バスの車内案内では多言語で停留所情報等を提供することができることが記載され ていること,同(2)のとおり,本件ダウンロードサイトには,外国人観光客に対して, 空港・駅等のアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する用途に用いること ができることが記載されていることなどからすると,顧客において,リクエスト情 報に含まれるIDコードに対応する案内音声の発音内容を表す情報について,当該\n案内音声とは異なる言語に対応する複数の情報を管理サーバに記憶させ,リクエス ト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報をスマートフォンに送信するよう にすることは,本件アプリにつき想定されていた使用態様の一つであるというべき である。そうすると,本件アプリは,「前記案内音声の発音内容を表す関連情報で\nあって,前記リクエスト情報に含まれるIDコードに対応するとともに,6個まで のアプリ使用言語に対応する複数の情報のうち,前記リクエスト情報のアプリ使用 言語に対応する情報を受信する受信手段」(構成1d)を備えていると認めるのが\n相当である。
(イ) 被告は,本件アプリが構成1dを備えていることを否認し,その理由として,\n
(1)被告サービスにおいて,被告は,本件スマートフォンが受信する情報を決定して おらず,これを選択,決定しているのは顧客であって,構成要件1D所定のものに\n限られないこと,(2)被告は,本件アプリに係る実証実験において,本件アプリを用 いて「案内音声である再生対象音の発音内容」を関連情報として出力したことはな く,外国語に翻訳した内容を関連情報として出力したこともないこと,(3)被告は, 今後,顧客に対し,案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報\nを提供することを禁ずる旨の約束をする意思があることを主張する。 しかしながら,被告の上記(1)の主張は,本件スマートフォンの受信する情報が構\n成要件1D所定の情報ではない場合があることを指摘するにとどまるものであり, 前記(ア)のとおり,本件広告及び本件ダウンロードサイトにおいても,案内音声の 発音内容を表し,リクエスト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報を受信\nする使用形態を回避させるような記述はなく,むしろ,そのような使用形態を想定 したものとなっていたというべきであるから,被告の実証実験では同構成要件所定\nの情報を受信しなかったこと(上記(2)),被告が今後も同構成要件所定の使用態様\nで本件アプリを使用しないことを約束する意思を有していること(上記(3))を併せ 考慮しても,前記認定を覆すに足りないというべきである。
ウ 構成要件1Dに係るあてはめ\n
構成要件1Bにおいて規定するとおりにコンピュータを機能\させるものであれば, 同構成要件を充足するとの前記(1)イにおける検討と同様に,構成要件1D所定の情\n報を受信する手段としてコンピュータを機能させるプログラムであれば,受信する\n情報が同構成要件所定のものではない場面があるとしても,同構\成要件を充足する と解すべきところ,本件アプリは,構成1dを備えており,スマートフォンを「前\n記案内音声の発音内容を表す関連情報であって,前記リクエスト情報に含まれるI\nDコードに対応するとともに,6個までのアプリ使用言語に対応する複数の情報の うち,前記リクエスト情報のアプリ使用言語に対応する情報を受信する受信手段」 として機能させるものであるから,本件スマートフォンが受信する情報を選択して\nいるのが顧客であるとしても,構成要件1Dを充足する。\n
4 争点4(本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか)につい て
(1) 争点4−1(本件発明1は乙2公報により進歩性を欠くか)について
・・・
(イ) 乙2発明1
前記(ア)によれば,乙2発明1は,放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり(【000 1】),テレビ番組の場面を識別する音声信号である音響IDを用い,ID解決サ ーバを介して当該場面に関連する情報を取得することを容易にした携帯端末装置等 を提供することを目的とするものであって(【0005】等),本件発明1に対応 する構成として,次の各構\成を有すると認められる。
「携帯端末装置を,
放送中のテレビ番組の放送音声と重畳して放音される,当該番組の場面を識別す る音声信号である音響IDを収音し,前記音響IDからIDコードにデコードする 情報抽出手段,
携帯端末装置に記憶されたIDコードをID解決サーバに送信する送信手段,
前記IDコード及び前記ID解決サーバが当該IDコードを受信した時刻に基づ いて当該ID解決サーバによりID/URL対応テーブルにおいて検索された対応 するURLを受信し,放送されたテレビ番組の場面に関連する情報を当該URLで 指示されるコンテンツサーバから受信する受信手段,及び,
前記受信手段が受信した情報を携帯端末装置上で表示する出力手段として機能\させるプログラム。」
(ウ) 乙2発明1と本件発明1の対比
乙2発明1と本件発明1を対比すると,これらは,次のaの点で一致し,少なく とも,次のbの点で相違すると認められる。
a 一致点
「コンピュータを,再生対象音を表す音響信号と識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段,前記情報抽出手段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段,\n前記情報要求に含まれる識別情報に対応する関連情報を受信する受信手段,および, 前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラム。」\n
b 相違点
(a) 相違点1−1(構成要件1B)\n
本件発明1では,「案内音声・・・を表す音響信号」と「当該案内音声である再生対\n象音の識別情報」が放音されるのに対し,乙2発明1では,「放送中のテレビ番組 の放送音声」と「当該番組に対応し,当該番組の場面を識別する音声信号である音 響ID」が放音される点
(b) 相違点1−2(構成要件1C)\n
本件発明1では,端末装置からサーバに送信される「情報要求」に含まれる情報 は,「識別情報」と「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」であるの に対し,乙2発明1では,携帯端末装置からID解決サーバに送信される情報は 「IDコード」のみであり,「端末装置にて指定された言語を示す言語情報」は含 まれない点
(c) 相違点1−3(構成要件1D(1))
本件発明1では,端末装置が受信する「関連情報」は,「案内音声である再生対 象音の発音内容を表す」のに対し,乙2発明1では,「放送されたテレビ番組の場\n面」に関連する内容を表す点\n
(d) 相違点1−4(構成要件1D(2))
本件発明1では,端末装置が受信する「関連情報」は,「相異なる言語に対応す る複数の関連情報のうち,前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関 連情報」であるのに対し,乙2発明1では,携帯端末装置がこれに対応する情報を 受信しない点
(エ) 相違点に関する被告の主張について
a 相違点1−1(構成要件1B)\n
被告は,乙2発明1の「IDコード」は,番組と同時に,番組の放送音声という 「再生対象音」も識別しているから,「再生対象音の識別情報」が放音される点で は本件発明1と相違しない旨主張する。 しかしながら,乙2公報に「この音響IDは,放送中の番組に対応するものであ り,放送音声に重畳されて放音される。」(【0014】)と記載されており,I D/URL対応テーブルを示す図4においても,受信時間帯に対応する番組の「シ ーン」が特定されていること(【0025】)などからすると,乙2発明1の「ID コード」は,放送中の番組に対応し,当該番組の場面を識別する音声信号であって, 番組の放送音声を識別するものではないから,本件発明1の「再生対象音の識別情 報」に対応する構成を有するものとは認められない。\n
b 相違点1−2(構成要件1C)\n
被告は,乙2発明1では,ユーザがボタンスイッチを押した時刻は「端末装置に て指定された・・・情報」に該当するから,「端末装置にて指定された・・・情報」が「言 語を示す言語情報」であるか「ボタンスイッチの操作タイミングを示す情報」であ るかの点でのみ本件発明1と相違する旨主張する。 しかしながら,乙2公報に「番組を視聴しているユーザ6は,番組を視聴し興味 ある場面が映し出されると,スマートフォン2を操作する(たとえばボタンを押下 する)。このときの操作により,スマートフォン2は記憶していたIDコードをI D解決サーバ4に送信する。」(【0014】)と記載されていることなどからする と,乙2発明1において,携帯端末装置から送信される情報はIDコードのみであ り,ID解決サーバは当該IDコード及び受信時刻で対応するURLを検索するも のであるから,本件発明1の「端末装置にて指定された・・・情報」に対応する構成を\n有するとは認められないというべきである。
c 相違点1−3(構成要件1D(1))
被告は,乙2発明1で,携帯端末装置が受信する情報は,番組の特定の場面に対 応する放送音声に関連するものであるから,端末装置が受信する「関連情報」が 「再生対象音」である点では本件発明1と相違しない旨主張する。 しかしながら,乙2公報に「この対応するURLは,ユーザ6がスマートフォン 2を操作したときに放送されていた(テレビ1の画面に映し出されていた,または 音声で再生されていた)場面に関連する情報を提供するインターネットサイトのU RLである。」(【0014】)と記載されていることなどからすると,乙2発明1 において,携帯端末装置が受信する情報は,放送されたテレビ番組の場面に関連す るものであり,放送音声に関連する情報であるとは認められない。
d 相違点1−4(構成要件1D(2))
被告は,乙2発明1では,番組中の相異なる場面に対応する「複数の関連情報」 が存在し,そのうち選ばれた情報を受信しているから,「関連情報」が対応してい るのが「言語」であるか「場面」であるかの点でのみ本件発明1と相違する旨主張 する。 しかしながら,乙2発明1において,携帯端末装置が受信する放送中の番組の場 面に関する情報は「相異なる言語に対応する」ものでもないから,ID解決サーバ に番組内の相異なる場面に対応する情報が複数記憶されていたとしても,これを構\n成要件1Dの「相異なる言語に対応する複数の関連情報」との構成に対応するもの\nと認めることはできない。
イ 乙4発明の内容等に係る事実認定
・・・
(イ) 乙4発明の概要 前記(ア)によれば,乙4公報には,概要,次のとおりの内容の乙4発明が開示さ れていると認められる。 すなわち,乙4発明は,利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館 や博物館等の展示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり(【000 1】),(1)電波によって情報を伝達する従来技術によると,対象物以外のガイド音 声を受信して利用者に誤った情報を提供するおそれがあったこと(【0005】) を踏まえ,展示物に固有のIDを赤外線等の無線通信波によって発信するID発信 機を展示物ごとに一定の間隔で設置し,利用者が携帯する携帯受信器が発信域に入 ると上記IDを受信し,展示物の音声ガイドが自動的に再生される構成を採用する\nことにより,情報提供するIDの受信範囲を限定することが容易になり,隣接する 対象展示物との混信を回避した音声ガイドシステムを可能とするという作用効果を\n奏するものであり(【0008】ないし【0010】,【0014】),また,(2) そのシステムを複数の言語に対応させようとすると,多数のチャンネルの割当てが 必要となり,その選択操作を利用者が行う必要があったこと(【0007】)を踏 まえ,多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信器に蓄積し,その中から 再生する言語を選択するという構成を採用することにより,多くの外国人利用者に\nも携帯受信器を操作することなくガイド音声を提供することができるという作用効 果を奏するものである(【0012】,【0020】)。
ウ 乙5発明の内容等に係る事実認定
・・・
(イ) 乙5発明の概要 前記(ア)によれば,乙5公報には,概要,次のとおりの内容の乙5発明が開示さ れていると認められる。 すなわち,乙5発明は,公共の場所等に掲載された文書等の掲載物を様々な言語 に翻訳して提供する情報提供装置等に関するものであり(【0001】),文書の 内容を様々な言語で利用者に正しく提供することを主たる課題とし(【000 6】),2次元コードと複数の言語に対応する言語コードをその内容として含むコ ード画像をユーザ端末装置によって読み取り,ユーザにおいて所望の言語を選択す るなどして,インターネットを介して,文書等の掲載物の翻訳ファイルにアクセス というものである(【0015】,【0025】,【0035】,【0038】)。
エ 容易想到性についての判断
被告は,(1)乙2公報は,音響IDとインターネットを用いて,放音装置から放音 された音響IDによって識別される識別対象の情報に対し,これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙2技術を開示しているところ,本件 発明1も乙2技術を採用するものであり,相違点1−1ないし同1−4は,識別対 象,複数の関連情報の選択条件,関連情報の内容に係る相違にすぎず,当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに,(2)当業者は,乙2技術を乙4課題の 解決に応用して,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成を容易に想\n到し得た旨主張する。 しかしながら,まず,被告の上記(1)の主張については,前記1(2)認定のとおり, 本件発明1は,コンピュータを,(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段,(ii)サーバに対し,抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段,(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し,情報要求に含まれる識別情報に\n対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段,(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明で\nあり,乙2公報等に音響IDとインターネットを利用するという点で本件発明1と 同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても,その手順や方法を具\n体的に特定し,使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供でき\nるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら,相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成が当業者において適宜設\n定できる事項であるということはできない。 また,被告の上記(2)の主張については,前記イのとおり,乙4公報に,発明が解 決しようとする課題の一つとして,システムを複数の言語に対応させること(以下, 単に「乙4発明の課題」という。)が記載されているものの,以下のとおり,乙2 発明1を乙4発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず,仮に,乙4発明の 課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなどして乙2発明1の構\成に変更を加え たとしても相違点1−1ないし同1−4に係る本件発明1の構成に到達しないから,\n採用することができない。
(ア) 乙2発明1を乙4発明の課題を組み合わせる動機付け
a 前記のとおり,乙2発明1は,放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり,放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響IDを用い,ID解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し,前記イ(イ)のとおり,乙 4発明は,利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり,展示物に固有のIDを赤外線 等の無線通信波によって発信し,携帯受信器が発信域に入ると上記IDを受信し, 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり,サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから,両発明は,想定される使用場\n面や発明の基本的な構成が異なっており,乙2発明1を乙4発明の課題に組み合わ\nせる動機付けは認められない。
b 被告は,(1)乙4発明は,放音装置を利用した情報提供技術という乙2技術と 同じ技術分野に属するものであること,(2)乙2技術は汎用性の高い技術であり, 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと(乙11ないし13),(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と(乙2,5,6,8,11ないし13等)などによれば,当業者において,乙2 技術を乙4課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら,乙2発明1と乙4発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ,また,本件優先日1当時,音 響IDとインターネットを利用し,又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙2公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても,いず れも乙4発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記の\nとおりであり,乙4発明の課題の解決のみを取り上げて乙2発明1を適用する動機 付けがあると認めるに足りない。
(イ) 乙2発明1に対する乙4発明等の適用
また,以下のとおり,乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照するなど\nして乙2発明1の構成に変更を加えたとしても,本件発明1の構\成に到達しない。
a 相違点1−1(構成要件1B)\n
(a) 前記のとおり,乙4発明は,展示物ごとに設置されたID発信機から赤外線 等の無線通信波によって展示物に固有のIDが発信されるものであり,「案内音声 ・・・を表す音響信号」を放音するものではなく,「当該案内音声である再生対象音の\n識別情報」を含む音響信号を放音するものでもないから,乙4発明の構成を参照し\nて乙2発明1の構成に変更を加えたとしても,相違点1−1に係る本件発明1の構\ 成に到達しない。
(b) 被告は,乙4発明の音声ガイドは「案内音声」に相当するから,「案内音声」 を識別する構成を採用することは容易であった旨主張するが,上記のとおり,乙4\n発明のIDは展示物を識別するものであり,当該展示物に係る音声ガイドを識別す るものではないから,乙4発明は「案内音声」を識別する構成を開示するものでは\nない。
b 相違点1−2(構成要件1C)\n
前記のとおり,乙4発明は,サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しないものであり,端末装置からサーバに「識別情報」と\n「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」が送信されることはないから, 乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照して乙2発明1の構\成に変更を加 えることによって,相違点1−2に係る本件発明1の構成に到達することはない。\n
c 相違点1−3(構成要件1D(1))
前記のとおり,乙4発明は,サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しておらず,IDによって識別される展示物のガイド音声を\n再生するものであって,端末装置が「案内音声である再生対象音の発音内容を表す」\n情報を受信することはないから,乙4発明の課題を踏まえ,乙4発明の構成を参照\nして乙2発明1の構成に変更を加えることによって,相違点1−3に係る本件発明\n1の構成に到達することはない。\n
d 相違点1−4(構成要件1D(2))
前記のとおり,乙4発明は,多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信 器に蓄積し,その中から再生する言語を選択することによって,IDによって識別 される展示物のガイド音声を所定の言語で再生するという構成を有するものの,サ\nーバに接続してインターネットを介して情報を取得するという構成を有していない\nから,端末装置が「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち,前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信することはなく,乙4発 明の構成を参照して乙2発明1の構\成に変更を加えることによって,相違点1−4 に係る本件発明1の構成に到達することはない。\n
・・・
5 争点6(差止めの必要性は認められるか)について
被告は,本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし,その理由とし て,(1)本件口頭弁論終結時点において,本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと,(2)被告は,平成30年5月以降,本件アプリの配信を中止し,多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており,本件訴訟の\n結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予定であること,\n(3)被告は,今後,顧客に対し,案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語\nの関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や,案内音声である第1言語の再生対 象音が表す発音内容を第2言語で表\現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,本件アプリは,本件発明1の技術的範囲に属 し,本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから, 前記第2の2(4)のとおり,被告は,少なくとも,平成29年5月頃から平成30年 6月頃まで,本件アプリを作成し,譲渡等及び譲渡等の申出をし,平成28年6月\nから平成29年3月までの間に3回にわたり本件アプリを使用することによって本 件特許権1を侵害していたものである。 これらに加えて,被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明1の技術的範囲 に属することを否認して争い,本件特許1について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること,弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も,ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ,被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなど\nも考慮すると,被告は,今後,本件特許権1を侵害するおそれがあるものというべ きであるから,原告が被告に対し,その侵害の予防のため,本件アプリの作成等の\n差止を求める必要性は認められるものというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.02.25
平成31(行ケ)10025 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
前記1の本件明細書の記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明に は,(1)「本発明」の気体溶解装置1は,気体を発生させる気体発生手段2 と,この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段3と,気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽4と,この液体が細管5a を流れることで降圧する降圧移送手段5とを備えること(【0029】, 図1),「本発明の気体溶解方法は,水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって,生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と,前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と, を少なくとも含む気体溶解装置において,前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと(【0023】),(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し,「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで,液体吸入口7から吸入した水に加圧溶解」され, 「水素を加圧溶解した水」は,「加圧型気体溶解手段」の吐出口9から吐 出され,溶存槽4に「過飽和の状態」で溶存されること(【0034】), 「20度Cにおける加圧型気体溶解手段3の圧力Yとしては,0.10〜1.0MPaであることが好ましく,0.15〜0.65MPaであることが より好ましく,0.20〜0.55MPaであることがさらにより好まし く,0.23〜0.50MPaであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで,気体を液体中に容易に溶解できる」こと(【0036】), (3)「降圧移送手段」に関し,「降圧移送手段5は,溶存槽4及び取出口1 0を接続する管状路5aにおいて,取出口10からの水素水の吐出動作に よる管状路5a内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば, 降圧移送手段5の管状路5aは,内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと(【0030】),「溶存 槽4に溶存された液体は,降圧移送手段5である細管5a内で層流状態を 維持して流れることで降圧され(S6),水素水吐出口10から外部へ吐 出される(S7)」こと(【0034】),「降圧移送手段5である細管 5aの内径Xが,1.0mm以上5.0mm以下であることが好ましく, 1.0mmより大きく3.0mm以下であることがより好ましく,2.0 mm以上3.0mm以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで, 特開平8−89771号公報記載の技術のように,降圧するために10本 以上の細管を設置する必要が無く,細管5aを1本有することで降圧する ことができるとともに,管内に層流を形成し得る」こと(【0035】), (4)「細管」の内径X及び長さL,「加圧型気体溶解手段」の圧力Yと「層 流」との関係に関し,「細管5aの内径をXmmとし,加圧型気体溶解手 段3により加えられる圧力をYMPaとしたときに,細管5a内に層流を 形成させるようなものであって,X/Yの値が,1.00〜12.00で あることを特徴とするものであり,さらに,X/Yの値が,3.30〜1 0.0であることが好ましく,4.00〜6.67であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が,かかる条件で細管5a中を 層流状態で流れて降圧移送されることで,気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ,さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと (【0031】),「上記発明において,前記管状路の内径及び長さをそ れぞれX,Lとし,前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をYと したときに,前記管状路内の水素水に層流を形成させるようX,Y及びL の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと(【0020】)の 記載がある。上記記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,「本 発明」の気体溶解装置は,「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し,この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され,「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口10に移送する構成を採用し,これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ,かかる過飽和の状態を安定\nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるものと認められる。
ここに「過飽和」とは,「気体の液体への溶解度は温度により異なるが, ある温度A(度C)における気体の液体への溶解量が,その温度A(度C)に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと(本件明細書の【0 031】),「層流」とは,一般に,速度の方向がそろった規則的な流れ であって,流速が十分遅いときに実現するものであること(甲39の1)をいう。また,細管の内径X及び長さL,加圧型気体溶解手段の圧力Yと\nいう変数に関し,L及びYの2つの変数の値が同じであれば,細管の内径 Xの値が大きいほど,細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること,加 圧型気体溶解手段の圧力Yの値が大きければ,気体を液体に多く溶解させ ることができるが,細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること,細管 の長さLの値が大きければ,細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは,技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり,本件明細書には,「上記発明において,前記管状路の 内径及び長さをそれぞれX,Lとし,前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をYとしたときに,前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようX,Y及びLの値が選択されていることを特徴としてもよい」(【0 020】)との記載があるが,水素水に層流を形成させるようにするには X,Y及びLの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載はない。 そこで,本件明細書記載の実施例1ないし13及び比較例1及び2に基 づいて,以下において検討する。なお,別紙2は,実施例1ないし13及 び比較例1及び2を一覧表にまとめたものである。(ア) まず,実施例1ないし3(【0053】ないし【0055】)を比 較すると,別紙2のとおり,3つの実施例で細管の内径Xの値は2mm, 長さLの値は1.6m及び水素水の流量の値は730cm3/minと同 じであるところ,加圧型気体溶解手段の圧力Yの値は,実施例1は0. 41Mpa,実施例2は0.25Mpa,実施例3は0.30Mpaで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Yの値が最も大きい実施例1の水素濃 度は6.5ppmと最も大きく,圧力Yの値が最も小さい実施例2の水 素濃度の値は2.6ppmと最も小さく,両実施例の差は3.9ppm である。 このような実施例1ないし3の比較の結果は,前記アの技術常識に照 らすと,細管の内径X及び長さLと水素水の流量の各値が同じであれば, 加圧型気体溶解手段の圧力Yの値が大きいほど,水素が水に多く溶け込 むため,生成時における水素濃度の値が大きくなる結果,測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に,実施例5(【0057】)と実施例7(【0059】)を比 較すると,別紙2のとおり,両実施例で細管の内径Xの値は2mm及び 水素水の流量の値は560cm3/minと同じであるが,加圧型気体溶解手段の圧力Yの値は,実施例5が0.38Mpa,実施例7が0.4 5Mpaで,実施例7は実施例5の約1.18倍であり,また,細管の 長さLの値は,実施例5が1.6m,実施例7が1.8mで,実施例7 は実施例5の約1.13倍である。水素濃度の値は,実施例5が3.8 ppm,実施例7が4.5ppmであり,両実施例の水素濃度の差は0. 7ppmであり,実施例2と実施例3との水素濃度の差3.9ppmと 比べると,その差はわずかである。このような実施例5と実施例7の比 較の結果は,細管の内径X及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて,加圧型気体溶解手段の圧力Yの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは,増加の前後で,水素濃度はおお むね同じであり,水素濃度が高まらないことを示している。 また,実施例10(【0062】)と実施例11(【0063】)を 比較すると,別紙2のとおり,両実施例で細管の内径Xの値は2mm, 水素水の流量の値は550cm3/minと同じであるが,加圧型気体溶 解手段の圧力Yの値は,実施例10が0.20Mpa,実施例11が0. 50Mpaで,実施例11が実施例10の2.5倍であり,細管の長さ Lの値は,実施例10が1.4m,実施例11が3mで,実施例11は 実施例10の約2.14倍である。水素濃度の値は,実施例10が2. 7ppm,実施例11が2.4ppmであり,実施例10が実施例11 よりも0.3ppm高いが,実施例2と実施例3との水素濃度の差3. 9ppmと比べると,その差はわずかである。このような実施例10と 実施例11の比較の結果は,実施例5と実施例7の比較の結果と同様に, 細管の内径X及び水素水の流量の各値が同じである場合において,加圧 型気体溶解手段の圧力Yの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは,増加の前後で,水素濃度はおおむね同じであり,水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例1ないし3の比較 の結果と前記アの技術常識から,細管の内径X及び水素水の流量の各値 が同じである場合に,水素濃度の値を高めるには,加圧型気体溶解手段 の圧力Yの値の増加割合が細管の長さLの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方,比較例1及び2については,別紙2のとおり,比較例1は, 細管の内径Xの値が2mm,細管の長さLの値が0.4m,加圧型気体 溶解手段の圧力Yの値が0.05MPa,水素水の流量の値が960c m3/min,水素濃度の値が1.6ppm,比較例2は,細管の内径 Xの値が3mm,細管の長さLの値が0.8m,加圧型気体溶解手段の 圧力Yの値が0.08MPa,水素水の流量の値が900cm3/mi n,水素濃度の値が1.8ppmであって,いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ(【0066】,【0067】),比 較例1及び2は,圧力Yの値が0.05又は0.08MPaであって, 実施例1ないし13における圧力Yの値(0.20ないし0.60MPa)と比べて相当小さかったため,そもそも,加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から,本件特許発明1の気体溶解装置は,水に水素を 溶解させて水素水を生成し,取出口から吐出させる装置であって,気体を 発生させる気体発生手段と,この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と,気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と,この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え,降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し,管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり,一方,必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴がある装置であり,一方,必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し,例えば,細管の内径(X)が1.0mmより大 きく3.0mm以下で,かつ,細管の長さ(L)の値が0.8mより大き く1.4mより小さい数値範囲のときであっても,「細管の内径X及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには,加圧型 気体溶解手段の圧力Yの値を大きくすればよく,この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Y及び細管の長さLの値をいずれも大きくして,水素濃度の 値を高めるには,加圧型気体溶解手段の圧力Yの値の増加割合が細管の長 さLの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 (前記イ)を勘案し,細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようX,Y及びLの値を選択することにより,「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ,かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明1の課題を解決できると認識できるものと認められる。 エ これに対し被告は,(1)当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から,細管の長さの値が0.8mより大きく1.4mより小 さい場合に,過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから,本件特許発明1は,サポート要件に適合 しない,(2)過飽和の状態が維持される条件として,降圧移送手段の管状路 (細管5a)の内径や長さのみならず,細管5aの材料,加圧型気体溶解 手段3により加えられる圧力,水素発生量,水の流量等の条件は,過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明1の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1にはそれらの 条件が記載されていないため,当業者は,細管の内径X及び長さがそれぞ れ本件特許発明1に規定された範囲内であれば,本件特許発明1の上記課 題を解決できると認識することはできないから,この点からも,本件特許 発明1は,サポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら,前記ウ認定のとおり,本件特許発明1において細管の長 さの値が0.8mより大きく1.4mより小さい場合においても,本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて,当業者が,本件 特許発明1の課題を解決できると認識できるものと認められるから,被告 の上記主張は,いずれも理由がない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2020.02.25
令和1(ネ)1635 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和2年2月14日 大阪高等裁判所
前記1で補正の上引用した原判決「事実及び理由」第4の2(2)におい て説示するとおり,控訴人は,食調瓶として,SSシリーズの細口瓶を 開発し,そのうち5種類のシリーズからなる原告商品は,縦長ですっき りしているが,安定感に乏しい印象を与えるものということができる (更に原告商品1から13までについては,その首部と胴部の接続部分 の形状から,肩が張った印象を与えるという点でも共通する。)。 これに対し,他のメーカーの食調瓶にも,縦長ですっきりしているが, 安定感に乏しい印象を呈する細口瓶(甲15の「調味料M200角」, 「ST150」,「ST150PP」,甲16の「SLD150A−H C」,甲18の「ゴージャス」シリーズ,甲19の「サエ」シリーズ, 「スイト」シリーズ)があると認められるところ,控訴人は,前記第2 の5(1)アのとおり,これらの食調瓶の形態が,原告商品の形態に類似し ないと主張し,原告商品の特徴を有する他業者の同種商品と,原告商品 との形状の違いを詳細に指摘する。 しかし,原告商品の形態による商品表示性は,上記5種類のシリーズ\nからなる原告商品に共通する特徴をもって特定されるところ,控訴人の 指摘する形状の違いがあるからといって,異なる印象を与えるとは認め られない。 なお,控訴人は,原告商品と,前述した特徴を有する他業者の同種商 品との間で,首部から肩部に係る傾斜角度(肩の張り方)が大きく異な ると主張するが,肩の張り方が異なることによって受ける印象の違いは, 縦長で安定感に乏しいという特徴の有無によって受ける印象の違いに比 べ,大きいとはいえない。 以上によると,控訴人が指摘する形状の違いがあるからといって,原 告商品の形態の特別顕著性が基礎づけられるものでもない。
イ 原告商品の形態の周知性について
控訴人は,原告商品の形態の周知性に関して,前記第2の5(1)イのと おり主張する。 しかし,控訴人が主張する直近の累計販売本数に係るデータに依った としても,一般瓶市場における原告商品の販売実績等が圧倒的であった 等の状況は認めるに足りないし,高級品市場に限れば,原告商品は相当 のシェアを有しているとの主張についても,これを裏付ける資料等はな い。また,過去に原告商品が出展された展示会における展示・陳列の様 子(甲41)に照らしても,控訴人がSSシリーズの複数の下位シリー ズの一部にまたがる原告商品を,改めて一つのシリーズとして構成し直\nすなどして宣伝していたというような事情を認めることはできない。 そうすると,控訴人のシェアや宣伝活動の状況からみて,原告商品の 形態が,特定の事業者の出所を表示するものとして周知となっていると\nいうこともできない。
(2) 混同のおそれの有無
控訴人は,前記第2の5(2)のとおり,被控訴人の営業活動や商社のカタ ログやウェブサイトにおける掲載内容から,被告商品を控訴人の商品と混同 するおそれがあると主張する。 しかし,前記1で補正の上引用した原判決「事実及び理由」第4の2(4) において説示するとおり,原告商品の形態をもって,商品等表示と認めるこ\nとができない以上,被告商品の形態が原告商品の形態と類似しているからと いって,被控訴人が被告商品を製造,販売する行為が,不正競争防止法2条 1項1号に該当するとはいえない。 なお,被控訴人が,不特定多数の需要者に対しても営業活動をしていると しても,その取引態様からすると,その相手方にとって,被告商品の製造・ 販売者が被控訴人であることは明らかであるから,控訴人の商品と混同する おそれがあるということはできない。 また,食品メーカー等がカタログやウェブサイトを閲覧してガラス瓶の購 入を検討することがあるとしても,それらの需要者が,当該ガラス瓶が自社 で製造する調味料等の内容物の充填工程や商品梱包等の工程に容器として適 合するか否かを確認等することなく,その購入を決定することは考えにくい。 そうすると,上記カタログ等の掲載態様をもって,混同のおそれがあると いう控訴人の主張も採用できない。
(3) アンケート調査結果について
ア 本件アンケートに関する事実関係(甲42〜44)
(ア) 本件アンケートの対象者,質問内容等
控訴人は,前記第2の5(3)アのとおり,原告商品及び被告商品を含 むガラス瓶の写真5点を示して,その製造者及びそのように製造者を 特定した理由を質問するという本件アンケートを,東京・大阪・名古 屋のガラス製品協同組合の加入者のうちの58社を対象として実施し た。このうち何らかの回答を返したものは16社である。
(イ) 上記16社の回答内容は,前記第2の5(3)イのとおりである。
イ 検討
(ア) アンケート対象者の選定について,母集団となった上記各地域のガ ラス製品共同組合の加入者は,原告商品及び被告商品の取引者に当た ると解される。 しかし,上記組合の加入者の中から,対象者58社をどのようにし て選定したのかは明らかではない。また,本件アンケートの各質問の 形式がいわゆるオープンクエスチョンとなっていることを踏まえても, 上記のような対象者に対して,原告商品2点及び被告商品2点を含む ガラス瓶の写真5点を示して製造者を回答させるというアンケートを 実施することが,原告商品や被告商品の形態のみから,その出所を特 定し得るかを判定するものとして有用といえるのか疑問がある。
(イ) 回答者は,上記アンケート対象者58社のうち16社にすぎない。 そして,被告商品5(質問1),原告商品2(質問2),被告商品9(質 問4)及び原告商品12(質問5)について,それぞれ,その製造者を いずれも控訴人であると回答したのは,順に8社,9社,5社及び7 社に過ぎず,このような少数の取引者が,上記各商品の製造者を控訴 人と回答したからといって,これらの商品に係る形態がその出所を示 すものとして周知となっていると評価することはできない。
(ウ) また,他社製品に関する質問3(調味料M200角の製造者)につ いての回答内容は,2社が控訴人,2社が日本山村硝子,12社が不 明(白紙を含む。)というものである。控訴人は,原告商品と日本山 村硝子の製品を区別できなかったのが2社のみというが,12社が回 答できなかったことに照らすと,これをもって,原告商品の形態に特 別顕著性を認めることはできない。
(エ) 上記回答内容によれば,被告商品5及び被告商品9について,製造 者を特定して回答した全員(順に8社,5社)が,その製造者を控訴 人と誤ったことが認められる。 しかし,食調瓶である原告商品及び被告商品の取引態様(認定事実 (2),前記(2))に照らせば,少数の取引者が上記のように誤った回答 をしたからといって,被告商品の形態が原告商品に類似することによ り混同が生じるおそれがあるということもできない。
◆判決本文
1審はこちら
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.02.25
平成31(行ケ)10045 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月20日 知的財産高等裁判所
これによれば,甲1文献においては,被覆層を貫通する「孔60」は, 傷からの体液を吸収層へ移動させるように機能するものであり,創傷を湿\n潤状態に保ち,傷の治癒を促進することができるのは,上記「孔」の機能\nによってではなく,吸収層において必要とされる吸収量にあわせて吸水性 の高い材料の量を調整し,特に,水吸収時にゲルを形成する物質を含ませ ることによってであると理解できる。
・・・
これによれば,甲10文献においては,創傷被覆材の,第1層と第3層 との間に第2層を挟み互いに分離しないようにすることは,甲10文献の 「創傷からの浸出液による適切な湿潤環境を維持しながら治療する方法に 好適な,さらに改良された創傷被覆材を提供する」という課題([000 9])の解決のために必須の構成であるというべきであり,甲10文献の\n第1層の貫通孔は,第1層を第2層と一体化させることで貯留空間を設け て滲出液を保持する機能を担わせることを前提とする構\成であることが理 解できる。
エ 容易想到性について
以上のとおり,甲1文献においては,甲1−1発明の被覆層ではなく, 組み合わされる吸収層が創傷を湿潤状態に保つ機能を有しているのであり,\n体液を吸収層へ移動させる機能を有する被覆層の「孔」に,さらに滲出液\nを保持する機能を担わせる改良を加えるべきことを示唆する記載はない。\nまた,甲10文献においては,第1層を第2層と一体化させることで貯 留空間を設けることを前提としているのに対し,甲1文献の傷手当用品は 被覆層と一体化する第2層に相当する構成を有しない。\nこのような甲1文献に記載された傷手当製品と甲10文献に記載された 創傷被覆材の構成の相違や,甲1−1発明の被覆層と甲10文献の第1層\nの有する機能の相違に照らせば,甲10文献から第1層の貫通孔に関する\n構成のみを取り出して,甲1−1発明における被覆層の「孔」に適用する\nことの動機付けは見出せない。 また,甲3〜12,14〜16,18文献にも,甲1−1発明における 「孔」に滲出液を保持する機能を担わせることについての記載ないし示唆\nはなく,これらの文献の記載を考慮しても,本件優先日当時の当業者が, 甲1−1発明に,甲10文献記載の技術事項を組み合わせ,相違点1cに 係る構成を採用することを容易に想到し得たということはできない。\nよって,甲1文献,甲3〜12,14〜16,18文献に基づいて,本 件発明1が進歩性を欠如するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.02.25
令和1(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月20日 知的財産高等裁判所
本件発明1と引用発明との対比について
本件決定は,前記第2の3(2)イのとおり,本件発明1と引用発明の一致点 及び相違点を認定するところ,甲1に記載された発明として,引用発明’を 認定するのが相当であることについては,前記(3)のとおりである。 ここで,引用発明’の「経編地」は,一定の伸縮性を有することが明らか であるから,本件発明1の「伸縮性経編地」に相当し,引用発明’の「非弾 性糸10からなる,ジャカード運動により振りが入れられている組織」は, 本件発明1の「ジャカード編成組織」に相当するものといえる。また,引用 発明’の「弾性糸12からなる組織」は,全ての編目位置においてループを 形成している点で,本件発明1の「弾性糸のみで構成されて全ての編目位置\nにおいてループが形成されている支持組織」と共通する。 したがって,本件発明1と引用発明’の一致点及び相違点は,以下のとお りであると認められる。
・・・
(5) 相違点の容易想到性の判断について 前記(4)のとおり,本件発明1は,「非弾性糸が全ての編目位置でループを形 成する組織を含まない」のに対し,引用発明’は,「全ての編目位置において ループを形成している非弾性糸11からなる,ジャカード編からなる経編で 編まれる組織」を含むものである。 この点に関し,本件決定は,甲1の図10に相違点に係る本件発明1の構\n成が開示されている旨の認定を前提にして,かかる構成を引用発明の構\成と 置換することは容易である旨判断した。そこで,この点について検討する。
ア 図10の組織図の意義
(ア) 甲1には,(1)図7〜図9は,「本発明で用いるサテン調トリコット組 織の表側の代表\的な組織図」であり,1繰り返し単位中にジャカード運 動により,図7は3つのコースに3針の振りを,図8は1つのコースに 3針の振りを,図9は1つのコースに1針の振りを入れたものを,それ ぞれ示すものであること(【0064】,【0066】,【0068】,【00 69】),(2)図10は,「本発明で用いるメッシュ調トリコット組織の表側\nの代表的な組織図の一例」であって,メッシュ調トリコット組織は,サ\nテン調トリコット組織に比べて,空間部分が大きく,単位面積当たりの 糸の密度が小さいことから,図7〜図9よりも緊迫力が弱いこと(【00 70】,【0072】),(3)甲7〜図10のような態様により,表側に現れ\nる地編トリコット組織をコントロールすることによって,比較的緊迫力 の強い部分と比較的緊迫力の弱い部分とを,所定部分にパターン状に設 けることができること(【0073】),(4)弾性糸の編み込み態様と,図7 〜図10のような地編トリコット組織による緊迫力の強弱の態様とを組 み合わせることにより,種々の強さの緊迫力を有する部分を,1つの経 編トリコット生地上に実現できること(【0097】),(5)図28の下着の 表側に現れる地編組織は,図7で説明した様なサテン調トリコット組織\n(133a,133c),図9で説明した様なサテン調トリコット組織(1 33b,133d),図10で示した様なメッシュ調トリコット組織(1 31a)などから構成され,133cの部分が最も緊迫力が強く,13\n1aの部分が最も緊迫力が弱くなること(【0151】,【0152】)が 記載されている。 そして,これらの記載によれば,図7〜図10に示された組織図は, いずれも,本発明で用いるサテン調又はメッシュ調トリコット組織の表\n側の組織を示したものであることを理解でき,また,これらの図では, いずれも全てのウェールに糸が供給されていることが示されているので, 2枚1組の「ジャカード筬」を2枚とも用いて編成されたものであるこ とを理解できる。
以上によれば,甲1の図10には,次の事項(以下「甲1に記載され た事項’」という。)が記載されていると認められる。 「図7〜図9に示されるサテン調トリコット組織と同様,2枚1組の ジャカード筬を2枚とも用いて編成される,ループが形成されていない 編目位置が存在するメッシュ調トリコット組織の表側の組織。」\n
(イ) これに対し被告は,甲1の図10は,メッシュ調トリコット組織と して,地編の表側と裏側の両方の組織を図示したものである旨主張し,\nその根拠として,(1)甲1の図9が表側の組織の調整によって緊迫度を下\nげた限界であること,(2)甲1に記載された様々な実施態様に示される経 編地は,特開平6−166934号に例示される2枚のジャカード筬と 1枚の地筬を具備した経編機で編成されるものであるところ,図10の 組織の編成には,2枚1組のジャカード筬を2枚とも必要とするから, 「ジャカード編からなる地編」として,それ以外の「裏側の組織」を編 成することができないことを挙げる。
まず,上記(1)の点について,図9に示したサテン調トリコット組織に おいては,1繰り返し単位中,1針の振りしか入っていないコースがX 7の1箇所存在するが(【0069】),当業者であれば,1針の振りしか 入っていないコースを2箇所以上にすることにより,更に緊迫力が低下 することを理解できるから,図9が表側の組織の調整によって緊迫度を\n下げた限界であるとは解されない。 そして,甲1に,「メッシュ調トリコット組織は,図10からも明らか な様にサテン調トリコット組織に比べて,空間部分が大きく,単位面積 あたりの糸の密度が小さく,従って,上述した図7〜図9のサテン調ト リコット組織に比べて,緊迫力が弱くなる。」(【0072】)との記載が あることに照らすと,図10は,地編の表側の組織の緊迫力の強弱を変\nえる方法として,図7〜図9のように,ガイドの振りの大きさ及びガイ ドの振りが入った割合を調整することとは別の方法として,空間部分の 大きさ及び単位面積当たりの糸の密度を調整することを示したものであ ると理解できる。
次に,上記(2)の点について,甲1の「ジャカード編からなる地編」と は,ジャカード筬と地筬とを備えるジャカード制御装置を有する経編機 を用いて編まれるものであるが,ジャカード筬のみを用いて編んだもの に限定されるものではなく,表側はジャカード筬を用いて編み,裏側は\n地筬を用いて編んだものも含まれることを理解できることについては, 前記(3)ウ(ウ)のとおりである。
そして,甲1には,「本発明で用いる経編生地は,実際にはジャカード 制御装置を有する経編機(例えば特開平6−166934号など参照) などを用いて,これらの経編機に地編用の非弾性糸と挿入糸用及び/又 は編み込み用の弾性糸とを供給して同時に編まれるのであるが,理解を 容易にするために,地編の部分をまず説明する。」(【0034】)との記 載があるが,上記記載をもって,甲1の各実施形態に示される経編地が 2枚のジャカード筬と1枚の地筬のみを具備した経編機で編成されるも のであることを記載したものとは解されない。むしろ,上記特開平6− 166934号は,具体的な装置としてRSJ4/1を挙げているとこ ろ,同装置は,2枚1組でフルゲージを構成するジャカード筬のほかに,\n3枚の地筬を備えるものであるから(甲10),かかる事実に照らしても, 被告の主張するような解釈を採ることはできないというべきである。 以上によれば,被告の上記主張を採用することはできない。
イ 引用発明’と甲1に記載された事項’との組合せについて
前記アのとおり,甲1の図10は,メッシュ調トリコット組織の表側の\n組織のみを示すものであって,表側と裏側の両方の組織を示すものではな\nいと理解できる。 そうすると,仮に,引用発明’に甲1に記載された事項’を適用しても, 引用発明’の「非弾性糸10からなる組織」が,甲1に記載された事項’ の「ループが形成されていない編目位置が存在するメッシュ調トリコット 組織」と置換されるだけであって,引用発明’の「全ての編目位置におい てループを形成している非弾性糸11からなる組織」は残ることとなるか ら,相違点’に係る本件発明1の構成(「非弾性糸が全ての編目位置でルー\nプを形成する組織を含まない」構成)に至るものではない。\nそして,そのほかに,甲1には,「全ての編目位置においてループを形成 している非弾性糸11」を含まないようにすることについて,これを示す 記載も,これを示唆する記載も存在しない。 したがって,当業者が,甲1に記載された発明に基づき,相違点’に係 る本件発明1の構成を容易に想到することができたものとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2020.02.20
平成30(ネ)10031 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月20日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1審原告は,特許法102条2項に基づく推定額から共有に係る特許権者である 訴外会社に生じた損害額を控除することはできない旨を,1審被告らは,侵害者の 得た利益の額を共有者の持分権の割合によって按分した額を当該共有者の受けた損 害額と推定すべき旨を,それぞれ主張する。 民法の原則の下では,特許権侵害による特許権者の損害の賠償を求めるためには, 特許権者において損害の発生及び額等につき主張立証しなければならないところ, 前記のとおり,特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設 けられたものであり,加害行為がなかった場合に想定される利益状態と加害行為に よって現実に発生した不利益状態とを金銭的に評価した場合の差額を「損害」とし て把握し,その填補賠償を目的とするという点で,民法上の不法行為による損害賠 償制度の枠内にあるものであることに違いはない。特許権の共有者は,それぞれ, 原則として他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができるも のの(特許法73条2項),その価値の全てを独占するものではないことに鑑みる と,特許法102条2項に基づく損害額の推定を受けるに当たり,共有者は,原則 としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定されると解するのが相当であ り,共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の割合を基準とすることは合 理的でない。なお,本件では,引用に係る原判決指摘のとおり,原告製品は本件発 明の実施品と認めるに足りる証拠はないものの,原告製品と被告製品とは市場にお いて競合関係にあるものといえる。このため,前記のとおり特許法102条2項の 適用が認められることから,本件においても上記と同様に解するのが相当である。 もっとも,特許発明の実施品(又は侵害品と競合する特許権者の製品)の販売利 益の減少等による特許権者の逸失利益と,侵害者から得べかりし実施料の喪失によ る逸失利益とは,類型的にその性質を異にするものである。また,共有者の一部が 当該特許発明を実施しなかったとしても(又は侵害品と競合する製品の製造等を行 っていなかったとしても),共有に係る特許権の侵害による侵害者の利益は,特許 権の共有者の一方の持分権の侵害のみならず他方の持分権の侵害にもよるものであ る以上,実施料相当額の逸失利益を観念することは可能であり,特許法102条3\n項もこのことを前提とするものと理解される。そうである以上,同条2項による損 害額の推定に基づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使す るに当たっては,同条2項に基づく損害額の推定は,不実施に係る他の共有者の持 分割合による同条3項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されるとするのが合 理的である。
また,1審原告は,本件における特別の事情として,訴外会社の1審被告らに対 する損害賠償請求権が1審原告に債権譲渡されていることを指摘する。 しかし,当該請求権は本件における1審原告固有の損害賠償請求権とその発生原 因を異にし,訴外会社の1審被告らに対する債権譲渡の結果,1審原告の下に両立 していると考えられること,1審原告が,債権譲渡を受けた損害賠償請求権を行使 しないで,固有の損害賠償請求権のみの行使を主張する旨明言していることなどに 鑑みると,本件においては,結果として同一人に帰属しているからといって,結論 を異にすべき事情ということはできない。 その他1審原告ないし1審被告らがるる指摘する事情を考慮しても,この点につ いてのそれぞれの主張はいずれも採用できない。
ウ 推定覆滅事由の存否(争点9)について
(ア) インターネット上のサイトに見られる原告製品及び被告製品に関する宣伝 文句に鑑みると,引用に係る原判決の認定のとおり,原告製品及び被告製品は,い ずれも脚口部分が前方に突出するように構成され,脚口部分及びお尻の部分がずり\n上がらないという特徴を有する点で共通すると認められるところ,これらは,本件 発明の作用効果に係るものということができる。また,原告製品及び被告製品は, いずれも,これらの機能に関係する形状を除き,そのデザイン面で特徴的というべ\nき形状ないし装飾は存在しない。ただし,原告製品にはハイウエストタイプの製品 及びテンセル素材の製品が存在しないのに対し,被告製品には存在するところ,丈 のタイプ及び素材は,いずれも下肢用衣料にとって重要な要素である着心地に直接 関わる要素であり,ハイウエストタイプやテンセル素材を好む需要者も一定程度存 在することは容易に推察されること,他方で,被告製品の販売実績に占める割合等 から,この点が需要者の購買に及ぼす影響は,限定的ながらも存在すると考えるの が相当である。
(イ) 価格については,一般に,同種かつ同程度の機能等の製品相互間では,製\n造者・販売者のブランド力等様々な要素が需要者の購買行動に影響するものの,価 格の顧客誘引力も大きな影響力を持つといえること,その影響力の程度は,製造者 等のブランド力等の影響をも受けつつ,製品相互間の機能面等での差異の程度に応\nじて相対的に変化することは,経験則上明らかである。その意味で,市場において 競合関係にあり,その機能面でも同種かつ同等ないし類似する関係にあると見られ\nる製品における価格帯の相違は,推定覆滅事由として考慮されることがあり得ると いうべきである。もっとも,本件においては,原告製品と被告製品との価格差をも って,顧客誘引力の点で大きな影響を及ぼすものとまでは認められない。
(ウ) 販売形態の相違について,1審被告らは,何らかの理由で店頭での商品購 入のみを行い,インターネット販売を利用しない需要者の存在を主張する。 しかし,これを具体的に裏付けるに足りる的確な証拠はないし,現在のインター ネット利用可能な端末それ自体やインターネット上での日用品取引の普及状況等に\n鑑みると,特許法102条2項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事由とはいえな い。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.02.20
令和1(ネ)10039 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年11月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,被告表示1は,被告各商品がタカギ社純正品であると誤認させ\nると主張する。しかし,「タカギ社純正品」であるとの表示が商品の品質等\nを表示していると理解するのは疑問であり,むしろ,商品の出所を表\示する ものと理解すべきであるから,控訴人主張の点は,不競法2条1項1号の問 題としてとらえるべきもので,同項14号の問題としてとらえるべきもので はない。そして,控訴人は,本訴においては同項1号該当の主張はしないと 明言しているのであるから,控訴人の上記主張は,それ自体失当である。 仮に,「タカギ社純正品」との表示が品質等の表\示に当たると見る余地が あり,かつ,一行目の「タカギ社製」が二行目の「交換用カートリッジ」を 修飾すると認識する需要者も一定程度は存在するとしても,例えば,被告表\n示1の直下には「待望の交換用カートリッジついに発売!!」という表示が\nあるところ,被告各ウェブページに接する需要者は控訴人製の浄水蛇口のユ ーザであって,もともと純正品の交換用カートリッジが控訴人によって提供 されていることを知っているのであるから,上記表示を読めば直ちに被告各\n商品が控訴人製の純正品ではないことを認識するはずであることや,被告表\n示1と近接した位置にある「お買い求めの前に」の欄に,「標準タイプ・高 除去タイプともに,純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが」と被 告各商品がタカギ社純正品ではないことを前提とした記述があることなどに 照らしてみれば,需要者は,被告各商品が控訴人の製品ではないと認識する と考えられる。 したがって,控訴人の上記各主張は,被告表示1が同項14号の表\示に当 たらない旨の判断を左右するものでなく,採用することができない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2020.02.20
令和1(行ケ)10125 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年2月12日 知的財産高等裁判所
商標法3条1項3号は,その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,\n用途,形状(包装の形状を含む。・・・),生産若しくは使用の方法若しくは時期そ の他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する 物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格\nを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けるこ\nとができない旨を規定しているが,これは,同号掲記の標章は,商品の産地,販売 地その他の特性を表示,記述する標章であって,取引に際し必要な表\示として誰も がその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのを公益 上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場 合,自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないことから,登録を許\nさないとしたものである。
同号掲記の標章のうち商品等の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能を\nより効果的に発揮させたり,商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選 択されるものであって,商品・役務の出所を表示し,自他商品・役務を識別する標\n識として用いられるものは少ないといえるのであり,需要者としても,商品等の形 状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは異なり,商品の機能\ や美感を際立たせるために選択されたものと認識し,出所表示識別のために選択さ\nれたものとは認識しない場合が多いといえる。また,商品等の機能又は美感に資す\nることを目的とする形状は,同種の商品等に関与する者が当該形状を使用すること を欲するものであるから,先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定 の者に独占させることは,公益上の観点から適切でないといえる。 したがって,商品等の形状は,同種の商品が,その機能又は美感上の理由から採\n用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り,普通に用\nいられる方法で使用する標章のみからなる商標として,同号に該当すると解するの が相当である。
(2) 本願商標は,前記第2の2(1)に記載の商標であり,「三つの略輪状の炎 の立体的形状」(本願形状)を付する位置が特定された位置商標である。 そして,本願形状を採用することにより,対流形石油ストーブの燃焼筒内の輪状 の炎が四つあるように見え,これにより対流形石油ストーブの美感が向上するから, 本願形状は,美感を向上するために採用された形状であると認められる。また,原 告特許は,特許請求の範囲を「1 燃焼室や赤熱体を囲繞する様に位置せしめ,か つ燃焼室の外殻を構成する燃焼筒をリング状の表\面凸凹部を形成するとともに耐熱 性の透明もしくは半透明物質で造製し,この燃焼筒の表面にTi,Zr,Fe等の\n金属もしくは金属化合物被膜を付着きせてなる暖房器。2 燃焼炎や赤熱体から発 する光が,金属被膜による干渉と屈折特性により多重かつ虹状に見ることが出来る 特許請求範囲第1項記載の暖房器。」とするものであって,「また燃焼筒をリング状 の表面凸凹部を形成せしめたから,前記発熱・発熱部が多段に見えるのを,凸凹部\nがレンズ状に拡大して観者に対して大きな炎の輪を多段に確実に詔めさせる効果が ある。この様にこの発明は透明もしくは半透明燃焼筒に金属被膜もしくは金属化合 物被膜を形成する簡単な構造によって暖房に最も適する波長の熱線を良好に透過せ\nしめると共に,該被膜によって燃焼炎より発生する光を干渉させて各色に色付いた 沢山の燃焼炎や赤熱体の像を形成して燃焼炎や赤熱体から発生する熱線が多方向か ら届く様になり,見せると共にリング状の凹凸部によるレンズ効果により,暖房効 果を高めるものであり,更に各色に色付いた沢山の燃焼炎や赤熱体の像は非常に美 しく,視覚的な暖房効果を高め,光の交差による優れたデザイン効果を生むもので ある。」(4段落の8行〜24行)との効果を生じさせるものであり,特許公報には 別紙図面が第1図として付けられているから,本願形状は,暖房効果を高めるとい う機能を有するものと認められる。\nそうすると,本願形状は,その機能又は美感上の理由から採用すると予\測される 範囲を超えているものということはできず,本願形状からなる位置商標である本願 商標は,商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標で あると認められる。 したがって,本願商標は,商標法3条1項3号の商標に該当するというべきであ る。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本願商標と同一又は類似する商標が同業他社によって使用され ていないことやグッドデザイン賞を獲得していることなどから,本願商標は,「独占 不許商標」や「自他商品識別力欠如商標」に該当しないと主張する。 しかし,本願商標が商標法3条1項3号の商標に該当することは,前記(2)のとお りであって,原告が主張する事実は,同号に該当するとの上記判断を左右するもの ではない。
イ 原告は,本願商標は,物理的な形状ではなく,石油ストーブの部品の形 状でもないから,模様に近いものであり,商標法3条1項3号の「商品の形状」に は当たらないと主張する。 しかし,前記(2)のとおり,本願商標は,三つの略輪状の炎からなる立体的形状の 位置商標であることは明らかである。そして,立体的形状は,商標法3条1項3号 の「商品の形状」に当たるから,本願商標の立体的形状も同号の「商品の形状」に 当たるというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2020.02.17
平成28(ワ)3928 製造販売差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月3日 大阪地方裁判所
本件技術資料に記載された数値等は,WBトランスを開発した川鉄電設ない しP2が,開発の過程で得られた実験値や実測値,あるいはトランスの容量等に応 じて推測した理論値や計算値を表形式に整理したものが多いと思われる。\nそうすると,WBトランスを製造,販売しようとする者が本件技術情報を入手し た場合,独自に実験を行って必要な値を計測・算出したり,部品の製造元等へ問い 合わせたりすることなく当該トランスの特性を予測したりすることができるという\n点において有用であるといえ,要件を充たせば,営業秘密として保護されるべきも のと解されるから,例えば,被告らが,当初契約を締結して平成7年技術資料を入 手し,未だWBトランスの製品が市場に出ていない段階で,原告の許諾を得ずにこ れを第三者に開示したとすれば,秘密保持義務違反の責めを負うべきものと解され る。 他方,上記検討したとおり,本件技術情報の開示を受けなければWBトラン スを製造することができないといった事情までは認められず,本件技術情報がWB トランスの製造に必須であることを前提に,本件各基本契約の性質を考えることは できない。 また,本件技術情報に記載された数値は,物理的に測定したり,計算によっ て求めることができるものと考えられるから,WBトランスが市場に出回り,リバ ースエンジニアリングを行って計測等ができるようになった段階で,公知になると いわざるを得ない。 本件各特許権の明細書等を参照し,流通に置かれたWBトランスに対するリバー スエンジニアリングを行ってもなお解明することができず,原告よりその開示を受 けない限り,WBトランスの製造はできないというようなノウハウが,本件技術情 報に含まれていると認めるべき証拠は提出されていない。
・・・
(1) 本件各基本契約の内容 本件各基本契約の内容は,前提事実(3)のとおりであり,文言上は,WBトランス 製造及び販売の実施許諾,指定された装置及び資材の使用,技術情報の提供,対価 としてのイニシャルフィー及びランニングロイヤルティの支払,その前提としての 実施報告,特許権等の実施許諾,改良技術の通知,秘密保持といった内容が双方の 権利または義務として定められており,原告が主張する技術情報の提供および秘密 保持も,被告らが主張する特許権の実施許諾も,いずれも本件各基本契約の内容と して定められているのであって,その関係をどのように解するかが問題となる。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,本件各基本契約は,ノウハウライセンス契約であって特許の実施許 諾を内容とするものではなく,イニシャルフィー及びランニングロイヤルティの支 払義務は,ノウハウの使用に対する対価であって,特許の使用許諾に対する対価で はないから,本件各特許権の消滅により影響されない旨を主張する。 しかしながら,ノウハウライセンス契約であるとの主張は,本件技術情報がなけ ればWBトランスを製造することができないとの原告の主張を前提とするものであ るところ,その主張が失当であることは既に述べたとおりである。
イ 既に認定したとおり,WBトランスとして定義されたものは,本件各特許権 の特許請求の範囲の文言と一致する部分が多く,当初契約の際の川鉄電設側の説明 によっても,特許権者の許諾を得ない限り,これを製造,販売することはできない と考えられる。 WBトランスの製造に使用する資材や装置にも,川鉄電設や川崎製鉄の権利が及 ぶものは多いと考えられ,権利者の許諾を得るか,権利者又はその許諾を得た者が 製造した資材や装置を購入等するのでなければWBトランスを製造,販売すること はできず,単に製造に関する技術情報やノウハウの提供を受けるのでは足りないと いうべきである。
ウ 本件各基本契約,特に当初契約の締結に至る経緯を考えても,前記認定のと おり,川鉄電設は工業会の会員に対し,特許の実施許諾であることを前提に,それ に付随するものとして情報提供,技術指導を行う旨を案内しているのであり,その 本質が特許の実施許諾ではなく,ノウハウライセンス契約であるとの説明が行われ た事実は認められない。
エ 前記認定したとおり,被告らの照会やトランスの設計依頼に応じて,川鉄電 設又は原告から情報提供が多数回にわたって行われているが,時期的なところに着 目すると,被告らが当初契約を締結し,WBトランスの設計,製造をしてその販売 を行い始めた平成9年から平成13年までの間になされたものが大部分であり,最 長20年にわたるランニングロイヤルティの支払と技術情報の提供ないし技術情報 とが対価関係に立つと解することは不合理である。 むしろ,従前にはなかった形式のものとして新たに開発したWBトランスについ ての実施許諾を行うに際し,被告らにおけるWBトランスの製造が軌道に乗るまで の間,WBトランスの開発者である川鉄電設又は原告が,技術情報を提供したり, 技術指導を行うというのは,通常予定されるところと考えられること,川鉄電設か\nら原告に契約関係を承継した際に,前記認定のとおり,当初契約に係るイニシャル フィーは承継せず,追加契約に係るイニシャルフィーは,実施分を控除して原告に 承継される扱いであったことからすると,本件各基本契約において,技術情報の提 供や技術指導の対価と認められるのは,契約当初に支払われるイニシャルフィーと 解するのが合理的である。
オ 以上を総合すると,本件各基本契約には,前記(1)で要約した複数の要素が含 まれるものの,その中心となるのは本件各特許権の実施許諾であり,本件技術情報 の提供は,これに付随するものというべきであるから,ランニングロイヤルティの 支払も,本件各特許権の実施許諾に対する対価と位置づけられるべきであり,これ を本件技術情報の提供に対する対価と考えることはできない。 原告は,本件各基本契約の体裁として,第2条にWBトランスの製造,販売の実 施権の許諾を,第3条に技術情報の提供を,第7条に特許権の実施許諾を定めた上 で,第4条の対価は第2条,第3条の対価である旨定めていることをその主張の根 拠とする。しかし,既に検討したとおり,そもそも本件各特許権の実施許諾なしに WBトランスを製造,販売することはあり得ないし,契約の第2条において,鉄心 巻込装置,コイルボビン,フレームについては川鉄電設が特許出願中のものを使用 すべきことが定められていることからしても,同条の実施許諾は,本件各特許権の 実施許諾を含むものであり,第7条の規定は,特許の登録後と出願中の場合とを分 けて規定したものと解されるから,第4条の対価に特許の実施許諾に対するものが 含まれないと解することはできない。
関連カテゴリー
>> 実施権
>> 営業秘密
>> ピックアップ対象
2020.02.17
平成29(ワ)7532 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月16日 大阪地方裁判所
本件再訂正発明の技術的意義は,LED基板のサイズを同一にして,部品点数 及び製造コストを削減できるとともに,LED基板の大きさを可及的に小さくして, 汎用性を向上させることができる点にある。このような技術的意義は,光照射装置 としての性能の向上に必ずしも直結するものではないといえるものの,ライン状の\n光を照射する光照射装置の製造者にとっては,これにより製品の販売価格をより廉 価とし得ることで競合品との価格競争力を高め得ることその他のメリットを期待し 得る。他方,そのような製品の使用者(需要者)にとっては,販売価格のより廉価 な製品を購入し得るというメリットはあるものの,それ以外には,メリットがある としても乏しいものと思われる。このため,本件再訂正発明の実施により他の競合 品の価格より競争力がある程度に廉価な製品を製造,販売しているのでなければ, 本件再訂正発明の実施による顧客吸引力は乏しいと評価すべきことになる。 しかるに,証拠(乙37)及び弁論の全趣旨によれば,原告各製品及び被告各製 品を含むライン状の光を照射する光照射装置(別紙競合品(被告主張)一覧表記載\nの各製品)の市場における実勢価格は,おおむね同程度であり,また,当該市場に おいて原告及び被告の各シェアは,いずれもトップにはないと認められる。被告各 製品のカタログ(甲3)及びウェブページ(甲4,13)においても,本件再訂正 発明の実施により,光照射装置としての性能が向上していること,部品点数及び製\n造コストの削減を図ることができていること又はこれを前提として他社製品より廉 価で販売可能であることなどをうかがわせる宣伝文句は見られず,他方で,「業界最\n高クラスの光量を実現」,「驚異の明るさを実現」と,被告各製品の機能を宣伝文句\nとしており,被告各製品に対する需要は,販売価格というよりもむしろ光量の大き さといった機能によって喚起されたことがうかがわれる。\nしかも,上記のような市場の状況にあるにもかかわらず,前記認定のとおり,原 告は,本件再訂正発明を実施しているとは認められない。 そうすると,本件再訂正発明は,その実施により光照射装置の性能を必ずしも向\n上するというものではなく,また,販売価格の面でも,実施によるコスト削減に伴 い他社製品との価格競争上同程度の地位に立つことを可能にすることはあり得ると\nしても,価格競争上他社より優位に立ち得る程度のメリットをもたらすものとまで はいえないと見られる。これを需要者の側から見ると,本件再訂正発明の実施品で あることは,そのこと自体により直ちに需要者の購買意欲を高めるものとはいえな いことになる。すなわち,本件再訂正発明は,その性質上,顧客吸引力は必ずしも 高くないものと評価すべきである。
(イ) もっとも,被告が約5年間にわたって本件再訂正発明を実施していたことに 鑑みると,本件再訂正発明を実施することに経済的な意義がないとは考え難く,少 なくとも,被告各製品の販売価格が,ライン状の光を照射する光照射装置の市場に おいて,他社製品に後れを取ることがない程度となることに本件再訂正発明の作用 効果が影響していると考えることには合理性がある。
(ウ) 証拠(甲3,4,13,乙37)によれば,原告各製品及び被告各製品を含 むライン状の光を照射する光照射装置の製品としての特徴は,別紙競合品(被告主 張)一覧表記載のとおりと認められる。本件においては,原告各製品と被告各製品\nとが市場において競合関係に立つ製品であることが前提となるところ,これを踏ま えて上記製品のうち被告各製品及び原告各製品以外のものを見ると,いずれも原告 各製品及び被告各製品と用途例が共通しており(同一覧表の「用途欄」において,\n具体的な用途が「不明」とされているものも,少なくとも原告各製品及び被告各製 品と同様の用途に用い得るとうかがわれる。),長さ寸法及び発光色も対応してい る。前記認定のとおり,これらの製品の価格帯もおおむね同程度である。他方,こ れらの製品の冷却方式は様々であるものの,被告各製品はいずれも自然空冷である 一方,原告各製品には自然空冷だけでなくファン空冷のものもあることに照らせば, その違いは競合関係を否定する事情とまではいえない。また,前記のとおり,本件 再訂正発明の実施によって光照射装置としての性能が向上するとはいえない。色及\nびサイズ展開の点も,機能面で大きな差異を生じるのでなければ,需要者にとって\nは必要とする特定の色及びサイズに対応した製品であれば足り,製品ラインナップ として多色展開していることや,希望サイズに対応するためにLED基板を複数とす るか1枚の基板で対応するかといったことは,需要者にとっては必ずしも重要でな いと思われる。 これらの事情に鑑みると,これらの製品は,原告製品及び被告各製品と市場にお いて競合関係に立つ製品であると認められる。 そうすると,原告各製品及び被告各製品の競合品としては,ライン状の光を照射 する光照射装置を想定するのが相当であり,多色展開していて,複数のLED基板を ライン方向に直列させることで多数のサイズ展開をしているライン状の光を照射す る光照射装置に限られないというべきである。
(エ) 以上の事情を総合的に考慮すると,本件においては,被告各製品の販売がな かった場合に,これに対応する需要が全て原告各製品に向かったであろうと見るこ とに合理性はなく,むしろ,本件再訂正発明の実施品ではない原告各製品に向かう 部分はごく限られると考える。そうすると,本件では,●(省略)●の限度で特許 法102条2項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。 これに対し,原告は,本件再訂正発明の顧客吸引力は大きいと主張するとともに, 競合品は,多色展開していて,複数のLED基板をライン方向に直列させることで多 数のサイズ展開をしているライン光照射装置に限られるなどと主張する。しかし, 上記のとおり,この点に関する原告の主張は採用できない。
(オ) そうすると,被告が本件特許権侵害行為によって得た利益の額は,別紙「損 害額算定表」の(3)欄のとおりであり,937万0447円であると認められる。 これに反する原告及び被告の各主張はいずれも採用できない
・・・
(カ) 共有者の存在について
a 前記のとおり,本件特許権は,被告による特許権侵害行為の継続した期間の うち,その始期である平成24年7月から平成26年11月21日までの間,原告 と三菱化学との共有に係るものであった。 特許権の共有者は,それぞれ,原則として他の共有者の同意を得ないでその特許 発明の実施をすることができるが(特許法73条2項),その価値の全てを独占す るものではないことに鑑みると,同法102条2項に基づく損害額の推定を受ける に当たり,共有者は,原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定さ れると解するのが相当であり,共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の 割合を基準とすることは合理的でない。 もっとも,特許発明の実施品又は侵害品と競合する特許権者の製品に係る販売利 益の減少等による特許権者の逸失利益と,侵害者から得べかりし実施料の喪失によ る逸失利益とは,類型的にその性質を異にするものである。また,共有者の一部が 当該特許発明を実施したり,侵害品と競合する製品の製造等を行ったりしていなか ったとしても,共有に係る特許権の侵害による侵害者の利益は,特許権の共有者の 一方の持分権の侵害のみならず他方の持分権の侵害にもよるものである以上,実施 料相当額の逸失利益を観念することは可能であり,同法102条3項もこのことを\n前提とするものと理解される。そうである以上,同条2項による損害額の推定に基 づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使するに当たっては, 同条2項に基づく損害額の推定は,不実施に係る他の共有者の持分割合による同条 3項に基づく特許発明の実施に対し受けるべき金銭相当額の限度で一部覆滅される とするのが合理的である。 これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
b なお,原告は,三菱化学から,その共有に係る特許権に基づく被告に対する 損害賠償請求権を譲渡されたと主張する。しかし,証拠(甲16)及び弁論の全趣 旨を総合しても,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。この点に関する原 告の主張は採用できない。 そこで,三菱化学の賠償請求し得る損害額を特許法102条3項に基づき算 定する必要があるところ,同項による損害額は,原則として,侵害品の売上高を基 準とし,そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。実施に対 し受けるべき料率を定めるに当たっては,当該特許発明の実際の実施許諾契約にお ける実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮 に入れつつ,当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他の ものによる代替可能性,当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益へ\nの貢献や侵害の態様,特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟 に現れた諸事情を総合的に考慮して,合理的な料率を定めるべきである。 まず,料率について,「実施料率〔第5版〕」(甲17)によれば,「民生用電 気機械・電球・照明器具」(イニシャル無)の技術分野における平成4年度〜平成 10年度の実施料率の平均値は4.6%であり,昭和63年度〜平成3年度に比較 してほぼ横ばいとなっている。また,平成4年度〜平成10年度の実施料率の最頻 値及び中央値はいずれも4%である。なお,上記技術分野は,民生用電気機械器具 製造技術及び電球・電気照明器具製造技術であり,具体的には,電球,蛍光灯,ネ オンランプ等の電球ないし電気照明器具のほか,電気アイロン,暖房用電熱器,扇 風機,電気洗濯機,電気冷蔵庫等を含む。 次に,本件再訂正発明の価値及び他のものによる代替可能性については,推定覆\n滅に関する前記事情に鑑みると,価値的には必ずしも高いとはいえず,また,競合 品による代替の余地は大きく,売上げに対する貢献の程度も同様である。 さらに,証拠(乙27)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告は,長年にわた って競業関係にあることが認められる。 これらの各事情を斟酌すると,本件において,本件特許権の実施に対し受けるべ き料率は,●(省略)●とするのが相当である。これに反する原告及び被告の主張 は,いずれも採用できない。 他方,本件特許権が共有されていた期間(本件期間1及び本件期間2)における 被告製品1〜6の売上高が●(省略)●円(本件期間1:●(省略)●円,本件期 間2:●(省略)●円)であることは,当事者間に争いがない
d なお,被告は,被告製品1〜6の売上高を基礎として実施に対し受けるべき 料率を算定することが不合理であると主張する。しかし,前記のとおり,被告製品 1〜6が本件再訂正発明の作用効果を全く奏していないとはいえないし,その程度 が乏しいとしても,その点は実施に対し受けるべき料率の算定に当たって斟酌すれ ば足りるのであって,被告製品1〜6の売上高を基礎として実施に対し受けるべき 料率を算定することが不合理であるとまではいえない。したがって,この点に関す る被告の主張は採用できない。
e 以上より,三菱化学に生じた損害の額は,別紙「損害額算定表」の(4)欄のと おり,合計26万6379円であると認められる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2020.02.14
平成28(ワ)42833等 特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害差止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月7日 東京地方裁判所
(1) 特許法102条2項の適用の有無(争点11−1) 原告は,被告らが特許権侵害行為により利益を受けているとして,特許法 102条2項の適用があると主張するのに対し,被告らは,原告が本件発明 1を実施していないこと,また,本件発明1は被告製品の販売に何ら寄与し ていないことから,被告製品の販売と原告の損害との間には因果関係がなく, 特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が存在しないから,特許法102条2項の適用がないと 主張する。
そこで検討するに,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかった ならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法10 2条2項の適用が認められると解すべきであり,特許法102条2項の適用 に当たり,特許権者において,当該特許発明を実施していることを要件とす るものではないというべきである(知財高裁平成24年(ネ)第10015 号同平成25年2月1日判決参照)。 そうすると,原告が本件発明1を実施していないことは,特許法102条 2項の適用を妨げる事情とはいえない。また,原告は,被告製品と同様にL TO−7規格に準拠する原告製品を販売しており(弁論の全趣旨),原告製 品と被告製品の市場が共通していることからすれば,特許権者である原告に, 侵害者である被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が認められるから,原告の損害額の算定につき,特許法 102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。被告らが主 張する,被告製品の販売における本件特許1の寄与の程度については,推定 覆滅の一事情として考慮すべきである(後記(4)参照)。 以上のとおり,被告らの主張は採用することができず,原告の損害額の算 定については,特許法102条2項の適用による推定が及ぶ。
(2) 輸出を伴う取引形態における利益の範囲(争点11−2)
被告OEM製品の取引形態のうち,取引形態2(被告OEM製品の製造業 者である被告SSMMが被告OEM製品を海外に輸出し,海外において被告 SSMM自身の在庫として保有しているものを,被告ソニー又は被告SSM\nSを介して海外の顧客に販売する取引形態)によって被告らが得た利益につ いて,特許法102条2項の推定が及ぶか否かについて検討する。この点, 被告らは,取引形態2によって得られた利益は,全て海外での販売行為によ り発生したものであるから,属地主義の原則から,これには上記推定が及ば ないと主張する。
弁論の全趣旨(被告準備書面(7))によれば,被告OEM製品の取引形態 2は,具体的には,(1)平成27年12月から平成29年3月までは,被告S SMMが,被告OEM製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に,被告 ソニーに対して販売し,さらに,被告ソ\ニーが,これを顧客に対して販売し ており,(2)平成29年4月から同年9月までは,被告SSMMが,被告OE M製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に,被告SSMSに対して販 売し,さらに,被告SSMSが,これを被告ソニーに対して販売し,その後,\n被告ソニーが,これを顧客に対して販売しており,(3)平成29年10月以降 は,被告SSMMが,被告OEM製品を日本国内で製造して海外に輸出した 後に,被告SSMSに対して販売し,さらに,被告SSMSが,これを顧客 に対して販売したことが認められる。 上記事実に照らせば,被告OEM製品の取引形態2における販売行為は, 形式的には全て被告SSMMが被告OEM製品を海外に輸出した後に行われ ているものである。しかしながら,被告OEM製品は,その性質上,被告ら (本件期間(1)においては被告ソニー及び被告SSMM)が,本件OEM供給\n先(HPE及びQuantum)の発注を受けて製造し,本件OEM供給先に対し てのみ販売することが予定されていたものであるから,被告SSMMが被告\nOEM製品を日本国内で製造して海外に輸出し,被告ソニーや被告SSMS\nに販売し,さらに被告ソニーや被告SSMSがこれを顧客(本件OEM供給\n先)に販売するという一連の行為が行われた際には,その前提として,当然, 当該製品の内容,数量等について,被告らと本件OEM供給先との密接な意 思疎通があり,それに基づいて上記の被告SSMMによる日本国内での製造 と輸出やその後における被告らによる販売が行われたことを優に推認するこ とができる。そうであれば,上記一連の行為の一部が形式的には被告OEM 製品の輸出後に行われたとしても,上記一連の行為の意思決定は実質的には 被告OEM製品が製造される時点で既に日本国内で行われていたと評価する ことができる。被告らは,被告SSMMが本件OEM供給先から提供を受け たフォーキャストと,実際の被告OEM製品の受注は必ずしも一致しないこ とから,被告SSMMの製造・輸出と,その後の販売行為は独立した別々の 行為である旨主張するが,被告SSMMは本件OEM供給先から提供される フォーキャストで示された予想される発注量に基づいて被告OEM製品を製\n造し,被告らはこれを販売していたものであるから,月々のフォーキャスト と受注が必ずしも一致しないことをもって,被告らの行為ないしその意思決 定の一連性が否定されるものではない。また,被告らは,本件OEM供給先 からの被告OEM製品の受注,被告OEM製品の海外倉庫からの出庫(海外 倉庫の管理を含む)及びOEM顧客への発送,並びにOEM顧客に対する請 求を,各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており,これらの業務 は全て,日本国内ではなく海外において行われたものであるとも主張するが, 単に事実行為の一部を海外の協力会社に委託していたと主張するにすぎない ものであって,上記一連の行為の意思決定が実質的に日本国内で行われてい たと評価することができるという上記結論を何ら左右するものではない。 加えて,少なくとも,本件特許権1の侵害行為である被告OEM製品の国 内での製造及び輸出が被告らによる共同不法行為であると認められる(前記 7参照)以上,被告らによる販売行為が,全て被告SSMMが被告OEM製 品を海外に輸出した後に行われたものであるとしても,被告らの販売行為に よる利益は,被告らによる国内における上記共同不法行為(被告OEM製品 の国内での製造及び輸出)と相当因果関係のある利益(原告にとっての損害) ということができ,侵害行為により受けた利益といえる。 したがって,取引形態2によって被告らが得た利益についても,特許法1 02条2項の推定が及ぶと解すべきであり,このように解しても,我が国の 特許権の効力を我が国の領域外において認めるものではないから,属地主義 の原則とは整合するというべきである。これに反する被告らの主張は採用で きない。
・・・
(4) 推定覆滅事由の存否及びその割合(争点11−4)
ア 被告製品が本件発明1の作用効果を奏していないとの主張について 被告らは,被告製品においては,硬度の高い磁性層表面を形成している\nことにより,裏写りを十分に抑制することができていること,また,本件\n発明1の構成要件1Cを充足する製品としない製品の保存試験(乙204,\n206)の結果などから,被告製品が本件発明1の作用効果を奏していな いと主張する。 しかしながら,前記5(4),(5)説示のとおり,本件明細書1・表1の記\n載からは,磁性層表面及びバックコート層表\面の10μmピッチにおける スペクトル密度,磁性層の中心面平均表面粗さ,六方晶フェライト粉末の\n平均板径のそれぞれが本件発明1−1に規定された範囲内である実施例は, 比較例よりも保存前後のSNRの変化が小さいことを読み取ることができ, そこから,本件発明1により発明の課題を解決することができるものと理 解できるから,そうである以上,本件発明1の技術的範囲に属する被告製 品は本件発明1の作用効果を奏していると認められ,これを覆すに足りる 証拠はない。 これに対し,被告らは,被告製品が本件明細書1の実施例に記載されて いる磁気テープとは材質・組成等が異なるものであり,構成要件を充足す\nるからといって当然に明細書に記載されている発明の効果を奏すると認め られるものではないと主張するが,本件明細書1の実施例に記載されてい る磁気テープと被告製品とは材質・組成等が異なるとしても,そのことに よって被告製品が本件発明1の発明の効果を奏していないものと認めるに 足りる証拠はない。被告らはその他るる主張するが,いずれも上記結論を 左右しない(なお,原告の製品が本件発明1の実施品でないとする主張に ついては,その主張の根拠である測定結果(乙116,117)が前記4 (2)イ(ア)の説示に照らして信用できないから,採用できない。)。
なお,被告らが主張する,被告製品が硬度の高い磁性層表面を形成して\nいる点について検討するに,確かに,証拠(乙197ないし199)によ れば,磁性層表面が硬いほど裏写りが生じにくいことが認められ,また,\n本件発明1の構成要件1Cを充足しないように調整した被告製品において,\n高温保存の前後でエラーレートに有意な変化は生じなかったこと(乙20 4)からすれば,本件発明1の構成要件1Cを充足しないように調整した\n被告製品においては,硬度の高い磁性層表面を形成していること(原告は\n特に争っていない)によって,高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑えら れているものと認められる。 (なお,原告は,甲96の実験を根拠に,磁性層の硬度を高めたとして も裏写りは防止できないと主張するが,同実験においては,磁気テープの 硬度の指標として引張り強度が用いられているところ,裏写りによる磁気 テープの電磁変換特性の悪化を防止するための磁性層の硬度の指標として は,押込み強度が用いられるべきである(乙197・段落【0024】, 【0026】,乙205)から,同実験によっても,磁性層の硬度(押込 み強度)を高めた場合に裏写りが防止できないものと認めることはできな い。また,原告は,エラーレートの検証がなぜ本件発明1の作用効果の検 証につながるのか説明がないなどと主張するが,磁気テープにおいて電磁 変換特性が悪化した場合,エラーレートが上昇すること(乙204)から すれば,エラーレートの変化を検証することで電磁変換特性の変化も検証 できるものと考えられる。)。 しかしながら,一方,証拠(乙206)によれば,本件発明1の構成要\n件1Cを充足する被告製品においても,高温保存の前後でエラーレートに 有意な変化は生じず,高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑制されている ものと認められるが,上記のとおり,本件発明1の技術的範囲に属する被 告製品は本件発明1の作用効果を奏していると認められるところ,被告製 品において,硬度の高い磁性層表面を形成していることにより,本件発明\n1の作用効果を超えて,独自の作用効果を奏していることを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件発明1の作用効果が被告製品の購入動機となっていないとの主張に ついて
被告らは,被告製品の顧客は,本件発明1の作用効果に着目して被告製 品を選択しているわけではなく,本件発明1の作用効果が被告製品の購入 動機となっていないと主張する。 そこで検討するに,特許法102条2項の趣旨からすれば,同条項の推 定を覆滅させる事由として認められるためには,特許権侵害がなかったと しても,被告製品の販売等による利益(の一部)は原告に向かわなかった であろう事由の存在が必要である。したがって,被告製品の顧客の購入動 機が単に本件発明1の作用効果に着目していなかったというのでは足りず (ゆえに,被告製品のパンフレットに本件発明1の作用効果がセールスポ イントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。),被 告製品の顧客の購入動機が,被告製品の独自の技術や性能に着目したもの\nであったことを具体的に主張立証する必要がある。 そして,被告らは,被告製品の顧客の主要な購入動機として,被告製品 が大記録容量及び高速データ転送速度を実現した製品である点,記録媒体 としての磁気テープの利点(保存時に通電が不要である点等),単一ドラ イブを用いて時期テープカートリッジへのデータ記録を行った場合におけ る,記録容量,転送レート及び記録速度の安定性(原告製品と比較してよ り優れた性能を有すること)を挙げるが,これらの点が被告製品独自のも\nのであることや,仮に独自のものであったとしても,それが原告製品と比 較して異なる程度,及び,これらの点が被告製品の顧客の主要な購入動機 となっていたことを認めるに足りる証拠はないから,仮に本件特許権1の 侵害がなかったとしても,これらの点のために,被告製品の販売等による 利益(の一部)は原告に向かわなかったであろうと認めるには足りない。 なお,前記アのとおり,本件発明1の技術的範囲に属する被告製品は本 件発明1の作用効果を奏していると認められるところ,被告製品において, 硬度の高い磁性層表面を形成していることにより,本件発明1の作用効果\nを超えて,独自の作用効果を奏していることを認めるに足りる証拠はない し,仮に,被告製品において,磁性層の素材の硬度を高めることにより本 件発明1と同様な独自の作用効果を一部奏しているとしても,そのような 被告製品独自の作用効果がどの程度生じているのかは不明である上,その 点が被告製品独自の購入動機となっていたとも認められない(被告自身が 本件発明1の作用効果は購入動機となっていない旨主張している。また, 被告製品の広告(甲97)では,データの長期保存について記載されてい るところ,本件発明1の作用効果である長期保存後の裏写りの防止は,デ ータの長期保存に資するものであるから,被告製品が本件発明1の作用効 果を有していることは,間接的には購入の動機の一因になっているものと 考えられるが,上記のとおり,そのような作用効果ひいては購入の動機が 被告製品独自の構成によって生じたり,高められたりしたものと認めるこ\nとはできない。)。したがって,仮に,被告製品が磁性層の素材の硬度を 高めることで本件発明1の作用効果を一部奏しているとしても,そのこと によって,仮に本件特許権1の侵害がなかった場合に,被告製品の販売等 による利益(の一部)は原告に向かわなかったであろうと認めることはで きない。
ウ 以上のほか,被告らは,本件発明1の技術的範囲に属さない代替製品を 製造・販売することできたことも主張するが,現にそのような代替製品を 製造・販売していたものではなく,その可能性にとどまるものであるから,\n推定覆滅事由として認めることはできない。 したがって,特許法102条2項の推定を覆滅させる事由を認めること はできない。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2020.02.12
令和1(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月4日 知的財産高等裁判所
特許法36条4項1号は,発明の詳細な説明の記載は,発明の属する技術 の分野における通常の知識を有する者が,その実施をすることができる程度 に明確かつ十分に記載したものでなければならないことを規定するものであ\nる。本願発明は,物の発明(特許法2条3項1号)であるから,本願発明が実 施可能要件を充足するためには,当業者がこれを生産し,かつ使用すること\nができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。そして,\n実施可能要件を満たすことは,出願人が立証責任を負う。\n
(2) 本願発明は「磁石及び対をなす電極が取り付けられた物体であって,それ らの電極間で放電が可能で,放電時に於いて運動する電子が作る磁界から磁\n石が受ける力を物体の推力として利用する もの。」(【請求項1】)とあ るように,本願発明に係る「物体」ないし「もの」(以下,本願発明に係る 「物体」及び「もの」並びに本願明細書に開示された「構造体」を,「「U\nFO飛行装置」」ということがある。)は,電磁力を利用して物体に推進力 を与えることができるものとされている。推進力を与えるものであるから, その速度が変化することは明らかである。なお,段落【0006】によれば, 重力加速度gに等しい大きさの推進力を与えることが可能であるとされてい\nる。
しかるに,本願明細書中には,「UFO飛行装置」内部の電子と磁石の関 係についての記載はあるものの,「UFO飛行装置」が装置の外部の電磁場 から影響を受ける旨の記載はないし,外部の電磁場の状態を特定するような 記載もない。かえって,段落【0006】によれば,「UFO飛行装置」を 取り付けた物体は,地球から月まで行くことができ,その中間地点まで加速 しそれ以降は減速できるとされているから,「UFO飛行装置」は,宇宙空 間においても地球上でも使用可能なものであり,外部の電磁場の状態に関わ\nりなく動作可能なものであることが前提とされていると考えられる。したが\nって,本願明細書に開示された「UFO飛行装置」は,装置の外部にある電 磁場との関係で生じる電磁力により推進力を得るものではないと解される。 また,電磁力以外の力についても,本願明細書には,「UFO飛行装置」 が,外部の物体を押すことによる反作用を受けるなど,何らかの物理的な力 を外部から受けることは記載されていない。さらに,「UFO飛行装置」が, 外部に物質を噴射するなどして質量を変化させることも記載されていない。 なお,原告も,「UFO飛行装置」は,周囲の媒介物等との間に,連続的 な反作用や他の外力が作用しないだけでなく,連続的でない反作用や他の外 力も作用しないこと,質量変化も生じないことを認めている。 以上によれば,本願発明の「UFO飛行装置」は,外部からの何らかの力 を受けることも,質量を変化させることもないにも関わらず,その速度を変 化させることができるとする発明であると解するほかない。これは,外力の 作用なく「UFO飛行装置」の運動量(質量×速度)が変化するということで あるから,運動量保存の法則に反する。また,「UFO飛行装置」の推進力 に対向する反作用の力が見当たらないから,作用反作用の法則にも反する。 このように,本願発明は,当業者の技術常識に反する結果を実現するとす る発明であるが,本願明細書には,本願発明の「UFO飛行装置」が推進し た事実(実験結果)は示されていない。 したがって,本願明細書の発明の詳細な説明には,当業者が「放電時に於 いて運動する電子が作る磁界から磁石が受ける力を物体の推力として利用す る」「UFO飛行装置」を生産し,かつ使用できる程度に明確かつ十分に記\n載されているとは認められない。
(3) 原告は,自動車の内部で燃料が燃焼を起こすことによりタイヤが回転し 車体が動くが,これが運動量保存の法則に反するとはされていない旨主張す る。 しかし,自動車の場合は,路面とタイヤとの間に摩擦力が働き,タイヤが 路面に及ぼす力と反対方向の力を,路面がタイヤに反作用として及ぼすこと で推進するのであって,自動車は路面という外部からの力を受けている。 これに対し,本願発明は,「UFO飛行装置」の外部との間に何ら力が働 かないにもかかわらず,推進することができるとするものであるから,自動 車の場合と相違することは明らかである。 その他,原告は,本願発明の原理としてるる主張するが,いずれも「UF O飛行装置」内部の現象にとどまり,「UFO飛行装置」全体が外部からの 力を受けることなく運動量を変化させられることを説明するものではないか ら,前記認定を左右しない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.02.12
平成31(行ケ)10023 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月31日 知的財産高等裁判所
本件訂正発明1は,前記1(2)のとおり,(1)作業者が天板の突出方向と反対側で作 業を行う場合には,天板の端を目視で確認しながら作業を行わなければならず,作 業の効率が低下してしまうという問題や(2)天板の突出方向の反対側にも同様の手摺 を取り付けたとしても,作業者が可搬式作業台を昇降する際に手摺を乗り越えたり, 手摺をくぐったりしなければならないことから,天板と主脚との間の移動を自由に 行うことができず,かえって作業の効率が低下してしまう問題を解決し,作業空間 を包囲することにより作業の効率化を図るとともに,天板と主脚との間の移動を容 易に行うことができる脚立式作業台を提供することを目的とするものであって,特 許請求の範囲請求項1の構成をとることによって,「作業の効率化を図ると共に,天\n板と主脚との間の移動を容易に行うことができる」という作用効果を奏するもので ある。本件訂正発明1の相違点1に係る構成も,上記のような課題を解決し,作用\n効果を奏させるための構成であるということができる。\nこれに対して,甲3発明は,容易に運搬できないかさばった構造のプラットフォ\nームラダーにおいて,高い安全性を損なわないようにしつつ,容易に運搬できるよ うにすることを課題として,その解決のために,前記(1)イのような構成をとったも\nのである。
そして,本件訂正発明1の相違点1に係る構成である,一対の前方バーについて,\n「作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認 識させる」ものであること,第1の状態において,「互いの先端部が隙間を介して対 向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され」ること,「前記軸着部 に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって,前記第1の\n状態となる位置と,前記第2の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可 能」であることについては,甲3には,それらの構\成を示唆する記載はなく,甲3 発明の上記技術的意義に照らしても,それらの構成が想起されるということはでき\nない。また,原告が周知技術と主張する甲5〜8,11及び12を併せて考慮して も,甲5〜8,11及び12には,周知技術としては,作業台の「軸支ピンを中心 に回動可能な手すり部材」が開示されているにすぎず,当業者が甲3発明及び周知\n技術に基づいて本件訂正発明1を容易に発明することができたとは認められない。
・・・
甲3発明の「前方バー107」及び甲4発明の「ゲート42,44」 は,共に,それぞれ略左右対称に回動可能であって,互いの先端部が対向して略直\n列に位置するように支持される状態と,作業者が作業空間へ移動可能な状態と,に\n変形可能な部材である点で共通する。\nしかし,甲3発明の「前方バー107」は,プラットフォーム50に登った作業 者の安全性を確保するためのレールの一部となるものであるのに対して,甲4発明 の「ゲート42,44」は,ラダーが不正に使用されないようにアクセスをブロッ クするためのものであるから,甲3発明の「前方バー107」の構成に代えて,甲\n4発明の「ゲート42,44」の構成を適用する動機付けはない。そして,甲3発\n明と甲4発明に原告が周知技術と主張する甲5〜8,11及び12を併せて考慮し ても,当業者が甲3発明と甲4発明に基づいて本件訂正発明1を容易に発明するこ とができたとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.02. 7
令和1(行ケ)10078 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和2年1月28日 知的財産高等裁判所
第4 被告の反論
・・・
上記の不使用取消審判制度の趣旨に鑑みれば,商標権者及び商標使用権者以 外の第三者による日本国内での使用を安易に商標権者又は商標使用権者による 使用と同視してはならず,かかる評価は極めて例外的かつ厳格に行う必要があ る。具体的には,商標権者又は商標使用権者が,登録商標を付した商品の譲受人 が日本国内でこれを販売することを単に事実として認識していただけでは足り ず,少なくとも商標権者又は商標使用権者が,第三者と締結する販売代理店契約 等に基づき第三者が商標権者を代理して日本国内で販売することを契約上認識 していることが必要であると解すべきである。
・・・
第5 裁判所の判断
・・・
証拠によれば,以下の事実を認定することができる。
(1) ランジュビオは,フランスに在住する日本人Aが運営するオンラインショッ プであり,日本語で運営され,日本向けに商品販売を行っている。(甲7,38)
(2) Aは,氏名のアルファベット表記としてAを用いている。(甲40)
(3) 原告は,Aに対し,2013年(平成25年)から,本件商標を付した瓶や スパチュラ(化粧品や料理に用いる「へら」)を含むさまざまな製品を販売し てきた。この販売に当たり,原告は,A がランジュビオを運営していること 及びランジュビオが上記製品を日本で消費者向けに販売していることを認識し ていた。(甲41)
(4) 本件要証期間中の2016年(平成28年)3月1日,原告はプラスチック 製の瓶及びガラス製の容器をAに販売した。(甲12,17,18)
(5) 本件要証期間中の同年2月から2018年(平成30年)8月までの間のラ ンジュビオのウェブページには,原告製品である瓶やガラス製容器が販売商品 として掲載され,日本円で価格が表示されている。(甲21ないし26)\n
(6) 本件要証期間中の2016年3月のランジュビオのウェブページには,原告 製品であるスパチュラが販売商品として掲載され,用途の一つとして「お料理 に」と記載され,日本円で価格が表示されている。(甲19,20)\n
(7) 原告が販売する製品の本体又は包装には,本件商標が直接表示されるか,本件商標を表\示したタグ又はラベルが付されるかしている。(甲27,38,39の各枝番)
2 上記1の各事実を総合すると,原告は,ランジュビオに対し,日本において消 費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を譲渡 し,ランジュビオは,本件要証期間中に,本件商標を付した状態で日本の消費者 に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし,少なくと も,ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。 かかる事実によれば,本件商標は,本件要証期間内に,商標権者である原告に よって,日本国内で,使用立証対象商品に,使用されたものと評価することがで きる。
3 被告の主張について
(1)被告は,商標権者が商標の使用をしたというためには,商標権者が,登録商 標を付した商品の譲受人が日本国内でこれを販売することを単に事実として 認識していただけでは足りず,少なくとも商標権者が,第三者と締結する販売 代理店契約等に基づき第三者が商標権者を代理して日本国内で販売すること を契約上認識していることが必要である旨主張する。 しかしながら,商標権者が,日本国内で販売されることを認識しつつ商標を 付した商品を譲渡し,実際に,その商標が付されたまま当該商品が日本国内で 販売されたのであれば,日本国内における上記商標の使用(商標を付した商品 の譲渡)は,商標権者の意思に基づく「使用」といえるから,それ以上に,被 告のいう「契約上」の「認識」なるものを要求する根拠はないというべきであ る。したがって,被告の主張は失当である。
2020.02. 6
令和1(ワ)60 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和元年11月18日 大阪地方裁判所
証拠(甲2,13)及び弁論の全趣旨によれば,原告が原告各雑誌を販売してい ること,その本体価格は別紙著作物目録の「本体価格(円)」欄にそれぞれ記載の とおりであることが認められる。 また,証拠(甲25の1〜25の4)によれば,平成27年〜平成30年にそれ ぞれ発行された調査報告書には,電子書籍の価格構造における出版社の利益率は,\n配信プラットフォームの違いに応じた代表的な複数の事例の中で,最も低いもので\n45%であることが認められる。本件各違法アップロード行為の対象となった原告 各雑誌に係る販売利益率がこの割合を下回ることをうかがわせる事情はないから, これが45%であるものとして算定することには十分な合理性がある。\n
(ウ) 逸失利益額
各雑誌に係るファイルごとのダウンロード数並びに雑誌ごとの本体価格及び販売 利益率を乗じると,1億5032万8192円となる。他方,被告P3は,「販売 することができないとする事情」(著作権法114条1項ただし書)について,何 ら主張立証していない。したがって,本件各違法アップロード行為による原告の逸 失利益額は,同額であると認められる。
イ 弁護士費用相当損害額
原告の逸失利益額(上記ア)その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告 らの本件各違法アップロード行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害額は, 1503万2819円と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2020.02. 6
平成31(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月31日 知的財産高等裁判所
原告は,甲1−1発明のマッサージ具の代表的な使用方法は,回転体8,\n9の回転軸を鈍角にし,人体の凸部分(皮膚10)に使用するものであると ころ,「一対のローラやマッサージ球の回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に 相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にしたマッサ ージ器具」及びそのマッサージ器具の作用効果は,本件出願当時,周知であ ったから,当業者は,甲1−1発明において,上記周知技術を適用し,甲1 −1発明の回転体8,9を揺動しないように固定した状態とする構成を採用\nすることの動機付けがあり,また,甲1−1発明のマッサージ具の回転体8, 9のなす角を鈍角に限定したとしても,甲1−1発明の全ての技術的意義が 失われるものではなく,技術的意義が縮小されることがあったとしても,そ の程度は極めて限定的なものであって,上記マッサージ器具の一定の作用効 果を得られる上,人体のほとんどの部分をマッサージすることが可能であり,\n甲1−1発明に上記周知技術を適用することに阻害要因があるとはいえない から,当業者が相違点2に係る構成に想到することは容易であり,これと異\nなる本件審決の判断は誤りである旨主張するので,以下において判断する。
ア 甲1には,甲1−1発明のマッサージ具について,「回転体軸が旋回軸 によって把手に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置される\nこと,及び旋回軸がフォーク形部の中央に,したがって回転体に関して中 央に延びているという構造を採用した」(【0006】)との開示がある。\n一方で,甲7,8,9の1及び10の1によれば,本件出願当時,「一 対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に相当する部材の長軸方向 の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」マッサージ器具の構成は周\n知であったことが認められる(以下,上記マッサージ器具の構成を「本件\n周知の構成」という。)。本件周知の構\成は,相違点2に係る本件特許発 明1の構成に相当するものと認められる。\n しかしながら,甲1には,甲1−1発明において,本件周知の構成を適\n用することについての記載も示唆もないから,甲1に接した当業者におい て,甲1−1発明において,本件周知の構成を適用する動機付けがあるも\nのと認めることはできない。
イ また,甲1の記載(【0007】,【0008】,【0018】,【0 019】)によれば,甲1−1発明は,「回転体軸が旋回軸によって把手 に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置され,旋回軸がフォ\nーク形部の中央に回転体に関して中央に延びている」構成を採用すること\nにより,回転体を支持するフォーク形部が旋回軸周りで揺動可能となり,\n回転体をマッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触 させ,多数の凸面部と凹面部,例えば眼窩,突出した頬骨,鼻,顎及び唇 のような部分がある顔面を処置するのに特に適するという効果を奏するこ とに技術的意義があることが認められる。 しかるところ,甲1−1発明における「回転体を支持するフォーク形部 が旋回軸周りで揺動可能」となるように把手に接続する構\成に代えて,本 件周知の構成(「一対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし,柄に相当\nする部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」構成)\nを採用した場合には,「回転体を支持するフォーク形部」が固定され,旋 回軸周りで揺動可能」とならなくなる結果,回転体をマッサージ中にマッ\nサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触させることができなくなり,又は接触させる範囲が制限され,多数の凸面部と凹面部,例えば眼窩,突 出した頬骨,鼻,顎及び唇のような部分がある顔面を処置するのに適さな くなるから,甲1−1発明に本件周知の構成を適用することには阻害要因\nがあるものと認められる。
ウ 以上によれば,当業者が甲1−1発明に本件周知の構成を適用する動機\n付けがあるものと認めることはできず,かえって,その適用には阻害要因 があることが認められるから,当業者が甲1−1発明及び周知技術に基づ いて,相違点2に係る本件特許発明1の構成を容易に想到することができ\nたものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2020.02. 6
平成29(ネ)10068等 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成30年2月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,仮に第三者が同種競合製品をもって市場に参入する機会があ ったとしても,現実に参入者との間で競争が生じない限り,知的財産権による独占 状態の影響が払拭されたと評価することはできないと主張する。 しかし,知的財産権の存在による独占状態は,知的財産権の存続期間が経過する ことにより解消し,知的財産権の存続期間中の独占状態に基づき生じた周知性も, 存続期間満了後の期間の経過に伴って漸減し,存続期間満了後相当期間が経過した 後は,知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響は払拭されたものと評 価することができる。 そして,被告商品の販売を開始した平成24年12月までの間に,原告商品のう ちS−O型については,実用新案権1の存続期間が満了した昭和54年6月23日 から約30年間,原告商品のうちL型,M型,S型については,実用新案権2の存 続期間が満了した昭和57年12月4日から約30年間,原告商品のうちS−II 型,LL型,L−II型については,実用新案権3の存続期間が満了した平成9年2 月26日から約15年間が経過しており,第三者が同種競合製品をもって市場に参 入する機会が十分にあったと評価し得ることは,前記1のとおり補正して引用する\n原判決の判示するとおりである。 また,控訴人は,被控訴人による原告商品の宣伝広告が実用新案権の存続期間満 了の前後を通じて基本的に変化がない旨を指摘するが,商品の形態の商品等表示性\nの要件である周知性を基礎付ける宣伝広告が,知的財産権の存続期間満了の前後を 通じて同様のものであったからといって,そのことが周知性を否定する根拠となる ものではないことは明らかである。 そして,原告商品について,実用新案権の存続期間満了後における広告・宣伝 や,継続的・独占的な大量の製造・販売により,遅くとも平成24年までには原告 商品の形状が出所を表示するものとして周知又は著名であるとの事情が認められる\nことは,前記1のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりである。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成27(ワ)24688
「特許権や実用新案権等の知的財産権の存在により独占状態が生じ,これ
に伴って周知性ないし著名性が生じるのはある意味では当然のことであり,
これに基づき生じた周知性だけを根拠に不競法の適用を認めることは,結
局,知的財産権の存続期間経過後も,第三者によるその利用を妨げてしま
うことに等しく,そのような事態が,価値ある情報の提供に対する対価と
して,その利用の一定期間の独占を認め,期間経過後は万人にその利用を
認めることにより,産業の発達に寄与するという,特許法等の目的に反す
ることは明らかである。もっとも,このように,周知性ないし著名性が知
的財産権に基づく独占により生じた場合でも,知的財産権の存続期間が経
過した後相当期間が経過して,第三者が同種競合製品をもって市場に参入
する機会があったと評価し得る場合など,知的財産権を有していたことに
基づく独占状態の影響が払拭された後で,なお原告製品の形状が出所を表\n示するものとして周知ないし著名であるとの事情が認められる場合であれ
ば,何ら上記特許法等の目的に反することにはならないから,不競法2条
1項1号の適用があるものと解するのが相当である。」
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2020.02. 6
平成30(行ケ)10157 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月30日 知的財産高等裁判所
特許に係る発明が,先行の公知文献に記載された発明にその下位概念と して包含されるときは,当該発明は,先行の公知となった文献に具体的に 開示されておらず,かつ,先行の公知文献に記載された発明と比較して顕 著な特有の効果,すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏さ れる効果とは異質の効果,又は同質の効果であるが際立って優れた効果を 奏する場合を除き,特許性を有しないものと解するのが相当である。 したがって,本件発明1は,甲1に具体的に開示されておらず,かつ, 甲1に記載された発明すなわち甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果 を奏する場合を除き,特許性を有しないところ,甲1には,本件発明1に 該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。 そこで,本件発明1が甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果を奏する ものであるかについて,以下検討する。
・・・
前記(イ)のとおり,甲1発明Aは,(1)広い温度範囲において析出する ことがない,(2)高速応答に対応した低い粘度である,(3)表示不良を生じ\nない,という効果を同時に奏する液晶組成物であることから,本件発明 1と甲1発明Aは,上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点 において,共通するものである。 そこで,本件発明1に特許性が認められるためには,上記三つの特性 において,本件発明1が,甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果を奏 することを要する。
a 効果(1)(低温保存性の向上)について
・・・
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は,甲1の実施例1〜52及び比較 例1の「下限温度」は,−40度及び−30度のいずれでも(ただ し,実施例21は「−40度では」)10日以内に結晶又はスメク チック相に変化したものと理解できるのに対し,本件明細書の実施 例1〜4は,−25度及び−40度で2週間又は3週間ネマチック 状態を維持したと記載されているから,甲1に記載された実験結果 より低い温度でより長い期間に渡り安定性が維持されるものと解す ることができ,本件発明1の低温保存性は,甲1に記載されていな い有利な効果である旨判断した。 しかしながら,そもそも,本件明細書に記載された低温保存試験 は,具体的な測定方法,測定条件について記載されていないため, 甲1に記載された低温保存試験と同じ測定方法,測定条件で実施さ れたものであるかについて,本件明細書の記載からは明らかでない。 また,液晶組成物の低温保存試験は,液晶組成物のその他の物性 値である粘度,光学異方性値,誘電率異方性値等と異なり,確立さ れた標準的な手法は存在しないところ(弁論の全趣旨),甲32(原 告従業員による平成30年7月12日付けの試験成績証明書)にお いては,試験管(P−12M)を用いた場合とクリーンバイアル瓶 (A−No.3)を用いた場合という容器の形状等の違いで実験結 果に差異が生じ,甲1の実施例20と甲82(株式会社UKCシス テムエンジニアリングによる平成31年4月17日付け試験報告 書)の実験結果の間でも,低温保存試験の条件によって実験結果が 異なることからすると,液晶組成物の低温保存試験においては,試 験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否 定できず(甲40),試験結果に著しい差異が生じる可能性がある\nものと認められる。 加えて,甲1の低温保存試験においては,化合物(1)ないし(3) の組合せやその配合量が顕著に異なる液晶組成物であっても,実施 例21(「Tc≦−30度」)を除いて,「Tc≦−20度」とい う同じ結果となっているのに対し,本件明細書の実施例1〜4と比 較例1は,フッ素原子を有する重合性化合物又はフッ素原子を有し ない重合性化合物という配合成分の差異のみで,−25度及び−4 0度におけるネマチック状態の維持期間が顕著に異なる結果とな っている。
(c) 以上の事情に照らすと,低温保存試験に関する甲1の実験と本件 明細書の実験が,同じ配合組成(配合成分及び配合量)の液晶組成 物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような,共通の試験 方法,試験条件において実施されたものとは,にわかに考え難いと いうべきである。 さらに,本件明細書において,実施例1〜4と対比されたのは, 重合性化合物にフッ素原子を有しない構造を有するというほかは,\n実施例1〜4と同様の配合組成を有する比較例1であって,その配 合組成は,甲1の実施例(1〜52)とは顕著に異なるものである。 そして,この点は,被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する乙14についても同様であることから,本件明細書及 び乙14の実験結果のみから,本件発明1の効果と甲1発明Aの効 果を比較することは困難である。 したがって,本件明細書に記載された実施例1〜4の下限温度と, 甲1に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較す るだけで,低温保存に係る本件発明1の効果が,甲1発明Aの効果 よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
b 効果(2)(低粘度)について
前記(イ)のとおり,甲1発明Aの具体例である実施例の液晶組成物 は,いずれも高速応答に対応した低い粘度のものであることが認めら れるところ,液晶組成物の粘度について,本件発明1が甲1発明Aと 比較して顕著な特有の効果を奏するものであることを認めるに足りる 証拠はない。 したがって,本件発明1が,甲1発明Aと比較して,低粘度に係る 有利な効果を奏するものとは認められない。
c 効果(3)(焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと)につ\nいて
(a) 本件発明1に関し,本件明細書には,実施例1〜6の液晶組成物, 及びフッ素原子を有しない重合性化合物を用い,かつ一般式(II −A)及び(II−B)で表される化合物を含まない比較例2の液\n晶組成物において,重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力 をプレチルト角の測定により確認した旨が記載されている(前記(1) イ(エ)c)。
一方,甲1発明Aに関し,甲1には,第三成分の好ましい割合は, 表示不良を防ぐために,第三成分を除いた液晶組成物100重量部\nに対して10重量部以下であり,さらに好ましい割合は,0.1重 量部から2重量部の範囲である旨が記載されている(前記(2)イ (エ))。
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は,本件明細書には,実施例1〜4 が,焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないという効果(効果(3))\nを奏することは具体的に記載されていないが,実施例1〜4におい ては,「環構造と重合性官能\基のみを持つ1,4−フェニレン基等 の構造を有する重合性化合物」に相当する重合性化合物(I−11)\nが用いられ,かつ,当該重合性化合物が添加された液晶組成物は, いずれも「アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用」して いないから,従来から公知の技術的事項に照らして,焼き付きや表\n示ムラ等が少ないか全くないものである蓋然性が高いといえる旨判 断した。 しかしながら,前記(a)のとおり,本件明細書には,実施例1〜6 及び比較例2に関し,「重合性化合物の液晶化合物に対する配向規 制力をプレチルト角の測定により確認した」旨が記載されているに 過ぎず,本件明細書及び被告の提出する実験報告書(甲46〜48) を参照しても,焼き付き等の表示不良の有無や程度についての評価\nが可能な,プレチルト角の経時変化及び安定性に関する実験結果は\n記載されておらず,VHR(電圧保持率)についても,いかなる条 件で得られた数値が,この評価の対象とされ,どの程度の数値を示 せば,焼き付き等の表示不良を生じないと評価できるのか等の詳細\nについて,何ら具体的な説明はされていない。 したがって,仮に,焼き付き等の表示不良とプレチルト角の経時\n変化及び安定性又はVHRとの間に一定の相関関係があったとし ても,本件明細書及び甲46〜48に示された実験結果に基づいて, 本件発明1が達成している焼き付き等の表示不良抑制の程度を評\n価することはできないというべきである。
(C)また,本件明細書には,式(I−1)ないし(I−4)の重合性 化合物を用いることにより,表示ムラが抑制されるか,又は全く発\n生しないこと,また,焼き付きや表示ムラ等の表\示不良を抑制する ため,又は全く発生させないためには,塩素原子で置換される液晶 化合物を含有することは好ましくないことが記載されているとこ ろ(前記(1)イ(イ)),甲1の実施例の半数以上(実施例5,7,1 1,13,26〜27,29〜52 )が,本件発明1の重合性化合 物(I−1)〜(I−4)のいずれかに相当する重合性液晶化合物 (化合物(3−3−1),(3−4−1),(3−7−1),(3 −8−1))を含有し,また,甲1の実施例の7割以上(実施例2 〜8,11〜16,19,21〜24,28〜30,35〜52) が,塩素原子で置換された液晶化合物を含有していない。 さらに,本件明細書において,実施例1〜6と対比されたのは, フッ素原子を有しない重合性化合物を用い,かつ一般式(II−A) 及び(II−B)で表される化合物を含まない比較例2であって,\nその配合組成は,甲1の実施例(1〜52)とは顕著に異なるもの であり,この点は,被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する甲46〜48についても同様であるから,仮に本件発 明1の実施例が比較例よりも有利な結果を示したとしても,甲1の 実施例に対しても同様に有利な結果を示すとは限らない。
(d) 以上の事情に照らすと,焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くな\nいことに係る本件発明1の効果が,甲1発明Aの表示不良が生じな\nい効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
d 小括
以上によると,本件発明1は,甲1の実施例で示された液晶組成物 では到底得られないような効果(低温保存性の向上,低粘度及び焼き 付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと)を示すものとは認められ\nないので,本件発明1が,甲1発明Aと比較して,格別顕著な効果を 奏するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2020.02. 6
平成30(行ケ)10170 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月29日 知的財産高等裁判所
本件決定は,(1)本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき出願時(本 件出願の優先日当時)の技術常識に照らして,当業者が,本件訂正発明4の 課題を解決できる範囲は,実施例に記載された「エチレンカーボネート(E C)とエチルメチルカーボネート(EMC)との混合物(体積比30:70) にLiPF6を1mol/Lの割合となるように溶解して調整した基本電解 液にフルオロスルホン酸リチウムを2.98×10−3mol/L以上0.5 96mol/L以下の範囲内で含有している非水系電解液であって,硫酸イ オンの含有量が1.00×10−7mol/L以上1.00×10−2mol/ L以下である,非水系電解液」である,(2)本件訂正発明1の特許請求の範囲 の記載には,実施例に記載された上記非水系電解液以外の非水系電解液も包 含されているが,本件出願の優先日当時の技術常識に照らしても,本件明細 書の発明の詳細な説明には,本件訂正発明4の課題を,本件訂正発明4によ って解決し得るまでの開示がされているとはいえないから,本件訂正発明4 は,発明の詳細な説明に記載したものとはいえず,サポート要件に適合しな い旨判断した。
原告は,本件決定の上記判断は,当業者が本件訂正発明4の課題を解決で きると認識できる範囲は本件明細書の実施例記載の非水系電解液に限定され ることを前提とするものであるが,「基本電解液」を「エチレンカーボネー ト(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)との混合物(体積比30: 70)とLiPF6を1mol/Lの割合となるように溶解して調整した基 本電解液」以外の一般的な基本電解液とし,フルオロスルホン酸リチウムの 含有量を本件訂正発明4の下限値の0.0005mol/L以上2.98× 10−3mol/L未満の範囲内のものとした場合であっても,本件訂正発明 4の課題を解決できると認識できるものといえるから,本件決定の上記判断 は誤りである旨主張するので,以下において判断する。
ア 本件明細書記載の実施例について
本件明細書には,実施例1ないし7に係る「試験例B」として,「エチ レンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)との混 合物(体積比30:70)に乾燥したLiPF6を1mol/Lの割合と なるように溶解して」調整した「基本電解液」に,「硫酸イオンを含むフ ルオロスルホン酸リチウムを表2に記載の割合となるように混合」して電\n解液を製造し(【0253】) ,表2記載の電解液を用いたシート状電池\nを作製して,「初期放電容量評価」及び「高温保存膨れ保存評価」(高温 保存前後の体積変化から発生したガス発生量の評価)を行ったこと(【0 254】,【0249】,【0250】)が記載されている。 表2には,実施例1ないし7は,電解液中のフルオロスルホン酸リチウ\nムの含有量が「0.025〜5質量%」(「2.98×10−3mol/L 〜0.596mol/L」)及び硫酸イオンの含有量が「9.21×10 −7mol/L〜7.27×10−3mol/L」の範囲内の電解液であり, 比較例2は,電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオンをい ずれも含有しない電解液,比較例3は,電解液中のフルオロスルホン酸リ チウムの含有量が「5質量%」(「0.596mol/L」)及び硫酸イ オンの含有量が「1.67×10−2mol/L」の電解液であることが示 されている。このうち,実施例2ないし7は,本件訂正発明4(フルオロ スルホン酸リチウムのモル含有量が「0.0005mol/L以上0.5 mol/L以下」,硫酸イオン分のモル含有量が「1.0×10−7mol /L以上1.0×10−2mol/L以下」)に含まれる電解液である。 そして,本件明細書には,「表2より,製造された電解液の硫酸イオン\nの量が1.00×10-7×mol/L〜1.00×10-2mol/Lの範 囲内であれば,初期放電容量が向上し,高温保存時のガス発生量が低下す ることから,電池特性が向上することが分かる。」(【0256】)との 記載がある。 また,表2の記載から,実施例2ないし7は,比較例2及び3よりも,\n初期放電容量が向上し,高温保存時のガス発生量が低下し,電池特性が向 上していることを理解できる。 一方で,本件明細書には,本件訂正発明4に含まれる「フルオロスルホ ン酸リチウムのモル含有量が0.0005mol/L以上2.98×10 −3mol/L(0.00298mol/L未満)」の電解液については, 実施例の記載がない。
イ 実施例記載の基本電解液と他の電解液との互換性について
(ア) 本件訂正発明4の特許請求の範囲(請求項4)には,本件訂正発明 4の非水系電解液の含有する非水系溶媒として「炭素数2〜4のいずれ か1種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネート」及び「炭素 数3〜7のいずれか1種以上の鎖状カーボネート」を含むことが記載さ れているが,飽和環状カーボネートと鎖状カーボネートの具体的な組成 及び混合割合を特定する記載はない。 次に,本件明細書には,(1)「飽和環状カーボネート」について,「本 発明において非水系溶媒として用いることができる飽和環状カーボネー トとしては,炭素数2〜4のアルキレン基を有するものが挙げられる。 具体的には,炭素数2〜4の飽和環状カーボネートとしては,エチレン カーボネート,プロピレンカーボネート,ブチレンカーボネート等が挙 げられる。」(【0036】),「飽和環状カーボネートの配合量は, 特に制限されず,本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが, 1種を単独で用いる場合の配合量の下限は,非水系溶媒100体積%中, 3体積%以上,より好ましくは5体積%以上である。…また上限は,9 0体積%以下,より好ましくは85体積%以下,さらに好ましくは80 体積%以下である。」(【0036】),(2)「鎖状カーボネート」につ いて,「本発明において非水系溶媒として用いることができる鎖状カー ボネートとしては,炭素数3〜7のものが挙げられる。具体的には,炭 素数3〜7の鎖状カーボネートとしては,ジメチルカーボネート,ジエ チルカーボネート,ジ−n‐プロピルカーボネート,ジイソプロピルカ\nーボネート,n‐プロピルイソプロピルカーボネート,エチルメチルカ\nーボネート…等が挙げられる。」(【0039】),「 鎖状カーボネー トは,1種を単独で用いてもよく,2種以上を任意の組み合わせ及び比 率で併用してもよい。…鎖状カーボネートの配合量は,より好ましくは 20体積%以上,さらに好ましくは25体積%以上であり,また,より 好ましくは85体積%以下,さらに好ましくは80体積%以下である。」 (【0043】),(3)「本発明において,フルオロスルホン酸リチウム, フルオロスルホン酸リチウム以外のリチウム塩を溶解する為の非水系溶 媒の代表的な具体例を以下に列挙する。本発明においては,これらの非\n水系溶媒は単独或いは複数の溶媒を任意の割合で混合した混合液として 使用されるが,本発明の効果を著しく損なわない限りこれらの例示に限 定されない。」(【0035】)との記載がある。これらの記載によれ ば,本件明細書には,「本発明において非水系溶媒として用いることが できる飽和環状カーボネート」の配合量は,「非水系溶媒100体積% 中,3体積%以上,より好ましくは5体積%以上」,「上限は,90体 積%以下,より好ましくは85体積%以下,さらに好ましくは80体積% 以下」であること,「本発明において非水系溶媒として用いることがで きる鎖状カーボネート」の配合量は,「より好ましくは20体積%以上, さらに好ましくは25体積%以上」,「より好ましくは85体積%以下, さらに好ましくは80体積%以下」であること,「鎖状カーボネート」 と「飽和環状カーボネート」の混合割合は,本発明の効果を著しく損な わない限り,実施例記載のものに限定されないことの開示があるものと 認められる。 そうすると,本件明細書の上記記載から,「試験例B」で用いられた 「エチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC) との混合物(体積比30:70)」以外の組成及び混合割合の「炭素数 2〜4のいずれか1種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネー ト」及び「炭素数3〜7のいずれか1種以上の鎖状カーボネート」を含 む混合物であっても,本件訂正発明の非水系溶媒として用いることがで きるものと理解できる。
(イ) 本件訂正発明4の特許請求の範囲(請求項4)は,本件訂正発明4 の非水系電解液中のLiPF6の含有量は「0.7mol/L以上1. 5mol/L以下」であることを規定している。 次に,本件明細書には,「LiPF6」の含有量について,「本発明 における非水系電解液は,特定量の硫酸イオン分を含有するフルオロ硫 酸リチウムを含有するが,さらにその他のリチウム塩を1種以上含有す ることが好ましい。その他のリチウム塩としては,この用途に用いるこ とが知られているものであれば,特に制限はなく,具体的には以下のも のが挙げられる。」(【0024】),「例えば,LiPF6,LiB F4,LiClO4,LiAlF4,LiSbF6,LiTaF6,LiW F7等の無機リチウム塩」(【0025】),「…さらに,これらの中 でも,LiPF6,LiBF4が好ましく,LiPF6が最も好ましい。」 (【0028】)との記載があるが,「LiPF6」の含有量について 一般的に述べた記載はなく,「試験例B」で用いられた基本電解液中の LiPF6の含有量(1mol/L)以外であっても,本件訂正発明4 に用いることができることについて述べた記載もない。 一方で,(1)甲37(特開2000−195546号公報)には,「本 発明で使用される非水溶媒としては,高誘電率溶媒と低粘度溶媒とから なるものが好ましい。高誘電率溶媒としては,例えば,エチレンカーボ ネート(EC),プロピレンカーボネート(PC),ブチレンカーボネ ート(BC)などの環状カーボネート類が好適に挙げられる。これらの 高誘電率溶媒は,1種類で使用してもよく,また2種類以上組み合わせ て使用してもよい。」(【0015】),「本発明で使用される電解質 としては,例えば,LiPF6,LiBF4…などが挙げられる。これら の電解質は,1種類で使用してもよく,2種類以上組み合わせて使用し てもよい。これら電解質は,前記の非水溶媒に通常0.1〜3M,好ま しくは0.5〜1.5Mの濃度で溶解されて使用される。」(【001 7】),(2)甲13(特開2011−054503号公報)には,「非水 電解液としては,リチウム塩を有機溶媒に溶解した溶液が用いられる。 リチウム塩としては,溶媒中で解離してLi+イオンを形成し,電池と して使用される電圧範囲で分解などの副反応を起こしにくいものであれ ば特に制限はない。例えば,LiClO4,LiPF6,LiBF4 ,L iAsF6 ,LiSbF6 などの無機リチウム塩…などを用いることが できる。」(【0084】),「このリチウム塩の電解液中の濃度とし ては,0.5〜1.5mol/lとすることが好ましく,0.9〜1. 25mol/lとすることがより好ましい。」(【0086】)との記 載がある。上記記載によれば,本件出願の優先日当時,高誘電率溶媒と 低粘度溶媒とからなる非水系溶媒に電解質として用いる「LiPF6」 の濃度は,0.5〜1.5mol/Lの範囲とすることが好ましいこと は技術常識であったものと認められる。 そして,上記技術上常識に照らすと,本件訂正発明4の非水系電解液 中のLiPF6の含有量(「0.7mol/L以上1.5mol/L以下」) は,LiPF6を「炭素数2〜4のいずれか1種以上のアルキレン基を有 する飽和環状カーボネート」及び「炭素数3〜7のいずれか1種以上の 鎖状カーボネート」を含む非水系溶媒に電解質として用いる場合におい て好ましい濃度範囲であることを理解できる。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び本件出願の優先日当時の技術常識から,当業者は,試験例Bに用い られた基本電解液(「エチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカ ーボネート(EMC)との混合物(体積比30:70)に乾燥したLi PF6を1mol/Lの割合となるように溶解して」調整した「基本電 解液」)以外の組成及び混合割合の本件訂正発明4に含まれる基本電解 液を用いた場合であっても,試験例Bに示されたように,フルオロスル ホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解液 に対して,「初期放電容量」を改善できるものと理解し,本件訂正発明 4の課題を解決できると認識できるものと認められる。
(エ) これに対し被告は,本件出願の優先日当時の技術常識((1)ECなど の誘電率の大きな溶媒とEMCなどの低沸点の低粘度溶媒とLiPF6 などの支持電解質の組合せやそれらの使用量比の変動に伴う,電解液組 成の変動によって,非水系電解液二次電池の電池特性も変動するため, 電池特性評価試験の結果に基づいて,満足な電池特性が得られない電解 液組成を選別するという最適化を行わなければ,満足な電池特性の非水 系電解液二次電池をもたらす電解液組成が得られないこと(乙1等), (2)非水系電解液の導電性について,電解質伝導度は電池の放電容量など に密接に関係し,電池性能に大きな影響を及ぼすこと(甲15))に照\nらすと,ECとEMCとの体積比やLiPF6の濃度が実施例の範囲内 のもの(試験例B)と異なる非水系電解液については,電池特性評価試 験の結果に基づく電解液組成の選別を行わないと,比較例3のような満 足な電池特性が得られない非水系電解液が含まれてしまうことになるか ら,当業者は,試験例Bに用いられている基本電解液を他の一般的な電 解液に変更したとしても,本件訂正発明4の課題を解決できるとは認識 しない旨主張する。
しかしながら,まず,被告の主張は本件訂正発明4の課題が「初期放 電容量が改善され,容量維持率および/またはガス発生量が改善された 非水系電解液二次電池をもたらすことができる非水系電解液を提供する こと」にあるというものであるが,前記(1)ウのとおり,本件訂正発明4 の課題は,フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として 含有しない非水系電解液に対して,初期放電容量等の電池特性を改善す る非水系電解液を提供することにあると認定すべきであるから,その前 提を欠くものである。 また,本件出願の優先日当時,非水電解液は,PC,ECなどの誘電 率の大きな溶媒とジメチルカーボネートなどの低沸点の低粘度溶媒とL iPF6などの支持電解質とから主に構成され,これら3種類の組合せ\nやそれらの使用量比などにより最適化されることは,技術常識であった こと(甲15(「電池ハンドブック」平成22年2月刊行)の373頁 等)に照らすと,当業者は,本件明細書の記載に基づいて最適化を行う ことにより,試験例Bに用いられた基本電解液以外の組成及び混合割合 の本件訂正発明4に含まれる基本電解液を用いた場合であっても,本件 訂正発明4の課題を解決できると認識できるものと認めるのが相当であ る。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ フルオロスルホン酸リチウムの含有量の下限値について 前記アのとおり,本件明細書には,本件訂正発明4に含まれる「フルオ ロスルホン酸リチウムのモル含有量が0.0005mol/L以上2.9 8×10−3(0.00298)mol/L未満」の電解液については,実 施例の記載がない。 しかるところ,本件明細書には,試験例Bの結果を示した表2において,\n本件訂正発明4に含まれる実施例2ないし7(電解液中のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量が「0.025〜2.5質量%」(「2.98×1 0−3mol/L〜2.98×10−1mol/L」)及び硫酸イオンの含有 量が「9.21×10−7mol/L〜8.23×10−3mol/L」の範 囲内の電解液)が電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオン をいずれも含有しない比較例2の電解液よりも,初期発電容量が向上して いること,実施例2ないし7のうち,電解液中のフルオロスルホン酸リチ ウムの含有量が最も少ない実施例7(フルオロスルホン酸リチウムの含有 量2.98×10−3mol/L,硫酸イオンの含有量9.21×10−7 mol/L)の初期発電容量は148.7mAh/g,比較例2の初期発 電容量は145.8mAh/gであることが開示されている。この開示事 項から,フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として添加 した非水系電解液は,これらをいずれも添加剤として含有しない非水系電 解液に対して,初期放電容量が改善できるものと理解できる。 そして,本件訂正発明4に含まれる「フルオロスルホン酸リチウムのモ ル含有量の下限値0.0005mol/Lは,実施例7のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量2.98×10−3mol/L(0.00298mo l/L)の約6分の1程度であり,実施例7よりも顕著に少ないとまでは いえないことに照らすと,当業者は,フルオロスルホン酸リチウムの含有 量が0.0005mol/Lの電解液を用いた場合であっても,フルオロ スルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解 液に対して,「初期放電容量」が改善し,本件訂正発明4の課題を解決で きると認識できるものと認められる。 これに反する被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願の優先 日当時の技術常識に基づいて,当業者が,本件訂正発明4の発明特定事項の 全体にわたり,本件訂正発明4の課題を解決できると認識できると認められ るから,本件訂正発明4は発明の詳細な説明に記載したものであることが認 められる。したがって,本件訂正発明4は,サポート要件に適合するものと認められ る。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2020.02. 6
平成31(行ケ)10021 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月29日 知的財産高等裁判所
(2) 訂正事項1−1ないし1−3の特許法126条5項の要件の適合性の判 断の誤りについて
原告は,本件審決が,本件訂正のうち,本件訂正前の請求項1の記載を本 件訂正後の請求項1に訂正する訂正事項1−1(請求項1の記載を引用する 請求項2,請求項2の記載を引用する請求項3ないし5,及び請求項1ない し5の記載を引用する請求項7も同様に訂正),本件訂正前の請求項2の記 載を本件訂正後の請求項2に訂正する訂正事項1−2(請求項2の記載を引 用する請求項3ないし5,及び請求項2ないし5の記載を引用する請求項7 も同様に訂正)及び本件訂正前の請求項6の記載を本件訂正後の請求項6に 訂正する訂正事項1−3は,本件訂正前の「売買取引開始時に,成行注文を 行うとともに,該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項 について,当該事項が「前記注文情報生成手段」によるものであり,「該成 行注文を決済するための指値注文」だけでなく,「前記成行注文を決済する ための逆指値注文」についても有効とするとの事項を追加したものであるが, 当該訂正事項については,願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の 範囲内においてしたものとはいえず,新規事項を追加するものであるから, 本件訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定 に適合しないと判断したのは誤りである旨主張するので,以下において判断 する。
・・・
以上によれば,本件明細書には,「本発明」の「一の実施形態」とし て,「注文情報生成手段」である「注文情報生成部16」が,「第一の 注文情報群」の生成をする際に,「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文」及び「第二注文」についてそれぞれ有効及び無効の設定を行い, 「約定情報生成手段」である「約定情報生成部14」が「第一の注文情 報群」に含まれる「第一注文51a」に基づく「成行注文」の約定処理 を行った時点で,その「成行注文」を決済するための「第二注文」(指 値注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理を 行うことの開示があることが認められる。 そうすると,本件明細書には,「注文情報生成手段」(「注文情報生 成部16」)が,「第一の注文情報群」の生成をする際に,「第一の注 文情報群」に含まれる注文情報の有効/無効の設定を行う技術的事項の 開示があるものと認められる。
また,「本発明」の上記実施形態においては,「注文情報生成手段」 (「注文情報生成部16」)が,「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文51a」の「成行注文」を決済するための「第二注文」(指値注 文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は,「約 定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)によって行われ,「注文 情報生成手段」(「注文情報生成部16」)が行うものではないが,本 件明細書には,「上記実施形態は本発明の例示であり,本発明が上記実 施の形態に限定されることを意味するものではないことは,いうまでも ない。」(【0076】)との記載があることに照らすと,「本発明」 は,「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」(指値 注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は, 「約定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)が行う形態のものに 限定されないことを理解できる。
イ 本件訂正後の特許請求の範囲(請求項1)には,・・・
上記記載によれば,訂正事項1−1により,本件訂正前の「売買取引開 始時に,成行注文を行うとともに,該成行注文を決済するための指値注文 を有効とし」との事項について,「該成行注文を決済するための指値注文」 だけでなく,「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有 効とするとの事項を追加したものであり,本件訂正発明1においては,「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに,該 成行注文を決済するための指値注文および前記成行注文を決済するための 逆指値注文を有効とし」とする処理を行うことを理解できる。 しかるところ,前記ア認定のとおり,(1)本件訂正前の請求項1には,「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに,該 成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との処理を行うことの記 載があり,本件明細書の【0009】には,本件訂正前の請求項1と同内 容の記載があること,(2)本件明細書には,「注文情報生成手段」(「注文 情報生成部16」)が,「第一の注文情報群」の生成をする際に,「第一 の注文情報群」に含まれる注文情報の有効/無効の設定を行う技術的事項 の開示があること,(3)本件明細書に記載された「本発明」の「一の実施形 態」では,「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文51a」の「成行 注文」を決済するための「第二注文」(指値注文)及び「逆指値注文」を 「無効」から「有効」に変更する処理は,「約定情報生成手段」(「約定 情報生成部14」)によって行われ,「注文情報生成手段」(「注文情報 生成部16」)が行うものではないが,本件明細書の【0076】の記載 に照らすと,「本発明」は,「第一注文」の「成行注文」を決済するため の「第二注文」(指値注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」 に変更する処理は,「約定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)が 行う形態のものに限定されないことを理解できることからすると,本件訂 正後の請求項1の「前記注文情報生成手段」は「売買取引開始時に,成行 注文を行うとともに,該成行注文を決済するための指値注文および前記成 行注文を決済するための逆指値注文を有効とし」との構成は,本件出願の\n願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面すべての記載事項を総合 することにより導かれる技術的事項の関係において,新たな技術的事項を 導入するものではないものと認められるから,訂正事項1−1は,本件出 願の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてしたもの であって,新規事項の追加に当たらないものと認められる。 したがって,訂正事項1−1は特許法126条5項の要件に適合するも のと認められる。同様に,訂正事項1−2及び1−3は同項の要件に適合 するものと認められる。
ウ これに対し,被告は,・・・
訂正事項1−1に係る本件訂正は,本件出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしたものではなく,新たな技術的事項を導入する ものであるから,新規事項の追加に当たる旨主張する。
しかしながら,前記ア(ア)認定のとおり,本件訂正前の請求項1の記載 から,本件発明1においては,「注文情報生成手段」が主体となって「売 買取引開始時」に「成行注文を行うとともに,該成行注文を決済するため の指値注文を有効とし」との処理を行うことを理解できるものであり,ま た,本件訂正前の請求項1に「注文情報生成手段」が上記処理を行うこと の記載があるかどうかの問題とその記載があることを前提とした場合にサ ポート要件に違反することになるかどうかの問題とは,別異の問題である から,上記(1)の点は採用することができない。 また,前記イ認定のとおり,本件明細書には,「注文情報生成手段」(「注 文情報生成部16」)が,「第一の注文情報群」の生成をする際に,「第 一の注文情報群」に含まれる注文情報の有効/無効の設定を行う技術的事 項の開示があること及び本件明細書の【0076】の記載に照らすと,「本 発明」は,「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」(指 値注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は, 「約定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)が行う形態のものに限 定されないことを理解できるから,上記(2)の点は採用することができない。 したがって,訂正事項1−1に係る本件訂正は,本件出願の願書に添付 した明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではなく,新規事項の追 加に当たるとの被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上のとおり,訂正事項1−1ないし1−3は特許法126条5項の要件 に適合するものと認められるから,訂正事項1−1ないし1−3が同項に適 合しないことを理由に本件訂正は認められないとした本件審決の判断は誤り である。かかる判断の誤りは,無効理由の存否の審理の対象となる発明の要 旨の認定の誤りに帰することになるから,審決の結論に影響を及ぼすもので ある。
◆判決本文
本件の対象特許とは、下記の侵害事件の対象特許です。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.02. 6
平成31(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月29日 知的財産高等裁判所
原告は,本件審決の相違点1−2に関する判断は,前件侵害訴訟判決の判断と矛盾していると主張する。証拠(甲24,30)によると,前件侵害訴訟事件及びその原審は,被告が,原告の本件特許権侵害を主張したものであるところ,原告が,「前記導入通路の出口は,前記ロータリバルブの外周面上にあり,前記吸入通路の入口は,前記軸孔の内周面 上にあり,前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持されること によって前記ロータリバルブを介して前記回転軸を支持するラジアル軸受手段とな っており,前記ラジアル軸受手段は,前記カム体から前記ロータリバルブ側におけ る前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段であり,」という訂正前の本 件特許の請求項1の構成要件Eについて,本件特許発明にいう「ロータリバルブ」\nとは,「導入通路を有するロータリバルブ」(構成要件A)及び「前記吸入通路の入\n口に向けて前記ロータリバルブを付勢する」(構成要件C)の記載に鑑みれば,回転\n軸の一部であって導入通路及びその近傍を意味するものであり,それゆえ,構成要\n件Eにおける「唯一のラジアル軸受手段」とは,吸入通路近傍のみにおいて軸受さ れていることを要すると主張したのに対し,前件侵害訴訟判決は,ロータリバルブ が「吸入通路入口近傍のみにおいて軸受されていることを要する」などという要件 は,本件特許の特許請求の範囲請求項1には記載されていないし,かえって,本件 明細書の【0019】,【0026】,【0033】及び【0040】の記載によると,本件明細書においては,回転軸がシリンダブロックに貫設された軸孔に挿通され, 軸孔の内周面で支持された構造を「直接支持される」としているのであって,本件\n特許発明の「前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持される」 とは,軸孔の内周面とロータリバルブの外周面との間に他の部材が存在しないこと を意味するものと解するのが相当であるし,「唯一のラジアル軸受手段」との用語は, 複数のラジアル軸受手段から,当該ラジアル軸受手段が唯一採用されたという意義 を有するものと解されるから,本件特許発明の「前記カム体から前記ロータリバル ブ側における前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段」とは,カム体か らロータリバルブ側における回転軸の部分について,直接支持されたラジアル軸受 手段の他にラジアル方向の軸受手段が存在しないことを意味するものと解するのが 相当であると判断していることが認められる。 この前件侵害訴訟判決の判断が,上記aの判断と矛盾するといえないことは明ら かである。
(エ) 以上によると,相違点1―2が存在し,これは実質的な相違点である\nと認められる。
・・・
前記(1)イによると,引用発明4は,円錐コロ軸受け10,11によって,ラジア ル軸受とスラスト軸受とを兼ねているものであるから,引用発明4において,相違 点4−1及び4−2に係る構成とするためには,円錐コロ軸受け10,11を,ラ\nジアル軸受とスラスト軸受とに分離し,それぞれを別の位置に設けることが必要と なる。 しかし,円錐コロ軸受け10,11を,ラジアル軸受とスラスト軸受とに分離す ると,部品が多くなり,構造がより複雑になるため,製造コストやメンテナンスコ\nストが上がり,故障の可能性も高くなるというデメリットがあるところ,このよう\nなデメリットがあるのにもかかわらず,あえて円錐コロ軸受け10,11を,ラジ アル軸受とスラスト軸受とに分離することに技術的意義があると認めるに足りる証 拠はない。 したがって,引用発明4において,円錐コロ軸受け10,11を,ラジアル軸受 とスラスト軸受とに分離することには動機付けがあるとはいえず,むしろ,阻害要 因があるといえる。
◆判決本文
侵害訴訟はこちらです。
平成26(ワ)34678
◆判決本文
第1次審決の取消訴訟はこちらです。
平成28(行ケ)10231
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2020.02. 5
平成30(ワ)4901 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年1月23日 大阪地方裁判所
以上より,乙12−1発明は,1つ又は複数の画像をカメラやネットワーク を通じて入手し,1つ又は複数の電話番号に対応付けてこれらの画像を記憶し,当 該電話番号から着呼があったときに,これらの画像を切り替えて表示させ,これに\nより,発信者を識別しやすくするという効果を有する,無線携帯端末に関する発明 であるということができる。
(3) 本件発明1と乙12−1発明との対比
ア 乙12−1発明に係る無線携帯端末において,1つの電話番号に2つの画像 を対応付けて記憶させた場合,当該電話番号から着呼があった際,2つの画像が, 時刻や着呼の回数等による一定の規則性に従って表示される。このとき,特定の着\n呼時に表示されない方の画像については,当該電話番号との対応関係を維持したま\nま,画像メモリに記憶され続けており,「表示選択がOFF」にされているといえ\nる(前記2(3)参照。)。乙12−1発明における「メモリ」及び「画像メモリ」は, それぞれ本件発明1における「電話帳データメモリ」及び「画像データメモリ」に 対応する。
イ そうすると,本件発明1と乙12−1発明との間には,(1)本件発明において は,画像をメモリ番号に対応付けているが,乙12発明においては,画像を電話番 号に対応付けている点(相違点(1)),(2)本件発明1においては,新たに入手・記憶 された第2画像が優先的に表示されるが,乙12発明においては,新たに入手・記\n憶された画像が優先的に表示されるか否か不明である点(相違点(2)),という相違 点が存するとも考えられるため,これらの相違点が設計上の微差にすぎないか,実 質的な相違点であるかについて,以下検討する。
ウ 相違点(1)について
本件特許1の出願当時,携帯電話やハンドフリー電話の分野においては,携帯電 話等の端末において,特定の電話番号をメモリ番号に対応付けて記憶させることは, 複数の名前や電話番号を含む情報を整理するなどの目的に広く使われる,周知の技 術であったことが認められる(乙13ないし15)。 そうすると,画像を,ある電話番号と対応付けられたメモリ番号に対応付けて記 憶させるか,それとも,直接,当該電話番号と対応付けて記憶させるかという違い は,設計上の微差にすぎないというべきである。
エ 相違点(2)について
乙12−1発明において,ある特定の電話番号に対して既に1つ又は複数の画像 が対応付けられて記憶されている場合において,新たな画像をカメラやネットワー クを通じて入手し,当該電話番号に対応付けて記憶させたとして,当該電話番号か ら着呼があった際,当然に,その新たな画像が優先的に着信画面に表示されるよう\nになるということはできない。 しかし,乙12の段落【0032】の記載(「複数の画像を一つの電話番号と対 応させ,着呼毎に変えたり,時間によって変えたり,着呼時に順番に出したりする こともできる。」)によれば,乙12−1発明は,複数の画像を一つの電話番号に 対応付ける機能部を有しており,これを使用して,当該電話番号の着呼に応じて,\n複数の画像から一つの画像を選択しており,かかる選択を,着呼毎に変更したり, 時間に応じて変更したり,一回の着呼に対して複数の画像を順番に変更したりする ことにより,様々な表示を行っているものと認められる。\nしたがって,乙12−1発明において,電話番号と対応する複数の画像からどの 画像を選択するかということは任意に設定することが可能であり,複数の画像のう\nち,新たに入手した画像を優先的に選択することや,上記機能部において,これま\nで記憶されていた複数の画像のうち,表示しない画像と当該電話番号との対応付け\nを削除するか否かということは,必要に応じて,当業者が適宜選択し得る設計的事 項である。また,かかる選択をしたことに伴う顕著な効果も認められない。 よって,乙12−1発明において,複数の画像のうち,新たに入手した画像を選択 して表示し,これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応付けを削\n除せずに,これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応関係を維持 することは,当業者が適宜選択し得る設計的事項であるといえ,奏せられる効果に 著しい差も認められない。したがって,相違点(2)についても,設計上の微差にすぎ ないということができる。
(4) まとめ
以上より,本件発明1は,実質的に,乙12−1発明と同一であるから,特許法 29条の2により特許を受けることができないものであって,同法123条1項2 号の無効理由があり,特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.02. 5
令和1(行ケ)10073 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所
商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある 商標」には,健全な商道徳に反し,著しく社会的妥当性を欠く出願行為に係る 商標も含まれると解される。 (1) そこで,まず,原告による本件商標の登録出願が,被告との関係で義務違 反となりうるかについて検討する。 前記1(1)(2)の各事実によれば,原告と被告とは,本件商標の登録出願が行 われた平成28年10月14日時点を含めて,平成11年頃から平成29年 10月12日頃までの間,被告が,原告に対し,独占的に本件被告商品やマ ナマリンなどを卸売りし,原告がこれを薬局薬店等に販売するという長期間 にわたる取引関係にあった。 かかる取引関係に関して,前記1(2)エのとおり,原告と被告とは,被告商 標の登録が完了した直後である平成16年3月25日,本件覚書(甲6)を 締結した。本件覚書の柱書,1条,3条の記載に照らすと,本件覚書は,被 告商標として登録された「仙三七」との商標を,本件被告商品に付して,販 売することを前提とするものであることが明らかである。また,本件覚書に は,被告及び原告は,第三者が被告商標の権利を侵害し又は侵害しようとし ていることを知ったときには互いに遅滞なく報告し合い協力してその排除に 努めるものとすること(第5条)や,被告及び原告は,信義に基づいて本件 覚書を履行するものとし,万一本件覚書に関して疑義が生じた場合には,被 告及び原告はお互いに誠意をもってこれを解決するものとすること(第7 条)とする合意が含まれていた。このように,被告が原告に使用許諾して 「仙三七」との商標を本件被告商品に付して販売することとされ,第三者か らの被告商標に係る商標権の侵害に対する対策も合意された上で,7条にお いて信義に基づいて本件覚書を履行するとされていたことに照らすと,本件
覚書において,原告自身が,三七人参を原材料とした健康食品との関連で 「仙三七」との商標を商標登録することは全く想定されていないといえる。 以上によれば,長期間にわたり,本件被告商品の卸売りを受けて,これに 被告商標と同じ「仙三七」との商標を付して販売し,利益を上げていた原告 は,被告との関係において,被告が「仙三七」との商標の商標権者として, かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則 上の義務を負っていたものということができる。 そして,原告による本件商標の登録出願は,被告商標と同じく「仙三七」 を横書きにしてなる商標について,本件被告商品を指定商品に含むものとし て登録出願するものである。かかる登録が認められることになると,被告 は,「仙三七」との商標の商標権者として,第三者に使用許諾をするなどし てかかる商標を付して本件被告商品を販売することはできなくなり,重大な 営業上の不利益を受けるおそれが生じる。 以上によれば,原告の本件商標の登録出願は,上記信義則上の義務に反す るものといわざるを得ない。
(2) 次に,原告の本件商標の登録出願の経緯及び目的についてみる。 前記1(3)イからエのとおり,原告は,上記出願の前後において,被告に対 し,被告商標が本件被告商品を指定商品に含んでいない可能性や自らが本件\n商標を登録出願することについて何ら告げることはなく,本件商標の設定登 録完了から4か月以上経過した後の平成29年8月18日付けの「申し入れ\n書」(甲7)において,初めて,本件商標の商標権者であることを明らかに した上で,原告と被告との本件被告商品の取引終了を一方的に申し入れると\nともに,被告に対し,マナマリンの商標の譲渡やそれを条件とした三七人参 の購入などを提案したものである。 これに対し,上記「申し入れ書」の内容に照らすと,原告自身は,当該\n「申し入れ書」を送付する前に,被告以外の第三者から,本件被告商品と同\n種の競合品を購入する段取りを既に整えていたと認められる。 そして,原告は,その後の被告とのやりとりの中で,原告から被告に対す る営業譲渡の申入れや被告商標の譲渡の依頼に応じてもらえなかったこと,\n被告の本件被告商品の仕入れ価格が高額であるために原告独自の商品を生産 することにしたことなどをも理由として挙げながら,原告としては被告の生 産する本件被告商品が原告の希望仕入れ価格に不適格であると判断し,原告 にて新しいブランドで生産から販売を開始することなどを伝えている。 このような原告の言動に照らすと,原告は,「仙三七」との商標が,本件 被告商品と同種の商品に付されることによって生じる利益を独占するべく, 被告に本件商標と競合する商標を登録出願されないように注意を払った上 で,自らは,同種商品の調達ルートを確立する一方で,被告との取引関係を 終了する準備を計画的に整えながら,本件商標の登録出願及び上記「申し入\nれ書」の送付に及んだものといえる。
(3) 以上によれば,原告による本件商標の登録出願は,被告が「仙三七」との 商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義 務を負うにもかかわらず,被告商標が本件被告商品を指定商品として含まな い可能性があることを奇貨として本件商標の登録出願を行い,本件商標を取\n得し,被告が「仙三七」のブランドで健康食品を販売することを妨げて,そ の利益を独占する一方で,その他の商品の取引に関する交渉を有利に進める という不当な利益を得ることを目的としたものということができる。 このような本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると,原告による本 件商標の出願行為は,被告との間の信義則上の義務違反となるのみならず, 健全な商道徳に反し,著しく社会的妥当性を欠く行為というべきである。 そうすると,このような出願行為に係る本件商標は,商標法4条1項7号 所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するも のといえる。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,「仙三七」との商標は原告の努力等によってその信用が築き上 げられたものであり,また取引者等は本件被告商品の出所は原告であると 認識するなどとして,かかる商標は原告のものであるなどと主張する。 しかしながら,原告は,本件覚書に基づいて「仙三七」の商標の使用を 許諾され,この許諾に基づいて,本件被告商品に「仙三七」との商標を付 して,長年にわたり販売してきたものである。その過程において,原告が 努力し,また販売者として表示されたことによって「仙三七」との商標の\n出所であると取引者や需要者に認識されたとしても,それは,あくまでも 被告の許諾を基盤として形成された信用なのであるから,原告が当然に 「仙三七」との商標の権利者として扱われるべきであるとする根拠となる ものではない。 前記のとおり,被告との関係で,原告による本件商標の出願行為が,信 義則上の義務違反となり,健全な商道徳に反し,著しく社会的妥当性を欠 く行為であるとの評価は,原告の主張によっても左右されない。
イ また,原告は,被告商標は本件被告商品を指定商品として含んでいなか ったなどとして,被告は「仙三七」との商標について何らの権利ももって いなかったなどと主張する。 確かに,被告商標について,本件被告商品を指定商品として含んでいな かった可能性が高いことは,被告も認めるところである。\nしかしながら,本件被告商品が,被告商標の指定商品の範囲に含まれて いなかったとしても,本件覚書を締結し,長年にわたりその有効性を前提 として取引関係にあった原告と被告の間においては,問題が生じた場合に は,本件覚書の第7条に基づき,お互いに誠意をもって解決すべきであ る。そして,原告としては,被告が,「仙三七」との商標の商標権者とし て,かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない 信義則上の義務を負っていたことは前記(1)に判示したとおりであることを も併せ考えると,原告において,抜け駆け的に本件被告商品を指定商品と するような商標で商標登録をすることが許されるわけではない。 むしろ,本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると,原告は,本件 被告商品を指定商品として含んでいなかった可能性や,自らが本件商標の\n登録出願をしようとしていることについては,何ら被告に告げておらず, 却って,前記1(3)アにみたとおり,平成28年9月頃(本件商標の登録出 願の直前頃と考えられる。)には,被告商標の譲渡を持ちかけて,その指 定商品に本件被告商品が含まれることを前提とするかのような言動を示し たものである。これらの原告の行為は,被告商標の保護範囲についての被 告の誤解を解消することなく,むしろ,被告の誤解を奇貨として,被告が 本件商標と同一の商標の登録出願をすることを著しく困難にするものであ ったと評価できる。それにもかかわらず,先願主義をそのまま適用して, 本件商標の有効性を肯定することは,当事者間の衡平を著しく欠くものと いえるから,前述の結論は左右されない。 なお,本件覚書7条は,覚書に関する疑義が生じた場合に誠意を持って 解決するとしていることからもうかがわれるとおり,本件覚書は,被告商 標に係る商標権が本件被告商品を指定商品として含むことを保証ないし当 然の前提とするものであるとまではいえないから,仮にこの点について疑 義が生じたとしても,そのことによって,当然に本件覚書が無効となるも のではない。
ウ また,原告は,被告に被告商標が空虚な権利であることを告げること は,自らを縛る道具を更に継続させるのみであることは明らかであるか ら,本件商標の登録出願を告知する義務はないなどと主張する。 しかしながら,被告商標の有効性に疑問があるというのであれば,それ を告知することによって本件覚書を適切に機能させることが本件覚書の趣\n旨なのであるから,原告の主張は,この趣旨に反し,信義にもとるもので あると言わなければならない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.02. 5
平成30(ワ)7538 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 令和2年1月14日 大阪地方裁判所(21部)
著作権法114条3項は,「著作権者…は,故意又は過失によりその著作権 …を侵害した者に対し,その著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する 額を自己が受けた損害の額として,その賠償を請求することができる。」旨規定し, 使用料相当額の請求を認めるところ,これは,民法709条,著作権法114条1 項及び2項の主張立証が困難な場合であっても,著作権者に最低限の損害賠償を保 証する趣旨であると解されている。 著作権の許諾は,多くの場合,特許権の実施許諾契約の場合に見られるように, 実施権者が,自らの製品の一部に当該特許発明を用いて製造するといった態様では なく,許諾を受けた者が,当該著作物をそのままの形で使用する態様が採られ,他 の著作物による代替も予定されていない。また,本件のような著名な芸術家による\n高価な芸術作品の複製に関する許諾の場合には,大量の複製品の製造及び流通は通 常予定されておらず,許諾を受けた者が制作する複製品の品質の評価が,著作者で\nある芸術家の評価に直接影響することから,許諾に際し,慎重な選考が行われたり, 複製品の製造数量が限定されたり,複製品の価格設定を著作権者が行ったり,比較 的高い料率が設定されたりすることが考えられる。 そうすると,このような場合において,「その著作権…の行使につき受けるべき 金銭の額」,すなわち許諾料相当額は,相手方又は第三者との間における当該著作 権に係る許諾契約における許諾料や,その算定において用いられた事情,あるいは 業界慣行等一般的相場を基礎として,著作物の種類及び性質や,当該著作権の許諾 を受けた者において想定される著作物の利用方法等を考慮し,個別具体的に合理的 な許諾料の額を定めるべきである。
(2)ア 本件において,前記1(4)のとおり,平成元年から平成23年までの間に, 本件各ブロンズ像について,各作品の販売価格を基礎としてその約10ないし4 0%の額の許諾料にて複製の許諾がなされていたこと,具体的な許諾料は,複製品 の制作者との協議の上で最終的に訴外直樹が決定しており,減額はされなかったこ と,前記1(5)のとおり,作品の販売価格についても訴外直樹が原則として値引きを 行わせなかったこと,平成18年ころにおける各作品の販売価格は,上記許諾料が 定められた際に基礎とされた販売価格とほぼ同水準であったこと等が認められる。
イ 一方で,許諾料相当額を算定するにあたっては,許諾を得た者が実際に支払 った許諾料の水準や,著作権が侵害された平成16年ころから平成28年ころまで の間に,許諾を得て複製された訴外直樹の作品が販売された数量,価格を考慮する 必要があるが,平成18年に原告が訴外直樹の著作権を相続した後,どの程度許諾 料を得たかについての証拠は提出されていないし,前記1(5)の平成18年の回顧展 の後に,訴外直樹の作品が,どのような価格で,どのような数量販売されたかにつ いての証拠も提出されていない。 また,「大将の椅子」について,平成23年以降は許諾を受けた者が倒産したた め製造販売されず,他の者に対する許諾もなされていないこと,令和元年における オークションにおける最低入札価格が68万円とされているところ,オークション が中古市場であることや最低入札価格と実際の販売価格との間には相当程度の開き が生じ得ることを考慮しても,同作品につき以前の販売価格(450万円)又はこ れに近い価格で取引が行われているかについては,不明といわざるを得ないし,前 記1(4)アの合意は,訴外直樹と業者との間で,平成元年から平成9年にかけてなさ れたものであることを総合すると,前記1(4)で合意された金額が,著作権侵害期間 である平成16年ころから平成28年ころまでの許諾料相当額としてそのまま妥当 するとすることは困難である。
ウ 他方,前記1(3)のとおり,被告は,無断で製造した本件各ブロンズ像の複製 品を,単価15万円から60万円程度という安価で販売し,鋳造及び着色業者に対 して,1体当たり15万円程度の対価を支払っていることから,複製品の製造によ り得た利益は多額とはいえないと考えられるし,被告から廉価で品質の劣る複製品 を購入した者は,それが禁止されていれば,直ちに高価な正規品を購入したであろ うとの関係も認め難い。 しかし,本件のように,著作権者の側が,一定の水準以下では複製も,複製品の 販売も認めないとしている場合に,無断で複製を行った者がこれを廉価で販売する ことで,侵害者の利益に合わせて許諾料相当額の水準を大きく下落させることは, 前記(1)で述べた,著作権法114条3項の趣旨を没却することになり,相当でない というべきである。
(3) 以上より,本件各ブロンズ像の許諾料相当額については,前記1(4)で認定し た,訴外直樹が,本件各ブロンズ像の販売価格を基礎として,許諾を受ける者との 協議の上で決定した価格を出発点としつつも,前記(2)イで検討した事情を総合して, 以下のとおり,侵害時期に対応する本件各ブロンズ像の許諾料相当額は,前記1(4) の各許諾料の半額とするのが相当であると考えられる。
(1) 「クリスマス・イブ」(小) 30万円
(2) 「パリ祭」 75万円
(3) 「初舞台」 40万円
(4) 「大将の椅子」 90万円
(5) 「トルコの貴婦人」 75万円
(6) 「トスカーナの女」 125万円
(4)まとめ
したがって,上記許諾料に,それぞれ,前記第2の1(2)及び第3の2のとおりの販売数を乗じると,合計6290万円となるところ,これが訴外直樹又は原告の損害額と認められる。
(計算式)30万円×39体+75万円×20体+40万円×16体+90万円×17体+75万円×11体+125万円×5体=6290万円
2020.02. 5
平成30(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月4日 知的財産高等裁判所
被告らは,引用例1に記載された東レポートという発明の構成の内容を理解する\nために,東レポートの添付文書である引用例2を参照することは許容され,本件審 決が引用例1と引用例2の2つから甲9発明を認定したことに,誤りはないと主張 する。 しかし,「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)の認定に当たり,特 定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせて認定 することは,新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく,新規性と進歩 性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し,原則として許され\nないというべきである。 よって,東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引\n用例1と,これと作成者も作成年月日も異なる,東レポートの仕様や使用条件を記 載した添付文書である引用例2の記載から,甲9発明を認定することはできない。 そして,引用例1には,東レポートの具体的な構成についての記載はなく,東レポ\nートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認\nめられないから,甲9発明が,引用例1に実質的に開示されているということもで きない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2020.02. 3
平成31(ネ)10018 損害賠償請求本訴,使用料規程無効確認請求反訴控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上のとおり,被控訴人は,地上テレビジョン放送事業者から管理 委託を受けた著作権及び著作隣接権の有線放送権に基づき再放送の利用 許諾をするに当たり,ほぼ全てのケーブルテレビ事業者との間で,3者 契約又は2者契約の方式により年間の包括的利用許諾契約を締結し,3 者契約の場合は本件基本合意に基づき,2者契約の場合は本件使用料一 覧(2者契約)に基づき定められた使用料額をケーブルテレビ事業者か ら徴収していることが認められる。 一方,被控訴人と3者契約又は2者契約の方式により年間の包括的利 用許諾契約を締結したケーブルテレビ事業者のうち,本件基本合意に基 づく減額措置(3者契約の場合)又は本件使用料一覧(2者契約)に基 づく減額措置(2者契約の場合)を受けることが可能であるにもかかわ\nらず,減額措置を受けずに,本件使用料規程に定められた区域内再放送 の使用料(1世帯1ch当たり年額120円)及び区域外再放送の使用 料(1世帯1ch当たり年額600円)を支払っている事業者は存在し ない。 そして,控訴人は,適法に同意を得て,又は総務大臣による同意裁定 を得て,毎日放送等6社の地上テレビジョン放送を同時再放送している ものであり,ケーブルテレビ連盟の会員でもあることから,仮に控訴人 が希望すれば,被控訴人との間で,本件基本合意に基づく3者契約又は 本件使用料一覧(2者契約)に基づく2者契約を締結することが可能で\nあって,その場合の再放送使用料は,上記減額措置の適用を受けて,区 域内再放送につき1世帯1ch当たり年額24円(3者契約)又は28 円(2者契約),区域外再放送につき1世帯1ch当たり年額120円 (3者契約)又は144円(2者契約)であり,平成26年度の再放送 使用料については,使用料の50%が軽減されるものと認められる(弁 論の全趣旨)。
以上のような,被控訴人とケーブルテレビ事業者との間で締結された 同時再放送に係る利用許諾契約の内容,控訴人による本件有線放送権の 利用の態様等の事実を考慮すると,上記利用許諾契約の締結に当たり適 用された実績が全くない,本件使用料規程の「年間の包括的利用許諾契 約によらない場合」(3条(2))又は「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ 場合」(3条(1))が,著作権法114条4項の「使用料規程のうちその 侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」 に該当するものとは認めらない。
(イ) これに対し被控訴人は,(1)使用料規程による使用料の算出方法が複 数あるときは各方法により算出した額のうち最も高い額を請求すること ができるとする著作権法114条4項を設けた趣旨に鑑みれば,「最も 高い額」となる算出方法による許諾実績がなくとも,同項の適用は妨げ られない,(2)実際にも,被控訴人は,著作権等管理事業を開始した平成 26年度以降,年間の包括的利用許諾契約によって区域外再放送を許諾 するに当たり,累計12社(平成27年度10社,同28年度9社,同 29年度9社)の有線テレビジョン放送事業者につき,本件減額措置を 施さずに,有料視聴世帯数に地上テレビジョン放送1波当たり年額60 0円を乗じた額の使用料を徴収している旨主張する。
まず,上記(1)の点について,著作権法114条4項は,同条3項により損害の賠償を請求する場合において,当該著作権等管理事業者が定め る使用料規程により算出した金額をもって,同条3項に規定する金銭の 額とする旨を定めるものである。そして,同条3項は,不法行為による 著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定し た規定であるところ,不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じ た現実の損害を填補することを目的とするものであるから,現実の損害 が発生しなかった場合には,それを理由とする賠償請求をすることがで きないことは自明である。 これを本件についてみるに,前記(ア)のとおり,被控訴人は,ほぼ全て のケーブルテレビ事業者との間で,3者契約又は2者契約の方式により 年間の包括的利用許諾契約を締結し,3者契約の場合は本件基本合意に 基づき,2者契約の場合は本件使用料一覧(2者契約)に基づき定めら れた使用料額をケーブルテレビ事業者から徴収しており,これらの事業 者のうち,本件基本合意に基づく減額措置又は本件使用料一覧(2者契 約)に基づく減額措置を受けることが可能であるにもかかわらず,これ\nを受けずに,それよりも遥かに高額な,本件使用料規程3条(1)又は(2)に 定められた区域内再放送及び区域外再放送の使用料を支払っている事業 者は存在しない。被控訴人と控訴人との交渉の過程においても,本件基 本合意に基づく3者契約又は本件使用料一覧(2者契約)に基づく2者 契約によることが,当然の前提とされていたものである。
そして,このような被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再 放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額,控訴人による本件 有線放送権の利用の態様,控訴人と被控訴人の間の再放送同意に係る利 用許諾契約に関する交渉経緯(前記ア(エ))等によれば,本件における使 用料相当額の算定に当たって,実際の利用許諾契約において用いられた 例がなく,かつ,上記減額措置を受ける場合と比較して使用料が遥かに 高額となる,本件使用料規程3条(1)又は(2)による場合の算定方法を用い ることは,被控訴人に生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現 実的というべきであり,相当でない。 次に,上記(2)の点について,被控訴人が,累計12社の有線テレビジ ョン放送事業者との間で,本件使用料規程に基づき,区域外再放送の使 用料を1世帯1ch当たり年額600円とする年間の包括的利用許諾契 約を締結し,同規程に基づき算定された金額を徴収していることについ ては,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また,被控訴人の 主張によれば,上記12社はいずれも重複波等の区域外再放送を行った 者であるところ,前記認定の被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の 同時再放送に係る利用許諾契約の締結状況に照らすと,上記12社は, 本件基本合意に基づく3者契約又は本件使用料一覧(2者契約)による 2者契約を締結した上で,本件基本合意(1)(3)の定めに基づき,「有料視 聴世帯数×1世帯1chあたり年額600円×区域外再放送(重複波等) ch数」の使用料を支払ったものであると推認される。そして,上記1 2社において,本件基本合意に基づく減額措置(3者契約の場合)又は 本件使用料一覧(2者契約)に基づく減額措置(2者契約の場合)を受 けることが可能であるにもかかわらず,減額措置を受けずに,本件使用\n料規程に定められた区域外再放送の使用料を支払っていることを認める に足りる証拠はない。 したがって,被控訴人の上記各主張を採用することはできない。
ウ 被控訴人は,控訴人が本件有線放送権を侵害したことにより被控訴人が 受けた損害の額として,著作権法114条3項及び4項により算定される 損害額を主張するところ,前記イのとおり,本件において著作権法114 条4項を適用して,本件使用料規程3条(1)又は(2)に基づいて被控訴人の損 害の額を算定することは,相当でない。そこで,同条3項により算定され る被控訴人の損害の額について,以下検討する。 同条3項は,著作権及び著作隣接権侵害の際に著作権者,著作隣接権者 が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。また,同項所定の 「その著作権…又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当 する額」については,平成12年法律第56号による改正前は「その著作 権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額」と 定められていたところ,「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得にな ってしまうとして,同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 そして,かかる法改正の経緯に照らせば,著作権及び著作隣接権侵害をし た者に対して事後的に定められるべき,これらの権利の行使につき受ける べき金銭の額は,通常の利用許諾契約の使用料に比べて自ずと高額になる であろうことを考慮すべきである。
これを本件についてみると,前記イ(ア)の被控訴人とケーブルテレビ事 業者との間の同時再放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額, 控訴人による本件有線放送権の利用の態様等の事実に加えて,控訴人と被 控訴人の間の再放送同意に係る利用許諾契約に関する交渉経緯など,本件 訴訟に現れた事情を考慮すると,著作権及び著作隣接権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき,本件での利用に対し受けるべき金銭の額は, 被控訴人とケーブルテレビ事業者との間における再放送使用料を現実に 規律していると認められる本件基本合意及び本件使用料一覧(2者契約) をベースとし,そこに定められた額を約1.5倍した額である,区域内再 放送につき1世帯1ch当たり年額36円及び区域外再放送につき1世 帯1ch当たり年額180円とし,平成26年度についてはその半額を下 らないものと認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
2020.01.30
平成31(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月28日 知的財産高等裁判所(1部)
原告は,本件各発明は物の発明であるから,構成要件Hは制御手段の存在に\nよって特定されるべきであり,この解釈を措くとしても,構成要件Hは空気式マッ\nサージ具による挟み動作と施療子による叩き動作という異質の2種類の施療手段を あえて同期させるものであるから,その制御手段を具体的に開示することが要請さ れるところ,本件明細書の発明の詳細な説明には制御手段の具体的な説明はなく, またかかる制御手段が技術常識であった事実は存在しないから,本件明細書の発明 の詳細な説明の記載は,実施可能要件に違反していると主張する。\n
しかし,本件明細書の発明の詳細な説明には,前記(2)アのとおり,機械式マッサ ージ器8の左右の施療子9がマッサージ用モータ10の回転を制御することで叩き 動作を行うことや,空気式のマッサージ具41が内部に備えた袋体(エアセル42) にコンプレッサー61から空気を供給し膨張させることで押圧動作を行うことが記 載されている。そして,機械式のマッサージ器による叩き動作と,空気式マッサー ジ器による押圧動作を「同時」に行うためには,両者の制御をその字義どおり時を 同じくして(甲25の1・2)行えば足り,それぞれを単独で動作させる場合の制御 と格別異なる制御を要するものではないから,このような制御手段について発明の 詳細な説明に記載がないとしても,そのことによって当業者が本件各発明の実施に 過度の試行錯誤を要するとは認められない。 イ 原告は,被告が本件出願の審査過程で主張した,左右の施療子によって使用 者の背中に対し左右交互に前後の叩き動作が繰り返されるという作用効果に関して は,制御手段としてさらに具体的な説明が必要であるのに,本件明細書の発明の詳 細な説明には何らの記載も存在しないとも主張する。 しかし,実施可能要件の適合性は,請求項に係る発明について,明細書の記載と\n出願時の技術常識とに基づいて判断され,その判断が,出願人の審査段階の主張に より左右されるとは解されない。実施可能要件の適合性の判断を,出願人が出願経\n緯において述べた事項が禁反言の法理等により技術的範囲の解釈に影響することが あるということと同様に考えることはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.01.30
平成31(行ケ)10031 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月28日 知的財産高等裁判所
本願発明は,管状に成形された鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接で 内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接したラインパイプ用溶接鋼管において,溶 接による熱影響部(HAZ)で優れた低温靭性を得るため,溶接部において,内面側 溶融線と外面側溶融線との会合部を内外面溶融線会合部とした際,内面側の前記鋼 板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L1と,外面側の前記鋼板\n表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L2とが0.1≦L2/L1\n≦0.86を満足し,前記鋼管の周方向を引張方向とした際,前記鋼板の引張強度 が570〜825MPaであるように規定したものである。 一方,引用発明は,管状に成形された鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接 で内面外面の順に内外面それぞれ一層シーム溶接した,ラインパイプに用いられる UO鋼管において,シーム溶接部に発生する低温割れを防止するため(【0014】),溶接部において,先行するシーム溶接により形成された溶接金属の厚さをW1,後 続するシーム溶接により形成された溶接金属の厚さをW2とする場合に,0.6≦ W2/W1≦0.8,あるいは1.2≦W2/W1≦2.5の関係を満足し,鋼板の 引張強度が850MPa以上1200MPa以下と規定したものである。 そうすると,本願発明と引用発明とは,いずれも,管状に成形された鋼板の突き 合せ部をサブマージアーク溶接で内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接したライ ンパイプ用溶接鋼管に関するものであり,技術分野において共通する。 しかしながら,本願発明は,外面入熱を大幅に低減して外面溶接熱影響部の低温 靭性を向上させ,内面溶接熱影響部の低温靭性を劣化させない範囲に内面入熱を制 御することで,十分な溶け込みを得ながら内外面両方の溶接熱影響部で優れた低温\n靭性を得ることを目的として(【0015】),内面側の前記鋼板表層から前記内外面\n溶融線会合部までの板厚方向距離L1と,外面側の前記鋼板表層から前記内外面溶\n融線会合部までの板厚方向距離L2の比を検討し,内外面両方の溶接熱影響部の低 温靭性を向上させることができるよう,L2/L1の上限及び下限を設定したもの である。これに対し,引用発明は,シーム溶接部に発生する低温割れを防止するた め,先行するシーム溶接の溶接金属内に発生する溶接線方向の残留応力の変化に着 目して,先行するシーム溶接の溶接金属の厚さW1と後続するシーム溶接の溶接金 属の厚さW2の比を検討し(引用例1【0041】),残留応力が大きくならない範 囲であり,かつ,低温における吸収エネルギーの低値の発生頻度が大きくない範囲 において,W2/W1の上限及び下限を設定したものである(引用例1【0042】)。
そうすると,本願発明と引用発明とは,本願発明が,外面溶接熱影響部における 低温靭性の向上を課題として,L2/L1の上限及び下限を規定しているのに対し, 引用発明は,内面溶接金属内におけるシーム溶接部に発生する低温割れの防止を課 題として,W2/W1の上限及び下限を規定しているのであるから,両者はその解 決しようとする課題が異なる。また,その課題を解決するための手段も,本願発明 は,外面熱影響部において,外面入熱を低減して粒径の粗大化を抑制するものであ るのに対し,引用発明は,先行するシーム溶接(内面)の溶接金属に発生する溶接線 方向の引張応力を低減するものである。したがって,引用例1には,外面溶接熱影 響部における低温靭性の向上のため,W2/W1をL2/L1に置き換えることの 記載も示唆もない。 そして,溶接ビード幅中央の位置における溶接金属の厚さであるW2/W1と, 母材表面から内外面溶融線会合部までの距離の比であるL2/L1とは,余盛部分\nの厚さや,内外面溶融線会合部から外面溶接金属の先端までの距離を考慮するか否 かにおいて,技術的意義が異なるところ,引用発明においてW2/W1に替えてL 2/L1を採用するなら,余盛部分の厚さや内外面溶融線会合部から外面溶接金属 の先端までの距離を含む溶接金属の厚さが考慮されないことになる。 また,W2/W1が一定であっても,内面側溶接金属の溶け込み量が変化すると, L2/L1は変動するから,W2/W1とL2/L1とは相関がなく,W2/W1 に対してL2/L1は一義的に定まるものではない。 以上によれば,引用発明のW2/W1をL2/L1に置き換える動機付けがある とはいえないというべきである。
イ 引用発明のW2/W1は,鋼板の引張強度が850MPa以上1200MP a以下という条件下での溶接金属内での残留応力を根拠として最適化されたもので あり,引用例1には,これを850MPa未満のものに変更することの記載も示唆 もない。 そうすると,本願出願時において,鋼管の周方向に対応する引張強度が600〜 800MPaの鋼板について,その突合せ部を内外面から1パスずつサブマージド アーク溶接することで,低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼管を製造すること が知られていたこと(引用例2【0002】,【0009】,【0059】,【0071】) を考慮しても,鋼板の引張強度が850MPa以上1200MPa以下という条件 下でW2/W1を最適化した引用発明において,鋼板の引張強度が570〜825 MPaのものに変更することについて,動機付けがあるとはいえない。
ウ よって,相違点1及び2は,引用発明及び引用例2の技術事項に基づいて, 当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.01.30
平成29(ワ)6334 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年1月16日 大阪地方裁判所(21部)
まず,原告の主位的主張について検討すると,被告らは被告製品を製造販 売等し,被告製品の包装箱には「発売元」として被告ナプラが,「製造販売元」と して被告ビー・エス・ピーが記載されていたこと,その株主及び代表取締役が同一\nであることを踏まえると,被告らは原告に対して共同不法行為に基づく損害賠償責 任を負うというべきである。 そして,原告と被告ナプラは理美容室向け毛髪化粧品の分野の競業企業であり, 原告は被告製品と競合する「エルジューダ サントリートメント セラム」という UVケアオイル(アウトバストリートメント)を販売しているから(弁論の全趣旨), 特許権者である原告に,被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得ら れたであろうという事情が存在すると認めることができる。したがって,本件には 特許法102条2項が適用される。
(2) 特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,侵 害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりその 製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり, その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである(知財高裁令和元年6 月7日判決・最高裁ウェブサイト)。 このような観点から,被告らの利益額を検討するが,被告らに共同不法行為が成 立することから,被告らを一個の製造,販売の主体と見て,被告らにいくらの利益 が生じたかという観点から検討する。
ア 被告製品の売上金額
被告らが一旦,被告製品1を1万0056個販売し,その売上金額が737 万5231円(税込)であったこと,被告製品2を4716個販売し,その売上金 額が557万6552円(税込)であったことは,当事者間に争いがない。 もっとも,被告らは,原告が損害賠償を請求している平成29年2月2日から平 成31年4月2日までの被告製品の出荷分についても返品があったとして,その売 上金額を差し引くべきと主張する。 そこで,この点について検討すると,上記期間の出荷分に返品があり,その返品 に係る売上金額が計上されない場合には,被告らにそれに相当する利益があったと いえないことは明らかである。したがって,特許法102条2項の利益の額の算定 に当たっては,上記期間の出荷分に返品があった場合には,売上金額の算定に当た って,返品に係る売上金額を控除すべきである。 そして,上記期間における被告製品の返品数は,乙39及び弁論の全趣旨によれ ば,被告製品1が124個(その売上金額は,合計9万1065円(税込)),被 告製品2が21個(その売上金額は,合計2万4948円(税込))と認められる。 原告は,返品されたのは平成29年2月1日以前の出荷分である旨主張するが, 乙39記載の返品時期に照らし,同月2日以降の出荷分である可能性は否定できず,\n前記認定に反する証拠があるわけでもないから,被告らに上記金額に相当する売上 げないし利益が生じたことを認めるには足りないというべきである。 したがって,被告製品の販売個数及び売上金額は,次のとおりと認められる。
販売個数 売上金額(税込)
被告製品1 9932個 728万4166円
被告製品2 4695個 555万1604円
合計 1万4627個 1283万5770円
イ 被告らの経費の額
(ア) 商品原価
被告らは,乙27記載の各経費を控除すべきと主張するのに対し,原告は これを否認して争い,予備的に,被告製品1について204円/個,被告製品2に\nついて330円/個の限度で控除するにとどめるべきと主張する。そこで,乙27 記載の各経費について,控除の可否を検討する。
a バルク原価(原料原価,調合光熱費及び調合手間)
乙40及び弁論の全趣旨によれば,被告らが被告製品を製造販売するに 当たり,バルク原価として,原料原価及び調合光熱費を要したと認められ,その性 質上,これらは侵害者である被告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売する ことによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認め られる。そして,上記書証等によれば,原料原価は(中略)円/kg,調合光熱費は (中略)円/kgを下らないと認められるところ,これによれば,被告製品1個当た りのこれらの費用は,被告製品1について(中略),被告製品2について(中略) を下らないと認められる。 これに対し,乙40では「調合手間」もバルク原価に含み,これは調合作業の人 件費に相当するものと説明されている。しかし,単に被告らの従業員が被告製品の 製造に関与しているというだけでは,侵害品である被告製品の製造販売に直接関連 して追加的に必要となった経費を要したと認めることはできず,これに当たること を認めるべき事情は主張立証されていない。したがって,「調合手間」については, 経費として控除すべきとはいえない。
b 容器,ポンプ,キャップ,一本箱,添付文書,内箱,外箱に係る費用
乙27及び弁論の全趣旨によれば,被告らが被告製品を製造販売するに 当たり,これらの費用を要したと認められ,その性質上,これらは侵害者である被 告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。そして,上記書証等に よれば,被告製品1個当たりのこれらの費用は,被告製品1について合計(中略) 円,被告製品2について合計(中略)円を下らないと認められる。
c 運賃,関税輸送費
乙27,39及び弁論の全趣旨によれば,被告らが被告製品を製造販売 するに当たり,これらの費用を要したと認められ,その性質上,これらは侵害者で ある被告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売することによりその製造販売 に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。そして,上記書 証等によれば,被告製品1個当たりのこれらの費用は,被告製品1について運賃(中 略)円,関税輸送費(中略)円,被告製品2について運賃(中略)円,関税輸送費 (中略)円を下らないと認められる。
d 手間
乙27,39では「手間」も商品原価に含み,これは女性7名による作 業や添付文書の差込みに関する経費である旨説明されている。しかし,前記aの「調 合手間」と同様の理由により,これを経費として控除すべきとはいえない。
e 原告の主張について
原告は乙27記載の各経費を要したことを否認し,仮定による試算結果 にすぎないなどと主張するが,被告製品の製造販売に当たって前記aないしcで控 除を認めた諸経費を要することは明らかであり,また前記認定に反する証拠がある わけでもないから,前記認定は左右されない(被告らの利益額の立証責任が原告に あることは前述したとおりである。)。
f 控除すべき経費の額
商品原価として控除すべき経費の額は,被告製品1について合計217. 02円/個,被告製品2について合計364.21円/個と認められ(弁論の全趣 旨によれば,これらの金額は税込みの金額と認められる。),これによると,商品 原価は合計386万5409円となる。 計算式:217.02×9932個+364.21円×4695個=386万5 409円(小数点以下切上げ)
(イ) UV防止効果の試験費用
被告らは,平成28年3月31日と同年5月20日付けで依頼したSPF・ UVAPF測定試験に係る費用(乙34の1ないし35の2)を経費として控除す べきと主張する。 しかし,同年3月31日付け依頼分については,被告の主張によっても,被告製 品を研究開発する過程で支出された費用にとどまるものといわざるを得ず,被告製 品そのものについて試験をしたものとは認められないから,この費用をもって,侵 害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たる ということはできない。 これに対し,同年5月20日付け依頼分について,原告はこれが被告製品に関す る試験であることを前提としつつ,平成29年2月2日以降に販売された製品その ものについて行われた試験ではないという理由で,経費として控除することを争っ ている。しかし,被告製品は,化粧料としての性質上,これを製造販売するために は,平成28年5月20日付け依頼分のような試験を行うことが必要不可欠であり, この試験は,平成29年2月2日以降に被告製品を販売するのにも必要であったと いうことができる。そうすると,上記試験の費用(86万4000円(税込))は, その全てが侵害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった 経費に当たるということはできないが,原告が本件で損害賠償を請求している期間 の被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったと認められる部分につ いては,経費として控除するのが相当である。 控除する金額については,原告が本件で損害賠償を請求している期間における被 告製品の調合量(弁論の全趣旨によれば,310kg)の,それ以外の期間も含めた 被告製品の調合量(弁論の全趣旨によれば,6070kg)に対する割合によって按 分して算定すべきであり,原告が本件で損害賠償を請求している期間の終期の後に も被告製品が販売されていることをも考慮して,原告が主張し,被告らも予備的に\n主張する4万円の限度で,原告が本件で損害賠償を請求している期間の被告製品の 製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と認めるのが相当である。
(ウ) 被告らの経費の額
以上によれば,被告らの経費の額は,合計390万5409円となる。 計算式:386万5409円+4万円=390万5409円
ウ 被告らの利益額
前記ア及びイによれば,被告らの特許権侵害行為による利益額は,893万 0361円となり,この額が原告の損害額と推定される。 なお,原告は予備的に特許法102条3項に基づく損害を請求しているが,原告\nが主張する同項に基づく損害額は上記金額を上回らないから,同条2項に基づく損 害額をもって原告の損害額とすべきである。
エ 弁護士費用
原告は,原告訴訟代理人弁護士に委任して,本件の各請求をしているところ, 差止請求分も考慮し,被告らの特許権侵害行為と因果関係のある弁護士費用は,1 10万円と認めるのが相当である。
オ 以上より,原告の損害額は,1003万0361円となる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.01.29
平成31(ネ)10018 損害賠償請求本訴,使用料規程無効確認請求反訴控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上のとおり,被控訴人は,地上テレビジョン放送事業者から管理 委託を受けた著作権及び著作隣接権の有線放送権に基づき再放送の利用 許諾をするに当たり,ほぼ全てのケーブルテレビ事業者との間で,3者 契約又は2者契約の方式により年間の包括的利用許諾契約を締結し,3 者契約の場合は本件基本合意に基づき,2者契約の場合は本件使用料一 覧(2者契約)に基づき定められた使用料額をケーブルテレビ事業者か ら徴収していることが認められる。 一方,被控訴人と3者契約又は2者契約の方式により年間の包括的利 用許諾契約を締結したケーブルテレビ事業者のうち,本件基本合意に基 づく減額措置(3者契約の場合)又は本件使用料一覧(2者契約)に基 づく減額措置(2者契約の場合)を受けることが可能であるにもかかわ\nらず,減額措置を受けずに,本件使用料規程に定められた区域内再放送 の使用料(1世帯1ch当たり年額120円)及び区域外再放送の使用 料(1世帯1ch当たり年額600円)を支払っている事業者は存在し ない。 そして,控訴人は,適法に同意を得て,又は総務大臣による同意裁定 を得て,毎日放送等6社の地上テレビジョン放送を同時再放送している ものであり,ケーブルテレビ連盟の会員でもあることから,仮に控訴人 が希望すれば,被控訴人との間で,本件基本合意に基づく3者契約又は 本件使用料一覧(2者契約)に基づく2者契約を締結することが可能で\nあって,その場合の再放送使用料は,上記減額措置の適用を受けて,区 域内再放送につき1世帯1ch当たり年額24円(3者契約)又は28 円(2者契約),区域外再放送につき1世帯1ch当たり年額120円 (3者契約)又は144円(2者契約)であり,平成26年度の再放送 使用料については,使用料の50%が軽減されるものと認められる(弁 論の全趣旨)。
以上のような,被控訴人とケーブルテレビ事業者との間で締結された 同時再放送に係る利用許諾契約の内容,控訴人による本件有線放送権の 利用の態様等の事実を考慮すると,上記利用許諾契約の締結に当たり適 用された実績が全くない,本件使用料規程の「年間の包括的利用許諾契 約によらない場合」(3条(2))又は「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ 場合」(3条(1))が,著作権法114条4項の「使用料規程のうちその 侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」 に該当するものとは認めらない。
(イ) これに対し被控訴人は,(1)使用料規程による使用料の算出方法が複 数あるときは各方法により算出した額のうち最も高い額を請求すること ができるとする著作権法114条4項を設けた趣旨に鑑みれば,「最も 高い額」となる算出方法による許諾実績がなくとも,同項の適用は妨げ られない,(2)実際にも,被控訴人は,著作権等管理事業を開始した平成 26年度以降,年間の包括的利用許諾契約によって区域外再放送を許諾 するに当たり,累計12社(平成27年度10社,同28年度9社,同 29年度9社)の有線テレビジョン放送事業者につき,本件減額措置を 施さずに,有料視聴世帯数に地上テレビジョン放送1波当たり年額60 0円を乗じた額の使用料を徴収している旨主張する。
まず,上記(1)の点について,著作権法114条4項は,同条3項により損害の賠償を請求する場合において,当該著作権等管理事業者が定め る使用料規程により算出した金額をもって,同条3項に規定する金銭の 額とする旨を定めるものである。そして,同条3項は,不法行為による 著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定し た規定であるところ,不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じ た現実の損害を填補することを目的とするものであるから,現実の損害 が発生しなかった場合には,それを理由とする賠償請求をすることがで きないことは自明である。 これを本件についてみるに,前記(ア)のとおり,被控訴人は,ほぼ全て のケーブルテレビ事業者との間で,3者契約又は2者契約の方式により 年間の包括的利用許諾契約を締結し,3者契約の場合は本件基本合意に 基づき,2者契約の場合は本件使用料一覧(2者契約)に基づき定めら れた使用料額をケーブルテレビ事業者から徴収しており,これらの事業 者のうち,本件基本合意に基づく減額措置又は本件使用料一覧(2者契 約)に基づく減額措置を受けることが可能であるにもかかわらず,これ\nを受けずに,それよりも遥かに高額な,本件使用料規程3条(1)又は(2)に 定められた区域内再放送及び区域外再放送の使用料を支払っている事業 者は存在しない。被控訴人と控訴人との交渉の過程においても,本件基 本合意に基づく3者契約又は本件使用料一覧(2者契約)に基づく2者 契約によることが,当然の前提とされていたものである。
そして,このような被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再 放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額,控訴人による本件 有線放送権の利用の態様,控訴人と被控訴人の間の再放送同意に係る利 用許諾契約に関する交渉経緯(前記ア(エ))等によれば,本件における使 用料相当額の算定に当たって,実際の利用許諾契約において用いられた 例がなく,かつ,上記減額措置を受ける場合と比較して使用料が遥かに 高額となる,本件使用料規程3条(1)又は(2)による場合の算定方法を用い ることは,被控訴人に生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現 実的というべきであり,相当でない。 次に,上記(2)の点について,被控訴人が,累計12社の有線テレビジ ョン放送事業者との間で,本件使用料規程に基づき,区域外再放送の使 用料を1世帯1ch当たり年額600円とする年間の包括的利用許諾契 約を締結し,同規程に基づき算定された金額を徴収していることについ ては,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また,被控訴人の 主張によれば,上記12社はいずれも重複波等の区域外再放送を行った 者であるところ,前記認定の被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の 同時再放送に係る利用許諾契約の締結状況に照らすと,上記12社は, 本件基本合意に基づく3者契約又は本件使用料一覧(2者契約)による 2者契約を締結した上で,本件基本合意(1)(3)の定めに基づき,「有料視 聴世帯数×1世帯1chあたり年額600円×区域外再放送(重複波等) ch数」の使用料を支払ったものであると推認される。そして,上記1 2社において,本件基本合意に基づく減額措置(3者契約の場合)又は 本件使用料一覧(2者契約)に基づく減額措置(2者契約の場合)を受 けることが可能であるにもかかわらず,減額措置を受けずに,本件使用\n料規程に定められた区域外再放送の使用料を支払っていることを認める に足りる証拠はない。 したがって,被控訴人の上記各主張を採用することはできない。
ウ 被控訴人は,控訴人が本件有線放送権を侵害したことにより被控訴人が 受けた損害の額として,著作権法114条3項及び4項により算定される 損害額を主張するところ,前記イのとおり,本件において著作権法114 条4項を適用して,本件使用料規程3条(1)又は(2)に基づいて被控訴人の損 害の額を算定することは,相当でない。そこで,同条3項により算定され る被控訴人の損害の額について,以下検討する。 同条3項は,著作権及び著作隣接権侵害の際に著作権者,著作隣接権者 が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。また,同項所定の 「その著作権…又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当 する額」については,平成12年法律第56号による改正前は「その著作 権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額」と 定められていたところ,「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得にな ってしまうとして,同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 そして,かかる法改正の経緯に照らせば,著作権及び著作隣接権侵害をし た者に対して事後的に定められるべき,これらの権利の行使につき受ける べき金銭の額は,通常の利用許諾契約の使用料に比べて自ずと高額になる であろうことを考慮すべきである。
これを本件についてみると,前記イ(ア)の被控訴人とケーブルテレビ事 業者との間の同時再放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額, 控訴人による本件有線放送権の利用の態様等の事実に加えて,控訴人と被 控訴人の間の再放送同意に係る利用許諾契約に関する交渉経緯など,本件 訴訟に現れた事情を考慮すると,著作権及び著作隣接権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき,本件での利用に対し受けるべき金銭の額は, 被控訴人とケーブルテレビ事業者との間における再放送使用料を現実に 規律していると認められる本件基本合意及び本件使用料一覧(2者契約) をベースとし,そこに定められた額を約1.5倍した額である,区域内再 放送につき1世帯1ch当たり年額36円及び区域外再放送につき1世 帯1ch当たり年額180円とし,平成26年度についてはその半額を下 らないものと認めるのが相当である。
◆判決本文
1審はこちらです。
2020.01.27
令和1(ネ)10036 特許権侵害差止等請求控訴事件 民事訴訟 令和2年1月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 推定覆滅の事情
特許法102条2項における推定の覆滅については,同条1項ただし書の事情と 同様に,侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば, (1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),(2)市場 における競合品の存在,(3)侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),(4)侵害品の 性能(機能\,デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について,特許法102 条1項ただし書の事情と同様,同条2項についても,これらの事情を推定覆滅の事 情として考慮することができるものと解される。また,特許発明が侵害品の部分の みに実施されている場合においても,推定覆滅の事情として考慮することができる が,特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅 が認められるのではなく,特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置 付け,当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相 当である。
イ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は,本件各発明等は,その全体が被告各製品の全体を対象とするもの の,特徴部分は,梁補強金具の外周部の軸方向の「片面側の端部に形成」した「フ ランジ部」であり,被告各製品においては,ダイヤリングの外周部の軸方向の「片 面側の端部に形成」した「つば状の出っ張り部の外周部」がこれに該当するところ, 侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合,すなわち特許発明の寄与 度を考慮すべきであり,上記推定は,少なくとも70%の割合で覆滅されるべきで あると主張する。 前記認定の本件明細書等の記載(引用に係る原判決「事実及び理由」第4の1(1)) によれば,本件各発明等は,各種建築構造物を構\成する梁に形成された貫通孔に固 定され当該梁を補強する梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造に関し\n(【0001】),梁に開設された貫通孔に対する配管の取り付けの自由度を高める とともに大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつつ必要な強度まで補 強することができ,柱梁接合部に近い塑性化領域における貫通孔設置を可能とする\n梁補強金具と,前記梁補強金具を用いた梁貫通孔補強構造とを提供するために(【0\n010】),梁に形成された貫通孔の周縁部に外周部が溶接固定されるリング状の梁 補強金具であって,その軸方向の長さを半径方向の肉厚の0.5倍〜10.0倍と し,前記貫通孔より外径が大きいフランジ部を前記外周部の軸方向の片面側に形成 し(訂正前の請求項1),さらに,フランジ部を前記外周部の軸方向の片面側の端部 に形成し,前記梁補強金具の軸方向の前記片面側の面は,前記梁補強金具の内周か ら前記梁補強金具の前記外周部の一部である前記フランジ部の外周まで平面である という構成を採用したものであって(訂正後の請求項1),梁に外力が加わったとき\n貫通孔の周縁部に生じる応力は,ウェブ部から貫通孔の中心軸に沿って離れるに従 って徐々に小さくなることから,梁補強金具の軸方向長さを必要以上に長くしない ように規制することにより,大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつ つ必要な強度まで補強することができ(【0012】),また,フランジ部により軸方 向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができるという効果を奏するものである (【0048】)。 このように,本件各発明等の特徴部分が,フランジ部のみにあるということはで きない。
(イ) また,控訴人は,本件各発明等の特徴部分であるフランジ部に特有の効果 は,「軸方向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができる」というものにとどまり, 同効果は,被告各製品の宣伝広告において,需要者に何ら積極的に訴求されていな いなどと主張する。 しかし,控訴人のウェブサイト(甲3)や被告各製品のカタログ(甲4)におい て,被告各製品のフランジ状の部分も図示され,被告各製品の特徴として,鉄骨梁 ウェブ開口に被告各製品をはめ込み,片面(つば状の出っ張り部の外周部)のみを 全周溶接することにより,取付けの際に梁の回転が不要となり施工性が大幅にアッ プするという点が挙げられている。このような施工が可能となるのも,梁補強金具\nにフランジ部に該当するつば状の出っ張り部を設けたからであると考えられ,被告 各製品の特徴は本件各発明等の構成に由来するものであると考えられる。\nこの点,控訴人は,控訴人のウェブサイトや被告各製品のカタログにおいては, 「つば状の出っ張り部の外周部」のみを溶接固定するため,「[梁の反転が不要]とな り施工性が大幅にアップ」する作用効果が需要者に訴求されているところ,これら は,控訴人により工夫された独自の工法により奏される顕著な作用効果であって, 本件各発明等の作用効果ではない旨主張する。 しかし,本件各発明等は,梁に形成された貫通孔にリング状の梁補強金具をはめ 込んで,フランジ部を含む外周部が溶接固定される梁補強金具であるところ,被告 各製品の,鉄骨梁ウェブ開口に被告各製品をはめ込み,片面(つば状の出っ張り部 の外周部)のみを全周溶接するという取付方法は,本件各発明等に係る梁補強金具 の取付方法として通常想定される態様の1つにすぎず,控訴人により工夫された独 自の工法とはいえないから,控訴人の主張は採用できない。
ウ 推定覆滅の事情は,侵害者が主張立証責任を負うものであるところ,以上に よれば,本件においては,損害額の推定を覆滅すべき事情があるとは認められない。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成29(ワ)26468
本件特許権の審取事件です。無効理由無しとした審決が維持されました。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.01.27
平成31(ワ)7788 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年11月6日 東京地方裁判所
1 争点3(消滅時効の成否)について
(1) 消滅時効は「権利を行使することができる時」から起算される(民法16 6条1項)ところ,特許法35条3項は,「従業者等は,契約,勤務規則そ の他の定めにより,職務発明について使用者等に特許を受ける権利…を承継 させ…たときは,相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定してい るから,同条項に基づく相当の対価の支払請求権は,原則として,特許を受 ける権利を承継させたときに発生し,その時点から,権利を行使することが できることになり,その時点が本件対価請求権の消滅時効の起算点となるも のというべきである。もっとも,勤務規則その他の定めに,使用者等が従業 者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その 支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解さ れる(最高裁平成13年(受)第1256号同15年4月22日第三小法廷 判決・民集57巻4号477頁参照)。
(2) これを本件についてみるに,前記のとおり,被告規則には特許出願時及び 特許登録時に譲渡補償金を支払う旨の明示的な規定はあるものの(同9条), いわゆる実績補償金については,「会社が職務発明に基づく発明の実施また は実施権の許諾もしくは処分により相当の利益を得たときは,会社は当該発 明者に褒賞金を支給することがある。」(同10条)と規定するのみで,一 義的に明確な支払時期の定めがあるということはできない。被告規則10条が,前記のとおり,「職務発明に基づく発明の実施または実施権の許諾」等を前提として褒賞金の支給について定めていることに照らすと,発明者である従業者等は,登録された特許に係る発明が実施又は実施 権の許諾等される以前に褒賞金の支払を求めることはできないものの,当該 発明が実施又は実施許諾等された場合には,褒賞金の請求権の行使が可能に\nなるということができる。 そうすると,被告規則に定められた褒賞金の支払時期については,本件発 明の実施又は実施許諾等により利益を取得することが可能になった時点,す\nなわち,特許権の設定登録時又はその実施若しくは実施許諾時のうちいずれ かの遅い時点であると解するのが相当である。
(3) これに対し,原告は,被告規則10条は,本件発明の実施がされる限り, 各事業年度の決算の結果を踏まえ,毎年4月1日に褒賞金を支払う旨を定め たものであることを前提とし,少なくとも平成20年度及び平成21年度の 実施に係る褒賞金については,消滅時効が完成していないと主張する。 しかし,同条は,被告が本件発明の実施等により相当の利益を得たときは, 発明者に褒賞金を支給することがあると規定するのみであり,支払時期につ いては一義的に明らかではないというべきであり,同条に基づき,褒賞金の 支払時期が毎年4月1日に到来すると解することはできず,また,被告にお いてそのような慣行や支払実態があったと認めるに足りる証拠もない。
(4) 第2の2(2)アのとおり,本件特許の登録時は平成7年12月8日であり, また,同(4)アのとおり,被告が平成元年11月頃から本件特許の実施品であ る被告旧製品を第三者に継続的に出荷していたことは当事者間に争いがない から,被告規則10条に基づく褒賞金,すなわち本件対価請求権の支払時期 は,平成7年12月8日となる。そうすると,その翌日である平成7年12月9日が消滅時効の起算日となり,同日から10年後の平成17年12月8日の経過をもって消滅時効が完成したので,本件対価請求権は時効消滅したものと認められる。
2020.01.27
平成28(ワ)10759 特許権に基づく製造販売禁止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 東京地方裁判所(40部)
(3) 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
前記(1)の譲渡数量に前記(2)の単位数量当たりの利益を乗じた額は,以下 のとおりとなる。
ア 被告日本生化学について
原告長寿乃里
21万3457個×1225円=2億6148万4825円
原告イング
23万9658個×993円=2億3798万0394円
イ 被告ブレーンコスモスについて
原告長寿乃里
17万0132個×1225円=2億0841万1700円
原告イング
19万1015個×993円=1億8967万7895円
ウ 被告ビーシーリンクについて
原告長寿乃里
135個×1225円=16万5375円
原告イング
152個×993円=15万0936円
(4) 特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」の 有無
ア 競合品の存在
証拠(甲8,乙24)によれば,シラスが配合された洗顔料が原告製品 及び被告製品のほかに8銘柄が存在したことが認められるが,販売数が多 いものでも,株式会社メディカルドーズの「お茶!入ったよ〜わっぜ!! 火山灰石けん」が平成22年9月から平成27年12月までに2万754 8個を販売したにとどまり,他の銘柄は,販売数が約1000個から38 00個程度にとどまるか,販売数が明らかではないから,これらの洗顔料 の存在が,「販売することができないとする事情」に当たるということは できない。
イ 原告製品の販売経過
被告日本生化学は,被告製品を販売していない月でも原告製品の販売が 落ちている月があることから,原告製品の販売は被告製品の販売に影響を 受けていなかったと主張するが,原告製品についてそのような販売経過と なった原因としては様々なものが考えられるのであり,上記の販売経過が 直ちに「販売することができないとする事情」に当たるとはいえない。
ウ 薬機法上の区分及び本件発明1の作用効果
被告日本生化学は,原告製品及び被告製品について,薬機法上の区分が 異なること及び宣伝広告の内容から,本件発明1の作用効果は原告製品及 び被告製品の販売に寄与していないと主張する。 しかし,消費者が薬機法上の区分を意識して商品を選択するとは考え難 く,前記判示のとおり,原告製品と被告製品はいずれもシラスが配合され た石けんという同種の商品であり,かつ,被告製品は本件発明1の作用効 果を奏するのであるから,両者は市場で競合する製品であるということが できる。 また,被告ブレーンコスモスは,被告製品の説明において,原告製品は 発売以来700万個以上が売れた大ヒット商品であると紹介するととも に,被告製品には,人工皮膚成分「リピジュア」が配合され,原告製品と 同じ価格だが,内容量が多いという2点が異なることを挙げて,被告製品 の宣伝をしていたことが認められ(甲14),このような宣伝内容によっ て,原告製品ではなく被告製品を購入した消費者も相当数いるものと考え られる。 そうすると,被告日本生化学が主張する上記事情は,「販売することが できないとする事情」に当たるとはいえない。
エ 販売ルートの違いについて
被告ブレーンコスモスらは,原告らは消費者に直接販売する小売である のに対し,被告ブレーンコスモスは販売数のうち95%は企業に対する卸 売りであり,販売ルートが異なるから,競合しないと主張する。 しかし,原告製品及び被告製品はいずれも最終的には一般消費者によっ て購入され,使用される石けんであり,被告製品が一般消費者に販売され る段階では原告製品と競合すると認められるところ,被告製品が存在しな ければ,被告ブレーンコスモスが他の企業に被告製品を卸売りすることも なく,ひいては被告製品が一般消費者に販売されることもないのであるか ら,被告ブレーンコスモスが卸売りを主たる取引形態とするからといって, 原告製品と被告製品が市場において競合することは左右されず,「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
オ 東日本大震災の義援金に充てる旨のアテンションシールについて
被告ブレーンコスモスらは,売上げの一部を東日本大震災の義援金に充 てる旨記載されたアテンションシールを被告製品に貼っていた期間(平成\n23年4月1日から同年9月30日まで)の販売数がそうでない期間の販 売数を上回っており,同シールが被告製品の売上げに寄与した旨主張する。 しかし,平成23年4月1日から同年9月30日まで被告製品に上記シ ールが貼られていたことを認めるに足りる証拠はない上,仮に同シールが\n貼付されていたとしても,平成23年1月から同年9月までの被告製品\n(100gのもの)の販売数は毎月概ね1万個程度で推移しており(丙1, 21),販売数の増加が同シールによるものとは認め難く,被告ブレーン コスモスらの主張はその前提を欠き,採用できない。
カ 海外市場における競合
被告ブレーンコスモスらは,被告ビーシーリンクは専ら海外に被告製品 を販売しているところ,原告製品と被告製品は海外市場において競合しな いと主張する。 しかし,証拠(甲76,77,84〜87,108〜112,丙25〜 28)によれば,被告ビーシーリンクは,平成25年2月から11月にか けて,米国,中国,シンガポール,ラトビアに被告製品を販売していたこ と,原告長寿乃里は,自ら又は株式会社フェローシップ等を介して,以下 のとおり海外に原告商品を出荷したことが認められる。
・・・
以上の事実関係に照らせば,原告製品と被告製品は,少なくとも米国及 び中国の海外市場において競合していたことが認められるから,被告ビー シーリンクが専ら海外において被告製品を販売していることは,「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
キ 以上のとおり,被告らが主張する事情は,いずれも「販売することがで きないとする事情」に当たらないから,特許法102条1項に基づく損害 額の推定は覆滅されない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成28(ワ)39687等 不正競争行為差止請求権不存在等確認等請求事件,不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 令和元年11月13日 東京地方裁判所
修正サービス契約6条(i)は,「トラスト及びサンエーは,それぞれ,本契約 から生じる又は本契約に関連する全ての法的手続のため,ニューヨーク州南部 地区連邦地方裁判所又はニューヨーク市に置かれるニューヨーク州裁判所の 専属的裁判管轄に服する。」と定めている。被告会社は,同条項の「トラスト」 との記載は単なる誤記にすぎず,同条項は被告会社とサンエー間の専属的裁判 管轄の合意を定めたものであるから,本訴請求について我が国の裁判所は管轄 権を有しないと主張する。 しかし,国際裁判管轄の合意は,その合意に係る管轄地に所在しない当事者 に大きな不利益を与えることになることから,書面によって合意されなければ ならないとされており(民事訴訟法3条の7),同合意の存在は当該書面の記 載に基づいて慎重に行うことが相当であるところ,修正サービス契約6条(i) は,専属的管轄合意の主体を,被告会社とは別の法人である「トラスト」と明 示しており,被告会社のスペルの誤りなどではないから,その記載から合意の 主体が被告会社であると認めることはできない。 修正サービス契約は,英文で起草された国際的な取引に関する企業間の契約 書であり,各条項については,契約当事者がその文言について慎重に精査・検 討した上で合意されたと考えるのが自然である。しかも,専属的裁判管轄の合 意において,合意の主体は最も基本的かつ重要な要素の一つであることを考慮 すると,修正サービス契約6条(i)に規定する専属的裁判管轄の合意主体はそ の文言に従って「トラスト」であると認めることが相当である。 また,原告を当事者とする他の契約についてみると,トラストと原告間の終 了合意書(甲7)7条(f),トラストと原告間の期限付き商標権譲渡契約6条, 原告と被告会社間のサービス契約9条(i)(甲30)及び原告,被告会社,トラ ストの三者間の商標権譲渡契約12条(甲51)においては,修正サービス契 約と同様,原告とトラストを合意主体とする専属的裁判管轄に関する規定が置 かれており,原告と被告会社間の管轄合意について規定した契約は存在しない。 この点について,被告会社は,修正サービス契約6条(i)の規定は,それ以前 に締結された「商標権譲渡契約(中国,香港及び台湾)」(乙6)やサービス 契約の規定をそのまま流用し,契約当事者もそれを看過したものであると主張 するが,仮に,被告会社の主張を前提としても,流用した規定が置かれたこと をもって,原告と被告会社との間において管轄合意がされたと認めることはで きない。上記のとおり,従前の契約には原告と被告会社間の管轄合意の規定は 存在せず,取り分け,原告,被告会社,トラストの三者間の商標権譲渡契約に おいては,原告とトラストとの間の管轄合意は置かれているものの,原告と被 告会社間の管轄合意の規定は設けられていないのであって,他に原告と被告会 社との間において専属的裁判管轄に関する合意形成のための交渉や話合いが 行われたことをうかがわせる証拠は存在しない。 そうすると,修正サービス契約6条(i)の規定の「トラスト」との表記が誤記\nであるとして,これを「被告会社」と読み替えることにより,両者間において 専属的裁判管轄の合意があったと認めることはできないというべきである。 したがって,原告と被告会社との間に,修正サービス契約から生じる紛争に ついて,その専属的裁判管轄をニューヨーク州の連邦又は州裁判所とする旨の 合意があったと認めることはできない。 (2) 本訴請求は,原告が,被告会社に対して,修正サービス契約3条(d)に基づ き,「サンプル及び諸経費」として支払済みの45万ドルの返金を求めるもの であるところ,かかる返金が原告の指定する口座にされるべきものであること は,被告会社の代表者であるA自身が原告に対して返金先を指示するように求\nめていること(甲31の4)からも明らかである。そして,日本国内に本店の 有する原告の指定する口座は,原告の国内口座であると考えられるので,修正 サービス契約3条(d)に基づく返還債務の履行地は日本国内にあると認められ る。 したがって,民事訴訟法3条の3第1号に基づき,我が国の裁判所は,本訴 請求に係る管轄権を有するというべきである。
2 争点2(被告会社の返金義務の存否及び返金額等)について
(1) まず,原告が「サンプル及び諸経費」として被告会社に対して支払う金員の 趣旨について検討する。
ア 前記前提事実(3)エ(イ)によれば,平成19年4月13日付けで締結された 修正サービス契約においては,同契約に基づき提供される業務の対価として, 原告が被告会社に対して,各契約年度の初日に合計80万〜100万ドルの 業務手数料の支払義務を負うが,このうち「サンプル及び諸経費」として定 められた金額は40万〜50万ドルであること(2条),被告会社は,業務 手数料に基づき,原告に対し,従来提供されてきた量と同等のサンプルを提 供する義務を負い,これを怠った場合,原告に対し,「サンプル及び諸経費」 に割り当てられたサービス料を比例計算で返金する義務を負う旨が定めら れていたこと(3条(d))が認められる。 このように,修正サービス契約は,被告会社が原告に従来提供されてきた 量と同等のサンプルを提供する義務を負うとした上で,「サンプル及び諸経 費」の対価を定め,更にサンプルを提供する義務を怠った場合の返金方法に ついても規定しているのであるから,同契約にいう「サンプル及び諸経費」 は,提供されるサンプルの対価であると認めるのが相当である。 また,「諸経費」については,修正サービス契約にその内容やサンプル費 用との関係についての記載はないが,「サンプル及び諸経費」(同契約2条), 「『サンプル及び諸経費』に割り当てられた業務手数料」(同3条(d))と一 体的に規定されていることによれば,サンプル代金の提供に必要な諸経費を 意味するものと解するのが自然である。そうすると,「サンプル及び諸経費」 は,被告会社が原告に提供するサンプルの対価及びサンプル提供のために必 要な経費を意味するものというべきである。
イ(ア) これに対し,被告会社は,修正サービス契約2条の「サンプル及び諸経 費」は,被告会社からサンプルの提供を受ける権利自体の対価の支払につ いて定めたものであり,このうち特に「諸経費」は,被告ジルのコレクシ ョン等の活動に基づき多大な恩恵を受ける原告が,その活動のための費用 を一部負担する趣旨のものであると主張する。 しかし,修正サービス契約には,「サンプル及び諸経費」がサンプルを 受ける権利自体の対価であると理解し得る規定は存在せず,被告会社の上 記主張が修正サービス契約の文理と整合しないことは明らかである。また, 前記前提事実(3)イによれば,サービス契約においても,原告が,被告会社 から提供を受けるサンプルの対価として,契約年度ごとに10万ドル〜1 1万ドルを年度の初日に先払いすることができること,被告会社が従来提 供してきた量と同等の量のサンプルを提供できない場合には,上記金額が 相応に減額される旨が定められているのであり,サービス契約の後に締結 された修正サービス契約においても,契約年度毎に支払われる対価は同様 の性質を有するものと認めることが相当である。
この点について,被告会社は,サービス契約締結時は期限付き商標権譲 渡契約が締結されていたのに対し,修正サービス契約締結時には商標権譲 渡契約が締結されて,被告側に商標権が戻らなくなったことから,原告が サンプルの提供を受ける権利自体の対価の支払をすることとなったもの であると主張するが,商標権譲渡契約により譲渡された商標権等について は対価が別途定められているのであるから,商標権譲渡契約の締結を契機 として,修正サービス契約において,サンプルの提供を受ける権利自体に 対価を要するようになったとは考え難い。 (イ) また,被告会社は,修正サービス契約における原告の支払金額がサービ ス契約と比較して大幅に増加したことを指摘するが,この点について,原 告は,原告としては高額のサンプル費用を一括で先払いすることで被告会 社から商品の購入圧力を受けずにサンプルの提供を確保することにメリ ットがあることから,増額に応じたものであると説明する。 この原告の説明は,(1)サービス契約6条においては,原告が一定数量の 商品を購入するように努める旨の規定が置かれているのに対し,修正サー ビス契約3条(e)においては,原告が被告会社等から商品の購入義務がな いとする規定のみが置かれていること,(2)JSインターナショナルのD (以下「D」という。)が平成24年11月9日にサンエーUSAの担当 者E(以下「E」という。)に対して「購入されていないスタイルのサン プルはお渡ししておりません」という電子メールを送信するなど,被告会 社は,修正サービス契約の下においても,なお,原告に対して,サンプル の提供に関連付けて商品の購入を求めていたことがうかがわれることな どに照らしても,合理的なものということができる。 そうすると,修正サービス契約において原告の支払金額が増加したこと をもって,修正サービス契約において,サンプルの提供を受ける権利自体 の対価の支払を要するようになったと認めることはできないというべき である。
(ウ) 被告会社は,Bの証言やサンプルの単価と提供枚数との関係からしても, 上記の45万ドルがサンプルの対価であるということはできないと主張 するが,被告会社が提供していたサンプルの量についてBが45万ドル分 であるとは証言しなかったとしても,それをもって,上記45万ドルがサ ンプルの対価ではないということはできず,また,上記のとおり,原告は 商品の購入圧力を受けずにサンプルの提供を確保することをメリットと 考えて支払金額の増加に応じたと認められることからすると,その金額が サンプルの単価に提供枚数を乗じた金額より高いとしても,そのことは同 金額がサンプルの対価であることを否定する根拠とはならないというべ きである。
(エ) 被告会社は,甲75,乙479,480などに基づき,原告が修正サー ビス契約の期間中,被告会社に「サンプル及び諸経費」としての45万ド ルとは別にサンプル代金を支払っていたと主張するが,被告会社が根拠と するインボイス等(乙479,480)は,サービス契約の締結日(平成 17年9月2日)より前の時期のものであり,甲75のインボイスに係る サンプルも修正サービス契約の締結前に注文されたものであるから,これ をもって,原告が修正サービス契約に基づき上記45万ドルとは別にサン プル代金を支払っていたと認めることはできない。
2020.01.24
平成30(ワ)2439 損害賠償請求事件 意匠権 民事訴訟 令和元年11月14日 大阪地方裁判所
原告と浪漫亭との間において定められた原告製品1の単価は,平成27年4月以 前は(中略)円であったと認められるところ(甲19,20),同年5月からは(中 略)円,同年7月の途中からは(中略)円となり,被告製品1の納入が開始された 平成28年1月以降も同額を維持したものの,同年2月から販売終了までの間は(中 略)円に下落した(別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」参照。)。\nまた,原告製品2の単価は,平成27年5月以前は(中略)円であったところ(甲 19,20),同月6月以降販売終了までの間は(中略)円に下落した。 前記認定事実によれば,原告は,P1から本件見積書を提示されたことにより, 被告らの提示価格(原告製品1と競合する製品について(中略)円,原告製品2と 競合製品について(中略)円。)と対抗するため,原告製品を値下げせざるを得な くなったという事情が認められる。
しかし,前記(2)で述べたとおり,この時点では,被告製品が本件意匠権を侵害す るものとなるかは未確定であり,被告静岡産業社が本件見積書を示して浪漫亭との 取引を誘引する行為自体には違法性がなく,これにより原告が原告製品の値下げを 余儀なくされたことも,それまで原告がこの種の製品について浪漫亭との取引を独 占していたところに競業者(被告ら)が現れたため,対抗するために価格を改定し たという原告の経営判断の結果であるということができる。 そうすると,被告らの本件意匠権の侵害行為による原告の損害を算定する際に基 準となる原告製品の単価は,値下げ前の単価ではなく,侵害行為時,すなわち,平 成28年1月時点の単価(原告製品1につき(中略)円,原告製品2につき(中略) 円)であるとするのが相当である。
控除経費
(a) 控除経費として争いのない費目は,(1)原材料費,(2)梱包費及び(3)運送費であ り,それぞれ,原告製品1個当たりの額は,以下のとおりである(甲13ないし18)。
(1) 原材料費
原告製品の原材料はレジンであり,原告製品は,仕入れたレジンをシート状に加 工した後,金型成形して製造される。 よって,原告製品1の1個当たりの原材料費は,レジンの仕入費用をそこから製 造される原告製品1の数で除し,シート状に加工し金型成形する際のロス率(10%) を掛けた金額であり,(中略)円となる。
(計算式)レジン平均単価((中略)円/Kg)/1000(g当たり換算)× 1シートのグラム数(83.5cm×97.5cm×0.045cm×比重0.9 1)×ロス1.05/1シート当たりの原告製品の数24個=(中略)円 なお,原告製品2の原材料費は,(中略)円(原告製品1の原材料費に,木目状 フィルム費(中略)円を足した額)である。
(計算式)木目用フィルム仕入単価(中略)m/円×0.975m/24個=(中略)円
(2) 梱包費
原告は,原告製品1080個を1枚のビニル袋に入れ,これを段ボール1ケース に梱包しているところ,それぞれの仕入単価は(中略)円及び(中略)円である。 原告は原告製品の梱包及び運送を100%子会社に委託しているところ,同会社 が支払った費用に10%上乗せした額を原告の経費とすることを争わない。 よって,原告製品1個当たりの梱包費は,(中略)円となる。
(計算式)((中略)円+(中略)円)/1080個×1.1=(中略)円
(3) 運送費
運送トラック1回の配送で,原告製品1080個の入った上記段ボール箱を12 6箱積載することが可能であり,1回当たりの運送費は(中略)円である。\n原告は,運送費についても上記梱包費と同様に,子会社が支払った費用に10% 上乗せした額を原告の経費とすることを争わない。 よって,原告製品1個当たりの運送費は,(中略)円となる。
(計算式)(中略)円/126箱/1080個×1.1=(中略)円
(b) 被告らは,原告製品の原材料につき,シート加工賃及び金型成型加工賃を含 めた金額とすべきであると主張し,また,上記(a)の経費に加えて,原告製品の製造 のために使用されている直接労務費及び電気代を控除すべきであると主張し,これ に沿う証人P3の供述(丙3)もある。 しかし,原告は原告製品を自己の工場内で製造しているものと解されるため,シ ート加工賃及び金型成型加工賃が通常の労務費とは別に発生するとは考えられない。 また,原告の製造する食品包装用容器全体のうち原告製品の占める割合はわずか である(甲18,原告代表者本人)ことからすれば,労務費及び電気代が原告製品\nの販売数量の増加に伴って追加的に発生する変動費であるということはできない。 したがって,上記被告らの主張を採用することはできない。
まとめ
以上より,原告製品1の単位数量当たりの利益の額は(中略)円,原告製品2の 単位数量当たりの利益の額は(中略)円となる。
・・・・
ウ 被告らの主張について
推定覆滅
(a) 被告静岡産業社は,被告製品における被告意匠の占める部分は,面積比にお いて約50%であるから,寄与度を50%とするか,被告製品の販売数量のうち5 0%について推定覆滅されるべきであると主張する。 しかし,被告意匠は,被告製品において,需要者の注意を引き,美感に訴えると いう点で,最も重要な位置を占めているというべきであり,被告意匠としての面積 比が製品全体に対して約50%であるからといって,寄与度を50%としたり,5 0%の推定覆滅を認めるべきことにはならない。
(b) 被告ヨコタ東北は,被告製品には原告製品よりも価格面,ブランド力及び製 品そのものの機能において優れていたことから,被告製品全量について原告には販\n売することができないとする事情(意匠法39条1項但書)があったと主張する。 しかし,前記認定事実のとおり,原告製品及び被告製品は,いずれも浪漫亭の製 造・梱包ラインに合致するように製造され,浪漫亭のみを納入先とするものであり, 被告製品の納入開始前は原告製品のみが浪漫亭に納入されていたのであるから,被 告製品の販売がなければ,浪漫亭は同数の原告製品を購入したと考えられ,上記被 告ヨコタ東北の主張を採用することはできない。
実施能力\n
被告ヨコタ東北は,原告の実施能力につき,被告製品納入前の原告製品1の販売\n数量が,被告製品1の平均販売数量(約50万個)よりも少ないから,原告の損害 額の主張は自己の実施能力を超えると主張する。\nしかし,平成27年5月及び6月の原告製品1の販売数量はいずれも約51万個 であるし(別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」参照。),原告は,食品用包装\n容器を多種類製造しており,その中において原告製品の占める割合はわずかである ことから,製造ラインを適宜調整することにより,被告製品の販売数量に相当する 受注に応じることは可能であったと考えられるから,被告ヨコタ東北の上記主張に\nは理由がない。
過失相殺
被告静岡産業社は,原告が被告製品の納入に気が付きながら放置したことにより, 原告の主張する損害を拡大させたとして,過失相殺の主張をするが,前記のとおり, 原告において被告らが本件意匠権を侵害していることを知りながらそれを放置した とは認められないので,被告静岡産業社の上記主張には理由がない。
エ まとめ
以上より,被告らによる本件意匠権の侵害行為により原告が被った損害額と して意匠法39条1項により推定される額は,被告製品1につき4555万067 0円,被告製品2につき397万4875円であり,合計5348万7589円(税 込。税抜4952万5545円。)となる。
(計算式)
被告製品1 (中略)個×(中略)円=4555万0670円
被告製品2 (中略)個×(中略)円= 397万4875円
被告静岡産業社は,株式会社帝国データバンクによる調査報告書(乙6)に 基づき,原告主張のとおり,原告製品の製造数量が全製品の製造数量に占める割合 が(中略)%であるとすると,原告製品の限界利益は870万円程度となるはずで あり,上記の金額は過大であると主張する。 しかし,上記調査報告書は,公開情報等に加え上記会社が独自に調査した結果を 掲載したものであるところ,上記会社は原告から売上資料等の開示を受けているわ けではないから(原告代表者本人),その情報の正確性には自ずと限界があるとい\nわざるを得ない。また,被告静岡産業社は,原告製品の1個当たりの利益額の算定 方法について,前記 具体的な問題点の指摘をせず,上記の算定結果が 不正確であることについての直接の主張・立証はない。 したがって,上記調査報告書に記載された情報のみから,上記原告の損害額(5 348万7589円)が過大であるということはできず,被告静岡産業社の上記主 張を採用することはできない。
(4) 値下げによる損害
ア 平成27年5月から同年12月までの期間について
前記(2)のとおり,被告静岡産業社がP1に対し本件見積書を提示したことは,本 件意匠権の侵害行為にもその他の不法行為にも当たらないから,平成27年5月以 降,原告が原告製品の価格を値下げしたことで生じた値下げ前の単価との差額分の 金額は,被告らの不法行為による損害であると解することはできない。 また,意匠法39条1項の算定に,平成27年4月以前よりも下落した平成28 年1月時点の原告製品の価格を用いたことは前述のとおりであるが,この下落が不 法行為によるものとは認められない以上,その差額分を民法709条による損害賠 償として,意匠法39条1項による算定額に加算することはできない。
イ 平成28年1月以降の期間について
平成28年1月以降の期間については,被告らに意匠権侵害が成立すると認 められるが,原告は,この部分について,前記検討した意匠法39条1項による損 害賠償とは別に,原告が,被告らと並行して浪漫亭に販売していた原告製品につい ても,被告らの意匠権侵害行為により値下げを余儀なくされたとして,原告が販売 した個数に値下額を乗じた額を,民法709条の損害賠償として請求する。 そこで検討するに,意匠権侵害が行われた場合に権利者に生じ得る損害とし ては,権利者側の商品の販売数量の減少や販売価格の低下による逸失利益が典型的 には想定され,本来的には,権利者において損害の発生及び額,並びに権利侵害と 損害発生との因果関係を立証しなければならないが,これらの立証が困難であるこ とから,意匠法39条は,侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量利益を乗じた額を 権利者の損害とすること(1項),侵害者が侵害行為により受けた利益を権利者の 損害と推定すること(2項),意匠の実施に対し受けるべき金銭に相当する額を, 権利者は損害賠償として請求し得ること(3項)を定めた。 そうすると,意匠権者が,意匠権侵害による損害賠償として,自己の商品の販売 数量の減少や販売価格の低下による逸失利益を個別具体的に立証することに替えて, 意匠法39条各項が定める算定・推定規定を利用して損害賠償請求を行った場合, 前記各項に基づく請求とは別に,民法709条による損害賠償請求をすることがで きるのは,意匠権により保護されるのとは別の法益が侵害されたり,前記各項が定 める算定・推定規定では評価されていない別の損害が生じたような場合であると考 えられる(一例として弁護士費用)。
原告は,意匠法39条1項により,被告静岡産業社が浪漫亭に譲渡した被告 製品の数量に,原告の単位利益を乗じた金額を,原告の損害として請求しているの であるから,同じ期間内に,被告らが被告製品を製造・販売したことによって原告 製品の販売数量が減少した,あるいは販売価格が低下したといった逸失利益につい ては,既に評価されているというべきであり,意匠権により保護されるのとは異な る法益が侵害された,あるいは意匠法39条1項による算定では評価されていない 損害が生じたと認めるべき事情は,本件では認められない。 また,仮に意匠法39条1項による算定とは別に,民法709条による損害 賠償請求を認めるべき場合であっても,被告らの意匠権侵害行為によって原告製品 の価格が低下したとの因果関係については,原告が立証責任を負うべきものである が,平成28年1月に被告製品が浪漫亭に納入された後,原告製品1の販売価格の 低下は平成29年2月に生じているところ,この原因が何であるかは証拠上明らか ではなく,この点についての因果関係の立証がなされているとは認められない。 以上より,平成28年1月以降の原告製品の価格の低下についての,民法7 09条に基づく損害賠償請求は,理由がないというべきである。
◆判決本文
被告製品と原告意匠の対比は以下です。
2020.01.24
平成31(行ケ)10042 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月21日 知的財産高等裁判所
本件審決は,明確性要件の判断において,構成要件G及びLについて判断したの\nみで,構成要件Fについては「請求人の主張の概要」にも「当合議体の判断」にも記\n載がなく,実質的に判断されたと評価することもできない。 したがって,本件審決には,手続的な違法があり,これが審決の結論に影響を及 ぼす違法であるということができる。
(3) 補正要件違反,分割要件違反及びサポート要件について
ア 本件審決には,補正要件違反等の原告の主張する無効理由との関係で,構成\n要件Fについての明示的な記載はない。 しかし,補正要件の適否は,当該補正に係る全ての補正事項について全体として 判断されるべきものであり,事項Fの一部の追加が新規事項に当たるという主張は, 本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にす ぎず,これと独立した別個の無効理由であるとまではいえない。その判断を欠いた としても,直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということはできない。 また,構成要件Fで規定する「開口」は,構\成要件H(「前記一対の保持部は,各々 の前記開口が横を向き,且つ前記開口同士が互いに対向するように配設されている」) の前提となる構成であって,事項Hの追加が新規事項の追加に当たらないとした本\n件審決においても,実質的に判断されているということができる。 そして,後記のとおり,当初明細書の【0037】,【0038】,【図2】には,断 面視において略C字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載され,「開口部」とは, 「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し,一般的な体格の成人の腕 部の太さよりも若干大きい幅とされ,そこから保持部内に腕部を挿入可能であるこ\nとが記載されているから,構成要件Fで規定する「開口」が,当初明細書に記載され\nていた事項であることは明らかである。
イ また,新規事項の追加があることを前提とした分割要件違反に起因する新規 性・進歩性欠如をいう原告の主張も,同様である。
ウ サポート要件についても,本件審決には,構成要件Fについての明示的な記\n載はない。 しかし,サポート要件の適合性は,後記4(1)のとおり判断すべきものであり,上 記アと同様,事項Fの一部についての判断を欠いたとしても,直ちに当該無効理由 について判断の遺脱があったということはできない。 また,構成要件Fで規定する「開口」は,上記アのとおり,構\成要件Hの前提とな る構成であり,本件審決においても実質的に判断されているということができる。\nそして,後記のとおり,本件発明1は,本件明細書の【0010】に記載された構\n成を全て備えており,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明に より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであり,加え て,本件明細書にも前記【0037】,【0038】,【図2】と同様の記載があることからすれば,構成要件Fで規定する「開口」が本件明細書の当該記載によってサポ\nートされていることも明らかである。
(4) 小括
以上のとおり,本件審決は,明確性要件についての判断を遺脱しており,この点 の審理判断を尽くさせるため,本件審決は取り消されるべきである。 もっとも,他の無効理由については当事者双方が主張立証を尽くしているので, 以下,当裁判所の判断を示すこととする。
・・・
ア 当初明細書の【0042】,【0044】,【0048】,【図5】,【0066】, 【0072】,【0074】,【図8】には,保持部の内面の略全体に空気袋が設けられている構成の記載がある。これらの記載に加えて,従来のマッサージ機においては,\n肘掛け部に例えばバイブレータ等の施療装置が設けられていないことが多く,被施 療者の腕部を施療することができないことが課題になっていたこと(【0003】) を併せて考えれば,当初明細書の上記各記載から,保持部の内面の対向する部分の 双方でなくとも,対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば,腕部が保持部 によって保持され,保持部の内面の一方の側から空気袋の膨張・圧縮に伴う力を受 けることで一定の施療効果が期待できることは明らかというべきである。 そうすると,保持部の内面の互いに対向する部分の双方でなく,対向する部分の 一方に空気袋が設けられていれば,座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき,被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題\nの課題解決手段として十分であることが容易に理解できる。\n
イ 当初明細書の【0042】には,保持部の形状について「略C字状」の断面形 状を有することの記載があり,【0037】,【0038】及び【図2】には,断面視 において略C字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載されており,「開口部」と は,「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し,一般的な体格の成人 の腕部の太さよりも若干大きい幅とされ,そこから保持部内に腕部を挿入可能であ\nることが記載されている。そして,【0100】には,腕部を保持する保持部は,【図 13】(a)に示されるものに限定されず,同図(b)〜(e)に示されるものとし てもよいこと,さらに,同図(c)は,開口を「所定角度で傾斜させた」ものであり, 同図(e)は,開口を「上方に開口」させたものであることが記載されている。 以上の記載を踏まえると,【図13】(a)は,開口が所定角度で傾斜せずに横を向 いている保持部を示していると理解するのが自然であり,そうすると,当初明細書 には,所定角度で傾斜したものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」い ている保持部が記載されているといえる。 そして,「開口が横を向」いている保持部であっても,腕部を横方向に移動させる ことで被施療者が腕部を保持部内に挿入することができ,座部に座った被施療者の 腕部を保持部の内面に設けた空気袋によって施療することができることが容易に認 識でき,被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当\n初明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解できるというべきである。
ウ 請求項2の「開口が真横を向いている」にいう「開口」とは,そこから保持部 内に腕部を挿入することを可能とするもの(【0038】,【図2】)であることから\nすれば,「開口が真横を向いている」とは,腕部の挿入方向に着目して,被施療者が 座部に座った状態で腕部を「真横」(水平)に移動させることで保持部内に腕部を挿 入することができるという技術的意義を有するものであると理解できる。 そして,当初明細書には,【図13】(a)及び(c)において,所定角度で傾斜し たものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」いている保持部が示され, 同図(a)は,開口が所定角度で傾斜せずに横を向いている保持部,すなわち,「開 口が真横を向」いている保持部を示していると理解するのが自然であるところ,「開 口が真横を向」いていれば,腕部を真横(水平)に移動させることで被施療者が腕部 を保持部内に挿入することができ,座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき,被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題\nを解決できることも容易に理解することができるというべきである。
エ 当初明細書には,【0037】,【0044】,【0046】などにも,前腕部を 挿入する第2保持部分の内面において,被施療者の手首又は掌に相当する部分に振 動装置が設けられていることが開示されている。加えて,保持部が,被施療者の上 腕を保持するための第1保持部分と被施療者の前腕を保持するための第2保持部分 とから構成され(【0037】,【図2】),第2保持部分の内面であって被施療者の手首又は掌に相当する部分に振動装置が設けられ,この振動装置が振動することによ\nり,被施療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっていること(【0044】,【図2】)も記載されている。\nそうすると,保持部内に挿入された被施療者の手首又は掌を,保持部の内面であ って,手首又は掌に相当する部分に設けられた振動装置を振動させることで,被施 療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっており,その前提として,保持\n部が,被施療者の手首又は掌を「保持可能」とするような構\成を有していることは 明らかである。
オ 当初明細書のうち,第1保持部分を幅方向へ切断したときの断面図である【図 5】,【図8】には,空気袋(11b,11c,26b,26c)が全体として保持部 の奥側(図の右側)よりも開口側(図の左側)の端部にて高さが高くなるよう盛り上 がる形状が示されており,当初明細書の【0042】の記載も踏まえると,【図5】 には,保持部分の内面の略全体において略一定の厚み幅を有する空気袋11bと, 当該空気袋11bの上に積層する形で空気袋11cが設けられ,当該空気袋11c は奥側から開口側に行くにしたがってその厚み幅が漸増しており,空気袋11bと 空気袋11cをあわせてみたときに,空気袋は開口側の部分の方が奥側の部分より も立ち上がるように構成されていることが記載されているといえる。\nそして,空気袋が保持部の開口側の部分の方が奥側の部分よりも立ち上がるよう に構成されていれば,空気袋の膨張・圧縮の程度が保持部の奥側の部分よりも開口\n側の部分の方が大きく,腕部がそのような空気袋の構成に応じた膨張・圧縮に伴う\n力を受けることで,座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に設けた空気袋に よって施療することができることが容易に認識でき,被施療者の腕部を施療するこ とが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題を解決できるこ\nとも容易に理解することができる。 カ 以上によれば,本件補正は,当初明細書の全ての記載を総合することにより 導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものとはいえ ない。
・・・
4 取消事由3(サポート要件に係る判断の誤り)について
(1) サポート要件について
特許請求の範囲の記載が,サポート要件を定めた特許法36条6項1号に適合す るか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請 求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細 な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
(2) 本件発明1について
ア 本件明細書の記載 本件明細書には,(1)椅子型のマッサージ機にあっては,肘掛け部にバイブレータ 等の施療装置が設けられていないことが多く,被施療者の腕部を施療することがで きないという問題があったことから(【0002】,【0003】),被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供することを課題とし(【0007】),(2)当 該課題を解決するための手段として,被施療者が着座可能な座部と,被施療者の上\n半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において,「前記座部の両 側に夫々配設され,被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と,前 記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と,を有し,前記保持部は,\nその幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されて いると共に,その内面に互いに対向する部分を有し,前記空気袋は,前記内面の互 いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ,前記一対の保持部は, 各々の前記開口が横を向き,且つ前記開口同士が互いに対向するように配設され」 ていること(【0010】),(3)本発明に係るマッサージ機によれば,空気袋によって 被施療者の腕部を施療することが可能となること(【0028】)が記載されている。\n
そして,本件明細書には,本件発明の「実施の形態1」の説明において,マッサー ジ機の全体構成やその動作について,保持部の構\成やその内面に設けられた空気袋 の構成や作用とともに記載され(【0037】,【0038】,【0042】〜【0045】,【0048】,【図1】,【図2】,【図5】),本件明細書の【0100】,【010\n1】及び【図13】には,本件発明のマッサージ機の保持部の種々の断面形状につい て説明がされているところ,マッサージ機を扱う当業者であれば,本件明細書の以 上の記載から,(1)の課題を解決するために(2)の解決手段を備え,(3)の効果を奏する 発明を認識することができる。 そして,本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2(1)のとおりで あるところ,本件明細書の【0010】には,同発明が記載されている。また,当業 者が,本件明細書の前記記載により本件発明1の課題を解決できると認識すること ができる。そうすると,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明 の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のも のであるということができ,本件発明1の記載についてサポート要件の違反はない。
イ 原告の主張について
原告は,(1)構成要件Gは,空気袋につき,保持部の内面の対向する部分の一方の\n部分のみに設ける構成も含むが,本件明細書には,かかる構\成であっても解決でき る課題につき何らの説明もなく,(2)構成要件Hは,保持部の形状につき,本件明細\n書の【図13】の(a),(c)から導かれる形状とするものであるところ,本件明細 書には,他の形状を示す同図(b),(d),(e)との関係で解決される課題につき,何らの説明もないと主張する。 しかし,本件明細書によれば,保持部の内面の対向する部分の双方でなくとも, 対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば,被施療者の腕部を施療すること が可能なマッサージ機を提供するという本件明細書に記載の課題の解決手段として\n十分であることが容易に理解することができる。また,保持部に形成する開口が横\nを向いていれば,腕部を横方向に移動させることで被施療者が保持部内に腕部を挿 入することができ,座部に座った被施療者の腕部を施療することが可能なマッサー\nジ機を提供するという本件明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解する ことができる。 したがって,原告の主張は理由がない。
5 取消事由5(引用発明に基づく進歩性判断の誤り)について
・・・
このように,甲13文献に示されるパッド31は,せいぜい,パッド35ととも に肢にフィットするように全体にc字形をしており,開口を患者の側に向けて,パ ッド35とともに椅子21(肘掛け)又は床の上に「置く」ことができることが開示 されているにとどまり,「一対の保持部」について,相違点2に係る,各々の開口が 横を向き,かつ開口同士が互いに「対向するように配設」するという技術思想が開 示されているとはいえない。
(ウ) したがって,引用発明に甲13技術を適用する動機付けはないし,これを 適用しても,相違点2に係る構成に至らないから,これを容易に想到することがで\nきたものとはいえない。
◆判決本文
関連事件です。こちらは無効理由無しとした審決が維持されています。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成31(行ケ)10060 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月14日 知的財産高等裁判所
本件明細書によれば,本件発明1に係るスクラブ石けんの製造方法について, 次の事項が記載されていることが認められる。
微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンをアルカリ溶液に浸漬し て,中空内部にアルカリ溶液を浸透させ,その後,アルカリ溶液に脂肪酸を添加す ることにより,前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに,中 空内部にも石けんを形成するものであり(【0029】),アルカリ溶液には,界面活 性剤を添加しているため,アルカリ溶液の表面張力が弱められて,シラスバルーン\n表面の微細なクラックからシラスバルーンの内部へ,アルカリ溶液を容易に浸入さ\nせることができ,シラスバルーン内部はアルカリ溶液で満たされることとなる(【0 032】,【0033】)。
通常石けんを製造する場合には,脂肪酸(又は油脂)の溶液に,アルカリ溶液を 徐々に添加するのが一般的であるが,脂肪酸溶液とシラスバルーンとを混合し,次 いで,アルカリ溶液を添加した場合,シラスバルーンの内部にある脂肪酸溶液と, シラスバルーン内に浸入してきたアルカリ溶液とが,シラスバルーンの表面で石け\nんを形成してしまい,アルカリ溶液の更なる浸入を妨げるため,シラスバルーン中 心部の脂肪酸溶液が未反応となりやすく,内包石けんが形成されにくいため,好ま しくない(【0039】,【0040】)。また,固形状又は半固形状の基材石けんに,シラスバルーンを混入させただけでは,単にシラスバルーンの表面に基材石けんが\n付着するのみであり,粘度の高い基材石けんがシラスバルーンの中空内部に入って 内包石けんとなることはない(【0043】)。これに対し,アルカリ溶液とシラスバ ルーンとを混合してアルカリ火山灰溶液を調製し,次いで,アルカリ火山灰溶液に 加温溶融した脂肪酸を添加すると,脂肪酸もまた徐々に表面のクラックを介してシ\nラスバルーン内に浸透することとなり(【0037】),シラスバルーンの表面で石け\nんを形成しても,反応当初は高濃度のアルカリ溶液が脂肪酸溶液に比して多量にあ るため,速やかに石けん分子が分散することとなり,シラスバルーン内部に脂肪酸 溶液が入るのを妨げることがなく,シラスバルーン内部に十分な量の内包石けんを\n形成することができる(【0041】,【0042】)。 具体的な工程は,次のとおりである。すなわち,加温可能で内部を減圧可能\に形 成した調合タンク等で,アルカリ溶液調製工程を行い,27.3重量部の水に,5. 55重量部の水酸化カリウムを徐々に添加して,水酸化カリウムを十分溶解し,ア\nルカリ水溶液をできるだけ室温に近い温度で調製し(【0051】〜【0053】), 界面活性剤添加工程で,3重量部のグリセリン,5重量部の保湿剤,3重量部の増 泡剤,3重量部の界面活性剤をそれぞれアルカリ溶液中に添加して均一になるまで, できるだけ室温に近い温度撹拌を行う(【0054】〜【0056】)。シラスバルー ン添加工程では,22.74重量部の予め膨化処理を施して微細な中空球状に成形し\nた火山灰(シラス),4重量部の白色顔料,0.01重量部の糖類を,界面活性剤を 含有するアルカリ溶液に添加し,この際,まず,プラネタリーミキサー等で液中及 び液面を穏やかに撹拌し,次いで,ディスパー等により,強力な渦流を発生させて 液中に巻き込むように撹拌混合を行ってシラスバルーンや白色顔料が粉塵として宙 に舞うことを防止するとともに,当初の時点で空気を抱き込ませずに撹拌を行うこ とで,シラスバルーンの中空内部まで,効率よく界面活性剤を含有するアルカリ溶 液を浸透させ,撹拌時には,80℃に達するまで徐々に液温を昇温する(【0057】 〜【0065】)。次に,浸透工程で調製した,界面活性剤を含有するアルカリ溶液と シラスバルーンとの混合液(アルカリ火山灰溶液)に,図1に示すB−1(脂肪酸) を添加する脂肪酸添加工程では,炭素数がC12〜C18で直鎖状の飽和又は不飽 和脂肪酸を好適に用い,脂肪酸の組成は,所望する石けんの性状に併せて適宜決定 することができ,本実施形態で用いる脂肪酸(又は脂肪酸塩)は,固体であるため, 70〜90℃に加熱溶融してから添加する(【0066】,【0069】〜【0071】)。 石けん調製工程では,アルカリ火山灰溶液に脂肪酸を混合した直後より,調合タン ク内の減圧を行い,混合液中に含まれる空気を脱気(脱泡)しながら,20分間撹拌 混合し,混合液の温度を75〜85℃,より好ましくは77〜83℃とすることに より,均一で滑らかであり,しかも,白色の際だったスクラブ石けんとすることが できる(【0072】〜【0077】)。 このようにして得られたスクラブ石けんは,シラスバルーンの内部にもペースト 状の石けんを含有している(【0082】)。
イ 以上によれば,本件明細書には,微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシ ラスバルーンを,界面活性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して,中空内部にアル カリ溶液を浸透させ,その後,アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより,前記 シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに,中空内部にも石けんを 形成するスクラブ石けんを製造する方法について,その実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載されていると認められる。\n
(3) 原告の主張について
原告は,中空状のシラスバルーンの中空内部に石けんが内包(形成)されている か否かを如何なる方法により観察(分析)できるのか,本件発明にかかる明細書に は何ら示されていないことから,本件明細書の記載は実施可能要件に適合しない旨\nを主張する。 しかし,本件明細書の記載から,シラスバルーンの中空内部に石けんが形成され ることが十分に理解できることは,前記(2)のとおりであり,分析方法についての説 明がないことをもって実施可能要件に適合しないとはいえないから,原告の主張は\n採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成30(ワ)8302 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年11月14日 東京地方裁判所
前記(1)の記載によると,次のとおり認められる。
ア 本件各発明以前にも,コンピュータシステムにおけるシステム利用者の 入力行為を支援する従来技術としては,マウスを右クリックすることによ り,マウスが指し示している画面上のポインタ位置に応じた操作コマンド のメニューが表示される「コンテキストメニュー」や,画面上でマウスポ\nインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマ ウスの左ボタンを押し,そのままの状態でマウスを移動させ,別の場所で マウスの左ボタンを離すマウス操作である「ドラッグ&ドロップ」などが あった。しかして,「コンテキストメニュー」には,マウスの左クリックを 行うまではメニューが画面に表示され続け,また,利用者が間違って右ク\nリックを押してしまった場合には,利用者の意に反して画面上に表示され\nてしまうので不便であるなどの課題があり,また,「ドラッグ&ドロップ」 には,継続的な動作,例えば,移動させる位置を決めないで徐々に画面を スクロールさせていくような動作に適用させるのが難しいという課題が あったところである(段落【0001】〜【0005】)。
イ 本件各発明は,このような課題を解決するため,入力手段における命令 ボタンが利用者によって押されてから,離されるまでの間に,ポインタの 位置を移動させる命令を受信すると,画像データである操作メニュー情報 を出力手段に表示させ,入力手段における命令ボタンが利用者によって離\nされると,出力手段に表示されていた操作メニュー情報の表\示を終了させ ることにより,普段は画面上に操作メニュー情報を表示させずに,利用者\nにとって必要な場合に簡便に表示させることを可能\にするという構成を\n採用したものといえる(段落【0022】,【0023】,【0051】)。そ して,スムーズな画面操作を可能とするため,操作メニュー情報が表\示さ れている状態において,これをポインタで指定した場合,すなわち,実行 される命令結果を利用者が理解できるように出力手段に表示した画像デ\nータである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲にポインタの座標 位置が入った場合に,「操作メニュー情報にポインタが指定された場合に 実行される命令」として特定された,例えば,出力手段に表示される画面\n(ビュー)をスクロールさせるような命令など,コンピュータシステムに 対する命令が実行され,操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に,ポ インタの座標位置が入らなくなるまで当該実行を継続するという構成を\n採用したものといえる(段落【0009】,【0012】,【0013】,【0 016】,【0023】,【0051】)。
ウ 以上のような,本件各特許請求の範囲の記載文言及び本件明細書の各記 載によれば,本件各発明は,コンピュータシステムにおけるシステム利用 者の入力行為を支援するため,「コンテキストメニュー」や「ドラッグ&ド ロップ」における,操作メニュー情報が利用者に意に反して表示されるこ\nとに関わる課題や,移動先を決めないで画面をスクロールさせるような継 続的な動作に関わる課題を解決すべく,操作メニュー情報については,普 段は画面上に表示させずに,利用者にとって必要な場合に簡便に表\示させ るという構成を採用し,その上で,物理的に操作メニュー情報が占める座\n標位置の範囲にポインタの座標位置が入っているときに,コンピュータシ ステムに対する命令が実行されるようにして,スムーズな画面操作が可能\nとなるという構成を採用したものといえる。このような構\成を採用した以 上,構成要件B,E,F及びGの「操作メニュー情報」とは,利用者にと\nって,その表示,非表\示を明確に認識できることが前提となっており,物 理的に操作メニュー情報が占める座標位置の範囲が明確になっている必 要があることは明らかである。 そうすると,構成要件B,E,F及びGの「操作メニュー情報」につい\nては,利用者にとっての,視覚的な見地からの,命令内容の表示や実行の\n簡便性を実現する構成を意味するものであるものといえ,そのような見地\nに照らし,同「操作メニュー情報」とは,利用者が,その表示の有無を視\n覚的に認識でき,その表示内容から,所望の命令を実行した結果について\nも理解できるような,画像データである必要があるものと解するのが相当 である。
そして,構成要件Fの,(1)「操作メニュー情報がポインタにより指定さ れる」と「操作メニュー情報に関連付いている命令」を「実行」する,及 び(2)「操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなるまで当該実行 を継続する」との文言については,画像データである操作メニュー情報の 座標位置が利用者に視覚的に認識できることを前提に,(1)画面上に表示さ\nれた画像データである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に,ポイ ンタの座標位置が入った場合に,特定の命令を実行し,(2)操作メニュー情 報が占める座標位置の範囲に,ポインタの座標位置が入らなくなるまで当 該実行が継続され,入らなくなった場合には,当該実行が継続されないこ とを意味し,かかる動作状況を満たす命令であることをもって,「操作メニ ューに関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当である。
(3) 「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F,G)の充足性\n
ア 以上を前提に,まず,「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F,G)\nの充足性につき検討するに,被告製品の構成のエ(イ)ないし(エ)及び\nオ(イ)ないし(エ)のとおり,本件ホームアプリにおける上ページ一部 表示及び下ページ一部表\示(以下「上ページ一部表示等」という。)は,画\n像データであり,その内容や表示位置からすれば,これを見た利用者は上\nページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえるから,利 用者が,その表示の有無を視覚的に認識でき,その表\示内容から,所望の 命令を実行した結果についても理解できるような,画像データに当たるも のというべきであって,「操作メニュー情報」を充足するものと認められる。 イ これに対し,被告は,上ページ一部表示等は,単にホーム画面が縮小表\ 示されることによって当該ホーム画面の隣のホーム画面が見えているに すぎず,実行される命令を表す文字も,矢印表\示等何らかの操作ができる ことを示す絵や記号も表示されておらず,表\示自体から上ページ又は下ペ ージにスクロールするといった実行される命令結果を理解できる画像で はない旨を主張する。 しかし,被告製品の構成エ(イ)及びオ(イ)のとおり,上ページ一部\n表示等が表\示されるのは,利用者が移動させたいショートカットアイコン をロングタッチして,ドラッグ操作をして同アイコンを移動させる等して, 縮小モードになった状態であることからすれば,同アイコンを移動したい 利用者が,1つ上のページ又は1つ下のページの一部を表示した画像であ\nる上ページ一部表示等を見て,上ぺージ又は下ページが存在することのみ\nならず,上ページ一部表示等までドラッグすれば,上ページ又は下ページ\nに画面をスクロールさせることができるものと理解することも可能とい\nうべきである。 以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
ウ 他方,原告は,上ページ一部表示等のみならず,「左上領域」「右上領域」\n又は「左下領域」「右下領域」(以下「左上領域等」という。)も「操作メニ ュー情報」に該当する旨を主張する。 しかし,左上領域等は,被告製品の構成エ(ウ)及びオ(ウ)のとおり,\n特定の座標位置で囲まれた領域にすぎず,利用者が,その表示の有無を視\n覚的に認識でき,その表示内容から,所望の命令を実行した結果について\nも理解できるような,画像データに当たるものとは認められない。前記ア の説示に照らしても,左上領域等が,「操作メニュー情報」に当たるとは認 められず,同説示のとおり,「操作メニュー情報」に該当するのは,上ペー ジ一部表示等に限られるというべきである。\n以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
(4) 「操作メニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報 に関連付いている命令」を「実行」する,及び「操作メニュー情報がポイン タにより指定されなくなるまで当該実行を継続する」(構成要件F)の充足性\n ア 被告製品においては,被告製品の構成のエ(ウ)(エ)及びオ(ウ)(エ)\nのとおり,左上領域等の占める座標位置の範囲に,原告が「ポインタの座 標位置」に当たると主張(前記第2の3(2)[原告の主張]イ)する「当該 ショートカットアイコンをドラッグしている指等のタッチパネル上の位 置」又は「当該ショートカットアイコンをドラッグしているマウスカーソ\nルの先端の位置」の座標位置(以下「指等及びマウスカーソルの先端の座\n標位置」という。)が入った場合に「上ページスクロール1」,「上ページス クロール2」,「下ページスクロール1」,「下ページスクロール2」を生じ させる命令(以下,併せて「ページスクロール命令」という。)が実行され, 左上領域等の占める座標位置の範囲に指等及びマウスカーソルの先端の\n座標位置が入らなくなるまでページスクロール命令が継続され,入らなく なった場合には当該実行が継続されないことが認められる。
しかし,前記(3)のとおり,被告製品において,「操作メニュー情報」に 該当するのは上ページ一部表示等であるところ,証拠(甲19,乙11〜\n13)によれば,上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲と左上領域\n等の占める座標位置の範囲とは必ずしも一致せず,上ページ一部表示等は,\n左上領域等と一部重なる座標位置に表示されているにすぎないことが認\nめられる。このため,(1)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に,\n指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていても,その位置が左\n上領域等の占める座標位置の範囲外であればページスクロール命令が実 行されず,また,(2)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に,指等\n及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていなくとも,その位置が左\n上領域等の占める座標位置の範囲内であればページスクロール命令が実 行・継続されることとなる。 このような被告製品の動作状況から検討すると,ページスクロール命令 の実行や継続は,指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が,利用者が\nその範囲を視覚的に認識することができない,左上領域等の占める座標位 置の範囲に入っているかどうかによるものであり,これが肯定されれば, 指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が上ページ一部表\示等の占め る座標位置の範囲に入っていなくても,ページスクロール命令が実行され 継続されるものである一方,上記が否定されれば,指等及びマウスカーソ\nルの先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入\nっていても,ページスクロール命令は実行され継続されないこととなるも のである。 すなわち,被告製品においては,指等及びマウスカーソルの先端の座標\n位置が,偶々,上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占める座\n標位置の範囲に入った場合に限って,ページスクロール命令が実行・継続 されているにすぎないものである。これに照らせば,ページスクロール命 令については,飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲 において実行・継続されるものであって,上ページ一部表示等の範囲にお\nいて実行・継続されるものではないのであるから,上ページ一部表示等に,\nページスクロール命令が関連付いているとまでは認めるに足りないとい うほかない。 したがって,上記のとおりの被告製品の構成は,構\成要件Fの「操作メ ニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報に関連付 いている命令」を「実行」する,及び「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」という文言(構成要件F)\nを充足するとは認められない。
イ 原告の主張について
(ア) まず,原告は,上ページ一部表示等のみならず左上領域等も「操作\nメニュー情報」に相当する旨主張するが,前記(3)に説示したとおり,左 上領域等は,「操作メニュー情報」には当たるとはいえない。
(イ) また,原告は,上ページスクロール1が生じるのは,処理手段が上ペ ージスクロール1を行うプログラムを実行していることを意味するとこ ろ,同プログラムは上ページ一部表示が表\示されていないと実行されな いから,上ページ一部表示と同プログラムとは関連付いている旨主張す\nる。 しかし,前記説示のとおり,本件発明の構成要件F(「関連付いている」)\nについては,画像データである操作メニュー情報の座標位置が利用者に 視覚的に認識できることを前提に,(1)画面上に表示された画像データで\nある操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に,ポインタの座標位置 が入った場合に,特定の命令を実行し,(2)操作メニュー情報が占める座 標位置の範囲に,ポインタの座標位置が入らなくなるまで当該実行が継 続され,入らなくなった場合には,当該実行が継続されないことを意味 し,かかる動作状況を満たす命令であることをもって,「操作メニューに 関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当であるところであ る。しかして,被告製品においては,指等及びマウスカーソルの先端の\n座標位置が,偶々,上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占\nめる座標位置の範囲に入った場合に限って,ページスクロール命令が実 行されているにすぎないものであって,ページスクロール命令について は,飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲において 実行・継続されるものであり,上ページ一部表示等の範囲において実行・\n継続されるものではないというのである。 以上によれば,原告の上記指摘をもって,直ちに,上ページ一部表示\nと上記プログラムとが関連付いており,上ページ一部表示等の有無とペ\nージスクロール命令の実行の可否が関連付いているとまで認めることは できず,他に,両者の関連付けを推認させるに足りる事情も見当たらな い。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 原告は,構成要件Fの「操作メニュー情報がポインタにより指定さ\nれなくなるまで当該実行を継続する」には,「終了」といった記載はない から,操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった際に当該 実行が終了することまで求めてはおらず,実行がいつ終了するかは同構\n成要件とは関係がない旨を主張する。 しかし,上記(2)ウで述べたとおり「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」とは,操作メニュー情報 がポインタにより指定されている場合に当該実行が継続されることのみ ならず,操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった場合に は当該実行が継続されなくなることまで意味するものと解すべきところ, 前記アで述べたとおり,被告製品において,指等及びマウスカーソルの\n先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入って\nいない場合であっても,左上領域等の占める座標位置に入っていればペ ージスクロール命令の実行が継続されるものである以上,被告製品は上 記の構成要件を充足しないというべきである。なお,原告の主張する「実\n行」の「終了」が何を意味するか必ずしも判然としないが,仮に,上記 構成要件の解釈として,操作メニュー情報がポインタにより指定されて\nいる場合に当該実行を継続することのみを意味し,操作メニュー情報が ポインタにより指定されなくなった場合に当該実行が継続されないこと までは含んでいないとする旨を主張する趣旨であるとしても,そもそも そのような解釈は,本件各特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載 に照らし,上記構成要件の解釈として失当と言わざるを得ない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成30(ワ)34728 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月17日 東京地方裁判所
本件事案に鑑み,まず,争点2(被告各製品が,本件発明に係る「物」の「生 産に用いる物(中略)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に 当たるか)について判断する。
(1) 本件特許請求の範囲は,前記第2の1 のとおりであり,その構成要件C\nは,「前記改質領域から延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出させな\nい状態で前記ウェーハの裏面を研削除去する研削手段を有する,」分割起点 形成装置という文言の記載であるところ,本件特許の特許出願の願書に添付 した明細書(以下「本件明細書」という。)には,発明の詳細な説明として, 次の記載がある(甲2)。
・・・
(2) 以上を前提に,以下判断する。
ア 本件特許請求の範囲の記載をみると,本件発明に係る「物」である「分 割起点形成装置」(構成要件A,D)は,「内部にレーザ光で改質領域を形\n成したウェーハを分割するための」装置であるものであって,上記の「形 成した」という記載文言からすれば,既にその内部にレーザ光で改質領域 が形成されたウェーハを加工対象物として,その割断のための分割の起点 を形成する装置であることが明らかである。 このことは,本件明細書の各記載からも裏付けられる。すなわち,本件 発明の課題は,チップ断面の改質領域の部分からの発塵やチップの破断等 を防ぎ,抗折強度の高い,安定した品質のチップを効率よく得るようにす ることにあるところ(段落【0010】,【0022】),本件発明は,研削 後においても,微小空孔が大きくなり亀裂が進展するものの,完全に基板 は分割されていない点に技術的特徴があり(段落【0051】),また,本 件発明の実施の形態によれば,研削によりレーザ光により形成された改質 領域内のクラックを進展させることができるため,チップCの断面にレー ザ光により形成された改質領域が残らないようにすることができる(段落 【0209】)というのである。これらによれば,本件発明は,その内部に 既にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを対象として所定の加工 等を行うに当たり,クラックの進展の程度を制御しようとする技術思想の ものであることが認められる。 そうすると,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,あくまでその\n内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハを製作するためのもので あり,本件発明に係る分割起点形成装置に対しては,その加工対象物を提 供するという位置付けを有するものにとどまるというべきであるから,こ のような被告各製品をもって,同分割起点形成装置の生産に用いる物とい うことはできないというほかない。 したがって,被告各製品は,本件発明に係る「物」の「生産に用いる物」 に当たるということはできない。
イ また,上記のとおり,構成要件A,Dは,既にその内部にレーザ光で改\n質領域が形成されたウェーハを加工対象物として,その割断のための分割 の起点を形成する装置であることを示すものであり,本件発明に係る上記 技術思想を実現する構成を特定するものではないことからすれば,本件特\n許請求の範囲の記載において,同技術思想について具体的に特定している 構成は,構\\成要件B(「前記ウェーハの前記改質領域を研削除去するための 研削手段であって,」),構成要件C(「前記改質領域から延びる微小亀裂を\n前記ウェーハの表面に露出させない状態で前記ウェーハの裏面を研削除\n去する研削手段を有する,」)にいう「研削手段」であるものというべきで ある。 そうすると,本件発明は,SDBGプロセス実行システムBを実現する 複数の装置の中で,上記「研削手段」により,課題を解決する発明である と解されるものであって,本件発明において,課題解決手段による作用効 果を直接もたらすものは,上記「研削手段」以外には存しないというべき であるから,「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるものは, 構成要件B,Cの「研削手段」であるというべきである。\nしかして,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,飽くまでウェー\nハ内部に改質領域を作るための装置であって,上記構成要件B,Cの「研\n削手段」を実現する装置ではない。そうすると,被告各製品は,「その発明 による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないというべきであ る。
ウ 以上のア,イによれば,被告各製品は,本件発明に係る「物」の「生産 に用いる物(中略)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」 に当たるとはいえないというべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本件明細書の記載(段落【0165】ないし【0168】,【0 170】ないし【0184】等)にあるように,改質領域の形成からウェ ーハの分割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて 技術的に意味があるものであることからすれば,SDレーザソー(被告各\n製品搭載)及び研削装置は,本件発明の「分割起点形成装置」を構成する\nものであるといえ,被告各製品は,本件発明に係る「物」の「生産に用い る物」に当たるといえる旨主張する。 しかし,原告が指摘する本件明細書の記載(段落【0165】ないし【0 168】,【0170】ないし【0184】等)が,研削除去工程だけでな く被告各製品が関わるレーザ改質工程についても触れたものとなってい るとしても,本件特許請求の範囲の記載は,飽くまで「内部にレーザ光で 改質領域を形成したウェーハを分割するための」(構成要件A),「分割起点\n形成装置」(構成要件D)というものであり,その記載文言上,既にその内\n部にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを加工対象物として,その 割断のための分割の起点を形成する装置であることが,一義的に明確なも のとなっているものと認められる。そうである以上,本件明細書の上記記 載がレーザ改質工程についても触れたものとなっていることを指摘する ことによって,本件特許請求の範囲の記載文言から導いた前記認定を左右 することはできないというべきである。 また,仮に,原告が指摘するように,改質領域の形成からウェーハの分 割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて技術的に 意味があるとしても,それぞれの工程を担う各装置自体は,不可分一体と なっているものではなく,改質領域を形成したウェーハを製作するための 装置,かかるウェーハに対して研削という加工をするための装置というよ うに,それぞれの各装置として具体的に把握できるものであって,上記の 技術的な意味を指摘することから当然に,本件特許請求の範囲の記載文言 から導いた上記認定が左右される根拠となるものとはいえない。 以上に照らせば,SDレーザソー(被告各製品搭載)及び研削装置が,\n本件発明の「分割起点形成装置」を構成するものであるとする根拠はない\nというほかなく,原告の上記主張は,採用することができない。
イ 原告は,本件発明の特徴的技術手段が,構成要件C(「前記改質領域から\n延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出されない状態で前記ウェー\nハの裏面を研削除去する」)の点にあることは前提としつつも,そのために は,研削手段による研削の仕方だけでなく,レーザ光による改質領域及び これから伸びる微小亀裂の作り込みが重要であることが明らかであり,ウ ェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出させな\nいことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光は,本件発明の特\n徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当するから,このレーザ光を照\n射する被告各製品は,当該構成を直接もたらす特徴的な部材に当たるとい\nえる旨主張する。 しかし,原告が指摘する,レーザ光による改質領域及びこれから伸びる 微小亀裂の作り込みの重要性について検討しても,そもそも,本件発明の 技術思想との関連で,研削工程と有意な関連性を有する改質領域形成手段 (ウェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出さ\nせないことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光)が備えるべ\nき具体的な構成,条件等についての説明は,本件明細書に何ら見当たらな\nいところであって,原告の上記指摘は,明細書の記載に根拠を有しない主 張といわざるを得ない。そうである以上,原告が指摘する上記改質領域形 成手段が,本件発明の特徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当する\nということはできないから,レーザ光によりウェーハ内部に改質領域を作 るため,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,本件発明に関して,\n「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないもの というべきである。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> 不可欠性
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成29(ワ)5108 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和元年12月17日 大阪地方裁判所
ア 要部認定の意義
被告意匠が本件意匠に類似するかは,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基 づいて判断すべきものであることは前述のとおりであるから,まず,意匠に係る物 品の需要者を想定し,物品の性質,用途,使用態様を前提に,需要者に生じる美感 が類似するか相違するかを検討すべきこととなる。 本件意匠と被告意匠については,前記(1)で述べたとおり,多数の共通点,差異点 が存するが,それが需要者に美感を与える程度は異なるから,単純に共通点,差異 点の多寡によって決したりすることはできず,需要者の注意を最も引きやすい部分 を意匠の要部として把握し,両意匠の構成態様の要部における共通点,差異点を検\n討し,全体として両者の美感が類似するか相違するかを判断することになる。
イ 物品の需要者及び使用態様
本件意匠及び被告意匠に係る物品は,いずれもトレーニング機器であって,背面 電極部から流れる電流により腹筋等を刺激し,腹部の筋肉等を引き締めるためのも のである点において共通する(各公報における「意匠に係る物品の説明」参照。)。 原告商品及び被告商品の商品説明や広告宣伝方法(前記1(3))からは,原告商品は 腹筋を鍛えることに特化したものである一方,被告商品は腹部以外への装着も予定\nされており,「理想のボディライン」を作ることに主眼が置かれているという違い が見られるものの,原告商品及び被告商品の需要者は,いずれも,上記公報の説明 のとおり,「腹部の筋肉等を引き締める」目的でトレーニング機器を使用しようと する一般消費者である。 また,原告商品及び被告商品は,いずれも使用者の身体に貼付して装着し,当該\n物品の背面に設けられている電極を直接肌に接触させて使用する物であるから,需 要者は主に正面ないし斜め上方部から当該製品を見ることが多く,背面については 着脱時等にある程度見る機会があるにとどまるというべきである。このことは,両 製品の商品説明や広告宣伝において,正面から撮影した写真や身体に装着した状態 の写真が多く用いられ,背面の写真は数少ないことからも推認することができる。
ウ 本件意匠の要部
以上を前提に検討すると,本件意匠については,前記2(2)アで基本的構成態\n様と指摘した部分は,本件意匠の特徴をなすものとして需要者の注意を引くと考え られるから,本件意匠の要部というべきであるが,本件意匠については,さらに, 同イの具体的構成態様のうちVないしVIIIとして指摘した内容,すなわち,各パッド 片の形状,各パッド片の結合方法(向き),各パッド間の切込みの形状,深さにつ いても,需要者に一定の美観を与え,需要者の注意を引くと考えられるから,これ ら指摘した部分も,本件意匠の要部であると認めるのが相当である。 他方,それ以外の点,すなわち前記2(2)イの具体的構成態様のうち,IXない しXII記載の点については,前述イの使用態様をも考慮すると,需要者の注意を特に 引くとは考えにくいので,要部には当たらないと解するのが相当である。
エ 双方の主張について
原告は,本件意匠出願時の公知意匠との対比において新規性を有することを 理由に,原告が基本的構成態様であると主張する部分(要旨,円形の電池部を中心\nに6枚のパッド片を左右対称2段3列に配置すること)のみが要部であると主張す るのに対し,被告は,前記部分はありふれており,要部には当たらないと主張する。 まず,原告の主張について検討するに,意匠に公知意匠にはない新規な構成\nがあるときは,その部分は需要者の注意を引く度合いが強く,逆に公知意匠に類似 した構成があるときは,その部分はありふれたものとして需要者の注意を引く度合\nいは弱いと考えられるから,その意味で,要部を認定するに当たり,公知意匠を参 照する意義はある。
しかしながら,この場合における要部の認定は,意匠の新規性を判断するのでは なく,需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通するか否かを判断するために行 うものであるから,公知意匠にはない新規な構成であっても,特に需要者の注意を\n引くものでなければ要部には当たらないというべきであるし,公知意匠と共通する いわばありふれた構成であっても,使用態様のいかんによっては需要者の注意を引\nき,要部とすべき場合もある。 すなわち,公知意匠との関係で新規性が認められれば,当然に要部とされるもの ではないし,新規性が認められる部分のみが要部となるわけでもなく,需要者に与 える美感を具体的に検討する以外にない。
仮に原告の主張する基本的構成(円形の電池部を中心に6枚のパッド片を左右対\n称2段3列に配置すること)をとった場合であっても,パッド片の形状やパッド片 をどのように結合するか,あるいはパッド片を区切る切込みの形状や深さをどのよ うにするかによって,需要者に与える美感は異なると考えられ,前記1の(1)及び(2) で認定した本件意匠に先行,後行する公知意匠を総合しても,本件意匠のパッド片 の形状等がありふれたものであるとか,需要者の注意を引くものではないというこ とはできない。 そうすると,本件意匠については,上記基本的構成のほか,各パッド片の形状,\n各パッドの結合方法(向き),各パッド間の切込みの形状や深さが全体として需要 者に一定の美感を与え,需要者の注意を引くというべきであるから,前記ウのとお り,これらについても本件意匠の要部と認めるのが相当である。 仮に,上記基本的構成のみが要部であり,その部分が共通でありさえすれば本件\n意匠と類似であると認められるとすると,パッド片の形状等がどれほど相違しても 本件意匠の類似の範囲内にあるとすることになるが,それは本件意匠権を,具体的 に得られる美感の観点を離れて抽象化,上位概念化することであり,原告の主張は 採用できない。
次に被告の主張について検討するに,前記1(1)及び(2)で認定した本件意匠に 先行又は後行する公知意匠を参照しても,前記2(2)アの基本的構成がありふれたも\nのであるとか,需要者の注意を引くものではないということはできない。 上記基本的構成は,各パッド片や切込みの形状とあいまって,全体として需要者\nに一定の美感を与え,需要者の注意を引くというべきであるから,上記基本的構成\nが本件意匠の要部には当たらないとする被告の主張は採用できない。
(3)類否の判断
ア 要部についての共通点
本件意匠の要部を前記(3)ウのように解すると,要部について本件意匠と被告意匠 が共通するのは,前記(1)ア(基本的構成態様)の(1)(本体シート状,6枚のパッド 片),(2)(2列3段,左右対称),(3)(略円形上の操作部)及び(4)(パッド背面の 電極)であり,少なくともその限度では,美感の類似性が認められる。
イ 要部についての相違点
本件意匠の要部を前記(3)ウのように解すると,要部における本件意匠と被告 意匠との差異点は,前記(1)ア(基本的構成態様)の(5)(パッド片の結合)及び(6)(左 右対称か上下対称か),並びに前記(1)イ(具体的構成態様)の(3)(上段,下段パッ ド片の形状,傾斜),(4)(中段パッド片の形状,傾斜),(5)(上下の切込みの形状, 深さ)及び(6)(左右の切込みの形状,開口の方向,深さ)ということになり,これ
本件意匠の美感と被告意匠
本件意匠は,中段パッド片が略横長隅丸4角形状で左右端が若干上に傾くように 配置され,上段及び下段パッド片は,略横長隅丸5角形状で,いずれも中段パッド 片との間に,略V字形の,深さが上段及び下段パッド片の2分の1程度の切込みが 設けられ,上段及び下段パッド片の各中央に略V字状の切込みが設けられているこ とから,各パッド片の各辺は概ね直線状となっていること,及び各パッド片の結合 する中心部分が略6角形状に見えることと合わせて,全体的に上向きでがっしりと した印象を与え,躍動感や力強さといった,原告商品を使用することによって達成 しようとする目標(鍛えられ6つに割れた腹筋)を想起させるものとなっている。 各パッド片の形状や切込みの形状は,機械的,幾何学的な形状と表現し得るもの\nであり,そのために先進的,未来的な印象を与えるものであるが,被告意匠からそ のような印象を受けることはない。
被告意匠の美感と本件意匠
被告意匠は,中央から左右端に向けて徐々に上下の幅が狭くなっている,略横長 隅丸台形状の中段パッド片の上下に,それぞれ上底又は下底が略弓形に湾曲してい る上段及び下段パッド片が略水平に配置されており,いずれも中段パッド片との間 に,先端部分を円弧状の頂点を有する細長い略3角形状の,切込みの深さが上段及 び下段パッド片の3分の1程度の切込みが設けられており,全体的に上下対称であ って,本体の輪郭線に曲線が多いこと,各パッド片の結合する中心部分が略柱状に 見えること,及び上部又は下部のパッド片の根元が湾曲形状部分に比べて細く引き 締まった印象を与えることから,全体的に,しなやかで柔らかく,引き締まった軽 快な印象を与える。 特に,上段パッド片について,中央の切込みが深くなく,左右のパッド片同士が 結合しているようにも見えること,上底が略弓形に湾曲していることから,一対の 羽根を広げた形状のような印象を受け,下段のパッド片がこれと上下対称となるよ う配置されていることは,独特の美感を生じさせているということができるが,本 件意匠にこのような要素はない。
まとめ
以上のように,本件意匠は,躍動感や力強さを感じさせる機械的,幾何学的な意 匠であるのに対し,被告意匠は,自然界に存在する羽根を想起させるやわらかで軽 快な印象を与える意匠であって,両者が与える美感の差異は大きく,この点は,前 記要部の共通点が存することによる美感の同一性を上回ると認められ,全体として 評価すると,本件意匠と被告意匠が与える美感は,需要者において区別可能な程度\nには異なるということができる。
(4)争点(2)の結論
前記前提事実のとおり,原告商品は被告商品に先行して販売され,前記1(3)アの 宣伝により,需要者に広く知られていると認められるから,被告商品を見た需要者 は,原告商品と同様の機能を有し,同様の用途に使用し得るEMS製品と考える可\n能性はあるものの,そのような広義の誤認混同のおそれは意匠法が規律するところ\nではなく,上記検討したとおり,本件意匠と被告意匠が与える美感が異なり,需要 者においてこれを区別することが可能である以上,被告意匠は本件意匠には類似し\nないというべきである。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成29(ワ)31544 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月30日 東京地方裁判所
上記グラフにおけるZn(青線)とPk(赤線)の線形性にほぼ差異はない 上,ZnとXcの差(Zn−Xc)のZnの値に対する比率((Zn−Xc)/Z n)は,Brix値が0%のとき約4.98%,10%のとき約3.82%, 20%のとき約2.75%,30%のとき約1.62%,40%のとき約1. 46%,50%のとき約0.99%であって,ZnとXcの値の差は全体的に かなり小さく,Zn≒Xcと評価しるものであって,そうすると,式(B)は, 重心であるZnの平均値を出しているにすぎないというべきである。 また,式(B)の分子の式(Zn+(Zn−Xc))については,(1)Xc値> Zn値の場合,(2)Xc値=Zn値の場合,(3)Zn値>Xc値の場合があり得るが, (2)の場合にはPkの値は重心位置と一致する上,上記計測結果のような(1)の 場合又は(3)の場合に,式(B)により算出されるPkの値(被告の主張によれ ば臨界角点)が理論上の臨界角点により近似することの合理的な説明はなさ れておらず,そのことを示す的確な証拠もない。そうすると,式(B)が臨 界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認めることはできず,む しろ,前記のとおり,ZnとXcの値の差は全体的にかなり小さく,Zn≒X cと評価し得るものであることを踏まえると,式(B)は重心であるZnの平 均値を出しているものというべきであり,さらに,被告製品において式(B) に基づき複数の試行を行っていることも,同製品が構成要件Eを充足すると\nの結論を左右しない。
ウ 式(C)について
本件発明における式(2)は,「Pc=Pc’+C」というものであると ころ,本件明細書等の段落【0035】〜【0038】,段落【0040】, 【0041】によれば,定数Cは,重心位置Pc’に加算して臨界角点Pc (=Pc’+C)を求めるための定数であり,屈折率が既知である試料を用 いた実験により予め決定された値であると認められる。そして,本件発明は,\nこのように式(1)と式(2)を組み合わせることにより,臨界角点を直接 求めるよりも,同点をより正確に求めることができるとの効果を奏するもの であると認められる。 他方,被告製品の用いている式(C)は,「ΔPc=PCT20−PC0」とい うものであるところ,被告製品説明書,証拠(甲7,8,乙1,9)及び弁 論の全趣旨によれば,PCT20は,式(A)により得られたZn値を式(B) により調整したPk値(前記判示のとおり,重心であるZnの平均値)を,2 0°Cの環境下での値に換算した値であるから,この値は,上記手順により調 整された光量分布曲線の一次微分曲線(あるいは一次差分曲線)の重心位置 のアドレス値(甲7・10頁における「ゼロセット後 10%測定」欄の「Bary T20」の値(30.146))であり,PC0は,20°Cの環境下で濃度0%の 水を用いて計測した重心位置のアドレス値(同頁における「水基準書き込み 後 水」欄の「CAL OffSet」の値(18.54758))であること,また, 水の屈折率は既知であるところ,被告製品の理論上の臨界角点のアドレス値 は18.50000であることが認められる。 そして,甲7によれば,被告製品は,(1)上記PCT20の値(上記「Bary T20」 の値)を入力し,(2)「Bary T20」の値から「CAL OffSet」(水書き込みアド レス値)を差し引いた値を計算する,(3)上記(2)の値をBrix値に換算し, 「Saccharin T20」(Brix値)を算出する,(4)ゼロセットオフセット値を 読み込む,(5)「Saccharin T20」(Brix値)から「ゼロセットオフ値」を 差し引き,その結果を「Brix Value」(Brix値)として算出する,(6)「Brix Value」(Brix値)を「Final Rfact」(屈折率)に換算するという順序 でプログラムが実行されているものと認められる。 上記のプログラム実行過程のうち(2)の計算式は,試料の重心位置のアドレ ス値である「Bary T20」(PCT20)の値から水の重心位置のアドレス値であ る「CAL OffSet」(PC0)の値を差し引くものであり,試料の重心位置のア ドレス値の原点を水の重心位置のアドレス値に改めるとの意味を有するも のであるところ,このPC0値(18.54758)は理論値(水の理論上の 臨界角点のアドレス値である18.50000)との差(0.04758) を含む値であるということができる。そうすると,上記(2)の計算式は,試料 の重心位置のアドレス値から水の重心位置のアドレス値を直接差し引くも のであるが,実質的には,PCT20及びPC0の双方から水の臨界角点の理論 値(18.50000)を控除していったん同理論値を原点とする試料の重 心位置と水の重心位置の各アドレス値を算出し,さらに前者から上記差の値 (0.04758)を調整しているに等しく,試料の重心位置のアドレス値 に,屈折率が既知である水を用いた実験により予め決定された定数(−0.\n04758)を加算する計算をしているのと同義であるということができる。 したがって,式(C)は,式(2)を充足する。
(3) 被告の主張について
ア 被告は,式(1)と式(A)が形式的に異なっているから,被告製品は構\n
成要件Eを文言充足しないと主張する。 しかし,式(1)は,光量分布曲線の一次微分曲線(あるいは一次差分曲 線)の重心位置Pc’を求めるものであって,式(A)と技術的思想を同じ くするものであり,かつ,式(A)は式(1)に変形し得るものであって, 当業者であれば,式(A)と式(1)が実質的に同一の式であると認識し得 るというべきである。 そうすると,式(1)の技術的範囲は式(A)を包含するものと認めるの が相当である。
イ 被告は,被告製品におけるZnは13回算出され,更にPkを5回算出して 臨界角点Pcを算出しているのに対し,本件発明は,重心位置Pc’を1回 算出し,これに定数Cを加えてPcを算出しているのであるから,技術的思 想が異なると主張する。 しかし,Znが重心位置を求める式であると認められるのは前記のとおり であり,これを13回にわたり求めて,平均値を算出するといった手法は当 業者が容易に採用し得る技術常識に属するものと解される。また,前記のと おり,式(B)が臨界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認め ることはできず,むしろ,重心であるZnの平均値を出しているものという べきであることは前記判示のとおりであるから,本件発明と被告製品の技術 的思想が異なるということもできないというべきである。
ウ 被告は,PC0はΔPcを算出するための基準数値にすぎないから定数Cに 対応する概念ではなく,ΔPcも本件発明の式(2)のPcに対応する概念 ではなく,フェーズが異なるなどと主張する。 しかし,ΔPcを算出する式(PCT20−PC0)が有する意義は前記のとお りであって,被告製品においても試料の重心位置につき差分を調整すること で臨界角点を求めている点で本件発明と変わりがないから,式(C)が式(2) と実質的に異なるということはできない。
エ 被告は,本件発明における式(2)に関し,Pc’は特定の装置における 測定値ベースの臨界角点であり,定数Cは当該装置毎の個体差を較正する値 にすぎないなどと主張する。 しかし,前記のとおり,式(1)により得られるPc’は光量分布曲線の 一次微分曲線(あるいは一次差分曲線)の重心位置であるから,臨界角点と は異なるものであって,本件発明がこれに定数Cを加えることで臨界角点を 求めるものであることは,前記判示のとおりである。
(4) 以上のとおり,被告製品は構成要件Eを充足し,また,被告製品が構\成要件 A〜D及びFを充足することは前記前提事実(3)ウのとおりであるから,被告 製品は,本件発明の技術的範囲に属する。
・・・
(1)特許法102条2項に基づく損害額について
ア 被告は,(1)平成28年9月9日から平成30年2月9日までの間に被告製 品を137個販売し,(2)その売上総額は204万4164円であり,(3)被告 製品1個当たりの製造原価は1万0249円であるが,(4)特許法102条2 項所定の被告の利益額を算出するに当たっては,(3)に加えて配送費合計16 00円を控除すべきと主張するところ,(1),(3)及び(4)については,当事者間 に争いがなく,証拠(乙10〜12)によれば,(2)の事実を認めることがで きる。 そうすると,原告の損害額は,特許法102条2項に基づき,63万84 51円(=204万4164円−(137個×1万0249円+1600円)) と推定される。被告がこれを超える利益を得たことを認めるに足りる証拠は ない。
イ 被告は,寄与率を考慮すべきと主張する。しかし,本件発明は,屈折率を 測定するための臨界角点の算定という,屈折計の本質的ないし根幹的技術に 関するものであって,その可分的な一部に関するものではないから,本件で 寄与率を考慮すべきとは認められない。被告主張の諸事情は,この結論を左 右しない。
(2) 弁護士・弁理士費用について
本件事案の難易,請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると,被告の侵 害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金として6万円を認めるの が相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成30(ワ)13400 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 東京地方裁判所
原告は,本件発明1のうち,挿入力の増加の防止のための構成がその本\n質的部分であるとした上で,被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから,被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず,同製品は本件発明1の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし,本件発明1は,特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて,従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり,他方, 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると,挿入力が強 くなり作業性が悪化することから,挿入力は弱いままで,抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる(本件明細書等の 段落【0009】,【0013】〜【0015】)。そうすると,本件発 明1の本質的部分は,挿入力は弱いままで,抜け力を強くするための構成\nにあり,従来技術との対比でいうと,特に抜け力の強化のための構成が重\n要であるというべきである。 そして,本件発明1は,上記課題の解決のため,(1)メインアーム部と, メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し,(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり,(3)サブアーム部の上端部を,上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより,取付孔 への挿入性の向上を図るとともに,アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が 加わったときは,係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる(特許請求の範囲,本件明細書等の段\n落【0017】,【0029】,【0032】,【0033】,【003 6】,【0037】)。
ウ 他方,被告製品においては,サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ,当該フック部と車体のルーフ孔の距離が0.3mmであると認め られるから(乙13),抜け方向に荷重が加わった際に,フック部は0. 3mm程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり,爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして,被告製品における抜け力に関し,被告が実施した実験結果(乙 5)によれば,本件発明1の実施品の抜け力は186Nであるのに対し, 被告製品の抜け力は,215.8N,227N,271N,295Nであ り,最小でも約30N,最大で約110Nの差が生じたことが認められる。 また,被告が実施した,被告製品のコの字型部材(サンプル(1))と,被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの(サンプル(2))を用 いた実験結果(乙14)によれば,前者の抜け力の平均値は227.60N,後者の抜け力の平均値は73.51N(いずれも10回実施)であり, フック部を備えたコの字型部材の方が,抜け力において約150N大きい ことが認められる。 前記のとおり,被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ,これに上記の各実験結果を併せて考慮すると,被告製品は, 本件発明1の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ,そ の抜け力の大きさは,同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり,少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。
なお,原告は,乙14実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が\nあるとして,乙14実験の信用性を争うが,サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり,上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり,乙14実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて10回ずつ実験を行っているところ,数値にば らつきはあるものの,サンプル(1)は200N以上であり,サンプル(2)は概 ね60〜100程度であり,全体的に100N以上の差が生じていること に照らすと,その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり,抜け力の増大という課題を解決するための構成は本\n件発明1の本質的部分ということができるところ,本件発明1はこの課題 をアンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し,被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ,そうす ると,被告製品は本件発明1と異なる構成により上記課題を解決している\nということができる。
そうすると,本件発明1と被告製品はその課題解決のための特徴的な構\n成において相違し,本件発明1と被告製品との相違点は,この課題解決に 必要な構成に関するものであるから,同相違点は本件発明1の本質的部分\nに関するものであるということができる。
オ したがって,本件発明1と被告製品の相違点は,本件発明1の本質的部 分に関するものではないということはできないので,被告製品は第1要件 を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2020.01.24
平成31(ネ)10035等 著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所 静岡地方裁判所
被控訴人は使用料規程により使用料を得ているのであるから,使用料規 程に従って算出される使用料相当額をもって,被控訴人の損害と認めるのが 相当である。 これに対し,控訴人らは,使用料規程のうち,入場料もなく無償で行わ れる著作物の演奏に対しても使用料を徴収する規定は,著作権法による保護 の範囲を超えており,憲法上の表現の自由及び幸福追求権などの権利を過度\nに制約するもので,公序良俗に反し無効であるし,本件におけるSUQSU Qでの演奏活動は著作権法の規制の範囲外のものであり,無償の範疇にあっ たと主張する。しかし,演奏権が及ばない場合については著作権法38条1 項が規定するとおりであり,使用料規程の内容に照らし,一般に演奏権が及 ぶ場合について使用料を規定したものであることは明らかであり,著作権の 保護範囲に関する控訴人らの主張は独自の見解であって採用できない。また, 控訴人らの行為が著作権法38条1項により演奏権が及ばない場合に該当し ないことは上記2(7)において説示したとおりであり,控訴人らの行為が著 作権法の規制の範囲外であるとの控訴人らの主張は失当である。 さらに,控訴人らは,使用料規程は具体性,合理性を欠くものであるこ とを主張する。しかし,使用料規程には,社交場として定義される施設にお いて,椅子又は座席以外の客席(客にダンスをさせるための場所を含む。) については面積を1.5m2で除した数を座席数とみなすことを含めた座席数 の算出方法,標準単位料金の算出方法(客1人あたりにつき通常支払うこと を必要とされる税引き後の料金相当額(いずれの名義をもってするかを問わ ない))が定められており,十分に具体性がある。また,著作権等管理事業\n者において締結する著作物の利用許諾契約の性質上,このような座席数及び 標準単位料金を基準に使用料を定めることにも合理性があるというべきであ る。 また,控訴人らは,損害額の算定に当たり,包括的利用許諾契約を締結 する場合の規定によるべきであるとか,本件店舗における生演奏はカラオケ と異ならないから使用料規程の別表7(2)記載の表中の2の区分が適用され\nるべきであるなどと主張するが,いずれも採用できない。
・・・
以上によれば,現SUQSUQに係る平成28年11月1日から 令和元年7月8日までの使用料相当額は139万3548円であり, 弁護士費用としては1割である13万9355円をもって相当と認め るから,その合計額は153万2903円である。
(ウ) 令和元年7月9日以降の損害ないし損失に係る請求について 将来の給付を求める訴えは,あらかじめその請求をする必要がある場 合に限り認められるところ(民訴法135条),継続的不法行為に基づ き将来発生すべき損害賠償請求権については,たとえ同一態様の行為が 将来も継続されることが予測される場合であっても,損害賠償請求権の\n成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず,具 体的に請求権が成立したとされる時点において初めてこれを認定するこ とができ,かつ,その場合における権利の成立要件の具備については債 権者においてこれを立証すべく,事情の変動を専ら債務者の立証すべき 新たな権利成立阻却事由の発生として捉えてその負担を債務者に課する のは不当であると考えられるようなものは,将来の給付の訴えを提起す ることのできる請求権としての適格を有しないものと解するのが相当で ある(最高裁昭和56年12月16日大法廷判決民集35巻10号13 69頁,最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決集民224号39 1頁等参照)。 以上によれば,現SUQSUQにおける,控訴審の口頭弁論終結日の 翌日である令和元年7月9日以降の不法行為に基づく損害賠償請求ない し不当利得返還請求に係る訴えは不適法であり,却下を免れない。
(5) 控訴人らの主張について
控訴人らは,被控訴人による実態調査の方法そのものに大きな問題があ り,その調査結果の信憑性は低いと主張するが,そのようにいえないことは 前記1において引用した訂正された原判決説示のとおりである。 使用料規程によれば,座席の配置,実際の売上げや来店者数や椅子の利 用状況により使用料額が変動するものではないから,これらの点についての 控訴人らの主張は採用できない。また,控訴人らの主張する補助椅子がどの ような椅子を指すのかは明らかではないが,甲10,24,25,41,4 2からは,本件店舗の各店の座席数は31〜40席であったものと認めら れ,これを覆すに足りる証拠はない。 控訴人らは,平成29年11月21日から同年12月11日にかけての 利用状況や営業時間についての主張をするが,いずれもこれを裏付ける的確 な証拠はなく,上記認定を左右するものではない。 控訴人らのその余の主張も採用できない。
4 小括
以上によれば,被控訴人の拡張後の請求は,(1)差止請求,(2)金銭請求 のうち,i)控訴人Xにつき,平成20年6月18日から平成28年10月31 日までの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償金合計から既払金を控除した 残額470万4605円(このうち51万3523円の限度で控訴人Yと連帯 して)及びこれに対する不法行為以後である同年12月14日から支払済みま で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,ii)控訴人Yにつき,平 成27年12月7日から平成28年10月31日までの著作権侵害の不法行為 に基づく損害賠償金51万3523円及びこれに対する不法行為以後である同 年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支 払(うち,51万3523円及びこれに対する平成28年12月14日から支 払済みまで年5分の割合による金員の限度で控訴人Xと連帯支払),iii)控 訴人らにつき,連帯して,同年11月1日から令和元年7月8日(控訴審口頭 弁論終結日)までの不法行為についての損害賠償金153万2903円の支払 を求める限度で理由があり,同月9日から管理著作物の使用終了に至るまでの 不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得金の将来請求に係る部分は不適法で あり,その余の請求は理由がないことになる。
したがって,原判決中,(1)の差止請求を認容した部分,(2)iii)の控 訴人らに対する請求について,令和元年7月9日以降に生ずべき損害賠償金又 は不当利得金の支払を求める訴えを却下した部分は相当である。(2)の i)の 控訴人Xに対する請求に関する部分については,470万4605円(このう ち51万3523円の限度で控訴人Yと連帯して)及びこれに対する平成28 年12月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を超え て認容するのは相当でないから,本件控訴に基づき変更すべきことになる。 (2)の ii)の控訴人Yに対する請求に関する部分については,51万352 3円及びこれに対する同年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割 合による遅延損害金の支払(うち,51万3523円及びこれに対する平成2 8年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で控訴人X と連帯支払)を,(2)の iii)の控訴人らに対する請求のその余の部分につい ては,153万2903円の連帯支払を命じるべきであるから,本件附帯控訴 に基づき変更すべきことになる。また,仮執行宣言については,被控訴人が求 める限度で付するのが相当である。
2020.01.24
平成31(行ケ)10036 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
ア まず,上記各書証の成立の真正についてみると,原本で提出されている もの(甲62から64まで,66,71)と写しが原本として提出されて いるもの(甲21,29から38まで,40,43,45,49,51, 52,65,67から70まで)とが存在する。そして,信用性の点につ き別途の検討を要するとしても,その記載内容や外観,この点に関する本 件審判手続の証人尋問におけるKの供述内容(甲58)によれば,当該各 書証の名義人として表示された者の意思に基づいて当該各書証が作成され\nたこと,すなわち各書証の成立の真正(写しを原本として提出する書証に ついてはその原本の存在も含む。)が認められる。
イ これに対し,被告は上記のとおり各書証の成立の真正を争うものの,被 告自身が名義人であるなど,被告がその作成過程を認識し得る書証は含ま れておらず,当該各書証に名義人として表示された特定の作成者の意思に\n基づかずに当該各書証が作成されたことについて具体的な事実関係を主張 するものではない。むしろ,被告の主張は,各書証の作成名義ではなく, その作成時期や記載内容の信用性を争うものである(前記第4の2(3)参 照)。そうすると,当該各書証の成立の真正に関する被告の主張は採用で きず,前記アの通り,前記(1)にみた各書証の成立の真正が認められる。
(3)次に,書証の信用性について検討する。
ア 前提として,各書証の作成経過についてみると,Kは,本件審判手続の 証人尋問(甲58)において,建設会社の従業員を辞めて事業を始める際 に,原告に相談したところ,原告から本件商標の使用を許されたため,平 成28年1月末頃から,「アンドホーム」の名称で,客から注文を受けて 建物の設計と建築をする住宅の事業を始めたこと,「アンドホーム」の名 称で,少なくとも3件の契約をしたこと,その3件の契約は,Kが,名刺 を渡して自己紹介をした上で,その注文者らと直接やりとりをしながら, 何度も資金計画表や建築図面等を修正して注文者らに提案し,最終的に契\n約書を交わして契約を締結したこと,上記建築図面は,K自らがラフな図 面を描いた上で他の設計士に依頼して作ってもらったこと,上記資金計画 表は全てKが作成したこと,資金計画表\の「建物の設計申請費用」とは,\n建築図面を作って市の検査に出すための費用であること,同表に記載され\nている「地盤改良工事費用」は,地盤調査費用及びその調査の結果土地が 軟らかいことが判明した場合に必要となる改良工事の費用が計上されてい ること,資金計画表の「建物工事費」及び消費税と,「建物付帯工事」費\n用の合計額から,先にもらっている「建物契約印紙費用」を引いて,「ア ンドホーム契約値引き(役員承認)」を引くと,契約書の請負代金額とな ること(なお,建物印紙の金額を足すかのような供述をするが,文脈に照 らし言い間違いであることは明らかである。),地盤調査は東昇技建に依 頼して行ってもらったこと,平成28年6月9日に「アンドホーム」から 「シンプルハウス」に名前を変えて法人化したこと,契約をした3件につ いてはいずれも建築工事を完了したことを供述する。 また,Kは,上記尋問において,建築確認申請書については,「アンド\nホーム」で出したか「シンプルハウス」で出したかは今手控えがないので 分からないとしつつも,平成28年6月9日以降,銀行との関係では, 「アンドホーム」で出した事前審査関係書類をシンプルハウス名義のもの に差し替えるなどしたが,役所の関係の申請等は現場監督がしていたので\n分からないなどという趣旨の供述をする。 そして,Kは,陳述書(甲19,50)においても,概ね同趣旨の供述 をしている。
イ 工事請負契約1に係る確認済証及びその添付書類一式(甲59)及び同 契約に係る建築計画概要書(甲60)は,行政官庁に提出され,行政官庁 において保管されていた文書の写しであるから,当該行政官庁に対して行 った手続の内容に関する証拠としては信用性が高いといえるところ,これ によれば,平成28年6月9日の建築確認申請の際にKが営業所名を「ア\nンドホーム」として手続をし,同月15日に営業所名を「株式会社シンプ ルハウス」に変更する手続をしたことが認められる。かかる事実は,前記 アのKの供述内容のうち,Kが,平成28年6月9日に「アンドホーム」 から「シンプルハウス」に名前を変えて法人化したが,それまでの間は 「アンドホーム」の名称で建物の建築等の事業を行っていたという,最も 重要な部分を裏付けるものである。 そうすると,前記アのKの供述内容のうち,「アンドホーム」の名称で の契約締結やその契約において提供した役務等に係る点については,上記 のとおり,重要な点において裏付けが存する上,その供述内容全体も,合 理的なものであって不自然な点は存しないから,基本的には信用できると いうべきである。 そして,本件では,工事請負契約1に関する契約書の写し(甲70)及 び工事請負契約3に関する契約書の原本(甲71)が提出されているとこ ろ,これらの各契約書の記載,特に注文者や建築時期等の記載は,上記工 事請負契約1に関する確認済証及び建築計画概要書の記載並びに工事請負 契約3に係る建物の登記事項証明書(甲56)及びその底地である土地の 登記事項証明書(甲55)といった各種公的書類の記載と合致しており, 少なくともこれらの契約が存在することが裏付けられている。 また,工事請負契約1及び3に関しては,契約の締結経過や役務の内容 に関する書証として,前記(1)ア及びウにみた各書証も提出されているとこ ろ,その作成時期及び記載内容は,上記契約書やKの供述と概ね合致して いる(例えば,工事請負契約書1及び3の工事請負代金についてみると, 工事請負契約書1の代金は,甲38記載の建物工事費にKの供述する計算 方法を適用したものと合致し,また,工事請負契約書3の代金も,同様の 計算方法を適用することにより,甲52の代金と概ね合致する。契約日に 近接する資金計画表は提出されていないが,これをもって本件において信\n用性が損なわれるものではない。また,工事請負契約3に係る地盤調査報 告書によれば,地盤改良工事は不要とされるところ,かかる地盤調査後に 作成された資金計画表(甲52)においても,なお地盤改良工事費用とし\nて7万9920円が計上されていることは,同書面における地盤改良工事 費用には,地盤調査の費用が含まれていることを裏付けるといえる。)。 注文者1及び3の陳述書(甲62,66)における陳述内容もこれに沿う ものである。
なお,これらの各書証にはマスキングされている箇所も存在するもの の,施工面積や敷地面積,把握できる建築場所等の記載を対照すると,各 資金計画表(甲30,31,33から35まで,38,43,45),各\n建築図面(甲29,32,36,37,40),保証書(甲64)が工事 請負契約1に関する書面であり,各資金計画表(甲51,52),保証書\n(甲69)及び地盤調査報告書(甲49)が工事請負契約3に関する書面 であると認められる。 以上によれば,少なくとも,工事請負契約1及び3に関する各工事請負 契約書(甲70,71),各資金計画表(甲30,31,33から35,\n38,43,45,51,52。以下,全てを指して「本件資金計画表」\nという。),各建築図面(甲29,32,36,37,40),各保証書 (甲64,69)及び地盤調査報告書(甲49)については,Kの供述又 は陳述(甲19,49,58)と相まってその信用性が認められる。ま た,注文者らの陳述書(甲62,66)についても,Kの供述及び陳述並 びに上記各書証と整合するものであるから,信用性が認められる。
(4) 被告の主張
ア 被告は,資金計画表や建築図面の注文者又は宛先がマスキングされてい\nることから証拠としての関連性がないと主張するが,工事請負契約1及び 3に関するマスキングされた各書証が,これらの契約に関する書面である と認められることは,前記(3)イで説示したとおりである。また,被告は, 写しが原本として提出されていることも問題とするが,写しであっても成 立の真正及び信用性が認められることは,前記(2)ア及び(3)イで説示したと おりである。
イ 被告は,資金計画表に書き込みがないことをもってねつ造であると主張\nするが,打ち合わせにおいて同表に書き込むことが打ち合わせの内容を記\n録する唯一の方法であるとはいえず,本件事情の下で,同表の信用性に疑\nいを抱かせるものではない。
ウ 被告は,原告が,当初,注文者の氏名等をマスキングしていたことをも って原告の提出する書証のねつ造を主張するが,注文者らと原告とは,K を介した希薄な関係しかないことに照らすと,原告が注文者らの個人情報 の開示を躊躇することも理解できる。本件においては,最終的に工事請負 契約1及び3についてマスキングを外した書証が提出され,各種公的書類 の記載等に照らし,各書証の成立の真正及び信用性が認められることは, 既に説示したとおりである。
エ 被告は,Kが要証期間に建築事務所として登録していなかったこと,K が建築工事中の看板に表示された標章についての供述を変遷させたこと,\nKが設計に関する供述を変遷させたことをもって,Kの本件審判手続の証 人尋問における供述及び陳述書の信用性を争う。しかしながら,Kは本件 審判手続において最初に提出した陳述書(甲19)の中で,当初から,設 計については一緒にやっている設計士がいること及び平成28年6月9日 になされた建築確認の申請の段階までは「アンドホーム」名で事業を行な\nっていたことを述べており,被告が指摘する証人尋問における供述の変遷 は,尋問におけるやりとりの中でそれを具体的に述べる際に,記憶の混乱 等が生じたものに過ぎないといえるから,Kの供述の信用性に疑いを生じ させるものとまではいえない。また,協力する設計士がいたことに照らす と,K自身が建築事務所として登録していなかったことは,Kが設計に関 与したとの供述の信用性に疑いを生じさせるものではない。
オ 被告は,原告提出の甲62から甲69の提出時期が遅いことなどをもっ て,提出の直前に作成されたものであるなどと主張する。書証の早期提出 が望ましいことはもちろんであるが,原告と注文者1及び3との関係が希 薄であることは前記のとおりであり,本件審決で本件商標が取り消された ことを受けて改めて協力を仰ぐなどしたとしても殊更に不合理であるとは 言い難い。なお,本件では,本件審判手続において提出されたKの陳述書 (甲19)においても言及されていた確認済証及びその付属書類一式が, 本件訴訟において甲59として原本で提出されて取り調べられており,そ の記載内容が,Kの供述の最も重要な部分を裏付けることは前記のとおり である。
カ 各書証の信用性を争うその他の主張も,信用性判断に関する上記認定を 左右するものではない。 したがって,各書証の信用性に関する被告の主張はいずれも採用でき ない。
(5) 以上の次第で,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら れる。
ア Kは,原告から本件商標の使用許諾を受け,平成28年1月頃から「ア ンドホーム」との名称を用いて,現場監督ができるもう一人の者ととも に,建築等の事業を開始した。(甲19,58)
イ Kは,平成28年4月7日,注文者1との間で,建物の建築工事を内容 とする工事請負契約1を締結し,同年9月20日頃,建物を完成させた。 かかる契約の締結の際,Kは,注文者1との間で,「アンドホーム」を請 負業者とする工事請負契約書1(請負代金額合計1302万3192円) を作成して,注文者1に交付した。(甲58,60,70)
ウ また,Kは,工事請負契約1に関して,土地を探すところから協力し, 少なくとも平成28年3月2日頃から同年5月14日頃にかけて,建物の デザインや設計についても注文者1と打ち合わせを複数回にわたって行 い,金銭面を含めて注文者1の要望を建築工事に反映させた。かかる打ち 合わせの際,Kは,「アンドホーム資金計画表」との標題が付された建築\n費用合計代金(3300万円台から3600万円台の金額である。)及び その内訳等を示す資金計画表(甲30,31,33から35,38,4\n3,45)や,建物の平面図や立面図が記載された建築図面を,打ち合わ せを踏まえた修正を加えつつ,複数回にわたり,注文者1に示すなどし た。 上記資金計画表のうち,作成日を平成28年3月23日以降とするもの\nについては,その右下に「◎土地契約時は土地手付け現金100万円+印 紙代…をご準備下さい。」,「◎建物契約時は建物手付け現金10万円+ 印紙代1万円…をご持参で当社にお越し下さい。」,「◎土地決済時に建 物着手金・上棟金として,1000万円を当社にお振り込み頂きま す。」,「◎最終の建物お引き渡し時に,残金を現金もしくはお振り込み 頂きます。」などと記載されている。 (甲29から38,40,43,45,58,62)
エ Kは,平成28年4月24日,注文者3との間で,建物の建築工事を内 容とする工事請負契約3を締結し,同年10月頃,建物を完成させた。か かる契約の締結の際,Kと注文者3は,「アンドホーム」を請負業者とす る工事請負契約書3(請負代金額合計1241万3270円)を作成して 注文者3に交付した。(甲56,58,71)
オ また,Kは,工事請負契約3に関し,ある程度土地が決まっている段階 で関与し始めて,少なくとも平成28年3月30日頃から同年5月29日 頃にかけて,建物のデザインや設計についても注文者3と打ち合わせを複 数回にわたって行い,金銭面を含めて注文者3の要望を建築工事に反映さ せた。 かかる打ち合わせの際,Kは,「アンドホーム資金計画表」との標題が\n付された建築費用合計代金(2600万円台から2700万円台の金額で ある。)及びその内訳等を示す資金計画表(甲51,52)や建築図面\nを,打ち合わせを踏まえた修正を加えつつ,複数回にわたり,注文者3に 示すなどした。 (甲51,52,56,58,66,71)
カ Kは,工事請負契約1及び3に関して,東昇技建に対し,地盤の調査を 依頼して,これを行わせた上で,その調査結果を注文者1及び3に説明し た。(甲19,50,58,62,64,66,69)
キ Kは,平成28年6月9日頃に株式会社シンプルハウスを設立し,「ア ンドホーム」との名称の使用をやめて,同月15日には工事契約1にかか る建築確認申請の工事施工者を,同社へと変更した。(甲19,58,5\n9,60)
2 取消事由2(Kによる本件商標の使用についての判断の誤り)について 原告は,Kが,前記1(5)カのとおり東昇技建に依頼して地盤の調査を行い, 同ウ及びオ記載の本件資金計画表を注文者1及び3に交付したことが商標法2\n条3項8号に該当し,「地質の調査」の役務について,本件商標を使用した (商標法50条2項)と主張するので,この点について検討する。
(1) まず,Kが,取消対象役務のひとつである「地質の調査」を提供したか否 かについてみると,Kは,前記1(5)カのとおり,工事請負契約1及び3に関 して,東昇技建に依頼して地盤調査を行うなどしている。 そして,前記1(5)イ及びエのとおり,Kは,「アンドホーム」の名称にて 工事請負契約1及び3を締結しているところ,これらの契約の前後に注文者 らに対して示した本件資金計画表において地盤改良工事費用の中に地盤調査\n費用が含まれており(前記1(3)イ参照),当該費用を含めた建築費用合計代 金の全額をKに支払うべきこととされて,現実に注文者らに対応したのは主 としてKであったことなどに照らすと,Kは,工事請負契約1及び3の締結 とともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものと 認められる。 そうすると,Kが東昇技建に依頼して行った地盤調査は,Kが注文者1及 び3から請け負った債務の履行としてされたものであるといえるから,Kが 「地質の調査」を提供したと認められる。
(2)次に,商標法2条3項8号の該当性についてみる。
本件では,Kが「地質の調査」の役務を提供することは,本件資金計画表\nの「地盤改良工事費用」「地盤調査の結果により工事費用が変動いたしま す。」などとの記載に表れており,本件資金計画表\は,上記役務に対応して 作成された見積書としての書面であるといえるから,上記役務に関する「取 引書類」に当たる。そうすると,前記1(5)ウ及びオのとおり,Kが,本件資 金計画表に,本件商標を付して,その作成日付頃(平成28年3月2日頃か\nら同年5月29日頃),それぞれ注文者1及び3に交付した行為は,商標法 2条3項8号所定の使用に該当する。
(3)これに対し,被告は,Kが本件商標を使用して工事請負契約1及び3を請 け負った後,実際に建築工事を開始した時点では,「シンプルハウス」へと 屋号を変更していたことなどをもって,取消対象役務を「アンドホーム」の 名称にて提供していないと主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,Kは,工事請負契約1及び3の締結と ともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものであ るところ,Kは,これらの契約に関して,平成28年3月2日頃から同年5 月29日頃にかけて,本件資金計画表を,注文者1及び3に交付しているか\nら,当該交付の時点で「アンドホーム」との標章に対する業務上の信用が発 生したといえる。その後,Kが,その事業について「シンプルハウス」との 名称に変更したとしても,かかる信用が,直ちに保護に値しなくなるもので はない。また,少なくとも工事請負契約3に係る地盤調査は,屋号変更前で ある同年5月25日に行われたことが明らかである。 したがって,Kは,「アンドホーム」との標章を取消対象役務のひとつで ある「地質の調査」について使用したといえる。
(4) また,被告は,Kによる本件商標の使用が名目的な使用であると主張す る。しかしながら,不使用取消に言及する被告から原告に対する連絡は平成 29年3月24日付けであって,Kが「アンドホーム」との標章を使用した 平成28年1月から同年6月頃までの期間よりも相当遅い時期であること (甲15)や,前記認定のKによる本件商標の使用態様に照らすと,Kによ る本件商標の使用が名目的な使用であるとまでは認められず,被告の主張は 採用できない。
(5)したがって,通常使用権者であるKが,要証期間内である平成28年3月 2日頃から同年5月29日頃にかけて,日本国内において,取消対象役務の ひとつである「地質の調査」について,本件商標を使用した(商標法50条 2項)と認められる。
◆判決本文
関連事件は下記です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2020.01.13
平成31(行ケ)10005 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
前記2(1)のとおり,引用文献1には,「近年,コンテンツマネジメントシステム (以下,CMS(Content Management System)という) によりウェブアプリケーションとして公開するコンテンツを構築し,管理すること\nが行われている(例えば,特許文献1参照)。ところで,近年,ネイティブアプリケ ーションをダウンロードしてインストールすることができるスマートフォンが普及 している。スマートフォンのユーザは,ネイティブアプリケーションをインストー ルする場合,アプリケーションを提供する所定のアプリケーションサーバにアクセ スし,所望のネイティブアプリケーションを検索する。しかしながら,CMSによ って構築されるウェブアプリケーションは,ウェブサイトとして構\築されるため, 検索サイトの検索結果として表示されることがあるものの,アプリケーションサー\nバから検索することができない。したがって,アプリケーションサーバにおいてネ イティブアプリケーションを検索したユーザに,CMSにより開発したウェブアプ リケーションを利用してもらうことができないという問題がある。これに対して, CMSによって構築したウェブアプリケーションと同等の機能\を有するネイティブ アプリケーションを開発し,当該ネイティブアプリケーションをアプリケーション サーバにアップロードすることも考えられる。しかしながら,ネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには,多大な開発工数が必要であった。本発明は,ネイ ティブアプリケーションを容易に生成することができるアプリケーション生成装置, アプリケーション生成システム及びアプリケーション生成方法を提供することを目 的とする。」(段落【0002】,【0004】〜【0007】)と記載されており,同記載からすると,引用発明は,CMSによって構築されるウェブアプリケーション\nは,アプリケーションサーバから検索することができないため,アプリケーション サーバにおいてネイティブアプリケーションを検索したユーザに,CMSにより開 発したウェブアプリケーションを利用してもらうことができないこと及びCMSに よって構築したウェブアプリケーションと同等の機能\を有するネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには,多大な開発工数が必要となることを課題とし,同 課題を解決するためのネイティブアプリケーションを生成する装置であることが認 められる。 引用発明は,上記課題を解決するために,前記(1)アで認定したとおり,既存のウ ェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアド レス等の情報を入力するだけで,当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更し\nて,同ウェブアプリケーションが表示する情報を表\示するネイティブアプリケーシ ョンを生成できるようにしたものと認められる。
イ 被告は,携帯通信端末の動きに伴う動作を行うネイティブアプリケーシ ョンを生成すること,特に,PhoneGapに係る技術が周知であると主張する。
(ア) 前記アのとおり,引用発明は,アプリケーションサーバにおいて検索で きるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題として,同課題を, 既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで,同ウェブア プリケーションが表示する情報を表\示できるネイティブアプリケーションを生成す ることができるようにすることによって解決したものであるから,ブログ等の携帯 通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表\示す るネイティブアプリケーションを生成しようとする場合,生成しようとするネイテ ィブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はな く,したがって,設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネ イティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はない。もっとも,引用文\n献1の段落【0024】には,ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられてお り,ゲームにおいては,加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないよう に制御する必要がある場合が考えられる(引用文献5参照)が,ウェブアプリケー ションとして提供されるゲームは,(1)常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要\nがあるとはいえないこと,(2)加速度センサにより,携帯通信端末の姿勢に対応した 画面回転表示を制御する機能\は携帯通信端末側に備わっており,端末側の操作によ って,表示画面を固定することができ,そのような操作は一般的に行われているこ\nと,(3)引用文献1の段落【0024】の「ゲームサイト」は,携帯通信端末の表示\n画面を固定する必要のないブログ,ファンサイト,ショッピングサイトと並んで記 載されており,また,引用文献1には,加速度センサについて何らの記載もないこ とからすると,当業者は,上記の「ゲームサイト」の記載から,パラメータを「携 帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必\n要性を認識するとまではいえないというべきである。 また,引用発明によって生成されるネイティブアプリケーションは,HTMLや JavaScriptで記述されるウェブページを表示できるから,引用発明によ\nり,乙4に記載されたHTML5 APIのGeolocationを用いて携帯 通信端末の動きに伴う動作を行うウェブアプリケーションの表示内容を表\示するネ イティブアプリケーションを生成しようとする場合も,生成されるネイティブアプ リケーションは,設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基 づいて,同ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し,取得したウ ェブページのHTMLやJavaScriptの記述に基づいて,同ウェブアプリ ケーションの内容を表示でき,したがって,ネイティブアプリケーションの生成に\n際して,設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ 機能を実行させるためのパラメータ」とする必要はない。\nさらに,被告主張周知技術に係る各種文献にも,引用発明の上記の構成の技術に\nおいて,「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に\n応じて設定ファイルを設定することの必要性等については何ら記載されていない (甲2〜5,7,8,乙1〜3)。
(イ) 前記アのとおり,引用発明は,簡易にネイティブアプリケーションを生 成することを課題として,既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入 力するだけで,当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表\示するネイティブ アプリケーションを生成できるようにしたのであり,具体的には,前記(1)アのとお り,入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び 表示態様に基づいて,テンプレートアプリケーション111に含まれる設定情報の\n内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表\示 できるネイティブアプリケーションを生成でき,テンプレートアプリケーション1 11に含まれるプログラムファイル113については,新たにソースコードを書く\n必要はないところ,証拠(甲3,5,7,乙1〜3)によると,PhoneGap によってネイティブアプリケーションを生成するためには,HTMLやJavaS cript等を用いてソースコード(プログラム)を書くなどする必要があるもの\nと認められるから,引用発明に,上記のように,新たにソースコードを書くなどの\n行為が要求されるPhoneGapに係る技術を適用することには阻害事由がある というべきである。
被告は,(1)PhoneGapでは,PhoneGapのプラグインの仕組みを使 って,GPSなど端末のネイティブ部分にアクセス可能であり,端末のGPS機能\ にアクセスすることで,GPSで取得した端末の現在位置が中心となるように地図 を表示することが可能\となるから,引用発明において地図表示アプリケーションを\n生成する際に,PhoneGapのフレームワークを採用することで,ネイティブ 機能であるGPS機能\が利用可能となり,携帯通信端末の動きに伴う動作を設定可\n能となり,また,(2)AndroidManifest.xmlに「android: screenOrientation =”landscape”」の1行を追加し たり(Androidの場合),「Landscape Right」又は「Lan dscape Left」のアイコンを選択すること(iOSの場合)で,スマー トフォンの画面を横画面に固定可能となり,縦画面に固定する設定を施す場合,A\nndroidManifest.xmlに「android:screenOri entation =”portrait”」の1行を追加したり(Android の場合),「portrait」のアイコンを選択すること(iOSの場合)で,ス マートフォンの画面を縦画面に固定可能となるから,引用発明において,アプリケ\nーションを生成する際に,PhoneGapのフレームワークを利用することで, 「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に応じて,\n携帯通信端末において実行される「アプリケーションの,携帯通信端末の動きに伴 う動作」を規定する設定ファイルを備えることとなると主張する。 しかし,上記のとおり,引用発明にPhoneGapの技術を適用することの動 機付けはないから,被告の上記主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。
(ウ) 以上からすると,引用発明に,被告主張周知技術を適用することの動機 付けは認められないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2020.01.11
令和1(行ケ)10104 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年12月26日 知的財産高等裁判所
ア 本願商標は,別紙のとおり,上段に,左向きの金色の牛の全身を表した\n図形を配し,当該図形部分の下方に,「EMPIRE」の黒色の欧文字と 「STEAK HOUSE」の黒色の欧文字を上下2段に横書きに書して なり,上下2段の文字部分の間に文字部分と幅を揃えた赤色の二重線を配 してなる結合商標である。 本願商標は,牛の図形部分,「EMPIRE」の文字部分及び「STE AK HOUSE」の文字部分の各構成部分が相互に一定の間隔を空けて,\n重なり合うことなく配置され,上記各文字部分の間に赤色の二重線が配さ れていることから,各構成部分は,それぞれが独立したものであるとの印\n象を与え,視覚上分離して認識されるものと認められる。
イ 「EMPIRE」の文字部分は,目につきやすい中央部に,「STEA K HOUSE」の文字部分よりも大きく表され,「EMPIRE」の文\n字部分の語頭及び語尾の「E」の文字は当該文字部分を囲って強調するよ うに他の文字よりも大きく表されていること,「EMPIRE」の文字部\n分の下に配された赤色の二重線は,「EMPIRE」の文字部分と「ST EAK HOUSE」の文字部分との区切り線のような印象を与えるとと もに,「EMPIRE」の文字部分を強調する下線のような印象をも与え ていることに鑑みると,本願商標の外観上,「EMPIRE」の文字部分 は,牛の図形部分及び「STEAK HOUSE」の文字部分よりも,強 く印象づける特徴を備えている。 そして,「EMPIRE」の文字部分に相応する「empire」の語 は,「帝国」の意味を有する基本的な英単語として知られており(新英和 中辞典(第7版),広辞苑(第七版),大辞林第三版(甲2)),本願商 標の構成中「EMPIRE」の文字部分から「エンパイア」の称呼が生じ\nる。
ウ(ア) 本願商標の構成中「STEAK HOUSE」の文字部分に相応す る「steakhouse」の語は,「ステーキ専門店」(ジーニアス 英和辞典第5版(乙2)),「ステーキハウス」(新英和中辞典(第7 版))の意味を有する英単語である。 証拠(乙3ないし25,30)によれば,(1)「レストランにおける飲 食物の提供」をする業界において,「STEAK HOUSE」又は「S TEAKHOUSE」(ステーキハウス)の語は,例えば,「WOLF GANG’S STEAKHOUSE」(ウルフギャング・ステーキハ ウス)(乙3),「BENJAMIN STEAK HOUSE」(ベ ンジャミンステーキハウス)(乙4),「MORTON’S THE S TEAKHOUSE」(モートンズ ザ ステーキハウス)(乙5), 「RUTH’S CHRIS STEAK HOUSE」(ルースクリ ス ステーキハウス)(乙6),「OUTBACK STEAKHOU SE」(アウトバックステーキハウス)(乙7),「JACK’S S TEAK HOUSE」(ジャッキーステーキハウス)(乙8),「L a Paysanne(ステーキハウス ラ・ペイザン)」(乙9), 「STEAK HOUSE ライおン」(乙10),「ステーキハウス 牛の松阪」(乙11),「STEAK HOUSE US・6(ステー キハウスUS・6)」(乙12),「Steak House JOY BULL」(ステーキハウス ジョイブル)(乙13),「ステーキハ ウス 柳鳳」(乙14)などのように,「ステーキ専門店」を表す語と\nして用いられ,上記各店舗は,例えば,「ウルフギャング」(乙15), 「ベンジャミン」(乙15),「モートンズ」(乙16),「ルースク リス」(乙17),「アウトバック」(乙18),「ジャッキー」(乙 19),「ラ・ペイザン」(乙20),「ライおン」(乙21),「牛 の松阪」(乙22),「US・6」(乙23),「ジョイブル」(乙2 4),「柳鳳」(乙25)などのように略称される場合があること,(2) 「日本標準産業分類」(総務省,平成25年10月改定,平成26年4 月1日施行。乙30)には,「ステーキハウス」は,「飲食サービス業」 の一業態の「7629 その他の専門料理店」として例示,分類されて いることが認められる。
上記認定事実によれば,我が国において,「STEAK HOUSE」 又は「STEAKHOUSE」(ステーキハウス)の語は,「ステーキ 専門店」を表す語として一般に用いられていること,上記語が「ステー\nキ専門店」の店名の一部に含まれる場合には,上記語を除いて,当該店 名が略称される場合があることも普通であることが認められる。 そうすると,「STEAK HOUSE」の語が本願の指定役務中「レ ストランにおける飲食物の提供」に使用される場合には,「レストラン」 の業態の一つである「ステーキ専門店」を表示する語として一般に認識\nされるものと認められるから,本願商標の構成中「STEAK HOU SE」の文字部分は,自他役務を識別する標識としての機能が微弱であ\nるというべきである。
(イ) これに対し原告は,(1)「STEAK HOUSE」の文字は,「ス テーキ専門店」の意味を有することは否定しないが,もともとは造語で あり,我が国では,ステーキの主流は鉄板焼きステーキであり,牛肉を グリル板や炉で焼くレストランの業態の一つの「ステーキハウス」は, 日本全国でも数えるほどしかなく,「STEAK HOUSE」の文字 は,ごく限られた店が使用しているにすぎない,(2)「STEAK HO USE」の文字を使用する場合であっても,ANAインターコンチネン タルホテル東京のレストラン「THE STEAKHOUSE/ ザ・ス テーキハウス」(甲26,27)のように,「THE」と結合して全体 として特定の店名を指標する造語の成分として使用されている,(3)世界 的に有名な米国のグルメガイド「ZAGAT」(2012年(平成24 年)ニューヨーク版。甲1)のステーキハウスカテゴリーにノミネート されている70のレストランの中で「STEAK HOUSE」の文字 を店名に含む店は原告の店舗「EMPIRE STEAK HOUSE」 のみであるなどとして,「STEAK HOUSE」の文字を役務「飲 食物の提供」の一業態を表すものとして一般に用いられているものとは\nいえない旨主張する。
しかしながら,上記(1)の点については,前記(ア)の認定事実に照らす と,「ステーキ専門店」において,「STEAK HOUSE」の文字 がごく限られた店が使用しているにすぎないということはできない。 また,上記(2)及び(3)の事実があるからといって,「STEAK HO USE」(ステーキハウス)の語が「ステーキ専門店」を表す語として\n我が国において一般に用いられていることを否定すべき理由にはならな い。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
エ 本願商標の構成中牛の図形部分は,別紙記載のとおり,本願商標の上段\nに位置し,下段の「EMPIRE」の文字部分及び「STEAK HOU SE」の文字部分が占める面積と同程度の面積を有し,その金色の色彩は 黒色の上記各文字部分とコントラストをなしている。 他方で,上記牛の図形部分から特定の象徴的な態様や特定のキャラクタ ―を看取できるとまではいえないこと,飲食店などの取引においては,提\n供される料理や食材などをモチーフにした図形を看板や広告などに表示す\nることは,一般的に採択されている手法であって,ステーキハウスを含む 牛肉などに関連した料理を提供する店舗においても,食材である牛の全身 又は一部をモチーフにした図形を用いることは,広く一般的に行われてい ること(乙31ないし40)に照らすと,本願商標に接した需要者は,上 記牛の図形部分は,「STEAK HOUSE」の文字部分と相まって「ス テーキハウス」(ステーキ専門店)で提供される食材の牛をモチーフにし た図形という印象を受けるものと認められる。 そうすると,本願商標の構成中牛の図形部分は,本願の指定役務中「レ\nストランにおける飲食物の提供」との関係においては,自他役務を識別す る標識としての機能が微弱であるというべきである。\n
オ 前記ア認定のとおり,本願商標中,牛の図形部分,「EMPIRE」の 文字部分及び「STEAK HOUSE」の文字部分の各構成部分は,外\n観上それぞれが独立したものであるとの印象を与え,視覚上分離して認識 されるものと認められるから,上記各構成部分を分離して観察することが\n取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認めら れない。 そして,前記イないしエ認定のとおり,本願商標の構成において,目に\nつきやすい中央部に配置された「EMPIRE」の文字部分は,牛の図形 部分及び「STEAK HOUSE」の文字部分よりも,外観上強く印象 づける特徴を備えており,「EMPIRE」の文字部分から「エンパイア」 の称呼及び「帝国」の観念が生じること,他方で,「STEAK HOU SE」の文字部分及び牛の図形部分は,本願の指定役務中「レストランに おける飲食物の提供」との関係においては,自他役務を識別する標識とし ての機能が微弱であることに鑑みると,本願商標は,「EMPIRE」の\n文字部分が,取引者及び需要者に対して上記役務の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えるものと認められるから,本願商標から「EMPI RE」の文字部分を要部として抽出し,これと引用商標とを比較して商標 そのものの類否を判断することは許されるというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(2) これに対し原告は,本願商標のうち,「EMPIRE」の文字部分及び「S TEAK HOUSE」の文字部分は,「EMPIRE STEAK HO USE」の全体をもって造語としての店名を構成して識別の用に供され,「帝\n国のステーキハウス」,「帝政(時代)のステーキハウス」という観念を生 じさせ,そこから高級な,並外れたステーキハウスであることがアピールさ れているから,本願商標から「EMPIRE」の文字部分を分離して観察す ることは不自然であることからすれば,本願商標から「EMPIRE」の文 字部分を要部として抽出することはできないから,「EMPIRE」の文字 部分と引用商標とを比較して,商標そのものの類否を判断することは許され ない旨主張する。 しかしながら,前記(1)ウ認定のとおり,我が国において,「STEAK HOUSE」又は「STEAKHOUSE」(ステーキハウス)の語は,「ス テーキ専門店」を表す語として一般に用いられていること,上記語が「ステ\nーキ専門店」の店名の一部に含まれる場合には,上記語を除いて,当該店名 が略称される場合があることも普通であることに照らすと,本願商標のうち, 「EMPIRE」の文字部分及び「STEAK HOUSE」の文字部分は, 「EMPIRE STEAK HOUSE」の全体をもって造語としての店 名を構成して識別の用に供されているものと認めることはできないから,原\n告の上記主張は,その前提において理由がない。
2 本願商標と引用商標の類否判断の誤りについて
(1) 前記(1)の認定事実を前提に,本願商標の要部である「EMPIRE」の 文字部分と引用商標を対比すると,引用商標は,「EMPIRE」の標準文 字からなるのに対し,本願商標の「EMPIRE」の文字部分は,語頭及び 語尾の「E」の文字は当該文字部分を囲って強調するように他の文字よりも 大きく表されている点において,両者の外観は,同一とはいえないが,紛ら\nわしいものといえること,本願商標の「EMPIRE」の文字部分と引用商 標は,「エンパイア」の称呼及び「帝国」の観念が生じる点において,称呼 及び観念が同一であること,「STEAK HOUSE」の文字部分及び牛 の図形部分は,本願の指定役務中「レストランにおける飲食物の提供」との 関係においては,自他役務を識別する標識としての機能が微弱であることに\n鑑みると,本願商標全体の外観と引用商標の外観が相違することを考慮して も,両商標が上記役務と同一又は類似の役務に使用された場合には,その役 務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものと認められるから,両 商標は全体として類似しているものと認められる。したがって,本願商標は,引用商標と類似する商標である。
(2) これに対し原告は,(1)原告の店舗「EMPIRE STEAK HOU SE」は,2010年(平成22年)に米国のニューヨークで創業された著 名なレストランであり,引用商標の登録出願当時,ニューヨークで2店舗を 営業し,年間売上げ800万米ドルを計上し,例えば,ウォールストリート ジャーナル,ニューヨークポスト,abcニュース,CBSニューヨークな どの著名メデイアに取り上げられて確固たる知名度を獲得し,終始一貫して その文字の全体「EMPIRE STEAK HOUSE」をもって識別さ れており,決して「EMPIRE」として識別されていないこと,(2)原告が 平成29年10月17日に東京都六本木に開店した店舗「EMPIRE S TEAK HOUSE」は,大変な注目を浴びて各種のインターネット記事 (甲7ないし21)で取り上げられ,上記記事では,「EMPIRE」ある いは「エンパイア」と呼ばれることは一切なく,「EMPIRE STEA K HOUSE」あるいは「エンパイアステーキハウス」と呼ばれており, また,上記店舗は,「客単価」1万円を越える敷居の高い高級店であり,客 は,飛び込みで来店することはなく,事前に店舗のことを調べ予約してから\n来店することなどの取引の実情の下においては,上記店舗の店名を「EMP IRE」あるいは「エンパイア」と誤解することは皆無であるという取引の 実情があることを考慮すると,本願商標と引用商標は,同一又は類似の役務 に使用された場合に,当該役務の出所について混同が生じるおそれはない旨 主張する。
しかしながら,上記(1)の点は,米国所在の原告の店舗に関する事情を述べ るものであり,我が国における取引の実情を反映したものとはいえない。 次に,上記(2)の点については,原告が挙げるインターネットの記事(甲7 ないし21)では,「NY人気ステーキハウス上陸 「エンパイアステーキ ハウス」の実力」(「日経トレンディネット」のホームページ。甲7),「N Yの高級ステーキ「エンパイア ステーキ ハウス」が日本初上陸! 今秋、 六本木にオープン」(「asoview! NEWS」のホームページ。甲 9)などのように,原告の六本木の店舗「EMPIRE STEAK HO USE」が「エンパイアステーキハウス」として紹介されていることが認め られるが,上記記事は,本願商標を直接引用して紹介したものではないから, 本願商標に接した需要者,取引者に対し与える印象等と直接結びつくものと はいえない。
加えて,「NY発『東京ステーキ戦争』 人気店が続々出店,熟成肉が売 り」の見出しの下,「昨年には『ベンジャミン』と『エンパイア』が相次ぎ 六本木に出店した。」(2018年9月1日付けの「FujiSankei Business i.」。乙26),「ステーキ激戦区,六本木,熱々, 本場NY発VS.日本発,家族・友達とわいわい,気分はマンハッタン。」 の見出しの下,「六本木通りを挟んで反対側には10月,『エンパイア ス テーキ ハウス』が上陸する。…マンハッタンのエンパイアを訪れたことが あるNY在住の…」(2017年9月18日付け「日経MJ(流通新聞)。 乙27),「六本木ステーキ戦線に異状あり!NY発『エンパイア』上陸で 混戦模様に」(2017年9月5日付け)の見出しの下,「エンパイアは, ジャック,ジェフ,ラスのシナナジ兄弟が2010年に立ち上げたステーキ ハウス。」,「エンパイアが提供する価値とは…店のコンセプトは,ずばり 『NYにあるエンパイアの再現』であり,『本場のNYスタイルを楽しんで 欲しい』とのこと。」(「マイナビニュース」のウェブサイト。乙28), 「六本木が『ステーキの街』に大変身した必然」(2017年10月29日 付け)の見出しの下,「六本木,芋洗坂の中腹に10月17日に開業した『エ ンパイアステーキハウス六本木』」,「エンパイアは今回,初めてとなる海 外進出先に六本木を選んだ。」,「ウルフギャングの後に続くのは冒頭のエ ンパイアだけではない。」(「東洋経済ONLINE」のウェブサイト。乙 29)などと記載したインターネットの記事のように,原告の六本木の店舗 は,「エンパイア」と略称で表示される例も見受けられる。\nしたがって,上記(1)及び(2)の点は,本願商標と引用商標が同一又は類似の 役務に使用された場合に,当該役務の出所について混同が生じるおそれはな いことを基礎付ける取引の実情に当たるものと認めることはできないから, 原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.01.11
平成30(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月26日 知的財産高等裁判所
原告は,本件審決が認定した本件発明2と甲5発明との相違点Aのうち, 甲5には,「頂部に設けられた横線シールは,前面パネルよりも裏面パネルに 近い側に位置し,かつ,裏面パネル側に倒され」る構成が開示されており,こ\nの構成に係る部分は相違点ではなく,一致点であるから,本件審決の上記認\n定は誤りである旨主張するので,以下において判断する。
ア 前記(1)の甲5の記載事項によれば,甲5には,「前面,裏面,側面,上 面及び底面を有し,上面が前面に向けて傾けられており,縦シール部分は 前面に設けられ,横シール部分が上面に設けられて裏面側に倒され,厚紙 の成形による折り込み片が上面上に折り畳まれている,厚紙の折り畳み式 包装容器」(甲5発明)が記載されていることが認められる。 また,甲5の「図1〜図4に示された包装容器1は,それ自体公知のよう に底と側壁と上壁領域とを有する被覆2からなる。包装容器は,上面が傾 けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器の形態で示されている。この 包装容器は,上面の領域に開口領域3を有している。」(5頁4行〜8行, 訳文5頁10行〜13行)との記載から,甲5の図1及び図4記載の包装 容器1は,「上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」である ことを理解できる。 そして,甲5の図1及び図4(別紙甲5図面参照)から,図4において左 右の三角形の折り込み片の頂点の上側に描かれている2個の小さな三角形 (別紙3−1の図4の拡大図参照)は,「横シール部分」を示したものと 認められる。
もっとも,甲5の図4には,2個の小さな三角形の間には「横シール部 分」は図示されていないが,一方で,(1)図4記載の包装容器1は,「上面が 傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」であること,(2)本件優先 日当時(本件優先日平成12年7月31日),紙製包装容器において,横線 シールを横方向に横断的に設け,横線シールをする際に対向するシール領 域同士が同じ長さとなるような構造とすることは,技術常識であったこと\n(前記(2)イ),(3)甲5の記載によれば,甲5の包装容器は,「蓋要素によ り再閉鎖可能な開口を備え,該開口は,最初の充填後に初めて開放する前\nには,前記開口を取り囲む前記被覆材料と少なくとも接続された実質的に 平たい封印要素によって閉鎖されている包装容器」に関する考案(実用新 案登録請求の範囲の請求項1ないし14)であり,「横シール部分」は,請 求項1ないし14の考案特定事項とされていないから,図4において「横 シール部分」の図示が省略されたとしても不自然ではないことに照らすな らば,甲5の図4の2個の小さな三角形の間の下側には,横方向に横断的 に設けられた「横シール部分」が存在するが,その描写が省略されていると 理解できる。
加えて,甲5発明のように片流れ屋根形状(「前面」の高さが「裏面」の 高さよりも低い形状のもの)であって,「横シール部分」が横方向に横断的 に形成されている場合には,横線シールをする際に形成される折り込み片 (フラップ)において対向するシールが同じ長さとなるので(例えば,別紙 3−2の展開図中の「横線シール位置」との記載の直下の青色の点の両側 のシール部分(「30」及び「30」の記載に対応する部分)参照),設計 上,必ず「横シール部分」は後方寄り(「裏面」に近い位置)に位置するこ とになるものと認められることに照らすと,甲5には,甲5発明において 相違点Aに係る本件発明2の構成のうち,「頂部に設けられた横線シール\nは,前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し,かつ,裏面パネル側に 倒され」る構成を備えていることが開示されているものと認められる。\nしたがって,相違点Aのうち,上記構成は,相違点ではなく,一致点であ\nるから,本件審決の相違点Aの認定には誤りがある。
イ これに対し被告は,別紙4のとおり,「横線シール」が前方寄りに位置す る「片流れ屋根形状」の容器の例が多数存在することからすると,「片流れ 屋根形状」であれば,設計上,必ず横線シールが後方寄りに位置することに なるものとはいえないから,甲5において,甲5発明の「横シール部分」が 「前面」よりも「裏面」に近い側に位置していることの開示があるものとは いえない旨主張する。
そこで検討するに,前記ア認定のとおり,甲5の図4記載の包装容器1 は「上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」であることに 照らすと,甲5発明の上面(「頂部」)の形状は,本件優先日当時の折り畳 み式包装容器の一般的な形状のものと理解するのが自然である。 しかるところ,別紙4の説明資料1の展開図により紙製包装容器を製造 するには,折り目線に沿って折り畳むに際して,水色の部分を内側に折り 込む工程がさらに必要となるものであり,甲5の記載を全体としてみても, 甲5記載の包装容器1において,このような展開図をあえて選択する必要 性は認められない。また,本件優先日当時,説明資料1に係る紙製包装容器 の形態が公知であったものと認めるに足りる証拠はない。 同様に,説明資料2の展開図により紙製包装容器を製造するには,折り 目線に沿って折り畳むに際して,折目線に沿って折り畳むに際して,紫色 の部分を外側に折り込む工程がさらに必要となるものであって,甲5の記 載を全体としてみても,甲5記載の包装容器1において,このような展開 図をあえて選択する必要性は認められない。また,本件優先日当時,説明資 料2に係る紙製包装容器の形態が公知であったものと認めるに足りる証拠 はない。
次に,説明資料3ないし5の展開図は,通常の長方形の形状の展開図と 比べ,複雑な形状の展開図である上,説明資料3ないし5の展開図により 紙製包装容器を製造するには,側面パネル上の三角形で示される折り込み 片を液体充填物が漏れないように接着するための工程がさらに必要となる ものであり,甲5の記載を全体としてみても,甲5記載の包装容器1にお いて,このような展開図をあえて選択する必要性は認められない。また,本 件優先日当時,説明資料3ないし5に係る紙製包装容器の形態が公知であ ったものと認めるに足りる証拠はない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
(4) 相違点Aの容易想到性の判断の誤りについて
本件審決は,相違点Aについて,(1)甲5発明の上面の横シール部分は,裏面 側に倒されているものの,前面よりも裏面側に位置するものではないし,甲 5の記載においても,展開図等で上面の横シール部分が裏面側に近い側に位 置することを示唆する記載はなく,しかも,「折り込み片」を上面に折り畳む ものであり,容器の裏面側の2隅を補強することについての記載もない,(2) 本件発明2は,片流れ屋根形状の頂部から「頂部成形による折り込み片が側 面パネル上に斜めに折り込まれ」るだけではなく,「頂部に設けられた横線シ ールは,前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し,かつ,裏面パネル側 に倒され」という構成を合わせて備えることにより,裏面パネル側に倒され\nた「横線シール」を,容器頂部の背面側の2隅若しくはその近傍に対して近接 させて補強するものであり,単に,甲5発明において横線シールを側面側に 折り込むことのみで,本件発明2の構成に到達できるというものではないな\nどとして,本件発明2の相違点Aに係る構成は,当業者が容易に想到するこ\nとができたものではない旨判断した。 しかしながら,前記(3)認定のとおり,甲5には,甲5発明において,相違 点Aのうち,「頂部に設けられた横線シールは,前面パネルよりも裏面パネル に近い側に位置し,かつ,裏面パネル側に倒され」る構成を備えていることが\n開示されているものと認められるから,上記構成に係る部分は,相違点では\nなく,一致点であるから,本件審決の上記判断には,その前提において誤りが ある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
平成31(行ウ)162 特許料納付書却下処分取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月23日 東京地方裁判所
原告は,本件特許権に係る特許料の納付期限を管理していたファイザー社の 担当者において,本件訂正時特許証の「登録日」欄の日付である平成25年9月3 0日が本件設定時特許証の「登録日」欄の日付である平成24年3月16日と異な っていたことから,特許料の納付期限の起算日となる本件特許権の設定登録日が本 件訂正時特許証のとおり訂正されたものと誤解し,本件期間徒過が生じたとし,(1) 特許料等に関する法107条ないし112条の3の各規定によって,訂正をすべき 旨の審決が確定しても設定登録日が変わらないことや特許証に複数の種類があるこ とを認識することはできないこと,(2)本件設定時特許証及び本件訂正時特許証には 「登録日」としか記載されていないため,どちらが本件特許権の設定登録日である か不明確であり,米国や欧州の実務と比べても,我が国の特許証の記載は紛らわし いものであること,(3)特許証の大半は設定登録時に発行されるものであるから,フ ァイザー社において,訂正すべき旨の審決が確定したときに発行される特許証が存 在することを当然に把握しておくべきであったとはいえないことなどに照らし,原 告には,本件期間徒過について法112条の2第1項所定の「正当な理由」が認め られる旨主張する。
(2) 本件特許権に係る特許料の納付期限を管理していた担当者は,原告の主張が 本件回復理由書及び本件審査請求書における主張(甲6,10)から変遷し,判然 としないが,ファイザー社の担当者において,前記のような誤解をしていたと認め られたとしても,以下のとおり,本件期間徒過について,原告が原特許権者として, 相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて追納期間内に特許料等を 納付することができなかったときに当たると認めることはできない。 ア すなわち,原告は,日本の特許権を保有していたのであるから,特許料の納 付等の管理を行うに当たり,一般に求められる相当な注意として,日本の特許法及 びその他の関係法令を理解しておくべきであるといえるところ,(1)特許料の納付期 限については,法107条,108条において,特許権の設定登録日から起算され ることが規定されており,訂正をすべき旨の審決が確定してその登録がされた場合 に特許権の設定登録日が変更される旨の規定は存在しないから,本件特許権につい て,本件審決が確定してその登録がされたからといって,特許権の設定登録日が変 更されないことは条文上明らかであること,(2)特許証の交付についても,法28条 1項において,特許権の設定の登録があったときに交付されることのほかに,訂正 をすべき旨の審決が確定した場合にその登録があったときなどにも交付されること が規定されていることなどからすると,担当者において,これらの規定を理解して いれば,本件訂正時特許証に「登録日」として「平成25年9月30日」と記載さ れていても,本件訂正時特許証に「この発明は,訂正をすべき旨の審決が確定し, 特許原簿に登録されたことを証する。」と記載されていることをも踏まえれば,上 記の「登録日」が本件審決の確定等に係る登録日を記載したものであり,特許料の 納付期限の起算日となる特許権の設定登録日が変更されたものではないと理解する ことは可能であったと認められる。\n
イ 本件訂正時特許証及び本件設定時特許証の「登録日」欄記載の年月日には1 年半ものずれがあり,特許権の設定登録日が訂正されたと考えることに疑念を生じ させるものであったといえるところ,特許権の設定登録日は,ウェブサイトに公開 されている特許情報や特許登録原簿等によっても確認することができるから,担当 者において,上記疑念を抱いて,相当な注意を尽くしてそのような確認をしていれ ば,本件特許権の設定登録日が変更されていないことを認識することは容易であっ たというべきである。
ウ 本件全証拠によっても,担当者において,本件訂正時特許証の「登録日」欄 の記載を上記アのように理解すること又は上記イのような確認をすることが困難で あったことをうかがわせる事情は認められない。
(3) したがって,本件期間徒過について法112条の2第1項所定の「正当な理 由」は認められない。
3 小括
以上によれば,本件納付書による特許料等の納付のうち,第4年分の特許料等に 係る部分について,本件期間徒過について法112条の2第1項所定の「正当な理 由」があるとはいえないとし,第5年分の特許料等及び第6年分の特許料に係る部 分について,第4年分の特許料等の追納が認められないために本件特許権は消滅し ているとして,本件納付書による追納手続を却下した本件却下処分が違法であると はいえない。
2020.01. 8
平成30(行ケ)10161 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月2日 知的財産高等裁判所
原告は,引用例から,「待機状態」から「操作可能状態」に遷移することは観念で\nきず,遷移を実行するための構成の開示もないから,本願発明に係る「遷移手段」を\n認定することはできないと主張する。 そこで判断するに,本願明細書の【0045】の記載によれば,本願発明の「待機 状態」とは,「例えば電源ケーブルを介して通電されているが,操作ができる状態と はなっていない場合」,又は,「利用者によりベッド動作の制限が行われている状態」 であると解される。 そして,引用発明の「キー6aが解放されず押し続けられている場合は,解放さ れるまで待機し,リモコン6のキー6aが解放され,さらに任意のキー6aを押し たときに,アクチュエータ4を起動する(STEP3)」構成によれば,電源を投入\nした後,STEP2で「キー6aが解放され」るまでの間は,本願発明の「待機状 態」に相当するということができる。 引用発明は,「キー6aが解放され」た後に,任意のキー6aを押せばアクチュエ ータ4を起動できる状態,すなわち,ベッドの操作が可能な状態になるから,キー\n6aの解放の前後で,「待機状態」から「操作可能状態」に遷移するということがで\nきる。また,本願発明の「遷移手段」は,「待機状態」から「操作可能状態」に遷移\nすることを手段として記載したものということができる。 したがって,引用発明が,キー6aの解放の前後で,「待機状態」から「操作可能\n状態」に遷移しているということができ,引用発明のリモコン6は,「遷移手段」に 相当する構成も当然に備えている。\n以上によれば,引用例には,本願発明における「待機状態から,操作可能状態に遷\n移させる遷移手段」の開示があることになるので,引用例から本願発明の「遷移手 段」を認定することができる。これと異なる旨をいう原告の主張は理由がない。
オ 構成要件B(待機状態)について\n
(ア) 引用発明の「リモコン6」が,「電源を投入した後」,STEP1及び2を経 て,「リモコン6のキー6aが解放され」るまでの間は,「アクチュエータ4を起動 する」ことができない状態であることは,本願発明の「ベッド操作装置は,通電され ると待機状態とな」ることに相当する。
(イ) 本願発明との対比判断の誤りをいう原告の主張について
原告は,引用例には本願発明の「待機状態」の開示がないと主張する。 しかしながら,本願発明の「待機状態」とは,前記エ(ウ)で説示したとおり,「例 えば電源ケーブルを介して通電されているが,操作ができる状態とはなっていない 場合」,又は,「利用者によりベッド動作の制限が行われている状態」であると解さ れる。これまでに説示したとおり,本件審決の引用発明の認定には誤りがないと認 められるところ,引用発明の「キー6aが解放されず押し続けられている場合は, 解放されるまで待機し,リモコン6のキー6aが解放され,さらに任意のキー6a を押したときに,アクチュエータ4を起動する(STEP3)」構成によれば,電源\nを投入した後,STEP2で「キー6aが解放され」,その後「さらに任意のキー6 aを押」すまでの間は,アクチュエータ4の動作を行うことができない。このよう に,電源を投入した後,STEP2で「キー6aが解放され」るまでの間は,アクチ ュエータ4の操作ができる状態にないのであるから,この間,リモコン6は「待機 状態」にあるということができる。 したがって,引用例には,本願発明における「待機状態」の開示があるものと認め られ,これと異なる旨をいう原告の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
平成30(行ケ)10108 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月2日 知的財産高等裁判所
イ 引用発明への甲2技術の適用
しかしながら,仮に引用発明に甲2技術を適用しても,甲2には,前記有機系廃 棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はないから,\n相違点2’に係る「前記重金属類が閉じ込められた 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶(トバモ ライト)構造」が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されると\nの構成には至らない。\nこの点につき,本件審決は,引用発明に甲2技術が適用されれば,「前記重金属類 が閉じ込められた 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶(トバモライト)構造」が「前記有機系廃\n棄物の固形物上に」いくらかでも「層」として「形成」されて,重金属の溶出抑制を 図ることができるものになる旨判断し,被告は,生成した造粒物の表面全体をトバ\nモライト結晶層で覆うことになるのは当業者が十分に予\測し得ると主張する。しか しながら,特開2002−320952号公報(甲8)にトバモライト生成によっ て汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても(【0028】,図1。図1\nは別紙甲8図面目録のとおり。),かかる記載のみをもって,トバモライト構造が「前\n記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されることが周知技術であった とは認められず,被告の主張を裏付ける証拠はないから,引用発明1に甲2技術を 適用して相違点2’に係る本願発明の構成に至るということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
平成30(ワ)32519等 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月30日 東京地方裁判所
原告は,被告グーグルが本件発信者情報2−2を保有している旨主張する。 しかしながら,被告グーグルは,原告の上記主張を否認しており,他に被告グー グルが本件発信者情報2−2を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はな い。 この点,証拠(甲6,7,乙5〜8)及び弁論の全趣旨によれば,本件サイトへ の動画投稿により広告収入を得ようとする利用者は,支払を受ける住所を登録して Google AdSenseアカウントを開設する必要があり,同アカウントの 中には被告グーグルが管理するものがあるが,同アカウントは,本件サイトへの動 画投稿の際に登録が必要となるアカウントとは独立した異なるものであることが認 められる。そうすると,本件各投稿者が本件各動画の投稿により広告収入を得る目 的でGoogle AdSenseアカウントへの登録をし,その結果,被告グー グルが本件各投稿者に係る支払先住所に係る情報を管理していたとしても,同情報 は,本件各動画の投稿に用いられた各アカウントを登録するために用いられたもの には該当しないから,被告グーグルが本件発信者情報2-2を保有しているというこ とはできない。 よって,原告の主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
令和1(行ケ)10101 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年12月19日 知的財産高等裁判所
前記(1)アないしウの認定事実を総合すると,(1)南三陸町飲食店組合の組 合員であるホテル及び飲食店6店舗(原告及び被告を含む。)は,平成2 1年12月から「南三陸キラキラいくら丼」の標章を使用し,イクラを中 心の食材とした南三陸産の具材を含む丼物の提供を開始した後,南三陸キ ラキラ丼シリーズ第2弾として「南三陸キラキラ春つげ丼」の標章を使用 し,春が旬の地元の魚介類や野菜を中心の食材とした丼物の提供を,南三 陸キラキラ丼シリーズ第3弾として「南三陸キラキラうに丼」の標章を使 用し,ウニを中心の食材とした南三陸産の具材を含む丼物の提供を,南三 陸キラキラ丼シリーズ第4弾として「南三陸キラキラ秋旨丼」の標章を使 用し,地元の魚介類と米を中心の食材とした丼物の提供を,提供店を網羅 した共通のパンフレットを作成したり,共同で試食会を行うなど共同で 広告宣伝をしながら,順次行うことによって,南三陸産の具材を含む丼物 の提供を南三陸キラキラ丼シリーズとして観光キャンペーン化し,同月か ら平成22年12月末までの約1年間で合計約4万5000食を売り上 げ,この間提供店は,6店舗から8店舗に増加したが,いずれも南三陸町 飲食店組合の組合員であったこと,(2)提供店は,共通の問合せ先を南三陸 町観光協会内の「南三陸時間旅行サポートセンター」とするなど南三陸町 観光協会から支援を受けながら,南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペー ン活動を行い,そのキャンペーン活動は,南三陸町のウェブサイト,南三 陸町観光協会作成のパンフレット,「宮城・仙台」の観光キャンペーン のガイドブック等に掲載され,新聞等の報道や旅行雑誌等による広告宣 伝が行われ,その報道等の中には,南三陸町飲食店組合の取組として紹介 されているものが見られたこと,(3)平成23年3月11日の東日本大震災 により,南三陸町は被災し,南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活 動は一時中断したが,平成24年2月25日の仮設商店街のオープンに合 わせて,南三陸町飲食店組合の組合員である同仮設商店街で営業を再開し た店舗及び「南三陸ホテル観洋」など9店舗で,「復活 南三陸キラキラ 丼」と称して,南三陸産の具材を含む丼物の提供を行うようになり,その キャンペーン活動が震災によって大きな被害を受けたと広く知られていた 南三陸地域の復興と関連付けて,新聞やテレビ放送等により報道されたこ とが認められる。
上記認定事実によれば,本件商標の登録出願時(平成24年11月29 日)までに,南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動及びその報道, 広告宣伝等により,南三陸キラキラ丼シリーズの丼物は南三陸産の具材を 含む丼物として知名度が高まり,南三陸キラキラ丼の標章は,本件商標の 登録出願時には,少なくとも宮城県及びその近隣県において,南三陸町飲 食店組合の組合員の取扱いに係る丼物の提供を表示するものとして,需要\n者の間に広く認識されていたことが認められる。 そして,南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動は,当初は南三 陸町飲食店組合の組合員の有志の団体による取組として始まったが,南三 陸町観光協会から支援を受けて進められ,南三陸キラキラ丼シリーズの丼 物の提供店は震災の前後を通じていずれも南三陸町飲食店組合の組合員で あったことなどから,次第に,南三陸町飲食店組合の取組として受け止め られるようになり,遅くとも本件商標の登録出願時には,南三陸町飲食店 組合は,南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動を組合の事業活動 として位置づけていたものと認められるから,本件商標の登録出願時点に おける「南三陸キラキラ丼」の標章の使用主体は,南三陸町飲食店組合で あったものと認めるのが相当である。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ(ア) これに対し原告は,「南三陸キラキラ丼」の標章は,「原告の発案 したキャンペーンに賛同して参加した南三陸町内のホテルや飲食店の集 まり」によって使用された結果,本件商標の登録出願時には,少なくと も宮城県及びその近隣県において,上記南三陸町内のホテルや飲食店の 集まりの取扱いに係る丼物の提供を表すものとして周知性を獲得したも\nのであるから,上記南三陸町内のホテルや飲食店の集まりが,本件商標 の登録出願時点における「南三陸キラキラ丼」の標章の使用主体である 旨主張する。
そこで検討するに,原告の経営する「南三陸ホテル観洋」が平成21 年11月から,「南三陸キラキラいくら丼と鮑踊り焼プラン」という名 称の一泊二食付き宿泊プランの提供を開始した後に,原告を含む南三陸 町飲食店組合の組合員である6店舗が同年12月から「南三陸キラキラ いくら丼」の提供を開始したこと(前記(1)イ(ア)),原告は,その頃か ら本件商標の登録出願時まで,原告が運営する「南三陸ホテル観洋」の ウェブサイト等で「南三陸キラキラ丼」シリーズのキャンペーン等に関 する広告宣伝を行ってきたこと(甲2,8,9,16,22の1ないし 3,23の1ないし19,25の1ないし5),2010年(平成22 年)5月16日付けの三陸新報(甲7)に,「好評「キラキラ丼シリー ズ」南三陸町」の見出しの下に,「南三陸町飲食店組合の有志が地域産 食材を使って提供している「南三陸キラキラ丼シリーズが好評だ。…テ レビ局の取材も相次いでおり,“日本一の丼のまち”を目指す取り組み がこれからのまちづくりにどう生かされるのか。地域活性化の鍵を握っ ている。」,「「キラキラ丼」シリーズの“火付け役”となったのは, 南三陸ホテル観洋の女将・Aさん。」などと記載した記事が掲載された ことからすると,南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動の立ち 上げ当初には,原告の積極的な関与があったことがうかがわれる。 しかしながら,これらの事実から直ちに「南三陸キラキラ丼」の標章 が本件商標の登録出願時において需要者の間で「原告の発案したキャン ペーンに賛同して参加した南三陸町内のホテルや飲食店の集まり」の 取扱いに係る丼物の提供を表すものとして広く認識されていたものと\n認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) また,原告は,関連訴訟判決が「南三陸キラキラ丼」の標章(「引 用商標2」)の使用主体として認定した「南三陸町地域を中心とする 飲食店の団体」には,「南三陸町飲食店組合」だけでなく,「南三陸 町観光協会」,「南三陸商工会」,「南三陸志津川復興名店運営組合」 等の複数の団体が存在するから,「南三陸町飲食店組合」が使用主体で あるとした本件審決の判断は,確定した関連訴訟判決とも矛盾・抵触す るものであって,誤りである旨主張する。 しかしながら,関連訴訟判決は,「南三陸キラキラ丼」の標章を用い た使用主体を,その時期に応じて,第一段階から第三段階に分けて検討 し,そのいずれについても,同一の団体が使用主体である旨を認定した ものであるが,原告が主張する複数の団体のうち,「飲食店」の団体は, 南三陸町飲食店組合のみである。 加えて,前記ア認定のとおり,南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペ ーン活動は,当初は南三陸町飲食店組合の組合員の有志の団体による取 組として始まったものが,そのキャンペーン活動が進められる中で,次 第に,南三陸町飲食店組合の取組として受け止められるようになり,遅 くとも本件商標の登録出願時には,南三陸町飲食店組合は,南三陸キラ キラ丼シリーズのキャンペーン活動を組合の事業活動として位置づけて いたものと認められるから,関連訴訟判決がいう「南三陸町地域を中心 とする飲食店の団体」は,本件商標の登録出願時点においては,南三陸 町飲食店組合を指すものとみても不合理ではない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3) 被告と南三陸町飲食店組合を同一人として取り扱うのが相当であるとし た判断の誤りについて
ア 前記(1)ア(イ)及びウの認定事実によれば,南三陸町飲食店組合は,南三 陸町の地域に住所を有し,料理店,その他飲食店の許可を受けた者を組合 員とし,組合員相互の信頼と親睦の上に経営の安定,公衆衛生の向上に努 め職域を通じて社会に奉仕することを目的とする組合であって,法人格を 有していないが,団体としての組織を備え,多数決の原則が行われ,構成\n員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,代表の方法,総会の運営,\n財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものと認められる から,権利能力のない社団(権利能\力なき社団)であることが認められる。 そして,前記(1)ウ及びエ(ウ)の認定事実によれば,(1)平成24年10月 26日開催の南三陸町飲食店組合の執行部会議において,南三陸町飲食店 組合が「南三陸キラキラ丼」の標章の商標登録を受けることの提案に関し, 南三陸商工会及び宮城県商工会連合会を通じて紹介を受けた宮城県発明協 会の担当者から,南三陸町飲食店組合は任意団体であるため,商標登録出 願は代表者個人で行うこと,出願及び登録費用などについての説明を受け,\nさらに,同年11月13日の会議において,上記担当者から,商標登録制 度の概要等について説明を受けるなどした後,同月16日の会議において, 当時の組合長であった被告個人名義で本件商標の商標登録出願を行うこと が決められたこと,(2)被告は,同月29日,本件商標の商標登録出願をし, 平成25年5月2日,その商標登録を受けたが,その商標登録出願に際し, 本件商標が南三陸町飲食店組合の業務に係る商品又は役務に使用すること を証明するための書類として被告と南三陸町飲食店組合との関係等を示し た被告作成の上申書(甲32の2)及び南三陸商工会E会長作成の平成2\n4年11月28日付けの「南三陸町飲食店組合「南三陸キラキラ丼」の取 組と経緯について(ご説明)」と題する書面(甲32の3)を提出したこ と,(3)平成25年5月17日開催の南三陸町飲食店組合の平成25年度通 常総会において,「南三陸キラキラ丼」について本件商標の商標登録が完 了したことなどの事業報告が行われ,承認されるとともに,「商標登録の 仕様基準」の作成に伴う規約の一部改正の承認の件が議案として提出され, 規約の一部改正について承認された後,同年6月4日に開催された南三陸 町飲食店組合の臨時総会において,仕様基準が承認されたこと,(4)上記仕 様基準には,本件商標について,登録名義人である組合長が退任した場合 には,新たに選任された組合長名義で登録の変更等の申請を行うことの定\nめがあることが認められる。 上記認定事実によれば,被告は,権利能力のない社団である南三陸町飲\n食店組合の代表者として,南三陸町飲食店組合のために本件商標の商標登\n録出願をし,その登録を受けたこと,南三陸町飲食店組合は,本件商標の 商標登録出願及びその商標登録について,総会の決議で承認していること が認められるから,本件商標権は,実質的には南三陸町飲食店組合が有し ているものと認められる。 そうすると,本件商標の商標登録出願及びその商標登録に関しては,被 告と南三陸町飲食店組合とは同一人とみなして取り扱うのが相当であるか ら,前記(2)ア認定の使用主体を南三陸町飲食店組合とする「南三陸キラキ ラ丼」の標章は,本件商標との関係では,「他人」の「業務に係る商品若 しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又\nはこれに類似する商標」に該当するものと認めることはできない。 したがって,本件商標は,その余の点について判断するまでもなく,商 標法4条1項10号に該当しない。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し原告は,(1)商標法上,法人格を有することが商標登録を受け るための要件とされており(7条参照),権利能力なき社団が商標登録を\n受けることは認められていないから,被告が「南三陸町飲食店組合」の組 合長であるからといって,被告個人の本件商標の商標登録の効力が,権利 能力なき社団である「南三陸町飲食店組合」の構\成員に及ぶことはあり得 ないこと,(2)本件商標の商標登録出願前に,被告の個人名義で本件商標の 商標登録出願を行うことについての総会決議や本件商標の仕様内容,使 用方法,使用できる者の範囲,企画,広報,予算などの取決めがされて\nおらず,被告は,独断で本件商標の商標登録を受け,事後的な報告をし たというのが実態であること,(3)被告が南三陸町飲食店組合の代表者を\n退任した後においても,未だに被告個人名義で本件商標の商標権を保有 していることからすると,被告は,南三陸町飲食店組合を代表して本件商\n標の商標登録出願をし,その登録を受けたということはできず,南三陸町 飲食店組合の一構成員である被告が個人として本件商標の商標登録出願を\nし,その登録を受けたというべきである旨主張する。 しかしながら,上記(1)の点については,商標法上,法人格を有すること が商標登録を受けるための要件とされており,権利能力のない社団が商標\n登録を受けることは認められていないが,権利能力のない社団の意思決定\nに基づいてその代表者の個人名義で商標登録出願をし,商標登録を受け,\nその登録商標を権利能力のない社団の財産として管理することは許容され\nるものと解される。この場合,実体的には,当該登録商標の商標権は,権 利能力のない社団の構\成員全員に総有的に帰属し,実質的には,当該社団 が有しているとみることができるから,当該登録商標の商標登録の効力が, 権利能力のない社団の構\成員に及ばないとはいえず,本件商標も,これと 同様である。 次に,上記(2)の点については,本件商標については,南三陸町飲食店組 合の執行部会議等による協議を経た上で,本件商標の商標登録出願に至っ たものであり,その商標登録後ではあるが,南三陸町飲食店組合の総会決 議で承認されていること,南三陸町飲食店組合は,本件商標の商標登録後, 総会決議で,本件商標の仕様基準を定めていることに照らすと,被告が, 独断で本件商標の商標登録を受けたということはできない。 さらに,上記(3)の点については,被告と南三陸町飲食店組合は,被告と 南三陸町飲食店組合のF組合長間の令和元年9月26日付け確認書に基づ いて,本件訴訟が終了するまでの間,本件商標の登録名義を被告名義とし ておくことを合意し,被告は,南三陸町飲食店組合に対し,本件訴訟終了 後,本件商標の登録名義を同訴訟終了時の同組合の組合長個人名に移転す ることを約していること(前記(1)エ(ウ))に照らすと,被告が南三陸町 飲食店組合の組合長を退任した後に本件商標の商標権の移転登録をして いないからといって,被告が南三陸町飲食店組合を代表して本件商標の商\n標登録出願をしたとの認定を覆すことはできない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
◆判決本文
判決中の拒絶審決が維持された審取は下記です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
令和1(行ケ)10074 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月23日 知的財産高等裁判所
本件訂正は,請求項1における「前記LED基板に搭載されるLEDの個 数を,順方向電圧の異なるLED毎に定まるLED単位数の最小公倍数とし ている光照射装置。」を,「前記LED基板に搭載されるLEDの個数を,順 方向電圧の異なるLED毎に定まるLED単位数の最小公倍数とし,複数の 前記LED基板を前記ライン方向に沿って直列させてある光照射装置。」に訂 正するものである。 そして,原告は,本件訂正は,本件訂正前は1枚のLED基板についての 発明であったものを,複数のLED基板をライン状に直列させて所望の長手 方向の長さの製品を得るという発明に変質させるものであり,実質上特許請 求の範囲を拡張し,又は変更するものであるから,特許法126条6項に違 反する旨主張する。 そこで,この点について検討する。
ア 本件特許の特許請求の範囲(請求項1)の「LED基板」の意義
(ア) 本件訂正前の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,「LED 基板」とは,「ライン状の光を照射する光照射装置」に「備え」られた「基 板収容空間を有する筐体」に「収容」され,「複数の同一のLEDを搭載 した」ものであって,「搭載されるLEDの個数を,順方向電圧の異なる LED毎に定まるLED単位数の最小公倍数と」するものであることを 理解できる。 一方,本件訂正前の特許請求の範囲(請求項1)には,「LED基板」 の個数について定義した記載はなく,「LED基板」の個数を単数に限定 して解釈すべき根拠となる記載はない。
(イ) 次に,前記(1)イのとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,「本 発明」は,複数の同一のLEDを搭載したLED基板と,前記LED基 板を収容する基板収容空間を有する筐体とを備えた光照射装置であっ て,電源電圧とLEDを直列に接続したときの順方向電圧の合計との差 が所定の許容範囲となるLEDの個数をLED単位数とし,前記LED 基板に搭載するLEDの個数を,順方向電圧の異なるLED毎に定まる LED単位数の公倍数とする構成を採用することにより,LED基板の\nサイズを同一にして,部品点数及び製造コストを削減できるという効果 を奏するものであり,さらに,上記LED基板に搭載するLEDの個数 を,上記LED単位数の最小公倍数とすることにより,LED基板の大 きさを同じにするだけでなく,その大きさを可及的に小さくして,汎用 性を向上させるという効果を奏する旨が記載されており,この点に本件 訂正前の特許請求の範囲(請求項1)の発明(以下「本件訂正前発明1」 という。)の技術的意義があると認められる。 また,当業者であれば,上記「汎用性を向上させる」とは,可及的に 小さな大きさのLED基板の直列枚数を変えることにより,LED基板 を様々な長さの光照射装置に用いることのできるようにすることなど を意味するものであることを理解できるものといえる。 そして,本件訂正前発明1の上記技術的意義に照らすと,上記LED 基板の個数を単数に限定する必然性はみいだし難い。 むしろ,本件明細書の【発明を実施するための最良の形態】に関する 記載は,複数の上記LED基板をライン方向に沿って直列させることが 可能であることを理解できるものであって(【0017】,【0041】,\n図1),このことも,上記理解を裏付けるものといえる。
(ウ) 以上の本件訂正前発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び 本件明細書の記載を総合すれば,本件訂正前発明1の「LED基板」は 個数が単数のものに限定されないと解される。 イ 訂正の適否について 本件訂正による訂正事項は,前記柱書のとおりであり,本件訂正前にお いては,LED基板の枚数や具体的な配置の特定がなかったものを,本件 訂正後においては,「複数の前記LED基板を前記ライン方向に沿って直列 させてある」ことを特定するものである。 そして,本件明細書には,2つのLED基板をライン方向に沿って直列 させること(【0017】,【0019】,図1)及びLED基板の直列させ る数を変更して,光照射装置の長さを変更させること(【0041】)が記 載されていることから,本件訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の 範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であると認められる。 また,本件訂正前発明1の「LED基板」は個数が単数のものに限定さ れないと解されることについては,前記アのとおりであり,本件訂正は, 訂正前に特定されていなかった基板の枚数や配置を特定するものに過ぎな いから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないと認 められる。 したがって,本件訂正は,実質上特許請求の範囲を変更するものではな く,訂正要件に適合するとした本件審決の判断に誤りはないから,原告主 張の取消事由1は理由がない。
・・・・
前記(1)のとおり,原告製品「IDB−L600/20RS」及び「ID B−L600/20WS」(甲5)として,本件出願前に公然実施をされた 甲5発明は,LED基板に搭載されるLEDの個数が,順方向電圧の異な るLED毎に定まるLED単位数の公倍数である,ライン状の光を照射す る照射装置であって,上記LED基板を2枚,上記ライン方向に沿って直 列させるものであるといえる。 しかしながら,上記の原告製品からは,いかなる技術思想に基づき,1 枚のLED基板に搭載されるLEDの個数を定めたのか,また,そのよう なLED基板を2枚長手方向に直列させることにしたのかは,明らかでな い(前記(1))。 また,前記2(1)及び3のとおり,本件出願当時,原告製品「IDB−1 1/14R」及び「IDB11/14W」(甲3)として甲3発明が,原告 製品「IDB−C11/14R」及び「IDB−C11/14B」(甲4) として甲4発明が,いずれも公然実施されており,これらの発明は,1枚 のLED基板に搭載されるLEDの個数が,順方向電圧の異なるLED毎 に定まるLED単位数の最小公倍数であるものであるが,他方で,上記の 原告製品からは,いかなる技術思想に基づき,同製品のLED基板に搭載 されるLEDの個数を定めたのかは,明らかでない(前記2(1),3)。 さらに,前記2(2)ウのとおり,本件出願当時,LED基板の設計におけ る技術分野では,故障を防ぎ,品質を保持し,作業を効率化するために, LED基板間の配線及び半田付けを極力減らすようにすることが技術常識 であった。
そうすると,甲5発明に接した当業者は,仮に,当該プリント基板(L ED基板)に搭載されるLEDの個数が,赤色LEDを直列に接続する場 合の個数と白色LEDを直列に接続する場合の個数の公倍数であることを 認識し,かつ,原告製品として公然実施されていた,1枚のプリント基板 (LED基板)に搭載されるLEDの個数が,順方向電圧の異なるLED 毎に定まるLED単位数の最小公倍数である甲3発明及び甲4発明を認識 していたとしても,甲5発明において,2枚のLED基板を長手方向に直 列させるという構成を維持したまま,1枚のプリント基板に搭載するLE\nDの個数を174個から,直列接続されている赤色LEDの個数「6」と 直列接続されている白色LEDの個数「3」の最小公倍数である6個に変 更する(相違点3に係る本件発明1の構成とする)ことの動機付けはなく,\nかかる構成とすることを容易に想到することができたものと認めることは\nできず,むしろ,1枚のプリント基板に搭載するLEDの個数を減らして, 同一数のLEDを配設するのに必要なプリント基板数を増やすことには阻 害要因があったと認められる。
イ 以上のとおり,当業者において,甲5発明に基づき,又は,甲5発明に 甲3発明ないし甲4発明を適用して,相違点3に係る本件発明1の構成に\n容易に想到することができるものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
平成31(行ケ)10027 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月25日 知的財産高等裁判所
ア 本件明細書には,(1)本件発明のマッサージ機は,施療者の臀部または大\n腿部が当接する座部11a,及び施療者の背部が当接する背凭れ部12a を有する椅子本体10aと,該椅子本体10aの両側部に肘掛部14aを 有する椅子式マッサージ機1aであり,前記背凭れ部12aは,座部11 aの後側にリクライニング可能に連結されていること(段落【0022】),\n(2)肘掛部14aは,椅子本体10aに対して前後方向に移動可能に設けら\nれ,背凭れ部12aのリクライニング角度に応じた所定の移動量を保持し ながら背凭れ部12aのリクライニング動作に連動して前記肘掛部14a が椅子本体10aに対して前後方向に移動するようにされていること(段 落【0054】),(3)肘掛部14aの下部に前後方向に回動するための回 動部141aを設けること(段落【0055】),(4)肘掛部14aの後部 で回動可能に背凭れ部12aの側部と連結する連結部142aを設けるこ\nと(段落【0055】)が記載されている。 また,【図4】は,背凭れ部12aが座部に対してリクライニングする と,背凭れ部12aに連結された肘掛部14aが前後方向に回動すること を概略的に図示している(段落【0054】,【0055】)。
イ 上記アによれば,本件明細書には,[1]肘掛部の後部と背凭れ部の側 部とを,「肘掛部全体が,前記背凭れ部のリクライニング動作に連動して, リクライニングする方向に傾くように」(構成要件E)連結する連結手段\nについては連結部142aによる回動関係が,[2]肘掛部全体を座部に 対して回動させる回動手段については回動部141aによる回動関係が開 示されているが,[3]背凭れ部をリクライニングするように座部に対し 連結する連結手段の具体的な構成は記載されていない。また,本件明細書\nには,「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身におけ る着座姿勢を保」つように(構成要件F),[1]肘掛部の後部と背凭れ\n部の側部とを,「肘掛部全体が,前記背凭れ部のリクライニング動作に連 動して,リクライニングする方向に傾くように」連結する連結手段(構成\n要件D,E),[2]背凭れ部のリクライニング動作の際に上記の連結手 段を介して肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段(構成要件D)\n及び[3]背凭れ部をリクライニングするように座部に対し連結する連結 手段(構成要件D)の具体的な組み合わせの記載はない。\n
ウ 審決は,本件明細書の【図4】は,背凭れ部が座部に対して回動し,背 凭れ部に連結された肘掛部が回動するという事項(段落【0054】,【0 055】)を概略的に図示したものであり,そのための「適宜の回動手段」 「適宜の連結手段」については当業者が過度の試行錯誤なく適宜に行い得 る程度のことであると認定する。 しかし,上記イのとおり,本件においては,構成要件D〜Fを充足する\nような,[1]肘掛部の後部と背凭れ部の側部を連結する連結手段,[2] 肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段及び[3]背凭れ部を座部 に対し連結する連結手段の具体的な組み合わせが問題になっており,した がって,これらの各手段は何の制約もなく部材を連結又は回動させれば足 りるのではなく,それぞれの手段が協調して構成要件D〜Fに示された機\n能を実現する必要がある。そうすると,このような機能\を実現するための 手段の選択には,技術的創意が必要であり,単に適宜の手段を選択すれば 足りるというわけにはいかないのであるから,明細書の記載が実施可能要\n件を満たしているといえるためには,必要な機能を実現するための具体的\n構成を示すか,少なくとも当業者が技術常識に基づき具体的構\成に至るこ とができるような示唆を与える必要があると解されるところ,本件明細書 には,このような具体的構成の記載も示唆もない。\n
エ 被告は,本件明細書の記載から当業者が実施し得る本件発明1の具体的 な構成として,別紙被告主張図面目録記載のとおり動作するマッサージ機\nの具体的構成(以下「被告主張構\成」という。)を主張する。 被告主張構成は,[1]肘掛部の後部と背凭れ部の側部とを本件明細書\nの【図4】同様の回動手段により連結し,[2]肘掛部の下部の椅子本体 に設けられた回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部に 挿入され,[3]座部の後端に軸心を設けて背凭れ部を回動させる回動手 段を設けた構成であり,リクライニング前は,肘掛部の下部に設けられた\n回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部の奥まで達して おり(【被告参考図(1)−2】),これをリクライニングすると,背凭れ部 のリクライニング動作に連動して肘掛部全体がリクライニングする方向に 傾くに従って,肘掛部全体が円柱状部材から上記空洞部に沿って遠ざかる ように移動する(【被告参考図(2)】から【被告参考図(3)】)というもので ある。 しかし,本件明細書には被告主張構成の記載や示唆はないから,被告主\n張構成が直ちに実施可能\要件適合性を裏付けるものではない上に,当業者 が,上記ア及びイのとおりの本件明細書の記載及び出願当時の技術常識に 基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,被告主張構成を採用し得た\nというべき技術常識ないし周知技術に関する的確な証拠もない。
オ 以上によれば,本件明細書には,当業者が,明細書の発明の詳細な説明 の記載及び出願当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要すること なく,本件発明1を実施することができる程度に発明の構成等の記載があ\nるということはできず,この点は,本件発明1を引用する本件発明2につ いても同様である。したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
平成31(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記(1)の認定事実によれば,本件発明1は,PCSK9とLDLRタンパク 質の結合を中和し,参照抗体1と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を,本件発明2は,PCSK9とLDLRタンパク質の結 合を中和し,参照抗体2と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を,それぞれ提供するものである。そして,本件各発明の課題は, かかる新規の抗体を提供し,これを使用した医薬組成物を作製することをもって, PCSK9とLDLRとの結合を中和し,LDLRの量を増加させることにより, 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し,高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し,又は予防し,疾患\nのリスクを低減することにあると理解することができる。 本件各明細書には,本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し,スクリーニングによってPCSK9に結合する抗体 を産生する2441の安定なハイブリドーマが確立され,そのうちの合計39抗体 について,エピトープビニングを行い,21B12と競合するが,31H4と競合 しないもの(ビン1)が19個含まれ,そのうち15個は,中和抗体であること, また,31H4と競合するが,21B12と競合しないもの(ビン3)が10個含 まれ,そのうち7個は,中和抗体であることが,それぞれ確認されたことが開示さ れている。また,本件各明細書には,21B12と31H4は,PCSK9とLD LRのEGFaドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 21B12は参照抗体1に含まれ,31H4は参照抗体2に含まれるから,21 B12と競合する抗体は参照抗体1と競合する抗体であり,31H4と競合する抗 体は参照抗体2と競合する抗体であることが理解できる。そうすると,本件各明細 書に接した当業者は,上記エピトープビニングアッセイの結果確認された,15個 の本件発明1の具体的抗体,7個の本件発明2の具体的抗体が得られることに加え て,上記2441の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても,同 様のエピトープビニングアッセイを行えば,参照抗体1又は2と競合する中和抗体 を得られ,それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに,本件各明細書には,免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製,免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製,21B12や 31H4と競合する,PCSK9−LDLRとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され,当業 者は,これらの記載に基づき,一連の手順を最初から繰り返し行うことによって, 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,参照抗 体1又は2と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。
以上によれば,当業者は,本件各明細書の記載から,PCSK9とLDLRタン パク質の結合を中和し,参照抗体1又は2と競合する,単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため,新規の抗体である本件発明1−1及び2−1のモノ クローナル抗体が提供され,これを使用した本件発明1−2及び2−2の医薬組成 物によって,高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減するとの課題を解決できること\nを認識できるものと認められる。よって,本件各発明は,いずれもサポート要件に 適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と,「結 合中和することができる」という解決すべき課題(所望の効果)のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ,競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから,サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし,本件各明細書の記載から,「結合中和することができる」ことと,「参照 抗体と競合する」こととが,課題と解決手段の関係であるということはできないし, 参照抗体と競合するとの構成要件が,パラメータ要件であるということもできない。\nそして,特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において,アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり,特定の結合特性を有する抗体を得るために, その抗体の構造(アミノ酸配列)をあらかじめ特定することが必須であるとは認め\nられない(甲34,35)。 前記のとおり,本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和し, 本件各参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗体を提供するもので,参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びPCSK9と LDLR間の相互作用(結合)を遮断(「中和」)することができるものであること を構成要件としているのであるから,控訴人の主張は採用できない。\n
・・・
控訴人は,本件各発明は,抗体の構造を特定することなく,機能\的にのみ定義さ れており,極めて広範な抗体を含むところ,当業者が,実施例抗体以外の,構造が\n特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには,膨大な 時間と労力を要し,過度の試行錯誤を要するのであるから,本件各発明は実施可能\n要件を満たさない旨主張する。 しかし,明細書の発明の詳細な説明の記載について,当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求\nめられるのは,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が容易にその実施をできる程 度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていないことに帰\nし,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる からである。
本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ, PCSK9との結合に関して,参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり,機能的にのみ定義されているとはいえない。そし\nて,発明の詳細な説明の記載に,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和す ることができ,PCSK9との結合に関して,参照抗体1又は2と競合する,単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば,当業者は,その実施をすることが可能というべきであり,特許発\n明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ ることまで記載されている必要はない。 また,本件各発明は,抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから,LDLRが認識するPCSK9上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体(EGFaミミック)が発明の詳細な説明の記載から実施可能に\n記載されているかどうかは,実施可能要件とは関係しないというべきである。\nそして,前記(1)のとおり,当業者は,本件各明細書の記載に従って,本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,本件各特許の特許請求の範 囲(請求項1)に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから,本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために,当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって,控訴人の主張は採用できない
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 限定解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2020.01. 8
平成31(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月19日 知的財産高等裁判所
本件和解契約2条は,「乙らは,自ら又は第三者を通じて,無効審判の 請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただ し,甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に,当該訴訟 における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではな い。」と規定する。
しかるところ,2条の上記文言によれば,同条は,「乙ら」(原告,セ ンティリオン及びB)は,「甲」(被告)に対し,被告が原告らに対し提 起した本件特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を 主張する場合(同条ただし書の場合)を除き,特許無効審判請求により本 件特許権の効力(有効性)を争ってはならない旨の不争義務を負うことを 定めた条項であって,原告が本件特許に対し特許無効審判を請求すること は,およそ許されないことを定めた趣旨の条項であることを自然に理解で きる。 そして,前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯によれば,本件和解契 約2条の文案については,被告の代理人弁護士と原告,センティリオン及 びBの代理人弁護士が,それぞれが修正案を提案するなどして十分な協議を重ね,最終的な合意に至ったものであり,このような交渉経緯に照らし\nても,同条は,その文言どおり,原告が本件特許に対し特許無効審判を請 求することは,およそ許されないことを定めた趣旨の条項と解するのが妥 当である。 そうすると,原告による本件特許無効審判の請求は,本件和解契約2条 の不争条項に反するというべきである。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し原告は,(1)本件和解契約1条,3条及び4条に関する交渉経 緯等の本件和解契約の締結経緯及び各条項に照らすと,本件和解契約2条 は,本件和解契約締結後の「将来の紛争」に備えて,本件特許権の効力を 特許無効審判等によっては争わないことを定めた不争条項であるが,ここ で想定されている「将来の紛争」とは,3条記載のJANコードで特定さ れる「本件商品」(過去製品)及び過去製品と同一の構成の製品に係る紛争に限られているというべきであるから,被告が過去製品とは別の構\成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合には,2条により,原告が 特許無効審判等によって本件特許権の効力を争うことが禁止されるもので はない,(2)原告は,被告が過去製品と同一の構成ではない,本件特許の権利範囲に属しない類似製品に対して本件特許権を行使する関連訴訟を提起\nしたため,これに対抗して本件特許無効審判を請求するものであるから, 本件特許無効審判の請求については本件和解契約2条の効力は及ばない旨 主張する。 しかしながら,本件和解契約2条には,被告が3条に規定する「本件商 品」(原告主張の「過去製品」)とは別の構成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合には,原告が特許無効審判請求によって本件特許権\nの効力を争うことが許される旨を定めた文言は存在せず,1条,3条及び 4条のいずれにおいても,原告の主張に沿う文言は存在しない。 また,前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯に照らしても,被告と原 告,センティリオン及びBとの間において原告の主張する上記場合には2 条の効力が及ばないことを確認したり,合意したことをうかがわせる事実 は認められない。 かえって,前記アで説示したように,本件和解契約2条の文言及び本件 和解契約の交渉経緯によれば,2条は,被告が原告らに対し提起した本件 特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を主張するこ と(同条ただし書の場合)は許されるが,原告が本件特許に対し特許無効 審判を請求することは,およそ許されないことを定めた趣旨の条項である と解するのが自然な解釈である。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3) 本件和解契約2条の不争条項の有効性の判断の誤りについて
原告は,(1)本件和解契約6条の和解金は,特許法102条2項の損害額に 相当するものであって,被告が原告に対して原告の過去の販売行為について 本件特許権を行使しないことの対価として支払われるものであるから,本件 和解契約は,実質的には,原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契 約(ライセンス契約)であることを前提とした上で,独占禁止法上の指 針(第4の4の「(7) 不争義務」)は本件和解契約にも妥当するものであ り,本件和解契約2条の不争条項の存在により,原告が特許無効審判等を請 求することができないとした場合,原告は,同条ただし書により特許侵害訴 訟における抗弁として本件特許の無効を主張することができるとしても,被 告が原告に対して特許侵害訴訟を提起するまでは本件特許の有効性を争うこ とができないため,本件特許に無効理由があるにもかかわらず,一度コスト をかけて製品を販売した後,被告の訴訟提起という原告にとって如何ともし 難い被告の行為を待つことになり,かかる事実状態は,原告の経済活動を不 当に制限するものであり,その結果,本来無効となるべき本件特許により二 重瞼形成用テープに係る市場における公正な競争が阻害され,まさに独占禁 止法上違法な状態が発生することとなるから,かかる事態は,特許法の制度 趣旨からしても許容されるべきものではない,(2)また,原告以外の利害関係 人が本件特許について特許無効審判を請求することができるとしても,その ような利害関係人が常に特許無効審判を請求するとは限らないし,原告と同 じ無効理由を主張するとも限らないから,本来特許を受けられない技術が特 許として存続し続けるおそれがあることに変わりなく,公益性が失われる, (3)さらに,実施許諾契約に不争条項が存在する場合であっても,特許の無効 理由の存在が明らかな場合には,当該特許を維持しつつ技術の利用を促進す る必要もないため,不争条項は無効と解すべきであるが,本件発明1,2, 4及び5は,本件出願前に日本国内において公然実施をされた発明(特許法 29条1項2号)に該当し,新規性欠如の無効理由があることは明らかであ り,本件特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないなどとして,仮 に本件和解契約2条の不争条項が,原告の本件特許件無効審判の請求を制限 するものであるとするならば,本件和解契約2条の不争条項は,公序良俗に 反し,無効である旨主張する。
しかしながら,上記(1)の点については,本件和解契約3条は,原告,セン ティリオン及びBが本件商品の販売を平成29年8月31日限りで中止する 旨を,4条は,同年9月1日以降,原告,センティリオン及びBが「本件商 品若しくは特許第3277180号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ 又は本件特許権の侵害品」の製造,譲渡等をしない旨を,6条は,原告,セ ンティリオン及びBが,被告に対し,連帯して本件商品の販売による利益額 に相当する4500万円の和解金を支払う旨を,8条は,「和解についての お知らせ」として,被告が本件特許を侵害していることを疑い,特許侵害行 為の中止等を求めて通告し,当事者間の協議の結果,原告及びセンティリオ ンが上記製品の販売を中止する形で和解が成立したこと,被告の知的財産権 その他の権利を侵害する行為については厳正な措置を講ずる所存であること を公表することを除き,本件和解契約の内容及び本件和解契約締結に至る経緯について相互に守秘義務を負う旨を定めたものであることに鑑みると,6\n条の和解金は,原告らによる本件特許権の過去の侵害行為に対する被告の損 害を填補する損害賠償金であって,被告が原告に対し本件特許権の実施を許 諾することの対価としての性質を有するものでないことは明らかであるから, 本件和解契約が実質的に原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契 約(ライセンス契約)の性質を有するものと認めることはできない。 そうすると,本件和解契約2条の不争条項により,二重瞼形成用テープに 係る市場における公正な競争が阻害され,独占禁止法上違法な状態が発生す る旨の上記(1)の点は,その前提を欠くものである。 次に,上記(2)の点については,本件和解契約2条の不争条項によって原告 以外の者が本件特許について特許無効審判の請求をすることが制限されるわ けではなく,また,私権である特許権について当事者間で不争義務を負う旨 の合意をすることによって直ちに公益性が失われるということはできない。 さらに,上記(3)の点については,上記のとおり,本件和解契約が実質的に 原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約(ライセンス契約)の性 質を有するものと認めることはできないから,その前提を欠くものであり, また,本件和解契約2条ただし書は,被告が原告に対し本件特許権侵害を理 由とする特許権侵害訴訟を提起した場合には,原告が無効の抗弁を主張して 本件特許の有効性を争うことが許容されていること(現に関連訴訟において 原告は無効の抗弁を主張して争っている。)に照らすと,同条の不争条項に よって,原告が本件特許無効審判の請求を制限されることが不当であるとは いえない。
2019.12.27
平成28(ワ)16912 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月4日 東京地方裁判所
2 争点1−1(被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別す る識別情報」に当たるか)について
(1) 証拠(甲6,7)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件不動産サイトにお ける物件の連絡先への架電等の仕組みは,以下のとおりであると認められる。
ア 本件不動産サイトにおいて,ユーザが特定の不動産物件の詳細情報を選 択すると,例えば,以下の画面のような,当該物件についてのウェブペー ジが表示され,同ページの下段・右側に「電話」ボタンが表\示される。
イ 上記「電話」ボタンをユーザが選択すると,例えば,次の画面に遷移す る。同画面には,架電番号が表示されるとともに「このページを開いて\nから10分以内にお電話をお願いいたします。」「上記無料通話番号は, 今回のお問合せ用に発行したワンタイムの電話番号です。」と表示される。\n
ウ ユーザが上記画面に表示された架電番号に架電すると,当該物件を管\n理する不動産業者に宜接通話が繋がるが,一定時間を経過すると,当該 架電番号に架電しでも電話は繋がらず,接続先がない旨の自動音声案内 が流れる。
エ 上記イの画像の表示から,架建言することなく10分以上経過してから, 間一携帯端末で,同一の不動産物件について架電番号を表示すると,例え\nば,以下のとおり,別の架電番号が表示される。\n
オ 上記ウにより繋がらなくなった架電番号は, 53Jのユーザ、端末や商品に 対応した電話番号として再利用し得る。なお,ユーザが,同架電番号に いったん架電をすると,その後も,同番号は端末上にリダイヤノレのため 再表示され,同時に,別の端末において異なる物件の連絡先として同ー\nの架電番号が表示され得る。\n
(2) 被告は,被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別する 識別情報J (構成要件(1))に該当しないので,被告プログラムは,構成要件\n(1)を充足しないと主張する。 しかしr識別情報」の意義については,本件明細書等の段落(0019) には「識別情報とは,架電先に関連付けられることによりその架電先を識別 する情報であj ると記載されているところ,証拠(甲6,7,乙2) によれ ば,被告プログラムを使用してサービスを提供している本件不動産サイトに おいては,ユーザが希望する物件を選択すると,当該物件の詳細情報が表示\nされた画面に問合せのための専用電話番号が表示され,当該番号が表\示され るとその時点で架電番号がロックされた状態となり,その表示から一定期間,\n当該架電番号に架電するとその不動産業者に架電されるとの事実が認められ る。そうすると,被告プログラムにおける架電番号は,「架電先に関連付け られることによりその架電先を識別する情報」であり,構成要件(1)にいう 「識別情報」に該当するということができる。
(3) また,原告が行った実験結果(甲8・実施結果1。なお,以下の実験結果 はいずれも被告プログラムを使用している本件不動産サイトを利用したもの である。)によれば,(i)本件不動産サイトのユーザが,端末を用い,特定 の物件の連絡先画面を表示させると,特定の架電番号が表\示された,(ii)そ のまま架電せずに前記連絡画面を閉じ,再び物件の連絡先画面を表示させる\nと同じ架電番号が表示された,(iii)ユーザが,異なる端末の電話機能を用い,\n同一の架電番号に架電しても,同一の連絡先である広告主に接続されたとの 事実が認められる。 上記結果は,被告プログラムにおいて,ある端末に特定の物件の連絡先に 繋がる架電番号を表示させると,それにより当該番号と架電先が関連付けら\nれ,それ以降は当該架電番号に対応する連絡先の不動産業者が識別されると の上記(1)の認定を裏付けるものであり,同結果に照らしても,被告プログ ラムにおける架電番号は,構成要件(1)にいう「識別情報」に該当するという ことができる。
(4) これに対し,被告は,架電番号と発信者番号とで架電先を識別するので, 架電番号は,本件発明にいう「識別情報」に当たらないと主張し,端末に表\n示させた架電番号に発信者番号非通知の設定で架電した場合,架電先にも接 続されないという実験結果(乙3)は被告主張を裏付けるものであると主張 する。 しかし,架電前においては,被告プログラムは当該ユーザの発信者番号を 知らないはずであるから,架電前において,同プログラムが架電番号と発信 者番号とで架電先を識別するとは考え難い。上記実験において端末に表示さ\nれた架電番号に架電した場合に架電先に接続されなかったのは,後記のとお り,被告プログラムが当該架電番号に架電した時点以降,架電番号と発信者 番号とで架電先が識別されていること(この点については当事者間に争いが ない。)に起因するものと考えるのが相当であって,上記実験結果は,架電 前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定するに\n足りるものではない。 むしろ,原告の行った実験結果(甲9)によれば,発信者番号を送信し得 ないパーソナルコンピュータに本件不動産サイトを表\示した場合であっても, 物件の連絡先に繋がる架電番号が表示され,携帯端末から当該番号に架電し\nたところ,当該連絡先に接続したとの事実が認められ,これによれば,被告 プログラムは,架電前の時点において,架電番号により架電先を識別してい ると推認することが相当である。
(5) 被告は,乙8の実験2の結果は,被告プログラムにおいて,1つの架電番 号が,同時に複数のユーザが複数の架電先に接続するために利用されている ことを示しているので,当該架電番号のみでは架電先を識別し得ないと主張 する。
しかし,上記実験は,(i)本件不動産サイトのユーザが,端末(1)を用い, 物件1の連絡先画面を表示させると架電番号が表\示された,(ii)端末(1)の電 話機能で当該番号に架電した後,1990台分の仮想端末を用い,それぞれ\n物件2の連絡先画面を表示させた,(iii)その後,上記(i)の時点から10分 以内に,端末(2)で物件2の連絡先画面を表示すると,同一の架電番号が表\示 された,(iV)上記(iii)の後,前記(i)から10分以内に,端末(1)で再び物件 1の連絡先画面を表示すると,同一の架電番号が表\示されたというものであ ると認められる。 同実験の(iii)において,端末(2)において物件2の連絡先画面が表示された\nのは,上記(i)のとおり,端末(1)により架電をした後であるから,物件2の 連絡先画面が表示された時点においては,物件1の連絡先は,架電番号のみ\nではなく,架電番号と発信者番号とで識別されるようになっており,それゆ えに,物件2の連絡先画面において同一の架電番号を表示することが可能\に なったものと考えられる。 そうすると,上記実験も,架電前において表示された架電番号と架電先が\n関連付けられることを否定するに足りるものではないというべきである。
(6) 被告は,乙10の実験結果も,同一の架電番号が同時に複数のユーザによ って未架電の異なる架電先に架電するための番号として用いられることを示 していると主張する。
ア 乙10の実験は,(i)本件不動産サイトのユーザが,端末(1)を用い,物 件1の連絡先画面を表示させると架電番号Xが表\示され,同番号に架電し た(午前2時10分),(ii)その後,端末(1)で物件2の連絡先画面を表示\nさせると,架電番号Yが表示された(午前2時10分),(iii)その後,1 994台分の仮想端末を用い,物件3の連絡先画面を表示させ,それぞれ\n架電番号を表示させた,(iV)端末(2)を用い,前記(ii)の表示から10分以\n内に,物件3の連絡先画面を表示させると,架電番号Yが表\示され(午前 2時14分),続いて端末(2)から架電番号Yに架電した(午前2時15 分),(v)端末(3)を用い,前記(ii)の表示から10分以内に,物件4の連\n絡先画面を表示させると,架電番号Yが表\示された(午前2時15分), (vi)前記(ii)の表示から10分以内に,端末(1)〜(3)において,再度各物件 について架電番号を表示させると,いずれの端末においても架電番号Yが\n表示されたというものであると認められる。\n
イ 上記実験結果のうち,(iv)〜(vi)において端末(1)〜(3)において架電番 号Yが表示されたこと,取り分け,端末(1)において架電番号Yに架電をし ていないにもかかわらず,端末(1)及び(3)に架電番号Yが表示されたことに\nついては,ある端末(この場合は端末(1))から架電すると,当該端末の発 信者番号が被告プログラムに登録され(この点は争いがない。被告準備書 面9の14頁参照),架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号に ついても,架電番号と発信者番号とで識別されることによるものであると 考えられる。 このことは,原告が行った実験結果(甲15)からも裏付けられる。す なわち,同実験(甲15・実験A−1,2)は,(i) 本件不動産サイト のユーザが,端末Aを用い,物件Aの連絡先画面を表示させると,架電番\n号Aが表示された,(i) 端末Aの電話機能で架電番号Aに架電した後,\n端末Aで物件Bの連絡先画面を表示させると,架電番号Bが表\示された, (iii) 前記(ii)から10分以内に,端末Bの電話機能を用い架電番号Bに\n架電しても,物件Bの連絡先である広告主には接続されなかった,(iv)他 方,前記(iii)の代わり,端末Aの電話機能を用いて架電すれば,物件Bの\n連絡先である広告主に接続されたというものであると認められる。同実験 結果によれば,架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号について も,架電番号と発信者番号とで識別されるものと認めるのが相当である。 そうすると,上記アの(iv)〜(vi)において架電番号Yが表示されたの\nは,その時点において,端末(1)及び(2)については,架電番号Yと各端末の 発信者番号により関連付けが行われていたからであり,同実験結果も,架 電前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定す\nるに足りるものではないというべきである。
(7) 以上によれば,被告プログラムにおいて,未架電の端末にのみ架電番号が 表示されている場合には,当該架電番号は,「架電先に関連付けられること\nによりその架電先を識別する情報」であり,構成要件(1)にいう「識別情報」 に該当するということができる。そして,前記判示のとおり,被告プログラ ムが架電後においては架電番号と発信者番号とで架電先を識別しているとし ても,このことは被告プログラムが構成要件(1)を充足するとの結論を左右す るものではないというべきである。 したがって,被告プログラムは,構成要件(1)を充足する。
・・・
(1) 特許法102条2項所定の利益の額について ア 特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は, 侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売すること によりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した 限界利益の額であり,その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべ きである(知的財産高裁平成30年(ネ)第10063号令和元年6月7 日判決参照)。 本件における計算鑑定の結果によれば,被告プログラムについては,平 成25年6月分から平成30年9月分までの間,別紙2−3(1)欄記載の売 上高があり,製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費の額は同 (2)欄記載のとおりであるので,その限界利益の額は同(3)欄記載のとおりで あると認めることができる。
イ これに対し,原告は,●(省略)●であることを指摘し,別紙2−3(2) 欄記載の変動費に含まれる●(省略)●からの仕入費の額については,そ の利益相当額50%を控除した額とするべきであると主張する(なお,当 裁判所は,この点に関する原告の主張のうち,●(省略)●が,被告サー ビスを実質的に運営する共同事業者であって,共同不法行為者に当たるな どとする主張については,時機に後れた攻撃防御方法を理由とする却下を した。)。しかし,●(省略)●されるべきものでないことは当然であり, また,その仕入価格が不当に高額に設定されていたといったような事情を 認めるに足りる証拠もないのであるから,この点に関する原告の主張を採 用することはできない。
ウ 他方,被告は,別紙2−3(2)欄記載の金額のほか,(1)通信回線及び通信 機器設備の利用料,(2)派遣労働者の費用,(3)専用プログラムの開発費も, 変動費又は個別固定費として控除すべきであると主張する。 しかし,証拠(乙30〜32)によれば,上記(1)〜(3)の費用は,被告プ ログラムにのみ費消されたものではなく,被告の提供する他のサービスに ついても費消されているものであると認められ,被告プログラムの作成や 販売に直接関連して追加的に必要となった経費であるということはできな い。 したがって,これを売上高から控除すべきであるとの被告主張は採用し 得ない。
エ もっとも,本件において,原告の請求の対象となる限界利益は,平成2 5年5月26日から平成31年4月30日までの利用に対するものである のに対し,前記計算鑑定は,平成25年6月分から平成30年9月分まで の売上を対象とするところ,乙27及び弁論の全趣旨によれば,これら各 月分の売上は,それぞれ前月分の利用に対応することが認められる。そこ で,平成25年5月の利用については,同年6月分の限界利益の額を日割 り計算し,平成30年9月から平成31年4月までの利用については,平 成30年4月分から同年9月分までの限界利益の額の平均額を採用するの が相当である。そうすると,特許法102条2項所定の利益の額は,この 計算によって得た別紙2−1(2)欄記載の額に,それぞれの時期における同 2−3(3)欄記載の消費税率を加算した額と計算されることになる。
(2) 推定覆滅事由について
被告は,被告サービスに対する本件発明の寄与率は0%と解すべきである として,特許法102条2項における推定覆滅事由があり,その割合は10 0%であると主張する。
ア 同条項における覆滅については,侵害者が主張立証責任を負うものであ り,侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害 する事情がこれに当たると解され,同条1項ただし書の事情と同様,同 条2項についても,これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すること ができるものと解される。(前掲知的財産高等裁判所判決参照)
イ 被告は,被告プログラムの訴求ポイントは,PhoneCookieと いう独自技術を用い,ウェブと電話から得られるトランザクション情報を 効果的に利用する点であるのに対し,本件発明の特徴点は,補正手続にお いて付加された構成要件(6)であるから,被告プログラムと本件発明は訴求 ポイントが異なると主張する。 しかし,本件発明は,その構成要件が一体となって所期の効果,すなわ\nち,「架電先を識別するための識別情報を広告情報ごとに動的に割り当て て,識別情報の再利用を可能とすることにより,識別情報の資源の有効活\n用及び枯渇防止を図る」(段落【0049】)とともに,「ウェブページ への提供期間や提供回数に応じて動的に識別情報を変化させることにより, 広告効果を時期や時間帯に基づき把握すること」(段落【0050】)を 可能にするものであり,構\成要件(6)が出願審査の過程において補正により 付加されたとしても,同構成要件のみが本件発明の特徴点であると解する\nことはできない。 他方,被告プログラムを使用している本件不動産サイト(甲6)におい ては,ユーザーによる架電の負担の軽減が課題として掲げられるとともに, 「その時・その人にだけ有効な『即時電話番号』を発行」し,「静的に電 話番号を割り振るのではなく,ユーザーのアクションに応じて動的に電話 番号を割り振」るとの内容を有することが記載されていることが認められ る。 上記本件不動産サイトに記載された「その時・その人にだけ有効な『即 時電話番号』を発行」し,「動的に電話番号を割り振」ることは,「識別 情報の資源の有効活用及び枯渇防止を図る」などの本件発明の効果を発揮 する上で不可欠な要素であり,被告プログラムにおいてもこうした構成を\n備えた結果,その顧客は本件発明と同様の効果を享受しているものという ことができる。 被告は,被告サービスの訴求ポイントについて,PhoneCooki eという独自技術を用い,ウェブと電話から得られるトランザクション情 報を効果的に利用することができる点にあると主張するが,同技術が被告 サービスの売上に貢献したことを具体的に示す証拠はない。 そうすると,被告プログラムがPhoneCookieという独自技術 を用いているとしても,この点を覆滅事由として考慮することはできない というべきであり,被告がそのために被告を特許権者とする特許技術(特 許第5411290号,特許第5719409号)を使用していることも, 上記結論を左右しない。
ウ 被告は,本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能は,従来技\n術にすぎないと主張する。 しかし,原告が従来技術として挙げるLRU方式は,前記判示のとおり, 使用されてから最も長い時間が経った架電番号から順に利用する方式であ り,本件特許とはその採用している方式が異なるものであり,本件発明が 従来技術として利用しているものではない上,市場において本件発明と同 様の効果を奏する代替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関\n係にあるということはできない。 また,被告は,被告を特許権者とする前記特許明細書に記載された方式 によっても,本件発明を代替することが可能であると主張するが,同方式\nは,架電番号の在庫が尽きた場合に,これを初期化し,その初期化したこ とを通知するものであり(乙18・段落【0095】),本件特許とはそ の採用している方式が異なるものであり,本件発明が従来技術として利用 しているものではない上,市場において本件発明と同様の効果を奏する代 替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関係にあるということ\nはできない。 以上のとおり,本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能が従\n来技術にすぎないとの被告主張は理由がなく,この点を推定覆滅事由とし て考慮することもできない。
エ したがって,本件においては,被告が得た利益の全部又は一部について 推定を覆滅する事由があるということはできない。
(3) 小括
前記のとおり,特許法102条2項の「利益」の額は,別紙2−1(2)欄記 載の額に同(3)欄の消費税率を乗じた額であり,同項における推定覆滅事由が あるとは認められないので,被告が賠償すべき額は,その10%に相当する 弁護士費用相当額を加算し,一円単位に切り捨てた別紙2−1(5)欄のとおり と計算される。また,弁論の全趣旨によれば,これらの損害の発生日は,遅 くとも,それぞれ同(6)記載の日であると認められるので,各同日から支払済 みまでの遅延損害金の請求をすることができる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12.27
平成30(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
前記(1)及び(2)を踏まえると,本件明細書には,本件発明に関し,次のよ うなことが開示されていると認められる。 従来,高温下の成形又は熱処理を要する鋼板においては,一般に亜鉛の融点を上 回る高い温度で熱処理が行われるため,鋼板に亜鉛被膜があると,亜鉛が溶融,流 動して熱間成形用ツールの働きを妨害し,さらに,急冷中に被膜が劣化すると考え られてきた。そのため,鋼板の被覆処理は,熱処理の前には行われず,熱間成形や 熱処理後の完成部品に対して行われていたが,そうすると,(1)部品の表面及び中空\n部分の十分な清浄化が不可欠であり,その清浄化には酸又は塩基を使用する必要が\nあるため,経済的な負担や作業員及び環境への危険があること,(2)鋼の脱炭及び酸 化を完全に防止するために,熱処理を管理雰囲気下で行う必要があること,(3)熱間 成形の場合に生じるカーボンデポジットが成形用ツールを損傷し,部品の品質を低 下させたり,ツールの頻繁な修理のためにコストが上がったりすること,(4)得られ た部品の耐食性を強化するために,当該部品の後処理が必要であるが,後処理は, 経費も高く作業も難しい上に,中空部分のある部品では不可能であることなどの問\n題があった。(【0002】,【0003】) そこで,本件発明は,熱間成形や熱処理の前に鋼板に被覆を形成することで,熱 処理における鋼板の脱炭や酸化を防止するなど,上記(1)〜(4)の従来技術の問題点を 解決することができる,極めて高い機械的特性値をもつ鋼板を製造する方法を提供 することを課題とするものであり,その解決に当たり,亜鉛又は亜鉛合金で被覆し た鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに,被膜が鋼板の 鋼と合金化した層を形成し,この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度 を持つようになるという,従来の定説とは異なる新たな知見が得られたことに基づ き,解決手段として,亜鉛又は亜鉛を50重量%以上含む亜鉛ベース合金(前記(2) のとおり,ここには金属間化合物からなる合金も含まれている。)で被覆された熱処 理用鋼板ブランクに対し,部品を得るための熱間型打ち前に,800℃〜1200℃ の高温を2〜10分間作用させる熱処理を行うことにより,腐食に対する保護及び 鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する,亜鉛−鉄ベース合金化合\n物及び亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化 合物(金属間化合物)を熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる工程を実施する\nものとしたことを特徴とするものである(【請求項1】,【0004】〜【0008】,
【0014】〜【0016】,【0021】)。 そして,本件発明は,熱処理用鋼板に上記合金化合物(金属間化合物)の被膜を 形成することにより,熱処理中又は熱間成形中の鋼の腐食防止及び脱炭防止,カー ボンデポジットの形成を阻止することによるツールの損耗防止,高温での潤滑機能\nの確保,得られた部品の酸洗い浴が不要となることによる経済的利点,成形部品の 耐疲労性,耐損耗性,耐摩耗性及び耐食性の強化などの効果を奏するものである(【0 024】〜【0027】)。
2 金属間化合物についての本件出願時の技術常識
(1) 金属間化合物とは,2種類以上の金属元素から形成される化合物であり, 本件出願時に,本件発明において熱処理後に生じるとされている(1)亜鉛−鉄ベース の金属間化合物として,亜鉛−鉄及び亜鉛−ニッケル−鉄の金属間化合物が,(2)亜 鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物として,亜鉛−鉄―アルミニウムと亜\n鉛−鉄−アルミニウム―ニッケルの金属間化合物がそれぞれ知られていた(甲3,\n7,8,14〜16,20,25,乙8,弁論の全趣旨)。 また,熱処理をして亜鉛に鉄を拡散させ,金属間化合物を形成することができる こと及び各金属間化合物について,組成の濃度に応じて複数の相が存在することが 本件出願時に知られていた(甲2,3,7,8,15,16,25,弁論の全趣旨)。
(2) 前記のとおり,本件発明においては,熱処理前の「亜鉛ベース合金」に,金 属間化合物が含まれ得るところ,本件出願時に,亜鉛と金属間化合物を形成して「亜 鉛を50重量%以上含む亜鉛ベースの金属間化合物」を構成し得る元素としては,\n鉄の他に,ニッケル,銀,金,クロム,マンガンなどが知られていた(甲2,23, 24,乙5,弁論の全趣旨)。
3 取消事由1(サポート要件についての認定判断の誤り)について
(1) 特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記 載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり,サポート要件の存在については,特許権者(被告)がその証明責任を負 うものである。 そして,前記のとおり,本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ,以下,この争点について,上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記1のとおり,本件明細書には,亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに,被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し,この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき,熱間成形や熱処理の前に, 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し,その後熱処理を行うことにより,腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する,亜鉛−鉄\nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ,これ によって,熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止,脱炭防止,高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され,実施例1として,鋼板を亜鉛で被膜し\nたものを950℃で熱処理して,亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと\nころ,同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され,さら に,実施例2として,50−55%のアルミニウム,45−50%の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ,極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると,当業者は,本件明細書の記載から, 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して,亜鉛−鉄ベース合金化合物(金属間化合物)又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物(金属間化合物)を生じさせ,高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た,当業者は,本件発明の合金化合物において,亜鉛が共通する主要な成分である から,本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記2で認定したとおり,亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること,熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る,すなわち,異なる金属間化合物に変化し得ることが,本件出願時の 技術常識であったことからすると,本件明細書の記載に接した当業者は,熱処理前 の被膜が実施例1とは異なり,亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても,実施例1 の記載及び上記技術常識を基礎にして,熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成, 熱処理の温度や時間等を適宜調節して,熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物(金属間化合物)を生じさせ,高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また,鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で,それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても,(1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して, 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例2が本件明細書に記載されていること,(2)前記2(1)のとおり,亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が,本件出願時,当業者に知られていた上,熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは,出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と,亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で,異なることを 示す根拠となる事情は認められず,基本的には異ならないと考えられることからす ると,熱処理前の「亜鉛ベース合金」が,実施例2に開示された亜鉛―アルミニウ\nムの固溶体からなる合金のみならず,亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても,熱処理前の同金属化合物の組成,熱処理の温度や時間等を適宜調節して, 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物(金属間化合物)を生じさせ,高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 エ 次に,その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には,前記2(2)で認定したとおり,多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で,本件明細書には,熱処理前の「亜鉛ベース合金」が,それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし,前記2(1)のとおり,本件出願時,本件発明にいう熱処理後に生じる3元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして,証拠上認定できるものは,(1)亜鉛−ニッケル−鉄,(2)亜鉛−鉄− アルミニウム,(3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの3種類のみである。 そうすると,上記のような3元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては, 鉄,アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして,ニッケルについては, 前記2(1)で認定したとおり,亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上,本件出願時から,ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた(甲2,乙8)から,当業者は, ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく, 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると, 本件明細書の記載に接した当業者は,前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて,熱処理前の「亜鉛ベース合金」が,亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も,それらの組成,熱処理の温度や時間を適宜調節して,亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ,高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして,本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と3元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から,鉄,アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により3元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると,当業者は,本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて,本件明細書の実施例2で開示された亜鉛重量50%−アルミニウム 重量50%の合金以外の「亜鉛ベース合金」として,亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物,亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し,これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物(金属間化合物)又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物(金属間化合物)を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ,そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は,(1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し,それを熱処理すること で,本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを,被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが,その主張立証が果たされていない,(2)亜鉛−鉄金属間化合物について, δ1相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると,当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして,本件発明の課題をできるとは認識しな い,(3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて,限られた温度の3元系状態図しか知られていなかったことからすると,当 業者は,熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは\nできないから,熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記(1)について,当業者が,「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て,亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物,亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し,これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは,前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記(2)について,本件発明は,亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに,被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し,この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり,かつ,実施例1,2で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる(実施例1,2と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。)以上,従来の 技術常識にかかわらず,当業者は,本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合,本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ,原告の主張は採用することができない。
ウ 上記(3)について,前記(2)で検討したとおり,当業者は,本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から,亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって,こ のことは,限られた温度の3元系状態図しか知られていなかったとしても,左右さ れるものではない。
エ 以上からすると,原告の上記主張は,前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって,原告主張の審決取消事由1は理由がない。
4 取消事由2(実施可能要件についての認定判断の誤り)について\n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ,方法の発明における発明の実施とは, その方法の使用をする行為をいうから(特許法2条3項2号),方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては,当業者が明細書の記載及び出願当時\nの技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして,実施可能要件についても特許権者(被告)がその証明責任を負\nう。
(2) 前記3で検討したところからすると,当業者は,本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて,「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として, 亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物,亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し,これらの被覆を熱処理することによって,高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから,本件明細書の詳細な説明には,本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり,実施可能要件は充足されている\nと認められる。
(3) 原告は,実施可能要件について,(1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると,いかなる金属間化合物が生じ,「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない,\n(2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない,(3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし,上記(1)について,前記3で検討したところからすると,当業者 は,「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として,亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物,亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し,これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記(2)について,前記3で検討したとおり,本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例1,2で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると,原告が主張するような事情を考慮しても,当業者は実施可能\nであると認識するものと認められる。
ウ 上記(3)について,前記3で検討したところからすると,当業者は,本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から,亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.12.27
平成30(ワ)5189 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
原告は,被告会社による共有特許権の侵害行為として,被告製品を製造販 売したことを主張し,被告会社が被告製品を販売したことは当事者間に争いがない ものの,被告らは被告会社が被告製品を製造したことを否認している。そして,被 告らは,むしろ,被告製品を製造したのは,共有特許の特許権者(共有者)である 被告P2であり,被告会社が販売したのは,被告P2が製造した製品であるとして, 共有特許権についての消尽の抗弁を主張するが,この点については,原告が否認し, 争っている(争点2)。そこで,事案に鑑み,被告製品が共有特許発明の技術的範 囲に属すると仮定して,争点2から判断する。 この点について,被告P2は,上記被告らの主張に沿う供述をしていることから, この供述の信用性について検討する。また,上述するとおり,原告は被告会社によ る被告製品の製造を特許権侵害行為として主張するところ,その事実が認められる かについても,ここで検討する。
・・・・
(ア) まず,原告は,被告会社の決算報告書(損益計算書)や法人事業概況 説明書(甲34,35,53,54)に不自然な点があると主張し,それと同旨の 供述をしているが,被告会社が被告製品を仕入れた旨の記載部分の信用性が認めら れることは,前記判示のとおりであり,これに反する原告の供述は採用できない。 また,原告は,甲39の被告製品の数量が658袋となっており,甲38記載の 526袋との差は被告会社が製造したものであるとも主張する。しかし,被告P2 は数え間違いによるものであると説明しているところ(乙24,被告P2供述), 被告会社が被告製品の原材料や製造装置等を用意していたことをうかがわせる証拠 がないことは前述のとおりであるし,被告会社が被告製品を製造したことをうかが わせる事実も認められない。したがって,数え間違いであるとの被告P2の説明は 否定し難く,上記事実から被告会社が被告製品を製造したと推認することはできな い。 そして,原告が被告会社の書類について指摘するその他の不自然な点については, 被告P2から裏付け証拠(乙3,16の1ないし16の3)を伴う形で説明がされ ており(乙24,被告P2供述),その説明を否定すべき事情は認められないし, その他に以上の判断を左右すべき証拠があるとはいえない。
(イ) 次に,原告は,被告会社が被告P2の一人会社であることなどを指摘 し,被告P2の行為は法人である被告会社の行為とみるのが自然であるなどと主張 する。しかし,被告P2は被告会社の代表取締役を務める一方で,「ケアシェルサ\nポート」という屋号で個人事業を営んでいるのであり,直ちに原告主張のように解 することはできない。むしろ,前記認定の事実によれば,被告P2は,個人の立場 で,解散会社から被告製品の原材料や製造装置を購入したり,従業員を雇用したり, 本件建物を賃借したりするなどしていると認められるから,これらの事実に照らせ ば,被告P2の行為を被告会社の行為と評価することはできず,これらの事実は被 告P2が個人の立場で被告製品を製造していたことを基礎付ける事実といえる。 この点に関し,原告は,甲52に被告会社が本件建物の6か月分の家賃として6 0万円を支払っていたと記載されていることを指摘し,被告製品を製造する本件建 物の家賃を被告会社が支出していたと主張するが,甲52の記載は誤記と認められ (乙23。なお,甲52には平成28年4月から9月までの家賃の支払が記載され ておらず,甲51の記載との連続性からすると,それ自体,不自然なことであるし, 乙19も踏まえると,誤記であるとの乙23の陳述は信用できる。),原告の上記 主張事実を認めることはできない。
(ウ) また,原告は,被告P2が被告製品の原材料等を被告会社の利益を使 って仕入れていたとして,被告製品の所有権を原始取得するのは被告会社である旨 主張する。しかし,被告会社が被告製品の原材料等を自ら仕入れていたことを認め るに足りる証拠はないし,被告らが取引基本契約を締結し,被告P2が被告会社に 被告製品を販売していたことをもって,原告主張のように評価することはできない。 むしろ,前記認定の事実によれば,被告P2は被告製品を被告会社に販売し,そこ から被告製品の製造に係る経費を回収していたと認めるのが相当である。したがっ て,被告製品の所有権は被告P2が製造することによって発生し,被告会社に販売 されることによって,被告会社がその所有権を取得したものと認められるから,原 告の上記主張は採用できない。なお,被告会社は被告P2が全株式を有する一人会 社であるから(被告P2供述,弁論の全趣旨),被告ら間の取引基本契約ないし売 買契約が民法108条本文や会社法356条1項により無効となることはないと解 される(最高裁昭和45年8月20日判決・民集24巻9号1305頁参照)。
(エ) 原告は被告会社の従業員数に照らせば,被告会社が被告製品を製造し ていないのは不自然であることも主張するが,被告会社の従業員は,被告P2自身 を除けば,被告P2の妻と,女性1人で,同人らの勤務時間は少なく,被告会社は 「しおさい」の販売業務等も行っているから(乙24,被告P2供述),原告指摘 の点が特別不自然であるとはいえない。 それだけでなく,原告は,被告P2が自ら被告製品を販売せず,被告会社が販売 している点について不自然である旨指摘しているが,被告P2は,顧客が法人から 仕入れたいと要望することがある旨供述しており,この説明自体,不自然,不合理 なものとはいえない。
(オ) 以上より,原告の主張・供述を採用することはできず,原告供述によ って被告会社が被告製品を製造していたことを認めることはできないし,被告P2 の供述の信用性が否定されるともいえない。 エ 以上のことに加え,被告P2の主張・陳述は本件訴訟の提起以来一貫し ていたことも踏まえると,被告製品を自ら製造し,被告会社に販売していた旨の被 告P2の供述は全体として採用することができる。また,原告は被告会社が被告製 品を製造していたと主張するが,これを認めるに足りる証拠はないから,この原告 の主張は採用できない。
(4) まとめ
共有特許権の共有者である被告P2(ケアシェルサポート)は,原告の同意を 得ることなく,共有特許発明を実施することができるから,被告P2が,仮に共有 特許発明の実施品として被告製品を製造し,これを被告会社に販売した場合には, 共有特許権はその目的を達成したものとして消尽し,共有特許権の共有者である原 告は,被告会社が被告製品を譲渡等することに対し,特許権を行使することはでき ないものと解される。 なお,被告会社は解散会社から購入した被告製品を第三者に販売したこともあっ たが,これは共有特許権の特許権者である原告及び被告P2から実施の許諾を受け て製造され,被告会社に販売されたものであるから,同じくその被告製品について も共有特許権は消尽したと解される。 したがって,被告製品が共有特許発明の構成と均等なものとして,その技術的範\n囲に属するか否かを論ずるまでもなく,被告製品の製造販売による共有特許権の侵 害を理由とする原告の請求には理由がないこととなる。
2 争点3(被告製品の製造販売について甲4特許権に対する特許法101条5 号の間接侵害が成立するか)について
(1) 原告は,甲4特許発明が方法の発明であることを前提として,被告製品の 販売について甲4特許権に対する特許法101条5号の間接侵害が成立すると主張 する(なお,前記1で判示したとおり,被告会社が被告製品を製造したとは認めら れない。)。これに対し,被告らは,甲4特許発明は物の発明であるなどとして, 同号の間接侵害は成立しないと主張する。
(2) そこで原告の主張について検討すると,そもそも,物の発明と方法の発明 とは,明文上判然と区別され(特許法2条3項),与えられる特許権の効力も明確 に異なっているのであるから(例えば,同法101条,104条,175条2項), 物の発明と方法の発明とを同視することはできないし,物の発明に関する特許権に 方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして,当該発 明がいずれの発明に該当するかは,まず,願書に添付した特許請求の範囲の記載に 基づいて判定すべきものである(同法70条1項参照)(最高裁判所平成11年7 月16日判決・民集53巻6号957頁参照)。 そこで,甲4特許の特許請求の範囲の請求項1を見ると,そこには機能的な表\現 がみられるものの,「…透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」 と明記されており,その文言上,物の発明について記載されたものであることが明 らかである。したがって,甲4特許発明は方法の発明ではなく,物の発明である。 なお,以上のことは,甲4特許の発明の名称が「透析機洗浄排水の中和処理用マ グネシウム系緩速溶解剤」とされていることや,甲4特許明細書の【0001】に 「本発明は個人用透析機排水の中和処理に利用される透析機洗浄排水の中和処理用 マグネシウム系緩速溶解剤に関する。」との記載があること(甲4)からも裏付け られる。また,原告は甲4特許の出願経過に照らし,方法の発明として特許査定さ れたと主張するが,その主張は前述した特許請求の範囲の記載に照らして採用でき ないし,原告は出願当初,マグネシウム系緩速溶解剤の製造方法に係る発明(これ は,物を生産する方法の発明と解される。)についても特許請求の範囲に含めてい たが(乙9),補正によりこれを削除し,さらに用途を限定したところ(乙12, 13),この経緯に照らせば,なおさら採用する余地はないというべきである。
(3) 以上より,甲4特許発明は物の発明であって,方法の発明ということは できないし,これに方法の発明と同様の効力を認める根拠も見出し難い。したがっ て,甲4特許発明が方法の発明であることを前提に特許法101条5号の間接侵害 が成立するとの原告の主張は,その前提を欠き,採用することができない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 間接侵害
>> ピックアップ対象
2019.12.27
平成31(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月11日 知的財産高等裁判所
平成26年法律第36号による特許法の改正により,特許無効審判は「利害 関係人」のみが請求できるものとされ(123条2項),代わりに,「何人も」 申立てをすることができる(113条柱書)特許異議の申\\立制度が導入された ことにより,現在においては,特許無効審判を請求できるのは,特許を無効に することについて私的な利害関係を有するもののみに限定されたものと解さざ るを得ない。 しかしながら,特許権侵害を理由に民事責任や刑事責任を追及されるおそれ のある関係にある者は,当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を 有し,特許無効審判請求を行う利益を有することは明らかである。
・・・
被告は,インターネット上のサービスの提供を行う会 社であって,原告と一定の競業関係にあるといえるから,過去又は将来の行為 を理由に,本件特許権侵害に係る民事上又は刑事上の責任を追及されるおそれ のある関係にある者に当たるということができる。更に言えば,被告は,原告 が提起した本件特許権の侵害を理由とする不当利得返還請求訴訟(別件特許権 侵害訴訟)において,グーグル合同会社と共同して被疑侵害品を開発した旨主 張されている(乙1)のであるから,原告から本件特許権の侵害を問題にされ るおそれがあることは明らかである。 以上によれば,本件審判の請求人(被告)は,本件特許権を無効にすること について利害関係を有するものと認められる。
・・・・
前記アのとおり,本件発明1の「少なくとも単独の受信者の識別子」と は,「遠隔サーバー」が送信する「操作者により決定された…更なる表現」\nを受信する者を識別するための情報であり,ハンドヘルド装置の操作者が, 同装置に前記識別子を入力することで,当該識別子により識別される特定 の者を,前記更なる表現を受信する者として指定できる機能\\を有するもの と解される。 一方,前記イのとおり,甲1に記載された「ランク」は,本件発明1の 「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を果たすも\nのではないから,これに相当するものとはいえない。 そうすると,本件審決が,「ランク」を「少なくとも単独の受信者の識 別子」と呼ぶことは任意であるとして,両者が実質的に同一であることを 前提に,当業者が相違点1−3に係る本件発明1の構成を容易に想到し得\nると判断したことは,その前提を誤るものといえる。 そして,演奏者から受け取った信号と伴奏とを組み合わせたパフォーマ ンスを,サーバにアクセスしている聴衆に同報通信する構成により,「ウ\nェブ/チャット型サービスによるグループ対話式音楽演奏」を実現した引 用発明1において,「少なくとも単独の受信者の識別子」を,演奏者に入 力させる構成を採用する動機付けとなる記載は,甲1には見当たらず,ま\nた,かかる構成を採用することが,「ウェブ/チャット型サービスによる\nグループ対話式音楽演奏」における周知技術であるとも認められない。 したがって,相違点1−3に係る本件発明1の構成は,当業者が容易に\n想到できたものであるとは認められない。
エ これに対し被告は,甲1には,ランクが高い演奏者が,参加する演奏グ ループを特定するために,どの演奏グループに参加するかの情報を HumSever に対して送信した後に演奏を開始することが,実質的に開示され ており,かかる情報は演奏グループを特定するものであって,演奏グルー プには少なくとも1人の聴衆が含まれるから,同情報は本件発明1の「少 なくとも単独の受信者の識別子」に相当するものであり,相違点1−3は 甲1に開示されている,あるいは,少なくとも実質的な相違点ではない旨 主張する。 しかしながら,前記ウのとおり,甲1に記載された「ランク」は,本件 発明1の「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を\n果たすものではなく,これに相当するものとはいえない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.12.27
令和1(ネ)10052 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 控訴人は,構成要件1Aは,画像情報を取得する機能\の有無に限らず, 「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」であると主張する。 本件発明1の構成要件1Aは,「画像情報,音声情報および言語を対応するパター\nンに変換するパターン変換器と,パターンを記録するパターン記録器と,」というも のであるところ,画像情報を取得する機能の有無に限らないという控訴人の主張に\nよると,本件発明1は,パターンに変換する画像情報が取得されたものでない場合 には,パターン変換器は,予め保持している画像情報を対応するパターンに変換す\nるものということになるが,このとき画像情報は,パターンに変換されることも,ま た,パターンとして記録されることもなく,画像情報として予め保持されていたも\nのということになる。 しかし,本件発明1の特許請求の範囲及び本件明細書等1には,画像情報が,パタ ーンに変換されることも,また,パターンとして記録されることもなく,予め保持さ\nれたものであるとは読み取ることができる記載はない上,かえって,本件明細書等 1の段落【0017】には,「【課題を解決するための手段】(請求項1に対応)」 として,「この発明における思考パターン生成機は画像情報,音声情報および言語を パターンに変換する。画像情報は画像検出器により検出され,対象物に応じたパタ ーンに変換される。・・・」と記載され,画像検出器により検出されるものとされて いる。 したがって,本件発明1の構成要件1Aが,画像情報を取得する機能\の有無に限 らないとの控訴人の主張を採用することはできない。 そして,本件装置が,外部から入力された表情等に関する画像をパターンに変換\nする機能を有していると認めるに足りる証拠がないことは,原判決「事実及び理由」\nの第4の2(2)イに判示するとおりである。 よって,本件装置が構成要件1Aを充足していると認めることはできない。\n
イ 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や被控訴人の主 張によると,本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関する情報(画 像情報)からディスプレイに表示するための画素データ(画像パターン)に変換され\nていることが分かると主張する。 しかし,構成要件1Aの「パターン変換器」が行うものとして記載された「画像情\n報・・・を対応するパターンに変換する」処理でいうところの「パターン」とは,画 像,音声及び言語に係る事象の特徴を,計算機たる検出器が識別することができる 「1」,「0」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味すると解されること は,原判決「事実及び理由」の第4の2(1)アが判示するとおりである。 そして,本件装置が,「本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関す る情報から,ディスプレイに表示するための画素データを作成する」としても,この\nことが,画像,音声及び言語に係る事象の特徴を,計算機たる検出器が識別すること ができる信号の組合せに変換する処理に当たらないことは明らかである。 したがって,控訴人の主張を採用することはできない。
ウ 以上によると,本件製品が構成1Aを充足すると認めることはできない。\n
(3) 争点2−2(構成要件1Bの充足性)について\n
ア 控訴人は,本件製品の紹介ビデオ(甲79)によると,顧客の銀行口座に 関する情報に対応するデータにパターンの変更が行われているから,本件装置はパ ターンを変更していると主張する。 しかし,「パターン」とは,画像,音声及び言語に係る事象の特徴が計算機たる検 出器が識別することのできる信号の組合せに変換されたものであり,「パターンの 変更」とは,このような信号の組合せ自体を変更するものである(原判決「事実及び 理由」の第4の2(3)ア)。顧客の銀行口座に関する情報に変更が行われているとし ても,このようなことは,パターンとパターンの結合関係を変更することによって も行うことができるから,本件装置の内部において,上記のような意味での「パター ンの変更」が行われていることを示すとは直ちに認められず,控訴人の主張を採用 することはできない。
イ 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や,本件製品の 紹介ビデオ(甲80)の説明によると,本件装置は「質問」に対し,学習の前と後で 回答内容が更新できるため,「回答内容」についてパターンの変更が実施されている と主張する。 しかし,本件装置が回答内容を更新しているということは,入力された言語情報 に対応する回答が変更されたということになるが,「言語に係る事象の特徴が変換 された信号の組合せ」が変更されたのか否かは明らかではないから,控訴人の主張 を採用することはできない。
ウ 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)や本件製品の紹介ペー ジ(甲81)に,「アメリアが文章をパーツに分解して,各単語の役割と,他の単語 との関係を解釈する」とある点について,本件装置は,「文章(=文,パターン)」 を「パーツ(文要素や単語)」に分解するという「変更」を実施していると主張する。 しかし,本件装置が,「文章(=文,パターン)」を「パーツ(文要素や単語)」 に分解するということは,文章を,文要素や単語に分解して認識していることを意 味しているにすぎないとも考えられ,言語の「パターン」を変更しているとは直ちに 認められない。
エ 以上によると,本件装置が構成要件1Bを充足するとは認められない。\n
(4) 争点2−4(構成要件1Dの充足性)について\n
ア 控訴人は,原判決が構成要件1Dについて,「有用と判断した情報のみを\n記録する」として,「のみ」を含むクレーム解釈をしたことが,請求項に記載のない ことを含めたものであり,誤りがあると主張する。 しかし,「有用と判断した情報のみを記録する」と解釈すべきことは,原判決「事 実及び理由」の第4の2(4)アが判示するとおりであり,控訴人の主張を採用するこ とはできない。
イ 控訴人は,甲31及び38に「業務に特化した情報を学習するため,業務 に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」との記載があることから,本件装 置が有用な情報のみを記録するとの機能を備えていると主張する。\nしかし,価値ある入力した情報のみを記録するということをしなくても,入力さ れたそれぞれの情報の結合関係を生成しながら知識体系を構築することは可能\であ る上,本件製品の紹介ビデオ(甲12の図5)には,「全ての質問がアメリアの経験 や知識に加えられる」との説明があるから,「業務に特化した情報を学習するため, 業務に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」からといって,本件装置が構\n成要件1Dの「有用な情報のみを記録している」とは認められない。
ウ 控訴人は,本件製品の紹介ビデオの説明(甲12の図5,甲79,80) やパンフレットの記載(甲11の2)によると,本件装置は,入力した情報の価値を 分析し,有用な情報を自律的に記録していると主張する。 しかし,上記の紹介ビデオの説明やパンフレットの記載は,アメリアが同僚と顧 客のやりとりを観察し,処理マップを自分で作成するというものや顧客に必要な質 問を投げかけ,それに対する顧客の回答に応答するというものであり,それから直 ちに有用な情報を取捨選択し有用な情報のみを記録しているとは認められない上, 本件製品の紹介ビデオ(甲12の図5)には,「全ての質問がアメリアの経験や知識 に加えられる」との説明があるから,本件製品が構成要件1Dの「有用な情報のみを\n記録している」とは認められない。
エ 以上によると,本件装置が構成1Dを充足すると認めることはできない。\n
(5) 争点3(構成要件2C等の充足性)について\n
ア 控訴人は,構成要件2C等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自\n律的に知識を構築」の関係は並列であると主張するが,控訴人の上記主張を採用す\nることができないことは,原判決「事実及び理由」の第4の3(2)ア及びイが判示す るとおりである。 したがって,構成要件2C等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自律的\nに知識を構築」の関係が並列であるとの控訴人の主張を採用することはできない。\n
イ 控訴人は,前記関係が直列の関係であるとしても,本件装置が構成要件\n2C等を充足すると主張する。 (ア) 意味の評価について
控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や本件製品の紹介ビデオ (甲12の図5)の説明などから,本件装置は,「同じ言葉の異なる用法」の中から 「最も文脈にあてはまる用法」がどれかを評価し,知識を構築しており,本件装置\nは,情報(意味)を評価し,知識の獲得を実施していると主張する。 しかし,本件製品のパンフレット(甲11の2の3頁)の「彼女は同じ言葉の異な る用法を見分けるために文脈をあてはめることで,暗示されている意味を完全に理 解します。」との記載は,本件装置が,文脈をあてはめて言葉の用法を見分けている というにすぎず,本件装置が情報(意味)を評価した上で,その評価を踏まえて妥当 性が確認された情報を知識として獲得していることを示していると認めることはで きない。 また,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質問がアメリア の経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,意味を評価した上で,その 評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると認めることは できない。 これに対し,控訴人は,本件製品の紹介ビデオ(甲12の図5)の上記説明につい て,意味を評価し,その結果に基づいて自律的に有益な知識を獲得する機能を有し,\n全ての質問を知識として加えるというケースはあり得ると主張するが,上記の説明 は,単に全ての質問を知識として加えるという意味に理解するほかなく,本件装置 が意味を評価した上で全ての質問を知識として加えるという意味に理解することは できないから,控訴人の主張を採用することはできない。
(イ) 新規性の評価について
a 控訴人は,本件製品のパンフレットの(甲11の2)の記載からする と,本件装置は,遭遇した状況が知識として記録している場面と似ておらず,自分で 問題に対処できないことを識別する機能を有するから,新規性を評価し,知識の獲\n得を実施している旨主張する。 しかし,本件発明2は,「自律的に知識を獲得」するというものであり,人の手を 介することを予定しているものではない。しかるところ,本件製品のパンフレット\n(甲11の2の9頁)には,「自力で問題に対処できない場合,人間の同僚にその問 題を引き継ぎます。」と記載されていて,人間の同僚が介入することが予定されてい\nる上,本件装置がその後同僚の様子を見て特定の状況に対する最善の手順を見つけ ることがあるとしても,本件製品の紹介ビデオ(甲80)では,「生成した処理ステ ップの使用を管理者が了承すると,直ぐに彼女は同様の質問に対して自分自身で対 応できるようになります」と記載されていて,管理者が了承しないと,知識として獲 得されないから,本件装置が「自律的に知識を獲得」するということはできない。 仮に,控訴人が主張するように,新しい処理ステップに関しては,本件装置の管理 者が了承する前に,既に生成し,記録しているとしても,本件装置の管理者が了承し なかった処理ステップまでが知識として獲得されるものではないから,本件装置が 「自律的に知識を獲得」すると認めることはできない。
b なお,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,新規性を評価 した上で,その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは,上記(ア)と同様である。
(ウ) 真偽を評価する機能\n
a 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)や紹介ビデオ(甲 12の図5,甲79,80)には,本件装置が的確な質問を発して,「真実を明らか にする」機能(=真偽を評価する機能\)を有していることが示されていると主張す る。 しかし,本件製品のパンフレット(甲11の2)には,「問題の根本を見極めるた めの的確な質問ができる能力を持った」,「問題を明らかにするために必要な質問を\n投げかけることで,答えを提示することができます。」(6頁)との記載や,「事実 を明らかにするための的確な質問を発し,人間と同じように問題の明確な性質を顕 在化させることができるのです。」(11頁)との記載があるところ,これらの記載 と本件製品の紹介ビデオ(甲79,80)によると,本件装置の質問は,顧客の要望 を明らかにするためのものであって,真偽を判断するためのものであるとは認めら れないから,本件装置が,真偽を判断した上で,自律的に知識を獲得していると認め ることはできない。
b 控訴人は,知識に対して論理を当てはめ,プロセス全体の各ステッ プを自律的に進め,論理的な結論を得るためには,本件装置は,何が真であり,何が 偽であるかを評価する必要があると主張する。 しかし,論理的な結論を得るためには,情報間の結合関係を正確にする必要はあ るが,必ずしも入力した言語情報の真偽の妥当性を評価する必要性は認められない。
c なお,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,真偽を評価し た上で,その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると 認めることはできないことは,前記(ア)と同様である。
(エ) 論理の妥当性について
a 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載や,本件製 品の紹介ビデオ(甲79)によると,本件装置は,「積極的に論理を当てはめ」,「事 実を明らかにするための明確な質問を発し」,「問題の明確な性質を顕在化し」,「論 理的な結論を得て」,「事実を明らかにするための的確な質問」及び「回答」を記録 して知識を獲得するという一連の動作を実施していることが分かるから,本件装置 は,情報を評価(論理の妥当性)し,知識の獲得を実施していると主張する。 しかし,「論理的な結論」,「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより, アメリアは問題を解決することもできます。彼女が知っている情報の本体に立ち返 ることで,自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするための的確な質問 を発し,人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができるのです。」 との本件製品のパンフレット(甲11の2の11頁)の記載や,アメリアの「質問」 に対する顧客の「回答」が記録された本件製品の紹介ビデオ(甲79)からは,本件 装置が入力した言語情報の論理の妥当性を確認しているとまでは読み取れないし, また,論理的な結論を得るためには,情報間の結合関係を正確にする必要はあるが, 必ずしも入力した言語情報の論理の妥当性を評価する必要性は認められないから, 控訴人の主張を採用することはできない。
b 控訴人は,本件製品のパンフレット(甲11の2)の記載によると, 本件装置は,論理を適用し(=論理の妥当性を評価し),経験を通して学習している (=記録している),すなわち,言語情報の論理の妥当性を評価し,経験した内容を 知識として獲得していると主張する。 しかし,本件装置が,「・・・論理を適用し,暗示されている内容を推定し,経験 を通して学び,感情すらも察知」(甲11の2の3頁)するものであるとしても,こ のことから本件装置が入力した言語情報の論理の妥当性を評価しているとは直ちに 認められないから,控訴人の主張は採用できない。
c 控訴人は,本件製品の紹介ビデオ(甲79)には,本件装置が条件付 き処理を実施していることから,論理的に対応し,情報を記録していると主張する。 しかし,本件装置が,顧客の回答が「はい(yes)」なら,受取人リストに追加し, 回答が「いいえ(no)」なら,受取人リストに追加しないという処理をするとしても, このことは,顧客の回答に基づいた処理をしていることを示すにすぎず,本件装置 が論理の妥当性を評価しているとは認められない。 d なお,本件製品の説明ビデオ(甲12の図5)によると,「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから,本件装置が,論理性を評価 した上で,その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは,前記(ア)と同様である。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12.23
平成31(行ケ)10022 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月18日 知的財産高等裁判所
甲12,甲13及び甲15の上記各記載によれば,本件特許の出願当時, 複数の受光素子が2次元的に配列されるとともに,当該受光素子ごとに集光レンズ (マイクロレンズ)が設けられた光学的センサを用いたカメラ装置にあっては,そ の中心部と周辺部とにおける光の入射角の相違による周辺部の光量不足が,集光レ ンズを採用しないものより大きくなるという課題が存在し,その課題を解決するた めに,複数のレンズで構成される結合レンズに対し,絞りを被写体側に配置して中\n心部と周辺部との入射角の差を小さくすることにより,周辺部の光量不足を緩和す ることは,当業者の周知技術であったと認められる。
(イ) 原告は,ビデオカメラ装置とコードリーダとでは技術分野が異なり,ビデ オカメラ装置の技術はコードリーダにも適用することができるような幅広い周知技 術でないと主張する。 しかしながら,コードリーダであるIT4400は,A「複数のレンズで構成さ\nれ,読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズ」と,B 「前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され,その受光し た光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次元的に配列されると 共に,当該受光素子毎に集光レンズが設けられた,CCDエリアセンサである,光 学的センサ」と,C「該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞り」とを備 えており,上記周知技術に係るビデオカメラ装置と共通する光学系及び撮像方式を 採用していることからみても,ビデオカメラ装置と全く異なる技術分野に属すると いうことはできない。
(ウ) そして,上記周知技術が解決しようとした課題である周辺部の光量不足とは, 撮像素子の受光素子ごとに,素子開口部より大きい口径のマイクロレンズを配設し, 同レンズで集光する構成を採用したことにより生じる事象であり,用途がカメラ装\n置である場合に特有のものではなく,同様の光学系及び撮像方式を採用したコード リーダであるIT4400においても生じ得る事象であることは,当業者が普通に 認識することができたものというべきである。
ウ 容易想到性
このように技術分野と課題が共通することからすると,公然実施されたIT44 00に上記周知技術を組み合わせて,周辺部の光量不足を緩和するために,「読み取 り対象からの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう,絞りを配置 することによって,光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し, 前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子に対して入射する前記読み取り対象 からの反射光が斜めになる度合いを小さくして,適切な読取りを実現」することは, 当業者が容易に想到することができたというべきである。
エ 原告の主張について
原告は,訂正によって生じた相違点4に係る本件発明の構成に関連して,IT4\n400は,いわゆるガンタイプのコードリーダで,ある程度の大きさが許容され, 周辺部の光量不足の課題が顕在化しにくいことや,ビデオカメラ装置と2次元コー ドリーダでは求められる機能の優先順位が異なり,発光手段の有無やコンパクト化\nのニーズを含めてレンズや絞りの設計思想自体,根本的に相違していることを挙げ, IT4400に対して,上記周知技術を組み合わせる動機付けを欠く旨主張する。 しかし,周辺部の光量不足は,マイクロレンズ付き撮像素子を採用することに起 因して生じる課題であって,ガンタイプのコードリーダであれば,マイクロレンズ 付き撮像素子を採用しても,当該課題が生じないということはできないから,その 解決手段として,上記周知技術を採用することについて動機付けを欠くということ はできない。また,原告の主張する,装置に求められる機能の優先順位の相違が,上\n記周知技術の採用を阻害する事情に当たるともいえない。 よって,原告の主張は採用できない。
オ 以上によれば,本件審決の相違点1に係る容易想到性の判断に誤りはない。
(5)相違点2に係る容易想到性について
相違点2に係る本件発明の構成は,「前記光学的センサの中心部に位置する受光素\n子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の 比が所定値以上となるように,前記射出瞳位置を設定して,露光時間などの調整で, 中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにした」というものであ\nり,光学的センサの「中心部」と「周辺部」との境界や,出力の比に関する「所定値」 については,具体的に特定されていない。 そして,本件明細書【0042】には,「適切な読み取りを実現するためには,セ ンサ周辺部にある受光素子41aからの出力レベルが所定レベル以上になる必要が ある。そのため,例えば,センサ中心部に位置する受光素子41aからの出力に対 するセンサ周辺部に位置する受光素子41aからの出力の比が所定値以上となるよ う射出瞳位置を設定することが考えられる。つまり,このような射出瞳位置となる ように絞り34aの位置を設定するのである。このようにしておけば,中央部と周 辺部の出力差を考慮しながら,例えば照射光の光量や露光時間などを調整すること が容易となり,中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる。」との\n記載がある。
本件明細書の上記記載に照らすと,相違点2に係る本件発明の構成は,その実質\nにおいて,露光時間の調整など所与の調整を行うことを前提とした上で,光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読み取ることが可能となるように\n射出瞳位置を設定することをもって本件発明の構成を特定しているということがで\nきる。 そうすると,公然実施されたIT4400において,相違点1に係る構成を採用\nし,絞りを被写体側に配置するに当たりその位置を具体的に決定する際に,射出瞳 位置を「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光 学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように」 設定し,「露光時間などの調整で,中心部においても周辺部においても読取が可能\nとなるように」することは,当業者において周辺部でも適切に読み取ることを可能\nとする2次元バーコードリーダを構成する上で,適宜に採用する事項にすぎない。\nそうすると,相違点2に係る本件発明の構成も,当業者において容易に想到する\nことができたものというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.12.23
平成30(ワ)28211 商標権移転登録手続等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年10月9日 東京地方裁判所
前記1で検討した両者間の交渉経緯等からすれば,原告と被告との間では, 平成27年12月31日までに,新規独占販売契約の締結に向けての交渉が行われ てそれぞれが作成した草案が交換されているものの,交換された原告と被告の草案 には相違点が存在し,それを巡って両者間に対立が生じていたのであって,同年中 にこれが解消することはなかったというべきである。さらに,前記1(14)ないし (17)のとおり,平成28年以降も新規独占販売契約の締結に向けた交渉が継続され ていたのであり,平成27年12月31日までに原告と被告との間に新規独占販売 契約が成立していたとは認め難く,その他,新規独占販売契約の成立を認めるに足 りる証拠はない。
(2) 原告は,本件条件概要書に沿った内容で新規独占販売契約を締結する旨の原 告と被告の意思表示の合致がある以上,本件条件概要書の基本事項の限度では新規\n独占販売契約が成立していたとも主張するが,同年中にやりとりがされていた原告 と被告の草案は,被告が原告に支払うべきロイヤルティの額に下限を設けるかどう かなどの実質的な点で相違するものであり(甲12,乙4,7),前記1(11)のとお り,それぞれの草案が本件条件概要書に沿ったものであるかどうかについても互い に認識の一致が見られない状況であったことからすれば,原告の上記主張は採用で きない。
3 争点2(本件条件(新規独占販売契約の締結)の成就が擬制されるか)につ いて
(1) 争点2−1(平成27年12月31日時点での条件成就が擬制されるか)に ついて
ア 被告は,平成27年10月9日に本件買戻権の行使の見送りを求める電子メ ールを送っているが(前記1(2)),原告が本件買戻権の書面による正式な行使(前 記 1(4))をする前にされたものであり,これによって本件買戻権行使後の新規独占 販売契約の締結を妨害したとはいえない。 また,被告は,上記電子メールと同日付けの書面で,本件PR契約を平成28年 以降延長しない旨を通知しているが(前記1(3)),本件買戻権の行使によって本件商 標権が被告から原告に移転することが見込まれる状況であったことからすれば,買 戻権行使後の本件商標権に関するプロモーション業務について,被告が本件PR契 約の見直しを希望することは特段不合理とはいえず,実際に本件PR契約を平成2 7年末で終了させたこと(前記1(15))を含め,新規独占販売契約の締結の妨害に 当たるとはいえない。
イ 原告は,被告において,新規独占販売契約の更新拒絶が制限されている上で, 被告のサブライセンシーから受けるロイヤルティ料率に下限を設けていないとの本 件条件概要書の規定内容を利用して,サブライセンスのロイヤルティ料率の引下げ 見込みを通知し(前記1(9)),原告に支払うロイヤルティを半永久的にゼロにでき る旨を示唆して,原告に本件買戻権の撤回を迫った旨主張する。 しかしながら,被告が通知した内容(甲13)には,本件条件概要書の規定内容 を利用して,原告に支払われるべきロイヤルティを半永久的にゼロにできるとの趣 旨の主張をしたことをうかがわせる記載はなく,また,被告が引下げの理由につい て殊更に虚偽の説明をしたと認めるに足りる証拠もない。そして,被告が,ロイヤ ルティ料率の引下げに反対する原告の意見(前記1(10),(12))を受けて,この問 題について原告との協議に応じる用意がある旨の意見を述べていたこと(前記1 (13)),原告と被告とが平成28年以降も新規独占販売契約の締結に向けて協議を継 続していたこと(前記1(14))も考慮すれば,ロイヤルティ料率の引下げ見込みの 通知に係る被告の対応が新規独占販売契約の締結を妨害するものであったとは認め られないというべきである。
ウ 原告は,本件買戻契約第8条(c)では「条件の詳細についても別途協議し決定 する」とされており,本件条件概要書に記載がない規定については,原告と被告と の協議が予定されていたにもかかわらず,被告は,原告の提案について本件条件概\n要書に記載がないことを理由に誠実に対応しなかったと主張する。 しかしながら,前記1(7)のとおり,原告第2草案においても含まれていた被告の 売上目標に関する規定やロイヤルティ額の下限に関する規定等は,単に形式的・手 続的な事項に留まらず,新規独占販売契約における原告及び被告の収支に直接的に 影響しうる条項を含むものであったということができ,このような内容についても 本件買戻契約第8条(c)で定められている協議の対象として許容されていたといえる かについては疑問があるところである。そして,被告は,前記1(11)のとおり,原 告第2草案が本件条件概要書からかい離した内容を含むと具体的に指摘した上で, 本件条件概要書に記載のない原告第2草案の規定を削除等するように求めていたの であるから,本件条件概要書に記載がないことを理由としてこれらの条項の追加に 応じなかった被告の態度をもって本件買戻契約第8条(c)の規定に反するものであっ たとはいえず,新規独占販売契約の締結を妨害したものともいえない。このことは, 被告第2草案に被告から原告へのロイヤルティの支払時期について本件条件概要書 の記載を変更する提案が含まれていたこと(乙4,10)を考慮しても同様である。 エ 以上によれば,原告の指摘する各点を考慮しても,平成27年12月31日 までに新規独占販売契約が締結されなかったことについて,その締結を被告が故意 に妨害したとはいえず,その他,この点を認めるに足りる証拠はない。 したがって,本件条件の成就について民法130条の適用があるとした場合でも, 平成27年12月31日の時点で本件条件の成就が擬制されるとはいえない。
(2) 争点2−2(本件調停終了時点(平成30年1月16日)での条件成就が擬 制されるか)について
ア 前記(1)で検討したとおり,平成27年中に双方が提示した草案には相違点が あり,原告が提示した草案に対して,被告が本件条件概要書に記載がない条項の追 加に応じないとの対応をしたことをもって,被告が新規独占販売契約の締結を妨害 したものとは認められない。 前記1(14)及び(16)の経緯からすれば,平成28年以降も,原告と被告との間に おいては,新規独占販売契約に向けた交渉や調停手続が継続していたものであるが, 原告と被告は,互いに平成27年中に自らが提示した草案から大きく主張を変更す ることはなく,そのために本件調停を経ても新規独占販売契約の締結に至らなかっ たものと認められる。 また,被告は,前記1(17)のとおり,本件調停終了後も原告が本件訴訟を提起す る直後まで原告親会社との間での協議に応じていたものであり,本件証拠上,平成 28年以降,被告が新規独占販売契約の締結に向けた協議を殊更に拒絶したとの事 情は認められない。 そうすると,前記(1)で検討した平成27年12月31日までの事情に加え,平成 28年以後の協議等の状況を考慮しても,本件調停が終了した平成30年1月16 日までに新規独占販売契約が締結されなかったことについて,その締結を被告が故 意に妨害したとはいえず,その他,この点を認めるに足りる証拠はない。
イ したがって,本件条件の成就について民法130条の適用があるとした場合 でも,本件調停が終了した平成30年1月16日で本件条件の成就が擬制されると はいえない。
2019.12.23
平成28(ワ)2067等 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月28日 大阪地方裁判所
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって,特\n許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従 来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。\nこの本質的部分については,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許 発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何で\nあるかを確定することによって認定するのが相当である。その認定に当たっては, 特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応 じて定められることからすれば,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書記 載の従来技術との比較から認定することが相当である。 その上で,第1要件の判断,すなわち,対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には,上記のとおり確定される特許発明の本質的部分 を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し,これを備えていると認められ る場合には,相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件の場合
(ア) 本件各発明の本質的部分
a 前記1(1)のとおり,本件明細書によれば,本件各発明は,歯に付着したプラ ークの除去及び歯茎のマッサージに好適なロール歯ブラシの製造方法及びその製造 装置に関するものである。上記製造方法等に関する従来技術は,ナイロン等の多数 の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の 溶着部を形成し,溶着部を加圧して扁平状とし,扁平部の軸孔となる部分をカット して,加圧することにより素線群の全体を略円形とし,かつ扁平部を略円形とし, その後,扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し,シート状のブ ラシ単体を製作するというものである。この従来技術には,ブラシ単体の厚みを均 一とするには熟練を要し,ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密 度が不均一となり,工程数が多く複雑な工程を要するので,一貫した連続製造が困 難で回転歯ブラシの製造コストも高くなるという課題があった。そこで,これを解 決するため,本件各発明は,回転歯ブラシの製造方法として本件発明1の構成を,\n回転ブラシのブラシ単体の製造方法として本件発明2の構成を採用することで,各\n工程を画一的に処理することが可能となり,高度な熟練を要することなく均一な厚\nさのブラシ単体の製作を可能とし,また,本件発明1及び2の方法を容易に実施で\nきて,所期の目的を達成するため,回転ブラシのブラシ単体の製造装置として本件 発明3の構成を採用したものである。\n前記1(2)及び(3)のとおり,本件発明2及び3は,素線群の突出端の中央に,エア を素線群が突出させられる方向とは反対方向から吹き込んで素線群を放射方向に開 かせることとしている(構成要件G及びN)。これは,これにより,ブラシ単体を\n構成する素線同士の重なりがほとんどなくなり,均一な厚さのブラシ単体を製作す\nることができるとともに,ブラシ単体の製作速度を早くした場合にも素線を傷付け るおそれが少なくなるため,素線群の開きを高速度で行うことが可能となって,効\n率良くブラシ単体を製作することができるからである。この点に鑑みると,本件発 明2及び3の特許請求の範囲の記載のうち「素線群の突出端の中央にエアを吹き込 んで素線群を放射方向に開く」とある部分は,従来技術には見られない特有の技術 的思想を有する本件発明2及び3の特徴的部分であるといえる。
b これに対し,被告らは,本件発明2及び3の本質的部分が,エアを吹き込む ことにより素線群を簡易に均等に開くことができ,その状態で溶着,切除すること によりブラシ単体の製造を簡易かつ高速に行うことができるという点にあり,吹き 込むエアの方向が,素線群を送り出す方向とは逆方向かという相違部分は,本件発 明2及び3の本質的部分ではないと主張する。 しかし,本件発明2及び3は,上記課題の解決方法として,素線群をノズルから のエアを用いて放射方向に開くという構成を採用し,均一な厚さのブラシ単体を効\n率良く製作するために素線群を高速度で放射方向に開かせるため,素線群の突出端 の中央にエアを意図的に吹き込ませるものである。このような工程の所期の目的を 実現するための構成及び機序は,素線群を送り出す方向を基準としてエアを吹き込\nませる方向が順逆異なるのであれば,必然的に異なるものとならざるを得ない。そ の意味で,本件発明2及び3におけるエアを吹き込ませる方向は,本件発明2及び 3の特徴的部分というべきである。したがって,この点に関する被告らの主張は採用できない。
(イ) 前記1のとおり,原告製造方法は,素線群の突出端の中央にエアを吹き込ん で素線群を放射方向に開かせるという工程を備えておらず,また,原告製造装置は, 素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開かせる装置を備え ていない。すなわち,原告製造方法は本件発明2の,原告製造装置は本件発明3の 本質的部分をいずれも備えていない。このように,本件発明2と原告製造方法との 相違部分,本件発明3と原告製造装置との相違部分はいずれも本質的部分であるか ら,原告製造方法及び原告製造装置は,均等の第1要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2019.12.23
令和1(ネ)10053 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月18日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
控訴人は,当審において,本件契約第25条にいう「条件」が法的効果を伴う ものであることを争い,仮に,法的効果を伴うとしても,解除条件を定めたものと みるべきであると主張して,それが契約の効力の発生に係る停止条件であることを 争い,さらに,停止条件を定めたものであるとしても,本件においては,その条件が 成就していると主張する。 これに対し,被控訴人は,原審における経緯を踏まえると控訴人が上記のように 主張することは,自白の撤回に当たり,許されず,民訴法2条所定の信義誠実義務 にも反するとして,その適否を争う。
(2) 本件記録によれば,本件の審理の経過について,以下の事実が認められる。
ア 控訴人は,平成29年3月17日,弁護士Aに委任して,ハリマ化成グルー プ及び被控訴人を被告として,本件訴えを提起した。
イ 訴状における請求原因は,(1)ハリマ化成グループの役員が,本件契約の契約 当事者がハリマ化成グループであると控訴人を誤信させて,被控訴人との間の本件 契約を締結させ,この行為が控訴人に対する不法行為を構成するから,ハリマ化成\nグループは,会社法350条により6000万円の損害を賠償すべき責任を負う(主 位的請求1),(2)ハリマ化成グループ及び被控訴人の従業員らが,前記役員と共謀し て,控訴人の特許技術を詐取し,この行為が控訴人に対する不法行為を構成するか\nら,ハリマ化成グループ及び被控訴人は,民法715条により6000万円の損害 を賠償すべき責任を負う(主位的請求2),(3)被控訴人は,本件契約に基づき,約定 の一時金4500万円を支払う義務がある(予備的請求),というものであった。\n
ウ 控訴人は,平成29年8月28日の第1回弁論準備手続期日において,訴状 を陳述した後,上記イの主位的請求1及び同請求に係る主張を全て撤回した。 被控訴人及びハリマ化成グループは,同期日において,第1準備書面(平成29 年8月4日付)を陳述し,被控訴人において本件一時金の支払を拒絶する理由が, (1)本件契約には本件契約第25条所定の「条件」が付され,当該「条件」は停止条件 であり,これが成就していないとする停止条件の未成就,(2)本件契約第21条に基 づく「本件特許権等の実施にあたる事業の中止」を理由とする本件契約の中途解約 及び(3)本件契約第22条第1項に基づく本件契約の解除であることを主張した。
エ 控訴人は,平成29年10月3日付「訴えの取下書」をもって,ハリマ化成グ ループに対する訴えを取り下げ,ハリマ化成グループは,同月16日の第2回弁論 準備手続期日においてその取下げに同意した。また,控訴人は,同期日において,請 求原因の構成を検討する旨陳述した。\n
オ 控訴人は,第4回弁論準備手続期日(平成30年2月1日)において,準備書 面3(平成29年12月7日付)を陳述し,請求原因を,(1)控訴人と被控訴人との間 で本件契約が成立していることを理由とする本件契約所定の本件一時金4500万 円の支払請求(主位的請求),(2)本件特許権の核心的ノウハウを控訴人に提供させて 被控訴人が当該ノウハウを詐取したことが不法行為であるとする4500万円の損 害賠償請求(予備的請求)に変更した。\n
カ 原審裁判所は,第6回弁論準備手続期日(平成30年5月15日)において, これまでにおける当事者双方の主張を踏まえ,主張と争点を書面で整理するとした 上,同年6月19日に「主張の骨子レベルの整理案」と題する書面を当事者双方に 提示した。 同書面では,「(明示的には主張のない内容も含むが,当事者の言わんとするとこ ろを忖度すると,大きな構成として以下のように整理することで争点が明確になる\nのではないか。検討されたい。大きな構成としてこれで良ければ,行為,対象等を特\n定すると共に,争点ごとの主張・反論の詳細な内容の整理に進む。)」との前置きを した上,当事者双方の主張が整理されており,このうち控訴人の主位的請求原因, これに対する被控訴人の反論及び争点については,別紙「主張の骨子レベルの整理 案(抜粋)」のとおりとされた。
キ その後に開かれた弁論準備手続期日と口頭弁論期日において,控訴人は,最 終準備書面(平成31年3月19日付)を含む3通の準備書面を陳述し,口頭弁論 は終結された。 各準備書面での主位的請求原因についての主張の内容は,本件契約第25条所定 の「条件」は停止条件であるところ,本件共同研究契約等が締結されなかったのは 被控訴人が本件一時金の支払を免れるために恣意的に本件共同研究契約等を締結し なかったものであるから,停止条件である本件契約第25条所定の「条件」は成就 したものとして本件共同研究契約等は締結されたものとみなされるべきであるとい うものだけであり,前記「主張の骨子レベルの整理案」の内容に沿っている。
ク 控訴人は,原審裁判所が「主張の骨子レベルの整理案」を提示する前には,本 件契約第25条所定の「条件」は,その条件が単に債務者の意思のみに係る純粋随 意条件である旨主張していたが,法的効果を伴うものではない,当該「条件」が停止 条件でない,あるいは解除条件であるといった主張は一切しておらず,原審裁判所 から「主張の骨子レベルの整理案」を提示された後は,専ら前記キの主張をするに 至っている。
ケ 原判決は,「第4 当裁判所の判断」「1 争点1(被告が故意に本件契約第 25条の停止条件の成就を妨げたか等)について」(1)の冒頭において,次のとおり 摘示している。 「原告が主位的請求において請求しているのは,本件契約に基づく一時金の支払 であるところ,本件契約において,契約が成立してから60日以内に,被告が原告 に一時金4500万円を支払うと定められていること(第4条),本件契約では,共 同研究契約等の締結を条件とする旨規定されており(第25条),これは停止条件を 定めたものであること,及び現在に至るまで共同研究契約等が締結されていないこ とは,当事者間に争いがない。」
(3)上記(2)の原審審理経過を踏まえれば,控訴人が当審において本件契約第25 条にいう「条件」が法的効果を伴う停止条件であることを争い,また,仮に停止条件 を定めたものであるとしても,本件ではその条件が成就していると主張することは, 成立した自白の撤回に当たり,控訴人において自白をしたことにつき錯誤があった とも認められないから,その撤回は許されないというべきである。
(4)なお,念のため付言すると,本件契約は,法人を当事者とし,書面において双 方の意思表示がされている契約であるところ,本件契約第25条の見出しとその文\n言からすれば,これが法的効果を伴わないとか,解除条件であると解する余地はな く,本件契約の効力の発生について停止条件を付すものであると解するほかないも のである。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.12.23
平成31(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月11日 知的財産高等裁判所
本件で主に問題とされているのは実施例2であるが,その検討の前提と して,本件当初発明の意義及び実施例2の変更元である実施例1について まず検討する。 本件当初発明は,特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所 定の位置に達した際に,出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え,エア圧の変化を介して前記\n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す\nるものであり(段落【0001】),流体圧シリンダの小型化,出力部材 の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである(段落【0 011】,【0021】ないし【0023】)。 実施例1は,第1エア通路21のエア圧を介して,出力部材4が上昇限 界位置にあることを検出する為の第1開閉弁機構30,第2エア通路22\nのエア圧を介して,出力部材4が下降限界位置にあることを検出する為の 第2開閉弁機構50を備えるクランプ装置1である(段落【0036】)。\n第1開閉弁機構30は,油圧導入室33が,油圧導入路34を介して,ク\nランプ油室14に接続され,クランプ油室14に油圧が供給されると,油 圧導入路34から油圧導入室33に油圧が導入され,その油圧が弁体本体 38を進出方向へ付勢し,閉弁状態から開弁状態となる。逆に,クランプ 装置1がアンクランプ状態になったとき,油圧導入室33の油圧がドレン 圧になり,ピストンロッド部材4aの大径ロッド部4eにより弁体本体3 8がキャップ部材32側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる(段 落【0057】ないし【0059】)。第2開閉弁機構50は,クランプ\n装置1がアンクランプ状態のとき,アンクランプ油室15の油圧が,油圧 導入孔(路)54から油圧導入室53へ導入され,油圧導入室53の油圧 により弁体51が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に, アンクランプ油室15の油圧をドレン圧に切換え,ピストンロッド部材4 aが下降限界位置まで下降すると,弁体本体58がピストン部4pにより 下方へ押動され,開弁状態から閉弁状態に切換わる(段落【0069】, 【0070】)。また,本件当初明細書には,実施例1の効果として,エ ア通路のエア圧を介して,クランプ状態になったこと,又は,出力部材の 所定の位置を確実に検知できること(段落【0070】,【0073】), 第1,第2開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため,油\n圧シリンダ1を小型化することができること(段落【0071】),第1, 第2開閉弁機構では,クランプ油室内(第2開閉弁機構\においてはアンク ランプ油室内)の油圧を油圧導入室に導入し,その油圧を弁体に作用させ て,弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため,信頼性と耐久性の面 で有利であること(段落【0072】)が記載されている。
イ(ア) 次に,本件当初明細書には,実施例2として,実施例1の第2開閉 弁機構50を部分的に変更し,弁体本体58Aの下端部分に形成した凹\n穴58dと油圧導入室53に圧縮コイルスプリング53aを装着するこ とで,弁体本体58Aが,油圧導入室53の油圧によって上方へ付勢さ れると共に,圧縮コイルスプリング53aによって上方へ付勢されるよ うにした第2開閉弁機構50Aが開示されている(段落【0074】,\n【図11】,【図12】)。ここで,圧縮コイルスプリング53aは「ク ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に,アンクランプ油室1 5に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における,弁体5 1の作動確実性を高める」(段落【0075】)ものとされているから, 実施例2において,弁体本体58Aを上方へ付勢する力は,主としてア ンクランプ油室15から油圧導入路54を通じて油圧導入室53に導入 される油圧によるものであって,圧縮コイルスプリング53aは,油圧 による付勢力が立ち上がるまでの間,補助的に用いられるものと認めら れる。
(イ) 発明の効果との関係で,第2開閉弁機構50Aは,「実施例1の油\n圧シリンダと同様の効果を得られる」(段落【0075】)ものである とされている。ここで,実施例1の油圧シリンダの効果の1つとして, アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し,その油圧を弁体に作 用させて,弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため,信頼性と耐 久性の面で有利であることが記載されていることは,前記アのとおりで ある。よって,実施例2における油圧導入室53と油圧導入路54は, 信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成\nといえる。 また,油圧シリンダの小型化という効果について,段落【0071】 には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの,段落【00 21】に,「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け,\nこの開閉弁機構は,弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え,\n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで,開閉弁機構を\nシリンダ本体内に組み込むことができるため,流体圧シリンダを小型化 することができる」と記載されていることからすれば,実施例2におい て油圧導入室53と油圧導入路54とを備えることが,油圧シリンダの 小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は,段落【002 1】の記載は,本件当初発明1に規定された「開閉弁機構」の構\成を列 挙したものにすぎないと主張するが,現に記載がある以上,それを無視 することはできない。 このように,実施例2において,油圧導入室53と油圧導入路54は, 発明の効果と結びつけられた構成といえる。\n
ウ 実施例3は,実施例1の第2開閉弁機構50を部分的に変更し,環状部\n材57を省略した第2開閉弁機構50Bとするものである(段落【007\n6】)。 実施例4は,実施例3の第2開閉弁機構50Bを部分的に変更し,キャ\nップ部材52Cの内部にカップ状のカップ部材52cを設けた第2開閉弁 機構50Cとするものである(段落【0080】,【0081】)。\n実施例5は,開閉弁機構を,弁体31D,51を可動弁体なしで弁体本\n体38,58のみで構成するとともに,出力部材の位置と開閉弁機構\の開 閉状態との関係を実施例1の場合と逆にした第1開閉弁機構30D,第2\n開閉弁機構50Dとするものである(段落【0084】,【0085】,\n【0089】,【0090】,【0092】)。 実施例6ないし8は,開閉弁機構については,実施例1または5と同様\nの構造である(段落【0096】,【0106】,【0112】,【01\n13】)。 このように,実施例3ないし8は,いずれも開閉弁機構については,実\n施例1と同様に,流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ て,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また,実\n施例3ないし8は,いずれも実施例1と同様の効果が得られるとされてい る(段落【0079】,【0083】,【0093】,【0100】,【0 111】,【0118】)
エ 段落【0119】及び【0122】には,前記実施例を部分的に変更す る例として,「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用\nすることができる。」とされているが,変更の具体的な内容は記載されて いない。
オ 本件当初発明7は,「前記開閉弁機構は,前記弁体を前記出力部材側に\n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項1に記載の流体圧 シリンダ。」というものである。 本件当初発明7は,本件当初発明1を引用するところ,本件当初発明1 は,「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ た状態に保持する流体圧導入室と,前記流体室と前記流体圧導入室とを連 通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから,本件当初発明7も, 流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり,段 落【0029】の記載も,かかる理解と整合的である。 カ 以上のとおり,本件当初明細書等の記載のうち,実施例2の構成は,油\n圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主と し,圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである (前記イ(ア))。かかる構成から,主である油圧による付勢に係る構\成を あえてなくし,補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢 するという構成を導くことはできないというべきであり,実施例2におい\nては,油圧導入室53と油圧導入路54が発明の効果と結びつけられて記 載されていること(前記イ(イ))を考慮するとなおさらである。段落【0 119】及び【0122】の記載は,具体的な変更内容を示すものではな いから(前記エ),上記認定を左右しない。また,本件当初明細書のその 他の実施例は,流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部 材側に進出させた状態に保持する構成である(前記ウ)。本件当初明細書\n等のその他の部分にも,流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に\nついての開示はない。 そのため,開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな\nく,弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する 構成は,当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること\nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,段落【0122】において開閉弁機構の改変が示唆され,実施\n例2においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること,\nその改変後の進出機構(実施例2)において,弾性部材を用いることも明\n示されていること,「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない\nし技術常識であることから,かかる構造を選択することは当業者にとって\n極めて自然であり,本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進 出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機(示 唆)が本件当初明細書等に含まれていると主張する。 しかし,段落【0122】の記載は,変更の具体的な内容を示すもので ないことは前記(3)エのとおりである。また,開閉弁機構の変更は,環状部\n材57の省略,キャップ部材52Cの内部にカップ状のカップ部材52c を設ける,出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると\nいうように,弁体を進出させる構成に係る変更に限られない(前記(3)ウ)。 一方,実施例1及びそれと同様の効果を有するとされている実施例2ない し8においては,流体圧導入室(油圧導入室)と流体圧導入路(油圧導入 路)は,発明の効果と結びつけて記載されているのである(前記(3)アない しウ)。そうだとすれば,段落【0122】の記載から,開閉弁機構を変\n更することは読み取れても,その変更の内容として,流体圧を用いない構\n成とすることは想定しがたい。 そのため,当業者にとって,流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出 させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても,段落【0\n122】等の記載から,本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を\n結びつけ,現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな\nい。
イ 原告は,本件当初明細書等には,(1)「出力部材が所定の位置に達したこ とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可 能で小型化可能\な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と, (2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧 シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という2つの別個独立の発明 が示されており,前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は 必須の構成ではないから,「弾性部材単独構\造」は,本件当初明細書の段 落【0122】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの であると主張する。 しかし,仮に,(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても, 実施例2を含む各実施例は,(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ\nているのであり(前記(3)アないしウ),そこから(2)の課題解決のための構\n成をあえてなくすことは,本件当初明細書等の記載から導けることではな い。 また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても,(1)の効果との 関係でも開閉弁機構が,「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える\nことが記載されている(前記(3)イ(イ))一方で,これらを備えない構成で\nの解決手段については何ら記載されていないから,「弾性部材単独構造」\nを採用することにはならない。
ウ よって,原告の主張は採用できない。
2 結論
以上のとおり,本件補正は,当業者によって本件当初明細書等のすべての記 載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的 事項を導入しないものであるとは認められず,この点に関する本件審決の判断 に誤りはないから,取消事由1は理由がない。そして,新規事項を追加する補 正をしたことは,そのこと自体が無効理由とされているから(特許法123条 1項1号),本件特許は,取消事由2(サポート要件)の理由の有無に関わら ず,無効とされるべきものである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2019.12.15
平成29(ワ)11147 損害賠償請求事件 特許権 令和元年11月11日 大阪地方裁判所
原告は,被告各製品の「第2の軸体8」が「流体の流れる方向が周期的に交互に 方向変換して流れる現象」の意味での「フリップフロップ現象」を発生させるため に使用される軸体であることを直接的に裏付け,これを認めるに足りる証拠を提出 しない。 かえって,証拠(乙40)によれば,被告が,「第2の軸体8」を通過するクー ラント液の状況を検証するため,被告製品(3/8inch)について,本来金属製である 接続機構6’を含む筒本体2及び入口側接続部材4を,下記【参考写真】のように\n透明プラスチック製のものにした上で(以下「実験対象物」という。),その内部 にクーラント液を通過させる実験を行ったところ,クーラント液につき,実験対象 物の入口側接続部材から流入し始めてから16分22秒の間,「第2の軸体8」の 軸部の外周面に形成された凸部32の間の交差流路を流れる際,その「流れる方向 が周期的に交互に方向変換して流れる現象」すなわち「フリップフロップ現象」の 発生が観察されなかったことが認められる。この実験結果の信用性につき,本来金 属製の部分を透明プラスチック製のものとしたことを考慮しても,疑義を差し挟む べき具体的な事情はない。
また,前記認定によれば,被告各製品の「第2の軸体8」の構成は,主として凸\n部32の形状につき各製品相互間で異なるものと見られる。もっとも,被告製品 (3/8inch)の「第2の軸体8」がフリップフロップ現象を発生させなかったにもか かわらず,他の被告製品(1/4inch,1/2inch,3/4inch,1inch)の「第2の軸体8」 がフリップフロップ現象を発生させるものであると見るべき具体的な事情はない。 原告自身,被告各製品の構成には,本件各発明の構\成要件充足性を検討するに当た って,有意な相違はないと主張しているところでもある。 以上によれば,被告各製品の「第2の軸体8」は,クーラント液を通過させても 「フリップフロップ現象」を発生させ得るものと認めることはできない。そうであ る以上,被告各製品の「第2の軸体8」は,「フリップフロップ現象発生用軸体」 (構成要件E,F)に当たらない(なお,仮に,被告各製品が,別紙「被告各製品\n構成目録(原告主張)」記載のとおりの構\成を有するとしても,その「第2の軸体 8」が,クーラント液を通過させると「フリップフロップ現象」を発生させ得るも のと認めることはできないことに変わりはないから,上記結論が異なるものではな い。)。 したがって,被告各製品の構成は,本件発明1の構\成要件E,Fを充足しない。 また,前記第2の2(4)のとおり,本件において,原告は,被告各製品の構成が本件\n特許の請求項2に係る発明の構成要件を充足するとの主張を撤回した。そうすると,\n被告各製品の構成は,本件発明3の構\成要件Mを充足しない。
(3) 原告の主張について
原告は,被告各製品の「第2の軸体8」が「フリップフロップ現象発生用軸体」 当たるとする根拠として,被告各製品のパンフレット(甲6)及び被告の特許に係 る特許公報(甲18の2及び3)の各記載を指摘する。 このうち,前者については,被告各製品である「ビックスは『フリップフロップ 流れ』を応用しています。水などの流体を菱型の柱を網目状に配列した四角の管に 通すと,管内に生じる渦により,管体から噴出する液体が,左右に規則正しくスイ ッチングする現象のことをフリップフロップ流れと言います。」などという記載が ある。しかし,ある性能等が製品のパンフレットに記載されているからといって,\n真実当該製品が当該性能等を有するとは限らない(そもそも,上記「フリップフロ\nップ現象」の説明は,原告主張に係る本件各発明での「フリップフロップ現象」の 意味とは異なる。)。 他方,後者については,そもそも被告各製品が後者の特許公報に記載された発明 の実施品であることを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,上記実験結果(乙40)にもかかわらず,これらの記載のみをもっ て,被告各製品の「第2の軸体8」がフリップフロップ現象を発生させ得ることを 認めること,ひいては被告各製品の「第2の軸体8」が「フリップフロップ現象発 生用軸体」であること(構成要件E,F)を認めることはできない。\nしたがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(4) 以上より,被告各製品の構成は,本件発明1の構\成要件E及びFを充足せず, 本件発明3の構成要件Mも充足しないから,被告各製品は,本件各発明の技術的範\n囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.12.15
平成30(行ケ)10110等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月14日 知的財産高等裁判所
原告らは,本件明細書の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の技術常識か ら,本件発明1の「粒子の最大長において,セレコキシブ粒子のD90が200 μm未満」という数値範囲の全体にわたり,当業者が本件発明1の課題を解決 できると認識できるものではないから,本件発明1は,サポート要件に適合せ ず,また,本件発明2ないし5,7ないし9も,同様に,サポート要件に適合 しないから,本件発明1〜5,7〜19は,サポート要件に適合するとした本 件審決の判断は誤りである旨主張するので,以下において判断する。
(1) 本件発明1のサポート要件の適合性について
ア 特許法36条6項1号は,特許請求の範囲の記載に際し,発明の詳細な 説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したもの であり,その趣旨は,発明の詳細な説明に記載していない発明について特 許請求の範囲に記載することになれば,公開されていない発明について独 占的,排他的な権利を請求することになって妥当でないため,これを防止 することにあるものと解される。 そうすると,所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について,特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件(サポート要件)に適合するか否かは, 当業者が,発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から,当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができ ると認識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 これを本件発明1についてみると,本件発明1の特許請求の範囲(請求 項1)の記載によれば,本件発明1は,「一つ以上の薬剤的に許容な賦形 剤と密に混合させた10mg乃至1000mgの量の微粒子セレコキシ ブ」を含む「固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物」に関す\nる発明であって,「粒子の最大長において,セレコキシブ粒子のD90が2 00μm未満である粒子サイズの分布を有する」ことを特徴とするもので あるから,所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。 そして,前記1(2)の本件明細書の開示事項によれば,本件発明1は,未 調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経口運搬\n可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することを課題とするも\nのであると認められる。
イ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には,セレコキシブの生物学的利用 能に関し,「発明の組成物は,粒子の最長の大きさで,粒子のD90が約\n200μm以下,好ましくは約100μm以下,より好ましくは75μ m以下,さらに好ましくは約40μm以下,最も好ましくは約25μm 以下であるように,セレコキシブの粒子分布を有する。通常,本発明の 上記実施例によるセレコキシブの粒子サイズの減少により,セレコキシ ブの生物学的利用能が改良される。」(【0022】),「カプセル若\nしくは錠剤の形で経口投与されると,セレコキシブ粒子サイズの減少に より,セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見した。したが\nって,セレコキシブのD90粒子サイズは約200μm以下,好ましくは 約100μm以下,より好ましくは約75μm以下,さらに好ましくは 約40μm以下,最も好ましくは25μm以下である。例えば,例11 に例示するように,出発材料のセレコキシブのD90粒子サイズを約60 μmから約30μmに減少させると,組成物の生物学的利用能は非常に\n改善される。加えて又はあるいは,セレコキシブは約1μmから約10 μmであり,好ましくは約5μmから約7μmの範囲の平均粒子サイズ を有する。」(【0124】),「湿式顆粒化過程にて,(必要ならば, 一つ又はそれ以上のキャリア材料とともに)セレコキシブは先ず粉砕さ れる若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕器若し くは破砕器が利用することが可能であるが,セレコキシブのピンミリン\nグのような衝撃粉砕により,他のタイプの粉砕と比較して,最終組成物 に改善されたブレンド均一性がもたらせる。例えば,液体窒素を利用し てセレコキシブを冷却することは,セレコキシブを不必要な温度へ加熱 させることを回避するために,粉砕中に必要なことである。前記にて議 論したように,上記粉砕工程中にD90粒子サイズを約200μm以下, 好ましくは約100μm以下,より好ましくは約75μm以下,さらに 好ましくは約40μm以下,最も好ましくは約25μm以下に小さくす ることは,セレコキシブの生物学的利用能を増加させるためには重要で\nある。」(【0135】)との記載がある。これらの記載は,未調合の セレコキシブを粉砕し,「セレコキシブのD90粒子サイズが約200μ m以下」とした場合には,セレコキシブの生物学的利用能が改善される\nこと,セレコキシブのピンミリングのような衝撃粉砕により,他のタイ プの粉砕と比較して,最終組成物に改善されたブレンド均一性がもたら せることを示したものといえる。
一方で,(1)本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,「粒子の 最大長において,セレコキシブ粒子のD90が200μm未満である粒子 サイズの分布を有する」構成とする具体的な方法を規定した記載はなく,\n本件発明1の「微粒子セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉 砕」により粉砕されたものに限定する旨の記載もないこと,かえって, 本件明細書の【0135】には,セレコキシブの微細化に関し,「さま ざなま粉砕器若しくは破砕器が利用することが可能である」との記載が\nあること,(2)本件明細書の【0008】には「セレコキシブは,水溶性 媒体には異常なほど溶解しない。例えば,カプセル形態で経口投与させ た場合,未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために, 容易には溶解せず,分散もしない。加えて,長く凝集した針を形成する 傾向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは,通常,錠剤成形 ダイでの圧縮の際に,融合して一枚岩の塊になる。他の物質とブレンド させたときでも,セレコキシブの結晶は,他の物質から分離する傾向が あり,組成物の混合中にセレコキシブ同士で凝集し,セレコキシブの不 必要な大きな塊を含有する,非均一なブレンド組成物になる。」との記 載があること,(3)本件優先日当時,粉砕によって薬物の粒子径を小さく し,比表面積(有効表\面積)を増大させることにより,薬物の溶出が改 善されるが,他方で,難溶性薬物については,溶媒による濡れ性が劣る 場合には,粒子径を小さくすると凝集が起こりやすくなり,有効表面積\nが小さくなる結果,溶解速度が遅くなることがあり,また,粒子を微小 化することにより粉体の流動性が悪くなり凝集が起こりやすくなること があることは周知又は技術常識であったことに照らすと,難溶性薬物で あるセレコキシブについて,「セレコキシブのD90粒子サイズが約20 0μm以下」の構成とすることにより,セレコキシブの生物学的利用能\ が改善されることを直ちに理解することはできない。
また,本件明細書の記載を全体としてみても,粒子の最大長における セレコキシブ粒子の「D90」の値を用いて粒子サイズの分布を規定する ことの技術的意義や「D90」の値と生物学的利用能との関係について具\n体的に説明した記載はない。
しかるところ,「D90」は,粒子の累積個数が90%に達したときの 粒子径の値をいうものであり,本件発明1の「D90が200μm未満で ある」とは,200μm以上の粒子の割合が10%を超えないように限 定することを意味するものであるが,難溶性薬物の原薬の粒子径分布は, 化合物によって様々な形態を採ること(甲イ72)に照らすと,200 μm以上の粒子の割合を制限しさえすれば,90%の粒子の粒度分布が どのようなものであっても,生物学的利用能が改善されるとものと理解\nすることはできない。 以上によれば,本件明細書の【0022】,【0124】及び【01 35】の上記記載から,「セレコキシブのD90粒子サイズが約200μ m以下」とした場合には,その数値範囲全体にわたり,セレコキシブの 生物学的利用能が改善されると認識することはできない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.12.11
平成29(ワ)1468 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 東京地方裁判所
3 争点2(本件各発明に対する被告の貢献度)について
特許法35条4項は,従業者等と使用者等の利害を調整する趣旨の規定であり, 同項の「使用者等が貢献した程度」を判断するに当たっては,使用者等が「その発明 がされるについて」貢献した事情のほか,特許の取得・維持●(省略)●に要した労 力や費用等を,使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情 として考慮し得るものと解するのが相当である。 そこで,検討すると, とおり,被告が,本件各発明に先立 ち,●(省略)●同イ認定のとおり,平成5年には,MらによるHIPEの重合物の 研究を行わせ,その中では,同ウ認定のとおり,平成8年以降の研究開発において用 いられたものと類似する組成の吸水性スポンジを作製するなどするとともに,HIP Eを連続で重合することや二段階で重合することを開示する131号特許を出願す るに至っていること,(2)同ウ認定のとおり,平成8年には,M,N及び原告にHIP Eの研究を指示して平成5年当時よりもより性能の高いFAMの作製を行っており,\n●(省略)●などしていたこと,(3)同エ認定のとおり,●(省略)●平成9年10月 にはFAMプロジェクトを立ち上げ,多数の研究員を研究開発に充てるとともに,同 (6)認定のとおり,FAMの研究に必要な機器や設備の調達を含めた開発費用を提供し, また,特許の取得及び維持の費用を支出し 認定のとおり,●(省 略)●本件各発明についての被告の貢献に係る事情であるといえる。 これに対し,本件各発明の発明者らは,被告の費用負担の下,被告に雇用された後 に得た知識経験に基づき,FAMプロジェクト内で知見を共有しつつ,発明に至った にとどまる。
そうすると,本件各発明が原告ら共同発明者の努力及び創意工夫によって創作され たことは確かであるが,他方で,共同発明者らは,被告による費用負担の下,被告入 社後に得た知識経験に基づき,FAMプロジェクトでの職務を通じて,本件各発明を 完成させるに至ったとみることができる。また,●(省略)●被告が●(省略)●そ のための研究開発を行っていたのみならず,●(省略)●本件各発明の共同発明者の みならず,その他の部署に属する多数の従業員の協力によるものであるということが できる。
以上の事情を総合考慮すると,本件各発明により被告が受けるべき利益につい て,被告の貢献度は高く,その貢献度は95%と認めるのが相当である。
原告の主張について
ア 原告は,(1)被告が平成5年に研究開発していたHIPEの重合物は,FAMと は異なるものであり,しかも,被告は,平成6年2月に同研究開発を中断しているこ と,(2)原告が,平成8年4月から自発的にFAMに関する研究開発を開始してこれを 主導し,同年6月5日,上記の被告の研究開発における原料とは異なるスチレン系の 原料を用いて初めてW/O比が45倍以上のFAMの作製に成功し,実質的な発明者 が原告である2件の特許出願につながっており,かつ上記の成果が,●(省略)●検 討を加速させたのであり,原告の貢献なしに平成9年10月以降のFAMの研究はな し得ないものであって,Mは管理者,Nは補助者として関与したにすぎないこと,(3) FAMプロジェクト立ち上げ後も原告のみがFAMの研究を行っていたこと,(4)原告 が,●(省略)●FAM製造に必要な特殊な攪拌用の羽根の情報を引き出してこれを 特注し,あるいは●(省略)●ほか,平成9年10月以降の被告におけるFAMの研 究に必要な種々の機器・設備の選定,導入等の研究環境の整備も行ったことなどの事 情を指摘して被告の貢献度は50%を超えるものではない旨主張する。
イ しかしながら,次のとおり,原告の指摘する事情は認めることができないか, 左右し得ず,原告の主張を採用することはできない。 原告の指摘する(1)の事情について 確かに131号特許に開示されたHIPE重合物の組成は,平成8年4月以降の研 究開発の対象の組成とは異なるが,前記 のとおり,被告が平成5年当時に得た知 見にも本件各発明に関連するものがある以上,同年当時に行われた研究成果は,その 後の研究開発の基礎となり,本件各発明にも寄与していると推認され,本件各発明に 対する被告の貢献に当たるというべきである。
原告の指摘する(2)の事情について
原告は,FAMの研究開発を自発的に行うこととしたきっかけの一つとして,平成 8年4月19日のミーティングで,Mから,●(省略)●HIPEの供給元を探して いることを聞いたことを認めている(甲23)が,Mがミーティングで●(省略)● 対応をする旨の被告の決定がされていたとみるのが自然であるし,それ以降の被告内 のHIPEの研究状況を見ても, 原告がMの指示を受けて研究 を進めたり,原告のみならずM及びNも,自らHIPE重合物を作製したり,原告と 役割を分担したりするなどして研究を進めるなどし,研究成果を3名で共有するなど もしているほか,これらの研究結果を踏まえてされた特許出願においても,発明者は 原告,M及びNの3名とされている。そうすると,平成8年4月以降に被告において 行われた研究は,被告の指示により上記3名が共同して行ったものというべきであり, 原告が自発的に行い,Mは管理者として,Nは補助者として関与した旨の原告の主張 は認めることができない。
原告の指摘する(3)の事情について
前記1 ないし 認定したとおり,FAMプロジェクト開 始後は,参加した研究員がそれぞれ役割を分担して研究を行い,定期的にミーティン グを行って知見を共有しながら研究を進めていたものということができるから,原告 のみがFAMの研究を行っていた旨の主張は認めることができない。
原告の指摘する(4)の事情について
原告が●(省略)●FAM製造に必要な特殊な攪拌用の羽根の情報を引き出してこ れを特注したり,あるいは●(省略)●が実現したり,原告が,このような情報を得 たことがあったとしても,Mと●(省略)●が話題とされていること(乙26)にも 照らせば,他の被告の従業員も関与する中で,被告の従業員の一員の立場で行われた ものとみるのが自然であり,そうすると,そのことをもって直ちに原告の本件各発明 に対する貢献度が大きいといえるものではない。また,原告が導入すべき機器や設備 を提案していたとしても,最終的にその機器や設備の導入を決定し,その資金を提供 したのは被告である以上,上記の提案の存在をもって,原告の本件各発明に対する貢 献の度合いに大きな影響を与える事情であるとはいえない。
被告の主張について
被告は,●(省略)●全社を挙げてFAMの研究開発を進めたこと,●(省略)● 被告の対応が大きく寄与していることなどを主張して,被告の貢献度は99%を下ら ない旨主張するが,被告の指摘する上記事情が被告の貢献として認められることは前 のとは認められず,被告の主張を採用することはできない。
・・・・
5 相当の対価の額
以上を前提に相当の対価の額を計算すると次のとおりとなる(いずれも1円未 満の端数は切り捨て。)。
ア 144号発明等 各発明につきそれぞれ●(省略)●円(●(省略)●円×0. 05×1/4=●(省略)●円) イ 642号発明等 各発明につきそれぞれ●(省略)●円(●(省略)●円×0. 05×1/9=●(省略)●円) ウ 811号発明等 各発明につきそれぞれ●(省略)●円(●(省略)●円×0. 05×2/5=●(省略)●円) 係る国内
出願及び国内特許登録について,同アの規定に従った出願補償金及び登録補償金の支 払をしている 国内特許に係る発明に係る相当の対価からこれらを控除 する必要がある。そして,同規定の定めに従えば,原告についての支払額は次のとお りと認められる(1円未満の端数があるものはいずれも切り捨て。)。
ア 144号発明 ●(省略)●円 出願補償金 ●(省略)●円(●(省略)●円×2×1/5=●(省略)●円) (乙114の1,2,乙129) 登録補償金 ●(省略)●円(●(省略)●円×1/5=●(省略)●円)
イ 642号発明 ●(省略)●円 出願補償金 ●(省略)●円(●(省略)●円×1/6=●(省略)●円)(乙 120の1,乙130) 登録補償金 ●(省略)●円(●(省略)●万円×1/9=●(省略)●円)
ウ 811号発明 ●(省略)●円 出願補償金 ●(省略)●円(●(省略)●円×1/5=●(省略)●円)(乙 124,131) 登録補償金 ●(省略)●円(●(省略)●円×1/5=●(省略)●円) 国内特許に関し 相当の対価 となる。
ア 144号発明 ●(省略)●円(●(省略)●円−●(省略)●円=●(省略) ●円)
イ 642号発明 ●(省略)●円(●(省略)●円−●(省略)●円=●(省略) ●円)
ウ 811号発明 ●(省略)●円(●(省略)●円−●(省略)●=●(省略) ●円)
以上によれば,相当の対価の額は合計226万4061円である。
ア 144号発明等 ●(省略)●円(●(省略)●円+●(省略)●円×3=● (省略)●円)
イ 642号発明等 ●(省略)●円(●(省略)●円+●(省略)●円×5=● (省略)●円)
ウ 811号発明等 ●(省略)●円(●(省略)●円+●(省略)●円×2=● (省略)●円)
エ アないしウの合計 226万4061円
2019.12.11
令和1(行ケ)10089 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和元年11月26日 知的財産高等裁判所
意匠法3条2項は,物品との関係を離れた抽象的モチーフとして意匠登 録出願前に日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色 彩又はこれらの結合を基準として,当業者が容易に創作をすることができ る意匠でないことを登録要件としたものであることに照らすと,意匠登録 出願に係る意匠について,上記モチーフを基準として,その創作に当業者 の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるものと認められな い場合には,当業者が容易に創作をすることができた意匠に当たるものと して,同項の規定により意匠登録を受けることができないものと解するの が相当である(最高裁昭和45年(行ツ)第45号同49年3月19日第 三小法廷判決・民集28巻2号308頁,最高裁昭和48年(行ツ)第8 2号同50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号287頁参 照)。
これを本願意匠についてみるに,前記1認定のとおり,本願意匠は,薄 い円形板に,角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を, 同一の方向性に向きを揃え,各抜き穴の中心部を結んだ線のなす角度が6 0°となるような千鳥状(「60°千鳥」)の配置態様で19個形成した 「押出し食品用の口金」の意匠であり,また,本願意匠に係る「押出し食 品用の口金」は,主にステンレス製の薄板で作成され,ハンディーマッシ ャー(押し潰し器)等に装着して使用され,抜き穴から食品を棒状に押し 出すことができるものであり,略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を 設けた上記調理器具に装着して使用されるものである。 しかるところ,前記(1)ア及びイの認定事実によれば,本願意匠に係る「押 出し食品用の口金板」の物品分野においては,抜き穴から食品を棒状に押 し出す調理器具に使用される金属製の円形板の口金板に設けられた,角部 に面取りを施した5つ又は6つの凸部からなる星形の抜き穴の形状は,本 願の出願当時,公然知られていたことが認められる。 加えて,前記(1)エ(エ)認定のとおり,板状の金属材料にデザイン性を持 たせるため,60°千鳥の配置態様で,複数個の「抜き孔」を設けること は,本願の出願当時,ごく普通に行われていたことであり,当業者にとっ てありふれた手法であったこと,19個の抜き穴を千鳥状に配置する形状 は公然知られていたこと(例えば,意匠3)に照らすと,本願意匠は,本 願の出願当時,円形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取 りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴(例えば,意匠1)を,当業 者にとってありふれた手法により,薄い円形板に,同一の方向性に向きを 揃えて,60°千鳥の配置態様で19個形成して創作したにすぎないもの といえるから,本願意匠の創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新 しさないし独創性があるものとは認められない。 したがって,本願意匠は,本願の出願前に公然知られた形状の結合に基 づいて,当業者が容易に創作をすることができたものと認められる。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し原告は,本願意匠は,星形の抜き穴を1枚の無垢の円形板 に複数個,均等に穿設する際に,円形板と,整列した抜き穴が構成す\nる図形と,抜き穴のない周縁部分が,唯一無二の美感を与えるように, 個々の抜き穴のサイズを決定し,抜き穴の数を19個とし,これを千 鳥状に配置したものであり,本願意匠は,抜き穴のうち外側に配置され た抜き穴が形成する正六角形と,その外側の蒲鉾状の周縁部分及び円 形板の円形の全てが,円形板の中心点を中心として均等に整然と配置 され,落ち着きと,併せてリズム感ないし安定性を表現している,こ\nれにより,本願意匠は,独特の美感をもたらし,これまでにない美感 を看者に与えるものであるから,本願意匠の創作には当業者の立場から みた意匠の着想の新しさないし独創性があるとして,本願意匠は,本願の 出願前に公然知られた形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をするこ とができたものとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記ア認定のとおり,本願意匠は,本願の出願当時,円 形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取りを施した5つの 凸部からなる星形の抜き穴(例えば,意匠1)を,当業者にとってありふ れた手法により,薄い円形板に,同一の方向性に向きを揃えて,60°千 鳥の配置態様で19個形成して創作したにすぎないものである。 そして,前記1(2)認定のとおり,本願意匠に係る物品「押出し食品用の 口金」は,略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を設けた調理器具に装 着して使用され,抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものであ ることに照らすと,調理器具の環状縁部と当接する口金の周縁部分に抜き 穴を形成することができない余白部分が生じ得ることは,当業者であれば, 当然想定するものといえる。また,円形板の口金に,角部に面取りを施し た5つの凸部からなる星形の抜き穴を,同一の方向性に向きを揃えて,6 0°千鳥の配置態様で19個配置する場合には,円形板の直径と円形板に 配置する星形の抜き穴に外接する円形の直径の比率,抜き穴と抜き穴の中 心間隔(ピッチ)等に応じて,口金の周縁部分の余白部分の大きさは一定 の範囲内のものに収まること,円形板の中心に星形の抜き穴を配置し,こ れを中心点として19個の星形の抜き穴を60°千鳥に配置した場合,外 側に配置された星形の抜き穴の周縁部側の凸部先端をそれぞれ直線で結ん だ図形は正六角形となり,この図形と円形板の外周とで形成される余白部 分が蒲鉾状となることは自明であることに照らすと,別紙第1記載の本願 意匠の余白部分の形状の創作に着想の新しさないし独創性は認められない。
2019.12.11
平成30(行ケ)101 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月28日 知的財産高等裁判所
前記(1)の甲1の内容,上記アで認定した本件優先日当時の公知文献の内 容や技術常識に鑑みて,相違点2が容易想到といえるかどうかについて検討する。
(ア) 前記(1)で認定したとおり,甲1には,GAR-トランスホルミラーゼ阻 害剤の治療効果を維持しつつ,その毒性を減少させることを課題とする旨が記載さ れているところ,甲1では葉酸をGAR-トランスホルミラーゼ阻害剤と組み合わせ て投与することによって同課題を解決できるとしており,同課題に関して,更に別 の活性成分,例えば,ビタミンB12を積極的に適用する動機や示唆は甲1には何ら 記載されていない。 これに加えて,上記ア(ア)(イ)の甲2〜4,44からすると,本件優先日前にMT Aの抗腫瘍活性を維持しつつ毒性を低減させるという目的のために,MTAと葉酸 を併用投与することに言及する公知文献は複数存在し,上記目的のためにMTAと 葉酸を併用投与することは技術常識になっていたものと認められるが,いずれの公 知文献にも,上記目的のためには葉酸補充だけでは不十分であるとする指摘はない\nし,葉酸補充に加えて他の活性成分を投与する必要性についても何ら指摘されてい ない。
(イ) 上記ア(イ)(ウ)のとおり,本件優先日当時,(1)ベースライン時のホモシス テイン値が10μM以上であると,MTAの毒性発現が高度に予測されること,(2) ホモシステイン値は,葉酸又は/及びビタミンB12が不足すると上昇すること,(3) 葉酸とビタミンB12を併せて投与すると,葉酸単独投与の場合に比して,より確実 にホモシステイン値を低下させることができることが,本件優先日当時に知られて いたことが認められるものの,以下のa,bからすると,それにより,甲1発明に ビタミンB12を投与することを組み合わせることは動機付けられないというべきで ある。
a 上記ア(イ)の各公知文献が指摘しているのは,本件優先日当時,ベー スライン時のホモシステイン値がMTAの毒性発現を予測させる指標であったとい\nうことだけであり,原告が主張するような「ベースライン時のホモシステイン値を 低下させておくとMTAの毒性発現が抑制される」ということまでが読み取れると はいえない。この点について,原告は,「ベースライン時のホモシステイン値」と「M TA投与後の毒性」との間に因果関係があると主張する。ベースライン時のホモシ ステイン値とMTAの毒性発現との間に単純な比例関係があれば,原告が主張する ようにいうことも可能であるが,本件証拠上,本件優先日当時,単純な比例関係に\nあることが知られていたとは認められない(かえって,甲115[212頁左欄5 行〜6行]には,葉酸の機能している状態と血漿ホモシステイン濃度とは,非線形\n的な逆相関を示す旨記載されている。)から,「ベースライン時のホモシステイン値 が高い場合にMTAの毒性発現を予測させる指標であること」から直ちに「ベース\nライン時のホモシステイン値を低下させておくとMTAの毒性発現が抑制されるこ と」ということができないことは明らかであり,原告の上記主張は理由がない。 また,「ベースライン時のホモシステイン値を低下させておくことで抗腫瘍活性が 維持される。」ということについても,甲44に葉酸補充により抗腫瘍活性が維持さ れて毒性が低減される旨の記載があるほかは,上記各公知文献は何も述べていない から,この点が技術常識であったとまでは認められない。 そうすると,原告が主張するような,「ベースライン時のホモシステイン値を低下 させておくと,毒性の発現が抑制され,かつ抗腫瘍活性が維持される。」ということ が,本件優先日当時に技術常識として存在していたとまで認めることはできないか ら,その点から動機付けがあるということはできない。
b 葉酸又はビタミンB12の欠乏により上昇するホモシステイン値とは 異なり,メチルマロン酸値はビタミンB12の欠乏により上昇するところ(上記ア(ウ) b),上記ア(イ)のとおり,本件優先日当時,ニイキザ文献は,ベースライン時のホ モシステイン値と毒性発現の間には相関関係があるものの,メチルマロン酸値と毒 性発現の間には相関関係がない旨を指摘していたのであるから,当業者は,ここか ら患者のビタミンB12の状態と毒性発現との間には相関関係がなく,むしろ,葉酸 の欠乏がベースライン時のホモシステイン値の上昇や毒性発現に関係していると考 え,葉酸を補充する方向へと進むものと推認される。現に,上記ア(イ)d のとおり, その注52でニイキザ文献を引用している甲44は,ベースライン時のホモシステ イン値10μMが毒性発現の閾値であると指摘しておきながら,葉酸補充にしか言 及していないし,ホモシステイン値を葉酸状態の指標であるととらえている。 また,葉酸とビタミンB12が併用されると,上記ア(ウ)aの図の左側にあるメチオ ニンを生成するためのメチル化反応が促進され,テトラヒドロ葉酸が再生されやす くなるから,ビタミンB12の投与は葉酸単独投与に比して葉酸の機能的状態の改善\nにより資するものといえるが,そのようなテトラヒドロ葉酸の再生の亢進が具体的 にどの程度葉酸の機能的状態に影響を与えるものなのかは本件証拠上不明であり,\nがん患者における葉酸の機能的状態を正常化するためには,葉酸を外部から補充す\nるだけでは不十分であり,ビタミンB12を補充することまでもが必要であったと本\n件優先日当時に当業者に認識されていたとは認められない。 そうすると,仮に当業者がMTAの毒性リスクを低減させるためにベースライン 時のホモシステイン値を10μMより低下させる必要があると考えたとしても,そ こからビタミンB12を追加することを動機付けられるとは認められない。
(ウ) 原告は,いまだに治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ (アンメット・メディカル・ニーズ)により,更なる高い効果を求めて別の活性成 分を加えることが動機付けられると主張する。 しかし,上記(ア)(イ)で検討したところからすると,葉酸代謝拮抗薬の抗腫瘍活性 の維持と毒性の低減という目的のためには葉酸の予備的処置だけでは十\分ではない ということが当業者に認識されていたとは認められないのであり,原告が主張する ようなアンメット・メディカル・ニーズが存在するからといって,そこから直ちに 上記目的のために甲1発明を更に改良する必要があると当業者が認識するとは認め られない。 また,仮にアンメット・メディカル・ニーズにより上記目的のために甲1発明を 改良することが動機付られるとしても,上記イ(イ)で検討したところに照らすと,そ こから更にビタミンB12を併用することが動機付られるということはできないので あり,原告の主張はその点からしても採用することができない。
◆判決本文
以下は、関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.12. 9
平成30(ネ)10064等 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年10月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 平成28年11月1日から平成29年3月22日まで
タイトルタグ及びメタタグにおける被告標章1及び2の使用
前提事実(4)アのとおり,一審被告グレイスランドが,平成28年11月15日 から平成29年3月22日までの間,被告ウェブページ1〜4のタイトルタグ及 びメタタグに原判決別紙1−1のタイトルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載し ていたこと,その結果,(1)グーグルや楽天市場でキーワード検索した場合に,検 索結果を表示する画面にタイトルとして被告標章1又は2が表\示され,空白部分 を挟んで「取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ」として 商品の種類が表示され,(2)楽天市場では,タイトルの横に被告商品の画像が表示\nされ,さらに,(3)グーグルでは,場合によって,タイトルの下に被告標章2を含 む「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ 浄水 カートリッジ(標準タイプ)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確 認の上,お買い求めください。」などの表示がされていたことが認められる。\n上記のような態様で被告標章1及び2を使用した場合,需要者は,独立して表\n示された被告標章1及び2及びその後に空白を挟んで表示されている語句(「取付\n互換性のある交換用カートリッジ」,「浄水器カートリッジ」,「浄水カートリッジ」)や被告標章1及び2の近くにある被告商品の写真から,被告標章1及び2が被告 商品の出所を示していると認識するといえる。 そして,このような表示は,タイトルタグやメタタグの記載によって実現され\nているものであるから,タイトルタグやメタタグに被告標章1及び2を記載する ことは,被告標章1及び2を,商品を表示する商品等表\示として使用(不競法2 条1項1号)するものと認められる。
被告ウェブページ1〜4における被告標章2の使用
前提事実(5)アのとおり,平成28年11月1日から平成29年3月22日まで の間,被告ウェブページ1〜4の下方に,原判決別紙2−1のウェブサイトの記 載欄のとおり,上記 と同様に,「タカギ」との被告標章2が表示され,空白部分\nを挟んで「取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ(標準タ イプ)※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上,お買い求めく ださい。」などの被告商品の種類に応じた被告標章2を含む表示(本件記載1)が\nされており,さらにその横には被告商品の写真が表示されていたものと認められ\nる。 本件記載1中に独立して表示された被告標章2\nは,被告標章2の後に空白を挟んで記載された語句や被告標章2の近くにある写 真が示す被告商品の出所を示すものとして用いられているものと認められ,商品 等表示に該当するものであると認められる。\n一審被告らは,「取付互換性のある交換用カートリッジ」や「当製品 はメーカー純正品ではございません」といった記載があること及び被告ウェブペ ージ1〜4における被告商品の外観写真が一審原告の純正品とは異なるものであ ることなどを挙げて,タイトルタグ,メタタグ及び被告ウェブページ1〜4にお いて,被告標章1及び2は,商品の出所を表示するものとして使用されていない\nと主張する。 しかし,「互換性」という用語は,製造販売者が同じ商品間でも用いられるもの (甲46)である上,「取付互換性」の語の意味は明確ではなく,需要者が「取付 互換性」という語から直ちに被告標章1及び2が商品の出所を示すものとして使 用されていないと認識するとはいえない。 また,「当製品はメーカー純正品ではございません」という記載については,被 告商品が一審原告の製品とは異なることを端的に述べたものではなく分かりにく い記載となっている上,需要者がウェブサイトの記載を注意深く読むとは限らず, 当該記載が末尾に記載されていることからすると,それが常に認識されるとはい えないし,被告商品と一審原告の製品との外観上の差異(乙10)についても, 本件浄水器に使用される交換用カートリッジが普段露出しているものではなく, 需要者が被告商品と一審原告製品との外観上の差異を明確に認識できるとは限ら ないから,需要者が被告標章1及び2が商品の出所を示すものとして使用されて いないと認識するとはいえない。 したがって,一審被告らの上記主張は上記 の判断を左右するものとはい えない。
イ 平成29年3月23日以降
平成29年3月23日以降の被告ウェブページ並びにそのタイトルタグ及びメ タタグにおける被告標章1及び2の使用は,以下のとおり,そのいずれもが出所 表示機能\,自他商品識別機能を有する態様での使用とはいえず,商品等表\示とし ての使用に該当しない。
平成29年3月23日から同年4月12日まで
前提事実(4)イのとおり,一審被告グレイスランドは,平成29年3月23日か ら同年4月12日までの間,被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに原 判決別紙1−2のタイトルタグ及びメタタグ欄のとおり記載していたこと,その 結果,楽天市場で「タカギ カートリッジ」とキーワード検索すると,「タカギに 使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含むタイトル\nが被告商品の写真と共に検索結果を表示する画面に表\示されるようになっていた ことが認められる。また,弁論の全趣旨によると,グーグルで同様に検索した場 合にも,「【楽天市場】タカギに使用できる出来る取り付け互換性のある交換用カ ートリッジ」という被告標章1を含む記載のあるタイトルが表示されるなどして\nいたと認められる。さらに,前提事実(5)イのとおり,被告ウェブページにおいて は,上記期間,その下方に「タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カ ートリッジ」との記載を含む表示がされていたことが認められる。\n上記各表示は,いずれも「タカギ」というカタカナ3文字の後に「に」という\n助詞が付加され,当該商品が一審原告製の本件浄水器に使用できるカートリッジ であるという,被告商品の商品内容を説明するまとまりのある文章と理解できる ものである。そうすると,需要者が上記各表示に接したとしても,「タカギ」との\n表示を,当該商品自体の出所を表\示するものとして認識するとは認められない。 したがって,上記各表示における被告標章1及び2の使用が,商品等表\示とし ての使用に該当するとは認められない。
平成29年4月13日以降
前提事実(4)ウのとおり,一審被告グレイスランドは,平成29年4月13日以 降,被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに原判決別紙1−3及び1− 4のタイトルタグ及びメタタグ欄のとおり記載していたこと,その結果,楽天市 場で「タカギ カートリッジ」とキーワード検索すると,「タカギの浄水器に使用 できる,取付け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含むタイトルが被\n告商品の写真と共に検索結果を表示する画面に表\示されるようになっていること が認められる。また,弁論の全趣旨によると,グーグルで同様に検索した場合に も,「【楽天市場】タカギの浄水器に使用できる,取付け互換性のある交換用カー トリッジ」という被告標章1を含む記載があるタイトルが表示されるなどしてい\nると認められる。さらに,前提事実(5)ウのとおり,平成29年4月13日以降, 被告ウェブページにおいては,その下方で「タカギの浄水器に使用できる,取付 け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含む表\示がされるようになって いることが認められる。 と同様に,「タカギの浄水器に使用できる」という文章は,被告商品が一 審原告製の本件浄水器に使用可能であるという商品内容を説明するものであると\n需要者に理解されるものと認められ,被告商品の出所を表示するものとして使用\nされているとは認められないから,上記各表示における被告標章1及び2の使用\nが,商品等表示の使用に該当するとは認められない。\n
一審原告の主張について
一審原告は,(1)誤認を招きやすいインターネット取引において,キーワード検 索をする需要者は,「タカギ カートリッジ」というキーワードに着目して表示を\n理解してしまう上,検索結果を表示する画面で被告標章1及び2を用いた文章が\n一審原告の製品の写真と共に表示されることからすると,需要者は「タカギ」の\n「カートリッジ」であるという先入観をもって各表示を理解すること,(2)片仮名 で表記されているのが,「タカギ」と「カートリッジ」のみであるところ,片仮名\nは目立ち,語句の切れ目を表示する役割も果たすことからすると,平成29年3\n月23日以降の被告標章1及び2の使用も商品等表示としての使用に当たると主\n張する。 しかし,上記 , で検討した各表示(「タカギに使用出来る取り付け互換性の\nある交換用カートリッジ」,「タカギの浄水器に使用できる,取付け互換性のある 交換用カートリッジ」)は,まとまりのある文章として,それが被告商品の説明で あることが容易に理解できるものであるから,需要者の注意力がそれほど高くな く,かつ「タカギ カートリッジ」というキーワード検索を経ていて,一審原告 の製品が共に表示されることがあるからといって,需要者が,「タカギ」と「カー\nトリッジ」のみに着目して,一審原告の主張するような先入観をもって上記各表\n示を理解するとは認められない。 また, 必ずしも片仮名が平仮名 や漢字に比して注意を引きつけるとまではいえない。 したがって,一審原告の上記主張は,上記 の判断を左右するものではな い。
(2) 被告標章3について
ア 前提事実(6)のとおり,平成28年11月1日から平成30年12月2 8日までの間に,被告ウェブページ及び被告ウェブサイト2の冒頭部分には,被 告標章3を含む本件記載2がされていた。 被告標章3である「タカギ社製」は,それが修飾する商品が「タカギ社」の製 造に係るものであること,すなわち,当該商品が一審原告の出所に係ることを示 す語句であるといえる。 そして,被告標章3(タカギ社製)を含む本件記載2は,「タカギ社製 浄水蛇 口の交換用カートリッジを お探しのお客様へ」と3段に分けて記載されている ものであって,文章の内容だけからしても,「タカギ社製」が,「浄水蛇口」では なく,「交換用カートリッジ」を修飾していると理解することが可能なものである。\nまた,前提事実(6)のとおり,本件記載2の上方及び下方の2か所に,本件記載 2より明らかに大きなサイズの文字で,より目立つように「交換用カートリッジ」, 「交換用カートリッジ ついに発売!!」などと表示され,かつ,交換用のカー\nトリッジそのものである被告商品の写真画像も併せて表示されているから,それ\nらの表示に接した需要者は,冒頭に独立して記載された「タカギ社製」の文字を,\nカートリッジに結びつけて理解しやすいといえる。 以上に加えて,前記2で検討したとおり,被告標章3(タカギ社製)の要部で あるタカギの文字部分が家庭用浄水器及びその関連商品の需要者の間で周知なも のであること並びに需要者の注意力がそれほど高くないことといった事情も併せ 考えると,需要者が,本件記載2の中で独立して最上段に記載されている「タカ ギ社製」が,本件記載2中の「交換用カートリッジ」を修飾する語句であると理 解することは十分にあり得るものと認められる。\nそうすると,本件記載2中の被告標章3(タカギ社製)は,被告商品について, 商品等表示として使用されているものと認められる。\n
イ 一審被告らは,(1)本件記載2が一連の呼びかけといえる文言であるこ と,(2)本件記載2の2行目が「浄水蛇口」から始まり,かつ「浄水蛇口」の次に 「の」という助詞が付されていることからすると,需要者は,被告標章3(タカ ギ社製)は「浄水蛇口」を修飾するものとして理解すると主張する。 しかし,上記(1)について,本件記載2が呼びかけといえる文言であるからとい って,被告標章3が商品等表示として使用されていないということにはならない\nし,上記(2)についても,一審被告らの主張する事情を考慮しても,上記アのとお り,需要者が,被告標章3(タカギ社製)が「交換用カートリッジ」を修飾する 語句であると理解することは十分にあり得るということができるから,一審被告\nらの上記主張は採用することができない。
(3) 小括
以上の検討のとおり,(1)平成28年11月15日から平成29年3月22日ま での間,前提事実(4)アで認定した態様で被告ウェブページ1〜4のタイトルタグ 及びメタタグで被告標章1及び2を使用した行為,(2)平成28年11月1日から 平成29年3月22日までの間,前提事実(5)アで認定した態様で被告ウェブペー ジ1〜4で被告標章2を使用した行為並びに(3)平成28年11月1日から平成3 0年12月28日までの間,前提事実(6)で認定した態様で被告標章3を使用した 行為は,それぞれ不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当する。\n
・・・・
以上の検討のとおり,本件不競法該当行為がされた期間は,平成28年 11月1日から平成30年12月28日であるところ,一審原告はそのうち平成 28年11月1日から平成30年11月30日までの間の損害賠償を請求してい る。 証拠(乙26の1〜6,乙27,28,乙29の1・2,乙30,乙31の1 〜7,乙32〜35,乙38の1〜22,乙39の1〜22,乙40の1〜20, 乙41の1〜3,乙43の1〜20)及び弁論の全趣旨によると,上記期間に対 応する各月ごとのパソコン等分利益,パソ\コン等分利益及びスマホ等分利益の合 計額は,別紙2〜4のとおりであると認められる。 また,上記期間に対応する(1)パソコン等分利益の合計額が228万6033円,\n
(2)パソコン等分利益及びスマホ等分利益の合計額が954万0740円であるこ\nとについては当事者間に争いがない。そして,上記パソコン等分利益228万6\n03円については不競法5条2項にいう「侵害行為による利益」に当たるものと 認められる(なお,推定の覆滅については(2)で後述する。)。
イ 一審原告は,スマホ等分利益725万4707円(954万0740 円―228万6033円=725万4707円)のうち5%についても「侵害行為 による利益」に含まれると主張する。 しかし,前提事実(3)イのとおり,スマホ・タブレット向けサイト内のウェブペ ージの最下部には,「表示モード:モバイル|PC」として被告ウェブサイトへの リンクがあり,スマートフォンやタブレットから仮想店舗へとアクセスした者は, 上記リンクを利用することで,被告ウェブサイトを表示させることができ,また,\nスマホ・タブレット向けサイト内のウェブページの最上部にも「PC」という文 字を○で囲んだ記号が表示されており,同表\示も被告ウェブサイトへのリンクと なっているものの,このようなスマホ・タブレット向けウェブサイトにおける被 告ウェブサイトへのリンクの表示位置や表\示の態様からすると,同リンクは需要 者が相当注意しないと気付かないような目立たないものである上,スマホ・タブ レット向けサイトの下方にあるリンクについては,他の表示に隠れてタップでき\nない場合がある(甲87,弁論の全趣旨)。そして,スマホ・タブレット向けウェ ブサイトと本件訴訟の対象となっている被告ウェブサイトとの間に見やすさや情 報量の点で差があることなどにより,スマートフォン及びタブレット経由で仮想 店舗にアクセスした需要者が敢えて被告ウェブサイトを表示させる積極的な要因\nがあるとも認められない。これらのことからすると,スマホ等分利益が,本件不 競法該当行為によって生じたものとは認められず,一審原告の上記主張は採用す ることができない。
ウ 以上からすると,不競法5条2項にいう「侵害行為による利益」に当 たるのはパソコン等分利益228万6033円のみであると認められる。\n
(2) 不競法5条2項における推定の覆滅については,侵害者が主張立証責任を 負うものであり,侵害者が得た利益と周知な商品等表示の主体が受けた損害との\n相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。 この点について,一審被告らは,(1)被告商品を2回以上購入したリピーターに よる購入が全体の売上げの約15%を占めているところ,リピーターについては誤 認混同が生じていないこと,(2)被告標章3の表示回数が1回であり,注意書きや\n打ち消し表示が多数されていることからすると,不競法5条2項に基づく推定が\n全て覆滅されると主張する。
ア 上記(1)について,確かに証拠(乙42)によると,被告商品について リピーターによる購入が一定割合あることは認められるが,リピーターであるか らといって,そのことから直ちに本件不競法該当行為とは無関係に被告商品を購 入したということはできないから,リピーターによる購入であることを理由とし て推定の覆滅を認めることはできない。
イ 次に,上記(2)について,前記4(1)ア及び(2)アのとおり,平成28年 11月1日から平成29年3月22日までは,被告ウェブページ1〜4において, 被告標章2が商品等表示として使用され,かつ被告ウェブページ1〜4及び被告\nウェブサイト2の冒頭部分に被告標章3が商品等表示として使用されていた上,\n平成28年11月15日から平成29年3月22日まではタイトルタグ及びメタ タグにおいて,被告標章1及び2が商品等表示として使用されていたところ,こ\nれに対して,一審被告らが打ち消し表示と主張するものについては,前記5(2)〜 (5)のとおり決して十分なものということはできないから,需要者が本件不競法該\n当行為とは無関係に被告商品を購入したとはいい難く,推定の覆滅は認められな い。
他方,前記4(1)イのとおり,平成29年3月23日以降,被告ウェブページ並 びにそのタイトルタグ及びメタタグにおいて,被告標章1及び2は,商品等表示\nとしては使用されておらず,前記4(2)アのとおり,被告標章3が被告ウェブペー ジ1〜6及び被告ウェブサイト2において商品等表示として使用されたのみであ\nるから,本件不競法該当行為とは無関係に被告標章を購入した者も一定数存在し たものと認められ,一定の推定の覆滅を認めることができる。その割合はこれま で認定した諸般の事情に照らすと,5割と認めるのが相当である。 (3) 以上からすると,不競法5条2項により一審原告の損害として推定される べき額は,以下の計算式とおり,119万1757円であると認められ,弁護士 費用としては,本件に表れた一切の事情を勘案して20万円を相当と認める。\nしたがって,一審被告らによる不正競争行為(本件不競法該当行為)によって 一審原告に生じた損害額の合計は,139万1757円(119万1757円+ 20万円=139万1757円)であると認められる。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2019.12. 5
平成30(行ケ)1017 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月4日 知的財産高等裁判所
前記1(1)によれば,本件明細書には,「課題を解決するための手段」として,「本 発明の一の態様による自動注入可能なアクセスポートは,コンピュータ断層撮影走\n査プロセスに用いられ,隔膜を保持するよう構成される本体と,皮下埋め込み後,\n前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構\築される,前 記アクセスポートの少なくとも1つの,前記自動注入可能なアクセスポートの,自\n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能\な情報と相関がありX線 で可視の,識別可能な特徴とを具え,前記自動注入可能\なアクセスポートは,機械 的補助によって注入され,かつ加圧されることができ,前記隔膜は,前記本体内に 画定された空洞内に,前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である。」 (【0009】)との記載があることに加え,アクセスポートは,機械的補助(自動注 入可能ポート)によって注入され,かつ加圧されることができること(【0013】),自動注入可能\ポートは,コンピュータ断層撮影(「CT」)走査プロセスにおいて使 用することができること(【0014】),典型的なアクセスポート10は,キャップ 14とベース16の間で隔膜18を保持するために構成することができ,これらが\n集合して,本体20に吐出ステム31の内腔29と流体連通している空洞36を画 定することができること(【0017】,【0018】,図1A,図1B),識別可能な特徴は,アクセスポートが患者の中に埋め込まれた後に知覚可能\であり,自動注射 可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること(【0015】),識\n別可能な特徴は,金属プレートのサイズや形状等,X線の画像化を通じて知覚する\nことができるものでもよいこと(【0016】,【0046】)が記載されている。 これらの記載によれば,特許請求の範囲請求項1に記載された本件発明1は,本 件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえる。
(3) 当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであること 前記1(1)のとおり,本件明細書の「発明が解決しようとする課題」には,従来の アクセスポートは,異なる製造業者または型式であっても,互いに区別することが できない実質的に同様の外形を有することがあり,一度アクセスポートが埋め込ま れると,アクセスポートの型式,様式またはデザインを見つけ出すのが難しくなり, 交換タイミング等の目的にとって好ましくないという問題があり(【0007】),皮 下埋め込み後に検知される,少なくとも1つの識別可能な特徴を設けたアクセスポ\nートを提供することは有利であること(【0008】)の記載がある。 また,「課題を解決するための手段」には,アクセスポートは,(例えば,針を含む 注射器を介して)手で注入されることができ,または,機械的補助(例えば,いわゆ る自動注入可能ポート)によって注入され,かつ加圧されることができること(【0\n013】,【0014】),アクセスポートの識別可能な特徴は,アクセスポートに関\n連する情報(例えば製造業者の型式またはデザイン)と相関関係を有することがで き,自動注射可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること(【0\n015】)の記載がある。 以上の記載によれば,本件発明1の課題は,自動注入可能なアクセスポートを埋\nめ込んだ後に,そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを\n識別可能とすることであると認められ,その課題の解決手段として,「皮下埋め込み\n後,前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構\築される, 前記アクセスポートの少なくとも1つの,前記自動注入可能なアクセスポートの,\n自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能\な情報と相関がありX 線で可視の,識別可能な特徴」を備えるようにしたものであることが認められる。\nそして,本件明細書には,「識別可能な特徴」に関し,触診又は目視観察によって\n知覚することができるもののほか,プレート又は他の金属形状の金属的な特徴のよ うにX線の画像化を通じて知覚できるものでもよく,その金属的特徴は,X線感光 フィルムを,アクセスポートを通過するX線エネルギーに曝すと同時に,X線エネ ルギーへのアクセスポートの露出によって生じるX線で示されること(【0016】, 【0046】),識別可能な特徴が,ひとたび観察され,または別の方法で決定され\nると,アクセスポートのそのような少なくとも1つの特徴の相関関係を達成するこ とができ,アクセスポートに関連する情報を得ることができること(【0015】) の記載がある。 これらの記載に接した当業者は,本件発明1の「識別可能な特徴」を採用したア\nクセスポートは,X線に曝すことで「識別可能な特徴」が知覚でき,これにより「自\n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能\な情報」との相関関係を 達成し,「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能\な情報」を得 ることができ,その結果,皮下埋め込み後に自動注入可能と識別できるものである\nことを認識することができるというべきである。 よって,特許請求の範囲請求項1に記載された本件発明1は,本件明細書の発明 の詳細な説明の記載により,当業者が本件発明1の課題を解決できると認識できる 範囲のものである。
(4) 被告らの主張について
被告らは,本件明細書には,「X線で可視の,識別可能な特徴」と「自動注入可能\ なアクセスポートの,自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能\ な情報」をどのように「相関」させるかという点について記載も示唆もないから,本 件発明1はサポート要件を欠いていると主張する。 しかし,本件明細書には,「識別可能な特徴は,前記アクセスポートに関連する情\n報・・・と相関関係を有することができる」ものであり,「アクセスポートからの識別可能な特徴は,異なる型式またはデザインの,別のアクセスポートの他の識別可能\な 特徴の,すべてではないにしても大部分に関して唯一のものである」(【0015】) との記載があり,触診によって知覚される識別可能な特徴の例として,本体を部分\n的な略ピラミッド状の形状とすること(【0020】,【0021】,図1A,図1B),X線の画像化を通じて知覚することができる識別可能な特徴の例として,アクセス\nポートの金属的な特徴のサイズ,形状,又はサイズと形状の両方が,アクセスポー トの識別のため選択的に調整されること(【0046】)が記載されている。 これらの記載によれば,「識別可能な特徴」を,当該アクセスポートに固有の形状\nやサイズにすることによりアクセスポートを特定可能にし,もって,「アクセスポー\nトに関連する情報…と相関関係を有することができる」ようにすることが開示され ている。そして,本件発明1の「自動注入可能なアクセスポートの,自動注入可能\に 定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」は,「アクセスポートに関連す\nる情報」であるから,上記記載は,「自動注入可能なアクセスポートの,自動注入可\n能に定格されていないアクセスポートと区別可能\な情報」と「X線で可視の,識別 可能な特徴」との「相関」の具体的態様の1つとして理解することができるという\nべきである。
・・・
(4) 相違点1の容易想到性
ア 各文献の記載事項
本件出願の優先日当時の各文献には,次の記載がある(下記記載中の甲11図1 0,甲12図2−1,2−3,2−4は別紙周知例図面目録のとおり。)。
(ア) 米国特許第5851221号明細書(甲11)には,(1)予め形成されたヘッ\nダモジュール12を機密封止筐体14に取り付けて製造される埋め込み型の医療機 器において,ヘッダモジュール12のハウジング20がX線不透過性のIDプレー ト60を備えること(第8欄23行〜34行,図10),(2)埋め込み型医療機器には, 埋め込み可能な薬剤供給装置,IPG(心臓ペースメーカ,ペースメーカ‐心臓除\n細動器,神経,筋肉及び神経刺激器,心筋刺激器など),埋め込み型心臓信号モニタ 及びレコーダなどが含まれること(第6欄39行〜54行)が開示されている。
(イ) IsoMedの説明書(甲12)は,肝動脈の注入治療のための臨床のレフ ァレンスガイドであり ,(1)IsoMed注入システムは,IsoMed定量ポンプ と,メドトロニック血管カテーテルを含み,化学療法用薬剤の肝動脈注入に使用す る場合,まずカテーテルをポンプに接続し,ポンプは腹部の皮下腔に配置し,カテ ーテルは腹壁内にくぐらせその端部は胃十二指腸動脈等に配置すること(2−2頁\n1行〜8行,図2−1),(2)IsoMed定量ポンプは,化学療法薬剤またはヘパリ ン化液剤を貯蔵するリザーバーと,セルフシーリング隔膜を有し,リフィル針によ りリザーバーにアクセス可能なセンターリザーバフィルポートとを備えること(2\n−3頁14行〜18行,2−4頁1行〜6行,図2−3),(3)IsoMed定量ポン プはさらに,X線識別タグ等を備え,X線識別タグは,メドトロニック識別子,ポン プの型番,リザーバーの体積及び流量を記録していること(2−4頁10行〜14 行,図2−4)が開示されている。
(ウ) Robert M. Steiner ほか「心臓ペースメーカの放射線学(The radiology of ca rdiac pacemakers)」と題する論文(RadioGraphics,Vol.6,No.3,p373−39 9。乙1)には,ジェネレーターのX線画像は,ペースメーカの製造業者,タイプ及 び作用機序を識別するために有用であるが,何十もの製造業者が何百ものモデルを\n製造しており,流通している全てのペースメーカに精通している医師はいないため, 製造業者から通常提供される,X線画像上の外観やX線不透過性コードを示す参照 チャートが利用可能であることが開示されている(379頁)。\n
(エ) Sergio L. Pinski ほか「植込み型除細動器:非電気生理学者への影響(Implan table Cardioverter-Defibrillators: Implications for the Nonelectrophysiologist)」と題す る論文(Annals of Internal Medicine Vol.122, No.10,p770−777。乙 2)には,全ての製造業者の植込み型除細動器は,X線不透過性の識別子を有する ので,緊急時にはX線を透過させることによりデバイスの識別が可能になることが\n開示されている(771頁左欄14行〜26行)。
(オ) John L. Atlee ほか「心調律管理装置(第2部)(Cardiac Rhythm Managemen t Devices (Part II) Perioperative Management)」と題する論文(Anesthesiology, Vol.95,No.6,p1492−1506。乙3)には,既存のほとんどのペースメーカ 及びICD には,これらのデバイスが埋め込まれている領域の胸部X線写真をみれ ば,デバイスの製造業者及びモデルが識別できる固有のX線不透過性コード(X線 又はX線画像上の署名)が刻印されていることが開示されている(1502頁左欄 11行〜右欄15行)。
(カ) 米国特許第4863470号明細書(甲14)には,(1)乳房用,ペニス,膀 胱,失禁用装置等のインプラントは,体内への埋め込み前及び後の両方において容 易に識別可能であると好都合であること(第1欄14行〜35行),(2)皮下移植用の インプラントについて,X線不透過性の識別マーカーを囲むX線透過部を含むよう にすることで,識別マーカーは埋め込み前において視認可能であるとともに,埋め\n込み後はX線撮影によって判読可能であること(第1欄49行〜57行),(3)識別マ ーカーは,インプラントのサイズのほか,製造業者,製造年,種類等を示すことがで きること(第2欄30行〜46行)が開示されている。
イ 周知技術の認定
(ア) 上記アの記載事項によれば,本件優先日当時,心臓用の医療装置(甲11, 乙1〜3),皮下埋込型の薬液注入装置(甲12),人工乳房(甲14)等の,人体に 埋め込まれて使用される医療機器において,人体に埋め込まれた後に当該装置を特 定する情報を含むX線不透過性の識別子,すなわち,X線で可視の識別可能な特徴\nを備えることは,既に臨床レベルで採用された,周知の技術であったと認められる。
(イ) 原告の主張について
原告は,甲11,甲12の各文献に記載されたわずか2件の発明を根拠に,人体 に埋め込まれて使用される医療機器一般について,X線で可視な特徴を備えること が周知技術と認定することはできず,また,乙1〜3,甲14の各文献の記載を考 慮したとしても,これらに開示されているのは,人体に埋め込まれて使用される心 臓用医療機器であるから,アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器全般におけ る周知技術を認定することはできないと主張する。 しかし,装置の型番を示すX線で可視な特徴を備えることは,心臓用医療機器の みならず,人工乳房,肝動脈に抗がん剤を投入するポンプなど,人体に埋め込まれ て使用される多様な医療装置において行われていたことは,上記アのとおりである。 そして,甲12には,化学療法用薬剤の肝動脈注入ポンプを腹部の皮下腔に配置 し,体外から薬剤を注入することが記載されていること,甲11には,X線で可視 な特徴としてX線不透過性のIDプレート60を備える医療機器の例として,心臓 ペースメーカ,植込み型除細動器などのほかに薬剤供給装置が挙げられており,薬 剤供給の用途が示唆されていることに照らすなら,装置の型番を示すX線で可視な 特徴を備えることは,アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器においても,周 知技術であったと認められ,原告の上記主張は採用できない。
ウ 容易想到性の判断
(ア) 引用発明は,造影CTにおいて,造影剤を注入するために用いられる皮下埋 込型のアクセスポートであって,人体に埋め込まれて使用される医療機器の分野に おける上記イの周知技術と同一の技術分野に属している。また,引用発明に上記周 知技術を適用することについて,阻害要因があることは認められない。そうすると, 引用発明に上記周知技術を適用し,人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情 報を含む,X線で可視の識別可能な特徴を備えるようにすることは,当業者が適宜\nなし得ることであるというべきである。 そして,引用発明である「自動注入可能なアクセスポート」を特定する情報は,自\n動注入可能なアクセスポートを自動注入可能\に定格されていないアクセスポートと 区別可能な情報である。そうすると,引用発明を特定する情報を含む,X線で可視\nの識別可能な特徴によって,上記「情報」を識別することができるから,上記識別可\n能な特徴は,「前記アクセスポートの少なくとも一つの,前記自動注入可能\なアクセ スポートの,自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能\な情報」 と「相関」があるということができる。 よって,引用発明に上記周知技術を適用し,相違点1に係る構成とすることは,\n当業者が適宜なし得ることである。
(イ) 原告の主張について
原告は,本件発明の「相関」は,添付文書に記載された情報に基づいて,「識別可 能な特徴」に,「自動注入可能\」であることを示すものとしての意味が直接的に付与 されていることが必要であり,医師等が添付文書などに基づいて,その「識別可能\nな特徴」の意味を理解できることを要し,単に「ポートの型式」が示されているだけ では,それ自体に「自動注入可能」かどうかの直接的な意味付けはない以上,「自動\n注射可能である前記アクセスポートと相関関係」があるとはいえないから,「前記自\n動注入可能なアクセスポートの,自動注入可能\に定格されていないアクセスポート と区別可能な情報と相関がありX線で可視の,識別可能\な特徴」に該当するとはい えない旨主張する。 しかし,本件発明1の特許請求の範囲には,「相関」の具体的態様について限定は ない上,本件明細書にも,「相関」について,添付文書に記載された情報に基づいて, 「識別可能な特徴」に,「自動注入可能\」であることを示すものとしての意味が直接 的に付与されていることが必要であり,医師等が添付文書などに基づいて,その「識 別可能な特徴」の意味を理解できることを要することの記載や示唆はない。\nそして,本件明細書の「識別可能な特徴が,ひとたび観察され,または別の方法で\n決定されると,アクセスポートのそのような少なくとも1つの特徴の相関関係を達 成することができ,そして,前記アクセスポートに関連する情報を得ることができ る」(【0015】)との記載によれば,「識別可能な特徴」と「アクセスポートに関連する情報」との「相関」が達成されると,「識別可能\な特徴」から「アクセスポート に関連する情報を得ることができる」ようになって,そのアクセスポートを特定で きるようになることを理解することができるところ,その具体的態様については, 当業者が適宜設定できるものと解される。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成29(ワ)38481 商標権に基づく差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年10月2日 東京地方裁判所
(2)ア 前記(1)ウ(被験者がパソコン画面を見ながら回答)の場合について\n
心理検査は,被験者が質問に回答し,その回答を基準に照らして判定(診 断及び解釈)し,判定結果を一定の目的のために利用するものであるから, 心理検査を役務としてみた場合,その中核は,同検査の実施主体(心理検査 の役務を提供する主体)による回答の判定(診断及び解釈)部分にあると解 される。 前記(1)ウの場合,心理検査の役務を提供するのは被告ソフトの購入者で\nあり,被告ソフトは,同役務の提供を受ける者(被験者)の利用に供する物\nに当たるところ,被告ソフトのパッケージにはそれぞれ本件商標と類似する\n被告標章3が付されており,被告は購入者をして同役務の提供をさせるため に被告ソフトを販売しているのであるから,かかる被告の行為は,少なくと\nも法37条4号のみなし侵害行為に当たる。
イ 前記(1)イ(1)(購入者が被告質問用紙等及び被告ソフトを使用)の場合\n この場合,心理検査の役務を提供する主体は被告各商品の購入者であり, 被告質問用紙等は,同役務の提供を受ける者(被験者)の利用に供する物に 当たるところ,被告質問用紙等にはそれぞれ本件商標と類似する被告標章1 又は2が付されており,被告は上記購入者をして同役務の提供をさせるため に被告質問用紙等を販売しているのであるから,かかる被告の行為は,少な くとも法37条4号のみなし侵害行為に当たる。
ウ 前記(1)イ(2)(被告サービスを利用)の場合につき検討する。 この場合も,心理検査の役務を提供する主体は被験者に受検をさせる被告 回答用紙等の購入者(被告サービスの委託者)と解されるが,上記委託者は, 検査結果の判定部分を被告に委託して心理検査を行っており,被告は,被告 サービスを受託することにより心理検査の役務の一部であるが中核たる判 定業務を実行しているといえるから,被告が被告サービスを提供する行為は, 委託者による心理検査の役務の一部をなす。一方,被告が被告サービスとい う役務を提供する直接の相手方は上記委託者であるが,同委託者は心理検査 の役務の需要者に含まれるし,被告の上記役務があってこそ同委託者の役務 が遂行される関係のものである。そうすると,被告による被告サービスの提 供は,心理検査の役務又はこれに類似する役務に当たるというべきである。 したがって,被告が被告サービスに基づいて委託者に交付する被告診断結 果書に本件商標に類似する被告標章4を付する行為は,「役務の提供に当た りその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務 を提供する行為」(法2条3項4号)に該当するから,かかる行為は,指定 役務又はこれに類似する役務についての登録商標に類似する商標の使用に 当たり,法37条1号のみなし侵害行為に該当する。
エ 広告について 被告は,心理検査の役務に類似する役務に当たる被告サービスの提供に係 る被告ウェブサイト上の広告に被告標章5を掲載しているのであるから,役 務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供す る行為(法2条3項8号)をしているということができる。かかる行為は, 指定役務たる心理検査の役務に類似する役務についての本件商標に類似す る商標の使用に当たるから,法37条1号のみなし侵害行為に該当する。
・・・
(1) 法26条1項3号にいう役務の「質」とは,その語義からして,役務の内容, 中身,価値,性質などを意味するものと解されるところ,「MMPI」は,前 記1のとおり,質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査の名称で ある「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」(ミネソタ多面的人\n格目録)の略称であり,本件商標の指定役務である心理検査の需要者,取引者 において,心理検査の一手法である本件心理検査又はその略称を示すものとし て周知であると認められるから,心理検査の内容,すなわち「質」を表すもの\nということができる。 また,被告各標章は,いずれも,明朝体様やゴシック体様といったありふれ た書体で構成されているものである。\n そうすると,「MMPI」を含む被告各標章は,いずれも本件商標の指定役 務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を,普通に用い られる方法で表示するものということができるから,被告各標章は,法26条\n1項3号に該当し,本件商標権の効力は及ばない。
(2) これに対し,原告は,「MMPI」は,役務の普通名称又は質を表示するも\nのではなく,原告が長年にわたり独占的に提供してきた心理検査等役務を表す\nものとして識別力を獲得していたものであって,被告は,自他を識別する態様 で本件商標に類似する被告各標章を使用していると主張する。 ア この点について,確かに,証拠によれば,原告が,昭和38年以降,原告 版の質問票や回答用紙に「MMPI」の標章を用いていること(甲43〜5 3,74,75),「MMPI」の標章を用いた原告版のカタログを毎年発 行していること(甲39〜42),「MMPI」の標章を用いた原告版のマ ニュアルを販売していること(甲32),原告が精神医学,心理学等の専門 誌,学会誌等に「MMPI」の標章を用いた広告を多数掲載してきたこと(甲 55〜60,100〜145),精神医学,心理学等の専門書等には,原告 版を本件心理検査の日本語版である趣旨の紹介をするものが多数あること (甲7〜9,81〜95)などの事実が認められる。
イ(ア) しかし,原告が昭和38年(1963年)から平成4年(1992年) まで使用していた質問票(甲43)は,表紙上部に「日本版MMPI質問\n票」と記載され,その下に原著がハサウェイとマッキンレーであることな どが記載されているから,「MMPI」の表示は,当該質問票を用いて行\nわれる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を示しており,需要者, 取引者にもそのように理解されるものというべきである。 また,平成27年(2015年)以降の新版質問票(甲44〜47,7 4)は,表紙左上部に「Minnesota」,「Multiphasic」,「Personality」, 「Inventory」と4段組みに記載されており,その直下にはハサウェイら の名前が記載され,その右側には「MMPI新日本版研究会」と記載され ているものであるが,同記載も,同様に行われる心理検査の種類・方法と しての本件心理検査を示しており,需要者,取引者にもそのように理解さ れるものというべきである。 新版回答用紙(甲48〜53,75)には,「MMPI III型 回答用 紙」などとあるだけで,原著作者の記載等はないが,回答用紙が通常は質 問票とセットで利用されるものであることからすると,需要者,取引者は 「MMPI」が行われる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を意 味するものと理解するものと考えられる。
(イ) 次に,原告版のカタログ(甲39〜42)につきみると,「MMPI」 が単独で表記されている部分もあるものの,昭和43年(1968年),\n昭和48年(1973年),平成5年(1993年)の各カタログ(甲3 9〜41)には,「MMPI」がハサウェイ教授らによって発表された心\n理検査である旨の解説が付されており,平成30年(2018年)のカタ ログ(甲42)にも「MMPIの実施法・まとめ」,「MMPI新日本版」 などと記載されている。これらの記載は,「MMPI」を心理検査の種類・ 方法としての本件心理検査を表示するものであり,需要者,取引者もその\nように理解するものというべきである。
(ウ) さらに,原告のマニュアル(平成5年(1993年)版。甲32)の表\n紙には前記の新版質問票と同様の記載があり,扉の部分には「新日本版M MPIマニュアル」と記載され,本文部分においても,「第1章 MMP Iの概要」に本件心理検査についての説明がされているのであるから,同 マニュアルにおいても,「MMPI」の表示は本件心理検査を意味するも\nのとして用いられているということができる。
(エ) その他,専門誌,学会誌等への広告(甲55〜60,100〜145) 及び精神医学,心理学等の専門書等(甲7〜9,81〜95)においても, 「MMPI」は心理検査の種類・方法であることを前提とした記載がされ ているにすぎず,これが原告の役務であることを示す記載は見当たらない。
(オ) 以上のとおり,原告作成に係る質問票,回答用紙,カタログ及びマニュ アル並びに広告や専門書における「MMPI」の使用は,いずれもこれが 心理検査の種類・方法としての本件心理検査を表示するものにすぎず,他\nに「MMPI」が,原告が提供する心理検査等役務を表すものとして識別\n力を獲得したと認めるに足りる証拠はない。 そうすると,原告が長年にわたり「MMPI」の商標を用いて独占的に 心理検査等役務を提供しており,その質問票,回答用紙,カタログ及びマ ニュアル並びに広告や専門書において「MMPI」との表示をしてきたと\nしても,それをもって,原告が提供する役務を表すものとして識別力を獲\n得したということはできない。 ウ 原告は,原告が行う心理検査等役務は,本件心理検査に由来・関連するが, 質問項目の言語,項目数及び配列,採点基準,実施方式において本件心理検 査と異なる原告独自のものであり,原告の提供する役務として識別力を獲得 したと主張するが,上記のとおり,原告は,質問票やカタログ等において, 「MMPI」の日本版であることを表示し,また,「MMPI」についてミ\nネソタ大学のハサウェイ教授等により発表\された人格目録テストであるな どの説明をしている上,質問項目数の差異も重複した質問を含むかどうかの 違いにすぎない。そうすると,原告が行う心理検査等役務は,我が国の社会, 文化等に合わせて「MMPI」を翻訳・標準化したものであって,原告が独 自に開発した心理検査であるということはできず,また需要者,取引者が原 告の提供する心理検査等役務を原告独自のものと認識していたことを示す 証拠もない。
エ 他方,被告が使用する各標章についてみると,(1)被告標章1は,被告質問 用紙の表紙上部に「MMPI−1 性格検査」と記載されたもの,(2)被告標 章2は,被告回答用紙に「MMPI−1 回答用紙」と記載されたもの,(3) 被告標章3は,被告ソフトのパッケージの表\紙に「MMPI−1性格検査」 と記載されたもの,(4)被告標章4は,診断結果書の1枚目に「MMPI−1 自動診断システム」と記載されたもの,(5)被告標章5は,被告のウェブサイ ト上の被告各商品や被告サービス等の広告において,「MMPI−1性格検 査」と記載されたものである。 原告は,被告各標章が自他の役務を識別する態様で使用されていると主張 するが,上記の被告各標章の表示内容及び態様によれば,被告各標章は,本\n件心理検査による「性格検査」,本件心理検査の質問項目に対する「回答用 紙」,本件心理検査を利用した「自動診断システム」を意味し,いずれも被 告各商品や被告サービスに係る心理検査の種類・方法が本件心理検査である ことを題号等において表示しているにすぎないというべきである。このよう\nに,被告各標章における「MMPI」は,本件心理検査を意味するものとし て使用されているのであるから,これを被告が識別力を有する態様で使用し たものであるということはできない。
(3) 以上のとおり,被告各標章は,いずれも本件商標の指定役務である心理検査 又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を,普通に用いられる方法で表示\nするものということができるから,法26条1項3号に該当し,本件商標権の 効力が及ばない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 役務
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ネ)1008 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報\nを含む売り注文情報を生成する」の意義について (ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載から,構成要件Dの「注文情報生成手段」は,「前記金融商品の買い注文を行うた\nめの複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」(構成要件B)と「前記買い注文の約定によって保有したポジションを,\n約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を 生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され,「売り注文情報」を生成するのは,構\成要件Dの「注文情報生成手段」のうちの「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから,構成要件Gの「注文情報生成手段」及び構\成要件Hの「前記注文情報生成手段」は,いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理 解できる。
そうすると,構成要件Hの「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の\n売り注文が約定されたことを検知すると,前記注文情報生成手段は, 前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の売り注文 のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情 報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」,「前 記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」と の記載は,「売り注文情報生成手段」が,「前記約定検知手段」の 「前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が 約定された」との「検知の情報を受けて」,当該「最も高い売り注 文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含 む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり,「売り注 文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。 次に,本件明細書には,「シフト機能」による注文は,「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文\nや決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯と は異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注さ せる態様の注文形態」であること(【0078】),この「シフト 機能」は,「相場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一\n注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し,相場価格 を反映した注文の発注を行うことができる」(【0018】)とい う効果を奏することの開示がある。そして,構成要件Hの文言及び本件明細書の上記記載から,構\成要件Hは,「シフト機能」のうち,\n更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注済の「決 済注文」(売り注文)がシフトする構成のものを規定したものであることを理解できる。他方で,本件明細書には,「シフト機能\」のうち,更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注 済の「決済注文」(売り注文)がシフトする構成の場合において,新たな「買い注文」の発注やその約定によって,「シフト機能\」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。 以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項1)及び本件明細書の 記載を総合すると,構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」,「前記複数の売り注文\nのうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは,「売り注文情 報生成手段」(前記注文情報生成手段)が,「前記約定検知手段」 の「前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文 が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて,「さ らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生 成する」構成のものであれば,新たな「買い注文情報」の生成や「買い注文」の約定又はその検知に関わりなく,構\成要件Hに含まれるものと解される。
(イ) これに対し控訴人は,(1)本件発明の特許請求の範囲(請求項1) の記載によれば,構成要件Hの「前記検知の情報を受けて,…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成\nする」とは,直前の検知の情報を条件として,これに続いて,前記 の売り注文が発生するという意味であって,これらの間に他の処理 が介在する記載はないこと,(2)本件明細書には,従前の新規注文B 1ないしB5及び従前の決済注文S1ないしS5が全部約定したこ とを検知し,この検知の情報を受けて,新たな新規注文B1ないし B5及び新たな決済注文S1ないしS5を一括発注するものであり (【0142】ないし【0154】,図35),「前記検知の情報 を受けて」(構成要件H)と,「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」(構\成要件H)との間に,他の手続が介在するもの,例えば,新たな新規注文B1ないし B5と新たな決済注文S1ないしS5とを新規に一括発注せずに, まずは新たな新規注文B1ないしB5を発注し,その約定を検知し てから,新たな決済注文S1ないしS5を発注するようなものにつ いての開示はないこと,(3)本件出願の経過において,被控訴人は, 拒絶理由通知を受けて,本件手続補正書及び本件意見書を提出して, 本件出願に係る旧請求項1に構成要件EないしGを新たに加え,構\ 成要件Hを補正する手続補正を行うとともに,本件意見書において, シフトが生じるための条件として,最も高い売り注文の約定状況の みを監視することとし,それ以外の処理を監視することを除外する 旨を主張したことを総合すると,構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記複数の\n売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高 い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう 「前記検知の情報を受けて」とは,「前記相場価格が変動して,前 記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文 価格の売り注文が約定されたことを検知すると」,他の処理を何も 介在せずに,直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り 注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張 する。
しかしながら,上記(1)の点については,本件発明の特許請求の範 囲(請求項1)の記載中には,構成要件Hの「前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数\nの売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ 高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に, 「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しな い。
次に,上記(2)の点については,前記(ア)で説示したとおり,構成要件Hは,「シフト機能\」(【0078】)のうち,更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注済の「決済注文」(売 り注文)がシフトする構成のものを規定したものであるところ,本件明細書には,「シフト機能\」のうち,更に「決済注文」(売り注文)が発注される際に,先に発注済の「決済注文」(売り注文)が シフトする構成の場合において,新たな「買い注文」の発注やその約定によって,「シフト機能\」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。また,控訴人が挙げる本件明細書の記載 (【0142】ないし【0154】,図35)は,「発明の実施の 形態の3」に係るものであるが,本件明細書には,「上記の「シフ ト機能」は,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態2の構\ 成において適用することもできる。」こと(【0151】)及び「上 記各実施の形態は本発明の例示であり,本発明が上記各実施の形態 のみに限定されることを意味するものではないことは,いうまでも ない。」こと【0164】の記載があることに照らすと,控訴人が 挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Hを限定解釈すべき理由はない。\n
さらに,上記(3)の点については,被控訴人は,本件手続補正書(乙 14)により,本件出願に係る旧請求項1について,「前記相場価 格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち, 最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると, 前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受 けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさら に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成 する」(下線は,補正箇所を示す。)と補正し,本件意見書(乙1 5)において,「本願発明においては,一の注文手続で生成された 複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情 報の生成…は,一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基 づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知され たことを基準に行われることになります。そのため,システムにお いては,特定の注文に係る注文情報(相場の移動方向側である,最 も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や,最も低い売 り注文価格の売り注文に係る売り注文情報)の約定状況のみを監視 すれば,新たな注文情報の生成(一の注文手続で生成された中で最 も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成 …を,ただちに生成することができ,システムの情報保持や情報監 視のための負担が大きくなることはありません。これにより,本願 発明においては,新たな注文情報の生成や,その注文情報に基づく 注文の発注等の処理を,システム負荷の軽い,簡易な手順によって 処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認 められるが,他方で,本件手続補正書及び本件意見書は,平成29 年4月11日付けの拒絶理由通知(乙18)において「引用文献1 に記載された発明に引用文献2に記載の技術を適用し,引用文献1 に記載された発明において,繰り返し注文を行う際,相場価格の上 昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成 するように構成することは,当業者ならば容易に為し得ることである。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに\n照らせば,本件手続補正書及び本件意見書は,本件発明が,複数の 売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて, 同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を 有し,進歩性を有する旨を主張したものであって,本件意見書の「約 定状況のみを監視すれば」,「ただちに生成する」といった記載か ら,両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する構\成を本件発明から除外したものということはできない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 構成要件Hの充足性について
(ア) 前記2(3)イ(イ)のとおり,(1)ないし(4)の売り注文のうち,最も高 い注文価格の番号113の売りの指値注文(指定価格114.90 円)が約定した後に,番号113の注文価格より「0.62円」高 い番号96の売りの指値注文(指定価格115.52円)がされて いることに照らすと,被告サーバにおいては,約定検知手段が複数 の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知す ると,注文情報生成手段が,この検知の情報を受けたことに基づい て,約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したこと が認められる。 したがって,被告サーバは,構成要件Hを充足するものと認められる。\n
・・・・
控訴人は,本件明細書の発明の詳細な説明には,構成要件Hに対応する「シフト機能\」に係る構成について,「いったんスルー注文」及び「決済トレー\nル注文」と組み合わせた,複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ1回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず,構成要件Hに含まれる「シフト機能\」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたもの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば,構\成要件 Hは,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから,特許 法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)に適合する とはいえない旨主張する。 ア そこで検討するに,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載中に は,構成要件Hの「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ\nとを検知すると,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて,前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において,「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから,当該「売り注文情報」は,複数の場合に限らず,一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,(1)「シフト機能」について,「金融商品取引管理装置1や金融商品取引管理システム1Aにお\nいて,既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち,「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能\である。この「シ フト機能」による注文は,上述した,「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文(例えば後述する「リピートイ\nフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)等に基づいて,新 規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文 や決済注文が発注される際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で,新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと(【0078】),(2)「シフト機能」は,「相場価格の変動により,元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場\n価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し,相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」(【0018】)という効果を奏すること,(3)「発明の 実施の形態3」は,「この実施の形態3の金融商品取引管理システムに おいては,「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを,「ら くトラ」による注文と組み合わせ,さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。」(【0138】)ものであるが,「上記の「シフト機能\」は,上記発明の実施の形態1や,発明の実施の形態2の構成において適用することもできる。」こと(【0151】)及び「上記各実施の形態\nは本発明の例示であり,本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは,いうまでもない。」こと(【016 4】)の記載がある。 上記(1)の記載から,「シフト機能」は,「新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに,更に新規注文や決済注文が発注される\n際に,先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で,新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり,シ フトされる先に発注済の注文には,「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構\成が含まれること,先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価格帯」をシフトさせる構\成のものが含まれることを理解できる。また,上記(1)ないし(3)の記載から,「シフト機能」は,「相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し,「いった\nんスルー注文」,「決済トレール注文」や,各種のイフダン注文(例え ば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)」 等の注文方法とは別個の処理であること,「シフト機能」にこれらの各種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。\n
ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には,図35に示す「実施の形態 3」(【0144】ないし【0148】)として,シフト機能に決済トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ,\n決済注文S5,S4が約定した後に,元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文B5,B4及び元の売り注文S5,S4と同じ注文価格の売 り注文S5,S4が再度生成されるが,この時点ではシフトは発生せ ず,通常のリピートイフダン注文が繰り返され,その後相場価格が変 動して,S1ないしS3の売り注文価格がトレールし,S1ないしS 3が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると,再度生成 された売り注文S5,S4は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして,S1ないしS5のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は,構成要件Hに含まれる,「シフト機能\」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一つであることが認められる。\nまた,シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には,図35において,S2及びS3の売り注文価格がトレールしないため,\nそれぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり,それぞ れ別々に約定し,その場合,実施の形態3の取引例でS5,S4が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に,S3,S2が約定 した段階ではシフトが生じず,その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのS1が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると,複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると,それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Hに係る構\成は,本 件明細書の上記記載から認識できるから,本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
(イ) これに対し控訴人は,図35には,S5,S4が約定した後に再 度S5,S4が生成されることの記載はなく,B5,B4には,直後 に「キャンセル」と記載されていることからすれば,S5,S4が約 定しても,元の買い注文B5,B4と同じ注文価格の買い注文B5, B4がそもそも生成されないか,生成されてもすぐにキャンセルされ ていると理解できること,加えて,本件明細書の【0144】ないし 【0147】にも,新たな新規注文B5及びB4は,個別に生成され るのではなく,(従前の)決済注文の全ての約定((従前の)決済注 文S1ないしS3の約定)を待って,新たな新規注文B1ないしB3 とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されている ことからすると,図35には,同図右上のS1ないしS3が同時に約 定し,もって,B5ないしB1及びS5ないしS1の全てが1回ずつ 約定した後に,「シフト機能」によるシフトが行われ,新たなB5ないしB1及びS5ないしS1が一括的に生成される場合が示されてい\nるに過ぎず,B5,B4に対応する決済注文S5,S4が約定すると, 元の買い注文B5,B4と同じ注文価格の買い注文B5,B4が再度 生成されることを看取できない旨主張する。 しかしながら,図35には,明示の記載はないが,決済注文S5, S4が約定した後に,元の買い注文と同じ注文価格の買い注文B5, B4及び元の売り注文S5,S4と同じ注文価格の売り注文S5,S 4が再度生成され,通常のリピートイフダン注文が繰り返されること は,「図30に示すように,相場価格64が上昇から下落に転じ,1 ドル=100.60円未満になると,約定情報生成部14は,決済注 文S4,S5を約定させる処理を行う。これにより,(新規注文情報 18114,18115に基づく)新規注文B4,B5と,(決済注 文情報18119,18120に基づく)決済注文S4,S5による イフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより,注文情報生成 部16は,元の新規注文B4,B5と元の決済注文S4,S5と同じ, 新たな新規注文B4,B5と元の決済注文S4,S5を生成する。」 (【0132】)との記載に照らしても明らかである。 したがって,控訴人の上記主張は,その前提において,採用するこ とができない。
エ 以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構\成のもの(実施の形態3)のほか,構成要件Hに含まれる,これ以外の構\成の もの(最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検 知すると,前記注文情報生成手段が,更に所定価格だけ高い「一の売り注 文情報」を生成するもの)についての開示があることが認められる。 したがって,構成要件Hは,本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが認められ,本件発明はサポート要件に適合するものと認\nめられるから,これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ワ)9909 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月23日 東京地方裁判所
被告は,上記ア記載のA邸工事の施工方法又は防水構造は本件各発明の構\ 成要件をすべて具備すると主張するのに対し,原告は,同方法又は構造は構\ 成要件D等を充足せず,本件各発明と相違点1において相違するので新規性 は欠如しないと主張する。
(ア) 構成要件D等における「封止する状態にして固定」の意義\n
そこで,まず,構成要件D等の「封止する状態にして固定」の意義につ\nいて検討する。 本件発明1及び3の特許請求の範囲の記載(構成要件D及びK)によれ\nば,内部水切り部材は,その固定板下面と屋根に設けた開口部周囲の野地 板上面又は防水シート上面との間で液体の流通を封止する状態にして固 定して,水が開口部に侵入することを防止する機能を有するものであるか\nら,ここにいう「封止」とは,液体の流通を封じ,止めること,すなわち, 水等の液体が開口部に侵入しない状態にすることをいうものと解される。 また,本件明細書等の記載をみても,「開口部を固定板で直接的且つ内 外液密的に覆うように内部水切り部材(インナーフラッシング)を配置す る」(段落【0011】),「内部水切り部材の固定板を野地板又は防水 シート上に密着した状態で固定するものとした本発明」(段落【0017】), 「開口部12を完全に覆うことのできるサイズの固定板21を,その下面 端縁側が密着する状態で内部水切り部材20を固定」(段落【0022】), 「密着状態で接着・固定して,固定板21下面と防水シート11上面との 間で水が流通しない状態に封止する。」(段落【0031】),「固定板 21の防水シート11側への密着性(封止性)が極めて高いものとなり優 れた防水機能を実現」(段落【0035】)などとされているから,内部\n水切り部材は,その固定板の下面端縁側を野地板等に密着させることで, 水等の液体の開口部への侵入を防止する機能を有するものであると解さ\nれる。 そうすると,構成要件D等における「封止する状態にして固定」とは,\n内部水切り部材の固定板の下面と野地板等を,水等の液体が開口部に侵入 しない程度に密着させて固定する状態をいうものと解するのが相当であ る。 これに対し,原告は,構成要件D等の「封止」とは,「精密部品などを\n外気に触れないように,隙間なく包むこと。または,その技術。」を意味 すると主張するが,この定義は精密機械等に外気が接することを念頭に置 いたものであり,外気ではなく液体の流通が問題となる本件各発明におい ては妥当しない。
(イ) 構成要件F等における「前記固定板外周に沿って防水テープが貼\付され ている」の意義
更に進んで,構成要件F等における「前記固定板外周に沿って防水テー\nプが貼付されている」の意義について検討する。\n本件発明2及び4に係る特許請求の範囲の記載によれば,内部水切り部 材の固定板外周に沿って防水テープを貼付するのは,同固定板下面と開口\n部周囲の野地板上面等との間で液体の流通を封止する状態にして固定す るためであり,また,構成要件F等においては,「固定板外周に沿って」\n防水テープを貼付するものとされているから,「前記固定板外周に沿って\n防水テープが貼付されている」とは,内部水切り部材の固定板の外周全体\nに防水テープが貼付されていることを意味すると解するのが自然である。\n本件明細書等の記載をみても,防水テープ15で固定板21の外周に沿っ てその全周にわたって貼付する態様の実施例のみが記載されている(段落\n【0032】,【図4】)。 そうすると,構成要件F等の「前記固定板外周に沿って防水テープが貼\ 付されている」とは,内部水切り部材の固定板の外周全体に防水テープが 貼付されていることを意味するものと認められる。\n
(ウ) A邸工事と本件発明1及び3との対比
上記(ア)及び(イ)の解釈を前提として,A邸工事の方法等と本件各発明と を対比すると,A邸工事は,アルミフラッシングの「固定板の下面が開口 部周囲の野地板上面に密着して配置され」,かつ,「上記アルミフラッシ ングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及び左右両側には,粘着剤層を有 する防水テープを貼付する」構\成を有するのであるから,A邸工事は,上 記固定板の下面が,野地板上面と,水等の液体が開口部に侵入しない程度 に密着して固定されている構成,すなわち「アルミフラッシングの固定板\n下面と開口部周囲の野地板上面との間で液体の流通を封止する状態にし て固定する」構成を有するものと推認することができる。\n したがって,A邸工事は構成要件D等を具備し,本件発明1及び3は新\n規性を欠くこととなる。
(エ) A邸工事と本件発明2及び4との対比
前記のとおり,本件発明2及び4の構成要件F及びMの「前記固定板外\n周に沿って防水テープが貼付されている」とは,内部水切り部材の固定板\nの外周全体に防水テープが貼付されていることを意味するところ,A邸工\n事においては,アルミフラッシングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及 び左右両側には防水テープが貼付されているが,その軒側にはこれが貼\付 されていないから,この点で両者は相違することとなる。 したがって,本件発明2及び4が新規性を欠くということはできない。
ウ 進歩性の有無について
前記判示のとおり,A邸工事の方法と本件発明2及び4の構成要件F等は,\n固定板の外周のうち軒側に防水テープが貼付されているかどうかにおいて\n相違するところ,防水テープは,開口部に水が浸入しないようにするために 内部水切り部材の固定板に貼付するものであるから,四角形状の固定板の縁\n部分の上記3辺に防水テープを貼付した上,更に念を入れて軒側の下辺にも\n防水テープを貼付することについて,当業者であれば当然に想到し得たもの\nと考えられる。 これに対し,原告は,インナーフラッシングの固定板の3辺に防水テープ を貼付して固定していた構\成を,全周にわたり防水テープを貼付する構\成に 置き換えると,部材や工数が増加して過剰なコストや手間を要することにな るから,阻害要因があると主張するが,A邸工事の開口部は1辺が40cm程 度であること(乙12資料3)からして,軒側の1辺に防水テープの貼付す\nる部材のコストや工数の負担はごくわずかなものと考えられるので,原告の 主張するような阻害要因があるということはできない。 したがって,本件発明2及び4は,公然実施されたA邸工事に基づき当業 者が本件特許出願当時に容易に想到し得たものであるというべきである。
エ 小括
前記イのとおり,本件各発明に係る特許出願より前である平成19年6月 28日に公然と実施されたA邸工事は,本件発明1及び3の構成要件を全て\n充足するから,本件発明1及び3は新規性を欠く。 また,前記ウのとおり,A邸工事は,アルミフラッシングの四角形状の固 定板の軒側縁部分に防水テープが貼付されていない点で本件発明2及び4\nと相違するが,当業者は,同部分にも防水テープを貼付する構\成に容易に想 到し得るといえるから,本件発明2及び4は進歩性を欠く。 したがって,本件各発明は,いずれも特許無効審判により無効にされるべ きものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ワ)28604 商標移転登録抹消請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年11月26日 東京地方裁判所
一般社団法人法は,理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をし ようとするときは,理事会において,当該取引について重要な事実を開示し, その承認を受けなければならない旨定める(同法84条1項2号,92条)。 本件譲渡は,前記第2の2(2)のとおり,原告の理事であった被告が,原告か ら,原告の財産である本件商標権を無償で譲り受けたものであり,理事が自 己のために一般社団法人と取引をした場合に当たるから,一般社団法人法8 4条1項2号所定の利益相反取引に該当する。
イ これに対し,被告は,オン社の唯一の株主及び代表取締役が被告であること\nに鑑みれば,本件譲渡は,実質的に本件登録前権利に係る譲渡契約の解除に 伴う原状回復義務の履行として,原告からオン社へ本件商標が返還されたと 評価されるべきであり,利益相反取引に該当しない旨主張する。 しかしながら,オン社は被告とは独立した法人格を有する株式会社であると ころ,原告はオン社に対して本件商標を譲渡したものではないから,そもそ も原状回復の問題ではなく,オン社ではない理事である被告への譲渡が原告 との間で利益相反行為となることは明らかである。被告の上記主張には理由 がない。
ウ 以上によれば,本件譲渡は,仮にこれが成立していたとしても,一般社団法 人法84条1項2号所定の利益相反取引に該当し,これについて原告の理事 会の承認を受けていないから,無効というべきである(最高裁昭和43年1 2月25日大法廷判決・民集22巻13号3511頁参照)。
2 争点2(原告が,理事会の承認又は決議の欠缺を理由に本件譲渡の無効を主張 することが信義則に反して許されないか否か)について
(1)前記前提事実に加え,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を 認めることができる。
ア 被告は,平成18年7月4日に原告が設立された当初より,専務理事兼事 務局長として原告の事業に従事し,原告の業務の遂行等に大きな役割を果 たしていた。 平成28年11月頃,原告の代表理事はC(以下「C」という。)であっ\nたところ,被告は,情報機器のリユース・リサイクルの促進等の事業を行う 新たな団体を設立することを計画し,これに賛同するBら複数の原告理事 らと共に,新団体の名称を考案したり,経済産業省に提出するための書類を 準備したりするなどした(甲13,乙2の1[4ないし9頁],31)。
イ 被告は,上記新団体の名称の候補として「IoT機器3R協会」を考案し, 平成28年11月25日,自身が代表取締役を務めるオン社を出願人とし\nて商標出願をした(甲10の2,乙1,2の1,2の2,31)。
ウ 平成29年5月23日,BがCに代わり原告の代表理事に就任した。原告\nと別に新たな団体を設立する構想が立ち消えになったところ,被告は,オ\nン社の代表者として,同年7月12日頃,原告に対し,本件登録前権利を\n譲渡した。この際に原告理事会の承認は受けなかった。(乙6,7の1)
エ 被告は,平成29年7月21日頃,原告内部に向けた「今後の当協会の方 向性と取り組みについて(案)」と題する資料を作成し,Bら原告の理事に 配布するなどした(乙29,弁論の全趣旨)。同資料において,被告は,I oT(Internet of Things)について「もはやはやり言葉の領域を超えて いると思われ,当協会としても積極的に対応すべき時代になったと考えて います。」,「IoT対応機器の普及が拡大している幅広い電子機器機械の3 Rへの新たなビジネス参入のチャンスをもっていると思われます。また, 当協会としてもこの分野への積極対応により,新たな会員様獲得のチャン スが生まれると考えます。」と記載して,原告のIoT対応機器分野への積 極的進出を提案すると共に,新しい協会名として「電子機器機械3R協会」 及び「IoT対応機器機械3R協会」を提案し,「なお,IoTからみの商 標申請が多数発生しているため,抑えとして最もシンプルな名前の『Io\nT機器3R協会』の名称については申請中。」と記載した(乙29)。\n
オ Bは,平成29年7月25日に開催された原告の理事会において,原告の 今後の課題として,原告の知名度の向上と組織内部の充実の2点を挙げ, 前者の具体策としてIoTに関連した分野の取り込み及びこれに伴い協会 名を変更すること等を提案し,同議案は可決された。理事会は,同日,上 記2点の課題を検討するために,副代表理事を委員長とする実行委員会を\n設け,同委員会が検討結果を理事会へ報告することとした。(乙9,10)
カ 平成29年8月22日,原告の理事会が開催され,そこで,上記オで設 けられた実行委員会は,組織内部の充実の観点から早急に対応が必要な事 項の一つとして,事務局長と専務理事を兼務する旨の定款の定めを削除す ることや,事務局の給与体系の制定など被告が事務局長を務める事務局の 体制の改革が提案された(甲17,乙11,12,35)。
キ 被告は,平成29年9月11日,本件商標を原告から被告に譲渡した旨の 譲渡証書を作成した(甲4,乙31)。同時点において,被告は,本件譲渡 につき原告の理事会の承認を受けていないことを認識していた(被告本人 [38頁])。
(2)ア 被告は,(1)原告は本件商標の発案・出願に関与していないこと,(2)本件商 標の登録や移転に関する費用を負担していないこと,(3)本件登録前権利の譲 り受けについても理事会の承認又は決議を得ていないこと,(4)Bを除く原告 理事は原告が本件商標を保有していることを認識していなかったこと,(5)本 件譲渡を指示した原告の代表理事であるBが理事会を招集しなかったこと\nを挙げ,原告が理事会の承認の欠缺を理由として本件譲渡の無効を主張する ことは信義則に反して許されない旨主張する。 しかしながら,前記(1)エ及びオによれば,原告は,本件譲渡当時,IoT 対応機器のリユース・リサイクル事業への進出とこれに伴う名称の変更を計 画していた。そして,本件商標はIoTの文字を含み,被告によって原告の 新名称の候補の一つとして提案されたものに類似していた。また,原告が本 件登録前権利を有していることは理事らにも認識されていたと認められる。 そうすると,本件商標は,原告の今後の事業展開にとって非常に重要なも のとなり得るものであった。そのことは原告の理事も理解し得たのであり, また,そのような重要なものとなり得る本件商標に係る本件登録前権利を 原告が有していたことは認識されていた。本件譲渡はそのような本件商標 を無償で被告に譲渡するものであり,原告に大きな不利益をもたらす反面, 被告に利益をもたらし得るものであるから,利益相反の程度は高い。 被告の主張する上記(1)ないし(3)の事情は,本件商標の登録に至る被告の 寄与や本件譲渡前の事情をいうものであるが,被告自身が特段の条件を付 さずにオン社から原告に対して本件登録前権利を譲渡したことも考慮する と,これらはいずれも原告が本件譲渡の無効を主張することが信義則違反 となることを基礎付けるものであるとはいえない。被告の主張する上記(4) の事情は,原告の代表理事であるBが本件商標を保有していることを認識\nしている以上,原告として本件商標を保有していることを認識していたと いえるのであるし,本件商標が客観的に原告にとり非常に重要なものとな り得るものであったことや,それが出願されていることは原告の理事らに も認識されていたことに照らしても,原告が本件譲渡の無効を主張するこ とが信義則違反となることを基礎付けるものであるとはいえない。また,上 記(5)について,被告は,平成29年8月22日の理事会終了後にBから本件 商標を被告に戻すように指示された旨主張し,本人尋問においても,これに 沿う供述をするほか,商標を戻すものであるから理事会の承認は必要ない 旨Bから言われた旨供述する(被告本人〔23ないし25頁〕)。しかし,前 記(1)クのとおり,被告は本件譲渡が理事会の承認を受けていないことにつ き悪意であるところ,法人の代表者と取引の相手方が共謀して理事会の承\n認を受けることなく利益相反取引をした場合,法人は,悪意の当該相手方に 同取引の無効を主張することができるというべきであり,仮に被告が主張, 供述する事実が認められたとしても,原告が信義則上本件譲渡の無効を主 張することができなくなるとはいえない。
イ 以上によれば,原告が本件譲渡の無効を主張することは信義則に反する 旨の被告の主張には理由がない。
2019.12. 3
令和1(行ケ)10086 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年11月26日 知的財産高等裁判所
前記アの認定事実を総合すると,ヘニングセンがデザインした本件商品の立体的形状は,被告による本件商品の販売が日本で開始された1976年(昭和51年)当時,独自の特徴を有しており,しかも,本件商品が上記販売開始後本件商標の登録出願日(平成25年12月13日)までの約40年間の長期間にわたり日本国内において継続して販売され,この間本件商品は,ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり,そのデザインが優れていること及び本件商品は被告(「ルイスポールセン社」)が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われた結果,本件商標の登録出願時までには,本件商品が日本国内の広範囲にわたる照明器具,インテリアの取引業者及び照明器具,インテリアに関心のある一般消費者の間で被告が製造販売するランプシェードとして広く知られるようになり,本件商品の立体的形状は,周知著名となり,自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至ったものと認められる。そうすると,本件商品の立体的形状である本件商標が本件商品に長年使用された結果,本件商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時(登録審決日・平成27年12月15日)において,被告の業務に係る商品であることを表\示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから,本件商標は,商標法3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するものと認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本件商品(「PH5」)は,デンマークのデザイナーであるヘニングセンがデザインした商品として,宣伝され,評価され,販売されてきたものであるから,PH5の立体的形状である本件商標は,ヘニングセンがデザインしたランプシェードの立体的形状として周知であるにとどまり,被告の業務に係る商品であることを表示するものとして,周知であるということはできない旨主張する。\nしかしながら,前記(2)イ認定のとおり,被告は1976年(昭和51年)から本件商標の登録出願日(平成25年12月13日)までの約40年間の長期間にわたり日本国内において本件商品を継続して販売し,その間,本件商品は,ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり,そのデザインが優れていること及び本件商品は被告(「ルイスポールセン社」)が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われてきたことに照らすと,本件商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,被告の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから,原告の上記主張は採用することができない。\n
イ 原告は,PH5に係る商標権,著作権等の知的財産権は,ヘニングセンに帰属するから,被告は,ヘニングセン及びその相続人から,商標権の譲渡を受け,又は使用許諾を受けていなければ,本件商標の商標登録を受けることはできない,PH5のデザインは,外国において商標登録されておらず,知的財産権の権利者が死亡し,パブリックドメインとなっているから,商標登録をさせてはならず,被告の本件商標の商標登録は無効とすべ きである旨主張する。しかしながら,商標法3条2項は,同条1項3号から5号までに該当する商標であっても,「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」については,商標登録を受けることができる旨を定めたものであるところ,原告の上記主張は,同条2項の文言の解釈に基づかないものであるから,その主張自体理由がないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 使用による識別性
>> 商4条1項各号
>> 立体商標
>> ピックアップ対象
2019.12. 1
平成31(ワ)5391 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和元年10月3日 東京地方裁判所
原告は,原告表示1−1ないし同2−3につき,原告の商品等表\示として 需要者の間に広く認識されている旨を主張する。しかしながら,次のとおり,原告主張に係る各表示は,いずれも原告の商品等表\示として需要者の間に広く認識されているとは認められない。
ア 原告表示1−2及び同2−2について\n
原告主張に係る原告表示1−2及び同2−2は,いずれもサーボモータ\nの外観を示したものであるところ,原告は,これらが単に原告表示1−1\n及び同2−1の型番が表示され,又は原告表\示1−3及び同2−3のラベ ルが貼付された状態を説明したものにとどまるものではなく,各サーボモ\nータの形態自体が,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されて\nいる旨を主張しているものとして,以下検討する。 この点,不競法2条1項1号にいう「商品等表示」とは,人の業務に係\nる氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営 業を表示するものをいい,しかして,商品の形態は,これに付される商標\n等とは異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではな\nい。そうすると,このような商品の形態自体が不競法2条1項1号の「商 品等表示」に該当するためには,(1)商品の形態が客観的に他の同種商品と は異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,(2)その形態が特定 の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な広告宣伝や 爆発的な販売実績等により,需要者においてその形態を有する商品が特定 の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を\n要するものと解するのが相当である。 これを本件について見るに,原告表示1−2及び同2−2のいずれにつ\nいても,他のサーボモータの形態と対比して客観的に異なる顕著な特徴を 具体的に含んでいることを的確に認めるに足りる証拠はないものであって, 同形態が上記(1)の特別顕著性を有しているとは認められないというべきで ある。 したがって,原告表示1−2及び同2−2はいずれも不競法2条1項1\n号にいう「商品等表示」に当たるとはいえない。\n
イ その他の表示について\n
原告は,原告表示1−1ないし同2−3の表\示が周知性を有することの 根拠として,原告商品が各種媒体において頻繁に使用例が掲載されている こと,最大手のオンライン通販市場の売上げランキングにおいて上位を独 占していること,(所在地省略)の小売店での販売実績の上位であること等 を挙げる。 しかしながら,各種媒体における掲載状況や小売店での販売実績につい ては,これを具体的に認めるに足りる客観的な証拠はなく,また,オンラ イン通販市場での売上げランキングについても,期間が限定された,断片 的な資料(甲7)が提出されているにすぎず,その他本件全証拠を精査し ても,原告主張に係るその他の表示(原告表示1−1,同1−3,同2−1\n及び同2−3)の付された商品を見た需要者において,商品の出所が原告で あると認識する状況になるまでに至っているものと認めるには足りないと いうべきである。 したがって,原告主張に係るその他の表示は,いずれも原告の商品等表\ 示として需要者の間に広く認識されているとは認められず,不競法2条1 項1号にいう「他人の商品等表示(中略)として需要者の間に広く認識さ\nれているもの」に当たるとはいえない。
(2) 類似性,混同のおそれの有無(争点1−2)について
以上の説示によれば,原告の請求はいずれも既に理由がないものであるが, なお念のため,原告表示1−3及び同2−3と被告表\示1−3及び同2−3 との類似性及び混同のおそれの有無につき検討する。 この点,各表示とも横書き3行の文字列で構\成されており,原告表示1−\n3は1行目が「Towerpro」,2行目が「MG996R」,3行目が「D IGI HI TORQUE」と表示されているのに対し,被告表\示1−3 は1行目が「TZT」と表示されており,2行目及び3行目は原告表\示1− 3と同様の文字が表示されている。\n また,原告表示2−3は1行目が「TowerPro」,2行目が「MG9\n95」,3行目が「DIGI HI−SPEED」と表示されているのに対し,\n被告表示2−3は1行目が「TZT」と表\示されており,2行目及び3行目 は原告表示2−3と同様の文字が表\示されている。 しかして,商標の類否ないし混同のおそれの有無は,同一又は類似の商品 に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象, 記憶,連想等を総合して,その商品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に 考察して決すべきものであるところ,原告表示1−3と被告表\示1−3及び 原告表示2−3と被告表\示2−3とをそれぞれ対比すると,1行目の表示が\n全く異なる文字列で構成され,この部分の外観,観念,称呼が異なることは\n明らかであり,また,2行目の「MG996R」及び「MG995」や3行 目の「DIGI HI TORQUE」及び「DIGI HI−SPEED」 は一致しているが,これは,上記各表示が使用される商品であるサーボモー\nタの型番や性状を示す部分にすぎないと認められる。 以上に照らし,サーボモータに係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察 すれば,表示全体として,原告表\示1−3と被告表示1−3及び原告表\示2 −3と被告表示2−3とが類似しているとは認め難いというほかなく,混同\nのおそれがあるということもできない。
(3) 以上によれば,被告による被告商品の販売行為等は,不競法2条1項1号 所定の不正競争行為に当たらない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2019.11.28
令和1(ネ)10043 著作権に基づく差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決(同平成11年(受)第9 22号,民集55巻4号837頁)は,言語の著作物に関してであるが, 著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な\n特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,\n新たに思想又は感情を表現することにより,これに接する者が既存の著作\n物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作\nする行為であるとしている。そして,翻案の意義は,本件問題のような編 集著作物についても同様であると解されるから,編集著作物の翻案が行わ れたといえるためには,素材の選択又は配列に含まれた既存の編集著作物 の本質的特徴を直接感得することができるような別の著作物が創作された といえる必要があるものと考えられる。
イ これを本件について検討してみるに,本件問題は,控訴人自身も主張す るとおり,題材となる作品の選択や,題材とされる文章のうち設問に取り 上げる文又は箇所の選択,設問の内容,設問の配列・順序に作者の個性が 現れた編集著作物であり,ここでは,このような素材の選択及び配列等に, その本質的特徴が現れているということができる。これに対し,被告ライ ブ解説は,作成された問題(すなわち,素材の選択及び配列等)を所与の ものとして,これに対する解説,すなわち,問いかけられた問題に対する 回答者の思考過程や思想内容を表現する言語の著作物であって,このよう\nな思考過程や思想内容の表現にその本質的特徴が現れているものである。\nこのように,編集著作物である本件問題と,言語の著作物である被告ライ ブ解説とでは,その本質的特徴を異にするといわざるを得ないのであるか ら,仮に,被告ライブ解説が,本件問題が取り上げた文を対象とし,本件 問題が提起したのと同一の問題を,その配列・順序に従って解説している ものであるとしても,それは,あくまでも問題の解説をしているのであっ て,問題を再現ないし変形しているのではなく,したがって,本件問題の 翻案には当たらないものといわざるを得ない。 この点について,控訴人は,本件問題と被告ライブ解説とはその本質的 特徴を同一にするとして種々主張しているけれども,上記に指摘した点に 照らし,採用することはできない。
(3) 被告ライブ解説は本件解説の翻案に当たるかについて
控訴人は,本件解説と被告ライブ解説とは,本件問題の読解対象文章及び 設問・選択肢の文章を前提としているということでは全く共通であるから, 個々の文言にほとんど共通性がないからといって,表現の本質的特徴に同一\n性がないということにはならない旨主張する。しかしながら,読解対象文章 及び設問・選択肢の文章を前提としていること自体からは,表現にわたらな\nい内容の同一性がもたらされるにすぎないから,表現の本質的特徴の同一性\nの有無は,別途,文言等の共通性等を通じて判断されるべきものである。し たがって,控訴人の上記主張は採用することができない。 また,控訴人は,本件ライブ解説の個々の箇所について,本件解説との間 で表現上の本質的特徴の同一性を有する旨主張する。しかしながら,本件解\n説と被告ライブ解説とがいずれも本件問題に対する解説であることに由来し て内容の類似性・同一性はみられ,被告ライブ解説は,その内容については 部分的に本件解説と本質的特徴を同一にするといえるものの,その表現につ\nいては,控訴人の主張を踏まえて検討しても,本件解説と本質的特徴を同一 にするとは認められない。したがって,控訴人の主張は採用することができ ない。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)14843 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和元年9月18日 東京地方裁判所
本件各写真は,本件各商品を販売するために撮影されたものであると認めら れるところ(甲33),以下のとおり,いずれも,商品の特性に応じて,被写体の 配置,構図・カメラアングルの設定,被写体と光線との関係,陰影の付け方,背景\n等の写真の表現上の諸要素につき相応の工夫がされており,撮影者の思想又は感情\nが創作的に表現されているということができる。\n
ア すなわち,本件写真1ないし4は,ト音記号,楽譜又は楽器の柄のネクタイ を被写体とするものであり,ネクタイの下端部を手前にして波打つように配置され, 背景はネクタイの下端部が配置された写真下部を白色,写真上部を暗い灰色又は黒 色とし,陰影が明確に付されるなどして,ネクタイの柄や質感を視覚的に認識しや すいものとなっており,商品の販売用の写真として相応の工夫がされているという ことができる。
イ 本件写真5ないし10は,弦楽器の柄のコインケース等の商品を被写体とす るものであり,本件写真5,7,9は,商品を中央に配置して全体を撮影したもの, 本件写真6,8,10は,柄の部分を大きく撮影したものであって,商品の配置の 仕方や陰影の付し方により,商品の質感や弦楽器の柄を視覚的に認識しやすいもの となっており,商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということがで きる。
ウ 本件写真11ないし40は,楽器を演奏する動物等の置物を被写体とするも のであり,本件写真11,14,17,20,23,26,29,32,35,3 8は,商品の前方を正面から撮影したもの,本件写真12,15,18,21,2 4,27,30,33,36,39は,商品の後方を斜め上から撮影したもの,本 件写真13,16,19,22,25,28,31,34,37,40は,動物等 の顔を斜め上から大きく撮影したものであって,背景は緑色,白色又はそれらのグ ラデーションとし,陰影を付すなどして,動物等の表情や演奏態様等を視覚的に認\n識しやすいものとなっており,商品の販売用の写真として相応の工夫がされている ということができる。
エ 本件写真41ないし44は,鍵盤等の柄のフロアマットを被写体とするもの であり,本件写真41及び43は,四角形状の商品の形態に沿って商品のみを大き く撮影したもの,本件写真42及び44は,その一部を大きく撮影したものであっ て,生地の質感や鍵盤等の柄を視覚的に認識しやすいものとなっており,商品の販 売用の写真として相応の工夫がされているということができる。
オ 本件写真45ないし50は,写譜用のペンを被写体とするものであり,本件 写真45,47,49は,商品を中央に配置して全体を撮影したもの,本件写真4 6,48,50は,ペンの先端部分を大きく撮影したものであって,商品に光を反 射させ,背景を白色とし,陰影を付すなどして,商品の質感や細かい模様を視覚的 に認識しやすいものとなっており,商品の販売用の写真として相応の工夫がされて いるということができる。
カ 本件写真51及び52は,写譜用のペンの替芯(5本)及びそのケースを被 写体とするものであり,ケースから突出する替芯につき長さを変えた状態で大きく 撮影したものであって,背景を白色とし,陰影を付すなどして,商品の形状を視覚 的に認識しやすいものとなっており,商品の販売用の写真として相応の工夫がされ ているということができる。
キ 本件写真53ないし61は,トランペット等の楽器の柄の黒色クリアファイ ルを被写体とするものであり,本件写真53,55,57,59は,商品を中央に 配置して全体を撮影し,柄の部分に光を反射させ,背景は黒色を基調とし,陰影を 付すなどしたもの,本件写真54,56,58,60は,柄の部分を大きく撮影し たものであって,トランペット等の楽器の柄を視覚的に認識しやすいものとなって おり,商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。ま た,本件写真61は,商品を中央に配置して柄のない方向から全体を撮影したもの であり,背景を白色と黒色のグラデーションとし,陰影を付すなどして,商品の形 状を視覚的に認識しやすいものとなっており,商品の販売用の写真として相応の工 夫がされているということができる。 ク 以上のとおり,本件各写真には,商品の販売用の写真として相応の工夫がさ れており,撮影者の思想又は感情が創作的に表現されているということができる。\n
(2)被告は,本件各写真が著作物であることを争い,取り分け,本件写真42な いし44は商品を上から撮影しているだけであり,本件写真45,46,50ない し52は商品の販売用の写真として一般的なものであるから,これらに創作性が認 められないことは明らかである旨主張するが,前記のとおり,本件各写真には,商 品の販売用の写真として相応の工夫がされており,撮影者の思想又は感情が創作的 に表現されているということができるのであって,被告の上記主張は採用すること\nができない。
(3) 以上によれば,本件各写真には創作性が認められ,前記前提事実(2)のとおり, これらは原告代表者によって原告の発意に基づき職務上作成されたものであるから,\nいずれも,原告の著作物であると認められる。
前記のとおり,被告は,原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害しており,これらについて,少なくとも,過失があると認められるから,不法行為による損害賠償責任を負っているところ,原告は,本件\n各写真の使用料相当額に係る損害(著作権法114条3項)として,著作権侵害に 係るものにつき合計46万3800円,著作者人格権侵害に係るものにつき合計4 万6800円の損害が生じたと主張する。
(2) そこで検討すると,前記のとおり,被告は,原告が本件各写真を原告ウェブ サイトに掲載することによって販売していた本件各商品を,本件各写真と実質的に 同一の被告各写真を被告ウェブサイトに掲載することによって販売していたもので あり,このような被告各写真の使用態様に加えて,被告各写真の掲載期間は長いも ので1年6か月にわたること,証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば,画像素材 の販売業者である「ペイレスイメージズ」のウェブサイトでは,画像素材の単品で の購入価格が432円から5400円までとされていると認められることなど,本 件訴訟に現れた事情を考慮すると,本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべ き金銭の額(著作権法114条3項)は,写真1枚当たり5000円と認めるのが 相当である。もっとも,原告の氏名表示権が侵害されたことによって,別途の財産\n的損害が生じたと認めるに足りない。
(3)ア これに対し,原告は,アマナイメージズの価格表において,画像素材1点\n当たりの使用期間1年までの使用単価は3万8880円,使用期間3年までの使用 単価は6万0480円,無断使用した場合には使用料金の200%を請求できると されていることを主張するが,弁論の全趣旨によれば,アマナイメージズは,画像 素材のレンタルや販売を業とする株式会社であると認められるのに対し,本件各写 真はレンタルや販売を目的として撮影されたものではないから,原告が主張する価 格表について本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法114条3項所定の損\n害額の算定に当たって大きく考慮することは相当とはいえない。 イ 他方で,被告は,(1)本件各写真の創作性の程度の低さなどに照らせば,販売 用の広告写真1枚当たりの使用料相当額はせいぜい1000円程度である,(2)被告 において学遊社に本件各写真と同じカットでプロカメラマンによる写真撮影の見積 りを依頼したところ,ライティングを施すことを含む見積額が8万円であったから, 本件各写真の使用料相当額に係る損害は高くても合計8万円である旨主張する。 しかしながら,(1)については,前記のとおり,本件各写真は,商品の販売用の写 真として相応の工夫がされているということができるから,創作性の程度が低いこ とを理由として著作権法114条3項所定の損害額を著しく低額にすべきであると いうことはできない。
(2)については,証拠(甲41,乙3)及び弁論の全趣旨によれば,学遊社は,被 告から提供を受けた本件各写真をサンプルとして参照し,本件各写真に対応する6 1カットの写真を半日でまとめて撮影した場合の撮影料を見積もったものと認めら れるところ,学遊社の見積りは,本件各写真をサンプルとして参照しているため, 被写体の配置,カメラアングル・構図等を検討する必要はなく,また,半日でまと\nめて撮影しているため,複数日にわたって撮影されたと認められる本件各写真と比 べて撮影費用が低額となっているとみる余地があることなどからすれば,見積額が 8万円であるからといって,本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法114 条3項所定の損害額が同程度であるということはできない。
(3) そうすると,本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべき金銭の額(著 作権法114条3項)は,合計30万5000円(5000円×61枚)であると 認められる。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)12609 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月9日 東京地方裁判所
本件発明1は,(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ\nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段,(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段,(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段,(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより,赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに,案内音声である再生対象音の識別情報に対\n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする(【0005】)。
エ 以上に加えて,本件発明1は,前記送信手段が,当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し,前記受信手段が,情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用することにより,相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指\n定された言語に対応する関連情報を受信することができ,使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである(【0006】等)。\n
・・・
被告は,(1)乙9公報は,音響IDとインターネットを用いて,放音装置から放音 された音響IDによって識別される識別対象の情報に対し,これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙9技術を開示しているところ,本件 発明1も乙9技術を採用するものであり,相違点1−5ないし同1−7は,情報要 求に含まれる情報の内容,複数の関連情報の選択条件,関連情報の内容に係る相違 にすぎず,当業者が適宜設定できるものである旨主張するとともに,(2)当業者は, 乙9発明1に,乙10発明又は乙5公報及び乙10公報記載の周知技術,並びに周 知技術(乙14等)を組み合わせるなどして,相違点1−5ないし同1−7に係る 本件発明1の構成を容易に想到し得た旨主張する。しかしながら,まず,被告の上記(1)の主張については,前記(1)エと同様に,乙9 公報等に音響IDとインターネットを用いた同種の情報提供が開示されていたとし ても,本件発明1は,その手順や方法を具体的に特定し,使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるから,相違点1−5ないし同1−7に係る\n本件発明1の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。\n
・・・
5 争点6(差止めの必要性は認められるか)について 被告は,本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし,その理由とし て,(1)本件口頭弁論終結時点において,本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと,(2)被告は,平成30年5月以降,本件アプリの配信を中止し,多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており,本件訴訟の結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予\定であること,
(3)被告は,今後,顧客に対し,案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や,案内音声である第1言語の再生対\n象音が表す発音内容を第2言語で表\\現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,本件アプリは,本件発明1の技術的範囲に属 し,本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから, 前記第2の2(4)のとおり,被告は,少なくとも,平成29年5月頃から平成30年 6月頃まで,本件アプリを作成し,譲渡等及び譲渡等の申出をし,平成28年6月から平成29年3月までの間に3回にわたり本件アプリを使用することによって本\n件特許権1を侵害していたものである。 これらに加えて,被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明1の技術的範囲 に属することを否認して争い,本件特許1について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること,弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も,ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ,被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなども考慮すると,被告は,今後,本件特許権1を侵害するおそれがあるものというべ\nきであるから,原告が被告に対し,その侵害の予防のため,本件アプリの作成等の差止を求める必要性は認められるものというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)16555 特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟 令和元年10月29日 東京地方裁判所
ア 本件発明の特許請求の範囲の記載は「患者の血清中でプロカルシトニン3 −116を測定することを含む,敗血症及び敗血症様全身性感染を検出する ための方法。」であり,その構成要件Aは「患者の血清中でプロカルシトニン\n3−116を測定することを含む」というものであるところ,特許請求の範 囲には,その意義について規定する記載はないが,「測定」とは,一般的に, 「長さ,重さ,速さなど種々の量を器具や装置を用いてはかること」(大辞林 (第3版))との意味を有する。 そうすると,特許請求の範囲の記載からは,構成要件Aの「プロカルシト\nニン3−116を測定すること」とは,敗血症等を検出するため,血清中に 含まれるプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味する ものと解するのが自然である。
イ また,前記1(2)のとおり,本件明細書の記載によれば,敗血症等の患者の 血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンについて,従前プロシ\nカルシトニン1−116と暫定的,一般的にみなされるなどしていたところ, 本件発明は,敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカル\nシトニンが,プロカルシトニン1−116ではなく,プロカルシトニン3− 116であるという発見に基づき,新規な敗血症等の診断方法を提供するこ とを目的とするものである。そして,本件明細書の発明の詳細な説明には, 「プロカルシトニン3−116を測定すること」の意義について,特段の記 載はない。そうすると,本件明細書の記載からも,構成要件Aの「プロカル\nシトニン3−116を測定すること」とは,敗血症の検出のため,上記の発 見に基づきプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味し, その測定結果が敗血症等の検出に用いられることと理解できる。
ウ 原告は,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定すること」と\nは,プロカルシトニン3−116を敗血症等の検出に必要な精度で測定する ことをいい,プロカルシトニン1−116と区別してプロカルシトニン3− 116を特異的・選択的に測定することを必須とするものではない旨主張し, その根拠として,本件明細書の実施例において,プロカルシトニン3−11 6を特異的・選択的に測定することが困難なイムノアッセイによりプロカル シトニンの濃度を測定することが記載されていること,本件明細書の記載等 を踏まえると,患者の血清中でプロカルシトニン1−116とプロカルシト ニン3−116とを区別することなくプロカルシトニン一般を測定したと しても,その濃度は,おおよそプロカルシトニン3−116の濃度であり, 測定されたプロカルシトニン3−116の濃度は敗血症等の検出に必要な 精度になっていることを指摘する。 しかし,本件明細書のイムノアッセイによる測定に関する記載について, 正常者及び敗血症患者の血清中のプロカルシトニン濃度の測定結果と,これ と同時に行われたこれらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対 比することにより,正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニ ンにおいて際立っていることを示すものである旨の記載があることからす ると(段落【0059】【0062】【0063】【表3】),上記測定は,「敗\n血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の実施例であるとは認 められないから,原告の上記主張の根拠となるとは認められない。 また,仮に,敗血症患者の血清中に含まれるプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン3−116であるという関係があるとしても,プロカルシ トニン3−116を測定することとプロカルシトニン一般を測定すること が同義とはいえないことは明らかである,また,敗血症等であるかどうかが 明らかではない患者については,その血清中のプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン3−116であるかどうかは明らかではないといえるほ か,本件明細書には,患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定すること により敗血症等を検出する技術は本件発明の優先日前に従来技術として存 在したところ,本件発明は,従来技術に対して新規のものである旨が記載さ れているのであって,原告の主張は採用することはできない。 以上によれば,原告の主張には理由がなく,これを採用することはできな い。
エ 以上によれば,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定する\nこと」とは,プロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味す るものと解される。
(2)前記前提事実(第2の1(4)のとおり,被告装置及び被告キットを使用する と,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116とを区別する ことなく,いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することができ, その測定結果に基づき敗血症等の鑑別診断等が行われていると認められる。被 告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出する過程で,プロカルシトニ ン3−116の量が明らかにされているとは認められない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告方法は,構成要\n件Aを充足するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成29(ワ)7576 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
以上を踏まえ,顧客吸引力の観点から被告第2製品における本件第2 及び第3特許の技術的意義の有無及び程度を検討すると,まず,本件被告カタログ 記載の「6つの特徴」の1つとして,被告第2製品は「素手で持っても痛くありま せん。」との記載がある。「テーパ部」の解釈に関する被告の主張をも考慮すると, これは「テーパ部」の存在をうかがわせるものとも理解し得るものの,いかなる構\n成によって「素手で持っても痛く」ないことを実現しているのかは具体的に示され ていない。当該記載に付された写真では,製品のアンカーボルト挿通用の開口部に 手指を通して握る形で,当該開口部を囲む部材のうち長辺部分をなす部材のうちの 1つを掌全体で把持していること(甲4,乙32)に鑑みると,「テーパ部」の存在 故に「素手で持っても痛く」ないという効果を奏しているとも断じ得ない。また, 本件第2発明の効果2に言及する記載もない。 さらに,本件被告カタログには,「6つの特徴」の1つとして,「スピード施工」 が挙げられているところ,その部分には,被告第2製品の片方の端部の接続部につ いて「連結構造」との説明が付されている。もっとも,「連結構\造」とされる接続部 の構造や接続の仕方ないし効果に関する説明はない。\nむしろ,前記認定のとおり,本件被告カタログでは,被告第2製品の強度や換気 性能,供給・品質・価格の安定性,カットしやすい独自の形状を有する省施工商品\nであること等が強調されている。 この点は,原告や同業他社のカタログ等にも共通する。このうち,原告のカタロ グ等には「テーパ部」や「接続部」に関する記載も見られるものの,その構造は具\n体的に示されておらず,作用効果も,他の記載と比較すると,強調の度合いは低い。 むしろ,全周敷き込みの簡単施工や特殊構造の換気スリット・防鼠材といった点が\n前面に出されて強調されている。 以上の事情に加え,被告第2製品が本件第2発明の効果を奏しない形で使用され ることがあり得ることは否定できないこと(ただし,実務上そのような使用態様が 採られる割合は不明である以上,この事情を推定覆滅に当たって過大視することは できない。),前述のとおり,台輪の幅方向への移動を防止する別の方法もあること を踏まえると,本件第2及び第3発明は,施工容易性の実現という観点から一定の 顧客吸引力を有するといえるものの,本件第2発明の「テーパ部」の構成や本件第\n3発明の構成要件3C〜3Gの構\成を有することによる顧客吸引力は,相対的には 小さいというべきである。 なお,被告は,被告第2製品の形状変更後に売上げが増加したことを指摘してい るが,その裏付けとなる資料(乙60)は形状変更後の4か月の売上額を集計した ものにすぎないし,売上げの変動要因としては様々なものが考えられることから, 上記事情が直ちに本件第2及び第3特許が被告第2製品の需要に与える影響が小さ いことを裏付けると見ることはできない。 これらの事情を総合的に考慮すると,本件では,7割の限度で特許法102条2 項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の 各主張はいずれも採用できない。
エ ミサワホームに生じた損害
本件第2及び第3特許がいずれも持分2分の1の割合による原告とミサワホ ームの共有であることは当事者間に争いはなく,また,弁論の全趣旨によれば,ミ サワホームが自社施工工事分を除きこれらの特許を実施していないことが認められ る。そして,原告及び被告いずれも,特許法102条3項に基づき損害額を算定す る場合の本件第2及び第3特許の相当実施料率を4%程度とし,これを不合理ない し不相当と見るべき事情もないことから,相当実施料率は4%と認められるところ, 相当実施料率を乗じる対象となる売上額を消費税込の金額とすべき証拠はない。 そうすると,次のとおり,1463万7125円をもってミサワホーム(なお, 同社が本件第2特許の持分を取得する以前の損害賠償請求権を持分譲渡人が有して いるのであれば,その譲渡人を含む。)の損害額と認めるのが相当である。 そして,侵害された特許権が共有であったことにより侵害者の賠償すべき損害額 が単独保有の場合に比較して増額されるいわれはないことなどから,原告との関係 においては,更にこの限度で,特許法102条2項による推定が覆滅されるとする のが相当である。
(計算式) 売上額7億3185万6254円(税抜)×4%×1/2=146 3万7125円
オ 原告の損害額
以上より,特許法102条2項に基づく原告の損害額は,別紙「被告第2製 品に係る損害額(裁判所の認定)」の「原告の損害額」欄記載のとおり,4867万 8376円と認められる。
(計算式) 被告の利益の額2億1105万1670円×0.3−1463万7125円=4867万8376円
(4) 原告の予備的主張について\n
原告は,被告工場製品の製造販売について,特許法102条2項に基づき推定 される損害額が同条3項に基づくそれを下回る場合には,予備的に,同項に基づく\n損害額を主張する。 しかし,前記認定から明らかなとおり,特許法102条3項に基づき推定される 原告の損害額は,同条2項に基づくそれを上回るものではないから,この点に関す る原告の主張は採用できない。 仮に,原告の主張が,被告工場製品を除く被告第2製品の販売による損害につい ては特許法102条2項に基づき賠償請求しつつ,被告工場製品の販売による損害 については,同項に基づき算定される損害額が同条3項に基づくそれを下回る場合 に,予備的に同項に基づく損害額を主張する趣旨であったとしても,前記3(2)ウ (オ)で判示したとおり,被告工場製品とそれ以外の製品とで訴訟物が異なると見るべ き根拠はないから,原告の主張は採用できない。
(5) 弁護士費用(本件第1特許権の侵害分も含む。)について
原告は本件訴訟代理人弁護士に訴訟の提起・追行を委任したところ,被告の本 件第1〜第3特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,510万 円と認めるのが相当である。なお,逸失利益に係る損害の発生状況に照らし,弁護 士費用に係る損害賠償支払債務のうち,平成29年8月17日の時点で遅滞に陥っ ていたのは460万円の損害賠償債務であると認めるのが相当である。また,被告 の不法行為終了時期が平成30年10月末であることを踏まえると,残額の損害賠 償債務の遅滞損害金の起算日は同月31日とするのが相当である。
(6) 原告の逸失利益に対する確定遅延損害金について
原告が確定遅延損害金を請求している期間の,被告第2製品の製造販売による 損害に対する遅延損害金の金額は,別紙「被告第2製品に係る損害額(裁判所の認 定)」の「H31.2.28までの確定遅延損害金」欄記載のとおりの方法で計算すると,合 計1231万6870円である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成31(ワ)256 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年10月3日 大阪地方裁判所
ア 本件商標は,欧文字の「CoCo」とカタカナの「バレエ」という標準文字 の文字列が横並びに配置されており,これから生ずる称呼は「ココバレエ」であり (争いなし。),バレエに関連する役務という観念を生じる。 被告各標章の外観及び称呼(「ココバレエスクール」)について,原告が要部と 主張する点以外に争いはない。 被告各標章からは,バレエスクールに関連する役務という観念を生じる。被告は, 被告各標章から,「『STUDIO COCO』のバレエスクール」という観念を 生じると主張するところ,バレエスクールの需要者(バレエを習おうとする者やそ の保護者)が,被告の家族が経営し,ほぼ売上のない事業である「STUDIO C OCO」を認識しているとは考えることはできないから(乙4,5),そのような 特定のバレエスクールとの観念を生じるという上記被告の主張は採用できない。
イ 本件商標及び被告各標章は,「CoCo」,「COCO」又は「ココ」の部 分とこれ以外の部分の結合により構成されている。\nもっとも,本件商標において,「CoCo」と「バレエ」は横並びで同じ大きさ の標準文字で記載されており,被告各標章の「COCO」又は「ココ」とそれ以外 の部分も,いずれも横並びで類似の字体・色・装飾・大きさであり,その間に挿入 される「♡」又は「❤」(被告標章1,3,5,6)もそれぞれ上記文字列と同じ色・ 大きさで記載されていることから,本件商標及び被告各商標の構成部分の一部がと\nりわけ強く需要者の注意を惹くとは考えられず,あえて分離して観察することは適 切ではないと解される。
ウ これを前提に,本件商標と被告各標章の全体について,外観・称呼・観念の 類否を検討する。
本件商標と被告各標章(被告標章2を除く。)の外観は,いずれも横並びで 同じ文字色の「CoCo」(本件商標)又は「COCO」(被告標章2を除く被告 各標章)と「バレエ」(本件商標),「バレエスクール」,「Ballet Sc hool」,「BALLET SCHOOL」(被告標章2を除く被告各標章)と いう文字で構成されており,「スクール」,「School」,「SCHOOL」\nには「学校」や「(バレエ)教室」という以外の特段の意味がないことに鑑みれば, 本件商標と被告標章2を除く被告各標章は,その字体,欧文字について大小文字の 区別,装飾,文字色及び間にハートマークが挿入されるか否かという小さな相違点 はあるものの,全体として外観が類似しているということができる。 また,被告標章2の外観は,「ココバレエスクール」という横並びのカタカナで あるところ,本件商標とは,「CoCo」と「ココ」という欧文字とカタカナの部 分が異なるが,「バレエ」というカタカナは一致しており,外観はある程度類似し ているといえる。 本件商標と被告各標章の称呼は,それぞれ「ココバレエ」と「ココバレエス クール」であり,上記のとおり「スクール」には特段の意味がないことに鑑みれば, 本件商標と被告各標章の称呼も類似しているということができる。 本件商標と被告各標章の観念について,いずれも「ココ」という称呼の部分 は特定の観念を持たないため,それぞれ,「バレエに関連する役務」と「バレエス クールに関連する役務」という観念となり,類似しているということができる。 以上より,本件商標と被告各標章を全体として観察すると,外観,称呼,観 念が類似するものと認められる。
(2) 出所混同のおそれ
ア 双方の使用の態様,経緯
被告は,平成13年より,相模原市,町田市において,教室を借りて被告ス クールを営むようになり,当初は「●略●」,平成13年より「●略●」の名称を 使用していた。被告の父であるP3は,平成20年8月,被告のために,バレエレ ッスン用のスタジオである「Studio CoCo」を町田市●略●に建て,以 後,被告は,同スタジオで被告スクールを営んだ。被告は,平成28年に病気をし たことを契機に,●略●の通称を使用するようになり,そのころ,これに伴って被 告スクールの名称も,スタジオの名称をとって「COCO♡Ballet Scho ol」に改め,以後これを使用するようになった。被告スクールは,地元だけで活 動してきた小さな教室とされる(甲3,13,15,乙4,5)。 被告は,被告ウェブサイト1のヘッダー及びフッター部分において被告標章 1を,ヘッダー部分及び「About」という項目の下の文章中において被告標章 2を,「News」という項目の下の文章中において被告標章3を,「Sched ule」という項目の下のスケジュール表のファイル名として被告標章4を,被告\nウェブサイト2のヘッダー部分において被告標章5を,問合わせ用のページにおい て被告標章6を使用していた(甲4,5)。 原告は,平成元年から大阪市内において原告スクールを運営し,自らのウェ ブサイトや定期発表公演のパンフレットにおいて本件商標を使用している。原告ス\nクールは被告スクールに比して規模が大きく,知名度においても上回っていると認 められる(甲9〜11)。 平成31年1月11日以前は,インターネット上の検索エンジンにおいて, 「ココバレエスクール」又は「COCOバレエ」を検索語として用いて検索した場 合,検索結果において,原告スクールと被告スクールが上下に並んで表示された(甲\n6,8)。
イ 検討
このような本件商標及び被告各標章の使用態様からすれば,需要者である,バレ エを習おうとする者やその保護者が,インターネットを利用して検索等した場合, 原告スクールと被告スクールとの間に何らかのつながりや提携関係があるものと誤 認する可能性があったというべきであり,本件商標と被告各標章には,出所混同の\nおそれがあったと認められる。
(3)被告の主張について
被告は,「COCO♡Ballet School」という被告スクールの名称や, これに由来する被告各標章は,P3が被告スクールと同じ場所で経営する「STU DIO COCO」の名称からとったものであり,被告スクールは小規模な地元密 着の教室であって,その旨は被告ウェブサイトにおいて明示されているから,出所 混同のおそれはないと主張し,被告本人及びP3は,これに沿う陳述書(乙4,5) を証拠として提出する。 しかし,P3の経営する「STUDIO COCO」は,バレエのレッスンや貸 しスタジオとして使用する小規模な教室であり,格別の周知性を有するとは認めら れないから(甲3,乙5),被告各標章に接した需要者が,「STUDIO CO CO」より派生した事業であると認識するとは考え難い。また,被告ウェブサイト において,被告スクールが東京都町田市所在であることや,生徒募集の範囲が町田 市及び相模原地域であることは記載されているものの,離れた地域にあるバレエ教 室が互いに提携関係にある可能性もあるから,被告ウェブサイトにおいて被告各標\n章に接した需要者が,原告スクールとつながりがあるものと誤認する可能性を否定\nすることはできない。 したがって,上記被告の主張を採用することはできない。
(4) まとめ
以上より,本件商標と被告各標章は,外観・称呼・観念が類似し,出所混同のお それがあり,前記前提事実のとおり指定役務が同一であると認められるから,全体 として,被告各標章は本件商標に類似するというべきである。
・・・
ア 使用料相当額
原告は,本件商標の使用料相当額について1か月あたり6万円と主張し,原 告スクールがニューヨーク市所在のバレエスクールと提携関係にあるとして(甲1 6),同スクールへの留学を希望する生徒の募集を目的とした首都圏のバレエスク ールとの提携や,そのために本件商標の使用を許諾して使用料を徴収することを構\n想している旨を主張するが,実際にそのような使用料額の支出を内容とする契約が 締結されたことの主張・立証はない。 前記認定のとおり,本件商標と被告各標章の誤認混同のおそれは,インター ネット上で生じるものと解されるが,本件商標が表象するのは,インターネット上\nの物品の販売又はサービスの提供ではなく,バレエの教授という現実に提供する役 務である。そして,原告スクールは大阪市に,被告スクールは町田市にあって地理 的に全く離れているから,原告スクールの会員が,被告各標章を見たことで被告ス クールに移籍したり,原告スクールに入会しようとした者が,被告各標章を見たこ とで被告スクールに入会するといった形で誤認混同が生じ,原告に経済的損失が生 じたとの事実は,主張も立証もされていない。 また,前記認定したところによれば,被告は,被告各標章を,本件商標の登 録以前より使用しており,P3が建てたスタジオの名称をとって被告各標章を定め たものであり,平成30年6月に原告に警告されて初めて本件商標の存在を知った と認められるから,本件商標の顧客吸引力や信用を利用することを目的として,被 告各標章を使用したものでないことは明らかである。 以上を総合すると,原告に 経済的損失が認められず, 被告各 抽象的に誤認混同のおそれのある被告各標章が排除されなかったことによる損害が認められるにすぎないから,これに対する損害金としては,1か月1万円をもって相当と認める。したがって,商標法38条3項により,原告の損害となるべき平成29年9月12日から平成31年1月11日までの使用料相当額は,16万円(1万円×16か 月)となる。
イ 弁理士費用相当額
本件訴訟提起に至る経緯,前記認定した被告の商標権侵害となる行為の態様等を 総合すると,被告の行為と,補佐人である弁理士の費用との間に,相当因果関係を 認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成31(ネ)10031 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月10日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
本件訂正発明は,構成要件A〜Dからなる「薬剤分包用ロールペーパ」に係る\n発明であるところ(構成要件E),構\成要件Aには薬剤分包装置に関する事項が, 構成要件B及びDにはロールペーパ及びその中空芯管並びにロールペーパに配\n設される複数の磁石(以下,併せて「本件ロールペーパ等」という。)に関する 事項が,構成要件Cには薬剤分包装置及びロールペーパに関する事項が,それぞ\nれ記載され,構成要件Aにおいて,ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき,\n前者が後者に「用いられ」るものとして記載されている。 本件訂正発明は,「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら れるところ,物の発明の特許請求の範囲の記載は,物の構造,特性等を特定する\nものとして解釈すべきであること,「用いられ」が,構成要件Aの中で「・・・\nようにした薬剤分包装置に用いられ,」とされていることからすると,「用いら れ」とは,本件ロールペーパ等が構成要件Aで特定される薬剤分包装置で使用可\n能なものであることを表\していると解される。
(3) 被告製品の構成要件充足性について\n
ア 前記(2)を前提に検討すると,構成要件Aのうち「ロールペーパの回\n転速度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」との記載は,本件ロ ールペーパ等の「複数の磁石」につき,支持軸の片端に設けられた角度センサに よる検出が可能な位置に配設されるものであることを特定するものと理解でき,\nまた,構成要件Aのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその\n固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設 け」との記載は,本件ロールペーパ等について,薬剤分包装置の中空軸と接する 中空芯管の端に,中空軸と着脱自在に固定する手段を設けることで,そのような 態様で回転させられるものであることを特定するものと理解できる。 そうすると,本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は,構\n成要件B〜Eと,構成要件Aによる上記特定に係る事項によって画されるもの\nであるから,被告製品が構成要件A〜Eで特定される本件ロールペーパ等とし\nての構成を備えていて,構\成要件Aで特定される薬剤分包装置に利用可能なも\nのについては,被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ, 被告製品が構成要件Aで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かと\nいうことは,上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。\n
イ(ア) 被告製品は,前提事実(6)のとおりの構成を有するところ,弁論\nの全趣旨によると,被告製品の構成a,b,c,dは,本件訂正発明の構\成要件 B,C,D,Eをそれぞれ充足するものと認められる。
(イ) 弁論の全趣旨によると,被告製品の中空芯管内部に配設された 3個の磁石は,支持軸の片端に設置された角度センサによる信号の検出が可能\nな位置に配設されたものであり,また,被告製品は,薬剤分包装置の中空軸に着 脱自在に装着されて,固定時に中空軸と一体となって回転し得るものであって, その手段がロールペーパと中空軸が接する端に設けられているものと認められ る。
(ウ) したがって,被告製品は,本件訂正発明の構成要件B〜Eと構\成 要件Aによる上記アの特定に係る事項を充足し,構成要件Aで特定される薬剤\n分包装置で使用可能なものであると認められる。\n
ウ よって,被告製品は,本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認め られる。
(4) 一審被告らの主張について
ア 一審被告らは,本件訂正発明が用途発明であり,また,本件訂正発明 において保護されるべき特徴的部分は,薬剤分包装置側の構成又は機能\である ことなどから,被告製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられては\nじめて本件特許権に対する侵害が成立すると主張する。 しかし,前記(2)で検討したとおり,本件訂正発明は用途発明ではない。また, 本件訂正発明の技術的意義は,前記(1)認定のとおりであって,本件訂正発明の 特徴的部分が薬剤分包装置のみにあるということはできない。 したがって,一審被告らの上記主張は採用することができない。 なお,特許庁の審査基準(甲22)も,サブコンビネーション発明について用 途発明と同様に解釈することを求めているものとは解されない。
イ 一審被告らは,一審原告は,本件補正に際して,本件訂正発明の技術 的特徴が構成要件Aにあることを主張していたと主張する。\n一審原告は,本件補正に際しての意見書(乙9)において,本件補正に先立つ 拒絶理由通知の引用文献記載の技術に対して,「本願発明では『回転角度と測長 センサの検出信号を検出してロールペーパの巻量が検出可能な位置に配置され\nた磁石』の構成を有し,かつ『角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不\n一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸との ずれを検出するようにした』薬剤分包装置に用いられることを前提とするロー ルペーパについての発明であり,部分的な構成部材の抽象的,総論的な構\成が公 知,周知であるという理由だけで,本願発明の全体の構成が全て否定されること\nにはならないと考えます。」と主張しているものの,そのことから直ちに一審原 告が構成要件Aを充足する薬剤分包装置で用いられることが必要であるとまで\n主張していたとは解されないから,一審被告らの上記主張を採用することはで きない。
ウ 一審被告らは,原審裁判所の暫定的見解について主張するが,原審裁 判所の暫定的見解によって当審の判断が左右されないことは明らかである。
・・・・
一審被告らは,非純正品であることを明示して販売していたことや 購入者が調剤薬局であることなどからすると,購入者は被告製品が非純正品で あること,すなわち,一審原告の製品ではないことを正確に認識しており,出所 表示機能\や品質保証機能が害されていないから,商標法26条1項6号が適用\nされるか,実質的違法性を欠き,商標権侵害が成立しないと主張する。 しかし,以下の(ア)〜(オ)の各事情を考え併せると,購入者の全てが,被告製 品が非純正品であること,すなわち,一審原告の製品ではないことを正確に認識 していたとは認められず,一審被告らの上記主張はその前提を欠くものであっ て,採用することができない。
(ア) まず,前記(1)イのとおり,被告製品については,ウェブサイト のみならず,ダイレクトメールやFAX等による宣伝活動もされており,顧客が 一審被告らのウェブサイトを経由することなく被告製品を購入する場合もあっ たと認められるところ,ダイレクトメールやFAXにおいて,どのような態様で 宣伝がされていたのかは証拠上必ずしも明らかではない。
(イ) 一審被告らは,顧客に対し,非純正品であることを説明していた と主張するが,一審被告らの下で稼働していた従業員は,その点に関し,刑事事 件の公判廷において,「電話で口頭で説明するときに,『純正の紙と違うので』 と説明した。」,「電子メールで顧客に説明する際にも電話での説明の場合と同 様に非純正であることを顧客に説明したように思うが,よく覚えてない。」と曖 昧な供述をしている(乙4)上,同供述の裏付けとなるような顧客への対応マニ ュアルや顧客に送付された電子メールといったようなものは何ら証拠として提 出されていないから,一審被告らの主張するような説明が常に顧客に対してさ れていたとは認められない。
(ウ) 被告製品の購入を申し込むために顧客が一審被告らに対して送\n付する「注文書兼使用許可書」についても,「非純正」の文字(乙25の1・2) は,後から記載されるもので,常に記載されていたのかは証拠上明らかではない し,また,「非純正」の文字が取り立てて大きく表示されたり,強調されたりし\nていないことからすると,仮に記載されていたとしても顧客がこれに気付かな いこともあり得る。そして,前記(1)イのとおり,顧客から使用済み芯管の送付 を受けることなく,被告製品が販売された事例があることからすると,上記の 「注文書兼使用許可書」が常に使用されるものであったとも認められない。 納品書(乙26)についても,「分包紙はお客様からお預かりした芯で作りま した。」とだけ記載されており,非純正品であることが明示されているわけでは ない。
(エ) 前記(1)ウのとおり,一審被告らのウェブサイトには「非純正分 包紙」という記載があったものの,被告ネクストウェブサイトの非純正品ウェブ ページ1では,「ユヤマ分包機対応」との記載に続いて各種の製品が表示されて\nいるのみで,非純正品であることが明示的に記載されていなかった上,被告ヨシ ヤウェブサイトの非純正品ウェブページ2でも,「ユヤマ分包機対応」という記 載と共に各種の製品が表示されており,「非純正分包紙」という記載が左欄に小\nさく記載されているにすぎないことからすると,一審被告らのウェブサイトに 接した購入者の全てが,被告製品が非純正品であると正確に認識するとは認め られない。
(オ) 購入者が調剤薬局であるからといって,その注意力が常に一般 消費者に比して高いとまではいえず,購入者の一人が,被告製品が非純正品であ ると認識していたことがある(乙19,113)からといって,それにより全購 入者が同じ認識であったとは認められない。 なお,一審被告らは,調剤薬局の薬剤師の間では,当該調剤薬局で使用してい る薬剤分包用ロールペーパの仕入先や問合せ先に関する情報が共有されている と主張するが,上記(ア)〜(オ)で検討してきたところによると,そもそも,調剤 薬局において,被告製品を非純正品(一審原告の製品でないもの)として購入す るとは限らないというべきであるから,仕入先や問合せ先に関する情報が共有 されるかどうかは,本件の結論を左右するものではない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 消尽
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成30(行ケ)10178 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月24日 知的財産高等裁判所
前記アの記載によれば,甲1は,2017年(平成29年)9月 1 日に インターネットで検索して表示された「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ 「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」と題する「FC2ブロ グ」のコピーであること,同ブログは,広告欄の「スポンサーサイト」, ブログ本文の「11/25 更新情報」,「最新コメント」,「関連記事」等の 各項目で構成されていること,「11/25 更新情報」の項目の右横には「20 11.11.25 23:18 Cat:旅日記」(画像3)との表示があること,同項目欄\nに掲載された記事(本件更新情報)には,「「友情のきずな」キャンペー ンを開催中です。」,「期間:11/25(金)14:00〜11/29(火)14:00」と の記載があること(画像4)が認められる。 上記記載から,本件更新情報は,「11/25 更新情報」の項目の右横に表\n示された「2011.11.25 23:18」(2011年11月25日23時18分) に更新され,保存されたことが認められる。 したがって,本件更新情報は,本件出願前(出願日平成25年9月27 日)の平成23年(2011年)11月25日,電気通信回線を通じて公 衆に利用可能となったものと認められる。\nそうすると,本件決定が本件更新情報に基づいて認定した引用発明1は, 本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当す\nるものと認められる。
ウ 原告の主張について
原告は,(1)甲1の「スポンサーサイト」の項目欄の直下には,本件出願 後の平成29年(2017年)7月21日に制作発表されたゲーム「みん\nなでにゃんこ大戦争」(甲20)の画像が表示されているから,本件更新\n情報が公衆に利用可能となったのは,早くても同日である,(2)甲1におい ては,少なくとも,ゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の画像が表示され\nた部分,「最新コメント」の項目欄の各コメント部分,「関連記事」の項 目欄の「【バトルイベント】神獣の魂【予告】(2011/12/09)」及び「エ レボスの坑道結果報告(2011/12/06)」の部分は,平成23年11月25 日より後に書き換えられたものであるから,本件更新情報についても,同 日より後に書き換えられた可能性を否定できない旨主張する。\nしかしながら,上記(1)の点については,甲1の「スポンサーサイト」の 項目欄には,「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場!」の画像の下に「上\n記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。」,「新し\nい記事を書く事で広告が消せます。」と表示されていること,「FC2ブ\nログ」の仕様等を定めた「FC2ブログマニュアル」(甲10)には,「ロ グの有効期間」の項目に,「(1か月新規投稿がない場合は,記事部にス ポンサー広告が表示されます。)」との記載があること,平成30年5月\n2日及び平成31年3月13日に甲1の URL を検索した際,本件更新情報 の記載がある一方で,スポンサーサイトの項目欄に表示された画像は,「み\nんなでにゃんこ大戦争 新機能登場!」とは異なる画像が表\示されたこと (甲11ないし13,乙1)に照らすと,甲1の「スポンサーサイト」の 項目欄に表示される広告は,甲1の URL を検索した時点で1か月以上ブロ グの更新がされていない場合に,FC2ブログの運営者であるFC2が契 約しているスポンサー広告が表示されるものであって,ブログの記載内容,\n更新日時とは関係しないことが認められる。 また,上記(2)の点については,甲1を構成する「11/25 更新情報」の項 目欄とは異なる他の項目欄に掲載された情報が平成23年11月25日よ り後に更新された事実があるからといって本件更新情報が同日より後に書 き換えられた可能性があることを基礎付けることはできない。\nしたがって,原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> その他特許
>> コンピュータ関連発明
>> 審判手続
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.11.17
平成31(ネ)10034 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
構成要件Gの「前記上位ノード変数データ」の意義について\n
a 本件発明の構成要件Fの「前記スクリプトは,当該ノードデータに\n含まれる変数データである自ノード変数データと,当該ノードの直系 上位ノードのノードデータに含まれる変数データである上位ノード変 数データを利用した演算を行って,前記自ノード変数データの値を求 める代入用スクリプトを含んでおり」との記載及び構成要件Gの「前\n記表示された木構\造のノードのうちの選択されたノードの前記自ノー ド変数データ,前記上位ノード変数データ及び前記スクリプトを表示\nするノードデータテーブル表示ステップ」との記載から,本件発明の\n「上位ノード変数データ」は,「当該ノードの直系上位ノードのノー ドデータに含まれる変数データ」であり,構成要件Fの「前記自ノー\nド変数データの値」を求める「代入用スクリプト」による演算に利用 される「変数データ」であることを理解できる。 次に,本件明細書には,「上位ノード変数データ」に関し,「変数 情報は,各ノードが保持するデータであって,変数名に対応させて記 憶される。記憶される変数は,下位ノードから参照される公開変数と, 自ノード内でのみ使用する限定変数を含む。また,変数の値(「変数 データ」と記述する場合もある。)は,固定値が設定されても,スク リプトの実行によって演算された値が設定されてもよい。また,UR Lが設定されてもよい。どのような値が設定されるかは任意である。」 (【0031】),「代入用スクリプトは,自ノードの変数の値を演 算するためのものである。代入用スクリプトは,自ノードの変数の値 である自ノード変数データと,そのノードの直系上位ノードの公開変 数の値である上位ノード変数データを利用して記述することが可能で\nある。」(【0032】),「公開変数表示領域に表\示される公開変 数は,自ノードの公開変数51と,直系上位ノードの公開変数52を 含み,直系上位のノードの公開変数52は,自ノードの公開変数51 と異なる色で表示される(図10では,フォントを変えて示してある。)。\nまた,公開変数には,固定値が入力される公開変数と,代入用スクリ プトの実行によって計算される公開変数があり,修飾領域に「なし」 あるいは「要計算」を表示することによりに区別される。」(【00\n65】)との記載がある。 そして,図10には,「直系上位ノードの公開変数の値である上位 ノード変数データ」として,「52」に「変数名」及びそれに対応す る「値」が示されている(例えば,「変数名」の欄「パネル色」・「値」 欄「KW−400」)。 これらの記載によれば,本件明細書には,「上位ノード変数データ」 にいう「変数データ」は,「変数の値」を含むデータであることの開 示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によ れば,構成要件Gの「前記表\示された木構造のノードのうちの選択さ\nれたノードの前記自ノード変数データ,前記上位ノード変数データ及 び前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表\示ステップ」に いう「前記上位ノード変数データ」は,「当該ノードの直系上位ノー ドのノードデータ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると解 される。
b これに対し控訴人は,本件明細書の【0032】における「変数の 値(「変数データ」と記述する場合もある。)」との記載は,「変数 データ」という用語を,文脈によって,変数の値を指す意味で用いる こともあるという注意書きであると理解できること,「変数データ」 は,変数名と変数の型を意味するというのが,プログラミングに関す る通常の用語であること(甲24),実質的にも,本件発明が「ノー ドデータテーブル表示ステップ」において上位ノード変数データを表\ 示させる目的は,表示された木構\造の個々のノードに対応付けられた 詳細情報を簡単に表示することができる(【0009】)ことにより,\n文書ファイル(プログラム)の編集を容易にする点にあり,変数名が 分かれば,その目的を達成することができることからすると,本件発 明の「上位ノード変数データ」は,本件明細書において文脈上変数の 値を意味すべき場合を除き,変数名を指すと解すべきである旨主張す る。 しかしながら,本件明細書には,「上位ノード変数データ」が変数 名のみで構成される場合を含むことについての記載や示唆はない。\nまた,前記aの本件明細書の記載に照らすと,【0032】の「変 数の値(「変数データ」と記述する場合もある。)」との記載は,「変 数データ」は「変数の値」を意味することを示した記載であると解す るのが自然であり,これが変数の値を指す意味で用いることもあると いう注意書きであるということはできない。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告プログラムにおける「ノードデータテーブル表示ステップ」の\n有無について
a 控訴人は,入力コネクタは,親ボックスから引き渡される値を記憶 する変数が図形化されたものであり,入力コネクタの名称が構成要件\nGにおける「上位ノード変数データ」に該当すること,インスペクタ 及びスクリプトエディタに表示される入力コネクタの名称に関する\n情報の表示は,上位ノード変数データを表\示するものであることから すると,被告プログラムは,「上位ノード変数データ」を表示する「ノ\nードデータテーブル表示ステップ」を備えている旨主張する。\nしかしながら,前記(ア)a認定のとおり,構成要件Gの「前記上位\nノード変数データ」は,「当該ノードの直系上位ノードのノードデー タ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると認められるところ, 入力コネクタの名称は,「変数の値」であるとはいえないから,控訴 人の上記主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。
b 控訴人は,被告プログラムの構成g’に関し,被告プログラムのS\nay Textボックスの「スクリプトエディタ」において「親から の変数を取得」機能を使う場合,上位ノードであるSayボックスの\n変数から利用可能なものを一覧表\示する機能があるから,被告プログ\nラムは,「上位ノード変数データ」を表示する「ノードデータテーブ\nル表示ステップ」を備えている旨主張する。\n しかしながら,控訴人の上記主張は,「スクリプトエディタ」にお いて,どのような「上位ノード変数データ」が表示されるのかについ\nて具体的に主張するものではないから,その主張自体理由がない。
c 以上によれば,被告プログラムは,「上位ノード変数データ」を表\n示する「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えているものと認\nめることはできないから,構成要件Gの「前記表\示された木構造のノ\nードのうちの選択されたノードの前記自ノード変数データ,前記上位 ノード変数データ及び前記スクリプトを表示するノードデータテーブ\nル表示ステップ」を備えているものと認めることはできない。\n
ウ まとめ
以上のとおり,被告プログラムは,構成要件Gの「木構\造を表示する木\n構造表\示ステップ」及び「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えて\nいるものと認められないから,構成要件Gを充足しない。\n
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.11.17
平成31(行ケ)10003 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月11日 知的財産高等裁判所
原告が本件発明の実施例であると主張する実施例4においては,錠剤硬度 117N,摩損度0.4パーセント(7/12)(ただし,括弧内は明らか なひび・割れ・欠けの個数/試験数),崩壊時間39秒(日局(補助盤な し)),7秒(日局(補助盤あり)),40秒(口腔内(静的))であった ことが記載されている。 他方,本件明細書の実施例の摩損度の評価は,錠剤の摩損度試験法(日局 参考情報)に従って行われるとされているところ(【0062】),日本薬 局方参考情報(乙1)によれば,錠剤の摩損度試験法においては,明らかに ひび,割れ,欠けが見られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとさ れている。 そうすると,「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が12錠中7錠であ り,摩損度が0.4%とする実施例4の摩損度の評価の記載を,日本薬局方 参考情報における錠剤の摩損度試験法で「明らかなひび・割れ・欠け」が見 られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとされていることとの関係 で一義的に整合するように理解することができない。そして,本件明細書に は「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が12錠中7錠である実施例4の場 合に,どのような方法で摩損度を測定した結果0.4%という数値を得たの かに関する説明はなく,この点についての当業者の技術常識を示す的確な証 拠もない。 以上によれば,当業者は,本件明細書の実施例4の記載から,当該実施例 において低い摩損度を含む本件課題が実現されていることを理解することが できないし,本件明細書のその余の部分にも,本件発明が,「高い原薬含有 率で,速やかな崩壊性,高い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの 口腔内崩壊錠を提供する」という本件課題を解決できることを示唆する記載 はなく,この点に関する技術常識を示す的確な証拠もない。 したがって,本件発明について,本件明細書に記載された発明で,発明の 詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであり,また,その記載や示唆がなくとも当業者が 出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるということができないから,本件発明がサポート要件に適合する ものということはできない。
(5) 原告の主張について
ア 原告は,「明らかなひび・割れ・欠け」は,摩損度とは異なる概念であ り,本件発明の課題には含まれない,また,仮に含まれるとしても,本件 発明の課題は,「速やかな崩壊性,高い硬度及び低い摩損度の両立」であ るから,本件発明はこれを解決するものであると主張する。 前記(3)ア及びイにみたとおり,本件明細書においては,発明を実施する ための形態,実施例の箇所において,それぞれ速やかな崩壊性,高い硬 度,低い摩損度の具体的な評価方法について記載している。特に,摩損度 について,発明を実施するための形態において,「『低い』摩損度とは, 例えば,錠剤の摩損度試験法(日局参考情報)に従い,試験を行うとき, 0.5%未満(明らかなひび・割れ・欠けなし)である。」(【005 0】)とされ,また,実施例において,「摩損度は,錠剤の摩損度試験法 (日局参考情報)に従い,試験を行った。摩損度の目標品質は,通常の錠 剤と変わらない取り扱いを目指し,0.5%未満(明らかなひび・割れ・ 欠けなし)とした。」(【0062】)と記載されている。 そして,本件明細書は,かかる評価方法に従って,崩壊性や硬度につい て,比較例や実施例を評価しており,摩損度については,明らかなひび, 割れ,欠けの個数も含めて評価している(【0068】,【0072】, 【0076】)。
また,摩損度について,本件明細書が引用する日本薬局方の参考情報 は,「試験後の錠剤試料に明らかにひび,割れ,あるいは欠けの見られる 錠剤があるとき,その試料は不適合である。もし結果が判断しにくいと き,あるいは質量減少が目標値より大きいときは,更に試験を二回繰り返 し,三回の試験結果の平均値を求める。多くの製品において,最大平均質 量減少(三回の試験の)が1.0%以下であることが望ましい。」(乙 1)として,摩損度試験の評価の際に,明らかなひび,割れ,欠けがある 場合にそもそも試料が不適合であるとしてかかる概念も含めて評価の対象 とするものである。 そして,前記(3)に引用した本件明細書の記載のほかに,本件明細書中に おいて,本件課題の具体的な評価方法としても,個別の実施例の記載につ いても,本件発明の課題解決をどのように評価するかについての基準や考 え方は窺われない。 以上によれば,本件課題である「速やかな崩壊性,高い硬度及び低い摩 損度の両立」が解決されたといえるためには,「低い摩損度」概念の中に 「明らかなひび・割れ・欠け」がないことも含んだ上で,「速やかな崩壊 性」,「高い硬度」及び「低い摩損度」を実現することが必要であると解 される。
イ 原告は,本件発明の課題が達成されているかどうかは市販品として問題 のない口腔内崩壊錠が提供されているかどうかという観点から判断される ものであるなどと主張する。 しかしながら,本件明細書には,原告の主張する「市販品として問題の ない口腔内崩壊錠が提供されているかどうか」について何らの記載もな く,本件明細書における摩損度試験法に関する明示的な記載に反してこの ような評価をすべき根拠は見当たらない。
ウ 原告は,実施例4の摩損度及び「明らかなひび・割れ・欠け」の記載に 接すると,当業者であれば,日本薬局方の参考情報(乙1)が想定する摩 損度が1パーセントを明らかに超えるようなレベルの「明らかなひび・割 れ・欠け」があるとまではいえないものがカウントされていると理解でき るなどと主張する。 しかしながら,そもそも,本件明細書は,摩損度試験について,日本薬 局方の参考情報(乙1)に従うとした上で,それと同様の表現をした「明\nらかなひび・割れ・欠け」の有無を問題としているのであって,本件明細 書と日本薬局方の「明らかなひび・割れ・欠け」が異なる概念であること は何ら読み取れない。
エ 原告は,本件特許出願時において,打錠圧を上げることによって「明ら かなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることや,予\圧をすることによ って「明らかなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることが技術常識で\nあったとして,このような技術常識に照らせば,本件発明は本件発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであることを主張する。 しかしながら,本件課題は,「高い原薬含有率で,速やかな崩壊性,高 い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの口腔内崩壊錠を提供す る」というものであるところ,甲41〜44,54,69〜74(枝番を 含む。)には,本件発明の口腔内崩壊錠について,打錠圧を上げ,あるい は,予圧をすることによって,「速やかな崩壊性,高い硬度及び低い摩損\n度を両立」することができることを示すものではない。本件発明の構成に\nついて,打錠圧を上げ,あるいは,予圧をすることによって本件課題を解\n決することができるとの技術常識があるとは認められない。 そして,かかる技術常識が存在しない以上,それを裏付ける実験データ (甲45,53)を考慮することはできない。 なお,本件明細書には,「適切な硬度が得られる打錠圧で所定の質量の 錠剤を製造する。」(【0059】)と記載されているものの,「ひび・ 割れ・欠け」の解消との関係で,打錠圧の調整をすべきことについては記 載がなく,当業者に対し,課題解決への示唆があるとも認められない。 037/089037
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.11.17
平成31(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月11日 知的財産高等裁判所
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合) において,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明 が明確であること」という要件に適合するといえるのは,出願時において当 該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか,又はお よそ実際的でないという事情が存在するときに限られる(最高裁平成24年 (受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号70 0頁参照)。
(2) 本件発明7について
本件発明7は,「前記溶剤処理が,リード線端部にアルミ芯線を溶接した 直後に行われるものである,請求項6に記載のタブ端子。」として,請求項 6の「前記の酸化スズ形成処理が,溶剤処理により行われる,請求項1また は2に記載のタブ端子。」を引用するものであり,「酸化スズ形成処理が溶 剤処理により行われる」との記載は製造方法であるから,特許請求の範囲に その物の製造方法が記載されている場合に当たる。 そうすると,本件発明7について明確性要件に適合するというためには, 出願時において本件発明7の「タブ端子」を,その構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在することを要するところ,原告はかかる事情について,具体的な主張立証を しない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本件明細書の記載(【0026】,【0028】)から,ウィ スカ発生の抑制を目的とした酸化スズが形成されているというタブ端子の 溶接部分の構造ないし特性を示す目的で「溶剤処理」という用語を用いていることが読み取れるとして,製造方法が物のどのような構\造又は特性を表しているのかは,本件発明の記載及び本件明細書の記載から極めて明白であり,上記(1)の不可能又は非実際的事情について検討するまでもなく,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確と\nいえないから,明確性要件に適合すると主張する。 しかし,本件明細書には,請求項3に係る「熱処理」及び請求項6に係 る「溶剤処理」により酸化スズ形成処理が施されたタブ端子についての記 載があるものの,これらの熱処理及び溶剤処理により形成された酸化スズ が,それぞれどのような構造又は特性を有するものであるのかについての記載はない。そうすると,本件明細書の記載から,本件発明7の引用する\n請求項6に係る溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するかが明らかであるとはいえないし,また,それが技術常識か\nら明らかであるとみるべき証拠もない。 したがって,原告の主張は採用できない。
イ また,原告は,仮に,本件発明において問題としている課題解決手段で ある酸化スズ形成処理を超えてその構造・特性や熱処理や溶剤処理を行うにタブ端子に対して生じる変化を事細かに規定しなければならないとす\nれば,それは上記(1)の最高裁判決に示す不可能又は非実際的事情に該当すると主張する。\nしかし,原告の主張する点は,本件発明7の「タブ端子」を,その構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか,又はおよそ実際的でないことを示す事情を示すものではなく,上記(2)の判断を左右するもので はない。
ウ さらに,原告は,審決が明確性要件の判断に先立ち,本件発明6につい ての進歩性の判断を行っていることは,実質的に本件発明が明確であるこ とを前提としていると主張する。 しかし,進歩性の欠如と明確性要件適合性は,異なる無効理由であり, 進歩性の判断と明確性要件適合性の判断に論理的な先後関係があるわけで はないから,原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2019.11. 1
令和1(行ケ)10073 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所
商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある 商標」には,健全な商道徳に反し,著しく社会的妥当性を欠く出願行為に係る 商標も含まれると解される。
(1) そこで,まず,原告による本件商標の登録出願が,被告との関係で義務違 反となりうるかについて検討する。 前記1(1)(2)の各事実によれば,原告と被告とは,本件商標の登録出願が行 われた平成28年10月14日時点を含めて,平成11年頃から平成29年 10月12日頃までの間,被告が,原告に対し,独占的に本件被告商品やマ ナマリンなどを卸売りし,原告がこれを薬局薬店等に販売するという長期間 にわたる取引関係にあった。 かかる取引関係に関して,前記1(2)エのとおり,原告と被告とは,被告商 標の登録が完了した直後である平成16年3月25日,本件覚書(甲6)を 締結した。本件覚書の柱書,1条,3条の記載に照らすと,本件覚書は,被 告商標として登録された「仙三七」との商標を,本件被告商品に付して,販 売することを前提とするものであることが明らかである。また,本件覚書に は,被告及び原告は,第三者が被告商標の権利を侵害し又は侵害しようとし ていることを知ったときには互いに遅滞なく報告し合い協力してその排除に 努めるものとすること(第5条)や,被告及び原告は,信義に基づいて本件 覚書を履行するものとし,万一本件覚書に関して疑義が生じた場合には,被 告及び原告はお互いに誠意をもってこれを解決するものとすること(第7 条)とする合意が含まれていた。このように,被告が原告に使用許諾して 「仙三七」との商標を本件被告商品に付して販売することとされ,第三者か らの被告商標に係る商標権の侵害に対する対策も合意された上で,7条にお いて信義に基づいて本件覚書を履行するとされていたことに照らすと,本件 覚書において,原告自身が,三七人参を原材料とした健康食品との関連で 「仙三七」との商標を商標登録することは全く想定されていないといえる。 以上によれば,長期間にわたり,本件被告商品の卸売りを受けて,これに 被告商標と同じ「仙三七」との商標を付して販売し,利益を上げていた原告 は,被告との関係において,被告が「仙三七」との商標の商標権者として, かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則 上の義務を負っていたものということができる。 そして,原告による本件商標の登録出願は,被告商標と同じく「仙三七」 を横書きにしてなる商標について,本件被告商品を指定商品に含むものとし て登録出願するものである。かかる登録が認められることになると,被告 は,「仙三七」との商標の商標権者として,第三者に使用許諾をするなどし てかかる商標を付して本件被告商品を販売することはできなくなり,重大な 営業上の不利益を受けるおそれが生じる。 以上によれば,原告の本件商標の登録出願は,上記信義則上の義務に反す るものといわざるを得ない。
(2)次に,原告の本件商標の登録出願の経緯及び目的についてみる。 前記1(3)イからエのとおり,原告は,上記出願の前後において,被告に対 し,被告商標が本件被告商品を指定商品に含んでいない可能性や自らが本件\n商標を登録出願することについて何ら告げることはなく,本件商標の設定登 録完了から4か月以上経過した後の平成29年8月18日付けの「申し入れ\n書」(甲7)において,初めて,本件商標の商標権者であることを明らかに した上で,原告と被告との本件被告商品の取引終了を一方的に申し入れると\nともに,被告に対し,マナマリンの商標の譲渡やそれを条件とした三七人参 の購入などを提案したものである。 これに対し,上記「申し入れ書」の内容に照らすと,原告自身は,当該\n「申し入れ書」を送付する前に,被告以外の第三者から,本件被告商品と同\n種の競合品を購入する段取りを既に整えていたと認められる。 そして,原告は,その後の被告とのやりとりの中で,原告から被告に対す る営業譲渡の申入れや被告商標の譲渡の依頼に応じてもらえなかったこと,\n被告の本件被告商品の仕入れ価格が高額であるために原告独自の商品を生産 することにしたことなどをも理由として挙げながら,原告としては被告の生 産する本件被告商品が原告の希望仕入れ価格に不適格であると判断し,原告 にて新しいブランドで生産から販売を開始することなどを伝えている。 このような原告の言動に照らすと,原告は,「仙三七」との商標が,本件 被告商品と同種の商品に付されることによって生じる利益を独占するべく, 被告に本件商標と競合する商標を登録出願されないように注意を払った上 で,自らは,同種商品の調達ルートを確立する一方で,被告との取引関係を 終了する準備を計画的に整えながら,本件商標の登録出願及び上記「申し入\nれ書」の送付に及んだものといえる。
(3) 以上によれば,原告による本件商標の登録出願は,被告が「仙三七」との 商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義 務を負うにもかかわらず,被告商標が本件被告商品を指定商品として含まな い可能性があることを奇貨として本件商標の登録出願を行い,本件商標を取\n得し,被告が「仙三七」のブランドで健康食品を販売することを妨げて,そ の利益を独占する一方で,その他の商品の取引に関する交渉を有利に進める という不当な利益を得ることを目的としたものということができる。 このような本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると,原告による本 件商標の出願行為は,被告との間の信義則上の義務違反となるのみならず, 健全な商道徳に反し,著しく社会的妥当性を欠く行為というべきである。 そうすると,このような出願行為に係る本件商標は,商標法4条1項7号 所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するも のといえる。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,「仙三七」との商標は原告の努力等によってその信用が築き上 げられたものであり,また取引者等は本件被告商品の出所は原告であると 認識するなどとして,かかる商標は原告のものであるなどと主張する。 しかしながら,原告は,本件覚書に基づいて「仙三七」の商標の使用を 許諾され,この許諾に基づいて,本件被告商品に「仙三七」との商標を付 して,長年にわたり販売してきたものである。その過程において,原告が 努力し,また販売者として表示されたことによって「仙三七」との商標の\n出所であると取引者や需要者に認識されたとしても,それは,あくまでも 被告の許諾を基盤として形成された信用なのであるから,原告が当然に 「仙三七」との商標の権利者として扱われるべきであるとする根拠となる ものではない。 前記のとおり,被告との関係で,原告による本件商標の出願行為が,信 義則上の義務違反となり,健全な商道徳に反し,著しく社会的妥当性を欠 く行為であるとの評価は,原告の主張によっても左右されない。
イ また,原告は,被告商標は本件被告商品を指定商品として含んでいなか ったなどとして,被告は「仙三七」との商標について何らの権利ももって いなかったなどと主張する。 確かに,被告商標について,本件被告商品を指定商品として含んでいな かった可能性が高いことは,被告も認めるところである。\nしかしながら,本件被告商品が,被告商標の指定商品の範囲に含まれて いなかったとしても,本件覚書を締結し,長年にわたりその有効性を前提 として取引関係にあった原告と被告の間においては,問題が生じた場合に は,本件覚書の第7条に基づき,お互いに誠意をもって解決すべきであ る。そして,原告としては,被告が,「仙三七」との商標の商標権者とし て,かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない 信義則上の義務を負っていたことは前記⑴に判示したとおりであることを も併せ考えると,原告において,抜け駆け的に本件被告商品を指定商品と するような商標で商標登録をすることが許されるわけではない。 むしろ,本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると,原告は,本件 被告商品を指定商品として含んでいなかった可能性や,自らが本件商標の\n登録出願をしようとしていることについては,何ら被告に告げておらず, 却って,前記1(3)アにみたとおり,平成28年9月頃(本件商標の登録出 願の直前頃と考えられる。)には,被告商標の譲渡を持ちかけて,その指 定商品に本件被告商品が含まれることを前提とするかのような言動を示し たものである。これらの原告の行為は,被告商標の保護範囲についての被 告の誤解を解消することなく,むしろ,被告の誤解を奇貨として,被告が 本件商標と同一の商標の登録出願をすることを著しく困難にするものであ ったと評価できる。それにもかかわらず,先願主義をそのまま適用して, 本件商標の有効性を肯定することは,当事者間の衡平を著しく欠くものと いえるから,前述の結論は左右されない。 なお,本件覚書7条は,覚書に関する疑義が生じた場合に誠意を持って 解決するとしていることからもうかがわれるとおり,本件覚書は,被告商 標に係る商標権が本件被告商品を指定商品として含むことを保証ないし当 然の前提とするものであるとまではいえないから,仮にこの点について疑 義が生じたとしても,そのことによって,当然に本件覚書が無効となるも のではない。
ウ また,原告は,被告に被告商標が空虚な権利であることを告げること は,自らを縛る道具を更に継続させるのみであることは明らかであるか ら,本件商標の登録出願を告知する義務はないなどと主張する。 しかしながら,被告商標の有効性に疑問があるというのであれば,それ を告知することによって本件覚書を適切に機能させることが本件覚書の趣\n旨なのであるから,原告の主張は,この趣旨に反し,信義にもとるもので あると言わなければならない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.11. 1
平成30(行ケ)10092 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所
上記(1)の認定事実によれば,本件発明1は,PCSK9とLDLRタンパク 質の結合を中和し,参照抗体1と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を,本件発明2は,PCSK9とLDLRタンパク質の結 合を中和し,参照抗体2と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を,それぞれ提供するものである。そして,本件各発明の課題は, かかる新規の抗体を提供し,これを使用した医薬組成物を作製することをもって, PCSK9とLDLRとの結合を中和し,LDLRの量を増加させることにより, 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し,高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。\n本件各明細書には,本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し,スクリーニングによってPCSK9に結合する抗体 を産生する2441の安定なハイブリドーマが確立され,そのうちの合計39抗体 について,エピトープビニングを行い,21B12と競合するが,31H4と競合 しないもの(ビン1)が19個含まれ,そのうち15個は,中和抗体であること, また,31H4と競合するが,21B12と競合しないもの(ビン3)が10個含 まれ,そのうち7個は,中和抗体であることが,それぞれ確認されたことが開示さ れている。また,本件各明細書には,21B12と31H4は,PCSK9とLD LRのEGFaドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 21B12は参照抗体1に含まれ,31H4は参照抗体2に含まれるから,21 B12と競合する抗体は参照抗体1と競合する抗体であり,31H4と競合する抗 体は参照抗体2と競合する抗体であることが理解できる。そうすると,本件各明細 書に接した当業者は,上記エピトープビニングアッセイの結果確認された,15個 の本件発明1の具体的抗体,7個の本件発明2の具体的抗体が得られることに加え て,上記2441の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても,同 様のエピトープビニングアッセイを行えば,参照抗体1又は2と競合する中和抗体 を得られ,それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに,本件各明細書には,免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製,免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製,21B12や 31H4と競合する,PCSK9−LDLRとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され,当業 者は,これらの記載に基づき,一連の手順を最初から繰り返し行うことによって, 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,参照抗 体1又は2と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば,当業者は,本件各明細書の記載から,PCSK9とLDLRタン パク質の結合を中和し,参照抗体1又は2と競合する,単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため,新規の抗体である本件発明1−1及び2−1のモノ クローナル抗体が提供され,これを使用した本件発明1−2及び2−2の医薬組成 物によって,高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって,本件各発明は,いずれもサポート要件に\n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と,「結 合中和することができる」という解決すべき課題(所望の効果)のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ,競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから,サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし,本件各明細書の記載から,「結合中和することができる」ことと,「参照 抗体と競合する」こととが,課題と解決手段の関係であるということはできないし, 参照抗体と競合するとの構成要件が,パラメータ要件であるということもできない。そして,特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において,アミノ酸配列が特\n定されていくことは技術常識であり,特定の結合特性を有する抗体を得るために, その抗体の構造(アミノ酸配列)をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない(甲34,35)。\n前記のとおり,本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和し, 本件各参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗体を提供するもので,参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びPCSK9と LDLR間の相互作用(結合)を遮断(「中和」)することができるものであること を構成要件としているのであるから,控訴人の主張は採用できない。(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性 なお,本件訂正発明1は,本件発明1の参照抗体1(構成要件1B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体1’(構\成要件1B’)とするものであり,本件訂正発明2は,本件発明2の参照抗体2(構成要件2B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体2’(構\成要件2B’)とするものであるから,本件各訂正発明も,いずれもサポート要件に適合するものと認められ る。
(5) 小括
以上によれば,本件各発明及び本件各訂正発明は,いずれもサポート要件に適合するというべきである。
4 争点(2)イ(実施可能要件違反)について\n
(1) 前記3(1)の認定事実によれば,本件各明細書の記載から,本件発明1−1及 び2−1の抗体及び本件発明1−2及び2−2の医薬組成物を作製し,使用するこ とができるものと認められるから,本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は,当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。\nしたがって,本件各発明は,いずれも,実施可能要件に適合するものと認められる。\n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,抗体の構造を特定することなく,機能\的にのみ定義さ れており,極めて広範な抗体を含むところ,当業者が,実施例抗体以外の,構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには,膨大な\n時間と労力を要し,過度の試行錯誤を要するのであるから,本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。\nしかし,明細書の発明の詳細な説明の記載について,当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が容易にその実施をできる程\n度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていないことに帰し,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる\nからである。 本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ, PCSK9との結合に関して,参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり,機能的にのみ定義されているとはいえない。そして,発明の詳細な説明の記載に,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和す\nることができ,PCSK9との結合に関して,参照抗体1又は2と競合する,単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば,当業者は,その実施をすることが可能というべきであり,特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ\nることまで記載されている必要はない。 また,本件各発明は,抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから,LDLRが認識するPCSK9上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体(EGFaミミック)が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは,実施可能\要件とは関係しないというべきである。そして,前記(1)のとおり,当業者は,本件各明細書の記載に従って,本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,本件各特許の特許請求の範 囲(請求項1)に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから,本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために,当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって,控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性\n
なお,前記3(4)のとおり,本件訂正発明1は,本件発明1の参照抗体1(構成要件1B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体1’(構\成要件1B’)とするものであり,本件訂正発明2は,本件発明2の参照抗体2(構成要件2B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体2’(構\成要件2B’)とするものであるから,当業者は,本件各明細書の記載から,本件訂正発明1 −1及び2−1の抗体及び本件訂正発明1−2及び2−2の医薬組成物を作製し, 使用することができるものと認められ,本件各訂正発明も,いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.11. 1
平成31(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記(1)の認定事実によれば,本件発明1は,PCSK9とLDLRタンパク 質の結合を中和し,参照抗体1と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を,本件発明2は,PCSK9とLDLRタンパク質の結 合を中和し,参照抗体2と競合する,単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を,それぞれ提供するものである。そして,本件各発明の課題は, かかる新規の抗体を提供し,これを使用した医薬組成物を作製することをもって, PCSK9とLDLRとの結合を中和し,LDLRの量を増加させることにより, 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し,高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。\n本件各明細書には,本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し,スクリーニングによってPCSK9に結合する抗体 を産生する2441の安定なハイブリドーマが確立され,そのうちの合計39抗体 について,エピトープビニングを行い,21B12と競合するが,31H4と競合 しないもの(ビン1)が19個含まれ,そのうち15個は,中和抗体であること, また,31H4と競合するが,21B12と競合しないもの(ビン3)が10個含 まれ,そのうち7個は,中和抗体であることが,それぞれ確認されたことが開示さ れている。また,本件各明細書には,21B12と31H4は,PCSK9とLD LRのEGFaドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 21B12は参照抗体1に含まれ,31H4は参照抗体2に含まれるから,21 B12と競合する抗体は参照抗体1と競合する抗体であり,31H4と競合する抗 体は参照抗体2と競合する抗体であることが理解できる。そうすると,本件各明細 書に接した当業者は,上記エピトープビニングアッセイの結果確認された,15個 の本件発明1の具体的抗体,7個の本件発明2の具体的抗体が得られることに加え て,上記2441の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても,同 様のエピトープビニングアッセイを行えば,参照抗体1又は2と競合する中和抗体 を得られ,それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに,本件各明細書には,免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製,免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製,21B12や 31H4と競合する,PCSK9−LDLRとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され,当業 者は,これらの記載に基づき,一連の手順を最初から繰り返し行うことによって, 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,参照抗 体1又は2と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば,当業者は,本件各明細書の記載から,PCSK9とLDLRタン パク質の結合を中和し,参照抗体1又は2と競合する,単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため,新規の抗体である本件発明1−1及び2−1のモノ クローナル抗体が提供され,これを使用した本件発明1−2及び2−2の医薬組成 物によって,高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し,又は予防し,疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって,本件各発明は,いずれもサポート要件に\n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と,「結 合中和することができる」という解決すべき課題(所望の効果)のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ,競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから,サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし,本件各明細書の記載から,「結合中和することができる」ことと,「参照 抗体と競合する」こととが,課題と解決手段の関係であるということはできないし, 参照抗体と競合するとの構成要件が,パラメータ要件であるということもできない。\nそして,特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において,アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり,特定の結合特性を有する抗体を得るために, その抗体の構造(アミノ酸配列)をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない(甲34,35)。\n前記のとおり,本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和し, 本件各参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗体を提供するもので,参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びPCSK9と LDLR間の相互作用(結合)を遮断(「中和」)することができるものであること を構成要件としているのであるから,控訴人の主張は採用できない。\n
(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性
なお,本件訂正発明1は,本件発明1の参照抗体1(構成要件1B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体1’(構\成要件1B’)とするものであり,本件訂正発明2は,本件発明2の参照抗体2(構成要件2B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体2’(構\成要件2B’)とするものであるから,本件各訂正発明も,いずれもサポート要件に適合するものと認められる。
(5) 小括
以上によれば,本件各発明及び本件各訂正発明は,いずれもサポート要件に適合 するというべきである。
4 争点(2)イ(実施可能要件違反)について
(1) 前記3(1)の認定事実によれば,本件各明細書の記載から,本件発明1−1及 び2−1の抗体及び本件発明1−2及び2−2の医薬組成物を作製し,使用するこ とができるものと認められるから,本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は,当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。\nしたがって,本件各発明は,いずれも,実施可能要件に適合するものと認められる。\n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は,本件各発明は,抗体の構造を特定することなく,機能\的にのみ定義さ れており,極めて広範な抗体を含むところ,当業者が,実施例抗体以外の,構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには,膨大な\n時間と労力を要し,過度の試行錯誤を要するのであるから,本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。\nしかし,明細書の発明の詳細な説明の記載について,当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が容易にその実施をできる程\n度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていないことに帰し,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる\nからである。 本件各発明は,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ, PCSK9との結合に関して,参照抗体と競合する,単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり,機能的にのみ定義されているとはいえない。そして,発明の詳細な説明の記載に,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和す\nることができ,PCSK9との結合に関して,参照抗体1又は2と競合する,単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば,当業者は,その実施をすることが可能というべきであり,特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ\nることまで記載されている必要はない。 また,本件各発明は,抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから,LDLRが認識するPCSK9上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体(EGFaミミック)が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは,実施可能\要件とは関係しないというべきである。そして,前記(1)のとおり,当業者は,本件各明細書の記載に従って,本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも,本件各特許の特許請求の範 囲(請求項1)に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから,本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために,当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって,控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性
なお,前記3(4)のとおり,本件訂正発明1は,本件発明1の参照抗体1(構成要件1B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体1’(構\成要件1B’)とするものであり,本件訂正発明2は,本件発明2の参照抗体2(構成要件2B)を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体2’(構\成要件2B’)とするものであるから,当業者は,本件各明細書の記載から,本件訂正発明1 −1及び2−1の抗体及び本件訂正発明1−2及び2−2の医薬組成物を作製し, 使用することができるものと認められ,本件各訂正発明も,いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.10.30
令和1(ネ)10045 標章使用差止反訴請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
まず,控訴人が主張する反訴原告主張合意については,これを記載した 契約書等の書面は作成されていない。また,控訴人が主張する平成14年 頃の反訴原告主張合意の成立にかかる事実経過(前記第2の5(控訴人の 主張)ア)も,これを裏付ける客観的な証拠は見当たらない。
ア そこで,控訴人と被控訴人との間の取引経過についてみると,各業態 の第1号店を出店する際の請求書をみても,店舗デザイン設計料とのみ あるだけで,反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムに係る制 作料,使用料については何ら記載されていない。そして,ロゴやピクト グラムについては,ハードオフ,オフハウス,モードオフ,ガレージオ フ,ホビーオフ,リカーオフといった各業態の第1号店を出店した(ハ ードオフのピクトグラムについては,平成7年頃に使い始めた)後は, コーナーの拡大などの必要に応じて更なるピクトグラムの制作・納品を しつつも,基本的にはそれまでに制作したロゴやピクトグラムを用いて 店舗デザインの設計等を行うのが恒例となっており,各業態によって差 はあるものの,制作したロゴ及びピクトグラムはその後の出店店舗でも 用いられていた。また,平成29年4月26日に請求するまで(前記1 において引用する原判決第3の1(15)),20年以上の長期間にわたっ て,控訴人は,反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムの使用 料を店舗デザイン設計(監理)料と別に請求したことはなく,制作料に ついても,その請求を裏付ける書面は基本的に存在しない。 ただし,控訴人から被控訴人に対する制作料の請求については,平成 16年3月22日の制作料(基本デザイン料)の請求(前記1⑴におい て改めた原判決引用部分第3の1(10))及び平成28年3月の制作料の請 求(前記1において引用する原判決第3の1(12)エ)が存在する。しか しながら,仮に反訴原告主張合意が存在したのであれば,かかる請求が できないことは控訴人にとって明らかであって,それにもかかわらず請 求したこと自体,それまでに作成・納品した制作料について将来も請求 できないことを認識していたからこそ,新たに作成・納品したロゴ等に ついて,制作料の支払合意を取り付けるべく,このような行為に及んだ と考えられるところである。なお,仮に,かかる2回の請求以外に,控 訴人が被控訴人に対し,口頭で,ロゴ等の制作料の請求をしたことがあ ったとしても同様である。 このような状況に照らすと,将来的に,控訴人,被控訴人の間におい て,店舗デザイン設計(監理)料等の名目で支払われた金員とは別に, 反訴原告標章及び反訴原告ピクトグラムの制作料・使用料を請求する権 利が留保されていたとは考えにくく,むしろ,これらの制作料及び使用 料の支払義務を前提とする反訴原告主張合意がなかったことが窺われる。
イ また,契約終了に当たり,控訴人が被控訴人に当初交付した書類の内 容は前記1(2)に記載のとおりであるところ,かかる記載内容からは,無 償使用許諾を前提とする反訴原告主張合意の存在というよりも,むしろ, 使用料は店舗のデザイン設計料に含まれていたとの認識が窺われる。ま た,同書面には,制作料そのものについての言及は存在しない。
ウ 加えて,被控訴人においては,仮に反訴原告標章や反訴原告ピクトグ ラムの使用ができなくなれば,重大な不利益が生じることが明らかであ る。したがって,仮に反訴原告主張合意のような合意が存在するのであ れば,これによって生じる不利益の重大性に鑑み,合意の内容を書面化 することが通常であると考えられるところ,そのような書面が存在しな いことは既に指摘したとおりである。
エ 以上によれば,被控訴人は,店舗デザイン設計料等とは別に,ロゴや ピクトグラムの制作料,使用料を支払う意思はなく,控訴人も,被控訴 人からの店舗デザイン設計の依頼を受ける際に,ロゴや平成7年頃以降 はピクトグラムの制作をも必要に応じて行うことを前提としつつも,こ れらの制作料や使用料については,将来的にも被控訴人から引き続き店 舗設計業務の依頼を受けられることを期待したことから,明示的に制作 料や使用料として請求することはせずに,店舗設計業務を継続して受注 していく中で,これらについて実質的に回収を図っていこうという意向 であったと考えられる。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.10.30
平成31(ネ)10018 損害賠償請求本訴,使用料規程無効確認請求反訴控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上のとおり,被控訴人は,地上テレビジョン放送事業者から管理 委託を受けた著作権及び著作隣接権の有線放送権に基づき再放送の利用 許諾をするに当たり,ほぼ全てのケーブルテレビ事業者との間で,3者 契約又は2者契約の方式により年間の包括的利用許諾契約を締結し,3 者契約の場合は本件基本合意に基づき,2者契約の場合は本件使用料一 覧(2者契約)に基づき定められた使用料額をケーブルテレビ事業者か ら徴収していることが認められる。 一方,被控訴人と3者契約又は2者契約の方式により年間の包括的利 用許諾契約を締結したケーブルテレビ事業者のうち,本件基本合意に基 づく減額措置(3者契約の場合)又は本件使用料一覧(2者契約)に基 づく減額措置(2者契約の場合)を受けることが可能であるにもかかわ\nらず,減額措置を受けずに,本件使用料規程に定められた区域内再放送 の使用料(1世帯1ch当たり年額120円)及び区域外再放送の使用 料(1世帯1ch当たり年額600円)を支払っている事業者は存在し ない。
そして,控訴人は,適法に同意を得て,又は総務大臣による同意裁定 を得て,毎日放送等6社の地上テレビジョン放送を同時再放送している ものであり,ケーブルテレビ連盟の会員でもあることから,仮に控訴人 が希望すれば,被控訴人との間で,本件基本合意に基づく3者契約又は 本件使用料一覧(2者契約)に基づく2者契約を締結することが可能で\nあって,その場合の再放送使用料は,上記減額措置の適用を受けて,区 域内再放送につき1世帯1ch当たり年額24円(3者契約)又は28 円(2者契約),区域外再放送につき1世帯1ch当たり年額120円 (3者契約)又は144円(2者契約)であり,平成26年度の再放送 使用料については,使用料の50%が軽減されるものと認められる(弁 論の全趣旨)。 以上のような,被控訴人とケーブルテレビ事業者との間で締結された 同時再放送に係る利用許諾契約の内容,控訴人による本件有線放送権の 利用の態様等の事実を考慮すると,上記利用許諾契約の締結に当たり適 用された実績が全くない,本件使用料規程の「年間の包括的利用許諾契 約によらない場合」(3条(2))又は「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ 場合」(3条(1))が,著作権法114条4項の「使用料規程のうちその 侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」 に該当するものとは認めらない。
(イ) これに対し被控訴人は,(1)使用料規程による使用料の算出方法が複 数あるときは各方法により算出した額のうち最も高い額を請求すること ができるとする著作権法114条4項を設けた趣旨に鑑みれば,「最も 高い額」となる算出方法による許諾実績がなくとも,同項の適用は妨げ られない,(2)実際にも,被控訴人は,著作権等管理事業を開始した平成 26年度以降,年間の包括的利用許諾契約によって区域外再放送を許諾 するに当たり,累計12社(平成27年度10社,同28年度9社,同 29年度9社)の有線テレビジョン放送事業者につき,本件減額措置を 施さずに,有料視聴世帯数に地上テレビジョン放送1波当たり年額60 0円を乗じた額の使用料を徴収している旨主張する。 まず,上記(1)の点について,著作権法114条4項は,同条3項によ り損害の賠償を請求する場合において,当該著作権等管理事業者が定め る使用料規程により算出した金額をもって,同条3項に規定する金銭の 額とする旨を定めるものである。そして,同条3項は,不法行為による 著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定し た規定であるところ,不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じ た現実の損害を填補することを目的とするものであるから,現実の損害 が発生しなかった場合には,それを理由とする賠償請求をすることがで きないことは自明である。
これを本件についてみるに,前記(ア)のとおり,被控訴人は,ほぼ全て のケーブルテレビ事業者との間で,3者契約又は2者契約の方式により 年間の包括的利用許諾契約を締結し,3者契約の場合は本件基本合意に 基づき,2者契約の場合は本件使用料一覧(2者契約)に基づき定めら れた使用料額をケーブルテレビ事業者から徴収しており,これらの事業 者のうち,本件基本合意に基づく減額措置又は本件使用料一覧(2者契 約)に基づく減額措置を受けることが可能であるにもかかわらず,これ\nを受けずに,それよりも遥かに高額な,本件使用料規程3条(1)又は(2)に 定められた区域内再放送及び区域外再放送の使用料を支払っている事業 者は存在しない。被控訴人と控訴人との交渉の過程においても,本件基 本合意に基づく3者契約又は本件使用料一覧(2者契約)に基づく2者 契約によることが,当然の前提とされていたものである。 そして,このような被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再 放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額,控訴人による本件 有線放送権の利用の態様,控訴人と被控訴人の間の再放送同意に係る利 用許諾契約に関する交渉経緯(前記ア(エ))等によれば,本件における使 用料相当額の算定に当たって,実際の利用許諾契約において用いられた 例がなく,かつ,上記減額措置を受ける場合と比較して使用料が遥かに 高額となる,本件使用料規程3条(1)又は(2)による場合の算定方法を用い ることは,被控訴人に生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現 実的というべきであり,相当でない。
次に,上記(2)の点について,被控訴人が,累計12社の有線テレビジ ョン放送事業者との間で,本件使用料規程に基づき,区域外再放送の使 用料を1世帯1ch当たり年額600円とする年間の包括的利用許諾契 約を締結し,同規程に基づき算定された金額を徴収していることについ ては,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また,被控訴人の 主張によれば,上記12社はいずれも重複波等の区域外再放送を行った 者であるところ,前記認定の被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の 同時再放送に係る利用許諾契約の締結状況に照らすと,上記12社は, 本件基本合意に基づく3者契約又は本件使用料一覧(2者契約)による 2者契約を締結した上で,本件基本合意(1)(3)の定めに基づき,「有料視 聴世帯数×1世帯1chあたり年額600円×区域外再放送(重複波等) ch数」の使用料を支払ったものであると推認される。そして,上記1 2社において,本件基本合意に基づく減額措置(3者契約の場合)又は 本件使用料一覧(2者契約)に基づく減額措置(2者契約の場合)を受 けることが可能であるにもかかわらず,減額措置を受けずに,本件使用\n料規程に定められた区域外再放送の使用料を支払っていることを認める に足りる証拠はない。 したがって,被控訴人の上記各主張を採用することはできない。
ウ 被控訴人は,控訴人が本件有線放送権を侵害したことにより被控訴人が 受けた損害の額として,著作権法114条3項及び4項により算定される 損害額を主張するところ,前記イのとおり,本件において著作権法114 条4項を適用して,本件使用料規程3条(1)又は(2)に基づいて被控訴人の損 害の額を算定することは,相当でない。そこで,同条3項により算定され る被控訴人の損害の額について,以下検討する。
同条3項は,著作権及び著作隣接権侵害の際に著作権者,著作隣接権者 が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。また,同項所定の 「その著作権…又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当 する額」については,平成12年法律第56号による改正前は「その著作 権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額」と 定められていたところ,「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得にな ってしまうとして,同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 そして,かかる法改正の経緯に照らせば,著作権及び著作隣接権侵害をし た者に対して事後的に定められるべき,これらの権利の行使につき受ける べき金銭の額は,通常の利用許諾契約の使用料に比べて自ずと高額になる であろうことを考慮すべきである。 これを本件についてみると,前記イ(ア)の被控訴人とケーブルテレビ事 業者との間の同時再放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額, 控訴人による本件有線放送権の利用の態様等の事実に加えて,控訴人と被 控訴人の間の再放送同意に係る利用許諾契約に関する交渉経緯など,本件 訴訟に現れた事情を考慮すると,著作権及び著作隣接権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき,本件での利用に対し受けるべき金銭の額は, 被控訴人とケーブルテレビ事業者との間における再放送使用料を現実に 規律していると認められる本件基本合意及び本件使用料一覧(2者契約) をベースとし,そこに定められた額を約1.5倍した額である,区域内再 放送につき1世帯1ch当たり年額36円及び区域外再放送につき1世 帯1ch当たり年額180円とし,平成26年度についてはその半額を下 らないものと認めるのが相当である。 そこで,かかる算定方式に基づく使用料について検討する。
・・・・
(ウ) 上記のとおり,控訴人が平成26年4月1日から平成30年3月3 1日までの間に本件有線放送権を侵害した行為につき,本件有線放送権 の行使につき受けるべき金銭の額に相当する4293万1238円が, 被控訴人の受けた損害の額となる(著作権法114条3項)。 エ 以上のとおりであるから,著作権法114条3項により算定される損害 額に弁護士費用を加えた金額が,被控訴人の損害額と認められる。 そして,控訴人の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は,前記ウ により算定される損害額の約1割に当たる429万円を下らないと認め るのが相当であるから,被控訴人の損害額は,4722万1238円(4 293万1238円+429万円)である。
したがって,被控訴人は控訴人に対し,上記4722万1238円のほ か,うち2006万8931円(平成26年度及び同27年度分の使用料 相当額(合計1824万8931円)と弁護士費用相当額(182万円) の合計)に対する平成28年9月10日から支払済みまでの遅延損害金, 及び,うち2715万2307円(平成28年度及び同29年度分の使用 料相当額(合計2468万2307円)と弁護士費用相当額(247万円) の合計)に対する平成30年4月1日から支払済みまでの遅延損害金の支 払を求めることができる。
なお,控訴人は,被控訴人を供託者とし,平成26年度ないし同29年 度の地上テレビジョン放送及びその番組の著作権,著作隣接権の使用料と して,4回にわたり,合計584万1772円を供託しているが(甲16, 18,32,乙75),これらの金額は,上記のとおり認定される本件有 線放送権の侵害に係る損害賠償額の1割ないし2割程度にすぎない。また, 上記供託金額は,本件基本合意において区域内再放送の使用料として定め られた「1世帯1chあたり年額24円」を,区域外再放送の使用料にも 用いて算定した金額であるところ,かかる算定方法は控訴人独自のもので あって,採用し難いものである。 したがって,控訴人による上記の各供託は,これを有効と解することは できない。
オ これに対し控訴人は,区域内再放送と区域外再放送のいずれについても, 本件基本合意で定められた区域内再放送の使用料に基づくのが相当であり, 有料視聴世帯数に対し,1世帯1ch当たり年額24円を乗じた金額から 15%を値引きしたものが損害額となる旨主張する。 しかしながら,本件有線放送権の侵害による被控訴人の損害賠償額を算 定するに当たっては,被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再放 送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額等を考慮するのが相当 であることについては,前記イ(ア)及びウのとおりである。 一方,被控訴人と3者契約又は2者契約を締結したケーブルテレビ事業 者にあって,本件基本合意又は本件使用料一覧(2者契約)に定められた 区域外再放送の使用料の算定方式に反して,1世帯1ch当たりの区域外 再放送の使用料として,区域内再放送と同額しか支払っていない者は存在 しない。 したがって,このような実情を考慮すれば,控訴人の上記主張を採用す ることはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.10.28
平成30(ネ)10043 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月3日 知的財産高等裁判所
本件特許請求の範囲の請求項1(本件発明1に係る特許請求の範囲)の 記載は,「第IX因子または第IXa因子に対する抗体または抗体誘導体であって, 凝血促進活性を増大させる,抗体または抗体誘導体(ただし,抗体クローンAHI X−5041:Haematologic Technologies社製,抗体 クローンHIX−1:SIGMA−ALDRICH社製,抗体クローンESN−2: American Diagnostica社製,および抗体クローンESN−3: American Diagnostica社製,ならびにそれらの抗体誘導体を 除く)。」であり,請求項4(本件発明4に係る特許請求の範囲)は請求項1を引用 している。ここで,「凝血促進活性を増大させる」との記載の意義については,本件 明細書においてこれを定義した記載はない上,「血液凝固障害の処置のための調製 物を提供する」(段落【0010】)という本件各発明の目的そのものであり,か つ,本件各発明における抗体又は抗体誘導体の機能又は作用を表\現しているのみで あって,本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではない。\n特許権に基づく独占権は,新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示する ことの代償として与えられるものであるから,このように特許請求の範囲の記載が 機能的,抽象的な表\現にとどまっている場合に,当該機能や作用効果を果たし得る構\成全てを,その技術的範囲に含まれると解することは,明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含めて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが,そのような解釈は,発明の開示の代償として独\n占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきで ある。
したがって,特許請求の範囲が上記のように抽象的,機能的な表\現で記載されて いる場合においては,その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすること はできず,上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し,そこに開示された具 体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。もっとも,このことは,特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定す\nるものではなく,明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ,実施す ることができるのであれば,同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。\n
イ そこで,本件明細書において開示された具体的構成に示されている技術思想について検討する。\n
(ア) ある抗体が,FIX又はFIXaに結合し,FIXaの凝血促進活性 を増加するか又はFVIII様活性を有することを示すための試験方法としては, 凝血試験や色素形成試験等があり,これらによって評価が可能である(段落【0013】,【0014】,【0037】,【0065】)。そして,FIXaに対する抗体を\nスクリーニングし,色素形成アッセイによってFVIII様活性を有するモノクロ ーナル抗体(モノスペシフィック抗体)が複数作製されており(実施例4,9),そ の中でFVIIIインヒビターを有する血漿の凝血をもたらす抗体(193/AD 3)も確認されている(実施例7)。したがって,当業者は,FIXaに対する抗体 をスクリーニングすることにより,過度の試行錯誤を要することなく,一定の割合 で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)を作 製できたと認められる。 また,凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体) からの誘導体も複数作製されているから(例えば,CDR3領域由来ペプチド及び その誘導体〔実施例11,12〕,キメラ抗体〔実施例13〕,Fabフラグメント 〔実施例15〕,単鎖抗体〔scFv。実施例10,16,18〕,ミニ抗体〔実施 例17〕),当業者は,凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体(モノスペシ フィック抗体)からの誘導体も作製できたと認められる。
(イ) バイスペシフィック抗体については,本件明細書において,実施例と して作製された例は記載されておらず,FIX又はFIXaに結合するアーム以外 のアームが結合する対象の抗原がいかなるものかも開示されていない。 しかし,バイスペシフィック抗体は,抗体誘導体の一態様として明記されている (段落【0019】及び【0026】)。そして,バイスペシフィック抗体ではない ものの,凝血促進活性を増大させるモノスペシフィック抗体からの誘導体も複数作 製されている(実施例10〜13,15〜18)。 また,FIX又はFIXaに対するバイスペシフィック抗体の作製法は,本件出 願日当時に複数知られており,その中でも,クワドローマ技術は簡便な方法であり, 本件出願日当時の当業者にとって,合理的な時間及び努力の範囲内でバイスペシフ ィック抗体を作製できる手法であったのであり,また,バイスペシフィック抗体を 産生するクワドローマを融合し及び選択する種々の方法及びプロトコルは,199 9年において,利用可能であり,良好に確立され,二重特異性のIgG分子を作製するのに幅広く用いられていた(本件明細書の段落【0026】,甲97,100〜\n104,甲140の1)のであるから,当業者は,本件出願日の技術常識から,F IX又はFIXaに対するバイスペシフィック抗体を作製可能であったと認められる。\nさらに,前記3(2)のとおり,バイスペシフィック抗体のFVIII補因子活性と 抗FIXのモノスペシフィック抗体とは乏しい相関関係しかなく,バイスペシフィ ック抗体のFVIII補因子活性は,抗FIX抗体由来の構造だけなく,抗FX抗体由来の構\造にも影響を受けるのであるが,バイスペシフィック抗体においては,FIX又はFIXaに対する結合部位は1価になるものの,1価でも凝血促進活性 を増大させる効果があり(本件明細書実施例10〜12,15,16,18),バイ スペシフィック抗体の二つの抗原間で立体干渉が生じない限り,モノスペシフィッ ク抗体の活性は維持される(甲140の1)。FIX又はFIXa以外の結合部位が FXである場合を想定すると,本件出願日当時,FIXaとFXaの構造が明らかとなっており,FIXaとFXaの立体構\造からすると,当業者は,FIXaとFXに結合するバイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体)で,FIXa結合部位の活性に対する干渉は起こりにくいと予測できる(甲140の1)。\nしたがって,当業者は,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型 バイスペシフィック抗体)が,モノスペシフィック抗体が有する凝血促進活性を増 大させる作用を維持できると予測できたと認められる。そうすると,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体)についても,\nモノスペシフィック抗体の活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体の一態 様として「抗体誘導体」に含まれると解される。
(ウ) 以上によると,本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには, 「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子 に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であるものの,バイスペシフ ィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体)は「抗体誘導 体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。 もっとも,FIX又はFIXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィッ ク抗体)がFIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には,別 異に解すべきである。すなわち,本件各発明の技術的範囲に属するというためには, 「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子 に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であると解されるところ,こ れには,FIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものではないFIX又はF IXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)は含まれないし, このようなモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)から誘導される抗体誘 導体(バイスペシフィック抗体もこれに含まれる。)も含まれないというべきである。 このような抗体誘導体(バイスペシフィック抗体)は,たとえ,それ自体がFIX aの凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても,本件各発明の 課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされ ているのであって,本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し,実施できるもの とはいえないというべきである。
(エ) 被控訴人は,(1)非対称型バイスペシフィック抗体の著しく高い活性 は,一つの分子が2種類のアームを有するというバイスペシフィック抗体に固有の 機序によって初めて実現されたもので,非対称型バイスペシフィック抗体は,本件 明細書においてハイブリドーマ方法によって得られたモノスペシフィック抗体とは 活性及び機序の点で大きく異なっており,本件各発明の課題解決手段とは異なる手 段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたされていることになる,(2)FVI II補因子活性は,抗FX腕によって影響を受けるため,抗FIX(a)腕及び抗 FX腕の何れの組合せが非対称型バイスペシフィック抗体のFVIII補因子活性 を発現するのか,予測することが困難である,(3)現時点においてすら,非対称型バ イスペシフィック抗体の適切な評価手法が確立できていないことなどからすると, 本件明細書は,非対称型バイスペシフィック抗体を想定していなかったといえると 主張する。 しかし,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィ ック抗体)が抗体誘導体の一態様として「抗体誘導体」に含まれ得ることは,既に 判示したとおりであって,このことは,被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体の凝血促進活性を増大させる効果が大きいことや,抗FIX(a)腕と 抗FX腕の何れの組合せが効果があるかを予測することが困難であることや現時点において,非対称型バイスペシフィック抗体の適切な評価方法が確立していないこ\nとによって左右されるものではない。 (オ) 本件明細書においては,凝血促進活性を図る方法について,2時間の インキュベーション後のFVIIIアッセイ(例えば,COATEST(登録商標) アッセイまたはイムノクロム(Immunochrom)試験)において少なくと も3のバックグラウンドの対測定値の比を示すとされている(段落【0013】,【0 014】。なお,「バックグラウンドの対測定値の比」は,「ネガティブコントロール との比」と同義である。)が,色素形成アッセイ以外にも凝固アッセイなどFVII I活性を決定するために使用される全ての方法が使用でき(段落【0037】,【0 065】),同じ色素形成アッセイであってもインキュベーション時間が2時間では ない例も記載されている(実施例2,4,5,実施例11・図18〜22,実施例 15〜18)。
このように,本件明細書に記載された凝血促進活性の評価方法は,複数存在して おり,一般に,評価方法が異なればその基準が同一であるとは限らないとはいえる ものの,本件明細書では,段落【0013】及び【0014】に前記2(1)クのとお り記載され,色素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が,1.7 程度(例えば,段落【0081】・図11において,198/AP1はネガティブコ ントロールとの比が1.7程度であるが,凝血促進活性を示さないとされている。 段落【0067】・図7A(196/AF2 35μM Pefabloc Xa〔登 録商標〕),段落【0068】・図7B(198/AM1 35μM Pefablo c Xa〔登録商標〕)も同様。)や2程度(段落【0105】・図20において,A 1/5はネガティブコントロールとの比が2程度であるが,有意な凝血促進活性は ないと評価されている。)の場合においては,「凝血促進活性を増大させる」とは評 価されていない。 本件明細書のこれらの記載に加え,前記アのような本件各発明の請求項の記載を 考慮すると,当業者は,本件各発明の範囲に含まれる抗体又はその誘導体は,複数 の評価方法のうち,色素形成アッセイ(FVIIIアッセイ)を実施した場合には, 少なくとも3のバックグラウンドの対測定値の比(ネガティブコントロールとの比) を示すものが本件各発明の抗体及び抗体誘導体であると理解すると認められるから, 「凝血促進活性を増大させる」とは,色素形成アッセイを実施した場合には,ネガ ティブコントロールとの比が3を超えることを意味すると認めるのが相当である。 これに対し,控訴人らは,「凝血促進活性を増大させる」について,当業者は,ネ ガティブコントロールとの比が1を超えるものであるか否かで判断する旨主張し, 本件明細書の段落【0013】の記載は,「最終的に生成された物の評価をする際に 何らかの値を決めておく必要があるので,とりあえず3としたという程度の意味で ある」(甲131の3頁),「任意に設定された仮の基準であり,すべての候補物質に 適応すべき必須の条件ではない」(甲132の3頁),「ノイズや測定誤差の大きさに 関する記載がない以上,統計学的議論から根拠をもった基準として3を導くことは できない」(甲136の1頁)などの意見書を提出するが,これらの意見書によると, 本件各発明の技術的範囲が当業者にとって明らかでないことになるから,これらの 意見書の意見や控訴人らの主張を採用することはできないことは,既に判示したと おりである。
(2) 上記(1)のとおり,「凝血促進活性を実質的に増大させる」とは,色素形成 アッセイを実施した場合のネガティブコントロールとの比が3を超えることを意味 するが,色素形成アッセイの測定方法について,控訴人らは,本件明細書の記載及 び技術常識によると,コンティニュアス法によるアッセイを行うのであればインキ ュベーション時間を2時間とし,サブサンプリング法によるアッセイを行うのであ れば第1ステップのインキュベーション時間を5分とし,長時間のインキュベーシ ョン時間をとるのであれば,酵素の最大反応速度をみるために,継続的に測定すべ きである旨主張する。
ア コンティニュアス法及びサブサンプリング法について 証拠(甲210,甲229の1)及び弁論の全趣旨によると,サブサンプリング 法とは,FXaを生成させる第1ステップと,生成したFXaを定量する第2ステ ップを分離して実施する色素形成アッセイの方法であり,第1のステップではFX aを生成させるのに必要な試薬と被験抗体を混合させ,一定時間インキュベーショ ンさせてFXaを生成し,第1ステップで生成されたFXaの反応をみるために, 第2ステップに移行する前にFXaの生成を止め,第2ステップで,上記混合物に 発色性合成基質を添付することで,第1ステップで生成されたFXaが発色性合成 基質を切断し,発色する様子を測定するという標準的な FVIIIアッセイで用い られている方法であること,コンティニュアス法とは,第1ステップ(FXa生成 反応)及び第2ステップ(FXaによる発色反応)からなる一連の反応を1ステッ プで行う方法であり,被験抗体,FIXa,FX,リン脂質,カルシウムイオン, 発色性合成基質等の一連の反応に必要な試薬を全て最初から投入し,第1ステップ であるFXa生成反応と,第2ステップである生成したFXaによる発色反応とを 同時に進行させて,吸光度を経時的に測定することにより,FXa生成量の推移を 継続的に観察するものであることが認められる。
イ 証拠(甲208,211,213,乙39)及び弁論の全趣旨によると, 本件明細書の段落【0013】に記載されているCOATEST(登録商標)やイ ムノクロムは,サブサンプリング法の色素アッセイキットであり,コアテストの仕 様書や,イムノクロムの後継品であるテクノクロムの仕様書にはインキュベーショ ン時間は5分間とされていることが認められるが,本件明細書の段落【0013】 においては,インキュベーション時間は2時間とされているから,本件明細書の段 落【0013】においては,サブサンプリング法を用いつつも,インキュベーショ ン時間を2時間として色素形成アッセイを実施したところ,少なくとも3のバック グラウンドの比を示すものが本件各発明である旨記載されていることになる。 この点について,控訴人らは,インキュベーション時間を2時間とすると,イン キュベーションの途中で,基質の消費に伴い,反応速度は最大反応よりも低下し, 第1ステップのインキュベーション時間の間,FIXaが失活してしまい,その結 果,FXaの生成速度も低下し,さらに,生成物であるFXaも自己消化を起こし, 血液凝血性やアミド活性を持たないFXaγに変換してしまうので,FXaの産出 量は本来の産出量より少なくなっていて,適切でなく,インキュベーション時間は 仕様書のとおり5分が適切であると主張する。 しかし,本件明細書には,上記のとおり,インキュベーション時間を2時間とし たものしか記載されていないのであって,本件明細書においては,インキュベーシ ョン時間を仕様書の記載に反してあえて2時間とし,そのときのFXaの産出量を もって,3のネガティブコントロールとの比を評価するときの産出量としているの であるから,当業者は,3のネガティブコントロールとの比を評価するに当たり, インキュベーション時間が5分の場合を想定することはできないというべきである。 なお,本件明細書において,インキュベーション時間を2時間とした理由につい ては,本件明細書に記載はなく,本件の証拠によるも必ずしも明らかでないが,そ のことは上記判断を左右するものではない。 そうすると,当業者は,本件各発明の「凝血促進活性を増大させる」というため には,インキュベーション時間を2時間とする測定を要すると理解すると解される。
ウ 以上によると,本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには,「第 IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対 するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当 該抗体を改変した抗体誘導体」であり,インキュベーション時間を2時間とする色 素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が3を超えるものを意味す ると認めるのが相当である。
・・・
エ 以上によると,被控訴人製品は,「第IXa因子の凝血促進活性を実質的 に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペ シフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」に該 当するとは認められない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 機能クレーム
>> ピックアップ対象
2019.10.21
平成30(ネ)10006等 特許権侵害行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
これに対し控訴人は,本件発明A1の「拡張ゲームプログラムおよび /またはデータ」は,標準のゲーム内容に加え,拡張されたゲーム内容 を楽しむことが可能となるものであるから(本件明細書Aの【0020】\n等),標準のゲーム内容を置き換えるゲームプログラム及び/又はデー タを含まないと解され,本件発明A1と公知発明1との間には,相違点 1−1及び1−2のほかに,相違点1−3ないし1−5が存在する旨主 張する。
そこで検討するに,本件発明A1の特許請求の範囲(請求項1)の記 載によれば,「所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータ」は, 「標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて,ゲームキャラ クタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および\n/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するためのゲー ムプログラムおよび/またはデータ」であり,「第2の記憶媒体」に「包 含」されるものであって,「上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装 填され」,「上記ゲーム装置が」「第1の記憶媒体」が「包含する」「所 定のキーを読み込んでいる場合に」,「上記標準ゲームプログラムおよ び/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの 双方によってゲーム装置を作動させ」ることを理解できる。 一方,上記特許請求の範囲には,「上記標準ゲームプログラムおよび /またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双 方によってゲーム装置を作動させ」た場合に動作する「上記標準ゲーム プログラムおよび/またはデータ」が,「上記標準ゲームプログラムお よび/またはデータ」の全部であると限定して解釈すべき根拠となる記 載はない。そして,本件明細書Aの発明の詳細な説明にも,「上記標準 ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムお よび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」る場合とは, 「上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータ」の一部しか作動し ない場合を含まないものであり,「上記標準ゲームプログラムおよび/ またはデータ」の全部が動作することが必要であると解釈すべき根拠と なる記載はない。 前記(ア)のとおり,本件公知発明1の「勇士の紋章DDII」は,魔洞戦 紀DDIから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが16以 上であるときには,(1)そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最 初から2となり,(2)神殿で祈ると「ゆうけんしのしそん じゅんくよ。 がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され,アイテム「くさのつゆ」\n及び「しろきのこ」が1つ増える,という動作機能を実行するゲームプ\nログラム及び/又はデータを包含するものである。 そうすると,上記(1)の点は,「勇士の紋章」の標準のゲーム内容であ ればレベル1からスタートするゲームキャラクタのレベル(乙A4の2・ 11枚目,乙A8の1・8頁)をレベル2からスタートできるようにす るものであり(乙A4の1・8枚目),上記(2)の点は,標準のゲーム内 容であれば金貨(GOLD)で支払わなければ取得できないアイテム(乙 A4の1・13枚目,乙A4の2・8枚目)を神殿で祈ることで取得で きるようにするものであって(乙A9・2頁,乙A10・3頁),いず れも新たな機能をゲームキャラクタに持たせるものであるから,これが\n「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」に当たることは明らかである。\nまた,上記(2)の点は,「勇士の紋章」の標準のゲームの内容であれば, 神殿で祈ると「あなたのたたかいが ぶじおわりますよう。あくまに わ ざわいを!」とのメッセージのみが表示される場面を,神殿で祈ると「ゆ\nうけんしのしそん じゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが 表示され,アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が1つ増えると\nいう場面とするものであるから,これが「場面の拡張」に当たることも 明らかである。 以上によれば,本件公知発明1の「勇士の紋章DDII」は,「標準ゲ ーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び/又はデータ」に加\nえて,「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面の拡張」を\n達成するためのゲームプログラム及び/又はデータ,すなわち,本件発 明A1の「拡張ゲームプログラムおよび/またはデータ」を包含するも のといえる。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
(ウ) 他方,被控訴人は,公知発明1における「所定のキー」に相当する「キ ャラクタ(じゅんく)のレベルが16以上であることを示す情報」とは, (1)魔洞戦紀DDIが装填されたことを示すデータ及び(2)キャラクタ(じ ゅんく)のレベルが16以上であるセーブデータである旨主張する。 そこで検討するに,証拠(甲A4の1,4の2,13の2)及び弁論 の全趣旨によれば,本件ゲームシステムA1において,まず,勇士の紋 章DDIIを装填し,次いで,「まどうせんきのAメンをいれてください」 というインストラクションに基づき,魔洞戦紀DDIを装填し,キャラ クタ「じゅんく」を選択した後,再度,勇士の紋章DDIIを装填した場 合には,勇士の紋章においてもキャラクタ「じゅんく」でプレイできる ことが認められる。 しかしながら,魔洞戦紀DDIを装填することにより当然に,本件発 明A1の「拡張ゲームプログラムおよび/またはデータ」に相当する, 本件公知発明1の「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面\nの拡張」を達成するためのゲームプログラム及び/又はデータと,標準 ゲームプログラム及び/又はデータの双方によって,ファミリーコンピ ュータが作動されるものではない。前記(ア)及び(イ)のとおり,本件公知 発明1の「標準ゲームプログラムおよび/またはデータと拡張ゲームプ ログラム及び/又はデータの双方によってファミリーコンピュータを作 動させ」るには,魔洞戦紀DDIから,キャラクタ(じゅんく)のレベ ルが16以上であるセーブデータを読み込むことが必要であり,かかる データを読み込んでいない場合には,上記のようにインストラクション に基づき魔洞戦紀DDIを装填するなどの作業をしたとしても,本件公 知発明1の「標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによって ファミリーコンピュータを作動させる」こととなる。 以上によれば,上記(1)のデータは,本件公知発明1の「拡張ゲームプ ログラムおよび/またはデータ」を作動させる条件であるとはいえない から,本件発明A1の「所定のキー」に相当する本件公知発明1の「キ ャラクタ(じゅんく)のレベルが16以上であることを示す情報」には, 上記(1)のデータは含まれないといえる。 したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 本件発明A1と本件公知発明1の対比 本件発明A1と本件公知発明1とを対比すると,以下の相違点が存在す ることが認められる。
(相違点1−1)
一の記憶媒体,二の記憶媒体が,本件発明A1は,「記憶媒体(ただし, セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」であるのに対し,本件公\n知発明1は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」である点。\n
(相違点1−2)
本件発明A1の「第1の記憶媒体」は,セーブデータを記憶可能な記憶\n媒体を除くから,「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し,本 件公知発明1では,魔洞戦紀DDIに包含される「所定のキー」が,魔洞 戦紀DDIに記憶されたセーブデータであって,魔洞戦紀DDIにセーブ されたキャラクタのレベルが21であることを示す情報である点。
ウ 相違点の容易想到性について
(ア) 本件公知発明1の技術思想
本件公知発明1の内容に加え,前記アに掲記の各証拠及び弁論の全趣 旨を総合すれば,(1)ディープダンジョン(DD)シリーズの後作「勇士 の紋章」は,前作「魔洞戦紀」の続編であって,両者は,魔洞戦紀にお いて,魔王が勇剣士に倒され平和を取り戻したものの,勇士の紋章にお いて,魔王が復活し,勇剣士が再び冒険するという一連のストーリーを 有するゲームであること,(2)「魔洞戦紀」の勇剣士のキャラクタを,「勇 士の紋章」に転送することにより,「魔洞戦紀」の「勇剣士」を,「勇 士の紋章」の「勇士」として復活させることができること,(3)「魔洞戦 紀」において,キャラクタのレベルが16以上であれば,レベル1から ではなく,レベル2のキャラクタとして「勇士の紋章」でプレイできる こと,(4)このような場合に,「魔洞戦紀」から転送されたレベル16以 上のキャラクタは,「勇士の紋章」においては「勇剣士の子孫」として 復活すること,(5)「魔洞戦紀」のキャラクタリストは,「魔洞戦紀」に おいて,特定のキャラクタでゲームをプレイしている途中で中断し,そ の後,中断した場面からゲームを再開してプレイするために,ディスク にセーブされたものと解されることが認められる。 上記認定事実によれば,本件公知発明1は,前作と後作との間でスト ーリーに連続性を持たせた上,後作のゲームにおいても,前作のゲーム のキャラクタでプレイしたり,前作のゲームのプレイ実績により,後作 のゲームのプレイを有利にしたりすることによって,前作のゲームをプ レイしたユーザに対して,続編である後作のゲームもプレイしたいとい う欲求を喚起し,これにより後作のゲームの購入を促すという技術思想 を有するものと認められる。
(イ) 相違点1−1について
前記(ア)のとおり,本件公知発明1は,キャラクタでプレイするゲーム において,セーブされたキャラクタを前作のゲームから後作のゲームに 転送するものであり,前作のゲームにおいて,プレイ途中でセーブして, なおかつ,キャラクタのレベルが16以上である場合に,後作のゲーム において,ゲームのプレイが有利になるという特典が与えられるもので ある。 そうすると,本件公知発明1は,少なくとも,前作において,ゲーム をプレイ途中でセーブするとともに,ゲームをある程度達成した,すな わち,前作のゲームにおいて,キャラクタのレベルが16以上となるま でプレイしたという実績があることが,後作においてプレイを有利にす るための必須の条件であり,「キャラクタ」,「プレイ実績」を示す情 報を前作の記憶媒体にセーブできることが本件公知発明1の前提であっ て,「キャラクタ」,「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体 を採用すると,前作のゲームにおける「キャラクタ」,「プレイ実績」 の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり,「前作のゲームのキャラ クタで,後作のゲームをプレイする」,「前作のキャラクタのレベルが 16以上であると,後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」 という本件公知発明1を実現することができなくなることは明らかであ る。 したがって,仮に,被控訴人の主張するとおり,ゲームプログラム及 び/又はデータを記憶する媒体としてCD−ROMを用いることが本件 特許Aの出願前において周知技術であり,また,同一タイトルのゲーム をCD−ROMやROMカセットに移植することが一般的に行われてい る事項であったとしても,本件公知発明1において,記憶媒体を,ゲー ムのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体(ただし,セ ーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に変更する動機付けはな\nく,そのような記憶媒体を採用することには,阻害要因がある。 以上のとおりであるから,本件公知発明1において,相違点1−1に 係る本件発明A1の構成とすることは,当業者が容易に想到し得たもの\nであるとは認められない。
(ウ) 相違点1−2について
前記(イ)と同様の理由により,本件公知発明1において,相違点1−2 に係る本件発明A1の構成を採用することは,動機付けを欠き,むしろ\n阻害要因があるというべきであるから,当業者が容易に想到し得たもの であるとは認められない。
(エ) 被控訴人の主張について
これに対し被控訴人は,相違点1−1及び1−2は,本件訂正Aによ り,「第1の記憶媒体」及び「第2の記憶媒体」から「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体」が除かれ,その結果,「所定のキー」からセーブ\nデータが除かれたこと(「除くクレーム」とされたこと)により生じた ものであることを前提として,除くクレームとする訂正により,形式的 に主引用発明との間に相違点が存在すると認められる場合は,(1)相違点 に係る構成によって,技術的観点から主引用発明と異なる作用効果が存\n在するか否かを検討し,(2)技術的意義が認められない場合には,実質的 な相違点とはいえず新規性が否定されると解すべきであり,(3)技術的意 義が認められた場合には,当業者において適宜なし得る設計事項に過ぎ ないか否かを検討し,設計事項に過ぎない場合には,進歩性が否定され ると解すべきであるところ,本件訂正Aは,シリーズ化された一連のゲ ームソフトを買い揃えていくことにより,豊富な内容のゲームを楽しむ\nことができるようにするという本件発明A1の課題との関係では,技術 的な解決手段を示したものとはいえず,技術的意義がないものであって, 本件発明A1の作用効果や技術的思想は,本件訂正Aの前後で変わらな いから,相違点1−1及び1−2は,実質的に相違点とはいえず,少な くとも,当業者が適宜なし得る設計事項である旨主張する。 しかしながら,前記(イ)及び(ウ)のとおり,本件公知発明1において, 相違点1−1及び1−2に係る本件発明A1の構成を採用することは,\n動機付けを欠き,むしろ阻害要因があるというべきものである。 また,本件発明A1において,「第1の記憶媒体」及び「第2の記憶 媒体」を「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすること\nは,前作のプレイ実績にかかわらず,後作において拡張ゲームプログラ ム及び/又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効 果を奏するものであって,技術的意義を有するものであることからする と,相違点1−1及び1−2は,実質的な相違点であるといえるし,当 業者が適宜なし得る設計事項であるとは認められない。 したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
(オ) 小括
以上のとおり,本件公知発明1において,相違点1−1及び1−2に 係る本件発明A1の構成とすることには,動機付けがなく,むしろ阻害\n要因があるため,当業者が容易に想到し得たこととは認められない。 したがって,本件発明A1は,当業者が本件公知発明1に基づき容易 に発明をすることができたものであるとは認められない。
・・・・
特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき 金銭の額に相当する額」については,平成10年法律第51号による改 正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭」と定められていたところ,「通常受けるべき金銭の額」では 侵害のし得になってしまうとして,同改正により「通常」の部分が削除 された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許 が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で,被許諾者が最 低保証額を支払い,当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの 実施料の返還を求めることができないなど様々な契約上の制約を受ける のが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し,技術 的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許 権侵害に当たるとされた場合には,侵害者が上記のような契約上の制約 を負わない。そして,上記のような特許法改正の経緯に照らせば,同項 に基づく損害の算定に当たっては,必ずしも当該特許権についての実施 許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく,特 許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,実施に対し受ける べき料率は,むしろ,通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろ うことを考慮すべきである。 したがって,実施に対し受けるべき料率は,(1)当該特許発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界に おける実施料の相場等も考慮に入れつつ,(2)当該特許発明自体の価値す なわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,(3)当 該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様,(4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に 現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。
(イ) 認定事実
a 本件特許Aについての実際の実施許諾契約の実施料率は,本件訴訟 に現れていない。 そして,証拠(乙A115,116,乙B28)及び弁論の全趣旨 によれば,以下の事実が認められる。
(a) 株式会社帝国データバンクが「知的財産の価値評価を踏まえた特 許等の活用の在り方に関する調査研究報告書〜知的財産(資産)価 値及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜(平成22年3月)」 (乙B28。本件調査報告書)を作成するに当たって行った,特許 権に関するロイヤルティ率情報のアンケート(以下「本件アンケー ト」という。)の結果を記載した表2−2には,技術分類を「家具,\nゲーム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は2.5%(最大値 4.5%,最小値0.5%,標準偏差1.5%)(件数14件)と 記載されている。
(b)本件調査報告書には,本件アンケート調査結果の回答及び集計に 当たっての前提条件について,(1)ライセンス・アウト(ライセンス を与える側)の立場での回答であること,(2)国内同業他社へのライ センスを想定していること,(3)通常実施権(ライセンス提供先を独 占的にする訳ではなく,複数の者とライセンスを行うことができる 形態)によるライセンスを想定していること,(4)正味販売高に対す る料率を想定していること,(5)特殊な事情(エンタイアマーケット バリュールール(特許技術が製品の一部に使われているだけだとし ても,侵害された部品を含む製品全体の単価に基づいて損害額を計 算するルール)によるロイヤルティ算定,契約相手の事情など)を 捨象したケースであること,(6)ロイヤルティ料率相場はカテゴリ選 択肢で回答であるが,集計時には各選択肢の中央値をロイヤルティ 料率として集計を行ったことが記載されている。
(C) 経済産業省知的財産政策室編の「ロイヤルティ料率データハンド ブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」(平 成22年8月31日発行)の「II 各国のロイヤルティ料率」には, (1)ロイヤルティ算定方式として最も広く採用されているのは,定率 方式であり,そのロイヤルティは,「対象製品の販売価格×ロイヤ ルティ料率」として算定されること,(2)販売価格の対象となるロイ ヤルティベースには,総販売価格,純販売価格(正味販売価格), 小売価格等が使用されるが,実務面では,純販売価格(正味販売価 格)が採用されることが比較的多いとされること,(3)純販売価格(正 味販売価格)は,総販売価格から一定の費用項目を控除した残額と して定義され,控除費用項目としては,一般的に,輸送費,保険料, 倉庫保管費用,リベート,包装梱包費等,販売地によって変動する 可能性のある費用項目が中心となるが,業界慣行や製品種類等によ\nって異なることが記載されている。
b 前記(1)アのとおり,本件発明A1は,ゲームプログラム及び/又は データを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシス テムを作動させる方法であって,上記記憶媒体は,少なくとも,所定 のゲームプログラム及び/又はデータと,所定のキーとを包含する第 1の記憶媒体と,所定の標準ゲームプログラム及び/又はデータに加 えて所定の拡張ゲームプログラム及び/又はデータを包含する第2の 記憶媒体とが準備され,上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填 されるとき,上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合 には,上記標準ゲームプログラム及び/又はデータと上記拡張ゲーム プログラム及び/又はデータの双方によってゲーム装置を作動させる ことにより,ユーザにとっては,一回の購入金額が適正なシリーズも のの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって,最終的に極めて豊富な 内容のゲームソフトを入手したのと同じになり,メーカにとっては,\n膨大な内容のゲームソフトを,ユーザが購入しやすい方法で提供でき\nるという効果をもたらすものである。 このように,本件発明A1は,ゲームシステム作動方法の発明であ り,その構成及び効果は上記のとおりであるところ,イ−9号方法等\nは本件発明A1の技術的範囲に属するものであり,イ−9号製品等は, ゲーム装置に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであって,\n本件発明A1の「第2の記憶媒体」に相当する,同発明を実施するた めに不可欠の物である。そして,前記(1)イのとおり,イ−9号製品等 は,本編ディスク(第1の記憶媒体)から所定のキーを読み込むこと により,アペンドディスク(第2の記憶媒体)に記録された標準のゲ ームプログラム及び/又はデータに加えて,拡張ゲームプログラム及 び/又はデータを作動させることができるものであるから,本件発明 A1は,イ−9号製品等にとって,相応の重要性を有するものといえ る。 また,家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作 動方法に関し,本件発明A1の上記技術についての代替技術が存在す ることはうかがわれない。
c(a) 前記bのとおり,本件発明A1は,イ−9号製品等に記録された 拡張ゲームプログラム及び/又はデータを作動するに当たり不可欠 な技術であるところ,家庭用ゲーム機本体に装着してゲームを楽し むゲームソフトにおけるゲームキャラクタのもつ機能\,場面,音響 が豊富であることは,通常,需要者の購入動機に影響を与えるもの といえる。 そして,被控訴人は,イ−9号製品等を販売するに当たり,製品 解説書(甲A5,7,8,10,11)において,MIXJOY機 能について紹介し,前作のディスク(本編ディスク)があると本作\n(アペンドディスク)とのMIXJOYを楽しむことができ,前作 のシナリオを本作のキャラクタでプレイしたり,前作では特定のキ ャラクタとのみ迎えることができたエンディングを全てのキャラク タと迎えることができたりする旨を説明している。 これらの事情を考慮すると,本件発明A1をイ−9号製品等に用 いることにより被控訴人の売上げ及び利益に貢献するものと認めら れる。
・・・
a 前記(イ)のとおり,本件訴訟において本件特許Aの実際の実施許諾 契約の実施料率は現れていないところ,本件特許Aの技術分野が属す る分野の近年の統計上の平均的な実施料率が,本件アンケート結果で は2.5%(最大値4.5%,最小値0.5%,標準偏差1.5%) であり,同実施料率は正味販売高に対する料率を想定したものである ことが認められる。そして,このことを踏まえた上,侵害品に係るゲ ームソフトにおいては,ゲームのキャラクタや内容,販売方法の工夫\n等が,その売り上げに大きく貢献していることは否定できないとはい え,本件発明A1に係る技術も,売上げの向上に相応の貢献をしてい ると認められることや,本件発明A1の代替となる技術は存在しない こと,控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど,本件訴訟に現れ た事情を考慮すると,特許権侵害をした者に対して事後的に定められ るべき,本件での実施に対し受けるべき料率(以下「本件実施料率A」 という。)は,消費税相当額を含む被控訴人の正味販売価格に対し, 3.0%を下らないものと認めるのが相当である。
b 被控訴人は,別紙1「販売開始日一覧表」記載の販売開始日から本\n件特許権Aの存続期間満了日までのイ−9号製品等の売上高(被控訴 人の卸売価格)が,別紙7「売上高(補正後)」の「売上高」欄記載 のとおりであると主張するところ,イ−9号製品等の売上高(被控訴 人の卸売価格)が上記金額を超えるものであることを認めるに足りる 証拠はない。そこで,同金額に消費税相当額(5%)を加えた金額を, 実施料算定の基礎となる価格とするのが相当である。 もっとも,前記(イ)c(C)のとおり,イ−9号製品等のうちには,本件 発明A1の「第2の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに,1\n個ないし5個の当該ゲームソフトと同一シリーズのゲームソ\フト(記 憶媒体)が含まれるパッケージ商品も存在するところ,これらのゲー ムソフトは,本件発明A1についての本件特許権Aを侵害するもので\nはなく,かつ,イ−9号製品等に含まれなくとも,単体で販売の対象 となる商品である。また,前記(イ)a(b)のとおり,本件調査報告書には, 本件アンケート調査結果の回答及び集計に当たっての前提条件につい て,特殊な事情(エンタイアマーケットバリュールール(特許技術が 製品の一部に使われているだけだとしても,侵害された部品を含む製 品全体の単価に基づいて損害額を計算するルール)によるロイヤルテ ィ算定,契約相手の事情など)を捨象したケースであることが記載さ れている。そうすると,侵害品以外のゲームソフトの価格に相当する\n部分については,本件実施料率Aを乗じるべき販売価格から控除する のが相当というべきであるから,イ−9号製品等の販売価格を侵害品 であるゲームソフトとそれ以外のゲームソ\フトとの合計数で除したも のをもって,本件実施料率Aを乗ずべき売上高とするのが相当である。 また,前記(イ)c(C)のとおり,イ−19及び23(2)号製品には,本件 発明A1の「第2の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに,「最\n強データ収録CD−ROM」やグッズが同梱されているものもあるが, 上記CD−ROMは,ゲームソフトで使用するデータ(キャラクタの\n能力値等が最大の状態のデータ)が記録されているに過ぎず,それら\nが単独で商品として流通するものではないから,当該製品の販売価格 全体をもって,本件実施料率Aを乗ずべき売上高とするのが相当であ る。 他方,イ−39号製品(「遥かなる時空の中で3十六夜記 プレミ アムBOX」(希望小売価格9800円))は,同日付で発売された イ−35号製品(「遥かなる時空の中で3十六夜記」(希望小売価格\n4980円))に対して,4820円高く価格が設定され,その製品 の相違は同梱グッズのみであって,イ−39号製品に含まれる同梱グ ッズの価格は,おおむね同製品の2分の1に相当するものといえるか ら,同製品の販売価格の2分の1を本件実施料率Aを乗ずべき売上高 とするのが相当である。 さらに,イ−40号製品(「遥かなる時空の中でプレミアムBOX コンプリート」)は,本件発明A1の「第2の記憶媒体」に該当する ゲームソフトのほかに,これと同一の「遥かなる時空の中でシリーズ」\nのゲームソフト5個が含まれるところ,同製品についても,イ−39\n号製品と同様に,同梱グッズの価格は,これと対応するゲームソフト\nの価格のおおむね2分の1に相当するものといえる。そうすると,同 製品の販売価格の12分の1をもって,本件実施料率Aを乗ずるべき 売上高とするのが相当である。
c 以上によれば,本件特許権Aの侵害について,特許法102条3項 により算定される損害額は,別紙10のとおり計算され,その合計額 は1億1667万3710円となる。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は,(1)本件発明A1及びA2は,イ号製品のユーザにおいて実 施されるゲームシステム作動方法であること,イ号製品のような本件特 許権Aの間接侵害を構成する製品の製造販売に関する特許権者の許諾は,\n当該製品がユーザに販売されることを当然の前提とすることなどから, 実施料率算定の基礎となるイ−9号製品等の売上高は,被控訴人の卸売 価格ではなく小売価格とすべきである,(2)イ−9号製品等に同梱される アイテムがある場合でも,イ号製品は,同梱されたアイテムを含む製品 全体で一個の商品(販売単位)であり,製品の販売等行為全体が一個の 特許権侵害を構成するから,イ−9号製品等の販売価格全体が本件実施\n料率Aに乗ずべき価格となる旨主張する。 しかしながら,上記(1)の点については,控訴人の主張を裏付けるに足 りる客観的な証拠はない。前記(イ)aのとおり,本件特許Aの技術分野が 属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率は,正味販売高に対する 料率を想定したものであることからすると,実施料算定の元となる売上 高は,被控訴人のイ−9号製品等の販売価格,すなわち卸売価格とする のが相当である。 上記(2)の点については,前記(ウ)bのとおり,イ−9号製品等のうち, 本件発明A1の「第2の記憶媒体」に該当するゲームソフト以外のゲー\nムソフトを含むものや,同梱されたグッズが,商品構\成や価格構成上,\n明らかにゲームソフトとは別の価値を有するもの,すなわち,別個の商\n品として扱われていると判断し得るものについては,これらのゲームソ\nフト及びグッズの価格に相当する金額を本件実施料率Aを乗ずべき価格 から控除するのが相当である。 控訴人の主張するその余の点も,前記(ウ)の判断を左右するものでは ない。
(オ) 被控訴人の主張について
被控訴人は,(1)実施料率算定の基礎となるべき正味販売価格に消費税 相当額は含まれない,(2)本件調査報告書によれば,「家具,ゲーム」の 技術分野には,「ビデオゲーム」のような全体の一部に特許発明が実施 されているもの以外に,「家具」,「カードゲーム,盤上ゲーム,ルー レットゲーム;小遊技動体を用いる室内用ゲーム」も含まれるため,本 件特許Aの実施料率は,上記実施料率の平均値(2.5%)より低くな る,(3)同梱グッズについても,別紙7「売上高(補正後)」記載のとお り,そのアイテム数に応じて売上高を補正すべきである,(4)本件発明A 1は,セーブデータを「所定のキー」とする方法,「拡張ゲームプログ ラム等」の一部を「所定のキー」とする方法,第2の記憶媒体に「拡張 ゲームプログラム等」のみを記憶する方法により,同発明と同様の作用 効果を奏しながら,同発明を回避することができる,(5)控訴人は,競業 者と特許クロスライセンス契約を締結し,「ライセンスなどの特許権の 有効活用を促進」するとしたプレスリリースを公開しており(乙A83 の1〜3),むしろ開放的ライセンスポリシーを採用している,(6)イ号 製品は,武将やステージを新規に追加するものというよりは,「違った 遊びを提供するという概念で開発」されたものであり,本編ディスクで はプレイできなかったモードを提供することが主眼となった製品であっ て,それ単体でも十分楽しめる内容である反面,MIXJOYをするこ\nとで可能となるのは,本編ディスクでプレイできたモードやシナリオを\nアペンドディスクでもプレイできるというものであり,MIXJOYを 行う場面は限定されている旨主張する。 しかしながら,上記(1)の点については,消費税相当額も被控訴人の販 売価格の一部としてそれに含まれているものであるから,損害額の算定 に当たって消費税相当額を控除すべき理由はない。 上記(2)の点については,前記(イ)a(a)のとおり,本件アンケート結果 を記載した,本件調査報告書の表2−2には,技術分類を「家具,ゲー\nム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は2.5%であり,件数は1 4件である旨が記載されているものの,アンケート回答者の保有する特 許の内容,特許の実施品について,具体的な記載はない。したがって, 本件調査報告書の記載からは,本件特許Aの実施料率が,上記実施料率 の平均値より低くなると認めることはできない。 上記(3)の点については,前記(イ)c(C)のとおり,イ−9号製品等に同梱 されているグッズは,本件発明A1の「第2の記憶媒体」に相当するゲ ームソフトの付属物というべきものであって,単独で商品として流通す\nるものではないから,イ−39及び40号製品に同梱されたグッズを除 き,当該製品の販売価格全体をもって,本件実施料率Aを乗ずべき売上 高とするのが相当である。
上記(4)の点については,i)前記(5)ウ(エ)のとおり,本件発明A1にお いて,「第1の記憶媒体」及び「第2の記憶媒体」を「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすることは,前作のプレイ実績にか\nかわらず,後作において拡張ゲームプログラム及び/又はデータによっ てゲームを楽しむことができるという技術的意義を有するものであり, セーブデータを「所定のキー」とする方法は,本件発明A1と同様の作 用効果を奏するものではなく,また,記憶媒体をセーブデータを記憶可 能なものにした場合は,大量の記憶容量を有し,安価で大量生産が可能\ なCD−ROM,DVD−ROM等の読み出し専用メモリーを用いるこ とができなくなること,ii)本件発明A1は,第1の記憶媒体に記憶され た「所定のキー」を読み込むだけで,第2の記憶媒体に記録された標準 ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによりゲーム装置を作動さ せるものであって,装置の作動中に第1の記憶媒体を入れ換え可能なも\nのであるが,「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とす る方法では,標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによるゲ ーム装置の作動中に,第1の記憶媒体を装填し続ける必要があること, iii)第2の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法 では,第2の記憶媒体単体で,標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプ ログラムによりゲーム装置を作動させることができないことから,これ らの方法が本件発明A1の代替技術であるとはいえない。
上記(5)の点については,たとえ,特許権者が開放的ライセンスポリシ ーを有しているとしても,そのことは,特許権侵害者に対して事後的に 定めるべき実施料率を下げる理由にはならないものというべきである。 上記(6)の点については,前記(イ)c(a)のとおり,本件発明A1により ゲームキャラクタのもつ機能,場面,音響が豊富になるという効果は,\n通常,需要者の購入動機に影響を与えるものであるといえ,イ−9号製 品等においても,MIXJOY機能により,前作のシナリオを本作のキ\nャラクタでプレイしたり,前作では特定のキャラクタとのみ迎えること ができたエンディングを全てのキャラクタと迎えることができたりする ものであって,被控訴人は製品解説書でかかる機能を紹介し,宣伝して\nいるものである。そうすると,本件発明A1は,これをイ−9号製品等 に用いることにより被控訴人の売上及び利益に相応の貢献をするものと 認められるものであって,イ−9号製品等が単体でも十分楽しめるもの\nか否かという点や,MIXJOYを行う場面が限定されているか否かと いう点は,上記判断を左右するものではない。 被控訴人の主張するその余の点も,前記(ウ)の判断を左右するもので はない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆判決本文
判決理由は、A、B事件にそれぞれ分けられています。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.10.18
平成29(ワ)44181 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月18日 東京地方裁判所
原告は,制御ルールのリストの例示である【図5】の「条件定義部」の 「受信者」欄に,「*@zzz.co.jp」が定められており,これはドメインを表\nすものであるから,「送信先」には電子メールアドレスのみならず,ドメ インを含むと主張する。 しかし,前記のとおり,本件明細書等1には,制御ルールに関し,「「条 件定義部」は,「発信者(送信元)」,「受信者(宛先)」,「その他条 件」から構成される。…「受信者(宛先)」には,メール送受信端末11\n0から取得する電子メールの宛先(To,Cc,Bcc)の電子メールア ドレス(受信者情報) が設定されている」(段落【0040】),「「発 信者(送信元)」,「受信者(宛先)」には,それぞれ電子メールアドレ スを複数設定することができ,アスタリスクなどのメタ文字(ワイルドカ ード)を使うことによって任意の文字列を表すこともできる」(段落【0\n041】)と記載されており,これらの記載によれば,上記「*@zzz.co.jp」 は,ドメインを意味するのではなく,「*」に任意の文字列を含み,ドメイ ン名を「zzz.co.jp」とする複数の電子メールアドレスを意味するという べきである。
原告は,「*@zzz.co.jp」がドメインを意味することは,複数の特許文献 (甲24,30〜32,乙15)などの記載からも裏付けられると主張す るが,特許請求の範囲や発明の詳細な説明において使用される言葉の意義 は各発明により異なることから,構成要件11D等の「送信先」の意義は\n本件特許に係る特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に基づいて 解釈されるべきである。本件明細書等1の「*@zzz.co.jp」がドメインを意 味すると解し得ないことは上記判示のとおりであり,原告の挙げる他の文 献等の記載は上記結論を左右するものではない。
(イ) 原告は,本件明細書等の段落【0061】及び【図4】のステップS4 02には,「受信者」の「宛先」単位で電子メールの分割をすることを記 載しているが「受信者」の「宛先」にはドメインも含まれると主張する。 しかし,段落【0061】には「各宛先(受信者)のそれぞれを単一の 宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する」と記載されているところ, 同エンベロープの生成を説明する【図12】には,送信先(受信者) の電 子メールアドレスとして設定されている「A」,「B」,「C」のそれぞ れを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成することが図示 されているのであるから,同段落の「各宛先(受信者)」とは電子メール アドレスを意味するというべきである。
(ウ) 原告は,本件明細書等1の段落【0003】に記載の従来技術である乙 15公報における「宛先」には「電子メールアドレス」又は「ドメイン」 であることが記載されており,本件発明1において分割する単位をドメイ ンとしてもこの従来技術の課題を解決することができると主張する。 そこで,乙15公報をみるに,その段落【0032】には,【図2】の 「項目203,205にあっては,アカウントを*として,ドメインのみ を指定するとした設定も可能である」と記載されているが,ここにいう項\n目203は送信メールの一時保留機能を利用する場合であって,一時保留\nせずに,即配信したいメールアドレスの即配信リストを設定する項目であ り,同図の項目205は,全ての送信保留中メールを本人(送信者)に配 送する場合であって,配送を希望しない送信保留中メールを本人(送信者) に送信しないメールアドレスの送信不要リストを設定する項目である(段 落【0030】)。【図2】
このように,項目203及び同205は即配信又は送信不要リストを設 定するためのものであるから,段落【0032】の趣旨は,一時保留せず に即配信したいメールアドレスの即配信リスト(項目203)や,送信保 留中メールを本人(送信者)に送信しないメールアドレスの送信不要リス ト(項目205)に,任意のドメイン名を有する複数のメールアドレスを 一括して設定することも可能であることを述べたものにすぎず,電子メー\nルの「宛先」にドメインが含まれることを示すものということはできない。 そうすると,同段落の記載をもって従来技術である乙15公報における 「宛先」に「ドメイン」が含まれると解することはできないので,原告の 上記主張は前提において採用し得ないというべきである。
(エ) 原告は,電子メールをドメイン単位で分割する場合でも本件発明1の課 題を解決し得ると主張する。 しかし,電子メールをドメイン単位で分割するとなると,同一ドメイン の複数の電子メールのうち,一つのみの送出を保留すべきような場合に上 記課題を解決し得ないことは,前記判示のとおりである。 原告は,本件発明1はいかなる場合でも電子メールの送出制御を効率的 に行うことを課題と設定しているのではないと主張するが,本件発明1が その課題を解決し得ない構成を含むとは考え難く,特許請求の範囲及び本\n件明細書等1の記載に照らしても,「送信先」にドメインを含むとは解し 得ないことも,前記判示のとおりである。
エ 以上のとおり,構成要件11D等における「送信先」は「電子メールアド\nレス」のみを指し,「ドメイン」を含まないと解することが相当である。
・・・・
特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書 記載の従来技術との比較から認定されるべきであるところ(知財高裁平成2 7年(ネ)第10014号同28年3月25日判決),本件明細書等1には, 従来技術の「複数の送信先が記載された電子メールに対しては,誤送信の可 能性がある送信先が1つでも含まれていれば,その他の送信先に対するメー\nル送信までもが保留,取り消しがされることとなる」(段落【0004】) という課題を解決するため,電子メールに設定された複数の送信先を個々の 送信先に分割し,記憶手段に記憶されている制御ルール等に従って,電子メ ールの送出に係る制御内容を決定し,決定された制御内容に従って電子メー ルの送信制御を行うなどの構成を備えることにより,「ユーザによる電子メ\nールの誤送信を低減可能とすると共に,宛先に応じた電子メールの送出制御\nを行うことにより効率よく電子メールを送出させることができる」(段落【0 008】)などの効果を奏するものである。
イ 原告は,本件特許1の特許メモ(乙9)などを根拠に,本件発明1の本質 的部分は,「送出制御内容を,電子メールの送信元と送信先とに対応付けた 制御ルールと,分割された電子メールの送信先と送信元とに従って,分割さ れた送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」(構\n成要件11E)にあると主張する。 しかし,本件発明1の従来技術として挙げられているのは乙15公報であ り,本件明細書等1に記載されている課題は「複数の送信先が記載された電 子メールに対しては,誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれ\nば,その他の送信先に対するメール送信までもが保留,取り消しがされるこ ととなる」というものであるところ,同課題を解決するためには,電子メー ルに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割した上で,制 御ルールを適用することが不可欠である。そうすると,構成要件11D等に\n係る構成は本件発明1の本質的部分というべきである。\n 原告は,特許メモ(乙9)の記載を根拠とするが,同メモには,本件特許 の出願時の複数の公知文献に本件発明1に係る構成が記載されているかど\nうかが記載されているにすぎず,本件発明1の従来技術として挙げられた乙 15公報との対比がされているものではなく,また,本件発明1の本質的部 分の所在を検討するものでもないので,同メモに基づいて,本件発明1の本 質的部分が構成要件11Eに係る構\成にあるということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.10.17
平成30(行ケ)10142 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月10日 知的財産高等裁判所(4部)
これに対し原告は,(1)引用例には,リソース情報をコア情報として含む\nべき「スケジューリング割当て」によるスケジューリング(初期送信のた めのスケジューリング)については何ら記載がないから,引用発明の「受 信成否情報の受信に基づく第2のデバイスへの第1のD2Dリンクのデー タの再送又は次のデータの送信」が「為され」る「サブフレーム」(サブ フレームml+2d+c(1303))は,再送のスケジューリングに関 する情報によってスケジューリングされているサブフレームにすぎず,ス ケジューリング割当てによってスケジュールされている「第3のサブフレ ーム」に該当しないこと,(2)引用例には,引用発明において,「D2Dオ ペレーションのためのスケジューリング割当て」が基地局とデバイスとの 間のD2Cオペレーションとして送受信されることが記載されているにす ぎず,「D2Dオペレーションのためのスケジューリング割当て」が,デ バイス間のD2Dオペレーションとして送受信されることについては,開 示も示唆もないことによれば,引用発明が本件構成E−1の「第3のサブ\nフレームが前記第1のサブフレームにおける前記D2Dオペレーションの ためのスケジューリング割当てによってスケジュールされ」るとの構成を\n備えているといえない旨主張する。
しかしながら,上記(1)の点については,第3のサブフレームにおけるD 2Dオペレーションのためのスケジューリングは,初期送信のためのスケ ジューリング及び再送のためのスケジューリングの双方が含まれることは 前記(1)ア(イ)のとおりであるから,その前提において理由がない。 また,上記(2)の点については,本件補正発明の特許請求の範囲(請求項 1)の記載中には,「D2Dオペレーションのためのスケジューリング割 当て」が基地局とデバイスとの間のD2Cオペレーションとして送受信さ れることを除外する記載はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.10.17
平成31(行ケ)10056 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月8日 知的財産高等裁判所
これに対し原告は,(1)甲1には,複数の売り注文の中で最も高い売り注 文価格の売り注文が約定されたことを注文情報生成部の約定検知手段が検 知する構成が開示されていること(【0146】,【0147】,図7A,\n図19),(2)甲2の記載事項([0085],図6,図7)によれば,甲2 発明の1は,1回限りのイフダンオーダー(繰り返さないLOCK注文) を前提として,「相場価格が上昇する状況」にあると予想した投資家が,\n上昇する相場に追従するように,従前のものより所定価格だけ増加させた イフダンオーダーを生成することを繰り返すことで,利益を得ることを可 能にした発明であるといえること,(3)甲1発明は,「複数の売り注文のう ちいずれかの売り注文が約定されたことを検知すると,同じ売り注文価格 の情報を含む売り注文情報を再度生成するものであって,相場価格が一定 の範囲内で変動する状況で利益を得ることを目的とする発明」であり,甲 2発明の1の従来技術に相当するものであるから,甲2発明の1は,甲1 発明に相当する発明に甲2発明の1を適用することを示唆していること, (4)甲1発明と甲2発明の1とは,金融商品の取引に関する技術分野に属し ている点で技術分野が共通すること,「顧客に利益をもたらす装置を提供 する」という目的(課題)が共通し,イフダンオーダーを利用することに よって機会喪失のリスクを低減するという機能においても共通することに\n照らすと,甲1及び甲2に接した当業者は,甲1発明における「約定検知 手段が,複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定 されたことを検知」した場合の「注文情報生成手段」の動作について,甲 2発明の1の「従前のものより所定価格だけ増加させたイフダンオーダー を生成する」という動作を適用する動機付けがあるから,甲1発明におい て,「約定検知手段が,複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の 売り注文が約定されたことを検知」した場合に「複数の売り注文のうち最 も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を 含む売り注文情報」を生成する動作とする構成(相違点1−1に係る本件\n発明1の構成)とすることを容易に想到することができたものである旨主\n張する。
しかしながら,上記(1)の点については,原告の指摘する甲1の記載は, 第一〜第五の注文情報群181s21〜181s25のうち,いずれの第 二注文(181u21〜181u25)が約定した場合においても,当該 第二注文を含む注文情報群を再度生成することを示したものであり,特に 最も高い売り注文価格の売り注文が約定した場合(181u25)に着目 した処理を記載したものではないし,前述のとおり,甲1には,本件明細 書記載の「シフト機能」(【0078】)に関する記載や示唆はない。\n 上記(2)及び(3)の点については,甲2には,甲2発明の1が,1回限りの イフダンオーダー(繰り返さないLOCK注文)を前提として,「相場価 格が上昇する状況」にあると予想した投資家が,上昇する相場に追従する\nように,従前のものより所定価格だけ増加させたイフダンオーダーを生成 することを繰り返すことで,利益を得ることを可能にした発明であること\nの開示があるものといえるが,他方で,甲2には,複数のイフダンオーダ ーによるLOCK処理を行うことについての記載も示唆もないことに照ら すと,甲1発明が甲2発明の1の従来技術に相当するものであるとはいえ ないし,甲2発明の1が,甲1発明に相当する発明に甲2発明の1を適用 することを示唆しているということもできない。また,甲1には,複数の イフダンオーダー(複数の売り注文)のうち,「最も高い売り注文価格の 売り注文」が約定されたことを検知すると,注文情報生成手段が「前記複 数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い 売り注文価格の情報を含む売り注文情報」を生成するという構成(構\成要 件1H)についての記載も示唆もない。
そうすると,甲1及び甲2に接した当業者においては,甲1発明と甲2 発明の1が,金融商品の取引に関する技術分野に属している点で技術分野 が共通し,イフダンオーダーを利用することにより,利便性を高めるなど の機能面においても共通すること(上記(4))を勘案しても,甲1発明にお ける「約定検知手段が,複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の 売り注文が約定されたことを検知」した場合の「注文情報生成手段」の動 作について,甲2発明の1における「インクリメントオプション」に係る 構成あるいは原告のいう「従前のものより所定価格だけ増加させたイフダ\nンオーダーを生成する」という動作を適用する動機付けがあるものと認め ることはできない。また,甲2発明の1の上記構成は,相違点1−1に係\nる本件発明1の構成全部を含むものではないから,甲1発明に甲2発明の\n1の上記構成を組み合わせることを試みたとしても,当業者が,甲1発明\nにおいて,相違点1−1に係る本件発明1の構成とすることを容易に想到\nすることができたものと認めることはできない。
◆判決本文
関連の侵害訴訟はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.10.11
平成30(ワ)13400 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 東京地方裁判所(40部)
均等論の本質的部分(第1要件)
本件発明1と被告製品との相違点は,本件発明1では,係止爪がサブアー ム部の上端部に位置するものであるのに対し,被告製品では,爪部の上部に フック部が設けられ,爪部がサブアーム部の上端部に位置するとはいえない 点にあるところ,被告は,原告の均等侵害の主張に対し,第4要件を充足す ることは争わないものの,その余の要件の充足性を争うので,以下検討する。
(2) 第1要件(非本質的部分)について
ア 均等侵害が成立するための第1要件にいう本質的部分とは,当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分であり,このような特許発明の本質的部分を対象\n製品等が共通に備えていると認められる場合には,相違部分は本質的部分 ではないと解される。
イ 原告は,本件発明1のうち,挿入力の増加の防止のための構成がその本\n質的部分であるとした上で,被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから,被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず,同製品は本件発明1の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし,本件発明1は,特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて,従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり,他方, 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると,挿入力が強 くなり作業性が悪化することから,挿入力は弱いままで,抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる(本件明細書等の 段落【0009】,【0013】〜【0015】)。そうすると,本件発 明1の本質的部分は,挿入力は弱いままで,抜け力を強くするための構成\nにあり,従来技術との対比でいうと,特に抜け力の強化のための構成が重\n要であるというべきである。 そして,本件発明1は,上記課題の解決のため,(1)メインアーム部と, メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し,(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり,(3)サブアーム部の上端部を,上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより,取付孔 への挿入性の向上を図るとともに,アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が 加わったときは,係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる(特許請求の範囲,本件明細書等の段\n落【0017】,【0029】,【0032】,【0033】,【003 6】,【0037】)。
ウ 他方,被告製品においては,サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ,当該フック部と車体のルーフ孔の距離が0.3mmであると認め られるから(乙13),抜け方向に荷重が加わった際に,フック部は0. 3mm程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり,爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして,被告製品における抜け力に関し,被告が実施した実験結果(乙 5)によれば,本件発明1の実施品の抜け力は186Nであるのに対し, 被告製品の抜け力は,215.8N,227N,271N,295Nであ り,最小でも約30N,最大で約110Nの差が生じたことが認められる。 また,被告が実施した,被告製品のコの字型部材(サンプル(1))と,被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの(サンプル(2))を用 いた実験結果(乙14)によれば,前者の抜け力の平均値は227.60 N,後者の抜け力の平均値は73.51N(いずれも10回実施)であり, フック部を備えたコの字型部材の方が,抜け力において約150N大きい ことが認められる。
前記のとおり,被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ,これに上記の各実験結果を併せて考慮すると,被告製品は, 本件発明1の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ,そ の抜け力の大きさは,同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり,少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。 なお,原告は,乙14実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が\nあるとして,乙14実験の信用性を争うが,サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり,上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり,乙14実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて10回ずつ実験を行っているところ,数値にば らつきはあるものの,サンプル(1)は200N以上であり,サンプル(2)は概 ね60〜100程度であり,全体的に100N以上の差が生じていること に照らすと,その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり,抜け力の増大という課題を解決するための構成は本\n件発明1の本質的部分ということができるところ,本件発明1はこの課題 をアンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し,被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ,そうす ると,被告製品は本件発明1と異なる構成により上記課題を解決している\nということができる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2019.10.10
平成31(行ケ)10062 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年10月9日 知的財産高等裁判所(1部)
前記認定事実(2)ア,ウによれば,原告は,昭和63年頃から原告商品の販売を開 始し,30年以上継続して販売していることがうかがわれ,その販売数は,平成1 2年及び平成15年から平成25年の12年間で約75万個に上っていること,平 成14年から平成18年にかけて生活産業新聞に75回にわたり,原告商品の広告が掲載されたほか,各種カタログ,チラシやアマゾンのウェブサイト等にも原告商 品の広告が掲載されたことが認められる。 しかしながら,原告が販売する原告商品の包装箱には,「らくらく椅子」,「らくら く正座椅子」又は「らくらく二段正座椅子」との標章が付されており,「らくらく」 の文字のみが単独で使用されたものはない(前記認定事実(2)イ)。 また,原告商品の広告等には,その多くにおいて「らくらく正座椅子」との標章が 付されており,「らくらく万能座椅子」,「らくらく万能\正座椅子」,「らくらく正座いす」,「らくらく椅子」の標章が付されたものもあるものの,「らくらく」の文字のみ が単独で使用されたものはない(前記認定事実(2)ウ)。 そうすると,原告の主張する引用商標「らくらく」が,本件商標の登録出願時及び 登録査定時において,原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されて\nいたものとは認められないというべきである。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,「らくらく正座椅子」は,「らくらく」と「正座椅子」とを結合した構\n成から成る結合商標であるが,「らくらく」の文字部分のみが商品の出所識別標識と して強く支配的な印象を与えるものであるから,この部分のみを原告の使用商標と して抽出すべきであると主張する。 しかし,「らくらく」は,「楽」であることを意味する語であり,足の痺れや膝頭の 痛みが緩和され,楽に正座をすることができるとの原告商品の機能を表\している。 また,「正座椅子」は,正座用の椅子を意味する語であり,原告商品の用途又は商品 の種類そのものを表している。よって,いずれも,それぞれの文字部分のみによっ\nて出所識別標識としての機能を発揮するとはいえない。\nそうすると,原告商品の表示から,「らくらく」の文字部分のみが商品の出所識別\n標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず,「らくらく」の文字部分のみ を要部として抽出することはできない。よって,原告の主張は採用できない。
イ また,原告は,「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出しているとの取引の実情に照らしても,「らくらく」の部分のみを原告の使用商標として抽出すべき であるとも主張する。 しかし,原告商品が「らくらく」と略称されているなどして,「らくらく正座椅子」 から「らくらく」を抽出していることを認めるに足りる証拠はない。原告は,取引者 である原告と被告が,「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出していることを 前提に本件審判請求やそれ以前の折衝を行っていたことをもって,「らくらく」を抽 出する取引の実情があるとも主張するが,本件審判手続における当事者の主張内容 をもって,「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出していることが取引の実情 であると認めることはできず,原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.10. 4
平成30(ワ)11399 商標権移転登録手続等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年9月19日 東京地方裁判所
(1) 争点(本件契約の締結の有無)について
ア 原告は,被告との間で,本件契約(平成15年7月の当初使用許諾契約 及び平成26年4月の本件修正合意)が締結されたと主張し,ダミアーニ 社及び原告の代表者であったA(甲12,16),セールスマネージャーで\nあったD(甲13)は,これに沿う陳述をする。 しかし,被告は,本件契約が締結された事実はないと主張し,被告代表\n者は,これに沿う陳述をするところ(乙1),原告が主張する本件契約(当 初使用許諾契約及び本件修正合意)の内容は,商標権者である被告が,商 標権者でない原告に対し,原告が真の権利者であって,被告の本件各商標 登録は原告の条件付き許諾によるものにすぎないことを認め(予備的請求\nに関係する部分),また,条件成就後には本件各商標権の移転登録手続をす ることを約するという(主位的請求に関係する部分),いずれも本件各登録 商標に係る商標権者である被告の立場を覆すような,商標権者でない原告 に一方的に有利な内容になっているものといえる。しかして,そのような 当事者双方にとって通常の取引とは質的に異なるような重大な内容である にもかかわらず,これらの内容が当事者間で合意され本件契約が締結され たことを具体的に裏付けるに足りるような,契約書,覚書その他の客観的 な証拠は見当たらない。
イ また,原告が本件各登録商標の真の権利者たる地位にあることを基礎付ける事由や,被告が本件各登録商標に係る商標権者である立場を覆すよう な合意を原告との間であえて行うことの合理的理由はいずれも見当たらな い。
すなわち,原告が主張するような,平成15年7月当時の日本国内にお いて,標章「ROCCA」がダミアーニ・グループやロッカ社のものとし て著名あるいは周知であったことや,日本国内及び日本国外において,ダ ミアーニ・グループが標章「ROCCA」に関して何らかの権利を有して いたことを具体的に認めるに足りる客観的証拠はない。そうすると,上記 認定事実にも照らし,平成15年7月頃における被告は,ダミアーニ・グ ループの商品を中心に取り扱うこととしたことからAに店舗名の相談をし たにすぎず,被告において,原告との間で,Aからの店舗名としての提案 を受け入れること以上に,「ROCCA」の使用許諾の契約(当初使用許諾 契約)まで締結する必要性は何ら認められないものであって,本件の事実 経過において,被告が,我が国における商標権者でない原告を,あえて「R OCCA」の真の権利者と扱ってその使用許諾を受ける合理的な理由はな い。また,原告においても,平成15年7月に当初使用許諾契約が締結さ れたとする以上,「ROCCA」に係る権利の確保には相当の関心を払って いたとみられるにもかかわらず,それから約2年半が経過して,被告が本 件登録商標1の商標登録出願をした平成18年2月までに至っても,我が国において「ROCCA」に係る商標登録出願をするなど真の権利者とし てその権利を確保する行動を何らとっていない。 この点,ダミアーニ社は,平成21年7月に至り,本件登録商標1につ き本件審判請求を行っているが,「ROCCA」が国際的著名商標であり本 件登録商標1は商標法4条1項11号,同15号,又は同19号に違反し て登録されたものであるという同社の主張は,平成22年2月の本件審決 により否定されているものである。原告は,その後,当事者間で交渉が重 ねられた旨をいうが,上記認定事実によれば,原告と被告との間には,平 成20年以降,ほぼ取引がない状況が続いていたのであって,平成26年 4月の時点で,上記のような,商標権者でない原告が一方的に有利な内容 になっている本件修正合意を被告との間で締結し得るような地位ないし立 場にあったことを客観的に示すものは何ら見当たらない。
ウ さらに,上記認定事実に照らし,被告の行動は,本件各登録商標に係る 商標権者である立場を覆すような本件修正合意とは相容れないものである。 すなわち,前記のように,本件修正合意は,商標権者である被告が,商 標権者でない原告に対し,原告が真の権利者であって,被告の本件各商標 登録は原告の条件付き許諾によるものにすぎないことを認め(予備的請求\nに関係する部分),また,条件成就後には本件各商標権の移転登録手続をす ることを約するという(主位的請求に関係する部分)ものであるところ, 被告は,「ROCCA」を店舗名として採用した後,本件登録商標1の商標 登録を受けたことを皮切りに,「ROCCA」が国際的著名商標であるなど のダミアーニ社の本件審判請求に対して争い,その前後にも本件登録商標 2ないし9の商標登録を受けるなど,「ROCCA」に係る権利を獲得,保 持する態度を一貫してとっており,上記のような内容の本件修正合意は, このような被告の行動とは全く相容れない。 それにもかかわらず,被告が原告との間で本件修正合意を行ったことが 認められるには,これにより被告において「ROCCA」に係る権利を手 放すことに見合う相応の利益があるなど,何らかの相当な理由がなければ ならないというべきである。しかし,本件修正合意の相手方である原告と の関係を見ても,平成20年には原告と被告との取引は終了しており,そ の後,原告が本件修正合意を締結したと主張する平成26年4月23日を 境に継続的な取引が再開した事実はなく,原告と被告との取引上の関係は, 原告が平成27年と平成28年に年に1回の被告の展示会に出展した程度 のものであり,被告に何らかの上記のような相応の利益があったとは認め られないものであって,その他,本件全証拠に照らしても,被告が従前の 態度を翻してまで原告との間で本件修正合意を行う相当な理由は認められ ないところである。
エ 以上によれば,原告の上記主張やこれに沿うA(甲12,16),D(甲 13)の上記各陳述は採用できず,その他,本件全証拠を精査しても,原 告の上記主張を認めるに足りるものはない。 よって,原告と被告との間の本件契約の締結の事実を認めることはでき ず,本件修正合意に係る前記第2の2(3)に基づく,本件各商標権の移転 登録手続請求(主位的請求)は理由がなく,また,本件修正合意に係る前 記2(1)及び(2)に基づく,原状回復請求としての,本件各商標登録の抹 消登録手続請求も理由がないことに帰する。
(2) 原告の主張について
なお,原告は,本件契約(当初使用許諾契約及び本件修正合意)につい て契約書,覚書等の書面が交わされていない事情について縷々主張し,A は,平成15年7月当時,日本国内においてダミアーニ・グループが「R OCCA」に関する何らかの権利を有していたかのように陳述する(甲1 2,16)ので,以下,これらの点につき補足的に検討を加える。 ア 原告は,本件契約(当初使用許諾契約及び本件修正合意)について書面 が交わされていないことにつき,ダミアーニ・グループがロッカ社の買収 を予定していたことや(当初使用許諾契約),当初使用許諾契約を締結した\n原告の意に反し,被告が自身を権利者として本件登録商標1の設定登録を 受けたこと(本件修正合意)などの,本件契約締結に至る経緯に照らして 口頭で合意されたものである旨主張する。 しかし,原告が主張する契約締結に至る経緯をみても,事柄の性質上, それらをもって,本件契約が口頭で合意された理由を合理的に説明するに 足りるまでの事情ということは困難である。かえって,原告が,「ROCC A」はロッカ社の国際的著名商標であり,当初使用許諾契約が締結された 当時,ダミアーニ・グループがロッカ社の買収を予定していたというので\nあれば,ダミアーニ・グループにとって「ROCCA」は重要な標章であ ったといえるから,当初使用許諾契約について,原告がその契約内容を書 面で客観的に残していないことは不自然である。また,原告が,当初使用 許諾契約を締結した原告の意に反し,被告が自身を権利者として本件登録 商標1の商標登録を受けたことが本件修正合意に至る発端であるというの であれば,その後も,本件修正合意に至るまでの間に,ダミアーニ社と被 告との間では,本件登録商標1の商標登録の有効性が争われ,本件審決後 も長年にわたり合意に至らず交渉が重ねてられてきたという以上,少なく とも本件修正合意に際しては,再び紛争が起こらないように書面で合意内 容を明らかにしておくことが自然であり,口頭で合意したということは考 え難い。
なお,原告は,原告と被告との間の他の取引契約も口頭で合意されてい る旨もいうが,仮に商品の発注,納品等の取引に係る契約において書面が 交わされていないとしても,前記のように,本件契約(当初使用許諾契約 及び本件修正合意)は,当事者双方にとって通常の取引とは質的に異なる ような重大な内容であるものであって,契約の性質・内容が異なるもので あるから,原告の上記指摘は,上記判断を直ちに左右するものとはいえな い。
イ Aは,その陳述書(甲12,16)において,平成15年7月当時,ダ ミアーニ・グループはロッカ社を買収すべく株式の過半数を有していたこ とから,Aがロッカ社の代表者と交渉し,日本において「ROCCA」を\n使用することの許諾を得ていたものであって,ダミアーニ・グループは, 平成15年には「ROCCA\CALDERONI」の商標登録(商標登 録第4639648号)を得ていたなど,あたかも,同年7月当時,日本 国内においてAが「ROCCA」に関する何らかの権利を有していたかの ように述べる。 しかし,ダミアーニ・グループが実際にロッカ社を買収したのは,約5 年後のことである上,かえって,上記「ROCCA\CALDERONI」 の商標については,これと矛盾する別の証拠が存するものである。すなわ ち,証拠(甲7)によれば,本件審判請求の審判手続において,ダミアー ニ社は,平成20年9月にダミアーニ・グループがロッカ社を買収したこ とにより,ロッカ社から上記「ROCCA\CALDERONI」の商標 を譲り受け,本件審判請求と同日である平成21年7月21日付けで特許 庁に「商標権移転登録申請書」を提出した旨を主張したこと,本件審決に\nおいて,同商標に係る商標権は,同日付けで「特定承継による本件の移転」 によって,ロッカ社からダミアーニ社に移転された旨の認定がなされてい ることがそれぞれ認められる。そうすると,ダミアーニ・グループが平成 15年には「ROCCA\CALDERONI」の商標登録(商標登録第 4639648号)を得ていたなどAの上記陳述の該当部分は,このよう な,客観的な記載といえる本件審決(甲7)の上記部分と明らかに矛盾す るものというべきであるから,Aの上記陳述内容は,全体として信用性が 乏しいものと評価せざるを得ないものである。
2019.10. 3
平成30(行ケ)10108 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月2日 知的財産高等裁判所
(ア) 技術分野の関連性について 引用発明は,「医療系廃棄物,家庭廃棄物,産業廃棄物等に含まれる有機系廃棄物 を高温高圧の蒸気を用いて処理し,処理後には,処理した廃棄物と液体とを分離し た状態で取出せる…液体分離回収方法」に関するものである(甲 1【0001】)。 他方,甲2技術は,「重金属を含有する土壌や焼却灰」のような「廃棄物」の「水 熱処理」を行うものである(甲2【0004】,【0005】)。 そうすると,両者の技術分野はいずれも水熱反応を利用した廃棄物の処理に関す るものであり,互いに関連するものといえる。
(イ) 課題の共通性について
a 引用発明は,一台の装置だけで,廃棄物を高温高圧の蒸気を用いて安全に処 理できるとともに,その処理に連続して処理された廃棄物と液体とを簡単な操作で 分離して回収できるようにするとの課題を解決することを目的とするものであるが (甲1【0004】),引用例1には,処理の対象となる有機系廃棄物として,「合成 樹脂製の注射器,血液の付着したガーゼ,紙おむつ,手術した内臓等の医療関係機 関等から廃棄された医療系廃棄物,生ごみ,プラスチック等の合成樹脂製容器等の 一般家庭から廃棄された家庭系廃棄物,食品加工廃棄物,農水産廃棄物,各種工業 製品廃棄物,下水汚泥等の産業廃棄物等に含まれる有機系廃棄物」(甲1【0035】)が挙げられている。 特開2006−55761号公報(甲3)には「有機廃棄物には,生物に有害な重 金属類を含んでいることが多く重金属類を不溶化あるいは除去する必要がある。」 (【0003】)との記載,特開2011−31180号公報(甲4)には「本発明に よれば,土壌,肥料,水,焼却灰,家畜の糞尿,工場排水,汚泥,下水等に含まれる 重金属,ダイオキシン,硝酸塩,及び農薬を効果的に分解し,無害化することができ る。」(【0011】)との記載,特開2004−24969号公報(甲5)には「重金属は,これらの都市ゴミや産業廃棄物の中に混じっていることが多い。そのため, 都市ゴミや産業廃棄物を焼却すると,燃焼排ガスに同伴して飛散する煤塵や焼却灰 中に,都市ゴミや産業廃棄物中の揮発性金属化合物に由来する重金属,例えば,亜 鉛,鉛,ニッケル,カドミウム,銅などの重金属,…が含まれている。このように, 重金属の拡散による弊害が大きな社会問題として指摘されている…」(【0003】),「従来,廃棄物の焼却時に発生する煤塵や焼却灰の処分には,飛散を防止するため に加湿処理をおこなったり,セメントやアスファルトで固形化して埋め立てに用い るか又は海洋投棄するなどの方法が採られてきた。海洋投棄する場合には,セメン トなどによって固定化するとともに,重金属が溶出しないように処理することが法 律に定められているが,これらの方法によって煤塵や焼却灰からの有害金属の溶出 を完全に抑制するには種々の問題がある。すなわち,上記の方法では,煤塵や焼却 灰中に含まれる重金属は可溶態のままであるため,煤塵や焼却灰を固形化しても重 金属が経時的に溶出し,二次公害が発生する恐れが残っている。…」(【0004】) との記載,特開2006−167509号公報(甲6)には「この発明は食品加工工 程で廃棄される魚介類残渣,鶏糞・豚糞,牛糞などの家畜の糞尿,野菜屑などの農産 廃棄物,更には生ゴミなどの動植物性食品残渣といった有機系廃棄物の処理システ ムに関する」(【0001】),「…魚介類残渣にはカドミウム,水銀,砒素当の重金属類が少なからず含まれており,これが発酵後の堆肥に含まれていると,事実上農作 物に使用することができなくなってしまう。…」(【0005】)との記載,特開20 08−155179号公報(甲7)には「…工場汚泥,工事汚泥,又は下水汚泥,生 活排水汚泥等の汚泥,並びに家畜糞尿等の汚水を含む被処理物…の熱処理方法であ って,…被処理物中の有機物の炭化及び/又は熱分解を介して,該被処理物中の重 金属等の異物を分離貯留するとともに,…ことを特徴とした環境に優しい被処理物 の熱処理方法。」(【請求項1】)との記載がある。 これらの記載によれば,産業廃棄物に限らず,土壌,肥料,水,焼却灰,家畜の糞 尿,工場排水,工場や工事の汚泥,下水や生活排水汚泥,都市ゴミ,魚介類残渣等の 種々の廃棄物が有機系廃棄物とともに重金属を含んでいること,廃棄物に含まれる 重金属を放置すると,堆肥等として使用することもできなくなるばかりか,その拡 散による弊害が大きな社会問題として指摘されていること,廃棄物の焼却時に発生 する煤塵や焼却灰の処分には,飛散を防止するため,加湿処理,固形化,あるいは海 洋投棄が行われてきたが,海洋投棄する場合には,セメントなどによって固定化す るとともに,重金属が溶出しないように処理することが法律に定められていること は,本願出願時において周知の事項であったものと認められる。 そうすると,引用発明において処理の対象となる「有機系廃棄物」にも,重金属が 含まれ得ること,及びその溶出を防止することは,引用発明が属する技術分野にお いて,当業者が当然に考慮すべき課題であると認められ,処理後の廃棄物と液体と の分離に焦点を当てた引用例1にそのことが明示的に記載されていなくても,引用 発明の自明の課題として内在しているものというべきである。
b 他方,甲2技術は,金属を含有する廃棄物の水熱処理の際に発生する重金属 を含有する排水を,排水処理設備を設けることなく,処理することができる廃棄物 の処理方法および処理装置を提供することを目的とするものであり(【0005】), シリカとカルシウム化合物とを反応させ,トバモライトなどの結晶性カルシウムシ リケートを発生させることによって,「重金属は,内部に閉じこめられ(固定化され),外部への溶出が抑制されるようになる」(【0031】)というものであるから,水熱 処理後の重金属含有排水からの重金属の溶出を防止することを課題とするものであ る。
c そうすると,引用発明と甲2技術とは,廃棄物中の重金属の溶出を防止する という点で,解決すべき課題が共通するものといえる。
(ウ) 作用・機能の共通性について\n
引用発明は,閉鎖空間を有する密閉容器内に有機系の廃棄物を収容して,固形状 の有機系廃棄物を破砕しつつ撹拌し,高温高圧の蒸気を噴出して炭化させるもので あるところ,水熱処理の条件として,「温度180〜250℃,圧力15〜35at m程度(判決注:1.5〜3.5MPa)」(【0040】)との開示がある。 一方,甲2技術は,水熱処理によりトバモライトなどの結晶性カルシウムシリケ ートを形成させるものであるところ,水熱処理の条件として,「130〜300℃程 度での飽和蒸気(判決注:同温度での飽和蒸気圧を計算すると0.28〜9.41M Pa)」(【0034】)との開示がある。 そうすると,引用発明では有機物が炭化されるのに対し,甲2技術では,トバモ ライト結晶が形成されるのであって,水熱反応によって起こる現象が異なるから, 引用発明に甲2技術を組み合わせる動機となるような,作用・機能の共通性は認め\nられない。もっとも,水熱処理における温度・圧力の条件自体は重複している以上, 組合せを阻害する要因となるものでもないと解される。
(エ) 以上によれば,引用発明と甲2技術とは,廃棄物の水熱処理という技術分野 において関連性があり,廃棄物から重金属の溶出を防止するという課題が共通して いるということができる。
イ 引用発明への甲2技術の適用
しかしながら,仮に引用発明に甲2技術を適用しても,甲2には,前記有機系廃 棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はないから,\n相違点2’に係る「前記重金属類が閉じ込められた 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶(トバモ ライト)構造」が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されると\nの構成には至らない。\nこの点につき,本件審決は,引用発明に甲2技術が適用されれば,「前記重金属類 が閉じ込められた 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶(トバモライト)構造」が「前記有機系廃\n棄物の固形物上に」いくらかでも「層」として「形成」されて,重金属の溶出抑制を 図ることができるものになる旨判断し,被告は,生成した造粒物の表面全体をトバ\nモライト結晶層で覆うことになるのは当業者が十分に予\測し得ると主張する。しか しながら,特開2002−320952号公報(甲8)にトバモライト生成によっ て汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても(【0028】,図1。図1\nは別紙甲8図面目録のとおり。),かかる記載のみをもって,トバモライト構造が「前\n記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されることが周知技術であった とは認められず,被告の主張を裏付ける証拠はないから,引用発明1に甲2技術を 適用して相違点2’に係る本願発明の構成に至るということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.10. 3
平成30(行ケ)10161 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月2日 知的財産高等裁判所
原告は,引用発明の「押されたか確認」する構成が本願発明の「選択状態検出手\n段」に該当しないと主張する。 そこで検討するに,引用発明の従来の技術(【0002】以下)に係る引用例の記 載は,前記(1)イのとおりであり,このうち【0003】においては,同別紙の図2に 基づき,引用発明のリモコン6が,ベッド本体2の上半身部の昇降動作させるアク チュエータ4にケーブル5によって接続され,アクチュエータ4の動作を操作,制 御するものであることが記載されている。このように,引用例には,リモコン6が アクチュエータ4の動作を操作,制御するものであり,アクチュエータ4がリモコ ン6によって操作,制御されるものであることが記載されている。 また,同別紙の図2は,引用例の実施例の説明においても参照されている(【00 10】【0011】)ところ,そこでいう,リモコン6の任意のキー6aが押されたか の確認とは,アクチュエータ4の動作の操作,制御の内容を構成するものであるか\nら,上記確認動作を行うものはリモコン6であり,そうすると,リモコン6は「押さ れたか確認」(STEP1)するための構成を有しているものということができる。\nそして,本願発明のベッド操作装置における「選択状態検出手段」とは,操作入力 手段が選択されている状態を検出するための構成であることからすれば,本願発明\nの「選択状態検出手段」と引用発明の「押されたか確認」(STEP1)する手段と が異なることはない。よって,原告の主張は理由がないというべきである。
ウ 構成要件E(選択解除検出手段)について\n
(ア) 引用発明の「STEP2」の「リモコン6のキー6aが押された時は,その 後,リモコン6のキー6aが解放されたか確認」することは,本願発明の「前記選択 状態検出手段により選択された状態が解除されたことを検出する」ことに相当し, 引用発明の当該「解放されたか確認」する構成は,本願発明の「選択解除検出手段」\n(構成要件E)に相当する。\n(イ) 本願発明と引用発明との対比判断の誤りをいう原告の主張について 原告は,引用発明の当該「解放されたか確認」する構成は本願発明の「選択解除検\n出手段」に該当しないと主張する。 しかしながら,リモコン6は,前記イ(ウ)で述べたのと同様の理由により,「解放 されたか確認」する構成を有しているということができる。\nしたがって,本願発明の「選択解除検出手段」と引用発明の「解放されたか確認」 (STEP2)する手段とが異なることはなく,原告の主張は理由がない。
エ 構成要件F(遷移手段)について\n
(ア) 引用発明の「キー6aが解放されず押し続けられている場合は,解放され るまで待機し,リモコン6のキー6aが解放され,さらに任意のキー6aを押した ときに,アクチュエータ4を起動する(STEP3)」構成においては,電源を投入\nした後,STEP2で「キー6aが解放され」るまでの間は,本願発明の「待機状 態」に相当する。 そして,引用発明は,「キー6aが解放され」た後に,任意のキー6aを押せばア クチュエータ4を起動できる状態,すなわち,ベッドの操作が可能な状態になるか\nら,キー6aの解放の前後で,「待機状態」から「操作可能状態」に遷移するものと\nいうことができる。 その上で,本願発明の「遷移手段」が,「待機状態」から「操作可能状態」に遷移\nすることを手段として記載したものといえることを踏まえると,引用発明は,キー 6aの解放の前後で,「待機状態」から「操作可能状態」に遷移しているといえるか\nら,引用発明の「リモコン6」は,「遷移手段」に相当する構成も当然に備えている\nということができる。
以上によれば,引用発明の「リモコン6」は,「リモコン6のキー6aが解放され」 たときに,「リモコン6」を待機状態から操作可能状態に遷移させているといえると\nころ,引用発明の「リモコン6のキー6aが解放され」たときは,本願発明の「前記 選択解除検出手段により選択された状態が解除されたことを検出したとき」に相当 し,引用発明の「リモコン6のキー6aが解放され」たときに「リモコン6」を待機 状態から操作可能状態に遷移させる構\成は,本願発明の「前記選択解除検出手段に より選択された状態が解除されたことを検出したときに,前記ベッド操作装置を前 記待機状態から,操作可能状態に遷移させる遷移手段」(構\成要件F)に相当する。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.10. 2
平成28(ワ)12296 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月10日 大阪地方裁判所
まず,被告が経費として主張する製造委託費,検査費等は,いずれ も侵害者である被告において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められるから,被告の利益額を算 定するに当たり,上記販売金額からこれらの経費の金額を控除すべきである。
b そして,乙53,56ないし61及び弁論の全趣旨によれば,製造 委託費(樹脂やプレートの材料代,プレートの組付費用を含み,金型の作成費用は 含まない。),検査費等として,別紙「被告の損害論における主張」の「被告の経 費額」欄記載の経費を支出したと認められる。
c 原告らは,被告主張の仕入価格には高すぎるなどの疑問があると主 張して,被告主張の経費のうち「製造委託費」の金額を争っている。 しかし,この主張は特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利 益の額の算定の問題に関連する主張であるが,そもそもその利益の額(限界利益の 額)の主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきであるから(知財高裁令和 元年6月7日判決・最高裁ウェブサイト),そのような観点から検討すると,原告 らは原告製品の製造販売に係る経費と対比をするのみで,被告製品の製造販売に係 る経費について具体的な立証をしているわけではない。 他方,被告製品の製造委託先は,被告と資本関係にあるわけではなく(乙62, 弁論の全趣旨),被告の主張する製品1個当たりの製造委託費は,別紙「被告主張 の被告製品1個当たりの経費額」の「製造委託費(材料費込)」欄記載のとおりで あるところ,その金額には一定の裏付け(乙56ないし61)がある。したがって, 原告らの上記指摘によって前記認定は左右されず,下記(ウ)で認定する金額を超え る利益が被告に生じていたことを認めることはできない。
(ウ) 被告の利益額
以上によれば,被告が本件特許権の侵害行為により受けた利益の額は,別 紙「被告の損害論における主張」の「被告の限界利益」欄記載のとおり,合計(中 略)円と認められる。
イ 推定覆滅事由の有無
(ア) 特許法102条2項における推定の覆滅については,侵害者が主張立 証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たると解され,例えば,(1)特許権者と侵害者の業務 態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),(2)市場における競合品の存在,
(3)侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),(4)侵害品の性能(機能\,デザイン 等特許発明以外の特徴)などの事情について,考慮することができるものと解され る(前掲知財高裁令和元年6月7日判決)。
(イ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 原告扶桑産業について(甲1,33) 原告扶桑産業は,資本金の額を2500万円とする会社であり,その従 業員数は30名程度である。そして,原告扶桑産業は,店装用備品等の企画,製造 販売,陳列器具及び店舗什器関連備品等の製造販売等を事業品目とし,全国スーパ ー量販店備品卸売業者,全国インテリア装飾・店装業者等を取引先としている。そ して,原告製品については,被告や他の企業に対して卸売販売され,そこを通じて 小売量販店に販売された(量販店の各店舗に設置された)ほか,原告扶桑産業から 直接,株式会社サンリオの直営店等の量販店に販売されることもあった。
b 被告について(乙1,53ないし55,65ないし66の5)
(a) 被告は,資本金の額を1億円とする会社であり,その従業員数は 3000人程度で,平成28年度の売上高は1220億円(グループ全体で346 0億円)であり,平成20年から東北楽天ゴールデンイーグルスのメインスポンサ ーとなっている。そして,被告は,生活用品の企画,製造,販売を事業内容として おり,販売している商品は,LED照明,家電,調理用品,日用品,収納用品,ハ ードオフィス・資材等多岐に渡っており,被告のこれらの商品は全国のホームセン ターで販売されている。
(b) 被告は,量販店等の店舗向けに,什器・備品を単体で販売するの ではなく,内装工事を含め,店舗のあらゆるスペースをデザイン・プロデュースし, 店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行っている。 そして,被告は,販売する什器について,500頁を超えるカタログ(乙1,5 4)を作成しており,そこに掲載されている什器は,カードケースを含むシステム 什器だけでなく,内装・棚下照明,陳列用什器,インフォメーション器具,販促用 品,オフィス家具,運営サポート用品及び照明・演出用品といったように,多岐に 渡っている。
(c) 被告が顧客との間で上記(b)の取引をする場合の流れは,次のと おりである。すなわち,まず顧客から要望についてヒアリングをした上で,それを もとに現地調査をする。その後,顧客から建築平面図等を取得し,什器の配置を検 討し,顧客と打合せをした上で,什器配置図等を作成するとともに,コストをシミ ュレーションする。そして,顧客の要望に応じた什器・オプションアイテムを提案 し,納品内容を確定した上で,現場への納品や施工の手配を行う。
(d) 被告が平成25年12月5日,ある株式会社に対して発行した見 積書(乙55)では,取引金額が合計(中略)万円(税抜)とされたが,そのうち カードケースの代金額は(中略)円(個数は合計(中略)個)であった。
(e) 平成26年の被告製品の販売金額は,合計(中略)円であったが, その大半((中略)円)はカードケースと他の店舗用品とを組み合わせて販売され るいわゆるバンドル取引によるものであった。
c 原告扶桑産業と被告との間の取引
(a) 被告は,遅くとも平成24年1月以降,原告扶桑産業から原告製 品を購入しており,同月から平成25年11月までの原告製品の販売数量は,次の とおりであった。
・・・・
(b) 上記(a)のうち平成25年の原告製品4(ただし,QPCII−65 を除く。)の販売数量・販売金額は次のとおりであったほか,平成26年ないし平 成28年の原告製品(ただし,QPCII−65を除く。)の販売数量・販売金額は, 次のとおりであった(乙78の2)。
・・・・
(ウ) 被告の主張について
a まず,被告は被告製品1,4,6及び10については,原告製品に 相当するものがないことを指摘している。 しかし,上記各被告製品は,原告製品と色やサイズが異なるだけであり,原告扶 桑産業が販売している他の色やサイズの製品が購入されなかったとまで認めること はできないし,原告扶桑産業が販売していた製品をみる限り,原告扶桑産業が被告 製品と同じ色やサイズの製品を製造し,販売することができなかったと認めること もできない。 したがって,被告の上記主張は推定覆滅事由とならない。
b 次に,被告は取引の実情として,被告製品の販売方法や,被告によ る販売力・営業努力・企業規模・ブランドイメージを理由とする推定覆滅を主張す る。
(a)(1) 前記認定のとおり,被告が販売している什器は多岐に渡ってお り,また量販店等の店舗向けに,什器・備品を単体で販売するのではなく,内装工 事を含め,店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行って いた。そして,前記認定事実によれば,被告製品は,その大半が他の店舗用品と組 み合わせて販売されるいわゆるバンドル取引によって販売されていた。 しかも,前記認定事実によれば,そのようなバンドル取引の取引額に占めるカー ドケースである被告製品の販売額はわずかであったと認められる。 このような被告製品に係る取引の実情によれば,被告製品の需要者の大半は,カ ードケースである被告製品に殊更に注目して被告製品を購入したというよりも,他 の店舗用品と組み合わせて購入できる利便性や,内装工事を含めて店舗全体又は売 り場全体の什器・備品を総合的に購入することができるという被告の販売体制に魅 力を感じて,被告と取引をするに至り,その取引の一環として被告製品を購入した と認めるのが相当である。
(2) 原告らの主張について
原告らは,被告がドン・キホーテの店舗内装を受注するに当たり, ドン・キホーテから原告製品を使用するよう指示されたため,原告扶桑産業と原告 製品の取引をするようになったとか,バンドル取引においても原告製品を組み込む 需要があり,被告がその需要に応え,顧客との取引を維持するために原告製品を侵 害品である被告製品に置き換えたなどと主張する。 確かに,被告は現在でも,原告扶桑産業から原告製品を購入しているから,本件 発明の技術的範囲に属する製品を購入し,エンドユーザーにこれを販売する一定の 需要があったというべきである。 しかし,原告らが主張する原告扶桑産業との取引開始の経緯や,被告が本件特許 のライセンスを求めたことについては,これを認めるに足りる証拠はないし,被告 が,被告製品のモデルチェンジをして,本件特許権の侵害とならないカードケース を販売するようになった後,被告のバンドル取引による売上げが減ったとの事情も 認められない。 以上の事情に加え,前記認定の被告製品の取引の実情を踏まえると,被告が顧客 との取引を維持するために原告製品を侵害品である被告製品に置き換えたとまで認 めることはできず,原告らの上記主張は採用できない。
(3) そうすると,被告主張の事情は,侵害者である被告が得た利益 と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を相当程度,阻害す る事情といえる。
(b) また,被告の企業規模や販売する製品の多様性は前記認定のとお りであり,被告が被告製品を販売するに当たり,被告自身の販売力や企業規模,ブ ランドイメージか需要者に与えた影響も小さくないものというべきである。 したがって,この事情も,上記(a)の事情と相まって,侵害者である被告が得た利 益と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を一定程度,阻害 する事情といえる。
(c) なお,被告はその他に自身の営業努力も推定覆滅事由として主張 するが,被告製品に関する事実関係が明らかではなく,事業者は,製品の製造,販 売に当たり,製品の利便性について工夫し,営業努力を行うのが通常であることを 踏まえると,推定覆滅事由として考慮すべきとまでいうことはできない。
c 被告は代替品・競合品(乙67ないし72)の存在を指摘している。 しかし,推定覆滅事由として考慮する競合品といえるためには,市場において侵 害品と競合関係に立つ製品であることを要するものと解される(前掲知財高裁令和 元年6月7日判決)。このような観点から被告主張の製品を検討すると,被告が指 摘する製品には,その具体的構成や使用方法が判然としないものも含まれているほ\nか,カードケースが上保持部と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本\n的部分を備えたものと認めることもできないから,被告指摘の製品を代替品ないし 競合品ということはできない。また,被告指摘の製品の販売時期等も不明である。 したがって,被告の上記指摘によって推定が覆滅されるとはいえない。
d 被告は,乙73ないし77の先行技術等の存在を指摘して,被告製 品の販売に対して本件発明の技術的意義が寄与する程度は低いということを主張す る。 しかし,被告が指摘する乙73ないし77はいずれも,カードケースが上保持部 と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本的部分を備えたものと認める\nことはできない。また,被告が指摘する乙77は,表示板支持棒の先端に表\示板が 取り付けられているものの,その取り付け方法は,指示棒の先端に平板部分を設け, その下面に突設されたピンに表示板を保持するというものであり(乙77の【考案\nの詳細な説明】の【0021】),本件発明の構成とは大きく異なっている。それ\nだけでなく,被告製品が販売されていた時期に,本件発明の作用効果の一部を奏す るとされる技術があったとしても,それだけで直ちに,原告扶桑産業において,本 件特許の全構成を備えた被告製品の販売による利益に相当する損害を被ったことが\n否定されるとはいえない。 したがって,被告の主張の技術的観点からの主張は採用できない。
e 以上より,本件では前記b(a)及び(b)記載の事情を推定覆滅事由と して考慮すべきところ,前記認定・判示の事情を踏まえると,6割の限度で推定が 覆滅されると認めるのが相当である。 この点に関し,被告は顧客が原告らに注文して原告製品を購入するという行動に 出たという可能性は皆無であったなどとして,推定覆滅率を99.09%とすべき\n旨主張する。 確かに,被告が原告扶桑産業から原告製品を購入すべき義務を負っていたという 事情はうかがえないから,被告が原告製品以外のカードケースを販売すること自体 は自由にできたことと認められる。 しかし,他方で,被告は遅くとも平成24年1月以降,原告製品を購入し,量販 店等のエンドユーザーに対して販売しており,以前原告製品を購入したことのある エンドユーザーがバンドル取引において原告製品を組み込むことを希望する可能性\nも否定できない。また,前記認定のとおり,被告製品の販売を開始した平成25年 2月以降も,原告製品の購入を完全にやめたわけではなく,量販店等のエンドユー ザーへの販売もされていたことが推認されるから,被告において原告製品を購入し, これをエンドユーザーに販売する必要性が全くなかったとまで認めることはできな い。むしろ,従前の経緯を踏まえると,被告が本件特許の侵害品を販売しなければ, 原告扶桑産業から原告製品を購入し続け,原告扶桑産業が利益を得ていた可能性も\n一定程度認められるものというべきである。 したがって,被告が主張するように99.09%もの推定覆滅を認めることは相 当でない。
f 他に共有者がいることによる控除(推定覆滅)
(a) 被告は,特許法102条2項に基づく原告扶桑産業の損害は,同 項に基づき算定される逸失利益の2分の1にとどまると主張する。 しかし,特許権の共有者は,それぞれ,原則として他の共有者の同意を得ないで その特許発明の実施をすることができるものの(特許法73条2項),その価値の 全てを独占するものではないことに鑑みると,特許法102条2項に基づく損害額 の推定を受けるに当たり,共有者は,原則としてその実施の程度に応じてその逸失 利益額を推定されると解するのが相当であり,共有持分の割合を基準に共有者各自 の逸失利益額を推定すべきものではない。本件においては,前記(1)オで検討したと おり,原告製品を製造して被告に販売するという実施による利益は原告扶桑産業に 帰属し,原告ソーグは,これに伴って金員を得ていたにすぎないから,原告扶桑産\n業の損害額を算定するに当たり,特許法102条2項に基づく利益額の算定から, 共有持分の割合に応じて2分の1を控除(推定覆滅)すべき理由はない。 しかしながら,原告ソーグについては,被告製品の販売により,特許法102条\n3項の実施料相当額の損害を観念し得ることは既に述べたとおりであり,この場合 に,特許権の共有者の一部(原告扶桑産業)が同条2項により侵害者に対し損害賠 償請求権を行使するに当たっては,同項に基づく損害額の推定は,不実施に係る他 の共有者(原告ソーグ)の同条3項に基づく実施料相当額(共有持分の割合により\n取得する。)の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である(知財高裁平成30 年11月20日判決・最高裁ウェブページ)。
(b) そこで,原告ソーグが被告に対して請求することができる特許法\n102条3項に基づく実施料相当損害金の額について検討する。 この点について,被告は原告らの間で支払われていた差益をもとに実施料率を算 定すべきと主張するが,原告らが指摘する差益は特許権の共有者間で支払われてい るものであり,その具体的内容や法的位置付けは判然としない(なお,原告らは訴 状において原告製品の原材料の売買による差益と主張していた。)から,この金額 を実施料相当損害金の額を算定するのに用いることは相当でない。 そこで,本件では業界における実施料の相場を考慮に入れつつ,相当な実施料率 を認定するのが相当である。 被告はそれを前提としつつも,本件発明の寄与度や被告による販売力等を考慮す ると,原告ソーグの共有持分(2分の1)に係る相当な実施料率は0.025%で\nあると主張するが,推定覆滅事由に関する前記判示によれば,本件発明の寄与度を 考慮するのは相当でない。そして,プラスチック製品(イニシャル・ペイメント条 件無し)の平成4年度から平成10年度までの実施料率の統計データによると,最 頻値は1%,中央値は3%,平均値は3.9%であること(乙83),本件発明の 構成によるとカードケースの使用者の操作性等が相当向上すると認められること,\n前記認定のとおり,被告による被告製品の売上には被告の販売力やブランドイメー ジ等が大きく影響したと認められること,その他本件に現れた事情に加え,さらに は特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,実施に対し受けるべき料 率は,通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと(前掲知財高裁令和 元年6月7日判決参照)をも考慮すると,本件で相当な実施料率は5%と認めるべ きであり,原告ソーグの特許法102条3項に基づく損害は(中略)円(計算式:\n被告製品の売上額(中略)円×5%×1/2(共有持分の割合))となる。
(c) そして,原告ソーグについて特許法102条3項により算定した\n(中略)円を,原告扶桑産業との関係では,前記eの推定覆滅に加え,さらに控 除(覆滅)すべきことになる。
ウ したがって,原告扶桑産業の特許法102条2項に基づく損害額は(中 略)円(計算式:(中略)円×4割(推定覆滅後)−(中略)円)と認められる。 なお,原告扶桑産業は特許法102条1項に基づく損害の主張もしているが,原 告ら主張の原告らの利益額は(中略)円であるところ,特許法102条1項ただし 書の「販売することができないとする事情」として考慮される事情は,同条2項の 推定覆滅事由として考慮される事情と変わるものではなく(前掲知財高裁平成27 年11月29日判決参照),本件では前記判示に照らすと,原告らの利益について 6割の限度で「販売することができないとする事情」があったと認めるのが相当で ある。そうすると,原告ら主張の利益額について立証されているかを検討するまで もなく,同条1項に基づく損害額が前記認定の同条2項に基づく損害額を下回るも のであることは明らかである。
エ 原告扶桑産業は,原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起 等を委任したところ,被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は(中 略)万円と認めるのが相当であり,原告扶桑産業の損害額は合計(中略)円となる。
(3) 原告ソーグの損害額\n
原告ソーグの特許法102条3項に基づく損害額は,上記認定のとおり,(中\n略)円と認められる。 そして,原告ソーグは,原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起等\nを委任したところ,被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は(中 略)万円と認めるのが相当であり,原告ソーグの損害額は合計(中略)円となる。\n
4 以上より,原告らの請求は,それぞれ主文第1項及び第2項に掲げる限度で 理由があるから,その限度で認容し,その余の請求はいずれも理由がないから,棄 却することとして,主文のとおり判決する。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2019.10. 2
平成31(行ケ)10036 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
(5)以上の次第で,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア Kは,原告から本件商標の使用許諾を受け,平成28年1月頃から「アンドホーム」との名称を用いて,現場監督ができるもう一人の者とともに,建築等の事業を開始した。(甲19,58)
イ Kは,平成28年4月7日,注文者1との間で,建物の建築工事を内容 とする工事請負契約1を締結し,同年9月20日頃,建物を完成させた。 かかる契約の締結の際,Kは,注文者1との間で,「アンドホーム」を請 負業者とする工事請負契約書1(請負代金額合計1302万3192円) を作成して,注文者1に交付した。(甲58,60,70)
ウ また,Kは,工事請負契約1に関して,土地を探すところから協力し, 少なくとも平成28年3月2日頃から同年5月14日頃にかけて,建物の デザインや設計についても注文者1と打ち合わせを複数回にわたって行 い,金銭面を含めて注文者1の要望を建築工事に反映させた。かかる打ち 合わせの際,Kは,「アンドホーム資金計画表」との標題が付された建築\n費用合計代金(3300万円台から3600万円台の金額である。)及び その内訳等を示す資金計画表(甲30,31,33から35,38,4\n3,45)や,建物の平面図や立面図が記載された建築図面を,打ち合わ せを踏まえた修正を加えつつ,複数回にわたり,注文者1に示すなどし た。上記資金計画表のうち,作成日を平成28年3月23日以降とするもの\nについては,その右下に「◎土地契約時は土地手付け現金100万円+印 紙代…をご準備下さい。」,「◎建物契約時は建物手付け現金10万円+ 印紙代1万円…をご持参で当社にお越し下さい。」,「◎土地決済時に建 物着手金・上棟金として,1000万円を当社にお振り込み頂きま す。」,「◎最終の建物お引き渡し時に,残金を現金もしくはお振り込み 頂きます。」などと記載されている。 (甲29から38,40,43,45,58,62)
エ Kは,平成28年4月24日,注文者3との間で,建物の建築工事を内 容とする工事請負契約3を締結し,同年10月頃,建物を完成させた。か かる契約の締結の際,Kと注文者3は,「アンドホーム」を請負業者とす る工事請負契約書3(請負代金額合計1241万3270円)を作成して 注文者3に交付した。(甲56,58,71)
オ また,Kは,工事請負契約3に関し,ある程度土地が決まっている段階 で関与し始めて,少なくとも平成28年3月30日頃から同年5月29日 頃にかけて,建物のデザインや設計についても注文者3と打ち合わせを複 数回にわたって行い,金銭面を含めて注文者3の要望を建築工事に反映さ せた。 かかる打ち合わせの際,Kは,「アンドホーム資金計画表」との標題が\n付された建築費用合計代金(2600万円台から2700万円台の金額で ある。)及びその内訳等を示す資金計画表(甲51,52)や建築図面\nを,打ち合わせを踏まえた修正を加えつつ,複数回にわたり,注文者3に 示すなどした。 (甲51,52,56,58,66,71)
カ Kは,工事請負契約1及び3に関して,東昇技建に対し,地盤の調査を 依頼して,これを行わせた上で,その調査結果を注文者1及び3に説明し た。(甲19,50,58,62,64,66,69) キ Kは,平成28年6月9日頃に株式会社シンプルハウスを設立し,「ア ンドホーム」との名称の使用をやめて,同月15日には工事契約1にかか る建築確認申請の工事施工者を,同社へと変更した。(甲19,58,5\n9,60)
2 取消事由2(Kによる本件商標の使用についての判断の誤り)について 原告は,Kが,前記1(5)カのとおり東昇技建に依頼して地盤の調査を行い, 同ウ及びオ記載の本件資金計画表を注文者1及び3に交付したことが商標法2\n条3項8号に該当し,「地質の調査」の役務について,本件商標を使用した (商標法50条2項)と主張するので,この点について検討する。 (1) まず,Kが,取消対象役務のひとつである「地質の調査」を提供したか否 かについてみると,Kは,前記1(5)カのとおり,工事請負契約1及び3に関 して,東昇技建に依頼して地盤調査を行うなどしている。 そして,前記1(5)イ及びエのとおり,Kは,「アンドホーム」の名称にて 工事請負契約1及び3を締結しているところ,これらの契約の前後に注文者 らに対して示した本件資金計画表において地盤改良工事費用の中に地盤調査\n費用が含まれており(前記1(3)イ参照),当該費用を含めた建築費用合計代 金の全額をKに支払うべきこととされて,現実に注文者らに対応したのは主 としてKであったことなどに照らすと,Kは,工事請負契約1及び3の締結 とともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものと 認められる。 そうすると,Kが東昇技建に依頼して行った地盤調査は,Kが注文者1及 び3から請け負った債務の履行としてされたものであるといえるから,Kが 「地質の調査」を提供したと認められる。
(2) 次に,商標法2条3項8号の該当性についてみる。
本件では,Kが「地質の調査」の役務を提供することは,本件資金計画表\nの「地盤改良工事費用」「地盤調査の結果により工事費用が変動いたしま す。」などとの記載に表れており,本件資金計画表\は,上記役務に対応して 作成された見積書としての書面であるといえるから,上記役務に関する「取 引書類」に当たる。そうすると,前記1⑸ウ及びオのとおり,Kが,本件資 金計画表に,本件商標を付して,その作成日付頃(平成28年3月2日頃か\nら同年5月29日頃),それぞれ注文者1及び3に交付した行為は,商標法 2条3項8号所定の使用に該当する。
(3)これに対し,被告は,Kが本件商標を使用して工事請負契約1及び3を請 け負った後,実際に建築工事を開始した時点では,「シンプルハウス」へと 屋号を変更していたことなどをもって,取消対象役務を「アンドホーム」の 名称にて提供していないと主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,Kは,工事請負契約1及び3の締結と ともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものであ るところ,Kは,これらの契約に関して,平成28年3月2日頃から同年5 月29日頃にかけて,本件資金計画表を,注文者1及び3に交付しているか\nら,当該交付の時点で「アンドホーム」との標章に対する業務上の信用が発 生したといえる。その後,Kが,その事業について「シンプルハウス」との 名称に変更したとしても,かかる信用が,直ちに保護に値しなくなるもので はない。また,少なくとも工事請負契約3に係る地盤調査は,屋号変更前で ある同年5月25日に行われたことが明らかである。 したがって,Kは,「アンドホーム」との標章を取消対象役務のひとつで ある「地質の調査」について使用したといえる。
(4) また,被告は,Kによる本件商標の使用が名目的な使用であると主張す る。しかしながら,不使用取消に言及する被告から原告に対する連絡は平成 29年3月24日付けであって,Kが「アンドホーム」との標章を使用した 平成28年1月から同年6月頃までの期間よりも相当遅い時期であること (甲15)や,前記認定のKによる本件商標の使用態様に照らすと,Kによ る本件商標の使用が名目的な使用であるとまでは認められず,被告の主張は 採用できない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2019.10. 1
平成31(行ケ)10005 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
本件審決は,引用発明に引用文献2〜5及び参考文献1記載の技術(同技術に乙 3文献記載の技術を併せて,以下「被告主張周知技術」という。)を適用することに より,本件補正発明に想到し得ると判断していることから,引用発明に被告主張周 知技術を適用する動機付けの有無について検討する。
ア 引用発明
前記2(1)のとおり,引用文献1には,「近年,コンテンツマネジメントシステム (以下,CMS(Content Management System)という) によりウェブアプリケーションとして公開するコンテンツを構築し,管理すること\nが行われている(例えば,特許文献1参照)。ところで,近年,ネイティブアプリケ ーションをダウンロードしてインストールすることができるスマートフォンが普及 している。スマートフォンのユーザは,ネイティブアプリケーションをインストー ルする場合,アプリケーションを提供する所定のアプリケーションサーバにアクセ スし,所望のネイティブアプリケーションを検索する。しかしながら,CMSによ って構築されるウェブアプリケーションは,ウェブサイトとして構\築されるため, 検索サイトの検索結果として表示されることがあるものの,アプリケーションサー\nバから検索することができない。したがって,アプリケーションサーバにおいてネ イティブアプリケーションを検索したユーザに,CMSにより開発したウェブアプ リケーションを利用してもらうことができないという問題がある。これに対して, CMSによって構築したウェブアプリケーションと同等の機能\を有するネイティブ アプリケーションを開発し,当該ネイティブアプリケーションをアプリケーション サーバにアップロードすることも考えられる。しかしながら,ネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには,多大な開発工数が必要であった。本発明は,ネイ ティブアプリケーションを容易に生成することができるアプリケーション生成装置, アプリケーション生成システム及びアプリケーション生成方法を提供することを目 的とする。」(段落【0002】,【0004】〜【0007】)と記載されており,同記載からすると,引用発明は,CMSによって構築されるウェブアプリケーション\nは,アプリケーションサーバから検索することができないため,アプリケーション サーバにおいてネイティブアプリケーションを検索したユーザに,CMSにより開 発したウェブアプリケーションを利用してもらうことができないこと及びCMSに よって構築したウェブアプリケーションと同等の機能\を有するネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには,多大な開発工数が必要となることを課題とし,同 課題を解決するためのネイティブアプリケーションを生成する装置であることが認 められる。
引用発明は,上記課題を解決するために,前記(1)アで認定したとおり,既存のウ ェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアド レス等の情報を入力するだけで,当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更し\nて,同ウェブアプリケーションが表示する情報を表\示するネイティブアプリケーシ ョンを生成できるようにしたものと認められる。
イ 被告は,携帯通信端末の動きに伴う動作を行うネイティブアプリケーシ ョンを生成すること,特に,PhoneGapに係る技術が周知であると主張する。
(ア) 前記アのとおり,引用発明は,アプリケーションサーバにおいて検索で きるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題として,同課題を, 既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで,同ウェブア プリケーションが表示する情報を表\示できるネイティブアプリケーションを生成す ることができるようにすることによって解決したものであるから,ブログ等の携帯 通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表\示す るネイティブアプリケーションを生成しようとする場合,生成しようとするネイテ ィブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はな く,したがって,設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネ イティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はない。もっとも,引用文\n献1の段落【0024】には,ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられてお り,ゲームにおいては,加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないよう に制御する必要がある場合が考えられる(引用文献5参照)が,ウェブアプリケー ションとして提供されるゲームは,1)常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要\nがあるとはいえないこと,2)加速度センサにより,携帯通信端末の姿勢に対応した 画面回転表示を制御する機能\は携帯通信端末側に備わっており,端末側の操作によ って,表示画面を固定することができ,そのような操作は一般的に行われているこ\nと,3)引用文献1の段落【0024】の「ゲームサイト」は,携帯通信端末の表示\n画面を固定する必要のないブログ,ファンサイト,ショッピングサイトと並んで記 載されており,また,引用文献1には,加速度センサについて何らの記載もないこ とからすると,当業者は,上記の「ゲームサイト」の記載から,パラメータを「携 帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必\n要性を認識するとまではいえないというべきである。 また,引用発明によって生成されるネイティブアプリケーションは,HTMLや JavaScriptで記述されるウェブページを表示できるから,引用発明によ\nり,乙4に記載されたHTML5 APIのGeolocationを用いて携帯 通信端末の動きに伴う動作を行うウェブアプリケーションの表示内容を表\示するネ イティブアプリケーションを生成しようとする場合も,生成されるネイティブアプ リケーションは,設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基 づいて,同ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し,取得したウ ェブページのHTMLやJavaScriptの記述に基づいて,同ウェブアプリ ケーションの内容を表示でき,したがって,ネイティブアプリケーションの生成に\n際して,設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ 機能を実行させるためのパラメータ」とする必要はない。\nさらに,被告主張周知技術に係る各種文献にも,引用発明の上記の構成の技術に\nおいて,「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に\n応じて設定ファイルを設定することの必要性等については何ら記載されていない (甲2〜5,7,8,乙1〜3)。
(イ) 前記アのとおり,引用発明は,簡易にネイティブアプリケーションを生 成することを課題として,既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入 力するだけで,当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表\示するネイティブ アプリケーションを生成できるようにしたのであり,具体的には,前記(1)アのとお り,入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び 表示態様に基づいて,テンプレートアプリケーション111に含まれる設定情報の\n内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表\示 できるネイティブアプリケーションを生成でき,テンプレートアプリケーション1 11に含まれるプログラムファイル113については,新たにソースコードを書く\n必要はないところ,証拠(甲3,5,7,乙1〜3)によると,PhoneGap によってネイティブアプリケーションを生成するためには,HTMLやJavaS cript等を用いてソースコード(プログラム)を書くなどする必要があるもの\nと認められるから,引用発明に,上記のように,新たにソースコードを書くなどの\n行為が要求されるPhoneGapに係る技術を適用することには阻害事由がある というべきである。
被告は,1)PhoneGapでは,PhoneGapのプラグインの仕組みを使 って,GPSなど端末のネイティブ部分にアクセス可能であり,端末のGPS機能\ にアクセスすることで,GPSで取得した端末の現在位置が中心となるように地図 を表示することが可能\となるから,引用発明において地図表示アプリケーションを\n生成する際に,PhoneGapのフレームワークを採用することで,ネイティブ 機能であるGPS機能\が利用可能となり,携帯通信端末の動きに伴う動作を設定可\n能となり,また,2)AndroidManifest.xmlに「android: screenOrientation =”landscape”」の1行を追加し たり(Androidの場合),「Landscape Right」又は「Lan dscape Left」のアイコンを選択すること(iOSの場合)で,スマー トフォンの画面を横画面に固定可能となり,縦画面に固定する設定を施す場合,A\nndroidManifest.xmlに「android:screenOri entation =”portrait”」の1行を追加したり(Android の場合),「portrait」のアイコンを選択すること(iOSの場合)で,ス マートフォンの画面を縦画面に固定可能となるから,引用発明において,アプリケ\nーションを生成する際に,PhoneGapのフレームワークを利用することで, 「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に応じて,\n携帯通信端末において実行される「アプリケーションの,携帯通信端末の動きに伴 う動作」を規定する設定ファイルを備えることとなると主張する。 しかし,上記のとおり,引用発明にPhoneGapの技術を適用することの動 機付けはないから,被告の上記主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.10. 1
平成31(ネ)10035等 著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所 静岡地方裁判所
著作権法38条1項は,1)営利を目的とせず,2)聴衆又は観衆から料 金を受けない場合で,3)実演家等に対して報酬が支払われない場合には, 演奏権が及ばないことを規定するところ,1)の非営利目的とは,当該利 用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものでないことをいうも のと解される。 上記1に認定した事実によれば,控訴人らは本件店舗の各店における バンド演奏によりバンド音楽を好む客の来集を図っているものというべ きであるから,本件店舗の各店におけるバンド演奏による管理著作物の 利用行為が,直接的にも間接的にも営利に結びつくものでなかったとい うことはできない。したがって,本件店舗の各店におけるバンド演奏に ついて,同条の規定する,演奏権が及ばない場合に当たるとはいえない。 控訴人らは,現SUQSUQにおけるセット代金は飲食代金であると か,演奏する者がスタッフによる無料サービスであるなどと主張して, 非営利性を主張するが,飲食店での客寄せのための演奏であることは自 認しており,間接的に営利に結びつくものでなかったといえないことは 明らかである。
2019.10. 1
平成30(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
本件各発明の方法は,1)ラテックスの第一層(請求項1)や織布又はメリヤ スの第一層(請求項2)が形成された型を,水性ラテックスエマルジョン中で浸漬 被覆することによりラテックスの第二層を形成し,2)ラテックスの第二層に離散し た多面的な塩の粒子を塗布することでラテックスの第二層をゲル化し,ラテックス の第二層の中の塩の粒子の形状を固定した上,3)ラテックスの第二層を熱硬化させ る前にラテックスの第二層から離散した多面的な塩の粒子を溶解し,4)その後,形 成した層を熱硬化させ,硬化した第二層を形成し,5)型から硬化したテクスチャー ド加工手袋を外すというものである。 そして,本件各発明の方法に用いられる「型」(【0013】),「凝固剤」(【0014】【0026】),「水性ラテックスエマルジョン」ないし「発泡体」に相当するもの(【0015】【0028】【0032】),「塩」ないし「離散粒子」に相当するもの(【0010】〜【0012】【0018】【0033】),「織布」ないし「メリヤス」(【0022】)については,いずれも本件明細書に具体的にその意義(使用目的),材料名,調合方法又は入手方法等が記載されている。 また,本件各発明の方法に係る具体的手法は,離散した塩粒子のサイズ及び塗布 方法(【0010】【0012】【0018】【0033】)や,塩の粒子の溶解がラテックスの第二層の熱硬化の前に行われること(【0009】【0018】【0034】 〜【0036】)を含めて,いずれも本件明細書に実施例を交えて詳細に記載されて いる(【0009】〜【0016】【0018】【0022】【0026】〜【003 8】)。 よって,本件明細書の発明の詳細な説明には,これに接した当業者が,本件各発 明の方法の使用を可能とする具体的な記載がある。\nイ また,本件各発明により生産されるのは,テクスチャード加工表面被覆を有\nする手袋であるところ,本件明細書の発明の詳細な説明には,テクスチャード加工 表面被覆は,離散粒子(塩)の逆像が多面的な痕となって残ったものであり,手袋の\n外側又は内側のいずれかに取り入れられることが記載されている(【0007】【0 009】【0011】)。
ウ このように,本件明細書には,その具体的な実施の形態の記載もあることか らすれば,当業者において,発明の詳細な説明の記載内容及び出願時の技術常識に 基づき,その製造方法を使用し,かつ,その製造方法により生産した手袋を使用す ることができる程度の記載があるということができ,使用のために当業者に試行錯 誤を要するものともいえない。 よって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,実施可能要件に適合するもの\nと認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本件各発明に係る手袋の生産方法が,甲1,甲2及び甲7に記載さ れた手袋の生産方法よりも優れた作用効果を有する手袋の生産をすることができる ように記載されていないとし,また,本件明細書に記載されたつまみ力試験ではグ リップ力の測定はできず,そこでされている従来の被告の自社製品等との比較も適 切なものでないとして,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,当業者が本件各 発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないと主張す\nる。
イ 甲1,甲2及び甲7には,次の各記載がある。
・・・・
ウ しかしながら,本件各発明の方法により製造される手袋が,原告の引用する 手袋(甲1,甲2及び甲7)よりも優れたグリップ力を有するか否か,及び,つまみ 力試験でグリップ力の測定ができるか否かは,本件明細書の発明の詳細な説明の記 載が実施可能要件を満たしているか否かとは関係がない。\nなお,証拠(甲18)によれば,原告の主張は,本件各発明が,甲1,甲2及び甲 7等の従来技術よりも手袋のグリップ力を向上させることを課題とするにもかかわ らず,その課題の達成が追試可能な形で示されていないという趣旨のものと理解で\nきないわけではない。しかし,そうであれば,結局のところ,本件各発明の上記従来 技術に対する進歩性を問題とするものであり,発明の公開の程度を問題とするもの ではないから,いずれにせよ実施可能要件の充足を争う主張としては失当というほ\nかない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.10. 1
平成30(ワ)5189 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
確かに,本件業務委託契約の第4条第1項では,中国の会社がカキ殻加工固形物 (「ケアシェル」)の製造技術指導等を受け,そのノウハウを利用して製造,販売 する一切の成果物を製造,販売することができることが明記されており,中国の会 社は共有特許の構成を有する養殖魚介類への栄養補給体を製造,販売することも可\n能と考えられる。\nもっとも,同項では,「日本国以外で」製造,販売できる旨明記されている上に, 共有特許権が存続する間は,原則として,上記成果物を日本国において製造,販売 することはできないものとされ,さらに違約金の定めもされている(同条第2項)。 それだけでなく,第8条第1項では,中国の会社は,共有特許権が存続する間は, 「ケアシェル」を日本で製造,販売,日本へ輸出しないことを誓約することが明記 されている。 この点に関し,第4条第1項ただし書及び第8条第1項ただし書では,被告会社 が文書により要請したときは,中国の会社は上記成果物を被告会社に販売できるこ とや,「ケアシェル」を日本に輸出できることが明記されているが,あくまでも中 国の会社がこれらをすることができるのは,被告会社が文書により要請する場合に 限られているから,上記各条項によって,中国の会社に対し,共有特許の日本国内 での実施が許諾されたものと認めることはできない。 そして,本件業務委託契約の他の条項を検討しても,中国の会社に対し,日本国 内での共有特許の実施を許諾することを内容とする条項が設けられているとは認め られないから,本件業務委託契約が中国の会社に対し,共有特許権についての通常 実施権を許諾することを内容とするものと認めることはできない。 以上より,これを前提とする原告の主張には理由がない。
(4) 次に,原告は,中国の会社が「ケアシェル」を製造し,これが共有特許発 明の技術的範囲に属していることを前提として,その製造が共有特許権の侵害に当 たると主張する。 しかし,中国の会社が「ケアシェル」を製造し,これが共有特許発明の技術的範 囲に属するもの(共有特許の実施品)であることを認めるに足りる証拠はないし, 中国の会社がこれを日本国内で製造したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって,中国の会社が共有特許権の侵害行為をしたと認めることはできない。
(5) 以上より,本件業務委託契約の内容とするところは,共有特許権の排他的 効力とは無関係であるから,被告会社が中国の会社と本件業務委託契約を締結した こと等が,共有特許権者である原告の権利を侵害したことを理由とする原告の請求 は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.09.22
平成30(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
原告は,審決で認定した引用発明は,必須の構成要件である1)ないし4) の各事項(上記第3の1(1)に記載)を欠いており,誤りである旨主張する。 確かに,原告が主張するように,引用文献1の【0128】ないし【0 142】で開示される実施例(以下「引用実施例」という。)においては, マットレス装置を構成する複数の部材の堅さの選択及び組合せとして多種\n多様な選択肢があり得るところ,審決は,そのうちの一つを取り出した構\n成を引用発明として認定している。また,この一つの例についても,頭部 と足部を入れ替え,又は表と裏とを入れ替えることによって,当該構\成の マットレス装置は更に4通りの堅さ分布による使用が可能であるところ,\n審決は,このことに言及していない。そして,原告の上記主張は,審決に よるこのような引用発明の認定の手法について,引用発明の課題(目的) を無視し,本願発明1との相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をし\nたものであって誤っている旨主張するのである。
イ よって検討するに,引用文献1の記載によれば,引用実施例に係るマッ トレス装置452が上記のように多種多様な部材の選択及び組合せや4通 りの使用方法を開示しているのは,引用実施例が「小売用テスト装置とし て」利用され【0142】,「小売業者は店舗内のテスト用マットレスの 台数を減ずることで床面積を節約し得ると共に,ユーザは小売業者から購 入しようとするマットレスの感触を適合調整し得る」【0128】ように, 店舗内のテスト用マットレスに特化した課題(目的)又は作用効果に関す る事項を強調するためであると解される。しかし,引用文献1には,「マ ットレス装置452は家庭または他の療養施設での個人使用の為にユーザ により購入されることもある」【0142】と記載されており,このよう に個人が使用する場合には,適切な感触を得られる硬さの部材の組合せが 既に決定されているのであるから,多種多様な部材の選択及び組合せ並び に4通りの使用方法があることは想定されない。 したがって,小売用テスト装置(店舗内のテスト用マットレス)に用途 を限定しない引用実施例のマットレス装置452において,多種多様な部 材の選択及び組合せ並びに4通りの使用方法があることは,一体不可分の 必須の技術思想に当たらず,その中から一つの組合せ及び使用方法を抽出 した例を引用発明とすることに支障はない。引用発明は,引用例に記載さ れたひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握可能\であれば足りる ところ,審決で認定された引用発明は,この要件を充たしているといえる。
ウ もっとも,審決が,引用文献1に開示された多種多様な部材の選択及び 組合せ並びに4通りの使用方法の中から,引用文献1に具体的には全く例 示されていない例を抽出したのであれば,原告のいうように,本願発明1 の相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をしたといえることもあろう。\nしかしながら,審決が認定した引用発明は,部材の選択及び組合せ(認 定に係る構成のK,O及びQ)については,引用文献1に「所望であれば」\n「好適には」として具体的に例示された構成を採用している。また,使用\n方法については,引用文献1の【図24】に具体的に示された例をそのま ま用いており,頭部と足部とを入れ替えることも,表と裏とを入れ替える\nこともしていない。このように,引用発明は,引用文献1に接した当業者 が特段の「深読み」を要せずして把握し得る構成を備えたものであるから,\n審決に,事後分析的な認定をしたという誤りもない。また,引用文献1の 例示に基づいて具体的に認定した引用発明に,例示であることを示す「所 望であれば」「好適には」という文言を加えなければならない理由もない。
エ なお,部材の選択及び組合せについて審決が認定した構成(K,O及び\nQ)をとるとき,頭部端ブロック490と足部端ブロック492の堅さは 等しいから,頭部側と足部側とを入れ替えたとしてもベッド使用者の身体 の各部位に相当するコア458の各部位の堅さは変わらない。また,引用 文献1において,トッパ発泡体の上側と下側及びキルティングパネルの頂 部と底部につき,厚さ又は堅さを違えることに関する言及は何らみられな いから,マットレス装置452を裏返すことに技術的意義があるとは考え 難い。これらの点からしても,4通りの使用方法があることを引用発明1 の認定において考慮しなかったことに誤りがあるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.09.22
平成31(行ケ)10012 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
前記(2)アのとおり,甲1には,「本発明」の実施の形態に係る作業機械 である油圧ショベル50は,クローラを備えた下部走行体51,下部走行 体51に旋回可能に設けられた上部旋回体52,上部旋回体52に配置さ\nれた運転室52a,運転室52aに設けられる機械側保守装置30等を備 えること(【0013】,図2)の記載がある。 そして,油圧ショベルが,エンジン,エンジンの動力により作動油を吐 出する油圧ポンプ,及び,油圧ポンプが吐出する作動油によりオペレータ のレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータを備えることは,甲1 に従来技術として記載されているほか(【0003】,図15),本件出 願前に頒布された複数の刊行物にも記載されていることから(乙1(【0 025】,【0027】,図1),乙2(【0007】,図1),甲12 (2頁19行〜3頁18行,第5図),甲13(【0002】,【000 3】,図4,5)),本件出願当時,当業者にとって技術常識であったも のと認められる。また,かかる構成において,エンジンが油圧ショベルの\n上部旋回体に配置されることは,自明である。 そうすると,当業者であれば,甲1の記載から,甲1の油圧ショベル50 が,上部旋回体52に配置されたエンジンと,エンジンの動力により作動 油を吐出する油圧ポンプと,油圧ポンプが吐出する作動油によりオペレー タのレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータとを備えるものであ ると理解することができる。 したがって,本件審決が,引用発明について,「オペレータのレバー操 作に応じて駆動する油圧アクチュエータ」を備える旨認定したことに,誤 りはない。
イ これに対し,原告は,1)甲1は,操作レバーにより作業機械を操作する ことによって生じる,保守員の作業現場出向が無駄になり保守効率が著し く低下する等の問題に鑑み,自動運転を行う作業機械を提示しており,自 動運転を前提とするものであるし,また,作業機械の保守管理は高度に専 門的な知識を要することから,オペレータによる保守管理目的の操作レバ ーの操作が従来から回避されてきたことを示唆している,2)甲1の記載に 接した当業者であれば,ショベルの保守管理時の操作方法として,オペレ ータによる操作内容スイッチの押下(【0026】,【0031】,【0 032】),又は,【0012】のスイッチ等の何らかのスイッチの押下 により,運転コントローラ40による自動運転を行うものと解するのが自 然である旨主張する。 そこで検討するに,まず,上記1)の点については,前記(2)イのとおり, 甲1には,i)従来の技術では,保守員がオペレータに所要の態様の運転を 依頼しても,確実にこれを伝えることが困難な場合が多く,また,作業機 械の自動運転は,事故が生じないように予め何らかの手段を講じなければ\nならず手間と時間を要し,そのような手段を講じてもまだ完全に安全では ないなどの課題があったこと,ii)「本発明」は,作業機械の保守を行う 管理部に作業機械の各種操作の内容を指示する手段を設けるとともに,作 業機械にその指示内容を表示する手段を設け,さらに,操作内容報知手段\nを作業機械に設けるとともに,報知された操作内容の表示部を管理部に設\nける構成を採用することにより,上記課題を解決するものであること,iii) これにより,オペレータに所要の態様の操作を確実に行わせ,保守員は正 確な保守用のデータを得ることができるとともに,オペレータが作業機械 の操作を行うために,自動運転におけるような危険を生じることがないと いう効果を奏する旨の記載がある。
以上の記載に照らすと,甲1に記載された発明は,自動運転を前提とす るものではなく,オペレータが作業機械を操作する構成のものであり,か\nかる操作が保守員の指示に従って正確に行われるようにするために,上記 構成を採用したものであると認められる。\nなお,原告は,甲1に問題点が記載された「自動運転」(【0006】) とは,保守員による「遠隔自動運転」(【0005】)を意味するもので あり,オペレータのスイッチ操作により自動運転がされる場合には,上記 問題は生じない旨主張する。しかしながら,【0006】で指摘されてい る上記の問題(課題)は,「遠隔自動運転」についてのみ生じるものでは なく,オペレータのスイッチ操作による自動運転でも起こり得るものであ ると考えられるため,同主張は失当である。 次に,上記2)の点についてみると,甲1には,保守を行うための所要の 態様の操作である,「ブーム上げと上部旋回体の複合操作」は,操作指示 表示部320の表\示により同操作の指示を確認したオペレータが,これに 対応する「操作内容スイッチ33bを押した後,油圧ショベルを操作して」 行うことが記載されている(【0026】)。 そして,操作内容スイッチ33bは,上記複合操作を行ったことを管理 部側に知らせる場合に用いられるものであるから(【0016】),上記 複合操作は,オペレータが操作内容スイッチ33bを押すことで,自動運 転により行われるのではなく,スイッチ33bの押下後に,オペレータが 「油圧ショベルを操作して」行うものであると認められる。 また,【0012】には,運転コントローラ40が各種センサの検出値 や各種スイッチの状態に基づいて油圧ショベルの水平掘削等の「制御」を 行うことの記載があるが,「制御」の契機となる,作業機械のセンサの検 出値やスイッチの状態は,オペレータが操作レバーを操作することでも変 わり得るものであるから(【0003】),【0012】の記載は,油圧 ショベル50の「操作」が,オペレータのスイッチ操作による自動運転で 行われることを示唆するものとはいえない。 そして,甲1の全体をみても,油圧ショベル50の操作がオペレータの スイッチ操作による自動運転で行われることを示唆する記載はない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(4) 相違点の看過の有無について
ア 本願発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,1)本願発明の 「規定動作の指示」は,「運転者が操作して作業を行うショベル」の「下 部走行体に搭載された上部旋回体」「に備えられたキャビン」「に設置さ れ」た「表示部」に「表\示」される「運転者に対」する「指示」であるこ と,2)「運転者」のレバー操作に応じた「前記油圧アクチュエータによる 前記規定動作の実行中における」,「動作に関連する物理量を検出する」 「前記センサからの検出値」が,「前記規定動作と対応付けて」「記憶部」 に記憶され,この「検出値」が「送信部」から「管理装置へ送信」される ことを理解できる。 一方,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)には,「規定動作」の内 容及び「指示」の表示方法につき,定義はされておらず,これを原告主張\nのように限定して解すべき根拠となる記載はない。
イ 次に,本願明細書の発明の詳細な説明には,「本発明」の実施形態とし て,キャビン10内に設置された画像表示装置40に,「姿勢を点線の位\n置に併せてください」,「フルレバーで一気にアームを閉じてください」, 「フルレバーで一気にバケットを閉じて下さい」という指示とともに,現 在の姿勢と規定動作の実行後の目標姿勢とをそれぞれ実線と点線とで表\nした,側面視におけるショベルの外形の画像を表示し,又は,「旋回停止\nの指示がでるまで旋回を続けて下さい」という指示とともに,平面視にお けるショベルの外形の画像と旋回方向を表示することが記載されている\n(【0062】,【0063】,【0070】,【0074】,図5,6, 8,9)。
他方で,本願明細書の「以上,本発明を実施するための形態について詳 述したが,本発明はかかる特定の実施形態に限定されるものではなく,特 許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において,種々の変形・ 変更が可能である。」(【0086】)との記載に照らすと,本願明細書\nには,「本発明の要旨の範囲内」であれば,「本発明」の実施形態が上記 実施形態に限定されるものではないことの開示がある。 しかるところ,本願明細書には,本願発明の「規定動作」の内容及び「指 示」の表示方法を定義した記載はなく,これらを特定の内容や方法に限定\nする記載もない。 また,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載から理解できる「規 定動作の指示」等の内容(前記ア),本願明細書の発明の詳細な説明に記 載された本願発明の効果等(前記(1)イ(イ))を総合すると,本願発明は, 運転者に対して規定動作の指示を表示し,運転者のレバー操作に応じた油\n圧アクチュエータによる規定動作の実行中における,センサからの検出値 を,規定動作に対応付けて記憶部に記憶し,送信部から管理装置へ送信す ることによって,管理装置側の専門スタッフにおいて,どのような動作条 件で実行されたデータであるかを容易に把握し,ショベルの状態判断を実 効的に行えるようにすることに,技術的意義があるものと認められる。 そして,本願発明の上記技術的意義に照らすと,「規定動作の指示」を, 原告が主張するように,本願明細書の図5,6,8,9に例示されるよう な,「それを見ながらオペレータがレバー操作を行っても個人のスキル等 によるバラツキが抑制されるよう配慮した具体的かつ一義的な操作指示」 に限定する必然性は見いだし難い。
ウ 以上の本願発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本願明細書の 記載に鑑みると,本願発明の「規定動作の指示」とは,ショベルの上部旋 回体に備えられたキャビンに設置された表示部に表\示されるものであり, 運転者に対し,油圧アクチュエータによる規定の動作を実行するよう指示 するものであれば足り,原告が主張するような操作指示に限定されるもの ではないと解すべきである。 そうすると,引用発明における「保守を行うための所要の態様の操作で ある「ブーム上げ単独操作」,「ブーム上げと上部旋回体の旋回との複合 操作」,「走行の単独操作」等の操作指示」は,油圧ショベル50の上部 旋回体52に配置された運転室52aに備えられた操作指示表示部32\n0に表示されるものであり,オペレータに対し,油圧アクチュエータによ\nる規定の動作の実行を指示するものであるから,本願発明の「規定動作の 指示」に相当するものといえる。 したがって,本件審決が,本願発明と引用発明とは,「キャビン内に設 置され,規定動作の指示を運転者に対して表示する表\示部」を備える点で 一致すると認定した点に誤りはなく,本件審決に相違点の看過はない。
(5)相違点の容易想到性の判断について
ア 前記(4)のとおり,甲1の「本発明」の実施の形態には,保守管理時に, オペレータが,操作指示に従って油圧ショベルを操作し,保守を行うため の所用の態様の操作を実行することが記載されている。 一方,甲1には,操作指示に従ってオペレータが油圧ショベルを操作す る際の操作方法について,明示した記載はない。 しかしながら,前記(3)アのとおり,引用発明は,「オペレータのレバー 操作に応じて駆動する油圧アクチュエータ」を備えるものであること,甲 1には,オペレータが操作指示を見て行う所要の態様の操作の操作時に, 通常時の操作であるレバー操作以外の態様で操作を行うとの記載はない ことに照らすと,甲1に接した当業者は,オペレータが操作指示を見て行 う操作の操作手段として,通常時に用いるために備えられた操作手段であ る操作レバーを用いることを,容易に想到することができたものと認めら れる。 したがって,本件審決における相違点1の容易想到性の判断に誤りはな い。
イ これに対し原告は,甲1には,オペレータによる保守管理目的の操作レ バーの操作が,従来から回避されてきたことが示唆されていることからす ると,引用発明において,オペレータが操作指示を見て行う保守のための 所要の態様の操作を,レバー操作により行わせることについての動機付け はなく,むしろ阻害要因がある旨主張する。 しかしながら,原告の上記主張は,甲1が,操作レバーにより作業機械 を操作することによって生じる問題に鑑み,自動運転を行う作業機械を提 示するものであって,自動運転を前提とするものであることや,甲1には, 操作内容スイッチ,又は,【0012】のスイッチ等の何らかのスイッチ の押下により,運転コントローラ40による自動運転が開始される旨が記 載されていることなどを前提とするものであるところ,かかる主張を採用 できないことについては,前記(3)イのとおりである。 したがって,原告の上記主張は,前提を欠くものであって,採用するこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2019.09.20
平成30(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記 載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり,サポート要件の存在については,特許権者(被告)がその証明責任を負 うものである。 そして,前記のとおり,本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ,以下,この争点について,上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記1のとおり,本件明細書には,亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに,被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し,この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき,熱間成形や熱処理の前に, 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し,その後熱処理を行うことにより,腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する,亜鉛−鉄\nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ,これ によって,熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止,脱炭防止,高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され,実施例1として,鋼板を亜鉛で被膜し\nたものを950℃で熱処理して,亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと\nころ,同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され,さら に,実施例2として,50−55%のアルミニウム,45−50%の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ,極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると,当業者は,本件明細書の記載から, 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して,亜鉛−鉄ベース合金化合物(金属間化合物)又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物(金属間化合物)を生じさせ,高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た,当業者は,本件発明の合金化合物において,亜鉛が共通する主要な成分である から,本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記2で認定したとおり,亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること,熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る,すなわち,異なる金属間化合物に変化し得ることが,本件出願時の 技術常識であったことからすると,本件明細書の記載に接した当業者は,熱処理前 の被膜が実施例1とは異なり,亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても,実施例1 の記載及び上記技術常識を基礎にして,熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成, 熱処理の温度や時間等を適宜調節して,熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物(金属間化合物)を生じさせ,高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また,鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で,それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても,1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して, 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例2が本件明細書に記載されていること,2)前記2(1)のとおり,亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が,本件出願時,当業者に知られていた上,熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは,出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と,亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で,異なることを 示す根拠となる事情は認められず,基本的には異ならないと考えられることからす ると,熱処理前の「亜鉛ベース合金」が,実施例2に開示された亜鉛―アルミニウ\nムの固溶体からなる合金のみならず,亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても,熱処理前の同金属化合物の組成,熱処理の温度や時間等を適宜調節して, 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物(金属間化合物)を生じさせ,高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。
エ 次に,その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には,前記2(2)で認定したとおり,多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で,本件明細書には,熱処理前の「亜鉛ベース合金」が,それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし,前記2(1)のとおり,本件出願時,本件発明にいう熱処理後に生じる3元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして,証拠上認定できるものは,1)亜鉛−ニッケル−鉄,2)亜鉛−鉄− アルミニウム,3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの3種類のみである。 そうすると,上記のような3元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては, 鉄,アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして,ニッケルについては, 前記2(1)で認定したとおり,亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上,本件出願時から,ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた(甲2,乙8)から,当業者は, ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく, 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると, 本件明細書の記載に接した当業者は,前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて,熱処理前の「亜鉛ベース合金」が,亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も,それらの組成,熱処理の温度や時間を適宜調節して,亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ,高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして,本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と3元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から,鉄,アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により3元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると,当業者は,本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて,本件明細書の実施例2で開示された亜鉛重量50%−アルミニウム 重量50%の合金以外の「亜鉛ベース合金」として,亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物,亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し,これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物(金属間化合物)又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物(金属間化合物)を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ,そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は,1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し,それを熱処理すること で,本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを,被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが,その主張立証が果たされていない,2)亜鉛−鉄金属間化合物について, δ1相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると,当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして,本件発明の課題をできるとは認識しな い,3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて,限られた温度の3元系状態図しか知られていなかったことからすると,当 業者は,熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは\nできないから,熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記1)について,当業者が,「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て,亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物,亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し,これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは,前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記2)について,本件発明は,亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに,被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し,この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり,かつ,実施例1,2で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる(実施例1,2と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。)以上,従来の 技術常識にかかわらず,当業者は,本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合,本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ,原告の主張は採用することができない。
ウ 上記3)について,前記(2)で検討したとおり,当業者は,本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から,亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって,こ のことは,限られた温度の3元系状態図しか知られていなかったとしても,左右さ れるものではない。
エ 以上からすると,原告の上記主張は,前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって,原告主張の審決取消事由1は理由がない。
4 取消事由2(実施可能要件についての認定判断の誤り)について\n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ,方法の発明における発明の実施とは, その方法の使用をする行為をいうから(特許法2条3項2号),方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては,当業者が明細書の記載及び出願当時\nの技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして,実施可能要件についても特許権者(被告)がその証明責任を負\nう。
(2) 前記3で検討したところからすると,当業者は,本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて,「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として, 亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物,亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し,これらの被覆を熱処理することによって,高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから,本件明細書の詳細な説明には,本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり,実施可能要件は充足されている\nと認められる。
(3) 原告は,実施可能要件について,1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると,いかなる金属間化合物が生じ,「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない,\n2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない,3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし,上記1)について,前記3で検討したところからすると,当業者 は,「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として,亜鉛−鉄金属間化合物,亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物,亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し,これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記2)について,前記3で検討したとおり,本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例1,2で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると,原告が主張するような事情を考慮しても,当業者は実施可能\nであると認識するものと認められる。
ウ 上記3)について,前記3で検討したところからすると,当業者は,本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から,亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
エ 以上からすると,原告の上記主張は,前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.09.19
平成31(行ケ)10020 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年9月12日 知的財産高等裁判所
(2) 本願商標の外観について
ア 本願商標は,前記第2の2(1)のとおりの外観であり,濃紺色で塗りつぶ した縦長長方形(本願素地)内の最上部中央に「SIGNATURE」の欧文字を 茶色で横書きしてなり,かなり間を空けて,同長方形内の中央部分に,図形と文字 との組合せ部分(本願図柄部分)を配した構成からなる結合商標であるが,本願図柄部分は,茶色の太線で大きく表\された円輪郭内(内部は黒地である。)に,「NO.」,「555」及び「STATE EXPRESS」の各文字(「555」の数字は,他 の文字に比して大きく表されている。)を茶色で三段に横書きした部分(本願円図形)と,本願円図形の上部に,紋章風の図形(本願紋章部分)とをまとまりよく配した\n構成からなり,本願紋章部分は,王冠,円内に「SE」の文字を結合しモノグラム状に表\した図形,2匹の仮想動物風の図形並びに「SEMPER」及び「FIDELIS」の各欧文字の記載がある2本のリボン状の図形等からなり,文字部分は縦 長長方形と同じ濃紺色とし,それ以外を茶色としたものである。
イ 本願商標においては,本願円図形は,本願素地の縦の約4割,横の約6 割の大きさで,ほぼ中央に配置され,本願円図形の直ぐ上に,本願紋章部分が配置 され,本願円図形と本願紋章部分を合わせた縦の長さは,本願素地の約半分となる と認められるから,本願図柄部分は,相当に目立つ態様で表示されているといえる。一方,「SIGNATURE」の文字は,上記のとおり,本願素地の最上部中央\nに,本願図柄部分とは離れて表示されているところ,その大きさは,本願円図形内の「555」の文字と比較すると,横は同程度,縦は半分程度であり,「NO.」や\n「STATE EXPRESS」の文字より若干大きいこと,「SIGNATUR E」の文字と本願図柄部分との間には間隔が空いており,その間隔は,本願図柄部 分の縦の長さの約3分の1,「SIGNATURE」の文字の高さの約5倍,本願 素地の縦の長さの約15%に相当するものであって,両者が一見して離れていると 認識されること,「SIGNATURE」の文字は,本願円図形内の「NO.55 5 STATE EXPRESS」の文字や本願紋章部分と,それ自体で何らかの 関連性があるとは認識されないことを総合考慮すると,「SIGNATURE」の 文字は,本願図柄部分と一体のものとは認識できず,また,相応に目立つ態様で表示されているというべきである。\n
(3) 「NO.555 STATE EXPRESS」のブランドが知られてい る程度について
ア ラリーチームにおける宣伝広告活動について
前記1(3)のとおり,BATは,スバルのラリーレースのレーシングチームのスポ ンサーとなり,同レースに使用されるスバル車には,「555」のロゴが大きく表示されていたところ,同レーシングチームは,平成7年から平成9年にかけて3年連\n続でコンストラクターズタイトルを獲得したことなどからすると,その頃のラリー レースに興味を持つ者の間では,「555」のブランドは相応に知られていたものと 認められる。 しかし,日本において,上記のラリーレースに興味を持っている者がどの程度い たのかは明らかではなく,また,上記のラリーレースがテレビで放映されていたの かやその他のメディアで上記レースの状況がどの程度取り上げられていたかも明ら かではないから,上記のラリーレースでの宣伝広告活動によって,日本において, 「555」のブランドは,ラリーレースに興味を持つ限られた範囲の者には知られ るようになったということはできるが,それ以上に,一般的に,本件指定商品の取 引者や需要者(喫煙者やこれから喫煙をしようとしている成人)に知られるように なったと認めることはできない。 また,前記1(3)のとおり,BATがスバルのレーシングチームのスポンサーとな っていたのは平成15年までであるところ,本件審決時までには,上記のスポンサ ー契約を解消してから約15年経過していることからすると,本件審決時に近い時 期においても,複数のウェブサイトで,「555」のロゴを大きく表示したスバルのレーシングカーの写真が掲載されるなどしていることを考慮しても,本件審決の時\n点では,上記のラリーレースにおける宣伝広告活動の効果は限定的であるというほ かない。
イ F1レースにおける宣伝広告活動について
前記1(3)のとおり,平成11年頃から,BARは,「555」のロゴが大きく表示されたレーシングカーを使用してF1レースに参戦している。\nしかし,同レースがテレビで放映されていたのかやその他のメディアで上記レー スの状況がどの程度取り上げられていたかは明らかではない。また,BARは,「L UCKY STRIKE」のロゴの表示があるレーシングカーも使用しており,ウェブサイトの「Rally−M」には,「また『555』はF1のスポンサーでもあ\nった?そうですが,同会社のラッキーストライクの方が有名みたいです。詳しくは 分かりません」と記載されている。 これらのことからすると,F1レースにおける上記宣伝活動によって,一般的に 「555」ブランドが,本件指定商品の取引者や需要者に知られるようになったと まで認めることはできない。 また,「555」のロゴが大きく表示されたレーシングカーがいつまで使用されていたのかも明らかではない。\n
ウ そして,前記1(3)のとおり,「NO.555 STATE EXPRE SS」のブランドのたばこは,日本において販売されていないことを併せて考慮す ると,日本において,本件指定商品の取引者や需要者の間で,同ブランドが知られ ている程度は相当に低いものと認められる。
(4) 「SIGNATURE」の識別力について
ア 前記1(1)アのとおり,「SIGNATURE」の文字は,「署名,サイ ン,特徴,特徴的な,典型的な,代表的な,特製の」等の多様な意味を有するところ,日本において,「署名,サイン」以外の意味が一般的に知られているとは認め\nられないから,本件指定商品の取引者や需要者は,本願商標の「SIGNATUR E」を「署名,サイン」という意味で理解するか又は「署名,サイン」という意味 が本願商標においてどのような意義を有するかを理解することが困難であることか ら,意味を理解できないものというべきである。本願商標の「SIGNATURE」 が,「シグネチャーブランド」,「特徴的な銘柄」,「代表的な銘柄」などと,指定商品の性質等を説明したものと認識されるとは認められない。\n
イ(ア) 前記1(1)イのとおり,複数のブランドのたばこのパッケージやケース に「SIGNATURE」や「signature」の文字が表示されているが,原告が提出した証拠における使用例は,四つのブランドにおける使用例のみであり,\nまた,これらの使用例を紹介したウェブサイトは,いずれも英語で表示されたウェブサイトであり,上記のたばこが日本において販売されていると認めるに足りる証\n拠もないから,同使用例のみから,日本において,たばこのパッケージ等に「SI GNATURE」の文字が表示された場合に,「SIGNATURE」の語が「シグネチャーブランド」,「特徴的な銘柄」,「代表\的な銘柄」の意味を有すると認めることはできないし,他に,この事実を認めるに足りる証拠はない。
(イ) 前記1(1)ウのとおり,「SIGNATURE」という語について,「シグ ネチャーモデル」の使用例があることが認められ,また,「シグネチャー」という語 について,「シグネチャーモデル」,「シグネチャーブランド」,「シグネチャーアイテム」等の使用例があることを紹介しているウェブサイトがあることが認められる(甲 33,34)ものの,このことから直ちに,日本において,「シグネチャーモデル」, 「シグネチャーブランド」,「シグネチャーアイテム」等の言葉が一般的に知られて いると認めることはできない。 また,「SIGNATURE」という語を,人物の名前等を併記せずに単独で使用 した場合に,「シグネチャーモデル」,「シグネチャーブランド」,「シグネチャーアイテム」等を意味するということはできないし,一般的に,「SIGNATURE」と いう言葉から,「シグネチャーモデル」,「シグネチャーブランド」,「シグネチャーアイテム」等が連想されるということもできない。
(ウ) したがって,上記(ア),(イ)の使用例があることは,上記アの認定を左右 するものではない。
(5) 取引の実情について
ア 前記1(2)で認定したとおり,たばこのパッケージは,概ね,目立つ位置 に目立つ態様で,メインブランドを示す文字や図形が表示されており,当該メインブランドにおいては,味やタール含有量等の違いによって,複数の種類のたばこが\n用意されており,同種類を示す文字(第2表示)が,メインブランドを示す文字の直近や離れた位置に,メインブランドに比べると目立たない態様で表\示されている。そして,第2表示としては,「MENTHOL」や「LIGHTS」といった味やタール量を連想させる文字があるものの,「CABIN RED」,「CASTE R WHITE」,「SPARK」,「Luckies」等,味やタール量と関連しな い文字もあり,これらの文字は,当該たばこの性質等を説明したものではなく,本 件指定商品の取引者や需要者から商標として認識されるものと認められる。 このように,たばこのパッケージに表示される第2表\\示が,必ず商品の性質等を 示す説明的な記載となることはなく,また,本件指定商品の取引者や需要者も,第 2表示が,たばこの性質等を示すものと認識するとは限らないというべきである。この点,原告は,たばこ業界においては,取引者や需要者は,メインブランドが\n出所識別標識であると認識していると主張するが,上記の「CABIN RED」, 「CASTER WHITE」等の第2表示の例からも明らかなように,第2表\\示 が出所識別標識として使用されることもあるのであるから,原告の上記主張は理由 がない。
イ 前記1(4)のとおり,引用商標の商標権者は,メインブランドを「GUD ANG GARAM」とするたばこを販売しており,同たばこには,「Signat ure」,「NUANNTARA」及び「Surya」等の種類があるところ,前記 1(4)で認定した事実からすると,上記のガラムブランドの商品のうちの「Sign ature」の文字は,複数の種類があるガラムブランドの商品のうちの一つの種 類であるガラムシグネチャー商品を示す商標として使用されており,また,同商品 のパッケージを見た取引者や需要者も,そのように認識するものと認められる。 この点,原告は,引用商標の商標権者は,引用商標を,パッケージの上端部に, 小さく「Signature MILD」,「Signature MENTHOL」 と表示して使用しており,商標として使用していない旨主張する。しかし,前記1(4)のとおり,「Signature」の文字は,「MILD」や「M ENTHOL MILD」とは一連に表示されておらず,「MILD」や「MENTHOL MILD」よりも大きく,また,異なる書体や色で表示されているから,「MILD」や「MENTHOL MILD」とは独立した表示として認識されるものであって,出所識別標識として使用されているものと認められる。\nしたがって,原告の上記主張は理由がない。
(6) 結論
ア 以上のとおり,1)本願商標の外観上,「SIGNATURE」の文字は, 本願図柄部分と一体のものとは認識できず,また,相応に目立つ態様で表示されていること,2)日本における「NO.555 STATE EXPRESS」又は「5 55」のブランドが知られている程度は相当に低いこと,3)本願商標の「SIGN ATURE」は,「署名,サイン」という意味に理解されるか又は意味を理解でき ないものであって,「SIGNATURE」が「シグネチャーブランド」,「特徴的 な銘柄」,「代表的な銘柄」の意味で理解されるとは認められないこと,4)たばこの パッケージに表示される第2表\\示は,必ずしも,商品の性質等を示す説明的な記載 となるとは限らないこと,5)引用商標の商標権者の引用商標の使用状況を考慮し得 るとしても,引用商標の商標権者は,「Signature」の文字をたばこのパッ ケージにおいて,出所識別標識として表示していることを総合考慮すると,本願商標に接した者は,通常,「SIGNATURE」の文字を本願図柄部分とは独立し\nて認識するものということができるから,同文字を本願図柄部分から分離して観察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認め ることはできないというべきである。 したがって,本願商標と引用商標との類否を検討するに当たっては,「SIGN ATURE」の部分を抽出して,この部分と引用商標との類否を検討し,両者が類 似するときは,両商標は類似するものと解するのが相当である。 そうすると,本願商標の「SIGNATURE」の部分と引用商標とは,称呼, 外観及び観念のいずれにおいても,共通するから,本願商標は,引用商標と類似す る。
イ(ア) 原告は,結合商標の一部を分離,抽出して商標の類否を判断すること は,「その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配 的な印象を与えるものと認められる場合」や「それ以外の部分から出所識別標識と しての称呼,観念が生じないと認められる場合」などの例外的な場合に限られるべ きであると主張する。 しかし,原告が挙げる上記の場合以外にも,各構成部分がそれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認め\nられない場合には,分離観察が許されると解するのが相当であり,本願商標の「S IGNATURE」の部分を抽出して商標の類否を判断することができることは上 記アのとおりである。 (イ) 原告は,たばこの消費者は,店頭や自動販売機に陳列された商品のパ ッケージを目視し,商品の銘柄,パッケージのデザイン・色等を確認してから購入 するから,たばこに関しては,商標の称呼のみで取引されるケースはほとんどない こと,たばこの購入に当たっては,「主要銘柄」,「種類名」,「商品パッケージのデザイン」という三つの要素が重要となるところ,そのうち,「主要銘柄」と「商品パッ ケージのデザイン」が自他商品識別標識となることからすると,本願商標において 種類名を示す「SIGNATURE」の部分のみに注目して実際の取引が行われる ことは皆無であり,必ず,パッケージ全体のデザイン及び主要銘柄「No.555 STATE EXPRESS」を確認,認識して指定商品の取引がされると主張す る。 しかし,消費者が,たばこを購入するに当たって,「SIGNATURE」に注目 して購入することがないとはいえないから,原告の上記主張は理由がない。
(ウ) 原告は,「SIGNATURE」という言葉が持つ記述的な意味は,英 語を理解する者の観点からすると,ごく一般的な意味の一つであり,このようなご く普通の記述的意味の存在を無視するとすれば,国際企業の商標選択の余地を不当 に妨げ,パッケージデザイン等の自由を過度に阻害すると主張する。 しかし,本願商標の登録出願が認められないのは,引用商標が登録されているに もかかわらず,「SIGNATURE」の文字を,本願図柄部分とは独立した態様で, かつ,相応に目立つ態様で表示していることなど,上記アで判示した諸事情を総合考慮した結果であり,国際企業の商標選択の余地を不当に妨げ,パッケージデザイ\nン等の自由を過度に阻害するということはできない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
(エ) 原告は,「SIGNATURE」という文字を含む複数の登録商標が, 引用商標と併存していることから,「SIGNATURE」の部分が本願商標の独立 した要部となることはない旨主張する。 前記1(1)エのとおり,たばこ等を指定商品とする登録商標には,「SIGNAT URE」の文字を含むものが複数存在する。 しかし,これらの登録例では,「SIGNATURE」と他の部分との結合の態 様等が本願商標とは異なっている。「SIGNATURE」の文字を含む登録商標 が複数存在することから直ちに,本願商標の「SIGNATURE」の文字を本願 図柄部分と分離して観察することができないことにはならないというべきである。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
(オ) 原告は,「JET」及び「Espresso」の欧文字が表示されたたばこパッケージと目される商標について,特許庁は,「Espresso」の部分\nは識別標識として機能しないと判断したところ,本件審決は,上記の判断と矛盾する旨主張するが,原告が指摘する上記の事例における登録出願商標及び引用商標は,\n本件とは異なるから,本件審決の判断が上記事例における判断と矛盾するというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.09.19
平成31(ネ)10032 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
専用実施権について、明文がなくても、実施義務を負っているかが争われました。1審は、実施義務については認めましたが、報告義務違反はないとして請求を棄却しました。控訴されましたが、知財高裁は控訴を棄却しました。
2 実施義務違反の有無について
(1) 被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反するものか(争点1)
ア 控訴人は,被告製品の製造工程には,稚魚をボイルした後に,粗熱をとって 冷ます工程が入っていることから,本件発明の製造工程に反し,そのことにより, 本件契約上専用実施権者に義務付けられた特許発明の実施がされていない旨主張す る。 しかしながら,本件において被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反して いると認めることはできない。 その理由は,後記イのとおり補正し,後記ウのとおり,当審における補充主張に 対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第4の1(原判決12頁 19行目から22頁20行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用す る。
イ 原判決の補正 原判決22頁15行目及び20行目の「本件特許」をいずれも「本件発明」に改め る。
ウ 当審における補充主張に対する判断
控訴人は,被告製品の製造工程に粗熱をとって冷ます工程を入れることの可否に ついては,確かに,本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には,稚魚をボイル した後に氷冷熟成すると記載されているだけで,粗熱をとって冷ます工程を入れる ことを禁じる旨の記載はないが,そのことから当然に「冷ます」工程を入れること が許容されることにはならないと主張する。 そして,本件発明は,しらすの旨味成分を維持しつつ長期間の保存を可能にする\nことを目的とするものであるのに,被告製品に含まれるイノシン酸と水分の量は, その2年以上前に本件発明の製造方法に従って製造された製品と比較しても少なく, 被告製品においてはイノシン酸による旨味成分の維持がされていないことからすれ ば,本件発明の製造工程に従って製造されていないと認めるべきであり,このこと は被控訴人の実施義務の違反を構成すると主張する。\nその上で,被告製品に含まれるイノシン酸と水分の量を示す証拠として,平成3 0年2月1日付け愛媛県産業技術研究所長作成の成績表(29産研分第252―\1 号。甲18)及び平成30年3月8日付け愛媛県産業技術研究所長作成の成績表(2\n9産研分第286号。甲24)並びに被告製品の写真(甲21)を提出する。 しかしながら,甲21の被告製品の写真は,上記各成績表に係る試料となる検体\nを撮影したものであると説明されているものの,上記被告製品は,賞味期限を平成 28年11月19日とするものであり(甲21,24),試験の依頼日である平成3 0年3月5日までに1年3か月以上経過していた。上記被告製品が上記試験までの 間どのように保存されていたかは,試験結果に影響を与え得る事情であると考えら れるが,その保存状況を明らかにする客観的な証拠は見当たらない。むしろ,上記 試験の結果によれば,イノシン酸の含有量の値が41と低く(甲18),被控訴人に おいて,粗熱を取ったしらすに対し冷凍と解凍を繰り返したときの試験結果(乙6 9)とイノシン酸の含有量の傾向が一致していることからすると,上記被告製品の 保存の状態も,同様に解凍と冷凍をしたものであったことがうかがわれる。 そうすると,上記の試験結果が被告製品の状態を的確に示すものといえるか否か については疑義があり,この疑義を払拭するに足りる的確な証拠はない。 よって,控訴人の上記主張は,その前提を欠き,理由がない。
(2) 被告製品の製造販売が実施義務の履行として十分なものでなかったか(争点2)\n
ア 控訴人は,被控訴人が本件契約の締結後すぐには被告製品を製造しなかった ことや,その後に支払われた実施料が少額であったことをとらえて,被告製品の製 造販売が実施義務の履行として十分なものでなく,そのことにより,本件契約上専\n用実施権者に義務付けられた本件発明の実施がされていない旨主張する。 しかしながら,本件事実関係の下において,被告製品の製造販売が実施義務の履 行として十分なものでなかったと評価することはできない。\nその理由は,後記イのとおり補正するほかは,判断の基礎となる事実関係につい ては,原判決の「事実及び理由」の第4の2(1)(原判決22頁25行目から28頁1 8行目まで)に記載されたとおりであり,判断については,同第4の2(3)(原判決2 9頁末行から33頁14行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用す る。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成29(ワ)41474 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月30日 東京地方裁判所
特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定められる ものであり(特許法70条1項),特許請求の範囲の記載の解釈は,明細書 の発明の詳細な説明の記載等を考慮して行うべきものである(同条2項)。 しかして,本件発明の構成要件Bにおける「タンパク質を抽出する」混\n合液との文言について解釈し,そのタンパク質抽出の態様を明らかにすべ く,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,1)従来,界面活性剤 の使用を前提とする方法により溶液中の対象物質(タンパク質等)を分離 (抽出)していたところ,界面活性剤を使用すると,分離(抽出)された 対象物質から界面活性剤を除去する工程が必要となり,煩雑さが生じてい たため,溶液中から対象物質を簡便に分離(抽出)するための混合液が求 められていたこと,2)そこで,上記課題を解決するため,界面活性剤を必 要的には含まず,所定の高級アルコール(第1の高級アルコール)と脂肪 酸を含む混合液によって,タンパク質と水性溶媒とを含む抽出対象液から タンパク質を簡便に分離(抽出)するという構成を採用したものが請求項\n1発明であり,本件発明は,かかる請求項1発明を前提としつつ,第1の 高級アルコールとは異なる高級アルコールと炭化水素を含む混合液によ って,タンパク質と水性溶媒と第1の高級アルコールと脂肪酸とを含む抽 出対象液からタンパク質を夾雑物の含有量が従来より少ない状態で抽出 するものであること,3)これによって,タンパク質と水性溶媒とを含む抽 出対象液からタンパク質を簡便に分離(抽出)できる混合液,及び,タン パク質の抽出方法が提供されることとなったこと,4)本件発明に係るタン パク質抽出剤には,従来使用されてきた対象物質の分離(抽出)のための エマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない量(例えば,タンパク 質抽出剤全体に対して0〜4質量%)の界面活性剤が含まれていてもよい こと,本件発明の目的を害さない限り,公知の添加剤(界面活性剤,炭素 数18未満の高級アルコール等)を添加してもよいことが記載されている 旨が認められる。
これらによれば,本件発明に係る,「タンパク質を抽出する」混合液とは, タンパク質と水性溶媒に加え所定の高級アルコールと脂肪酸を含む抽出対 象液から,上記とは別の高級アルコールと炭化水素を含むことによって, タンパク質を夾雑物の含有量がより少ない状態で分離(抽出)できる混合 液であり,界面活性剤の含有の有無を問わないが,従来のエマルション等 に含まれる界面活性剤よりも少ない量の界面活性剤の含有を,従来必要と されていた除去工程を不要にする限度において許容することによって,上 記の分離(抽出)を簡便に行うことができる混合液という技術思想に係る ものであるというべきである。そうすると,上記「タンパク質を抽出する」 混合液において,その含有される界面活性剤の程度は,分離等された対象 物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とするもので あり,そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解するのが相 当であり,分離(抽出)されたタンパク質から界面活性剤を除去する工程 が必要となるものは,上記「タンパク質を抽出する」混合液には当たらな いというべきである。 なお,この解釈は,本件特許の特許出願の経過(「早期審査に関する事情 説明書」(乙2),「意見書」(乙3))において,原告自身が,先行技術にお いては,タンパク質の抽出につき界面活性剤を使用することが必要的であ ったところ,本件原出願の実施形態は,界面活性剤を必要的に用いること はせず,高級アルコールを必要的に用いるものであり,この構成の差によ\nり,界面活性剤を抽出結果物から除去する工程を不要とすることが可能と\nなり,また,タンパク質への界面活性剤の悪影響を回避することが可能と\nなるという効果を奏し(乙2),さらに,界面活性剤を含まなくとも,抽出 対象液からタンパク質を簡便に分離できるという,従来技術からは予測し\n得ない異質な効果を奏する(乙3)旨述べていることにも沿うものであり, 何ら矛盾するものではない。
イ 原告の主張について
これに対し,原告は,本件明細書(段落【0056】)には,「本発明の 目的を害さない限り,公知の添加剤(界面活性剤,炭素数18未満の高級 アルコール等)を添加してもよい」と記載されているが,本件発明の目的 を害する場合とは,タンパク質の分離・抽出作用が機能しない場合,例え\nば,界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の全部が乳化して二層 に分離せず,結果として界面が生じない場合などの極めて例外的な場面を 指すものであって,上記のようなタンパク質の分離抽出においておよそ想 定されない添加物の添加以外は,むしろ広く公知の添加物の添加をさらに 許容することを明示したものと解釈されるべきである旨主張する。 しかし,上記説示のとおり,本件発明に係る「タンパク質を抽出する」 混合液において,その含有される界面活性剤の程度は,分離(抽出)され た対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とする ものであり,そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解する のが相当であるというべきであり,本件明細書の具体的記載を精査しても, 原告が主張するような,界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の 全部が乳化して二層に分離せず,結果として界面が生じない場合などの極 めて例外的な場面を除いて広く界面活性剤の添加を許容することが読み取 れるような記載は見当たらない。したがって,原告の上記主張は,本件明 細書の具体的記載から離れた独自の主張というほかなく,採用することが できない。
被告製品と構成要件Bとの対比\n
ア 証拠(乙18,28ないし31)によれば,被告製品は界面活性剤を「● (省略)●」質量%含むこと,従来,タンパク質の分離等のために使用さ れてきた界面活性剤の量は抽出剤と対象液とを合わせた全体量に対して 0ないし2質量%であったことが認められる。 そして,上記のとおり被告製品に含まれる界面活性剤の量からすれば, 「従来使用されてきた対象物質の分離等のためのエマルション等に含ま れる界面活性剤よりも少ない量(例えば,タンパク質抽出剤全体に対して 0〜4質量%)の界面活性剤が含まれていてもよい。」(段落【0041】) という本件明細書の記載との関係で見ても,また,上記のとおり従来使用 されてきた界面活性剤の量との関係で見ても,被告製品における界面活性 剤の含有量が,従来のエマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない 量であるものとは認められず,その含有される界面活性剤の程度が,分離 (抽出)された対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度 であるとは認めるに足りない。 そうすると,このような被告製品は,そのタンパク質抽出の態様の観点 からして,構成要件Bの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充\n足しないというほかない。
イ これに対し,原告は,従来の「抽出剤」を,「抽出対象液」に添加した総 量に対する界面活性剤の「終濃度」については,CMC(臨界ミセル形成 濃度)を意識して2ないし4%前後とされているところ,実験の操作性の 観点から,前段階である「抽出剤」における界面活性剤の濃度は,その1 0ないし20倍程度が概ね目安となることからすると,同濃度は,通常2 0ないし80%であることとなり,そうすると,界面活性剤を「●(省略) ●」質量%含む被告製品は,従来の「抽出剤」よりも界面活性剤の含有量 が少ないものといえる旨を主張する。 しかし,原告のいう界面活性剤の「終濃度」が「2ないし4%前後とさ れている」こと,「抽出剤」における界面活性剤の濃度がその10ないし2 0倍程度が目安となることを認めるに足りる的確な証拠はなく,従来使用 されてきた抽出剤における界面活性剤の含有量にかかる原告の上記主張 は採用しがたい。また,仮に,原告の上記主張(被告製品が,従来の「抽 出剤」よりも界面活性剤の含有量が少ないこと)を前提としても,そのこ とから直ちに,界面活性剤を「●(省略)●」質量%含む被告製品が,そ の界面活性剤の含有の程度につき,分離(抽出)された対象物質から界面 活性剤を除去する工程が不要である程度のものであると認められること とはならず,被告製品が,そのタンパク質抽出の態様の観点からして,構\n成要件Bの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充足しないとの 上記結論が左右されることにはならない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所
特定事項A及びBは,本願発明が,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり, 当該脂質含有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち,一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ,特定事項Cは, 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し,\n特定事項D及び特定事項EないしHは,重畳的に,これに更に特定を加えるもので ある。
そうすると,特定事項Iは,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,脂質含 有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について,これが,特定事項CないしHによって特定された構成\nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Aの明確性
以上によれば,特定事項Aは,「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当 該脂質含有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち,一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって,特定事項Aを,こ のように解釈することは,その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は,本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を,ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ,「指標として」という記 載は抽象的であり,いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから,本願発明の外延は明確ではない,要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては,明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,年齢,性別等の対象の要素 をメルクマールにして,その脂質含有配合物の構成を決定すれば,要素を「指標と\nして」使用したといえる。また,これにより決定される脂質含有配合物の構成があ\nりふれたものであったとしても,ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると,「指標として」という記載が,第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また,対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは,本願発明 の技術的範囲を画定し,対象方法を認定した上で,これらを比較検討して判断する ものである。そして,脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは,対象方法の認定に係る問題であって,本願 発明の技術的範囲の画定の問題,すなわち,明確性要件とは無関係である。 したがって,被告の上記主張は採用できない。
(イ) 被告は,特定事項EないしIは,特定事項Dにおける「ω−6脂肪酸対ω −3脂肪酸の比」及び「それらの量」が「一つ以上の要素」に,どのように基づい ているのかを特定しようとする記載と解すべきである旨主張する。 しかし,特定事項Dと特定事項EないしHは,いずれも特定事項Cによって特定 された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について,更に,それぞれ\n異なる観点から特定するものである。特定事項E及びGには「一つ以上の要素」に 関する記載が全くないのであるから,これらと選択関係にある特定事項EないしH との関係から,特定事項Dの技術的意義を解すべきとはいえない。 したがって,被告の上記主張は採用できない。
(ウ) 被告は,本願明細書は「要素」の使用方法を明らかにするものではなく, それが技術常識でもない旨主張する。 被告の上記主張は,本願発明は,対象に投与する脂質含有配合物を選択するため に,どのように「要素」を使用するかについて特定した方法であるという解釈を前 提とするものである。 しかし,特定事項F及びHに係る特許請求の範囲の記載においては,「要素」で ある食餌及び生活圏周囲の温度範囲を,どのように使用するかについて特定されて いるものの,これらの特定事項と選択関係にある特定事項E及びGには,「要素」 の使用方法に関する記載はない。特定事項F及びHは,本願発明の方法によって選 択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定するものにすぎないと解すべき\nである。そして,その余の本願発明に係る特許請求の範囲の記載には,「要素」の 使用方法に関する記載はない。 したがって,被告の上記主張は,特許請求の範囲の記載を離れた本願発明の解釈 を前提とするものであるから,採用できない。なお,本願発明の課題を解決するた めには,脂質含有配合物の選択に当たり,特定の「要素」をどのように使用するか についてまで特定しなければならないにもかかわらず,特許請求の範囲に記載され た発明が,脂質含有配合物の選択に当たり,特定の「要素」を使用する方法につい て特定するにとどまるというのであれば,それは,サポート要件の問題であって, 明確性要件の問題ではない。明確性要件は,出願人が当該出願によって得ようとす る特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって,それが,発明の 課題を解決するための構成又は方法として十\分か否かについて判断するものではな い。
ク 小括
以上によれば,特定事項Aは,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当該 脂質含有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち,一つ又は複数を「指 標」として使用する方法である旨特定するものである。特定事項Aに係る特許請求 の範囲の記載が,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということは できない。
・・・
本件審決は,サポート要件について,「ω−6の増加が緩やかおよび/また はω−3の中止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」と の技術的事項が,本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから,本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして,本件審決は,本願発明が,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて,何ら検討判断していない。 (2) しかしながら,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記 載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると,本願発明が,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて,何ら検討することなく,選択関係にある特 定事項EないしHのうち特定事項G「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3 の中止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」との技術的 事項が,本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって, サポート要件に適合しないとした本件審決は,誤りである。
(3) 加えて,以下のとおり,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3の中 止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」との特定事項G の技術的事項は,本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち,まず,本願明細書【0042】には,「長鎖ω−3脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質/栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか,またはω−6脂肪酸が突然増加すると,全身性の炎症応答(毛細血管 漏出,発熱,頻脈,呼吸促迫),多臓器不全(消化器,肺,肝臓,腎臓,心臓)お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも,様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3 の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は,本願明細書【0042】 に記載されている。
また,本願明細書には,菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって19〜30 歳及び31〜50歳の男性に投与する脂質組成物のω−6脂肪酸の用量を40g以 下とすること(実施例3【表9】),多量のシーフード摂取者であって上記と同年\n齢の男性に投与する脂質組成物のω−6脂肪酸の用量を40g以下とすること(実 施例3【表11】),及び,医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成\n物のω−6脂肪酸の用量を40g以下とすること(実施例6【表13】)が,それ\nぞれ記載されている。このように,「ω−6の用量が,40グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は,本願明細書の実施例3【表9】【表\11】及び実施 例6【表13】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。\nさらに,上記のとおり,本願明細書【0042】には,「ω−6の増加が緩やか および/またはω−3の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも, 様々な疾患が生じ得ることが記載されており,これは,「ω−6の増加が緩やかお よび/またはω−3の中止が緩やかであ」る投与方法が,特定の対象に限らず,一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると, このような投与方 法と,実施例3【表9】【表\11】及び実施例6【表13】のそれぞれ一部に記載\nされた「ω−6の用量が,40グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法,すなわち,例えば,菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって19〜 30歳及び31〜50歳の男性に,40g以下の用量のω−6脂肪酸を投与し,そ の際,ω−6脂肪酸を緩やかに増加させ及び/又はω−3脂肪酸を穏やかに中止す るという,脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は,本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって,本件審決は,サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく,そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず,その判断 枠組み自体に問題がある。よって,取消事由3は,その趣旨をいうものとして理由 がある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成30(ネ)2523 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和元年9月5日 大阪高等裁判所
本件意匠に係る物品の需要者及び物品の性質,用途等
本件意匠に係る物品である検査用照明器具は,工場等において製品の 傷やマーク等の検出(検査)に用いられるものであるから,意匠の類否 判断における取引者・需要者は,製造工場等における機器等の購入担当 者,検査業務の従事者等である。この検査用照明器具は,LEDや光学 素子を内蔵して,前端部から光を照射するものであるところ,LEDを 使用すると熱を発生し,器具内の温度が上昇して,発光出力が低下する ことから,放熱の必要性が指摘されている(甲21,22,24)。 本件意匠は,そのような検査用照明器具の放熱部の意匠であるから, 上記需要者は,放熱部材の表面積の大小や部材相互の空隙の大小から放\n熱性能の高低を推し量るという観点から,放熱部材であるフィン構\造体 の,発光部との位置関係,フィンの形状,数,大きさ(支持軸体の径との 関係),配置(フィン相互の間隔)に注目するものと考えられる。
ウ 公知意匠等の参酌
ところで,前記1(1)ウ,オに認定したとおり,本件意匠の登録出願前 までに,検査用照明器具の物品分野における放熱部の意匠として,乙7 等意匠,乙12意匠が開示されており,これらは,前記1(3),(5)で検 討したとおり,本件意匠の基本的構成態様(A〜D)と同じ構\成態様を 備えているほか,本件意匠の具体的構成態様のうちE,I及びJの各一\n部並びにF,K及びLと同じ構成態様を備えている。そうすると,これ\nらの構成態様に係る形態は,本件意匠の意匠登録出願前に公知であった\nと認められる。 また,一審原告は,本件意匠の構成態様とは,中間フィンの枚数のみ\nを異にする意匠を,本件意匠の関連意匠として,意匠登録している(前 提事実(2)イ)。 そうすると,上記イの各点のうち,フィンの枚数,厚み,縁の面取り, フィン相互の間隔,フィンの大きさと支持軸体の径との関係(支持軸体の 太さ)については,それらにわずかな違いがあっても,需要者がその差異 に注目するとは考えられないが,これらが大きく異なれば,需要者が受 ける視覚的な印象は異なるものと考えられる。 他方で,本件意匠の後端フィン及び中間フィンの各面には,支持軸体 の通過部分以外には貫通孔がなく,平滑であるという形態(本件意匠の 具体的構成態様M)は,乙7等意匠や乙12意匠にはないものであり\n(なお,類似の物品である照明器に係る意匠である乙4意匠にもそのよ うな形態がないことは,前記1(1)エ,(4)のとおりであるし,甲14で 開示されている意匠でも,フィン様の突状が施されているケース本体の 上側に貫通孔が設けられている。),また,前記1(6)及び(7)で検討し たとおり,公知意匠の組み合わせに基づいて容易に創作することができ るともいえないから,公知意匠にはない,新規な創作部分であると認め られる。そして,電源ケーブルの引き出し位置は,検査用照明器具とし ての使用態様に関わるから,この形態(具体的構成態様M)は,需要者\nの注意を惹くものと認められる。 これに対し,一審被告は,公知意匠として乙8意匠も参酌すべきであ り,同意匠では,後端フィンの後端面は平滑であるから,本件意匠の具 体的構成態様Mは,新規な創作部分とはいえない等と主張する。\nしかし,前記1(1)イのとおり,そもそも,乙8意匠は,検査用照明器 具の後方部材に係る意匠ではないから,これを,本件意匠の要部認定に おいて,公知意匠として参酌すべきものとは解されない。一審被告の主 張は採用できない。
エ 本件意匠の要部
以上を総合すれば,本件意匠の要部は,原判決別紙「裁判所認定の構\n成態様」のうち,次のとおり認められる。 (フィン構造体と発光部との位置関係について)\n
(ア) 前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材である。
(イ) 後方部材の中心には,検査用照明器具の前方部材の後端面より後方 に延伸する支持軸体が設けられている。 (フィンの形状,数,大きさ〔支持軸体との関係〕,配置について)
(ウ) 支持軸体には,薄い円柱状の,中間フィンが2枚と,後端フィン1 枚が取り付けられている。
(エ) 後端フィンの厚みは,中間フィンの厚みの約2倍である。
(オ) 支持軸体の径は,フィンの径の5分の1程度である。
(カ) 中間フィン及び後端フィンの径は,前方部材の最大径とほぼ同じで ある。
(キ) フィン相互の間隔は,フィンの径の8分の1程度の等間隔である。 (フィンの形状のうち貫通孔の有無について) (ク) 中間フィン及び後端フィンには,支持軸体の通過部分以外に貫通孔 はなく,その各面は平滑である。
(4) 本件意匠とイ号意匠との類否
ア 対比
本件意匠の要部(前記(3)エ)と,これに対応するイ号意匠の構成態様\nを対比すると,1) 中間フィンの枚数は,本件意匠が2枚である(要部 (ウ))のに対し,イ号意匠では3枚であり(原判決別紙「裁判所認定の構\n成態様」イ号g1),2) 後端フィンは,本件意匠では中間フィンの約2 倍である(要部(エ))のに対し,イ号意匠では約1.3倍であり(イ号h 1),3) 支持軸体の径は,本件意匠がフィンの径の5分の1程度である (要部(オ))のに対し,イ号意匠では3分の1強であり(イ号j1),4) フィン相互の間隔が,本件意匠ではフィンの直径の8分の1程度である (要部(キ))のに対し,イ号意匠では約10分の1であり(イ号e1), 5) フィンの各面の形状について,本件意匠では,貫通孔がなく平滑であ る(要部(ク))のに対し,イ号意匠では,後端フィンの後面中心にねじ穴 が1箇所ある(イ号m1)という差異があるが,その余の点(要部(ア), (イ),(カ))は共通すると認められる。
イ 類否判断
上記アの差異点に関して,1)の中間フィンの枚数,2)のフィンの厚み, 3)の支持軸体の太さ,4)のフィン相互の間隔については,需要者がそれ らのわずかな違いに注目するとは考えられないが,これらが大きく相違 すれば,異なる印象を生じさせる場合があることは前述のとおりである。 ところで,需要者が,検査用照明器具の放熱部としてのフィン構造体\nの特徴を把握しようとする際には,正面視で,フィンの配置状況等を観 察するほか,斜め前方から(左側面視)又は斜め後方(右側面視)から見て, フィンの形状や発光部とフィン構造体との位置関係等も観察するものと\n考えられる。 このような観察によると,2)のフィンの厚みについて,イ号意匠の後 端フィンには面取が施されている分,その厚みが中間フィンよりも厚い という印象を与えるということができる。その一方で,本件意匠と比較 した厚みの程度の差は一見して明らかとはいえないし,1)のフィンの枚 数,3)の支持軸体の太さ,4)のフィン相互の間隔の粗密の違いも,それ ほど目立つとはいえず,視覚的に異なる印象をもたらすとまでは認めら れない。 また,5)のフィンの各面の形状について,イ号意匠の後端フィンの後 面のねじ穴は,支持軸体の中心に穿設されていて,中間フィンに貫通孔 はなく(原判決別紙「被告製品の後端フィンの後面に設けられたねじ穴 に関する意匠(構成態様)」参照),この穴の存在は正面視や左側面視\nでは認識できず,右側面視にて初めて認識されるところ,ねじ穴にすぎ ないことに照らせば,需要者において,その存在に特に注意を向けると は考えにくく,これを美感の違いとして捉えることはないものと認めら れる。 そうすると,イ号意匠は,これを全体として観察すると,本件意匠の 要部とは複数の差異点が存するものの,それらはいずれも大きな差異と は認められず,その他の点において共通しているということができるか ら,本件意匠と共通の美感を起こさせるもので,本件意匠に類似すると 認められる。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 部分意匠
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成30(ネ)10071 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
このような乙2の記載によれば,サーバーコンピューター330 とクライアントコンピューター370がワールドワイドウェブ36 0を介して接続され,サーバーコンピューター330に登録された ユーザーによって入力される連絡相手情報を含むユーザー情報デー タベース340が設けられた構成において,1)メンバーA(本件各 発明における第一の登録者)がメンバーB(本件各発明における第 二の登録者)に任意の許可レベルでリンクされ,メンバーBがメン バーC(本件各発明における第三の登録者)に任意の許可レベルで リンクされる場合に,メンバーCがメンバーBに友人の友人許可を 与え,メンバーBもメンバーAに友人の友人許可を与える場合には, メンバーAは,メンバーCについての友人の友人通知を受信する資 格があること,2)「友人テーブル」がユーザー(本件各発明におけ る登録者)を互いに関連付け,3)「友人の友人システム」によって, 第1のユーザー(本件各発明における第一の登録者)は,第1のユ ーザーと同じ都市に住んでいるか,又は第1のユーザーが所属する グループに所属する連絡相手の連絡相手の名前を探索でき,第1の ユーザーが友人の友人探索を実行し,友人の友人である第2のユー ザー(本件各発明における第三の登録者)の場所を特定した後に, 第1のユーザーは第1のユーザーの個人アドレス帳に第2のユーザ ーを追加するために,第2のユーザーにリンクすることができ,4) 第1のユーザーが第2のユーザーを指定すると,第2のユーザーは, 第1のユーザーが第2のユーザーに「リンクした」という通知を受 信し,5)第2のユーザーがリンクに応じることを選択する場合には, 第2のユーザーはデータフィールド許可を設定して第1のユーザー のために個人情報等の閲覧を許可することの通知を送信し,この通 知を受信したときに,第1のユーザーの個人アドレス帳に第2のユ ーザーの職業や個人情報等を表示する構\成の記載がある。
c 以上のとおりの本件優先日当時の従来技術に照らせば,より広範で 深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人間関係登録システ ムを提供するとの課題について,上記のような解決手段が存在したも のということができる。
ウ このように,本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載 されているところは,優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て 不十分なものであるから,本件明細書に記載されていない上記イ(イ)のと おりの従来技術も参酌して従来技術に見られない特有の技術的思想を構\n成する特徴的部分を認定すべきことになる。 そして,上記イ(イ)のとおりの従来技術に照らせば,本件各発明は,主 要な点においては,従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示する にとどまり,従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し, その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから, 本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり,上記従来技術 に照らし,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分につ\nいては,本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定する のが相当である。
エ そうすると,被告サーバが構成要件1D及び2Dの構\成を備えていない のは前記1に説示のとおりであるから,被告サーバは本件各発明の本質 的部分の構成を備えるということはできず,均等の第1要件を充足しな\nい。
オ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は,引用発明は具体的にはネットワークを通じて連絡相手情 報を管理する発明であって,相互に情報を交換し合うことによって新 たに人間関係を締結するというソーシャルネットワーキングサービス\n(SNS)の発明ではないから,本件各発明とは技術思想が根本的に 異なるものであり,本件各発明の本質的部分を認定するに当たり参照 されるべき従来技術ではないと主張する。 しかし,本件明細書にはソーシャルネットワーキングサービス(SN\nS)であることの記載はなく,上記イに説示したところに照らせば,本 件各発明と引用発明は,いずれも共通の人間関係を結んでいる登録者の 検索を可能とし,新たに人間関係を結び,これを登録することができる\n発明である点で共通するものであるから,本件各発明の従来技術として 引用発明を参照することができるというべきである。
(イ) 控訴人は,本件各発明の構成のうち,従来技術に見られない特有の\n技術的思想を構成する特徴的部分は,「登録者が互いにメッセージを\n送信し合うことによって人間関係を結ぶ(友達になる)という意思が 合致した場合(合意が成立した場合)に,当該登録者同士を関連付け て記憶するという技術を前提として,共通の人間関係を結んでいる登 録者(友達の友達)の検索を可能とし,新たに人間関係を結ぶことが\nできるようにすることによって,より広範で深い人間関係を結ぶこと ができるという構成」にあると主張する。\nしかし,従来技術との比較において本件各発明の貢献の程度は大きく なく,本件各発明の本質的部分は特許請求の範囲とほぼ同義のものと認 定すべきことは上記イ及びウに説示したとおりである。
(ウ) 控訴人は,2人の個人が互いに人間関係を結んでいるかどうかは, 多分に個人の主観的な評価を伴う問題であって,引用発明において個 人情報の閲覧を許可したからといって,人間関係を結ぶことを承諾し たということにはならないと主張する。しかし,引用発明は,第1の ユーザーが第2のユーザーをリンクすると,第2のユーザーはその旨 の通知を受信し,リンクに応じる場合は第2のユーザーが第 1 のユーザ ーにデータフィールド許可を設定でき,第2のユーザーは第1のユー ザーに個人情報許可,仕事情報許可,経路交差通知許可などを与える ことができるのであり,これは,人間である第1のユーザーと人間で ある第2のユーザーが関係を結ぶことに他ならないから,第1のユー ザーと第2のユーザーが人間関係を結ぶものと理解することができる。
(エ) さらに,控訴人は,乙2の【0072】,【0073】に「友人の 友人システム」という表現は存在するものの,その実質は,自己の個\n人アドレス帳に他のメンバーが登録されている場合に,当該他のメン バーの個人アドレス帳の中を検索するというものにすぎず,「友人」 とは,本件各発明における当事者間の合意によって結ばれるところの 「人間関係」とは別物であると主張するが,本件各発明において「人 間関係を結ぶ」ことの意義について,引用発明における構成を除外す\nることを示す記載はなく,引用発明において,第1のユーザーがリン クし,第2のユーザーがリンクに応じることにより,人間関係が結ば れるといえることについては,上記説示のとおりである。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成29(ワ)22417
本件特許権の別被告(ミクシィ)の事件があります。
こちらも、1審、控訴審とも非侵害と判断されています。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.09.12
平成29(ワ)8272 損害賠償等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和元年8月29日 大阪地方裁判所(26部)
ア 本件登録意匠及び被告意匠の各構成態様を対比すると,別紙「構\成対比表\n(裁判所の認定)」の「本件登録意匠」欄及び「被告意匠」欄に各記載のとおりで あるところ,このうち下線部を付した箇所が差異点であり,それ以外の箇所が共通 点である。
イ 本件登録意匠の要部について
被告意匠も,水路部のレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成るもの であり(基本的構成態様A,C,D),この点で本件登録意匠と被告意匠は共通す\nる。この共通点により,両意匠とも,ウォータースライダー型及び流水プール型の 各そうめん流し器を別個独立に捉えた場合とは異なる新規な構成を有するという印\n象を生じる。
ウ 本件登録意匠の要部以外の部分について
(ア) 意匠全体に対して物理的に大きな割合を占めるだけでなく,需要者が関心を持 つレール部の形態については,被告意匠の構成態様は,ヘアピンカーブ状に湾曲後\nに僅かに凹弧状に湾曲しているか否かを除けば,本件登録意匠の構成態様と共通す\nる(具体的構成態様G)。\nこのうち,共通点は,意匠全体に対して占める物理的な割合が大きいことから, 原告旧商品意匠のレール部の形態と同様の形態であるといっても,全体の印象に与 える影響は大きいといえる。 他方,差異点は,かなり注意を払わなければ認識し難いほどに僅かな差異であり, 全体の印象に与える影響は小さいといえる。
(イ) 需要者が関心を持つトレイ部内部の形状については,被告意匠の構成態様は,\n回転器の上面の凹陥部の形状を除けば,本件登録意匠の構成態様と共通する(具体\n的構成態様I)。\nこのうち,共通点は,トレイ部内部の形状の中でも需要者が特に関心を持つと考 えられるそうめんが流れる流路の形状についてのものであることから,流水プール 型のそうめん流し器に係る前記各公知意匠と同様の形状であるといっても,全体の 印象に与える影響は大きいといえる。 他方,差異点は,意匠全体に対して占める物理的な割合は小さいことから,全体 の印象を左右するほどのものとはいえない。
(ウ) そのほか,被告意匠には,1)トレイ部の外形状(基本的構成態様D),2)水路 部の上端部分における吐水口部分の形状(具体的構成態様F)及び3)トレイ部にお ける左方基端部の中央支柱が接続するブロック材状部材の嵌装の有無(具体的構成\n態様I)において,本件登録意匠と差異がある。 このうち,1)については,本件登録意匠及び被告意匠のいずれにおいても,真上 から見た場合には水路部上端部分の皿状部材にその大部分が隠れる位置関係にある とともに,トレイ部内部のそうめんが流れるトラック形部分の壁面を構成しない左\n方部分における差異であるから,流しそうめんを楽しむ際に需要者がさほど関心を 向けない部分といえる。また,3)については,トレイ部内部のそうめんが流れる部 分に隣接するものの,そうめんの流れと直接的に関わるものではないことなどから, 需要者がそうめん流しを楽しむ際に必ずしも関心を向けない部分である。これらの ことから,1)及び3)の各差異点は,いずれも全体の印象に与える影響は小さいとい える。
他方,2)については,そうめんを流すための水が吐出される部分であり,そうめ んを流す際に必然的に需要者が目にする部分ではある。しかし,当該部分が意匠全 体に対して物理的に占める割合は必ずしも大きくはなく,また,需要者がそうめん 流しを楽しむに当たって吐水口部分の形状に強い関心を持つとも思われない。した がって,2)の差異点は,全体の印象に大きな影響を与えるものではない。 オ 以上の点を踏まえると,両意匠は要部を共通にし,需要者に対し,本件登録 意匠の意匠登録出願前に存在したウォータースライダー型及び流水プール型のそう めん流し器とは異なり,両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器である という共通の印象を与えた上で,全体的に同様の形状をも備えているという印象を 強く与えており,このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるも のではない。したがって,被告意匠は,本件登録意匠に類似するものと認められる。 これに反する被告の主張はいずれも採用できない。 そうすると,被告による被告商品の販売等の行為は,本件意匠権を侵害するもの である。
2 争点1−2(無効理由の存否)について
被告は,本件において,本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効に されるべき理由として3点を主張している。 しかし,前記第2の2(4)の認定事実に加え,証拠(甲45)及び弁論の全趣旨に よれば,本件において本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効にされ るべき理由として被告が主張する新規性欠如1及び同2並びに創作非容易性欠如は, それぞれ本件審判請求の無効理由1〜3と「同一の事実及び同一の証拠」に基づく ものといえる。 被告は,特許法167条を準用する意匠法52条により,確定した本件審決に係 る本件審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて本件意匠権の設定登録 につき意匠登録無効審判を請求することができない。このため,被告は,本件にお いて主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求する ことは,もはやできない。 意匠法52条が準用する特許法167条の趣旨は,紛争の一回的な解決を図るた め,審決が確定した後に同一の当事者等が同一の事実及び証拠に基づいて再び審判 を請求することにより紛争を蒸し返すことを許さない点にある。そうすると,同条 に当たる事情が存するときは,意匠法41条が準用する特許法104条の3の「当 該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」に当たら ず,意匠権侵害訴訟における同条の主張は認められないと解するのが相当である。 したがって,本件意匠権の設定登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべ きものとはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。
3 差止請求・廃棄請求の可否について
(1) 意匠権に関する請求関係 以上のとおり,被告商品の製造,販売等は,本件意匠権の侵害行為を構成すると\nころ,被告の応訴態度に鑑みると,被告が被告商品を製造,販売等するおそれは依 然としてあるといえる。したがって,被告商品の製造,販売等の差止めの必要性は あるから,差止請求は認められる。 他方,証拠(乙15〜28,47〜55)及び弁論の全趣旨によれば,被告は, 輸入した被告商品を平成29年6月13日に販売したのを最後に,これ以降被告商 品を製造,販売等した実績は認められず,現在,輸入した被告商品を全て販売済み であり,在庫を保有しているとは認められない。そうである以上,被告商品の廃棄 については,その必要性を欠き,廃棄請求を認めることはできない。 (2) 不正競争防止法に関する請求関係 原告は,予備的に,被告商品の販売が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競\n争に当たることを前提に,同法3条2項に基づく廃棄請求をする。 しかし,上記(1)と同様に,被告が被告商品の在庫を保有しているとは認められな い以上,被告商品の販売が不正競争に当たるか否かについて判断するまでもなく, 同項に基づく廃棄請求は認められない。
2019.09.11
平成31(ワ)3277 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月29日 大阪地方裁判所
ア 前記1で認定したところによれば,1)被告P5,被告日本知財開発及び被告 ジンムは,本件各特許権を被告P5と被告日本知財開発の共有とし,これに被告ジ ンムの専用実施権を設定した上で,本件各特許権を細分化して譲渡するという枠組 みを考案したこと,2)この枠組みは,被告日本知財開発を管理委託機関とし,被告 日本知財開発より委託を受けたリーフ,被告ecoリーフあるいはさらにその下請 けであるはなみずきその他が顧客に案内し,代金等を収受するものであること,3) リーフらの担当者又は代表者であるP9,P10,被告P3らは,原告に対し,被\n告ら側が本件地盤特許侵害訴訟に勝訴することや,本件ナビ特許について大手企業 とロイヤリティについて契約したり,多額の対価を得て本件ナビ特許を売却したり することにより,本件各特許権の共有持分の価値が上がり,原告に莫大な利益が還 元されるかのような説明をし,これにより,原告が本件各特許権の持分を購入する に至ったこと,4)原告の前記購入後,被告日本知財開発は,被告P5が作成した報 告書を原告に送付したが,その内容は,前記3)に沿うものであったこと,以上の事 実が認められる。
イ 他方,前記1によれば,原告が前記購入した時点で,1)本件各特許権の残存 期間はごくわずかであったこと,2)被告P5及び被告日本知財開発が被告ジンムよ り専用実施権の対価を得ていたことは認められず,これ以外に,本件各特許権につ いて第三者からのライセンス料が得られるような具体的案件が進行中であった,あ るいは将来的に本件特許権の価値が上昇し,高額で転売し得る見込みがあったこと を示すような客観的証拠は何ら提出されていないこと,3)本件地盤特許については, 権利存続期間満了の直前にこれを無効とする審決があり,本件地盤特許侵害訴訟に ついては請求棄却となっているが,被告日本知財開発やリーフらの関係者が,これ を適切に原告に説明していたとは認められず,かえって,訴訟がうまくいっていな いことを理由に原告に本件地盤特許を本件ナビ特許に振り替えさせ,その際に,新 たに本件ナビ特許の持分を購入させたこと,4)本件で現れたどのような事情を考慮 しても,本件地盤特許の2万分の1の持分を60万円,本件ナビ特許の持分10万 分の1の持分を20万円と評価すべき理由は見出されないこと,5)実際に,被告P 5又は被告日本知財開発が,本件各特許権について,ライセンス収入や損害賠償な ど,持分の譲受人に対し配分可能な収入を得たと認めるべき証拠はなく,3口分の\n解約に伴う返戻金を除き,被告らから原告に金員が支払われた事実がないこと,6) 原告は,持分の転売が可能との説明を受けたが,原告の持分取得については,被告\n日本知財開発が作成した証書に記載されるにとどまり,特許原簿への登録がないた め,権利者としての保護はないこと,以上の点を指摘することができる。
ウ 以上ア及びイで述べたところを総合すると,原告が本件各特許権の持分の譲 渡を受けた際に,リーフ,被告ecoリーフ,はなみずきの担当者又は代表者であ\nるP9,P10,被告P3らがした前記⑴ア3)の説明は,客観的裏付けのない,原 告に金員を出させることのみを目的とした虚偽のものであったといわざるを得ない。 そして,本件各特許権の持分を細分化して高額で譲渡するという基本的枠組みは, 被告P5,被告日本知財開発,被告ジンムの関与がなければ成立し得ないものであ り,前記P9らは,被告日本知財開発らが定めた基本的枠組み,あるいは被告P5 が作成し被告日本知財開発が配布した報告書の内容に沿って案内をしたものと認め られるから,前記P9らが被告P5,被告日本知財開発及び被告ジンムと無関係に, 原告に案内,説明したと考える余地はなく,同被告らは,前記P9らが原告に前記 虚偽の説明をして本件各特許権の持分を取得させたことを認識していたものと認め ることができる。
(2) 共同不法行為の成立について
ア 前記1で認定したとおり,原告に対する本件各特許権の持分の譲渡は,4年 余りの間,13回にわたって行われたものであり,前半は本件地盤特許について, 書面上は被告ecoリーフを譲渡店とし,その下請けのはなみずきを介して行われ, 後半は本件ナビ特許について,書面上はリーフを譲渡店として行われたものである。 しかしながら,既に検討したとおり,本件地盤特許と本件ナビ特許の各持分の譲 渡は,いずれも被告P5,被告日本知財開発及び被告ジンムが設定した同様の枠組 みに従って行われており,また本件地盤特許侵害訴訟がうまくいかなくなるや,そ れを契機として本件ナビ特許の案内を行い,原告にその持分を取得させているので あるから,本件地盤特許の持分の譲渡も,本件ナビ特許の持分の譲渡も,全体とし て一連のものとして行われたというべきであり,被告P5,被告日本知財開発,被 告ジンム,リーフ,被告ecoリーフ及びはなみずきの責任を,本件地盤特許の持 分の譲渡と,本件ナビ特許の持分の譲渡とに分断して考えることはできない。 そして,前述のとおり,原告が被告ecoリーフの下請けであるはなみずきのP 9から本件地盤特許について虚偽の説明を受け,リーフの担当者であるP10又は 代表者である被告P3から,本件ナビ特許について虚偽の説明を受けたことにより,\n代金及び手数料を支払ったことが認められ,被告P5,被告日本知財開発及び被告 ジンムはこれを認識していたと認められるのであるから,被告ecoリーフ,はな みずき,リーフ,被告P5,被告日本知財開発及び被告ジンムは,原告が,虚偽の 説明により,本件各特許権の持分代金及び手数料の名目で金員を詐取されたことの 全体について,共同不法行為責任を負うというべきである。
イ また,本件各特許権の持分譲渡受申込要項(甲3,26)には,権利金の支\n払は保証するものではない旨の記載があり,リーフが書証として提出するチェック シート(乙4の1)には,原告により,平成27年1月22日に本件ナビ特許の持 分を譲り受けた際に,権利金は現在未確定である旨の説明を受けたこと,説明中に 断定的な収入例,又は誇大表現で収入例を強調されていないこと等のチェック欄に\nつき,いずれも「はい」の欄に丸が付けられている。 しかしながら,このような形式的記載によって,前記検討した上記被告らの不法 行為責任は,左右されるものではない。
2019.09.11
平成30(ワ)2554 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月27日 大阪地方裁判所
被告は,「挟み込んで保持する」という文言について経時的に解釈し,これを, 第二保持部がブレースボルトをその軸方向に沿って外周側から挟み込み,これを仮 に保持した状態でブレースボルトの軸方向に移動して位置調整を行った後に,ナッ トで締め付けて保持するという操作方法に限定される旨を主張し,ブレースボルト を第二保持部が挿通する場合はこれに含まれないから,ブレースボルトを第二保持 部に挿通する被告製品は,本件発明の構成要件を充足しないと主張する。\nしかしながら,構成要件1Cの「挟み込んで保持する」は,物の発明の一要素と\nして,ブレースボルトが,これを包囲する包囲部によりベース板部に固定されるこ と,すなわち「狭着保持」(本件各明細書の段落【0044】,【0049】ない し【0052】等)を意味すると解するのが相当である(なお,被告は,「挟着」 と「狭着」の違いについて,前者は「挟み込む」という予備的動作を指すのに対し,\n後者は「狭める」という最終的操作を意味する,と主張する。しかし,本件各明細 書においては,「挟み込んで保持する」及び「挟み込んで狭着保持する」という2 通りの言い回しがみられるものの,これらが被告の主張のように明確に区別して用 いられているということはできず,「挟み込んで」,「挟着」及び「狭着」という 文言は基本的に同義であると解すべきである。)。 本件各明細書の段落【0008】に,「この構成によれば,(中略)固定片の孔\n部に第二棒状体を挿通させる必要がなく」との記載がある点については,従来技術 において,ブレースボルトが長過ぎる場合,これを切断する等して調整せざるを得 ないが,本件発明の場合,固定片のナットをゆるめて,外周側からブレースボルト を挟むことができるということを,特別な場合における利点として述べたにすぎず, ベース板部と固定片の間に形成される孔部にブレースボルトを挿通することのでき る通常の場合にまで,外周側からブレースボルトを挟み込むことを要件とする趣旨 とは解し得ない。 そうすると,被告の主張するような上記操作方法は,本件発明における構成要件\n充足性の判断を左右するものではない。
(3) 被告製品の施工方法について(甲19,乙4,22)
被告が,被告製品1の施工に際し,安全性確保等の見地から,ブレースボルトを 第二保持部に外周側から挟み込むことはせずに,第二保持部にあらかじめブレース ボルトを挿通できる程度の間隙を開けておき,ブレースボルトを第二保持部の当該 間隙に挿通させて使用する(被告製品2については,第二保持部が開口部の狭いル —プ状板部で構成されるため,ブレースボルトを第二保持部に挿通して使用するこ\nとは明らかである。)ことは当事者間に争いはないが,上記⑴及び⑵で検討したと ころによれば,上記施工方法の結果は,本件発明の「挟み込んで保持する」に該当 するというべきであり,これに反する被告の主張は採用できない。
・・・
被告は,乙13を適宜設計変更したものとして副引用発明を設定するところ, 乙13発明は,同一平面上に配置された2本の棒状体の交差する箇所において,乙 13に記載された物品(以下「本物品」という。)を2つ,各棒状体をそれぞれ覆 うようにして対向配置させて装着し,それぞれの本物品の角度調整用の弧形状の孔 (角度調整用長穴)を利用してボルトにより緊結することにより,2本の棒状体を 連結・固定するものである。 これに対し,副引用発明は,本物品と,本物品から包囲部を取り除いた状態の平 面の板状部材(以下「平面部材」という。)から構成されているところ,平面部材\nは棒状体を覆うことができないので,本物品と平面部材を組み合わせても乙13に 記載されたような交差連結具として使用することはできない(本物品1個と平面部 材1個を組み合わせた場合,保持可能な棒状体は1本のみである。)。また,本物\n品及び平面部材は互いの角度を調整する必要がないから,両部材に存する上記弧形 状の孔の存在意義がなくなってしまう。 したがって,当業者が,乙13発明から副引用発明を導くことは困難である。 また,被告は,乙13以外にも乙12,14ないし20を引用し,天井から 吊設機器を吊り下げるボルトが交差する部位を連結する揺れ止め用交差連結具も慣 用技術であると主張し,当業者は,乙1発明の両端の外側狭着体の平面域に,斜め 支持体に代えて副引用発明を適用して連結することで,被告製品1(すなわち本件 発明)を容易に発明することができる,と主張する。 しかし,乙12,14ないし20に記載された発明も,乙13発明と同様に,同 一平面上に配置された2本の棒状体を,その交差する箇所を覆うように装着するこ とで,連結・固定して振れ止めするための交差固定金具に係るものであって,被告 の主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。\nなお,被告は,このほかにも,乙8,10,24ないし28を引用して,1本の 棒状体を狭着して固定するにあたって,狭着する一方が棒状体を包囲する包囲部を 備えた部材,他方が平面上の部材である慣用技術である旨主張し,乙8ないし11 を引用して,2本の棒状体を狭着して固定する連結具も慣用技術である旨主張する が,いずれにおいても,一対の部材のうち,一方の部材にのみ包囲部を設け,もう 一方の部材を平面状とする交差固定金具の技術は開示されておらず(乙8及び乙2 6に開示された発明は,2つの固定具の間に平板の基板を挟み込む形を採るが,そ れぞれの固定部が包囲部を備えている点については上記の他の発明と同様である。), 被告が主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。\n以上より,副引用発明は,乙13を含めて乙8ないし20のいずれにも開示 されているとはいえない。
オ 容易想到性について(相違点1)
被告は,本件発明や乙1発明のようなコーナー固定金具と,乙12ないし20に 開示されるような交差固定金具とは,同一の技術分野に属し,また,施工現場で同 じ吊設機器において併用されることが多いから,当業者には,コーナー固定金具の 第二支持部に交差固定金具を適宜設計変更して適用する動機付けがある旨主張する。 乙12ないし20に記載される発明から,被告が主張するような副引用発明が導 けないことは上記エで述べた通りであるが,仮にこの副引用発明の具体的構成を措\nくとしても,交差固定金具とコーナー固定金具は,固定する棒状体の本数も固定の 態様も全く異なるものであるところ,単に吊設機器上の近い位置で用いられる2種 類の金具であるからといって,適用の動機付けを認めることはできない。 したがって,設計変更される副引用発明の具体的構成がどうあれ,乙1発明に上\n記刊行物記載の発明を適用する動機付けがあるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.09. 9
平成30(行ケ)10084 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所
本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件発明1は,アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法の発明であって,アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして,「35ppm未満の遊離SO2」と,「3 00ppm未満の塩化物」と,「800ppm未満のスルフェート」とを有することを特徴とするワインを意図して製造するステップを含むものであるから,所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1の課題を明示 した記載はないが,【0002】ないし【0004】の記載(前記(1)イ(ア)) から,本件発明1の課題は,アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすることであり,ここ にいう「ワインの品質」は,「ワインの味質」を意味するものと理解で きる。 そして,本件明細書の【0038】ないし【0042】及び表1には,\n白ワインの保存評価試験の結果として,パッケージングされた白ワイン を30℃で6ヶ月間保存した後に,味覚パネルによる官能試験により,\n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が\nあることに照らすと,本件明細書の発明の詳細な説明には,ワインの品 質(味質)が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判\n断されることの開示があることが認められる。
一方,上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され\nた」ワインについて,表1には,別紙のとおり,保存期間「6ヶ月」に\n対応する「Al mg/L」欄及び「初期に対するAl含有量上昇率(%)」 欄に,アルミニウム含有量0.72mg/L,含有量上昇率44%(「直 立」状態で保存の缶),アルミニウム含有量0.68mg/L,含有量 上昇率36%(「倒立」状態で保存の缶)であったことの記載があるが, 表1を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても,当該ワ\nインの保存開始時(「初期」)の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また,本件明細書の【0003】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質,及び,ワインと容器との反応生成物の,ワイン品質,特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【0034】の「良 好に架橋された不透過性膜によって,保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から,アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの, 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても,アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに,アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず,上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも,本件優先日当時,遊離SO2とアルミニウムとの間の酸化還元 反応により硫化水素が発生し,この硫化水素によってワインのフレーバ ーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと(甲50, 51等)が認められるが,かかる技術常識に照らしても,遊離SO2の濃 度にかかわらず,ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワイン の味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明の記載から,本件発明1 の課題(「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質(味質) が保存中に著しく劣化しないようにすること」)を解決できるかどうか を確認する方法は,味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを\n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ,前記(ア)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明に は,白ワインの保存評価試験(【0038】ないし【0042】及び表\n1)において「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」\nワインの保存開始時(「初期」)の塩化物及びスルフェートの各濃度に ついての具体的な開示はなく,仮にこれらの濃度が,本件発明1で規定 するそれぞれの濃度(「300ppm未満の塩化物」及び「800pp m未満のスルフェート」)の範囲内であったとしても,それぞれの上限 値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから,上 記保存評価試験の結果から,本件発明1の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲(300ppm未満)及びスルフェートの濃度範囲(8 00ppm未満)の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された\nものと認識することはできないというべきである。 また,甲1及び甲43(「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」200 2年,Zairyo-to-kankyo,51,p.293〜298)によれば,ワインを組成する 一般的な物質のうち,遊離SO2,塩化物イオン(Cl−)及びスルフェ ート(SO4 2−)以外にも,リンゴ酸,クエン酸等の有機酸がアルミニウ ムの腐食原因となることは,本件優先日当時の技術常識であったことが 認められる。このような技術常識に照らすと,本件明細書の発明の詳細 な説明には,白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成につい ての記載はないものの,これらのアルミニウムの腐食原因となる物質も, 当該ワインの組成に含まれており,表1記載の保存期間「6ヶ月」に対\n応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験結果に影\n響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。\n以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から,当業者が本件発明1に含まれる塩化物の濃度30 0ppm未満及びスルフェートの濃度800ppm未満の数値範囲の全 体にわたり本件発明1の課題を解決できると認識できるものと認められ ないから,本件発明1は,サポート要件に適合するものと認めることは できない。
(3) 原告の主張について
原告は,本件優先日当時,1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度は, 生産国・地域,品種,収穫年,製造条件等の違いによりワイン毎に様々であ り,いずれの濃度分布も広範囲に亘っており,塩化物の濃度は3ppmから 1148ppmの範囲で,スルフェートの濃度は38.6ppmから242 0ppmの範囲で分布していること,及び,「300ppm」以上の塩化物 及び「800ppm」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存在す ること(甲31,59ないし63,136の1),2)「淡水」とは塩分濃度 が500ppm以下,塩化物濃度が約300ppm以下の水であること(甲 137の1,2,139,140),3)塩化物イオン(Cl−)及びスルフェ ート(SO4 2−)が,アルミニウムやステンレスの局部腐食(不動態被膜の孔 食)の原因となるイオンであること(甲78,80ないし84,137の1, 2)は,技術常識であったことに加えて,本件明細書の「このような不成功 の理由は,ワイン中の物質の比較的攻撃的な性質,及び,ワインと容器との 反応生成物の,ワイン品質,特に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」 (【0003】)との記載を考慮すれば,当業者であれば,アルミニウムの 腐食原因であるワイン中の物質が「低い」濃度レベルであることを規定する, 本件発明1の「35ppm未満」の遊離SO2,「300ppm未満」の塩化 物及び「800ppm未満」のスルフェートとの要件を満たすワインをパッ ケージング対象とすることによって,これらの腐食原因物質の濃度が高いワ インがアルミニウム缶にパッケージングされることを確実に防止できるとい う本件発明1の効果を容易に認識可能であり,本件発明1は,この効果によ\nって,「アルミニウム缶内にワインをパッケージングし,これによりワイン の品質が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題(「アルミニウ ム缶の腐食によって保存中にワインの中で増加してしまうアルミニウムイオ ン及び硫化水素によって,ワイン品質(味,色,臭い)が保存中に著しく劣 化しないようにする」という課題)を解決するものであることを容易に認識 できること,そして,アルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を 300ppmよりも低くすればするほど,同腐食原因である「スルフェート」 の濃度を800ppmよりも低くすればするほど,アルミニウム缶の腐食防 止効果がより高まることは容易に認識できることからすると,本件発明1の 上記効果は,特許請求の範囲の全てにおいて奏する効果であることを当業者 が認識できることは明らかであり,本件明細書の【0038】ないし【00 42】記載の試験結果を参酌しなくても,本件優先日当時の技術常識に照ら し,本件明細書のその余の発明の詳細な説明の記載及び本件発明1の特許請 求の範囲の記載から,本件発明1は,当業者が本件発明1の課題を解決でき ると認識できる範囲のものであるといえるから,本件発明1は,サポート要 件に適合する旨主張する。
しかしながら,前記(2)イ(ア)認定のとおり,本件発明1の課題は,アルミ ニウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化し ないようにすることにあるものと認められるところ, 原告主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても,当業者が,本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から,本件発明1は,「35ppm未満」の遊離SO2, 「300ppm未満」の塩化物及び「800ppm未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によっ て,本件発明1の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認 めることはできない。 また,原告が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を300ppmよりも低くすればするほど,同腐食原因である「スル フェート」の濃度を800ppmよりも低くすればするほど,アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても,前記(2)イ(ア)認定のとお り,アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく,本件発明1の上記課題 を解決できるかどうかを確認する方法は,味覚パネルによる官能試験の試験\n結果によらざるを得ない。そして,本件明細書の【0038】ないし【00 42】及び表1記載の白ワインの保存評価試験の結果から,本件発明1の対\n象とするワインに含まれる塩化物の濃度範囲(300ppm未満)及びスル フェートの濃度範囲(800ppm未満)の全体にわたり「ワインの味質」 が保存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果に\nより確認されたものと認識することはできないことは,前記(2)イ(イ)のとお りである。 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から,当業者が本件発明1に含まれる塩化物の濃度300ppm未 満及びスルフェートの濃度800ppm未満の数値範囲の全体にわたり本件 発明1の課題を解決できると認識できるものと認められないから,原告の上 記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.09. 9
平成31(ネ)10002 不正競争行為差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審(東京地裁29部)は、周知性、類似までは認めましたが、「混同を生じさせる行為」とはいえないとして、請求棄却していました。
原告商品の形態は,控訴人が昭和59年に「SBバック」の商品名で原告 商品の販売を開始した当時から,他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を 有していたものであり,その後被告商品の販売が開始された平成30年1月 頃までの約34年間の長期間にわたり,他の同種の商品には見られない形態 として,控訴人によって継続的・独占的に使用されてきたことにより,少な くとも被告商品の販売が開始された同月頃の時点には,需要者である医療従 事者の間において,特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別 機能を獲得するとともに,原告商品の出所を表\示するものとして広く認識さ れていたこと,原告商品と被告商品は,同一の形態に近いといえるほど形態 が極めて酷似し,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似することは,前 記2(2)ア及び3(1)ウ認定のとおりである。
そして,前記1の認定事実によれば,医療機器の取引プロセス等に係る取 引の実情として,1)医療機関が医療機器を新規に購入する場合,医療従事者 が,医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者から,商品説明会等で当 該医療機器の特色,機能,使用方法等に関する説明を受けた後,臨床現場で\n当該医療機器を1週間ないし1か月程度試行的に使用し,使い勝手,機能性\n等の評価を経た上で新規採用を決定し,医療機器メーカー又は販売代理店に 対して当該医療機器を発注することが一般的であり,一定の病床数を有する 医療機関にあっては,医師,看護師その他の医療スタッフから構成される「材\n料委員会」が開催され,その構成メンバーによる協議を経て,当該医療機器\nの新規採用が決定されているが,一方で,個人病院や病床数が少ない医療機 関にあっては,材料委員会が開催されることなく,医師の意向により新規採 用が決定される場合も少なくないこと,2)医療機関が従前から使用している 医療機器を継続的に購入する場合,各種医療機器の画像,品番,仕様,価格 等が記載された医療カタログに基づいて,医療機器メーカー又は販売代理店 の販売担当者に対して品番等を伝えて発注し,また,インターネット上のオ ンラインショップで購入する場合があること,3)消耗品等の比較的安価な医 療機器については,医療機関が新規に購入する場合においても,医療カタロ グに基づいて医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等 を伝えて購入したり,オンラインショップで購入することもあること,4)医 療機関においては,用途が同じであり,容量等が同様の医療機器については, 一種類のみを採用し,新たな医療機器を一つ導入する際には同種同効の医療 機器を一つ減らすという「一増一減ルール」が存在するが,「一増一減ルー ル」は,主に大学病院,総合病院等の大規模な医療機関において採用されて おり,小規模の医療機関においては,各医師がそれぞれ使いやすい医療機器 を使用する傾向が強いため,そもそも「一増一減ルール」が採用されていな い場合があり,また,「一増一減ルール」を採用している医療機関において も,徹底されずに,医師の治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定し て使用したり,新規の医療機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間 があるなど,同種同効の医療機器が複数同時に並行して使用される場合があ り得ること,5)バーコードで医療機器を特定して発注や在庫管理を行い,ま た,医療機関で使用される物品の発注,在庫管理,病棟への搬送などのサー ビス(SPD)を事業者に委託している医療機関もあるが,全ての医療機関 において,このようなバーコードを利用した医療機器の発注,在庫管理やS PDの委託を行われているわけではなく,SPDの委託率も決して高いもの ではないこと,6)原告商品及び被告商品は,消耗品に属する医療機器であり, カタログ販売のほかに,商品画像とともに,品番,型番,価格等掲載された オンラインショップ(「アスクル」のウェブサイト)による販売が行われて いることなど,両商品の販売形態は共通していることが認められる。 以上を総合すると,原告商品の形態が,控訴人によって約34年間の長期 間にわたり継続的・独占的に使用されてきたことにより,需要者である医療 従事者の間において,特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識 別機能を獲得するとともに,原告商品の出所を表\示するものとして広く認識 されていた状況下において,被控訴人によって原告商品の形態と極めて酷似 する形態を有する被告商品の販売が開始されたものであり,しかも,両商品 は,消耗品に属する医療機器であり,販売形態が共通していることに鑑みる と,医療従事者が,医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商 品画像等を通じて原告商品の形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した 場合には,商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるものと認められ るから,被控訴人による被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行 為に該当するものと認められる。
(2) これに対し被控訴人は,1)医療機関においては,多数の医療従事者が関与 し,試用期間を設けて商品の機能や安全性等に着目して慎重に医療機器の選\n定が行われ,製品名や規格等に着目して販売代理店を通じた発注や物品の管 理が行われるのであるから,通常,医療機器の購入に際して,商品の形態に 着目したり,形態を手がかりに商品が購入されることはなく,このことは, 医療機器カタログやオンラインショップを通じて医療機器が購入される場合 であっても同様であること,2)医療機関が臨床での試用や機能性等の評価を\n経て採用した商品を継続購入する場合は,医療機器カタログやオンラインシ ョップを通じて購入するが,医療機関においては,商品名や品番等により採 用している医療機器と同一の医療機器を発注するよう管理しており,商品の 形態だけを見て発注することはないし,カタログ購入やオンラインショップ 購入の場合でも,これまで医療機関が発注したことのない医療機器が新たに 発注されたときには,必ず医療機関に連絡を行い,試用を勧めることが通常 であること,3)原告商品と被告商品がオンラインショップ等で同一の機会に 販売されることがあったとしても,そもそも,医療従事者は商品形態には着 目しない上,オンラインショップにおいては商品の商品名及び製造販売元等 が明記されているのであるから,医療従事者が,その形態のみから,原告商 品と被告商品の出所を誤認混同することはないこと,4)医療機関においては, 用途が同じであり容量等が同様の医療機器については一種類のみを採用する という,いわゆる「一増一減ルール」が採用され,一つの医療機関又は診療 科において,原告商品と被告商品が同時に採用されるといった事態は生じ得 ず,医療従事者が原告商品と被告商品を取り違えたり,使用方法を誤るとい った事態の発生を想定することができないし,仮に単一の医療機関において 同種の複数の医療機器が同時に用いられることがあったとしても,原告商品 及び被告商品にはそれぞれ商品名及び会社名が明確に表示されている上,原\n告商品及び被告商品は,控訴人及び被控訴人のそれぞれが製造販売する専用 のカテーテル以外に接続することができない専用設計品となっており(乙1 3),相互に互換性がなく,このことは添付文書(乙1)等からも確認できる から,実際の発注や使用において両商品の取り違えが生じることはないこと, このような取引の実情を踏まえると,需要者である医療従事者において,原 告商品の形態及び被告商品の形態に基づいて商品の出所の同一性について混 同が生ずるおそれはないから,被控訴人による被告商品の販売は,原告商品 と混同を生じさせる行為に該当しない旨主張する。 しかしながら,上記1)ないし3)の点については,前記2(2)ア認定のとおり, 原告商品の形態は,控訴人によって約34年間の長期間にわたり継続的・独 占的に使用されてきたことにより,需要者である医療従事者の間において, 特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得するとと\nもに,原告商品の出所を表示するものとして広く認識されていたことに照ら\nすと,医療従事者が,原告商品の形態に着目して,医療機器カタログやオン ラインショップを通じて医療機器が購入する場合もあり得るものと認められ る。また,前記2(2)イ認定のとおり,バーコードで医療機器を特定して発注 や在庫管理を行い,また,SPDを事業者に委託している医療機関もあるが, 全ての医療機関において,このようなバーコードを利用した医療機器の発注, 在庫管理やSPDの委託が行われているわけではなく,SPDの委託率も決 して高いものではない。
上記4)の点については,前記(1)認定のとおり,小規模の医療機関において は,そもそも「一増一減ルール」が採用されていない場合があり,また,「一 増一減ルール」を採用している医療機関においても,徹底されずに,医師の 治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定して使用したり,新規の医療 機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間があるなど,同種同効の医 療機器が複数同時に並行して使用される場合があり得ることからすると,「一 増一減ルール」が存在するからといって,原告商品の形態と極めて酷似する 被告商品の形態に接した場合には,商品の出所が同一であると誤認するおそ れがあることが否定されるものではない。また,原告商品及び被告商品は, 控訴人及び被控訴人のそれぞれが製造販売する専用のカテーテル以外に接続 することができない専用設計品となっており,その点においては相互に互換 性がないとしても,そのことから直ちに原告商品又は被告商品を購入する際 に両商品の形態が極めて酷似することにより商品の出所が同一であると誤認 するおそれがあることが否定されるものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2019.09. 9
平成30(ネ)10040 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について,特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件(サポート要件)に適合するか否かは, 当業者が,発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から,当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識で きるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 イ(ア) これを本件についてみるに,本件発明の特許請求の範囲(請求項1) の記載によれば,本件発明は,アルミニウム缶内にワインをパッケージ ングする方法の発明であって,「35ppm未満の遊離SO2」と,「3 00ppm未満の塩化物」と,「800ppm未満のスルフェート」と を有することを特徴とするワインを製造するステップを含むものである から,所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明の課題を明示し た記載はないが,【0002】ないし【0004】の記載(前記(1)イ(ア)) から,本件発明の課題は,アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすること,ここにいう 「ワインの品質」は,「ワインの味質」を意味するものと理解できる。 そして,本件明細書の【0038】ないし【0042】及び表1には,\n白ワインの保存評価試験の結果として,パッケージングされた白ワイン を30℃で6ヶ月間保存した後に,味覚パネルによる官能試験により,\n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が\nあることに照らすと,本件明細書の発明の詳細な説明には,ワインの品 質(味質)が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判\n断されることの開示があることが認められる。
一方,上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され\nた」ワインについて,表1には,別紙のとおり,保存期間「6ヶ月」に\n対応する「Al mg/L」欄及び「初期に対するAl含有量上昇率(%)」 欄に,アルミニウム含有量0.72mg/L,含有量上昇率44%(「直 立」状態で保存の缶),アルミニウム含有量0.68mg/L,含有量 上昇率36%(「倒立」状態で保存の缶)であったことの記載があるが, 表1を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても,当該ワ\nインの保存開始時(「初期」)の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また,本件明細書の【0003】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質,及び,ワインと容器との反応生成物の,ワイン品質,特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【0034】の「良 好に架橋された不透過性膜によって,保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から,アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの, 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても,アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに,アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず,上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも,本件優先日当時,遊離SO2とアルミニウムとの間の酸化還 元反応により硫化水素が発生し,この硫化水素によってワインのフレー バーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと(甲3 9,40等)が認められるが,かかる技術常識に照らしても,遊離SO 2の濃度にかかわらず,ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいて ワインの味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明の記載から,本件発明の 課題(「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質(味質) が保存中に著しく劣化しないようにすること」)を解決できるかどうか を確認する方法は,味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを\n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ,前記(ア)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明 には,白ワインの保存評価試験(【0038】ないし【0042】及び 表1)において「許容可能\なワイン品質が味覚パネルによって確認され た」ワインの保存開始時(「初期」)の塩化物及びスルフェートの各濃 度についての具体的な開示はなく,仮にこれらの濃度が,本件発明で規 定するそれぞれの濃度(「300ppm未満の塩化物」及び「800p pm未満のスルフェート」)の範囲内であったとしても,それぞれの上 限値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから, 上記保存評価試験の結果から,本件発明の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲(300ppm未満)及びスルフェートの濃度範囲(8 00ppm未満)の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された\nものと認識することはできないというべきである。 また,乙29及び甲175(「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」2 002年,Zairyo-to-kankyo,51,p.293〜298)によれば,ワインを組成 する一般的な物質のうち,遊離SO2,塩化物イオン(Cl−)及びスル フェート(SO4 2−)以外にも,リンゴ酸,クエン酸等の有機酸がアル ミニウムの腐食原因となることは,本件優先日当時の技術常識であった ことが認められる。このような技術常識に照らすと,本件明細書の発明 の詳細な説明には,白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成 についての記載はないものの,これらのアルミニウムの腐食原因となる 物質も,当該ワインの組成に含まれており,表1記載の保存期間「6ヶ\n月」に対応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験\n結果に影響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。\n以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から,当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度300 ppm未満及びスルフェートの濃度800ppm未満の数値範囲の全体 にわたり本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められない から,本件発明は,サポート要件に適合するものと認めることはできな い。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は,本件優先日当時,1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度 は,生産国・地域,品種,収穫年,製造条件等の違いによりワイン毎に様々 であり,いずれの濃度分布も広範囲に亘っており,塩化物の濃度は3ppm から1148ppmの範囲で,スルフェートの濃度は38.6ppmから2 420ppmの範囲で分布していること,及び,「300ppm」以上の塩 化物及び「800ppm」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存 在すること(甲24,41,42,51,57,58,101,乙67), 2)「淡水」とは塩分濃度が500ppm以下,塩化物濃度が約300ppm 以下の水であること(甲167,168,169の1,2),3)塩化物イオ ン(Cl−)及びスルフェート(SO4 2−)が,アルミニウムやステンレスの 局部腐食(不動態被膜の孔食)の原因となるイオンであること(甲88ない し90,115ないし117,169の1,2)は,技術常識であったこと に加えて,本件明細書の「このような不成功の理由は,ワイン中の物質の比 較的攻撃的な性質,及び,ワインと容器との反応生成物の,ワイン品質,特 に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」(【0003】)との記載を 考慮すれば,当業者であれば,アルミニウムの腐食原因であるワイン中の物 質が「低い」濃度レベルであることを規定する,本件発明の「35ppm未 満」の遊離SO2,「300ppm未満」の塩化物及び「800ppm未満」 のスルフェートとの要件を満たすワインをパッケージング対象とすることに よって,これらの腐食原因物質の濃度が高いワインがアルミニウム缶にパッ ケージングされることを確実に防止できるという本件発明の効果を容易に認 識可能であり,本件発明は,この効果によって,「アルミニウム缶内にワイ\nンをパッケージングし,これによりワインの品質が保存中に著しく劣化しな いようにする」という課題(「アルミニウム缶の腐食によって保存中にワイ ンの中で増加してしまうアルミニウムイオン及び硫化水素によって,ワイン 品質(味,色,臭い)が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題) を解決するものであることを容易に認識できること,そして,アルミニウム 缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を300ppmよりも低くすればする ほど,同腐食原因である「スルフェート」の濃度を800ppmよりも低く すればするほど,アルミニウム缶の腐食防止効果がより高まることは容易に 認識できることからすると,本件発明の上記効果は,特許請求の範囲の全て において奏する効果であることを当業者が認識できることは明らかであり, 本件明細書の【0038】ないし【0042】記載の試験結果を参酌しなく ても,本件優先日当時の技術常識に照らし,本件明細書のその余の発明の詳 細な説明の記載及び本件発明の特許請求の範囲の記載から,本件発明は,当 業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる から,本件発明は,サポート要件に適合する旨主張する。 しかしながら,前記(2)イ(ア)認定のとおり,本件発明の課題は,アルミニ ウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しな いようにすることにあるものと認められるところ,控訴人主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても,当業者が,本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から,本件発明は,「35ppm未満」の遊離SO2, 「300ppm未満」の塩化物及び「800ppm未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によって, 本件発明の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認めるこ とはできない。
また,控訴人が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を300ppmよりも低くすればするほど,同腐食原因である「スル フェート」の濃度を800ppmよりも低くすればするほど,アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても,前記(2)イ(ア)認定のとお り,アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく,本件発明の上記課題を 解決できるかどうかを確認する方法は,味覚パネルによる官能試験の試験結\n果によらざるを得ない。そして,本件明細書の【0038】ないし【004 2】及び表1記載の白ワインの保存評価試験の結果から,本件発明の対象と\nするワインに含まれる塩化物の濃度範囲(300ppm未満)及びスルフェ ートの濃度範囲(800ppm未満)の全体にわたり「ワインの味質」が保 存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により\n確認されたものと認識することはできないことは,前記(2)イ(イ)のとおりで ある。 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から,当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度300ppm未満 及びスルフェートの濃度800ppm未満の数値範囲の全体にわたり本件発 明の課題を解決できると認識できるものと認められないから,控訴人の上記 主張は採用することができない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.09. 3
平成30(ネ)10092 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所(46部)
2 不競法2条1項4号,5号,7号及び8号所定の不正競争行為の成否について
前記1(3)のとおり,本件鑑定の結果によれば,鑑定対象とされた300組のソー\nスコードのペアは,類似箇所1ないし4について,共通ないし類似すると判断され たことが認められる。 そこで,かかる鑑定結果を踏まえて,一審被告らが本件ソースコードを使用した\nと評価することができるかについて,以下検討する。
(1) 類似箇所1について
ア 類似箇所1は,字幕データの標準値を格納するクラスメンバ変数を宣言する ものである。 本件鑑定の結果によれば,被告ソフトウェアのソ\ースファイルSourceDe fault.hで宣言されている変数30個のうち,20個の宣言が型,注釈,イ ンデントを含めて原告ソフトウェアのソ\ースファイルGlobalSetting s.hのものと完全に一致し(表記方法が複数あると考えられる●●●●●●●●\n●●●●●●●●●●●●の注釈を含む。),5個では少なくとも変数の名前がGl obalSettings.hのものと一致しており,残りの5個では一致してい ない。 また,本件ソースコードと被告ソ\フトウェアのソースコードに共通してみられる\n特徴として,1)クラスメンバ変数の名前がアンダースコア(_)で始まること,2) 複数の英単語から構成される変数名において,各単語の先頭が大文字になっている\nこと,3)型名にLONGが多用されていること,4)HorizontalをHor iz,VerticalをVertと略していること,5)変数宣言の順番が似てい ること,6)メンバ変数の型を記述する部分に3個のタブ(12個のスペース)を用 いていること,7)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のコメントがタブ文 字を含めて完全に一致していることが指摘されている(以下,順に,それぞれ「共 通点1)」などという。)。 そして,鑑定人は,上記共通点3)ないし7)から,原告ソフトウェアと被告ソ\フト ウェアの開発者は同一人物であると判断した上で,変数の一致箇所が多いことと, 共通点6)7)を理由に,被告ソフトウェアが原告ソ\フトウェアを参照して開発された と考えるのが自然である旨述べていることが認められる。
イ 本件ソースコードの類似箇所1に係る部分について\n
(ア) 本件ソースコードの類似箇所1に係る部分は,原告ソ\フトウェアの字幕デ ータの標準値を,GlobalSettings.hのCGlobalSetti ngsクラスのパブリック・メンバ変数に格納し,字幕データの標準値を格納する 変数を宣言するものであって,処理を行う部分ではない。 また,本件ソースコードのうち,被告ソ\フトウェアのソースコードと一致又は類\n似するとされた25個の変数名は,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●というものである。そして,上記括弧内の注釈に記載された とおり,上記の変数は,それぞれ,字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数\nと解される。
これらの変数名は,字幕制作ソフトウェアで使用する一般的な内容をごく短い英\n単語で表記したものであり,その形式は,変数の命名をアンダースコアで始め(共\n通点1)),各英単語の先頭を大文字にして一体化したもの(共通点2))となっている が,鑑定人は,共通点1)2)について,変数の命名規則として,クラスメンバ変数の 名前の先頭にアンダースコア(_)があり,各単語の先頭を大文字とする命名規則 もWindowsでよくみられ,開発者の慣習であるから,異なる開発者間でも一 致することがあり得るとの意見を述べており,変数名の付け方は,特徴的とはいえ ないと認められる。 さらに,上記25個の変数についてのデータの型名のうち,両者で一致するとさ れた23の変数のデータ型は,LONG型,CString型,BOOL型が使用 されているところ,これらは,マイクロソフト社が提供する標準のデータ型であっ\nて(乙57〜60),特別なものではない。 なお,前記1(3)イ(ア)のとおり,本件鑑定の結果によれば,類似箇所1に係る本件 ソースコードと被告ソ\フトウェアのソースコードは,字幕データの標準値(変数名)\nをパブリック・メンバ変数(公開変数)に格納している点で一致しているとされる。 しかし,これらの変数は字幕データの標準値を設定するものであって,他のクラス の関数から参照されることが前提であるから,パブリック・メンバ変数とすること は通常のことであると解され,本件鑑定においても,この点は有用な一致点とはさ れていない。
(イ) 共通点1)ないし7)について
共通点1)2)は,異なる開発者であっても一致することがあり得るものであること は,前記(ア)で検討したとおりである。 共通点3)は,LONG型が多用されているというもの,共通点4)は単語の略し方 の特徴,共通点5)は,変数宣言の順番であるが,いずれもプログラムの制作者が同 一であれば,同じになることは自然であると解される。また,共通点6)は,変数名 の開始位置を揃えるため,メンバ変数の型を記述する部分にタブ文字を使う際に, 被告ソフトウェアでは2個のタブに相当するスペースを配置すれば十\分で,3個の タブに相当するスペースを与える必然性はないにもかかわらず,3個のタブを使っ ている点で原告ソフトウェアと共通するというものであるが,被告ソ\フトウェアに おいては,タブが2個以上であれば変数名の開始位置を揃えることができるから, 3個のタブを使用したことが不自然とまではいえない。 そうすると,共通点3)ないし6)は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアの制作 者が同一であれば不自然な一致とはいえないことから,いずれも,一審被告らが本 件ソースコードを使用したことを推認させるものではない。\n他方,共通点7)は,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のコメントがタ ブ文字を含めて完全に一致しているというものであり,鑑定人は,「特に,『(0:無 し 1:フェードイン)』や『(0:無し 1:フェードアウト)』という表記そのもの,\n『種別』と『(0:無し)』の間にタブ文字が置かれていることは,双方のソースコー\nドの共通点・類似点を強く示唆している。仮に,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウ ェアの開発者が同一人物で,その人物の記憶を手がかりとしても,原告ソフトウェ\nアのソースコードを参照せずに,これほど細かい特徴を一致させるのは難しいので\nはないかと考える。」との意見を述べている。そうすると,共通点7)によれば,一審 被告らが,本件ソースコードの変数定義部分を参照した可能\性を否定できないとい うべきである。
ウ 検討
上記イ(イ)のとおり,類似箇所1に係る本件ソースコードと被告ソ\フトウェアの ソースコードとの共通点7)によれば,一審被告らが,本件ソースコードの変数定義\n部分を参照した可能性は否定できない。\nしかし,上記イ(ア)によれば,類似箇所1に係る本件ソースコードは,変数定義部\n分であり,字幕データの標準値を格納する変数を宣言するもので,処理を行う部分 ではないこと,変数は,いずれも字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数で\nあること,変数名は,字幕制作ソフトで使用する一般的な内容を表\す,ごく短い英 単語に基づくものであって,その形式も開発者の慣習に基づくこと,変数のデータ の型は,マイクロソフト社が提供する標準のデータ型であること,注釈の内容も,\n変数名が表す字幕の意味をそのまま説明したものであることが認められる。\nそして,字幕表示に必要な設定項目は,原告ソ\フトウェアの設定メニューから把 握できること(乙64),変数の定義の仕方として,変数名,型,注釈で定義するこ とは極めて一般的であること,変数名は字幕ソフトが使用する一般的な名称である\nこと,データの型はマイクロソフト社が提供する標準の型であること,注釈も一般\n的な説明であることによれば,類似箇所1に係る本件ソースコードの情報の内容(変\n数定義)自体は,少なくとも有用性又は非公知性を欠き,営業秘密とはいえない。 一審被告らが,類似箇所1に係る本件ソースコードの変数定義部分を参照して,\n被告ソフトウェアのソ\ースコードを作成したとしても,このことから他の部分を参 照したことまで推認されるものではない上,それ自体が営業秘密とはいえない変数 定義部分を参照したことのみをもって,本件ソースコードを使用したとも評価でき\nないというべきである。
エ 小括
以上によれば,一審被告らが,類似箇所1について,本件ソースコードの変数定\n義部分を参照した可能性が否定できないとしても,そのことをもって,一審被告ら\nが本件ソースコードを使用したとは評価できない。\n
(2) 類似箇所2及び3について
ア 類似箇所2,3は,それぞれ,字幕データの標準値を格納するオブジェクト の代入演算子,比較演算子のオーバーロードを定義するものであるから,類似箇所 1と同じ変数が使用される。これらの変数は,誤入力を避けるために類似箇所1を コピーして作成したと考えるのが自然であり,類似箇所2,3は,類似箇所1に基 づいて発生したものと解される。 鑑定人も,「類似箇所2,3については,原告ソフトウェア,被告ソ\フトウェアの いずれも,類似箇所1の変数やコメントをコピーし,類似箇所2と類似箇所3のコ ードを記述した可能性を否定できず,類似箇所1に基づいて発生していると考えら\nれるため,類似箇所2,3に基づいて,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアの開 発者の同一性を判定したり,被告ソフトウェアの独自性を判定することはできない。」\nとの意見を述べている。
イ 一審原告は,類似箇所3における比較演算子のオーバーロードは,編集中の 字幕フォーマット情報を保存しようとする際,既存のフォーマットのリストの中に, 保存しようとする前記フォーマット情報と同一のものがあるか否かを判断するため に呼び出される比較処理部分であるところ,そもそも被告ソフトウェアにはフォー\nマット情報をファイルに保存してリスト化する機能はないから,この部分は被告ソ\ フトウェアにとって不要であると主張し,B大阪大学大学院情報科学研究科准教授 作成の意見書(甲143。以下「B意見書」という。)は,類似箇所3について,被 告ソフトウェアのソ\ースコードには必要のないコードが存在していることを,流用 の根拠として指摘する。 しかし,演算子のオーバーロードは,C++言語のプログラムでは普通に実装さ れるものであり,被告ソフトウェアのCSourceDefaultクラスの比較\n演算子のオーバーロードは,フォーマット情報をファイルに保存してリスト化する 機能に特化されたものとは認められないから,被告ソ\フトウェアにとって不要なも のとはいえない。 そして,他に,類似箇所2,3が,類似箇所1とは別個に生じた類似箇所である ことを認めるに足りる証拠はなく,類似箇所2,3によって,一審被告らが本件ソ\nースコードを使用したことを推認することはできない。
(3) 類似箇所4について
ア 類似箇所4は,字幕データの標準値をADOインターフェースでmdb形式 のデータベースに格納するためのプログラムに関し,原告ソフトウェアのSSTD\nB.cppのソースコードと被告ソ\フトウェアのMdb.cppのソースコードに\nおいて,52個のフィールド名が一致したというものである。 上記フィールド名自体はmdbファイルから参照可能であるところ,一審被告ら\nは,旧SSTとの互換を得るため,mdbファイルを参照してMdb.cppファ イルを実装したことを認めており,類似箇所4に係るフィールド名の一致は,その ことによって生じたものと推認される。
イ 一審原告は,被告ソフトウェアにおいて,Template.mdbを利用\nし,旧SSTのプロジェクトファイルと互換性のあるプロジェクトファイルをエク スポートできていることは,Template.mdbのセマンティクス,すなわ ち,Template.mdbの解析アルゴリズム(解析ロジック)を利用してい ることを意味するところ,本件鑑定において,類似箇所4から生じるセマンティク スの正確な把握は困難であると指摘されており,Template.mdbのセマ ンティクスの利用は,本件ソースコードを使用していることにほかならない旨主張\nする。
(ア) セマンティクスの意味
セマンティクスとは,データの形式や構造ないし枠であるシンタックスに対応す\nる概念であり,データの意味,内容のことであるとされる(甲95)。 Template.mdbは,旧SSTにおいて生成された字幕データを書き出 すためのmdb形式のファイルを作成するためのひな型であり,ひな型を構成する\nフィールド名,データ型がシンタックスであるのに対し,各フィールドが表す意味,\n各フィールドのデータ型に従った個々のデータ値の表す意味がセマンティクスであ\nると解される。例えば,Globalsテーブル1行目の「strGlobFon tName」(甲48,50)では,フィールド名「strGlobFontNam e」,データ型「テキスト型」がシンタックスであり,フィールドの意味が,字幕本 文フォント名を表し,「MSゴシック」というように文字列(テキスト)で記述する\nということが,セマンティクスに当たる。 この点,一審原告は,セマンティクスとは,解析アルゴリズムであると主張する。 しかし,Template.mdbは,mdb形式のファイルを作成するためのひ な型であり,プログラムではないから,そのセマンティクスに解析アルゴリズムが 含まれるとは解されず,一審原告の主張は採用できない。
(イ) セマンティクスの把握方法
a 類似箇所4に係るフィールド名は,Template.mdbに具体的な字 幕データ等を上書きしたファイルであるmdbファイルをマイクロソフトAcce\nssで開けば見ることができるところ,フィールド名には,「Font」,「Edge」など,字幕制作に携わる者であれば容易に分かる名称が用いられていることから, それ自体から,フィールドの意味を理解することができるものと認められる。例え ば,フィールド名「strGlobFontName」であれば,「FontNam e」の意味は本文フォント名を表すことを理解することができ,「str」の記載か\nら,データ型がハンガリアン記法(変数の型を名前の先頭に付与しておき,変数名 から変数へのアクセス方法に関する情報を伝えようとする記法)により,「CStr ing」,すなわち,文字列型であることを推測することができる。さらに,mdb ファイルのプロパティを見れば,データ型も見ることができるから(甲50),デー タ型がテキスト型(文字列型)であることを確認することができ,本文フォント名 を表し,テキスト型(文字列型)で記載されるフィールドであるというセマンティ\nクスを把握できる。 フィールド名からすぐにはその内容がわからないものについても,mdbファイ ルを参照し,記録されている具体的な字幕データの数値を変えて字幕の変化を見た り,目標とする字幕を見つけて該当項目の数値を確認し,字幕の設定を変えて数値 の変化を確認したりすることにより,データの属性を把握することができると解さ れる。例えば,mdbファイルで保存した字幕ファイルには,strGlobFo ntNameのデータとして,「MSゴシック」のように字体の名称が記載されてい るところ(甲89),これを手掛かりとして,本文フォントの字体の設定を変えたと きに,mdbファイルのstrGlobFontNameのデータがどのように変 化するかを試すことにより,どのような名称の字体が記述されるセマンティクスな のかを把握することは可能であると認められる。\n
また,「strFormat」は,標準設定と異なる個別設定をする際のフォーマ ット情報が格納されたフィールドであり,文字修飾の個別設定を指定すると,md bファイルのstrFormat欄にその個別設定に対応する数字や文字列が格納 される(乙24,28)。そうすると,字幕データの入力内容を変化させ,その変化 に対して格納される数字や文字列がどのように変化するかを確認することで,st rFormatの値がいかなる文字修飾を意味するものであるかを把握できるもの と認められ,セマンティクスを把握することができるというべきである。 以上によれば,一審被告らが,Template.mdbのセマンティクスを利 用しているとしても,かかるセマンティクスは,本件ソースコードを使用しなくて\nも把握可能であるものと認められる。\n
b 鑑定人は,「各フィールドがどのようなセマンティクスを持つのかを正確に 把握するのは,容易なことではない。例えば,iGlobOrientation フィールドが格納している整数値のセマンティクスはかなり複雑である。」との意 見を述べている。 しかし,SSTG1操作マニュアルによれば,原告ソフトウェアにおいては,「表\ 示位置・行配置」欄において,6箇所の表示位置と5箇所の行配置を指定すること\nができるとされるところ(乙25),mdbファイルを参照すれば,iGlobOr ientationのデータ値と「表示位置・行配置」とは,「4」と「横下中央」,\n「1」と「横下中頭」,「8」と「横下中末」,「16」と「横下行頭」というように 1対1の対応で把握することができることが認められる(乙29)。そうすると,本 件ソースコードを参照しなくても,iGlobOrientationフィールド\nのセマンティクスを把握することができるものと認められる。 もっとも,iGlobOrientationは,16進表記で表\されており(甲 101),その各桁の数値と,字幕の表示位置・行配置とがそれぞれ対応していると\n思われるところ,かかる各桁の数値からその意味を把握することは困難であり,鑑 定人の上記意見は,この点を指して正確なセマンティクスを把握するのは容易では ないとするものと推察される。しかし,データ値と「表示位置・行配置」の1対1\nの対応関係を把握できれば互換を得ることができるのであれば,それ以上に,iG lobOrientationのセマンティクスを正確に把握する必要はないと解 されるから,互換を得るために必要なiGlobOrientationのセマン ティクスは,mdbファイルから把握可能であり,本件ソ\ースコードを参照しない 限り把握できないものとはいえない。
(ウ) 以上によれば,一審被告らが,旧SSTとの互換を得るため,mdbファイ ルを参照してMdb.cppファイルを実装していることは,本件ソースコードを\n使用していることを意味するものではない。
ウ 一審原告は,本件鑑定書は,SSTDB.cppファイルとMdb.cpp ファイルは,ファイル自体が類似・共通すると指摘しており,フィールド名の一致 は,両ファイルが一致していると判断する理由の一つにすぎない上,SSTDB. cppファイルの行数は優に3000行を超えるのであるから,類似箇所は52の フィールド名の一致にとどまるものではないと主張し,B意見書は,52のフィー ルド名が一致しており,ファイルが巨大であることから,処理も一致している可能\n性が高いとの意見を述べる。 しかし,本件鑑定において,鑑定人は,原告ソフトウェアのSSTDB.cpp\nと被告ソフトウェアのMdb.cppとの目視確認を行った上で,類似箇所は52\n個のフィールド名にあると鑑定したのであり,処理も含めて両ファイルが類似・共 通すると鑑定していないことは明らかである。 また,B意見書は,被告ソフトウェアのソ\ースコードを視認せずに,類似した処 理を含んでいる可能性が高いと述べているにすぎない上,ファイルの行数が多いこ\nとが処理の一致を意味すると解すべき根拠はないから,採用することはできない。 そして,被告ソフトウェアにおいて,本件ソ\ースコードを参照して原告ソフトウ\nェアの解析アルゴリズムを把握し,同じ処理を行っていることを認めるに足りる証 拠はない。かえって,エクスポートされるmdbファイルの字幕の配置に関するi GlobOrientationフィールドとiOrientationフィール ドのデータ値は,エクスポート前においては,原告ソフトウェア及び被告ソ\フトウ ェアのいずれも変数名を●●●●●●●●●●●●とする変数に格納されているが, 原告ソフトウェアにおいては,データ型をLONG型とし(甲99,原判決別紙a),\n表示位置・行配置の設定について,水平位置,垂直位置,行揃え,縦書き横書きの\n4種の情報を16進表記の特定の桁に割り当て,特定の桁をマスクビットを用いて\nビット演算により抽出している(甲100〜102)のに対し,被告ソフトウェア\nにおいては,データ型を列挙型としており(原判決別紙a),表示位置・行配置の設\n定について,水平位置,垂直位置,行揃え,縦書き横書きの4種の情報を16進表\n記の特定の桁に割り当て,特定の桁をマスクビットを用いてビット演算により抽出 するものではないと解され,表示位置・行配置の設定処理のアルゴリズムは同一で\nはないことが認められるのであって,本件ソースコードを参照したものではないこ\nとが推認されるというべきである。
エ 小括
以上によれば,類似箇所4は,一審被告らによる本件ソースコードの使用を意味\nするものではないのであって,一審原告の主張は採用できない。
(4) 一審被告らによる本件ソースコードの使用の有無\n
ア 以上の検討によれば,類似箇所1については,一審被告らが本件ソースコー\nドの変数定義部分を参照したことにより生じた可能性を否定できないものの,当該\n変数定義部分は営業秘密とはいえない以上,これのみをもって,本件ソースコード\nを使用したとは評価できない。 また,類似箇所2,3は,類似箇所1とは別個に生じた類似箇所ではない。 類似箇所4は,本件ソースコードを参照したことにより生じた一致とはいえない\n上,旧SSTとの互換を得るために本件ソースコードを参照したとも認められない。\nそして,本件鑑定の結果によれば,300組のソースコードのペア中,類似箇所\n1ないし5に該当する118行の他には本件ソースコードと被告ソ\フトウェアのソ\nースコードとが一致ないし類似する部分があったとは認められず,鑑定の対象とな ったソースコード2万9679行(コメント,空行を除いた有効行)のうち2万9\n561行は非類似であって,非類似部分が99%以上となる。 以上によれば,一審被告らが,類似箇所1に係る部分以外に本件ソースコードを\n参照したとは認められず,また,類似箇所1に係る変数定義部分を参照した可能性\nが否定できないことをもって,本件ソースコードを使用したとは評価できない。そ\nうすると,本件ソースコードについて,不競法2条1項7号にいう「使用」があっ\nたとはいえないというべきである。
イ 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は,本件鑑定は最低限度の共通性の言及にとどまり,類似箇所や共 通箇所を網羅的に指摘したものではないから,本件鑑定の結果によって,類似箇所 1ないし4以外は類似しないとは認定できない旨主張し,B意見書も,本件鑑定手 法は不十分であり,他に類似箇所がないとはいえない旨の意見を述べる。\nしかし,鑑定人は,「表1.2に示した(判決注:類似箇所1ないし5)以外の場\n所では,類似・共通すると認定できる箇所は見つからなかった」と明記しており, 本件鑑定の結果によっては,他に類似・共通する箇所があるとはいえないことは明 らかである。そして,前記(3)ウのとおり,B意見書は,被告ソフトウェアのソ\ース コードを参照しておらず,具体的な一致箇所を指摘するものではないから,採用の 限りではなく,他に本件鑑定の結果を左右するに足りる証拠はない。よって,一審 原告の主張は理由がない。
(イ) 一審原告は,類似箇所1ないし4の他にも,一審被告らによる本件ソースコ\n
ードの使用を推認させる事実が多数存在するとも主張する。 しかし,以下のとおり,一審原告の主張は,いずれも理由がない。 a 一審原告は,被告ソフトウェアに原告ソ\フトウェアで使用されているsdb 形式の字幕データベースが実装されていたことは,一審被告らが本件ソースコード\nを不当に入手,利用していることを推認させる旨主張する。 しかし,被告ソフトウェアのプログラムファイルに,sdbとの記載があること\nは認められるものの(甲51の1〜5),sdb形式の字幕データベースが実装され ていたことを認めるに足りる証拠はないから,一審原告の主張は,その前提を欠く ものである。
b 一審原告は,被告ソフトウェアと原告ソ\フトウェアには,1)字幕の全体設定 (デフォルト)を縦書きに設定して作成されたmdbファイルをインポートした場 合に,原告ソフトウェアも被告ソ\フトウェアも横書きでインポートされてしまう, 2)一審被告フェイスは平成22年に設立されていて,それ以降に開発された被告ソ\nフトウェアからエクスポートしたExcelファイルの拡張子は「.xlsx」と なるはずであるところ,被告ソフトウェアのエクスポート先の拡張子は「.xls」\nである,3)Excelの言語設定を英語にした状態で,Excelファイルをエク スポートすると,原告ソフトウェアも被告ソ\フトウェアもハングアップする,4)エ クスポート先をC:¥に設定してExcelファイルをエクスポートすると,原告 ソフトウェアと被告ソ\フトウェアもハングアップする,5)横書きで,例えば「ワシ ントンD.C.」と入力した字幕を縦書きに変換すると,原告ソフトウェアも被告ソ\ フトウェアも「D.C.」のピリオドの位置がおかしくなってしまうとの共通したバ グが存在することも,一審被告らによる本件ソースコードの使用を推認させると主\n張する。 しかし,本件鑑定の結果によれば,1)の事象は,被告ソフトウェアでは発生する\nものの,原告ソフトウェアでは発生していないとされ,そもそも事象の共通性が認\nめられない,2)については,原告ソフトウェアは拡張子の情報がリソ\ースの文字列 定数として格納されているのに対し,被告ソフトウェアではC#のソ\ースコード中 で直接記述されているという差異がある,3)については,原告ソフトウェアと被告\nソフトウェアはExcelのAPIを読み出すために異なるアプローチを採用し,\n不具合が発生する直接の原因は原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアでは異なる, 4)については,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアとでは不具合が発生する原因 が異なる,5)については,表示位置を左上から右上に修正させる処理が,原告ソ\フ トウェアと被告ソフトウェアとでは,大きく異なっているとの意見が述べられてい\nる。かかる本件鑑定の結果によれば,これらのバグが共通することは,一審被告ら が,本件ソースコードを使用したことを裏付ける事実とは認められない。\n
c 一審原告は,本件ソースコードと被告ソ\フトウェアのソースコードでは,ス\nペルミスが一致するところ,かかる一致は,一審被告らが本件ソースコードを複製\nしたものでなければ到底発生し得ないものである旨主張する。 しかし,本件鑑定の結果によれば,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアとで共 通するスペルミスは圧倒的に少ないから,共通するスペルミスの存在は一審被告ら が原告ソフトウェアを複製したことの根拠とならないとされる。また,原告ソ\フト ウェアと被告ソフトウェアとで共通して,rubyの複数形をrubiesとすべ\nきところがrubysとなっていたり,ルビの綴りは正しくはrubyであるにも かかわらず,rubiという綴りが混在しているほか,alignmentをal ign,horizontalをhorz又horizと略す傾向があるところ, これらは,原告ソフトウェアを参照しなくても,同一開発者の一貫した記憶間違い\nや発想によっても生じ得るとされる。そうすると,共通するスペルミスも,一審被 告らによる本件ソースコードの使用を推認させる事実とは認められない。\n
d 一審原告は,被告ソフトウェアでは,C++/CLI言語による無用なコー\nディングが行われており,C++言語の本件ソースコードを流用したことを推認さ\nせる旨主張する。 しかし,本件鑑定の結果によれば,鑑定人は,C++言語とC#言語を使い分け るというのは,「Visual Studio」を用いた開発においては合理的な選 択と考えられ,C++/CLI言語は,C++言語とC#言語の間を橋渡しするた めに用いられていると考えられるとの意見を述べている。そうすると,被告ソフト\nウェアにおけるC++/CLI言語でのコーディングの存在も,一審被告らが,一 審原告から持ち出したC++言語のソースコードを流用したことを裏付ける事実と\nは認められない。
e 一審原告は,被告ソフトウェアの開発が開始した平成24年頃には,「Vis\nual Studio2008」,「Visual Studio2010」という 2つの新しい開発環境がリリースされ,広く一般的に利用されていたにもかかわら ず,被告ソフトウェアの当初の開発環境が,原告ソ\フトウェアの開発環境と同じ「V isual Studio2005」であることは,被告ソフトウェアにおいて,\n「Visual Studio2005」で開発された本件ソースコードを流用し\nたことを推認させると主張する。 しかし,本件鑑定の結果によれば,「Visual Studio2005」は, Windows7までしか対応しておらず,被告ソフトウェアの開発環境もWin\ndows7であるから,被告ソフトウェアを開始した時期に,「Visual St udio2005」を開発環境として採用することに,特段の矛盾は見つからない とされる。そうすると,被告ソフトウェアの開発環境が「Visual Stud io2005」であることも,一審被告らが本件ソースコードを流用して被告ソ\フ トウェアのソースコードを作成したことを推認させる事実とは認められない。\nf その他,一審原告は,るる主張するが,いずれも採用できない。
(5) まとめ
以上によれば,一審被告Yの行為は,不競法2条1項7号の営業秘密の使用に該 当せず,一審被告フェイスについても,同項8号の不正競争行為は認められない。 また,同項4号,5号の不正競争行為についても認定することはできない。 その余の争点については判断するまでもないが,原判決が,将来バージョンアッ プされた後の被告ソフトウェアについて,本件ソ\ースコードを使用するものか否か 審理することなく,その使用等の差止めを認めたことは,その範囲が過大であって, 相当でないことを付言する。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.09. 3
平成28(行ケ)10239 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所
意匠法2条2項は,「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にす\nるために行われるものに限る。)の用に供される画像であって,当該物品又はこれと 一体として用いられる物品に表示されるもの」は,同条1項の「物品の部分の形状,\n模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれ,意匠法上の意匠に当たる旨を規定 する。同条2項は,平成18年法律第55号による意匠法の改正(以下「平成18 年改正」という。)によって設けられたものである。 ところで,平成18年改正前から,家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボ タン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え,この画面上に表示された図形等\nからなる,いわゆる「画面デザイン」を利用して操作をする機器が増加してきてい た。このような画面デザインは,機器の使用状態を考慮して使いやすさ,分かりや すさ,美しさ等の工夫がされ,家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要 素となってきており,企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大してい る状況にあった。
しかしながら,平成18年改正前においては,特許庁の運用として,意匠法2条 1項に規定されている物品について,画面デザインの一部のみしか保護対象としな い解釈が行われ,液晶時計の時計表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立\nたない画面デザインや,携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠 な画面デザインについては,その機器の意匠の構成要素として意匠法によって保護\nされるとの解釈が行われていたが,それら以外の画面デザインや,機器からの信号 や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについ\nては,意匠法では保護されないとの解釈が行われていた(意匠登録出願の願書及び 図面の記載に関するガイドライン−基本編−液晶表示等に関するガイドライン[部\n分意匠対応版])。 そこで,画面デザインを意匠権により保護できるようにするために,平成18年 改正により,意匠法2条2項が設けられた。
このような立法経緯を踏まえて解釈すると,同項の「物品の操作…の用に供され る画像」とは,家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品 に代わって,画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができる\nものを指すというべきであるから,特段の事情がない限り,物品の操作に使用され る図形等が選択又は指定可能に表\示されるものをいうものと解される。 これを本願部分についてみると,本願部分の画像は,別紙第1のとおりのもので あって,「意匠に係る物品の説明」欄の記載(補正後のもの,別紙第1)を併せて考 慮すると,画像の変化により運転者の操作が促され,運転者の操作により更なる画 像の変化が引き起こされるというものであると認められ,本願部分の画像は,自動 車の開錠から発進前(又は後退前)までの自動車の各作動状態を表示することによ\nり,運転者に対してエンジンキー,シフトレバー,ブレーキペダル,アクセルペダ ル等の物理的な部品による操作を促すものにすぎず,運転者は,本願部分の画像に 表示された図形等を選択又は指定することにより,物品(映像装置付き自動車)の\n操作をするものではないというべきである(甲1,5)。 そうすると,本願部分の画像は,物品の操作に使用される図形等が選択又は指定 可能に表\示されるものということはできない。また,本願部分の画像について,特 段の事情も認められない。 したがって,本願部分の画像は,意匠法2条2項所定の「物品の操作…の用に供 される画像」には当たらないから,本願意匠は,意匠法3条1項柱書所定の「工業 上利用することができる意匠」に当たらない。
2 原告は,平成18年改正により意匠法2条2項が設けられた趣旨は,形態が, 物品と一体として用いられる範囲において,「物品の操作…の用に供される画像」に 関するデザインを広く保護しようとすることにあり,それ以上に保護対象を限定す る意図は読み取れず,本願部分の画像は,「映像装置付き自動車」という物品におけ る「走る」という機能を発揮できる状態にするための,シフトレバー等の操作の用\nに供されるものということができるから,同項の要件に適合すると主張する。 しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は,前記1のとおりであり,これによると,本願部分の 画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも,前記1のとおり である。原告は,本願意匠に係る物品の「操作」は,「機械など」に相当するシフト レバーをあやつって働かせることであり,「一定の作用効果や結果」に相当する「走 る」機能を得るために,「物品の内部機構\等」に相当するトランスミッション等に指 示を与えるものであると主張するが,ここでいう「映像装置付き自動車」という「物 品の操作」とは,「走る」という機能を発揮できる状態にするための「一定の作用効\n果や結果」を得るために「物品の内部機構等」であるトランスミッション等に対し\n指示を与えることをいうのであるから,シフトレバー等は,あやつって働かせる対 象である「機械など」に相当するものではなく,「物品の操作の用に供される」もの であって,このシフトレバー等「の操作の用に供される画像」であるか否かを検討 しても,意匠法2条2項所定の画像であることが認められるものではない。 したがって,原告の主張は,理由がない。
3 原告は,審決が,1)操作ボタン等の画像が表示されること,2)表示された画\n像を用いて操作を行うものであることを,意匠法2条2項所定の画像に当たるかの 判断基準としたことが,これまでの意匠登録例(甲9〜11)に照らしても同項の 解釈として誤りであると主張する。 しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は,前記1のとおりであり,これと同旨と解される上記 判断基準に誤りはない。 また,前記1の同項の解釈は,これまでの意匠登録例により直ちに左右される性 質のものではないから,甲9〜11に基づく原告の主張を採用することはできない。 したがって,原告の主張は,理由がない。
4 原告は,被告が,物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は\n指定可能に表\示され,物品の内部機構等に指示を与えることができることが認識可\n能に表\示される画像であることを,意匠法2条2項所定の画像の要件としたことが, 十分な根拠なく条文を限定解釈して恣意的に要件を定めたものであり,客観的な判\n断基準として不適切であると主張する。 しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は,前記1のとおりである。前記1の同項の解釈は,同 項が設けられた立法経緯を踏まえて,同項の「操作の用に供される」という文言を 解釈し,同項の「物品の操作の用に供される画像」の意義を明らかにしたものであ り,同項の文言を離れて恣意的に要件を定めたものではない。また,前記1の同項 の解釈が,客観的な判断基準として不適切であるとする根拠はない。 したがって,原告の主張は,理由がない。
5 原告は,本願部分の画像は,縮小画像図1〜16の一連の画像が,その画像 の変化により運転者の操作が促されると同時に,その運転者の操作により更なる画 像の変化を引き起こすというように,画像変化と操作がインタラクティブに連携し て一体感を奏する「映像装置付き自動車」の開錠から前進及び後退までの,走る「操 作の用に供される画像」ということができると主張する。 しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は,前記1のとおりであり,これによると,本願部分の 画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも,前記1のとおり である。映像装置の故障等により本願部分の画像が表示されず,本願部分の画像が\nなかったときでも,エンジンキー,シフトレバー,ブレーキペダル,アクセルペダ ル等の物理的な部品が正常であれば,映像装置付き自動車における「走る」という 機能を発揮できる状態にするための「物品の操作」を行うことは可能\である一方で, 本願部分の画像が正常に表示されているときでも,エンジンキー,シフトレバー,\nブレーキペダル,アクセルペダル等の物理的な部品が故障していれば,上記「物品 の操作」を行うことはできないのであるから,このことからしても,映像装置付き 自動車における「走る」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作の\n用に供される」ものは,エンジンキー,シフトレバー,ブレーキペダル,アクセル ぺダル等の物理的な部品であって,本願部分の画像ではないというべきである。 したがって,原告の主張は,理由がない。
6 原告は,本願部分の画像によって映像装置付き自動車を操作することは,「操 作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合に相当するから, 本願部分の画像は,これと同様に意匠法2条2項所定の画像に当たると主張する。 しかしながら,画像に表示された物品の操作に使用される図形等をタッチパネル\nにより直接的に選択又は指定せず,リモコンによる遠隔操作を行う場合であっても, 画像上の図形等を選択又は指定する手段がリモコンに変わるだけで,物品の操作に 使用される図形等を選択又は指定することに変わりはない。原告は,「操作の用に供 される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合には,「3)操作されたリモコン は,(物品に対して)信号を発信し,この信号は,物品の内部機構に指示を与える。\n4)物品は,内部機構に与えられた指示に従い,物品と一体として用いられる表\示機 器上の,操作の用に供される画像を変化(選択又は指定に相当)させる。」というス テップを踏むとした上で,これと,本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」 を操作する場合における「3)操作されたシフトレバーは,トランスミッションに対 して指示を与える。4)映像装置付き自動車は,トランスミッションに与えられた指 示に従い,物品と一体として用いられる表示機器上の,操作の用に供される画像を\n変化させる。」とが1対1で対応していると主張するが,「操作の用に供される画像」 によってリモコンで遠隔操作を行う場合に,3)物品の内部機構であるトランスミッ\nションに対してシフトレバー(の移動)が指示を与えることと対比すべきものは, 画像に表示された物品の操作に使用される図形等(のリモコンによる選択又は指定)\nが物品の内部機構等に対して指示を与えることであって,画像上の図形等を選択又\nは指定する手段にすぎないリモコンを物品の内部機構に対して指示を与えるシフト\nレバーと対比する点において,失当である。
◆判決本文
関連事件は以下です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所(1部)
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だ けではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願 当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで,本願発明に係る特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不当に害され るほどに不明確であるか否かについて,検討する。なお,以下,本願発明の発明特 定事項について,次のとおり分説し,それぞれ「特定事項A」ないし「特定事項I」 ということがある。
A 対象の一つ以上の要素の,前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択 するための指標としての使用であって,
B 前記対象の一つ以上の要素は,以下:前記対象の年齢,前記対象の性別,前 記対象の食餌,前記対象の体重,前記対象の身体活動レベル,前記対象の脂質忍容 性レベル,前記対象の医学的状態,前記対象の家族の病歴,および前記対象の生活 圏の周囲の温度範囲から選択され,
C ここで前記配合物が,1又は複数の,相互に補完する一日用量のω−6脂肪 酸およびω−3脂肪酸を含む脂肪酸を含み,
D ここでω−6脂肪酸対ω−3脂肪酸の比,およびそれらの量が,前記一つ以 上の要素に基づいており;
E ここでω−6対ω−3の比が,4:1以上,ここでω−6の前記用量が40 グラム以下であり;
F または前記対象の食餌および/または配合物における抗酸化物質,植物化学 物質,およびシーフードの量に基づいて1:1〜50:1;
G またはここでω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3の中止が緩やかで あり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり;
H またはここで前記脂肪酸の含有量は,下記表6:(表\は略)と適合する,
I 前記使用。
(2) 「対象の一つ以上の要素の,前記対象への投与のための脂質含有配合物を選 択するための指標としての使用」との記載(特定事項A)の明確性
ア 特定事項A及びB
本願発明は,「対象の一つ以上の要素の,前記対象への投与のための脂質含有配 合物を選択するための指標としての使用であって,」と特定され(特定事項A), 続いて,「前記対象の一つ以上の要素は,以下:前記対象の年齢,前記対象の性別, 前記対象の食餌,前記対象の体重,前記対象の身体活動レベル,前記対象の脂質忍 容性レベル,前記対象の医学的状態,前記対象の家族の病歴,および前記対象の生 活圏の周囲の温度範囲から選択され,」と特定されている(特定事項B)。 そうすると,特定事項A及びBは,本願発明が,少なくとも,下記の方法である 旨特定するものと解釈するのが合理的である。
記
脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当該脂質含有配合物を選択するため に,当該対象の「要素」,すなわち,年齢,性別,食餌,体重,身体活動レベル, 脂質忍容性レベル,医学的状態,家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち, 一つ又は複数を「指標」として使用する方法
イ 特定事項C
本願発明は,「ここで前記配合物が,1又は複数の,相互に補完する一日用量の ω−6脂肪酸およびω−3脂肪酸を含む脂肪酸を含み,」と特定されている(特定 事項C)。そして,「ここで前記配合物」とは,特定事項A及びBで特定された方 法によって選択される対象物である「脂質含有配合物」をいうものである。 そうすると,特定事項Cは,本願発明の方法によって選択される対象物である脂 質含有配合物がω−6脂肪酸及びω−3脂肪酸を含む脂肪酸を含むなどと,本願発 明の方法によって選択される対象物の構成を特定するものということができる。\n
ウ 特定事項DないしHによって特定される目的物
特定事項DないしHは,ω−6脂肪酸とω−3脂肪酸の用量の比率を特定したり (特定事項D,E,F),ω−6脂肪酸及び/又はω−3脂肪酸の用量を特定した り(特定事項D,E,G),脂肪酸に含まれるω−9脂肪酸,ω−6脂肪酸及びω −3脂肪酸の重量%を特定したり(特定事項H),ω−6脂肪酸及び/又はω−3 脂肪酸の摂取量の経時的変化(特定事項G)を特定したりするものである。 そうすると,特定事項DないしHは,特定事項Cによって特定された本願発明の 方法によって選択される対象物の構成,すなわち,対象物である脂質含有配合物が\nω−6脂肪酸及びω−3脂肪酸を含む脂肪酸を含むという構成について,ω−6脂\n肪酸,ω−3脂肪酸又は脂肪酸に含まれるω−9脂肪酸等の比率,用量,重量%又 は摂取量の経時的変化に着目することにより,更に特定するものということができ る。
エ 特定事項DないしHの関係
(ア) 特定事項DないしHは,それぞれ「;」で区切られているから,それぞれ の発明特定事項ごとに,個別の技術的意義を有すると解すべきものである。
(イ) そして,特定事項Dは「ここで」で始まり,特定事項Eは「ここで」で始 まり,特定事項FないしHは「または」で接続されているから,特定事項Dないし Hは,特定事項Dと特定事項EないしHに更に区別され,特定事項EないしHは選 択関係にあるものである。
(ウ) さらに,特定事項Dと特定事項EないしHとの関係について検討する。 これらの特定事項は,特定事項Cによって特定された本願発明の方法によって選 択される対象物の構成について,ω−6脂肪酸,ω−3脂肪酸又は脂肪酸に含まれ\nるω−9脂肪酸等の比率,用量,重量%又は摂取量の経時的変化に着目することに より,更に特定するものである。 そして,特定事項Dは,特定事項Cによって特定された本願発明の方法によって 選択される対象物の構成について,脂質含有配合物が投与される対象の「要素」,\nすなわち,年齢,性別,食餌,体重,身体活動レベル,脂質忍容性レベル,医学的 状態,家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち,一つ又は複数に基づいて特 定しようとするものである。 一方,特定事項EないしHは,特定事項Cによって特定された本願発明の方法に よって選択される対象物の構成について,客観的な比率,用量,重量%又は摂取量\nの経時的変化に基づいて特定しようとするものである。 このように,特定事項Dと特定事項EないしHは,いずれも特定事項Cによって 特定された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について,更に特定す\nるものであるところ,その特定の仕方が異なり,特定事項Dと特定事項EないしH による特定の間で矛盾が生じるものではないから,重畳して適用されるものという べきである。
オ 特定事項I
特定事項A及びBは,本願発明が,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり, 当該脂質含有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち,一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ,特定事項Cは, 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し,\n特定事項D及び特定事項EないしHは,重畳的に,これに更に特定を加えるもので ある。 そうすると,特定事項Iは,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,脂質含 有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について,これが,特定事項CないしHによって特定された構成\nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Aの明確性
以上によれば,特定事項Aは,「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当 該脂質含有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち,一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって,特定事項Aを,こ のように解釈することは,その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
・・・
特定事項Cで特定される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の構成は「一日\n用量」の脂肪酸を含むものであるところ,特定事項Cに係る特許請求の範囲の記載 だけからでは,1)脂質含有配合物が,「一日用量」に相当する「ω−6脂肪酸およ びω−3脂肪酸」を含み,更にその余の脂肪酸を含んでもよいのか,それとも2)脂 質含有配合物が,「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含み,かつ,当該「脂肪酸」 が「ω−6脂肪酸およびω−3脂肪酸」を含むのか,について,一義的に明らかで はない。
(イ) そこで,本願明細書の記載を考慮する。
a 本願明細書において,対象に投与される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の 量について具体的に明示する記載は,実施例1,3,5及び6のみである。 そして,実施例1には,「この配合物は,およそ10〜100グラムの1日総脂 肪の,均衡のとれた脂肪酸組成物を供給できる。」と記載され,脂質含有配合物に 含まれる「脂肪酸」の「一日用量」について記載されている。一方,「ω−6脂肪 酸」及び「ω−3脂肪酸」の「一日用量」に関する記載はない。 また,実施例3,5及び6には,【表9】ないし【表\13】が記載され,各表に\nついて,「総脂肪酸内容物についての用量範囲(単位:グラム),一価不飽和脂肪 酸対多価不飽和脂肪酸の比率範囲および一価不飽和脂肪酸対飽和脂肪酸の比率範囲, ω−6脂肪酸含有量の範囲(単位:グラム),ω−9脂肪酸対ω−6脂肪酸の比率 範囲,ω−3脂肪酸含有量の範囲(単位:グラム)およびω−6脂肪酸対ω−3脂 肪酸の比率範囲を,性別および年齢群により示すものである。」と説明されている。 実施例3,5及び6の各表は,脂質含有配合物に含まれる「脂肪酸」の「一日用量」\nを示した上で,当該「脂肪酸」の内訳として,一価不飽和脂肪酸,多価不飽和脂肪 酸,飽和脂肪酸,ω−6脂肪酸,ω−9脂肪酸及びω−3脂肪酸の量を示すもので ある。
b 一方,本願明細書には,発明を実施するための形態として「脂質配合物」に ついて開示されている(【0022】〜【0036】)。その中で,「ω−6脂肪 酸およびω−3脂肪酸両方の最適な1日送達量」と記載されているが,同記載は「一 態様」として開示されているものであって(【0022】),「ω−6脂肪酸」及 び「ω−3脂肪酸」以外の「脂肪酸」の均衡について言及する「実施形態」も開示 されている(【0030】)。 また,実施例3,5及び6の各表は,脂質含有配合物に含まれる「ω−6脂肪酸」\n及び「ω−3脂肪酸」の用量を示すものであるが,その余の脂肪酸の用量について も示されている。 そうすると,ω−6脂肪酸及びω−3脂肪酸の用量を開示するこれらの本願明細 書の記載は,その余の脂肪酸の用量を適宜定めてよいとするものではないから,上 記1)を前提とするものではないというべきである。
c したがって,本願明細書は,脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の量について, まず「脂肪酸」の「一日用量」に着目した上で説明するものであって,上記2)を前 提とするものということができる。
(ウ) このように,特許請求の範囲の記載に加え,本願明細書の記載を考慮すれ ば,特定事項Cは,2)脂質含有配合物が,「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含 み,かつ,当該「脂肪酸」が「ω−6脂肪酸およびω−3脂肪酸」を含む旨特定す るものということができる。
・・・
本件審決は,サポート要件について,「ω−6の増加が緩やかおよび/また はω−3の中止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」と の技術的事項が,本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから,本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして,本件審決は,本願発明が,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて,何ら検討判断していない。
(2) しかしながら,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記 載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると,本願発明が,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて,何ら検討することなく,選択関係にある特 定事項EないしHのうち特定事項G「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3 の中止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」との技術的 事項が,本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって, サポート要件に適合しないとした本件審決は,誤りである。
(3) 加えて,以下のとおり,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3の中 止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」との特定事項G の技術的事項は,本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち,まず,本願明細書【0042】には,「長鎖ω−3脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質/栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか,またはω−6脂肪酸が突然増加すると,全身性の炎症応答(毛細血管 漏出,発熱,頻脈,呼吸促迫),多臓器不全(消化器,肺,肝臓,腎臓,心臓)お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも,様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3 の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は,本願明細書【0042】 に記載されている。 また,本願明細書には,菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって19〜30 歳及び31〜50歳の男性に投与する脂質組成物のω−6脂肪酸の用量を40g以 下とすること(実施例3【表9】),多量のシーフード摂取者であって上記と同年\n齢の男性に投与する脂質組成物のω−6脂肪酸の用量を40g以下とすること(実 施例3【表11】),及び,医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成\n物のω−6脂肪酸の用量を40g以下とすること(実施例6【表13】)が,それ\nぞれ記載されている。このように,「ω−6の用量が,40グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は,本願明細書の実施例3【表9】【表\11】及び実施 例6【表13】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。\nさらに,上記のとおり,本願明細書【0042】には,「ω−6の増加が緩やか および/またはω−3の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも, 様々な疾患が生じ得ることが記載されており,これは,「ω−6の増加が緩やかお よび/またはω−3の中止が緩やかであ」る投与方法が,特定の対象に限らず,一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると, このような投与方 法と,実施例3【表9】【表\11】及び実施例6【表13】のそれぞれ一部に記載\nされた「ω−6の用量が,40グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法,すなわち,例えば,菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって19〜 30歳及び31〜50歳の男性に,40g以下の用量のω−6脂肪酸を投与し,そ の際,ω−6脂肪酸を緩やかに増加させ及び/又はω−3脂肪酸を穏やかに中止す るという,脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は,本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって,本件審決は,サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく,そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず,その判断 枠組み自体に問題がある。よって,取消事由3は,その趣旨をいうものとして理由 がある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成29(ワ)37350 標章使用差止請求反訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年5月21日 東京地方裁判所
反訴被告標章1,2及び5の作成,使用等によって,反訴原告標章1,2 及び5についての反訴原告の複製権又は翻案権が侵害されるか否かを検討 するため,反訴被告標章1と反訴原告標章1が同一性を有する部分について みると,これらは,深緑色の長方形(横長)の中に白いアルファベット文字 が配置されていること,そのアルファベット文字の書体,大きさ,文字間の 間隔及び配置のバランス,全ての文字が円の構成要素とされていること,「O\nFF」と「USE」のアルファベット文字の上部に三つの白丸で弧を描くよ うな装飾が施されていることなどで共通している。 アルファベット文字について著作物性を肯定するためには,その文字自体 が鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていなければならないと解 するのが相当である。反訴被告標章1と反訴原告標章1のアルファベット文 字が反訴被告の店舗で使用等をするために様々な工夫を凝らしたものであ ることは反訴原告が主張するとおりであるとしても,それらの工夫による反 訴被告標章1と反訴原告標章1のアルファベット文字は,いずれも「オフハ ウス」という名称をよりよく周知,伝達するという実用的な機能を有するも\nのであることを離れて,それらが鑑賞の対象となり得るような美的特性を備 えるに至っているとは認められない。また,その余の共通点については,い ずれもアイデアが共通するにとどまるというべきであり,仮にアイデアの組 合せを新たな表現として評価する余地があるとしても,それらはありふれた\nものであるといわざるを得ないから創作性は認められない。 したがって,反訴原告標章1と反訴被告標章1は,表現それ自体でない部\n分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,\n仮に反訴原告標章1が著作物であるとしても,反訴被告標章1を作成等する 行為は反訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものとはいえない。また,上 記と同様の理由から,反訴被告標章2及び5を作成等する行為についても反 訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものではない。
ウ 反訴被告ピクトグラムの作成,使用等により反訴原告ピクトグラムについ ての反訴原告の著作権が侵害されるか否かを検討するため,反訴原告ピクト グラムと反訴被告ピクトグラムが同一性を有する部分についてみると,反訴 原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは,いずれも,反訴被告で取り扱 う商品である具体的な工業製品の外観を示した図といえるものである。そし て,これらは,Tシャツの前部中央に表示された表\現が異なる反訴原告ピク トグラム4−01ないし4−03及び反訴被告ピクトグラム4−01ない し4−03を除く全てについて,具体的な形状が異なる製品を選択してこれ を表現したものである。したがって,反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク\nトグラムは,基本的に,同じジャンルの製品を選択してその外観を表してい\nる点において共通するにとどまるといえるものである。また,反訴原告ピク トグラムと反訴被告ピクトグラムにおいて,選択された製品の配置の角度, 複数の製品の種類の選択,レイアウトにおいて共通するものはあるが,これ らは,いずれも,アイデアであるか同種の表現を行うに当たり通常考え得る\nありふれた表現といえるものであり,反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク\nトグラムが創作性のある部分において共通するとはいえない。また,反訴原 告ピクトグラム4−01ないし4−03及び反訴被告ピクトグラム4−0 1ないし4−03におけるTシャツの形状は概ね同じであるが,これらは極 めてありふれたTシャツの形状であり,その形状についての表現に創作性が\nあるとは認められない。 これらを考慮すると,反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは, 表現それ自体でない部分又は表\現上の創作性がない部分において同一性を 有するにすぎないから,仮に反訴原告ピクトグラムの全部又はその一部が著 作物であるとしても,反訴被告ピクトグラムを作成等する行為は反訴原告の 複製権又は翻案権を侵害するものではない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成29(ワ)12529 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月16日 大阪地方裁判所
原告は,被告が本件発明の構成部材である本件機械のチャック爪を少なく\nとも20回修理交換したとして,その行為は本件特許の実施品の生産行為に該当す ると主張している。 そして,原告は被告に対して平成27年2月20日頃,チャック爪を2個販売し, 被告はその数年後,これを使用して本件機械のチャック爪を交換したことを認めて いるが,原告はこの交換が本件特許の専用実施権の侵害に当たるとは主張していな いから,原告の損害賠償請求や差止請求との関係では,被告がこれ以外に本件機械 のチャック爪を交換したかどうかが問題となる。
(2) そこで,原告の主張する事実が認められるかを検討すると,まず原告の主 張を直接裏付ける証拠があるわけではない。 また,そもそも本件機械のチャック爪は,原告が図面を作成した上で,鉄工所に 委託して製造しているもので,汎用品ではない(原告代表者供述)から,被告が原\n告からチャック爪を購入せず,また原告に依頼せずにチャック爪を交換するために は,被告がチャック爪を自作するか,原告以外の第三者に製造を委託するなどして チャック爪を調達してくる必要がある。しかし,原告以外の者が本件機械のチャッ ク爪を製造していたことを認めるに足りる証拠はないから,そのような証拠状況の 下で,被告が,原告から購入したチャック爪を使用した交換以外にチャック爪を交 換したと推認することはできない。 さらに,原告はチャック爪は少なくとも7000mの掘削を施工するごとに修理 交換する必要があるという前提で,被告が本件機械を使用して合計13万2800 mの掘削を行ったと主張しているが,被告はこれを否認している。原告が主張する 修理交換の頻度については,客観的かつ具体的な裏付けがあるわけではないし,こ れを措くとしても,原告において被告が本件機械を使用して施工した杭引抜き工事 が多数あることを具体的に主張立証しているわけではないから,被告が平成27年 2月20日頃に購入したチャック爪を使用した交換以外に,本件機械のチャック爪 の交換を必要とする状況があったことの立証もされていない。
以上の事実を総合すると,被告が,原告から購入したチャック爪を使用した交換 以外に本件機械のチャック爪を交換していた事実を推認することはできず,その他 に原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない。 なお,原告が指摘するように,被告取締役は,本件機械の平爪よりもさらに先に 設置されている爪を頻繁に交換したことを認めているが,その爪はチャック爪より も先端側に設置されていて,掘削作業により摩耗し得るものであって,チャック爪 の外側にはガードフレームやガード板が設置されていることを踏まえると,上記の チャック爪とは別の爪を頻繁に交換していることから,直ちに原告主張の事実が推 認されるとまでいうことはできない。
(3) そうすると,争点2について判断するまでもなく,被告において原告が有 する本件特許の専用実施権を侵害する行為をしたとは認められない。したがって, 原告による損害賠償請求及び差止請求には理由がないことになる。
・・・・
2 争点4(原告と被告は,被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注した ときに使用料を支払う旨の本件使用料合意をしたか)について
(1) 原告は,被告との間で,被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注し たときは,工事代金額の5%(消費税別)を使用料として支払う旨の本件使用料合 意が成立したと主張し,原告代表者はこれに沿う供述をしている。そこで,以下,\nこの供述の信用性について検討する。
ア まず,被告は原告から本件機械を代金420万円(消費税込)で購入し て本件機械の所有権を取得し,本件機械を自由に使用収益することができる立場に あるから,被告が本件機械を購入したにもかかわらず,これを使用する都度,原告 に対し使用料を負担することは,直ちに経済合理性があるものとはいえず,特段の 合意としての本件使用料合意が,明確に立証されなければならない。 この点につき,原告代表者は,被告との間の合意の前提として,本件特許の特許\n権者との間で,本件機械を使用して杭引抜き工事を施工した場合には,特許使用料 を支払う旨合意しており,現にこれを支払っていたなどと供述している。しかし, 原告と本件特許の特許権者との間の合意の存在を直接裏付ける証拠は何ら提出され ていない。 そして,原告の主張立証によっても,被告が原告主張の合意をすることが経済的 に合理的といえる程の事情は明らかとなっていないといわざるを得ない。
イ また,本件売買契約に際しては,注文書と注文請書が作成され,これに は「ケーシングを販売するにあたり,類似品作成はご遠慮願います。」とか「ケー シングの販売後,修理不可能になった場合は,スクラップ処理願います。」とか「ケ\nーシングは(株)大枝建機工業様以外の使用はご遠慮願います。」との記載がされ ている(甲3,乙4)一方で,原告主張の使用料に関することは何ら明記されてい ない。それだけでなく,注文書や注文請書には,被告が本件機械を使用する杭引抜 き工事を受注したことを原告に対して報告しなければならないということさえ記載 されていない。 上記注文書と注文請書は,その性質上,それらが相手に交付され,その内容が一 致していれば,契約当事者における合意内容になると考えられる。そうすると,上 記認定の注文書等の記載内容は原告と被告の合意内容になるが,そこには原告主張 の使用料に関する記載はなく,そのことは,原告と被告との間でそのような合意が されなかったことを強くうかがわせるものといわざるを得ず,原告代表者の供述と\nは必ずしも整合しない。原告代表者は,業界では契約書や合意書等の書面を作成し\nないのが通例であるとか,書面で契約書を交わすというのが知識としてなかったな どと供述しているが,上記注文書等には上述した別の合意の内容が記載されている ことに照らし,採用できない。
ウ さらに,原告代表者の供述は,本件機械の販売後の原告の行動と必ずし\nも整合しない。すなわち,原告は被告に対して4件の杭引抜き工事を発注し,各工 事では本件機械が使用されたところ,原告は被告が本件機械を使用したことを当然 に認識し得たのであるから,本件使用料合意が成立していたのであれば,これに基 づく使用料を請求するか,原告が被告に対してその工事の代金を支払う際に,使用 料相当額を相殺処理するなどして精算することは容易であった。しかし,原告は各 工事の代金を支払う際に,いずれも使用料の精算をすることなく工事代金の全額を 支払うのみならず,未払の使用料がある旨を被告に指摘した事実も認められないの であって,これらの事情は,原告代表者の供述と必ずしも整合しないといわざるを\n得ない。 この点に関し,原告代表者は,事務員が被告への工事代金の支払に当たり,使用\n料を差し引くのを漏らしていた旨供述しているが,原告による工事代金の支払はそ の請求時期(平成28年6月20日ないし平成29年4月20日)に近接した時期 に3回に分けて行われたと推認され,毎回処理を漏らしていたとするには疑問があ るし,その時期は,後記エで検討する他の業者への使用料支払請求の時期(平成2 8年8月22日。甲8,9)とほぼ同じ時期であることに照らせば,原告代表者の\n上記供述を直ちに採用することはできない。
エ 原告は,原告からケーシングを購入した他の業者が,それを使用した工 事を受注した際に,工事代金から使用料を控除することによって,使用料を支払っ たことを主張している(甲8ないし10)。しかし,これは被告とは別の業者の話 にすぎず,このような事実があったとしても,直ちに被告との間で本件使用料合意 が成立したと推認することはできない。そして,上記ウのとおり,被告は原告から, 使用料を控除されることなく工事代金全額の支払を受けるなど,異なる事実関係が 認められるから,上記事実から,被告との間に本件使用料合意が成立したと推認す ることは困難である。 なお,原告代表者は,本件売買契約の後に,被告取締役が被告において使用料を\n支払う義務があることを認めていた旨を供述するが,被告取締役はこれを否定して おり,原告代表者の上記供述以外にこれに沿う証拠は何ら提出されていないから,\n上記のような事実を認めることもできない。
オ 以上のように,原告代表者の供述は,本件売買契約に際して作成された\n注文書等の記載内容や原告自身の行動と必ずしも整合しないから,これによって本 件使用料合意の成立を認めることはできないというべきである。
(2) 本件においては,他に本件使用料合意の成立を認めるに足りる証拠は提出 されていないから,この点についての原告の主張を認めることはできず,本件使用 料合意に基づく使用料の請求は理由がない。
2019.09. 2
平成30(行ケ)10047 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
本件訂正事項は,本件訂正前の請求項21の「内層として形成される複 数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる3つ のプレーン層」と「信号を送受信する3つの信号層」を備える「配線層」 に限定するものである。そして,本件訂正後の請求項21の文言から,「グ ランドまたは電源となる3つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー ン層」は,「配線層」であって,半導体装置の基板に搭載された「ドライ ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して,電源電圧が供給され る電源線として機能することを理解できる。\n次に,本件明細書には,「電源回路5は,ホスト1側の電源回路から供 給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し,これ ら内部直流電源電圧を半導体装置100内の各回路に供給する。」(【0 011】),「略長方形形状を呈する基板8の一方の短辺側には,ホスト 1に接続されて,上述したSATAインタフェース2,通信インタフェー ス3として機能するコネクタ9が設けられている。コネクタ9は,ホスト\n1から入力された電源を電源回路5に供給する電源入力部として機能す\nる。」(【0012】),「図4は,基板8の層構成を示す図である。基\n板8には,合成樹脂で構成された各層(絶縁膜8a)の表\面あるいは内層 に様々な形状で配線層8bとして配線パターンが形成されている。配線パ ターンは,例えば銅で形成される。基板8に形成された配線パターンを介 して,基板8上に搭載された電源回路5,DRAM20,ドライブ制御回 路4,NANDメモリ10同士が電気的に接続される。…」(【0013】), 「基板8の各層に形成された配線層8bは,図5に示すように,信号を送 受信する信号層,グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」\n(【0015】)との記載がある。また,図5には,基板8の内層として, 「3層」,「4層」及び「6層」に「信号層」を,「2層」及び「7層」 に「プレーン層(GND)」を,「5層」に「プレーン層(電源)」を配 する層構成が示されている。\nこれらの記載事項によれば,図5の「5層」の「プレーン層(電源)」 は,配線層であって,半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」 や「不揮発性半導体メモリ」である「NANDメモリ」に対して,電源回 路5において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され る電源線として機能することを理解できる。\n以上によれば,本件訂正後の請求項21の「グランドまたは電源となる 3つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は,本件明細書に 記載されているものと認められるから(【0011】ないし【0013】, 【0015】,図5),本件訂正は,本件明細書に記載された事項の範囲 内においてしたものであって,新規事項の追加に当たらないものと認めら れる。
イ これに対し原告は,本件明細書の【0015】記載の「電源線」とは, 基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり,「発 電機または電池のように,外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味 する「電源」(甲62,63)とは全く異なる概念であるが,本件訂正事 項は,「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり,本件訂正事項 のとおりに請求項21を訂正した場合には,配線層の中に「電源」がある こととなって,本件明細書の「電源はホスト1にある」旨の記載とも矛盾 するから,本件訂正は,本件明細書に記載されていない新規事項を追加す るものであって,本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの とはいえない旨主張する。 しかしながら,前記ア認定のとおり,本件訂正後の請求項21の「グラ ンドまたは電源となる3つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン 層」は,半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発 性半導体メモリ」に対して,電源電圧が供給される電源線として機能する\n「配線層」であって,「電源」そのものではないから,原告の上記主張は, その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり,本件訂正は,本件明細書に記載された事項の範囲内におい てしたものであって,新規事項の追加に当たらないから,これと同旨の本件 審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由1は理由がない。
・・・・
原告は,本件特許発明1,14及び21の「第1の値が7.5%以下」及 び「前記第1の平均値と前記第2の平均値はともに60%以上」並びに本件 特許発明1,2,5,6,17,21及び25の「配線密度が80%以上」 は,いずれも原出願当初明細書に記載されていないから,本件出願は,分割 出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり,これと異なる本件審 決の判断は誤りである旨主張するので,以下において判断する。
ア 「第1の値が7.5%以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば,原出願当初明細書には,「本発明」は, 平面視において長方形形状の基板を用いる場合に,基板の反りを抑える ことができる半導体装置を提供することを目的とし(【0005】), 上層(基板の層構造の中心線よりも表\面層側に形成された層)全体の配 線密度と下層(基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層)\n全体の配線密度とが略等しくなることで,基板の上層全体に占める絶縁 膜(合成樹脂)と配線部分(銅)との比率が,基板の下層全体に占める 合成樹脂と銅との比率と略等しくなり,上層と下層とで熱膨張係数も略 等しくなるため,基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す ること(【0014】,【0015】,【0023】,【0024】, 図5)の開示があることが認められる。
次に,原出願当初明細書には,1)「基板8の各層に形成された配線層 8bは,図5に示すように,信号を送受信する信号層,グランドや電源 線となるプレーン層として機能」し,「各層に形成された配線パターン\nの配線密度,すなわち,基板8の表面面積に対する配線層が占める割合」\nを「図5に示すように構成している」こと(【0015】),2)「本実 施の形態では,グランドとして機能する第8層をプレーン層ではなく網\n状配線層とすることで,その配線密度を30〜60%に抑え」,「基板 8の上層全体での配線密度は約60%となって」おり,「第8層の配線 密度を約30%として配線パターンを形成することで,下層全体での配 線密度を約60%とすることができ,上層全体の配線密度と下層全体の 配線密度とを略等しくすることができる」こと,「なお,第8層の配線 密度は,約30〜60%の範囲で調整することで,上層全体の配線密度 と略等しくなるようにすればよい」こと(【0016】),3)「本実施 の形態では,第8層の配線密度は,約30〜60%の範囲で調整し,上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので,熱 膨張係数も略等しくなる」ため,「基板8に反りが発生するのを抑制す ることができる」こと(【0024】)の記載がある。また,図5には, 「第1の実施の形態」に係る8層構造の配線層の上層の配線密度につい\nて,「1層」が「約60%」,「2層」が「約80%」,「3層」が「約 50%」,「4層」が「約50%」,上層全体(「1層」ないし「4層」) で「約60%」であること,下層の配線密度について,「5層」が「約 80%」,「6層」が「約50%」,「7層」が「約80%」,「8層」 が「約30〜60%」,下層全体(「5層」ないし「8層」)で「約6 0%〜67.5%」であることが示されている。 そして,図5,【0016】及び【0024】の記載(上記2)及び3)) から,図5の「8層」の配線密度を「約30%」とした場合には下層全 体の配線密度が「約60%」(計算式(80+50+80+30)÷4) になり,「8層」の配線密度を「約60%」とした場合には下層全体の 配線密度が「約67.5%」(計算式(80+50+80+60)÷4) になること,図5に示す上層全体の配線密度が「約60%」の場合,下 層全体の配線密度が「約60%〜67.5%」であるときは,「上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので,熱膨張 係数も略等しくなる」ため,「基板8に反りが発生するのを抑制するこ とができる」ことを理解できる。
さらに,これらの記載事項から,図5の「8層」の配線密度を「約3 0%〜60%」の範囲で調整すると,上層全体の配線密度の平均値(約 60%)と下層全体の配線密度の平均値(約60〜67.5%)の差が 「約0%〜7.5%」の範囲で調整され,両者の配線密度が略等しくな り,熱膨張係数も略等しくなるため,基板8に反りが発生するのを抑制 することができるものと理解できる。
そうすると,原出願当初明細書には,「本発明」の「第1の実施の形 態」として,配線層の上層全体の配線密度の平均値(「第1の平均値」 に相当)と下層全体の配線密度の平均値(「第2の平均値」に相当)と の差を「7.5%以下」とすることが記載されていることが認められる から,本件特許発明1,14及び21の「第1の値が7.5%以下」は, 原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら れる。 したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は,原出願当初明細書には,基板の反りが発生する のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密 度との差が何%かについての記載はなく,また,【0016】の「なお, 第8層の配線密度は,約30〜60%の範囲で調整することで,上層全 体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は,第8層 の配線密度を約30〜60%の範囲で調整することを可能とすることで,\n上層全体の配線密度を67.5%とした場合(例えば,第3層の配線密 度を80%とした場合)であっても,第8層の配線密度を60%とする と,下層全体の配線密度も67.5%となり,上層全体の配線密度と略 等しくすることで,反りを防止していることを意味するものであり,上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて,「第1の値が 7.5%以下」とすることについての記載はないから,本件特許発明1, 14及び21の「第1の値が7.5%以下」は,原出願当初明細書に記 載されていない旨主張する。 しかしながら,前記(ア)認定のとおり,図5,【0016】及び【0 024】から,図5に示す上層全体の配線密度が「約60%」の場合, 下層全体の配線密度が「約60%〜67.5%」であるときは,「上層 全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので,熱膨 張係数も略等しくなる」ため,「基板8に反りが発生するのを抑制する ことができる」ことを理解できるから,原出願当初明細書には,上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて,「第1の値が7. 5%以下」とすることについての記載はあるものと認められる。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成30(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
第1次補正は,旧請求項1について,「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し,「2枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を\n取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク トを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」(第1次補正後の請求\n項1)に補正(下線部は補正箇所)するものである。 しかるところ,当初明細書等には,第1次補正後の請求項1の「複数の 排気ダクト」の用語について定義した記載はない。
そして,1)甲2(特開2014−148882号公報)の「これらのう ち,横流換気方式は,トンネル軸方向から見たときに全体が逆T字状断面 となるように,トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト,他方の側を排気ダクトとしたものであり,…交通量が多い場合に は,十分かつ安定した換気性能\を確保することが可能であるため,特に長\n大トンネルでは,数多く採用されてきた。」(【0004】)との記載, 2)甲3(特開2014−132146号公報)の「送気ダクト側天井板パ ネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)は,それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)により支 持される。送気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル (2)の長さを,天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)との水平距離 より大きくすることにより,両側の天井板パネルは山型の構造をもち,送\n気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)がお互 いに押し合うことで,トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく,隔壁板下側受台(6)と天井板受台(3) との位置ずれを防止する程度の固定で,通行部分(9)への落下を防止す ることができる。」(【0008】)との記載及び図1,3)甲4(登録実 用新案第3183422号公報)の「この天井構造の連結具6の頂部とト\nンネル1の最頂部1aの間に,仕切板7が張られており,仕切板7によっ て,天井板4,5の上方には,従来と同様に左右で送気路9,排気路10 が形成されている。もっとも,この仕切板7には,従来のように,天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」(【0017】)との記載を総 合すれば,本願の出願日当時,トンネルの技術分野において,「排気」と 「送気」は明確に区別され,「排気ダクト」と「送気ダクト」は,別の用 語として,使い分けられていたこと,トンネル内の換気を行うために,天 井,天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」とは,「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり,これには,排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に,当初明細書等には,図1の従来のトンネルの構成図に関し,「4\nは天井1に取り付けられたナットで構成される結合部,吊り金具3は該結\n合部4に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具3の他端は固着\n部5を介して天井板2に取り付けられ,天井板2を吊っている。このよう に,天井板2でトンネルを2分しているのは,排気を行なうためである。 10,11はトンネル内を照らすライトである。」(【0002】),「即 ち,吊り金具3に沿って隔壁を設け,その一方を送風ダクト,他方を排気 ダクトとして,トンネル内の換気を行なっているものである。」(【00 03】)との記載がある。上記記載によれば,図1の従来のトンネルにお いて,天井1と天井板2の間の空間が吊り金具3に沿った隔壁によって2 分され,一方を「送風ダクト」,他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には,上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより,トンネルに「複数の排気ダク\nト」を形成することについては記載も示唆もない。 以上によれば,第1次補正後の請求項1の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は,当初明細書等に記載は なく,当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また, 上記技術常識に照らすと,排気ダクトと送風ダクトとは,「対」となって 換気機能を果たすことからすれば,排気ダクト及び送風ダクトを備える換\n気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは,技術的思想を異にする ものと認められる。 したがって,第1次補正は,当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入 するものと認められるから,当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。
(3) 原告の主張について
原告は,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」とは,複数の排 気を含めた換気が可能なダクト程の意味であり,当初明細書の【0002】,\n【0003】及び図2には,「複数の排気ダクト」として,2分され,又は 隔壁が設けられたことにより,一方が送風ダクト,他方が排気ダクトとされ たものが示されているから,第1次補正は,当初明細書等に記載された事項 の範囲内においてした補正である旨主張する。 しかしながら,前記(2)ア認定のとおり,第1次補正後の請求項1の「複数 の排気ダクト」とは,「排気ダクト」が複数存在することを意味するもので あり,これには,排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相 当であるから,原告の上記主張は,その前提において採用することができな い。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.08.30
平成30(行ケ)10164 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年8月28日 知的財産高等裁判所
前記(3)イのとおり,各文献には,ショ糖の約650倍の甘味を有する非代謝 性のノンカロリー高甘味度甘味料であるスクラロースが,アスパルテーム,ステビ ア,サッカリンナトリウム等の他の高甘味度甘味料と比較して,甘味の質において ショ糖に似ているという特徴があることから,多くの種類の食品において嗜好性の 高い甘味を付与することが見込まれているとの記載があり,加えて,前記(3)アのと おり,本件出願前に,ショ糖や,アスパルテーム,ステビア,サッカリンといった慣 用の高甘味度甘味料が酸味のマスキング剤としての機能を備えることが,当業者に\n周知であったことからすると,引用発明のアスパルテームに代えてスクラロースを 採用してみることは,当業者が容易に想到することができたというべきである。
イ また,前記(3)イのとおり,各文献には,スクラロースをその甘さが感じられ る閾値より低い濃度で用いた場合でも,塩なれ効果,卵風味の向上効果を奏するこ と,製品100重量部に対して0.0001〜0.1重量部(製品に対して0.00 01〜0.1重量%)のスクラロースを用いた実施例によれば,カプサイシン0.0 01%のとき,甘味度が0である0.0001重量部(同0.0001重量%)又は 0.005重量部(同0.005重量%)で辛味増強効果を奏すること,スクラロー スの甘味を感じさせない0.0025重量%のアルコール/スクラロース水溶液で エチルアルコールの苦味の抑制効果を奏することの各記載がある。 以上の記載によれば,スクラロースの添加については,向上させようとする風味 や製品によって使用量は上下するものの,下限値として,製品に対して0.000 1重量%,0.0025重量%,0.005重量%で用いたものなどが知られてお り,スクラロースの甘味を感じさせない量であっても製品の風味の向上が可能であ\nることを当業者は認識していたものと認められる。 他方,引用例には,アスパルテームによる酸味緩和効果を得るための下限値とし て1mg%(0.001重量%),1.5mg%(0.0015重量%),5mg% (0.005重量%)が挙げられ,上記のスクラロースと同様のレベルの使用量で 酸味のマスキングが行えることが記載され,更に,アスパルテームの甘味により, 食品・調味料の呈味バランスが崩れないようアスパルテームの添加量は食品・調味 料の種類に応じ,適宜設定すべきであるとされている。 また,酸味のマスキングは,甘味の付与を目的とするものではなく,所望の酸味 のマスキング効果を奏する場合には,甘味がつきすぎて味のバランスが崩れること がないように,甘味料の使用を減らすことは考えても,増量することは考えないか ら,スクラロースを酸味のマスキング剤に使用する場合であっても,当業者は,酸 味のマスキングが実現可能な低い濃度でスクラロースを使用することを指向する。\nそうすると,スクラロースを,引用発明の食酢を含む食品(ドレッシング,ソー\nス,漬物,及び調味料などの製品)における,酸味のマスキング剤として使用するに あたり,酸味緩和効果が得られるものの,スクラロースの甘味により前記製品の旨 味バランスを崩さない濃度範囲のうち低い濃度を,製品ごとに選択して,スクラロ ースの従来の使用濃度である0.0001〜0.005重量%に重複する0.00 28〜0.0042重量%という濃度範囲に至ることは,当業者に容易であったと いうことができる。
ウ そして,本件明細書の実施例2〜4を参照しても,0.0028〜0.004 2重量%の濃度範囲を境にして,当業者の期待,予測を超える格別顕著な効果を奏\nしているとは評価できない。
エ 以上によれば,アスパルテームを製品濃度1〜200mg%(=0.001 〜0.2重量%)で添加する引用発明から,スクラロースを製品の0.0028〜 0.0042重量%で添加することは,容易に想到することができたものである。
(5) 被告の主張について
ア 被告は,トレハロースや甘味料であるネオヘスペリジンジヒドロカルコンが, 酸味の増強作用を有することを指摘して,相違点2は容易に想到できないと主張す る。 しかし,証拠(甲48)によれば,トレハロースは,食品の低甘味化に使用される ものであるから,アスパルテーム,ステビア,サッカリン等の高甘味度甘味料と同 様に論じることはできない。また,同じ文献(甲48)には,トレハロースを添加し た際に,酸味料の種類や他の呈味物質の存在によって,酸味が強調されたり,マス キングされたりすることを,不可解な現象であると説明されていることからすると, 高甘味度甘味料一般が酸味を緩和させる効果を有すると認定する上での支障となる とまではいえない。 また,ネオヘスペリジンジヒドロカルコンが,レモネードの酸味を増強する作用 を有する旨を理由中で説示した判決(甲15)があるものの,前記のとおり,ショ糖 やアスパルテームを含めた複数の慣用の高甘味度甘味料が酸味のマスキング剤とし ての機能を備えることが,当業者に広く知られていたと認められることからすると,\n特定の酸味飲料(レモネード)のみを対象にし,実験内容及び実験結果の詳細が証 拠上明らかでないネオヘスペリジンジヒドロカルコンの酸味増強作用に基づいて, 高甘味度甘味料一般の酸味緩和効果を否定する判断には至らない。 この点について,本件審決は,トレハロースのように醸造酢の酸味を増強する甘 味料も存在することを根拠の1つに挙げて,引用発明並びに甲2文献,甲3文献, 甲7文献及び甲8文献の記載から,高甘味度甘味料一般が酸味を緩和させる効果を 有することまで導き出すことはできないと判断しているが,上記説示したところに 照らし,誤りというべきである。
イ 被告は,甘味料の酸味マスキング効果とされるもののうちほとんどは,甘み という別の呈味によって酸味を覆い隠すものであり,甘味の閾値以下で酸味のマス キング効果を示す甘味料は,本件発明以前には,アスパルテームのみであったから, 甘味料一般について知られていたのは,甘味という別の呈味によって酸味を覆い隠 すことができるということであり,甘味の閾値以下でも酸味のマスキング効果のあ ることが技術常識になっていたものではないとして,本件発明が容易に想到できな かった旨を主張する。 しかしながら,被告の主張するように甘味料の酸味マスキング効果とされるもの のほとんどが甘味の閾値を超えた条件で甘みという別の呈味によって酸味を覆い隠 すものであることを明示的に示す証拠はない。かえって,既に説示したとおり,ス クラロースが甘味閾値以下でも所望の風味改善効果を奏することは,複数の文献(甲 4,23,80,81)に示されているから,甘味料一般に関して甘味の閾値以下で 酸味のマスキング効果を奏することが技術常識であったか否かにかかわらず,スク ラロースを,アスパルテームと同様に甘味の閾値以下で用いることは,当業者に格 別の創意工夫を要するものではなかったというべきである。
ウ 被告は,アスパルテームとスクラロースは,アミノ酸系甘味料と合成甘味料 という別のカテゴリーに分類されていたものであり,アスパルテームと単に「高甘 味度甘味料」というカテゴリーが同じなだけのスクラロースが酸味をマスキングで きるかもしれないなどとは考えない,そもそもショ糖の600倍も甘く(アスパル テームですら200倍),ごく少量添加しただけで味のバランスを大きく崩すことが 予想され,扱いの難しいスクラロースを,あえて酸味のマスキングに使用する動機\n付けは存在しない,とも主張する。 しかしながら,前記のとおり,本件出願日当時,ショ糖,アスパルテーム,ステビ ア,サッカリンといった,化学構造において別のカテゴリーに分類され,甘味の大\nきく異なる複数の甘味料が,酸味のマスキング剤に用いられていたことからすれば, アスパルテーム等と比べて各種の風味改善効果に優れているスクラロースを添加す ることによっても酸味のマスキングが可能であると予\測し,スクラロースを,添加 する製品ごとの味のバランスが崩れにくい濃度範囲で使用して,その酸味マスキン グ効果を確認しようとすることは,当業者が容易に想到することができたというべ きである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.08.30
平成31(ネ)10023 不正競争行為差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 前記1(3)のとおり,控訴人は,本件覚書により,本件子会社との間で,(ア) 本件子会社に対し,控訴人の保有するインコア及びイヤーパッドに係る一切の特許 の使用を許諾し(第5条前段),その許諾に係る対価を請求せず(同条後段),(イ) 本件子会社に対し,控訴人のイヤーパッドを使用した商品の開発及び販売を許諾し, イヤーパッドの供給に協力する(第6条)旨合意したことが認められる。 また,前記1(4)のとおり,原告製品は,控訴人の供給するイヤーパッドを使用し て本件子会社において開発された商品であるものと認められる。 そして,被控訴人は,前記1(5)のとおり,平成28年11月15日付けで原告製 品の製造,販売に係る事業を本件子会社から譲り受け,同事業を継続したというの であり,このことは,本件覚書第9条において控訴人によりあらかじめ承諾された ものである。 そうすると,被控訴人は,本件覚書においてされた本件特許権1に係る特許発明 の実施の許諾に基づいて原告製品を製造し販売していたものと認められる。 また,上記の実施許諾の趣旨が原告製品の製造販売にあることに照らせば,本件 特許権1に係る特許発明の実施許諾の際に,本件意匠権についても黙示に許諾があ ったものと推認される。 以上によれば,被控訴人の原告製品の製造販売は,控訴人の許諾の範囲であり, 控訴人の本件知的財産権を侵害していないというべきである。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,本件覚書が,平成22年に控訴人と本件子会社との間で締結され た本件実施許諾契約と一体のものとして,作成・合意されたものであると解した上, 被控訴人は,同契約の第6条により,原告製品の開発,販売に関して控訴人に報告 する義務を負っていたにもかかわらず,これを履行しないので,平成29年4月3 日付けの文書(乙7)で催告をし,同月12日に控訴人代表者から本件子会社の代\n表者であるAに宛てて送信されたメール(乙6)により同契約を解除する旨の意思\n表示をし,その結果,本件覚書における許諾の合意も失効した旨主張する。\nしかしながら,前記1で認定した事実関係に照らせば,本件覚書は,平成22年 4月から平成28年3月までに生じた事情を踏まえた上,後の事業譲渡も視野に入 れた上で,控訴人と本件子会社との間に新たな権利関係を設定するために作成され たものというべきであり,その合意の内容に照らしても,本件覚書が本件実施許諾 契約と一体のものとして作成・合意されたものと解することは困難である。 以上の次第であるから,本件実施許諾契約を解除する旨の意思表示をしたことに\nより本件覚書における合意も失効した旨をいう控訴人の主張は,その前提を欠き, 理由がない。
イ 控訴人は,本件覚書と本件実施許諾契約とが一体で,本件子会社又は被控訴 人が同契約に基づく本件報告義務を負うものと認識していたことから,本件覚書に 係る合意には要素の錯誤があるので無効であると主張し,また,法的拘束力のある 契約としては本件実施許諾契約があるだけで,本件覚書に契約としての拘束力はな いという認識の下に本件覚書に押印したものであり,相手方である本件子会社にお いてもこのような控訴人の真意を知っていたから,本件覚書に係る合意は心裡留保 により無効であるとも主張する。 しかしながら,本件覚書による合意においては,当事者双方の意思表示が書面に\nよってされている。控訴人のいう認識の内容は本件覚書の内容との関係では意思表\n示の動機に当たり,この動機が表示され,法律行為の要素になっているとは認めら\nれないから,錯誤無効の主張は理由がない。また,前記アで説示したところに照ら せば,本件覚書の当事者双方において,本件覚書に契約としての拘束力はないとの 認識があったとは認められないから,心裡留保による無効の主張も理由がない。
(3) 小括
以上によれば,被控訴人の原告製品の製造販売は,控訴人の許諾の範囲であり, 控訴人の本件知的財産権を侵害していない。 よって,本件行為において告知され,流布されている事実は,虚偽であると認め られる。
3 本件知的財産権に係る消尽の成否について
念のため,消尽の成否についても検討を加える。
(1) 特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製 品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力 は,当該特許製品を使用し,譲渡し,又は貸し渡す行為等には及ばず,特許権者は, 当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される(最高裁平成 7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299 頁,最高裁平成18年(受)第826号同19年11月8日第一小法廷判決・民集6 1巻8号2989頁参照)。このように解するのは,特許製品について譲渡を行う都 度特許権者の許諾を要するとすると,市場における特許製品の円滑な流通が妨げら れ,かえって特許権者自身の利益を害し,ひいては特許法1条所定の特許法の目的 にも反することになる一方,特許権者は,特許発明の公開の代償を確保する機会が 既に保障されているものということができ,特許権者から譲渡された特許製品につ いて,特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存 在しないためである。そして,この趣旨は,意匠権についても当てはまるから,意匠 権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。
(2)前記1(6)のとおり,被控訴人は,本件知的財産権を有する控訴人から,本件 知的財産権の実施品である被告製品(イヤーパッド)を購入し,これを,原告製品で あるイヤホン,無線機本体,原告製品を媒介するコネクターケーブル及びPTTス イッチボックスと併せて,それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ,原告製品の保 証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売しているという のである。 このような事実関係に照らすと,被控訴人は,原告製品に被告製品を付属させて 販売していたものであり,被告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたも のとはいえず,控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって,被告製品に ついては本件知的財産権は消尽するものと解される。そうすると,控訴人において は,もはや被控訴人に対して本件知的財産権を行使することは許されないから,被 控訴人において原告製品を製造等する行為は,控訴人の有する本件知的財産権を侵 害するものではないというべきである。
(3) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,消尽の根拠となる特許製品の「譲渡」とは,典型的には,権利者が 特許製品を市場の流通に置くことをいい,特許製品が市場の流通に置かれたといえ るか否かは,1)権利者である特許製品の譲渡人が十分な対価を得ているか,2)当該 特許製品が転々流通することを権利者が想定していると認められるか,3)権利者で ある特許製品の譲渡人と譲受人との関係,4)特許製品の性質等を考慮して,個々の 譲渡内容を精査して判断する必要があると主張する。そして,本件事実関係の下に おいては,特許製品が市場の流通に置かれたものではないので,消尽の根拠となる 特許製品の「譲渡」がないと主張する。 しかしながら,特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合におい て消尽が認められ,特許権者は,当該製品について特許権を行使することは許され ないものと解されることの根拠は,前記のとおり,第一義的には,特許製品につい て譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると,市場における特許製品の円滑 な流通が妨げられ,かえって特許権者自身の利益を害し,ひいては特許法1条所定 の特許法の目的にも反することになるということにある。そうだとすると,消尽の 効果が生じるか否かを,第三者には知り得ない,譲渡人と譲受人間における事情に 係らせることは,消尽を認める趣旨に沿わないものというべきである。控訴人の主 張は理由がない。
イ なお,控訴人は,譲渡により消尽の効果が生じた場合であっても,譲渡に錯 誤無効があり,又は解除がされたときは,消尽の効果は失われるとも主張し,本件 がそのような場合に当たるとも主張する。 しかし,本件において控訴人が錯誤無効や解除を主張しているのは本件覚書につ いてであり,消尽の根拠となっている被告製品の譲渡についてではないから,消尽 の効果を争う主張としては,それ自体失当というべきである。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 意匠その他
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2019.08.29
平成30(行ヒ)69 審決取消請求事件 令和元年8月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 知的財産高等裁判所
上記事実関係等によれば,本件他の各化合物は,本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの,いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって,引用発明1に係るものではなく,引用例2との関連もうかがわれない。そして,引用例1及び引用例2には,本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに,当業者が本件各発明の効果の程度を予\測することができたということはできず,また,本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると,本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって,本件各発明の効果の程度が,本件各発明の構\成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。しかるに,原審は,本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず,その他,本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。\n そうすると,原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構\成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構\成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十\分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく,このような原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。\n
5 以上によれば,原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法 令の違反がある。論旨は,この趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を 免れない。そして,本件各発明についての予測できない顕著な効果の有無等につき\n更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.08.27
平成31(行ケ)10037 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年8月7日 知的財産高等裁判所
これに対し原告は,1)商標法4条1項8号の趣旨が第三者の人格権の保 護であるとしても,同法は,同号の「他人の氏名」の該当性を判断するに 当たり,第三者の人格権のみを考慮することは予定していないというべき\nであり,同法の目的である産業発展の寄与ないし需要者の利益保護の観点 から,登録が拒絶されることで受ける者の不利益も十分に考慮しなければ\nならないから,同号の「氏名」に該当するか否かは,特定人の同一性を認 識させるに足りる表記であるか,あるいは,本願商標がブランドとして一\n定の周知性を有するかという観点から総合的に判断されるべきであり,同 号の「他人」に当たるか否かは,その承諾を得ないことにより人格権の毀 損が客観的に認められるに足る程度の著名性・希少性等を有する者かとい う観点から判断すべきである,2)諸外国においても,「他人の氏名」であれ ば,その全てについて,その他人の承諾がない限り商標登録を認めないと いう判断はしておらず,特許庁の過去の審決例においても,自己の氏名を モチーフしたと考えられる多数の商標が登録査定を受けている旨主張する。 しかしながら,上記1)の点について,商標法4条1項8号の趣旨は,前 記アのとおり,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われること がないという人格的利益を保護することにある。そして,同号は,その規 定上,雅号,芸名,筆名,略称については,「著名な雅号,芸名若しくは筆 名若しくはこれらの著名な略称」として,著名なものを含む商標のみを不 登録とする一方で,「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」については, 著名又は周知なものであることを要するとはしていない。また,同号は, 人格的利益の侵害のおそれがあることそれ自体を要件として規定するもの でもない。したがって,同号の趣旨やその規定ぶりからすると,同号の「他 人の氏名」が,著名性・希少性を有するものに限られるとは解し難く,ま た,「他人の氏名」を含む商標である以上,当該商標がブランドとして一定 の周知性を有するといったことは,考慮する必要がないというべきである。 次に,上記2)の点については,諸外国における他人の氏名を含む商標の 登録に関する法制や取扱いが,直ちに我が国における法解釈に影響を及ぼ すものではないし,特許庁の過去の審決例において,自己の氏名をモチー フしたと考えられる商標が登録査定を受けているとの事実があったとして も,本件審決における本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断が,こ れに左右されるものではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.08.27
平成31(ネ)10026 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年8月7日 知的財産高等裁判所 横浜地方裁判所 川崎支部
控訴人は,編集著作物において素材の選択,配列を決定した者は問題 とならず,配列を行ったのは控訴人であるなどと主張する。しかしなが ら,控訴人の主張が,決定権限を持たずに素材の配列に関与した者,例 えば,単なる原案,参考案の作成者や,相談を受けて参考意見を述べた 者までがおよそ編集著作者となるというものであるとすれば,そのよう な主張は,著作者の概念を過度に拡張するものであって,採用すること はできない。また,本件において本件書籍の分類項目を設け,選択され た作品をこれらの分類項目に従って配列することを決定したのが被控訴 人であることは先に引用した原判決認定のとおりであって,当審におけ る控訴人の主張を踏まえてもかかる認定は左右されない。
イ また,控訴人は,被控訴人の前件訴訟における訴訟行為を捉えて,本 件において被控訴人は自分自身が編集著作者であると主張することは許 されないなどと主張する。 しかしながら,そもそも控訴人が前提とするところの,前件訴訟にお いて被控訴人が編集著作者でないと自白し,本件書籍が編集著作物であ れば控訴人が編集著作者であると認めたなどとする事実関係を裏付ける 証拠はないから,控訴人の主張はその前提を欠くものである。かえって, 控訴人による本件訴訟は,前件訴訟においてAが敗訴したことを受けて, 原告を控訴人とするとともに,Aは控訴人の代理人であったなどとして, 実質的には前件訴訟と同様の事実関係の主張を繰り返すものに過ぎず, 前件訴訟の蒸し返しであるといわざるを得ない。 上記の控訴人の主張は採用できない。
(3) 以上によれば,控訴人が決定し,Aに行わせたとする事務自体,本件書 籍における素材の配列について,創作性を有する行為であったとはいえな いから,控訴人が本件書籍の編集著作者であるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.08.27
平成31(ネ)10016 競業差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月7日 知的財産高等裁判所(3部) 東京地方裁判所 立川支部
本件競業行為が本件各合意に違反するか(争点1)
(1) 退職者に対する競業の制限(以下「競業制限」という。)は,退職者の 職業選択の自由や営業の自由を制限するものであるから,個別の合意あるい は就業規則による定めがあり,かつその内容が,これによって守られるべき 使用者の利益の内容・程度,退職者の在職時の地位,競業制限の範囲,代償 措置の有無・内容等に照らし,合理的と認められる限り,許されるというべ きである。
(2) 就業規則及び退職時合意の効力
ところで,控訴人の就業規則には,1)社員は,退職後も競業避止義務を 守り,競争関係にある会社に就労してはならない,2)社員は,退職または解 雇後,同業他社への就職および役員への就任,その他形態を問わず同業他社 の業務に携わり,または競合する事業を自ら営んではならないとの規定があ るが,この定めは,退職する社員の地位に関わりなく,かつ無限定に競業制 限を課するものであって,到底合理的な内容のものということはできないか ら,無効というほかはない。 また,被控訴人が退職時に提出した「誓約・確認書」には,前述のとおり, 退職後2年間,国分寺市内の競合関係に立つ事業者に就職しないとの約束を することはできない旨の被控訴人の留保文言が付されていたのであるから, これによって競業制限に関する合意が成立したということはできない。 これに対し,控訴人は,控訴人が「誓約・確認書」に「この文言は,当社 が指定した書式ではないので,無効。会社記載文言のみ有効。また,既に入 社時誓約書に記載もあるので,そちらの誓約書を根拠とすることも可能。」\nと記載してその旨説明し,被控訴人も「わかりました」と述べたものである から,「誓約・確認書」の不動文字のとおりの合意が成立したと主張するが, 控訴人の主張する事実を裏付ける的確な証拠はないし,仮に,このような事 実があったとしても,これにより「誓約・確認書」の不動文字どおりの合意 が成立したと解することはできない。
(3) 入社時合意の効力
ア 控訴人は,入社時合意について,被控訴人が,退職後2年間,国分寺市 内でアイリスト業務に従事することを禁止したものであると主張するか ら,入社時合意の効力が問題となる。
イ 入社時誓約書には,1)被控訴人は,退職後2年間は,在職中に知り得た 秘密情報を利用して,国分寺市内において競業行為は行わないこと(13 項),2)秘密情報とは,在籍中に従事した業務において知り得た控訴人 が秘密として管理している経営上重要な情報(経営に関する情報,営業 に関する情報,技術に関する情報…顧客に関する情報等で会社が指定し た情報)であること(10 項),3)被控訴人は,秘密情報が控訴人に帰属 することを確認し,控訴人に対して秘密情報が被控訴人に帰属する旨の 主張をしないこと(12 項)が記載されている(甲3)。 そこで,「秘密情報」の意義が問題となるが,上記入社時誓約書の記 載によれば,入社時合意における「秘密情報」とは「秘密として管理」 された情報であることを要することが理解できる。また,入社時誓約書 の秘密情報に関連する規定は,その内容に照らし,不正競争防止法と同 様に営業秘密の保護を目的とするものと解される。そして,入社時誓約 書には「秘密として管理」の定義規定は存在せず,「秘密として管理」 について同法の「秘密として管理」(2条6項)と異なる解釈をとるべ き根拠も見当たらない。そうすると,入社時誓約書の「秘密として管理」 は,同法の「秘密として管理」と同義であると解するのが相当である。 また,「競業行為」とは,控訴人に在籍中の被控訴人が提供していた 役務の性質に照らせば,他のまつげエクステサロンの経営及び他のまつ げエクステサロンにおけるアイリスト業務への従事を意味すると解され る。 以上によれば,入社時合意は,被控訴人が,退職後2年間は,在職中 に知り得た「秘密情報」を利用して,国分寺市内において他のまつげエ クステサロンの経営をせず,他のまつげエクステサロンにおけるアイリ スト業務に従事しない旨の合意であり,ここにいう「秘密情報」とは秘 密管理性を有する情報であることを要するものと解される。
ウ 被控訴人は,入社時合意は被控訴人の職業選択の自由及び営業の自由を 不当に制限するものであって無効であると主張する。 しかし,上記イのとおり,入社時合意は,2年という期間と国分寺市 内という場所に限定した上で,秘密管理性を有する情報を利用した競業 行為のみを制限するものと解されるから,職業選択の自由及び営業の自 由を不当に制限するものではなく,その制限が合理性を欠くものである ということはできない。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.08.26
平成28(ワ)8552 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年4月18日 大阪地方裁判所(21部)
まず,原告イラストと被告イラスト1ないし4は,丸まって眠っている猫を 上方から円形状にほぼ収まるように描くとともに,片前足と片後ろ足と尻尾をほぼ 同じ位置でまとめて描きつつ,耳や片後ろ足を若干円形状から突出して描いている 点で共通している。これらの共通点は,前記1で認定した原告イラストの創作性が 認められる表現上の特徴部分そのものであり,上記各被告イラストの表\現上の特徴 は,原告イラストのそれと共通しているといえる。 他方,原告イラストでは猫の目の周囲が黒いのに,上記各被告イラストはそうで はないが,全体からすると微差にとどまるものというべきである。 また,上記各被告イラストでは,猫の胴体部分に波様の紋様が描かれており,原 告イラストの雲様の紋様とは異なっているが,前述のとおり,原告イラストの表現\n上の特徴は,上半分に猫と分かるよう描かれた模様が徐々に変化して抽象的な紋様 につながり,猫の片前足の付け根の模様が,下半分の紋様にも使われるなど,猫を 描いた部分と抽象的な紋様とが連続的,一体的に構成され,全体として略円形状の\nマークのような印象を与える点にあると解され,上記各被告イラストは,これらを すべて有していると認められるが,下半分の抽象的な紋様にどのようなものを用い るかは表現上の本質的特徴といえるものではない。\n以上より,原告イラストと上記各被告イラストとの上記共通点に照らせば,上記 各被告イラストは,原告イラストを有形的に再製したものと認めることができる。
イ 被告イラスト5ないし8について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト1ないし4の共通点は,被告 イラスト5ないし8にも認められる。 他方,被告イラスト5ないし8には,猫の前足が2本とも描かれる一方で,ひげ が描かれておらず,抽象的な紋様が唐草様であるといった相違点もみられるが,そ れらの前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており,前記1で認 定した原告イラストの表現上の特徴は維持されているといえるし,ひげの有無等の\n相違点は微差であり,抽象的な紋様の相違は本質的ではない。 以上より,上記各被告イラストは,原告イラストを有形的に再製したものと認め ることができる。
ウ 被告イラスト9ないし12について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト1ないし4の共通点は,被告 イラスト9ないし12にも認められる。 他方,被告イラスト9ないし12には,猫の前足が2本とも描かれ,そのうち左 前足が円形状の外に突出しているという相違点や,足裏(肉球)が見えるように描 かれている(したがって,猫が両前足を上げているように描かれている)という相 違点等が認められる。 しかし,右前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており,前記 1で認定した原告イラストの表現上の特徴が基本的に維持されているということが\nできるし,左前足が円形状から突出しているものの,耳や片後ろ足の円形状からの 突出の程度は原告イラストと同程度にすぎず,丸まって眠っている猫を上方から描 き,猫を描いた部分と抽象的紋様の部分が連続的,一体的に構成され,全体として\n略円形状のマークのように見えるという原告イラストの基本的な特徴は維持されて おり,上記相違点によって,原告イラストの表現上の本質的な特徴を感得できなく\nなるものとは認められない。 以上より,上記各被告イラストは,原告イラストの表現上の本質的な特徴の同一\n性を維持しつつ,一部を変更したものと認めることができる。
エ 被告イラスト13ないし16について
被告イラスト13ないし16は,被告イラスト5ないし8と類似している点 が多く,被告イラスト13ないし16では,顔の傾きや2本の前足の重ね具合,片 後ろ足が円形状の中に収められている点等が異なっているものの,ひげが描かれて いる点で原告イラストに近く,全体として前記イの判断が妥当するといえる。 したがって,上記各被告イラストは,原告イラストを有形的に再製したものと認 めることができる。
オ 被告イラスト17ないし20について
被告イラスト17ないし20は,そもそも丸まって眠っている猫を描いたも のではなく,前記1で認定した原告イラストの表現上の特徴との共通点がみられな\nい。したがって,上記各被告イラストは原告イラストを有形的に再製したものとは 認められないし,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持していると認めること\nもできない。
・・・・
原告は,要旨,被告の卸売先である販売店の小売価格に,原告が利用するT シャツ販売サイトに準じた使用料率を乗じて,著作権法114条3項の損害の額を 算定すべきであると主張するのに対し,被告は,被告の販売店に対する販売金額(基 準卸値,卸売価格)に,より一般的な使用料率を乗じ,さらに販売店から返品され たものについては控除して,これを算定すべきであると主張する。
イ 被告に販売店から返品された商品の売上げを含むことの当否 著作権法114条3項に基づく損害を算定する基礎となる譲渡数量に,被告 が販売店から返品を受けた商品の数を含むべきか,換言すれば,使用料率を乗じる 売上額から返品分に係る売上額を控除すべきかについて,当事者間に争いがある。 しかし,被告は返品を受けた被告商品を含めて製造し,その時点で原告イラスト についての原告の複製権又は翻案権の侵害が発生し,それを販売店に販売すること によって一旦売上げが計上されたのであるから,被告が製造し,販売店に販売した 被告商品の数をもって上記譲渡数量と認めるのが相当であり,返品を受けた商品の 数(売上げ)を控除すべき旨の被告の主張は採用することができない。 この点については,被告が提出する乙14の第6条において,ジャージやTシャ ツに関する商品化権許諾契約の対価(使用料)は使用料単価に「製造数量」を乗じ て算定することとされ,その「製造数量」には見本品,試供品その他販売,頒布を 目的としない商品についても含まれるものとされており(同1条3項),まさに製 造された商品の数量によって使用料を算定することが定められている。被告商品は 上記契約の対象とされるジャージやTシャツと同じ種類の物品であるから,乙14 の上記条項は,被告商品についても,製造され,販売店に販売された商品の数量(売 上げ)をもとに使用料を算定することを正当化する根拠になると考えられる。
ウ 使用料率
(ア) 原告の主張について
まず,原告は自らがデザイナー登録してTシャツ等を販売しているサイト における報酬割合(甲24の2)や報酬パーセンテージ(甲45)を引用したり, 原告が実際に支払を受けていた報酬額と販売価格とを対比したりして,本件では少 なくとも25%の使用料率が相当であると主張している。 しかし,原告がデザイナー登録しているサイトは,前記1(1)で認定したとおり, デザイナー等を応援することをコンセプトとしたものであったり,デザイナーが自 らデザインしたイラストを付したTシャツを販売したりするためのサイトとしての 性質も有しており,原告イラストあるいは原告の作品自体を入手することを目的と して購入する者が多いと考えられるのに対し,被告による商品の販売態様は,主と して,ショッピングモールに店舗を構えるなどして,多種多様な商品を販売する販\n売店(量販店)に対して商品を販売するというものであり,販売態様が大きく異な っている。 また,原告がデザイナー登録しているサイトにおいては,上記性質上,必ずしも 一般的に,商品登録の際に多くの販売(売上げ)が見込まれるという性質のものと まで認めることはできないのに対し,被告は上記のような量販店に商品を販売する ことから,被告商品の製造販売を開始する時点で,ある程度の販売数(売上げ)が 見込まれるのが一般的と推認される。 このように,商品の販売実態も,原告が引用している販売サイトの例と,被告の 例とでは大きく異なっているから,上記のように著作物が複製等された商品が量販 店に対して販売され,かつ,ある程度の販売数(売上げ)が見込まれる本件におい て,「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するに当た り,商品の販売態様や販売実態の異なる原告主張の販売サイトの報酬割合等を参考 にすることは相当でないといわざるを得ない。なお,原告は甲46ないし48の例 も引用しているが,その実態は以上検討した例と変わるものではなく,甲46ない し48にも以上の判示が同じく妥当する。
(イ) 本件の使用料率
a 上記(ア)の判示を踏まえると,本件では,著作物が複製等された商品 が量販店に対して販売され,かつ,ある程度の販売数(売上げ)が見込まれる場合 を前提とした使用料率によるのが相当であるところ,そのような契約の例としては, 被告が引用している乙14の契約の例が挙げられ,被告商品の販売態様・販売実態 と同じ例と認められるから,本件の使用料率を算定にするに当たって,これを参考 にするのが相当である。
b また,乙14の契約は,乙17ないし19(甲54の1ないし3も 参照)の各商品について商品化権を許諾した契約であるから,これらとは商品にお ける著作物の使用割合等が異なれば,当然,使用料単価(使用料率)も異なってく るものと考えられる。したがって,本件において乙14の契約の例を参考にするに 当たっては,被告商品における原告イラストを複製又は翻案した被告イラスト(被 告イラスト17ないし20を除く。以下同じ。)の使用割合,ないし売上げへの寄 与を考慮すべきである。 そのような観点から被告商品を見てみると,被告商品においては,被告イラスト のみを単独で付したようなものはなく,被告において作成した他のデザイン,他の 紋様と組み合わせる形で,全体的なデザインの一部として被告イラストが使用され ており,例えば,被告商品4,16,18及び21のように,被告イラストが比較 的目立つように付されている商品がある一方で,被告商品5のように被告イラスト が見えにくい商品や,被告商品19のように別のイラストの方が相当目立つ形で付 されている商品等があり,商品における被告イラストの使用割合は相当異なってい る。 したがって,本件の使用料率を認定するに当たっては,原告イラストを複製又は 翻案した被告イラストの商品における使用割合(大きさや数)を考慮するのが相当 であり,その際には,乙14で使用料単価(使用料率)が定められた乙17ないし 19の各商品においては,キャラクターが比較的大きく描かれていることを踏まえ つつ,相当な使用料率を認定すべきと考えられる。
c 被告の主張について
被告は,被告商品では被告のオリジナルな図柄も描かれていることを指 摘しているが,そのことは乙17ないし19の各商品においても同じであるから, 乙14を参考にする場合には,上記bで述べた被告商品における被告イラストの使 用割合の中で考慮すれば足りると考えられる。 また,被告は,被告イラストごとに,原告イラストと関連する程度に応じて使用 料率を考慮すべき旨を主張しているが,被告イラストは原告イラストを複製又は翻 案したもので,前記2の判示によれば,原告イラストの表現上の本質的な特徴を強\nく感得することができるものと認められるから,上記被告が主張する点を,使用料 率の認定に当たり考慮する必要はないというべきである。 さらに,被告は乙14の契約の例が国民的人気を誇るキャラクターについての契 約であることを強調しているが,乙14の契約においてどのような点を考慮して使 用料単価(使用料率)が定められたのかは不明であるし,また乙14の契約は商品 の小売価格が1万1000円ないし1万7000円であることを前提としたもので あるところ,被告商品の小売価格は,一部1万円を超えるものがあるものの,大半 は7000円程度であり,安い商品では5000円を下回っている(甲6ないし1 4,16ないし18,弁論の全趣旨)から,乙14の契約の例では,結果的に使用 料単価が高く設定されているとみることもでき,本件で乙14の契約の例よりも使 用料率を低くすべき事情があるとまでいうことはできない。
d 小売価格と卸売金額のいずれをもとに算定すべきか 著作権法114条3項の著作権の行使につき受けるべき金銭の額を算定 するに当たっては,特段の事情のない限り,販売店に対する卸売価格ではなく,販 売店における小売価格を基準とするのが相当であるが,その場合においても,被告 が当初販売店に卸売りした際に予定していた価格(定価,標準価格)に固定するの\nではなく(原告はそれを前提とする主張をする。),被告商品においては,季節の 変わり目に被告商品を値下げして販売することもやむを得ないと解されるから,販 売店が値下げして販売した場合には,その値下げ後の価格をもとに算定するのが相 当である。 そして,本件では,被告商品が販売店において,実際にいくらで販売されたかを 認めるに足りる証拠はないが,被告の卸売金額から逆算して販売店での販売価格を 認定することができ,被告は,販売店がこの金額で被告商品を販売することを前提 に,販売店に卸売りしたのであるから,この販売店での販売価格に基づき,原告が 受けるべき金銭の額を算定するのが相当である。 被告が販売店に対して卸売りした被告商品に係る卸売金額(返品分を含む。)は, 別紙「損害額(販売店関係)計算表(裁判所認定)」の「販売店関係の売上額(円) …4)」欄記載のとおりであるところ(乙12,13),被告は販売店に卸売りする に当たり,原則として小売価格を基準卸値の2倍の金額に設定していること(弁論 の全趣旨)を踏まえると,販売店における販売額は,その金額の2倍に相当する金 額(同別紙の「販売店における販売額(円)」欄記載のとおり)と認めることができ る。 以上に対し,被告が通販サイトにおいて小売りした被告商品については,被告が 実際に販売した金額(別紙「損害額(通販サイト関係)計算表(裁判所認定)」の\n「通販サイト関係の売上額(円)」欄記載の金額。乙13)をもとに算定することに なる。
e 上記a及びbで判示した諸事情を考慮しつつ,乙14を参考にする と,本件の使用料率は次の通り認定するのが相当である(別紙「損害額(販売店関 係)計算表(裁判所認定)」及び「損害額(通販サイト関係)計算表\(裁判所認定)」 の「使用料率」欄参照)。
(a) 被告イラストの使用割合,ないし売上げへの寄与が比較的高いもの 小売価格の5%被告商品4,16,18,21
(b) 被告イラストの使用割合,ないし売上げへの寄与が比較的小さいもの 小売価格の3%
被告商品19
(c) 被告イラストの使用割合,ないし売上げへの寄与が極めて小さい もの 小売価格の2%
被告商品5
(d) 被告イラストの使用割合,ないし売上げへの寄与が平均的なもの 小売価格の4%
上記(a)ないし(c)記載の商品以外のもの
f 上記d及びeをもとに著作権法114条3項に基づく損害の額を算 定すると,次のとおりとなる。
(a) 被告が販売店に販売した商品に係る分 別紙「損害額(販売店関係)計算表(裁判所認定)」の右下欄記載の\nとおり,合計121万9681円となる。
(b) 被告が通販サイトにおいて小売価格で販売した商品に係る分 別紙「損害額(通販サイト関係)計算表(裁判所認定)」の右下欄記\n載のとおり,合計3889円となる。
(c) 以上より,著作権法114条3項に基づく損害は,合計122万 3570円である。
(2) 慰謝料
本件で認定した被告の行為態様が,原告イラストを複製又は翻案した被告イラ ストを多種多様な衣類等に付して幅広く販売し,被告商品の写真を被告が運営する ホームページにアップロードするというものであること,原告イラストと被告イラ ストとが類似又は酷似しているにもかかわらず,被告は,本件訴訟で著作権侵害等 を争っていること,他方で,被告は,被告イラストを商業的に利用しているのであ って,原告イラストを揶揄したりすることを目的に翻案等しているのではないこと, 以上の点を指摘することができるのであり,その他の本件に現れた一切の事情を総 合すると,原告の著作者人格権侵害による慰謝料は30万円と認めるのが相当であ る。 原告イラストは以下です http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option1.pdf 被告イラストおよび対比は以下です http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option2.pdf
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.08.26
平成30(行ケ)10094 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月25日 知的財産高等裁判所
前記2(1)で認定した引用文献3の記載によると,引用文献3には以下の 発明(引用発明)が開示されているものと認められる。 「医療用ガイドワイヤを摺動可能に受け入れるガイドワイヤ内腔を備える遠位ス\nリーブと,遠位スリーブに結合され,患者の生理的パラメータを測定して生理的パラメータを表す信号を生成するように適合されたセンサと,
遠位スリーブに結合され,患者の外部の位置へのセンサからの信号を通信するた めの通信チャネルを成し,患者の解剖学的構造内のセンサの位置決めを容易にする\nために適用される近位部分と,
近位部分を移動させるための手段と,
を備え,
センサは,遠位スリーブを,医療用ガイドワイヤ上を所望の位置に摺動させるこ とによって,患者内に配置することができ,
センサは,遠位血圧Pdを測定する狭窄病変部の下流の位置に配置することがで き,次いでセンサは,近位血圧Ppを測定する狭窄病変部の上流の位置に配置する ことができ,
処理装置が,センサからの生理的パラメータ信号を処理し,
FFRは,単に遠位血圧の近位血圧に対する比,すなわちFFR=(Pd/Pp) とされ,
FFRをPdの平均値とPpの平均値に基づいて求め,
FFRにより血管中の狭窄病変部の重症度の評価が行われるシステム。」
(2) したがって,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりとな る。
ア 一致点 「流体で満たされた管内の狭窄部を評価するシステムであって, 前記管に沿った様々な位置で圧力測定を行う第1の測定センサを有する消息子と, 前記管を通して前記消息子を牽引する機構と,\n前記圧力測定から,前記管に沿った様々な位置で行われた圧力測定の比を計算す るプロセッサと を含む,システム。」
イ 相違点
(ア) 相違点1
血管内の二つの位置の血圧の比の計算において,本願発明は,一つの測定センサ によって,瞬間的に各位置の血圧の測定を行い,同測定によって得られた各血圧の 比を計算するのに対して,引用発明は,一つ又は複数の測定センサによって,継続 して遠位血圧Pdと近位血圧Ppの測定を行い,各血圧の平均値を測定し,同測定 によって得られたPdの平均値のPpの平均値に対する比を計算する点。
(イ) 相違点2
血管内の二つの位置の血圧の比の計算において,本願発明は,薬剤を投与して血 流を最大に増加させた状態ではない通常の状態で,各位置の血圧を測定するのに対 して,引用発明は,薬剤を投与して血流を最大に増加させた状態で,各位置の血圧 を測定する点。
(ウ) 相違点3
本願発明は,第1の測定センサにより各即時圧力測定が行われる位置に対する位 置データを供給する位置測定器を有するのに対して,引用発明は,その点が不明で ある点。
(エ) 相違点4
管を通して前記消息子を牽引する機構に関して,本願発明は,前記機構\は電動機 構であるのに対して,引用発明は,その点が不明である点。\n
(3) 相違点1の容易想到性について検討する。
ア 前記(2)イ(ア)のとおり,引用発明は,Pdの平均値とPpの平均値の比を 計算するものであるところ,本願発明は,各位置における瞬間の血圧を測定し,そ の比を計算するものである。しかるところ,当業者において,引用文献3に記載さ れた事項から,引用発明の構成について,血管の各位置の瞬間の血圧を測定し,そ\nの比を計算するという構成を具備するものとすることを容易に想到できるというべ\nき事情は認められない。
イ 被告は,引用文献3の段落【0073】の「システム1200は,時間 平均やその他の信号処理を用いてFFR計算の数学的な変形(例えば,平均,最大, 最小,等)を生成できる。」,段落【0096】の「FFR=Pp/Pdであり,P pとPdは平均値,又は他の統計学的表現又は数値表\現であってよい」との記載か らすると,引用文献3には,引用発明に加えて,Pd及びPpの瞬間的な圧力(収 縮期血圧及び拡張期血圧)を求めることが記載されており,FFR計算のPpとP dがPpとPdの最大値(収縮期血圧)又は最小値(拡張期血圧)でもよいことが 示唆されているといえるから,Pdの平均値とPpの平均値に代えて,即時圧力測 定されたPd及びPpの内の最大値(収縮期血圧)又は最小値(拡張期血圧)を採 用することは,引用文献3の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たと主張する。 しかし,被告が指摘する引用文献3の上記各段落のPd及びPpの最大値又は最 小値を測定するには,血圧が最大又は最小となるタイミングを特定するために,1 心周期以上継続して血圧を測定し続ける必要があるから,この場合の血圧測定は, 1心周期以上継続した測定であり,瞬間的な測定ということはできない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.08.26
平成30(行ケ)10091 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年8月22日 知的財産高等裁判所
本願発明の特許請求の範囲(請求項1)には,本願発明の「三次元リア ルタイムMR画像下での手術システム」にいう「三次元リアルタイムMR 画像」の意義を規定した記載はないが,その文言上,「三次元」の「リア ルタイムMR画像」であることを理解できる。そして,本願発明の特許請 求の範囲(請求項1)の記載から,「リアルタイムMR画像」は,「MR I装置からのMR画像を連続的に伝送することにより」生成される画像で あること,「三次元リアルタイムMR画像下での手術システム」は,術者 がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置を画像(「三 次元リアルタイムMR画像」)によって確認し,処置する生体物及びマイ クロ波デバイスの位置を確認しながら手術できる手術システムであること を理解できる。 次に,本願明細書には,「三次元リアルタイムMR画像」の用語を定義 した記載はないが,【0015】には,「例えば特許文献「特開2008− 167793」が開示する画像ソフトでは,縦型オープンMRI装置の術\n前3Dデータをリアルタイム画像と組み合わせ,デバイス位置のリアルタ イム情報として,三次元画像とともにモニターにして手術支援に用いる画 像ナビゲーションを可能とする。この場合の3次元とは生体や臓器表\面の 立体化だけでなく,内部構造を透視状態でみられる(深部情報)立体化で\nある。これにより,MR画像を身体のどの位置においても立体的にリアル タイムモニター画像として使うことができる。…」との記載がある。本願 明細書の上記記載によれば,本願明細書では,「三次元画像」にいう「三 次元」とは,生体や臓器表面の立体化だけでなく,「内部構\造を透視状態 でみられる(深部情報)立体化」を意味する語として用いていることを理 解できる。また,本願明細書の【0021】には,「実施例2」に関し, 「加えて,3DリアルタイムMR画像にて…手術機器の位置確認が可能で\nあり,さらに軟性導体内視鏡下に直接術野が見え,デバイスの先端部分の 生体内位置と共に隣接内部構造もMR画像として同時に確認できる。」,\n「加えて,実施例1で示したように,本発明のシステムでは,臓器の内部 構造も切る前に確認できる。」との記載がある。\n
イ 以上の本願発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本願明細書の 開示事項を総合すると,本願発明の「三次元リアルタイムMR画像下での 手術システム」は,手術機器の位置,生体や臓器の表面のみならず,臓器\nの内部構造を透視状態でみられる立体的なリアルタイムMR画像によって,\n術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置を画像 (「三次元リアルタイムMR画像」)によって確認し,処置する生体物及 びマイクロ波デバイスの位置を確認しながら手術できる手術システムを意 味するものと解するのが相当である。
(2) 引用発明の手術支援装置について,
引用文献5の記載事項(【0023】,【0028】,【0033】)に よれば,引用発明の「術具815を含む Volume Rendering 画像814」は, 「患者60をMRI装置10の撮像空間に配置し」,「術具位置を含む断面 の撮像を行」うことで得られたMR画像であって,「手術時には,三次元位 置検出装置を用いて術具位置を追随することにより,時系列的に変化」(【0 033】)するから,リアルタイム画像である。 次に,乙1(笠井俊文ほか「診療画像機器学」平成18年12月5日第1 版第1刷発行)には,1)「(b)ボリュームレンダリング法(VR)…体内 の三次元表示である,三次元表\示の主役であり,SR処理も行える。」(2 03頁),2)「「3) 三次元表示(3D表\示)」 三次元表示(画像)とい\nってもホログラフィなどとは異なり,あくまでも二次元であるモニタやフィ ルム上で立体的に見えるよう表示するものである。厳密には疑似三次元表\示, 2.5次元表示とでもいうべきものである。三次元表\示作成手順は一般に「モ デリング…」と「レンダリング…」という作業が必要である。モデリング→ 三次元の立体形状のデータを作成,編集する作業,レンダリング→三次元立 体形状データをもとに立体的に見える二次元画像を作成する作業。」(20 5頁),3)「(b)ボリュームレンダリング法(VR) VR法 volume rendering は物体の表面形状ばかりか内部形状をも三次元的に表\示する方法である。… さらに,不透明度や色・色彩の情報もボクセルに与えられるためデータが膨 大となる。高性能のコンピュータが必要となるが内部形状を透かして表\現す ることができ,しかもボリュームレンダリング法で作成した表面像はSR法\nよりも緻密で優れている処理法である。」,「処理手順 ア) モデリング(ボ リュームデータを作成する) イ) 不透明度の設定:ボリュームレンダリン グ法では不透明度(オパシティ opacity)が導入される。ボリュームデータ を構成するボクセルすべてに対し不透明度が設定される。不透明度とはボク\nセルに背後から光を当てたときに光を通す程度を表すもので,0〜1までの\n数値で示される。… ウ) レンダリング(投影変換):観察する視点を決め, 視点から見た形状の位置や前後関係を計算する。そして投影経路上に存在す るボクセル全てについて不透明度や色彩が計算される。この操作をα−ブレ ンディングと呼ぶ。投影方向として平行投影法と遠近投影法がある。エ) 画 像表示処理:処理が完了すれば,拡大表\示や視点を変えて表示することも可\n能である(図6.109)」(207頁〜208頁)との記載がある。上記\n記載によれば,「Volume Rendering 画像」は,「物体の表面形状ばかりか内\n部形状をも三次元的に表示」し,「内部形状を透かして表\現することができ」 るボリュームレンダリング法で作成した画像であるから,生体や臓器の表面\nのみならず,「臓器の内部構造を透視状態でみられる」三次元画像であるも\nのと認められる。
以上によれば,引用発明の「術具815を含む Volume Rendering 画像81 4」は,本願発明の「三次元リアルタイムMR画像」に相当するものと認め られる。 したがって,引用発明の手術支援装置は,術具の位置,生体や臓器の表面\nのみならず,臓器の内部構造を透視状態でみられる三次元リアルタイムMR\n画像である「術具815を含む Volume Rendering 画像814」によって,術 者がリアルタイムに生体の内部状況と術具の位置を確認し,処置する生体物 及び術具の位置を確認しながら手術できる手術システムであるものと認めら れる。 そして,本願発明のマイクロ波デバイスも術具の一種であることに照らす と,術具の位置,生体や臓器の表面のみならず,臓器の内部構\造を透視状態 でみられる立体的なリアルタイムMR画像によって,術者がリアルタイムに 生体の内部状況と術具の位置を確認し,処置する生体物及び術具の位置を確 認しながら手術できる手術システムである点において,本願発明と引用発明 は,実質的に一致するものと認められるから,両発明が「三次元リアルタイ ムMR画像下での手術システム」である点で一致するとした本件審決の認定 に誤りはない。
(3) 原告の主張について
原告は,1)本願発明の「三次元リアルタイムMR画像下での手術システム」 とは,術者(医師等)が,処置する生体物の位置及びマイクロ波デバイス の位置を,予め取得した生体内画像と比較しながら,生体の内部構\造を透 視状態でみられる立体画像でリアルタイムに確認しながら手術できる手術 システムをいうものである,2)引用発明の「術具」は,引用発明の課題を 解決するための手段である「警告手段」を達成するために,術具の処理によ り目的物の位置や形状を大きく変化させない,マイクロ波デバイスではなく かつ先端の形状が単純な穿刺針・カテーテルであることを要すること,引用 発明の「術具815を含む Volume Rendering 画像814」は,術前画像を含 まない,術中の3軸2次元画像を単に結合した Volume Rendering 画像であっ て,生体の内部構造を透視状態で見られる立体画像ではないことからすると,\n引用発明の手術支援装置は,術具の種類,警告手段の有無,術前画像の有 無及び立体画像の種類が本願発明と異なるから,本願発明の「三次元リア ルタイムMR画像下での手術システム」であるとはいえない旨主張する。 しかしながら,上記1)の点については,本願発明の特許請求の範囲(請求 項1)の記載には,「術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デ バイスの位置を画像によって確認し,処置する生体物及びマイクロ波デバイ スの位置を確認しながら手術できる手術システム」との記載はあるが,処置 する生体物の位置及びマイクロ波デバイスの位置を「予め取得した生体内\n画像と比較しながら」との記載はない。また,本件明細書の実施例1に は,「好ましくは,術者は,「前もって撮像した画像をもとに,メインワー クステーションに術中の画像を再構成して得られた三次元リアルタイム画\n像」を確認しながら,内視鏡・手術デバイスの操作・制御を実視できる。」 (【0020】)との記載があるところ,この記載から,「三次元リアルタ イム画像」は,「前もって撮像した画像をもとに」再構成して得られたこと\nを理解することができるが,術者が生体の内部状況とマイクロ波デバイスの 位置を「前もって撮像した画像」自体と比較しながら,手術を行うことを示 したものとはいえない。 したがって,上記1)の点は,本願発明の特許請求の範囲の記載に基づか ないものであって採用することはできない。
次に,上記2)の点については,前記(2)認定のとおり,術具の位置,生 体や臓器の表面のみならず,臓器の内部構\造を透視状態でみられる立体的な リアルタイムMR画像によって,術者がリアルタイムに生体の内部状況と術 具の位置を確認し,処置する生体物及び術具の位置を確認しながら手術でき る手術システムであれば,術具がマイクロ波デバイスでなくても,本願発明 の「三次元リアルタイムMR画像下での手術システム」であるものと認めら れ,また,引用発明の「術具815を含む Volume Rendering 画像814」は, 本願発明の「三次元リアルタイムMR画像」に相当するものと認められるか ら,上記2)の点は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.08.23
平成31(ネ)500 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年7月25日 大阪高等裁判所 棄却
控訴人は,被控訴人が旧大阪駅前店等の運営を控訴人に委託していたとい う両者の関係に照らし,被控訴人は控訴人に対し信義則上競業避止義務を負 うとも主張する。
被控訴人が旧大阪駅前店等の運営を控訴人に委託することになったのは, 眼科医であるP4が,その経営する会社においてコンタクトレンズ販売店を 営もうと考え,当時提携関係にあり,コンタクトレンズ販売店経営の豊富な 経験を有するP1に相談したことがきっかけであった(甲28,30,乙3 0,31)。この時P4は,控訴人への運営委託を通じて販売店経営のノウ ハウを蓄積し,いずれは独力で販売店経営を行うことを当然想定しており, P1もこれを当然承知していたと認められる。その意味で,控訴人と被控訴 人は,いずれもコンタクトレンズ販売店の経営を行う会社として,旧大阪駅 前店等の運営委託関係があった当時から競業関係にあったといえる。 競業者同士が提携関係にある状況においては,提携によって利益を得つつ, 一方が他方を出し抜いて自己の営業上の利益のみを追求する行動に出ること は,信義則に反すると評価される場合があり得ると考えられる。そのような 場合,信義則上相互に競業避止義務を負うと説明することもできるであろう。 しかし,提携関係が解消された後においては,両者とも営業の自由を有する のであるから,競業避止義務について特に合意をしたのでない限り,自由競 争の範囲内において自己の営業上の利益を追求して競業することが妨げられ ることはないのであって,一方が他方に対し信義則上競業避止義務を負うと いうことはできない。
控訴人と被控訴人は,平成28年6月までには提携関係を解消しており, また,上記(1)において判断したとおり,その間に競業避止義務についての 合意があったとは認められない。したがって,その後,被控訴人が控訴人に 対し信義則上競業避止義務を負っていたということはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.08.22
平成29(ワ)15518 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月26日 東京地方裁判所
(2) 争点2−1(構成要件1Aの充足性)について\n
以下のとおり,本件装置が「画像情報を対応するパターンに変換するパター ン変換器」を有すると認めることはできないので,同装置は構成要件1Aを充\n足しない。
ア 構成要件1Aは,「画像情報,音声情報および言語を対応するパターンに\n変換するパターン変換器と,パターンを記録するパターン記録器と,」であ るところ,本件特許1の特許請求の範囲の記載によれば,「パターン」は, 本件発明1の自律型思考パターン生成機を構成する「パターン変換器」によ\nり画像等の情報から変換され,「パターン記録器」に記録され,「パターン 制御器」において設定,変更がされ,あるいはパターン同士の結合関係が生 成されるものであるから,これらにより処理可能なものであると解すること\nができる。
次に,本件明細書等1の記載を参酌すると,「パターン」は,「対応する 事象の特徴を検出器が識別する信号の組合せにより表現したもの」であり\n(段落【0017】),例えば,画像情報として「犬」を入力すると,犬の 画像パターンが生成され,パターン記録器に犬の画像パターンとして記録さ れることとなる(段落【0018】)。そして,本件発明の実施形態1につ いて説明した段落【0039】においては,画像,音声及び言語の情報をそ れぞれ識別する信号の組合せに変換したものをパターンと呼び,パターンの 要素を「ON」,「OFF」又は「1」,「0」で表現することにするとさ\nれ,【図2】には,画像パターンの例として「IG=[0.0.1.1.・・・] T,とのパターン例が例示されている。 これらの記載によれば,本件発明1における「パターン」とは,画像,音 声及び言語に係る事象の特徴を,計算機たる検出器が識別することができる 「1」,「0」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味し,構成要\n件1Aは,少なくとも,「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパ ターン変換器」,すなわち,画像情報を上記信号の組合せに変換する変換器 を有することを特定したものであるということができる。
イ 原告は,本件製品のパンフレットや動画において,アメリアが「感情的な 対応力」を有するとされ,アメリアの表情が「EQ(共感指数)」により変\n化させられ,ユーザがアメリアの感情を画像で確認できるようになっている ことなどを根拠として,本件装置は「画像情報・・・を対応するパターンに 変換するパターン変換器」を有していると主張する。 しかし,被告は,本件装置がアメリアの感情に対応した画像を予め保有し\nており,状況に応じてその場に適した表情の画像を表\示可能であるとしても,\n画像情報を対応するパターンに変換する機能は備えていないと主張すると\nころ,原告が指摘する本件パンフレットの記載や動画を総合すると,本件装 置が様々な感情に対応する表情のアメリアの画像を保有し表\示することが できるとは認められるものの,本件装置が,外部から入力された表情等に関\nする画像をパターンに変換する機能を有していると認めるに足りる証拠は\nない。
ウ 原告は,本件装置が,その感情に対応した画像を予め保有しており,状況\nに応じてその場に適した表情の画像を表\示可能な構\成を備えているにすぎ ないとしても,構成要件1Aの「画像パターン」とは,画像情報から生成さ\nれ,人工知能を構\成するソフトウェアが利用できる「一塊のデータ」の全て\nを含むのであるから,人工知能がアメリアの感情に対応する画像を表\示する 際に,画像作成時のデータ形式から別のデータ形式に変換する場合も同構成\n要件を充足すると主張する。
しかし,原告の主張する「パターン」の意義は,特許請求の範囲及び本件 明細書等の根拠を欠くものである上,本件装置がアメリアの感情に対応した 画像を予め保有しているのであれば,それは既にアメリアが利用できるデー\nタ形式で保有しているものと解するのが自然であり,更に異なるデータ形式 に変換する必要があるとは考え難い。そうすると,本件装置が様々な表情の\nアメリアの画像を表示し得ることをもって,本件装置が入力された画像情報\nからパターンに変換する機能を有するということはできず,他に本件装置に\nおいて,かかる変換をする変換器が存在することを認めるに足りる証拠はな い。
なお,原告は,アメリアとは別の画像処理用のコンピュータにより画像デ ータを作成したとしても,「アメリアの感情に対応した画像を計算機で処理 可能な形態(パターン)に変換する」という工程を実施していることになる\nから,アメリアが構成要件1Aを充足することに変わりはないとの主張もす\nるが,アメリアとは別のコンピュータが,アメリアが利用できるデータ形式 の画像データを作成する場合に,本件装置が上記工程を実施しているといえ ないことは明らかである。
エ 以上のとおり,本件装置は構成要件1Aを充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.08.15
平成29(ワ)4311 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月18日 大阪地方裁判所
後記検討する【図2】及び【図3】の問題を除けば,上記検討した本件明細 書の記載には,肘置き部が,施術部よりも上方部で施術部に連結していなければな らないことを積極的に示すような内容は存しないと思われるのに対し,本件発明の 効果の観点では,肘置き部は,施術の対象である被施術者の目の部分に近接する位 置で,施術部に連結されると解するのが合理的である。 そして,本件発明1の文言において,「上方位置」と「施術者の上方部」とは近 接する位置で使用されており,本件補正により追加された際にも,当然両者を認識 の上,別異の意味を有するものとして使用されたと解されるところ,前述のとおり, 「上方位置」が施術部よりも上方部の意味である以上,「施術部の上方部」はこれ とは異なる意味であると解され,このことに,上記検討した本件明細書の記載内容 を総合すると,構成要件Cの「施術部の上方部」は,施術部における上方部,すな\nわち,施術部の上下方向における略中心を想定し,それよりも上方の部分を指すと 解するのが相当である。 被告らは,構成要件Cが本件補正により追加された要件であるところ,特許\n請求の範囲の補正に当たって新たな技術的事項の導入は許されないとして,本件明 細書の【図2】及び【図3】においては,肘置き部の上方位置の背面に連結部であ る水平軸が設けられていることから,本件発明における「上方部」は,構成要件B\nの「上方位置」と同様,「施術部の,それより上の部分」(施術部を含まず,施術 部に対して上)と解釈せざるを得ないと主張する。 確かに,本件明細書の【図3】では,肘受け部の回転軸が,施術部の上縁より少 し上方に存するように見えるが,これが実施例にすぎないことは本件明細書にも明 示されているし(【0015】),回転軸が,施術部の上縁に接する状態であれば, これも,施術部における上方部に,肘置き部が連結されているといえなくもない。 その他の【図】で開示されている実施例では,肘置き部がどの位置で施術部に連 結され,回転軸がどの位置に存在するかは全く不明といわざるを得ないが,少なく とも,施術部における上方部に肘置き部を連結する構成と,明らかに矛盾するよう\nな内容は存しない。
イ 出願経過及び本件意見書の記載について
本件意見書には,「4.特許法第29条第2項の拒絶の理由がないことの説 明」という表題の下,「(a)本願第1発明の説明」として,本件発明1につき,\nアイメイクの施術部位は被施術者の目尻,目頭,瞼,まつ毛,眉毛等であるため, この施術部位の周辺に施術者の手を配置すれば,必然的に肘の位置は手の位置を基 点とした範囲内(被施術者の頭部周辺)になるところ,その範囲で肘を支える部材 として肘置き部を備えたのが本件発明1であること,肘置き部が施術部の上方部を 基点として,これを軸に施術部に対して回動することで施術部に対する角度が変化 するが,肘置き部がどのような角度に調整された場合であっても,回動する範囲は 施術部の周囲(頭部の左右位置,もしくは左右位置及び上方位置)において一定で あるため,肘置き部が回動する範囲は,施術部位周辺に施術者が手を配置した際に その施術者の肘が配置される範囲と常に一致すること,これにより,施術者は肘置 き部により肘を固定させて施術することができるため,施術が安定するとともに施 術効率を向上させることができる旨が記載されている。 また,原告は,上記に続く「(b)本件拒絶理由通知書における認定」にお いて,本件拒絶理由通知の概略を,1)「被施術者の頭部を載置する施術部が形成さ れている施術台において,前記施術部の周囲であって,載置される前記被施術者の 頭部の左右位置,もしくは左右位置及び上方位置に,施術者の肘を固定可能な肘置\nき部を設けることで施術者の施術における負担の軽減を図るものは,例えば,引用 文献2の第1図における肘掛け34a,34b(中略)にみられるように周知技術 (以下「周知技術1」という。)であり,引用発明1において上記周知技術1を適 用し,前記施術部の周囲であって,載置される前記被施術者の頭部の左右位置,も しくは左右位置及び上方位置に,施術者の肘を固定可能な肘置き部を設けたものと\nする(中略)ことは当業者が容易になし得たものである。」,及び2)「さらに,施 術者の肘を固定可能な肘置き部を水平を軸にして回動可能\なものとすることも,例 えば,引用文献3(中略),引用文献4(中略)にみられるように周知技術(以下 「周知技術2」という。)であり,引用発明1において上記周知技術2を適用し, 前記肘置き部は水平を軸にして回動可能であるものとすることも当業者が容易にな\nし得たものである。」とまとめた上で,それに続く「(c)本願第1発明と引用発 明との対比」において,引用発明2について,「ヘッドレスト33が傾倒するもの であり,肘掛け34a,34bは個別に回動するものではありません。また,肘掛 け34a,34bの取り付け位置は,ヘッドレスト33の左右方向です。」「した がって,引用発明1に,上記した各引用発明のいずれを適用したとしても,本件発 明1のように,『肘置き部が前記施術部の上方部に連結され,水平を軸にして前記 施術部に対して回動可能』な構\成とはならない」と記載した。 被告らは,上記原告の引用発明2に関する文章(「肘掛け34a,34bの 取り付け位置は,ヘッドレスト33の左右方向です。」)を理由に,本件意見書に おいて,原告は,肘置き部の取付け位置が施術部の左右である構成を排除した旨を\n主張する。 しかしながら,本件意見書の上記文章は,引用発明2について,肘掛けの取付け 位置がヘッドレストの左右であるものの,肘掛けが回動しない点で本件発明とは異 なる旨を指摘したものと解することができ,被告の主張は採用できない。
ウ まとめ
以上検討したところを総合すると,構成要件Cの「施術部の上方部」とは,施術\n部における上方部の意味に解すべきであるが,肘置き部の回転軸が施術部の上縁に 接するよう連結する構成も含み得るとすると,その範囲については,別紙原告図面\nのうち,赤で示された部分を指すと解すべきこととなる。
(2)構成要件Cの「連結」の意義について\n
ア 「連結」の字義的意味は,「つらねむすぶこと。むすびあわせること。」で あるところ,本件明細書には,特に「連結」についての定義や,具体的な連結方法 についての記載はない。 本件明細書の【図2】及び【図3】には,肘置き部と施術部が,それぞれ支持部 材と背面部材を介して,水平軸の位置でつながっている形態が示されており,段落 【0018】も上記形態について説明する。 また,本件意見書には,肘置き部が,施術部の上方部を基点として,これを軸に 施術部に対して回動すること,引用発明3及び引用発明4においては,枕F(また は head rest 2)と肘受24(または head rest 4)とが連動せず別々に動作するこ とが望ましいと考えられるため,引用発明1にこれらの発明を適用したとしても本 件発明1の構成要件Cのような構\成にはならないことが記載されている。 そうすると,構成要件Cにおける「連結」とは,施術部と肘置き部が別々に動作\nすることができない形態でつながっていることを意味し,それ以上具体的な連結方 法について定めるものではないと解するのが相当である。
イ 被告らは,本件明細書の【図1】及び【図6】に示される実施形態から,構\n成要件Cの「連結」とは,「肘置き部が,その上方位置の背面において,前記施術 部の上方部に連結され」と解釈すべきであると主張するが,同図は,1つの実施形 態にすぎないから,そこから具体的な連結部位についてまで定められていると解す べきではない。
(3) 被告製品の構成\n
ア 別紙被告製品写真1ないし4及び別紙「被告製品の説明書」によれば,構成\n要件Cに対応する被告製品の構成cは,施術部の左右側面のうち,上下方向におけ\nる中央線よりも上の部分において,回動部材を介して施術部とリクライニングアー ムとがつながる構成をとり,施術部を左右方向に横切るような仮想の回転軸を中心\nにリクライニングアームが回動するものであると認められる。
イ 被告らは,被告製品の肘置き部が施術部の「左右位置」において回転自在に 支持されていることから,本件発明の構成要件Cを充足しないと主張するが,構\成 要件Cの「施術部の上方部」が施術部の左右側面を排除しない概念であることは前 述のとおりであり,また,構成要件Cの「連結」が具体的な連結方法や連結部位を\n定めるものではないことも前述のとおりであるから,上記被告らの主張を採用する ことはできない。
ウ また,被告らは,被告製品について,仮想の回転軸が施術部を貫通している ことから,回転軸が施術部の背面にあり,また施術部よりも上方にある本件発明と 比較して,肘置き部を回転させた時に肘置き部の左右位置と施術部との間の距離が 比較的短く施術しやすい,という本件明細書から記載された発明からは導き出せな い技術的事項を有すると主張するが,本件発明の回転軸が施術部よりも上方にある との主張は採用できず,被告らの主張は理由がない。
(4) まとめ
以上より,被告製品のリクライニングアームは,施術部の上方部に連結され,水 平を軸として施術部に対して回動可能であると認められるから,本件発明の構\成要 件Cを充足する。
・・・
上記(1)及び(2)によると,被告製品の売上高(税込)から原価(税込)を控除した 額は,951万7032円(別紙被告計算表の「粗利(総計売上税込−総計原価税\n込)」欄参照。)であり,同額を被告らの利益の額と認め,原告の損害額を算定す る基礎とするのが相当である。 なお,消費税基本通達5−2−5に鑑みれば,知的財産権の侵害に基づく損害賠 償金は,消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当し,消費税の課税対象となると解 するのが相当であり(消費税法2条1項8号,同法4条1項),本件における損害 賠償金も,特許権の侵害に基づく損害賠償金として消費税の課税対象となると解さ れるところ,上記被告らの利益の額は,税込売上高から税込原価を控除したもので あり,消費税相当額を含む額であるから,原告の損害額を算定する際に,さらに消 費税相当額8%を加算する必要はない。
イ 被告らの主張について
被告らは,消費税に関し,特許法102条2項の「利益」の算定方法について主 張するほか,そもそも,同項により推定される損害賠償金は逸失利益であるから, 一般的に消費税の課税の対象とならないか,本件の個別事情に照らし,損害賠償金 は対価性がないため消費税の課税の対象とならないこと,仮に本件における損害賠 償金が消費税の課税の対象になるとしても,原告と被告との間において内税方式, 外税方式のいずれを採用するかについての合意がない以上,内税方式によるべきで あることを主張する。 しかしながら,特許権侵害に対する損害賠償請求訴訟では,典型的には,特許権 者のみが発明の実施品を製造,販売している状態を想定し,侵害品の販売により特 許権者側の売上等が減少したことを損害と捉え,認定又は推定の方法により算定し た損害賠償額金を得させることで,権利侵害のなかった原状に可及的に復させよう とするものであるところ,その回復の対象となる原状において,特許権者が発明の 実施品を製造,販売すれば,売上,経費いずれの面でも消費税は考慮されるはずで ある。 そうすると,本件のように,回復の対象である原状において,消費税が考慮され る事案においては,その回復の手段として逸失利益の損害賠償を算定する際におい ても消費税の負担は考慮すべきことになり,これに反する被告らの主張は採用でき ない。 そして,その計算としては,前述のとおり,消費税相当額を考慮した売上額から, 消費税相当額を考慮した経費額を控除すれば足りると解され,これによって算定し た損害額に,さらに消費税相当額を加算する必要はないし,当事者間に特段の合意 がなければ内税方式により計算すべきであるとの被告らの主張も理由がない。 また,被告らは,消費税相当額分の遅延損害金の起算日は,その額が確定した日, すなわち判決確定日であって不法行為時ではないと主張するが,上記アのとおり, 原告に支払われるべき損害賠償金は,消費税相当額を含むものの,全体としては特 許法102条2項により原告の損害と推定される額であるから,全部につき不法行 為の日から遅滞に陥ると解するのが相当である。
(4) 推定覆滅又は寄与率について
ア 被告らは,本件発明の被告製品に対する技術的寄与及び顧客吸引力は小さく, 寄与率は50%程度であると主張する。 しかし,本件発明3の構成要件Fは,リクライニング機構\が付与されていること とされており,本件明細書の段落【0020】及び【0021】にも,電動式を含 むリクライニング機構が付与されていることにより,異なるアイメイク施術を1台\nで済ませることができたり,被施術者が仰向けになったときの下半身の負担を軽減 したりすることができる旨の記載がある。また,本件発明はアイメイク用施術台全 体に関するものであって,リクライニングアームのみに関する発明ではない。 よって,本件発明の,被告製品に対する技術的寄与が少ないという上記被告らの 主張を採用することはできない。
イ また,被告製品の価格(11万8000円(税抜))と本件発明の実施品の 価格(18万2000円(税抜))との差は6万4000円であるところ(乙29), これが直ちに顧客吸引力に大きな差が生じるまでの金額ということはできない。ま た,被告らは,高田ベッド製作所がアイメイク用施術台の分野において特別なブラ ンド力を有することや,被告製品の広告宣伝において,高田ベッド製作所のブラン ド力を使用していること等の主張立証をせず,リクライニング機構が本件発明3の\n構成要件となっていることは,上記アのとおりである。\nよって,本件発明が,顧客の購買に寄与する要素が極めて小さいという上記被告 らの主張を採用することはできない。
ウ したがって,本件において特許法102条2項の推定を覆滅すべき事情は認 められない。
(5) 特許法102条4項後段に関する主張
原告は,平成28年10月31日付け及び同年12月5日付けで,被告アイラッ シュに対し,本件特許権の侵害について2回にわたり警告し,被告アイラッシュも これに回答していることから(甲5ないし8),被告らにおいて被告製品が本件特 許の権利範囲外であると考えたことについて,故意または重過失がなかったとして 損害賠償の額を定めるにつきこれを参酌すべき場合であるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2019.08.13
平成30(行ケ)10169 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
証拠(甲1,2)によれば,両意匠の物品は,いずれも「トレーニング機 器」と同一であって,背面電極部から流れる電流により腹筋等を刺激し,当 該部位の筋肉等を引き締めるためのものである点において共通する(各証拠 の【意匠に係る物品の説明】参照)。また,その需要者についても,いずれ もそのようなニーズを有する一般消費者であると認められる。 そして,両意匠に係る物品は,これを使用者の腹部に載せ,当該物品の背 面に設けられている電極を腹部に接触させて使用する物であるから(甲1及 び2の【意匠に係る物品の説明】の記載,並びに甲2の【使用状態を示す参 考図】参照),着脱時には,直接肌に触れることになる背面も,ある程度の 注意をもって見る機会があるものの,需要者は主に当該物品の表面を正面な\nいし斜め上方向から見る機会が多いというべきである。両意匠を実施してい ると解される物品及び同種の物品を紹介するカタログ,ポスター等において も,これらの物品を単独で,又は腹部に装着した状態の物品の表面を,それ\nぞれ正面から撮影した画像が多く使用されており(甲3の2〜3の4,4, 15,16の2),上記の観察方法の正当性を裏付けるものといえる。
(2) 以上を前提として,両意匠が需要者の視覚を通じて起こさせる美観が類似 するか否かを検討する。
ア 両意匠の形態上の共通点について
(ア) 両意匠は,全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略左右 対称であり,左右の上パッド,中央パッド及び下パッドが合計6つ配置 された本体と,本体の正面中央に設けられた略円形の強弱調整ボタンで 構成されている点(共通点(A)),中央パッドと上パッド,中央パッド と下パッドの各隙間は,いずれも略倒扁平「V」字状である点(共通点 (A−2)),本体の上辺及び下辺中央に切り欠き部が形成されている 点(共通点(B)),強弱調整ボタンは,正面側が閉塞しており,本体に 一体に設けられている点(共通点(C)),本体背面中央に,強弱調整ボ タンよりも大きい円形の線模様が設けられ,各パッドに,周囲に余白を 残して電極が配置され,各電極が中央の円形模様と接続されて,円形模 様の内側中央にコイン掛け溝を有する電池部蓋が設けられている点(共 通点(D)),並びに強弱調整ボタンの正面上下に,「+」及び「−」の 表示が設けられている点(共通点(E))において,共通する形態を有し ている。
(イ) まず,共通点(A)のうち,全体が,正面から見て,薄いシート状で あって,略左右対称であり,パッドが複数配置された本体と,本体中央 に設けられた略円形の強弱調整ボタンで構成されている点は,本件登録\n意匠の出願前に販売されていた同種の商品にも広く見られる態様と認め るのが相当である(甲3の2,3の3,5)。 しかし,上パッド,中央パッド及び下パッドが左右対称に合計6つ設 けられているという形態についてみると,当該形態は本件登録意匠の出 願前に販売されていた同種の商品にも相当数見られるものの,採用され ているパッド数には様々なものがあること(甲5)に鑑みると,これを 両意匠に係る物品において普遍的に見られるありふれた形態とまでいう ことはできない。かえって,当該形態は両意匠の全体の輪郭の大要を形 成するものであること,パッド部が意匠全体に占める面積が大きいこ と,各パッド間の区切りも明瞭であることに加え,需要者は主に両意匠 に係る物品の表面を正面ないし斜め上方向から見る機会が多いとの観察\n方法を併せ考慮すると,当該形態は需要者の注意を強く引く構成態様と\n評価するのが相当である。
(ウ) 次に,1)共通点(A−2),2)共通点(B)に関し,本体の上辺又は下 辺中央に切り欠き部が形成されている点,3)共通点(C),4)共通点(E) については,本件登録意匠の出願前に販売されていた同種の商品にも広 く見られる態様であるか(甲3の2,3の3,5),あるいは,これら の形態が意匠全体に占める割合も大きくないものであるから,両意匠に 係る物品の観察方法も併せ考慮すると,これらの共通点が類否判断に及 ぼす影響は小さいというべきである。
(エ) また,両意匠は,背面の形態に関し,共通点(D)において共通する が,上記(1)のとおり,需要者が当該物品の背面に着目する程度は高く ないと認められるから,この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は 小さいというべきである。
イ 両意匠の形態上の相違点について
(ア) 相違点(a),相違点(a−2)及び相違点(b)についてみると,本 件登録意匠は,略倒隅丸台形状の中央パッドの上下に,先端が円弧状の 隙間を介して,上端又は下端が略弓状に膨出した上パッド及び下パッド が配置され,本体の上辺及び下辺中央に略「U」字状の切り欠きがあ り,切り欠き部に連なる本体上辺及び下辺の角部付近が上方又は下方に 僅かに膨出していることから,全体として上下対称となっていることと 相まって,総じてうねりを伴う流線的かつ柔らかでゆったりとした印象 を与えるものである。 これに対し,甲2意匠は,中央パッドが略横長隅丸4角形状で,左右 端が若干上に傾くように配置され,先端が先細りの隙間を介して,上パ ッドが略横長隅丸5角形状で,左右端が中央パッドよりも上に傾くよう に配置され,同様に先端が先細りの隙間を介して,下パッドが略横長隅 丸5角形状で,左右端が中央パッドよりも下に傾くように配置されてお り,本体の上辺及び下辺中央に略「V」字状の切り欠きが設けられてい ることから,各パッドの各辺が概ね直線状となっていることと相まっ て,変化に富み,いきいきとした躍動感や力強さといった,当該意匠に 係る物品を使用することによって達成しようとする目標に沿う印象を需 要者に与えるものである。 そうすると,これらの相違点により需要者に与える印象の違いは極め て大きいというべきである。
(イ) 次に,相違点(c)についてみると,本件登録意匠は,上パッド及び 下パッドにおいて,上端又は下端に沿って明調子の筋状模様が,内側の 稜線寄りに明調子の略倒扁平三角形状模様がそれぞれ配されていること から,当該各パッドが浮き上がったような印象を与えるとともに,上パ ッド及び下パッドには,左右のパッドにまたがってごく僅かに突出した 略「M」字状又は略「W」字状の帯状部が形成され,中央パッドには左 右のパッドにまたがってごく僅かに突出した略倒紡錘形状部が強弱調整 ボタンを囲むように形成されていることから,当該意匠の物品が「トレ ーニング機器」であることを考え合わせると,これらの形態は腹部の筋 肉の盛り上がりをイメージさせるものといえる。 そして,甲2意匠は,外周を縁取る線模様がパッドごとに分断して合 計6つ設けられ,その内側に,各パッドの外形に相似するような隅丸略 5角形状の線溝が,相似形に3本施されていることから,同様に当該意 匠の物品が「トレーニング機器」であることを考え合わせると,これら の形態は腹部の筋肉の盛り上がりを強くイメージさせるものといえる。 そうすると,この点が需要者に与える印象の違いはそれほど大きくな いというべきである。
(ウ) 相違点(d)についてみると,強弱調整ボタンの形状が略円錐台形 状であるか略円筒状であるか,基部が設けられているか否かは,目につ きにくい部分における細かな差異にすぎないから,需要者に与える印象 の違いは小さいというべきである。
(エ) 相違点(g)については,甲2意匠に設けられている通気孔は,本体 中央に設けられている強弱調整ボタンの斜め上下左右という比較的需要 者の注意を引く位置にあり,形状が略隅丸3角形であることから,シャ ープな印象を与えるものといえるが,その孔自体それ程目立つものでは なく,通気孔の部分が全体に占める割合もごく小さいことから,この点 が需要者に与える印象の違いは小さいというべきである。
(オ) 相違点(h)のうち,電源ボタンの有無については,本件登録意匠 では,当該電源ボタンが本体の中央という非常に目につきやすい箇所に 設けられていることから,一定程度異なる印象を需要者に与えるといえ る。 しかし,「+」及び「−」の表示が明調子に表\されているか否かにつ いては,需要者に与える印象の違いは小さいというべきである。
(カ) その余の相違点については,両意匠を全体としてみたときに,ごく 限定された部分又は目につきにくい部分における細かな差異にすぎず, 他の共通点・相違点から生ずる美感を左右するほどのものとはいえな い。
ウ 総合評価
(ア) 基本的構成態様における共通点(A)のうち,上パッド,中央パッド 及び下パッドが左右対称に合計6つ設けられているという形態について は,需要者の注意を強く引く構成態様と評価することができる。\n これに対し,その余の共通点については,これらが両意匠の類否判断 に及ぼす影響は小さい。
(イ) 他方,基本的構成態様における相違点(a),(a−2),(b)及び (c)によってもたらされる印象は,両意匠ともに,盛り上がった腹部の 筋肉という,当該意匠に係る物品を使用することによって達成しようと する目標に沿う印象を与えるとの点において共通するものの,本件登録 意匠は,流線的かつ柔らかでゆったりとした印象を与えるのに対し,甲 2意匠は,変化に富み,いきいきとした躍動感や力強さといったよう な,当該意匠に係る物品の使用による達成目標により沿うものとなって おり,これらの相違点が与える印象の違いは,上記共通点がもたらす印 象をはるかに凌駕するものである。
(ウ) そうすると,その余の共通点,相違点がもたらす印象を考慮して も,両意匠は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にするという べきである。
◆判決本文
本件意匠は下記です。
◆意匠登録1593189
先行意匠は下記です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2019.08.13
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
原告は,構成Eの「直ちに」との文言を追加する本件補正は,本件当初\n明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底\n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信\n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構\成」という。)が,本件当 初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構\成が記載されていると認めること はできない。 (イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0 008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】, 【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には, 先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決め るための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響 信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるもので あって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】, 【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には, 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船 上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識 をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上\nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底 局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件 発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,…\n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で 行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を, 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明 らかに不自然である。 したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されている\nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構\n成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算\nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細 書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの というべきである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2019.08.13
平成30(ワ)28391 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月12日 東京地方裁判所
原告は,平成31年2月21日,被告コーアイセイを相手方として,本件各 製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に含まれることを立証するため,本件製剤 1に関する平成30年2月15日付け医薬品製造販売承認書に記載されてい る「成分及び分量又は本質」に係る部分について,特許法105条1項に基づ く書類提出命令の申立てをした。\n当裁判所は,同年4月11日,同条2項に基づくインカメラ手続を行い被告 コーアイセイから対象書類の提示を受けた上,同書類には本件製剤1にクロス ポビドンが含まれるかどうかや,クロスポビドンの医薬組成物中の含有率等に 関する情報が記載されているが,本件製剤1の組成物又は含有率は本件訂正発 明に規定するものと異なっている一方,同情報は被告コーアイセイにとって秘 密性の高い重要な技術的情報であると認められるから,被告コーアイセイには 書類の提出を拒むことについて正当な理由があるなどと判断して,同申立てを\n却下した。
・・・・
本件訂正発明の構成要件Cは,「前記崩壊剤が,クロスポビドンであり,前記\nクロスポビドンの医薬組成物中の含有率が5.6〜12質量%であり,但し,崩 壊剤がGRANFILLER−D(登録商標)から成る錠剤は除く,」というも のであるところ,原告は,本件各製剤が構成要件Cを充足すると主張する。\n しかし,本件各製剤が,1)崩壊剤としてクロスポビドンを含有すること,2)そ の医薬組成物中の含有率が5.6〜12質量%であること,3)同崩壊剤がGRA NFILLER−D(登録商標)から成る錠剤でないことについては,これを認 めるに足りる証拠がない。 原告は,本件各製剤は原告製剤の後発医薬品であることや,原告による本件製 剤1の分析によっても,本件製剤1がクロスポビドンの含有を否定するデータは 得られていないことなども指摘するが,本件各製剤が原告製剤の後発医薬品であ るとしても,そのことから直ちに本件各製剤が構成要件Cを充足するということ\nはできず,また,本件製剤1がクロスポビドンの含有を否定するデータは得られ ていないことは,むしろ,同製剤が構成要件Cに規定された含有率のクロスポビ\nドンを含有すると認めるに足りる客観的な証拠が存在しないことを示すもので ある。 したがって,本件各製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に属すると認めること はできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.08. 8
平成31(ネ)10005 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
なお、「原判決30頁17行目から31頁3行目までを次のとおり改める。」とありますが、原審のどの部分を改めるのか?は、上記範囲とはズレていますので、不明です。
また,請求項1においては,係合部が設けられている揺動部材と他方の揺動部材が,それぞれ開閉機構を有することが規定されるのみで,いずれの開閉機構\をどのような手順で操作するかについては何ら特定がなく,前述の本件発明の技術的意義からもかかる点につき限定する理由はないから,係合部を設けた揺動部材の側に力を加えることによって,他の揺動部材が同時に開く仕組みになっていることは,本件発明において必須の構成ではない。\n以上を踏まえると,構成要件Eの「係合部」とは,これによって外力を伝達し,その結果,いずれか一方の揺動部材の開操作をもって,2対の揺動部材を同時に開くことを可能\にするものであるというべきである。
イ 「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義
次に,かかる係合部の意義を踏まえて,「揺動部材の一方に…係合部 が設けられている」の意義について検討する。 まず,「設けられている」との文言の一般的な意味は,「そなえてこ しらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず(広辞苑・甲 13),当該文言自体からは,「係合部」が一方の揺動部材と一体であ るのか,別の部品であるのかを読み取ることはできない。前記の本件発 明の技術的意義に照らしても,「係合部」が一方の揺動部材と一体のも のでなければその機能を果たせないとはいえず,別の部品によって係合\n部を設けることを除くべき根拠は見当たらない。そうすると,係合部が 揺動部材に「設けられている」という構成が,係合部が揺動部材の一部\nを構成しているものに限定されるとはいえない。\nそして,「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」という特許 請求の範囲の文言に照らすと,係合部が,「一方の」揺動部材に設けら れていることを要することは明らかである。このことは,特許請求の範 囲における請求項3及び4が,2対の揺動部材について,いずれに「係 合部」が設けられているかを区別できることを前提としていることから も裏付けられる。 以上によれば,「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」とは, 「係合部」が,揺動部材に設けられており,かつ,それが2対のいずれ の揺動部材に設けられているのか区別できることを要し,またそれをも って足りると解される。
・・・
被告製品の構成eは,「揺動部材1,2の各下側揺動部には後部に開\n口部が設けられ,各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿 通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材1と揺動部材2が 組み合わせられたときに,開口部に留め金の突起部がはめ込まれ,ピン 用孔に角度調整器の2本のピンを挿通された状態で揺動部材2の上側揺 動部と下側揺動部を相互に開いていくと,留め金の突起部と角度調整器 のピンがそれぞれ揺動部材1の下側揺動部と上側揺動部を押圧して,揺 動部材2と一緒に開くようになっている」ものである(前記第2の3に おいて引用した原判決「事実及び理由」の第2の2⑸)。 このように,被告製品における角度調整器の2本のピンと留め金の突 起部は,外力の伝達により,いずれか一方の揺動部材の開操作をもって, 2対の揺動部材を同時に開くことを可能にするものであるから,角度調\n整器のピン及び留め金の突起部は,構成要件Eの「係合部」を充足する。\nまた,上記のとおり,角度調整器のピン及び留め金の突起部は,開操 作の前に,組み合わせられた揺動部材1及び2の開口部に留め金の突起 部がはめ込まれ,ピン用孔に角度調整器の2本のピンが挿通された状態 に固定されるものである。このような固定態様に照らすと,「係合部」 である角度調整器のピン及び留め金の突起部が,揺動部材1又は2に設 けられているといえる。そして,証拠(甲3,乙6,10)によれば, 角度調整器は,施術者から視認できるように揺動部材1側からピンが挿 通されて揺動部材1に固定されることが認められるから,少なくとも角 度調整器のピンは,揺動部材1に設けられていると認識できることは明 らかである。そして,留め金の突起部も,角度調整器のピンと一体とな って揺動部材の開操作に関わっているのであるから,この両者は,全体 として揺動部材1に設けられていると評価するのが素直である。したが って,「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部をもって, 構成要件Eの「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」との要件\nは充足されることになる。 そして,「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部が, 2対の揺動部材の開操作の前にこれらの揺動部材に固定されることは上 記のとおりであって,これらを同時に開いていく間にかかる固定が解除 されることはない(乙6,10)。したがって,構成要件Eの「他方の\n揺動部材と組み合わせられたときに」揺動部材の一方に係合する係合部 が設けられているといえる。 控訴人は,被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部が,揺動 部材1及び2と別の部品であることから,直ちにいずれの揺動部材に上 記ピン及び上記突起部が固定されているのかの区別ができなくなるとい う前提で主張するが,上記説示したところに照らし,採用できない。
カ 結論
以上のとおり,被告製品は構成要件Eを充足し,他の構\成要件を充足 することについては既に説示したとおりであるから,被告製品は,本件 発明1及び2の技術的範囲に属する。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> ピックアップ対象
2019.08. 8
平成29(ワ)44053 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月29日 東京地方裁判所
(3) 本件明細書1及び3の発明の詳細な説明の記載
ア 本件明細書1及び3の【0015】,【0017】
本件明細書1及び3の発明の詳細な説明の記載は,前記1(1)のとおりであり,発 明を実施するための形態として,「本発明の併用療法は,治療法が同時に行われ, すなわち抗CD20抗体は,同時にまたは同じ時間枠(すなわち,治療は同時に進 んでいるが,薬剤は全く同時に投与されるわけではない)で投与される。本発明の 抗CD20抗体はまた,他の治療法の前または後に投与されてよい。」(【001 5】),「また本発明には,化学療法の前,その最中,または後に,治療上有効量 のキメラ抗CD20抗体を患者に投与することを含んでなる,B細胞リンパ腫の治 療法が含まれる。そのような化学療法は,少なくとも,CHOP,ICE,ミトザ ントロン,シタラビン,DVP,ATRA,イダルビシン,ヘルツァー(hoelzer) 化学療法,ララ(LaLa)化学療法,ABVD,CEOP,2−CdA,FLAG& IDA(以後のG−CSF治療有りまたは無し),VAD,M&P,C−Week ly,ABCM,MOPP,およびDHAPよりなる群から選択される。」(【0 017】)と記載されている。 しかしながら,上記において,抗CD20抗体ないしキメラ抗CD20抗体とし て示されるリツキシマブの投与時期について,【0015】では,「他の治療法の 前または後」と「同時にまたは同じ時間枠(すなわち,治療は同時に進んでいるが, 薬剤は全く同時に投与されるわけではない)」が併記されるにとどまり,また, 【0017】では,「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにと どまっており,化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされ ていないから,これらの記載をもって,リツキシマブをCHOP療法の各薬剤の投 薬期間中に投与するという本件発明1の用途を認識することは困難であり,もとよ り,リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各 サイクルの1日目に投与するという本件発明3の用途を認識することもできない。 このことに加えて,前記のとおり,本件発明1及び3は,いずれも,リツキシマ ブを含む医薬組成物について,対象疾患,併用される化学療法及び投与時期を特定 した用途発明であるところ,【0015】では,対象疾患及び併用される化学療法 が特定されておらず,【0017】でも,対象疾患が特定されておらず,併用され る化学療法であるCHOP療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっ ているから,その意味でも,これらが本件発明1及び3の用途を記載又は示唆する ものと認めるに足りない。
イ 本件明細書1の【0069】ないし【0071】,【0092】
(ア) また,本件明細書1の【0069】ないし【0071】及び【0092】の SWOGによる臨床試験に係る部分において,本件発明1の対象疾患である「低グ レード/濾胞性非ホジキンリンパ腫(NHL)」の患者に対するリツキシマブとC HOP療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの,次のとおり,これら は,リツキシマブを含む医薬組成物をCHOP療法の各薬剤の投薬期間中に投与す るという本件発明1の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。 a すなわち,まず,本件明細書1の【0069】ないし【0071】には, 「新に診断された再発性低悪性度NHLまたは濾胞性NHLにおけるCHOPとリ ツクシマブ(登録商標)との併用を評価するために第II相試験」(【0069】) について,「CHOPは,標準用量で3週間毎にリツクシマブ(登録商標)(37 5mg/m3)を6回注入する6サイクルを行った。リツクシマブ(登録商標)注入 1と2は,最初のCHOPサイクル(これは8日目に開始した)の前の1日目と6 日目に投与した。リツクシマブ(登録商標)注入3と4は,それぞれ第3および第 4のCHOPサイクルの2日前に投与し,注入5と6は,6回目のCHOPサイク ル後のそれぞれ134日目と141日目に投与した。」(【0070】)と記載さ れており,参考文献21として甲38文献が参照されていること(【0071】) などに照らすと,これらは,甲38文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試 験を記載したものと認められる(なお,【0070】の「第3および第4のCHO Pサイクルの2日前」は「第3及び第5のCHOPサイクルの2日前」の誤記であ ると認められる。)。 そうすると,【0070】の「リツクシマブ(登録商標)注入1と2」及び「注 入5と6」は,CHOP療法全体の開始前及び終了後の投与であり,また,「注入 3と4」も,Czuczmanらによる臨床試験の3回目及び4回目のリツキサンの投与と 同様に,CHOP療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって,当業者は,いずれに ついても,CHOP療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識する と認められる。 したがって,【0069】ないし【0071】は,リツキシマブを含む医薬組成 物をCHOP療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明1の用途を記載 又は示唆するものではない。
b また,本件明細書1の【0092】には,「SWOGにより行われた新に診 断された濾胞性リンパ腫でCHOPの後にリツクシマブ(登録商標)を使用する第 II相試験もまた,完了している。」として,SWOGによる臨床試験について記載 されているものの,同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「CHOP の後」であるから,リツキシマブを含む医薬組成物をCHOP療法の各薬剤の投薬 期間中に投与するという本件発明1の用途を記載又は示唆するものではない。 (イ) さらに,本件明細書1の【0092】には,「マントル細胞リンパ腫が未治 療の40人の患者でリツクシマブ(登録商標)とCHOPの第III相試験も,ダナ ファーバー研究所(Dana Farber Institute)で行われている。21日毎の6サイ クルで,リツクシマブ(登録商標)は1日目に投与され,CHOPは1〜3日目に 投与される。この試験の発生項目は完了している。」として,ダナファーバー研究 所による臨床試験について記載されているものの,本件明細書1には,同臨床試験 の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明1の対象疾患である「低グレード /濾胞性非ホジキンリンパ腫(NHL)」に含まれることは記載されておらず,そ のように認めるに足る証拠もないから,上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明 1の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ 本件明細書3の【0090】,【0092】
(ア) また,本件明細書3の【0090】において,本件発明3の対象疾患である 「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫(NHL)」の患者に対するリツキ シマブとCHOP療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの,その内容 は,「別の試験では,中または高悪性度NHLを有する31人の患者(女性19人, 男性12人,平均年齢49才)に,6回の21日サイクルのCHOPの1日目にリ ツクシマブ(登録商標)を投与した(35)。」というものであり,CHOP療法 の各薬剤の投与時期は記載されていない。 また,本件明細書3の発明の詳細な説明に,参考文献35として記載されている 乙9文献においても,前記1(2)イのとおり,Linkらによる臨床試験で,1サイクル 21日間(3週間)のCHOP療法を繰り返し実施するに当たり,リツキシマブは CHOP療法の各サイクルの1日目に投与されたのに対し,シクロホスファミド, ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの3日目に投与され,プレドニソ\ ンは各サイクルの3日目から7日目まで投与されたことが認められる。 したがって,【0090】は,リツキシマブとCHOP療法の各薬剤をCHOP 療法の各サイクルの1日目に投与するという本件発明3の用途を記載又は示唆する ものとは認められない。
(イ) さらに,本件明細書3の【0092】には,前記のとおり,ダナファーバー 研究所による臨床試験について記載されているものの,本件明細書3には,同臨床 試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明3の対象疾患である「中悪性 度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫(NHL)」に含まれることは記載されてお らず,そのように認めるに足る証拠もない。 また,「21日毎の6サイクルで,リツクシマブ(登録商標)は1日目に投与さ れ,CHOPは1〜3日目に投与される。」というだけでは,CHOP療法の各薬 剤が全て各サイクルの1日目に投与されたかは必ずしも明らかでないから,いずれ にしても,上記の臨床試験に係る記載部分がリツキシマブとCHOP療法の各薬剤 をCHOP療法の各サイクルの1日目に投与するという本件発明3の用途を記載又 は示唆するものとは認められない。
(4)原告らの主張について
ア 本件発明1
原告らは,本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は,化学療法 の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与する 異日投与レジメンによっていたところ,本件明細書1の【0015】,【0017】 には,異日投与レジメンと区別して,化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の 投薬期間中にリツキシマブを投与する同日投与レジメンが記載されていると主張す る。 しかしながら,本件原出願日当時,原告らが主張する異日投与レジメンによって リツキシマブと化学療法が併用されていたとしても,前記のとおり,【0015】, 【0017】には,化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る記載は なく,化学療法の開始前,終了後,化学療法に用いられる薬剤の休薬期間中にリツ キシマブを投与するレジメンと区別して,化学療法に用いられる薬剤の投薬期間中 にリツキシマブを投与するレジメンが記載されているとはいえないから,これらの 記載が本件発明1の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
・・・
被告製剤についてみると,前記第2の2⑸ウのとおり,被告製剤の添付文書には, 用法・用量欄に「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合」が記載され,用法・用量に関 連する使用上の注意として,「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は,先行バイオ 医薬品の臨床試験において検討された投与間隔,投与時期等について,【臨床成 績】の項の内容を熟知し,国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」 と記載されている。また,臨床成績欄には,被告製剤の臨床成績として,未治療 の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に,被告製剤又は先行バイオ医薬品がR−CVP レジメンによって投与されたことが記載されているほか,先行バイオ医薬品の臨 床成績として,国外臨床第III相試験(PRIMA試験)において,ろ胞性非ホジ キンリンパ腫(NHL)の患者に,R−CVPレジメンによる寛解導入療法等が 実施されたことが記載されている。 そして,証拠(甲12,35)及び弁論の全趣旨によれば,被告製剤の添付文書 に記載されているR−CVPレジメンは,リツキシマブを1日目に投与するととも に,シクロホスファミド(CPA)及びビンクリスチン(VCR)を1日目,プレ ドニゾロン又はプレドニソン(PSL)を1日目から5日目まで投与するレジメン\nであると認められる。 そうすると,被告製剤は,添付文書に記載されたR−CVPレジメンがシクロホ スファミドを1日目にのみ投与するものであり,1日目から5日目まで投与するも のでない点で,構成要件2Bの「CVP」を充足するとはいえない。\n
・・・
以上のとおり,本件特許1及び3は特許法36条6項1号に違反しており,いず れも特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから,同法104条の 3第1項により,本件特許1及び3に係る専用実施権者である原告による権利行使 は認められない。 また,被告製剤は本件発明2の技術的範囲に属するとはいえないから,被告製剤 の製造販売等が本件専用実施権2を侵害するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.08. 7
平成30(行ケ)10131等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月22日 知的財産高等裁判所
以上によれば,本件発明1と引用発明3の一致点及び相違点は次のとお りであると認められる。
(ア) 対比
a 前記ア(イ)のとおり,本件発明1の「相互作用マスタ」は,「一の医 薬品」及び「他の一の医薬品」が販売名(商品名)か一般名かこれを 特定するコードや,薬効,有効成分及び投与経路を特定することがで きるコードのレベルの概念で統一して格納され,1)A薬品から見たB 薬品の相互作用が発生する組み合わせについての情報と,2)B薬品か ら見たA薬品の相互作用が発生する組み合わせについての情報とは, データとして個々別々のものとして格納され,また,1)A薬品から見 たB薬品に関する相互作用が発生する組み合わせについての情報と, 3)A薬品から見たC薬品の相互作用が発生する組み合わせについての 情報とも,データとして個々別々のものとして格納されるものである。 これに対し,前記イ(ア)のとおり,引用発明3の相手テーブル部の一般 名コード,薬効分類コード,BOXコードの各欄には,必ずしもすべ てにコードが格納されているとは限らない。
したがって,引用発明3の「医薬品相互作用チェックテーブル10 5」と,本件発明1の「相互作用マスタ」とは,「一の医薬品から見 た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互 作用をチェックするためのマスタ」である点で共通するが,本件発明 1が「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医 薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用 が発生する組み合わせを格納する」のに対し,引用発明3では,「一 の医薬品から見た他の医薬品の一般名コード,薬効分類コード,BO Xコードかの少なくともいずれかについて,相互作用が発生する組み 合わせを格納し,また,他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コー ド,薬効分類コード,BOXコードかの少なくともいずれかについて, 相互作用が発生する組み合わせを格納する」点で相違する。
b 本件発明1は「自己医薬品と相手医薬品との組み合わせ」と, 「相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせ」についての合 致の有無を判断するものであるのに対し,前記第2の3ウ(ア)及び上 記イ(イ)によれば,引用発明3は,1)医薬品相互作用チェックテーブル 105において,「自己テーブル部」に,「自己医薬品」に係る「一 般名コード」,「薬効分類コード」,「BOXコード」が存在するか をそれぞれ検索し,2)いずれかのコードが存在していれば,処方医薬 品相互作用チェックテーブルTの形態で「一時記憶テーブル110」 に記憶し,3)「一時記憶テーブル110」に記憶したデータの「相手 テーブル部」に,「相手医薬品」に係る「一般名コード」,「薬効分 類コード」,「BOXコード」が存在するかをそれぞれ検索し,4)い ずれかのコードが存在していれば,「自己医薬品」と「相手医薬品」 とが相互作用を有する組み合わせが存在すると判断するものである。 そうすると,引用発明3の「検索処理」と本件発明1の「相互 作用チェック処理」とは,いずれも,「入力された新規処方データ の各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし,自己医薬品と相手 医薬品の組み合わせについて,相互作用をチェックするためのマ スタに基づいて相互作用をチェックするための処理」を実行する 点で共通するものの,引用発明3の「検索処理」は,自己医薬品 と相手医薬品と間で,一般名コード,薬効分類コード,BOXコ ードのいずれかの組み合わせが存在すれば相互作用を有する組み 合わせであると判断するものであり,自己医薬品と相手医薬品と の組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと の,医薬品の組み合わせ同士の合致を判断しているとはいえない から,本件発明1の「自己医薬品と相手医薬品との組み合わせと 相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせが合致するか否か を判断することにより,相互作用チェック処理を実行する」「相 互作用チェック処理」とは相違する。
(イ) 一致点及び相違点
以上によれば,本件発明1と引用発明3は,次の一致点において一致 し,前記第2の3(2)ウ(ウ)記載の相違点4−1のほか次の相違点におい て相違することが認められる。
a 一致点
「一の医薬品から見た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせを個 別に格納する相互作用をチェックするためのマスタを記憶する記憶手 段と, 入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品 とし,自己医薬品と相手医薬品の組み合わせについて,上記マスタに 基づいて相互作用をチェックするための処理を実行する制御手段と, 前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用をチェ ックするための処理の結果を,表示する表\\示手段と, を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェック装置」
b 相違点
〔相違点4−8〕
相互作用をチェックするためのマスタが,本件発明1では,「一の 医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見 た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する 組み合わせを格納する」のに対し,引用発明3では,「一の医薬品か ら見た他の医薬品の一般名コード,薬効分類コード,BOXコードか の少なくともいずれかについて,相互作用が発生する組み合わせを格 納し,また,他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コード,薬効分 類コード,BOXコードかの少なくともいずれかについて,相互作用 が発生する組み合わせを格納する」点。
〔相違点4−9〕
相互作用をチェックするための処理が,本件発明1では,自己医薬 品と相手医薬品との組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の 組み合わせが合致するか否かを判断するのに対し,引用発明3では, 「自己テーブル部」に「自己医薬品の一般名コードが存在するか」, 「自己医薬品の属する薬効分類コードが存在するか」,「自己医薬品 に付与されたBOXコードが存在するか」をそれぞれ検索して,いず れかのコードが存在していれば,処方医薬品相互作用チェックテーブ ルTの形態で一時記憶テーブル110に記憶し,一時記憶テーブル1 10に記憶したデータの「相手テーブル部」に,「相手医薬品の一般 名コードが存在するか」,「相手医薬品の属する薬効分類コードが存 在するか」,「相手医薬品に付与されたBOXコードが存在するか」 をそれぞれ検索して,いずれかのコードが存在していれば,「自己医 薬品」と「相手医薬品」とが相互作用を有する組み合わせが存在する と判断するものである点。
エ 以上のとおりであるから,審決は,本件発明1と引用発明3の相違点の 認定に際し,相違点4−8,4−9を看過したものであり,相違点の認定 の誤りがあるというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.08. 7
平成30(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月22日 知的財産高等裁判所(3部)
2 取消事由1(引用発明の認定の誤りに基づく相違点の看過)について
(1) 甲1文献の記載
甲1文献には,次の記載がある
・・・
しかし,仮にα<0.3に近い領域においては散乱光強度が粒径の 3乗に比例する関係が成立し,α>5に近い領域においては散乱光強 度が粒径に反比例する関係が成立するとしても,その間における散乱 光強度と粒径との関係については,審決は何ら明らかにしていないの であるから,これによって,常に長波長光に比べ短波長光は,相対的 に等しい振幅信号を生成するといえるかどうかは明らかではないとい わざるを得ない。この点について,被告は,「レイリー散乱領域から ミー散乱領域よりもαが大きい条件の領域に向かって,レイリー散乱 領域に近い側では,αが大きくなるに従って散乱強度が大きくなり, いずれかで必ず極大値に達し,その後αが大きくなるに従って散乱強 度が小さくなって,ミー散乱領域よりも大きい条件の領域に近づく。」 と主張するが,この主張は,散乱強度の大きさの変化を説明している のにとどまるから,散乱強度と粒径と間の定量的な関係について説明 がないという問題は,依然として解消されていない。
また,審決の見解は,散乱角の違いによるばらつきを考慮していな いという点においても問題があるものといわざるを得ない。すなわち, レイリー散乱領域よりαが大きい領域においては,上記(ア)b,cのと おり,散乱光強度は散乱角に依存して大きく変化し,αが変化した場 合の散乱光強度の変化の仕方や程度は,散乱角θによってまちまちで あることがわかる。そうすると,散乱光強度に対する粒径の影響は, 散乱角θによって異なるといわざるを得ないのであるから,この点を 考慮していない審決の見解には問題があるものといわざるを得ないの である(なお,引用発明の争いのない構成においては,第1の照明か\nら照射される光と第2の照明から照射される光とでは,散乱角が異な ることになるから,散乱角θによる影響はより一層複雑なものになら ざるを得ないものと予想される。)。\nそうすると,審決の上記理解には問題があるといわざるを得ないか ら,ミー散乱領域を考慮したとしても,「長波長光が,小さな粒子の 場合に小さな振幅信号を生成し,大きな粒子の場合に大きな振幅信号 を生成するのに対し,短波長光が,大小の粒子いずれの場合にも相対 的に等しい振幅信号を生成する」ということはできない。
c そして,他に記載4)が成り立つことを裏付けるに足りるような根拠 を見出すこともできないから,結局,記載4)を記載3)及び記載5)と整 合的に説明することはできないものといわざるを得ない。
そうすると,当業者は,甲1文献から,引用発明の争いのない構成\nにおいて「長波長光からの振幅信号と短波長光からの振幅信号との比 を比較することにより煙粒子の大きさを判定」するという技術的思想 を認識することはできないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.08. 6
平成30(行ケ)10160 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月30日 知的財産高等裁判所
原告は,「甲1発明は,『芯材13』の存在により,『外装カバー15』が, 『表面から内方に窪んだ凹部』を有しない構\成となっており,この点が,本件特許 発明1と甲1発明の相違点1となっている」ことを前提に,本件特許発明1の甲1 発明との相違点1の容易想到性は,甲1発明から芯材13を取り除くことが容易で あるか否かに帰着すると主張する。 しかし,相違点1は,前記第2,3(6)のとおりであって,芯材13の有無のみが 相違点ではないから,この点において原告の主張は失当である。 本件特許発明は,前記1(2)のとおり,棒状のハンドル本体に表面から内方に窪ん\nだ凹部を形成し,該凹部をハンドルカバーによって覆うことで,ハンドルを上下又 は左右に分割した場合に比べて,ハンドルの成形精度や強度を高く維持することが できるとともに,ハンドルの内部を容易に密閉できるようにして組立て作業性を向 上したものであるところ,このような課題は,甲1にも甲2にも記載されておらず, 技術常識であったとも認められない上,甲1発明においては,上下に分割された一 対の外装カバー14,15の表面がハンドル12の表\面を構成しているのに対し,\n甲2事項においては,透明窓部6が設けられた背面カバー部材5により,凹部のう ちヘッド部3の部分を覆い,ハンドルカバーにより凹部のうち把持部2の部分を覆 い,本体ケース4の把持部2の表面及びハンドルカバーの表\面により,把持部2の 表面を構\成しているのであって,ハンドルの構成が大きく異なる。\nまた,甲1の段落[0018]及び[0019]の記載によると,甲1発明の芯 材13は,1)その外周に外装カバー14,15が被覆されて,複数のネジ16によ り固定されるものであること,2)二叉部12aに対応する部分において,一対のロ ーラ支持軸17が設けられて,ローラ支持軸17の基端部は芯材13の中心部に形 成された空間に嵌入され,同ローラ支持軸17の先端部は,二叉部12aから突出 していること,3)このような構成としたことによって,ハンドル12の外表\面(外 装カバー)の導電金属メッキされた導電部と,ローラ支持軸17とは,電気的に絶 縁されていることが認められ,甲1発明において,芯材13は,外装カバー14, 15が被覆されて,ネジ16により固定されるものであるから,ハンドルの外装カ バーの文字どおりの芯材としての機能を有するとともに,ローラ支持軸を保持し,\n外装カバーの外表面の導電メッキされた導電部と,ローラ支持軸との間の電気的絶\n縁が保たれるように離間させる,絶縁材としての機能を有するものと認められる。\nこのような機能を有する芯材13を甲1発明から取り除くことは容易とはいえず,\n芯材13に代えて,甲2に示された背面カバー5の一部に相当する部材(背面カバ ー相当部材)を用いることはできない。 したがって,甲1発明に甲2事項を適用する動機付けがあると認めることはでき ない。
イ 原告は,仮に,本件特許発明1が,ハンドルが上下に分割されるものを 除外するものであったとしても,甲1発明において,ハンドル本体に相当する外装 カバーの大きさは,設計事項の範囲で任意に選択可能であるため,甲1発明の外装\nカバー15の縁部分を甲1の図3の上側にまで伸長し,外装カバー14を,当該凹 部を覆う大きさに構成した上で,甲2事項の結合方法を採用すれば,相違点1は,\n容易に想到することができると主張する。しかし,甲1発明の外装カバー14,1 5は上下に分割されたものとなっており,そのような外装カバー15の縁部分を甲 1の図3の上半分の側にまで伸長することが容易想到と認めるべき事情はない。し たがって,原告の上記主張を採用することはできない。
ウ よって,甲1発明に甲2事項を適用することによって,相違点1を容易 に想到することができたとは認められないから,相違点2及び3の容易想到性につ いて判断するまでもなく,本件特許発明1は,甲1発明及び甲2事項から容易に想 到できたとは認められない。
なお,以上の判断は,甲1発明において,「芯材13及び一対の外装カバー14, 15がそれぞれ別のパーツ」であることや,甲2に「把持部2の内部には,背面カ バー5の一部が存在し,ネジなどの締結手段で背面カバー5が本体ケース4に固定 されており,把持部2の内部の背面カバー5には,ハンドルカバーが,差し込まれ ることで,本体カバー4とハンドルカバーとによって,把持部2の表面が構\成され ている。」という技術的事項が含まれるかどうかによって左右されるものでないこ とは,既に判示したところから明らかである。 また,甲4〜10に記載されている事項は,いずれも,一対の分岐部をハンドル 本体の長手方向の一端に一体的に形成するという技術を,甲16〜19に記載され ている事項は,いずれも太陽電池パネルとローラシャフトを電気的に接続する技術 を開示するにすぎないから,これらに基づき相違点1に係る構成を容易想到とする\nことはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成29(ワ)7764 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月11日 大阪地方裁判所
(4) 本件サイトにおける被告がランキング1位であるとの表示(本件ランキン\nグ表示)の品質誤認表\示該当性
ア 上記のような本件サイトを閲覧する者の認識からすると,本件ランキン グ表示は,掲載業者の中での,投稿された口コミの件数及び内容に基づく評価との\n間にかい離がないのであれば,品質誤認表示に該当するとはいえない。\nそこでまず,被告への口コミの件数についてみると,本件サイトの表示上,他の\n業者への口コミ件数よりも絶えず多くなっている(甲5の3,甲6の1ないし3, 甲21の1ないし4)。また,被告への口コミの内容についてみると,本件サイト の表示からうかがうことができるものについて,別紙「被告への口コミ内容一覧\n表」記載のとおりの口コミが投稿されている。\nこのように本件サイトの表示からうかがうことができる範囲に限ってみると,被\n告への合計32件の口コミは,一部を除いて基本的に,工事の質や接客態度といっ た被告の提供するサービスの質,内容を高く評価するものであるところ,このこと に,原告も被告への口コミが高評価のものばかりであると主張しているという弁論 の全趣旨を併せ考えると,被告への口コミは,証拠上本件サイトの表示からうかが\nうことができない範囲のものについても,被告の提供するサービスの質,内容を高 く評価するものであると推認される。 このように被告への口コミは,その件数が最も多いだけでなく,その内容も軒並 み高評価のものであることからすると,本件ランキング表示(本件サイトにおける\n被告がランキング1位であるとの表示)と,被告への口コミの件数及び内容に基づ\nく評価との間にかい離はないと認められる。
イ もっとも,そもそも被告への口コミが虚偽のものである場合,例えば, 被告が自ら投稿したものであったり,形式的には施主又は元施主(以下「施主等」 という。)からの投稿であったとしても,その意思を反映したものではなかったり などする場合は,本件サイトの表示上の被告への口コミの件数及び内容をそのまま\nのものとして受け取ることが許されなくなり,その結果,本件ランキング表示との\nかい離があるということとなる。そこで,次にこの点を検討する。
・・・・
以上からすると,本件サイト公開前の日付となっている5件の投稿は,被告の関 与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした架空の投稿であると認められる。そして, 確かに,同様の日付の投稿は他の業者についても存在するが,それらの投稿はいず れも各4件である(甲21の2ないし4。甲21の5でも同様である。)から,被 告については,これらにより,本件サイトの公開時点から,既にランキング1位と 表示されていたと推認され,その表\示は虚偽であったといえる。
・・・
また,乙10によれば,被告は,平成24年6月当時,コメントを書いた施主等 にプレゼントを進呈していたと認められ,また,甲15によれば,被告は,平成2 9年9月頃,本件サイトに関する新聞社の取材に対し,「顧客の感想を社員が聞き 取って(自社の口コミとして)投稿したことはあったが虚偽は書いていない」と回 答したと認められ,このように被告が施主等から聞き取った内容を自ら口コミとし て投稿したことがあることは,当事者間に争いがないところ,この対応からすると, 何とかして被告への口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れる。そしてまた, 乙10によれば,被告の担当者は,平成24年6月28日にヒューゴとの間で本件 サイトの改修を打ち合わせるメールの中で,「過去コメント分の編集(入力日時) の変更はできないでしょうか?」と述べていたと認められるところ,このメールか らは,施主等から投稿される口コミをそのまま反映させようとしない作為的な態度 が見て取れる。
以上のような重大な疑問と被告の態度に加え,前記(ア)のとおり,被告は,その関 与の下に本件サイトの公開時点で架空の投稿が表示されるようにしていたことを考\n慮すると,上記の「地域」が表示された投稿も架空のものと認めるのが相当である。\n
・・・・
ウ 以上からすると,本件サイトにおける被告がランキング1位であるとい う本件ランキング表示は,実際の口コミ件数及び内容に基づくものとの間にかい離\nがあると認められる。 そして,本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは,投稿者の主\n観に基づくものではあるが,実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の 意見が集積されるものである点で,需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすもので ある。したがって,本件サイトにおけるランキングで1位と表示することは,需要\n者に対し,そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として,その提供 するサービスの質,内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示\nする点で,役務の質,内容の表示に当たる。そして,その表\示が投稿の実態とかい 離があるのであるから,本件ランキング表示は,被告の提供する「役務の質,内容\n・・・について誤認させるような表示」に当たると認めるのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成30(行ケ)10148 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月18日 知的財産高等裁判所(2部)
イ 次に,本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」の物品分野の当業者 が,慶弔用品の分野における意匠1及び意匠2の形態を「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到するかどうかについて検討する。
(ア) 「卓上敷マット」は一般のテーブルや机に敷かれるものを含む日常生 活に用いられる物品である一方,証拠(乙2〜4,17,18)及び弁論の全趣旨 によると,意匠1の「マット」や意匠2の「盆茣蓙」は,現在では主として盆の時 期に精霊棚や仏壇の前に置く経机や小机の上に敷き,上に位牌やお供え物などを置 く慶弔用品の分野の物品であり,その物品分野は「卓上敷マット」とは異なるもの である。 しかし,いずれもテーブルや机という「卓」(乙1によると,「卓」にはテーブル や机が含まれると認められる。)の上に敷かれて使用されるものであるという点で その用途が共通している。また,意匠1の「マット」や意匠2の「盆茣蓙」の形状 は,いずれも「卓上敷マット」と同じマット状であり,上に物を載置することがで きる点においてその機能が共通している。\n
(イ) そして,証拠(乙5〜8,12〜15)及び弁論の全趣旨によると, 本願の出願日前において,「盆茣蓙」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテ ーブル掛けなどの物品が,同一の見本市などに出品されることがあり,「卓上敷マッ ト」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が,「盆茣蓙」のような慶弔用品の 形態に接する機会は十分あったものと認められる。\n
(ウ) 以上を考え併せると「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品 分野の当業者は,物品分野は異なるものの,意匠1から着想を得て,真菰を並べて 形成された「卓上敷マット」を想到し,更に真菰を並べて形成された慶弔用品の「盆 茣蓙」である意匠2の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到することができたと認められる。 なお,「卓上マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野と「盆茣蓙」などの慶弔 用品の物品分野では,常に物が載置されるかどうかや一定の時期にのみ使用される かどうかに違いがあるとしても,これらの違いは,上記認定の用途や機能の共通性\nに比べるとささいな違いというほかなく,上記判断が左右されることはない。
ウ 原告は,1)「盆茣蓙」と「卓上敷マット」とは,用途や機能が異なって\nいて非類似であること,2)意匠1や意匠2のような真菰で形成されたマットは,慶 弔用品で仏具の上に敷かれるものであるところ,日常生活で使用されている机に慶 弔用品を祀ることは,浄・不浄の概念からもあり得ないこと,3)前記ギフトショー についての審決の論理を前提とすると,百貨店などであらゆる商品が同スペースで 展示されていることから,全てのあらゆる物品分野間で創作容易性が肯定されてし まうこと,4)自らの商品デザインにつき異業種商品のデザインを盗用することは信 義に反すること,5)慶弔用品としての真菰で形成された「盆茣蓙」に接した取引者, 需要者は,「盆茣蓙」の上にあるお供え物に注目することなどを理由として,「盆茣 蓙」についての形態を「卓上敷マット」に転用することを考えないと主張する。
(ア) 上記1)について,前記1で説示したとおり,意匠法3条2項は,物品 との関係を離れた抽象的な公然知られたモチーフを基準として,当業者の立場から みた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるから,物品が非類似であ ることが直ちに創作が容易でないことに結びつくものではない。そして,本件で転 用を容易に想到できることは前記イのとおりである。
(イ) 上記2)について,原告の主張は,「盆茣蓙」が慶弔用品であって,宗教 的感情によって転用が妨げられるというものであると解されるが,証拠(乙2)に よると,「盆茣蓙」について,かつては,「丁半博打で,壺を伏せる場所へ敷くござ」 という慶弔用品以外の用途もあったと認められる上,前記イ(ア)認定の用途や機能の\n共通性に照らすと,宗教的感情によって当業者における意匠1及び意匠2の形態の 転用が妨げられるとは解されない。
(ウ) 上記3)について,前記イの判断は,見本市などにおいて,慶弔用品と 「卓上敷マット」を含む物品が出品されていることのみを理由とするものではなく, 前記イ(ア)認定の用途や機能の共通性も理由としているから,全てのあらゆる物品分\n野間で形態の創作容易性が認定されてしまうことにはならない。
(エ) 上記4)について,本願意匠に創作容易性を認めたからといって,デザ インの盗用を認めることにはならず,デザインの盗用とは関係がない。
(オ) 上記5)について,創作容易性の基準となるは取引者,需要者ではなく, 「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であって,その視点 や着眼点が取引者,需要者と同じとはいえず,また,当業者において転用を容易に 想到できることは前記イのとおりである。
(カ) 以上からすると,原告の上記主張は採用することができない。
(2) 相違点1,2についての判断
前記(1)のとおり,意匠2の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に 転用することは容易であると認められるから,次に,前記4で認定した意匠2と本 願意匠との相違点1,2について,創作が容易であるかについて検討する。
ア 相違点1について,証拠(乙9,10)及び弁論の全趣旨によると,「卓 上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者にとって,「卓上敷マット」 の縦横比を必要に応じて適宜調整することはありふれた手法であると認められる。 したがって,意匠2の平面視略横長長方形の縦横比を本願意匠の縦横比に変更す ることについて,意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえない。
イ 相違点2について,本願意匠と意匠2で用いられている編み糸の色彩自 体に違いはなく,本願意匠の構成は,意匠2の構\成から紫色の糸と赤色の糸の配置 を入れ替えたにすぎないものである。また,証拠(乙9)及び弁論の全趣旨による と,「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野において,色彩を適宜変更 することはよく見られる手法であると認められる。 そうすると,意匠2の5本の編み糸のうち,紫色の糸と赤色の糸の配置を入れ替 えて本願意匠の構成にすることについて,意匠の着想の新しさや独創性があるとは\nいえない。
ウ 以上からすると,本願意匠は,意匠2の形態に基づいて,当業者におい て容易に創作できたものと認められる。
エ 原告は,本願意匠と意匠2との間には,縦横比や5本の編み糸の色彩と いった,共通点を凌駕し得る非常に重要かつ大きな特徴的相違があるから,本願意 匠と意匠2は非類似であり,意匠2の形態に基づいたとしても,本願意匠は,当業 者において容易に創作できないと主張する。 しかし,前記1のとおり,意匠法3条2項は,公然知られたモチーフを基準とし て,当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とする規定であって, 物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする同条1項3 号とは考え方の基礎を異にするものである。したがって,意匠法3条1項3号の類 似性の判断と同条2項の創作容易性の判断とは必ずしも一致しないものである。そ して,これまでに検討してきたところに照らすと,本願意匠と意匠2の相違点1, 2は,いずれも「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であれ ば容易に創作できたものであるといえ,これに反する原告の主張を採用することは できない。
◆判決本文
関連事件です。
2019.08. 2
平成29(ワ)29604 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月24日 東京地方裁判所
(1) 前記認定のとおり,被告が本件技術情報をPOSCOに開示した時期は●(省 略)●までの間であると認められる。
(2) そして,証拠(甲94,95)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら れる。
ア 方向性電磁鋼板は,磁束密度が高いほど良好な磁気特性を有すると評価され, 従来型の方向性電磁鋼板に対して,磁束密度が一定以上のものがハイグレードな方向 性電磁鋼板であるHGOとされている。また,方向性電磁鋼板の品質を評価する上で, 磁束密度の他に,「鉄損」という重要な指標があり,鉄損が小さい方が優れた品質であ る。●(省略)●
イ ●(省略)●
ウ ●(省略)●
エ ●(省略)●
オ ●(省略)●
カ 鉄鋼・非鉄金属のライセンス料率の平均値は,イニシャル・ペイメントがある 場合が3.5%であり,イニシャル・ペイメントがない場合が3.3%である。また, 件数としては,ライセンス料率を3%とするものが最も多い。
(3)上記(1)及び(2)の事実関係からすると,POSCOは●(省略)●HGOの生産 販売を開始したところ,●(省略)●販売数量が増加した●(省略)● そうすると,平成19年から平成28年までの10年間において,本件技術情報の ライセンス料相当額を算定すると,少なくとも,41億0400万円(年間●(省略) ●トン×●(省略)●万円/トン×10年×2%)を下回ることはないと認められる。 (4) 以上によれば,被告は原告に対して,不競法4条に基づき,少なくとも損害賠 償金9億3000万円及び弁護士費用相当額9300万円の合計額である10億2 300万円及びこれに対する不正競争後の日である平成24年4月30日から支払 済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うと認められる。
2019.08. 2
平成30(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月18日 知的財産高等裁判所
(2) 訂正事項2が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは,訂正の効果は出願時に遡って 生じ(特許法128条),訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると,同法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す るもの」であるか否かの判断は,訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり,「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また,特許請求の範囲の記載に関し,同法36条5項前段は,特許請求 の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は,一つの請求項から発明 が把握されるようにするため,各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから, 客観的にみると,一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても,相互に矛盾するものでなければ,特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に,訂正事項2が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項1のただし書の「ただし,R1 及びR2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は,その文理上,R1 及びR2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり,R1 又はR2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ,本件訂正前の請求項1の記載全体をみると,「R1はフッ 素であり」及び「R2は塩素であり」との記載があり,この記載は,「R1」 を「フッ素」に,「R2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして,この記載は,R1 及びR2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから,その点においては,ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが,相互に矛盾するものではない。 また,本件明細書の「前記化学式1において,…R1 及びR2 は各々水素 原子,C1−C6アルコキシ,C1−C6アルキルまたはハロゲンであり,…前 記ハロゲンはフッ素,塩素,臭素またはヨー素を意味する。」(【000 9】)及び「本発明による前記化学式1で表される化合物において,特に\n好ましくは,…R1 及びR2 は水素原子,F,Cl,メチルまたはメトキシ であり」(【0010】)との記載中には,化学式1のR1 及びR2 の例と してF(フッ素)及びCl(塩素)が開示されているから,本件訂正前の 請求項1において「R1」を「フッ素」に,「R2」を「塩素」に特定する ことは,本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると,ただし書の記載と「R1 はフッ素であり」及び「R2 は塩素 であり」との記載は,「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり,本件訂正前 の請求項1におけるR1 及びR2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項2は,本件訂正前の請求項1記載の「R2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから,特許請求の範囲を変更するもので ある。また,本件訂正前の請求項1の「R1 はフッ素であり」及び「R2 は 塩素であり」との記載文言から,R1 は「フッ素又は水素」を,R2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから, 訂正事項2による特許請求の範囲の変更は,減縮的な変更には当たらない。 そして,訂正事項2により,請求項1に係る発明は,本件訂正前の請求 項1に記載される化合物1の置換基である「R2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「R2」が水素である化合物群に変更されることになるから,こ の変更により,本件訂正前の請求項1の記載の表示を信頼した第三者に不\n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって,訂正事項2は,実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから,特許法126条6項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは,本件訂正前の請求項1の記載及び本件明細書の記載を考慮し, また,本件特許の出願経過を参酌すれば,本件訂正前の請求項1の本文の 「R 1 はフッ素であり,R2 は塩素であり」との記載は,ただし書の「R1 及 びR2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり,実質 的に,本文のR1 及びR2 の範囲は,塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され,訂正事項2は,実質的に理解されるR2の範囲から塩素を削除す ることによりR2の範囲を限定するものであるから,実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら,前記(2)イのとおり,本件訂正前の請求項1の特許請求の範 囲の記載によれば,本件訂正前の請求項1の本文の「R1はフッ素であり」及 び「R2は塩素であり」との記載は,「R1」を「フッ素」に,「R2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり,ただし書の「R1 及びR 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが,相互に矛盾するものではなく,本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから,本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に,本件特許の出願経過によれば,本件訂正前(本件特許の設定登録時) の請求項1は,本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第2次補正によ り第1次補正後の請求項1が補正されたものであるが,本件拒絶査定不服審 判の審判請求書(乙3)には,「3.2.上記補正は,請求項1において, R1 をフッ素に限定し,R2 を塩素に限定し(特許請求の範囲の限定的減縮に あたります),…適正な補正です。」,「3.3.上記補正により,本願発 明の化合物は,本願明細書の表2に記載される薬理試験結果において,当業\n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ\nれる化合物に限定され,審査官殿が指摘された,「引用文献3の化合物42 と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物(例えば化合物52,73,11 5,136,157,193など)」は明確に排除されています。」との記 載があり,この記載から,上記補正は,請求項1におけるR1をフッ素に限定 し,R2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして,本件 明細書記載の化合物52,73にはR2に水素が,化合物115,136,1 57にはR1に水素が含まれており,本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は,本件明細書の記載とも整合することからすると,本件訂正前の請 求項1におけるR1及びR2の定義が不明瞭であるということはできない。 また,本件拒絶査定(甲16)には,「本願発明の化合物10は,引用文 献3の化合物42に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが,この記載は,原告らが述べるような審査官が化合物10を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし,特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり(特許法36条5項),原告らは,自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると,本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより,本件訂正前の請求項1におけるR1 及びR2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに,原告らは,本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として, 第2次補正における「R2は塩素であり,」との記載は,審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが, 原告ら主張の合意は,第三者との関係からすれば,出願経過における願書, 願書に添付した明細書,特許請求の範囲,図面等の審査に係る書類,拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず,本件訂正前 の請求項1の解釈において参酌することはできない。 したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成30(ネ)10090 自由発明対価等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月28日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
前記(1)のとおり,サントリーがA教授と控訴人に対し,研究期間を平 成15年8月1日から同年12月31日までとして委託した研究については,同年 12月8日に被控訴人に対してその報告書が提出されている(甲2)ところ,その 研究の内容は,健常な日本人成人52名を対象に行った日本版「アーバンス」神経 心理テストを紹介し,同テストが加齢に伴う高次脳機能障害の簡便かつ正確な評価\nに有用であるというものであって,本件発明の内容とは異なる。これに対し,同時 期に,サントリーが控訴人に対して,上記研究とは別の内容の研究を委託したこと を認めるに足りる証拠はない。そして,1)控訴人は,平成15年当時,金沢大学の 助教授として,記憶障害や注意・集中力障害などの高次脳機能障害に関する基礎的\nかつ臨床的研究を行っていたこと,2)後記のとおり,控訴人は,南ヶ丘病院の患者 に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験について,兼業許可を受\nけていたとは認められないことに照らすと,上記比較試験に係る研究は,金沢大学 における控訴人の職務であるというべきである。したがって,本件発明は,サント リーが控訴人に対して委託した研究に基づくものではなく,控訴人の金沢大学にお ける職務に属するものというべきである。
イ 前記(1)のとおり,金沢大学とサントリーは,平成16年12月27日, 本件共同研究契約を締結したものと認められる。そして,前記(1)のとおり,本件 共同研究契約書では,研究目的及び内容を「アラキドン酸含有油脂の高次脳機能に\n及ぼす影響を検討する」としているのであるから,本件共同研究契約書の記載と本 件発明の内容とは一致するというべきである。また,本件共同研究契約書では,控 訴人の研究分担を「神経機能の測定」としているが,研究目的及び内容についての\n上記の記載に照らすと,「神経機能の測定」とは,本件発明の効果の検証のために\n被験者に対して認知機能の比較試験を行うことを意味するものと理解することがで\nきる。そうすると,本件発明は,本件共同研究の対象とされたものと認められる。 なお,本件共同研究契約書には,研究実施場所として金沢大学のみを記載し,南 ヶ丘病院は記載されていないが,本件共同研究において,研究の場所を金沢大学に 限定しなければならない理由はなく,本件共同研究契約書も,研究の場所を金沢大 学に限定する趣旨で上記の実施場所の記載をしたものとは認められない。 したがって,本件共同研究を南ヶ丘病院で行うことは禁止されておらず,南ヶ丘 病院で本件発明のための研究を行えば,同研究は,金沢大学における控訴人の職務 に属するものというべきである。 この点,控訴人は,平成16年2月,金沢大学に対して南ヶ丘病院での兼業許可 申請を行い,金沢大学からその許可を得ていると主張する。\nしかし,前記(1)のとおり,控訴人が主張する兼業許可申請に係る申\請書(甲2 3)には,兼業先である南ヶ丘病院で行う職務として,脳神経外科外来及び入院患 者の診療と記載されており,同記載を前提に兼業許可がされているのであるから, 南ヶ丘病院で患者に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験を行う\nことについてまで兼業の許可がされているわけではない。
ウ 前記(1)のとおり,金沢大学の職務発明取扱規程においては,●●●●・・・ ●●●●●●●●●,控訴人は,金沢大学知的財産本部長に対し,本件発明の発明届出書を提出し,これを受けて,金沢大学知的財産本部長は,控訴人に対し,本件発明を職務発明であると認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送し,控訴人は,上記発明届出書に,共同発明の場合に添付する共同研究契約書として本件共同研究契約書の写しを添付し た。前記アのとおり,本件発明は,控訴人の金沢大学における職務に属する発明であることから,控訴人は,金沢大学に対して,本件発明について,上記職務発明の届出をしたものと認められる。
エ 以上のとおり,控訴人が,金沢大学の職務として本件発明をしたことは 明らかであって,本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を,サントリーを「使 用者等」とした職務発明と認めることはできない。
オ 控訴人は,本件発明のための研究は,本件共同研究契約が締結される前 に事実上終了しており,また,本件原出願は,本件共同研究契約を締結してから半 年程度でされているが,本件発明は,半年程度で完成するものではないと主張する。 しかし,既に認定したとおり,南ヶ丘病院の患者に対するアラビタ投与の前後に おける認知機能の比較試験に係る研究は,金沢大学における控訴人の職務であって,\nその研究の成果を利用して本件発明が完成し,本件原出願がされたのであるから, 本件発明のための研究が,本件共同研究契約締結前にかなりの程度行われており, 本件原出願は,本件共同研究契約を締結してから半年程度でされているとしても, 本件発明は金沢大学の職務発明であるとの認定を何ら左右するものではない。
カ 控訴人は,甲18契約に係る契約書には,本件発明のための研究内容に 沿った記載があるから,甲18契約を締結することによって,本件発明のための研 究が,サントリーと金沢大学との間で締結された共同研究契約に含まれるものにし ようとしたという趣旨の主張をするが,甲18によると,甲18契約は,本件共同 研究の研究期間後の平成18年4月19日に締結され,それ以降の研究を対象とし ていることが認められるから,控訴人の上記主張は理由がない。
キ 控訴人は,原審における本人尋問において,本件発明の発明届出書に本 件共同研究契約書を添付したのは,金沢大学からそのようにするよう言われ,また, 金沢大学の学長からのプレッシャーにより,本件共同研究契約書を添付することを 断れなかったからであり,本件発明が本件共同研究によって発明されたものとは認 識していなかった旨供述する(13,30頁)。 しかし,本件発明が本件共同研究によってされたものではないにもかかわらず, 上記のような理由から,本件共同研究契約書を本件発明の発明届出書に添付するこ とは考え難いというべきである。 控訴人は,金沢大学の学長からプレッシャーをかけられたと供述するが,そのプ レッシャーの内容やプレッシャーがかかる理由が不明であり,また,本件共同研究 契約書の添付について,金沢大学側と交渉をしたこともうかがわれず,控訴人の上 記供述は不自然である。 したがって,控訴人の上記供述は信用することができない。
(3) 控訴人の主位的請求は,本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分がサン トリーを「使用者等」とする職務発明であることを前提とするところ,前記(2)の とおり,同部分はサントリーを「使用者等」とする職務発明ではないから,その余 の点(争点2,3)について判断するまでもなく,控訴人の主位的請求は理由がな い。
2 争点4,5(予備的請求1の成否及び額)について\n
(1) 控訴人は,本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサントリー に譲渡したかについて,以下検討する。
ア 前記1(2)のとおり,控訴人は,金沢大学における控訴人の職務として 本件発明をしたところ,前記1(1)のとおり,控訴人は,金沢大学知的財産本部長 に対し,本件発明の発明届出書を提出し,これを受けて,金沢大学知的財産本部長 は,本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を職務発明と認定した上で,控訴人 に対し,本件発明を職務発明であると認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送 しているのであるから,本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分は,金沢 大学に承継されたものと認められる。そして,このことは,前記1(1)で判示した とおり,本件共同研究契約において,同契約の成果である発明に係る特許を受ける 権利のうち控訴人の持分は金沢大学が承継する旨記載されていることにも沿うもの ということができる。 なお,特許を受ける権利が共有に係るときは,同権利を譲渡するには,他の共有 者の同意が必要である(特許法33条3項)としても,前記1(1)で判示した本件 共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関する定めからすると,Bは, 本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を金沢大学に承継させることにつ いて同意しているものと推認できるし,実際にも,乙10証書及び甲24証書に よって,Bが上記の同意をしていることが確認されている。 控訴人も,乙11証書を作成して,本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の 持分を金沢大学に承継させたことを確認している。 一方,前記1(2)のとおり,本件発明は,本件共同研究の対象であるところ,前 記1(1)で判示した本件共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関す る定めからすると,サントリーが控訴人から本件共同研究の対象である本件発明に 係る特許を受ける権利の控訴人の持分の譲渡を受けることは予定されておらず,控\n訴人とサントリーとの間で,本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサ ントリーに譲渡することを内容とする契約が締結されたことを認めるに足りる証拠 はないし,サントリーが本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を譲り受 ける動機その他の事情も認められない。 したがって,本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲 渡されたと認めることはできない。
イ これに対し,控訴人は,乙10証書を根拠に,本件発明に係る特許を受 ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲渡されたと主張する。 しかし,前記1(1)で判示した経緯からすると,乙10証書(乙10,42)及 びこれと同内容の甲24証書(甲24,乙41)は,控訴人とBが本件発明に係る 特許を受ける権利のそれぞれの持分を,控訴人は金沢大学に,Bはサントリーに譲 渡するとともに,控訴人はBの譲渡について,Bは控訴人の譲渡についてそれぞれ 同意したことを確認する趣旨で作成されたものと認められる。なお,控訴人は,ま ず,控訴人が甲24の書式を作成し,これに控訴人及びBが署名した甲24証書を 控訴人が保管し,控訴人は,そのコピーをBに交付し,その後,サントリーにおい て,同コピーを基に乙10の書式を作成し,これに控訴人及びBが署名して乙10 証書が作成された旨主張するが,本件訴訟において控訴人が提出した甲24は写し であり,その原本は被控訴人が乙41として提出していることから,控訴人は,甲 24証書の原本を保管していないものと認められ,したがって,控訴人の上記主張 は事実と異なることは明らかである。
2019.08. 2
平成30(行ケ)10145 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月18日 知的財産高等裁判所
前記(ア)及び(イ)によれば,甲1ないし3,5に接した当業者は, 過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わせて使用する甲1発明には,有効 塩素剤の添加により有害なトリハロメタンが生成するという課題があ ることを認識し,この課題を解決するとともに,使用する薬剤の濃度を 実質的に低下せしめることを目的として,甲1発明における有効塩素剤 を,トリハロメタンを生成せず,有効塩素発生剤である次亜塩素酸ナト リウムよりも少量で付着抑制効果を備える海生生物の付着防止剤であ る甲2記載の二酸化塩素に置換することを試みる動機付けがあるもの と認められるから,甲1及び甲2,3,5に基づいて,冷却用海水路の 海水中に「二酸化塩素と過酸化水素とをこの順もしくは逆順でまたは同 時に添加して,前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させる」 構成(相違点1に係る本件発明1の構\\成)を容易に想到することができ たものと認められる。
イ これに対し被告らは,1)甲1記載の有効塩素発生剤は,過酸化水素との 酸化還元反応によって一重項酸素を発生させる化合物であるから,甲1発 明における有効塩素発生剤を,過酸化水素と反応しても一重項酸素を発生 しない二酸化塩素に置換する動機付けはない,2)二酸化塩素は,不安定か つ酸化力の強い化合物であるため,本件優先日当時,過酸化水素と組み合 わせた場合,両者が反応して消費され,共存できないと考えられており, また,両者の反応により二酸化塩素は,海生生物の付着防止効果が劣る亜 塩素酸イオンとなるので,二酸化塩素を単独で使用した方が,二酸化塩素 と過酸化水素を併用するよりも海生生物の付着防止効果は高いことから すると,当業者においては,過酸化水素に二酸化塩素を組み合わせること についての動機付けがなく,むしろ阻害要因がある旨主張する。 しかしながら,上記1)の点については,甲1には,過酸化水素と有効塩 素発生剤との組み合わせについて,「特に有効塩素との組み合わせの場合 には,次式に示す酸化−還元反応によって一重項の酸素(OI)が発生し て相乗的に抑制効果が高まるものと考えられる。H2O2+ClO−→H2 O+C1−+OI」(前記(2)ア(ウ))との記載があるが,一重項酸素の発生 により「相乗的に抑制効果が高まるものと考えられる。」と推論している に過ぎず,一重項酸素による付着抑制効果の有無及びその程度を実証的な データ等により確認したものではない。 また,甲1には,過酸化水素と有効塩素発生剤との併用以外にも,過酸 化水素とヒドラジンとを併用した「実施例3」として,過酸化水素とヒド ラジンとの併用の結果,過酸化水素と有効塩素発生剤との併用の結果と同 様の抑制効果が得られたことの記載があり(前記(2)ア(オ)),過酸化水素 とヒドラジンとの併用によって一重項酸素が発生することは想定できな いことに照らすと,二酸化塩素が過酸化水素との併用により一重項酸素を 発生しないとしても,そのことから直ちに甲1発明における有効塩素発生 剤を二酸化塩素に置換する動機付けを否定することはできない。
次に,上記2)の点については,二酸化塩素は,不安定かつ酸化力の強い 化合物であるため,本件優先日当時,過酸化水素と組み合わせた場合にお いて,両者が反応して消費され,およそ共存できないと考えられていたこ とを具体的に裏付ける証拠はない。もっとも,甲3には,「二酸化塩素は, 極めて不安定な化学物質であるため,その貯蔵,輸送は非常に困難である が,このように二酸化塩素発生器を用いた場合には,現場での二酸化塩素 の製造が可能であり,取り扱いが非常に簡単である。」(【0018】)\nとの記載があるが,この記載から,海水中で,二酸化塩素と過酸化水素を 併用した場合,両者が反応して消費され,およそ共存できないと読み取る ことはできない。また,本件明細書の【0010】には,「二酸化塩素と 過酸化水素との併用は,塩素剤と過酸化水素との併用と同様に酸化還元反 応により両薬剤が消費され,水系において安定に共存できないという技術 常識が存在していたためと考えられる。」,「実際に本発明者らが試験した ところによると,…当業者であれば,次亜塩素酸ナトリウムより酸化還元 電位が高い二酸化塩素は過酸化水素と安定に共存できるはずがないと考 えるのが自然である。」,【0012】には,「…その結果,これまで共存が 不可能と考えられてきた二酸化塩素が海水中で過酸化水素剤と準安定的\nに共存できることを意外にも見出し…」との記載があるが,当業者は,本 件優先日前に本件出願後に公開された本件明細書の記載に接することが できないのみならず,酸化還元電位については,「一方の系の標準酸化還 元電位が,他方の系のそれより高い(正である)場合,前者の方がより強 い酸化剤となり,前者が還元され,後者が酸化される方向に進みうる。」 こと,「酸化還元電位によって予言できるのは反応方向であり,反応速度\nではない」ことは,技術常識であること(「化学大辞典3」縮刷版904 頁・共立出版2003年)に照らすと,酸化還元電位から反応速度まで予\n測できるものとはいえないから,本件明細書の上記記載をもって,海水中 で,二酸化塩素と過酸化水素を併用した場合,両者が反応して消費され, およそ共存できないということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成29(ワ)43269 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月18日 東京地方裁判所
「空間を形づくる非伸縮性の接合部」の意義について,本件明細書には,マ スク布地の中央部に鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性の接合部 を形成したので,会話等で唇を動かしても,呼吸をしても,ニット布地による 拡大,縮小といった変化を生じることがなく,安定して会話や呼吸を行うこと ができること,非伸縮性の接合部を形成する手段として,マスク本体の中央部 を左右に分離させた上,鼻下及び唇部との間に一定空間を保つような外膨らみ の扇形状に裁断し,可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合するとの 記載がある(段落【0020】【0059】【0060】【0092】)。 そうすると,「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは,少なくとも,会話や 呼吸の妨げにならないように,マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない\n程度の空間が保たれるよう,マスク本体の中央部を左右に分離させ,外膨らみ の扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構\n成を含むと解するのが相当である。
証拠(甲5,21の1・2,乙37)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品 は,マスク本体の中央部を左右に分離させ,外膨らみの扇形状に裁断して縫合 する構成を有しており,それによって,マスク本体の中央部に非伸縮性の接合\n部が形成され,会話や呼吸の妨げにならない程度に,マスクの本体が鼻下及び 唇の表面に接触しない程度の空間が保たれていると認められる。\nしたがって,被告製品は,「空間を形づくる非伸縮性の接合部」(構成要件D)\nを充足するといえる。
これに対し,被告は,「非伸縮性の接合部」について,「非」とは,後に続く 語句について「そうでない」という意味であり,「非伸縮性」とは,伸縮しない, 又は,伸縮するものを除くという意味であると主張するが,本件明細書には, 前記のとおりの記載があり,他方,「非伸縮性」について全く伸縮性を有しない とは記載されていない。また,本件発明はニット生地のマスクに関する発明で あり,一切伸縮しない製品のみを想定しているとは考え難い。 被告は,本件明細書の記載(段落【0060】【0061】)から,「非伸縮性」 の接合部とは,二重の縫合であることが必須の構成であると主張するが,本件\n明細書の段落【0061】には,「例えば・・・二重の縫合を施すことで可及的 な非伸縮性を得ることができる。」との記載があるとおり,二重の縫合はあく まで実施形態の一つとして例示されているにすぎず,「非伸縮性」の接合部の 構成が二重の縫合に限定されるとは認められない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成30(行ケ)10166 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月20日 知的財産高等裁判所
前記2(1)〜(3)のとおり,周知技術Aは,引用文献1が属する対戦型コ ンピュータゲームの分野における周知技術である。 そして,前記2(2),(3)のとおり,引用文献3には,プレイヤキャラクタと敵キャ ラクタの強さのバランスをとることを目的とし,プレイヤキャラクタの強さに応じ た強さの敵キャラクタを出現させることで,プレイヤキャラクタに対して強すぎた り弱すぎたりすることのないようにして,ゲームの興味を持続させる効果を生じさ せることが記載され,また,引用文献4には,ユーザの競技レベルに相応しい他の ユーザを対戦相手とすることを目的とし,ユーザの競技レベルに応じた競技レベル の対戦相手を選択することで,相手が弱すぎたり強すぎたりすることがなくなり, 各ユーザは実力が伯仲した相手との対戦を楽しむことができるという効果を生じさ せることが記載されていることからすると,周知技術Aは,ゲームに抽出されるキ ャラクタやプレーヤのレベルをキャラクタやプレーヤのレベルに合わせることによ り,ゲームを楽しいものとするという技術思想に基づくものであると認められると ころ,引用発明1も,前記3(1)で認定したとおり,支援すべきプレイヤの支援度合 いに応じた人数の第三者勢力を登場させて,プレイヤ同士の操作経験に基づく優劣 のアンバランスを調整することにより,拮抗かつ緊張感のあるゲームとするという 技術思想に基づくものであると認められるから,周知技術Aと引用発明1とは共通 の技術思想を有しているといえる。 したがって,引用発明1及び周知技術Aは,技術分野及び技術思想が共通するか ら,引用発明1に周知技術Aを適用する動機付けはあるというべきである。
(イ) 原告は,引用文献3,4に記載された技術は,いずれも,第3者登場 型に属する対戦アクションゲームに関する技術ではないし,また,第1のプレーヤ キャラクタの情報及び第2のプレーヤキャラクタの情報の組合せに基づいて第3者 キャラクタが抽出されるというものでもないから,本願発明とは技術分野を異にす ると主張する。 しかし,前記(ア)のとおり,引用発明1に周知技術Aを適用することの動機付けは 認められるというべきであり,動機付けが認められるためには,第三者登場型対戦 ゲームであるという点の共通性は必要ないというべきである。 したがって,周知技術Aが第三者登場型対戦ゲームではないことを前提とする原 告の上記主張は理由がない。
エ(ア) ところで,相違点1は,第3者キャラクタを抽出してマッチングさせ る設定処理に関して,本願発明は,「複数のキャラクタの中から,第3者キャラクタ を抽出」しているのに対して,引用発明1は,「NPC人数を増減設定」している点 である。すなわち,本願発明と引用発明1とは,第3者キャラクタを抽出してマッ チングさせる設定処理に関して,当該第3者キャラクタが,複数のレベルのキャラ クタの中からレベルの合うキャラクタが抽出されるのか,それとも,同一のレベル のキャラクタが抽出され,その人数を増減させることによりレベルを合わせるのか の点で相違するのであるから,第3者キャラクタを抽出してマッチングさせる設定 処理に関して,引用発明1の「NPC人数を増減設定」するという構成(同一のレ\nベルのキャラクタが抽出され,その人数を増減させることによりレベルを合わせる という構成)に代えて,周知技術Aの「複数の種類のキャラクタ又はプレーヤの中\nから,キャラクタ又はプレーヤのレベルに応じて特定のキャラクタ又はプレーヤを 抽出すること」という構成にすることで,本願発明の構\成となるものと認められる。
(イ) 原告は,本願発明の課題は,「対戦者同士の操作経験に基づくゲーム優 劣のアンバランスを第3者キャラクタを登場させることにより調整する従来技術が, 対戦ゲームとしての面白みに欠ける」ことであり,プレーヤのレベル等に応じた相 手側キャラクタを抽出するというものではないから,引用発明1及び周知技術1と は課題が異なる旨主張するが,本願発明の課題が上記のとおりであるとしても,引 用発明1に周知技術Aを適用することが困難となるということはできず,また,引 用発明1に周知技術Aを適用すると,本願発明の構成となるのであるから,原告の\n上記主張は理由がない。
オ 以上より,引用発明1に周知技術Aを適用して,本願発明を容易に想到 することができるというべきである。
カ なお,原告は,本願発明は,第3者キャラクタの参戦により従来にない 白熱した対戦ゲームを楽しむことができるという各引用文献に記載の発明の作用効 果とは異なる格別の作用効果を奏する旨主張するが,同効果は,引用発明1に周知 技術Aを適用した発明にも認められる作用効果であって,格別のものとはいえない から,原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成31(ネ)10019 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び前記(2)の本件明細 書の開示事項を総合すると,本件発明の技術的意義は,従来の住宅地図に おいては,建物表示に住所番地及び居住者氏名も全て併記されていたため,\n肉眼でも判別可能な実用性を確保するために縮尺度を低いものにする必要\nがあり,これに伴って全体として地図の大型化や大冊化を招き,この大型 化や大冊化が氏名の記載変更作業の実地調査に係る人件費と相俟って住宅 地図を高価格なものとし,更に氏名の公表を希望しない住人についても住\n宅地図に氏名を登載してしまうこととなるため,プライバシーの保護とい う点からも問題を有し,また,従来の住宅地図の付属の索引は,住所の丁 目及びそれぞれの丁目に該当するページだけが掲載されていたため,「目 的とする居住地(建物)を探し出す作業」(検索)が,煩雑で面倒であり, 迅速さに欠け,非能率な作業となっていたという課題があったことから,\n本件発明の住宅地図は,この課題を解決するため,検索の目安となる公共 施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については,居住人氏名や建物 名称の記載を省略し,住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載すること により,縮尺度の高い,広い鳥瞰性を備えた構成の地図とし(構\成要件B 及びC),地図の各ページを適宜に分割して区画化した上で,地図に記載 の全ての住宅建物の所在番地を,住宅建物の記載ページ及び記載区画を特 定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索引欄を設ける構成(構\成要 件DないしF)を採用することにより,小判で,薄い,取り扱いの容易な 廉価な住宅地図を提供することができ,また,上記索引欄を付すことによ って,全ての建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容 易に分かるため,簡潔で見やすく,迅速な検索の可能な住宅地図を提供す\nることができるという効果を奏することにあるものと認められる。
イ この点に関し控訴人は,本件発明の技術的思想(技術的意義)は,「検 索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については 居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地のみ を記載すると共に,縮尺を圧縮して」(本件発明の構成要件B及び構\成要 件Cの前半)という構成により,「記載スベースを大きく必要とせず」(本\n件明細書の【0039】),これにより「広い鳥瞰性を備えた地図を構成」\n(構成要件Cの後半)する点にある旨(前記第2の4(1)エの「当審におけ る控訴人の主張」(ア))を主張する。
しかしながら,発明の技術的意義は,明細書に開示された従来技術の課 題について,特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づいて,当該発 明がその課題の解決手段として採用した構成及びその構\成による効果を踏 まえて認定すべきものと解されるところ,控訴人の上記主張は,本件明細 書において,従来の住宅地図の付属の索引には,住所の丁目及びそれぞれ の丁目に該当するページだけが掲載されていたため,「目的とする居住地 (建物)を探し出す作業」(検索)が,煩雑で面倒であり,迅速さに欠け, 非能率であるという課題があったこと(【0003】),本件発明は,上\n記課題を解決するための手段として,地図の各ページを適宜に分割して区 画化した上で,地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を,住宅建物の記 載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索 引欄を設ける構成(構\成要件DないしF)を採用したことにより,全ての 建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容易に分かるた め,簡潔で見やすく,迅速な検索を可能としたという効果を奏すること(【0\n039】)の開示があることを考慮しないものであるから,採用すること ができない。
・・・
控訴人は,仮に本件発明の構成要件Dの「区画化」の構\成が,地図が記載 されている各ページについて,記載されている地図を線その他の方法によっ て仕切って複数の区画に分割し,その各区画を特定する番号又は記号番号を 付し,利用者が,線その他の方法及び記号番号により,当該ページ内にある 複数の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割す ることを意味するものと解し,また,仮に構成要件Fの「索引欄に…住宅建\n物の所在する番地を前記地図上における…記載ページ及び記載区画の記号番 号と一覧的に対応させて掲載した」との構成が,索引欄に所在番地の記載ペ\nージ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載される構成に限られ\nると解した場合には,被告地図は,各ページに線その他の方法及び記号番号 が付されていない点及び「特定の緯度・経度を含む地点データと縮尺レベル 19ないし20を含むURL」が画面に「一覧的に」表示されていない点で\n本件発明と相違することとなるが,被告地図は,均等の成立要件(第1要件 ないし第3要件)を満たしているから,本件発明と均等なものとして,本件 発明の技術的範囲に属する旨主張する。 しかしながら,前記1(3)ア認定の本件発明の技術的意義に鑑みると,本件 発明の本質的部分は,検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住 宅及び建物については,居住人氏名や建物名称の記載を省略し,住宅及び建 物のポリゴンと番地のみを記載することにより,縮尺度の高い,広い鳥瞰性 を備えた構成の地図とし(構\成要件B及びC),地図の各ページを適宜に分 割して区画化した上で,地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を,住宅建 物の記載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属 の索引欄を設ける構成(構\成要件DないしF)を採用することにより,小判 で,薄い,取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することができ,また, 上記索引欄を付すことによって,全ての建物についてその掲載ページと当該 ページ内の該当区画が容易に分かるため,簡潔で見やすく,迅速な検索の可 能な住宅地図を提供することができる点にあるものと認められる。\n
しかるところ,被告地図においては,前記2(1)ウ及び(2)認定のとおり, 地図を記載した各ページを線その他の方法及び記号番号によりユーザの目に 見える形で複数の区画に仕切られておらず,索引欄に住宅建物の所在番地の 記載ページ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載されていない ため,構成要件D及びFを充足せず,ユーザが所在番地の記載ページ及び区\n画の記号番号の情報から検索対象の建物の該当区画を探し,区画内から建物 を探し当てることができないから,このような索引欄を利用した迅速な検索 が可能であるということはできない。\nしたがって,被告地図は,本件発明の本質的部分を備えているものと認め ることはできず,被告地図の相違部分は,本件発明の本質的部分でないとい うことはできないから,均等論の第1要件を充足しない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.07.24
平成31(ネ)10010 不当利得返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月10日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから,特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に\n見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許\n発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定することが相当である。\nその認定に当たっては,特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術 と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば,特許請求の範囲及び明 細書の記載,特に明細書記載の従来技術との比較から認定することが相当である。 第1要件の判断,すなわち,対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかど うかを判断する際には,上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品 等が共通に備えているかどうかを判断し,これを備えていると認められる場合には, 相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件における第1要件の成否
本件発明に係る特許請求の範囲及び明細書の記載は,前記(1(2)のアイ)のとお りであり,要するに,本件発明は,液晶表示装置に用いられる平面照光装置に関し,導光板の下面に多数の多面プリズムを設ける従来技術の下では,乱反射が起きて上\n面に向かう光量が減り,照光面である上面に極端な明暗のコントラストが生じるな どの問題があったところ,液晶表示装置を均一にかつ高い輝度で照らすという課題を解決するため,導光板である板状体の両面のうち,照光面とは反対側の面に回折\n格子を設け,この回折格子の回折機能によって,導光板である板状体に入射した光が照光面の側において均一にかつ高い輝度を発揮するようにしたものである。\nそして,照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたのは,本件明細書 の記載(前記1(2)イの(エ)(オ)(カ))によれば,本件発明においては,透明な板状体か らなる導光板の両面のうち照光の効果を生じさせるのとは反対の面(裏面)に,光 の入射角と臨界角をもとに適切に決められた間隔で,回折格子(刻線溝)が加工さ れており,これにより,導光板の一端面から裏面に向けて入射した光は,上記回折 格子によって導光板の表面(照光の効果を生じさせる面)に向かって回折され,導光板の表\面がこれに直交する高強度の出射光と導光板内に導かれる全反射光によって極めて明るく照らされるようにしたからであり,以上が本件発明における回折機 能の機序であるものと認められる。このような機序が本件発明の技術的思想を構\成していることからすれば,照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたこと,すなわち本件発明のうち板状 体の裏面に回折格子を設けるとの部分は,本件発明における本質的部分であるとい うべきである。 そして,被告製品が板状体の裏面に回折格子を設けるという部分を備えていない ことは,既に文言侵害との関係において検討したとおりであるから,結局,本件発 明と被告製品との相違部分は本質的部分であって,均等の第1要件を充足しないと いうべきである。
◆原審(平成28(ワ)4759)
では以下のように判断されていました。
以上からすると,本件発明が課題とするところは,いずれも本件特
許の出願時の従来技術によって,同様の解決原理によって解決されていたといえる。
・・・
刻線溝又はエンボス型のホログラムを用いた点にあるが,回折格子としては後者の方がむしろ通常であること(前記1(4)ウ(ア),(エ),(オ))からすると,本件発明の従来技術に対する貢献の程度は大きくないというべきである。
ウ 以上よりすれば,本件発明の本質的部分については,特許請求の範囲の
記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2019.07.22
平成30(行ケ)10152 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月11日 知的財産高等裁判所
本願意匠(別紙1)及び引用意匠(別紙2)の各形態,本願意匠と引用意 匠の共通点及び相違点に関する本件審決の認定(前記第2の2(2))に誤りが ないことは,当事者間に争いがない。
両意匠の意匠に係る物品は,電動歯ブラシの本体(把持部)であり,主な需 要者は,電動歯ブラシを使用する一般消費者である。そして,かかる需要者が, 電動歯ブラシを使用するときは,通常,シャフト部にブラシヘッドを装着した 電動歯ブラシの本体を手に取り,歯磨き粉を付けたブラシヘッドを口腔内に 入れてから本体の動作制御釦を押して始動した後,本体を把持しながら,ブラ シヘッドを歯に当てて歯磨きを行うことからすると,本体把持部の握りやす さや操作の容易さを重視し,本体把持部の全体形状に特に注目をするものと 認められる。 しかるところ,両意匠は,「全体は,隅丸長方形状の底部より,僅かに正面 側に偏心しながら,円状の上面部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の電 動歯ブラシ本体把持部と,該本体把持部上面に設けられた,該上面の略半径を 直径とする略円柱状の基台部とその上に配された縦長板状のシャフト(シャフ ト部)で構成をされている点」(共通点1)及び「シャフトについて,本体把\n持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し,正面視中央部に横断する段差が設 けられ,背面側には略縦長矩形の凹部が設けられている点」(共通点2)で共 通する。 そして,共通点1は,底面に対して僅かに正面側に偏心した本体把持部の全 体形状に係るものであって,本体把持部の握りやすさ及び操作の容易性に及ぼ す影響が大きいこと,共通点2は,本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに 傾倒したシャフト部の形状に係るものであって,本体把持部の偏心した形状と 相まって歯に当たるブラシヘッドの角度に影響を及ぼすことに照らすと,共通 点1及び共通点2は,これを見る需要者に対し,全体として,共通の美感を起 こさせるものと認められる。
他方で,両意匠は,相違点1(本願意匠は,本体把持部の正面に上端より全 長約3分の1の箇所と,約2分の1の箇所に僅かに凹部をなす略円状の電動歯 ブラシ動作制御用釦が縦に2つ配されているのに対して,引用意匠は,上端よ り全長約3分の1の箇所に1つ配されるものとなっている点),相違点2(本 願意匠は,電動歯ブラシ動作制御用釦の外形線が一重の円状であるのに対して, 引用意匠は,該動作制御用釦の外形線が二重の円状となっている点),相違点 3(環状細線の位置),相違点4(本体把持部の下部の形状及び切り替えの有 無)及び相違点5(シャフト部の基台部の形状)において相違するが,これら の相違点から受ける印象は,両意匠の上記共通点から受ける印象を凌駕するも のではない。 したがって,本願意匠と引用意匠は,これらの相違点を考慮しても,需要 者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認めら れるから,本願意匠は,引用意匠に類似するものと認められる。
(2)ア これに対し原告は,1)共通点1に係る「全体は,隅丸長方形状の底部よ り円状の上部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の本体把持部と,略 円柱状の基台部と略縦長板状のシャフトとを有する電動歯ブラシ本体」の 構成態様は特徴的な形状であるとはいえない,2)共通点1のうち,「本体 把持部が僅かに偏心していること」は,需要者に与える印象という観点か らは,従来から存在する上部にかけて側面視背面側をただ窄めただけの形 状と明確な区別のつくものではないため,特徴的な形状とはいえない,3) 共通点2に係る「シャフト部の背面側に略縦長形状の凹部が設けられてい る点」は,その部位があまりに小さく,背面に備えられていることと相ま って,需要者の注意をひく部分とはなり得ないため,特徴的な形状という ことはできないとして,本願意匠の基本的構成態様は,需要者である使用\n者の注意を強くひくものとはいえず,共通点1及び2に係る態様は,需要 者に共通の美感を起こさせるものとはいえない旨主張する。 しかしながら,上記1)の点は,共通点1のうち,一般的な電動歯ブラシ の本体が有する形状と共通する一部の形状のみを取り上げたものであり, 共通点1の有する全ての形状について言及したものとはいえない。 また,上記2)の点は,本体把持部の全体形状に特に着目する需要者(前 記(1))においては,本体把持部が僅かに偏心している本願意匠の形状と 本体把持部の底面に対して軸を垂直にしたまま上部にかけて側面視背面 側を窄めただけの形状とを容易に区別するものと認められる。 さらに,上記3)の点は,共通点2のうち,一部の形状のみを取り上げた ものであり,シャフトが本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し ている点及びシャフトの正面視中央部に横断する段差が設けられている 点を看過している。
以上のとおり,原告の上記主張は,共通点1及び共通点2の形状の一部 のみに着目したものであって,これらの共通点の全体が与える視覚的効果 を踏まえたものといえないから,採用することができない。
イ 次に,原告は,1)歯を磨くという電動歯ブラシの機能の観点からは,需要\n者が電動歯ブラシを操作する動作制御釦の位置,大きさ及び形態が最も強 く需要者の注意をひく部分であり,要部である,2)需要者は電動歯ブラシ を使用する際に必ず動作制御釦部を観察するから,動作制御釦部が,全体 と比較して僅かな範囲のものであるとしても,需要者に対し,強い印象を 与えること,釦が2つの場合は,それぞれの釦の機能を考慮しながら釦を\n操作するため,2つの釦を注視することとなり,釦が1つの場合と比べて, 釦の形態により注意が向けられることに照らすと,本願意匠の釦が縦に2 つ配されている態様(相違点1に係る本願意匠の態様)は,上の釦の径よ り,下の釦の径がやや小さく形成されているという点と相まって,需要者 の注意を強くひくものであり,釦が1つ配されている態様の引用意匠とは 異なる美感を起こさせるものであるとして,本願意匠の要部である動作制 御釦が需要者に与える印象は引用意匠とは大きく異なるから,両意匠は, 全体として類似しない旨主張する。 しかしながら,前記(1)認定の電動歯ブラシの通常の使用態様に照らすと, 需要者は,本体把持部の握りやすさや操作の容易さを重視し,本体把持部の 全体形状に特に注目をするものと認められ,動作制御釦の位置,大きさ及び 形態は,電動歯ブラシの操作時に需要者の一定の注意をひく部分であると しても,最も強く需要者の注意をひく部分であるとはいえない。 また,甲2(意匠登録第1478109号の意匠公報)記載の「電動歯ブ ラシ本体」の意匠(別紙3)及び甲3(意匠登録第1219080号の意匠 公報)記載の「電動歯ブラシ」の意匠(別紙4)によれば,電動歯ブラシに 動作制御釦を2つ配することは,本願の優先日前に,普通に行われていたも のと認められる。そして,本願意匠の2つの動作制御釦は,1つは,本体把 持部上端より全長約3分の1の箇所に配され,引用意匠の動作制御釦とそ の位置が共通し,他の1つは,上記動作制御釦の垂下にあたる本体把持部上 端より全長約2分の1の箇所に配され,特異な位置にあるとの印象を与え るものではない。
加えて,本体把持部の上部側に配された動作制御釦の直径より,その下部 に配された動作制御釦の直径が僅かに小さく形成されている2つの動作制 御釦を有する電動歯ブラシの本体把持部の形態は,本願の優先日前に公知 であったこと(乙1)に照らすと,本願意匠の動作制御釦が,2つ縦に配さ れ,僅かに凹部をなし,上の釦の径より,下の釦の径がやや小さく形成して いる点は,特徴的なものとはいえず,需要者の注意を特にひくものとはいえ ないから,本願意匠の動作制御釦と引用意匠の動作制御釦の構成態様の違\nいが需要者の視覚を通じて起こさせる両意匠の全体的な美感に影響するも のと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2019.07.22
平成30(ワ)16791 著作権に基づく差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和元年5月15日 東京地方裁判所
争点(1)(本件問題及び本件解説の著作物性の有無)について
(1) 証拠(甲4の1,5の1)によれば,本件問題のうち,国語Aの1は物語 文の,同2は論説文の読解問題であり,いずれも問1〜10から構成され,\n国語Bの1は物語文の,同2は説明文の読解問題であり,いずれも問1〜5 から構成されていることが認められる。\n また,証拠(甲4の2,5の2)によれば,本件解説には,解答部分,配 点部分,解説部分から構成され,解説部分には,設問ごとに,問題の出題意図,\n題材とされた文章のうち着目すべき箇所,当該箇所に係る文章の理解方法, 正解を導き出すための留意点等が記載されている。 他方,被告ライブ解説(甲1)は,本件問題について,同問題に係るテス トの終了後に,被告の担当者等がウェブ上の動画において口頭でその解説を するものであり,本件問題及び本件解説が画面上に表示されることはない。\n
(2) 著作権法12条は,「編集物…でその素材の選択又は配列によって創作性 を有するものは,著作物として保護する。」と規定するところ,被告は,本 件問題について,「どの部分を問題とするのか」,「何を問うのか」は問題 作成におけるアイデアにすぎないとして,本件問題は編集著作物に該当しな いと主張する。 しかし,国語の問題を作成する場合において,数多くの作品のうちから問 題の題材となる文章を選択した上で,当該文章から設問を作成するに当たっ ては,題材とされる文章のいずれの部分を取り上げ,どのような内容の設問 として構成し,その設問をどのような順序で配置するかについては,作問者\nが,問題作成に関する原告の基本方針,最新の入試動向等に基づき,様々な 選択肢の中から取捨選択し得るものであり,そこには作問者の個性や思想が 発揮されているということができる。本件問題についても,題材となる作品 の選択,題材とされた文章のうち設問に取り上げる文又は箇所の選択,設問 の内容,設問の配列・順序について,作問者の個性が発揮され,その素材の 選択又は配列に創作性があると認めることができる。 したがって,本件問題は編集著作物に該当する。
(3) 本件解説は,前記のとおり,本件問題の各設問について,問題の出題意図, 正解を導き出すための留意点等について説明するものであり,各設問につい て,一定程度の分量の記載がされているところ,その記載内容は,各設問の 解説としての性質上,表現の独自性は一定程度制約されるものの,同一の設\n問に対して,受験者に理解しやすいように上記の諸点を説明するための表現\n方法や説明の流れ等は様々であり,本件解説についても,受験者に理解しや すいように表現や説明の流れが工夫されるなどしており,そこには作成者の\n個性等が発揮されているということができる。 したがって,本件解説は創作性を有し,言語の著作物に該当するというべ きである。
2 争点(2)(複製又は翻案該当性)について
(1) 複製について
原告は,被告が本件問題及び本件解説の複製を自ら行っているか,仮に, 自ら複製行為を行っていないとしても,保護者又は生徒をいわば手足のよう に利用して複製をさせているのであるから,被告自身が複製を行ったと同視 し得ると主張する。 しかし,被告は,複数の原告学習塾の生徒から問題の原本を入手し解説を 行っている事実は認めるものの,問題を複製した事実は否認するところ,本 件においては,被告が自ら本件問題及び本件解説文を複製したと認めるに足 りる証拠はない。 また,被告が,指導者としての強い立場を利用し,保護者又は生徒に本件 問題等の複製を依頼し,あるいは,複製の費用を負担し,金銭や便宜を供与 するなどの働きかけをして保護者や生徒に本件問題等の複製を依頼したとの 事実を認めるに足りる証拠もない。そうすると,仮に,保護者又は生徒が本 件問題等の複製を行い,複製した本件問題の写しを被告に交付したとしても, そのことから直ちに被告自身が複製を行ったと同視することはできない。 したがって,被告が原告の有する複製権を侵害したとの主張は理由がない。
(2) 翻案について
ア 著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ, その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的な表\現に修正, 増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することによ\nり,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得す\nることのできる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁平成11年(受) 第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁 参照)。
イ 被告ライブ解説においては,前記1(1)のとおり,本件問題の全部又は一 部の画像を表示しておらず,また,口頭で本件問題の全部又は一部を読み\n上げるなどの行為もしていない。そうすると,被告ライブ解説は本件問題 の本質的な特徴の同一性を維持しているということはできず,被告ライブ 解説に接する者が本件問題の素材の選択又は配列に係る本質的な特徴を直 接感得することができるということはできない。 したがって,被告ライブ解説が本件問題を翻案したものであるとは認め られない。
ウ 本件解説に関し,原告は,被告ライブ解説と本件解説は同様の問題につ いて,同じ視点から解説したものであり,同じ目的の下,同じ解答に至る 考え方を説明したものであるから,その本質的な特徴は同一であると主張 する。 しかし,原告が翻案権侵害を主張する設問について,本件解説と被告ラ イブ解説の対応する記載を対比しても,表現が共通する部分はほとんどな\nい。例えば,国語Aの1の問5に関する本件解説と被告ライブ解説を比較 しても,共通する表現は「険のある」,「祐介」など,ごくわずかな部分に\nすぎず,被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持している ということはできない。本件解説の他の設問に係る部分についても,本件 解説と被告ライブ解説とで表現が共通する部分はほとんど存在せず,当該\n各設問に係る被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持して いるということはできない。 したがって,本件ライブ解説が本件解説を翻案したものであるとは認め られない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.07.22
平成30(ワ)10157 独占的通常実施権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月22日 東京地方裁判所
(1) 構成要件1Eは「前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は,0.5\nkg/cm2〜3.5kg/cm2の範囲であること」,同7Hは,「前記ノ ズルの噴射孔から前記溶出液が噴射されて前記ガラス基板の外面を0. 5kg/cm2〜3.5kg/cm2の範囲の圧力で衝撃する」という構\n成を含むものであり,いずれも,ノズルから噴射された溶出液がガラス 基板の外面を衝撃する際の圧力が「0.5kg/cm2〜3.5kg/c m2」の範囲内であることをその内容とするものである。
(2) 原告は,構成要件1E及び7Hの「圧力」の数値の意義について,1cm\n2当たりの平均の圧力ではなく,溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの 衝撃圧力を意味すると理解すべきであると主張する。 しかし,構成要件1E及び7Hの「圧力」の単位は「kg/cm2」であ り,これは,通常の意味としては,ある程度の面積を有する面に所定の時間 にわたり作用する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算したものと解 するのが自然である。 また,本件明細書等には,構成要件1E及び7Hの「圧力」の意義や測定\n方法に関する明確な定義は存在しないものの,段落【0034】には,「こ の際,各ノズル4の各噴射孔41と外面との距離(図3にdで示す)は重要 な要素である。距離dがあまり大きくなると,送液ポンプ54による送液圧 力をかなり高くしなければ,上記範囲内の圧力で外面を衝撃することができ なくなってしまい,実用的に難しくなる。」との記載が存在する。液滴の大 きさや衝撃力は距離により変化するものではないので,上記明細書の記載は, 上記各構成要件の「圧力」が単位面積当たりの作用力の大きさであることを\n示唆するものということができる。
(3) これに対し,原告は,本件明細書等の段落【0015】及び【0017】 における,ノズルから噴射された溶出液の衝撃により外面の材料が溶け出し, 溶出液が衝撃により流出していく旨の記載を根拠として,構成要件1E及び\n7Hの「圧力」は,溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの衝撃圧力を意 味すると主張する。しかし,上記記載は,構成要件1E及び7Hの「圧力」\nの測定について特定の方法によるべきことを含意するものではなく,同記載 をもって,同各構成要件の「圧力」が,ガラスを溶出液が衝撃するそのスポ\nットの衝撃圧力を意味すると解することはできない。
また,原告は,甲21の1〜3に依拠し,本件特許出願当時,本件特 許に近い技術分野においても,原告が主張するような意味で「圧力」と いう用語が用いられていたと主張する。しかし,甲21の1は,「気中ウ ォータージェットピーニング技術」であって,約1000MPaの非常 に高い衝撃圧力が生じるものであり,甲21の2及び3も,高速液体噴 流による洗浄・ピーニングに関する技術及び漁船等に付着した貝などを 除去するための高圧噴流ノズルに関する技術であって,本件特許のよう なガラスの基板の研磨に関する技術分野とは異なる技術分野であり,そ こで想定されている「圧力」の大きさも異なるというべきである。 むしろ,本件ノズルと同種のノズルを昭和30年代から製造している いけうち(乙4)においては,その測定に当たり,1cm×1cmの正 方形の圧力受領域を有する「受圧プレート」が使用されていると認めら れ(乙3),また,いけうちと同様に長年にわたりスプレーノズルを製造 している共立合金製作所においても,一定の面積の受圧部を使用してい ることが認められる(乙5参考資料1)。これによれば,本件特許出願当 時,ノズルから噴射された溶出液がガラス基板の外面を衝撃する際の圧 力の測定方法としては,一定面積を有する面に所定の時間にわたり作用 する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算することが標準的であ ったというべきである。
(4) 原告は,本件ノズルを製造したいけうちの作成したスプレーノズル流量線 図(甲8)などに基づき,被告NSCの用いる方法又は装置におけるフッ酸 の噴射圧力は約1.224kgf/cm2であるとした上で,ノズルからフ ッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラス基板に加わる衝撃の圧力は ほとんど変わらないので,被告方法は構成要件1E及び7Hを充足すると主\n張する。 しかし,証拠(乙1資料4〜6,乙2)によれば,本件ノズルは,ノズル 吐出口の直径は約3mm,吐出口の面積が約7mm2であり,ノズルの先端 とガラス基板との間には190mmの距離があり,薬液は65〜70°の噴 霧角度(噴角)に均等な流量分布で広がって円錐形に噴霧されるので(乙2 の1頁左上写真参照),ノズルから190mm離れたガラス基板上に噴霧さ れる領域は,ノズルの噴霧圧力が0.1〜0.2MPaの場合,直径約24 2〜約266mmの円形領域となり,その面積は約4万5973〜約5万5 543mm2であると認められる。 このように,本件ノズルは,65〜70°の噴霧角度に広がり均等な流量 分布で円錐形に噴霧されるものであり,液滴の分布は一様に広がりながらガ ラス基板の外面に到達するのであるから,その分薬液の単位面積当たりの圧 力は大幅に低減するというべきである。 そうすると,ノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラ ス基板に加わる衝撃の圧力がほとんど変わらないことを前提とし,被告方法 が構成要件1E及び7Hを充足するとの原告の主張は理由がない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.07.21
平成30(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所
(2) 以上を前提に,サポート要件の具備の有無について検討する。 本件発明の各特許請求の範囲は,いずれも,「正または負の誘電異方性を有する極 性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって」と記載されているから,いずれも, n型の液晶化合物に基づく液晶媒体を含んでいる。 ところが,前記(1)のとおり,本件明細書には,p型の液晶化合物が用いたディス プレイを前提として,しきい値電圧の低減をK1を減少させることにより実現する ことが記載されているのみである。本件明細書には,n型の液晶化合物が用いられ るディスプレイについて,K1を減少させることによってしきい値電圧を低減させ ることができるとの記載はなく,また,そのような技術常識があったとは認められ ないし,本件明細書の実施例にも,n型の液晶化合物は一切含まれていない。した がって,n型の液晶化合物については,当業者は,本件明細書から,発明の課題を 解決できるものと認識することはできないというべきである。以上のとおり,本件発明は,いずれも,発明の詳細な説明の記載により,発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲を超えているというべきである。
なお,原告は,甲54実験,甲59実験,甲90実験について主張する。 しかし,上記のとおり,本件明細書には,n型の液晶化合物を用いたディスプレ イにおいてK1を減少させることによって,しきい値電圧を低減できることは記載 されておらず,また,上記実験結果が,本件特許の出願日当時,当事者の技術常識 であったとも認められないから,上記実験結果を参照して,n型液晶化合物を用い たディスプレイにおいて,K1を減少させることによって,しきい値電圧を低減でき ることをサポート要件の判断に当たって考慮することはできないというべきである。 また,その他,原告が主張するところによっても,サポート要件に関する上記判
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.07.21
平成31(ネ)10004 販売差止め及び損害賠償等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 本件登録意匠の要部の認定について
(ア) 控訴人は,本件登録意匠は,本件登録意匠美感を有しており,構成\nイウエの各構成は,それぞれが関連しあって一体となり一つの強い意匠的効果を発\n揮しているところ,その製品を購入する際に需要者が最も重要視する部分は,上記 一体となって発揮される美感であり,先端部のビーズではない旨主張する。 しかし,本件登録意匠は,アイマスクのマスク部の両脇より延びる耳かけストラ ップ部分の部分意匠であり,ストラップ部において,中間部及び先端部の2箇所に ビーズが現れることは,需要者の印象に大きく残るものであると認められる。これ に,公知意匠(乙10〜13)も考慮すると,原判決(第3,1,(3),ウ)が認 定するとおり,「耳かけストラップの中間部及び先端部の二箇所にビーズが現れる 形態」(構成イ)を含む本件登録意匠の構\成全体が本件登録意匠の要部であると認 めるのが相当であり,控訴人の上記主張を採用することはできない。
(イ) 控訴人は,本件意見書は,拒絶理由通知の引用意匠(乙13)と本 件登録意匠との間に実際に存在している相違点を指摘しているにすぎず,要部であ ると主張したものではないし,本件登録意匠美感を凌駕するほどに強い美感を発揮 していると主張したものではない旨主張する。 しかし,本件意見書が本件登録意匠と引用意匠との相違点(耳掛けストラップの 先端部にもビーズが存する形態)が類否判断の上で重要であることを指摘している と認められることは,原判決(第3,1,(3),エ)が判示するとおりであって, 本件登録意匠の要部を認定するに当たり考慮することができるというべきである。 したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 公知意匠の認定について 控訴人は,乙11〜13が公知意匠としての適格性を欠いており,また,乙10 〜13の要部が本件登録意匠とは異なる旨主張する。 しかし,乙11〜13を公知意匠とし,これも参酌して本件登録意匠の要部を認 定することができることについては,原判決(第3,1,(3),イ及びウ)が判示 するとおりである。 乙10については,乙10の意匠が本件登録意匠の構成要件イウエの各構\成は有 していないことは認められるが,ストラップの先端部にビーズ形状が現われている アイマスクの意匠であるから,これをアイマスクの部分意匠(ストラップ部分につ いての意匠)である本件登録意匠の公知意匠とし,これを参酌して本件登録意匠の 要部を認定することができるというべきである。 また,乙11〜13の物品が本件登録意匠の構成要件イウエの構\成そのものを備 えていないとしても,「アイマスクの左右端の上部又は下部から伸びた紐が左右端 (左右同順)の下部又は上部(上下同順)に到達し,上記紐の中間部の一箇所に物 体が設けられ,上記中間部の物体は,上位紐を束ねており,移動可能である態様」\nを備えているから,これをアイマスクの部分意匠(ストラップ部分についての意匠) である本件登録意匠の公知意匠とし,これを参酌して本件登録意匠の要部を認定す ることができるというべきである。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 本件登録意匠とイ号意匠の美感の類似性について 控訴人は,両意匠の一部の差異は,共通点の有する美感を陵駕しておらず,全体 としての美感を共通にしているから,両意匠は類似していると主張する。 しかし,両意匠が類似していないことは,原判決(第3,1,(4))が判示する とおりである。 控訴人は,本件登録意匠のデザインからビーズ一つを削除する改変は,ありふれ た改変であると主張するが,そうであるとしても,両意匠が類似していることには ならない。
(2) 不正競争行為該当性について
ア 商品等表示の判断枠組みについて\n
控訴人は,原判決が,商品の形態自体が出所を表示する二次的意味を有し,不正\n競争防止法2条1項1号及び2号にいう「商品等表示」に該当するための要件の一\nつとして,特別顕著性という要件を考慮したことが,明文のない要件のハードルを 過剰に高いものにしたと主張し,顕著性の程度の判断には,類似品が販売されてい たか否かだけでなく当該類似品が一般に出回っていることを広く需要者一般が通常 認識する態様であったのかどうかも検討すべきであると主張する。 商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有する\nものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至\nる場合があるため,このような商品については,不正競争防止法により,出所表示\n機能が保護されるものであって,そのためには,原判決(第3,2,(1))が判示 するとおり,特別顕著性と周知性が必要であると解される。そして,特別顕著性の 判断に当たっては,当該商品の類似品が一般に出回っているか否かも考慮すること にはなるものの,当該商品の形態に客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴が あるか否かを判断するのであるから,必ずしも類似品が一般に出回っていることを 広く需要者一般が認識する必要はないというべきである。
イ 控訴人の商品形態と類似商品があること
(ア) 控訴人は,乙2,3,26及び27の商品は,控訴人及び控訴人の 代理店など当業者においても被控訴人ら主張を受けて初めて認識するに至ったほど に人知れず発売されていた商品であり,あえてもろもろの検索条件で根気強く検索 を試みなければヒットしないような商品ばかりであると主張する。 しかし,乙3及び27の商品は,日経流通新聞に掲載されたものであることが認 められるし,乙2の商品は,パンジーストアと題するウェブサイトに,平成23年 9月6日付けニュースとして新規発売が紹介されており,乙26の商品も,株式会 社山善のウェブサイトに平成24年10月23日付けで新製品として紹介されてい るものであるから,控訴人及び控訴人の代理店などの当業者が被控訴人ら主張を受 けて初めて認識するに至ったほどに人知れず発売されていた商品であるとは認めら れない。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできず,これらの商品の 形態を本件原告商品の形態の特別顕著性の判断に当たって考慮することができると いうべきである。
(イ) また,証拠(乙5,29)及び弁論の全趣旨によると,乙5及び2 9は,いずれも平成30年の発売情報であることが認められる。 しかし,証拠(乙2,3,4,26,27)によると,既に,平成23年〜同2 4年頃には本件特徴又はこれと極めて類似した特徴を有する複数の商品が市販され ていることが認められるところ,平成30年頃にも,本件特徴又はこれと極めて類 似した特徴を有する複数の商品が市販されているという,乙5及び29によって認 められる事実は,平成23年,同24年頃から平成30年頃までの間,本件特徴又 はこれと類似する特徴を有する商品が継続して多数販売されていたことを裏付ける ものとなる。乙5及び29は,上記のような意味において,本件原告商品の形態が 特別顕著性を有していたかどうかの判断に用いることができるものである。 なお,仮に,乙4について,株式会社ポーラとの間で控訴人が主張するようなや り取りがあったとしても,乙4の商品が発売された事実は認められるのであって, 本件原告商品の形態が特別顕著性を有していないとの原判決(第3,2,(2),ウ) の判断を左右するものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 意匠その他
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2019.07.21
平成30(行ケ)10179 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年7月11日 知的財産高等裁判所
前記1によると,被告のカタログオーダーギフト事業においては,「受取手」 に被告が発行したギフトカタログが送られ,「受取手」は被告に同ギフトカタログに 掲載された各種の商品の中から選んで商品を注文し,被告から商品を受け取り,そ の商品の代金は,「贈り主」から被告に支払われるのであるから,被告は,「贈り主」 との間では,「贈り主」の費用負担で,「受取手」が注文した商品を「受取手」に譲 渡することを約し,「受取手」に対しては,「受取手」から注文を受けた商品を引き 渡していると認められる。したがって,被告は,ギフトカタログに掲載された商品 について,業として,ギフトカタログを利用して,一般の消費者に対し,贈答商品 の譲渡を行っているものと認められるから,被告は,小売業者であると認められ, 小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を行っているものと認められ る。そして,上記便益の提供には,本件使用カタログが用いられているから,本件 使用カタログは,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」と認 められる。
(2)ア これに対し,原告は,被告の事業は,「贈り主」から「受取手」への贈 答の媒介又は代行であり,これによって「ギフトを通じて人と人とを結びつけ」る という役務を提供している,「受取手」に対する商品の配送業務は,ギフトカタログ の販売に付随するものであって,独立した商取引の対象となってないなどと主張す る。 しかし,被告,「贈り主」及び「受取手」の間で行われる一連の取引の流れからす ると,被告は,「受取手」に対し,「受取手」が被告に注文した商品を「贈り主」の 費用負担のもとに譲渡しているということができるのであって,これは,贈答の媒 介又は代行をしているということはできず,また,独立した商取引であると認めら れ,「受取手」に対する商品の配送も単なる付随的なものということはできないから, 原告の上記主張を採用することはできない。 なお,被告がプレスリリースにおいて,被告の事業を「ギフトを通し人と人を結 びつけ」ると記載している(甲5)としても,被告の事業についての紹介(宣伝) の文言であって,上記判断を左右するものではない。
イ 原告は,被告も,被告の事業において需要者が「贈り主」であることを 認めていると主張する。 しかし,被告は,被告の事業について,前記「第4 被告の主張」のとおり主張 しており,被告の事業の需要者は「贈り主」だけでなく「受取手」も需要者である と主張している(被告が「贈り主」が需要者であると主張したからといって,「受取 手」も需要者であると主張することが妨げられる理由はない。)。そして,上記(1)の とおり,被告の事業を全体的にみると,被告は,需要者である「受取手」に対し, 「受取手」が被告に注文した商品を「贈り主」の費用負担のもとに譲渡したものと 認められる。
ウ 上記(1)のとおり,被告の事業は,被告が「受取手」に対し,「受取手」 が注文した商品を譲渡しているということができるのであって,この注文が「贈り 主」の費用負担のもとにギフトカタログを利用して行われ,また,ギフトカタログ が二次流通することがあるとしても,上記のとおり小売の業務における便益の提供 が行われているということができるものである。 また,被告の事業が資金決済に関する法律3条1項2号の前払式支払手段の発行 に当たるとしても,上記のとおり,小売の業務における便益の提供が行われている ということができるのであり,前払式支払手段の発行がされているかどうかは上記 判断を左右するものではない。
(3)前記1によると,本件要証期間内である平成29年に発行された被告の本 件使用カタログには,本件使用カタログ標章が表示されているところ,その中のや\nやデザイン化した「MUSUBI」の文字(本件使用商標)は,本件商標と社会通 念上同一と認められる。そして,前記1によると,本件使用カタログには本件使用 商品1及び2が掲載され,被告は,同カタログに掲載された本件使用商品1及び2 を,それぞれ同年12月2日又は同年11月27日までに,「受取手」に送付したこ とが認められるところ,本件使用商品1は商品「家具」の範ちゅうに属する商品で あり,本件使用商品2は商品「台所用品」の範ちゅうに属する商品であることが認 められる。
そうすると,被告は,本件要証期間内に日本国内において,本件審判の請求に係 る指定役務中「家具・金庫及び宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客 に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供」について,「役務の提供に当たりその提供を 受ける者の利用に供する物」に当たる本件使用カタログに本件商標と社会通念上同 一と認められる本件使用商標を付し,これを用いて小売の業務において行われる顧 客に対する便益の提供という役務を提供したと認めることができる。この行為は, 商標法2条3項3号「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に 標章を付する行為」及び同項4号「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用 に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」に該当するので,被 告は,本件要証期間内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定役務につ いて本件商標の使用をしていることを証明したと認められる。 したがって,原告の請求は理由がないことになる。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2019.07.17
平成29(ワ)31572 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和元年6月18日 東京地方裁判所
判決文の最後にバックなど形状を示す写真があります。
原告商品は, で述べたとおり,わずかな例外を除いて本件形態 1´を備え,メッシュ生地又は柔らかな織物生地に,相当多数の硬質な三角 形のピースが,2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて敷き詰めるよ うに配置されることにより,中に入れる荷物の形状に応じてピースに覆われ た表面が基本的にピースの形を保った状態で様々な角度に折れ曲がり,立体\n的で変化のある形状を作り出す。一般的な女性用の鞄等の表面は,布製の鞄\nのように中に入れる荷物に応じてなめらかに形を変えるか,あるいは硬い革 製の鞄のように中に入れる荷物に応じてほとんど形が変わらないことから すれば,原告商品の形態は,従来の女性用の鞄等の形態とは明らかに異なる 特徴を有していたといえる。このことは,新聞や雑誌といったメディアにおいて「画期的なデザインのバッグ」(前記(1)カウ),「シンプルなピースが集 まって 自在に変化するユニークな形」前記(1)カカ),「三角形のパーツをつなぎあわせたフューチャリスティックなデザイン(前記(1)カテ),「特徴 がはっきりしているので販売企業がイッセイミヤケだとすぐ判別でき」る 前記(1)カセ)などと,そのデザインの独特さ,斬新さが取り上げられ,平 成19年秋にはデザイン性と機能性を併せ持ったアイテムだけを厳選して\n掲載するニューヨーク近代美術館のデザインショップ・カタログの表紙に採\n用されたことからも裏付けられ,原告商品の形態は,これに接する需要者に 対し,強い印象を与えるものであったといえる。 したがって,原告商品の本件形態1´は,客観的に他の同種商品とは異な る顕著な特徴を有していたといえ,特別顕著性が認められる。
・・・
原告商品1ないし6は,ショルダーバッグ,携帯用化粧道具入れ,リュック サック及びトートバッグであり,いずれも物品を持ち運ぶという実用に供され る目的で同一の製品が多数製作されたものであると認められる。 著作権法は,著作権の対象である著作物の意義について,「思想又は感情を 創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するも\nのをいう」(同法2条1項1号)と規定しているところ,その定義や著作権法の 目的(同法1条)等に照らし,実用目的で工業的に製作された製品について, その製品を実用目的で使用するためのものといえる特徴から離れ,その特徴と は別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できないもの は,「思想又は感情を創作的に表現した美術の著作物」ということはできず著\n作物として保護されないが,上記特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性 を備えている部分を把握できる場合には,美術の著作物として保護される場合 があると解される。
(3) これを原告商品1ないし6についてみるに, のとおり,原告商品1な いし6は,物品を持ち運ぶという実用に供されることが想定されて多数製作さ れたものである。
そして,原告らが美的鑑賞の対象となる美的特性を備える部分と主張する原 告商品1ないし6の本件形態1は,鞄の表面に一定程度の硬質な質感を有する\n三角形のピースが2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて敷き詰める ように配置され,これが中に入れる荷物の形状に応じてピースの境界部分が折 れ曲がることにより様々な角度がつき,荷物に合わせて鞄の外観が立体的に変 形するという特徴を有するものである。ここで,中に入れる荷物に応じて外形 が立体的に変形すること自体は物品を持ち運ぶという鞄としての実用目的に 応じた構成そのものといえるものであるところ,原告商品における荷物の形状\nに応じてピースの境界部分が折れ曲がることによってさまざまな角度が付き, 鞄の外観が変形する程度に照らせば,機能的にはその変化等は物品を持ち運ぶ\nために鞄が変形しているといえる範囲の変化であるといえる。上記の特徴は, 著作物性を判断するに当たっては,実用目的で使用するためのものといえる特 徴の範囲内というべきものであり,原告商品において,実用目的で使用するた めの特徴から離れ,その特徴とは別に美的鑑賞の対象となり得る美的構成を備\nえた部分を把握することはできないとするのが相当である。 したがって,原告商品1ないし6は美術の著作物又はそれと客観的に同一な ものとみることができず,著作物性は認められないから,その余の点について 判断するまでもなく,原告らの著作権侵害に基づく請求には理由がない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2019.07.12
平成31(ネ)10001等 特許権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月26日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(2)本件において乙17の1及び乙18の1を主引例として無効を主張でき るか。(当審における追加主張)
ア 特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は,同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ, その趣旨は,無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると,侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い,審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には,同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは,特段 の事情がない限り,訴訟上の信義則に反するものであり,民事訴訟法2 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 控訴人は,無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれ ている立場の質的相違等から,特許法167条の趣旨は,侵害訴訟に適 用されないと主張するが,上記説示したところに照らし採用できない。 また,控訴人は,第三者の無効審判請求により特許権が無効とされるべ き場合にまで侵害訴訟において無効の抗弁を主張できないのは不当であ るという趣旨の主張もしているが,控訴人自身は,無効審判手続におい て無効主張をする機会を十分に与えられ,かつ無効不成立審判に対して\n審決取消訴訟を提起する機会も与えられていたのであるから,審決取消 訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させた結果,もはや当該審判手 続において主張していた特許の無効事由を主張できないこととなったと しても,その結果を不当ということはできない。
イ 認定事実
(ア) 本件無効審判請求1において,控訴人は,本件発明1は,1)乙1 7の1に記載された発明(乙17発明)に,乙18の1に記載された 発明(乙18発明),乙19又は23,42ないし45,33,34 に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて,当業者が 容易に発明することができたものである,2)乙18発明に,乙17発 明,乙19又は23,42ないし45,33,34に記載された技術 事項及び従来周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明するこ とができたものである,とそれぞれ主張した。(甲14)(本件審決 1における甲1,2,3,7ないし13は,順に本件訴訟における乙 17,18,19,23,42ないし45,33,34に対応する。) このほか,控訴人は,乙20ないし22も証拠として提出していた。
(イ) しかしながら,本件審決1は,主引例である乙17の1及び乙1 8の1には,ローラの直交2方向への移動(及び移動に伴う肌の摘み 上げと押圧)という技術思想が存在せず,また,控訴人が提出した各 種証拠から認められる技術事項及び周知技術を考慮しても,この点を 容易に想到することができるとはいえないとして,上記無効理由のい ずれも認めず,本件発明1は,特許法29条2項の規定により特許を 受けることができないものとはいえないと判断した。(甲14)
ウ 乙17の1又は乙18の1を主引例とする進歩性欠如の無効主張の可 否
本件訴訟において,控訴人は,乙17の1,乙18の1をそれぞれ主 引例とした上,これに,乙17発明(乙18の1を主引例とする場合) 又は乙18発明(乙17の1を主引例とする場合),及び乙19ないし 23,33ないし35,42ないし45,101及び104に記載の副 引例又は周知技術を併せれば,本件発明1は容易想到であると主張して いる。 しかしながら,乙17の1及び乙18の1は,本件審判請求1におい ても主引例とされていたもの,乙19,23,33,34及び42ない し45は,副引例又は周知技術を認定する証拠として提出されていたも のであり,乙20ないし22も,明示的には主張されていないものの, 周知技術を認定する証拠等として提出されていたものと認められるから, 結局,本件審決1と本件訴訟における控訴人の主張立証との間では,主 引例は全く共通である上,副引例又は周知技術,証拠もほとんど共通し, 両者で共通していないのは,副引例ないし周知技術の証拠である乙35, 101及び104のみである(しかも,乙101は,乙35から分割出 願された発明であるから,両者は極めて類似している。)ことになる。 そして,乙35,101及び104は,いずれも4個のローラの直交2 方向への移動ということはおよそ想定していないものであるから,本件 審決1が認定した本件発明1と乙17発明及び乙18発明との相違点を 埋めるものであるとはおよそいい難いものである。
このように,本件訴訟独自の証拠である乙35,101及び104は 価値の乏しいものであるから,結局,本件訴訟における控訴人の主張は, 本件審判1と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」(特許法167条) に基づくものと評価されるべきものである。 そして,本件審決1は,控訴人による審決取消訴訟が提起されること なく確定している上,本件において,前記アの特段の事情も窺われない。 したがって,本件訴訟において,控訴人が,乙17の1又は乙18の 1を主引例とする進歩性欠如の無効を主張することは,信義則に反し, 許されないといわざるを得ない。
(3) 結論 よって,控訴人の乙17の1又は乙18の1を主引例とする無効の抗弁 の主張はいずれも許されず,乙104発明を主引例とする無効の抗弁には 理由がない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.07.12
平成31(ネ)10009 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
前記第2の1の前提事実と一件記録によれば,本件訴訟の経過等として, 次の事実が認められる。
(ア) 控訴人日進は,平成26年12月頃から,調剤薬局等に対し,控訴 人日進と控訴人セイエーが共同開発した被告製品を販売するようになっ た。 控訴人日進,控訴人OHU及び控訴人セイエーの3者間には,被告製 品に関し,控訴人日進が控訴人OHUに対して被告製品を発注し,この 発注を受けた控訴人OHUが控訴人セイエーに対して被告製品の製造を 委託し,この委託を受けた控訴人セイエーが被告製品を製造して,控訴 人日進に供給し,これにより,控訴人セイエーは控訴人OHUに対し, 控訴人OHUは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継 続的な取引関係があった。
(イ) 被控訴人は,平成28年7月4日,控訴人らによる被告製品の製造, 販売が被控訴人の有する本件特許権の間接侵害等に当たる旨主張して, 控訴人らに対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の連帯 支払を求める本件訴訟を原審に提起した。 控訴人らは,同年12月8日の原審第2回弁論準備手続期日において, 準備書面(2)(無効論)に基づき,明確性要件違反,乙22を主引用例と する新規性欠如,乙23を主引用例とする新規性欠如の無効理由による 無効の抗弁を主張し,平成29年3月16日の原審第4回弁論準備手続 期日において,準備書面(5)(無効論)に基づき,上記無効理由に加えて, 乙22を主引用例とする進歩性欠如,乙23を主引用例とする進歩性欠 如,補正要件違反,サポート要件違反,明確性要件違反(「2つ折りさ れたシート」に係るもの)の無効理由による無効の抗弁を主張した。 その後,控訴人らは,同年6月30日の原審第6回弁論準備手続期日 において,準備書面(7)(無効論)に基づき,新たに乙23(乙23’発 明)を主引用例,乙22(乙22発明)を副引用例とする進歩性欠如の 無効理由による無効の抗弁を主張した。
(ウ) 控訴人日進は,平成29年7月10日,本件特許の設定登録時の請 求項1及び2に係る発明についての特許を無効にすることを求める別件 無効審判を請求した。控訴人日進が別件無効審判で主張した無効理由は, 明確性要件違反(「無効理由1」),「審判甲1」(乙22)を主引用 例とする新規性欠如(「無効理由2」),「審判甲1」(乙22)を主 引用例とし,「審判甲7」(乙49)に記載された事項(「甲7事項」) を副引用例とする進歩性欠如(「無効理由3」),「審判甲2」(乙2 3)を主引用例とし,「審判甲1」(乙22)に記載された事項(「甲 1事項」)等を副引用例とする進歩性欠如(「無効理由4」),「審判 甲2」(乙23)を主引用例とし,「甲7事項」等を副引用例とする進 歩性欠如(「無効理由5」)である。上記「無効理由3」は,乙22を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由と,上記「無効理 由4」及び「無効理由5」は,乙23を主引用例とする本件訂正発明の 進歩性欠如による無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものである。
被控訴人は,同年10月6日,別件無効審判において,本件訂正をし た後,同月19日の原審第9回弁論準備手続期日において,第7準備書 面に基づき,本件訂正と同一内容の訂正に係る訂正の再抗弁の主張をし た。また,控訴人らは,上記弁論準備手続期日において,別件無効審判 の審判請求書(乙46)を書証として提出した。 控訴人らは,同年12月11日の原審第10回弁論準備手続期日にお いて,準備書面(9)に基づき,被控訴人の訂正の再抗弁に対する反論をし た。
原審の受命裁判官は,平成30年1月29日の原審第11回弁論準備 手続期日において,本件の侵害論の審理を終了し,損害論の審理を進め ると述べた。
控訴人らは,同年3月12日の原審第12回弁論準備手続期日におい て,別件無効審判に係る被控訴人作成の同年2月2日付け「口頭審理陳 述要領書(2)」(乙56)を書証として提出した。
(エ) 特許庁は,平成30年6月26日,本件訂正を認めた上で,控訴人 日進主張の「無効理由1」ないし「無効理由5」により本件特許を無効 とすることはできないとして,別件無効審判の請求は成り立たないとの 別件審決をした。その後,控訴人日進は,出訴期間内に別件審決に対す る審決取消訴訟を提起しなかったため,別件審決は,確定し,同年8月 28日,その旨の確定登録が経由された。 原審は,同月24日,原審第2回口頭弁論期日において,口頭弁論を 終結した後,同年12月18日,被控訴人の請求を一部認容する原判決 を言い渡した。原判決は,控訴人ら主張の無効の抗弁はいずれも理由が ないものと判断した。
(オ) 控訴人は,平成30年12月28日,本件控訴を提起した。 その後,控訴人は,平成31年2月15日付け控訴理由書において, 原判決には,乙22を主引用例とする進歩性欠如,乙23を主引用例と する進歩性欠如,明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由の判 断に誤りがあることを主張するとともに,新たに本件出願に分割要件違 反があることを前提とした乙60を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由を主張した。 当審は,令和元年5月16日の本件第1回口頭弁論期日において,口 頭弁論を終結した。
イ 特許法167条は,特許無効審判の審決が確定したときは,当事者及び 参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができないと規定している。この規定の趣旨は,先の審判の当事者及び参 加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず,審決が 確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができ るとすることは不合理であるため,同一の当事者及び参加人による再度の 無効審判請求を制限することにより,紛争の蒸し返しを防止し,紛争の一 回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し 返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は,無効審判手続においてのみ妥 当するものではなく,侵害訴訟の被告が同法104条の3第1項に基づく 無効の抗弁を主張するのと併せて,無効の抗弁と同一の無効理由による無 効審判請求をし,特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のい わゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきで ある。 そうすると,侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに,当該無 効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請 求をした場合において,当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定し たときは,上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは, 訴訟上の信義則に反するものであり,民事訴訟法2条の趣旨に照らし許さ れないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに,前記アの認定事実によれば,1)控訴人らは, 本件訴訟の原審において,本件特許について,明確性要件違反,サポート 要件違反,乙22を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如,乙23を 主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如等の無効理由による無効の抗弁 を主張したこと,2)控訴人らのうち,控訴人日進のみが本件特許を無効に することを求める別件無効審判を請求し,本件特許の設定登録時の請求項 1及び2に係る発明の無効理由として「無効理由1」ないし「無効理由5」 を主張し,被控訴人は別件無効審判手続において本件訂正をしたところ, 特許庁は,本件訂正を認めた上で,控訴人日進主張の「無効理由1」ない し「無効理由5」により本件特許を無効とすることはできないとして,別 件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決をしたこと,3)控訴人日進 が別件審決に対する審決取消訴訟を提起しなかったため,別件審決は,原 判決の言渡し前に確定したことが認められる。 加えて,控訴人日進が原審及び当審において主張する乙22を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は,確定した別件審決で排斥 された「無効理由3」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくもの と認められるから(前記ア(ウ)),被控訴人日進が当審において乙22を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を 主張することは,訴訟上の信義則に反するものであり,民事訴訟法2条の 趣旨に照らし許されないと解すべきである。
ウ 次に,控訴人セイエー及び控訴人OHUについて検討するに,1)控訴人 セイエー及び控訴人OHUは,別件無効審判の請求人又は参加人のいずれ でもないが,控訴人日進,控訴人OHU及び控訴人セイエーの3者間には, 被告製品に関し,控訴人セイエーは控訴人OHUに対し,控訴人OHUは 控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係が あり,本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には,被控訴人の控訴 人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので,別件無効審判 に関する利害は,控訴人ら3者間で一致していること,2)控訴人セイエー 及び控訴人OHUは,原審において,控訴人日進の主張する無効の抗弁と 同一の無効の抗弁を主張し,また,控訴人日進とともに,別件無効審判の 審判請求書(乙46)及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」(乙 56)を書証として提出していることからすると,控訴人セイエー及び控 訴人OHUは,別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し,別件\n無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認 められること,上記1)及び2)の事実関係の下においては,控訴人セイエー 及び控訴人OHUは,別件無効審判の請求人の控訴人日進と同視し得る立 場にあるものと認めるのが相当であるから,確定した別件審決で排斥され た「無効理由3」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙22を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の 主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人OHUに認めることは,紛争 の蒸し返しができるとすることにほかならないというべきである。 したがって,控訴人セイエー及び控訴人OHUにおいても,控訴人日進 と同様に,当審において乙22を主引用例とする進歩性欠如の無効理由に よる無効の抗弁を主張することは,訴訟上の信義則に反するものであり, 民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないと解すべきである。 エ 以上によれば,被控訴人の前記主張は理由があるから,その余の点につ いて判断するまでもなく,乙22を主引用例とする本件訂正発明の進歩性 欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
(6) 争点(4)カ(乙23を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理 由の有無)について
被控訴人は,控訴人ら主張の乙23を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は,別件無効審判における「無効理由4」及び「無効理由5」と実質的に 同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから,別件無効審判の請求人 である控訴人日進並びに控訴人日進と密接な取引関係にある控訴人セイエ ー及び控訴人OHUの3者が,当審において,上記無効理由による無効の抗 弁を主張することは,訴訟上の信義則に反し,許されない旨主張する。 そこで検討するに,控訴人らが原審及び当審において主張する乙23を主 引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は,前記(5)ア(ウ)認定 のとおり,控訴人日進及び被控訴人間の確定した別件審決で排斥された「無 効理由4」及び「無効理由5」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものと認められる。 そうすると,前記(5)ウ及びエで説示したのと同様の理由により,控訴人 らが当審において乙23を主引用例とする進歩性欠如の無効理由による無 効の抗弁を主張することは,訴訟上の信義則に反するものであり,民事訴訟 法2条の趣旨に照らし許されないと解すべきであるから,被控訴人の上記主 張は理由がある。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,乙23を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 間接侵害
>> ピックアップ対象
2019.07.12
平成30年(ワ)第466号 著作権に基づく差止等請求事件 令和元年7月11日 奈良地方裁判所
著作権法は,著作権の対象である著作物の定義について「思想又は感情を 創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属する\nものをいう。」(同法2条1項1号)と規定しており,作品等に思想又は感情 が創作的に表現されている場合には,当該作品等は著作物に該当するものと\nして同法による保護の対象となる一方,思想,感情若しくはアイディアなど 表現それ自体ではないもの又は表\現上の創作性がないものは,著作物に該当 せず,同法による保護の対象とはならないと解される。 また,アイディアが決まればそれを実現するための方法の選択肢が限られ る場合,そのような限られた方法に同法上の保護を与えるとアイディアの独 占を招くこととなるから,この点については創作性が認められず,同法上の 保護の対象とはならないと解される。
(2)そこで,原告作品の基本的な特徴に着目すると,1)公衆電話ボックス様の 造形物を水槽に仕立て,その内部に公衆電話機を設置した状態で金魚を泳が せていること,2)金魚の生育環境を維持するために,公衆電話機の受話器部 分を利用して気泡を出す仕組みであることが特徴として挙げることができる。 このうち,1)については,確かに公衆電話ボックスという日常的なものに, その内部で金魚が泳ぐ、という非日常的な風景を織り込むという原告の発想自 体は斬新で独創的なものではあるが,これ自体はアイディアにほかならず, 表現それ自体ではないから,著作権法上保護の対象とはならない。\nまた,2)についても,多数の金魚を公衆電話ボックスの大きさ及び形状の 造作物内で泳がせるというアイディアを実現するには,水中に空気を注入す ることが必須となることは明らかであるところ,公衆電話ボックス内に通常 存在する物から気泡を発生させようとすれば,もともと穴が開いている受話 器から発生させるのが合理的かつ自然な発想である。すなわち,アイディア が決まればそれを実現するための方法の選択肢が限られることとなるから, この点について創作性を認めることはできない。 そうすると,上記1),2)の特徴について,著作物性を認めることはできな いというべきである。
(3)他方,原告作品について,公衆電話ボックス様の造作物の色・形状,内部に 設置された公衆電話機の種類・色・配置等の具体的な表現においては,作者\n独自の思想又は感情が表現されているということができ,創作性を認めるこ\nとができるから,著作物に当たるものと認めることができる。
2 争点2(被告作品による原告作品の著作権侵害の有無)について
(1)被告作品と原告作品の対比
被告作品と原告作品を対比すると,次の点を指摘することができる(甲7, 22,25,26,51の1.2)。
ア 公衆電話ボックス様の造作物
原告作品と被告作品は,いずれも我が国で見られる一般的な公衆電話ボ ックスを模した,垂直方向に長い直方体で,側面の4面がガラス張りの造 作物内部に水を満たし,その中に金魚を泳がせている。 しかしながら,原告作品は屋根部分が黄緑色様であるのに対し,被告作 品は屋根部分が赤色である。また,被告作品は実際に使用されていた公衆 電話ボックスの部材を利用しているのに対し,原告作品はこれを使用せず, アルミサッシや鉄枠等を組み合わせて制作されている。 イ造作物内部に設置された公衆電話機 原告作品と被告作品は,いずれも上記造作物内部に棚板を二枚設置し, 上段に公衆電話機が設置されている。 しかしながら,原告作品の公衆電話機は黄緑色様であるのに対し,被告 作品の公衆電話機は灰色であり,公衆電話機のタイプも異なっている。ま た,棚板について,原告作品は水色で,形は二段とも正方形であるのに対 し,被告作品は銀色で,下段の形は三角形である。
ウ 受話器部分
原告作品と被告作品は,いずれも受話器がハンガー部分又は本体から外 された状態で水中に浮かんでおり,受話器の受話部分から気泡が発生して いる。
(2)検討
ア 著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであり,既存\nの著作物に依拠して作成,創作された著作物が,思想,感情若しくはアイ ディア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表\現上の創作 性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合に は,著作物の複製には当たらないものと解される。
イ 前記1で判示したところによれば,原告が同一性を主張する点(前記第 2の3(2)ア(ア))は著作権法上の保護の及ばないアイディアに対する主張で あるから,原告の同一性に関する上記主張はそもそも理由がない。 なお,事案に鑑み,具体的表現内容について原告作品と被告作品との間\nに同一性が認められるか否かについて検討するに,前記(1)で指摘したとお り,原告作品と被告作品は,1)造作物内部に二段の棚板が設置され,その 上段に公衆電話機が設置されている点,2)同受話器が水中に浮かんでいる 点は共通している。しかしながら,1)については,我が国の公衆電話ボッ クスでは,上段に公衆電話機,下段に電話帳等を据え置くため,二段の棚 板が設置されているのが一般的であり,二段の棚板を設置してその上段に 公衆電話機を設置するという表現は,公衆電話ボックス様の造作物を用い\nるという原告のアイディアに必然的に生じる表現であるから,この点につ\nいて創作性が認められるものではない。また,2)については,具体的表現\n内容は共通しているといえるものの,原告作品と被告作品の具体的表現と\nしての共通点は2)の点のみであり,この点を除いては相違しているのであ って,被告作品から原告作品を直接感得することはできないから,原告作 品と被告作品との同一性を認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> ピックアップ対象
2019.07. 9
平成30(行ケ)101 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月13日 知的財産高等裁判所
そして,引用発明及び引用文献8に記載された技術は,いずれも,Aβ 結合剤をアルツハイマー病等の患者の血液中のAβに結合させることによって,A βを除去し,アルツハイマー病等の疾患を治療するというものであり,技術分野は 同一であること,引用文献8には,四量体ペプチドA及びポリエチレングリコール 架橋キャリアゲルを含む組成物は,Aβに効果的かつ不可逆的に結合し,Aβと最 大の結合能力を示したとの記載があること,前記2(1)のとおり,引用文献1には, 「アミロイドβ結合化合物」の第2部分として,ポリエチレングリコールのような 高分子を用いてもよいことが記載されている(段落[0056])ことからすると, 引用発明に引用文献8に記載された技術を適用する動機付けがあると認められる。 この点について,原告は,引用文献1の段落[0056]は,「全身投与」に関す る記載であり,透析とは無関係であると主張するが,引用文献1の同部分の記載は, 血液中のAβに結合するAβ結合化合物の第2部分がポリエチレングリコールでも よいというものであるところ,このことが,体内への投与の場合と透析の場合で異 なると認めるに足りる証拠はなく,少なくとも,引用文献1の上記部分に接した当 業者は,透析の場合においても,Aβ結合化合物の第2部分としてポリエチレング リコールを用いることも適しているものと認識するというべきである。
ウ したがって,引用発明に引用文献8に記載された技術を適用して,引用 発明におけるアミロイドβ結合化合物を四量体ペプチドA及びポリエチレングリコ ール架橋キャリアゲルを含む組成物とし,かつ,同組成物を調整する工程を含ませ ることは,当業者にとって,容易に想到できると認められる。
(2) 顕著な効果について
原告は,本願発明は,1)β-アミロイドへの特定の結合作用を提供する,2)β-ア ミロイドの除去の物理的特性に依存せず,代わりに,血液の構成要素からβ-アミロ イドを捕捉する結合剤を用いるだけである,3)組織的に高い結合能力を形成するプ\nロセスを提供する,4)体内に外的物質を導入することを含まず,それにより逆のリ スク事象に移行し得る潜在的免疫システム反応を除去したプロセスを提供するとい う顕著な効果を有する旨主張する。 しかし,上記4)については,血液透析によりAβの除去を行う引用発明が当然備 える効果であり,上記1)〜3)については,引用発明において,「Aβ結合化合物」と して,結合能の高い化合物を採用することよって獲得される効果にすぎないから,\n原告の上記主張は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,引用文献1に記載されたAβ結合化合物は,すべて天然由来の ものであるから,合成物である四量体ペプチドAを用いる動機付けはないなどと主 張する。 しかし,前記のとおり,引用文献8には,四量体ペプチドAはAβと効果的に結 合する旨の記載がある以上,引用発明において,Aβ結合化合物として四量体ペプ チドAを用いる動機付けはあるというべきであり,このことは,引用文献1に記載 されたAβ結合化合物が天然由来であるか否かに左右されない。
イ 原告は,引用文献1に膨大な数のアミロイドβ結合化合物が記載されて いる中で,引用文献1に記載のない,四量体ペプチドAをわざわざ適用することに は阻害要因があると主張するが,引用文献1に記載されたAβ結合化合物の数が膨 大であることによって,Aβ結合化合物として,引用文献8に明記されている四量 体ペプチドAを用いることが阻害されるということはできない。
ウ 原告は,引用発明は,一般的な透析法によりアミロイドβを除去する発 明であるのに対して,引用文献8に記載された技術は,アミロイドβ化合物と結合 し得る物質(医薬製剤)を生体内に存置するものであるから,技術分野が異なり, また,阻害要因もあると主張する。 しかし,前記のとおり,引用発明及び引用文献8に記載された技術は,いずれも, Aβ結合剤をアルツハイマー病の患者等の血液中のAβに結合させることによって, Aβを除去するというものであり,技術分野は同一である。そして,生体内での使 用が想定されているAβ結合化合物を血液透析で使用することができない理由があ るとは認められないから,阻害要因も認められない。 この点について,原告は,体内で使用する物質を血液透析で使用することに阻害 要因があることの理由について,透析法は,体内使用における患者の負担の軽減の ために採用するものである旨の主張をするが,体内使用における患者の負担の軽減 のために透析法を採用するということが,体内での使用が想定されているAβ結合 化合物を血液透析で使用することの阻害事由となるとは認められず,むしろ,体内 での使用について安全性が確認されている物質であれば,血液透析でも使用しよう と考えるのが通常であるといえる。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は,引用文献8に記載された発明は,生体内で使用するデポ剤であ るため,その不活性及び安全性のためにRIペプチドを集めるためのプラットホー ムとして,ポリエチレングリコールが採用されているが,引用発明は,透析法によ りアミロイドβを除去する発明であり,生体内における不活性及び安全性という必 要性がないから,生体内での不活性及び安定性のためのものとして開示されている ポリエチレングリコールを,捕捉結合剤と結合したアミロイドβが透析装置の透析 膜から戻ることを防止して透析法においてアミロイドβを効率よく除去するために キャリアゲルとして使用する動機付けはないと主張する。 しかし,引用発明において,Aβ結合化合物として,四量体ペプチドA及びポリ エチレングリコール架橋キャリアゲルを含む組成物を用いる動機付けが認められる ことは既に判示したとおりである。そして,前記2(2)のとおり,引用文献8には, ポリエチレングリコール(PEG担体)は,RIペプチドの複数のコピーを付着さ せ,Aβとの結合能を向上させると記載されているから,当業者は,引用文献8に\n記載された発明を引用発明に適用するに際し,ポリエチレングリコールを共に用い る動機付けがあるというべきである。引用発明においては,生体内で使用するため の安定性や安全性を考慮する必要がないとしても,上記認定が左右されることはな い。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
オ 原告は,引用発明から出発して,アミロイドβ除去能を向上しようとす\nれば,引用文献1に多数列挙されているアミロイドβ結合化合物からアミロイドβ 結合能力の少しでも高いものを選択するのが通常であって,わざわざキャリアゲル\nで修飾することの動機付けはないと主張する。 しかし,引用発明において,Aβ結合化合物として,四量体ペプチドA及びポリ エチレングリコール架橋キャリアゲルを含む組成物を用いる動機付けが認められる ことは,既に判示したとおりであって,キャリアゲルで修飾することの動機付けも あるというべきである。
カ 原告は,透析液は正常な血液に近い成分・濃度の電解質溶液に調製する のが当業者の常識であるから,引用発明にキャリアゲルを添加することには阻害事 由があると主張する。 しかし,透析液にキャリアゲルを添加することによって,正常な血液に近い成分・ 濃度の電解質溶液に調製することが妨げられることを認めるに足りる証拠はないか ら,透析液(透析緩衝液)にキャリアゲルを添加することに阻害事由があるとは認 められない。
キ 原告は,引用文献1の段落[0080]には,「半透膜は10,000ダ ルトンの分子量カットオフを有する」と記載されているところ,二量体を超える高 分子量種(四量体,八量体,それ以上の高分子量種)のAβの分子量は,10,0 00ダルトンを超えるため,引用文献1記載の透析方法では,半透膜を通ることが できず,透析槽側に拡散し得ないから,二量体を超える高分子量種のAβも含めて 除去する本願発明とは,技術思想が全く異なると主張する。 しかし,本願発明の特許請求の範囲には,除去すべきAβの分子量や半透膜を通 過する分子の大きさについては何ら記載されていないから,本願発明も,半透膜の 仕様によっては,二量体を超える高分子量種のAβは半透膜を通ることができず, これを除去することはできないものである。したがって,二量体を超える高分子量 種のAβも含めて除去できるか否かによって,本願発明と引用発明の技術思想が異 なるということはできない。
ク 原告は,引用文献1のapoE3は極めて高価あるから,引用発明に引 用文献8記載の技術を適用することには阻害要因があると主張する。 しかし,製剤の製造コストを可能な限り削減することは当業者にとって重要な課\n題であるから,apoE3が高価であるということは,これに代えて引用文献8に 記載された四量体ペプチドA及びポリエチレングリコール架橋キャリアゲルを含む 組成物を用いることの阻害事由とはならず,むしろ,動機付けとなるというべきで ある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.07. 9
平成30(行ケ)10139 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年6月20日 知的財産高等裁判所
本件審判請求は,本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び付属品」に ついてされたものであるところ,原告が,「自動車並びにその部品及び付属品」につ いて,本件審判請求の登録日である平成28年10月3日の前3年以内に本件商標 を使用した事実を認めるに足りる証拠はないし,また,使用していないことについ て正当な理由があったとも認められない。 したがって,本件商標登録は,その指定商品中「自動車並びにその部品及び付属 品」について取消しを免れないというべきである。 この点,原告は,商標登録の不使用取消審判の請求が認められるのは,請求に係 る指定商品又は指定役務の全部について登録商標の使用がされていない場合である ところ,原告は,電動スクーターや二輪自転車については本件商標を使用している と主張する。しかし,商標登録の不使用取消審判の請求は,当該商標の指定商品中 の任意の指定商品についてすることができる。そして,その請求がされた指定商品 のいずれかについて商標の使用が立証されない限り,請求された指定商品すべてに ついて商標登録が取り消される。しかるところ,本件審判請求は,指定商品を「自 動車並びにその部品及び付属品」としてされたのであるから,「自動車並びにその部 品及び付属品」のいずれかについて商標の使用が立証されない限り,本件審判請求 に係る上記指定商品すべてについて商標登録の取消しを免れない。原告が,電動ス クーターや二輪自転車について本件商標を使用しているとしても,そのことは,上 記判断を左右するものではない。
2019.07. 5
平成30(行ケ)10181 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和元年7月3日 知的財産高等裁判所(1部)
本件意匠は,3枚のフィンが垂直方向に並べて設けられているのに対し,タワ ー型ヒートシンクである引用意匠1では,4枚のフィンが水平方向に並べて設けら れており,両意匠は,縦横の位置関係が異なる。 そこで,仮に引用意匠1を右に90°回転させて対比してみると,本件意匠と の共通点及び相違点は,次のとおりである。 前記の認定(1(1)(2))によれば,本件意匠と引用意匠1とは,aのうち,ともに機 器に設けられる放熱部であるという限度で重なり合うところがあり,また,bその中 心に支持軸体が設けられ,c支持軸体の中間及び後端に,薄い円柱状の,支持軸体よ りも径の大きい,同一径のフィンが複数枚,間隔を空けて設けられ,f各フィンが, 中心軸を合致させ,互いに等しい間隔で設置されているという点,j各フィンの各面 が,支持軸体の通過部分以外は平滑である点においても共通する。 他方,aについても,本件意匠が前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられ た後方部材(放熱部)であるのに対し,引用意匠1は汎用的なタワー型ヒートシンク であるという点では相違し,また,eフィンの枚数について,本件意匠では中間フィ ンと後端フィンを合わせて3枚であるのに対し,引用意匠1では4枚である点,gフ ィンの厚みについて,本件意匠ではフィンの上下で差がないのに対し,引用意匠1の フィンは中央部の厚みが最も大きく,上下にいくにつれて次第に薄くなっている点, i本件意匠の支持軸体の直径がフィンの直径の約5分の1であるのに対し,引用意 匠1では約3分の1である点においても相違する。
ウ 本件意匠と引用意匠1との類否
(ア)前記イ(ア)のとおり、本件意匠と引用意匠1は視覚を通じて起こさせる美観が 縦横の位置関係からして,全く異なる。
(イ)また,仮に引用意匠1を右に90°回転させて対比してみたとしても,1)本件 意匠が,前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であ るのに対し,引用意匠1はそうでなく,汎用的なタワー型ヒートシンクであるという 点,2)本件意匠のフィンが3枚で,後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約2倍で あるのに対し,引用意匠1のフィンでは4枚がほぼ同形同大のものであるという点, 3)本件意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し,引用意匠1のフィンは中 央部の厚みが最も大きく,上下にいくにつれて次第に薄くなっている点,4)支持軸体 の直径が本件意匠では細いのに対し,引用意匠1ではやや太い点において相違し,こ れらの相違点が前記の共通点を凌駕するというべきであり,本件意匠と引用意匠1 とでは,視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。 したがって,本件意匠と引用意匠1とは類似しないというべきである。
エ よって,取消事由1は理由がない。
(2) 取消事由2(引用意匠1に基づく創作容易性判断の誤り) ア 意匠法3条2項は,物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内 又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準と して,そこからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容 易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり,その要件 の該当性を判断するときには,上記の公知のモチーフを基準として,当業者の立場か らみた意匠の着想の新しさないし独創性が問題となる(最高裁昭和45年(行ツ)第 45号同49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁,最高裁昭和4 8年(行ツ)第82号同50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号28 7頁参照)。
イ 検討
これを本件についてみると,複数のフィンが水平方向に並べて設けられてい る,「タワー型」の引用意匠1には,それらを垂直方向に並べることの動機付けを認 めるに足りる証拠はないから,引用意匠1に基づいて本件意匠を創作することが容 易であるとはいえない。 また,引用意匠1を右に90°回転させて対比した場合の前記((1)イ)の各相 違点に係る本件意匠の構成が,周知のもの又はありふれたものと認めるに足りる証\n拠もないから,引用意匠1のみに基づいて当業者が本件意匠を創作することが容易 であったとは認められない。
ウ よって,取消事由2は理由がない。
(3) 取消事由3(引用意匠1及び同2に基づく創作容易性判断の誤り)及び取消事 由4(引用意匠1及び同3に基づく創作容易性判断の誤り)
ア 原告は,引用意匠1に同2又は同3をそれぞれ組み合わせれば,それらに基づ き本件意匠を容易に創作することができたとも主張する。
イ 検討
しかしながら,本件意匠は,3枚のフィンが垂直方向に並べて設けられている のに対し,タワー型ヒートシンクである引用意匠1では,4枚のフィンが水平方向に 並べて設けられているところ,タワー型の引用意匠1には,それらを垂直方向に並べ ることの動機付けを認めるに足りる証拠はないから,引用意匠1及び同2又は同3 に基づいて本件意匠を創作することが容易であるとはいえない。 また,仮に引用意匠1を右に90°回転させて対比してみても,1)本件意匠が, 前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であるのに対 し,引用意匠1はそうでなく,汎用的なタワー型ヒートシンクであるという点,2)本 件意匠のフィンが3枚で,後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約2倍であるの に対し,引用意匠1のフィンでは4枚がほぼ同形同大のものであるという点,3)本件 意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し,引用意匠1のフィンは中央部の 厚みが最も大きく,上下にいくにつれて次第に薄くなっている点,4)支持軸体の直径 が本件意匠では細いのに対し,引用意匠1ではやや太い点において相違し,これらの 相違点が前記の共通点を凌駕することは,前記(1)のとおりである。そして,タワー型 ヒートシンクである引用意匠1に検査用照明器具に係る引用意匠2又は同3を組み 合わせる動機付けを認めるに足りる証拠はない。また,少なくとも相違点4)に係る本 件意匠の構成が引用意匠2又は同3にあらわれているということができないことか\nらすれば,引用意匠1に引用意匠2又は同3を組み合わせてみても,本件意匠には至 らない。したがって,それらに基づき当業者において本件意匠を創作することが容易 であったとは認められない。
◆判決本文
本件の侵害事件です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 創作容易性
>> 部分意匠
>> ピックアップ対象
2019.07. 5
平成31(行ケ)10004 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年7月3日 知的財産高等裁判所(1部)
前記(2)認定のとおり,本願商標は,世界有数の自動車メーカーである原告が, 電動車ブランドを示す商標として採択したものであること,原告は,モーターショ ーにおいて,「EQ」を新しい電動車ブランドとして公表するとともに,「EQ」ブラ\nンドのコンセプトカーを発表し,各モーターショーの展示内容等は多くの自動車専\n門雑誌や自動車関連情報のウェブサイトにおいて紹介され,雑誌の発行部数は,多 いものでは23万部に達していること,原告は,原告ウェブサイトや顧客向け定期 機関誌の記事,全国紙での新聞広告等によって,原告の電動車ブランド「EQ」につ いて宣伝を行ったことが認められる。 また,上記の雑誌等の記事の中には,原告の「EQ」ブランドの紹介に特化したも のもあること(甲29の6・10,35〜37),原告の顧客向け定期機関誌の発行 部数は,平成30年度には年間17万部に達していることも勘案するなら,著名な 自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目する取引者,\n需要者が類型的に存在することが認められる。 そして,広告宣伝の具体的態様も,前記のとおり,原告ウェブサイトやブックレ ット等では,「メルセデス・ベンツは約1年前のパリモーターショーで『コンセプト EQ』を紹介すると同時に,『EQ』という新ブランドを立ち上げることを発表した」\n(甲9の1),「メルセデスの新ブランド『EQ』が目指す,クルマと人との未来」 (甲9の2),「新たな電気自動車ブランドとして“Electric Intel ligence”を示す『EQ』が誕生します」(甲48)などと宣伝され,雑誌や ウェブサイトの記事等においても,「電気駆動のモデルに特化したメルセデス・ベン ツのサブブランド『EQ』」(甲29の9),「『EQ』は,メルセデスベンツが2016年に立ち上げた電動パワートレイン車に特化した新ブランド」(甲31),「EQブ ランド」(甲4,29の10・21,31,40等),などと紹介されており,本願商 標が原告のブランドの名称であることが強調されている。 以上によれば,本願商標については,著名な自動車メーカーである原告の発表す\nる電動車やそのブランド名に注目する者を含む,自動車に関心を持つ取引者,需要 者に対し,これが原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で,集中 的に広告宣伝が行われたということができる。加えて,本願商標は,本件審決時ま でに,出願国である英国及び欧州にて登録され,国際登録出願に基づく領域指定国 7か国にて保護が認容されており,世界的に周知されるに至っていたと認められる ことも勘案するなら,本願商標についての広告宣伝期間が,パリモーターショー2 016で初めて公表された平成28年9月29日から本件審決時(平成30年9月\n7日)までの約2年間と比較的短いことや,原告が平成29年から販売している「E Q POWER」との名称のプラグインハイブリッド車の販売台数が多いとはいえ ないこと等の事情を考慮しても,本願商標は,原告の電動車ブランドを表す商標と\nして,取引者,需要者に,本願商標から原告との関連を認識することができる程度 に周知されていたものと認められる。
(4) 被告の主張について
ア 被告は,本願商標は,電動自動車の抽象的なブランド名ではあるが,単独で 車名として採択されておらず,販売実績もない上,原告の広告宣伝活動が行われた のはわずか2年間で,一般の需要者に周知されているというには十分とはいえない\n旨主張する。 しかし,商標が,単独で車名として採択されていないとしても,原告が電動車の ブランド名として本願商標を採択し,商品のシリーズ名やブランド名として使用す るに先立って,強力な広告宣伝を行ったことにより,当該商標が,需要者にブラン ドとして認識され,識別力を獲得することはあるというべきである。 また,本願商標についての広告宣伝期間は確かに約2年間であるが,期間が短く ても,集中的に広告宣伝がされることにより,識別力を獲得できる場合はある。そ して,著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目\nする取引者,需要者が類型的に存在すると認められることは前記のとおりであり, 本願商標を原告の業務に係る標章であると認識している取引者,需要者が相当程度 存在するといえるから,本願商標は,広く知られるに至ったと認めるのが相当であ る。
イ 被告は,「E」(e)及び「Q」の欧文字を組み合わせた欧文字2字は,本願の 指定商品に含まれる自動車及び二輪自動車と関連する商品分野において,原告以外 の者によっても採択,採用されているから,本件指定商品の分野において,本願商 標の原告による独占使用が事実上容認されているとまではいえないと主張する。 確かに,平成24年9月26日以前にトヨタ自動車の電動自動車「eQ」が公表\nされたことが認められる(乙7)。しかし,同標章が本件審決時において使用されて いることを認めるに足りる証拠はなく,過去に電動自動車の商品名として使用され た標章があることをもって,原告による独占使用の容認が否定されるとはいえない。 また,現代自動車の「ジェネシス」ブランドの超大型ラグジュアリーセダン「EQ 900リムジンモデル」(乙8),鄭州日産のライトトラック「EQ1060」(乙9),Laufennのプレミアム超高性能夏タイヤ「S Fit EQ」(乙12),ア ルパインのカーナビ「EX11Z−EQ」(乙13),TOWNIEの電気自転車「7 DEQ」,「3iEQ」(乙14),ALIBIの自転車「ALIBI SPORT E Q」(乙15)は,いずれも「EQ」の欧文字と他の欧文字や数字等が組み合わされ た標章であって,品番や型式を示すものと解され,英国日産自動車製造の小型乗用 車「プリメーラ」の開発コードである「EQ」(乙10)は,開発コードであるから, いずれも何人かの出所を表すものとはいえない。\nしたがって,これらの他者による「EQ」の使用を考慮しても,本願商標に登録商 標としての保護を及ぼすことを否定すべきとはいえない。
ウ よって,被告の主張はいずれも採用できない。
3 結論
以上のとおり,本願商標は,商標法3条1項5号の極めて簡単で,かつ,ありふれ た商標に該当するものの,同条2項の使用をされた結果需要者が原告の業務に係る 商品であることを認識することができるものに該当するから,商標登録をすること ができないとした本件審決には誤りがある。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2019.07. 3
平成30(行ケ)10146 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所(4部)
前記(1)の記載事項によれば,本願明細書には,本願発明に関し,次のよ うな開示があることが認められる。
ア 遊技性を向上させるために,貯留部に遊技領域を流下する遊技球そのも のを物理的かつ一時的に保持して,遊技球の流下タイミングを遅延させる ように構成し,遊技者が手元のボタンを押下することで貯留した遊技球が\n落下可能となるようにした従来のパチンコ機は,例えば,大当たり遊技中\nに遊技者がボタンを操作すれば,貯留部内の遊技球が大入賞口に向かって 一気に放出されるため,多くの遊技球を大入賞口に入賞させることができ たが,遊技球を物理的に貯留する手段を設ける必要があるため,部品点数 が多くなり,コストが嵩むといった課題があり,また,遊技球が流下する 領域を狭めることとなり,好ましくなく,その一方で,大当たり遊技中に 単に遊技球を発射して大入賞口内に入賞させるだけでは,遊技の面白みに 欠けるという実情があった(【0004】,【0006】)。
イ 「本発明」は,上記実情に鑑み,推奨する遊技球のルートを遊技者が容 易に打ち分けることができ,遊技性を向上させることのできるパチンコ機 を提供することを目的とし,この目的を達成するための手段として,遊技 領域に打ち出された遊技球が特別電動役物へ向かう,少なくとも2つのル ートが前記遊技領域内に設けられ,前記2つのルートは,共に遊技球が物 理的に貯留されることなく流下可能に構\成されていると共に,一方のルー トに比べて他方のルートの方が,遊技球が遊技領域に打ち出されてから前 記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され,前記一\n方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ,前記他方の ルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ,前記一方のルー トを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと,前記他方のルー トを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと,前記大入賞口に 入賞した遊技球を検出する大入賞口検知センサと,前記2つのルートのう ち推奨するルートを遊技者に報知する推奨ルート報知手段と,をさらに備 え,大当たり遊技制御手段は,前記大入賞口を開放するよう前記特別電動 役物を作動させた後に,前記大入賞口にM個(ただし,Mは自然数)の遊 技球が入賞したことを条件に前記大入賞口を閉鎖するよう前記特別電動役 物を作動させるラウンド遊技を複数回行う内容の前記大当たり遊技を提供 し,前記推奨ルート報知手段は,遊技球が前記他方のルートを流下してい る状態で,前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に, 前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした構\n成を採用した(【0007】,【0009】)。 これにより「本発明」は,推奨する遊技球のルートを遊技者が容易に打 ち分けることができ,遊技性を向上させることのできるパチンコ機を提供 することができるという効果を奏する(【0011】)。
・・・
被告は,引用発明と引用例2に記載された事項は,共に遊技球を流下さ せるルートが複数あり,そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が 有利となる状態がある遊技機に関する発明又は技術であり,技術分野が共 通しているといえるから,引用発明に引用例2に記載された事項を適用す る手がかりがあり,引用発明に引用例2に記載された事項を適用すること ができることからすると,当業者は,引用発明のパチンコ遊技機に,引用 例2に記載された事項を適用して,相違点2及び3に係る本願発明の構成\nとすることを容易に想到することができたものであるから,これと同旨の 本件審決の判断に誤りはない旨主張する。 そこで検討するに,引用例1には,引用発明において,「一方のルート」 に相当する「遊技球滞留部32」を流下する遊技球を検知する遊技球検知 センサ及び「他方のルート」に相当する「遊技球流下部31」を流下する 遊技球を検知する遊技球検知センサを設けることについての記載や示唆は ない。また,引用例1には,遊技球が「遊技球流下部31」を流下してい る状態で,当該遊技球を検知する遊技球検知センサが所定個数の遊技球を 検知した後に,「遊技球滞留部32」を推奨するルートとして遊技者に報 知する手段を設けることについての記載や示唆はない。
次に,前記2(2)イ認定のとおり,引用例1には,「本発明」は,遊技者 が可変入賞装置の入賞口の開放前に,報知装置による入賞口の開放の予告\nに基づいて,まず「遊技球滞留部」を狙って遊技球を発射し,次に「遊技 球流下部」を狙って遊技球を発射する打ち分けを可能とし,これにより「遊\n技球滞留部」からの遊技球と「遊技球流下部」からの遊技球とが合流して, 可変入賞装置に入賞することとなるため,時間の経過に応じて遊技球を打 ち分けることにより,可変入賞装置への大量の入賞を狙うことを可能とし\nた効果を奏すること(【0009】,【0011】)の開示があるところ, その実施形態である引用発明においては,大入賞口が10秒後に開放され ることを予告する報知用ランプ17aと大入賞口を開放する5秒前に点灯\nする報知用ランプ17bとを設け,遊技者は,報知用ランプ17aの点灯 により大入賞口が10秒後に開放されることを知ったとき,「遊技球滞留 部32」を狙って遊技球を発射し,「遊技球滞留部32」に複数の遊技球 を滞留させ,大入賞口を開放する5秒前に報知ランプ17bが点灯するこ とにより,「遊技球流下部31」を狙って遊技球を発射し,合流地点に設 けられた可変入賞装置11の大入賞口に,短時間で大量の遊技球が入賞す るようにした構成(構\成e,g)を備えている。このように引用発明は, 大入賞口が開放されるまでの時間を報知用ランプ17a又は17bの点灯 により報知することにより,時間の経過に応じて遊技球を打ち分けること を可能とした発明であるといえる。\n
一方,前記(1)イ認定のとおり,引用例2には,第1の方向側の遊技領域 (例えば,左側の遊技領域)及び第2の方向側の遊技領域(例えば,右側 の遊技領域)にそれぞれ通過ゲート,始動口等が設け,右打ちをすべき遊 技状態のときに,左側の遊技領域に設けられた左通過ゲートに遊技球が通 過すると,左打ちが行われていると判定して,液晶表示装置に右打ちを促\nす画像を表示させ,左打ちをすべき遊技状態(通常遊技状態)のときに,\n右側の遊技領域に設けられた右通過ゲートに遊技球が通過すると,液晶表\n示装置に左打ちを促す画像を表示させていた従来の遊技機においては,遊\n技者が遊技状態に合わせて正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる 発射操作を行っているにもかかわらず,たまたま少量の遊技球が誤った方 向側の遊技領域を流下し,誤った方向側の遊技領域に設けられた通過ゲー トや始動口等を通過してしまったときに,正しい方向側の遊技領域に遊技 球を発射させることを促すことが報知され,正しい方向側の遊技領域に遊 技球を発射させている遊技者に煩わしさや不快感を与えるという問題があ ったため(【0007】),「本発明」は,第2の方向側の第2通過領域 を進入した遊技球を検出する第2通過領域検出手段により検出された検出 回数の計数を行う第2通過領域計数手段によって予め定められた検出回数\nが計数されると,報知手段により第1の方向側の遊技領域に遊技球を発射 することを促す発射操作情報の報知を行わせる構成を採用し,これにより,\n現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回 数(検出回数)を参照して発射操作情報の報知を行うので,たまたま少量 の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定で きるため,遊技者の発射操作に対応したより正確な発射操作に関する報知 を行うことができ,快適な遊技を行わせることができるという効果を奏す ること(【0008】,【0018】)の開示がある。このように引用例 2記載の遊技機は,第1の方向側の遊技領域(左側の遊技領域)を流下す る遊技球を検出する検出手段,第2の方向側の遊技領域(右側の遊技領域) を流下する遊技球を検出する検知手段及び第1の方向側又は第2の方向側 の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知手段を備え, 報知手段による報知を現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた検出手段 によって検出された遊技球が進入した回数(検出回数)を参照して行うこ とにより,遊技者が正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操 作を行っているにもかかわらず,たまたま少量の遊技球が誤った方向側の 遊技領域を流下したとしても誤差として判定し,正しい方向側の遊技領域 に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにして, 遊技者に煩わしさや不快感を与えることのないようにしたものといえる。
そうすると,引用発明と引用例2記載の遊技機は,共に遊技球を流下さ せるルートが複数あり,そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が 有利となる状態がある遊技機において,上記有利となる状態となった場合 にその有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うこ とに関する発明又は技術である点において,技術分野が共通しているとい えるが,他方で,引用発明では,遊技者が可変入賞装置の入賞口(大入賞 口)の開放前に,大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置によ り予告(報知)することにより,有利な方向の遊技領域に遊技球を発射す\nることを促すものであるのに対し,引用例2記載の遊技機は,遊技者が有 利な方向(正しい方向側)の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行 っているにもかかわらず,たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領 域を流下したとしても誤差として判定し,正しい方向側の遊技領域に遊技 球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにしたもので あり,報知の目的及びタイミングが異なるものと認められる。
また,引用発明において引用例2記載の遊技機の構成(本件審決認定の\n引用例2に記載された事項)を適用することを検討したとしても,具体的 にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできないというべきで ある。そうすると,引用例1及び引用例2に接した当業者は,大入賞口が開放 されるまでの特定の時間を報知装置により予告(報知)する引用発明にお\nいて,報知の目的及びタイミングが異なる引用例2記載の遊技機の構成(本\n件審決認定の引用例2に記載された事項)を適用する動機付けがあるもの と認めることはできない。したがって,当業者は,引用発明及び引用例2に記載された事項に基づいて,相違点2及び3に係る本願発明の構成を容易に想到することができ\nたものと認めることはできないから,被告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.07. 2
平成29(ワ)30826 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月26日 東京地方裁判所(46部)
原告は,本件シールブックが「折り重ねることによって形成されるシール 領域」を有していないという相違点(本件相違点)があるとしても,本件シ ールブックは本件発明1の構成と均等なものとして,本件発明1の技術的範\n囲に属すると主張する。本件シールブックが本件発明1の構成と均等である\nというためには,特許請求の範囲に記載された構成中被告製品と異なる部分\nが特許発明の本質的部分でないことが必要である。 そして,特許発明における本質的部分とは,当該特許発明に係る特許請求 の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特\n徴的部分であると解すべきであり,特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細 な説明の記載に基づいて,特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把 握した上で,特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見ら れない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定するこ\nとによって認定されるべきである。
イ 本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと,本件発明1は,シール 付き印刷物に関する発明であり,それまで知られていた特許文献1ないし3 (特開2007−334037号公報,特開2006−82542号公報, 特開2004−314621号公報〔乙2〕)に開示されたシール付き印刷 物では,「シール及びシール台紙は平面状であるため,立体的な広がりのあ る使い方を提供できるものではな」く,また「通常のシールを製造する方法 が適用される」ため製造が容易でないとの課題が存在した(段落【0006】, 【0007】)。ここにいう「通常のシールを製造する方法」は,本件明細書 には直接記載はされていないが,上記各特許文献において,紙本体の少なく とも一箇所を折り重ねることによってシール領域を形成する方法が開示さ れていたと認めるに足りる証拠はない。 本件発明1は,従来技術における上記課題を踏まえ,「容易に製造するこ とが可能」なシール付き印刷物を提供することを目的の1つとしており(段\n落【0007】),本件特許請求の範囲記載の構成,具体的には,シール及び\n台紙となる印刷が施された紙本体と,その少なくとも一箇所を折り重ねるこ とによって形成されるシール領域との構成を有するシール付き印刷物とし,\n紙本体を折り重ねることで形成されたシール領域を有するもの(段落【00 13】)と認められる。 また,実施例である【図1】及び【図2】については,「シール(5,6) 及び台紙(4)となる印刷がされた紙本体2を折り重ねることでシール領域 3と台紙領域4が形成される。」(段落【0046】),「紙本体2を印刷する 工程の延長線上で,紙本体2にコーティング層32と粘着層31A,31B を形成して貼り合わせることでシール領域3となるため,起立シール5を含\nむシールブック1を容易に製造することができる」(段落【0049】)と説 明されている。 これらの本件明細書における記載からすれば,本件発明1が解決しようと する課題である「容易に製造することが可能」となるための構\成には,少な くとも,1枚の「紙本体2」の両面に印刷を施した上で(段落【0020】 【0021】,図3),「紙本体2」を折り重ねて貼り合わせることによって\nシール領域を形成することにより(段落【0021】【0046】),製造さ れたシール付き印刷物であるという構成を有することが含まれていると解\nすることができる。 したがって,本件特許請求の範囲の記載のうち,「紙本体の少なくとも一 箇所を折り重ねることによって形成されるシール領域」との構成は,従来技\n術に見られない特有の技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分である\nといえる。
ウ これに対し,原告は,本件発明の本質的部分は,同種の紙素材を重ねて貼\nり合わせてシール領域と台紙領域を形成することであり,「折り重ねること によって形成されるシール領域」は本件発明1の本質的部分ではないと主張 する。 しかし,前記イのとおり,「紙本体の少なくとも一箇所を折り重ねること によって形成されるシール領域」との構成は,従来技術に見られない特有の\n技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分であり,原告の主張は採用する\nことができない。 したがって,原告の上記主張は採用できない。
エ 前記のとおり,被告製品である本件シールブックは,構成要件1Cの「折\nり重ねることによって形成」との文言を充足しないから,本件発明1とはそ の本質的部分において相違し,少なくとも均等の第1要件を充足しない。 したがって,被告製品である本件シールブックは,本件発明1と均等なも のとして,その技術的範囲に属するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2019.07. 2
平成30(ネ)10024 特許権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許法123条2項は,同条1項6号の冒認出願に該当することを理由と する特許無効審判は,特許を受ける権利を有する者に限り,請求することが できる旨を規定する。 ところで,同法2条1項は,「発明」とは,「自然法則を利用した技術的 思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し,同法70条1項は,「特許 発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定め なければならない。」と規定している。これらの規定によれば,「発明者」 とは,当該発明の創作行為に現実に加担した者をいい,特許発明の「発明者」 といえるためには,特許請求の範囲の記載によって具体化された当該特許発 明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し,又は,その着想 を具体化することに創作的に関与したことを必要とすると解するのが相当 である。
そこで,以上を前提に,1審被告の従業員らが本件出願前に本件発明をし, 1審被告がその特許を受ける権利を承継したかどうかについて判断する。
・・・
(イ)a 1審被告は,FCM−A及びFCM−Cの稼働状況を撮影した動 画として,乙17の1及び乙18の1を提出する。 これらの各動画には,「型式FCM−A」,「取得年月86年9月 30日」,「(株)加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が付さ れた装置(乙17の1)及び「型式FCM−C」,「取得年月88年 2月29日」,「(株)加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が 付された装置(乙18の1)において,コイル巻き後に切断分離する 方法によるタングレス螺旋状コイルインサートの製造場面が撮影され ている。上記場面の撮影時期は平成27年12月であるが,上記各装置につ いて製造方法に関する構成が大きく変えられたことをうかがわせる証\n拠はないことに照らすと,乙17の1及び乙18の1は,昭和61年 ないし63年当時に1審被告がFCM−A及びFCM−Cを使用して 本件発明を実施していたことを裏付けるものといえる。
・・・
(ウ) 前記(ア)及び(イ)の認定事実とFCM−A及びFCM−Cの開発経 緯(前記2(2))によれば,1審被告は,昭和61年ころには,1審被告 らの従業員らの設計したFCM−Aを製造し,本件発明を実施していた ことが認められる。 そして,1審被告らの従業員らによるFCM−Aの設計は,前記1(2) 認定の本件発明の技術的思想を着想し,その着想の具体化に創作的に関 与する行為に当たるものと認められる。 したがって,1審被告らの従業員は,そのころ,本件発明を完成させ たものと認められる。
イ FCM−Bは,FCM−Aとサイズ違いのファミリー機種(乙133) であり,抜き潰し加工が一定間隔で施された線材をコイル巻きしてから加 工部分の中央で切断することを繰り返すもの(乙132)であるから,F CM−A及びFCM−Cと同様,本件発明を実施する装置であるものと認 められる。 そして,前記2(3)のとおり,昭和62年ころに5台のFCM−Aが福島 工場に移管されて稼働を開始し,同年から昭和63年にかけて5台のFC M−B及び1台のFCM−Cが福島工場に設置されて稼働を開始したこと, これらのFCM−A各機種は,平成7年11月,1台のFCM−Bを残し て,英国子会社に移管されたことが認められる。 したがって,1審被告は,昭和62年ころから平成7年11月までの間, 福島工場において,これらのFCM−A各機種を使用してタングレス螺旋 状コイルインサートを製造することにより,本件発明を実施していたこと が認められる。
・・・
エ 小括
以上のとおり,1審被告らの従業員は,昭和61年ころ,FCM−Aを 設計することにより本件発明を完成し,1審被告は,昭和62年ころから 平成7年11月までの間,福島工場において,FCM−A各機種を使用し てタングレス螺旋状コイルインサートを製造することにより,本件発明を 実施していたことが認められる。 上記認定事実によれば,1審被告は,本件発明の発明者である1審被告 らの従業員らから,昭和62年ころまでに,本件発明の特許を受ける権利 を承継したものと認めるのが相当である。
・・・
(ウ) 1審原告の当審における主張と原審における主張とを対比すると, 1)1審原告代表者が本件発明を着想するに至った時期(原審では「平成\n11年ころ」である旨主張していたのに対し,当審では「平成10年こ ろ」である旨主張している点),2)1審原告代表者の本件発明の着想の\n経緯,3)1審原告代表者が三晃のJに対し線材のサンプルの作製を依頼\nした時期(原審では「平成11年ころ」である旨主張していたのに対し, 当審では「平成10年ころ」である旨主張している点),4)1審原告代 表者が1審被告を訪れて線材の試作サンプルを1審被告のHに示した時\n期(原審では「平成11年5月10日ころ」である旨主張していたのに 対し,当審では「平成10年6月11日」である旨主張している点), 5)1審原告代表者のK弁理士に対する本件出願の依頼の経緯(原審では,\n1審原告代表者が1審被告を訪れた際に応対したHの無礼な態度に驚き,\nその日のうちにK弁理士に対し,1審被告から持ち帰った「試作品の線 材」と「タング無しコイルの実物」を渡して本件出願を依頼した旨主張 していたのに対し,当審では,1審原告代表者が本件発明が将来何かの\n役に立つこともあろうかと考え,「平成11年5月10日」に,K弁理 士に対し,「アキュレイト販売から入手していたタングレス螺旋状コイ ルインサートの現物」を手渡して,本件出願を依頼した旨主張している 点)などにおいて,大きく変遷し,その変遷の理由について合理的な説 明がされていない。 しかるところ,上記変遷した部分に係る1審原告の当審における主張 に沿う証拠としては,1審原告代表者の手帳(「Business D iary’98」。甲42)の「予定表\」中の「6月11日」欄に「H 部長 線材渡し タングレス」との記載部分,1審原告のMが2005 年(平成17年)6月9日に1審被告のHに送信した電子メール(甲4 3)中の「(1審原告代表者が)「将来何かの役に立つ事も有ろうかと\n考え特許出願した。」と申しております。」,「提案の日時は1998\n年6月11日」,「提案の場所は株式会社アドバネックス本社社長室」 との記載部分がある。 しかし,これらの証拠からは,1審原告代表者が平成10年6月11\n日に1審被告を訪れてHに対してタングレスの線材を渡した事実を認定 することができるものの,当審における1審原告の主張に係る1審原告 代表者が本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯,1審原告主\n張の上記線材を三晃のJに作製させるに至った経緯,1審原告代表者の\nK弁理士に対する本件出願の依頼の経緯を認めることはできない。他に これを認めるに足りる証拠はない。 また,1審原告代表者が1審被告のHに渡したタングレスの線材は,\n凹部及びテーパ部が加工済みであったことが認められるものの,上記の とおり,1審原告主張の上記線材を三晃のJに作製させるに至った経緯 を認めるに足りる証拠はない以上,上記のような形状の線材が存在する からといって直ちに1審原告代表者が本件発明をしたものと認めること\nはできない。
イ かえって,以下のような事情が認められる。 (ア)a 前記2(5)ア認定のとおり,1審原告代表者が平成10年6月11\n日に1審被告のHに渡した凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材は,1審原告代表者が三晃のJに依頼して作製されたものと認\nめられる。 しかるところ,1審原告代表者が,1審原告を設立し,1審原告が\n1審被告が製造するタング付き螺旋状コイルインサート(商品名「ス プリュー」)を販売するに至った経緯(前記2(1)),1審原告代表者\nが,1審被告の監査役に在任中に,福島工場をしばしば訪問しており (前記2(6)イ),その際に,同工場の製造ラインを視察する機会があ ったものと認められること,1審原告代表者は,本件出願をK弁理士\nに依頼する際に,本件発明の内容を口頭で説明していること(前記2 (5)イ)を総合すると,1審原告代表者は,螺旋状コイルインサートの\n形状,タング付きとタングレスの違い,螺旋状コイルインサートの材 料として用いる線材の形状,螺旋状コイルインサートの一般的な製造 方法等について知識を有していたものと認められる。 そして,1審原告代表者が,福島工場を訪問した際に1審被告の従\n業員から福島工場におけるタングレス螺旋状コイルインサートの製造 状況等について話を聞いたり,取引関係者と話をする中で,福島工場 では,凹部及びテーパ部が加工済みのタングレスの線材を使用してタ ングレス螺旋状コイルインサートを製造していることを認識するに至 ったものと推認することができる。 そうすると,1審原告代表者が,自ら本件発明をしたものでないと\nしても,三晃のJに対し,凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材のサンプルの作製を依頼することは可能であったものと認めら\nれる。また,三晃は,1審被告に対し,螺旋状コイルインサート用の 線材を供給していたから(前記2(1)イ),タングレス螺旋状コイルイ ンサート及びその材料の線材の形状,螺旋状コイルインサートの一般 的な製造方法等について知識を有していたものと認められ,1審原告 代表者から詳細な説明を受けたり,具体的な線材のサンプルを示され\nなくても,自社の螺旋状コイルインサート用の線材を加工して1審原 告代表者から依頼のあった上記加工済みサンプルを作製することが可\n能であったものと認められる。\nしたがって,1審原告代表者が上記加工済みのタングレスの線材を\n三晃のJに依頼して作製させたことは,1審原告代表者が本件発明を\nしたことの裏付けとなるものではないというべきである。
・・・
ウ 前記ア及びイの認定事実に照らすと,1審原告代表者の供述及び前記陳\n述書(甲11)中の1審原告代表者が本件発明をした旨の部分は措信する\nことができない。他に1審原告代表者が本件発明の技術的思想(前記1(2)) を着想し,又は,その着想を具体化することに創作的に関与したことを認 めるに足りる証拠はない。
・・・
4 反訴請求−争点(2)ア(本訴の提起及び追行の違法性)及びイ(1審被告の損
・・・
これを本件についてみると,前記2(8)のとおり,1審原告は,本訴提起前 の平成27年3月23日付け回答書をもって,1審被告から,1審原告代表\n者は本件発明者の真の発明者ではなく,1審原告代表者を発明者とする本件\n出願は冒認出願であり,本件特許には冒認出願の無効理由があるから,特許 法104条の3第1項により,本件特許権を行使することができない旨の指 摘を受けていたにもかかわらず,同年11月10日に本訴を提起したもので あること,前記3(2)で説示したとおり,1審原告代表者が本件発明の発明\n者であることを裏付ける客観的な証拠がないのみならず,1審原告代表者が\n本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯,1審原告代表者のK弁理\n士に対する本件出願の依頼の経緯などの1審原告代表者が本件発明をした\nことに関する重要な部分の主張を大きく変遷させ,変遷後の当審における1 審原告の主張に沿う証拠はほとんど提出されていないものと認められるこ とに照らすと,1審原告においては,本訴で主張する権利又は法律関係が事 実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常人であれば 容易にそのことを知り得たのにあえて本訴を提起し,これを追行したものと 認められる。 そうすると,1審原告による本訴の提起及び追行は,裁判制度の趣旨目的 に照らして著しく相当性を欠くものといえるから,1審被告に対する違法な 行為に当たるものと認められる。 705/088705
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.06.28
平成30(行ケ)10043 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月26日 知的財産高等裁判所(3部)
被告は,【0029】及び【0116】を含む本件明細書の記載並びに 技術常識からすれば,当業者は,1) ヒスチジンの置換箇所を特定するた めに,抗体の可変部位のアミノ酸残基220個について1つずつ網羅的に ヒスチジン置換した抗体を作製し,そのKD値を測定して置換位置を特定 する試験(以下「前半の試験」という。),及び2) 上記1)により所望のp H依存性を示す(有望であることないしpH依存的結合特性がもたらされ たことが判明した)場合に血中動態の試験(以下「後半の試験」という。) を行うことにより,本件発明1を実施することができると主張する(被告 主張ヒスチジンスキャニング)。 そこで検討するに,本件明細書の【0029】にはアラニンスキャニン グに関する記載があり,本件出願日当時,アミノ酸配列の各残基を1つず つアラニンに置換して各残基の役割を解析する手法としてアラニンスキャ ニングは技術常識であったと認められる(乙19〜23)。したがって, 本件明細書に接した当業者は技術常識に基づき,抗体の可変部位のアミノ 酸残基220個について1つずつ網羅的にヒスチジン置換をした抗体を作 製することは可能であるということができる。\n被告は,抗体を作製した後のヒスチジン置換位置の特定について,「所 望のpH依存性を示す(有望であること,ないし,pH依存的結合特性が もたらされたことが判明した)箇所」という基準により行うことを主張し ているが,本件明細書にはこのような記載はないし,本件明細書や証拠上 現れた技術常識によってもどのような基準に基づいてヒスチジン置換位置 を特定すれば,本件発明1に含まれる医薬組成物全体について実施するこ とができるのかが明らかではない。 このように,本件明細書には,被告主張ヒスチジンスキャニングによっ て,どのようにヒスチジン置換位置を特定するかの情報が不足しており, 本件明細書の発明の詳細な説明に,当業者が,明細書の発明の詳細な説明 の記載及び出願当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要すること なく,本件発明1を実施することができる程度に発明の構成等の記載があ\nるということはできない。
イ 仮に,被告主張ヒスチジンスキャニングの前半の試験におけるヒスチジ ン置換位置の特定について,1)本件明細書の【0029】に記載された「変 異前と比較してKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が大きくなった」箇所,あるいは, 2)特許請求の範囲に記載された「所定のpH依存的結合特性を有する」箇 所を意味すると理解するとしても,次のとおり,このような被告主張ヒス チジンスキャニングにより本件発明1に係る医薬組成物全体を実施できる とはいえない。
(ア) 本件発明1の「少なくとも可変領域の1つのアミノ酸がヒスチジンで 置換され又は少なくとも可変領域に1つのヒスチジンが挿入されている ことを特徴とする」「抗体」は,複数のヒスチジン置換がされた抗体を含 むものであるところ,被告は,複数のヒスチジン置換がされた抗体のヒ スチジン置換位置の特定については,前半の試験により特定された単独 のヒスチジン置換位置を組み合わせれば足りると主張する。
(イ) そこで,被告の主張する単独の置換位置を組み合わせる方法により, 本件発明1の複数のヒスチジン置換がされた抗体における,ヒスチジン 置換位置を常に特定することができるかを検討する。 a 本件明細書には,本件発明1の,複数のヒスチジン置換がされたこ とを特徴とする,所定のpH依存的結合特性を有する抗体におけるヒ スチジン置換箇所について,必ず被告主張ヒスチジンスキャニングの 前半の試験により特定できることを示す記載は見当たらない。また, このことについての本件出願日当時の技術常識を示す的確な証拠もな い。
そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明に,複数のヒスチジン 置換がされた場合について実施することができる程度に発明の構成等\nの記載があるということはできない。
◆判決本文
関連事件です。いずれも同じように実施可能要件を満たしていないと判断されています。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.06.27
平成30(行ウ)424 その他 行政訴訟 令和元年6月18日 東京地方裁判所
特許法112条の2第1項は,同法112条4項の規定により消滅したもの とみなされた特許権の原特許権者は,同条1項の規定により特許料を追納する ことができる期間内に特許料等を納付することができなかったことについて の「正当な理由」があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その特 許料等を追納することができると規定する。 この規定は,平成23年法律第63号による改正前の特許法112条の2第 1項では,期間徒過後に特許料等を追納できる場合について原特許権者の「責 めに帰することができない理由」により追納期間内に特許料等を納付できなか った場合と規定していたところ,国際調和の観点から,より柔軟な救済を可能\nとすることを目的として,手続期間を徒過した場合の救済を認める要件につき, 特許法条約の規定を踏まえて「Due Care(相当な注意)」の概念を採用 したものであると解される。 これらを踏まえると,特許法112条の2第1項にいう「正当な理由」があ るときとは,原特許権者(その手続を代理する者を含む。)において一般に求め られる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観的な 事情により,同法112条1項の規定により追納することができる期間内に特 許料等を納付することができなかった場合をいうと解するのが相当である。 原告らは,本件特許事務所から平成25年11月に本件特許権について第4 年分の年金のリマインダの送付を受け,電子メールに添付した本件注文書によ って,本件特許事務所に対して本件特許権の第4年分の年金納付の指示をした と主張する。 しかし,上記電子メールや本件注文書には特許番号が記載されておらず,ま た,特許番号に代替し得る本件特許権を特定するための情報は全く記載されて いなかった。特許番号を記載しなかった理由は,原告らの年金納付担当者の気 力がなかったというものであった。かえって,本件特許権の第4年分の年金の 納付期間の終期が平成25年12月3日であったにもかかわらず,電子メール 及び本件注文書には,年金納付を指示する特許権の年金が第17年分のもので あり,その納付期間の終期が同月16日であることをうかがわせる記載のみが あった。本件特許事務所は原告らの特許権について多数の特許出願及び更新手 続を管理しており,その特許権の中には年金の納付期間の終期が前同日のもの が含まれていた。
更に,本件特許権について年金納付の指示をしたのであれば,本件特許事務 所からそれに対応してその指示の受領の通知と本件特許権についての請求書 等が送付されるところ,そのような通知や請求書の送付はなく,原告らがそれ に気付くことはなかった。 これらによれば,本件注文書に「2013年11月15日付けの最終連絡に 基づく」旨が記載されていて,原告ら主張のとおり同最終連絡に仮に本件特許 権の年金納付の要否を尋ねる旨の記載があったとしても,原告らは,年金納付 をする特許権を容易に特定することができ,また,本件特許事務所が管理する 原告らの特許権には年金納付をする必要がある別の特許権があるにもかかわ らず,本件注文書やその電子メールをもって,本件特許事務所に対し年金納付 の対象の特許権が本件特許権であることを明確に認識できる形でその納付を 指示したとは到底いい難い。そして,原告らは,年金納付の指示をすれば当然 あるはずの請求書の送付等がないことを看過していた。原告らについて,本件 において,一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと 認められる客観的な事情があるとは認められない。 これに対し,原告らは,本件特許事務所は世界的なランキングに掲載される 有力な事務所であり,年金納付が確実に行われるように体制を整備していたの であって,そのような外部組織を適切に選任した以上,原告らには特許法11 2条の2第1項の「正当な理由」があるなどと主張する。 しかし,前記のとおり,本件特許権の年金の納付についての原告らの指示が 明確であったとはいい難く,また,その後,原告らは,当然あるはずの請求書 の送付等がないことを看過していたのであって,本件特許事務所を選任したこ とによって「正当な理由」があるとはいえない。 以上によれば,本件期間徒過について「正当な理由」(特許法112条の2第 1項)があるとはいえないから,原告らの請求には理由がない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2019.06.25
平成30(ワ)10130 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年4月24日 東京地方裁判所(29部)
ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なか った技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想 に基づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にあることに照らすと,特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のう\nち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。\n
イ これを本件についてみると,前記のとおり,本件発明は,従来の現金主義に 基づく公会計では,政策レベルの意思決定に利用することは困難であったことに鑑 みて,国民が将来負担するべき負債や将来利用可能な資源を明確にして,政策レベルの意思決定を支援することができる会計処理方法及び会計処理を行うためのプロ\nグラムを記録した記憶媒体を提供することを課題とし,その課題を解決するための 手段として,純資産の変動計算書勘定を新たに設定し,当該年度の政策決定による 資産変動を明確にするとともに,将来の国民の負担をシミュレーションすることが できる会計処理方法を提案するものである。 そして,前記のとおり,本件発明の処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘 定)は,国家の政策レベルの意思決定を記録,会計処理するために設定された勘定 であるのに対し,資金収支計算書勘定は,従来の公会計において単式簿記システム で扱ってきた資金(現金及び現金同等物)の受入と払出を記録するものであり,閉 鎖残高勘定(貸借対照表勘定)及び損益勘定(行政コスト計算書勘定)も,企業会計における複式簿記・発生主義会計として用いられてきたものであるから,本件発\n明の課題解決手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民 の負担のシミュレーションは,国家の政策レベルの意思決定を対象とする処分・蓄 積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)によって行われるものと解するのが相当で ある。その上で,本件発明は,資金収支計算書勘定と閉鎖残高勘定(貸借対照表勘定),損益勘定(行政コスト計算書勘定)と処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計\n算書勘定),処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)と閉鎖残高勘定(貸 借対照表勘定)の各勘定連絡を前提として,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に,当該年度における純資産増加(C3,C4)及び純資産減少(C1,\nC2)並びにこれらの差額(収支尻)である純資産変動額(C5)が表示される構\ 成を採用しており,将来の国民の負担をシミュレーションするためには資産変動の 内訳も認識される必要があると認められることにも照らせば,本件発明の課題解決 手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミ ュレーションは,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に表示される純資産増加(C3,C4)及び純資産減少(C1,C2)並びにこれらの差額(収支\n尻)である純資産変動額(C5)によって行われるものと解するのが相当である。 また,上記のような解釈は,本件発明によるシミュレーションに関する本件明細 書の説明とも整合する。すなわち,本件明細書には,「次に,本発明の特徴である シミュレーションについて説明する。損益外純資産変動計算書には,行政コストと, 当期に費消する財源措置で国民の純資産として将来に残る資産の科目からなる財源 措置とそれ以外の科目からなる財源措置と,当期に調達する財源で国民の純資産と して将来に残る資産の科目からなる財源とそれ以外の科目からなる財源と,国民の 純資産として将来に残る資産の原因別増減額と,再評価による差額と,国民の純資 産として将来に残る資産の原因別増減額充当のために手当てされた財源と,会計処 理により,それらから導き出された現役世代の負担額と,将来世代の負担額,赤字 公債相当額,建設公債相当額などの金額が表の中に表\示される。」(【0069】), 「本発明によるシミュレーションは,現役世代の負担額と,将来世代の負担額,赤 字公債相当額,建設公債相当額などの金額に,目標とするべき金額を設定して,行 政コストや財源措置をどのように調整すれば目標とするべき金額が達成できるかを 演算するための手順を予め複数のプログラムとして設定する。」(【0070】)などとして,本件発明によるシミュレーションについて,損益外純資産変動計算書に表\示される行政コスト,財源措置,財源及び資産の原因別増減額等から導き出される 現役世代の負担額,将来世代の負担額,赤字公債相当額及び建設公債相当額等によ って行われることが説明されており,本件発明の課題解決手段である当該年度の政 策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミュレーションが処分・蓄 積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に表示される純資産増加(C3,C4)及び純資産減少(C1,C2)並びに純資産変動額(C5)によって行われるという\n上記の解釈と整合する。
そうすると,本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,国家の政策レベルの 意思決定に係る会計処理を対象とする処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘 定)を採用した上で,同勘定に表示される純資産減少(C1,C2)を構\成する勘 定科目の内容を具体的に規定する構成要件Hは,本件発明の課題解決手段を具体化する特有の技術的思想を構\成する特徴的部分であると認めるのが相当である。したがって,本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,社会保障給付等の損 益外で財源を費消する取引を「財源措置(C2)」に含める構成(構\成要件H)は, 本件発明の本質的部分であると認められる。
ウ この点,原告は,社会保障給付を処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書 勘定)の「財源措置(C2)」に含める構成は,本件発明の非本質的部分であるとし,その理由として,1)本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的原理は,純資産 変動計算書勘定の存在,4つの勘定の勘定連絡の設定,自動仕訳と勘定連絡を通じ 政策レベルの意思決定と将来の国民の負担をシミュレーションできる会計処理方法 のプログラミングにあり(本件明細書【0008】,【0010】,【0021】, 【0031】参照),社会保障給付を行政コスト計算書に計上する被告製品の構成は,本件発明の特徴的原理と無関係であること,2)社会保障給付を処分・蓄積勘定 (損益外純資産変動計算書勘定)の借方の財源措置に計上する構成を,損益勘定(行政コスト計算書勘定)に計上する構\成に置換したとしても,損益勘定(行政コスト計算書勘定)は処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)に振り替えら れるから,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の借方と貸方の差額 (収支尻)に示されている損益外の純資産変動額は同額となり,純資産変動額や将 来償還すべき負担の増減額を財務諸表の中に表\示することにより当該年度の政策決 定による資産変動を明確にするとともに,将来の国民の負担をシミュレーションで きるという同一の作用効果を奏することなどを主張する。 しかしながら,前記のとおり,本件発明は,国家の政策レベルの意思決定を対象 とするものとして,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)という新たな 勘定を設定するものであり,当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の 国民の負担のシミュレーションを通じた政策レベルの意思決定の支援は,処分・蓄 積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)によって実現されるものと解するのが相当 であり,本件明細書においても,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定) 以外の勘定を用いて将来の国民の負担のシミュレーション等が行われることは説明 されていない(原告が指摘する本件明細書【0031】は,適切な勘定連絡を設定 することがシミュレーションをする前提として必要になることを説明するものであ り,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)以外の勘定を用いてシミュレ ーションを行うことを説明するものとは認められない。)。 そうすると,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の借方に計上され る金額の総額及び貸借差額が結果的に同一になるとしても,処分・蓄積勘定(損益 外純資産変動計算書勘定)以外の勘定を参照しなければ,国家の政策レベルの意思 決定に関する勘定科目(社会保障給付を含む)及びその金額が明らかにならないよ うな構成は,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)を通じて国家の政策レベルの意思決定を支援する本件発明とは作用効果が異なるというべきである。\n
エ また,原告は,従来技術に対する本件発明の貢献の程度は大きいから,本件 発明の本質的部分は,「処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の導入に より,将来世代に対して負担が現実的に先送りされた金額や将来利用可能な資源の増加額を可視化する」という構\成要件Hを上位概念化したものであって,被告製品は,そのような構成を備えていると主張する。原告の主張は必ずしも明確でないが,従来技術に対する本件発明の貢献の程度に\n照らし,本件発明の構成のうち,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計算書勘定)の設定以外のものは非本質的部分であると主張する趣旨であれば,本件出願日前に\n頒布された刊行物である乙12文献において,資金収支計算書勘定,貸借対照表勘定及び行政コスト計算書勘定に加えて,納税者,すなわち,国民の資産の変動を明\nらかにするための勘定として,財源措置・納税者持分増減計算書勘定を設ける構成が示されていることに照らし,少なくとも,処分・蓄積勘定(損益外純資産変動計\n算書勘定)の設定のみを従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると認めることはできないから,採用することができない。\n
オ そこで,被告製品をみると,被告製品では,前記のとおり,社会保障給付が 行政コスト計算書に計上されており,純資産変動計算書には,行政コスト計算書の 収支を基礎付ける勘定科目(社会保障給付を含む)及びその金額が示されていない ことが認められ,「純経常費用(C1)と並んで財源措置(C2)という項目もあ るが,これは具体的に言えば社会保障給付や…を指しており」(構成要件H)を充足するとはいえないから,本件発明と本質的部分において相違する。したがって,\n被告製品は,均等の第1要件を満たすとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.06.21
平成29(ワ)9201 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月20日 大阪地方裁判所
特許法102条3項は,「特許権者…は,故意又は過失により自己の特許権 …を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨 規定する。そうすると,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準と し,そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 ここで,特許法102条3項については,「その特許発明の実施に対し通常受け るべき金銭の額に相当する額」では侵害のし得になってしまうとして,平成10年 法律第51号による改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。また,特 許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許の効力が明らか ではない段階で,被許諾者が最低保証額を支払い,当該特許が無効にされた場合で あっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなど,様々な契約上の制 約を受けるのが通常である状況の下で,事前に実施料率が決定される。これに対し, 特許権侵害訴訟で特許権侵害に当たるとされた場合,侵害者は,上記のような契約 上の制約を負わない。これらの事情に照らせば,同項に基づく損害の算定に当たっ て用いる実施に対し受けるべき料率は,必ずしも当該特許権についての実施許諾契 約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく,むしろ,通常の実施 料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべきである。 したがって,特許法102条3項による損害を算定する基礎となる実施に対し受 けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それ が明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,2)当該特 許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能\n性,3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態 様,4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。
(イ) 実施料の相場(1))
「実施料率〔第5版〕」(社団法人発明協会研究センター編,平成15年発行。 甲38)によれば,「医薬品・その他の化学製品」(イニシャル無)の技術分野に おける平成4年度〜平成10年度の実施料率の平均値は7.1%であり,昭和63 年度〜平成3年度に比較して上昇しているところ,その要因として,「実施料率全 体の契約件数は減少しているものの,8%以上の契約に限れば件数が増加しており, この結果,…実施料率の平均値が高率にシフトしている。」,「この技術分野が他 の技術分野と比較して実施料率が高率であることと,実施料率の高率へのシフト傾 向は,医薬品が支 れている。また,「バイオ・製薬」の技術分野においては,平均6.0%,最大値 32.5%,最小値0.5%とされている。
(ウ) 本件における実施料率を考えるにあたり考慮すべき事情(2)〜3))
a 原告は,本件各発明の技術的価値は極めて優れたものであり,また,速乾性 手指消毒剤の市場における泡状の製品の占めるシェアの動向から,経済的にもその 価値は高いなどと主張する。 泡状の速乾性手指消毒剤である被告各製品に係る宣伝広告(甲5,7,8),製 品情報(甲6,9)及び医薬品インタビューフォーム(甲10)では,液状の速乾 性手指消毒剤では手に取ったときにこぼれやすく,ジェル状の速乾性手指消毒剤で は増粘剤が配合されているためにポンプのノズルの詰まりや繰り返し塗布したとき の使用感が問題になることがあったところ,被告各製品は,これらの問題点を解決 する製品である旨がうたわれていることが認められる。 また,本件各発明の実施品である泡状の速乾性手指消毒剤(平成23年6月発売。 甲39,41の1〜41の5,弁論の全趣旨)の販売業者が医療関係者向けに開設 したウェブサイト(甲40)には,泡が目に見えるので消毒範囲が確認できるとと もに,泡が消えるまで塗り広げることが消毒時間の目安にもなる点や,増粘剤が入 っていないので,ポンプが詰まらず,手に擦り込んでもヨレ(増粘剤入りの消毒剤 や化粧品を手に擦り込んだ際に出る糊状の剥離物)が出ないことがうたわれている。 さらに,平成30年9月26日付け薬事日報ウェブサイトの新薬・新製品情報に関 する記事(甲44)においては,第三者の販売に係る「医薬品として日本で初めて 承認された低アルコール濃度72vol%の手指殺菌・消毒剤」の出荷開始予定について\n報じる中で,「同品の登場によって,手指消毒剤の課題であったアルコールによる 手肌への刺激が低減され,…このほか,▽きめ細かく弾力のある泡で,手からこぼ れるリスクを軽減する▽泡が目でしっかり見えるため,手指消毒の状態を確認でき る−といった使用感も特徴。」,「現在,医療分野における手指消毒剤市場は約1 60億円とされ,構成比は液状が6割,ジェル状が3割,泡状が1割という状況。\nただ,液状の構成比は年々減少しており,今後はジェル状と共に泡状も伸びていく\nことが見込まれている。」とされている。 加えて,被告サラヤが実施したアンケートによれば,アンケート対象者である医 療従事者の施設で使用されている速乾性手指消毒剤の種類は,平成25年にはジェ ルタイプ67%,液タイプ27%,泡タイプ6%であったものが,平成27年には それぞれ66%,24%,10%となっている(甲42,43)。 以上の事情を総合的に見ると,被告各製品と本件各発明の実施品に加え,第三者 の製品も,本件各発明の奏する作用効果(前記3(2)ア)と同趣旨と見られる効果を 利点としてうたっていることなどに鑑みれば,泡状の手指消毒剤において本件各発 明が持つ技術的価値は高いものと見られる。また,手指消毒剤の市場において,泡 状の製品のシェアが徐々に高まっていることがうかがわれることに鑑みると,本件 各発明の経済的価値も積極的に評価されるべきものといえる。もっとも,後者に関 しては,ジェル状の製品のシェアはなお維持されているといってよいことに鑑みる と,その評価は必ずしも高いものとまではいえない。実施料率の決定要因としては, 当該特許発明の技術的価値よりも経済的価値の方がより影響力が強いと推察される ことに鑑みると,このことは軽視し得ない。 これに対し,被告らは,本件各発明は平均的な発明に比して技術的に優れた発明 ではなく,また,泡状の手指消毒剤のシェアの拡大は直接的には当該製品の販売事 業者の営業努力によるものであり,シェア拡大をもって特許の経済的価値が高いと はいえないなどと主張する。 しかし,進歩性が認められる本件各発明の奏する作用効果と同趣旨と見られる効 果が実際の製品の利点としてうたわれていることなどに鑑みれば,上記のとおり本 件各発明の技術的価値は高いものと評価するのが相当である。また,販売事業者が 営業活動に当たって相応の営業努力を行うことは当然である上,泡状の手指消毒剤 に係る営業方法等が,ジェル状ないし液状のものに係る営業方法等と比較して,格 別のものであると見るべき事情もない。 これらのことから,この点に関する被告らの主張は採用できない。
b 被告各製品は,被告製品1(500mLの泡ポンプ付が定価1760円,3 00mLの泡ポンプ付が1200円,80mLの泡ポンプ付が670円,600m Lのディスペンサー用が2000円。甲5,28,乙13),被告製品2(500 mLの泡ポンプ付が1760円,300mLの泡ポンプ付が1200円,200m Lの泡ポンプ付が930円,80mLのものが670円,600mLのディスペン サー用が2000円。甲8,29,乙14)いずれも比較的低価格である。反面, これを踏まえて被告各製品の売上高を見ると,その販売数量は多いといえるから, 被告各製品はいわゆる量産品であり,利益率は必ずしも高くないと合理的に推認さ れる。この点は,本件各発明を被告各製品に用いた場合の利益への貢献という観点 から見ると,実施料率を低下させる要因といえる。
(エ) 小括
上記(イ)及び(ウ)の各事情を斟酌すると,特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき,本件での実施に対し受けるべき料率については,7%とするのが相当 である。これに反する原告及び被告らの各主張は,いずれも採用できない。 ウ 「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」 以上によれば,原告が被告らによる本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額 に相当する額は,売上高に7%を乗じて算定すべきこととなる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.06.21
平成30(ワ)38579 著作権 民事訴訟 平成31年4月26日 東京地方裁判所
そこで検討するに,被告株式会社フジテレビジョン作成のDVDに収録されている 音声には,「A」(甲57の1),「ストップ。ははははは。」(甲61の1),「あたた」(甲62の1)と認識される可能性が否定できないものがあるが,これらの音声はいずれもその発言者が上記のように認識される可能\性がある音声を偶々発言したにす ぎないものと認められるから,その意味内容や表現として,原告の名前を発言したも\nのとも,原告の平穏生活権を侵害する発言とも,原告作品を発言したものとも認めら れない。そして,原告が提出する映像(甲1ないし68の各1)には,上記以外に, その反訳書(甲1ないし68の各2)において原告が指摘する発言が収録されている とは認められないから,被告らにおいて,原告の著作権(複製権,翻案権,同一性保 持権又は公表権),名誉権,プライバシー又は平穏生活権を侵害し,又は脅迫若しく\nは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと又はそのDVDを販売する などしたことを認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。そうす ると,原告の被告らに対する請求はいずれも理由がない。
2019.06.17
平成30(ネ)10081等 不正競争行為差止等請求控訴事件等 不正競争 民事訴訟 令和元年5月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審被告らは,一審被告会社は,「マリカー」の標準文字からなる本件商標を 有しており,「マリカー」という標章を使用する正当な権限を有するから,仮に 被告標章第1の使用行為が不正競争行為に該当するとしても,差止請求や損害賠 償請求は認められない旨主張する。 しかし,本件商標の登録出願がされたのは平成27年5月13日であるところ, 前記4(2)で検討したとおり,その頃までには,原告文字表示マリオカート及び「M ARIO KART」表示は日本国内で著名となっており,かつ原告文字表\示マリカーも, 「マリオカート」を示すものとして,日本国内の本件需要者の間で周知になってい て,かつ後記8のとおり,一審被告会社の代表者である一審被告Yはそのことを知\nっていたものと認められる。
これに加え,1)一審被告会社が設立当初の商号を敢えて「株式会社マリカー」と していたこと,2)平成28年11月15日当時に品川第1号店において配布されて いた本件チラシには,「マリオのコスプレをして乗ればリアルマリオカート状 態!!」と記載されていたこと(甲3,4),3)平成28年8月12日当時に品川 第1号店サイト1には,「みんなでコスプレして走れば,リアルマリカーで楽しさ 倍増」と記載されるとともに,「マリオ」のコスチュームを着用した人物の写真が 同記載に併せて掲載され,また,平成29年2月23日当時に品川第1号店サイト 1に「みんなでコスプレして走れば,リアルマリカーで楽しさ倍増」と記載されて いたこと(甲6の1,甲35),4)平成29年2月23日当時に,河口湖店サイト に「スーパーマリオのコスプレをして乗れば,まさにリアルマリオカート状態!!」 と記載されていたこと(甲6の2),5)後記6認定のとおり,一審原告の著名な商 品等表示である原告表\現物に類似する被告標章第2のコスチュームを用いた宣伝行 為や本件各コスチュームを用いた本件貸与行為が行われ,特に,平成27年11月 2日にアップロードされた本件動画1(甲42の1,甲43の1)の0:05秒時 点には「MARIOKART」という英語の音声が収録され,かつ同音声について,「マリ オカート」の日本語字幕が付けられていたことも考え併せると,一審被告会社は, 周知又は著名な原告文字表示及び「MARIO KART」表示が持つ顧客吸引力を不当に利\n用しようとする意図をもって本件商標に関する権利をゼント社より取得したものと 推認することができる。
したがって,一審被告会社が,一審原告に対し,本件商標に係る権利を有すると 主張することは権利の濫用として許されないというべきであり,一審被告らの上記 主張は理由がない。
なお,一審被告らは,原告文字表示マリカーは本件需要者である訪日外国人の間\nでは周知ではないと主張するが,これまで検討してきたとおり,本件需要者は訪日 外国人に限られないから,一審被告らの主張はその前提を欠いており,採用するこ とができない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2019.06.12
平成28(ワ)11067 著作権侵害差止請求事件 令和元年5月21日 大阪地方裁判所
プログラムは,「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこ\nれに対する指令を組み合せたものとして表現したもの」(著作権法2条1項10号\nの2)であり,所定のプログラム言語,規約及び解法に制約されつつ,コンピュー ターに対する指令をどのように表現するか,その指令の表\現をどのように組合せ, どのような表現順序とするかなどについて,著作権法により保護されるべき作成者\nの個性が表れることになる。\nしたがって,プログラムに著作物性があるというためには,指令の表現自体,そ\nの指令の表現の組合せ,その表\現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり, かつ,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性,すなわち,表\現上の創作性 が表れていることを要するといわなければならない(前掲知財高裁平成24年1月\n25日判決)。
(2) 原告プログラムのソースコードの創作性について\n
ア 原告プログラムのソースコードのうち創作性が認められ得る部分\n前記1のとおり,原告プログラムは,原告が作成していたレジアプリケーション ソフトを基に,原告と被告が協議しつつ,原告がソ\ースコードを書くことにより完 成したものであって,顧客の携帯電話端末を注文端末として使用することができる 点や,店舗において入力した情報を店舗(クライアント)側ではなくサーバー側プ ログラムを介してデータベースに保持し,主要な演算処理を行う点等について,従 来の飲食店において使用されていた注文システムとは異なる新規なものであったと 一応推測することができる。また,原告の書いた原告プログラムのソースコード(甲\n3)は,印刷すると1万頁を超える分量であって,相応に複雑なものであると推測 できる(原告本人)。 そして,6)データベースにおける正規化されたデータの格納方法や,注文テーブ ル及び注文明細テーブルに全てのアプリケーションからの注文情報を集約するため の記述(甲18)等に,原告の創作性が認められる可能性もある。\n
イ コンピュータに対する指令の創作性について 前記(1)のとおり,プログラムの著作物性が認められるためには,プログラムによ り特定の機能を実現するための指令の表\現,表現の組合せ,表\現順序等に選択の幅 があり,ありふれた表現ではないことを主張立証することが必要であって,これら\nの主張立証がなされなければ,プログラムにより実現される機能自体は新規なもの\nであったり,複雑なものであったとしても,直ちに,当該プログラムをもって作成 者の個性の発現と認めることはできないといわざるを得ない。
コンピュータに対する指令(命令文)の記述の仕方の中には,コンピュータに特 定の単純な処理をさせるための定型の指令,その定型の指令の組合せ及びその中で の細かい変形,コンピュータに複雑な処理をさせるための上記定型の指令の比較的 複雑な組合せ等があるところ,単純な定型の指令や,特定の処理をさせるために定 型の指令を組合せた記述方法等は,一般書籍やインターネット上の記載に見出すこ とができ,また,ある程度のプログラミングの知識と経験を有する者であれば,特 定の処理をさせるための表現形式として相当程度似通った記述をすることが多くな\nるものと考えられる(乙12,被告代表者)。\nそうすると,ソースコードに創作性が認められるというためには,上記のような,\n定型の指令やありふれた指令の組合せを超えた,独創性のあるプログラム全体の構\n造や処理手順,構成を備える部分があることが必要であり,原告は,原告プログラ\nムの具体的記述の中のどの部分に,これが認められるかを主張立証する必要がある。
ウ 本件における主張立証
被告は,原告プログラムについて,1)レジ,2)キッチンモニター及び3)マスタメ ンテナンスの各プログラムのソースコードは,汎用性のあるソ\ースコードであり創 作性が認められないと主張し,被告代表者の陳述書(乙12)において,上記1)〜 3)の各プログラムのソースコード(甲4〜6)の大部分について,指令の表\現に選 択の幅がなく,一般書籍(乙6)やインターネット上にも記載のあるありふれたも のであることを指摘する。また,被告は,原告プログラムのうち他の構成について\nも,指令の組合せがありふれたものであると主張する。 これに対し,原告は,4)スタッフオーダー等によって入力された情報を,5)サー バー側プログラムを経由して飲食店用に最適化された6)データベースにおいて一括 管理し,レジやキッチンに出力する機能が一体となる点に創作性が認められる旨主\n張するが,これは,プログラムにより実現される機能が新規なもの,複雑なもので\nあることをいうにとどまり,それだけでプログラムに創作性が認められることには ならないことは前述のとおりであるところ,原告は,具体的にどの指令の組合せに 選択の幅があり,いかなる記述がプログラム制作者である原告の個性の発現である のかを,具体的に主張立証しない。 むしろ,乙6,12によれば,原告が開示した原告プログラムの1)レジ,2)キッ チンモニター及び3)マスタメンテナンスのソースコード(甲4〜6)に表\れる指令 の組合せのうちの多くは,原告プログラムの作成日以前から一般的に使用されてい る指令であり,変数や条件等の文字列の場所が決まっているため独創的な表現形式\nを採る余地のないものであって,インターネット上に使用例が公開されているもの も多いことが認められる。
エ まとめ
前記認定したところによれば,原告は,平成23年3月の時点で,一定のレ ジアプリケーションを完成していたが,これは「でんちゅ〜」そのものではなく, 「でんちゅ〜」を事業化しようとする被告代表者と協議しながら,「でんちゅ〜」\nのプログラムを開発したこと,平成24年12月までの原告と被告との法的関係は 不明であるが,「でんちゅ〜」の事業化の主体は被告であり,原告は,被告の依頼 又は内容に関するおおまかな指示を受けてプログラムの開発を行ったこと,「でん ちゅ〜」は平成23年に飲食店に試験導入され,平成24年以降本格導入されたこ と,原告は,少なくとも同年12月から平成27年7月の退社までの2年半余り, 被告の被用者として被告の指示を受け,前記導入の結果を踏まえ,「でんちゅ〜」 の改良,修正等に従事したこと,以上の事実が認められる。 上記事実の中で,平成24年5月22日の時点における原告プログラムの構\n成が,ありふれた指令を組み合わせたものであるには止まらず,原告の個性の発現 としての著作物性を有していたと認めるに足りるものであることの立証がなされて いないことは,既に述べたところから明らかである。 また,平成23年の導入以降,「でんちゅ〜」については,段階的に改良や 修正が施され,原告自身も,少なくとも2年半余り被告の従業員としてその開発, 修正に従事しており,前記認定のとおり,原告プログラムと被告プログラムには相 当程度の差異が認められるのであるから,仮に原告プログラムの一部に,原告の個 性の発現としての創作性が認められる部分が存したとしても,その部分と同一又は 類似の内容が被告プログラムに存すると認めるに足りる証拠はなく,結局のところ, 平成24年5月22日時点の原告プログラムの著作権に基づいて,現在頒布されて いる被告プログラムに対し,権利を行使し得る理由はないといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2019.06.11
平成14(ワ)13569等 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成16年4月20日 大阪地方裁判所
。 ア 被告サイトのトップ頁には、「就職・転職」、「採用」、「株式会社ディスコについて」の項目がある。求職者は、無料の登録手続を採った後、被告サイト上の情報を無料で入手、利用することができる。被用者を募集しようとする企業は、被告に依頼し、被告サイトに自己の情報を掲載することができる。
イ 被告サイトの「就職・転職」の頁には、被用者を募集している企業の「会社名」、「業種」、「ポジション」、「勤務地」及び「オンライン応募」が一覧できる頁がある、また、その頁から、各会社ごとの情報が掲載された頁に移ることができる。そこには、「企業情報」欄の「企業名」「業種」「会社案内」、「グループインフォメーション」欄の「設立年月日」「資本金」「本社、支社所在地」「社員数」等、「募集要項」欄の「職種」「勤務地」「給与」「職務内容」「選考方法」等、「採用基準」欄の「資格内容」「志願者状況」「対象職種」「職歴年数」「専攻」「学位」「言語スキル」等の各項目が設定されており、各会社のそれぞれの情報が掲載されている。
この中で、「企業情報」欄の「会社案内」には、「今後の事業展開において活躍フィールドはどんどん広がっていきます」、「国内市場・北米市場はもとより、ヨーロッパ・発展途上国を含めて、目標とする世界No.1MT専門メーカーを実現していきます」などといった、採用基準の枠にとらわれない、当該企業の今後の展望、目標、それに伴う採用傾向等が記載されている。
ウ 被告サイトの「採用」の頁においては、「外国人を雇用する」の表題の下、「HR Talk−外国人を雇用している企業のインタビュー」と題して、7社の名称が挙げられている。
各社ごとの頁には、「東アジアでナンバー1をめざす」等インタビュー記事の中の一節などが冒頭に挙げられ、「化学商品を次々とマーケットに送り出している」等の簡単な会社紹介や、「海外マーケットで一部商品が成熟化するなか、商品の起爆剤となるのは『発展途上の10億人市場』である中国だ。『このマーケットを制する企業こそが21世紀を制する』を標語に、着々と有力な外国人採用に入っている。採用の対象は『ずばりマーケティング』。人事担当者の狙いも理路整然としている。」等の前文を置いて、採用内容、採用実績、会社業績、事業目標、外国人採用についての採用傾向等を、人事担当者と聞き手とのインタビュー形式の記事にして掲載している。
・・・・
オ 効率的に人材を確保するために、特に学生の採用については、企業のイメージ作りや企業に対する理解度をアップさせるような広報の重要性を指摘されることがあり、そのような広報としては、現在の活動目的、将来像、社会への貢献状況、企業理念を明らかにし、求めている人材像を明確に具体的に打ち出すものが想定されていること、そのような広報の作成においては、「アイデアや専門知識で勝負している就職情報会社と上手につきあうことは多くのプラスがある。」、就職情報会社は、「企業を客観的に見ることができ、新鮮な目で自社の魅力を新発見してくれる可能性があ」り、「種々の表\現技術を持っており、現代の学生達の価値観に併せた求人ツールを企画することができる」などとされている(甲第29号証)。 カ 従来より、新聞においては、「人事募集広告」あるいは「求人広告」と称される欄が存在し、この欄には、募集する事業者名、連絡先、募集する職種、労働条件等が記載されており、同一の文字が配置されるだけのものもあれば、強調したい部分の文字の大きさや太さを変えたり、勧誘的文言が付加されたりすることもある(甲第9、第10号証)。 キ 広告ないし広告代理業と求人情報提供業務を同一の事業主が行う例がある(公知の事実)。
・・・・
(4) 被告は、商標法における広告とは、第三者が広告主のために、広告主を明示して、他人を介さずに広告主の商品、サービス、アイデア等について消費者に告知、説得することを目的とするものであるのに対し、求人情報の提供とは、他人である雇用希望主のために、雇用希望主を明示して、雇用希望主が労働者を募集することを求職者層に対し、他人を介さずに告知、勧誘する活動を行うことを目的とするものであると主張し、広告と求人情報の提供とでは、対象とする需要者も全く異なると主張する。 「広告」とは、国語辞典によれば、「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や工業物などについて、多くの人に知られるようにすること。」(広辞苑[第5版])、「1)広く世の中に知らしめること。2)人々に関心を持たせ、購入させるために、有料の媒体を用いて商品の宣伝をすること。また、そのための文書類や記事。」などとされており、特に、商品の購入等を誘引するために宣伝するという意味合いで一般的に用いられることからすれば、「求人情報の提供」との間には、被告が主張するような差異があることも否定できない。被告商標権が、先願である原告商標権の存在にもかかわらず登録になったことは、このような点が考慮されたものと考えられる。
しかし、商標権侵害の成否に関しての役務の類否の判断に当たっては、具体的な取引の実情を考慮すべきである。
これを本件についてみると、前記(2)認定の事実によれば、被告は、インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して、採用希望企業の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内容等の求人事項、並びに、当該企業の経営理念や活動目的、将来像、それらに適合する採用傾向等の情報を、興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で、誰もが閲覧し得る状況に置くことによって、提供しているということができる。\n そして、求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、被告自身も広告代理をその業務の1つとしている(なお、商標法施行令及び同法施行規則による役務の区分において、「求人情報の提供」は、従前は、気象情報の提供と並べて第42類に分類されていたが、平成13年の改正により、「広告」と同じ第35類に移されていることも、現代では両者が近い関係にあるとされていることを示しているといえる。)。
したがって、役務の提供の手段、目的又は場所の点においても、提供に関連する物品(本件の場合は情報)においても、需要者の範囲においても、業種の同一性においても、被告が被告サイトにて行っている業務は、広告代理業務と同一ないし類似するということができる。
なお、前記のとおり、被告は被告商標権の登録を受けているが、その指定役務は「求人情報の提供、職業のあっせん」等であって、「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」まで含んでいるわけではないから、上記登録の事実は、被告が行っている上記業務が原告商標権の指定役務に類似すると判断することの妨げになるものではない。
関連カテゴリー
>> 役務
>> 類似
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成30(ネ)10063 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月7日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(3) 推定覆滅事由について
ア 推定覆滅の事情
特許法102条2項における推定の覆滅については,同条1項ただし書の事情 と同様に,侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と特許権者 が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば, 1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),2)市 場における競合品の存在,3)侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),4)侵害 品の性能(機能\,デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について,特許法1 02条1項ただし書の事情と同様,同条2項についても,これらの事情を推定覆滅 の事情として考慮することができるものと解される。また,特許発明が侵害品の部 分のみに実施されている場合においても,推定覆滅の事情として考慮することがで きるが,特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の 覆滅が認められるのではなく,特許発明が実施されている部分の侵害品中における 位置付け,当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するの が相当である。
イ 控訴人らは,炭酸ガスを利用したパック化粧料全てが競合品であることを 前提に,他の炭酸パック化粧料の存在が推定覆滅事由となると主張する。 しかし,そもそも,競合品といえるためには,市場において侵害品と競合関係 に立つ製品であることを要するものと解される。 被告各製品は,炭酸パックの2剤型のキットの1剤を含水粘性組成物とし,炭 酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ,得られた二酸化 炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック 化粧料である。そして,化粧料における剤型は,簡便さ,扱いやすさのみならず, 手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり,各消費者の必 要や好みに応じて選択されるものであるから,剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用 したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人ら が競合品であると主張する製品は,その販売時期や市場占有率等が不明であり,市 場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。
ウ 控訴人らは,被告各製品が利便性に優れているとか,被告各製品の販売は 控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。 しかし,事業者は,製品の製造,販売に当たり,製品の利便性について工夫し, 営業努力を行うのが通常であるから,通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても, 推定覆滅事由に当たるとはいえないところ,本件において,控訴人らが通常の範囲 を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 控訴人らは,被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると\n主張する。 侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても,そのことから\n直ちに推定の覆滅が認められるのではなく,当該優れた効能が侵害者の売上げに貢\n献しているといった事情がなければならないというべきである。
・・・
(ウ) 被告各製品及び原告製品は,いずれも本件発明1−1及び本件発明2−1 の実施品であり,炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生さ せ,得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ,皮膚に 適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより,美肌,部分肥満改善等に 効果を有するものであると認められるのであり,上記(ア)及び(イ)に認定した事実に よっても,被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し,これが控訴人\nらの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず,ほかにこれを認める に足りる的確な証拠はない。
オ 控訴人らは,被告各製品が控訴人ネオケミアの有する特許発明の実施品で あるなどとして,これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべき であると主張する。 侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても,そのことから直ちに推定の覆 滅が認められるのではなく,他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献 しているといった事情がなければならないというべきである。控訴人ネオケミアが, 二酸化炭素外用剤に関連する特許である,1)特許第4130181号(乙A18), 2)特許第4248878号(乙A19),3)特許第4589432号(乙A20), 4)特許第4756265号(乙B全7)を保有していることは認められるが,被告 各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠は ないから,そもそも,被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができ ない。よって,これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない。 なお,被告各製品の中には,上記特許権の存在や,特許取得済みであることを 外装箱に表示したり,宣伝広告に表\示したりしているものがあったことが認められ る(甲7,8,17,20)が,特許発明の実施の事実が認められない場合に,そ の特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないか\nら,この点による推定の覆滅を認めることもできない。
カ 控訴人らは,従来技術との比較の観点から,本件発明1−1及び本件発明 2−1の技術的価値が低いことを主張するが,控訴人らが指摘するジェルと粉末を 組み合わせる化粧料の技術(資生堂614及び日清324)は,炭酸ガスを利用し た化粧料に係るものではないし(乙A103,乙E全9,35,36),2剤混合 型の気泡状の二酸化炭素を発生する化粧料(石垣発明1及び2)は,炭酸ガスの気 泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の技術であって,二酸 化炭素を気泡状で保持する二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのものではない (乙E全4,5,37,38)から,いずれも本件発明1−1及び本件発明2−1 を代替するものではない。そうすると,これらの従来技術の存在は,被控訴人の受 ける損害とは無関係であるから,推定覆滅事由に当たるということはできない。 キ 控訴人らは,乙A3の実験結果によれば,ブチレングリコールが配合され た被告各製品においては,本件発明1−1及び本件発明2−1の寄与は限定的であ ると主張する。しかし,本件発明1−1及び本件発明2−1は二酸化炭素含有粘性 組成物を得るための2剤型の化粧料のキットの発明であるところ,被告各製品は, 炭酸塩を含むジェル剤と酸を含む顆粒剤を混合して使用するパック化粧料のキット であるから,本件発明1−1及び本件発明2−1は被告各製品の全体について実施 されているというべきである。また,被告各製品にブチレングリコールが配合され たことによる効果が控訴人らの売上げに貢献しているといった事情も認められない 本件において,ブチレングリコールが配合されていることは,被控訴人の受ける損 害とは無関係であるから,控訴人らが指摘する乙A3の実験の結果は,控訴人らの 上記主張を基礎付けるものではない。
・・・
6 損害(特許法102条3項)(争点6−2)
(1) 特許法102条3項について
ア 被控訴人は,選択的に,別紙「損害額一覧表」の「被控訴人主張額」「3\n項による損害額」欄記載のとおり,特許法102条3項により算定される損害額も 主張している。特許法102条3項は,特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最 低限度の損害額を法定した規定である。
イ 特許法102条3項は,「特許権者…は,故意又は過失により自己の特許 権…を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す る額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」 旨規定する。そうすると,同項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準 とし,そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。
(2) その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
ア 特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については,平成10年法律第51号による改正前は「その特許 発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ, 「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして,同改正により 「通常」の部分が削除された経緯がある。
特許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許が無効に されるべきものか否かが明らかではない段階で,被許諾者が最低保証額を支払い, 当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることがで きないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施 料率が決定されるのに対し,技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものと はいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には,侵害者が上記のような契 約上の制約を負わない。そして,上記のような特許法改正の経緯に照らせば,同項 に基づく損害の算定に当たっては,必ずしも当該特許権についての実施許諾契約に おける実施料率に基づかなければならない必然性はなく,特許権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき,実施に対し受けるべき料率は,むしろ,通常の実施 料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって,実施に対し受けるべき料率は,1)当該特許発明の実際の実施許諾 契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の相場 等も考慮に入れつつ,2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重 要性,他のものによる代替可能性,3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上 げ及び利益への貢献や侵害の態様,4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の 営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。
・・・・
ウ 実施に対し受けるべき金銭の額
上記のとおり,1)本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料 率は現れていないところ,本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平 均的な実施料率が,国内企業のアンケート結果では5.3%で,司法決定では6. 1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決 金を売上高の10%とした事例があること,2)本件発明1−1及び本件発明2−1 は相応の重要性を有し,代替技術があるものではないこと,3)本件発明1−1及び 本件発明2−1の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること, 4)被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど,本件訴訟に現れた事情を考慮す ると,特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,本件での実施に対し 受けるべき料率は10%を下らないものと認めるのが相当である。なお,本件特許 権1及び本件特許権2の内容に照らし,一方のみの場合と双方を合わせた場合でそ の料率は異ならないものと解すべきである。 したがって,本件各特許権侵害について,特許法102条3項により算定され る損害額は,別紙「損害額一覧表」の「裁判所認定額」「3項による損害額」欄記\n載のとおりとなる。
(3) 控訴人らの主張について
控訴人らは,被告各製品における本件各特許の寄与が限定されることを根拠に 実施に対し受けるべき料率を低くすべきであると主張するが,前記5(3)に説示し たところに照らし,本件発明1−1及び本件発明2−1を被告各製品に用いたこと による売上げ及び利益への貢献が限定されるとは認められないから,控訴人らの主 張は前提を欠く。 また,控訴人らは,被控訴人のビジネスモデルが不当に競争を制限するもので あると主張するが,前記5(1)イにおいて認定したとおり,被控訴人は本件各特許 の実施品を製造販売しているのであるから,被控訴人のビジネスモデルが不当に競 争を制限するものであると解する根拠がない。控訴人らの,MLMによる販売手法 に関する主張は具体的な主張を欠き,失当である。 控訴人らの主張するその余の点も,上記判断を左右するものではない。
7 総括
(1) 被控訴人キアラマキアート(被告製品5)については,上記6で認定した 特許法102条3項に係る損害額が,前記5で認定した同条2項に係る損害額より も高いから,同条3項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。 他方,その余の控訴人らについては,いずれも前記5で認定した同条2項に係 る損害額の方が高いから,この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。
なお,控訴人コスメプロらは,被告各製品を製造,販売するに至った経緯等に 照らし控訴人コスメプロらには故意又は重大な過失はなかったとして,同条4項に 基づき,このことを控訴人コスメプロらの損害賠償額を定めるについて参酌すべき であると主張する。しかし,控訴人コスメプロ,控訴人アイリカ,控訴人ウインセ ンス,控訴人コスメボーゼ及び控訴人クリアノワールは,化粧品の製造会社であり, 仮に同控訴人らの主張する諸事情があったとしても,同控訴人らにつき,特許権侵 害についての故意又は重大な過失がなかったということはできないから,控訴人ら の上記主張は採用できない。
◆要旨
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成30(ワ)2082 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年3月25日 大阪地方裁判所
本件記録ビデオは,被告P2らの挙式等の様子を撮影・編集したビデオで あり,そのサムネイル画像(甲38)も参酌すると,挙式等が進行する状況に応じ た撮影対象の選択や構図等に創作的工夫が施されていると認められるから,著作権\n法2条3項に規定する「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせ る方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物」であり,同法10条1項7\n号所定の「映画の著作物」に当たると解される。
そして,前記1で認定した事実によれば,挙式等の撮影については基本的には原 告の裁量に委ねられており,原告は様々な工夫をして撮影をしたと認められるから, 原告は,原告撮影ビデオについて,「映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した 者」(著作権法16条)としてその著作者であると認められ,本件記録ビデオはその 複製著作物又は二次的著作物である。
(2) そこで,被告らが主張する著作権法29条1項の適用の有無について検討 する。 著作権法29条1項にいう「映画製作者」とは,「映画の著作物の製作に発意と責 任を有する者」をいい(同法2条1項10号),映画の著作物を製作する意思を有し, 同著作物の製作に関する法律上の権利義務が帰属する主体であって,同著作物の製 作に関する経済的な収入・支出の主体となる者のことをいうと解される。 前記1で認定した事実のとおり,本件では,被告Beeは,社内の人間だけでは 撮影業務をこなせないことから複数の外部業者に撮影業務を委託するようになり, 原告はその外部業者の一人であったことからすると,被告Beeは,各婚礼のビデ オ撮影業務の担当を各外部業者に割り振って委託することにより,全体としての婚 礼ビデオの製作業務を統括して行っていたといえる。 また,エフ・ジェイホテルズから委託を受けて,新郎新婦から婚礼ビデオ製作の 申込みを受け,その意向を聴取して打合せをするのは被告Beeであり,婚礼ビデ\nオを完成させて納品するのも被告Beeである。また,被告Beeは,原告による 撮影に不備があった場合の新郎新婦に対する責任も負担している。そうすると,婚 礼ビデオを適切に製作し,納品する義務は,エフ・ジェイホテルズからの委託の下, 被告Beeが負っていたといえる。 加えて,現場での撮影業務自体は基本的には原告の裁量と工夫に委ねられていた が,被告Beeも,新郎新婦に特段の意向がある場合には原告にそれを伝えて撮影 の指示を行っており,原告の裁量等も被告Beeからの指示という制約を受けるも のであったほか,被告Beeは,婚礼ビデオを完成させるに当たり編集作業を行い, その中では,被告Beeが独自に製作した「プロフィールビデオ」等の上映シーン を加工し,そのBGMを音源から採取して差し込むなど,独自の演出的な編集も行 っているから,製作するビデオの内容を最終的に決定していたのは被告Beeであ るといえる。
そして,被告Beeは,原告に対して撮影料と交通費を支払っているほか,それ 以外の製作費用も負担しているから,本件記録ビデオの製作に関する経済的な収 入・支出の主体となっているのは原告ではなく被告Beeである。なお,被告Be eは,本件記録ビデオに収録された楽曲についての著作権使用料等の支払をしてい ないが,原告は,本件記録ビデオに収録された楽曲の著作権使用料は被告Beeが 負担することとなっていたと主張しており,この主張は,上記のとおり本件記録ビ デオの製作に関する経済的な収入・支出の主体が被告Beeであることと符合する (この点については,被告Beeも,別件の福岡地方裁判所小倉支部に提起された 事件で原告の上記主張を争うに当たり,結婚式の様子を撮影したビデオ等に結婚式 の映像とともに式場で流された音楽が収録された場合に,その音楽について日本音 楽著作権協会等に対して著作権使用料を支払うべき義務があるかは法律上確定され ているものではなく,支払義務があるとしても,それを原告が支払った場合には求 償権の問題が発生すると主張するにとどまり〔乙3,7〕,日本音楽著作権協会等に 対する支払義務がある場合にそれを被告Beeが負担すべきことを特段争っていた わけではないと認められる。)。 以上からすると,本件記録ビデオの製作に発意と責任を有する者は,被告Bee であり,被告Beeは「映画製作者」に当たると認めるのが相当である。 そして,原告は,被告Beeから委託を受けて原告撮影ビデオの撮影をしたので あるから,被告Beeに対して本件記録ビデオの製作に参加することを約束したも のといえる。 したがって,著作権法29条1項により,本件記録ビデオの著作権は被告Bee に帰属するから,原告は著作権を有しない。 これに対し,原告は,ビデオ撮影に当たっての自己の負担や工夫をるる主張する が,それらは,原告が著作者であることを基礎付けるものであっても,被告Bee が映画製作者であることを否定するに足りるものではない。
(3) したがって,原告は本件記録ビデオの著作権を有しないから,その著作権に 基づく請求は理由がない。
4 争点5(著作者人格権侵害のおそれの有無)について
(1) 同一性保持権についてみると,本件記録ビデオは原告撮影ビデオを編集し たものであるが,前記1で認定した事実からすると,原告は,被告Beeが原告撮 影ビデオを適宜編集することを承諾していたと認められるから,本件記録ビデオは 原告の同一性保持権を侵害して製作されたものではない。 したがって,仮に被告らが本件記録ビデオを複製,頒布するとしても,意に反す る改変を行うことにはならないから,同一性保持権の侵害は生じない。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成29(ワ)5011 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成31年3月28日 大阪地方裁判所
(5) 推定覆滅事由等
ア 被告製品1関係について
(ア) 意匠権侵害関係について
a 意匠権侵害関係については,原告実施品の販売減少による逸失利益が問題となるところ,前記認定の被告製品1の利益の額がその損害額と推定されるから,この推定に関する覆滅事由等が問題となる。
b 本件登録意匠が部分意匠であることの考慮について 本件登録意匠は部分意匠であり,意匠の対象となっているのは操作レバ ーとカバー部である(別紙「本件登録意匠の構成」参照)のに対し,被告製品1は\n爪切り全体であるから,本件意匠権侵害行為による原告の損害額と推定されるのは, 被告製品1の販売等による利益の額のうち,本件意匠権侵害部分である操作レバー とカバー部に相当する額である。そして,被告は,それらの爪切り全体に占める割 合について,表面積にしてせいぜい40%であるとか,その部分の製造原価は高く\nても20%程度であると主張している。 確かに,本件登録意匠の対象部分が爪切りの一部であり,表面積としてみても,\n爪切りの大半を占めるわけではないことは被告主張のとおりであるし,また爪切り における重要部分が刃であり,爪切り全体に占める操作レバーやカバー部の製造原 価が一部にとどまることも,被告主張のとおりと推測される。 しかし,ここで被告製品1の全体に占める本件意匠権侵害部分の割合を検討する 趣旨は,被告製品1の販売利益に占める本件意匠権侵害部分の割合を明らかにする ためであるから,その割合は,顧客吸引力の観点から,できる限り被告製品1の意 匠全体に対する本件意匠権侵害部分の貢献割合によって決めるべきものであり,被 告が主張する表面積や製造原価,特に製造原価の割合は,それを検討するための出\n発点として分かりやすいものではあっても,一要素であるにすぎない。 そこで,本件登録意匠の特徴を検討すると,本件登録意匠のうち,操作レバーの 末端部側が紡錘状となる形状を備え(別紙「本件登録意匠の構成態様」の構\成C), カバー部も,操作レバーの末端部側よりも一回り大きい紡錘状となる形状を備え (同構成D),操作レバーが先端部側から末端部側に至る中心面から上下に対称な\n湾曲した稜線を介して上下に傾斜して下る形状を備え(同構成E),カバー部が中\nほどの紡錘状の稜線を介して操作レバー側に窪み,その窪みにおける稜線の中央近 傍側でより深く窪んだ形状を備えている(同構成F)点は,爪切りを手に持ち,あ\nるいは置いて見たときに大きく目立つ点であり,本件の証拠に見られる他の爪切り の意匠(甲10,61ないし64,66ないし68,乙17,28ないし31)に は見られない特徴点で,爪切り全体の美感に与える影響が大きいと認められる。こ のことは,原告のホームページで,原告実施品(甲56の写真参照)について,機 能性だけでなく,「やさしさを感じさせる曲面フォルム」に触れられていることや,\nグッドデザイン賞の審査委員から,「バッタの様にも見える有機的な形態が魅力の爪 切りである。その新鮮なデザインを評価したい。」と評価されていることからもうか がわれる。そして,爪切りの先端側の形状は,それ自体には上記の他の爪切りの形 状と比べて顕著な特徴があるとはいえないが,上記の末端側に比べて細くすぼまる 形状や,各部分の大きさ(同別紙の構成H及びI)のバランスは,「バッタの様に\nも見える有機的な形態」との印象を与えるのに寄与しているといえる。 他方,被告製品1でも操作レバー及びカバー部の意匠は,本件登録意匠とほぼ同 一であり,爪切り全体の意匠としても原告実施品とほぼ同一であると認められると ころ,操作レバー及びカバー部以外の部分(別紙「本件登録意匠の構成」の点線部\n分に相当する部分)は,爪切り全体の中で相応に大きな面積割合を占めており,そ の形態も合わさって全体が「バッタの様にも見える有機的な形態」との印象を与え ることにもなっているものの,その部分の形態自体には,他の爪切りとの美感上の 顕著な差は認められない。そして,別紙「被告意匠の構成」の「パッケージ」欄の\nとおり,被告製品1がドン・キホーテの店舗で販売される際には,クリアケースを 通してその平面視の状態を,末端側が若干だけ隠れた形で視認できるように陳列さ れていたから(甲3ないし6),需要者は主として平面視の意匠を認識することにな る。そうすると,被告製品1の意匠全体の美感に対して本件意匠権侵害部分が与え る影響は高いというべきであり,被告が指摘する表面積や製造原価の点を考慮した\nとしても,被告製品1の意匠全体に占める本件意匠権侵害部分の割合は7割と認め るのが相当である。
c 本件意匠権侵害関係で被告が主張する他の推定覆滅事由について
(a) 被告は,本件登録意匠と同一の基本的構成態様を有する爪切りは\n多数存在するとして乙28の1ないし3の各意匠の存在を指摘するところ,この主 張は,本件登録意匠の被告製品1の顧客吸引力への寄与の低さをいうことにより, 被告製品1についての後記(b)以下の事情の重要性をいう趣旨であると解される。 確かに,乙28の1の意匠では,カバー部と操作レバーの末端部側がそれ以外の 部分と比べて若干ふくらんでいるように見える。しかし,本件登録意匠は,操作レ バーの末端部側を丸みを帯びた紡錘状となる形状とすること(構成C)と併せて,\nカバー部の末端部側をそれよりも一回り大きい紡錘状となる形状とすること(同 D)によって,爪切りをたたんだ場合に,その末端部側がふくらんでいることが強 調されている。これと対比すると,乙28の1の意匠では操作レバーの末端部側は カバー部の末端部側とほぼ同じ形態とされているにすぎず,全体として異なる美感 を有するものと認めるほかない。 また,乙28の2及び28の3については,爪切りがたたまれた場合の形態が不 明であるが,乙28の2の意匠はカバー部の末端部側がそれ以外の部分よりもすぼ んでいるように見えるから,本件登録意匠と異なる美感を有するものといわざるを 得ない。さらに,乙28の3の意匠はカバー部が操作レバーよりも末端部側がふく らんだ形態を有しているように見えるが,本件登録意匠の構成Bと異なり,操作レ\nバーがほぼ平坦なように見え,末端部側へ向かって緩やかに湾曲して下る形状を有 しているとは認められない。そして,上述のとおり,本件登録意匠では,爪切りを たたんだ場合に,その末端部側がふくらんでいることが強調されているところ,そ れには本件登録意匠の構成Bも寄与していると認められるから,同構\成を有してい ない乙28の3の意匠と本件登録意匠の美感が共通しているとは認められない。 以上より,乙28の各意匠の存在が,本件登録意匠の被告製品1の顧客吸引力へ の寄与の低さを基礎付けるとはいえないから,これにより推定が覆滅されるとはい えない。むしろ,前記bで述べたところからすると,本件登録意匠は,原告実施品 とほぼ同一の形態である被告製品1について,「バッタの様にも見える有機的な形 態」との印象を与える特徴的な意匠であるというべきである。
(b) 次に,被告は,被告製品1特有のデザインの存在を主張している。 しかし,被告が主張する被告製品1特有のデザインについて,美感に与える影響が 大きいとはいえないから,これを推定覆滅事由として考慮することはできない。
(c) もっとも,爪切りは爪を切るために使用する実用品であり日用品 であるから,需要者が購入するに当たっては,一般にその切れ味等の性能や使いや\nすさ,それらと価格とのバランスを重視するものと考えられ,商品のデザインを重 視して商品を購入することが多いとはいえない。確かに,原告実施品の場合は,複 数の百貨店や東急ハンズ等で販売され,日本製で定価が2000円(税抜)とされ ており,爪切りの市場においては,販売価格が500円を下回る爪切りや,100 0円前後の爪切りが販売されている(乙28,29,弁論の全趣旨)のと比べると, 爪切りの販売価格としては高いから,原告実施品は,価格の高い高級品として販売 されているといえ,そのような原告実施品を購入する需要者には,品質と並んでデ ザインを重視する者も多くいると考えられる。これに対し,被告製品1は,専らド ン・キホーテという総合ディスカウントストアで販売されており,店頭販売価格が 1280円(税抜)と他の爪切りにも見られる価格帯であり,それが専ら売られて いたドン・キホーテにおいても,1000円前後の爪切りやそれよりも安い爪切り が販売されていたことが推認される(乙31は侵害行為があった時期と異なる時期 のものであるが,これによっても推認可能である。)から,このような店舗と価格で\n被告製品1を購入した需要者において,商品のデザインを重視して商品を購入する ことが多いとは考え難い。また,爪切り市場において原告のシェアが高いとも認め られない。 したがって,以上の点は,推定の一部覆滅事由たり得るというべきである(なお, 被告は,自身の営業努力を主張するが,被告製品1をドン・キホーテで販売できる ようにしたという以上に,被告主張の営業努力が通常のものを超えたものであると いうことはできない。)が,前記のとおり本件登録意匠が爪切りのデザインとして特 徴的なものであり,相応の顧客吸引力を有すると考えられること,被告製品1と原 告実施品の価格差が著しいというわけでもないこと,原告実施品の利益率が被告製 品1の利益率に比べて特に低いともうかがわれないこと(なお,被告は,原告がO EM供給している製品については利益率が低いと主張しているが,そのような事実 を認めるに足りる証拠はない。)も考慮すると,推定覆滅率は60%と認めるのが相 当である。
d したがって,被告製品1の意匠権侵害行為に係る損害の額は,被告 製品1の利益の額の28%(0.7×0.4)となる。
・・・
(6) 原告の損害額
ア 以上の認定・判示によれば,意匠法39条2項及び不正競争防止法5条 2項に基づく原告の損害額は,次のとおり,●(省略)●円である。 (計算式) 被告製品1に係る被告の利益●(省略)●円×0.38(意匠 権侵害行為に係る損害と14号の不正競争行為に係る損害分)+被告製品2に係る 被告の利益●(省略)●円+被告製品3に係る被告の利益●(省略)●円×0.1 ≒●(省略)●円
イ また,原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人弁護士に委任したとこ ろ,被告の不法行為及び不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用は●(省 略)●万円と認めるのが相当である。 ウ 以上より,被告の不法行為及び不正競争行為による原告の損害額は,合 計76万1265円となる。
関連カテゴリー
>> 部分意匠
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成30(行ケ)10173 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年5月30日 知的財産高等裁判所
原告は,平成29年4月11日ころ,D及び国際建機販売を被告として, D及び国際建機販売による被告商標が付された名刺の使用,コンクリート ポンプ車の販売等が本件商標権の侵害に当たるなどと主張して,商標法3 6条等に基づき,被告商標を付したコンクリートポンプ車の販売及び営業 活動の差止め等,謝罪広告の掲載及び不法行為による損害賠償を求める訴 訟(東京地方裁判所平成29年(ワ)第12058号事件。以下「別件訴訟」 という。乙122)を提起した。 被告は,別件訴訟の係属中の同年6月1日,本件審判を請求した。
イ 東京地方裁判所は,平成30年6月28日,別件訴訟について,本件商標 が商標法4条1項19号に該当する旨の無効の抗弁を認め,D及び国際建 機販売に対し,本件商標権に基づく権利行使ができないとして,原告の請 求をいずれも棄却する判決(以下「別件原判決」という。乙142)をした。 原告は,別件原判決のうち,損害賠償請求を棄却した部分のみを不服と して,控訴(知的財産高等裁判所平成30年(ネ)第10057号事件)を提 起した。 その後,特許庁は,同年10月29日,本件商標の商標登録を無効とする 旨の本件審決をした。
ウ 知的財産高等裁判所は,平成31年1月29日,別件原判決と同様の理 由により,原告の損害賠償請求は理由がないと判断し,原告の控訴を棄却 する判決(乙174)をした。その後,同判決は確定した。
・・・
前記1の認定事実を総合すれば,「GSF Inc.」の名称でコンクリ ートポンプ車の輸入,販売等を行っていた原告代表者は,日本国内において,\n原告代表者自らが又は原告が被告からウォンジン産業を通じて仕入れた被告\n製コンクリートポンプ車の販売及びその営業活動を行う中で,本件商標の登 録出願時点までに,被告商標が付された被告製コンクリートポンプ車は,韓 国のトップ商品であること,被告商標が被告製コンクリートポンプ車を表示\nするものとして韓国国内のコンクリート圧送業者の間で広く知られていたこ とを認識していたが,被告が日本に進出してその営業拠点を作り,事業展開 を行うための営業活動に着手したことを知るや,被告商標が商標登録されて いないことを奇貨として,被告の日本国内参入を阻止又は困難にするととも に,本件商標を有償で被告に買い取らせ,あるいは原告が日本における被告 の販売代理店となる販売代理店契約の締結を強制させるなどの不正の目的を もって,原告による本件商標の商標登録出願をしたものと認められる。
(3) 以上によれば,本件商標は,被告の業務に係る被告商品を表示するものと\nして,韓国における需要者の間に広く認識されている被告商標と類似の商標 であって,不正の目的をもって使用をするものといえるから,商標法4条1 項19号に該当するものと認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.06. 6
平成30(行ケ)10176 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年5月30日 知的財産高等裁判所
審決は、”「リブーター」は,特定の商品の名称を表すものとして一般に広く使用されているといった事実は認められないから,「リブーター」の文字が,本件商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質等を具体的に表\すものとして取引上普通に使用されていると認めることはできない”と判断していました。
前記1のとおり,「リブート」は,「reboot」という英語を片仮名で 表した語であるところ,「reboot」は,再起動するという意味の動詞であり(当\n裁判所に顕著な事実),また,「リブート」は,コンピュータなどを再起動すること を意味する語として,各種の用語辞典(用語事典)に掲載されており,さらに,多 くの雑誌やウェブサイト,さらには公開特許公報にも,上記の意味で使用されてい ることからすると,「リブート」という語は,再起動することを意味する普通名称で あると認められる。そして,前記1(4)で認定した事実からすると,情報・通信の技 術分野では,英語を片仮名で表した言葉が非常に多く存在すること,一般的に,英\n語の動詞の語尾に「er」,「or」等を付することにより,当該動詞が表す動作を\n行う装置等を意味する名詞となり,「エディタ」,「エンコーダ」,「カウンタ」,「デコーダ」,「プリンタ」,「プロセッサ」等,動詞を名詞化した語も多数存在することが認められるから,情報・通信の技術分野に属する者は,「リブーター」から,「re boot」の語尾に「er」を付した語である「rebooter」を容易に思い 浮かべるものと認められる。
さらに,前記1(2),(3)で認定した各事実からすると,コンピュータやルーター 等の機器を再起動する装置の需要があり,実際にそのような装置が販売されている ことが認められるところ,前記1(2)のとおり,このような再起動装置を「リブータ ー」又は「リブータ」と呼ぶ例があることが認められる。これに対し,本件証拠上, 「リブーター」の語が,他の意味を有するものとして使用されているという事実は 認められない。なお,前記1(4)ウ,エで認定したウェブサイトの記載によると,情報・通信の技術分野においては,英語を片仮名表記した場合は,語尾の長音符号を省く慣例があるものと認められるから,語尾の長音符号を有するか否かで別の語になるというこ\nとはできず,上記の「リブータ」も「リブーター」も同一の語であるということが できる。
以上からすると,情報・通信の技術分野においては,通常,「rebooter」 及びこれを片仮名で表した「リブーター」は,再起動をする装置と理解されるもの\nというべきである。 したがって,「リブーター」は,再起動装置の品質,用途を普通に用いられる方法 で表示する語と認められるから,指定商品が再起動装置又は再起動機能\を有する電 源制御装置である場合は,本件商標は,商標法3条1項3号の商標に該当するとい うべきである。 一方,再起動機能を有さない電源制御装置が指定商品である場合は,本件商標は,\n同号の商標には該当しない。
(2)ア これに対し,被告は,「チーター」を,「cheat」に「er」を加え た言葉とはいえず,これと同様に,「リブーター」を,「reboot」に「er」 を加えた言葉と解することはできないと主張する。 しかし,動物である「チーター」の英語は,「cheetah」であるから,語尾 に「er」を加えた言葉ということはできない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
イ また,被告は,甲4文献及び甲6サイトでは,リブーターの機能等の説\n明もされており,このことは,リブーターという語のみからは,その機能等が理解\nできないことを意味する旨の主張をする。 しかし,前記(1)で判示したとおり,情報・通信の技術分野においては,リブータ ーという語は,再起動する機能を有する装置と理解されるのであり,このことは,\n甲4文献や甲6サイトの記載によって左右されないというべきであるから,被告の 上記主張は理由がない。
ウ なお,被告は,甲38文献に記載された「リブーター」は何を意味する か理解できないと主張するが,前記1(2)カで認定した甲38文献の記載からすると, 同文献におけるリブーターは,再起動の機能を有する装置であると理解でき,少な\nくとも,再起動の機能を有さない他の装置を意味するものとは認識できないから,\n「リブーター」が再起動装置とは異なる別の物を意味する語として使用されている ということはない。
・・・
(1) 前記2のとおり,情報・通信の技術分野においては,通常,「reboot er」及びこれを片仮名で表した「リブーター」は,再起動をする装置と理解され\nるところ,再起動機能を有さない電源制御装置に,「リブーター」という語を使用す\nると,需要者,取引者は,当該電源制御装置が再起動機能を有しているものと誤解\nするおそれがあるというべきである。 したがって,指定商品が再起動機能を有さない電源制御装置である場合は,本件\n商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり,商標法4条1項16号の商標に 該当するというべきである。
本件商標は以下の通り
商標 リブーター(標準文字)
登録番号 第5590686号
出願日 平成25年2月8日
登録日 平成25年6月14日
指定商品
第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品」
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.06. 5
平成29(ワ)781 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年4月19日 大阪地方裁判所
著作権法2条1項6号は,レコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義しているところ,「レコードに…音を…固定」とは,音の媒体たる有体物をもって,音を機械的に再生することができるような状態にすること(同項5号も参照),すなわち,テープ等に音を収録することをいう。そうすると,レコード製作者たり得るためには,当該テープ等に収録されている「音」を収録していることはもとより,その「音」を「最初」に収録していることが必要である。
ところで,著作権法96条は,「レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ,ある固定された音を加工する場合であっても,加工された音が元の音を識別し得るものである限り,なお元の音と同一性を有する音として,元の音の「複製」であるにとどまり,加工後の音が,別個の音として,元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。本件では,上記(2)の音楽CDの制作工程からすると,販売される音楽CDに収録されている最終的な音源は,ミキシング等の工程で完成するものの,ミキシング等の工程で用いられる音は,そこで初めて録音されるものではなく,既にレコーディングの工程で録音されているものである。そして,レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ,編集するというミキシング等の工程の性質(上記(2)イ及びウ)からすると,ミキシング等の工程後の楽曲において,レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難く,現に,本件マスターテープ2に収録されている音が,本件マスターテープ1に収録されている音を識別できないものになっているとは認められない。そうすると,本件音源についてのレコード製作者,すなわち本件音源の音を最初に固定した者は,レコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであるから,原告がミキシング等を行ったことによりそのレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。
これに対し,原告は,ミキシング等の工程後の楽曲は,レコーディングの工程で録音された音とは全く別物になり,その楽曲こそが販売されるレコードの音であるから,レコード製作者はミキシング等の工程を行った者であると主張する。確かに,ミキシングの工程は,楽曲の仕上がりやサウンドを大きく左右する重要な工程であって,多額の費用を投下する場合もあると考えられる。しかし,前記のとおりミキシング等は,レコーディングの工程で録音されたマルチチャンネルの音を組み合わせ,編集するものであって,その目的上,元の音を識別できないほどに変容させることは考え難いから,原告の上記主張は採用できない。
(4) 原告によるレコード製作者の権利の承継取得の有無について
ア 前記認定のとおり,本件音源に係る演奏のレコーディングは米国で行われたから,その音源たる本件マスターテープ1の音源は,米国法の下では録音物として著作権により保護される(米国著作権法102条)が,日本法の下では,著作権法8条4号ロにより,保護されるレコードとして,レコード製作者の権利により保護される。本件では,日本国内において被告が本件音源を複製した行為が問題とされていることから,原告が本件マスターテープ1の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を有しているか否かが問題となるところ,原告は,自己がレコード製作者として本件音源の権利を原始取得したものでないとしても,P1から本件マスターテープ1の音源の権利を承継取得したと主張している。
イ そこで,まず,P1が本件マスターテープ1の音源についてのレコード製作者の権利を有していたか否かについて検討すると,確かに,前記認定の「ベースマガジン5月号」の編集部の記事では,P1は録音スタジオのエンジニアであるとされているから,通常はP1自身がレコード製作者であるとは考え難く,また,同記事ではP1がレコード製作者の権利を買い取った旨の消息筋の意見が記載されているものの,明確な裏付けがあるわけではない。また,甲12のKCCスタジオの録音記録も,日付の記載が空欄であるなど,どの時点のものか判然としない。しかし,P1は,本件音源のレコーディング時のマスターテープ(本件マスターテープ1)を所持しているところ,マスターテープは,その商業上の重要性からすると,通常はそれを複製して商業用レコードを製作する権利を有する者が所持するはずのものである。そして,原告は,P1から本件マスターテープ1を取得して本件CDを制作し,20年以上にわたり販売しているところ,ジャコが世界的に著名なベーシストでありながら,それまではスタジオ録音によるソロアルバムが2枚しかなか\nった状況にあって,本件CDが幻のサードアルバムとも位置付けられ(甲8・45頁),本件音源は米国で制作された本件映画にも使用されたことからすると,本件CDはベース業界においては相応に知られていたと推認されるから,本件音源について他に権利を有する者がいれば,原告に対してクレームが寄せられてしかるべきであるが,そのような事実は認められない。もっとも,前記認定のとおり,ジャコの遺族が関係するジャコ社は,本件音源について100%の著作権(米国著作権の趣旨と解される。)を有することを保証した上でスラング社に対してその使用を許諾しているが,本件原盤許諾契約書においても,本件映画に表記するクレジットは「“Birth of Island” Written and Performed by Jaco Pastorius」とされており,これによれば,ジャコは,日本法の下では,著作権と実演家の権利を有する立場にとどまり,レコード製作者の権利を有する立場には通常はない上,ジャコ社が本件マスターテープ1と同様のマスターテープを別途所持しているといった事情もうかがわれないから,ジャコ社がジャコの遺族が関係する会社であるとしても,本件マスターテープ1の音源のレ コード製作者としての権利を有していることの根拠は不明というほかない。
以上に加え,前記の「ベースマガジン5月号」の編集部の記事において,P1が本件音源の権利を取得した経緯がそれなりに記されていることや,本件契約書においてP1がマスターレコーディングの権利を有することを保証していることを併せ考慮すると,本件楽曲に係る本件音源については,P1が日本法の下でのレコード製作者の権利を有していたと認めるのが相当である。
ウ そして,原告は,そのP1から本件契約書によりマスターレコーディングに関する全ての権利を独占的に譲り受けたのであるから,本件マスターテープ1の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を承継取得し,本件音源についての同権利も有すると認められる。
2019.05.31
平成31(ネ)10006 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
クレームが凄いですね。「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定することを含む,敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」です。
本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件発明 の「プロカルシトニン3−116」は,「患者の血清中」から「測定」 されるものであり,測定結果が「敗血症及び敗血症様全身性感染」の「検 出」のために用いられることを理解できる。 そして,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)には,「プロカルシ トニン3−116を測定すること」の意義について規定する記載はない が,「測定」とは,一般的に,「長さ,重さ,速さなど種々の量を器具 や装置を用いてはかること」(大辞林(第3版))との意味を有する。 したがって,特許請求の範囲の記載によれば,本件発明の「患者の血 清中でプロカルシトニン3−116を測定すること」とは,患者の血清 中のプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味するも のと解される。
(イ) また,本件明細書の発明の詳細な説明には,従来技術として,患者 の血清中のプロカルシトニンの測定が,敗血症の検出にとって有益な診 断手段であることが知られていたこと,「本発明」の開始点は,敗血症 等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが,プ\nロカルシトニン1−116ではなく,プロカルシトニン3−116であ るという発見であり,そこから新規な診断及び治療方法,そこで使用可 能な物質等を導き出したことの開示がある(前記1(1)イ)。一方,本件 明細書の発明の詳細な説明には,「プロカルシトニン3−116を測定 すること」の意義について明示した記載はない。 そして,このような本件明細書の記載に照らしても,本件発明の「患 者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定すること」とは,患者 の血清中のプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを意味 し,その測定結果が敗血症等の検出に用いられることを理解できる。
(ウ) 以上の特許請求の範囲及び本件明細書の記載事項を総合すると, 「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定すること」とは, 患者の血清中のプロカルシトニン3−116の量を明らかにすることを 意味するものと解される。
イ これに対し控訴人は,構成要件Aの「患者の血清中でプロカルシトニン\n3−116を測定すること」とは,敗血症患者の血清中でプロカルシトニ ン3−116を敗血症の検出に必要な精度で測定することをいうと解すべ きであり,プロカルシトニン1−116と区別してプロカルシトニン3− 116を測定することを必須とするものではない旨主張し,その根拠とし て,1)本件明細書の記載事項(【0002】〜【0008】等)から,患 者の血清中でプロカルシトニン1−116等とプロカルシトニン3−11 6を区別することなくプロカルシトニン一般を測定したとしても,敗血症 等の検出に必要な精度でプロカルシトニン3−116を測定できることが 当業者に明らかであること,2)本件明細書には,本件特許に係る「敗血症 及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例として,血中か ら検出されるプロカルシトニンの濃度を一般的なイムノアッセイにより測 定することが記載されているが(【0062】,表3),通常のイムノア\nッセイでは,プロカルシトニン1−116と区別してプロカルシトニン3 −116を測定することは不可能であることを挙げる。\nしかしながら,「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定す ること」とは,患者の血清中のプロカルシトニン3−116の量を明らか にすることを意味するものと認められることについては,前記アのとおり である。
上記1)の点については,患者の血清中のプロカルシトニン3−116を プロカルシトニン1−116等と区別することなく測定することとは,患 者の血清中のプロカルシトニンを測定することと同義であるところ,本件 明細書には,患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定することにより 敗血症等を検出する技術は,本件出願の優先日前に従来技術として存在し たものであり,「本発明」は,かかる従来技術に対して新規のものである 旨が記載されていること(前記1⑵イ,ウ)からすると,かかる従来技術 が本件発明に係る方法に含まれると解することはできない。 なお,本件明細書には,敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシ トニンの大部分がプロカルシトニン3−116であることを発見した旨 の記載があるが(【0009】,【0010】),たとえそのような関係 があるとしても,プロカルシトニン3−116を測定することと,プロカ ルシトニン一般を測定することとが同義とはいえないことは明らかであ る。更に付け加えれば,敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシト ニンの大部分はプロカルシトニン3−116であるとの知見が存在する としても,敗血症等であるかどうかが明らかではない(だからこそ,その 診断を要する)患者については,その血清中のプロカルシトニンの大部分 がプロカルシトニン3−116であるかどうかは明らかではないはずで ある。したがって,敗血症等であるかどうかの診断に当たり,検出された プロカルシトニン一般の大部分がプロカルシトニン3−116であると の前提に立つことはできないというべきであるから,上記知見の存在は, 前記アの判断を左右するものではない。 また,上記2)の点については,本件明細書には,正常者及び敗血症患者 の血清中のプロカルシトニン濃度を測定した旨が記載されているところ (【0062】),【0062】に明示の記載はないが,上記測定は,【0 023】と同様に,市販のプロカルシトニンアッセイを用いて行われたも のと理解することができる。 しかしながら,本件明細書には,かかる測定は,これと同時に行われた これらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対比することによ り,正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニンにおいて際 立っていることを示すものである旨の記載があることからすると(【00 59】,【0062】,【0063】,表3),上記測定が,本件特許に\n係る「敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例と して記載されたものであるとは認められない。したがって,上記2)の主張 は,その前提を誤るものである。 以上によれば,控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 被告方法について
前記前提事実のとおり,被告装置及び被告キットを使用すると,患者の 検体中において,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−1 16とを区別することなく,いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度 を測定することができ,その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行わ れていると認められるものの,本件全証拠によっても,被告装置及び被告 キットを使用して敗血症等を検出する過程で,プロカルシトニン3−11 6の量が明らかにされているとは認められない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告方法は,構\n成要件Aを充足するものとはいえない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 間接侵害
>> ピックアップ対象
2019.05.24
平成29(ワ)27298 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年3月19日 東京地方裁判所
前記オの事実に,本件元従業員らが,平成26年10月以降,原告を順 次退職し,被告会社に転職したこと(前記1)を総合すると,株式会社ジョ ーエイ製機製の製造番号555番及び597番のキーマシン(計2台)は, 本件元従業員らのうちの誰かが,原告内に置かれていたものを持ち出したか, 又は,仕事等のために持ち出し,そのまま返却せずに被告会社に移して,業 務に使用したものと認められる。
イ もっとも,本件元従業員らのうちの誰かが上記キーマシン(2台)を持ち 出したことは認められるものの,その中の誰が上記キーマシン(2台)を持 ち出したかは不明であり,被告B又は被告Cが上記キーマシン(2台)を持 ち出したと認めるに足りる証拠はない。
・・・・
以上のとおり,原告が主張する各不法行為のうち,本件元従業員らのうちの誰 かがキーマシン及びグンマジを持ち出した行為(前記2(2),(3))は,原告に対す る不法行為を構成するというべきである。また,これらの行為は,遅くとも,本\n件元従業員らのうち,最も遅く原告を退職した被告Cの退職日である平成27年 3月31日までに行われたと認められる。 もっとも,被告B又は被告Cが上記不法行為をしたと認めるに足りず,また, 被告B,被告C及び被告Aが上記不法行為に共謀等によりその不法行為に加担し たとも認めるに足りないから,被告B,被告C及び被告Aが不法行為責任を負う とは認められない。
他方,上記キーマシンやグンマジが原告から持ち出された時期は不明であるも のの,これらの工具等は,原告から持ち出された後,いずれかの時期に,被告所 有の車両や本件倉庫に移され,また,被告会社従業員が使用しているのであるか ら,持ち出した者がその時点で既に被告会社の従業員であったか,又は,少なく とも,持ち出した者と意を通じて,被告会社の管理下に移すことに協力した被告 会社の従業員がいたと推認することができる。 そして,上記工具等は,被告会社が行う開錠業務で使用するために持ち出され たものであると認められるから,工具等を持ち出した者,又は,その協力者は, 被告会社での業務のために,工具等を持ち出し,原告に損害を加えているのであ り,使用者である被告会社は,原告に対し,使用者責任に基づく損害賠償責任を 負うというべきである。 これに対し,被告会社は,本件元従業員らの行動を把握していなかったことな どから使用者責任を負うことはないと主張するが,被告会社が被用者の選定やそ の事業の監督について相当な注意をしたとも,相当な注意をしても損害が生ずべ きであったとも認められず,被告会社は使用者責任に基づく損害賠償責任を免れ ないというべきである。
・・・・
キーマシンを持ち出したことによる損害について 証拠(甲16〜19)及び弁論の全趣旨によれば,被告会社の車両及び本件 倉庫に置かれていた原告所有の株式会社ジョーエイ製機製の製造番号555 番及び597番のキーマシンの販売価格は32万円であると認められ,2台の 販売価格合計64万円が損害額となる。
グンマジを持ち出したことによる損害について
原告は,本件元従業員らがグンマジを持ち出したことによって,原告がグン マジの開錠方法を独占的に使用することで得られていた市場による優位性を 喪失し,得べかりし利益を喪失したと主張する。 しかし,原告は,本件講座において,原告従業員ではなく,また,原告従業 員になるとは限らない本件講座の受講生にもグンマジの解錠技術を教え,原告 に入社せずに,鍵師として自らで開錠業務を行うことを考えている元受講生に 対してもグンマジを販売していたといえるから,原告がグンマジの開錠方法を 市場において独占的に使用していたとは認められない。また,グンマジによっ て開錠することができるというスイッチサムターンの一般家庭における普及 率は明らかではなく,スイッチサムターンでない鍵はグンマジを使用しなくて も開錠することができるのであり,原告においても,開錠依頼があった案件の 全てでグンマジが使用されていたわけではない。また,被告会社が開錠業務を 行っていた規模が原告の業務に影響を及ぼす程度であったことを認めるに足 りる証拠はない。(甲36,K〔18-20頁〕,被告B〔18-19頁〕,前記 4)。
以上によれば,本件元従業員らがグンマジを持ち出したことによって,原告 が市場による優位性を喪失したことによる損害が生じたとは認められない。も っとも,本件倉庫にあった構成部品と併せて,F及び本件元従業員らのうちの\n誰かが,合計少なくとも2台のグンマジを持ち出したと認められ,被告会社は この行為について使用者責任に基づく損害賠償責任を負うところ,グンマジの 販売価格は1台29万8000円であったから,2台の販売価格相当額の合計 59万6000円が損害となるといえる。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.05.24
平成30(ワ)11204 商標権侵害差止請求事件 商標権 民事訴訟 平成31年4月10日 東京地方裁判所(40部)
引用商標と原告商標の類否について
ア 商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用さ れた場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあ るか否かによって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外 観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して 全体的に考察すべきであり,かつ,その商品又は役務に係る取引の実情を 明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当 である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号3 99頁,最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号10 55頁参照)。
この点に関し,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるもの\nについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と\n比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが, 商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別\n標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外 の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合 などには,その部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判 断することも許されるも 察し得るところ,「ABC」はアルファベットの最初の三文字を並べたも のであり,「初歩。基本。いろは。」などの観念も生じる語として需要者 に馴染みのある上,「ABC」の文字は役務の内容等を具体的に表すもの\nでもないことからすれば,原告商標の指定役務に係る取引者,需要者に対 し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ る。そうすると,原告商標の要部は「ABC」の部分であり,この部分の みを抽出して引用商標と比較して商標の類否の判断をすることが許される というべきである。 原告商標の構成部分である「ABC」と引用商標である「ABC」は,\nその外観,観念及び称呼がいずれも同一であり,整体院等の店舗における 役務の提供に当たり使用されるという実情を踏まえても,原告商標と引用 商標とが同一又は類似の役務に使用された場合に,役務の出所につき誤認 混同を生ずるおそれがあるということができる。
ウ これに対し,原告は,「ABC」の文字には英単語としての意味がない ことから,原告商標の「ABC」の部分はそれのみで役務の出所識別標識 としての機能を有するものではないと主張する。\nしかしながら,「ABC」の文字に英単語として特定の意味を有するも のではないとしても,アルファベットの最初の三文字として需要者にとっ て馴染みがあることは前記判示のとおりであり,「カイロプラクティック」 という部分が,原告商標の指定役務との関係において,役務の種類ないし 内容を表示するものにすぎないのに対し,「ABC」という部分は役務の\n内容等を具体的に表すものでもないことも考慮すると,同部分は,それの\nみで役務の出所識別標識としての機能を有するものということができる。\nまた,原告は,原告商標の「ABC」の部分は,役務の内容や役務を提 供する方針等と関連する略語として使用される実情があるため,原告商標 の「ABC」の部分は「カイロプラクティック」という役務の内容と関連 する何らかの略語という印象を与えるのが自然であると主張する。 しかし,「ABC」という語が役務の内容や役務を提供する方針等の略 語として使用されるのが一般的であるということはできず,むしろ,前記 のとおり,アルファベットの最初の三文字として理解されるのが通常であ るというべきである。そうすると,原告商標の「ABC」の部分が「カイ ロプラクティック」という役務の内容と関連する何らかの略語という印象 を需要者に与えるということはできない。 したがって,原告の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.05.24
平成28(ワ)8552 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年4月18日 大阪地方裁判所
ウ 原告イラストの表現上の特徴\n
原告イラストについては,以下の表現上の特徴を看取することができる。\n
(ア) 原告イラストは,丸まって眠っている猫を上方から描くに当たり,円 形状の上部に配された猫の顔のあごの下から片前足を出して,その片前足を片後ろ 足や尻尾とほぼ同じ場所でまとめて描くことによって,ほぼ全体を略円形状の輪郭 の中に収める一方で,輪郭より外の部分等は描いていないため,全体が一個のマー ク(原告は家紋と表現する。)であるかのような印象を与える。\n
(イ) 原告イラストの基本的輪郭は円形状であるが,耳や片後ろ足が円から 若干突出して描かれているほか,猫の後頭部から肩にかけての部位は若干ふくらむ ように描かれ,機械的な真円ではないことから,猫がきれいに丸まっているという 基本的な印象を維持しつつも,柔らかく自然な印象を与える。
(ウ) 略円形状の上半分には,猫の頭部,片前足,片後ろ足及び尻尾が猫と 分かるように描かれているのに対し,略円形状の下半分は,雲を想わせる抽象的な 紋様となっているところ,略円形状の輪郭に沿って右回りにたどると,猫の顔や首 の白黒の模様が徐々に変化して雲を想わせる紋様となり,さらにたどると,猫の片 後ろ足と尻尾になるという形で連続的に変化しており,また,猫の片前足の付け根 は渦巻状になっているが,これを白黒反転させた紋様が下半分の雲を想わせる紋様 の中に三個存在するため,全体として,猫を描いた部分と抽象的な紋様の部分とが, うまく一体化している。
(2) 被告の主張について
被告は,平成23年9月以前から,原告イラストと同種のイラスト又は写真(乙 1ないし4)が存在していたことを理由に,原告イラストはありふれたものであっ て創作性がなく,美術の著作物に該当しないことを主張する趣旨と解される。 しかしながら,乙1及び2は,実物の猫が鍋の中で丸まって眠っている様子を上 方又は横から撮影した写真であるが,原告イラストは,実物の猫をそのまま忠実に デッサンしたものではないから,これらの写真によって原告イラストの創作性が否 定されるとはいえない。 また,乙3及び4は猫が丸まって眠っている様子を上方から描いたイラストであ るが,乙3及び4の絵には原告イラストとは異なる点が相当数みられ,これらによ っても,原告イラストがありふれたものであると認めることはできない。 なお,被告は,被告イラストを作成する過程で乙5を入手し,被告デザイナーに 渡した旨主張しているが,これが原告において原告イラストを作成した平成23年 9月までの時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない(甲31,32参 照)。
(3) 争点1についての判断
原告イラストは,前記(1)ウで述べたとおり,表現上の特徴を有するところ,前\n記(2)で検討したとおり,これらはありふれたものということはできず,創作性が認 められるから,原告イラストは,原告がこれを作成した時点で,美術の著作物とし て創作されたものと認められる。原告は,前記(1)ア及びイで認定した経緯により,原告イラスト作成後,それを広めるために,あるいは商業的に利用するために,Tシャツ販売サイトを介して,原告イラストを付したTシャツを販売したことが認められるが,これは原告が創作した美術の著作物を用いたTシャツを販売したにすぎないから,このことは,原告イラストの著作物性を否定する理由とはならず,原告イラストが応用美術に属するものとして,その著作物性を否定する被告の主張は,採用できない。
◆判決本文
原告表現、被告製品は以下です。
2019.05.23
Amgen Inc. v. Sandoz Inc., Appeal No. 2018-1551 (Fed. Cir. May 8, 2019)
関連カテゴリー
>> 均等
>> 外国
>> ピックアップ対象
2019.05.22
平成30(行ケ)10061 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月25日 知的財産高等裁判所
甲3には,引用発明2(実施例4記載の用時混合型の医療溶液)が「急性血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。一方で,甲3には,前記(1)イ(イ)認定のとおり,「本発明」の目的の1つは,滅菌されかつ沈殿物を含まず,保存及び使用の間に渡り良好な安定性を保証する「医療溶液」(血液透析,血液透析濾過,血液濾過及び腹膜透析用の透析液,腎疾患集中治療室内での透析用の溶液,通常は緩衝物質を含む置換液又は輸液,並びに栄養目的のための溶液)を提供することにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療室内での透析用の溶液」とは,救急・集中治療領域において,急性腎不全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むことは自明である。
また,甲3には,前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり,1)急性腎不全に罹患している患者に適応となる治療法は,数週間を通しての持続的腎機能代替療法(CRRT)であり,血液濾過が用いられるが,血清リンレベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果,定期的な週3回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で,低リン血症が起こり得るものであること,2)低リン血症は,リンの投与によって予防,治療されるが,医療溶液にリンを導入する場合,沈殿する様々なリン酸カルシウムの形成の問題があり,生理的pHに等しいpH値を有する生理溶液では,リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題があること,3)「本発明」の発明者らは,特定のpH範囲等の如き一定の条件下では,カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及びリン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ,滅菌の安定なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからすると,「本発明」の実施例である引用発明2の「医療溶液」は,急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。以上の点に照らすと,甲3に接した当業者においては,甲3記載の実施例4(引用発明2)において,当該「医療溶液」を「用時混合型急性血液浄化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。したがって,当業者は,引用発明2において,相違点(甲3−1−4’)に係る本件訂正発明1の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。これと異なる本件審決の判断は,誤りである。
(イ)これに対し,被告らは,引用発明2が具体的に「腎疾患集中治療室内での透析用の溶液」あるいは「急性血液浄化用薬液」である旨示した記載はないこと,引用発明2が,明示的な記載なくして,当然に「急性血液浄化用薬液」であると解すべき技術常識はないことからすると,「医薬溶液」として記載された引用発明2を「急性血液浄化用薬液」にすることは,当業者が容易に想到し得たことではないから,相違点(甲3−1−4’)は当業者が容易に想到し得たものではない旨主張する。しかしながら,前記(ア)のとおり,甲3の記載事項に照らすと,当業者は,引用発明2において,相違点(甲3−1−4’)に係る本件訂正発明1の構成とすることを容易に想到することができたものと認められるから,被告らの上記主張は採用することができない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.05.16
平成29(ワ)6906 商標権侵害差止等請求事件 商標権 平成30年11月5日 大阪地方裁判所
被告各商品において,被告各標章は,ミニオンの図柄とともに表示されて\nいるところ,被告各商品のようなTシャツ,下着,帽子,靴下等の服飾品には,一 般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが 多く見られ,被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も,そのようなデ ザインとしての性質を有すると認められる。他方,服飾品では,被告各商品で被告 各標章が付されている位置には,装飾的なデザインと兼ねてブランド名が表示され\nる場合もある(前記1(6))。このことからすると,被告各商品に接した需要者が, 被告各標章を「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様に より使用されていない商標」(商標法26条1項6号)と認識するか否かは,ミニ オンの図柄や被告各標章が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にし つつ,更に被告各標章の使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要があ る。
(2) 前記1(1)ア(ア)で認定したとおり,ミニオンは,それが登場する米国の映 画が大ヒットとなり,●(略)●という対象者を限定した被告のアンケートにおい てであるとはいえ高い周知度があったことから,一般的に高い周知性を有している とキャラクターであると推認される。そして,被告各商品はそのようなミニオンの キャラクターグッズであるから,需要者は,ミニオンのキャラクターに関心を有し, 被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入 するものと考えられる。
そして,前記1(1)イのとおり,被告各商品は主としてUSJのパーク内及び近隣 の直営店舗で公式グッズとして販売されているところ,USJを訪れる需要者が上 記のような関心を有することに加え,パーク内のキャラクターとしてミニオンが導 入されていることからすると,需要者にとっては,ミニオンが,USJ(被告)が 擁するキャラクターであり,被告各商品は,そのUSJ(被告)がパーク内と近隣 で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもっ て,他の商品との出所の識別としては十分であり,それ以上に被告各商品の出所の\n識別を意識する動機に乏しいと考えられる。 また,前記1(2)のとおり,パーク内及び近隣の直営店舗では,ミニオンのキャラ クターグッズは,服飾品である被告各商品に限らず,服飾品でない文房具,歯ブラ シ,コップ,菓子に至るまで多岐にわたって展開されており,それらに広く被告各 標章ないし「BELLO!」が付されている。また,USJのパーク内でも,具体 的商品を離れて,周知のミニオンのキャラクターに関連して,看板等に「BELL O!」との表示がされている。このように,被告各標章や「BELLO!」が,広\nくミニオンのキャラクターとセットで使用されていることからすると,パーク内及 び近隣の直営店舗を訪れた需要者は,被告各標章や「BELLO!」をもって,少 なくとも周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレー ズとして認識すると考えられる(なお,被告は,「BELLO」という語は,ミニ オンが用いるミニオン語として認識されると主張する。しかし,映画の設定上はそ のようにされているとしても,ミニオン語は18種類以上あり,映画の宣伝等でも ミニオン語〔特にBELLO〕に着目した宣伝がされているとも認められないこと 〔前記1(1)ア(イ)〕からすると,ミニオンというキャラクターが周知であることを 超えて,「BELLO」という語がミニオン語であることまでが被告各商品の需要 者の間で周知となっているとは認められないから,需要者が「BELLO」という 語がミニオン語であるとまで認識するとは認められない。)。 これらの状況からすると,パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者が,被告 各標章をミニオンの図柄とは関連のないものと認識し,それによって被告各商品の 出所を識別するとは考え難く,需要者は,被告各標章をもって少なくともミニオン のキャラクターと関連する何らかの語ないしフレーズとして認識し,被告各商品の 出所については,それがUSJ(被告)の直営店舗で販売されるミニオンのキャラ クターの公式グッズであることや,被告各商品にも一般に商品の出所が表示される\n部位である商品のタグやパッケージに本件被告ロゴが表示されていることによって\n識別すると認めるのが相当である。
(3) もっとも,本件各商標が周知なものであれば,需要者は,それを既知の出 所表示として認識しているから,被告各標章が周知のミニオンの図柄と共に表\示さ れ,上記のような状況で販売される場合でも,被告各標章を出所表示として認識す\nることになると考えられる。そして,上記1(5)のとおり,原告が,その創業以来, オリジナルブランドを周知させるべく,「BELLO」の文字ないしその筆記体風 の文字で構成される本件各商標を取り扱う商品に付すなどしてきたことは認められ\nる。
しかし,原告が取り扱う商品が掲載された雑誌は印刷部数が格別多いわけでもな い男性誌に限られ(乙29ないし31,弁論の全趣旨),掲載された頻度も,上記 1(5)ウのとおり短期間に限られている。また,上記1(5)アのとおり百貨店等で原 告が取り扱う商品の販売コーナーが設けられたこと自体は,原告が取り扱う商品の 需要者層に対する訴求力があるとはいえ,販売コーナーはさほど大きなものではな く,コーナーが設けられた期間も短期間にとどまっている。また,原告は,その取 り扱う商品を複数の展示会に出展しているが,いずれも短期のものである上に,回 数も5回にとどまっている。さらに,検索エンジンである「Google」で「BELL O 帽子」等の検索ワードで検索した場合に原告の取り扱う商品に関するウェブペ ージが上位にヒットすること(甲9の1ないし4)は,原告以外にも「BELL O」という文字を含むブランド名を採用する同業者がある程度存在しないのであれ ば,当然のことであって,それをもって本件各商標の周知性を推認することはでき ない。これらからすると,本件各商標が被告各商品の需要者の間で周知性を有する とは認められないから,その既知性に基づいて被告各商品の需要者が被告各標章を 出所表示として認識するとはいえない。\n
(4) 以上に対し,原告は,1)被告各標章が幅広く使用され始めたのは,被告各 商品の販売開始時期の頃ではなく比較的最近のことであり,需要者が,被告各標章 を何らかの出所表示として認識する具体的可能\性が否定される前提を欠く,2)US Jではコラボ商品としてコラボ先の出所が表示された商品が販売されていたり,ウ\nェブサイトではミニオンのキャラクターに係る権利のライセンス先がライセンス商 品を販売したりしていることに照らせば,需要者が,被告各標章を何らかの出所表\n示として認識する可能性は否定されないと主張する。\nまず,1)についてみると,確かに,被告各標章の使用状況が,被告各商品の販売 時期から次第に拡大している可能性は否定できない。しかし,乙54の各写真自体\nには,撮影年月日の表示はないものの,被告において商品販売等を担当する部署の\n者が,新たな店舗展開や装飾展開をするに当たり,これらの履歴を保存しておくた めに店舗状況を写真撮影しておいたという被告の説明に格別不自然な点はない。し たがって,乙54の各写真は,被告が各写真ファイルの作成日から特定したと主張 する各写真の撮影年月日に撮影したものと認められ,この写真から認められる状況 に加え,新規の訪問客を開拓し,リピーターを増やすためにキャラクターを導入し ていると考えられる被告のキャラクターグッズに係るマーケティング戦略としては, 当初からある程度の商品ラインアップを揃えることが合理的に想定されることを考 慮すれば,被告は,ミニオンのキャラクターグッズの販売開始当初から,既に多様 な商品について被告各標章を使用していたと推認するのが合理的である。したがっ て,原告の上記1)の主張は採用できない。 次に,2)についてみると,確かに,上記1(3)のとおり,ミニオンについては,こ れまで複数のコラボレーション商品やライセンス商品が販売されてきたと認められ る。しかし,上記1(3)で認定した事実によれば,コラボレーション商品の場合には, 各商品主体において,それがコラボレーション商品である旨を明示していると認め られるところ,コラボレーション商品は,異なる商品主体同士がコラボレーション することで商品価値の相乗効果を狙う商品であるから,コラボレーション商品であ りながらその旨を明記しないことは通常考え難いことである。そうすると,USJ (被告)の直営店舗で販売されるミニオンのキャラクターの公式グッズであるとい う以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しい需要者において,コラボ レーション商品であることを特に表記していない被告各商品について,他社とのコ\nラボレーション商品であるとの認識が生じる可能性は乏しいと考えられる。また,\nライセンス商品の場合には,一般的にはライセンス先の商標等が表示されることも\n多いと考えられるが,本件では前記のように多岐にわたる商品群や看板等について 被告各商標ないし「BELLO!」が使われていることからすると,上記のような 需要者において,被告各標章が特定のライセンス先の出所を表示するものであると\nの認識が生じる可能性も乏しいというべきである。したがって,原告の上記2)の主 張は採用できない。
(5) また,被告各商品は,USJのオンラインストアでも販売されているが, USJのオンラインストアのトップページには,本件被告ロゴが表示され,USJ\nのオンラインストアであることが明確に認識されるようになっている(乙50)上, 弁論の全趣旨によれば,USJのオンラインストアでは,USJのパーク内及び近 隣の直営店舗で販売されているのと同じ商品が販売されていると認められるから, 同ストアを訪れた需要者は,そこで販売されているキャラクターグッズがUSJの 公式グッズであると認識すると考えられる。 このことからすると,USJのオンラインストアで被告各商品が販売される局面 でも,被告各商品に接した需要者は,それがUSJの公式のキャラクターグッズで あるという以上に商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられ,また,同 ストアには多数の公式キャラクターグッズが掲載されているのであるから,やはり, 需要者が,商品の写真に写っている被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないも のとして,それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難いというべきであ る。
(6) また,被告各商品は,USJのオンラインストア以外のオンラインストア 等で第三者により販売されることもあるが,上記1(4)のとおり,アマゾンでの販売 では,出品者が「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」,商品が「USJ 公式 限定 商品 《ミニオン キッズ キャップ》ミニオン グッズ」と記載され,フ リルでの販売でも,商品が「ハロウィン 子供 ミニオン ミニオンズ ハット キャップ 子供 帽子 USJ」と記載され,いずれも出所がUSJであるミニオ ンのキャラクターグッズであると明記されている一方,それらの商品の写真に写っ ている「BELLO!」ないし「bello!」について言及する記載はない。そ して,被告各商品のような公式グッズは,被告ないしUSJを出所とする公式グッ ズとしての独自の価値があることからすると,第三者が被告各商品を販売するに当 たり,これらと異なり,被告各商品の出所が被告ないしUSJであることを明記し ないとは考え難い。 これらからすると,USJのオンラインストア以外のオンラインストア等で被告 各商品に接した需要者は,USJが自前のミニオンというキャラクターを用いた商 品として,その出所をその表記によって識別すると考えられ,被告各標章をミニオ\nンの図柄とは関連のないものとして,それによって被告各商品の出所を識別すると は考え難いというべきである。
(7) 以上からすると,証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り, 被告各商品が販売されているいずれの局面においても,被告各標章が出所表示とし\nて機能していないから,被告各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品…であ\nることを認識することができる態様により使用されていない」(商標法26条1項 6号)と認められる。また,将来の被告各標章の使用についても,取引の実情の変 化の有無やその態様が明らかではないから,将来における取引の実情の変化を前提 とする判断をすることはできない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.05.13
平成30(ネ)10082 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年4月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(3) 相違点1−2’に係る容易想到性の判断について
ア 公然実施品1のサッシュは,断面形状が複雑であるため,製造コストが 掛かること,サッシュ自体の体積に比べて余分なスペースを大きく取るた めに保管や輸送の際に保管コストや輸送コストも掛かることは,当業者に とって自明なことであり,これらのコスト(製造コスト等)を削減するた めに,公然実施品1のサッシュを複数の部品で構成し,公然実施品1の製\n造時に,当該複数の部品を接合してサッシュとすることは,当業者の通常 の創作能力の発揮にすぎない。\nそして,乙13公報に開示されている「誘導加熱調理器において,サッ シュ(枠体2)とは別部材により構成され,かつサッシュ(枠体2)に当\n接させてねじで接合した,金属板からなる補強板(L字金具9)」(以下 「乙13技術事項」という。)は,公然実施品1のサッシュに相当する部 材を複数の部材で構成する技術であり,乙13技術事項の補強板(L字金\n具9)とサッシュ(枠体2)とを接合したものの方が公然実施品1のサッ シュよりも製造コスト等がかからないのは,当業者にとって自明の事項で あるから,誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品1と 乙13技術事項に接した当業者であれば,製造コスト等を削減する目的で 公然実施品1に乙13技術事項を適用することに格別の困難性があるとは 認められない。 したがって,公然実施品1に乙13技術事項を適用して,相違点1−2’ に係る本件発明1の構成とすることは,当業者が容易に想到し得たことで\nあるといえる。
イ 控訴人の主張について
控訴人は,1)乙13公報における「断面凸形状9a」の実質は,調理器 本体ケース5内への浸水を防止するためだけの役割を担った「浸水防止部 材」であるから,かかる「断面凸形状9a」は本件発明(構成要件D)の\n「補強板」には当たらないし,乙13公報に記載の構成によれば,「断面\n凸形状9a」は調理プレート1から離れる方向に相当強い力で引っ張られ るのであり,実質的に見ても「断面凸形状9a」が調理プレート1を補強 しておらず「補強板」とはいえないから,公然実施品1及び乙13公報に, 本件発明の構成要件Dに係る構\成は開示されていない,2)公然実施品1と 乙13公報に記載の技術とは,主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆, 技術分野の関連性及び課題や作用・機能の共通性が認められないから,公\n然実施品1に乙13公報に記載の技術を適用する動機付けもない,などと 主張する。
しかしながら,乙13公報において,本件発明の「補強板」に相当する ものは「断面凸形状9a」ではなく「L字金具9」全体であって,あたか もそれが「断面凸形状9a」に限定されるかのような控訴人の主張は,そ もそもその前提において誤解がある。また,たとえ乙13公報における課 題そのものは調理器本体内部の浸水防止を図る点にあったとしても,「L 字金具9」全体の形状を見れば,それが本件発明の「補強板」に相当する 機能を果たし得ることは,当業者であれば容易に想起できるものと認めら\nれる(この点は,「断面凸形状9a」が調理プレート1から離れる方向に 相当強い力で引っ張られるとしても変わりがない。「断面凸形状9a」に どのような方向の力が掛かっているかと,それが補強材としての機能を有\nしているかどうかとは関わりのない事柄だからである。)から,前記1)の 指摘は当を得ているとはいえない。 また,前記アのとおり,公然実施品1のサッシュは,製造コスト等が掛 かるものであるということは,当業者にとって自明のことといえるから, 公然実施品1には,かかる製造コスト等を削減するという自明の課題があ る。そして,誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品1 と乙13技術事項に接した当業者であれば,公然実施品1に乙13技術事 項を適用すると製造コスト等を削減できるのは明らかであるから,公然実 施品1に乙13技術事項を適用する動機付けはあるといえる。したがって, 前記2)の指摘も当を得ているとはいえない。
(4) 以上によれば,原判決がした,本件発明と公然実施品1との対比(一致点 及び相違点の認定)と認定した相違点(相違点1−2’)に係る容易想到性 の判断はいずれも正当であり,これによれば,本件特許について無効の抗弁 が成立する。 したがって,無効の抗弁の成立を争う控訴人の主張は採用できない。 被控訴人は,本件訂正の再抗弁につき,時機に後れた攻撃防御方法に当たる として,民事訴訟法157条1項に基づく却下を求めている。 しかしながら,本件訴訟の経過に鑑みると,控訴人による本件訂正の再抗弁 の提出が,時機に後れているか否かはともかくとして,訴訟の完結を遅延させ ることとなるとまでは認められないから,同条項に基づきこれを却下するのは 相当でない。 そこで,以下,本件訂正の再抗弁の成否について判断する。
(1) 控訴人は,平成30年12月14日,本件特許の明細書及び特許請求の範 囲を訂正することについて訂正審判を請求した(本件訂正,甲40)。
(2) 本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(構成\n要件の分説は控訴人に従う。下線部は訂正箇所を示す。)。
A 誘導加熱をする第1及び第2の加熱器を左右に内設した本体ケースと,
この本体ケースの上面に設けられたトッププレートと,
前記トッププレートの周囲に設けられたサッシュとを具備し,
被組込家具に組み込まれる加熱調理器において,
B’ 前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし(ただし,トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じものを除く),
C 前記第1及び第2の加熱器の各中心部を,前記本体ケースの左右に等分した両側部の各中心部より外側であって,前記トッププレートの左右に等分した両側部の各中心部より中央側に配置すると共に,
D 前記トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に前記被組込家具が位置する箇所に,前記サッシュとは別部材に構成され,かつ前記サッシュに当接させた,金属板から成る補強板を設け,
E この補強板と前記トッププレートとの間,又は補強板の下方に断熱層を形成したこと
F を特徴とする加熱調理器。
(3) 進歩性の判断
事案に鑑み,本件訂正後の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件訂正 発明)の進歩性から検討する。
ア 本件訂正発明と公然実施品1との対比
(ア) 「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義 本件訂正事項は,構成要件Bの「前記トッププレートの幅を前記本体\nケースの幅より大きくし,」との構成から「トッププレートの幅と本体\nケースの幅がほぼ同じもの」を除外する,というものである。 控訴人は,本件明細書等の記載や出願時の技術常識等(キッチン設備 のJIS規格等)を踏まえると,本件訂正事項により除外される「トッ ププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義は,本件特許 の出願当時における従来製品の加熱調理器のことと理解すべきであって, 具体的には,トッププレートの幅が約600mm,本体ケースの幅が5 50mm前後の加熱調理器を指していることは,本件明細書等の記載に 接した当業者にとって明らかである,と主張する。 しかしながら,控訴人が主張するトッププレートの幅が約600mm, 本体ケースの幅が550mm前後の加熱調理器やJIS規格(甲25) について,本件明細書等には何ら記載されておらず,示唆もない(本件 明細書等には,例えば,【背景技術】や【発明を実施するための最良の 形態】の欄においても,加熱調理器の寸法について具体的な数値は一切 記載されておらず,JIS規格等の引用もない。)。また,控訴人が主 張するJIS規格(甲25)も,機器を落とし込んで組み込む場合の「ワ ークトップの開口の呼び寸法」と「ワークトップの開口部の開口寸法」 について一定の数式を示しているだけで,「トッププレートの幅と本体 ケースの幅がほぼ同じもの」といえば,当然にトッププレートの幅が約 600mm,本体ケースの幅が550mm前後の加熱調理器を指すとい うことを認めるに足る具体的な記載はない。控訴人は,主要各社の製品 カタログや刊行物等を示して,従来製品の加熱調理器はトッププレート の幅が約600mm,本体ケースの幅が550mm前後のものであった とも主張するが,たとえ本件特許の出願時においてかかる寸法のものが 主流であったとしても,加熱器の配置との関係でトッププレートの幅と 本体ケースの幅の大小の関係を規定する本件訂正発明において,その技 術的範囲から除外される「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ 同じもの」が当然にトッププレートの幅が約600mm,本体ケースの 幅が550mm前後の加熱調理器に限定されると解すべき理由はないと いうべきであるから,控訴人の主張は失当である。
そこで,本件明細書等の【0002】を見ると,「…図7は,そのも のを平面図で具体的に示しており,第1及び第2の加熱器1,2を左右 に内設した本体ケース3と,これの上面に設けたトッププレート4とは, その各幅W3,W4がほゞ同じで,第1及び第2の加熱器1,2の各中 心部O1,O2は,本体ケース3の左右に等分(W3/2)した両側部 の各中心部RO3,LO3(W3/4)とほゞ合致し,且つ,トッププ レート4の左右に等分(W4/2)した両側部の各中心部RO4,LO 4(W4/4)とも合致している。」と記載されている。この記載は, 前段の「…本体ケース3と,…トッププレート4とは,その各幅W3, W4がほゞ同じで,」に続く後段の部分で,「トッププレートの幅と本 体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義を規定しており,同部分(後段の 部分)は,第1及び第2の加熱器1,2の各中心部が,それぞれ,「ト ッププレート4の両側部の中心部に合致する」状態で,なおかつ,「本 体ケース3の両側部の中心部とほぼ合致する」状態であることを表すも\nのと認められる。ここで,本体ケース3の両側部の中心部と第1及び第 2の加熱器1,2の中心部との距離をDとすると,D=W4/4−W3 /4となり,トッププレート4の幅W4と本体ケース3の幅W3との差 は,W4−W3=4Dとなる。 このDがどの程度の距離であるかについて,本件明細書等には明示的 な記載がないが,1)第1及び第2の加熱器1,2の中心部は,それぞれ, 本体ケース3の両側部の中心部とほぼ合致するものとする【0002】 の記載や図7の記載からは,O1とRO3やO2とLO3が隣接してい ると理解し得ること,2)従来技術の課題を解決する手段の一部として, トッププレートの幅と本体ケースの幅については,単に,(トッププレ ートの幅)>(本体ケースの幅)としていること等の事情を勘案すると, D≒0であり,Dは,製造上や計測上の誤差程度と解するのが相当であ る。そして,加熱調理器に関するJIS規格(甲25)には,公差とし て,2〜5mmとする例が記載されていることを勘案すれば,Dについ ては,0<D≦5(mm),すなわち,大きく見積もっても5mmを超 えない程度のものと解することができる。 そうすると,トッププレートの幅と本体ケースの幅との差4Dは,0 <4D≦20(mm)となり,構成要件B’の「トッププレートの幅と\n本体ケースの幅がほぼ同じもの」は,トッププレートの幅と本体ケース の幅との差が,大きく見積もっても20mmを超えないものとなる。
(イ) 本件訂正発明と公然実施品1との対比
以上のとおり,本件訂正発明における構成要件B’の「トッププレー\nトの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」は,トッププレートの幅と本 体ケースの幅との差が,大きく見積もっても20mmを超えないものを 指すと認められる。 これを踏まえると,トッププレートの幅が599mm,本体ケースの 幅が550mmであって,それらの差が49mmである公然実施品1は, 本件訂正発明における構成要件B’の「トッププレートの幅と本体ケー\nスの幅がほぼ同じもの」とはいえないから,構成要件B’は,本件訂正\n発明と公然実施品1との相違点とはならない。 そうすると,本件訂正発明と公然実施品1との一致点及び相違点は, 以下のとおりになると認められる。
(一致点)
本件訂正発明と公然実施品1とは,構成要件A,B’,C,E及びF\nについて一致する。
(相違点)
本件訂正発明は,サッシュとは別部材に構成され,かつサッシュに当\n接させた,金属板から成る補強板を有するのに対し,公然実施品1はサ ッシュ自体が補強板となっており,サッシュとは別部材に構成され,か\nつサッシュに当接させた,金属板から成る補強板は有しない点。
イ 上記相違点についての判断
上記相違点は,本件訂正前の本件発明と公然実施品1との相違点(相違 点1−2’)と実質的に同じであるから,前記1(3)のとおり,本件発明と 同様に,本件訂正発明についても,公然実施品1及び乙13技術事項に基 づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4) 以上によれば,本件訂正発明は,そもそも特許を受けることができないも のである(特許法29条2項)から,本件訂正は独立特許要件(特許法12 6条7項)を満たすものではなく,また,本件訂正によって本件特許に係る 無効理由が解消するものでもない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正の再抗弁 は理由がない。
◆判決本文
一審はこちらです。
◆平成29(ワ)22884
こちらは関連事件の控訴審判決です。
「構成要件Eを充足しない」として非侵害です。\n原告被告は同じで、対象特許が異なります。
◆平成30(ネ)10078
構成要件Eのうち,「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義につい\nて検討する。
上記各文言は,調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり,\n文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから,本件明細
書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで,1⑴にお
いてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると,本件明細書等(【0003】,
【0005】,【0021】,【0028】,【0029】,【0030】,【0
032】)には,リング状枠はトッププレート上に印刷表示され,調理容器を有効\nに加熱できる領域として使用者に示されるものであること(【0003】),リン
グ状枠は加熱部の領域を示し,鍋の最大径と同径で,鍋の外殻を表すものであるこ\nと(【0005】,【0021】)及び加熱部は最大の鍋径と同径で,リング状枠
であること(【0028】,【0029】)が示され,これ以外に,上記各文言の
意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると,「最
大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し,\nまた,リング状枠と同径のものであり,また,「調理容器の外殻」と一致するもの
であると解するのが一般的かつ自然である。
この点,被告は,構成要件Eの内容は不特定であるなどと主張するが,同主張は,\n前記認定に照らし採用することができない。
(2) 被告製品関連製品の構成\n
ア 原告は,別紙3被告製品説明書(原告)において,被告各製品は,「左IH
ヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である
直径26cmの領域を示す外殻線11,12」という構成を有し,これが「調理容\n器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして,被告各製品を
除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。\nイ しかしながら,前記(1)において認定したとおり,「調理容器の外殻」及び「最
大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域\nの領域を示すリング状枠と同径のものであるところ,原告の主張する外殻線11,
12は,原告において付しているものにすぎず,トッププレート上に表示されてい\nるものではないから,これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であ
るとみることはできない。そして,本件全証拠によっても,被告各製品には,加熱
部及び有効加熱領域を示す直径26cmのリング状枠が表示されているとは認めら\nれず,加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」
及び「最大径の調理容器」が直径26cmであると認めることもできない。
原告は,「調理容器の外殻」は,鍋底の最大径であり,被告は被告各製品におい
て鍋底が直径26cmまでの鍋を使用することができる旨説明しているから,被告
各製品の「最大径の調理容器」は26cmのものであると主張する。しかしながら,
被告において上記のように説明することが,被告各製品で使用可能な最大径の鍋底\nを示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても,前記(1)において認定し
たとおり,「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠
及び有効加熱領域は,トッププレートに表示される必要があるのであって,表\示さ
れていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。
(3) 小括
以上のとおり,被告各製品は,原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最
大径である直径26cmの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められな\nいから,この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Eを充足するという原告の主張\nは採用できず,ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また,被告各製品を除く
被告製品関連製品が構成要件Eを充足することを認めるに足りる証拠もない。\nしたがって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品関連製品は,構\n成要件Eを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな
い。
一審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.05.10
平成24(ワ)33752 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成27年2月26日 東京地方裁判所
本件意匠2と被告意匠は,上記第3,2,(1),アのとおり,1)正面視にお いて,板状体の正面ガラス板は隅丸横長四角形形状であり,板状体の正面に は,4つの隅丸縦長四角形形状の電極部分が上下左右に配置されており,上 側の左右に配置された2つの電極部で囲まれた領域のほぼ中央には隅丸横長 四角形の液晶表示窓があり,該液晶表\示窓の下側であって,かつ,上側に配 置された2つの電極部分の上辺を結んだ線,左側に配置された2つの電極部 分の左辺を結んだ線,下側に配置された2つの電極部分の下辺を結んだ線, 右側に配置された2つの電極部分の右辺を結んだ線からなる四角形の対角線 の交点を中心として隅丸四角形からなるスイッチ模様を複数配置して構成さ\nれており,2)側面視において,透明ガラス板と本体背面部とを積層一体とし た構造であるという構\成を有する点で共通している。
相違点について検討すると,正面視において,上記第3,2,(1),イのと おり,本件意匠2と被告意匠とでは透明ガラス板の縦横比が異なっている(本 件意匠2が約1:1.4であり,被告意匠が約1:1.43である。)ものの, その差異は極めて小さく,いずれも看者に対し横長長方形であるという印象 を与えるものというべきである。また,被告意匠には,液晶表示窓の周囲に\nある縁取模様があることが認められるが,これは液晶表示窓の大きさと比較\nしてさほど大きいものではなく,正面視において目立つ色彩でもない。さら に,透明ガラス板の隅丸半径,電極部分の幅と長さの比,液晶表示窓の底辺\nと上側の左右に配置された電極の底辺との関係やスイッチ模様の個数に差異 があるが,これらは,透明ガラス板の形状がほぼ同じであることから看者に 対して与える共通の美感を凌駕するものとはいえない。 本件意匠2と被告意匠とでは,背面視において,上記第3,2,(1),イの とおり,本体部の背面の形状に差異があるが,これは要部における差異では ない。 さらに,上記第3,2,(1),イのとおり,被告意匠には側面視において不 透明プロテクタ体があるが,不透明プロテクタ体は本体背面部と同系統の色 彩であり厚みも薄いことから,この点も要部における具体的構成の共通性か\nら看者に与える美感の同一性を凌駕するものとはいえない。 したがって,本件意匠2と被告意匠とは上記のような差異点があることを 考慮しても,看者に対して共通の美感を与えるものと認められるから,本件 意匠2と被告意匠は類似しているというべきである。
・・・
被告は,被告製品の売上への被告意匠以外の要因が寄与していると 主張する。
証拠(甲30の1,乙23,24,26,28,86)及び弁論の全 趣旨によれば,a 被告は,原告に先んじて体組成計の販売を開始し, 平成15年までは体組成計の年間シェア(数量)の62.9%以上を占 めていたこと,b 平成23年の体組成計の年間シェア(数量)は被告 が38.7%で1位,原告が32.3%で2位あり,3位の企業は14. 5%であること,c 被告が販売する体組成計を購入した者の25.7 7%が被告ブランドを理由に購入していること,d 日経BPコンサル ティングが実施している「ブランドジャパン2011」において消費者 からみた総合力の上昇ランキングで9位とされていること,e 「ブラ ンドジャパン2013」においてコンシューマー市場編総合力と因子指 数において60位とされたこと(原告は同ランキングで183位であっ た。),f 被告が,平成23年7月19日,平成24年6月11日及び 平成25年5月28日にMDBネットサーベイを利用して行ったアンケ ートによれば,体組成計や体脂肪計のメーカーのイメージが強い最も強 い企業を選ぶ問いに対し被告と答えた者が順に68.2%,71.6%, 71.8%であったことが認められる。 以上の事実によれば,被告は体組成計のシェアを長期間にわたり安定 的に有しており,被告が製造する体組成計を購入した者の中には被告の ブランド力を理由とする者も多数おり,被告がブランド力の調査におい て上位にされることがあったのであるから,被告製品の売上に被告のブ ランド力の有する顧客吸引力の貢献もあるというべきである。 しかしながら,一方で,証拠(甲8の2ないし4,27の1・2,3 8)によれば,a 原告製品1又は2を購入した者に対するアンケート 結果では,商品を選択した理由として「デザイン(見た目)が良い」と いう回答をしている者が順に●(省略)●%,●(省略)●%に上って いること,b 一方,同アンケート結果では,「メーカー名」を挙げる 者は各●(省略)●%に過ぎなかったこと,c 体組成計を取り上げた テレビ番組でも,原告製品1について「従来無かったデザイン性の高さ が人気といいます。」,原告製品2について「コンパクトなタイプ。デザ インとカラーで人気を集めています。」などと報道されたこと(平成2 4年12月18日放送・ワールドビジネスサテライト)が認められるか ら,デザインが体組成計の購入動機とならないとはいえない。 なお,前示のとおり,本件意匠2はその出願時点における公知意匠と は異なる構成を有するものであるから,被告が本件意匠2について無効\n審判を請求していることを考慮しても,その創作性の程度が低いという ことはできない(なお,上記無効審判請求については,平成26年12 月24日に請求不成立の審判がされた〔乙99の2〕)。また,本件意匠 2は,部分意匠ではないし,被告意匠は全体として本件意匠2と類似す るのであるから,被告意匠が本件意匠2の一部と類似するに過ぎないと いうこともできない。 したがって,被告製品の売上には被告意匠以外の要因として被告ブラ ンドの顧客吸引力も寄与しているといえるから,このような事情につい ては原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができ ないとする事情として考慮することができるというべきである。
(イ) 被告は,原告が原告製品1及び2を追加的に販売する際に注文に対 応できない台数の割合があることを考慮すべきと主張する。しかしなが ら,原告は1か月に●(省略)●台の原告製品1及び2を輸入,販売す ることができると認められるところ(甲42),原告が原告製品1及び2 が売れすぎたために品切れを起こし販売を中止した期間があると認める に足りる証拠はない。したがって,原告が原告製品1及び2を追加的に 販売する際に注文に対応できない台数の割合があることを原告が被告製 品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができないとする事情とし て考慮することはできないというべきである。
(ウ) 被告は,原告製品1及び2には被告製品の他に競合品があると主張 する。確かに,体組成計について,原告製品1及び2の他に原告や被告 の他多数の企業から多数の製品が販売されていることは当事者間に争い がないが,証拠(甲30の1)によれば,平成23年の体組成計の年間 シェアは被告が38.7%で1位,原告が32.3%で2位あり,3位 の企業は14.5%であることが認められ,被告と原告とで体組成計の 年間シェアの71%を占めていることからすると,被告製品がなかった 場合,被告製品の購入者の大部分は被告が販売する製品か原告が販売す る製品を購入するものというのが相当である。そして,前示のとおり被 告製品を購入した者はメーカー名よりもデザインに着目して購入してい るところ,証拠によっても,平成24年10月から平成25年9月30 日までの間に被告が販売する被告製品以外の体組成計にその意匠が本件 意匠2と同一又は類似するものがあるとは認められないのである。そう すると,原告製品1及び2には被告製品の他にも競合品があるという事 情は,被告製品が販売されていた期間において原告製品1及び2か被告 製品しか選択肢がないという状況ではなかったから,被告製品がなかっ たとしても被告製品の譲渡数量の全てについて原告製品1又は2が購入 されたということはできない(しかし,大部分は原告製品1又は2が購 入されたといえる。)という程度において,原告が被告製品の譲渡数量の 全部又は一部を譲渡することができないとする事情として考慮すること ができるにとどまるというべきである。
(エ) 以上によれば,被告製品の売上には被告ブランドの顧客吸引力の寄 与もあるという事情,原告製品1及び2には被告製品の他に競合品があ り,被告製品が販売されていた期間において原告製品1及び2か被告製 品しか選択肢がないという状況ではなかったという事情は,上記説示の 範囲で,原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することがで きないとする事情として考慮することができる。また,前示のとおり, 被告製品の生産等は本件意匠権1を侵害しないという事情があり,これ も原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができない とする事情として考慮することができる。これらの諸事情を考慮すれば, 被告製品の譲渡数量のうち50%に当たる●(省略)●台(小数点以下 切り捨て。)について原告が譲渡することができない事情があるというべ きである。
オ 前記前提事実のとおり,原告は,1か月に●(省略)●台の原告製品1 及び2を輸入,販売することができたから,平成24年10月から平成2 5年9月までの間,原告製品1及び2を併せて●(省略)●台を輸入,販 売することができた。 カ 以上によれば,意匠法39条1項により損害の額とされる額は1億17 41万3662円である。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.05. 8
平成30(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月19日 知的財産高等裁判所
ア 甲5発明には,T細胞を処理するための組成物の用途が,「T細胞による インターロイキン−17(IL−17)産生を阻害する」ためであるとの特定がな いが,前記(2)アのとおり,甲5発明の「T細胞を処理する」とは,IL−12によ るT細胞の処理,すなわちTh1誘導によるT細胞刺激を阻害することを指すもの であって,甲5には,記載も示唆もされていない「T細胞によるインターロイキン −17(IL−17)産生を阻害する」ことを指すものではないことは明らかであ る。 他方,本件特許発明1におけるIL−23のアンタゴニストを含む組成物の用途 は,「T細胞によるインターロイキン−17(IL−17)産生を阻害するため」で あるが,本件明細書(【0071】〜【0081】,【0083】,【表1】,【図2A】,【図4A】)には,従来から知られていたTh1誘導条件(IL−12+抗IL−4)下及びTh2誘導条件(IL−4+抗IFN−γ)下では,いずれもIL−17産\n生が増加しなかったのに対し,IL−23存在下ではIL−17産生が増加したこ とに加え,Th1誘導条件下に比べIFN−γ産生が著しく低かったこと,IL− 23が介在するIL−17の産生は,IL−23のp40サブユニットの中和抗体 によって遮断されたことが記載されている。 これらの記載によると,本件特許発明1における「T細胞によるインターロイキ ン−17(IL−17)産生を阻害するため」という用途は,IL−23によるT 細胞の処理によってT細胞におけるIL−17の産生が増加するという知見に基づ き,IL−23によるT細胞の処理により引き起こされるIL−17の産生を阻害 することを用途とするものであり,上記知見は,従来から知られていたTh1誘導 やTh2誘導によるT細胞刺激とは異なるものであると認められる。 したがって,本件特許発明1における「T細胞によるインターロイキン−17(I L−17)産生を阻害するため」という用途は,従来から知られていたTh1誘導 によるT細胞刺激とは異なる,IL−23によるT細胞の処理により引き起こされ るIL−17の産生を阻害することを用途とするものであるから,甲5発明の「T 細胞を処理するため」とは明確に異なるものであり,相違点5は,実質的な相違点 であると認められる。
イ 原告は,審決は,甲5発明の抗体含有組成物の用途を「T細胞を処理す るため」と認定したにもかかわらず,本件特許発明1との対比においては,甲5発 明の抗体含有組成物の用途が「Th1誘導によるT細胞刺激の阻害」に限定される ものとして,相違点5を認定しており,そもそも矛盾していると主張する。 しかし,甲5発明の抗体含有組成物の用途を「T細胞を処理するため」と認定し たことにより,甲5発明の「T細胞を処理する」の意義を甲5の記載を離れて解釈 してよいことになるものではないから,審決が,本件特許発明1との対比に当たり, 甲5発明の「T細胞を処理する」の意義を甲5の記載に基づいて解釈することは正 当であって,何らの誤りもない。
ウ 原告は,甲5X発明に係る抗体含有組成物の用途は,「T細胞の処理によ る乾癬治療」であるが,乾癬患者について格別の限定又は選別をすることなく,「T 細胞の処理による乾癬治療」を実施すると,当然に,「T細胞によるインターロイキ ン17(IL−17)産生阻害」も生じるから,甲5X発明の「T細胞の処理によ る乾癬治療」と本件特許発明1の「T細胞によるインターロイキン17(IL−1 7)産生阻害」とは,用途として同一であり,甲5X発明と本件特許発明1との間 に相違点はないなどと主張する。この主張を,甲5発明について,甲5に記載され ている用途も考慮して本件特許発明1の新規性を判断すべき旨の主張と解したとし ても,次のとおり理由がない。
(ア) 前記アのとおり,本件特許発明1は,IL−23によるT細胞の処理に よってT細胞におけるIL−17の産生が増加するという知見に基づいて,「IL −23のアンタゴニストを含む組成物」について「T細胞によるIL−17産生を 阻害するための(インビボ処理方法において使用するための)」という用途の限定を 付したものであると認められるところ,慢性関節リウマチの患者であってもIL− 17濃度の上昇がみられなかった者がいるように(甲17〔審判乙1〕),すべての 炎症性疾患においてIL−17濃度が上昇するものではないし,特定の炎症性疾患 においてもすべての患者のIL−17濃度が上昇するものではないと認められるか ら,本件特許発明1の組成物を医薬品として利用する場合には,特にIL−17を 標的として,その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものという ことができる。
(イ) 他方,前記(1)のとおり,甲5には,IL−23のアンタゴニストにより T細胞によるIL−17産生の阻害が可能であることは,記載も示唆もされていな\nいから,甲5発明が,「IL−23のアンタゴニストを含む組成物」を,T細胞によ るIL−17産生を阻害するために,IL−17濃度の上昇が見られる患者に対し て選択的に利用するものではないことは,明らかである。このことは,甲5発明の 「IL−23のアンタゴニストを含む組成物」を乾癬治療のために使用することが できるという甲5に記載されている用途を考慮しても,左右されるものではない。
(ウ) そうすると,本件特許発明1の「T細胞によるインターロイキン−17 (IL−17)産生を阻害するため」という用途と,甲5発明の「T細胞を処理す るため」という用途とは,明確に異なるものということができる。そして,このこ とは,本件優先日当時,IL−17の発現レベルを測定することが可能であったこ\nとによって左右されるものではない。
エ 原告は,本件特許発明は,せいぜい,IL−23アンタゴニストに備わ った「T細胞によるIL−17産生を阻害する」という性質又は機序を明らかにし て,これを説明する構成要件を付加したにすぎないから,甲5X発明と異なる新規\nな方法(用途)とはいえないなどと主張する。この主張を,甲5発明について,甲 5に記載されている用途も考慮して本件特許発明1の新規性について判断すべき旨 の主張と解したとしても,前記ウのとおり,本件特許発明1の「T細胞によるイン ターロイキン−17(IL−17)産生を阻害するため」という用途と,甲5発明 の「T細胞を処理するため」という用途とは,明確に異なるのであるから,本件特 許発明1の用途が,甲5発明の用途を新たに発見した作用機序で表現したにすぎな\nいものとはいえないことは,明らかである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2019.05. 8
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底\n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信\n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構\成」という。)が,本件当 初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構\成が記載されていると認めること はできない。
(イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0 008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】, 【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には, 先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決め るための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響 信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるもので あって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】, 【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には, 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船 上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識 をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上\nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底 局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件 発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,…\n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で 行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を, 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明 らかに不自然である。 したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されている\nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構\n成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算\nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細 書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの というべきである。 したがって,この点についての審決の判断には誤りがあり,その誤りは 結論に影響を及ぼすものである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2019.04.24
平成30(行ケ)10148 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月18日 知的財産高等裁判所
本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」の物品分野の当業者 が,慶弔用品の分野における意匠1及び意匠2の形態を「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到するかどうかについて検討する。
(ア) 「卓上敷マット」は一般のテーブルや机に敷かれるものを含む日常生 活に用いられる物品である一方,証拠(乙2〜4,17,18)及び弁論の全趣旨 によると,意匠1の「マット」や意匠2の「盆茣蓙」は,現在では主として盆の時 期に精霊棚や仏壇の前に置く経机や小机の上に敷き,上に位牌やお供え物などを置 く慶弔用品の分野の物品であり,その物品分野は「卓上敷マット」とは異なるもの である。 しかし,いずれもテーブルや机という「卓」(乙1によると,「卓」にはテーブル や机が含まれると認められる。)の上に敷かれて使用されるものであるという点で その用途が共通している。また,意匠1の「マット」や意匠2の「盆茣蓙」の形状 は,いずれも「卓上敷マット」と同じマット状であり,上に物を載置することがで きる点においてその機能が共通している。\n
(イ) そして,証拠(乙5〜8,12〜15)及び弁論の全趣旨によると, 本願の出願日前において,「盆茣蓙」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテ ーブル掛けなどの物品が,同一の見本市などに出品されることがあり,「卓上敷マッ ト」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が,「盆茣蓙」のような慶弔用品の 形態に接する機会は十分あったものと認められる。\n
(ウ) 以上を考え併せると「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品 分野の当業者は,物品分野は異なるものの,意匠1から着想を得て,真菰を並べて 形成された「卓上敷マット」を想到し,更に真菰を並べて形成された慶弔用品の「盆 茣蓙」である意匠2の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到することができたと認められる。 なお,「卓上マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野と「盆茣蓙」などの慶弔 用品の物品分野では,常に物が載置されるかどうかや一定の時期にのみ使用される かどうかに違いがあるとしても,これらの違いは,上記認定の用途や機能の共通性\nに比べるとささいな違いというほかなく,上記判断が左右されることはない。
ウ 原告は,1)「盆茣蓙」と「卓上敷マット」とは,用途や機能が異なって\nいて非類似であること,2)意匠1や意匠2のような真菰で形成されたマットは,慶 弔用品で仏具の上に敷かれるものであるところ,日常生活で使用されている机に慶 弔用品を祀ることは,浄・不浄の概念からもあり得ないこと,3)前記ギフトショー についての審決の論理を前提とすると,百貨店などであらゆる商品が同スペースで 展示されていることから,全てのあらゆる物品分野間で創作容易性が肯定されてし まうこと,4)自らの商品デザインにつき異業種商品のデザインを盗用することは信 義に反すること,5)慶弔用品としての真菰で形成された「盆茣蓙」に接した取引者, 需要者は,「盆茣蓙」の上にあるお供え物に注目することなどを理由として,「盆茣 蓙」についての形態を「卓上敷マット」に転用することを考えないと主張する。
(ア) 上記1)について,前記1で説示したとおり,意匠法3条2項は,物品 との関係を離れた抽象的な公然知られたモチーフを基準として,当業者の立場から みた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるから,物品が非類似であ ることが直ちに創作が容易でないことに結びつくものではない。そして,本件で転 用を容易に想到できることは前記イのとおりである。
(イ) 上記2)について,原告の主張は,「盆茣蓙」が慶弔用品であって,宗教 的感情によって転用が妨げられるというものであると解されるが,証拠(乙2)に よると,「盆茣蓙」について,かつては,「丁半博打で,壺を伏せる場所へ敷くござ」 という慶弔用品以外の用途もあったと認められる上,前記イ(ア)認定の用途や機能の\n共通性に照らすと,宗教的感情によって当業者における意匠1及び意匠2の形態の 転用が妨げられるとは解されない。
(ウ) 上記3)について,前記イの判断は,見本市などにおいて,慶弔用品と 「卓上敷マット」を含む物品が出品されていることのみを理由とするものではなく, 前記イ(ア)認定の用途や機能の共通性も理由としているから,全てのあらゆる物品分\n野間で形態の創作容易性が認定されてしまうことにはならない。
(エ) 上記4)について,本願意匠に創作容易性を認めたからといって,デザ インの盗用を認めることにはならず,デザインの盗用とは関係がない。
(オ) 上記5)について,創作容易性の基準となるは取引者,需要者ではなく, 「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であって,その視点 や着眼点が取引者,需要者と同じとはいえず,また,当業者において転用を容易に 想到できることは前記イのとおりである。
(カ) 以上からすると,原告の上記主張は採用することができない。
(2) 相違点1,2についての判断
前記(1)のとおり,意匠2の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に 転用することは容易であると認められるから,次に,前記4で認定した意匠2と本 願意匠との相違点1,2について,創作が容易であるかについて検討する。
ア 相違点1について,証拠(乙9,10)及び弁論の全趣旨によると,「卓 上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者にとって,「卓上敷マット」 の縦横比を必要に応じて適宜調整することはありふれた手法であると認められる。 したがって,意匠2の平面視略横長長方形の縦横比を本願意匠の縦横比に変更す ることについて,意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえない。
イ 相違点2について,本願意匠と意匠2で用いられている編み糸の色彩自 体に違いはなく,本願意匠の構成は,意匠2の構\成から紫色の糸と赤色の糸の配置 を入れ替えたにすぎないものである。また,証拠(乙9)及び弁論の全趣旨による と,「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野において,色彩を適宜変更 することはよく見られる手法であると認められる。 そうすると,意匠2の5本の編み糸のうち,紫色の糸と赤色の糸の配置を入れ替 えて本願意匠の構成にすることについて,意匠の着想の新しさや独創性があるとは\nいえない。
ウ 以上からすると,本願意匠は,意匠2の形態に基づいて,当業者におい て容易に創作できたものと認められる。
◆判決本文
関連事件です。
2019.04.24
平成30(ネ)10068等 損害賠償請求控訴事件同附帯控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審の東京地裁(40部)は、33万円の請求を認めましたが、双方が控訴しました。知財高裁(2部)は、被控訴人(一審被告)敗訴部分を取り消していますが、損害額は妥当としました。取り消した原因は、被控訴人(一審被告)は原告に対して弁済をしたとので、損害賠償債権は消滅したというものです。
ア 本件記載1〜3は,平成27年記事中の記載であるところ,平成27年 記事の内容からすると,同記事を閲読した者が,普通の注意と読み方によって本件 記載1,2の部分を理解すると,同部分には,控訴人が,本件サイトにおいてジョ レン本社の商品を販売しているが,同商品はジョレン本社の商品の真正品ではない こと(同事実を,以下「本件事実1)」という。)が摘示されており,本件事実1)と 共に,控訴人の商品の仕入先が不明であること,控訴人は,ジョレン本社と取引が ないこと,控訴人が販売している商品の価格は極端に安価であること,被控訴人は, ジョレン本社に報告し,控訴人は,販売の中止を求められたが,販売を継続してい ること,控訴人の店舗は,本件サイト上に記載された住所にはないこと,ジョレン 本社では控訴人には大変困っていること(これらの事実を併せて,以下「本件事実 2)」という。)が摘示されており,また,控訴人は,厚生労働省の許認可を受けず に上記商品を販売しており,同行為は薬事法に違反すること(以下「本件事実3)」 という。)が摘示されていると理解するものと認められる。 そして,本件事実1),3)は,同記載を閲読した者に対し,控訴人は,ジョレン社 の商品の真正品でない商品を販売しており,また,同販売行為は薬事法に違反して いると認識させるのであるから,本件記載1,2の掲載によって,控訴人の社会的 評価は低下し,控訴人の信用,名誉が毀損されたというべきである。
・・・
本件記載4は,平成26年記事中の記載であるところ,平成26年記 事を閲読した者が,普通の注意と読み方によって,本件記載4を理解すると,同記 載部分には,最近,顧客からの報告で,商品を,香港経由でアメリカに入れ,本件 商品の真正品と告知して,カリフォルニアなどから,発送している業者を発見した ことが摘示されていると理解するものと認められる。そして,本件記載4では,そ のような業者が控訴人であるとは特定されておらず,また,平成26年記事全体の 記載を考慮しても,上記業者が控訴人であると認識することはできない。 したがって,本件記載4が掲載されたことによって,控訴人の社会的評価が低下 するということはできないから,本件記載4の掲載は控訴人の信用,名誉を毀損す るとは認められない。
(イ) 本件記載5は,平成26年記事中の記載であるところ,平成26年記 事を閲読した者が,普通の注意と読み方によって,本件記載5を理解すると,同記 載部分には,パッケージ,説明書,容器が日本語表記であり,国内発送であること\nを確認し,ジョレンジャパン,日本真正品などの表記のある店舗で本件商品の真正\n品を購入すべきことが摘示されていると理解するものと認められる。 ところで,平成26年記事には,「たとえ,アメリカ真正品であってもパッケー ジが英語表記の物は,保証は致しかねます。」との記載もあり,同記載からすると,\n本件商品については,「アメリカ真正品」も販売されており,パッケージや説明書 等が英語表記であったり,また,日本の正規代理店以外の店舗で販売された本件商\n品の中には「アメリカ真正品」も含まれていると理解することができる。そうする と,平成26年記事を閲読した者は,控訴人商品が,パッケージや説明書等が英語 表記であったり,日本の正規代理店で販売されていないとしても,「アメリカ真正\n品」であると認識することが考えられるから,本件記載5から,直ちに控訴人商品 が真正品ではないと認識するとは認められないし,他に,本件記載5について控訴 人の社会的評価を低下させる記載があるとは認められない。 したがって,本件記載5が掲載されたことによって,控訴人の社会的評価が低下 するということはできないから,本件記載5の掲載は控訴人の信用,名誉を毀損す るとは認められない。
・・・・
ア 本件記載6は,薬事法上の許認可を有しない者が,インターネット等で, 本件商品を並行輸入により販売することは薬事法違反となるという内容であり,同 記事を閲読した者も,そのように理解するものと認められる。 そして,本件記載6が含まれる冒頭記事には,控訴人が薬事法上の許認可を有し ていないことについては一切記載されておらず,控訴人が薬事法上の許認可を有し ないことが本件ウェブページの閲読者に知られていると認めるに足りる証拠もない から,冒頭記事を閲読した者に,控訴人が控訴人商品を販売することが薬事法に違 反することになると認識されることはなく,したがって,本件記載6の掲載により, 控訴人の信用,名誉が毀損されたと認めることはできない。
・・・
本件記載1,2を掲載して本件事実3)を摘示した行為によって,控訴人が被った 損害の額は,上記掲載がインターネット上に公開する方法で行われたこと,その公 開された期間(約1年4か月間)等諸般の事情を考慮すると,30万円と認めるの が相当であり,また,上記行為と相当因果関係の認められる弁護士費用は3万円と 認めるのが相当である。
◆判決本文
原審はこちらです。
2019.04.23
平成29(ワ)7764 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月11日 大阪地方裁判所
本件サイトを閲覧する者がまず目にすることになる本件サイトのトッ プページ(本件トップページ)の上部には,本件共通表示のタイトルとして「みん\nなのおすすめ,塗装屋さん」の文字が他の文字よりも大きく表示されている(甲5\nの1等)上,その右部には,本件ランキング表が表\示されている。前記のとおり, 本件サイトを訪問する需要者が,サービスの質,内容に言及した口コミを基にした 評価が掲載されているという先入観を持っており,そのような需要者が,「みんな のおすすめ」のタイトルの下でのランキングに接することからすると,本件トップ ページを閲覧した者は,投稿された口コミを基にして外壁塗装業者やリフォーム業 者の提供するサービスの質,内容に関するランキングが作成されており,そのラン キングにおいて1位にランク付けられている業者の提供するサービスの質,内容は, 掲載業者の中で最も「おすすめ」,つまり最も「優良」であると評価されていると 基本的には認識すると考えられる。そして,本件トップページに表示されている\n「みんなのおすすめ,塗装屋さん」という表示及び本件ランキング表\は,本件サイ トのいずれのページにおいても表示されていることに照らせば,本件サイトの閲覧\nを続けていく限り,上記認識は補強されていくものと考えられる。 これに対し,被告は,本件サイトでのランキングは口コミ件数のみに基づくもの であり,閲覧者もそのように認識すると主張し,1)本件サイト説明ページには, 「ランキングは今の所口コミ件数で で決定されているとは通常想定されないことである。 この観点から見ると,前記のうちの2)の本件口コミランキングページの記載につ いては,その直後に「口コミの内容については,投稿後に一定時間を経過してから ランキングへと自動反映される仕組みになっています。」と,口コミ内容を基にし てランキングを作成しているように理解される内容の表示がされており,口コミ件\n数を基にしてランキングを作成しているという内容の表示を文字通りのものとして\n受け取って良いのかに疑問を抱かせてしまう表示になっている。\nまた,前記のうちの1)の本件サイト説明ページの記載については,文字自体は赤 字という比較的目立つものではあるが,その記載場所は同ページの下部にある「管 理人のつぶやき」欄の末尾という目立ちにくい場所にあり,かえって同ページの上 部にある説明本文欄では,その冒頭で本件サイトを「利用者からの投稿によりおす すめ業者をランク付けしたサイト(口コミサイト)」と説明しており,より目立つ 上部の本文欄の記載によって,口コミを基にして業者をサービスの内容,質により ランク付けをしているとの認識を補強することとなっている。 さらに,前記のうちの3)については,確かに本件サイトにはランキング評価上考 えられる諸要素をどのように考慮してランキングを作成したのかについては,全く 記載されていないが,本件サイトのランキングが「おすすめ」の口コミランキング とされている以上,それに接した需要者は,何らかのやり方で口コミに基づいて業 者が提供するサービスの良・不良を評価していると認識するのが通常であると考え られるから,点数等の表示がないからといって,本件サイトのランキングが,投稿\nされた口コミの件数だけを基にして作成されたものであるとの認識が生じるとは認 められない。 したがって,上記の点によっては,口コミを基にして業者をサービスの内容,質 によりランク付けがされているとの上記認識が払拭されるとは認め難く,被告の上 記主張は採用できない。そうすると,結局のところ,本件サイトを閲覧した者は, 本件ランキング表を始めとする本件サイトにおけるランキングは,外壁塗装業者や\nリフォーム業者の提供するサービスの質,内容に関して,投稿された口コミの件数 だけでなく,その内容をも基にして作成されたものであり,本件ランキング表示に\nついては,そのランキングにおいて1位にランク付けられている被告の提供するサ ービスの質,内容が,掲載業者の中で最も優良であると評価されていると認識する と認められる。
(イ) 他方,本件サイトを閲覧した者は,本件サイトが口コミサイトである と認識している以上,本件サイトのランキングも,所詮は口コミという主観的な評 価を集積したものにすぎないということは当然認識しているはずであるから,本件 サイトのランキングにおいて問題とされているサービスの質,内容に関する評価が, それらの客観的な優劣を問題にするものではないことも認識していると認められる。 そして,前記のとおり,本件サイトにはランキング評価上考えられる諸要素をどの ように考慮してランキングを作成したのかについて全く記載されていないことから すると,本件サイトを閲覧した需要者は,結局のところ,そこに記載されている口 コミの中で,高評価の件数が多く,低評価の件数が少なければ上位にランキングさ れ,逆であれば下位にランキングされるといった程度の認識を生じるにすぎないと 認めるのが相当である。 この点について,原告は,本件サイトを閲覧した者が,本件サイトのランキング を見て,外壁塗装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質,内容に関する客 観的な優劣がランク付けされたものであり,そのランキングにおいて1位にランク 付けられている被告の提供するサービスの質,内容が客観的に最も優良であると認 識するかのような主張をする。しかし,上記のとおり,本件サイトを閲覧した者は, 口コミランキングである本件サイトのランキングが,口コミという主観的な評価を 集積したものにすぎないということは当然認識しているはずである。また,外壁塗 装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質,内容において重要視される諸要 素は,個々人の価値観によって異なるものであるため,これらに関する客観的な優 劣をランク付けすることなどそもそも不可能であることは,誰にでも容易に認識で\nきることである。以上の諸点に照らせば,本件サイトを閲覧した者は,本件サイト のランキングを見ても,外壁塗装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質, 内容に関する客観的な優劣がランク付けされたものであるとは認識せず,口コミを 投稿した者の主観的な評価を基にランク付けしたものであると認識すると認められ るから,原告の主張は採用できない。
(ウ) 次に,原告は,本件サイト説明ページでは,本件サイトが「日本全国 で営業している外壁塗装業者を対象に…おすすめの業者をランク付けしたサイト」 であると説明されていること(甲5の2)から,本件サイトを閲覧した者は,本件 ランキングが全国のあらゆる外壁塗装業者の中でのランキングであって,こうした ランキングにおいて被告が1位とされていることから,被告が全国のあらゆる外壁 塗装業者の中で最も優良な業者であるとの認識が生じると主張する。 しかし,本件掲載業者一覧ページを見れば,本件ランキングの対象とされる掲載 業者の範囲が,一覧表示することが可能\な程度のものにすぎないこと(甲5の4 等)は容易に認識できるから,本件サイトの閲覧者において,本件サイトのランキ ングが全国に存在するありとあらゆる外壁塗装業者やリフォーム業者を対象にする ものであるとの認識が生じるとは認められない。そして,本件掲載業者一覧ページ に掲載されている業者の本店所在地が,関西地方の「大阪府」及び「兵庫県」,関 東地方の「東京都」及び「神奈川県」,中部地方の「愛知県」及び「石川県」並び に九州地方の「福岡県」というように各地方にまたがっており,店舗数も7店舗の ものから155店舗のものが掲載されていること(甲5の4,甲17の1及び2, 甲26の1及び2)に照らせば,「日本全国で営業している外壁塗装業者を対象」 というのは,全国的に営業活動を行う事業者を全国各地からピックアップして対象 としたという程度の意味にすぎず,本件ランキングも,そうしてピックアップした 掲載業者の中でのランキングであると理解すると考えられる。したがって,原告の 主張は採用できない。
(エ) 以上のとおりの本件サイトを閲覧する者の認識を前提とすれば,本件 サイトのランキングは,投稿された口コミの件数及び内容を基に作成された,本件 掲載業者一覧ページに掲載されている業者の提供するサービスの質,内容に関する 評価のランク付けを表示したものであって,被告がランキング1位であることは,\n投稿された口コミの件数及び内容に基づき,被告の提供するサービスの質,内容が, 本件掲載業者一覧ページに掲載されている業者の中で投稿者の主観的評価として最 も優良であると評価されていると表示したものである。\n
(4) 本件サイトにおける被告がランキング1位であるとの表示(本件ランキン\nグ表示)の品質誤認表\示該当性
ア 上記のような本件サイトを閲覧する者の認識からすると,本件ランキン グ表示は,掲載業者の中での,投稿された口コミの件数及び内容に基づく評価との\n間にかい離がないのであれば,品質誤認表示に該当するとはいえない。\nそこでまず,被告への口コミの件数についてみると,本件サイトの表示上,他の\n業者への口コミ件数よりも絶えず多くなっている(甲5の3,甲6の1ないし3, 甲21の1ないし4)。また,被告への口コミの内容についてみると,本件サイト の表示からうかがうことができるものについて,別紙「被告への口コミ内容一覧\n表」記載のとおりの口コミが投稿されている。\nこのように本件サイトの表示からうかがうことができる範囲に限ってみると,被\n告への合計32件の口コミは,一部を除いて基本的に,工事の質や接客態度といっ た被告の提供するサービスの質,内容を高く評価するものであるところ,このこと に,原告も被告への口コミが高評価のものばかりであると主張しているという弁論 の全趣旨を併せ考えると,被告への口コミは,証拠上本件サイトの表示からうかが\nうことができない範囲のものについても,被告の提供するサービスの質,内容を高 く評価するものであると推認される。 このように被告への口コミは,その件数が最も多いだけでなく,その内容も軒並 み高評価のものであることからすると,本件ランキング表示(本件サイトにおける\n被告がランキング1位であるとの表示)と,被告へのく評価との間にかい離はないと認められる。\n
イ もっとも,そもそも被告への口コミが虚偽のものである場合,例えば, 被告が自ら投稿したものであったり,形式的には施主又は元施主(以下「施主等」 という。)からの投稿であったとしても,その意思を反映したものではなかったり などする場合は,本件サイトの表示上の被告への口コミの件数及び内容をそのまま\nのものとして受け取ることが許されなくなり,その結果,本件ランキング表示との\nかい離があるということとなる。そこで,次にこの点を検討する。 (ア) まず,本件サイトの公開日は平成24年3月5日であるところ,被告 への口コミとして表示されている口コミのうち5件の口コミについては,口コミ内\n容とともに表示されている日付が,同日より前のもの(同年2月2日,同月11日,\n同月13日,同月21日及び同月25日付け)になっている(同年6月11日時点 の表示として甲21の1)。このような事態は,それらの投稿が真に施主等による\nものであれば,考え難いものである。 この点について,被告は,サイト公開前にヒューゴが入力したテスト投稿の消し 忘れの可能性を指摘する。しかし,被告が,これら5件の口コミが既に投稿されて\nいたと認められる平成24年6月11日(甲21の1)よりも後の同月28日に, ヒューゴに対してバックデイト機能を要求したり,その要求の際に投稿された口コ\nミが直ぐに反映されずにタイムラグが生じるという問題点も併せて指摘したりして いること(乙10)からすると,被告は,それ以前に本件サイトに投稿された口コ ミを確認していたと考えられ,その場合に公開日前の日付が投稿日として表示され\nている口コミがテスト投稿の消し忘れであれば,これを放置するとは考え難いから, そのまま残されている上記5件の口コミが,ヒューゴによるテスト投稿の消し忘れ であるとは考え難い。
また,被告は,1)平成24年2月14日よりも後になって初めて口コミが投稿で きるようになったと思われるにもかかわらず,上記5件の口コミのうち3件はそれ 以前の日付が投稿日となっていること,2)被告の施主等から本件サイトの公開前に 返送されてきたアンケートの存在(乙14)に照らせば,上記5件の口コミについ てはヒューゴが本件サイトの公開後に施主等の投稿をバックデイトしたものである 可能性が高いと主張する。しかし,ヒューゴは被告からの依頼を受けて本件サイト\nを制作したにすぎず,本件サイトの公開後にヒューゴが被告の依頼を受けて注力し ていたのも各種キーワードによる検索順位の向上にすぎない(乙6ないし12)か ら,そのようなヒューゴが,本件サイトの歴史を少しでも長く見せようなどとして, 本件サイトの公開後に投稿された口コミを独断でバックデイトしようとする動機が そもそも見いだし難い(なお,被告が平成24年6月28日にヒューゴにバックデ イト機能を要求していることからすると,それ以前に表\示されていた上記5件の投 稿が,被告がバックデイトを指示したものであるとも考え難い。)。そして,上記 1)の主張は,本件口コミ投稿フォームが完成するまでの間については,ヒューゴで あっても口コミを投稿できないことを前提とするものであるが,本件サイトの仕組 みに照らせば,制作者であるヒューゴであれば,本件口コミ投稿フォームが完成す る前でも口コミの投稿作業をすることは不可能ではなかったと認められる(甲5,\n28,29,弁論の全趣旨)。また,上記2)の主張については,本件サイトの公開 前に返送されたアンケートは,飽くまで本件サイト外でのアンケートにすぎないか ら,仮に上記5件の投稿内容がアンケート結果に即したものであったとしても,上 記5件の投稿が本件サイトの公開後にされたものをバックデイトしたものであると 推認されるわけではない。また,この点はおくとしても,被告以外の業者に関する 口コミについても,口コミ内容とともに表示されている日付が本件サイトの公開日\nである平成24年3月5日より前になっているものがあること(甲21の2ないし 4。なお,甲21の5については時期が明らかでない。)に照らせば,被告に対す るアンケートの存在から,口コミ内容とともに表示されている日付が本件サイトの\n公開日である平成24年3月5日より前になっている理由を説明できるものではな い。したがって,被告の上記主張は採用できない。 以上からすると,本件サイト公開前の日付となっている5件の投稿は,被告の関 与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした架空の投稿であると認められる。そして, 確かに,同様の日付の投稿は他の業者についても存在するが,それらの投稿はいず れも各4件である(甲21の2ないし4。甲21の5でも同様である。)から,被 告については,これらにより,本件サイトの公開時点から,既にランキング1位と 表示されていたと推認され,その表\示は虚偽であったといえる。
(イ) 次に,本件サイト公開後の投稿を見ると,1)掲載業者に対する投稿フ ォームは,(a)平成24年6月11日時点では,「地域」と「口コミ内容」を入力す るものであった(甲33の1)のが,(b)同年12月16日までには,「名前」, 「メールアドレス」,「ウェブサイト」及び「コメント」を入力するものに変更さ れ(甲33の2),その後,(c)セキュリティのための計算式の回答の入力が加わり (甲6),その状態が平成27年5月25日時点でも維持されていた(甲28の 1)こと,2)掲載業者以外の業者に対する投稿フォームは,平成27年5月25日 時点でも(a)と同じであったこと(甲27の1)が認められる。 これによれば,掲載業者に対する投稿については,少なくとも平成24年12月 16日以降は「地域」を入力することがないはずであるが,その後の被告及び他の 1社の情報の掲載ページでは,氏名が表示されるべき欄に地域が表\示されているも のが見られる(被告についての甲6の1では3件,他社についての甲6の3では2 件)。しかも,乙10によれば,本件サイトでの掲載業者への投稿は,平成24年 6月28日以降は投稿内容が即時に反映させる仕様になっていたと認められるから, 上記の投稿もそれによるもののはずである。そうすると,上記の投稿は不可解とい うほかなく,この点について被告から合理的な説明はないから,それらの投稿が真 に施主等がした真正なものであるかについては重大な疑問を抱かざるを得ない。 また,乙10によれば,被告は,平成24年6月当時,コメントを書いた施主等 にプレゼントを進呈していたと認められ,また,甲15によれば,被告は,平成2 9年9月頃,本件サイトに関する新聞社の取材に対し,「顧客の感想を社員が聞き 取って(自社の口コミとして)投稿したことはあったが虚偽は書いていない」と回 答したと認められ,このように被告が施主等から聞き取った内容を自ら口コミとし て投稿したことがあることは,当事者間に争いがないところ,この対応からすると, 何とかして被告への口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れる。そしてまた, 乙10によれば,被告の担当者は,平成24年6月28日にヒューゴとの間で本件 サイトの改修を打ち合わせるメールの中で,「過去コメント分の編集(入力日時) の変更はできないでしょうか?」と述べていたと認められるところ,このメールか らは,施主等から投稿される口コミをそのまま反映させようとしない作為的な態度 が見て取れる。
以上のような重大な疑問と被告の態度に加え,前記(ア)のとおり,被告は,その関 与の下に本件サイトの公開時点で架空の投稿が表示されるようにしていたことを考\n慮すると,上記の「地域」が表示された投稿も架空のものと認めるのが相当である。\n (ウ) もっとも,上記(ア),(イ)で述べた投稿を除いても,被告への投稿件数 が1位であることに変わりはない。そして,乙10によれば,被告の担当者は,平 成24年6月28日,ヒューゴとの間で本件サイトの改修を打ち合わせるメールの 中で,「あと技術的な部分の確認なのですが,コメント入力後の即反映に変更する ことはできないでしょうか?プレゼントを差し上げるため,お客様に入力確認の連 絡を頂いているのですが,タイムラグが発生してしまい上手く進んでいません。」 と述べていたと認められるところ,このメールからすると,施主等自身が実際に投 稿をすることがあったと認められるから,被告への口コミとして表示されている口\nコミのうち,投稿日が本件サイトの公開日以降となっているもの全てが虚偽のもの であるといえないことは明らかである。しかし,上記のとおり平成24年3月5日 の時点で被告は架空の投稿を表示し,同年12月16日以降も架空の投稿をしてい\nるのであって,施主等への通常の投稿の勧誘により被告への高評価の投稿数が1位 になるのであれば,そのような架空の投稿までする必要はないはずである。このこ とに加え,前記のとおり上記の間の同年6月28日の時点でも被告は施主等からの 投稿日を変更しようとする作為的な態度を示していたことからすると,被告は,架 空の投稿を相当数行うことによって,ランキング1位の表示を作出していたと推認\nするのが相当である。
ウ 以上からすると,本件サイトにおける被告がランキング1位であるとい う本件ランキング表示は,実際の口コミ件数及び内容に基づくものとの間にかい離\nがあると認められる。 そして,本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは,投稿者の主\n観に基づくものではあるが,実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の 意見が集積されるものである点で,需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすもので ある。したがって,本件サイトにおけるランキングで1位と表示することは,需要\n者に対し,そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として,その提供 するサービスの質,内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示\nする点で,役務の質,内容の表示に当たる。そして,その表\示が投稿の実態とかい 離があるのであるから,本件ランキング表示は,被告の提供する「役務の質,内容\n・・・について誤認させるような表示」に当たると認めるのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.04.22
平成30(ネ)10053等 育成者権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件 その他 民事訴訟 平成31年3月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,1)青果物としてのしいたけ市場において,被控訴人のしい たけには,99.9%の圧倒的なシェアを占める強力な競合品が存在し ていたこと,2)漬物製造・販売メーカーである控訴人(侵害者)が従来 の取引を通じて培ってきた小売店における販路と,小売店,問屋の担当 者に対する営業努力による市場開拓の結果がしいたけの販売実績につな がったこと,3)侵害品は,被控訴人のしいたけに比べて,低価格の個別 包装品であり,一般消費者向けの見た目を備える等品質が良好であった こと,4)業務用の被控訴人のしいたけと,一般消費者向けの控訴人のし いたけ(被告各しいたけ)の市場が非同一であることなどを指摘して, 被控訴人には,譲渡数量の全部又はその99.9%に相当する数量を育 成者権者が「販売することができないとする事情」(法34条1項ただ し書)があったと認めるのが相当であると主張する。 しかしながら,前記1)の市場占有率(非占有率)がそのまま「販売す ることができないとする事情」(その割合)に反映されるとの考え方は 極論であって採用できないというべきであるし,前記2)の控訴人が漬物 の製造・販売によって築いた信用や販売力というものを殊更しいたけの 市場において重要視することも,その関連性が客観的な証拠に裏付けら れているとまではいえない以上,採用できない。また,前記3)及び4)の 点も,原判決が認定した70%という割合を超えて「販売することがで きないとする事情」があったと認めるには足りない。 結局のところ,控訴人が当審で主張する諸点はいずれも原審における 主張の繰り返しにすぎず,採用できないものといわざるを得ない。
(ウ) 被控訴人の主張(当審における主張)について
他方,被控訴人は,正当な権利に基づかない販売(侵害品の販売)を 前提に市場競争力等を論ずること自体失当であるとして,被控訴人は控 訴人による侵害行為がなければ,本件品種に係るしいたけを全部販売し て1kg当たり152円の利益を上げることができたのであるから,法 34条1項ただし書の「販売することができないとする事情」は皆無で あった,などと主張する。 しかしながら,侵害行為の前後で控訴人・被控訴人の市場占有率が大 きく変わっていることなどの事情は具体的に示されておらず,ほかに原 判決が認めるよりも更に「販売することができた」と認めるに足る客観 的事情はない。 したがって,この点に関する被控訴人の主張も採用できない。
キ 小括
以上を前提に,本件で認められるべき逸失利益の額を検討すると,次の とおりとなる。 すなわち,控訴人に本件育成者権侵害の不法行為が成立する期間は平成 24年6月から平成25年1月までの8か月間であり,この間の譲渡数量 (損害額算定の基礎となる譲渡数量)は15万5579.297kgであ って,これに被控訴人のしいたけ1kg当たりの利益額152円を乗じる と,その額は2364万8053円となる。 ただし,このうち70%については被控訴人において「販売することが できないとする事情」があったと認められることから,その7割を減じる こととすると,本件で認められるべき被控訴人の逸失利益の額は,709 万4415円となる。
・・・
(2) 調査費用
証拠(甲19〜21)によれば,被控訴人は,本件育成者権侵害の事実を 調査するため,1)侵害状況記録書等作成費用11万6260円,2)品種調査 資料作成費用143万9778円及び3)DNA解析費用46万7882円(合 計202万3920円)を支出したものと認められる。しかるところ,本件 においては,法2条5項2号に基づく収穫物に対する権利行使が一部制限さ れること等の事情に鑑みれば,前記金額のうち,その2分の1に相当する1 01万1960円に限り,控訴人の侵害行為と相当因果関係のある損害と認 めるのが相当である。
(3) 弁護士費用
本件の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害としては, 81万円を認めるのが相当である。
2019.04.22
平成29(ワ)849 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 平成31年3月28日 大阪地方裁判所
また,具体的構成態様については,各収納部の底部と開口部(収納口)の位置関\n係(同イの一部,ウ),大型収容部の左側面窓部の透明のフィルムの有無(同オの一 部),ベルトの金属製の留め具の有無等(同ク),背面部の形態(同ケ)及び表面の\n色や生地(同コ)を除き,共通している。
そして,共通点のうちベルトの形状(具体的構成態様キ)及び各収納部の大きさ\n(具体的構成態様ア)は本件意匠の主たる要部であり,それにより,被告意匠には,\n本件意匠と同様のスマートでシンプルという印象が生じている(なお,被告意匠の ベルトは,本件意匠のベルトよりも数mm程度太いが,それによって以上の判断は左 右されない。)。 他方,本件意匠と被告意匠とは,各収納部の底部と開口部の位置関係(具体的構\n成態様イの一部,ウ)という副次的な要部において相違しており,確かに,被告意 匠では,各収納部の底部の位置がほぼそろえられていることによって,本件意匠と 対比すると,よりまとまりのある印象を与えているということはできる。しかし, 本件意匠の要部の検討で述べたとおり,引用意匠3ないし9と対比した場合の本件 意匠の大きな特徴は,各収納部やベルトの形態(主たる要部)によってスマートで シンプルな印象を与えるという点にあり,被告意匠が各収納部の底部と開口部の位 置の差異によって,よりまとまりのある印象を与えているとの点は,上記のスマー トでシンプルな印象の範囲内での相違にすぎず,それによって本件意匠と被告意匠 の美感が異なるものになったとまでいうことはできない。なお,原告は,原告製品 とは異なり,小型収納部の底部を大型収納部の底部とそろえた製品を販売するに至 ったが,これによって以上の判断は左右されない。 この点について,被告は,原告製品と被告各製品を購入した者がインターネット に書き込んだコメントの内容が異なっている旨主張し,乙37を提出しているが, 意匠に関するコメントは必ずしも多くないし,被告製品1の「おしゃれ」とか「か っこいい」というのが上記のスマート又はシンプルさを排斥するものとまで認める ことはできないから,これによって前記判断が左右されるとはいえない。 また,被告は,被告意匠では両収納部の底部の位置がほぼそろえられ,小型収納 部の開口部が大型収納部の開口部よりも下側にあることから,小型収納部にクリー ナーを収納できることを指摘するが,それは,そのような使い方もできるという程 度のものにすぎず,そのことによって小型収納部の形状自体が新規なものになって いるというわけでもないから,その点によって前記判断が左右されるとはいえない。
(イ) また,本件意匠と被告意匠のその他の差異点は,要部に関するもので はないことなどから,それによって本件意匠と被告意匠の美感が異なるものになる とも認められない。
この点,被告は,被告意匠2ないし6に関し,生地に関する差異点(具体的構成\n態様コ)によって,共通点を凌駕する程度に別異性が認められるとも主張している が,本件意匠は生地の態様に特徴のあるものでなく,被告意匠2ないし6も生地に 顕著な特徴があるとはいえないし,本件意匠に係る物品は電子タバコケースである から,需要者がまず着目するのは製品の形状であり,基本的にはケースの生地や色 が美感に与える影響が大きいとはいえないから,その差異点が上記共通点による美 感を凌駕すると認めることはできない。
ウ したがって,本件意匠と被告意匠とは一致点の印象が差異点の印象を凌 駕し,類似していると認めるのが相当である。
2 争点2(被告による先使用権の成否)について
・・・
上記の被告代表者の陳述及び供述のとおりであるとすると,被告は,本件\n意匠の登録出願日である平成28年6月20日の時点で,原告製品とは関係なく被 告各製品のデザインを決定し,その製造委託の発注までをシャインカラー社に対し て行うとともに,IMP社から被告製品2の販売を受注していたことになるから, 少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備をしていたことにな る。そこで,上記の被告代表者の陳述及び供述の信用性について検討する。\n
・・・
ところで,原告製品は同年5月8日に発売されたから,創作者である被 告代表者が本件意匠を知らないで被告意匠を創作したといえるためには,同日以前\nの被告の開発状況が重要になる。そして,被告代表者の陳述及び供述では,シャイ\nンカラー社と最初に協議したのは同年5月4日であり,そこでデザインを決めてサ ンプル製作を指示した次の協議が上記の同年6月15日とされているから,同年5 月4日の時点での協議内容(前記(1)イ)の信用性が重要となる。
(ア) まず,被告各製品の開発についてのシャインカラー社との協議が平成 28年5月4日に行われたことについては,被告代表者の打合せノートの5月4日\nの記載(乙30の1及び2)がある。そして,同ノートの記載については,前記の とおり同年6月初旬ころないし同月15日の記載(乙30の4ないし6)が信用し 得ると認められることから,被告代表者が日常業務の上で作成していたものとして\n基本的に信用できると考えられる。また,被告代表者が同年4月から5月にかけて\n新規のIQOSケースの開発を考えたということには,被告が同年4月当時,セパレー トタイプのIQOSケースを開発し,同商品が同年5月18日までに販売されていたと 認められること(乙32)から,時期的にもあり得ることである。
(イ) そこで,乙30の1の記載を見ると,「サンプル」として,1)「セパレ ート」,2)「ガラ携のベルトケース」,3)「2段のスマホケース」が記載されている から,これらを見ながら協議したと認められるところ,1)が被告が開発していたセ パレートタイプ(乙12,32)であり,3)が中国で販売されていた2段重ねタイ プ(乙15,16)であると認められる。このうち2)は,「実用NG?」と記載され ているから候補から外れたと認められ,被告代表者も同旨を述べている。次に,1) については,「充のみ」と「充+カートリッヂ(タバコ)」の2通りが検討された記 載となっており,これが特段排除された記載はない。しかし,被告代表者は,セパ\nレートタイプは,金具で無理矢理つなげる点や男性的で客層を狭くする点に難点が あったことや,被告代表者の息子が作った商品であるために真似をしたくないとの\n思いがあったと供述しており,この供述は自然かつ合理的なものである。そうする と,この協議において,1)のタイプは採用されず,3)の2段重ねタイプが採用され たとの被告代表者の陳述及び供述は信用できると考えられ,その場合,乙15及び\n16の例のとおり,大型収納部と小型収納部を同方向に重ね,それらの幅や高さを タバコパッケージや携帯用充電器の大きさとほぼ同じようにするのは自然なことで ある。 そして,乙30の1においては,「別でクリーナーやミニUSBケーブル」との記 載があるから,クリーナーを入れられるようにしたり,ミニUSBケーブルを通す 孔を設けたりすることが検討されたと認められるところ,前者の点からすると,被 告各製品のように両収納部の底部の位置をそろえることにより,小型収納部の上部 に余裕空間を設けるのが合理的であり,そのようにすることが乙15及び16の例 からも自然であるから,このような方針となった旨の被告代表者の陳述及び供述は\n信用し得る。なお,前記のとおり後の同年6月15日の時点で,被告代表者は,サ\nンプルに対して小型収納部の底部を大型収納部の底部と同じ位置まで下げるよう指 示しているが,この点について,被告代表者は,サンプルで底がそろっていなかっ\nたのは,その方が縫製が楽であることから,シャインカラー社が構造的に楽なもの\nを作ったためであると供述しており,この点も被告代表者の同陳述及び供述と整合\n的である。 また,背面部の上端を正面まで伸長させたベルトについても,絞り込まれて幅が 細く,正面まで伸長させるものは乙15及び17にもあり,被告自身が販売し,人 気のあった手帳型の携帯電話のケースでは先端が半楕円形であって,平坦で,その 幅が均一で,細いベルトが備えられていたから(乙18,50),被告代表者が被告\n意匠のベルトの形状等に着想することは自然なことといえる。そして,このことは, 前記の同年6月15日のサンプルのチェック時には,ベルトについて修正指示がな かったこととも整合的である。 また,底部の携帯充電器用の孔や左側面の窓部についても,前者については上記 のとおり同年5月4日の打合せにおいて協議されていたことであり,その発想から すると後者についても協議されていても不合理ではない。 なお,前記のとおり,被告代表者は,同年6月15日のサンプルのチェック時に,\n裏の生地をハイクラス(合成皮革のライチ柄)にするよう修正指示しているが,同 年5月4日の打合せノートでも「ライチ柄(ハイクラス)」とされている(乙30の 1)から,その指示も同日の指示に従うよう求めたにすぎないと認められる。 そして,被告代表者は,このときの訪中時に,シャインカラー社に対してサンプ\nルを発注したことは,乙30の2から認められる。 以上のとおり,被告代表者は被告各製品の開発(被告意匠の創作)過程について\n具体的な供述をしており,その内容は各証拠とも整合していること,同年5月4日 の協議から同年6月15日のサンプル確認まで何らかの連絡協議が行われたともう かがわれず,かえって,被告代表者の月に1回程度訪中しているとの供述は,1回\nの訪中時に数日をかけて数社との打合せをしていること(乙30)と整合している ことを考慮すると,被告意匠を同年5月4日の協議の時点で創作していた旨の被告 代表者の陳述及び供述は,その信用性を認めることができる。\n
ウ 原告の主張について
原告は,原告製品が平成28年5月8日から楽天市場において販売されてお り,楽天市場で1位にランクインしたことがあることや,中国で模倣品が製造され ていること(甲15,16)を指摘し,被告代表者が本件意匠を知っていたと主張\nしている。 しかし,製品の開発過程で他社製品を参照することは一般的に行われることでは あるが,前記のとおり本件では,原告製品が発売されるより前に被告代表者がシャ\nインカラー社に対して被告各製品のサンプル製作を指示していたことにつき相応の 裏付け証拠があることからすると,原告製品とは関係なく被告各製品を開発した旨 の被告代表者の陳述及び供述は信用し得るというべきであり,原告主張の事情は,\n上記認定を左右するに足りるものではない。また,中国の実情(甲15,16)も 一般論にすぎず,被告代表者が本件意匠を知っていたことを直ちに推認させるもの\nとはいえない。
(3) 以上の検討からすると,被告は,本件意匠の登録出願日までに,本件意匠 を知らないで被告意匠を創作し,一部の被告各製品の製造の委託をシャインカラー 社に発注し,これは被告が日本国内で被告各製品の販売を行うためにされたことで あり,またIMP社から被告製品2の販売を受注するに至っていたと認められるか ら,被告は,少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備を行っ ていたというべきである。
2019.04.22
平成30(行ケ)10152 意匠権 行政訴訟 平成31年4月11日 知的財産高等裁判所
両意匠の意匠に係る物品は,電動歯ブラシの本体(把持部)であり,主な需 要者は,電動歯ブラシを使用する一般消費者である。そして,かかる需要者が, 電動歯ブラシを使用するときは,通常,シャフト部にブラシヘッドを装着した 電動歯ブラシの本体を手に取り,歯磨き粉を付けたブラシヘッドを口腔内に 入れてから本体の動作制御釦を押して始動した後,本体を把持しながら,ブラ シヘッドを歯に当てて歯磨きを行うことからすると,本体把持部の握りやす さや操作の容易さを重視し,本体把持部の全体形状に特に注目をするものと 認められる。 しかるところ,両意匠は,「全体は,隅丸長方形状の底部より,僅かに正面 側に偏心しながら,円状の上面部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の電 動歯ブラシ本体把持部と,該本体把持部上面に設けられた,該上面の略半径を 直径とする略円柱状の基台部とその上に配された縦長板状のシャフト(シャフ ト部)で構成をされている点」(共通点1)及び「シャフトについて,本体把\n持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し,正面視中央部に横断する段差が設 けられ,背面側には略縦長矩形の凹部が設けられている点」(共通点2)で共 通する。 そして,共通点1は,底面に対して僅かに正面側に偏心した本体把持部の全 体形状に係るものであって,本体把持部の握りやすさ及び操作の容易性に及ぼ す影響が大きいこと,共通点2は,本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに 傾倒したシャフト部の形状に係るものであって,本体把持部の偏心した形状と 相まって歯に当たるブラシヘッドの角度に影響を及ぼすことに照らすと,共通 点1及び共通点2は,これを見る需要者に対し,全体として,共通の美感を起 こさせるものと認められる。 他方で,両意匠は,相違点1(本願意匠は,本体把持部の正面に上端より全 長約3分の1の箇所と,約2分の1の箇所に僅かに凹部をなす略円状の電動歯 ブラシ動作制御用釦が縦に2つ配されているのに対して,引用意匠は,上端よ り全長約3分の1の箇所に1つ配されるものとなっている点),相違点2(本 願意匠は,電動歯ブラシ動作制御用釦の外形線が一重の円状であるのに対して, 引用意匠は,該動作制御用釦の外形線が二重の円状となっている点),相違点 3(環状細線の位置),相違点4(本体把持部の下部の形状及び切り替えの有 無)及び相違点5(シャフト部の基台部の形状)において相違するが,これら の相違点から受ける印象は,両意匠の上記共通点から受ける印象を凌駕するも のではない。 したがって,本願意匠と引用意匠は,これらの相違点を考慮しても,需要 者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認めら れるから,本願意匠は,引用意匠に類似するものと認められる。
(2)ア これに対し原告は,1)共通点1に係る「全体は,隅丸長方形状の底部よ り円状の上部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の本体把持部と,略 円柱状の基台部と略縦長板状のシャフトとを有する電動歯ブラシ本体」の 構成態様は特徴的な形状であるとはいえない,2)共通点1のうち,「本体 把持部が僅かに偏心していること」は,需要者に与える印象という観点か らは,従来から存在する上部にかけて側面視背面側をただ窄めただけの形 状と明確な区別のつくものではないため,特徴的な形状とはいえない,3) 共通点2に係る「シャフト部の背面側に略縦長形状の凹部が設けられてい る点」は,その部位があまりに小さく,背面に備えられていることと相ま って,需要者の注意をひく部分とはなり得ないため,特徴的な形状という ことはできないとして,本願意匠の基本的構成態様は,需要者である使用\n者の注意を強くひくものとはいえず,共通点1及び2に係る態様は,需要 者に共通の美感を起こさせるものとはいえない旨主張する。 しかしながら,上記1)の点は,共通点1のうち,一般的な電動歯ブラシ の本体が有する形状と共通する一部の形状のみを取り上げたものであり, 共通点1の有する全ての形状について言及したものとはいえない。 また,上記2)の点は,本体把持部の全体形状に特に着目する需要者(前 記(1))においては,本体把持部が僅かに偏心している本願意匠の形状と 本体把持部の底面に対して軸を垂直にしたまま上部にかけて側面視背面 側を窄めただけの形状とを容易に区別するものと認められる。 さらに,上記3)の点は,共通点2のうち,一部の形状のみを取り上げた ものであり,シャフトが本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し ている点及びシャフトの正面視中央部に横断する段差が設けられている 点を看過している。
以上のとおり,原告の上記主張は,共通点1及び共通点2の形状の一部 のみに着目したものであって,これらの共通点の全体が与える視覚的効果 を踏まえたものといえないから,採用することができない。
イ 次に,原告は,1)歯を磨くという電動歯ブラシの機能の観点からは,需要\n者が電動歯ブラシを操作する動作制御釦の位置,大きさ及び形態が最も強 く需要者の注意をひく部分であり,要部である,2)需要者は電動歯ブラシ を使用する際に必ず動作制御釦部を観察するから,動作制御釦部が,全体 と比較して僅かな範囲のものであるとしても,需要者に対し,強い印象を 与えること,釦が2つの場合は,それぞれの釦の機能を考慮しながら釦を\n操作するため,2つの釦を注視することとなり,釦が1つの場合と比べて, 釦の形態により注意が向けられることに照らすと,本願意匠の釦が縦に2 つ配されている態様(相違点1に係る本願意匠の態様)は,上の釦の径よ り,下の釦の径がやや小さく形成されているという点と相まって,需要者 の注意を強くひくものであり,釦が1つ配されている態様の引用意匠とは 異なる美感を起こさせるものであるとして,本願意匠の要部である動作制 御釦が需要者に与える印象は引用意匠とは大きく異なるから,両意匠は, 全体として類似しない旨主張する。 しかしながら,前記(1)認定の電動歯ブラシの通常の使用態様に照らすと, 需要者は,本体把持部の握りやすさや操作の容易さを重視し,本体把持部の 全体形状に特に注目をするものと認められ,動作制御釦の位置,大きさ及び 形態は,電動歯ブラシの操作時に需要者の一定の注意をひく部分であると しても,最も強く需要者の注意をひく部分であるとはいえない。 また,甲2(意匠登録第1478109号の意匠公報)記載の「電動歯ブ ラシ本体」の意匠(別紙3)及び甲3(意匠登録第1219080号の意匠 公報)記載の「電動歯ブラシ」の意匠(別紙4)によれば,電動歯ブラシに 動作制御釦を2つ配することは,本願の優先日前に,普通に行われていたも のと認められる。そして,本願意匠の2つの動作制御釦は,1つは,本体把 持部上端より全長約3分の1の箇所に配され,引用意匠の動作制御釦とそ の位置が共通し,他の1つは,上記動作制御釦の垂下にあたる本体把持部上 端より全長約2分の1の箇所に配され,特異な位置にあるとの印象を与え るものではない。
加えて,本体把持部の上部側に配された動作制御釦の直径より,その下部 に配された動作制御釦の直径が僅かに小さく形成されている2つの動作制 御釦を有する電動歯ブラシの本体把持部の形態は,本願の優先日前に公知 であったこと(乙1)に照らすと,本願意匠の動作制御釦が,2つ縦に配さ れ,僅かに凹部をなし,上の釦の径より,下の釦の径がやや小さく形成して いる点は,特徴的なものとはいえず,需要者の注意を特にひくものとはいえ ないから,本願意匠の動作制御釦と引用意匠の動作制御釦の構成態様の違\nいが需要者の視覚を通じて起こさせる両意匠の全体的な美感に影響するも のと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成28(ワ)28925等 損害賠償請求事件(本訴),使用料規程無効確認請求事件(反訴) 著作権 民事訴訟 平成31年2月1日 東京地方裁判所
(ウ) 次に,本件使用料規程における使用料の差違が合理性を有するかにつ いて検討する。
a 本件使用料規程は著作権等管理事業法13条に基づいて文化庁長官 に届出のされたものであるが,同法は,著作物の利用の円滑性確保と いう観点から著作物等管理事業者に対して,使用料規程の作成,届 出義務を定めている。そして,同法は,使用料規程作成に当たって の利用者又はその団体から予め意見を聴取する努力義務と,使用料\n規程を届け出た場合における使用料規程の概要の公表義務を定め,\n恣意的な使用料規程の作成を防止するとともに(同法13条),使 用料規程において不相当に高額な使用料の額が設定され著しく利用 者の利益を害する場合などには,文化庁長官が一定の要件の下で, 業務改善命令(同法20条)による是正措置を講じることとされて いる。このように,同法においては,使用料規程の不合理な使用料 の規定の是正を図るための規定が置かれているところ,本件におい ては,文化庁長官による原告に対する業務改善命令がなされた等の 事実はうかがわれない。
b また,日本音楽著作権協会,日本シナリオ作家協会,日本文芸著作 権保護同盟,日本放送作家組合,日本芸能実演家団体協議会の権利者\nの5団体は,昭和50年以降,個々のケーブルテレビ事業者に再放送 の許諾を与えており,その際に用いられた使用料の算定式は,区域外 再放送と区域内再放送の使用料に6倍の差を設けるものであって,上 記団体の一部については,現在も同様の算定式に基づいて使用料の徴 収が行われているとの事実が認められる(弁論の全趣旨)。
c さらに,地上基幹放送事業者は,それぞれの放送対象地域内におい て放送を行っているところ,有線テレビジョン放送事業者の提供する 区域外再放送は,視聴者にとってはその区域においては当然には視聴 することのできない番組の視聴が可能になるものであるため,強い顧\n客吸引力を有していることがうかがわれ(甲25),さらに日本放送 協会の受信料が1波・1世帯当たり年額6800円であること(甲2 0)なども考慮すると,本件使用料規程の定める使用料が不合理に高 額であるということはできず,また区域外再放送と区域内再放送の使 用料及びその間の差(5倍)が不合理であるということはできない。
d これに対し,被告は,放送事業者が区域内再放送に比べて区域外再 放送の場合に多額の費用を投じている事情もなく,有線放送テレビジ ョン事業者は,放送対象地域を越えて飛び出している電波を受信して 再放送を行なっているにすぎず,大阪を中心にすると徳島県は兵庫県 北部や京都府北部と距離的に変わらないなどと主張する。 しかし,総務省が平成25年に行った調査によれば,被告が讀賣テ レビの区域外再放送を行っている徳島県板野郡北島町,松茂町及び上 板町のいずれにおいても,電界強度が放送法関係審査基準の基準値未 満であり,画質についても継続的に良好な受信が可能であるとまでは\nいえない状態であったとの事実が認められる(乙6)。また,毎日放 送等の親局(大阪局)の放送エリアには上記3町は含まれず,その中 継局の放送エリアにも同各町は含まれていない(甲24)。
以上によれば,区域外と区域内で電波の受信状況は必ずしも同一と いうことはできず,放送事業者が区域内再放送に比べて区域外再放送 の場合に多額の費用を投じる必要がないと認めるに足りる証拠もない。
e 被告は,水道事業等の公共事業においては料金について原価主義の 考え方が採られていることに鑑みても,区域内再放送と区域外再放送 とを区別する合理的な理由はないと主張する。 しかし,原告の行う管理事業は水道事業のような公営事業ではなく, また,水道法においては,水道事業者の定める供給規程が「料金が、 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものである\nこと。」との要件に適合しなければならないと定められている(同法 14条1項1号)のに対し,著作権等については再放送使用料を原価 に基づいて設定すべきことが義務付けられているものではない。 このように,水道等の公益事業と原告の行う管理事業とは,その根 拠法令,制度趣旨,使用料の算定の方法等が異なっているのであり, 水道事業等の公共事業との対比において本件使用料規程の合理性を判 断することは相当ではない。
f 被告は,徳島県は,関西広域連合の一員であるところ,徳島県鳴門 市の視聴者が隣接する兵庫県南あわじ市の視聴者の5倍から50倍の 視聴料を払わなければならないのは不合理であると主張する。 しかし,前記判示のとおり,放送法は放送対象地域の内と外で明確 に区別をしており,区域内再放送と区域外再放送とで一定の異なる 扱いをすること自体は法が予定している以上,隣接した市町村であ\nったとしても,放送対象地域が異なる場合には視聴料が異なるのは やむを得ないというべきである。そして,本件使用料規程における 使用料の額及び区域内再放送と区域外再放送の使用料の差が不合理 とはいえないことは前記判示のとおりである。 なお,被告は,本件使用料規程の年間の包括的利用許諾契約によ らない場合の区域外再放送の使用料(年間で計算すると1200円) と本件基本合意の区域内再放送の使用料(年間24円)とを対比し て,50倍の格差があると主張するが,本訴の請求は本件使用料規 程の算式によるものであるから,区域内再放送と区域外再放送の使 用料の格差の合理性については,同規程の同一種別についての料金 を比較して判断すべきであり,本件使用料規程と本件基本合意のし かも異なる種別における料金を比較することは相当ではない。
g 被告は,関東広域圏,中京広域圏,近畿広域圏のケーブルテレビの 視聴者は全体の約73%にのぼっていることなどを指摘し,再放送の 同意につき公平・公正な使用料は1世帯1ch当たり年額24円であ り,この金額を超える使用料には合理的な理由がないと主張する。 しかし,後記のとおり,本件基本合意は,本件使用料規程第4条に 基づき減額措置を定めるものであり,しかも年額24円という使用料 はその中でも最も低い金額であるから,同金額を超える使用料が合理 性を欠くということはできない。本件使用料規程における使用料の 額が不合理とはいえないことは前記判示のとおりである。
h 以上のとおり,本件使用料規程における使用料の額及び区域内再 放送と区域外再放送の使用料の差が不合理ということはできない。
(エ) 被告は,年間の包括的利用許諾契約を締結する場合と締結しない場 合を分けて使用料を設定することは不合理であると主張する。
しかし,年間の包括的利用許諾契約を結んだ場合には毎月使用料を 徴収する等の事務処理が軽減されることを考慮すると,年間の包括的 利用許諾契約を締結しない場合の使用料を一定程度高く設定するこ とは合理的であり,また,その使用料が年間の包括的利用許諾契約 を締結する場合と比較して不合理に高額であるということはできな い。
したがって,年間の包括的利用許諾契約を締結する場合と締結し ない場合を分けて使用料を設定することが不合理であるということ はできない。
2019.04.17
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所(1部)
原告は,拒絶査定不服審判事件において,本件拒絶理由通知を受けたことか ら,新たに請求項19ないし47を追加する本件補正をしたところ,審判合議体が, 本件補正で追加した請求項について,新たに拒絶理由通知をせず,また本件審決に おいて判断しなかったことが,特許法47条に実質的に違反する旨主張する。 しかし,特許法は,一つの特許出願に対し,一つの行政処分としての特許査定又 は特許審決がされ,これに基づいて一つの特許が付与され,一つの特許権が発生す るという基本構造を前提としており,請求項ごとに個別に特許が付与されるもので\nはない。このような構造に基づき,複数の請求項に係る特許出願であっても,特許\n出願の分割をしない限り,当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定 又は拒絶査定をするほかなく,一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし, 他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは 予定されていない。このことは,特許法49条,51条の文言のほか,特許出願の\n分割という制度の存在自体に照らしても明らかである(最高裁平成19年(行ヒ) 第318号同20年7月10日第一小法廷判決・民集62巻7号1905頁参照)。 そうすると,審判合議体は,拒絶査定不服審判において,一の請求項について拒 絶理由があると判断すれば,それのみで請求不成立審決をすることができ,その余 の補正で追加された請求項について判断しなくても,違法ではないというべきであ る。 なお,特許出願人は,請求項の数を増加する補正をする際には,手続補正書を提 出する際に手数料を納付しなければならない(特許法施行規則11条4項)。そし て,拒絶査定不服審判請求後において請求項の数を増加する補正の場合,手続補正 書の提出によって,審査の続審である審判手続が,その増加した請求項について潜 在的に係属するといえる。そうすると,その際に納付すべき手数料を,出願審査の 請求に当たり必要な手数料及び審判の請求に当たり必要な手数料とすることは,不 合理なものといえず,また,手数料の納付時期を,手続補正書の提出時点とする同 規則の規定は,立法政策の問題というべきである。 本件において,審判合議体は,特許請求の範囲【請求項1】の記載は明確性要件 及びサポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知(甲11)をし,本件 補正により補正された同請求項の記載も,明確性要件及びサポート要件に適合しな いとして,本件審決をしたものである。審判合議体が,本件補正で追加した請求項 について,新たに拒絶理由通知をせず,また本件審決について判断しなかったこと をもって,審判手続に違法があるということはできない。
(2) 原告は,審判合議体が本件拒絶査定における理由の一部についてしか判断し ていないこと,審判官が専門とする技術分野が本願発明の技術分野とは異なること などから,本件は実質的に審理されたものということはできず,審理不尽の違法が あると主張する。 しかし,審判合議体は,特許請求の範囲【請求項1】の記載は明確性要件及びサ ポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知をし,本件補正により補正さ れた同請求項の記載も,明確性要件及びサポート要件に適合しないとして,本件審 決をしたものである。審判合議体は,拒絶査定不服審判において,拒絶査定に挙げ られた全ての理由について判断することが求められているものではない。また,本 件審決をした審判官につき除斥又は忌避事由があったことを窺わせる証拠はない。 その他,審判合議体が本件を実質的に審理しなかったことを認めるに足りる証拠も ない。 したがって,本件につき審理不尽の違法がある旨の原告の主張は採用できない。
・・・
以上によれば,特定事項Aは,「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当 該脂質含有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち,一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって,特定事項Aを,こ のように解釈することは,その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は,本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を,ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ,「指標として」という記 載は抽象的であり,いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから,本願発明の外延は明確ではない,要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては,明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,年齢,性別等の対象の要素 をメルクマールにして,その脂質含有配合物の構成を決定すれば,要素を「指標と\nして」使用したといえる。また,これにより決定される脂質含有配合物の構成があ\nりふれたものであったとしても,ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると,「指標として」という記載が,第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また,対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは,本願発明 の技術的範囲を画定し,対象方法を認定した上で,これらを比較検討して判断する ものである。そして,脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは,対象方法の認定に係る問題であって,本願 発明の技術的範囲の画定の問題,すなわち,明確性要件とは無関係である。 したがって,被告の上記主張は採用できない。
・・・・
本件審決は,サポート要件について,「ω−6の増加が緩やかおよび/また はω−3の中止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」と の技術的事項が,本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから,本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして,本件審決は,本願発明が,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて,何ら検討判断していない。
(2) しかしながら,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記 載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると,本願発明が,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて,何ら検討することなく,選択関係にある特 定事項EないしHのうち特定事項G「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3 の中止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」との技術的 事項が,本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって, サポート要件に適合しないとした本件審決は,誤りである。
(3) 加えて,以下のとおり,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3の中 止が緩やかであり,かつω−6の用量が,40グラム以下であり」との特定事項G の技術的事項は,本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち,まず,本願明細書【0042】には,「長鎖ω−3脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質/栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか,またはω−6脂肪酸が突然増加すると,全身性の炎症応答(毛細血管 漏出,発熱,頻脈,呼吸促迫),多臓器不全(消化器,肺,肝臓,腎臓,心臓)お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも,様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように,「ω−6の増加が緩やかおよび/またはω−3 の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は,本願明細書【0042】 に記載されている。
また,本願明細書には,菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって19〜30 歳及び31〜50歳の男性に投与する脂質組成物のω−6脂肪酸の用量を40g以 下とすること(実施例3【表9】),多量のシーフード摂取者であって上記と同年\n齢の男性に投与する脂質組成物のω−6脂肪酸の用量を40g以下とすること(実 施例3【表11】),及び,医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成\n物のω−6脂肪酸の用量を40g以下とすること(実施例6【表13】)が,それ\nぞれ記載されている。このように,「ω−6の用量が,40グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は,本願明細書の実施例3【表9】【表\11】及び実施 例6【表13】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。\nさらに,上記のとおり,本願明細書【0042】には,「ω−6の増加が緩やか および/またはω−3の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも, 様々な疾患が生じ得ることが記載されており,これは,「ω−6の増加が緩やかお よび/またはω−3の中止が緩やかであ」る投与方法が,特定の対象に限らず,一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると, このような投与方 法と,実施例3【表9】【表\11】及び実施例6【表13】のそれぞれ一部に記載\nされた「ω−6の用量が,40グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法,すなわち,例えば,菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって19〜 30歳及び31〜50歳の男性に,40g以下の用量のω−6脂肪酸を投与し,そ の際,ω−6脂肪酸を緩やかに増加させ及び/又はω−3脂肪酸を穏やかに中止す るという,脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は,本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって,本件審決は,サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく,そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず,その判断 枠組み自体に問題がある。よって,取消事由3は,その趣旨をいうものとして理由 がある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成29(行ケ)10236等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月14日 知的財産高等裁判所
ア 前訴判決は,前記(1)のとおり,本件発明7は,第6取引を除く本件各取 引によって公然実施されたと判断しているから,この部分に拘束力が及び,審判手 続においてこれに反する主張をすることは許されないものというべきである。した がって,この点についての第二次審決の判断に誤りがあるということはできない。
イ 被告は,前訴判決は,原告又はY社とα社〜ε社との間の信義則上の秘 密保持義務の有無について判断しておらず,前訴判決の拘束力は,信義則上の秘密 保持義務についての主張立証には及ばないと主張する。 しかし,前訴判決の拘束力が及ぶ範囲は,上記アのとおりであって,前訴判決が 信義則上の秘密保持義務について明示的に判断しているかどうかで,この拘束力が 及ぶ範囲が左右されることはない。
(3) なお,念のため,被告の主張する原告又はY社とα社〜ε社との間の共同 開発に基づく信義則上の秘密保持義務の有無についても検討する。 被告は,1)取引量が少量であること,2)本件各取引において供給されたBPEF が「サンプル」とされ,研究開発部門が受入窓口となるなどしていたこと,3)被告 とδ社との取引経緯,4)原告のBPEFの融点の公表時期,5)原告とY社がα社等 とポリマーに係る発明について●●●●をしていたことなどから,共同開発の事実 及び信義則上の秘密保持義務の存在が推認できると主張する。 ア まず,上記1),2)については,取引量が少量で,かつ対象物のBPEF が「サンプル」で,受入先が研究開発部門などとされている場合でもあっても,例 えば,受入先が,BPEFを原料としたポリマーの研究開発を行っているにすぎず, BPEFについては特に共同開発が行われていないといったことが容易に想定され るのであるから,被告主張の上記1),2)は,そもそも共同開発の事実を推認させる ものではないといえる。Aの供述は,この判断を左右するものではないし,ゼオネ ックスという光学用樹脂の例(乙14)については,BPEFとは異なる物質に関 するものである上,乙14の12頁でも,ゼオネックスが,販売開始後も当初はサ ンプルとしての供給が多く,数百キロ程度しか売れなかったとされていることに照 らすと,上記判断を左右するものではない。 イ 上記3)については,被告とδ社が,平成17年1月頃からBPEFを原 料とするポリマーの共同開発をしていたとしても,そこから,原告及びY社とα社 〜ε社との共同開発の事実が直ちに推認されるというものではない。 また,原告がδ社に提供したBPEFの中に,融点が三つある多形体混合物(ロ ット番号0610209)があったことについても,原告が単体でBPEFの製造 方法の改良を試み,その結果生じたものである(甲120)としても不自然とはい えず,やはりそれをもって共同開発の事実を推認させるものとはいえない。
ウ 上記4)については,証拠(甲186〜189,甲190の1・2)及び 弁論の全趣旨からすると,原告が供給するBPEFについて,その融点(162℃) を含む物性情報が,本件優先日前である平成15年12月頃に東京化成工業株式会 社の試薬データベースに登録されることで第三者に広く開示され得る状態になって いた上,同年頃から,東京化成工業株式会社の代理店を通じて,不特定多数の者が, 原告の供給するBPEFを入手できる状態になっていたと認められるから,原告の ホームページにBPEFの物性が記載されていなかったからといって,それが被告 の主張するBPEFの共同開発の事実に結びつくとはいえない。 エ 上記5)については,被告がその論拠とする各発明(乙7の1の1・2, 乙7の2の1・2,乙7の3・4,乙8の1・2,乙9の1〜8,乙10の1・2, 乙48)の中には,BPEFを原料としたポリマーに関する発明があると認められ るものの,原告又はY社が,ポリマー合成会社等とポリマーに関する共同開発をし ていたからといって,そこから直ちに原料であるBPEFについても共同開発をし ていたと推認することはできない。
オ 以上のとおり,被告が主張する上記1)〜5)の事実は,共同開発及びそれ に基づく信義則上の秘密保持義務の存在を推認させるものではなく,他に信義則上 の秘密保持義務の存在を認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成30(行ケ)10119 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
上記1(2)のとおり,4つのウェブメディアにおいて,平成21年1 月に,原告が開始した原告サービスについて「ブロマガ」という名称と 共に紹介する記事が掲載されたことが認められるが,原告が主張する上 記各ウェブメディアの月間PV数(約100万〜2000万PV)から は,上記各記事自体のPV数は明らかではない。また,上記各記事は同 じ日に掲載されたものであり,掲載日から本件出願日までに約3年8か 月以上が経過していることも併せ考えると,上記各記事が掲載された事 実は,本件出願日における引用商標の周知性を裏付けるものとはいえな い。
(イ) 上記1(3)のとおり,複数の書籍に原告サービスに関する記載がある ことが認められるが,各書籍の販売部数は明らかではなく,各書籍が発 行された事実は引用商標の周知性を裏付けるものとはいえない。 また,上記1(3)の1)及び2)からは,平成21年8月から平成22年2 月までの間にFC2ブログの管理画面ないし管理ページの映像面が変更 されたことがうかがわれ,上記書籍の記載のみから,原告が,原告サー ビスの開始時から本件出願日までの期間を通じ,FC2ブログのうちの いかなるウェブサイトにいかなる方法で引用商標を表示していたかは明\nらかではない。したがって,FC2ブログの利用者の間において引用商 標が周知性を獲得したことを認めることは困難である。
(ウ) 上記1(4)のとおり,Qが原告の提供する原告サービスについて言及 したツイートを4回したことが認められる。そのツイッターアカウント のフォロワー数は多いが,多数のユーザーから大量のツイートが投稿さ れ,これらのツイートがタイムラインに順次表示されるというツイッタ\nーの性質上,上記4回のツイートがされたことによって,引用商標が周 知性を獲得したということはできない。また,同人が原告サービスを利 用していたとしても,原告サービスを通じた購読者数は多くないことが 認められるから,購読者を通じて引用商標が周知性を獲得したとはいえ ない。 なお,上記メールマガジンについて報道したITmediaの平成22年11 月30日付け記事(甲21)自体のPV数は不明で,この記事が掲載さ れた事実が周知性を裏付けるものとはいえないのは,上記(ア)に説示した ところと同様である。
(エ) 上記1(5)のとおり,平成24年8月頃の「niconico新サービス発表\n会 in ニコファーレ」において引用商標について質問されたことが認め られるが,発表会における1度の質問が引用商標の周知性を裏付ける事\n実といえないのは明らかである。
(オ) そして,本件出願日までに約3年8か月の間,引用商標が使用されて いたこと,及び本件出願日の属する平成24年9月における原告サービ スの売上げは●●●●●●であったことが認められるものの(上記1(1)), 以上に説示した点や,原告サービスの利用者数や上記売上げに係るブロ グ記事の数量は不明であり,また,原告が提供する原告サービスに関し, 本件出願日までにされた広告の回数,方法及びこれに費消した金額も明 らかではないことからすれば,本件出願日当時,引用商標が原告の業務 に係る役務を表示するものとして需要者の間で周知であったと認めるに\nは足りないというべきである。
ウ したがって,本件商標について商標法4条1項10号に該当する事由が あるとはいえない。
(2) 原告の主張について
原告は,FC2ブログが多数のユーザーが利用する著名なサービスである ことを主張するが,仮にそうであるとしても,直ちに引用商標が周知である ということにはならない。原告は,引用商標がFC2ブログの操作画面等に も表示されるようになったこと,FC2ブログのユーザーが利用する管理画\n面には常に「ブロマガ」の紹介がされ,数百万のユーザーに対して,随時, 「ブロマガ」について周知の措置がとられていたことを主張するが,上記(1) イ(イ)のとおり,このような事実を裏付ける的確な証拠はない。
原告は,原告サービスがインターネット上で大きく取り上げられたこと, 日本有数の発信力を誇るQが原告サービスのユーザーであり,原告サービス についてツイートしていること,「niconico新サービス発表会 in ニコファ ーレ」において引用商標について質問があったことを主張するが,これらの 事実により引用商標が周知性を獲得したといえないのは,上記(1)イに説示し たとおりである。また,原告は,Rの息子として知られ書籍を出版している Sが原告サービスのユーザーであると主張するが,このような事実は引用商 標の周知性を裏付けるものではない。
原告は,平成21年1月から平成25年9月までの原告サービスを利用し たブログの売上げは合計●●●●●●●●●●●●であると主張するが,こ の売上げからは,原告サービスの利用者数も上記売上げに係るブログ記事の 数量も明らかではなく,上記事実があったとしても,引用商標が本件出願日 までに周知性を獲得したことを認めるには足りない。 以上のとおりであるから,原告の主張はいずれも採用できない。
3 商標法4条1項15号該当性について
(1) 商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれがある商標」における「混 同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他\n人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役\n務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関 連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実 情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者にお いて普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである(最 高裁平成10年(行ヒ)第85号平成12年7月11日第三小法廷判決)。 本件においては,引用商標について周知性が認められないのは上記2に説 示したとおりであり,本件商標が,同号にいう「混同を生ずるおそれがある 商標」に当たるということはできない。 よって,本件商標について同号に該当する事由があるとはいえない。
(2) 原告の主張について
原告は,引用商標は相当広範囲で認知されていたものであるところ,周知 性が認められないからといって,商標法4条1項15号「混同を生ずるおそ れがある商標」に当たらないということはできない旨主張する。 しかし,同号の規定は,周知表示又は著名表\示へのただ乗り(いわゆるフ リーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し,\n商標の自他識別機能を保護することにより,商標を使用する者の業務上の信\n用の維持を図り,需要者の利益を保護することを目的とするものであると解 される。また,引用商標が周知でなければ,それが需要者に一般的に認識さ れることはなく,したがって,原告の業務に係る商品又は役務との混同(狭 義の混同,広義の混同のいずれも含む。)のおそれが生じることもないと考 えられるのであって,これらのことを併せ考えれば,引用商標が周知性さえ も備えていないと認められる場合に,商標法4条1項15号が適用される余 地はないというべきであるし,「周知著名性の程度」(したがって,最低限 の周知著名性は備えていることが前提になると解される。)を問題とする上 記最高裁判決も,以上のことを前提にしているものと解される。したがって, 原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成29(ワ)27741 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年2月28日 東京地方裁判所(47部)
著作権法2条1項1号は,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,\n文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ,印 刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには,それが従来の印刷用 書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり, かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければなら ないと解するのが相当である(最高裁判所平成10年(受)第332号平成1 2年9月7日第一小法廷判決・民集54巻7号2481頁)。
(2) そこで,本件タイプフェイスにつき検討する。 この点,原告は,本件タイプフェイスが著作物性を有するかどうかの判断を するにあたっては,タイプフェイスがそれぞれの文字相互に統一感を持たせる ように大きさや太さをデザインしているものであるから,個々の文字をそれぞ れ独立に見て判断するべきではない旨を主張する。しかしながら,複製権等の 侵害の成否は,現に複製等がされた部分に係る著作物性の有無によって判断す べきであること,タイプフェイスは各文字が可分なものとして制作されている ことからすれば,被告により現に利用された文字につき著作物性を判断するの が相当である。したがって,以下では本件タイプフェイスのうち,被告により 利用された文字に限って判断する。 ア 対比表記載の本件タイプフェイス以外の各タイプフェイス(以下「対比タ\nイプフェイス」という。)欄の括弧内に記載された各証拠及び弁論の全趣旨 によれば,対比タイプフェイス欄に記載された制作年に対比タイプフェイス がそれぞれ制作されたことが認められるところ,原告の主張に係る本件タイ プフェイスの制作年である平成12年(2000年)までに制作された対比 タイプフェイスに限って対比した場合においても,被告により使用された文 字のうち,「シ」,「ッ」,及び「ギ」「ジ」「デ」「ド」「バ」「ブ」「ベ」「ボ」における濁点「゛」の部分(以下,単に「濁点」という。)以外の文字について は,本件タイプフェイスに類似する対比タイプフェイスの存在が認められ, 本件タイプフェイスの制作時以前から存在する各タイプフェイスのデザイ ンから大きく外れるものとは認めがたい。
イ 他方,本件タイプフェイスにおける「シ」,「ッ」,及び濁点の各文字につい ては,2つの点をアルファベットの「U」の字に繋げた形状にしている点に おいて従来のタイプフェイスにはない特徴を一応有しているということは できる。しかしながら,2つの点が繋げられた形状のタイプフェイス(CL EAR KANATYPE(乙17,97)及び曲水M(乙15))の存在を 考慮すれば,顕著な特徴を有するといった独創性を備えているとまでは認め がたい。
ウ 以上からすれば,本件タイプフェイスが,前記の独創性を備えているとい うことはできないし,また,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性 を備えているということもできないから,著作物に当たると認めることはで きない。
(3) これに対し,原告は,1)本件タイプフェイスのうち,「シ」「ッ」などの文字 は,2つの点を繋いで1本の曲がったラインで表現することにより文字の流れ\nを演出しているものであること,2)「ス」については,構成するラインを水平\n及び垂直に交わるように組み立てをし,全体を20度傾けることでカタカナの 「ス」であることがよく分かる構造となっていること,3)その他の文字につい ては,線が交わる部分を曲線にする手法,及び横画に細い線,縦画に太い線を 用いるという手法を巧みに組み合わせて全体の統一感を持たせたこと等を主 張する。 しかしながら,1)の点については,前記のとおり,従来のタイプフェイスに 比して,顕著な特徴を有するといった独創性を備えているという評価にまで至 るものではない。また,2)の点については,構成するラインを水平及び垂直に\n交わるように組み立てたものとしてMOULDISM Katakana(乙 14,102),全体を20度傾けたものとしてOVERLOADER(乙1 4,28の2)等の対比フォントが存在し,さらに3)の点については,Tec hnopolish(乙14,57)及びHappy Frame(乙14,7 2)等の対比フォントが存在することを考慮すれば,上記各点をもって本件タ イプフェイスが,従来のタイプフェイスに比して特徴を有するとは認められない。
2019.04. 8
平成29(行ケ)10206 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年3月26日 知的財産高等裁判所
被告は,沖縄の伝統的な獅子像である「シーサ」の観念を生じさせようとして本 件商標を創造した旨主張する。 「シーサ」は,「シーサー」を指すものと解されるところ,「シーサー」は,「獅子 さん」の意味であり,沖縄で,瓦屋根等にとりつける素朴な焼き物の唐獅子像であ って,魔除けの一種である(広辞苑第六版。甲5)。「シーサー」の形状には,様々 なものがあり,概ねその特徴とされる点としては,たてがみや首飾り,剥き出した 牙,渦巻くような毛並み,太くふっくらとした尻尾等があり,また,頭部が体全体 に占める割合が相当大きく,目や口も大きく,その姿勢としては,上体を起こした 状態で前足をついたものが多いが,四つん這いになったもの,前かがみのもの,後 足だけで立ち上がったもの等,様々な形態があり,多くの場合には尻尾が上空に向 かって炎のように逆立ち,その先端はすぼんでいる(甲6)。 本件商標を上記の一般的な「シーサー」と比べると,首飾りのような模様,前足・ 後足の関節部分における飾り又は巻き毛のような模様,尻尾の全体的に丸みを帯び て先端が尖った形状等は,いずれも一般的な「シーサー」の特徴とされているとこ ろと一致する。しかし,本件商標は,頭部が体全体に占める割合が相当小さく,口 に当たる位置にギザギザの白線の模様はあるが,目に当たる位置に目に見える記載 はなく,四足動物が跳び上がるように前足と後足を大きく開いている姿勢は,「シー サー」の形態として一般的なものとはいえない。 そうすると,本件商標の図形が,四足動物を表現したものと看取することはでき\nても,「シーサー」を表現したものと看取することは困難である。\nしたがって,本件商標から「シーサー」の観念が生じると認めることはできない。
・・・
前記アのとおり,本件商標と引用商標は,そのシルエット,内部に白 線による模様があるかなどにおいて異なるが,全体のシルエットは,似通っており, 本件商標において,内部の白い線の歯のような模様,首の回りの飾りのような模様, 前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配さ れている白い線がシルエット全体に占める面積は,比較的小さく,細い白い線の花 柄のような細かい模様は,それほど目立たないものである。 したがって,本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの,外 観全体の印象は,相当似通ったものであるということができる。 また,前記イ及びウのとおり,本件商標と引用商標は,本件商標からは何らかの 四足動物の観念が生じ,特定の称呼は生じないが,引用商標からは,「PUMA」ブ ランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なっているところ,本件商標から 何らかの四足動物以上に特定された観念や,特定の称呼が生じ,それが引用商標の 観念,称呼と類似していない場合と比較して,その違いがより明確であるというこ とはできない。
(イ) 前記(2)イのとおり,引用商標は,原告の業務に係る「PUMA」ブ ランドの被服,帽子等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く\n認識されて周知著名な商標となっていたものである。 また,本件商標は,「Tシャツ,帽子」を指定商品とするところ,前記(2)イのと おり,「PUMA」ブランドの商品としても,Tシャツ,帽子が存在し,引用商標と 同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから,本件商標の指定商品は, 原告の業務に係る商品と,その性質,用途,目的において関連するということがで き,取引者,需要者にも共通性が認められる。 さらに,本件商標の指定商品である「Tシャツ,帽子」は,一般消費者によって 購入される商品である。
(ウ) これらの事情を総合考慮すると,本件商標の指定商品たるTシャツ, 帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,本件商標を 指定商品に使用したときに,当該商品が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係 若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営\n業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。 したがって,本件商標には,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」 があるといえる。
◆判決本文
関連事件です。
いずれも無効理由なしとの審決維持です。本件と異なり、文字商標が存在しており、
図形がシーサーであるとの観念が生ずるというものです。
7号、11号、15号違反が争点となってますが、いずれも無効理由なしと判断されています。
◆平成29(行ケ)10205
7号違反のみ争点で無効理由なしと判断されています。
◆平成29(行ケ)10204
7号違反のみ争点で無効理由なしと判断されています。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.04. 5
平成30(行ケ)10156 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月19日 知的財産高等裁判所
特許の出願人が在外者である場合,拒絶査定不服審判請求や分割出願を行 うためには,特許法施行令1条1号に定める場合を除いて,特許管理人たる代理人 を選任する必要があるが(特許法8条1項),その場合であっても,同在外者は, 誰を代理人に選任するのかについて,自己の経営上の判断に基づきこれを自由に選 択することができる。そうすると,出願人から委任を受けた代理人に「その責めに 帰することができない理由」があるといえない場合には,出願人本人に何ら落ち度 がない場合であっても,特許法121条2項所定の「その責めに帰することができ ない理由」には当たらないと解すべきである(最高裁昭和31年(オ)第42号同 33年9月30日第三小法廷判決・民集12巻13号3039頁参照)。
(2) 本件においては,前記第2の1のとおり,D弁理士は,本願からの分割出 願について,特許法44条1項3号の適用があり,拒絶査定不服審判請求をする必要はないものと誤信し,拒絶査定不服審判請求についての法定期間を徒過してし まったものである。 弁理士法3条によると,弁理士には,業務に関する法令に精通して,その業務を 行う義務があるところ,通常の注意力を有する弁理士が,通常期待される法令調査 を行えば,本件拒絶査定後,本願から適法に分割出願を行うためには,拒絶査定不 服審判請求を分割出願と同時にする必要があると認識することは十分に可能\であっ たと認められる。したがって,D弁理士が上記のように誤信をしたことは,弁理士 として通常期待される法令調査を怠った結果であるというほかない。D弁理士以外 の他の本件代理人らについても,いずれも原告本人から委任を受けた弁理士である 以上,適宜,必要な処置を講じて,本件のような過誤の発生を防止すべき義務があっ たといえ,D弁理士同様,弁理士として通常期待される注意を尽くしていなかった ものというべきである。 以上のとおり,本件代理人らが通常期待される注意を尽くしていたとはいえない 以上,本件において,特許法121条2項にいう「その責めに帰することができな い理由」があったとすることはできない。
(3)ア 原告は,本件代理人らの過誤は,原告本人にとって思いもかけないこと であり,外国法人である原告本人が,非本質的な手続である本件審判請求について の本件代理人らの過誤を防ぐことは不可能であったことなどから,「その責めに帰\nすることができない理由」があると主張する。 しかし,本件審判請求が,分割の機会を得るためだけにされたものであるとして も,そのことによって「その責めに帰することができない理由」があるとすること ができないのは,前記1(2)エで述べたとおりである。 また,前記(1)のとおり,原告本人は,自らの経営上の判断として,本件代理人ら に委任したのであるから,原告本人には過失がなかったとしても,自己が委任した 本件代理人らに過失がある以上,「その責めに帰することができない理由」はなかっ たと判断されるのもやむを得ないものというべきである。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は,本件分割出願1と本件分割出願2が同内容であることからする と,失効した権利の回復を無制限に認めることにはならず,また,第三者の監視負 担が増大することはないと主張するが,そのような本件における個別具体的な事情 を理由に,「その責めに帰することができない理由」があるとすることはできない。
関連カテゴリー
>> 分割
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2019.04. 3
平成30(ワ)27253 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年3月13日 東京地方裁判所(29部)
被告らは,いずれも加工食品の製造及び販売等を業とする株式会社であり,業として,被告商品を販売していたのであるから,その製造を第三者に委託していたとしても,補助参加人等に対して被告イラストの作成経過を確認するなどして他人のイラストに依拠していないかを確認すべき注意義務を負っていたと認めるのが相当である。 また,前記認定のとおり,本件イラストと被告イラストの同一性の程度が非常に 高いものであったことからしても,被告らが上記のような確認をしていれば,著作 権及び著作者人格権の侵害を回避することは十分に可能\であったと考えられる。に もかかわらず,被告らは,上記のような確認を怠ったものであるから,上記の注意 義務違反が認められる。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.04. 3
平成30(ワ)4954 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 平成31年3月14日 大阪地方裁判所
原告商標の文字部分,すなわち「TeaCoffee」の語は,頭文字の「T」の文字 だけでなく,「C」の文字も大文字で表記されており(甲2),「Tea」は「茶,紅 茶」を,「Coffee」は「コーヒー」を意味する英単語としていずれも日本社会にお いてよく知られていることに照らせば,取引者,需要者は,これを「Tea」と 「Coffee」の2語を接続した語と認識すると認められる。
b ところで,前記(ア)aで認定した別紙「複数の原材料を組み合わせた飲料の 商品名等一覧表」のとおり,複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等について\nは,原材料を構成する物の名前を接続した語とする例が数多く見られる。そして,\nその中には,「ミルクコーヒー」,「Cafe au Lait」,「ミルクティー」,「レモ ンティー」等のように,既に一つの日本語として定着している語がある。また,特 定の業者ではなく缶飲料やペットボトル飲料を販売する大手各社が,紅茶とその他 の原材料を組み合わせた飲料として「アップルティー」,「梅ティー」,「レッド グレープティー」等,抹茶と牛乳を組み合わせた飲料として「抹茶ラテ」,ほうじ 茶と牛乳を組み合わせた飲料として「ほうじ茶ラテ」等,その他として「ゆずはち みつ」,「はちみつレモン」等のように,様々な組合せの語を使用している。また, 飲料の名前から生じる認識を検討するに当たっては,このような大手各社が販売す る飲料だけでなく,「最新アイスドリンク」(乙32,33),「New Arrange Drink」(乙33)などとして,実際に創作的か否かはともかく,創作的な飲料を 提供しようとしていることがうかがわれるカフェのメニューで使用されている例も 参考になり得るところ,同別紙のとおり,「ハニーレモンティーソーダ」,「ピー\nチゼリーティ−」,「アイスマンゴーティー」があるほか,「抹茶ミルク」,「ゆ ず緑茶」,「ほうじ茶ジンジャエール」,「ソイマンゴー」,「バナナ酢ミルク」\n等のように,メニュー名自体は,原材料を構成する物の名前を単に接続した語が使\n用されている。 これらの多数の例において,各原材料の語自体は,食用又は飲用に供される物の 名前として一般に認識されている語であるから,上記の各商品名等に接した取引者, 需要者は,それらの語の間に,「と」,「+」,「×」などといった,ある物にあ る物を加えるとか,ある物とある物を掛け合わせるといった際に用いられる文字や 記号が使用されていなくても,それらの飲料がそれらの原材料を組み合わせた飲料 であると認識すると推認される。
c 以上は,飲料一般についてのものであるが,茶(日本茶,紅茶)とコーヒー を組み合わせた飲料等については,別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販 売開始時期や商品名等一覧表」記載のとおり,原告商品が販売される以前からその\nような商品やメニューが少なからず存在し,その中には,「お茶コーヒー」(同別 紙の番号1),「抹茶カフェオレ」(同3),「コーヒーほうじ茶」(同6。ティ ーバッグの形で販売されていた〔乙17〕。),「グリーンティーコーヒー」(同 9),「ほうじ茶カプチーノ〜黒蜜添え〜」(同10),「抹茶カプチーノ」(同 13),「ほうじ茶カプチーノ」(同13),「ほうじ茶珈琲」(同18。ティー バッグの形で販売されていた〔乙16〕。)という,茶を意味する語とコーヒー等 を意味する語を接続しただけの商品名等のものがあったほか,料理レシピとしても, 「緑茶コーヒー」(同14,17)という,茶を意味する語とコーヒーを意味する 語を接続しただけの名前のものがあったと認められる。しかも,このような茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等は,1)大手缶コーヒー業者である日本コカ・コーラ社 (同5,8)やJT社(同7),2)大手コンビニエンスストアチェーンであるファ ミリーマート(同9),3)コーヒー等のドリップバッグ商品の通信販売業者である ブルックス(同12),4)カフェ店であるカフェ・ド・クリエ(同10)という, 飲料等の販売形態を細分化して見れば業界を異にする,それぞれの業界において著 名な業者等から,販売されていただけでなく,日本コカ・コーラ社からは第1弾商 品が販売された約6か月後に第2弾商品を販売されるほどのものであった。 これらからすると,「TeaCoffee」との表記に接した需要者,取引者が,それが\n複数の原材料を組み合わせた他の飲料の商品名等と同様に,「Tea」と「Coffee」 を組み合わせた飲料等を意味すると認識することに妨げはなく,そのように認識す ると認めるのが相当である。
(ウ) 原告の主張について
a 原告は,お茶入りコーヒーについて「TeaCoffee」というネーミングはされ ておらず,取引者,需要者に「Tea」のような「Coffee」であるのか,「Tea」と 「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるか ら,自他商品識別力を有すると主張する。 確かに,原告商品が販売される前から存在した茶とコーヒーを組み合わせた飲料 等の販売等に当たっては,茶とコーヒーを組み合わせることが新しい試みであると いう趣旨の宣伝文句が常套文句になっており,被告商品の販売が開始される際にも 「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ!」などという宣伝文句を用いられているこ と(甲5)に照らせば,被告が被告商品の販売を開始するまでの時点(平成30年 4月)においても,茶とコーヒーを組み合わせた飲料等は定番のものになっていな かったと認められる。また,本件において,原告商品が発売されるまでに,茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等について「TeaCoffee」という名前が使用された例が あるとは認められない。したがって,「TeaCoffee」という名前が,茶とコ 料名を接続した商品名等とすることが一般によく見られるものであることからする と,取引者,需要者がそのような商品名等に接した場合には,そのような原材料の 組合せが飲料等として想定し得ないものでない限り,その飲料等がそれらの原材料 を組み合わせたものであると認識することは自然なことである。そして,茶とコー ヒーの組合せが飲料等として想定し得ないものとはいえない上,それらを組み合わ せた飲料等において,その組合せの新規さをうたいつつ,その商品名等として 「茶」を表す語と「コーヒー」を表\す語を接続したものが多数見られてきたのも, その商品名等によってその飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認 識されることを多くの業者が前提としてきたことによるものと解される。 したがって,お茶入りコーヒーのネーミングとして「TeaCoffee」が一般的でな いという原告の主張を前提としても,「TeaCoffee」との語は,原告商標の指定商 品について使用するときには,商品の品質(内容)又は原材料を直接的に示すにす ぎないものとして,自他商品識別力を有しないと認めるのが相当である。
・・・・
(d) このように原告商標の文字部分(「TeaCoffee」)は,それと同じ称呼がさ れ得る「teacoffee」,「TEACOFFEE」及び「ティーコーヒー」を含めて見ても,そ もそも使用されている頻度が低い上に,使用されても,自他商品識別標識であると 認識され得る別の表示(京茶珈琲)とともに使用されていたり,記述的表\示である と認識され得ることにつながりかねない表示(TEA×COFFEE)とともに使用されて いたりするなど,自他商品識別標識であるとは認識されにくい形で使用されてきた ことが多いといえる。 以上の点を踏まえると,「TeaCoffee」の語が,原告による原告商品の販売に伴 って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得するに至ったとは認められな い。
ウ 以上からすると,「TeaCoffee」の語は,被告が使用する標章の使用時点に おいて,原告商標の指定商品である「茶,コーヒー,茶入りコーヒー,コーヒー 豆」に使用されるときには,茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品の品質(内 容)又はその原材料を記述的に表示しているものとして,取引者,需要者によって\n一般に認識されるものであって,自他商品識別力を欠くものというべきである。し たがって,原告商標の構成中,「TeaCoffee」の文字部分については,原告商標の 要部ということはできないから,原告商標については,「TeaCoffee」の文字部分 と図形部分から成る全体の構成が一体となって,初めて自他商品識別力を有するに\n至っているものというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.04. 2
平成30(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月14日 知的財産高等裁判所
(6)周知技術の認定 前記(1)〜(5)によると,本願出願日当時,タイヤの技術分野において,クラウン部 の外周にタイヤ周方向に巻き付ける被覆コード部材の断面形状を略四角形状とする こと,また,上記断面形状は略四角形状,円形状又は台形状等から選択可能である\nことが周知技術であったことを認定することができる。
(7) 甲1発明に周知技術を適用することの可否
ア 前記(6)のとおり,本願出願日当時,クラウン部の外周にタイヤ周方向に 巻き付ける被覆コード部材の断面形状は,略四角形状,円形状又は台形状等から選 択可能であることは周知技術であった。\nまた,前記(2),(3)のとおり,周知文献3の【0007】には,「本発明の請求項1 に記載のタイヤでは,タイヤ周方向に螺旋状に巻かれる補強コード部材のタイヤ軸 方向に隣接する部分同士を接合していることから,例えば,補強コード部材のタイ ヤ軸方向に隣接する部分同士を接合しないものと比べて,タイヤ骨格部材に接合さ れる補強コード部材で構成される層(以下,適宜「補強層」と記載する。)の剛性が\n向上する。これにより,上記補強層が接合されるタイヤ骨格部材の剛性を向上させることができる。」と記載され,また,周知文献3の【0049】には,「補強コー ド部材22のタイヤ軸方向に隣接する部分同士の接合は,一部分でも全部でも構わ\nないが,接合面積が広いほど補強コード部材22で構成される補強層28の剛性が\n向上する。」と記載され,周知文献2の【0063】にも,「補強コード部材22の タイヤ軸方向に隣接する部分同士の接合は,一部分でも全部でも構わないが,接合\n面積が広いほど補強コード部材22(補強層28)によるタイヤケース17の補強 効果が向上する。」と記載されている。そうすると,本願出願日当時,タイヤ軸方向 に隣接する補強コード部材同士を接合しないものに比べて,これを接合したものは 補強コード部材で構成される補強層の剛性を向上させることができ,その接合面積\nが広いほど補強層の剛性が向上し,補強層が接合されるタイヤ骨格部材の剛性を向 上させることができることが知られていた。そして,補強コード部材(被覆コード 部材)の断面形状が円形状のものよりも,略四角形状のものの方が,タイヤ軸方向に隣接する補強コード部材同士の接合面積を広くし得ることは,明らかである。
以上によると,タイヤ軸方向に隣接する被覆コード部材同士を溶融接合している 甲1発明において,前記(6)の周知技術を適用して,断面形状が円形状の被覆コード 部材に代えて,これと適宜選択可能な関係にある断面形状が略四角形状の被覆コー\nド部材を採用することは,当業者が容易に想到し得るものと認められる。 イ 前記(2),(3)のとおり,周知文献3には,断面形状が略四角形状であり, タイヤ軸方向に隣接する部分同士が接合(溶着)された補強コード部材22につい て,クラウン部16に一部が埋め込まれても構わないことが記載され(【0046】,\n【0049】,【0050】,【0053】),また,周知文献2には,断面形状が略四角形状であり,タイヤ軸方向に隣接する部分同士が接合(溶着)された補強コード 部材22について,長手方向の両端部22Aがクラウン部16に埋め込まれて長手 方向の中間部22Bよりもクラウン部16の内周面16B側に配置されるのであれ ば,長手方向の中間部22Bがクラウン部16に埋め込まれても構わないことが記\n載されている(【0057】,【0058】,【0061】,【0063】)。 そうすると,タイヤ軸方向に隣接する被覆コード部材同士を溶融接合している甲 1発明において,前記(6)の周知技術を適用して,断面形状が円形状の被覆コード部 材に代えて,これと適宜選択可能な関係にある断面形状が略四角形状の被覆コード\n部材を採用することに,製造上の阻害要因があるものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.04. 1
平成29(ネ)10090 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年4月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
実際に用いられていたアルミピロー包材と同じ品番のアルミピロー包材の中に は,底部の折り曲げ部分のアルミが剥がれているものもある(甲18,26)。ま た,防湿性を確保したアルミピローの製造は,医薬品メーカーの管理方法を含めた 製造方法に大きく依存する旨指摘されている(乙48)。実際に用いられていたア ルミピロー包材に対して,専門家による立会いの下,リーク試験が行われ,気密性 が担保されていることが確認された旨報告されているものの(乙49),同リーク 試験は,検体を水没させ,一定の減圧条件(槽内圧力−40kPa,保持時間30 秒間)において,気泡が発生しないことを目視検査するというものである。水没試 験による気泡確認によって医薬包装の完全性を試験する方法は,個人の技量による 判別量の差や水槽内の細菌・水の表面張力による検出限界などの問題を有する旨指\n摘されているほか,−40kPaの圧力下において,直径5μmの孔からは5分経 過後も気泡が確認できず,直径10μmの孔においても,気泡の発生にばらつきが みられるとされている(甲27)。上記リーク試験の結果をもって,実際に用いら れたアルミピロー包材が気密性を有していたと確定することはできない。そうする と,サンプル薬が,長期間にわたって,アルミピロー包装下で保管されている間に, 湿気の影響を受けて水分含量が増加した可能性も,十\分にあり得るものである。 なお,サンプル薬の測定時の水分含量と,実生産品の水分含量(後記ウ(ア))や, 203サンプル薬を再製造したとされる錠剤の水分含量(2.18〜2.26質量%。 乙54〜56)は,ほぼ同じである。しかし,そもそも,サンプル薬と,実生産品 や203サンプル薬の再製造品が同一工程により製造されたものとは認められない から,この事実をもって,サンプル薬の測定時の水分含量が,製造時の水分含量と ほぼ同じであったということはできない。
(ウ) したがって,サンプル薬の測定時の水分含量が本件発明2の範囲内である からといって,4年以上も前の製造時の水分含量も本件発明2の範囲内であったと 推認できるものではない。
・・・
以上のとおり,サンプル薬を製造から4年以上後に測定した時点の水分含量 が本件発明2の範囲内であるからといって,サンプル薬の製造時の水分含量も同様 に本件発明2の範囲内であったということはできない。また,実生産品の水分含量 が本件発明2の範囲内であるからといって,サンプル薬の水分含量も同様に本件発 明2の範囲内であったということはできない。かえって,サンプル薬の顆粒の水分 含量を基に算出すれば,サンプル薬の水分含量は本件発明2の範囲内にはなかった 可能性を否定できない。その他,サンプル薬の水分含量が本件発明2の範囲内にあ\nったことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,控訴人が,本件出願日までに製造し,治験を実施していた本件2m g錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量は,いずれも本件 発明2の範囲内(1.5〜2.9質量%の範囲内)にあったということはできない。
(3) サンプル薬に具現された技術的思想
ア 仮に,本件2mg錠剤のサンプル薬又は本件4mg錠剤のサンプル薬の水分 含量が1.5〜2.9質量%の範囲内にあったとしても,以下のとおり,サンプル 薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明であるということはでき ない。
イ 本件発明2の技術的思想
前記1のとおり,本件発明2は,ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含 量に着目し,これを2.9質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制 し,これを1.5質量%以上にすることによって5−ケト体の生成を抑制し,さら に,固形製剤を気密包装体に収容することにより,水分の侵入を防ぐという技術的 思想を有するものである。
ウ サンプル薬に具現された技術的思想
(ア) 控訴人が,本件出願日前に,サンプル薬の最終的な水分含量を測定したと の事実は認められない。
(イ) また,203サンプル薬及び303サンプル薬の製造工程では,A顆粒及 びB顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●●にする旨定 められているものの(乙23の1・2,25の1・2),A顆粒及びB顆粒以外の 添加剤の水分含量は不明である。また,サンプル薬には吸湿性の高い崩壊剤や添加 剤が含まれているにもかかわらず,打錠時の周囲の湿度,気密包装がされるまでの 管理湿度などは不明である。 そうすると,サンプル薬に含有されるA顆粒及びB顆粒の水分含量について,● ●●●●にする旨定められているからといって,控訴人が,サンプル薬の水分含量 が一定の範囲内になるよう管理していたということはできない。
(ウ) さらに,012実生産品及び062実生産品の製造工程では,B顆粒の水 分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●にすると定められており (乙24,26の1・2),サンプル薬と実生産品との間で,B顆粒の水分含量の 管理範囲が●●●●●●●●から●●●●●●●●へと変更されている。控訴人は, サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。
(エ) したがって,控訴人は,本件出願日前に本件2mg錠剤のサンプル薬及び 本件4mg錠剤のサンプル薬を製造するに当たり,サンプル薬の水分含量を1.5 〜2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたと も,1.5〜2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していた とも認めることはできない。
エ 以上のとおり,本件発明2は,ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分 含量を1.5〜2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものである のに対し,サンプル薬においては,錠剤の水分含量を1.5〜2.9質量%の範囲 内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく,また,錠剤の水 分含量を1.5〜2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存 在しない。 そうすると,サンプル薬に具現された技術的思想が,本件発明2と同じ内容の発 明であるということはできない。
オ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は,水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成する ことは技術常識であったから,控訴人は,本件2mg錠剤及び本件4mg錠剤の治 験薬製造前から,錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張する。 しかし,一般的に,医薬組成物において製剤中の水分が類縁物質生成の原因にな るという技術常識(乙8〜10)や,ピタバスタチンについては水分含量を調整し なければならないという技術常識(乙12〜14,20,57)が認められるとし ても,水分含量の調整方法は様々であるから,このような技術常識のみから,ピタ バスタチン又はその塩と特定の崩壊剤から成る錠剤であるサンプル薬について,錠 剤としての水分含量を一定の範囲内となるように管理することを控訴人が認識して いたといえるものではない。 したがって,本件出願日前の技術常識をもって,控訴人がサンプル薬の水分含量 を管理する必要性を認識していたということはできない。
(イ) 控訴人は,サンプル薬について,水分含量を調整することにより,水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない,長期安定な薬剤を製造する点は,確定し ていた旨主張する。 しかし,控訴人が,サンプル薬について,ラクトン体及び5−ケト体の生成の程 度について測定し,安定な製剤であることを確認していたとしても,前記のとおり, 控訴人が,サンプル薬を製造するに当たり,その水分含量を1.5〜2.9質量% の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも,1.5〜2. 9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることは できない。サンプル薬において,5−ケト体の生成を抑制できていたとしても,こ れをもって,控訴人が,サンプル薬の水分含量を1.5質量%以上に管理していた と推認できるものではなく,また,これが,控訴人がサンプル薬の水分含量を1. 5質量%以上に管理するという技術的思想を有していた結果として生じたものと評 価できるものでもない。 したがって,サンプル薬について,何らかの方法を採用することにより,水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない,長期安定な薬剤を製造する点が確定され ていたとしても,これをもって,サンプル薬に具現された技術的思想が,本件発明 2と同じ内容の発明であるということはできない。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成27(ワ)30872 (東京地裁29部)
本件出願日(平成24年8月8日)までに,被
告の社内において,本件発明2の内容を知らないでこれと同じ内容の発明がされて
いた(被告が被告の従業員等から当該発明を知得していた)と認めることは困難で
あるし,この点を措くとしても,後記(3)のとおり,本件出願日までに,本件2mg
製品及び被告製品(本件4mg製品)の内容が,本件発明2の構成要件Eを備える\nものとして,一義的に確定していたと認めることはできず,本件発明2を用いた事
業について,被告が即時実施の意図を有し,かつ,その即時実施の意図が客観的に
認識される態様,程度において表明されていたとはいえないから,被告に先使用権\nが成立したということはできない。
・・・
しかし,被告の提出に係る書証からは,実生産品とサンプル薬が同一の工程によ
り製造されたものであると直ちに認めることは困難である。すなわち,本件で問題
となるのは,「PTP包装してなる医薬品」を構成する「錠剤」の「水分含量」が\n「1.5〜2.9質量%」の範囲となるよう管理されていたか否かであるところ,
水分は,有効成分でないばかりか,積極的な添加物でもなく,不純物として扱われ
るものでもないため,錠剤が製造された後,PTP包装された状態で,錠剤の水分
含量がいかなる値となるかという観点から工程の同一性を論じるためには,被告の
提出に係る全ての書証をもってしても,情報が不足しているというほかはない(少
なくとも,打錠工程の湿度環境や打錠後の保管条件は,PTP包装された錠剤の水
分含量に影響するといわざるを得ないが,被告の提出にかかる書証では,これらの
条件は明らかにされていない。)。
イ 被告は,本件2mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:PTVD−203)及
び本件4mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:TVD−303)の水分含量につい
て,いずれも本件発明2の構成要件Eの数値範囲内にあったと主張し,乙32号証\n(以下「乙32実験報告書」という。)を提出する。
しかし,乙32実験報告書に示される本件2mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:
PTVD−203)及び本件4mg錠剤のサンプル薬(ロット番号:TVD−30
3)の水分含量の測定値は,これらの錠剤が製造されたとされる日から4年以上が
経過した時点のものである。そして,被告ないし同報告書の説明するところによれ
ば,これらの錠剤は,その製造後,PTP包装とアルミピロー包装がされ,その状
態により,被告の中央研究所の検体保管庫に温度20℃,成り行き湿度(実測値:
75%RH)で保存されていたものであり,検体1錠をPTP包装から取り出して,
乳鉢で粉砕してカールフィッシャー法により水分測定を行ったというのであるが,
上記の条件下で4年以上が経過しても,錠剤の水分含量がそのまま保持されること
を直接裏付ける証拠はない。
かえって,1)本件2mg製品の使用期限が2年6か月とされ,本件4mg製品(被
告製品)の使用期限が3年とされていること(甲4〔52頁〕)からすれば,4年
以上という期間は,予定されている保存期間を大きく超えるものであって,水分含\n量を含む錠剤の状態に影響を及ぼす可能性を否定できないこと,2)ピタバスタチン
からラクトンが生成する反応は,脱水縮合であって,水が脱離することから,水分
含量増加の原因となり得ること,3)アルミピロー包装に使用される材料の防湿性が
高いことがうかがわれる(乙33)としても,PTP包装された上記サンプル薬を
収納したアルミピロー包装には,チャックがついていて(乙32,39),当該材
料のみでは構成されてはおらず,また,湿気等の影響を受けやすい商品の包装には\n充分に注意する必要があるとされていること(甲18),4)PTP包装やアルミピ
ロー包装が施された他の医薬品について,所定の保存期間経過後に水分含量が増加
しているとみられる例があること(甲15,19)などからすれば,PTP包装と
アルミピロー包装により,直ちに上記サンプル薬の水分含量の増加が完全に抑えら
れていたと断ずることは,困難である。
被告は,上記サンプル薬の水分含量がそれぞれ本件2mg錠剤の実生産品(ロッ
ト番号:B062)及び本件4mg錠剤の実生産品(ロット番号:B012)とほ
ぼ同じ値であることから,保存期間中の吸湿の可能性が否定される旨主張するよう\nであるが,かかる被告の立論は,本件2mg錠剤のサンプル薬が本件2mg錠剤の
実生産品と同一の工程により製造され,また,本件4mg錠剤のサンプル薬が被告
錠剤(本件4mg錠剤の実生産品)と同一の工程により製造されていたことを前提
とするものであるところ,既に説示したとおり,本件2mg錠剤のサンプル薬及び
本件4mg錠剤のサンプル薬が,それぞれ本件2mg錠剤の実生産品や本件4mg
錠剤の実生産品(被告錠剤)と同一の工程により製造されたと認めるに足りる証拠
はないものというべきである。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10034 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
2 取消事由1(手続違背)について
(1) 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合,審判の請求に 理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事\n者等にしなければならない(特許法164条の2第1項)。上記「経済産業省令で 定めるとき」として,特許法施行規則50条の6の2が規定されている。同条3号 は,同条1号又は2号に掲げる審決の予告をした後であって事件が審決をするのに\n熟した場合にあっては,「当該審決の予告をしたときまでに当事者…が申\し立てた 理由又は特許法153条第2項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理 由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)に\nよって,審判官が審判の請求に理由があると認めるとき」は,審決の予告をしなけ\nればならない旨規定する。 この規定によれば,先に行われた審決の予告までに当事者が申\し立てた理由のう ち,当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効\nにすべきものと判断する場合のように,「当該理由により審判の請求を理由がある とする審決の予告をしていない」場合は,実質的に訂正の機会が与えられなかった\nものであり,再度の審決の予告をしなければならない。他方,そうでない場合,す\nなわち,先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にす\nべきものと判断する場合のように,実質的に訂正の機会が与えられていた場合は,審判長は,更に審決の予告をする必要はないものと解される。審決予\告の制度は, 特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求につき,それに 起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復による審理の遅延ひいては審決の確定 の遅延を解消する一方で,特許無効審判の審判合議体が審決において示した特許の 有効性の判断を踏まえた訂正の機会を得られるという利点を確保するために,審決 取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することと併せて設けられたものであると ころ,上記の解釈は,この制度趣旨にかなうものである。
(2)第1予告及び第2予\告の内容等
ア 第1予告\n
第1予告で示された認定判断のうち,サポート要件に係る部分は,以下のとおり\nである。
(ア) 本件特許に係る発明の課題
「補償膜において,広い視野範囲にわたり,例えば輝度の増大といった光学的性 質を改善すること」,及び「補償膜を構成する重合性液晶組成物を製造するにあた\nり,配向,及び重合に高温を要しないものとすること」である。
(イ) 判断
a 「補償膜において,広い視野範囲にわたり,例えば輝度の増大といった光学 的性質を改善する」という課題は,「ホメオトロピック配向または傾斜したホメオ トロピック配向を有する補償膜」とすることにより解決されるものである。
b 当時の請求項1記載の発明は,「補償膜において,広い視野範囲にわたり, 例えば輝度の増大といった光学的性質を改善する」という課題を解決するものであ る。 また,当該発明の発明特定事項は全文訂正明細書に記載されている。 したがって,当該発明は,発明の詳細な説明において,発明の課題が解決できる ことを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているとはいえない。
c 当時の請求項4〜14記載の発明についても同様である。
d したがって,当時の請求項1,4〜14記載の発明は,発明の詳細な説明に 記載されたものではないとはいえない。
イ 第2予告\n
第1予告を受け,原告は,平成28年2月8日付け訂正請求を行った。第2予\告 は,これを受けて行われた。
(ア) サポート要件について
a 当時の請求項1,4〜14及び25〜32の解決しようとする課題
上記ア(ア)に同じ。
b 当該課題を解決するための手段
「重合性メソゲン物質の混合物の重合あるいは共重合によって得られる少なくと\nも1つのアニソトロピックポリマー層がホメオトロピックまたは傾斜したホメオト\nロピック分子配向を有する補償膜,および該補償膜を備えた液晶表示デバイスの提\n供」をするものである。
c 判断
(a) 当時の請求項1記載の発明の「式 I」の定義を満たすメソゲンの全てが\n「ホメオトロピック又は傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好 適に作製できる範囲にあるとは認められない。 当該発明の「式 I」を満たすメソゲンの中には,置換基における炭素数が1つ違\nうだけでも,その液晶としての物性が大きく異なる場合が存在しており,メソゲン\nの分子量や立体構造や極性基の有無などによっても,その液晶としての物性が大き\nく異なることも当業者の技術常識であるから,当時の全文訂正明細書の例1A〜例 2において試験された化合物(1)〜(6)以外のメソゲンの全てが「ホメオトロピックま\nたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲 にあるとは認められない。
(b) 当時の請求項4〜14及び25〜32記載の発明についても同様である。
(c)したがって,当時の請求項1,4〜14及び25〜32記載の発明は,発明 の詳細な説明に記載されたものではない。
(イ) 新規性及び進歩性について
a 引用発明の認定
第2予告において認定された甲1記載の発明(以下「甲1の2発明」,「甲1の\n3発明」という。)は,以下のとおりである。
(a) 甲1の2発明
偏光板と液晶セルの間に光学補償板として使用できる光学異方フィルムを配置す る液晶表示素子であって,前記光学異方フィルムは,下記の式(I)の化合物25 重量部,
下記の式(m)の化合物25重量部,
下記の式(a)の化合物50重量部
からなる重合性液晶組成物99重量部と光重合開始材1重量部から成る重合性液晶組成物を光重合させて得られた,ホモジニアス配向の光学異方フィルムである, 前記液晶表示素子(判決注:上記式(I),(m)及び(a)は,別紙2「引用発 明」記載1のものと同一である。)。
(b) 甲1の3発明
重合性液晶組成物を光重合させて得られた,光学補償板として使用することがで きるホメオトロピック配向の光学異方フィルムであって,下記の式(a)の化合物 50重量部, 及び下記の式(d)の化合物50重量部 からなる重合性液晶組成物100重量部と光重合開始剤1重量部からなる重合性 液晶組成物を,2枚のガラス基板の間に挟持させ,ホメオトロピック配向している ことを確認した後,紫外線を照射して光重合させて得られた,前記光学異方フィル ム(判決注:上記式(a)及び(d)は,別紙2「引用発明」記載2のものと同一 である。)。
b 当時の請求項14記載の発明について
当時の請求項14記載の発明は,甲1の2発明であるから,特許法29条1項3 号に該当する。
(ウ) 第2予告を受け,原告は,本件訂正請求を行った。\n
(3) サポート要件について
ア 本件審決と第2予告は,いずれもサポート要件につき,特許請求の範囲の記\n載は,発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるとは認められず,また,その記載や示唆がなくとも当 業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるとも認められないとして,サポート要件に適合しないと判断したもので ある。
イ 本件訂正発明の解決しようとする課題
(ア) 本件審決が認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は,前記第2の 3(2)アのとおりである。また,第2予告が認定した本件訂正発明の解決しようとす\nる課題は,前記(2)イ(ア)aのとおりである。
(イ) 本件審決と第2予告がそれぞれ認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は,表\現こそ異なるものの,実質的には同じ内容を意味するものと理解される。
ウ 以上によれば,サポート要件との関係では,サポート要件違反により審判の 請求を理由があるとする第2予告の後,原告には実質的に訂正の機会が与えられた\nものといえるから,更に審決の予告をすべき場合には当たらない。\n
(4) 新規性及び進歩性について
ア 本件審決及び第2予告において判断の対象とされた新規性・進歩性の判断に\n当たり対比される主引用例は,いずれも甲1(引用例)であり,同一である。
イ 引用発明の認定
(ア) 本件審決の認定した引用発明1A及び1Bは,前記第2の3(3)のとおりで ある。また,第2予告が認定した甲1の2発明及び甲1の3発明は,前記(2)イ(イ) aのとおりである。
(イ) 引用発明1Bと甲1の3発明とを対比すると,本件審決の認定と第2予告\nの認定は同一である。他方,引用発明1Aと甲1の2発明については,本件審決で は式(N−a)の化合物を含むのに対し,第2予告ではこれを含まない点その他の\n点で,液晶表示素子に係る混合物を構\成する重合性液晶組成物の一部が相違する。 しかし,甲1を主引用例として認定された引用発明に基づき,新規性又は進歩性 が欠如するとの無効理由により審判の請求を理由があるとする第2予告により,上\n記無効理由に関しては,実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。 よって,新規性及び進歩性との関係では,第2予告の後更に審決の予\告をすべき 場合には当たらない。
(5) まとめ
以上のとおり,本件審決は,第2予告をしたときまでに当事者が申\し立てた理由 で,当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしたものを判断の\n対象としたものであり,「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予\n告をしていないとき」に該当しないから,第2予告の後更に審決の予\告をしなけれ ばならない場合には当たらない。 したがって,再度の審決の予告をしないまま審決をしたことにつき,本件審決に\n違法はない。
(6) 原告の主張について
ア 原告は,本件審決が認定した本件訂正発明の課題は第2予告で認定されたも\nのと異なるなどと主張する。 しかし,本件訂正明細書においては,液晶表示デバイスの補償膜に係る従来技術\n及びそれが抱える欠点等につき前記1(1)ア(イ)のとおり説明し,これを受ける形で, 「本発明の課題の一つは」などとして,前記1(1)ア(ウ)のとおり,解決しようとす る課題及び本件訂正発明がこの課題を解決できる旨が記載されている。本件審決は, これを踏まえ,本件訂正発明の課題を認定したものと理解される。 他方,第2予告においても,これらと同旨の記載が当時の全文訂正明細書にある\nことを根拠に,発明の課題の認定が行われている。 このことと,第2予告の認定において,「補償膜において,・・・光学的性質を改善\nすること」と「補償膜を構成する・・・高温を要しないものとすること」とは「及び」\nにより接続されていることを踏まえると,本件審決と第2予告とがそれぞれ認定した発明の課題が異なるものということはできない。\nなお,原告は,課題の認定につき,第1予告では,第2予\告と同様の認定がされ ながらサポート要件を満たすものとして通知されていたために,それ以降サポート 要件についての議論はさほどされなかったなどといった経緯から,第2予告のサポ\nート要件違反の理由につき,本件審決において変化する理由は推測できないなどと 指摘する。
しかし,上記のとおり,本件審決と第2予告とで認定した発明の課題が異なると\nはいえない上,特許法施行規則50条の6の2第3号に基づく審決の予告と理解さ\nれる第2予告においてサポート要件違反とする理由が明確に示され,原告もこれに\n対する反論を現に行っていること(甲68−1)に鑑みると,第1予告の内容がど\nうであれ,第1予告から第2予\告,その後の本件審決へと至る経緯を考慮しても, 本件審決に先立ち,第3の審決の予告を行って原告に主張立証や訂正の機会を与え\nなければならないとはいえない。
イ 原告は,本件審決が第2予告で指摘していない式Iの例をサポート要件違反\nの根拠とし,また,審尋における質問に対する回答によって一旦解消した問題を不 意打ち的に蒸し返して判断したなどと主張する。 しかし,本件審決が括弧書で示した化合物は,実施例記載の具体的な化合物(1)〜 (6)以外のメソゲンが本件訂正発明の課題を解決しないことを説明するための例示に\nすぎず,その記載の有無が結論に影響を及ぼすものではない。その意味で,これら が第2予告において示されていなかったとしても,再度の審決の予\告を行い訂正の 機会を与える必要性を裏付けるものとはいえない。 また,原告主張に係る審尋における審判合議体の質問で例示された化合物に関し ては,「その「重合性基(P)」がアクリレート基であるとした場合に,その「P −Sp−」の選択肢として,例えば「CH2CHCOO−O−(CH2)m−」や 「CH2CHOO−OCOO−(CH2)m−」のような化学構造のものまでもが本\n件第2訂正発明1の範囲に含まれてしまいます。」とされている。他方,本件審決 で例示されたものは,「Pがプロペニルエーテル基又はエポキシ基であり,Spが −O−CH2−C≡CH2−O−であり,Xが−O−である場合のメソゲン物質」(本件訂正発明1)や「Pがプロペニルエーテル基であり,Spが−O−CH2−C≡C−CH2−O−CH2−O−COO−CH2−CO−S−であり,Xが−O−である場合のメソ\ゲン物質」(本件訂正発明4,5,7,8,10〜14,25〜34),「Pがプロペニルエーテル基であり,Spが−O−CH2−O−であり, Xが−O−である場合のメソゲン物質」(本件訂正発明6)であり,第2予\告で例 示された化合物と一致しない。そうである以上,上記「解決済み」との原告の主張 は,その前提を欠く。
ウ 原告は,本件訂正発明に係る好適なホメオトロピック配向の効果の有無を認 定することがないまま審決に至った点で,本件審決には審理不尽があるなどと主張する。
しかし,本件審決は,本件訂正発明のうち進歩性を欠くとしたものについては, いずれもその判断において,発明の効果につき「当業者が予測し得る範囲内のもの\nである。」旨の判断を示している。そうである以上,本件審決に至る審理において 本件訂正発明の効果に関する検討が行われていないとはいえない。
エ 原告は,第2予告における引用発明が本件審決において別の発明にすり替わ\nっており,その変更の理由も述べられていないことと併せ,本件審決には手続違背 があるなどと主張する。 しかし,本件審決における引用発明1Aと第2予告における甲1の2発明とで相\n違があるとしても,実質的に見て,第2予告により原告には訂正の機会が与えられ\nたものといえることは,前記のとおりである。
オ 原告は,本件訂正発明14につき,第2予告では新規性欠如との理由が示さ\nれていたのに対し,本件審決では新規性及び進歩性欠如の理由が示されており,無 効理由が実質上も形式上も一致していないなどと主張する。 しかし,第2予告においても,その当時の訂正発明14につき新規性欠如及び進\n歩性欠如がいずれも無効理由として主張され,判断の対象とされていた(甲66)。 このこと及び第2予告後に請求項14の訂正を含む本件訂正請求が行われたことに\n鑑みると,審判合議体が審決に当たり新規性についてのみならず進歩性についても 判断を示す必要があると考えたとしても,再度更に審決の予告をして原告に訂正の\n機会を与える必要があるとはいえない。
・・・・
3 取消事由2(サポート要件違反の判断の誤り)について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。そして,サポート要件の存在は,特許権者が証明責任を負うものと解される。
・・・・
ア 前記のとおり,特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには, 明細書の発明の詳細な説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において 認識できるように記載しなければならない。そして,本件訂正発明におけるメソゲ\nン化合物a,a1,a2を定義する式 I ないし I’は,請求項によってその具体的 内容を多少異にするものの,いずれも当該式を構成する重合性基P,スペーサー基\nSp,結合基X,メソゲン基MG,末端基Rといった基本骨格部分において非常に\n多くの化合物を含む表現である上,これらに結合する置換基の選択肢も考慮すれば,\nその組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものとなっている。\nこのような場合に,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合する ためには,発明の詳細な説明は,上記式が示す範囲と得られる効果との関係の技術 的な意味が,特許出願時において,具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか,又は,特許出願時の技術常識を参酌して,当該式が示す範囲内で あれば,所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示 して記載することを要するものと解するのが相当である。換言すれば,発明の詳細 な説明に,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に,具体例を開 示せず,特許出願時の当業者の技術常識を参酌しても,特許請求の範囲に記載され た発明の範囲まで,発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる とはいえない場合,サポート要件に適合するとはいえない。
イ 前記のとおり,本件訂正発明におけるメソゲン化合物a,a1,a2を定義\nする式 I ないしI’は,その組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものと\nなっている。 他方,本件訂正発明の実施例である例1A〜例3においてメソゲン化合物として\n用いられている化合物(1)〜(8)は,いずれも式 I において,重合性基Pがアクリレー ト基(CH2=CHCOO−),Sp(スペーサー基)が炭素数3又は6個の直鎖 状アルキレン基,Xが−O−,nが1という,化学構造が類似するごく限られた化\n合物に限られる。 例えば,重合性基Pがメタクリレート基であるモノマーを含むと安定な配向を得 にくくなる場合が生じてくることが知られている(乙4)。また,例えばスペーサ ー基Spを構成する(その一部の置換えも含む。)アルキレン基として炭素数が1\nの場合と20の場合とでは化合物の特性が大きく異なることが予測されることなど配合するメソ\ゲン化合物の化学構造がその配向性や配向膜の特性に影響することは,\n現に引用例において様々な構造の化合物につき検討されていることからもうかがわ\nれるように,本件優先日当時における当業者の認識であったと考えられる。そうす ると,本件訂正明細書の発明の詳細な説明における他の記載を参酌しても,補償膜 の調製に用いる混合物につき,上記具体例として示された化合物とは構造が異なる\n化合物を成分とする混合物に係る本件訂正発明の範囲にまで拡張ないし一般化した 場合,すなわち本件訂正発明に係る式 I で表される広範な重合性メソ\ゲン化合物の いずれかを含む混合物とした場合に,これによって,前記認定に係る本件訂正発明 の課題を解決するような補償膜として好適なフィルムが得られるとはいえない。 したがって,本件訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは, 本件特許の特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発 明であり,本件訂正発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえない。そのように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識 を認めるに足りる証拠もない。
ウ 本件訂正発明の解決しようとする課題のうち,「高融点を示し配向および重 合に高温を要するという欠点を有していない」点について,本件訂正明細書の発明 の詳細な説明には,「低融点,好ましくは100℃またはそれ以下,特に60℃ま たはそれ以下の融点を有する重合性混合物を使用すると好ましく,これにより低温 で混合物の液晶相において硬化を行うことができる。…60℃以下の硬化温度は特 に好ましい。」との記載がある。加えて,実施例(例1A)には,基板に塗布し, 50℃で溶剤を蒸発させることによってホメオトロピック配向膜を得られることが 示されている。もっとも,「高温を要するという欠点」を回避し得る融点を具体的 に特定する記載はない。
他方,本件訂正明細書で液晶の配向に高温を要する例として掲げたJP05−1 42531(乙1)の【化2】で表される化合物について,引用例には,「108〜211℃という非常に高い温度範囲でネマチック相を示し,実際にこの化合物を\n含有する重合性組成物を液晶状態で重合して作製した光学異方フィルム(カラー偏 光板)は外観も不均一であり,むらが生じる欠点があった。」と記載されている。 また,本件訂正明細書で同様に「高融点を有し,従って配向および重合に高温を要」 するものとして例示された Heynderickx, Broer 等の刊行物(乙2)に記載されて いる‘Scheme 1’の化合物については,引用例にも,「一般式(R−2)において, R5がメチル基の化合物80重量部及びR5が水素原子の化合物20重量部から成 る液晶組成物は,80〜121℃と室温よりかなり高い温度範囲でネマチック層を 示し,また予期しない熱重合に起因してこのような重合性液晶組成物を用いて作製される光学異方フィルムのメソ\ゲンの配向が不均一となるという欠点があった。」 と記載されている。ところが,これらの化合物はいずれも,本件訂正発明に係る式 I で定義される広範な化合物に含まれるのであって,本件訂正明細書の内部でいわ ば記載内容に矛盾を生じている。
そうすると,本件訂正発明に係る式 I で定義されるメソゲン化合物を含む混合物\nは,その全てが本件訂正発明の課題を解決し得る「高融点を示し配向および重合に 高温を要するという欠点を有していない」ものとはいえない。その点からも,本件 訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは,本件特許の特許請求 の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明であり,本件訂正 発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえず,また,その ように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識を認めるに足り る証拠もない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10078 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
前記2(1)イ〜エ,カの記載によれば,甲1発明は,「発泡作用によりマッ サージ効果を得る化粧料について,最高度に気泡が発生することを色によっ て判断できるようにすること」を課題とし,当該課題を,「炭酸水素ナトリ ウムを含む第1剤と,前記炭酸水素ナトリウムと水の存在下で混合したとき に気泡を発生するクエン酸,酒石酸,乳酸及びアスコルビン酸のうちの1又 は2以上の成分を含む第2剤と,前記第1剤と第2剤に夫々分散された異色 のものからなり,混合により色調を変え,使用可能な状態になったことを知\nらせるための2色の着色剤A,Bと,前記第1剤又は第2剤の一方又は双方 に含まれた,化粧料としての有効成分とからなる組成」を有する「常態では 粉状」の化粧料とし,これにより,「2色の着色剤A,Bを第1剤,第2剤 に夫々混合し,使用前,個有(原文のまま)の色分けを行なうとともに使用 時第1,第2両剤を混合し,一定の色調になったときに良く混合したことが 判断できかつ,最適の反応が行なわれる」ようにすることで,解決しようと したものである。すなわち,甲1発明は,最高度に気泡が発生することを色 によって判断できるようにするために,炭酸塩を含む第1剤と酸を含む第2 剤に分けてあえて異色の構成とし,これらを混合することによって色調が変\nわるようにしたものであると認められる。 そうすると,たとえ,アルギン酸ナトリウムが水に溶けにくい性質を持つ ことや,一般的な用時調製型の化粧料において,ジェルと固体(顆粒や粉末 等)の2剤型のものが周知であったとしても,甲1発明において,炭酸塩と 酸が2剤に分離されてそれぞれが異色のものとされている構成を,甲2記載事項の「粉末パーツ」のようにあえていずれか一方(1剤)に統合して複合\n粉末剤等とすると,そもそも甲1発明の目的(2剤の色分けと混合による色 調の変化を利用して最高の発泡状態か否かを判断する)を達成できなくなる ことは明らかであるから,そのような変更を当業者が容易に想到し得るとは いい難く,その意味で,甲1発明に甲2に記載された技術(甲2記載事項) 等を組み合わせようとすることについては動機付けがなく,むしろ阻害要因 があるといえる。
(3) これに対し,原告は,甲1発明は,気泡状の二酸化炭素(炭酸ガス)を経 皮吸収させることを機能の一つとする化粧剤であるから,拡散問題(炭酸ガ\nスが大気中に拡散すること)は甲1発明に内在する自明の課題であるとした上で,甲1発明に対しアルギン酸ナトリウム慣用技術(甲2記載事項)を適 用することについては,自明の課題である拡散問題を軽減するために,閉じ 込め効果(アルギン酸ナトリウムを事前に水に添加して万遍なく行き渡らせ ることにより,網目状の高分子化合物が形成され,気泡状の二酸化炭素〔炭 酸ガス〕を水溶液中に閉じ込めることが可能となること)を利用するという\n積極的な動機付けがある,などと主張する。
しかしながら,甲1発明は,前記のとおり,発泡作用(炭酸ガスの発泡, 破裂作用)によりマッサージ効果を得る化粧料について,最高度に気泡が発 生することを色によって判断できるようにすることを目的とするものであっ て,そこに炭酸ガスを体内に取り込もうとする技術的思想はない(二酸化炭 素の泡がはじけることによる物理的な刺激を効果的に得ようとしているにす ぎない)から,「気泡状の二酸化炭素(炭酸ガス)を経皮吸収させることを 機能の一つとする化粧料」であるとはいえず,原告の主張はそもそもその前\n提において誤りがある。そうである以上,原告主張の拡散問題が甲1発明に 内在する自明の課題であるとはいえないし,甲1発明におけるアルギン酸ナ トリウムは飽くまで気泡発生を助成するための起泡助長剤として添加されて いるにすぎないから(甲1【0013 】),アルギン酸ナトリウムが含まれ ているからといって,それだけで直ちに事前に水に添加して利用する技術(アルギン酸ナトリウム慣用技術)を適用することについての積極的な動機付け があるともいえない。この点,原告は,アルギン酸ナトリウムが増粘剤とし ても機能するものであることを根拠に甲1発明におけるアルギン酸ナトリウ\nムが気泡の発生とその安定化の双方に寄与するものであることを当業者は当 然に認識するとも主張するが,甲1発明の目的を離れた主張であって,論理 に飛躍があり,採用できないというべきである。
また,原告は,阻害要因に関して,甲1は,技術分野の同一性を理由とし て本件発明の課題を解決するための主引例として選択されたものであり,容 易想到性の判断に際して,甲1に記載された目的に反する方向での変更か否 かは関係がない,などとも主張するが,特定の公知文献(公知技術)からの 容易想到性の問題である以上,当該公知文献に記載された目的を度外視した 判断はできないというべきであり,上記主張は,やはり採用できないという べきである。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(ネ)10060 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
まず,構成要件Fの「入力」との文言の意味について検討する。
(ア) 本件明細書には,構成要件Fの「入力」の意味を直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらない。\n他方で,本件明細書には,複数の箇所で「入力」との文言が使用され ているところ,例えば,段落【0008】の「摩擦力による入力を,直 接的または間接的に検出する」のように「物理的な力を加えること」と の意味や,段落【0012】の「図14は,…文字を入力する例を示し た図である。」のように「コンピュータに情報を与えること」との意味 など,同一の文言であるにもかかわらず文脈によって異なる意味で使用 されている。 なお,本件訂正審決は,本件明細書の段落【0035】及び【006 2】の記載に基づいて,本件発明の「『当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの(判決注:原文のまま)記憶部に\n記憶させる』とは,(背景の変更などの)変更結果を,(フォルダYに 保存することなどの)表示対象に対する情報として記憶することを意味しているといえる。」と判断しているが,これは構\成要件Fの「入力」 は「コンピュータに情報を与えること」を意味すると解したものといえ る。
(イ) この点について,控訴人は,構成要件Fの「入力」は,「力入力検出手段」により検出された当該表\示対象に対する「力入力」,すなわち「物理的な力を加えること」を意味すると主張する。 しかし,この解釈は,構成要件H,A及びDでは,「物理的な力を加えること」として「力入力」との文言が明示的に使用されているにもか\nかわらず,構成要件Fでは敢えて「入力」のように異なる文言が使用されていることと整合しない。\n
また,構成要件Fの「入力」は,「当該変更結果」,すなわち,「保持された表\示対象以外の表\示態様を変更することにより,当該表\示対象を相対的に変更させた結果」を目的語としていると解し得るところ,こ の場合に「入力」を「物理的な力を加えること」と解釈することは不自 然である。さらに,「として」は,前に置かれた語を受けて,その状態, 資格,立場等であることを表す語であるところ,「入力」を「物理的な力を加えること」と解すると,「入力として・・・記憶させる」との文言が\n意味するところを理解できないというべきである。
(ウ) 控訴人は,本件訂正審決が「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として・・・記憶部に記憶させる」とは,「(背景の変更などの)変更結\n果を,(フォルダYに保存することなどの)表示対象に対する情報として記憶することを意味している」と判断したことを指摘して,当該判断\nは控訴人の上記主張と整合するとも主張する。 しかし,「物理的な力を加えること」と「コンピュータに情報を与え ること」とは別個の概念であるから,構成要件Fの「入力」を「物理的な力を加えること」と解した上で,本件訂正審決の判断のように「コンピュータに情報を与えること」との意味をも有すると直ちに理解することは困難である(物理的な力が加わったことをコンピュータに検出させる場合には,両者の意味が重なっているともいい得るが,本件においては,上記説示のとおり,少なくとも「物理的な力を加えること」と解することは不自然であるから,両者の意味が重なっている場合と断ずることもできない。)。\n
(エ) 以上によれば,控訴人の主張によっては,構成要件Fの「入力」の意味を一義的に理解することは困難であるというほかない。\n
イ 仮に,構成要件Fの「入力」を,本件訂正審決が判断したように,「コンピュータに情報を与えること」と解したとしても,次のとおり,構\成要件Fの意義は依然として不明確であるというべきである。
(ア) 構成要件Fの「当該表\示対象」は,構成要件Cの「前記位置入力手段にて検出された位置の表\示対象」をいうと解される。本件明細書には,この「表示対象」の意味についても,直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらないものの,発明の詳細な説明の記載に照らせば,アイコン等(【0021】),アイコンや文字列等(【0029】),アイコンや文字,記号,図形,立体表\示対象など(【0035】)がこれに当たるものと解される。 しかし,表示画面にアイコン等を表\示させ,利用者が当該表示画面に接触した位置を検出し,当該接触位置に応じて処理を行う入出力装置においては,表\示画面に表示するアイコン等のデータそのもの(例えば,スマートフォンの画面に表\示されているカメラ様の画像データ)と,当該アイコン等と紐づけされた実体(例えば,カメラアプリケーション) とは,別個のものとされていることが多いと解されるところ,本件明細 書の記載を精査しても,本件発明における「表示対象」が具体的にどのようなものであるのかは明らかといえない。\n
(イ) また,上記ア(イ)のとおり,構成要件Fの「当該変更結果」は,「保持された表\示対象以外の表示態様を変更することにより,当該表\示対象を相対的に変更させた結果」と解し得るところ,「相対的に変更させた結果」についても,背景として設定されている画像が移動したピクセル数や,保持された表示対象と重なることとなったアイコン等の有無及びその種類など,さまざまなものがあり得る。\n そして,構成要件Fによれば,この「相対的に変更させた結果」は,「当該表\示対象」に対する情報として与えるものであるが,ある対象に与え得る情報は,当該対象がアプリケーションかデータかや,その実装方法によっても大きく異なるものと解される。 そうすると,上記(ア)のとおり,「当該表示対象」が具体的に意味するところが明らかでない上に,「相対的に変更させた結果」の意味内容も特定されていないことを考え合わせると,「当該変更結果を当該表\示対象に対する入力として記憶部に記憶させる」の意義も明らかでないというべきである。
(ウ) この点に関し,本件訂正審決は,本件明細書の段落【0035】及び 【0062】の記載に基づいて,「当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの(判決注:原文のまま)記憶部に記憶させる」とは,「表\示要素『B』のデータをフォルダXからフォルダYに移動させて保存することを意味している」と判断した。しかし,本件訂正審決の説示においても,「表示要素『B』のデータ」がいかなるデータであるのかが具体的に特定されているとはいい難い。\n また,本件明細書の段落【0035】記載の「フォルダX」及び「フォルダY」と段落【0062】記載の「WINDOW1」及び「WINDOW2」の関係も明らかでなく,いかなる情報が「相対的に変更させた結果」に該当し,「フォルダXからフォルダYに移動させ」ると理解することになるのかについても具体的な指摘がされているとはいえない。
ウ 以上検討したところによれば,結局のところ,構成要件Fの意義は不明確というべきである。そして,構\成要件Fの意義が不明確である以上,被告各製品が構成要件Fを充足すると認めることはできない。\n
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10086 審決取消請求事件 実用新案権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
本件考案1の実用新案登録請求の範囲の分説Bには,「前記底座体の前 部に回動自在に設置された第一駆動ホイールが第一モータに連結され,前 記第一駆動ホイールに第一偏心軸の入力端部が固定されると共に,前記第 一偏心軸の出力端部は第三8字形リンクロッドを介して前記上板の前部に 連結され,」(第一駆動系)と,分説Cには,「前記底座体の後部に回動 自在に設置された第二駆動ホイールが第二モータに連結され,第二駆動ホ イールに第二偏心軸の入力端部が固定されると共に,第二偏心軸の出力端 部はリンクロッドを介して前記中心軸に連結された」(第二駆動系)と記 載されている。そして,「介して」は「間におく。さしはさむ。中に立て る。」といった意味であるが(甲6,7),このような実用新案登録請求 の範囲の記載のみからは,「第一偏心軸の出力端部」と「上板の前部」と が「第三8字形リンクロッド」を「介して」どのように連結固定されるの か,「第二偏心軸の出力端部」と「中心軸」とが「リンクロッド」を「介 して」どのように連結固定されるのかが必ずしも明らかではない。 そこで,本件考案の技術的意義について,本件明細書の記載をみるに, 本件明細書の【0007】〜【0009】,【図1】及び【図2】には, 「底座体4」,「上板1」,「中心軸2」,「第一8字形リンクロッド8 1」,「第二8字形リンクロッド82」,「第一モータ91」,「第一駆 動ホイール61」,「第一偏心軸71」,「第三8字形リンクロッド83」, 「第二モータ92」,「第二駆動ホイール62」,「第二偏心軸72」, 「リンクロッド3」の本件考案の各機械要素の位置関係又は連結固定関係 が記載されている。また,【0010】〜【0012】には,本件考案の 振動器が上記の機械要素を用いて,上板に,1) 上下振動,2) 前後振動, 3) 両者を複合した振動を発生させるものであり,1)は,「第二モータ9 2」は停止させ,「第一モータ91」を作動させて「第一駆動ホイール6 1」を回転させると当該「第一駆動ホイール61」に固定された「第一偏 心軸71」が回転し,当該「第一偏心軸71」が「第三8字形リンクロッド83」を動かすことで「上板1」を上下方向に振動させるものであるこ と(【0010】),2)は,「第一モータ91」は停止させ,「第二モー タ92」を作動させて「第二駆動ホイール62」を回転させると当該「第 二駆動ホイール62」に固定された「第二偏心軸72」が回転し,当該「第 二偏心軸72」が「上板1」に設けた「中心軸2」に連結されている「リ ンクロッド3」を動かすことで,「上板1」に前後方向に振動させるもの であること(【0011】),3)は,「第一モータ91」と「第二モータ 92」を同時に作動させたときに「上板1」を上下方向と前後方向に同時 に移動することで生じる1)と2)を複合した弧形の振動であること(【00 12】)が記載されている。また,これ以外の態様は記載されていない。 以上に照らせば,本件考案の技術的意義は,第一駆動系により上板を上 下方向に振動させ,第二駆動系により上板を前後方向に振動させることで, 複数方向の振動を発生させることにあるといえる。そうすると,本件考案 1の分説B及び分説Cにおける「介する」は,第一駆動系により上板を上 下振動させ,第二駆動系により上板を左右振動させるような連結固定関係 としたものを意味するものであることは,明らかである。
イ 以上によれば,実用新案登録請求の範囲の記載は,その記載それ自体に 加え,本件明細書の記載及び図面並びに当業者の技術常識を基礎にすると,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確なものとは認められないから, 明確性要件関する本件審決の判断の結論に誤りはなく,この点に関する原 告の主張は採用することができない。
(3) 原告の主張について
原告は,分説B及び分説Cは,「介して」という「間におく。さしはさむ。 中に立てる。」という意味の用語を用いているのに止まり,本件考案を特定 するために必要不可欠な技術的事項の記載が欠落しており,原告指摘振動器 1及び原告指摘振動器2を含み得るように広く記載されているから,請求項 1の記載が不明確である旨主張する。 しかし,上記(2)に説示したとおり,分説B及びCの「介して」の用語の意 義を理解できるから,請求項1の記載は,第三者に不測の不利益を及ぼすほ どに不明確なものとは認められない。
3 取消事由1(サポート要件違反についての判断の誤り)について
(1) サポート要件に適合するかどうかは,実用新案登録請求の範囲の記載と考 案の詳細な説明の記載とを対比し,実用新案登録請求の範囲に記載された考 案が,考案の詳細な説明に記載された考案で,考案の詳細な説明の記載によ り当業者が当該考案の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該考案の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。
(2) 以上を前提に,本件考案1のサポート要件適合性について判断するに,本 件考案の技術的意義については,上記2(2)アのとおりであり,本件考案の採 用する課題解決手段もそのとおりに理解することができる。 そうすると,実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載は,考案の詳細な 説明に記載された考案で,当業者が,技術常識に照らし,考案の詳細な説明 の記載により当該考案の課題(美容あるいは運動用の振動器において,複数 方向の振動を発生させ,様々なニーズに応じた美容効果を得ることができる 振動器を提供すること)を解決できると認識できる範囲のものであるといえ る。 よって,本件考案1は,サポート要件に適合しているから,サポート要件 関する本件審決の判断の結論に誤りはなく,この点に関する原告の主張は採 用することができない。 したがって,取消事由2は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本件考案1には,上下方向の振動しかしない原告指摘振動器1 と前後方向の振動しかしない原告指摘振動器2が含まれると主張する。 しかし,上記2(2)アで述べたところに照らせば,原告指摘振動器1及び 原告指摘振動器2は,本件考案1には含まれないというべきであるから, 原告の主張は前提を欠く。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10118 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月25日 知的財産高等裁判所
a 引用発明1の課題は,1)背肩近辺の側面側,特に肩ぐうと呼ばれるつぼをマ ッサージすること,2)背面側にマッサージを行う場合に,身体が施療手段により押 されて前方に動くのを防ぐこと,である。 これに対し,引用発明2の課題は,1)下腿の臑の前外側,特に三里,豊隆と呼ば れるつぼをマッサージすること,2)下腿にマッサージを行う場合に,被施療者の下 腿を拘束しないこと,である。
b まず,引用発明1と引用発明2の課題は,1)身体の側面ないし前面に位置す るつぼのマッサージを行うという限度で共通するが,その対象部位及び対象部位に 位置するつぼの種類が異なる。 そして,引用発明1と引用発明2におけるマッサージの対象部位及び対象部位に 位置するつぼの種類を比較するに,背肩と下腿においては,その形状,重量や椅子 型マッサージ機にかかる荷重,可動範囲などが大きく異なるから,それに応じて椅 子型マッサージ機の構成は異なるものとならざるを得ない。また,定型的な動きし\nかできない椅子型マッサージ機においては,背肩近辺の側面側と下腿の臑の前外側 に位置するつぼをどのような強度,角度及び範囲で押圧するかによって,その施療 子部分の構成も異なるものとならざるを得ない。\nそうすると,椅子型マッサージ機である引用発明1と引用発明2において,マッ サージの対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なることは,両発明の課 題が有する意義に差異をもたらすものというべきである。
c 加えて,引用発明1と引用発明2の課題は,2)身体の動作を防止してその自 由度を下げようとするか,身体を拘束しないようにしてその動作の自由度を上げよ うとするかという点では正反対のものということができる。
d よって,引用発明1と引用発明2との課題は,マッサージを行おうとする対 象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なること,身体の動作の自由度を下 げようとするか上げようとするかで異なることから,相違するものというべきであ る。
(ウ) 作用機能\n
引用発明1は,背もたれ部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部の内側面 に配設されたエアバッグが膨出し,身体を左右両側から挟圧するという作用機能を\n有する。 これに対し,引用発明2は,後側空気袋の膨張によって,支持部に枢着されてい る左右の受板が前方へ回動し,受板の前側に配された前側空気袋が膨張することに よって,臑の外側部分を押圧するという作用機能を有する。\nしたがって,引用発明1と引用発明2の作用機能は,膨出(膨張)するエアバッ\nグ(前側空気袋)によって身体を押圧するという点で共通するものの,当該エアバ ッグ(前側空気袋)を配設する部材が,側壁部か,支持部に枢着された回動可能な\n受板かという点で相違する。
(エ) 示唆
引用例1又は引用例2の内容中に,引用発明1に引用発明2を適用することにつ いての示唆は見当たらない。
(オ) 動機付け
以上のとおり,引用発明1と引用発明2とは,椅子型マッサージ機という限度で 技術分野が共通するものの,マッサージを行おうとする対象部位及び対象部位に位 置するつぼの種類が異なることなどから課題が相違し,身体を押圧するエアバッグ を配設する部材のそもそもの可動性が異なることから作用機能も相違するほか,引\n用発明1に引用発明2を適用することについて示唆も見当たらない。 したがって,引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがあるということはできない。
(カ) 原告の主張について
a 原告は,当業者が通常の創作能力を発揮すれば,引用発明1において相違点\nに係る構成を採用することができる旨主張する。\nしかし,前記のとおり,椅子型マッサージ機においては,身体が着座姿勢で固定 され,また身体の各部位の形状等が異なることから,その構成は,マッサージの対象部位に応じて異なるものになる。また,椅子型マッサージ機は定型的な動きしか\nできないから,椅子型マッサージ機の施療子部分の構成は,対象となるつぼの種類\nによっても異なるものになる。 したがって,引用発明1において,椅子型マッサージ機及びその施療子部分の構\n成に関連する相違点を採用することが,通常の創作能力の発揮であるということは\nできない。
b 原告は,引用例2には,引用発明2と同じ機構が下腿だけではなく,足の甲\nの部分にも適用できることが記載されているから,当業者は,引用発明2が下腿だ けではなく,身体の他の部分にも適応可能な機構\であることを理解し,また,他の 部分に適用することを示唆される旨主張する。 しかし,前記のとおり,椅子型マッサージ機の構成は,マッサージの対象部位に\n応じて異なるものになり,その施療子部分の構成も,対象部位に位置するつぼの種\n類に応じて異なるものになる。引用発明2と同じ機構が,下腿だけではなく,足の\n甲の部分にも適用できたとしても,当業者は,これを,身体の形状等が大きく異な り,施療子部分の構成も変更する必要がある背肩近辺にも適用可能\な機構であると\nは理解しないし,背肩近辺に適用することについて示唆を受けるものでもない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.03.28
平成30(行ケ)10095 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月19日 知的財産高等裁判所
前記ア認定のとおり,建築部材等の工業製品において,面と面との交わ りのかどに斜面又は丸みをつける「面取り」は,本件出願当時,周知であ ったことが認められる。 また,前記イ及びウのとおり,甲16には基台2の下面の両縁部の角が 斜面になっている構成が,甲17には,プラスチック等非腐蝕体(4)の\n下面の両縁部の角が斜面になっている構成がそれぞれ開示されている。\nしかしながら,甲1には,「面取り」に関する記載や,甲1発明の台座 の基盤1の下面縁部と側壁との間に下面又は側壁に対して傾斜する斜面の 記載はなく,ましてや,そのような斜面を基盤1の「延在方向に沿って設 け」ることについての記載も示唆もない。 かえって,甲1発明の台座においては,基盤1の側壁に突部tと凹部h を有し,隣り合う台座間で突部tと凹部hとを係合して接続するものであ ること(前記(2)ア及びエ)からすると,突部tや凹部hの一部を削って斜 面を設けることは考え難いというべきである。 加えて,甲1には,甲1発明の台座において,基盤1等の稜線に人が接 触して怪我をしないようにする措置を講じる必要があることをうかがわせ る記載はない。
そうすると,甲1,甲16及び17に接した当業者において,甲1発明 の台座に上記周知技術,甲16又は17記載の構成を適用して,基盤1の\n下面縁部と側壁との間に下面又は側壁に対して傾斜する斜面を設け,当該 斜面が基盤1の延在方向に沿って設けられる構成(相違点3に係る本件発\n明1の構成)とする動機付けがあるものと認めることはできない。\nしたがって,当業者が,甲1発明において,相違点3に係る本件発明1 の構成とすることを容易に想到することができたものといえないから,こ\nれと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.03.28
平成30(行ケ)10032 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月26日 知的財産高等裁判所
本件明細書には,1)「本発明」の「リボン」は, 1つ又は複数のストランドから成り,1つのストランドから成る場合は, リボンの幅に平行に伸長する長繊維の集合体から成り,複数のストラン ドから成る場合は,「所与の幅の層を製造するために寸法取りされる」 ストランドの集合体(各々が長繊維の集合体から成る)から成ること(【0 027】,【0028】,【0030】,図1及び2),2)「一般に, 炭素ストランドの場合,1,000から80,000本の長繊維を含み, 12,000から24,000本の長繊維を含むのが有利である」こと (【0029】),3)「特に,リボンが複数のストランドの一方向層か ら成る場合,ストランドは,接近して配置」され,「リボン作製の前に, 幅の標準偏差が最小で,一方向層の全幅を一定にするように調整する場 合,層の幅は,材料中のいかなる間隔(英語で「gap」)又は重なり 部分(英語で「overlap」)をも最小にし,さらに回避すること によって調整する」こと(【0028】),4)「ストランド(単数又は 複数)」は,「寸法合わせの段階」の前に拡幅器によって幅が拡幅され (【0030】,図6),「寸法取り段階」(寸法合わせの段階)では, 「所与の幅の開口部,特に,ローラーに切れ込む平底の溝の形状にある 開口部とすることができる寸法取り器」,又は「1つ又は複数のストラ ンドをベースにした単一のリボンの場合における,2個の歯の間の開口 部の寸法取り器」,又は「図7に示すように,並行して複数のリボンを 作製する場合における,複数のストランドに寸法取りをする開口部を規 定する寸法取りコームの寸法取り器」上で,「層又はストランドを通過 させることによって行われ」ること(【0031】,図7),5)「複数 のストランドからなる層を作製する場合,実際,厳密に言えば,層の幅 の寸法取りは外側の2本のストランド上においてのみ行われ,他のスト ランドは拡幅ユニットの前方に配置されたコームにより案内され,その 結果,層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない」こと(【00 31】),6)「炭素ストランド又は複数のストランド1は,クリール1 01に装着された炭素スプール100から巻き戻され,コーム102を 通過し,ガイドローラー103によって機械の軸中に誘導」され,「炭 素ストランドは,次に,加熱バー11及び拡幅バー12により拡幅され, 次に,寸法取り器で寸法取りをされ,所望の幅を有する一方向層が得ら れる」こと(【0038】,図5)の記載がある。 これらの記載事項によれば,本件明細書には,「本発明」の実施の形 態として,1つのストランド(長繊維の集合体)又は複数のストランド (各々が長繊維の集合体)から成る「リボン」を作製するに当たり,1 つ又は複数のストランドを,拡幅バーにより幅を拡幅し,次いで,拡幅 したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器(ローラーに 切れ込む平底の溝を有する寸法取り器,寸法取りコーム,又は2個の歯 を有する寸法取り器)上を通過させることによって,所望の幅を有する 一方向層が得られること,これにより一方向層の層の幅は,材料中のいかなる間隔又は重なり部分をも最小にし,さらに回避することによって 調整することができ,その結果,層の内側のストランド間に緩い空間が 存在しないことの開示があることが認められる。 そして,複数のストランドの集合体(各々が長繊維の集合体)が,「接 近して配置され,間隔又は重なり部分をも最小にし,さらに回避する」 とは,「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから,「複数 のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして,「複数の ストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解すること ができる。
そうすると,訂正事項2に係る訂正は,本件明細書のすべての記載を 総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術 的事項を導入するものではないものと認められるから,本件特許明細書 等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって,これと異なる本件決定の判断は誤りである。
(ウ) これに対し被告は,1)本件明細書には,「拡幅器,次いで寸法取り 器に,複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は 長繊維間に間隔が存在しない」ようにするという事項についての直接的 ないし明示的な記載は存在しない,2)本件明細書において「複数のストランド」を通過させる「寸法取り器」に相当する構成は,【0039】\n及び図7に示されているものにほかならず,これら複数のストランドの 間には間隔が存在する,3)本件明細書の【0028】の記載は,「複数 のストランド又は長繊維」について「間隔が存在しない」ことを記載す るものではないため,本件特許明細書等の記載を総合しても,事項Aを 導くことができるとはいえず,訂正事項2(請求項1)に係る訂正は, 新規事項の追加に当たる旨主張する。 しかしながら,上記1)の点については,本件明細書に直接的な記載は ないが,前記(イ)のとおり,複数のストランドの集合体(各々が長繊維 の集合体)が,「接近して配置され,間隔又は重なり部分をも最小にし, さらに回避する」とは,「間隔が存在しない」ことと同義であると解さ れるから,「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」こと についての開示があるものと認められる。 次に,上記2)の点についてみると,図7は,「単一のストランドをベ ースにして複数のリボンを同時に作製する場合」(【0025】)を示 した図であり,図示されているのは,「単一のストランドから成る複数 のリボン」であって,複数のストランドではないから,複数のストラン ドの間に間隔が存在することを示すものではない。 また,本件明細書の【0039】の「複数のリボンを同時に製造する ことも同様に可能であり,その場合,リボンを構\成する各ストランド又 はストランドの集合体は,必要ならば拡幅され,個々に寸法取りがなさ れ,切断を可能にするために各ストランド間に十\分な間隔を置き,異な るリボンが互いに間隔をあけて配列される。ストランドと間隔を覆う単 一の不織材料が,次に,図8に示すように,リボンの各面上で全てのリ ボンと結合される。次に,図8に示したような機器,及び平行で,リボ ンの幅ごとに間隔をあけられ片寄らされた切断器120の複数(図示し た例では2つ)のラインを用いて,切断間に不織材料の屑を生じることなく各リボンの間で切断を優先的に行うことができる。」との記載中の 「各ストランド間に十分な間隔を置き」とは,複数のリボンを同時に製\n造する場合に,複数のラインを用いて各リボンと結合した不織材料の切 断を可能にするために,各リボンが互いに間隔をあけて配列されること\nを意味するものであり,リボンを構成するストランドそのものについて\n述べたものではない。 さらに,上記3)の点については,前記(イ)のとおり,本件明細書の【0 028】の記載は,リボンが複数のストランドの一方向層から成る場合 に,当該ストランドが接近して配置され,リボン作製の前に,ストラン ド間の間隔が存在しないように調整することが記載されているものと 認められる。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.03.28
平成27(ワ)4292 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月28日 大阪地方裁判所
「共同不法行為が成立するためには,各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や,各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など,各侵害者に,他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして,例えば,製造業者が小売業者に製品を販売し,これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は,極めて一般的なものであり,製造業者と小売業 者双方が,このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても, これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると\nはいえない。
・・・
被告アンプリーは,被告ネオケミアから被告製品8を仕入れ,これを被告リズ ムに転売していたところ,被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており,その中で被告製品8を仕入れることになり,被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった(乙B12の 1)。これに対し,被告アンプリーは,OEMメーカーではあったが,被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し,販路として育成していこ うと考え,被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし,被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る(乙B13の1,弁論の全趣旨)。そして,本件訴訟では,被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり,被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる(以上につき弁論の全趣旨)。そして,被告リズムによる売上額は 3億円を超えており,被告アンプリー自身の売上額も1億円を超えており,他の被 告の他の製品の売上額と比較しても,桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは,以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され,両社は相互に利用補充しながら,被告製品8 の製造,販売をしてきたということができる。したがって,両社の行為には,客観 的に密接な関連共同性があったといえ,共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し,被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると,被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの,被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品(被告製品1,3,4及び15)を 製造するなどし,被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば,被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし,同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より,被告製品8に関し,被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> サポート要件
>> その他特許
>> 間接侵害
>> 賠償額認定
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成30(行ケ)10076 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月13日 知的財産高等裁判所
被告は,原告の主位的主張につき,審判段階で審理の対象とされたものではなく 本件審決の違法事由として主張できない旨主張する。 特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては,審判で審理判断されなかった 公知事実を主張することは許されないが(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同5 1年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁),審判において審理判断され た公知事実に関する限り,審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審 決と異なる主張をすることは,それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実と の対比の枠を超えるということはできないから,取消訴訟においてこれらを主張す ることが許されないとすることはできない。 本件特許の特許権者である原告は,もとより審判で審理判断されなかった公知事 実を無効原因として主張するものではなく,審判において審理判断された公知事実 と審判の対象とされた発明との相違点について本件審決と異なる主張をするにすぎ ないものであって,これを許されないものとすべき事情はない。 したがって,この点に関する被告の主張は採用できない。
(ウ) 原告の主位的主張について
a 原告は,本件各発明の本質は,豆乳発酵飲料について,pHが4.5未満であり,ペクチンの添加量の割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質 量%に対して20〜60質量%の範囲にあり,かつ,粘度が5.4〜9.0mP a・sの範囲にあるという構成を採用する場合に,タンパク質成分等の凝集の抑制\nと共に,酸味が抑制され,後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が得られ るところにあるから,相違点1−1〜1−4に相当する構成は互いに技術的に関連\nしており,これらを1つの相違点1−Aとして認定すべきであるなどと主張する。 b しかし,本件明細書によれば,本件各発明は,タンパク質成分等の凝集を抑 制するという効果を奏する点では共通するものの,ペクチンの添加量の割合が30 〜60質量%の場合(本件発明6)はこれに加えて「後に残る酸味が低減され,か つ口当たりが滑らかな」ものとなるとの効果を奏し(【0019】),30〜50 質量%とされた場合(本件発明7)は「後に残る酸味が低減されるとともに,酸っ ぱい風味が抑制され,また口当たりがより一層滑らかになる」との効果を奏するこ と(【0020】)が記載されている。また,こうした記載が先行するにもかかわ らず,【発明の効果】としては,「タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵 飲料の提供が可能」,「タンパク質等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の製造が可\n能」といった点が挙げられるにとどまる(【0024】)。これらの記載に照らす\nと,酸味が抑制され,後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果は,本件各発 明に共通する効果とは必ずしも位置付けられていないものということができる。 他方,官能評価試験の結果,「ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの\n割合が60質量%〜0質量%」の範囲では,「酸っぱい風味」及び「後に残る酸味」 の評点がいずれも低く,「酸味が抑制されていた。」,「後味がより優れていた。」 との評価がされている(【0080】,【0081】)。これらの記載によれば, 上記各効果は本件各発明に共通し,そのうち特に優れた効果を奏するものを本件発 明6及び7として取り上げたと理解する余地はあり得る。もっとも,試験結果に係 る上記分析は,本件明細書の記載上,本件各発明の効果の記載(【0024】)に は反映されていない。そして,本件明細書において各評価項目の評価基準,評価手 法等が明らかにされていないことや,試験結果の数値のばらつきを考慮すると,前 記のような理解の合理性ないし客観性には疑問がある。 このように,本件各発明の効果に関しては,本件明細書の内部において不整合が あるといわざるを得ず,原告の上記主張はその前提自体に疑問がある。
c その点を措くとしても,タンパク質成分等の凝集抑制の効果について,本件 明細書によれば,請求項2,【0011】及び【0072】に記載された試験方法 により沈殿量を評価した場合の沈殿量が0cm超かつ11cm未満にある場合,タ ンパク質成分等の凝集がより抑制されると説明されている(【0011】,【00 12】)。また,表4及び図3には,pH4.3及び4.5それぞれの場合におい\nてペクチン添加量の割合を変化させた豆乳発酵飲料の沈殿量を示す実験結果が記載 されているところ,沈殿量が0cm超かつ11cm未満を満たさないものはペクチ ン及び大豆多糖類を共に含まないサンプルNo.1(pH4.3及び4.5),大 豆多糖類のみを含むNo.12(pH4.3及び4.5),ペクチンを10質量% で含むNo.11(pH4.3及び4.5)に止まり,ペクチンを20〜100質 量%で含むNo.2〜No.10は,pHの高低に依拠することなくタンパク質成 分等の凝集の抑制効果を奏することが示されている。 この点に鑑みると,タンパク質成分等の凝集の抑制効果につき,ペクチン添加量 の割合が20〜60質量%の範囲内にあることやpHの高低との関連性を見出すこ とは,必ずしもできない。 また,本件明細書によれば,pH4.5の場合でも,No.2〜No.10ではペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによりタンパク質成分等の凝集の 抑制効果があるとされているところ(【0076】),このうちペクチンを50〜 20質量%含むNo.7〜No.10は,7℃における粘度が5.4mPa・s未 満である(表3及び図2)。この点に鑑みると,タンパク質成分等の凝集の抑制効\n果と5.4〜9.0mPa・sの粘度範囲との間に何らかの関連性を見出すことは できない。 以上によれば,タンパク質成分等の凝集の抑制効果は,ペクチン添加量,pH及 び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは 認められない。
d 酸っぱい風味,後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの効果について,pH を4.3で固定した場合である表5及び図4の実験結果によると,酸っぱい風味は,\nペクチンと大豆多糖類を併用したサンプルのうち,おおむね,ペクチンのみを含むNo.2で酸っぱい風味が強く,大豆多糖類の量が増えるに従いこれが低減される 傾向がうかがわれ,No.6〜No.12(ペクチンの割合が60〜0質量%)に つき「酸味が抑制されていた」との評価がされ,中でもNo.7〜No.10(ペ クチンの量が50〜20質量%)で特に抑制されているとの評価がされている (【0080】,図4)。他方,ペクチンを60質量%含むNo.6は,大豆多糖 類のみを含むNo.12やペクチンを10質量%含むNo.11よりも酸っぱい風 味が強いとの評価がされている(【0080】)。 また,後に残る酸味の点では,ペクチンを60〜0質量%で含むNo.6〜No. 12がより優れていると評価され(【0081】,表5,図5),口当たりの滑ら\nかさの点では,ペクチンを60〜30質量%で含むNo.6〜No.9が優れてい ると評価されている(【0082】,表5,図6)。もっとも,ペクチンのみを含\nむNo.2も,後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの両面でこれらの範囲内にあ る評点を得ている。また,口当たりの滑らかさの点では,ペクチンを20質量%含 むNo.10は口当たりの滑らかさの評点が低く,逆に,大豆多糖類のみを含むN o.12は口当たりの滑らかさで優れているとされる上記サンプルの数値の範囲内 に含まれる。 このように,pH4.3の場合の官能評価の結果からも,酸味の抑制,後に残る\n酸味の低減,口当たりの滑らかさに係る効果は,ペクチンと大豆多糖類を併用しな い場合やペクチンの添加量が20〜60質量%から外れる場合でも得られることが示されているから,これらの効果は,pH,粘度及びペクチン添加量の全てが請求 項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。
e このほか,本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較 対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると,本件明細書からは,本 件各発明につき,相違点1−1〜1−4に係る構成を組み合わせ,一体のものとし\nて採用したことで,タンパク質成分等の凝集の抑制と共に,酸味が抑制され,後に 残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成30(行ケ)10023 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月14日 知的財産高等裁判所
被告は,本件決定は,本件出願前に販売されていた日本発条製の商品「ニ ッパレイEXT」と,甲5のカタログ記載のニッパレイEXTの物性値,甲 4及び甲5のカタログ記載のニッパレイEXGの物性値及び日本発条に対す るニッパレイEXTに関する問合せの回答結果に基づいて本件公知発明を認 定したものであり,その認定に誤りはない旨主張するので,以下において判 断する。
ア ニッパレイEXTの構造について\n
被告は,本件決定は,本件明細書の「実施例2」記載のニッパレイEX Tが「非発泡のポリエチレンテレフタレート(PET)シート(厚さ50 μm)上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シ ート」(【0106】)という構造を有していることを,甲5のカタログ\nを参照し,日本発条に問い合わせて確認して認定したものであり,本件決 定の認定に誤りはない旨主張する。 しかしながら,当業者は,本件出願前に,本件出願後に公開された本件 明細書に接することはできないから,ニッパレイEXTが本件明細書の記 載のとおりの構造を有しているかどうかを確認することはできない。\nまた,本件においては,本件決定の合議体が,本件決定をするに当たり, 日本発条に対してどのような方法で問合せをし,どのような回答が得られ たのか,その問合せ方法が,行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者 でも採り得る通常の方法であることを認めるに足りる証拠はない。もっと も,被告が本件訴訟提起後に日本発条にした問合せに対する同社の回答を 記載した本件回答書(乙2の1)には,ニッパレイEXTは,「PETの 上にEXGを一体発泡させたものがEXTです。(厚さは違いますが)」 との記載がある。この記載によれば,ニッパレイEXTは,上記構造を有\nしているものと認められるが,本件回答書の記載事項は被告が本件出願後 に取得した情報であって,一般の第三者が本件出願前に知り得た情報であ るとは直ちにはいえない。 加えて,前記(1)ウ認定のとおり,甲5のカタログには,ニッパレイEX Tや貼付されたサンプルの具体的な構\造についての記載がないのみならず, 当業者が,貼付されたサンプルを視認し,又は自ら測定することにより,\nニッパレイEXTの上記構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はなく,\nましてやニッパレイEXTが,PETフィルム上にニッパレイEXGが積 層一体化されてなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足り る証拠はない。 以上によれば,被告主張の本件決定における上記認定手法は相当とはい えず,本件においては,ニッパレイEXTが「非発泡のポリエチレンテレ フタレート(PET)シート(厚さ50μm)上にポリウレタン系樹脂発 泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有しているこ\nとが本件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めるに足りる証拠 はない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
イ ニッパレイEXTの物性値について
(ア) 被告は,本件決定は,ニッパレイEXTの物性値のうち,「引張強 さ」,「伸び」及び「ショアA硬度」については,甲5のカタログに記 載がないが,ニッパレイEXTは,ニッパレイEXGの片面に50μm 厚のPETフィルムを沿わせて構成しただけのものと認められるので,\n甲5のカタログ記載のニッパレイEXGの「引張強さ」,「伸び」及び 「ショアA硬度」と同じであるとみて差し支えないと考え,ニッパレイ EXGの各数値に基づいて,本件明細書の「表1」記載のとおりである\nことを確認して認定したものであり,本件決定の認定に誤りはない旨主張する。 しかしながら,前記ア認定のとおり,当業者が,本件出願前にニッパ レイEXTが,PETフィルム上にニッパレイEXGが積層一体化され てなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足りる証拠は ない。 また,仮に被告が主張するように当業者がニッパレイEXTの上記構\n造を知り得たとしても,前記アのとおり,当業者は,本件出願前に,本 件出願後に公開された本件明細書に接することはできないから,ニッパ レイEXTが本件明細書の記載のとおりの物性値を有していることを 確認することはできない。 かえって,甲5のカタログに接した当業者においては,ニッパレイE XGについては6項目の物性値の全てについて記載があるのに,ニッパ レイEXTについては,6項目のうち,「引張強さ」,「伸び」及び「A 硬度 Shore−A」が空欄となっているのは,これらの物性値は測 定できないか,あるいはニッパレイEXGの物性値とは異なるものであ ると認識するというべきである。また,ニッパレイEXGのようなポリ ウレタン系樹脂発泡シートはスポンジ状で柔軟な性質を有するのに対し,PETフィルムは結晶性樹脂であるため強靭性を有し,各種ベース フィルムとして用いられること,異なる物性の材料を積層した積層体は, その構成部材の性質や状態によって全体としての物性が変化し得るも\nのであることは,本件出願当時の技術常識であったものと認められる (甲26)。かかる技術常識を踏まえると,甲5のカタログに接した当 業者においては,ニッパレイEXTの「引張強さ」,「伸び」及び「シ ョアA硬度」については,ポリウレタン系樹脂発泡シートであるニッパ レイEXGの各数値と同じ値であることを理解するものとはいえない。 以上によれば,本件決定におけるニッパレイEXTの物性値の「引張 強さ」,「伸び」及び「ショアA硬度」の各数値の上記認定手法は相当 とはいえず,これらの各数値が,甲5のカタログ記載のニッパレイEX Gの値と同じ値であることが,本件出願時に公然知られ得る事項であっ たと認めることはできない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告は,ニッパレイEXTの物性値のうち,甲5のカタログに記載 のない「引張強さ」,「伸び」及び「ショアA硬度」については,当業 者が,日本発条に問い合わせること,カタログに貼付されたサンプルを\nJIS規格等に従って測定すること,日本発条が顧客に製品の納品の際 に提供する「製品検査成績表」を同社から取得することなどにより,極\nめて容易に確認することができるから,公然知られ得る状態にある事項 であり,現に被告は日本発条に対して再度の問合せを行い,日本発条から本件回答書(乙2の1)及び本件データシート(乙3)を得た旨主張 する。 しかしながら,前記アで説示したとおり,本件回答書の記載事項は被 告が本件出願後に取得した情報であって,一般の第三者が本件出願前に 知り得た情報であるとは直ちにはいえないし,また,その問合せ方法が, 行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法 であることについての立証はない。 また,本件回答書(乙2の1)は,甲5のカタログの「引張強さ」, 「伸び」及び「ショアA硬度」の3項目に値が記載されていない理由と して,「PETが一体であるため測定できないからです。」と回答して いること,本件データシート(乙3)には「EXTはペットサポートタ イプの為,引張強さ,伸びの物性は測定不能となります。」との記載があることに鑑みれば,当業者が日本発条に問い合わせたとしても,ニッ\nパレイEXTの「引張強さ」,「伸び」及び「ショアA硬度」を容易に 確認することができたものと認めることはできない。 さらに,甲5のカタログに貼付されたサンプルをJIS規格等に従っ\nて測定した場合に,ニッパレイEXTとニッパレイEXGの「引張強さ」, 「伸び」及び「ショアA硬度」が同じ値となることを認めるに足りる証 拠はない。同様に,日本発条が顧客に製品の納品の際に提供する「製品 検査成績表」(ニッパレイEXGについては,甲38の別紙4))を同社 から取得できたとしても,ニッパレイEXTの物性値の「引張強さ」, 「伸び」及び「ショアA硬度」が,甲5のカタログ記載のニッパレイE XGの値と同じ値であることが本件出願時に公然知られ得る事項であ ったことを認めることはできない。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
ウ まとめ
以上のとおり,ニッパレイEXTが「非発泡のポリエチレンテレフタレ ート(PET)シート(厚さ50μm)上にポリウレタン系樹脂発泡シー トが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることが本\n件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めることはできない。ま た,仮にニッパレイEXTの上記構造が公然知られ得る状態にあったとし\nても,ニッパレイEXTの物性値のうち,「引張強さ」,「伸び」及び「シ ョアA硬度」が,甲5のカタログ記載のニッパレイEXGの値と同じ値で あることが,本件出願前に公然知られ得る状態にあったものと認めること はできない。 したがって,本件決定認定の本件公知発明のうち,少なくとも「引張強 さ」,「伸び」及び「ショアA硬度」の認定に誤りがあるというべきであるから,本件決定における本件公知発明の認定は誤りである。
(3) 小括
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件決定は,公 知発明の認定を誤り,その結果本件発明3と本件公知発明との一致点の認定 を誤り,相違点を看過したことが認められる。 したがって,本件発明3は,本件公知発明及び甲7(本件決定・引用文献 1)に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた とした本件決定の進歩性の判断は誤りである。同様に,本件決定における本 件発明3の特定事項を全て含む本件発明4の進歩性の判断も誤りである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成30(行ケ)10121 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年3月12日 知的財産高等裁判所
(1) 複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の\n各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不\n可分的に結合しているものと認められないときには,その構成部分の一部を抽出し,\n当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される場合が あり,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識\nとして強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出 所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成\n部分の一部だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される(最 高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻 12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法 廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20 年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 以下,上記判断枠組みに沿って本件商標について,「キリン」の部分を要部として 抽出することができるかどうかについて検討する。
(2) 本件商標は,前記第2の1のとおり,本件指定商品を第31類「とうもろ こし」とするもので,その構成は,「キリンコーン」の片仮名を茶色で縁取りし,そ\nの内側を黄色で表してなるもので,「キリンコーン」の文字が,同一の書体,色彩で\n横一連に表示されたものである。\nもっとも,1)本件商標の構成中,「コーン」の文字部分が「とうもろこし」の意味\nを有する英語である「corn」 の読みを片仮名で表したものであること(甲9〜\n12,44,45),2)「キリン」の文字部分が,「(a)中国で聖人の出る前に現れ ると称する想像上の動物。(b)最も傑出した人物のたとえ。(c)ウシ目キリン科 の哺乳類。」との意味を有していること(乙24),3)「キリンコーン」が特段の意 味を有しない造語であることからすると,本件商標は,「キリン」と「コーン」とを 結合した結合商標と理解することができるものである。 また,上記のように「コーン」が本件指定商品である「とうもろこし」の意味を 有する英語である「corn」 の読みを片仮名で表したものであることは,わが国\nにおいても広く知られていること(甲44,45,弁論の全趣旨)からすると,本 件指定商品との関係では,本件商標の構成中,「コーン」の文字部分は,本件指定商\n品そのものを意味するものと捉えられ,その識別力は低いものといえる。 他方で,上記のような意味を有する「キリン」は,本件指定商品との関係で,「コーン」よりも識別力が高く,取引者,需要者に対して強く支配的な印象を与えると いうべきである。 そうすると,本件商標の「キリン」の文字部分と「コーン」の文字部分とが,分 離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している とは認められず,本件商標から「キリン」の文字部分を要部として観察することは 許されるというべきである。
(3) 被告は,1)その構成からして本件商標を「キリン」と「コーン」に区切っ\nて称呼することは明らかに不自然であること,2)「コーン」という用語は,特に食 品業界においては,「スイートコーン」などのように,「○○コーン」,「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている実情があることからすると, 本件商標に接した需要者は,これを一体の商標として認識し,称呼すると主張する。 上記1)について, 色彩で横一連に表\n示されたものであるが,「キリン」と「コーン」を統合したものと理解されるので あって,分離して観察することができるものである。 上記2)について,被告が指摘する各例は,いずれも「コーン」と他の語が結合さ れることによって,「○○コーン」や「コーン○○」が,それ自体として,特定の 意味を有する一つの語として機能しているものである。他方,本件商標「キリンコ\nーン」は,前記のように造語であってそれ自体としては一つの語として特段の意味 を有しないものであるから,それらの例をもって本件商標が一体として認識,称呼 されるとはいい難いところである。 以上からすると,被告の上記主張は採用することができず,前記(2)の判断は左右 されない。
2 本件商標と引用商標の類否について
(1) 本件商標から要部である「キリン」の文字部分を抽出した場合,同部分か らは「キリン」との称呼が生じるとともに,「中国で聖人の出る前に現れると称する 想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」との観念が生じる。 この点について,本件審決は,本件商標が茶色と黄色で表示されていることから\nすると,「キリン」の文字部分は「ウシ目キリン科の哺乳類」のみを表したものとす\nる。しかし,「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」の色彩について, これがはっきりと定まっているわけではないことからすると,本件商標の構成中の\n「キリン」の文字部分から「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」との観念が生じないとはいえない。 (2) 引用商標は,別紙のとおりの構成からなるものであり,いずれからも本件\n商標と同じ「キリン」との称呼が生じる上,引用商標1〜4,6,7からは「中国 で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」 との観念が生じ,引用商標5からは「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上 の動物」との観念が生じるから,本件商標と引用商標を観念で区別することはでき ない。 また,「キリン」の片仮名を縦又は横に記載した引用商標1,2,6と本件商標と は,「キリン」の文字部分の色彩や書体に違いはあるものの,本件商標の「キリン」 の文字部分とは,「キリン」の文字は同じであるから,外観上,類似するものといえ る。 以上に加え,本件指定商品である第31類「とうもろこし」の需要者に一般消費 者が含まれることも併せて考慮すると,本件商標と引用商標は,出所について誤認 混同を生ずるおそれがある類似する商標というべきである。 3 被告の主張する取引の実情について 被告は,1)実店舗において,「かに太郎」との屋号が表示されており,実店舗にお\nける販売では,近隣にある旭山動物園にちなんで名付けられた本件商標を付した「と うもろこし」が,同様に上記動物園にちなんで名付けられた「ライオンコーン」な どと共に販売されていること,2)インターネットにおける販売でも,同様に「かに 太郎」との屋号が用いられて被告の氏名等がウェブサイトに記載されるなどしてい る上,本件商標を付した「とうもうろこし」が,「ライオンコーン」などと共に販売 されたり,「旭山動物園キリンコーン」などと記載されたりしていて,「とうもろこし」の生産者,販売者が原告であると誤認混同するおそれはないと主張する。 しかし,被告の上記主張は,現在の販売形態について主張するものにすぎず,一 般的,恒常的な事情とまではいい難いものである。 また,「かに太郎」との屋号や被告の氏名等が表示されていたしても,販売されて\nいる商品について,その生産者・製造者と消費者への最終的な販売者が異なること があり得ることからすると,そのことをもって誤認混同のおそれが生じなくなるも のではない。 さらに,「旭山動物園キリンコーン」との表示がされている点や本件商標を付した\n「とうもろこし」が,「ライオンコーン」などと共に販売されている点など被告が主張する点を考慮したとしても,各ウェブサイトにおいて,写真中に「キリンコーン」, 「送料無料」,「10本」とのみ表示した「とうもろこし」の写真が掲載されている\nこと(乙3の1枚目,乙16の2枚目,乙23の2枚目)や本件指定商品の需要者 が一般消費者であって,かつ本件指定商品が比較的安価なものであることからする と,消費者が注意深く観察せずに,本件商標が付された商品を購入することもあり 得るものといえることからすると,被告が主張する点により直ちに誤認混同のおそ れが生じなくなるとはいえないところである。 以上からすると,被告の上記主張は採用することができず,前記2の認定判断を 左右するものではない。 なお,被告は,本件商標登録の出願をした経緯や原告が「とうもろこし」を生産・ 販売していないこと,原告が本件商標と同じ商標を出願して商標登録を得たことを 主張するが,これらは,何ら前記2の認定判断を左右するものではない。
4 商品の類否について
(1) ア 本件指定商品は,「第31類 とうもろこし」であるところ,商標法施 行令別表(以下「政令別表\」という。)は,第31類を「加工していない陸産物,生 きている動植物及び飼料」と定めている。そして,本件商標登録出願時の平成28 年経済産業省令第109号による改正前の商標法施行規則別表(以下「旧省令別表\」 という。)は,第31類に属するものを1から15に分類し,そのうちの1で「1 あ わ きび そば ごま とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし」として,「とうもろこし」を他の雑穀や穀物と並べて記載していたが,「10 野菜」には,とうも ろこしは記載されていなかった。 また,本件商標登録出願時における特許庁の旧審査基準(甲32)では,「とうも ろこし」は,「あわ きび そば ごま ひえ 麦 籾米 もろこし」,「豆」,「米 脱 穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」と同一の類似群(33A01)に属するとされ ていた。 これらのことからすると,旧省令別表第31類1にいう「とうもろこし」は,「穀\n物」としての「とうもろこし」であったと解するのが相当であり,「第31類 とう もろこし」とする本件指定商品の範囲は,少なくとも「穀物」としての「とうもろこし」に及ぶものである。
イ また,商標法施行規則別表における細分類の表\示は飽くまで例示である ところ,政令別表は,前記のとおり,本件指定商品が含まれる第31類を「加工し\nていない陸産物,生きている動植物及び飼料」と定めており,本件商標の出願後に 施行された平成28年経済産業省令第109号が,商標法施行規則別表の第31類\n1中の「とうもころし」を「とうもろこし(穀物)」とし,同類10「野菜」に「と うもろこし(野菜)」を加えたように,第31類の中には,「穀物」としての「とう もうころし」と「野菜」としての「とうもろこし」の双方が含まれるということが できる。このことに照らすと,本件指定商品「第31類 とうもろこし」は,「穀物」 としての「とうもろこし」だけでなく,「野菜」としての「とうもろこし」も含むと 解することが相当である。本件商標に類似群コードとして「33A01」が付され ていることはこの認定を左右しない。
ウ 以上の検討からすると,本件指定商品の範囲には,「野菜」としての「と うもころし」及び「穀物」としての「とうもろこし」のいずれもが含まれると解さ れるのであり,これを前提にして商品の類否の判断をするのが相当である。
エ 被告は,1)従前から「野菜」である「とうもろこし」を生産,販売して おり,「穀物」である「とうもろこし」は生産,販売したことがないし,今後も生 産,販売するつもりはないこと,2)被告が,「野菜」としての「とうもろこし」に 本件商標を使用する意図で,「野菜」としての「とうもろこし」の資料とともに本件商標の出願をしたこと,3)類似群コードが特許庁により付されたものであることな どから,本件指定商品は,「野菜」としての「とうもろこし」と解すべきであると主 張する。 しかし,本件指定商品は「第31類 とうもろこし」であるから,前記ア〜ウの とおり解されるのであって,上記1)〜3)の事情は,この認定を左右するものではな い。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(2)ア 前記(1)を踏まえて,本件指定商品と引用商標の各指定商品が類似する かどうかを検討するに,指定商品が類似のものであるかどうかは,商品自体が取引 上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく,それらの商品 が通常同一営業主により製造・生産又は販売されている等の事情により,それらの 商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一の営業主の製造・生産又は販売に かかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には,たとえ, 商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても,類似の商品に当 たると解するのが相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月 27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。
イ 本件指定商品の範囲に含まれる「穀物」としての「とうもろこし」と, 引用商標1の指定商品中の「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」と引用商標 4の指定商品中の「豆」とは,いずれも「穀物」に属するものであって,その生産 者,販売者が一致することが通常あり得るものと認められるし,その需要者にはい ずれも一般消費者が含まれるものである。 したがって,それらの商品に同一又は類似の商標が使用されたときには,同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができ,本 件指定商品と,引用商標1の指定商品中の「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大 麦」及び引用商標4の指定商品中の「豆」は,商標法4条1項11号にいう類似の 商品に当たるというべきである。
ウ 次に,引用商標2の指定商品中の「野菜(「茶の葉」を除く。)」には,「野 菜」としての「とうもろこし」が,引用商標2,4,5の指定商品中の「冷凍野菜」 には「冷凍とうもろこし」が,引用商標4〜7の指定商品中の「加工野菜」には, 「加工済みスイートコーン」のような「加工済みのとうもろこし」が,引用商標3, 5,6の指定商品中の「穀物の加工品」には,「炒ったとうもろこし」がそれぞれ含まれるものと認められる。 本件指定商品には「とうもろこし(野菜)」が含まれているから,本 件指定商品は,この点において,引用商標2の指定商品中の「野菜(「茶の葉」を除 く。)」と同一である。
b また,本件指定商品である「とうもろこし(野菜)」と引用商標2, 4,5の指定商品中の「冷凍野菜」に含まれる「冷凍とうもろこし」とは,同じ「野 菜」としての「とうもろこし」からなるものであって,生産者・製造者,販売者が 同一の場合もあり得るものと認められる。 したがって,本件指定商品である「とうもろこし(野菜)」と引用商標2,4,5 の「冷凍野菜」に同一又は類似の商標が使用されたときには,同一の営業主の生産・ 製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから,本件 指定商品である「とうもろこし(野菜)」と引用商標2,4,5の指定商品中の「冷 凍野菜」は,商標法4条1項11号にいう類似の商品に当たるというべきである。 本件指定商品である「とうもろこし(穀物)」と引用商標2,4,5の 指定商品中の「冷凍野菜」,引用商標4〜7の指定商品中の「加工野菜」,引用商標 3,5,6の指定商品中の「穀物の加工品」及び引用商標2の指定商品中の「野菜 (「茶の葉」を除く。)」とは,「穀物」か「野菜」か,加工の有無,程度又は方法に ついて差異があるとはいえ,いずれも「とうもろこし」からなるものという点では 変わりがなく,「とうもろこし(穀物)」と引用商標2〜7の上記各指定商品の生産 者・製造者,販売者が一致することもあり得るものと認められる。そして,その需 要者にはいずれも一般消費者が含まれる。したがって,本件指定商品である「とうもろこし(穀物)」と引用商標2〜7の上 記各指定商品に同一又は類似の商標が使用されたときには,同一の営業主の生産・ 製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから,本件 指定商品である「とうもろこし(穀物)」と引用商標2,4,5の指定商品中の「冷 凍野菜」,引用商標4〜7の指定商品中の「加工野菜」,引用商標3,5,6の指定 商品中の「穀物の加工品」及び引用商標2の指定商品中の「野菜(「茶の葉」を除く。)」は,商標法4条1項11号にいう類似の商品に当たるというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成29(ワ)1752 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年2月28日 大阪地方裁判所(26部)
原告は被告が実施義務を負っていることを前提として,それに違反した債務不 履行があると主張している。 確かに,本件契約には,被告の実施義務を定めた条項は設けられておらず,被告 が本件特許の実施に努めることさえも規定されていない。 もっとも,本件契約は専用実施権設定契約であり,被告は本件契約に基づき本件 特許の専用実施権を取得し,本件特許を独占的に実施し得る地位を獲得するのに対 し,原告は本件契約を締結することによって,本件特許を実施することや他の者に 実施許諾することができないにもかかわらず,特許維持費用の支払義務は負うとい う立場に立つことになる。また,本件契約では,イニシャルペイメントが「0円」 と明記され,またランニング実施料の金額も,実施の有無にかかわらず一定額が支 払われる条項とはされず,被告が販売した本件特許権に基づく製品の販売価格に所 定の割合(2ないし5%)を乗じた額とするにとどめられていたから,原告は,被 告が本件特許を実施しないことには,実施料の支払を全く受けられないことになる。 本件契約の当事者である原告と被告が置かれる以上のような状況を踏まえると, 専用実施権者である被告は,本件特許の実施が可能であるのに,それを殊更に実施\nしないとか,その実施に向けた努力を怠るなどということは許されず,信義則に基 づき,本件特許を実施する義務を一定の限度で負うと解すべきである。 もっとも,上述したように,本件契約では被告の実施義務に関係する条項は何ら 設けられず,またランニング実施料の金額も販売価格に一定割合を乗じた額とする にとどめられており,被告としては製品が販売できた場合にのみ実施料の支払負担 が発生するにとどまるというリスク負担を前提に本件契約を締結したものであるか ら,本件特許を実施した製品を製造販売するための努力の程度について被告に過大 な義務を負わせることは相当でない。また,被告は本件特許の製造法によって製造 したしらすを製造販売することによって本件特許を実施することになるが,本件特 許は解凍後真空包装し,加圧加熱処理することをも構成として含むものであり,被\n告はそれを行うための機械を有していなかったから,そのための準備期間が不可避 的に生ずるし,結果的に,商品が消費者に十分受け入れられず,思うように商品が\n販売できないなどという事態も生じ得る。 以上のような本件の事情を考慮すると,被告が本件特許の実施義務を負うといっ ても,本件特許を実施するために必要な事項等を踏まえつつ,その時々の状況を踏 まえ,特許の実施に向けた合理的な努力を尽くすことで足りると解するのが相当で ある。
(3) 被告の実施義務違反の有無
ア 上記(2)のような観点から,被告が本件特許の実施のための努力を怠ったといえるかを検討すると,前記(1)で認定した事実によれば,被告は,平成26年3 月28日に本件契約を締結した後,速やかに,自社ではできないパック詰め作業を 委託する業者を探して,同年5月22日までにはその目途をつけた後,パッケージ 等の製造や,そのデザインを別の業者に依頼し,同年10月末までにその目途をつ けて,製造の準備をほぼ整えたと認められる。また,被告は,以上のような製造に 向けた準備と同時並行で,元々取引のあった愛媛県内のスーパーやデパートに本件 特許の製造法によって製造したしらすの販売を持ちかけたり,P4に対してその販 売の取次を依頼したりし,幅広く本件特許の製造法により製造したしらすを販売す るための交渉等を進めたが,成果は芳しくなく,その後,同年12月までには「婦人画報」への掲載が決まり,平成27年3月には商品の製造を開始し,同年4月頃 に販売された「婦人画報」に「オレの惚れたしらす丼セット」が掲載され,実際に その販売が開始されるに至ったのである。以上のように,被告は,本件契約の締結 後,本件特許の実施に向けた準備を進め,実際に,実施にこぎつけたと認めること ができる(なお,被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反すると認められな いことは前記1で判示したとおりである。)。 イ もっとも,本件契約の締結から商品の製造や販売開始まで1年程度要し ていることから,被告が前記(2)で判示した本件特許の実施のための努力を尽くした といえるかを検討する。
(ア) 確かに,被告代表者自身も陳述書(乙40)において,「準備に思った\nより時間…が掛かりました」と述べているように,製造販売の準備行為に相当の時 間を要しており,さらに早期に商品の製造や販売の準備を整えることができた可能\n性も否定はできない。 しかし,被告は,パック詰め作業をする設備機械を保有していなかったのである し,パッケージ等の製造も他の業者に委託しなければならなかったのであるから, 製造準備を整えるまでに前記のような期間を要したことが,本件特許の実施を不当 に遅延したとはいえない。また,前記認定の経過によれば,被告が実際に被告製品 の製造を開始したのが平成27年3月となったのは,当初の地元のスーパーやデパ ートへの営業が販売価格の面で折り合わず,芳しくなかったが,同年4月頃に販売 される「婦人画報」に「オレの惚れたしらす丼セット」が掲載され,それを見た消 費者に対する販売が相当程度見込まれたからと推認される。そして,被告も営利企 業として事業を営んでいる以上,ある程度まとまった販売が見込まれない段階で商品の製造を開始することは現実的ではないし,信義則上も被告にそれを強いること は相当とはいえないから,被告が結果として,ある程度まとまった販売が見込まれ るに至った同年3月から商品の製造を開始したこと(それまでは本件特許の製造法 によるしらすを製造しなかったこと)が,製造販売への努力を不当に怠ったという ことはできない。
以上によれば,製造販売の準備行為に時間を要したことによって製造開始が遅れ たとまで認めることはできないし,平成27年3月からの製造開始となったことが 被告の努力が足りなかったことによるものと認めることもできない。 また,製造販売を開始した後の販売状況も,決して順調とはいえないものではあ るが,被告は,Smile Circle株式会社以外の取引先にも営業を行って少量ながら取 引をしていることからすると,販路拡大のための努力を不当に怠っていたと認める ことはできない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.03.20
平成30(行ケ)10132 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月7日 知的財産高等裁判所
以上の(1)ア,イから明らかなように,太陽電池モジュールを構成するに際\nして,略円形状の半導体ウエハを切断せずにそのまま用いた太陽電池セルを用いる ことで,材料ロスを少なくし,低コストのものとすることは,本願出願前において 周知の技術であると認められる。 太陽電池パネルにおいて低コスト化を図ることは,一般的な課題といえるのであ って,甲1発明に係る「太陽電池パネル材」においても,低コストのものとするこ とは,当然に要求されるものであるところ,甲1発明の「円形状の太陽電池セル3 0」を得るにあたり,同じ形状を持つ太陽電池セルである,略円形状の半導体ウエ ハを切断せずにそのまま用いた上記周知技術の太陽電池セルを採用することは,当 業者が容易に想到し得ることである。
・・・
原告は,1)本願発明は,ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用\nして流体加熱を可能とする発明は,本質的には,流体加熱を可能\とすることであり, ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して野菜の栽培を可能\とす る発明は,本質的には,野菜の栽培を可能とすることであるから,ウエハ間の空白\n部分から日光を透過させる構成を備える本願発明と甲1発明とは,上記構\成におい て異なる,2)屋根に用いた太陽光パネルにより発電する構成と,屋根に用いた温水\nパネルにより流水を加熱する構成とを一体化するシステム構\成を,周知技術と判断 することには無理があるから,上記システム構成が周知技術であることを理由に,\n当該事項が甲1に記載されているに等しい事項であるとすることは誤りである,3) 甲1において,農業施設の屋根に太陽電池パネル材を用いることは示唆されている としても,ウエハ間の隙間を透過した日光を利用して「野菜の栽培」を可能とすることまで示唆されているとはいえない旨主張する。\nしかし,本願発明の「天窓,縦窓,流体加熱,野菜の栽培を成し得る」の解釈は, 前記3(1)イのとおりであるところ,甲1発明においても太陽電池パネル材を流体加 熱や野菜の栽培の用途に用いることが可能であるから,この点において本願発明と\n相違していない。
なお,乙1(特開2013−2709号公報)には,光透過性を有するソーラー\n発電パネルとソーラー温水パネルを組み合わせたソ\ーラーシステムが,乙2(特開 2004−176982号公報)には,太陽電池パネルの裏面側に通水管を備えた 太陽電池組込み集熱ハイブリッドモジュールが,それぞれ開示されているから,当 業者は,甲1から,甲1発明に係る太陽電池パネル材を使用した建物において,流 水加熱も行い得ることを認識することができ,このことは,甲1発明が,太陽電池 パネル材を流体加熱に用いることが可能である点において,本願発明と相違してい\nないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。 また,甲1には,農業用施設についての記載(【0010】)がある上,乙3(国 際公開第2012/128244号公報),乙4(国際公開第2012/04338 1号公報)及び乙5(特開2012−216609号公報)には,それぞれ,屋根 に太陽光を施設内に導入し得る太陽電池パネルを設けた施設内で,植物を栽培する ことが記載されているから,これらのことは,甲1発明が,太陽電池パネル材を野 菜の栽培に用いることが可能である点において,本願発明と相違していないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.03.20
平成30(行ケ)1007 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
前記(1)のとおり,甲13には,最適化されたナッツ,種子及びナッ ツ油といった複数の供給源による脂肪酸や抗酸化物質,ポリフェノールなど,それ ぞれの栄養素の量を最適化すること(【請求項3】,【0022】)や,異なる供給源 を使用することにより,過剰の場合は有害な特定の植物性化学物質の高濃度での送 達を回避すること(【0031】)が示唆されている。 そうすると,甲13発明において,植物性化学物質を,複数の異なる供給源に由 来するものとすることは,当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(イ)a 原告は,甲13の「ω−3脂肪酸に対して比較的高率のω−6脂肪 酸」,「抗酸化剤及び植物性化学物質[原告注:ファイトケミカル]全般を含む組成 物」という教示,又は,「ファイトケミカルの高濃度での送達が回避される」という 教示は,特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤を まとめて提供する前提で,複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用 することを教示するものではない旨主張する。
原告の上記主張は,本願補正後発明1が「特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で,複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくものであることを 前提とするものであると解されるが,その主張を採用することができないことは, 前記(2)のとおりであるから,原告の上記主張は,理由がない。
b なお,原告は,ω-6 脂肪酸,抗酸化剤及びポリフェノールの含有量 は,食品供給源や,作物,産地によって異なり,複数の異なる供給源に由来する, ω-6脂肪酸及びポリフェノールを含む抗酸化剤の特定の量を維持しながら,異なる 供給源に由来するファイトケミカルを利用することは技術的に困難である旨主張す る。 ファイトケミカルの供給源であって,ω-6 脂肪酸の前駆体であるリノール酸を含 有するピーナッツ油,コーン油,ヒマワリ油等(甲21の【0004】【表1】,【0\n033】【表2−1】,【0034】【表\2−2】)や,ポリフェノールを含有するオリーブ油(甲21の【0084】),アーモンド・クルミ・ペカン・クリ・ピーナッツ 等の抗酸化物質を含有するナッツ類(甲21の【0024】〜【0026】)は,い ずれも当業者によく知られたものである。そして,ポリフェノールは,抗酸化剤の 例である(甲15,弁論の全趣旨)。
また,証拠(甲1,2,13,14,21)によると,供給源そのものや複数の 供給源から製造される組成物に含まれる ω-6 脂肪酸,ポリフェノールの含有量は, それぞれ測定可能であることが認められる。\nそうすると,ω-6 脂肪酸,抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が,供給源によ って異なるとしても,目的とするω-6 脂肪酸,抗酸化剤の配合量とするために植物 由来の栄養素の供給源を適切に組み合わせて各成分の合計量を調節することは,技 術的に困難であるとはいえない。 また,ω-6 脂肪酸,抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が,作物,産地等によ って異なるとしても,それは単一の供給源でも生じ得る問題であって,異なる供給 源を組み合わせる場合に固有の問題ではなく,上記のとおり,供給源のω-6 脂肪酸, ポリフェノールの含有量が測定可能であることからすると,上記認定を左右するも\nのではない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
c 原告の相違点 1 に係るその余の主張は,いずれも,本願補正後発明 1が「特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤をま とめて提供する前提で,複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用す る」との技術思想に基づくことを前提とするものであると解されるところ,前記(2) のとおりであって,採用することができない。
イ 相違点2について
(ア) 前記(1)のとおり,甲13には,甲13発明に係る組成物に抗酸化物 質(【0022】,【0023】,【0031】,【0035】),ポリフェノール(【0023】)が含まれることが示唆されており,ポリフェノールが抗酸化剤であることは,本願出願時における技術常識であった(甲15,弁論の全趣旨)から,甲13発明 に係る組成物において,少なくとも一種の処方物をポリフェノールを含む抗酸化剤 を含むものとすることは,当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(イ) 原告は,「ピーナッツ」は,異なる供給源に由来するファイトケミカ ルを使用した「処方物」ではなく,甲13は,「抗酸化剤」自体を教示しているもの であって,特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤 をまとめて提供することや,当該提供を維持したまま,複数の異なる供給源に由来 するファイトケミカルを使用することを教示するものではないと主張する。 原告の上記主張は,本願補正後発明1が「特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で,複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくことを前提とする ものであると解されるところ,前記(2)のとおりであって,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.03.15
平成30(ワ)19731 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年2月28日 東京地方裁判所
写真は,被写体の選択・組合せ・配置,構図・カメラアングルの設定,シャ\nッターチャンスの捕捉,被写体と光線との関係(順光,逆光,斜光等),陰影 の付け方,色彩の配合,部分の強調・省略,背景等の諸要素を総合してなる一 つの表現であり,そこに撮影者等の個性が何らかの形で表\れていれば創作性が 認められ,著作物に当たるというべきである。 これを本件についてみると,本件写真2は,別紙写真目録2記載のとおりで あるところ,フローリング上にスリッパを履いて真っすぐに伸ばした状態の両 脚とテーブルの一部を主たる被写体とし,大腿部の上方から足先に向けたアン グルで,右斜め前方からの光を取り入れることで陰影を作り出すとともに脚の 一部を白っぽく見せ,また,当該光線の白色と,テーブル,スリッパ及びショ ートパンツの白色とが組み合わさることで,脚全体が白っぽくきれいに映るよ うに撮影されたカラー写真であり,被写体の選択・組合せ,被写体と光線との 関係,陰影の付け方,色彩の配合等の総合的な表現において,撮影者の個性が\n表れているものといえる。したがって,本件写真2は,創作的表\現として,写真の著作物であると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
2 争点2(公衆送信権侵害の成否)
(1) 本質的特徴を感得できるかについて
著作物の公衆送信権侵害が成立するためには,これに接する者が既存の著 作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを要する。\nこれを本件についてみると,証拠(甲3の2,9)及び弁論の全趣旨によ れば,本件画像には,本件写真2の下側の一部がほんの僅かに切り落とされ ているほかは,本件写真2がそのまま用いられていることが認められる。そ して,本件画像は,解像度が低く,本件写真と比較して全体的にぼやけたも のとなっているものの,依然として,上記1で説示した,本件写真2の被写 体の選択・組合せ,被写体と光線との関係,陰影の付け方,色彩の配合等の 総合的な表現の同一性が維持されていると認められる。\nしたがって,本件画像は,これに接する者が,本件写真2の表現上の本質\n的な特徴を直接感得することができるものであると認められる。これに反す る被告の主張は採用できない。
(2) 本件画像アップロードと本件投稿の関係について
ア 前記前提事実(3),証拠(甲3,5,6,11ないし13)及び弁論の 全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 「たぬピク」は,「up@vpic(省略)」宛てに画像を添付したメール を送信すると,当該画像がインターネット上にアップロードされたUR Lが,送信元のメールアドレス宛てに返信され,当該URLを第三者に 送るなどして,当該画像を第三者と共有することができるサービスであ る。
(イ) 本件掲示板を含むたぬき掲示板(2ch2(省略))をスマートフォンで 表示する場合には,「たぬピク」により取得した,画像のURLが投稿されると,当該URLが表\示されるのではなく,当該URLにアップロ ードされている画像自体が表示される仕組みとなっている。これにより,\n当該URLをクリックしなくても,たぬき掲示板上において,他の利用 者と画像を共有することが可能となっている。\n
(ウ) 本件画像は,平成30年3月22日午後11時53分41秒に,「up @vpic(省略)」宛てにメール送信され,本件画像URL上にアップロ ードされた(本件画像アップロード)。
(エ) 本件画像URLは,同日午後11時54分46秒に,被告の提供する インターネット接続サービスを利用して,本件掲示板に投稿された(本 件投稿)。
イ 以上の事実関係を前提に,本件投稿によって公衆送信権の侵害が成立す るか検討する。
まず,本件画像は,前記ア(ウ)のとおり,本件投稿に先立って,インター ネット上にアップロードされているが,この段階では,本件画像URLは 「up@vpic(省略)」にメールを送信した者しか知らない状態にあり,いま だ公衆によって受信され得るものとはなっていないため,本件画像を「up @vpic(省略)」宛てにメール送信してアップロードする行為(本件画像ア ップロード)のみでは,公衆送信権の侵害にはならないというべきである。 もっとも,本件においては,前記ア(ウ)及び(エ)のとおり,メール送信に よる本件画像のアップロード行為(本件画像アップロード)と,本件画像 URLを本件掲示板に投稿する行為(本件投稿)が1分05秒のうちに行 われているところ,本件画像URLは本件画像をメール送信によりアップ ロードした者にしか返信されないという仕組み(前記ア(ア))を前提とすれ ば,1分05秒というごく短時間のうちに無関係の第三者が当該URLを 入手してこれを本件掲示板に書き込むといったことは想定し難いから,本 件画像アップロードを行った者と本件投稿を行った者は同一人物であると 認めるのが相当である。そして,前記ア(イ)のとおり,本件画像URLが本 件掲示板に投稿されることにより,本件掲示板をスマートフォンで閲覧し た者は,本件画像URL上にアップロードされている本件画像を本件掲示板上で見ることができるようになる。そうすると,本件投稿自体は,UR Lを書き込む行為にすぎないとしても,本件投稿をした者は,本件画像を アップロードし,そのURLを本件掲示板に書き込むことで,本件画像の データが公衆によって受信され得る状態にしたものであるから,これを全 体としてみれば,本件投稿により,原告の本件写真2に係る公衆送信権が 侵害されたものということができる。以上の認定に反する被告の主張は採 用できない。
3 小括
以上からすれば,本件投稿により,原告の本件写真2に係る著作権(公衆送 信権)が侵害されたことが明らかであると認められる。また,原告がかかる著 作権侵害の不法行為による損害賠償請求権を行使するためには,被告が保有す る別紙発信者情報目録記載の情報が必要であると認められる。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 公衆送信
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2019.03.14
平成27(ワ)16423 不正競争 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所(46部)
本件鑑定で用いられたソースコードの分析の手法及びその鑑定結果の概要\nは以下のとおりである。(鑑定の結果〔4頁ないし12頁,17頁,24頁ない し27頁〕)
ア 本件鑑定においては,原告の意見等も踏まえ,本件ソースコードのうち1\n14種類のソースファイルが鑑定対象とされ,本件ソ\ースコードのうち一つ または複数のソースコードに対して被告ソ\フトウェアの複数のソースコー\nドを比較すべき場合があることから,300組のソースコードのペアについ\nて,一致点の有無等が判断された。
イ 前記の300組のソースコードのペアについて,類似性や共通性を判断す\nるため,8種類のコードクローン検出(コードクローンとはソースコード中に相互に一致又は類似したコード断片をいう。)を実施した。\n8種類のコードクローン検出の方法の概要は,1)識別子とリテラルのオー バーラップ係数を用いて名前の包含度合いを確認する,2)識別子とリテラル のコサイン係数を用いて名前の一致度合いを確認する,3)識別子とリテラル の部分文字列のオーバーラップ係数を用いて名前の文字並びの包含度合い を確認する,4)識別子とリテラルの部分文字列のコサイン係数を用いて名前 の文字並びの一致度合いを確認する,5)コメントの部分文字列のオーバーラ ップ係数を用いてコメントの文字並びの包含度合いを確認する,6)コメント の文字列のコサイン係数を用いてコメントの文字並びの一致度合いを確認 する,7)キーワードや記号の系列にSmith−Watermanアルゴリ ズムを適用してソースコードの文字並びの一致度合いを確認する,8)前記ア ルゴリズムをソースコードの長さで正規化してソ\ースコードの構造の一致\n度合いを確認するというものであった。
ウ 前記イの8種類のコードクローン検出を実施し,1種類以上の方法で類似 性についての一定の閾値を超えたものを要注意コード・ペアとして取り扱っ た。この要注意コード・ペアは,300組中57組存在した。
エ 前記ウの結果を参考にしつつ,鑑定人が300組全てのソースコードのペ\nアについて目視確認を行い,共通性や類似性が疑われるソースコードのペア\nを選んだ。その結果,原告ソフトウェアのソ\ースファイルと被告ソフトウェアのソ\ースファイルには,1)「GlobalSettings.h」と「S ourceDefault.h」(順に,原告ソフトウェアのソ\ースファイル と被告ソフトウェアのソ\ースファイル。以下,同じ。),2)「GlobalS ettings.cpp」と「SourceDefault.cpp」,3)「S STDB.cpp」と「Mdb.cpp」,4)「AutoLocker.h」 と「SafeLocker.h」,5)「AutoLocker.cpp」と「S afeLocker.cpp」につき,共通性や類似性が疑われる箇所が発見された(類似箇所1ないし5)。
・・・・
鑑定人は,類似箇所1ないし4について原告と被告のソースコードが不自\n然に類似・共通する箇所が存在すると判断し,類似箇所5については原告と 被告のソースコードに類似性や共通性が見られるがその理由が不自然であ\nるとまではいえないと判断した。
・・・
キ 鑑定人は,類似箇所1ないし5について,原告ソフトウェアを参照せずに\n被告らが独自に作成することが可能であるか否かにつき,以下のとおり判断\nした。
類似箇所1について
原告ソフトウェアのソ\ースコードの一部がサンプルで公開されていた などといった外部要因がないことを前提とすれば,原告ソフトウェアと被\n告ソフトウェアの開発者は必ず同一人物である。被告ソ\フトウェアを開発 する際に原告ソフトウェアを参照した可能\性が高いが,参照せずに開発す ることが全く不可能であるとまでは言い切れない。\nもっとも,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアの開発者が同一人物で あり,その人物の記憶を手掛かりとしても,原告ソフトウェアのソ\ースコ ードを参照せずに類似箇所1で見られるような細かい特徴まで一致させ ることは難しいと考えることが自然である。
・・・
類似箇所1ないし3について,本件ソースコードの被告\nらによる使用等があったと認められる。そして,Bが,原告ソフトウェアの開\n発に携わった者の一人であり,被告ソフトウェアについて実際の開発,制作を\n担当したこと(前提事実 )及び弁論の全趣旨から,Bは,被告ソフトウェア\nの開発の際,本件ソースコードの類似箇所1ないし3に対応する部分を使用し\nて被告ソフトウェアを制作等し,もって,類似箇所1ないし3を被告フェイス\nに対して開示し,また,被告フェイスにおいてそれを取得して使用したと認め られる。
類似箇所4について
前記1(1)によれば,類似箇所4については,被告ソフトウェアのデータベー\nスで用いられている52件のフィールドの名前が原告ソフトウェアのデータ\nベースで用いられているものと同じであると指摘されており,被告らもTem plate.mdbの複製について認めていることに照らせば,類似箇所4に ついては,類似箇所1ないし3についてと同様の理由から,Bから被告フェイ スに対する開示及び被告フェイスによるその使用があったと認められる。
・・・
イ 原告ソフトウェアが開発されるに至った経緯や原告ソ\フトウェアの開発 の際のBの勤務の形態等に照らしても,原告ソフトウェアの開発,制作は原\n告の指示に基づきされたといえるものであり,本件ソースコードは原告が保\n有すると認められる。そして,原告ソフトウェアの開発,制作に携わった者\nの一人であるBは,類似箇所1ないし3が本件ソースコードの一部であるこ\nとや,販売用ソフトウェアのソ\ースコードという本件ソースコードの性質や\nその開発等の経緯等から,それが原告が保有する営業秘密であることを認識 できたといえる。 これらを考慮すると,Bが原告ソフトウェアと販売上も競合する被告ソ\フ トウェアを開発,制作するに当たって類似箇所1ないし3を使用したことは原告から示された営業秘密を,図利加害目的をもって被告フェイスに開示し たものと認めることが相当である(不競法2条1項7号)。 被告フェイスは,被告ソフトウェアが原告ソ\フトウェアと同種の製品であ り,字幕データファイル等について互換性を有するという特徴を有するもの であることや,上記のような機能を有する被告ソ\フトウェアの開発を具体的 に行うBが原告ソフトウェアの開発に携わった者の一人であったことは認\n識していたと認められる。これらのことから,被告フェイスは,被告ソフト\nウェアの具体的な開発を委託したBによる被告ソフトウェアの開発過程等\nにおいて違法行為が行われないよう特に注意を払うべき立場にあった。不競 法2条1項8号にいう重過失とは,取引上要求される注意義務を尽くせば容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらずその義務に違反した場合を いうところ,被告フェイスにおいて,前記の事情に照らせば,前記の注意義 務を尽くせば被告ソフトウェアの開発過程等においてBの不正開示行為が\n介在したことが容易に判明したといえ,被告フェイスは,少なくとも重過失 により,原告の営業秘密である類似箇所1ないし3をBから取得し,それら を被告ソフトウェアに用いて販売したと認めるのが相当である(不競法2条\n1項8号)。 Aについて,被告ソフトウェアの開発,制作に当たって,具体的な本件ソ\ ースコードを被告フェイスに開示した事実を認めるには足りないし,その他, Aにおいて,不正競争行為となる事実を認めるに足りる証拠はない。したが って,Aについて,不正競争行為は認められない。
イ 被告らは,類似箇所1ないし3が被告ソフトウェアのソ\ースコードと一致 ないし類似するに至った原因は,Bが,原告ソフトウェアを開発するに際し\nてライブラリの選択等のために独自に自らのパソコンで作成し,そのパソ\コ ンに残っていた簡易な評価プログラムやそのプログラムに含まれる変数定 義部分を被告ソフトウェアの開発の際にも参照したことにあり,そのような\n行為は非難されるべきものではないなどと主張する。しかしながら,同事実関係を裏付ける証拠はない。また,前記の評価プロ グラムは,それが作成,使用されたとしても,その評価の対象となる本件ソ\nースコードの存在を前提として作成,使用されたものと考えられ,変数定義 部分が前記評価プログラムの作成又は使用によってBのパソコンに残って\nいたとしても,それが本件ソースコードの一部である以上,前記に述べたと\nころと同様の理由により,原告から示された営業秘密であるとするのが相当 であり,また,Bにおいて,そのことを認識することができたといえる。こ れらに照らせば,被告らの主張は,Bにおいて類似箇所1ないし3を被告ソ\nフトウェアの開発の際に使用する行為が不競法2条1項7号にいう不正競 争に該当するなどの前記結論を左右するものではない。
・・・
前記(1)アのとおり,被告ソフトウェアの販売数は,主として業務用として\n利用されるドングル版が●(省略)● ここで,オンライン版とスクール版の前記個数については同一顧客によっ て更新された回数が含まれているところ,オンライン版とスクール版につい ては,価格(更新の価格も含む。)がドングル版に比較して相当安価に設定さ れていて,同一顧客による同内容のソフトウェアの継続利用とその更新を前\n提としている部分があると認められる。このことに原告ソフトウェアの価格\nから推測されるその利用方法を考慮すると,本件においては,オンライン版 とスクール版については,不競法5条1項にいう「譲渡数量」としては,同 一顧客に対する販売を1個とすることが相当であるというべきである。 したがって,不競法5条1項における被告ソフトウェアの譲渡数量は,ド\nングル版が●(省略)●であると認めるのが相当である。
イ 原告ソフトウェアの単位数量当たりの利益の額\n
前記 ウのとおり,主として業務用に利用される原告ソフトウェアの価格は,基本編集機能\を搭載したもので28万円である。また,前記 オのとお り,主として教育用に利用される原告ソフトウェアの価格は,割引を考慮し\nない場合は2万4800円である。 そして,平成21年から平成23年までの間及び平成27年について,減 価償却費や人件費を控除して算出された原告商品の利益率は,最も利益率が 低い期間の利益率においても53.2パーセントを超えること(甲38の2, 甲133)及び弁論の全趣旨から,原告ソフトウェアの限界利益の利益率は,\n少なくとも40パーセントであると認められる。 以上によれば,主として業務用に利用される原告ソフトウェアの前記利益\nの額は11万2000円(28万円×0.4),主として教育用に利用される 原告ソフトウェアの前記利益の額は9920円(2万4800円×0.4)\nであると認められる。 これに対し,原告は,原告ソフトウェアの価格は90万7200円である\nと主張する。しかしながら,前記 廉価版である「SSTG1 Lite」を14万2000円で販売している。 また,90万7200円という金額は高等機能オプションやデータのインポ\nート/エクスポートオプション等の大部分を搭載した場合における金額で あるところ,前記 のとおり,原告ソフトウェアを利用する顧客の中には\n個人の顧客もかなりの割合で存在しており,そのような個人の顧客が基本編 集機能に加えてそれらのオプションを搭載したものを購入しているか否か\nは証拠上明らかではなく,むしろ,証拠(乙5,42)によれば個人の顧客 の97パーセントは基本編集機能のみを購入していることがうかがわれる。\nしたがって,原告の前記主張は採用できない。
ウ 小括
前記ア及びイによれば,以下の計算式のとおり,主として業務用に利用さ れるソフトウェアの関係では2654万4000円が原告の損害額と推定\nされ,主として教育用に利用されるソフトウェアの関係では1123万93\n60円が原告の損害額と推定される(合計3778万3360円)。
(計算式)
●(省略)●
エ 推定覆滅事由についての検討
前記3のとおり,被告ソフトウェアに関連し,原告の営業秘密である類似\n箇所1ないし3についてB及び被告フェイスの不正競争行為が認められる。 ここで,類似箇所1ないし3はいずれも変数定義部分等であり,ソフトウェ\nアの動作に不可欠な有用な部分ではあるが,ソフトウェアの画面表\示,イン ターフェイスや動作といったソフトウェアの利用者に関係する機能\等の制 御に直接的に関係する部分ではなく,また,類似箇所1ないし3の内容に照 らし,それらが被告ソフトウェアに対して他のソ\フトウェアでは一般的とは いえない特別の動作をもたらすものであるとは認められない。他方,前記1 とおり,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアのソースコードは,類似\n箇所1ないし5以外に類似している箇所があるとは認められず,ソフトウェアの利用者に関係する機能\等の制御に直接的に関係する部分については原 告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアの間に共通する部分は存在していない ともいえる。 これらを考慮すると,被告らの不正競争行為が被告ソフトウェアの利用者\nに関係する機能を同種のソ\フトウェアに関する機能と大きく異なるものに\nしたとは直ちにはいえず,被告ソフトウェアの売上げは,基本的には,被告\nソフトウェアの不正競争行為ではない行為により作成された機能\に基づく 商品としての価値や被告フェイスの営業努力等によって実現されていたと するのが相当である。
以上によれば,被告ソフトウェアの譲渡数量のうちの相当程度の数量の原\n告ソフトウェアについて,原告が販売することができなかった事情があると\n認めるのが相当であり,以上のほか,本件にあらわれた一切の事情を総合的 に勘案すれば前記ウの推定は95パーセントの限度で覆滅し,被告フェイス 及びBによる不正競争によって原告に生じた損害は,前記ウ記載の損害の5 パーセントであると認めるのが相当である。また,弁護士費用としては,10万円をもって相当と認める。 なお,被告らは,「おこ助」と称する字幕ソフトウェアがシェアを拡大して\nおり,原告ソフトウェアとの競合品が存在していることが推定覆滅事由に該\n当するなど主張するが,前記「おこ助」の販売台数や機能等の詳細は明らか\nでなく,むしろ,証拠(乙38,39)によれば前記「おこ助」は主として 聴覚障がい者向けの字幕制作のためのソフトウェアであることがうかがわ\nれることに照らせば,前記「おこ助」が原告ソフトウェアの競合品であるこ\nとを理由とした被告らの前記主張は認められない。
◆判決本文
前訴はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> 営業秘密
>> ピックアップ対象
2019.03.14
平成30(行ケ)10099 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月6日 知的財産高等裁判所
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確 定したときは,審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件につい て更に審理を行い,審決をすることとなるが,審決取消訴訟は行政事件訴訟法 の適用を受けるから,再度の審理ないし審決には,同法33条1項の規定によ り,当該取消判決の拘束力が及ぶ。そして,この拘束力は,判決主文が導き出 されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから,審判官は取 消判決の当該認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがっ て,再度の審判手続において,審判官は,当事者が,取消判決の拘束力の及ぶ 判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り 返すこと,あるいは当該主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべ きではなく,審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は,その限りにおいて適法であり,再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができない。 このように,再度の審決取消訴訟においては,審判官が当該取消判決の主文の よって来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上,その拘束力に従って された再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは,確定 した取消判決の判断自体を違法として非難することにほかならず,再度の審決 の違法(取消)事由たり得ないと解される(平成4年最高裁判決参照)。
2 これを本件についてみると,上記第2,1(3)及び(4)並びに2において認定 したとおり,一次判決は,本件発明1及び3については,その発明者が原告で あると認めることはできないとして,一次審決のうち,本件特許の請求項1及 び3に係る部分を取り消した。そして,一次判決の確定後にされた本件審決は, 一次判決の拘束力に従って,本件発明1及び3については,その発明者が原告 であると認めることはできないものと判断した。 したがって,本件発明1及び3の発明者についての本件審決の判断は,一次 審決の拘束力に従ってされた適法なものであるから,関係当事者である原告は, 当該判断に誤りがあるとして本件審決の取消しを求めることができないという べきである。
3 原告の主張について
(1) 原告は,平成4年最高裁判決は,「拘束力は,判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたる」と判示しているから,一次判決の 拘束力が及ぶのは,一次判決のうち,本件発明1及び3に係る部分を取り消 すとの判決主文が導き出される根拠とされた事実(証拠)の認定及び当該事 実(証拠)に基づいてされた法律判断のみであって,新たな証拠に基づく事 実認定や法律判断にまで拘束力は及ばないところ,新たな証拠によれば本件 発明1及び3の発明者は原告であると認定されるべきであるから,これに反 する本件審決の判断は誤りであると主張する。 しかし,平成4年最高裁判決によれば,判決主文が導き出されるのに必要 な事実認定及び法律判断に対して拘束力が及ぶのであるから,当事者として は,この事実認定に反する主張をすることは許されないのであり,したがっ て,新たな証拠を提出して,上記事実認定とは異なる事実を立証し,それに 基づく主張をしようとすることも,取消判決の拘束力に反するものであって 許されないといわなければならない。このことは,上記判決自身が,「再度 の審決取消訴訟において,取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りであるとして,これを裏付けるための新たな立証をし,更には 裁判所がこれを採用して,取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違 法とすることが許されない。」と明言していることからも明らかである。 そして,本件訴訟における原告の主張は,一次判決において審理の対象と なっていた冒認出願(平成23年法律第63号による改正前の特許法123 条1項6号),すなわち,本件発明1及び3は,被告が発明したものである にもかかわらず,原告がその名義で出願した,という同一の無効理由に関し, 本件発明1及び3の発明者が原告であると認めることはできない,との一次 判決が認定した事実そのものについて,一次判決に係る訴訟における原告の 主張を補強し,又は,原告に不利な認定を誤りであるとして,確定した一次 判決の当該認定判断を覆そうとするものにすぎないから,そのような主張が 許されないことは明らかである。
(2)ア もっとも,原告が指摘するとおり,取消判決に民事訴訟法338条所定 の再審事由がある場合には,当該取消判決は再審の訴えによって取り消さ れるべきものであるから,これに拘束力を認めるのは相当でないと解する 余地がある。 そして,原告は,一次判決の認定判断の基礎となった被告及びAの陳述 (一次審決に係る審判手続において,宣誓の上で実施された被告の当事者 尋問における陳述を含む。)に,民事訴訟法338条1項6号及び7号の再審事由があると主張するものと解されるが,同条1項ただし書の場合に 該当しないこと,及び同条2項の要件を満たすことについては何ら主張立 証がないから,原告の再審事由に関する主張は,既にこの点において理由 がないものといわざるを得ない。また,念のため内容について検討してみ ても,やはり理由がないものといわざるを得ない。
イ すなわち,一次判決は,本件各発明の発明者を認定判断するに当たり, 被告が主張した,1)平成22年10月5日までに,燃焼室クリーナーの流 量調整等の問題を解決するために,ノズル管を加熱・冷却してその管内に ゲート構造を形成するとの着想を得て,これを具体化した甲33に係るノズル(一次判決における甲26ノズル)を製作しその噴出量のテストを行\nった,2)その後,同月28日ころには,本件各発明を完成させ,同年11 月3日ころには,本件各発明を実施することに用いるゲート構造を備えたノズルを製作するための機器を完成させた,との各事実につき,一次審決\nに係る審判手続において,宣誓の上で実施された被告の当事者尋問の録音 反訳書(甲48。一次判決における甲37)を,その認定の基礎としてい ることが認められる(甲8・29頁)。
この点に関し,原告は,被告との打合せの際,「…誰もやってない時に プライヤーで潰して針金入れたやつ見せたじゃないですか。」との原告の 発言に対し,被告が「…プライヤーで潰した針金?」,「…あれが,これ と何が違うんですか。」,「…あれ持って行った時にはすでに僕は…」と 発言したこと(甲60・40頁)を根拠として,被告は原告が甲33に係るノズルを作製したことを認めていたのであるから,上記の審判手続にお ける被告の陳述は虚偽であると主張する。しかし,被告は,上記のやりと りの直後に「あれ持って行った時にはすでに僕はもうつくってあったじゃ ないですか。」と発言している上に,原告がその発言中で指摘する対象物 を示した時期などを特定するに足りる事情も見当たらないことからすると, 原告が指摘するやりとりをもって,被告が甲33に係るノズルの作製者は 原告であると認めていたと断ずることはできない。
また,原告は,Aとの打合せの際,「そのゲートのそれをやるという, アイディア。そしてあと,熱で刺した,ここに差したのを,熱でやるとい うアイディア。全部,私じゃん」との原告の発言に対し,Aは「ええ。」と発言したこと(甲61の2・2頁)を根拠として,Aは原告が本件各発 明を着想したことを認めていたと主張する。確かに,前後の文脈を踏まえ ると,原告の当該発言部分はノズルのゲートに関する事柄であることがう かがわれる。しかし,当該発言部分で触れられている技術的事項は,それ 自体抽象的である上に,本件各発明が備える構成のごく一部にすぎないから,上記のやりとりから直ちに,Aにおいて,原告が本件各発明の着想者\nであることを認めたとまで認定することは困難である。このほか原告が指摘する種々の証拠を考慮しても,上記の審判手続における被告の陳述が虚偽であると断ずることはできない。
ウ 次に,原告は,一次判決が事実認定の基礎としたA及び被告の陳述書(甲 76,77。一次判決における甲62,63)について論難するが,いず れも私文書である当該各陳述書に記載された内容が虚偽であると主張する にとどまるものであって,これらが偽造又は変造されたものであることを 認めるに足りる証拠はない。 また,原告は,甲55が黒塗りされていたことを指摘して,被告及びA が提出した書類について虚偽報告や変造が常態となっていたとも主張する が,一次判決において判断の基礎とされた証拠が偽造又は変造されたもの であることを具体的に指摘するものであるとはいい難い(そもそも,甲5 5は一次判決において判断の基礎とされたものではない。)。
(3) さらに,原告は,一部の証拠について,一次判決に係る訴訟手続において 提出できなかった事情など,種々の主張をするが,いずれも上記1及び2の判断を左右するに足りないというべきである。
◆判決本文
一次判決はこちらです。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> 審判手続
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.03.13
平成30(ワ)6962 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年2月20日 東京地方裁判所(29部)
特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し,又は貸し渡す行為等には及ばず,特許権者は,当該特許製品がそのままの形態を維持する限りにおいては,当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁,最高裁平成18年(受)第826号同19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁参照)。そして,このように解するのは,特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると,市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ,かえって特許権者自身の利益を害し,ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方,特許権者は,特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ,特許権者から譲渡された特許製品について,特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないためであり,この趣旨は,意匠権についても当てはまるから,意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。
(2)前記第2の2の前提事実(3)のとおり,原告は,本件知的財産権を有する被告か ら,本件知的財産権の実施品である被告製品を購入しているところ,証拠(甲12〜 15)によれば,原告は,被告から購入したイヤーパッドである被告製品を,原告製 品であるイヤホン,無線機本体,原告製品を媒介するコネクターケーブル及びPTT スイッチボックスと併せて,それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ,原告製品の保 証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売していると認め られ,そうであれば,原告製品に被告製品を付属させて販売していたにすぎないと認 められるのであり,被告による被告製品の譲渡によって被告製品については本件知的 財産権は消尽すると解される。 よって,原告が原告製品を製造等する行為は,被告の有する本件知的財産権を侵害 しない。
(3)この点,被告は,原告は,本件報告義務に違反して被告製品を販売したものであって,当該販売は不適法な拡布に当たるから,本件知的財産権は消尽しないと主張 する。しかしながら,本件報告義務違反によって消尽の効果が直ちに覆されるといえるかについての判断は措くとして,被告の上記の主張は,原告による契約上の義務違反を いうものにすぎず,本件知的財産権を有する被告によって被告製品が拡布,すなわち 適法に流通に置かれた事実を争うものではないから,被告の上記主張は,その前提を 欠き,採用することができない。
(4)そうすると,原告は,本件知的財産権を侵害していないから,本件行為におい て告知され,流布されている原告が本件知的財産権を侵害している旨の事実は,虚偽 であると認められる。
関連カテゴリー
>> 消尽
>> 意匠その他
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成30(行ケ)10141 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年3月7日 知的財産高等裁判所
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると,欧文字「AAA」について, 次のとおり,認められる。
a 欧文字「AAA」は,広辞苑第六版(乙3の1)にも,大辞林第三 版(乙3の2)にも収載されていない。 もっとも,広辞苑第六版付録のアルファベット略語において,「AAA;Aaa; aaa(トリプルエー)」は,「格付けでの最高点」を意味するものとされている。 また,「エー【A・a】」は,「1)アルファベットの最初の文字。2)転じて,第一位。」などを意味する語(広辞苑第六版,岩波書店,平成20年1月11日),あるいは, 「1)英語のアルファベットの第一字。エイ。2)第一の,最上の,の意を表す。」などを意味する語(大辞林第三版,三省堂,平成18年10月27日)として,知られ\nている。
b 金融商品又は企業・政府などについて,その信用状態に関する評価 の結果を記号や数字を用いて表示した等級を信用格付けというが,「AAA」又は「Aaa」は,長期格付の最高位を表\す格付記号である(甲35,88〜91)。長期格付の最高位を表す格付記号としての「AAA」又は「Aaa」は,本件商標の査定日(平成29年2月21日)前においても,多くの新聞記事において広く\n用いられており,そこでは,その意味を特に説明することなく,「トリプルA」など と表記することもされていた(甲92,93)。また,生命保険会社であるアリコジャパンにおいては,世界的な二つの格付け会社から保険財務力が最上級の「AAA」\n又は「Aaa」と評価されていることに基づいて,CMやウェブサイトにおいて, 「アリコは,最上級のトリプルA」というキャッチフレーズを用いていた(甲94 〜96,102)。
c 東洋経済新報社は,平成27年11月24日発売の「CSR企業総 覧2016年版」において,上場企業を中心とする有力・先進1325社について, 人材活用,環境,企業統治,社会性の4指標を各企業のCSR評価として,成長性, 収益性,安全性,規模の4指標を財務評価として,それぞれ「AAA」,「AA」,「A」などの記号で格付けを行った(甲98)。
d 三井住友海上は,平成28年12月現在,最長5年間の研修期間を経て保険代理店経営者として独立後の保険代理店に対する評価制度として,「専属 プロ代理店」の上に「プロ新特級代理店」を設け,売上規模,要員体制等に加え, 「業務品質」「組織管理」「販売力・増収力」といった質を重視した基準を高いレベ ルで満たす代理店に対して,「TGA・AAA・AA・A+・A」の5段階の認定を 行っていた(甲97)。
・・・
(イ) 前記(ア)によると,欧文字「AAA」は,金融商品又は企業・政府など の信用状態に関する評価である長期格付の最高位を表す格付記号として,一般に知られていることが認められる。\nまた,欧文字「AAA」は,信用格付けにおける長期格付だけでなく,CSR(企 業の社会的責任)に関する人材活用,環境,企業統治,社会性の指標における格付 けや,保険代理店における売上規模,要員体制,業務品質,組織管理,販売力・増 収力等に基づく格付けにも用いられていたことが認められる。 さらに,欧文字「AAA」は,本件商標の査定日(平成29年2月21日)前に おいて,データセンターのセキュリティー水準の格付け,食の安全を担保する業務 の達成度の評価,カンパニー制における各カンパニーや工場に対する社内格付け制 度,排出量の削減実績などにおいても,最上級の評価として用いられていたほか, 東京都知事選挙の立候補予定者に対する評価や超大型ゲームに対する評価にも用いられていたことが認められる。\n
(ウ) 前記(イ)認定の事実に,我が国の学校の成績や各種評価においても,A を最上位とするABC評価が一般的な評価手法の一つであることをも考え併せると,最上を意味する「A」を重ねた「AAA」は,本件商標の査定日(平成29年2月 21日)において,信用格付けにおける長期格付にとどまらず,一般に,最上位又 は優良な評価を意味する表示であると認識されていたものと認められる。前記(ア)のとおり,本件商標の査定日後には,化粧品の分野においても,欧文字「A AA」を品質の優良性を示す趣旨で使用した,被告の商品を含む商品が複数のメー カーから販売されているが,これも,化粧品の取引者,需要者において,「AAA」 が最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されることを期待したものであるから,上記認定に沿うものということができる。\n
エ 本件商標の構成部分の一部による類否判断の可否
前記イ,ウによると,本件商標の構成部分である欧文字「BULK」は,本件商標の指定商品の取引者,需要者に,出所識別標識として認識されるものである一方,\n欧文字「AAA」は,最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されるものであるから,欧文字「BULK」の部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別\n標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 したがって,本件商標と引用商標2の類否判断に当たり,本件商標の構成部分である欧文字「BULK」の部分を抽出し,この部分だけを引用商標2と比較して商\n標そのものの類否を判断することが許される。
オ 被告の主張について
(ア) 被告は,「BULK」は通常の辞書に載っている一般的な英単語であ り,これ単独で造語とみなされて強い識別力を発揮することはないし,「BULK」 は,化粧品分野では,化粧品の中身を意味する語として広く一般に使用されている から,より一層識別力の弱い語であるなどと主張する。 しかし,前記イのとおり,欧文字「BULK」は,「船舶のばら積みの貨物」など を意味する英単語として知られていたのであり,本件商標の指定商品である「化粧 品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き」に付された本件商標に接した取引者,需要 者において,「化粧品の中身」を意味する語として知られていたことを認めるに足りる証拠はないから,本件商標について出所識別標識としての機能を十\分に果たすも のということができる。
(イ) 被告は,本件商標の構成中「AAA」の文字は,それ単体での商標登録が認められる識別力のある語であるし,「AAA」が本件商標の指定商品において\n品質表示として用いられている事実はないなどと主張する。しかし,欧文字「AAA」が,信用格付けにおける長期格付にとどまらず,一般\nに,最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されていることは,前記ウのとおりである。\n前記ウ(ア)iのとおり,欧文字「AAA」についての商標登録例・査定例も認めら れるが,本件商標が欧文字「AAA」の前に欧文字「BULK」を組み合わせて成 る商標であり,「AAA」による最上位又は優良な評価が「BULK」に対し向けら れているものと容易に認識することができるのに対し,上記商標登録例・査定例は, いずれも,欧文字「AAA」のみ又は片仮名「トリプルエー」と組み合わせて成る 商標であって,欧文字「AAA」の前に異なる単語を組み合わせた商標ではないか ら,上記商標登録例・査定例の存在は,前記エの判断を左右するものではない。
(ウ) 被告は,本件商標は,全体としてまとまりよく一体に表されているし,「バルクトリプルエー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るから,一体不可分の商標というべきものであるなどと主張する。\nしかし,前記アのとおり,本件商標は,「BULK」と「AAA」との間に1文字 分の空白があるから,「BULK」と「AAA」との複数の構成部分を組み合わせたものと容易に理解されるところ,前記イのとおり,「BULK」は,出所識別標識と\nして認識されるものである一方,前記ウのとおり,「AAA」は,最上位又は優良な 評価を意味する表示であると認識されるものであるから,本件商標全体がまとまりよく一体に表\されていることや,「バルクトリプルエー」の称呼が無理なく一連に称呼し得ることを考慮しても,本件商標に接した取引者,需要者において,本件商標 を一体不可分の商標と認識するものということはできない。
(3) 引用商標2について
ア 引用商標2の構成態様
引用商標2は,前記2の3(1)イのとおり,上段に「BULKHOMME」と横書 きし(以下,この部分を「上段部分」という。),下段左側に「SIMPLE/LU XURY」と二段に横書きし(以下,この部分を「下段左側部分」という。),縦線 を挟んで,下段右側に「TRUE LUXURY IS ABOUT/SIMPL ICITY.THIS IS WHAT/OUR BRAND IS BASED UPON.」と三段に横書きして(以下,この部分を「下段右側部分」という。) 成るものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解される。そして,その構\成文字の書体や大きさ等を見ると,上段部分は,同じ大きさで等間隔に記載されているが,「BULK」は「HOMME」に比し線幅が略2倍の太文 字で記載されている。また,上段部分と下段左側部分,下段右側部分との縦(上下 方向)の幅は略同一であるから,下段左側部分の文字は,上段部分の文字の略2分 の1の大きさであり,下段右側部分の文字は,上段部分の文字の略3分の1の大き さである。 上記認定の構成態様によると,上段部分は,引用商標2に接した取引者,需要者に対し,下段左側部分,下段右側部分に比し,商品の出所識別標識として強く支配\n的な印象を与えるものと認められる。 もっとも,上記認定のとおり,上段部分においても,欧文字「BULK」が欧文 字「HOMME」に比し線幅が略2倍の太字で記載されているから,上段部分が一 体として商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるの か,欧文字「BULK」又は「HOMME」の一方が商品の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えるものと認められるのかを,更に検討する。
イ 欧文字「BULK」について
前記(2)イと同様に,欧文字「BULK」は,本件商標の査定日において,本件商 標の指定商品の取引者,需要者に,引用商標2の指定商品(男性用の化粧品,男性用のおしろい,男性用の化粧水,男性用のクリーム,男性用の紅,男性用の頭髪用 化粧品,男性用の香水類,男性用のせっけん類,男性用の歯みがき,男性用の香料, 男性用の薫料,男性用のつけづめ,男性用のつけまつ毛)に関連する用語として知 られていたものではないから,上記指定商品との関係において,出所識別標識とし て認識されるものということができる。
ウ 欧文字「HOMME」について
(ア) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると,欧文字「HOMME」につい て,次のとおり,認められる。
a 欧文字「HOMME」と綴りを同じくする「homme」は,「人間, 人類,男,男性」などの意味を有するフランス語である(仏和大辞典,白水社,昭 和56年4月25日)。日本語の辞書にも,「オム【homme】」は,「1)男性。人 間。2)ファッションで男性用。」を意味する語として収載されており(大辞林第三版, 三省堂,平成18年10月27日),また,カタカナ語辞典には,「オム【homm e】」として,「男性。転じて衣服が男性用であることを示す。」(カタカナ語・略語 辞典第三版,旺文社,平成12年8月25日),「1)人間。男。2)男物。」(コンサイ スカタカナ語辞典第3版,三省堂,平成17年1月20日)の意味を有する語とし て収載されている。
・・・
(イ) 前記(ア)によると,欧文字「HOMME」は,「男性」の意味を有する フランス語であるところ,我が国においても,本件商標の査定日(平成29年2月 21日)の10年以上前から,日本語の辞書や複数のカタカナ語辞典において,男 性用のものを意味する語として収載されていたことが認められる。また,化粧品業 界の関係者が,男性用化粧品には女性用化粧品と差別化するために「HOMME」 を商品等に表示することが普通に行われており,一般消費者も「HOMME」を男性用の商品を示す語と理解していると思われる旨陳述しているところ,原告の商品\nのみならず,多数のメーカーにおいて,男性用化粧品や衣料品のブランドに「HO MME」を付加していること(本件商標の査定日後の事実については,上記陳述の 信用性を裏付ける限度で考慮する。)も,上記陳述を裏付けるものである。そうすると,欧文字「HOMME」は,本件商標の査定日において,化粧品等の 分野では,男性用のものを意味する語として知られていたものと認められる。
エ 引用商標2の構成部分の一部による類否判断の可否前記ア〜ウによると,引用商品2の構\成部分である「BULK」は,引用商標2の指定商品との関係において,出所識別標識として認識されるものである一方,欧 文字「HOMME」は,引用商標2の指定商品が含まれる分野では,男性用のもの を意味する語として認識される上,引用商標2の指定商品は男性用のものに限られ ていること,「HOMME」は,「BULK」よりも細い字体で記載されていること を併せて考慮すると,欧文字「BULK」の部分が取引者,需要者に対し商品の出 所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 したがって,本件商標と引用商標2の類否判断に当たり,引用商標2の構成部分である欧文字「BULK」の部分を抽出し,この部分だけを本件商標(前記(2)のと おり,本件商標の構成部分である欧文字「BULK」の部分)と比較して商標そのものの類否を判断することが許される。\n
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成30(行ケ)10162 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
ア 前記第2の3(1)の本件審判における原告らの主張によると,原告らは, 本件審判において,甲55と同一の内容及び同一の添付物のチラシが複数作成され, 頒布されており,甲41の4は,そのうちの一つの写しである旨主張していたので あるから,写しである甲41の4と甲55の原本に当たるものは,同一であること を前提に主張していたものと解される。 そして,本件審決は,甲41の4につき,原告らが「甲41の4に現れているつ りピンロールは公然に頒布された物品に係るもので,本件特許は公然知られた発明 である」旨主張していることを挙げた上,「甲第41号証の4又は同号証で示された つりピンロールが本件特許の遡及日前に頒布されたものと認めることはできない。」 と判断している。 したがって,本件審決は,結論としては,前記第2の3(2)のとおり,甲2に記載された発明,甲4に記載された発明又は甲55に記載された発明を引用発明とする 新規性違反の有無について判断しているが,甲41の4を引用発明とする新規性判 断の誤りについても判断していると認められる。
イ 証拠(甲41の4・5,甲69)及び弁論の全趣旨によると,被告は, 被告外1名を原告,原告ら外3名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において, 当該事件の原告訴訟代理人弁護士C及び同Dが平成19年5月22日に東京地方裁 判所に証拠として提出した甲41の4及び証拠説明書として提出した甲41の5を, その頃受領していること,甲41の5には,甲41の4の説明として,「被告シンワ のチラシ(2006年用)」,「写し」,作成日「2006(平成18)年」,作成者「(有)シンワ」,立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨記載されていることが認められるところ,甲41の4には,「2006年販売促進キャンペーン」,「キャンペーン期間 ・予約5月末まで ・納品5月20日〜9月 末」,「有限会社シンワ」,「つりピンロールバラ色 抜落防止対策品」,「サンプル価 格」,「早期出荷用グリーンピン 特別感謝価格48000円」などの記載があり, 複数の種類の「つりピン」が記載されており,その中には,5本のピンが中央付近 においてそれぞれハの字型の1対の突起を有するとともに,そのハの字型の間の部 分を2本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のもの(つりピンロールバ ラ色と記載された部分の直近下に写し出されているもの)があることが認められる。 上記「つりピン」の形状は,証拠(甲41の3〜5)及び弁論の全趣旨により, 上記事件の上記原告訴訟代理人が,平成19年5月22日に,甲41の4とともに, 上記商標権侵害差止等請求事件において,東京地方裁判所に証拠として提出したと 認められる甲41の3に「つりピンロール(バラ色)抜落防止対策品」として記載 されているピンク色の「つりピン」と,その形状が一致していると認められる。証 拠(甲41の3〜5)及び弁論の全趣旨によると,甲41の3は,甲41の4と同 じ証拠説明書による説明を付して,提出されたものであると認められ,「2006年 度 取扱いピンサンプル一覧」,「有限会社シンワ」,「早期出荷用」などの記載がある。 また,証拠(甲41の1〜5)及び弁論の全趣旨によると,甲41の4は,上記 商標権侵害差止等請求事件の上記原告訴訟代理人が,平成19年5月22日に,甲 41の4とともに,「被告シンワのチラシ(2005年用)」,「写し」,作成日「2005(平成17)年」,作成者「(有)シンワ」,立証趣旨「被告シンワが原告むつ家 電得意先へ営業した事実を立証する。」旨の証拠説明書による説明を付して,上記商 標権侵害差止等請求事件において,東京地方裁判所に提出したと認められる甲41 の1と,レイアウトが類似しているところ,甲41の1には,「2005年開業キャ ンペーン 下記価格は2005年4月25日現在の価格(税込)です。」,「有限会社 シンワ」,「当社では売れ残り品は販売しておりません。お客様からの注文後製造い たします。」などの記載がある。
以上によると,甲41の3及び4は,いずれも,原告シンワが,被告の顧客であ った者に交付したものを,平成19年5月22日までに,被告が入手し,原告シン ワが,被告の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして,上記商標権侵害 差止等請求事件において,提出したものであると認められる。 そして,甲41の4の上記記載内容,特に「販売促進キャンペーン」,「納品5月 20日〜」と記載されていることからすると,甲41の4と同じ書面が,平成18 年5月20日以前に,原告シンワにより,ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客に 配布されていたことを推認することができる。
ウ また,前記イの認定事実及び弁論の全趣旨によると,甲41の4に記載 されている,5本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の1対の突 起を有するとともに,そのハの字型の間の部分を2本の直線状の部分が連通する形 で連結された形状のものは,原告シンワにより見込み客に配布されていた前記イの 甲41の4と同じ書面にも添付されていたと認められる。
エ 前記の5本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の1対 の突起を有するとともに,そのハの字型の間の部分を2本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のものの形状は,両端部において折り返した部分の端部の形 状が,甲41の4では,下から上へ曲線を描いて跳ね上がっているのに対し,本件 特許に係る図面(甲119)の図8(a)では,釣り針状に下方に曲がっている以 外は,上記図8(a)記載の形状と一致している。 そして,上記図8(a)は,本件発明に係るロール状連続貝係止具の実施の形態 として記載されたものである。
オ そうすると,前記イ,ウ及びエの5本の「つりピン」が中央付近におい てそれぞれハの字型の1対の突起を有するとともに,そのハの字型の間の部分を2 本の直線が連通する形で連結された形状のものは,形状については,本件発明1の 構成要件にある形状をすべて充足する。そして,証拠(甲41の1〜5)及び弁論\nの全趣旨によると,その材質は,樹脂であり,「つりピンロール」とされていること から,ロール状に巻き取られるものであり,その連結材は,ロール状に巻き取られ ることが可能な可撓性を備えているものと認められる。したがって,甲41の4に\n記載されている「つりピン」は,本件発明1の構成要件を全て充足すると認められ\nる。 また,上記の「つりピン」は,ロープ止め突起の先端と連結部材とが極めて近接 した位置にあり,2本のロープ止め突起の先端の間隔よりも一定程度狭い縦ロープ との関係では,2本の可撓性連結材の間隔が,貝係止具が差し込まれる縦ロープの 直径よりも広くなるから,本件発明2の構成要件も全て充足すると認められる。\nさらに,上記の「つりピン」が,ロール状に巻き取られるものであることは,上 記のとおりであるから,上記の「つりピン」は,本件発明3の構成要件も全て充足\nすると認められる。
カ したがって,本件発明1〜3は,本件原出願日である平成18年5月2 4日よりも前に日本国内において公然知られた発明であったということができ,新 規性を欠き,特許を受けることができない。
(2) 被告は,甲41の4から認定できるのは,平成19年5月22日の時点でサンプルシート(甲41の4)が頒布されていたということだけであり,1)甲3及 び5には納品日の記載がないのに,甲41の4に納品日の記載がある点,2)顧客か ら価格が分かるようにしてほしいという要望を受けてサンプルシートを改訂したの であれば,価格だけを追記すれば済むのに,甲41の4には,キャンペーン期間や 納品期間が記載されている点,3)甲5には,価格の記載がない点を挙げて,甲41 の4の記載内容は不自然であるから,甲41の4は,甲41の4のサンプルシート が平成18年5月20日以前に頒布されたことを裏付けるに足りる証拠ではない旨 主張する。 甲3は,「2005年販売ピン一覧」という表題が記載された書面であり,価格の\n記載もキャンペーン期間の記載もない。甲5は,「2009年色が変って新登場 新 色キャンペーン」という表題が記載された書面であり,色の変更についての記載は\nあるが,価格の記載も日や月を区切ったキャンペーン期間の記載もない。そうする と,これらの文書の作成目的は,専ら顧客に原告シンワが取り扱う商品の一覧を示 すことにあると認められる。これに対し,甲41の4は,「2006年販売促進キャ ンペーン」という表題が記載された書面で,「キャンペーン期間」,「早期出荷用グリ\nーンピン 特別感謝価格」という記載もされているのであるから,期間を区切って 特別に有利な価格を提示することを目的に含む,販売促進キャンペーン用のチラシ であると認められる。これらの記載内容,特に表題から認められる文書の目的の違\nいを考えると,1)甲41の4には納品日の記載があり,甲3及び5に納品日の記載がないことは不自然ではないし,また,2)顧客の価格が分かるようにしてほしいと いう要望を受けてサンプルシートを改訂する際に,期間を区切った販売促進キャン ペーンを企画し,そのチラシに価格と共にキャンペーン期間や納品期間を記載して も不自然ではないし,さらに,3)甲5に価格の記載がないことは,不自然ではない。 したがって,被告の上記主張は,前記(1)の認定を左右するものではない。 他に前記(1)の認定判断を覆すに足りる主張,立証はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成29(ワ)16958 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年2月28日 東京地方裁判所
原告DVDと被告DVDの項目アにおける共通点である動画に社名を 表示することは,アイデアである。\n他方,項目イ及びウにおける原告DVDと被告DVDの共通点は,白い 扉を抜け,その先に英会話を学ぶ動機となるフレーズと共に写真が現れる というもので密接に関係するものといえるところ,英会話の宣伝,紹介用 のDVDにおいて,教材を利用することで新しい状況となることについて, 紺色の背景とする白い扉やその奥に広がる宇宙で表現するとともに,教材\nにより達成できる状況について,扉の奥に,その状況を表しているともいえる写真を英会話を学習する動機を示すフレーズとともに複数回示すこ\nとで表現しているものといえ,その表\現は,全体として,個性があり,創 作性があるといえる。 項目エにおける原告DVDと被告DVDの共通点のうち,英会話の宣伝, 紹介用のDVDにおいて,外国人と話している様子を用いる点はアイデア であり,そこにおける問いかけの表現は通常よく使用される,ありふれた\n表現といえる。\n項目オにおける原告DVDと被告DVDの共通点は,教材を学ぶことで 状況が変わることを,二度にわたる太陽の光を含む空の情景で示し,また, 自社の商品を用いることで交流の範囲が広がることなどを人物が写った 多数の写真を自社商品の周りを回転させることなどで表現しているもの\nといえ,その表現は,全体として,個性があり,創作性があるといえる。\n以上によれば,イントロダクションの部分の原告DVDと被告DVDは, 少なくとも,項目イ,ウ及びオにおいて表現上の創作性がある部分におい\nて共通するといえる。そして,上記共通する内容に項目イ,ウ及びオの内 容等を考慮すれば,上記部分の原告DVDの表現上の本質的な特徴を被告\nDVDから直接感得することができると認められる。
イ 受講者インタビュー(その1)(項目カ)
前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVD は,当該部分において,「(商品名)を始めた人の中にはすでに新しいステー ジへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」という音声 が流れ,その後,海外で活躍する女性を紹介し,その女性へのインタビュー の様子となる点,「英語を話す原点になったのが(商品名)だったのです」と いう音声が流れるとともに,同趣旨が赤色の文字テキストで表示される点な\nどが共通する。 他方,原告DVDと被告DVDの当該部分において,登場人物やインタビューの内容,表現は異なっている。\n上記共通点のうち,英会話教材の宣伝,紹介用の動画において,海外で活 躍する受講者を紹介した上でその受講者へのインタビューの様子を用いる ことや,その受講者の活躍の契機となったのが自社の教材であるという説明 をすることは,アイデアであるといえるし,また,それらを上記のような順 序で構成することは,通常行われることといえ,これらをもって表\現上の創 作性があるとはいえない。また,「(商品名)を始めた人の中にはすでに新し いステージへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」, 「英語を話す原点になったのが(商品名)だったのです」との部分について, 英会話教材を宣伝,紹介する際に,教材による学習によって自らの状況が変 わったことを新たなステージへと人生を開くと表現することや,その契機等\nとなった商品を原点と表現することはありふれたものであるといえ,いずれ\nも創作性があるとは認められない。 したがって,受講者インタビュー(その1)の部分の原告DVDと被告D VDの共通点は,いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表\現 上の創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
・・・・
エ その他受講者インタビュー(項目ク)
前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVD は,当該部分において,受講者への複数のインタビューの様子である点,「人 生が変わりました」との文字テキストが表示される点で共通している。\n 他方,原告DVDと被告DVDの当該部分において,登場人物やインタビ ューの内容,表現は異なっている。\n上記共通点のうち,英会話教材の宣伝,紹介用の動画において,受講者と される人物のインタビューの様子を用いることはアイデアであるといえる。 また,「人生が変わりました」という文字テキストは,表現であるということ\nができるとしても,教材を宣伝,紹介する場面で,教材による学習によって 自らの状況が変わったことを人生が変わると表現することは,ありふれた表\ 現であるといえ,創作性があるとは認められない。そして,インタビューの 様子に文字テキストを組み合わせることについても,普通に行われることで あり,このことをもって表現上の創作性があるとはいえない。\nしたがって,その他受講者インタビューの部分の原告DVDと被告DVD の共通点は,いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表\現上の 創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
オ 商品紹介(項目ケ)
前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVDは,当該部分において,まず,画面上部が光り,雲が浮かんでいる空の 様子となった後,画面の上方から階段が伸びてきて,階段を下から見上げ る構図となり,その後,空を背景に,最下段の階段の側面に英語学習のス\nテップのフレーズが表示され,そのフレーズの読み上げが終わると一段上\nの階段の側面が拡大されると同時に,その階段の側面に次の英語学習のス テップのフレーズが右からスライドして表示されるとともに,そのフレー\nズがナレーションされ,それを7回繰り返して,7つ目の英語学習のステ ップが表示されると,側面にフレーズが記載された階段が最下段まで表\示 されるという点で共通している。また,各階段の側面に表示されるフレー\nズは,原告DVDでは1)「聞くことを習慣化する」,2)「単語やフレーズの 音がキャッチできるようになる」,3)「言っていることが理解でき短い言 葉で反応できるようになる」,4)「短い言葉で自分の意思を伝えられるよ うになる」,5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,6)「言 葉のキャッチボールが長く続くようになる」,7)「意識せずに自然に外国 人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し,被告DVDでは1)「流 して聞くことを習慣化する」,2)「単語,フレーズの音が聞き取れるように なる」,3)「言っていることが分かり,短いフレーズで返事ができるように なる」,4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」, 5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,6)「言 葉のキャッチボールが長く続くようになる」,7)「意識せずに自然に外国 人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し,被告DVDでは1)「流 して聞くことを習慣化する」,2)「単語,フレーズの音が聞き取れるように なる」,3)「言っていることが分かり,短いフレーズで返事ができるように なる」,4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」, 5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,6)「言葉のキャッ チボールが長く続けられる」,7)「意識せず,自然に外国人との会話が楽し めるようになる」であり,その内容,表現はほぼ共通している。\n 他方,原告DVDでは,階段は側面も含めて青色であり,フレーズが白 色の文字で表示されるのに対し,被告DVDでは,階段は側面を含めて白\n色であり,フレーズが青色の文字で表示される。また,原告DVDと被告\nDVDにおいて,階段の背景はいずれも白色の雲がある青空であるが,具 体的な光景は異なる。
(イ)項目ケの部分の原告DVDと被告DVDの上記 の共通点は,空に浮か んだ階段を下から見上げる構図とすることによって,階段を上っていくイ\nメージを抱かせ,階段と英語学習のステップが結び付くものであり,原告 DVDと被告DVDでほぼ共通するフレーズの内容に照らしても,一定の 段階を踏んで英語学習を進めることができるなどのイメージを与えるも のである。そのようなステップが7段階あり,その内容がほぼ同一である ことをも考慮すると,この共通点は,作成者の個性が現れており,全体と して創作的な表現であると認められる。\nそして,上記共通する内容に項目ケの内容等を考慮すれば,項目ケの原 告DVDの表現上の本質的な特徴を被告DVDから直接感得することが\nできると認められる。
・・・・
原告は,原告DVDと被告DVDが,1)イントロダクション,2)受講者イン タビュー,3)商品紹介,4)商品特徴の説明,5)開発者等のインタビュー,6)商 品特徴の説明,7)エンディングという全体的な構成が類似することも主張する\nので,以下,検討する。
ア 前記前提事実 及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVD は,いずれも,1)イントロダクション(項目アないしオ),2)受講者インタビ ュー(項目カないしク),3)商品紹介(項目ケ),4)商品特徴の説明(項目コ ないしシ),5)開発者等のインタビュー(項目ス),6)商品特徴の説明(項目 チ及びツ),7)エンディング(項目テ,ト)という構成を有するということが\nできる。なお,上記各項目においては, 基 本的に,使われている写真,光景,登場人物やインタビューを受けた者が話 す内容などは異なる。
イ 原告DVDと被告DVDは,いずれも英会話教材の宣伝,紹介用のもので あり,このようなDVDにおいて,宣伝の対象である商品の購入等を促すと いう目的のために,商品の内容や特徴,商品を利用した場合の効果,サポー ト体制の説明をすることは,ごく一般的であるといえる。そして,商品の内 容,特徴や商品を利用した場合の効果を説明するために,受講者や開発者に 対するインタビューを用いることも,一般的であるといえる。 原告DVDと被告DVDの全体的な構成は,前記アのとおり,原告が主張\nする7つという少なくない要素において一致するが,その各要素は,上記の とおり,同種の目的を有するDVDにおいては,いずれもごく一般的といえ るものである。また,原告DVD及び被告DVDにおけるそれらの各要素の 順序について,特別の印象を与えるようなものであるとはいえない。これら を考慮すると,原告DVDと被告DVDの原告主張の全体的な構成について,\nそその各要素が共通する点をもって創作的な表現であるとは認められない。\nまた,前記 のとおり,被告DVDは,複数の部分において,原告DVD の表現上の本質的な特徴を感得することができる。しかし,それらの本質的\nな特徴を感得することができる表現について,英会話教材の宣伝,広告用の\n動画における表現としては関連するとはいえるが,それ以上にそれらが表\現 上及び内容上,相互に密接に関連しているものとはいえない。このことに, 全体的な構成の各要素が同種の目的を有するDVDにおいてごく一般的な\nものであること,被告DVDには,原告DVDの表現上の本質的な特徴を感\n得することができるとはいえない部分も多いこと(前記 )を考慮すると, 被告DVDに原告DVDの表現上の本質的な特徴を感得することができる\n部分があるとしても,原告DVD全体についての表現上の本質的な特徴を被\n告DVDから感得することができるとまではいえない。
(4)小括
以上によれば,被告DVDは,少なくとも,項目イ,ウ,オ,ケ,テ及びト において,原告DVDの表現上の本質的特徴を被告DVDから直接感得するこ\nとができる。 そして,対照表」及び「DVDスクリプト内容対照表\」における共通点の内容等及び弁 論の全趣旨に照らし,被告DVDは,原告DVDに依拠して作成されたものと いえる。 これらのことに,前記のとおり,原告DVDと被告DVDでは,画面自体は 異なり,原告DVDの表現に一定の修正,増減,変更等が加えられて別の表\現 となっていることなどから,被告DVDは,少なくとも,上記各項目において, 原告DVDを翻案したものと認められる。
2 争点2(編集著作物としての複製権,翻案権侵害の有無)及び争点3(言語の 著作物としての複製権,翻案権及び譲渡権侵害の有無)について
原告の主位的な主張のうち,編集著作物としての侵害の主張は,別紙「DVD の内容の対照表」の「イントロダクション」などの標題によって区切られた部分\nを一つの素材として,その選択と配列について創作性を有すると主張するもので ある。しかし,この主張は,少なくとも,前記1(3)の全体的な構成に関する類似\nの主張において述べたところと同様の理由により,理由がない。また,原告は, 予備的に,原告DVDに含まれるスクリプト部分の言語の著作物の侵害を主張す\nるところ,共通するスクリプトは,事実を述べるものか,英会話教材の宣伝,紹 介用の動画において,ありふれたものということができ,その順序にも表現上の\n創作性があるとは認められないから,原告の主張は理由がない。
◆判決本文
両当事者は、宣伝のキャッチフレーズについて著作権侵害を争っていましたが、こちらは1審、2審とも著作物性無しと判断しています。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成29(行ケ)10200 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月18日 知的財産高等裁判所
相違点1に係る,本件発明1の「回転数適応型の動吸振器(5)が, 油影響に関連して,駆動装置の励振の次数qよりも所定の次数オフセッ ト値qFだけ大きい有効次数qeffに設計されている」ことの意義につい てみると,本件発明1の特許請求の範囲には,「所定の次数オフセット qF」をいかに設定するかについて,「油影響に関連して」されるもので あること以上に特定する記載はないから,「油影響」について何らかの 関連を有し,何らかの次数オフセットqFだけ大きい有効次数qeffに設 計されているという程度の意味であると理解できる。 さらに,本件明細書についてみると,1) 図3に関する【0038】 〜【0039】の記載から,同じ設計の動吸振器であれば,回転する油 質量体の下では次数値が低くオフセットされるため,その抑制次数qFに 相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが,遠心力に 抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 されているといえる。また,2) 【0043】によれば,qFは自由に選 択可能な値として規定されていてもよいし,励振の個々の次数に対して,\nそれぞれ固定の値が設定されていてもよいとされているから,次数オフセットqF自体は,任意に設定し得る値であることが読み取れる。
(イ) 以上によれば,qFは,1)のような実験的な測定に基づき設定される ものに限られず,2)のような任意の値も採り得るものであるといえる。 そして,動吸振器の幾何学的次数が,駆動装置の励振の次数(q)より も任意の値(qF)の分だけ大きい数値(qeff)になるように設計され ているということは,オーバーチューニングに当たるといえる。そうす ると,本件発明1の「回転数適応型の動吸振器(5)が,油影響に関連 して,駆動装置の励振の次数qよりも所定の次数オフセット値qFだけ大 きい有効次数qeffに設計されていること」は,「油影響」を受ける状況 下においては,動吸振器の次数が低下することから,任意の値の次数オ フセットにより,動吸振器をオーバーチューニングしたという程度の意 味と解される。
ウ 「油影響に関連して…設計されている」構成の容易想到性\n
上記ア(イ)の技術常識によれば,油中に浸漬され,油という液体の影響を 受ける遠心振り子のような動吸振器にあっても,回転する油中であるか否 かにかかわらず,その固有振動数(又は次数)に何らかの影響,特に,そ の固有振動数(又は次数)が低下するような影響が生じるであろうことは, 当業者にとって当然に予測し得ることといえる。\nそして,回転数適応型の動吸振器において,理論上最も効果的に駆動装 置側の振動を減衰できるのは,遠心振り子の固有振動数が駆動装置の励振 の振動数と一致する場合なのであるから(上記ア(ア)),油の影響を受ける 回転数適応型の動吸振器において,効果的に駆動装置の振動を減衰させる ためには,油の影響によって固有振動数(又は次数)が低下することから, 動吸振器の固有振動数(又は次数)について,任意の値の次数オフセット によりオーバーチューニングするという,相違点1に係る構成を採用することは,当業者が容易に想到し得たことであるといえる。\nよって,相違点1に係る構成は,甲4発明及び技術常識から容易に想到\nすることができたものである。
・・・
(2) 上記を前提に,サポート要件違反について検討する。
ア 上記2(3)イのとおり,本件発明1の特許請求の範囲には,「所定の次数 オフセットqF」について,「油影響に関連して」設定されるものであるこ とのほかに具体的な設定の手法等についての特定はないから,「回転数適 応型の動吸振器(5)が,油影響に関連して,駆動装置の励振の次数qよ りも所定の次数オフセット値qFだけ大きい有効次数qeffに設計されてい る」とは,「油影響」を受ける状況下においては,動吸振器の次数が低下することから,任意の値の次数オフセットにより,動吸振器をオーバーチ ューニングしたという程度の意味に解される。 そして,本件明細書の発明の詳細な説明には,1) 図3に関連する【0 038】,【0039】の記載から,同じ設計の動吸振器であれば,回転 する油質量体の下では,次数値が低くオフセットされるから,その抑制次 数に相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが,遠心力 に抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 され,この記載の対応する限度では,当業者は,本件発明の課題(上記1(3)ウ)を解決できるものと認識できるといえる。 しかし,上記のとおり,特許請求の範囲には,次数オフセットqFについ ての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく,2) 本件明細書【00 43】のとおり,任意に設定された次数オフセットqFだけ高い次数値への 次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが,このような任 意に設定した次数オフセットqFをとった場合については,本件明細書の記 載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえな い。 そうすると,本件発明1は,当業者が発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるとはいえないから,サポート要件に適合するとはい えない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成29(ワ)10909等 損害賠償等請求事件(本訴),損害賠償請求反訴事件(反訴) 著作権 民事訴訟 平成31年2月15日 東京地方裁判所
ア 以上のとおり,被告が本件業務契約に基づかずに各経費を算入したこと により,本来分配すべき金員を理由もなく減額し,その分,本来原告が分 配を受けるべき金員を支払わなかったということができるのであるから, 原告は,被告に対して,未払収益分配金の支払を求めることができる。
イ 被告の原告に対する平成28年4月分から平成29年3月分までの未払 収益分配金は(下記4))は,別紙2のとおりである(式:(1)本件事業か らの収益金−2)算入すべき経費)÷2)−3)既払収益分配金)。 なお,平成29年2月及び同年3月における本件事業からの収益金は, グーグルからの売上げについては,平成29年2月が304万1745円, 同年3月が355万2469円であったと認められ(甲9の12,乙12 の1),その他の売上げについては,平成28年2月から平成29年1月 までの月平均売上金額に基づいて計算すると,別紙3のとおりであると認 められる。そして,同各月について計上すべき経費は,別紙1−11及び 1−12記載の各金額に前記第4の1(2)セのとおりマネタイズパート ナーのコンサルティング費用5万4000円をそれぞれ加えた金額である ので,同各月の被告の未払収益分配金は,別紙2のとおりの金額(小数点 一位は切下げ)となる。
(4) したがって,原告は,被告に対し,平成28年4月分から平成29年3 月分までの未払収益分配金として1148万2957円及びこれに対する 遅延損害金の支払を求めることができる。
・・・・
前記判示のとおり,被告は,原告に対し,本件業務契約に基づく収益分 配金の支払義務を履行しなかったのであるから,原告による債務不履行を 理由とする同契約の解除は有効であるということができる。 債務不履行解除に伴う逸失利益について,原告は,平成28年4月分か ら平成29年3月分までの収益分配金を基礎として5年間は同程度の収益 を上げることができたと主張する。 この点について,逸失利益の算定の基礎については,原告の主張すると おり,本件解除の直前である平成28年4月から平成29年3月までの収 益分配金に基づいて算定することが相当である。他方,逸失利益を認める 期間については,本件事業の売上げが平成27年頃に比べると減少してい ること,本件事業のようなポータルサイトは同様のサービスを提供する事 業者が出現するなどして比較的短期間で事業環境が変化する可能性がある\nことなども考慮し,2年間と認めることが相当である。 したがって,原告の被告に対する債務不履行に伴う逸失利益は3039 万7348円となる。 (計算式)1519万8674円(別紙2の3)及び4)の合計額)×2年 =3039万7348円
2019.03.12
平成30(ネ)10074 営業差止等請求,不正競争行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成31年2月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
争点(1)(控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権 1ないし3の移転登録請求権を有するか否か)について
(1) 被控訴人は,平成24年2月1日,商標1ないし3につき,自らの名で商標 登録出願し,これらの商標は,同年7月6日に設定登録されたものである。 そして,被控訴人は,商標1ないし3を自己の業務に係る役務について使用する 限り,商標法所定の要件のもとで,商標登録を受けることができる。このことは, 商標1ないし3が,本件営業譲渡契約の目的物である本件事業,すなわち,Aが開 発・実践することで注目を集めるようになったパーソナルトレーニングに関する業\n務に係る役務について使用するものであったとしても,同様である。 そうすると,商標権1ないし3が本件営業譲渡契約の目的物である本件事業から 発生したものということはできない。 したがって,商標権1ないし3が,本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復の 対象となり得ないことは明らかである。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,商標権1ないし3の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠 として本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権が存在すると主張する。 しかし,被控訴人は,本件営業譲渡契約の解除に基づき,控訴人を本件営業譲渡 契約の締結前の原状に復させる義務を負うにとどまるものである。控訴人は,本件 営業譲渡契約の締結前に,商標権1ないし3を有していたものではなく,商標1な いし3の商標登録出願により生じた権利を有していたものでもない。また,本件営 業譲渡契約の目的物である本件営業権等を有する者であれば,社会通念上,商標権 1ないし3を取得するということもできない。 したがって,本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権は,商標権1ないし3の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠にはならない。
イ 控訴人は,被控訴人は本件営業譲渡契約により商標権7の移転登録を受けて いたから,それに類似する商標3の商標登録出願について商標法4条1項11号の 不登録事由に該当することなく商標登録を受けることができた,商標1ないし3の おおもとは商標7である,などと主張する。 しかし,仮に,被控訴人が本件営業譲渡契約により商標権7の移転登録を受けて いたから,それに類似する商標3の商標登録を受けることができたものであるとし ても,商標権1ないし3は,被控訴人による商標登録出願を受けた設定の登録によ り発生したものである。被控訴人が商標権7を有していたことは,商標法4条1項 11号の不登録事由の不存在の根拠になったにすぎず,商標1ないし3のおおもと が商標7である,ということはできない。 したがって,商標1ないし3が商標登録されるに至った経緯を考慮しても,これ らの商標権が原状回復義務の対象になるということはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.03.12
平成30(行ケ)10143 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月27日 知的財産高等裁判所(1部)
商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「役務の…質,提供の用に 供する物…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当する\nというためには,需要者又は取引者によって,当該商標が,当該指定役務の質又は 提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足\nりるというべきである。そこで,本件商標の査定時において,本件商標が,本件役務の需要者又は取引者によって,本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得るか否かについて検討する。\n
(2) 「LOG」の使用状況
ア 役務の主体を表示するものとしての使用\n
証拠(各項末尾掲載のもの)によれば,本件商標の査定日以前において,次のと おり,役務を提供する主体の名称の一部に,「LOG」が使用されていたことが認 められる。
・・・
イ 役務の客体を表示するものとしての使用\n証拠(各項末尾掲載のもの)によれば,本件商標の査定日以前において,次のと おり,役務の提供の用に供する物の名称の一部に,「LOG」が使用されていたこ とが認められる。
・・・・
オ 以上によれば,本件役務に関する分野では,本件商標の査定日以前において, 役務の提供の用に供する物の内容について,それが丸太で構成される建物等である\nことを表示するために,その役務の主体や客体の名称の一部に,「LOG」と社会\n通念上同一と認められる「Log」「log」が数多く使用されるとともに,丸太 で構成される建物等に関するものであることを表\示するために,「Log」が他の 単語と組み合わさって使用されていたということができる。
・・・・
ウ 「丸太」を想起する過程
被告は,「LOG」が「丸太」の意味を認識させるのは,「ハウス」といった特定 の言葉と結合し,あるいは関連付けられた場合のみであり,「LOG」から「丸太」 の意味が一義的に想起されるものではないなどと主張する。 しかし,本件役務の提供の用に供する物は建物それ自体であり,かつ,前記(2) ないし(4)で認定したとおり,本件役務の分野において,「LOG」,「ログ」などが, 丸太で構成される建物等と関連付けられて使用されている事実は多数に及ぶもので\nある。そうすると,「LOG」が建物に関する単語と結合し,又は建物に関連付けられているか否かにかかわらず,「LOG」自体が,本件役務によって提供される 建物の種別について,丸太で構成される建物等という一定の内容を示しているであ\nろうと需要者又は取引者に明らかに認識させるというべきである。たとえ,「LO G」が,建物に関する単語と結合し,又は建物に関連付けられることで,丸太で構\n成される建物等を想起させることがあったとしても,「LOG」のみからも,本件 役務によって提供される建物の種別について,本件役務の需要者又は取引者に一定 の内容を想起させるものである。 したがって,「LOG」から「丸太」の意味が一義的に想起されないなどの被告 の前記主張は,結論に影響するものではない。
(7)小括
このように,本件商標の査定時において,「LOG」は,本件役務の提供の用に 供する建物の種別について,ログハウス,ログキャビンなどの丸太で構成される建\n物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを,本件役務の\n需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。したがって,本 件商標は,その査定時において,本件役務の需要者又は取引者によって,本件役務 の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る。\nよって,「LOG」は本件役務の質又は提供の用に供する物を普通に用いられる 方法で表示するものというべきであるから,「LOG」のみからなる本件商標は,\n本件役務との関係において,商標法3条1項3号に該当するものと認められる。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成30(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
訂正発明2の「庫内差圧検出手段」の意義等について
(ア) 訂正発明2の特許請求の範囲(請求項2)の記載によれば,訂正発 明2の「庫内差圧検出手段」は,「上記排気量制御手段により制御され る排気処理手段による上記暴露部の暴\露空間内のバイオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出」する検出手段であり,訂正発明2 においては,「上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内 差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され,上記排気量制御手段により 上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより,上\n記暴露部の庫内差圧を一定にする」ことを理解できる。\nまた,訂正発明2の特許請求の範囲(請求項2)中の「上記排気処理 部により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御するバイオ\nガスの排気量制御手段」との文言によれば,訂正発明2の「排気量制御 手段」は,「上記排気処理部により上記暴露部から排気するバイオガス\nの排気量を制御」する制御手段であることを理解できる。 そして,訂正発明2の特許請求の範囲(請求項2)の記載によれば, 訂正発明2の核酸分解処理装置は,「暴露部」の「バイオガスのホルム\nアルデヒド成分の濃度」の「ガス濃度情報」が「生成ガス量制御手段」 に帰還され,「上記生成ガス量制御手段」及び「上記排気量制御手段」 により「バイオガス発生部」における「生成ガス量」及び「暴露部」か\nら排気する「バイオガスの排気量」を制御することにより,「暴露部」\nの「庫内ガス濃度」を一定にし,かつ,「庫内差圧情報」が「排気量制 御手段」に帰還され,「上記排気量制御手段」により「暴露部から排気\nするバイオガスの排気量」を制御することにより,「暴露部」の「庫内差圧」を一定にすること,すなわち,「暴\露部」の「ガス濃度情報」及 び「庫内差圧情報」を基に,「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」 を制御し,「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一\n定にする制御を行うものであることを理解できる。 しかるところ,訂正発明2の特許請求の範囲(請求項2)には,「庫 内差圧検出手段」及び「排気量制御手段」の具体的な構造や装置構\成に ついて規定した記載はなく,また,「暴露部」の「庫内差圧」をいかな\nる数値又は数値範囲で一定にするのかについて規定した記載もない。
(イ) 次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,「本発明」の実施形態 として,核酸分解処理装置100の制御部150が,暴露部120に設\nけられたガス濃度センサ129から供給された暴露空間内のガス濃度\n情報に基づき,バイオガス発生部110へのエア供給量及びメタノール供給量の制御及び排気処理部140の排気ブロア143の吸入量の制 御により,暴露部120の庫内の濃度を一定にする制御を行うとともに,\n暴露部120に設けられた庫内圧力センサ132から供給された暴\露 空間内の圧力情報に基づき,排気処理部140の外気導入バルブ142 の開閉度及び排気ブロア143の回転数の制御により,陰圧範囲内を目 標値とした暴露部120の庫内差圧を一定にする制御を行うことが記\n載されている(【0028】,【0103】,【0111】,【014 0】〜【0148】,【0150】,【0161】〜【0164】,【0 182】,【0183】,図10)。これらの記載は,制御部150に より暴露部120の庫内差圧を陰圧の数値範囲に制御することを開示\nするものと認められる。 他方で,本件明細書の「本発明の実施の形態について,図面を参照し て詳細に説明する。なお,本発明は以下の例に限定されるものではなく, 本発明の要旨を逸脱しない範囲で,任意に変更可能であることは言うま\nでもない。」(【0026】)との記載に照らすと,本件明細書には, 「本発明の要旨を逸脱しない範囲」であれば,「本発明」の実施形態が 上記実施形態に限定されるものではないことの開示がある。 しかるところ,本件明細書には,「庫内差圧検出手段」及び「排気量 制御手段」を特定の構造や装置構\成のものに限定する記載はないし,また,「暴露部」の「庫内差圧を一定にする」にいう「一定」の数値範囲\nを定義した記載もない。
また,訂正発明2の特許請求の範囲(請求項2)の記載から,訂正発 明2の核酸分解処理装置は,「暴露部」の「ガス濃度情報」及び「庫内\n差圧情報」を基に,「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」を制御 し,「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一定にする制御を行うものであることを理解できること(前記(ア)),本件明細 書の発明の詳細な説明には,「本発明」は,訂正発明2の構成を採用し\nたことにより,フィードバック制御により暴露部の暴\露空間内における 温度,湿度,濃度の定量的制御を行うことができ,検体の種類に対応し た短時間で高効能を発揮する条件を定義することができるという効果を\n奏すること(【0021】,【0196】)の開示があること(前記(1) イ(イ))を総合すると,訂正発明2は,フィードバック制御により暴露\n部の暴露空間内の温度,湿度,「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の定\n量的制御を行うことにより,検体の種類に対応した短時間で高効能を発\n揮する条件を定義することができるようにしたことに技術的意義がある ことが認められる。 そして,訂正発明2の上記技術的意義に照らすと,「庫内差圧」を陰 圧の数値範囲に制御する必然性は見いだし難い。また,本件明細書全体 をみても,「庫内差圧」を陰圧の数値範囲に制御することによって,陽 圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的 意義があることについての記載も示唆もない。
(ウ) 以上の訂正発明2の特許請求の範囲(請求項2)の記載及び本件明 細書の記載に鑑みると,訂正発明2の「庫内差圧検出手段」の検出の対 象となる「庫内差圧」は,「庫内」(暴露部の暴\露空間内)の圧力と暴露空間外の圧力との差圧であれば,特定の数値範囲のものに限定される\nものではなく,陰圧の数値範囲のものに限定されるものでもないと解す べきである。 したがって,訂正発明2の「庫内差圧検出手段」は,「滅菌タンク内 がタンク外よりも陰圧であることを検出する庫内差圧検出手段」であっ て,滅菌タンク内のMRガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出するものであると限定解釈した本件審決の判断は誤りである。
イ 甲2の開示事項について
・・・
このように,甲2における「本発明」の第2の実施の形態は,ホルム アルデヒドガスの給排気状況に依存して生じる被殺菌空間の室内と室外 との圧力差を検出する微差圧検出器56を備え,微差圧検出器56によ り検出された検出値がコントロールユニット58に帰還(フィードバッ ク)され,コントロールユニット58により被殺菌空間内の室内から室 外に排気される空気に含まれるホルムアルデヒドガス等の排気量及び室 内に給気する空気の給気量を制御することにより,被殺菌空間の室内の 圧力を一定にするという構成を備えるものである。\nそうすると,甲2における「本発明」の第2の実施の形態の「微差圧 検出器56」,「コントロールユニット58」及び「排気量調整電磁弁 74及び送風機82」は,それぞれ,訂正発明2における「庫内差圧検 出手段」,「上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内差 圧情報が…帰還され」る「上記排気量制御手段」及び「上記排気量制御 手段により制御される排気処理手段」に相当するものと認められる。 したがって,甲2には,相違点2に係る訂正発明2の構成が開示され\nているものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2019.03. 3
平成30(行ケ)10136 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
原告は,Mainmarkグループは,ニュージーランドにおいて,「m ainmark」の欧文字からなる引用商標2を使用して多数の液状化対策 工事を施工し,高い売上高及び市場シェアを得ていること,ニュージーラン ド地震の象徴ともいえる「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震 災復旧工事を施工したこと,建築関係の専門雑誌においても豊富な経験と高 い技術を持つ企業として紹介されていること,日本の企業からも業務提携の 相手方とされていることなどからすれば,引用商標2は,Mainmark グループの役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時(登録出願日\n平成27年8月25日)及び登録査定時(登録査定日平成28年1月7日) において,ニュージーランドにおいて,需要者である建設業界の関係者又は その工事の注文者の間で,広く認識されていた旨主張するので,以下におい て判断する。
ア ニュージーランドにおける引用商標2の使用態様について
引用商標2が,Mainmarkグループの役務を表示するものとして,\nニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたというためには,引 用商標2が,Mainmarkグループの業務に係る役務に使用された結 果,自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り,Mainm\narkグループの役務であることを表示するものとして,ニュージーラン\nド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり,このこ とは,Mainmarkグループそのものが需要者の間に広く認識されて いたかどうかとは別個の問題である。 しかるところ,本件においては,引用商標2がニュージーランドにおい てMainmarkグループの業務に係る役務について具体的にどのよう に使用されていたのか,その具体的な使用態様を認めるに足りる証拠はな い。
イ ニュージーランドにおける売上高及び市場シェアについて
原告は,Mainmarkグループのニュージーランドにおける売上高 及び市場シェアに照らすと,本件商標の登録出願当時,取引者の間では, 引用商標2はMainmarkグループの業務に係る役務を表示するもの\nとして周知であった旨主張する。 そこで検討するに,原告は,Mainmarkグループのニュージーラ ンドにおける液状化対策事業に係る売上高を記載した書面として,Mainmarkグループのオーストラリア法人のA経理長の作成に係る書面(甲107の1)を提出するところ,同書面には,「Mainmarkの売上高」と題する表に,2003年から2017年までの会計年度ごとに,ニュージーランド及びオーストラリアの売上高とされる数字が記載されている。\nしかしながら,上記書面は,作成日付が記載されていない上に,作成経 緯も明らかではなく,通常業務として作成された会計の資料とは認められ ないものであり,作成に際し依拠した原資料も明らかではなく,記載内容 を裏付けるに足りる資料も提出されていないから,その信用性は低いとい わざるを得ず,同書面がMainmarkグループの売上高を正確に記載 したものであるとは認められない。他にMainmarkグループの売上 高を認めるに足りる証拠はない。 また,仮にMainmarkグループの売上高が上記書面記載のとおり であったとしても,Mainmarkグループによる引用商標2のニュー ジーランドにおける具体的な使用態様を示す証拠はないから,引用商標2 がMainmarkグループの役務であることを表示するものとして需要\n者の間に広く認識されるに至ったことを裏付けることはできない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
・・・・
このほか,ニュージーランドの「Geotech Consulti ng Ltd.」在籍の地盤エンジニア主任B作成の陳述書(甲73・ 訳文甲74)中には,「mainmark」という名称が地盤工学業界 においてよく知られており,この名称は,Mainmarkグループの 同義語として認識されている旨の記載部分があるが,上記記載部分を裏 付ける客観的な証拠はないことに照らすと,上記記載部分を直ちに措信 することはできない。他に引用商標2が本件商標の登録出願時及び登録査定時においてMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとしてニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。\n
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月26日 知的財産高等裁判所
本件は、経緯が複雑です。前訴では、前件審決が本件訂正のうち,請求項9及び10に係る訂正を認めなかった判断に誤りがあるとした上で,更に本件訂正後の請求項9ないし11に係る発明の容易想到性について審理し,これらの容易想到性を認めることはできない旨の判断をし,前件審決のうち,本件特許の請求項9ないし11に係る部分を取り消すとの判決(以下「前訴判決」という。)をしました。その後,前訴判決は,確定しています。
被告は,確定した前訴判決(取消判決)の拘束力に従って認定判断した本件 審決の取消しを求める本件訴訟は,前訴判決による紛争の解決を専ら遅延させ る目的で提起されたものであり,本件訴えの提起は,訴権の濫用として評価され るべきものであるから,本件訴えは,不適法であり,却下されるべきである旨主 張する。 そこで検討するに,原告主張の本件審決の取消事由中には,前訴判決が判断し なかった相違点についての本件審決の判断に誤りがあることを理由とするもの (前記第3の3(1)ア)が含まれていることに照らすと,本件訴えの提起が,前訴の蒸し返しであるものと直ちにいうことはできず,訴権の濫用に当たるものと認 めることはできない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
2 取消事由1−1(甲5を主引用例とする本件訂正発明9の進歩性の判断の誤 り)について
(1) 前訴判決の拘束力等について
確定した前訴判決は,請求項9に係る本件訂正を認めなかった前件審決の 判断に誤りがあるとした上で,1)前訴被告(本件訴訟の原告)は,本件訂正 による請求項9に係る訂正が認められる場合でも,本件訂正発明9は「引用 発明1」(本件審決の引用発明5)に基づき容易に想到できる旨主張し,前 訴原告(本件訴訟の被告)の反論も尽くされているので,進んで,本件訂正 発明9の容易想到性について判断する,2)本件訂正発明9と「引用発明1」 は,前件審決が認定した本件発明9と「引用発明1」との相違点9−2に加 えて,少なくとも相違点9−A及び相違点9−Bの点でさらに相違すること が認められる,3)相違点9−Aに関し,「引用発明1」の製造方法は,本件 訂正発明9の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し,銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く),それにより発生す る空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なることが明らかであり,甲 5は,銀フレークを端部でのみ焼結させて,端部を融合させる方法を開示す るにとどまり,焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって, 銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり,端部でのみ融着する 場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではないから,「引用発明1」に基づいて,相違点9−Aに係る構成を想到するこ\nとはできない,4)よって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂 正発明9は,当業者が,「引用発明1」に基づき容易に想到できるというこ とはできない旨判断し,前件審決のうち,本件発明9は甲5に記載された発 明と周知技術に基づいて容易に発明をすることができたことを理由に,本件 特許の請求項9に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消した。 前訴において,原告は,平成29年5月29日付け準備書面(1)(甲5 6)に基づいて,甲5には,「銀フレークがその端部(銀フレークの周縁部 分)でのみ融着している場合」の記載がないから,甲5に記載された発明は, 銀フレークがその端部(銀フレークの周縁部分)でのみ融着している構成の\nものとはいえず,相違点9−Aは,本件訂正発明9と甲5に記載された発明 の相違点ではない旨主張した。これに対し被告は,同年6月29日付け準備 書面(原告その2)(甲53)に基づいて,甲5には,端部(周縁部分)を 有する銀フレークを用い,該銀フレークの端部(周縁部分)のみで,銀フレ ーク同士を融着させる製造法であり,銀フレークの周縁部分のみ融着した導 電性材料を得られるものであることについて十分にサポートされている旨主\n張し,原告の上記主張を争った。
前訴判決の上記認定判断及び審理経過によれば,前訴判決が前件審決のう ち,本件特許の請求項9に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消すとの結論を導いた理由は,本件訂正を認めなかった前件審決の判断に誤 りがあること,本件訂正後の請求項9に係る発明(本件訂正発明9)は,当 業者が甲5に記載された発明に基づいて相違点9−Aに係る本件訂正発明9 の構成を容易に想到することができないから,甲5に記載された発明に基づ\nき容易に発明をすることができたとはいえないとしたことの両者にあるもの と認められ,かかる前訴判決の理由中の判断には取消判決の拘束力(行政事 件訴訟法33条1項)が及ぶものと解するのが相当である。 そして,前訴判決確定後にされた本件審決は,前訴判決と同様の説示をし, 本件訂正発明9は,当業者が甲5に記載された発明(引用発明5)に基づいて相違点9−3(相違点9−Aと同じ)に係る本件訂正発明9の構成を容易\nに想到することができないから,その余の点について判断するまでもなく, 引用発明5に基づき容易に発明をすることができたとはいえないと判断した ものである。 そうすると,本件審決の上記判断は,確定した前訴判決(取消判決)の拘 束力に従ってされたものと認められるから,誤りはないというべきである。
(2) 原告の主張について
原告は,1)前訴判決は,本来,専門的知識経験を有する審判官の審判手続に より審理判断をすべき本件訂正発明9の無効理由について,審判官の審判手続に よる審決を経ずに,技術常識を無視した認定判断をしたものであり,最高裁昭和 51年3月10日大法廷判決の趣旨に反するものであるから,前訴判決の上記 認定判断に拘束力を認めるべきではなく,前訴判決の拘束力に従った本件審決 の相違点9−3の認定及び判断は誤りである,2)甲5の図3,甲40の【0 033】ないし【0035】及び図5の記載事項に照らすと,甲5記載の銀 粒子融着構造は,本件訂正発明9の銀粒子融着構\\\造と一致するから,本件審 決における引用発明5の認定に誤りがあり,その結果,本件審決は,相違点 9−3の認定及び判断を誤ったものである旨で主張する。 しかしながら,上記最高裁大法廷判決は,特許無効の抗告審判で審理判断さ れなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において新たに主張することは許されない旨を判断したものであるところ,前訴判決 は,前件審決で審理判断された甲5を主引用例として,甲5に記載された発 明と本件訂正発明9とを対比し,本件訂正発明9の進歩性について判断した ものであり,上記最高裁大法廷判決は,前訴判決と事案を異にするから,本件 に適切ではない。 次に,前訴判決が,前記(1)のとおり,前訴被告(本件訴訟の原告)は,本件訂正による請求項9に係る訂正が認められる場合でも,本件訂正発明9は 「引用発明1」に基づき容易に想到できる旨主張し,前訴原告(本件訴訟の 被告)の反論も尽くされているので,進んで,本件訂正発明9の容易想到性 について判断するとした上で,甲5を主引用例とする本件訂正発明9の進歩 性について判断したことは,裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に 属する事柄であるといえるから,相当である。 さらに,原告は,本件審決における相違点9−3の認定及び判断に誤りが あることの根拠として,前訴判決と同一の引用例である甲5とともに,甲4 0を挙げるが,甲40は,甲5の記載事項の認定に関する原告の主張を補強 する趣旨で提出されたものであって,新たな公知事実(引用例)を追加する ものではないから,前訴判決の拘束力を揺るがすものとはいえない。 したがって,本件審決における相違点9−3の認定及び判断に誤りがある との原告の上記主張は,理由がない。
◆判決本文
前訴判決はこちらです
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(ネ)10046 承継参加申立控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年2月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
2 本件各発明の内容は前記1のとおりであるが,本件各発明が控訴人の従業員 によって発明されたと認めることができるかについて,以下検討する。
(1) 本件発明1について
ア 本件発明1と控訴人発明とを対比する。
(ア) 本件発明1と対応する控訴人発明は,別紙「控訴人発明と本件特許権 1との構成要件の対比」の対比表\の「控訴人の発明内容」欄記載の発明であるとこ ろ,同記載によると,控訴人発明が共通構成1を具備していないことは明らかであ\nる。 すなわち,共通構成1の構\成は,別紙「控訴人発明と本件特許権1との構成要件\nの対比」の対比表の「請求項の内容」欄のうち,「請求項1」の上から3番目及び\n4番目の欄,「請求項2」の欄,「請求項3,請求項4」の欄,「請求項3」の欄、 「請求項5」の欄、「請求項6」の欄,「請求項7」の上から2番目の欄,「請求項 8」の欄,「請求項9」の上から3番目の欄,「請求項10」の欄,「請求項11」 の上から2番目の欄,「請求項12」の欄,「請求項13」の上から2番目の欄に記 載されているが,同構成に対応する「控訴人の発明内容」欄に記載された構\成は, 共通構成1の「前記画像情報,前記位置情報,前記識別情報の順の変化に応じて,複数の,前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記携帯端末装置に提供する」\nこと(「前記画像情報,前記位置情報,前記識別情報の順の送信に応じて,複数の, 前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記情報処理装置から受信する」こと) と同一でないことは明らかである。また,上記対比表の「控訴人の発明内容」欄の\nその他の欄の記載に係る構成中に,共通構\成1と同一の構成が存在すると認めるこ\nともできない。
(イ) 控訴人は,控訴人発明は,起動情報として,1)画像情報,2)位置情報 及び3)識別情報を用いている旨主張する。 しかし,共通構成1は,起動情報として,上記の三つの情報を含むというだけで\nはなく,これらの三つの情報の順の変化に応じて,複数のコンテンツを提供すると いう構成であるから,控訴人の上記主張を踏まえて控訴人発明の構\成を特定したと しても,控訴人発明の構成は,共通構\成1と同一であるとはいえない。 イ 前記アのとおり,控訴人発明の構成は,本件発明1の構\成と異なるので あるから,その余の点を検討するまでもなく,本件発明1は,控訴人の従業員に よって発明されたと認めることはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(ネ)20 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成31年2月21日 大阪高等裁判所
控訴人は,被控訴人が,被告標章2を商標として使用していると主張し,当 審においては,その理由として前記第2の5(1)のとおり述べる。しかし,次の とおり,いずれの主張も採用することはできない。
(1) 標章が商品の型式名の一部として使用されることについて
控訴人は,従来の裁判例において商標としての使用が否定され得る使用態 様として,1) 標章が単に商品等の属性・内容・由来等について説明するため の表示として付されていたり,別の商品の名称,種類等を示す表\示として付 されていたりすると認識される場合,2) 標章が商品等の装飾・意匠として付 されていると認識される場合,3) 標章が専ら商品の宣伝のためのキャッチフ レーズや宣伝文句として付されていると認識される場合を挙げ,本件はその どれにも当たらないと主張する。 そこで,本件における被告標章2の使用態様を検討すると,上記2),3)に 当たらないことは明らかである。しかし,引用に係る原判決「事実及び理由」 第3の5(5)イのとおり,被告標章2は,専ら,極めて多数の型式が存する被 告商品の中で,基本となる型式,発光色,寸法等を間違いなく発注,納品等 し得るようにするための型式名の一部として用いられており,それ以外の役 割を果たしていると認めることができないので,上記1)に準じて考えること ができる。また,この点を措くとしても,後記(2)のような使用態様に照らすと,被告標章2は,商品の出所を表示したり,顧客を吸引したりする機能\を 有していないというべきである。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) 被告標章2の使用態様について
控訴人は,現在の被控訴人のカタログやウェブサイトに被告標章2が直接 表示されていないからといって,被告標章2が商標として使用されているこ\nとを否定する根拠とはならないと主張する。 しかし,商標としての使用というためには,出所表示機能\を発揮する態様での使用でなければならないので,どのような態様で表示されているかが重\n要であるところ,引用に係る原判決「事実及び理由」第3の5(5)のとおり, 被控訴人が現在使用する本件カタログに被告標章2が表示されていないだけ\nでなく,被告標章2に相当する記載は,製品の仕様の詳細を示す一覧表にお\nける型式名の一部として,あるいは製品の仕様及び価格を列挙した価格表に\nおける型式名の一部として表示されるにとどまっている。\n以上によると,被告標章2が商標として使用されていると認めることはで きない。
(3) 画像処理用LED照明装置の取引の実情について
控訴人は,画像処理用LED照明装置の分野において,商品名(型式名) のみで商品を特定する取引が少なからず行われていると主張し,証拠(甲2 6,27,29)を提出する。 たしかに,甲26(現品票)及び甲27(請求書)には,同装置の売買に 際し,型式名をもって商品を特定していることが認められる。しかし,これらの文書は,商品の購入が決まり,注文があった後に作成されたものである。 そして,当該商品を注文するに至るまでの間,どのようなやり取りがされた か不明であり,上記各文書に記載された型式名だけで注文が行われたとまで 認めることはできない(これらの文書に記載された型式名は,前記(1)のとお り,基本となる型式,発光色,寸法等を間違いなく発注,納品等し得るよう にするために使用されているものということができる。)。 また,甲29によれば,インターネット通販サイトにおいて,「日進電子 工業 直接照射照明 リング型 DRシリーズ」と「CCS(シーシーエス) リ ング照明 LDR2シリーズ」の表示のもとに,各商品が販売されていること\nが認められる。このようにメーカー名も左上部に表示されていることからも,\n需要者において型式名のみで商品を買い受けているとは認め難い。
(4) 以上のとおりで,被告標章2は,商標としては使用されていないと認められる。
4 本件商標1に係る商標権の損害額について
被控訴人が被告標章1を使用したことによる控訴人の損害額,被控訴人の不 当利得額について検討する。なお,本件商標1登録後の平成23年9月1日か ら平成29年7月31日までの被控訴人の売上を算定の基礎とすることは争 いがない。
(1) 損害の基礎となる金額
ア 被告商品の売上総額
被控訴人における平成24年12月1日から平成25年10月31日 までの被告商品の売上高は3億0191万5347円,同年11月1日か ら平成29年7月31日までの売上高は12億5406万9731円,合 計15億5598万5078円であった(争いがない)。 なお,控訴人は,平成23年9月1日から平成25年10月31日の間 について不当利得の返還を請求するが,被控訴人は,平成24年12月1 日から平成25年10月31日までの間の売上高を開示し,その額は上記 のとおり3億0191万5347円である。控訴人は,同額を平成23年 9月1日から平成25年10月31日までの算定の基礎とすることとし た。
イ 被告標章2を付した商品の売上額 一方,被告商品のうち,被告標章2を付した被告商品1−1−1ないし 6の,平成18年11月1日から平成25年10月31日までの売上高は 4848万1830円,同年11月1日から平成29年7月31日までの 売上高は2012万6460円,合計6860万8290円であった(争 いがない)。
ウ 算定の基礎となる金額
被告標章1は,被告商品に付されているのではなく,カタログに使用されているので,これによる個別の損害額を算定することは困難であるが, 商標の自他識別機能を害する形態で使用されているので,不法行為に基づ\nく損害賠償として使用料相当額の請求が認められる(商標法38条3項)。 また,不当利得返還請求としても使用料相当額を認めることができる。 ところで,前記3に説示したとおり,被告標章2については商標権侵害 が成立しないところ,被告標章1の使用にかかる販売額を算定するに当た り,前記イの額を控除する必要はない。 したがって,控訴人が算定の基礎として主張する,平成23年9月1日 から平成29年7月31日までの「被告標章1固有の販売額」は,前記ア の15億5598万5078円ということになる。
(2) 使用料相当額
被告標章1は,本件カタログの比較的目立つ位置に掲載されているところ, 顧客がこれに目にする可能性は高いが,「照明の解決」という意味内容は,\n被告商品及び役務の特長を直接的に表すものであり,一定の顧客吸引力を有\nすると認められるものの,照明装置のカタログに付すものとしては,常識的 な発想の範囲内の言葉である。 引用に係る原判決「事実及び理由」第3の5(4)のとおり,画像処理用LE D照明装置の需要者・取引者が商品に求めるものは特定の機能や性能\であり, 一定期間の検討を経て購入の決定に至るのが一般的と考えられ,一般家庭用 の商品でもないから,カタログに記載された文言が顧客を強く吸引し,購入 の有無に強く影響するということも考え難い。また,被告標章1は,平成2 7年の本件カタログには使用されているものの,従前のカタログ(平成8年, 11年,15年,16年)には使用されておらず,価格表やウェブサイト,\nあるいは被告商品自体に付された事実もなく,被告標章1が,被告商品に関 する惹句として,あるいは企業としての被控訴人自体を需要者に印象付ける 語句として,継続的に,あるいは広範囲に使用されたとの事実を認めることはできない。よって,上記認定した被告標章1の顧客吸引力の程度,被告標章1使用の 態様を総合すると,被告標章1が被控訴人の取引に影響した程度は極めて低 いというべきであり,支払うべき許諾料相当額は,不法行為及び不当利得に 基づく請求のいずれの期間においても,算定の基礎となる被控訴人の売上高 の0.2%と認めることが相当であるから,その額は311万1970円(不 当利得につき上記3億0191万5347円の0.2%である60万383 1円,不法行為につき上記12億5406万9731円の0.2%である2 50万8139円)となる。
◆判決本文
1審判決はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(行ケ)10073 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月7日 知的財産高等裁判所
ウ 本願発明1は,インクカートリッジICチップに関し,前記イのような インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことを課題とする(【0 001】,【0006】)。
(3) 前記1によると,「課題を解決するための手段」欄のインクカートリッジI Cチップに係る記載(【0007】〜【0009】)には,本願発明1に含まれるイ ンクカートリッジICチップの構成が記載されているが,このようなインクカートリッジICチップの構\成とすることにより,前記(2)ウのインクカートリッジ位置の 検出過程における誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆も なく,当業者が本願出願日当時の技術常識に照らしても,上記記載のみによって, 本願発明1の課題を解決できると認識できるものとは認められない。 そこで,実施例の記載を見ると,本願明細書には,具体的な実施例として,少な くともインタフェースユニットと制御ユニットを含み,インタフェースユニットは, イメージング装置に電気的に接続され,イメージング装置から送られる光制御指令 の受信に用いられ,前記光制御指令は,インクカートリッジICチップ上の発光ユ ニットを発光させるのに用いられる発光指令を含み(本願発明1とは異なり,消光 指令を含むか否かは明らかでない。),制御ユニットは,前記インタフェースユニッ トが光制御指令を受信したときに,インクカートリッジICチップの状態に応じて その光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられるインクカートリッジ ICチップにおいて,前記インクカートリッジICチップの状態は,実行可能な状\n態と実行不可能な状態を含み,前記制御ユニットは,前記インタフェースユニット\nが発光指令を受信したときに,前記インクカートリッジICチップが実行可能な状\n態にある場合,前記発光ユニットを発光させるのに用いられる実施例が記載されて いる(【0016】,【0017】)。この実施例は,発光指令を受信したときに, インクカートリッジICチップが実行可能な状態にある場合には,その発光指令を実行\nするものであるが,これを含む上記実施例のように構成することにより,前記(2)ウ のインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができる理由に ついては何らの記載も示唆もなく,当業者が本願出願日当時の技術常識に照らして も,上記実施例の記載のみによって,本願発明1の課題を解決できると認識できる ものとは認められない。上記実施例記載のインクカートリッジICチップを用いて も,前記(2)ア・イの従来技術と同じ機会に同じインクカートリッジのみが発光する ように,発光指令が実行可能な状態において受信される構\成では,本願発明1の課 題が解決できないことは明らかである。
また,本願明細書には,本願発明1に含まれる実施例として,第1種のインクカ ートリッジICチップ(【0021】〜【0033】),第2種のインクカートリッジ ICチップ(【0035】〜【0042】),第5種のインクカートリッジICチップ (【0056】〜【0057】)が記載されており,発光指令を受信したときに,イ ンクカートリッジICチップが実行可能な状態にある場合には,その発光指令を実\n行し,実行不可能な状態にある場合には,その発光指令を実行しないものであるが\n(【0021】,【0026】,【0035】,【0056】),これを含む上記各実施例のように構成することにより,前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程におけ る誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆もなく,当業者が 本願出願日当時の技術常識に照らしても,上記各実施例の記載のみによって,本願 発明1の課題を解決できると認識できるものとは認められない。なお,第3種のイ ンクカートリッジICチップ(【0044】〜【0050】)及び第4種のインクカ ートリッジICチップ(【0051】〜【0055】)は,インクカートリッジIC チップの状態はインクカートリッジICチップの指令受信状態であり,指令受信統 計ユニットに記録された指令受信状態に応じて,インタフェースユニットが受信し た光制御指令を実行するかどうかを制御するものであるから,本願発明7及びこれを更に限定した本願発明8〜13に係る実施例であって,インクカートリッジIC チップの状態が実行可能な状態と実行不可能\な状態とを含むものではない点におい て,本願発明1に含まれる実施例とは認められない。 さらに,本願明細書には,正対位置検出とそれに引き続く隣接光検出とからなる インクカートリッジ位置検出について,初期状態で発光指令を実行できる状態とさ れているインクカートリッジICチップにおいて,1)インクカートリッジの正対位 置検出のために,そのインクカートリッジを発光させる発光指令を受信した場合に は,発光指令を実行できる状態に応じて,その発光指令を実行して,そのインクカ ートリッジを発光させる(発光指令を実行できる状態のその余のインクカートリッ ジも発光させる。)とともに,そのインクカートリッジを発光させる発光指令を実行不可能な状態とし,2)次いで受信する消光指令を実行してそのインクカートリッジ を消光し(前記1)で発光させたその余のインクカートリッジも消光させる。),3)以 後,隣接光検出等のために,発光指令を受信した場合には,実行不可能な状態に応\nじて,その発光指令を実行しないように制御する実施例が記載されている(【002 0】,【0024】,【0084】〜【0091】)。上記実施例の記載によると,正対位置検出時に比し,隣接光検出時に一部の隣接インクカートリッジの発光をカット することにより,正対位置検出時に受光部に届く光の量が条件を満たすようにしな がら,隣接光検出時には受光部に光が届かない又はわずかな光しか届かないように して,イメージング装置の誤報率を減らすことができ,本願発明1の課題を解決で きると認識することができる。 そして,本願明細書には,「イメージング装置の種類によっては,そのインクカー トリッジの数,インクカートリッジ装着方法,検出順番と検出方法等も異なるため, 上記のインクカートリッジ検出に関する説明はあくまでも参考例に過ぎ」ない旨記 載されているが(【0092】),検出順番や検出方法等が異なるイメージング装置に ついて,適切な制御手順を構築する方法についての記載や示唆はないし,上記実施\n例(【0020】,【0024】,【0084】〜【0091】)以外に,前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができ,本願発明1 の課題を解決できると認識することができる実施例は見当たらない。
そうすると,本願明細書に接した当業者は,本願発明1のうち,上記実施例(【0 020】,【0024】,【0084】〜【0091】)に該当するものについては,本願発明1の課題を解決できると認識するが,本願発明1のうち,その余の構成のも\nのについては,本願発明1の課題を解決できると認識することはできないと認めら れる。
(4) 本願発明1は,前記第2の2(1)のとおりであり,「前記制御ユニットは,前 記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに,インクカートリッジI Cチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御する」について,「インクカートリッジICチップの状態」である「実行可能な状態」と「実行不可\n能な状態」のそれぞれに応じて,「光制御指令を実行するかどうか」をどのように制\n御するのかが特定されておらず,また,「インクカートリッジICチップの状態」の 設定や変更についても特定されていないから,上記実施例(【0020】,【0024】,【0084】〜【0091】)のものに限定されていないことは明らかである。 そうすると,本願発明1は,発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり,本願発 明1に係る特許請求の範囲の記載は,特許法36条6項1号(サポート要件)に適 合するものとは認められない。
(5) 前記1によると,本願明細書の【0084】,【図5】においては,発光指令 を受信したときは,発光標識部の状態に応じて,発光標識部が実行可能な状態にあ\nる場合には,発光指令を実行することにより発光ユニットを発光させ,発光標識部 が実行不可能な状態にある場合には,発光指令を実行しないことにより発光ユニッ\nトを発光させない一方,消光指令を受信したときは,発光標識部の状態にかかわら ず,消光指令を実行することにより発光ユニットを消光させることが記載されてい る。また,本願発明1に含まれる【0095】,【図10】においても,判断の手順 こそ違うものの,同様に,発光指令を受信したときは,発光標識部の状態に応じて, 発光標識部が実行可能な状態にある場合には,発光指令を実行することにより発光\nユニットを発光させ,発光標識部が実行不可能な状態にある場合には,発光指令を\n実行しないことにより発光ユニットを発光させない一方,消光指令を受信したときは,発光標識部の状態にかかわらず,消光指令を実行することにより発光ユニット を消光させることが記載されている。このような実施例の存在を参酌すると,本願 発明1に係る特許請求の範囲請求項1の記載から,インクカートリッジICチップ の状態が実行可能な状態にある場合には,光制御指令(発光指令と消光指令を含む)\nを実行し,インクカートリッジICチップの状態が実行不可能な状態にある場合に\nは,光制御指令(発光指令と消光指令を含む)を実行しないものと一義的に解釈することはできず,この点からしても,インクカートリッジICチップの状態である 実行可能な状態と実行不可能\な状態のそれぞれに応じて,光制御指令を実行するか どうかをどのように制御するのかは特定されていないというべきである。この点に ついて,原告は,本願明細書の【0099】の実施例には,インクカートリッジI Cチップの状態が実行不可能な状態であれば,消光指令を実行しないことが記載さ\nれているなどと主張するが,前記1のとおり,上記実施例は,「発光カウントユニッ トを設置し,発光ユニットが発光したときにカウントを開始し,発光カウントユニ ットがある所定値までカウントすると,自動的に発光ユニットを消光させる」もの であり,発光指令,消光指令の実行の有無の制御という本願発明1の発明特定事項 とは異なる方法を付加して発光ユニットの消光を達成するものである上,上記実施 例を考慮したとしても,本願発明1に係る特許請求の範囲請求項1の記載が多義的 であることが示されるにすぎず,上記判断を左右するものではない。 そうすると,本願発明1は,発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり,本願発 明1に係る特許請求の範囲の記載は,特許法36条6項1号(サポート要件)に適合するものとは認められない。
(6) 原告は,本願発明1の制御ユニットは,インクカートリッジICチップが実 行可能状態にある際に,発光指令を含む光制御指令を受け付けた場合,これに応じ\nて発光ユニットを発光させる制御を実行し,実行不可能状態にある際に,発光指令\nを含む光制御指令を受け付けても,発光ユニットの発光を実行しないから,本願明 細書の【図8a】〜【図8c】,【0087】〜【0090】に記載した検出を行う ことができ,ひいては「誤報率を減らす」という課題を解決することができること を当業者であれば理解することができるなどと主張する。 しかし,本願発明1の特許請求の範囲の記載が本願明細書の【図8a】〜【図8 c】,【0087】〜【0090】の実施例のものに限定されていないことは,前記 (4)認定のとおりであるから,本願発明1は,サポート要件に適合しないものである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.02.25
平成30(ネ)960 不正競争行為差止等,損害賠償,損害賠償等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成31年2月14日 大阪高等裁判所
控訴人は,上記のうち秘密管理性の点につき,本件技術情報は,電子デー タと電子データを印刷した紙ベースで保管され,それらの情報にアクセスで きる者を福島工場の従業員18人と役員等の限られた控訴人の従業員に限り, また,就業規則に従業員の秘密保持義務を定めるほか,秘密保持の誓約書の 提出を受けていた旨主張するとともに,それらの従業員は,本件技術情報が 控訴人にとって重要な技術情報であり,社外に持ち出したり,漏洩したりし てはいけない秘密の情報であることは十分に認識できていたから,営業秘密\nとして管理されていたと主張する。 証拠(甲31の1〜31の18,甲32,33,36)によれば,控訴人 主張の情報の管理状況や,就業規則の定め,従業員から誓約書を徴求してい る事実が認められ,その対象の情報が控訴人において重要な技術情報である と認識できるとの点も,そのとおり認めることができる。
(3) 外注先との関係における管理について
証拠(甲93の1〜93の4)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人が外注 先と製作請負契約を締結するに当たり,控訴人が外注先に対して貸与した物 件等を対象とした秘密保持契約を文書により締結することがあったことが認 められる。しかし,証拠として提出された当該秘密保持契約に係る契約書は, 平成14年の作成日付のもの2通と,平成15年の作成日付のもの及び平成 21年の作成日付のもの各1通にとどまる。 また,控訴人代表者の陳述書(甲21)には,控訴人が被控訴人サン・ブ\nリッドから控訴人製品の部品の一部の供給を受けていた旨の記載がある一方, 控訴人は,被控訴人サン・ブリッドではなく,被控訴人太陽工業から控訴人 製品の部品の一部の供給を受けていたことを認めている。控訴人が部品の供 給を受けていたのが被控訴人太陽工業らのうちいずれであれ,その際には, 控訴人から被控訴人太陽工業らに対して,少なくとも当該部品を製造するの に必要な範囲で,控訴人製品の図面等の情報が交付されていたことを推認で きるが,控訴人と被控訴人太陽工業らとの間で秘密保持契約が締結された形 跡はない。
(4) 被控訴人銀座吉田等との関係における管理について
被控訴人銀座吉田は,前提事実(1)エ,(2)アのとおり,平成6年頃から, 香港,シンガポール及び中国における控訴人の唯一の代理店として,控訴人製品の販売及びメンテナンスサービスを担当していたのであるから,控訴人 は,長年にわたり,被控訴人銀座吉田に対し,それらの業務に必要な,控訴 人製品に関する図面等の情報を数多く交付してきたことが推認される。 そして,被控訴人銀座吉田は,控訴人から交付を受けた控訴人製品に関す る図面等の情報で,本件技術情報を含むものの例として,戊1号証から戊6 4号証までを提出する。これらのうち,控訴人が,自ら交付したことを積極 的に争っておらず,かつ,本件訴訟において,控訴人の営業秘密に関する記 述があるとして,民事訴訟法92条1項2号に基づき,閲覧等の制限を申し\n立てた部分の内容は,次のとおりである。
・・・
上述のとおり,控訴人内部における本件技術情報の管理状況については控 訴人の主張どおり認められるものの,控訴人が外注先に対して控訴人製品の 図面等の情報を交付する際には,必ずしも秘密保持契約を締結しておらず, むしろ締結しなかった方が多かったことがうかがわれる。また,控訴人は, 香港,シンガポール及び中国における控訴人の唯一の代理店として,控訴人 製品の販売及びメンテナンスサービスを担当していた被控訴人銀座吉田に対 しても,長年にわたり,少なくとも本件技術情報の一部を含む多くの技術上 の情報を交付しながら,秘密保持契約を締結することも,交付した情報の取 扱いや用済み後の回収について何らかの要請をすることもなかったと認めら れる。控訴人が,被控訴人銀座吉田に対し,控訴人の交付する技術上の情報 を秘密として管理されるべきものであることを表明した形跡はない。\nまた,控訴人は,長年にわたり,被控訴人銀座吉田に対し,香港等におけ る控訴人製品の販売及びメンテナンスサービスの業務に必要な図面等の情報 を数多く交付してきたことが推認されるので,本件技術情報のうち,PLC プログラム等一部のものについてのみ,被控訴人銀座吉田との関係において, 他の情報と異なる管理がされていたと認めることもできない。 そうすると,本件技術情報は,全て,不競法にいう「秘密として管理され ていた」とは認められないというべきである。
◆判決本文
原審はこちらです。
2019.02.22
平成30(行ケ)10104 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明が,「断熱性に優れた発泡 積層シートを成形してなる容器において,端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固 に止着させうる容器の提供」(【0009】)を「発明が解決しようとする課題」とし ていることが,当該課題に直面するに至った背景(【0002】〜【0007】)と ともに記載され,当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解 決手段」が,【0010】に記載され,これにより,本件発明の容器が,「断熱性に 優れ,上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ,下面側が平坦 に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」 (【0012】)という効果を奏し,上記課題を解決することが記載されているから, 本件明細書の発明の詳細な説明には,発明が解決しようとする課題及びその解決手 段が記載されており,当業者は,その技術上の意義を理解することができる。 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,特許法施行規則24条の 2で定めるところにより,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十\n分に記載したものということができ,特許法36条4項1号に規定する要件を満た している。
イ(ア) 原告は,断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい て,その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体,本件明細書の発 明の詳細な説明には,客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし,仮 に怪我が生じ得るとしても,本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で きることが,発明の詳細な説明において,何ら客観的・科学的な証明はされていな い旨主張する。 しかし,「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において,その端縁 部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については,発泡積層シートの熱 可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか, 発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった か(圧縮の程度),発泡積層シートの切断面の状態,発泡積層シートに対して指先等 がどのように接触するか(指を押し当てる強さ,指を移動させる方向・早さ等)に 応じて,怪我が生じる可能性があることは,当業者において,客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき,「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も,\n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積 が異なる結果,怪我を防止することができることも,当業者において,客観的・科 学的な証明がなくとも容易に理解できるから,原告の上記主張には理由がない。
(イ) 原告は,1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬 さの差により,切断面(外側端面)に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい 熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり,且つ熱可塑性樹脂フィ ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく,容器に触れた際に,硬いフィルムで指等 を裂傷する虞があり」(【0005】)との記載には根拠がない,2)「フィルム端縁で 指等を裂傷するという課題を解決するために,突出部の上下面にジグザグとなる凹 凸を形成させる」(【0007】)との記載は,特許文献3(甲21)に記載されてい る,それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成\nされた容器に関するもので,本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ ルムとは異なると主張する。 しかし,上記1),2)については,前記(ア)のとおりであって,特許文献3(甲21) に記載されているのが薄手のシートの成形品で,本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって,前記(ア)の認定は左右されない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.02.22
平成30(行ケ)10129 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月19日 知的財産高等裁判所(4部)
以上のとおり,原告使用商標においては,楕円状リングの図形部分 によって,外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間に配置された文 字部分と,内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とがま とまりよく配置されており,これらの文字部分及び図形部分はひとまと まりのものとして看取されることに照らすと,原告使用商標に接した需 要者においては,原告使用商標は,ひとまとまりの文字部分及び図形部 分からなる結合商標として認識されるものであって,原告使用商標のう ちの引用商標1の構成に相当する部分(楕円状リングの図形部分,「d\niptyque」の文字部分,「paris5e」の文字部分及び「3 4 boulevard saint germain」の各文字部分) が,独立の商標として認識されるものと認めることはできないい。 したがって,原告による原告使用商標を付した原告商品の販売が引用 商標1の使用に当たるものと認めることはできない。
ウ 以上によれば,原告が原告商品に引用商標1を独立の商標として使用し た事実は認められないから,引用商標1及びその構成中の楕円状リングの\n図形部分が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,使用による 識別力を獲得し,原告の業務に係る原告商品を表示するものとして需要者\nの間に広く認識されていたものと認めることはできない。 エ(ア) これに対し原告は,原告が2008年(平成20年)5月に挙行し た原告商品の新商品発売パーティーに,女性向け雑誌又はファッション 雑誌の編集長や編集者など149名が参加し,これらの雑誌に原告商品 が掲載されたことは,平成20年当時既に原告商品及び引用商標1が周 知であったことを裏付けるものである旨主張する。 しかしながら,上記新商品発売パーティーに女性向け雑誌又はファッ ション雑誌の編集長や編集者が参加した事実から直ちに引用商標1が周 知であったことを裏付けることはできないし,また,原告商品の雑誌へ の掲載についても,引用商標1が単独で付された原告商品が掲載された というものではないから,引用商標1が周知であったことを裏付けるこ とはできない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
(イ) また,原告は,原告商品の需要者は,原告商品を初めて知り,それ らに接する初期の段階では,原告商品に付された原告使用商標の構成中\nの楕円状リングの図形部分及び「diptyque 34 boule vard saint germain paris5e 34 bo ulevard saint germain」の文字部分(引用商標 1の構成に相当する部分)を見て原告商品と認識するかもしれないが,\n原告使用商標の構成中の上記文字部分の文字は小さく,かつ,楕円状リ\nングの図形部分の内側の文字や図形等は商品ごとにそれぞれ異なること から,やがて上記文字部分又は楕円状リングの図形部分の内側の文字や図形等をいちいち見なくとも,楕円状リングの図形部分を一瞥すること により,原告商品であると認識するといえるから,引用商標1の構成中\nの楕円状リングの図形部分は,本件商標の登録出願時及び登録査定時に おいて,使用による識別力を獲得した旨主張する。 しかしながら,原告使用商標のうちの楕円状リングの図形部分の識別 力は微弱である上(前記イ(イ)),原告が原告商品に引用商標1を独立 の商標として使用した事実は認められないから(前記ウ),ましてや引 用商標1の構成要素である楕円状リングの図形部分のみを独立の商標と\nして使用された事実も認められない。 したがって,原告の上記主張は,理由がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成29(ワ)6322 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年1月24日 大阪地方裁判所
ア 原告は,本件チラシの表現のうち,1)「検査時間 受診代金[注:各文 言の上に『×』の記号あり]」や「検査なし スグ買える!」という宣伝文句(キャ ッチフレーズ)(上記(1)のア及びイ),2)「コンタクトレンズの買い方比較」という 表(同ア)及び3)「なぜ検査なしで購入できるの?」という箇所における説明文言 (同ア)の3点について,創作性があるとして,本件チラシに著作物性が認められ ると主張している。
イ しかし,まず上記1)は,旧大阪駅前店において採用された眼科での受診 (検査)なしでコンタクトレンズを購入することができるという特徴を表現したも\nのであり,眼科での受診(検査)が不要であると,検査時間や受診代金が不要とな り,また検査が不要である結果,コンタクトレンズをすぐ買えることになると認め られる。そして,上記1)の宣伝文句は,以上のビジネスモデルによる顧客の利便性を消費者に分かりやすく表現しようとしたものと認められるが,不要になる事項を\n文字(単語)で抽出し,その文字(単語)の上に「×」を付すことはありふれた表\n現方法であるし,「検査なし スグ買える!」という表現は,眼科での受診(検査)\nなしでコンタクトレンズをすぐ買えるという旧大阪駅前店のビジネスモデルによる 利便性を,文章を若干省略しつつそのまま記載したものにすぎず,そこに個性が現 れているということはできない上に,強調したい部分に着色等したり,「!」を付し たりするなどして強調することもありふれた表現方法にすぎない。以上より,上記\n1)に創作性があるとは認められない。 また,上記2)はマトリックスの表形式にすることによって,旧大阪駅前店と他の\n店舗や他の販売方法との違いを分かりやすく表現したものである。確かに,表\現方 法としては文章で伝えるなどの別の方法が存することは原告主張のとおりであるが, 本件チラシは販売宣伝のために作成されたものであるから,その性質上,表現が記\n載されるスペースは限られ,また見た者が一目で認識,理解し得るような表現をす\nべきことも求められるから,表現方法の選択の幅はそれほど広いとは認められない。\nそして,文字で表現しようと思えばできる事項を表\形式にまとめることは通常行わ れる手法であり(例えば,甲5の1枚目の料金表,甲23の1頁目の略歴の表\,乙 12の表,反訴状と題する書面の15頁の表\,反訴状訂正申立書の1ないし2頁の\n表参照),表\形式で比較するに当たり,縦の欄に旧大阪駅前店と他の店舗や他の販売方法を並べ,横の欄に複数の事項を列記し,マトリックス形式でまとめるというの も,ありふれた手法にすぎない(例えば,甲11,14,乙13及び14の表,反\n訴状と題する書面の12ないし13頁の表2つ参照)。そしてまた,ここで比較の対\n象としている事項の選択も,眼科での受診(検査)を不要とし,店舗に来店して購 入するという旧大阪駅前店でのビジネスモデルから自ずと導き出されるものばかり である。以上より,上記2)に創作性があるとは認められない。 さらに,上記3)の説明文言は,旧大阪駅前店では眼科での受診(検査)なしでコ ンタクトレンズを購入することができる理由を文章で説明したもので,その内容は 法規の内容や運用を説明した上で,旧大阪駅前店では,顧客の経済的・時間的な負 担の観点から,販売時に処方箋の有無を前提としていないことを説明したものにすぎない。これは上記のビジネスモデルの客観的な背景や方針をそのまま文章で記載 したものにすぎず,文章表現自体に特段の工夫があるとはいえない上,その記載方\n法も相当の文字数を使用して,しかも小さな文字で記載したものにすぎないから, その表現方法に何らかの工夫がみられるわけでもない。以上より,上記3)に創作性 があるとは認められない。 以上より,上記1)ないし3)の各記載について,創作性は認められない。
ウ 以上の点につき原告は,提携眼科を設けないでコンタクトレンズ販売店 をオープンさせるというのは,かなり思い切った試みであったとか,検査なしでコ ンタクトレンズを購入できる理由を書いた説明文言は適法性を支える要素となって いるなどと主張しているが,旧大阪駅前店におけるビジネスモデル自体が著作権に よる保護の対象になるわけではなく,そのビジネスモデルを表現した本件チラシに\nおける各表現方法自体がありふれたものにすぎないことなどは,上記認定・判示の\nとおりである。したがって,原告の上記主張によって,上記判断は左右されない。
(3) 本件チラシの各表現の組合せによる著作物性
原告は上記(2)の1)ないし3)等の組合せに著作物性が認められるべきであるとも 主張している。 確かに,上記1)ないし3)は,眼科での受診(検査)を不要とし,コンタクトレン ズをすぐ買えるという旧大阪駅前店でのビジネスモデルを強調するために,それが可能な理由等を小さな文字で説明する(上記3))とともに,当該ビジネスモデルに よって不要となる事項を文字(単語)で抽出し,その上に「×」を付すなどしてキ ャッチフレーズを用いたり(上記1)),マトリックスの表形式で他の店舗や他の販売\n方法と比較したりした(上記2))もので,それらを組み合わせることによって当該 ビジネスモデルを強調し,読み手に分かりやすく説明しようとしたものということ はできる。しかし,何かを強調し,分かりやすく伝えるために,説明文とキャッチ フレーズと表形式のものを組み合わせることそれ自体は,特徴的な手法とは認めら\nれないから,上記(2)で判示したとおり上記1)ないし3)の各表現に創作性が認められ\nないことを踏まえると,これらの組合せ自体にも創作性は認められない。 なお,本件チラシでは,さらに視力検査をしている男の子のイラストが組み合わ されているが,原告はイラスト自体の著作物性を主張するものではない上,広告宣 伝において適宜関連するイラストを配することもありふれた表現方法にすぎないか\nら,このイラストと組み合わせることによって,創作性が基礎付けられるとはいえ ない。 また,原告は当初,被告チラシの各商品の配列等が本件チラシとほとんど同一で あることを主張していた。しかし,本件チラシにおいては商品の写真を掲げつつ, その下側に商品名や値段等を記載し,適宜商品の説明やアピールポイント等を付加 しているところ,そのような各商品の配列等は,コンタクトレンズ販売店の広告と してありふれたものであると認められるから(乙1ないし6),創作性は認められず,原告の上記主張によって本件チラシの著作物性は基礎付けられない。
(4) 以上より,本件チラシに著作物性は認められないから,その余の争点につ いて判断するまでもなく,被告の行為に著作権・著作者人格権侵害が成立するとは いえない。したがって,被告の著作権・著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害 賠償請求には理由がない。
◆判決本文
原告、被告のチラシはこちらです。
2019.02.20
平成29(ワ)9834 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年1月31日 大阪地方裁判所
ア 本件ウェブページ1及び2の閲覧者について
本件ウェブページ1及び2が掲載された被告ウェブサイトは,不特定多数の一般 人に対して公開されているが,本件ウェブページ1及び2を含む本件連載が「50 周年記念サイト」内のコンテンツであること,被告代表者の自伝であること,社内\n報における連載記事の再掲であること等から,本件ウェブページ1及び2の閲覧者 の多くは,被告の事業内容,あるいは被告代表者の業績や人柄に関心を抱く者,具\n体的には被告の関係者や取引業者,競争相手,油圧式杭圧入引抜機を使用した工事 を行う工事業者といった当該業界の者が中心になると考えられる。 したがって,これらの者が,本件掲載文1ないし3に接した際,本件連載中の他 の記事と合わせてどのような認識を持つかについて検討すべきことになる。
イ 当該業界の認識について
平成29年当時,油圧式杭圧入引抜機の製造販売事業を行う会社は,高知県 内においては原告及び被告以外には存在しなかったこと,昭和54年から55年頃 まで,土佐機械工業がサイレントパイラーの部品の製造の下請けをしていたこと,P3が垣内商店でサイレントパイラーの図面作成等に関与した後,土佐機械工業を 経て原告に勤務していること,被告が土佐機械工業に対し同社の製品は被告の発明 の技術的範囲に属する旨を通告したことは前記1で認定したとおりであり,原告の 資本金が2300万円であるのに対し,被告の資本金が80億5567万0215 円であること(甲1,5)を考慮すると,被告代表者であるP1が,本件掲載文1\nないし3として,「当社の下請けで加工を任せていた高知の小さな会社」,「この 会社は平然とコピー機を製造している」,「当社の機械のコピー機をせっせとつく っている件の会社」と記載した際に,土佐機械工業又は原告を指す意図でしたこと は明らかである。 そして,上記各事情は,当該業界の者にとっては知り得ることであったと考えら れるし,前記1で認定したところによれば,被告と土佐機械工業及び原告との間に は,長年にわたって特許権等に関する紛争があり,これらの事情は,当該業界の者 にとって周知であったとされるのであるから,当該業界の者は,本件掲載文1ない し3に記載されている会社が土佐機械工業及びその事業を承継した原告を指すとい うことを容易に理解するものと解されるし,現に,原告の取引先は,本件ウェブペ ージ1及び2に接して原告のことを指すものと理解し,原告に連絡しているのであ る。
(イ)被告は,本件掲載文3について,原告ではなく中央自動車興業を指すもので あると主張する。しかし,「件の会社」という表現は,以前に言及された会社を指す表\現であると解するのが当然であるところ,中央自動車興業は本件連載において本件掲載文3以前に一度も言及されておらず(乙35,被告代表者),中央自動車興業が高知県内\nに本店又は支店を有していたことはないことから(甲28),第28回である本件 ウェブページ2の「件の会社」については,直前の第27回である本件ウェブペー ジ1にある「平然とコピー機を製造販売している高知の小さな会社」を受けた表現\nと解するのが相当であり,逆に,これを中央自動車興業と解する余地はないといわ ざるを得ない。
(2)「コピー機」との表現について\n
ア 「コピー」という表現は,一般には,同一性を保ちつつ,転写,複製,演奏\n等を行うことと解され,権利者の許諾を得ずに著作物,商標,意匠あるいは商品形 態についてのコピーをした場合,多くの場合に権利侵害が成立することから,コピ ー品の製造販売や輸入が違法であることは,一般的な警告の対象とされている(甲 21ないし26,33ないし35,乙22)。 特許権との関係でコピーという表現が使われることは多くはないが,上述した同\n一性の保持を前提とすると,相手方の製品が自身の製品のコピーであると表現する\nことができるのは,外観,構造等が同一,あるいは区別し得ない程度に類似してい\nるような場合か,少なくとも,相手方の製品が,自身の有する特許発明の技術的範 囲に属し,特許権侵害が肯定されるような場合に限られると解される。 そうすると,外観等が類似はしていても,全体としては同一とはいえない場合や,機能や基本となる原理が類似していても,特許発明の技術的範囲に属するのではな\nい場合に,これをコピーと表現した場合,本来は特許法その他の法律により違法と\nされる範囲外の行為について,違法との印象を与える内容を告知することになる。
イ 本件について見るに,原告の製品は,被告のサイレントパイラーと同じ圧入 原理を利用する油圧式杭圧入引抜機であるが,この基本原理自体は,サイレントパ イラーの開発以前である昭和35年から公知であったものであるし,原告の製品の 形状は,サイレントパイラーの形状と一部類似することが認められるが,油圧式杭 圧入引抜機という機械の機能を発揮するためにはある程度決まった構\造・形状を採 らざるを得ないと合理的に推測できるのであって,他の会社がかつて製造していた 油圧式杭圧入引抜機も,サイレントパイラーと主要な構造や形状が類似していたこ\nとが認められる。また,サイレントパイラーの図面作成に携わったことのあるP3 らが,その後土佐機械工業へ転職したことが認められるが,同社は油圧式杭圧入引 抜機の開発に際し,被告の有する特許権等の権利を侵害するおそれがないか弁理士 と相談して調査したとされることは前記認定のとおりである。 そして,被告の特許申請については拒絶査定が確定し,土佐機械工業において杭\n打込引抜機についての特許を取得していることは既に認定したとおりであって,本 件において,土佐機械工業または原告が自らの杭打込引抜機を製造販売することが, 特許権を含む被告の何らかの排他的権利を侵害すると認めるに足りる事実の主張, 立証はなされていない。
ウ 以上によれば,被告は,原告の製品が,被告の製品をコピーしたものである と表現し得る場合ではないにもかかわらず,本件掲載文1ないし3において,原告\nの製品を「コピー機」と記載したものであるから,これは,虚偽の事実に当たると いうべきであるし,既に検討したところに照らし,競争関係にある原告の営業上の 信用を害する行為に当たるというべきである。
エ 被告は,本件連載が被告代表者の自伝であるという性質から,主観的であり\n価値判断を含む記載であることが考慮されるべきであって,本件ウェブページ1及 び2の全体の表現ぶりや,本件掲載文2の「当社が発明した機械ではあるが,一社\nで市場を完全に独占するのはやはり罪悪である。」,「業界の小さな“鬼っ子”にむしろ感謝している。」等の表現から,「コピー機」を作っているとする会社を否\n定的に評価するものではないと主張する。 しかし,本件連載を通じ,被告代表者がサイレントパイラーを発明したことが強\n調されており,本件ウェブページ1においても,「世界ではじめて杭圧入機を実用 化し,世の中になかった「圧入業界」をつくり」との記載がある中で,本件掲載文 2及び3においては,「平然とコピー機を製造している」,「当社の機械のコピー 機をせっせとつくっている」との表現がなされているのであるから,「コピー機」\nという表現が,被告の発明品であるサイレントパイラーの技術を,被告の権利を侵\n害し,あるいは,違法な手段で盗用・模倣したという否定的な文脈で用いられてい ることは明らかであり,この表現に接した者は,原告の製品が被告の製品の模造品や模倣品,違法な権利侵害品であるとの印象を受けるものと認められる。\n上記被告の主張を採用することはできない。
(3) 「引き抜かれた」との表現について\n
本件ウェブページ2の前半は,昭和58年頃,被告の取引先の一つが会社更生手 続開始決定を受けたことをきっかけに,被告代表者が被告の営業担当者に対して社\n外への外出を禁止するという措置を執り,これに反発した営業幹部の多くが退職し, その一部は「件の会社」に引き抜かれたというものであり,被告代表者の措置に反\n発した営業幹部の退職が先行し,引抜きにより退職したとするものではない。 しかしながら,本件ウェブページ1の記載を前提に本件ウェブページ2を見た場 合,本件掲載文3の「当社の機械のコピー機をせっせと作っている件の会社」は土 佐機械工業又はその事業を承継した原告と解されることは前記認定のとおりである し,「コピー機をせっせと作っている件の会社」という否定的表現の中で「引き抜\nかれた」という表現が用いられれば,これに接する者は,土佐機械工業又は原告が,\n違法,不当な手段を用いて,被告の従業員を転籍させたとの印象を抱くものと解さ れる。 本件において,昭和58年1月31日付けで退職した被告の従業員が,土佐機械 工業に転職したとの事実は認められないし,土佐機械工業又は原告が被告の従業員 に対して違法・不当なはたらきかけをしたという事実も認められないから,被告が,本件掲載文3に「件の会社に引き抜かれた」と記載したことは,競争関係にある原 告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことになる。
2019.02.20
平成30(ネ)10066 損害賠償等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて
本件は,平成29年12月20日に東京簡易裁判所に訴えが提起され,平成30 年2月9日に東京地方裁判所に移送され,3回の弁論準備手続期日を経て,同年6 月21日の口頭弁論期日において弁論が終結されたところ,弁論の全趣旨によると, 東京地方裁判所は,同年3月30日,控訴人(一審原告)訴訟代理人に対し,被侵 害利益が公表権(著作権法18条),氏名表\示権(著作権法19条),同一性保持 権(同法20条)又は著作権法に定めのない権利利益であるのか,具体的に明らか にすることなどを求めるファックス文書を送付したこと,控訴人(一審原告)訴訟 代理人は,同年4月25日,被侵害利益は「氏名表示権(著作権法19条)」であ\nる旨を記載した同日付け原告第1準備書面を東京地方裁判所に提出し,同書面は同 日の第1回弁論準備手続期日において陳述されたことが認められる。そうすると, 控訴人は,被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の 著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張を, 遅くとも原審の口頭弁論終結日である平成30年6月21日までにすることが可能であったといえるから,これを当審において初めて主張することは「時機に後れて\n提出した攻撃又は防御の方法」(民訴法157条1項)に該当することが認められ る。 しかし,控訴人は,本件の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成30年11月21 日)において,被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三 者の著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張 をしたものであって,本件は,第2回口頭弁論期日において弁論が終結されたこと からすると,上記の時点における上記主張により,訴訟の完結を遅延させることと なると認めるに足りる事情があったとはいえない。 したがって,上記主張に係る時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては,認め\nられない。
・・・
証拠(甲1,甲1の2)及び弁論の全趣旨によると,本件書籍1は,D VD付きの書籍であり,書籍には,写真,イラスト,文章等が,DVDには映像が 掲載されていることが認められる。そして,前記アのとおり,本件書籍1の奥付に は,控訴人以外の多くの個人又は団体の名が,様々な立場から本件書籍1の成立に 関与したものとして記載されていること,「監修」が「書籍の著述や編集を監督す ること」(広辞苑第7版)を意味することからすると,本件書籍1が編集著作物で あるとしても,前記アの記載から,その編集著作物の著作者が,控訴人であると推 定すること(著作権法14条)はできず,著作者が控訴人であるとは認められない。 また,その他に,控訴人が,本件書籍1につき,素材の選択又は配列によって創 作性を発揮したものと認めるに足りる主張・立証はない。 この点について,控訴人は,株式会社ビックスとの間における作業過程に照らし てみても,控訴人が実態として編集著作物の著作者となる旨主張する。 しかし,控訴人が主張する本件書籍1への控訴人の関与については,控訴人の陳 述書(甲8)以外の証拠はなく,また,上記陳述書によっても,「明確に覚えてい ない」というのであって,控訴人が,「監修」,すなわち,書籍の著述や編集を監 督することを超えて編集著作物の著作者と評価し得る作業を行ったことを認めるこ とはできないから,控訴人の上記主張は,採用できない。 したがって,控訴人が本件書籍1の編集著作者であるとは認められない。
そうすると,本件書籍1については,控訴人の主張する被侵害利益は,その根拠 を欠くから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の被控訴人に対する被侵害 利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の著者であると偽ら れない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存するとは認められない。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(行ケ)10059 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年1月29日 知的財産高等裁判所(2部)
(2)ア 前記(1)アで認定した78頁最下部部分の本件太字部分の記載と本件説 明部分の記載を併せて読むと,本件太字部分のうちの「QRコード(R)リーダー”Q”」 又は「”Q”」の部分が商品名を記載したものであり,本件説明部分が上記商品の機 能等を説明した記載であると認められる。\nそして,上記事実に,本件カタログは,被告の総合カタログであり,被告の商品 の紹介等がされていること,78頁最下部部分には,「ダウンロード(無料)はこち らから!」との記載とQRコード規格の2次元コードのラベルの記載があり,上記 商品「QRコード(R)リーダー”Q”」又は「”Q”」のダウンロードの案内がされている ことを併せ考慮すると,78頁最下部部分は,本件商品2に含まれる上記商品「Q Rコード(R)リーダー”Q”」又は「”Q”」の広告であると認められる。 なお,前記(1)アで認定した78頁最下部部分の記載からすると,上記商品「”Q”」 は,QRコード規格の2次元コードの読み取り等の機能を有するプログラムソ\フト ウェアであるから,本件商標の指定商品のうちの「電子応用機械器具及びその部品」 に含まれる。
イ 前記(1)アのとおり,使用商標3は,本件商品2の広告である78頁最下 部部分に記載されているところ,前記(1)イのとおり,78頁最下部部分が掲載され た本件カタログは,要証期間内である平成27年3月6日に本件展示会の会場で頒 布されている。
ウ 次に,使用商標3が、本件商品2についての自他商品等を識別するもの として使用されているかどうかを検討する。
(ア) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
a 株式会社技術評論社が発行する「最新パソコン用語事典2006−’\n07」及び「最新パソコン・IT用語事典2010−’11」には,「QRコード」\nの項目に,「株式会社デンソーウェーブが開発した,2次元コード(縦と横の両方\n向に意味を持たせてある符号)の一種。・・・1999年にJIS,2000年に ISOの国際規格として制定されている。」との記載がある(甲24,25)。
b 株式会社秀和システムが発行する「最新標準パソコン用語事典20\n13−2014年版」には,「QRコード」の項目に,「1994年に自動車メー カーでもあるデンソー社が開発した,バーコードに代わる2次元のマトリクス式コ\nードの1つ。・・・1999年にはJIS X0510に,2000年にはISO /IEC18004として標準化された。」との記載がある(甲26)。
c 被告は,「QRコードについては(株)デンソーウェーブの登録商標\nです。」との表示をしているほか,「QRコード」には「○R 」の表示を付している\n(甲81,甲92の1,甲98の1,乙1,27)。また,被告以外の会社の開設 した複数のウェブサイトにおいても「QR Code」又は「QRコード」につい て被告の登録商標である旨の表示がされている(乙23の1〜5)。さらに,原告の\n広告においても,「QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。」との\n記載がある(乙24〜26)。
d スマートフォン用のQRコードリーダー等のアプリのアイコンとして,図形と,その下に「QRコード」,「QR Code」又は「QR code」 と記載されたものが多数存在する(以下,同アイコンを「甲52アイコン」と総称 する。)ところ,甲52アイコンのうちの文字部分は,いずれも,何ら特徴のない白 抜きの文字である(甲52の2)。
e 平成18年8月22日付けの新聞には,「QRコード」は,カメラ付 き携帯電話の普及に伴い,爆発的に普及したものであり,現在は被告の登録商標で あるとの記事がある(甲70)。
(イ) 前記(ア)の事実によると,「QR Code」及び「QRコード」は,2 次元コードの規格の一種であると認識されることがあるものと認められるが,他方, 被告は,本件商標登録を有しており,前記(ア)のとおり,「QRコードについては(株) デンソーウェーブの登録商標です。」との表\示をしたり,「○R 」の表示を付して,\n商標登録を有していることを広く知らせており,また,前記(ア)のとおり,被告以外 の会社も,原告を含め,そのウェブサイトや広告において,「QR Code」又は 「QRコード」が被告の登録商標である旨の表示をしていることを考慮すると,「Q\nR Code」又は「QRコード」が常に2次元コードの規格の一種であるとのみ 認識されると認めることはできず,自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用さ\nれることがあり得るというべきである。
(ウ) 使用商標3は,前記(1)ア(ア)のような態様で表示されているもので,\n他の記載とは独立して表示されている。そして,使用商標3は,「Q」の文字の右\n端の部分と「R」の文字の左端の部分が重なっており,僅かではあるが図形化され ており,赤色で表示されているものであって,単に,商品名であると認識される「Q\nRコードリーダー”Q”」又は「”Q”」の説明として記載されているものと認めるこ とはできず,上記商品についての識別標識として記載されているものと認められ, 本件カタログを見た需要者・取引者もそのように認識するものと認められる。 したがって,使用商標3は,本件商品2についての自他商品等の識別機能を有し\nていると認められる。 なお,甲52アイコンの各文字部分は,使用商標3とは表示態様が全く異なるか\nら,甲52アイコンの存在によって,使用商標3が自他商品等の識別機能を有しているという上記の判断が左右されるものではない。\n
(エ) 原告は,「QR コード」及び「QR Code」の文字からは,2 次元コードの規格の一種であるQRコード規格との認識しか生じ得ないことは,特 許庁が15例にも上る拒絶理由通知及び拒絶理由で一貫して認定していると主張す るが,いずれも本件とは異なる事例についての特許庁の判断であり,使用商標3が 自他商品等の識別機能を有しているとの上記の判断が左右されるものではない。\nまた,原告は,「『QR Code』はデンソーウェーブの登録商標です。」との表\ 示は,虚偽表示(商標法74条1号違反)であると主張するが,後記エのとおり,\n本件商標は,「QR Code」と社会通念上同一のものであるから,この表示が虚\n偽表示ということはできない。\n
(オ) 原告は,1)本件カタログに用いられている商標は「DENSO WAV E」又は「デンソーウェーブ」である,2)使用商標3は,本件カタログのうち,Q Rコード規格についての解説等をする頁で使用されており,被告の製品を紹介する場面で使用されていないから,一般の需要者・取引者からは,単に当該2次元コー ドが「QRコード規格に基づいた2次元コード」であると理解されるにすぎず,自 他商品等の識別標識として理解されることはない,3)使用商標3,「ダウンロード (無料)/はこちらから!」という記載及びQRコード規格の2次元コードの配置 からすると,使用商標3が本件商品2のアプリとの具体的関係において使用されて いると理解することは不可能である,4)本件商品2は本件カタログの78頁のQR コード規格等についての技術的な解説,紹介の中で隅に記載されているにすぎない ことからすると,本件カタログが本件商品2を紹介するものではなく,本件商品2 の広告に該当しないと主張する。 しかし,既に認定,判断したとおり,使用商標3は,78頁最下部部分において, 本件商品2についての広告として使用されているものであり,このことは,本件カ タログの商標として「DENSO WAVE」又は「デンソーウェーブ」が使用され\nていることや使用商標3が本件カタログの「基礎知識」の頁に記載されていること によって妨げられるものではなく,また,前記(1)ア(ア)で判示した78頁最下部部分 の記載内容からすると,使用商標3は,本件商品2との具体的な関係において使用 されていることも明らかであるから,原告の上記主張はいずれも理由がない。
エ 次に,使用商標3が本件商標と社会通念上同一といえるかどうかについ て検討する。
(ア) まず,本件商標は,別紙1のとおり,「QR コード」及び「QR C ode」を上下二段に配置した商標であり,上段の「コード」の部分は,下段の「C ode」の部分を片仮名にしたものと理解されるから,「キューアールコード」の称 呼が生じ,また,QRコード規格の2次元コードの観念が生じる。 一方,使用商標3からも,「キューアールコード」の称呼と,QRコード規格の2 次元コードの観念が生じる。 このように,本件商標と使用商標3とは,称呼及び観念において共通する。
(イ) 次に,本件商標と使用商標3の外観を比較すると,使用商標3は,本 件商標の下段の「QR Code」とは,同一の文字綴りであり,上段の「QR コード」とは,片仮名及びローマ字の文字表示を相互に変更するものであり,この点で共通性が認められるが,1)本件商標は,「QR コード」及び「QR Code」 の標準文字が上下二段に配置されているのに対し,使用商標3は,「QR Code」 のみから構成されている点,2)使用商標3は,「Q」の文字の右端の部分と「R」の 文字の左端の部分が重なっており,同重なり部分が,両文字の一部を兼ねているよ うに 図形化されている点,3)使用商標3は,赤色で記載されている点で異なって いる。 しかし,前記(ア)のとおり,「QR コード」は,「QR Code」の「Code」 の部分を片仮名にしたものと理解されるのであり,「QR コード」及び「QR C ode」の称呼及び観念は同一であることからすると,上記1)の相違点の存在が, 使用商標3が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの判断に影響を与えるもの ではないというべきである。 また,「Q」の文字と「R」の文字が重なった部分は僅かであり,双方の文字を独 立した文字として認識できること,図形化の程度も僅かであることからすると,上 記2)の相違点の存在が,使用商標3が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの 判断に影響を与えるものではないというべきである。 さらに,商標に色を付けても,通常,商標の同一性を失わせるような変更とはえ いないから,上記3)の相違点の存在が,使用商標3が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの判断に影響を与えるものではないというべきである。
(ウ) 以上からすると,使用商標3は本件商標と社会通念上同一であると認 められる。
(エ) この点について,原告は,本件商標上段の「QR コード」から下段 の「QR Code」以外のものを想起させるし,下段の「QR Code」から 上段の「QR コード」以外のものを想起させると主張するが,本件商標は,「QR コード」と「QR Code」を上下段に配置した商標であって,前記ウのとお り,「QR コード」及び「QR Code」が2次元コードの規格としても知られ ていることを考慮すると,「QR コード」と「QR Code」からそれら以外の ものを想起することは考え難いというべきである。このことは,被告が「QR コ ード」と「QR Code」について商標登録出願をしていることによって左右さ れるものではない。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
オ 次に,本件商品2が商標法上の「商品」に当たるかどうかについて検討 する。
(ア) 後掲証拠によると,以下の事実が認められる。
a 被告の開設しているウェブサイトには,平成26年11月6日付け で,以下の記載がある(甲61)。
(a) 「デンソーウェーブとレピカが資本・業務提携/QRコード(R)によ るクラウドサービス『Q−revoTM』活用の第一弾として,/食品及び工業製品 の『トレーサビリティ』サービスの提供を開始」
(b) 「レピカは,子会社であるアララ株式会社を通じてスマートフォン 事業を手がけており,コンシューマー向けにQRコードをトリガーとしたAR(A RAPPLI(アラプリ)』を展開しています。両社はこれまでにより精度の高いス マートフォン向けQRコードリーダーアプリの開発において共同でプロジェクトを 行っており,今後更に両者のノウハウを活用してより付加価値の高い事業を展開し ていくため,デンソーウェーブがレピカに出資することにしました。」\n
(c) 「両社は,今後,『Q−revo』および『QR Code Re ader “Q”』を活用し,食品をはじめ,工業製品において,『トレーサビリテ ィ』をキーワードに両社のノウハウを活かしたサービスを展開していきます。」 b payment naviのウェブサイトには,平成26年11月 10日付けで,以下の記載がある(乙16)。
(a) 「デンソーウェーブとレピカがQRコードによるクラウドサービス提供」\n
(b) 「両社では,提携の第一弾として,SQRC,フレームQRなど, 進化したQRコードの生成・配信,読み取り,データ蓄積を行うクラウドサーバと 『QR Code Reader “Q”』を活用した次世代型サービス『Q−re vo』を開発。今後は,食品や工業製品において,『トレーサビリティ』をキーワー ドに両者のノウハウを活かしたサービスを展開していく方針だ。」
(c) 「なお,具体的な売り上げ目標については,トレーサビリティシス テムの検証を進め,サービスとして整った際,発表する方針だ。」\n
(イ) 商標法上の商品というためには,商取引の対象となり得ることが必要 であり,そのためには,必ずしも当該商品が有償で譲渡される必要はなく,当該商 品自体は無償で譲渡されるものであっても,当該商品の譲渡によって利益を得る仕 組みがあり,その仕組みの一環として,当該商品が無償で譲渡されるのであれば, 当該商品は交換価値を有し,商取引の対象となっていると認めることができるとい うべきである。 前記(1)ア(ア)で認定した事実からすると,本件商品2は,無償でダウンロードでき ることが認められるが,前記(ア)で認定したウェブサイトにおける記載からすると, 被告は,アララ社と共同で,本件商品2を活用したサービスを展開していく計画を 有していることが認められるところ,同サービスを利用するためには,本件商品2をスマートフォンにダウンロードしておく必要があるのであるから,本件商品2の 無償配布は,同サービスの展開に大きく寄与するものと考えられ,したがって,本 件商品2の無償配布は,本件商品2を利用したサービスを提供し,同サービスの提 供によって利益を得るというビジネスモデルの一環としてされたものと評価できる。 したがって,本件商品2には交換価値があるものと認められ,本件商品2は,商 取引の対象となり得るというべきである。 なお,このように,本件商品2を無償配布した上で,本件商品2を活用したサー ビスを提供することにより利益を得るというビジネスモデルにおいても,本件商品 2を無償配布する際の商取引の対象は,あくまでも本件商品2であり,使用商標3 は,本件商品2の広告に付されたものであり,上記サービスの商標として使用され たものではない。
カ 以上のとおり,被告は,本件商標と社会通念上同一であると認められる 使用商標3を付した,商標法上の「商品」に当たる本件商品2の広告を,要証期間 内に頒布したことが認められる。
キ 原告は,使用商標3は,197号商標の一部にすぎず,使用商標3のみ が独立して認識されることはない,被告は本件QRアイコンについて商標の登録を 受けているから,本件商品2の識別標識となり得るのは本件QRアイコンのみであ る,197号商標が登録された以降は,本件商品2について197号商標を表示す\nる行為は,専ら197号商標を使用するものであることから,本件パンフレットに 表示されている商標は,197号商標であって,使用商標3ではないなどと主張す\nる。 しかし,使用商標3は,前記(1)ア(ア)のとおり,本件カタログの78頁最下部部分 に記載されており,本件QRアイコンとは完全に独立していることは明らかである から,197号商標が登録されているかどうかや本件QRアイコンについて商標登 録がされているかどうかにかかわらず,独立の商標として認識できるものである。 また,同一の商品の商標として,複数の商標を付することも認められるから,1 97号商標が登録された以降は,その一部である使用商標3を商標として使用でき ないという理由はない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
ク 原告は,本件商品2に係る無料アプリは,アララ社が提供するものであって,被告が提供するものではないから,被告が,本件カタログにアララ社が提供 する本件商品2を掲載すると共に使用商標3を付して頒布したとしても,商標法5 0条1項の「使用」に該当することはないと主張する。 しかし,本件カタログにおける広告は,被告が,前記オで認定したビジネスモデ ルの一環として行っているものであって,本件商品2はアララ社が提供するもので あったとしても,前記認定の本件商標の「使用」の事実が左右されることはない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(ネ)10057 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成31年1月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
また,控訴人は,KCP社の売上げは,平成28年以降はほとんどない旨主 張するが,乙18によると,平成28年の売上げは平成25年及び平成26年より も高いことが認められる上に,そもそも,商標法4条1項19号の周知性の判断の 基準時は,登録出願時及び査定時であるところ(商標法4条3項),本件商標の出 願及び査定は,いずれも平成27年にされている以上,KCP社商標の周知性の判 断は,平成28年における売上高に左右されない。
(ウ) さらに,控訴人は,KCP社の英語表記は,「KCEP HEAVY IN DUSTRIES CO.,LTD.」であると主張するので,同主張について,以下検討する。
a 前記(1)アのとおり,KCP社は,設立後,「KCEP」ではなく,「KC P」の文字からなるKCP社商標を,同社の製品に付して販売し,また,型番の一 部にも使用していることからすると,KCP社及び同社の製品を示す表示として,\nKCP社商標が使用されていることは明らかである。 また,控訴人代表者も,代表\者尋問において,本件商標出願の時点で,KCP社 がKCP社商標を使用していたことを認識していた旨供述していること,KCP社 の理事に送信したメールの韓国語の文書に,KCP社を「KCP」と記載している こと(乙90)からすると,控訴人代表者自身も,KCP社の英語表\記をKCPで あると認識しているものと認められる。
b 控訴人は,KCP社の正式な英語表記は「KCEP」であると主張する。\nしかし,前記のとおり,KCP社は,自社製品に「KCP」との英語の表記を\n付しており,また,証拠(乙107,114)によると,KCP社は,外国企業へ の見積もり送り状や外国企業との契約書において,自社を「KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」と表記していることが認められる。\n一方で,本件証拠上,KCP社が「KCEP」との英語表記を用いた事実は認\nめられない。なお,証拠(甲63,乙130)によると,KCP社の韓国貿易協会 の会員登録における英語表示が,「KCP」から「KCEP」に変更され,その後,\n「KCP」に戻ったことが認められるが,上記の「KCEP」への変更は控訴人の 働きかけによるものであり(乙129),KCP社が関与していたとは認められな いから,同事実によって,KCP社が,自社の英語表示として「KCEP」を使用していたと認めることはできない。\nしたがって,KCP社は,同社の英語表記として「KCP」を選択して使用し\nたものと認められ,このことは,KCP社の商号を韓国語から英語に訳する際の訳 語いかんによって左右されるものではない。 c 以上より,KCP社及び同社の製品を示す表示として,KCP社商標が使\n用されているのであり,前記(ア)の判断は左右されない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(ネ)10067 商号使用禁止等請求控訴事件 その他 民事訴訟 平成31年2月14日 知的財産高等裁判所 さいたま地方裁判所
加えて,前記認定事実によれば,控訴人が平成24年9月に控訴人の保有する被控訴人の株式全部を被控訴人代表者(A)に譲渡して,控訴人と被控訴人との資本関係及び業務委託関係(業務提携)を解消した際,控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が上記解消後に被告商号を継続して使用することについて異議を述べたり,被控訴人の商号を別の商号に変更するよう求めなかったこと,その後も,控訴人は,平成29年6月17日に本件訴訟を提起するまでの約4年9か月間,被控訴人が被告商号を使用して営業活動を行っていることを認識しながら,被控訴人に対し,被告商号の使用を差し控えるよう求めなかったことが認められる。また,控訴人は,控訴人の保有する被控訴人の株式全部をAに譲渡する前は,被控訴人の発行済株式の過半数を有する株主であったから,Aに株式全部を譲渡する前に,被告商号が株式譲渡後に確実に変更されるための対策を講じようと思えば,講じることが可能な立場にあったにもかかわらず,控訴人がそのような対策を講じることを検討した形跡はうかがわれない。\nこれらの諸事情を勘案すると,被控訴人は,控訴人が新築した建物の顧客に対するアフターケア業務を代行して担当する子会社として設立され,被告商号が,控訴人と被控訴人の間に資本関係及び業務委託関係(業務提携)が存在することを踏まえて決定されたという経緯があったからといって,控訴人及び被控訴人のいずれにおいても,被控訴人の設立の際に,控訴人と被控訴人の資本関係及び業務提携が解消されたときは,被控訴人の商号を被告商号から別の商号へ変更する意思又は意向を有していたものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
2019.02.20
平成30(行ケ)10100 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
本件訂正事項1は,要するに,請求項1における「皮膚」を「皮膚(但し, 皮膚は表皮及び真皮から成る。以下同様)」に訂正するものである。\n原告が指摘するとおり,「皮膚」がどのような組織を意味するのかという点 について,本件明細書中に定義や示唆はない。そこで,証拠として提出されて いる各種辞典類(甲40・広辞苑,甲41・生化学辞典,甲77・化粧品辞典) の記載を総合的に検討すれば,通常,「皮膚」なる用語には,「表皮・真皮」\nを指す場合と,「表皮・真皮・皮下組織」を指す場合の二通りの意味があるも\nのと認められる。 すなわち,甲40(広辞苑)には,「【皮膚】後生動物の体を包む外被。体 の保護,体温・水分蒸発などの調節,各種の感覚の受容のほか,皮膚呼吸も営 む。動物によりさまざまに変形適応する。高等脊椎動物では表皮・真皮・皮下\n組織,および各種の付属器官から成る。」の後に「表皮と真皮のみを指す場合\nもある。」と明記されている。 甲41(生化学辞典)には,「皮膚[cutis,skin] 表層にある上皮性の表\ 皮とその下の結合組織性の真皮から成る.その下は皮下組織で多くの場所で脂 肪組織に変わっている.…」とある。 甲77(化粧品辞典)には,「皮膚は大きく3層(表皮,真皮,皮下組織)\nからなる」という記載がある一方で,「皮膚の厚さ(表皮と真皮を足した厚さ)\nは1.0〜4mmで,一般に女性よりも男性が厚く,幼児よりも成人が厚い.…たんなる物理的な壁ではなく,生体の保護を中心とする絶対不可欠な機能を\nもった組織である.」という記載もある。 以上のとおり,「皮膚」は,広義では,動物(高等脊椎動物)の表皮・真皮\nのみならず皮下組織をも含むものとして観念されるものの,その機能の多様性\nに照らし,表皮・真皮のみを指す場合もあるといえ,文脈を離れて一義的にそ\nの意味するところを決することはできない。 本件訂正事項1は,このうち後者の場合,すなわち,皮下組織を含まないも のと定義することによって技術的に明瞭な記載とすることを意図したものであ り,不明瞭な記載の釈明を目的とするものに該当する。また,かかる訂正によ って本件発明の解釈に支障や混乱を来すとは認められない。 以上に反して,(皮下組織をも含むものとして)皮膚概念は一義的に明確で あるとする原告の主張は,一面的な見方であって,直ちに採用できないというべきである。
・・・
本件訂正事項4は,本件訂正前の請求項1に記載された「経皮吸収製剤」か ら「目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されるか,あるいは縦 孔に収容されることによって基剤に保持されている経皮吸収製剤」(除外製剤) を除外するものであるところ,原告の主張は,要するに,この除外製剤が物と して技術的に明確でないとするものである。 そこで検討するに,除外製剤における「医療用針」が,目的物質を注入する ための注射針やランセット,マイクロニードルなどを意味することは,出願時 の技術常識に照らして明らかであるといえる。また,「チャンバ」又は「縦穴」 が当該「医療用針」内に設けられたものであること,及び「目的物質」が「チ ャンバに封止されるか,あるいは縦孔に収容されることによって基剤に保持さ れている」ことは,いずれも除外製剤の構造を特定するものであって,その特\n定に不明確な点があるとは認められない。 そうすると,上記除外製剤が,特定の構造を有する「医療用針」である「経\n皮吸収製剤」を意味していることは明らかであるから,上記除外製剤は物とし て技術的に明確であり,さらには,かかる除外製剤を除く「経皮吸収製剤」に ついても,発明の詳細な説明の記載,例えば,【0070】の「基剤に目的物 質を保持させる方法としては特に限定はなく,種々の方法が適用可能である。\n例えば,目的物質を基剤中に超分子化して含有させることにより,目的物質を 基剤に保持させることができる。その他の例をしては(判決注:「その他の例 としては」の誤記と認める。),溶解した基剤の中に目的物質を加えて懸濁状 態とし,その後に硬化させることによっても目的物質を基剤に保持させること ができる。」に接した当業者であれば,出願時の技術常識を考慮して,物とし て明確に理解することができるといえる。
そうである以上,本件訂正事項4によって訂正された請求項1の記載は明確 であるというべきであって,これに反する(あるいは前提を異にする)原告の 主張はいずれも採用できない。
◆判決本文
第3次までの取消訴訟は以下です。
◆平成28(行ケ)10160
侵害訴訟事件です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(行ケ)10138 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
再開された審判手続において,原告はその請求に係る役務を,”ゴルフ用ビデオの制作等”と一部を取り下げました。これは、商標法においても指定商品役務毎に無効主張ができますが、15号違反の場合、包括概念の一部についてのみ無効理由がある場合があるから、このような無効対象役務を特定する必要があるのでしょうね。
本件商標は,「コナミスポーツクラブマスターズ」の片仮名15文字を標準文字で表して成る文字商標であって,外観的には,同一の大きさ・書体の文字により,全体が等間隔で一行にまとまりよく配置されており,一連一体のものとして構\成されていることが明らかである。そして,前記のとおり,我が国においては,「コナミスポーツクラブ」は 被告子会社が運営するスポーツクラブの名称として周知であるということが できる一方で,「マスターズ」は原告主催のゴルフ・トーナメントの略称の みならず,熟練者ないし中高年を含む一定年齢以上の年齢層を対象とした各 種スポーツ競技ないし競技大会をも指す語として,スポーツ愛好者等の間に 広く知られており,現にゴルフはもちろん,ゴルフ以外の競技においても, 大会名において「マスターズ」の語が広く使用されている事実が認められる ことからすると,本件商標を目にした者が直ちに「マスターズ」の部分のみ に着目して原告主催のゴルフ・トーナメントを連想するということはできず, むしろ,語頭の「コナミスポーツクラブ」の部分に着目して「コナミスポー ツクラブが関連する何らかのマスターズ競技ないしその競技大会」と理解す ると考える方が合理的である。したがって,外観(文字構成),称呼及び観\n念に照らしても,本件商標と引用商標の類似性の程度はそれほど高いとはい えない。
また,「マスターズ・トーナメント」という大会それ自体は世界的に周知・ 著名なゴルフ競技会であるとしても,元々「masters」が「名人,達 人」を意味する「master」の複数形にすぎず,原告の造語でないこと は原告自身も認めているところであるし,ゴルフというスポーツの技を競い 合う競技会の名称に,技術に長けた人を表す「名人,達人」の語を用いるこ\nとは,語義に忠実な用法であって,特に奇抜性があるとか斬新であるという こともできないから,当該表示や当該表\示を選択したことについて独創性が あるともいえない。
さらに,商品・役務間の関連性や取引者・需要者の共通性という点につい ても,本件商標の指定役務のうち無効請求役務は,いずれもゴルフに関連す る役務であるから,その限りにおいて,原告の役務との間で関連性や需要者の共通性が認められるというべきであるが,他方で,原告はその主催する「マ スターズ・トーナメント」がよく知られているという以外には,特に日本国 内でゴルフ競技会を開催しておらず,また,日本国内でゴルフ関連事業(商 品の販売や役務の提供)がよく知られているとも認められない。すなわち, 原告提出の証拠(甲56〜76など)によれば,原告は,一応,日本国内に おいても,ライセンス等により引用商標を表示したゴルフ用品の販売を行っ\nていることや,「マスターズ・トーナメント」の開催時期に合わせてグッズ や関連商品の販売を行っていることが認められるが,その売上高や広告宣伝 等(事業規模)の詳細は不明であって,この程度の立証では,引用商標が「マ スターズ・トーナメント」以外に原告の提供する商品それ自体の出所識別を 表示するものとしても我が国で周知著名であると認めるには足りない。\n以上のことからすると,本件において,役務の関連性や需要者の共通性は それほど重視すべき事情であるとはいえない。また,原告は経営多角化の可 能性についても言及するが,何ら具体性のある主張立証はなされておらず,\nこの点についても特にみるべき事情があるとはいえない。
(3) 以上によれば,引用商標が原告主催のゴルフ・トーナメントの略称として も周知著名であることや,引用商標と本件商標との間に「ゴルフ」という共 通項があることを踏まえても,本件商標を指定役務(無効請求役務)に使用 したとき,当該役務が,原告の業務に係る役務であるとか,原告との間にい わゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商\n品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務である(4) 原告の主張について 原告は,本件商標について法4条1項15号該当性を認めなかった本件審 決の認定判断は誤っているとして種々主張するが,その主張は要するに,「マ スターズ」の語に原告主催の「マスターズ・トーナメント」以外の意味が認 められないことや,「コナミスポーツクラブ」の周知性が認められないこと を前提とするものであって,その前提自体が採用できないものであることは, 既に説示したとおりである。 また,原告は,本件審決が本件商標と引用商標の類似性の程度が低いと認 定した点や,「マスターズ」及び「Masters」の独創性が高いとはい えないと認定した点についても誤りであると主張するが,その主張が採用で きないことも既に説示したとおりである。
◆判決本文
第1次取消訴訟はこちらです。
◆平成28(行ケ)10083
関連事件(対象が第5712040号)です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(行ケ)10054 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月4日 知的財産高等裁判所(3部)
原告は,本件発明1は,引用発明1に甲2文献記載の技術事項を組み合 わせることにより,当業者が容易に想到することができたものであると主 張する。
イ そこで検討するに,甲1文献における「比較例4,8〜10は発泡性, ガス保留性試験においては実施例2同様良好であったが,経日安定性に著 しく劣った。」(上記2(1)ケ)との記載から,引用発明1には経日安定性 に問題があることが理解され,当業者は,経日安定性の改善を課題として 見いだすといえる。 そして,1) 甲1文献に「後記特定組成の発泡性化粧料は,2剤型であ る為経日安定性に優れ,」(同エ)との記載があり,経日安定性試験の結 果が◎又は○である実施例1〜11(第1表)は2剤型の構\成であること (同ク),2) 経日安定性が○である比較例3(第2表)は,同様の第1\n剤と炭酸水素ナトリウムのみをPEGで被覆した粉末の2剤型の構成であ\nること(同ケ)から,炭酸塩と酸とを2剤に分ければ経日安定性が向上す ること,及び酸を水溶液とし,炭酸塩をPEG被覆すればアルギン酸ナト リウムが存在せずとも経日安定性は十分となることが理解できる。そうす\nると,これらの甲1文献に開示された事項に基づき,引用発明1の経日安 定性を改善しようとした場合,炭酸塩と酸との反応で経日安定性が低下す ることを避けるため,引用発明1において,「アルギン酸ナトリウム・炭 酸塩含有PEG被覆粉末1+酸含有PEG被覆粉末2の混合物」という構\n成を,「アルギン酸ナトリウム・炭酸塩含有PEG被覆粉末1」と「酸含有PEG被覆粉末2」との2剤に分けることは,当業者であれば容易に想 到するといえる。
このように,甲1文献の記載から,経日安定性の改善のために引用発明 1の構成を2剤に変更するという解決手段を読み取れるにもかかわらず,\nさらに,甲2文献記載の技術事項を組み合わせる動機付けは見当たらない。 また,引用発明1は二酸化炭素による血行促進作用によって皮膚を賦活 化させるための化粧料で,アルギン酸ナトリウムは安定な泡を生成し,二 酸化炭素の保留性を高めるために配合されているのに対し,甲2文献には 二酸化炭素の発生についての記載はなく,甲2文献記載の技術事項におけ るアルギン酸ナトリウムは二価以上の金属塩類との反応により皮膜を形成 するためのものであって,化粧料の使用目的もアルギン酸ナトリウムの配 合目的も異なるものである。そして,甲1文献及び甲2文献には,引用発明1に甲2文献記載の技術事項を組み合わせた場合に引用発明1における 発泡性及びガス保留性を維持することができることを示唆する記載もない から,このことからも,引用発明1に甲2文献記載の技術事項を組み合わ せる動機付けがあることは否定される。
ウ 以上によれば,本件発明1について,当業者が,引用文献1に甲2文献 記載の技術事項等を適用することによって容易に想到することができたと いうことはできない。また,以上に述べたところは,本件発明9における相違点Dについても妥当する。これによれば,本件発明2〜8,10〜13についても,同様 に,容易に想到することができたとはいえない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,引用発明1にはダマ形成問題及び攪拌問題が存在するから,こ れらの課題を解決するために,甲2文献記載の技術事項を組み合わせる動 機付けがあると主張する。
(ア) ダマ形成問題について
ダマとは粉末の水和が早いことにより起こり,粉末の回りを水分子が 取り囲んで塊となり,粉末の内部まで水が浸透していかず,粉末が均一 に水に分散しない状態をいうと解され,アルギン酸ナトリウムを水に溶 解する際にダマが生じる問題があることが認められる(甲2,59〜6 2)。 しかし,甲1文献にはこのような問題について記載も示唆もない。そ して,引用発明1のように炭酸塩とアルギン酸ナトリウムの混合物がP EGで被覆された粉末においては,アルギン酸ナトリウムは少しずつ水 に溶解することが容易に理解され,このような炭酸塩とアルギン酸ナト リウムとの混合物がPEGで被覆された粉末と,被覆のないアルギン酸 ナトリウム粉末では水和のし易さが異なるから,引用発明1において, アルギン酸ナトリウムを水に溶解する際の一般的な問題が同等に当ては まるということはできず,当業者が,引用発明1につきダマ形成問題の 課題を見出すとは認められない。 また,原告は,甲44文献の記載によれば,PEGの被覆によりダマ 形成問題は解消しないと主張するが,原告の指摘する「主成分(ママコ を生じ易い糊料)の特性が阻害されたり,糊液粘度も変動する等の問題 点を抱えており,ママコの形成方法ないし消失法として効果的でなかっ た」との記載は,PEGの被膜によりママコが消失したとしても,異な る問題が生じ得ることを示したものと解され,引用発明1においてダマ 形成問題があることの根拠とはならないのは明らかであるから,原告の 主張は採用できない。 以上によれば,当業者は,引用発明1においてダマが形成されるとい う問題が生じるとは理解しないというべきである。
(イ) 攪拌問題について
原告は,引用発明1において,アルギン酸ナトリウムがダマを形成し, また,アルギン酸ナトリウムの水溶液濃度の上昇に伴って粘度が飛躍的 に上昇し,これと並行して炭酸塩と酸の反応が進行するから,少しでも 多くの二酸化炭素を取り込むためには難溶解性のアルギン酸ナトリウム の溶解及び均一化をできる限り短時間で行うことが求められ,そのため の徹底的な攪拌が不便かつ煩わしいという問題があると主張する。 しかし,このような問題は甲1文献に記載も示唆もなく,かえって,発泡性及びガス保留性は◎という引用発明の試験結果に照らせば,引用 発明の構成において,少しでも多くの二酸化炭素を取り込むために,素\n早く徹底的な攪拌操作をする必要があり,これが煩わしいという課題が あるとは解し得ない。
イ 以上のとおり,引用発明1において,当業者が原告の主張する課題を見 いだすとは認められないから,引用発明1に甲2文献記載の技術事項を組 み合わせることの動機付けがあるということはできず,原告の主張は採用 できない。
◆判決本文
こちらは分割出願に関する関連事件(審決取消事件)です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成30(行ケ)10124 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
(1)本件商標は,指定商品を「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェ\nア」として,別紙「本件商標」記載のとおり,「envie CHAMPAGNE GLAY」の 欧文字と「アンヴィ シャンパングレイ」の片仮名を上下二段に書してなるもので あ る と こ ろ , こ の 欧 文 字 と 片 仮 名 と は , 「 envie 」 と 「 ア ン ヴ ィ 」 ,「CHAMPAGNE」と「シャンパン」,「GLAY」と「グレイ」が,それぞれ対応 する関係にあることは,取引者及び需要者にとって容易に理解できる。 そして,前記認定に係る辞書,事典,雑誌,新聞等の記載内容及び掲載媒体等に 鑑みれば,本件商標のうち「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の表示は,「フ\nランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味する語であって, 生産地域,製法,生産量など所定の条件を備えたぶどう酒にだけ使用できるフラン スの原産地統制名称であって,本件商標の登録査定時以前から,日本において,シ ャンパーニュ地方産スパークリング・ワインの名称としてにとどまらず,発泡性ぶ どう酒の代名詞のようなイメージを持たれるほどに取引者のみならず消費者に広く 認識され,多大な顧客吸引力を有する極めて著名な表示であったことが認められる。\nしかも,商標法4条1項7号に当たるとされたとはいえ,「CHAMPAGNE(シャ ンパン)」の文字をその構成に含む商標や,これを模した商標が様々な指定商品又\nは指定役務につき出願されたことに鑑みると,日本において,上記表示は,ぶどう\n酒という商品分野に限られることなく,取引者及び需要者に対して高い顧客吸引力 を有するものであることがうかがわれる。 他方,本件商標を構成する他の要素のうち「envie」,「アンヴィ」は,フラン ス語で「羨望」を意味するとしても,一般の取引者及び需要者になじみのある語と はいい難い。また,他の要素である「GLAY」,「グレイ」は,「灰色」を意味する英語ないし外来語として広く認識されているということができるものの,これと 「CHAMPAGNE」,「シャンパン」とを一体的に結合した「CHAMPAGNE GRAY」,「シャンパングレイ」については,原告ないし訴外会社の商品及び他社 の商品において色彩を示す表示として使用された例は認められるものの,色彩を表\ 示する語としても,その他の意味を示す語としても,広く一般的に認識されている 語と認めるに足りる証拠はない。まして,これと「envie」,「アンヴィ」を一体 的に結合した「envie CHAMPAGNE GLAY」,「アンヴィ シャンパングレイ」 の語が広く一般的に認識されていると認めるに足りる証拠はない。 これらの事情を踏まえると,本件商標からは,「アンヴィ シャンパングレイ」 の称呼及び観念を生じるのみでなく,「シャンパン」の称呼及び「フランスのシャ ンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」との観念をも生じるということができ る。
(2) 前記各認定事実によれば,本件商標のうち「CHAMPAGNE」,「シャンパ ン」の部分は,フランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワイン (発泡性ぶどう酒)を意味する語であるところ,フランスにおいて,1908年 (明治41年)には法律により「CHAMPAGNE」という名称が法律上指定され, その後,原産地統制名称法(1935年7月30日付けデクレ)その他の法令により原産地統制名称として保護されていることが認められる。具体的には,公立行政 機関である原産地名称国立研究所(INAO)が定める生産区域,ぶどうの品種,生 産高,最低天然アルコール純度,栽培方法,醸造方法,蒸留方法に関する諸生産条 件を満たすぶどう酒のみがその名称として「CHAMPAGNE」(シャンパン)を使 用する権利を有することとして,シャンパーニュ地方産ワイン製品の品質につき厳 格な管理・統制が行われる一方でその生産者が保護されており,被告は,その製品 の専門的利益を防禦することをその任務とし,フランス国内及び国外において, 「CHAMPAGNE(シャンパン)」の原産地統制名称を保護する等の活動をしてい る。こうした被告をはじめとするシャンパーニュ地方のワイン生産者等の努力の結果,「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の表示及びその対象であるシャンパーニ\nュ地方産のスパークリング・ワインは,周知著名性を獲得,維持し,高い名声,信 用ないし評判が形成されている。 これらの事情に鑑みると,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の表示及びその対\n象であるシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインは,フランス及びフラン ス国民の文化的所産というべきものとなっており,重要性が極めて高いものである ことが認められる。 また,日本においても,遅くとも第二次世界大戦後,「CHAMPAGNE」(シャ ンパン)の表示につき,フランス国内法が尊重されている。\n
(3) 以上のような本件商標の文字の構成,指定商品の内容,本件商標のうちの\n「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の文字がフランスにおいて有する意義や重要 性,日本における周知著名性等を総合的に考慮すると,本件商標をその指定商品に 使用することは,フランスのシャンパーニュ地方におけるぶどう酒製造業者の利益 を代表する被告のみならず,法令により「CHAMPAGNE(シャンパン)」の名声, 信用ないし評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し,日本とフランスと の友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり,国際信義に反し, 両国の公益を損なうおそれが高いといわざるを得ない。 したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当するというべきである。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,「envie CHAMPAGNE GLAY」は原告ないし訴外会社が販売する コンタクトレンズブランド「envie」において「シャンパングレイ色」のカラーコ ンタクトレンズを示すものであり,「CHAMPAGNE」,「シャンパン」は色彩を 表示するものであり,これと色彩を示す「GLAY」,「グレイ」とが一体不可分で あることから,色彩以外の意味合いを想起することはないなどと主張する。 イ しかし,前記のとおり,「CHAMPAGNE GLAY」,「シャンパングレイ」 や「envie CHAMPAGNE GLAY」,「アンヴィ シャンパングレイ」が一体不可分のものと認識されているとはいえない。 また,「シャンパン」の語が色彩を意味する例があるといっても,「シャンパン 色(緑黄又は黄褐色)」(甲17),「シャンパン色,淡黄[緑黄]色」・「シャ ンパン(色)の」(甲18),「シャンパン色(緑黄色又は琥珀(こはく)色)」 (甲19),「シャンパン色(緑黄又は黄褐色)」(甲20),「シャンパン色の (淡い黄色)」(甲21)とされ,色彩としての「シャンパン」に相当する色彩の 表現が「緑黄色」,「黄褐色」,「琥珀色」などと必ずしも一致していないことか\nらもうかがわれるとおり,いずれもスパークリング・ワインとしてのシャンパンを 想起させることによって,いわば比喩的に「シャンパン」の語を用いて色彩を表現\nしているものである。このことは,前記のとおり,本件商標が「シャンパン」の称 呼及び「シャンパーニュ地方産のスパークリング・ワイン」の観念を生じることを むしろ裏付けるものといえる。 その他,原告は他の商標との関係や米国での商標登録の実情などをるる指摘する けれども,いずれも本件と直接関係するものではない。 したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成30(行ケ)10048 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
(4) 相違点3の容易想到性について
ア 前記認定に係る各文献の記載によれば,まず,甲9の軸受保持部材28は, 鍔部及び係止爪と類似する構成であるフランジ34と突起32とを有するものの,\n当該軸受保持部材28は,回転するカッター軸38を回転自在に支持するものでは なく,オイルシール40と,ころがり軸受であるオイルレスベアリング42とを支 持するものであり,軸受け部材に相当するものではない。 他方,甲5〜8,10〜16及び18は,いずれも,軸受け部材に関する技術が 記載されたものと認められるところ,弾性変形可能な係止爪が外周に突出し,基端\n側に鍔部を有し,また,係止爪は先端側に向かうほど当該軸受け部材における軸の 回転中心との距離が短くなる斜面を有している軸受け部材を,固定された板状体に 対して装着し,当該板状体に設けられた穴に軸を回転自在に支承するものである点 で共通するものの,固定された板状体以外の部材に装着することについての記載や 示唆はない。 また,甲17においては,軸受Aが装着されるボス(6)自体は板状体ではないもの の,ボス(6)は板状のベース(5)に固定されたものであり,軸受Aのフランジ板(1)と爪 片(4)の係合突起(4a)との間にのみボス(6)が配置されるものである。そうすると, 甲17と甲5〜8,10〜16及び18とは,直接に装着する対象そのものが板状 体であるか否かという点で違いはあるものの,いずれも装着される部材は板状体又 は板状のものに固定された部材であり,これをフランジと爪片との間で狭持するよ うにして固定する軸受け部材である点で共通するといえる。 以上を踏まえると,甲5〜8及び10〜18により,「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する,滑り軸受けである軸受け部材において,弾性変形可能な\n係止爪が外周に突出しており,基端側に鍔部を有しており,同係止爪は先端側に向 かうほど軸受け部材における軸の回転中心との距離が短くなる斜面を有している軸 受け部材。」を周知技術として認定することができる。これは,本件審決認定に係 る周知軸受け部材に相当する。なお,甲5〜18の全ての文献から,軸受け部材に 関する周知技術というべき共通の技術事項を認めることはできない。
イ また,その余の文献の記載を見ても,まず,甲2〜4は,いずれもY字形を なし,二股に分かれた部分の先端付近に一対の回転体を設けて構成される美容器に\nおいて,回転体が非貫通状態で軸に支持されることを開示するものの,当該回転体 の支持構造として,本件発明1のような「係止爪」及び「段差部」を用いるものではない。\n次に,甲19の1のマッサージローラーは,その内装面に周囲を巡る凹部を備え, 「段差部」に類似する構成を有するものといい得るものの,マッサージローラー自\n体が弾性材料より構成されることにより,鞘の外装面の周囲を巡る隆起との間でス\nナップ結合をすることができるようにしたものである点で,本件発明1とは異なる。 他方,甲20の1のプラグ200は,フランジ201及びラッチアーム204に 突起205を有する点で,本件発明1の軸受け部材に類似する構成を有するものと\nいい得るものの,プラグ200は,2つのモジュールを固定するものであって,支 持軸に設けられる軸受け部材として機能するものではない。加えて,プラグ200\nは,モジュール140の貫通した孔からロックピン240を挿入することにより, プラグ200のラッチアーム204がモジュールの開口のラッチ凹部から離脱する のを防止するものであるから,非貫通状態の回転体を支持するために用いることを 前提としないことは明らかである。 そうすると,軸受け部材を用いて軸に対して非貫通状態の回転体を支持する際に, 回転体の内面に段差部を設けるとともに,軸受け部材には当該段差部に係止する係 合爪を用いる構成が開示されていることを認めるに足りる証拠はない。\n
ウ そもそも引用発明1は,ベアリング12及びL型ベアリング13という2つ の軸受け部材を用いることによって,ローラー4を回転自在に支承するものであるところ,これを1つの軸受け部材に置き換えることが可能であることを記載ないし\n示唆する証拠は見当たらない。 また,仮に引用発明1のベアリング12及びL型ベアリング13を1つの軸受け 部材に置き換えることが可能であったとしても,引用発明1のローラー4は,顔面\nに接触させて回転させるものであり,その長手方向と直交する方向に荷重がかかる ことは明らかであるところ,1つの軸受け部材に置き換えてしまうと,ローラーを その根元の部分でのみ支承することとなってしまい,ローラーを安定して回転させ ることが困難となることは容易に推察される。 そうすると,引用発明1のベアリング12及びL型ベアリング13を1つの軸受 け部材に置き換える動機付けはなく,むしろ阻害要因が存するといえる。
エ 以上より,引用発明1に甲2〜20の1記載の事項を適用することによって, 相違点3に係る本件発明1の構成を採用することは,当業者にとって容易に想到し\n得ることとはいえない。
オ 原告の主張について
(ア) 原告は,甲5〜18記載の事項を引用発明1に適用することが容易である ことを理由として無効理由の主張を行っているのではなく,これらの文献から共通して抽出される構成が周知の軸受け部材であるとし,これを引用発明1に適用する\nことが容易であったと主張しているにもかかわらず,本件審決は,各文献記載の事 項を個別に判断しており,その判断手法に誤りがあるなどと主張する。 しかし,甲5〜18の全ての文献から軸受け部材に関する周知技術というべき共 通の技術事項を見出すことはできないことは,前記のとおりである。本件審決は, その記載を通じて見れば,そのような理解を前提とした上で,個々の証拠における 軸受け部材を引用発明1に適用できるかを検討したものと理解されるのであり,そ の判断手法に違法があるものとはいえない。
(イ) 原告は,本件審決による周知軸受け部材の認定には誤りがある旨主張する けれども,この点に関する本件審決の判断に誤りがないことは前記のとおりである。
(ウ) 原告は,本件審決につき,実施可能要件適合性の判断においては甲5〜1\n8の記載を参酌し,板状体ではない回転体に使用する軸受け部材に係る係止片を弾 性変形させる場合に所定のクリアランスを設けることは技術常識であると認定する 一方で,進歩性の判断においては,甲5〜18の周知技術の認定として,これが技 術常識でないことを前提として判断しており,その認定・判断に矛盾があるなどと 主張する。 この点に関する原告の主張の趣旨は,やや判然としないが,そもそも,本件審決 は,実施可能要件適合性の判断の際,「係止爪を弾性変形させるために所定のクリ\nアランスを設けること」を技術常識として認定するにあたり,甲5〜18を参酌し たものではない。また,上記技術常識が認められるか否かと,甲5〜18の記載か ら原告主張に係る周知軸受け部材を認定し得るか否かとは,直接的な関係はない。 すなわち,「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する,滑り軸受けである 軸受け部材において,弾性変形可能な係止爪が外周に突出しており,基端側に鍔部\nを有しており,同係止爪は先端側に向かうほど軸受け部材における軸の回転中心と の距離が短くなる斜面を有している軸受け部材」(本件審決認定に係る周知軸受け 部材)において,「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する」ことは,係 止爪が弾性変形するためのクリアランスを設けることを前提とするか否かとは直接 的な関係がないことから,仮に係止爪が弾性変形するためのクリアランスを有する ことが技術常識であることを前提としても,その認定が異なることはない。
(エ) その他原告がるる指摘する点を考慮しても,この点に関する原告の主張は 採用できない。
(5)小括
以上のとおり,少なくとも,引用発明1に甲2〜20の1記載の事項を適用する ことによって,相違点3に係る本件発明1の構成を採用することは,当業者にとっ\nて容易に想到し得たものとはいえない。そうである以上,その余の点を論ずるまで もなく,本件発明1を容易に発明することができたとはいえない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成30(ネ)10033 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1 争点3−4(乙64の1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由の有無)に ついて
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて\n
被控訴人は,控訴人が当審において追加主張した乙64の1を主引用例と する進歩性欠如(争点3−4)を無効理由とする特許法104条の3第1項 の規定に基づく無効の抗弁(以下「本件無効の抗弁」という。)について, 民事訴訟法157条1項に基づき,時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下することを求める申立てをしたので,以下において判断する。\n
ア 前記第2の1(前提事実等)の(6)及び一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 控訴人は,平成27年4月17日の原審第4回弁論準備手続期日に おいて,被告準備書面(2)に基づき,実施可能要件違反の無効理由(争点\n3−1)による無効の抗弁の主張をし,同年9月14日の原審第7回弁 論準備手続期日において,被告準備書面(5)に基づき,明確性要件違反(争 点3−2)の無効理由による無効の抗弁の主張をした。 その後,原審の受命裁判官は,同年10月27日の第8回弁論準備手 続期日において,本件の侵害論の審理を終了し,損害論の審理を進める と述べた上で,控訴人に対し,被控訴人の損害主張に対し具体的に認否 反論し,必要な書面を提出するよう求めた。
(イ) 控訴人は,平成28年5月19日,本件発明1,2,6及び8につ いての本件特許を無効にすることを求める別件無効審判を請求した。 同年12月13日の原審第12回弁論準備手続期日において,控訴人 は,被告準備書面(10)に基づき,別件無効審判と同一の無効理由(サポー ト要件違反(争点3−3)の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理 由を含む。)による無効の抗弁を追加して主張したのに対し,被控訴人 は,同期日において,上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下 することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は,被控訴人の上記\n申立てを容れて,控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。\n
(ウ) 特許庁は,平成29年12月15日,本件訂正後の請求項1,6及 び8に係る発明についての本件特許には,サポート要件違反(争点3− 3)の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして, 上記特許を無効とする別件審決をした。 同月20日の原審第18回弁論準備手続期日において,控訴人は,被 告準備書面(15)に基づき,別件審決が認めたサポート要件違反の無効理 由及び本件無効の抗弁に係る無効理由による無効の抗弁を再度追加して 主張したのに対し,被控訴人は,上記主張は時機に後れた攻撃防御方法 として却下することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は,被控訴人の上記申\立てを容れて,控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。 原審は,同日,原審第2回口頭弁論期日において,本件訴訟の口頭弁 論を終結した後,平成30年3月22日,被控訴人の請求を一部認容す る原判決を言い渡した。 この間の同年1月20日,被控訴人は,別件審決の取消しを求める別 件審決取消訴訟を提起した。
(エ) 控訴人は,平成30年4月9日,本件控訴を提起した。控訴人は, 同年6月5日付けの控訴理由書において,被告準備書面(10)及び(15)を 引用して,サポート要件違反(争点3−3)の無効理由による無効の抗弁 及び本件無効の抗弁を記載した。 同年7月24日の当審第1回弁論準備手続期日において,控訴人は, 控訴理由書に基づき,本件無効の抗弁を主張し,被控訴人は,控訴答弁 書に基づき,上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下すること を求める申立てをした。\n同年10月15日の当審第2回弁論準備手続期日において,控訴人は, 同年8月31日付けの控訴人準備書面(1)及び同年9月14日付けの控 訴人準備書面(2)に基づき,本件無効の抗弁の主張を補足し,被控訴人は, 同年10月1日付けの被控訴人第1準備書面に基づき,本件無効の抗弁に対する反論及び訂正の再抗弁を主張した。 その後,当裁判所は,同年12月10日の第1回口頭弁論期日におい て,本件口頭弁論を終結した。
イ 前記アの認定事実によれば,控訴人の当審における本件無効の抗弁の主 張は,原審において侵害論の審理を終了し,損害論の審理に入った段階で 提出されたため,時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨 のものであるが,控訴人は,原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る 無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされた のを受けて,当審において再度提出したものであること,控訴人は,控訴 理由書に本件無効の抗弁を記載し,当審の審理の当初から本件無効の抗弁 を主張していたことが認められるから,当審における控訴人による本件無 効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということはできない。また,当審の審理の経過に照らすと,控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出 により,訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。 したがって,当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張を時機に 後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
(2) 本件明細書の記載事項等について
ア 本件発明1,2及び6の特許請求の範囲(請求項1,2及び6)の記載 は,前記第2の1(前提事実等)の(2)のとおりである。
・・・
前記aの記載事項によれば,乙64の2には,押しボタン式バルブ の下側で不燃性液体の上側の位置に,通気性を有する「連続気泡状パ ッキング」を挿入した,不燃性液化ガスを充填した噴射口を有する「噴 気式清掃機」の記載があり,その「連続気泡状パッキング」は,缶体 を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れて液体 のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があるこ とが認められる。 そして,乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」は,連続気泡 を有する多孔質体であり,図2(別紙3)から円筒状の缶体内に挿入 された円板状の形状であることを理解できるから,「円板状多孔質 体」として,本件発明1の「通気性蓋状部材」に該当するものと認め るのが相当である。
(イ) 乙64の1には,スプレー缶を倒立状態で使用した場合や缶を倒立 状態で保管する場合に液漏れの原因となり,可燃性液化ガスの液漏れに より火炎が発生するおそれがあるため,吸収性能・保液性に優れた吸収\n体を提供することが課題であること(【0004】,【0054】)の 記載がある。 一方で,乙64の2には,乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」 は,缶体を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れ て液体のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があ ることは,前記(ア)bのとおりである。 そうすると,乙64の1及び乙64の2に接した当業者は,乙64の 1の第1発明において,スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸収体 に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にするために,乙6 4の1の第1発明に乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」の構成\nを適用する動機付けがあるものと認められる。 また,乙64の1の「具体的には,スプレー缶形状に合わせて,その 内径に適した大きさの円筒状の成形体とすると,充填が容易にできる上, 使用中も安定してスプレー缶内に保持することができる。」(【003 2】)との記載から,スプレー缶の使用中に吸収体を安定して保持する 必要性があることを理解できる。 以上によれば,当業者は,スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸 収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にし,吸収体を 安定して保持するために,乙64の1の第1発明において,乙64の2 の連続気泡状パッキングを適用する際に,乙64の2記載の連続気泡状 パッキングの構成のものを吸収体の表\面に密接に配置し,相違点2に係 る本件発明1の構成を容易に想到することができたものと認められる。\n
(ウ) これに対し被控訴人は,乙64の2記載の「連続気泡状パッキング4」は,バルブ2の下側に空間を形成するため缶体1に固定されている 必要があるため,肩部からバルブ側に押し込むように固定され(図2), バルブ2側に十分大きい空間が形成されないので,倒立状態では,比重\nの重い液体が下側(バルブ2側)へ移動し,バルブ側の空間に容易に液 が漏れることになって,倒立状態のまま噴射を継続することができない こと,乙64の2には,図2以外に,「連続気泡状パッキング4」の充 填状態について具体的に説明する記載はないことからすると,乙64の 1の第1発明に乙64の2記載の「連続気泡状パッキング」を組み合わ せる動機付けはないし,また,乙64の1の第1発明に乙64の2記載 の「連続気泡状パッキング」を組み合わせたとしても,本件発明1の通 気性蓋状部材の構成に至ることはない旨主張する。\nしかしながら,乙64の1の第1発明において,スプレー缶を倒立状 態で使用した場合の吸収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防 止を確実にするために,乙64の1の第1発明に乙64の2記載の「連 続気泡状パッキング」の構成を適用する動機付けがあることは,前記\n(イ)のとおりである。 また,乙64の2には,連続気泡状パッキングが図2で示された位置 に配置することが不可欠である旨の記載はなく,連続気泡状パッキング の具体的な設置方法及び設置場所は,当業者が適宜決定すべき事項であると認められる。 さらに,乙64の2の【0012】の「連続気泡状パッキング4を挿 入し,たとえ缶体1を逆さまにして使用しても不燃性液体3が液体のま ま噴出することなく,ガスの整流性が良くなる。」との記載に照らすと, 乙64の2の「噴気式清掃機」が連続気泡状パッキングを挿入したため に倒立状態のまま噴射を継続することができないものと理解すること はできない。 したがって,被控訴人の上記主張は,採用することができない。
・・・
(7) まとめ
以上のとおり,本件発明1,2及び6は,乙64の1の第1発明及び乙6 4の2記載の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた ものと認められ,進歩性を欠くものであるから,本件特許には,特許法29 条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)があり,特許無効審判 により無効とされるべきものと認められる。
2 争点3−5(訂正の再抗弁の成否)(本件発明1及び6に関し)について
被控訴人は,本件訂正により,訂正前の請求項1及び6(本件発明1及び6) の無効理由は解消され,かつ,被告製品は,本件訂正発明1及び6の技術的範 囲に属するから,被控訴人は,控訴人に対し,本件特許権を行使することがで きる旨主張する。 そこで検討するに,本件訂正発明1(本件訂正後の請求項1)は,灰分含有 量を「1重量%以上12重量%未満」とするものであり,本件発明2と同一の 構成であるところ,前記1(5)のとおり,本件発明2は,乙64の1の第1発明 及び乙64の2の技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで きたものと認められるから,本件発明1の無効理由は,本件訂正により解消されるものとはいえない。 また,前記1(6)で説示したのと同様の理由により,本件発明6の無効理由は, 本件訂正により,解消されるものとはいえない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,被控訴人の上記主張 は理由がない。
3 結論
以上によれば,本件発明1,2及び6は,進歩性を欠くものであり,本件特 許には,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)があ り,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから,被控訴人は, 同法104条の3第1項の規定により,控訴人に対し,本件特許権を行使する ことはできない。
◆判決本文
関連の審決取消し訴訟です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成29(ワ)34450 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月31日 東京地方裁判所(46部)
前記(1)によれば,本件発明の意義は以下のとおりであると認められる。 従来の住宅地図は,建物表示に住所番地だけでなく居住者氏名も全て併記さ\nれていたため,氏名を記載するためのスペースを確保するために住宅地図の縮 尺を高くすることができず,そのため,地図の大きさも比較的大きくする必要 があるとともに,地図に氏名が記載されることによるプライバシー侵害や利用 者の検索への支障を生じたり,地図の更新作業のための調査に膨大な労力と人 件費がかかったりするという課題があった。また,住宅地図に付されている索 引についても,住所のうち丁目と,それぞれの丁目に該当するページが掲載さ れているだけであったため,同一の丁目の中で番地が異なっている多くの建物 の中から目的とする建物を探し出す必要があった。 本件発明は,居住者氏名を記載しないため,高い縮尺度で地図を作成するこ とにより小判で,薄い,取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することや, 地図の更新のために氏名調査等の労力を要しないことによって廉価な住宅地 図を提供することを可能にするとともに,地図上に公共施設や著名ビル等以外\nは住宅番地のみを記載し,地図のページを適宜に分割して区画化したうえで建 物の所在する番地と記載ページと記載区画の記号番号を一覧的に対応させた 索引欄を付すことによって,簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅地図\nを提供することを可能にするものである。\n
2 争点1−4(構成要件D(「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画\n化し」)についての文言侵害の有無) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告地図プログラムは,ユーザが,インターネット上の「https:/ /以下省略」のURLにアクセスし,所定の操作をするなどすると,ユーザ の端末にインストールされているWebブラウザを介して,ユーザ端末のデ ィスプレイに地図を表示できるようにしたプログラムである。\n被告地図プログラムにより表示される地図では,縮尺レベルが1〜20の\n20段階に分かれており,縮尺レベル20が最も詳細(縮尺率が小さい)な もので,縮尺レベル1が最も広域(縮尺率が大きい)なものである。各縮尺レベルに応じて,地図用のデータが存在する。 りディスプレイの画面に表示さ\nれる地図の画面表示等は,別紙「被告地図プログラムの構\成(分説)」記載の とおりである。(以上につき,甲13ないし19,乙1,22,弁論の全趣旨)
イ 被告地図において,市区町村名,町名,丁目及び番の表示の右側に〔地図〕\nと表示された部分等にはハイパーリンクが設定されており,そのハイパーリ\nンクに係るURLは,冒頭に「https://以下省略」と記載され,そ の後の記載がパラメータであることを示す「?」が記載された後に,「lat =…&lon=…&ac=…&az=…」及び「z=…」という記載を含む ものである。前記のlat,lon,ac,azが示す各値は,それぞれ当 該地点に係る緯度,経度,都道府県及び市区町村の住所コード,町,丁目, 番又は号の番号を示し,zが示す値は縮尺レベルを示す。ユーザがディスプ レイ画面上で当該ハイパーリンクをクリックすると,その緯度経度を含む地点データと縮尺データを含むURLが被告地図の地図提供サーバに送信さ れる。地図提供サーバが,この地点データに係る地点を含み,かつ,縮尺デ ータに係る縮尺のメッシュ地図を地図データベースサーバから読み出し,ユ ーザのパソコンに送信することにより,ユーザのディスプレイ画面上におい\nて当該緯度経度を中心とした所定の縮尺の地図が表示される。(甲4ないし\n19,弁論の全趣旨)
ウ インターネットに接続した状態で被告地図をユーザのディスプレイ画面 に表示し,その後,インターネットの接続を停止した上で地図表\示画面をス クロールさせると,地図が表示されない部分が画面上に表\示される。(甲3 4,弁論の全趣旨)
エ 被告地図プログラムにおける縮尺レベル19の縮尺は,概ね1/1250 から1/2857の範囲であり,被告地図における縮尺レベル20の縮尺は, 概ね1/615程度である。(甲33,乙1,弁論の全趣旨)
(2)本件明細書には、前記1(1)記載のほか、(発明の実施の形態)として以下 の記載がある。なお,以下の図1ないし5は,それぞれ,本判決別紙本件明細 書図1ないし5である。 ア 段落【0017】
・・・
(3)構成要件Dの「適宜に分割して区画化」について\n
構成要件Dの「適宜に分割して区画化」の意義について,特許請求の範囲の\n「各ページを適宜に分割して区画化し,…住宅建物の所在する番地を前記地図 上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対 応させて掲載」という記載(構成要件D,E及びF)に照らせば,構\成要件D の「適宜に分割して区画化」とは,記号番号を付すことや番地と対応する区画 を一覧的に示すことができる区画を作成することが可能となるように,検索す\nべき領域の地図のページを分割し,認識できるようにすることといえる。 そして,本件発明は, 前記1(2)のとおり、地図上に公共施設や著名ビル等以 外は住宅番地のみを記載するなどし,全ての建物が所在する番地について,掲 載ページと当該ページ内で分割された該当区画を一覧的に対応させて掲載し た索引欄を設けることによって,簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅\n地図の提供を可能にするというものであり,本件発明の地図の利用者は,索引\n欄を用いて,検索対象の建物が所在する地番に対応する,ページ及び当該ペー ジにおける複数の区画の中の該当の区画を認識した上で,当該ページの該当区 画内において,検索対象の建物を検索することが想定されている。そのために は,当該ページについて,それが線その他の方法によって複数の区画に分割さ れ,利用者が該当の区画を認識することができる必要があるといえる。そうす ると,本件明細書に記載された本件発明の目的や作用効果に照らしても,本件 発明の「区画化」は,ページを見た利用者が,線その他の方法及び記号番号に より,検索対象の建物が所在する区画が,ページ内に複数ある区画の中でどの 区画であるかを認識することができる形でページを区分することをいうとい える。 前記(2)のとおり、本件明細書には、発明の実施の形態において,本件発明を 実施した場合における住宅地図の各ページの一例として別紙「本件明細書図2」 及び「本件明細書図5」が示されているところ,これらの図においては,いず れも道路その他の情報が記載された長方形の地図のページが示されたうえで, そのページが,ページ内にひかれた直線によって仕切られて複数の区画に分割 されており,その複数の区画にそれぞれ区画番号が付されている。また,本件明細書図4の索引欄には,番地に対応する形でページ番号及び区画番号が記載 されており,利用者は,検索対象の建物の番地から,索引欄において当該建物 が掲載されているページ番号及び区画番号を把握し,それらの情報を基に,該 当ページ内の該当区画を認識して,その該当区画内を検索することにより,目 的とする建物を探し出すことが記載されている(段落【0028】)。ここでは, 上記の特許請求の範囲の記載や発明の意義に従った実施の形態が記載されて いるといえる。そして,「区画化」の意義に関係して,他の実施の形態は記載さ れていない。
以上によれば,構成要件Dの「区画化」とは,地図が記載されている各ペー\nジについて,記載されている地図を線その他の方法によって仕切って複数の区画に分割し,その各区画に記号番号を付すことであり,索引欄を利用すること で,利用者が,線その他の方法及び記号番号により,当該ページ内にある複数 の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割するこ とを意味すると解するのが相当である。 原告は,被告地図において,縮尺レベル19の住宅地図及び縮尺レベル20 の住宅地図がそれぞれ構成要件Dの「該地図を記載した各ページ」に該当する\nと主張した上で,被告地図のデータは,画面に表示されるときに区分された形\nでその一部が表示されるから構\成要件Dの「適宜に分割して区画化」されると 主張するとともに,「メッシュ化」され,また,複数のデータとして管理されて いるから構成要件Dの「適宜に分割して区画化」することになると主張する。\nしかし,仮に,縮尺レベル19の住宅地図及び縮尺レベル20の住宅地図が それぞれ構成要件Dの「該地図を記載した各ページ」に該当するとしても,利\n用者は,画面に表示されている地図を見ているのであって,線その他の方法及\nび記号番号により,ページにある複数の区画の中で,検索対象の建物が所在す る地番に対応する区画を認識することができるとはいえない。被告地図におい て「メッシュ化」がされていて,また,被告地図に係るデータが複数のデータ として管理されているとしても,被告地図プログラムの構成(分説)及び前記\nアないしウに照らし,利用者は,「メッシュ化」されている範囲や区分された データを通常認識しないだけでなく,それらに対応する記号番号を認識するこ とはない。したがって,被告地図において,線その他の方法及び記号番号によ り,ページにある複数の区画の中で,検索対象の建物が所在する地番に対応す る区画を認識することができるとはいえない。そうすると,前記 に照らし, 被告地図において,「各ページ」が,「適宜に分割して区画化」されているとは いえない。 これらによれば,被告地図について,構成要件Dの「適宜に分割して区画化」\nがされているとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.02. 7
平成30(ワ)3018 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所(46部)
前記(2)のとおり、本件各名作書には、本件参照抗体と競合する,PCSK 9−LDLR結合中和抗体を同定,取得するための,免疫プログラムの手順 及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法,ハイブリドーマの作製 方法,スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載 されている。そして,当該方法によれば,本件各明細書で具体的に開示され た以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。 そうすると,本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が,本件各\n明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1 若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られる とはいえない。したがって,本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範\n囲が本権各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定のアミノ酸 の1もしくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限ら れることを前提として,本件各発明の技術的範囲が本件各明細書記載の具体 的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のア ミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるとの被告の主張 は採用することができない。
(4)また,被告は,1)本件各明細書では,本件参照抗体と競合する抗体であれ ば,PCSK9とLDLRの結合を中和することができるという技術思想を 読み取ることはできない,2)本件各明細書の実施例に記載された3グループ ないし2グループの抗体のみによって,本件参照抗体と競合する膨大な数の 抗体全てがPCSK9−LDLR結合中和抗体であるとはいえず,本件各明 細書には,本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体がPCSK9−LDLR 結合中和抗体であることの根拠は全く示されていないと主張する。 しかしながら,前記 のとおり,本件各明細書には,本件参照抗体がP CSK9−LDLR結合中和抗体であること,本件参照抗体がPCSK9に 結合するエピトープと同じエピトープに結合する抗体,又は,本件参照抗体 とPCSK9との結合を立体的に妨害するような上記エピトープに隣接する エピトープに結合する抗体である,本件参照抗体と競合する抗体は,本件参 照抗体と類似した機能的特性を有すると予\想されることが記載されている。 そして,前記 のとおりのスクリーニング等によって得られた本件各明細書の表2記載の30の抗体(21B12参照抗体と31H4参照抗体を除く。)\nのうち,24の抗体はPCSK9−LDLR結合中和抗体であり,かつ,本 件参照抗体と競合する抗体であること,表37.1.のビン1(21B12\n参照抗体と競合し,31H4参照抗体と競合しない抗体)に属する19の抗 体のうち16個,ビン2(21B12参照抗体とも,31H4参照抗体とも 競合する抗体)に属する抗体のうち2個及びビン3(31H4参照抗体と競 合し,21B12参照抗体と競合しない抗体)に属する10の抗体のうちの 7個は,表2に記載された抗体であり,これら16個と2個と7個の抗体の\nうち,27B2抗体並びに21B12参照抗体及び31H4参照抗体を除く 少なくとも20個はPCSK9−LDLR結合中和抗体であることが記載さ れている。そうすると,本件各明細書には,特定のスクリーニング等を経て 得られた抗体のうち,本件参照抗体と競合する複数の抗体がPCSK9−LDLR結合中和抗体であることが示されているといえる。 なお,この点に関係し,被告は,本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体 がPCSK9−LDLR結合中和抗体であることの根拠は全く示されていな いと主張するが,本件各明細書に記載された抗体以外に,本件参照抗体と競 合するがPCSK9−LDLR結合中和抗体ではない具体的な抗体が示され ているものではなく,また,本件参照抗体と競合する抗体中,PCSK9− LDLR結合中和抗体でないものの割合が大きいことも明らかではない。 さらに,被告は,本件参照抗体と競合する抗体は,PCSK9−LDLR 結合中和抗体であるとは限らないとも主張する。しかし,本件各発明は,P CSK9−LDLR結合中和抗体であることを構成要件とするものであるか\nら(構成要件1A,2A),上記のような例外的な抗体は本件各発明の技術\n的範囲に含まれない。
(5)証拠(甲5,7の1,2,甲8〜10)及び弁論の全趣旨によれば,本件 各発明について,被告が主張する限定的な解釈を採らない限り,被告モノク ローナル抗体は,本件発明1−1及び本件発明2−1の各構成要件を全て充\n足し,被告製品は,本件発明1−2及び本件発明2−2の各構成要件を全て\n充足すると認められるから,被告モノクローナル抗体は,本件発明1−1及 び本件発明2−1の技術的範囲に属し,被告製品は,本件発明1−2及び本 件発明2−2の技術的範囲に属すると認められる。なお,被告モノクローナ ル抗体は,本件訂正発明1-1及び本件訂正発明2−1の技術的範囲にも属 し,被告製品は,本件訂正発明1−2及び本件訂正発明2−2の技術的範囲 にも属すると認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 7
平成29(ワ)3572 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月17日 大阪地方裁判所
本件発明は,前述のとおり,塩素化塩化ビニル系樹脂の洗浄方法について, 装置の小型化や使用水量の削減といった生産性の向上を図ろうとするものであると ころ,原告らがこれについて特許を受ける権利を被告に承継したことによる相当の 対価を検討するに当たっては,前記イで述べたような,被告において単にこれを実施し得ることによる利益を考えるのではなく,本件発明が特許として登録され,そ の禁止的効力によって,競業者は本件発明を実施することができなくなり,被告が 競争上優位な立場に立つことによって得られる利益をもって,算定の基礎とすべき ことになる。 そして,既に検討したとおり,本件特許の登録後,競業者は,本件発明を実施す ることはできないが,公知濾過方式については実施することができるのであるから, 両者にコストや生産性の面で差があり,競業者が本件発明を実施できないことによ って被告が競争上優位な立場に立つのであれば,これによって得られる利益を,相 当の対価算定の基礎とすることができる。
エ 原告らの主張,立証について
原告らは,公知濾過方式は実用化されておらず,競業者は,本件発明が実施 できなければデカンタ方式によることを余儀なくされるとして,デカンタ方式から 本件洗浄方式に切り替えたことによるコストの削減が,被告の排他的利益の内容で あると主張する。 しかしながら,公知濾過方式が実用化されていることは既に検討したとおりであ るし,本件発明の排他的利益を検討するに当たっては,前述のとおり,本件発明と 構成として共通する面の多い公知濾過方式と対比するのが相当であるから,原告ら\nの主張は失当である。 また,原告らは,前記ウで述べたような形での,公知濾過方式と対比する形での 本件発明による排他的利益については,予備的にも主張しない旨を明示している。\n以上によれば,特許法35条3項の相当の対価が存すると認めるに足りる主張,立証はないといわざるを得ない。
2019.02. 4
平成30(行ケ)10027 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月28日 知的財産高等裁判所
本件発明1における揮発性作業流体は,ストリッピング処理過程に付 す前に海産油に添加される液体であって,当該ストリッピング処理過程 において,海産油中に存在するある量の環境汚染物質が当該揮発性作業 流体と一緒に該海産油から分離されるものである。また,当該揮発性作 業流体はC10〜C22の遊離脂肪酸を含む。さらに,当該揮発性作業 流体はストリッピング処理過程で油から分離されるものであるから,「揮 発性」とはトリグリセリド等の油よりも揮発性が高いことを意味すると 解される(本件明細書の段落【0014】,【0021】,【0057】, 【0059】〜【0061】)。
これに対し,甲2発明1におけるリノール酸は,ストリッピング処理 過程に付す前にサケ頭油に添加される液体であって,当該ストリッピン グ処理過程において,コレステロールと共に蒸留されるものである(上 記(1)ウ)。そして,リノール酸はC18の不飽和脂肪酸であって,トリ グリセリドと比較すると揮発性が高い(上記(1)ア)。 そうすると,本件発明1における揮発性作業流体と,甲2発明1にお けるリノール酸とは,除去対象物質が環境汚染物質であるかコレステロ ールであるかとの点で違いがあるものの,いずれもトリグリセリドと比 較して揮発性が高く,除去対象物質と共に蒸留される液体であるとの点 で共通する。また,リノール酸は,本件明細書において揮発性作業流体 として例示された「C10〜C22の遊離脂肪酸」に該当する。 したがって,甲2発明1におけるリノール酸は,本件発明1における 揮発性作業流体に当たると認めるのが相当である。 よって,この点についての本件審決の認定には誤りがある。
(オ) 小括
以上によれば,本件審決には,相違点6について,リノール酸が揮発 性作業流体といえるのか否かが明らかではないと認定した点において, 誤りがあるというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 補正・訂正
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成30(ネ)10027 特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月12日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ この点に関し,控訴人らは,1)本件特許権がCMライセンス契約の対象 特許となっていることについて,被控訴人らからこれを裏付ける証拠は提 出されていないこと,2)被控訴人クアルコムは,控訴人アップルと被控訴 人クアルコム間のドイツ訴訟において,2016年(平成28年)第4四 半期以降,CMとの間で,新たな特許や訴訟の対象特許を取り込むための 交渉を一切行っていないことを自認しており,CMライセンス契約の有効 性やその許諾対象特許の範囲について疑義があること,3)被控訴人クアル コムは,台湾の公平交易委員会(TFTC)が2017年(平成29年) 10月20日にCMを含む携帯通信端末の製造販売業者との間で締結し ているライセンス契約について,ライセンス条件の再交渉を行うことを命 じる旨の是正命令を受けて,被控訴人クアルコムとCMとの間でCMライ センス契約の再交渉が開始されており,CMライセンス契約の条件は今後 変更される可能性があること,4)被控訴人クアルコムは,控訴人アップル に対し,自社が保有する必須宣言特許をほぼ完全に網羅する約2000頁 に及ぶ特許リスト(本件特許を含む。)(甲7)及び自社の保有する必須 宣言特許(本件特許を含む)のクレームチャート(甲14)を提示するこ とにより,「直接ライセンスなしでは(absent a direct license)」被控訴人クアルコムの必須宣言特許(本件特許を含む。)が控訴人アップルに よって侵害されているとの認識を示したこと,5)被控訴人クアルコムが, 控訴人アップルの求めに応じて提供した一覧表やクレームチャートに本\n件特許の米国対応特許及び中国対応特許が含まれていたことなどに照ら せば,本件特許権はCMライセンス契約の対象特許となっているとはいえ ず,また,控訴人アップルと被控訴人クアルコム間のライセンス交渉の中 で,被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を 含む被控訴人クアルコムの保有する数多くの特許権を侵害していると主 張したことは明らかである旨主張する。
(ア) しかしながら,前記1(7)認定のとおり,被控訴人らは,本件弁論を 終結した当審の第1回口頭弁論期日において,被控訴人クアルコムは, CMに対し,本件特許権を含む特許について,原告製品の生産,譲渡等 に係るライセンスを付与しており,控訴人らは,CMから全ての原告製 品の供給を受けているから,被控訴人らは,控訴人らに対し,現在,本 件特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を行使する意思は ないし,日本法上行使できるものとも考えていない旨を表明しているこ\nとに照らすと,本件の口頭弁論終結時点において,本件特許権が被控訴 人クアルコムとCM間のCMライセンス契約におけるライセンス対象 とされていることが認められる。 控訴人らが述べるように2016年(平成28年)第4四半期以降, 被控訴人クアルコムとCMとの間で,新たな特許や訴訟の対象特許を取 り込むための交渉を行っていないとしても,そのことは,CMライセン ス契約の内容が変更されたり,又は契約自体の効力が喪失したことを直 ちに意味するものではない。また,被控訴人クアルコムがTFTCの是正命令(処分)を受けてCMとの間でCMライセンス契約の再交渉を開 始したことを認めるに足りる証拠はない。 他に上記認定を左右するに足りる証拠はない。
(イ) 前記1(2)認定のとおり,控訴人アップルと被控訴人クアルコムのラ イセンス交渉は,CMへの既存のライセンスに依拠することに代えて, 控訴人アップルに直接ライセンスを提供することを目的としていたこ とに照らすと,控訴人アップルが送付した甲9のレター記載の●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●との文中の「absent a license」の語は,「ラ イセンスがない場合に」を意味するものであり,CMに対するライセン スを含め,およそライセンスが存在しない場合を想定したものと認めら れる。 そして,前記1(2)の認定事実によれば,被控訴人クアルコムは,控 訴人アップルから被控訴人クアルコムに対してライセンスがない場合 に原告製品が侵害していると被控訴人クアルコムが考えている特許権 の特定を求められたことを受けて,控訴人アップルに対し,被控訴人ク アルコムがETSI(欧州電気通信標準化機構)に開示した特許の一覧\n表(甲7)及びサンプルクレームチャート(甲14)を提供したことが\n認められることに照らすと,上記一覧表及びクレームチャートに本件特\n許の米国対応特許及び中国対応特許が含まれているからといって,控訴 人アップルと被控訴人クアルコム間のライセンス交渉の中で,被控訴人 クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を侵害して いることを主張したものと認めることはできない。
(ウ) したがって,控訴人らの前記主張は理由がない。
」 (2) 原判決17頁4行目の「(3)」を「(3)ア」と改め,同頁19行目末尾に行 を改めて次のとおり加える。
「イ この点に関し,控訴人らは,被控訴人クアルコムは,本件訴訟では, CMライセンス契約の存在を理由として,本件特許権に基づく損害賠償 請求権及び実施料請求権を有しない又は行使できない旨主張している ものの,米国訴訟においては,CMライセンス契約の存在にかかわらず, 携帯通信SEPポートフォリオに含まれる特許につき,FRAND条件 の適合性やFRAND条件でのロイヤルティの確認を求める申立てを\nするなど,控訴人アップルによる被控訴人クアルコムの保有する特許権 の侵害を前提とする主張を行っており,被控訴人クアルコムの両主張が 矛盾することは明らかであり,このような被控訴人クアルコムの米国訴 訟における本件訴訟と矛盾した主張は本件訴えの確認の利益を基礎付 けるものといえる旨主張する。
しかしながら,前記1(6)認定のとおり,被控訴人クアルコムが,米国 訴訟において,反訴として,被控訴人クアルコムのライセンス提案がF RAND宣言に適合していること及び仮にFRAND宣言に適合しな い場合はFRAND条件によるロイヤルティの確認の申立てを行っていること,被控訴人クアルコムが,同訴訟において,2018年(平成\n30年)6月19日,控訴人アップルが本件特許の米国対応特許を侵害 している旨の専門家意見書を提出したことは,被控訴人クアルコムが, 本件訴訟において,被控訴人クアルコムからライセンスを受けたCMか ら原告製品の供給を受けている控訴人らに対し,本件特許権に基づく損 害賠償請求権及び実施料請求権を行使する意思はないし,日本法上行使 できるものとも考えていない旨主張していることと何ら矛盾するもの ではない。したがって,控訴人らの上記主張は理由がない。」
2019.02. 1
平成29(ワ)27374 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年12月11日 東京地方裁判所(47部)
1 本件楽曲は未公表の著作物であったか(争点(1)ア)について
(1)前記前提事実(3)エのとおり、本件楽曲は、被告Bが本件番組内で本件録音 データを再生した時点より前に,公衆に提供又は提示されていなかったから, 本件楽曲は法18条1項にいう「著作物でまだ公表されていないもの」に当\nたる。 この点,被告らは,原告が芸能リポーターである被告Bに対して本件録音\nデータを提供したことは公衆に提示したものと同視し得るから,本件楽曲は 本件番組内で放送された時点で「著作物でまだ公表されていないもの」には\n当たらない旨主張する。 しかしながら,法にいう「公衆」とは飽くまでも不特定多数の者又は特定 かつ多数の者をいう(法2条5項参照)のであって,被告B個人が公衆に当 たると解する余地はない。したがって,原告が被告Bに対して本件録音デー タを提供したことにより,本件楽曲が公表されたものとは認められない。\n2 公衆送信及び公表につき黙示の許諾があったか(争点(1)イ)について 証拠(甲7,乙A4)及び弁論の全趣旨によると,原告が被告Bに対して 本件録音データを提供した経緯について,次の事実が認められる。 ア 原告は,平成27年12月上旬頃,自らが執筆した自叙伝の原稿につい て芸能リポーターである被告Bの感想等を聞くため,知人を介して被告B\nの連絡先を入手した。そして,原告は,被告Bと電話で連絡を取り,その 感想等を求める趣旨であることを伝えた上,被告Bに対して上記原稿のデ ータをメールで送付した。
イ その後,原告は,被告Bと電話で連絡を取り,被告Bが上記原稿を読ん だ感想等を聞いた。その際,原告が被告Bに自らが音楽活動を行っている ことを伝え,自らが創作した曲を聴いた感想等を聞かせてほしいと頼んだ ところ,被告Bは,この依頼を承諾した。 (なお,原告は,被告Bに感想等を求めた際に,提供する楽曲を公表し\nないように求めた旨主張し,その陳述書(甲7)には,これに沿う部分が あるが,被告Bの陳述書(乙A4)にはこれに反する記載がある上,当該 主張は原告の平成30年3月6日付け準備書面で初めてされたものであっ て,それ以前はかかる明示的な求めはないことを前提とした主張がされて いたという経緯も考慮すると,原告の上記主張及び陳述部分は採用できな い。)
ウ そこで,原告は,平成27年12月22日,被告Bに対し,本件録音デ ターをメールで送信した。 被告らは,原告は音楽活動を再開したことが被告Bによってテレビ放送等 で告知されることを期待して本件録音データを提供したものであるから,本 件楽曲を公衆送信及び公表することを黙示に許諾したというべきであると主\n張する。 しかしながら, 上記(1)の認定事実によれば,原告は,本件楽曲を聴いた 被告Bの感想等を聞くために,被告Bに対して本件録音データを提供したに すぎないから,原告が本件録音データを提供したことをもって,本件楽曲を 公衆送信ないし公表することを黙示に許諾したとは認められない。被告Bが\n芸能リポーターであるからといって,それのみでは上記説示を左右しない。\n
3 被告らによる公衆送信行為は法41条所定の時事の事件の報道のための利用 に当たるか (争点(1)ウ)について 被告らは,本件楽曲は,1)視聴者に対して原告による覚せい剤使用の事実 の真偽を判断するための材料を提供するという点において「警視庁が原告を 覚せい剤使用の疑いで逮捕する方針であること」という時事の事件を構成す\nるものであるし,2)原告が執行猶予期間中に更生に向けて行っていた音楽活\n動の成果物であるという点において「原告が有罪判決後の執行猶予期間中に\n音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という時事の事件を構成\nするものである旨主張する。 上記1)の主張について検討するに,前記前提事実(3)イおよびウによれば,本 件楽曲は,警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予\n定であることやこれに関連する報道がされた際に放送されたものであると認 められるところ,警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求 する予定であることが時事の事件に当たることについては,当事者間に争い\nがない。しかしながら,本件楽曲は,警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで 逮捕状を請求する予定であるという時事の事件の主題となるものではないし,\nかかる時事の事件と直接の関連性を有するものでもないから,時事の事件を 構成する著作物に当たるとは認められない。これに反する被告らの主張は採\n用できない。
次に,上記2)の主張について検討する。
ア 前記前提事実(3)イおよび乙B第1号証によると,以下の事実が認められる。 警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定で\nあることやこれに関連する報道がされた放送時間は,コマーシャルや他 のニュースが放送された時間を除くと約62分間であった。 このうち,本件録音データの再生に伴って原告の音楽活動に言及があ った時間は,午後3時31分頃から同36分頃までの約5分間であるが, うち約3分間はコマーシャルが放送された時間であった。具体的内容は, 別紙本件楽曲放送部分に記載のとおりである。 すなわち,本件番組の司会者は,「うーん。で,ASKA さんが,来月 ですか,新曲を YouTube で・・・。」「まあ,発表されるってことで,B\nさんが・・・」と切り出し,被告Bは,この発言を受けて,「実は,昨 年送ってきた曲がありますんで,コマーシャルの後にちょっとお伝えし たいと思います。」と発言した。 コマーシャルの放送後,被告Bは,「これ,送られてきたんで。えー, 去年の 12 月 22 日で,まあ,タイトルとしては『20年東京オリンピ ック曲』っていうふうについてたんです。」と説明した上で本件録音データを再生した。本件司会者は,本件楽曲を聴いた感想として,「今ま での曲調とは全然違いますよね。」,「どっちかというと幻想的な。」 と発言し,被告Bも,この感想に同調し,「ちょっと違う感じしますよ ね。まあ,きれいなメロディではあると思いますけど。」と発言した。 また,本件司会者は,「こういうのを作って,来月 YouTube で発表し\nようと。音楽活動に向けて動こうと。」と発言し,被告Bも,「そうで すね,この時点では,ご本人もいろいろブログを自分で書いているん で。」などと発言して,本件録音データの再生を止めた。 そして,本件録音データの再生が終わるとすぐに,本件番組の司会者 その他の出演者は,再び,警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕す る方針であることを話題にし,それぞれ意見を述べるなどした。 また,上記 以外の部分でも,原告の音楽活動に関する部分がある (14:23頃,14:29頃,14:33頃,15:08頃)ものの, その内容は,上記 と同様に,原告が,2020年のオリンピックのテ ーマソングとして作曲した本件楽曲を被告Bに送付し,来月,YouTube でアルバムを発売したり,友人のライブに出たりといった音楽活動に向 けて動こうとしている,ということを断片的に紹介する程度にとどまっ ている。
イ 上記認定事実によれば,本件番組中における原告の音楽活動に関する 部分は,警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕する予定であること\nを報道する中で,ごく短時間に,原告が2020年のオリンピックのテ ーマソングとして作曲した本件楽曲を被告Bに送付し,来月,YouTube で 新曲を発表するなど音楽活動に向けて動こうとしている,ということを\n断片的に紹介する程度にとどまっており,本件楽曲の紹介自体も,原告 がそれまでに創作した楽曲とは異なる印象を受けることを指摘するにす ぎないもので,これ以上に原告の音楽活動に係る具体的な事実の紹介は ないものであるから,このような放送内容に照らせば,本件番組中にお ける原告の音楽活動に関する部分が「原告が有罪判決後の執行猶予期間\n中に音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という「時事の 事件の報道」に当たるとは,到底いうことができない。
4 被告らによる公衆送信行為は法32条1項所定の引用に当たるかエ)について
前記1で判示したとおり,原告が被告Bに対して本件録音データを提供した ことにより,本件楽曲が公表されたものとは認められず,本件番組の放送時に\nおいて本件楽曲は未公表の著作物であったと認められるから,被告らによる本\n件楽曲の公衆送信行為は法32条1項所定の引用には当たらない。
5 正当業務行為等により公表権侵害の違法性が阻却されるか(争点(1)オ)につ いて
被告らは,本件楽曲の公表は,原告が逮捕されそうであるという差し迫っ\nた状況において,有罪判決後の原告の音楽活動や更生に向けた活動等を具体 的に報道するとともに,視聴者に対して原告による覚せい剤使用の事実の真 偽を判断するための材料を提供するという目的で行われたものであり,その 具体的事情の下では,法41条の趣旨の準用,正当業務行為その他の事由に より違法性が阻却される旨主張する。 しかしながら,本件番組では原告の音楽活動にごく簡単に触れたに止まり, それに係る具体的な事実の紹介がないことは前記3で説示したとおりである し,本件楽曲が原告による覚せい剤使用の事実の真偽を判断するための的確 な材料であるとも認められないから,被告らの上記主張は,その前提を欠く ものであり採用できない。 また,被告Bは,原告が逮捕見込みであるとの報道に関連して,原告が更 生していることを示すために,本件録音データの一部のみを再生したもので あるから,芸能リポーターとしての正当な業務行為として違法性がない旨主\n張する。 しかしながら,原告の音楽活動に係る具体的な事実の紹介がないまま,本 件録音データの一部を再生したからといって,原告が更生していることを具 体的に示すことにはならないから,被告Bの上記主張も,その前提を欠くも のであり採用できない。
6 被告Bは公衆送信権及び公表権の侵害主体となるか カ)について
前記前提 Bは,本件番組の生放送中に出演者として本件楽曲の録音データ(本件録音データ)の一部を再生し,被告讀賣テレビは本件番組を放送したのであるところ,前記1ないし5の説示を踏まえれば,被告らは共同して原告が本件楽曲につき有する公衆送信権及び公表権を侵害したものと認められる。これに対し,被告Bは,被告讀賣テレビによる放送の履行補助者にすぎなかった旨主張するところ,その趣旨は判然としないものの,上記説示に照らして採用できない。
7 故意・過失の存否
被告Bはいわゆる芸能リポーターを業とし,被告讀賣テレビは基幹放送事\n業を業とするものであるから,被告らは,放送番組中において楽曲を再生し 放送する場合には著作権や著作者人格権の侵害がないように十分注意すべき\n高度の注意義務を負っているというべきところ,原告が本件楽曲を公衆送信 及び公表することを黙示に許諾したとは認められないにもかかわらず,その\n認識を欠いて本件楽曲を公衆送信及び公表することが許されると誤信した点\nなどにおいて,少なくとも過失があったと認められる。これに反する被告ら の主張は採用できない。 なお,原告は,本件楽曲を公表した際の本件番組の司会者と被告Bとのや\nり取りや本件番組の放送終了後の上記両名の言動を見れば,被告らが本件楽 曲を公衆送信及び公表することにつき原告の同意がないことを認識していた\nことは明らかであるから,被告らには故意がある旨主張する。 しかし,本件楽曲を公表した際の本件番組の司会者と被告Bとのやり取り\nは前記3(3)ア(イ) で認定したとおりであるところ,これらのやり取りを見ても, 上記両名が本件楽曲を公表することにつき原告による黙示の許諾がないこと\nを認識していたことはうかがわれない。また,証拠(乙A4)及び弁論の全 趣旨によれば,原告が本件番組の放送翌日に,被告Bに対して電話で本件楽 曲を放送したことを抗議した際,被告Bは,原告が本件楽曲を公表すること\nに同意していると認識していた旨の弁明をしていないものの,原告の抗議は 未発表であった本件楽曲を公表\したことを明示的に指摘したものではなかっ たことが認められるから,被告Bが上記のような弁明をしなかったからとい って,本件楽曲を公表することにつき原告の同意がないことを認識していた\nとは認められない。さらに,弁論の全趣旨によれば,本件番組の司会者と被 告Bは,平成28年12月23日に放送された番組内で,原告に対して謝罪 していることが認められるものの,その謝罪が未発表の本件楽曲を公表\した ことに対するものであったと認めるに足りる証拠はない。 その他,被告らが,本件楽曲を公表することにつき原告の同意がないと認\n識していたことや公衆送信権ないし公表権侵害の故意を有していたことを認\nめるに足りる証拠はないから,被告らの故意に係る原告の主張は採用できな い。
8 損害の有無およびその額(争点(3))について
(1)法114条3項による損害金
ア 証拠(甲3)によると,一般社団法人日本音楽著作権協会が,使用料規 程において,放送及び当該放送の録音に音楽著作物を利用する場合の使用 料について,年間の包括的利用許諾契約を締結する方法と1曲1回当たり の使用料を積算する方法とを定めているところ,著作権侵害による損害額 を算定するに当たっては,音楽著作物の継続的な利用を前提とする前者の 方法を基準とするではなく,1曲1回の利用ごとに使用料が発生すること を前提とする後者の方法を基準とするのが合理的であり,これに反する被 告らの主張は採用できない。 イ 上記使用料規程によれば,全国放送の場合,1曲1回当たりの使用料は, 利用時間が5分までは6万4000円,その後利用時間が5分を超えるご ろ,本件番組において本件楽曲が放送された時間は約1分間であった(前 記前提事実 )から,その相当対価額は6万4000円と認めるのが相 当である。
公表権侵害による慰謝料\n
前記2(1)及び3(3)で認定した各事実並びに証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば,本件楽曲は平成32年(2020年)に開催される東京オリンピ ックのテーマ曲として応募することを目的として創作されたものであり,原 告としては,本件楽曲を聴いた感想を聞くために,被告Bに対して本件録音 データを提供したにすぎなかったにもかかわらず,本件番組(日本テレビ系 列28社により放送されている。)において本件楽曲が放送されたことによ り,原告は本件楽曲を創作した目的に即した時期に本件楽曲を公表する機会\nを失ったこと,しかも,本件楽曲は,本件番組において,警視庁が原告に対 する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定であるという報道に関連す\nる一つの事情として紹介されたことにより,本件番組の司会者及び被告Bの 発言と相まって,本件番組の視聴者に対して原告が本件楽曲を創作した目的 とは相容れない印象を与えることとなったことが認められる。 なお,原告は,本件番組において,原告が覚せい剤の使用により精神的に 異常を来したかのような報道をされたことにより,原告の音楽家としてのイ メージを毀損され,精神的苦痛を受けた旨主張し,その陳述書(甲7)には これに沿う陳述部分があるが,本件における慰謝料請求は飽くまで本件楽曲 に係る公表権侵害を理由とするものであるから,上記認定のとおり,公表\権 侵害の方法・態様として評価し得る事情の限度で考慮するにとどめるのが相 当である。 これらの事情に加え,本件で顕れた一切の事情を併せ考慮すると,被告ら による公表権侵害に対する慰謝料の額は100万円と認めるのが相当である。\n
2019.02. 1
平成27(ワ)8974 特許権侵害差止等請求事件 特許権 平成30年12月13日 大阪地方裁判所
(4) 被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為についての直接侵害の成否
ア 被告表示器Aはプログラマブル表\示器であり,被告製品3はそれらにイ ンストールするソフトウェアであり,前提事実(前記第2の2(4)エ)のとおり,被 告表示器Aは被告製品3のソ\フトウェアがなければ作動せず,被告製品3のソフトウェアは被告表\示器においてのみ有効に機能する関係にあると認められるから,ユ\nーザがそれらの一方のみを使用することはないといえる。このため,原告は,1)被 告表示器Aと被告製品3は,その販売形態にかかわらず,実質的には常にセット販売されていると評価すべきものであり(セット販売理論),また,2)被告製品3のソフトウェアはユーザの下で必ず被告表\示器にインストールされるのであるから,ユーザは被告の道具としてインストールを行うにすぎない(道具理論)として,被告 表示器Aと被告製品3の各製造,販売等は,同一機会でされるものであるか否かを問わず,被告製品3のOSがインストールされた被告表\示器Aの製造,販売等と同視すべきであると主張する。
イ 被告表示器A,被告製品3は,それらが個別に販売される場合はもとより,同一の機会に販売される場合であっても,被告製品3の基本機能\OS及び拡張/オプション機能OSのうちの回路モニタ機能\等部分のインストールがいまだされ ない状態であるから,それらは直接侵害品(実施品)としての構成を備えるに至っておらず,それを備えるにはユーザによるインストール行為が必要である。\nこのような場合,確かに,ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害 品(すなわち実施品)が完成する場合であっても,そのための全ての構成部材を製造,販売する行為が,直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。\nしかし,構成部材を製造,販売する行為を直接侵害行為(すなわち実施品の製造,販売行為)と同視するということは,ユーザが構\成部材から実施品を完成させる行為をもって構成部材の製造,販売とは別個の生産行為と評価せず,構\成部材の製造, 販売による因果の流れとして,構成部材の製造,販売行為の中に実質的に包含されているものと評価するということであるから,そのように評価し得るためには,製\n造,販売された構成部材が,それだけでは特許権の直接侵害品(実施品)として完成してはいないものの,ユーザが当然に予\定された行為をしてそれを組み合わせる などすれば,必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要 があると解するのが相当である。換言すれば,ユーザの行為次第によって直接侵害 品が完成するかどうかが左右されるような場合には,構成部材の製造,販売に包含され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから,構\成部材を製造,販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても,直接侵害の責任を負うことは ないと解すべきである。
ウ このような観点から本件の事実関係について検討すると,前記(2)キ(イ) で認定した事実によれば,被告表示器Aにおいて回路モニタ機能\等を使用するため には,ユーザが,被告製品3をインストールしたパソコンで,動作設定を「回路モニタ」とする拡張機能\スイッチが配置されたプロジェクトデータを作成する必要があり,拡張/オプション機能OSのうちの回路モニタ等部分が転送対象として自動的に選択されるのも,ユーザが上記のようなプロジェクトデータを作成した場合の\nみであると認められる。これを換言すれば,そもそもユーザによって上記のような プロジェクトデータが作成されず,したがってこれが被告表示器Aにインストールされない場合には,ユーザが敢えて拡張/オプション機能\OSのうちの回路モニタ等部分を転送対象として選択しない限り,被告表示器Aに回路モニタ機能\等が備わることはないのである。 また,被告製品1−2については一部の機種では,そもそも回路モニタ機能等を使用できない。また,回路モニタ機能\等が使用可能な機種についても,これを使用\nするためにはオプション機能ボードを購入して設置する必要がある。そして,そもそもこれはオプションの部材であるから,ユーザがこれを購入して設置することが\n当然に予定されていると認めることはできないし,乙17及び18によれば,回路モニタ機能\等に対応している被告製品1−2を購入した者のうち,オプション機能\nボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められる(原告は,乙17及び1 8は裏付け証拠がないから信用性を欠く旨主張するが,記載内容は一定の具体性を持っており,その内容が不合理であることをうかがわせる事情も認められず,かえ って,オプション機能ボードがまさにオプション品であることからすると,相当程度の者が購入しないというのは合理的であるから,具体的な割合はともかく,少な\nくともオプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められるという限度ではその信用性を認めるのが相当である。)。\nなお,被告製品1−1では,回路モニタ機能等が標準装備されているが,前記(2) ア(オ)での認定のとおり,被告製品1−1は他の点でも被告製品1−2にない機能を有しており,特にラダー編集機能\は,甲5のカタログでも回路モニタ機能等と並ん\nで強調されているものであることからすると,被告製品1−1を購入する者が須く 回路モニタ機能等を使用することを当然の前提としてこれを購入するとまで認めることは困難である。そして,これらの事情は,被告表\示器2Aについても妥当すると考えられる。
以上のことを踏まえると,被告が販売した被告表示器Aや被告製品3だけでは,直ちに本件発明1の直接侵害品(実施品)が完成するわけではないし,ユーザが被\n告表示器Aを被告製のPLCに接続した上で,被告製品3の拡張/オプション機能\ OSのうちの回路モニタ機能等部分をインストールすることが必ず予\定された行為 であると認めることもできない。したがって,ユーザの行為によって直接侵害品が 完成するかどうかが左右されるような場合に該当するといわざるを得ない。
エ 以上に対し原告は,被告が被告製品1や2等のカタログにおいて,回路 モニタ機能等を強調していることや,被告表\示器Aが他の被告製品と比べて高額で あること等からすると,本件発明1を全く実施しないという使用態様が被告表示器Aと被告製品3のユーザの下で経済的,商業的又は実用的な使用形態としてあると\nは認められないと主張している。 しかし,前記ウで述べた事情からすると,カタログで強調されているからといっ て,ユーザが必ず回路モニタ機能等を使用するとまで認めることはできない。原告は,他の回路モニタ機能\等を使用できない被告製品(被告製品1−3等)との価格差も指摘するが,当該他の機種では回路モニタ機能等を使用することはできないものの,前記認定の被告表\示器Aと他の機種との画面サイズや機能の違いを踏まえる\nと,被告表示器Aを購入する者が回路モニタ機能\等を使用することを当然の前提としてこれを購入するものであるとまで認めることもできない。 なお,原告は,他社が回路モニタ機能等を使用できない廉価な製品を販売していること(甲23,24)を指摘しているが,それと被告表\示器Aや被告製品3とでは回路モニタ機能等以外の機能\が異なっており,またハード面での差異や購入後の サポートの内容も異なっていること(甲5,23,乙17)などを踏まえると,原 告のこの指摘によって上記事情が基礎付けられるともいえない。 以上より,本件発明1を全く実施しないという使用態様が,被告表示器Aと被告製品3の経済的,商業的又は実用的な使用形態でないと認めることはできないから,\n原告の上記主張は採用できない。なお,原告は東京地裁平成13年10月31日判 決を引用しているが,本件と事案を異にするから,本件には妥当しないというべき である。
オ 以上より,直接侵害の成立は認められない。したがって,仮に被告表示器Aと被告製品3の販売行為を実質的にセット販売と評価し得るとしても,その販\n売行為をもって本件特許権1の直接侵害行為と評価することはできない。
(5) 以上より,被告による被告表示器Aと被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権1の直接侵害行為に該当しない。\n
カ 主観的要件について
(ア) 特許法101条2号においては,「発明が特許発明であること」(主観 的要件1))及び発明に係る特許権の直接侵害品の生産に用いる「物がその発明の実 施に用いられること」(主観的要件2))を知りながら,その生産,譲渡等をすること が間接侵害の成立要件として規定されている。
(イ) 主観的要件1)について
a 被告は,本件発明1(本件特許1に係る発明)の存在を知った時期 は,本件第1特許の特許請求の範囲を本件発明1に係る構成要件のように訂正することを認めるとの審決(甲20)がされたことを知った平成28年11月16日で\nあると主張している。 そこで,まず,特許発明について特許請求の範囲の訂正があった場合には,訂正後の特許請求の範囲に係る発明を知った時に主観的要件1)を満たすことになるのか, それとも,訂正前の特許請求の範囲に係る発明を知っていれば,特許請求の範囲が 訂正された後の発明との関係でも,主観的要件1)を満たすことになるのかを検討す る。 特許法101条2号が主観的要件1)を間接侵害の要件とした趣旨は,同号の対象 品は適法な用途にも使用することができる物であることから,部品等の販売業者に 対して,部品等の供給先で行われる他人の実施内容についてまで,特許権が存在す るか否かの注意義務を負わせることは酷であり,取引の安全を害するとの点にある。 他方,特許請求の範囲等の訂正は,特許請求の範囲の減縮や誤記等の訂正等を目的 とするものに限られ(特許法126条1項),特許請求の範囲等の訂正は,願書に (最初に)添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にお いてしなければならず(同条5項),かつ,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変 更するものであってはならないとされている(同条6項)。そして,特許請求の範囲 等の訂正をすべき旨の審決が確定したときは,その訂正後における特許請求の範囲 により特許権の設定の登録がされたものとみなされる(同法128条)。 以上のように,特許請求の範囲の訂正が認められる場合が上記のように限定され ていることを踏まえると,訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば, 特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも,主観的要件1)を満たすこ とになると解するのが相当である。このように解しても,特許法101条2号が主 観的要件1)を求めた趣旨に反するわけではないし,第三者にとって不意打ちとなる こともないからである。 なお,本件第1特許の特許請求の範囲の訂正も誤記の訂正及び特許請求の範囲の 減縮を目的とするもので,その他の訂正の要件も満たしており(甲19の1ないし 20),被告製品3は本件発明1の技術的範囲に属する以上,上記訂正前の本件発明 1の技術的範囲にも属することは明らかである。
b 本件では,被告は訂正前の本件発明1の存在を知っていたことを自認しているものの,その時期は原告からの警告書を受領した平成25年4月2日で あると主張している。これに対し,原告は被告が訂正前の本件発明1の存在をその 登録時の平成17年7月22日から知っていたと主張していることから,以下,被 告が平成25年4月2日よりも前に訂正前の本件発明1の存在を知っていたかを検 討する。
(a) 証拠(甲1,5,34,乙1ないし3,19,20)及び弁論の 全趣旨によれば,次の事実が認められる。
・・・
確かに,上記(a)の4)と5)の事実だけを見れば,原告の主張は理解し得ないわけで はないが,表示されたラダー回路の接点・コイルの指定による検索機能\\\自体は,被 告自身が平成8年12月以降,販売している「MELSEC QnA」という汎用シーケンサにおいて採用されていたのであり,GOT900で初めて採用された機 能とは認められない。そして,GOT900では,「MELSEC QnA」とは異なり,タッチパネル によって接点・コイルを指定するものとされており,これは変更点であり,訂正前 の本件発明1との共通点ではあるが,このような変更がされたのは,そもそもの操 作方法が「MELSEC QnA」ではキーボードであったのに対し,GOT90 0ではタッチパネルが採用されていたためとみることも可能である。したがって,上記事実から,被告が本件第1特許の出願を知っていたことが推認されるとまでい\nうことはできない。 そして,GOT1000でワンタッチ回路ジャンプ機能が採用されたのは,GOT900においてタッチパネル上で接点・コイルを指定して検索する機能\能\\が採用さ\nれていたことの延長線上にあるものと見ることも決して不合理ではない。 以上のような事実関係に照らせば,被告が本件第1特許の登録時に訂正前の本件 発明1の存在を知っていたとまで推認することはできない。そして,平成25年4 月2日にされた原告から被告への警告書の送付以外に,被告が訂正前の本件発明1 の存在を認識し得たことをうかがわせる事情は認められない。
なお,原告は,被告と原告はトヨタからの受注を獲得すべくしのぎを削っていた こと(甲32)や,原告や被告が他社との契約において,納入品の製作・納入に当 たり,第三者の特許権等を侵害しないよう,万全の注意を払うべき旨が明記されて いること(甲41)を指摘しているが,これらは一般的な事項にすぎず,上記具体 的な事実関係に照らせば,被告が訂正前の本件発明1を知っていたことを推認させ る事実になるとはいえない。 したがって,被告が平成25年4月2日より前に訂正前の本件発明1の存在を知 っていたと認めることはできない。
c 以上より,被告が訂正前の本件発明1の存在を知ったのは平成25年4月2日であると認められる。
(ウ) 主観的要件2)について
a 被告は,被告製品3には本件発明1を実施しない実用的他用途が存 在しており,また基本的に販売代理店に対して被告製品3を販売しているにすぎな いから,被告製品3がユーザの下で本件発明1の実施に用いられることを知らない と主張している。
b まず,どのような場合に主観的要件2)を満たすものと考えるべきか, すなわち,適法な用途にも使用することができる物の生産,譲渡等が特許「発明の 実施に用いられることを知りながら」したといえるのはどのような場合かについて 検討する。 そもそも,特許法101条2号の間接侵害は,適法な用途にも使用することがで きる物(多用途品)の生産,譲渡等を間接侵害と位置付けたものであるが,その成 立要件として,主観的要件2)を必要としたのは,対象品(部品等)が適法な用途に使用されるか,特許権を侵害する用途ないし態様で使用されるかは,個々の使用者 (ユーザ)の判断に委ねられていることから,当該物の生産,譲渡等をしようとす る者にその点についてまで注意義務を負わせることは酷であり,取引の安全を著し く欠くおそれがあることから,いたずらに間接侵害が成立する範囲が拡大しないよ うに配慮する趣旨と解される。 このような趣旨に照らせば,単に当該部品等が特許権を侵害する用途ないし態様 で使用される一般的可能性があり,ある部品等の生産,譲渡等をした者において,そのような一般的可能\性があることを認識,認容していただけで,主観的要件2)を 満たすと解するのでは,主観的要件2)によって多用途品の取引の安全に配慮するこ ととした趣旨を軽視することになり相当でなく,これを満たすためには,一般的可 能性を超えて,当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあり,そのことを当該部品等の生産,譲渡等をした者において認識,認\n容していることを要すると解するべきである。 他方,主観的要件2)について,部品等の生産,譲渡等をする者において,当該部 品等の個々の生産,譲渡等の行為の際に,当該部品等が個々の譲渡先等で現実に特 許発明の実施に用いられることの認識を必要とすると解するのでは,当該部品等の 譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあることを認識, 認容している場合でも,個別の譲渡先等の用途を現実に認識していない限り特許権 の効力が及ばないこととなり,直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許権の効力を及ぼすとの特許法101条2号のそもそもの趣旨に沿わないと解される。\n以上を勘案すると,主観的要件2)が認められるためには,当該部品等の性質,その客観的利用状況,提供方法等に照らし,当該部品等を購入等する者のうち例外的 とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に 存在し,部品等の生産,譲渡等をする者において,そのことを認識,認容している ことを要し,またそれで足りると解するのが相当であり,このように解することは, 「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても 不合理な解釈ではない。
ア 本件の間接侵害への特許法102条1項の適用の可否
上記認定事実のとおり,本件では,被告製品3はプログラム(ソフトウェア)\nであるのに対し,原告の製品は表示器(ハードウェア)に予\めプログラム(ソフト\nウェア)がインストールされた完成品であるという相違がある。このことも踏まえ, 被告は,間接侵害には特許法102条1項は適用されないと主張している。 特許法102条1項本文は,侵害者が「侵害の行為を組成した物」を「譲渡した ・・数量」に,特許権者等が「その侵害行為がなければ販売することができた物」の 「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額を,特許権者等が受けた損害の額と することができる旨を定める。この規定は,侵害行為がなければ特許権者等が利益 を得たであろうという関係があり,そのために特許権者等に損害が発生したと認め られることを前提に,特許権者等の損害額の立証負担を軽減する趣旨に基づくもの であるが,そこに定める損害額の算定方法からすると,これにより算定される損害 の額は,特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の逸失 販売利益に係る損害の額であることを前提にしており,さらに,侵害者の「侵害の 行為を組成した物」の譲渡行為と特許権者等の「その侵害行為がなければ販売する ことができた物」の販売行為とが同一の市場において競合する関係にあることも前 提としているものと解される。 他方,物の発明に係る間接侵害が対象とするのは,実施品の「生産に用いる物」 の譲渡等であり,実施品を構成する部品だけでなく,実施品を生産するための道具\nや原料等の譲渡等もこれに含まれるから,必ずしも侵害者の間接侵害品の譲渡行為と特許権者等の製品(部品等のこともあれば完成品のこともある)の販売行為とが 同一の市場において競合するとは限らない。そして,本件のように間接侵害品が部 品であり,特許権者等が販売する物が完成品である場合には,前者は部品市場,後 者は完成品市場を対象とするものであるから,両者の譲渡・販売行為が同一の市場 において競合するわけではない。しかし,この場合も,間接侵害品たる部品を用い て生産された直接侵害品たる実施品と,特許権者等が販売する完成品とは同一の完 成品市場の利益をめぐって競合しており,いずれにも同じ機能を担う部品が包含さ\nれている。そうすると,完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限り では,間接侵害品たる部品の譲渡行為は,それを用いた完成品の生産行為又は譲渡 行為を介して,特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合す る関係にあるといえるから,その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許 法102条1項を適用する素地がある。 したがって,本件では,以上の考え方に基づき各要件の解釈をすることを前提に,特許法102条1項の適用を肯定するのが相当である。
イ 「侵害の行為がなければ販売することができた物」について
(ア) この要件に該当する「物」について,原告は,プログラム(ソフトウ\nェア)を表示器(ハードウェア)にインストールした原告の製品全体であると主張\nするのに対し,被告は,原告がハードウェアとソフトウェアを別個に販売していな\nいことから,原告の製品はソフトウェアである被告製品3と競合関係にないとして,\n原告の製品が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たらないと主 張している。 しかし,前記アで述べたところからすると,本件のような間接侵害の場合の「侵 害の行為がなければ販売することができた物」とは,特許権者等が販売する完成品 のうちの,侵害者の間接侵害品相当部分をいうものと解するのが相当である。
(イ) これを本件についてみると,原告の製品では回路モニタ機能や「追い\nかけモニタ機能」及び「ズームアップ検索機能\」が使用可能で,これは被告製品3\nで使用可能な回路モニタ機能\やワンタッチ回路ジャンプ機能(本件発明1の構\成要 件1E及び1Fの構成を充足する機能\)と同様の機能であって,これが原告の製品\nに予めインストールされているプログラム(ソ\フトウェア)による機能であること\nは明らかである。したがって,原告の製品と被告製品3を用いた完成品とは,その ようなソフトウェアが格納又はインストールされているという点で共通していると\nいうことができるから,原告の製品は,被告製品3を用いた完成品と市場で競合する物であるということができる。 そうすると,本件での「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは, 原告の製品全体のうちの,被告製品3に対応するプログラム(ソフトウェア)部分\nである。
ウ 「譲渡数量」(侵害者が譲渡したその侵害の行為を組成した物の数量)に ついて
本件では被告による被告製品3の生産,譲渡等の行為について間接侵害の成 立が認められるから,被告製品3が「その侵害の行為を組成した物」に該当する。 なお,原告は被告表示器Aもこれに含まれると主張して,原告の製品(完成品)\nの単位利益に乗じるものとして被告表示器Aの販売数を問題としているが,被告表\ 示器Aの製造,販売について間接侵害が成立しないことは,前記3(1)及び(2)エ(ア) で判示したとおりであり,そうである以上,特許法102条1項の適用に当たって, 被告表示器Aが「その侵害の行為を組成した物」に該当することはないというべき\nである。 そして,原告は,被告製品3を「その侵害の行為を組成した物」とする場合の予\n備的な主張として,被告製品3の販売数を譲渡数量としているところ,平成25年 4月1日から平成29年12月末までの被告製品3の販売数は,合計●(省略)● 台である(前記(2)ウ)。 被告が本件発明1(本件特許1)の存在を知ったのは平成25年4月2日であり, 同日以降の被告製品3の譲渡等について間接侵害が成立することから,上記認定の販売数から同月1日の販売数を控除する必要がある。本件の主張立証から同日の販 売数は明らかでないから,同月の販売数(●(省略)●台)を4月の日数である3 0で除した●(省略)●台(1台未満は四捨五入)を同月1日の販売数と認めるほ かない。したがって,同月2日から平成29年12月末までの被告製品3の販売数 は,合計●(省略)●台と認められる。 なお,被告は,間接侵害が成立するのは主観的要件を具備して行った被告製品3 の生産,譲渡等のみであり,その立証がされていないと主張しているが,被告の行 為が間接侵害の主観的要件を具備していることは,前記3(2)カで判示したとおりで ある。
エ 侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益 額について
(ア) 原告の製品全体の平成25年度の1台当たりの限界利益額が●(省略) ●円であることは,当事者間に争いがなく(前記(2)イ),その他の年度についても同様と推認されるところ,上記イで認定したとおり,「侵害の行為がなければ販売す ることができた物」に当たるのは原告の製品のうちのプログラム(ソフトウェア)\n部分であるから,原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額をもって「単位\n数量当たりの利益額」に当たるとみるべきことになる。
(イ) この点に関し,被告は,自らの製品のカタログ(甲5)記載の表示器\n(被告製品1−1)とソフトウェア(被告製品3−1)の参考標準価格を参考にし\nて,原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額を算出すべき旨主張している。\nこれに対し,原告は被告が被告表示器の価格を高く設定し,ソ\フトウェアである被 告製品3の価格を低く設定するビジネスモデルをとっているから,被告の価格設定 を参考とすべきではなく,本件発明1の価値の高さに鑑み,ソフトウェア部分の寄\n与度は9割を下らないと主張する趣旨と解される。 被告製品1−1の参考標準価格は22万円から53万円,被告製品1−2の参考 標準価格は22万円から43万円であるのに対し,被告製品3−1の参考標準価格 は,単体ライセンス品で●(省略)●万円,200ライセンスまで登録可能なサイ\nトライセンス品で4万円である(前記2(2)ア(カ),(キ)参照)。このように,サイト ライセンス品と単体ライセンス品との価格差がわずかであり,被告表示器のような\n生産設備に用いる装置の場合,通常は複数台が購入され,その場合にはサイトライ センス品が購入されると考えられることからすると,通常の場合には,被告表示器\n1台当たりに必要なソフトウェア費用が極めて安価になり,原告が指摘するようなソ\フトウェアで利益を上げないビジネスモデルが存在している可能性もある。その\nため,サイトライセンス価格や実際の被告表示器1台当たりのソ\フトウェア費用 (被告の主張によっても平成26年における被告表示器Aの販売台数は被告製品3\nの販売枚数の約60倍であるから被告主張のとおり単価は500円となる。)を参考 として,被告表示器の参考標準価格と比較する場合には,ソ\フトウェアの価値が不 当に低く算定されることになり,相当でないと考えられる。しかし,単体ライセン ス品の参考標準価格を用いる場合には,被告表示器1台のみを購入する場合が想定\nされるから,この場合にはソフトウェアによる採算も軽視されないはずであるし,\n単体ライセンス品の参考標準価格は●(省略)●万円であるから,被告表示器のよ\nうなハードウェアと被告製品3のようなソフトウェアに要する一般的な原価の差も\n考えると,ハードウェアとソフトウェアの価値が相応に反映されていると考えられ\nる。
他方,原告は,原告の製品における本件発明1の寄与度が9割を下らないと主張 するが,前記1の認定・判示によれば,従来技術を参酌して導かれる本件発明1の 特徴的技術手段は,表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力要素を検索す\nるに当たり,出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎないから,製品全 体に対するその寄与度は9割を大きく下回ると考えられる。 以上からすると,本件で原告の製品の利益におけるソフトウェア部分の利益を算\n定するには,被告表示器1Aと被告製品3−1の参考標準価格を参考にして原告の\n製品におけるソフトウェア部分の限界利益額を算定するほかないというべきである。\nこれを参考にして被告表示器1Aと被告製品3−1の合計額に占める被告製品3\n−1の価格割合を算定すると,被告表示器1A(ただし,被告製品1−2のうちそ\nもそも回路モニタ機能等を使用できない機種及び生産を終了した機種は除く。)のカ\nタログ記載の参考標準価格は,平均すると●(省略)●円(税抜)であり(甲5), 被告製品3−1の通常の単体ライセンス品の参考標準価格は●(省略)●万円であ る(税抜)から,被告製品3−1の価格の全体に占める割合は,●(省略)●%(0.1%未満四捨五入)と認められる。 なお,被告は被告製品1−1の参考標準価格の平均値をもとに算定しているが, 被告製品3−1がインストールされて回路モニタ機能等が使用され得る被告製品に\nは被告製品1−2も含まれるから,被告製品1−2の参考標準価格も参考にすべき である。また,被告は1枚の被告製品3が約60台の被告表示器Aにインストール\nされていることを前提に,被告製品3の価格を500円として算定しているが,そ のような場合の価格が被告製品3の価値を反映したものであるのかについては前記 のとおり問題があるから,被告製品3−1の通常の単体ライセンス品の参考標準価 格である●(省略)●万円をもって同製品の価格であると認めるのが相当である。
(ウ) 以上より,原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額(1台当\nたりの金額)は,上記(ア)記載の金額に●(省略)●%を乗じた4118円と認めら れる。
オ 「販売することができないとする事情」の有無
(ア) まず,被告は被告製品3と原告の製品とが競合することはないから, 原告の譲渡数量の全部について,原告が販売することができない事情が存在すると 主張しているが,この主張に理由がないことは,前記アで認定・判示したとおりで ある。
(イ) 次に,被告は,被告製品3を購入した者の全てが回路モニタ機能を使\n用しているわけではないとか,回路モニタ機能を使用するのにオプション機能\ボー ドの設置が必要な被告製品1−2を購入した者のうちオプション機能ボードを購入\nしたのは約4分の1にとどまり,実際に回路モニタ機能等を使用していないユーザ\nはさらに多く存在すると主張する。 特許法101条2号に係る間接侵害品たる部品等は,特許権を侵害しない用途な いし態様で使用することができるものである。そして,そのような部品等の譲渡は,譲渡先での使用用途ないし態様のいかんを問わず間接侵害行為を構成するが,実際\nに譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には,譲渡先 の顧客は当該特許発明の価値に吸引されて当該部品等を購入したわけではないから, 間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与しておらず,そのような譲渡先については, 間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになる。し たがって,特許権者等の損害額の算定に当たっては,そのような事情は,特許法1 02条1項ただし書の事由を構成すると解するのが相当である。\nこれを本件についてみると,先に2(4)イ(イ)で述べたとおり,乙17及び18に よれば,回路モニタ機能等に対応している被告製品1−2を購入した者のうち,オ\nプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められ,被告製品1\n−1や被告表示器2Aのユーザが須く回路モニタ機能\等を目的にこれらを選ぶとま で認めることは困難である。このように譲渡先が回路モニタ機能等を利用しない場\n合があることは,特許法102条1項ただし書の事由として考慮すべきであるが, その程度が明らかでないから,その考慮は極めて限定的になし得るにとどまるとい うべきである。
(ウ) 次に,被告は,1)原告がPLC用表示器の市場において意味のあるシ\nェアを有していないこと,2)原告の製品のソフトウェアに占める本件発明1の貢献\n度(寄与度)は高くても0.1%を上回ることはないこと,3)原告が宣伝広告活動において「追いかけモニタ機能」や「ズームアップ検索機能\」を重視していなかっ たことを指摘している。
a 特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事 情」は,侵害行為がなければ特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できた との相当因果関係を阻害する事情を対象とするものである。
b そして,被告の主張1)について,前記(2)エ認定の事実によれば,プ ログラマブル表示器について,原告のシェア(販売数量)と被告のシェア(販売数\n量)との間には,非常に大きな差異があったと認められるところ,シェアの格差に は,製品の魅力以外にも,営業力やブランド力等の差異も多分に影響するものであ るから,原告と被告のシェアに大きな格差があるという事情は,このような営業力 やブランド力等の差異という観点から,「販売することができないとする事情」を基 礎付ける1つの事情にはなるといえる。
c また,原告のシェアが小さいという上記の被告の主張1)は,被告以 外の他社の同種製品(競合品)が市場に多数存在しているから,被告製品3が販売 されなかったとしても,被告の製品が吸収した需要は他社の競合品が吸収し,原告 の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨を含み,また,同様に上記の被告の主 張2)は,本件発明1の価値が低いから,被告製品3が販売されなかったとしても原 告の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨と解される。 この点については,一般に侵害者の侵害品は特許発明の作用効果を奏するものと して顧客吸引力を有する製品であるから,それと同等の機能ないし効果を奏するも\nのでなければ,特許発明の実施品に対抗して需要を吸収し得る競合品として重視す ることができない。しかし,前記1の認定・判示によれば,従来技術を参酌して導 かれる本件発明1の特徴的技術手段は,表示されたラダー回路の出力要素を指定し\nて入力要素を検索するに当たり,出力要素の指定をタッチにより行うという点にす ぎない。また,前記1で認定したとおり,従来製品として,モニタ上に表示される\n異常種類のうち特定のものをタッチして指定すると,その指定された異常種類に対 応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示され,さらにそのラダー回路\nの接点をタッチしてコイルを検索することができ,1回前に検索されたラダー図と 前回路の検索もできる構成を備える製品(乙11のもの)や,同様の製品において\n異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデ バイス名又はデバイス番号を入力して行う製品(被告のGOT900)も存在して いた。そうすると,本件発明1に係る機能をすべて使用することができる製品が被\n告の製品以外に存在していなかったとしても,上記のような製品は存在しており, そのような製品でも,異常現象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の 異常原因を特定したり,原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していった りすること自体は可能であり,それほど複雑な操作を要するものではないと認められるから,原告の製品とほぼ同様の機能\を備えたものであるといえる。 また,原告の製品が,上記の本件発明1の特徴的技術手段を備えるか否かも必ず しも明らかでない。 したがって,本件では,競合品の存在により,被告製品3が販売されなかったと きに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は,かなり大きな程度で阻 害されると認めるのが相当である。
d また,上記被告の主張3)は,原告の製品において本件発明1の機能\nは重要なものではないから,被告製品3が販売されなくとも,需要者が原告の本件 発明1の機能に惹かれて原告の製品を購入することがないとの趣旨と解される。\nしかし,原告は,カタログに甲26の図を掲載することに加え,各製品の主な特 徴の1つとして,「異常発生時,画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ る」ということを記載していたのであるから,実際に重要な機能として位置付けら\nれており,そして,これらの機能を顧客に対してアピールしていたと認められ,こ\nの点については被告の上記主張は採用できない。
(エ) 以上のことを踏まえると,本件では,被告製品3が販売されなかった ときに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は,かなり大きな程度で 阻害されると認められる。 しかし,本件における被告製品3の譲渡数量は,前記のとおり●(省略)●枚で あるが,被告によれば,平成26年の被告表示器Aの販売台数は被告製品3の約6\n0倍であるというのであるから,少なくとも被告製品3は1枚当たり約60台の被 告表示器Aにインストールされたといえる。これに対し,原告の製品は,表\示器に ソフトウェアがインストールされた完成品であり,前記エで認定したそのソ\フトウ ェア相当部分の単位利益の額は,表示器1台のソ\フトウェア相当部分の利益額であ り,その販売数量も表示器の販売数量と同じになるべきものである。そうすると,\n本件において,「販売することができないとする事情」として,侵害行為がなければ 特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係を阻害する 事情の程度を判断するに当たっては,このような数量ベースの差を考慮すべきであ り,原告の製品のソフトウェア部分の数量ベースから見ると,いわば被告製品3の\n販売数量が実質的には約60倍ある関係にあることになるから,そのことを踏まえ て,被告製品3の販売行為がなければ原告の製品のソフトウェア部分を被告製品3\nの販売数量と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係がどの程度阻害されるかを 検討すべきである。 そして,このような考慮に基づく場合には,前記(イ)及び(ウ)で述べた諸事情を考 慮するとしても,本件において,被告製品3の譲渡数量●(省略)●枚の全部又は 一部を「販売することができないとする事情」があるとは認められない。
カ 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
上記ウないしオの判断を踏まえると,特許法102条1項に基づく原告の損 害額は,次のとおり,●(省略)●円と認められる。
(計算式) ●(省略)●台×4118円=●(省略)●円
(4) 原告の特許法102条2項に基づく主張について
ア 特許法102条2項は,侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ,この規定の趣旨は先に同条1 項について述べたのと同様であると解される。したがって,先に同条1項について 述べたのと同様の考え方の下に,本件において同条2項の適用を肯定するのが相当 である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
(ア) これについて,原告は,被告による被告表示器Aの販売利益も含めて\n特許法102条2項の損害推定が働くと解すべきと主張している。 しかし,特許法102条2項は「その者(注:侵害者)がその侵害の行為により 利益を受けているときは,その利益の額」を特許権者等が受けた損害の額と推定す ると規定しているところ,本件で原告の本件特許権1の侵害が認められたのは,被 告による被告製品3の生産,譲渡等であり,被告表示器Aの製造,販売については\n間接侵害の成立は否定されたから,被告による被告表示器Aの販売利益が上記「利\n益の額」に含まれないことは明らかである。これに反する原告の主張は条文の文言 に照らして採用できない。
(イ) 原告は被告製品3について,販売数や平均売価,限界利益率を推計し て主張しているが,これらを認めるに足りる証拠がないことは,前記(2)ウで判示し たとおりである。そこで,被告の利益額は,被告が開示した販売額(売上額)及び 限界利益率をもとに算定するほかない。
a 被告製品3の売上額
前記(2)ウで認定した別紙「被告製品3の販売数量・販売額」記載の販売 額等をもとに,被告が本件発明1(本件特許1)の存在を知った平成25年4月2 日から平成29年12月末までの売上額(販売額)を認定すると,次のとおり,● (省略)●円と認められる(平成25年4月1日の販売数を●(省略)●枚とみる ことにつき,前記(3)ウ参照)。 (計算式) ●(省略)●円−●(省略)●円(平成25年4月1日から同年9 月末までの販売数)×●(省略)●(同年4月2日から同年9月末までの販売数) ÷●(省略)●(同年4月1日の販売数を含んだもの)=●(省略)●円(計算過 程で生ずる1円未満の端数は四捨五入)
b 被告の限界利益率
前記(2)ウで認定した被告の限界利益率は,●(省略)●%である(別紙 「被告の変動費の内訳,加重平均値及び限界利益率」の(3)参照)。
c 被告の利益額
上記a及びbによれば,●(省略)●円と認められる。なお,これによ れば,被告製品3の1枚当たりの利益額は,●(省略)●円である(計算式:● (省略)●円÷●(省略)●台=●(省略)●円)。これは,前記原告の製品のソフ\nトウェア部分の単位利益額の約●(省略)●倍である。
ウ 推定覆滅事由について
(ア) 原告は被告製品3につき本件発明1の寄与度を50%と主張している のに対し,被告はこれを1万分の1と主張するとともに,被告製品3の特徴的技術 手段の顧客への訴求力が極めて低いとか,本件発明1の技術的・商業的な価値は高 くないなどと主張している。 ここで考えるべき寄与度は,製品の顧客吸引力上の寄与度であるから,被告が主 張するようなデータ量などという物理的な側面に着目することは相当でないが,先 に特許法102条1項ただし書について述べたところ((3)オ(ウ)b,c)と同様, 本件発明1の特徴的技術手段は,表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力\n要素を検索するに当たり,出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎず, 異常発生時のラダー回路の検索機能を備えた競合品も存在していたことに加え,被\n告製品3は回路モニタ機能等以外の様々な機能\を使用可能とするプログラム(描画\nソフトを含む。)が格納されていることからすると,被告製品3における本件発明1の寄与度は相当程度に低いということはできる。\nしかし,そうであるとしても,原告が原告の製品のソフトウェア部分をどの程度\n販売することができたかについては,先に特許法102条1項について述べたとこ ろ(前記(3)オ(エ))と同様,被告製品3と原告の製品のソフトウェア部分とでは,\n数量ベースが異なり,被告製品3の販売数量が,原告の製品のソフトウェア部分の\n数量ベースから見ると実質的には約60倍ある関係にあることを踏まえる必要があ る。
(イ) 他方,単位数量当たりの限界利益の額の差も推定覆滅に影響するとこ ろ,その点については,被告製品3が原告の製品のソフトウェア部分の約●(省略)\n●倍大きいこと(逆にいえば,原告の製品のソフトウェア相当部分が被告製品3の\n約●(省略)●%にとどまること)も考慮する必要がある。
(ウ) 以上の事情を踏まえると,推定覆滅率は●(省略)●%と認めるのが 相当である。
(エ) 以上より,特許法102条2項に基づく原告の損害額は,次のとおり,●(省略)●円と認められる。ただし,前記(3)で認定した同条1項に基づく原告の 損害額(●(省略)●円)の方が高いことから,その額を認容することとする。 (計算式) ●(省略)●円×●(省略)●=●(省略)●円
(5) 弁護士費用
原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ(当裁判所に顕著 な事実),被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,430万円と 認めるのが相当である。
(6) 以上より,原告の損害額は合計4702万8368円と認められる。
9 争点7(本件特許権1又は3の間接侵害を理由とする被告製品3及び4の生 産,譲渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否)
(1) 被告による被告製品3の製造,販売及び同製品に係るコンピュータ・プロ グラムの使用許諾について,本件特許権1の間接侵害(特許法101条2号)が成 立するから,被告製品3(被告製品3に係るソフトウェアを記録した媒体と解され\nる。)の生産,譲渡及び同製品に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾について の差止めを認容すべきである。 また,被告製品3の製品は本件特許権1の侵害の行為を組成した物に当たり,ま た被告は現在に至るまで被告製品3を生産,譲渡等していることに照らせば,同製 品が同特許権を侵害する用途として使用されるおそれがあるから,その侵害の予防\nのために同製品の廃棄を命じる必要性・相当性が認められる。
(2) なお,被告は,被告製品3には適法な用途があるから,その生産,譲渡等 を全面的に差し止め,廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。 しかし,被告製品3に適用な用途があるとしても,被告製品3が本件発明1の特 徴的技術手段を担う不可欠品であり,その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋 然性が高い状況が現実にあり,そのことを被告において認識,認容していると認め られる以上,その生産,譲渡等を全面的に差し止め,その廃棄を命じるのが,多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととし た特許法101条2号の趣旨に沿うものというべきであるし,そのように解しても, 被告は,被告製品3から本件発明1の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば 間接侵害を免れるのであるから,被告製品3の生産,譲渡等の差止め命令及び廃棄 命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない(なお,被告製品3にこのよ うな設計変更をした場合でも,製品名が変わらない場合には,差止判決の対象外と するために請求異議訴訟を経ることが必要になるが,そのような起訴責任を転換す る負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。)。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成28(ワ)6494 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月18日 大阪地方裁判所
イ 構成要件Aの「用いられ」の意味
前記アを前提に検討すると,構成要件Aのうち「ロールペーパの回転速度を\n検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は,本件ロールペーパ等の「複 数の磁石」につき,そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき, また,構成要件Aのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固\n定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は,本件ロールペーパ等について,そのような態様で回転させられることを 特定するものと理解できるし,構成要件Cの「測長センサ」も,構\成要件Aの記載 によって特定されると理解できる。 そうすると,本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は,構成要件\nBないしDと,構成要件Aによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから\n画されるものと解されるから,一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって,一体化製品が構\成要件Aを充足する薬剤分包装 置に実際に使用されるか否かは,上記構成要件充足の判断に影響するものではない\nと解される。 被告らは,原告製使用済み芯管に,輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプ ラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Aの「用いられ」を充足するた\nめには,一体化製品に,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用\n途が存在しないことが必要であると主張し,予備的に,仮にこれが認められないと\nしても,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用\n効果を奏するものであるから,現実に構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いら\nれることが必要であると主張する。 しかしながら,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用可能\な構成を有し,そ\nの他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産,譲渡され\nれば,その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって,その後に構成要件Aを\n充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは,特許権侵害の成 否を左右するものではない。 被告らは,本件発明の出願経過に照らし,構成要件Aを充足する薬剤分包装置に\n一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張 するが,原告が,手続補正の際に提出した意見書(乙25)において,本件発明は 構成要件Aを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。\nさらに,被告らは,本件無効審判において,本件訂正後の発明に新規性が認めら れるための構成が特定されたところ,その中には薬剤分包装置に関するものがある\nので,一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために,どのような 薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが,前記検討し た構成要件Aと,構\成要件BないしDとの関係に照らし,採用できないといわざる を得ない。
ウ まとめ
以上検討したところによれば,本件発明においては,構成要件Aの「用いられ」\nは,構成要件Aの記載によって構\成要件B以下の内容が特定されることを意味する ものとして使われているというべきであるから,そのように特定された構成要件を\n一体化製品が充足する場合には,構成要件Aの「用いられ」を充足すると解され,\nこれ以上に,構成要件Aの「用いられ」が,一体化製品が構\成要件Aを充足する薬 剤分包装置以外には使用されないこと,あるいは現実に構成要件Aを充足する薬剤\n分包装置が存在することを,要件として定める趣旨と解することはできない。
(2)争点(1)イ(一体化製品は「2つ折りされたシート」(構成要件A)を充足す\nるか。)について
ア 被告らは,構成要件Aの「2つ折りされたシート」とは,ロールペーパを薬\n剤分包装置内で2つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提として おり,あらかじめ2つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を 主張する。
イ そこで,検討するに,本件明細書【0018】には,「分包部は,三角板4 で2つ折りにされた際にホッパ5から所定量の薬剤が投入された後,ミシン目カッ タを有する加熱ローラ6により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシー ルするように設けられている。」との記載があるが,本件明細書【0011】の記 載によれば,本件発明は,一定の張力を保ったままシートを分包部に供給すること により,シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする\nものであり,この技術的思想に関しては,給紙部から分包部に送られてくるシート があらかじめ2つに折り畳まれたダブルタイプであっても,折り畳まれてい ション現象が生じるため,)張力変動により分包部でシートを2つ折りした際にシ ートの縁部が正確に重ならない,いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は,シング ルタイプのロールペーパを分包部において2つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入 した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても,ダブルタイプの ロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても,同様に生じ得る。 さらに,原告は,本件特許につき拒絶理由通知(乙24)を受けて本件補正を行 っているが,本件明細書【0018】の記載に基づくものであり,元の記載がシン グルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは 相当ではない(乙25)。
ウ 以上によれば,ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も,「2 つ折りされたシート」(構成要件A)を充足するというべきである。
(3) 争点(1)全体についての判断
ア 被告らは,一体化製品につき,構成要件Aのうち,「測長センサ」,「シー\nトを送りローラで送り出す給紙部」,「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」, 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが,原告製造 の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり,構\成要件Aと構成要件B以下\nとの関係を前述のとおり解する以上,意味のない主張といわざるを得ない。
イ 一体化製品は,前記第2の1(5)のとおりの構成を有するところ,被告らは,\n構成要件Aに関し,争点(1)ア及びイについて争うものの,構成要件B以下の充足性\nについては争うことを明らかにしておらず(当初,構成要件B及びDの充足を争っ\nたが,後に撤回した。),弁論の全趣旨によれば,一体化製品の構成aは本件発明\nの構成要件Bを,構\成bは構成要件Cを,構\成cは構成要件Dを充足すると認めら\nれ,一体化製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置において使用されることが可\n能な構\成を有すると認められる。
ウ 以上によれば,一体化製品は,構成要件AないしEをすべて充足するから,\n本件発明の技術的範囲に属すると認められる。
エ なお,原告は,被告日進が前訴において構成要件Aの充足性を争わなかった\nことから,本訴訟において構成要件Aの充足性を争うことは信義則に反する旨を主\n張するが(争点(1)ウ),被告日進は,前訴とは異なる製品の関係で,構成要件Aの\n充足性を本訴訟で主張したと認められるから,この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。
3 争点(2)(特許権侵害が成立するか。)について
(1) 問題の所在
ア 前記2によれば,一体化製品を完成して譲渡すれば,その時点において特許 権侵害が成立することになるが,前記第2の1(4)及び(5)のとおり,被告らは,一体 化製品それ自体を生産,譲渡しておらず,プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シ ートを巻き回したロールペーパ,すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のな い物を被告製品として生産,譲渡し,これを入手した利用者が,輪ゴムを介してロ ールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し,これを一体化製品とした上で,薬剤分 包装置に使用している。
イ この点について,原告は,1)被告製品は,一体化製品の生産にのみ用いる物 であるとして,特許法101条1号の間接侵害を主張するほか,2)被告らの行為は, 顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること,3)被告らの行為は,顧客の特 許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので,まず間接侵害の成否に ついて検討する。
(2) 争点(2)ア(被告製品は,一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められる か。)について
ア 被告製品の販売方法
証拠(甲4,5,21,36,文中掲記のもの)によれば,以下の事実が認めら れる。
被告日進の販売するロールペーパの製品には,商品名の冒頭に「A」の付く 製品(被告製品。以下「Aタイプ」という。)と「B」の付く製品(以下「Bタイ プ」という。)があり,両タイプは,それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙 又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成28年11月に公開していたウェブサイト(甲20)によれ ば,Aタイプの分包紙の芯管内径は67mmであって,「外径65mm前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ,Bタイプの分包紙の芯管内径は52mmであって,「外径 50mm前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。\n薬剤分包用ロールペーパとして,外径65mm前後の芯管を製造しているのは 原告のみであり,外径50mm前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみ である(弁論の全趣旨)。
前記ウェブサイトの「よくある質問Q&A」の欄には,「Q.他社分包機に 装着するには特別な道具が必要ですか?」という質問に対し,「A.弊社分包紙は, 『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって,お客様ご使用の分包 機に装着することができます。つまり,『使用済み分包機メーカー製芯管』が1個 お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成28年1月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明 資料(甲9)には,「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告 日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより,芯管の空回りを防止しながら被 告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に 説明されている。
まとめ
以上によれば,被告日進が販売する分包紙のうちAタイプ(被告製品)は,原告 製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として 生産され,原告製の薬剤分包装置を使用し,既に原告製使用済み芯管を保有してい る者に対し,購入の案内がされたものと認められる。
イ 他の用途について
被告日進製の薬剤分包装置
前記被告日進のウェブサイト(甲20)には,「複数メーカー機に装着可能」と\nいう文言と共に,「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり,各社分包機メーカー 及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で,承認を受けた製品ではありません。」 という記載があり,前記説明資料(甲9)にも同様の記載があることが認められる。 しかし,被告らの主張によっても,被告日進は,経済産業省により「平成25年 度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定され た後,平成26年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し,平成2 7年にカタログを作成し,平成28年5月12日に1台,同年10月25日に1台 の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる(甲17,乙 1,11,36)。 他方,被告製品は平成26年12月から販売されており,原告代理人は,平成2 8年1月頃に,被告らに対し,本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を 求める警告書(甲10)を送付し,同年7月4日に本訴を提起したことが認められ る。 前記時系列によれば,被告製品の販売が開始された当初,これを被告日進製 の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず,むしろ,原告との紛争\nが顕在化した後に,わずか2台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置(甲19,乙2,14〜16) 被告製品を,エルク製分包装置において使用されている芯管(外径約60mm。以 下「エルク製芯管」という。)に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するため には,被告製品の空回りを防止するために厚さ3.2mm程度のOリングを2個,エ ルク製芯管に装着することが必要であり,さらに,被告製品の外径(約193mm) が大きすぎるため,そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず,使用開始 に当たって長さ330mの分包紙中約88ないし100m分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって,被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無 駄を伴い,経済的に合理性のある使用とはいえない。
ウエダ製分包装置(甲23,乙17,18)
ウエダ製分包機については,特定の顧客が,その支持軸を独自に製作した支持軸 に取り換えるという改造を施すことにより,被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし,同顧客の保有するウエダ製分包機は20年以上前に販売が終了している 機種であり,ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品 を使用することは考えにくいし,改造を施さないウエダ製分包装置において,被告 製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって,被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは,一般的な使用 方法ということはできない。
タカゾノ製分包装置(乙20,21)
株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペ ーパが,被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。\n
まとめ
被告日進製の薬剤分包装置については,被告製品の販売が一定期間行われた後に, わずか2台が製造,販売されたにとどまるものであるから,被告製品が使用された としてもごくわずかといわざるを得ないし,被告以外の薬剤分包装置に被告製品を 使用することには困難が伴い,現実的ではないといわざるを得ないから,被告製品 については,原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は,実質的には存在しない といわざるを得ない。
ウ 争点(2)アについての判断
前記ア及びイで検討したところによれば,被告製品は,原告製使用済み芯管と一 体化し,一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産,譲 渡され,これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから,被告製品 は,一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。
(3) 特許権侵害についての判断
被告らが被告製品を生産,譲渡した段階では,回転角度の検出に用いる磁石を配 置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず,本件特許の構成要件の全部を\n充足するものではないが,前記(2)で検討した通り,被告製品は,原告製使用済み芯 管と一体化して,本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予\定されて おり,他の用途が実質的に存在せず,一体化製品の生産にのみ用いられるものと認 められるのであるから,被告製品の生産,譲渡は,特許権の直接侵害に至る蓋然性 が極めて高いものとして特許法101条 1 号の間接侵害に当たり,本件特許権を侵 害するものとみなすべきものである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> のみ要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成28(ワ)4759 不当利得返還請求事件 特許権 平成30年12月20日 大阪地方裁判所
(エ) 以上によれば,乙8には,「ホログラムの単位幅における格子部幅/非 格子部幅の比が,導光板の前面出射面から出射する光を効率よく,また,面内で均 一に出射されるように,管状光源から離れる側の方が増大せしめられている」構成\nが開示されているといえる。
ウ したがって,乙8発明は,本件発明の構成要件Bと同一の構\成を備える ものであるから,相違検討点2は相違点とはいえない。
エ 原告の主張について
原告は,乙8には,導光板に設けるホログラムの面積密度を増減させる技術思 想が開示されているだけで,回折格子の単位幅における格子部幅/非格子部幅の比を変化させる技術思想は開示されていないと主張する。 しかし,前記アのとおり,本件発明も,格子部の面積の変化を通じて,導光板の 表面における輝度を増大させ,かつ均一化させるものであり,本件発明と乙8発明\nはその解決課題と解決原理を共通にしている。 そして,上記のとおり,乙8には,本件発明の構成要件Bの構\成を備えたホログ ラムの構成が開示されていると認められるから,本件発明の構\成要件Bはこれを別 の表現で記述したものにすぎず,同一の構\成が開示されていることに変わりはない。 したがって,原告の主張は採用できない。
(6) 小括
以上によれば,本件発明と乙8発明とは,前記の相違検討点1において相違す るから,同一の発明とはいえず,乙8による特許法29条の2違反の無効理由が存 するとは認められないが,本件発明と乙8発明とは,その解決課題及び解決原理を 共通にしており,解決手段たる回折格子の種類についてのみ相違するにすぎないと いうことができる。
・・・
(ア) 本件明細書に記載された従来技術及びその課題
前記認定のとおり,本件明細書では,本件発明に関する従来技術として, 導光板の下面に多数の多面プリズムをもつ透明アクリル樹脂からなり,プリズムに よる光の全反射を利用する導光板が記載されており,その具体例として,特開平5 −127157号公報記載の平面照光装置(本件明細書の図6参照)が挙げられて いる。 そして,その従来技術によっても液晶表示パネルを下方から輝度ムラが少なく明るく照らすことができると記載されているが(【0003】),1)導光板の下面にある 多面プリズムの一辺が例えば0.16mmと,光の波長に比べて相当大きいものである うえ,各プリズムが協同することなく個別に光を全反射するものであるため,導光 板の輝度を全体に高めようとすると,各プリズムの間の谷間にあたる箇所で乱反射 が起きて上面に向かう光量が減り,照光面である上面に極端な明暗のコントラスト が生じるという課題,及び2)このような導光板を設けた平行照光装置を電池で駆動 される液晶表示装置に用いると,照光面に向かう上記光量の減少を補って高輝度を\n得るべく,光源を大電流で照らす必要があるため,電池の寿命が短くなって,長期 使用ができなくなるという課題があったことが記載されている(【0004】)。
(イ) 本件発明の課題解決手段
本件発明は,従来技術の上記課題を解決するため,「光の幾何光学的性質を 利用した従来のプリズムによる全反射でなく,・・・光の波動の性質に基づく回折現象 を利用して,従来より遥かに高く,かつ均一な輝度を照光面全体に亘って得ることが でき,ひいては光源の電力消費の低減による電池の長寿命化も図ることができる導 光板を提供すること」を目的として(【0005】),本件発明の構成を採用したもの\nである。その構成は,(a)透明な板状体である導光板の裏面に回折格子を設け,導光 板の少なくとも一端面から入射する光源からの光をその表面側へ回折させるという点(構\成要件A),(b)上記回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅/非 格子部幅の比の少なくとも1つを,上記導光板の表面における輝度が増大し,かつ\n均一化されるように変化させる点(構成要件B)である。
(ウ) 本件発明の作用効果
本件発明の導光板は,α 少なくとも一端面から光源からの光が入射する透 明な板状体の裏面に設けられた回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅 /非格子部幅の比の少なくとも1つが,上記導光板の表面における輝度が増大し,\nかつ均一化されるように変化せしめられているので,光の波長に比べて寸法が大き く互いに協同することなく個別に光を幾何光学的に全反射する従来の導光板裏面のプリズムと異なり,ミクロン単位の互いに隣接する微細な格子が協同,相乗して波動 としての光を格段に強く回折できるうえ,β 上記一端面から離れて光源から届く光 量が減じるほど,光をより強く回折するように上記断面形状または単位幅における 格子部幅/非格子部幅の比が調整されているので,導光板の表面は高輝度で非常に\n均一に照らされる。 したがって,γ この導光板を電池で駆動される液晶表示装置,液晶テレビ,非常口 を表示する発光誘導板などに適用すれば,従来に比して格段に少ない消費電力で明\nるく均一な照明を得ることができ,光源および電池の寿命を延ばし,長期使用を可 能にすることができる(【0009】,【0023】)
(エ) もっとも,本件の場合,本件明細書に従来技術が解決できなかった課 題として記載されているところは,以下のとおり,出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分なものと認められる。
a 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減るとの課題(上記(ア)1))を,導光板の裏面に回折格子を設け,回折現象を利用して解決する構成(上記(イ)の(a),上記(ウ)α)について
本件明細書では,導光板の従来技術として,プリズムによる全反射を利用したもののみが記載され,回折現象は今まで導光板に用いられることがなかった と記載されている。 しかし,原告は平成6年3月11日に自ら,発明の名称を「回折格子を利用した バックライト導光板」とし,特許請求の範囲(請求項1)を「成形加工及び印刷 (転写を含む)された回折格子を裏面に有する事を特徴とするプラスチック製のバ ックライト導光板。なをここで裏面とは,液晶面と反対側の面と定義する。」とする 特許の出願をし,その明細書では,【課題を解決するための手段】の項において, 「導光板裏面に光と干渉する程度に微細なスリット形状を成形加工ないし印刷(転 写を含む)し,この反射格子により導光板の一端から入射する光を液晶面側に回折 させる。」(【0006】)と記載し,【発明の効果】の項において,この発明によれば蛍光管からの光を回折格子という極小単位の形状(格子スリットのピッチがサブミ クロンから数十ミクロン)の大きさのものの作用により,導光板面を均一に輝らす\n事ができるので,従来からのドット印刷や全反射を利用した導光板裏面加工による 方式に比較して,格段の面輝度とその均一性が可能になる。」(【0017】)と記載\nしていた(特願平6−79172)(乙10,20)。そして,これは本件発明の構\n成要件Aと同じ構成を備えた発明と認められる。\nまた,前記1で技術的意義等を認定した乙8発明も,回折格子の種類は同じとは 認められないものの,導光板の裏面に回折格子を設け,回折現象を利用して光量の 増大を図る発明である(乙8発明のようないわゆる拡大先願発明も参酌すべきこと は後記のとおりである。)。 以上より,導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減ると の課題は,本件特許の出願日において,本件発明と同じく導光板の裏面に回折格子 を設け,回折現象を利用することによって既に解決されている課題であったと認め られる。
b 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題(上記(ア)1))を,回折格子の断面形状ま たは単位幅における格子部幅/非格子部幅の比の少なくとも1つを,上記導光板の 表面における輝度が増大し,かつ均一化されるように変化させることにより解決す\nる構成(上記(イ)の(b),上記(ウ)β)について 先に争点2−2(前記1)について述べたとおり,乙8発明も,導光板 の裏面にホログラムの回折格子を設け,回折現象を利用するものであり,かつ,本 件発明の構成要件Bと同一の構\成を備え,それにより,導光板の表面から出射する\n光を効率よく,また,面内で均一に出射されるようにするものである。もっとも, この乙8発明に係る特許の出願日は平成7年10月27日であり,本件特許の出願 よりも前に出願されたものであるが,乙8発明に係る特許について出願公開がされ たのは平成9年5月16日であり(乙8),本件特許の出願後であるから,乙8発明 はいわゆる拡大先願発明に該当するにすぎない。しかし,特許法29条の2は,特 許出願に係る発明が拡大先願発明と同一の発明である場合を特許要件を欠くものとしているところ,その趣旨の中には,先願の明細書等に記載されている発明は,出 願公開等により一般にその内容が公表されるから,たとえ先願が出願公開等をされ\nる前に出願された後願であっても,その内容が先願と同一内容の発明である以上, さらに新しい技術を公開するものではなく,そのような発明に特許権を与えること は,新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみ て妥当でないとの点がある。このように特許法が,先願の明細書等に記載された発 明との関係で新しい技術を公開するものでない発明を特許権による保護の対象から 外している法意からすると,均等侵害の成否の判断のために発明の本質的部分とし て従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定するに当た\nっては,拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当である。 そうすると,導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題は,本件特許の出願日において,回折格 子として刻線溝又はエンボス型のホログラムを用いるか体積・位相型のホログラム を用いるかの違いがあるとはいえ,本件発明と同じく,回折格子の単位幅における 格子部幅/非格子部幅の比を,導光板の表面における輝度が増大し,かつ均一化されるように変化させることによって既に解決されている課題であったと認められる。\n
c そして,本件発明の,少ない消費電力で明るく均一な照明を得るこ とができないとの課題(上記(ア)2))は,上記a及びbで述べた課題が解決されるこ とに伴い解決されるものである(上記(ウ)γ)から,やはり既に解決されている課題 であったと認められる。
d 以上からすると,本件発明が課題とするところは,いずれも本件特 許の出願時の従来技術によって,同様の解決原理によって解決されていたといえる。 本件発明がそれらの従来技術と異なる点は,回折格子の単位幅における格子部幅/ 非格子部幅の比を,導光板の表面における輝度が増大し,かつ均一化されるように変化させることについて,体積・位相型のホログラムではなく,刻線溝又はエンボ\nス型のホログラムを用いた点にあるが,回折格子としては後者の方がむしろ通常で あること(前記1(4)ウ(ア),(エ),(オ))からすると,本件発明の従来技術に対する 貢献の程度は大きくないというべきである。
ウ 以上よりすれば,本件発明の本質的部分については,特許請求の範囲の 記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。 この点について,原告は,本件発明の本質的部分は,光の波動の性質に基づく回 折現象を利用して,回折格子の断面形状又は単位幅における格子部幅/非格子部幅 の比に着目した点にあると主張するが,これまで述べたことに照らして採用できな い。
エ そうすると,被告製品の導光板では,前記のとおり,微細構造体が回折\nされた光が進行する側に設けられていることから,構成要件Aでいうところの「表\ 面」に微細構造体が設けられ,光源からの光が「表\面」側に回折させられている。 したがって,被告製品の導光板は構成要件Aの「板状体の裏面に設けられた回折格\n子」という部分を充足していない。よって,被告製品が本件発明の本質的部分を備えているということはできず,本件発明と被告製品とは本質的部分において相違すると認められるから,被告製品は,均等の第1要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成29(ワ)33490 営業差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年12月20日 東京地方裁判所
原告は,1)原告商標を被告店舗の看板に掲示して居住用建物清掃業を営んだ 期間が,平成28年3月11日から平成29年9月10日までの18か月であ ること,2)同期間における被告店舗の売上げが月額100万円を下らないこと, 3)原告商標の使用料率は,被告店舗の売上げの10%相当額を下回ることはな いことを前提にして,180万円と算定されるべきである旨を主張する。 そこで検討するに,まず上記1)の期間の点については,証拠(甲8及び9) 及び弁論の全趣旨によって,そのとおり認められる(上記2(2)参照)。 しかしながら,上記2)の被告店舗の売上月額については,原告の主張する金 額を認めるに足りる証拠はなく,かえって,証拠(乙B6ないし乙B26)及 び弁論の全趣旨からすれば,被告らの主張するとおり月額30万0234円で あると認められる。 また,上記3)の使用料率については,原告主張に係る10%という数字につ き的確な根拠は見当らないこと,経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ 料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」(平成22年8月。経済産業調査会)の16頁及び509頁においては,国 内アンケートの結果,原告商標の指定役務の属する第37類におけるロイヤル ティ料率の平均値が2.1%で,3%未満が全体の8割超を占めているとされ ていること等からすれば,原告標章である「おそうじ本舗」の知名度等,原告 指摘の諸点を考慮しても,3%とするのが相当である。 以上を前提に,1)18か月の期間につき,2)月額30万0234円の売上げ につき,3)月額3%の使用料率であるとして計算すると,16万2126円(た だし,1円未満は切り捨て。)となる。
(2) 弁護士費用
上記(1)の金額に加え,本件事案の内容,本件訴訟における主張立証の状況等 を総合考慮すると,商標権侵害を内容とする不法行為と相当因果関係の認めら れる弁護士費用の金額は,10万円である。
2019.02. 1
平成29(ネ)10049等 損害賠償請求控訴事件,同反訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月26日 知的財産高等裁判所(2部) 東京地方裁判所
1 争点(1)ケ(特許権の移転登録の要否及び「別段の定」の有無)について
(1) 事案に鑑み,争点(1)ケから判断する。
特許権の移転は,相続その他の一般承継によるものを除き,登録しなければ,そ の効力を生じないから(特許法98条1項1号),被控訴人は,本件特許権1の特 許権者(共有持分権者)である(甲1)。 控訴人は,被控訴人の特許法98条1項1号を根拠とする主張は,時機に後れた 攻撃防御方法として却下すべきであると主張するが,被控訴人が本件特許権1に係 る特許原簿に特許権者(共有持分権者)として登録されていた事実(甲1)は,既 に訴状において控訴人が主張していたのであり,控訴人において被控訴人は無権利 者である旨の主張をする際にあらかじめ検討しておくべき事項であるから,上記主張は採用できない。 また,控訴人は,特許法98条1項1号は,通常の特許権の移転について登録を 効力発生要件としたものであって,本件のように,移転が解除されたことにより特 許権が譲受人から譲渡人に対し復帰的に物権変動するときには登録は不要であるな どと主張するが,同号は,相続その他の一般承継による移転には適用されない旨を 明示した上で,「特許権の移転」を対象としていること,同法74条2項は,特許 がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき (同法123条1項6号)であっても,その特許に係る発明について特許を受ける 権利を有する者の請求に基づく特許権の移転の登録があったことを要件として,そ の特許権が初めからその登録を受けた者に帰属していたものとみなすとしているこ とに照らすと,本件には同法98条1項1号の適用がない旨の主張は採用できな い。 そうすると,特許法73条2項の「別段の定」をした場合を除き,被控訴人は, 他の共有者の同意を得ないで,本件発明1−1の実施をすることができるから,続 いて,本件4者間の「別段の定」の有無を検討する。
(2) 控訴人は,本件共同出願契約書13条は,本件固定的役割分担合意を規定 するものであり,本件固定的役割分担合意の一部が特許法73条2項の「別段の 定」に該当すると主張するところ,前記第2の2(4)のとおり,本件共同出願契約 書には,中国語で記載され,作成日付及び本件4者の署名があるもの(甲6契約書)と,日本語で記載され,作成日付及び本件4者の署名がないもの(甲5契約 書)とがあるが,甲6契約書には作成日付及び署名があることに加え,B及びAが 中国語を理解し日本語を理解しないこと,甲6契約書は被控訴人従業員が中国語に 翻訳したものであり,控訴人も中国語を理解すること(以上の事実につき,証人 E,弁論の全趣旨)を併せ考慮すると,本件4者は,作成日付及び署名がある甲6 契約書をもって,本件共同出願契約を締結したと認めるのが相当である。
(3) 前記第2の2(4)ア(ク)のとおり,甲6契約書13条には,「事前の協議・ 許可なく,本件の各権利(本件特許権)を新たに取得し,又は生産・販売行為を行 った場合,本件の各権利は剥奪される。(甲,乙,丙及び丁の全員が対象である)」と記載されている。 同条の「生産・販売行為」の対象は,その文理に照らし,「本件の各権利(本件 特許権)」の実施品であると合理的に解釈できるから,同条は,契約当事者間にお いて「本件の各権利(本件特許権)」の実施品の生産・販売行為を制限する趣旨の 条項である。そうすると,契約当事者の合理的意思として,同条の「事前の協議・ 許可なく」とは,「事前の協議及び許可なく」の意味であると解釈でき,同条の 「生産・販売行為」とは,「生産又は販売行為」の意味であると解釈できる。前者 では「・」を「及び」と解釈し,後者では「・」を「又は」と解釈することになる が,いずれも契約当事者の合理的意思に沿うものであり,矛盾はない。また,前記 第2の2(4)ア(ア),(イ)によると,本件特許権1は,甲6契約書にいう「本件特許 権」に該当する。
以上によると,同条は,本件特許権1の共有者がその特許発明の実施である生産 又は販売をすることについて,事前の協議及び許可を要するものとして制限するも のであるから,特許法73条2項の「別段の定」に該当する。 そして,前記第2の2(5),(6)のとおり,被控訴人は,平成28年4月以降,日 本において,本件製造会社に本件発明1−1の実施品である被告各商品を製造さ せ,被告各商品を独自に販売しているが,これについて,事前の協議及び許可を経 たことは,本件全証拠によっても認められない。
したがって,被控訴人が,平成28年4月以降,日本において,本件製造会社に 本件発明1−1の実施品である被告各商品を製造させ,被告各商品を独自に販売し たことは,「別段の定」である甲6契約書13条に違反するものである。
(4) 被控訴人は,本件共同出願契約書7条には,本件発明の実施は,協議によ り別途定める旨の規定があるから,本件共同出願契約には,製造,販売等について の何らかの役割分担に関する合意は含まれないことが明らかであり,同契約書13 条は「別段の定」を規定したものではない旨の主張をする。 しかし,前記第2の2(4)ア(オ)のとおり,甲6契約書7条は,「甲,乙,丙及び 丁は,本件発明の実施に対する協議の後,別途に定める。」と規定するものである から,同契約書13条が,本件特許権1の共有者がその特許発明の実施である生産 及び販売をすることについて,事前の協議及び許可を要するものとすることと矛盾 するものではない。 そして,1)Bが中国国内の工場で本件発明1−1の実施品を製造し,2)これをA が梱包し,3)これを控訴人が仕入れ,4)さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販 売するという本件販売形態が本件共同出願契約締結後,長年にわたり続けられてき たことは,当事者間に争いがないから,本件販売形態は,同契約書13条の「事前 の協議・許可」を経たものということができる。このように,製造,販売等につい ての役割分担を含む本件販売形態については,同契約書13条の「事前の協議・許 可」を経たものであるから,同契約書13条と矛盾するものではない。 また,前記第2の2(4)ア(カ)のとおり,甲6契約書8条は,「甲,乙,丙及び丁 は,他の全ての当事者の同意を得なければ,本件特許権を乙,丙及び丁が自ら経営 する法人以外の第三者に譲渡し,或いは本件発明の実施を許諾してはならない。」 と規定するものであるから,同契約書13条が,本件特許権1の共有者がその特許 発明の実施である生産及び販売をすることについて,事前の協議及び許可を要する ものとすることと矛盾するものということはできない。本件共同出願契約書を起案した弁護士が,甲6契約書8条と概ね同様の共同出願契約書案8条の「乙,丙及び 丁のいずれかが主体となって事業を営む法人」という文言に添えたコメントには, 「X様やA様,B様が経営している会社については,同意がなくても製造販売等が 可能です。」と記載されているが(甲49),本件4者が合意に達した甲6契約書で\nはなく,契約書作成過程の書面に付されたものにすぎないし,契約当事者のうち被 控訴人を除く控訴人ら3者が自然人であったことから,控訴人ら3者が将来的に法 人化して事業を営む際にも支障が生じない旨を説明したものと理解できるから,上 記コメントにより,甲6契約書13条が,本件特許権1の共有者がその特許発明の 実施である生産及び販売をすることについて,事前の協議及び許可を要することを 定めたものではないということはできない。 さらに,本件共同出願契約には,靴紐の購入単価又はその決定方法についての条 項はなく,被控訴人が控訴人から靴紐を購入しなければならないことを規定する条 項もないからといって,甲6契約書13条についての上記判断が左右されるもので はない。
(5) 被控訴人は,控訴人が,被控訴人との協議・許可なしに,COOLKNO Tという商品名又はブランド名により本件特許権の実施品を販売しているから,こ の控訴人の販売及び被控訴人の製造販売のいずれも,本件共同出願契約書13条に は違反しないとするのが,契約当事者の合理的意思である,本件特許権の持分を剥 奪されるのは控訴人であり,被控訴人ではないと主張するが,前記(3)のとおり, 甲6契約書13条の文理等に照らし,採用できない。
(6) 被控訴人は,本件共同出願契約書13条後段は,同条前段と合わせて読む べきところ,同条前段は,本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新 たに取得することを禁止しているから,同条後段は,実質的同一の範囲内で新たに 取得された特許権について,その実施品の生産・販売を禁止しているものと理解で きると主張する。 しかし,甲6契約書13条前段は,その文理に照らすと,事前の協議及び許可な く,「本件の各権利(本件特許権)」を未取得の国において,「本件の各権利(本件 特許権)」を新たに取得することを禁止するものと解すべきであるから,同条前段 が本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新たに取得することを禁止 しているとは認められない。また,同条前段は,「本件の各権利(本件特許権)」を 新たに取得したことのみによって「本件の各権利」を剥奪すると定めていることか らすると,同条後段が,その新たに取得された「本件の各権利(本件特許権)」の実施品を生産又は販売したことによって「本件の各権利」を剥奪することのみを定 めたものと解釈するのは不合理である。同条後段は,既に取得されているか,新た に取得されたものであるかを問わず,「本件の各権利(本件特許権)」の実施品の生 産又は販売行為を無断で行うことを禁止したものと解するのが相当である。
(7) 被控訴人は,本件共同出願契約書13条後段は,日本以外の国での販売行 為を定めた同契約書14条に違反した場合の効果を規定した条項であると理解で き,仮に日本での生産・販売行為について規定したものであるとすると,被控訴人 は,既に販売中の靴紐について,日本での販売中止を前提に本件共同出願契約を締 結したこととなり,著しく不合理であると主張する。 しかし,前記(3)のとおり,甲6契約書13条後段の文理に照らし,日本以外の 国での行為に限定されたものとは解釈できないし,被控訴人が本件共同出願契約締 結当時行っていた本件販売形態は,同条の「事前の協議・許可」を経たものとして 禁止されないから,被控訴人が本件共同出願契約締結当時被告各商品を既に販売し ていたことは,同条後段が禁止する対象から日本での行為を除外して解釈すべき理 由とはならない。
(8) 被控訴人は,本件共同出願契約書13条後段の内容は,同契約書16条の 協議を経なければ空文であり,これを法的請求の根拠とすることはできないと主張 するが,同契約書16条は,裁判外における紛争解決の方法を定めたものと合理的に解釈できるのであって,同条の協議を経なければ疑義が生じた契約条項の内容が 空文であり,法的請求の根拠とすることができないものとは認められない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.01.28
平成30(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月24日 知的財産高等裁判所
イ 前記アの記載事項を総合すると,2次元コード読取装置の技術分野にお いては,本件出願当時(出願日平成9年10月27日),1)「周波数成分 比」とは,2次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」 (パターン)の中心を横切る(通る)走査線における「白(明)」が連続 する長さと「黒(暗)」が連続する長さの比を意味すること,2)「位置決 め用シンボル」は,同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されてお り,その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるた め,「周波数成分比」は「所定」の比率であること,3)「所定の周波数成 分比」の「検出」とは,2次元コード読取装置の2次元画像検出手段から 出力される画像信号(走査線信号)を2値化した後の走査線信号中から, 周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有 無を検出する処理を意味することは,技術常識であったものと認められる。 ウ これに対し原告は,同一出願人が出願した発明に係る2件の公開特許公 報(甲5,18)のみから,本件出願当時の技術常識を認定することはで きない旨主張する。 しかしながら,甲5(公開日平成8年7月12日)及び甲18(公開日 平成7年10月3日)は,マトリックス型2次元コード(いわゆるQRコ ード)の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認め\nられるから,甲5及び18から,前記イの本件出願当時の技術常識を認定 することは妥当である。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3) 明確性要件の適合性について
ア 構成Dの「所定の周波数成分比」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言によれば,構成Dの\n「所定の周波数成分比」は,カメラ部制御装置において,読み取り対象 の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して,閾値に基づ いて2値化し,2値化された信号の中から検出され,その検出結果が出 力されるものであるが,請求項1には,「所定の周波数成分比」の値を 具体的に規定した記載はない。 次に,本件明細書(甲6,8,乙2の2)には,「所定の周波数成分 比」の語を定義した記載はない。一方で,本件明細書の記載事項(【0 029】ないし【0031】,図4)によれば,本件明細書には,実施 例として,2次元コード読取装置のCCDエリアセンサ41が撮像した 2次元画像を水平方向の走査線信号として出力し,カメラ部制御装置5 0において,これをAGCアンプ52及び補助アンプ56によって増幅 し,増幅された走査線信号は2値化回路57によって閾値に基づいて2 値化され,周波数分析器58は2値化された走査線信号の内から「所定 の周波数成分比」を検出し,その検出結果を画像メモリコントローラ6 1に出力することの開示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言,本件明細書の 開示事項及び2次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識(前記(2)イ)に鑑みると,本件発明の構成Dの「所定の周波数\n成分比」は,上記技術常識における用語と同義であるものと認められる から,読み取り対象の画像(2次元コードマトリックス)に配置された 「位置決め用シンボル」(パターン)の中心を横切る(通る)走査線に おける「白(明)」が連続する長さと「黒(暗)」が連続する長さの比 (「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の 比率)を意味するものと解される。 したがって,本件発明の構成Dの「所定の周波数成分比」の内容は明\n確である。
(イ) これに対し原告は,構成Dの「周波数成分比」との文言は一般的な\n用語ではなく,本件明細書にも,「周波数分析器58は,2値化された 走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載(【003 1】)があるのみで,いかなるものが「所定の周波数成分比」であるの か何ら説明がないから,構成Dの「所定の周波数成分比」の記載は,明\n確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記(ア)認定のとおり,本件出願当時の技術常識を踏 まえると,構成Dの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえ\nるから,原告の上記主張は理由がない。
イ 構成Fの「相対的に長く設定し」に(ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の構成Fの記載は,「前記\n読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズ に入射するよう,前記絞りを配置することによって,前記光学的センサ から射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」というものである。 上記記載から,「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的 に長く設定」することは,「読み取り対象からの反射光が絞りを通過し た後で結像レンズに入射するよう,絞りを配置すること」の結果として 得られるものであることを理解することができる。 また,本件明細書には,光学的センサから射出瞳までの距離(射出瞳 距離)は,光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば,それ に伴って長くなるところ,従来の光学情報読取装置では,複数の結像レ ンズ間に絞りが配置されていたものを,「本発明」では,読取り対象か らの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置 する構成を採用したことにより,光学的センサから射出瞳位置までの距離(射出瞳距離)を相対的に長く設定することができること(【000\n9】,【0040】,【0041】,図6)の開示があることが認めら れる。 以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言及び本件明細書 の開示事項に鑑みると,本件発明の構成Fの「相対的に長く設定し」と\nは,絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過し た後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと 比較して,光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」 することを意味するものと解される。 したがって,本件発明の構成Fの「相対的に長く設定し」の内容は明\n確である。
(イ) これに対し原告は,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)におい て,「相対的に」の基準が明確でないため,「相対的に長く設定し」の 記載からは,射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを 意味するのか,どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのか を理解することができないから,構成Fの「相対的に長く設定し」の記\n載は,明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記(ア)の認定事実によれば,「相対的に」の基準と なる比較の対象は,絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前 記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたもの ではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかである\nから,原告の上記主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。
ウ 構成Gの「所定値」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)には,構成Gの「前記光学\n的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的 センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」にお ける「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。 一方で,請求項1における「前記読み取り対象からの反射光が前記絞 りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう,前記絞りを配置する ことによって,前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に 長く設定し,」(構成F),「前記光学的センサの中心部に位置する受\n光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素 子からの出力の比が所定値以上となるように,前記射出瞳位置を設定し て,露光時間などの調整で,中心部においても周辺部においても読取が 可能となるようにしたこと」(構\成G)の記載によれば,本件発明にお いては,「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう,前記絞りを配置すること」によって「射 出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することがで きる。 また,本件明細書には,構成Gの「所定値」に関し,「最終的には適\n切な読み取りを実現することが目的であるので,本発明の光学情報読取 装置においては,光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力 に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所 定値以上となるように,射出瞳位置を設定している。このようにしてお けば,中央部と周辺部の出力差を考慮しながら,例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり,中心部においても周辺部に おいても適切に読取が可能となる。」(【0011】),「適切な読み\n取りを実現するためには,センサ周辺部にある受光素子41aからの出 力レベルが所定レベル以上になる必要がある。そのため,例えば,セン サ中心部に位置する受光素子41aからの出力に対するセンサ周辺部に 位置する受光素子41aからの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳 位置を設定することが考えられる。つまり,このような射出瞳位置とな るように絞り34aの位置を設定するのである。このようにしておけば, 中央部と周辺部の出力差を考慮しながら,例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり,中心部においても周辺部において も適切に読取が可能となる。」(【0042】)との記載がある。\n以上の本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の文言及び本件明細書 の記載に鑑みると,構成Gは,「前記読み取り対象からの反射光が前記\n絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう,前記絞りを配置す ること」によって「射出瞳位置を設定」することを前提とした上で,「露 光時間などの調整」により,「光学的センサの中心部においても周辺部 においても読取が可能となるように」すること,すなわち,光学的セン\nサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を2値化するために用 いられる閾値に基づいて,光学的センサの周辺部に位置する受光素子か ら得られた信号を2値化することが可能であるような強さの光を,周辺\n部に位置する受光素子が受光できるように,射出瞳位置を設定すること を特定したものであることが認められる。 そうすると,構成Gの「所定値」とは,「露光時間」の「調整」など\n読取りに際して所与の調整を行うことにより,「光学的センサの中心部 においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位\n置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位 置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。 したがって,本件発明の構成Gの「所定値」の内容は明確である。
(イ) これに対し原告は,構成Gの「所定値」については,本件発明の特\n許請求の範囲(請求項1)に規定がなく,本件明細書にも,それがいか なる値を意味するのかの手掛かりとなる記載がないため,本件明細書に 接した当業者は,「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解 決されるのかを理解することができないし,また,中心部に位置する受 光素子からの出力信号を2値化するために用いられる「閾値」は明らか にされておらず,「所定値」の値は,特許請求の範囲の記載から一義的 に定まるものではないから,構成Gの「所定値」の記載は,明確であるとはいえない旨主張する。\nしかしながら,構成Gの「所定値」とは,あらかじめ一律に定められ\nた特定の数値をいうものではなく,「露光時間」の「調整」など読取り に際して所与の調整を行うことにより,「光学的センサの中心部におい ても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設\n定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する 受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光 素子からの出力の比」の値を意味するものであることは,前記(ア)認定 のとおりである。 また,「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に,「露光時間」の 「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより,「光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位\n置に射出瞳位置を設定することは,当業者が適宜考慮して定める設計的 事項であるというべきであるから,請求項1に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって,構成Gの「所定値」の内容が明確で\nないとはいえない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。
・・・
(1) 実施可能要件の適合性について
ア 「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Dについて
原告は,構成Dの「所定の周波数成分比」の記載が明確でなく,また,\n本件明細書には,「所定の周波数成分比」の「検出」の実現方法について も何ら記載されていないから,当業者は,本件明細書に基づいて,本件発 明を実施することができない旨主張する。 しかしながら,構成Dの「所定の周波数成分比」の内容が明確であるこ\nと,本件明細書には,実施例として,2次元コード読取装置のCCDエリ アセンサ41が撮像した2次元画像を水平方向の走査線信号として出力し, カメラ部制御装置50において,これをAGCアンプ52及び補助アンプ 56によって増幅し,増幅された走査線信号は2値化回路57によって閾 値に基づいて2値化され,周波数分析器58は2値化された走査線信号の 内から「所定の周波数成分比」を検出し,その検出結果を画像メモリコン トローラ61に出力することの開示があることは,前記1(3)ア(ア)認定の とおりである。 また,2次元コード読取装置の技術分野において,「所定の周波数成分 比」の「検出」とは,2次元コード読取装置の2次元画像検出手段から出 力される画像信号(走査線信号)を2値化した後の走査線信号中から,周 波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することが,本件出願当時,技術常識であったこと は,前記1(2)イ認定のとおりである。 そうすると,当業者は,本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識 に基づいて,「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Dを実施できたも\nのと認められるから,原告の上記主張は理由がない。
イ 「相対的に長く設定し」の記載を含む構成Fについて
原告は,構成Fの「相対的に長く設定し」との記載が明確でなく,また,\n当業者は,本件明細書から,射出瞳位置をどのように設定すれば「相対的 に長く設定」することができるのかを理解することができないから,本件 明細書に基づいて,本件発明を実施することができない旨主張する。 しかしながら,構成Fの「相対的に長く設定し」の内容が明確であるこ\nと,本件明細書には,光学的センサから射出瞳までの距離(射出瞳距離) は,光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば,それに伴って 長くなるところ,従来の光学情報読取装置では,複数の結像レンズ間に絞 りが配置されていたものを,「本発明」では,読取り対象からの反射光が 絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用\nしたことにより,光学的センサから射出瞳位置までの距離(射出瞳距離) を相対的に長く設定することができることの開示があることは,前記1(3) イ(ア)認定のとおりである。 そうすると,当業者は,本件明細書の記載に基づいて,「相対的に長く 設定し」の記載を含む構成Fを実施できたものと認められるから,原告の\n上記主張は理由がない。
ウ 「所定値」の記載を含む構成Gについて
原告は,構成Gの「所定値」の記載が明確でなく,また,当業者は,「所\n定値」がどのようなものであるかを理解することができない以上,構成G\nの「所定値以上となるように,前記射出瞳位置を設定」することもできな いから,本件明細書に基づいて,本件発明を実施することができない旨主 張する。しかしながら,構成Gの「所定値」の内容が明確であることは,前記1\n(3)ウ(ア)認定のとおりである。 そして,本件明細書の【0011】及び【0042】の記載に加えて, 「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レン ズに入射するよう」絞りの配置をする際に,「露光時間」の「調整」など 読取りに際して所与の調整を行うことにより,「光学的センサの中心部に おいても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を\n設定することは,当業者が適宜考慮して定める設計的事項であること(前 記1(3)ウ(イ))からすると,当業者は,本件明細書の記載に基づいて,「所 定値」の記載を含む構成Gを実施できたものと認められるから,原告の上\n記主張は理由がない。
◆判決本文
元の訂正審決の取消訴訟はこちらです。
関連カテゴリー
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> ピックアップ対象
2019.01.28
平成30(ネ)10038 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成31年1月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
不競法2条1項3号により保護される原告商品の形態について
ア 原告商品(検甲2)は,別紙「原告商品の形態」のとおりのサックス用 ストラップであり,その基本的構成態様(全体的形態)及び具体的構\成態 様は,別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「原告商品」欄記載の\nとおりである。 すなわち,原告商品は,1)基本的構成態様は,V型プレート,革パッド,\nブレードクリンチ,ブレード(紐)及びフックの5つのパーツにより構成\nされ,5つのパーツは,ブレードクリンチの留めネジ(六角ボルト)を緩 めてブレード(紐)を外すことにより,分解することができる,2)V型プ レートは,中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり,両 翼の先端(左右の端)のそれぞれに穴が1つずつ,中央部に穴が4つある という基本的形状を有し,V型プレートの厚みは約0.3cm,左右の幅(左 端から右端までの直線距離)は約14cm,中央部の四角形状の底辺の長さ は約2cm,高さは約3cm である,3)革パッドは,2枚の革を張り合わせ, 内部に丸みを帯びた三角形状の2つのクッションを配置し,中央部にクッ ションを入れずに窪みを設け,中央部から左右の端に向けて幅が狭くなっ たテーパー型のパッドであり,左右の端にはブレード(紐)を通すための 金属のハトメがあり,中央部から左右の端までの長さは約22.5cm,中 央部の幅は5.5cmである,4)ブレードクリンチは,革パッドの左右の端 のハトメを通したブレード(紐)を固定するための空洞の円柱状の金具で ある,5)ブレード(紐)は,黒色の編み込みの紐であり,革パッドの左右 の端のハトメからブレードクリンチを経てV型プレートの左右の端の穴を 通り,中央部の四角形状の4つの穴を通ってまとめられ,フックをぶら下 げるための輪を形成している,6)フックは,光沢のある銀色の金属フック であり,ブレード(紐)を通す輪とサックスにかけるフック部分からなる という形態を有している。
イ この点に関し被控訴人は,サックス用ストラップにおいて,V型プレー トによって,ストラップ装着時に首元を圧迫しない構造にすること,革\nパッドにクッションを入れて衝撃を緩和すること,V型プレートに穴を開 けてブレード(紐)を通す構造にすることは,「当該商品の機能\を確保す るために不可欠な形態」(不競法2条1項3号括弧書き)であり,また, 原告商品の基本的構成態様(前記ア1)),V型プレートの形態(前記ア2)) 及び革パッドの形態(前記ア3))は,ありふれた形態であるから,原告商 品の形態は,同号の保護の対象とならない旨主張する。 (ア) しかしながら,サックス用ストラップにおいて,頸部や肩を圧迫し ない構造にするために革パッドにクッションを入れる構\造とし,ブレー ド(紐)の長さを調節するためにブレード(紐)を通す穴を有するアジャ スターを設ける必要はあるものと認められるが(乙1ないし5),革パッ ド及びアジャスターの具体的形態については,様々な選択肢が考えられ, 必然的に原告商品の革パッド及びV型プレート(アジャスターに相当) の形態を選択せざるを得ないものではない。 したがって,原告商品の革パッド及びV型プレートの形態は,「当該 商品の機能を確保するために不可欠な形態」(不競法2条1項3号括弧\n書き)に当たるものとは認められない。
(イ) 次に,不競法2条1項3号は,他人が資金,労力を投下して商品化 した商品の形態を他に選択肢があるにもかかわらず,ことさら模倣した 商品を,自らの商品として市場に提供し,その他人と競争する行為は, 模倣者においては商品化のための資金,労力や投資のリスクを軽減する ことができる一方で,先行者である他人の市場における利益を減少させ るものであるから,事業者間の競争上不正な行為として規制したものと 解される。 このような同号の趣旨に照らすと,同号によって保護される「商品の 形態」とは,商品全体の形態をいい,その形態は必ずしも独創的なもの であることを要しないが,他方で,商品全体の形態が同種の商品と比べ て何の特徴もないありふれた形態である場合には,特段の資金や労力を かけることなく作り出すことができるものであるから,このようなあり ふれた形態は,同号により保護される「商品の形態」に該当しないと解 すべきである。そして,商品の形態が,ありふれた形態であるか否かは, 商品を全体として観察して判断すべきであり,全体としての形態を構成\nする個々の部分的形状を取り出してそれぞれがありふれたものであるか どうかを判断することは相当ではない。 しかるところ,乙1(「オリジナル・ツェブラ・サックス・ストラッ プ ホームページ」)には,アジャスター(調節つまみ),革パッド, ブレード(紐)及びフックのパーツにより構成される「ツェブラ・スト\nラップ」の写真が掲載されているところ,アジャスターは,中央部から 左右斜め上方に伸びる辺(両翼)を有するY字状であり,中央部の形状 が四角形状でない点,両翼の角度が約90度であり,鈍角ではない点, 中央部の穴の位置などにおいて原告商品のV型プレートの形態(別紙「原 告商品の形態」)と明らかに相違し,基本的構成態様においても,ブレー\nドクリンチを有していない点で,原告商品の全体としての形態と相違す る。 また,乙2(「Protec LC305M Neck Strap」) に掲載された「Neck Strap」は,ブレードクリンチを有して いない点で原告商品の形態と相違するほか,アジャスターは,中央部か ら左右に伸びる辺(両翼)を有する形状であるものの,中央部の形状が 四角形状でない点,中央部の穴が3つであり,4つでない点,中央部の 穴の位置などにおいて原告商品のV型プレートの形態と相違し,基本的 構成態様においても,ブレードクリンチを有していない点で,原告商品\nの全体としての形態と相違する。 さらに,乙3(国際公開公報(WO 00/41589)・訳文乙1 1)記載の「キャリングストラップ」の「滑車装置」(図11)(アジャ スターに相当)は,T字状であり,中央部が四角形状でない点,乙4(再 公表特許公報(WO2008/107939))記載の「楽器用ストラッ\nプ」の「楽器連結具」(アジャスターに相当)は,細長い棒状である点, 乙5(「新型説明書公告本」(TWM443110U1)・訳文乙12) 記載の「吊り部品」の「支持ロッド」(図3,4)(アジャスターに相 当)は,細長い棒状であり,4つの穴のある四角形状部と「吊り紐」で 連結している点において,いずれも原告商品のV型プレートの形態と明 らかに相違し,基本的構成態様においても,革パッド部分の形状が原告\n商品の全体としての形態と相違する。 そうすると,乙1ないし5から,原告商品の販売が開始された平成2 8年3月当時,原告商品の形態がありふれた形態であったものと認める ことはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
・・・
ウ 被控訴人は,旧原告商品からモデルチェンジされた商品である原告商品 の形態と旧原告商品の形態は実質的に同一であるから,原告商品の形態は, 旧原告商品の形態とは別の形態として,不競法2条1項3号により保護さ れるものではない旨主張する。 そこで検討するに,旧原告商品(検甲1)は,別紙「旧原告商品目録」 のとおりのサックス用ストラップであり,基本的構成態様が,V型プレー\nト,革パッド,ブレードクリンチ,ブレード(紐)及びフックの5つのパー ツにより構成され,5つのパーツは,ブレードクリンチの留めネジ(六角\nボルト)を緩めてブレード(紐)を外すことにより,分解することができ る点,V型プレートは,中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺 からなり,両翼の先端(左右の端)のそれぞれに穴が1つずつ,中央部に 穴が4つあるという基本的形状を有する点,革パッドは,2枚の革を張り 合わせ,内部に丸みを帯びた三角形状の2つのクッションを配置し,中央 部にクッションを入れずに窪みを設け,中央部から左右の端に向けて幅が 狭くなったテーパー型のパッドである点において,原告商品(検甲2)の 形態と共通する。 しかしながら,原告商品のV型プレートと旧原告商品のV型プレートの 形態は,別紙「原告商品と旧原告商品の変更点」記載の図4(a)及び(b) のとおり,原告商品のV型プレートは,旧原告商品のV型プレートと比べ, 中央部の四角形状から左右に伸びる両翼の形状及び幅が大きく変更され, 細長くなっており,両者の形態は一見して明らかに相違することが認めら れる。 加えて,サッククス用ストラップの形態において,V型プレート(アジャ スターに相当)は,需要者が注意を引きやすい特徴的部分であることを踏 まえると,V型プレートの形態の上記相違により,原告商品から受ける商 品全体としての印象と旧原告商品から受ける商品全体としての印象は異な るものといえるから,原告商品の形態は,商品全体の形態としても,旧原 告商品の形態とは実質的に同一のものではなく,別個の形態であるものと 認められる。
・・・
この点に関し原判決は,1)原告商品は,旧原告商品からモデルチェンジ された商品であり,V型プレート,革パッド及びブレード(紐)が旧原告 商品からの変更部分である,2)原告商品の形態が,旧原告商品の形態の保 護期間(不競法19条1項5号イ)が経過した後であっても,同法2条1 項3号の保護を受け得るのは,そのV型プレートの変更部分が商品の形態 において実質的に変更されたものであり,その特有の形状が美観の点にお いて保護されるべき形態であると認められることによるものであるから, 同号による保護を求め得るのは,この変更部分に基礎を置く部分に限られ る旨判断したが,前記イ(イ)で説示したとおり,同号の趣旨に照らすと, 同号によって保護される「商品の形態」とは,商品全体の形態をいうもの であり,また,上記のとおり,原告商品の形態と旧原告商品の形態は,実 質的に同一の形態とは認められないから,原判決の上記2)の判断は妥当で はない。
エ 以上によれば,原告商品の形態は,その商品全体の形態が,不競法2条 1項3号により保護されるべきものと解される。
(2) 形態の実質的同一性について
ア 被告商品(検甲3)は,別紙「被告商品の形態」のとおりのサックス用 ストラップであり,その基本的構成態様(全体的形態)及び具体的構\成態 様は,別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「被告商品」欄記載の\nとおりである。
すなわち,被告商品は,1)基本的構成態様は,V型プレート,革パッド,\nブレードクリンチ,ブレード(紐)及びフックの5つのパーツにより構成\nされ,5つのパーツは,ブレードクリンチの留めネジ(六角ボルト)を緩 めてブレード(紐)を外すことにより,分解することができる,2)V型プ レートは,中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり,両 翼の先端(左右の端)のそれぞれに穴が1つずつ,中央部に穴が4つある という基本的形状を有し,V型プレートの厚みは約0.3cm,左右の幅(左 端から右端までの直線距離)は約14cm,中央部の四角形状の底辺の長さ は約2cm,高さは約2.5cm である,3)革パッドは,2枚の革を張り合わ せ,内部に丸みを帯びた三角形状の2つのクッションを配置し,中央部に クッションを入れずに窪みを設け,中央部から左右の端に向けて幅が狭く なったテーパー型のパッドであり,左右の端にはブレード(紐)を通すた めの金属のハトメがあり,中央部から左右の端までの長さは約21.5cm, 中央部の幅は5cmである,4)ブレードクリンチは,革パッドの左右の端の ハトメを通したブレード(紐)を固定するための空洞の円柱状の金具であ る,5)ブレード(紐)は,黒色の編み込みの紐であり,革パッドの左右の 端のハトメからブレードクリンチを経てV型プレートの左右の端の穴を通 り,中央部の四角形状の4つの穴を通ってまとめられ,フックをぶら下げ るための輪を形成している,6)フックは,光沢のある金色の金属フックで あり,ブレード(紐)を通す輪とサックスにかけるフック部分からなると いう形態を有している。
イ そして,原告商品(検甲2)の形態と被告商品(検甲3)の形態とを対 比すると,1)両者は,基本的構成態様が,V型プレート,革パッド,ブレー\nドクリンチ,ブレード(紐)及びフックの5つのパーツにより構成され,\n5つのパーツは,ブレードクリンチの留めネジ(六角ボルト)を緩めてブ レード(紐)を外すことにより,分解することができる点,V型プレート は,中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり,両翼の先 端(左右の端)のそれぞれに穴が1つずつ,中央部に穴が4つあるという 基本的形状を有する点,革パッドは,2枚の革を張り合わせ,内部に丸み を帯びた三角形状の2つのクッションを配置し,中央部にクッションを入 れずに窪みを設け,中央部から左右の端に向けて幅が狭くなったテーパー 型のパッドである点において共通し,2)V型プレートをはじめとする各パーツの具体的な構成態様においても,形状,色彩,光沢及び質感におい\nて多数の共通点(別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」のC,D,F,\nHないしK,N,P,Q,S,T,VないしX,aないしd,fないしh の各欄のとおり)があり,原告商品と被告商品から受ける商品全体として の印象が共通することによれば,商品全体の形態が酷似し,その形態が実 質的に同一であるものと認められる。 もっとも,原告商品と被告商品とは,V型プレートにおける中央部の側 面及び下面(底辺)の形状,中央部の4つの穴のうち,上部の2つの穴の 位置及び間隔,両翼の角度及びその先端部分の角度,光沢,ロゴの位置, 革パッドの内側の革の色,革パッドの長さ及びクッションの大きさ,ブレー ドクリンチの色彩及び光沢,フックの色彩等において相違するが,次に述 べるとおり,これらの相違は,商品の全体的形態に与える変化に乏しく, 商品全体からみると,ささいな相違にとどまるものと評価すべきものであ るから,原告商品の形態と被告商品の形態が実質的に同一であるとの上記 判断を左右するものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.01.22
平成30(ワ)6943 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年12月26日 東京地方裁判所(29部)
著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又\nは音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)ところ,創作的に表現さ\nれたというためには,厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではな く,作成者の何らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが,他方,文\n章自体がごく短く,又は表現上制約があるため他の表\現が想定できない場合や,表現\nが平凡かつありふれたものである場合には,作成者の個性が表現されたものとはいえ\nないから,創作的な表現であるということはできない。\n
イ これを本件についてみるに,前記第2の2前提事実(2)及び前記(1)に認定したと おり,本件マニュアルは,本件システムの機能や操作方法の説明を目的として作成さ\nれたものであり,その作成目的に従い,本件コメントは,各頁に表示された本件シス\nテムの画面の内容を説明し,同画面に関連する本件システムの機能を説明し,又は同\n画面に関連する本件システムの操作といった客観的事実を説明することを目的とし て作成されており,その性質により,機能や操作方法を分かりやすく,一般的に用い\nられるありふれた表現で示すことが求められることから,表\現の選択の幅は狭いもの である。そして,本件コメントでは,本件システムの機能等を説明するためにコンピ\nュータに関する用語が選択されているものの,当該説明において他の表現を用いるこ\nとは想定し難く,また,その他の表現も操作等を説明するものとして特徴的な言い回\nしが存するともいえない。 そうすると,本件コメントに原告の個性が表現されているとはいえないのであって,\n本件マニュアルに著作物性があるということはできない。これに反する原告の主張は 採用することができない。
2019.01.22
平成28(ワ)25956等 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月27日 東京地方裁判所(46部)
以上によれば,式(1)には上限値は定められておらず,下限値である2 30以上の数値の全てにわたり式(1)を満たすことになるにもかかわらず, 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるH c×(1+0.5×SFD)の範囲は,230.1〜245.8(又は24 7.5)に限られることになる。そして,本件明細書にはこの範囲よりも大 きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができること に関する記載はない。 これらによれば,式(1)には,Hc×(1+0.5×SFD)の値の上 限値がないところ,実施例で示されているのは前記の範囲であって,その値 が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた,式(1)の 関係が満たされることとなる場合において,当業者が,前記の課題を解決で きると認識できたとはいえないとするのが相当である。
エ 更に,本件発明においては,Hcの上限値やSFDの下限値は定められて いないから,ΔH,ひいてはSFDの値を大きくせず,Hcの値を例えば2 30以上の数値にすると,SFDの値が実施例を大きく下回る場合も式(1) の関係を満たすこととなる。しかし,このように実施例を大きく下回るSF Dの値の場合に当業者が前記課題を解決できると認識できるとはいえない。 原告は,文献(乙9),実施例2及び実施例4の記載に接することで,SFD が実施例の数値を大きく下回るなどの場合でも,式(1)によって課題を解 決できると認識することできると主張するが,式(1)の技術的意義,実施 例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり,採用することがで きない。
オ したがって,当業者は,本件明細書の記載から,式(1)によって記録電 流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず,ま た,本件出願当時の技術常識から,上記課題を解決できると認識できるとも いえない。 以上によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載が,本件明細書の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである とはいえず,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照 らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえな いから,本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。
3 本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について(争点 )
原告は,本件訂正によって,いわゆるサポート要件違反が解消したと主張す るので,以下,この点について検討する。
訂正事項1−1は,保持力Hcを210以上,221以下とするものである (構成要件F2)。
前記2 アのとおり,式(1)について,磁気記録媒体の技術分野で広く 知られている式であることを認めるに足りる証拠はなく,本件明細書におい て,式(1)の意義に関する記載はない。また,同イのとおり,原告の主張 は,式(1)の意義に関して,オーバーカレント状態において,磁性粒子自 体のHcのばらつきが大きくなることによって,そのばらつきが大きくない 場合に比べ,再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることをい うものといえるが,本件明細書にそのことを述べる記載がなく,また,本件 出願当時,当業者にとってそのことが技術常識であったことを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件明細書をみると,本件明細書の発明の詳細な説明には,前記2 アの とおり,実施例1ないし4及び比較例1及び2の数値が記載されている。 そして,Hcが210以上という本件訂正事項1−1によって,実施例2 は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって,実施例は,実施例3及び 実施例4のみであり,また,前記2 のとおり,「最適記録電流」の点から 実施例3が実施例とならないとすると,実施例は,実施例4のみとなる。 そうすると,式(1)には上限値は定められておらず,下限値である23 0以上の数値の全てにわたり式(1)を満たすことになるにもかかわらず, 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるH c×(1+0.5×SFD)の数値(範囲)は,245.8(又は245. 8〜247.5)に限られることになる。そして,本件明細書にはこの数値 (範囲)よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を確保すること ができることに関する記載はない。
これらによれば,式(1)には,Hc×(1+0.5×SFD)の値の上 限値がないところ,実施例で示されているのは前記の数値(範囲)であり, その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた,式 (1)の関係が満たされるといえる場合において,当業者が,前記の課題を 解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。
ウ 更に,本件訂正発明においては,Hcの上限値は定められたが,SFDの 下限値は定められていない。そして,例えば,Hcが上限値である221の 場合,SFDが0.082であっても,式(1)を満たすこととなるが,実 施例4のSFDは0.341であり,実施例よりも大幅に小さいSFDの値 の場合に,当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。被告は,上記のような場合でも,文献(乙9),実施例2及び実施例4の記載に 接することで,式(1)によって課題を解決できると認識することできると 主張するが,式(1)の技術的意義,実施例が示す範囲や本件明細書の記載 は前記のとおりであり,採用することができない。 以上によれば,当業者は,本件訂正後も,本件明細書の記載から,式(1) によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できる とはいえず,また,本件出願当時の技術常識から,上記課題を解決できると認 識できるともいえない。
そうすると,本件特許には特許法123条1項4号の事由があり(前記2), 本件訂正によってもその事由が解消したとは認められないから,本件訂正請求 が訂正要件を満たすか(争点 )など,その他の争点を検討するまでもな く,原告は,特許法104条の3第1項により,本件特許権を行使することが できない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.01.22
平成30(ワ)13381 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年12月26日 東京地方裁判所(29部)
これを本件についてみるに,前記認定のとおり,原告商品は,携帯用ディス ポーザブル低圧持続吸引器であるSBバックのうちの排液ボトル及び吸引ボトルで 構成されるものであるところ,携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器には様々な形\n態のものが存在する中で,SBバックのように主たる構成として2つの透明のボトル\nから構成される形態,取り分け,直方体の排液ボトル,丸みを帯びた略立方体の吸引\nボトル本体及びその上部に取り付けられた球体のゴム球体という形状の異なる3つ のパーツをまとまりよく一体化して構成されている形態は,平成30年1月頃に被告\n商品が販売されるまでは,SBバック以外の製品にはみられない形態であったのであ り,吸引方法が異なる蛇腹(バネ)吸引や握り型吸引に属する吸引器はもととより,同 じくバルーン吸引に分類される吸引器であり,株式会社メディコンが製造し,販売す る「デイボール リリアバック」の形態もSBバックの形態とは,大きく異なってい る(甲11,25,乙4)。そうすると,原告商品の形態は,1)特別顕著性,すなわち,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していると認められる。 これに対し,被告は,原告商品は,医療従事者を需要者とする医療機器であり,医 療従事者が,患者の生命及び身体の安全に関わる医療機器を選定するに当たって重視 するのは,当該商品の機能であってその形態ではないことなどから,原告商品の形態\nは,自他識別機能及び出所表\示機能をおよそ備えていない旨を主張する。しかしなが\nら,医療機器であっても,その使用に当たっては商品の形態が使用感や使いやすさ, 利便性等に大きな影響を与えるのであるから,医療機関が商品を選定する際に考慮要 素になると考えられるのであり,このことは,被告が行ったアンケート結果において も,利便性(乙6の1),使いやすさ(乙6の2,3,9,乙7の2),使い勝手(乙 6の5,7,9,乙8の3),大きさ・寸法(乙6の2,6)等が挙げられていること から裏付けられている。したがって,原告商品の形態が自他識別機能及び出所表\示機 能をおよそ備えていないということはできない。\nまた,被告は,原告商品の形態は,携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器として の機能及び効用を発揮するために選択されたものであり,同種製品でも採用されてい\nる一般的なありふれた形態を組み合わせたものにすぎない旨を主張する。しかしなが ら,原告商品を構成する直方体の排液ボトルの形状,略立方体の吸引ボトルの本体及\nびその上部に取り付けられた球体のゴム球それぞれの形態が個々の形態としてあり ふれた形状であったとしても,原告商品の形態は,これらを組み合わせて一体化した ものであり,しかも,他の同種製品にはみられない形態であったのであるから,原告 商品の形態がありふれた形態ということはできない。
イ そして,前記認定のとおり,原告は,昭和59年から,SBバックを,その形 態を変更することなく製造し,販売しているところ,SBバックの形態は,平成30 年1月頃に被告商品が販売されるまでは,SBバック以外の製品にはみられない形態 であったこと,平成18年から平成28年までのポータブル低圧持続吸引器国内市場 におけるSBバックの販売数量は同市場において30%程度を占め,業界首位であっ たこと,原告は,SBバックの販売開始以来,平成14年頃から発行している医療機 器の総合カタログを定期的に更新し,医療機関に頒布してきたほか,少なくとも平成 10年から医療機器の展示会等にSBバックを展示するなど,医療機関に対する説明 会や個別の説明を常時実施してきたこと,SBバックの形態が多数の医療従事者向け 書籍等に掲載されてきたことなどからすれば,原告商品の形態は,2)その形態が原告 によって長期間独占的に使用されてきたことにより,少なくとも被告商品が販売され た平成30年1月頃には,原告の出所を示すものとして需要者である医療従事者に広 く認識されるに至ったということができる。 これに対し,被告は,原告商品の形態が掲載されている書籍等において,原告商品 の形態のみならず,常に原告の会社名や商品名も併せて記載されていることなどから, 原告商品の形態自体がその形態のみで出所表示機能\を発揮しているのではない旨主 張するが,上記説示のとおり,原告商品の形態は,その形態が原告によって長期間独 占的に使用されてきたことにより周知性を獲得したと認められるのであるから,個別 の表示の態様が原告商品の形態と原告の会社名や商品名とが併せて表\示されていた としても,上記認定を左右しないというべきである。
ウ さらに,前記認定のとおり,原告商品の形態は,携帯用ディスポーザブル低圧 持続吸引器に様々な形態のものが存在し,排液ボトルや吸引ボトルの形状にも様々な 選択肢がある中で,これらを組み合わせて一体的に構成されたものであるから,商品\nの形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地の\nない不可避的な構成に由来する場合には該当しないと認められる。\nこれに対し,被告は,原告商品の形態は,単に機能を発揮する観点から選択された\nにすぎず,その機能及び効用を発揮するために必然的,不可避的に採用せざるを得な\nい商品形態である旨を主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,原告商品は,創腔からの滲出液の集液量増加に 伴う吸引圧の変動が小さく,創腔に常に適切な陰圧を負荷できること,採取された滲 出液が逆流する陽圧発生の危険がなく取扱い容易であること,集液ゾーンと陰圧保持 ゾーンが分離され,集液貯留が全て剛性容器で行われるため,使用中は常に集液量測 定を精度良く簡便に行うことができるとともに,途中の吸引再セット時の排液操作が 必要なく,集液を追加できることなどの機能を有しているところ,このような機能\を 有するための構成としては,ボトルの数,形状及び透明性,目盛の形状,排液口の位\n置,大きさ,形状及び色彩,集液ポートの位置及び形状,排液ボトルと吸引ボトルの 連結態様,ゴム球の位置,大きさ,形状及び排気弁の有無等の様々な選択肢があるの であるから,被告の主張は採用できない。
(3) 以上のとおり,原告商品の形態は,少なくとも被告商品が販売された平成30 年1月頃には,不競法2条1項1号にいう商品等表示として需要者の間に広く認識さ\nれたものとなっていたと認められる。
3 争点2(原告商品の形態と被告商品の形態とは類似するか)について
(1) 不競法2条1項1号の「類似」に該当するか否かは,取引の実情の下において, 需要者又は取引者が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両 者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべきである。
(2)これを本件についてみるに,前記認定のとおり,原告商品の形態と被告商品の 形態とは,外観において,主たる構成として排液ボトル及び吸引ボトルの2つのボト\nルを有している点で共通するほか,排液ボトル及び吸引ボトル自体の形状も多数の点 が共通し,その寸法もほぼ共通する。他方,排液ボトルについては,目盛や文字の色 等が相違し,吸引ボトルについては,「吸引ボトル」の文字や,社名,商品名等の文字 の色,ゴム球の色等が相違し,社名や商品名の称呼も相違する。 以上の共通点及び相違点を総合すると,外観上の共通点が極めて多数に上ることに 比して,相違点はいずれも細部の相違であり,色彩の相違も同系色での相違にすぎず, 社名や商品名の表示の相違も全体的な構\成からは一部分にとどまることからすれば 上記共通点は,上記相違点よりも需要者に強い印象を与えるものであると評価するこ とができる。したがって,原告商品の形態と被告商品の形態については,称呼が相違 するものではあるが,需要者が外観に基づく印象として,両者を全体的に類似のもの と受け取るおそれがあると認められ,不競法2条1項1号の「類似」に該当すると認 められる。
4 争点3(被告商品の製造販売は,原告商品と混同を生じさせるか)について
原告は,被告商品の形態は,原告の商品等表示である原告商品の形態に酷似するも\nのであるから,被告商品に接した需要者において,被告商品を原告商品又は原告のシ リーズ商品,原告のグループ会社の商品又は原告のライセンス商品であるとの誤認混 同が生じるおそれが高い旨を主張する。 不競法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」とは,商品又は役務について出所 が同一であると誤認させ,あるいはその営業につき主体が同一であると誤認させる場 合に限られず,他人の周知の商品等表示と同一又は類似のものを使用する者と当該他\n人との間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係等の緊密な営業上の関係又は同 一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為も含\nまれると解される。 そこで,これを本件についてみるに,前記認定によれば,原告商品及び被告商品の 取引態様については,専門家である医療従事者が,医療機器の製造販売業者や販売業 者の担当者から,当該医療機器の特色,機能,使用方法等に関する説明を受けて,当\n該医療機器の購入を決め,医療機器専門の販売業者に対して当該医療機器を発注する というプロセスをたどって取引されているのであり,しかも,多くの医療機関におい ては,医療機器の使用について,医療機関が医療機器を採用するにあたっては,同種 の医療機器については,一種類のみを採用するという原則的な取扱いであるいわゆる 一増一減のルールが採用されているというのである。そして,原告商品と被告商品に は商品自体には商品名及び会社名が記載され,それぞれ別々のパンフレット(甲1, 20)が作成されて別々に販売される上,需要者である医療従事者も医療機器に関す る専門知識を有する者なのであるから,被告商品の販売行為によって需要者である医 療従事者において原告商品と被告商品の出所が同一であると誤認するおそれがある とは認められない。また,原告及び被告は,医療機器の分野において,相当程度のシ ェアを有する競合会社であり,ポータブル低圧持続吸引器国内市場における原告のシ ェアは約30ないし40%,被告のシェアは約5ないし15%である。上記の取引形 態等からすると,需要者である医療従事者において原告と被告が競合関係にあること を十分に認識している状況であり,原告商品の形態と被告商品の形態が類似している\nことのみから,原告と被告との間に親会社,子会社の関係や系列関係等の緊密な営業 上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信\nするおそれがあるとは認められない。そうすると,被告による被告商品の製造販売行 為が,不競法2条1項1号にいう「混同を生じさせる行為」に当たると認めることは できず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2019.01.12
平成29(ワ)22543 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年12月27日 東京地方裁判所
証拠(甲54,55)及び弁論の全趣旨によれば,原告が入手した中 国国内で製造された原告標章と同一又は類似した形状を有する本件模倣 品の中国国内の販売店の販売価格は約6668円(389.5人民元× 17.12円(平成28年4月25日の人民元の公表仲値))であり,そ\nの日本への輸送手数料が約3766円(220人民元×17.12円) であったと認められる。被告は,被告商品を中国から輸入,販売していること(前提事実 )から,侵害品の販売のために直接要した経費として,少なくとも,被告 商品の仕入れの際の購入費用や輸送手数料があると認められる。そして, 本件模倣品の販売価格や輸送手数料が上記の額であったこと,被告は被 告商品のことを「今までで最も精巧なリプロダクト」と宣伝しており(甲 2の3〔4枚目〕),被告商品は,一定の品質を確保し,同種の商品より も製造コストが高い商品であることがうかがわれないわけではないこと, 他方,本件模倣品の前記価格は販売店における販売価格であり,同販売 店の仕入れ価格はそれよりも低額であると推認されること,その他の諸 事情を考慮し,被告商品について,売上額から控除すべき上記経費の合 計は1台当たり1万2000円を超えることはないと認める。そうする と,被告が被告商品を販売することによって得た利益額を算定するに当 たり控除すべき経費は538万8000円(1万2000円×449個) となり,前記アの売上額の合計930万0586円から538万800 0円を控除した391万2586円が原告の損害額であると推定される。
(イ)これに対し,被告は,被告の平成28年7月1日から平成29年6月 30日までの期間における被告全体の売上高が1億8365万2099 円であること,売上原価が1億3902万6337円であること,人件 費その他の管理費が合計4459万3678円(人件費497万703 8円,荷造運賃763万3167円,インターネット経費2486万7 197円,広告宣伝費295万7335円,その他経費415万894 1円)であり,それを控除した営業利益が3万2084円であることが 記載された公認会計士作成の決算状況説明書(乙15)を提出した上で, 被告が被告商品によって得た利益は,売上高全体の被告商品の売上高の 比率(約5%)に照らし,1403円であると主張し,他に,被告製品 の利益や経費に関する具体的な金額についての証拠を提出しない。 しかし,商標法38条2項に基づく損害額の算定において侵害者の利 益を算定するに当たり,侵害品の売上額から控除すべき経費は侵害品の 販売のために直接要した変動費であると解されるところ,上記決算状況 説明書によっては,被告商品の上記変動費を認定することはできない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 立体商標
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.01. 7
平成30(行ケ)10103 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年12月20日 知的財産高等裁判所(3部)
本件商標は,前記第2の1(1)のとおり,ゴシック体風の「ブロマガ」 の片仮名とセンチュリー体風の「BlogMaga」の欧文字を上下2段 に配置した商標であり,上段と下段の間は文字の高さの半分程度の間隔が あり,上段と下段のフォントの大きさは概ね同じで,上段より下段の方が やや横幅が大きく構成されている。上段の「ブロマガ」部分からは,「ブロマガ」という称呼が生じる。また,下段の「BlogMaga」部分は,「Maga」が大文字の「M」で始まること,「dog」,「frog」のような「og」の語尾を持つ\n一般的な英語で「g」の発音を省略することはないこと,「Blog」は ウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起させることから, 全体として「ブログマガ」という称呼が生じるものと認められる。そうす ると,本件商標からは,「ブロマガブログマガ」という称呼が生じるとい える。 また,「ブロマガ」及び「BlogMaga」はいずれも造語であり, 特段の観念を生じるとは認め難く,本件商標からは特段の観念を生じない。
イ 他方,本件使用商標は「ブロマガ」の文字のみからなるものであるから, 本件商標とは使用する文字の一部が共通するものの,外観,観念及び称呼 のいずれについても同一とはいえない。
ウ 以上に照らせば,本件使用商標について,本件商標の「書体のみに変更 を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の 表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標,外\n観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標(本件商標) と社会通念上同一と認められる商標」ということはできない。 エ また,原告は,原告のウェブサイトのURL中の「blomaga」の 文字の使用について,本件商標と「社会通念上同一の商標」の「使用」に 当たると主張するが,仮にURLにおける「blomaga」の使用が商 標法50条1項所定の「商標」の「使用」に当たるとしても,「blom aga」は本件商標と外観,観念及び称呼のいずれにおいても同一とはい えないことは本件使用商標と同様であるから,本件商標と「blomag a」の文字からなる「商標」が「社会通念上同一」であるとは認められな い。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,欧文字の称呼については,特定の発音に固執せず,ある程度幅 のある発音を念頭に,日本における一般的な認識や連想等を含めて,総合 的に判断すべきであるとして,「HongKong」,「Ping-Pon g」,「Sign」,「Foreign」のように「g」を発音しない例 がしばしば存在する一方,「KING KONG」では「G」を発音する という風に日本で欧文字を読む際に「g」を発音する場合と発音しない場 合があること,2語からなる外来語や固有名詞等の略語の生成において各 語の冒頭の二拍ずつ取るのが基本であることから,本件商標の下段の「B logMaga」部分は「ブロマガ」の称呼を生じると主張する。 しかし,原告が指摘する「g」を発音しない例は「ng」,「gn」と いう語尾を有するから本件商標の欧文字部分には妥当しないし,造語の欧 文字である「BlogMaga」から原告主張の略語が生じるとも認めら れない。 さらに,原告は,社会一般では「BlogMaga」の表記を「ブロマ\nガ」と記載していることが多いと主張するが,原告がその立証のために提 出した証拠(甲36〜38)から,社会一般において「BlogMaga」 を「ブロマガ」と表記していることは認められない。また,上記(1)アのと おりの本件商標の構成からは「ブロマガ」が「BlogMaga」の表\音 であるとは認め難い。
イ 原告は,「BlogMaga」は,「Weblog」の略語である「B log」と雑誌を意味する「Magazine」の略語である「Maga」 が結合された造語であり,いろいろなブログを配信するサービスという観 念が生じ,「ブログ」と「マガジン」の略語が結合した「ブロマガ」から も,いろいろなブログを配信するサービスという観念が生じるから,「B logMaga」と「ブロマガ」から生じる観念は同一であると主張する。 しかし,本件商標の「ブロマガ」は4文字の造語で,同種同大のフォン トが均等の間隔で配置されていることからすれば,「ブロ」の部分を分離 して観念を想起し得るかは疑問であり,「ブロマガ」からブログとマガジ ンの略語の結合を想起するとはいえない。したがって,「BlogMag a」と「ブロマガ」がブログとマガジンの略語が結合したものとして理解 され,同一の観念を生じさせるとは認められない。
◆判決本文
関連事件です。同一商標権についての別の指定役務についての取消審判の取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2019.01. 4
平成30(ネ)10059 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求控訴事件 特許権 民事訴訟平成30年12月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
2 争点(1)
(被控訴人が控訴人に対し,本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益)について
(1)前提事実(引用に係る原判決第2の1(5))のとおり,被控訴人は,別件米国訴訟において,控訴人補助参加人に対し,控訴人補助参加人が本件各製品を製造販売した行為について,本件米国特許権の侵害を理由として損害賠償請求をしているものである。そして,前提事実(引用に係る原判決第2の1(3)及び(4))のとおり,本件各製品の製造のために用いられた本件各機械装置を製造し,これを控訴人補助参加人に販売したのは控訴人である。また,当審第1回口頭弁論期日において,被控訴人が,被控訴人は控訴人に対し,本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有する旨陳述したことは,当裁判所に顕著である。そうすると,控訴人と被控訴人との間に本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権の存否について争いがあり,控訴人は,被控訴人から,上記損害賠償請求権を行使されるおそれが現に存在するというべきである。したがって,被控訴人が控訴人に対し,本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴えは,即時確定の利益を有する。
(2)被控訴人の主張について
ア 被控訴人は,控訴人による本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を行使しない旨明確にしているから,上記損害賠償請求権の不存在を確認する訴えは,即時確定の利益を欠くと主張する。しかし,被控訴人が,本件訴訟の提起前に,控訴人に対し,控訴人による本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を主張し,又はこれを行使したことはなく,さらに,原審第4回弁論準備手続期日において,被控訴人は控訴人に対し,上記損害賠償請求権を将来にわたって主張及び行使しない旨の一部和解に応じられる旨述べていたとしても,控訴人と被控訴人の間では,上記損害賠償請求権の存否については争いが存在するものである。また,被控訴人は,上記のとおり述べたとしても,これにより上記損害賠償請求権を行使しないことについて法的義務を負うに至ったものではなく,将来にわたって確実に権利行使をしないことを保証するものとはいえない。したがって,前記損害賠償請求権の不存在を確認する訴えについて即時確定の利益を欠くとの被控訴人の前記主張は,採用できない。
イ 被控訴人は,控訴人らが,別件大阪訴訟を提起したから,本件訴訟は確認の利益を欠く旨主張する。しかし,別件大阪訴訟は,控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人補助参加人による本件米国特許権の侵害を理由として別件米国訴訟を提起したことについて,不法行為又は本件実施許諾契約の債務不履行に当たるとして損害賠償金の支払等を求めるものである(乙4,5)。一方,本件訴訟の争点(1)に係る部分は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による本件各特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めるものである。両訴訟の訴訟物が相違するだけではなく,審理の対象となる不法行為ないし債務不履行行為の内容も,全く異なる。よって,控訴人らが原判決後に別件大阪訴訟を提起したからといって,本件訴訟の確認の利益が失われることはなく,被控訴人の上記主張は,採用できない。
(3)以上によれば,被控訴人が控訴人に対し,本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益は,存するというべきである。
・・・
よって,被控訴人が控訴人及び控訴人補助参加人に対し,本件各特許権の侵害を 理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認するとの訴えに は,確認の利益があるから,原判決のうち,この訴えを却下した部分を取り消し, 当該部分につき本件を東京地方裁判所に差し戻すこととし,また,本件控訴のうち その余の部分は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決す る
2019.01. 4
平成29(ネ)10086 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月18日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
無効理由1は,本件無効審判請求と同じく,乙24公報に記載の主引 例と乙25〜31の1公報に記載の副引例ないし周知技術に基づいて進 歩性欠如の主張をしたものであるから,無効理由1は本件無効審判請求 と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。そして,本件 審決は確定したから,被控訴人は無効理由1に基づいて本件特許の特許 無効審判を請求することができない(特許法167条)。 特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は,同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ, その趣旨は,無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると,侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い,審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には,同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは,特段 の事情がない限り,訴訟上の信義則に反するものであり,民事訴訟法2 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 そして,本件において上記特段の事情があることはうかがわれないか ら,被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由1を主 張することは許されない。
イ 被控訴人は,特許法104条の3第1項の適用がないとしても,本件 特許は無効理由1により無効にされるべきものであるから,本件特許権 の行使は衡平の理念に反するし,いわゆるキルビー判決は,特許権を対 世的に無効にする手続から当事者を解放した上で衡平の理念を実現する というものであるから,控訴人が被控訴人に対し,本件特許権を行使す ることは権利の濫用として許されないと主張する。 しかし,被控訴人は,本件訴訟と同一の当事者間において特許権を対 世的に無効にすべく無効理由1に基づく無効審判請求を行い,それに対 する判断としての本件審決が当事者間で確定し,上記アのとおり,無効 理由1に基づいて特許法104条の3第1項による特許無効の抗弁を主 張することが許されないのであるから,本件において,控訴人が被控訴 人に対して本件特許権を行使することが衡平の理念に反するとはいえず, 権利の濫用であると解する余地はない。
(3) 無効理由2について
無効理由2は,無効理由1と主引例が共通であり,本件審決にいう相違 点1A及び相違点2Aについて,「生体に印加する直流電源に太陽電池を 用いること」が周知技術である,あるいは,副引例として適用できること を補充するために,新たな証拠(乙44公報及び乙45公報)を追加した ものといえる。 本件審決は,相違点1B及び相違点2Bに係る構成の容易想到性を否定\nし,相違点1A及び相違点2Aについては判断していないのであるから, 被控訴人が相違点1A及び相違点2Aに関する新たな証拠を追加したとし ても,相違点1B及び相違点2Bに関する判断に影響するものではない。 そうすると,無効理由2は,新たな証拠(乙44公報及び乙45公報)が 追加されたものであるものの,相違点1B及び相違点2Bの容易想到性に 関する被控訴人の主張を排斥した本件審決の判断に対し,その判断を蒸し 返す趣旨のものにほかならず,実質的に「同一の事実及び同一の証拠」に 基づく無効主張であるというべきである。したがって,本件審決が確定し た以上,被控訴人は無効理由2に基づく特許無効審判を請求することがで きない。 そうすると,無効理由2についても上記(2)アにおいて説示したところ が妥当するから,被控訴人が本件訴訟において無効理由2に基づき特許無 効の抗弁を主張することは許されないものというべきである。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.01. 4
平成30(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年12月18日 知的財産高等裁判所
1 訴えの利益について
(1) 本件審決に係る別紙審決書(写し)の記載及び弁論の全趣旨によれば,本件 審決は,被告及び訴外会社が共同審判請求人となり,原告らを被請求人として請求 された特許無効審判事件に係るものである。また,本件において,原告らは,被告 のみを相手方とし,訴外会社については被告としていないことは,当裁判所に顕著 な事実である。なお,訴外会社との関係では,本件審決の送達日である平成30年 3月29日から30日の出訴期間を既に経過している。 そうすると,本件審決(無効審決)は,訴外会社との関係においては,原告らが 訴外会社に対する審決取消訴訟を提起することのないまま出訴期間を経過したこと により,既に確定したこととなる。その結果,本件特許の特許権は初めから存在し なかったものとみなされるから(特許法125条本文),本件訴えは,訴えの利益 を欠く不適法なものとして却下されるべきである。
(2)原告ら及び被告の主張について
ア これに対し,原告らは,特許無効審判の請求人が複数いたとしても,審決取 消訴訟の提起により対象となる審決の確定は遮断されるから,請求人全てをその被 告とする必要はないなどと主張する。 そこで,共同で特許無効審判が請求され,無効審決がされたのに対し,被請求人 が共同審判請求人の一部の者のみを被告として審決取消訴訟を提起した場合の規律 について検討する。 同一の特許権について特許無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これら の者は,共同して審判を請求することができる(特許法132条1項)。これは, 本来,各請求人は,単独で特許無効審判請求をし得るところ,同一の目的を達成す るためにこのような共同での審判請求を行い得ることとし,審判手続及び判断の統 一を図ったものである。もっとも,この場合の審決を不服として提起される審決取 消訴訟につき固有必要的共同訴訟であるとする規定はなく,審決の合一的確定を図 るとする規定もない。 また,同一特許について複数人が同時期に特許無効審判請求をしようとする場合 の特許無効審判手続の態様としては,1)上記の共同審判請求の場合のほか,2)別個 独立に請求された審判手続が併合された場合(同法154条1項),3)別個独立に 請求された審判手続が併合されないまま進行する場合の3つが考えられる。しかる ところ,まず,上記3)の場合において無効審決がされたときは,その取消訴訟をも って必要的共同訴訟と解する余地がないことに鑑みると,事実及び証拠が同一であ るか異なるかに関わりなく,複数の特許無効審判請求につき,請求不成立審決と無 効審決とがいずれも確定するという事態は,特許法上当然想定されているものとい うことができる。また,別個独立に請求された審判手続がたまたま併合された上記 2)の場合において無効審決がされたときも,上記3)の場合と取扱いを異にすべき合 理的理由はない。そうすると,上記1)の場合に,被請求人である特許権者の共同審 判請求人に対する対応が異なった結果として上記と同様の事態が生じることも,特 許法上想定されないこととはいえない。1)及び2)の場合にされた請求不成立審決に 対し,その請求人の一部のみが提起した審決取消訴訟がなお適法とされる(最高裁 平成7年(行ツ)第105号同12年1月27日第一小法廷判決・民集54巻1号 69頁,最高裁平成8年(行ツ)第185号同12年2月18日第二小法廷判決・ 判例時報1703号159頁参照)のも,このためと解される。 このように,共同審判請求に対する審決につき合一的確定を図ることは,法文上 の根拠がなく,その必然性も認められないことに鑑みると,その請求人の一部のみ を被告として審決取消訴訟を提起した場合に,被告とされなかった請求人との関係 で審決の確定が妨げられることもないと解される。
イ なお,この点について,被告は,本案前の答弁として,複数の審判請求人が いる場合の無効審決に対する審決取消訴訟は固有必要的共同訴訟であり,被告のみ を相手方として提起した原告らの本件訴えは不適法であるなどと主張する。 しかし,前記のとおり,共同審判請求に対する審決につき合一的確定を図ること は法文上の根拠がなく,その必然性も認められないことから,当該審決に対する取 消訴訟をもって固有必要的共同訴訟ということはできない。
ウ そうすると,共同での特許無効審判請求に対し無効審決がされたところ,被 請求人である特許権者が,共同審判請求人の一部のみを被告として当該審決の取消 訴訟を提起したにとどまり,被告とされなかった共同審判請求人との関係で出訴期 間を経過した場合には,同人との関係で当該無効審決が確定し,当該特許権は対世 的に遡って無効となることから,上記審決取消訴訟は,訴えの利益を欠く不適法な ものとして却下されるべきこととなる。
2019.01. 4
平成30(行ケ)1008 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年12月20日 知的財産高等裁判所
本願商標の指定商品は,第9類「電子出版物」及び第16類「雑誌,書 籍」(本願指定商品)を含むところ,近年,「従来は本や雑誌の形で提供 されていた情報を,デジタル化したソフトの形で,あるいはパソ\コン,タ ブレット端末,スマートホン,電子書籍リーダーなどを使ってアクセスで きる形で提供する出版」である電子出版が盛んになり,現に,紙に印刷さ れた商品「印刷物」の一種である「雑誌」や「書籍」の内容(コンテンツ) が,電子化された「電子出版物」として需要者へ広く配信(販売)される など,両者は相互に密接な関連性を有している。 そして,本願指定商品はいずれも,主に書籍や雑誌,電子出版物などの 出版を行う事業所である出版社により制作,販売される商品であり,多岐 にわたる年代層の個人から各種教育機関等の幅広い需要者に対して,書店 又はオンライン書店を通じて販売されている。 イ 引用商標の指定役務中,第35類「印刷物の小売又は卸売の業務におい て行われる顧客に対する便益の提供」(以下,この役務中,小売と関連す る役務を「引用小売役務」という。)は,雑誌や書籍等の印刷物及び印刷 物と密接な関連性を有する電子出版物を取り扱う小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供である。 そして,引用小売役務は,主に書籍や雑誌,電子出版物を小売する書店 により提供される役務であり,多岐にわたる年代層の個人から各種教育機 関等の幅広い需要者に対して,主として書店又はオンライン書店において 提供される。
(3) 本願指定商品と引用小売役務との関連性について
本願指定商品と引用小売役務は,いずれも電子出版物又は印刷物を取り扱 う商品又は役務であるところ,その商品の販売場所及び役務の提供場所が一 致し(書店又はオンライン書店),需要者の範囲も一致(幅広い需要者層) する。 さらに,本願指定商品と引用小売役務は,主に出版社又は書店により製造, 販売又は提供されているとはいえ,同一営業主により製造,販売又は提供さ れている実情があり,いわゆる出版社が自己又はそのグループ会社が運営す るウェブサイト又は店舗において,電子出版物,書籍又は雑誌を販売(小売) している事例に加え,書店として小売事業を展開する事業者が,書籍や雑誌 の制作,出版をする事例も複数挙げることができる(乙8〜20)。
(4) 以上のとおり,本願指定商品と引用小売役務は,その商品の販売場所及び 役務の提供場所,並びに需要者の範囲が一致するため,相互に密接な関連性 を有する。さらに,これらは同一の営業主によって製造,販売又は提供され ている実情がある。このような取引の実情を踏まえると,これら商品及び役 務に同一又は類似の商標を使用するときは,同一営業主の製造,販売又は提 供に係る商品又は役務と誤認混同を生じるおそれがあるというべきである。 したがって,本願指定商品は引用小売役務と類似する。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 役務
>> 類似
>> ピックアップ対象
2018.12.27
平成29(ワ)18184 特許権侵害行為差止請求 特許権 民事訴訟 平成30年12月21日 東京地方裁判所
第5要件に関し,被告は,構成要件Eは本件補正によって追加されたも\nのであるところ,本件拒絶理由通知に対する本件意見書における「本発明 25 は,2組の揺動部材を備える点,および,揺動部材の一方に,他方に係合 する係合部を備える点において,引用文献1に記載された発明…と相違し ています。」との記載によれば,原告は,被告製品のように係合部を別部 材とする構成を特許発明の対象から意識的に除外したと理解することが\nできるから,均等侵害は成立しないと主張する。
しかし,本件意見書には,「引用文献1には,端部が回転可能に連結さ\nれることにより開閉可能に5 設けられた一対のジョーを備えた開創器アセ ンブリが開示されています。」,「このような構成(判決注:本件発明に\n係る構成)によれば,2組の揺動部材を同時に開かせることにより,骨に\n形成した切り込みの拡大作業を容易にし,また,切り込みの切断面に局所 的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができる」,「2つの開創器 アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構\成を導く ことはできません。」「引用発明1には,切り込みの切断面に作用する押 圧力を低減するという課題,および,2つの開創器アセンブリを一体で開 動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません」などの記載が ある。
上記記載によれば,本件意見書の主旨は,特許庁審査官に対し,引用例 1が一対の揺動部材を開示していることを指摘し,それに対し,本件発明 は,開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ,一方の揺動部材を他方の揺\n動部材に係合するための係合部を設けることにより,両揺動部材が同時に 開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきで\nある。そして,同意見書には,係合部の構成,すなわち,係合部を揺動部\n材の一部として構成するか,揺動部材とは別の部材により構\成をするかを 意識又は示唆する記載は存在しない。
そうすると,被告の指摘する「2組の揺動部材を備える点,および,揺 動部材の一方に,他方に係合する係合部を備える」との記載は,上記説明 の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないというべきで\nあり,同記載をもって,同意見書の提出と同時にされた本件補正により構\n成要件Eが追加された際に,原告が,係合部を揺動部材とは別の部材とす る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2018.12.21
平成30(行ケ)10101 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年12月19日 知的財産高等裁判所
カンパニョロの指定商品は、第12類「競技用自転車の部品及び付属品・・・」です。問題の商標は、判決文の最後にあります。原告は、「POTENZA」と同一の標章について,第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品とする防護標章登録を受けていました。カンパニョロの登録に対して、異議申し立てをしましたが、当該指定商品については、類似しないとして登録されていました。\n
イ 本件使用商品の柄の部品(クランク)の中央には,横長の白塗りの平行 四辺形内に黒色のデザイン化された文字で表された「POTENZA」の\n欧文字と,「POTENZA」の欧文字の4文字目の「E」が表された箇\n所の背後に重なるように交差する縦長の白塗りの平行四辺形内に黒色で表\nされた「11」の数字とからなる,別紙記載の本件使用商標(甲14の1, 15,16)が付されている。 しかるところ,「POTENZA」の欧文字部分は,横長の白塗りの平 行四辺形内に横書きで表されているのに対し,「11」の数字部分は,縦\n長の白塗りの平行四辺形内に縦書きで表示されていること,「11」の数\n字部分は,上に重なった「POTENZA」の欧文字部分を表する横長の\n平行四辺形によって中央で上下に分断され,数字の一部が隠されているの に対し,「POTENZA」の欧文字部分は,分断された「11」の数字 部分の前面に表されていることからすると,「POTENZA」の欧文字\n部分は,他の構成要素と分離して観察することが取引上不自然と思われる\nほど不可分的に結合しているとはいえない。 そして,「POTENZA」の欧文字部分は,「11」の数字部分の前 面の目につきやすい位置にまとまりよく配置されており,本件使用商標全 体から「ポテンザ」あるいは「ポテンツァ」の称呼が自然に生じることか らすると,「POTENZA」の欧文字部分は,その部分のみから自他商 品識別標識としての機能を発揮しているものと認められる。\n一方で,「11」の数字部分は,上記のとおり,中央で上下に分断され, 数字の一部が隠されており,注視しなければ,数字の「11」と判読でき ないことに照らすと,「11」の数字部分の自他商品識別標識としての機 能は,「POTENZA」の欧文字部分よりも,明らかに低いものと認め\nられる。また,「POTENZA」の欧文字部分が表されている横長の白\n塗りの平行四辺形は,ありふれた形状であって,黒と白のコントラストに より,「POTENZA」の欧文字部分を構成する黒色の7文字を目立つ\nように表示するための背景図形であると認識されるから,それ自体に自他\n商品識別標識としての機能があるものとはいえない。\nそして,本件使用商標の「POTENZA」の欧文字部分と本件商標と を対比すると,「POTENZA」の欧文字部分は,標準文字の本件商標 と字体の違いがあるが,構成する文字は同一であり,その字体の違いも特\nに目立ったものではないこと,両者の称呼は同一であることからすると, 本件使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標であるものと認められ る。
(2) これに対し原告は,1)本件使用商標は,2種の略平行四辺形を前後に重ね て,それぞれの中に「POTENZA」と「11」を配置した,統一感のあ るスタイリッシュなロゴデザインであること,本件使用商標の「11」を含 む部分は,被告の自転車用ギアクランクにおいて11速を暗示させる識別標 識として機能していること,「POTENZA」の部分は,特段特徴的な態\n様で表されているとはいえず,他に比して目立っているような事情もないこ\nとからすると,本件使用商標は,「POTENZA」,「11」,略平行四 辺形の図形等の各構成要素が一体として結合した態様によって識別性が発揮\nされており,本件使用商標から「POTENZA」の部分だけを分離抽出す ることはできない,2)本件使用商品に付された本件使用商標の隣には,「P OTENZA」の部分と同じデザインで,横長の白塗りの「CAMPAGN OLO」の欧文字が表された平行四辺形が配されており,これに接した需要\n者,取引者は,本件使用商標と「CAMPAGNOLO」の欧文字が表され\nた平行四辺形の態様を含めた全体を使用商標と認識することもあるとして, 本件使用商標は,「POTENZA」の標準文字からなる本件商標とは明ら かに異なり,本件商標と社会通念上同一とはいえない旨主張する。 しかしながら,上記1)の点については,前記(1)イ認定のとおり,本件使用 商標の「POTENZA」の欧文字部分は,他の構成要素と分離して観察す\nることが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえず, 「POTENZA」の欧文字部分のみから自他商品識別標識としての機能を\n発揮しているものと認められる。また,原告が述べるように「11」の数字 が,被告の自転車用ギアクランクにおいて11速を暗示させるものであった としても,前記(1)イ認定のとおり,「11」の数字部分は,中央で上下に分 断され,数字の一部が隠されており,注視しなければ,数字の「11」と判 読できないことに照らすと,「11」の数字部分が11速を暗示させる識別 標識として機能しているものと直ちにはいえない。\n
次に,上記2)の点については,本件使用商品の柄の部品(クランク)には, 「POTENZA」の欧文字が表された平行四辺形の右隣に「CAMPAG\nNOLO」の欧文字が表された平行四辺形が付されているが(甲14の1,\n15,16),二つの平行四辺形の間には,スペースがあり,それぞれの平 行四辺形内の「POTENZA」の欧文字部分と「CAMPAGNOLO」 の欧文字部分とは,明瞭に区別される態様で示されている。加えて,前記1 の認定事実によれば,本件商標の指定商品の需要者である自転車競技や競技 用自転車に関心のある者の間では,被告は,競技用自転車の部品メーカーと して広く知られていたものと認められることに照らすと,本件使用商品に接 した需要者は,「CAMPAGNOLO」の欧文字は,被告の名称を外国語 表記したものとして,それ自体を独立の商標として認識するものと認められ\nるから,本件使用商標と「CAMPAGNOLO」の欧文字が表された平行\n四辺形の態様を含めた全体がひとまとまりの商標として認識されるというこ とはできない。
・・・・
3 本件使用商品の本件商標の指定商品該当性について
(1) 前記1の認定事実によれば,本件使用商品は,競技用自転車の部品メーカ ーである被告が製造,販売する自転車用ギアクランク(クランクセット)で あること,本件使用商品について,「新ラインナップに加わったポテンツァ 11は,スーパーレコードに採用されているエンブレイステクノロジーをは じめとした,トップグレードの性能とデザインを継承した機械式アルミグル\nープセット」,「ハードな変速ラインにも対応するレーシングパーツ」など と雑誌(甲15)に紹介されていることが認められる。 上記認定事実によれば,本件使用商品は,自転車競技に使用される自転車 のギアクランクとして用いることができるものと認められる。 そして,本件商標の指定商品「競技用自転車の部品及び付属品(自転車の フレーム・タイヤ・チューブ・車輪・リム・スポークを除く。)」にいう「競 技用自転車」の用語について,「競技」の具体的なレベルを特に限定する記 載はないこと,自転車競技は,プロのロードレーサーなどが参加する世界的 な競技のほかに,趣味として競技を行っている者を含め,様々なレベルの者 が参加できる競技が行われていることは一般に知られていることに照らすと, 自転車競技に使用される自転車に用いることができる部品であれば,本件商 標の指定商品にいう「競技用自転車の部品」に含まれるものと認められる。 そうすると,本件使用商品は,本件商標の指定商品に該当するものと認め られる。
(2) これに対し原告は,1)原告は,原告の著名な登録商標である「POTEN ZA」と同一の標章について,第12類「二輪自動車・自転車並びにそれら の部品及び附属品」を指定商品とする防護標章登録を受けていること,特許 庁は,別件異議申立事件について,「競技用自転車は,競技用としてその用\n途が限られ,かつ,専門性の高い商品」であると認定した上で,本件商標の 商標登録時の指定商品の一部を取り消す旨の別件異議決定をしたことなどの 事情を勘案すると,本件商標の指定商品は,競技専用又はそれに近い商品を 意図するものといえるから,「競技用としてその用途が限られ,かつ,専門 性の高い商品」と理解すべきである,2)被告の最上位機種の「SUPERR ECORD」と本件使用商品とでは,商品の性能が格段に異なり,その用途\n及び需要者の範囲も異なる上,本件使用商品の需要者は一般の自転車愛好家 であることからすると,本件使用商品は,「競技用としてその用途が限られ, かつ,専門性の高い商品」とはいえないとして,本件使用商品は,本件商標 の指定商品に該当しない旨主張する。 しかしながら,上記1)の点については,別件異議決定(甲30)の理由中 に,「被請求人の主張及び職権による調査によれば,競技用自転車は,競技 用としてその用途が限られ,かつ,専門性の高い商品であることから,一般 用自転車に比して高額であり,需要者の範囲も限られ,かつ,販売場所も専 門店やウェブサイトにおける注文販売などが一般的であることが認められる から,需要者が,自己の自転車に装着する商品を申立人又はブリヂストンサ\nイクルの商品であると誤認混同することは考えがたいというのが相当であ る。」との記載部分(6頁)があるが,この記載部分は,一般用自転車と対 比する意味で,「競技用自転車は,競技用としてその用途が限られ,かつ, 専門性の高い商品」であることを示したものにすぎず,自転車競技の具体的 なレベルや商品の具体的な性能についてまで述べたものではないから,本件\n商標の指定商品にいう「競技用自転車」の用語を特定のレベルの競技に限定 する根拠とはならない。また,原告がその登録商標である「POTENZA」 と同一の標章について上記防護標章登録を受けたのは平成24年4月27日 (甲23)であって,別件異議決定日(平成23年10月3日)よりも後で あるから,原告が防護標章登録を受けたことは,別件異議決定の認定及び判 断に影響を及ぼしたものとは認められない。
次に,上記2)の点については,本件使用商品が,被告の最上位機種の「S UPERRECORD」ではなく,ミドルクラスの機種であるからといって, 本件商標の指定商品にいう「競技用自転車の部品」に該当しないということ はできない。
2018.12.21
平成30(行ケ)10067 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年12月10日 知的財産高等裁判所
(4) 混同の有無
ア 後掲証拠によると,以下の事実が認められる。
(ア) 株式会社高石洋服店のウェブサイトでは,「非常に残念なことですが,多くの方がデパートの主力ブランドのpolo ralph laurenの偽物だと認識しているようです。ブランド名,ロゴマークは似ておりますが,実際は全く別のライセンスをキッチリ取得して生産されたブランドになります。」との記載とともに,原告製の衣服の写真を掲載し,同衣服の広告をしている(乙69の1)。
・・・
「Rakutenラクマ」のウェブサイトの「ポロベビー」という題 名の出品ページに,「ブランド」として「POLO RALPH LAUREN」と 記載された商品が出品され,同商品の写真には,原告使用商標と類似した商標が付 されている(乙74の1)。
イ 前記アの事実によると,原告製の衣服をラルフ社製の衣服と誤認して, その中古品をウェブサイトに出品している事例が少なからずあり,また,原告製の 衣服をラルフ社製の衣服と誤認して購入したり,原告製の衣服をラルフ社製の衣服 と誤認してウェブサイトで紹介したりする事例もあることが認められる。 さらに,原告製の衣服を販売している会社が,その広告において,わざわざ,多 くの人は,原告製の衣服はラルフ社製の偽物であると認識しているようであるが, 実際は,ラルフ社製の偽物ではなく,別のライセンスを取得している旨説明してい る。 以上の事実からすると,多くの者が,原告製の商品をラルフ社製の商品と誤解し て購入等しているものと推認される。 したがって,原告使用商標又は,それに似た商標を付している商品とラルフ社製 の商品との間に,現実に出所の混同が生じていることは明らかであるから,本願商 標についても出所の混同が生じるものと認められる。
ウ 原告の主張について (ア) 原告は,前記アで認定したメルカリへの出品について,買い手を意図 的に誤認させる悪意の出品である旨の主張をしているが,原告の主張は,前記アで 認定した各出品者が詐欺行為をしたことについての具体的な裏付けを伴うものでは\nなく,憶測にすぎないことから,採用できない。また,原告は,メルカリにおいて は,ブランドタグの選択肢に「ラルフローレン」しかない旨の主張をするが,そう であるとしても,前記イ記載の誤認混同が生じていることの理由とは認め難い。
(イ) 原告は,ヤフオクにおいては,原告製の商品とラルフ社製の商品との 間に混同が生じた事例はなく,また,業者と一般消費者間の取引においては,原告 製の商品とラルフ社製の商品との間に混同は生じていないと主張し,その証拠とし て,甲47,甲53の1〜8を提出するが,同証拠から直ちに,原告の上記主張事 実を認めることはできず,前記イの認定を左右するに足りるものではない。
(ウ) 原告は,甲40の1、3から,消費者が,原告製の商品をラルフ社製 の商品と区別して購入する事実がある旨主張する。 しかし,甲40の1の記事は,写真に掲載した原告製の商品がラルフ社製の商品 ではないことを注意喚起するものであり,甲40の3の記事は,一見したところラ ルフ社製の商品であると思ったが,よく確認すると,原告製の商品であることが分 かったというものであるから,原告製の商品をラルフ社製の商品と誤認する可能性\nが高いことを示すものである。したがって,上記記載は,原告製の商品とラルフ社 製の商品との間に混同が生じやすいことを裏付けるものといえる。
(5)以上からすると,引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低い ことを考慮しても,本願商標をその指定商品に使用した場合,当該商品がラルフ社 の業務に係る商品であると誤信され,出所の混同を生ずるおそれがあることは明ら かである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2018.12.21
平成29(ワ)28884 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月28日 東京地方裁判所
(1)「プロカルシトニン3−116を測定すること」の意義
ア 構成要件Aは「患者の血清中でプロカルシトニン3−116を測定すること\nを含む」というものであるところ,一般に,「測定」に,長さ,重さ,速さといっ た種々の量を器具や装置を用いてはかるという字義があることからすると,「プロ カルシトニン3−116を測定すること」は,プロカルシトニン3−116の濃度 等の量を明らかにすることを意味すると解するのが文言上自然である。 また,前記1(2)認定のとおり,本件発明は,敗血症等の患者の血清中に比較的高 濃度で検出可能なプロカルシトニンがプロカルシトニン1−116ではなく,プロ\nカルシトニン3−116であることが確認されたことを踏まえて新規な敗血症等の 検出方法を提供することを目的とするものであり,このような本件発明の目的に照 らせば,本件発明は,患者の血清中においてプロカルシトニン3−116が比較的 高濃度で検出されるか否かを見ることを可能とすることが求められているというこ\nとができる。 以上から,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定すること」は,プ\nロカルシトニン3−116の濃度等の量を明らかにすることを意味すると解するの が相当である。
イ この点につき,原告は,「プロカルシトニン3−116を測定すること」は, プロカルシトニン3−116を敗血症等の検出に必要な精度で測定ないし検出する ことができれば,プロカルシトニン3−116だけを特異的,選択的に測定するこ とに限られず,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116及びそ の他のプロカルシトニン由来の部分ペプチドとを区別することなく測定することも 含むと主張しており,その意味するところは明確でないが,血清中のプロカルシト ニン3−116を検出しさえすれば足りるものである旨の主張であるとすれば,そ れはプロカルシトニン3−116の存在を明らかにすることで足り,その量を明ら かにすることは必要ではないことをいうものであって,前記アでみた「測定」の文 言の解釈に反するものであり,採用することができない。 また,血清中のプロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116等と を区別することなく測定することがプロカルシトニン3−116を測定することに 該当すると主張するものであると解しても,そのような測定方法では,血清中にプ ロカルシトニン3−116が存在するかも明らかにならず,もとより,血清中のプ ロカルシトニン3−116の量も確認できないから,これを「プロカルシトニン3 −116を測定すること」に該当するというのは文言上困難である。
(2)被告方法
前記第2の2(5)ア認定のとおり,被告装置及び被告キットを使用すると,患者の 検体中において,プロカルシトニン3−116とプロカルシトニン1−116とを 区別することなく,いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することが でき,その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行われていると認められるもの の,本件全証拠によっても,被告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出す る過程で,プロカルシトニン3−116の量が明らかにされているとは認められず, 更にいえば,プロカルシトニン3−116の存在自体も明らかになっているとはい えない。 したがって,被告方法は,構成要件Aの「プロカルシトニン3−116を測定す\nる」を充足するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.12.13
平成30(ワ)3018 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所(46部)
本件発明は,前記1のとおり,「ホルダ」に該当する部材によって回転体を支 持する支持軸を固定するものであるところ,原告は,被告製品のソーラーパネ\nル取付台が支持軸を固定していると主張するのに対し,被告はこれを否定する。 証拠(甲10,14)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,回転体の支 持軸の本体側先端部分にフランジが形成されていること,被告製品の本体内部 のソーラーパネル取付台の支持軸側先端部分には一対の段差及び半円形状の\n凹部が形成され,それらは回転体の支持軸及び支持軸に形成されたフランジの 形状に係合すること,ソーラーパネル取付台の先端部で回転体の支持軸を覆っ\nてソーラーパネル取付台を被告製品本体にネジで固定するとソ\ーラーパネル 取付台に支持軸のフランジが引っかかり,支持軸の先端部分がソーラーパネル\n取付台の段差及び半円形状の凹部に組み付けられること,その組付け後は回転 体を支持する支持軸に接着剤の塗布などはなかった被告製品においても支持 軸が本体から直ちには外れることがなかったことが認められる。これらによれ ば,被告製品のソーラーパネル取付台の先端部分の段差及び半円形状の凹部は,\n回転体の支持軸を固定するための構成であり,同部分が回転体の支持軸を覆い,\n支持軸を押し付けることによって支持軸を固定し,支持軸が抜けないようにし ていると認められる。
そうすると,被告製品のソーラーパネル取付台は構\成要件B及び構成要件C\nの「ホルダ」に該当し,被告製品は構成要件Bの「前記各支持軸の基端側をホ\nルダの両端部で押さえる」及び構成要件Cの「ホルダ」を充足するといえる。\nこれに対し,被告は,ソーラーパネル取付台の半円形状の凹部はリード線の\nハンダ付け部分をカバーするためのものであり,ソーラーパネル取付台をかぶ\nせただけでは支持軸は固定されず,支持軸を接着剤で被告製品本体内部に接着 固定しなければ,支持軸は簡単に抜けることからもソーラーパネル取付台は支\n持軸を固定する機能を有していないなどと主張する。\nしかしながら,ソーラーパネル取付台の段差及び半円形状の凹部の形状は,\n回転体の支持軸に係合する形状に形成されていて,リード線のハンダ付け部分 をカバーするために形成されていると認めるに足りる証拠はない。また,回転 体の支持軸を固定するために接着剤が塗布されている被告製品があるとして も,その塗布がされたことをもってソーラーパネル取付台が回転体の支持軸を\n固定する機能を有していることが直ちに否定されるものではなく,前記のとお\nりのソーラーパネル取付台の先端部の構\造,接着剤の塗布がなかった場合の回 転体の支持軸の被告製品本体からの着脱の状況等からすれば,ソーラーパネル\n取付台は回転体の支持軸を固定する機能を有しているということができ,被告\nの主張は採用することができない。
3 争点 −ア(乙11文献に基づく新規性欠如)
争点を検討するに当たり,まず,本件発明の「前記各支持軸の基端側をホル ダの両端部で押さえる」(構成要件B)の意義について検討する。\nア 「押さえる」とは,物に力を加えて,動かないように固定するという意味 を一般的に有する(乙3の1ないし3)。 そして,本件明細書には,前記1 アないしオの記載のほか,「発明を実施 するための形態」として,「図4及び図5に示すように,前記ベース体13の 両支持筒18には,金属製の一対の支持軸20がシールリング21を介して, 交差軸線L1,L2上に位置するとともに外側に突出した状態で嵌合支持さ れている。このシールリング21は,支持軸20の周りからハンドル12の 内部へ向かう水の侵入を防止している。各支持軸20の基端には,大径状の 抜け止め頭部20aが形成されている。図4及び図9に示すように,両支持 軸20の基端部間においてベース体13上には,ホルダ22が配置されてい る。このホルダ22の両端部には,各支持軸20の基端側を押さえるための ほぼ半円筒状の押さえ部22aが形成されている。ホルダ22の中間部には, 円筒状のネジ止め部22bが形成されている。そして,ホルダ22の両端の 押さえ部22aにより両支持軸20の基端が押さえられた状態で,ホルダ2 2の中間のネジ止め部22bがネジ23によりベース体13に固定される ことによって,各支持軸20がベース体13の支持筒18に対する嵌合支持 状態に抜け止め固定されている。すなわち,支持軸20の組み付け時には, ハンドル12のベース体13に形成された一対の支持筒18に外側(図4の 左側)から支持軸20をそれぞれ嵌挿して,交差軸線L1,L2上に位置す るように配置する。次に,図5及び図9に示すように,両支持軸20の基端 間におけるベース体13上にホルダ22を配置し,そのホルダ22の両端の 押さえ部22aにより両支持軸20の基端側を押さえる。これにより,図4 及び図9に示すように,各支持軸20の基端の抜け止め頭部20aが押さえ 部22aの端縁に係合される。この状態で,ホルダ22の中間のネジ止め部 22bをネジ23によりベース体13に固定すると,一対の支持軸20がベ ース体13に対して同時に抜け止め固定される。」(段落【0013】),「従っ て,この実施形態によれば,以下のような効果を得ることができる。(1)こ の美容器においては,ハンドル12の先端部に交差軸線L1,L2上に位置 する一対の支持軸20が設けられている。各支持軸20の先端側には回転体 27が回転可能に支持され,それらの回転体27により身体に対して美容的\n作用が付与されるようになっている。前記ハンドル12における両支持軸2 0の基端部間の位置には,ホルダ22がその中間部において固定されている。 そして,このホルダ22の両端の押さえ部22aにより,各支持軸20の基 端側がハンドル12に対して押し付け保持されるようになっている。このた め,1つのホルダ22からなる簡単な固定構成により,一対の支持軸20を\nハンドル12に対して容易に固定することができて,製造コストの低減を図 ることができる。」(段落【0019】)との記載がある。
上記のとおり,本件明細書の段落【0013】,【0019】には,ホルダ の両端部に各支持軸の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が 形成され,この押さえ部が支持軸の基端に接し,それをハンドルに押し付け ることによって支持軸を保持し,支持軸が抜けることがないように固定する という実施形態が記載されており,これは,前記のとおりの「押さえる」の 一般的な意味とも整合する。 そうすると,本件発明の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さ える」とは,支持軸の基端部をホルダの両端部に接するようにし,ホルダの 両端部から支持軸の基端部に対して押し付けること,すなわち力を加えるこ とによって,支持軸を抜けることがないように固定することを意味するもの と解するのが相当である。
イ これに対し,被告は,本件明細書の【図4】や段落【0013】の記載か ら,「押さえる」とは,支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部, その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するも\nのであると主張する。 しかし,本件明細書の段落【0013】の記載は前記アのとおりであり, ホルダが支持軸に力を加えずに,部材の勘合・係合のみによって固定する態 様が記載されているとはいえず,本件明細書のその他の記載中にも被告の主 張するような固定態様に関する記載はない。また,本件明細書の【図4】か らもそのような固定態様を看取することはできない。被告の主張は,「押さ える」の一般的な意味と一致するものでは必ずしもなく,かつ,本件明細書 にその主張を裏付ける記載はないといえるのであり,採用することができな い。
(2)。乙11発明と本件発明の対比
ア 本件特許の出願日前に公開されていた乙11文献には,1)ハンドルの先端 部に交差軸上に位置する一対の支持軸が設けられていること(乙11文献の 【図6】〜【図8】),2)腕部の先端側にマッサージを行うためのローラが回 転可能に支持されていること(乙11文献の段落【0001】【0013】),\n3)ローラ取付部材の左右両端部にそれぞれ腕部を含むローラ連結部の一端 を回転軸により軸支固定すること及び当該回転軸をローラ取付部材の穴に 挿通してEリングによって抜け止めすること(乙11文献の段落【0008】 〜【0010】),4)ローラ取付部材の中間部をローラ連結部を介してハンド ルに固定すること(乙11文献の段落【0008】【図1】【図2】),5)以上 の構成を有する美容器である乙11発明が開示されていることは当事者間\nで争いはない。 そこで,本件発明と乙11発明を対比すると,本件発明は,支持軸の基端 部をホルダの両端部で力を加えて支持軸を抜けないように固定する構成で\nあるのに対し(構成要件B),乙11発明の支持軸の固定方法はそのような\n構成を有していない点で相違する。
イ 被告は,本件発明の構成要件Bの「押さえる」とは支持軸の基端に設けら\nれた抜け止め頭部や押さえ部,その他支持筒等の部材との勘合・係合によっ て固定される構成を包含するものであることを前提として,本件発明の構\成 要件Bと乙11発明の構成3)とが同一であると主張する。 しかし,構成要件Bの「押さえる」に関する被告の主張を採用することが\nできないことは とおりであり,乙11発明の構成3)が本件発明の構\n成要件Bと同じであるということはできない。 したがって,乙11文献には構成要件Bの構\成が開示されているとはいえず, 乙11発明と本件発明は同一ではないから,本件発明が新規性を欠くというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.12.13
平成30(行ケ)10041 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年12月6日 知的財産高等裁判所
(1) 審決は,本願発明1は,少なくともセシウム及びストロンチウムを含む放 射性物質を,1382℃未満の温度(例えば1000℃)で焼成する場合を 含むと解され得るが,1382℃未満の温度で焼成をすると,「前記放射性 物質として含まれるセシウム及びストロンチウム」のうちのセシウム(沸点 671℃)が気化するため,本願発明1の効果である「放射性物質の気化温 度未満で焼成」し,「放射性物質や灰分が残渣として残り,放射性物質が気 化されて大気中に放出されないようにする」とともに「有機物を気化若しく は無機化させること」を実現できないとして,特許請求の範囲の記載はサポ ート要件に適合しないと判断した。
(2)ア そこで検討するに,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか 否かについては,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対 比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載され た発明で,発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記 載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を 解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のと解される。
イ 本件についてみると,本願発明1は,焼成汚染材を「測定下限値を超え る放射能濃度で放射性物質を含んだ動植物類,焼却灰,汚泥スラッジ,海\n洋泥砂,河川泥砂,湖泥砂,街路樹木,がれき,汚染水,土砂のうちの何 れか一つ以上を含む汚染材を,前記放射性物質として含まれるセシウム及 び/又はストロンチウムの気化温度未満で焼成した放射性物質を含有する」 ものと特定するものである。 そうすると,本願の請求項1にいう,「汚染材に放射性物質として含ま れるセシウム及び/又はストロンチウム」には,汚染材に放射性物質とし て「セシウム及びストロンチウム」の両者が含まれる場合のみならず,「セ シウム又はストロンチウム」,すなわち「セシウム」,「ストロンチウム」 のいずれか一方のみが含まれる場合も含まれているというべきである。
ウ また,本願明細書には,前記1(1)カのとおり,「前処理工程1001で は,図15に示すように,汚染材を地殻様組成体20の原料として使用す る前に,汚染材の焼成処理を行う。ここでの焼成温度は,放射性物質の気 化温度未満とし,放射性物質や灰分が残渣として残り,放射性物質が気化 されて大気中に放出されないようにする。このように,汚染材は,焼成処 理されることで,有機物を気化若しくは無機化させることが出来る。」(【0 133】),「セシウム−134は,沸点が671℃である。従って,例 えば,焼成温度を671℃未満としたときには,大分部分(判決注:原文 のまま)の放射性物質が気化することを防止することが出来る。」(【0 135】)と,焼成温度を汚染材に含まれる放射性物質の気化温度未満と することにより,放射性物質の気化を防止できることが記載されている。 これに対し,本願明細書には,汚染材に含まれる放射性物質の気化温度以 上の温度で焼成することについての記載はない。 このような本願明細書の記載に鑑みれば,本願発明1の上記特定事項に ついては,セシウム及びストロンチウムを放射性物質として含む,すなわ ち,セシウムとストロンチウムの両者を同時に放射性物質として含む場合 には,セシウム及びストロンチウムの気化温度未満で汚染材を焼成,すな わち,両者の気化温度に共通する部分となる(より低い気化温度である) セシウムの気化温度未満で焼成するものと解するのが自然である。また, セシウム又はストロンチウムのいずれか一方のみを放射性物質として含む 場合には,当該放射性物質の気化温度未満で焼成するものと解される。
エ したがって,請求項1に記載された発明は,発明の詳細な説明に記載さ れた発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解 決できると認識できる範囲のものであるというべきである。
4 取消事由2(引用発明の認定の誤り)について
(1) 審決は,引用文献には引用発明が記載されていると認定し,本願発明1は 引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたと判断した。
(2)ア そこで検討するに,進歩性の判断に際し,本願発明と対比すべき特許法 29条1項各号所定の発明は,通常,本願発明と技術分野が関連し,当該 技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されると ころ,同条1項3号の「刊行物に記載された発明」は,当業者が,出願時 の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうか を判断する基礎となるべきものであるから,当該刊行物の記載から抽出し 得る具体的な技術的思想でなければならない。
イ 本件についてみると,引用文献は,その表題から,放射性物質が検出さ\nれた下水汚泥焼却灰等の処分に向けた検討状況を1枚の資料にまとめたも のと認められる。 そして,引用文献の「1 これまでの経緯と今後の予定」の項の記載か\nら,1)平成23年9月から,「放射性物質対策検討特別部会」において下 水汚泥焼却灰等の安全な処分に向けた検討が開始されたこと,2)同年10 月から,下水汚泥焼却灰等の処分に関する安全性評価検討業務委託がされ, 委託先の有識者委員会である汚染焼却灰等処分安全性評価委員会が3回開 催されたこと,3)平成24年3月に東日本大震災対策本部会議が開催又は 予定され,処分に向けた検討の方向性について確認されること,4)同年4 月以降,実現に向けた課題の抽出や整理が行われる予定であることが理解\nできる。
また,「2 第1〜3回汚染焼却灰等処分安全性評価委員会での有識者 からの主な意見」の項の記載は,上記有識者委員会での主な意見をまとめ たものと理解できるところ,「(前提)」の欄に,「今回の安全性評価の 中では,セシウム(Cs134,Cs137)を対象としたことを前提条 件として明示することが望ましい」との記載があることから,放射性物質 としてセシウムが検討対象になっていたことが把握できる。 さらに,「(方針)」の欄に,「再利用(下水汚泥焼却灰のセメント原 料化)の再開を目指すことは望ましい」,「めやす値より低いからそれで 良しとするのではなく,さらに,できる限り影響が小さくなるよう対策す る姿勢が重要」との記載があることから,上記有識者委員会において,放 射性物質としてセシウムを含む下水汚泥焼却灰のセメント原料化の再開を 目指すこと,放射線の影響はできる限り小さくするよう対策すべきことが, 方針に関する有識者の意見として存在したことをそれぞれ理解できる。 その一方で,引用文献には,放射性物質が検出された下水汚泥をどのよ うに焼却するか,下水汚泥焼却灰はどの程度の放射性物質を含むものであ るか,下水汚泥焼却灰をセメント原料化する際,できる限り影響が小さく なるようにどのような対策をするのか等,下水汚泥焼却灰を処分するに当 たっての具体的な方法,手順,条件など,技術的思想として観念するに足 りる事項についての記載は一切存在しない。
そうすると,引用文献には,単に放射性物質が検出された下水汚泥焼却 灰等の処分に向けた方針,及び当該方針に関する有識者の意見が断片的に 記載されているにすぎず,下水汚泥焼却灰等の安全な処分方法というひと まとまりの具体的な技術的思想が記載されているとはいえない。
ウ したがって,その余の点について認定,判断するまでもなく,引用文献 に審決が認定した引用発明が記載されているとはいえない。
(3) 被告の主張について
被告は,引用文献の記載から,「下水汚泥焼却灰のセメント原料化」が再 開されていないことがうかがわれるからといって,引用文献に「下水汚泥焼 却灰のセメント原料化」を行う方法が開示されていないことにはならないし, 「下水汚泥焼却灰のセメント原料化」を行う方法は一般的に確立されていた 技術といえるから,原告の主張は失当であると主張する。 しかし,引用文献中の「再開を目指すことが望ましい」との記載からは, 下水汚泥焼却灰のセメント原料化が引用文献の作成時点において中止されて いたことが明らかであるところ,上記(2)のとおり,引用文献には下水汚泥焼 却灰を処分するに当たっての具体的な方法など,技術的思想として観念する に足りる事項についての記載は一切存在しないのであるから,同文献に「下 水汚泥焼却灰のセメント原料化」を行う方法が開示されているとはいえない。 また,被告が証拠として提出した乙4〜6は,いずれも「下水汚泥焼却灰 のセメント原料化」技術に関する刊行物であるものの,放射性物質を含む下 水汚泥焼却灰のセメント原料化についての記載はないから,これらの証拠を もって,引用文献が対象とする「放射性物質が検出された下水汚泥焼却灰等」 におけるセメント原料化が確立された技術ということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2018.12. 9
平成29(行ケ)10230 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年11月28日 知的財産高等裁判所
ア 前記(1)で認定した甲3文献の【請求項1】,段落【0006】,【007 2】,甲7文献の段落【0043】,【0061】,乙2文献の【請求項2】,段落【0187】,【0246】の各記載によると,本件特許の出願当時,光透過性に優れた ポリイミドを得るために,波長400nm,光路長1cmの光透過率が80%以上 のテトラカルボン酸誘導体を使用することは,当業者にとって周知であったと認め られる。
イ また,前記(1)で認定した甲3文献の段落【0102】,甲7文献の段落 【0055】,甲8文献の段落【0027】,甲9文献の「1.2.2」,乙3文 献のS93頁の概要(Abstract)の欄の1行〜7行,S94頁29行〜3 4行,S105頁3行〜6行によると,本件特許の出願当時,光透過性に優れたポ リイミドを得るために,モノマーとして,着色の少ないジアミン誘導体を使用する ことは,当業者にとって周知であったと認められる。
ウ しかし,光透過性に優れたポリイミドを得るために,純水又はN,N− ジメチルアセトアミドに10質量%の濃度に溶解して得られた溶液に対する波長4 00nm,光路長1cmの光透過率(以下「本件光透過率」という。)が90%以 上である芳香環を有しないジアミン誘導体又は本件光透過率が80%以上である芳 香環を有するジアミン誘導体を使用することは,当業者にとって周知であったとは いえない。理由は以下のとおりである。
(ア) 確かに,着色の少ないジアミン誘導体を使用するということは,光透 過性の高いジアミン誘導体を使用することを意味するものと理解できる。 しかし,本件証拠上,モノマーとして,本件光透過率が80%〜90%以上のジ アミン誘導体を使用することについて記載した文献は一切ない(なお,被告は,光 透過性に優れたポリイミドの指標として,「フィルムとしたときの波長400nm の光透過率」を用いることは周知であると主張するが,同周知事項は,モノマーの 光透過性の指標として用いられるものではない。)。
(イ) また,前記(1)のとおり,甲9文献には,「モノマーの純度も重要なフ ァクターであり,見た目きれいな結晶をしていても僅かな不純物が光透過性を悪化 する原因となる。図8には用いたジアミンの再結晶前後の光透過性について示した ものである。活性炭を用いて再結晶した後のモノマーを用いた方が光透過性にやや 優れている。光透過性では僅かな差ではあるが,着色の差としてはっきりと表れる。\n」との記載があり,同記載からすると,着色の度合いと光透過性との間の相関の程 度は不明といわざるを得ず,他にこの点を認めるに足りる証拠もない。したがって ,モノマーとして,着色の少ないジアミン誘導体を使用することが周知であるとし ても,そのことから,本件光透過率が80%〜90%以上となるジアミン誘導体を 使用することまでも周知であるということはできないというべきである。
エ このように,光透過性に優れたポリイミドとするために,モノマーとし て,本件光透過率が80%〜90%以上のジアミン誘導体を使用することが周知で あったということはできないから,甲4発明に本件証拠によって認められる周知技 術を適用しても,本件発明1の構成に到らず,したがって,本件発明1は進歩性が\nないということはできない。
オ 被告の主張について
被告は,1)可視光領域(可視域)の吸収をなくして,光透過性に優れたポリイミドを 合成することは,当業界における周知の課題である,2)光透過性に優れたポリイミ ドの指標として,「フィルムとしたときの波長400nmの光透過率」を用いること は周知である,3)光透過性に優れたポリイミドとするためには,可視光を吸収する 要因を排除すればよく,そのためには,光透過性を悪化する原因となる不純物がな いよう,充分に精製した純度の高いモノマーを用いることは周知である,4)ポリイ ミド原料モノマーのうち,少なくともテトラカルボン酸二無水物において,上記の 「光透過性を悪化する原因となる不純物がないよう,充分に生成した純度の高いモ ノマー」であることの指標として,当該モノマーを適当な溶媒に溶解したときに波 長400nmの光透過率(溶媒にモノマーを溶解させた溶液の光路長1cmの光透 過率)がなるべく高いものであることを用いることは周知である,5)ポリイミドの 原料モノマーのうち,ジアミン誘導体についても,再結晶や蒸留等により精製して, 純度が高く,着色の少ないものを用いることは周知であるとした上で,甲4発明に 上記各周知技術を適用することにより,相違点1−1に係る構成を備えた本件発明\n1は容易に想到できる旨主張する。
(ア) しかし,前記ウのとおり,光透過性に優れたポリイミドとするために, モノマーとして,着色の少ないジアミン誘導体を使用することが周知であったとし ても,同周知技術から,本件光透過率が80%〜90%以上のジアミン誘導体を使 用することを導き出すことはできないところ,このことは,被告の指摘する上記の すべての周知技術を考慮しても変わるものではない。
(イ) この点,被告は,ジアミンに含まれる光透過性を悪化する原因となる 不純物が,そのままポリイミドにも含まれることとなり,ポリイミドの光透過性に 影響することから,光透過性に優れたポリイミドとするために,テトラカルボン酸 二無水物を溶媒に溶解した溶液の波長400nmの光透過率が90%以上のものを 用いるのであれば,ポリイミドを構成するもう一方のモノマーであるジアミンにつ\nいても,テトラカルボン酸二無水物と同程度の光透過率のものとすることは,当業 者であれば当然に理解する旨主張する。 a 被告の上記主張は,透明性の優れたポリイミドを製造するためには, ポリイミドの純度を高める必要があり,そのためには,モノマーであるジアミン誘 導体の純度も高める必要がある,そのジアミン誘導体の純度を光透過率に置き換え ると,もう一つのモノマーであるテトラカルボン酸誘導体に要求される光透過率と 同程度であるというものと理解できるが,本件証拠上,ジアミン誘導体及びテトラ カルボン酸誘導体のそれぞれの純度と光透過率との間の相関の程度は明らかではな く,後記bのような実験結果もあるから,透過性に優れたポリイミドの製造のため に,ジアミン誘導体の光透過率をテトラカルボン酸誘導体の光透過率と同程度とす ることが導き出されるということはできず,また,当業者もそのような理解をする とは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2018.12. 6
平成29(行ウ)297 異議申し立て棄却処分取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年11月20日 東京地方裁判所
(1)特許法112条の2第1項は,同法112条4項の規定により消滅したも のとみなされた特許権の原特許権者は,同条1項の規定により特許料を追納 することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなか ったことについて「正当な理由」があるときは,経済産業省令で定める期間 内に限り,特許料等を追納することができると規定する。 そして,特許法112条の2の上記文言が,特許法条約(Patent Law Tre aty)において手続期間を徒過した場合に救済を認める要件としての「Du e Care(いわゆる『相当な注意』)」を取り入れて規定されたこと(平 成23年法律第63号による改正,乙12)からすれば,同条の「正当な理 由」があるときとは,原特許権者として,特許料等の追納期間の徒過を回避 するために相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的な事情により これを回避することができなかったときをいうものと解するのが相当である。
(2) 本件について,原告は,「正当の理由」として,主に,本件追納期間中は 別件訴訟の対応で心身ともに余裕がなかったこと,同期間中にうつ病等の複 数の疾患を抱えており,特許料等を納付できる状態ではなかったことを主張 する。 しかしながら,一般的に自己を当事者とする訴訟を追行していたとしても, それ以外の事務を行うことができなくなるものではなく,特許料の納付期限 等について注意を払うことは十分に可能\であったといえるから,原告の主張 する別件訴訟に係る事情は,追納期間の徒過を回避することができなかった と認められる客観的な事情とは評価できない。 また,原告は,本件追納期間中にうつ病等の複数の疾患に罹患していたと 主張し,原告について診断日を平成22年3月25日として「遷延性抑うつ 反応」との診断を受けたことが認められる(甲9の1)。しかし,本件追納 期間(平成25年6月12日から同年12月11日まで)中に原告が精神科 に通院するなどしてうつ病の治療を受けていたことを認めるに足りる証拠は ないほか,原告は,1)上記診断において「遷延性抑うつ反応」に罹患したと される平成20年11月10日(本件交通事故による受傷日)以降も複数の 特許出願を行なっていたことがうかがわれること(甲9の1,乙7〔3枚 目〕,2)本件追納期間中もほぼ毎週整形外科に通院していたこと(甲15, 乙7〔平成26年5月15日付け青森県立中央病院医師作成の診断書から始 まる添付資料の2,4,8,13,14枚目,2013/4/02(44)との記載から 始まる添付書類の5ないし16枚目),3)本件追納期間経過後から間もない 平成26年4月に本件特許権が消失していることを知ると,同月17日頃に は特許庁に対して特許料追納手続を問い合わせる電子メールを送信し,同月 23日には,特許庁から送付された電子メールの記載に従った追納分の特許 料相当額の印紙を貼付した本件納付書を提出し,正当な理由に該当する旨を\n記載した回復理由書を提出したこと(乙5の1,2,乙7〔2枚目,「登録 室」から2014年4月17日午前10時24分に送られた電子メールの記 載から始まる【添付資料】の1枚目〕)などからすれば,原告が本件追納期 間中に「遷延性抑うつ反応」あるいは他の疾患により行動等の制限を受ける ことがあったしても,それが特許料納付の妨げになる程度のものであったと 認めるには足りず,原告の疾病に係る事情もまた,追納期間の徒過を回避す ることができなかったと認められる客観的な事情とは評価できない。 更に,原告は,特許庁から特許料納付に係る請求書の送付がなかったとも 主張するが,特許料及びその納付期限については特許法107条以下に定め られるなどしていて,相当な注意を尽くして情報を収集すれば容易に知るこ とができたというべきであるから,上記事情は追納期間の徒過を回避するこ とができなかったと認められる客観的な事情とはいえない。 その他,追納期間の徒過を回避することができなかったと認められる客観 的な事情は認められない。
(3)以上によれば,本件納付書による特許料等の納付のうち,第4年分の特許 料等に係る部分について,本件期間徒過につき正当な理由があるとはいえな いとし,第5年分の特許料に係る部分について,第4年分の特許料等の追納 が認められないために本件特許権は消滅しているとして,本件納付書による 納付手続を却下した本件却下処分には,特許法112条の2第1項の解釈適 用を誤った違法があるとはいえない。 原告は,本件却下処分または本件決定によって本件特許権が回復しないこ とが憲法29条に違反するとも主張するが,特許権は,性質上,法が定める 条件に従って,国家から付与され存続する権利であるから,法が定める特許 料の納付等の手続を経なければこれを失うものであり,前記のとおり追納を 認めなかった本件却下処分に違法があるとはいえないことから,本件特許権 が回復しないことが憲法29条に違反することはない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2018.12. 6
平成29(ネ)10055 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
争点2−3−1(時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立て)について
ア 証拠(甲4,乙69の4・5)及び弁論の全趣旨によると,控訴人らは, 被控訴人外1名を原告,控訴人ら外3名を被告とする商標権侵害差止等請求事件に おいて,当該事件の原告訴訟代理人弁護士G及び同Hが平成19年5月22日に東 京地方裁判所に証拠として提出した乙69の4及び証拠説明書として提出した乙6 9の5を,その頃受領していること,乙69の5には,乙69の4の説明として, 「被告シンワのチラシ(2006年用)(写し)」,作成日「2006(平成18) 年」,作成者「(有)シンワ」,立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業 した事実を立証する。」旨記載されていることが認められる。 したがって,控訴人らは,平成19年5月22日頃には,乙69の4・5の存在 を知っていたものと認められる。
イ 控訴人らは,控訴人シンワ代表者Aが,平成21年1月13日〜19日,\n控訴人シンワが平成17年7月6日〜8日頃に噴火湾の漁民らにサンプルを示して 本件明細書等の図8(a)と同一形状の製品を販売していたことにつき,陳述書(乙 38の1〜13)を集め,控訴人進和化学工業の代表者であった故Eに送付したと\n主張している。 上記主張によると,控訴人らは,平成21年1月頃には,上記陳述書の存在を 知っていたものと認められる。
ウ 本件は,平成28年6月24日に東京地方裁判所に提訴され,平成29 年1月26日に口頭弁論が終結され,その後和解協議が行われたところ,上記ア, イの事実によると,控訴人らは,無効理由3(新規性欠如)に係る抗弁を,遅くと も平成29年1月26日までに提出することは可能であったといえるから,これは\n「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」(民訴法157条1項)に該当する ことが認められる。 しかし,控訴人らは,本件の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成29年8月3日) において,控訴人シンワは,本件特許が出願されたとみなされる日より前に,本件 各発明の構成要件を充足する製品を販売したので,本件特許は新規性を欠く旨の主\n張をしたものであって,上記期日において,次回期日が指定され,更なる主張,立 証が予定されたことからすると,この時点における上記主張により,訴訟の完結を\n遅延させることとなると認めるに足りる事情があったとは認められない。
エ したがって,上記主張に係る時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては,認められない。\n
(3) 争点2−3−2(新規性欠如)について
ア(ア) 前記(2)アのとおり,控訴人らは,被控訴人外1名を原告,控訴人ら 外3名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において,当該事件の原告訴訟代理 人弁護士G及び同Hが平成19年5月22日に東京地方裁判所に証拠として提出し た乙69の4及び証拠説明書として提出した乙69の5を,その頃受領しているこ と,乙69の5には,乙69の4の説明として,「被告シンワのチラシ(2006 年用)(写し)」,作成日「2006(平成18)年」,作成者「(有)シンワ」,立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨記載され ていることが認められるところ,乙69の4には,「2006年販売促進キャン ペーン」,「キャンペーン期間 ・予約5月末まで ・納品5月20日〜9月末」, 「有限会社シンワ」,「つりピンロールバラ色 抜落防止対策品」,「サンプル価格」, 「早期出荷用グリーンピン 特別感謝価格48000円」などの記載があり,複数 の種類の「つりピン」が添付されており,その中には,5本のピンが中央付近にお いてそれぞれハの字型の1対の突起を有するとともに,そのハの字型の間の部分を 2本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のもの(つりピンロールバラ色 と記載された部分の直近下に写し出されているもの)があることが認められる。 上記「つりピン」の形状は,上記事件の上記原告訴訟代理人が,平成19年5月 22日に,乙69の4とともに,上記商標権侵害差止等請求事件において,東京地 方裁判所に証拠として提出した乙69の3に「つりピンロール(バラ色)抜落防止 対策品」として記載されているピンク色の「つりピン」と,その形状が一致してい ると認められる。乙69の3は,乙69の4と同じ証拠説明書による説明を付して, 提出されたものであり,「2006年度 取扱いピンサンプル一覧」,「有限会社シ ンワ」,「早期出荷用」などの記載がある。 また,乙69の4は,上記事件の上記原告訴訟代理人が,平成19年5月22日 に,乙69の4とともに,「被告シンワのチラシ(2005年用)(写し)」,作成日 「2005(平成17)年」,作成者「(有)シンワ」,立証趣旨「被告シンワが原 告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨の証拠説明書による説明を付し て,上記商標権侵害差止等請求事件において,東京地方裁判所に提出した乙69の 1と,レイアウトが類似しているところ,乙69の1には,「2005年開業キャ ンペーン 下記価格は2005年4月25日現在の価格(税込)です。」,「有限会 社シンワ」,「当社では売れ残り品は販売しておりません。お客様からの注文後製造 いたします。」などの記載がある。 以上によると,乙69の3及び4は,いずれも,控訴人シンワが,被控訴人の顧 客であった者に交付したものを,平成19年5月22日までに,被控訴人が入手し, 控訴人シンワらが,被控訴人の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして, 上記事件において,提出したものであると認められる。 そして,乙69の4の上記記載内容,特に「販売促進キャンペーン」,「納品5月 20日〜」と記載されていることからすると,乙69の4と同じ書面が,平成18 年5月20日以前に,控訴人シンワにより,ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客 に配布されていたことを推認することができる。
(イ) また,前記(ア)の認定事実及び弁論の全趣旨によると,乙69の4に 記載されている,5本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の1対 の突起を有するとともに,そのハの字型の間の部分を2本の直線状の部分が連通す る形で連結された形状のものは,控訴人シンワにより見込み客に配布されていた前 記(ア)の乙69の4と同じ書面にも添付されていたと認められる。
(ウ) 前記の5本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の 1対の突起を有するとともに,そのハの字型の間の部分を2本の直線状の部分が連 通する形で連結された形状のものの形状は,両端部において折り返した部分の端部 の形状が,乙69の4では,下から上へ曲線を描いて跳ね上がっているのに対し, 本件明細書等の図8(a)では,釣り針状に下方に曲がっている以外は,本件明細 書の図8(a)記載の形状と一致している。 そして,本件明細書等の図8(a)は,本件各発明に係るロール状連続貝係止具 の実施の形態として記載されたものである。
(エ) そうすると,前記(ア)及び(イ)の5本の「つりピン」が中央付近にお いてそれぞれハの字型の1対の突起を有するとともに,そのハの字型の間の部分を 2本の直線が連通する形で連結された形状のものは,形状については,本件発明1 の構成要件1A〜Hにある形状をすべて充足する。そして,証拠(乙69の1〜5)\n及び弁論の全趣旨によると,その材質は,樹脂であり,「つりピンロール」とされ ていることから,ロール状に巻き取られるものであり,その連結材は,ロール状に 巻き取られることが可能な可撓性を備えているものと認められる。したがって,乙\n69の4に記載されている「つりピン」は,本件発明1の構成要件1A〜Hを,す\nべて充足すると認められる。 また,上記の「つりピン」は,ロープ止め突起の先端と連結部材とが極めて近接 した位置にあり,2本のロープ止め突起の先端の間隔よりも一定程度狭い縦ロープ との関係では,2本の可撓性連結材の間隔が,貝係止具が差し込まれる縦ロープの 直径よりも広くなるから,本件発明2の構成要件である2Aも充足すると認められ\nる。 さらに,上記の「つりピン」が,ロール状に巻き取られるものであることは,上 記のとおりであるから,上記の「つりピン」は,本件発明3の構成要件である3A\n及び3Bも充足すると認められる。
(オ) そうすると,本件発明1〜3は,本件特許が出願されたとみなされ る日である平成18年5月24日よりも前に日本国内において公然知られた発明で あったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。
イ 被控訴人は,乙69の4につき,平成19年5月22日に手元にあった ことを認めつつ,誰が,いつ,どこで入手したのかは記憶がなく,控訴人ら提出の 証拠によって,本件特許が出願されたとみなされる日前にこれが配布されていたこ とが立証されたとはいえないと主張する。 しかし,乙69の5に記載された立証趣旨に鑑みると,平成19年5月22日当 時,被控訴人は,乙69の4が控訴人シンワにより被控訴人の得意先への営業に用 いられたと認識していたことが認められるのであって,被控訴人がそれ以前にその 顧客から原本又は写しを入手したものと認められる。 乙69の4の記載内容に,販売の申出のためのチラシとして不自然なところはな\nく,上記のとおり,その記載内容によって,平成18年5月20日以前にこれが控 訴人シンワにより見込み客に配布されたことが推認される。 被控訴人は,平成18年5月24日以前に乙69の4のピンと同様の形状のピン が見込み客に配布されたことを裏付けるものとして控訴人らが提出した陳述書等の 書証の成立及び信用性について主張するが,乙69の4が上記の東京地方裁判所に おける事件において平成19年5月22日に上記のとおり被控訴人から提出された ことは動かし難い事実であり,被控訴人がその成立又は信用性を争うその他の書証 が存在しなくとも,前記アのとおりの認定をすることができる。また,被控訴人が その成立又は信用性を争う書証は,前記アの認定と矛盾するものではなく,むしろ, 間接的にこれを裏付けるものということができる。そして,これらに記載された供 述内容について,矛盾や曖昧な点があるとしても,それらは記憶の希薄化等により 起こり得ることであって,これらをもって,乙69の4等に基づき認定し得る前記 アの事実の認定を左右するに足りるものではない。さらに,特許庁における控訴人 シンワ代表者A,証人C,証人Iの各供述(乙146)についても,同様に,矛盾\nや曖昧な点や変遷があるとしても,これらをもって,乙69の4等に基づき認定し 得る前記アの事実の認定を左右するに足りるものではない。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2018.12. 4
平成30(ネ)10045等 商標権侵害行為差止請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成30年11月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人標章1は,別紙控訴人標章目録記載1のとおり,図形部分と, その上方に毛筆体で横書きした「大観」の文字部分及び「白砂青松」の 文字部分とからなる結合商標である。 図形部分は,長方形の黒色の枠線の中に,背後に白い山が見える,白 い砂浜に松林の続く海岸の風景画を図形化したものであり,図形部分の 大きさは,控訴人標章1全体の約5分の4を占めている。 しかるところ,「大観」の文字部分及び「白砂青松」の文字部分は, 図形部分と重なっていないこと,「大観」の文字部分は図形部分の長方 形の黒色の枠線からやや離れた上方に配置されていることから,長方形 の黒色の枠線で囲まれた図形部分と「大観」の文字部分及び「白砂青 松」の文字部分は,明瞭に区別して認識することができる。 また,図形部分の左下部には毛筆体で縦書きした「大観」の署名及び 落款印の印影が表記されており,図形部分は,横山大観作の「白砂青\n松」という作品名の絵画を図形化したものであることが認められるが (乙68ないし82),横山大観作の上記絵画が,原告商標の指定商品 「日本酒」の需要者である一般消費者の間に広く認識されるに至ってい るものと認めるに足りる証拠はないことに照らすと,需要者の多くは, 図形部分の風景画は,「白砂青松」の文字部分から連想,想起させる風 景を描いたものと認識することはあっても,横山大観作の上記絵画 景を描いたものと認識することはあっても,横山大観作の上記絵画であ ると認識するものと認めることはできないし,「大観」の文字部分及び 「白砂青松」の文字部分は,図形部分の絵画の作者が横山大観であり, その作品名が「白砂青松」であることを表示するものとして図形部分と\n一体的な関係にあると認識するものと認めることもできない。 そうすると,図形部分と「大観」の文字部分及び「白砂青松」の文字 部分は,分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的 に結合しているものとは認められない。 次に,「大観」の文字部分及び「白砂青松」の文字部分から全体とし て「タイカンハクサセイショウ」又は「タイカンハクシャセイショウ」 の称呼が生じるが,「大観」の文字部分は,控訴人標章1の上方左端に, 「白砂青松」の部分は,「大観」の文字部分よりも大きな文字で控訴人 標章1の上方中央にそれぞれ表示され,「大観」の文字部分は「白砂青\n松」の文字部分よりもやや上方に位置していること,「大観」の文字部 分を構成する文字と「白砂青松」の文字部分を構\成する文字は,字体が 異なり,文字の間隔は「白砂青松」の文字部分の方が広いことに照らす と,「大観」の文字部分と「白砂青松」の文字部分は,明瞭に区別して 認識することができるから,分離して観察することが取引上不自然と思 われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 そして,「白砂青松」の文字部分は,控訴人標章1の上方中央に毛筆 体の大きな文字で表示され,「白砂青松」の文字部分から「ハクサセイ\nショウ」又は「ハクシャセイショウ」の称呼が自然に生じること,「白 砂青松」の文字部分の下方に表示された図形部分は,需要者の多くによ\nって「白砂青松」の文字部分から連想,想起させる風景を描いたものと 認識されることからすると,控訴人標章1が原告商標の指定商品である日本酒に使用された場合には,控訴人標章1の構成中の「白砂青松」の\n文字部分は,取引者,需要者に対し,被告商品の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えるものと認められる。 以上によれば,控訴人標章1から「白砂青松」の文字部分を要部とし て抽出し,これと原告商標とを比較して商標そのものの類否を判断する ことも,許されるというべきである。
(イ) これに対し控訴人は,1)控訴人標章1は,被告商品の瓶のラベルに 使用されているところ,需要者が店頭で日本酒を購入する場合,日本酒 の瓶のラベルにどのような絵柄や文字が記載されているかを確認して商 品を識別するから,ラベルに表示されている文字や絵柄は,全体として\n自他商品識別機能を有しており,しかも,被告商品の瓶のラベルに占め\nる上記絵画部分は,非常に大きいこと,2)「大観 白砂青松」の文字部 分は,横山大観の自筆のものであり,この文字部分から,通常,横山大 観が描いた「白砂青松」という作品名の絵画を連想させるところ,絵画 部分は横山大観作の「白砂青松」という作品名の絵画であることからす れば,上記文字部分と上記絵画部分は,分離して観察することが取引上 不自然と思われるほど不可分的に結合しているといえるから,控訴人標 章1から「白砂青松」の文字部分を抽出し,これと原告商標とを比較し て商標そのものの類否を判断することは許されない旨主張する。 しかしながら,控訴人標章1を構成する図形部分と「大観」の文字部\n分及び「白砂青松」の文字部分とを明瞭に区別して認識することができ ることは,前記(ア)認定のとおりである。 また,上記1)の点については,日本酒を購入する場合,瓶のラベルに どのような絵柄や文字が記載されているかを確認することがあるからと いって,一般に,ラベルに表示されている文字や絵柄が全体としてのみ\n自他商品識別機能を有しているということはできない。\nさらに,上記2)の点については,仮に控訴人標章1の「大観」の文字 部分及び「白砂青松」の文字部分が横山大観の自筆のものであったとし ても,そのことが需要者である一般の消費者の間に広く認識されるに至 っているものと認めるに足りる証拠はない。また,前記(ア)認定のとお り,需要者の多くは,控訴人標章1の図形部分から,その図形部分の風 景画が横山大観作の「白砂青松」という作品名の絵画であると認識する ものと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2018.12. 1
平成30(行ケ)10060 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年11月28日 知的財産高等裁判所
(イ) 前記(1)イ(ウ)認定のとおり,マットレス付き原告ベッドは,原告ベ ッドの機能(底板の背部の背上げ機能\及び膝部の膝上げ機能,土台の傾\n斜機能)の組合せにより,本願商標と同一の形状をとることができるこ\nとからすると,マットレス付き原告ベッドの購入者又は利用者は,その 使用時に,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形状を認識する 機会があり得るものといえる。 しかしながら,本願商標は,別紙1記載のとおり,ベッドの土台が, 頭側を上にして傾斜し,ベッドの底板が,頭側を上にして足側にかけて 全体としてS字状に屈曲し,背部が立ち上がり,腰部から足部にかけて の中間の膝部が起伏し,かつ,頭側の端部がヘッドボードの上端部の右 方に近接して位置した形状であり,マットレス付き原告ベッドを本願商 標と同一の形状とするには,原告ベッドの上記機能を組み合わせて,土\n台の傾斜角度,底板の背部の立ち上げ角度及び膝部の起伏の高さなどを 調節して設定する必要があること,マットレス付き原告ベッドの利用者 は,通常は,マットレスの上に布団をかけた状態で原告ベッドを使用す ることに照らすと,マットレス付き原告ベッドの購入者又は利用者は, その使用時に,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形状を認識 する機会は多いものとは認められないし,また,その形状を認識したと しても,それが印象に残ることは少ないものと認められる。 さらに,原告は,本社及び全国8支店のショールームに原告の総合カ タログ(甲1)及び単品カタログ(甲2)を常備し,マットレス付き原 告ベッドを展示して,販売活動を行っていること(甲5,弁論の全趣旨) に照らすと,マットレス付き原告ベッドの購入者は,その購入の際に, 総合カタログ及び単品カタログに接することがあり得るものと認められ るが,総合カタログ及び単品カタログには,別紙1の下部の写真と同様 の構図(斜視図)の写真は掲載されていないため,総合カタログ及び単\n品カタログのみから,本願商標と同一の形状を認識することはできない。 また,上記ショールームにおいてマットレス付き原告ベッドが本願商標 と同一の形状で展示されていたことを認めるに足りる証拠はない。
(ウ) マットレス付き原告ベッドを含む「楽匠Zシリーズ」の商品の新聞 広告及び雑誌広告には,1)人が横たわっている,マットレス,枕及び掛 け布団を設置した,底板及び土台が頭側に傾斜した状態のマットレス付 きベッドを表したB商標,2)マットレス,枕及び掛け布団を設置した, 土台が頭側に傾斜し,底板の背部が立ち上がった状態のマットレス付き ベッドを表したD商標,3)マットレス及び枕を設置した,土台が頭側に 傾斜し,底板の背部が立ち上がった状態のベッドに人が枕に頭をのせ, 背中を付けて座っているマットレス付きベッドを表したE商標の写真が\n掲載されていることは,前記ア(イ)認定のとおりである。 しかしながら,これらのB商標,D商標及びE商標の写真は,人,枕 及び掛け布団が写されている部分を除いても,別紙1記載の本願商標の 形状の写真と一致しないことに照らすと,B商標,D商標及びE商標を 掲載した新聞広告及び雑誌広告から,本願商標と同一の形状又は社会通 念上同一の形状を認識することはできないものと認められる。 また,同様に,マットレスの設置されていない,土台が頭側に傾斜し, 底板の背部が立ち上がった状態のベッドを表したA商標が掲載された新\n聞及び雑誌から,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形状を認識することはできないものと認められる。 次に,マットレス付き原告ベッドを含む「楽匠Zシリーズ」の商品の テレビCMには,マットレスの足元側にカバーをつけたマットレス付き ベッドにおいて,土台が水平で,土台が頭側に傾斜した状態,底板及び 土台が頭側に傾斜した状態,土台が頭側に傾斜し,底板の背部が立ち上 がった状態を表したF商標の画像,土台が頭側に傾斜し,底板の背部が\n立ち上がった状態のマットレス付きベッドを表した標章の画像が表\示さ れていることは,前記ア(ウ)認定のとおりである。 しかしながら,これらのF商標及び上記標章の画像は,マットレスの 足元側のカバーが写されている部分を除いても,別紙1記載の本願商標 の形状の写真と一致しないことに照らすと,F商標及び上記標章が表示\nされたテレビCMから,本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形 状を認識することはできないものと認められる。 (エ) 前記ア(エ)のとおり,本件アンケートは,福祉用具レンタル卸業者, 貸与業者及び販売業者,ケアマネージャー(介護支援専門員),福祉用 具鑑定士,福祉用具プランナー等を対象者とするものであり,介護用品 の利用者及びその家族等の一般需要者が対象者に含まれていないから, 本件アンケートの結果は,需要者(前記(ア))の認識を適切に反映した ものとは認められない。
(オ) 以上によれば,原告によるマットレス付き原告ベッドの販売(前記 ア(ア)),新聞広告,雑誌広告及びテレビCMによる広告宣伝(前記ア(イ), (ウ)),本件アンケートの結果(前記ア(エ))を総合考慮しても,本件 審決時(審決日平成30年3月22日)までに,本願商標が,マットレ ス付き原告ベッドを表示するものとして,需要者の間に広く認識される\nに至ったものと認めることはできない。 したがって,本願商標は,マットレス付き原告ベッドについて,「使 用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識する ことができるもの」(商標法3条2項)に該当するものとはいえない。
ウ 原告の主張について
原告は,1)本願商標は,極めて斬新で特徴的な形状(「傾斜ベッド」と 「フットボード」の形状)を有しており,その特徴的な形状は,強く需要 者の目を引くこと,2)本願商標の使用商品(マットレス付き原告ベッド) は,発売後短期間に多数の販売実績を上げていること,3)積極的,集中的 かつ商品形状の露出を前面に押し出した効果的な本願商標の使用商品の宣 伝活動とも相まって,需要者である福祉用具レンタル事業者において,本 願商標の特徴的な形状は,印象的かつ鮮明に記憶され,その特徴的な形状 自体が原告の出所を表示する標識として認識されるに至っており,このこ\nとは,本件アンケート調査の結果によって裏打ちされていることからする と,本願商標は,本願商標の使用商品について,「使用をされた結果需要 者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」 (商標法3条2項)に該当すると主張する。
しかしながら,上記1)のうちの「傾斜ベッド」の形状とは,土台の傾斜 機能により,フットボード側が低くなった形状をいうものであるところ,\n原告が述べるように土台の傾斜機能は従来の介護用ベッドにない機能\であ るとしても,本願商標の構成全体の中で土台が傾斜した形状が強く需要者\nの印象に残るものとは認められない。また,上記1)のうちの「フットボー ド」の形状とは,樹脂製のボードを採用し,全体に丸みをつけて,ボード の上端がつかまりやすいグリップ形状となっている点及び外側に「収納カ バー」が設けられ,木目調のシートが貼ってある点をいうものであるとこ\nろ,グリップできるように,フットボードの上部左右に穴を設けた形状及 びフットボードの一部に木目調の模様がある形状は,他の介護用ベッドに おいても採用されている形状又は装飾であって(乙4ないし6,14,1 5),いずれも独特なものとはいえず,強く需要者の目を引くものとは認 められない。
そして,マットレス付き原告ベッドの販売実績及び広告宣伝,本件アン ケートの結果を総合考慮しても,本件審決時(審決日平成30年3月22 日)までに,本願商標が,マットレス付き原告ベッドを表示するものとし\nて,需要者の間に広く認識されるに至ったものと認めることはできないこ とは,前記イ(オ)で説示したとおりである。したがって,原告の上記主張は,理由がない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 立体商標
>> ピックアップ対象
2018.12. 1
平成30(行ケ)10024 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年11月14日 知的財産高等裁判所(2部)
原告は,甲3発明に甲4技術事項を適用し,さらに甲4技術事項を適用し た甲3発明に原告主張甲2技術事項を適用して,本件発明1を容易に想到すること ができた旨主張するので,同主張について検討する。 ア 前記2(3)のとおり,甲3発明は,テープ・ドライブのサーボ系を安定化 させる目的で(段落【0007】),テープ・カートリッジがテープ・ドライブに挿 入されるたびに,該テープ・ドライブのサーボ制御用低域通過フィルタの係数を, 挿入されたテープ・カートリッジに応じて設定し直すようにした発明(段落【00 09】)であって,甲3文献には,テープに記録されるサーボ・パターン自体はタイ ミング・ベース・サーボの基礎をなす既知のものだとされているが(段落【002 0】),サーボ・パターンによって何等かの情報を符号化して埋め込むことについて の記載はなく,また,そのような符号化が必要であるとの示唆もなく,ましてや, サーボバンド識別情報を同一のサーボバンド内に符号化することの必要性について の示唆はない。
したがって,甲3発明にサーボバンド上に各種の情報を符号化する技術である甲 4技術事項やサーボバンド識別情報を同一のサーボバンド内に符号化する技術であ る原告主張甲2技術事項を適用する動機付けがあると認めることはできない。 また,甲3発明に甲4技術事項を適用した上で,さらに原告主張甲2技術事項を 適用することは,タイミング・ベース・サーボを前提として,サーボバンド上に情 報の符号化をすることについて何らの開示がない上記の甲3発明に,甲4文献で開 示されているタイミング・ベース・サーボにおける情報の符号化の方法を示した甲 4技術事項と,アンプリチュード・サーボにおいて同一のサーボバンド内にサーボ バンド識別情報を符号化することを示した原告主張甲2技術事項を重ねて適用する ものであるが,甲3文献には,サーボバンド上に情報を符号化することの記載すら ないのであるから,そのような状況で,同一のサーボバンド内にサーボバンド識別 情報を符号化することを示した技術を適用することが容易であったということはで きないというべきである。
イ 原告の主張について
原告は,甲3発明は複数のサーボバンドを有する磁気テープである点で原告主張 甲2技術事項と共通すること及び複数のサーボバンドを有する磁気テープにおいて は,サーボ読取りヘッドが自らが位置するサーボバンドを何らかの方法によって特 定する必要があるという課題が存在し,この課題は周知であることから,上記動機 付けが存在することは認められる旨主張する。 しかし,甲3発明は複数のサーボバンドを有する磁気テープであり,また,複数 のサーボバンドを有する磁気テープにおいて,サーボ読み取りヘッドが自らが位置 するサーボバンドを何らかの方法によって特定する必要があることは周知であると しても,甲3発明は,前記アのようなものであるから,甲3発明に甲4技術事項を 適用した上で,さらに原告主張甲2技術事項を適用することが動機付けられるとい うことはできない。このことは,タイミング・ベース・サーボにおいて,非平行な 縞を構成する線の位置をテープ長手方向にずらすことによりデータを符号化するこ\nとが,当業者にとって周知となっていたとしても,左右されるものではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2018.12. 1
平成28(ワ)12791 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成30年11月6日 大阪地方裁判所(21民)
登録意匠と対比すべき意匠とが類似であるか否かの判断は,需要者の視 覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う(意匠法24条2項)ものとされており, 意匠を全体として観察することを要するが,この場合,意匠に係る物品の性質,用 途及び使用態様,並びに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して,取 引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,登録意匠と 対比すべき意匠とが,意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを重視\nして,観察を行うべきである。 そして,本件意匠に係る物品の説明によれば,本件意匠に係る物品である検査用 照明器具は,工場等において製品の傷やマーク等の検出(検査)に用いられるもの であるから,そのような検査を必要とする製品の製造業者等によって購入されるも のであると推認される。したがって,意匠の類否判断における取引者・需要者は, そのような製造業者等である。 そこで,このような需要者の観点から,本件意匠の要部について検討する。
イ 公知意匠
平成15年6月16日に発行された意匠公報(乙12)において,乙 12意匠(別紙「乙12意匠の図面」参照)が開示されていた。そして,乙12意 匠は,前記1(8)イで認定したとおり,本件意匠の基本的構成態様AないしDと同じ\n構成態様を備えているほか,本件意匠の具体的構\成態様E,H,I及びJの一部並 びにF,K及びLと同じ構成態様を備えている。\nそうすると,以上の構成態様は,検査用照明器具の物品分野の意匠において,本\n件意匠の意匠登録出願前に広く知られた形態であったと認められる。 他方で,後端フィン及び中間フィンの各面が,支持軸体の通過部分以 外には貫通孔がなく,平滑であるという構成態様(同M)は,乙12意匠において\nも開示されておらず,前記1(8)で述べたとおり,検査用照明器具においてそのよう な構成態様を備えたものは公知意匠として存在していなかった(甲14で開示され\nている意匠においても,後端フィン及び中間フィンの上側に貫通孔が設けられてい る。)。この点,乙8意匠はタワー型のヒートシンクの意匠であり,その後端面は 平滑であるが,前記1(3)で判示したとおり,これがどのような物品の放熱部として 用いられるものかは明らかでなく,これと他の部材との位置や大きさの関係,ある いはヒートシンクの各部分の具体的な寸法等も明らかでないし,そもそも乙8の文 献はヒートシンクに関する一般的説明をしたものにすぎないから,要部の認定に当 たって参酌すべき公知意匠というべきものとはいえない。 そして,前記1で判示したとおり,本件意匠の具体的構成態様Mは,その意匠登\n録出願前の公然知られた意匠に基づき,容易に創作することができたものとはいえ ないから,公知意匠にない新規な創作部分であると認められる。
ウ 意匠に係る物品の性質,用途,使用態様等
一定の機能及び用途を有する「物品」を離れての意匠はあり得えないから,\n部分意匠においても,部分意匠に係る物品において,意匠登録を受けた部分がどの ような機能及び用途を有するものであるかを,その類否判断やその前提となる要部\n認定の際に参酌すべき場合がある。 このような観点から検討すると,本件意匠に係る物品は検査用照明器具でありL ED等を内蔵するところ,LEDを使用すると熱を発生し,器具内の温度が上昇す ることから,その放熱(設計)の必要性が指摘されている(甲21,22,24な いし25の2)。そして,本件意匠はその放熱部の意匠であり,特にそこに設けら れたフィンは放熱するための部材(放熱フィン)であるから,放熱を必要とする検 査用照明器具の需要者は,放熱効率という観点から,本件意匠の部材の形態や配置 の状況に着目すると考えられ,具体的には,放熱部である後方部材が前方部材の延 伸上にあること,放熱部である後方部材が,前方部材と同程度の大きさ(径)であ ること,複数枚のフィンが間隔を空けて配置されていること,フィンよりも支持軸 体の方が径が小さく,支持軸体の貫通孔以外のフィンの部分が放熱に寄与すること に着目すると思われる。 また,前記1で検討した公知意匠の内容に照らすと,フィンの枚数,間隔及び厚 みを変更したり(中間フィンと後端フィンの厚みの関係も含む。),フィンに面取 りを加えたり,支持軸体の径を変更したりすることは,ありふれた手法というべき であって,需要者がそのわずかな違いに着目するとは考えられないが,需要者が放 熱を重視する場合,少なくとも,フィンの枚数や厚み,支持軸体とフィンの径の関 係,フィンの間隔とフィンの径の関係が大きく変われば,受ける美感は異なってく ると考えられる。 他方,乙12意匠等の公知意匠では,後端面(後端フィンの後面)から電源ケー ブルが引き出されており,そのために後端フィンや中間フィンの上側に貫通孔が設 けられ,又は後端フィンの中心部に孔が設けられていたところ,電源ケーブルの引 き出し位置がどこであるかは,検査用照明器具としての使用態様に関わることであ るから,後端フィン及び中間フィンについて,支持軸体の通過部分以外に貫通孔が なく,その各面が平滑である点は,本件意匠において,公知意匠にはない,需要者 の注意を惹く点であると認められる。
エ 要部の認定
以上によれば,公知意匠との関係や,需要者が着目しその注意を惹くという 観点から,前記基本的構成態様及び具体的構\成態様を総合し,以下の点を本件意匠 の要部とするのが相当である。 前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材である。 後方部材の中心には,検査用照明器具の前方部材の後端面より後方に 延伸する支持軸体が設けられている。 支持軸体には,薄い円柱状の中間フィン2枚及び後端フィン1枚が設 けられている。 後端フィンは,中間フィンよりも厚くなっている。 支持軸体の径は,フィンの径の5分の1程度である。 中間フィン及び後端フィンの径は,前方部材の最大径とほぼ同じであ る。 フィン相互の間隔は,フィンの径の8分の1程度である。 中間フィン及び後端フィンには,支持軸体の通過部分以外に貫通孔は なく,その各面は平滑である。
(4) 被告製品の構成態様\n
別紙「被告製品の図面」及び弁論の全趣旨によれば,被告製品の構成態様は,\n別紙「裁判所認定の構成態様」の「イ号物件」ないし「ヘ号物件」欄記載のとおり\nと認められる(符号は原告の主張をベースにしているが,構成態様の内容は,原告\nも異論がないとしている別紙「被告主張の構成態様」の内容等も踏まえ,一部変更,\n付加した。)。なお,「共通」とあるのは,「本件意匠」欄記載の構成態様と同じ\n構成態様であるという意味である。\n
(5) 本件意匠とイ号物件ないしハ号物件の意匠との類否
ア 本件意匠の要部(前記(3) いし )と前記(4)で認定した被告製品 の構成態様とを対比すると,イ号物件ないしハ号物件については,中間フィンが3\n枚であること(同 参照),支持軸体の径がフィンの径の3分の1強であること(同 参照),フィン相互の間隔がフィンの径の約10分の1ないし約6分の1である こと(同 参照),イ号物件及びハ号物件については,後端フィンの後面中心にね って,その後面又は各面が平滑でないこと(同 参照)といった差異点があり,そ の余は共通点であると認められる。
イ まず,中間フィンの枚数,支持軸体とフィンの径の関係,フィンの間隔 とフィンの径の関係について,大きく相違すれば異なる美感を生じさせる場合があ ることは前述したところであるが,本件意匠とイ号物件ないしハ号物件の各意匠と の差異はわずかであり,格別異なる美感を生じさせるとまでは認められない。
ウ 本件意匠の要部(ク)については、イ号物件ないしハ号物件の中間フィンに 貫通孔はなく,その各面は平滑であるものの,後端フィンについては,ねじ穴又は 貫通孔があり,その後面又は両面が平滑でない点で相違する。 しかしながら,イ号物件及びハ号物件については,後端フィンの後面中心にねじ 穴が設けられているため,ねじ穴自体は支持軸体の中にあって,中間フィンに貫通 孔はなく,ロ号物件については,後端フィンの左右対称位置にねじ穴があって,後 端フィンは貫通しているものの,中間フィンに貫通孔は存しない(別紙「被告製品 の後端フィンの後面に設けられたねじ穴に関する意匠(構成態様)」参照)。\n需要者が検査用照明器具の商品としての特長を把握しようとする際には,正面, あるいは斜め前方,斜め後方から見て,発光部の構造,放熱部の構\造,両者の構造\n的関係を把握しようとすると考えられ,この場合,後端フィンのみならず中間フィ ンにも貫通孔のある乙12意匠のような製品であれば,容易に貫通孔の存在を認識 するのに対し,イ号物件ないしハ号物件の場合,正面,あるいは斜め前方から観察 した程度では,ねじ穴の存在を認識することはなく,後方から観察した場合に初め て後端フィンのねじ穴の存在を認識すると考えられ,ねじ穴があるという機能の違\nいを認識することはあっても,格別これを美感の違いとして認識することはないと 思われる。
エ アないしウを総合すると,本件意匠の要部である前記(3)エ(ア)ないし(ク) とイ号物件ないしハ号物件の構成態様とを対比すると,差異点は存するものの,い\nずれも細部といえる点であって,需要者に視覚を通じて起こさせる美感が異なると いえるような大きな差異点はなく,基本的な構造としてはむしろ共通点が多いから,\nイ号物件ないしハ号物件の意匠は,いずれもこれを全体として観察した場合,本件 意匠と共通の美感を生じさせるものであって,本件意匠に類似するということがで きる。
・・・
(3) 本件意匠の寄与度ないし推定覆滅事由
ア 被告は,本件意匠の被告製品の売上げ(利益)に対する貢献や寄与は低 く,その寄与率は0.2%にも満たないと主張し,推定覆滅事由の存在についても 主張している。これに対し,原告は本件意匠の寄与度は100%であると主張し, 被告の主張を争っている。
イ そこで本件意匠の寄与度ないし推定覆滅事由について検討する。 まず,本件意匠に係る物品は検査用照明器具で,本件意匠はその後方 部材の意匠であるところ,イ号物件ないしハ号物件全体の中で,上記後方部材に相 当する部分が占める割合は,正面視における面積比において,最大でも4割程度と 考えられる(乙18参照)。そして,各物件には,本件意匠に係る物品と同じく, 前方部材には光導出ポート等が設けられ,LED等が内蔵されていると考えられる から,イ号物件ないしハ号物件全体の製造原価の中で後方部材の製造原価が占める 割合は,かなり低いと考えられる。 また,既に検討したとおり,イ号物件ないしハ号物件の意匠と本件意 匠には種々の共通点がみられるものの,これらの共通点に係る構成態様は,検査用\n照明器具の物品分野の意匠において,本件意匠の意匠登録出願前に広く知られた形 態であり,本件意匠の要部とはされない部分も多い。したがって,イ号物件ないし ハ号物件が部分意匠である本件意匠に類似するとしても,これが需要者の購買動機 に結びつく度合いは低いといわざるを得ない。 原告は,本件意匠の実施品とされる「第2世代HLVシリーズ」の製 品の販売開始に当たって,「従来品に比べ2倍以上明るい」こと,「従来より均一 度3倍アップ,明るさも26%アップした」ことを強調し,その特徴として,「低 消費電力・低発熱で環境にやさしい」ことや,「長寿命でメンテナンスコストを削 減」したこと,「軽量・小型設計で場所を取らず省スペース」であることなど,製 品自体の性能や機能\等を強調する一方で,本件意匠には言及すらしていない(甲1 5,16)。また,原告は同製品が掲載されたカタログにおいて,高輝度スポット 照明に関し,電源ケーブルを検査用照明器具の側周面から引き出した図面を掲載し つつも,その宣伝文句として,「明るさと均一度をアップした」ことや,「軽量・ コンパクト設計,しかも低消費電力で長寿命」であることを記載するとともに,製 品の説明において,「高コントラスト撮影が可能」,「従来比2倍の光量アップを\n実現」などと,製品自体の性能や機能\等を強調しており(甲8,乙6),甲17の 製品のカタログにおいても同様であった(甲17)。 被告も,製品のカタログにおいて,「鏡面ワークに最適 軽量・コンパクト」と いうことや,「パッケージ・液体・印字などの透過検査に最適」であることを強調 しており(甲5),乙23添付の他のカタログにおいても同様である(乙23)。 以上によれば,検査用照明器具の需要者は,検査を必要とする製造業者等である ことから,イ号物件ないしハ号物件を購入するに当たり,主に検査用照明器具それ 自体の性能や機能\等に着目すると認められ,本件意匠との類似性が購買の動機とな る程度は高くないといわざるを得ない。
◆判決本文
下記に、問題の意匠が掲載されています。
関連カテゴリー
>> 部分意匠
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2018.11.28
平成30(行ケ)10063 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年11月7日 知的財産高等裁判所
また,本件商標は「エナジア」の称呼を生じ,引用商標2は「エネルギア」の称 呼を生じるが,中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が4音と5音という短 い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから,離隔的観察においても,\n称呼上の相違を十分認識することができる。\nさらに,本件商標が特定の観念を生じないのに対し,引用商標2は原告のブラン ドという観念を生じるから,本件商標と引用商標2とは観念において相違する。 以上によると,本件商標と引用商標2とは,外観,称呼,観念のいずれにおいて も相紛れるおそれはないから,本件商標は,引用商標2に類似する商標には当たら ないものと認められる。
・・・
イ 原告は,引用商標1及び2の「EnerGia」の欧文字は,一般的な 辞書等に掲載されていない造語であるが,1)辞書等の記載,2)先行商標採択例,3) 商標使用例,4)被告の本件商標の使用等の一般的,恒常的な取引の実情において「エ ナジア」の称呼をもって使用されているから,少なくとも「エネルギア」と「エナ ジア」の二つの称呼が生じると主張する。 しかし,前記(2)ウ,(3)イのとおり,引用商標1及び2は,中国地方のみならず 全国で,その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務におい て,「エネルギア」という称呼により,原告の業務に係る役務を表示するものとして\n取引者,需要者の間に広く認識されているものである。そうすると,引用商標1及 び2に接した取引者,需要者は,そのような認識を有するのであるから,引用商標 1及び2を「エネルギア」と称呼するものということができ,引用商標1及び2を 「エナジア」と称呼するものとは認められない。 そして,このことは,「EnerGia」の欧文字が,英語「energy」(エ ナジー)になぞらえて,英語風に「エナジア」と称呼し得ることや,現に「エナジ ア」と称呼させる先行商標採択例や商標使用例があることによって,左右されるも のではない。 また,本件商標の「エナジア」の片仮名文字が「energia」に由来し,被 告ホームページにおいて本件商標が「energia」の文字とともに使用されて いるといった原告主張の事情については,前記アのとおりである。 ウ(ア) 原告は,審決が,引用商標1及び2が「エネルギア」と「エナジア」 の二つの称呼を生じるなど,二つ以上の称呼,観念を生じる場合と認定したにもか かわらず,一つの称呼,観念を生じると認定したことは,商標法4条1項11号該 当性の判断基準に照らし許されないと主張する。 しかし,引用商標1及び2は,いずれも,「エネルギア」の称呼を生じ,原告のブ ランドの観念を生じることは,前記(2),(3)のとおりであり,引用商標1及び2は, 二つ以上の称呼,観念を生じるものではない。
(イ) 原告は,審決のように,対比商標が二つ以上の称呼,観念を生じる場 合でも,一つの称呼,観念のみを生じると認定することは,あたかも禁止権を放棄 し,類似範囲が収縮し消滅したものと取り扱うことになり,商標制度に沿わない結 果を招来するものであって,許されないなどと主張する。 しかし,商標法4条1項11号の類否判断は,商標登録出願された商標に係る査 定時又は審決時において,この商標が引用商標に類似するか否かを判断すべきもの であるから,上記の基準時において,引用商標に接した取引者,需要者において二 つ以上の称呼,観念を生じると認められるときは,その二つ以上の称呼,観念をも って,類否判断すべきである一方,上記の基準時において,引用商標に接した取引 者,需要者において一つの称呼,観念のみを生じると認められるときは,その称呼, 観念をもって,類否判断すべきものである。このように解しても,引用商標に接し た取引者,需要者において一つの称呼,観念のみを生じると認められるときは,こ の称呼,観念をもって類否判断した結果,引用商標と相紛れるおそれのない非類似 である商標については,引用商標との間において出所の混同を生じるおそれはない から,商標制度に沿わないものとはいえない。
(ウ) 原告は,引用商標1及び2が,「エネルギア」と称呼され,中国地方で 周知著名性を獲得しているという事実は,特殊的,限定的な取引の実情であるから, これを考慮することは許されないと主張する。 しかし,引用商標1及び2が,中国地方のみならず全国で,その指定役務である 「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において,「エネルギア」という称呼 により,原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者,需要者の間に広く認\n識されているという事実は,単にその商標が現在使用されている役務についてのみ の特殊的,限定的な取引の実情ということはできないから,本件商標と引用商標1 及び2の類否判断に当たりこれを考慮すべきものである。
(エ) 原告は,審決が,引用商標1及び2が,中国地方を越え,例えば,関 東地方の「電気の供給」の役務の取引者,需要者の間で周知著名性を獲得していた か否かについて,何ら認定していないにもかかわらず,関東地方など周知著名性を 獲得していない地域まで含めて,一つの称呼,観念のみを生じると認定しているこ とは,自己矛盾であるなどと主張する。 しかし,引用商標1及び2が,中国地方のみならず全国で,その指定役務である 「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において,「エネルギア」という称呼 により,原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者,需要者の間に広く認\n識されていることは,前記(2)ウ,(3)イのとおりである。
◆判決本文
関連事件はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.11.27
平成29(ワ)21145 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年8月17日 東京地方裁判所
不競法2条1項3号の「商品の形態」とは,「需要者が通常の用法に従った 使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状 並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感」をいうところ(同条4 項),原告ソフトウェアは,タブレットとは別個に経済的価値を有し,独立して取引の対象となるものであることから「商品」ということができ,また,これを起動する際にタブレットに表\示される画面や各機能を使用する際に表\示される画面の形状,模様,色彩等は「形態」に該当し得るというべきである。
(2) 実質的同一性の有無について
そこで,以下,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアの形態が実質的に同一 であるかどうかについて検討する。
ア 原告は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアは,フィールド領域に作成 されたカード及び連結したカードが表示される点で一致し(一致点1)),こ の一致点は原告ソフトウェアの本質的部分に関するものであると主張する。しかし,学校において黒板等に貼\り付けられていたカードをタブレット上で表現し,複数のカードをプレゼンテーションの順序等に応じて連結することは,抽象的な特徴又はアイデアにすぎず,不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当するものではない。\n原告ソフトウェア及び被告ソ\フトウェアにおけるカード及び連結された カードの具体的な画面表示を比較すると(別紙(3),乙5の21頁「カード 結合」欄2)),1)原告ソフトウェアには,カード右上に円で囲まれた黄色の矢印が表\示されるのに対し,被告ソフトウェアにはそのような表\示はない,2)連結されたカードは,原告ソフトウェアにおいては,フィールド領域各所に配置されたカードが曲線又は直線の矢印で連結されるのに対し,被告ソ\フトウェアにおいては,フィールド領域に平行かつ一直線の形で各カードが直 線で連結される(相違点4)),3)原告ソフトウェアは,黄色の細い曲線等によりカードを結び,各カードを結んでいる線はそれぞれ独立し同一の線ではないのに対し,被告ソ\フトウェアは黒色の太い一つの直線でカード間を結んでいる,4)原告ソフトウェアは連結されたカードを2行で表\示することもで きるのに対し,被告ソフトウェアでは,複数のカードを複数行で表\示するこ とはできない,5)原告ソフトウェアではプレゼンテーション時に最初に表\示 されるカードの左横に黄色の丸で囲まれた「−」の表示があるのに対し,被告ソ\フトウェアでは黒色の○に白抜きで「start」と表示されている,6)原 告ソフトウェアではプレゼンテーションにおいて最後に表\示されるカード の右上に黄色の丸で囲まれた矢印が表示されているのに対し,被告ソ\フトウ ェアでは黒色の丸に白抜きで「−」の表示がされているなどの点で相違し,全体的な印象も類似していないということができる。以上によれば,原告ソ\フトウェア及び被告ソフトウェアでは,カード及び\n連結されたカードの画面表示が実質的に同一であるということはできず,むしろ相当程度異なると認めるのが相当である。
イ 原告は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアは,フィールド領域にラン チャーメニュー表示ボタン,カード作成メニューボタン,カード送受信領域が表\示される点で一致する(一致点2))と主張する。 しかし,フィールド領域にランチャーメニュー表示ボタン,カード作成メニューボタン,カード送受信領域を設けることは,アイデア,抽象的な特徴又は機能\面の一致にすぎず,不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当するものではない。
そして,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアのランチャーメニュー表示ボタン,カード作成メニューボタン,カード送受信領域の具体的な画面表\示を対比すると(別紙(3),乙5の3頁,4頁),1)ランチャーメニューは, 原告ソフトウェアにおいては,画面右に表\示されるタブをタップすることに より画面右側に縦一列で表示されるのに対し,被告ソ\フトウェアにおいては, 画面左上のボタンをタップすることで画面左側に縦一列で表示される(相違点3)),2)カード作成メニューボタンは,原告ソフトウェアでは画面左上部に縦一列で表\示されるのに対し,被告ソフトウェアではフィールド領域をタップすることにより,リング状の表\示がされる(相違点2)),3)カード送受 信領域については,原告ソフトウェアにおいては,メイン画面の左下に「資料箱」,「提出」,「送る」などの個別の提出先のアイコンが設けられているのに対し,被告ソ\フトウェアにおいては,提出先としてメイン画面の中央下に矢印を付した四角いアイコンが設けられているなどの点で相違している。 以上によれば,原告ソフトウェア及び被告ソ\フトウェアでは,ランチャー メニュー表示ボタン,カード作成メニューボタン,カード送受信領域の画面表\示が実質的に同一であるということはできず,むしろ相当程度異なると認めるのが相当である。
ウ 原告は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアは,「カメラ」等の機能を使用すると画面全体に被写体が表\示され,撮影に必要な機能がボタンで表\示される点で一致する(一致点3))と主張する。 しかし,カメラ撮影のための機能を使用すれば,画面全体に被写体が表\示 されるのはその性質上当然であり,カメラ撮影のためにはシャッターボタン など撮影に必要な機能を使用するための表\示が不可欠であるから,一致点3) は機能を使用するために必要な表\示における一致にすぎない。
エ 原告は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアは,原告ソフトウェアの「テキスト」機能\及び被告ソフトウェアの「文字」機能\において,文字入力画面が表示される点で一致する(一致点4))と主張する。 しかし,一致点4)は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアがいずれもカ ードにテキストを入力する機能を有するという機能\面での一致をいうにす ぎず,また,原告ソフトウェア及び被告ソ\フトウェアのテキスト作成画面の 表示(別紙(5))もありふれたものにすぎない。
オ 原告は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアは,描画領域及び各種描画 ツールが表示される点で一致する(一致点5))と主張する。 しかし,一致点5)は,原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアがいずれもカ ードに描画する機能を有するという機能\面での一致をいうにすぎず,また, 原告ソフトウェアと被告ソ\フトウェアの描画作成画面の表示(別紙(6))も ありふれたものにすぎない。
2018.11.21
平成29(ワ)24174 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月24日 東京地方裁判所
イ 被告サーバにおける「注文情報」
(ア) 前記第2の2(4)イ認定のとおり,被告サービスにおいて注文が行われると, 別表のとおり被告サーバの処理が記録されるところ,前記2認定の被告サービスの内容,別表\の各欄の内容及び被告サーバの処理に照らすと,被告サーバにおいて,注文が行われた時点,すなわち,「注文日時」欄記載の日時に,同欄記載の注文を 識別するための注文番号,「注文日時」欄記載の注文日時,「取引」欄記載の新規 注文又は決済注文の別,「通貨P」欄記載の取引対象となる通貨の種類,「売」欄 記載の売り注文であるか否か,「買」欄記載の買い注文であるか否か,「新規注文」 欄記載のイフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,「執行条件」欄記載の成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別,「指定R」欄記載の指定価格,「期\n限」欄記載の注文の有効期限といった個々の注文の内容を規定する情報が生成され ていると推認することができる。 また,被告サーバにおいて,市場に発注された個々の注文が約定等したことが検 知されると,「注文状況」欄に,その注文が「無効」,「約定」,「取消」のいず れの状況にあるかが,「約定R」欄に,約定価格が,「約定等日時」欄に,注文が 約定等した日時が,すなわち,約定等の結果に係る情報が記録されていると推認す ることができる。 そうすると,少なくとも,被告サーバに記録されている注文番号,注文日時,新 規注文又は決済注文の別,取引対象となる通貨の種類,売り注文であるか,買い注 文であるか,イフダンオーダーを構成する新規注文の注文番号,成行注文,指値注文,逆指値注文の注文種別,指定価格,注文の有効期限といった個々の注文の内容\nを規定する情報は,個々の買い注文又は売り注文を行うために必要となる情報であ るということができ,本件発明の「注文情報」に該当する。 (イ) 以上より,被告サーバでは,本件発明の構成要件BないしHの「注文情報」に相当する情報が生成されていると認められる。
ウ 小括
前記のとおり,被告サーバでは,構成要件BないしHの「注文情報」に相当する情報が生成されているところ,これらの構\成要件の充足性について,後記(2),(3)に おいて検討する構成要件G及びHを除いた構\成要件BないしFの充足性については 次のとおりであり,被告サーバは構成要件BないしFをいずれも充足する。すなわち,本件発明の「注文情報」に関する前記判示を踏まえ,被告サーバの構\成を構成要件BないしFと対比すると,被告サーバは,例えば,番号114,111,108,105の買い注文に係る買い注文情報のような複数の買い注文情報を\n生成する買い注文情報生成手段を備えるものであるから,「金融商品の買い注文を 行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段」(構成要件B)を備えており,また,例えば,番号113,110,107,104の売り注文に\n係る売り注文情報のような複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段を 備えるものであるから,「前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約 定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文 情報生成手段とを有する注文情報生成手段」(構成要件C及びD)を備えている。さらに,被告サーバは,別表\に「注文状況」欄及び「約定等日時」欄等があることから明らかなように,「前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検 知手段とを備え」(構成要件E)るものであり,また,例えば,番号113,110,107,104の売り注文のように,指定価格が114.90円,114.2\nなるものであるから,「前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は, それぞれ等しい値幅で価格が異なる情報」(構成要件F)を備えている。
(2) 争点1−2(被告サーバは構成要件Hを充足するか)
ア 構成要件Hは,「前記相場価格が変動して,前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する\nと,前記注文情報生成手段は,前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて,前記 複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する…」というものであり,文言上,「複 数の売り注文のうち,最も高い売り注文価格の売り注文」1個が約定したときに 「複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り 注文価格の情報を含む売り注文情報」1個が生成される構成を含むと解するのが相当である。\nこれを被告サーバについてみると,前記2(2)認定のとおり,被告サーバは,約定 検知手段が,例えば,番号113,110,107,104の売りの指値注文のよ うな複数の売り注文のうち,指定価格を114.90円とする最も高い売り注文価 格の番号113の売り注文が約定されたことを検知すると,注文情報生成手段は, この検知の情報を受けて,指定価格を番号113の指定価格114.90円より0. 62円高い115.52円とし,これを含む売り注文情報である番号96の新たな 売りの指値注文を生成するものであるから,構成要件Hを充足する。
イ 被告は,構成要件Hは,「複数の売り注文」全てが約定したときに,「注文情報生成手段」が新たに「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ことを意味す\nると解すべきであるとし,その理由として,1)構成要件Hの「最も高い売り注文価格の売り注文注文が約定されたことを検知」したときは,「最も高い売り注文価格」\nより低い価格の売り注文が既に約定していることが明らかであるから,構成要件Gの「前記複数の売り注文情報」が全て約定したときを意味すること,2)本件明細書 の【0145】ないし【0147】においては,全ての売りの指値注文が約定して 初めて,新たな買いの指値注文(B1ないしB5)及び売りの指値注文(S1ない しS5)の全てが同時に行われていること,3)構成要件Hの「前記注文情報生成手段」が引用している構\成要件C及びDにおいて,「注文情報生成手段」は「複数の売り注文情報」全て「を生成する」ものであるとされていることなどを主張する。 しかしながら,被告が理由として挙げる1)については,構成要件Hの文言にない限定を付すものである上,「注文情報生成手段」が「複数の売り注文情報」を「一\nの注文手続」で生成することを規定しているにすぎない構成要件Gについて,「注文情報生成手段」が常に「複数の売り注文情報」を生成することを規定するとの限\n定を加えた解釈を前提としていることから,採用することはできない。 また,被告が理由として挙げる2)についても,本件明細書の【0145】ないし 【0147】は,構成要件Hに対応する「シフト機能\」に「決済トレール機能」等を組み合わせた実施例にすぎないから採用し得ない。後記4(1)のとおり,全ての売 り注文が約定しなければ「シフト機能」を適用できないとするものでもない。したがって,被告の主張は採用することができない。
ウ また,被告は,被告サーバが「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報」に係る「売り注文情報を 生成する」時点は,「前記約定検知手段が,前記複数の売り注文のうち,最も高い 売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知」したときではなく,買いの成行 注文の約定を検知したときであるから,構成要件Hを充足しないと主張し,買いの成行注文が売り注文に先行して行われていることを示す事情として,別表\において,番号96の売りの指値注文が「2014/11/7 22:29」に約定すると, 同一時刻に番号89の買いの成行注文だけが行われ,約定しているのに対し,番号 85の売りの指値注文は「2014/11/7 22:30」に行われていること などを指摘する。 被告の主張の趣旨は必ずしも明確でないが,仮に,個々の注文が有効なものとし て市場に発注された時点で,被告サーバで「注文情報」が生成されると主張するも のであれば,前記2(3),3(1)イ認定のとおり,被告サーバにおいて,市場に発注前 の売りの指値注文及び逆指値注文であっても,他の注文とともに,注文が行われた 時点で,注文番号等の注文情報が生成されていることと整合せず,採用することが できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.11.16
平成29(ネ)10073 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記前提事実からすると,被控訴人サービスは,買い注文から入った場 合は,取引開始後の最初の買い注文を成行注文とし,同注文と対をなす売り注文を 指値注文とし,同売りの指値注文が約定することをトリガとして新たな価格帯での 取引として,買いの成行注文に係る注文情報を生成させることとし,その後,同買 いの成行注文と対をなす売りの指値注文が約定することをトリガとして,更に新た な価格帯での取引を行い,以降,これを繰り返すという構成を採用していることが\n認められる。
被控訴人サービスの上記構成を前提として,被控訴人サービスの構\成と本件発 明の構成とを比較すると,まず,本件発明においては,第一注文情報及び第二注文\n情報とも指値注文とする構成であるのに対し,被控訴人サービスにおいては,1)第 一注文情報のうち取引開始後最初の取引の第一注文情報と,相場価格の変動後の新 たな価格帯での最初の取引の第一注文情報のみを成行注文とする構成である点で異\nなり,この点で,被控訴人サービスは構成要件E2)を充足しないが,特定の事項を トリガとして生成する成行注文においては,トリガとなる事項をどのように構成す\nるかの点もその内容となっているものと解されること,被控訴人サービスにおいて は,2)相場変動後の新たな価格帯での最初の成行注文に係る注文情報の生成を,旧 価格帯における成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして行わせる構成と\nしたことが,上記1)の構成と一体となって技術的な意義を有するものと解されるこ\nとから,上記1)及び2)の構成(以下「本件相違構\成」)を本件発明の構成との相違\n点として把握して検討するのが相当である。 この点,控訴人は,被控訴人サービスと本件発明とは,本件発明が「検出され た前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合に」,新\nたな価格の「買いの指値注文」を設定するのに対し,被控訴人サービスは,「検出 された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となり,売りの指\n値注文が約定した場合に」,新たな価格の「買いの成行注文」を設定する点で相違 すると主張して均等侵害の主張をしているが,同主張は,被控訴人サービスにおい ては変動後の価格帯で生成されるすべての買い注文が成行注文であるとして,本件 設定できることからすると,相場価格が指定価格となることをトリガとする構成が\n想到し易いものと考えられる。
また,前記1のとおり,本件発明は,同じ価格帯でイフダンオーダーを自動的 に繰り返すことのできる従来の発明の課題を解決したものであり,同じ価格帯での イフダンオーダーを自動的に繰り返すことを前提としているところ,被控訴人サー ビスのように本件相違構成を採用すると,新たな価格帯における取引を行わせるた\nめに必要な相場価格の変動幅は,取引開始時に設定された第二注文情報の指値注文 と取引開始時の相場価格の差額と一致することになり,その結果,同じ価格帯での イフダンオーダーを継続させるためには,相場価格が変動した場合に,旧価格帯の 成行注文と対をなす売りの指値注文の約定をトリガとして,旧価格帯における指値 注文に係る注文情報群も生成させる構成を採用するなどの工夫をする必要が生じる\n(被控訴人サービスでは,同一の価格帯でのイフダンオーダーを継続させるために は,No.113の売りの指値注文の約定をトリガとして,新たな価格帯の取引で あるNo.97の買いの成行注文に係る注文情報を生成するだけでなく,旧価格帯 の取引であるNo.100及びNo.99の各注文に係る注文情報群をも生成させ る必要がある。なお,本件発明においても,顧客が「予め設定された値」を第二注\n文情報の指値価格と第一注文情報の指値価格の差額以下の値と設定することを可能\nとするのであれば,同じ価格帯でのイフダンオーダーを継続させるためには,相場 価格が変動しても,旧価格帯での取引を継続させる構成としておく必要があるが,\n上記の設定ができないようにすれば,上記の構成とする必要はない。)。このよう\nな理由から,被控訴人サービスは,本件相違構成を採用するためには,相場価格が\n変動した場合に,旧価格帯の成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして, 旧価格帯における指値注文に係る注文情報群も生成させる必要があり,この点を考 慮すると,本件発明に本件相違構成を適用するに当たっては,相応の検討が必要で\nあったというべきである。 以上のことに,本件全証拠によっても,被控訴人サービスが開始された時点に おいて,本件相違構成を採用した金融商品取引に係るサービスが存在したことや,\n本件相違構成を開示した文献があったとは認められないことを併せ考慮すると,本\n件相違構成に係る置換をすることは当業者が容易に想到することができたとは認め\nられないというべきである。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第3要件(置換容易性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.11.13
平成29(行ケ)10117 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年11月6日 知的財産高等裁判所
よってまず,引用例1から本件取消決定が認定した引用発明1を認定する ことができるかどうかについて検討する。 特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」は,当業者が,出願 時の技術水準に基づいて本願発明(本件特許発明)を容易に発明することが できたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから,当該刊行物の記 載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。また,本件特許 発明は物の発明であるから,進歩性を検討するに当たって,刊行物に記載さ れた物の発明との対比を行うことになるが,ここで,刊行物に物の発明が記 載されているといえるためには,刊行物の記載及び本件特許の出願時(以下 「本件出願時」という。)の技術常識に基づいて,当業者がその物を作れる ことが必要である。
かかる観点から本件について検討すると,引用例1の記載及び本件出願時 の技術常識を考慮しても,引用発明1のデバイスを当業者が作れるように記 載されているとはいえない。理由は以下のとおりである。 ア 本件取消決定は,引用発明1をP1タンパク質に対するモノクローナル 抗体を用いて,患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエの検出を 行うラテラルフローデバイスに関する発明として認定しているところ,ラ テラルフローデバイスは,イムノクロマトグラフィー法に基づく検出デバ イスであり,イムノクロマトグラフィー法による抗原検出においては,抗 体と抗原がサンドイッチ複合体を形成する必要があると認められ(甲8〜 10,弁論の全趣旨),また,モノクローナル抗体の場合には,抗原を挟 み込む二つの抗体が同じものでは不都合であり,少なくとも,二つの異な る抗体を用いることが必要であると認められる(この点は特に当事者に争 いがない。)。 その一方で,異なる二つのモノクローナル抗体でありさえすれば,抗体 と抗原がサンドイッチ複合体を形成するとの本件出願時の技術常識も見当 たらず,また,サンドイッチ複合体を形成しさえすれば,必ず患者サンプ ル中のマイコプラズマ・ニューモニエを検出できると直ちにいうこともで きない。
たとえば,引用例2の199頁図1には,捕獲抗体として特異性の異な る二つのポリクローナル抗体を用い,ペルオキシダーゼ標識モノクローナ ル抗体(検出抗体)を変えてマイコプラズマ・ニューモニエ抗原の捕獲ア ッセイを行った試験の結果を表す二つのグラフが示されている。捕獲抗体\nが抗Mp−IgG(右)の場合,試験されたペルオキシダーゼ標識抗体で は,いずれも,標識抗体100ngで450nmにおける吸光度が2を超 え,標識抗体1μgにおいて,450nmにおける吸光度が3を超えてい る。これに対し,捕獲抗体が抗P1−IgG(左)の場合には,標識抗体 がP1.25又はM74では,1μgで450nmにおける吸光度が3を 超えていても,標識抗体がM57では,1μgでも吸光度が1に満たない。 このように,同じ捕獲抗体を用いた場合であっても,検出抗体によって検 出感度が異なり,サンドイッチ複合体の形成に基づく検出は,抗体の組合 せによって,検出感度が大きく異なる場合があると理解されるから,モノ クローナル抗体を用いてサンドイッチ複合体の形成に基づく検出を行う場 合には,適切な抗体を組み合わせて用いる必要があると認められる。 本件取消決定が認定した引用発明1のラテラルフローデバイスも,サン ドイッチ複合体の形成に基づく抗原の検出デバイスであるから,P1タン パク質に対するモノクローナル抗体を用いて,患者サンプル中のマイコプ ラズマ・ニューモニエを検出するラテラルフローデバイスを作るためには, 第1のモノクローナル抗体と第2のモノクローナル抗体として適切な組合 せのモノクローナル抗体を用いる必要があると認められる。 そこで,第1のモノクローナル抗体と第2のモノクローナル抗体の組合 せに関して引用例1の記載を検討するに,引用例1には,ラテラルフロー デバイスに用いる二つの抗体について,具体的なモノクローナル抗体の組 合せを示す記載は見当たらない。また,本件出願時において,ラテラルフ ローデバイス等のサンドイッチ複合体を形成できる具体的なモノクローナ ル抗体の組合せが周知であったことを示す証拠もない(引用例2の199 頁図1の左側のグラフに示されている実験において,P1.25とM74 は,それぞれ,抗P1−IgG又は抗Mp−IgGを捕獲抗体とした場合 に,抗原を検出可能としていることから,当該捕獲抗体と抗原とからなる\nサンドイッチ複合体を形成するものと考えられるが,引用例2に記載され ていることをもって,直ちにこれらの抗体が周知であるということはでき ないし,そもそも,当該捕獲抗体はいずれもポリクローナル抗体であるか ら,異なる二つのモノクローナル抗体の組合せが明らかにされているとは いえない。ほかにサンドイッチ複合体を形成できる具体的なモノクローナ ル抗体の組合せを明らかにする証拠はない。)。 次に,引用例1に記載された具体的なイムノクロマトグラフィー(IC T)デバイスについての唯一の実施例である実施例4は,抗rCARDS 抗体を用いたもので,P1タンパク質に対する抗体を用いたものではない。 また,引用例1におけるP1タンパク質に対する抗体に関する具体的な記 載は,実施例3のみであるが,実施例3における抗原の検出は,サンドイ ッチ複合体の形成とは異なる,市販の二次抗体である抗ウサギ又は抗マウ ス抗体を用いた方法によるものである。したがって,これらの実施例の記 載から,サンドイッチ複合体を形成可能なモノクローナル抗体を知ること\nはできない。
さらに,引用例1には,P1タンパク質に対するモノクローナル抗体と して,マウスのモノクローナル抗真正P1タンパク質抗体H136E7(【0 012】)とrP1に対するモノクローナル抗体(【0096】)に関す る記載があるが,P1タンパク質に対する具体的なモノクローナルは,H 136E7が記載されているにとどまり,rP1に対するモノクローナル 抗体については,その当該モノクローナル抗体を生産する細胞株も,モノ クローナル抗体のアミノ酸配列等の情報も,H136E7とのサンドイッ チ複合体の形成の有無に関する手掛かりとなる情報も記載されていない。 このような引用例1の記載に基づいて,ラテラルフローデバイスを作るた めには,モノクローナル抗体として一つはH136E7を用いるとしても, もう一つ,H136E7とサンドイッチ複合体を形成可能な別のモノクロ\nーナル抗体を用いる必要があるが,引用例1には,そのようなモノクロー ナル抗体の構造について手掛かりとなる記載がなく,何らかの方法でモノ\nクローナル抗体を入手し,それらのモノクローナル抗体が,H136E7 とサンドイッチ複合体を形成可能であるかを調べ,試行錯誤によって,H\n136E7と組み合わせて患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニ エを検出するラテラルフローデバイスを構成できるモノクローナル抗体を\n見つけ出す必要がある。
以上を踏まえれば,たとえ様々なモノクローナル抗体を得る技術自体は 周知技術であるとしても,本件取消決定が認定した引用発明1のラテラル フローデバイスは,引用例1の記載及び本件出願時の技術常識から,直ち に作ることができるものとはいえない。 したがって,引用例1に引用発明が記載されている(あるいは,記載さ れているに等しい)ということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2018.11.13
平成29(行ケ)10191 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月29日 知的財産高等裁判所
イ(ア) 本願明細書には,前記(1)イのとおり,中間水について,少なくとも− 40度付近の温度において,規則化(コールドクリスタリゼーション)する傾向を 強く有するものと推察されること,規則化する強い傾向の存在により,不規則な状 態で凝固した状態からの加熱において,−40度付近で規則化に伴う発熱がみられ ること,規則化に伴う発熱量は,規則化を生じている水の量,すなわち,中間水の 量に比例するものと推察されることが記載されている。 (イ) 前記(1)ウの甲1〜5の記載によると,中間水の量(Wfb)は,次の式 のとおり,低温結晶化した水におけるエンタルピー変化量(ΔHcc)と,水の融解熱 (Cp)から得ることができることが理解される。
Wfb=ΔHcc/Cp
この式を変形すると,ΔHcc=Cp×Wfb となり,低温結晶化した水におけるエン タルピー変化量(ΔHcc),すなわち,コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量 は,比例定数を Cp として,中間水の量(Wfb)に比例するといえる。 このことも,前記アと同様の理由により,日本バイオマテリアル学会の構成員や\n関係者には,平成21年の時点において,知られていたと認められるのであって, 本願明細書に記載された内容の「中間水」の量の計算方法は,本願出願時において, 当業者の技術常識になっていたと認められることができるというべきである。 そして,Cp は,純水の融解熱と等しいと考えられ,純水の融解熱が 334J / g であ ることも,前記ウの甲2及び甲4の記載並びに証拠(甲11)及び弁論の全趣旨に よると,当業者の技術常識であったと認められる。 したがって,当業者は,中間水の量の算出方法については,本願明細書の記載及 び本願出願時の技術常識に基づいて明確に理解することができたというべきである。
(3)ア 被告は,本願明細書から,「コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量 は,中間水の量に比例するものと推察される。」という認定aだけではなく,「中間 水の量は,コールドクリスタリゼーションに伴う発熱ピークの挙動(コールドクリ スタリゼーションに伴う発熱量は含水量の増加に伴って増加するが,ある含水量以 上では変化しなくなること)と,全含水量とから求めることができる。」という認定 b及び「中間水の量は,各含水量におけるコールドクリスタリゼーションに伴う発 熱量と0度付近の吸熱量の関係から中間水の最大量を求めてW0(試料の乾燥重量) で除することにより求められる。」という認定cも認定できるところ,これらの認定 が共存するため,本願明細書から,当業者が中間水の量をどのように算出したらよ いのか明確に理解することはできない旨主張する。 認定bは,前記(1)イ(イ)b(b)の本願明細書の記載に基づくものであり,認定cは, 前記(1)イ(イ)b(c)の本願明細書の記載に基づくものであるが,いずれも,中間水の量 を求める方法についての具体的な内容の説明はされていない。 一方,認定aは,前記(1)イ(イ)b(a)の本願明細書の記載に基づくものであるが,前 記(2)イのとおり,上記記載を含む本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識から, 中間水の量の算出方法を明確に理解することができる。 そうすると,当業者は,本願明細書に前記(1)イ(イ)b(b)及び(c)の記載があるからと いって,本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識から明確に理解できる中間水 の算出方法を理解できなくなるというものではないというべきである。 イ 被告は,当業者は,発明の詳細な説明の記載に基づき,中間水のコール ドクリスタリゼーションは通常の水の凍結とは異なる相転移であると理解されるか ら,中間水のコールドクリスタリゼーションの単位潜熱(中間水の量を算出するた めの比例定数)は,通常の水の凍結の場合の単位凝固潜熱334J/gとは異なる 値であると考えるのが自然である旨主張する。 しかし,前記(2)イのとおり,比例定数(Cp)は,純水の融解熱に等しいと考えら れている。本願明細書に記載されたPMEAのコールドクリスタリゼーションに伴 う発熱量の最大値を中間水量で除した値が313J/gであるとしても,純水の融 解熱が334J/gであることは,当業者の技術常識である以上,当業者は,31 3J/gの方が誤差を含む数値であると考えるのか通常であると解されるのであっ て,このことにより,当業者が,中間水のコールドクリスタリゼーションの単位潜 熱(中間水の量を算出するための比例定数)が,純水の単位凝固潜熱334J/g とは異なる値であると考えるとはいい難い。 ウ 被告は,甲1〜5は,本願発明者やその共同研究者による文献であり, 中間水の概念は,本願発明者らの研究グループが独自に提唱したもので,本願発明 者らの研究グループ以外の当業者に,本願出願時までに広く知れ渡り,技術常識に なっていたことを示す証拠はない旨主張する。 「中間水」の概念が本願発明者であるAにより構築されたことは,前記(2)アのと おりであるが,前記(2)ア,イのとおり,「中間水」の概念及びその量の算出方法は当 業者の技術常識となったことが認められる。
エ 被告は,甲5は本願明細書で引用したものではなく,仮に当業者が甲5 を本願明細書の記載から探し当てることができたとしても,その記載内容が実質的 に発明の詳細な説明に記載されたに等しいものであるということはできない旨主張 する。
しかし,本願明細書の【0007】には【先行技術文献】として,「【非特許文献 1】バイオマテリアル 28−1,2010」と記載されているから,当業者であれ ば,これは,バイオマテリアルという雑誌の28巻1号(出版年2010年)とい うものであると理解する。そして,甲5は,その雑誌のその号に掲載されている。 しかも,上記の「非特許文献1」は,本願明細書の【0013】においても,「所定 量の水を含水した水和性組成物を一旦十分に冷却し,その後に比較的ゆっくりした\n速度で加熱した場合に,0℃以下の特定の温度域において所定の発熱を生じると共 に,−10度近辺から0度までの広い温度範囲において吸熱が観察されることが明 らかにされている(例えば,非特許文献1等を参照)。」という形で引用されている。 そうすると,当業者は,本願明細書の記載から,容易に甲5に行き着くものと考え られるから,甲5は本願の発明の詳細な説明【0007】で引用されたものである と認められる。
そして,甲5が,「中間水」の概念及びその量の算出方法が当業者の技術常識とな ったことを裏付け得るものであることは,前記(2)ア,イのとおりである。 オ 被告は,本願発明の「中間水の量が1wt%以上,且つ30wt%以下」 がどの時点の中間水の量を意味するかについて,発明の詳細な説明に,発熱量が最 大値になる含水量の場合と飽和含水になった時点での含水量の場合という,相異な る二通りの記載があるから,本願発明の技術的範囲が定まらない旨主張する。 しかし,前記(2)イのとおり,当業者は,本願明細書の記載及び出願当時の技術常 識に基づいて,中間水の量は,コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量と水の 融解熱から得ることができることが理解されるから,当業者が本願補正発明を実施 するに当たり,水和性組成物について,発熱量が最大値の中間水の量と,飽和含水 になった時点の中間水の量の二通りが記載されているとしても,水和性組成物の中 間水の量は,含水量にかかわらず,コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量と 水の融解熱から一義的に決まるものであって,本願補正発明の技術的範囲が定まら ないということはできない。
・・・
本件審決は,当業者が本願出願時の技術常識に照らしても本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができないから,表2に中間水量が記載され\nた具体的な組成物以外のものについては課題が解決できると認識することはできな い旨判断したが,当業者が本願出願時の技術常識に照らして本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができることは,前記2のとおりであるから, 本件審決のサポート要件の有無の判断は,前提を欠き,誤りがある。
4 取消事由3(実施可能要件違反)について
本件審決は,当業者が本願出願時の技術常識に照らしても本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができないから,本願補正発明1及び4を当
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.11.13
平成29(ワ)10038 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月25日 東京地方裁判所(47部)
前記(1)アないしウ及びオの認定事実によれば,原告代表者は,顧客である被\n告代表者から自動洗髪機の開発依頼を受け,先行特許の調査等を経て,エアバ\nッグを利用する方法を着想するに至り,それを踏まえて本件特許発明の構成が\n全て開示されている全体構想計画案等を自ら作成したものであるから,本件特\n許発明の発明者に当たるというべきである。
他方,被告代表者については,前記(1)イ,エないしカの認定事実からすれば, 自動洗髪機の開発につき原告代表者に依頼し,本件特許発明につき特許出願す\nる段取りを整えたり,事業計画を策定して公的補助を受ける準備をしたりした ことは認められるが,本件特許発明の完成に当たり,発明者と評価するに足る だけの貢献をした具体的事実は認められない。
これに対し,被告は,かねてから人間の手に近い感覚で頭皮のマッサージが できる自動洗髪装置の開発を志向していた被告代表者が,平成26年2月頃,\n被告手動洗髪用具の指状の突起部と同様の形状の突起部を有する装置で,被洗 髪者の頭を覆い,エアバッグ(袋状体)の振動を利用して頭皮をマッサージし ながら洗う機械を着想し,乙第2号証の図面を作成し,その後の同年3月7日 の打合せで,上記技術内容を被告代表者に対し説明して,具体的に機械の設計\nを依頼したものであって,この時点で本件特許発明は既に完成していたのであ るから,本件特許発明の発明者は被告代表者であって,原告代表\者ではない旨 を主張し,これに沿う証拠としては,被告代表者の陳述書(乙20)及び本人\n尋問における供述(以下,併せて「被告代表者の供述等」という。)がある。\n
しかしながら,被告代表者の供述等については,乙第2号証の図面につき本\n件特許発明の構成が開示されているとは認め難く,他に上記打合せの時点で本\n件特許発明を被告代表者が完成させていたと認めるに足りる客観的な裏付け\nがないこと,前記(1)サで認定したとおり,乙第3号証に係る被告の主張等が大 きく変遷等していること(被告は当初,原告代表者が作成した全体構\想計画案 は被告代表者が作成した乙第3号証をほぼなぞっただけのものである旨主張\nしていたのに,原告から矛盾点の指摘を受けるや主張を変遷させ,被告代表者\n本人尋問においても,上記の当初の主張内容を訴訟代理人に説明していないな どと不合理な供述をしていること),被告代表者の供述等は,本件特許発明を\n着想するに至った経緯について曖昧かつ抽象的な内容に終始していること等 を併せ考慮すれば,その信用性は低いものといわざるを得ない。また,本件特 許発明の発明者が被告代表者であったと認めるに足りる他の証拠も見当たら\nない。そこで,被告の前記主張は採用できない。
さらに,被告は,前記(1)カで認定したとおり,原告代表者がAから電子メー\nルに添付された出願関係書類の案の送付を受けた際,被告代表者が発明者とな\nっていること等につき何ら異議を述べず,本件訴訟に至るまで自らが発明者で あるとの主張を一切してこなかった点を指摘するが,前記(1)アで認定した原告 の業態からすれば,前記(1)カで認定したとおり,原告が開発した機械を製造す ることにより経済的利益を得られる限り,特許の取得等についてはこだわらな いという方針をとることも不合理ではないことからすれば,上記の点から直ち に被告代表者が本件特許発明の発明者ないしは共同発明者であったと推認す\nることはできず,原告代表者が本件特許発明の発明者であったという前記認定\nを左右するものではない。以上のとおり,本件特許発明の発明者は原告代表者であって,被告代表\者ではない。そうすると,原告代表者が本件特許発明の特許を受ける権利を有する一方,被告は本件特許発明の特許を受ける権利を有さないから,被告による出願は冒\n認出願であって特許法123条1項6号に該当する。したがって,原告代表者\nから特許を受ける権利を承継した原告は,被告に対し,特許法74条1項に基 づく特許権移転登録手続請求権を有する。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2018.11.13
平成28(ワ)38103 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月17日 東京地方裁判所
(1)原告は,まず,原告が太陽光発電装置の請負契約を締結する場合の請負代金 額を基に,太陽光発電パネルの出力1kw当たりの請負代金額は32万円であると して,これに本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じた1億1581万440 0円を民法709条所定の損害であると主張する。 しかしながら,太陽光発電装置の施工について,被告が本件各土地で施工してい なければ,原告がこれらを受注して施工することができたと認めるに足る証拠はな いから,原告の主張する上記の損害は被告の行為と相当因果関係のある損害である と認めることはできない。
(2) 原告は,次いで,本件特許に係る「単位数量当たりの利益の額」(特許法1 02条1項)は太陽光発電パネルの出力1kwを1単位として算定すべきであると して,太陽光発電パネルの出力1kw当たりの利益の額は9万8000円であり, これに本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じた3546万8160円を特許 法102条1項による損害額であると主張する。
しかしながら,原告の上記の主張は,アルバテック又は原告による太陽光発電装 置の施工に係る見積書(甲22の1,甲23の1)等の書面に基づくものであり, これらが実際の取引金額を反映したものであると認めるに足る証拠はないから,本 件各土地における太陽光発電装置の施工に対応する原告の単位数量当たりの利益の 額を算定する根拠として不十分である。\nその他本件特許に係る単位数量当たりの利益の額を認めるに足る証拠はなく,し たがって,特許法102条1項による損害額として,原告の主張する上記の損害を 認定することはできない。
(3)ア 原告は,さらに,原告が本件特許の実施許諾をする場合の実施料は出力1 kw当たり3万円であるとして,これに本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗 じた1085万7600円を特許法102条3項による損害額であると主張する。 イ そこで検討すると,証拠(甲24)によれば,原告は,平成25年12月1 5日,他社との間で,本件特許に係る通常実施権を許諾する旨の特許権実施許諾契 約を締結しており,同契約3条(1)において,実施料については,本件特許に係る施 工方法を用いて施工された太陽光発電パネルの出力1kwに対して3万円を乗じた 額とされたことが認められる。そして,本件全証拠によっても,この実施料額が高 額にすぎて不相当であると認めることはできない。 したがって,本件発明の実施に係る実施料率としては,太陽光発電パネルの出力 1kw当たり3万円と認めるのが相当であり,本件における特許法102条3項に よる損害額は,3万円に本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じて算定するの が相当である。 そうすると,本件各土地の太陽光発電パネルの出力は,前記第2の2前提事実(4)のとおりであって,合計361.92kwであるから,本件における特許法102 条3項による損害額は合計1085万7600円(本件土地1につき3万円に84. 24kwを乗じた252万7200円,本件土地2につき3万円に277.68k wを乗じた833万0400円の合計)である。
ウ これに対し,被告は,特許権の実施料率が請負代金の10%強となることは およそ考えられず,請負代金を基準とした場合にはその1%程度の金額にとどまる 旨主張するが,その理由を具体的に主張しておらず,裏付けとなる証拠を提出して いないから,実施料率を基礎付ける事情として採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2018.11. 5
平成29(ワ)1129 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成30年9月21日 東京地方裁判所
以上のとおり,高気圧酸素補給カプセルにおいて,その全体形状が胴 部及び側部からなる円筒状をしていること(構成A),胴部の長手方向\nに正面視左端側から略中央まで及び,周方向に略中央からから上端を超 えた位置に及ぶ横長隅丸矩形状の開口部を設けること(構成B),胴部\nの内周側壁側に開口部の長手方向にスライドするスライド式ドアを設 けること(構成C)は,いずれも先行意匠にみられるものであるところ,\nその構成態様はその機能\や使用方法に基づくありふれた態様であり,取 引者,需要者の注意を惹く程度はそれほど大きくないということができ る。
d これに対し,原告は,本件意匠の基本構成態様を個別に開示する公知\nIV意匠が存在していたとしても,本件意匠における胴部における開口部の 配置及び位置並びにドアの構成の組合せを開示する公知意匠は存在し\nないと主張する。 しかし,上記各構成は先行意匠に普通に見られるありふれた態様であ\nり,取引者,需要者の注意を強く惹くものであるとはいえないことは前 記判示のとおりであり,同各構成を組み合わせることにより,取引者,\n需要者に強い印象を与えるような構成となるということもできない。\n また,原告は,上記各先行意匠は本件意匠に係る物品とはその性質を 異にするので,本件意匠の美感を検討するに当たりこれらの意匠を参照 することは相当ではないと主張する。 しかし,上記各先行意匠に係る物品は,いずれも酸素や大気等を充填 させた空間を有し,利用者が同装置内に入り横たわるなどした状態で充 填された酸素や大気等の補給を受ける点で本件意匠に係る物品と用途 及び機能を共通にするものであるから,本件意匠と被告各意匠の類否の\n検討に当たり,これらの意匠を参照することを妨げる理由はないという べきである。
e したがって,構成A〜Cは,基本的構\成態様を構成するものではある\nが,これらの構成が要部であるということはできない。
(イ)a 他方,本件意匠は,前記のとおり,側部がいずれも部分球形状であり, 透明で内部のベッドを覗き見ることを可能にする構\成態様(構成b),\nドアは透明な胴部の円弧に沿う形状であり,閉めた状態でも内部のベッ ドを覗き見ることを可能にする構\成態様(構成c)を備えている。\n この点について,本件公報(甲3)の【意匠の説明】には,以下のと おりの記載がある。 「カプセル両端の部分球形状に突出した部分は透明であり,内部のベ ッドを覗き見ることができる。カプセルの胴部分の出入口に設置されて IVいるドアは透明であり,閉めた状態でも内部のベッドを覗き見ることが できる。ドアを閉じた状態の参考斜視図及びドアを途中まで開けた状態 の参考斜視図において,透明部分には円弧状の平行斜線を施している。」 上記のとおり,本件公報の【意匠の説明】には,カプセル両端の部分 及びドアが透明であり,内部のベッドを覗き見ることができる構成とな\nっていることが強調され,胴部における開口部の配置及び位置やドアの 構成との組合せについての記載は存在しない。そして,上記各参考斜視\n図には,透明な側部部材及びドアの構成態様とともに,これらの透明な\n部分越しに見ることのできる高気圧酸素補給カプセル内部のベッドや 補強リブの構成態様などが示され,透明部分を設けることによって,物\n品外部の構成要素と物品内部の構\成要素が一体となって,本件意匠全体 の美感を形成している様子が示されている。
本件意匠のこのような特徴,特に,胴部のドア部分にとどまらずドア より大きな部分球形状の側部全体が透明となっているという構成態様\nにより,利用者は,外部から同物品を見る場合にはこれらの透明な部分 を通じて内部のベッドや補強リブなどを目にすることのできるととも に,内部に横たわった場合は,同部分を通じて内部の構成要素に加えて\n外部の景観を目にすることができる。かかる特徴を備えることにより, 本件意匠は,透明な部分がない又は少ない同種物品と比較して,利用者 を含む取引者,需要者に対し,開放感があって明るく広々した印象を与 えるとともに,物品外部の構成要素と物品内部の構\成要素の形状が一体 となって本件意匠全体の美感を形成する点において看者に強い印象を 与えると考えられる。
b これに対し,原告は,側部が透明であることは,意匠を構成する形状を\n補足的に特定する素材を示すにすぎないと主張する。 しかし,本件意匠に係る物品の側部が透明であることは,単に意匠を構\n成する素材を特定するにとどまるものではなく,その美感に大きな影響を 与えることは前記判示のとおりである。
また,原告は,筐体の一部を透明,半透明,不透明に変更する程度のこ とは一般的に行われており,本件意匠の透明の側部を半透明,不透明に変 更したとしても,美感に大きな影響を与えないと主張する。 しかし,上記先行意匠においても,胴部のドアを透明にした上で,更に 側部全体を透明にしているものは存在しないので,酸素カプセル等の側部 及び胴部のドアを透明にすることが一般的でありふれたものであるとい うことはできない。そして,側部及びドアを透明にすることにより,外部 の構成と内部の構\成が一体となって本件意匠の美感を形成し,また,本件 意匠に係る物品が明るく開放的な印象を与えることは,前記判示のとおり である。
c したがって,本件意匠の要部は,物品の側部全体及びドアが透明であり, 内部のベッド等を覗き見ることができる構成(構\成b,c)にあるという べきである。
イ 本件意匠と被告各意匠の類否
被告各意匠の基本的構成態様及び具体的構\成態様は前記のとおりである ところ,本件意匠と被告各意匠は,その要部において構成態様が相違するこ\nとは明らかである。これにより,被告各意匠においては,取引者,需要者が 本件意匠のような開放感があって明るく広々とした印象を受けることはな く,また物品外部の構成要素と物品内部の構\成要素が一体となって本件意匠 全体の美感を形成することもない。このように,本件意匠と被告各意匠とは その美感が大きく異なるものである。 したがって,本件意匠と被告各意匠がその構成態様において類似している\nということはできない。
2018.11. 5
平成28(ワ)9003 意匠権等侵害差止等請求事件 平成30年9月7日 東京地方裁判所
原告は,原告商品の形態と被告商品の形態との間の他の共通点(形態 IV(ア),(オ)及び(コ))も創作的であると主張するが,これらの共通点に係る 形態は,女性用コートとして一般的なものであり,特に特徴的なもので あるということはできない。 また,原告商品と被告商品は,いずれもビジューの付いた装身具が設 けられ,その装着位置,形状において共通すると認められるが,女性用 コートにおいてビジューの付いた装身具を設けること自体が特徴的であ るということはできず,また,原告商品のビジューブローチは取り外し 可能であるのに対し,被告商品のビジューボタンがコートに縫い付けら\nれているという相違点も存在するので,この点をもって原告商品と被告 商品が実質的に同一であるということもできない。 以上によれば,原告商品と被告商品との間の上記各共通点をもって両 商品の実質的に同一であるということはできないというべきである。
ウ 原告商品と被告商品の相違点は,上記(3)イ記載のとおりであると認め られるが,このうち,ポケットは,原告商品においては,コート胴部の 両側に水平状に形成され,略横長長方形状のフラップが取り付けられて おり,コート前面において需要者の目を引くアクセントとなっていると いうことができる。 これに対し,被告商品においては縦の切替え線に沿って布部材がコー ト本体に縫い付けられ,フラップが形成されていないので,ポケットは それほど目立たず,コート前面は比較的シンプルで縦に流れる線が需要 者の目を惹く態様となっているということができる。 以上によれば,原告商品と被告商品の前面については,ポケットの形 状の差異により,需要者が受ける印象が相当程度異なるというべきであ る。
エ また,原告商品と被告商品とは,背面における飾りベルトの有無が相 違することは,前記のとおりである。 原告商品における飾りベルトは,腰部に水平方向に設けられ,その幅 も太い上,原告商品の背面には同ベルトに匹敵する目立つ構成部分は存\n在しないことから,当該飾りベルトは,コート背面において特に需要者 の注目を惹くものであるということができる。そして,この点において は,原告自身も,そのウェブサイトにおいて,「バックスタイルのベル トがポイント!!」(乙6),「バックウエストには飾りベルトを効か せて,後ろ姿にもメリハリをプラス」(甲7の2)などと強調しており, このことは,原告自身も飾りベルトが原告商品のデザイン上の特徴点で あるとの認識を有していたことを示している。 これに対し,被告商品では,飾りベルトが設けられておらず,切替え 線が設けられているにとどまることから,その背面は比較的シンプルで 目立つ構成部分が存在せず,すっきりした印象を与えるということがで\nきる。
以上によると,原告商品は,その胴部のほぼ同じ高さに飾りベルトと ポケットが取り付けられていることから,コートの正面視,側面視,背 面視ともに,横方向に流れる強い印象を与える構成が需要者の目を惹く\nのに対し,被告商品は,その前面及び背面ともに需要者の目を惹く態様 の構成が設けられていないため,全体としてシンプルな印象であり,身\n体のラインに沿った縦の線が需要者の目を惹く態様となっているという ことができる。このため,原告商品と被告商品は,コートの正面視,側 面視,背面視ともに,需要者に異なる印象を与えるというべきである。
オ 原告商品と被告商品のフードとを対比すると,原告商品に取り付けら れたフードは,背面視においてその横幅が肩口に及ばず,側面視におい て膨らみの少ないものであるのに対し,被告商品に取り付けられたフー ドは,背面視においてその横幅がが肩口まで及び,側面視において膨らみ の多い大きさである点で異なると認められる。このようなフードの大き IVさや形状の差違は,コート背面における美感に影響を与えるものであり, 飾りベルトの有無やフードとコート本体の色合いの違い(形態(サ))もあ いまって,需要者に背面におけるデザインが異なるとの印象を与えるも のであるということができる。
カ 以上のとおり,原告商品と被告商品との形態の相違点は,需要者の注 目を集める形態についての差違であり,その美感に対して異なる印象を 与えるものであるから,両者を実質的に同一の形態ということはできな い。
(5) 原告の主張について
これに対し,原告は,被告商品のポケットやベルト等の形態は,女性用 コートとしてありふれたものにすぎず,原告商品の形態をこれに置き換え ることは極めて容易である上,その相違点は,部分的かつ些細なものであ り,全体の形態に影響を与えないと主張する。 しかし,被告商品のポケットやベルト等の形態が特に特徴的なものでな く,置換が容易であるとしても,被告商品において飾りベルトやポケット の形状が需要者の目を惹き,コート全体の美感に影響を及ぼすものである ことは前記判示のとおりであり,その相違点が部分的かつ些細なものであ るということはできない。 また,原告は,平成28年から平成29年にかけて雑誌に掲載された女 性用コートの説明文から着目点を抽出したところ,ベルトやポケット等に 注目した記載は非常に少ないとの結果を得たと主張する。 しかし,上記の結果においてもポケットやベルトが着目点として一定程 度挙げられているように,女性用コートのポケットやベルトはコートの胴 部という目につき易いところに配置され,そのデザインも多様であること から,需要者がコートを選択する際の着目点となることは否定し難い。ま た,商品の形態が実質的に同一かどうかは,事案ごとに個別的に判断すべ IVきところ,本件においては,被告商品における飾りベルトやポケットの形 状が需要者の目を惹き,コート全体の美感に影響を及ぼすものであること は前記判示のとおりである。
◆判決本文
前者の関連事件はこちらです。
関連カテゴリー
>> 意匠その他
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2018.11. 5
平成29(ワ)27980 債務不履行に伴う契約解除により返還請求と,その契約不履行と相当因果関係にある損害の賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月25日 東京地方裁判所
◆特許5926470号
前記前提事実,各項末尾に記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事
実が認められる。
(1) 被告Bは,特許の翻訳を業とする被告会社の代表取締役であり,被告会社\nが設立される以前は,比較的大手の特許事務所に勤務していたが,弁理士で
はない。原告も,そのことを認識していた。
(2) 原告は,本件特許発明の米国特許出願のため,平成28年1月,被告会社
に本件明細書等の翻訳を一定の報酬支払を約して依頼し,被告会社はこれを
承諾した(本件契約)。
(3) なお,原告は,本件契約以前,本件明細書の翻訳を翻訳者である訴外Dに
も依頼していたため,被告会社は,当初は訴外Dによる翻訳をチェックして
いたが,当該翻訳に適切でない部分が多かったため,次第に翻訳を初めから
行うことになっていった。(甲36,乙50,弁論の全趣旨)
(4) 翻訳の対象となる本件明細書等は,それが記載された特許公報が本文だけ
で69頁,図も合わせると81頁にも及ぶ非常に大部なものである上,その
内容は,原告自身も自認するように,相当に複雑で難解なものであった。(甲
7,乙17,23,46,47)
(5) 本件契約が締結された同年1月当時,米国特許出願における特許請求の範
囲の記載(日本語)は確定していなかった。原告は,少なくとも同年2月1
5日,翻訳の対象となる特許請求の範囲の記載に修正を加えた。(乙3,4,
弁論の全趣旨)
(6) 同年2月22日には,原告は被告Bに対し,自らが翻訳ソフトを購入し,\n翻訳者が抜けのない翻訳をしているかを自分で確認する旨記載したメールを
送信した。(乙6)
(7) 同年3月3日には,原告は被告Bに対し,被告会社が修正を加えた翻訳を
訴外インド人弁理士に送付し,同人が1か月程度で校正を行い,被告会社が
最終版を作成するとの手順を示すメールを送信した。(乙7)
(8) 同日以降も,原告は,翻訳の対象となる本件明細書等について,断続的に
修正等を行い,その修正等についての翻訳を,被告会社に指示した。その際,
まず訴外Dに翻訳をさせ,当該翻訳を被告会社に送付し,それを参考にして
翻訳するよう指示していた。同年4月11日,原告は,被告会社に対して
,「収束に向かってください。拡散した自分が,どんどんと文章を広げました。
D様もその為に,意味不明になりました。自分にも責任があります。」とメ
ールした。しかし,同月16日には,「基本請求項を早朝作成します。出来
た後に,再度,B様とC様で打合せをしてください。結果が大丈夫なら,そ
の他の従属項を3人で作成します。」などとメールし,同日の後刻には,「大
変迷走させまして,無駄な時間をお掛けしました。」などとメールした。(乙
8ないし21,50)
(9) 同年4月17日,被告会社は,「ご確認いただき,修正すべき点がありま
したらご連絡ください。特に問題がないようであればインド代理人への送付
をお願い致します。」,「エンドレスな作業となっておりますので,ここで
一度区切りとさせてください。」などとメールに記載して,翻訳を一旦終了
し,原告に当該翻訳をメールにて送付した。この時点で,本件明細書等の大
部分について翻訳が終了していた。(甲47,弁論の全趣旨(平成30年8
月16日付け原告準備書面23,26頁))
(10) 同日以降も,原告は,累次にわたって,特許請求の範囲の記載の修正等,
それに伴う明細書等の修正等を行い,その都度,被告会社にその修正等につ
いての翻訳を指示し,このような指示は少なくとも同年5月17日まで続い
た。その間,原告は,被告会社が原告に送付した翻訳について修正や変更を
求めたり,翻訳の内容について質問をしたりすることはなかった。(乙23
ないし41,50)
(11) 原告は,同年5月19日(米国時間),被告会社の事務所において,本件
米国出願を行った。被告会社は,本件米国出願までの間に,本件翻訳を原告
に対して引き渡した。
(12) 原告は,同年1月から7月にかけて,被告会社に対し,本件契約の代金と
して合計269万2000円を支払い,被告会社はこれを異議なく受領した。
(甲6)
(13) 米国特許商標庁は,平成29年2月7日(米国時間),本件拒絶理由通知
を発出した。本件米国出願から本件拒絶理由通知までの間に,原告から被告
らに対して,本件翻訳の内容について批判が述べられたり,質問等がされた
りしたことはなかった。(甲11,弁論の全趣旨)
(14) 原告は,同年4月3日,被告会社に対し,内容証明郵便により,本件翻訳
についての報告を求めた。また,原告は,同年5月18日,被告会社に対し,
内容証明郵便により,被告会社に債務不履行があるとして,本件契約の解除
の意思表示をし,契約代金の返還を求めた。(甲33,34)\n
・・・・
前記認定事実のとおり,本件契約は,原告が被告会社に対し,本件明細書
等の翻訳を一定の報酬支払を約して依頼し,被告会社がこれを承諾したもの
であること,その後,原告は,本件契約の対価として,被告会社に対して合
計269万2000円を支払い,被告会社はこれを異議なく受領したことが
認められる。そうすると,本件契約は,被告会社が仕事の完成を約し,原告
がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約したものであるから,その
法的性質は請負契約(民法632条)であると解するのが相当である。
なお,原告は,本件契約における被告の業務内容には米国特許出願事務や
PCT国際出願事務も含まれているかのような主張をしており,被告はこれ
を争っているところ,本件の全証拠を検討しても,本件契約に米国特許出願
事務及びPCT国際出願事務の委任が含まれているものと認めるに足りる証
拠はない。原告は,被告会社が原告に対してPCT国際出願に関する助言を
行っているメール(甲39)を証拠として提出するが,これは被告会社が原
告の問い合わせに応じて返答しているものにすぎず,このようなやり取りを
もって本件契約にPCT国際出願事務の委託が含まれていたものと認めるこ
とはできない。また,原告は被告事務所において本件米国出願を行っている
が,そのことから本件契約に米国特許出願事務の委任が含まれていたものと
認めることもできない。
2018.11. 1
平成28(ワ)3856 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月19日 東京地方裁判所(29部)
以上のとおり,「第1の表示欄」は動画を表\示するために確保された領域(動画表\n示可能領域),「第2の表\示欄」はコメントを表示するために確保された領域(コメン\nト表示可能\領域)であり,「第2の表示欄」は「第1の表\示欄」よりも大きいサイズで いずれも固定された領域であると解されるところ,被告ら各装置においては,動画表\n示可能領域(被告ら装置1における「StageオブジェクトA」,被告ら装置2及\nび3における<iflame>要素又は<video>要素)とコメント表示可能\領 域(被告ら装置1における「CommentDisplayオブジェクトD」,被告 ら装置2及び3における<canvas>要素)は同一のサイズであるから,被告ら 各装置は,「第1の表示欄」及び「第2の表\示欄」に相当する構成を有するとは認め\nられない。したがって,被告ら各装置は,本件発明1−1の「第1の表示欄」(構\成要 件1−1C,1−1E,1−1F)及び「第2の表示欄」(構\成要件1−1D,1−1 E,1−1−1F)を充足するとは認められず,本件発明1−1の技術的範囲に属するとは認められない。 そして,被告ら各装置は,同様に,本件発明1−5の「第1の表示欄」及び「第2\nの表示欄」(構\成要件1−5J)を充足せず,そうである以上,「第2の表示欄」を構\ 成要素とする「コメント表示部」(構\成要件1−1D,1−2H,1−5J,1−6L)も充足しないから,本件発明1−2,1−5及び1−6の技術的範囲に属するとは認 められない。 また,本件発明1−9及び1−10は,発明の対象が「プログラム」であるが,発 明の対象を「表示装置」とする本件発明1−1及び1−2と対応するものである。したがって,被告ら各プログラムは,本件発明1−1及び1−2と同様に,「第1の表\ 示欄」(構成要件1−9B,1−9E)及び「第2の表\示欄」(構成要件1−9E)を\n充足せず,本件発明1−9を引用している本件発明1−10の構成要件1−10Hも\n充足しないから,本件発明1−9及び1−10の技術的範囲に属するとは認められない。以上のとおりであるから,被告ら各装置及び被告ら各プログラムは,文言上,本件 発明1の技術的範囲に属するとは認められない。
・・・
ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかっ た技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから,特許発明にお\nける本質的部分とは,当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に 見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。そして,\n上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて, 特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で,特許発明に係る特許請 求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部\n分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(知財高裁平成27年 (ネ)第10014号同28年3月25日特別部判決・判時2306号87頁参照。)。
イ これを本件についてみると,前記2(3)で説示したとおり,本件発明2は,複数 のコメントが書き込まれても,コメントの読みにくさを低減させることができる表示\n装置,コメント表示方法及びプログラムを提供することを目的とするものであって,\nコメント表示部によって表\示されるコメントが他のコメントと重なるか否かを判定 し,コメントが重なると判定した場合に,コメント同士が重ならない位置にコメント を表示させるようにし,複数のコメントが表\示される場合において,コメント同士が 動画上で重なってしまい,各コメントが判読できなくなってしまうことを防止するこ とができるようにするとともに,動画の再生中に他の端末装置から入力されたコメン トをリアルタイムに受信して当該動画上に表示し,そのコメントをダイナミックに変\n動させることにより,リアルタイムな双方向のコミュニケーションを可能にし,大人\n数でコメントを交換する面白みを増加させる発明である。上記の「動画の再生中に他 の端末装置から入力されたコメントをリアルタイムに受信して当該動画上に表示し,\nそのコメントをダイナミックに変動させることにより,リアルタイムな双方向のコミ ュニケーションを可能にする」という作用効果は,コメント配信サーバが端末装置か\nらコメント情報を受信してそれを送信するタイミングがリアルタイムに行われるこ と,すなわち,構成要件2−1Cに規定されているように「前記コメント配信サーバ\nが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信 されるコメント情報を受信」との構成によって実現されているのであり,本件特許2\nの出願経過においても,上記構成は,表\示すべき文字情報があらかじめ決定されてい る従来技術との比較において,「ユーザの端末装置から送信されるコメントを受信し て表示するものであり,コメントを受信する毎に,表\示するコメントがダイナミック に変動する点」が相違すると説明されている。そうすると,構成要件2−1Cは,動\n画の再生中に他の端末装置から入力されたコメントをリアルタイムに受信して当該 動画上に表示し,そのコメントをダイナミックに変動させることにより,リアルタイ\nムな双方向のコミュニケーションを可能にする」という作用効果を奏する構\成を具体 的な構成として特定したものであり,この構\成が従来技術にみられない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分であり,本件発明2における本質的部分であるというべき\nである。
ウ 他方,前記のとおり,被告ら各装置は構成要件2−1Cを充足せず,被告ら各\nプログラムは構成要件2−9Bを充足しないから,被告ら各装置及び被告ら各プログ\nラムが本件発明2の本質的部分を備えているということはできず,本件発明2と被告 ら各装置及び被告ら各プログラムは本質的部分において相違すると認められる。
(3) 第5要件(特段の事情)について
前記2(2)において認定したとおり,本件特許2の出願経過として,1)特許庁審査官 は,平成22年11月24日を起案日とする拒絶理由通知書(乙24)において,出 願当初の特許請求の範囲請求項1ないし6及び8ないし12に係る各発明について, 特許法29条2項の規定により特許を受けることができない旨を通知し,2)原告は, 平成23年1月31日付け手続補正書(乙25)において明細書を補正し,請求項1 に「前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信し,前記コメント情報記憶部に 記憶する受信部と,」との構成を,請求項9に「前記コメント配信サーバが前記端末装\n置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメン ト情報を受信し,」との構成を付加して変更し,3)特許庁審査官はこれに対して特許 査定をしたものである。 上記の出願経過からすれば,原告は,拒絶理由を回避するために構成要件2−1C\n及び構成要件2−9Bを備えた発明に限定して特許を受けたものといえるから,上記\n構成要件の全部又は一部を備えない発明について,本件発明2の技術的範囲に属しな\nいことを承認したか,少なくとも外形的にそのように解される行動をとったものと理 解することができる。 したがって,均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり,均等の第5 要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.10.31
平成29(行ケ)10129 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年5月24日 知的財産高等裁判所
前記のとおり,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否か は,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請 求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発 明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決 できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がな くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 また,発明の詳細な説明は,「発明が解決しようとする課題及びその解 決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が 義務付けられているものである(特許法施行規則24条の2)。 以上を踏まえれば,サポート要件の適否を判断する前提としての当該発 明の課題についても,原則として,技術常識を参酌しつつ,発明の詳細な 説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。 かかる観点から本件発明について検討するに,本件明細書の発明の詳細 な説明には,米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を 制御することなく加えると,プロテアーゼによりアミノ酸,オリゴペプチ ドが生成し,うまみ調味料様の雑味がついてしまい,用途が限られたこと (【0002】),食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖 化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが,甘味, コク(ミルク感)等の風味は十分に改善されておらず,必ずしも満足でき\nるものではなかったこと,さらに,グラノーラ,パンケーキ等が流行する 一方,牛乳アレルギー,大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり,風味が 改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと(【0003】)な どが背景技術として記載されている。その上で,発明の詳細な説明には, 発明が解決しようとする課題として,「本発明は,米糖化物含有食品のコ ク,甘味,美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ね た結果見出されたものである。すなわち,本発明は,コク,甘味,美味し さ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに,従 来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可 能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある(【000\n6】)。
これらの記載からすれば,本件発明は,「コク,甘味,美味しさ等を有 する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものである ことが明確に読み取れるといえる。 イ これに対し,異議決定は,「本件発明1の課題は,本件特許明細書の『コ ク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』(【0 006】)との記載及び実施例(【0031】〜【0043】)において, 『コク(ミルク感)』,『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について 評価を行っていることから,『コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供すること』と認められる。」と,一旦は上記アと同様に本 件発明1の課題を認定しながら,最終的なサポート要件の適否判断に際し ては,「本件発明1の課題は,上記aのとおり,具体的には,実施例1− 1のライスミルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて 優位な差を有するものを提供することであ(る)」とその課題を認定し直 し,課題の解決手段についても,「本件発明1が課題を解決できると認識 できるためには,…実施例1−1のライスミルクに比べてコク(ミルク感), 甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要 である。」としている(異議決定12頁16〜25行)。 この点について,被告は,発明が解決しようとする課題とは,出願時の 技術水準に照らして未解決であった課題であるから,本件発明1の「コク, 甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題 は,本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品(具体的には,実\n施例1−1のライスミルク)に比べて,コク,甘味,美味しさ等を有する 米糖化物含有食品を提供することであり, したがって,異議決定において は,本件発明1の課題について,「具体的には,実施例1−1のライスミ ルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて優位な差を有 するものを提供すること」としたものである(したがって,異議決定の課 題の認定に誤りはない)と主張する。 確かに,発明が解決しようとする課題は,一般的には,出願時の技術水 準に照らして未解決であった課題であるから,発明の詳細な説明に,課題 に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては,技 術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないでは ないと考えられる。
しかしながら,記載要件の適否は,特許請求の範囲と発明の詳細な説明 の記載に関する問題であるから,その判断は,第一次的にはこれらの記載 に基づいてなされるべきであり,課題の認定,抽出に関しても,上記のよ うな例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。 したがって,出願時の技術水準等は,飽くまでその記載内容を理解する ために補助的に参酌されるべき事項にすぎず,本来的には,課題を抽出す るための事項として扱われるべきものではない(換言すれば,サポート要 件の適否に関しては,発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる 以上は,これに従って判断すれば十分なのであって,出願時の技術水準を\n考慮するなどという名目で,あえて周知技術や公知技術を取り込み,発明 の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でな いし,相当でもない。出願時の技術水準等との比較は,行うとすれば進歩 性の問題として行うべきものである。)。 これを本件発明に関していえば,異議決定も一旦は発明の詳細な説明の 記載から,その課題を「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食 品を提供すること」と認定したように,発明の詳細な説明から課題が明確 に把握できるのであるから,あえて,「出願時の技術水準」に基づいて, 課題を認定し直す(更に限定する)必要性は全くない(さらにいえば,異 議決定が技術水準であるとした実施例1−1は,そもそも公知の組成物で はない。)。 したがって,異議決定が課題を「実施例1−1のライスミルクに比べて コク(ミルク感),甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提 供すること」と認定し直したことは,発明の詳細な説明から発明の課題が 明確に読み取れるにもかかわらず,その記載を離れて(解決すべき水準を 上げて)課題を再設定するものであり,相当でない。 以上によれば,異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず, 被告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2018.10.30
平成28(ワ)6539 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成30年10月18日 大阪地方裁判所
被告ごみ箱の意匠は本件意匠に類似する(争いがない)から,被告ごみ箱を販売 する行為については,本件意匠権を侵害する行為である。
・・・
被告ごみ箱の形態が原告ごみ箱のそれと実質的に同一であり(争いがない),こ の形態同一性は依拠の事実も推認させるところ,この推認を覆す事情は認められな いから,被告ごみ箱は原告ごみ箱の形態を模倣した商品であると認められる。した がって,被告が平成27年1月31日までに被告ごみ箱を販売した行為(被告ごみ 箱販売1)については,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に当たる。 他方,被告が同年2月1日以降に被告ごみ箱を販売した行為(被告ごみ箱販売2及 び3)については,原告ごみ箱が最初に販売された日から3年が経過しており,同 号所定の不正競争行為に当たらない(同法19条1項5号イ)。
上記(1)イのとおり,被告が平成27年2月1日から同年6月14日まで の間に被告ごみ箱を販売した行為(被告ごみ箱販売2)については,不正競争行為 に当たらないし,本件意匠権侵害について過失があったとは認められないところ, 原告は,被告ごみ箱販売2については公正な自由競争秩序を著しく害するものであ るから,一般不法行為を構成すると主張する。\nしかし,現行法上,創作されたデザインの利用に関しては,著作権法, 意匠法及び不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律がその排他的な使用権等の 及ぶ範囲,限界を明確にしていることに鑑みると,創作されたデザインの利用行為 は,各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護され た利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではない\nと解するのが相当である。 したがって,原告の主張が,被告が原告ごみ箱の商品形態を模倣した被告ごみ箱 を販売したことが不法行為を構成するという趣旨であれば,不正競争防止法で保護\nされた利益と同様の保護利益が侵害された旨を主張しているにすぎないから,採用 することはできない。
ウ また,これと異なり,原告の主張が,被告が被告ごみ箱を販売すること によって原告の原告ごみ箱に係る営業が妨害され,その営業上の利益が侵害された という趣旨であれば,上記の知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の 利用による利益とは異なる法的に保護された利益を主張するものであるということ ができる。しかし,我が国では憲法上営業の自由が保障され,各人が自由競争原理 の下で営業活動を行うことが保障されていることからすると,他人の営業上の行為 によって自己の営業上の利益が害されたことをもって,直ちに不法行為上違法と評 価するのは相当ではなく,他人の行為が,殊更に相手方に損害を与えることのみを 目的としてなされた場合のように,自由競争の範囲を逸脱し,営業の自由を濫用し たものといえるような特段の事情が認められる場合に限り,違法性を有するとして 不法行為の成立が認められると解するのが相当である。 そして,本件では,原告の主張を前提としても上記特段の事情があるとは認めら れない。
・・・
被告は,上記(1)アのとおり,平成27年10月8日頃,原告から,被告ごみ箱を 輸入,販売する行為が本件意匠権を侵害するとの指摘を受けたことから,同月22 日付けで,被告に対し,被告ごみ箱を販売する行為は本件意匠権を侵害する可能性\nがあると判断して直ちに販売を中止した旨回答した(甲5)だけでなく,現に販売 を中止し,本件訴訟においても被告ごみ箱を販売する行為が本件意匠権を侵害する ことになることを争っていない(弁論の全趣旨)。したがって,被告がさらに被告 ごみ箱を輸入するおそれは認められず,また,被告は中国の業者から被告ごみ箱を 輸入して販売しているにすぎない(乙19)から,被告ごみ箱を自ら製造するおそ れも認められない。 しかし,被告は,被告ごみ箱を平成26年7月に合計3024個輸入し(乙1 6),それを平成27年10月22日の販売中止までに合計774個販売した(乙 10)と認められるから,多数の在庫を保有していると推認されるところ,被告が それら在庫を廃棄したことをうかがわせる証拠はない。そうすると,被告は,現在 も被告ごみ箱の在庫を保有していると考えざるを得ず,そうである以上,被告が被 告ごみ箱を販売するおそれを否定することはできない。したがって,被告ごみ箱の 差止請求については,その販売及び広告宣伝の差止めを求める限度で理由がある。
・・・
a 被告の過失ある本件意匠権侵害行為の期間は,被告ごみ箱販売1に 係る平成27年6月15日から同年10月21日までと認められるところ,被告ご み箱の単位数量当たりの仕入原価が205.543円であることは当事者間に争い がなく,この期間の被告による被告ごみ箱の合計販売数量は前記のとおり666個 と認められる。そして,被告がこの期間に被告ごみ箱を666個販売して得た売上 高が16万0380円であること(乙11)に照らせば,被告ごみ箱の販売の単位 数量当たりの売上高は240.811円(小数点第4位以下四捨五入)である。した がって,被告が被告ごみ箱を666個販売して得た利益は,2万3488円(1円 未満四捨五入)であると認められる。
(240.811−205.543)×666≒23,488
そうすると,2万3488円が意匠権者である原告の受けた損害の額と推定され るところ,上記推定を覆滅する事由に関する主張,立証はないから,原告の損害額 は,2万3488円であると認められる。
b これに対し,原告は,被告の平成27年7月及び同年10月におけ るインテリア計画メガマックス千葉NT店に対する販売については,販売額が仕入 原価を下回っており,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法第6項に 規定する不当廉売に当たるから,被告ごみ箱の販売の単位数量当たりの売上高を算 定するに当たっては,上記販売における売上額に基づくべきではなく,平成26年 8月における販売の売上額に基づくべきである(これに従えば,単位数量当たりの 売上高は540円となる。)と主張する。 しかし,販売額が仕入原価を下回るからといって直ちに独占禁止法が禁止する不 当廉売に当たるわけではない上,意匠法39条2項は,侵害者が実際に得た利益の 額をもって意匠権者の損害の額と推定する規定であるから,侵害者が原価以下で販 売した場合でも,それが実質的に見て侵害物の廃棄処分と同視し得るといった事情 のない限り,実際の販売額に基づいて侵害者の利益を算定すべきものである(意匠 権者がそれにとどまらない損害額の賠償を求めるためには,同条1項による損害額 を主張立証する道が用意されている。)。そして,上記で原告が指摘するインテリ ア計画メガマックス千葉NT店に対する販売のうち平成27年7月のものについて は,被告が原告から通知書(甲4)を受領する前の時期であるから,通常の取引行 為によるものと見るべきであり,その販売単価と同年10月の販売単価は同額であ る(甲10)から,それらの販売を実質的に見て侵害物の廃棄処分と同視すること はできない。 また,原告が被告ごみ箱の販売の単位数量当たりの売上高を算定するに当たって 基礎とすべきであるという平成26年10月における被告の販売(被告ごみ箱販売 1における販売)については,上記(1)イのとおり,被告が不法行為(本件意匠権侵 害)に基づく損害賠償責任を負うものではない。
関連カテゴリー
>> 意匠その他
>> 著作物
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2018.10.29
平成29(行ケ)10113 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月25日 知的財産高等裁判所
特許法36条6項2号の趣旨は,特許請求の範囲に記載された発明が明確 でない場合に,特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となることによ り生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで,特許を受 けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載のみならず, 願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願時にお ける技術的常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不 利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断すべきものと解 される。
(3)ア そこで検討するに,本件明細書には,泡に関し,「本明細書で用いられ る「泡」は,混合されて,可変長の時間持続する構造を有する小さい気泡\nのマスを形成する液体及び気体を意味する。」(【0036】),「気泡 は,液体のフィルムで取り囲まれた気体のセルである。」(【0037】) との定義が記載されている。また,本件発明の発泡性組成物の作用効果に 関し,本件発明の組成物は,発泡性であるために,適用された部分に留ま ることができ(【0015】),表面上に容易に広がる泡として分配でき\nる(【0018】)ものであって,空気と混合されるときに安定な泡を与 え,この泡は,個人的洗浄用又は消毒目的のために使用でき,例えばユー ザーが両手をこすったとき又は表面上に塗布されたときに壊れること(【0\n041】),本発明の重要かつ驚くべき成果は,消毒に適する組成物が40% v/vより多量のアルコールを含有すること,そして低圧容器及びエアゾール 包装容器の両者から化粧品として魅力的な泡として分配され得ること(【0 044】)がそれぞれ記載されている。
イ この点に関連して,泡に関する技術常識についてみると,「入門講座 泡 の化学」と題する論文(オレオサイエンス第1巻第8号。2001年発行。 甲12)には,「深い井戸からくみ上げた水に生ずる泡はきわめて微小な 気泡が多数水中に分散している。このように気体が液体または固体に包ま れた状態を気泡(Bubble)という。泡は各種界面活性物質,または界面活 性剤の気・液界面への吸着によって起こる現象であって,洗濯時の洗濯機 の中の液やビールの泡のようにこれが多数集まって薄膜を隔てて密接に存 在するものを泡沫(Foam)と呼ぶ。気泡と泡沫の区別は形態的であるが前 者はただ一つの界面を有するのに対し,後者は2つの界面を有する。」(8 63頁左欄)との記載がある。 この論文の公開時期に鑑みれば,泡には,形態的に区別される気泡と泡 沫とがあり,気泡(Bubble)は,気体が液体又は固体に包まれた状態を指 し,ただ1つの界面を有するのに対し,泡沫(Foam)は,気泡が多数集ま って薄膜を隔てて密接に存在し,2つの界面を有するものであることは, 親出願の出願日当時における当業者の技術常識であったと認められる。
ウ 以上のとおり,上記アに摘示した本件明細書に記載された定義と,本件 発明における泡の作用効果に関する記載からすると,本件発明における「泡」 との語は,上記イ記載の泡沫を意味するものであることは明らかである。 そして,本件明細書の記載及び親出願の出願日当時における当業者の技 術的常識を基礎とすると,本件発明1に係る特許請求の範囲の記載が,第 三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。
(4) 原告の主張について
原告は,本件明細書の段落【0036】における1)「可変長の時間持続す る構造」が表\す時間の長さ,2)「構造」とは,気泡と気泡のマスのいずれを\n指すのか,3)「小さい気泡」とは,何と比較して小さいのか,がいずれも不 明であるから,請求項1の記載が不明確であると主張する。 しかし,上記(3)において説示したとおり,当業者は,本件発明における「泡」 との語が泡沫を意味すること,泡沫とは,気泡が多数集まって薄膜を隔てて 密接に存在するものであるから,これはすなわち気泡のマスであること,そ して,本件明細書の段落【0036】における「構造」とは気泡のマスであ\nることをそれぞれ理解できるというべきである。 また,当該段落の「可変長の時間持続する」との語については,本件発明 の組成物が発泡性組成物であることによる作用効果に関する本件明細書の記 載からすると,本件発明の組成物は,適用された部分に留まることができ, かつ,表面上に容易に広がる泡として分配できるものであって,例えばユー\nザーが両手をこすったとき又は表面上に塗布されたときに壊れる程度の安定\n性を有するほどに,泡の持続時間が様々であることと理解できる。 さらに,「小さい」との語についても,上記本件明細書における本件発明 の作用効果に関する記載に照らせば,化粧品として魅力的な泡といえる程度 の大きさをいうものと解するのが相当である。 したがって,この点についての原告の主張を採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.10.26
平成29(ワ)22884 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月5日 東京地方裁判所
相違点1−2’は,単に公然実施品1において,「補強板」であるサッシュを金 属板からなる補強板とサッシュに分けて,補強板をサッシュに当接させるようにす れば実現される構成にすぎない。
また,公知技術である特開2002−270353号(乙13。以下「乙13公 報」という。)や公知技術である特開平7−6869号(乙11。以下「乙11公 報」という。)には,誘導加熱調理器においてサッシュと本体ケース連結金属板と を別部材により構成して両者を当接させてねじで接合することが記載されている。\n製造コストが高い機械加工により製造した部品を,製造コストが安い機械加工であ るプレス加工により製造するために金属板部品に置き換えることは,原告も主張す るとおり,機械加工分野における技術常識であるから,公然実施品1において製造 コストを下げるために乙13公報及び乙11公報に示されたプレス加工可能な金属\n板を採用することは当業者における単なる設計的事項の適用の問題にすぎず,極め て容易になし得ることである。 なお,原告は,相違点1−2は,トッププレートの幅を本体ケースよりも大きく したことに関連して新たに見出した課題に関するものであると主張するが,これは 相違点1−1の存在を前提とした主張であって前提において誤りである。また,原 告は,公然実施品1のサッシュをサッシュと金属板とに分けることに想到し得たと しても,金属板を長くする理由はなかったと主張するが,公然実施品1のガラス板 を長くすれば,それに伴い,サッシュと本体ケースを接続する金属板を長くするこ とは当然であるから,原告の主張は失当である。
c 小括
以上によれば,本件発明は,公然実施品1と同一であるか,本件出願日当時,当 25 業者が公然実施品1に基づいて容易に発明をすることができたものであって,新規 性又は進歩性を欠く。よって,本件特許は特許法29条1項2号又は同条2項に違 反してされたものであって,同法123条1項2号の無効理由があるから,特許無 効審判により無効とされるべきものである。 したがって,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができない(特許 法104条の3第1項)。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.10.26
平成29(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月24日 知的財産高等裁判所
原告は,「個人的に記録されたカセット」においては,オーバーライト の可能性がない場合には記録が可能\とされ,オーバーライトの可能性が発\n見された場合には,3つの態様(1)「記録機能は全く阻止される」,2)「問 い合わせおよび確認の後トリガされ得る」,3)「更に個々の記録に対して 記録機能の全くのブロッキングを付加データに対して設けられたメモリ\nの箇所における相応のエントリにより行なわせることもできる」)のいず れかによって「既に存在している記録の不本意乍らのオーバーライトない し消去の防止」が図られること,そのうちの1)の「記録機能は全く阻止さ\nれる」の態様の場合には,第2バイトの情報によって,カセット全体につ いて「追加記録または再生のみ可能」という用途に応じた記録の制御が行\nわれることが記載されているとして,引用発明1の第2バイトの情報(「x 01」)は,「追加記録または再生のみ可能」という用途を指示する「用\n途識別情報」(構成要件F)に該当する旨主張する。
(ア) そこで検討するに,甲1の記載事項(前記(2)ア(ア),(エ)ないし (キ),図2)によれば,甲1には,1)甲1記載の「磁気テープカセット 用メモリ装置」は「制御データを含んでおり,該制御データによっては 記録および/又は再生機器の動作モードの選択的ブロッキングが可制 御であることを特徴とする」こと(請求の範囲1項),2)「個人的に記 録されたカセット」の場合,「第2のメモリ領域にてカセットが個人的 使用のものであることが当該識別子により指示される場合次のメモリ 領域の分割も規定」され,また,第2バイトの「次のメモリ領域」(第 3バイト以降)には,初期時間及び終了時間と付加的に情報に対する複 数のバイトからなるデータセットが設けられていること,3)個人的に記 録されたカセット」の「2.1記録上の保護」として,「既に存在して いる記録の不本意乍らのオーバーライトないし消去の防止は次のよう にして達成される,即ち実際のテープ位置とメモリにおけるエントリと の比較を記録装置が常に行うようにするのである。当該比較によりオー バーライトの可能性のないことが指示された際のみ記録機能\がトリガ される。但しオーバーライトの可能性が発見されると,記録機能\は全く 阻止されるか,又は問い合わせおよび確認の後トリガされ得る」こと, 4)個人的に記録されたカセット」の「2.2チャイルドプルーフのブロ ック」として,「さらなる機能はそれぞれの個々の記録に対する再生の\nブロックの初期の解放(レリーズ)である。このことは同様に付加デー タに対して設けられた箇所にてエントリにて行われ得る。そのようにし て,正当な権限のないものに対する再生を例えば子どもによる不当な操 作に対する防止保護の形態で阻止することができる」ことが記載されて いるものと認められる。
上記記載を総合すれば,甲1には,「個人的に記録されたカセット」 の「第2バイト」(第2のメモリ領域)に記憶されている識別子により カセットが「個人的使用のもの」であることが指示され,それに対応し た用途として記録及び再生の双方が可能となることを前提として,第2\nバイトの「次のメモリ領域」(第3バイト以降)に設けられた「エント リ」によって「既に存在している記録の不本意乍らのオーバーライトな いし消去の防止」といった記録再生機器の記録動作の制御や「正当な権 限のないもの」に対する「再生のブロック」といった記録再生機器の再 生動作の制御を可能(「可制御」)としたことが開示されているものと\n認められる。
そうすると,引用発明1(「個人的に記録されたカセット」による発 明)の「第2バイト」に記憶されている情報(「x01」)は,記録再 生機器に対して,記録及び再生の双方が可能というカセットの用途に対\n応した記録動作又は再生動作の制御内容を示す情報に相当するものと いえるから,本件発明の「用途識別情報」に該当することが認められる。 また,甲1の記載事項(前記(2)ア(キ),図2)によれば,引用発明 1においては,追加記録のみ可能,すなわち,上書き禁止の制御は,「第\n2バイト」の次のメモリ領域(第3バイト以降)の付加データに対して 「エントリ」(図2記載の第13バイトの「付加データ 本例 オーバ ライト阻止」)を設けることによって行われていることからすると,第 2バイトの「x01」は,「追加記録または再生のみ可能」の用途を示\nすものとはいえない。
さらに,「個人的に記録されたカセット」においては,「既に存在し ている記録の不本意乍らのオーバーライトないし消去の防止」の態様と して,2)及び3)の態様もあり得ることに照らすと,「個人的に記録され たカセット」であることを示す第2バイトの識別子のみによって,1)な いし3)の態様を区別することは困難である。
(イ) 以上によれば,引用発明1の第2バイトの情報(「x01」)は, 「追加記録または再生のみ可能」という用途を指示する情報であるとの\n原告の前記主張は採用することができない。
イ 以上によれば,引用発明1は,構成要件Fの「ユーザが改変することが\nできず,前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可能」とされて\nいる「用途識別情報」に相当する構成を備えていない点において,本件発\n明と相違するから,結論において,本件審決における相違点2の認定に誤 りはない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2018.10.26
平成30(ネ)10042 損害賠償請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成30年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,被告各商品に被控訴人の著名表示が付されていることは認めつつ,\n需要者がその出所につき控訴人であり被控訴人ではないと認識し得る場合であり, 著名表示は商品のデザインとしてのみ使用されていることから,著名表\示が「商品 等表示」として使用されているとはいえないなどと主張する。\nしかし,不正競争防止法2条1項2号は,同項1号と異なり,「他人の商品又は 営業と混同を生じさせる行為」であることを要件としていない。これは,同項2号 の趣旨が,著名な商品等表示について,その顧客吸引力を利用するただ乗りを防止\nすると共に,その出所表示機能\及び品質表示機能\が希釈化により害されることを防 止するところにあることによるものである。このため,他人の著名な商品等表示と\n同一又は類似の表示が,商品の出所を表\示し,自他商品を識別する機能を果たす態\n様で用いられている場合には,商品等表示としての使用であると認められるのであ\nって,需要者が当該表示により示される出所の混同を生じるか否かが直ちにこの点\nを左右するものではない。 また,原告標章は著名性を有し,高い出所識別機能を有するものであること,原\n告モノグラム表示の使用態様として,商品に応じてその一部分のみを商品に付して\n使用されており,必ずしも「LOUIS VUITTON」との文字商標を必要と はしていないことは,前記のとおりである(引用に係る原判決「事実及び理由」第 4の2(1)及び(2)。他方,被告標章1〜7は,原告標章を構成する原告記号a〜d\nと同一の記号により構成され,その配置も原告標章と同一の規則性に基づくものの\n一部分ということができ,また,被告標章8は,被告記号eの存在や配色において 原告標章と異なるものの,配置の規則性の点では原告標章と同一に配置されたもの の一部分ということができる。このような原告標章の著名性や,原告標章と被告各 標章との構成要素及び使用態様の共通性に鑑みると,被告各標章は,いずれも,こ\nれを見た者の認識において,容易に著名表示である原告標章を想起させるものであ\nることは明らかである。このことは,控訴人が取引の実情として指摘する「REM AKE」,「VINTAGEのLOUIS VUITTONの生地を…落とし込ん だ」,「カスタム」,「CUSTOM」といったウェブ上の記載の存在や「JUN KMANIA」という屋号の表示の存在等を考慮しても異ならない。\n以上より,被告各標章は,それがデザインとして認識されるか否かはさておき, 出所識別機能を有する態様で用いられているものと認められるのであって,この点\nに関し控訴人がるる指摘する事情を考慮しても,控訴人の主張は採用できない。 イ さらに,控訴人は,不正競争防止法2条1項2号に該当するには著名表示の\n主体の営業上の利益が侵害されるような場合でなければならないと主張する。 しかし,後記のとおり,表示希釈及び表\示汚染という観点をも含め,控訴人の行 為により被控訴人に現に損害を生じていると認められることから,仮に控訴人の主 張を前提としても,この点をもって不正競争防止法2条1項2号該当性が否定され ることにはならない。
ウ したがって,控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為 に該当する。
(2)損害の額について
ア 控訴人は,需要者は,被告各商品が被控訴人によって販売されていない商品 であることを認識しながら,敢えて控訴人の商品を購入しており,控訴人による被 告各商品の展示販売行為がなければ被控訴人が利益を得られたであろうという関係 にはないなどと主張する。 しかし,原告標章と被告各標章との類似性の程度,原告商品及び被告商品の販路 の共通性並びに需要者層の重なり合いの蓋然性に鑑みると,被控訴人には,控訴人 による侵害行為がなければ利益を得られたであろうという事情が認められることは, 前記のとおりである(引用に係る原判決「事実及び理由」第4の3(1))。
イ 控訴人は,被告各商品の販売により受けた利益は12万3442円であり, かつ,この利益額への原告標章の貢献の程度はその50%にとどまるなどと主張す る。 不正競争防止法5条2項に基づく損害額は,侵害者の売上額から原材料の仕入価 格その他の変動経費を控除した限界利益と解すべきであって,売上高の多寡にかか わらず発生し得る販売費及び一般管理費等は原則として控除されないと解される。 そして,控訴人は,経費の控除につき,その項目を区別することなく,決算書上 「経費」として計上したもの全額の控除を主張するにとどまり,変動経費の額に関 する具体的な主張立証はない。 また,推定覆滅事情は控訴人において主張立証すべきところ,控訴人主張の被告 各商品の売上げに対する原告標章の貢献の程度を裏付けるに足りる証拠はないから, この点に関する控訴人の主張も採用し得ない。
ウ 控訴人は,被告各商品の展示販売により被控訴人の信用が毀損されることは ないなどと主張する。 しかし,前記のとおり(引用に係る原判決「事実及び理由」第4の3(2)),原告 標章は著名性を獲得した商品等表示であり,また,被控訴人は,その商品の品質及\nびブランドイメージを維持管理するために多大な努力を払ってきたことが認められ る。他方,被告各商品の中には,被告商品4のように,品質の点で原告商品と比較 して粗雑というべきものが含まれていると認められることに加え,控訴人自身,被 告各商品は,原告標章(ないし原告モノグラム表示)の著名性に便乗し,被控訴人\nの商品の「高級感を揶揄し風刺する意図」で製作販売された「チープな商品」と主 張しているものであり,客観的にも,その構成等から,そのような意図等で製作販\n売された商品であることが容易にうかがわれる。 このような被告各商品が市場に存在することが,原告商品の品質及びブランドイ メージに悪影響を及ぼし得ることは明らかである。 そうすると,控訴人による不正競争行為は,被控訴人が長年の企業努力により獲 得した原告標章の著名性及びそれにより得られる顧客誘引力を不当に利用して利得 するものであり,被控訴人の企業努力の成果を実質的に減殺するものであって,著 名な原告標章を希釈化するのみならず,これを汚染するものというべきである。こ れにより,需要者の原告商品又は原告標章に対する信用や価値が毀損され,被控訴 人は無形の損害を被ったものと認められる。 エ したがって,この点に関する控訴人の主張はいずれも採用できず,不正競争 防止法5条2項に基づく損害額は108万1490円,信用毀損等の無形損害の額 は50万円及び弁護士費用相当額15万円を,いずれも下回ることはない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.10.26
平成29(ワ)22041 差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月19日 東京地方裁判所(40部)
原告は,被告製品の把持体外側の外郭部分全体の形状は「逆台形状」である から,構成要件Bを充足すると主張する。\n構成要件Bの「逆台形状」の意義に関し,本件明細書の段落【0008】,\n【0018】,【0023】,【0024】には,本件発明の把持部12が「逆 台形形状」である旨の記載があるが,その形状の定義や意義についての記載 は存在しない。そこで,一般的な用法を参酌すると,広辞苑第六版(乙1)に は,「台形」とは「一組の対辺が平行な四辺形」であると記載され,かつ,上 底が下底より短い四辺形の図が掲載されている。これによれば,「逆台形」と は,「上底が下底より長く一組の対辺が平行な四辺形」をいうと解するのが相 当である。 このような理解に立って本件明細書の図2に図示された把持部をみると, その上部(引き手から遠い部分を「上部」,引き手に近い部分を「下部」とい う。)の直線が下部の直線より長く,その側辺が直線状であるので,本件明細 書における「逆台形状」という語の意義は,上記の一般的用法に沿うものであ ると認められる。 他方,証拠(甲3)によれば,被告製品の把持体(前記第3の1(1)〔被告 の主張〕掲記の「被告製品の把持体」の赤線で囲まれた部分)は,下底は直線 状であるものの,下底から上部に向かう側辺は全体が曲線であり,把持体の 中央部分で最大幅となり,その後,上部に向かい先端部に行くほど幅が狭く なっている上,上底も直線状ではなく,曲線から構成されていることが看取\nされる。そうすると,被告製品の把持体は,平行な対辺もなく四辺形でもない ことから「逆台形状」ということはできず,むしろ「楕円形状」というべきで ある。 これに対し,原告は,「逆台形状」の「状」とは,「…のような形である」 の意味であるから,本件発明の「逆台形状」は必ずしも正確な「逆台形」に限 られないと主張する。しかし,被告の把持体が厳密な意味での「逆台形状」の 定義を満たすことは要しないとしても,少なくとも,逆台形としての基本的 な形状は備えていることを要すると解されるところ,被告製品の把持体は, 側辺及び上部が曲線で「四辺形」ということは到底できず,「楕円形状」とい うべきものであり,逆台形の基本的な形状を備えているということはできな いことは前記判示のとおりである。 したがって,被告製品の把持体は「逆台形状」とは言えず,構成要件Bを充\n足しない。
(2)争点1−2(構成要件Cの充足性)について
原告は,被告製品は,スライダーが10〜50%露出しているので,構成\n要件Cを充足すると主張する。 しかし,被告製品の写真である証拠(乙19の1の4枚目,19の2の5 枚目,19の3の3枚目,19の4の3枚目,19の5の4枚目,19の6 の4枚目,19の7の4枚目,19の8の3枚目,19の9の3枚目)によ れば,被告製品において,スライダーがファスナーカバーに収まった状態に おいて閉口端側に露出することはあるものの,その露出割合は10%を超え ないと認めることが相当である。 また,被告製品1の吊り下げヘッダー裏面にはスライダーをファスナーカ バーに収めた状態が図示されているが(甲3の1の図5),同図においても, スライダーはファスナーカバーから閉口端側に露出していない。これによれ ば,被告製品の通常の用法においては,スライダーがファスナーカバーに収 められた際に閉口端側に露出することは想定されていないものというべき である。
これに対し,原告は,被告製品1の実測値(別紙被告製品説明書の図1を 再度実測したとされるもの。原告第1準備書面11頁の図1)によれば,被 告製品1のファスナーカバーの長手方向の全長は約25mmであり,露出部 分が約3.5mmであるから,被告製品のスライダーは約14%(3.5/ 25×100=0.14)露出していると主張する。 しかし,原告が根拠とする上記の実測値は,被告製品の把持体を弾性のあ るファスナーカバーにどの程度強く押し込んだ上で実測されたかが明らか ではなく,訴状に添付された同製品に係る別紙被告製品説明書の図1(甲3 の1の図3)においては,被告製品1のスライダーの露出部分は約3mm程 度にとどまっている上,前記のとおり,吊り下げヘッダー裏面の図(甲3の 1の図5)においては,スライダーがファスナーカバーから閉口端側に露出 していないことなどに照らすと,上記の再実測図(原告第1準備書面11頁 の図1)は,被告製品1のスライダーを通常使用される態様より強くファス ナーカバーに押し込んで実測されたものであると推認される。 この点,原告は,本件発明の技術的範囲は,被告製品がスライダーをファ スナーカバーから所定の割合で露出させることが可能かどうかで判断され\nるべきであるから,スライダーを強くファスナーカバーに押し込んだ状態で 露出割合が10%を超えるのであれば構成要件Cを充足すると主張するが,\n被告製品におけるスライダーの露出割合は,当該製品が通常使用される状態 において測定されるべきであり,弾性を有するファスナーカバーにスライダ ーを強く押し込んだ状態においてスライダーの露出割合が10%を超える としても,それによって構成要件Cを充足するということはできない。\nしたがって,被告製品は構成要件Cを充足しない。
(3) 争点1−4(構成要件Eの充足性)について
原告は,被告製品は,ファスナーカバーに把持体が「収まった状態」となっ ているので,構成要件Eを充足すると主張する。\n構成要件Eの「収まった状態」との語に関し,本件明細書には,拡大把持体\nがカバー体にどの程度覆われていることを意味するかについての直接的な記 載はないが,本件発明に係る洗濯用ネットの開口部を開口及び閉口する際の 手順を記載した本件明細書の段落【0020】及び段落【0022】の記載に よれば,本件発明は,洗濯ネットの閉口時にはスライダ構成体を「確実にカバ\nー体に収」め,開口時には 閉口端側からスライダ3を押すことにより,拡大 把持体1の「先の部分」を一定量カバー体から露出させ,その部分を指でつか んで引き抜くことにより開口するものであると認められる。 このような,本件発明に係る洗濯ネットの開閉時の手順及び仕組みによれ ば,閉口時において拡大把持体は,その「先の部分」まで「確実に」カバー体 に覆われた状態にあるものと解するのが相当であり,本件明細書の【図4】 (C)にも,開口部を閉じた際に拡大把持体1が完全にカバー体に収められ た状況が図示されている。
そうすると,構成要件Eの「収まった状態」とは,拡大把持体がカバー体に\n完全に覆われた状態をいうものと解すべきであり,このような理解は,「収ま る」という語が,一般的には「ある範囲内に全部が残らず入る」ことなどを意 味すること(乙3)とも整合するというべきである。 また,仮に,原告の主張するように閉口時において拡大把持体がカバー体 に完全に覆われることを要しないと解し得るとしても,上記の開閉時の手順 及び仕組みによれば,少なくとも,拡大把持体は,開口時にその先の部分を指 でつまんでそのまま開口することができない程度までカバー体に覆われてい ることを要するというべきである。 以上に基づき被告製品についてみると,証拠(甲3,乙19)によれば,被 告製品はいずれも開口時に閉口端側からスライダーを押して把持体の先の部 分を露出することを必要とせず,そのまま把持体を指でつまんで開口するも のであり,これを可能にするように,開口部側において把持体のリング部分\nの一部が指でつまむことができる程度にファスナーカバーから露出している ことが認められる。 このように,被告製品は,閉口時に把持体がファスナーカバーに完全に覆 われておらず,少なくとも,把持体が指でつまむことができる程度に露出し ているのであるから,被告製品は構成要件Eの「拡大把持体が収まった状態」\nにあるということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.10.26
平成30(ネ)10020 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年10月18日 知的財産高等裁判所(1部) 大阪地方裁判所
(エ) 以上より,乙1公報には,以下の乙1発明が記載されていると認められる。
携帯用光学式カード1などの表面の所定領域を白色に形成した情報記録領域2を,一方向に等間隔で複数の単位情報記録領域2−1〜2−nに区分けし,単位情報記\n録領域2−1〜2−nそれぞれを,マトリクス状に2×2の四つの単位領域a〜d に区分けし,各単位情報記録領域は,隣接する四つの単位領域a〜dごとに「マー ク無し」,「マーク有り」の二つの状態を記録するカルラコードにおいて,隣接す る四つの単位領域a〜dに対して,「マーク有り」の状態の単位領域には,赤色の 第1のマークMK1,緑色の第2のマークMK2及び黄色の第3のマークMK3の いずれかを印刷し,上記三色のマークに加え白色の四色で4値の情報を一の単位領 域に対して与えることで,2×2のマトリクスを形成する隣接する四つの単位領域 からなる一の単位情報記録領域2−1では4値の組合せで44=256種類の情報 の記録が可能なコード。
(3) 本件発明と乙1発明との対比
ア 「反射又は放射の波長特性が異なる3種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され」(構\成要件A)について
(ア) 乙1発明の「単位領域」は,「単位領域a〜dごとに『マーク無し』, 『マーク有り』の二つの状態を記録するものである。ここで,乙1発明の「マーク」 は,「赤色の第1のマークMK1,緑色の第2のマークMK2及び黄色の第3のマ ークMK3のいずれかを印刷し」たものであるから,「マーク有り」の状態の単位 領域は,「赤色,緑色,黄色の三色」のうちいずれかの色を表示するものである。また,乙1発明の「単位領域」は「白地に形成した情報記録領域2」を区分けした\nものであるから,「マーク無し」の状態の単位領域は「白色」を表示するものである。\nしたがって,乙1発明の「単位領域」は,第1のマークMK1,第2のマークM K2及び第3のマークMK3のいずれか又はマークなしを表示する「表\示領域」に 相当する。
(イ) また,乙1公報の「単位領域」に赤色(第1のマークMK1),緑色(第 2のマークMK2),黄色(第3のマークMK3)及びマーク無し(白色)のいず れが表示されているかを判別する手法として,乙1公報には,第1の光源及び第2の光源のそれぞれから波長の異なる放射光を単位領域に照射し,単位領域により反\n射された光のレベルによって,上記放射光に対する吸収率ないし反射率の高いマー クが記録されているものと判定して単位領域の色を判別する手法(【0030】〜 【0033】,【0035】〜【0038】,【0040】,【0041】,【0 043】)が記載されている。この記載に鑑みれば,乙1発明は,色ごとに反射の 波長特性が異なることを利用した技術であることが理解できる。そうすると,乙1 発明の「単位領域」は,反射の波長特性が異なる4種の色のいずれかを表示する領域といえることから,本件発明の「反射又は放射の波長特性が異なる3種以上の表\示領域」に相当する。
(ウ) さらに,乙1発明の「単位領域」は,一つの単位情報記録領域を「マトリ クス状に2×2の四つの単位領域a〜dに区分け」したものであるから,乙1発明 の単位情報記録領域は,四つの「単位領域」をマトリクス状に2×2に配列したも のといえる。同様に,乙1発明の単位情報記録領域は,「情報記録領域」を一方向 に等間隔で複数(n個)に区分けしたものであるから,乙1発明の「情報記録領域」 は,単位情報記録領域を一方向に等間隔で複数(n個)配列したものといえる。 そうすると,乙1発明の「情報記録領域」は,「単位領域」をマトリクス状に2 ×2に配列した単位情報記録領域を一方向に等間隔で複数(n個)配列したもの, すなわち,「単位領域」をマトリクス状に2×2nに配列したものといえるところ, 表示領域に相当する「単位領域」をマトリクス状に2×2nに配列することは,「単位領域」を縦方向に2行,横方向に2n列に並べること,すなわち,縦方向及\nび横方向からなる二次元的な配列で並べることにほかならない。
(エ) したがって,乙1発明と本件発明とは,「反射(又は放射)の波長特性が 異なる3種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され」ている点で共通する。
イ 「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表\示の要素とした」 (構成要件B)について
(ア) 乙1発明の「単位情報記録領域」のそれぞれは,「44 =256種類の 情報の記録が可能」であるから,256種類の情報のうち1種類を表\示する「情報 表示の要素」といえる。
(イ) また,乙1発明では「2×2のマトリクスを形成する隣接する四つの単位 領域からなる一の単位情報記録領域では4値の組み合わせで44 =256種類の 情報の記録が可能」となるところ,当該「4値」は,「単位領域」に記録された「第1のマークMK1」,「第2のマークMK2」及び「第3のマークMK3」並\nびに「マーク無し」の状態に対応するそれぞれ異なった反射の波長特性を持つ4色 によって単位領域に与えられたものである。そうすると,乙1発明の「4値の組み 合わせ」は,本件発明の「表示領域の波長特性の組み合せ」に相当する。
(ウ) したがって,乙1発明の反射の波長特性が異なる「三色のマークに加え白 色の四色で4値の情報を一の単位領域に対して与えることで,2×2のマトリクス を形成する隣接する四つの単位領域からなる一の単位情報記録領域2−1では4値 の組合せで44=256種類の情報の記録が可能」であることは,本件発明の「この配列における表\示領域の波長特性の組み合せを情報表\示の要素とした」ことに相\n当する。
ウ 「ことを特徴とする二次元コード」(構成要件C)について
上記アによれば,乙1発明の「コード」は,「反射(又は放射)の波長特性が異 なる3種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され」たものであって,四つの単位領域からなる単位情報記録領域に対して「44 =256種類の情報の記 録が可能」であるから,情報を4色の単位領域の二次元的な配列によって記録したものである。\n「コード」には「情報を表現する記号・符号の体系。また,情報伝達の効率・信頼性・守秘性を向上させるために変換された情報の表\現,また変換の規則。」といった意味があるところ,本件明細書及び乙1公報は,いずれも「コード」につき上 記の意味において使用しているものと理解される。 そうすると,乙1発明の「コード」は,4色のうち1色を取る単位領域を二次元 的に配列したコードであるといえ,本件発明の「二次元コード」に相当する。この ことは,乙1公報に「本発明は,カルラコードなどマーク状に情報が記録された光 学式カードおよびその読取装置に関するものである。」(【0001】)との記載 や,カルラコードが二次元バーコードの一種であること(本件明細書【0048】, 甲25)とも整合する。
エ 小括
以上を総合すると,本件発明と乙1発明とは,「反射又は放射の波長特性が異な る3種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて形成され,この配列における表\示 領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたことを特徴とする二次元コード。」である点で一致し,相違するところがない。\n(4) 控訴人の主張について
ア 控訴人は,本件発明は,一次元コードでは多くの情報を表示するためにはバーコードラベルが大型化し実用的でなくなるという課題を解決するためのものであ\nり,二次元コードにおける「二次元」とは,単に表示領域が二次元方向に幾何学的に配列されているのみではなく,この組合せにより二方向に情報表\示の要素を有することを意味するなどと主張する。 しかし,そもそも,本件発明の構成要件において二次元的に配列されるとするのは「表\示領域」であって,「情報表\示の要素」を二次元的に配列にすることは規定\nされていない。そして,乙1発明においては,本件発明の「表示領域」に相当する「単位領域」が「2×2nに配列」されていることは,上記のとおりである。\nまた,本件明細書は,「バーの本数を増加したロングバーコードと標準型のバー コードを並べて印刷することにより,情報表示量の不足をカバーしようと」する方法は「根本的な解決策にはなっていない。」(【0005】),「モノクロ…のバ\nーコードで,このような多くの情報を表示しようとすると,表\\示パターンが複雑化 すると共にバーコードラベルが大型化し,実用的でなくなる」(【0006】), 及び「モノクロの情報コードの情報表示量の限界のため実用的なシステムを作ることは困難」(【0008】)との問題点を指摘した上で,「本発明は,表\示パターンを変えなくても表示できる情報量を大幅に増大して,上記問題を解決できる情報コードを提供することを目的とする。」(【0009】)として,本件発明の課題\nを提示している。これらによれば,本件発明はモノクロのバーコードで多くの情報 を表示するためにはバーコードラベルが大型化し実用的でなくなるという課題を解決するためのものであって,必ずしも一次元コードにおける課題を解決するための\nものではないと認められる。そうすると,控訴人の主張は,本件発明の課題につい ての誤った認定に基づいたものというべきである。 その点をおくとしても,情報表示の要素を一次元に並べた場合(乙1発明)と二次元的に並べた場合(控訴人主張に係る本件発明)とで,必要な情報表\示の要素数及び表示領域の数に変化はない。そうである以上,情報表\\示の要素を二次元的に並 べた二次元コードにより控訴人主張に係る本件発明の課題が解決されるとは必ずし も認められない。控訴人の主張は,本件発明の課題解決手段についての誤った前提 に基づいたものである。 さらに,控訴人は,乙1発明におけるコードの読取方法から,乙1発明のコード の情報表示の要素は水平方向のみにしかないと指摘する。しかし,前記のとおり,本件発明が二次元的に配列していると規定するのは「情報表\示の要素」ではなく「表示領域」である。また,乙1発明の読取装置が,光学式カードを長手方向に間欠送りするという動作と,カード送り方向と直交する方向に走査するという動作と\nを共に必要とするということは,当該カードに記録されたコードは,二つの方向で, すなわち二次元的に読み取る必要があることを示すものであり,当該コードの表示領域は二次元的な配列で並べられているものと理解するほかない。
イ 控訴人は,本件発明の「コード」とは,独立コード,すなわち,コード化の 対象となる情報を表すシンボル(有意情報)と,バーコードに記載されているデータを読み取るために必要な取り決め(構\造情報)の二つの要素を含むものを意味するなどと主張する。 しかし,本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書のいずれの記載にも,「二次 元コード」ないし「コード」を限定する趣旨の規定はない。また,本件明細書【0 048】においては,本件発明の「二次元コード」の例示としてカルラコードが挙 げられていることからすると,かえって,本件発明にいう「二次元コード」又は 「コード」は,それが構造情報を有するものか否かは問わないものであると解するのが相当である。\nさらに,本件発明が「構造情報」を有しないコードであるカルラコードが普及しなかったことを受けて開発されたものであることは,本件明細書に記載されておら\nず,立証もされていない。有意情報と構造情報とを共に備えない限りコードが発明として成立しないことも,何ら立証されていない。\nその他控訴人がるる指摘する点を考慮しても,この点に関する控訴人の主張は採 用し得ない。
ウ 控訴人は,乙1発明では波長特性の組合せが情報表示の要素とされていないなどと主張する。\nしかし,前記認定のとおり,乙1発明は,反射の波長特性が異なる「三色のマー クに加え白色の四色で4値の情報を一の単位領域に対して与えることで,2×2の マトリクスを形成する隣接する四つの単位領域からなる一の単位情報記録領域2− 1では4値の組合せで44=256種類の情報の記録が可能」なものであり,「この配列における表\示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした」ものであ\nるから,この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。 エ 控訴人は,本件発明と乙1発明とは技術方式における相違があるなどと主張 する。 しかし,その指摘に係る情報波長特性の組合せ組成方式,情報領域に記録される 情報記録方式,情報領域に記録された情報の読み取り方式のいずれについても,本 件発明に係る特許請求の範囲に記載されたものではなく,また,本件明細書にも, 本件発明につきそのような限定がされていることをうかがわせる記載が見当たらな いことなどから,この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.10.25
平成29(ワ)6293 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年9月27日 東京地方裁判所
本件動画1ないし16は,インターネット上の動画共有サービスで あるYouTubeにアップロードされたものであり,本件動画1ないし3, 5ないし12及び16については,その冒頭において被告会社が行う本 件レンタル事業に関する動画であることが表示されている。また,本件\n動画4は本件レンタル事業に係る利用者がコスチュームを着用して公道 カートを運転する様子が撮影された動画であり,本件動画13及び14 は本件レンタル事業について紹介するテレビ番組の当該紹介部分を切り 取って作成された動画であり,本件動画15は本件ロゴ等がペイントさ れた公道カートを運転する本番組の当該部分を切り取って作成された動画であり,いずれも被告会社あるいは関係団体が,本件レンタル事業を広く紹介するために動画共有 サービスにアップロードしたものと認められる。 そして,被告がその役務である本件レンタル事業を紹介する動画にお いて,原告の商品等表示といえる原告表\現物と類似の表示がされた場合,\nその表示は,少なくとも被告会社が提供している役務に関する広告にお\nいて営業の出所を示す表示としてされたということができる。\n 本件動画1ないし16においては,いずれも原告表現物の特徴の一部\nを備えたコスチューム(被告標章第2の1ないし10のいずれかのコス チューム)を着用した人物が表示されていること,これらの人物はいず\nれも公道カートに乗車していること,「マリオ」,「ルイージ」,「ヨ ッシー」,「クッパ」がカートの運転手となるゲームシリーズ「マリオ カート」が日本及び全世界において相当の出荷本数を有すること(前記 2(1)イ(ア)),これらの動画の冒頭に「MARICAR」などという表示がさ\nれていたことからすれば,これらのコスチュームを着用した動画上の人 物は,本件レンタル事業の需要者をして,ゲームシリーズ「マリオカー ト」のキャラクターである「マリオ」,「ルイージ」,「ヨッシー」, 「クッパ」を連想させ,上記各人物と,本件レンタル事業の需要者にお いて周知の商品等表示である原告表\現物とを類似のものと受け取らせ, その商品等表示と被告会社が行っている役務に関連性があると誤認させ,\n被告会社と原告との間に同一の営業を営むグループに属する関係又は原 告から使用許諾を受けている関係が存すると誤信させるおそれがある。 (オ) コスチュームを着用した被告従業員
前記(イ)及び(ウ)のとおり,本件マリオコスチューム,本件ルイージコ スチューム,本件ヨッシーコスチューム及び本件クッパコスチューム (被告標章第2の1ないし10の各コスチューム)は原告表現物の特徴\nの一部を備えるところ,これらを着用し,カートツアーの先導者として 「MARICAR」「MariCar」といった被告標章第1を表示する公道カートに\n乗車することは,前記(ウ)と同様の理由により,需要者をして,ゲーム シリーズ「マリオカート」のキャラクターである「マリオ」,「ルイー ジ」,「ヨッシー」及び「クッパ」を連想させ,その先導者と,本件レ ンタル事業の需要者の間において周知の商品等表示である原告表\現物と を類似のものと受け取らせ,被告会社と原告との間に同一の営業を営む グループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存する と誤信させるおそれがある。
(カ) 本件マリオ人形
本件マリオ人形(被告標章第2の11の人形)は,原告表現物マリオ\nの特徴を全て備えており,原告表現物マリオと類似するといえる。\n そして,本件マリオ人形が設置されている被告会社の店舗において本 件レンタル事業が行なわれていること,「マリオ」等がカートの運転手 となるゲームシリーズ「マリオカート」が日本及び全世界において相当 の出荷本数を有すること(前記2(1)イ(ア))からすると,同設置行為は, 少なくとも提供している役務に関する広告において営業の出所を示す表\n示としてされたものといえ,原告表現物マリオが本件レンタル事業の需\n要者において周知の原告の商品等表示であることから,被告会社と原告\nとの間に同一の営業を営むグループに属する関係又は原告から使用許諾 を受けている関係が存すると誤信させるおそれがある。
ウ 以上によれば,被告が,被告標章第2を使用して行った本件宣伝行為 (本件写真1の表示を除く,以下同じ。)は,原告の周知の商品等表\示と 類似する標章を商品等表示として使用しているものであり,これに接した\n需要者に対し,被告会社と原告との間に,原告と同一の商品化事業を営む グループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存するも のと誤信させるものと認められる。
・・・
4 不競法に基づく本件ドメイン名の使用差止及び登録抹消請求の可否
(1) 争点7(本件ドメイン名の使用行為が不競法2条1項13号の不正競争 に該当するか否か)について
ア 本件ドメイン名と原告文字表示の類否
原告の特定商品等表示である原告文字表\示マリカーと,本件各ドメイン 名の類否について ,本件ドメイン名のうち「.jp」,「.co.jp」及び 「.com」部分は多くのドメイン名に共通して用いられるものであるから, 出所を表示する機能\を有する部分は「maricar」又は「fuji-maricar」であり,同部分が本件各ドメイン名の要部と認められる。このうち「maricar」部分については,前記2(1)イで述べたとおり,原告文字表示マリカーと類似すると認められる。\nまた,「fuji-maricar」について,前記のとおり「maricar」部分が原 告文字表示マリカーと類似し,「fuji-」の部分は「maricar」に付加され たものと受け取ることができるものであり,「fuji-maricar」も,原告文 字表示マリカーと類似するものといえる。\n したがって,本件ドメイン名はいずれも原告文字表示マリカーと類似す\nる。
イ 図利加害目的の有無
前記2(1)イ(イ)で述べたとおり,原告文字表示マリカーは,被告会社が\n設立された平成27年6月4日の相当程度以前である平成22年頃から, 原告の販売するゲームシリーズ「マリオカート」の略称として,ゲームに 関心を有する需要者の間で全国的に知られており,被告会社がこれを認識 していなかったとは認め難いこと,被告会社は,本件訴訟提起前の平成2 9年2月23日当時,本件ドメイン名1ないし3を使用して開設したサイ ト(被告会社サイト,品川店サイト1,河口湖店サイト)において,「マ リオカート」シリーズに登場する主要キャラクターである「マリオ」「ル イージ」等のコスチュームを着用した利用者が公道カートを運転するとい う本件レンタル事業のサービス内容を写真等と共に宣伝し,「みんなでコ スプレして走れば,リアルマリカーで楽しさ倍増。」と記載しており,被 告会社の意図が,原告の「マリオカート」シリーズにおけるゲームの世界 を現実世界で体験することを売りにして顧客を惹きつけようとするもので あったと推認できることからすれば(甲6の1ないし3),被告会社は, 原告文字表示マリカーと類似する本件各ドメイン名を使用することにより,\n同文字表示が有する高い知名度を利用し,原告の公認あるいは協力の下で\n本件レンタル事業を営んでいるかのような外観を作出し,不当に利益を上 げる目的があったものと認めることができる。 したがって,本件各ドメイン名の使用につき,「不正の利益を得る目的」 を有していたと認めることができる。 ウ 小括
以上によれば,被告会社は,本件レンタル事業の宣伝行為のために,不 正の利益を得る目的をもって,原告の特定商品等表示である原告文字表\示 マリカーと類似する本件各ドメイン名を使用したと認められるから,同行 為は不競法2条1項13号所定の不正競争行為に該当する。
5 著作権法に基づく原告表現物の複製又は翻案の差止請求並びに本件写真等\nの抹消及び廃棄請求の可否
(1) 争点10(複製又は翻案の差止請求の可否及び範囲)について
原告は,請求の趣旨第4項において,原告表現物の複製又は翻案の差止\nめを求め,請求の趣旨第5項において,原告表現物の複製物又は翻案物の\n自動公衆送信又は送信可能化の差止めを求めている。\n 原告表現物を複製又は翻案する行為には,広範かつ多様な行為があると\nころ,原告の請求は,絵画の著作物である原告表現物を絵画上複製すると\nいう行為がされていない本件において,差止めの対象となる行為を具体的 に特定することなく,広範かつ多様な態様な行為のすべてを差止めの対象 とするものといえ,自動公衆送信又は送信可能化の差止めについても,そ\nの差止めの対象自体を複製物又は翻案物とすることから,同様のものとい える。このような無限定な内容の行為について,被告会社がこれを行うお それがあるものとして差止めの必要性を認めるに足りる立証はされていな い。原告の前記請求には理由がない。
(2) 争点9(本件各写真及び本件各動画が原告表現物の複製物又は翻案物に\n当たるか否か)及び争点11(本件各コスチュームが原告表現物の複製物\n又は翻案物に当たるか否か)について
本件各写真及び本件各動画が原告表現物の複製物又は翻案物に当たるか\n否か(争点9)については,これらが複製物又は翻案物に当たることを前 提とする請求である請求の趣旨第4項,第5項に係る請求が前記3(1)の 理由により認められないため,判断するに及ばない。 また,原告は,請求の趣旨第11項において,本件各コスチュームが原 告表現物の複製物又は翻案物に当たることを前提として会社である被告会\n社にその貸与の禁止を求めている。本件各コスチュームである別紙貸与物 目録記載1ないし6の各コスチュームは,それぞれ,被告標章第2の2, 3,5,6,8,10のコスチュームである。ここで,不競法に基づく請 求の趣旨第6項に係る請求には被告会社がこれらのコスチュームを使用 (貸与)することの禁止を求める請求が含まれると解され,この部分は, 請求の趣旨第11項に係る請求と選択的併合の関係に立つと解される。前 記3のとおり,不競法に基づき被告会社がこれらのコスチュームの貸与を することが禁止されることによって,請求の趣旨第11項に係る請求につ いて判断をするに及ばなくなるから,本件各コスチュームが原告表現物の\n複製物又は翻案物に当たるか否か(争点11)は判断するには及ばない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.10.19
平成29(行ケ)10232 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月17日 知的財産高等裁判所(2部)
問題の請求項1は下記です。
【請求項1】
A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって,
B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と,
C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と,
D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え,
E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと,
F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする,
G ステーキの提供システム。
以上によると,本件特許発明1は,ステーキ店において注文を受けて配 膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの,これ にとどまるものではなく,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機 器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し,他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより,本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避的\nに生じる要請を満たして,「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という 本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。
(2) 本件特許発明1の発明該当性
前記(1)のとおり,本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術 的手段の構成及びその構\成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと,本件特許 発明1は,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機 等)を,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するため の技術的手段とするものであり,全体として「自然法則を利用した技術的思想の創 作」に該当するということができる。 したがって,本件特許発明1は,特許法2条1項所定の「発明」に該当するとい うことができる。
(3) 被告らの主張について
ア 被告らは,本件特許発明1には,「札」から「計量機」へ,「計量機」か ら「印し」又は「シール」へと「テーブル番号」を伝達させる工程や,この「テー ブル番号」を本件特許発明1において特定されている各ステップの間で伝達するた めの工程は明示的に存在せず,例えば,「札」のテーブル番号を計量機に情報として 伝達する主体が何であるのかは,特許請求の範囲において何ら特定されていないな どと主張する。 しかし,前記(1)エのとおり,本件特許発明1は,「札」に「お客様を案内したテー ブル番号が記載され」,「計量機」が,「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計 量」し,「計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出 力」し,この「シール」を「お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のも のと区別する印し」として用いることにより,お客様の要望に応じてカットした肉 が他のお客様の肉と混同が生じないようにすることに,その技術的意義がある。本 件ステーキ提供方法の各ステップ間で,誰が,どのような方法によりテーブル番号 を伝達するのかということは,上記技術的意義との関係において必須の構成という\nことはできないから,特許請求の範囲において,上記主体や工程に係る構成が特定\nされていないことは,本件特許発明1の発明該当性についての前記判断を左右する ものではない。 イ 被告らは,本件特許発明1において,「テーブル番号」は,その番号が「テ ーブル」に割り当てられており,お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてス テーキを食べるという人為的な取決めを前提に初めて意味を持つものであるから, そのようなテーブル番号を含む情報が伝達されるからといって,本件特許発明1の 技術的意義が自然法則を利用した技術的思想として特徴付けられるものではないな どと主張する。 しかし,お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べることが 人為的な取決めであることと,そのテーブル番号を含む情報を本件計量機等により 伝達することが自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかとは,別の問題 であり,前者から直ちに後者についての結論が導かれるものではない。そして,本 件計量機等が,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決す るための技術的手段として用いられており,本件特許発明1が「自然法則を利用し た技術的思想の創作」に該当することは,前記(2)のとおりである。
ウ 被告らは,本件特許発明1において,特定のお客様が要望する量の肉と 他のお客様の肉との混同が生じないのは,「テーブル番号」を「キー情報」として「お 客様」と「肉」とを1対1に対応付けたことによるものであって,「肉の量」そのも のとは何らの関係がないなどと主張する。 確かに,本件明細書には,「この混同が生じないようにカットした肉Aに付すシー ルSに変えて,テーブル番号が記載された旗をカットした肉Aに刺す等の方策によ り,混同を防止する印しとしても良い。」(【0013】)と記載されており,「テーブル番号」を「キー情報」として「お客様」と「肉」とを1対1に対応付けるという 技術的思想をうかがうことができる。 しかし,前記(1)エのとおり,肉の量は,お客様ごとに異なるものである。そして, 本件明細書には,「計量機から打ち出された,ステーキの種類及び量,価格,テーブ ル番号が記された2枚のシールの内の一枚をステーキのオーダー票とし,先のステ ーキ以外のオーダー票に貼着することにより保管し」(【0012】),「焼かれ,加熱した鉄皿に乗せられたステーキを,ライス等の他のオーダー品と共に・・・,保管したオーダー票でその商品を確認し,オーダー票と共にお客様のテーブルに運ぶ」\n(【0014】)ことが記載されており,肉の量を記載したシールによって他のお客 様の肉との混同が生じていないことを確認することが記載されている。 そうすると,本件特許発明1は,本件訂正によりその技術的範囲に含まれないこ ととなった「テーブル番号が記載された旗をカットした肉Aに刺す」ことを混同防 止の印しとする方法とは異なり,計量機が出力したシールに記載された肉の量とテ ーブル番号という複数の情報を合わせて利用して,他のお客様の肉との混同を防止 するものということができるから,肉の量の情報が他のお客様の肉との混同を防止 するという効果に寄与しないものとはいえない。
エ 被告らは,本件特許発明1には,お客様が案内されるテーブルとカット ステージとが店内の別の場所に存在すること,お客様が案内されたテーブルからカ ットステージまで移動し,カットステージにおいてカットされた肉を確認した後, 案内したテーブルに戻るといった手順は,何ら特定されていないから,必ずしも特 定のお客様の肉と他のお客様の肉との混同が生じるものとはいえないなどと主張す る。 しかし,前記(1)エのとおり,他のお客様の肉との混同を防止することは,お客様 に好みの量のステーキを提供することを目的(課題)として,「お客様からステーキ の量を伺うステップ」及び「伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするス テップ」を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成(前記(1)ア(イ)1))を採用した ことから,カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必 要が生じたことによって不可避的に生じる要請であり,被告ら主張の上記手順が特 定されなければ,他のお客様の肉との混同を防止する必要が生じないということは できない。
オ 被告らは,本件特許発明1において,「札」,「計量機」,「印し」又は「シ ール」は,それぞれ独立して存在している物であって,単一の物を構成するものではなく,また,本来の機能\の一つの利用態様が特定されているにすぎないなどと主張する。 しかし,「札」,「計量機」及び「シール(印し)」は,単一の物を構成するものではないものの,前記(1)エのとおり,いずれも,他のお客様の肉との混同を防止する という効果との関係で技術的意義を有するものであって,物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか,人為的な取決めにおいてこれらの物を\n単に道具として用いることが特定されているにすぎないということはできない。
2018.10.18
平成29(行ケ)10165等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月11日 知的財産高等裁判所
業者が,相違点2に係る本件発明6の構成,すなわち,引用発明2−1\nに係る4/2/1投与計画による本件抗体の投与を,本件発明6に係る8/6/3 投与計画による本件抗体の投与とすることを,容易に想到することができたか否か について検討する。
(イ) 前記のとおり,当業者は,本件優先日当時,乳がんの治療薬を含む一般的 な医薬品において,投与量を多くすれば,投与間隔を長くできる可能性があり,医\n薬品の開発の際には,投与量と投与間隔を調整して,効能と副作用を観察すること,\n抗がん剤治療において,投与間隔を長くすることは,患者にとって通院の負担や投 薬時の苦痛が減ることになり,費用効率,利便性の観点から望ましいということを 技術常識として有していたものである。 そして,引用例2には,本件抗体の薬物動態を観察するに当たり,本件抗体が週 1回10〜500mgの短持続期間の静脈注入が行われた旨記載されている。ここ で,週1回10〜500mgの投与は,患者の体重が60kgの場合は0.167 〜8.33mg/kg,70kgの場合は0.143〜7.14mg/kgに相当 する。そうすると,引用例2には,本件抗体を週1回8mg/kg程度までの投与 量で投与できることは,示唆されているといえる。 また,引用例2には,本件抗体の臨床試験において,本件抗体の毎週の投与と化 学療法剤の3週間ごとの投与を組み合わせるという治療方法が記載されている。 さらに,引用例2には,本件抗体の薬物動態として,本件抗体は投与量依存的な 薬物動態を示し,投与量レベルを上昇させれば,半減期が長期化する旨記載されて いる。
そうすると,上記のとおりの技術常識を有する当業者は,引用発明2−1のとお り本件抗体を4/2/1投与計画によって投与するだけではなく,本件抗体の投与 量と投与間隔を,その効能と副作用を観察しながら調整しつつ,本件抗体の投与期\n間について,費用効率,利便性の観点から,併用される化学療法剤の投与期間に併 せて3週間とすることや,本件抗体の投与量について,8mg/kg程度までの範 囲内で適宜増大させることは容易に試みるというべきである。そして,当業者が, このように通常の創作能力を発揮すれば,本件抗体を8/6/3投与計画によって\n投与するに至るのは容易である。
(ウ) 被告の主張について 被告は,本件優先日前には,4/2/1投与計画のみが臨床的に用いられ,本件 抗体の半減期も1週間程度と考えられていたから,8/6/3投与計画のように投 与間隔について半減期を大きく超える3週間にすることなどは,技術の最適化とは いえないと主張する。 しかし,引用例2には,本件抗体を週1回8mg/kg程度までの投与量で投与 できることが示唆され,また,本件抗体の投与量レベルを上昇させれば,半減期が 長期化する旨記載されている。さらに,丙323の1には,投与間隔が半減期に比 べて長い場合を前提とした留意事項が記載されている。そして,前記のとおりの技 術常識を有する当業者が通常の創作能力を発揮すれば,4/2/1投与計画による\n本件抗体の投与を,8/6/3投与計画による本件抗体の投与とすることは容易に 想到し得るものである。なお,A博士の宣誓書(乙8)には,がん専門臨床医は, 未試験の投与レジメンを実験することは患者の生命をリスクにさらすことになるか ら,本件抗体を8/6/3投与計画で投与することを動機付けられないなどと記載 されているが,臨床医が薬剤の新たな用法用量を臨床的に試みる動機付けがないこ とをもって,薬剤の新たな用法用量の開発を試みる動機付けを否定するものにはな らない。
(エ) よって,当業者は,引用例2の記載及び技術常識に基づき,相違点2に係 る本件発明6の構成を容易に想到することができたというべきである。\n
イ 効果について
(ア) 引用発明2−1に基づく本件発明6の進歩性を判断するに当たっては,相 違点2に係る本件発明6の構成に至ることが容易かどうかだけではなく,本件発明\n6が予測できない顕著な効果を有するか否かについても併せ考慮すべきであり,本\n件発明6に予測できない顕著な効果があることを基礎付ける事実は,特許権者であ\nる被告において,主張,立証する必要がある。 そして,本件において,被告は,本件抗体を8/6 可能である。そうすると,8/6/3投与計画は,相応の治療効果を維持しつつ,\n引用発明2−1と比較して投与間隔を3倍にするものということはできる。 しかし,引用例2には,本件抗体は投与量依存的な薬物動態を示し,投与量レベ ルを上昇させれば半減期が長期化すること,本件抗体を4/2/1投与計画で投与 すれば約79μg/mlのトラフ血清濃度を維持できたことが記載されている。そ して,この記載から,本件抗体を8/6/3投与計画で投与すれば,17μg/m l程度のトラフ血清濃度を維持できるであろうことは予測できる。\nそうすると,実施可能要件やサポート要件に関しては格別,進歩性に関しては,\n本件発明6が過去の臨床試験で求められる程度の治療効果を有しつつ,単に投与間 隔が3倍になったことをもって,本件発明6の治療効果が引用発明2−1と比較し て予測できない顕著なものということはできない。
(ウ) 治療効果
a 引用例2には,本件抗体を4/2/1投与計画で投与した場合の治療効果と して,16週と32週の間で,トラスツズマブ血清濃度は,定常期に達し,平均ト ラフ濃度及び平均ピーク濃度は,それぞれ,約79μg/ml,123μg/ml となったこと,化学療法剤単独の場合と比較すれば,病勢進行の期間が著しく長期 化し,1年間の生存率が高まったことが記載されている。 b 他方,本件明細書には,本件抗体を8/6/3投与計画で投与した場合,「お よそ10−20μg/mlのトラフ血清濃度を維持」される(【0114】),「血 清中濃度が過去のハーセプチンIV臨床試験の目標トラフ血清濃度の範囲(10− 20mcg/ml)で,17mcg/mlとなることを示唆している。」(【01 16】)と記載されている。もっとも,本件明細書には,本件抗体を8/6/3投 与計画で投与した場合における,病勢進行の期間の長期化や生存率に関する具体的 な記載はない。
c ところで,本件明細書には,本件抗体を8/6/3投与計画で投与した場合 における,病勢進行の期間の長期化や生存率に関する具体的な記載はないから,本 件発明6の治療効果は不明であって,引用発明2−1と同等の治療効果を有すると は直ちにはいえない。 また,一般にトラフ血清濃度は,一連の薬剤投与における最少の持続した有効薬 剤濃度であるから(本件明細書【0044】),一連の薬剤投与において維持され るトラフ血清濃度が高い場合には,それだけ有効薬剤濃度が高く,治療効果も高い と評価することは可能である。しかし,引用発明2−1と本件発明6のトラフ血清\n濃度を比較するに,引用発明2−1において維持されるトラフ血清濃度は約79μ g/mlであるのに対し,本件発明6において維持されるトラフ血清濃度はせいぜ い17μg/mlにとどまる。そうすると,トラフ血清濃度において比較した場合 においても,本件発明6の治療効果は引用発明2−1と同等の治療効果を有すると はいえない。 なお,本件明細書には,本件抗体を8/6/3投与計画で投与した場合における 副作用の抑制効果に関する記載もないから,副作用の抑制という観点からも,本件 発明6は,引用発明2−1と同等の治療効果を有するとはいえない。 d よって,本件発明6が引用発明2−1と同等の治療効果を有すると認めるこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2018.10.12
平成29(行ケ)10222 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年10月10日 知的財産高等裁判所
引用商標の周知性について検討するに,まず,原告の使用商品の販 売状況をみると,前記ア(ア)の認定事実によれば,1)原告は,昭和59 年から30年以上にわたり,日本国内において,引越業者等に対し,引 用商標を付した原告商品を継続して販売していること,2)平成17年度 から平成25年度の規格品の販売数量は,年平均1万2199個(合計 10万9791個)であること,3)上記販売数量のうち,大手引越業者 に対する販売数量は,平成21年度が1300個,平成22年度が50 24個,平成23年度が3582個,平成24年度が7914個及び平 成25年度が5277個(いずれもサカイ引越センター分)であり,大 手引越業者以外の引越業者等に対する販売数量が半数を超える相当の割 合を占めていることが認められる。 次に,広告宣伝の状況をみると,前記ア(イ)の認定事実によれば,1) 平成18年ころまでは,「流通サービス新聞」,「トラック経営」,「引 越情報 月刊レポート」,「日刊運輸新聞」などの業界紙に引用商標を 付した使用商品の広告が数回掲載されたことがあったが,その後は,平 成24年5月1日発行の「企業概況ニュース」以外には,業界紙におけ る広告掲載の実績がないこと,2)平成20年から平成25年にかけて, 毎年,「工場・作業現場のプロツール総合カタログ」である「オレンジ ブック」に原告の使用商品の広告が掲載されたが,「オレンジブック」 は分野別に1巻ないし10巻に分かれ,約36万アイテムが掲載された カタログ雑誌であり,原告の使用商品が特に目立って掲載されたもので はないことが認められる。 また,原告は,平成11年以降,毎年,引用商標を付した使用商品を 掲載した,自社商品の「総合カタログ」を3000部から5000部作 成し,業界大手4社を含む引越業者等200社程度に対し,送付又は持 参して配布していたことは,前記ア(イ)認定のとおりであるが,一般貨 物自動車運送事業者数は約5万7600であり,このうち,引越専門業 者数は少なくとも4136であること(前記イ)に照らすと,上記「総 合カタログ」の配布先は,引越専門業者の1割にも満たないといえる。 さらに,原告は,引用商標を付した使用商品のチラシを昭和60年及び 平成10年にそれぞれ配布したことが認められるが,その配布数量や具 体的な配布先は明らかではない。 以上によれば,本件商標の登録出願時において,引越業者,運送業者 等の間で,原告による使用商品の前記販売及び広告宣伝によって,引用 商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されて\nいたものと認めることはできない。
(イ) この点に関し,原告は,日刊運輸新聞(平成16年3月3日号)の 記事(甲118)によれば,同紙が引越運送を行っている各社に対し反 復資材の使用などについてアンケート調査を実施したところ,反復資材 としての「梱包用ハイパット」の使用率が80%を超える結果であり, 「梱包用ハイパット」は,引用商標を付した使用商品を指すものである から,上記アンケート調査の結果は,遅くとも平成16年3月時点で, 引用商標は,引越業者の間では原告の業務に係る商品を表示するものと\nして周知著名であったことを示すものといえる旨主張する。 しかしながら,上記アンケート調査におけるアンケートの対象企業数, 回答数,回答方法等のアンケート結果の信頼性を基礎づける事実は明ら かではない。また,仮に原告が主張するように平成16年3月当時にお ける反復資材としての「梱包用ハイパット」の使用率が80%を超えて おり,「梱包用ハイパット」が原告の使用商品を指すものとして,引越 業者に認識されていたとしても,約7年後の本件商標の登録出願時にお いても同様の認識が当然に維持されていたということにはならない。 したがって,原告の上記主張を前提としても,本件商標の登録出願時 において,引越業者,運送業者等の間で,引用商標が原告の業務に係る 使用商品を表示するものとして広く認識されていたということはできな\nい。
このほか,全国引越専門協同組合連合会,引越専門協同組合,アート コーポレーション,セイノー引越株式会社,名鉄運輸株式会社の担当者 作成の平成28年12月付けの各確認書(甲67の1ないし5)中には, 「ハイパット」というマークが原告の「キルティング製梱包用具」につ いて使用されているマークであることを平成23年9月22日以前より 認識していたことを確認する旨の記載部分があり,サカイ引越センター の代表取締役作成の平成30年2月2日付けの陳述書(甲117)中に\nは,サカイ引越センターは昭和59年から継続的に原告の使用商品を購 入して使用しており,遅くとも平成13年には引越業界で「ハイパット」 といえば知らない者はいないくらいによく知られていたのではないかと 思われる旨の記載部分があるが,上記各記載部分は,上記確認書及び陳 述書の作成者の認識を示したものであり,引用商標が,本件商標の登録 出願時において,引越業者,運送業者等の間で,引用商標が原告の業務 に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていた事実を客観的\nに裏付けることにはならない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
◆判決本文
類似案件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.10. 9
平成29(行ケ)10229 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月3日 知的財産高等裁判所
上記認定事実及び甲1の【0034】ないし【0036】の記載事項に よれば,甲1記載のゴルフシャフト設計装置における「スイング応答曲面」 は,ゴルファーが,シャフトの3つの設計因子である曲げ剛性,ねじれ剛 性及び曲げ剛性分布が異なる複数のゴルフクラブを使用して試打した時の 計測データから算出された移動軌跡(3次元座標データ),軸回転データ と,シャフトの設計因子(ねじり剛性,曲げ剛性及び曲げ剛性分布)の関 係式であって,「スイング応答曲面」を算出するには,シャフトの設計因 子の異なる複数のゴルフクラブを使用することが必要であるものと認めら れる。なお,甲1の【0026】の「ゴルファーは,スイングを行う際に 使用したクラブの曲げ剛性やねじれ剛性などを考慮に入れ,そのクラブ特 性にあわせたスイングを行うため,所定の特性を有する1本のゴルフクラ ブを使用してスイングの計測データを取得して,スイングの解析を行って も妥当な解析結果を得ることができない場合がある。」との記載は,ゴル フクラブが1本の場合にはシャフトの設計因子が一定のものであるためス イングの計測データから適切な「スイング応答曲面」を算出することがで きない結果,妥当な解析結果を得ることができないことを示唆するものと 認められる。 しかるところ,本件決定が認定した引用発明1においては,試打に使用 されるゴルフクラブがシャフトの設計因子の異なる複数のゴルフクラブで あることが特定されていないため,ゴルフクラブが1本のみの場合も含ま れることになるから,甲1に記載された発明の認定としては不適切であり, この点において,本件決定には誤りがあるといえる。 そして,前記アの記載事項を総合すると,甲1には,原告主張の原告引 用発明1(前記第3の1(1)ア(イ))が記載されているものと認めるのが相 当である。 しかしながら,本件発明1と原告引用発明1との一致点及び相違点は, 本件決定が認定した本件発明1と引用発明1の一致点及び相違点と同様で あり(争いがない。),本件決定は相違点の容易想到性について判断を示 しているから,本件決定における上記認定の誤りは,本件決定の結論に直 ちに影響を及ぼすものではない。
・・・
これに対し原告は,原告引用発明1においてセンサーユニットをグリッ エンドに対して着脱可能に取り付ける構\成とした場合,1)試打に用いら れるゴルフクラブの総重量や重心が変わるため,原告引用発明1が意図す る本来のスイング((試打用ではない)通常のゴルフクラブを使用してス イングした際のスイング)の計測データが得られなくなる(阻害要因1)), 2)ゴルフクラブ全体の外観が変化し,試打者の視界も悪化するため,原告 引用発明1が意図する本来のスイングの計測データが得られなくなる(阻 害要因2)),3)ゴルフクラブと6軸センサとの対応関係が乱される結果, 原告引用発明1の課題を解決できなくなるおそれがある(阻害要因3))と いった重大な弊害が生じるため,原告引用発明1に相違点2に係る本件発 明1の構成を適用することに阻害要因がある旨主張する。\nしかしながら,甲1には,「ゴルフシャフトの最適設計を行う際にはゴ ルフクラブを使用するゴルファーのスイング特性を考慮に入れて,ゴルフ ァーの技量や癖を確実に把握して,技量や癖に合致したゴルフシャフトの 設計を行う必要がある。」(【0008】),「9本のゴルフクラブ1は, 6軸センサ11,送信部12等をシャフト内に挿入することによりゴルフ クラブ1の総重量が重くならないように,6軸センサ11,送信部12及 びこれらを動作させるために必要な機器全体の重量を20gに抑えている。 これにより,市販の軽量グリップを用いることで総重量の増加を抑えるこ とができるためクラブの重量増加によるスイングへの悪影響を与えないよ うにしている。」(【0029】)との記載があることに照らすと,甲1 に接した当業者であれば,原告引用発明1の6軸センサ及び送信部(セン サーユニット)をグリップエンドに対して着脱可能に取り付ける構\成とす る場合,ゴルフクラブの総重量や重心の変化によりスイングへの悪影響を 与えないようにしたり,試打者の視界を妨げないようにすることは,ゴル ファーの技量や癖を確実に把握するために当然に配慮し,通常期待される 創作活動を通じて実現できるものと認められるから,原告主張の阻害要因 1)及び2)は採用することができない。
次に,原告引用発明1の6軸センサ及び送信部をグリップエンドに対し て着脱可能に取り付ける構\成とする場合,ゴルフクラブと6軸センサとの 対応関係が乱される結果がないように設計することも,上記と同様に,当 業者が通常期待される創作活動を通じて実現できる事柄であり,また,試 打者が,複数のゴルフクラブを使用して試打を行う場合であっても,実際 に試打を行う際に使用するゴルフクラブは特定の1本であることからする と,システムの使用時に6軸センサ及び送信部の取り付けの誤りによって 上記対応関係が乱されるおそれがあるものとは考え難いし,仮にそのよう なおそれがあるとしても,それを回避する措置を適宜とることも可能であ\nるものと認められるから,原告主張の阻害要因3)も採用することができな い。
したがって,原告引用発明1に相違点2に係る本件発明1の構成を適用\nすることに阻害要因があるとの原告の上記主張は,理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2018.10. 4
平成27(ワ)2570 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年9月20日 大阪地方裁判所
これらのフラダンスの特徴からすると,特定の楽曲の振付けにおいて, 各歌詞に対応する箇所で,当該歌詞から想定されるハンドモーションがとられてい るにすぎない場合には,既定のハンドモーションを歌詞に合わせて当てはめたにす ぎないから,その箇所の振付けを作者の個性の表れと認めることはできない。\nまた,フラダンスのハンドモーションが歌詞を表現するものであることからする\nと,ある歌詞部分の振付けについて,既定のハンドモーションどおりの動作がとら れていない場合や,決まったハンドモーションがない場合であっても,同じ楽曲又 は他の楽曲での同様の歌詞部分について他の振付けでとられている動作と同じもの である場合には,同様の歌詞の表現として同様の振付けがされた例が他にあるので\nあるから,当該歌詞の表現として同様の動作をとることについて,作者の個性が表\ れていると認めることはできない。 さらに,ある歌詞部分の振付けが,既定のハンドモーションや他の類例と差異が あるものであっても,それらとの差異が動作の細かな部分や目立たない部分での差 異にすぎない場合には,観衆から見た踊りの印象への影響が小さい上,他の振付け との境界も明確でないから,そのような差異をもって作者の個性の表れと認めるこ\nとは相当でない。また,既定のハンドモーションや他の類例との差異が,例えば動 作を行うのが片手か両手かとか,左右いずれの手で行うかなど,ありふれた変更に すぎない場合にも,それを作者の個性の表れと認めることはできない。\nもっとも,一つの歌詞に対応するハンドモーションや類例の動作が複数存する場 合には,その中から特定の動作を選択して振付けを作ることになり,歌詞部分ごと にそのような選択が累積した結果,踊り全体のハンドモーションの組合せが,他の 類例に見られないものとなる場合もあり得る。そして,フラダンスの作者は,前後 のつながりや身体動作のメリハリ,流麗さ等の舞踊的効果を考慮して,各動作の組 合せを工夫すると考えられる。しかし,その場合であっても,それらのハンドモー ションが既存の限られたものと同一であるか又は有意な差異がなく,その意味でそ れらの限られた中から選択されたにすぎないと評価し得る場合には,その選択の組 合せを作者の個性の表れと認めることはできないし,配列についても,歌詞の順に\nよるのであるから,同様に作者の個性の表れと認めることはできない。\n
エ 他方,上記で述べたのと異なり,ある歌詞に対応する振付けの動作が, 歌詞から想定される既定のハンドモーションでも,他の類例に見られるものでも, それらと有意な差異がないものでもない場合には,その動作は,当該歌詞部分の振 付けの動作として,当該振付けに独自のものであるか又は既存の動作に有意なアレ ンジを加えたものいうことができるから,作者の個性が表れていると認めるのが相\n当である。 もっとも,そのような動作も,フラダンス一般の振付けの動作として,さらには 舞踊一般の振付けの動作として見れば,ありふれたものである場合もあり得る。そ して,被告は,そのような場合にはその動作はありふれたものであると主張する。 しかし,フラダンスのハンドモーションが歌詞を表現するものであることからする\nと,たとえ動作自体はありふれたものであったとしても,それを当該歌詞の箇所に 振り付けることが他に見られないのであれば,当該歌詞の表現として作者の個性が\n表れていると認めるのが相当であり,このように解しても,特定の楽曲の特定の歌\n詞を離れて動作自体に作者の個性を認めるものではないから,個性の発現と認める 範囲が不当に拡がることはないと考えられる。
オ ところで,フラダンスのハンドモーションが歌詞を表現するものである\nことからすると,歌詞に動作を振り付けるに当たっては,歌詞の意味を解釈するこ とが前提になり,普通は言葉の通常の意味に従って解釈すると思われるが,作者に よっては,歌詞に言葉の通常の意味を離れた独自の解釈を施した上で振付けの動作 を作ることもあり得る。そして,原告は,その場合には解釈の独自性自体に作者の 個性を認めるべきであると主張する趣旨のように思われる。しかし,著作権法は具 体的な表現の創作性を保護するものであるから,解釈が独自であっても,その結果\nとしての具体的な振付けの動作が上記ウで述べたようなものである場合には,やは りその振付けの動作を作者の個性の表れと認めることはできない。\n他方,被告は,たとえ歌詞の解釈が独自であり,そのために振付けの動作が他と 異なるものとなっているとしても,当該解釈の下では当該振付けとすることがあり ふれている場合には,当該振付けを著作権法の保護の対象とすることは結局楽曲の 歌詞の解釈を保護の対象とすることにほかならず許されないと主張する。しかし, 歌詞の解釈が独自であり,そのために振付けの動作が他と異なるものとなっている 場合には,そのような振付けの動作に至る契機が他の作者には存しないのであるか ら,当該歌詞部分に当該動作を振り付けたことについて,作者の個性が表れている\nと認めるのが相当である。そして,このように解しても,個性の表れと認めるのは\n飽くまで具体的表現である振付けの動作であって,同様の解釈の下に他の動作を振\nり付けることは妨げられないのであるから,解釈自体を独占させることにはならな い。 これに対し,歌詞の解釈が言葉の通常の意味からは外れるものの,同様の解釈の 下に動作を振り付けている例が他に見られる場合には,そのような解釈の下に動作 を振り付ける契機は他の作者にもあったのであるから,当該解釈の下では当該振付 けとすることがありふれている場合には,当該歌詞部分に当該動作を振り付けたこ とについて,作者の個性が表れていると認めることはできない。\n
カ 以上のハンドモーションに対し,ステップについては,上記のとおり典 型的なものが存在しており,入門書でも,覚えたら自由に組み合わせて自分のスタ イルを作ることができるとされているとおり,これによって歌詞を表現するもので\nもないから,曲想や舞踊的効果を考慮して適宜選択して組み合わせるものと考えら れ,その選択の幅もさして広いものではない。そうすると,ステップについては, 基本的にありふれた選択と組合せにすぎないというべきであり,そこに作者の個性 が表れていると認めることはできない。しかし,ステップが既存のものと顕著に異\nなる新規なものである場合には,ステップ自体の表現に作者の個性が表\れていると 認めるべきである(なお,ステップが何らかの点で既存のものと差異があるという だけで作者の個性を認めると,僅かに異なるだけで個性が認められるステップが乱 立することになり,フラダンスの上演に支障を生じかねないから,ステップ自体に 作者の個性を認めるためには,既存のものと顕著に異なることを要すると解するの が相当である。)。また,ハンドモーションにステップを組み合わせることにより, 歌詞の表現を顕著に増幅したり,舞踊的効果を顕著に高めたりしていると認められ\nる場合には,ハンドモーションとステップを一体のものとして,当該振付けの動作 に作者の個性が表れていると認めるのが相当である。\n
キ 以上のようにして,特定の歌詞部分の振付けの動作に作者の個性が表れ\nているとしても,それらの歌詞部分の長さは長くても数秒間程度のものにすぎず, そのような一瞬の動作のみで舞踊が成立するものではないから,被告が主張すると おり,特定の歌詞部分の振付けの動作に個別に舞踊の著作物性を認めることはでき ない。しかし,楽曲の振付けとしてのフラダンスは,そのような作者の個性が表れ\nている部分やそうとは認められない部分が相俟った一連の流れとして成立するもの であるから,そのようなひとまとまりとしての動作の流れを対象とする場合には, 舞踊として成立するものであり,その中で,作者の個性が表れている部分が一定程\n度にわたる場合には,そのひとまとまりの流れの全体について舞踊の著作物性を認 めるのが相当である。そして,本件では,原告は,楽曲に対する振付けの全体とし ての著作物性を主張しているから,以上のことを振付け全体を対象として検討すべ きである。 そしてまた,このような見地からすれば,フラダンスに舞踊の著作物性が認めら れる場合に,その侵害が認められるためには,侵害対象とされたひとまとまりの上 演内容に,作者の個性が認められる特定の歌詞対応部分の振付けの動作が含まれる ことが必要なことは当然であるが,それだけでは足りず,作者の個性が表れている\nとはいえない部分も含めて,当該ひとまとまりの上演内容について,当該フラダン スの一連の流れの動作たる舞踊としての特徴が感得されることを要すると解するの が相当である。
・・・
本件振付け6では,大きく分けて,1)両手の掌を下に返して右肘を 少し曲げ,そのまま両腕を下ろしながら胸の高さまで持って行き,胸の前で体に沿 うように両腕を交差させて両手の掌を内側に向け,一連の動作は右に270度ター ンするステップの中で行われる,2)次に,ターンにより左斜め後ろを向いたまま, 両腕を伸ばしきるまで下ろしながら左斜め後ろへ左足右足を交互に2歩ずつ前進す る,という2つのパートからなる動作をしている。 まず,1)の動作についてみると,原告は,右回りに回転しながら両腕を下ろし胸 の前で交差させることで,暗い夜が続き,暗く寒くなっていることを表していると\n主張する。この点,甲25の他の振付け及び乙12の他の振付けはいずれも,手の 動きについては本件振付け6と同様の動きをしているものの,その際にターンする ものはない。ターンは通常のステップの一種ではある(乙5のスピンターン)が, 「夜」や「寒い」といった静的な歌詞からターンすることはが通常想定されない上, 両腕を降ろしながらターンすることによって体全体の躍動感を高めていることから, なお有意な差異があるというべきである。
これに対し,被告は,手の動作が既存の ハンドモーションであり,足の動作が既存のステップであり,これらを組み合わせ た動作はありふれたものであると主張するが,上記のとおり採用できない。 次に,2)の動作について見ると,原告は,聴衆と反対(後ろ)に向かって歩いて いくことで彼が孤独であることを表し,両腕を下ろすことで抱きしめる者がおらず\n一人で寒い夜を過ごしていることを表していると主張する。そして,この動作は,\nここでの歌詞から想定されるものでない上,これと同様の動作を行っている類例は 認められないから,本件振付け6独自のものであると認められる。これに対し,被 告は,このような動作があらゆる舞踊においてありふれた動作であることを指摘す るが,こうした被告の主張が採用できないことは,上記(1)エのとおりである。
c したがって,ここの歌詞に対応する振付けは,原告の個性が表現さ\nれていると評価できる。
2018.10. 4
平成30(行ケ)10053 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年9月26日 知的財産高等裁判所
上記認定事実からすると,1)被告の靴は,昭和46年頃から本件使用行為がされ た平成25年1月28日までの間に,日本において「スペリー・トップサイダー」, 「スペリートップサイダー」あるいは「トップサイダー」というブランド名で継続 的に販売されており,大手のメーカーや靴の小売店などによって全国的に相当数が 販売されてきたものと推認されること,2)本件使用行為がされた時期に近接した3 年間に,引用商標を付した被告の靴が約5万足販売されていること,3)引用商標は, 被告の靴(デッキシューズ)とともに,本件使用行為に近接する時期である平成1 9年から平成25年までの間に,合計で10回程度,雑誌で取り上げられたほか, 引用商標の要部である「TOP−SIDER」を含んだ欧文字や「TOP SID ER」及びそれを含む欧文字並びにそれらを片仮名読みした文字が多くの雑誌や新 聞で被告の靴(デッキシューズ)とともに紹介されるなどしたこと,4)辞書や小説 にも取り上げられていることが認められる。これらの事実に,引用商標は独創性が 高いものであることや丸井社が本件使用商標について上記認定のような紹介文を付 していたことも考え併せると,引用商標は,平成25年1月28日頃には,被告の 靴(デッキシューズ)を表示するものとして,靴(デッキシューズ)の取引者及び\nその需要者である一般消費者の間で,広く知られていたものと認められる。 この点について,原告は,引用商標が表示されていた雑誌の記事は限られたもの\nである上,「トップサイダー」等の文字が掲載されただけでは引用商標の周知性は基 礎づけられないと主張する。確かに引用商標が表示された雑誌の記載は,上記認定\nのとおり限られた数にとどまるが,被告の靴は長年にわたって相当数が販売されて きたと推認されるところ,引用商標は商品である被告の靴にも付されており,また, 「TOP−SIDER」,「TOP SIDER」,「トップサイダー」等の表示は,\n引用商標の要部又はそれを想起させる表示であって,これらの表\示が数多く雑誌や 新聞に掲載されたことは,引用商標の周知性を基礎づけるものということができる。 なお,原告は,被告の靴の売上額をクラークス社の「CLARKS」ブランドの 売上額との比較で主張しているが,商標の周知性の有無は必ずしも売上額のみで決 まるものではなく,上記の引用商標の周知性についての判断が左右されることはな い。
(3) 本件使用商品と引用商標が付された商品との関連性
本件使用商品であるシャツと引用商標が使用されていた靴(デッキシューズ)は, いずれも身に着けて使用するアパレル製品であって,同じブランドで統一されてコ ーディネイトの対象となったり,同一の店舗内で販売されたりすることがあるもの ということができ,現に証拠(甲11,36,44,70)によると,被告の靴が, 衣料品店でシャツなどの衣料品と一緒に販売されている事例があることが認められ る。また,シャツと靴(デッキシューズ)について,同一の営業主によって製造さ れることもあり得るものである。 加えて,本件使用商品は,一般消費者向けのシャツであって,引用商標が付され ていた靴(デッキシューズ)も,一般消費者向けの商品であると認められるもので ある。 したがって,本件使用商品と引用商標が付された靴とは,販売場所や需要者を共 通にするなど高い関連性を有するものということができる。
(4) 本件商標の使用態様等について
本件使用商標には,本件商標にはない,雲を想起させる図形とヨットの図形が付 加されており,本件使用商標は引用商標と外観上極めて類似したものとなっている。 また,本件使用商標は,本件使用商品の襟の部分に付されていたほか,本件使用商 品には本件使用商標を記載した下げ札が二つ付されており(甲79),本件使用商標 は,取引者や需要者が容易に認識できるような形で使用されていた。
(5) 「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」かどうかについての判断
以上のとおり,引用商標は,被告の靴(デッキシューズ)を表示するものとして\n取引者及び需要者の間で,広く知られているところ,本件使用商品であるシャツと 引用商標が使用されている靴(デッキシューズ)が関連性の高いものであることや, 本件使用商標は,本件商標に雲を想起させる図形とヨットの図形が付加されていて, 引用商標と極めて類似するものであることからすると,本件使用商品に接した取引 者や需要者たる一般消費者にとって,本件使用商品が被告の業務に係る商品である との混同を生じるおそれが十分にあるというべきである。\n (6) 原告のその他の主張について
原告は,別件異議決定(甲101)では,本件使用行為より後の時点でも引用商 標が周知性を獲得していない旨の判断がされていると主張するが,別件異議決定は, 本件とは異なる事件についての特許庁の決定であって,本件についての前記(5)の 判断を左右するものではない。 また,原告は,旧会社は,原告が本件商標を被服に使用しても,出所混同は生じ ないと認識していたと推測されることから,本件において出所混同のおそれはない と主張する。確かに旧会社が,指定商品を「第17類 被服(運動用特殊被服を除 く),布製見回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」とする本件 商標を原告に譲渡したという過去の経緯からすると,旧会社としては,原告が「T OP−SIDER」の欧文字からなる本件商標を,被服等の上記指定商品に使用し ても出所混同は生じないとして容認していたものと推認できる。しかし,そうであ るからといって,そのことから直ちに,旧会社が,水甚社が本件でしていたように, 本件商標に雲を想起させる図形とヨットの図形を付加し,引用商標に極めて類似す る構成で使用することについても出所混同が生じないとして容認していたとはいえ\nないのであるから,前記(5)の判断を左右するものではない。
2018.10. 4
平成29(行ケ)10173 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月26日 知的財産高等裁判所
なお、判決文1ページに「被告は,平成17年9月30日,発明の名称を「ドライブスプロケット支持構造」とする発明につき,特許を出願し(特願2005−287276号),平成24年2月24日,設定登録(特許第4933764号)を受けた(請求項の数3。甲1。以下「本件特許」という。)。被告は,平成27年3月23日,本件特許の請求項1〜3に係る発明について特許無効審判を請求した(無効2015−800071号。甲16,乙1)。」とありますが、冒頭の「被告は,平成17年・・」は、「原告は,平成17年・・・」の誤記と思われます。
前記の2の甲2の図1及び2において,ドライブスプロケット21 の左側張出部の外側は,変速機ハウジング51にボルト52aで固定されたカバー 52の内側に接しているよう図示されており,ドライブスプロケット21の右側張 出部の外側の右端は,変速機ハウジング張出部の内側に接しているよう図示されて いる。 しかし,甲2は,公開特許公報であり,甲2に掲載された前記2の図1及び2は いずれも特許出願の願書に添付された図面に描かれたものであるところ,一般に, 特許出願の願書に添付される図面は,明細書の記載内容を補完し,特許を受けよう とする発明の技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから,当該発明の 技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていれば足り,設計図面に要 求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。 甲2において,図1は「本発明に係るポンプハブ支持構造を有したトルクコンバ\nータおよび油圧ポンプ駆動系を示す断面図」であり,図2は,「上記ポンプハブ支持 構造部分を示す断面図」であるところ,前記2認定の甲2の記載に鑑みると,これ\nらの図面は,トルクコンバータのポンプハブの支持構造に関し,ポンプハブ11を\nステータシャフト6にニードルベアリング12によって支持し,このニードルベア リング12に対して,径方向にほぼ重なるようにして,すなわち,軸方向にほぼ同 位置において,ドライブスプロケット21がスプライン結合して,ドライブスプロ ケット21に作用する径方向力をドライブスプロケット21の内径側に位置するニ ードルベアリング12により受けるようにしたことを示すために,その位置関係を 示すべく,甲2に記載されたものであって,設計図面に要求されるような正確性を もって描かれているとは考えられない。
(イ) 前記2のとおり,甲2には,「ドライブスプロケット21に作用する 径方向力は,ドライブスプロケット21の内径側に位置するニードルベアリング1 2により受ける。このように,ニードルベアリング12およびドライブスプロケッ ト21を軸方向ほぼ同じ位置に重なるように配設することにより,ドライブスプロ ケット21に作用する力をニードルベアリング12により確実に受けることができ るだけでなく,この部分の軸方向寸法を短縮してこの部分の構造をコンパクト化す\nることができる。」(【0010】)と記載されている。したがって,甲2発明は,ド ライブスプロケット21に作用する径方向力は,ドライブスプロケット21の内径 側に位置するニードルベアリング12により受けるものである。この記載のみでは, ドライブスプロケット21に作用する径方向力を外径側でも受けるかどうかは必ず しも明らかでないものの,そのような必要性があるというべき事情は認められない 上,全体として一体化したケースに対し,ドライブスプロケットのような回転する 部材を,内周面及び外周面で同時に軸受等により支持することは,回転する部材や 周囲の部材の寸法誤差の許容範囲を狭めることになり,過度の工作精度を要求する ことになるから,通常行われるものとは考え難い(全体として一体化したケースに 対し,ドライブスプロケットのような回転する部材を,内周面及び外周面で同時に 軸受等により支持する例があることを認めるに足りる証拠もない。)。 また,回転する部材と回転しない部材が,回転する部材の回転中,一時的にしろ, 接触するような状態となることがあれば,回転する部材の円滑な回転が損なわれ, 異音が発生したり,部材の摩耗が生じるといった不具合を生じることも想定される のであって,当業者は,回転する部材であるドライブスプロケット21が,回転し ない部材であるカバー及び変速機ハウジングと接触するという設計を,通常は行わ ないと解される。 さらに,甲2の図2には,ドライブスプロケット21の左側張出部の外周面とカ バー52の内周面との間の対向面,及び,ドライブスプロケット21の右側張出部 の外周面の右端と変速機ハウジング張出部の内周面との間の対向面の軸方向の長さ は,ニードルベアリング12の長さに比べて著しく短いものとして記載されている。 仮に,ドライブスプロケット21の左側張出部の外周面とカバー52の内周面との 間の対向面,及び,ドライブスプロケット21の右側張出部の外周面の右端と変速 機ハウジング張出部の内周面との間の対向面がすべり軸受として接するように設定 されているとするならば,ドライブスプロケットにかかる径方向の負荷が,当該接 触面である対向面にも負荷されることになるところ,この場合には,小さい接触面 に対して集中した負荷がかかることになると考えられる。そして,このような局所 的に集中した負荷は,当該接触面である対向面に潤滑油の介在があるとしても,早 期の摩耗等の不具合が生じるおそれがあるといえるから,通常行われるものではな いと解される。 以上によると,甲2発明におけるドライブスプロケット21は,その内周面がポ ンプハブ11を介してニードルベアリング12で支持されるのであって,ドライブ スプロケット21の左側張出部の外周面とカバー52の内周面,及び,ドライブス プロケット21の右側張出部の外周面の右端と変速機ハウジング張出部の内周面は, ドライブスプロケット21の静止時のみならず回転中も接触することがないように 間隙を設定することが前提になっている,すなわち,原告が主張する技術思想2)に よるものと解することができる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2018.10. 4
平成30(ネ)10044 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
当裁判所は,平成30年8月8日の当審の第1回口頭弁論期日において, 控訴人が同月3日付け準備書面(1)に基づいて提出した,特許請求の範囲の訂 正により無効理由が解消されることを理由とする訂正の再抗弁の主張につ いて,被控訴人の申立てにより,時機に後れた攻撃防御方法に当たるものと\nして却下したが,その理由は,以下のとおりである。
ア 一件記録により認められる本件訴訟の経緯等は,次のとおりである。
(ア) 本件特許に係る侵害訴訟と特許無効審判
控訴人は,平成28年8月12日,被控訴人に対し,本件特許権に基 づき,被告製品の販売の差止め等及び損害賠償を求める本件訴訟を提起 した後,カシオ計算機株式会社(以下「カシオ計算機」という。)に対 し,本件特許権に基づき,2次元コードリーダの販売の差止め等及び損 害賠償を求める訴訟(東京地方裁判所平成28年(ワ)第32038号。 以下「別件侵害訴訟」という。)を提起した。 その後,米国法人のハネウェル・インターナショナル・インク(以下 「ハネウェル社」という。)は,平成29年8月3日,本件特許につい て,「IT4400(公然実施コードリーダ)」の発明などを主引用例 とする進歩性欠如の無効理由(特許法29条2項,123条1項2号) が存在することを理由として,特許無効審判(無効2017−8001 03号。以下「別件無効審判」という。)を請求した。
(イ) 本件訴訟の経緯
a 原審における経緯
被控訴人は,平成28年12月26日の原審第2回弁論準備手続期 日において,同月20日付け準備書面(3)に基づいて,乙5を主引用例 とする進歩性欠如,サポート要件違反,明確性要件違反及び実施可能\n要件違反の無効理由が存在するとして,特許法104条の3第1項の 規定に基づく無効の抗弁(以下「無効の抗弁」という。)を主張した。 その後,被控訴人は,平成29年7月25日の原審第6回弁論準備 手続期日において,同月7日付け準備書面(8)に基づいて,IT440 0に係る発明を主引用例とする進歩性欠如の無効理由が存在するとし て,新たな無効の抗弁(以下「本件無効の抗弁」という。)を主張し た。 原審は,合計11回の弁論準備手続期日を経て,平成30年2月1 4日の第2回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。控訴人は, 原審の口頭弁論終結時までに,本件無効の抗弁に対し,訂正の再抗弁 を主張しなかった。なお,控訴人は,原審の口頭弁論終結前に,本件 訴訟のうち,被告製品の販売の差止め等請求に係る部分について訴え の取下げをし,被控訴人は,これに同意した。 原審は,平成30年4月13日,本件無効の抗弁は理由があるもの と認め,控訴人の請求を棄却する旨の原判決を言い渡した。
b 当審における経緯
控訴人は,平成30年4月19日,本件控訴を提起した。当審の第 1回口頭弁論期日は同年8月8日と指定され,控訴理由書の提出期限 は同年6月8日(控訴提起日から50日後の応当日)と定められた。 控訴状等の送達後,控訴理由書に対する被控訴人の準備書面の提出期 限は同年7月26日と定められた。 控訴人は,同年6月8日,控訴理由書を提出し,被控訴人は,同年 7月26日,控訴答弁書及び同日付け準備書面(1)を提出した。なお, 控訴人は,控訴理由書において,本件無効の抗弁に対する訂正の再抗 弁を主張しなかった。 その後,控訴人は,同年8月4日,同月3日付け準備書面(1)を提出 した。上記準備書面(1)には,被控訴人作成の上記準備書面(1)に対する 反論のほか,1)控訴人が,別件無効審判において,「IT4400(公 然実施コードリーダ)」の発明を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は理由があるから,本件発明についての本件特許を無効とする旨の 同年7月9日付けの審決の予告(以下「別件審決の予\告」という。) を受けた旨,2)控訴人が,別件無効審判において,同月31日付けで, 本件特許の特許請求の範囲(請求項1及び2)の訂正を求める訂正請 求(以下「別件訂正請求」という。訂正後の請求項1は,別紙3のと おり。)をした旨,3)当審において,別件訂正請求と同内容の訂正に よる本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁(以下「本件訂正の再抗弁」 という。)を主張する旨の記載がある。 同年8月8日の当審第1回口頭弁論期日において,控訴人は,上記 の同月3日付け準備書面(1)に基づいて,本件訂正の再抗弁を主張し, これに対し被控訴人は,同月7日付け準備書面(2)に基づいて,控訴人 の本件訂正の再抗弁の主張は,時機に後れた攻撃防御方法に当たるも のであるから,却下を求める旨の申立てをするとともに,本件訂正の\n再抗弁の主張が却下されない場合には,追って追加反論する予定であ\nる旨を述べた。
(ウ) 別件侵害訴訟における経緯
東京地方裁判所は,平成29年11月9日,別件侵害訴訟の口頭弁論 を終結し,平成30年1月30日,控訴人のカシオ計算機に対する請求 をいずれも棄却する旨の判決(乙80)を言い渡した。 上記判決の理由は,カシオ計算機が主張したIT4400により実施 (公然実施)された発明を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁(本 件無効の抗弁と同じ抗弁)は理由があると判断したものである。なお, 控訴人は,別件侵害訴訟の口頭弁論終結時までに,上記無効の抗弁に対 し,訂正の再抗弁を主張しなかった。 その後,控訴人は,別件侵害訴訟の上記判決を不服として,控訴を提 起した。
(エ) 別件無効審判における経緯
控訴人は,平成29年11月3日,別件無効審判において,ハネウェ ル社主張の無効理由に対する答弁書を提出した。 その後,特許庁は,平成30年4月23日に口頭審理を行った後,同 年7月9日付けで,「IT4400(公然実施コードリーダ)」の発明 を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由があるから,本件発明に ついての本件特許を無効とする旨の別件審決の予告(甲24)をした。\nこれに対し控訴人は,同月31日付けで,別件訂正請求(甲25の1 及び2)をした。
イ 前記アの事実関係によれば,1)控訴人は,原審において,平成29年7 月25日の原審弁論準備手続期日において被控訴人から本件無効の抗弁 が主張され,別件侵害訴訟及び別件無効審判においても,本件無効の抗弁 と同じ無効の抗弁又は無効理由が主張され,さらに,平成30年1月30 日に別件侵害訴訟において上記無効の抗弁を容れた請求棄却判決の言渡 しがされたが,同年2月14日の原審口頭弁論終結時までに本件無効の抗 弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったこと,2)その後,同年4月13 日に本件無効の抗弁を容れた原判決がされたが,控訴人は,控訴理由書提 出期限の同年6月8日に提出した控訴理由書においては本件無効の抗弁 に対する訂正の再抗弁を主張せず,その後同年7月26日に被控訴人から 控訴理由書に対する反論の準備書面が提出された後,当審第1回口頭弁論 期日(同年8月8日)の4日前の同月4日になって初めて,本件訂正の再 抗弁の主張を記載した準備書面(準備書面(1))を提出したことが認められ る。
一方で,控訴人において,当審第1回口頭弁論期日の4日前になるまで, 本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったことについて,や むを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。 もっとも,控訴人は,別件無効審判において,平成29年11月3日に 本件無効の抗弁と同じ無効理由を含むハネウェル社主張の無効理由に対す る答弁書を提出した後,平成30年7月9日付けの別件審決の予告を受け\nるまでは,特許法126条2項,134条の2第1項の規定により,本件 無効の抗弁と同じ無効理由を解消するための訂正審判の請求又は別件無効 審判における訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。し かしながら,このような事情の下では,本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張するために,現にこれらの請求をしている必要はないというべ きであるから(最高裁平成28年(受)第632号平成29年7月10日 第二小法廷判決・民集71巻6号861頁参照),当該事情は,特段の事 情に該当しないというべきである。
そして,無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張は,本来,原審におい て適時に行うべきものであり,しかも,控訴人は,当審において,遅くと も控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁の主張をすることができたに もかかわらず,これを行わず,第1回口頭弁論期日の4日前になって初め て,本件訂正の再抗弁の主張を記載した準備書面を提出したのであるから, 本件訂正の再抗弁の主張は,控訴人の少なくとも重大な過失により時機に 後れて提出された攻撃防御方法であるものというべきである。 また,当審において,控訴人に本件訂正の再抗弁を主張することを許す ことは,被控訴人に対し,訂正の再抗弁に対する更なる反論の機会を与え る必要が生じ,これに対する控訴人の再反論等も想定し得ることから,こ れにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで,控訴人の本件訂正の再抗弁の主張は,民事訴訟法297条にお いて準用する157条1項に基づき,これを却下したものである。
2018.10. 4
平成30(行ケ)10046 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年9月26日 知的財産高等裁判所
上記認定事実によれば,被告による本件付箋紙の配布行為は,上記各併設 展示会の展示ブースにおいて,被告の販売する医療用ウィッグ等の商品の広 告の一環として行われたものと認められる。 そして,本件付箋紙の見開き内面部分に掲載された本件使用商標は,全体 として「スヴェンソンのウィッグ」商品の出所識別標識として認識することができる態様で使用されているものと認められることは,前記2(2)認定の とおりである。 そうすると,本件付箋紙は,被告の販売する医療用ウィッグ等の商品(「ス ヴェンソンのウィッグ」商品)の広告媒体に当たるものであって,被告による本件付箋紙の配布行為は,上記商品に関する広告に本件使用商標を付\nして頒布する行為(商標法2条3項8号)に該当するものと認められる。 したがって,本件審決における商標法2条3項8号該当性の判断に誤 りはない。
(2) これに対し原告は,1)本件商標は,被告のウェブサイト,被告が運営 する通販サイト,商品「ウィッグ」のいずれにも,これまで一切使用された ことはなく,被告の公式キャラクターも,これまで商品「ウィッグ」に使用 されたことはなかったことに照らすと,本件付箋紙は,被告そのものを広告 するためのノベルティ(販促品)と認識されるにとどまる,2)本件付箋紙の 見開き内面部分の文章の記載は,「ウィッグ」の語が含まれているというだ けであって,商品自体を宣伝したものではなく,「ウィッグ」の前に「スヴ ェンソンの」と付いているように,被告と商品「ウィッグ」との関係を強調したものであり,本件使用商標と商品「ウィッグ」とのつながりを示すもの\nとはいえないなどとして,本件付箋紙は,単なる被告を宣伝広告するノベル ティ(販促品)に過ぎず,商品「ウィッグ」の宣伝広告とはいえないし,商 品「ウィッグ」との具体的関係において使用されているものとはいえないか ら,本件付箋紙は,商標法2条3項8号所定の「商品に関する広告」に該当 せず,被告による本件付箋紙の配布行為は,同号に該当しない旨主張する。 しかしながら,前記(1)認定のとおり,被告による本件付箋紙の配布行為 は,前記各併設展示会の展示ブースにおいて,被告の販売する医療用ウィッ グ等の商品の広告の一環として行われたものであり,本件付箋紙は,被告の 販売する医療用ウィッグ等の商品(「スヴェンソンのウィッグ」商品)の広告媒体に当たり,上記商品に関する広告に該当するものと認められる。\nもっとも,本件付箋紙の表紙部分を含む本件付箋紙全体の記載内容(前記2(1))に照らすと,本件付箋紙は,被告それ自体を広告する広告媒体とし ての機能をも有するものと認められるが,そのことは,本件付箋紙が上記商品に関する広告に該当することを否定する事情になるものではない。また,\n本件付箋紙に「ウィッグ」に関する具体的な商品情報の記載がないことは, 本件使用商標が本件付箋紙において「スヴェンソンのウィッグ」商品の出所識別標識として認識することができる態様で使用されているとの認定の妨\nげになるものではなく(前記2(3)),しかも,被告による本件付箋紙の配 布行為は,前記各併設展示会の展示ブースにおいて,被告の販売する医療用 ウィッグ等の商品の展示とともに行われたのであるから,本件付箋紙の配布 を受けた参加者は,本件付箋紙は,上記商品の広告のために配布されたもの と認識したものと認められる。
2018.10. 4
平成30(行ケ)10065 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年9月19日 知的財産高等裁判所
本件商標の構成中,欧文字部分は,AとCがやや図案化されているもの\nの,その形状から,「AiCOM」の文字からなるものと認識できるから,同部分か らは「アイコム」との称呼が生じる。「亜太電信」からなる本件商標の漢字部分から は「アタデンシン」との称呼が生じる。 上記のような両部分から生ずる称呼に加え,欧文字部分と漢字部分が,いずれも 造語であって何らの観念も生じないものであること,欧文字部分と漢字部分が,異 なる種類の文字で,前記のとおり上下に2段に分けて横書きで記載されていること を考え併せると,欧文字部分と漢字部分との間に外観や観念上,何らかの関連性が あるとは認められないものである。また,この両部分を併せた称呼である「アイコ ムアタデンシン」はやや冗長である。 本件商標の構成中,図形部分についても,何らの称呼や観念も生じないものであ\nり,外観,称呼及び観念の各点で欧文字部分及び漢字部分のいずれとも何らの関連 性が認められないものである。 そして,上記のような各構成部分は,いずれも指定商品との関係でその内容,属\n性,品質等を表すものとはいえず,各構\成部分は,指定商品との関係でそれぞれ独 立して出所識別機能を有し得るものといえる。\nさらに,上記アのとおり,「AiCOM」の欧文字部分が,図案化されて漢字部分 よりも大きく記載され,かつ「i」の部分に赤色が用いられている。 そうすると,本件商標の各構成部分が,分離して観察することが取引上不自然で\nあると思われるほど不可分的に結合しているとは認められず,本件商標から「Ai COM」の欧文字部分を要部として観察することが許されるというべきである。 なお,結合商標においては要部が複数生じることもあるのであり,「亜太電信」の 漢字部分が要部となるとしても,そのことによって直ちに「AiCOM」の欧文字部 分が要部とならなくなるものではない。
(2) 原告は,本件商標の欧文字部分の冒頭が「V」を逆にしたものであること などから,欧文字部分は,「AiCOM」とは認識されないと主張する。 しかし,欧文字部分の冒頭の文字について,確かに欧文字の「A」をそのまま記 載したものではないが,同じ長さの2本の直線が上部において鋭角に交差されてい るという外郭の形状は,「A」と同一である。また,本件商標と同様に,「A」の文 字の内側にある直線を省略して図案化している例は,他の企業の標章にも複数見受 けられる(乙20〜26)。一方,欧文字部分の冒頭の文字について,それが原告の 主張するように,欧文字の「V」を逆にしたものであると認識させる契機となるよ うなものは,何ら見当たらない。そうすると,本件商標に接した者が,欧文字部分 の冒頭の文字を「V」を逆にしたものと認識するとは認められず,上記のとおり, 「A」と認識するものと認められる。 また,欧文字部分の3文字目についても,図案化されてはいるものの,円弧の右 側に開口部があり,同開口部が円弧の中央部にあるなどの特徴は欧文字の「C」と 同一である。加えて,他の標章について,本件商標と同じような態様で「C」を図 案化している例や本件商標と同様に「C」の右側開口部に他の欧文字を挟み込んで 図案化している例が見受けられること(乙27〜38)も踏まえると,本件商標に 接した者が,欧文字部分の3文字目を欧文字の「C」と容易に認識するものと認め られる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.10. 4
平成30(行ケ)10040 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年9月12日 知的財産高等裁判所
本願商標は,前記第2の2のとおり,本件図形部分と欧文字「OGGY」 とを横一列に記載して成る。欧文字「OGGY」の高さは,本件図形部分の高さの 半分程度であるが,本件図形部分及び欧文字「OGGY」の下端は概ね同一線上に あり,本件図形部分及び欧文字「OGGY」の間隔は,本件図形部分と「O」との 間隔も含め,概ね等間隔である。
(2) 本件図形部分は,横長の楕円形状を半分にし,その断面に当たる左側の縦 線の上下両端に,左向きに矩形の小さな突起を配した図形の全体を黒塗りにし,そ の中央部に右横向きの四足動物と思しき絵柄をシルエット状に白抜きにしたもので ある。本件図形部分は,左側が縦線,右側が弧線の半楕円形状の輪郭を有し,その 内部の相当部分が白抜きとなっている点において,厚みのあるセリフ(字画末端部 にある爪のような張り出し部)を有する欧文字「D」と共通した形状を有している (乙3,4)。 前記(1)のとおり,本件図形部分及び欧文字「OGGY」は,その下端が概ね同一 線上にあり,概ね等間隔に配置されている上,欧文字「OGGY」は直ちに特定の 意味を有する成語とは認識できないところ,本件図形部分が上記のような形状を有 していることから,本件図形部分を欧文字「D」であるとして,本願商標全体をみ ると,「DOGGY」という構成となる。これが「犬の」という意味を有する英単語\nであることは,我が国においても容易に理解されるものであり(甲13〜23,2 5〜30,乙6),特定の意味を有する平易な英単語として認識することができる。 また,本件図形部分の内側に白抜きされた右横向きの四足動物と思しき絵柄は, 三角形の耳を立てているという形状や,胴体の半分に満たない長さの細い尾を胴体 と略平行に持ち上げているという尾の形状,その他,顔,胴体,足等の各部位の大 きさ,形状,配置等から,「犬」を表したものと容易に理解することができる。\nそこで,本件図形部分を欧文字「D」であるとした場合の本願商標全体の欧文字 の構成と,本件図形部分の内側に白抜きされた絵柄との間にも,関連性があること\nを容易に理解することができる。 そうすると,本願商標に接した需要者は,本件図形部分は,欧文字「D」を図案 化したものであると理解するものと認められる。
(3) 本願商標は,前記(1)のとおり,本件図形部分及び欧文字「OGGY」の下 端を概ね同一線上にして,概ね等間隔で,横一列に記載して成るものであり,また, 前記(2)のとおり,欧文字「D」を図案化した本件図形部分と,欧文字「OGGY」 とは,一体として一つの英単語を構成しているものである。\nそうすると,本願商標は,欧文字「DOGGY」と理解されるその全体の構成か\nら,「ドギー」という称呼を生じ,「犬の」という観念を生じるものと認められる。
・・・
前記1,2のとおり,本願商標と引用商標からは,「ドギー」という同一の称呼及 び「犬の」という同一の観念が生じる。 また,本願商標と引用商標とは,外観において,欧文字「DOGGY」と理解さ れる構成を有する点において共通する。\nそうすると,本願商標と引用商標とは,外観において,「D」の図案化の有無や, 片仮名部分の付加の有無などが相違するが,その図案化の程度や片仮名部分が欧文 字部分の読みを表したものにすぎないこと等を勘案すると,両商標を場所と時間を\n異にして離隔的に観察した場合,両商標の称呼及び観念が同一であり,外観におい ても欧文字「DOGGY」と理解される構成を有する点が共通することから,商品\nの出所を誤認混同するおそれがあるものと認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.09.28
平成29(ワ)43698 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年9月12日 東京地方裁判所
不競法2条1項2号の「類似」に該当するか否かは,取引の実情の下において, 需要者又は取引者が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両 者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべきである。 イ これを本件についてみるに,原告表示と被告標章とは,外観において,いずれ\nも,円形に収まるように描かれた鶴ないし鳥類の頭部,首元及び翼から成り,正面か らみて左を向いた鶴ないし鳥類の頭部及び首元を囲むような態様で,下部から頂点に 向かって円形の外周に沿うように翼が描かれた全体として円形の赤色の図形であり, 鶴ないし鳥類の頭部,首及び翼の形状や赤色の色彩が共通する。他方,被告標章の図 形には鶴ないし鳥類の頭部に目とみられる白抜きされた小さい円形様の部分が存在 するのに対して,原告表示にはそれが存在しない点,原告表\示と被告標章の円形の内 側下部には,円形の直径と比較して縦が5分の1ないし7分の1程度,横が2分の1 程度の大きさで白色の文字が記されているところ,原告表示には「JAL」との文字\nが,被告標章には「南急」との文字が記載されている点で相違する。また,原告表示\nのうち「JAL」との文字は,「ジャル」との称呼を有するのに対し,被告標章のうち 「南急」との文字は「ナンキュウ」との称呼を有し,これらの称呼は相違する。さら に,原告表示と被告標章は,全体として鶴ないし鳥類の観念を生ずる点が共通する。\n以上の共通点及び相違点を総合すると,相違点である白抜きされた部分や文字部分 は,図形全体に占める割合がそれほど大きなものではなく,地の色と同じ色彩である 白色が用いられていること,文字部分は図形全体の下方に一般的なフォントで示され ているにすぎないことからすれば,原告表示及び被告標章の図形全体及び各構\成部分 の形状や色彩の共通点は,上記相違点よりも需要者に強い印象を与えるものであると 評価することができる。したがって,原告表示と被告標章については,称呼が相違す\nるものではあるが,需要者が外観及び観念に基づく印象として,両者を全体的に類似 のものと受け取るおそれがあると認められる。
ウ これに対し,被告は,全体を観察すれば,原告表示と被告標章は役務の出所に\nつき誤認混同を生ずるおそれはなく,類似するとはいえない旨を主張するが,不競法 2条1項1号の不正競争においては,混同が発生する可能性があるのか否かが重視さ\nれるべきであるのに対し,同項2号の不正競争にあっては,著名な商品等表示とそれ\nを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し,稀釈化を引き起こすような程度 に類似しているような表示か否か,すなわち,容易に著名な商品等表\示を想起させる ほど類似しているような表示か否かを検討すべきものであるから,被告指摘の事情は\n類似性の判断に影響を与えるものではなく,失当である。
関連カテゴリー
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.09.28
平成30(ム)10003 特許権侵害行為差止等請求再審事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月18日 知的財産高等裁判所
(ム)の事件番号は初めてみました。
1 特許法104条の4は,特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条3号 所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの(以下, 「3号訂正審決」という。)が確定したときは,上記訴訟の当事者であった者は終局 判決に対する再審の訴えにおいて3号訂正審決が確定したことを主張することがで きないと規定している。その趣旨は,特許権侵害訴訟の当事者は,同法104条の 3により,無効の抗弁及びいわゆる訂正の再抗弁(訂正により無効の抗弁に係る無 効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張することができ,判決の基礎 となる特許の有効性及びその範囲につき,主張立証する機会と権能を有しているこ\nとから,そうであるにもかかわらず,上記訴訟の判決が確定した後に,特許の有効 性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として確定判 決を覆すことができるとすることは,紛争の蒸し返しであり,特許権侵害訴訟の紛 争解決機能や法的安定性の観点から適切ではないことにあると解される。そして,\n特許法施行令8条2号は,特許権侵害訴訟の終局判決が特許権者の敗訴判決である 場合には,「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無 効審判により無効にされないようにするためのものである審決」が3号訂正審決に 当たると規定している。前記第2の2(3)のとおり,再審被告両名は,基本事件にお いて無効の抗弁を主張していないから,本件訂正認容審決は,特許法施行令8条2 号所定の「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無 効審判により無効にされないようにするためのものである審決」ではなく,3号訂 正審決には当たらない。
2 しかし,特許法は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面を訂正 するために訂正審判を請求することを認める一方(同法126条1項本文),その訂 正は,特許請求の範囲の減縮を含む所定の事項を目的とするものに限って許される ものとし(同項ただし書),さらに,「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す るものであってはならない」としている(同条6項)。これは,訂正を認める旨の審 決が確定したときは,訂正の効果は特許出願の時点まで遡って生じ(同法128条), しかも,訂正された明細書,特許請求の範囲又は図面に基づく特許権の効力は不特 定多数の一般第三者に及ぶものであることに鑑み,特許請求の範囲の記載に対する 一般第三者の信頼を保護することを目的とするものであり,特に,同法126条6 項の規定は,訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範 囲に含まれることとなると,第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるた め,そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解される。このよ うに,特許法は,訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は,訂正後 の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているのであるから,被疑侵害品 が特許発明の技術的範囲に属しないことを理由とする請求棄却判決が確定した後に, 特許権者が訂正認容審決を得て,再審の訴えにおいて被疑侵害品が訂正後の特許発 明の技術的範囲に属する旨主張することは,特許法がおよそ予定していないものと\nいうべきである。そして,再審原告は,基本事件において,前訴判決の基礎となる 本件特許に係る発明(本件発明及び本件訂正発明)の技術的範囲につき,主張立証 する機会と権能を有していたのであるから,前訴判決が確定した後に,本件訂正認\n容審決が確定したという,特許法がおよそ予定していない理由によって,前訴判決\nを覆すことができるとすることは,紛争の蒸し返しであり,特許権侵害訴訟の紛争 解決機能や法的安定性の観点から適切ではなく,特許法104条の4の規定の趣旨\nにかなわないということができる。なお,再審原告は,前記第2の2(3)のとおり, 基本事件の係属中に第一次訂正を行っていたのであり,基本事件の係属中に本件訂 正認容審決を得ることができなかったというべき事情も認められない。 これらの事情を考慮すると,再審原告が本件訂正認容審決が確定したことを再審 事由として主張することは,特許法104条の4並びに同法126条1項ただし書 及び同条6項の各規定の趣旨に照らし許されないものというべきである。 3 前記2によると,再審原告は,本件訂正認容審決が確定したことを主張する ことができないから,前訴判決の基礎となった行政処分である本件特許権に係る特 許査定が後の行政処分である本件訂正認容審決により変更されたことを理由として 民訴法338条1項8号の再審事由がある旨の主張は,その前提を欠くものであり, 理由がない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2018.09.28
平成29(ワ)10742 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月19日 東京地方裁判所
構成要件Eのうち,「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義につい\nて検討する。 上記各文言は,調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり,\n文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから,本件明細 書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで,1⑴にお いてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると,本件明細書等(【0003】, 20 【0005】,【0021】,【0028】,【0029】,【0030】,【0 032】)には,リング状枠はトッププレート上に印刷表示され,調理容器を有効\nに加熱できる領域として使用者に示されるものであること(【0003】),リン グ状枠は加熱部の領域を示し,鍋の最大径と同径で,鍋の外殻を表すものであるこ\nと(【0005】,【0021】)及び加熱部は最大の鍋径と同径で,リング状枠 であること(【0028】,【0029】)が示され,これ以外に,上記各文言の 意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると,「最 大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し,\nまた,リング状枠と同径のものであり,また,「調理容器の外殻」と一致するもの であると解するのが一般的かつ自然である。 この点,被告は,構成要件Eの内容は不特定であるなどと主張するが,同主張は,\n前記認定に照らし採用することができない。
(2) 被告製品関連製品の構成\nア 原告は,別紙3被告製品説明書(原告)において,被告各製品は,「左IH ヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である 直径26cmの領域を示す外殻線11,12」という構成を有し,これが「調理容\n器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして,被告各製品を 除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。\nイ しかしながら,前記⑴において認定したとおり,「調理容器の外殻」及び「最 大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域\nの領域を示すリング状枠と同径のものであるところ,原告の主張する外殻線11, 12は,原告において付しているものにすぎず,トッププレート上に表示されてい\nるものではないから,これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であ るとみることはできない。そして,本件全証拠によっても,被告各製品には,加熱 部及び有効加熱領域を示す直径26cmのリング状枠が表示されているとは認めら\nれず,加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」 及び「最大径の調理容器」が直径26cmであると認めることもできない。 原告は,「調理容器の外殻」は,鍋底の最大径であり,被告は被告各製品におい て鍋底が直径26cmまでの鍋を使用することができる旨説明しているから,被告 各製品の「最大径の調理容器」は26cmのものであると主張する。しかしながら, 被告において上記のように説明することが,被告各製品で使用可能な最大径の鍋底\nを示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても,前記⑴において認定し たとおり,「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠 及び有効加熱領域は,トッププレートに表示される必要があるのであって,表\示さ れていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。
(3) 小括
以上のとおり,被告各製品は,原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最 大径である直径26cmの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められな\nいから,この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Eを充足するという原告の主張\nは採用できず,ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また,被告各製品を除く 被告製品関連製品が構成要件Eを充足することを認めるに足りる証拠もない。\nしたがって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品関連製品は,構\n成要件Eを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな い。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2018.09.28
平成29(ワ)22417 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年8月29日 東京地方裁判所
(2)本件各発明の意義
上記(1)の本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の特許請求の範囲請 求項1及び3の記載によれば,本件各発明は,より広範で深い人間関係を結ぶための, 人脈関係登録システム,人脈関係登録方法とサーバ,人脈関係登録プログラムと当該 プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体に関するものであり,より広\n範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートするために,上記人脈関係登録シス テム等を提供することを目的とするものであって,登録者相互間の合意によって人間 関係が結ばれたとき,記録手段を備えたサーバに,人間関係を結んだ登録者の個人情 報又は識別情報を関連付けて記憶することで,個人情報又は識別情報を含む検索キー ワードによって第二の登録者と人間関係を結んでいる第三の登録者の個人情報又は 識別情報を検索することができるようにするという発明である,と認められる。
2 被告サーバの構成について\n証拠(甲16,乙4,7)及び弁論の全趣旨によれば,被告サーバにおいて,人間 関係を記憶する手順は,次のとおりであり,これを図示すると,別紙「被告サーバの 動作フロー」のとおりである(同別紙では,アカウント1号を甲,アカウント2号を 乙と表記している。)と認められる。すなわち,他のユーザと人間関係を結ぶ申\請をす ることを意味する「友達申請」(以下,単に「友達申\請」という。)をするユーザを「アカウント1号」,友達申請をされるユーザを「アカウント2号」として説明すると,1) アカウント1号が「友達申請をする」と示されたボタンをクリックする(画面08),\n2)被告サーバがアカウント1号に確認画面を送信する,3)アカウント1号が「送信す る」と示されたボタンをクリックする(画面09),4)被告サーバが記憶手段に友達申\n請に係るデータを登録する,5)被告サーバが記憶手段にアカウント1号及びアカウン ト2号の人間関係が結ばれた旨の友達リストの仮登録をする,6)被告サーバがアカウ ント2号に友達申請がされたことを通知する(画面12),7)被告サーバがアカウン ト1号に友達申請の完了画面を送信する(画面11),8)アカウント2号が被告サー バにアカウント1号のプロフィールを要求する(画面13,14),9)被告サーバが記 憶手段からアカウント1号のプロフィールを取得する,10)被告サーバがアカウント2 号にアカウント1号のプロフィールを送信する,11)アカウント2号が「友達になる」 と示されたボタンをクリックする(画面15),12)被告サーバが記憶手段の友達リス トを更新して本登録をし,友達として関連付けることが完了する,13)被告サーバがア カウント1号に友達申請が承認されたことを示すメール(甲16)を送信する,とい\nうものである。 そうすると,被告サービスにおいては,被告サーバの記憶手段にアカウント1号と アカウント2号の人間関係が結ばれたとして関連付けられた後に,アカウント1号に 対して友達申請が承認されたことを示すメールが送信されるという処理がされるの\nであり,アカウント1号とアカウント2号が友達として記憶された後に,仮にアカウ ント1号に対し友達申請が承認された旨が通知されなかったとしても,被告サーバに\nおいては,アカウント1号とアカウント2号が友達であると記憶されているといえる。
3 争点1(被告サーバは,文言上,本件各発明の技術的範囲に属するか)について 事案に鑑み,まず,争点1−3(被告サーバは構成要件1D及び2Dを充足するか)\nについて判断する。
(1) 構成要件1Dは,「上記第二のメッセージを送信したとき,上記第一の登録者\nの個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段 と,」というものであり,本件発明1においては,サーバが,第二の登録者と人間関係 を結ぶことを希望する旨の第一の登録者からのメッセージである「第一のメッセージ」 を受信して同メッセージを第二の登録者の端末に送信し,第二の登録者からこれに合 意する旨のメッセージである「第二のメッセージ」を受信して,同メッセージを第一 の登録者に送信したことを条件として,又は送信した後で,第一の登録者の個人情報 と第二の登録者の個人情報とを関連付けて記憶手段に記憶するものとして規定して いるということができる。 そして,構成要件1Dの「個人情報」が「識別情報」に置き換えられているほかは,\n構成要件1Dと文言を共通にする構\成要件2Dについても,サーバが第二のメッセー ジを送信したことを条件として,又は送信した後で,第一の登録者の識別情報と第二 の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶するものとして規定していると 認められる。
(2) この点,原告は,構成要件1D及び2Dにおける「送信したとき」の「とき」\nは「ある幅をもって考えられた時間」という意味であるとして,構成要件1D又は2\nDは,第一の登録者の個人情報又は識別情報を第二の登録者の個人情報又は識別情報 とが関連付けられた後に第二のメッセージが送信される場合をも含む旨を主張する が,「送信したとき」とは,送信したことを条件とする旨表す表\現であると解釈するの が一般的かつ自然な解釈であるというべきであり,また,これが時を表す表\現である と解釈したとしても,送信という動作が完了していることを表す表\現が用いられてい ることからすると,送信することが関連付けることに先行すると解釈するのが一般的 かつ自然であって,本件明細書その他にも異なる解釈を導く説明は見当たらない。 したがって,構成要件1D及び2Dの記載は,送信の実行が先行し,その後に関連\n付ける旨の実行がされることを規定していると解され,原告の上記主張を採用するこ とはできない。
(3)そこで,被告サービスについてみると,前記2において認定したとおり,被告 サービスにおいては,被告サーバの記憶手段に第一の登録者に相当するアカウント1 号と第二の登録者に相当するアカウント2号が友達として登録されて関連付けるこ とが終了した後に,アカウント1号に対して友達申請が承認されたことを示すメール\nが送信されるという処理がされるのであるから,被告サーバは,「第二のメッセージ を送信したとき」に,「上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを 関連付けて上記記憶手段に記憶する手段」又は「上記第一の登録者の識別情報と第二 の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段」を有しているとい うことはできない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告サー バは,構成要件1D及び2Dを充足しない。\nよって,被告サーバは,文言上,本件各発明の技術的範囲に属すると認めることは できない。
・・・・
これを本件についてみると,前記1(2)で説示したとおり,本件各発明は,より 広範で深い人間関係を結ぶための,人脈関係登録システム,人脈関係登録方法とサー バ,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記\n録媒体に関するものであり,より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポート するために,上記人脈関係登録システム等を提供することを目的とするものであって, 登録者相互間の合意によって人間関係が結ばれたとき,記録手段を備えたサーバに, 人間関係を結んだ登録者の個人情報又は識別情報を関連付けて記憶することで,個人 情報又は識別情報を含む検索キーワードによって第二の登録者と人間関係を結んで いる第三の登録者の個人情報又は識別情報を検索することができるようにするとい う発明である。そして,登録者相互間の合意は,メールの交換によって行われるもの されている(段落【0011】,【0015】)。そうすると,本件各発明の構成要件1D及び2Dの「第二のメッセージを送信したとき,…関連付けて上記記憶手段に記憶\nする」という構成は,登録者相互間の合意(メッセージの交換)によって人間関係が\n結ばれたとき,記録手段を備えたサーバに,人間関係を結んだ登録者の個人情報又は 識別情報を関連付けて記憶するという課題解決手段を具体的な構成として特定した\nものであって,この構成が従来技術に見られない特有の技術的思想を構\成する特徴的 部分であり,本件各発明における本質的部分というべきである。 これに対し,原告は,より広範で深い人間関係を結ぶために共通の人間関係を結ん でいる登録者の検索を容易にするということが本件各発明の本質であり,本件各発明 における友達申請メッセージ(第一のメッセージ)や承認メッセージ(第二のメッセ\nージ)のやり取りに係る構成は,人間関係を結ぶための「合意の手段」としての意味\nを有するにすぎず,本件各発明において非本質的な部分である旨主張する。 しかしながら,本件各発明の構成要件1D及び2Dの「第二のメッセージを送信し\nたとき,…関連付けて上記記憶手段に記憶する」という構成が,本件各発明の課題解\n決手段を具体的な構成として特定したものであることは前記のとおりであるから,個\n人情報又は識別情報を関連付けて記憶する過程のみを切り離して,それらの処理のタ イミングを規定したものにすぎないということはできず,本件各発明の非本質的部分 であるということはできない。また,本件各発明は,個人情報又は識別情報を含む検 索キーワードによって第二の登録者と人間関係を結んでいる第三の登録者の個人情 報又は識別情報を検索することを内容とするものである(構成要件1Eないし1G,\n2E)が,それを超えて,共通の人間関係を結んでいる登録者の検索を容易にすると いうことが,本件各発明の課題又は目的とされて本件各発明の構成として具体的に反\n映されているとはいえず,原告の主張を裏付けるに足る本件明細書の記載その他の証 拠はない。 したがって,原告の主張は採用することができない。
ウ そうすると,本件各発明の構成要件1D及び2Dの「第二のメッセージを送信\nしたとき,…関連付けて上記記憶手段に記憶する」という構成は,本件各発明におけ\nる本質的部分であると解されるところ,前記説示のとおり,被告サーバは,メッセー ジを交換する前に,登録者相互間の関連付けが終了するのであって,上記構成を有し\nていないから,その相違部分が本件各発明の本質的部分ではないとはいえず,均等の 第1要件(非本質的部分)を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.09.27
平成29(行ケ)10193 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月25日 知的財産高等裁判所
本件審決は,本件発明1における相違点1のうち,構成要件1I) の「ジル コニア充填部に設けた電極と開口用貫通穴との隙間から,ジルコニア充填部 の表面を露出させること」に関し,引用発明2の1に甲3技術1を適用して\n接着剤表面アルミナ層とするに当たり,1) 甲3の記載から,接着剤表面アルミナ層が,第1電極や第2電極の表\面の周縁部と重複してしまうと,第1電極又は第2電極の他の部分,及び,接着剤表面アルミナ層の他の部分と比較して厚くなってしまうことから,\nアルミナからなる接着剤の層を導体層の平坦部と略面一にすることによって,各未焼成シート又は各未焼成スペーサに亀裂が発生することを防止するという目的が果たせなくなることは当業者にとって明らかであるから,アルミナからなる接着剤の層と導体層が略面一であることが必須であるのに対して,アルミナからなる接着剤の層と導体層の側面とが隙間を空けることなく接することは必須ではないことは,当業者にとって明らかである, 2) 第1電極又は第2電極の表面の周縁部に,接着剤表\面アルミナ層を隙間なく接触させるように設計又は製造を行うと,避けることのできない製造誤差により,第1電極又は第2電極と接着剤表面アルミナ層が重複することがあり得るので,そのような事態を回避するために,第1電極及び第2電極と接着剤アルミナ層との間に隙間を設けることによって余裕を持たせ,第1電極及び第2電極と接着剤表\面アルミナ層との重複を回避することは,当業者が適宜なし得ることである, 3) そして,その隙間をどの程度にするかは,製造誤差の程度等を勘案して 当業者が適宜設定し得るものであって,固体電解質体の表面が露出する程\n度の隙間とすることも適宜設定し得る範囲内のものである, と判断した。
(5) そこで検討するに,本件審決が認定したとおり,甲3には,甲3技術1が 記載されており,本件特許に係る出願当時,積層タイプのガスセンサ素子に おいて,これを構成する各未焼成シートをアルミナからなる接着剤を介して\n積層することは,当業者にとって周知の技術であったと認められる。しかし, 甲3には,1)接着剤が導体層の周縁部に重複すると,亀裂の発生を防止する ことができないから,導体層と接着剤とが隙間なく接することは必須ではな いことや,2)避けることのできない製造誤差により,接着剤が導体層の周縁 部に重複すること,また,3)製造誤差の程度を勘案して,固体電解質体の表\n面が露出する程度の隙間を設定することは,記載も示唆もされていないし, 上記1)〜3)の事項が,当業者にとって当然の技術常識であると認めるに足り る証拠も見当たらない。 仮に,「製造誤差」を考慮して接着剤の量を調整することが,当業者の技 術常識であるとしても,甲3の段落【0049】及び【0050】の記載, 及び当該段落が引用する図6〜9に接した当業者は,接着剤の量は,導体層 に設けられた平坦部と略面一となるように,すなわち,当該平坦部との間に できるだけ隙間を生じないように調整するものと理解すると認めるのが相当 である。 そうすると,引用発明2の1に甲3技術1を適用するに当たり,当業者が 「電極と接着剤との間に隙間を設ける」構成を採用する動機付けがあると認\nめることはできず,構成要件1I)に係る「上記ジルコニア充填部に設けた上記 電極と上記開口用貫通穴との隙間から,上記ジルコニア充填部の表面を露出\nさせる」構成を,当業者が容易に想到できたということはできない。
(6) 原告の主張について
この点に関連して,原告は,甲3に導体層等の周りを接着剤で埋めること についての記載はないから,導体層と接着剤とを隙間なく密着させることま でが必要とされているのではないと主張する。 甲3に,導体層等の周りを接着剤で埋めるとの文言が明記されていないの は原告が主張するとおりであるが,甲3に,上記(5)の1)〜3)の事項が記載も 示唆もされていないことは,上記(5)において説示したとおりである。 そして,甲3の段落【0049】には,接着剤を導体層における平坦部と 略面一になるように塗布したと記載されている上に,当該段落が引用する図 6及び7,並びに段落【0050】が引用する図8及び9には,当該接着剤 が導体層に隙間なく接するように塗られている図が描かれていることからす ると,これらの記載に接した当業者は,接着剤を当該平坦部との間にできる だけ隙間を生じないように塗布するものと理解するのが自然というべきであ る。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2018.09.27
平成29(ネ)10064 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記のとおり(引用に係る原判決「事実及び理由」第4の1(1)イ(原判決 65頁6行目〜21行目)),本件訂正発明1の1及び1の2の従来技術には,基 礎杭等の造成にあたって地盤を掘削する掘削装置として一般に使用されるアースオ ーガ装置では,オーガマシンの駆動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必 要となるが,リーダの長さが長くなると,傾斜地での地盤掘削にあっては,クロー ラクレーンの接地面とリーダの接地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長く とれず,掘削深さが制限されるという課題等があった。そこで,本件訂正発明1の 1及び1の2は,これらの課題を解決するために,掘削装置について,掘削すべき 地盤上の所定箇所に水平に設置し,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させる が,当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケーシ ング回り止め部材を備えるものとして,リーダではなく,ケーシング回り止め部材 によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明と認められる。 ここで,回転駆動装置の回転反力を受支するには,1)回転駆動装置の回転反力が 固定ケーシングによって受支されるとともに,2)固定ケーシングの回転反力がケー シング回り止め部材によって受支されなくてはならない。そうすると,1)を具体的 に実現する「固定ケーシングが,掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の 機枠に一体的に垂下連結される」構成及び2)を具体的に実現する「ケーシング回り 止め部材が,掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の 横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,固定ケーシングを上下方 向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシン グ挿通孔を有する」構成により,ケーシング回り止め部材によってケーシング,ひ\nいては回転駆動装置の回転反力を受支するようにしたことが,従来技術には見られ ない特有の技術的思想を有する本件訂正発明1の1の特徴的部分であり,その本質 的部分というべきである。
(ウ) したがって,固定ケーシングが回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結さ れる構成を有しない被告装置1−3〜1−8は,本件訂正発明1の1と本質的部分\nを異にするものであり,第1要件を満たさない。
・・・
このことから,本件訂正発明1の1の「固定ケーシング5」は,「固定ケーシン グ5が円筒状ケーシングからなるため,地盤への固定ケーシング5の打ち込み及び 引き抜きが容易となり」【0028】とも記載されているように,回転駆動装置1 の下部から垂下され,ケーシング回り止め部材7のケーシング挿通口8に挿入され, 掘削軸部材2及びダウンザホールハンマー4と共に地盤の掘削により地盤に打ち込 まれ,地盤を所定深度まで掘削したら,ダウンザホールハンマー4の作動を停止さ せた後,昇降操作用ワイヤーWを巻取り操作して,掘削軸部材2及びダウンザホー ルハンマー4と共に引き上げられることを前提としたものである。 そうすると,本件訂正発明1の1の掘削装置においては,掘削後に引き抜くこと を前提にケーシングと回転駆動装置の機枠とを一体的に連結することによって,回 転駆動装置とケーシングを掘削後に引き抜く際に,地盤内でケーシングにかかる土 圧による抵抗に抗してこれを引き抜くことが可能になるものということができる。\nこれに対し,ケーシングと回転駆動装置との機枠とを一体的に連結するのでなく 着脱自在の構成にした場合,そもそも着脱自在の構\成はケーシングを掘削後に残置 させることができるという作用,効果を奏するものであるし,仮にこの構成でケー\nシングを引き上げるとすると,ケーシングと回転駆動装置の機枠との連結部の強度 が十分でないために,引き抜くことが不可能\ないし極めて困難となり,本件訂正発 明1の1の目的を達成することができない。 したがって,掘削後にケーシングを引き抜くことを前提とした本件訂正発明1の 1の掘削装置において,回転駆動装置にケーシングを着脱自在に連結する構成を採\n用すると,本件訂正発明1の1の目的を達成することが困難となり,同一の作用効 果を奏しなくなる。 そして,被告装置1−3〜1−8の構成につき,いずれも回転駆動装置の下部に\n連結された中空スリーブに設けられたスリット状の切り欠きとケーシング外周軸方 向に固設された角鉄とを係合させることにより,中空スリーブとケーシングとを着 脱自在に係合するものであるとする限りでは,当事者間に争いがない。 (イ) 以上によれば,被告装置1−3〜1−8は,第2要件を満たさない。
◆判決本文
1審判決はこちら。
◆平成25(ワ)10958
関連の無効審決の取消訴訟はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 賠償額認定
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.09.26
平成29(行ケ)10045 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月18日 知的財産高等裁判所
ア 実施可能要件適合性について
(ア) 原告は,「当業者が,エピトープについて具体的に特定する記載がな い本件明細書の記載に基づいて,エピトープを決定してLRP6結合分 子を得るためには,過剰な実験を行う必要がある。」との本件異議申立\n書記載の主張に対し,本件明細書には,LRP6に関連するエピトープ が示されており,当業者であれば,本件特許の優先日当時に利用可能な\n技術を用いることにより,インビトロで,エピトープを含む特定のペプ チド(すなわち,プロペラ1領域又はプロペラ3領域のアミノ酸配列) に結合する本件発明の候補となるLRP6抗体を十分な数で特定するこ\nとができ,また,本件明細書の記載及び本件特許の優先日当時の周知技 術を用いることにより,製造された結合分子の結合性及び活性を調べ, その有用性を確認することができたと主張する。 (イ) 検討 a 物の発明について,明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要\n件に適合するというためには,当業者が,明細書及び図面の記載並び に出願時の技術常識に基づいて,その物を生産でき,かつ,使用する ことができるように具体的に記載されていることが必要であると解す るのが相当である。
b 本件明細書の記載について
上記1(2)において認定したとおり,本件明細書には,本件発明に係 るLRP6結合分子のLRP6上の結合部分や結合によるWntリガ ンドの結合阻害についての説明(【0015】,【0033】等)と ともに,実施例1には,優先的にWnt1又はWnt3a誘導Wnt シグナル伝達を阻害する抗LRP6アンタゴニストFabs(実験時 のプライベートネームであるFab003,Fab004,Fab0 15など7つのFabで記載)が同定された旨が記載されている(【0 226】〜【0228】)。 しかし,本件明細書には,上記各Fabがいかなる抗原結合部分を 含んでいるのか,すなわち,抗原結合部分やそれが認識するエピトー プがいかなるアミノ酸配列等によって特定されるのかについて,これ を具体的に示す記載はなく,その手掛かりとなる記載も見当たらない。 また,実験結果が記載されていたと推測される図は,全て欠落してい る。
c 本件発明1〜22,31〜33は特定のアミノ酸配列の抗原結合部 分を含むLRP6結合分子,すなわち化学物質の発明である。そして, 上記bにおいて説示したとおり,本件明細書の記載から,実施例で得 られた各Fabのアミノ酸配列等の化学構造や認識するエピトープを\n把握することはできない。また,本件明細書には,Wnt1特異的等 の機能的な限定に対応する具体的な化学構\造等に関する技術情報も記 載されていない。そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明におけ る他の記載及び本件特許の出願時の技術常識を考慮しても,特許請求 の範囲に規定されている300程度のアミノ酸の配列に基づき,Wn t1に特異的である等の機能を有するLRP6結合分子を得るために\nは,当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤をする必要があると認 めるのが相当である。 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者が,本件明 細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて,本件発明に 係る物を生産でき,かつ,使用することができるように具体的に記載 されているとはいえない。
(ウ) 原告の主張について
a 原告は,特定のエピトープに対応する抗原結合部分を有する抗体は, 汎用のファージディスプレイ法により取得することができるから,本 件発明に係る結合分子を得るために,当業者が期待し得る程度を超え る試行錯誤は要しないし,本件明細書記載の機能アッセイにより得ら\nれた抗体の機能(Wnt特異性)についても,当業者は容易に確認す\nることができると主張する。 確かに,原告が主張する技術は,いずれも本件発明が属する技術分 野における一般的な技術である,抗体類の製造方法やリガンド・受容 体の結合アッセイ法であって,例えば,抗原又はエピトープが特定さ れている場合に,ファージディスプレイ法等の周知の技術を適用する ことによって,それに対応する抗体が得られることは技術常識である といえる(この点,当事者間に争いはない)。しかし,本件発明に係 る「モノクローナル抗体の抗原結合部分がWnt1特異的であり,優 先的にWnt1誘導シグナル伝達経路を阻害するが,Wnt3a誘導 シグナル伝達経路を阻害しない」「LRP6結合分子」を生産するた めには,まず,本件発明に係るLRP6の第1又は第3プロペラに相 当するそれぞれ300程度のアミノ酸の配列から,本件発明に係る特 異性を満たすエピトープになり得ると予想される特定の塩基配列を選\n定した上で,ファージディスプレイ法などの周知の手法によってそれ らに対応する化学構造(アミノ酸配列)を有するペプチド(すなわち\nFab)を取得し,得られた多数のFabの中から,「Wnt1特異 的であり,優先的にWnt1誘導シグナル伝達経路を阻害するが,W nt3a誘導シグナル伝達経路を阻害しない」との機能を有するFa\nbを特定することが必要である。 これに対し,本件明細書には,本件発明に係る特異性を満たすエピ トープとなり得ると予想される特定の塩基配列の具体的な選定方法に\nついて何ら記載がないから,本件明細書に基づいて本件発明のLRP 6結合分子を得ようとする当業者は,結局,発明者が本件発明を発明 した際に行ったのと同程度の試行錯誤をしなければならないところ, これは当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を強いるものという べきである。
すなわち,エピトープを特定すれば,それに対応する抗体は周知の 手法により得ることができるとはいえるものの,本件明細書には,そ のエピトープについて,具体的なアミノ酸配列等のその構造に関する\n技術的特徴が実施例として開示されておらず,また,本件明細書にお ける他の記載及び出願時の技術常識に基づいても,エピトープ又はそ れに対応する抗体結合部分の具体的構造等を特定することができない\n以上,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて本 件発明に係る結合分子を容易に生産することができるとはいえない。
・・・
特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請 求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範 囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明 の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも 当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解する のが相当である。
b これを本件についてみると,本件発明1の技術的特徴は,原告が主 張するとおり,特定のWntとLRP6におけるその特定の結合部位 との関係(例えば,Wnt1の結合部位はプロペラ1の領域であるこ と等)を有し,具体的な抗原結合部分(Fab)を備える「Wnt1 アンタゴニスト抗体」及び「Wnt3aアンタゴニスト抗体」にある と認められる。そして,特許請求の範囲に記載されているとおり,「抗 原結合部分が,配列番号:1のアミノ酸20−326;または…のい ずれかに含まれるか,またはいずれかと重複しているヒトLRP6(配 列番号:1)のエピトープに結合し」,「モノクローナル抗体の抗原 結合部分がWnt1特異的であり,優先的にWnt1誘導シグナル伝 達経路を阻害するが,Wnt3a誘導シグナル伝達経路を阻害しない」 等の主として機能によって特定される広範な化学物質の発明について\n特許を受けようとするものである。
一方,上記ア(イ)bにおいて説示したとおり,本件明細書には,具 体的な抗体の抗原結合断片Fabを得たことをうかがわせるプライベ ート番号(Fab003,Fab015など)が記載されているもの の,それらの具体的なFabの構造(アミノ酸配列)も,当該抗原結\n合断片が認識するエピトープ(LRP6中の数個のアミノ酸配列)も 記載されていない(なお,上記のとおり,実験結果が記載されていた と推測される図が全て欠落しているため,これらのFabが有する詳 細な機能・特性の検証自体が事実上不可能\である。)。そして,特許 請求の範囲には,「モノクローナル抗体の抗原結合部分がWnt1特 異的であり,優先的にWnt1誘導シグナル伝達経路を阻害するが, Wnt3a誘導シグナル伝達経路を阻害しない」という機能的な特徴\nを有することが記載されているものの,これらの機能と得られたFa\nbの構造上の特徴等を関連づける情報も何ら記載されていない。\n
そうすると,本件発明1について,特許請求の範囲に記載された発 明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記 載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるとも,また,当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の 課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。 このことは,本件発明2〜22,31〜33についても同様である。
・・・
そこで検討するに,特許異議の申立てについての決定には,決定の結論及\nび理由を記載しなければならない(特許法120条の6第1項4号)。 この点に関連して,特許法157条2項4号は,審決をする場合には審決 書に理由を記載しなければならないと定めている。この趣旨は,審判官の判 断の慎重,合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること, 当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与 えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあ るというべきであり,したがって,審決書に記載すべき理由としては,当該 発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は 技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示 す場合であるなど特段の事由がない限り,前示のような審判における最終的 な判断として,その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示 することを要するものと解するのが相当である(最高裁昭和59年3月13 日第三小法廷判決・集民141号339頁)ところ,このことは特許異議の 申立てに係る決定についても同様と解される。\n
(3) 本件についてみると,上記第2の5において認定したとおり,本件取消決 定に係る決定書そのものには,結論に至った具体的な判断過程も,その根拠 となるべき証拠による認定事実も何ら記載されていない。 しかし,当該決定書には,「平成28年5月13日付けで取消理由を通知 し」,「上記の取消理由は妥当なものと認められる」との記載がされており, 本件取消理由通知書には,取消理由の要旨と,詳細については本件異議申立\n書を参照のこととの記載がされ,本件異議申立書には,本件特許が取り消さ\nれるべきであることについての理由が,証拠を具体的に摘示して,詳細に記 載されているのであるから,本件異議申立書,本件取消理由通知書及び本件\n取消決定に係る決定書の全体をみれば,当該決定書の記載が,審決の公正を 保障し,当事者が決定に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに 便宜を与え,決定の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にするという趣 旨に反するものとはいえない。また,本件異議申立手続において,被告が本\n件取消理由通知をしたのに対し,原告が応答をしなかったという経緯も踏ま えれば,本件取消決定に係る決定書そのものに,結論に至った具体的な判断 過程や,その根拠となるべき証拠による認定事実が何ら記載されていないと しても,上記の結論に変わりはないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2018.09.26
平成29(ワ)40193 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月6日 東京地方裁判所
プレートがゲーム空間内の所定の範囲に適用されることがあることが記載さ れ,また,前記(2)イのとおり,本件明細書には,発明を実施するための形態と して,プレイヤがテンプレートの作成を指示したとき,「範囲選択画面」が表\n示され,そこにおいては,ゲーム空間の一部について,テンプレートが作成さ れる範囲が表示されていること,テンプレートが作成される範囲について,例\nとして,プレイヤが任意の2点をタップして,当該2点を対頂点とすることで 定められることがあること,ゲーム空間の一部に対して,そのテンプレートが 適用されることが記載されている。他方,本件明細書には,「ゲーム空間」の 選択に関して,上記内容とは異なる内容の記載はない。 さらに, 原告は,本件意見書において,補正により加えられた「プレイヤによって選択されたゲーム空間の全体」との記載について,プレイヤがゲーム空間のうちのテンプレートが作成される範囲を指定するという段落【0037】の記載を挙げた上で,プレイヤがゲーム空間の左上の点および右下の点をタップすることで,ゲーム空間の全部の範囲を選択することができることを意味する旨述べて,その記載が当初明細書から自明であると述べている。
以上によれば,本件明細書には,本件各発明のテンプレートはゲーム空間内 の所定の範囲について作成,適用されるもので,その範囲についてプレイヤが 定めることが記載されており,原告もそのことを前提として,プレイヤがゲー ム空間内の全部の範囲をテンプレートの範囲とすると定めることによりゲー ム空間の全体が選択されることになるという意見を述べたといえる。 上記の本件明細書及び本件意見書の記載を参酌すれば,構成要件1C及び2\nDの「プレイヤによって選択されたゲーム空間の全体」における「選択」とは, テンプレートの作成について,プレイヤがテンプレートとするゲーム空間内の 一定の範囲を選択することを前提として,テンプレートを作成する際に,プレ イヤがゲーム空間内の全部の範囲を選択することを意味するものと解釈する のが相当である。
これに対し,原告は,構成要件1C及び2Dにおける「ゲーム空間の全体」\nとは文字通りゲーム空間全体を意味するのであってゲーム空間のうちどの部 分を選択するかの決定権をプレイヤが有していることを必須の構成要素とは\nするものではないと主張し,また,本件明細書の第1及び第2実施形態は,テ ンプレートの作成,適用の具体例を示したにすぎないなどと主張する。 しかし,「ゲーム空間の全体」がプレイヤによって選択されるとしても,プレ イヤによってどのような態様による選択がされるかについては,特許請求の範 囲の記載からは明らかではない。本件明細書には,テンプレートの作成に当た って,プレイヤがゲーム空間内の一定の範囲を選択することは記載されている が,それ以外の選択に関する構成については何ら記載も示唆もないから,前記\nと異なる態様でのプレイヤによる選択について,本件明細書に記載や示唆が あるとはいえないし,原出願日の当業者の技術常識に照らして明らかであると もいえない。また,原告は,本件特許の出願経過(甲22)において,プレイ ヤがタップする任意の2点をゲーム空間の左上及び右下の点とすれば「ゲーム 空間の全体」になるなどと説明しており,この説明はプレイヤにおいてゲーム 空間内の一定の範囲を選択することを前提としているものといえ,前記 の解 釈に沿うものといえる。原告の主張は採用することができない。
上記(1)で認定のとおり,本件ゲームは,プレイヤが基本画面においてレイア ウトエディタのアイコンをタップしてレイアウトエディタ画面を表示させ,レ\nイアウトに対応する縮小画面を選択,保存することによって新たなレイアウト を作成するというものである。そうすると,そこにはプレイヤがゲーム空間内 の一定の範囲を選択するという機能や動作は全く存在していない。したがって,本件プログラム及び本件携帯端末は,いずれも構\成要件1C及び2Dを充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.09.25
平成28(ワ)35026 損害賠償請求事件 平成30年8月30日 東京地方裁判所
不競法2条1項3号は,他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等を不正 競争行為とするところ,同号によって保護される「商品の形態」とは,「需要 者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商 品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質 感」(同条4項)をいい,商品の個々の構成要素を離れた商品全体の形態をい\nう。また,特段の資力や労力をかけることなく作り出すことができるありふ れた形態は,同号により保護される「商品の形態」に該当しないと解すべき である。
・・・
ア 原告各商品(14FW)と被告商品の形態を比較すると,別紙対比表の\nとおり,次の共通点があることが認められる(甲3,21,乙9)。 すなわち,基本的形態については,1)正面視において,全体が裾広がり 略Aライン形状であること(構成A),2)側面視において,全体が略Aライ ン形状であるが,前丈より後ろ丈の方が長いため,ブルゾンの裾が前身頃 から後ろ身頃に向かって下り傾斜していること(構成B),3)背面視におい て,全体が裾広がりの略Aライン形状であること(構成D)が,それぞれ\n共通している。
また,具体的形態については,1)前身頃において,比翼仕立てになって いることから,裾部から襟部までにかけて,中央部やや左側に,縦に一本 線が入っており,中央部やや右側に,これに略平行な薄い一本線が入って いること(構成E),2)フードにおいて,見頃部から取り外し可能なフード\nが襟部に沿って設けられ(構成F),当該フードの前部分略中央に,約11\ncm程度のファスナーが縦方向に付され(構成G),当該ファスナーを覆うよ\nうに縦長の比翼が設けられ,当該比翼の内側には,前記ファスナーの左わ き上下に設けられた2つのドットボタンに対応する2つのドットボタンが 付されており(構成H),ファスナー引手の開口部には,平面状の黒色の紐\nが通され,フード左右端部から下方へ垂れており,紐の先端には略細長円 筒状の金色の金具が付され(構成I),フードの前側端部分において,三角\n形状が連続するステッチが施されていること(構成J),3)ポケットにおい て,裾から少し上の部分より胴体部の中間あたりにかけて,縦長形状のポ ケットのフラップが形成されていること(構成K),4)後身頃において,両 肩の内側部分に肩部から裾部へ向かって縦方向にダーツが施されることに より,2本の縦線が生じており(構成L),裾は円弧を描き,円弧が最も膨\nらむ後裾の略中央部が略縦長三角形状に切欠かれ(構成M),当該切欠きの\n上に,横長長方形状のステッチが存在すること(構成N),5)袖部において, 端が三角形状のベルトが設けられ(構成O),当該ベルト三角形状部の裏側\nにはドットボタンが付され(構成P),袖部下方中央部の左側及び右側にも\nこれに対応するドットボタンが付されていること(構成Q)が,それぞれ\n共通している。
イ 原告各商品(14FW)と被告商品の形態を比較すると,次の2点にお いて,一応相違すると認められる。 まず,原告各商品(14FW)のフードには,フード端に弾力のあるワイ ヤーが縫い込まれているため,側面視において,同フードが身頃部分から 立ち上がって立体的な略正三角形状となるのに対し(構成C),被告商品の\nフードには,前記のワイヤーが使用されておらず,側面視において,同フ ードが身頃部分に折り重なる形状となる(構成C’,甲1,2,乙9)。\n また,原告各商品(14FW)の素材はポリエステル65%及びナイロ ン35%であるのに対し,被告商品の素材はポリエステル100%であり, それぞれの素材や加工方法に応じた質感を有する(甲1,争いのない事実)。
(3)1960年代にアメリカ軍によって開発,使用された防寒服であるM65パ ーカは,1)前身頃において比翼仕立てになっている点(構成E),2)身頃部か ら取り外し可能なフードが設けられている点(構\成F),3)縦長形状のポケッ トのフラップが形成されている点(構成K)において,原告各商品と共通し\nている(乙1)。 また,原告各商品が発売された平成26年より前から,M65パーカ等のア メリカ軍が使用した防寒服の形態をベースにデザインされた,ミリタリーパ ーカ,ミリタリージャケット,モッズコート等と呼ばれるファッションのカ テゴリーが存在して,複数の製品が存在し,原告各商品もこれに含まれる(甲 1,9,15)。
(4) 以上を踏まえ,原告各商品(14FW)と被告商品の形態が実質的に同一と いえるかどうかについて検討する。
ア 原告各商品(14FW)と被告商品とは,前記(2)アで述べたとおり,そ の基本的な形態から具体的な細部の形態に至るまで多数の共通点が認めら れ,その形状はほぼ同一であるといえる。 一方,原告各商品(14FW)と被告商品には,前記(2)イで述べた2つ の点において一応相違すると認められるが,これらは,フードの立体感や 生地の質感に若干の相違を与えることがあったとしても,その違いは大き いものではなく,需要者が通常の用法に従った使用に際してその違いを直 ちに認識することができるとまではいえないものであり,原告各商品(1 4FW)と被告商品の全体の印象を異なったものとするものとはいえない。 イ 前記(3)のとおり,原告各商品とM65パーカには複数の共通点があるが, M65パーカが,兵士が野外における活動の際に身につける防寒着である のに対し,原告各商品は,女性がファッションとして身につける上着とし てデザインされたもので,基本的形態が略Aラインで,全体として女性的 かつ都会的な印象を与えるものであって,M65パーカと異なる形態を有 するものといえる。
また,原告各商品が発売された平成26年以前において,ミリタリーパー カなどと呼ばれるファッションの一形態として複数の製品が販売されてお り,原告各商品もその範疇に入る商品であると認められる。しかし,原告各 商品は,基本的な形態が略Aラインであること(構成AないしD),身頃部\n分から取り外し可能なフードがあること(構\成F),フードの右左端部から 黒色の紐が下方へ垂れ下がり,紐の先端に細長円筒状の金色の金具が付さ れていること(構成I),フードの前側端部分に三角形状が連続するステッ\nチが施されていること(構成J),フード部分に本体と独立したファスナー\nが設けられていることにおいて特徴を有しているところ,ミリタリーパー カなどと呼ばれる製品において,これら原告各商品の特徴的な形態を全て 備え,商品全体の形態において原告各商品と酷似する商品が他に存在した ことを認めるに足りる証拠はない(甲2,乙13)。そうすると,原告各商 品の形態が,個々の形態の組み合わせとして個性を有しないということは できず,他の商品に見られるありふれたものということはできない。
ウ 以上によれば,原告各商品の形態はありふれたものではなく,「商品の形 態」(不競法2条1項3号)に該当するところ,原告各商品(14FW)と 被告商品は,基本的な形態から具体的な細部の形態に至るまで多数の共通 点が認められる一方,相違する点は需要者が通常の用法に従った使用に際 してこれらの違いを直ちに認識することができるとまではいえないもので あって,原告各商品(14FW)と被告商品の形態は実質的に同一であると 認められる。
2 争点(1)イ(被告商品の形態が原告各商品に依拠したものであるか)について 前記1のとおり,原告各商品のうち14FWと被告商品の形態は,実質的に同 一であるところ,同じミリタリーパーカに属するコートであっても,フード,襟 部,袖部といった相当数の個別の部分があり,全体的形態においても各個別的形 態においても,それぞれ相当数の選択肢が存在するのであるから,これらが偶然 に一致することは考えがたい。
また,前記前提事実(2)及び(3)のとおり,14FWが発売されたのは平成26 年8月から平成27年1月頃までであるのに対し,被告商品の発売は,それから 1年以上が経過した平成28年2月26日であり,被告商品の製造者において, 市場において14FWを入手するなどの何らかの方法によって,その形態を把 握することは十分に可能\であったといえる。 したがって,被告商品は,原告各商品のうち14FWの形態に依拠して製作さ れたものと認めるのが相当である。
2018.09.25
平成29(行ケ)10171 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月19日 知的財産高等裁判所
前記アの記載事項を総合すると,本件出願の優先日(平成7年3月25 日)当時,1)乾燥温度等の乾燥条件の調節により,水和水の数の異なる炭 酸ランタン水和物を得ることができること,2)水和物として存在する医薬 においては,水分子(水和水)の数の違いが,薬物の溶解度,溶解速度及 び生物学的利用率,製剤の化学的安定性及び物理的安定性に影響を及ぼし 得ることから,医薬の開発中に,検討中の化合物が水和物を形成するかど うかを調査し,水和物の存在が確認された場合には,無水物や同じ化合物 の水和水の数の異なる別の水和物と比較し,最適なものを調製することは, 技術常識又は周知であったものと認められる。
(4) 相違点1の容易想到性の有無について ア 甲1には,慢性腎不全患者におけるリンの排泄障害から生ずる高リン血 症の治療のための「リン酸イオンに対する効率的な固定化剤,特に生体に 適応して有効な固定化剤」の発明として,「希土類元素の炭酸塩あるいは 有機酸化合物からなることを特徴とするリン酸イオンの固定化剤」が開示 され,その実施例の一つ(実施例11)として開示された炭酸ランタン1 水塩(1水和物)のリン酸イオン除去率が90%であったことは,前記(2) イのとおりである。
前記(3)イ認定の本件出願の優先日当時の技術常識又は周知技術に照ら すと,甲1に接した当業者においては,甲1記載の炭酸ランタン1水和物 (甲1発明)について,リン酸イオン除去率がより高く,溶解度,溶解速 度,化学的安定性及び物理的安定性に優れたリン酸イオンの固定化剤を求 めて,水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付けが あるものと認められる。
そして,当業者は,乾燥温度等の乾燥条件を調節することなどにより, 甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)を,水和水の数が3ないし 6の範囲に含まれる炭酸ランタン水和物の構成(相違点1に係る本件発明1の構\成)とすることを容易に想到することができたものと認められる。これと異なる本件審決の判断は,前記(3)イ認定の本件出願の優先日当時 の技術常識又は周知技術を考慮したものではないから,誤りである。
イ これに対し被告は,1)甲1には,水和水の数の違いにより,リン酸イオ ン除去率に違いが生じることについての記載も示唆もないし,また,本件 出願の優先日当時,炭酸ランタン水和物の水和水の数を変更すると,リン 酸(塩)結合能力に影響が出るであろうことを示唆する技術常識又は周知技術は存在しない,2)甲1に接した当業者は,水和水の数を変更すること に着目することはなく,むしろ,甲1に列挙された各種の有機酸を含む希 土類元素の有機酸化合物を調製するか,あるいはアルカリ金属やアルカリ 土類金属を含有する複塩を調製し,リン酸イオン除去率を調べるはずであ る,3)甲1には,炭酸ランタン1水和物を用いた実施例11について,問 題となる点が何ら記載されておらず,完結した発明として記載されている から,この実施例を見た当業者は,炭酸ランタン1水和物で充分と考え, 炭酸ランタン1水和物における水和水の数を変更しようなどとは考えなか ったはずである,4)炭酸ランタン水和物は,水又は有機溶媒にほとんど溶 解しないから(甲51),溶解特性の面から水和水の数の違いについて検 討を試みる動機付けはないなどとして,甲1に接した当業者においては, 甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)を相違点1に係る本件発明 1の構成に置換する動機付けはないから,相違点1は当業者が容易に想到し得たものとはいえない旨主張する。
しかしながら,上記1)ないし3)の点については,前記(3)イのとおり,水 和物として存在する医薬においては,水分子(水和水)の数の違いが,薬 物の溶解度,溶解速度及び生物学的利用率,製剤の化学的安定性及び物理 的安定性に影響を及ぼし得ることから,医薬の開発中に,検討中の化合物 が水和物を形成するかどうかを調査し,水和物の存在が確認された場合に は,無水物や同じ化合物の水和水の数の異なる別の水和物と比較し,最適 なものを調製することが,本件出願の優先日当時,技術常識又は周知であ ったことに照らすと,甲1自体には,水和水の数の違いによりリン酸イオ ン除去率に違いが生じることや炭酸ランタン1水和物を用いた実施例11 について問題点の記載がないからといって,甲1に接した当業者において, 甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)について水和水の数の異な る炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付けがあることを否定すること はできない。また,リン酸(リン酸イオン)の固定化反応は,炭酸ランタ ン水和物が溶解して生成されたランタンイオンがリン酸イオンと反応する ことにより固定化するものであるところ(前記(2)ア(エ)の甲1記載事項), 上記のとおり,水和物として存在する医薬については,水分子(水和水) の数の違いが,薬物の溶解度及び溶解速度に影響を及ぼし得るのであるか ら,溶解度又は溶解速度の向上によりランタンイオンの溶存濃度を高め, ひいてはリン酸(リン酸イオン)の固定化反応の促進(リン酸結合能力)に影響を及ぼし得ることは自明である。
次に,上記4)の点については,仮に被告が主張するように炭酸ランタン 水和物は水又は有機溶媒にほとんど溶解しないとしても,上記のとおり, リン酸イオンの固定化反応は,炭酸ランタン水和物が溶解して生成された ランタンイオンがリン酸イオンと反応することにより固定化するものであ る以上,炭酸ランタン水和物が水又は有機溶媒に全く溶解しないものとは いえないこと,溶解度が低い水和物についても,無水物や水和水の数が異 なる化合物の調製の検討が行われていること(例えば,甲9では,「水に 極めて溶けにくい」エリスロマイシン(甲54)について,1水和物,2 水和物及び無水物の比較検討をしている。)(前記(3)ア(ア)bの「(1)」) に照らすと,炭酸ランタン水和物においても,水和水の数の違いが溶解度, 溶解速度,化学的安定性及び物理的安定性に影響を及ぼし得るものといえ るから,甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)について水和水の 数の異なる炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付けがあることを否定 することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2018.09.25
平成30(行ケ)10018 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月10日 知的財産高等裁判所
被告は,産業機械器具等の製造等を業とする株式会社であり,平成7年頃から生 海苔異物除去装置の製造販売業に参入する方針を立て,同年8月,株式会社親和製 作所(以下「親和製作所」という。)との間で,業務提携契約を締結し,同契約に基 づき,親和製作所製造に係る生海苔異物除去装置を「ダストール」との商品名を付 して販売することになったが,平成9年秋頃から,親和製作所との関係が悪化し, 上記業務提携契約の解消を検討するようになった。 そこで,被告は,その頃,独自に,生海苔異物分離除去装置の製造をすることと し,ダストールの新型の開発に取りかかり,平成10年2月頃から,その試験機の 試験運転をするようになった。上記開発には,海苔生産者の協力が必要であったた め,被告は,上記の開発に当たって,被告の地元であるF地区で海苔生産機械等の 販売店を営み,同地区の海苔生産者とのつながりが強い西部機販の代表取締役であ\nるBに対し,上記装置の開発についての協力を依頼し,Bは,同依頼を受け,被告 に,試験運転を行う生産者を紹介し,試験機の試験運転に立ち会うなど,同開発に 協力した。 なお,西部機販は,被告が本件発明共回り防止構成を有したダストールを製造す\nるようになってからは,同ダストールを被告から仕入れて販売するようになり,A ダストールも,西部機販が被告から仕入れて,Aに販売したものである。
(イ) 本件会議の開催
平成10年4月28日,被告の技研工場において,本件会議が開催された。Bは, 被告から本件会議への出席を要請され,本件会議に出席した。 本件会議では,出席者に,本件文書が配布されたが,本件文書には,「ダストール の試験機,展示会機から新型への変更点」,「1998年4月28日 フルタ電機(株) 技研工場」との表示の下,「選別ケースの外周に共回り防止ゴムをつける 選別タン ク内の海苔濃度を濃くできる事により良品タンクへの海苔濃度が濃くできる」等の 記載がある。
(ウ) 甲52特許
被告の子会社であるフルテックは,平成10年1月26日に,甲52特許の特許 出願をし,被告は,同年6月12日に,本件特許の特許出願をした。 甲52公報には,本件発明基本構成に相当する「生海苔排出口を有する選別ケー\nシング,回転板及び異物排出口を設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混 合液槽を有する生海苔異物分離除去装置」の構成が開示されている。
(エ) Aダストール及び九研ダストール
Aダストールの写真を掲載した甲第15号証には,Aダストールの型番は「ダス トールFD380D−2K」,同製品が納入された日は平成12年1月18日,同写 真の撮影日は平成28年12月3日であると記載されている。同証拠に掲載されて いるAダストールの回転板には,L字形をした板状の金具(L字金具)が取り付け られており,L字の短い方の金具の一部が回転板からはみ出している。 また,九研ダストールの写真を掲載した甲第31号証には,九研ダストールの型 番は「ダストールFD−380S」,同製品が納入された日は平成10年,同写真の 撮影日は平成29年4月25日であると記載されている。同証拠に掲載されている 九研ダストールの選別ケーシングの外周には共回り防止ゴムを取り付けるための穴 があり,また,回転板にはL字金具を取り付けるためのネジが付いている。また, 共回り防止ゴムとL字金具が袋入りで保管されている状況の写真があり,L字金具 の形状は,AダストールのL字金具の形状と同じである。
(オ) 被告と西部機販との紛争
被告は,平成27年及び平成28年に,東京地方裁判所に対し,それぞれ,西部 機販等を被告として,本件特許権の侵害を理由に,差止め及び損害賠償等を求める 訴えを提起した。なお,被告の各請求は,いずれも一部が認容され,また,同判決 に対する西部機販の各控訴はいずれも棄却された。
イ 以上の認定に対し,原告は,Bは,被告のダストールの新型の開発に協 力するよう依頼されておらず,試験運転をする海苔生産者の紹介を依頼されただけ であると主張する。 しかし,B作成の陳述書には,「G氏より開発協力を依頼された」との記載のほか, 被告に試験運転を行う生産者を紹介したこと,試験機の問題点及びその対策の具体 的内容,並びに試験機に問題が発生すると,被告の関係者を現場に呼んで,その現 象を確認してもらったことが記載されており(甲27),また,Bは,証人尋問(当 審)において,ダストールの改良のために色々とアイデアを出した旨証言しており, 上記陳述書の記載及び証言からすると,Bが被告からダストールの新型の開発の協 力を依頼され,同依頼に基づき,同開発に協力したことは明らかである。
ウ また,被告は,本件文書は,本件会議において配布されたものではなく, 本件会議の議事録を基に作成された文書である可能性が極めて高い旨主張する。\nしかし,Bは証人尋問(当審)において,平成10年4月28日に被告の技研工 場において開催された本件会議に参加して,本件文書の交付を受けた旨証言すると ころ,実際に,本件訴訟において,本件文書は,Bの保管していた資料ファイルの 一部であるとして,証拠(甲8)として提出されていること,Bが作成した日記(甲 9,25)には,本件文書に記載されている日付と同じ平成10年4月28日の欄 に,「フルタ本社より技研工場まで送ってもらう」,「フルタ本社」,「フルタ技研」,「ダストルー会議」などの記載があり,同記載は,Bの上記証言を裏付けているこ とから,Bの上記証言は信用できるというべきである。 この点について,被告は,本件文書は,その内容からすると,本件会議前に作成 されたものではなく,事後的に作成されたものであると主張するが,本件文書は, 「新型への変更点」について記載したものであるから,本件会議の前から,変更予\n定事項等によって期待できる効果や今後の対策が記載されていても不自然ではない。 したがって,本件文書は本件会議において配布されたものと認められ,被告の上 記主張は採用できない。
(2) 以上を前提に,本件文書の配布によってBに対して,本件発明の構成が開\n示されたといえるかについて検討するが,それに当たっては,特許出願時の技術常 識を考慮することができることはもとより,Bがそれまで有していた知識も考慮す ることができるというべきである。
ア まず,本件発明共回り防止構成が開示されたといえるかについて検討す\nる。
(ア) 本件文書の記載について
前記(1)ア(イ)のとおり,本件文書には,「選別ケースの外周に共回り防止ゴムをつ ける 選別タンク内の海苔濃度を濃くできる事により良品タンクへの海苔濃度が濃 くできる」との記載があるが,同記載からは,「共回り防止ゴム」の形状は明らかで はなく,共回り防止ゴムの設置方法としては,例えば,選別ケースの外周全体を囲 むように付ける方法や,選別ケースの外周の一定の箇所に極めて薄いゴムを付ける 方法等種々の方法が考えられる以上,「共回り防止ゴム」を選別ケースの外周に付け た場合,同「共回り防止ゴム」の形状が突起物状のものとなるとは限らないから, 同記載から,共回り防止ゴムの形状が突起物状のものであるとの構成が開示された\nということはできない。
(イ) 技術常識及びBの知識について
本件特許出願時において,本件文書に記載された「共回り防止ゴム」の形状が突 起物であるとの技術常識があったことを認めるに足りる証拠はないし,B及びC作 成の各陳述書(甲27,29,32,70),Bの証人尋問(当審)における証言並 びにその他の証拠を検討しても,Bが,上記「共回り防止ゴム」の形状が突起物状 のものであることを理解していたとは認められない。 この点につき,Bは,共回り防止ゴムの大きさ及び形状について,主尋問におい て,「選別インペラーと選別ケースのクリアランスに入った海苔を取り除くための ものですから,それなりの大きさ,形状が必要だと思いました。」と証言し,また, 再主尋問において,「大きさとしては,・・・ドライバーの先端くらいの大きさだと 思います。」と証言する。 しかし,Bの主尋問における上記証言は,抽象的であり,前記(ア)のとおり,選別 ケースの外周に取り付ける共回り防止ゴムの形状及び大きさは種々のもの考えらえ ることからすると,同証言内容からは,共回り防止ゴムの形状が突起物状のもので あると認識していたとは認められない。また,Bの再主尋問における上記証言につ いても,本件文書が交付されたのは,Bの証人尋問が行われた日の20年以上も前 のことであり,Bが,その頃の認識を正確に記憶しているとは考え難いこと,Bは, 本件会議後に本件発明共回り防止構成を備えたダストールの販売をしており,その\n構造についての知識があること,Bは,L字金具を取り付けたAダストールを販売\nしており,「ドライバーの先端くらいの大きさ」という証言も,上記L字金具を念頭 に置いたものと考えると,形状の点で整合することからすると,Bは,本件会議後 に得た認識と本件会議における認識とを混同している可能性も十\分考えられるとい うべきである。また,そもそも,前記ア(オ)のとおり,Bが代表者を務める西部機販\nは,被告から,本件特許権の侵害を理由とした損害賠償請求等の訴えを提起された ことがあり,このようなBの立場を考慮すると,この点からしても,Bの上記証言 の信用性には疑義があるというべきである。 以上の点を考慮すると,Bの上記証言から,Bが,本件会議の時点で同証言のと おりの認識を有していたと認めることはできない。
(ウ) なお,本件会議における説明を考慮するとしても,本件会議は本件特 許が出願された平成10年6月12日の1か月半前の同年4月28日に開催されて いるが,本件会議が開催された時点では,本件発明の具体的内容が固まっていない ことも十分考えられるから,共回り防止ゴムの具体的な形状等の本件発明共回り防\n止構成のうちの具体的な構\成については本件会議で説明されなかったことも十分考\nえられるというべきである。そして,本件会議に出席したBも,証人尋問(当審) において,本件会議で共回り防止ゴムの形状や大きさについての話がされたか否か は覚えていない旨証言しており,また,C陳述書にも,本件会議で共回り防止ゴム の形状が突起物状のものであるとの説明があった旨の記載がなく,その他,本件会 議における説明内容について認定できる的確な証拠はない。
(エ) したがって,Bが,本件文書の配布によって,共回り防止ゴムの形状 が突起物状であると認識したと認めることはできないというべきである。
イ 以上より,本件文書の配布によって,本件発明共回り防止構成のすべて\nが開示されたと認めることはできないから,本件文書の配布によって,本件発明が, 公然知られた発明となったと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2018.09.25
平成30(行ケ)10035 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年9月6日 知的財産高等裁判所(3部)
以上を前提に本件商標と引用商標の類否について検討する。
(ア) 本件商標と引用商標は,外観において,書体が異なる点,本件商標 の末尾に「.」があるのに引用商標にはこれがない点,引用商標には6 文字目に「I」があるが,本件商標にはこれがない点で異なる。 他方,本件商標及び引用商標は,いずれも9文字のアルファベットか らなり,「.」「I」を除いては,同じM,O,N,T,A,G,N, Eのアルファベットを同じ順序で含んで構成されており,使用される文\n字及びその使用の順序が近似している。また,いずれの商標も等間隔の アルファベットによりひとかたまりでまとまりよく構成されている。そ\nして,本件商標と引用商標の書体が相違するとしても,いずれの書体も デザイン化されていない読みやすい普通に用いられる書体であり,看者 に強い印象を与えるものではない。さらに,本件商標の「.」は末尾に 付され,大きさも小さいこと,引用商標における「I」は6文字目にあ って他の文字より幅がかなり狭いことから,これらの相違する文字は, 看者の印象に残りにくい。 以上によれば,本件商標と引用商標は,外観において,相紛らわしい ものといえる。
(イ) 本件商標及び引用商標は,いずれも特定の観念を想起させない。
(ウ) 本件商標は「モンタグネ」,「モンターニュ」の称呼を,引用商標 は「モンタイグネ」,「モンテーニュ」の称呼を生じる。 このうち,「モンタグネ」と「モンタイグネ」は,5音ないし6音の うち,冒頭の3音が共通しており,また,末尾の「グネ」も共通してい るし,差異音である「イ」の音は弱音であるから,両称呼を一連に称呼 した場合,称呼全体の語調,語感が近似したものとなる。 また,「モンターニュ」と「モンテーニュ」は,いずれも長音を含む 5音よりなり,一連に称呼した場合に,比較的聴別されにくい中間部に おいて「タ」の音と「テ」の音の差異を有するが,この差異音は子音を 共通にし,母音である「a」と「e」の音も近似しているから,両称呼 を一連に称呼した場合,称呼全体の語調,語感が著しく近似したものと なる。 そうすると,本件商標と引用商標は,称呼において相紛らわしいとい える。
(エ) 以上のとおり,本件商標と引用商標は観念において比較できないも のの,外観及び称呼は相紛らわしいものである。 そして,本件取消に係る商品と引用商標の指定商品の需要者である一 般の消費者が通常有する注意力を踏まえると,これらの一般の消費者が 必ずしも商標の構成を細部にわたって記憶して取引するとはいえないこ\nとから,本件商標と引用商標を時と所を異にして隔離的に観察した場合, 商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがあるといえる。
(オ) したがって,本件商標は,引用商標に類似する商標であるといえる。
2 原告の主張について
(1) 指定商品の類否について
原告は,本件取消に係る商品のうち「カーボン製のスーツケース」に関し, 引用商標の指定商品とは原材料,商品の性状や外観(カーボン製は硬質感の あるハードタイプであるのに対して,革製又は人工皮革製は軟質のソフトタ\nイプである。)が明確に異なり,生産部門,販売部門,原材料,品質,用途及 び需要者がいずれも異なる非類似の商品であると主張する。 しかし,「カーボン製のスーツケース」と引用商標の指定商品である革製 又は人工皮革製の旅行かばんの用途は同じであり,同一の生産者ないし製造 者により取り扱われることがあり,需要者が共通するのは,上記1(1)説示 のとおりであり,原告の主張は採用できない。
(2) 商標の類否について
ア 原告は,本件商標は「.」部分が,引用商標は「I」の文字が非常に大 きな存在感を示すこと,書体も大きく異なること,本件商標は略長方形の 中に収まるような態様の文字部分から「.」部分が飛び出るような態様で 書されているのに対し,引用商標は「A」の文字を中心として4文字ずつ 左右対称であるかの如くバランス良く配されているから,両商標から受け る印象は大きく相違し,本件商標と引用商標とは,外観上非類似の商標で あると主張する。 しかし,本件商標の「.」の位置や大きさからすれば「.」が大きな存 在感を有するとはいえないし,引用商標の「I」の文字の幅は他の文字よ りかなり細いことから「I」が大きな存在感を有するともいえないことは, 上記1(2)エ(ア)に説示したとおりである。また,本件商標及び引用商標の 書体,文字数,使用されている文字及び語順並びにその配置からすれば, 両商標全体から受ける印象が大きく相違するとはいえないものであり,原 告の主張は採用できない。
イ 原告は,本件商標から生じる観念は,「(何かの末尾としての)山」, 「山(さらに省略されたもの)」ないし「山」であり,引用商標から生じる 観念はフランスの人名(モンテーニュ)であるから,本件商標及び引用商 標からそれぞれ生じる観念は,著しく異なっていると主張する。 しかし,本件取消に係る商品及び引用商標の指定商品の需要者,取引者 がこれらのフランス語を容易に理解すると判断する理由はなく,本件商標 と引用商標はいずれも特定の観念を想起させるものではないというべきで あるから,原告の主張は採用できない。
ウ 原告は,電子メールアドレスやインターネットのURLに日常的に触れ る需要者,取引者にとっては,非常に長い称呼であっても「ドット」の称 呼は省略せずに必ず称呼するのが常識であり,本件商標の「.」から「ド ット」の称呼を生じるから,本件商標からは「モンターニュドット」,「モ ンタグネドット」又は「モンターネドット」の称呼が生じ,「.」を無視 した称呼は生じ得ないと主張し,これを前提に,本件商標と引用商標の称 呼は非類似であると主張する。 しかし,電子メールアドレスやウェブサイトのURLは,アルファベッ トのまとまりが複数あり,そのまとまりとまとまりの間に「.」が配置され るのが通常であるのに対し,本件商標は8文字のアルファベットの末尾に 「.」を付した構成である。これによれば,本件商標に接した需要者,取引\n者が電子メールアドレスやウェブサイトのURLを連想するとはいえず, 本件商標の「.」から「ドット」の称呼が生じるとはいえないから,これを 前提とする原告の主張は採用できない。
エ 原告は,取引の実情として,1) 本件商標は原告オリジナルの商品ブラ ンドを示す商標として需要者,取引者の間で既に認識・理解されており, 他方,引用商標について顧客吸引力を有しているのは「LOUIS VU ITTON」又は「ルイ ヴィトン」ブランドであって引用商標ではなく, 本件商標と引用商標について現実に誤認混同が生じていないこと,2) 大 手百貨店のバイヤーにおいても本件商標と引用商標のブランドが類似して いると認識していないこと,3) 本件商標に関連する家具やキャリーケー ス,アタッシュケース等は十万円前後から数十\万円にわたる価格帯であり, 申立人の商品はさらに高価で類似品や偽物も多いため,需要者,取引者は\n細心の注意を払って慎重に商標を観察して取引にあたることを主張する。 しかし,商標の類否判断において参酌されるべき取引の実情とは,その 指定商品全般についての一般的,恒常的なそれを指すものであって,当該 商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的,限定的なそれを指 すものではない(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同年4月25日第一 小法廷判決・審決取消訴訟判決集昭和49年443頁参照)。原告の主張 する上記事情は,いずれも本件商標及び引用商標が現在使用されている商 品についてのみの限定的な事情であることが明らかであるから,これらの 事情は商標の類否の判断を左右するものではない。なお,甲64,79等 は,上記1)の事実を認めるに足りる証拠とはいえず,他にこれを認めるに 足りる証拠はないし,上記2),3)の事実は,直ちに本件商標と引用商標と の類似性を否定するに足りる事情とはいえないのであるから,原告の上記 主張は,内容に立ち入って検討してみても,やはり失当である。 また,原告は,本件取消に係る商品及び引用商標の指定商品は,慎重に 選択する選択性の高い商品であり,需要者,取引者は,自ら商品を手に取 り,ブランド,デザイン,色,サイズ,素材,価格等を確かめて,商品を 購入するか否かを決めるというのが取引の実情であると主張する。 しかし,本件取消に係る商品及び引用商標の指定商品の需要者は一般の 消費者であり,これらの商品はいわゆるブランド品や,デザイン性やファ ッション性が高い商品に限られず,その価格帯も多様であるから,これら の商品の需要者に,上記の取引の実情が一般的,恒常的に当てはまるとは いえない。上記1(2)エに説示したとおりの本件商標と引用商標の類似性の 程度に照らせば,本件商標と引用商標が同一又は類似の商品に使用された 場合には,出所の誤認混同を生ずるというべきである。原告の主張は採用 できない。
3 以上のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を総合して全 体的に考察すれば,互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であ り,また,本件取消に係る商品と引用商標の指定商品は類似すると認められる から,本件取消に係る商品についての商標登録は,商標法4条1項11号に該 当するものである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.09.21
平成30(行ケ)10019 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年9月10日 知的財産高等裁判所
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構\ 成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否 を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識 として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出 所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,原則とし て許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12 月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第 103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁 平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事22 8号561頁)。 そこで,本件商標と引用商標との類否の判断に当たって,本件商標の一部である 「UNITED」を抽出して,引用商標と比較することができるかについて検討す る。
・・・
前記のとおり,「UNITED」の語は,「結合した,連合した」などの 意味を有する形容詞であり,「TOKYO」の語は名詞であるから,「UNITED」 の語は「TOKYO」の語を修飾しており,「UNITED TOKYO」という語 は,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東京連合」と訳される。その言葉は必 ずしも一般的に用いられているものではないが,東京には,数多くの人が居住し, また,特色,歴史及び文化の異なる多くの地域があることからすると,それらの連 合体を観念することができ,したがって,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東 京連合」をそのような意味で理解することも可能であるというべきである。そうす\nると,本件商標は,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東京連合」という観念 上一体のものとして理解されることもあり得るというべきである。
ウ 一方,「UNITED」という語は,「結合した,連合した」などの意味 を有する形容詞であるから,他の語と一体となって,その語を修飾するために用い られるのであり,単独では意味を取りにくい語であるといえる。また,前記のとお り,被服又は靴類を指定商品として「UNITED」を含む商標が登録された例は 非常に多いことから,ファッション業界においては,「UNITED」という語はあ りふれているものと認められる。さらに,本件証拠上,「UNITED」が原告の商 品又は営業を示すものとして周知であるといった事情も認められない。
エ 以上からすると,本件商標は,一連一体のものとして理解されるという べきであって,「UNITED」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与 えるとか,「TOKYO」の部分から出所識別標識としての称呼,観念を生じないな どということはできないから,引用商標との類否の判断において,「UNITED TOKYO」から「UNITED」の部分を抽出して,同部分と引用商標とを比較 することは相当ではないというべきである。 (3)ア 原告は,「TOKYO」の語が被服等に用いられた場合,そのブランド の発信地を意味するものとして需要者に認識されるのであるから,本件商標のうち 「TOKYO」の部分は商品の品質,産地あるいは役務の提供地を表示するものに\nすぎず,「TOKYO」の部分には識別力がない旨主張する。 しかし,前記(2)のとおり,本件商標のうち,「UNITED」の語は形容詞であ り,これに続く「TOKYO」の語を修飾していること,「UNITED」の語意か らすると,単独では意味を取りにくく,他の語と併せて一つの意味のある言葉とな ること,本件証拠上,「UNITED」が原告の商品や原告の営業を表示するものと\nして,周知であるといった事情も認められないこと,一方,「UNITED TOK YO」の語からは,「結合した東京」,「連合した東京」又は「東京連合」という観念 が生じ得ることなどからすると,「UNITED TOKYO」のうち「TOKYO」 の語が,「UNITED」とは切り離された独立のものとしてブランドの発信地を意 味し,商品の品質,産地あるいは役務の提供地を表示するものにすぎないと理解さ\nれることはないというべきである。 イ 原告は,被告は会社名に「TOKYO」を使用しているほか,ウェブサ イト等において,「UNITED TOKYO」が東京のリアルなモードスタイルを 発信していくブランドであることを強調していることから,本件商標のうち,「TO KYO」の部分は,東京発のブランドであることを示すために用いられていると主 張する。
証拠(甲29〜31,37,38)によると,被告の開設するウェブサイトには, 「TOKYOブランドにこだわり,TOKYOのリアルなモードスタイルを世界へ 発信」,「伝統的なモノ,最先端のモノ,異文化のモノも絶妙なバランス感覚で調和 できる『TOKYO』特有の感性」,「東京のクリエーションと日本の技術のプラッ トホームになれば良いそんな想いと創造を東京/日本から世界へ発信」,「TOKY Oを代表するクリエーターと共に,TOKYOのクリエーションを『UNITED\nTOKYO』のフィルターを通して提案していきます」との記載があり,また,他 のウェブサイトの被告を紹介した記事の中に「東京を拠点とするクリエーターとコ ラボレーションしたアイテムを展開する」との記載があることが認められる。 上記事実からすると,ウェブサイトにおいて,被告のブランドが東京発のブラン ドであるとの記載があることが認められるが,前記(2)イのとおり,「UNITED TOKYO」から東京に居住する人々や東京の各地域の連合体という観念を生じ得 ることからすると,被告のブランドが東京発のブランドであると記載されることは 自然なことであって,被告のブランドが東京発のブランドであるとの記載があるこ とから直ちに,本件商標の「TOKYO」の部分が商品の品質,産地あるいは役務 の提供地を表示しているにすぎないということはできないというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.09.21
平成29(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月10日 知的財産高等裁判所
前記第2の2(2)のとおり,本願補正発明の「特定演出」は,「前記有利 量付与決定手段により決定された有利量の付与」を「前記有利状態中」において「報 知可能」なものである(構\成要件E)。 そして,「前記有利量付与決定手段」は,「有利量を付与すること」を決定するも のであるから(構成要件C),「特定演出」における報知の対象は,有利量付与決定\n手段により有利量を付与することが決定されたという事実であると解するのが相当 である。 もっとも,「特定演出」は,「前記有利状態中」に実行されるものであるが,「前記 有利状態」は,「付与された有利量を消費することによって・・・制御」されるもの であるから(構成要件D),「特定演出」における報知の対象が,「特定演出」を実行\nする際の有利状態を制御するために消費中の有利量を付与することが決定されたと いう事実を指すのか,この消費中の有利量の付与とは別に,有利量を付与すること が決定されたという事実を指すのかは,特許請求の範囲の記載のみにより一義的に 明確に理解することはできない。
(イ) そこで,本願明細書を参酌すると,「課題を解決するための手段」欄に おいて,「特定演出(連続演出)」は,1)所定期間(50ゲーム)における残り期間 が特定期間(5ゲーム)となるまでに,前記所定期間が経過した後においても継続 して,複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内 部抽選処理)の決定結果に応じた決定結果情報を報知する(ATモード中における ナビ演出を実行するための処理)か否かを決定する継続決定手段(継続抽選,図2 5)により,継続すると決定したときに,前記特定期間において実行される(図3 0,図31参照)とともに,2)前記継続決定手段で継続しないと決定したときであ っても,前記所定期間における残り期間が特定期間(5ゲーム)となってからその 所定期間が経過するまでに,所定の特別条件(特別条件,イチゴ当選)が成立した ことを条件に,前記決定結果情報を報知する期間を,前記所定期間以上の期間(5 0ゲーム,60ゲーム)延長する第2延長手段により,前記所定期間以上の期間延 長する場合に実行される(図31(c)(d)参照)とされている(【0009】,【0036】)。また,「特定演出」によって,所定期間における残り期間が特定期間とな ったときには,所定期間が経過した後においても継続して決定結果情報が報知され るか否かを煽ることができるとされている(【0037】)。 また,「発明を実施するための形態」欄においては,RTであるときであって,演 出状態がATモードであるときに,所定期間として50ゲームにわたり制御される ATモードの残りゲーム数が5ゲームとなったときに実行される「連続演出」(【0 244】,【0436】,【0440】,【図30】,【図31】)が,「特定演出」に相当するとされており(【0459】),ATモードの残りゲーム数が6ゲーム以上存在する場合に,所定表示領域の右上にATモードの残りゲーム数を表\示するAT用演出 (【0437】,【図29】)は,「特定演出」に相当するものとはされていない。そして,「特定演出」に相当するとされる上記「連続演出」は,ATモードの残り5ゲー ムにわたり一連の物語を展開する演出を行った後に,物語の結末としてATモード が継続するか否かを報知する演出であり,これにより,ATモードの残り5ゲーム にわたって,ATモードが継続することに対する遊技者の期待感を煽ることができ るとされ,味方キャラクタと敵キャラクタとが戦う演出を行った後,敵キャラクタ が倒れるとともに「WIN +1set」といったメッセージが表示されて,AT\nモードが継続することが報知されるとされている(【0443】,【0446】,【0449】,【0459】,【図30】,【図31】)。 このような本願明細書の記載によると,本願補正発明における「特定演出」は, 有利状態が継続する所定期間における残り期間が特定期間となったときに,上記所 定期間が経過した後においても上記有利状態が継続することに対する遊技者の期待 感を煽ることを目的とするものであって,「特定演出」を実行する際の有利状態を制 御するために消費中の有利量を付与することが決定されたという事実を報知するも のを含むものではなく,上記所定期間経過後に継続して有利状態を制御するための 有利量など,現に消費中の有利量とは別の有利量を付与することが決定されたとい う事実を報知するものであると解するのが相当である。
イ 引用発明1の「チャンスゾーン演出」について 引用発明1の「チャンスゾーン演出」(構成e1)は,その具体的な演出内容は刊\n行物1に記載されていないものの,遊技状態がRT1〜RT3に制御されてから開 始され,ボーナスに入賞するか又はゲームが所定回数(RT1は50回,RT2は 40回,RT3は5回)行われることにより終了するものである(前記(2)イ(エ)c)。 そうすると,「チャンスゾーン演出」は,RT1〜RT3に制御されたゲームを所定 回数行える状態にあることを報知するにとどまるものと認められ,現に消費中の有 利量(ゲーム数)とは別の有利量を付与することが決定されたという事実を報知す るものであるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2018.09.21
平成29(行ケ)10172 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月4日 知的財産高等裁判所(1部
特許請求の範囲の記載が,サポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の 記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か,また,発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 (2) 特許請求の範囲の記載 本件各発明に係る特許請求の範囲は,前記第2の2【請求項1】ないし【請求項 3】のとおりである。
・・・
そうすると,当業者は,原出願日時点において,キレート配位子となり得る構造\nを有する分子が,何らかの方法により,インテグラーゼ阻害作用に関与する可能性\nがあることは認識していたものの,キレート配位子となり得る構造を有する分子が\nインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの技術常識を有していたというべ きである。
(6) 当業者が本件各発明の課題を解決できると認識し得るかについて 本件各発明の課題は,インテグラーゼ阻害作用を有する化合物を含有する医薬組 成物を新たに提供するというものである。 しかし,本件明細書には,本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を 有することを示す薬理データは,一つも記載されておらず,本件各発明に係る化合 物がインテグラーゼ阻害作用を示すに至る機序についても記載されていない。 また,原出願日時点におけるインテグラーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾\n変化によって,そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの前記の技 術常識に照らせば,A群等試験例化合物及びB群等試験例化合物がインテグラーゼ 阻害作用を有することを示す薬理データをもって,当業者が,本件各発明に係る化 合物についてもインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することはできない。 さらに,原出願日時点におけるキレート配位子となり得る構造を有する分子がイ\nンテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの前記の技術常識に照らせば,本件 各発明に係る化合物がキレート配位子となり得る構造を有することをもって,当業\n者が,本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると認識すること はできない。 その他,本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると当業者に 認識させ得るような原出願日時点における技術常識も見当たらない。 したがって,本件各発明に係る化合物は,当業者がインテグラーゼ阻害作用を有 する化合物を含有する医薬組成物を新たに提供するという本件各発明の課題を解決 できると認識し得る範囲のものとはいえないというべきである。
◆判決本文
こちらは対応の侵害訴訟です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2018.09.21
平成29(行ウ)559 手続却下処分取消請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年8月30日 東京地方裁判所(47部)
特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるときとは,特段の事情 のない限り,特許出願を行う出願人として,相当な注意を尽くしていたにもか かわらず,出願審査請求期間の徒過に至ったときをいうものと解するのが相当 である。
(2)これを本件についてみるに,原告は,従来から,本件現地事務所が,本件国 内事務所に対し出願審査の請求手続を指示するメールを送信後,メールの到達 を確認する手順を踏まない運用をしていたこと,他方で,本件国内事務所は, 元々,国内移行の段階で審査請求を行う日にちの指示がない場合には,出願審 査請求期間満了の1か月前までに指示するよう本件現地事務所に依頼してお り,逐一その旨は連絡しておらず,同期間満了の1か月前までに指示がない場 合には審査請求を行わないものとみなす運用をしていたこと,そして,かかる 運用でも特段の問題は生じていなかったところ,本件では,本件現地事務所が 本件国内事務所に対し,平成28年4月1日,本件特許出願について出願審査 請求をするようメールで指示したにもかかわらず,本件国内事務所の所内のサ ーバー及びメールサーバーが同年3月28日から同年4月4日までの間,ウイ ルス感染により使用不可能な状況となっていたため,本件国内事務所において\n 上記メールを受信することができなかったこと等をるる主張する。 しかしながら,原告の主張する運用には,本件現地事務所と本件国内事務所 との間のメールの送受信に問題が生じた場合に対する何らの対策も含まれて おらず,この運用に沿って行動したからといって,本件現地事務所あるいは本 件国内事務所が相当な注意を払ったとは認めがたい。
また,原告は,突発的な事象として,本件国内事務所の所内サーバー及びメ ールサーバーのウイルス感染を主張するものと解されるところ,前記1?で認 定した限度で,本件国内事務所の関連会社内のサーバーに関してランサムウェ アの感染に係る問題が認識されていたことは認められるとしても,原告の主張 する期間において,本件国内事務所の所内のサーバーなどが使用不可能な状況\nになっていたと認める足りる的確な証拠はない。そして,仮に原告の主張する とおりの状況があったとしても,本件国内事務所が本件特許出願に係る出願審 査請求期間(本件期間)の終期につき,平成28年4月29日と認識していた のであれば,その1か月前である平成28年3月29日の時点でサーバーが使 用不可能な状態になっていたことになる以上,本件国内事務所としては,通常\nの運用がどうであれ,本件現地事務所に出願審査請求の指示のメールを送信し た事実の有無を確認すべきであるし,サーバーが使用可能になった時点から本\n件期間の終期まで1か月弱の期間があったことからすれば,かかる確認をする 時間的猶予は十\分にあったというべきである。 そうすると,結局,本件において,本件現地事務所あるいは本件国内事務所 が相当な注意を払ったとは,到底認めがたいし,特段の事情があったとも認め られない。 なお,原告は,自らの判断に基づき,本件現地事務所あるいは本件国内事務 所に委任して特許出願に係る手続を行わせることとした以上,原告が相当な注 意を払ったか否かという点において本件現地事務所あるいは本件国内事務所 についての前記の判断と別個の判断をすべき理由はない。
(3)したがって,本件特許出願について本件期間内に出願審査の請求をすること ができなかったことについて,特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」 があったとは認められず,その結果,本件手続については本件特許出願の取下 擬制(特許法48条の3第4項)により客体が存在しないこととなるから,本 件却下処分は適法である。
2018.09.14
平成29(行ケ)10189 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月4日 知的財産高等裁判所(3部)
特許法36条6項2号の趣旨は,特許請求の範囲に記載された発明が明確 でない場合に,特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となることによ り生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで,特許を受 けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載のみならず, 願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願当時に おける技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不 利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきであ る。
(2) この点,原告は,審決が,特許請求の範囲の「カバーが水槽の底部面に概 ね面一」について,「面一」とは,止水時において,水槽の底部面とカバー の頂部とがつまずくことを防止できる程度にほぼ同じ高さになることを意味 するものと解釈できると説示したのに対して,「止水時において,水槽の底 部面とカバーの頂部とがつまずくことを防止できる程度」というのは,排水 口のために水槽の底部面に形成された円筒状陥没部のR面を含む傾斜面の形 状等やカバー自体の形状でも異なるほか,当該傾斜面の形状や傾斜角度とカ バーの形状の組合せによっても異なり,さらには,使用者の年齢や性別,体 格等によっても異なる以上,「カバー(特にカバーの頂部)が水槽の底部面 に概ね面一」が「つまずくことを防止できる程度」という趣旨であるとすれ ば,権利の及ぶ範囲が不明確であり,本件発明に接した第三者は不測の不利 益を被る,などと主張する。 しかしながら,本件明細書の【0013】には,「カバーにつまづくこと を防止するため,カバーの頂面60が水槽の底部1面と概ね面一になるよう 円筒状陥没部10の縁とカバー6の縁との位置を略一致させることがよい。」 との記載があるものの,【0008】には,「カバーが水槽の底部面と概ね 面一にされ,排水口部を覆うことになって排水口部内の汚れを覆い隠すこと ができ,見栄え良くできる。」との記載もあり,かかる記載を根拠にすると, 「概ね面一」とは,「排水口部を覆うことになって排水口部内の汚れを覆い 隠すことができ,見栄え良くできる程度」と定義していると理解することも 可能である。\nそもそも,本件発明の排水栓装置は,洗面化粧台,浴槽,流し台などあら ゆる水槽が含まれるところ,「カバーにつまづくことを防止できる程度」と いうのは,飽くまで浴槽の観点からみた理解であるから(この定義が明確と いえるかどうかの点はひとまず措く。),このように理解できたとしても, 浴槽以外の,例えば,洗面化粧台における「概ね面一」の範囲が直ちに明ら かになるわけではない。 したがって,原告の主張は,「カバー(特にカバーの頂部)が水槽の底部 面に概ね面一」が「つまずくことを防止できる程度」を意味するとの理解を 前提とする限りにおいて正当な指摘を含んでいるが,それでは足りないとい うべきである。
(3) そこで,さらに進んで検討するに,本件明細書には,「概ね面一」の意味 するところを説明する確たる定義はないけれども,本件明細書の図1には, 水槽の底部面とカバーの頂部(頂面60)とがほぼ同じ高さになる状態が示 されており,この状態をもって「カバーが水槽の底部面に概ね面一」と理解 することは自然である。そして,寸法誤差,設計誤差等により,水槽の底部 面とカバーの頂部(頂面60)とが完全に同じ高さとならない場合が存する ことは技術常識であるといえるから,カバーと水槽の底部面との高さの差が, このような範囲にとどまるものを「概ね面一」と理解するなら,洗面化粧台, 浴槽,流し台などあらゆる水槽について,「カバーが水槽の底部面に概ね面 一」の意味内容を統一的に理解することができる。 審決の,「概ね面一」とは,「止水時に,カバーを水槽の底部面に対し積 極的に出没させた位置に設けようとするものではない」との説示もこうした 趣旨と理解できる。 そうとすれば,「概ね面一」の語を用いているがゆえに特許請求の範囲の 記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえず,これ に反する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2018.09.14
平成29(行ケ)10210 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月6日 知的財産高等裁判所(3部)
本件訂正後の特許請求の範囲にいう「平均分子量が2万〜4万のコンド ロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が,本件出願日当時,重量 平均分子量,粘度平均分子量,数平均分子量等のいずれを示すものである かについては,本件訂正明細書において,これを明らかにする記載は存在 しない。もっとも,このような場合であっても,本件訂正明細書における コンドロイチン硫酸又はその塩及びその他の高分子化合物に関する記載を 合理的に解釈し,当業者の技術常識も参酌して,その平均分子量が何であ るかを合理的に推認することができるときには,そのように解釈すべきで ある。
イ 上記1(2)カのとおり,本件訂正明細書には,「本発明に用いるコンドロ イチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物であり,平均分子量が0.5 万〜50万のものを用いる。より好ましくは0.5万〜20万,さらに好 ましくは平均分子量0.5万〜10万,特に好ましくは0.5万〜4万の コンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかるコンドロイチン硫酸又は その塩は市販のものを利用することができ,例えば,生化学工業株式会社 から販売されている,コンドロイチン硫酸ナトリウム(平均分子量約1万, 平均分子量約2万,平均分子量約4万等)が利用できる。」(段落【00 21】)と記載されている。 上記の「生化学工業株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナ トリウム(平均分子量約1万,平均分子量約2万,平均分子量約4万等)」 については,本件出願日当時,生化学工業株式会社は,同社製のコンドロ イチン硫酸ナトリウムの平均分子量について重量平均分子量の数値を提供 しており,同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として当 業者に公然に知られた数値は重量平均分子量の数値であったこと(上記(3) イ(ア))からすれば,その「平均分子量」は重量平均分子量であると合理的 に理解することができ,そうだとすると,本件訂正後の特許請求の範囲の 「平均分子量が2万〜4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平 均分子量も重量平均分子量を意味するものと推認することができる。加え て,本件訂正明細書の上記段落に先立つ段落に記載された他の高分子化合 物の平均分子量は重量平均分子量であると合理的に理解できること(上記 (2)イ),高分子化合物の平均分子量につき一般に重量平均分子量によって 明記されていたというのが本件出願日当時の技術常識であること(上記(2) ウ)も,本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万〜4万のコン ドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が重量平均分子量である という上記の結論を裏付けるに足りる十分な事情であるということができ\nる。
ウ よって,本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を充足するも のと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2018.09.14
平成22(ワ)18041 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成25年7月11日 大阪地方裁判所
原告は,本件特許1の出願当初,構成要件B1に相当する部分を「駆動回路7\nに電圧を提供する電源1の電圧を検出する検出手段5」としていたが,平成19 年5月2日付け拒絶理由通知を受けた後,「交流電圧の電源1から整流されて駆 動回路7に提供される直流電圧を検出する検出手段5」と補正した(乙1〜3)。 しかし,平成19年5月2日付け拒絶理由通知は,特許法36条4項(実施可 能要件)及び同条6項2号(明確性要件)の要件を満たしていないとするもので,\n新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかったし,電圧の検出手段に係る記 載の不備を指摘するものでもなかった(乙2)。原告が手続補正書とあわせて提 出した意見書においても,電圧の検出手段に関して特段の説明をしているわけで はない。 このような経過からすれば,原告の上記補正について,新規性や進歩性の欠如 を回避するなどのため,電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外した\nものとは言い難い。 また,他に均等の成立を否定すべき特段の事情も認められない。
・・・
被告自身,本件特許発明1と乙28発明は,次のとおり相違していることを認 めている。すなわち,本件特許発明1の電源電圧が「90〜264Vの間」の 「交流電圧」であり,これを「整流」した上で「分圧」して検出するのに対し, 乙28発明の電源電圧が「12〜48Vの間」の「直流電圧」で,必然的に「整 流」はなく,検出前に「分圧」しているか明らかでない点で相違する(後記相違 点2),3))。
・・・・
エ 以上より,本件特許発明1の乙28発明と対比したときの相違点は, 当業者にとって,周知慣用技術及び技術常識を適用することで容易に想到できる 構成といえる。\n よって,本件特許発明1は進歩性を欠如しており,本件特許1は特許無効審判 により無効にされるべきものと認められるから,原告は,本件特許権1に基づく 権利を行使することはできない。
◆判決本文
控訴審でも、無効は維持されました。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.09.13
平成30(行ケ)10026 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年8月29日 知的財産高等裁判所
ア 本件商標のように,標準文字で一連に記載されたものであっても,それ がいくつかの文字等を組み合わせた結合商標と解されるもので,かつその一部が需 要者に対して,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの である場合やそれ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認 められる場合などには,当該一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して 商標そのものの類否判断をすることも許される(最高裁昭和37年(オ)第953 号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成 3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号500 9頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁 判集民事228号561頁参照)。
イ これを本件についてみるに, 本件商標である「VANSNEAKER」 は,全体としてみた場合,それ自体としては何の意味もない造語である。そして, 前記1で検討したように,「VANS」の欧文字からなる引用商標が,スニーカーを 中心とした履物の分野で周知であり,出所識別標章として,一般消費者の間で強い 識別力を持つものであることからすると,本件商標の語頭にある「VANS」も本 件商標の指定商品である「履物」との関係では強い識別力を持つものといえる。 他方,本件商標から語頭の「VR」はそれ自体としては何の意味もない語であるところ,そこに直前に置かれた「S」(換言すると,「VANS」に用いられている「S」)を足した「SNEAKER」は,指定商品である履物の一種であるスニーカーを表示する語として,我が国においても広く知られていること,一般消費者向けの商品等に関して,二つの語を結合するときに,一方の語の末尾と他方の語の語頭とで共通する文字を敢えて省略して商品名等をネーミングする手法が見られること(乙76の1,乙77〜81)からすると,「NEAKER」は,直前に「S」を足して,「SNEAKER」と認識される可能\性が高いということができる。しかるところ,「SNEAKER」の語は,指定商品である履物の一種を表す語として,指定商品との関係では,識別力を有さないものであるから,「NEAKER」の部分は,指定商品との関係での識別力は,上記のように周知で識別力の強い「VANS」と比して明らかに弱いものといえる。以上からすると,本件商標からその要部として「VANS」の部分を抽出して,類否判断することが許されるというべきである。\n
(2) 類否判断
本件商標からその要部である「VANS」を抽出した場合,本件商標の要部であ る「VANS」と標準文字で欧文字の「VANS」を横書きしてなる引用商標は, 外観が同一といえる上,両者からは共に「ヴァンズ」との称呼が生じる。 また,前記で認定したように,「VANS」ブランドについて,スニーカーを中心 とした商品が日本において相当多数量販売されており,かつ引用商標や「VANS」 の欧文字をデザイン化した使用商標がスニーカーなどとともにファッション雑誌等 で多数回取り上げられるなど大規模な広告宣伝活動がされているから,本件商標の 要部である「VANS」及び引用商標からは,共に「スニーカーを中心として展開 されている異議申立人の業務に係るVANSブランド」といった観念も生じるもの\nと認められる。 以上のとおり,本件商標の要部と引用商標は,外観,称呼及び観念を共通にして おり,本件商標がその指定商品である「履物」に使用された場合,引用商標と出所 混同のおそれがあるということができるから,本件商標と引用商標は類似している ものと認められる。
(3) 原告の主張について
原告は,1)本件商標に接した者が,明示的な示唆等もないのに,前半部「VAN S」の最後の文字「S」を後半部を認識するためにもう一度使用することはない, 2)本件商標に接した者は,本件商標中の「SNEAKER」から「スニーカー」を 想起するなどし,前半の「VAN」を認識して,本件商標を「ヴァンスニーカー」 などと一体として称呼,認識する,3)本件商標から「VANS」を取り出した残り は「NEAKER」であるが,「NEAKER」が商品の出所識別標識としての機能\nを有していて省略されるべきではないことからすると,本件商標は一体として「ヴ ァンズニ―カー」などと称呼,認識される可能\性もある,4)「VANS」の語は固 有の意味を有しない造語であるから,商品等のネーミング手法の一つとして,二つ の語を各語の構成文字の一部を省略し結合する他の例と同列に論じることはできな\nい,5)「VANS」を含み,指定商品を「靴及び運動用特殊靴」とする「vans ydical」が登録されていることが,被告の主張と反するなどと主張し,本件 商標について「VANS」の部分を抽出して類否判断することは許されない旨を主 張する。 しかし,上記1)〜3)については,上記で検討したように,指定商品に関して使用 された本件商標に接した場合,接した者の注意は,識別力の強い語頭の「VANS」 に向けられるとともに,「VANS」と「SNEAKER」の間で「S」が重なり合 っていると理解し,本件商標について,「VANS」と「SNEAKER」を組み合 わせて構成されたものと認識することが十\分にあり得るところであって,原告の主 張するように常に一体として認識されるとはいえず,原告の主張は採用できない。 また,上記4)についても,前記1のとおり,「VANS」は,指定商品「履物」と の関係では,周知性のある識別力の高い語であって,かつ上記のように「スニーカ ーを中心として展開されている異議申立人の業務に係るVANSブランド」という\n観念が指定商品の需要者である一般消費者の間に生じるものであるから,「VAN S」が固有の意味を有しないということはできず,原告の主張はその前提において 失当である。 さらに,上記5)についても,原告が挙げる商標の構成は,本件商標のそれとは異\nなっているから,原告が挙げる商標が登録されているからといって,それが本件商 標と引用商標との類否の判断に直ちに影響を及ぼすものとはいえず,原告の主張は 採用できない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.09.13
平成30(行ケ)10014 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年8月29日 知的財産高等裁判所
商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合 に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであ るが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によ って取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきで あり,かつ,その商品の取引の実情を明らかにしうる限り,その具体的な取引状況 に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43 年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。 また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の\n構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支\n配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識と しての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,当該部分だけを他人の商 標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである(最高裁昭和 37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1 621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・ 民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8 日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁)。
(2) 本願商標と引用商標1との類否
ア 本願商標は,前記第2の2(1)のとおり,「TENRYU」の欧文字を標 準文字で表したものであり,「テンリュー」の称呼が生じる。\nまた,上記称呼から,本願商標は,「天竜,天龍」を意味するものと理解するの が一般的であり,「天竜,天龍」からは「天の竜(龍)」の観念が生じるから,本 願商標からは「天の竜(龍)」の観念が生じる。
イ 引用商標1は,前記第2の2(3)のとおり,別紙記載1の商標であり,「テ ンリュー」の称呼が生じ,「天の竜(龍)」の観念が生じる。 ウ 本願商標と引用商標1とは,外観は異なるものの,称呼及び観念は同一 である。 そして,引用商標1は漢字を用いているのに対し,本願商標は欧文字を用いてい るが,引用商標1をローマ字で表記すると本願商標となることは明らかである。我\nが国においては,漢字を同じ称呼のローマ字で表記することは一般的に行われてい\nるという事情を考慮すると,文字種が異なることによる本願商標と引用商標1の外 観の相違は,両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるもの ではないというべきである。 以上の事情を総合考慮すると,本願商標は引用商標1に類似しているというべき である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.09. 7
平成28(ワ)15812 不正競争 民事訴訟 平成30年8月17日 東京地方裁判所(40部)
前記認定のとおり,アマゾン社は,平成27年12月4日に購入者 より本件商品1に関する真贋に関する連絡があったことを理由として, 原告商品の出品を停止し(甲20〜22),同月6日,複数の購入者か ら本件商品1及び3に関する真贋に関する連絡があったことなどを理 由として,原告の出品アカウントを停止した(甲5)。 他方,アマゾン社は,同様にジョレン本社から出品停止の要求を受け たセレブスタイルについては出品停止措置を採ったものの,出品アカ ウントの停止は行わず,カリフォルニアマートについては何らの措置 も採らなかったことは前記認定のとおりである。
原告商品の購入者のアマゾン社に対する連絡内容及び同社の調査内 容は明らかではないものの,前記のとおり,平成27年8月27日付 けのジョレン本社からアマゾン社への連絡文書(乙1の1)には本件 商品1(真正品)の外箱,容器等の写真が添付されており,アマゾン社 は真正品の外箱や容器等の外観を把握した上で原告商品に対する審査 を行ったと考えられることや,同種の製品を販売する上記三社のうち 原告に対して最も厳しい措置が採られていることを考慮すると,アマ ゾン社は,購入者からの連絡内容等を慎重に審査した上で原告商品が 真正品ではないとの判断に至ったものと考えられる。
これに対し,原告は,アマゾン社は,被告又はジョレン本社からの通 知内容に依拠してアカウント停止に及んだと主張するが,アマゾン社 が自社の運営・管理する本件サイトの利用者に対して出品アカウント 停止という厳しい措置を講じるに当たって,被告又はジョレン本社の 通知内容にそのまま依拠したとは考え難く,その基準に照らして慎重 に審査を行ったと推認するのが相当である。 そうすると,アマゾン社が原告に対し原告のアカウント利用停止措 置を講じたとの事実も,原告商品が真正品ではないことを示す事情で あるということができる。
e 以上を総合すると,原告商品はジョレン本社が製造,販売する本件 商品の真正品ではないものと推認するのが相当であり,これを覆すに 足りる証拠はない。 したがって,原告商品がジョレン本社の販売している真正品ではな い旨の本件記載1の記載が虚偽であるということはできない。
・・・・
被告は,原告が厚生労働省から必要な許認可を得ることなく原告商品 の販売を行っている旨の記載が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事 実の摘示であると主張するところ,調査嘱託の結果によれば,カリフォ ルニア州法に基づいて設立された法人である原告が,日本国内の消費者 に対し,米国内で仕入れた医薬部外品である本件商品を直接送付するこ とにより販売する行為は,医薬品医療機器法2条13項所定の「製造販 売」に該当しないため,同法12条1項所定の医薬部外品製造販売業許 可を得る必要はないものと認められる。そうすると,上記記載は,虚偽 の事実を摘示したものであり,これに接した一般人は,原告が関連法令 に違反している業者であるとの印象を受けると考えられるので,原告の 営業上の信用を害するものであるということができる。 これに対し,被告は,調査嘱託先と原告が事前に折衝を行い,事実と 異なる情報が提供されたことから,これを前提とする回答内容の信用性 を低いと主張するが,上記調査嘱託の回答者は嘱託書に記載された事実 に基づき,所管法令の解釈に関する見解を示したものであり,原告との 事前の折衝が当該回答に影響を及ぼしたとの被告主張は理由がない。
ウ 競争関係の有無について
原告商品と被告の販売する商品は,原告商品が真正品であるかどうかに かかわらず,いずれも日本国内の消費者を対象とし,その内容はクリーム ブリーチであることから,競争関係にあることは明らかである。
エ 小括
以上によれば,上記イ1)〜4)の各事実のうち,原告が厚生労働省から必 要な許認可を得ることなく原告商品の販売を行っている旨の事実(上記4)) の摘示は不競法2条1項15号にいう「他人の営業上の信用を害する虚偽 の事実の流布」に該当するが,その余の事実の摘示は同号の不正競争行為 には該当しないというべきである。
2018.08.29
平成30(行ケ)10037 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年8月23日 知的財産高等裁判所
(1) 使用商標は,「旧」の文字と「関西国際学友会日本語学校」の文字とを半 角又は全角の空白を介して結び,かつ全体を括弧で囲んで表したものである。
(2) まず,これらの文字は,書体も大きさも同一であり,全体が括弧で囲まれ ているものの,「旧」と「関西国際学友会日本語学校」とは,空白によって 明確に分離されていること,「旧」は,「昔。過去。」といった意味を有し, 「今は主流ではないもの,過去のものとなっていることを表す語」であり(広\n辞苑〔第7版〕),その後に続く語がかつて用いられていた名称等であるこ とを指し示すものとして一般的に多用されている語であること(乙5の1〜 5の5)からすると,使用商標に接した需要者は,「旧 関西国際学友会日 本語学校」の意味は,かつての名称が関西国際学友会日本語学校であったこ とにあると理解すると認められる。 続いて,「関西国際学友会日本語学校」の部分について検討する。 ア この文字部分中,「日本語学校」は,教育の分野において,日本語を教 授する教育機関又は施設を意味する一般的名称と認められ(甲7の1〜7 の8),一般通常人にとっても馴染みのある語というべきであるから,需 要者が「関西国際学友会日本語学校」の文字に接したときに,これは「関 西国際学友会」と「日本語学校」の各語を組み合わせたものであると理解 することは明らかである。
イ 次に,「関西国際学友会」についてみると,「学友会」の文字部分だけ をみれば,学生及び卒業生の交流を図る会ないし団体といった程度の一般 的な意味を有する語と解する余地があるものの,その前に「関西国際」が 付されていることを考え合わせると,これに接した需要者は,全体として, 関西地方に所在し又は同地方において活動している,国際的に学生等の交 流を図ることを目的として設立された特定の団体の名称であると理解する と認めるのが相当である。 また,上記のとおり,「日本語学校」は,日本語を教授する教育機関又 は施設を意味する一般的名称と認められるから,需要者は,「日本語学校」 の部分を,提供される役務の内容,又はその役務を提供する施設を示して いるものと理解し,当該部分が出所を表示する機能\を有するものであると は考えないと認めるのが相当である。
ウ 上記イにおいて説示した各語が有する意味合いに鑑みると,「関西国際 学友会日本語学校」は「関西国際学友会」が運営する「日本語学校」とい った程度の意味を有する語として理解されるというべきである。 そして,「関西国際学友会」と「日本語学校」とは,一体不可分の関係 にあると理解されなければならない語であるとは言い難い上に,「日本語 学校」は,日本語を教授する教育機関又は施設を意味する一般的名称であ るから,需要者は,使用商標中の「関西国際学友会日本語学校」につき, 「関西国際学友会」の部分が出所を示す機能を果たしていると認識すると\nいうべきである。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2018.08.29
平成29(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年8月22日 知的財産高等裁判所
前記で認定したような本願発明において,撹拌羽根 の形状,寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ,当初 明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし,当初明細書の 【0012】には,1)撹拌にET−3Aを用いること,2)「撹拌羽」は,回転中心 となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹\n拌羽」であること,3)「撹拌羽」の回転半径は,内容量が200mlで内径約6c mのビーカー等の円筒形容器の半径(約3cm)より僅かに小さいことが記載され ているところ,前記(1)イの事実によると,当初明細書に記載されている上記「撹拌 羽」の形状,寸法は,ET−3Aの付属品である200mlビーカー用の本件撹拌 羽根のそれと一致するものである。また,前記(1)イの事実によると,ET−3Aは, 昭和60年頃から長年にわたって販売されており,多数の当業者によって使用され てきたと推認される実験用の機械であるところ,販売開始以来,付属品である本件 撹拌羽根の形状,寸法に変更が加えられたことは一度もなく,しかも,遅くとも平 成17年7月頃には,本件撹拌羽根は,ET−3Aとともに日光ケミカルズのカタ ログに掲載されていた。さらに,当初明細書の記載に適合するような形状,寸法の ET−3A用の撹拌羽根が,ET−3A本体とは別に市販されていたことは証拠上 認められない。
以上の事実を考え併せると,当業者が,当初明細書等に接した場合,そこに記載 されている撹拌羽が,ET−3Aに付属品として添付されている200mlビーカ ー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そし て,特定事項aは,200mlビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するもの であるから,特定事項aを本願の請求項1に記載することが,明細書又は図面の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を 導入するものとはいえず,新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があ る。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2018.08.27
平成29(ワ)9989 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年7月19日 大阪地方裁判所(26部)
次に,「なが〜く使える」の出所識別標識力について検討するに,妊 産婦用商品の販売に際して,出産前だけ又は出産後だけに限らずその両方の期間に またがって使用できる商品であることの宣伝文句として,「産前産後」も「長く使 える」や「長〜く使える」という商品表示が原告商品や被告各商品以外の妊産婦向\n5 けの商品の宣伝にも多くの例でされてきていること(本件事実経過一覧表の青色で\n着色した部分参照)に照らせば,「なが〜く使える」の語は,出産前だけでなく出 産後も長期間使用できるという商品の性質を指す語として,出所識別標識力がない と認めるのが相当である(このことは,当事者間に争いがない。)。
(ウ) そうすると,「なが〜く使える マタニティベルト」との原告表示は,\nこのような商品の性質を表す語と商品の普通名称を組み合わせた語にすぎないから,\nそれが原告商品の商品表示として周知性を獲得したとしても,その出所識別標識力\nは,「なが〜く使える マタニティベルト」という一連の語としてのみ認められる ものというべきである。
(2) 被告各商品の商品表示との類否\n被告各商品パッケージの構成(別紙被告商品パッケージ目録参照)は,別紙被告\n商品表示目録(被告主張)記載1及び2のとおりのものであり,被告商品1の商品\n表示については,リング状の図形(左半分は赤色,右半分は青色)の中に,1段目\nに「長〜く使える」の文字を,2段目に「ピジョン」の文字を,3段目に「産前産 後」の文字(産前は赤色,産後は青色)を,4段目に「マタニティ」の文字を,5 段目に「ベルト」の文字を,6段目に「助産師推奨」の文字を配して構成されてお\nり,被告商品2の商品表示については,1段目に「ピジョン」の文字を,2段目に\n「長〜く使える」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(他の文字より大きく, かつ,連結した色の異なる2つの円形図形中に表示されている。)を,4段目に\n「マタニティベルト」の文字を配して構成されている,とそれぞれ認められる。\nこのような被告各商品パッケージの構成を被告各商品の商品表\示として捉える場 合,被告各商品の商品表示は,「長〜く使える」「マタニティベルト」の各語のほ\nかに,少なくとも「ピジョン」,「産前産後」の語が付加されている上,「ピジョ ン」の語は,育児用品等の製造販売を業とする被告が販売する商品の出所識別標識 として,取引者ないし需要者の間で広く認識された著名な表示である(「ピジョ\nン」や「PIGEON」の商標が日本有名商標集に掲載されていること〔乙42〕 や,原告被告双方から書証として提出された妊産婦向け雑誌の質,量は,これを裏 付けるに十分なものである。)から,原告表\示の出所識別標識力が「なが〜く使え る マタニティベルト」という一連の語としてのみ認められることを考慮すると, 両者は称呼及び外観を異にしており,類似するとはいえない。
また,原告が主張するとおり,被告各商品が「長〜く使える産前産後マタニティ ベルト」として宣伝広告され,紹介されていること(甲22及び25の各号,乙3 9の5ないし7)から,その商品表示を「長〜く使える産前産後マタニティベル\nト」として捉える場合であっても,原告表示の出所識別標識力が「なが〜く使える\nマタニティベルト」という一連の語としてのみ認められることを考慮すると,やは り両者は称呼及び外観を異にしており,類似するとはいえない。 したがって,いずれにせよ,被告各商品の商品表示が原告表\示と類似するとはい えない。 なお,被告各商品の商品表示を「長〜く使えるマタニティベルト」と捉えること\nについては,被告各商品パッケージの構成において「産前産後」の文字が「長〜く\n使える」の文字と「マタニティベルト」の文字との間に他と比べて大きく目立つ態 様で配置されていることや,被告各商品の上記宣伝広告や紹介においても「長〜く 使える産前産後マタニティベルト」との表示が使用されていることから,「長〜く\n使える」の文字と「マタニティベルト」の文字のみを抽出・連結して,「長〜く使 えるマタニティベルト」を被告各商品の商品表示と捉えることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.08.27
平成30(ネ)10023 著作権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成30年8月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,本件映画において,本件使用部分においても,エンドクレジ ットにおいても何ら出所表示をすることなく本件各映像を利用したことが「公正な慣行」に合致しないとして引用の抗弁(著作権法32条1項)を\n認めなかった原判決の認定判断に誤りがあると主張する。 よって検討するに,本件映画において,被控訴人が報道用として編集管 理する本件各映像がその著作権者である被控訴人の名称を全く表示することなく,無許諾で複製して使用されている事実は当事者間に争いがないと\nころ,もともと出所の明示は引用者に課された著作権法上の義務(著作権 法48条1項1号)である上に,本件の場合,本件映画中の控訴人製作部 分と本件使用部分とは,原判決が指摘するとおり,画面比や画質の点にお いて一応区別がされているとみる余地もあり得るとはいえ,映画の中で, これらの部分が明瞭に区別されているわけではなく,その区別性は弱いも のであるといわざるを得ないから,本件使用部分が引用であることを明ら かにするという意味でも,その出所を明示する必要性は高いものというべ きである。また,本件のようなドキュメンタリー映画の場合,その素材と して何が用いられているのか(その正確性や客観性の程度はどのようなも のであるか)は,映画の質を左右する重要な要素であるといえるから,こ の観点からしても,素材が引用である場合には,その出所を明示する必要 性が高いものと考えられる。他方,本件においては,引用する側(本件映 画)も引用される側(本件各映像)も共に視覚によって認識可能な映像であって,字幕表\示等によって出所を明示することは十分可能\であり,かつ,そのことによって引用する側(本件映画)の表現としての価値を特に損なうものとは認められない。これらのことに,原判決が指摘する「公正な使\n用(フェア・ユース)の最善の運用(ベスト・プラクティス)についての ドキュメンタリー映画作家の声明」(乙17)の内容等を併せ考えると, 適法引用として認められるための要件という観点からも,本件映画におい て本件各映像を引用して利用する場合には,その出所を明示すべきであっ たといえ,出所を明示することが公正な慣行に合致し,あるいは,条理に 適うものといえる。そして,このことは,本件映画の総再生時間が2時間 を超えるのに対し,本件各映像を使用する部分(本件使用部分)が合計3 4秒にとどまるといった事情や,本件各映像が番組として編集される前の 映像であるといった事情によっては左右されない。 したがって,控訴人が何ら出所を明示することなく被控訴人が著作権を 有する本件各映像を本件映画に引用して利用したことについては,(単に 著作権法48条1項1号違反になるというにとどまらず)その方法や態様 において「公正な慣行」に合致しないとみるのが相当であり,かかる引用 は著作権法32条1項が規定する適法な引用には当たらない。よって,こ れと同旨をいう原判決の認定判断に誤りがあるとは認められない。 イ これに対し,控訴人は,1)「公正な慣行」の立証責任を利用者の側に負 わせるべきではない,2)本件における引用の抗弁の成否に関しては,被控 訴人が本件各映像の利用を許諾しなかった理由(不許諾理由)こそが考慮 されてしかるべきである,3)エンドクレジットへの掲載は賛辞を意味する という「公正な慣行」が存在するため,控訴人としては,許諾申請が拒否された以上,被控訴人の許諾があったかのような記載を避ける必要があっ\nた,4)そもそも出所を明示していないことを理由に引用の抗弁を退けるこ と自体が誤りである,などと主張する。 しかしながら,次のとおり,上記各主張はいずれも採用できない。 上記1)について,著作権法32条1項は,飽くまで著作権行使の制限規 定である以上,その適用については,基本的に適用を主張する側が要件充 足の主張立証責任を負うものと解するのが相当である
◆判決本文
原審は以下のように判断しました。
◆平成28(ワ)37339
(3) 本件映画と本件各映像(本件使用部分)との関係についてこれをみると,本
件映画は,資料映像・資料写真とインタビューとから構成されるドキュメンタリー映画であり,その中で資料映像として使用されている本件各映像は,テレビ局であ\nる原告の従業員が職務上撮影した報道映像である。
そして,本件映画のプロローグ部分のうち,被告制作部分は,画面比が16:9
の高画質なデジタルビデオ映像であり,他方,本件使用部分は,画面比が4:3で
あり,被告制作部分に比して画質の点で劣っているから,被告制作部分と本件使用
部分とは,一応区別されているとみる余地もある。
しかし,本件映画には,本件使用部分においても,エンドクレジットにおいても,
本件各映像の著作権者である原告の名称は表示されていない。被告は,上記のとおり本件映画において原告の名称を表\示しない理由について,映像の出所は劇場用映画などからの引用の場合以外は表記しないとか,資料写真の出所は写真家の名前を伝える必要がある場合に限って表\記するなど,制作上の方針を主張するにとどまり,本件映画のようなドキュメンタリー映画の資料映像として
報道用映像を使用するに際し,当該使用部分においても,映画のエンドクレジット
においても著作権者の名称を表示しないことが,「公正な慣行」に合致することを認めるに足りる社会的事実関係を何ら具体的に主張,立証しない。被告が提出する\n乙第17号証は,「公正な使用(フェア・ユース)の最善の運用(ベスト・プラク
ティス)についてのドキュメンタリー映画作家の声明」であり,フェアユースに関
する規定を有する米国著作権法を念頭に置いたものであるが,同声明においても,
「歴史的シークエンスにおける著作物の利用」に関し,「この種の利用が公正であ
るという主張を支持するためには,ドキュメンタリー作家は以下の点を示すことが
できねばならない。」として,「素材の著作権者が適切に明確化されている。」と
されており,何らかの方法により素材の著作権者を明確化することを求めているの
である。
実質的にみても,資料映像・資料写真を用いたドキュメンタリー映画において,
使用される資料映像・資料写真自体の質は,資料の選択や映画全体の構成等と相俟って,当該ドキュメンタリー映画自体の価値を左右する重要な要素というべきであ\nるし,テレビ局その他の報道事業者にとって,事件映像等の報道映像は,その編集
や報道手法とともに,報道の質を左右する重要な要素であり,著作権法上も相応に
価値が認められてしかるべきものであるから(著作権法10条2項が,報道映像に
つき著作物性を否定する趣旨でないことは,その規定上明らかである。),ドキュ
メンタリー映画において資料映像を使用する場合に,そのエンドクレジットにすら
映像の著作権者を表示しないことが,公正な慣行として承認されているとは認め難いというべきである。\nそうすると,総再生時間が2時間を超える本件映画において,本件各映像を使用
する部分(本件使用部分)が合計34秒にとどまることを考慮してもなお,本件映
画における本件各映像の利用は,「公正な慣行」に合致して行われたものとは認め
られない。
したがって,著作権の行使に対する引用(著作権法32条1項)の抗弁は成立し
ない。
2018.08.24
平成27(ワ)1190 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年5月29日 東京地方裁判所(46部)
前記前提事実・・によれば,1)本件実施発明が平成8年5月から平成 13年3月までの間に発明の報告がされたこと,2)被告がFN社を設立し, 対象実施権を含む知的財産権のライセンス事業その他のFeliCa関連事 業を行わせていることが明らかである。
(3)ア 使用者が特許を受ける権利を承継して特許が登録された場合に,使用者 が発明の実施等によって利益を受けたことによって相当の対価を算定する 場合には,「使用者等が貢献した程度」(旧法35条4項)として,発明が されるについての使用者の貢献度のほか,実施品の売上げを得たことに対 する使用者の貢献度等の諸事情を総合的に考慮して,相当の対価を算定す ることが相当というべきである。
イ 上記(1)及び(2)の事実関係に加え,前記前提事実(3)及び前記3(2)エ(ア)のと おりの本件実施発明の内容及び意義によれば,本件実施発明は,被告入社 前からコンピュータ等について知見を有していた原告が,その知見を活用 し努力及び創意工夫をすることにより着想した面がある。 もっとも,被告においては昭和60年代から無線ICタグの開発がされ て,A発明がされ,その後もAが率いる無線ICタグの研究チームで研究 が続けられていて,原告も同チームに属していた。上記の着想の背景には, 原告が,被告による費用負担の下で,被告入社後にOSやコンピュータの 開発を行って知識経験を獲得し,また,被告における無線ICタグの開発 チームに所属して,その開発チームによる技術的蓄積に触れていたことが あったともいえる。そして,被告として製品を納入することを検討してい た案件において,発注者から細かな仕様が要求されたところ,本件実施発 明は,それらの要求に応じる製品の開発の過程において着想され,具体化 されたという面もある。
その後,被告製品が鉄道事業者等に多数納入されることとなるが,製品 化に当たっては,新たに各種の開発が必要であったのであり,被告におい ては,相当数の被告の従業員がその開発を行った。また,継続的なシステ ムにも関わり得るという被告製品の性質上,被告製品の導入に当たっては 一般的に発注者がその供給等についての継続性や大量の製品の供給可能性等を重視する場合も多いといえるが,その際には企業としての被告の実績,\n規模等が影響したことが推認できる。その他,被告とJR東日本等との契 約に基づく共同開発その他の過程を経て,被告製品が開発されて被告製品 が多数納入される環境が構築され,また,FN社やビットワレット株式会社の設立及びその後の事業の運用により電子マネーその他の鉄道の改札以\n外の用途が確立し,カードの利便性が高められて被告製品の販売数が向上 したということができる。被告においては,相当額の投資を行い,こうし た需要や顧客の要望に応え得る被告製品の生産体制の確立も行われた。加 えて,FeliCaのシステムは,暗号方式の変更等の改良が継続的に加 えられるなど,被告が継続的に技術的な改良等を行い,被告製品の売上げ が維持されている面もある。これらのことは,発明者以外の被告の従業員 等の関与があって初めて実現し得ることである。
ウ 被告の貢献度に関し,原告は,開発チームの一員として又はFeliC a事業部長として上記発注者や担当者らとの交渉や被告製品の活用方法の 提案等を行っていたこと,被告が原告の提案を受け入れなかったために本 来得られる利益を得られなかったことなどを主張する。 しかし,職務発明の発明者の行動のうち,営業面,販売面における行動 は,発明者しか行うことができない行動であれば格別,基本的には発明者 もその一員である従業員としての貢献として考慮されるものといえる。そ の他,原告は,A発明が被告製品において実施されていない上に特許の無 効理由を有するなどとも主張するが,少なくとも上記に述べた理由により, 本件実施発明がされるまでの間における被告の研究等の活動は,使用者の 貢献として考慮されるといえる。 なお,証拠(乙184)によれば,原告は,平成11年に41歳で統括 部長に,平成13年に事業部長に,平成14年にFeliCa開発・技術 部門の部門長に就任し,平成15年4月から平成17年7月の退職時まで 情報技術研究所の統括部長の地位にあり,また,上記各就任時の原告の年 齢は上記各地位の平均年齢よりも若く,特に部門長に就任した際は5歳以 上若かったと認められ,従業員等としての貢献に対しても相応の待遇を受 け,給与及び退職金についても高い処遇を受けていたといえる。
●省略●
(4) 以上の事情その他本件に現れた全事情を総合考慮すると,本件実施発明の 実施に係る相当の対価の算定に当たっての被告の貢献度は大きなものであり, その割合は95%と認めるのが相当である。
2018.08.24
平成29(ワ)14637 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年7月26日 東京地方裁判所
平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は15 日から)平成29年3月22日までの間の被告ウェブページのタイトルタ グ及びメタタグ並びに被告ウェブページにおける被告標章1及び2の使用 )について
証拠(甲19)及び弁論の全趣旨によれば,被告グレイスランドは,平成28年11月15日から平成29年3月22日までの間,被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに別紙1−1のタイトルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載したこと,その記載によって「楽天市場」のウェブサイトで「タカギ」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した場合の検索結果の表示画面において,被告商品の写真が表\示されるとともにその横に「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ浄水器カートリッジ 浄水カートリッジ(標準タイ...」といった,被告商品の種類に対応したタイトル(上記タイトルタグ冒頭の【楽天市場】を省略した記載の冒頭部分又は上記メタタグの記載の冒頭部分と同一内容のもの)が表示されたこと,それらのタイトルの下には「グレイスランド」,「楽天市場店」と表\示されたこと,それらのタイトル部分を選択することで当該種類の被告商品を販売する被告ウェブページに移動することができたこと,その検索結果の表示画面においては上記のほかにタイトルタグに記載された説明は表\示されず,メタタグに記載された説明も表示されなかったことの各事実が認められる。\n
また,証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば,上記の平成28年1 1月15日から平成29年3月22日までのタイトルタグ及びメタタグの 記載により,一般の検索サイト(Google)において「タカギ」,「浄 水器」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した場合の検索 結果の表示画面に「【楽天市場】タカギ 取付互換性のある交換用カート リッジ 浄水器カートリッジ..」といった被告商品の種類に対応したタイ トルが表示され,その下に上記タイトルより小さい文字で被告商品の種類\nに対応して「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カー トリッジ 浄水カートリッジ(高除去タイプ)※当製品はメーカー純正品 ではございません。ご理解の上,お買い求めください。」といった表示が\nされたこと,それらのタイトル部分を選択することで当該種類の被告商品 を販売する被告ウェブページに移動することができたこと,その検索結果 の表示画面のタイトル部分には上記表\示のほかにはタイトルタグに記載さ れた説明は表示されなかったことの各事実が認められる。\n 以上のとおり,平成28年11月15日から平成29年3月22日まで の間,タイトルタグ及びメタタグの記載によって,検索結果を表示するウ\nェブサイトにおいて,タイトルとして被告標章1又は2が表示され,その\n後に空白部分があり,さらにその後に商品の品名が表示されたり,説明と\nして被告標章2が表示され,その後に空白部分があり,さらにその後に商\n品の品名や説明が表示されたりした。このような態様での被告標章1及び\n2の使用は,写真や品名で説明される商品の出所を示すものであると認め ることが相当である。そして,タイトルタグやメタタグにおける記載によ って,ウェブサイトにおいて上記のような表示がされ,同サイトを閲覧し\nた者もその表示を見ることができることに照らすと,タイトルタグやメタ\nタグにおいて,被告標章1及び2は,商品を表示する商品等表\示として使 用(不競法2条1項1号)されたものと認められる。また, とおり,被告ウェブページにおいて,被告商品を購入するために商品選択 をする部分にも,別紙2−1のウェブサイトの記載欄のとおり,上記と同 様に,「タカギ」との被告標章2が表示され,その後に空白部分があり,\nさらにその後に商品の品名や説明が表示されており,これらの表\示も商品 の出所を示すものであると解するのが相当である。 これに対し,被告らは,「取付互換性のある交換用カートリッジ」,「当 製品はメーカー純正品ではございません」等といった表示があることや被\n告ウェブページ上における被告商品の外観写真が原告の純正品とは異なる ものであることなどを挙げて,タイトルタグ,メタタグ,被告ウェブペー ジにおいて,被告標章1及び2は商品の出所を表示するものとして使用さ\nれていない旨主張する。しかし,上記のとおり,被告標章1及び2の後に 空白部分があり,さらにその後に商品の品名等が記載されているという表\n示の態様,「互換性」という用語は製造販売者が同じ商品間でも用いられ ること(甲46),検索結果の表示画面において表\示される内容やそこで の説明の文字の大きさ,当該商品の性質やウェブページでの表示であるこ\nとに鑑み需要者は全ての記載を注意深く観察しない可能性が相当程度ある\nことなどに照らし,被告らの主張は採用することができない。
イ 平成29年3月23日以降の被告ウェブページのタイトルタグ及びメタ タグ並びに被告ウェブページにおける被告標章1及び2の使用(前提事実 及び 並びに証拠(甲20ないし22)及び弁論の全趣旨によれば,被告グレイスランドは,平成29年3月23日以降,被告ウェブ ページのタイトルタグ及びメタタグに別紙1−2(同年4月12日まで) 並びに同1−3及び1−4(同月13日から)のタイトルタグ欄及びメタ タグ欄のとおり記載したこと,その記載によって「楽天市場」のウェブサ イトで「タカギ」,「カートリッジ」という語をキーワードとして検索した 場合の検索結果の表示画面に被告商品の写真及びその横に「タカギに使用\n出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ(標準タイプ)※ はメーカー純正...」,「【標準タイプ1本パック】タカギの浄水器に使用で きる,取付け互換性のある交換用カートリッジ。...」といった被告商品 の種類に対応したタイトル(上記タイトルタグ冒頭の【楽天市場】を省略 した記載の冒頭部分又は上記メタタグの記載の冒頭部分と同一内容のもの) が表示されたこと,それらのタイトルの下には「グレイスランド」,「楽天\n市場店」との表示がされたこと,それらのタイトル部分を選択することで\n当該種類の被告商品を販売する被告ウェブページに移動することができた こと,その検索結果の表示画面には上記表\示のほかにはタイトルタグに記 載された説明は表示されず,メタタグに記載された説明も表\示されなかっ たことの各事実が認められる。以上のとおり,平成29年3月23日以降, タイトルタグ及びメタタグの記載によって,検索結果を示すウェブサイト に上記のとおりの表示がされ,また,ウェブサイトによっては,検索結果\nの表示画面に別紙1−2,1−3,1−4のメタタグ欄記載の説明が表\示 されることになったと推認されるが,それらにおいては,いずれも「タカ ギ」というカタカナ3文字の後に「に」又は「の」という助詞が付加され, 当該商品が原告商品に対応するものであるという,商品内容を説明するま とまりのある文章が表示されている。\nそして,このような表示内容に照らせば,需要者が上記の表\示に接した場合には,それらにおける「タカギ」との表示は,当該商品が対応する商品を示すものであると受け取り,当該商品自体の出所を表\示するものであると受け取ることはないと認められる。 そうすると,平成29年3月23日以降のタイトルタグ及びメタタグにお いて,被告標章1及び2は不競法2条1項1号にいう商品等表示として使\n用されたものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.08.10
平成29(行ケ)10218 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年8月9日 知的財産高等裁判所
引用発明1はコンピュータ上の対話型処理を行うシステムである。また,当業者 は,本願出願日時点において,コンピュータ上の対話型処理システムである引用発 明1には,コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」という周知の課題が あることを理解し,引用発明1の通信端末に,キャラクタが動いているような表示\nをするとの周知の解決手段の適用を試みるということができる。 一方,引用発明2はコンピュータ上の対話型処理を行うナビゲーション装置であ る(引用例2【0038】【0050】【0051】)。また,引用発明2は,表\n示装置にエージェントを表示し,回答時に当該エージェントの口が開くというもの\nであるから,当業者は,かかる構成を,コンピュータによる対話型処理の「円滑化\nを図る」という周知の課題を解決するための,周知の解決手段の一つ,すなわち通 信端末にキャラクタが動いているような表示をする構\成の一つであると理解する。 そうすると,引用発明1に上記周知の課題があることを認識し,これに上記周知 の解決手段の適用を試みる当業者は,同じ技術分野に属し,かかる課題を解決する 手段である引用発明2を,引用発明1に適用することを動機付けられるというべき である。
ウ 原告の主張について
(ア) 原告は,周知の課題として「メディアコミュニケーションの円滑化を図る」 などと認定することは,課題を殊更に上位概念化するものであると主張する。 しかし,引用発明1及び2は,いずれもコンピュータ上の対話型処理システムの 技術分野に関するものである。そして,このような技術分野に関する前記各文献に は,「ユーザが自然に計算機へ音声入力できる雰囲気」(周知例1・97頁),「反 応のない機械に対して発話するために間が掴み辛い」(甲6【0002】),「ユ ーザと電子機器とがコミュニケーションを取り易い環境を構築」(乙9【0019】),\n「人間を相手にしているかのような自然なコミュニケーションを通じた情報入力」 (乙10【0008】),「より自然な対話を実現」(乙11・31頁右欄)など と,コンピュータ上の対話型処理システムにおいて,対話型処理の「円滑化を図る」 必要性が複数指摘されている。 したがって,本願出願日時点において,コンピュータによる対話型処理の「円滑 化を図る」ことは,周知の課題であったと認定することができ,これは課題を殊更 に上位概念化するものということはできない。
(イ) 原告は,引用例1には本件補正発明の課題が記載されていないから,当業 者には,引用発明1に基づき相違点に係る本件補正発明の構成に到達しようという\n動機付けがないと主張する。 しかし,前記のとおり,引用発明1及び2は,コンピュータ上の対話型処理シス テムの技術分野に関するものであって,このような技術分野では,本願出願日時点 において,コンピュータによる対話型処理の「円滑化を図る」ことは周知の課題で あったものである。そして,本件補正発明は,システム上で仮想オペレータとユー ザが対話を行うというものであり(本件補正明細書【0001】【0046】), コンピュータ上の対話型処理システムの技術分野に関するものであるから,本件補 正発明は,引用発明1及び2と同様に,上記周知の課題を含むものである。また, そもそも,引用発明1を出発点として本件補正発明の構成に到達するか否かを検討\nするに当たり,引用発明1が本件補正発明の課題を必ず有していなければならない ということはできない。 したがって,引用例1には本件補正明細書に記載された本件補正発明の課題と同 じ課題が記載されていないから動機付けを欠く,との原告の主張は採用することが できない。
(4) 引用発明2を適用した引用発明1の構成
ア 前記(2)ウ(ウ)のとおり,引用発明2には,「現実の事業者のオペレータを模 造した人物を表示装置に表\示するナビゲーション装置において,当該模造した人物 が話しているように表示するため,待機中と比較して,回答側センターの応答音声\nデータをスピーカから出力させる際に,当該模造した人物の口を開くように当該模 造した人物を表示すること。」との具体的な構\成が含まれている。 イ 一方,本件補正発明の構成は,通信端末において,回答メッセージ等を再生\nする際,これを再生しない時と比較し,仮想オペレータの「一部が大きな動作を行 うように」仮想オペレータを表示するというものである。そして,仮想オペレータ\nの一部の大きな動作がどのようなものであるかについて,本件補正明細書において 何ら特定されていない。 また,仮想オペレータの一部の大きな動作について,本件補正明細書【0071】 には,「仮想オペレータの口や目を動かすようにしてもよい。あるいは手を動かす など,説明を行うジェスチャーをするようにしてもよい。すなわち,メッセージが 再生されていない時と比較し,仮想オペレータの一部がより大きな動作を行うよう にプログラムを構成してもよい。」と記載されている。したがって,待機中と比較\nして模造された人物が「口を開く」との構成は,本件補正発明における「一部」の\n「大きな動作」に含まれるものである。 さらに,仮想オペレータの一部が大きな動作をすることによって得られる効果に ついて,本件補正明細書【0072】には,「音声合成技術を活用して仮想オペレ ータと対話するため,ユーザは無機質な対話を強制されることなく,自然な対話を 行うことができる」と記載されている。もっとも,「自然な対話」の程度について は何ら特定されておらず,回答時に模造された人物が「口を開」けば,回答時にお いても待機中と同様に口を閉じている場合と比較して,円滑なコミュニケーション が図られているような印象を与えることができる。したがって,回答時に模造され た人物が「口を開く」との引用発明2の構成によって,「自然な対話を行う」とい\nう本件補正発明の効果を奏することができる。
ウ したがって,引用発明2における前記具体的な構成を引用発明1に適用すれ\nば,本件補正発明の構成に至るというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.08.10
平成29(ワ)30499 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年7月30日 東京地方裁判所
上記イのとおり,原告各商品は,裾に向かって若干広がったノースリーブブラウス にフリル袖を縫い付けたブラウスであるが,ノースリーブブラウスの部分には特徴的 な点はないから,原告各商品のうち,特徴的であり需要者の目を引く部分は,フリル 袖であるといえる。 そこで,袖について検討すると,原告各商品と被告各商品は,いずれもノースリー ブに縫い付けられフリルを設けたものである点で共通するものの,上記相違点1)のと おり,フリル袖の広がり及びフリルのボリュームの相違という袖形状の相違は,袖全 体の形状であり着用時も含めて需要者の印象を大きく左右するものであるから,その 相違の程度が些細なものであるとはいえず,形態の全体的な印象に影響を及ぼすもの といえる。また,原告各商品と被告各商品には,黒いリボンの有無という相違がある。 原告各商品の黒いリボンは,正面から見たときに見える部分に付されており,袖の長 さからはみ出す長さであるから,ブラウスの装飾として存在感があり,フェミニンさ を強調するものである。さらに,地色が淡い原告商品3(オフホワイト色)及び原告 商品4(白地に黒のギンガムチェック)においては,黒いリボンの存在は更に印象的 である。したがって,リボンの有無は,全体的な印象を左右するものであるといえる。 以上によれば,需要者の着目するフリル袖の部分に上記相違(相違点1))があるか ら,商品全体の形態として対比した場合に,原告各商品と被告各商品が全体として酷 似しているということはできない。よって,被告各商品の形態は,原告各商品の形態 と実質的に同一であると認めることはできず,これに反する原告の主張はいずれも採 用できない。
2018.08. 6
平成30(行ケ)10007 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年6月21日 知的財産高等裁判所
(1) 商標法4条1項7号が規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,1)その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,2)当該商標の構成自体が用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,3)他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されていることにより,同号該当性が認められる場合,4)特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合のほか,5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合などが含まれるものと解される。本件商標に関していえば,上記1)ないし4)に該当しないことは明らかであるから,以下,上記5)の場合に該当するか否かについて検討する。
(2) この点につき,原告は,長男Aは親族間で共有していた共有商標1ないし 3を故意に消滅させ,その上で,これを独占する意図で本件商標の登録出願 を行ったものであり,かかる行為は,長男Aと長男A以外の共同権利者との 間の信義則上の義務違反となるのみならず,適正な商道徳に反し,著しく社 会的妥当性を欠く行為というべきであるから,本件商標は商標法4条1項7 号に規定する商標に該当し,その商標登録は同号の規定に違反してされたも のとして無効にされるべきである旨主張する。 確かに,長男Aは,「千鳥屋」のグループ企業を営む経営者同士で共有し その事業で使用していた共有商標1ないし3を事実上代表して管理する立場\nにありながら,存続期間を更新するために必要な手続(書換登録申請)を取\nらずにその権利を消滅させる傍らで,共有商標1ないし3と構成をほぼ同じ\nくする長男商標1ないし4や本件商標を単独で出願してその登録を得ており, かかる行為の外形のみに着目すれば,本件出願は,商標の独占を図った不当 な出願であって,適正な商道徳に反し,著しく社会的妥当性を欠く行為であ るとの評価を行うことも全くあり得ないことではないと考えられる。
(3) しかしながら,他方で,長男Aが単独で本件出願を行った目的や経緯につ いてみると,本件においては,次のような事情が認められる。 すなわち,その目的や経緯について,被告らは,本来であれば,Fの相続 人間で本件商標を含む権利関係を処理する必要があったが,長男Aは,これ までのFの相続に関する紛争の経過や,三男Cによる単独での商標登録出願 の動き等から事前協議による解決は困難であると判断し,自ら単独で権利を 取得した後に改めて「千鳥屋」グループの事業に関連する兄弟及びその関係 者(本件4者)間での共有に移そうと考えたものであり,決して本件商標等 の独占を図ったものではない旨を主張している。 しかるところ,確かに,Fの遺産相続に関しては,「千鳥屋」の事業を行 う長男Aら兄弟4名とそれ以外の相続人3名との間でも,また長男Aら兄弟 間においても,必ずしも円滑に協議が進んでいなかったことがうかがわれ(甲 20及び21は,Fの遺産分割調停に係る調停調書であり,平成9年の調停 申立てから平成15年の調停成立まで約6年を要していることが分かる。ま\nた,乙5及び6は,「千鳥屋」の内紛を報じる報道記事であり,経営者一族 間で「(Fの)遺産相続を巡りトラブルが発生」していることや,「兄弟7 人が骨肉の争いを演じ」ていることが記載されている。),三男Cに関して も,Fの死後,独自に「千鳥屋宗家」の商標登録出願をしたり(乙7),長 男Aが経営する総本家の商号と類似する「千鳥総本家」の商標登録出願をし たり(乙11),長男Aが事業を営む地域(東京)に関連する「江戸千鳥」 (乙12)や,二男B及び四男Dが事業を営む地域(福岡)に関連する「博 多千鳥」(乙13)の商標登録出願を行ったりするなど,実際に,他の兄弟 との間で緊張を生じさせかねない動きがあったことがうかがわれる。 なお,平成13年には,「西村千鳥屋」なる登録商標(登録第19219 33号)につき,Fの持分を長男Aら兄弟4名に移転する持分移転登録申請\nがされ,平成18年には,「チロリアン」なる登録商標(登録第70755 8号)につき,長男Aら兄弟4名の申請で書換登録申\請がされ,いずれもI 弁理士が申請人代理人となっている事実が認められるが(甲13,22),\nこれらは飽くまで共有商標1ないし3とは異なる商標に関する手続であって, 利害関係が全く同一であるとはいえないし,Fの遺産分割に関する相続人間 の協議が全体として円滑に進んでいなかったことは上記のとおりであるから, これらの事実をもってしても,被告らの主張が全面的に信用できないことに はならない。 また,長男Aは,本件商標等の取得後,少なくとも,本件商標に関してい えば,実際に,長男A(総本家)の関係者である被告Y1のみならず,二男 Bの経営する被告総本舗,四男Dの関係者である被告Y2の3者間の共有名 義に移しており,原告に対しても,I弁理士を通じて,他の長男商標等を含 めて,最終的に「J家関係の4者」のみでの共有とする意思があることを表\n明している(これらは,権利の独占とは明らかに反する行動であるといえる。)。 そして,被告総本舗の代表取締役であり二男Bの関係者であるGと,四男D\nの関係者(千鳥屋本家の代表者)である被告Y2が,長男Aの方針に理解を\n示して,長男Aによる本件商標等の出願及び商標登録を承認するとの意向を 示していることも,前記認定のとおりである。 さらに,現時点において本件商標権を共有する被告Y1,被告総本舗及び 被告Y2や,長男商標1ないし4を保有する総本家や長男Aが,原告及びそ の関係者に対し,これらの商標の使用を禁止するような動きは,証拠上一切 うかがわれない。 これらの事情を総合すると,被告らが主張するところもあながち不合理と はいえず,首肯できる面があるというべきである。 そうであるとすれば,原告が主張する点を考慮しても,なお,長男Aによ る本件商標の登録出願(本件出願)が,本件商標の独占を図る意図の下に行 われたと認めるには足りないというべきであり,ほかに本件商標が前記5)の 場合に該当するというべき事情は特に見当たらない。
(4) 以上によれば,本件商標は商標法4条1項7号に該当するとはいえず,こ の点に関する審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.07.31
平成30(行ケ)10004 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年7月25日 知的財産高等裁判所
被告商品の雑誌等の出版物への掲載状況をみると,前記(1)ウ(イ) のとおり,被告商品は,1990年(平成2年)から2013年(平成 25年)ころまでの間,家具に関する書籍,照明に関する雑誌・カタロ グ,インテリア雑誌,ファッション雑誌,経済雑誌等の多数の出版物に おいて,被告商品の形態(立体的形状)が認識できるような写真と共に 紹介されており,その基本的な内容は,被告商品は,20世紀を代表す\nるデザイナーであるヘニングセンが1958年にデザインし,被告が販 売する世界のロングセラー商品であり,そのデザインが優れていること を強調するものといえる。
エ 前記イ及びウで認定した被告商品の販売状況及び広告宣伝状況に加えて, 被告商品は,平成9年度通商産業省選定グッド・デザイン外国商品賞(イ ンテリア用品部門)を受賞し,平成24年には高等学校の教科書において, 被告商品の写真と共に,「モダンデザインの代表的ペンダント PH5… ポール・ヘニングセン」として掲載されたこと(前記(1)エ)を総合すると, 被告商品は,その販売が開始された1976年(昭和51年)当時,その 2層目から5層目が組み合わさった形状において,他のランプシェード商 品には見られない独自の特徴を有しており,しかも,被告商品が上記販売 開始後本件商標の登録出願日(平成25年6月14日)までの約40年間 にわたり全国的に継続して販売され,この間被告商品のデザインを印象づ けるような広告宣伝が継続して繰り返し行われた結果,本件商標の登録出 願時までには,被告商品が日本国内の広範囲にわたる照明器具,インテリ アの取引業者及び照明器具,インテリアに関心のある一般消費者の間で被 告が製造販売するランプシェードとして広く知られるようになり,被告商 品の立体的形状(引用商標)は,周知著名となり,自他商品識別機能ない\nし自他商品識別力を獲得するに至ったものと認められる。 そうすると,引用商標が被告商品に長年使用された結果,引用商標は, 本件商標の登録出願時及び登録査定時(登録査定日・同年12月27日) において,被告の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本\n国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められる。
・・・
加えて,原告は,平成25年2月当時,被告商品を元にできるだけ忠実 に復刻生産したランプシェードの商品(原告商品)を「ポール・ヘニング センPH5」のリプロダクト品として原告のウェブサイト上で販売してい たこと(前記(1)ア及びイ)を併せ考慮すると,原告は,本件商標の登録出 願時(同年6月14日)において,被告商品は,ヘニングセンがデザイン した被告が製造販売する商品であること及び被告商品の立体的形状(引用 商標)について十分に認識していたことが認められる。\n
◆判決本文
関連事件です。こちらは19号違反なしと判断されました。上記案件とは商標が異なります。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 立体商標
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2018.07.26
平成30(行ケ)10029 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年7月19日 知的財産高等裁判所
電子掲示板に係る事業は,電子掲示板の名称等の商標のほか,ドメイン 名を使用する権利,電子掲示板に表示される広告に関する契約及びインタ\nーネットサービス提供に関する契約を含む複数の財産を用いて行われてい るものであるから,電子掲示板に係る事業を譲渡するに当たっては,これ らの複数の財産を移転し,その対価を支払うことを内容とする合意をする のが通常であるところ,本件事業譲渡の合意の具体的な内容は明らかでは ない。 そして,事業譲渡をするに当たっては,移転の対象となる具体的な財産 を特定し,事業譲渡の対価を定めるほか,対価の履行期及び履行方法,譲 渡の対象となる財産の移転方法(第三者の承諾等を要する場合にはその手 続の履行期及び履行方法等)を定めるのが通常であり,移転の対象となる 財産の内容によっては事業譲渡の基準日時点での債権債務の処理について 定める場合も考えられる。さらに,本件事業譲渡のように,当事者の一方 が法人である場合には,なおさら慎重な手続がとられるのが一般であるし, 本件事業譲渡は渉外法律関係を含むから準拠法の問題を生じ得ることから しても,口頭のみで契約を行うことは考えにくい。以上に照らせば,本件 事業譲渡につき契約書等の書面を作成せずに契約を締結するとはにわかに 考え難いというべきところ,本件事業譲渡に係る契約書等の処分証書の提 出はない。
イ また,本件記事において,1) 平成24年12月に,被告が本件電子掲 示板上の違法薬物に関する書き込みを放置したとして検察庁に送致された 旨,2) 平成25年3月に,本件電子掲示板上の違法薬物に関する書き込 みの削除措置がとられたために被告が不起訴処分となった旨,3) 同年8 月に,被告が本件電子掲示板に係る高額の広告収入をパケットモンスター 社から受領したとして東京国税局から指摘を受けた旨が記載されており(上 記1(7)),これによれば,被告は,平成21年1月以降も本件電子掲示板 の運営を含む本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していたことがう かがわれる。
ウ 以上のとおり,本件事業譲渡の合意の具体的な内容が明らかでないこと, 本件事業譲渡に係る契約書がないのはそれ自体不自然であること,本件事 業譲渡がされたという時期以降も被告が本件電子掲示板に係る事業に実質 的に関与していたことがうかがわれることに照らせば,本件事業譲渡がさ れた事実を認めることはできない。
エ 原告の主張について
(ア) 原告は,平成21年1月2日に本件ドメイン名のWhois情報上の登録 者がパケットモンスター社に変更されたことは,本件ドメイン名を使用 する権利が移転したことを意味し,これは本件事業譲渡を裏付けると主 張する。 しかし,上記1(2)のとおり平成12年から平成21年までの間に本件 ドメイン名のWhois情報上の登録者は何度も変更されているところ,これ らの登録者の変更が本件ドメイン名を使用する権利の実体上の移転を伴 うものであるかどうかは明らかではない(むしろ,登録者の変更が事業 譲渡を反映しているのだとすると,上記1(2)アないしオによれば,平成 12年から平成21年の間に本件事業譲渡を含む3回の事業譲渡が行わ れたことになるが,本件事業譲渡に対応する平成21年1月の登録者変 更以外の登録者変更に関しては,それが事業譲渡に伴うものであったこ とをうかがわせる証拠は全く存しないのであって,このことは,登録者 の変更が,必ずしも事業譲渡に伴うものではないことをうかがわせる事 情であるといえる。)。また,パケットモンスター社の設立時(平成2 0年10月13日)の株主は被告であるから(上記1(6)),パケットモ ンスター社は被告と関連を有する会社であったものとうかがわれる。以 上によれば,本件ドメイン名のWhois情報上の登録者がパケットモンスタ ー社に変更されたことをもって,本件ドメイン名を使用する権利の移転 やこれを伴う本件事業譲渡を直ちに裏付けるものとみることはできない。 なお,平成25年8月18日時点のパケットモンスター社の役員及び株 主が被告でないこと(上記1(6))は,この判断を左右するものではない。
(イ) 次に,原告は,本件ブログ及び本件書籍並びに本件記事における記載 は,本件事業譲渡を裏付けると主張する。 しかし,本件書籍及び本件ブログの「2ちゃんねる(ないし2ch) を譲渡」との記載自体からはこれが法律上の事業譲渡を意味するのかが 不明であるし,本件書籍にはこの「譲渡」の後も被告が「2ちゃんねる アドバイザー」であった旨の記載もある。また,本件記事には,被告を 「元管理人」と称し,被告が「本件電子掲示板を運営管理する権利を譲 渡したと公表した」とする部分があるが,その一方で,被告が平成21\n年1月以降も本件電子掲示板の運営に深く関与していることを示唆する 内容も含まれており,本件記事を事業譲渡を裏付ける証拠と断定するこ とはできない。 以上によれば,本件ブログ及び本件書籍並びに本件記事における記載 から,本件事業譲渡がされた事実を認めることはできない。
(ウ) さらに,原告は,本件電子掲示板上にパケットモンスター社の記載が あることは本件事業譲渡を裏付けると主張するが,本件電子掲示板をパ ケットモンスター社が運営管理している旨の記載(上記1(5))からは, パケットモンスター社が事業主体であるのか,事業主体から電子掲示板 の運営管理の委託を受けているのかが明らかではなく,本件事業譲渡を 裏付けるものとはいえない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2018.07.24
平成29(行ケ)10234 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成30年7月19日 知的財産高等裁判所
原告は,本件証明書に記載されている公開意匠(Arpege story「5wayコクーンコート」の意匠)と引用意匠は実質的同一の意匠であると主張しているので,要するに,原告が特許庁長官に提出した本件証明書(甲2の1)が引用意匠についての意匠法4条3項所定の証明書に当たる旨を主張しているものと解される。
よって検討するに,本件証明書に記載された公開意匠は,本件審決の「別 紙第3」のとおりであって,「5wayコクーンコート」なる商品名の女性 用コート(原告商品)であること,その販売価格は5万6160円であるこ と,同コートには,フードと袖口のファーとブローチが付いていること,こ れらのフードと袖口のファーとブローチはいずれも取り外しが可能であるこ\nと,袖口のファーはネック(コートの襟)に装着可能であることが,その記\n載内容から理解できる。もっとも,フードにファーが付くことや,フードの ファーが取り外し可能であることについては,本件証明書に一切記載されて\nおらず(これを示す写真も説明文もない。),本件証明書の記載から直ちに そのことを理解するのは困難である(甲2の1,乙12)。
他方,引用意匠は,本件審決の「別紙第2」のとおりであって,「【Ar pege story限定】コクーンコート」なる商品名の女性用コート(原 告商品)であること,その販売価格は6万3720円であること,同コート は,フードと袖口のファーとブローチのほか,フードのファーも付いている こと,これらのフードと袖口のファーとブローチとフードのファーはいずれ も取り外しが可能であること,袖口のファーはネック(コートの襟)に装着\n可能であることが,引用意匠に係る原告のウェブサイト(甲61,乙10の\n1及び2)の記載から理解できる。また,同ウェブサイトには,「ファー, フード,ビジューはそれぞれ取り外しが可能なので,自由に印象を変えて,\nアレンジを楽しめるのも大きな魅力!」,「”限定ポイント”アプの大人気 5WAYコートに袖とフードの両方にファーをつけました。」なる記載も認 められる。 以上によれば,公開意匠に係る商品も,引用意匠に係る商品も,共に「5 wayコクーンコート」なる商品名の女性用コート(原告商品)であって, フードと袖口のファーとブローチが付いている点,これらのフードと袖口の ファーとブローチはいずれも取り外しが可能である点及び袖口のファーはネ\nック(コートの襟)に装着可能である点で共通するが,引用意匠に係る商品\nは公開意匠に係る商品の限定品であって,袖口のほかにフードにもファーが 付いており,かかるフードのファーも袖口のファーと同様に取り外しが可能\nである点において,公開意匠にはない特徴を有するものと認められる。
(4) 上記のとおり,引用意匠は,フードにファーが付く点及びフードのファー が取り外し可能である点において公開意匠と明らかに相違すると認められる\nところ,かかる変化の態様が,本件証明書において説明ないし図示されてい なかったとしても,物品の性質や機能に照らして十\分理解することができる 範囲内のものであると認められれば,なお,引用意匠は公開意匠と実質的に みて同一であると評価する余地がある。 しかしながら,フードやファー,ベルト,ブローチなどを取り外して複数 の組合せを楽しむことができる女性用コートであれば,説明や図示がなくて も,通常はフードにファーが付くことや,当該フードのファーが取り外し可 能である,ということを十\分理解できると認めるに足る証拠はなく,商品名 に「5way」なる文言が付されていることも直ちにその認定を左右するも のとは認められない(アパレル業界,少なくともコートの業界において,「5 way」なる文言が多義的な意味で用いられていることは,被告提出の証拠 〔乙24ないし27等〕によっても明らかであるし,これらの証拠によれば, むしろ,変化の態様が公開意匠に近いものであっても,フードにファーが付 かないタイプのコートが現に存在することが認められる。)。 また,女性用コートの意匠において,フードにファーが付くことそれ自体 はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても,現にフードにファーが付\nくか否かによって,その意匠から受ける需要者の印象が異なり得ることは明 らかというべきであるし,このことは原告自身も認めているところである(原 告は,原告準備書面(2)の3頁において,「通常,ファーはエレガント感を強 めるので,フードのファー,袖のファーの取付け,取り外しが簡単にできる ようにして,カジュアル感がなくならないように配慮したものである。」と 主張しており,これによれば,原告は,ファーの有無がエレガント感やカジ ュアル感の強弱に影響を与える意匠的特徴の一つであることを自ら認めてい るといえる。)。 そうすると,引用意匠及び公開意匠が,共にいわゆる動的意匠であって変 化の態様を有することを踏まえたとしても,フードにファーが付く点及びフ ードのファーが取り外し可能である点が物品の機能\や性質に照らして十分理\n解することができる範囲内のものであると評価することはできず,この点の 相違は実質的な相違に当たると認めるのが相当である。
(5) 以上によれば,引用意匠が本件証明書に記載されている公開意匠と実質的 に同一の意匠であるとは認められず,したがって,原告が特許庁長官に提出 した本件証明書(甲2の1)が引用意匠についてのものであると認めること はできない。 してみると,引用意匠については,そもそも,意匠法4条3項所定の証明 書が提出されていないことに帰するから,原告は引用意匠について同条2項 の適用を受ける余地はない。
2018.07.24
平成29(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年7月19日 知的財産高等裁判所
原告は,本件審決が甲8発明に相違点1に係る構成が記載されていると認\n定しながら,公知発明(主引用発明)と甲8発明の組合せによる本件発明1 及び8の容易想到性の有無を判断していない点において,判断遺漏の違法が ある,と主張する。 しかしながら,主引用発明が同一であったとしても,主引用発明に組み合 わせる技術が公知発明における一部の構成か,あるいは,周知技術であるか\nによって,通常,論理付けを含む発明の容易想到性の判断における具体的な 論理構成が異なることとなるから,たとえ公知技術や周知技術認定の根拠と\nなる文献が重複するとしても,上記二つの組合せは,それぞれ異なる無効理 由を構成するものと解するのが相当である。\n
しかるところ,本件審判手続において,原告は,「本件発明1及び8は, 公知発明及び周知技術Y1に基づいて,当業者が容易に発明できた」という 無効理由1−2の主張に関連して,「キャラクタの置かれている状況に応じ て間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」技術が「周知技術」である と主張し,その根拠の一つとして甲8発明の内容を主張立証するにとどまっ ており,更に進んで,動機付けを含む公知発明と甲8発明それ自体との組合 せによる容易想到性については一切主張していない。 そうすると,原告が本件訴訟において主張する無効理由(公知発明と甲8 発明の組合せによる容易想到性)は,本件審判手続において主張した無効理 由1−2(公知発明と甲8発明を含む周知技術Y1の組合せによる容易想到 性)とは異なる別個独立の無効理由に当たるというべきである。 したがって,本件審決が,公知発明と甲8発明との組合せによる容易想到 性について判断していないとしても,本件審決の判断に遺漏があったとは認 められない。
(2) これに対し,原告は,審判において審理された公知事実に関する限り,複 数の公知事実が審理判断されている場合に,その組合せにつき審決と異なる 主張をすることは,それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対 比の枠を超えるということはできず(知財高裁平成28年(行ケ)第100 87号同29年1月17日判決),甲8発明の内容については本件審決にお いて具体的に審理されていることから,被告による防御という観点からも問 題はなく,また,紛争の一回的解決の観点からも,公知発明と甲8発明の組 合せによる容易想到性を本件訴訟において判断することは許される,と主張 する。
しかしながら,この主張が,本件審決の手続上の違法(判断の遺漏)を主 張するものではなく,実体判断上の違法(進歩性の判断の誤り)を主張する ものであるとしても,本件審判手続において,甲8発明の内容を個別に取り 上げて公知発明に適用する動機付けの有無やその他公知発明と甲8発明の組 合せの容易想到性を検討することは何ら行われていない。したがって,かか る組合せによる容易想到性の主張は,専ら当該審判手続において現実に争わ れ,かつ,審理判断された特定の無効原因に関するものとはいえないから, 本件審決の取消事由(違法事由)としては主張し得ないものである(最高裁 昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2 号79頁〔メリヤス編機事件〕参照)。 なお,原告が指摘する上記知財高裁判決は,審判手続で主張されていない 引用例の組合せについて,審決取消訴訟において審理判断することを当事者 双方が認め,なおかつ,その主張立証が尽くされている事案であるから,本 件訴訟とは事案を異にするというべきである。 また,原告は,特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」の意義に ついて,特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視して広 く解釈されてしまうと,本件審決が確定した後に公知発明と甲8発明の組合 せによる容易想到性を争うことが同条により許されないと解釈されるおそれ があり(知財高裁平成27年(行ケ)第10260号同28年9月28日判 決),その場合,原告による本件特許の無効を争う機会を奪うことになり不 当であるから,本件訴訟で公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性に 関する本件審決の判断の遺漏及び違法を争うことは許される,とも主張する。 しかしながら,本件審判手続においても,本件訴訟手続においても,公知 発明と甲8発明の組合せによる容易想到性という無効理由の有無については 何ら審理判断されていないのであるから,特許法167条の「同一の事実及 び同一の証拠」に当たるということはないというべきである。
(3) 以上によれば,本件訴訟手続において,公知発明と甲8発明の組合せによ る本件発明1及び8の容易想到性を判断することは許されないというべきで ある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2018.07.24
平成30(ネ)10018 特許権に基づく差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年7月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明に係る特許請求の範囲には,「吸着面」について,1) 攪拌装 置から牌を取り上げる汲上機構を構\成する円筒回転体には円筒回転体の 一側端から「牌の横幅ほどの幅」の「吸着面」が配設されること(構成\n要件C,H,I),2) 「吸着面」の中心には磁石を埋没し,「吸着面」 に磁気力により牌を吸着して下方から上方に吸い上げるように円筒回転 体を回転させること(構成要件J),3) 汲上機構によって取り上げら\nれた牌を一方向に整列して送り出すための整列機構には,円筒回転体に\n吸い上げられた牌の方向を揃えるため「吸着面」の外側の軌道に沿って 配設した案内部材が設けられること(構成要件D,K)の記載がある。\nそして,自動麻雀卓における「牌」は,字面に垂直な方向からみて 「横幅」が「縦幅」より短い長さとなる長方形状であるから(原判決別 紙図2),構成要件Iの「牌の横幅ほどの幅」との特定は,「吸着面」\nの幅が「牌の縦幅」より「牌の横幅」に近い幅をもつことを特定するも のと解するのが文言上自然である。
イ もっとも,特許請求の範囲の記載のみからは「横幅ほど」の外延は必ずしも明らかではないことから,本件明細書の記載について検討する。 本件明細書には,上記1(2)のとおりの本件発明の課題の解決手段とし て,円筒回転体の周面部位に円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅 をもつ吸着面を配設し,磁性体を埋設した牌を,中心に磁石を埋没した 吸着面に磁気力により吸着し,円筒回転体に吸い上げられた牌の方向を 揃えるため前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材を設け, 前記円筒回転体によって下方位置にて取り上げられた牌は,前記案内部 材にそって牌の向きを揃えながら上方に移動する(段落【0008】) ことが記載されている。そして,円筒回転体は牌の縦幅と略等しい長さ の高さ寸法であり(段落【0009】,【0021】),円筒回転体の 一側端から「牌の横幅」と略等しい幅の吸着面が形成される(段落【00 21】)ことが記載されており,これらの記載からは,「牌の縦幅」と区 別される「牌の横幅」を「吸着面の幅」に相当するものとしていること が理解され,このような理解は特許請求の範囲の記載とも整合する。 さらに,本件明細書の段落【0033】〜【0035】には,吸着面 401Bに様々な角度で吸着した牌10につき,案内部材501の入り 口付近で吸着面401Bからはみ出た側面が,案内部材先端502に接 触して抵抗を受け,磁石により吸引されて回転しながら向きを変え,縦 長方向に整列することが記載され,図10及び図11における吸着面4 01Bの幅は牌の横幅に近似する幅であることが見て取れる。
ウ 以上のとおりの各構成要件相互の関係及び本件明細書の記載によれば,\n本件発明において「牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」とした技術的意義 は,吸着面の幅を「牌の横幅」分の幅とすれば,牌が少しでも斜めに吸 着した場合には牌が吸着面からはみ出るから,はみ出た牌の側面に吸着 面の外側の軌道に配設した案内部材を接触させ,接触による力学的な作 用と牌に埋設された磁石と吸着面の中心に埋設された磁石との吸引力に よって牌を回転させて長手方向の向きに揃えるようにしたことにあると 解することができる。 そして,このような技術的意義に照らせば,構成要件Iの「牌の横幅ほ\nどの幅」とは,吸着面の幅が,牌の横幅(短辺)と同一か,様々な角度 で吸着面に吸着した牌の側面が当該吸着面からはみ出る部分を有し,は み出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えること ができる程度の幅を意味し,牌の縦幅に近似する幅はこれに含まれない と解すべきである。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> ピックアップ対象
2018.07.20
平成29(行ケ)10114 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年7月18日 知的財産高等裁判所(4部)
原告らは,本件審決は,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズ マ濃度」の記載について,本件国際出願明細書には,「1〜2ng/mlプ ラズマ濃度」との文言の記載はないが,「0.1〜2ng/mlプラズマ濃 度」との記載があり,「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲は,「0. 1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲の約半分ほどの範囲を占める部 分であり,当該範囲は,他の数値範囲からは予測できない特段の意味を有す\nる数値範囲でもなく,新たな技術的事項を導入するものでもないから,本件 発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本件発明4ないし12は, 本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり,原文新規事項に該当し ない旨判断したが,1)「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクス メデトミジンの作用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度における デクスメデトミジンの作用とは,明らかに異質なものであり(甲9x,9y, 10),「1ng/mlプラズマ濃度」を数値範囲の境界値として本件特許 の請求項3に記載することは,新たな技術的事項を導入するものであるから, 原文新規事項に該当する,2)本件国際出願明細書と本件国内書面によれば, 国際出願時の請求項3で「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」とされてい たものが,本件国内書面の請求項3で「1〜2ng/mlプラズマ濃度」と なったようであるが,既に特許登録されている請求項3を「0.1〜2ng /mlプラズマ濃度」に訂正する手段はないから,原文新規事項に該当する というほかないとして,本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。 そこで検討するに,本件国内書面(甲77の2)には,プラズマ濃度に関 し,「デクスメデトミジンの投与量の範囲は,標的プラズマ濃度として記載 することができる。ICUにおける患者の人々に鎮静を提供することを期待 されるプラズマ濃度範囲は,鎮静の目的レベルおよび患者の全体的な状態に 依存して0.1〜2ng/mlの間で変わる。これらのプラズマ濃度は,瞬 時投与(bolus dose)および規則的な維持注入(steady maintenance infusion) による継続投与を用いて静脈内投与によってなされることができる。たとえ ば,ヒトにおいて前記プラズマ濃度範囲に到達するための瞬時の投与量範囲 は,約10分間またはそれよりゆっくり投与されるため,約0.1〜2.0 μg/kg,好ましくは約0.5〜2μg/kg,より好ましくは1.0μ g/kgであり,ついで,約0.1〜2.0μg/kg/h,好ましくは約 0.2〜0.7μg/kg/h,より好ましくは0.4〜0.7μg/kg /hが維持投与される。デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る 塩の投与期間は,目的の使用持続期間に依存している。」(【0028】) との記載がある。上記記載によれば,【0028】には,ICUにおける患 者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲は,「鎮静の 目的レベルおよび患者の全体的な状態に依存して0.1〜2ng/mlの間 で変わる」ことが開示されていることが認められるが,一方で,本件国内書 面の発明の詳細な説明及び図面には,【0028】以外に,「0.1〜2n g/mlプラズマ濃度」に関して言及した記載はない。また,この点につい ては,本件国際出願明細書も,本件国内書面と同様であることが認められる。 そして,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」は,【0 028】記載の「0.1〜2ng/ml」の数値範囲内にあるから,ICU における患者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲に あることは明らかである。 そうすると,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の 記載が,本件国際出願明細書のすべての記載を総合することにより導かれる 技術事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるということはで きない。
(2) この点に関し,原告らは,甲9x,9y,10を根拠として挙げて,デク スメデトミジンのプラズマ濃度が「1〜2ng/ml」に達すると,患者は 深く眠ってしまって覚醒できなくなるが,プラズマ濃度が「0.1〜1ng /ml」であれば,音声指示によって容易に目を覚ますことが可能であるか\nら,「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジンの作 用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジ ンの作用とは,明らかに異質なものである旨主張(上記1)の主張)する。 しかし,原文新規事項に該当するかどうかは,本件国際出願明細書の全て の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術 的事項の導入に当たるかどうかを判断すべきであるところ,甲9x,9y, 10は,本件国際出願明細書とは別の文献であり,しかも,原告らが根拠と して挙げる上記各文献の具体的な記載内容が,本件優先日当時技術常識であ ったとまで認められないから,原告らの上記1)の主張は,採用することがで きない。 また,原告らは,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当することの根拠として,請求項3の「1〜2n g/mlプラズマ濃度」の記載を「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」に 訂正する手段がないことを挙げるが(上記2)の主張),そのように訂正する 手段があるかどうかの問題と請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当するかどうかの問題とは別個の問題であるとい うべきであるから,原告らの上記2)の主張は失当である。
(3) 以上によれば,本件発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本 件発明4ないし12は,本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり, 原文新規事項に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるとの原告らの 上記主張(取消事由5)は,理由がない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2018.07.19
平成29(ワ)32433 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年6月21日 東京地方裁判所(46部)
争点 (2)−2(本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの保守管理 業務に伴う複製権又は翻案権侵害)について
ア 原告は,被告マルイチ産商と被告テクニカルパートナーは,被告マルイチ 産商のコンピュータ保守管理のための人材派遣契約を締結し,被告テクニカ ルパートナーらは,上記派遣契約に基づき,被告マルイチ産商のコンピュー タの保守管理業務を行っており,本件基本契約が終了した平成26年9月1 7日以降も,保守管理業務の一環として,本件共通環境設定プログラムの複 製又は翻案を行ったと主張する。 しかし,保守管理業務の一環として本件共通環境設定プログラムの複製又 は翻案が行われた事実を認めるに足りる証拠はなく,原告の主張を採用する ことはできない。
イ また,仮に,被告らが本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラム の保守管理業務に伴い,本件共通環境設定プログラムの複製又は翻案を行っ たとしても,本件基本契約26条は,「著作権・知的財産権および諸権利の帰 属」に関する定めが本件基本契約の終了後も有効であると定めており,被告 マルイチ産商は,本件基本契約終了後も「著作権・知的財産権および諸権利 の帰属」に関する定めである本件基本契約21条3項 に基づき,本件共通 環境設定プログラムを複製等することができると解するのが相当であるか ら,複製権又は翻案権侵害は成立しないと解するのが相当である。 これに対し,原告は,本件基本契約は更新しない旨の意思表示による解約\n(28条1項但書)により終了したのであり,本件基本契約26条の「本契 約が合意の解約により終了した場合および解除により終了した場合」に直接 該当しないし,本件基本契約26条が規定するのは「著作権・知的財産権お よび諸権利の帰属」であり,本件基本契約21条3項が定める権利の帰属主 体が契約終了によっても変わらないことを定めているとしても,同項(2)の利 用に関する定めは射程外であると主張する。 しかし,本件基本契約26条は,「契約終了後の権利義務」との見出しの下 で「本契約が合意の解約により終了した場合および解除により終了した場合 でも」と定めており,他の原因による終了の場合にも適用されることを前提 にしていると解され,本件基本契約中に他の原因による契約終了時の権利義 務等を定める条項がないことからしても,本件基本契約26条は,更新しな い旨の意思表示による解約による契約終了の場合の権利義務の帰趨も定め\nていると解釈すべきである。
また,本件基本契約26条における「著作権・知的財産権および諸権利の 帰属」との文言は,本件基本契約21条の見出しと同一であること,また, 同条3項は,成果物の著作権・知的財産権および諸権利の帰属を定めるとと もに,著作権が共有となる場合(同項 )には双方が利用することができる ことを定め,原告のみに帰属する場合(同項 )には被告マルイチ産商に対 して利用することができる範囲を定めており,著作権の帰属の違いに対応し て利用することができる範囲をそれぞれ定めているものであり,そのような 定めにおいて,契約終了後,著作権の帰属の定めのみ有効に存続すると解す るのは不自然であること,契約中に契約終了後の利用やその禁止についての 定めはないことからすると,本件基本契約26条において契約終了後も有効 とされる「著作権・知的財産権および諸権利の帰属」の定めとは,同21条 の定め全体を指し,同条が定める利用に関する定めも含んでいると解釈する のが相当である。原告が主張する本件基本契約の解釈によれば,本件新冷蔵 庫等システムの使用のために必要となる本件共通環境設定プログラムは本 件基本契約終了により一切複製等できなくなり,本件共通環境設定プログラ ムのサーバ移行等を行うことができず,本件新冷蔵庫等システム自体の使用 を継続することも不可能ないし困難となるが,そのような解釈は不合理であ\nる。
関連カテゴリー
>> プログラムの著作物
>> 複製
>> ピックアップ対象
2018.07.19
平成29(ワ)14142 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月28日 東京地方裁判所(47部)
乙8文献の段落【0053】「検知器32は,感圧方式,電磁誘導方式, 静電容量方式等のセンサにより,ユーザが検知器32に触れたこと,及び, 離れたことを検知することができる。」及び【0056】「ユーザ側に板状 の検知器32が配置され,ユーザが指で触れた操作をその位置と共に検知す ることができるようになっている。」との記載によれば,乙8文献には,構\n成要件A「表示画面にスライドせずに接触したオブジェクトの力入力を,直\n接的または間接的に検出する力入力検出手段と,」及び構成要件B「前記オ\nブジェクトが前記表示画面に接触した位置を検出する位置入力手段と,」の\n各構成が開示されているといえる。\nまた,乙8文献の段落【0061】の「オンルートスクロールというのは, 経路上を移動する点(移動点)を表示面上の基準点に一致させた地図をスク\nロールさせるものである」,段落【0073】の「ユーザから見れば「指で 触れている自車位置マークCが移動(スクロール)を開始し,経路関連情報 の存在する地点に自車位置マークCが到達したため,自車位置マークCが振 動する」というように感じることができ」との各記載に併せて図7の記載も 考慮すれば,乙8文献記載の発明(図7から認定される発明)は,「地図」 (本件発明の「表示対象以外」に相当)が移動すること(本件発明の「表\示 態様を変更」に相当)で,あたかも「自車位置マーク」(本件発明の「表示\n対象」に相当)が移動しているように見えるよう制御されているといえる。 したがって,乙8文献には,構成要件C「前記位置入力手段にて検出された\n位置の表示対象を前記位置に保持しつつ,」,構\成要件D「前記力入力検出 手段により検出された前記力入力に応じて,当該表示対象以外の表\示態様を 変更することにより,」及び構成要件E「当該表\示対象を相対的に変更さ せ,」の各構成が開示されているというべきである。\nさらに,乙8文献の段落【0065】には,「検知器32は未検知状態に あると判定した場合に進むS140では,オンルートスクロールを一旦停止 し,上述したS105に処理を戻す」と記載されていることから,乙8文献 記載の発明においても,「自車位置マーク」に対する「地図」の変更結果を 記憶部に記憶していることは自明のことというべきである。したがって,乙 8文献には,構成要件F「当該変更結果を当該表\示対象に対する入力として 記憶部に記憶させる変更手段と,」の構成が開示されているといえる。\nまた,乙8が情報処理装置(構成要件G)を開示していることは明らかで\nある。 以上によれば,乙8文献に記載された発明と本件発明とは同一であると認 められる。
原告の主張について
ア これに対し,原告は,本件明細書の段落【0039】には,表示画面へ\nの接触による力の有無を検出する手段が記載されているが,当該手段は, 表示画面に加えられた力の有無を間接的に検出する手段であって,乙8文\n献に開示されている単なる接触の有無を検出する手段とは異なるから,乙 8文献には,本件発明の構成要件A「表\示画面にスライドせずに接触した オブジェクトの力入力を,直接的または間接的に検出する力入力検出手段 と,」(ひいては構成要件D及びFも)の構\成が開示されていない旨主張 する。
イ 本件明細書の段落【0039】には,次の記載がある。 「なお,上記のように検出装置112が機械的に直接,摩擦力または押 下力を検出することに限られず,間接的に摩擦力または押下力が検出され てもよい。例えば,後述する制御部102が,タッチパネルへの接触によ る入力位置の占める領域が,所定の形状から変化した場合に,所定の摩擦 力を検出してもよい。(判決注:中略)また,検出装置112は,表示画\n面への接触による力の強さを検出することに限られず,表示画面への接触\nによる力の有無を検出してもよい。この場合,表示画面に対して非接触の\n場合に,所定の押下力または摩擦力が検出されないものとし,表示画面に\n対して接触があった場合に,所定の押下力または摩擦力があったものとし て検出してもよい。」
ウ 原告が主張するように,上記段落【0039】の記載が,「力の強さ又 は有無を間接的に検出する手段」について述べたものであるとしても,該 「力の強さ又は有無を間接的に検出する手段」の一例として,「表示画面\nに対して非接触の場合に,所定の押下力または摩擦力が検出されないもの とし,表示画面に対して接触があった場合に,所定の押下力または摩擦力\nがあったものとして検出」する手段が記載されていることは明らかである。
エ そして,本件発明の構成要件Aは「表\示画面にスライドせずに接触した オブジェクトの力入力を,直接的または間接的に検出する力入力検出手段 と,」というものであるところ,そこにおいては,「力入力」の「検出」 に関し,それ以上に具体的な規定は何らされておらず,また,上記「力の 強さ又は有無を間接的に検出する手段」の一例である,「表示画面に対し\nて非接触の場合に,所定の押下力または摩擦力が検出されないものとし, 表示画面に対して接触があった場合に,所定の押下力または摩擦力があっ\nたものとして検出」する手段を排除する格別な理由も見当たらないことか らすれば,構成要件Aは,「表\示画面への接触・非接触による力の有無を 検出」することも含むと解すべきである。
オ したがって,乙8文献に開示されている接触の有無を検出する手段が, 本件発明の構成要件A「表\示画面にスライドせずに接触したオブジェクト の力入力を,直接的または間接的に検出する力入力検出手段と,」の構成\nと異なることを前提とする原告の上記主張は,その前提を欠くものであり, 採用できない。 (4)小括 以上のとおり,乙8文献に記載された発明は本件発明と同一であるから, 本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められる。
・・・
(なお,原告は,本件特許について訂正審判を請求したとして平成30年6月21日付けで口頭弁論の再開を申し立てたが,当裁判所は,原告にはより早い時期に訂正の再抗弁を主張する機会が十\分にあったこと等を考慮して,口頭弁論を再開しない。)。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2018.07.12
平成28(ワ)32742 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年6月19日 東京地方裁判所(47部)
制作工程写真は,別紙「制作工程写真目録」記載のとおり,故一竹によ る「辻が花染」の制作工程の各場面を撮影したものであるところ,これら 制作工程写真の目的は,その性質上,いずれも制作工程の一場面を忠実に 撮影することにあり,そのため,被写体の選択,構図の設定,被写体と光\n線との関係等といった写真の表現上の諸要素はいずれも限られたものとな\nらざるを得ず,誰が撮影しても同じように撮影されるべきものであって, 撮影者の個性が表れないものというべきである。したがって,制作工程写\n真は,いずれも著作物とは認められない。これに反する原告らの主張は採 用できない。
イ 美術館写真について
美術館写真は,別紙「美術館写真目録」記載のとおり,一竹美術館の外 観又は内部を撮影したものであるところ,これら美術館写真の目的は,そ の性質上,いずれも一竹美術館の外観又は内部を忠実に撮影することにあ り,そのため,被写体の選択,構図の設定,被写体と光線との関係等とい\nった写真の表現上の諸要素はいずれも限られたものとならざるを得ず,誰\nが撮影しても同じように撮影されるべきものであって,撮影者の個性が表\nれないものである。したがって,美術館写真は,いずれも著作物とは認め られない。これに反する原告らの主張は採用できない。
(2) 制作工程文章の著作物性について
制作工程文章は,別紙「制作工程文章目録」記載のとおり,「辻が花染」 の各制作工程を説明したものである。その目的は,各制作工程を説明するこ とにあるため,表現上一定の制約はあるものの,制作工程文章が,同様に「辻\nが花染」の制作工程について説明した故一竹作成の文章(甲41)とも異な っていることに照らしても,各制作工程文章の具体的表現は,その作成者の\n経験を踏まえた独自のものとなっており,作成者の個性が表現されていると\nいえるから,制作工程文章は全体として創作性があり,著作物と認められる。 これに反する被告の主張は採用できない。
(3) 旧HPコンテンツの著作物性について
旧HPコンテンツは,別紙「旧HPコンテンツ目録」記載のとおりであり, 旧HPコンテンツ1は「辻が花染」の歴史的説明,旧HPコンテンツ2は故 一竹と「辻が花染」との関わり,旧HPコンテンツ3はフランス芸術文化勲 章シュヴァリエ章勲章メッセージの和訳,旧HPコンテンツ4はスミソニア\nン国立自然史博物館からの感謝状の和訳である。旧HPコンテンツ1及び2 はいずれも歴史的事実に関する記述ではあるものの,その事実の取捨選択, 表現の仕方には様々なものがあり得,その具体的表\現には筆者の個性が表れ\nているといえるから,創作性があり,著作物と認められる。また,旧HPコ ンテンツ3及び4はいずれも仏語ないし英語の翻訳であるが,翻訳の表現に\nは幅があり,用語の選択や訳し方等その具体的表現に翻訳者の個性が表\れて いるといえるから,創作性があり,著作物と認められる。これに反する被告 の主張は採用できない。
複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再 製することをいうところ(著作権法2条1項15号参照),著作物の複製と は,既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現\nに修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現する\nことなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が\n既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作\n成する行為をいうものと解すべきである。また,翻案とは,既存の著作物に 依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表\ 現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現する\nことにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接\n感得することができる別の著作物を創作する行為をいうものと解すべきであ る(最高裁判所平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷 判決・民集55巻4号837頁参照)。 被告作品集130−131頁(甲9)と制作工程文章を別紙「原被告作品 対比表」記載1のとおり比較対照すると,被告作品集130−131頁の制\n作工程に関する各文章は,制作工程文章1ないし7及び9の各文章と全く同 一か,又はほとんど同一であり,一部改変され,相違点はあるものの,全体 として制作工程文章の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。\nよって,被告は被告作品集130−131頁において制作工程文章1ないし 7及び9を複製ないし翻案したものと認められ,複製権ないし翻案権を侵害 する。そして,上記改変は著作者の意に反する改変といえるから,同一性保 持権を侵害する。 これに対して,被告は,両各文章は創作性のない部分について同一性を有 するにすぎず,複製にも翻案にも当たらないと主張するが,上記のとおり, 制作工程文章の創作的部分において同一性が認められるから,被告の主張は 採用できない。
原告らは,被告作品集の販売に係る損害額について原告作品集の利益額 に基づき114条1項の適用があると主張するのに対し,被告はこれを争 うため,以下検討する。
(ア) 原告作品集の販売主体及び原告らの販売能力
原告作品集の奥付には「(C)1998 (株)一竹辻が花」と記載され,原告作 品集は訴外一竹辻が花のウェブサイトにおいて販売されていることが認 められる(甲8,29)ところ,訴外一竹辻が花(昭和59年5月8日 に「株式会社オピューレンス」から商号変更)は平成22年まで原告A が代表者を務めていた会社であり(甲50の1及び2),原告工房も含\nめて実質的には原告Aらの経営によるものと認められ,その販売主体は 実質的には原告らとみることができる。また,原告作品集の制作には, 故一竹を引き継いで「辻が花染」を制作する原告Aの関与が大きいもの と考えられることも併せ考慮すれば,原告らには原告作品集の販売能力\nがあると認められる。 これに対し,被告は,そもそも原告らが原告作品集を販売しておらず, 販売能力がないから,被告作品集への114条1項の適用の基礎を欠く\nと主張するが,上記説示に照らして採用できない(なお,被告は,原告 作品集の奥付に「制作(株)便利堂」と記載されていること(甲8)も 指摘するが,この点は販売能力とは関係がない。)。
(イ) 原告作品集と被告作品集の代替性
原告作品集と被告作品集は,その大部分において,着物作品(部分を 含む。)を1頁に大きく配置して紹介するとともに,観賞の対象とする ものであり,そのほかの部分においても,故一竹の略歴,制作工程の説 明,美術館の紹介が記載されており,内容は類似するものと認められる (甲9,51)。また,上記内容の共通性に照らして,着物作品の観賞 を主としつつ,故一竹と「辻が花染」について理解を深めるという利用 目的・利用態様も基本的には同一であると認められる。そうすると,後 記のとおり,販売ルートの違いはあるものの,両作品集には代替性が認 められる。被告は,内容,利用目的・利用態様及び販売ルートの相違か ら,原告作品集と被告作品集には代替性がないと主張するが,上記説示 に照らして採用できない。
(ウ) 以上からすれば,被告作品集の販売に係る損害額について原告作品集 の利益額に基づき著作権法114条1項の適用があるというべきである。
イ 原告らが販売することができないとする事情(推定覆滅事情)
被告は,販売市場の相違,被告の営業努力,被告作品集の顧客吸引力に より,被告作品集の譲渡数量の全数について販売することができないとす る事情があると主張する。 そこで検討するに,原告作品集は訴外一竹辻が花のウェブサイトにおい てインターネット上で販売されている(甲29)のに対し,被告作品集は 一竹美術館のショップ内で販売されており(前記前提事実(4)ア),顧客層 に一定の違いがあると考えられること,また,被告作品集は,美術館のシ ョップにおいてまさに一竹作品等を観賞した者に対して販売されているこ とにより,販売態様の異なる原告作品集とは顧客誘引力に違いがあると考 えられること,以上の事情を踏まえると,被告作品集の30%については, 原告らが販売することができないとする事情があったと認めるのが相当で ある。
◆判決本文
問題となった著作物は以下です。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> 公衆送信
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2018.07.11
平成29(ワ)12058 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年6月28日 東京地方裁判所
ア 周知性について
上記アの各事実によれば,KCP社は,平成14年5月15日の 設立以来,14年程度の比較的長期間にわたり,同社の商号の一部と もいえるKCP社商標を同社の製品に付すなどして継続的に使用する とともに,同社製品の販売台数及び売上げを徐々に伸ばし,平成24 年以降,コンクリートポンプ車の韓国国内の市場において,同社の製 品の占有率は3割5分から4割を維持し,1位であったと認められる。そ うすると,KCP社商標は,本件商標の商標登録出願日(平成27年 2月18日)当時において,韓国のコンクリート圧送業者等の需要者 の間において,KCP社の商品を示すものとして広く認識されていた と認められる。 これに対し,原告は,KCP社の売上げ等の根拠となった資料(乙 15ないし18)は同社の社内データにすぎず,信用性は低い旨主張 するが,同資料記載の平成27年の総売上高(1169億8230万 8109ウォン,乙18)は韓国金融監督院の売上公開情報における 売上高(乙99)と一致しており,その他の数字についても,この信 用性を覆すに足りる証拠はない。 したがって,KCP社商標は,「外国における需要者の間に広く認識 されている商標」に当たる。
イ 本件商標とKCP社商標の同一性
本件商標は「KCP」とのアルファベットを標準文字で横書きしたも のであるのに対し,KCP社商標もまた「KCP」とのアルファベット を横書きしたものであるから,両商標は同一または類似の商標といえる。
ウ 不正の目的
上記で認定した各事実によれば,原告代表者は,1)平成24年1 2月から平成27年1月頃まで,日本国内においてKCP社の製品で あるコンクリートポンプ車等を宣伝・販売していたこと(上記イ), 2)平成27年1月頃,KCP社が日本への進出を計画し,被告Yが日 本国内のコンクリート圧送業者への営業活動を行っていることを知る と,直ちにKCP社商標と同一又は類似の本件商標につき登録出願を 行ったこと(同エ及びオ),3)同登録出願後,本件商標につき登録 査定がされる以前である同年4月頃,KCP社に対し,本件商標を無 償で譲渡等することはできない旨述べたこと(同,4)同様に同登 録出願後,登録査定以前である同年5月28日,被告Yに対し,日本 における営業活動をしないように求めるとともに,これをKCP社に 報告するように求め,本件商標の使用には原告の日本におけるこれま での営業活動に対する見返りが必要である旨の発言をしたこと(同オ ,5)同様に同登録出願後,登録査定以前である同年5月29日頃, 原告以外の販売店等がKCP社商標の付されたコンクリートポンプ車 を販売することが商標権侵害に当たることを警告するパンフレットを 作成・配布したこと(同オ(エ),6)本件商標の登録後間もない同年8月 12日,KCPジャパン社及び被告会社に対し,KCP社商標の使用 停止と削除を求める文書を送付したこと(同オ(オ))が認められる。 これらの事実からすれば,原告代表者は,KCP社が日本に進出し\nようとしていることを知ると,未だKCP社商標が商標登録されてい ないことを奇貨として,同社の日本国内参入を阻止・困難にするとと もに,同社に対し本件商標を買い取らせ,あるいは原告との販売代理 店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために,KCP社商標と 同一又は類似する本件商標を登録出願し,設定登録を受けたものと推 認せざるを得ない。 したがって,原告は,「不正の目的」をもって本件商標を使用するも のと認めることができる。
これに対し,原告は,KCP社の国内参入を阻止または困難にする 目的等の存在を否定し,原告代表者も,KCP社の日本進出前である\n平成26年秋頃には本件商標の登録を弁理士に依頼した等と述べて, 上記主張に沿う供述をする(原告代表者〔15及び16頁〕)。\nしかしながら,原告代表者が平成26年秋頃に本件商標の登録を計\n画していたことを裏付ける客観的証拠は存在しない上,同人の供述は, 本件商標出願の理由については「別にありません」と述べ,「KCP」 との文字の組み合わせを出願しようと決定した理由については,「コン クリートポンプ車か,コンストラクションプロダクツか,韓国のコン ストラクションプロダクツか,コンクリートポンプ車か,複雑な意味 を持っていますが,はっきりは,表向きには言わなかったです。」と述\nべるなど(原告代表者〔15及び16頁〕),KCP社商標と同一又は\n類似の商標を登録出願した理由を合理的に説明するものではなく,信 用性は低い。 加えて,原告代表者は,本件商標出願以前にKCP社の商品に係る\n営業活動を行っていた2年超の間は,「KCP」との文字を含む商号を 使用することはあったとしても((1)イ(ウ)),「KCP」について排他的 効力を有する商標権を得ようとまではしていなかったにもかかわらず, KCP社の日本進出と同時期にこれを取得したことにつき,正当な理 由は見いだしがたい。 したがって,原告の上記主張は採用できない。
エ 以上によれば,本件商標は,他人の業務に係る商品を表示するものと\nして韓国国内における需要者の間に広く認識されているKCP社商標と 同一または類似の商標であって,不正の目的をもって使用するものであ るから,商標法4条1項19号に該当する。 したがって,本件商標は,商標登録無効審判により無効とされるべきものと認められ,原告は,被告らに対し,その権利を行使することができない(商標法39条,特許法104条の3)。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2018.07.11
平成30(行ケ)10011 商標登録維持決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年7月10日 知的財産高等裁判所
商標法43条の3第4項は,審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が同法\n43条の2各号所定の登録異議事由のいずれかに該当すると認めないときは,その 商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない旨を規定し,また,同法43 条の3第5項は,同決定に対しては不服を申し立てることができないと規定する。\nこのように,本件決定に対しては不服を申し立てることができないのであるから,\n請求の趣旨1項に係る本件決定の取消しを求める訴えは,そもそも同法43条の3 第5項の規定に違反するものであって,不適法なものである。
2 請求の趣旨2項に係る訴えの適法性について
請求の趣旨2項に係る訴えは,原告が,本件登録異議事件について商標登録取消 決定をすべき旨を被告特許庁長官に命ずることを求めるものであり,行政事件訴訟 法(以下「行訴法」という。)3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴\nえとして提起するものと解される。 しかしながら,同号所定の義務付けの訴えは,当該法令に基づく申請又は審査請\n求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えと 併合して提起しなければならないところ(行訴法37条の3第3項2号),上記取 消訴訟又は無効等確認の訴えが不適法なものであれば,上記処分又は裁決はもとよ り取り消されるべきものとはいえない。よって,上記義務付けの訴えは,行訴法3 7条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠くものであって,不適法なものとなる。 そうすると,本件決定が行訴法37条の3第1項2号所定の「当該法令に基づく 申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決」に該当するとしても,\n請求の趣旨1項に係る本件決定の取消しを求める訴えが前記1のとおり不適法であ る以上,請求の趣旨2項に係る義務付けの訴えは,同号所定の訴訟要件を欠くもの であって,不適法なものである。
3 その余の各訴えの適法性について
(1) 裁判所法3条1項の規定にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対 象となるのは,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に 限られるところ,このような具体的な紛争を離れて,裁判所に対し抽象的に法令等 が憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないと解するのが相当であ る(最高裁昭和27年(マ)第23号同年10月8日大法廷判決・民集6巻9号7 83頁,最高裁平成2年(行ツ)第192号同3年4月19日第二小法廷判決・民 集45巻4号518頁参照)。
(2) 請求の趣旨3項に係る訴えの適法性について
請求の趣旨3項に係る訴えは,具体的な紛争を離れて,抽象的に商標法43条の 3第5項の規定が違憲無効であることの確認を求めるものにすぎない。 したがって,上記訴えは,前記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判 の対象となるものとはいえず,不適法なものである。
(3) 請求の趣旨4項及び5項について
請求の趣旨4項に係る訴えは,具体的な紛争を離れて,抽象的に一つの法令解釈 が違憲無効であることの確認,請求の趣旨5項に係る訴えは,具体的な紛争を離れ て,抽象的に商標登録異議事件における一つの審理方法が違憲無効であることの確 認を,それぞれ求めるものにすぎない。 したがって,上記各訴えは,前記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審 判の対象となるものとはいえず,いずれも不適法なものである。 仮に,上記各訴えが本件登録異議事件において審判体がした法令解釈や審理方法 の違憲無効をいうものであったとしても,これらの訴えは,本件決定に関する具体 的な紛争を解決するものにはならないから,確認の利益を欠き,いずれも不適法な ものである。
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2018.07. 8
平成29(行ケ)10143 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年7月5日 知的財産高等裁判所
ところで,本件訂正発明のような有機アンモニウム化合物を含有するレジ スト除去・洗浄剤では,レジスト除去は塩基の作用によるものであって,塩 基の濃度が高い,あるいは,pHが高いほど,その除去作用が強いという傾向 にあることは当業者における技術常識である(弁論の全趣旨)。また,回路 に用いられる代表的な導電性金属である銅やアルミニウムの腐食性が,接触\nする組成物・溶液の種類とそのpHに依存することも,当業者における技術常 識であり,例えば,アルミニウムは,接触する溶液の種類によるものの, pH が12以上で不安定化する傾向にあることは周知の技術常識である(甲48)。
これらの技術常識に照らせば,当業者は,一般論として,塩基の濃度とpH を調整することにより,レジスト除去に代表されるポリマー,エッチング・\nアッシング残渣の除去作用の強弱と,回路材料である金属の腐食作用の強弱 とを変化させることが可能であると一応理解できるというべきである。さら\nに,当業者は,本件明細書の段落【0089】の記載から,レジスト除去を より高温で,より長時間行うと,より完全となる傾向があることも理解する ことができる。 しかし,本件明細書の発明の詳細な説明には,実際のpHが明らかにされた 具体的な組成物の記載は一切存在しないし(例えば,W3,W11〜W13 はpH<7,W5及びW6はpH>12であることが記載されているものの,具体的に pHがいかなる値であったのかは明らかでない。),上記(3)において説示した とおり,訂正後発明1に係る成分を含有し,基板からのポリマー,エッチン グ・アッシング残渣除去と金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲 に抑えることが両立している具体的な組成物の例も記載されていない。 また,本件明細書に記載されているその余の組成物についても,基板から のポリマー,エッチング・アッシング残渣の除去作用と回路材料である金属 の腐食作用の各程度を,同一の組成物について具体的に評価した例は発明の 詳細な説明に記載されておらず,実際のpHの値が具体的に明らかにされた組 成物すら記載されていない。
(5) 以上検討したところによれば,本件明細書に接した当業者は,塩基の濃度 及びpHと,基板からのポリマー,エッチング・アッシング残渣の除去作用, 及び回路材料である金属の腐食作用との間に関係性があるとの技術常識を考 慮して,pHを調整することにより,ポリマー,エッチング・アッシング残渣 の除去と金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることの両 立が可能であることを一応理解できるとはいえるものの,反面,本件明細書\nの発明の詳細な説明においては,当該調整の出発点となるべき具体的組成物 の実際のpHの値が一切明らかにされていない上,基板からのポリマー,エッ チング・アッシング残渣の除去作用と回路材料である金属の腐食作用との関 係において,どの程度のpHの調整が必要であるのかについての具体的な情報 が余りにも不足しているといわざるを得ない。そのため,当業者が,本件明 細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて,本件訂正発明に係る組成物を生 産しようとする場合,具体的に使用するレジストや回路材料等を念頭に置い て,基板からのポリマー,エッチング・アッシング残渣の除去と回路の損傷 量を許容し得る範囲に抑えることとが両立した適切な組成物を得るためには, 的確な手掛かりもないまま,試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざる を得ないところ,このような試行錯誤は過度の負担を強いるものというべき である。 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,訂正後発明1〜7 の組成物を生産でき,かつ,使用することができるように具体的に記載され ているものとはいえない。
・・・
しかし,上記2において説示したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明 には,上記2つの性質が両立していると具体的に評価された実施例に関する 記載はなく,技術常識を併せ考慮したとしても,当業者が本件訂正発明に係 る組成物を生産しようとする場合,過度の試行錯誤によって各成分の配合量 を探索せざるを得ない。 したがって,本件訂正発明1〜7に係る特許請求の範囲の記載は,技術常 識を考慮しても,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載から,集 積回路基板等から,ポリマー,エッチング残渣,アッシング残渣,又はそれ らの組合せの除去と回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることとを両立さ せることのできる組成物と認識できる範囲内のものであるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.07. 6
平成29(ネ)10103等 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成30年6月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 著作権法2条1項1号所定の「創作的に表現したもの」というためには,\n作成者の何らかの個性が表れている必要があり,表\現方法がありふれている場合な ど,作成者の個性が何ら表れていない場合は,「創作的に表\現したもの」というこ とはできないと解するのが相当である。
ラダー図は,電機の配線図を模式化したシーケンス図をさらに模式化したもので あるから,ラダー図は配線図に対応し,配線図が決まれば,ラダー図の内容も決ま ることとなり(乙ロ1),したがって,その表現方法の制約は大きい。ラダー図に\nおいては,接点等の順番やリレー回路の使用の仕方を変更することにより,理論的 には,同一の内容のものを無数の方法により表現できるが,作成者自身にとってそ\nの内容を把握しやすいものとし,また,作成者以外の者もその内容を容易に把握で きるようにするには,ラダー図全体を簡潔なものとし,また,接点等の順番やリレ ー回路の使用方法について一定の規則性を持たせる必要があり,実際のラダー図の 作成においては,ラダー図がいたずらに冗長なものとならないようにし,また,接 点等の順番やリレー回路の使用方法も規則性を持たせているのが通常である(乙ロ 1,3)。
イ 控訴人プログラム1)は,控訴人19年車両の車両制御を行うためのラダ ー図であるが,共通ブロックの各ブロックは,いずれも,各接点や回路等の記号を 規則に従って使用して,当該命令に係る条件と出力とを簡潔に記載しているもので あり,また,接点の順番やリレー回路の使用方法も一般的なものであると考えられ る。
すなわち,例えば,ブロックY09は,リモコンモード,タッチパネルモード及 びメンテナンスモードという三つのモードのモジュールを開始する条件を規定した ブロックであるところ,同ブロックでは,一つのスイッチに上記三つのモードが対 応し,モードごとの動作を実行するため,上記各モードに応じて二つの接点からな るAND回路を設け,スイッチに係るa接点と各AND回路をAND回路で接続し ているが,このような回路の描き方は一般的であると考えられる。また,同ブロッ クでは,上段にリモコンモード,中段にタッチパネルモード,下段にメンテナンス モードを記載しているが,控訴人プログラム1)の他のブロック(Y11,Y23, Y24,Y25,Y26)の記載から明らかなように,控訴人プログラム1)では, リモコンモード(RM),タッチパネルモード(TP),メンテナンスモード(M M)の順番で記載されている(なお,これらにリモコンオンリーモード(RO)が 加わる場合は,同モードが一番先に記載される。)から,ブロックY09において も,それらの順番と同じ順番にしたものであり,また,メンテナンスモードを最後 に配置した点も,同モードがメンテナンス時に使用される特殊なモードであること を考慮すると,一般的なものであると評価できる。さらに,「これだけ!シーケン ス制御」との題名の書籍に,「動作条件は一番左側」と記載されている(乙ロ3) ように,ラダー図においては,通常,動作条件となる接点は左側に記載されるもの と認められるところ,ブロックY09の上記各段の左側の接点は,各モードを開始 するための接点であり,同接点がONとなることを動作条件とするものであるから, 通常,上記左側の各接点は左側に記載され,これと右側の接点とを入れ替えるとい うことはしないというべきであり,したがって,上記各段における接点の順番も一 般的なものである。したがって,同ブロックの表現方法に作成者の個性が表\れてい るということはできない。
また,ブロックY17は,拡幅待機中であることを規定するブロックであるとこ ろ,拡幅待機中をONにする条件として,10個のb接点をすべてAND回路で接 続しているが,上記条件を表現する回路として,関係する接点を全てAND回路で\n接続することは一般的なものであると考えられる。また,上記各接点の順番も,リ モコンオンリーモード,リモコンモード,タッチパネルモード及びメンテナンスモ ードの順番にし,各モードごとに開の動作条件と閉の動作条件の順番としたもので あるところ,前記のとおり,上記各モードの順番は,他のブロックの順番と同じに したものであり,開の動作条件と閉の動作条件の順番も一般的なものである。した がって,同ブロックの表現方法に作成者の個性が表\れているということはできない。 さらに,ブロックY25は,ポップアップフロアを上昇させる動作を実行するた めのブロックであるが,拡幅フロアの上昇又は下降に関しては,拡幅フロア上昇に 関する接点及び拡幅フロア下降に関する接点がそれぞれ四つずつ存在するという状 況下において,同ブロックでは,拡幅フロア上昇に関する接点をa接点,拡幅フロ ア下降に関する接点をb接点とした上で,四つのa接点及び四つのb接点をそれぞ れOR回路とし,これら二つのOR回路をAND回路で接続している。拡幅フロア の上昇と下降という相反する動作に関する接点が存在する場合において,目的とす る動作のスイッチが入り,目的に反する動作のスイッチが入っていないときに,目 的とする動作が実行されるために,目的とする動作の接点をa接点,これと反する 動作の接点をb接点としてAND回路で接続し,命令をONとする回路で表現する\nことは,a接点及びb接点の役割に照らすと,ありふれたものといえる。また,同 一の動作に関する接点が複数あり,目的とする動作の接点であるa接点のいずれか がONとなったときに目的とする動作が実行されるようにするため,それらの接点 をOR回路で表現することもありふれたものといえる。さらに,OR回路で接続さ\nれた四つの段においては,リモコンオンリーモード,リモコンモード,タッチパネ ルモード及びメンテナンスモードの順番としているが,前記のとおり,この順番は, 他のブロックの順番と同じにしたものである。ブロックY26は,ポップアップフ ロアを下降させる動作を実行するためのブロックであり,上記のブロックY25で 述べたのと同様のことをいうことができる。加えて,ブロックY25及びブロック Y26のAND回路で接続された各二つの列においては,上昇又は下降のa接点, 下降又は上昇のb接点の順番としているが,前記のとおり,ラダー図においては動 作条件となる接点は左側に記載されるところ,ブロックY25及びブロックY26 の各1列目は,「拡幅フロア上昇」又は「拡幅フロア下降」の動作条件となる接点 であると認められるから,通常,同ブロックのとおりの順番で接続され,1列目と 2列目を入れ替えるということはしないものということができる。したがって,こ れらのブロックの表現方法に作成者の個性が表\れているということはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2018.07. 2
平成29(ワ)39658 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年6月7日 東京地方裁判所
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,1)原告は,平成29年6月頃,ウェ ブサイト上に掲載する漫画の制作依頼を受けたところ,この依頼において, 掲載期間を1年間(2年目以降も掲載する場合には契約更新を行う。)とし, 原稿料は,漫画本編は1頁当たり2万円,カラー扉絵は4万円との条件を示 されたこと(甲12),2)原告は,平成28年頃,書籍の表紙用のカラーイラ\nスト(スーツを着て,ペンとメモ帳を持った女性のイラスト)及び当該書籍 中の扉絵4点を制作したところ,原稿料は,表紙のイラストについて3万円,\n扉絵について3000円であったこと(甲14の1・2),3)原告は,平成2 9年の年賀状用のカラーイラスト(餅と鳥を組み合わせたイラスト)を制作 したところ,原稿料は2万4000円であったこと(甲15の1・2),以上 の事実が認められる。 これらの事実に加え,本件各イラストの内容(前提事実 ),本件サイトは インターネットメディア事業を行うことなどを目的とする被告が運営し,そ の閲覧数に応じて被告が収入を得るものであること(弁論の全趣旨),その 他本件における諸事情を総合すると,本件各イラストの使用に対し受けるべ き金額は1年当たり3万円とするのが相当である。 そして,弁論の全趣旨によれば,被告が本件サイト上に本件各イラストを 掲載していた期間は,平成26年7月31日から平成29年6月8日までで あると認められるから,原告が,本件各イラストの使用に対し受けるべき金 銭の額は合計27万円(1年当たりの使用料3万円×3点×3年分)となる。 イ これに対し,原告は,原告が制作するイラストの使用料は1年当たり10 万円を下らないと主張し,原告本人の陳述書中にも同旨の記載がある(甲1) が,上記アの認定事実に照らし,原告の主張は採用することはできない。
ウ 他方,被告は,ツイッターのサービス利用規約上,ツイート自体を埋め 込む方法によって他のウェブサイトに掲載することが認められている点 を損害額の算定において考慮すべきであると主張するが,被告の主張を前 提としても,本件における被告の掲載行為が適法となる余地はなく,上記 に述べた本件サイトの性質等に照らしても,被告の上記主張は採用するこ とができない。 また,被告は,本件各イラストが掲載されていた本件サイトのPV数は 公開後約2か月間に集中しており,その後はほとんど閲覧されていないか ら,掲載期間全部を損害額算定の根拠することは不当であると主張する。 しかしながら,本件において原告が受けるべき金員の額は,被告による本 件各イラストの掲載行為の内容等を踏まえて算定すべきであるから,被告 の上記主張は採用することができない。
さらに,被告は,原告が本件訴訟提起前に被告に対し本件各イラストの 著作権侵害による損害賠償金として9万円(1点3万円×3点)を請求し ていたこと,上記ア1)について,漫画の原稿料にはストーリー制作作業に 対する対価も含まれると考えられること,同2)について,書籍の表紙とな\nるイラストと本件各イラストでは完成度が異なることから,いずれも本件 各イラストの使用料相当額の算定資料としては適切ではなく,むしろ,本 件各イラストの性質上,同2)の書籍の扉絵の原稿料(1点3000円)が 算定資料になり得る事例であり,本件各イラストは3点(描かれた場面の 数は合計14枚)であり,構図も3種類程度しかないこと等を踏まえると,\n本件各イラストの使用料は高くても1回2〜3万円程度であると主張す る。
しかしながら,本件訴訟提訴前に一定の金額を提示したとしてもその金 額が直ちに本件各イラストの使用料相当額であるとはいえない。また,本 件各イラストにおいては,複数の場面が多色カラーで描かれ,各場面に合 わせた説明文も記載されており,これらの場面設定や説明文についても原 告が創作していることを踏まえると,本件各イラストの使用料相当額が, 漫画や書籍の表紙の原稿料と比べて低額になるとはいえず,被告の主張は\n採用することができない。被告は,被告が本件各イラストの掲載によって得た利益は2500円程度に過ぎないとも主張するが,本件サイトの性質等を踏まえても,上記ア で認定した本件各イラストの使用に対し受けるべき金銭の額が不相当で あるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2018.07. 2
平成29(行ケ)10178 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年6月27日 知的財産高等裁判所
(1) サポート要件の適合性について
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1に関し,「医薬品や食品 のような経口投与用組成物等の品質を損なわずに優れた識別性を有する経 口投与用組成物を得ることができ,かつ,生産性にも優れたマーキング方 法を開発するという課題」を解決するための手段として,「本発明」は,酸 化チタン,黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少な くとも1種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の表面に,所\n定のレーザー光を走査することにより,変色誘起酸化物を凝集させること に起因した変色が生じるようにした構成を採用したことの記載があること\nは,前記1(1)イ認定のとおりである。
イ 次に,本件明細書の発明の詳細な説明には,1)実施例1ないし16にお いて,表1のレーザー装置及び照射条件(波長355nm,平均出力8W),\n表3のレーザー装置及び照射条件(波長266nm,平均出力3W)又は表\ 4のレーザー装置及び照射条件(波長532nm,平均出力12W)で,酸 化チタン,黄色三二酸化鉄又は三二酸化鉄錠剤を配合した,フィルムコー ト錠等に対し,文字又は中心線をマーキングしたこと(【0038】〜【0 056】,表1,表\3及び表4),2)表1のレーザー装置及び照射条件かつ\n走査速度1000mm/secで,実施例13のフィルム錠にレーザー照 射を行い,レーザー照射前後の二酸化チタンの粒子の状態を透過型電子顕 微鏡(TEM)により観測した結果,レーザー照射後に二酸化チタンの粒子 が凝集していることが確認されたこと(【0057】〜【0059】,図3, 図4),3)レーザー波長に関し,レーザーは,その波長が200〜1100 nmを有するものを用いることができ,好ましくは1060〜1064n m,527〜532nm,351〜355nm,263〜266nm又は2 10〜216nmの波長であり,より好ましくは527〜532nm,3 51〜355nm又は263〜266nmの波長であること(【0022】), 4)レーザー出力に関し,レーザーを走査する際の平均出力は,対象とする 経口投与用組成物の表面がほとんど食刻されない範囲で使用することがで\nき,例えば,その平均出力は,0.1W〜50Wであり,好ましくは1W〜 35Wであり,より好ましくは5W〜25Wであるが,単位時間あたりの レーザー照射エネルギーが強すぎると,アブレーションにより錠剤表面で\n食刻が発生し,変色部分まで剥がれてしまい,また,出力が弱いと変色が十\n分ではないこと(【0023】),5)レーザーの走査速度(スキャニング速 度)に関し,スキャニング速度は,特に限定されるものではないが,20m m/sec〜20000mm/secであり,また,スキャニング速度は, 高いほどマークの識別性に影響を与えることなく生産性を上げることがで きることから,例えば,レーザー出力5Wでは,スキャニング速度は,80 mm/sec〜10000mm/sec,好ましくは90mm/sec〜 10000mm/sec,より好ましくは100mm/sec〜1000 0mm/secであり,レーザー出力が8Wの場合には,スキャニング速 度は,250mm/sec〜20000mm/sec,好ましくは500 mm/sec〜15000mm/sec,より好ましくは1000mm/ sec〜10000mm/secであること(【0024】),6)単位面積 当たりのエネルギーに関し,単位面積当たりのレーザーのエネルギーは, マーキングの可否及び経口投与用組成物の食刻の有無の観点から,390 〜21000mJ/cm2であり,好ましくは400〜20000mJ/c m2,より好ましくは450〜18000mJ/cm2であり,また,390 mJ/cm2より低い場合には,マークを施すことができないのに対し,2 1000mJ/cm2より大きい場合には,食刻が生じるため,好ましくな いこと(【0025】)の記載がある。 上記1)ないし6)の記載を総合すると,本件明細書に接した当業者は,請 求項1記載の波長(200nm〜1100nm),平均出力(0.1W〜5 0W)及び走査工程の走査速度(80mm/sec〜8000mm/se c)の各数値範囲内で,波長,平均出力及び走査速度を適宜設定したレーザ ー光で,酸化チタン,黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択 される少なくとも1種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の 表面を走査することにより,変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させ\nてマーキングを行い,「医薬品や食品のような経口投与用組成物等の品質 を損なわずに優れた識別性を有する経口投与用組成物を得ることができ, かつ,生産性にも優れたマーキング方法を開発する」という本件発明1の 課題を解決できることを認識できるものと認められる。 したがって,本件発明1は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載され たものといえるから,請求項1の記載は,サポート要件に適合するものと 認められる。同様に,請求項2ないし22の記載も,サポート要件に適合す るものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2018.07. 2
平成30(行ケ)10021 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成30年6月27日 知的財産高等裁判所
本件登録意匠と甲1意匠とは,本件審決が認定するとおり,意匠に係る 物品が「検査用照明器具」である点で共通し,共に検査用照明器具の放熱 に係る用途及び機能を有し,正面視全幅の約1/3以上の横幅を占める大\nきさ及び範囲を占め,正面視右上に位置する点で,物品の部分の用途及び 機能並びに位置,大きさ及び範囲の点で共通する(争いがない。)。\nそこで,本件登録意匠と甲1意匠との類否について検討するに,甲18 の2(各図面は別紙5参照)及び弁論の全趣旨によれば,「横向き円柱状 の軸体に,それよりも径が大きい複数のフィン部を等間隔に設けて,最後 部のフィン部の形状について,中間フィン部とほぼ同形として幅(厚み) を中間フィン部に比べて大きくし,後端面の外周角部を面取りした」構成\n態様(共通点Aに係る構成態様)は,検査用照明機器の物品分野の意匠に\nおいて,本件登録意匠の意匠登録出願前に広く知られた形態であることが 認められる。
そうすると,共通点Aに係る構成態様(全体の構\成態様)は,需要者の 注意を強く惹くものとはいえず,本件登録意匠と甲1意匠との類否判断に 及ぼす影響は小さいものといえる。また,共通点Bに係る構成態様(フィ\nン部の数が6つであること)についても,需要者が特に注目するとは認め られず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいものといえる。
一方で,本件登録意匠と甲1意匠とは,各フィン部の形状について,本 件登録意匠では,各フィン部の右側面形状が「下部を切り欠いた円形状」 であって,その切り欠き部は底面から見た最大縦幅が各フィン部の最大縦 幅の約2分の1を占める大きさであり,かつ,平面から見た各フィン部の 左側面側外周寄りに傾斜面が形成されているのに対し,甲1意匠では,各 フィン部の右側面形状が「円形状」であって,切り欠き部が存在せず,平 面から見た各フィン部に傾斜面が形成されていないという差異(差異点a 及びb)があるところ,各フィン部の形状の上記差異は,需要者が一見し て気付く差異であって,本件登録意匠は甲1意匠と比べて別異の視覚的印 象を与えるものと認められる。
以上のとおり,本件登録意匠と甲1意匠は,共通点Aに係る構成態様(全\n体の構成態様)及び共通点Bに係る構\成態様(フィン部の数)は,需要者 の注意を強く惹くものとはいえないのに対し,差異点a及びbに係る各フ ィン部の形状の差異は,需要者が一見して気付く差異であって,本件登録 意匠と甲1意匠を別異のものと印象付けるものであること,本件登録意匠 と甲1意匠には,上記差異のほかに,差異点cないしeに係る差異もある ことを総合すると,本件登録意匠と甲1意匠は,視覚を通じて起こさせる 美観が異なるものと認められるから,本件登録意匠は甲1意匠に類似する ということはできない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 部分意匠
>> ピックアップ対象
2018.07. 1
不服2017-012293
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.07. 1
平成28(ネ)10104 販売差し止め等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成30年2月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品に つき,その登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為は,許諾を受けな い限り,商標権を侵害する(商標法2条3項,25条)。しかし,そのような商品の 輸入であっても,1)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許 諾を受けた者により適法に付されたものであり,2)当該外国における商標権者と我 が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得 るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示\nするものであって(以下,「第2要件」という。),3)我が国の商標権者が直接的に又 は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国 の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質 的に差異がないと評価される(以下,「第3要件」という。)場合には,商標権侵害 としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。(最高裁第一小法廷平成 15年2月27日判決民集57巻2号125頁) そして,商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品に つき,その登録商標と同一の商標を広告に付する行為は,許諾を受けない限り,商 標権を侵害する(商標法2条3項,25条)。しかし,そのような行為であっても, 登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為と同様に,商標権侵害として の実質的違法性を欠く場合があり,その場合の上記1)の要件は,当該商品に当該商 標を使用することが外国における商標権者との関係で適法であること(以下,「第1 要件」という。)とすべきである。
イ 第1要件について
(ア) 前記1(1)のとおり,PVZ社は,本件商標2と同一の標章を用いて その商品を販売している。PVZ社商標は,別紙PVZ社商標目録のとおり,デザ イン化した「NEONERO」の欧文字の下部に左から右にかけて緩やかにカーブ しながら下がる曲線を配し,その曲線の下に小さく「FORME PREZIOS E」の欧文字を記したものである。「NEONERO」の文字が「FORME PR EZIOSE」の文字より格段に大きいこと,前記1(1)のとおり,PVZ社は「N EONERO」の本件ブランド名を用いて身飾品を製造及び販売してきたことから すると,PVZ社商標の要部はデザイン化された「NEONERO」の文字部分で あるものと認められる。 控訴人標章2は,別紙控訴人標章目録のとおり,「PIZZO D’ORO」の欧 文字を上段に小さく,「NEONERO」の欧文字を下段に大きく配してなるもので あり,その文字の大小に各段の差があることから,要部は「NEONERO」部分 であるものと認められる。したがって,控訴人標章2の要部は,PVZ社商標の要 部とその外観が類似し,称呼を同一にする。以上より,PVZ社商標と控訴人標章 2とは,類似する。 控訴人標章1は,別紙控訴人標章目録のとおり,「NEONERO」の欧文字を書 してなるものであるから,PVZ社商標の要部とその外観が類似し,称呼を同一に するものであって,PVZ社商標と控訴人標章1は類似する。 そうすると,控訴人標章1及び2は,欧州においては,PVZ社の許諾なくして 適法に使用することはできないものであると認められる。
(イ) 上記のとおり,控訴人標章1及び2は,PVZ社商標と類似するもの であるが,前記(1)のとおり,控訴人商品は,いずれもPVZ社から輸入されたもの である上,控訴人がこれに手を加えて販売したとも認められないから,控訴人が控 訴人商品の広告に控訴人標章1及び2を付する行為は,PVZ社の商標権の出所識 別機能や品質保持機能\を害するものではなく,PVZ社との関係で適法なものとい うことができる。
(ウ) したがって,本件被疑侵害行為は,第1要件を充足する。
ウ 第2要件について
第2要件は,内外権利者の実質的同一性をいうものであって,「法律的に同一人と 同視し得るような関係がある」とは,外国における商標権者と我が国の商標権者が 親子会社の関係や総販売代理店である場合をいい,「経済的に同一人と同視し得るよ うな関係がある」とは,外国における商標権者と我が国の商標権者が同一の企業グ ループを構成している等の密接な関係が存在することをいうものである。\n前記1(6)のとおり,被控訴人はPVZ社と本件ブランド商品について日本におけ る本件販売代理店契約を締結し,被控訴人はPVZ社の日本における独占的な販売 代理店となったものであるから,PVZ社と被控訴人とは,法律的に同一人と同視 し得るような関係にあるといえ,本件被疑侵害行為は,第2要件を充足する。
エ 第3要件について
(ア) 第3要件は,我が国の商標権者の品質管理可能性についていうもので\nあるところ,外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視で きる場合には,原則として,外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者\nの品質管理可能性は同一に帰すべきものであるといえる。ただし,外国の商標権者\nと我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合であっても,我が国 の商標権の独占権能を活用して,自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持\nを図ってきたという実績があるにもかかわらず,外国における商標権者の出所に係 る商品が輸入されることによって,そのような品質又は信用を害する結果が生じた といえるような場合には,この利益は保護に値するということができる。
(イ) 前記1の認定事実によると,PVZ社は,本件商標登録以前から本件 ブランドを付した商品を控訴人及び被控訴人に対して販売し,日本において流通さ せていたところ,被控訴人が本件商標権を登録したのは,PVZ社の商品を独占的 に輸入し販売するためであり,その登録は,PVZ社の許諾を得て行ったものであ り,本件商標1は本件ブランド名そのものであり,本件商標2は,PVZ社が本件 ブランドのために使用していた標章を用いたものであると認められる。本件におい て,被控訴人商品は身飾品であり,使用者が他人から見えるように装用して,商品 の美しさでもって使用者を飾るという機能を有するところ,前記1(16)のとおり, 被控訴人が,PVZ社パーツの組合せや鎖の長さなどを指定し,引き輪やイヤリン グのパーツを取り付けたことは認められるものの,引き輪やイヤリングのパーツは 身体を飾るという被控訴人商品の主たる機能からみて付随的な部分にすぎない。被\n控訴人のウェブサイトには,PVZ社作成の画像及びPVZ社が使用するのと同じ 本件ブランドのロゴが用いられ,PVZ社パーツのレース状の模様は明確に認識で きるが,被控訴人が独自に付したパーツが強調されている部分はなく,また,PV Z社パーツのレース状の細工以外のデザインが良いことや,引き輪やイヤリングの パーツが使用しやすいといったことは,上記ウェブサイトには記載されておらず, このような事項が需要者に認識されていたとは認められない。さらに,被控訴人は, 被控訴人商品について保証書を発行していたものの,その内容は,「品番」「仕様」 のみであり(甲23),保証内容から被控訴人独自のパーツが付されていることを購 入者が認識できるものとは認められない。 これらの事情を総合考慮すると,被控訴人が,PVZ社とは独自に,被控訴人の 商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるとまで認めることはでき ず,控訴人商品の輸入や本件被疑侵害行為によって,被控訴人の商品の品質又は信 用を害する結果が生じたということはできない。したがって,被控訴人に保護に値 する利益があるということはできない。 なお,被控訴人は,独自の検査体制によって商品の品質維持を図り,販売した商 品の無償での部品交換に応じて商品の信用維持に努めているなどと主張するが,被 控訴人が身飾品の輸入販売業者が通常行っている品質や信用を維持するための行為 を超えてこれらの行為を行っているとまで認めるに足りる証拠はなく,上記判断を 左右するものではない。
(ウ) 以上より,控訴人商品と被控訴人商品とは,本件商標の保証する品質 において実質的に差異がないと評価すべきであり,本件被疑侵害行為は,第3要件 を充足する。
(3) 以上より,本件被疑侵害行為は,第1要件〜第3要件をいずれも充足し, 実質的違法性を欠く。
◆判決本文
原審はこちら。
2018.07. 1
平成29(ワ)123 差止請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年2月14日 東京地方裁判所(29部)
そこで,まず,本件指定役務と被告商品1(緑みかんシロップ)の類否につ いて検討すると,本件指定役務は「加工食料品」という特定された取扱商品につい ての小売等役務であるのに対して,前記前提事実(3),(4)のとおり,被告商品1は, 「シロップ」であって,第32類の「清涼飲料」に属する商品であると認められる (被告商品1が第29類の「加工野菜及び加工果実」に含まれる旨の原告の主張は 採用することができない。)ところ,「清涼飲料」と「加工食料品」は,いずれも 一般消費者の飲食の用に供される商品であるとはいえ,取引の実情として,「清涼 飲料」の製造・販売と「加工食料品」を対象とする小売等役務の提供とが同一事業 者によって行われているのが通常であると認めるに足る証拠はない。 そうすると,被告商品1に本件商標と同一又は類似の商標を使用する場合に,需 要者において,被告商品1が「加工食料品」を対象とする小売等役務を提供する事 業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められる関係には なく,被告商品1が本件指定役務に類似するとはいえないというべきである。
(3)ア 他方で,前記前提事実(3),(4)のとおり,被告商品2(梅ジャム)及び3 (ブルーベリージャム)については,いずれも「ジャム」であって,第29類の 「加工野菜及び加工果実」に属する商品であり,本件指定役務において小売等役務 の対象とされている「加工食料品」と関連する商品であると認められる。
イ しかしながら,一般に,ジャム等の加工食料品の取引において,製造者は小 売業者又は卸売業者に商品を販売し,小売業者等によって一般消費者に商品が販売 される業態は見られるところであり,本件の証拠上も,被告は,その製造に係る梅 ジャム等の商品をパルシステム,生協,ケンコーコム等に販売し,これらの事業者 によって一般消費者に商品が販売されていると認められるほか(上記1(2)),原告 も,商品を自ら一般消費者に販売する以外に,らでぃっしゅぼーや,生協,デパー トに販売し,これらの事業者によって一般消費者に商品が販売されていたと認めら れる(上記1(1))。 そうすると,他方で,ジャム等を製造して直接一般消費者に販売する事業者が存 在するとして原告が提出する証拠(甲40の1・2)の内容を踏まえたとしても, ジャム等の加工食料品の取引の実情として,製造・販売と小売等役務の提供が同一 事業者によって行われているのが通常であるとまでは認めることができないという べきである。
ウ また,商品又は役務の類否を検討するに当たっては,実際の取引態様を前提 にすべきところ,被告標章2を包装に付した被告商品2及び3の取引態様は,上記 1(2)イで認定したとおり,被告と継続的な取引関係があるケンコーコムにおいて, 被告から商品を購入して自社が運営する通販サイトを通じて一般消費者に販売する というものであり,その通販サイトには,ケンコーコムの名称及びロゴが表示され\nていると共に,商品ごとに製造・販売者が表示されている。\nそうすると,ケンコーコムにおいて,被告商品2及び3が小売等役務を提供する 事業者の製造又は販売に係る商品であると誤認するおそれがあるとは認め難く,ま た,通販サイトで被告商品2及び3を購入する一般消費者においても,製造・販売 者とインターネット販売業者を区別して認識すると考えられるから,小売等役務を 提供するインターネット販売業者の製造又は販売に係る商品であると誤認するおそ れがあるとは認め難い。 なお,原告は,将来,原告がケンコーコムと取引を開始した場合には,同社にお いて誤認混同のおそれが生じる旨主張するが,上記1(1)で認定した原告の取引態様 を前提とする限り,同社において小売等役務を提供する事業者の製造又は販売に係 る商品と誤認するおそれを生じるとは認め難い。
エ 以上のとおり,本件の証拠上,ジャム等の加工食料品の取引の実情として, 製造・販売と小売等役務の提供が同一事業者によって行われているのが通常である とまでは認めることができないというべきであり,被告商品2及び3の実際の取引 態様を踏まえて検討しても,被告商品2及び3に本件商標と同一又は類似の商標を 使用する場合に,需要者において,被告商品2及び3が本件小売等役務を提供する 事業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係には ないというべきである。
関連カテゴリー
>> 役務
>> 類似
>> ピックアップ対象
2018.07. 1
平成28(ワ)10736 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年2月27日 東京地方裁判所(46部)
一般的な折り畳み傘は,折り畳んで包袋に入れた状態において円筒形の形 態をしているのに対し,原告商品の形態は,折り畳んで包袋に入れた状態に おいて,原告商品形態を有しているところ,当該形態によって,原告商品は, 全体的に薄く扁平な板のような形状を有することが認められ,円筒形でない だけでなく,それが全体的に薄く,扁平な板のような形状である点で,一般 的な折り畳み傘の形状とは明らかに異なる特徴を有しているといえる。 そして,上記 のとおり,原告商品の広告では原告商品が薄いことが強調 されたこと(上記 ウ ),発売から間もない平成17年1月頃に日本経済 新聞社が主催する2004年日経優秀製品・サービス賞の優秀賞及び日経産 業新聞賞を受賞し,原告商品の形態が説明された上で「新しい時代に先駆け た独創的な新製品」との評価を受けたこと(上記 カ),新聞,雑誌,テレビ 番組等の多数のメディアにおいて原告商品が取り上げられたところ,そこで は原告商品が薄いことが強調されていること(上記 エ),そもそも原告商 品の形態がそれまでの商品の形態とは明らかに異なる原告商品形態である ことから上記のような多数の媒体で取り上げられたと考えられること,一般 消費者もインターネット上の商品販売サイト等に原告商品が薄いとの原告 商品形態を強調する感想を多く書き込んでいること(上記 オ)などからす ると,原告商品は需要者に対し,全体的に薄く扁平な板のような形状を有す る商品であるという強い印象を与えるものといえる。そうすると,原告商品形態は,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していたといえ,原告商品形態には特別顕著性があるといえる。
イ これに対し,被告は,原告商品の他にも折り畳んで包袋に入れた状態が薄 く扁平な板のような形状となる折り畳み傘(乙5(乙15〜17は乙5の折 り畳み傘の写真である。),7,18〜21)や折り畳んだときの形状が薄く 扁平な板のような形状になる折り畳み傘の骨組み(乙10,11,13)が 存在し,このうち,乙第5号証及び乙第7号証の商品は原告商品が販売され るより前から販売されていたこと,折り畳んだときの傘の骨組みが直方体と なる形状の実用新案登録及び特許出願もされていた(乙1〜4)ことから, 薄く扁平な板のような形状を有する折り畳み傘はありふれた形態であって 原告商品形態に特別顕著性はない旨主張する。
しかし,原告商品が販売される前から,一定の形状の折り畳み傘の骨組み が存在し,また,骨組みの形状に関する実用新案登録等がされていたとして も,それは骨組みに関するものであって,それを利用した折り畳み傘の形態 は不明であり,折り畳み傘の形態としての原告商品形態の特別顕著性の有無 を直ちに左右するものとはいえない。また,被告が指摘する商品(乙5,7, 18〜21)には,折り畳んで包袋に入れた状態が円筒形ではなく,直方体 に似た形状を有するものもある。しかし,被告が指摘する商品はいずれも販 売数量及び売上高は明らかになっておらず,市場において広く流通している 商品であると認めるに足りる証拠はないこと,乙第5号証及び乙第7号証の 商品は既に販売が終了していること(乙6,8,41)などからすると,上 記各商品によって,原告商品形態がありふれており,他の商品と識別し得る 特徴を有しないとはいえない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.07. 1
平成29(ワ)5423 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年3月26日 東京地方裁判所(29部)
被告は,被告は被告各商品に原告標章の一部を使用したが,それは飽くまでデザイ ンとしての使用であり,原告標章と同一又は類似のものを商品等表示として使用した\n商品を販売等していない旨主張するので検討する。
不正競争防止法2条1項2号の趣旨は,著名な商品等表示について,その顧客吸引\n力を利用するただ乗りを防止するとともに,その出所表示機能\及び品質表示機能\が稀 釈化により害されることを防止するところにあると解されるから,同号の不正競争行 為というためには,単に他人の著名な商品等表示と同一又は類似の表\示を商品に付し ているというだけでは足りず,それが商品の出所を表示し,自他商品を識別する機能\ を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。 これを本件についてみるに,前記認定のとおり,原告はバッグ類,袋物及び被服等 で知られる世界的に著名な高級ブランドを擁するフランス法人であるところ,原告標 章は,1896年から現在まで原告商品に使用されて世界的に広く知られる標章であ り,原告商品にのみ付され,大規模かつ継続的な宣伝広告により,著名性を有するも のであることからすれば,高い出所識別機能を有する商品等表\示として使用されてい るものである。そして,その使用態様は,商品に応じて原告モノグラム表示の一部を\n切り取って商品に付されて使用されるという特徴を有しており,必ずしも「LOUI S VUITTON」との文字商標を必要とはしていない。
被告標章1ないし7は,原告標章を構成する原告記号aないしdと同一の記号によ\nり構成され,その配置も原告標章と同一なものの一部分であり,被告標章8は,被告\n記号eや,被告記号aないしdをカラーにした点が異なるが,それらの記号が原告標 章と同一の配置とされたものの一部分であり,被告各商品に応じて被告各標章の一部 を切り取って商品に付されて使用されている。 このような被告各標章の使用態様からすると,被告各標章は出所識別機能を有する\n態様で用いられているものと認められ,デザインとしての使用であり商品等表示とし\nて使用ではない旨の被告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> 著名表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.06.29
平成30(行ケ)10001 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年6月21日 知的財産高等裁判所
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類 似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を 生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用され た商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記 憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引 の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するの が相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2 号399頁参照)。 また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,\n商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思\nわれるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽\n出し,当該部分だけを他人 色で縁取りされた白色無地の扇形とで構成される図形と,当該扇形の内側\nに黒色の明朝体風の書体で横一列に「ありがとう」の文字が記載されたも ので,結合商標と解される。
イ 引用商標の構成中,「ありがとう」の文字部分は,図形の内部に記載さ\nれているものの,引用商標の中央下部に位置し,商標の横幅いっぱいの大 きさがある白色無地の扇形の中というひときわ目立つ場所に,当該扇形の 横幅全体を使うほどの大きさで,黒色の読み取りやすい書体で明瞭に記載 されているから,外観上,主として招き猫とそれが支持する扇形とからな る図形部分(招き猫の図形部分)と一見して明確に区別して認識できる。 そして,「ありがとう」の語は,平仮名5文字からなる極めて平易なもの であって,称呼しやすく,感謝の意を表す際に日常的に多用される馴染み\nのある言葉であることを考え合わせると,「ありがとう」の文字部分は, 引用商標を見る者に強い印象を与えるとともに,その注意を強く引くもの であると認めるのが相当である。 これに対し,招き猫の図形部分と「ありがとう」の語とが,観念的に密 接な関連性を有しているとは考え難いし,一連一体となった何かしらの称 呼が生じるともいえない。また,招き猫の図形部分及び「ありがとう」の 文字部分は,指定役務との関係で,当該役務の質等を表すものともいえな\nい上,このほかに各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足\nりる的確な証拠も見当たらない。 これらの事情を総合すると,招き猫の図形部分と「ありがとう」の文字 部分とが,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不 可分的に結合していると認めることはできないから,当該図形部分と当該 文字部分は,それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であるという\nべきである。
ウ 以上によれば,引用商標においては,その全体から「アリガトウ」の称 呼及び「感謝の意を表す招き猫」といった程度の観念がそれぞれ生じると\n認められる。 そして,招き猫の図形部分からは特定の称呼を生じないものの,「招き 猫」との観念が生じ,また,「ありがとう」の文字部分から,「アリガト ウ」の称呼及び「感謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念がそれ ぞれ生じると認められる。
(4) 本願商標と引用商標の類否
本願商標と,引用商標の要部である「ありがとう」の文字部分とは,外観 上,書体の相違以外は同一であり,さらに,上記(2)及び(3)において説示し たとおり,両者は称呼上も観念上も同一である。 したがって,本願商標と引用商標とは,出所について誤認混合を生ずるお それがあり,両商標は類似するものというべきである。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.06.28
平成29(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年6月26日 知的財産高等裁判所
本願について,特許協力条約規則17.1(a),(b)及び(bの2)の要件 のいずれも満たされないこと,並びに,JPOが,事情に応じて相当の期間内に原 告らに優先権書類を提出する機会を与えたことは,当事者間に争いがない。 原告らは,JPOが,本願について,特許協力条約実施細則715(a)の定め るところにより本件基礎出願に基づく優先権書類を電子図書館から入手可能である\nとみなされることをもって,特許協力条約規則17.1(d)にいう,指定官庁が 実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た\nるから,JPOは,同規則17.1(d)により,本件基礎出願に基づく優先権の 主張を無視することができない旨主張する。
ア 特許協力条約実施細則の定め しかし,まず,本件基礎出願の出願日(優先日)から16か月後の平成21年1 2月1日時点において効力を有する特許協力条約実施細則には,電子図書館に関す る規定は存在しない(乙11)。したがって,本願について,JPOは,「実施細 則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能」ではないから,特\n許協力条約規則17.1(d)により,本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視 することができないということはできない。そうすると,JPOは,同規則17. 1(c)により,相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えた上で, 優先権の主張を無視することができるところ,原告らが,特許法施行規則38条の 14に規定する期間内に,優先権書類を提出していないことは当事者間に争いがな い。よって,JPOは,特許協力条約規則17.1(c)により,本件基礎出願に基 づく優先権の主張を無視することができる。
イ 特許協力条約実施細則715(a)の事後的な充足 特許協力条約実施細則715は,本件基礎出願の出願日の16か月後である平成 21年12月1日時点においては存在しなかったものであるが,本願についてJP Oが出願人に優先権書類を提出する機会を与えた相当の期間(特許法施行規則38 条の14に規定する期間)が経過する前である平成22年1月1日に効力が生じた ものである。 仮に,特許協力条約規則17.1(c)及び(d)の規定について,出願人に優 先権書類を提出する機会を与えた相当の期間内に,JPOが特許協力条約実施細則 715(a)(i)の「通知」をするなどすれば,JPOは優先権の主張を無視で きないと解釈したとしても,後記ウのとおり,JPOが,同実施細則715(a) (i)の「通知」をしたとの事実は認められない。 したがって,JPOが特許協力条約実施細則715(a)に定めるところにより 本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとはみなされないから,\nJPOは,特許協力条約規則17.1(d)の規定の適用上,優先権書類を電子図 書館から入手可能な場合に当たらない。JPOは,同規則17.1(d)により,\n本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできな い。 よって,仮に,特許協力条約規則17.1(c)及び(d)の規定について,上 記のとおり解釈したとしても,本願は,同規則17.1(d)にいう,指定官庁が 実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た\nらないから,JPOは,同規則17.1(c)により,本件基礎出願に基づく優先 権の主張を無視することができる。
2018.06.28
平成30(ネ)10001 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (a) 1審被告Aは,1審被告白石の代表取締役であり,1審被告白\n石の事業全般を統括していたが,平成22年6月4日,1審被告白 石宛ての1審原告の通知書(親和製作所の装置の販売が本件特許権 侵害である旨を指摘するもの)を受領し,本件特許権の存在を知る に至った。さらに,1審被告Aは,平成24年1月12日,1審被 告白石宛ての1審原告の通知書(親和製作所と1審原告の和解に関 するもの)を受領した。(甲15の資料5,資料9,乙73)
(b) 東京地方裁判所は,本件仮処分申立事件についての平成26年\n10月8日の審尋期日において,被告装置(WK型)が本件特許権 に係る発明の技術的範囲に属する旨の心証開示をした。(甲18)
(c) 1審被告白石は,平成26年10月24日から同月28日まで の間に,渡邊機開から,被告装置(WK型)を合計14台,本件板 状部材153個及び本件固定リング123個を購入した。1審被告 白石の平成23年から平成25年にかけての本件固定リングの購入 数は合計20個未満であり,平成26年10月24日から同月28 日までの本件固定リングの購入量はこれまでの取引状況に比して突 出して多い。(甲17の1,2)
(d) 東京地方裁判所は,平成26年10月31日,渡邊機開による 被告製品(WK型),本件固定リング及び本件板状部材の販売等を 差し止める旨の本件仮処分決定をし,1審原告は,同年11月4日 付け通知により1審被告白石に対しその旨を通知した。(甲15の 資料10)
(e) 1審被告白石は,本件仮処分決定後は,平成26年11月14 日頃から平成27年4月1日にかけて被告装置を販売した。
(f) 1審被告白石は,平成27年2月26日,鶴商に型式名を「L S−S」とする被告装置(実質は「WK−550」)を販売し,ま た,同年5月までには,渡邊機開からWK型として仕入れた被告装 置(「WK−600」)に,構成の変更がないのに「LS−G」型\nの表示を付したものを取り扱っていた。(上記2(1),甲22)
c 1審被告Aは,1審被告白石の事業全般を統括していたのであるか ら,1審被告白石の取引実施に当たっては,第三者の特許権を侵害し ないよう配慮すべき義務を負っていたというべきである。この観点か ら1審被告Aの責任について検討してみると,まず,平成22年6月 4日及び平成24年1月12日の時点で,1審被告Aにおいて,被告 装置が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属することを知っていた ことを認めるに足りる証拠はない。なお,平成24年1月12日頃に 1審被告白石が1審原告から通知書を受領したことは上記b(a)のと おりであるが,その通知書の内容は親和製作所の装置に関するもので あり,渡邊機開製の被告装置とは直接関わるものではなかったのであ るから,1審被告Aが上記時点において被告装置につき専門家に問い 合わせるなどの調査等をせず,被告装置の販売を中止しなかったから といって,1審被告Aに重過失があったとすることはできない。 これに対し,上記b(d)によれば,1審被告Aは平成26年11月 初旬には本件仮処分決定について知ったものと認められるから,これ によって被告装置が本件特許権を侵害するおそれが高いことを十分に\n認識することができたと認められる。ところが,1審被告Aは,本件 仮処分決定を踏まえて,中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討 をした形跡もないまま,取引を継続し,さらに被告装置の型式名につ いて工作をするなどしているのであり,これら上記bに認定した本件 仮処分決定前後の経過に照らせば,同月以降の1審被告白石による被 告装置の販売を中止するなどの措置をとらなかった1審被告Aには, 1審被告白石による本件特許権侵害について悪意又は少なくとも重大 な過失があったというべきである。 よって1審被告Aは,1審被告白石による被告装置の販売に係る 同月以降の本件特許権侵害について,会社法429条1項の責任を負 う。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> ピックアップ対象
2018.06.28
平成29(ネ)10029 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被控訴人は,本件再訂正に係る訂正審判請求等がされていないし,今後, このような手続が可能であるとはいえないから,本件再訂正がされたこと\nを前提とする本件再訂正発明3に基づく権利主張はできないと主張する。 この点について検討するに,特許権者が,事実審の口頭弁論終結時まで に訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に訂正審決等が 確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り, 特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,特許法1 04条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。すな わち,特許権侵害訴訟において,特許権者は,原則として,事実審の口頭 弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなければならない。(最高裁平成 29年7月10日第二小法廷判決・民集71巻6号861頁参照)。 本件についてみると,被控訴人は,平成29年8月7日の当審第2回口 頭弁論期日において,甲26(参考資料3)発明に周知技術である基板ア ライナーを直接適用することによっても,相違点4に係る構成が容易に想\n到できるという,新たな組合せに基づく無効の抗弁を主張し,控訴人は, これを踏まえて,同年10月11日の当審第3回口頭弁論期日において, 本件再訂正に係る訂正の再抗弁の主張をした(裁判所に顕著な事実)。そ して,本件審決に係る審決取消訴訟は当裁判所に係属しており,控訴人は, 当審の口頭弁論終結時までに,本件再訂正に係る訂正審判請求等を法律上 することができなかった(特許法126条2項,134条の2第1項)。 そうすると,特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手 続内で迅速にかつ一回的に解決することを図るという特許法104条の3 及び104条の4の各規定の趣旨に照らすと,本件の事実関係及び審理経 過の下では,被控訴人による新たな無効の抗弁に対する本件再訂正に係る 訂正の再抗弁を主張するために,現に本件再訂正に係る訂正審判請求等を している必要はないというべきである。 また,仮に,本件審決に係る審決取消訴訟において,本件審決を取り消 す旨の判決がされ,これが確定した場合には,本件無効審判手続が再開さ れるところ,この再開された審判手続等において,控訴人が本件再訂正に 係る訂正請求をすることができないとは直ちにいえない。
◆判決本文
対応する審取です。
関連カテゴリー
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2018.06.27
平成29(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年6月19日 知的財産高等裁判所
上記記載事項によれば,めっき処理を行った亜鉛又は亜鉛系め っき鋼板において,酸化性雰囲気中で加熱を行うことによって,亜鉛の蒸 発を阻止するバリア層として酸化皮膜層が形成されるが,亜鉛又は亜鉛系 めっきの共通成分は亜鉛であり,亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がいずれも均 一な酸化皮膜を形成し,塗膜密着性,耐食性が良好という共通の性質を有 することが理解できる。そうだとすれば,当業者であれば,当然,本件発 明1の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」 であると理解すると認められる。 してみると,本件発明1の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」 が,亜鉛系めっきに由来する亜鉛の酸化皮膜を意味することは明確である といえる。このことは,本件発明1を引用する本件発明2ないし6及び(同 様の文言を有する)本件発明7についても同様である。
ウ 原告の主張について
原告は,本件訂正によって,特許請求の範囲の記載にあった「亜鉛また は亜鉛系合金のめっき層」に代えて,「スズ−亜鉛合金めっき層」などの 具体的な合金めっき層が記載されたこと,本件明細書においては,「スズ −亜鉛合金めっき」の具体例としては,「スズ−8%亜鉛合金めっき」の みが記載されている(【0038】)こと,「スズ−8%亜鉛合金めっき」 を加熱した場合に生ずる変化については本件明細書に全く記載がないこと などを挙げて,「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が亜鉛の酸化皮膜でな ければならないと当然に解釈できるとはいえないから,金属酸化物の種類 が不明確であると主張する。 しかしながら,本件明細書の記載から,亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がい ずれも均一な酸化皮膜を形成し,塗膜密着性,耐食性が良好という共通の 性質を有することが理解でき,当業者であれば,本件発明1の「加熱時の 亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」であると理解する と認められることは,前記ア,イのとおりである。他方,「スズ−8%亜 鉛合金めっき」についてのみ,これと異なる理解をすると認めるべき合理 的事情はない。
したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
(2) 酸化皮膜の形成時期について
ア 原告は,本件訴訟におけるのと同様に,先行事件訴訟においても,「亜 鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期が明らかでないと主張して明確 性要件を争っており,その結果,原告の主張を排斥する先行事件判決がな され,同判決は既に確定しているものである(当裁判所に顕著な事実)。 そうすると,原告が本件訴訟において再びこの点を争うことは,実質的 に前訴の蒸し返しに当たり,訴訟上の信義則に反するものとして許されな いというべきである。
よって,この点に関する原告の主張も採用できない。
イ 念のため,中身について検討してみても,この点に関しては,先行事件 判決が示すとおり,本件明細書の【0018】には,酸化皮膜は熱間プレ スに先立つ加熱前にある程度形成されることが必要で,その後熱間プレス 加工のための700〜1000℃の加熱によっても形成が進むと推測され ることが記載され,【0042】及び【0043】には,酸化皮膜は,熱 間プレス加工のため700〜1000℃に加熱する前に,予め形成されて\nいる場合と形成されていない場合があることを前提として,予め酸化皮膜\nが形成されている材料の場合には,酸化皮膜の維持に悪影響がない限り熱 間プレスのための加熱方法については特に制限がないことが記載され,さ らに,【0064】及び【表5】には,実施例No.2,3として,電気\nめっきを施した後,熱間プレスに先立つ加熱を大気炉で850℃,3分間 行ったものについて均一な酸化皮膜が形成されたことが記載されていると ころ,電気めっきにおいては,めっき層は加熱されないことから,上記実 施例はいずれも熱間プレスに先立つ加熱前に予め酸化皮膜が形成されてい\nない場合であって,この場合の酸化皮膜は,熱間プレスのための加熱(大 気炉で850℃,3分間)により形成されたものと理解することができる。 そうすると,本件発明の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は, 熱間プレスの加熱前に,予め形成されている場合,ある程度形成されてい\nてその後熱間プレスの加熱時に形成が進む場合,予め形成されていないが\n熱間プレスの加熱により形成される場合のいずれでもよいことから,その 形成時期は熱間プレスの直前までであればよいと解するのが相当である。 したがって,本件発明1及びこれを引用する本件発明2ないし6並びに 本件発明7の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期は, 本件明細書の発明の詳細な説明を参照すれば明確というべきであるから, 原告の主張はいずれにしても失当である。
(3) 「700〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス 用」について
ア 本件明細書の【0016】ないし【0018】,【0029】,【00 34】,【0042】,【0044】,【0048】,【0050】及び 【0064】には,熱間プレスは700〜1000℃という温度で加熱す ることを意味すること,熱間プレス成形の特徴として成形と同時に焼き入 れを行うことから,そのような焼き入れを可能とする鋼種を用いること,\n熱間成形後に急冷して高強度,高硬度となる焼き入れ鋼,例えば表1にあ\nるような鋼化学成分(鋼種A等)の高張力鋼板が実用上は特に好ましいこ と,700〜1000℃の温度で加熱してから熱間プレスを行い,めっき 層表面に亜鉛の酸化皮膜が,下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層\nとして全面的に形成されていること,具体的には,表1に示す鋼種Aを,\n大気雰囲気の加熱炉内で950℃×5分加熱して,加熱炉より取り出し, このままの高温状態で円筒絞りの熱間プレス成形を行うこと,また,熱間 プレスに先立つ加熱を,大気炉で850℃,3分間行うことが記載されて いる。 そして,これらの記載によれば,本件発明1の「700〜1000℃に 加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」という文言において, 1)「700〜1000℃に加熱されて」は,熱間プレスの加熱条件であり, 2)「プレスされ焼き入れされる」は,成形と同時に焼き入れを行う熱間プ レス成形の特徴であり,3)「用」という文言の意味は,「(接尾語的に) …に使うためのものの意を表す」(広辞苑第六版)であることからすると,\n「熱間プレス用」は,後に続く,本件発明1の「鋼板」を修飾し,鋼板が 熱間プレスに使うためのものであることを意味するものと理解できる。 してみれば,「700〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れさ れる」は,「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現するものと理解でき\nるから,本件発明1の「700〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き 入れされる熱間プレス用」という文言は明確である。このことは,本件発 明1を引用する本件発明2〜6及び(同様の文言を有する)本件発明7に ついても同様である。
イ 原告の主張について
原告は,本件発明は用途発明であるとした上で,種々理由を述べて,「7 00〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」 という記載の意味が不明確であると主張する。 しかしながら,前記アのとおり,「700〜1000℃に加熱されてプ レスされ焼き入れされる」は,「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現\nするものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,本 件発明1の「700〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる 熱間プレス用」という文言の意味は明確である。 また,本件発明1が用途発明であるか否かは,その結論を左右するもの ではない。
◆判決本文
関連事件は以下です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.06.25
平成29(ネ)10096 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本質的部分について、上位概念化できるかについての判断基準について言及しています。
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なか った技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想 に基づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって,\n特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち, 従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきで\nある。
そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許 発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範 囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が\n何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち,特許発明の 実質的価値は,その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定め られることからすれば,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記 載,特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。そして,従来 技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には,特許請求の 範囲の記載の一部について,これを上位概念化したものとして認定され,従来技術 と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には,特許 請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。
ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところ が,出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には,明細書に記載さ\nれていない従来技術も参酌して,当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には,特許\n発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に 比べ,より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり,均等が認められる範囲が より狭いものとなると解される。
・・・・
本件特許出願日以前に,キャラクター画像情報に対する課金方法として,携帯端 末自体を改めて販売する態様ではないもの,すなわち,毎月100円を支払うこと により携帯電話機へ毎日異なるキャラクタ画面データを配信するiモード上での上 記サービス「いつでもキャラっぱ!」が公知であったこと(乙6),及びiモード においてはコンテンツプロバイダー(情報提供者)がコンテンツの情報料をNTT ドコモから携帯電話の通信料と合わせて課金し得るシステムが採用されていたこと (乙9)が認められる。このことに鑑みれば,本件特許出願日において,「サービ ス提供者にとっても,…キャラクター画像情報を更新するには,携帯端末自体を改 めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情報により効率良く利益を得るの は困難であった。」(本件明細書【0003】)との課題が未解決のままであった とは認められない。
d しかるに,本件明細書には,乙6,8及び9記載の上記技術についての記載 はない。したがって,本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載さ れているところは,本件特許出願日における従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。\nそうすると,本件発明の本質的部分は,本件明細書の記載に加えて,乙6,8及 び9記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。
(オ) そして,本件明細書の記載並びに乙6,8及び9記載の前記技術によれば, キャラクター選択・変更等の態様に関する構成(前記1)並びに2)及び3)の組合せ) について,本件明細書は,複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラクターを 創作決定すること(前記2)及び3))を携帯端末サービスシステムで提供する(前記 1))という発想自体を開示するにとどまり,このようなシステムの実装における未 解決の技術的困難性を具体的に指摘し,かつ,その困難性を克服するための具体的 手段を開示するものではないので,従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さ いというべきである。 キャラクターの選択等に対する課金に関する構成(前記2)及び3)並びに4)の組合 せ)についても,本件明細書は,複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラク ターを創作決定し(前記2)及び3)),当該決定したキャラクターに応じた情報提供 料を通信料に加算する(前記4))という発想自体を開示するにとどまり,このよう な課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し,かつ,その困 難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので,従来技術に対する 本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。 そうすると,本件発明の本質的部分については,特許請求の範囲の記載とほぼ同 義のものとして認定するのが相当である。
・・・・
前記認定の出願経過によれば,控訴人は,構成要件A〜C及びHからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)及び構\成要件A〜E及びHからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項2に係る発明)については,特許 を受けることを諦め,これらに代えて構成要件A〜Hからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に同2及び5を統合した発明,すなわち本件発明)に限定\nして,特許を受けたものということができる。 そうすると,控訴人は,構成要件F及びGの全部又は一部を備えない発明について,本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか,少なくとも外形的にその\nように解されるような行動をとったものと理解することができる。 したがって,均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり,均等の第 5要件を充足しない。
ウ 控訴人の主張について
この点につき,控訴人は,被告システムは「仮想モール」に相当する構成を有しているから,本件特許の出願経過を参酌したとしても,均等の成立を妨げる特段の\n事情があるとはいえない旨主張する。 しかし,前記のとおり,本件発明の「仮想モール」は「ショップ」というカテゴ リーを選択することによってアイテムを購入する仕組みを包含するものではなく, また,本件明細書【0045】は本件発明の「仮想モール」を説明するものと見る ことができない以上,当該段落が当初から残存していたという本件特許の出願経過 も,本件発明の「仮想モール」の技術的意義を左右するものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2018.06.20
平成30(行ケ)10015 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年6月13日 知的財産高等裁判所
原告は,1)本件商品が平成29年3月15日に被告のオンラインショップ でタオルとして販売開始されていること,2)「TL」という品番からして本件商品 は当初から「タオル」であって「ふきん」ではないと考えられること,3)アシスト 社への販売価格がライフブリッジ社からの仕入価格と同一であって不自然であるこ となどからすると,甲30〜33,36の信用性には重大な疑いがあると主張する。 まず,上記1)の主張は,被告のオンラインショップで発売されたタオル(甲2) が,本件商品と全く同一のものであることを前提としていると解されるが,被告代 表者は,当審において,オンラインショップで発売されたタオル(甲2)は,素材\nやデザイン等は本件商品と同一であるものの,本件商品とは別に,当初から「タオ ル」として,本件使用商標を付すことなく生産した本件商品とは異なる物であると 述べている。そして,この供述は,オンラインショップで発売されたタオル(甲2) には本件下げ札が付けられていないことと整合している上,内容的に明らかに不自 然な点も見当たらない。そうすると,本件商品と同じ素材やデザイン等からなる「タ オル」が被告のオンラインショップで平成29年3月から発売されたとしても,不 自然ではなく,前記2の認定を左右するものということはできない。 また,上記2)の主張について,「TL」という品番から直ちに本件商品が実際には 「タオル」であったとまで断ずることはできず,また,被告においては,オンライ ンショップでの販売は主たる事業ではなく,卸売が主たる事業であって,オンライ ンショップで販売される商品は,全取扱商品の20パーセントに満たない程度の商 品であり,オンラインショップの担当者がその判断で品名と発売時期を決定してい るものと認められる(被告代表者[当審])から,ふきんがオンラインショップで販\n売されていないとしても不自然ではない。 さらに,上記3)の主張について,証拠(甲18,19,被告代表者[当審])及び\n弁論の全趣旨によると,被告とアシスト社は代表者を同じくするグループ会社であ\nると認められることや被告がその他の商品と合わせて単価を決定した旨主張してい ることからすると,仕入価格と販売価格が同一であるとしても,直ちに不自然であ るとはいえない。
(2) 原告は,1)一緒に写りこんでいる商品のオンラインショップにおける発売 時期からすると,商品写真(甲29)は実際には平成29年2月末又は3月初めに 撮影されたものである,2)被告とアシスト社との関係やその内容からすると,証明 書2(甲37)は信用できない,3)請求書(甲35)は宛名がなく不自然である, 4)出荷伝票(甲34)は品番に誤りや不自然な点があって信用できないなどと主張 する。 まず,上記1)の主張について,上記(1)記載のとおり,被告においてはオンライン ショップでの販売は主たる事業ではなく,卸売が主たる事業であって,オンライン ショップの担当者がその判断で品名と発売時期を決定していることを踏まえると, 一緒に写りこんでいる他の商品が平成29年になって被告のオンラインショップで 発売されたからといって,商品写真(甲29)が,原告の主張するとおり,平成2 9年になってから撮影されたものと断ずることまではできない。 また,上記2)の主張について,証明書2(甲37)は,被告のグループ会社であ るアシスト社の従業員によって作成されたものであるが,他の証拠(甲34,35, 被告代表者[当審])と符合しており(前記2(2)),その限度では信用することがで きるものである。特許庁に提出された回答書(甲25)の内容に言及している点は, 自らが経験していない事実についての言及を含むものであるが,そうであるからと いって,その他の点まで信用することができないということにはならない。 さらに,上記3)の主張について,請求書(甲35)には宛名が記載されていない が,代表者を同じくするグループ会社間の取引について発行されたものであること\nを踏まえると,不自然で,請求書そのものの信用性が失われるとまではいえない。 そして,上記4)の主張について,出荷伝票(甲34)に記載された品名がオンラ インショップや被告のウェブサイトに記載された品名と異なっているからといって, 直ちに誤りであるとか不自然であるとか捏造されたということはできない。
(3) 原告は,1)口頭審理を拒否するなどの審判における被告の対応,2)4500 枚の本件商品のうち本件店舗に引き渡されたわずかのもの以外の行方が明らかとさ れていないこと及び3)第三者が作成した客観的な書類が提出されていないことなど からも,被告による本件商標の使用事実は存しないと主張する。 しかし,被告は,本件商標のブランド化がうまく進まない中で,本件商標を維持 するために費用や時間を費やすのに消極的な姿勢を見せているのであり(被告代表\n者[当審],弁論の全趣旨),そのような被告が,弁理士に要する費用や本件に対応 するための時間を節約しようと考えて,口頭審理を拒否するなど必要最小限の主張 立証しかしなかったとしても,直ちに不自然,不合理であるとはいえない。 また,本件では第三者たるライフブリッジ社の納品責任者が作成した客観的な取 引書類といえる納品書(甲31)が提出されているのであって,その他の第三者が 作成した書類が提出されていないからといって,前記2の認定が左右されるもので はない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2018.06.15
平成30(ネ)10009 損害賠償等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成30年6月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,原告商品は,直針状の出口ノズルがフィーダ本体部の先端か ら突き出た形状で,配線チューブ等がフィーダ本体上部後端からまっすぐ に伸びている上,小型かつ軽量である点に特徴があるところ,被告各製品 もこの点において共通する形態及び構成を有していると主張する。\n この点につき検討するに,半田フィーダは,径の小さい半田(直径が1 ミリメートルに満たないものもある)を,半田付けしようとする位置に案 内するために用いられるものであるから,正確に位置決めをしたり,他の 機器との干渉を防いだりするために,供給する半田の出口に当たる出口ノ ズルを細長い直針状の形態とすることは,半田フィーダとしての機能を確\n保するために不可欠な形態というべきである。このことは,他社の半田フ ィーダが同様の形態を採用していることからも明らかである(乙11,1 2)。 また,出口ノズルに向けて半田を供給する際には,チューブ等の供給・ 支持部材と半田とが接触して,半田が曲がったり,摩擦による抵抗が生じ たりすることをできるだけ抑制し,安定して半田を供給する必要があると 考えられるところ,そのために,半田フィーダにおいて,半田の供給口に 当たる部材を出口ノズルの反対側の位置に出口ノズルに対してまっすぐに 取り付ける構成を採用することは,ごく自然な着想といえる。このことは,\n同様の構成を有する他社の半田フィーダが存在することによっても裏付け\nられているというべきである(乙12,15〜17)。 さらに,配線チューブがフィーダ本体上部後端からまっすぐに伸びてい る点についても,ある機器に何らかのチューブが取り付けられている場合 に,取り回し等の観点から複数のチューブをまとめて同方向に取り出すこ とは,他社の半田フィーダにおいても同様の構成が採用されていることが\n認められるように(乙15〜17),極めて容易に着想し得る一般的な構\n成というべきである。 なお,商品の重量そのものは,不競法2条4項が定める「商品の形態」 に当たるとはいえない。 以上によれば,控訴人が原告商品の特徴的形状であると主張する形態は, いずれも半田フィーダという商品が通常有する形態にすぎないというべき である。
・・・
著作権法上の美術の著作物として保護される ためには,仮にそれが産業用の利用を目的とするものであったとしても, 美的観点を全く捨象してしまうことは相当でなく,何らかの形で美的鑑賞 の対象となり得るような創作的特性を備えていなければならないというべ きである。 控訴人が主張するように,原告商品は,ステッピングモータの一部分が 飛び出している点を除き,出口ノズルから配線チューブ等に至るまで,各 構成が概ね直線状にコンパクトにまとめられた形態を有していることが認\nめられる。しかし,原告商品の外観からは,社会通念上,この機器を動作 させるために必要な部材を機能的観点に基づいて組み合わせたもの,すな\nわち技術的思想が表現されたものであるということ以上に,端整とか鋭敏,\n優雅といったような何かしらの審美的要素を見て取ることは困難であると いわざるを得ず,原告商品が美的鑑賞の対象となり得るような創作的特性 を備えているということはできない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2018.06.15
平成29(行ケ)10228 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年6月13日 知的財産高等裁判所
この点に関し原告は,フィールドハウスのヴァンヂャケットに対する本件 ベルトの譲渡行為は,関連会社間の単なる商品の移動であって,本件商標の 登録の不使用取消しを免れる目的で,名目的に本件使用商標を使用する外観 を呈する行為にすぎないから,商標法2条3項2号の使用に該当しない旨主 張する。 そこで検討するに,原告が主張するように,被告の代表取締役のAは,フ\nィールドハウス及びヴァンヂャケットの筆頭株主であること,被告の取締役 のBは,ヴァンヂャケットの社長であること,フィールドハウスの代表者の\nCは,ヴァンヂャケットの取締役であることが認められ(甲3ないし5,弁 論の全趣旨),被告,フィールドハウス及びヴァンヂャケットは,役員の一 部が共通し,相互に資本関係のある関連会社であるといえる。 しかしながら,被告,フィールドハウス及びヴァンヂャケットは,別個の 法人であって,前記1(1)認定のとおり,フィールドハウスのヴァンヂャケッ トに対する本件使用商標を付した本件ベルトの販売,納品は,売買取引の実 体を伴うものであり,関連会社間の単なる商品の移動ということはできない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
2018.06.14
平成29(行ケ)10214 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年6月12日 知的財産高等裁判所
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,称呼において相紛らわしいものであっ て,外観においても相紛らわしい点を含むものということができる。
(3) 引用商標の周知著名性及び独創性の程度
ア 怪獣映画に登場する怪獣である「ゴジラ」は,原告によって創作されたもの であり(甲4),「ゴジラ」が著名であることは当事者間に争いがない。 イ 怪獣映画に登場する怪獣である「ゴジラ」には,昭和30年,欧文字表記として引用商標が当てられ,その後,引用商標が「ゴジラ」を示すものとして使用さ\nれるようになったものである(甲7,8)。欧文字表記の引用商標は,我が国において,遅くとも昭和32年以降,映画の広告や当該映画中に頻繁に使用され(甲7,\n8,21,39〜43,46〜50,55,79,80,81の1〜3,82,8 4),遅くとも昭和58年以降,怪獣である「ゴジラ」を紹介する書籍や,これを 基にした物品に多数使用されていること(甲17,18,21,22,26,45, 52〜54,56〜61,63〜73,77,78,86の1,92,101の3, 102の4,162),さらに,怪獣である「ゴジラ」の英語表記として多くの辞書にも掲載されていること(甲125〜129,143〜153)からすれば,引\n用商標は著名であるということができる。
ウ 語頭が「G」で始まり,語尾が「ZILLA」で終わる登録商標は,引用商 標の他には,本件商標を除き見当たらない。架空の怪獣の名称において,語頭が濁 音で始まり,語尾が「ラ」で終わる3文字のものが多いとしても,これらは怪獣「ゴ ジラ」が著名であることの影響によるものと認められ(甲173,174),さら に,欧文字表記において,引用商標と類似するものも見当たらない。エ 以上によれば,引用商標は周知著名であって,その独創性の程度も高いとい うべきである。
(4) 商品の関連性の程度,取引者及び需要者の共通性
ア 商品の関連性の程度
本件指定商品は,第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用 機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」である。本件指定商品には,専門的・ 職業的な分野において使用される機械器具が含まれる。また,これに加えて,本件 指定商品のうち,「荷役機械器具」には,油圧式ジャッキ,電動ジャッキ,チェー ンブロック,ウインチが,「農業用機械器具」には,刈払機,電動式高枝ハサミ, ヘッジトリマ,草刈機が,含まれる(甲225,226,231〜234,243, 253,乙18)。
これに対し,原告の主な業務は,映画の制作・配給,演劇の制作・興行,不動産 経営等のほか,キャラクター商品等の企画・制作・販売・賃貸,著作権・商品化権・ 商標権その他の知的財産権の取得・使用・利用許諾その他の管理であり(甲135), 多角化している。原告は,百社近くの企業に対し,引用商標の使用を許諾している ところ,その対象商品は,人形やぬいぐるみなどの玩具,文房具,衣料品,食料品, 雑貨等であるなど,多岐にわたる(甲12,83〜96,98〜102,199〜 211(枝番を含む。))。
本件指定商品のうち専門的・職業的な分野において使用される機械器具と,原告 が引用商標の使用を許諾した玩具,文房具,衣料品,食料品,雑貨等とは,前者が, 工場や事業所などの産業現場で,人間の業務を補助する機械であって,専らその性 能や品質などが商品選択の基準とされるのに対し,後者は,日常生活で,一般消費者によって使用される物であって,同種製品との差別化が難しいものであるから,\n性質,用途及び目的における関連性の程度は高くない。 一方,本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ,電動ジャッキ,チェーンブロッ ク,ウインチ,刈払機,電動式高枝ハサミ,ヘッジトリマ,草刈機等の商品は,ホ ームセンター等の店舗やオンラインショッピング,テレビショッピングにおいて, 一般消費者に比較的安価で販売され得るものである(甲235〜242,244〜 252,254(枝番を含む。))。そうすると,これらの商品は,日常生活で, 一般消費者によって使用される物であって,同種製品との差別化が難しいものとい うことができる。これらの商品は,一般的な玩具等とは異なり,使用方法によって は,身体・財産に危険が生じるものではあるが,比較的小型の機械器具であって, その操作方法も比較的単純であるから,専門的な業務用途に限られるものではなく, 特別な知識,能力を有する者のみにその使用が限定されるものでもない。したがって,本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ,電動ジャッキ,チェーンブロック,\nウインチ,刈払機,電動式高枝ハサミ,ヘッジトリマ,草刈機等と,原告が引用商 標の使用を許諾した玩具,雑貨等とは,ホームセンター等の店舗やオンラインショ ッピング,テレビショッピングにおいて,一般消費者に比較的安価で販売され得る ものであり,日常生活で,一般消費者によって使用されるなど,性質,用途又は目 的において一定の関連性を有しているといわざるを得ない。 よって,本件指定商品に含まれる商品の中には,原告の業務に係る商品と比較し た場合,性質,用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれていると いうべきである。
イ 取引者及び需要者の共通性
本件指定商品に含まれる前記油圧式ジャッキ等の,比較的小型で,操作方法も比 較的単純な荷役機械器具及び農業用機械器具の需要者は一般消費者であり,その取 引者は,これらの器具の製造販売や小売り等を行う者である。また,原告が引用商 標の使用を許諾した玩具,雑貨等の需要者は一般消費者であり,その取引者は,こ れらの商品の製造販売や小売り等を行う者である。本件指定商品の取引者及び需要 者の中には,原告の業務に係る商品の取引者及び需要者と共通する者が含まれる。 そして,商品の性質,用途又は目的からすれば,これら共通する取引者及び需要者 は,商品の性能や品質のみを重視するということはできず,商品に付された商標に表\れる業務上の信用をも考慮して取引を行うというべきである。(5) 出所混同のおそれ 以上のとおり,「混同を生じるおそれ」の有無を判断するに当たっての各事情に ついて,取引の実情などに照らして考慮すれば,本件指定商品に含まれる専門的・ 職業的な分野において使用される機械器具と,原告の業務にかかる商品との関連性 の程度は高くない。
しかし,本件商標と引用商標とは,称呼において相紛らわしいものであって,外 観においても相紛らわしい点を含む。また,引用商標は周知著名であって,その独 創性の程度も高い。さらに,原告の業務は多角化しており,本件指定商品に含まれ る商品の中には,原告の業務に係る商品と比較した場合,性質,用途又は目的にお いて一定の関連性を有するものが含まれる。加えて,これらの商品の取引者及び需 要者と,原告の業務に係る商品の取引者及び需要者とは共通し,これらの取引者及 び需要者は,取引の際に,商品の性能や品質のみではなく,商品に付された商標に表\れる業務上の信用をも考慮して取引を行うものということができる。そうすると,本件指定商品に含まれる商品の中には,本件商標を使用したときに, 当該商品が原告又は原告との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の 関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるものが含まれるといわざるを得な\nい。
ウ 被告は,本件商標は引用商標にただ乗りするものではないし,本件商標を使 用しても引用商標の希釈化は生じないと主張する。 しかし,前記イのとおり,本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ等の取引者及 び需要者は,引用商標が有する力強いイメージに誘引されて,取引を行うことが十分に考えられるから,本件指定商品に本件商標が使用されれば,引用商標の持つ顧\n客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリュ ージョン)を招く結果を生じかねない。
また,被告は,平成8年頃から,コンクリート等を圧搾する機能を有する被告アタッチメントに本件商標を付して使用していることからすれば(甲130,167\n〜170),被告は,引用商標が有する力強いイメージを想起させることを企図し て,被告アタッチメントに,引用商標と称呼において相紛らわしく,外観において も相紛らわしい点を含む本件商標を付していたものといわざるを得ない。さらに, 被告は,本件商標の商標出願日である平成23年11月21日以降ではあるものの, 原告が使用していた「SUPER GODZILLA」「SPACE GOZIL LA」と相紛らわしい「SUPER GUZZILLA」「SPACE GUZZ ILLA」を使用している(甲30,55,62,131,132,136〜13 8,155〜158,161〜165,198)。また,被告は,本件商標の商標 出願日以降ではあるものの,本件商標をタオル,腕時計,手袋,帽子,Tシャツ, パーカー等に付して,広く無償配布及び販売している(甲178〜188,218, 228,229)。加えて,被告は,本件商標の商標登録日以降ではあるものの, 我が国における周知著名な商標と相紛らわしい「ガリガリ君」や「STUDIO G ABULLI」との文字から成る商標につき商標登録出願もしている(甲139〜 142)。これらの被告の行為は,本件商標の商標登録出願時において,本件指定 商品に本件商標が使用されれば,引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希 釈化を招く結果を生じかねなかったことを間接的に裏付けるものといえる。 このように,本件指定商品に本件商標が使用されれば,引用商標の持つ顧客吸引 力へのただ乗りやその希釈化を招く結果を生じかねないから,被告の主張は採用で きない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2018.06.14
平成29(ネ)10033等 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年5月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許請求の範囲の記載によれば,構成要件Eの「前記背後壁」は,「既\n設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる」(構成要件B)ものであり,\n改修の前後でその「高さ」が変わるものではない。他方,同「改修用下 枠」は,その「室外寄りが,スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接 して支持されると共に,」その「室内寄りが,前記取付け補助部材で支 持され」(構成要件D)るものである。このため,構\成要件Eの「前記 背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」であることに寄与し ているのは,主ということができる。 この「取付け補助部材」について,本件明細書等の記載を見ると, 「既設引戸枠の形状,寸法に応じた形状,寸法の取付け補助部材を用い る」(【0018】),「その取付用補助部材106の高さ寸法を変え ることで,異なる形状の既設下枠56にも同一形状の改修用下枠56 (裁判所注,改修用下枠69の誤記であると認める。)を,その支持壁 89と背後壁104を同一高さに取付けることが可能である。」(【0\n091】)との記載がある。しかも,段落【0018】には,上記記載 に先行して,「既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去したので, 改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく,有効開 口面積が減少することがなく,広い開口面積が確保できる。」との記載 もある。 これらの事情を総合すると,構成要件Eの「同じ高さ」とは,「取付\nけ補助部材」で「改修用下枠」を支持することにより,「背後壁の上端」 と「改修用下枠の上端」とを,その間に高さの差が全くないという意味 での「同じ高さ」とした場合を意味するものと理解するのが最も自然で ある。 他方,「ほぼ同じ高さ」について,定義その他その意味内容を明確に 説明する記載は,本件明細書等には見当たらないが,以上に検討した点 を併せ考えると,ここでいう「ほぼ同じ高さ」とは,「取付け補助部材」 の高さ寸法を既設下枠の寸法,形状に合わせたものとすることにより, 「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを,その間に高さの差が全 くないという意味での「同じ高さ」とする構成を念頭に,しかし,その\nような構成にしようとしても寸法誤差,設計誤差等により両者が完全に\nは「同じ高さ」とならない場合もあり得ることから,そのような場合を も含めることを含意した表現と理解することが適当である。\n
イ(ア) このように解することは,本件明細書等の図1に示された実施の形 態につき「前壁102の上端部から室内68に向かって上方へ傾斜する …底壁103の最も室内68側の端部に連な」る「背後壁104」が, 「室内側案内レール67と同一高さまで立ち上がる」ものとされ(【0 027】),また,同図6に示された実施の形態につき「既設下枠56 の背後壁104の上端部に室内68側に向かう横向片104aを有し, この横向片104aと改修用下枠69の支持壁89の上端が同一高さで ある」と記載されている(【0069】)一方で,図1及び6の実施の 形態と比較すると「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」の「高さ」 に図面上明らかに差が認められる図10及び11の実施の形態について は,「例えば,図10に示すように取付け補助部材106の高さ寸法を 大きくして室内側壁部108を底壁103に当接し,かつ室内側案内レ ール115にビス110で取付ける。…この場合には,支持壁89が背 後壁104より若干上方に突出する。」(【0092】)と記載され, 「同一高さ」等の表現が用いられていないこととも整合する。\n
(イ) 本件特許の出願経過に鑑みても,構成要件Eについては上記のよう\nに解釈することが適当というべきである。 すなわち,被控訴人らが構成要件E「前記背後壁の上端と改修用下枠\nの上端がほぼ同じ高さであり」を追加したのは,拒絶査定不服審判の請 求と同時にされた手続補正書による補正後の請求項1〜6に係る発明に 対する進歩性欠如の拒絶理由通知,これを受けての被控訴人らによる補 正案の作成と特許庁審判官によるその了承,サポート要件違反の拒絶理 由通知という経過を経た後の手続補正においてである。そうすると,構\n成要件Eの追加は,上記サポート要件違反の拒絶理由を解消するために のみなされたか,これと同時に上記進歩性欠如の拒絶理由も解消するた めになされたかのいずれかの意図によるものと理解される。 そして,サポート要件違反の拒絶理由通知には「本願の請求項1〜6 には,広い開口面積を確保する本願の課題に対応した構成が記載されて\nいない。」と記載されている。本件明細書等の記載によれば,この「広 い開口面積を確保する本願の課題」については,1)既設下枠に存在した 室外側案内レールを切断撤去してできたスペースを利用することで広い 開口面積を確保し,「有効開口面積が減少することが少ない」(本件明 細書等【0060】)ようにすることを意味するものと理解することが できる一方で,2)「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「ほぼ 同じ高さ」とすることで「有効開口面積が減少することがな」い(【0 018】)ようにすることを意味するものと理解することも可能である。\nしかし,「広い開口面積を確保する本願の課題」を1)の意味に理解す る場合,このような課題は本件明細書等の記載から見て本件発明により 当然に解決されるべきものであるから,本件特許に係る出願の審査段階 の当初から拒絶理由として通知されてしかるべきものである。ところが, 実際には,サポート要件違反の拒絶理由は,審査段階のみならず審判段 階でも1度目の拒絶理由通知では指摘されず,審判段階での2度目の拒 絶理由通知で指摘されたのであり,このような経緯に鑑みると,「広い 開口面積を確保する本願の課題」の意味を1)の趣旨でサポート要件違反 の拒絶理由通知がされたものと理解することは不自然というべきである。 他方,上記経過につき,審判合議体が,進歩性欠如の拒絶理由は「前 記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」(構成要件\nE)との構成が追加されることで解消されると判断し,被控訴人らに更\nに補正の機会を与えるために,「広い開口面積を確保する本願の課題」 につき2)の意味を念頭にサポート要件違反の拒絶理由を通知したものと 理解するならば,2度目の拒絶理由通知の段階において敢えてサポート 要件違反の拒絶理由のみを通知したことも合理的かつ自然なこととして 把握し得る。現に,審判合議体は,「既設引戸を改修用引戸に改修する 際に有効開口面積が減少してしまうとういう課題を解決するものあっ て」,「当該構成は引用文献や他の文献から容易になし得たものである\nとはいえず」との審決書の記載から明らかなとおり,サポート要件違反 の拒絶理由通知を契機として「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端が ほぼ同じ高さであり」という構成要件Eが追加されたことによりサポー\nト要件違反及び進歩性欠如の拒絶理由がいずれも解消されたものとして 判断しており,このことは上記理解と整合的である。
ウ 被控訴人らの主張について
(ア) 被控訴人らは,本件発明において,改修用下枠の上端と背後壁の上 端との高さの差に一定の制限を設けないと,室外側案内レールを切断 撤去することにより従来技術に比べ開口面積の減少を少なくし,広い 開口面積を確保することが可能になったにもかかわらず,その取付け\nスペースを利用しないことにより改修用下枠が取付けスペース内に沈 み込まないために,本件発明の効果を達成し得ない構成も文言上包含\nされてしまうことから,本件発明の効果を達成できる範囲内において, 既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの関係を規定した のが構成要件Eの「ほぼ同じ高さ」であると主張する。\nしかし,取付けスペースを利用することを規定したいのであれば,例 えば,改修用下枠の一部が,既設下枠の室外側案内レール(切断して撤 去されている。)が存在した高さよりも低い位置に挿入されることを規 定するなど,端的に取付けスペースを利用することを明確にする補正を すればよいのであって,取付けスペースを利用しない構成を除外する目\n的で既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの関係を請求項 に記載することの合理性は乏しいというべきである。
(イ) また,被控訴人らは,改修用引戸枠を既設引戸枠にかぶせて取り付 けるものである以上,有効開口面積は必ず減少するのであるから,本 件発明の課題(作用効果)を既設引戸を改修用引戸に改修する際に有 効開口面積を減少することがないようにすること(本件明細書等【0 018】)と理解するのは誤りであるとする。 しかし,本件明細書等には「有効開口面積が減少することが少ない」 (【0060】)と「有効開口面積が減少することがな」い(【001 8】)という異なる表現が用いられているのであるから,両者を区別し\nた上で,「有効開口面積が減少することがない」ことの意味を探求しよ うとするのはむしろ当然である。そして,本件明細書等の記載からは, 本件発明は改修引戸装置の下枠の態様に重点が置かれたものと考えられ るのであるから,その作用効果の説明を理解するに当たり下枠に着目し, 改修用引戸の取付けにより客観的には有効開口面積が減少していても, 「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」を文字通り「ほぼ同じ高さ」 とすることにより下枠に関しては「有効開口面積を減少することがない」 という作用効果が得られることが表現されていると解することには十\分 な合理性があるといえる。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成26(ワ)7643
この特許権の無効審判の審取はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2018.06. 8
平成28(ワ)41720 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年5月31日 東京地方裁判所(47部)
緊急地震速報で発表する内容は以下のとおりである。
(ア) 緊急地震速報(警報)
・地震の発生時刻,震源の位置
・強い揺れ(震度5弱以上)及び震度4の地域の名称
(イ) 緊急地震速報(予報)
・地震の発生時刻,震源の位置,地震の規模(マグニチュード)
・強い揺れ(震度5弱以上)及び震度4の地域の名称
・予想される震度
・主要動の到達予想時刻
ウ 緊急地震速報の処理の流れは,以下のとおりである。
(ア) 観測点における震源推定処理
地震波を検知した観測点において地震波形を解析し,P波初動の時刻, 震央距離(B−Δ法による),震央方向(主成分分析法による),最大振幅, リアルタイム震度等を求める。この処理は地震検知を契機に実施され,そ の後毎秒,処理中枢(気象庁本庁・大阪管区気象台の処理中枢:EPOS) に送信される。
(イ) EPOS中枢処理における震源推定処理
EPOSにおいて震源を推定する処理では,最初にどこかの観測点で地 震波を検知してから,時間が経過して「地震波を検知する観測点が増える」 のに合わせ,様々な手法により震源計算を繰り返す。震源計算の手法には, IPF法,着未着法,EPOSによる自動震源決定処理があり,概ね時間 とともに精度が高くなる。
(ウ) マグニチュードの計算
前記の処理で推定した震源と観測した地震波の最大振幅を用いて,地震 の規模(マグニチュード)を毎秒推定する。
(エ) 震度等の予想
震源とマグニチュードを元に,地予想震度の精度も時間の経過とともに向上することが期待できる。
(オ) 情報の発表
震度等の計算結果が,発表条件・更新条件を満たすと,人手を介するこ\nとなく直ちに緊急地震速報を発表する。
(7) 上記(5),(6)のとおり,被告(気象庁)が行う緊急地震速報では,地震の観 測,データ処理,情報の発表を行うにすぎず,「受信」行為を行っていない(緊\n急地震速報を受信するのは,被告(気象庁)以外の第三者である。)。 また,仮に上記第三者の受信行為まで考慮に入れたとしても,被告の緊急地 震速報では,本件発明の「検出センタ」に相当する処理装置から「予想震度」\nや「到達予想時刻」が出力されており,受信機側で「予\想震度」や「到達時刻」 の演算が行われることは想定されておらず,したがって,個々の受信位置ごと に異なる個別の情報が提供されることもない。 さらに,被告の緊急地震速報で発表される情報は,上記(6)イのとおりであ り,その中に「地震の到来方向」は含まれていない。なお,インターネット検 索サイト Yahoo!JAPAN のニュースサイトに掲載された,高度利用者向け受信端 末の緊急地震速報に係る画像(甲5)上も,各地の予想震度を1つの地図内に\n図示しているにすぎず,地震データをそのまま告知に利用しており,個々の受 信機の受信位置ごとに異なる個別の情報である「地震の到来方向」を提供して いない。したがって,上記地図をみた者は,自らの所在地と震源地とを比較す ることで「地震の到来方向」を判断できるとしても,同地図上,「地震の到来方 向」自体が「警報・通報」されているものとはいえない。 このように,被告が行う緊急地震速報は,1)「受信」行為が含まれていない ほか,仮に第三者の受信行為まで考慮に入れたとしても,2)受信機側で「予想\n震度」や「到達時刻」の演算が行われることが想定されておらず,3)地震デー タをそのまま告知に利用しており,「地震の到来方向」を演算したり,これを警 報・通報することを想定していないから,いずれにしても,本件発明の構成要\n件(4)及び(5)を充足しない。これに反する原告の主張は,上記説示に照らして 採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.06. 6
平成30(行ケ)10010 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成30年5月30日 知的財産高等裁判所
意匠法3条2項は,公然知られた形状等に基づいて容易に意匠の創作をする ことができたときは,意匠登録を受けることができない旨を規定している。公然「知 られた」との文言や,同条1項が,刊行物に記載された意匠(同条1項2号)と区別 して「公然知られた意匠」(同条1項1号)を規定していることと対比すれば,「公然 知られた」というためには,意匠登録出願前に,日本国内又は外国において,現実に 不特定又は多数の者に知られたという事実が必要であると解すべきである。
イ 引用意匠1は,昭和54年に公開された公開実用新案公報に記載された意匠 であり,引用意匠2は,昭和61年に公開された公開実用新案公報に記載された意 匠である。したがって,引用意匠1の記載された公報は,本願意匠の登録出願時ま でに37年が,引用意匠2の記載された公報は,同じく30年が,それぞれ経過し ている。 特許庁発行の公報は,閲覧・頒布等によりその内容を周知する目的のものであり, 多数の公共機関に対し交付され,これらの機関の多くにおいて一般の閲覧に供され ている。引用意匠1の記載された公報が発行された翌年の昭和55年当初における 交付先施設数は225か所で,このうち,一般の公開に供している地方閲覧所は1 15か所であり,昭和54年の一般地方閲覧所の公報類の閲覧者数は23万387 9人である(乙1の1・2)。引用意匠2の記載された公報が発行された昭和61年 当初における交付先施設数は211か所で,このうち,一般の公開に供している地 方閲覧所は109か所であり,同年の一般地方閲覧所の公報類の閲覧者数は17万 1665人である(乙2)。 さらに,特許庁では,平成11年3月にインターネットを通じて産業財産権情報 を無料で提供する「特許電子図書館(IPDL)」サービスを開始した。また,その 後,その運営の移管を受けた独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)に おいて,平成27年3月から「特許情報プラットフォーム(J−PlatPat)」 の提供を開始している。J−PlatPatでは,明治以降発行された1億件を超 える公報類や諸外国で発行された公報を蓄積しており,文献番号,各種分類,キー ワード等により検索することが可能である(乙3)。\n
ウ 以上の事実を総合すると,引用意匠1及び引用意匠2の記載された公報が, いずれも,本願意匠の登録出願時まで長期にわたって公然知られ得る状態にあって, 現実に不特定又は多数の者の閲覧に供されたことが認められる。そして,これらの 事実によれば,これら公報に記載された引用意匠1及び引用意匠2に係る形状が, 現実に不特定又は多数の者に知られた事実を,優に推認することができる。
(2) 創作容易性について
本願意匠は,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とし,その形 状は,正面視をハット状,平面視を縦長長方形の板状としたものである。 引用意匠1は,建築構成材や建築構\造材に固定される横長長方形板状の支持具の 表面に現れるボルトの頭部を,支持具全体を被覆して保護するボルトカバーに係る\n意匠であり,横長長方形板の左側端部を内側にコ字状に屈曲させ,右側端部をL字 状に屈曲させた形状のものである(甲1)。 引用意匠2は,建築用の支持材に係る意匠であり,全体形状を,長手方向に垂直 な断面をハット状に形成した板状の長尺材としたものである(甲2)。 引用例1によれば,引用意匠1のボルトカバー(7)は,固定板(1)の係止リブ (8a)(8b)に形合するように,その端部の形状が形成されているものであり, 端部の形状は,ボルトカバーを取り付ける箇所等に応じて,当業者が任意に選択で きるものと解される。また,ボルトカバーの幅や長さも,当業者が適宜選択できる ものである。そうすると,建築部材の分野における当業者であれば,引用意匠1の ボルトカバーに,引用意匠2の形状を適用して,ボルトカバーの端部の形状を変更 するとともに,その幅及び長さを変更して,正面視をハット状,平面視を縦長長方 形の板状とすることは,容易になし得ることであるから,本願意匠は,当業者が,引 用意匠1に,引用意匠2を適用して,容易に創作することができたものと認められ る。
◆判決本文
関連事件です。
2018.06. 4
平成29(行ケ)10197 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年5月30日 知的財産高等裁判所
原告は,特許出願手続においては,代理人の追加選任がされた場合には, 新たな代理人(新たな代理人が複数の場合は,その筆頭代理人)に対し,書類の送 付を行う実務運用がされてきたのであって,その実務運用には法規範性が認められ, 特許庁長官が,その実務運用に反する名宛人及び場所に送達をした場合,当該送達 には方式の瑕疵があり,適法な送達と認められない旨主張する。 日本弁理士会の対庁協議事項集(甲12)には,特許庁が,昭和54年4月1日 以前において,特許出願につき,「代理人が追加受任された場合は,新たな代理人を 筆頭の代理人とし,特許庁からの手続は,新たな代理人に対して行うが,筆頭代理 人の変更を希望しない旨の申出があったときは,この限りでない。」との取扱いを行\nっていた旨記載されており,日本弁理士会の対庁協議事項集(甲13)には,平成 28年3月17日においても,同様の取扱いを行っていたことが記載されている。 しかし,特許法12条は,前記のとおり,代理人の個別代理を定めているから, 特許庁が上記のような取扱いをしており,それが対庁協議事項集に記載されている からといって,新たな代理人以外の代理人に対する送達の効力を否定することはで きないものと解される。特許庁の上記取扱いに法規範性を認めることはできず,原 告の上記主張を採用することはできない。 そして,上記の結論は,A弁理士に任務懈怠があったとしても,左右されるもの ではない。
(5) なお,本件においては,前記1のとおり,特許庁は,本件拒絶査定の謄本 を,平成27年2月17日,発送し,当該謄本は,A弁理士に対して送達されたと ころ,同月25日には,A弁理士の代理人解任届が提出されている。原告の代理人 であった米国の法律事務所のパートナーは,平成26年10月頃以降,それより前 には定期的に連絡してきていたA弁理士から,連絡がなくなり,同年11月,A弁 理士が出願を行った別件の日本特許出願につき,拒絶査定があり,A弁理士がこれ に対して応答しなかったため,当該特許出願が失効していたことが判明したことを 契機に,A弁理士を解任し,別の代理人に業務を引き継がせることにしたというの であるから(甲3),原告は,遅くとも代理人解任届が提出された平成27年2月2 5日には,上記特許出願以外の特許出願(本願を含む。)についても,A弁理士に対 し,拒絶査定が送達され,同弁理士が応答していない可能性があることを認識し得\nたといえる。しかし,原告は,平成27年2月25日当時は,拒絶査定不服審判請 求が可能である期間中であったにもかかわらず,当該請求を行わず,当該期間を徒\n過したのであるから,実質的にみても,前記の結論を覆すに足りる事情はない。
2018.05.30
平成29(行ケ)10129 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年5月24日 知的財産高等裁判所
前記のとおり,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否か は,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請 求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発 明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決 できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がな くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 また,発明の詳細な説明は,「発明が解決しようとする課題及びその解 決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が 義務付けられているものである(特許法施行規則24条の2)。 以上を踏まえれば,サポート要件の適否を判断する前提としての当該発 明の課題についても,原則として,技術常識を参酌しつつ,発明の詳細な 説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。
かかる観点から本件発明について検討するに,本件明細書の発明の詳細 な説明には,米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を 制御することなく加えると,プロテアーゼによりアミノ酸,オリゴペプチ ドが生成し,うまみ調味料様の雑味がついてしまい,用途が限られたこと (【0002】),食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖 化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが,甘味, コク(ミルク感)等の風味は十分に改善されておらず,必ずしも満足できるものではなかったこと,さらに,グラノーラ,パンケーキ等が流行する一方,牛乳アレルギー,大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり,風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと(【0003】)などが背景技術として記載されている。その上で,発明の詳細な説明には,発明が解決しようとする課題として,「本発明は,米糖化物含有食品のコ\nク,甘味,美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ね た結果見出されたものである。すなわち,本発明は,コク,甘味,美味し さ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに,従 来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可 能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある(【000\n6】)。
これらの記載からすれば,本件発明は,「コク,甘味,美味しさ等を有 する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものである ことが明確に読み取れるといえる。
イ これに対し,異議決定は,「本件発明1の課題は,本件特許明細書の『コ ク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』(【0 006】)との記載及び実施例(【0031】〜【0043】)において, 『コク(ミルク感)』,『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について 評価を行っていることから,『コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供すること』と認められる。」と,一旦は上記アと同様に本 件発明1の課題を認定しながら,最終的なサポート要件の適否判断に際し ては,「本件発明1の課題は,上記aのとおり,具体的には,実施例1− 1のライスミルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて 優位な差を有するものを提供することであ(る)」とその課題を認定し直 し,課題の解決手段についても,「本件発明1が課題を解決できると認識 できるためには,…実施例1−1のライスミルクに比べてコク(ミルク感), 甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要 である。」としている(異議決定12頁16〜25行)。
この点について,被告は,発明が解決しようとする課題とは,出願時の 技術水準に照らして未解決であった課題であるから,本件発明1の「コク, 甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題 は,本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品(具体的には,実\n施例1−1のライスミルク)に比べて,コク,甘味,美味しさ等を有する 米糖化物含有食品を提供することであり, したがって,異議決定において は,本件発明1の課題について,「具体的には,実施例1−1のライスミ ルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて優位な差を有 するものを提供すること」としたものである(したがって,異議決定の課 題の認定に誤りはない)と主張する。 確かに,発明が解決しようとする課題は,一般的には,出願時の技術水 準に照らして未解決であった課題であるから,発明の詳細な説明に,課題 に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては,技 術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないでは ないと考えられる。
しかしながら,記載要件の適否は,特許請求の範囲と発明の詳細な説明 の記載に関する問題であるから,その判断は,第一次的にはこれらの記載 に基づいてなされるべきであり,課題の認定,抽出に関しても,上記のよ うな例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。 したがって,出願時の技術水準等は,飽くまでその記載内容を理解する ために補助的に参酌されるべき事項にすぎず,本来的には,課題を抽出す るための事項として扱われるべきものではない(換言すれば,サポート要 件の適否に関しては,発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる 以上は,これに従って判断すれば十分なのであって,出願時の技術水準を\n考慮するなどという名目で,あえて周知技術や公知技術を取り込み,発明 の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でな いし,相当でもない。出願時の技術水準等との比較は,行うとすれば進歩 性の問題として行うべきものである。)。
これを本件発明に関していえば,異議決定も一旦は発明の詳細な説明の 記載から,その課題を「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食 品を提供すること」と認定したように,発明の詳細な説明から課題が明確 に把握できるのであるから,あえて,「出願時の技術水準」に基づいて, 課題を認定し直す(更に限定する)必要性は全くない(さらにいえば,異 議決定が技術水準であるとした実施例1−1は,そもそも公知の組成物で はない。)。 したがって,異議決定が課題を「実施例1−1のライスミルクに比べて コク(ミルク感),甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提 供すること」と認定し直したことは,発明の詳細な説明から発明の課題が 明確に読み取れるにもかかわらず,その記載を離れて(解決すべき水準を 上げて)課題を再設定するものであり,相当でない。 以上によれば,異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず, 被告の主張は採用できない。
(2) 課題を解決できると認識できる範囲について
ア 上記のとおり,本件発明の課題は,コク,甘味,美味しさ等を有する米 糖化物含有食品を提供することであると認められるので,本件発明が,発 明の詳細な説明の記載から,「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供する」という課題を解決することができると認識可能な範\n囲のものであるか否かについて検討する。
・・・
(エ) そして,上記試験例1,2及び4の結果を総合すれば,本件発明4に ついても,課題が解決できる範囲のものであることが裏付けられている といえる。
エ 以上によれば,本件発明は,いずれも,発明の詳細な説明の記載から, 「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という 課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるといえる。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2018.05.30
平成30(行ケ)10003 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年5月28日 知的財産高等裁判所
原告の提出する証拠(甲5,7,9〜12,25)から認められるのは,せいぜい,本件商品が本件セールの際に倉庫からセール会場に移動され,各500円(消費税別)で販売されたという事実にすぎず,本件セールにおいて,本件商品に本件タグが付されて展示,販売された事実を推認させるものではなく,そのほかに,原告の主張を認めるに足りる証拠はない。原告の主張は,客観的な裏付けを欠くものであり,以下のアないしウの事実に照らしても,不自然,不合理であって,採用できない。
ア 本件タグは,その表面に本件商標が表\示され,その裏面に,原告の名称のほ か,当該商品の品番,サイズ,素材,生産国,バーコード情報,本体価格,税込価 格等が表示されているところ,この税込価格は,消費税率を5%として計算したも\nのである(甲3,4の1・2)。しかし,我が国の消費税率は,本件セールの開催 日より2年半以上前の平成26年4月1日に,5%から現行の8%に改定されてい る(乙3)。この点について,原告は,特価であることの理由を示すために発売当 時の下げ札をそのまま付けておいた旨主張するが,消費税改定後に展示販売する商 品に消費税改定前の税込価格を表示したタグを付すことは,商品の購入者を混乱さ\nせたり,当該商品が古い物であるという印象を与えたりしかねないことから,通常 は,そのような取扱いはされないものと考えられる。
イ 本件タグに表示された前記アの情報は,購入者にとって重要な情報であり,\nかかる情報が表示されたタグは,それが付された商品とともに購入者に引き渡すの\nが通常であると考えられる。また,タグは,紐や結束バンドによって被服に取り付 けられるのが通常であるところ,本件タグは,タグの上部に結束バンドがくくり付 けられており,結束バンドは切断されていない(甲3,4の1・2)。かかる事実 は,本件タグが,本件商品を顧客に引き渡した際に本件商品から取り外されたもの ではないことを推認させるものである。なお,原告は,本件タグは結束バンドでは なく下げ紐により本件商品にくくり付けられていた旨主張するが,下げ紐を取り外 す際に,ハサミなどで切断せずに,その都度紐をほどくという煩瑣な方法をとって いたというのは,不自然である。また,原告は,上記のとおり購入者にとって重要 な情報が表示された本件タグを本件商品の購入者に引き渡さなかった理由について,\n何ら合理的な説明をしていない。
ウ 原告は,平成30年3月11日に,本件セールと同じ会場において,本件セ ールと同様のファミリーセールを開催し,そこで展示された原告商品の中には,本 件商品と同じ500円均一の価格(消費税別)と表示されたものも存在するが,「本\n体価格 ¥500」等の価格表示以外のタグは付されていない(乙1,2)。そう\nすると,仮に,本件セールにおいて本件商品が販売された事実があるとしても,本 件商品を展示して販売する際に,本件タグが付されていなかった可能性は高い。な\nお,原告は,上記平成30年のセールにおいて展示販売された原告の在庫資産であ る商品には,本件タグと同様の下げ札が付されていた旨主張するが,これを裏付け る的確な証拠はない。
(3)以上のとおり,原告が本件セールにおいて本件商品に本件タグを付して展示 販売することにより,本件商標を使用したとの事実を認めることはできない。また, 原告は,そのほかに,指定商品のうち第25類「被服」について,本件商標を要証 期間内に使用したことの主張立証をしない。
(4) 小括
よって,本件商標が要証期間内に指定商品のうち第25類「被服」について使用 されたとの事実は認められないというべきであり,本件商標の指定商品のうち第2 5類「被服」についての商標登録は,商標法50条の規定により取り消されるべき ものである。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2018.05.23
平成29(ネ)10102 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年5月21日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
本件各発明の意義は,充填された液体に臭いが移ることがな く,自立的に形状を維持でき,内部に空気を送り込むことなく,充填された液体の ほぼ全量を排出可能なウォーターサーバー用ボトルを提供するという課題を達成す\nるために,本件各発明の構成を採用することにある。すなわち,本件各発明は,全\n体をPET樹脂によって形成することで,液体を充填した際でも自立的に形状を維 持でき,液体に臭いが移ることがないようにし,胴部に上下方向に伸縮自在な蛇腹 部を設けることで,潰れやすさを向上させ,さらに,蛇腹部と底部との間に裾絞り 部を形成することで,ボトルが大気圧で押し潰れていく際に,裾絞り部が蛇腹部の 方に引き込まれていき,蛇腹部の内部の容積を削減する機能を有するようにしたも\nのである。 このような,本件明細書に記載された,蛇腹部と底部との間に裾絞り部を形成す ることの技術的意義に鑑みると,構成要件Hの「内部の液体の排出に伴って,前記\n裾絞り部がボトル内部に引き込まれること」とは,ウォーターサーバー用ボトル内 部の液体の排出に伴って,裾絞り部が蛇腹部の内部に引き込まれることを意味する ものと解される。 また,かかる解釈は,本件各発明の実施の形態として本件明細書に記載されてい る唯一の実施例において,内部の液体の排出に伴って【図4】(B),【図5】(A), 【図5】(B)と変化することが記載され,【図5】(B)において,裾絞り部が 蛇腹部の内部に引き込まれていることとも整合する。 ウ 以上のとおり,特許請求の範囲の記載,本件明細書の記載及び本件発明1に おける裾絞り部の技術的意義を総合すれば,構成要件Hの「内部の液体の排出に伴\nって,前記裾絞り部がボトル内部に引き込まれること」とは,ウォーターサーバー 用ボトル内部の液体の排出に伴って,裾絞り部が蛇腹部の内部に引き込まれること を意味するものと解される。
エ 控訴人の主張について
控訴人は,裾絞り部がボトル内部に引き込まれることの効果は,ボトル内の残水 を減らすことにあり,これを達するには,裾絞り部がボトル内部の方向に引き込ま れれば足り,蛇腹内部に裾絞り部が引き込まれることまで要求されるものではない から,構成要件Hの「裾絞り部がボトル内部に引き込まれる」とは,裾絞り部が蛇\n腹部の方向,つまり裾絞り部から見てボトル内部の方向に引き込まれることを意味 すると解される旨主張する。 しかし,前記イのとおり,蛇腹部と底部との間に裾絞り部を形成することの技術 的意義は,ボトルが大気圧で押し潰れていく際に,裾絞り部が蛇腹部の内部に引き 込まれていき,蛇腹部の内部の容積を削減する機能を有するようにしたことにある\nところ,単に裾絞り部がボトル内部の方向に引き込まれるというだけでは,本件明 細書に記載された本件各発明の上記効果を奏するものではなく,裾絞り部が蛇腹部 の内部まで引き込まれることによって,上記効果を奏するものである。 また,控訴人は,本件特許の出願時の請求項1を特許請求の範囲から削除し,出 願時の請求項2に構成要件Hを追加して請求項1とするなどの補正をした際に(乙\n6),審査官に対し,本件発明1は構成要件FないしHの構\成を備えることにより, 「ボトルが大気圧で押し潰れていく際,裾絞り部が蛇腹部の方に引き込まれていき, 蛇腹部の内部の容積を削減する機能があり(本件明細書【0020】),ボトル内\nの残水を減らす効果がある。」旨の意見を述べていたものであり(乙7),控訴人 の前記主張は,本件特許の出願経過における控訴人の主張とも異なるものである。 したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2018.05.22
平成28(ネ)10101 発信者情報開示請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成30年4月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記(1)のとおり,本件アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている\n画像は,流通情報2(2)の画像とは異なるものである。この表示されている画像は,\n表示するに際して,本件リツイート行為の結果として送信された HTML プログラム や CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,上記のとおり 画像が異なっているものであり,流通情報2(2)の画像データ自体に改変が加えら れているものではない。 しかし,表示される画像は,思想又は感情を創作的に表\現したものであって,文 芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものとして,著作権法2条1項1号にいう 著作物ということができるところ,上記のとおり,表示するに際して,HTML プロ グラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどを指定されたために,本件ア カウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3〜5のよ\nうな画像となったものと認められるから,本件リツイート者らによって改変された もので,同一性保持権が侵害されているということができる。 この点について,被控訴人らは,仮に改変されたとしても,その改変の主体は, インターネットユーザーであると主張するが,上記のとおり,本件リツイート行為 の結果として送信された HTML プログラムや CSS プログラム等により位置や大きさ などが指定されたために,改変されたということができるから,改変の主体は本件 リツイート者らであると評価することができるのであって,インターネットユーザ ーを改変の主体と評価することはできない(著作権法47条の8は,電子計算機に おける著作物の利用に伴う複製に関する規定であって,同規定によってこの判断が 左右されることはない。)。
また,被控訴人らは,本件アカウント3〜5のタイム ラインにおいて表示されている画像は,流通情報2(1)の画像と同じ画像であるから, 改変を行ったのは,本件アカウント2の保有者であると主張するが,本件アカウン ト3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は,控訴人の著作物である本\n件写真と比較して改変されたものであって,上記のとおり本件リツイート者らによ って改変されたと評価することができるから,本件リツイート者らによって同一性 保持権が侵害されたということができる。さらに,被控訴人らは,著作権法20条 4項の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,本件 アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートが行 われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむを得 ない」改変に当たると認めることはできない。
イ 氏名表示権(著作権法19条1項)侵害
本件アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像には,控訴人\nの氏名は表示されていない。そして,前記(1)のとおり,表示するに際して HTML プ ログラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,本件 アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3〜5の\nような画像となり,控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから,控\n訴人は,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆 への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができ\nる。
・・・
(7) 「侵害情報の流通によって」(プロバイダ責任制限法4条1項1号)及び 「発信者」(同法2条4号について
前記(5)ア,イのとおり,本件リツイート行為は,控訴人の著作者人格権を侵害す る行為であるところ,前記(5)ア,イ認定の侵害態様に照らすと,この場合には,本 件写真の画像データのみならず,HTML プログラムや CSS プログラム等のデータを 含めて,プロバイダ責任制限法上の「侵害情報」ということができ,本件リツイー ト行為は,その侵害情報の流通によって控訴人の権利を侵害したことが明らかであ る。そして,この場合の「発信者」は,本件リツイート者らであるということがで きる。
◆判決本文
一審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2018.05.22
平成28(ワ)30183 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年5月11日 東京地方裁判所(40部)
原告は,不競法2条1項1号にいう「使用」の意義について,自他識別力 のある使用といえるかどうかは独立の要件ではなく,営業主体の混同のおそ れの有無の判断において考慮すべき要素にすぎないと主張する。しかし,同 号は,人の業務に係る商品又は営業(以下「商品等」という。)の表示につ\nいて,その商品等の出所を表示して自他商品等を識別する機能\,その品質を 保証する機能及びその顧客吸引力を保護し,事業者間の公正な競争を確保す\nることを趣旨とするものであるから,同号にいう「使用」というためには, 単に他人の周知の商品等表示と同一又は類似の表\示を商品等に付しているの みならず,その表示が商品等の出所を表\示し,自他商品等を識別する機能を\n果たす態様で用いられていることを要するというべきである。
ア 本件表示1〜3
これを前提として,被告のホームページ上の本件表示1〜3について検\n討するに,前記認定のとおり,被告のホームページには,そのヘッダー部 に被告学習塾の名称が表示され,またメインコンテンツ部には「中学受験\nドクターのプロ講師による」との記載があるのであるから,同ホームペー ジに掲載されたサービスの提供主体が被告であることは明らかである。 また,メインコンテンツ部の最上部の囲み枠に「塾別!今週の戦略ポイ ント」「SAPIX・日能研・四谷早稲アカの授業の要点を毎週解説!」\nなどと記載されていることによれば,被告が原告学習塾のみならず他の大 手学習塾の授業の解説を行っていることは容易に理解し得る。 その上で,本件表示1〜3をみると,本件表\示1(「SAPIX 8月 マンスリー」)は,その表示がされたバナー内の他の記載と併せ考慮する\nと,被告の行うライブ解説の対象が原告学習塾のマンスリーテストである と理解し得るのであり,その解説の主体が原告又はその子会社等であるこ とを表示するものではなく,またそのように誤認されるおそれがあるとは\n認められない。
次に,本件表示2(「SAPIX生のための復習用教材」)についても,\n原告学習塾に通う生徒のための復習教材を被告が販売していると理解し得 るのであり,その教材の販売主体が原告又はその子会社等であることを表\n示するものではなく,またそのように誤認されるおそれがあるとは認めら れない。 さらに,本件表示3(「SAPIX今週の戦略ポイント Daily Support」) についても,解説等の対象が原告学習塾の教材であることを意味するにす ぎず,その教材の販売主体が原告又はその子会社等であることを表示する\nものではなく,またそのように誤認されるおそれがあるとは認められない。 以上によれば,本件表示1〜3は,いずれも,商品等の出所を表\示し, 自他商品等を識別する機能を果たす態様で用いられているものということ\nはできない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.05.21
平成29(ワ)1443 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年4月24日 大阪地方裁判所
原告が主張する営業秘密は,訴訟提起段階から変遷しているが,最終的に確 定したところよると,生春巻きを大量に安定的に生産するために,ライン上で全工 程を行うとともに,通常は水で戻すライスペーパーを,状況に応じた適切な温度の 湯で戻すという生春巻きの製造方法であり,ラインの長さ,作業時間,ライスペー パーの質,ラインを流す速度,工場の状況などを踏まえて,温度を管理するもので あって,ライスペーパーを戻す湯の温度は,製造する本数に応じて,ラインの速度 を変え,それに応じて40度から80度までの幅で変えることに特徴があり,具体 的には,温度を40度から50度程度に設定する場合は,ラインの人数を10名程 度にし,一つのラインでの1時間の製造本数を400本から500本程度とし,温 度を60度から80度に設定する場合は,ラインの人数を12名程度に増やし,一 つのラインでの1時間の製造本数を600本から800本程度とするというもので ある。
(2)ア そこで,まず上記主張に係る製造方法が「秘密として管理されている」(不 正競争防止法2条6項)といえるか検討するに,原告は,1)原告工場の立ち入りを 厳重に管理し,食品関係者の工場見学は,紹介により協力工場となる会社の場合な どに限られていること,2)従業員は競業他社の関係者が入社しないよう注意し,退 社時に秘密保持誓約書を作成させ徴求していることを主張している。
イ しかし,前者については,原告の主張する第三者の出入りの管理は,それ自 体は,証拠(乙8,乙9)により認められる食品工場の場合における衛生管理のた めにする人の出入りの管理と何ら変わらないものであるし,食品関係者の工場見学 は紹介により協力工場となる会社に限られるとの点も,現に被告の場合は,前日か 当日かの争いはあるとしても,短い電話による依頼だけで工場見学を許されており, 原告主張のような厳格な扱いがされていたとは認められない。 この点,原告は,被告が協力工場となることを見学の条件とし,被告がこれを承 諾したように主張するが,協力工場となる以上,事業者間で継続的契約が締結され る必要があるから,短時間の電話のやり取りだけで取引条件の詳細を詰めずに確定 的な合意に至ったとはおよそ考えられず,むしろ原告代表者の陳述書(甲6)は,\n工場見学前に協力工場になることの条件を承諾した旨の記載がないだけでなく,か えって工場見学後の被告代表者の話し振りから「私はもうすっかり協力工場になっ\nてくれるものと信じていました。」との記載があり,結局,協力工場になることが 確定的でない状態で原告工場の見学をさせたことを自認する内容になっている。な お,その後,原告担当者が被告の九州工場を視察していることからすると,被告代 表者は,協力工場となることに対して積極的方向で回答をしたことは優に認められ\nるが,そうであったとしても,それをもって事業者間での法的拘束力のある合意と 評価できないことはいうまでもない。 したがって,原告主張の工場見学の条件は,結局,その実質は,当面の競業会社 ではなく協力関係となることが十分期待できるということと変わりがないことにな\nるのであって,秘密管理のための工場見学の制限としては不十分といわなければな\nらない。
ウ また後者の従業員に対する管理の点についても,入社時の選別を実際になし ている点の証拠はないし,退職時の秘密保持誓約書(甲5)が実際に用いられてい るか否かをさておき,少なくとも,入社時に同趣旨の誓約書が徴求されているわけ ではなく,また在職中の守秘義務について定めたものは認められないから,これで は従業員に対する関係でも秘密管理が十分なされていたとはいえない。\nそのほか,証拠(甲6,乙10,乙19)及び弁論の全趣旨によれば,1)被告代 表者は,平成25年7月3日,原告工場を原告代表\者の案内で見学するとともに, 工場内施設の撮影もし,また原告代表者からは,生春巻きの製造方法の説明も受け\nたが,それに先立ち,見学で得られる技術情報について秘密管理に関する合意は原 告と被告間でなされなかったばかりか,原告代表者からその旨の求めもなされなか\nったこと,2)原告のウェブサイトには,原告工場内で商品を生産している状況を説 明している写真が掲載されており,その中には生春巻きをラインで製造している様 子が分かる写真も含まれていることが認められ,これらの事実からも,原告におい て,その主張に係る営業秘密の管理が十分なされていなかったことが推認できる。\n
エ したがって,原告主張の製造方法は,不正競争防止法2条6項の要件にいう 「秘密として管理」されていたとは認められないから,原告主張の製造方法をもっ て同法の「営業秘密」として認められず,「営業秘密」であることを前提とする損 害賠償請求は,その余の点の判断に及ぶまでもなく理由がない。 なお,原告は,被告代表者が工場訪問のお礼のメールに「ノウハウ」を教えても\nらったことを感謝する記載があることを指摘するが,そのメールをした真意はさて おき,ここで問題にしているのは,原告自身が営業秘密の要件を満たす秘密管理を していたか否かであって,被告代表者が「ノウハウ」としての価値を認め,すなわ\nち非公知で有用なノウハウであると評価していたからといって,秘密管理性の欠如 が補えるわけではない。
2018.05.18
平成29(行ケ)10096 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年5月15日 知的財産高等裁判所
本件訂正発明1と甲1発明との相違点である,甲1発明におけるSiO2粒 子(非磁性材)の含有量を「3重量%」(3.2mol%)から「6mol%以上」とする ことについて,当業者が容易に想到できるといえるか否かを検討する。
イ 動機付けの有無について
(ア) 上記3(1)において認定したとおり,本件特許の優先日当時,垂直磁 気記録媒体において,非磁性材であるSiO2を11mol%あるいは15〜40vol% 含有する磁性膜は,粒子の孤立化が促進され,磁気特性やノイズ特性に 優れていることが知られており,非磁性材を6mol%以上含有するスパッタ リングターゲットは技術常識であった。 そして,本件特許の優先日前に公開されていた甲4(特開2004− 339586号公報)において,従来技術として甲2が引用され,甲2 に開示されている従来のターゲットは「十分にシリカ相がCo基焼結合金 相中に十分に分散されないために,低透磁率にならず,そのために異常\n放電したり,スパッタ初期に安定した放電が得られない,という問題点 があった」(段落【0004】)と記載されていることからも,優れた スパッタリングターゲットを得るために,材料やその含有割合,混合条 件,焼結条件等に関し,日々検討が加えられている状況にあったと認め られる。 そうすると,甲1発明に係るスパッタリングターゲットにおいても, 酸化物の含有量を増加させる動機付けがあったというべきである(磁気 記録方式の違いが判断に影響を及ぼさないことについては,後記オ(ア) に説示するとおりである。)。
(イ) 次に,具体的な含有量の点についてみると,被告も,非磁性材の含有 量を「6mol%以上」と特定することで何らかの作用効果を狙ったものでは ないと主張している上,証拠に照らしても,6mol%という境界値に技術的 意義があることは何らうかがわれない。 さらに,本件明細書の段落【0016】及び【0017】に記載され ているスパッタリングターゲットの作製方法は,本件特許の優先日当時, 一般的に使用・利用可能であった通常の強磁性材及び非磁性材を用い,\n様々な原料粉の形状,粉砕・混合方法,混合時間,焼結方法,焼結温度 を選択することにより,本件訂正発明に係る形状及び寸法を備えるよう にできるというものであるから,甲1発明に基づいて非磁性材である酸 化物の含有量が6mol%以上であるターゲットを製造することに技術的困難 性が伴うものであったともいえない。 そうすると,磁気特性やノイズ特性に優れたスパッタリングターゲッ トの作製を目的として,甲1発明に基づいて,その酸化物の含有量を6mol% 以上に増加させる動機付けがあったと認めるのが相当である。
ウ 阻害要因の有無について
(ア) 審決は,ターゲットの組成を変化させるとターゲット中のセラミック 相の分散状態も変化することが推測され,例えば,当該セラミック相を 増加させようとすれば,均一に分散させることが相対的に困難になり, ターゲット中のセラミック相粒子の大きさは大きくなる等,分散の均一 性は低下する方向に変化すると考えるのが自然であって,実施例1の「3 重量%」(3.2mol%)から本件訂正発明1の「6mol%以上」という2倍近い値 まで増加させた場合に,ターゲットの断面組織写真が甲1の図1と同様 のものになるとはいえず,本件訂正発明1における非磁性材の粒子の分 散の形態を変わらず満たすものとなるか不明であると判断した。 被告も,甲1発明において酸化物含有量を「3重量%」(3.2mol%)から 「6mol%以上」に増加させた場合に,組織が維持されると当業者は認識し ない,すなわち,組織が維持されるかどうか不明であることは,甲1発 明において酸化物含有量を増やすことの阻害要因になると主張する。
(イ) この点について,上記2(2)オにおいて認定したとおり,甲1には, 実施例4(酸化物の含有量は1.46mol%)について,「このターゲットの 組織は,図1に示した酸化物(SiO2)が分散した微細混合相とほぼ同様 であった。」(段落【0022】),実施例5(同1.85mol%)及び同6 (同3.19mol%)についても「このターゲットの組織は,図1に示した組 織とほぼ同様であった。」(段落【0024】及び【0026】)との 各記載があるように,非磁性材である酸化物の含有量が1.46mol%(実施 例4)から3.19mol%(実施例6)まで2倍以上変化しても,ターゲット の断面組織写真が甲1の図1と同様のものになることが示されている。 さらに,上記3(2)において認定したとおり,メカニカルアロイングに おける混合条件の調整,例えば,十分な混合時間の確保等によってナノ\nスケールの微細な分散状態が得られることも,本件特許の優先日当時の 技術常識であった。 そうすると,甲1に接した当業者は,甲1発明において酸化物の含有 量を増加させた場合,凝集等によって図1に示されている以上に粒子の 肥大化等が生じる傾向が強まるとしても,金属材料(強磁性材)及び酸 化物(非磁性材)の粒径,性状,含有量などに応じてメカニカルアロイ ングにおける混合条件等を調整することによって,甲1発明と同程度の 微細な分散状態を得られることが理解できるというべきである。 また,上記イのとおり,甲1発明に基づいて非磁性材である酸化物の 含有量が6mol%以上であるターゲットを製造することが,何かしらの技術 的困難性を伴うものであると認めることはできない。 したがって,甲1発明において酸化物の含有量を「3重量%」(3.2 mol%) から「6mol%以上」に増加した場合に,分散状態が変化する可能性がある\nとか,上記本件組織が維持されるかどうかが不明であることが,直ちに 非磁性材の含有量を増やすことの阻害要因になるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2018.05.16
平成29(ワ)9779 商標権侵害行為差止請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年4月27日 東京地方裁判所
前記認定のとおり,被告商品に貼付されたラベルには,その中央上方に\n「白砂青松」の各文字が,上部左側に「大観」の各文字が配されているが, 「白砂青松」と「大観」は同じ毛筆体でも異なる字体であり,文字の大き さは明らかに「白砂青松」の各文字の方が大きく,文字間の間隔について も「白砂青松」の文字の方が広い。そして,同ラベルの下方には横山大観 の日本画の絵柄が付されている。 上記ラベルの下部に配された絵柄については,被告製品を収める外箱に は付されておらず(乙11,41),被告商品の商品名も「大観 白砂青 松」として販売されていること(乙3〜7)に照らすと,商品に貼付され\nたラベルのデザインというべきものであり,自他識別標識としての機能を\n有するものではないというべきである。また,同絵柄が上記各文字部分と 一体となって被告商品の出所を示すものとして需要者に認識されていた ことをうかがわせる証拠もない。そうすると,上記ラベルのうち,被告標 章として自他商品の識別標識としての機能を有するのは「大観」及び「白\n砂青松」の各文字部分であると認められる。
ウ 対比
そこで,原告商標と,被告標章として自他商品の識別標識としての機能\nを有する「大観」及び「白砂青松」の各文字部分を対比する。 前記のとおり,被告商品に貼付されたラベルにおいて,「白砂青松」と\n「大観」の各文字部分は,文字の大きさ,字体などが異なり,視覚上,両 部分は一体不可分のものではなく,分離して看取することができる。そし て,「白砂青松」と「大観」の各文字部分を比較すると,「白砂青松」を 構成する各文字の方が大きく,中央に記載されており,各文字間の間隔も\n「白砂青松」の方が広いことは明らかである。 また,被告商品を納める外箱においても,「白砂青松」と「大観」の各 文字部分は容易に分離して看取することができ,「白砂青松」を構成する\n各文字の方が相当程度大きく,中央に記載されており,各文字間の間隔も 「白砂青松」の方が広い。 そうすると,被告標章において,需要者に対して商品の出所識別標識と して強く支配的な印象を与えるのは,「白砂青松」の文字部分であるとい そこで,原告商標と被告標章の「白砂青松」との文字部分を対比すると, いずれもその称呼は「ハクサセイショウ」であり,「白い砂と青い松」と の観念が生じる。また,その文字の字体は異なるが,構成される文字は同\n一であることから,その外観も類似する。
◆判決本文
被告の商品は下記ですが、削除される可能性があります。\n
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2018.05.16
平成29(ワ)5274 特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年4月26日 東京地方裁判所
確認の訴えは,現に,原告の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が 存在し,これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切 な場合に限り許されるものである(最高裁判所昭和27年(オ)第683号 同30年12月26日第三小法廷判決・民集9巻14号2082頁参照)。
・・・
本件において,原告らは,CM4社から全ての原告製品の供給を受けて いるところ,被告クアルコムとCM4社との間にはCMライセンスが存在 し,本件特許権もその対象である(認定事実 )。 被告らは,これらの事実を認めた上で,このことを理由として,本件訴 訟において,一貫して被告らは原告らによる原告製品の生産,譲渡等に つき,本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権及び本件特許権に基づく 実施料請求権を有しないことを表明している。\nそして,上記アないしエのとおり,原告アップルと被告クアルコムとの 従前の交渉において,原告製品が本件特許権を侵害していると被告クア ルコムが主張したことがあるとは認められないし,他の訴訟等において も,被告クアルコムにおいて,被告らによる上記表明を矛盾する行動を\nとったことがあるとは認められない。その他,被告クアルコムにおいて, 原告アップルの有する権利又はその法律上の地位に危険,不安を生じさ せる行動をとったことを認めるに足りる証拠はない。 これらを総合すれば,被告クアルコムとの関係において,原告アップル の有する権利又はその法律上の地位に危険又は不安があるとは認められ ない。
2018.05.16
平成29(行ケ)10217 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年4月26日 知的財産高等裁判所
引用商標は,別紙記載2のとおり,「咲蔵」の文字を標準文字で表して成る\nものであるところ,引用商標のように「サククラ」などと二つの音が重なる場合,一文字分を省略して「サクラ」と読むことなどは,経験則上,よくあるこ とであって特段珍しいことではない上に,商品名や店舗名などにおいて,「咲」 の文字の訓読みである「サ(ク)」から,「サ」の文字の当て字として「咲」 の漢字を利用することも,取引上よくみられることであって(乙10〜14は, その一例を示すものといえる。),やはり特段珍しいことではない。したがっ て,本願商標のように振り仮名が振られていなくても,「咲蔵」の文字から「サ クラ」の称呼が生じるものということができる。 よって,引用商標からも,本願商標と同様に,「サクラ」の称呼と,「花が 咲く蔵」,あるいは「桜の花」といった観念が生じるものと認められる。
・・・
原告は,国語辞典(甲21:広辞苑第二版補訂版874頁)には,「咲蔵」 と同様に「咲」を語頭に含む漢字2字から成る熟語が「咲分(サキワケ)」 しか記載されておらず,このような熟語において「咲」を「サ」と訓読みす る慣行はないし,「咲蔵」は造語であって常用されている言葉ではないから, 送り仮名が省略されることもないとして,「咲蔵」なる文字部分からは,基 本となる訓読みと訓読みの組合せで「サキクラ」又は「サキグラ」という称 呼しか生じず,「サクラ」という称呼は生じないと主張する。 しかしながら,本願商標のように振り仮名が振られていなくても,「咲蔵」 の文字から「サクラ」の称呼が生じるものということができることは,前記 3のとおりである。したがって,原告の主張は失当である。
(3) 「咲蔵」の文字から生じる観念に関し
原告は,「咲く蔵(クラ)」又は「蔵(クラ)が咲く」なる表現は常識的\nに思い付くような状態を示しておらず,その意味を全く想起することができ ないと主張する。 しかしながら,「咲く」という言葉が,花のつぼみが開くこと,すなわち, 花が咲くことを意味することは,常識に属することであって,かかる意味を 有する「咲」という文字と「蔵」という文字の組合せからは,前記2のとお り,「花が咲く蔵」といった華やか(にぎやか)なイメージを想起すること ができ,その意味するところも十分認識できる。\nしたがって,少なくとも「咲く蔵(クラ)」なる表現は,「花が咲く蔵」\nとして常識的に思い付くような状態を示しており,その意味を想起すること ができるといえるから,原告の主張は失当である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.05.16
平成28(ワ)6074 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年4月17日 大阪地方裁判所
被告標章1及び4である「堂島プレミアムロール」は,「堂島」,「プレミアム」,「ロール」の3語で構成されているが,この\nうち,「プレミアム」との語は,優れたあるいは高品質なものを意味する語であり, 商品が優れたり,高品質なものであったりすることを表現するため商品名に「プレ\nミアム」という文字が付加される例も多い(乙C7の1,2,乙C8の1参照)こ とが一般的に認められるから,「プレミアム」の部分は,これと結合する他の単語 で表示される商品の品質を表\すものと理解され,商品の出所識別機能があるものと\nは認められない。他方,「堂島」は地名,「ロール」は「ロールケーキ」の普通名 詞の略称を表す語であるが,「プレミアム」が上記のとおり,品質を示す意味しか\n有しないことからすると,「プレミアム」を挟んで分離されているものの,被告標 章1及び4からは,プレミアムな,すなわち高品質な「堂島ロール」との観念が生 じ,これは原告の商品等表示として周知である「堂島ロール」の観念と類似してい\nるといえるし,また称呼も同様に類似しているといえる。 そうすると,被告標章1及び4と原告標章とは,被告標章4のみならず字体に特 徴のある被告標章1を含め,取引者,需要者が外観,称呼又は観念の同一性に基づ く印象,記憶,連想等から,両者を全体として類似のものとして受け取るおそれが あるというべきである。
ウ また被告標章2については,「(株)堂島プレミアム」と「プレミアムロー ル」との語を2段重ねで一体的に表示したものであるが,「(株)」というのは会\n社の種類を示す株式会社の略語にすぎないから,これ自体に出所識別機能は認めら\nれない。そこで,これを除くと,被告標章2は,「堂島プレミアム」と「プレミア ムロール」が2段重ねで一体化している表示であるが,上段,下段で重複して使用\nされている「プレミアム」という語は,上記で判示したとおり,独自の出所識別機 能を有しない語であるし,また取引の現場では長い名称の商品名は略して称呼され,\n観念されることが多いと考えられるから,繰り返される「プレミアム」の部分は一 単語に省略され,さらにそれ自体の出所識別機能がないことも合わさって,「堂島\nプレミアム,プレミアムロール」から,「堂島」と「ロール」という2語が需要者 に強く印象付けられると考えられる。したがって,被告標章2からは被告標章1及 び4についてみたのと同様,プレミアムな,すなわち高品質な「堂島ロール」とい う観念が生じるということができ,これは原告の商品等表示として周知である「堂\n島ロール」の観念と類似しているといえる。 また,称呼の点も,同様に「ドウジマプレミアムロール」との称呼が生じるとい えるから,原告標章の「ドウジマロール」との称呼と類似しているといえる。 そうすると,被告標章2と原告標章とは,取引者,需要者が外観,称呼又は観念 の同一性に基づく印象,記憶,連想等から,両者を全体として類似のものとして受 け取るおそれがあるというべきである。
エ さらに被告標章3は,被告標章2の上段部分の「(株)堂島プレミアム」部分 を,下段の「プレミアムロール」より小さな文字で表示しているものであるが,上\n下段の一体性を損なうほど,文字の大きさに差はないから,被告標章2と同様の理 由から,取引者,需要者は被告標章3と原告標章を類似のものと受け取るおそれが あるということができる。
オ 被告標章5は,被告標章2及び3の「(株)」の部分を「株式会社」,「(株)」 又は同部分に相当する部分がないものとしている標章であるが(ただし,2段重ね という限定はない。),「(株)」については既に説示したとおりであり,「株式会 社」についても,単なる会社の種類を表示する語にすぎないから,これが全くない\n場合も含め,被告標章5と原告標章が類似しているといってよいことは,上記ウ, エで説示したところと同じである。
カ 以上のとおり,被告標章は,いずれも原告標章と類似しているものと認めら れる。
・・・
P1は,被告会社設立時のただ一人の取締役として代表取締役を務め,平成\n26年8月1日まで,その職にあったが,その間,被告標章1を使用した被告商品 をP3に委託して製造し,P4に販売していた(甲3)。
イ P1が代表取締役を務めている間に,被告会社は,原告から平成24年11\n月14日付け及び同年12月13日付けの内容証明郵便で,被告標章1の使用が不 正競争行為に当たる旨の警告を受け,被告会社は被告標章1の使用を平成25年4 月頃に止め,その後,被告標章2を使用した被告商品を販売するようになった。な お,被告標章2を使用した被告商品の一括表示には,被告商品の箱記載の商品名で\nある被告標章2とは異なる被告標章4が記載されていた(甲24)。
ウ P2は,平成26年8月1日付けで被告会社の取締役に就任するともに代表\n取締役に就任し,同日,P1は,被告会社の代表取締役及び取締役を辞任した。ま\nた,被告会社は,同日付けで本件所在地をリーガロイヤルホテル大阪の住所地に移 転する旨の登記をした(甲3,甲23)。
エ 原告は,同年9月29日付けで,被告会社宛てに変更後の被告標章2の使用 も不正競争行為に当たる旨警告する内容証明郵便を送付したが,リーガロイヤルホ テル大阪の住所地へは郵送できなかった(甲22,甲24)。
オ 被告会社は,平成27年4月頃,被告標章2の使用を止め,同月頃から被告 商品に被告標章3を使用するようになった。
・・・
(2) 以上よりP1及びP2の会社法429条1項の損害賠償責任の有無について 検討するに,P1は,原告標章が周知となった後に設立された被告会社の唯一の取 締役であり,代表取締役として原告標章に類似する被告標章1を使用して,その唯\n一の事業である被告商品の販売事業を遂行していたものであり,その間,原告から 不正競争である旨の警告を受けるも,使用標章を類似の範囲にある被告標章2に変 更するに留めて同事業を継続させていたものである。 そしてP2は,平成26年8月1日にP1に替わって取締役に就任すると同時に 代表取締役に就任し,上記事業の遂行責任者となった者であるが,就任と同時に,\nその本店所在地を,リーガロイヤルホテル大阪の所在地に移転登記するなど,被告 商品の販売事業者を対外的に不明な状態にし,また原告が仮処分命令を申し立てた\n後も,これを争って,その販売を継続して事業を遂行し,本件仮処分命令が発令さ れた後も,販売先であるP4においては被告商品の販売を継続していた。 したがって,以上によれば,P1及びP2は,ともに被告会社が違法行為となる 不正競争行為に該当する事業を取締役として積極的に遂行したものとして,その職 務を行うことについて悪意とまで断ずることができなくとも,少なくとも重大な過 失があったことが認められるから,会社法429条1項に基づき,その在任期間に 上記不正競争により原告に生じた損害を賠償する責任があるものというべきである。
・・・
以上より,被告会社が,被告商品を販売したことにより受けた利益の額は,上記 ア認定の被告商品1個当たりの利益の額145円に上記イ認定の販売数量23万6 280個乗じて認定される3426万0600円であると認められる。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.05. 9
平成29(ワ)29099 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年4月26日 東京地方裁判所(46部)
上記1のとおり,本件写真の撮影者はAであるから,Aが本件写真の著作者であり,著作権者であったと認められる。そして,証拠(甲3の1,甲4)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成29年4月19日,Aから本件写真に係る著作権及び被告に対する本件不法行為に基づく損害賠償請求権(同日までに発生した請求権)を譲り受けたと認められる。
2018.05. 9
平成27(ワ)21684 特許権 民事訴訟 平成30年4月20日 東京地方裁判所(40部)
ところで,耐食コーティングに用いる材料の種類や成分の違いにより, 缶内の飲料に与える影響に大きな差があることは,本件特許の出願日当時, 当業者に周知であるということができる(乙34〜36)。例えば,特開平 7−232737号公開特許公報(乙36)には,「エポキシ系樹脂組成物 を被覆した場合,ワイン系飲料に含まれる亜硫酸ガス(SO2)をはじめと するガスに対するガスバリヤー性が劣っており,かつフレーバー成分の収 着性が高い。例えば,ワイン系飲料等を充填した場合,含有する亜硫酸ガ ス(SO2)が塗膜を通過して下地の金属面を腐食する虞があり,場合によ っては内容物が漏洩することもある。この亜硫酸ガスは下地の金属と反応 して硫化水素(H2S)を発生させるが,この硫化水素(H2S)は悪臭の 主要因となるばかりでなく,飲料の品質保持のため必要な亜硫酸ガス(S O2)を消費するため飲料の品質を劣化させフレーバーを損なうこととな る。また,この樹脂組成物は飲料中のフレーバーを特徴付ける成分を収着 しやすく,飲料用金属容器の内面に被覆するには官能的に充分満足のでき\nるものではない。」(段落【0004】),「一方,ビニル系樹脂組成物を被覆 した場合,…エポキシ系樹脂組成物と同様に亜硫酸ガス(SO2)等に対す るガスバリヤー性に乏しく,やはり腐食や漏洩の危険性及び官能的な問題\nがある。」(段落【0005】)との記載がある。これによれば,耐食コーテ ィングに用いる材料や成分が,ワイン中の成分と反応してワインの味質等 に大きな影響を及ぼすことは,本件特許の出願日当時の技術常識であった ということができる。
上記のとおり,耐食コーティングに用いる材料の成分が,ワイン中の成 分と反応してワインの味質等に大きな影響を及ぼし得ることに照らすと, 本件明細書に記載された「エポキシ樹脂」以外の組成の耐食コーティング についても本件発明の効果を実現できることを具体例等に基づいて当業 者が認識し得るように記載することを要するというべきである。 この点,原告は,本件発明の課題は,ワイン中の遊離SO2,塩化物及び スルフェートの含有量を所定値以下にすることにより達成されるのであ り,耐食コーティングの種類によりその効果は左右されない旨主張する。 しかし,塗膜組成物の組成を変えることにより塗膜の物性が大きく変動し, 缶内の飲料に大きな影響を及ぼすことは周知であり(乙34の第1表,乙\n35の第2,3表等),ワイン中の遊離SO2,塩化物及びスルフェートの\n含有量を所定値以下にすれば,コーティングの種類にかかわらず同様の効 果を奏すると認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,具体例の開示がなく とも当業者が本件発明の課題が解決できると認識するに十分な記載があると\nいうことはできない。そこで,本件明細書に記載された具体例(試験)によ り当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得たかについて,以下検討 する。
ア 本件明細書には,「パッケージングされたワインを,周囲条件下で6ヶ 月間,30℃で6ヶ月間保存する。50%の缶を直立状態で,50%の缶 を倒立状態で保存する。」(段落【0038】)との方法で試験が行われ た旨の記載がある。しかし,本件明細書には,当該「パッケージングされ たワイン」の「遊離SO2」,「塩化物」及び「スルフェート」の濃度,そ の他の成分の濃度,耐食コーティングに用いる材料や成分等については何 ら記載がなく,その記載からは,当該「パッケージングされたワイン」が 本件発明に係るワインであることも確認できない。
イ また,本件明細書には,試験方法について,「製品を2ヶ月の間隔を置 いて,Al,pH,°ブリックス(Brix),頭隙酸素及び缶の目視検査に関 してチェックする。…目視検査は,ラッカー状態,ラッカーの汚染,シー ム状態を含む。…官能試験は,味覚パネルによる認識客観システムを用い\nる。」(段落【0039】)との記載がある。「頭隙酸素」については, 乙29文献(4頁下から2行〜末行)に「ヘッドスペースの酸素は,アル ミニウムの放出に関して非常に重大である」との記載があるとおり,ワイ ンの品質に大きな影響を与え得る因子であり,「官能試験」はワインの味\n質の検査であるから,いずれもその方法や結果は効果の有無を認識する上 で重要である。しかし,本件明細書には,「頭隙酸素」のチェック結果や 「目視検査」の結果についての記載はなく,「官能試験」についても「味\n覚パネルによる認識客観システム」についての説明や試験結果についての 記載は存在しない。
ウ さらに,本件発明に係る特許請求の範囲はワイン中の三つの成分を特定 した上でその濃度の範囲を規定するものであるから,比較試験を行わない と本件発明に係る方法により所望の効果が生じることが確認できないが, 本件明細書の発明の詳細な説明には比較試験についての記載は存在しな い。このため,当業者は,本件発明で特定されている「遊離SO2」,「塩 化物」及び「スルフェート」以外の成分や条件を同程度としつつ,「遊離 SO2」,「塩化物」及び「スルフェート」の濃度を特許請求の範囲に記載 された数値の範囲外とした場合には所望の効果を得ることができないか どうかを認識することができない。 加えて,耐食コーティングについては,試験で用いられたものが本件明 細書に記載されている「エポキシ樹脂」かどうかも明らかではなく,まし て,エポキシ樹脂以外の材料や成分においても同様の効果を奏することを 具体的に示す試験結果は開示されていない。
エ 以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「試験」は, ワインの組成や耐食コーティングの種類や成分など,基本的な数値,条件 等が開示されていないなど不十分のものであり,比較試験に関する記載も\n一切存在しない。また,当該試験の結果,所定の効果が得られるとしても, それが本件発明に係る「遊離SO2」,「塩化物」及び「スルフェート」の 濃度によるのか,それ以外の成分の影響によるのか,耐食コーティングの 成分の影響によるのかなどの点について,当業者が認識することはできな い。 そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載された 「試験」に関する記載は,本件発明の課題を解決できると認識するに足り る具体性,客観性を有するものではなく,その記載を参酌したとしても, 当業者は本件発明の課題を解決できるとは認識し得ないというべきであ る。
オ この点,原告は,本件発明の特徴的な部分は,従来存在しなかった技術 思想であり,「塩化物」等の濃度には臨界的な意義もないので,その裏付 けとなる実験結果等の記載がないとしてもサポート要件には違反しない と主張する。 しかし,前記判示のとおり,特許請求の範囲に記載された構成の技術的\nな意義に関する本件明細書の記載は不十分であり,具体例の開示がなくて\nも技術常識から所望の効果が生じることが当業者に明らかであるという ことはできない。また,「遊離SO2」,「塩化物」及び「スルフェート」 に係る濃度については,その範囲が数値により限定されている以上,その 範囲内において所望の効果が生じ,その範囲外の場合には同様の効果が得 られないことを比較試験等に基づいて具体的に示す必要があるというべ きである。
・・・
(5) 以上のとおり,本件発明に係るワインを製造することは困難ではないが, 本件発明の効果に影響を及ぼし得る耐食コーティングの種類やワインの組成 成分について,本件明細書の発明の詳細な説明には十分な開示がされている\nとはいい難いことに照らすと,本件明細書の発明の詳細の記載は,当業者が 実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできず,特許\n法36条4項1号に違反するというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.04.26
平成27(ワ)21897等 著作権侵害行為差止等請求事件,損害賠償請求反訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月28日 東京地方裁判所
原告は,原告が平成16年8月10日に完成させた同日版「eBASEserv er」は,1)合計22個の辞書がそれぞれ様々な辞書情報を備えており,データベ ースの体系的な構成の中で各データ項目と紐付けられて辞書網を構\成している点に 創作性が認められ,2)個々の辞書が,それ単独でも,体系的構成及び情報の選択に\nおいて創作性が認められるから,それ自体が,データベースの著作物と認められる べき旨主張する。 原告の主張によれば,「eBASEserver」は,食品の商品情報を広く事 業者間で連携して共有する方法を実現するためのデータベースを構築するためのデ\nータベースパッケージソフトウェアであって,食品の商品情報が蓄積されることに\nよりデータベースが生成されることを予定しているものである。そうすると,この\nような食品の商品情報が蓄積される前のデータベースパッケージソフトウェアであ\nる「eBASEserver」は,「論文,数値,図形その他の情報の集合物」(著 作権法2条1項10号の3)とは認められない。 原告は,「eBASEserver」に搭載されている辞書情報を「情報」と捉 え,この集合物をもって「データベース」と主張するものとも解されるが,原告の 主張によっても,これらの辞書ファイルは,商品情報の登録に際して,当該商品情 報のうち特定のデータ項目を入力する際に参照されるものにすぎないのであって, 辞書ファイルが備える個々の項目が,「電子計算機を用いて検索することができる ように体系的に構成」(著作権法2条1項10号の3)されていると認めることは\n困難である。 したがって,「eBASEserver」は,著作権法上の「データベース」に 当たるものとは認められないから,その創作性につき検討するまでもなく,データ ベースの著作物ということはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2018.04.25
北京市高等裁判所(2017)京民終454 号、判決日:2018 年3月28日
事件の概要など、詳しくは、林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所の
◆西電捷通VS ソニーのWAPI 特許侵害事件に関する検討
を参照ください。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> 外国
>> ピックアップ対象
2018.04.24
平成29(ネ)10087 専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年4月18日 知的財産高等裁判所(4部) 大阪地方裁判所
他方,甲4契約の締結された当時,本件特許発明は実用化されたとはいえない段 階にあって事業の将来見込みが不確実であったところ,被控訴人は,控訴人に合計 2500万円の契約金を支払った。さらに,被控訴人は,少なくとも約1300万 円を支出して,本件特許発明に係る方法の実施に適するよう,汎用電子レンジを改 造して本件機械を開発した。本件機械の導入によって,歯科医院において本件特許 発明に係る方法を容易に実施できるようになり,被控訴人が歯科医院から義歯を預 かって本件特許発明を実施していたときよりも,顧客層が大きく拡大することに なった。このことは,本件特許発明を実施する上で必要な本件液の販売数が,平成 27年初めは月約700本であったところ,平成27年後半には月少なくとも約1 300本に増加していること(乙44)からも裏付けられる。 また,控訴人は,本件訴訟提起前の平成27年4月24日,被控訴人に対し,本 件機械と本件液の売上高の各3%の実施料の支払を求め,被控訴人は,暫定的支払 としつつも現在まで上記額の支払を継続し,控訴人はこれを受領している。 これらの事情のほか,本件訴訟に現れた事情を総合考慮すれば,本件機械の販売 に係る実施料は,売上高の6%をもって相当と認める。
(ウ) 控訴人の主張について
控訴人は,社会通念上相当な実施料は,本件機械の売上高から製造原価を控除し た額(粗利)の25%,そうでないとしても,本件機械の売上高の10%であると 主張する。 しかし,まず,粗利の額は,被控訴人の営業秘密である製造原価を明らかにしな ければ算定不能であること,売上高は双方にとって簡便かつ明確な算定基準となる\nこと,甲4契約においても販売価格と通常価格の差額(2条7項。具体的には加工 単価を基に算定している。)や第三者からの実施許諾料(同条8項)を算定基準と していることに照らせば,粗利ではなく売上高を算定基準とするのが当事者の意思 に合致するものと解される。そして,控訴人主張の利益三分法ないし四分法は,ラ イセンス料を定めるに際しての一つの指針にすぎず,売上高ないし粗利の25%を 原則的なライセンス料と考えることは相当でない。本件においても,前記(イ)のと おり,被控訴人自身が実施していた当時の実施料,被控訴人が契約締結時に支払っ た実施料や本件機械の開発費用等の先行投資額,本件機械の導入による顧客層の拡 大,従前の交渉経緯等を総合考慮すれば,売上高の6%をもって相当と認める。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2018.04.24
平成29(行ケ)10138 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年4月18日 知的財産高等裁判所
原告は,図1に示された気体溶解装置は,加圧型気体溶解手段3によって生成さ れ,溶存槽4に貯留された水素水を気体溶解装置の内部で循環させるようには構成\nされておらず,図3に示された気体溶解装置は,その内部に,「溶存槽4(41,4 2)」に貯留された水素水を「加圧型気体溶解手段3」に送出する「加圧送水通路」 を備えてはいないから,本件発明1は,図1に示された気体溶解装置,図3に示さ れた気体溶解装置のいずれによってもサポートされていない旨主張する。 しかし,本件明細書には,図1に示された気体溶解装置について,「溶存槽4に保 存された液体は,降圧移送手段5である細管5a内で層流状態を維持して流れるこ とで降圧され(S6),水素水吐出口10から外部へ吐出される(S7)。」(【003 4】)との記載がある一方で,「本発明の気体溶解装置1は,加圧型気体溶解手段3 で加圧して気体を溶解した液体を,排出せずに循環して加圧型気体溶解手段3に送 り,循環した後に,降圧移送手段5に送る」(【0037】)との記載がある。したが って,図1に示された気体溶解装置は,加圧型気体溶解手段3によって生成され, 溶存槽4に貯留された水素水を気体溶解装置の内部で循環させるように構成されて\nいると認められる。 また,本件明細書には,前記イのとおり,本件発明1の「溶存槽」と「加圧型気体 溶解手段」との間に水素水を循環させる経路として,ウォーターサーバーを用いる 場合,水槽を用いる場合,加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解した液体を, 排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る経路を用いる場合の開示がある一方, これらの場合に循環の経路が限定されるとの記載や示唆はない。したがって,当業 者であれば,本件発明1においては,水素水が,これらの場合を含む何らかの経路 で循環すればよく,図3に示された気体溶解装置は,水素水を「送出し加圧送水し て循環させ」る経路の例示にすぎないことを理解できる。 よって,原告の主張は採用することができない。
・・・
原告は,請求項1及び8はウォーターサーバーを発明特定事項としていないが, 実施例1,3ないし13には,図3に示すウォーターサーバーに気体溶解装置を接 続した場合の実験条件しか記載されていない,また,実施例2は,図1に示す気体 溶解装置を用いたものであるが,どのように水素水を生成,循環させたのか不明で あるから,本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明1及び8を実施できる程度 に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨主張する。\nしかしながら,本件発明1及び8は,本件明細書に例示された,ウォーターサー バーを用いる場合,水槽を用いる場合,加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解 した液体を,排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る場合を含む,何らかの 経路により水素水を循環させるものであることは,前記2(3),(4)で検討したとおり である。そして,本件明細書には,ウォーターサーバーを用いた実施例1,3ないし 13の実験条件が,他の経路により循環させる構成について当てはまらないと解す\nべき根拠となる記載はない。 また,実施例2についても,加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解した液体 を,排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る場合を含む,何らかの経路によ り水素水を循環させるものであると理解することができる。 そうすると,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明を参考にして,本件発明 1及び8を実施することができるといえるから,原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.04.24
平成29(行ケ)10078 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年4月17日 知的財産高等裁判所
前記認定の諸事実及び本件商標の登録出願の経緯によれば,本件商標が,その登 録出願時及び登録査定時に出所として表示するのは,古武道の一流派である本件流\n派そのものであって,原告及び被告もこれに属するものであると認められる(なお, 原告が被告に対し本件流派から破門する旨を通知したことは,上記認定を左右する ものではない。)。 そして,本件商標は,その表記に応じて,本件流派(戸田派武甲流薙刀術)を,\n取引者,需要者に想起させるものであるから,客観的表記に基づく需要者の認識と\n登録出願の経緯等に基づく出所の主体の間にも齟齬はないものと認められる。 他方,審判における原告主張の無効理由のうち,商標法4条1項8号に関して主 張する「他人」とは,「遅くとも昭和10年以降,代表者として宗家を置き,「戸田\n派武甲流薙刀術」との名称で薙刀術の教授等をしている社団」であるから,本件流 派そのものである。同条1項10号に関して主張する「他人」の商標とは,「「戸田 派武甲流薙刀術」の教授等の役務を示すものとして需要者の間で広く認識されてい る商標」であって,本件流派を出所とする商標である。同条1項15号に関して主 張する「他人」とは,「原告が宗家代理を務める本件流派」と記載されるが,実質的 には,原告が宗家代理を務める本件流派に限定されるものではなく,遅くとも昭和 10年以降,代表者として宗家を置き「戸田派武甲流薙刀術」の教授等を行ってき\nた本件流派を「他人」として主張するものと善解される。同条1項19号に関して 主張する「他人」とは,「需要者の間で著名な「戸田派武甲流薙刀術」」であるから, 本件流派そのものである。 以上のとおり,原告が無効理由として主張する商標法4条1項8号,10号,1 5号及び19号における「他人」とは,いずれも本件流派を指すものであるところ, 本件商標がその出所として表示するのも,本件流派そのものであるから,両者は同\n一であるといえる。そうすると,前記各号に関して原告が主張する「他人」が,本 件商標が出所を表示する主体と異なる者とは認められないから,前記(1)のとおり, 商標法4条1項8号,10号,15号及び19号に基づいて,本件商標が商標登録 を受けることができない商標と認めることはできず,原告の主張は,理由がないも のといわざるを得ない。 この点,審決は,先代宗家から,本件流派の運営及び管理等を原告と共に依頼さ れた被告が流儀代表手続をしたことが不当なものとまでいうことができないとした\n上で,被告が,振興会の常任理事会において,本件流派の流儀代表者として了承さ\nれた後,古武道大会等に本件流派の代表者として参加しており,各種新聞,雑誌に\nおいて,本件流派の代表者として掲載されているといった事情を考慮して,被告は,\n本件商標の登録出願時及び登録査定時に本件流派との関係において,商標法4条1 項8号,10号,15号及び19号に規定する「他人」に該当するということはで きないと判断した。 しかしながら,本件商標がその出所として表示するのは,古武道の一流派である\n本件流派そのものであることは前記のとおりであり,被告個人が,本件商標につい て,本件流派との関係において,上記「他人」に該当するか否かは,商標法4条1 項8号,10号,15号及び19号該当性の判断に,直ちに影響を及ぼすものでは ない(原告は,被告が商標登録した本件商標が,「他人」である本件流派との関係で 無効理由があると主張するものと解される。)。 したがって,審決が,本件商標の出所等を検討することなく,被告個人が,本件 流派との関係において,上記「他人」に該当しないことを理由に,商標法4条1項 8号,10号,15号及び19号該当性の判断をした点には誤りがあるといわざる を得ない。しかしながら,本件商標について,商標法4条1項8号,10号,15 号及び19号に該当しないとの審決の判断は,結論において誤りはないといえる。
(3) 原告の主張について
原告は,本件流派の宗家代理の地位にあり次期宗家の決定権限を有する原告が承 認しないにもかかわらず,被告が,本件流派の宗家であると名乗った上で,振興会 等に登録手続を行い,演武大会に出場し,また,原告に無断で本件商標の登録出願 手続をしたなどと主張する。 しかしながら,本件商標がその出所の主体として表示するのは,古武道の一流派\nである本件流派そのものであって,原告が他人として主張する団体と同一のもので あることは前記のとおりであり,本件商標の登録出願の経緯や本件流派の代表者が\n原告であるのか否かなどの点については,本件商標について原告が無効理由として 主張する商標法4条1項8号,10号,15号及び19号該当性に関する前記判断 を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.04.24
平成28(ワ)27057 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年4月13日 東京地方裁判所
以上のとおり,乙9〜12によれば,光学的センサの周辺部に位置す る受光素子に入射する光束の光量が減少するのを防止するため,「読み 取り対象からの反射光が絞りを通過した後に結像レンズに入射するよう, 絞りを配置することによって,光学的センサから射出瞳位置までの距離 を相対的に長く設定」するという構成とすることは,本件特許出願当時,ビデオカメラ等の分野において周知であったと認めることができる。
(イ) 原告は,ビデオカメラ等と2次元バーコードリーダーの技術的意義は 異なるので,当業者がビデオカメラ分野の技術(乙9〜12)を当然の こととして2次元コードリーダの読取装置に適用することを考えるもの ではないと主張する。 しかし,その主たる目的が色彩等の再現性にあるか2次元バーコード の読取りにあるかという点で異なる面があるとしても,集光レンズ付き CCDエリアセンサを通常の目的で使用する限りは,光学的センサの周 辺部に位置する受光素子に入射する光束の光量が減少することにより光 学素子に入射する光束の光量が低下して検出感度が低下するという課題 は共通しており,当業者であれば,2次元バーコードリーダーにおける 同課題の解決のため,光学系の近接した技術分野であるスチルカメラ, デジタルカメラ,ビデオカメラ等の技術を適用することについての動機 付けを得ることは容易であるというべきである。 そして,前記(1)ウのとおり,ICX084ALデータシート(乙39) には,ICX084ALが2次元バーコードリーダー,PCインプット カメラに適している旨の記載が,1995年9月25日付けの日経エレ クトロニクス(乙64の3)には,ICX084ALを含むソニーの全画素読出し方式CCDが電子スチルカメラ,2次元バーコードリーダー\n等に適している旨の記載があり,また,平成9年7月13日付け日経産 業新聞(乙57)には,「バーコード読み取り手持ち型機器を発売・・・ デジタルカメラの技術を応用し」との記載があることも,バーコードリ ーダーとデジタルカメラとが技術を共通にする関係にあることを裏付け るものということができる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.04.24
平成29(行ケ)10051 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年4月12日 知的財産高等裁判所(3部)
そうすると,本願発明の目的である「サイドチャネルを利用した攻撃 から回路を保護すること」は,段落【0009】,【0010】及び 【0041】で言及されているサイドチャネルを利用した攻撃から関数 鍵 kc を保護することを意味し,この保護は関数鍵 kc を第2の鍵(又は 非機能の鍵)ki でマスクする,すなわち kc と ki を XOR 演算することに よって達成されるものと理解される。換言すれば,本願発明の暗号回路 においてサイドチャネルを利用した攻撃の目標として想定されているの は関数鍵 kc であり,この関数鍵 kc をそのような攻撃から保護するため に第2の鍵 ki を必要とし,関数鍵 kc を第2の鍵 ki と XOR 演算すること によってマスクする(マスク鍵 kc(+)ki とする)という方法によって,関 数鍵 kc の保護が達成されるものと把握される。 さらに,本願明細書等には,サイドチャネルを利用した攻撃の具体的 な目標として関数鍵 kc 以外のものは記載されていない。 このように,本願発明が想定している攻撃目標は関数鍵 kc であり, それ以外の攻撃目標を想定しない以上,本願発明の暗号回路が出力する 暗号文 y の秘密性は関数鍵 kcに依拠し,暗号文の計算手順(すなわち本 願発明の「暗号化アルゴリズム」)に依拠するものではないと認められ る。そうであれば,関数鍵 kc が判明すれば,本願発明により出力され る暗号文 y を解読し得ることになる。これは,本願発明の暗号回路が出 力する暗号文 y の暗号鍵が関数鍵 kcであることを意味する。すなわち, 本願発明は,秘密情報である関数鍵 kcを用いて平文 x から暗号文 y を計 算する関数を F で表したとき,y=F(x,kc)を満たす暗号文 y を出力す る暗号回路であると認められる(以下,この技術思想を「本願技術思想 1)」という。)。 このように理解することは,本願明細書等の「関数鍵 kc が回路21 の暗号化を実施する役割を果たす。この暗号化は例えばレジスタ22の 内部で入力変数 x を暗号化された変数 y=DES(x,kc)に変換する DES アルゴリズム23である。」(【0040】)との記載とも整合する。
・・・
上記本願技術思想1)及び2)によれば,本願発明の暗号回路を具現化 するためには,暗号回路によって実際に計算された暗号文と,暗号化ア ルゴリズム F に基づいて計算された暗号文とが等しいこと,すなわち G(x,kc(+)ki)=F(x,kc) を満たすことが要求される(以下,この要求を「本願発明の技術的要求」 という。)。 しかし,本願発明の技術的要求を満たす関数 G を構成する計算方法\nが,当業者の技術常識に鑑みて自明であると認めるに足りる証拠はない。 そこで,G(x,kc(+)ki)の具体的な計算方法が本願明細書等に示されて いるかについて,以下検討する。
・・・
以上のとおり,本願明細書等の図1及び2に示される回路において は,そもそもマスク鍵 kc(+)ki が計算されているとは認められないこと から,両図の回路をもって関数 G(x,kc(+)ki)の具体的態様を開示し たものということはできない。 d また,段落【0028】記載の「【数2】K(+)M」は,2つの値が XOR 演算されているという点で本願発明のマスク鍵と共通するもの の,記号が異なることから,本願発明を説明したものとは認められな い。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.04.24
平成29(行ケ)10180 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月28日 知的財産高等裁判所
登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け,剥離すること\nを繰り返すと,粘着剤層が多数積層して,登記識別情報を読み取りにくくなるとい う登記識別情報保護シールにおける本件課題は,登記識別情報保護シールを登記識 別情報通知書に何度も貼り付け,剥離することを繰り返すと必然的に生じるもので\nあって,登記識別情報保護シールの需要者には当然に認識されていたと考えられる (甲15)。現に,本件原出願日の5年以上前である平成21年9月30日には, 登記識別情報保護シールの需要者である司法書士に認識されていたものと認められ る(甲26の3)。そして,登記識別情報保護シールの製造・販売業者は,需要者 の要求に応じた製品を開発しようとするから,本件課題は,本件原出願日前に,当 業者において周知の課題であったといえる。 そうすると,本件課題に直面した登記識別情報保護シールの技術分野における当 業者は,粘着剤層の下の文字(登記識別情報)が見えにくくならないようにするた めに,粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないように工夫するものと認 められる。甲3発明は,秘密情報に対応する部分には実質的に粘着剤が設けられて いないものであり,甲3発明と甲1発明は,秘密情報保護シールであるという技術 分野が共通し,一度剥がすと再度貼ることはできないようにして,秘密情報の漏洩\nがあったことを感知するという点でも共通する。したがって,甲1発明に甲3発明 を適用する動機付けがあるといえる。 甲1発明に甲3発明を適用すると,粘着剤層が登記識別情報の上に付着すること がなくなり,本件課題が解決される。したがって,甲1発明において,甲3発明を 適用し,相違点に係る構成とすることは,当業者が容易に想到するものと認められ\nる。
ウ 被告の主張について
(ア) 被告は,甲3発明には,シールを何度も貼り付け,剥離することを繰\nり返すという課題は存在せず,その使用目的から容器又はシールを使い回すことは 倫理上許されないから本件課題とは矛盾し,阻害要因がある,と主張する。 しかし,甲3発明のシールは何度も貼り付け,剥離することを予\定されていない としても,一度剥がした後に新たなシールを貼付することは可能\である。また,甲 3発明が,医療,保健衛生分野において使用される検体用容器等に使用される場合 には,何度も貼り付け,剥離することはないのは,検体用容器等の用途がそのよう\nなものであるからであって,甲3発明自体の作用,機能に基づくものではなく,甲\n3発明は保健,衛生分野に限って使用されるものではないから,甲1発明と組み合 わせるのに阻害要因があるとはいえない。したがって,被告の主張には,理由がな い。
◆判決本文
同じ特許発明に関する別の無効審判の取消事件です。
こちらも進歩性無しと判断されました。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2018.04.19
平成29(行ケ)10139 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年4月16日 知的財産高等裁判所
引用発明の衝突対応車両制御は,衝突対応制御プログラムが実行されることによ って行われる。同プログラムは,S1の自車線上存在物特定ルーチン及びS2のA CC・PCS対象特定ルーチンにおいて,自車線上の存在物であるか否かという条 件の充足性が判断され,その後に処理されるS5のACC・PCS作動ルーチンに おいて,自車両の速度,ブレーキ操作部材の操作の有無,自車両と直前存在物との 衝突時間や車間時間等の条件に応じて,特定のACC制御やPCS制御が開始され, 又は開始されないというものである。
(イ) 条件判断の順序の入替えについて
本願補正発明では,ターゲット物体との相対移動の検知に応答してアクションを 始動するように構成された後に,自車線上にある存在物を特定し,アクションの始\n動を無効にするという構成が採用されている。したがって,引用発明を,相違点に\n係る本願補正発明の構成に至らしめるためには,少なくとも,まず,自車線上の存\n在物であるか否かという条件の充足性判断を行い,続いて,特定のACC制御やP CS制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行うという引用発明の条件 判断の順序を入れ替える必要がある。 しかし,引用発明では,S1及びS2において,自車線上の存在物であるか否か という条件の充足性が判断される。この条件は,ACC制御,PCS制御の対象と なる前方存在物を特定するためのものである(引用例【0091】)。そして,引 用発明は,これにより,多数の特定存在物の中から,自車線上にある存在物を特定 し,ACC制御,PCS制御の対象となる存在物を絞り込み,ACC制御,PCS 制御のための処理負担を軽減することができる。一方,ACC制御,PCS制御の 対象となる存在物を絞り込まずに,ACC制御,PCS制御のための処理を行うと, その処理負担が大きくなる。このように,引用発明において,自車線上の存在物で あるか否かという条件の充足性判断を,ACC制御,PCS制御のための処理の前 に行うか,後に行うかによって,その技術的意義に変動が生じる。 したがって,複数の条件が成立したときに特定のアクションを始動する装置にお いて,複数の条件の成立判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更であ ったとしても,引用発明において,まず,特定のACC制御やPCS制御を開始す るために自車両の速度等の条件判断を行い,続いて,自車線上の存在物であるか否 かという条件の充足性判断を行うという構成を採用することはできない。\nよって,引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが,単なる設計変更 であるということはできないから,相違点に係る本願補正発明の構成は,容易に想\n到することができるものではない。
(ウ) 本件周知技術の適用
a 引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが単なる設計変更であっ たとしても,条件判断の順序を入れ替えた引用発明は,まず,自車両の速度等の条 件判断がされ,続いて,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断 され,その後,特定のACC制御やPCS制御が開始され,又は開始されないもの になる。そして,これに本件周知技術を適用できたとしても,本件周知技術を適用 した引用発明は,まず,自車両の速度等の条件判断がされ,続いて,自車線上の存 在物であるか否かという条件の充足性が判断され,その後,特定のACC制御やP CS制御が開始され,又は開始されないものになり,加えて,特定の条件を満たし た場合には,当該ACC制御やPCS制御の始動が無効になるにとどまる。 ここで,本件周知技術を適用した引用発明は,特定の条件を満たした場合に,P CS制御等の始動を無効にするものである。そして,本件周知技術を適用した引用 発明においては,PCS制御等の開始に当たり,既に,自車線上の存在物であるか 否かという条件の充足性が判断されているから,自車線上の存在物であるか否かと いう条件を,再度,PCS制御等の始動を無効にするに当たり判断される条件とす ることはない。 これに対し,相違点に係る本願補正発明の構成は,「横方向オフセット値に基づ\nいて」,すなわち,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断に基づ いて,少なくとも1のアクションの始動を無効にするものである。 したがって,引用発明に本件周知技術を適用しても,相違点に係る本願補正発明 の構成には至らないというべきである。
b なお,本件周知技術を適用した引用発明は,自車両の速度等の条件判断と, それに続く,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断をもって,P CS制御等を開始するものである。PCS制御等の開始を,自車線上の存在物であ るか否かという条件の充足性判断よりも前に行うことについて,引用例には記載も 示唆もされておらず,このことが周知慣用技術であることを示す証拠もない。 したがって,引用発明に本件周知技術を適用しても,その発明は相違点に係る本 願補正発明の構成には至らないところ,さらに,PCS制御等の開始を,自車線上\nの存在物であるか否かという条件の充足性判断よりも前に行うことにより,当該発 明を,相違点に係る本願補正発明の構成に至らしめることができるものではない。
c そもそも,本願補正発明では,ターゲット物体との相対移動の検知に応答し てアクションを始動するように構成された後に,自車線上にある存在物を特定し,\nアクションの始動を無効にするという構成が採用されている。本願補正発明は,タ\nーゲット物体との相対移動の検知に応答してアクションを始動するという既存の構\n成に,当該構成を変更することなく,単に,自車線上の存在物であるか否かという\n条件の充足性判断を付加することによって,アクションの始動を無効にするという ものであり,引用発明とは技術的思想を異にするものである。
(エ) 以上のとおり,引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが単な る設計変更ということはできず,また,引用発明に本件周知技術を適用しても,相 違点に係る本願補正発明の構成には至らないというべきであるから,相違点に係る\n本願補正発明の構成は,引用発明に基づき,容易に想到できたものとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2018.04.19
平成29(行ケ)10208 審決取消請求事件 行政訴訟 平成30年4月11日 知的財産高等裁判所(4部)
イ 本願商標の「マイナンバー」の構成部分を類否判断の対象とすることの可否\n本願商標は,「マイナンバー実務検定」というものであり,その全体の構成から,\n「マイナンバージツムケンテイ」との称呼を生じ,「マイナンバーについての実務検 定」との観念を生じる。 また,本願商標の「マイナンバー」の構成部分は,著名な標章である「マイナンバ\nー」とその構成文字を同じくするものであるから,当該構\成部分は,役務の出所識 別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 他方,本願商標の指定役務には,「検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関 する情報の提供」,「検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の 提供」が含まれるところ,本願商標の「実務検定」の構成部分は,上記指定役務との\n関係では,「実務」の「検定」であることを一般的に表示するものにすぎず,当該構\ 成部分から役務の出所識別標識としての称呼,観念は生じないというべきである。 以上によれば,本願商標からは,「マイナンバージツムケンテイ」との称呼及び「マ イナンバーについての実務検定」との観念のみならず,「マイナンバー」との称呼及 び著名な標章である「マイナンバー」と同一の観念,すなわち,「マイナンバー法に 基づく社会保障・税番号又は個人番号,社会保障・税番号制度であるマイナンバー 制度」との観念も生じ得る。 よって,本願商標のうち,「マイナンバー」という構成部分を抽出し,当該構\成部 分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきであ る。
・・・・
原告は,本願商標からは,「マイナンバー実務検定」としての一連の称呼,観念の みを生じると主張する。
1)原告が,文部科学大臣の許可法人,文部科学省生涯学習政策局の所管の団体と して,平成11年10月15日に設立が認可された一般財団法人であり(甲67, 129),情報教育に関する技能検定試験を実施し,また,情報教育に関する講習会\nを開催するとともに,情報学習に関する調査研究及び出版物の刊行を行うことによ り,情報に係る生涯学習を推進していること(甲68),2)原告が,産経新聞社,角 川アスキー総合研究所の後援を得て,平成27年8月2日から平成29年12月1 7日までの間に,全国の主要都市の合計138会場において,12回にわたり,「マ イナンバー実務検定」との名称の検定試験を実施しており,その受験申込者は,合\n計4万5968名に達していること(甲69〜71,82〜95,112,133, 134),3)原告が,ウェブサイト「マイナンバー実務検定」を紹介するほか(甲7 0,71),「マイナンバー実務検定」の広告動画を大手動画サイトであるYouT ubeにアップロードし(甲72,74,123〜126),テレビでコマーシャル 映像を合計502回放映し(甲73,116,117の1〜6,127,128,1 35,136の1〜4,137〜143,144の1・2),新聞にも広告記事を掲 載し(甲75,76,133,134),いずれにおいても,「マイナンバー実務検 定」の文字が表示されていること,4)原告が,「マイナンバー実務検定」に関するパ ンフレット,案内ビラ,ポスター等を作成の上,配布又は展示しており(甲77〜9 4,118),これらにおいても,「マイナンバー実務検定」の文字が表示されている\nこと,5)原告が,マイナンバー実務検定のテキストや過去問題集等を発行しており (甲97〜102,131,132),その印刷部数は,平成29年5月の時点で, Web販売のみの7000部を含めて3万部に達し(甲119,120),その全て に「マイナンバー実務検定」の文字が表示されていること等の取引の実情に照らす\nなら,本願商標に,一定の周知性はあるものと認められる。 しかし,本願商標の「マイナンバー」の構成部分が,役務の出所識別標識として強\nい印象を与えるのに対して,「実務検定」の構成部分は,役務の出所識別標識として\nの呼称,観念を生じるものではないことから,「マイナンバー」の構成部分を抽出し,\nこの部分だけを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されることは, 前記イのとおりである。そうすると,本願商標から「マイナンバー実務検定」として の一連の称呼及び観念を生じるほか,「マイナンバー」の構成部分のみを抽出した場\n合には,「マイナンバー」との称呼や,「マイナンバー法に基づく社会保障・税番号又 は個人番号,社会保障・税番号制度であるマイナンバー制度」との観念も生じるか ら,本願商標から,「マイナンバー実務検定」としての一連の称呼,観念のみを生じ るとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.04.17
平成28年(行ケ)第10182号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年4月13日 知的財産高等裁判所(特別部)
本件審判請求が行われたのは平成27年3月31日であるから,審判 請求に関しては同日当時の特許法(平成26年法律第36号による改正前の特許法) が適用されるところ,当時の特許法123条2項は,「特許無効審判は,何人も請求 することができる(以下略)」として,利害関係の存否にかかわらず,特許無効審判 請求をすることができる旨を規定していた(なお,冒認や共同出願違反に関しては 別個の定めが置かれているが,本件には関係しないので,触れないこととする。こ の点は,以下の判断においても同様である。)。 このような規定が置かれた趣旨は,特許権が独占権であり,何人に対しても特許 権者の許諾なく特許権に係る技術を使用することを禁ずるものであるところから, 誤って登録された特許を無効にすることは,全ての人の利益となる公益的な行為で あるという性格を有することに鑑み,その請求権者を,当該特許を無効にすること について私的な利害関係を有している者に限定せず,広く一般人に広げたところに あると解される。 そして,特許無効審判請求は,当該特許権の存続期間満了後も行うことができる のであるから(特許法123条3項),特許権の存続期間が満了したからといって, 特許無効審判請求を行う利益,したがって,特許無効審判請求を不成立とした審決 に対する取消しの訴えの利益が消滅するものではないことも明らかである。
イ 被告は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する特許権の存続期 間満了後の取消しの訴えについて,東京高裁平成2年12月26日判決を引用して, 訴えの利益が認められるのは当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具 体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られる旨主張する。 しかし,特許権消滅後に特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの 訴えの利益が認められる場合が,特許権の存続期間が経過したとしても,特許権者 と審判請求人との間に,当該特許の有効か無効かが前提問題となる損害賠償請求等 の紛争が生じていたり,今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係があることが認められ,当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が\n具体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られるとすると,訴えの利 益は,職権調査事項であることから,裁判所は,特許権消滅後,当該特許の有効・ 無効が前提問題となる紛争やそのような紛争に発展する可能性の事実関係の有無を調査・判断しなければならない。そして,そのためには,裁判所は,当事者に対し\nて,例えば,自己の製造した製品が特定の特許の侵害品であるか否かにつき,現に 紛争が生じていることや,今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係が存在すること等を主張することを求めることとなるが,このような主張\nには,自己の製造した製品が当該特許発明の実施品であると評価され得る可能性がある構\成を有していること等,自己に不利益になる可能\性がある事実の主張が含ま\nれ得る。 このような事実の主張を当事者に強いる結果となるのは,相当ではない。
ウ もっとも,特許権の存続期間が満了し,かつ,特許権の存続期間中にさ れた行為について,何人に対しても,損害賠償又は不当利得返還の請求が行われた り,刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存する場合,例えば,特許権の存続期間が満了してから既に20年が経過した場合等\nには,もはや当該特許権の存在によって不利益を受けるおそれがある者が全くいな くなったことになるから,特許を無効にすることは意味がないものというべきであ る。したがって,このような場合には,特許無効審判請求を不成立とした審決に対す る取消しの訴えの利益も失われるものと解される。
エ 以上によると,平成26年法律第36号による改正前の特許法の下にお いて,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は,特許 権消滅後であっても,特許権の存続期間中にされた行為について,何人に対しても, 損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり,刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り,失われることはない。\nオ 以上を踏まえて本件を検討してみると,本件において上記のような特段 の事情が存するとは認められないから,本件訴訟の訴えの利益は失われていない。
(2) なお,平成26年法律第36号による改正によって,特許無効審判は,「利 害関係人」のみが行うことができるものとされ,代わりに,「何人も」行うことがで きるところの特許異議申立制度が導入されたことにより,現在においては,特許無効審判請求をすることができるのは,特許を無効にすることについて私的な利害関\n係を有する者のみに限定されたものと解さざるを得ない。 しかし,特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り,そのような問題を提起されるおそれのある者は,当該特許を無効にすることについて私的な\n利害関係を有し,特許無効審判請求を行う利益(したがって,特許無効審判請求を 不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益)を有することは明らかであるから, 訴えの利益が消滅したというためには,客観的に見て,原告に対し特許権侵害を問 題にされる可能性が全くなくなったと認められることが必要であり,特許権の存続期間が満了し,かつ,特許権の存続期間中にされた行為について,原告に対し,損\n害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり,刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情が存することが必要であると解すべきである。\n
・・・
特許法29条1項は,「産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる 発明を除き,その発明について特許を受けることができる。」と定め,同項3号とし て,「特許出願前に日本国内又は外国において」「頒布された刊行物に記載された発 明」を挙げている。同条2項は,特許出願前に当業者が同条1項各号に定める発明 に基づいて容易に発明をすることができたときは,その発明については,特許を受 けることができない旨を規定し,いわゆる進歩性を有していない発明は特許を受け ることができないことを定めている。
上記進歩性に係る要件が認められるかどうかは,特許請求の範囲に基づいて特許 出願に係る発明(以下「本願発明」という。)を認定した上で,同条1項各号所定の 発明と対比し,一致する点及び相違する点を認定し,相違する点が存する場合には, 当業者が,出願時(又は優先権主張日。以下「3 取消事由1について」において 同じ。)の技術水準に基づいて,当該相違点に対応する本願発明を容易に想到するこ とができたかどうかを判断することとなる。
このような進歩性の判断に際し,本願発明と対比すべき同条1項各号所定の発明 (以下「主引用発明」といい,後記「副引用発明」と併せて「引用発明」という。) は,通常,本願発明と技術分野が関連し,当該技術分野における当業者が検討対象 とする範囲内のものから選択されるところ,同条1項3号の「刊行物に記載された 発明」については,当業者が,出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明 をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから,当該刊行 物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。そして,当該刊 行物に化合物が一般式の形式で記載され,当該一般式が膨大な数の選択肢を有する 場合には,当業者は,特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優 先的に選択すべき事情がない限り,当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る 具体的な技術的思想を抽出することはできない。 したがって,引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であ って,当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され,当該一般式が膨大な数の選 択肢を有する場合には,特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に 選択すべき事情がない限り,当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出す ることはできず,これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当であ る。
この理は,本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条 1 項3号所 定の「刊行物に記載された発明」(以下「副引用発明」という。)があり,主引用発 明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたか どうかを判断する場合において,刊行物から副引用発明を認定するときも,同様で ある。したがって,副引用発明が「刊行物に記載された発明」であって,当該刊行 物に化合物が一般式の形式で記載され,当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場 合には,特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択す べき事情がない限り,当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出すること はできず,これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。 そして,上記のとおり,主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明 を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には,1)主引用発明又は 副引用発明の内容中の示唆,技術分野の関連性,課題や作用・機能の共通性等を総\n合的に考慮して,主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあ るかどうかを判断するとともに,2)適用を阻害する要因の有無,予測できない顕著\nな効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する 取消訴訟においては,上記1)については,特許の無効を主張する者(特許拒絶査定 不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取\n消訴訟においては,特許庁長官)が,上記2)については,特許権者(特許拒絶査定 不服審判の審決に対する取消訴訟においては,特許出願人)が,それぞれそれらが あることを基礎付ける事実を主張,立証する必要があるものということができる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2018.04.17
平成28(ワ)29320 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月29日 東京地方裁判所(46部)
上記(1)の記載によれば,本件発明1及び2は,熱可塑性樹脂発泡シートに 非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートを成形してなる容 器について,熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬さの差 により,容器に触れた際に,硬いフィルムで指等を裂傷するおそれがあるが, 突出部の上下面に凹凸を形成すると,蓋体を外嵌させる際に突起部が係合さ れる突出部の下面側にも凹凸形状が形成されることとなって強固な係合状態 を形成させることが困難となり,端縁部での怪我を防止しつつ蓋体などを強 固に止着させることが困難であるという課題を,本件発明1の構成,特に上記端縁部の上面に凹凸形状を形成する一方で下面は平坦とする形状とすることによって解決することとしたものということができる。\nまた,上記(2)の記載を参酌すると,本件発明1及び2は,上記端縁部を, 厚みが圧縮されて薄肉化されたもので,かつ,上面に凹凸形状が存在するも のとすることにより,その強度を強め,これによって蓋体を強固に止着させ るという課題を解決するものということができる。 以上によれば,本件発明1及び2は,容器の突出部の端縁部の形状につい て,上面に他の部分との厚みの差を付けて凹凸形状を形成するという形状と することで端縁部での怪我を防止するとの課題を解決し,端縁部につき上記 の端縁部の形状とすることに加えて下面を平坦にすることで,蓋の強固な止 着を実現するという課題を解決し,これによって上記各課題の双方を解決す ることを技術的意義とする発明である。
・・・・
以上によれば,本件明細書においても,発明の構成につき特許請求の範囲の記載と同様の記載がされ,その実施例においても,側周壁部の上端縁であり,被収容物が収容される収容凹部のへりといえる開口縁から外側に\n張り出して形成されているものが突出部とされている。実施例を示す図面 には突出部が水平で平坦な容器が示されているが,発明の詳細な説明欄に は,突出部が平坦であることについての説明はなく,本件発明1及び2の 突出部を突出部が平坦なものに限る趣旨の記載は見当たらない。これらに よれば,「開口縁」及び「突出部」については,上記アのように解するの が相当であり,「突出部」は水平で平坦なものには限られない。
ウ これに対して,被告は,出願経過に照らし,本件発明1及び2は突出部 が水平で平坦である容器に関する発明であると主張する。 原告は,前記1(2)のとおり,「前記突出部の端縁部の…且つ該端縁部の」 と補正をしたものであるところ,証拠(乙12〔2〕)によれば,審判請 求書において,上記補正の根拠として,突出部の端縁部において熱可塑性 樹脂発泡シートが圧縮されて薄肉とされたものであることを明確にしたも のであり,この点が本件明細書の例えば段落【0019】や【図3】b) に記載されているもので,願書に添付した明細書及び図面に記載された事 項の範囲内のものである旨記載したことが認められる。 上記認定事実によれば,補正の前後に係る特許請求の範囲をみても,補 正された部分は「端縁部の上面」と「収容凹部の開口縁近傍の突出部の上 面」の位置関係と端縁部における形状についてであって,突出部の形状が 水平で平坦である旨の明示的な記載も示唆も見当たらないし,原告が主張 したのは本件明細書において発明の実施の形態として記載(段落【001 9】や【図3】b))があることから補正の要件を満たすということであ るから,突出部の形状が水平で平坦なものに限定する趣旨を読み取ること ができない。したがって,本件発明1及び2の容器の突出部が水平で平坦 であると解することはできず,被告の主張は採用できない。
・・・・
上記記載によれば,本件発明1及び2は前記1(3)のとおりの技術的意義 を持つもので,端縁部の下面が平坦であることとその厚みが薄いことの双 方が備わることで,それぞれの効果が生じ,蓋の強固な止着が実現するの であって,端縁部が圧縮されて薄くなっていることと上面の位置との関係 に何らかの技術的意義があるものでないし,実施例においても何らの効果 も示されていない。そうすると,物の態様として「ように」の語が特段の 意味を有すると解することはできず,前記ア1)及び2)の各構成が両立していれば足りると解するのが相当である。
ウ これに対し,被告は,「突出部の端縁部において…薄くなっており」と いう構成によってのみ「前記突出部の…下位となる」構\成が実現しなけれ ばならないと解釈すべき旨を主張し,その根拠として本件明細書の記載 (段落【0019】),審判請求書(乙12)において上記部分に係る補正 の根拠を本件明細書の「例えば段落0019や図3(b)」と主張したと いう出願経過を挙げる。 しかし,上記の本件明細書の記載(段落【0019】)は実施例の記載 であり,こうした実施例があることから上記のとおり解釈することは相当 でないし,当該記載が引用する【図3】b)によれば端縁部の下面も端縁 部以外の突出部の下面に比して下位となっており,端縁部を圧縮して薄く しなくても端縁部の上面が端縁部以外の突出部の上面に比して下位となっ ているとみる余地がある。補正の根拠に関する主張は,補正に係る部分が 本件明細書の記載の範囲内であることを指摘したものであって,説明した 部分に補正に係る部分の解釈を限定する趣旨を読み取ることはできない。 被告の主張は採用できない。
・・・
上記 1)によれば,プラスチック製品や容器についての一般的な実施 料率は2〜4%程度ということができる。また,・・・によれば, 本件発明1及び2の技術的意義が現れているのは容器の一部である端縁 部の形状に限定されるところ,一般的には端縁部における手指の切創を 防止することは顧客吸引力を持ち得るといえるものの,原告の製品にお いて行われている上記「セーフティエッジ」加工は,蓋の端縁部の加工 であって本件発明1及び2の包装用容器に係る加工であるとは認め難く, 原告においても平成27年以降はこの加工の存在をカタログ等において 顧客に告知していない。被告においても,端縁部において手指の怪我が 生じ得るという課題を認識して顧客に告知する一方で,その部分の怪我 防止の措置について顧客に告知をしていない。そうすると,本件発明1 及び2の技術的意義が容器の売上げに寄与する程度は相当程度小さいも のとならざるを得ないから,上記の一般的な実施料率よりも相当程度低 くすべきである。 以上によれば,本件発明1及び2の実施によって受けるべき相当な実 施料率は●(省略)●と認めるのが相当である。
ウ 損害の額
上記ア及びイによれば,本件発明1及び2の実施に対し受けるべき金銭 の額に相当するのは,1694万4217円であると認められる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2018.04.13
平成29(行ケ)10127 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月29日 知的財産高等裁判所
原告は,平成13年(2001年)以降でさえ,先行技術(甲20)と 技術常識に基づいて,外部から侵入した水分による劣化を防止しているとはいえ ない程度に蛍光体の沈降が抑えられた濃度分布の実現は不可能であったのであり,\n本件明細書の「フォトルミネセンス蛍光体を含有する部材,形成温度,粘度やフ ォトルミネセンス蛍光体の形状,粒度分布などを調整することによって種々の分 布を実現することができ」(【0047】)との記載は,本件構成に対応する技\n術的手段が単に抽象的に記載されているだけで,当業者が発明の実施をすること ができない記載にすぎないことを意味するものに他ならないから,実施可能要件\nを欠くというべきであって,審決の結論には明らかな違法がある旨主張する。 明細書の発明の詳細な説明の記載は,当業者がその実施をすることができ る程度に明確かつ十分に記載したものであることを要する(特許法36条4項1号)。\n本件発明は,「発光装置と表示装置」(発光ダイオード)という物の発明であるとこ\nろ,物の発明における発明の「実施」とは,その物の生産,使用等をする行為をい うから(特許法2条3項1号),物の発明について実施をすることができるとは,そ の物を生産することができ,かつ,その物を使用することができることであると解 される。 本件明細書には,「蛍光体の分布は,フォトルミネセンス蛍光体を含有する部材, 形成温度,粘度やフォトルミネセンス蛍光体の形状,粒度分布などを調整すること によって種々の分布を実現することができ,発光ダイオードの使用条件などを考慮 して分布状態が設定される。」(【0047】)との記載があることから,蛍光体の濃 度分布を適宜調整することにより,本件発明の「コーティング樹脂中のガーネット 系蛍光体の濃度が,コーティング樹脂の表面側からLEDチップ側に向かって高く\nなっている」発光ダイオードを生産することができ,かつ,使用することができる ことは,本件明細書に接した当業者にとって明らかであると認められる。 したがって,発明の詳細な説明の記載は,当業者が本件発明を実施することがで きる程度に明確かつ十分に記載されているものと認められるから,その旨の審決の\n判断に誤りはない。 これに対し,原告が主張する,外部から侵入した水分による劣化を防止している とはいえない程度に蛍光体の沈降が抑えられた濃度分布とは,本件構成に係る「コ\nーティング樹脂中のガーネット系蛍光体の濃度が,コーティング樹脂の表面側から\nLEDチップ側に向かって高くなっている」ものではない状態を示すものである。 そうすると,仮に,このような濃度分布について,発明の詳細な説明や出願時の 技術常識を考慮しても実現することができない,又は,その実現に過度の試行錯誤 を要するとしても,このことは,本件明細書の発明の詳細な説明が,当業者が本件 発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとの前記認定を左右するも\nのではない(発光ダイオードの製造工程において,蛍光体がコーティング樹脂中を 沈降することによって,本件構成を満足するものを製造することができることにつ\nいては,当事者間に争いがないものと解される。)
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.04.13
平成29(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月29日 知的財産高等裁判所
イ 上記アによれば,本件訂正明細書には,アナターゼ型酸化チタンは光触 媒作用が強いため,熱可塑性樹脂等の高分子化合物に添加されるとそれを分解等し てしまうことから,SiO2などで表面処理を行うのが好ましいこと,すなわち,\n本件訂正発明1の表面処理に用いられるSiO2は,光触媒作用が強いアナターゼ\n型酸化チタンが,熱可塑性樹脂等の高分子化合物を分解等しないようにするための ものであることが記載されているものと認められる。
・・・
上記イによれば,SiO2(シリカ)とシロキサンは,共に酸化チタン を被覆するものであること,SiO2(シリカ)は,Si−O−Si結合を有して いるものの,テトラアルコキシシランが加水分解及び重合し,反応すべきものが全 て反応したときの反応物であるのに対して,シロキサンは,Si−O−Si結合を 含むものの総称であって,化学式SiO2で表されるものではないこと,したがっ\nて,SiO2(シリカ)とシロキサンは,化学物質として区別されるものであるこ とが認められる。
エ 前記認定のとおり,本件訂正発明1の「SiO2で表面処理された・・・\n酸化チタン粒子」とは,文言上,「酸化チタン粒子」が,「SiO2(シリカ)」で表\n面処理されているものであることは明らかである。 これに対し,甲1文献には,酸化チタン粉末の表面処理のいずれの方法によって\nも,甲1発明の酸化チタン粉末の表面にシロキサンの被膜が形成されたことが記載\nされていることが認められるものの,甲1文献の上記記載は,甲1発明の酸化チタ ン粉末の表面に「Si−O−Si結合」を含有する被膜が形成されていることを示\nすにとどまるものであって,「SiO2(シリカ)」の被膜が形成されていることを 推認させるものではない(前記認定のとおり,シロキサンは,Si−O−Si結合 を含むものの総称であって,SiO2(シリカ)とは化学物質として区別されるも のである。)。また,その他,甲1発明の酸化チタン粉末の表面に「SiO2(シリ\nカ)」が生成されていることを認めるに足りる証拠はない。 さらに,甲1文献には,テトラアルコキシシラン及び/又はテトラアルコキシシ ランの部分加水分解縮合物について反応すべきものが全て反応したことについては, 記載も示唆もされていないのであるから,この点においても,甲1発明の酸化チタ ン粉末の表面に「SiO2(シリカ)」が生成されていると認めることはできない。\nしたがって,甲1発明において,酸化チタン粉末の表面に,「SiO2(シリカ)」\nが生成されているとは認めることができず,甲1発明の酸化チタン粉末が「SiO 2(シリカ)」で表面処理されているということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2018.04.13
平成29(行ケ)10211 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年3月29日 知的財産高等裁判所
本願商標は,前記第2,1 のとおりの構成であり,オレンジ色で,3つの図形\nを横に並べて表記されているものである。本願商標中,左部分は,左下から右斜め\n上に向かって伸びる斜線と,それに比べ2倍程度太い縦線とが,上部で接した図形 (デザイン部分1),中央部分は,アルファベットのM字状の図形(右端の縦線は, 他の直線より2倍程度太い線で表されている。デザイン部分3),右部分は,右中程\nから,上部及び左側に向けて円弧を描き,その円弧の右途中から円の中心に向けて 直線を描くことで,円弧の右側中程の一部を開口した図形(左側曲線部分は一部2 倍程度太く表されている。デザイン部分2)である。そして,本願商標の上記各部\n分は,それぞれ同じ大きさ,同色であり,構成の一部分を他の部分のより2倍程度\n太く表しているなど,デザイン化の手法も類似して,まとまりよく表\されているも のと認められる。 本願商標の構成中,デザイン部分3は,アルファベットの「M」の語とその形状\nを同じくし,「M」をデザイン化した図形であり,これを連想させるものとして表記\nしたものと理解するのが自然である。 また,証拠(乙4〜7)及び弁論の全趣旨によれば,アルファベットの「G」が デザイン部分2のような構成にデザイン化されて表\される事例があることが認めら れる。そうすると,本願商標の構成中,デザイン部分2及び3は,両者相まって,\nデザイン部分3は「M」を,デザイン部分2は「G」をデザイン化して表したもの\nと容易に理解し,認識されるものと認められる。 デザイン部分1は,その右部分に,デザイン化された「M」,「G」のアルファベ ットとともに,均等に配置され,同色で,しかも,構成の一部分を他の部分より2\n倍程度太く表しているなど同じ手法でデザイン化されて表\されていることが認めら れる。そして,デザイン部分1は,三角形の形状であるから,アルファベットの「A」 が想起されるものであり,「A」がデザイン部分1のような構成にデザイン化されて\n表される事例が多数あること(乙8〜18)を考慮すると,デザイン部分1は,「A」\nをデザイン化して表したものと容易に理解し,認識されるものと認められる。\n以上によれば,本願商標は,「AMG」をデザイン化して表したものと認められる\nから,本願商標からは,「エイエムジイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないもの である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.04.11
平成29(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月29日 知的財産高等裁判所
前記1(1)の認定事実によれば,本件発明は,ユーザがシリーズ化された一連のゲ ームソフトを買い揃えるだけで,標準のゲーム内容に加え,拡張されたゲーム内容\nを楽しむことを可能とすることによって,シリーズ化された後作のゲームの購入を\n促すという技術思想を有するものと認められる。 これに対し,前記1(2)の認定事実によれば,公知発明は,前作と後作との間でス トーリーに連続性を持たせた上,後作のゲームにおいても,前作のゲームのキャラ クタでプレイをしたり,前作のゲームのプレイ実績により,後作のゲームのプレイ を有利にすることによって,前作のゲームをプレイしたユーザに対し,続編である 後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより,後作のゲームの購 入を促すという技術思想を有するものと認められる。 そうすると,公知発明は,少なくとも,前作において実際にプレイしたキャラク タをセーブするとともに,前作のゲームにおいてキャラクタのレベルが16以上と なるまでプレイしたという実績(以下「プレイ実績」という。)をセーブすることが, その技術思想を実現するための必須条件となる。そのため,前作において実際にプ レイしたキャラクタ及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体を採用し た場合には,後作のゲームにおいても,前作のゲームのキャラクタでプレイをした り,前作のゲームのプレイ実績により,後作のゲームのプレイを有利にすることが できなくなる。このことは,前作のゲームをプレイしたユーザに対し,続編のゲー ムをプレイしたいという欲求を喚起することにより,後作のゲームの購入を促すと いう公知発明の技術思想に反することになる。 したがって,当業者は,公知発明1のディスクについて,前作において実際にプ レイしたゲームのキャラクタ及びプレイ実績をセーブできない記憶媒体,すなわち, 「記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に変更しよう\nとする動機付けはなく,かえって,このような記憶媒体を採用することには,公知 発明の技術思想に照らし,阻害要因があるというべきである。 仮に,先行技術発明A等(甲20の1及び2,甲21の1及びの2,甲91,甲 92のゲーム等を含む。以下同じ。)のように,2本のゲームのROMカセットを所 有し,ゲーム機のスロットに挿入するのみで拡張されたゲーム内容を楽しめるゲー ムが周知技術であったとしても,これを公知発明1に対して適用するに当たり,公 知発明1のディスクを,ゲームのプレイ実績をセーブできない記憶媒体,すなわち, 「記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に変更すると,\n上記のとおり,後作のゲームにおいても,前作のゲームのキャラクタでプレイをし たり,前作のゲームのプレイ実績により,後作のゲームのプレイを有利にすること ができなくなるから,前作のゲームをプレイしたユーザに対し,後作のゲームの購 入を促すという公知発明の技術思想に反することになる。 また,仮に,ゲームに登場するキャラクタをゲームプログラムにプリセットして おき,プレイヤーがキャラクタを適宜選択できるようにすることが,本件特許の出 願当時において,技術常識であったとしても,公知発明1の「キャラクタのレベル が16以上である」というゲームのプレイ実績を,プリセットされたキャラクタに 係る情報に変えると,後作のゲームにおいても,前作のゲームのキャラクタでプレ イをしたり,前作のゲームのプレイ実績により,後作のゲームのプレイを有利にす ることができなくなるから,上記と同様に,公知発明の技術思想に反することにな る。 以上によれば,公知発明1において,所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能\nな記憶媒体,一の記憶媒体及び二の記憶媒体を,ディスクから「記憶媒体(ただし, セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に変更して相違点1ないし3に係る\n構成とすることは,当業者が容易になし得たことであるとはいえないとした審決の\n判断に誤りはなく,取消事由1は,理由がない。
(3) 原告の主張について
原告は,公知発明1の技術思想について,魔洞戦紀DDI(前作ゲーム)に記憶 された切換キーがゲーム装置で読み込まれている場合に,勇士の紋章DDII(後作 ゲーム)で,標準ゲームプログラムに加えて,拡張ゲームプログラムでもゲーム装 置を作動させるものであり,これによりゲーム内容を豊富化してユーザに前作の購 入を促すというものであるから,本件発明の技術思想と同じであると主張する。そ して,原告は,上記主張を前提とした上で,上記切換キーには,「魔洞戦紀DDIが 装填された」という条件1に係る情報と「キャラクタのレベルが16以上である」 という条件2に係る情報とが含まれているところ,公知発明1の技術思想である「ユ ーザに前作の購入を促す」ことは,切換キーのうち「魔洞戦紀DDI」が装填され たという条件1に係る情報のみで達成できるのであるから,当業者であれば,その 目的を達成するために,「キャラクタのレベルが16以上である」という条件2に係 る情報を切換キーから除くなどして,記憶媒体についてもセーブデータが記憶可能\nな記憶媒体としないことは容易であり,かえって,このような場合には,よりユー ザの負担なく拡張ゲームプログラムが楽しめるようになるのであるから,前作の購 入を促すことが可能であるともいえ,公知発明1の切換キーに「キャラクタのレベ\nルが16以上である」という条件2に係る情報であるセーブデータを含ませるか否 かは,当業者が適宜選択できる設計事項であると主張する。 しかしながら,上記(2)のとおり,公知発明は,前作と後作との間でストーリーに 連続性を持たせた上,後作のゲームにおいても,前作のゲームのキャラクタでプレ イをしたり,前作のゲームのプレイ実績により,後作のゲームのプレイを有利にす ることによって,前作のゲームをプレイしたユーザに対し,続編である後作のゲー ムもプレイしたいという欲求を喚起することにより,後作のゲームの購入を促すと いう技術思想を有するものと認められる。 そうすると,公知発明は,少なくとも,前作のキャラクタをセーブするとともに, キャラクタのプレイ実績をセーブすることが,その技術思想を実現するための必須 条件となるから,キャラクタ及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体 を採用した場合には,公知発明の技術思想に反することになる。 したがって,「キャラクタのレベルが16以上である」という条件2に係る情報を 切換キーから除くなどして,記憶媒体についてセーブデータが記憶可能な記憶媒体\nとしないことは,公知発明を都合よく分割してその必須条件を省略しようとするも のであるから,上記のとおり,公知発明の技術思想に反することは明らかである。 以上によれば,原告の主張は,その余の点を含め,公知発明の技術思想を正解し ないものに帰し,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.04.11
平成29(ネ)10082等 損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件 商標権 民事訴訟 平成30年3月29日 知的財産高等裁判所 長野地方裁判所
1審被告は,当審においても,1審被告商品はいずれも適法に購入さ れた真正商品であり,1審被告商品がマニアの集めたプロダクトキーを拾ってきた ものであると記載された1審被告の供述調書(甲16)の信用性は低いなどと主張 する。 しかしながら,前記引用に係る原判決の認定事実によれば,1審被告は,平成2 6年5月27日,1審被告商品をインストールしても認証エラーとなった購入者に 対し,同人が1審被告から送信されたクラックツールのダウンロードURLではク ラックツールが既に削除されていたことから,再度,上記と異なるクラックツール のダウンロードURLを送信したことが認められる。 上記認定事実によれば,1審被告は,1審被告商品の購入者に対し,1審被告商 品と併せてクラックツールのダウンロードURLを送信していたのであるから,こ のような行為は,1審被告商品がいずれも適法に購入された真正商品であるという 上記主張と矛盾するものである。かえって,上記捜査段階における1審被告の供述 内容は,マイクロソフトの業務用パッケージであるMSDNに係るDVDの販売につき,マイクロソ\フトからID停止を受け,その後,MSDN関係の販売に使用していたヤフーIDも,ソフトウェア保護団体からの警告で頻繁に停止されるようになったことから,ID停止に関係のない独自のショッピングサイトを設立し,クラ\nックツールのURLに関する情報の販売をメインとして生計を立てていた当時の実 情を述べるものであって,その内容は,具体的かつ詳細なものである上,上記認定 事実にも沿うものである。しかも,1審被告は,顧客に送信したプロダクトキーを 記載したメールを全て削除したとして,プロダクトキーの内容及び入手ルートさえ 明らかにしていないのであり,上記主張を客観的に裏付ける証拠を何ら提出するも のではない。 以上のとおり,上記捜査段階における1審被告の供述は,具体的かつ詳細なもの であって,客観的事実に沿うものである上,これに反すると認めるに足りる客観的 証拠が存在しないことからすると,その信用性が十分に高いというべきである。したがって,1審被告の上記主張は,採用することができない。
(イ) その他の当審における1審被告の主張は,独自の見解をいうもの,又 は証拠の裏付けを欠くものにすぎず,これに対する判断は,前記引用に係る原判決 が説示するとおりであり,上記主張を採用することはできない。
◆判決本文
原審(平27(ワ)36号)における商品に関する判断は以下の通り。
〔原告の主張〕
商標法上の「商品」には,無体物も含まれる。そして,原告商標の指定商品である第9類の「その他の電子応用機械器具及びその部品」には,ダウンロード可能なプログラムが含まれるところ,プロダクトキーは,プログラムをコンピュータで利用するために必要不可欠な部品であり,電子応用機械器具の部品に当たる。したがって,被告商品は,原告商標の指定商品である「その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる。また,被告商品が原告商標の指定商品である第9類の「その他の電子応用機械器具及びその部品」と同一でないとしても,ソ\フトウェアとプロダクトキーは,用途において密接な関係があり,通常,同一店舗において同一需要者に販売されるものであるから,プログラム利用のために必要となるプロダクトキーの販売に関する広告を内容とする情報に登録商標に類似する商標を付して使用するときは,同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがある。したがって,被告商品は原告商標の指定商品である「その他の電子応用機械器具及びその部品」と類似する商品に当たる。
〔被告の主張〕
原告商標の指定商品である「電子応用機械器具」は有体物であるから,「その部品」も当然に有体物である。これに対して,プロダクトキーは,ソフトウェアの部品と考えることができるところ,ソ\フトウェアは有体物ではなく,プロダクトキーもアルファベットや数字を組み合わせた情報であり,有体物ではない。また,「電子応用機械器具及びその部品」にダウンロード可能なプログラムが含まれるとしても,「プログラム」とは,電子計算機を機能\させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものである。これに対して,プロダクトキーは「指令を組み合わせたもの」ではないから「プログラム」には該当しない。そして,プログラムが電子計算機の機械とは独立して取引されるという近時の取引形態を考慮すれば,電子計算機とプログラムは類似しない。さらに,原告は,原告商標の商標登録出願の際に商品区分から意識的に「電子計算機用プログラム」を除外している。それにもかかわらず,本件の侵害訴訟の段階で,被告商品が原告商標の指定商品である「電子計算機用プログラム」ないしその「部品」と類似する旨主張することは禁反言の原則に反する。したがって,被告商品は,原告商標の指定商品である「その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれず,またこれと類似するものではない。
・・・
(1) 弁論の全趣旨によれば,原告製品のプロダクトキーは,英・数字が組み合わされた製品毎に固有の25桁のコードからなる情報鍵であって,1)ユーザーがアプリケーションプログラムをパソコンにインストールする際に,プロダクトキーの入力が求められ,これが入力されなければ,インストール作業を続行できず,2)アプリケーションプログラムをパソコンにインストールする過程で,プロダクトキーに対応する(未認証の)プロダクトIDがパソ\コン内に生成され,これが,ハッシュ値化されたパソコンのハードウェア情報とともに,原告の認証センターにインターネットを通じて送信され,3)原告の認証センターは,送信された情報をデーターベースと照合し,適法なインストールであると認めた場合は,ライセンス認証済みのプロダクトIDをユーザーパソコンに送信し,4)ユーザーパソコン(プログラム)は,原告から受信した認証済みプロダクトIDを記憶装置に記録し,それを検知することでプログラムのインストール作業が終了し,ユーザーは制限のないプログラムの使用が可能\となるものであることが認められる。このように,プロダクトキーは,ユーザーが原告製品をコンピュータ記憶装置内に物理的にインストールするために必要なものである上,原告製品として制限のないプログラムの使用を可能とする認証済みプロダクトIDの発行を原告から得るためにその入力が不可欠とされるものである。\n
(2) ところで,商標法上の「商品」には,無体物も含まれると解され,商標法施行規則別表第9類十\五は「電子応用機械器具及びその部品」として「電子計算機用プログラム」を挙げているが,当該規定は例示であって,それ以外の無体物を含む部品を除外するものではない。そして,前記(1)のとおり,プロダクトキーは,原告製品をコンピュータ記憶装置内に物理的にインストールするために必要なものである上,原告製品として制限のないプログラムの使用を可能とするライセンス認証を得るために不可欠な情報鍵である。そうすると,プロダクトキーは,「電子応用機械器具」(「電子計算機用プログラム」)に相当する原告製品をコンピュータで利用するために必要不可欠な部品であり,電子応用機械器具の部品に該当する。したがって,原告商標の指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」には,原告が著作権を有するOS又はアプリケーションプログラムのソ\フトウェア製品である原告製品のみならず,プロダクトキーが含まれるというべきであるから,被告商品は,原告商標の指定商品と同一のものということができる。
(3) 被告の主張について
ア 被告は,原告商標の指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」は有体物であるのに対し,ソフトウェア及びプロダクトキーは有体物ではなく,また,「電子計算機」とプログラムは類似しない旨主張するが,同主張に理由がないことは,前記(2)のとおりである。
イ 被告は,原告商標の商標登録出願の際に商品区分から意識的に「電子計算機用プログラム」を除外しているにもかかわらず,本件の侵害訴訟の段階で,被告商品が,原告商標の指定商品である「電子計算機用プログラム」ないしその「部品」と類似する旨主張することは禁反言の原則に反する旨主張するが,本件全証拠によっても,原告が原告商標の商標登録出願の際に,商品の区分及び指定商品から意識的に「電子計算機用プログラム」を除外した事実を認めることはできない。
2018.04.11
平成29(ネ)10083 不正競争行為差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成30年3月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1 時機に後れた攻撃防御方法について 被控訴人は,控訴人の当審における各主張及び各証拠の提出が時機に後れた攻撃 防御方法であるとして,当該攻撃防御方法の却下の申立てをした。\nそこで検討するに,控訴人の上記各主張及び各証拠は,原審口頭弁論終結時まで に容易に提出し得たものと認められるから,時機に後れたものというほかない。し かしながら,当該攻撃防御方法の内容に照らすと,実質的には,控訴人の原審にお ける従前の主張を補充的に繰り返すものにすぎず,これにより訴訟の完結を遅延さ せることになるものとは認められない。 したがって,被控訴人の上記申立ては,却下するのが相当である。\n
・・・・
控訴人は,被控訴人の請求は公正な競争秩序の維持を目的とする不正競争防止法 の趣旨に反するものであって,明らかにクリーンハンズ原則に反する請求であり, 権利の濫用であると主張する。 そこで検討するに,現行法上,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法, 著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し, 一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その 反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約 することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内 容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にして いる(最高裁平成13年(受)第866号,第867号同16年2月13日第二小 法廷判決・民集58巻2号311頁)。 上記各法律の趣旨,目的に鑑みると,不正競争防止法2条にいう不正競争によっ て利益を侵害された者が他人の意匠権を侵害する事実が認められる場合であっても 当該意匠権の侵害行為は意匠法が規律の対象とするものであるから,当該事実のみ によっては,直ちに被控訴人が不正競争によって利益を害された者による不正競争 防止法に規定する請求権の行使を制限する理由とはならないと解するのが相当であ る。 これを本件についてみると,仮に,被控訴人商品が訴外株式会社ヤマグチの意匠 権を侵害していたとしても(なお,控訴人は,侵害の有無について,被控訴人商品 の形態が要部において上記意匠権と類似している点のみを主張する。),上記のとお り,このような事実のみによっては,直ちに不正競争防止法に規定する請求権の行 使を制限する理由とはならないというべきである。かえって,前記引用に係る原判 決の認定事実によれば,控訴人商品は,被控訴人商品形態の形態的特徴1)ないし6) を全て模倣するものであって,控訴人商品を販売する行為は,被控訴人商品の出所 について混同を明らかに生じさせることからすれば,事業者間の公正な競争を確保 するという不正競争防止法の趣旨,目的に鑑みると,競争秩序を著しく乱すもので あって,これを規制する必要性が高いものといえる。 そうすると,被控訴人による差止請求及び廃棄請求は,権利の濫用に当たらない と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2018.04.11
平成29(ワ)36543 債務不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月27日 東京地方裁判所(46部)
本件は,原告が被告に対し,原告は被告との間で本件各特許のライセンス契 約を締結したことはないにもかかわらず,被告から本件各特許に係るライセン ス料の支払を請求されたとして,本件各特許のライセンス契約に基づくライセ ンス料支払債務を負わないことの確認を求める事案である。 被告は,原告が被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結した事実を 主張立証しない。むしろ,本件における被告の主張は,原告が被告とライセン ス契約を締結せずに本件各特許に係る特許技術を使用していることを問題とす るものであって,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結され ていないことを前提としているものといえる。 以上によれば,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結され たとは認められず,被告が原告に対して本件各特許のライセンス契約に基づく 特許権者から「ライセンス契約していないのにライセンス料を支払えとの請求を受けました」。ありました。債務が存在しないことを確認する」との主文です。
2018.04.11
平成29(行ケ)10120等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年4月4日 知的財産高等裁判所
イ 前記アのとおり,甲4には,ブロックパターンの改良に関し,耐摩耗性能を\n向上せしめるとともに,乾燥路走行性能,湿潤路走行性能\及び乗心地性能をも向上\nせしめた乗用車用空気入りラジアルタイヤを提供することを目的とする発明が記載 されている(前記ア(イ)b)。 そして,タイヤ踏面の幅方向センター部に踏面幅の50%以内の領域において3 本のストレート溝をタイヤ周方向に環状に設けるとともに,これらのストレート溝 からタイヤ幅方向に延びる複数の副溝を配置したブロックパターンにおいて,1)全 溝面積比率を25%とし,かつ,領域W(タイヤ踏面の幅方向(タイヤ径方向)F F’のセンター部における踏面幅Tの50%以内)の全溝面積比率を残りの領域の 全溝面積比率の3倍とすること,2)ストレート溝aと副溝bとにより区画されたブ ロック1の表面に独立カーフcをタイヤ幅方向FF’に形成すること,3)ブロック 1の各辺とカーフcの各辺のタイヤ幅方向FF’全投影長さ(LG)とタイヤ周方 向EE’全投影長さ(CG)との比を「LG/CG=2.5」とすることにより, 良好な耐摩耗性及び乗心地性能を享受し,かつ,湿潤路運動性能\も低下しないよう にしたものである(前記ア(イ)c)。 したがって,甲4には,「センター領域を含めた全ての領域が溝により複数のブ ロックに区画されたブロックパターンについて,1)全溝面積比率を25%とし,か つ,前記領域(タイヤ踏面の幅方向(タイヤ径方向)FF’のセンター部における トレッド踏面幅Tの50%以内の領域)の全溝面積比率を残りの領域の全溝面積比 率の3倍となし,2)前記ストレート溝と前記副溝とにより区画されたブロックに独 立カーフをタイヤ幅方向に形成し,3)前記ブロックの各辺と前記カーフの各辺のタ イヤ幅方向全投影長さLGとタイヤ周方向の全投影長さCGとの比LG/CG=2. 5とする。」との技術的事項,すなわち,甲4技術Aが記載されていると認められ る。
ウ 本件審決の認定について
本件審決は,甲4に甲4技術が記載されていると認定した。 しかし,前記アのとおり,甲4には,特許請求の範囲にも,発明の詳細な説明に も,一貫して,ブロックパターンであることを前提とした課題や解決手段が記載さ れている。また,前記イのとおり,甲4には,前記イ1)ないし3)の技術的事項,す なわち,溝面積比率,独立カーフ,タイヤ幅方向全投影長さとタイヤ周方向全投影 長さの比に関する甲4技術Aが記載されている。 そこで,これらの記載に鑑みると,上記イ1)ないし3)の技術的事項は,甲4に記 載された課題を解決するための構成として不可分のものであり,これらの構\成全て を備えることにより,耐摩耗性能を向上せしめるとともに,乾燥路走行性能\,湿潤 路走行性能及び乗心地性能\をも向上せしめた乗用車用空気入りラジアルタイヤを提 供するという,甲4記載の発明の課題を解決したものと理解することが自然である。 したがって,甲4技術Aから,ブロックパターンを前提とした技術であることを 捨象し,さらに,溝面積比率に係る技術的事項のみを抜き出して,甲4に甲4技術 が開示されていると認めることはできない。よって,本件審決における甲4記載の 技術的事項の認定には,上記の点において問題がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2018.04. 4
平成29(ネ)10091 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月14日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
イ号製品の構造上,「フック部」に相当し得るのは,先端部2及び曲折部1であり,\n「ボディ部」に相当し得るのは,2枚の樹脂板からなる,本体部3であり,「腹部」 に相当し得るのは,それぞれの樹脂板の,眼瞼縁又は医療用ドレープと対向する矩 形状の底面部分である。 証拠(甲18〜20,甲24の1,乙5,9)及び弁論の全趣旨によると,イ号 製品において,フック部に導かれた液体のうち,それぞれの樹脂板の矩形状の底面 部分を伝うものもあるが,その大部分は,2枚の樹脂板が対向する側面の間を伝っ て排出されるものと認められる。したがって,それぞれの樹脂板の矩形状の底面部 分は,フック部により導かれた液体の大部分を伝わせて排出するものではないから, イ号製品は,構成要件Gを充足しない。
ウ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は,本件特許明細書における「腹部」とは,ボディ部の「腹側」 にあり,排液器と眼瞼縁との間で排液のための動力を生み出す「隙間」を形成する 部分を指し,「腹部」以外の「腹側」とは,上記「隙間」から離れたボディ部の側面 にあって,その形状によって大きな表面積を確保し,流路を拡大する機能\を営む部 分である,と主張する。 しかし,本件特許明細書の【図5】に係る実施例においては,腹部103aは, 丸みをもたせ,断面が略円形状であって,液体が表面を伝うに適した形状であると\n特定され(【0028】),【図11】に係る実施例においては,断面略V字形状に形 成されている箇所が腹部1103aと特定されている(【0041】)のであるから, これらの箇所は,控訴人が主張するところの「濡れ性を利用して流路を拡大する部 分」も含んでいると認められる。また,【図5】に係る実施例において,液体の流量 が増え液面が上昇すると,液面と腹部の表面との「接点」が上昇する(【0028】)\nとされていることから,本件特許明細書においては,液体の流量が少ないときに液 面が接していなかった,「濡れ性を利用して流路を拡大する部分」も「腹部の表面」\nの一部とされていると認められる。 さらに,上記【0028】,【0041】の記載に鑑みると,控訴人が指摘する「ボ ディ部103の腹部103aの表面と医療用ドレープ240とで形成された隙間が\n毛細管として機能し」(【0029】)及び「腹部1103aと眼瞼縁233との間に\n形成された隙間が毛細管として機能し」(【0042】)との記載は,腹部のうち眼瞼\n縁又は医療用ドレープに近接する部分が,眼瞼縁又は医療用ドレープとの間で毛細 管として機能していることを述べていると解すべきであって,これらの記載から,\n毛細管として機能する部分のみが腹部であるということはできない。【図5】の「1\n03a」の文字から出た線及び【図11】の「1103a」文字から出た線が指し 示す位置は,腹部の範囲(上限位置)を示すものとは解されない。 本件特許明細書の【図13】及び【図15】に係る実施例においては,控訴人が 主張するところの「毛細管現象を引き起こす部分」と「濡れ性を利用して流路を拡 大する部分」からなる凹凸の位置を説明するために「腹側」との表現が用いられて\nいるにすぎず,そのうちの「毛細管現象を引き起こす部分」を「腹部」であると解 する根拠とすることはできない。 したがって,毛細管として機能するか否かによって「腹部」が特定されていると\nも,「毛細管現象を引き起こす部分」か「濡れ性を利用して流路を拡大する部分」か で,「腹部」と「腹側」との表現を使い分けているともいえない。控訴人の主張には,\n理由がない。
◆判決本文
原審はこちら。平成28(ワ)6357
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.04. 4
平成27(ワ)6555等 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年3月15日 大阪地方裁判所
原告は,上記のうち秘密管理性の点につき,本件技術情報は,電子データと 電子データを印刷した紙ベースで保管され,それらの情報にアクセスできる者を福 島工場の従業員18人と役員ほかの限られた原告の従業員に限り,また就業規則に 従業員の秘密保持義務を定めるほか,秘密保持の誓約書の提出を受けていた旨主張 するとともに,それらの従業員は,それらの本件技術情報が原告にとって重要な技 術情報であり,持ち出したり,漏洩したりしてはいけない秘密の情報であることは 十分に認識できていたから,営業秘密として管理されていたと主張する。\nこの点,証拠(甲31の1ないし18,甲32,甲33,甲36)によれば,原 告主張の情報の管理状況や,就業規則の定めや,従業員から誓約書を徴求している 事実が認められ,またその対象の情報が,原告において重要な技術情報であると認 識できるとの点も,そのとおりということができる。
(3) しかしながら,原告の取締役であったP1及び原告の代理店としてその販売 のみならず海外でのメンテナンスを担当していた被告銀座吉田は,原告が,何ら秘 密保持義務を負わせることなく,また後日の返還を求めることもなく,原告製品の 図面等,製品に関わる情報を,取引先,製造下請業者,メンテナンスを担当する業 者にも交付していたことを主張しているところ,ゴミ貯溜機の設計図面等の管理に 関して以下のような事実が認められる。 ア 原告が営業秘密と主張する図面の中には,発行者を「日本クリーンシステム (株)福島工場」として,日付け入りの「発行」とするスタンプと「製作用」とのス タンプが押されているもの(別紙営業秘密目録記載1の機械図面中,2の八角部分 の図面に含まれる甲24の2,4のドラム内の分割羽根部分の図面に含まれる甲2 6の1ないし11,甲27の2ないし4,5の蓋ジョイント部分の図面に含まれる 甲28の3,4,5,7)が存し,これら図面が部品を製造する業者に交付されて いたことがうかがわれる。
イ 被告らが本件製品1の製造に関わっていたことを示すものとして原告が証拠 として提出したメール(甲73)の記載内容によれば,原告製品のメンテナンスの ためには,メンテナンス業者において,必要な部品を図面で第三者に請け負わせて 作成させる場合もあることが認められる。そうすると原告は,過去に被告銀座吉田 に対して海外での原告製品の設置やメンテナンスをさせていたというのであるか ら,メンテナンスを担当していた被告銀座吉田に対し,それらの作業に必要な図面 等を交付していたはずと考えられる(なお,被告銀座吉田は,第11回弁論準備手 続期日において陳述した被告銀座吉田準備書面(8)において,本件製品1,2の 製造に関与したことを推認させる事情となり得る過去販売した原告製品の図面等を 保有していることを自認している。)。また,同メールによれば,中国成都におけるゴミ貯溜機の購入設置者は,メンテナンス業者を競争入札により選ぼうとしていることがうかがえるが,このことからは,ゴミ貯溜機を購入した者は,業者を任意に選んで,上記内容のメンテナンスを実施することが可能であるということ,すなわち,ゴミ貯溜機を購入した者は,メンテナンスに必要な図面類等を原告から交付されていたことを推認することができる。
ウ 原告は,過去に被告サン・ブリッドに対して原告製品の部品の一部を供給さ せていた(甲21)というのであるから,それに伴い被告サン・ブリッドに対し, 少なくとも当該部品を製造するに必要な設計図を交付していたことが認められる。
(4) このように,原告が本件において営業秘密として主張する本件技術情報と同 種の技術情報であると考えられる原告製品の図面等が被告銀座吉田はもとより,原 告製品購入者,あるいは部品製造委託先に交付されていた事実が認められることに 加え,そもそも原告は,P1及び被告銀座吉田による秘密管理性を否定する事実関 係の主張について全く沈黙しており,その指摘に係る図面等の技術情報の外部提供 について,営業秘密の管理上,いかなる配慮をしていたか一切明らかにしていない ことも併せ考慮すると,原告のゴミ貯溜機を製造するに必要な設計図面等の多くは, P1及び被告銀座吉田が主張するように,特段の留保もなく購入者はもとより取引 関係者に交付されていたことを認めるのが相当である。 そうすると,別紙営業秘密目録記載1,3の技術情報そのものが,上記図面等に 含まれていると的確に認めるに足りる証拠はないものの,かといって,これら技術 情報についてのみ他の同種技術情報と異なる特別の管理がされていたと認めるに足 りる証拠もない以上,同様の管理状況であったと推認するほかなく,したがって, これでは,上記技術情報が不競法にいう「秘密として管理されていた」ということ はできないということになる。
2018.04. 4
平成29(ワ)25465 著作者人格権確認等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年3月26日 東京地方裁判所
原告は,本件訴えにおいて,原告が本件CMを制作した事実の確認を求めている。 しかし,確認の訴えは,原則として,現在の権利又は法律関係の存在又は不存在 の確認を求める限りにおいて許容され,特定の事実の確認を求める訴えは,民訴法 134条のような別段の定めがある場合を除き,確認の対象としての適格を欠くも のとして,不適法になるものと解される(最高裁昭和29年(オ)第772号同3 6年5月2日第三小法廷判決・集民51号1頁,最高裁昭和37年(オ)第618 号同39年3月24日第三小法廷判決・集民72号597頁等参照)。 したがって,本件訴えのうち,原告が本件CMを制作した事実の確認を求める訴 えは不適法である。 なお,事案に鑑み付言するに,仮に,原告が,本件CMを制作した事実ではなく, 原告が本件CMにつき著作権ないし著作者人格権を有することの確認を求めたとし ても,確認の訴えは,現に,原告の有する権利又はその法律上の地位に危険又は不 安が存在し,これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切で ある場合に,その確認の利益が認められるところ(最高裁昭和27年(オ)第68 3号同30年12月26日第三小法廷判決・民集9巻14号2082頁参照),前 記前提事実(第2,2),証拠(甲18ないし20,23ないし25,19,乙1, 2)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,アストロミュージックから許諾を受けて 本件キャッチフレーズを使用しているにとどまり,本件CMについて被告が著作権 ないし著作者人格権を有するなどとは主張していないから,原告が有する権利又は 法律上の地位に存する危険又は不安を除去するために,本件CMの著作権ないし著 作者人格権の存否につき被告との間で確認判決を得ることが必要かつ適切であると は認め難く,結局,確認の利益を欠くものとして不適法というほかない。
2 争点3(被告は,原告に対し,原告が本件キャッチフレーズを考えた本人で あるとの事実を被告の社内報に掲載する旨を約したか)について
原告は,被告が原告に対し,原告が本件キャッチフレーズを考えた本人であると の事実を被告の社内報に掲載する旨を約したと主張し,同事実を被告の社内報に掲 載するよう請求するところ,同主張は,原告と被告との間で,被告が同掲載義務を 負うことを内容とする契約が成立した旨を主張するものと解される。 そこで検討するに,原告と被告代表者が平成23年6月頃面会したこと,その後\n程なくして,原告と被告の宣伝課長が面会し,原告の写真を撮影したことは,当事 者間に争いがない。 しかし,原告本人尋問の結果によっても,原告と被告の宣伝課長との面会の場に おいては,被告の社内報に,誰がどのような内容の記事を作成し,いつまでに掲載 するのかなど,記事の掲載をどのように実現させていくかについては,何ら明確に 合意しなかったというのである。そうすると,仮に,原告本人が供述する事実関係 が認められたとしても,それのみをもっては,被告が行うべき給付義務の内容が具 体的に定まっていたとはいえず,原告と被告との間に,法的拘束力を有する契約と して,被告に履行を強制し得るまでの合意があったと評価することは困難である。 また,原告本人尋問の結果によっても,被告のホームページへの掲載が話題とな った形跡はおよそうかがえないから,原告と被告との間に,この点に関する契約が あったとみる余地はない。 したがって,被告の社内報及びホームページに,原告が本件キャッチフレーズを 考えた本人であるとの事実を掲載することを求める原告の請求には理由がない。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2018.04. 4
平成27(ワ)21897等 著作権侵害行為差止等請求事件,損害賠償請求反訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月28日 東京地方裁判所
原告は,原告が平成16年8月10日に完成させた同日版「eBASEserv er」は,1)合計22個の辞書がそれぞれ様々な辞書情報を備えており,データベ ースの体系的な構成の中で各データ項目と紐付けられて辞書網を構\成している点に 創作性が認められ,2)個々の辞書が,それ単独でも,体系的構成及び情報の選択に\nおいて創作性が認められるから,それ自体が,データベースの著作物と認められる べき旨主張する。 原告の主張によれば,「eBASEserver」は,食品の商品情報を広く事 業者間で連携して共有する方法を実現するためのデータベースを構築するためのデ\nータベースパッケージソフトウェアであって,食品の商品情報が蓄積されることに\nよりデータベースが生成されることを予定しているものである。そうすると,この\nような食品の商品情報が蓄積される前のデータベースパッケージソフトウェアであ\nる「eBASEserver」は,「論文,数値,図形その他の情報の集合物」(著 作権法2条1項10号の3)とは認められない。 原告は,「eBASEserver」に搭載されている辞書情報を「情報」と捉 え,この集合物をもって「データベース」と主張するものとも解されるが,原告の 主張によっても,これらの辞書ファイルは,商品情報の登録に際して,当該商品情 報のうち特定のデータ項目を入力する際に参照されるものにすぎないのであって, 辞書ファイルが備える個々の項目が,「電子計算機を用いて検索することができる ように体系的に構成」(著作権法2条1項10号の3)されていると認めることは\n困難である。 したがって,「eBASEserver」は,著作権法上の「データベース」に 当たるものとは認められないから,その創作性につき検討するまでもなく,データ ベースの著作物ということはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2018.03.29
平成29(行ケ)10170 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年3月22日 知的財産高等裁判所
上記(2)ア及びオによれば,外国における本件商品の主要メーカーのウェ ブサイトでは,本件商品を指す用語として「paint protection film」及び 「PPF」の語が特段の注記もなく使用されており,自社商品を識別する ために,3M社は「Scotchgard」,Avery Dennison社は「AWF 1500シリーズ」,XPEL社は「XPEL ULTIMATE」等といった独自の商標を 用いていることが認められる。さらに,インターネット上の百科事典とい えるウィキペディア(英語版)には,「Paint protection film」の項目に, 「PPF」の語と共に本件商品の説明が記載されている(なお,ウィキペ ディアは,誰もが自由に記事を執筆できるものであるが,正確性を担保す るための一定の仕組みが構築されているし(甲45の2から45の4),\n本件において問題となっている項目の記載内容は,本件商品の主要メーカ ー等のウェブサイトにおける記載と整合しているから,信用するに足りる ものというべきである。)。これらの事実によれば,英語圏においては, 本件商標の登録査定当時,「paint protection film」の語は本件商品の一 般的名称として,「PPF」の語はその略称(「paint protection film」 の各単語の頭文字を組み合わせたものであることは明らかである。)とし て,それぞれ使用されていたと認めるのが相当である。
ウ そして,上記(2)イからエにおいて認定したとおり,本件商品の国内メー カーや施工業者のウェブサイト,雑誌の記事及び広告,ブログの投稿記事 において,本件商品が,アメリカ発の先端的商品としてしばしば紹介され, かつ,その記事の中で,本件商品を指す用語として,「ペイントプロテク ションフィルム」,「PPF」,「ペイント・プロテクション・フィルム (PPF)」の各語が繰り返し使用されていたことも明らかである。 そうすると,本件商品の取引者や需要者は,本件商標登録査定当時,(2) イからエに認定したような国内の記事を通じて,あるいは,(2)アに認定し た国外の商品紹介記事等に直接接することによって(アにおいて認定した とおり,本件商品の需要者は,高級車や外国車を保有する消費者であるか ら,車やその美観の維持等について関心や意識が高いことが予想され,ま\nた,取引者は,そのような需要者を相手とする業者であることを考えると, 国内の記事に関心を持った需要者や取引者が,国外の情報をも得ようとす ることは十分に考えられるところであるし,現に,そのようなことが起こ\nっていたことがうかがわれる。),「ペイントプロテクションフィルム」 は,車の保護フィルムである本件商品一般を指す言葉であり,「PPF」 はその略称であると認識していたものと認められる。
エ この点,ゲンロク平成27年9月号から平成28年3月号にかけて掲載 された被告の広告には,いわゆるチェックマークと「Yes!PPF P AINT PROTECTION FILM」を組み合わせて意匠化した ロゴと,「ペイント・プロテクション・フィルム(PPF:ピーピーエフ)」 の語が記載されているところ(甲57の10から57の12),これらの 広告のみを見る限りにおいては,「PPF」の語が,被告の販売・施工す る自動車用車体・ガラス保護フィルムの出所識別標識として使用されてい るとみる余地もある。 しかし,これらの広告は,本件商標の登録査定日の約半年前からされた ものにすぎず,それ以前からされている他者による「PPF」の語の使用 状況に鑑みると,本件商品の取引者及び需要者においては,「PPF」の 語が本件商品の一般的な略称として用いられていたとの判断を左右するに 足りないというべきである。 オ 以上によれば,本件商品の取引者及び需要者は,本件商標の登録査定時 において,「PPF」の語を本件商品の一般的な略称と認識していたと認 めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2018.03.28
平成29(ネ)10007 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所(4部) 東京地方裁判所 立川支部
原告製品1のPCソースコード(甲19),原告製品2のPCソ\ースコード (甲21),原告製品3及び4のPCソースコード(甲23)を,それぞれ,被控訴\n人が被告製品1のPCソースコードの一部として提出するもの(甲20),被告製品\n2のPCソースコードの一部として提出するもの(甲22),被告製品3及び4 の PCソースコードの一部として提出するもの(甲24)と対比すると,一致する表\ 現が多数認められる。 そして,被告製品1ないし4のPCソースコードには,以下のとおり,原告製品\n1ないし4のPCソースコードに依拠して作成されたことをうかがわせる記載がある。
1) 原告製品1と被告製品1の対比
a 甲19の1頁3行ないし6行の冒頭には,いずれも,「Private」との 記載があるところ,甲20の1頁3行ないし6行の冒頭は,いずれも「'」を付した 「'Private」との記載であり,甲19の命令文を非実行化するものである。
b 甲19の1頁59行には,「lblCh.Caption=txtRecCh.Text&“ch" '20101016 Ver2.2.3」との記載があるところ,甲20の2頁4行には,「'」を付した「'lblCh.Caption=txtRecCh.Text&“ch" '20101016 Ver2.2.3」との記載であり,甲19の命令文を非実行化するものである。
c 甲19の3頁24行から25行に,「'2010/03/11 メールにて変 更要求−−−−−'『測定停止』の例外処理追加'D」との記載があるところ, 同記載は,2010年3月11日にDが修正を行ったことを示すものである。甲2 0の3頁36行から37行には,これと全く同一の記載があり,Dが被告製品1の PCソフト作成を依頼された日以前に行われた修正の記載が残っている。\n
a 甲23の1頁10行に,「Dim flgExceotion1 As Boolean 'PICバグ対策フラグ 一時使用 2012/10/16追加」との記載があるところ,同記載は,2012年10月16日に追加修正を行ったことを示すものである。甲24の1頁10行には,これと全く同一の記載があり,Dが被告製品3及び4のPCソフト作成を依頼された日以前に行われた修正の記載が残っている。\n
b 甲23の1頁13行に,「'2012/3/6追加」との記載があり,同記載 は,2012年3月6日に追加修正を行ったことを示すものである。甲24の1頁 13行には,これと全く同一の記載があり,Dが被告製品3及び4のPCソフト作\n成を依頼された日以前に行われた修正の記載が残っている。
c 甲23の1頁32行に,「'MRS-23RWTLのPICバグがありPIC 修正まで一時的に補正する2012/10/16」との記載があるところ,同記 載は,2012年10月16日に「MRS-23RWTL」,すなわち原告製品3の バグの一時的補正を行ったことを示すものである。甲24の1頁32行には,これ と全く同一の記載があり,Dが被告製品3及び4のPCソフト作成を依頼された日\n以前に,原告製品3の修正をしたとの記載が残っている。
d このほか,甲23の1頁37行の「'−−−−−64QAM用アプリにする場 合−−−−−'2012/12/26」との記載は,甲24の1頁33行と,甲23 の1頁41行の「'コマンドライン引数を取得しデバッグモード確認 2012/ 3/7追加」との記載は,甲24の1頁38行と,甲23の2頁44行の「'64 QAMで10H Endlessに変更する 2013/1/23」との記載は, 甲24の2頁39行と,甲23の3頁10行の「'64QAMモードのみ〔外部接 点制御〕インジケータを表示する 2013/1/23」との記載は,甲24の3 頁1行と,甲23の3頁56行の「pid=1 'ポート番号は1に固定する 2013/2/14」との記載は,甲24の3頁37行と,それぞれ同一の記載であ り,甲23において,Dが被告製品3及び4のPCソフト作成を依頼された日以前\nに行われた修正等の記載が,そのまま甲24に記載されている。 以上によれば,Dは,被告製品1ないし4のPCソースコードを作成するに当た\nって,原告製品1ないし4のPCソースコードに依拠したことが推認される。\n
1)原告製品1と被告製品1の対比
a 甲19の1頁3行ないし6行の冒頭には,いずれも,「Private」との 記載があるところ,甲20の1頁3行ないし6行の冒頭は,いずれも「'」を付した 「'Private」との記載であり,甲19の命令文を非実行化するものである。
2018.03.28
平成29(行ケ)10062 取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所(4部)
引用発明Aでは,第1のワイヤが接続されるpn接合ダイオードの一の電 極及びショットキーバリアダイオードの一方の電極は,いずれもカソード電極とな\nる。 そして,引用例には,IGBT4とダイオード5との組合せを,SiCMOSF ETとショットキーバリアダイオードとの組合せに置き換える場合,置換えの前後 で動作を異ならせる旨の記載や示唆はない。 また,引用発明Aは,「トランスファーモールド樹脂で封止した電力用半導体装 置には,主端子に大電流を流すことができるブスバーの外部配線が,ねじ止めやは んだ付けで固定されるため,電力用半導体装置の組み立て時において,主端子部に おおきな応力が働き,この応力により,主端子の外側面とトランスファーモールド 樹脂との接着面に隙間が発生したり,トランスファーモールド樹脂本体に微細なク ラックが発生する等の不具合を主端子部に生じ,電力用半導体装置の歩留まりが低 くなり生産性が低下するとともに,信頼性も低下する」ことを課題とし,「トラン スファーモールド樹脂により封止された電力用半導体装置であって,主回路に接続 される主端子に大電流を流すことのできる外部配線を接続しても,外部配線の接続 により主端子部に発生する不良を低減でき,歩留まりが高く生産性に優れるととも に,信頼性の高い電力用半導体装置を提供すること」を目的とする発明であって(【0 007】,【0008】),この目的を達成することと,SiCMOSFETの型 や並列接続するショットキーバリアダイオードの接続方向を変更することは,無関 係である。 したがって,当業者が,引用発明Aにおいて,上記目的を達成するために,「前 記PN接合ダイオードの一の電極」及び「前記ショットキーバリアダイオードの一 方の電極」をカソード電極からアノード電極に変更する動機付けがあるとはいえな\nいから,相違点1’に係る本件発明1の構成を当事者が容易に想到できたものであ\nるとは認められない。
(イ) さらに,本件発明は,MOSFETに寄生しているpn接合ダイオードに 電流が流れると,MOSFETの結晶欠陥が拡大してデバイス特性が劣化し,特に, SiCMOSFETでは,寄生pn接合ダイオードに電流が流れると,オン抵抗が 増大するという課題があったが,ショットキーバリアダイオードを並列接続しても pn接合ダイオードに電流が流れてしまう現象が生じていることから(【0002】 〜【0004】,【0006】),本件発明1の構成を採用し,第2のワイヤに寄\n生するインダクタンスによって,pn接合ダイオードの順方向立ち上がり電圧以上 の逆起電力が発生しても,pn接合ダイオードに電流が流れないようにする(【0 014】)との作用効果を奏するものである。 しかし,引用発明Aの課題及び目的は,前記(ア)のとおりであり,引用例には, ダイオード5やワイヤーボンド7にインダクタンスが寄生することについての記載 や示唆はないことから,引用例に接した当業者が,引用発明Aに本件発明の作用効 果が期待されることを予想できたとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2018.03.28
平成29(行ケ)10085 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所(4部)
本件決定は,本件発明1の特許請求の範囲のうち「寄生ダイオード(131)の 立ち上がり電圧」は「上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの記載が, いかなる電流が流れる場合のことを表したものであるか不明であるから,明確性要\n件に適合しないと判断した。
(2) 前記2(3)イのとおり,請求項1において,寄生ダイオード(131)の「立 ち上がり電圧は,上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高く」と特定されてい るのは,本件発明1の構成として,同期整流を行う際,寄生ダイオード(131)\nの立ち上がり電圧を,ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くするという技術的 事項を採用する旨特定するものである。 そして,本件発明1に係る電力変換装置において使用される還流電流の程度が限 定されていないことと,同期整流を行う際には,常に,寄生ダイオード(131) の立ち上がり電圧を,ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くすることとは,関 係がない。
(3) したがって,「寄生ダイオード(131)の立ち上がり電圧」は「上記ユニ ポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの本件発明1の特許請求の範囲の記載が, 第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。同記載 が明確ではないから,本件各発明の特許請求の範囲の記載は,明確性要件に適合し ないとする本件決定の判断は誤りである。
・・・・
引用発明は,モータの回生モードにおいて,回生電力の消費能力を高めると\nいう課題に対して,順方向電圧降下が高いボディダイオードに電流を流し,回生電 力を消費させるというものである。 このように,引用発明は,モータの回生モードにおいて,ボディダイオードに電 流を流し,ボディダイオードにおいて回生電力を損失させるという課題解決手段を 採用したものである。一方,本件周知技術は,寄生ダイオード側に電流を流さず, 発熱損失を低減させるというものであるから,引用発明の課題解決手段と正反対の 技術思想を有するものである。したがって,当業者は,引用発明におけるモータの 回生モードにおいて,正反対の技術思想を有する本件周知技術を適用することはな い。 そして,引用例には,引用発明の電力変換装置において,力行モードを回生モー ドから切り離し,力行モードの動作のみを変更することを示唆するような記載はな いから,当業者は,力行モードにおける動作のみを変更することを容易に想到する ことはない。 したがって,引用発明に本件周知技術を適用する動機付けはないというべきであ る。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2018.03.28
平成29(行ケ)10148 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所(4部)
本件審決は,引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが示唆され ている旨判断した。
a この点について,被告は,本願発明の「固定情報」は,複数の取引ごとに変 化しない情報であればよく,取引のたびごとに生成削除されたとしても,生成のた びに同じ値の「仮情報」が生成されていれば「固定情報」であるといえる,実際, 引用発明において,仮情報は,口座取引の内容と無関係に生成される値であり,口 座取引内容に応じて値を変化させる必要がない旨主張する。 しかし,引用例1の【図3】のステップS310〜S311には,「仮情報」を 口座情報に基づいて生成することの記載はないし,「仮情報」はセキュリティの観 点から取引ごとに異なるものとすることが通常であるところ,引用例1にこれを同 じにすることを示唆する記載もない。したがって,引用発明において,生成のたび に同じ値の「仮情報」が生成されることが示唆されているとはいえない い。
b 被告は,引用例1の「ホストコンピュータ30においては,事前に仮情報デ ータと顧客口座情報の対応を検証し,ホスト側データ保管部302に保管しておい ても構わない。」(【0045】)との記載は,「仮情報」を複数の取引にまたが\nって用い得ることを示唆している旨主張する。 しかし,前記イ(イ)のとおり,事前に仮情報データと顧客口座の対応が検証され る場合であっても,「仮情報」は取引終了時に削除されることからすれば,「仮情 報」が複数の取引にまたがって用い得ることが示唆されているとはいえない。
c 被告は,引用例1の「仮情報使用の有効期限と有効回数を設けることも可能\nである。」(【0086】),「仮情報に有効期限と有効回数を設けることにより, 第3者等による不正利用防止のセキュリティを向上させることができる。」(【0 087】)との記載によれば,引用発明の「仮情報」を有効期限や有効回数が設け られた情報のような固定情報として生成することが示唆されている旨主張する。 しかし,「有効期限」(【0086】【0087】)は,携帯端末装置が仮情報 を受け取ってから,現金自動取引装置に仮情報を入力するまでの期限のことと解さ れ,「有効期限」の定めがあるからといって,1回の取引を超えて「仮情報」が使 用されることを示唆するとはいい難い。そして,「有効回数」(【0086】【0 087】)は,仮情報の使用回数を,1回限りではなく,数回としたものと解され るが,前記イ(イ)のとおり,引用発明は,課題解決手段として,顧客口座情報を用 いない手段を採用しているのであるから,「有効回数」の定めがあるからといって, 「固定情報」であることが示唆されているとはいい難い。
d したがって,引用発明の「仮情報」は「固定情報」であることが示唆されて いる旨の本件審決の判断には誤りがあるが,相違点2を容易に想到することができ た旨の本件審決の判断は,結論において正当である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.03.28
平成29(ネ)10092 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記1(2)のとおり,本件発明1の意義は,熱放散ブリッジに軸方向空気通 路を貫設せずに電力電子回路を冷却することにより,電子構成部品の配置に利用可\n能な空間を十\分に確保するという課題を達成するために,熱放散ブリッジの底面を 冷却流体通路の一方の壁とする構成を採用したことなどにある。すなわち,本件発\n明1は,冷却流体が,横方向に吸い込まれて,後部軸受けの中央スロット4b及び 4cの方に流れ,熱放散ブリッジの下方で冷却流体通路内を循環し,熱放散ブリッ ジの底面及び冷却フィンを,それらの全長にわたって掃引した後,後部軸受けの側 部スロット4a及び4dを通って排出される構成とすることにより,熱放散ブリッ\nジの上面に搭載された電力電子回路が,冷却フィン及び熱放散ブリッジを介して, 伝導によって冷却されるという効果を奏するようにしたものである。 そして,このように構成要件1Gの冷却流体通路が,熱放散ブリッジを冷却する\nための構成であり,同通路を流れる冷却流体が,熱放散ブリッジの底面をその全長\nにわたって掃引するものであることからすると,冷却流体通路の長手方向壁のうち, 少なくとも熱放散ブリッジの底面により形成される壁は,冷却効率の観点から,冷 却流体通路の全長にわたっている必要がある。
(イ) 一方,本件明細書1には,構成要件1Gの冷却流体通路が,同通路の他方\nの長手方向壁を形成している後部軸受けを冷却するための構成であることは何ら記\n載されていない。そして,前記1(2)のとおり,本件発明1は,軸方向を流れる冷却 流体によって,機械内の冷却流体全体の流量が増加し,オルタネータの内部部品を はるかに良好に冷却することができるという効果を奏するものであることからする と,後部軸受けの冷却は,冷却流体通路を通る空気によってではなく,主に,空間 22を通る軸方向空気流により機械内の空気流量全体が増加することによって達成 されるものであると認められる。 そうすると,後部軸受けをもって冷却流体通路の壁を形成する構成とすることは,\n空気の流れを冷却流体通路に沿わせる目的を持つのみということになるため,必ず しも,冷却通路全体にわたる必要はない。例えば,本件発明1の実施形態において, 後部軸受けの中央スロット4b及び4cの直上にある空気は,ファンによって後部 軸受け内部に流入し,絶えず側方からの空気と入れ替わるので,その直上の熱放散 ブリッジを冷却する空気流を形成することは,【図2】に示される構造から明らか\nであり,熱放散ブリッジを冷却するという機能に鑑みれば,中央スロット4b及び\n4cの部分には後部軸受けにより形成される壁はないものの,冷却流体通路に該当 するといえる。
(ウ) 以上のとおり,本件明細書1に記載された冷却流体通路の技術的意義に鑑 みると,構成要件1Gの冷却流体通路は,熱放散ブリッジの底面により形成される\n長手方向壁が全長にわたって設けられることを必要とする一方,後部軸受けにより 形成される長手方向壁が全長にわたって設けられることは,必ずしも必要ではない と解される。 また,かかる解釈は,冷却流体通路と冷却フィンとの関係とも整合する。すなわ ち,本件明細書1には,「この冷却手段は,通路17内に配置されて,選択された 通路に冷却流体を流す。」(【0054】)との記載があり,かつ,【図2】によ れば,冷却フィンが熱放散ブリッジの底面の半径方向全長にわたって配置され,後 部軸受けが対向しない箇所にも存在していることが読み取れるのであるから,熱放 散ブリッジと中央スロット4b及び4cとが対向する箇所は,冷却フィンが配置さ れる箇所という観点からも,熱放散ブリッジと後部軸受けとが対向する箇所と同様, 通路17の内部といえる。 加えて,仮に,熱放散ブリッジの底面及び後部軸受けの双方が壁をなしている部 分のみが冷却流体通路に該当すると解するならば,冷却流体通路の半径方向外側の 端部は,熱放散ブリッジの外周か後部軸受けの外周のうち軸側の部分となるところ, 【図2】を参照すると,後部軸受けの外周が保護カバー11に到達しておらず,後 部軸受けと保護カバーとの間に隙間が存在することは明らかであるから,冷却流体 通路は保護カバーと連通していないと理解される。しかし,本件明細書1には,「本 発明によれば,保護カバーは,流体通路17と向き合う位置に開口19を有する。 この開口は,通路17の外周と連通している。」(【0049】)として,通路1 7が保護カバーの開口と連通していることが記載されており,前記理解と整合しな い。
ウ 以上のとおり,特許請求の範囲の記載,本件明細書1の記載及び本件発明1 における冷却流体通路の技術的意義を総合すれば,冷却流体通路は,熱放散ブリッ ジの底面が冷却流体通路の全長にわたり長手方向壁を形成していることを要する一 方,後部軸受けにより形成される長手方向壁は冷却流体通路の全長にわたる必要は ないと解される。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2018.03.27
平成29(ワ)21107 不正競争行為差止等請求事件 平成30年3月19日 東京地方裁判所
原告商品と旧原告商品のV型プレートは,中央下部の幅,4個の穴の位置,そ れぞれの穴の距離,中央下部の窪みの位置・角度,両翼下部の角度,両翼の長さ,両 翼の穴の位置が共通するが,両翼の上部が削られてその形状及び幅が両翼にかけて細 長く変更されている。上記変更により,原告商品のV型プレートの美観から受ける印 象は旧原告商品のV型プレートとは相当に異なるものといえる。そうすると,上記変 更は,V型プレートの形態としてはその美観において実質的に変更されたと評価し得 る変更であって,しかも,V型プレートはサックス用ストラップの美観における特徴 的部分であり需要者が着目する部分であるといえるから,V型プレートの変更後の形 態は,美観の点において保護されるべき形態であると認められる。もっとも,V型プ レートを有するサックス用ストラップは,旧原告商品はもとより他にも同種商品が存 在し(乙1,2),細長形状の形態も公開されているところであるから(乙4),ここ で保護されるのは,V型プレートの中央部の形状や両翼の角度・形状等を総合した特 有の形状に限られるというべきである。
・・・
以上のとおり,原告商品のV型プレートの変更部分は,商品の形態において実 質的に変更されたものであり,その特有の形状が美観の点において保護されるべき形 態であると認められるから,原告商品が「日本国内において最初に販売された日」は, 旧原告商品が最初に販売された日ではなく,原告商品が最初に販売された日である平 成28年3月頃であると認められる。
2018.03.16
平成29(行ケ)10188 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成30年3月12日 知的財産高等裁判所
前記(1)によれば,意匠の創作非容易性は,その意匠の属する分野における通 常の知識を有する者(当業者)を基準に,公然知られた形状,模様若しくは色彩又 はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたか否かを判断して 決するのが相当である(意匠法3条2項)。 本願意匠の「アクセサリーケース型カメラ」は,アクセサリーケースとしての用 途と機能を有し,併せて相手に分からないように撮影し,録画するという隠しカメ\nラとしての用途と機能を有するものである。アクセサリーケースに隠しカメラを設\n置する場合,多種多様な隠しカメラの撮像部の配置を参考にして,適切な設置場所 を決定すると考えられるから,本願意匠に係る当業者は,アクセサリーケースの分 野における通常の知識と,隠しカメラの分野における通常の知識を併せて有する者 である。 前記1(4)のとおり,引用意匠3は,ガム等の収納容器の内部に撮影機能を組み込\nんだ「撮影機能付ボトルケース」であり,引用意匠4は,ティッシュボックスの収\n納容器の内部に撮影機能を組み込んだ「撮影機能\付ティッシュボックス」である。 したがって,「アクセサリーケース型カメラ」の当業者にとって,隠しカメラで ある引用意匠3及び4は,出願前に公然知られた形態といえるから,本願意匠にお ける撮像部の設置場所を決定するに当たり,引用意匠3及び4を参考にすることが できる。
イ 原告は,1)本件審決の認定と異なり,本願意匠と引用意匠3及び4は同じ分 野に属さない,2)本願意匠に係る当業者には,防犯用隠しカメラの分野に関する意 匠を転用する習慣などなく,防犯用隠しカメラの形態が広く知られていたとはいえ ない,などとして,引用意匠3及び4を相違点Aの創作容易性の根拠とすることは, 誤りであると主張する。 しかし,1)本件審決は,本願意匠に係る当業者が,アクセサリーケースと隠しカ メラの双方について,通常の知識を有するものと判断しているのであって,本願意 匠と引用意匠3及び4が同一の分野に属すると判断しているのではないから,原告 の上記主張は前提を異にするものである。また,2)アクセサリーケースに隠しカメ ラを設置する場合,隠しカメラの分野においていかなる形態で撮像部が設置されて いるかを参考にすると考えられるから,本願意匠に係る物品の当業者にとって,公 然知られた隠しカメラの形態は,公知というべきである。 したがって,本件審決が,引用意匠3及び4を相違点Aの創作容易性の根拠とし たことに誤りはない。
(3) 相違点AないしCの創作容易性
ア 引用意匠3(別紙4。甲4)及び4(別紙5。甲5)の形状からすれば,こ れに接した当業者は,隠しカメラの撮像部を収納部とすることを示唆されている。 引用意匠1は,アクセサリーケースを開いて指輪を見せ,ひざまずいた状態でプ ロポーズを行うというアメリカの風習(甲13)に適するよう,撮像部を上蓋部に 設けたものである(甲2)。そこで,これと異なる形で,アクセサリーケースを使 用する場合にも適するよう,撮像部の位置を変更する動機付けが認められる。した がって,撮像部を収納部に設置した引用意匠3及び4を参考にしつつ,引用意匠1 の撮像部を上蓋部から収納部に変更することは,当業者が,容易に創作することが できたものである。 また,一つの要素をある箇所に設ける際に,その箇所の上下左右対称の中心部分 に配置する造形処理は,工業デザイン一般において通常行われていることであるか ら,撮像部を収納部の中央部分に配置することは,特段困難なことではない。そし て,カメラの撮像部の形態を円形とすることはごく普通にみられる広く知られた形 状であり,撮像部の直径を13%から15%に大きくすることは,多少の改変にす ぎない。 したがって,相違点Aに係る本願意匠の形態には着想の新しさ・独創性があると はいえず,引用意匠1に引用意匠3及び4を組み合わせることによって,当業者が 容易に創作することができたものである。
イ 相違点Bについて,引用意匠1の上蓋部の形態を,引用意匠2(甲3。別紙 3)の上蓋部のように,上蓋上面が平坦な略直方体状とすることに,着想の新し さ・独創性があるとはいえず,当業者が,容易に創作することができたものである。
ウ そして,相違点Cについて,スイッチ等の操作部を大きくするような変更は, 操作性の向上等のために行われる特段特徴のない変更である。そうすると,引用意 匠1のスイッチの形態を,特段特徴のない変更をして広く知られた形態である略円 柱状にすることに,着想の新しさ・独創性があるとはいえず,当業者が容易に創作 することができたものである。
2018.03.16
平成29(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年2月27日 知的財産高等裁判所
特許法131条の2第1項本文は,請求書の補正は,その要旨を変更し てはならない旨規定するのに対し,同条2項は,審判長は,請求書に係る請求の理 由の補正がその要旨を変更するものであっても,当該補正が審理を不当に遅延させ るおそれがないことが明らかなものであり,かつ,被請求人も同意したことその他 の同項各号のいずれかに該当する事由があるときは,決定をもって,当該補正を許 可することができる旨を規定し,同条4項は,同条2項の決定に対しては,不服を 申し立てることができない旨を規定する。\n上記各規定は,請求の理由の要旨を変更する補正については,審理対象を変動さ せるものであるから,審理の遅延を防止する観点から,これを許可することができ ないとする一方,要旨を変更する補正であったとしても,審理の遅延という観点か ら不当なものではなく,被請求人も同意するなど特段の事情が認められる場合には, 審判長の裁量的判断として当該補正を許可することができるものとし,このような 場合において,仮に不許可の決定がされたとしても,審判請求人はいつでも別途の 無効審判請求をすることが可能であるから,審判請求人は,当該不許可決定に対し\nては不服を申し立てることができないとしたものである。\nそうすると,審判請求人が,請求書の補正が要旨を変更するものではない旨争っている場合において,審判合議体において当該補正が要旨を変更するものであるこ とを前提として,これを許可することができないと判断するときは,審判合議体は, 同条1項に基づき,当該補正を許可しない旨の判断を示すのが相当である。それに もかかわらず,審判長が,同条1項に基づく不許可の判断を示さず,同条2項に基 づき,裁量的判断として補正の不許可決定をする場合には,審判請求人は,同条4 項の規定により,審判手続において,当該決定に対しては不服を申し立てることが\nできず,審決取消訴訟においても,上記決定が裁量権の範囲を逸脱又は濫用するも のでない限り,上記決定を争うことができなくなるものと解される。このような結 果は,審判請求人に対し,要旨の変更の可否を争う機会を実質的に失わせることに なり,手続保障の観点から是認することができない。
イ これを本件についてみると,証拠(甲26,甲27及び甲30)及び弁 論の全趣旨によれば,原告は,平成27年12月24日付け上申書及び平成28年\n2月25日付け審判事件弁駁書を提出したこと,原告は,これらの書面において, 請求の理由を補正して,結晶方位差が所定角以内の結晶子どうしの配置状況を制御 できなければ,同一結晶方位領域の平均円相当径を目標値に制御することは不可能\nであり,また,同一結晶方位領域を解析する際に,粉末充填密度をどのような値に 設定するのかが何ら記載されていないため,本件明細書における発明の詳細な説明 の記載は,実施可能要件を充足するものではないと主張したこと,原告は,審判手\n続においても,当該補正は,無効理由1における間接事実をいうものであり,要旨 を変更するものではないと主張したものの,審判長は,平成28年5月20日付け で,格別理由を付することなく,上記補正については許可しない旨の決定をしたこ と,審決は,上記主張について,平成28年5月20日付け補正許否の決定により, 無効理由に追加することは許可しないとの決定を行ったから,本件の審理範囲内の 主張ではないと判断したこと(審決50頁),原告は,本件訴訟においても,上記決 定の違法を主張するに当たり,上記補正が要旨を変更するものではないことを一貫 して主張していること,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,原告は,審判手続において,上記補正が要旨を変更する ものではない旨争っていたにもかかわらず,審判長は,当該補正が要旨を変更する ものであることを前提として,特許法131条の2第1項ではなく,同条2項に基 づき,格別理由を付することなく,上記補正を許可することができないと決定した ものと認められる。 そうすると,審決には,同条についての法令の解釈適用を誤った結果,要旨変更 の存否についての審理不尽の違法があるといわざるを得ない。原告の主張は,上記 の趣旨をいうものとして理由がある。
ウ もっとも,審決は,無効理由1’’の主張が請求書に記載されていたと仮 定した場合であっても,本件発明1の空気極材料及び本件発明2の固体酸化物型燃 料電池は,無効理由1と同旨の理由により,本件明細書及び図面の記載並びに本件 出願当時の技術常識に基づき,当業者が製造することができるといえるから,当該 主張は,合理性が認められず,採用することができないとしている。 そこで検討するに,無効理由1’’に係る主張は,結晶方位差が所定角以内の結晶 子どうしの配置状態の制御及び同一結晶方位領域の解析時の粉体充填密度の不明を いうものであって,前者については,本件発明に係る「同一結晶方位領域」の定義 に関する事項をいうものであり,既に審理の対象とされている事項につき補充主張 するものにすぎず,後者については,無効理由1において主張した6つの不明な製 造方法に係る制御因子のほかに,製造方法に密接に関連する解析条件に係る問題点 を補充的に指摘するものにすぎないから,要旨を変更するものではないと解するの が相当である。 そして,無効理由1’’に係る主張の内容を検討するに,前者については,本件発 明にいう「同一結晶方位領域」は,「結晶方位差が5度以上の境界によって規定され る領域」と一義的に定義されているのであるから,当該定義を前提とすれば,原告 の主張にかかわらず,EBSD法によって「同一結晶方位領域」を計測することが できることは明らかである。また,後者については,前記(1)のとおり,粉体充填密 度が同一結晶方位領域の大きさを左右することを立証し得る証拠及び技術常識を認 めることができない。 したがって,原告の主張は,いずれも実施可能要件に係る前記3の判断を左右す\nるものとはいえない。
エ 以上によれば,審決の判断は,結論において取り消すべき違法はなく, 原告の主張は,審決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものにす ぎず,採用することができない。
2018.03.15
平成27(ワ)8736 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年2月15日 大阪地方裁判所
以上より,乙43発明は,同公報において,本件発明の課題として,開閉操作 部がチャック部を跨ぐように配置されていることから,保持の仕方によっては容器を 保持する手は充填部の一部に重なって充填物の量を確認しにくいという課題がある ことを前提に,開閉操作部とチャック部の位置関係につき,チャック部を開閉操作部 の下側になるよう特定したものと理解できる。 そして確かに,本件発明の実施例は,すべて開閉操作部がチャック部を跨ぐように なっているものの,本件発明の特許請求の範囲において,チャックの位置関係は何ら 特定されているわけではない。そうすると,乙43発明に,本件発明において特定さ れていないチャック部と開閉操作部の位置関係を特定することで進歩性があるとし ても,結局,片手操作で栄養剤注入するという本件発明の改良形にすぎないことは明 らかであって,本件発明1を実施している以上に技術的に積極的な意味はなく,被告 製品の販売拡大に貢献している程度はさほど大きいものとは認められない。
e 乙44ないし乙46意匠
乙44意匠ないし乙46意匠は,被告製品そのものを対象として出願し登録された 意匠といえるが,乙45意匠,乙46意匠は乙44意匠の部分についての部分意匠と して登録されているにすぎないから,結局,本件で問題とすべきは,被告製品が乙4 4意匠を実施していることということになる。 しかし,その意匠は,乙41発明,乙42発明の実施例と同じものにすぎないし, 栄養供給バッグという商品の性質上,登録意匠のもたらす美観が需要を喚起すること は考えにくいから,登録意匠を実施していることをもって,本件特許権侵害を理由と する法102条2項の推定を覆滅する事由となるものとは認め難い。
f まとめ
以上を総合すると,被告製品は,確かに乙40発明ないし乙43発明及び乙44意 匠ないし乙46意匠を実施しているが,本件発明に技術的に付与するものは乙43発 明のみであり,その付与の程度がさほど大きくないことは上記のとおりである。 したがって,その事情が,法102条2項の推定覆滅事由となるにしても,5%を 減じるにとどまるというべきである。
ウ 被告製品の売上げについての被告の営業力,ブランド力の貢献
被告は,被告製品の売上げは被告の営業力,ブランド力よるものであり,技術面の 寄与度はせいぜい30%であると主張する。 確かに証拠(甲18,乙57)及び弁論の全趣旨によれば,連結売上高で原告は5 76億3600万円であるのに対し,被告は3596億9900万円であり,従業員 数でも原告はグループ総数で6777名にとどまるのに対し,被告のそれは2万74 15名であって,企業規模としては被告の方が圧倒的に大きく,したがって原告が全 国に支社,営業所を有していることを考慮しても,営業力,ブランド力とも被告の方 が強いことは否定できない。 しかし,証拠(乙47)によれば,本件で問題とすべき経腸栄養バッグ(空バッグ) の分野に限れば,当該市場は,●(省略)●のシェアを占め,その余を他社が占める というのであり,とりわけ「片手の指を挿入するためのシート状の1対の開閉操作部」 を有する経腸栄養バッグに限れば,市場には原告と被告の製品以外は存しないから, 市場を●(省略)●を占めるという関係にあり,当該分野に限れば,限られた需要者 の間において原告がブランド力を確立していることは容易に推認され,原告との間で, 営業力,ブランド力の差が生じているものとは認められない。 したがって,原告と被告の営業力,ブランド力の差をもって,法102条2項によ る推定が覆滅されるとする被告の主張は採用できない。
(5) 総括
以上を総合すると,法102条2項の規定により原告の損害として認定されるべき 額は,上記(3)で認定した被告製品の販売により受けた利益の額●(省略)●に,上 記(4)で認定した減額事由を考慮し,以下の計算式のとおり3718万0364円と 認定するのが相当である。
(計算式)
●(省略)●=37,180,364 円
また,上記損害額に本件に現れた一切の事情を斟酌すると,本件と因果関係のある 弁護士及び弁理士費用相当の損害額は380万円と認定するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2018.03.15
平成27(ワ)31774等 特許権侵害差止等請求事件 特許権 平成30年3月2日 東京地方裁判所(40部)
まず,原告代表者自身の陳述書(甲11)によれば,原告代表\者は普 通高校を卒業後,本件特許の出願当時まで螺旋状コイルインサートの販 売事業に従事した経験を有するのみであって,螺旋状コイルインサート の設計や製造に関わった経験はないものと認められ,螺旋状コイルイン サートに関して原告代表者を発明者とする特許出願や原告が執筆した論\n文等も存在しない(乙25の1及び2,乙26)。 また,原告代表者自身,本人尋問において,タングレス螺旋状コイル\nインサートの技術については「素人なので一切知らない」旨の供述をし ているとおり(原告代表者〔本人調書8頁〕。以下,同様に本人調書の\n該当頁を併記する。),原告代表者がタングレス螺旋状コイルインサー\nトに関して専門的な知識を有していたことはうかがわれない。 さらに,前記(2)イのとおり,原告は,平成11年当時,被告の製造す る製品の販売会社にすぎず,螺旋状コイルインサートの製造設備や実験 設備を有していたとは認められない。 したがって,そもそも,原告代表者に本件発明を着想し,これを具体\n化するだけの知識,経験及び環境が備わっていたといえるのか,疑問が ある。
イ 発明の動機について
原告は,原告代表者が被告の製造するタングレス螺旋状コイルインサ\nートについてどうしたら生産性を上げられるか考え悩んでいたことが本 件発明の動機であると主張する。 しかし,原告代表者の供述によれば,被告の製造するタングレス螺旋\n状コイルインサートの生産性が低いという認識を持ったのは,被告の営 業担当者と飲食を共にしたときに聞いたというのみであり,原告代表者\nは,上記営業担当者の氏名は供述せず,そのような話を聞いた際の具体 的な状況についても明らかにしない。 しかも,原告代表者は,生産効率の低さを聞いたのは本件特許の出願\n後だと思うとも供述し(原告代表者〔16,17頁〕),また,生産効\n率の低さを聞いていたとしながらも,これを改善する方策を検討するに 当たり,被告にどのような問題があって,実際にどのように生産してい たかという点を「調べてない」と供述している(原告代表者〔20\n頁〕)。 以上のとおり,本件発明の動機に関する原告代表者の供述は抽象的で\n不自然な点が多く,被告のタングレス螺旋状コイルインサートの生産性 の向上が本件発明の動機であったと認めることはできない。
・・・・
訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである 上,提訴者が,そのことを知りながら,又は通常人であれば容易にそのこと を知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度 の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるもの と解するのが相当である(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月 26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁,最高裁平成7年(オ)第16 0号同11年4月22日第一小法廷判決・裁判集民事193号85頁参照)。 本件においてこれをみるに,原告の本訴請求は理由がないところ,前記2 (5)に説示したとおり,原告代表者は福島工場において本件発明を知得した\n上,本件特許を出願したものといわざるを得ないのであって,原告による本 件特許の出願は冒認出願であったというべきである。 そして,本件特許の出願をD弁理士に依頼したのは原告代表者自身であり,\n被告の福島工場を訪れたのも原告代表者自身であって,本件特許の出願につ\nいては原告代表者が主体的に関わったものと認められることなどによれば,\n原告代表者が記憶違いや通常人にもあり得る思い違いをして本件特許出願に\n及んだということもできない。 加えて,原告が本訴提起前に被告から本件特許の出願が冒認出願であると の指摘を受けながらあえて本訴提起に及んだと認められることは,前記2 (2)シ(イ)及び(ウ)記載のとおりである。
そうすると,本訴請求において原告の主張した権利又は法律関係が事実的, 法律的根拠を欠くものであることはもちろん,原告が,そのことを知りなが ら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴え を提起したというべきであるから,本訴の提起は裁判制度の趣旨目的に照ら して著しく相当性を欠くものと認められるといわざるを得ない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告による本訴の 提起は被告に対する違法な行為というべきである。
(2) 被告の損害発生の有無及びその額
ア 本訴の防御のための弁護士・弁理士費用その他の費用
証拠(乙58〜68,101〜107,122〜125,134〜1 37,142〜143,152〜154(いずれも枝番を含む。))によれば,被告は,本訴事件に応訴するため,弁護士との間で訴訟代理の委任契約を締結するとともに,特許業務法人との間で補佐人の委任契約を締結し,相当額の報酬額を負担したほか,郵送料,謄写費用その他各種手続費用を負担したことが認められるところ,本訴の事案の内容,訴額,審理の経過及び期間,立証の難易度その他本件に現れた諸般の事情に照らすと,このうち原告の不法行為と相当因果関係のある費用は500万円と認めるのが相当である。 イ 反訴のための弁護士費用
反訴の事案の内容,経過,認容額その他本件に現れた諸般の事情に照らすと,反訴提起のための弁護士費用のうち50万円を原告に負担させるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2018.03.13
平成29(行ケ)10169 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年3月7日 知的財産高等裁判所(2部)
本件商標は,前記第2,1のとおり,「ゲンコツコロッケ」の片仮名を, 毛筆で書したかのような字体で,「ゲ」「コ」「ケ」をやや大きく,その余の文字をや や小さく一連に書してなり,「ゲンコツコロッケ」の称呼を生じるものである。そし て,本件商標のうち「ゲンコツ」は,「にぎりこぶし。げんこ。」を意味する(甲6)。 証拠(甲54〜58,60,61,63,乙3)及び弁論の全趣旨によると,本件 登録審決日当時,「ゲンコツ」は,食品分野において,ゴツゴツした形状や大きさが にぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあったものと認 められる。「コロッケ」は,「揚げ物料理の一つ。あらかじめ調理した挽肉・魚介・ 野菜などを,ゆでてつぶしたジャガイモやベシャメル・ソースと混ぜ合わせて小判\n形などにまとめ,パン粉の衣をつけて油で揚げたもの。」を意味する(甲5)。 本件商標は,「ゲンコツ」と「コロッケ」の結合商標と認められるところ,その全 体は8字8音とやや冗長であること,上記のとおり「コ」の字がやや大きいこと, 「ゲンコツ」も「コロッケ」も上記の意味において一般に広く知られていることか らすると,本件商標は,「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することが取引 上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。 また,本件商標の指定商品のうち本件訴訟において争われている指定商品は,い ずれも,「コロッケ入り」の食品であるから,本件商標の構成のうち「コロッケ」の\n部分は,指定商品の原材料を意味するものと捉えられ,識別力がかなり低いもので ある。これに対し,上記のとおり,「ゲンコツ」は,食品分野において,ゴツゴツし た形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられること があることから,「ゲンコツコロッケ」は,「ゴツゴツした,にぎりこぶし大のコロ ッケ」との観念も生じ得るが,常にそのような観念が生ずるとまではいえず,また, 本件商標の指定商品の原材料である「コロッケ」は,ゴツゴツしたものやにぎりこ ぶし大のものに限定されていないのであるから,「ゲンコツ」は,「コロッケ」より も識別力が高く,需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。 さらに,証拠(甲51,66〜72)及び弁論の全趣旨によると,被告が,本件 商標を使用して,「ゲンコツコロッケ」の販売を開始したのは,平成26年6月3日 であり,販売開始は新聞の電子版で報道され,「ゲンコツコロッケ」は,人気商品と なって,販売開始から短期間で多数個が販売されたことが認められる。しかし,本 件登録審決日は上記の販売開始から約3か月間経過後であること,コロッケのよう な食品の需要者はきわめて多数にのぼると考えられることからすると,上記のよう な被告による販売の事実があるとしても,「ゲンコツコロッケ」が不可分一体と認識 されると認めることはできない。 以上より,本件商標の要部は「ゲンコツ」の部分であると解すべきである。
イ 本件商標の要部「ゲンコツ」と引用商標とは,外観において類似し,称 呼を共通にし,観念を共通にする。したがって,両者は,類似しているものと認め られる。
(2) 被告の主張について
ア 被告は,1)本件商標は外観上全体として統一感ある印象を与え,2)称呼 も短く,一連に称呼できるから,全体で一体不可分の語として認識,理解されるべ きである,と主張する。 しかし,本件商標が全体として不可分なものであって,「ゲンコツ」と「コロッケ」 を分離して観察することができないといえないことは,前記(1)のとおりである。
イ 被告は,1)本件商標の指定商品は「コロッケ」ではなく,2)「コロッケ」 が商品の原材料を表すものと認識される場合であっても,需要者は「にぎりこぶし\nのような大きさや形状のコロッケ」が入った「パン,サンドイッチ,ハンバーガー, 弁当」等であると認識するから,「ゲンコツコロッケ」を一体的に理解する,と主張 する。 しかし,本件商標の構成のうち「ゲンコツ」の部分が,需要者に対して強く支配\n的な印象を与えることは,前記(1)のとおりであり,需要者が,「ゲンコツコロッケ」 を一体的に理解するとは認められない。
ウ 被告は,本件商標は周知であるから,「ゲンコツコロッケ」は常に一体不 可分のものとして認識される,と主張する。 しかし,この主張を採用することができないことは,前記(1)のとおりである。 2 指定商品の類否について
本件商標の指定商品のうち,第30類「コロッケ入りパン,コロッケ入りサンド イッチ,コロッケ入りハンバーガー,コロッケ入り弁当,コロッケ入りの調理済み 丼物,コロッケ入りの調理済みのカレーライス,コロッケ入りのチャーハン」は, 引用商標の指定商品である第30類「おにぎり,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅう まい,すし,たこ焼き,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパ イ,ラビオリ」に同一又は類似することについて,当事者間に争いはない。
3 以上より,本件商標は,指定商品「コロッケ入りパン,コロッケ入りサンド イッチ,コロッケ入りハンバーガー,コロッケ入り弁当,コロッケ入りの調理済み 丼物,コロッケ入りの調理済みのカレーライス,コロッケ入りのチャーハン」につ き,商標法4条1項11号に該当するから,原告の取消事由の主張には,理由があ る。
◆判決本文
類似事件はこちら。
◆平成28(行ケ)10164
この事件では、商標「ゲンコツメンチ」は商標「ゲンコツ」(5100230号)と非類似と判断されています。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.03. 5
平成29(ワ)5074 特許権に基づく差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年1月30日 東京地方裁判所
本件発明に係る特許請求の範囲の記載に加え, 上記(1)の本件明細書の各記載, 特に【課題を解決するための手段】として「該円筒回転体の周面部位には前記 円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面を配設し,」,「前記円 筒回転体に吸い上げられた牌の方向を揃えるため前記吸着面の外側の軌道に 沿って配設した案内部材」「を設け,前記円筒回転体によって下方位置にて取 り上げられた牌は,前記案内部材にそって牌の向きを揃えながら上方に移動す る」(段落【0008】)との記載を勘案すると,本件発明の構成要件I及びK\nは,それぞれ円筒回転体の周面部位に配設された「円筒回転体の一側端から牌 の横幅ほどの幅をもつ吸着面」上で,吸着面からはみ出た牌の部分に「前記吸 着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」を当接させることによって,牌 の向きを揃えるという技術的意義を有するものと認められる(なお,本件明細 書の「図10及び図11を参照して、吸着面401Bに様々な角度にて吸着し た牌10が、整列機構500により縦長方向に整列する動作について説明する。\n案内部材501の入り口付近で吸着面401Bからはみ出た側面が、案内部材 先端502に接触して抵抗を受けるが、牌10に埋設されている磁石11の中 心が、円筒回転体401に埋設されている磁石401Cの中心に吸引されて回 転しながら向きを変え、当該側面が案内部材501の内壁面501Aと並行状 態になって整列機構500の内部に進入する。」との実施例の記載(段落【00\n33】)も上記認定を裏付けるものといえる。)。 そうすると,本件発明の構成要件Iの「円筒回転体の一側端から牌の横幅ほ\nどの幅をもつ吸着面」は,吸着面の幅が,牌の横幅(短辺)と同一か,牌の吸 着面からはみ出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃え ることができる程度に狭くなっていることを意味し,少なくとも牌の縦幅に近 似した幅を有する吸着面はこれに含まれないと解するのが相当である。また, 構成要件Kの「前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」は,吸着\n面の幅が上記のようなものであることを前提として,吸着面からはみ出した牌 の部分に当接して牌の向きを揃えることができる位置に案内部材を配設する ことを意味し,少なくとも吸着面の外側の軌道に近似する線よりも内側に配設 された案内部材はこれに含まれないと解するのが相当である。 そこで,まず,構成要件Iの充足性について検討するに,各被告製品の吸着\n面の幅(円筒回転体の一側端からの幅)が32.6mmであるのに対し,牌の横 幅は24.0mm,牌の縦幅は32.9mmであって(乙4及び当事者間に争い がない事実),各被告製品の吸着面の幅はむしろ牌の縦幅に近似するものと認 められるから,構成要件Iの「円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をも\nつ吸着面」を充足しない。 これに対し,原告は,1)吸着面の幅は牌の横幅より9mmほど長めであるに すぎない,2)本件明細書の段落【0009】の記載からすると,円筒回転体の 幅が牌の縦幅と略等しい場合にも構成要件Iを充足することが強く示唆され ているなどと主張する。 しかしながら,まず,上記1)について,各被告製品は,吸着面の幅が牌の横 幅より9mmも長い一方で牌の縦幅よりわずかに0.3mm短いにすぎないの であるから,円筒回転体の周面部位に配設された「円筒回転体の一側端から牌 の横幅ほどの幅をもつ吸着面」上で,吸着面からはみ出た牌の部分に「前記吸 着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材」を当接させることによって,牌 の向きを揃えるという本件発明の技術的意義(上記(2))を発揮させることができ ない。また,上記2)について,被告が指摘する本件明細書の段落【0009】 の記載は,「円筒回転体の幅は牌の縦幅と略等しい寸法でよく」としているに すぎず,吸着面の幅が牌の縦幅とほぼ等しい場合に構成要件Iを充足すること\nの根拠となるものとは認め難い(なお,本件明細書の段落【0021】及び図 7には,円筒回転体の幅が牌の縦幅と略等しい長さ(lL )であるのに対し, 吸着面の幅が牌の横幅分の長さ(ls )である実施例が開示されている。)。し たがって,原告の主張はいずれも採用の限りでない。 次に,構成要件Kの充足性について検討するに,乙2の写真3及び4並びに\n弁論の全趣旨によれば,各被告製品の案内部材は吸着面の外側の軌道から約5. 6mmも内側に配設されていると認められるから,前記(2)に説示したところに よれば,各被告製品は,構成要件Kの「前記吸着面の外側の軌道に沿って配設\nした案内部材」も充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2018.03. 3
平成29(行ケ)10168 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年2月20日 知的財産高等裁判所
本件商標と引用商標1及び2とでは,外観を異にするものと認められるものの, 称呼としては,本件商標が少なくとも「ミソヤ」との称呼を生じるのに対し,引用\n商標1及び2も「ミソヤ」との称呼を生じるものであると認められる。また,観念\nについても,本件商標からは,全体として「味噌を売る店」との観念を生じるとと もに,本件指定役務との関係においては,味噌味の飲食物を提供する店との観念も 生じ得るものといえるのに対し,引用商標1からは,「味噌を売る店」の観念を生 じるとともに,引用商標1の指定役務との関係においては,味噌味の中華料理を主 とする飲食物を提供する店との観念も生じ得るものといえる。さらに,引用商標2 からも,「味噌を売る店」の観念を生じるとともに,引用商標2の指定役務との関 係においては,味噌味のラーメンを提供する店との観念も生じ得るものといえる。 したがって,本件商標と引用商標1及び2とは,称呼と観念とは共通するものと いうことができる。
オ 取引の実情について
引用商標の指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」及び「ラーメンの提 供」は,前記のとおり,本件指定役務「飲食物の提供」に含まれるものであるとこ ろ,本件指定役務及び引用商標の指定役務は,いずれも基本的には,さほど高価と はいえないものを含む日常的に消費される性質の商品(飲食物)の提供であり,そ の需要者は,高度の注意力をもって役務の提供を受けるとは限らないから,本件指 定役務については,引用商標と同一営業主の提供に係る役務と誤認され,役務の出 所について誤認混同を生じるおそれが否定し難いといえる。また,本件指定役務は 引用商標の指定役務を包含する役務であり,その取引者,需要者には,広く一般の 消費者が含まれるから,役務の同一性を識別するに際して,その名称,称呼の果た す役割は大きく,重要な要素となるというべきである。なお,一般の消費者として は,商標の外観を見て役務の出所を判断することも少なくないと考えられるもの の,我が国において,外来語以外でも同一語の漢字表記と平仮名(又は片仮名)表\ 記又はローマ字表記が併用されることが多く見られる事情があることなどを考慮す\nると,本件指定役務及び引用商標の指定役務の需要者にとって,図形等がほとんど 使用されず,文字のみが主体となる商標において,文字種が異なることは,本件商 標と引用商標が別異のものであることを認識させるほどの強い印象を与えるもので はないといえる(しかも,本件商標が,平仮名,漢字又はローマ字を書してなるも のであるのに対し,引用商標は,漢字を書してなるもの(引用商標2では平仮名を 含む。)であって,「味噌屋」の文字部分については,本件商標と引用商標に共通す るものといえる。)。 そうすると,本件商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,上記のような 取引の実情をも考慮すると,外観をさほど重視することはできず,外観及び観念に 比して,称呼を重視すべきであるといえる。
カ まとめ
以上によれば,本件商標と引用商標は,称呼において同一であり,両商標からは 同一又は類似の観念を生じるものといえるから,本件指定役務の需要者にとって, 引用商標と同一の称呼を生じる本件商標を付した役務を,引用商標を付した役務と 誤認混同するおそれがあるものと認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2018.03. 1
平成29(行ケ)10063 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年2月20日 知的財産高等裁判所
本件明細書の記載(【0003】,【0004】,【001 8】)のほか,証拠(甲9,14,76,77,乙3,8,15)及び 弁論の全趣旨によれば,リフロープロセスにおいては,プリヒート時の 熱によりはんだ粉末の表面に酸化物が生成されると,その酸化物に覆わ\nれたはんだ粉末は,ぬれ性が悪く,溶融した部分と一体化せず,また, はんだ粉末を構成する金属の酸化物は融点が1000℃に近く,はんだ\n粉末の融点付近の温度では溶融しないため,未溶融物を生じ,はんだ付 け不良を起こすことは,本件特許出願当時の技術常識であったことが認 められる。 この技術常識によれば,本件発明1,甲1発明いずれにおいても,は んだ付け性が低下する原因は加熱に伴うはんだの再酸化にあるというこ とができるところ,甲1文献記載のはんだ広がり試験は,プリヒートを 行うものではなく,また,共晶はんだも対象とされているためそれほど 高い温度に加熱する必要はない点において,本件明細書におけるはんだ 付け性試験とは異なるとしても,両試験は,はんだの再酸化が防止され ているかどうかを確認したものである点で共通するものということがで きる。
(イ) 前記のとおり,甲1文献には分子内に第3ブチル基のついたフェノ ール骨格を含む酸化防止剤がはんだ粉末の再酸化を防止することが記 載されているところ,本件発明1におけるヒンダードフェノール系化 合物からなる酸化防止剤は,分子内に第3ブチル基のついたフェノー ル骨格を含む酸化防止剤に該当するものである。このため,分子内に 第3ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤を含みさえす れば,はんだ粉末の再酸化が防止され,はんだ付け性が向上すること は,甲1文献及び技術常識から,当業者が予測し得たことといってよ\nい。
(ウ) また,本件発明1においては,酸化防止剤の分子量が少なくとも5 00であるとの限定を有するが,以下のとおり,このような限定を付 すことによって格別の効果が得られたことを裏付けるに足りる証拠は ないから,本件発明1の効果は,甲1文献及び本件特許出願当時の技 術常識から当業者にとって予測し得ない格別顕著なものであるとは認\nめられない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2018.03. 1
平成29(ネ)10089 虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求,特許権侵害差止等反訴請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年2月22日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,縷々理由を述べて,控訴人による本件ニフティ宛文書の送付は, 社会通念上必要と認められる範囲のものであり,正当な権利行使の一環とし て違法性が阻却されるべき行為であるとか,これについて控訴人に過失はな いなどと主張する。 しかしながら,控訴人が本件ニフティ宛文書の送付に当たり無効理由の有 無について何ら調査検討を行っていないことは,控訴人自身が認めていると ころ,本件特許権1等の出願の経緯や,NTTコムのプロジェクト(本件サ ービスの開発に係る本件プロジェクト)に控訴人自身が参画していた経緯に 照らせば,本件発明1については,本件サービスや甲11発明等の関係で拡 大先願(特許法29条の2)や公然実施(特許法29条1項2号)などの無 効理由が主張され得ることは容易に予測できることであって,たまたま被控\n訴人との間の事前交渉において,かかる無効主張がなされなかったとしても, そのことだけで直ちにかかる無効理由についての調査検討を全く行わなくて もよいということにはならないというべきである。 また,証拠(甲12の1,15の1,16の1,18等)及び弁論の全趣 旨によれば,控訴人は,本件ニフティ宛文書の送付に先立つ平成22年11 月頃から平成23年5月頃にかけて,数か月にわたり,被控訴人との間で, 弁護士・弁理士等の専門家を交えて,被控訴人製品の使用等が本件特許1等 に抵触するものであるか否かについて交渉を行っており,その後,抵触を否 定する被控訴人との間で交渉が暗礁に乗り上げていたにもかかわらず,被控 訴人に対して再度交渉を求めたり,あるいは,訴訟提起を行ったりすること なく,平成26年3月頃から,被控訴人の顧客等に対して控訴人とのライセ ンスを持ちかける文書を送付するようになり,被控訴人から同文書の送付を 直ちに中止するよう求められても,これを中止するどころか,ニフティに対 し,明示的な侵害警告文書である本件ニフティ宛文書を送付するに至ったも のと認められる。 上記のような事情に照らせば,本件ニフティ宛文書の送付は,特許権侵害 の有無について十分な法的検討を行った上でしたものとは認められず,その\n経過も,要するに,被控訴人との交渉では埒が明かないことから,その取引 先に対し警告文書を送ることによって,事態の打開を図ろうとした(すなわ ち,侵害の成否について公権的な判断を経ることなく,いわば既成事実化す ることによって,競争上優位に立とうとした)ものであるといえる(なお, 控訴人は,本件書状3を送った時点では,ニフティが被控訴人の取引先であ るとは知らなかったとも主張するが,事実経過に照らして直ちに信用するこ とはできないし,少なくとも,本件書状4及び本件メールを送った時点では, 既にこれを明確に認識していた〔甲16〕のであるから,かかる事由をもっ て,違法性がないとか,過失がないということもできない。)。 このような控訴人の行為が,社会通念上必要と認められる範囲のものであ り,正当な権利行使の一環として違法性が阻却されるべき行為であるといえ ないことは明らかであり,また,これについて控訴人に過失が認められるこ とも明らかである。 したがって,本件ニフティ宛文書の送付は違法であり,かつ,控訴人には 少なくとも過失が認められるというべきであるから,これに反する控訴人の 主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2018.03. 1
平成29(行ケ)10121 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年2月14日 知的財産高等裁判所(2部)
引用文献の【0027】には,はんだ合金に,Biを添加することで,さらに温 度サイクル特性を向上させることができ,添加するBiの量は,1.5〜5.5質 量%が好ましいことが記載されている。したがって,引用発明1〜3のビスマスの 量を,上記好ましい量の範囲内である,4.8質量%を超過し,5.5質量%まで の範囲とする動機付けがあるといえる。 そして,本件発明2〜8においてビスマスの含有割合が所定の範囲内であること の効果は,「優れた耐衝撃性を得ることができ,また,比較的厳しい温度サイクル条 件下に曝露した場合においても,優れた耐衝撃性を維持することができる」(本件明 細書【0031】)ことにある。引用発明1〜3においてビスマスの含有割合を上記 好ましい範囲内とすることの効果は,温度サイクル特性を向上させること(引用文 献【0027】)であるが,ここにいう温度サイクル特性とは,「−40℃から+1 25℃の温度サイクル試験を3000サイクル近く繰り返しても,微量なはんだ量 のはんだ接合部にもクラックが発生せず,また,クラックが発生した場合において も,クラックがはんだ中を伝播することを抑制」する(引用文献【0021】)とい う性質である。温度サイクル試験後のはんだ接合部にクラックが発生せず,クラッ クが発生してもその伝播を抑制する効果が高まれば,厳しい温度サイクル条件下の 耐衝撃性も高まるものといえる。そして,厳しい温度サイクル条件下の耐衝撃性が 高ければ,そのような厳しい条件下にない場合の耐衝撃性も高いことが予想される。\nしたがって,本件発明2〜8におけるビスマスの含有割合を所定の範囲内とするこ との上記効果は,引用発明1〜3のビスマスの量を4.8質量%を超過し,5.5 質量%までの範囲とする上記効果と比較して,格別顕著な効果であるとはいえない。 以上より,引用発明1〜3において,Bi:3.2質量%の数値を,相違点2に 係る,「4.8質量%を超過し,5.5質量%まで」の範囲の本件発明2〜8の構成\nとすることは,当業者が容易になし得たものである。 イ 相違点4について 引用文献の【0028】には,はんだ合金に,Coを添加することで,Niの効 果を高めることができ,添加する量は,0.001〜0.1質量%が好ましいこと が記載されている。したがって,引用発明4〜6にコバルトを添加し,その量を0. 001質量%〜0.1質量%とする動機付けがあるといえる。 本件発明2〜8においてコバルトの含有割合が所定の範囲内であることの効果は, 「優れた耐衝撃性を得ることができ,また,比較的厳しい温度サイクル条件下に曝 露した場合においても,優れた耐衝撃性を維持することができる」(本件明細書【0 037】)ことにある。そして,引用発明4〜6においてコバルトの含有割合を上記 好ましい範囲内とすることの効果は,Niの効果を高めること,すなわち,はんだ 付け界面付近に発生する金属間化合物層の金属管化合物を微細化して,クラックの 発生を抑制するとともに,一旦発生したクラックの伝播を抑制する働きをする(引 用文献【0024】,【0028】)という効果を高めることである。クラックの発生 を抑制し,一旦発生したクラックの伝播を抑制すれば,耐衝撃性がより優れ,これ が維持されるといえる。したがって,本件発明2〜8におけるコバルトの含有割合 が所定の範囲内であることの効果は,引用発明4〜6においてコバルトを添加し, その含有割合を0.001質量%〜0.1質量%とすることの効果と比較して,格 別顕著なものであるとはいえない。 以上より,引用発明4〜6にコバルトを添加し,その量を0.001質量%〜0. 1質量%として,相違点4に係る,「コバルトの含有割合が,0.001質量%以上 0.1質量%以下(本件発明6については0.003質量%以上0.01質量%以 下)」の本件発明2〜8の構成とすることは,当業者が容易になし得たものである。\n ウ 被告の主張について 被告は,本件発明2〜8と,引用発明1〜6との間には,ビスマスの含有量又は コバルトの含有量について明確な相違点があり,これを容易想到とする理由はない, と主張する。 しかし,前記ア及びイのとおり,引用発明1〜3において相違点2に係る構成を\n採用すること,及び引用発明4〜6において相違点4に係る構成を採用することの\n動機付けがあり,本件発明2〜8のビスマスの含有量及びコバルトの含有量につい て格別顕著な効果があるともいえないから,引用発明1〜6に相違点2及び4の構\n成を採用することは,容易想到である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 数値限定
>> ピックアップ対象
2018.03. 1
平成29(ワ)39594 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年2月28日 東京地方裁判所
被告は,本件登録防護標章と同一の標章が付され,本件防護標章登録の指定商品に該当するステッカーである被告各商品をネット通販サイトから入手した上で,平成29年6月19日,「ヤフオク!」に,被告各商品合計4枚が一枚の台紙に付されたものを1800円で出品し,同月21日,これを落札した原告従業員に対して売り渡したとの事実が認められる。被告の上記行為は,商標法67条1号及び2号に該当し,本件商標権を侵害する。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2018.02.17
平成28(行ケ)10218 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年1月30日 知的財産高等裁判所
本願明細書の上記記載によれば,同配列アンタゴニスト化合物は, アゴニスト作用を示していたIMOについて,「GACG」部分に化学修飾を導入し て同部分をN2N1CGモチーフにすることにより,アンタゴニスト作用を示すに至 ったことが認められる(以下,当該作用変化を「本件反転作用」という。)。 このような記載に接した当業者は,本件反転作用を生じさせた原因となる部分は, その他の配列が同一である以上,化学修飾を導入したN2N1CGモチーフに存在す るものと理解するのが自然である。のみならず,本願明細書の前記a(c)の記載に接 した当業者は,細菌性及び合成DNAの塩基配列には様々なものがあるにもかかわ らず,TLR9がそれらに存在する非メチル化CpGモチーフを認識するのである から,IMOの「GACG」部分にある非メチル化CpGモチーフがTLR9に結 合するものと理解するといえる。そのため,本件反転作用の原因は,TLR9に結 合する「GACG」部分に化学修飾を導入し,これをN2N1CGモチーフとするこ とによって,上記の結合部分に何らかの変化が生じたことによるものと理解するの が自然である。 そうすると,12種類化合物の配列は,N2N1CGモチーフの5’末端側に隣接 するオリゴヌクレオチド部分配列(以下「5’末端側隣接配列」という。)が全て「C TATCT」という一つの配列のみであり,かつ,N2N1CGモチーフの3’末端 側に隣接するオリゴヌクレオチド部分配列(以下「3’末端側隣接配列」という。) が「TTCTCTGT」又は「TTCTCUGU」という類似する二つの配列のみ であるものの,当業者は,本件反転作用を生じさせた部分は,N2N1CGモチーフ 自体であって,5’末端側隣接配列又は3’末端側隣接配列ではないと理解するの であるから,N2N1CGモチーフを有する本願IRO化合物も,12種類化合物と 同様に,アンタゴニスト作用を奏する蓋然性が高いものと論理的に理解するのが自 然である。そして,当業者は,TLR9のアンタゴニストとして作用し得る本願I RO化合物が,少なくともTLR9のアゴニスト作用が原因となる癌,自己免疫疾 患,気道炎症,炎症性疾患,感染症,皮膚疾患,アレルギー,ぜんそく又は病原体 により引き起こされる疾患を有する脊椎動物を治療的に処置し得ることを十分に理\n解することができるといえる。 したがって,本願明細書に接した当業者は,本願IRO化合物が高い蓋然性をも ってTLR9のアンタゴニスト作用を奏し,かつ,TLR9のアンタゴニストとし て作用し得る本願IRO化合物がTLR9のアゴニスト作用を原因とする上記各疾 患を治療的に処置し得ることを理解することができるのであるから,本願明細書中 の発明の詳細な説明の記載は,当業者によって本願出願当時に通常有する技術常識 に基づき本願発明の実施をすることができる程度の記載であると認めるのが相当で ある。
以上によれば,本願明細書の記載により,本願IRO化合物が全て,TLR9の アンタゴニスト作用を有するものであることを当業者が認識できるとはいえないな どとして,本願発明が実施可能要件に適合するものではないとした審決の判断には\n誤りがあり,TLR9についての原告の取消事由3は,理由がある。
c これに対し,被告は,実施例11に示されている同配列アンタゴニス ト化合物につき,5’末端側隣接配列が「CTATCT」であり,かつ,「N1N2N 3−Nm」が「TTCTCTGT」である化合物が示されるのみであって,それ以外 の本願IRO化合物は示されていないことからすると,アンタゴニスト作用が「C pGジヌクレオチド」に結合した結果であるのか,あるいは,それ以外の共通する 部分に結合した結果であるのかは定かでなく,また,本願明細書の発明の詳細な説 明には,本願IRO化合物のうち,実施例11に示された化合物以外のものが,実 施例11に示された化合物と同様にアンタゴニスト作用を有することを示唆する記 載もなく,この点が技術常識であるともいえないなどと主張する。 しかしながら,同配列アンタゴニスト化合物は,上記bにおいて説示するとおり, アゴニスト作用を示していたIMOについて,「GACG」部分についてのみ化学修 飾を導入して同部分をN2N1CGモチーフにすることにより,本件反転作用を奏す るに至ったのであるから,このような記載に接した当業者は,本件反転作用を生じ させた部分は,化学修飾を導入したN2N1CGモチーフに存在するものと論理的に 理解するのが自然であるといえる。そうすると,当業者は,実施例11に示された 化合物以外のものであっても,少なくともTLR9については,N2N1CGモチー フが存在すれば,高い蓋然性をもってアンタゴニスト作用を示すものと理解すると 認めるのが相当である。 したがって,被告の主張は,その他の主張を含め,本件反転作用の技術的意義を 正解しないものに帰し,採用することができない。
このような適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は,複数の発明が同時に 出願されている場合の拒絶査定不服審判において,従前の拒絶査定の理由が解消さ れている一方,複数の発明に対する上記拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由につい て,一方の発明に対してはこれを通知したものの,他方の発明に対しては実質的に これを通知しなかったため,審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発 明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず,特許要件を充\n足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れ る機会を失ったといえるときにも,当然妥当するものであって,このようなときに は,当該審決に,特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手続違背の 違法があるというべきである。 イ これを本件についてみると,前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全 趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
・・・
(ウ) 原告は,本件拒絶査定不服審判において,平成27年9月16日付け の拒絶理由通知(甲16)を受けた(以下,当該拒絶理由通知を「本件拒絶理由通 知」といい,本件拒絶理由通知に係る拒絶理由を「本件拒絶理由」という。)。請求 項1,請求項8及び請求項13に対する本件拒絶理由は,大要次のとおりである。 a 請求項1,3,4及び7ないし17(請求項3を追加する前のもの) 証拠(甲16)及び弁論の全趣旨によれば,本件拒絶理由通知では,実施例にお いてアンタゴニスト作用を有することが証明された化合物のうち,本願IRO化合 物に含まれるものは,IRO5,10,17,25,26,33,34,37,3 9,41,43及び98であるとして,これらの12種類化合物に限定して検討を 加えていること,12種類化合物は,いずれもTLR9に対してアンタゴニスト作 用を有するものであるが,IRO5に限り,TLR9のほか,TLR7及び8に対 してもアンタゴニスト作用を有するものであること,本件拒絶理由通知では,12 種類化合物を全体として比較して,N2N1CGモチーフの5’末端側に隣接する部分 の塩基配列及びN2N1CGモチーフの3’末端側に隣接する部分の塩基配列が,それ ぞれ類似の二通りのみであることを根拠として,請求項1,3,4及び7ないし1 7に係る各発明の実施可能要件及びサポート要件違反を示していること,そのため,\n本件拒絶理由通知では,IRO5に固有の問題を検討するものではなく,TLR9 に対するアンタゴニスト作用を有する12種類化合物のみの問題を検討しているこ と,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,本件拒絶理由通知は,TLR9に対してアンタゴニスト 作用を有する12種類化合物のみの問題を検討するにとどまり,TLR7及び8に 対してもアンタゴニスト作用を有するIRO5に固有の問題を検討した上で拒絶理 由を通知するものではないから,実質的にはTLR7及び8に対する拒絶理由を示 すものではないと認めるのが相当である。
b 請求項8,13,16及び17(請求項3を追加する前のもの) 証拠(甲16)及び弁論の全趣旨によれば,本件拒絶理由通知は,請求項8に係 る発明につき,「本願明細書ではTLRとして「TLR7」,「TLR8」及び「TL R9」に対する各種IROのアンタゴニスト作用を確認しただけであって,他のT LRに対してもアンタゴニスト作用を有することは確認されていない。」,「請求項 8の「TLR媒介免疫反応」のうち,「TLR7」,「TLR8」又は「TLR9」の 媒介免疫反応以外の免疫反応については,本願発明のIRO化合物が阻害効果を示 すことが確認できない。」と記載し,また,請求項13に係る発明につき,「請求項 13の「TLRにより媒介される疾患」のうち,「TLR7」,「TLR8」又は「T LR9」によって媒介される疾患以外の疾患については,本願発明のIRO化合物 が治療効果を示すことが確認できない。」と,それぞれ記載していることが認められ る。 上記認定事実によれば,本件拒絶理由通知は,文言上,少なくとも,TLR7な いし9については,アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認され たことをいうものと理解するのが自然である。
・・・
(オ) その後,特許庁は,原告に対し,改めて拒絶理由を通知することなく, 平成28年5月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。 ウ 前記イ(ウ)aによれば,本件拒絶理由通知は,TLR9に対してアンタゴ ニスト作用を有する12種類化合物のみの問題を検討するにとどまり,TLR7及 び8に対してアンタゴニスト作用を有するIRO5に固有の問題を検討した上で拒 絶理由を通知するものではないから,実質的にはTLR7及び8に対する拒絶理由 を示すものではないことが認められる。のみならず,TLR7及び8については, 本件反転作用を裏付ける実施例はない上,そもそも認識するアゴニストの対象が, TLR9とは異なり,一本鎖RNAウイルスであると認められるのであるから,T LR7及び8の拒絶理由には,TLR9の拒絶理由とは異なる固有の理由が存在す ることは明らかであるにもかかわらず,本件拒絶理由通知は,これを通知していな いことが認められる。
そして,前記イ(エ)によれば,原告は,本件拒絶理由を受けて,その理由を解消す るために,TLR1ないし6に係る発明部分を削除しているのであり,このような 経緯に鑑みると,原告は,TLR7及び8についても拒絶理由を実質的に通知され ていた場合には,TLR7及び8に係る発明部分についても,TLR1ないし6に 係る発明部分と併せて補正によって削除した可能性が高いものと認められる。\nのみならず,前記イ(ウ)bによれば,請求項8,13,16及び17に係る各発明 に対する本件拒絶理由通知は,文言上,少なくとも,TLR7ないし9については, アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認されたことをいうものと 理解するのが自然であるから,このような記載に接した原告が,少なくともTLR 7ないし9については,アンタゴニスト作用を有することが確認されたため,実施 可能要件及びサポート要件違反はないものと理解したのもやむを得ないところであ\nる。現に,原告は,前記イ(エ)によれば,本件拒絶理由通知を踏まえ,請求項9及び 14においては,TLR1ないし6を削除して,TLR7ないし9に限定する補正 をしている事実が認められるのであるから,このような事実からも,上記の原告の 理解が十分に裏付けられるといえる。そうすると,TLR7ないし9についてもア\nンタゴニスト作用を有するものであるとすることはできないとして,本願発明が実 施可能要件及びサポート要件に適合しないとした審決の判断は,実質的にみれば,\n上記の経過に照らし,原告にとっては,不意打ちというほかなく,不当であるとい うほかない。
これらの事情の下においては,本件拒絶査定不服審判において,従前の拒絶査定 の理由とは異なる拒絶理由について,TLR9に係る発明に対してはこれを通知し たものの,TLR7及び8に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しなかった ため,原告が補正により特許要件を欠くTLR7及び8に係る各発明を削除する可 能性が認められたのにこれを削除することができず,特許要件を充足するTLR9\nに係る発明についてまで本件拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会 を失ったものと認められる。 したがって,審決には,特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手 続違背の違法があるというべきであり,当該手続違背の違法は,審決の結論に影響 を及ぼすというべきであるから,取消事由1は,理由があるものと認められる。
エ これに対し,被告は,前記イ(ウ)aのとおり,サポート要件違反と実施可能\n要件違反をいう請求項1に係る本件拒絶理由は,旧請求項3及び4,7なしい17 についても存在する旨通知されているのであるから,審決が本件拒絶理由とは異な る新たな拒絶理由に基づき実施可能要件及びサポート要件に適合しないと判断した\nとする原告の主張は,前提を欠くものであるなどと主張する。 しかしながら,上記ウで説示したとおり,本件拒絶査定不服審判において,本件 拒絶理由通知では,TLR9に関する拒絶理由のみを通知し,実質的にはTLR7 及び8に関する拒絶理由を通知しなかったため,原告はTLR7及び8に係る各発 明を削除するなどの補正をする機会を失うことになり,実施可能要件及びサポート\n要件をいずれも充足するTLR9に係る発明まで最終的に特許を受けることができ ないことになったものと認められる。このような結果は,原告にとって,不意打ち となるため,原告に過酷というほかなく,審判請求人の手続保障を規定する特許法 159条2項の趣旨に照らし,相当ではないというべきである。 かえって,被告は,本件訴訟に至っては,そもそもTLR7及び8が認識するも のと,TLR9が認識するものが異なるという技術常識に基づけば,TLR9に対 して本願IRO化合物がアンタゴニスト作用を奏するとする原告の作用機序の説明 が,TLR7及び8には妥当し得ないことは明らかであるなどとして,現にTLR 7及び8に固有の拒絶理由を具体的に主張しているのであるから(準備書面(第1 回)13頁),実質的にみても,上記のように,本件拒絶査定不服審判においてTL R7及び8に固有の拒絶理由を通知することが,審判合議体にとって困難なもので あったとは認められない。 したがって,被告の主張は,審判請求人の手続保障を規定する特許法159条2 項の意義を正解しないものに帰し,採用することができない。
なお付言するに,本願IRO化合物が治療効果を有するかどうかの点につき,本 件拒絶理由では,TLR7ないし9によって媒介される疾患以外の疾患については 治療効果を示すことが確認できないとしているところ,原告は,本件拒絶査定不服 審判においては,TLR7ないし9によって媒介される疾患については治療効果を 示すことが確認されたものと理解した上,本件拒絶理由を踏まえてTLR1ないし 6を削除する補正をし,さらに,その後の意見書において,この点に係る拒絶理由 が解消されたとまで述べているのであるから,審決においてTLR7ないし9によ って媒介される疾患についても治療的に処置することができるといえる根拠がない と判断するのであれば,審判請求人の手続保障を規定する特許法159条2項の法 意に照らすと,本件拒絶査定不服審判において,この点についても改めて拒絶理由 を通知することが相当であったものと認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2018.02.14
平成27(ワ)7855 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年1月26日 東京地方裁判所
原告は,本件原告製品の1)胴板の板厚,2)内鏡板の形状,3)入口チューブ の直径,4)入口チューブの長さ,5)入口チューブの穴の配置,6)入口チュー ブの穴径,7)入口チューブの穴の個数,8)出口チューブの直径,9出口チュ ーブの穴径,10)出口チューブの穴の個数,11)本体と鏡板の接合部,12)出口チ ューブの穴の配置方法,13)出口チューブの長さ,14)出口チューブの穴の配置 及びこれらの組合せ並びにこれに基づく減音量,圧力損失及び製造コストに 係る本件情報が,原告の営業秘密であると主張する。 (2) しかし,証拠(乙25〜27)によれば,本件原告製品に係る本件情報のう ち上記1)ないし14)は,本件原告製品を構成する部品等の形状,寸法,個数又はその相互の配置に関する情報であり,いずれも本件原告製品の寸法等を測定\nすることにより市場で同製品を購入した者が容易に知り得る情報であるから, 公然と知られていない情報であるということはできない。 また,本件原告製品の減音量及び圧力損失は,本件原告製品が備えるべき 性能として被告が指定し(甲6の2,20の2〜5),そのような性能\を有す るものとして被告の顧客に販売されるものであるから,原告の保有する営業 秘密ということはできず,また,原告製品が注文されたとおりの減音量及び 圧力損失を備えているかどうかは容易に測定し得るものである(甲31の2, 乙33)。 さらに,原告が営業秘密として主張する「製造コスト」(甲35の1の@以 下の数字,甲40の1の「見積金額」,甲41の1〜3)は,製造原価等に関 する情報ではなく,被告に提示される本件原告製品の見積金額又は販売価格 であり,非公知の情報であるということはできない。
上記の点について,原告は,1)本件原告製品は不特定多数の購入者が存在 する市場で販売される最終製品とは異なる特注品である,2)本件原告製品は 被告のブロワに組み込まれるので,被告の顧客はその内部構造等を知り得ない,3)本件原告製品の減音量,圧力損失及び製造コストは製品自体から直接 感得される情報ではない等と主張する。 しかし,被告のブロワが不特定多数の消費者に広く販売されるものではな いとしても,ブロワに関する市場において不特定の需要者を対象とし,国内 外の顧客に販売されているものであり(乙5,23),その需要者が特定少数 者に限定されると認めるに足る証拠はない。また,本件原告製品が被告の製 品に組み込まれているとしても,被告のブロワの購入者がリバースエンジニ アリングにより本件原告製品に係る本件情報を取得することが困難であると 認めるに足りる証拠もない。さらに,本件原告製品の減音量,圧力損失及び製 造コストが非公知といえないことは前記判示のとおりである。
(3) 原告は,本件情報に関し,被告との間において黙示の秘密保持契約を締結 し,又は,本件原告製品の性質上,被告は当然に秘密保持義務を負うと主張 する。 しかし,原告と被告との間で黙示の秘密保持契約が締結されたことをうか がわせる事情は認められない。また,本件情報は,いずれも本件原告製品の寸 法等を測定することにより同製品の購入者等が容易に知り得る情報又は本件 原告製品が備えるべき性能として被告が指定した情報であり,かつ,本件原告製品は被告のブロワに組み込んで第三者であるユーザに売却することを前\n提としたものであるから,その性質上当然に被告及びその顧客が秘密保持義 務を負うべきものということもできない。
2018.02.14
平成29(ワ)14909 不正競争 民事訴訟 平成30年1月23日 東京地方裁判所
前提事実に加え,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は昭和54年に発足 したこと(甲1),学研プラスが平成26年6月に発行した平成26年雑誌に おいて本件原告広告記事と概ね同一内容の原告の広告記事が掲載されたこと, 平成26年雑誌は発行予定部数が10万部であったこと,平成26年12月3\n1日時点での歯科医師の数は10万3972人であること(乙A1),本件雑 誌発行時点における原告の会員は63名であること(甲1)が認められる。 原告は,「WDSC」の表示は原告の商品等表\示であって需要者の間で広く 認識されており,本件雑誌に掲載された本件各記事において被告Aが「WDS C」の表示を自己の広告に使用したことが原告の商品等表\示を使用した不正競 争行為に該当する旨主張する。
本件雑誌は,「本気で探す 頼りになるいい歯医者さん 2016」という 題名の雑誌であって,表紙には「歯科治療の悩み&不安を解消!」という記載\nもあり,多くの歯科医師の紹介欄があり(甲1),歯科治療を受けることを考え ている者を主たる読者とするものである。本件各記事は,いずれも歯科医師で ある被告Aや被告Aが経営する歯科医院を紹介する記事である。これらからす ると,本件における需要者は,歯科治療を受けることを考えている者といえる。 原告は,平成26年雑誌及び本件雑誌を購読した全国の読者が需要者である旨 主張するが,上記に照らし採用することができない。
そこで,歯科治療を受けることを考えている者の間で「WDSC」の表示が\n周知であったかについて検討すると,原告は,昭和54年の発足後,会員であ る歯科医師らによる歯科医療に係る自主学習グループとして,定期的に勉強会 等を開催していたことがうかがわれる(甲1)。しかし,原告の会員数は全国の 歯科医師数の約0.06パーセントにすぎず,原告の会員を通じて「WDSC」 の表示が広く認識されていたとは認めることはできない。また,本件証拠上,\n本件雑誌が発行されるまで,原告が全国誌に取り上げられるなどして「WDS C」の表示が歯科治療を受けることを考えている者に対して広く使用されたの\nは,平成26年雑誌において前記のとおりの記事が掲載されたのみであり(原 告は,「WDSC」の表示の周知性の根拠として本件雑誌のほか平成26年雑\n誌における原告に関する記事の存在のみを主張し,平成29年10月2日の弁 論準備手続期日において「WDSC」の表示の周知性について追加の主張を行\nう予定はない旨述べた。),同雑誌の現実の発行部数も明らかではない。原告は\n平成26年雑誌の発行予定部数10万部が発行されたと主張するが,これを認\nめるに足りる証拠はない。これによれば,平成26年雑誌によって「WDSC」 の表示に接した者は,本件の需要者のうちの限られた者である。\nこれらのことからすると,本件雑誌が発行された平成27年10月29日の 時点までに「WDSC」の表示が,原告の商品等表\示として全国の歯科治療を 受けることを考えている者の間で広く認識されていたと認めることはできな い。
2018.01.19
平成29(行ケ)10107 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年1月15日 知的財産高等裁判所(4部)
被告は,原告といきいき緑健は,本件商標に係る商標権を共有するところ,原告 は,単独で本件審決の取消しを請求するから,本件訴えは不適法であると主張する。 しかし,いったん登録された商標権について,登録商標の使用をしていないこと を理由に商標登録の取消審決がされた場合に,これに対する取消訴訟を提起するこ となく出訴期間を経過したときは,商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみ なされることとなり,登録商標を排他的に使用する権利が消滅するものとされてい る(商標法54条2項)。したがって,上記取消訴訟の提起は,商標権の消滅を防 ぐ保存行為に当たるから,商標権の共有者の1人が単独でもすることができるもの と解される。そして,商標権の共有者の1人が単独で上記取消訴訟を提起すること ができるとしても,訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。 また,商標権の設定登録から長期間経過した後に他の共有者が所在不明等の事態 に陥る場合や,訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えら れるところ,このような場合に,共有に係る商標登録の取消審決に対する取消訴訟 が固有必要的共同訴訟であると解して,共有者の1人が単独で提起した訴えは不適 法であるとすると,出訴期間の満了と同時に取消審決が確定し,商標権は審判請求 の登録日に消滅したものとみなされることとなり,不当な結果となりかねない。 さらに,商標権の共有者の1人が単独で取消審決の取消訴訟を提起することがで きると解しても,その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には,その取消しの効 力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項),再度,特許庁で共有者全 員との関係で審判手続が行われることになる(商標法63条2項の準用する特許法 181条2項)。他方,その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には,他の共有 者の出訴期間の満了により,取消審決が確定し,商標権は審判請求の登録日に消滅 したものとみなされることになる(商標法54条2項)。いずれの場合にも,合一 確定の要請に反する事態は生じない。なお,各共有者が共同して又は各別に取消訴 訟を提起した場合には,これらの訴訟は,類似必要的共同訴訟に当たると解すべき であるから,併合の上審理判断されることになり,合一確定の要請は充たされる。 以上によれば,商標権の共有者の1人は,共有に係る商標登録の取消審決がされ たときは,単独で取消審決の取消訴訟を提起することができると解するのが相当で ある(最高裁平成13年(行ヒ)第142号同14年2月22日第二小法廷判決・ 民集56巻2号348頁参照)。 よって,原告は,単独で本件審決の取消しを請求することができる。被告の本案 前の抗弁は,理由がない。
・・・・
以上のとおり,甲1カタログ,甲2カタログ及び甲3雑誌は,いずれも要証期間 内に頒布されたものとは認められない。また,そもそも,本件商標は,「緑健青汁」, 「りょくけん青汁」,「リョクケン青汁」及び「RYOKUKEN AOJIRU」 の文字を4段に書して成るものであるのに対し,甲1カタログ,甲2カタログ及び 甲3雑誌に記載された商標は,「緑健青汁」の文字のみを書して成るものである。 このような本件商標と使用商標とは,商標法50条1項にいう「平仮名,片仮名及 びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ず\nる商標…その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」であると,直 ちに認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2018.01.19
平成29(行ケ)10155 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年1月15日 知的財産高等裁判所
商品等の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果的に発揮\nさせたり,商品等の美観をより優れたものとする等の目的で選択されるものであっ て,直ちに商品の出所を表示し,自他商品を識別する標識として用いられるもので\nはない。このように,商品等の製造者,供給者の観点からすれば,商品等の形状は, 多くの場合,それ自体において出所表示機能\ないし自他商品識別機能を有するもの,\nすなわち,商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また,\n商品等の形状を見る需要者の観点からしても,商品等の形状は,文字,図形,記号等 により平面的に表示される標章とは異なり,商品の機能\や美観を際立たせるために 選択されたものと認識するのであって,商品等の出所を表示し,自他商品を識別す\nるために選択されたものと認識する場合は多くない。 そうすると,客観的に見て,商品等の機能又は美観に資することを目的として採\n用されると認められる商品等の形状は,特段の事情のない限り,商品等の形状を普 通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標として,商標法3条1項3号 に該当することになる。 また,商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は,同種の商品等に\n関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから,先に商標出願した ことのみを理由として当該形状を特定人に独占使用を認めることは,公益上適当で ない。 よって,当該商品の用途,性質等に基づく制約の下で,同種の商品等について,機 能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予\測し得る範囲のもので あれば,当該形状が特徴を有していたとしても,同号に該当するものというべきで ある。
・・・・
イ 一般的な杭の形状との対比
本願の指定商品である杭については,先端を円錐状に尖らせ,頭部の先端(打込 部)を円盤状に平らにした,長い棒状の形状から成る商品が市販されていることが 認められる(甲1,123,乙4,5,9〜19)。 この点,原告は,一般的な杭は,頭部から先端までが同一径の円管で,鉄パイプを 切断しただけの状態のものである「単管杭」であり,本願商標をこれと対比すべき 旨主張するが,かかる「単管杭」のみならず,先端を円錐状に尖らせ,頭部の先端を 円盤状に平らにした長い棒状の杭も市販されているから,原告の主張は採用できな い。
・・・・
(ウ) そうすると,本願商標に係る立体的形状は,杭の形状として,機能又は美観\nに資することを目的として採用されたものと認められ,また,需要者において,機 能又は美観に資することを目的とする形状と予\測し得る範囲のものであるから,商 品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標として,商標 法3条1項3号に該当するというべきである。
・・・・
前記1のとおり,商標法3条2項は,商品等の形状を普通に用いられる方法で表\n示する標章のみから成る商標として同条1項3号に該当する商標であっても,使用 により自他商品識別力を獲得するに至った場合には,商標登録を受けることができ ることを規定している。 そして,立体的形状から成る商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどう かは,1)当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否,2)当該商標が 使用された期間,商品の販売数量,広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情 を総合考慮して判断すべきである。 なお,使用に係る商標ないし商品等の形状は,原則として,出願に係る商標と実 質的に同一であり,指定商品に属する商品であることを要するが,機能を維持する\nため又は新商品の販売のため,商品等の形状を変更することもあり得ることに照ら すと,使用に係る商品等の立体的形状が,出願に係る商標の形状と僅かな相違が存 在しても,なお,立体的形状が需要者の目につきやすく,強い印象を与えるもので あったか等を総合勘案した上で,立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得する に至っているか否かを判断すべきである。
(2) 本願商標に係る商品の形状及び当該形状に類似した他の商品の存在
本願商標は,指定商品である杭の立体的形状に係るものであり,その形状は,(ア) 円柱状の中央部分から頭部と先端部に向けて,円錐状の絞り加工部分があり,(イ)頭 部側,先端部側ともに,絞り加工部分の途中に1本の外周線があり,(ウ)頭部側につ いては,外周線を越えた後も絞りは続くが,絞り切る前に,絞り加工部分より大径 のリング部分及びリング部分より小径の台形部分があり,これが頭部の末端となり, (エ)先端部についても,外周線を越えた後も絞りが続くが,絞り切る前に,絞り加工 部分より大径のリング部分及び絞りの線よりも鋭角の線による円錐部分があり,こ れが先端部の末端となるというものであるところ,前記1のとおり,円柱状の中央 部分(上記(ア)),頭部の末端の台形部分(上記(ウ)),先端部の末端の円錐部分(上 記(エ))から成る杭は,他にも市販されている。また,上記(ア),(ウ),(エ)の頭部と 先端部に向けた絞り加工や,上記(エ)の絞り加工より大径のリング部分,上記(イ)の 外周線も,機能又は美観に資することを目的とする形状と予\測し得る範囲のもので あって,本願商標は,杭の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるもの とまではいえない。 さらに,本願商標と実質的に同一の形状から成る複数の杭が,第三者の取扱いに 係る商品として販売されていること,原告は,これに対して何らの権利行使も行っ ていないことも認められる(乙20〜22,弁論の全趣旨)。 したがって,原告商品の立体的形状自体が他の商品にない特徴的なものであると はいえない。
・・・・
以上のとおり,1)原告商品の立体的形状は,他の同種商品にはない特徴的なもの とはいえないこと,2)一定の販売実績を挙げてきたものの,そのシェアは不明であ り,実用新案権や意匠権が存在していたこと,原告商品の広告宣伝展示が継続して 行われたとしても,取引者,需要者は,併せ使用された「くい丸」の文字商標に注目 して自他商品の識別を行ってきたと認められること,これらの事情を総合すると, 原告商品の立体的形状が,文字商標から独立して,その形状のみにより自他商品識 別力を獲得するには至っていないというべきである。 したがって,本願商標は,使用をされた結果自他商品識別力を獲得し,商標法3 条2項により商標登録が認められるべきものということはできない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> 立体商標
>> ピックアップ対象
2018.01.19
平成28(行ケ)10278 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年1月15日 知的財産高等裁判所(4部)
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Aについて,本件出願当初明細書等には,おおむね,次のとおり記載が ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Aに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Aは,本件出願当初明細書等におい て名付けられたものである(【0007】)。
(イ) そして,本件出願当初明細書等【0008】には,結晶多形Aに該当する具体的な結晶多形として,【0008】(1)は,本件出願時の特許請求の範囲【請求 項1】で特定される結晶多形を挙げるほか,【0008】(5)は,2θで表して,構\ 成要件Eで特定されるのと同様の26個の角度において,ピークを有する特徴的な X線回析図形を示し,FT−IR分光法と結合した熱重量法により測定した含水量 が3〜15%であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており,後者の結 晶多形は,構成要件Eで特定される結晶多形を含むものである。このように,本件\n出願当初明細書等【0008】の記載は,結晶多形Aには,構成要件Eで特定され\nる結晶多形だけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される 結晶多形も,該当する旨説明するものである。
(ウ) また,本件出願当初明細書等【0009】は,「結晶多形Aの一つの具体 的形態」として,2θで表して,構\成要件Eで特定されるのと同様の26個無偏差 相対強度図形を示す結晶多形を例示しており,この結晶多形は,構成要件Eで特定\nされる結晶多形を含むものである。そうすると,本件出願当初明細書等【0009】 の記載は,構成要件Eで特定される結晶多形は,結晶多形Aの具体的な態様の一つ\nである旨説明するものである。
(エ) さらに,本願出願当初明細書等【0047】には,【0047】に記載さ れた製造方法によって,結晶多形Aが得られること,当該結晶多形AのX線粉末回 析図形は,構成要件Eと同様の26個無偏差相対強度図形を示したことが記載され\nている。本件出願当初明細書等【0047】の記載は,特定の製造方法によって生 成された結晶多形AのX線粉末回析図形を説明するにとどまり,構成要件Eで特定\nされる結晶多形のみが結晶多形Aである旨説明するものではない。
(オ) したがって,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特\n定される結晶多形Aだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特 定される結晶多形Aも,導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特定される結晶多形A\nだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される結晶多形A も,導くことができるから,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定され る結晶多形Aから,構成要件Eで特定される結晶多形Aを除くものを,本件出願当\n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。 したがって,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加す\nる本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件出願当初明細書等 に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は,本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Aを,26個のピークの回 折角2θ及びその相対強度で特定しなくても,6個のピークの回析角2θ等によっ て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。 しかし,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,26個のピークの回折角2 θ及びその相対強度で特定される結晶多形Aだけではなく,6個のピークの回析角 2θ等によって特定される結晶多形Aも導くことができる。本件補正は,26個の ピークの回折角2θ及びその相対強度で特定される結晶多形を,6個のピークの回 析角2θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから,被告の 上記主張は,前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加\nする本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではない。そして,本件補正の その余の部分について,被告は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件 出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した がって,本件補正は,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2018.01.18
平成29(ネ)233等 損害賠償 著作権使用料請求控訴事件,同附帯控訴事件 著作権 民事訴訟 平成29年12月28日 大阪高等裁判所(8部)
被控訴人は,この損害項目について,中止された本件公演を実施して いれば被控訴人が得られたであろう利益であるとの趣旨の主張をするが, それは,契約上の履行利益の賠償を求めるものであるから,控訴人が主 張するとおり,不法行為による損害賠償における損害としては請求する ことができない。しかし,同じ逸失利益であっても,前記のとおり,被 控訴人が同時期に他の公演を企画・実施していれば通常得られたであろ う利益であれば,不法行為に基づく損害賠償における損害として請求す ることができると解され,被控訴人の主張はこの趣旨を含むものと解さ れる。
・・・・
以上のとおりであるが,被控訴人が,実施された本件公演から算定し たと主張する,中止した公演の公演利益(4か月分の逸失利益)が42 84万0846円であることからすると,被控訴人の平成21年9月か ら平成24年8月までの間の各年度の4か月分の公演利益と同程度以下 であるということができる(後述するとおり,当裁判所の算定結果に よっても,中止した公演の公演利益は3003万4702円に過ぎな い。)。したがって,中止された本件公演を実施していれば得られたで あろう公演利益をもって,被控訴人が同時期に他の公演を企画・実施し ていれば通常得られる利益として損害を算定することとする。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2018.01.18
平成29(ネ)10053 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成29年12月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ Eが主宰する極真会館は,Eの死後,いずれもEの生前の極真会館と同 一性を有しない複数の団体に分裂しており,被控訴人らもその一団体と代 表者にすぎない。この点,被控訴人Yは,自身が極真関連標章の主体たる\n地位,すなわちEが主宰する極真会館の事業を承継した旨主張するが,極 真会館とE個人とが同一であるとはいえない以上,Eの相続人である被控 訴人Yが極真会館の事業を当然に相続したとはいえないし,E死亡当時, 被控訴人Yは極真会館の事業活動に全く関与していなかったこと,Eが後 継者を公式に指定しなかったこと,極真会館において世襲制が採用されて いなかったこと等の事情に鑑みると,被控訴人Yは相続以外の原因で極真 会館の事業を承継した者であるとも認められず,この点を覆すに足る証拠 はない。したがって,被控訴人らを含むいずれの団体とその代表者も,他\nの団体に対し,極真会館の事業承継や極真関連標章の自己への正当な帰属 を直ちに主張し得る立場にはなかった。
ウ 極真関連標章については,従前,Bが複数の標章について商標登録出願 をし,自己名義の商標登録を受けたことがあったが,これに対し,被控訴 人Y自身が商標法4条1項7号違反を理由に商標登録の無効審判を請求し, 商標登録を無効とする審決がなされ,同無効審決はBが提起した審決取消 訴訟を経て確定していた。
なお,前記認定のとおり,上記審決取消訴訟の判決は,Bによる商標登 録が公序良俗等に反する理由として,極真会館にとって極めて重要な財産 である極真関連標章についての商標登録出願を行うに当たっては,(当時 の代表者として)極真会館内部の適正な手続を経る必要があるのに,それ\nを怠った出願が行われ,その後,極真会館が複数の団体に分裂し,極真空 手の道場を運営する各団体が対立競合している状況において,上記の出願 に基づき,極真会館とは同一性を有しない一団体の代表者に商標権が付与\nされるのは,商標法の予定する秩序に反するという点を指摘しているが,\n極真会館内部での適正な手続(分裂後にあっては,他の団体との協議等) を経ないまま商標登録出願が行われている点や,その出願に基づき商標権 が付与されるのが,極真会館とは同一性を有しない一団体の代表者(又は,\n当該代表者が経営する会社)である点では,本件各商標も,上記判決が指\n摘したのと同様の問題点を抱えているものといわざるを得ない。 エ また,被控訴人らは,本件各商標の登録を受ける中で,1審被告Aに対 しては,権利侵害ないし規約違反を理由に極真関連標章の使用禁止と違約 金名目で高額の金員の支払を求める通知を行い,Fらに対しては,極真関 連標章の使用を禁止する旨の警告を行ったばかりか,Bが代表を務める団\n体に対しては,本件各商標権に基づき標章使用の差止めと損害賠償の支払 を求める訴訟を提起し,総極真に対しては,極真関連標章の使用差止めを 求める訴訟を提起するなど,本件各出願を行った後,極真会館の他の団体 やその代表者に対し自らの影響力を強めようとする姿勢が顕著であるとこ\nろ,このような行為は,客観的に見れば,極真会館にとって重要な財産で ある極真関連標章に係る権利を盾に取って,自己の利益を図ろうとするも のと評されてもやむを得ないものといわざるを得ない。
(2) 以上のとおり,本件各出願を行った時点で,被控訴人らは,極真会館関係 者にとって極真関連標章が重要な財産及び象徴であることを当然認識し得る 立場にあり,また,分裂した各団体の中で極真会館の事業の承継を正当に主 張し得る者がない状況にあることも明確に認識し得る立場にあったものと認 められる。そして,被控訴人らによる本件各商標権の取得は,極真会館とは 同一性を持たない分派が多数併存する中で,その一分派にすぎない一団体(そ の代表者や当該代表\者が経営する会社)が,極真会館にとって極めて重要な 財産であり象徴である極真関連標章について,いわば抜け駆け的に商標登録 出願を行い,その権利を独占しようとするという,前記審決取消訴訟判決が, 商標法の予定する秩序に反する旨を指摘したのと同様の状況で行われたもの\nなのであるから,やはり,商標法の予定する秩序に反するものといわなけれ\nばならない。特に,被控訴人らの場合,Bの出願に係る商標登録を公序良俗 等に反するとして無効にする一方で,自らの利益のために,客観的に見れば Bと同様の手法により商標権を取得しているのであるから,その不当性は更 に強度だといわざるを得ないのであって,この点からしても,その商標登録 は認められるべきものではない。 してみると,本件各出願に係る本件各商標は,本件各出願の目的及び経緯 に照らし,商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するお それがある商標」に該当するものといえる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2018.01.18
平成29(ネ)10027 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所(2部) 東京地方裁判所
引用発明1は,前記ア(イ)のとおり,「毎度の自動売買では自動売買テーブルでの 約定価より真下の安値の買取り及び約定価より真上の高値の売込みが同時に発注さ れるよう設定されたものであって,それにより,先に約定した注文と同種の注文を 含む売込み注文と買取り注文を同時に発注することで,株価が最初の売買価の値段 の範囲から上下に変動する場合に,所定の収益を発生させることに加え,口座の残 高及び持ち株の範囲において,株の現在価を無視して株の値段への変動を一向に予\n測することなく,従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買い取り,買 取り値より株価が上がると所定量を売り込むこと」を特徴とするものである。 このように,引用発明1において,従前の株の買取り値より株価が下落すると所 定量を買い取り,買取り値より株価が上がると所定量を売り込む,という,連続し た買取り又は売込みによる口座の残高又は持ち株の増大をも目的とするものである から,このような設定に係る構成を,約定価と同じ価格の注文を含む注文を発注対\n象に含めるようにし,それを「繰り返し行わせる」設定に変更することは,「約定価 より真下の安値の買取り」及び「約定価より真上の高値の売込み」を同時に発注す ることにより,「従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買取り,買取り 値より株価が上がると所定量を売込む」という,引用発明1の特徴を損なわせるこ とになる。 そうすると,引用発明1を本件発明の構成1Hに係る構\成の如く変更する動機付 けあるといえないから,構成1Hに相当する構\成は,引用発明1から当業者が容易 に想到し得たものとはいえない。
エ 被控訴人の主張について
被控訴人は,本件発明1と引用発明1との相違点は,引用発明1が本件発明1の 構成1Fのうち「前記一の注文価格を一の最高価格として設定し」ていない点であ\nり,その余の点では一致していることを前提に,本件発明1は,引用発明1から容 易想到である,と主張する。 しかし,前記イのとおり,本件発明1と引用発明1とは,引用発明1が本件発明 1の構成1Hの構\成を有していない点について相違している。被控訴人の主張は, その前提を欠き,理由がない。
・・・・
4 なお,被控訴人は,口頭弁論終結後に,本件発明1が無効とされるべきであ ることが明白である事由があるとして,口頭弁論再開を申し立てるが,無効事由の\n根拠となるべき資料は10年以上前に作成されていたものであり,上記無効事由は, 被控訴人が重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であって, これによって訴訟の完結を遅延させることとなるから,却下されるべきものである から,口頭弁論を再開しない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 分割
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2018.01.11
平成29(行ケ)10029 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年12月26日 知的財産高等裁判所
前記アのとおり,本件明細書には,「EVOH層の界面での乱れに起因す るゲル」は,ロングラン成形により発生するゲルとは異なる原因で発生するゲルで あると記載されているものの,本件明細書には,「EVOH層の界面での乱れに起因 するゲル」が,乙15における「ゲル状ブツ」の原因となるゲルと,その形状,構\n造等がどのように異なるのかを明らかにする記載は見当たらない。 また,本件明細書においては,前記イのとおり,「EVOH層の界面での乱れに起 因するゲル」は,目視観察できるものであるとされ,乙15における「ゲル状ブツ」 は,前記ウのとおり,肉眼で見ることができるものとされているところ,本件明細 書には,「目視観察」の定義は見当たらず,後者は肉眼で見分けられ,前者は肉眼で 見分けられないものを含む旨の特段の記載はないから,本件発明における「EVO H層の界面での乱れに起因するゲル」と背景技術(乙15)における「ゲル」を, 観察方法において区別することができるとは,理解できない。 このように,本件明細書には,本件発明における「EVOH層の界面での乱れに 起因するゲル」は,本件特許出願前の技術により抑制することができるとされてい るロングラン成形により発生するゲルとは異なる原因で発生する旨の記載があるも のの,その記載のみでは,ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどう かは,明らかでないというほかない。 この点について,被告は,「不完全溶融EVOH」が発生する機序について主張し, これは,従来から知られていた「熱架橋ゲル」とは異なる旨主張する。しかし,本 件明細書には,被告が本訴において主張するようなことは何ら記載されておらず, 被告が本訴において主張するような技術常識が存したとも認められないから,本件 発明における「EVOH層の界面での乱れに起因するゲル」が被告が本訴において 主張するようなものと認めることはできない。 そうすると,本件発明における「EVOH層の界面での乱れに起因するゲル」の 意義は明らかでないというほかなく,本件特許出願時の技術常識を考慮しても,「成 形物に溶融成形したときにEVOH層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく, 良好な成形物が得られ」るという本件発明の課題は,理解できないというほかない。 オ したがって,本件明細書の記載には,本件発明の課題について,当業者 が理解できるように記載されていないから,「特許法第三十六条第四項第一号の経\n済産業省令で定めるところによる記載は,発明が解決しようとする課題及びその解 決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明 の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければなら ない。」と定める特許法施行規則24条の2の規定に適合するものではない。
(2) 以上のとおり,本件発明についての本件明細書の発明の詳細の説明の記 載は,特許法36条4項1号の規定に適合しないから,審決のこの点に係る判断に は誤りがあり,取消事由3には理由がある。
・・・
前記2(1)オのとおり,本件明細書には,本件発明の課題について,当業者が理解 できるように記載されていないから,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の 詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲の ものであると認めることはできないし,発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも, 当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲 のものであるとも認められない。 この点について,被告は,「本件発明は,粒径500μm(0.5mm)未満の微 粉の含有量を0.1重量%以下に制御すること(新規な解決手段)により,『不完全 溶融EVOH』に起因する界面での乱れによるゲル(点状に分布する透明な粒状の 不完全溶融ゲルであり,EVOHの一部が極端な場合には他の樹脂層に突出するよ うな形態)の発生(斬新な課題)を抑制することができる(新規課題解決効果の奏 効)という特別な効果を得る」ものであると主張するが,前記2(1)のとおり,この 課題は,本件明細書及び技術常識から理解することができない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2018.01.11
平成29(行ケ)10025 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所
本件発明1と引用発明とを対比すると,少なくとも,1)「金融商品の売 買取引を管理する金融商品取引管理装置であること,2)前記金融商品の売買注文を 行うための売買注文申込情報を受け付ける注文入力手段を備えること,3)該注文入 力受付手段が受け付けた前記売買注文申込情報に基づいて金融商品の注文情報を生\n成する注文情報生成手段を備えること,及び,4)一の前記売買注文申込情報に基づ\nいて,所定の前記金融商品の売り注文又は買い注文の一方を成行又は指値で行う第 一注文情報と,該金融商品の売り注文又は買い注文の他方を指値で行う第二注文情 報と,を含む注文情報群を複数回生成することで共通し,5)引用発明が,「前記金融 商品の売り注文又は買い注文の前記他方を逆指値で行う逆指値注文情報」を生成し ていない点で相違している。
イ 本件発明1の構成1Gは,「前記第二注文情報に基づく該指値注文が約定\nされたとき,次の注文情報群の生成を行うと共に,該生成された注文情報群の前記 第一注文情報に基づく前記成行注文の価格と同じ前記価格の指値注文を有効に」(1 G前段)するとともに,「以後,前記第一注文情報に基づく前記指値注文の約定と, 前記第一注文情報に基づく前記指値注文の約定が行われた後の前記第二注文情報に 基づく前記指値注文の約定と,前記第二注文情報に基づく前記指値注文の約定が行 われた後の,次の前記注文情報群の生成とを繰り返し行わせる」(1G後段)という ものである。構成1G前段は,売買取引開始時において,同じ注文情報群に含まれ\nる第一注文情報に基づく成行注文が約定した後で,第二注文情報に基づく該指値注 文が約定されたときに,次の注文情報群の前記第一注文情報に基づく注文が,上記 売買取引開始時に約定された成行注文の価格と同じ価格の「指値注文」として有効 に生成されることとを意味するものである。 これに対し,引用発明は,前記2(2)のとおり,代替実施形態においては,パート 1注文とパート2注文とで形成されるLOCK注文を再度自動的に繰り返すもので ある。このことは,引用文献の図6では,代替実施形態において情報を入力する際 に「指値注文」と「成行注文」を選択する欄しかない上,引用文献の[0085] には,「『サイクル数44』の追加によって,投資家は,より多くの利益を得ること を望んで,LOCK処理に自動的に再入力できるようになるであろう。」と記載され ており,図7には,サイクル数選択「44」を経て同じ注文が繰り返される旨の矢 印が記載されていることからしても,明らかであるということができる。したがっ て,1回目のLOCK注文の第一注文が成行注文である場合には,繰り返されるL OCK注文の第一注文も成行注文であり,1回目のLOCK注文の第一注文が指値 注文である場合には,繰り返されるLOCK注文の第一注文も指値注文であるとい うことができる。
ウ 以上より,本件発明1と引用発明とは,本件発明の構成1Gの点におい\nて相違している。
◆判決本文
◆関連発明(特5525082号)についての審決取消訴訟です。こちらも権利有効維持です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2018.01.11
平成29(行ケ)10072 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所
以上より,甲5文献記載の発明は,ポリメチルシルセスキオキサンの製 造方法に関するものであり(前記ア2)),塩素原子の含有量が少なく,アルカリ土類 金属やアルカリ金属を含有せず,自由流動性の優れた粉末状のポリメチルシルセス キオキサンの製造方法を提供することを目的とし(前記ア3)),アンモニアまたはア ミン類を,原料であるメチルトリアルコキシシラン中に残存する塩素原子の中和剤, 並びに,メチルトリアルコキシシランの加水分解及び縮合反応の触媒として用いる という製造方法を採用したものである(前記ア4))と認められる。
(2) 引用発明の粉末のシラノール基量及び撥水性を甲4実験に基づき認定し た点について
ア 甲1文献の実施例1において用いたポリメチルシルセスキオキサン粉末 は,「甲5文献記載の方法により得た平均粒子径5μm」のものである。決定は,甲 4実験は,甲1文献の実施例1を追試したものであり,甲4実験のポリメチルシル セスキオキサン粒子は,シラノール基量が0.08%であること,及び,撥水性の 程度が「水及び10%(v/v)メタノール水溶液に対して300rpmで1分間 攪拌後において,粒子が分散しない程度」であることを示していると認定した上で, 引用発明のポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を認定 した。 しかし,甲1文献の実施例1にいう,甲5文献記載の方法によることが,甲5文 献の実施例1によることで足りるとしても,以下のとおり,甲4実験は甲1文献の 実施例1を再現したものとは認められない。
イ 甲5文献の実施例1を含む甲1文献の実施例1の方法と,甲4実験とを 比較すると,少なくとも,1)攪拌条件,及び,2)原料メチルトリメトキシシランの 塩素含有量において,甲4実験は,甲1文献の実施例1の方法を再現したとは認め られない。
(ア) 攪拌条件について
真球状ポリメチルシルセスキオキサンの粒子径をコントロールするために,反応 温度,攪拌速度,触媒量などの反応条件を選定すること(乙2 489頁左欄6行 〜11行),ポリアルキルシルセスキオキサン粒子の製造方法として,オルガノトリ アルコキシシランを有機酸条件下で加水分解し,水/アルコール溶液,アルカリ性 水溶液を添加した後,静止状態で縮合する方法において,弱攪拌又は攪拌せずに縮 合反応させることによって,低濃度触媒量でも凝集物を生成しない粒子を得ること ができるが,粒径が1μm以上の粒子を製造するのに不適切であることが本件発明 の従来技術であったこと(本件明細書【0006】)からすると,ポリメチルシルセ スキオキサン粒子の製造においては,攪拌条件により,粒子径の異なるものが得ら れるものといえる。 甲5文献の実施例1には,攪拌速度は記載されておらず,甲4実験においても, 攪拌速度が明らかにされていない。したがって,実験条件から,得られたポリメチ ルシルセスキオキサン粒子の平均粒径を推測することはできない。加えて,甲4実 験においては,甲5文献の実施例1で追試して得られたとするポリメチルシルセス キオキサン粒子の粒径は計測されていない。したがって,甲4実験において甲5文 献の実施例1を追試して得られたとするポリメチルシルセスキオキサン粒子の平均 粒子径が,甲1文献の実施例1で用いられたポリメチルシルセスキオキサン粉末と 同じ5μmのものであると認めることはできない。
(イ) 原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量について
甲5文献記載の発明は,前記(1)イのとおり,塩素原子の含有量が少ないポリメチ ルシルセスキオキサンの製造方法を提供するものであり,塩素原子を中和するため にアンモニア又はアミン類を用いるものである。そして,アンモニア及びアミン類 の使用量は,アルコキシシラン又はその部分加水分解縮合物中に存在する塩素原子 を中和するのに十分な量に触媒量を加えた量であるが,除去等の点で必要最小限に\nとどめるべきであり,アンモニア及びアミン類の使用量が少なすぎると,アルコキ シシラン類の加水分解,さらには縮合反応が進行せず,目的物が得られない(前記 (1)ア4))。実施例1〜5及び比較例1〜3においては,原料に含まれる塩素原子濃 度並びに使用したアンモニア水溶液の量及びアンモニア濃度が記載されている(前 記(1)ア5)6))。以上の点からすると,塩素原子の中和に必要な量でありかつ除去等 の点で最小限である量のアンモニア及びアミン類を使用するために,塩素原子の量 とアンモニア及びアミン類の量を確認する必要があり,そのために,甲5文献の実 施例1においては,用いたメチルトリメトキシシランのメチルトリクロロシランの 含有量が塩素原子換算で5ppmであることを示したものと理解される。 ところが,甲4実験で甲5文献の実施例1の追試のために原料として用いたメチ ルトリメトキシシランの塩素原子含有量は計測されていない。したがって,甲4実 験で用いられたメチルトリメトキシシランに含有される塩素原子含有量と甲5文献 の実施例1で用いられたメチルトリメトキシシランに含有される塩素原子含有量と が同一であると認めることはできない。そうすると,甲4実験において,甲5文献 の実施例1と同様にアルコキシシラン類の加水分解,縮合反応が進行したと認める ことはできず,その結果,得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子が,甲5文 献の実施例1で得られたものと同一と認めることはできない。
ウ 以上より,甲4実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は,甲 1文献の実施例1で用いられたものと同一とはいえないから,甲4実験で得られた ポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を,甲1文献の実 施例1のそれと同視して,引用発明の内容と認定することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2018.01. 6
平成29(行ケ)10080 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年12月25日 知的財産高等裁判所
本件商標と引用商標は,全体的な構図として,黄色系暖色調の無地の背景図形の\n前に,左向きに描かれて角を突き出した赤色の躍動感のある姿勢をした雄牛の図形 が配置されるなどの基本的構成を共通にするものであり,本件商標が使用される商\n品である自動車用品関連商品等の商品の主たる需要者が,商標やブランドについて 正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者を含み,商品の購入に際して 払われる注意力はさほど高いものとはいえないことなどの実情や,引用商標が高度 の独創性を有するとまではいえないものの我が国において高い周知著名性を有して いることなどを考慮すると,本件商標が,指定商品に使用された場合には,これに 接した需要者(一般消費者)は,それが引用商標と基本的構成が類似する図形であ\nることに着目し,本件商標における細部の形状などの差異に気付かないおそれがあ るといい得る。 また,引用商標は,自動車関連の分野においても,レッドブル社の商品等を表示\nするものとして,取引者,需要者の間において著名であり,引用商標をその構成と\nする使用商標について,多数のライセンスが付与され,自動車関連商品等の多様な 商品について引用商標を含む使用商標が付されて販売されているところ,本件商標 の指定商品には,引用商標の著名性が取引者,需要者に認識されている自動車関連 の商品を含むものといえるのであるから,本件商標をその指定商品に使用した場合 には,これに接する取引者,需要者は,著名商標である引用商標を連想,想起して, 当該商品がレッドブル社又は同社との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示によ\nる商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信 するおそれがあるものというべきである。 したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するものとして商標登録 を受けることができないというべきであるから,これと異なり,本件商標が同号に 該当しないとした審決の判断には誤りがあるといわざるを得ない。
(8) 被告の主張について
ア 被告は,本件商標と引用商標とは,牛の体勢,色彩の差異及び牛以外の 構成物の差異により,その印象が明らかに異なるから,外観において容易に区別し\n得るものであり,いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから,相紛れ ることのない非類似の商標である旨主張する。 確かに,本件商標と引用商標とを直接対比すると,前記(2)イのとおり,具体的な 構成においていくつかの相違点が認められるものである。しかしながら,引用商標\nが高い著名性を有していたことや,本件商標と引用商標からはほぼ同一の観念が生 じることなどに照らせば,被告が指摘するような具体的構成における外観上の差異\nが存在するとしても,引用商標と基本的構成が共通すると認められる本件商標を自\n動車用品関連の商品を含む本件商標の指定商品に付して使用した場合には,これに 接する取引者,需要者において,当該商品がレッドブル社又は同社との間に緊密な 営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある\n者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべきである。 また,本件商標には,外観上,具体的な構成において引用商標と相違する点があ\nるとしても,その基本的構成が引用商標と比較的類似性の高いものであるから,一\n般の消費者の注意力などを考慮すると,出所の混同を生ずるおそれがあることは前 記(6)のとおりである。 なお,商標法4条1項15号該当性の判断は,当該商標をその指定商品等に使用 したときに,当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営 業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営\n業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれが存するかどうかを問題とする ものであって,当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは,上記判断における 考慮要素の一つにすぎないものである。被告が主張するような外観上の差異が存在 するとしても,それらの点が,本件商標の構成において格別の出所識別機能\を発揮 するとはいえないし,単に本件商標と引用商標の外観上の類否のみによって,混同 を生じるおそれがあるか否かを判断することはできない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.12.28
平成28(行ケ)10254 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年12月25日 知的財産高等裁判所(1部)
(1) 原告は,平成29年5月31日,被告Yの本人尋問の申立てをしたところ,\n尋問事項に関する原告の主張は,被告らが共謀して原告の利益を害する目的をもっ て原審決をさせたことである(第3回口頭弁論調書参照)。
(2) 当裁判所は,同年6月14日,第2回口頭弁論期日において,被告らの共 謀の存否を明らかにするには,当審において被告Yの本人尋問を行う必要があると して,上記(1)の申立てを採用するとともに,本人尋問期日を同年10月11日に指\n定した。なお,被告Yは,同年8月31日までに陳述書を提出することとされた。 (第2回口頭弁論調書参照)
(3) 被告Yは,同年8月25日付けで,被告Shapesの代表者や関係者と\n共謀したことはない旨を記載した陳述書を提出した(乙ア34)。
(4) 被告Yは,適式の呼出しを受けたにもかかわらず,当裁判所に対し事前の 連絡なく,本人尋問期日に出頭しなかった。なお,被告Yは,当裁判所に対し,診 断書その他出頭できない理由を証明する書類を一切提出していない。
(5) 被告Yの代理人は,本人尋問期日において,被告Yには民訴法208条の 不出頭の効果を説明して出頭しないと不利益になる旨を告げて出頭を促したものの, 本人からはそのことを承知の上で出頭しないと告げられた旨述べた(第3回口頭弁 論調書)。
(6) 当裁判所は,上記の経過を踏まえ,弁論を終結した。なお,被告Shap es及び被告Yの各代理人は,弁論を終結することにつき,異議を述べなかった。 2 民訴法208条該当性
上記認定事実によれば,被告Yが当事者本人の尋問期日に正当な理由なく出頭し なかったものと認められるから,民訴法208条に基づき,被告らが共謀して本件 商標権を害する目的をもって本件商標に係る登録商標を取り消す旨の原審決をさせ たという原告の主張は,真実と認めることができる。 したがって,被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決をさせた とは認められないとした審決の判断には誤りがあるから,原告の取消事由は理由が ある。
2017.12.28
平成29(行ケ)10126 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年12月25日 知的財産高等裁判所(1部)
上記認定事実によれば,本件折込チラシ1には,「ベガス発寒店ファンのお 客様へ」と記載されている部分が認められ,この部分には本件文字部分(ベガス) が使用されており,本件文字部分は本件商標と同一のものと認められる。他方,本 件折込チラシ1の下部には,登録商標であることを示す○R の文字を付した「ベガス ベガス(R)」という文字が大きく付されているほか,「VEGAS VEGAS」,「ベ ガスベガス発寒店」という文字も併せて記載されている。 これらの事実関係によれば,本件折込チラシ1に接した需要者は,同チラシにお いて,パチンコ,スロットマシンなどの娯楽施設の提供という役務に係る出所を示 す文字は,同チラシにおいて多用されている「ベガスベガス」又は「VEGAS V EGAS」であって,一箇所だけで用いられた本件文字部分は,店内改装のため一 時休業する店舗の名称を一部省略した略称を表示したものにすぎず,本件折込チラ\nシ1に係る上記役務の出所自体を示すものではないと理解するのが自然である。 そうすると,本件折込チラシ1に本件文字部分を付する行為は,本件商標につい て商標法2条3項にいう「使用」をするものであると認めることはできない。 したがって,本件文字部分が出所識別機能を果たし得るものと認定した上,本件\n折込チラシ1に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されていると認定 した審決の各判断には,いずれも誤りがあるから,取消事由4及び5は,理由があ る。
(2) これに対し,被告は,本件文字部分が「ベガスベガス発寒店」の略称表示\n又は愛称表示として解釈できるのであるから,本件折込チラシ1には本件商標と社\n会通念上同一と認められる商標が付されたといえるなどと主張する。 しかしながら,被告が本件文字部分を「ベガスベガス」又は「VEGAS VEG AS」の略称表示であると認めるとおり,本件折込チラシ1に係る役務の出所を示\nす表示は,多用された「ベガスベガス」又は「VEGAS VEGAS」の標章であ ると認めるのが相当であるから,これらと異なる標章である本件文字部分が出所識 別機能を果たし得るとは認められない。かえって,「ベガス」という略称表\示の使用 をもって,本件商標についての使用であると認めることは,実質的には商標として は異なる略称表示に係る信用までを保護することを意味するから,商標法50条1\n項の不使用取消制度の趣旨に照らしても,相当ではない。のみならず,実質的にみ ても,前記認定事実によれば,被告が「ベガス発寒店」という文字を使用したチラ シは,同文字を一箇所でのみ使用した本件折込チラシ1のほかは一切提出されてい ないのであるから,そもそも「ベガス発寒店」という文字に係る標章の信用を保護 すべき特段の事情もうかがわれず,被告の上記主張は,前記認定を左右するもので はない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2017.12.22
平成29(行ケ)10058 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所(4部)
引用発明と甲2技術は,いずれも空気入りタイヤに関するものであり,技術分野 が共通する。 また,引用発明は,ランフラットタイヤのサイドウォール部の補強ゴムから発生 した熱をより早く表面部に移動させて放熱効果を高め,カーカスやサイド補強ゴム\nの破壊を防止することを課題とする。甲2技術は,空気入りタイヤのブレーカ端部 の熱を逃がし,ブレーカ端部に亀裂が生じるのを防止することを課題とする。した がって,引用発明と甲2技術の課題は,空気入りタイヤの内部に発生した熱を迅速 に逃すことにより当該部位の破壊を防止するという点で共通する。 さらに,引用発明は,タイヤの外側表面の一定部位を,適当な表\面パターン形状 にすることによって,タイヤの回転軸方向の投影面積の表面積を大きくし,サイド\n補強層ゴムから発生した熱をより早く外部表面に移動させ,外気により効果的に拡\n散させるものである。甲2技術は,タイヤの外側表面の一定の領域に,多数の凹部\nを形成することによって,その領域で広い放熱面積を形成して,温度低下作用を果 たさせるものである。したがって,引用発明と甲2技術の作用効果は共通する。 加えて,甲2技術は,多数の凹部を形成することによって温度低下作用を果たさ せるに当たり,引用発明のように表面積の拡大だけではなく,乱流の発生も考慮す\nるものである。 よって,引用発明に甲2技術を適用する動機付けは十分に存在するというべきで\nある。
イ 引用発明における凹凸のパターン12の具体的な構造として,甲2技術を適\n用した場合,その凹凸部の構造は,「5≦p/h≦20,かつ,1≦(p−w)/\nw≦99の関係を満足する」ことになり,これは,相違点2に係る本件発明1の構\n成,すなわち「10.0≦p/h≦20.0,かつ,4.0≦(p−w)/w≦3 9.0の関係を満足する」という構成を包含する。\nそして,本件明細書(【0078】【0079】)には,「乱流発生用凹凸部で は,1.0≦p/h≦50.0の範囲が良く,好ましくは2.0≦p/h≦24. 0の範囲,更に好ましくは10.0≦p/h≦20.0の範囲がよい」「1.0≦ (p−w)/w≦100.0,好ましくは4.0≦(p−w)/w≦39.0の関 係を満足することが熱伝達率を高めている」との記載があり,「1.0≦p/h≦ 50.0」「1.0≦(p−w)/w≦100.0」というパラメータを満たす場 合においても放熱効果が高まる旨説明されている。「10.0≦p/h≦20.0」 「4.0≦(p−w)/w≦39.0」という数値範囲に特定する根拠は,「好ま しくは」と,単に好適化である旨説明するにとどまる。 また,本件明細書の【表1】【表\2】には,p/h及び(p−w)/wと耐久性 の関係についての実験結果が記載されているところ,本件発明1の数値範囲のうち p/hのみを満たさない実施例3(p/h=8)の耐久性は,本件発明1の数値範 囲を全て満たす実施例8,11,12,18,19の耐久性よりも高く,本件発明 1の数値範囲のうち(p−w)/wのみを満たさない実施例13,15,16((p −w)/w=44,99,59)の耐久性は,本件発明1の数値範囲を全て満たす 実施例8,11,12,18,19の耐久性よりも高いという結果が出ている。 加えて,本件明細書の【図29】には,p/hと熱伝達率の関係についてのグラ フが記載され,【図30】には,(p−w)/wと熱伝達率の関係についてのグラ フが記載されているところ,これらのグラフは,p/h又は(p−w)/wの各パ ラメータと熱伝達率の関係を示すにとどまり,両パラメータの充足と熱伝達率の関 係を示すものではない。そして,タイヤ表面の凹凸部によって発生する乱流により,\n流体の再付着点部分の放熱効果の向上に至るという機序によれば,凹凸部のピッチ (p),高さ(h)及び幅(w)の3者の相関関係によって放熱効果が左右される というべきであって,本件発明1において特定されたピッチと高さ,ピッチと幅と いう2つの相関関係のみを充足する凹凸部の放熱効果が,これらを充足しない凹凸 部の放熱効果と比較して,向上するといえるものではない。そうすると,p/h又 は(p−w)/wの各パラメータと熱伝達率の相関関係を示すグラフ(【図29】 【図30】)から,「10.0≦p/h≦20.0,かつ,4.0≦(p−w)/ w≦39.0の関係を満足する」凹凸部の構造が,これを満足しない凹凸部の構\造 に比して,熱伝達率を向上させるということはできない。 そうすると,本件発明1は,凹凸部の構造を,「10.0≦p/h≦20.0,\nかつ,4.0≦(p−w)/w≦39.0」の数値範囲に限定するものの,当該数 値範囲に限定する技術的意義は認められないといわざるを得ない。 よって,引用発明に甲2技術を適用した構成における凹凸部の構\造について,パ ラメータp/hを,「10.0≦p/h≦20.0」の数値範囲に特定し,かつ, パラメータ(p−w)/wを,「4.0≦(p−w)/w≦39.0」の数値範囲 に特定することは,数値を好適化したものにすぎず,当業者が適宜調整する設計事 項というべきである。
・・・
(ア) 被告は,引用例2は,放熱効果を向上させるための凹部のピッチと凹部の 深さ及び直径Dとの関係について全く開示しないと主張する。 しかし,引用例2には,多数の凹部によって生じる乱流によって温度低下作用が 果たされる旨記載があり(【0007】【0014】),また,引用例2はそのよ うな凹部について,ピッチ(p),深さ(d)及び直径(D)のサイズの範囲が具 体的に記載されている(【0009】【0010】【0012】)。そして,前記 (3)ウ(ア)のとおり,本件特許の優先日当時,当業者は,乱流による放熱効果の観点 から,タイヤ表面の凹凸部における,突部のピッチ(p)と突部の高さ(h)との\n関係及び溝部の幅(p−w)と突部の幅(w)との関係について,当然に着目する ものである。したがって,当業者は,引用例2に記載された凹部のピッチと凹部の 深さ及び直径Dについて,放熱効果を向上させるという観点からその関係を理解す るというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.12.22
平成29(行ケ)10083 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所
以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば,本件訂正後の 特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は,本件発 明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の構造又は特性を有する精白米を製造す\nる際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり,「無洗米機(21)にて」 という記載は,上記精白米から前記ウ(c)の構造又は特性を有する無洗米を製造する\n際に無洗米機を用いることを意味するものであって,前記ウ(a)ないし(c)のほかに本 件発明に係る無洗米の構造又は特性を表\すものではないと解するのが相当である。 そして,本件発明に係る無洗米とは,玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去さ\nれ,亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し,米粒の50%以上に「胚芽の表\面部を削 りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており,糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に 粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」が分離除去された米で\nあるといえる。 そうすると,請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機(21) にて」という製造方法が記載されているとしても,本件発明に係る無洗米のどのよ うな構造又は特性を表\しているのかは,特許請求の範囲及び本件明細書の記載から 一義的に明らかである。よって,請求項1の上記記載が明確性要件に違反するとい うことはできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.12.13
平成29(行ケ)10110 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年11月27日 知的財産高等裁判所
次に,本願商標の表示方法について検討するに,本願商標は,前記のと\nおりありふれた氏である「森本」と同一の称呼観念を有する語をローマ字 表記にした上,「mori」と「moto」を上下二段に分けて配置した\nものであり,その字体も,文字の角を丸めたやや太めの書体を採用したに すぎないものである(Fontworks社のスーラEBという特定の書 体を採用した点についても,同社のウェブサイト〔乙35,36〕におい て,同書体がDTP〔デスクトップパブリッシング〕の代表的な書体であ\nり,近年多くの場所で使用されている旨謳われていることからすれば,格 別特徴的であるとはいえない。)。 商取引において,氏や名称をローマ字で表記することは,一般的に行わ\nれていることであるし,標章の構成文字を複数の段に分けることや,構\成 文字の書体をある程度デザイン化することも特段珍しいことではなく,表\n示上格別の工夫を凝らしたものであるとはいえない(これらのことは逐一 立証するまでもない公知な事実であり,被告提出の乙6ないし34からも 明らかといえる。なお,これらの書証の中には,必ずしも原告と同じ業界 でないものの例も含まれているが,複数の業界を跨いで同じような例があ るということは,それだけ一般的に行われていることを示すものといえる から,これらの証拠を総合して取引の実情を認定したとしても何ら差し支 えない。)。 したがって,上記の程度の表示態様(外観)では,いまだ「森本」の氏\nとは別の称呼観念が生じ得るほどに(すなわち,独占の弊害を生ずるおそ れがないといい得るほどに)特徴的であるということはできず,本願商標 は,外観上も,ありふれた氏を「普通に用いられる方法」で表示する域を\n出ないものと評価するのが相当である。 よって,この点に関する審決の認定判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2017.12.13
平成29(行ケ)10071 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年11月29日 知的財産高等裁判所
前記第2の1記載の事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実 が認められる。
(1) 原告は,平成23年11月23日,冒頭に「Coverderm Product Order Form」 と付した本件ウェブサイトにおいて,本件商標及び日本語でこれを仮名書きした「カ バーダーム」という名称を表題に付して,「カバーダームは最先端のスキンケア化粧\n品の専門ブランドです。」,「輝かしい歴史を誇り,さらに成長を続ける製品ラインナ ップを,長年にわたり80ヶ国以上の国々にお届けしています。」,「顔や体の気にな る箇所をカバーしてくれる,理想的なアイテムを多数揃えています!」,「世界中の 皮膚科医やメイクアップアーティストにも長年支持されています!」という文章を 掲載した。 そして,原告は,その下に「下記の空欄に必要事項をご記入のうえ,ご注文くだ さい。」という文章を掲載した上,名,姓,住所,製品名,数量,メールアドレス, コメントの記入欄と送信ボタンを設けるなどして,原告の商品をインターネットで 注文できるように設定するとともに,その下に「弊社製品に関する詳しい説明はこ ちらをクリックしてください。」という文章を掲載し,COVERDERMの商品の 紹介ページにリンクさせていた。 なお,本件ウェブサイトの末尾には,「Copyright Farmeco S.A. Dermocosmetics All rights reserved.」と表記され,本件ウェブサイトの著作権者が原告である\nことが明記されている。(甲14の1)
(2) 原告の代表者は,平成20年10月30日から少なくとも本件口頭弁論終\n結時まで,本件ウェブサイトに係る「coverderm.jp」という日本のドメイン名を個 人名で取得し,これを原告に使用させていた(甲14の2,甲20の1ないし3, 甲44の1及び2)。
(3) 本件ウェブサイトは,本件商標が付された原告のCOVERDERMの商 品につき,日本における販売促進及び日本の消費者から直接注文を受けることを目 的として,平成20年に作成されたものである。また,原告のインターネット経由 での売上げは,平成23年が7863.49ユーロ,平成24年が8129.44 ユーロ,平成25年が7555.50ユーロ,平成26年上半期が4289.94 ユーロであることがそれぞれ認められる(甲15)。
2 商標法50条1項該当性
上記認定事実によれば,原告は,少なくとも本件要証期間内である平成23年1 1月23日に,本件ウェブサイトにおいて,日本の需要者に向けて原告の「COV ERDERM」の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付し て電磁的方法により提供していたことが認められる。 したがって,原告は,本件商標について,少なくとも本件要証期間内に日本国内 で商標法2条3項8号にいう使用をしたものといえるから,同法50条1項に該当 するものとは認められず,原告の前記第3の3の取消事由は,理由がある。
3 被告の主張について
被告は,本件ウェブサイトは日本語で作成されているものの,リンク先とされる COVERDERMの商品の紹介ページは原告の英語ウェブサイトであり,商品の 発送方法や代金の支払等について何ら記載がないのであるから,本件ウェブサイト が日本の需要者を対象とした注文サイトとして機能しているかどうかは疑わしく,\n仮に,本件ウェブサイトにおける本件商標が広告として機能されることがあるとし\nても,日本の需要者の目に触れることのない状況において,本件ウェブサイトは形 式的にインターネット上にアップされているにすぎず,正当な商標の使用とはいえ ないなどと主張する。
しかしながら,前記1の認定事実によれば,本件ウェブサイトは,日本語で本件 商標に関するブランドの歴史,実績等を紹介するとともに,注文フォーム及び送信 ボタンまで日本語で記載されているのであるから,リンク先の商品の紹介が英語で 記載されているという事情を考慮しても,本件ウェブサイトが日本の需要者を対象 とした注文サイトであることは明らかである。そうすると,審決が認定するとおり, 本件商標を付した商品が日本の需要者に引き渡されたことまで認めるに足りないか 否かはさておき,少なくとも,原告は,本件商標について本件要証期間内に日本国 内で商標法2条3項8号にいう使用をしたものと認められる。 また,証拠(甲63の1ないし3)によれば,グーグルで検索する場合において, 検索キーワードを「カバーダーム」,「COVERDERM 化粧品」としたとき及び日本語の ページを検索するように設定した上で検索キーワードを「COVERDERM」としたときは, 本件ウェブサイトのリンク及び本件ウェブサイトの説明が表示されるものと認めら\nれるから,本件ウェブサイトは形式的にインターネット上にアップされているとは いえず,被告の主張は,その前提を欠くものである。
2017.12.13
平成29(ワ)393 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月30日 東京地方裁判所(46部)
被告製品の不織布が構成要件Aの「不織布シート」に当たることは当事者\n間に争いがないところ,原告は,その表面にシリカ(SiO2)が付着して\nいるから,構成要件Aの「表\面に吸着・乾燥剤を付着させた」を充足すると 主張する。
(2)本件発明の特許請求の範囲にはいかなる物が「吸着・乾燥剤」に当たるか は記載されていないが,本件明細書(甲2)には,「吸着・乾燥剤としては, 二酸化珪素(SiO2)等の吸水性,吸着性を有する無機粉体を採用するの が好ましい。」と記載されている(段落【0020】)から,吸水性,吸着性 を有するシリカ(SiO2。証拠(乙11)及び弁論の全趣旨によれば, 「シリカ」は二酸化ケイ素の通称であると認められる。)の無機粉体は「吸 着・乾燥剤」に当たり得ると解される。
・・・
イ 上記ア の認定事実によれば,剥離紙を除く被告製品に一定量のシリカ が含まれているということができる。 しかし,前記前提事実(3)のとおり,剥離紙を除く被告製品には不織布以 外の層があるところ,上記ア の計量においては,剥離紙を除く被告製品 全体を試料としているから,不織布の表面以外の部分に含まれるシリカが\n検出された可能性を否定することができない。加えて,同 の試験におい ては,被告製品から剥離紙,粘着剤及び粘着剤のついたフィルムを除いた 試料からシリカが検出されることはなかったこと,同 のとおり被告製品 の不織布層の表面において乾燥剤に該当し得ない物体以外のものが検出さ\nれなかったことにも鑑みると,被告製品の不織布の表面にシリカが付着し\nていると認めることはできない。また,被告製品に一定量のシリカ(Si O2)が含まれているとしても,それが吸収性,吸着性を有するものとし て被告製品に存在することを認めるに足りる証拠もない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2017.12.11
平成28(ワ)23604 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成29年11月30日 東京地方裁判所
上記(1)ア及びウの認定事実によれば,被告が原告に依頼したのは食品製造 会社等が商品の包装において使用するデザインであること,そのような包装 デザインについては,原告が被告に提出した後に被告が顧客である食品製造 会社等にデザインを提案するが,その後,顧客が被告に対して修正等の指示 を出すことがあり,その場合,被告は顧客の承諾等を得るまでデザインを修 正し,複数回の修正がされることも多いこと,原告は被告から包装デザイン の依頼を受けるようになる前から,デザイン会社から顧客に包装デザインが 提出された後に顧客の指示によりデザインの修正が必要となることがあるこ とやこうした場合に原告に連絡がなければ,原告以外の者が修正を行うこと になることを認識していたことを認めることができる。また,前記(1) 認定事実によれば,原告が被告に提出したデザインはその後被告が修正する ことができた。そうすると,原告が作成し被告に提出していた包装デザイン については,その提出後に顧客の指示等により修正が必要となることが当然 にあり得るというものであったのであり,かつ,原告は,このことを認識し, また,原告以外の者が上記デザインの修正をすることができることも認識し ていたといえる。他方,原告と被告間で,原告が被告にデザインを提出した 後の顧客の指示等による上記修正について,何らかの話がされたり,合意が されたりしたことを認めるに足りる証拠はない。 そして,前記(1)オの認定事実によれば,原告は,写真の使用権につき意識 していて,一般に著作権に関する権利関係が生じ得ることを理解していたこ とがうかがわれるところ,前記(1)エ,カ〜コの認定事実のとおり,原告は, 原告以外の者によって原告デザインに何らかの改変がされたことを認識して いながら,被告から依頼されて継続的に包装デザインを作成して被告に提出 し,更には被告に対して新たな仕事を依頼し,デザイン料の改定を求めるな どの要求はしたものの,改変について何らの異議を唱えず,又は,被告にお いてデザインを改変したことを明示的に承諾するなどしていた。原告が改変 を承諾していなかったにもかかわらず原告デザインの改変に対して被告に異 議を唱えることができなかった事情やデザインの改変を真意に反して承諾し なければならなかった事情を認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,原告は,被告からの依頼に基づいて作成された原告デザイ ンにつき,被告による使用及び改変を当初から包括的に承諾していたと認め ることが相当である。
(3) これに対し,原告は,1)原告と被告の間で契約書を作成しておらず,注文 書,請求書等においても著作権に関する記載がないこと,2)デザイン料は1 点当たり1万5000円程度であって改変の許諾を前提とするものと考え難 いこと,3)原告はデザイン作成のたびに修正等がある場合は依頼をするよう に伝えていたこと,4)被告が原告の著作権を侵害した包装デザインを見つけ る都度,原告がこれを購入して写真撮影して証拠化していたこと,5)原告が 異議を述べなかったのは,早く納品するため,仕事の依頼を減らされた状況 において原告が被告との関係を悪化させないようにするためという事情によ ることを主張し,また,6)デザインの作成等の仕事を多数依頼することを条 件に承諾していたとの趣旨を供述し(原告本人〔22〜24〕),包括的な改 変の承諾を否定する。 上記1)については,著作権に関する承諾等は必ずしも文書によりされるも のとは限らないから,そうした記載がされた文書がなければ改変の承諾がな いと解することはできない。上記2)については,本件の証拠上,改変を前提 とする場合の通常のデザイン料が明らかでなく,原告の主張する評価を採用 し難い。上記3)については,前記(1)イ及びウの認定事実によれば,原告は, 被告にデザインの原案を提出した段階で修正等があれば連絡するよう伝えて いたものであって,顧客に対する提示案が固まるまでの間に修正等がある場 合にその作業を原告に依頼するよう求めていたにすぎないから,上記提示案 が固まった後の改変についても原告の承諾が必要であったと直ちに認めるこ とはできない。上記4)については,仮にそのとおりであるとしても,前記(1) エの認定事実によれば,原告以外の者による改変を平成25年8月〜9月頃 までに把握したのであるから,原告が改変を問題と考えていたのであれば, その証拠化後に何らかの異議を唱えるのが通常であるというべきであるとこ ろ,前記(1)エ〜コの認定事実のとおり,本件訴訟の提起に至るまで,原告は 改変について何らの異議を唱えていない。上記5)及び6)については,前記(1) エの認定事実によれば,平成25年8〜9月頃から仕事量が激減してその状 況が好転しなかったものであり,また,証拠(乙106の1及び2)によれ ば,遅くとも平成28年1月頃からは仕事量とデザイン料の不均衡を理由に 被告からの依頼を断るようになったと認められ,異議を述べる障害となる事 由が解消ないし軽減したということができるにもかかわらず,原告は,デザ イン料の改定を求めるなど被告に対して書面をもって一定の要求をする一方 で,原告デザインの改変について本件訴訟の提起に至るまで何らの異議も唱 えていない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2017.12.11
平成29(ネ)10038 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記イを踏まえて,構成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を\n移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」を検討\nすると,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とは,タ ッチパネルを含む入力手段から,画面上におけるポインタの座標位置を移動させる 命令(電気信号)を処理手段が受信することである。そして,利用者がマウスにお ける左ボタンや右ボタンを押す操作に対応する電気信号ではなく,マウスにおける 左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動させる操作(ドラッグ操作)に対応 する電気信号を,入力手段から処理手段が受信することを含むものである。また, 本件発明1は,利用者が入力手段を使用してデータ入力を行う際に実行される入力 支援コンピュータプログラムであり,利用者が間違ってマウスの右クリックを押し てしまった場合等に利用者の意に反して画面上に操作コマンドのメニューが表示さ\nれてしまう等の従来技術の課題を踏まえて,システム利用者の入力を支援するため, 利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させる\n手段を提供することを目的とするものである。 そうすると,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」と は,タッチパネルを含む入力手段から,画面上におけるポインタの座標位置を,入 力支援が必要なデータ入力に係る座標位置(例えば,ドラッグ操作を開始する座標 位置)からこれとは異なる座標位置に移動させる操作に対応する電気信号を,処理 手段が受信することを意味すると解するのが相当である。 そして,前記第2の1(3)イのとおり,本件ホームアプリにおいて,控訴人が「操 作メニュー情報」に当たると主張する左右スクロールメニュー表示は,利用者がシ\nョートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであるが,ロ\nングタッチは,ドラッグ操作などとは異なり,画面上におけるポインタの座標位置 を移動させる操作ではないから,入力手段であるタッチパネルからロングタッチに 対応する電気信号を処理手段が受信することは,「入力手段を介してポインタの位置 を移動させる命令を受信する」とはいえない。 したがって,ロングタッチにより左右スクロールメニュー表示が表\示されるとい う本件ホームアプリの構成は,構\成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を 移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」という\n構成を充足するとは認められない。\n
エ 控訴人は,本件ホームアプリでは,タッチパネルに指等が触れると,「ポ インタの座標位置」の値が変化し,「カーソル画像」もこの位置を指し示すように移\n動するところ,ロングタッチは,タッチパネルに指等が触れるといった動作を含む から,被控訴人製品の処理手段はロングタッチにより「『ポインティングデバイスに よって最後に指示された画面上の座標』を移動させる命令」を受信するといえ,本 件ホームアプリは,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」 という構成を有していると主張する。\nしかし,本件ホームアプリにおいて,ロングタッチに含まれるタッチパネルに指 等が触れることに対応して,ポインタの座標位置を,「ポインティングデバイスによ って最後に指示された画面上の座標」位置から,指等がタッチパネルに触れた箇所 の座標位置に移動させることを内容とする電気信号が生じる(甲7の1・2)とし ても,前記ウのとおり,ロングタッチは,画面上におけるポインタの座標位置を移 動させる操作ではないから,上記電気信号は,画面上におけるポインタの座標位置 を移動させる操作に対応する電気信号とはいえない。また,「ポインティングデバイ スによって最後に指示された画面上の座標位置」は,ロングタッチの直前に行って いた別の操作に係るものであり,入力支援が必要なデータ入力に係る座標位置では ないから,上記電気信号は,画面上におけるポインタの座標位置を,入力支援が必 要なデータ入力に係る座標位置からこれとは異なる座標位置に移動させることを内 容とするものでもない。 そうすると,本件ホームアプリのロングタッチ又はこれに含まれるタッチパネル に指等が触れることに対応して,ポインタの座標位置を,「ポインティングデバイス によって最後に指示された画面上の座標」位置から,指等がタッチパネルに触れた 箇所の座標位置に移動させることを内容とする電気信号が生じることをもって,構\n成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信する」とい う構成を充足するとはいえない。\n オ 控訴人は,タッチパネルでは,指等が触れていれば継続的に「ポインタ の位置を移動させる命令」である「ポインタの位置を算出するためのデータ」を受 信し,「ポインタの位置」が一定時間,一定の範囲内に収まっている場合にはロング タッチであると判断されるから,ロングタッチを識別するために入力されるデータ 群には「ポインタの位置を移動させる命令」が含まれると主張する。 しかし,前記第2の1(3)イのとおり,本件ホームアプリは,ロングタッチにより 左右スクロールメニュー表示がされる構\成であるところ,ロングタッチは,継続的 に複数回受信するデータにより算出された「ポインタの位置」が一定の範囲内で移 動している場合だけでなく,当初の「ポインタの位置」から全く移動しない場合を 含むことは明らかであり(甲8),ロングタッチであることを識別するまでの間に「ポ インタの位置」を一定の範囲内で移動させることを内容とする電気信号は,前者に おいては発生しても,後者においては発生しないのであるから,そのような電気信 号をもって,構成要件Eの「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を\n受信する」という構成を充足するとはいえない。\n カ 以上によると,本件ホームアプリが構成要件Eを充足すると認めること\nはできない。
(2) 均等侵害の成否
ア 控訴人は,本件ホームアプリにおける「利用者がタッチパネル上のショ ートカットアイコンを指等でロングタッチする操作を行うことによって操作メニュ ー情報が表示される」という構\成は,「利用者がタッチパネル上の指等の位置を動か して当該ショートカットアイコンを移動させる操作を行うことによって操作メニュ ー情報が表示される」という本件発明1の構\成と均等であると主張する。 そこで検討すると,前記(1)ア及びイによると,本件発明1は,コンピュータシス テムにおけるシステム利用者の入力行為を支援する従来技術である「コンテキスト メニュー」には,マウスの左クリックを行う等するまではずっとメニューが画面に 表示され続けたり,利用者が間違って右クリックを押してしまった場合等は,利用\n者の意に反して画面上に表示されてしまうので不便であるという課題があり,従来\n技術である「ドラッグ&ドロップ」には,例えば,移動させる位置を決めないで徐々 に画面をスクロールさせていくような継続的な動作には適用が困難であるという課 題があったことから,システム利用者の入力を支援するための,コンピュータシス テムにおける簡易かつ便利な入力の手段を提供すること,特に,1)利用者が必要に なった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表示させ,2)必要である間 についてはコマンドのメニューを表示させ続けられる手段の提供を目的とするもの\nである。 そして,本件発明1は,上記課題を解決するために,本件特許の特許請求の範囲 請求項1の構成,すなわち,本件発明1の構\成としたものであるが,特に,上記1) を達成するために,「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことに よる開始動作命令を受信した後…において」(構成要件D),「入力手段を介してポイ\nンタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示\nする」(同E)という構成を採用し,上記2)を達成するために,「利用者によって当 該押されていた命令ボタンが離されたことによる終了動作命令を受信するまで」(同 D),「操作メニュー情報を…出力手段に表示すること」(同E,F)を「行う」(同\nD)という構成を採用した点に特徴を有するものと認められる。\nそうすると,入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すること によってではなく,タッチパネル上のショートカットアイコンをロングタッチする ことによって操作メニュー情報を表示するという,本件ホームアプリの構\成は,本 件発明1と本質的部分において相違すると認められる。
イ 控訴人は,利用者がドラッグ&ドロップ操作を所望している場合に操作 メニュー情報を表示することが本質的部分であると主張する。\nしかし,前記(1)ア及びイのとおり,マウスが指し示している画面上のポインタ位 置に応じた操作コマンドのメニューを画面上に表示すること自体は,本件発明1以\n前から「コンテキストメニュー」という従来技術として知られていたところ,前記 (2)アのとおり,本件発明1は,この「コンテキストメニュー」がマウスを右クリッ クすることにより上記メニューを表示することに伴う課題を解決することをも目的\nとして,利用者が必要になった場合にすぐに操作コマンドのメニューを画面上に表\n示させるために,「入力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによ る開始動作命令を受信した後…において」(構成要件D),「入力手段を介してポイン\nタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示す\nる」(同E)という構成を採用した点に特徴を有するものと認められる。したがって,\n本件発明1において,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部\n分は,利用者がドラッグ&ドロップ操作といった特定のデータ入力を所望している 場合にその入力を支援するための操作メニュー情報を表示すること自体ではなく,\n従来技術として知られていた操作コマンドのメニューを画面に表示することを,「入\n力手段における命令ボタンが利用者によって押されたことによる開始動作命令を受 信した後…において」(構成要件D),「入力手段を介してポインタの位置を移動させ\nる命令を受信する」(同E)ことに基づいて行うことにあるというべきである。 そうすると,入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すること によってではなく,タッチパネル上のショートカットアイコンをロングタッチする ことによって操作メニュー情報を表示するという,本件ホームアプリの構\成は,既 に判示したとおり,本件発明1と本質的部分において相違するというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.12.11
平成27(ワ)23087 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月6日 東京地方裁判所
特許法36条4項1号は,明細書の発明の詳細な説明の記載は「その発明 の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが できる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めると\nころ,この規定にいう「実施」とは,物の発明においては,当該発明にかか る物の生産,使用等をいうものであるから,実施可能要件を満たすためには,\n明細書の発明の詳細な説明の記載は,当業者が当該発明に係る物を生産し, 使用することができる程度のものでなければならない。 そして,医薬の用途発明においては,一般に,物質名,化学構造等が示さ\nれることのみによっては,当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効 量を予測することは困難であり,当該医薬を当該用途に使用することができ\nないから,医薬の用途発明において実施可能要件を満たすためには,明細書\nの発明の詳細な説明は,その医薬を製造することができるだけでなく,出願 時の技術常識に照らして,医薬としての有用性を当業者が理解できるように 記載される必要がある。
(2) 本件の検討
本件についてこれをみるに,本件発明1では,式(I)のRAが−NHC O−(アミド結合)を有する構成(構\成要件B)を有するものであるところ, そのようなRAを有する化合物で本件明細書に記載されているものは,「化 合物C−71」(本件明細書214頁)のみである。そして,本件発明1は インテグラーゼ阻害剤(構成要件H)としてインテグラーゼ阻害活性を有す\nるものとされているところ,「化合物C−71」がインテグラーゼ阻害活性 を有することを示す具体的な薬理データ等は本件明細書に存在しないことに ついては,当事者間に争いがない。 したがって,本件明細書の記載は,医薬としての有用性を当業者が理解で きるように記載されたものではなく,その実施をすることができる程度に明 確かつ十分に記載されたものではないというべきであり,以下に判示すると\nおり,本件出願(平成14年(2002年)8月8日。なお,特許法41条 2項は同法36条を引用していない。)当時の技術常識及び本件明細書の記 載を参酌しても,本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業 者が理解し得たということもできない。
・・・
すなわち,上記各文献からうかがわれる本件優先日当時の技術常識と しては,ある種の化合物(ヒドロキシル化芳香族化合物等)がインテグ ラーゼ阻害活性を示すのは,同化合物がキレーター構造を有しているこ\nとが理由となっている可能性があるという程度の認識にとどまり,具体\n的にどのようなキレーター構造を備えた化合物がインテグラーゼ阻害活\n性を有するのか,また当該化合物がどのように作用してインテグラーゼ 活性が阻害されるのかについての技術常識が存在したと認めるに足りる 証拠はない。
・・・
以上の認定は本件優先日当時の技術常識に係るものであるが,その ほぼ1年後の本件出願時にこれと異なる技術常識が存在したことを認め るに足りる証拠はなく,本件出願当時における技術常識はこれと同様と 認められる。このことに加え,そもそも本件明細書には,本件特許化合 物を含めた本件発明化合物がインテグラーゼの活性部位に存在する二つ の金属イオンに配位結合することによりインテグラーゼ活性を阻害する 2核架橋型3座配位子(2メタルキレーター)タイプの阻害剤であると の記載はないことや,本件特許化合物がキレート構造を有していたとし\nても,本件出願当時インテグラーゼ阻害活性を有するとされていたヒド ロキシル化芳香族化合物等とは異なる化合物であることなどに照らすと, 本件明細書に接した当業者が,本件明細書に開示された種々の本件発明 化合物が,背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した2核架橋\n型3座配位子構造(2メタルキレーター構\造)と末端に環構造を有する\n置換基とを特徴として,インテグラーゼの活性中心に存在する二つの金 属イオンに配位結合する化合物であると認識したと認めることはできな い。 以上によれば,本件出願当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌して も,本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業者が理解し得 たということもできない。 したがって,本件明細書の記載は本件発明1を当業者が実施できる程度に 明確かつ十分に記載したものではなく,本件発明1に係る特許は特許法36\n条4項1号の規定に違反してされたものであるので,本件発明1に係る特許 は特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきも のである。
3 争点(1)イ(イ)(サポート要件違反)について
上記2で説示したところに照らせば,本件明細書の発明の詳細な説明に本件 発明1が記載されているとはいえず,本件発明1に係る特許は特許法36条6 項1号の規定に違反してされたものというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.12. 8
平成28(行ケ)10279 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月30日 知的財産高等裁判所
1 平成23年改正前特許法30条4項は,同条1項の適用を受けるための手続 的要件として,1)特許出願と同時に,同条1項の適用を受けようとする旨を記載し た書面(4項書面)を特許庁長官に提出するとともに,2)特許出願の日から30日 以内に,特許法29条1項各号の一に該当するに至った発明が平成23年改正前特 許法30条1項の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(4項 証明書)を特許庁長官に提出すべきことを定めているが,同条4項には,その適用 対象となる「特許出願」について,特定の種類の特許出願をその適用対象から除外 するなどの格別の定めはない。 また,平成16年改正前特許法41条に基づく優先権主張を伴う特許出願(以下, 「国内優先権主張出願」という。)は,同条2項に「前項の規定による優先権の主張 を伴う特許出願」と規定されるとおり,基礎出願とは別個独立の特許出願であるこ とが明らかである。 そうすると,国内優先権主張出願について,平成23年改正前特許法30条4項 の適用を除外するか,同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定 がない限り,国内優先権主張出願に係る発明について同条1項の適用を受けるため には,同条4項所定の手続的要件として,所定期間内に4項書面及び4項証明書を 提出することが必要である。
2 そこで,国内優先権主張出願について,平成23年改正前特許法30条4項 の適用を除外するか,同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定 があるかどうかについて検討すると,まず,分割出願については,平成18年改正 前特許法44条4項が原出願について提出された4項書面及び4項証明書は分割出 願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす旨を定めているが,国内優先権主 張出願については,これに相当する規定はない。 また,平成16年改正前特許法41条2項は,国内優先権主張出願に係る発明の うち基礎出願の当初明細書等に記載された発明についての平成23年改正前特許法 30条1項の適用については,国内優先権主張出願に係る出願は基礎出願の時にさ れたものとみなす旨を定めているが,これは,同項が適用される場合には,同項中 の「その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願」にいう「特許 出願」については,国内優先権主張出願の出願日ではなく,基礎出願の出願日を基 準とする旨を規定するに止まるものである。平成16年改正前特許法41条2項の 文理に照らし,同項を根拠として,基礎出願において平成23年改正前特許法30 条4項所定の手続を履践している場合には,国内優先権主張出願において同項所定 の手続を履践したか否かにかかわらず,基礎出願の当初明細書等に記載された発明 については同条1項が適用されると解釈することはできない。 特許法のその他の規定を検討しても,国内優先権主張出願について,平成23年 改正前特許法30条4項の適用を除外するか,同項所定の手続的要件を履践するこ とを免除する格別の規定は,見当たらない。
3 平成16年改正前特許法41条2項は,基本的にパリ条約による優先権の主 張の効果(パリ条約4条B)と同等の効果を生じさせる趣旨で定められたものであ り,国内優先権主張出願に係る発明のうち基礎出願の当初明細書等に記載された発 明について,その発明に関する特許要件(先後願,新規性,進歩性等)の判断の時 点については国内優先権主張出願の時ではなく基礎出願の時にされたものとして扱 うことにより,基礎出願の日と国内優先権主張出願の日の間にされた他人の出願等 を排除し,あるいはその間に公知となった情報によっては特許性を失わないという 優先的な取扱いを出願人に認めたものである(甲19)。 そして,平成16年改正前特許法41条2項が,国内優先権主張出願に係る発明 のうち,基礎出願の当初明細書等に記載された発明の平成23年改正前特許法30 条1項の規定の適用については,上記国内優先権主張出願は,上記基礎出願の時に されたものとみなす旨を規定していることは,上記趣旨(国内優先権主張出願が, 基礎出願の日から国内優先権主張出願の日までにされた他人の出願等やその間に公 知となった情報によって不利な取扱いを受けないものとすること)を超えるものと いえるが,その趣旨は,同条1項が「第29条第1項各号の一に該当するに至った 発明は,その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明 についての同条第1項及び第2項の規定の適用については,」と規定して,特許出願 の日を基準として新規性喪失の例外の範囲を定めていることから,国内優先権主張 出願の日を基準としたのでは,上記趣旨により基礎出願の日を基準とすることにな る新規性の判断に対する例外として認められる範囲が通常の出願に比べて極めて限 定されるという不都合が生じることに鑑み,国内優先権主張出願の日ではなく基礎 出願の日を基準とすることを定めたものと解するのが相当である。 そうすると,平成16年改正前特許法41条2項が平成23年改正前特許法30 条1項の適用について規定していることは,その趣旨に照らしても,上記規定が適 用された場合には,国内優先権主張出願の日ではなく基礎出願の日を基準とする旨 を規定するに止まり,これをもって,同条1項の適用について,基礎出願の当初明 細書等に記載された発明については,基礎出願において手続的要件を具備していれ ば,国内優先権主張出願において改めて手続的要件を具備しなくても,上記規定の 適用が受けられるとすることはできない。
4 以上によると,国内優先権主張出願に係る発明(基礎出願の当初明細書等に 記載された発明を含む。)について,平成23年改正前特許法30条1項の適用を受 けるためには,同条4項所定の手続的要件として,所定期間内に4項書面及び4項 証明書を提出することが必要であり,基礎出願において提出した4項書面及び4項 証明書を提出したことをもって,これに代えることはできないというべきである。
5 本願は,出願Aの分割出願である本願の原出願をさらに分割出願したもので あるところ,分割出願については,原出願について提出された4項書面及び4項証 明書は分割出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす旨の定めがあるが, 原告は,出願Aにおいて,その出願と同時に,4項書面を特許庁長官に提出しなか ったのであるから,本願は,平成23年改正前特許法30条1項の適用を受けるこ とはできない。 そして,同条1項が適用されないときには,審決の刊行物A発明の認定並びに本 願発明との一致点及び相違点の認定及び判断に争いはないから,本願発明は,刊行 物A発明であるか,同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの である。 そうすると,本願は,その余の請求項について検討するまでもなく拒絶すべきも のであるから,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
6 これに対して,原告は,国内優先権制度における優先権の発生時期は,パリ 条約4条Bに規定される優先権の発生時期から類推して,先の出願がされた時であ る,基礎出願において平成23年改正前特許法30条4項所定の手続をした場合の 国内優先権主張出願については,国内優先権の本質からみて,基礎出願の当初明細 書等に記載された発明について優先権が発生し,平成16年改正前特許法41条4 項の手続をすることにより,上記発明に係る特許法29条,平成23年改正前特許 法30条1項〜3項等の適用については基礎出願の時にされたものとみなされる効 果が発生するが,新規性・進歩性についての規定(特許法29条)の適用に係る前 記効果については,基礎出願において平成23年改正前特許法30条4項所定の手 続をしている場合には,新規性喪失の例外規定(同法30条1項〜3項)に係る前 記効果についても発生しているから,この効果をも含む上記発明の新規性について の優先権の主張の効果が発生するというべきであるなどと主張する。 しかし,平成16年改正前特許法41条1項の「優先権」(国内優先権)の主張の 効果は,同条2項に規定されたものであり,パリ条約の規定を類推することによっ て定まると解することはできない。 また,既に判示した平成16年改正前特許法41条2項の文言及び同項の趣旨に 照らすと,同項は,国内優先権主張出願に係る発明のうち,基礎出願の当初明細書 等に記載された発明について,特許法29条を適用する際には,同条中の「特許出 願前に」にいう「特許出願」は基礎出願時にされたものとみなし,平成23年改正 前特許法30条1項を適用する際には,同項中の「その該当するに至った日から6 月以内にその者がした出願」にいう「特許出願」は基礎出願時にされたものとみな すことを規定するものであり,新規性喪失の例外規定(同法30条1項)と新規性・ 進歩性についての規定(同法29条)とを一体として取り扱うべきことは,平成1 6年改正前特許法41条2項の文理上はもとより,その趣旨からも導くことはでき ない。
7 原告は,平成16年改正前特許法41条には,同条2項に列挙される各条項 が適用されるための手続として,平成23年改正前特許法30条4項のような手続 は規定されていないから,そのような手続は不要であり,例えば,特許法29条の 適用について基礎出願の時にされたものとみなされるための手続として,平成16 年改正前特許法41条4項の手続をすれば十分であるなどと主張する。\nしかし,国内優先権主張の効果である平成16年改正前特許法41条2項が,基 礎出願において平成23年改正前特許法30条4項所定の手続を履践している場合 には,国内優先権主張出願において同項所定の手続を履践したか否かにかかわらず, 同条1項が適用されることを定めるものではないことは,前記2,3のとおりであ る。平成16年改正前特許法41条4項に平成23年改正前特許法30条4項のよ うな手続が定められていないからといって,国内優先権主張出願に係る発明のうち 基礎出願の当初明細書等に記載された発明について,平成23年改正前特許法30 条1項が適用される手続的要件として,国内優先権主張出願において同条4項所定 の手続を履践することを不要とする理由にはならない。 また,特許法29条の適用には格別の手続的要件はないから,平成23年改正前 特許法30条4項所定の手続の履践を手続的要件とする同条1項の適用と同列に論 じることはできない。
8 原告は,平成23年改正前特許法30条4項が,基礎出願の際に既に同項所 定の手続を履践した国内優先権主張出願に際し,同主張出願における平成16年改 正前特許法41条2項に規定の発明について同項で列挙された所定の条項の規定の 適用につき,改めてその手続を履践させるための規定でもあるとすると,それは単 なる重複手続のための規定であって,法がそのようなことを求めていると解するこ とはできないなどと主張する。 しかし,平成23年改正前特許法30条4項がその対象となる「特許出願」から, 基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先権主張出願において,基 礎出願の当初明細書等に記載された発明について同条1項の適用を求める場合の当 該国内優先権主張出願を除外していると解することができないことは,前記1〜4 のとおりであって,原告の主張は,法令上の根拠がなく,理由がない。
9 原告は,平成23年改正前特許法30条4項は,国内優先権主張を伴わない 通常の出願,あるいは,国内優先権主張出願であって,基礎出願において同条1項 又は3項の新規性喪失の例外適用を求めた発明以外の発明について,同条1項又は 3項の適用を求めようとする場合に適用されるものであり,基礎出願において同条 4項所定の手続により同条1項又は3項の適用を求めた発明について優先権を主張 する出願には,適用されないと主張する。 しかし,同条4項が,基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先 権主張出願について,その対象となる「特許出願」から除外しているとは解釈でき ないことは,前記1〜4のとおりであって,原告の主張は,理由がない。
10 原告は,平成23年改正前特許法施行規則31条1項は,基礎出願におい て平成23年改正前特許法30条1項又は3項の新規性喪失の例外適用を求めた発 明以外の発明について,同条1項又は3項の適用を求める出願に適用される規定で あると主張する。 しかし,同条4項が,基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先 権主張出願について,その対象となる「特許出願」から除外しているとは解釈でき ないことは,前記1〜4のとおりであるから,平成23年改正前特許法施行規則3 1条1項を原告が主張するように解することはできず,原告の主張は,理由がない。
11 原告は,基礎出願において新規性喪失の例外規定が適用された発明に基づ いて国内優先権を主張する場合,出願人が敢えて,国内優先権主張出願では上記発 明について新規性喪失の例外規定の適用を受けないことは通常考えにくいから,国 内優先権主張出願の際に改めて新規性喪失の例外適用申請の意思を確認する必要は\nないし,また,国内優先権主張出願の願書には必ず基礎出願の番号を記載している ことなどの事情から,出願人にとっても第三者にとっても,国内優先権主張出願に おいて新規性喪失の例外適用のための書面等を再度提出する必要性は何ら存在しな いなどと主張する。 しかし,基礎出願において平成23年改正前特許法30条4項所定の手続を履践 している国内優先権主張出願において,基礎出願の当初明細書等に記載された発明 について同条1項又は3項の適用を求める場合の同条4項所定の手続の履践の必要 性について,仮に原告主張のような見方が成り立つとしても,立法論としてはとも かく,同項の解釈として,同項がその対象となる「特許出願」から,基礎出願にお いて同項所定の手続を履践している国内優先権主張出願を除外していると解するこ とは,法令上の根拠がなく,できないことは,前記1〜4のとおりである。
12 原告は,平成11年法律第41号による特許法の改正において,平成11 年改正前特許法44条の分割出願制度については,手続簡素化のための規定が新た に検討され,同条4項が新設されたが,国内優先権制度については,出願人の手続 の簡素化を図る趣旨は同様にあてはまるはずであるにもかかわらず,手続規定の見 直しも,手続簡素化のための新たな規定の導入などの検討もされなかったという事 実は,国内優先権制度については,法改正をするまでもなく,既に手続が簡略化さ れた規定となっていることの証左であると主張する。 しかし,平成23年改正前特許法30条4項が,基礎出願において同項所定の手 続を履践している国内優先権主張出願について,その対象となる「特許出願」から 除外しているとは解釈できないことは,前記1〜4のとおりであって,そのことは, 平成11年改正において国内優先権制度について改正がされなかったとの原告上記 主張事実により左右されるものではない。
13 原告は,国内優先権主張出願に係る発明のうち,基礎出願において平成2 3年改正前特許法30条4項所定の手続を履践することにより同条1項の適用を受 けた発明について,国内優先権主張出願において同項の適用を受けるために同条4 項の手続を求めている特許庁の運用は違法であると主張する。 しかし,特許庁の上記運用が違法でないことは,既に説示したところから明らか である。
14 原告は,平成16年改正前特許法41条2項が平成23年改正前特許法3 0条4項を対象としていない趣旨は,平成18年改正前特許法44条2項が平成2 3年改正前特許法30条4項を適用除外している趣旨とは異なるなどと主張する。 しかし,同項が,基礎出願において同項所定の手続を履践している国内優先権主 張出願について,その対象となる「特許出願」から除外しているとは解釈できない ことは,前記1〜4のとおりであって,平成16年改正前特許法41条2項が平成 23年改正前特許法30条4項を対象としていない趣旨により左右されるものでは ない。
15 原告は,被告が国内優先権主張出願において,新たな事項を追加すること が想定されること,出願後に通常出願に戻り得ることが,なぜ平成11年法律第4 1号により導入された分割出願に係る手続の簡素化を,国内優先権主張出願にも導 入することを困難にするのかについての理由は,不明であるなどと主張する。 しかし,平成23年改正前特許法30条4項が,基礎出願において同項所定の手 続を履践している国内優先権主張出願について,その対象となる「特許出願」から 除外しているとは解釈できないことは,前記1〜4のとおりであって,平成11年 法律第41号により導入された分割出願に係る手続の簡素化の趣旨が国内優先権主 張出願に妥当するかどうかによって上記解釈が左右されるものではない。
16 原告は,第三者は,基礎出願において新規性喪失の例外規定が適用された 発明について,国内優先権主張出願において敢えてその適用を受けないことなど予\n測する必要はないから,その適用の有無は基礎出願において表示されていれば十\分 であり,国内優先権主張出願においてその表示がないことによる不測の不利益は生\nじないなどと主張する。 しかし,平成23年改正前特許法30条4項が,基礎出願において同項所定の手 続を履践している国内優先権主張出願について,その対象となる「特許出願」から 除外しているとは解釈できないことは,前記1〜4のとおりであって,仮に第三者 に不測の不利益を与えることがないとしても,それによって上記解釈が左右される ものではない。
2017.12. 8
平成28(行ケ)10078 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月30日 知的財産高等裁判所
(1) 新規事項追加禁止要件違反について
ア 前記1(1)のとおり,本件補正前の請求項6の命令スレッドのタイプは, いずれも,単に「タイプ」と記載されており,「(S,C)」の記号を伴わないもので あったところ,前記第2の1のとおり,原告は,平成26年8月26日付けで,甲 1発明等を引用例とする進歩性の欠如を理由とする拒絶査定を受けた(甲7,10) 後,本件補正をした。
イ 本件補正後の請求項6の,「(S,C)」は,それ自体のみからその技術的 な意義を読み取れず,また,本件補正後の請求項6の記載中に,その技術的な意義 を明確にする定義等の記載は見当たらない。 本件補正後の請求項6の従属項である同請求項7〜10にも,本件補正後の請求 項6の「(S,C)」の技術的な意義を明確にする記載はない。
ウ(ア) 当初明細書等には,命令スレッドのタイプについては,二つ以上ある こと(【0013】,【0014】,【0017】,【0020】),【0039】,【0042】,【0046】),三つ以上ある場合もあること(【0062】)が記載されており,命令スレッドのタイプが第1のタイプと第2のタイプである場合において,命令スレットの第1のタイプが計算タイプであり,第2のタイプがサービスタイプである 場合があることが記載されている(【0039】,【0042】,【0043】,【0044】,【0046】,【0047】,【0050】)。 また,当初明細書等には,命令スレッドのタイプは,1)アプリケーションプログ ラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパラメータ(計算タイプ:H TCALCUL,サービスタイプ:HT_SERVICE)に基づく場合(【002 1】,【0042】,【0050】),2)プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ(CALCUL,SERVICE)に基づく場合(【0022】,【004 3】,【0050】),3)命令スレッドの起動元のアプリケーションを自動的に認識す ることによって決定される場合(【0045】)があることが記載されている。 さらに,命令スレッドと仮想プロセッサの関係については,仮想プロセッサのタ イプは,パラメータC及びパラメータSによって識別され,パラメータCは計算タ イプに,パラメータSはサービスタイプに関連付けられ,仮想プロセッサ24C及 び26Cは計算タイプであり,仮想プロセッサ24S及び26Sはサービスタイプ である場合(【0046】〜【0048】)があることが記載されている。
(イ) 以上によると,当初明細書等においては,「S」及び「C」は,仮想プ ロセッサのタイプとして記載されていること,命令スレッドのタイプとしては,「計 算タイプ」及び「サービスタイプ」という文言が用いられていることが認められる。 しかし,前記(ア)のとおり,仮想プロセッサのタイプは,パラメータC及びパラメ ータSによって識別され,パラメータCは計算タイプに,パラメータSはサービス タイプに関連付けられ,仮想プロセッサの24C及び26Cは「計算タイプ」,同2 4S及び26Sは「サービスタイプ」とされている。また,命令スレッドのタイプ がアプリケーションプログラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパ ラメータ(計算タイプ:HTCALCUL,サービスタイプ:HT_SERVIC E)や,プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ(CALCUL, SERVICE)に基づく場合があることが記載されているところ,C が計算(c alculation),Sがサービス(service)の頭文字に由来すること も明らかである。
エ そうすると,当初明細書等の記載を考慮して,特許請求の範囲に記載さ れた用語の意義を解釈すると,本件補正後の請求項6〜8で命令スレッドのタイプ とされている記載「タイプ(S,C)」は,「サービスタイプ」,「計算タイプ」の意 味であると解することができる。
オ 以上によると,本件補正は,本件補正前の請求項6において,命令スレ ッドの「タイプ」は,どのような種類のタイプが存在するのかについて,記載がな かったのを,「タイプ(S,C)」とし,当初明細書等に記載されていた「タイプ(サ ービスタイプ,計算タイプ)」としたものであり,当初明細書等に記載された事項の 範囲内を超えるものではない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2017.12. 7
平成29(ネ)10066 特許権侵害行為の差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 第1要件について
(ア) 控訴人は,本件発明1の本質的部分は,本件各作用効果を奏する上で重要 な部分であるピンの前方部が後方部から斜め前方向に方向づけられ,第2壁面の前 方部に向かって延在している点にあるところ,ピンの前方部7aが第2壁面9の前 方部9aに接触することの有無は,本件各作用効果を奏するための必須の構成では\nないから,ピンの前方部7aが第2壁面9の前方部9aに接触している否かという, 本件発明1と被告製品の相違点は,本件発明1の本質的部分ではなく,被告製品は 均等の第1要件を充足する旨主張する。
(イ) 特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載 のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解\nすべきであり,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明の課題及び 解決手段とその効果を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従 来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定す\nることによって認定されるべきである。 ・・・のとおり,本件発明1は,従来の固定手段では, ピンが作動可能位置から移動してしまうことで側面開口部を通る出口を見つけられ\nずにスリーブ内部で変形する危険性や,周囲の骨物質に移動するピンの前端部の部 分が有利に曲がった状態へ変形しない危険性があったことを従来技術における課題 とし,これを解決することを目的として,特許請求の範囲請求項1記載の構成,具\n体的には,ピン7の前方部7aが,ピンの後方部7eから第2壁面9に向かって斜 め前方向に延びて湾曲前端部7fに至り,案内面12に近接する第2壁面9の前方 部9aに至るようにすることを定めており,この点は,従来技術には見られない特 有の技術的思想を有する本件発明1の特徴的部分であるといえる。
(エ) 被告製品は,前記2(2)のとおり,構成要件Fの「(前方部(7a)は,)\nピンの後方部(7e)から斜め前方向に方向づけられて前記湾曲前端部(7f)に 至り,前記案内面(12)に近接する前記第2壁面(9)の前方部(9a)まで延 在する」との文言を充足しないから,本件発明1とは,その本質的部分において相 違するものであり,均等の第1要件を充足しない。
(オ) 控訴人の主張について
控訴人は,本件発明1の本質的部分は,本件各作用効果を奏する上で重要な部分 であるピン7の前方部7aが後方部7eから斜め前方向に方向づけられ,第2壁面 9の前方部9aに向かって延在している点にあり,ピン7の前方部7aの第2壁面 9の前方部9aへの接触の有無は本件各作用効果を奏するための必須の構成ではな\nく,上記相違点は本件発明1の本質的部分ではないと主張する。 しかし,本件発明1において,本件各作用効果を奏するのは,ピン7の前方部7 aが,ピンの後方部7eから第2壁面9に向かって斜め前方向に延びて湾曲前端部 7fに至り,案内面12に近接する第2壁面9の前方部9aに至ることで,ピン7 の前方部7aと第2壁面9との間の遊びがなくなり,ピン7の第2壁面に向かう方 向の移動が抑制されることによるものであり,ピン7の前方部7aが前方部9aの 付近に位置しているだけでは,本件各作用効果を奏するものとは認められないこと については,前記2(1)イ(イ)のとおりである。よって,ピン7の前方部7aが第2 壁面9の前方部9aに接触していることは,本件発明1の本質的部分であると解さ れる。したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2017.12. 6
平成28(ワ)7649 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月21日 大阪地方裁判所
「裾絞り部」の形状については,構成要件Gで特定されているとおり「底部に近\nづくに連れて先細りとなる」ものであり,本件明細書において,「裾絞り部」につ き,「垂直に延在するのではなく,裾絞り状に傾斜している」(【0015】)と 説明されている上,構成要件G及びHを含まない出願当初の特許請求の範囲の請求\n項 1 を削除した上記(2)認定の本件特許の出願経過に照らしても,裾絞り部は,それ が直線であっても,曲線であっても,少なくとも,垂直の部分を含むことなく,蛇 腹部から底部にかけて,徐々に先細りになっていくものに限定されていると解され る。
(5) まとめ
したがって,構成要件Gにいう「裾絞り部」とは,胴部において「蛇腹部」と「底\n部」の間にあって,それぞれに接続部で連続して存在するものであり,また「蛇腹 部」との接続部において「垂直に延在」する部分があっても許容されるが,それは 極く限られた幅のものにすぎないのであり,またその形状は,「蛇腹部」方向から 「底部」方向に向けて,徐々に先細りになっているものということになる。
(6) 以上の「裾絞り部」の解釈を踏まえ,被告容器が裾絞り部を備え,構成要件\nGを充足しているかを検討する。
ア 原告は,別紙「被告容器の構成(原告の主張)」記載の図面で「湾曲部」と\n指示した部分が「裾絞り部」に相当し,同部分の存在により構成要件Gを充足する\nと主張し,併せて,その上部にある垂直部分は,本件明細書の【0015】にいう 「接続部」にすぎないとしている。 しかしながら,上記検討したとおり,「裾絞り部」は,「蛇腹部」から接続部で 連続しているものであるが,この接続部は,極く限られた幅の範囲であるべきであ って,上記図面に明らかなように,被告容器における原告主張に係る「裾絞り部」 に相当する湾曲部と蛇腹部の間に存する,湾曲部と高さ方向の幅がほぼ一緒である 垂直に延在する部分をもって「接続部」にすぎないということはできない。 したがって,被告容器は,上記定義した「裾絞り部」で構成されるべき「蛇腹部」\nから「底部」にかけて胴部の大半が,「裾絞り部」に該当しない部分で構成されて\nいるということになるから,被告容器は,「裾絞り部」を備えているものというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2017.12. 6
平成28(行ケ)10222 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月29日 知的財産高等裁判所(3部)
前記(2(1)〜(3))のとおり,本件各発明は,焼鈍分離剤用の酸化マグネ シウム及び方向性電磁鋼板に関するものであるところ,方向性電磁鋼板の磁 気特性及び絶縁特性,並びに市場価値は,脱炭焼鈍により鋼板表面に SiO2被 膜を形成し,その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗\n布して乾燥させ,コイル状に巻き取った後に仕上げ焼鈍することにより, SiO2 と MgO が反応して形成されるフォルステライト(MgSiO4)被膜の性能,\n具体的には,その生成しやすさ(フォルステライト被膜生成率),被膜の外 観及びその密着性並びに未反応酸化マグネシウムの酸除去性の4点に左右さ れるものであり,このフォルステライト被膜の性能は,これを形成する焼鈍\n分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存するものということができる。\nそこで,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及びこれに含有される微量成分 についての研究が行われ,複数の物性値を制御し,フォルステライト被膜の 形成促進効果を一定化させ,かつフォルステライト被膜の品質を改善する試 みが多く行われてきたが,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに課せられた要求 を完全に満たす結果は得られていない。 このような状況の下,本件各発明は,磁気特性及び絶縁特性,更にフォ ルステライト被膜生成率,被膜の外観及びその密着性並びに未反応酸化マグ ネシウムの酸除去性に優れたフォルステライト被膜を形成でき,かつ性能が\n一定な酸化マグネシウム焼鈍分離剤を提供すること,更に本件各発明の方向 性電磁鋼板用焼鈍分離剤を用いて得られる方向性電磁鋼板を提供することを 目的としたものである。
(3) 検討
ア 本件各発明は,上記のとおり,方向性電磁鋼板に適用される焼鈍分離剤 用酸化マグネシウム粉末粒子を提供するものであるところ,本件課題を 解決するための手段として,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム中に含まれ る微量元素の量を,Ca,P 及び B の成分の量で定義し,更に Ca,Si,P 及 び S のモル含有比率により定義して(前記2(4)イ),本件特許の特許請求 の範囲請求項1に記載された本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲 内に制御するものである。 そして,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される上記各微量元素 の量を本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲内に制御することによ り,本件課題を解決し得ることは,本件明細書記載の実施例(1〜19) 及び比較例(1〜17)の実験データ(前記2(5)〜(11))により裏付けら れているということができる。 そうすると,当業者であれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載 に基づき,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいて,本件特許の特許請 求の範囲請求項1に記載のとおり Ca,P,B,Si 及び S の含有量等を制御 することによって本件課題を解決できると認識し得るものということが できる。
・・・
これらの記載によれば,焼 鈍分離剤用酸化マグネシウムの CAA とサブスケールの活性度とのバラ ンスが取れていない場合,フォルステライト被膜は良好に形成されない こととなるのは事実であるといえる。
(イ) しかし,本件明細書の発明の詳細な説明の記載から把握し得る発明 は,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される Ca,Si,B,P,S の含 有量に注目し,それらの含有量を増減させて実験(実施例1〜19及 び比較例1〜17)を行うことにより,最適範囲を本件特許の特許請 求の範囲請求項1に規定されるもの(本件微量成分含有量及び本件モ ル比)に定めたというものである。その理論的根拠は,Ca,Si,B,P 及び S の含有量を所定の数値範囲内とすることにより,ホウ素が MgO に侵入可能な条件を整えたことにあると理解される(本件明細書の\n【0016】。前記2(4)カ)。
他方,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を見ても,CAA 値を調 整することにより本件課題の解決を図る発明を読み取ることはできない。 むしろ,これらの記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明中に CAA 値に関する記載があるのは,第1の系統及び第2の系統それぞれ において,実施例及び比較例に係る実験条件が CAA 値の点で同一であ ることを示すためであって,フォルステライト被膜を良好にするために CAA 値をコントロールしたものではないことが理解される。 そして,CAA の調整は,最終焼成工程の焼成条件により可能である\n(特開平9−71811号公報(甲7)「この発明の MgO では40% クエン酸活性度を30〜90秒の範囲とする。…かかる水和量,活性度 のコントロールは最終焼成の焼成時間を調整することにより行う。」 (【0026】)との記載参照。)から,焼鈍分離剤用酸化マグネシウ ムにおいて,本件微量成分含有量及び本件モル比のとおりに Ca,P,B, Si 及び S の含有量等を制御し,かつ,焼成条件を調整することによって, 本件各発明の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいても,実施例におけ る110〜140秒以外の CAA 値を取り得ることは,技術常識から明 らかといってよい。 したがって,本件審決は,本件各発明の課題が解決されているのは CAA40%が前記数値の範囲内にされた場合でしかないと判断した点に おいて,その前提に誤りがある。
(ウ) そもそも,本件明細書によれば,本件特許の出願当時,焼鈍分離剤 用酸化マグネシウムについては,被膜不良の発生を完全には防止でき ていないことなど,十分な性能\を有するものはいまだ見出されておら ず,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分について 研究が行われ,制御が検討されている微量成分として CaO,B,SO3,F, Cl等が挙げられ,また,微量成分の含有量だけでなく,微量成分元素を 含む化合物の構造を検討する試みも行われていたことがうかがわれる\n(前記2(2))。
・・・・
そうすると,本件特許の出願当時,フォルステライト被膜の性能改善\nという課題の解決を図るに当たり,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含 有される微量元素の含有量に着目することと,CAA 値に着目すること とが考えられるところ,当業者にとって,いずれか一方を選択すること も,両者を重畳的に選択することも可能であったと見るのが相当である\n(なお,微量元素の含有量に着目する発明にあっても,焼鈍分離剤用酸 化マグネシウムの CAA 値とサブスケールの活性度とのバランスが取れ ていない場合には,その実施に支障が生じる可能性があることは前示の\nとおりであるが,この点の調整は,甲1,5〜7,67,乙4等によっ て認められる技術常識に基づいて,当業者が十分に行うことができるも\nのと認められる。)。
(エ) 以上を総合的に考慮すると,当業者であれば,本件明細書の発明の 詳細な説明には,本件微量成分含有量及び本件モル比を有する焼鈍分 離剤用酸化マグネシウムにより本件課題を解決し得る旨が開示されて いるものと理解し得ると見るのが相当である。
ウ 以上によれば,CAA 値について何ら特定がない酸化マグネシウムにお いて,本件微量成分含有量及び本件モル比のみの特定をもってしては, 直ちに本件課題を解決し得るとは認められないとした本件審決には誤り があるというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 要旨認定
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2017.12. 5
平成28(行ケ)10225 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月29日 知的財産高等裁判所
前記(2)イのとおり,乙1,乙2及び甲1の各記載から,ジヨード化合物 と固体硫黄と,更に「重合停止剤」とを含む混合物を溶融重合させること によって製造されるPAS樹脂について,ヨウ素含有量が1,200pp m以下のものが得られること,上記のいずれの例においても重合禁止剤(重 合停止剤)が添加されていることが理解でき,このような,ヨウ素含有量 が少ないPAS樹脂を製造することができること自体は,優先日において 周知の技術的事項であったといえる。 しかしながら,上記各文献からは,このような,1,200ppm以下 の低ヨウ素量のPAS樹脂を製造するために必要な条件,すなわち,重合 時の温度や圧力,重合時間等は必ずしも明らかでない。また,前記(2)ウの 技術常識からは,重合禁止剤の種類や添加の割合のみならず,添加の時期 (タイミング)によっても,得られる樹脂の重合度や不純物としてのヨウ 素含有量が異なることが予測されるところ,それらとの関係についても一\n切明らかにされていない。してみると,これらの各文献に記載された事項 から,直ちに先願明細書(甲5)にヨウ素含有量が1,200ppm以下 であるPAS樹脂組成物が記載されているとの結論を導くことはできない というべきである。 この点,被告は,1)先願明細書発明Bも本件発明4と同様の目的・問題 意識の下で,ジヨード芳香族化合物と硫黄元素とを含む反応物を溶融重合 する方法を改良するものであり,重合禁止剤を添加してポリマー鎖末端の ヨウ素量を減じることで低ヨウ素含有量を達成していること,2)重合禁止 剤の添加時期はヨウ素含有量と無関係であること(本件発明4において特 定されているヨウ素含有量の範囲が,重合開始直後から重合禁止剤を添加 する製造方法により得られるとの原告主張は誤りであること),3)先願明 細書発明Bでは,重合禁止剤(実施例においては,4−ヨード安息香酸, 2,2’−ジチオビス安息香酸など)に加えて,(重合鎖の成長を止める という点において重合禁止剤と同じ機能を有する)重合中止剤(ベンゾチ\nアゾール類など。実施例においては,2,2’−ジチオビスベンゾトリア ゾール。ただし,被告は,「2,2’−ジチオビスベンゾチアゾール」の 誤記であると主張する。)を併用したことによってヨウ素量がより減少し ていると考えられること等を挙げて,先願明細書発明Bに係るPAS樹脂 のヨウ素含有量は,本件発明4と同程度に少ないものであると主張する。 しかしながら,上記1)については,例えば,上記各文献(乙1,乙2及 び甲1)から,ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を溶融重合 するPAS樹脂の製造方法において,重合禁止剤を添加することのみによ って必ず相違点1に係る低ヨウ素含有量を実現できることが導き出せると はいえず,ほかにこれを認めるに足る証拠もない。したがって,先願明細 書発明Bと本件発明4は,必ずしも,同じ方法で,同じ程度に低ヨウ素含 有量を実現しているとはいえず,その前提自体に誤りがある。 上記2)についても,被告自身,「本件明細書の記載からは,本件発明4 のヨウ素含有量が得られるのは,重合禁止剤の添加時期によらないと理解 される」と述べているように,飽くまで,本件明細書の記載からは関係が 読み取れないというだけで,およそ重合禁止剤の添加時期がヨウ素含有量 に影響を与えないことについての主張立証まではなされていない。むしろ, 前記のとおり,技術常識を踏まえると,重合禁止剤の種類や添加の割合の みならず,添加の時期(タイミング)によっても,得られる樹脂の重合度 や不純物としてのヨウ素含有量が異なることが予測されるのであって,こ\nれによれば,重合禁止剤の添加時期と本件発明4のヨウ素含有量が無関係 であるとは,直ちに断定できない(本件発明の製造方法で起こる化合物等 の反応工程として原告が説明する工程が本件明細書に記載されている反応 工程とは異なるとの被告の主張も,この点を左右するものではない。)。 上記3)についても,被告の主張は,本件明細書の実施例1ないし4で重 合禁止剤(4,4’−ジチオビス安息香酸)の使用量(添加量)が増えれ ばPAS樹脂中の残留ヨウ素量が減るとの関係があることを前提とするも のであると解されるが,先願明細書発明Bと本件明細書の実施例とでは, (重合禁止剤に関する誤記の点は措くとしても)少なくとも重合禁止剤の 添加時期が異なることから,先願明細書発明Bにおいても重合禁止剤の添 加量とヨウ素含有量との間に(本件発明4におけるそれと)同様の関係が 導き出せるとは限らない。 結局のところ,先願明細書発明Bに記載されたPAS樹脂のヨウ素含有 量を具体的に推測できるだけの根拠は,先願明細書の記載や本件特許の出 願時における技術常識を参酌しても導き出すことができず,ほかに先願明 細書発明Bに係るPAS樹脂のヨウ素含有量が本件発明4と同程度に少な いことを認めるに足りる証拠はない。 イ 実験報告書(甲9実験)について 決定は,甲9の実験報告書によれば,甲5の実施例5と同様に製造した PAS樹脂のヨウ素含有量が850ppmであると認められることから, 本件発明4で特定するPAS樹脂組成物のヨウ素含有量は,先願明細書発 明BにおけるPAS樹脂のヨウ素原子含有量と重複一致する蓋然性が高い と判断している。 しかしながら,まず,異議申立人による上記実験報告書では,重合反応\nが80%程度進んだ段階で,「重合禁止剤2,2’−ジチオビスベンゾト リアゾル」を25g添加したとされているが,異議申立人自身が,先願の\n国内移行出願において,かかる物質名で定義される化合物は存在せず,誤 記である旨を主張(自認)して,当初明細書である甲5の記載を正しい記 載に訂正する手続補正を行っており(甲30),それにもかかわらず,な ぜ追試である上記実験報告書にあえて存在しない化合物名がそのまま記載 されているのか,疑問がないとはいえない(この点は,上記実験報告書を 作成するに当たり,当初明細書の誤記をそのまま引き写してしまっただけ の単純ミスである可能性も否定できないが,重合禁止剤として実在しない\n化合物名が記載されているということは,その内容の杜撰さを示す一例と みざるを得ないのであって,実験報告書全体の信用性を疑わせる一つの事 情となることは否定できない。)。 また,この点は措くとしても,上記実験報告書の「1.実験方法」の欄 には,「「5)Chip cutting:反応完了した樹脂をN2加圧して,小型スト ランドカッターを使用したpellet形態に製造。」との記載があり,かかる 記載が,甲5の実施例5における,「反応が完了した樹脂を,小型ストラ ンドカッター機を用いてペレット形態で製造した。」との記載に対応する ものであって,同実施例と同様に,反応が完了した樹脂を小型ストランド カッターによってペレット形態とすることを示すものであることは理解で きるが,「N2加圧」処理を行うことの技術的な意味は明らかではないし (すなわち,いかなる状態の樹脂に対して,何のために行うのか,例えば, 溶融状態の樹脂に対して加圧処理を行うのか,ストランド〔細い棒状〕に 形成するための押し出しをN2による加圧で行うのか,形成されたストラ ンドに対して行うのかなどの点が不明である。),少なくともカッティン グの前に樹脂を「N2加圧」することが当該技術分野における技術常識で あるとはいえない。また,高温の樹脂に対しN2加圧を行うことによって, 樹脂中のヨウ素が抜ける可能性がないとはいえず(少なくともその可能\性 が全くないことを示す証拠はない。),かかる「N2加圧」がヨウ素含有 量に対してどのような影響を及ぼすのかも不明である。 この点,被告は,上記ストランド押し出しを窒素加圧下で行うことが記 載されている乙9ないし12を引用して,N2加圧が周知の技術的事項で ある旨反論するが,仮にストランドを形成するための押し出しをN2加圧 によって行うことが周知の手段であっても,上記実験報告書における「N 2加圧」がこれらの乙号証に記載された工程と同じものを意味するものと は限らないし,結局,かかる「N2加圧」がヨウ素含有量に対してどのよ うな影響を及ぼすのかが不明であることに変わりはない。 以上によれば,実験報告書(甲9)は,必ずしも甲5の実施例5を忠実 に追試したものであるとはいえず,かかる実験報告書(甲9実験)に基づ いて,甲5の実施例5と同様に製造したPAS樹脂のヨウ素含有量が85 0ppmであるとか,本件発明4で特定するPAS樹脂組成物のヨウ素含 有量は,先願明細書発明BにおけるPAS樹脂のヨウ素原子含有量と重複 一致する蓋然性が高いなどと認めることはできないというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.12. 2
平成29(行ケ)10003 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月21日 知的財産高等裁判所
本件審決は,確定した前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)により, 相違点1及び相違点2については,いずれも引用例1及び引用例2に接した当業者 が容易に想到することができたものであるとされ,相違点3については,単なる設 計事項にすぎないとしつつ,化合物Aは「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定 化効果(高いヒスタミン放出阻害率)を有すること,また,AL−4943A(化 合物Aのシス異性体)は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常 に広いことは,いずれも引用例1,引用例3及び本件特許の優先日当時の技術常識 から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり,進歩性を判断するにあたり,引用発明1と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして,本件各発明は\n当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断したものである。
・・・
以上のとおり,本件特許の優先日において,化合物A以外に,ヒト結膜肥満細胞 からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られ ていたことなどの諸事情を考慮すると,本件明細書に記載された,本件発明1に係 る化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が,当業者 にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということはできない。なお,本件発明1の顕著な効果の有無を判断す\nる際に,甲39の内容を参酌することができないことについては,前記イのとおり であるが,仮にその内容を参酌したとしても,上記のとおり,本件特許の優先日に おいて,化合物A以外に,高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物が複数存在し, その中には2.5倍から10倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害 効果を維持する化合物も存在したことを考慮すると,甲39に記載された,本件発 明1に係る化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が, 当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということもできない。\nしたがって,本件発明1の効果は,当業者において,引用発明1及び引用発明2 から容易に想到する本件発明1の構成を前提として,予\測し難い顕著なものである ということはできず,本件審決における本件発明1の効果に係る判断には誤りがあ る。
・・・・
なお,本件審判の審理について付言する。 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定し たときは,審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審 理,審決をするが,再度の審理,審決には,行政事件訴訟法33条1項の規定によ り,取消判決の拘束力が及ぶ。そして,この拘束力は,判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから,審判官は取消判決の認定 判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって,再度の審判手続に おいて,審判官は,取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤 りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと,あるいは上記主張を裏付けるた めの新たな立証をすることを許すべきではない。また,特定の引用例から当該発明 を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により,容易に発明 することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取 り消されて確定した場合には,再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果,審 判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することがで きたとはいえないと認定判断することは許されない(最高裁昭和63年(行ツ)第 10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照)。 前訴判決は,「取消事由3(甲1を主引例とする進歩性の判断の誤り)」と題す る項目において,引用例1及び引用例2に接した当業者は,KW−4679につい てヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(ヒト結膜肥満細胞安定化 作用)を有することを確認し,ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易 に想到することができたものと認められるとして,引用例1を主引用例とする進歩 性欠如の無効理由は理由がないとした第2次審決を取り消したものである。特に, 第2次審決及び前訴判決が審理の対象とした第2次訂正後の発明1は,本件審決が 審理の対象とした本件発明1と同一であり,引用例も同一であるにもかかわらず, 本件審決は,本件発明1は引用例1及び引用例2に基づき当業者が容易に発明でき たものとはいえないとして,本件各発明の進歩性を認めたものである。 発明の容易想到性については,主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻 害要因の有無のほか,当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり,当事者は,第2次審判及びその審決取消訴訟において,\n特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も,これを否定する事 実の主張立証も,行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴 判決を確定させた後,再び開始された本件審判手続に至って,当事者に,前訴と同 一の引用例である引用例1及び引用例2から,前訴と同一で訂正されていない本件 発明1を,当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは, 特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず,訴訟経済に反す るもので,行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし,問題があったといわ ざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2017.12. 2
平成28(ワ)10147 職務発明対価等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月15日 東京地方裁判所
(イ) 原告は,平成27年3月31日,被告を定年退職した。Bは,同日,原告に 対し,職務発明に関する規程は半年をめどに作成すること,本件特許権についても それまでは現状のままとさせて欲しいとの内容を含む電子メールを送信した(甲3)。
(ウ) 原告は,平成27年9月18日,Bに対し,経過を報告するよう促したとこ ろ,Bは,同月28日,原告に対し,「特許に関する規定の件ですが,職務発明等 褒賞金規定と知的財産取扱い規定の制定を行いました。…両規定とも27年9月以 降の適用となっておりますが,当社の過去の特許においても該当する案件には今回 の規定を適用することといたしました。/よって,Aさんに対しましても,出願報 奨金10,000円と登録報奨金50,000円が該当いたします。手続きを進め たいと存じますので,振込口座をお教えください。」との記載のある本件メールを 送信した。
これに対し,原告は,ひとまず本件各規程を送付するよう求めたが,Bは,同年 10月13日,原告に対し,「今回制定した社内規定については退職者に対しては 開示できませんのでご了承ください。弊社としては,今回特別にお支払する6万円 でAさんの特許に対する対応は完了とさせていただきます。」との電子メールを送 信した。 原告は,本件各発明に係る対価の支払を被告が拒絶したと解釈し,同日,Bに対 し,法的根拠に基づく手続を始める旨の電子メールを送信した。 (以上につき,甲3,5,6,原告本人,証人B)
(エ) 原告は,平成27年10月30日,被告を相手方とし,本件各発明に係る特 許権を移転した対価5115万1430円の支払を求める民事調停を申し立てたが,\n同調停は平成28年3月17日,不成立により終了した。原告は,同月30日,本 件訴えを提起した。
イ 上記認定事実に関し,事実認定の理由を次に補足説明する。
被告は,Bが,平成27年2月2日に原告と面談した際,本件回答書を原告に交 付し,本件対価請求権については時効が完成している旨説明したと主張し,Bも証 人尋問において同旨の証言をする。 被告は,平成26年12月12日に,原告から本件各発明についての対価の請求 を受け,弁護士に依頼して対応を検討しているところ,弁護士から被告の従業員に 宛てた電子メールが証拠として提出されており(乙4),その記載内容と本件回答 書(乙2)の記載内容が概ね符合していることからすれば,弁護士において本件回 答書を作成して被告に交付したことは認められる。他方,原告は,平成27年2月 2日に本件回答書をBから受け取った事実及び時効の完成について説明を受けたと の事実を否認し,本人尋問においてもその旨供述するところ,原告が本件回答書を 受領したことを示す客観的な証拠はなく,また,Bの証言によっても,Bが原告に 説明した内容については判然としないところがあるから,同日の面談において,B が本件回答書を原告に交付し,また時効の完成について明確に説明したとの事実を 認定するには至らない。もっとも,本件回答書は,原告からの対価の請求への対応 として,弁護士が被告の立場に沿って作成したものであることからすれば,少なく とも,Bは,同日,原告に対し,本件回答書に基づき,被告としては対価の支払に は応じられない旨を説明したとの事実は認めることができる。
(3)上記認定事実に基づき検討する。
本件対価請求権は,原告が本件各発明についての特許を受ける権利を被告に承継 させたことに伴い,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基 づき発生する相当の対価の支払請求権である。原告が被告に上記特許を受ける権利 を承継させた平成14年当時,被告には,特許を受ける権利の承継に関する「勤務 規則その他の定」は存在しなかったのであるから,上記承継は,原被告間の契約に 基づくものであって,本件対価請求権も,平成27年に被告が策定した本件各規程 に基づき発生したものではない。したがって,Bが,同年9月28日,原告に対し, 本件各規程に基づき6万円を原告に支払う用意がある旨が記載された本件メールを 送付したことのみをもって,被告が本件対価請求権の支払債務を承認したものと評 価することは困難である。 また,前記認定事実((2)ア(ウ))によれば,被告は,原告から本件各発明の対価の 請求を受けた平成26年12月12日以降,被告には対価の支払義務がないとの立 場を示していたのであって,Bが本件メールを送付して原告に6万円の支払をする 用意があると伝えたのは,その後の電子メールに「今回特別にお支払する6万円で Aさんの特許に対する対応は完了とさせて頂きます。」との記載にあるように,本 件各発明に関する原被告間の紛争を全て収束させるための解決金との趣旨で提案さ れたものとみるのが相当である。 この点について,原告は,本件メールに「両規定とも27年9月以降の適用とな っておりますが,当社の過去の特許においても該当する案件には今回の規定を適用 することといたしました。」(判決注:下線を付した。)と記載されていることを 捉えて,被告が支払を提案した6万円は本件対価請求権の一部であることが明白で あるから,被告は本件対価請求権の支払債務を承認したと主張する。しかし,本件 各規程に基づく褒賞金と本件対価請求権とはその発生原因が異なるのであるから, 本件各規程に基づく褒賞金の支払を提案したからといって,当然には本件対価請求 権の支払債務を承認したものとみることはできない。また,前記認定事実((2)ア(ウ), (エ))によれば,原告は,Bから本件各規程に基づく6万円の支払を提案された際も, ひとまず本件各規程を送付するよう求め,Bからこれを拒絶されると直ちに法的手 段を執る旨の電子メールを送信し,現実に法的手続に移行しているのであるから, 原告と被告との間で,本件各規程に基づく6万円の支払をもって,本件対価請求権 に充当する旨の合意等が成立していたとみる余地もないというべきである(なお, 原告本人も,本件メールにより提案された6万円について,対価ではないと理解し た旨供述しているところである。)。
(4)以上のとおり,Bが原告に対して本件メールを送付したことをもって,被告 が本件対価請求権の支払債務を承認したと評価することはできないから,被告が本 件対価請求権に係る消滅時効の時効援用権を放棄したとか,消滅時効の援用が信義 則に反して許されないということはできない。
3 結論
以上によれば,本件対価請求権の消滅時効は,その権利を行使することができる 時である平成14年9月3日から進行するところ,平成16年法律第79号による 改正前の特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を求める請求権は,従業 者等と使用者等との衡平を図るために法が特に設けた債権であるから,その消滅時 効期間は10年と解すべきところ(民法167条1項),原告が被告を相手方とし て民事調停を申し立てた平成27年10月30日には,本件対価請求権について1\n0年の消滅時効期間が経過していたことが明らかである。したがって,被告が平成 28年5月18日にした時効援用の意思表示により,本件対価請求権は消滅したと\nいうべきである。
2017.11.17
平成28(ワ)8468 特許権移転登録手続等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年11月9日 大阪地方裁判所
(1) 特許法74条1項の特許権の移転請求制度は,真の発明者又は共同発明者 がした発明について,他人が冒認又は共同出願違反により特許出願して特許権を取得した場合に,当該特許権又はその持分権を真の発明者又は共同発明者に取り戻さ せる趣旨によるものである。したがって,同項に基づく移転登録請求をする者は, 相手方の特許権に係る特許発明について,自己が真の発明者又は共同発明者である ことを主張立証する責任がある。ところで,異なる者が独立に同一内容の発明をし た場合には,それぞれの者が,それぞれがした発明について特許を受ける権利を個 別に有することになる。このことを考慮すると,相手方の特許権に係る特許発明に ついて,自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証するためには,単 に自己が当該特許発明と同一内容の発明をしたことを主張立証するだけでは足りず, 当該特許発明は自己が単独又は共同で発明したもので,相手方が発明したものでな いことを主張立証する必要があり,これを裏返せば,相手方の当該特許発明に係る 特許出願は自己のした発明に基づいてされたものであることを主張立証する必要が あると解するのが相当である。そして,このように解することは,特許法74条1 項が,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者であることと並ん で,特許が123条1項2号に規定する要件に違反するときのうちその特許が38 条の規定に違反してされたこと(すなわち,特許を受ける権利が共有に係るときの 共同出願違反)又は同項6号に規定する要件に該当するとき(すなわち,その特許 がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたこと) を積極的要件として定める法文の体裁にも沿うものである。
(2) そこで,まず本件特許発明1の内容等について検討する。
・・・・
ウ 以上のことを踏まえると,本件特許発明1は,便座昇降機を不要とする 課題を解決するために,使用時に便座を上昇させるのではなく,予め便座と便器の\n間に嵩上げ部を設けて便座の位置自体を高くしておき,その嵩上げ部にくり抜き部 を形成し,そこから拭き取りアームを挿入して臀部を拭き取るようにすることによ\nって,使用時の便座昇降機による便座の上昇を不要としたものと認められる。そし て,このような課題解決方法に照らせば,本件特許発明1は,便座昇降機が必要と されていた理由を,便座の位置が低く,便座と便器の間に拭き取りアームを挿入す る隙間がない点に求め,便座の位置を高くして,便器との隙間を生み出すことによ って,課題を解決しようとしたものであると認めるのが相当であり,そのために, 次に述べる原告第1出願の明細書の記載に見られるような便座と便器の間の隙間を 小さくしたり,拭き取りアームの厚さを薄くしたりすることについて特段の記載は されていない。 そして,以上の本件特許発明1について,本件優先権出願の明細書及び図面には, 本件基礎出願の明細書図面と同一の内容が記載されていると認められる。 (3) 以上を踏まえ,本件特許発明1の発明者について検討する。原告は,平成 24年9月初旬に完成したという原告第1発明と本件特許発明1は同一の発明であ り,原告第1発明について特許を受けるために原告第1出願を行ったと主張し,こ れに沿う陳述をしていることから,まず,原告第1出願に係る発明について検討す る。
・・・
そして,上記の原告の発明に係る臀部拭き取り装置では,紙を取り付けることが\nできる紙つかみヘッド(3)が本件特許発明1の「拭き取りアーム」に該当し,紙 つかみヘッドを移動させる4軸型可動型装置が本件特許発明1の「拭き取りアーム 駆動部」に該当すると認められる。 他方,本件特許明細書によれば,本件特許発明1の「嵩上げ部」は,便器と便座 との間に設けられ,便座全体を上げて便器との間に間隙を設ける部材を意味すると 解され,補高便座のほか複数の支柱状の器具も想定されているところ,原告第1出 願に係る装置は,「水洗式洗浄型便座と便器の間において使用する」(【0009】) もので,その図2の左側面図及び正面図によれば,便座の下部に薄いガイド板ない し保護ガイド(6)が設けられ,「実際の取り付けは,標準でついている便座の1c mのゴム足を除去して,取り付けるため便座の高さは2cmの高くなるだけ」(【0 010】)であるから,少なくともガイド板ないし保護ガイドの部分においては図示 されない便器と便座の間に3cmの隙間が設けられることになる。しかし,それだ けでは便座全体がどのように上げられるのかが明らかでないから,原告第1出願に 係る明細書や図面において「嵩上げ部」に該当する部材が記載されていると認める ことは困難である。 もっとも,原告第1出願に係る発明においては,便座全体を3cm持ち上げるこ とを想定していると解するのが合理的であるから,原告においては,ガイド板ない し保護ガイド単体又はそれと組み合わせて何らかの形で便座全体を上げることを想 定していた可能性があり,その場合には,その構\造が「嵩上げ部」に該当し,ガイ ド板ないし保護ガイド内の紙つかみヘッドの移動空間が「嵩上げ部に設けられたく り抜き部分」に該当する可能性もあり得るところである。\nそうすると,原告は,原告第1出願がされた平成24年9月25日の時点で,原 告第1出願に係る発明により,本件特許発明1を完成させていた可能性があるとい\nうべきである。
ウ もっとも,原告第1出願に係る発明は,同時に,臀部拭き取り装置にあ\nるトイレットペーパーの紙つかみヘッドを限りなく薄くし,3cm程の隙間でも, 容易に臀部の下に差し入れることができるようにすることにより,トイレ使用者が\n一般のトイレの使用時と変わることのない着座位置となるようにして,便座昇降機 の除去を可能としたものとされている。また,併せて,トイレットペーパーを掴ん\nだ紙つかみヘッドを臀部のふき取り位置あたりで80度ほど回転させることで,臀\ 部にフィットさせるものとされている。 以上のことを踏まえると,原告第1出願に係る発明は,ヘッドを限りなく薄くし て,ヘッドを臀部の下に差し入れるのに要する隙間を少なくするとともに,ヘッド\nを回転させることでヘッドが薄くても臀部にフィットするようにし,使用時の便座\n昇降機による便座の上昇を不要としたものと認められる。そして,このような課題 解決方法に照らせば,原告第1出願に係る発明は,便座昇降機が必要とされていた 理由を,ヘッドの形状やその動作の仕方に求め,それらを工夫することによって, 課題を解決しようとしたものであると認めるのが相当である。そうすると,原告第 1出願に係る発明と本件特許発明1とは,解決しようとしている抽象的な課題は共 通していても,その課題の生ずる具体的な原因の捉え方が異なっており,そのため に,具体的な課題の捉え方や,課題解決の方向性や主たる手段も異なることになっ たと認められる。
(4) そこで次に,原告が原告第1出願に係る発明により本件特許発明1を完成 させていた可能性があることに鑑み,被告が,原告第1出願に係る発明に基づいて,\n本件特許に係る特許出願をしたと認められるかについて検討する。この点について, 被告は,被告代表者が本件特許発明1を完成したと主張し,被告代表\者はこれに沿 う陳述をしている。
ア 前記1での認定事実によれば,被告代表者は,平成24年9月25日午\n前中に,P4と打合せをしている。この打合せの内容を直接に示す証拠はないが, 同日の午後1時に被告代表者がP4に「先ほどは有難うございました。参考までに,\nかさ上げ便座部品の記載されたカタログを送付させて頂きます。」として,補高便座 のカタログを送信していることからすると,被告代表者は,同日午前の打合せにお\nいて,補高便座を用いた発明の説明をしたと推認される。また,翌26日の午後4 時48分にP4が被告代表者にアームがどこから出てくるのか明確にしたいとのメ\nールを送信しており,前日のカタログの送信から本メールまでの間に被告代表者と\nP4が打合せをしたことは何らうかがわれないことからすると,本メールは,前日 25日午前の打合せの際に,被告代表者が補高便座からアームが出る構\造の臀部拭\nき取り装置の発明を説明したのに対して,P4が質問をしたものであると推認され る。そして,本メールの直後の同日午後5時07分に被告代表者がP4に「補高な\nのでその一部を切り取るか,構造によっては中をくりぬいて,最大6センチメート\nルのすき間でアームを出入りさせたらと,考えています。」と返信していることから すると,被告代表者は,同月25日午前にP4に対して補高便座からアームが出る\n構造を説明した時点で,既に補高便座を「かさ上げ便座部品」として利用し,補高\n便座を切り取り,又はくり抜いてアームを出すことで便座昇降機を利用しない臀部\n拭き取り装置の着想を得て,本件特許発明1を完成していたと推認するのが相当で あり,このことは,被告代表者の陳述(乙24)は以上の経緯と整合的である。\nイ この点について,原告は,被告代表者が,同月25日午後6時の原告か\nらのメールを受け取るまでは,本件特許発明1の着想を得ていなかったと主張する。 しかし,前記の被告代表者とP4のやりとりの流れからすると,被告代表\者が当 初にP4に補高便座のカタログを送信したことが,臀部拭き取り装置の開発と関係\nのないものであったとは考え難いから,被告代表者は,同日午前にP4と打合せを\nした時点で,便座をかさ上げしてアームを通すものとして補高便座に着目していた と認めるのが相当であり,そうである以上,前記のとおり,同日午前の時点で被告 代表者は本件特許発明1の着想を得ていたと推認するのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2017.11.16
平成29(行ケ)10132 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年11月14日 知的財産高等裁判所
ウ 前記イの認定事実によると,本願商標の指定商品である「コンピュータソフ\nトウェア」と,引用商標1の指定商品である「半導体チップ,半導体素子」とは, 1)いずれも電子の作用を応用したものであり,コンピュータ等の電子機器を稼働す るために構成上不可欠なものであって,その用途及び機能\において密接な関連を有 するものであること,2)両商品を生産している事業者が相当数存在すること,3)様々 な商品を取り扱っている総合ショッピングサイトや家電量販店だけでなく,半導体 素子等を含む電子部品を専門に扱う相当数の販売店においても,両商品が販売され ていること,4)両商品の需要者は,一般の個人需要者や電子機器等の製造メーカー において共通する場合があることなどの事情に照らすと,両商品の原材料及び品質 が異なること,完成品と部品の関係にないことなどを考慮したとしても,両商品に 同一又は類似の商標が使用されるときは,同一営業主の製造又は販売に係る商品と 誤認混同するおそれがあると認められる関係にあり,商標法4条1項11号にいう 「類似する商品」に当たると解するのが相当である。
エ 原告の主張について
(ア) 原告は,本願商標の指定商品のうち,理化学装置の制御用コンピュータソ\nフトウェア等は,その機能・用途によれば,むしろ第9類の「理化学機械器具」に\n属する商品(専用ソフトウェア)であり,10A01の類似群コードが付される商\n品の範疇であるともいえ,その場合,引用商標1の指定商品である半導体素子等が 含まれる「電子応用機械器具」とは類似群コードが異なり,両商品は,明らかに異 なるものである旨主張する。 しかし,本願商標の指定商品は,理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア\n等に限られるものではなく,コンピュータソフトウェア全般を指定商品とするもの\nであり,コンピュータソフトウェアと半導体素子等とが,商標法4条1項11号に\nいう「類似する商品」に当たると解するのが相当であることについては,前記ウの とおりである。
(イ) 原告は,ソフトウェア業界は,巨大企業数社と無数の零細メーカーの二極\n構造であるのに対し,半導体業界は,その製造に大規模かつ最新の設備を必要とす\nる代表的な装置産業であることから,両商品は業界自体が異なるだけでなく,生産\n部門において一致しない旨主張する。 しかし,コンピュータソフトウェアと半導体素子等との両商品を製造する事業者\nが相当数存在することについては,前記イ(イ)のとおりである。また,一般社団法 人電子情報技術産業協会(JEITA)における,コンピュータソフトウェアに関\n連するソフトウェア事業委員会を構\成する8社のうち6社は,半導体事業に関連す る半導体部会の構成企業でもあり,同協会の半導体部会と一般社団法人コンピュー\nタソフトウェア協会の両方の登録会員である企業も存在すること(甲3,7,乙3\n9の1・2)に鑑みても,両商品の生産部門は一致しないものではない。
(ウ) 原告は,コンピュータソフトウェアは,一般消費者向けに取引を展開する\nウェブサイトにおいても,「パソコンソ\フト」のジャンル名で多数取引されている のに対し,半導体素子等は,半導体を専門的に取り扱う商社等を通じて主に販売さ れるものであり,自作パソコンの製作を試みるパソ\コンマニア向けに,一部のパソ\nコンショップやネットショップで半導体素子等が販売されている事実があるとして も,半導体素子等の販売取引市場全体を見れば,ごく僅かな一部の事情を示すにす ぎない旨主張する。 しかし,様々な商品を取り扱っている総合ショッピングサイトや家電量販店だけ でなく,半導体素子等を含む電子部品を専門に扱う相当数の販売店においても,コ ンピュータソフトウェアと半導体素子等の両商品が販売されていることについては,\n前記イ(ウ)のとおりである。また,前記イ(エ)のとおり,一般の個人需要者の中に は,パソコンを自作する者のほか,所有するパソ\コンの性能を向上させること等を\n目的として,半導体素子等に含まれるCPUなどの電子部品及びコンピュータソフ\nトウェア等を購入し使用する者もいるのであって,両商品を購入する者は,自作パ ソコンを製作する一部のパソ\コンマニアに限られるものではない。さらに,一般消 費者向けに取引を展開するウェブサイトである楽天市場の「全てのカテゴリー」に おいて,引用商標1の指定商品に包含される「CPU」,「サーミスタ」,「トラ ンジスタ」及び「ダイオード」を検索すると,それぞれ,17万1333件,1万 1865件,2万1603件及び7万0232件が検出されること(乙41〜44) に鑑みても,両商品の販売部門は一致しないものではない。
(エ) 原告は,コンピュータソフトウェアは,あらゆるビジネス分野の事業者だ\nけでなく,幅広い年齢の個人利用者をその需要者とするのに対し,半導体素子等は, 半導体を組み込んだ各種産業製品を生産する事業者がその主たる需要者であり,ソ\nフトウェア独自のビジネス構造においても顕著な差異を有しており,両商品は需要\n者の範囲において比較し得ない旨主張する。 しかし,両商品の需要者は,一般の個人需要者や電子機器等の製造メーカーにお いて共通する場合があることについては,前記イ(エ)のとおりである。
(オ) 原告は,コンピュータソフトウェアはバージョンアップやアンインストー\nルを容易に行うことができ,半導体素子等にはないソフトウェア特有の特徴を備え\nていることを考慮すると,両商品は用途において顕著に異なる旨主張する。 しかし,両商品は,いずれも電子の作用を応用したものであり,コンピュータ等 の電子機器を稼働するために構成上不可欠なものであって,その用途及び機能\にお いて密接な関連を有するものであることについては,前記イ(ア)のとおりである。 コンピュータソフトウェアのインストール,バーションアップ等は,当該商品の利\n用方法における一つの特徴を述べたものにすぎない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.11.16
平成29(行ケ)10109 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年11月14日 知的財産高等裁判所
(ア) 前記(1)ウのとおり,本件雑誌には,少なくとも最近約10年間にわたり, ほぼ毎号,化粧品についての記事が掲載されている。男性ファッション誌の主な対 象は服飾品であるものの,化粧品はファッション全般に関するものとして,男性フ ァッション誌の対象とされているというべきである。 したがって,男性化粧品と男性ファッション誌は,共にファッションに関するも のとして少なからぬ関連性を有するというべきである。
(イ) 男性化粧品と男性ファッション誌の需要者は,いずれも男性向けファッシ ョンに関心のある者と考えられ,共通するというべきである。男性化粧品と男性フ ァッション誌の取引者が異なるからといって,需要者の共通性は何ら否定されない。 したがって,男性化粧品と男性ファッション誌については,需要者が共通する。
(ウ) 本件商標の指定商品は,日常的に消費される性質の商品であり,その需要 者は特別の専門的知識経験を有する者ではないことからすると,これを購入するに 際して払われる注意力は,さほど高いものでないというべきである。
(3) 商標法4条1項15号該当性
以上のとおり,1)本件商標は,引用商標と外観において極めて類似し,観念及び 称呼において共通するのであって,本件商標と引用商標は,極めて類似したもので あること,2)引用商標は,独創性が高いとはいえないものの,数十年にわたり,需\n要者の間に広く認識されていること,3)本件商標の指定商品(男性用化粧品)は, 原告の業務に係る本件雑誌(男性ファッション誌)の対象として,少なからぬ関連 性を有するもので,本件雑誌と需要者が共通することその他需要者の注意力等を総 合的に考慮すれば,本件商標を指定商品に使用した場合は,これに接した需要者に 対し,引用商標を連想させて,当該商品が原告あるいは原告との間に緊密な営業上 の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主\nの業務に係る商品であると誤信され,商品の出所につき誤認を生じさせるおそれが あるものと認められる。 そうすると,本件商標は,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれが ある商標」に当たると解するのが相当である。
・・・
イ 被告は,本件雑誌の一部に掲載されているにすぎない化粧品について雑誌と の強い関連性を認めるのは,本件雑誌で紹介される全ての商品について雑誌との強 い関連性を認めることとなり,ひいては指定商品「雑誌」について不当に広い権利 範囲を認めることとなり,不合理であると主張する。 しかし,前記(2)ウのとおり,本件雑誌にはほぼ毎号化粧品に関する記事が掲載さ れ,化粧品自体,本件雑誌の対象であることが明らかな服飾品と少なからぬ関連性 を有するものである。そして,引用商標は長期間にわたって周知のものであること に加え,原告がコラボレーション企画等を行っていることをも併せ考慮すれば,い わゆる広義の混同が生じるおそれが認められる。 したがって,指定商品を男性用化粧品とする本件商標を15号該当とすることが 不合理であるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2017.11.10
平成29(行ケ)10118 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年10月26日 知的財産高等裁判所(2部)
ア 本件チラシ1の下段に記載されている「ピーアールタイムズ」の片仮名 は,本件商標の下段の片仮名と同一であるから,本件商標と社会通念上同一の標章 であると認められる。
イ 本件チラシ2の下段に記載されている「PRTIMES」の欧文字は, 本件商標の上段の欧文字と同一であるから,本件商標と社会通念上同一の標章であ ると認められる。
(3) 使用役務等について
上記1(2)のとおり,本件チラシ1には,「広告をご検討の事業主の皆様!まずは お気軽にご相談ください」,「広告のプロが広告主様と一緒に,売上・集客に繋がる 広告戦略を練らせていただきます。広告の事なら何でもご相談ください。」と記載さ れており,被告が広告の役務を提供することを広告しているものと認められる。 上記1(3)のとおり,本件チラシ2には,「広告をご検討の事業主の皆様!まずは お気軽にご相談ください」,「広告出稿や広告に関するコンサルティングの事なら」 と記載されており,被告が広告の役務を提供することを広告しているものと認めら れる。 そして,上記1(2)及び(3)のとおり,本件チラシには被告の会社名及び連絡先が 記載されており,本件チラシは,合計3000部作成され,頒布されたのであるか ら,被告は,本件チラシを見た者が被告に広告依頼などの連絡をしてくればこれに 応じ,業として広告の役務を提供する意思であったと認められる。 したがって,被告は,広告の役務に関する広告に本件商標と社会通念上同一の商 標を付して頒布し,これを使用したものと認められる。
ア 本件チラシの頒布に関する証拠である,本件チラシ(甲6,12),並び に,ニューアシストから被告に対する領収書(甲7,13)及び納品書(甲8,1 4)は,いずれも,当法廷において被告から原本が提示されており,その作成日当 時作成され,授受されたものであることに合理的な疑いを差し挟むべき不自然な点 はない。
イ ニューアシストのホームページに記載されているのは,「事業概要」であ って(甲21の2),その余の業務を行っていないという趣旨とは解されないから, ニューアシストがチラシの作成やポスティングの業務を行っていないとまではいえ ない。 被告の本店所在地と池尻大橋駅が遠く離れているとはいい難い上,チラシの配布 地域や配布部数などは,広告を行う者がその広告戦略などを考慮して決定するもの であるから,本件チラシの配布場所が池尻大橋駅周辺であり,配布部数が合計30 00部であることなどは,本件チラシの頒布を否定すべき事情とはいえない。広告 業務はその態様によって価格が異なるものと考えられる上,個別に連絡してきた者 に対して説明することもできるから,本件チラシに価格が記載されていないことは, 本件チラシの頒布を否定すべき事情とはいえない。 上記1(2)(3)のとおり,本件チラシ,領収書及び納品書によって,本件チラシの 頒布の事実が認定できるから,その他の取引に関する契約書,Eメールのやりとり, 報告書等が証拠として提出されていないことは,本件チラシの頒布を認定すること を妨げる事情とはならない。各2通の領収書(甲7,13)と納品書(甲8,14) の内容が同一であることは,同一の取引を2回行ったことを示すものにすぎず,ま た,被告の住所の誤りは,同一のデータを使いまわしたことによるものであると推 認されるから,これらの書証の信用性を疑わせる事情とはならない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2017.11.10
平成28(ワ)35182 特許権 平成29年10月30日 東京地方裁判所(29部)
これを本件について見ると,前記2で詳述したとおり,本件発明は,「その決定 したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」(構成\n要件C)ており,また,「表示部に仮想モールと,基本パーツを組み合わせてなる\n基本キャラクターとを表示させ」(構\成要件F),「基本キャラクターが,前記仮 想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」(構成要件G)構\成を有し ているのに対し(なお,「仮想モール」は,内部に複数の仮想店舗と遊歩のための 空間とが表示されるものをいい,「基本キャラクター」と同時に表\示される必要が あると解すべきこと,「仮想モール中に設けられた店」で「パーツ」を購入する際 にも「基本キャラクター」が表示される必要があると解すべきことも,前記2のと\nおりである。),被告システムは,少なくとも,「キャラクターに応じた情報提供 料」を「通信料」に「加算」する構成を備えていない点,「仮想モール」に対応す\nる構成を有していない点において,それぞれ本件発明と相違するところ,以下のと\nおり,これらの相違部分は,本件発明の本質的部分に当たるというべきであるから, 被告システムは,均等の第1要件(非本質的部分)を満たさない。
イ 本件明細書の前記1(2)アないしエの各記載によれば,本件発明は,携帯端末 の表示部に気に入ったキャラクターを表\示させることができる携帯端末サービスシ ステムに関するものであって(【0001】),あらかじめ携帯端末自体のメモリ ーに保存してある複数のキャラクター画像情報から,気に入ったものを選択して, その携帯端末の表示部に表\示するなどの従来技術では,携帯端末自体のメモリーに 保存できる情報量には限りがあるため,キャラクター選択にあまり選択の幅がなく, ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなく,サービス提供者にとっても,キ\nャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であったことから(【00 02】,【0003】),同問題点を解決し,「ユーザーが十分な満足感を得るこ\nとができ,且つ,サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシス テムを提供する」ため(【0004】),本件特許請求の範囲の請求項1記載の構\n成(構成要件Aないし同Hの構\成)を備えることにより,ユーザーにとっては,キ ャラクター選択をより楽しむことができ,また,サービス提供者にとっては,キャ ラクター画像情報の提供により効率良く利益を得ることができ(【0005】), さらに,ユーザーは,種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作するという ゲーム感覚の遊びをすることができ,十分な満足感を得ることができ,また,「仮\n想モールと,基本キャラクターとが表示された表\示部を見ながら,基本キャラクタ ーを自分に見立て,さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で, その仮想モール内に出店された店に入り,パーツという商品を購入することで,基 本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替えて,楽しむことができ,新た な楽しみ方ができて十分な満足感を得ることができる」(【0006】)というも\nのとされていることが理解できる。 そうすると,本件明細書では,本件発明は,サービス提供者がキャラクター画像 情報により効率良く利益を得るのは困難であったという従来技術の問題点を解決し て,サービス提供者が画像情報の提供により効率良く利益を得ることができる携帯 端末サービスシステムを提供することを目的の一つとするものであって,構成要件\nCの「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段 を備え」るとの構成は,まさに,従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決\n(サービス提供者がキャラクター画像情報により効率良く利益を得ることができる 携帯端末サービスシステムを提供すること)を実現するための,従来技術に見られ ない特有の技術的思想に基づく解決手段(課金手段)としての具体的な構成として\n開示されているものいうべきである。また,本件発明は,ユーザーに十分な満足感\nを与え得るものではなかったという従来技術の問題点を解決して,ユーザーが十分\nな満足感を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供することを他の目的 とするものであって,「表示部に仮想モールと,基本パーツを組み合わせてなる基\n本キャラクターとを表示させ」るとの構\成を含む構成要件F及び「基本キャラクタ\nーが,前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」との構成を含\nむ構成要件Gは,さながら自分が仮想モール内を歩いているようなゲーム感覚で商\n品を購入するなどして十分な満足感を得ることができるという本件発明に特有な作\n用効果に係るものであって,構成要件A,同B,同D及び同Eとともに,まさに,\n従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決(ユーザーが十分な満足感を得る\nことができる携帯端末サービスシステムを提供すること)を実現するための,従来 技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段(ゲーム感覚の実現)として の具体的な構成として開示されているものというべきである。\n他方で,後述する引用例1(乙6)の開示(iモード上に用意された複数のキャ ラクタ画像を受信し,これを待受画面として利用することができる携帯電話機)及 び引用例2(乙7)の開示(画像情報の提供に係る対価の課金を通話料金に含ませ るもの)に照らすと,本件明細書において従来技術が解決できなかった課題として 記載されているところは,客観的に見て不十分であるといい得るが,本件明細書の\n従来技術の記載に加えて,引用例1及び同2の開示を参酌したとしても,本件発明 は,ユーザーが十分な満足感を得ることができ,かつ,サービス提供者が利益を得\nることができる携帯端末サービスシステムを提供するものであり,従来技術では達 成し得なかった技術的課題の解決を実現するための具体的な構成として,構\成要件 AないしHを全て備えた構成を開示するものであるから,これら全てが従来技術に\n見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分に当たるというほかない。\n以上によれば,本件発明と被告システムとの相違部分は,いずれも本件発明の本 質的部分に係るものと認めるのが相当である(なお,上記認定判断は,後述する本 件特許の出願経過とも整合するところである。)。
・・・・
上記アの出願経過に照らせば,原告は,構成要件A,同B,同C及び同Hからな\nる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)及び構成要件A,同B,\n同C,同D,同E及び同Hからなる発明(出願当初の特許請求の範囲の請求項2に 係る発明)については,特許を受けることを諦め,これらに代えて,構成要件A,\n同B,同C,同D,同E,同F,同G及び同Hからなる発明(出願当初の特許請求 の範囲の請求項1に同2及び同5を統合した発明,すなわち本件発明)に限定して, 特許を受けたものといえる。 そうすると,原告は,構成要件F(「表\示部に仮想モールと,基本パーツを組み 合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」)及び同G(「基本キャラクターが,\n前記仮想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」)の全部又は一部を 備えない発明については,本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか,少 なくともそのように解されるような外形的行動をとったものといえる。 したがって,「仮想モール」に対応する構成を有していない被告システムについ\nては,均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり,同システムは,均 等の第5要件(特段の事情)を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2017.11.10
平成28(行ケ)10215 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月26日 知的財産高等裁判所(2部)
前記第2の2の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると,本件 発明について,以下のとおり認められる。 高速連続鋳造において,鋳造速度が大きくなると,凝固シェル厚みが薄くなり, これに伴って,バルジングが大きくなることから,バルジング性湯面変動が発生し, モールドパウダーの巻き込みが発生する原因となっている。鋳片表面にモールドパ\nウダーが付着していない方が二次冷却における冷却効率が良く,凝固シェル厚みが 厚くなるので,バルジング性湯面変動を抑制するには,鋳片からの剥離性の良いモ ールドパウダーが望ましい。 そこで,本件発明は,二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能\とす る,鋳片表面からの剥離性に優れる,鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供する\nことを,その目的とするものである。
2 取消事由1(サポート要件についての判断の誤り)について
・・・・ (2) 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すると,前記 1(1)ウの【0010】及び【0011】における第1の発明についての記載は,請 求項1の記載と一致する。 また,同【0012】の記載のうち,「前記モールドパウダー・・・特徴とする」 という部分は,請求項2において,本件発明1をさらに特定する事項の記載と一致 する。
(3)ア 前記1(1)イのとおり,本件発明の課題は,二次冷却帯における鋳片の 冷却能を高めることを可能\とする,鋳片表面からの剥離性に優れる,鋼の連続鋳造\n用モールドパウダーを提供することである(【0009】)。 イ そして,前記(2)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明【0010】, 【0011】及び【0012】には,課題を解決する手段として,「第1の発明」及 び「第2の発明」のモールドパウダー,すなわち,本件発明が記載され,また,前 記1(1)オのとおり,剥離性の試験結果を示した図1及び図2に基づき,請求項1に 記載された式(1)及び(2)を満たすモールドパウダーが,剥離性に優れること が分かったとされている(同【0018】〜【0024】)。
具体的には,
・・・・
この記載は,モデル実験の結果を示す図1及び図2から導かれ た式(1)及び(2)を満たすモールドパウダーは,連続鋳造に用いた場合に,実 際に鋳片からの剥離性に優れ,二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可\n能とするものであるかどうかを,バルジング湯面変動の抑制効果によって評価する\nことを意図したものであると認められる。
ウ 実施例について
(ア) 証拠(甲3,5,7,8,10,19)及び弁論の全趣旨によると, 次の技術常識が認められる。
a バルジング性湯面変動は凝固シェルの厚みが薄くなることに起因し て激しくなる。凝固シェルは溶鋼が鋳型内で冷却されて形成されるものであり,鋳 型内抜熱強度が低い場合(鋳型に抜けていく熱が少なく,鋳型内が冷却されにくい 場合)には凝固シェルの厚みが薄くなる。
b 鋳型内における冷却強度の指標としてモールドパウダーの凝固温度 が用いられる。このパウダーの凝固温度は,一定温度に保持した坩堝中において円 筒を回転するなどして粘性を求め,測定温度に対し粘性をプロットした図において, 温度の低下に伴って急激に粘性が高くなる温度とされている。この急激な粘性の変 化は温度の低下に伴いパウダーが結晶化し,見掛けの粘性が高くなるためであると 考えられており,この凝固温度が高い場合はパウダーフィルム内の結晶相(固着相) 厚みが厚いため鋳型−凝固シェル間の熱抵抗が大きくなり,緩冷却が実現されると されている。
c モールドパウダーの凝固温度は,その組成によって変化する。
(イ) これらの技術常識を考え合わせると,凝固シェルの厚みは,鋳型直下 でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却\n効率のみによって決まるものではなく,モールドパウダーの組成によって異なる凝 固温度にも影響されると認められる。
(ウ) 本件明細書記載の実施例において,モールドパウダーBとモールド パウダーAについて,鋳型内における冷却強度の指標となる凝固シェルの厚みに影 響を与え得る凝固温度は記載されていない。また,モールドパウダーAとモールド パウダーBの組成が記載された表1には,化学成分として,SiO2,Al2O3,C\naO,MgO,Na2Oのみが挙げられ,それらの量を合計しても,モールドパウダ ーAで80.6%,モールドパウダーBで78.7%であり,残りの成分が何であ ったのか不明であるから,その組成から凝固温度を推測することもできない。 また,本件明細書記載の実施例において,(1)式及び(2)式を満たすものと満 たさないものについての連続鋳造の際のバルジング性湯面変動の測定は,それぞれ, モールドパウダーBとモールドパウダーAの一つずつで行われたにとどまる。 これらのことから,本件明細書の発明の詳細な説明において,モールドパウダー BがモールドパウダーAよりもバルジング性湯面変動を抑制できたことが示されて いても,モールドパウダーBがモールドパウダーAと比較してバルジング性湯面変 動を抑制することができたのは,モールドパウダーが(1)式及び(2)式を満た す組成であることによるのか否かは,本件明細書の発明の詳細な説明からは,不明 であるといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2017.11.10
平成29(行ケ)10128 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年10月26日 知的財産高等裁判所(2部)
「・・・他方,「スタ」という片仮名部分は,それ自体に特定の意味がないところ,これと結合する「軽」という漢字部分からは指定役務との関係で「軽自動車」が想起され ること,本件商標の査定日である平成27年11月16日以前から,「新しいまちづ くりをスタートさせるスタッフ」を意味するものとして4音の「まちスタ」が使用 されていたほか(乙9),「おはようスタジオ」というテレビ番組を「おはスタ」と 略称する(甲5の1・2)など,「スタ」が略称として用いられることが少なからず あったこと(弁論の全趣旨)からすると,本件商標の指定役務の需要者には,「スタ」 という片仮名部分も特定の単語の略称であると想起されることがあり得るというこ とができる。 しかし,「スタ」という片仮名部分が特定の単語の略称であると想起されるとして も,冒頭2字を略称にするとは限らないし,「スタ」から始まる片仮名の単語につい ては,広辞苑(第6版)掲載のものに限っても,「スター」,「スタート」,「スタイリッシュ」,「スタイル」,「スタジアム」,「スタジオ」,「スタッフ」,「スタディー」のほか(甲4),「スタミナ」,「スタメン」,「スタンダード」,「スタンド」,「スタンバイ」などがあり,いずれも「スタ」と略称される可能性があるということができる(甲5の1・2,甲6〜9,乙6〜9)。そして,本件商標の指定役務との関係や,\n「軽自動車」の略称と考えられる「軽」という漢字部分との組み合わせを考えても, 本件商標の指定役務の需要者において,これらの「スタ」から始まる多数の単語の うち,いずれかのみを強く想起するということはできない。 そうすると,本件商標に接した本件商標の指定役務の需要者は,本件商標が軽自 動車と「スタ」から始まる何らかの単語を組み合わせたものの略称と考えられるこ とまでを想起するとしても,本件商標全体から特定の観念を想起することはできな いというべきである。
3 引用商標は,前記第2の3(2)のとおり,「軽スタジオ」という漢字1字と片 仮名4字を横書きした構成からなるが,これらの文字は,同一の書体,同一の大き\nさ,同一の間隔で表されており,外観上,一体的に看取,把握されるものである。\nまた,引用商標からは,その構成文字に応じて,「ケイスタジオ」の称呼を生じ,\nこの称呼は6音であることから,一気に称呼し得るものである。 さらに,引用商標は,「軽」という漢字と「スタジオ」という片仮名から構成され\nるものであるところ,その指定役務が「自動車及びその部品の小売又は卸売の業務 において行われる顧客に対する便益の提供,自動車リース事業の運営及び管理,自 動車の売買契約の媒介」であること,「軽」が「軽自動車」の略称として用いられて いることからすると,「軽」という漢字部分からは「軽自動車」が想起される。他方, 「スタジオ」は,1)画家,彫刻家,写真家,デザイナーなど芸術家の仕事場,2)映 画や写真の撮影所,3)音楽の録音室・練習室,4)放送局の放送室などといった意味 を有する単語であり(甲4,乙1〜5),引用商標の指定役務と直ちに結びつくもの ではないが,「軽自動車」の略称である「軽」と結合して用いられていることから, 引用商標全体からは,「軽自動車に関する役務の提供が受けられる場所」といった観 念を想起するものと認められる。
4 前記1〜3によると,本件商標と引用商標の外観は,「軽スタ」という文字部 分が共通であるものの,本件商標が3字であるのに対し,引用商標は5字であり, 離隔的観察においても,外観上の相違を十分認識することができる。\nまた,本件商標と引用商標の称呼は,「ケイスタ」が共通であるものの,本件商標 が4音であるのに対し,引用商標は6音である上,差異音である「ジオ」は,濁音 を含む明瞭に発音されるものであるから,離隔的観察においても,称呼上の相違を 十分認識することができる。\nさらに,引用商標からは,「軽自動車に関する役務の提供が受けられる場所」とい った観念が生じるが,本件商標からは,特定の観念を想起することはできないから, 本件商標と引用商標とは,観念が共通するものではない。 以上のとおり,本件商標と引用商標とは,外観及び称呼において相紛れるおそれ はなく,観念が共通するものでもないから,これらを総合して判断すると,本件商 標は,引用商標に類似する商標に当たらない。
・・・・
なお,原告は,被告の商号が「軽スタジオ茅ヶ崎株式会社」であること,被告が 「軽スタジオ」に代えて「軽スタ」という本件商標の使用を開始したこと,その後 も被告が「軽スタ」と表記した自己のウェブサイトに誘導するために「軽スタジオ」\nというキーワードメタタグを用いていること,被告は,被告の店舗において,「軽ス タ」と「軽スタジオ」を混在して継続使用することを表明していることなどを指摘\nするが,これらは,いずれも商標権者である被告に係る個別具体的な事情であって, 本件商標の指定役務全般に係る一般的,恒常的な取引の実情ではないから,上記判 断を左右するものではない。また,被告が,「軽スタジオ」と「軽スタ」のいずれの 標章も使用してきたとしても,被告の認識が,本件商標と引用商標を離隔的に(場 所と時間を異にして)観察する需要者の認識と一致するものとする根拠はないから, この点からしても上記判断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.11.10
平成29(行ケ)10032 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月7日 知的財産高等裁判所(4部)
本件審決は,本件発明10は,値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導 電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し,本件訂正発明10は,大量 の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく,導電性材 料を得ることを目的とするものであり,本件訂正発明10が達成しようとする目的 及び効果は,訂正事項10−1による訂正で変更されたと認められるから,訂正の 前後における発明の同一性は失われており,訂正事項10−1は,実質上特許請求 の範囲を変更するものであると判断した。 イ しかし,本件明細書には,従来技術において,酸化銀等の銀化合物の微粒子 を還元性有機溶剤へ分散したペースト状導電性組成物を基板上に塗布して加熱し配 線を製造する方法が知られていたが,ミクロンオーダーの銀粒子を使用した場合, 高い反応熱によりガスが大量発生し,不規則なボイドが形成されて導電性組成物が 破壊されやすくなったり,取扱上の危険性があるという問題点があり(【0004】 〜【0007】,【0010】),銀ナノ粒子を含む導電性組成物を用いると,銀ナノ 粒子の値段が高いという問題点があったこと(【0009】,【0010】)が記載さ れており,本件発明は,安価かつ安定な導電性材料用組成物を用いて得られる導電 性材料を製造する方法を提供することを目的とするとの記載があるのであるから (【0012】),本件発明の目的は,従来技術においてミクロンオーダーの銀粒子を 使用する際にガスが大量発生することによる問題を解消するとともに,値段が高い 銀ナノ粒子を使用することなく,導電性材料を製造することにあると認められる。 そして,本件発明10においては,その目的を,「銀の粒子が,0.1μm〜15 μmの平均粒径(メジアン径)を有する銀の粒子からなる」という構成,及び「第\n2導電性材料用組成物を,酸素,オゾン又は大気雰囲気下で150℃〜320℃の 範囲の温度で焼成して,前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」とい う構成を備えることによって達成している。\n他方,本件訂正発明10は,大量のガスを発生させることなく導電性材料を得る という目的を達成するため,「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより, 前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」という構成を備えている上,\n銀の粒子が,0.1μm〜15μmの平均粒径(メジアン径)を有するものから, 2.0μm〜15μmの平均粒径(メジアン径)を有するものに訂正されたことに より,訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており,値段が高い銀ナノ粒子を 使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について,より限定された ものとなっている。
ウ したがって,訂正事項10−1による訂正は,本件発明10が達成しようと する目的及び効果を変更するものではない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2017.11. 7
平成28(ワ)7143 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年10月25日 東京地方裁判所(40部)
本件得意先・粗利管理表(甲9)につき,原告は,原告代表\者のパソコ\nン内に入れられており,他の従業員はアクセスできない状態であったので, 秘密として管理されていたと主張する。 しかし,被告・被告会社代表者甲は,本件得意先・粗利管理表\について も従業員のパソコンからアクセスすることができたと供述しており,従業\n員全てがアクセスすることができないような形で同管理表が保管されてい\nたことを客観的に示す証拠はないから,上記原告の主張は採用できない。 また,原告は,本件得意先・粗利管理表を印刷したものを定例会議の際\nの資料として配布していたが,その際には「社外持出し禁」と表示した書\n面(甲16の1枚目)とともに配布したと主張する。 しかし,被告・被告会社代表者甲は,本件得意先・粗利管理表\につき打 ち合わせの際などに紙媒体で渡されたことはあるが,「社外持出し禁」と 表示した書面とともに本件得意先・粗利管理表\が配布されたことはないと 供述しており,定例会議が開催された際に本件得意先・粗利管理表が「社\n外持出し禁」などの表示が付された甲16の1枚目と同様の書面とともに\n従業員に配布されていたことを裏付ける証拠はないから,上記原告の主張 は採用できない。かえって,本件得意先・粗利管理表(甲9)自体には\n「社外持出し禁」などの表示が一切付されていないことからすると,本件\n得意先・粗利管理表は,定例会議などの打ち合わせの際に,「社外持出し\n禁」という表示を付すことなく,配布されていたと認めるのが相当である。
ウ 以上によれば,本件機密情報が記載された本件得意先・粗利管理表,本\n件規格書,本件工程表,本件原価計算書は,いずれも,原告において,そ\nの従業員が秘密と明確に認識し得る形で管理されていたということはでき ない。 これに対し,原告は,原告のような小規模な会社においては,その事業遂 行のために取引に関する情報を共有する必要があるから,従業員全てが機密 情報に接することができたとしても,秘密管理性が失われるわけではないと 主張する。しかし,原告における本件機密情報の上記管理状況によれば,原 告の会社の規模を考慮しても,同情報が秘密として管理されていたというこ とはできない。 また,原告は,従業員全員から入社時において業務上知り得た情報を漏え い,開示しない旨の誓約書兼同意書を徴求していた上,原告代表者は,会議\nの際などに本件機密情報を漏えい,開示してはならないことを従業員に伝え ていたと主張する。しかし,従業員全員から秘密保持を誓約する書面の提出 を求めていたとの事実は,本件機密情報が秘密として管理されていなかった との上記認定を左右するものではなく,また,原告代表者が定例会議等の際\nに本件機密情報を漏えい,開示してはならないと従業員に伝えていたとの主 張を客観的に裏付けるに足る証拠はない。 エ したがって,本件得意先・粗利管理表,本件規格書,本件工程表\,本件 原価計算書に記載された情報は,被告甲が秘密保持義務を負う機密情報に は当たらない。
2017.11. 7
平成29(行ケ)10053 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年10月25日 知的財産高等裁判所(1部)
そして,本件商標が,漢字を書してなるものであるのに対し,引用商標は,片仮 名又はローマ字を書してなるものであるから,本件商標と引用商標の外観は同一で あるとはいえない。もっとも,本件商標と引用商標は,いずれも格別の特徴を有し ない文字からなる商標であり,我が国において,外来語以外でも同一語の漢字表記\nと片仮名表記又はローマ字表\記が併用されることが多く見られる事情があること, 証拠(甲34〜36)及び弁論の全趣旨によれば,「千鳥屋」をローマ字で表記する\nことも一般的に行われていることが認められることなどを考慮すると,本件指定商 品及び引用商標の指定商品の需要者にとって,文字種が異なることは,本件商標と 引用商標が別異のものであることを認識させるほどの強い印象を与えるものではな いというべきである。 次に,本件商標から,「千鳥屋」という菓子屋の屋号又は商号との観念が生じるこ とについては当事者間に争いがなく,本件商標からは,「千鳥屋」という菓子屋の屋 号又は商号との観念が生じるものと認められる。 また,証拠(甲39)及び弁論の全趣旨によれば,「チドリヤ」という語は,広辞 苑等の辞書に掲載されていないものの,広辞苑第6版には,「チドリ」に関して「千 鳥」の語が掲載され,「1)多くの鳥。2)チドリ目チドリ科の鳥の総称。」などの意味 の記載と共に,「ちどり−あし【千鳥足】」,「ちどり−やき【千鳥焼】」などの例が挙げられていること,「屋」という語が,屋号又は商号を表す際に用いられるものであ\nることなどが認められる。そして,本件商標の登録査定時において,「千鳥屋」が, 九州地区,関西地区,関東地区では著名な菓子屋の屋号及び商号であり,「千鳥屋」 という屋号及び商号が全国的にその名を知られているものであることについては当 事者間に争いがなく,引用商標は,「千鳥屋」の称呼を片仮名又はローマ字で表記し\nたものといえることからすると,本件商標と同様に,引用商標から「千鳥屋」とい う菓子屋の屋号又は商号との観念が生じるものと認めるのが相当である。このこと は,検索サイトの検索結果(甲24)において,「チドリヤ」及び「CHIDOR IYA」の検索結果として,「千鳥屋」が多数検索されることや,「チドリヤ」の 文字を検索した際に,「千鳥屋」の検索の誤りであることを指摘する検索サイトが複 数あることからも裏付けられる。
ウ 本件指定商品及び引用商標の指定商品は,いずれも基本的には,さほど 高価とはいえない日常的に消費される性質の商品(食品)であり,これらは同一の 営業主により製造又は販売されることがあり,同一店舗で取り扱われることも多い ことからすると,本件指定商品については,同一営業主の製造又は販売に係る商品 と誤認され,商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるといえる。このよ うに,本件指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品であり,その取引者,需要 者には,広く一般の消費者が含まれるから,商品の同一性を識別するに際して,そ の名称,称呼の果たす役割は大きく,重要な要素となるというべきである。なお, 一般の消費者としては,商標の外観を見て商品の出所を判断することも少なくない と考えられるものの,前記認定のとおり,本件商標と引用商標の外観については別 異のものであることを認識させるほどの強い印象を与えるものではない。そうする と,本件商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,上記のような取引の実情 をも考慮すると,外観及び観念に比して,称呼を重視すべきであるといえる。 以上によれば,本件商標と引用商標は,称呼において同一であり,両商標からは 同一の観念を生じるものといえるから,本件指定商品の需要者にとって,引用商標 と同一の称呼を生じる本件商標を付した商品を,引用商標を付した商品と誤認混同 するおそれがあるものと認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.10.30
平成28(行ケ)10185 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月23日 知的財産高等裁判所(3部)
(1) 原告は,特許権取得のための支援活動等を行う個人事業主であり,自らも 特許技術製品の開発等を行っている。
(2) 特許願(甲54)の請求項に記載されている発明(原告発明)は,自分(原 告)の発明である。
(3) 原告発明に係るおむつの開発に着手した理由は,日頃から医療分野に興味 を持っていたこと,特に子供の頃から●●(省略)●●ことや,●●(省略) ●●,排せつの問題に関する知識があったこと,さらには,災害の発生,外 国人の需要などにより,商品開発をして市場に提供するチャンスがあると考 えたことによる。
(4) 原告発明は,紙おむつの外層シートに新たな構造を付加することを特徴と\nするものであり,弾性構造のない部分を有し,かつ,(テープ型でなく)パ\nンツ型のおむつが最も適する。
(5) 原告としては,自ら発明を実施する能力がないので,ライセンスや他の業\n者に委託して製造してもらうことなどを考えており,製品化の準備として, 市販品のおむつ(被告製品など)に手を加えて試作品(サンプル)を製作し ていた。
(6) 実際に上記試作品をおむつの製造業者等に持ち込んだことはまだないが, インターネット上で特許発明の実施の仲介を行う業者や不織布を取り扱う業 者に対し,原告発明の実施の可能性について尋ねたことはある。
(7) その際,原告としては,原告発明を製品化する場合,被告の本件特許に抵 触する可能性があると考えていたので,率直にその旨を上記の業者らに伝え\nたところ,いずれも,その問題(特許権侵害の可能性)をクリアしてからで\nないと,依頼を受けたり,検討したりすることはできないといわれ,それ以 上話が進められなかった。
(8) 原告としては,設計変更等による回避も考えたが,原告発明を最も生かせ る構造(実施例)は,被告の本件特許発明の技術的範囲にあると思われたた\nめ,原告発明を実施する(事業化する)には,本件特許に抵触する可能性を\n解消する必要性があると判断し,また,専門家から本件特許に無効理由があ るとの意見をもらったことから,本件無効審判請求を行った。
3 検討
以上のとおり,原告は,単なる思い付きで本件無効審判請求を行っているわ けではなく,現実に本件特許発明と同じ技術分野に属する原告発明について特 許出願を行い,かつ,後に出願審査の請求をも行っているところ,原告として は,将来的にライセンスや製造委託による原告発明の実施(事業化)を考えて おり,そのためには,あらかじめ被告の本件特許に抵触する可能性(特許権侵\n害の可能性)を解消しておく必要性があると考えて,本件無効審判請求を\n害の可能性)を解消しておく必要性があると考えて,本件無効審判請求を行っ\nたというのであり,その動機や経緯について,あえて虚偽の主張や陳述を行っ ていることを疑わせるに足りる証拠や事情は存しない。 以上によれば,原告は,製造委託等の方法により,原告発明の実施を計画し ているものであって,その事業化に向けて特許出願(出願審査の請求を含む。) をしたり,試作品(サンプル)を製作したり,インターネットを通じて業者と 接触をするなど計画の実現に向けた行為を行っているものであると認められる ところ,原告発明の実施に当たって本件特許との抵触があり得るというのであ るから,本件特許の無効を求めることについて十分な利害関係を有するものと\nいうべきである。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2017.10.30
平成28(行ケ)10189 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月25日 知的財産高等裁判所(3部)
・・・以上のような発明の詳細な説明の記載を総合してみれば, 本願発明における本願組成要件と本願物性要件との関係に関して,次のよ うな理解が可能といえる。すなわち,まず,Nb2O5成分は,屈折率を高\nめ,分散を大きくしつつ部分分散比を小さくし,化学的耐久性及び耐失透性 を改善するのに有効な必須の成分であること(段落【0033】)から,本 願組成要件において,その含有量が40%超65%以下とされ,組成物中で 最も含有量の多い成分とされていることが理解できる。また,ZrO2成分 は,屈折率を高め,部分分散比を小さくする効果があり(段落【0031】), 他方,TiO2成分は,屈折率を高め,分散を大きくする効果がある反面, その量が多すぎると部分分散比が大きくなること(段落【0029】)から, 「部分分散比が小さい光学ガラス」を得るためには,ZrO2及びNb2O5 の含有量に対してTiO2の含有量が多くなりすぎることを避ける必要が あり,そのために,TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値を一定以下とす るものであること(段落【0073】)が理解でき,これが,本願組成要件 において,各成分の含有量とともに規定される「TiO2/(ZrO2+N b2O5)が0.2以下であり」との特定に反映され,本願発明の課題の解決 (高屈折率高分散であって,かつ,部分分散比が小さい光学ガラスを提供す ること)にとって重要な構成となっていることが理解できる。
ウ 他方,本願明細書の発明の詳細な説明における実施例の記載をみると,本 願組成要件を満たす実施例(No.8,9,21,24〜38,41,44, 45,48〜57,60〜66)に係る組成物が,本願物性要件の全てを満 たすことが示されているが,これらの組成物の組成は,本願組成要件に規定 された各成分の含有比率,「TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値」及び 「SiO2,B2O3,TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO,Sr O,Li2O,Na2Oの合計含有量」の各数値範囲の一部のもの(具体的に は,別紙審決書4頁23行目から5頁8行目までに記載のとおりである。) でしかなく,上限から下限までの数値範囲を網羅するというものではない。 すなわち,本願組成要件に規定された各数値範囲は,実施例によって本願物 性要件を満たすことが具体的に確認された組成の数値範囲に比して広い数 値範囲となっており,そのため,本願組成要件で特定される光学ガラスのう ち,実施例に示された数値範囲を超える組成に係る光学ガラスについても, 本願物性要件を満たし得るものであることを当業者が認識できるか否かが 問題となる。
そこで検討するに,まず,光学ガラスの製造に関しては,ガラスの物性が 多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため,個々の成分 の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして,所望の物性のための 必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能\であり,そのた め,ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり,当該 物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには,既知の光学 ガラスの配合組成を基本にして,その成分の一部を,当該物性に寄与するこ とが知られている成分に置き換える作業を行い,ターゲットではない他の 物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤 を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順であること が認められ,このことは,本願出願時において,光学ガラスの技術分野の技 術常識であったものと認められる(甲5,6,17,18,21,22。以 上のような技術常識の存在については,当事者間に争いがない。)。 そして,上記のような技術常識からすれば,光学ガラスの製造に当たっ て,基本となる既知の光学ガラスの成分の一部を,物性の変化を調整しなが ら,他の成分に置き換えるなどの作業を試行錯誤的に行うことは,当業者が 通常行うことということができるから,光学ガラス分野の当業者であれば, 本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして,特定の成分の含有量 をある程度変化させた場合であっても,これに応じて他の成分を適宜増減 させることにより,当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して,も との組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能で\nあることを理解できるものといえる。そして,前記イのとおり,当業者は, 本願明細書の発明の詳細な説明の記載から,本願物性要件を満たす光学ガ ラスを得るには,「Nb2O5成分を40%超65%以下の範囲で含有し, かつ,TiO2/(ZrO2+Nb2O5)を0.2以下とする」ことが特に 重要であることを理解するものといえるから,これらの条件を維持しなが ら,光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のよ うな成分調整を行うことにより,高い蓋然性をもって本願物性要件を満た す光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきであ\nる。なお,これを具体的な成分に即して説明するに,例えば,本願発明の最 多含有成分であるNb2O5についてみると,当業者であれば,実施例中最 多の含有量(53.61%)を有する実施例50において,TiO2/(Z rO2+Nb2O5)を0.2以下とする条件を維持しながら,必須成分であ るTiO2(6.48%),ZrO2(1.85%)又は任意成分であるNa 2O(9.26%)から適宜置換することによって,本願物性要件を満たし つつ,Nb2O5を増やす調整を行うことも可能であることを理解するもの\nと考えられ,同様に,実施例中Nb2O5の含有量が最少(43.71%)で ある実施例24において,TiO2/(ZrO2+Nb2O5)を0.2以下 とする条件を維持しながら,もう1つの主成分であるSiO2(24.76 %),必須成分であるZrO2(10.48%)又は任意成分であるLi2O (4.76%)への置換により,本願物性要件を満たしつつ,Nb2O5を減 らす調整を行うことも可能であることを理解するものと考えられる(以上\nのことは,本願組成要件に係るNb2O5以外の成分についても,同様にい えることであり,この点については,原告の前記第3の2⑵記載の主張が参 考となる。)。 してみると,本願明細書の実施例に係る組成物の組成が,本願組成要件に 規定された各成分の含有比率,「TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値」 及び「SiO2,B2O3,TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO, SrO,Li2O,Na2Oの合計含有量」の各数値範囲の一部のものにす ぎないとしても,本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時に おける光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば,当業者は,本願組成要件に規 定された各数値範囲のうち,実施例として具体的に示された組成物に係る 数値範囲を超える組成を有するものであっても,高い蓋然性をもって本願 物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るという べきであり,更に,そのように認識し得る範囲が,本願組成要件に規定され た各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか 否かについては,成分ごとに,その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行 うことによって判断される必要があるものといえる。
エ これに対し,本件審決は,本願明細書の実施例に記載されたガラス組成の 数値範囲については,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを 確認することができるが,実施例に記載されたガラス組成の数値範囲を超 える部分については,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが, 実施例の記載により裏付けられているとはいえないとし,また,その他の発 明の詳細な説明のうち,部分分散比に影響を与える成分であるTiO2,Z rO2,Nb2O5,WO3及びLi2Oの記載(段落【0029】等)につい ても,好ましい範囲等として記載される数値範囲が実施例に記載されたガ ラス組成の数値範囲より広い範囲となっていることから,実施例の数値範 囲を超える部分について,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られるこ とを裏付けるとはいえないとし,更に,本願出願時の技術常識(光学ガラス の物性は,ガラスの組成に依存するが,構成成分と物性との因果関係が明確\nに導かれない場合の方が多いことなど)に照らしても,本願組成要件の数値 範囲にわたって,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業 者が認識し得るとはいえないと判断したものである。 このように,本件審決の判断は,本願組成要件に規定された各成分の含有 比率,「TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値」及び「SiO2,B2O3, TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO,SrO,Li2O,Na2O の合計含有量」の各数値範囲のうち,当業者が本願物性要件を満たす光学ガ ラスが得られるものと認識できる範囲を,実施例として具体的に示された ガラス組成の各数値範囲に限定するものにほかならないところ,上記ウで 述べたところからすれば,このような判断は誤りというべきである。本件審 決は,上記ウのとおり,本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必 要とされる,本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを 認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全 体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく,実 施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の 一部にとどまることをもって,直ちに本願のサポート要件充足性を否定し たものであるから,そのような判断は誤りといわざるを得ず(更に言えば, 上記のような具体的な検討の結果に基づく拒絶理由通知がされるべきであ ったともいえる。),また,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものとい える。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2017.10.27
平成29(行ケ)10094 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年10月24日 知的財産高等裁判所
原告は,平成6年に,伝統的工芸品産業振興協会の伝統工芸士認定事業に 参加し,構成員10名が伝統工芸士の認定を受け,伝統的工芸品表\示事業を開始し て,伝統証紙(経済産業大臣が指定した技術・技法,原材料で製作され,産地検査 に合格した製品に貼られる,「伝統マーク」をデザインした証紙)の表\示を始めた。 そして,原告は,その頃から,原告の商標として「豊岡杞柳細工」の使用を開始し, 平成13年には,更に構成員5名が伝統工芸士の認定を受けた。(甲6の9,7,\n8,9の4)
(ウ) 平成18年4月1日,地域団体商標制度が導入されたことから,原告は, 別紙引用商標目録記載のとおり,「豊岡杞柳細工」の文字からなる引用商標を出願 し,平成19年3月9日,指定商品を兵庫県豊岡市及び周辺地域で生産された杞柳 細工を施したこうり,柳・籐製のかご及び柳・籐製の買い物かごとする地域団体商 標として,設定登録を受けた。(甲2) なお,地域団体商標の制度は,従前,地域の名称と商品(役務)の名称等からな る文字商標について登録を受けるには,使用により識別力を取得して商標法3条2 項の要件を満たす必要があったため,事業者の商標が全国的に相当程度知られるよ うになるまでの間は他人の便乗使用を排除できず,また,他人により使用されるこ とによって事業者の商標としての識別力の獲得がますます困難になるという問題が あったことから,地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り,地域ブラン ドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として,いわ ゆる「地域ブランド」として用いられることが多い上記文字商標について,その商 標が使用された結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表\示するもの として需要者の間に広く認識されているときは,商標登録を受けることができると するものである。また,地域団体商標は,事業者を構成員に有する団体がその構\成 員に使用をさせる商標であり,商品又は役務の出所が当該団体又はその構成員であ\nることを明らかにするものである。
・・・・
(オ) 前記(イ)のとおり,「豊岡杞柳細工」は,伝統的工芸品に指定されている ため,通商産業省伝統的工芸品産業室が監修し伝統的工芸品産業振興協会が編集し て年1回発行される冊子「伝統的工芸品の本」に毎回掲載され,豊岡杞柳細工の歴 史,特徴,製法等について,原告商品の写真と一緒に紹介されている。また,前記(ウ) のとおり,引用商標は,地域団体商標として設定登録されているため,経済産業省・ 特許庁が年1回発行する冊子「地域団体商標」に毎回掲載され,引用商標の構成,\n権利者,指定商品,原告商品の写真,連絡先及び関連ホームページのアドレスなど が紹介されている。(甲6の9,21,22)
・・・
イ 前記アの認定事実によれば,豊岡杞柳細工は,豊岡地方において古くから製 作されてきたものであり,経済産業大臣により伝統的工芸品に指定され,「豊岡杞 柳細工」という引用商標が,地域団体商標として設定登録されているものである。 また,引用商標を付した原告商品は,豊岡地方に所在する店舗やミュージアム等の 施設で展示・販売されるほか,東京都内の百貨店等で展示会を開催し,インターネ ットを介した通信販売をするなどして,豊岡地方以外でも販売されている。さらに, 原告商品は,伝統的工芸品に指定され,地域団体商標の登録を受けていることから, 経済産業省がそれぞれ年1回発行する冊子に毎年掲載されているほか,多数の書籍, 雑誌,テレビ等において,豊岡地方の伝統的工芸品であることや,その歴史,製法, 特徴等が紹介されている。これらの事情を考慮すると,引用商標を付した原告商品 は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告又はその構成員の業務を\n示すものとして,需要者の間に広く認識されており,一定の周知性を有していたも のと認められる。 なお,引用商標は,地域の名称である「豊岡」と商品の普通名称である「杞柳細 工」を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる地域団体商標であるから,\nその構成自体は,独創的なものとはいえない。
(4) 商品の関連性その他取引の実情
ア 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (ア) 被告は,京都府に在住し,「拓心」の屋号で,かばんの企画,製造,販売 等の事業を営む者である。被告は,平成20年に,伝統的工芸品の作り手とデザイ ナーやプロデューサーなど様々な分野の専門家が交流を図り,パートナーを選択し て新商品開発研究を行って試作品を作り,発表し意見を求める展示会に参加する本\n件事業に加わり,原告のパートナーとなったが,新商品の開発には至らず,同事業 は終了した。(甲13の1〜5,23の2) しかし,被告は,杞柳細工に商品価値を見出したことから,平成22年に本件商 標を出願し,平成23年に本件商標の設定登録を受けた。そして,被告は,本件商 標を付した柳細工のかばん(バッグ,アタッシュケース等。以下,被告の販売する 上記かばんを総称して「被告商品」ということがある。)の製造を開始した。(甲 1,12,23の2・5)
(イ) 被告商品は,豊岡地方のほか,京都府に所在する被告の店舗や百貨店等で 販売されている。また,平成25年及び平成26年に,社団法人京都国際工芸セン ターにおいて,「豊岡柳KAGO展」などと題する展示会が1週間開催されるなど した。(甲23の3・4) さらに,被告商品は,被告が開設したウェブページや他のインターネットのサイ トを介するなどして,通信販売も行われている。(甲23の1)
(ウ) 被告が作成した被告商品のパンフレットや,被告商品の展示会を紹介する ウェブページには,本件商標及び被告商品の写真が掲載されている。そして,上記 パンフレット等に掲載された被告商品の写真は,原告のパンフレット等に掲載され た,原告商品である杞柳細工のかばん類や籠類と外観が類似するものも少なくない。 (甲9の1〜5,10の1〜3,23の1,23の3〜6) イ 本件商標の指定商品は,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具 入れ,かばん金具」である。一方,前記(3)のとおり,原告商品は,引用商標の指定 商品であるこうり(第18類),かご及び買い物かご(第20類)のほかに,ハン ドバッグ,アタッシュケース等のかばん類も含むものである。 したがって,本件商標の指定商品と原告商品とは,商品の用途や目的,原材料, 販売場所等において共通し,同一又は密接な関連性を有するものであり,取引者及 び需要者が共通する。 また,前記アのとおり,被告商品のパンフレット等に掲載されている被告商品の 写真は,原告商品と外観が類似するものも少なくない。そして,本件商標の指定商 品である「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具」が日常的に 使用される性質の商品であることや,その需要者が特別の専門的知識経験を有する 者ではないことからすると,これを購入するに際して払われる注意力は,さほど高 いものではない。 このような被告の本件商標の使用態様及び需要者の注意力の程度に照らすと,被 告が本件商標を指定商品に使用した場合,これに接した需要者は,前記(2)のとおり 周知性を有する「豊岡杞柳細工」の表示を連想する可能\性がある。
(5) 小括
以上のとおり,1)本件商標は,外観や称呼において引用商標と相違するものの, 本件商標からは,豊岡市で生産された柳細工を施した製品という観念も生じ得るも のであり,かかる観念は,引用商標の観念と類似すること,2)引用商標の表示は,\n独創性が高いとはいえないものの,引用商標を付した原告商品は,原告の業務を示 すものとして周知性を有しており,伝統的工芸品の指定を受け,引用商標が地域団 体商標として登録されていること,3)本件商標の指定商品は,原告商品と同一又は 密接な関連性を有するもので,原告商品と取引者及び需要者が共通することその他 被告の本件商標の使用態様及び需要者の注意力等を総合的に考慮すれば,本件商標 を指定商品に使用した場合は,これに接した取引者及び需要者に対し,原告の業務 に係る「豊岡杞柳細工」の表示を連想させて,当該商品が原告の構\成員又は原告と の間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属す\nる関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され,商品の出所につき誤認を 生じさせるとともに,地域団体商標を取得し通商産業大臣から伝統的工芸品に指定 された原告の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその\n希釈化(いわゆるダイリューション)を招くという結果を生じかねない。 そうすると,本件商標は,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれが ある商標」に当たると解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2017.10.27
平成29(ネ)10061 著作者人格権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成29年10月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,原判決が,本件建物外観(外装スクリーン部分に限られない。 以下同じ。)の設計に関し,控訴人代表者の創作的関与並びに共同創作の意\n思及び事実を認めず,また,本件建物外観を控訴人外観設計の二次的著作物 とも認めなかったのは誤りであるとして,要旨,次のとおり主張する。 ア 控訴人設計資料(甲7,7の2)及び控訴人模型(甲8)から成る控訴 人外観設計(外装スクリーン部分に限られない。以下同じ。)は,控訴人 設計資料により平面上で具体的に表現され,かつ,控訴人模型により立体\n物として具体的に表現されており,二次元での平面表\現としても,当該平 面及び模型から観念される立体表現としても,単なるアイデアではなく,\n具体的な表現である。
イ そして,控訴人外観設計は,具体的な立体形状の組亀甲柄を建築物の外 観に適用したことその他多くの点(本質的特徴部分)において,表現上の\n個性が発揮されているから,創作性を有するものであり,表現としてあり\nふれているとはいえない。
ウ したがって,控訴人外観設計は,それ自体,「建築の著作物」(著作権 法10条1項5号)であるとともに,形状,色彩,線及び明暗で思想又は 感情を表現したものであるから,「美術の著作物」(同項4号)又は単な\nる「美術」(同法2条1項1号)の範囲に属する「著作物」にも該当する。 エ 本件建物外観は,控訴人外観設計に表現された建物の本質的特徴を感得\nすることができるものであって,控訴人外観設計に基づいて制作されたも のであるところ,控訴人と被控訴人竹中工務店は,控訴人の設計を被控訴 人竹中工務店が引き継ぐ形において,共同で本件建物の外観を設計したと いえるので,本件建物外観は共同著作物である。万が一,共同著作物では ないとしても,被控訴人竹中工務店は,控訴人外観設計の本質的特徴を複 製又は翻案する形で本件建物外観を設計したから,本件建物外観は控訴人 外観設計を原著作物とする二次的著作物に当たる。
(2) しかしながら,控訴人の主張は採用できない。理由は次のとおりである。 ア まず,控訴人(控訴人代表者)は,控訴人設計資料を作成するに当たり,\n外装スクリーン部分以外は全て被控訴人竹中工務店作成に係る資料を流用 しており,手を加えていない事実を自認している。したがって,控訴人外 観設計のうち外装スクリーンを除くその余の部分については,そもそも控 訴人代表者の創作的関与を認める余地がない。\nイ 次に,外装スクリーン部分について,控訴人設計資料及び控訴人模型に 基づく控訴人代表者の提案内容が「建築の著作物」の創作に関与したと認\nめ得るだけの具体性ある表現といえないことは,原判決が指摘するとおり\nであって,控訴理由を踏まえてもその認定判断は覆らない。 控訴人は,控訴人代表者の上記提案が「実際建築される建物に用いられ\nる組亀甲柄より大きいイメージ」として作成されていた点に関し,たとえ そうであったとしても,「具体的な建物の外観が視覚的に,一般人にとっ て看取可能な形で図面上表\現されていれば,それは具体的な表現である(か\nら,上記提案がアイデアにすぎないことの根拠にはならない)」などとも 主張するが,格子の大きさ一つ取っても,その大きさ次第で,いくらでも 集合体としての外観デザインが変わり得ることは後記のとおりであるから, 控訴人が想定していた現実の外観は,控訴人設計資料及び控訴人模型をも ってしては,いまだ「視覚的に,一般人にとって看取可能な形で図面上表\ 現されていた」といえず,その主張はやはり採用できないといわざるを得 ない。
ウ また,仮に,控訴人設計資料及び控訴人模型に現れた外装スクリーン部 分の表現そのもの(図案)に関して,「建築の著作物」に限らず,何らか\nの著作物性(創作性)を認め得るとしても,(外装スクリーンに関する) 控訴人代表者の提案と現実に完成した本件建物の外観とでは,2層3方向\nの連続的な立体格子構造(組亀甲柄)が採用されている点と,せいぜい色\n(白色)が共通するのみであり,少なくとも立体格子の柄や向き,ピッチ, 幅,隙間,方向が相違することは原判決が認定するとおりであるところ, 実際に本件建物の外観を撮影した写真(甲5の1・2)と控訴人設計資料 及び控訴人模型とを見比べてみても(あるいは,乙2の比較図面を参照し ても),例えば,個々の格子を意識させるものであるかどうか(本件建物 は全体として細かい編み込み模様になっており,遠目に見ると個々の格子 をそれほど意識させない態様であるのに対し,控訴人代表者の提案は,個々\nの格子が大きく,格子を構成する直線も際立っており,遠目に見てもその\n存在を意識させるとともに,六角形のデザインがより強調される態様とな っている。),編み込み模様の編み目の向き(本件建物は横方向を意識さ せるのに対し,控訴人代表者の提案は縦方向を意識させる。),外装スク\nリーンの裏側にある建物自体の骨格を意識させるかどうか(本件建物の外 装スクリーンは編み目が細かく,裏側にある建物自体の骨格を意識させな いのに対し,控訴人代表者の提案のそれは編み目が粗く,裏側にある建物\n自体の骨格が透けて見えてその存在を意識させる。)などの点において大 きく異なっており,全体としての表現や見る者に与える印象が全く異なる\nことは明らかといえる。 この点,控訴人は,控訴理由書等において,立体格子のピッチ,幅,隙 間や,向き,方向などの相違は,いずれも本件建物の外観(見た目)に特 段の違いをもたらすとはいえず,表現の本質的特徴を違えるほどの違いと\nはいえない旨主張するが,同じ組亀甲柄を採用したデザインでも,上記の 諸要素等の違い(格子自体のデザインはもちろん,その大きさや配置,組 み合わせ方等の違い)により,様々な表現があり得ることは,本件で提出\nされている関係各証拠(甲30〜34,乙12,13など。乙号証は枝番 号を含む。)からも明らかといえるし,実際に本件建物外観と控訴人代表\n者の提案とで表現が大きく異なることは前記のとおりであるから,採用で\nきない。
エ そうすると,結局のところ,外装スクリーン部分に関し本件建物外観と 控訴人代表者の提案とで共通するのは,ほぼ2層3方向の連続的な立体格\n子構造(組亀甲柄)を採用した点に尽きるのであって,それ自体はアイデ\nアにすぎない(前記のとおり,建物の外観デザインに組亀甲柄を採用する としても,その具体的表現は様々なものがあり得るのであるから,組亀甲\n柄を採用するということ自体は,抽象的なアイデアにすぎない。)という べきであるから,控訴人代表者が本件建物外観について創作的に関与した\nとは認められないし,控訴人代表者の提案が本件建物の原著作物に当たる\nとも認められない。
(3) 以上によれば,原判決が,本件建物外観の設計に関し,控訴人代表者の創\n作的関与並びに共同創作の意思及び事実を認めず,かつ,本件建物外観を控 訴人外観設計の二次的著作物とも認めなかったことは相当であり,その認定 判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2017.10.27
平成29(ネ)10042 損害賠償請求控訴事件(本訴),著作権侵害差止等請求控訴事件(反訴) 著作権 民事訴訟 平成29年10月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
著作権法は思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(著作\n権法2条1項1号),複製に該当するためには,既存の著作物とこれに依拠して作 成された物の共通する部分が著作権法によって保護される思想又は感情の創作的な 表現に当たることが必要である。
1審原告追加部分は,本件1審被告ファイルに対し,1)「ご希望時間」欄 を新設して同欄内に午前10時から午後5時30分までの30分刻みの表示をし,\n2)「住所・TEL」欄を「住所」欄と「電話番号」欄に分け,住所欄に「〒」の表\n示をし,3)「事故発生状況」欄の空白部分の代わりに「□その他」を新設し,4)「 あなた」欄の「□自動車運転」「□自動車同乗」を併せて「□自動車(□運転,□ 同乗)」とするとともに,「□バイク運転」「□バイク同乗」を併せて「□バイク (□運転,□同乗)」とし,5)「初診治療先」「治療先2」「治療先3」欄をそれ ぞれ「治療先1/通院回数」「治療先2/通院回数」「治療先3/通院回数」とした 上で,それぞれの欄内に「病院名: /通院回数: 回」の表示をし,6)「自賠責 後遺障害等級」「簡単な事故状況図をお書きください。」「受傷部位に印をつけて ください。」の各欄を設けた上,「受傷部位に印をつけてください。」欄に人体の 正面視図及び後面視図を設け,7)相談者の「保険会社・共済名」欄内のチェックボ ックス及び選択肢を削除し,「加害者の保険」「保険会社名」の各欄を「加害者の 保険会社名」欄にするとともに同欄内のチェックボックス及び選択肢を削除したも のである。これに対し,1審被告アンケート1及び2は,いずれも上記6)の人体の 正面視図及び後面視図のデザインが1審原告追加部分と異なるが,その他の点は上 記1)から7)の点において1審原告追加部分と同一の記載がされている。 まず,1審原告追加部分と1審被告アンケート1及び2に共通する上記1) の点については,相談希望者から必要な情報を聴取するという本件1審原告ファイ ルの目的上,相談の希望時間を聴取することは一般的に行われることで,そのため に「ご希望時間」欄を設けて欄内に一定の時間を30分ごとに区切った時刻を掲記 することは一般的にみられるありふれた表現であるから,著作者の思想又は感情が\n創作的に表現されているということはできない。\nまた,1審原告追加部分と1審被告アンケート1及び2に共通する上記2)〜5)及 び7)の点は,いずれも,本件1審被告ファイルの質問事項欄を統合又は分割し,あ るいは,各質問事項欄内の選択肢やチェックボックスなどを相談者が記載しやすい ように追加又は変更したものであり,いずれも一般的にみられるありふれた表現で\nあるから,著作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない。\nさらに,1審原告追加部分と1審被告アンケート1及び2に共通する上記6)の点 については,相談希望者から必要な情報を聴取するという本件1審原告ファイルの 目的に照らすと,事故状況や被害状況を聴取するために,自賠責後遺障害等級を質 問事項に設け,事故状況図や受傷部位を質問事項に入れ,受傷部位について正面視 及び後面視の各人体図を設けて印を付けるよう求めたことは,いずれも一般的に見 られるありふれた表現であるから,著作者の思想又は感情が創作的に表\現されてい るということはできない。 以上によると,1審原告追加部分と1審被告アンケート1及び2の共通する部分 は,いずれも著作権法によって保護される思想又は感情の創作的な表現には当たら\nないから,1審被告アンケート1及び2は1審原告追加部分の複製には該当しない というべきである。なお,1審原告追加部分と1審被告アンケート1及び2では, 正面視及び後面視の各人体図のデザインが異なるから,人体図について1審被告ア ンケート1及び2が1審原告追加部分の複製に該当することはない。 1審原告は,1審被告において1審原告追加部分に著作物性があることを認めて いるから,この点について裁判上の自白が成立し,裁判所を拘束すると主張するが, 本件訴訟において,1審被告が1審原告追加部分の著作物性を自認したものとは認 めることができないから,1審原告の上記主張は失当である。
5 争点8(本件1審被告ファイルの編集著作物性の有無)について
ある編集物が編集著作物として著作権法上の保護を受けるためには,素材 の選択又は配列によって創作性を有することが必要である(著作権法12条1項)。
(2) 本件1審被告ファイルには,「氏名・フリガナ」,「年齢・性別・職業」, 「住所・TEL」,「メールアドレス」,「事故日」,「事故発生状況」,「あな た」(判決注:相談希望者),「加害者」,「受傷部位」,「傷病名」,「症状」, 「治療経過」,「初診治療先」,「治療先2」,「治療先3」,「あなたの保険」, 「保険会社・共済名」,「加害者の保険」,「保険会社名」の欄が順に設けられ, それぞれ左欄には上記の各項目タイトルが,右欄には各項目に対応する情報を記載 する体裁となっていること,これらの各欄に引き続いて,「相談内容・お問い合わ せ」欄が設けられ,その下に情報を記載するための空白が設けられていることが認 められる。また,本件1審被告ファイルの「事故発生状況」,「あなた」,「加害 者」,「受傷部位」,「傷病名」,「治療経過」,「あなたの保険」,「保険会社 ・共済名」,「加害者の保険」,「保険会社名」の右欄には,複数の選択肢とそれ に対応したチェックボックスが設けられていることが認められる。
(3) まず,相談者から相談に先立ち交通事故に関する必要な情報を把握すると いう本件1審被告ファイルの性質上,1)相談者個人特定情報,2)交通事故の具体的 状況,3)相談者の受傷及び治療の状況並びに4)事故関係者の保険加入状況に関する 情報のほか,5)具体的な相談希望内容についての情報を収集する必要があることは, 当然のことであると考えられる。本件1審被告ファイルは,「氏名・フリガナ」, 「年齢・性別・職業」,「住所・TEL」,「メールアドレス」,「事故日」,「 事故発生状況」,「あなた」,「加害者」,「受傷部位」,「傷病名」,「症状」, 「治療経過」,「初診治療先」,「治療先2」,「治療先3」,「あなたの保険」, 「保険会社・共済名」,「加害者の保険」,「保険会社名」の欄を順に設け,これ らの各欄に引き続いて,「相談内容・お問い合わせ」欄を設け,その下に情報を記 載するための空白を設けているが,これらの事項は,上記の本件1審被告ファイル の性質上,当然に設けられるべき項目であって,その順番も,上記1)から5)の順に, それぞれの必要項目を適宜並べたに過ぎないというほかないから,これらの項目を 上記のとおり設けたことによって,素材の選択又は配列による創作性があるという ことはできない。 また,上記のような本件1審被告ファイルの性質上,これらの事項に関連する具 体的な項目の選択についても自ずと限定されるところ,本件1審被告ファイルのチ ェックボックスを付した各項目は,いずれもありふれたものというほかなく,その ような項目を適宜並べたものというほかないから,素材の選択又は配列による創作 性があるということはできない。この点について,1審被告は,特に,「事故発生 状況」及び「傷病名」の項目の選択について主張するが,「事故発生状況」につい ての「□追突」,「□正面衝突」,「□出合い頭衝突」,「□信号無視」,「□無 免許」,「□飲酒」という項目及び「傷病名」についての「□脳挫傷」,「□捻挫 挫傷」,「□打撲」,「□脱臼」,「□骨折」,「□靱帯損傷」,「□醜状痕」, 「□偽関節変形」,「□神経症状」,「□CRPS」,「□機能障害」,「□神経\n麻痺」,「□筋損傷,「□その他( )」という項目は,交通事故において は通常見られる事故態様及び傷病名であって,素材の選択又は配列による創作性が あるということはできない。なお,1審被告が主張するように,事故現場の図面や 「事故当日の天候」,「道路の見とおしの状況」,「道路状況」,「標識や信号機 の有無や場所」,「交通量」などを記載させることも考えられるが,これらの項目 は,事故態様そのものである「□追突」,「□正面衝突」,「□出合い頭衝突」, 「□信号無視」,「□無免許」,「□飲酒」といった項目に比べて必要性が高いと はいえず,上記の事故現場の図面や「事故当日の天候」等の項目がないことは,素 材の選択又は配列による創作性があることを基礎づけるということはできない。 さらに,チェックボックスを,上記のような項目と組み合わせて配置したからと いって,素材の選択又は配列による創作性が認められるものではない。 そして,他に本件1審被告ファイルにおいて素材の選択又は配列による創作性が あると認めるに足りる証拠はないから,本件1審被告ファイルが編集著作物に当た るとは認められない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2017.10.27
平成28(ネ)10074等 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年10月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
一審被告製品は,本件発明2の構成要件2Fを充足しないので,その技術的範囲\nに属するとは認められない。その理由は,以下のとおり原判決を補正するほかは, 原判決の第3の3記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決51頁6行目〜52頁6行目を,以下のとおり改める。
「ア 一審原告は,乙1のSIMS分析結果によると,一審被告製品において, 活性層のp型窒化物半導体層側の障壁層B11〜障壁層BLの領域に含まれる複数の 障壁層のSi濃度は,5×1016/cm3未満であると合理的に推認される旨主張する。 そこで,検討すると,乙1のSIMSチャート図では,Si濃度は,n型窒化物 半導体層側からp型窒化物半導体層側に向かって下降し,いったん5×1016/cm3 付近まで落ちた後,p型窒化物半導体層側に向かって上昇していることが観察され る。 この点について,一審原告は,Si濃度の上昇は試料の表面汚染の影響を受けた\nものであり,この表面汚染の影響を除外して考えれば,Siをアンドープにした後,\np側に向けて再びSiをそれよりも高い濃度でドープすることは考えられないから, Si濃度は,5×1016/cm3未満であると考えられると主張する。しかし,一審被告 製品における表面汚染の有無及び程度は明らかでなく,一審被告製品における表\面 汚染について定量的な主張立証がされているわけでもない。また,証拠(甲37, 39,乙44,45)と弁論の全趣旨によると,井戸層にはSiがドープされてい ないから,そのためにSIMSチャートでは障壁層のSi濃度が低く現れることが あること,Si濃度のプロファイルには,ノイズによる「ゆれ」があることが認め られるから,Si濃度がいったん5×1016/cm3付近まで落ちていることから,直ち に,一審被告製品において障壁層のSi濃度が5×1016/cm3を下回っていたと認 めることは困難である。 そうすると,乙1のSIMSチャート図から,p型窒化物半導体層側の障壁層B Lを含む複数の障壁層のSi濃度は,5×1016/cm3未満であると合理的に推認され ると認めることはできない。・・・」
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2017.10.12
平成29(ネ)10020等 競業行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成29年9月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記認定事実を踏まえて,控訴人と被控訴人の間の契約の性質が,請負 契約であるのか,雇用契約等であるのかについて検討するに,控訴人と被 控訴人との間で締結された本件基本契約の各条項(甲1)をみる限りは, その内容が請負を内容とするものであることは否定できないところであ る。 しかしながら,使用者と労働者との間における労働契約の存否について は,明示された契約の形式のみによることなく,その労務供給形態の具体 的実態に照らし事実上の使用従属関係があり,当該使用従属関係を基盤と する契約を締結する旨の当事者間に客観的に推認される黙示の意思の合致 があるか否かにより判断されるべきものといえる。特に,本件では,被控 訴人が控訴人に現に雇用されていた状況の下で,控訴人代表者からの提案\nにより,当該雇用関係が解消され,本件基本契約の締結に至ったという経 過があるところ,一般に,労働者の立場にある者が使用者から上記のよう な提案を受けた場合,これを容易に拒絶し難いであろうことは,推察し得 るところである。また,この時点において,被控訴人が,労働関係法令に よって保護される労働者としての地位をあえて放棄し,リスクの高い個人 事業者の地位を選択し,控訴人との契約を請負契約に切り替えようとする 積極的な理由は認め難いのであり,これらの事情を勘案すれば,被控訴人 が真にその自由意思によって控訴人との雇用契約関係を解消し,請負を内 容とする本件基本契約を締結したと断ずることには疑問がある。してみる と,本件においては,控訴人と被控訴人の間で本件基本契約が締結された 事実があるからといって,当該契約に規定された各条項どおりの契約が成 立したものと直ちに断ずることはできないのであり,本件基本契約の各条 項に従った請負契約の成立が認められるためには,本件基本契約締結以後 の被控訴人による労務提供の実態や報酬の労務対価性等が,それ以前の雇 用関係の下におけるものと異なっており,真に請負契約としての実質を備 えたものであることが認められる必要があるのであって,そうでない限り は,従前と同様の雇用契約関係が継続しているものと解するのが,客観的 事実から推認される当事者間の黙示の意思に適合するものというべきであ る。
イ そこで,上記認定事実に基づき考察するに,まず,被控訴人による労務 提供の実態をみると,業務の内容,勤務場所,勤務時間,業務遂行上の指 揮監督の状況において,本件基本契約締結の前後で格別の相違は見られな い。また,本件基本契約締結以後の業務においては,その勤務時間からし て,被控訴人が控訴人以外の業務を受注し得る状況にはなく,現に,その 実績もないのであり,業務の専属性は高いものといえるし,そのような状 況もあって,被控訴人が控訴人から求められた業務を断る自由(諾否の自 由)があったとは考えにくい。そのほか,本件基本契約締結以後の業務に おいても,被控訴人が使用する主要な機材(パソコン)は控訴人所有のも\nのであり,業務上使用する名刺も控訴人の社員用のものであって,いずれ も本件基本契約締結以前と異ならない。 他方,報酬の労務対価性に関しては,報酬の決め方や支払方法が,前記 (1) 本件基本契約締結の前後で相違していることが認められる。しかしながら,控訴人発行の発注書の記載には,「業務の内容」として,「開発業務」との概括的な記載しかなく,その対価である「委託料」についても総額が記載されるのみである。一般に,請負契約において発注書等で請け負うべき業務の内容やその対価の額を定める場合に は,業務内容の詳細やそれに対応した対価の額の内訳を記載し,当事者間 の認識を明確化し,後の紛争防止を図るのが通常といえるのであり,これ からすれば,上記のような概括的な記載しかない発注書によって報酬の額 を定める方法は,業務の成果と報酬との具体的な対応関係が明らかではな く,真に請負としての実質を備えたものと評価することは困難である。む しろ,上記発注書の記載は,「本契約の発効日」から「業務の完了期日」 まで,控訴人における「開発業務」に従事すること全般に対する対価を定 めたもの(すなわち,雇用契約上の報酬額を,それが,労働基準法の定め に合致するかどうかはともかくとして,月々の給与としてではなく,不定 期の期間ごとに区切って,その都度定めたもの)と理解することが可能で\nあるといえる。 以上によれば,本件基本契約締結以後の被控訴人による労務提供の実態 や報酬の労務対価性等をみても,それ以前の雇用関係の下におけるものと 異なるものではなく,真に請負契約としての実質を備えたものであること が認められるとはいえないから,控訴人と被控訴人の間の契約の性質は, 本件基本契約締結以後においても,それ以前と同様の雇用契約のままで あったと解するのが相当である。そして,そうである以上,本件基本契約 のうち,雇用契約の性質に反する条項は,その効力を有しないものという べきである。
ウ 他方,控訴人は,控訴人と被控訴人の間では,本件案件に係る成果物が 特定されており,被控訴人は控訴人に対し特定の成果物提出義務を負って いた旨(すなわち,控訴人と被控訴人の間の契約は請負契約である旨)を 主張し,これを示す事情として,A社ス案件及びC社ア案件について,被 控訴人が,甲10及び11工数見積表,その前提となる詳細見積書(甲6\n6の2,67の2),それらをスケジュール化した甲12開発計画及び顧 客向けの見積試算表(甲70の2)や見積資料(甲72の2)を作成して\nいた事実を挙げる。 しかし,被控訴人が,控訴人の受注したA社ス案件及びC社ア案件につ いて,開発責任者又はプログラマーとして開発業務に当たっていた以上, これらの案件において想定される最終的な成果物を把握し,この点につい て控訴人との共通認識があったことは当然のことであり,このことは,控 訴人と被控訴人の間の契約が,請負であるか,雇用であるかに関わらない ことである。また,控訴人の要求に応じて,これらの案件に係る工数見積 表等の資料を作成することは,開発責任者等としての業務の範囲内のこと\nと考えられるのであり,このことも,控訴人と被控訴人の間の契約が,請 負であるか,雇用であるかに関わらないことといえる。 したがって,控訴人の上記主張は,控訴人と被控訴人の間の契約の性質 いかんに関わる事情を指摘するものではないから,これによって上記イの 判断が左右されるものではない。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2017.10.12
平成28(ワ)14131 特許権侵害行為差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年9月28日 東京地方裁判所(47部)
上記各記載によれば,乙15には,「ヒトにおいて乾癬を処置するために皮 膚に塗布するための混合物であって,1α,24-dihydroxycholecalciferol(タ カルシトール),及びBMV(ベタメタゾン吉草酸エステル),並びにワセリ ンとを含有する非水性混合物であり,皮膚に1日2回塗布するもの」が記載さ れていると認められる。 そして,本件発明12と上記の乙15発明とを対比すると,両発明は,「ヒ トの乾癬を処置するための皮膚用の医薬組成物であって,ビタミンD3の類似 体からなる第1の薬理学的活性成分A,及びベタメタゾンまたは薬学的に受容 可能なそのエステルからなる第2の薬理学的活性成分B,並びに少なくとも1\nつの薬学的に受容可能なキャリア,溶媒または希釈剤を含む,非水性医薬組成\n物であり,医学的有効量で局所適用されるもの」で一致し,前記第2,1(7)記 載の相違点1及び3において相違すると認められる(なお,相違点1及び3の 存在については,当事者間に争いがない。)。 なお,原告は,相違点2(本件発明12は非水性医薬組成物であるのに対し, 乙15発明は非水性組成物であるか定かではない点。)の存在を主張するが, 以下の理由により,相違点2の存在は認められない。 すなわち,乙15にはTV−02軟膏についてはワセリン基剤であることが 記載されている。軟膏は基剤に活性成分を混合分散させたものといえるが,ワ セリンは油脂性基剤であって,混和性の点から,ワセリンと水が併用されるこ とは考えにくい。また,乙15では,TV−02軟膏塗布と白色ワセリン塗布 とが比較され(432頁),D3+BMV混合物塗布とBMV+ワセリン混合 物塗布とが比較されており(431頁,433頁),通常,比較においては, 活性成分以外の条件は揃えるから,TV−02の基剤はワセリンであると考え られる。そうすると,TV−02軟膏に,水は基剤として添加されていないと 考えるのが自然であるし,TV−02軟膏と混合するBMV軟膏についても, 混和性の点から,油脂性基剤が使用され,水は基剤として添加されてはいない と考えるのが妥当である。したがって,乙15発明に係るTV−02軟膏とB MV軟膏の混合物(D3+BMV混合物)についても,水が基剤として添加さ れていないものと理解される(なお,仮に,相違点2を一応認定するとしても, それは実質的なものとはいえないから,当業者であれば,相違点2に係る構成\nは容易に想到できるものといえる。)。
2017.10.12
平成28(ワ)39582 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年9月28日 東京地方裁判所
不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」とは,「人の業務に係る\n氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を 表示するもの」をいうところ,商品の形態は,商標等と異なり,本来的には\n商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定\nの出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,商品の形\n態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不正競争防止法2条1項\n1号にいう「商品等表示」に該当するためには,1)商品の形態が客観的に他 の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,2)その 形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣 伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその形態を有する商品 が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)\nを要すると解するのが相当である。
・・・
以上のとおり,被告商品の販売が開始された平成27年2月時点ま でに,奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに傾斜した計量台とい う構成を備えている重量検品ピッキングカートや,奥側から手前側に向\nかって下方向に緩やかに傾斜した台を備えているピッキングカートが相 当数存在し,その他にも,ショッピングカート等において,被収容物を 収容するためのかご等を載置する部分を奥側から手前側に向かって下方 向に緩やかに傾斜させる構造も従来から多数存在したものである。これ\nらの事実によれば,重量検品ピッキングカートにおいて,「上下段にピ ッキングされた商品を入れるコンテナ,段ボール,トレイ等を置く計量 台が作業者の奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに前傾し,」と いう構成(本件特徴1)’)は,ごくありふれた構成というべきであり,\nそれが,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴であるとは到底認 められない。
・・・
以上のとおり,被告商品の販売が開始された平成27年2月時点ま でに,先端を略半円状ないしそれに近い形状に上向きに湾曲させた2本 の(独立した)把持部という構成を備えている重量検品ピッキングカー\nトやピッキングカートが相当数存在し,その他にも,ベビーカーにおい て,把持部の先端が上向きの略半円状ないしそれに近い形状となってい る構成も多数存在するものである。これらの事実によれば,重量検品ピ\nッキングカートにおいて,「カート上段の左右端に設置された2本の把 持部の先端が略半円状に上向きに湾曲している」という構成(本件特徴\n2))も,ごくありふれた構成というべきであり,それが,客観的に他の\n同種商品とは異なる顕著な特徴であるとは到底認められない。
エ 特別顕著性についての小括
上記イ及びウのとおり,本件特徴1)’及び2)は,いずれもありふれた形 態というべきであり,客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴とはいえ ない。なお,ありふれた形態を併せただけでは,顕著な特徴とはいえない し,そもそも,上記イ及びウのとおり,本件特徴1)’及び2)の両方を備え る他の同種製品も,被告製品の販売開始時までに存在している(株式会社 イシダの「さいまるカート」(乙4及び乙5),株式会社IHIエスキュ ーブの「計量検品ピッキングカート(4ハカリ)」(乙6),株式会社椿 本チエインの「つばきクイックカート」(乙11))。 したがって,原告の主張を善解してもなお,原告商品の形態は,客観的 に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているということはできず, 不正競争防止法2条1項1号の商品等表示には当たらない。\n(なお,上記認定のとおり,本件特徴1)’及び2)は,原告により独占的に 使用されてきたとは認められないし,また,原告の製造販売する重量検品 ピッキングカートに係るカタログ(甲1〜4)及び広告記事等(甲5の1 ないし12,6,17〜50)においても,本件特徴1)’及び2)が商品の 特徴として強調されているとは認められないから,これらの事情によれば, 本件特徴1)’及び2)が原告の商品等表示として周知になっているとも認め\nられない。)
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2017.10.10
平成29(ネ)245 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成29年9月21日 大阪高等裁判所
イ 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品に つき,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を 受けない限り,商標権を侵害するが,そのような商品の輸入であっても, 1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受 けた者により適法に付されたものであり,2) 当該外国における商標権者 と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一 人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商 標と同一の出所を表示するものであって,3) 我が国の商標権者が直接的 に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該 商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証 する品質において実質的に差異がないと評価される場合には,いわゆる真 正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと 解される(フレッドペリー事件最高裁判決)。
(2) 被控訴人標章1が付された被控訴人商品の販売等について
ア 前記2のとおり,被控訴人標章1が記載された被控訴人タグは,ゾ社に よって被控訴人商品に付されたと認められる。 他方,証拠(甲53)及び弁論の全趣旨によれば,ゾ社は,イランにお いて,「ZOLLANVARI」をペルシア文字で表記した商標の登録を出願し\nたが拒絶され,「ZOLLANVARI」に関する商標について商標権を取得し ていないことが認められる。しかし,証拠(甲33)によれば,ゾ社は世 界各地に直営店を設けている中で,日本においては,控訴人が,ゾ社の総 代理店として,直営店と同じ扱いと待遇を受けていると認められる。それ に加えて,控訴人は,前記第2の2(3)のとおり,ゾ社から権限を授与さ れて初めて控訴人商標の登録を受けることができたのであるから,ゾ社が イランにおいて商標権を有している場合と実質的には変わるところがない といえる。 そうすると,被控訴人が,被控訴人標章1が付された被控訴人商品を輸 入した上,これを販売し,販売のために被控訴人ウェブサイトに掲載した 行為は,控訴人商標の出所表示機能\を害することがないといえる。
イ 本件の証拠上,ゾ社と控訴人との間の総代理店契約において,控訴人が 控訴人商品の品質管理に直接関与していることを示すものはなく,控訴人 商品の品質管理は,基本的にはゾ社において行われているものと認められ る。 これに対し,被控訴人商品については,前記2のとおり,ゾ社から,被 控訴人が日本国内で販売することを前提として販売されたものであると認 められるから,被控訴人商品の品質については,これが日本において販売 されることを前提としてゾ社において管理しているものと認められる。 そうすると,ゾ社が外国における商標権者でなくても,控訴人商品につ き,控訴人商標の保証する品質は,控訴人がゾ社を通じて間接的に管理を していて,そのゾ社が,控訴人商品と同じく日本に輸出して日本において 販売される商品として被控訴人商品の品質を管理しているのであるから, 被控訴人商品と控訴人商品とは,控訴人商標の保証する品質において実質 的に差異がないといえる(本件は,被控訴人商品と控訴人商品のいずれも, ゾ社の下で製造されているという点において,フレッドペリー事件最高裁 判決の事案と異なるということがいえる。)。 この点に関し,控訴人は,被控訴人商品がゾ社の製品であるとしても, それはイラン国内のバザールで販売していた製品であり,ゾ社が日本輸出 向けとして選別し控訴人タグを付した控訴人商品とは品質の点で異なる旨 主張し,A及びBの説明(甲34,52)には,被控訴人商品に付されて いる別紙3のタグ(前記1(9))は,国内市場でのみ使用し,輸出向け商 品には使用しないとの趣旨の部分がある。 証拠(乙22の3)及び弁論の全趣旨によれば,ゾ社の取り扱うじゅう たんは,工場で生産されるものではなく,イラン国内において複数の織子 から仕入れる手織りのものをゾ社において仕上げていると認められる。そ うすると,製品ごとにその品質には相当のばらつきがあることが推認され るから,控訴人が主張するように,輸出向けと国内販売向けの製品を選別 するという取扱いも十分考えられるところである。\nまた,証拠(甲48の1,甲49の1,甲50の1,乙27の2,乙2 9の1,乙30の1,乙34の1,乙35の1,乙36の4)によれば, 控訴人商品のゾ社からの購入代金は1m2当たり224ないし715米ドル であるのに対し,被控訴人商品のゾ社からの購入代金は1m2当たり40な いし70米ドルであると認められ,明らかに控訴人商品の方が高いといえ る。 しかし,被控訴人代表者及びCが作成した,CとBとの間の会話を反訳\n及び翻訳した文書(乙49)の注記には,控訴人が取り扱っている商品が 主にルリバフなどの高級品であるのに対し,被控訴人はギャッベなどの比 較的安価な商品を取り扱っており,控訴人と被控訴人とでは同じゾ社の製 品でも取り扱っている商品が違う,顧客層が違うとの記載があるが,直ち に,両者の品質が異なるということにはならない。 また,証拠(乙25)によれば,別紙3のタグが付された被控訴人商品 の中には,当該タグを収納しているビニール袋の内側に,当該タグに記載 されたのと同じ寸法及び控訴人代表者の姓である「D」との文字が,おそ らく意図せずに転写されているものが複数あったことが認められる。この ことは,ゾ社において,控訴人向けとなる商品と,被控訴人向けとなる商 品とが重なり合っていることを示すものといえる。 そして,上記のとおり,控訴人商品についても,その品質管理を実質的 に行っていると認められるゾ社自身が,控訴人商品と同じく日本に輸出し て日本において販売される商品として被控訴人商品を被控訴人に販売して いる以上は,被控訴人商品と控訴人商品とは,控訴人商標の保証する品質 において実質的に差異がないとの評価は左右されず,被控訴人商品と控訴 人商品の品質が同一とまではいえなくても,控訴人商標の品質保証機能を\n害することはないというべきである。 そうすると,被控訴人が,被控訴人標章1が付された被控訴人商品を販 売し,販売のために被控訴人ウェブサイトに掲載した行為は,控訴人商標 の品質保証機能を害することがないといえる。
ウ 前記ア及びイのとおり,被控訴人が,被控訴人標章1が付された被控訴 人商品を販売し,販売のために被控訴人ウェブサイトに掲載した行為(前 記(1)ア2)の行為)は,控訴人商標の出所表示機能\及び品質保証機能を害\nすることがなく,また,以上に述べたところによれば,商標を使用する者 の業務上の信用及び需要者の利益を損なうものでもないから,商標権侵害 としての実質的違法性を欠くというべきである。
(3) 被控訴人ウェブサイトにおける被控訴人各標章の使用について
ア 被控訴人商品の広告に被控訴人各標章を付して被控訴人ウェブサイトに 掲載する行為(前記(1)ア3)の行為)については,これまでの認定及び判 断に基づくと,次のとおり指摘することができる。 まず,被控訴人各標章が付された広告において宣伝された被控訴人商品 は,被控訴人が,控訴人商標の外国における商標権者と同視できるゾ社か ら,日本国内で販売することを前提として,購入して輸入したものである。 そして,控訴人は,ゾ社の日本における総代理店であって,ゾ社の直営店 と同じ扱いと待遇を受けており,控訴人商標の出所表示機能\を検討する際 には,控訴人とゾ社とは同視することができる。そうであれば,被控訴人 商品の広告に,控訴人商標と類似する被控訴人各標章を付して被控訴人 ウェブサイトに掲載しても,控訴人商標の出所表示機能\を害することがな いといえる。 また,被控訴人商品と控訴人商品とは,控訴人商標の保証する品質にお いて実質的に差異がないといえるから,被控訴人商品の広告に,控訴人商 標と類似する被控訴人各標章を付して被控訴人ウェブサイトに掲載しても, 控訴人商標の品質保証機能を害することがないといえる。
イ そうすると,被控訴人商品の広告に被控訴人各標章を付して被控訴人 ウェブサイトに掲載する行為は,控訴人商標の出所表示機能\及び品質保証 機能を害することがなく,また,以上に述べたところによれば,商標の使\n用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なうこともないから,商 標権侵害行為としての実質的違法性を欠くというべきである。
2017.10.10
平成28(ワ)24175 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年9月21日 東京地方裁判所(46部)
前記1(2)で述べたとおり,本件明細書の記載によれば,従来技術には, 気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ,過飽和の状態を安定に維持して外 部に提供することが難しく,ウォーターサーバー等へ容易に取付けること ができないという課題があった。本件発明1は,このような課題を解決す るために,水に水素を溶解させる気体溶解装置において,水素水を循環さ せるとともに,水素水にかかる圧力を調整することにより,水素を飽和状 態で水素水に溶解させ,その状態を安定的に維持し,水素水から水素を離 脱させずに外部に提供することを目的とするものである。 本件発明1では,水素を飽和状態で水に溶解させ,その状態を安定的に 維持するために,加圧型気体溶解手段で生成された水素水を循環させて, 加圧型気体溶解手段に繰り返し導いて水素を溶解させることとし,「前記 溶存槽に貯留された水素を飽和状態で含む前記水素水を加圧型気体溶解 手段に送出し加圧送水して循環させ」る(構成要件F)という構\成を採用 している。また,気体溶解装置において,気体が飽和状態で溶解した状態 を安定的に維持し,水素水から水素を離脱させずに外部に提供するために は,水素を溶解させた状態の水素水が気体溶解装置の外部に排出されるま での間に,水素水にかかる圧力の調整ができなくなることを避ける必要が ある。このため,本件発明1では「前記溶存槽及び前記取出口を接続する 管状路」(構成要件E)という構\成を採用し,水素を溶解させた水素水が 導かれる溶存槽と水素水を気体溶解装置外に吐出する取出口との間を管 状路で直接接続し,水素水にかかる圧力の調整ができなくなることを避け ているものと解される。 以上のような本件発明1の課題,解決方法及びその効果に照らすと,生 成した水素水を循環させるという構成のほか,管状路が溶存槽と取出口を\n直接接続するという構成も,本件発明1の本質的部分,すなわち従来技術\nに見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分に該当するというべ\nきである。 被告製品は,管状路が溶存槽と取出口を接続するという構成を採用して\nいないことは前記4のとおりであるから,被告製品の構成は,本件発明1\nと本質的部分において相違するものと認められる。
イ これに対し,原告は,本件発明1の本質的部分は,生成された水素水が 大気圧に急峻に戻るのを防ぐため,管状路を加圧状態から大気圧状態まで の圧力変動があり得る構成と構\成の間に接続することであり,被告製品で は,冷水タンクにおいて水素水にかかる圧力が大気圧となるから,カーボ ンフィルタと冷水タンクを細管で接続する構成は本件発明1と本質的部分\nにおいて相違しない旨主張する。 しかし,被告製品のように,溶存槽から取出口までの間に水素水にかか る圧力が大気圧となる構成を設けた場合には,被告製品の取出口から水素\n水が取り出される前に,生成された水素水に対する圧力の調整ができなく なって水素が離脱し得ることになってしまい,「水素水から水素を離脱させ ずに外部に提供する」という効果を奏することができない。したがって, 本件発明1において,溶存槽と大気圧状態までの圧力変動があり得る構成\nの間に管状路を接続することが本質的部分であると解することはできず, 原告の主張は採用することができない。
エ したがって,被告製品は,均等侵害の第一要件を満たさない。
第二要件及び第三要件
ア 原告は,第二要件につき,被告製品と本件発明1とは,管状路を通して 徐々に生成した水素水を大気圧に降圧することにより,水素濃度を維持す る点が共通するから,「管状路に当たる細管が,カーボンフィルタの出口と 気体溶解装置内に設けられた冷水タンクの入口を接続する」という被告製 品の構成を,管状路が溶存槽と取出口を接続するという本件発明1の構\成 に置換することができると主張する。 しかし,前記 で判示したとおり,被告製品の上記構成では,装置の内\n部において水素水にかかる圧力の調整ができなくなり,「水素水から水素を 離脱させずに外部に提供する」という効果を奏することができず,被告製 品の構成と本件発明1の構\成は作用効果が同一であるとはいえない。した がって,被告製品は,均等侵害の第二要件も満たさない。
イ 原告は,第三要件につき,取出口の前に冷水タンクを設け,この冷水タ ンクに管状路を接続することは容易であると主張する。しかし,取出口の 前に大気圧となる冷水タンクを設けることは,「水素水から水素を離脱させ ずに外部に提供する」という本件発明1の課題解決原理に反するものであ るから,当業者としては,本件発明1に被告製品の上記構成を採用するこ\nとの動機付けを欠くものといえる。したがって,被告製品は,均等侵害の 第三要件も満たさない。 以上で述べたとおり,「管状路に当たる細管が,カーボンフィルタの出口と 気体溶解装置内に設けられた冷水タンクの入口を接続する」という被告製品 の構成は,均等侵害の第一要件,第二要件及び第三要件を満たさないから,\n被告製品の上記構成が本件発明1の構\成要件Eと均等であるとは認められ ない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> ピックアップ対象
2017.10. 7
平成28(行ケ)10265 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月3日 知的財産高等裁判所(4部)
引用発明Aが検知の対象とするタグと引用例3事項の付け札とは,いずれ も盗難防止装置に使用されるタグ(付け札)の技術分野に関するものである。 また,引用発明Aと引用例3事項の付け札が使用される電子物品管理システムは, いずれも,タグ(付け札)が警報動作を開始する際には,電波送出パネル22(出 口送信機ユニット)が信号を発信し,タグ1(付け札)がこれを受信するものであ って,警報動作を終了する際には,コード信号出力ユニット(勘定所送信機ユニッ ト又は携帯送信機ユニット)が信号を発信し,タグ1(付け札)がこれを受信する ものである。このように,引用発明Aと引用例3事項の付け札が使用される電子物 品管理システムとは,タグ(付け札)が警報動作を開始する際及び終了する際の作 用機序において共通する。 さらに,引用発明Aは,警報動作を開始させる所定の周波数の電波及び警報動作 を終了させるコード信号のみを使用するものであるが,引用例3事項の付け札が使 用される電子物品管理システムは,これらに相当する信号(出口メッセージ及び終 了メッセージ)に加えて,能動的包装メッセージ,オーディオ包装メッセージ,受\n動的包装メッセージ及び保管メッセージを含む信号を使用し,電子物品監視システ ムの作動能力を拡張するものである。このように,引用例3事項の付け札は,引用\n発明Aが検知の対象とするタグと比較して,その作動能力が拡張されたものである。
(イ) 以上によれば,当業者は,引用発明Aが検知の対象とするタグに,盗難防 止装置に使用されるものであって,警報動作の開始及び終了の作用機序が共通し, さらに作動能力が拡張された引用例3事項の付け札を適用する動機付けがあるとい\nうべきである。
エ 引用例3事項を適用した引用発明Aの構成
(ア) 本件訂正発明8において,盗難防止タグは,警報出力手段が作動可能であ\nる状態及び警報出力状態を解除するに当たり,「一致判定手段が「前記識別手段が 識別した解除指示信号に含まれる」暗号コードが一致するか否かを判定する」もの である。一致判定手段は,前記識別手段が解除指示信号を識別した後に,その解除 指示信号に含まれる暗号コードと,暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致する か否かを判定するから,識別手段による解除指示信号の識別に用いられるコードと, 一致判定手段による暗号コードの一致判定に用いられるコードとは無関係なものと いうことができる。
・・・
(ウ) そうすると,警報動作を終了させるに当たり,本件訂正発明8の盗難防止 タグは,解除信号の一部に含まれる,解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コー ド」と,記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し,引用例3事項を適用 した引用発明Aのタグは,解除信号である「コード信号」と,記憶された「それぞ れ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うものであ る。したがって,引用発明Aに引用例3事項を適用しても,相違点2に係る本件訂正 発明8の構成に至らないというべきである。
オ 本件審決の判断について
(ア) 本件審決は,引用例3事項の「終了メッセージを含む信号」は,警報オフ とする点において,「解除指示信号」と共通するとした上で,引用例3,甲5(米 国特許第5148159号明細書。平成4年公開)及び甲6(「NEC MOS集 積回路 μPD6121,6122データシート」NEC株式会社。平成7年公開) から,「信号が設定可能なコードを一部に含み,一致判定手段が前記信号に含まれ\nる前記コードが一致するか否かを判定する」という周知技術(以下「審決認定周知 技術」という。)が認められるから,引用例3事項を適用するに当たって,引用例 3事項の「終了メッセージを含む信号」を,設定機能によって所望に設定できるコ\nードを一部に含み,引用発明Aの一致判定手段において信号に含まれるコードが一 致するか否かを判定するように構成することは,当業者にとって格別困難ではない\nと判断した。
(イ) 本件審決は,引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり,周知技術を 考慮して変更した引用例3事項を適用することによって,本件訂正発明8を容易に 想到することができるとするものである。 しかしながら,前記エのとおり,引用発明Aに引用例3事項を適用しても,相違 点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ,さらに周知技術を考慮して引\n用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし,後記(ウ)のとおり,引 用例3事項を適用するに当たり,これを変更する動機付けも認められない。主引用 発明に副引用発明を適用するに当たり,当該副引用発明の構成を変更することは,\n通常容易なものではなく,仮にそのように容易想到性を判断する際には,副引用発 明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから,本件審\n決の上記判断は,直ちに採用できるものではない。
◆判決本文
本件特許の侵害事件の控訴審です。こちらは技術的範囲に属しないと判断されています。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 限定的減縮
>> ピックアップ対象
2017.10. 7
平成28(行ケ)10266 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年9月27日 知的財産高等裁判所(1部)
前記(1)によれば,本願商標の形状と一般的なカードシューの形状とは,横長の箱 状であり,上面をなだらかに傾斜させるとともに,前面を傾斜させ,半円状の開口 部が設けられているという点において共通するものであり,その共通する形状は, トランプを格納して,上から一枚ずつ取り出せるカード容器の基本的な形状であっ て,トランプ繰り出し装置という機能を効果的に発揮させるために通常採用されて\nいる形状であることが認められる。 そして,本願商標の立体的形状は,全体として曲線を輪郭として用いていること など,一定の特徴的形態を有するものであるけれども,このような曲線を輪郭とす るカードシューは,他にも存在するのであって(乙4,11),通常採用されてい る形状の範囲を超えるものとまでは認められず,本願商標に接した需要者が,商品 の美感に資することを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであると認\nめられる。 また,本願指定商品は,「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認 識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログ\nラムを内蔵してなる」ものであるところ,前記認定のとおり,ランプやボタン等 は,電子的にトランプカードを識別認識してゲームの結果を表示する,又は電子機\n器を制御するために設けられたものであると認められる。このような電子的な機能\nを有する商品には,その機能を発揮させるために,ランプやボタン,スイッチ等を\n搭載することが通例であるといえ,本願商標のランプやボタン,スイッチ等の特徴 的形態については,本願商標に接した需要者が,商品の機能を効果的に発揮させる\nことを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであると認められる。\n以上によれば,本願商標の立体的形状は,客観的に見れば,機能又は美感に資す\nることを目的として採用されたものと認められ,また,需要者において,機能又は\n美感に資することを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであるから,\n商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として,商\n標法3条1項3号に該当するものと認められる。
・・・
商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,こ のような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章,あるい\nは,商品等の形状を表示する標章であって,取引に際し必要適切な表\示として何人 もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのを公益 上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場 合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによる\nものである。また,商標法3条2項は,同条1項3号に該当する商標のように,本 来は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとと もに,自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであっても,\nその使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識 することができるものについては,自他商品識別力を獲得したものとして,例外的 に商標登録を受けることができる旨を定めたものである。そして,商標法は全国一 律に適用されるものであって,商標権が全国に効力の及ぶ更新登録可能な排他的な\n権利であることからすると,商標法3条2項により商標登録が認められるために は,同条1項3号に該当する商標が,現実に使用された結果,指定商品又は指定役 務の需要者の間で,特定の者の出所表示として我が国において全国的に認識される\nに至ったことが必要であると解される(そうである以上,指定商品又は指定役務の 需要者は,通常,全国的に存在していることが前提となるものである。)。上記の理 は,商標法3条1項4号及び5号に該当する商標について,同条2項により商標登 録を受けることができる場合においても異なるところはないといえる。
本願商標及び使用に係る商品の構成態様
本願商標は,前記1 に認定したとおりの構成からなるものであるのに対し,証\n拠(甲1〜4,6,18,22,37,49)及び弁論の全趣旨によれば,原告 は,本願商標と類似する形状の商品「バカラ電子シュー」(本件使用商品)を製造 及び販売しているところ,本件使用商品は,「トランプに内蔵印刷されたトランプ 識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗\nを判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置」であり,本願指定商 品に属するものであること,本件使用商品と本願商標の立体的形状は,ランプの数 や曲面の形状,カード繰り出し口の形状等において若干相違するものもあり,完全 に同一の形状からなるものということはできないものの,実質的に同一性を有する ものであるといえることなどが認められる。なお,証拠(甲1,2,18,24, 37,41)及び弁論の全趣旨によれば,本件使用商品は,その上面に,看者の注 意を惹くように書された「ANGEL EYE」等の文字が記載されていることが 認められるが,商品等は,その販売等に当たって,その出所たる企業等の名称や記 号・文字等からなる標章などが付されるのが通例であることに照らすと,使用に係 る立体形状にこれらが付されているということのみで,直ちに本願商標の立体的形 状について,商標法3条2項の適用を否定することは適切ではなく,上記文字商標 等を捨象して残された立体的形状に注目して,独自の自他商品識別力を獲得するに 至っているか否かを判断するのが相当である。 以上を前提に,本願商標について検討するに,本願商標の立体的形状と実 質的に同一の形状を有する本件使用商品が,輸出専用の商品であって我が国におい て流通していないことは,当事者間に争いがない。そして,原告が主張するよう に,本件使用商品が輸出され,又は輸出を前提としてのみ譲渡若しくはそのための 展示がされることにより,本願商標が使用されているとしても,本件使用商品の取 引に関係する者は国内の販売代理店に限定されており,本願商標を原告の出所表示\nとして認識し得る需要者は限られた範囲にとどまるから,本願指定商品の需要者が 全国的に存在していると認められない。のみならず,本件使用商品が輸出されるこ とにより,諸外国で使用されており,諸外国のカジノ関係者に知られているとして も,その周知性が我が国に及んでいると認めるに足りる証拠はないから,本願商標 が,現実に使用された結果,本願指定商品の需要者の間で,原告の出所表示として\n我が国において全国的に認識されるに至ったものと認めることはできない。 したがって,本願商標は,商標法3条2項により商標登録を受けることができる ものということはできない
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2017.10. 4
平成28(行ケ)10183 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月3日 知的財産高等裁判所(4部)
引用例1には,黒鉛粉末とリチウム金属粒子とを混合粉砕することにより,リチ ウム粒子が微粉末になると同時に,その一部が微粉末化された黒鉛の層間にインタ ーカレートし,リチウム元素微粒子をゲストとする層間化合物を形成すること,実 施例3で形成された層間化合物の層間距離が3.71Å(0.371nm)であり, これはリチウムが黒鉛の層間に入って形成された層間化合物の公知の層間距離3. 72Å(0.372nm)にほぼ一致するものであることが記載されている(【0 026】〜【0028】)。また,証拠(甲22)によれば,リチウムをゲストと するステージ1の黒鉛層間化合物における層間距離は3.706Åであることが認 められる。 そうすると,本件引用発明1における「層間化合物」は,ホストである黒鉛の層 間に,リチウム元素微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた, 黒鉛層間化合物であるといえる。 したがって,本件審決が,引用例1には金属の元素微粒子が金属層となっている ことは記載も示唆もされていないとして,相違点1は実質的な相違点であると認定 したことについては,誤りがある。
・・・・
ア 本件各発明は,高容量と長いサイクル寿命とを共に実現することを可能にす\nる負極及びこの負極を用いた二次電池を提供することを目的とし,構成として,負\n極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能なSn,Si,P\nb,Al又はGaから選択される金属の微粒子がゲストとしてインターカレートさ れた,黒鉛層間化合物から成ることにより,リチウムと合金化可能な金属が黒鉛の\n層間という導電性マトリックス内にあるようにし,これにより,金属と黒鉛との電 気的な接触が充分になされ電気伝導性を確保することができ,また金属を微粒子化 しても,導電性マトリックス内に囲われているので,金属の微粒子によって電解液 が分解しないように抑制することができ,そして,負極活物質がリチウムと合金化 可能な金属を有するので,負極を備えた電池の容量を高めることが可能\になる,と いうものである。 これに対し,本件引用発明1は,従来技術である,金属を加熱して気相で黒鉛と 接触反応させる方法や電気化学的な方法を用いて製造された黒鉛複合物には,黒鉛 中に層間化合物と金属とが十分に微細分散されておらず,リチウム二次電池の負極\n材料として使用した場合に,充放電を繰り返すうちに上記金属が剥離して負極活物 質として作用しなくなるという不具合があったことから,粉砕法によって,黒鉛粒 子,金属微粒子及び層間化合物とが微細に分散した黒鉛複合物を形成し,それによ り,層間に多量のリチウムイオンをインターカレート可能な黒鉛粒子を使用可能\と したり,微細化により導電性を高めようとしたりするものである。 このように,本件引用発明1においては,粉砕法によって黒鉛複合物を形成する ことが中核を成す技術的思想ということができる。また,引用例1には,リチウム と合金化可能な金属が黒鉛の層間という導電性マトリックス内にあるようにするこ\nとにより,電気伝導性を確保し,金属を微粒子化しても電解液が分解しないように 抑制することができ,負極を備えた電池の容量を高めるという,本件各発明の技術 思想は開示されていない。 したがって,引用例1に接した当業者が,本件引用発明1におけるゲストとして インターカレートされる「リチウム金属の微粒子」を「リチウムと合金化可能なS\nn,Si,Pb,Al又はGaから選択される金属の微粒子」に置き換えた上で, さらに,黒鉛層間化合物の製造方法について,本件引用発明1において中核を成す 粉砕法に換えて,微細分散工程のない塩化物還元法や気体法その他の方法を採用す ることを容易に想到できたということはできない。
イ また, 前記2(2)のとおり,Si及びAlは,単体金属原子として黒鉛の層間 にインターカレートすることはできないことから,これらの元素微粒子と黒鉛粒子 とを粉砕法により混合粉砕しても,黒鉛層間化合物を製造することはできないもの と認められ,証拠(甲6)によれば,Gaについても,Si及びAlと同様に,こ の元素微粒子と黒鉛粒子とを粉砕法により混合粉砕しても,黒鉛層間化合物を製造 することはできないものと認められる。そして,Sn及びPbについても,本件特 許の出願当時,これらを単体金属原子として黒鉛の層間にインターカレートするこ とができるなど,これらの元素微粒子と黒鉛粒子とを粉砕法により混合粉砕するこ とにより,黒鉛層間化合物を製造することができるとの知見が存在したとは認めら れない。 したがって,引用例1に接した当業者が,本件引用発明1におけるゲストとして インターカレートされる「リチウム金属の微粒子」を「リチウムと合金化可能なS\nn,Si,Pb,Al又はGaから選択される金属の微粒子」に置き換えて,これ らの金属の微粒子と黒鉛粒子とを粉砕法により混合粉砕することにより,これらの 金属をゲストとする黒鉛層間化合物を製造することを容易に想到できたということ もできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.09.28
平成28(行ケ)10236 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年9月21日 知的財産高等裁判所(第2部)
以上の記載事項A〜Iについての検討を総合すると,本件発明1の無洗米 の製造装置は,少なくとも,摩擦式精米機(記載事項F)と無洗米機(記載事項C) をその構成の一部とするものであり,その摩擦式精米機は,全精白構\成の終末寄り から少なくとも3分の2以上の工程に用いられているものである(記載事項E)上, 精白除糠網筒(記載事項F)と精白ロール(記載事項G)をその構成の一部とする\nものであり,その精白除糠網筒の内面は,ほぼ滑面状であって(記載事項F),精白ロ ールの回転数は毎分900回以上の高速回転とするものである(記載事項 G)と認 められる。 したがって,上記の無洗米の製造装置の構造又は特性は,記載事項A〜Iから理\n解することができる。
しかしながら,請求項1の無洗米の製造装置の特定は,上記の装置の構造又は特\n性にとどまるものではなく,精米機により,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,\n米粒の50%以上について胚盤又は表面部を削り取られた胚芽を残し,白度37前\n後に仕上がるように搗精し(記載事項B),白米の表面に付着する肌ヌカを無洗米機\nにより分離除去する無洗米処理を行う(記載事項C)ものであり,旨味成分と栄養 成分を保持した無洗米を製造するもの(記載事項D,I)である。 このうち,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,米粒の50%以上について胚盤\n又は表面部を削り取られた胚芽を残し,白度37前後に仕上がるように搗精する(記\n載事項B)ことについては,本件明細書の発明の詳細な説明において,本件発明に 係る無洗米の製造装置のミニチュア機で,白度37前後の各白度に搗精した精米を, 洗米するか,公知の無洗米機によって通常の無洗化処理を行い,炊飯器によって炊 飯し,その黄色度を黄色度計で計り,黄色度11〜18の内の好みの供試米の白度 に合わせて搗精を終わらせる時を調整して,本格搗精をすることにより行うこと (【0035】),このようにして仕上がった精白米は,亜糊粉細胞層が米粒表面をほ\nとんど覆っていて,かつ,全米粒のうち,表面が除去された胚芽と胚盤が残った米\n粒の合計数が,少なくとも50%以上を占めていること(【0036】)が記載され ており,結局のところ,ミニチュア機で実際に搗精を行うことにより,本格搗精を 終わらせる時を調整することにより実現されるものであることが記載されている。 したがって,本件明細書には,本件発明1の無洗米の製造装置につき,その特定の 構造又は特性のみによって,玄米を前記のような精白米に精米することができるこ\nとは記載されておらず,その運転条件を調整することにより,そのような精米がで きるものとされている。そして,その運転条件は,本件明細書において,毎分90 0回以上の高速回転で精白ロールを回転させること以外の特定はなく,実際に上記 のような精米ができる精白ロールの回転数や,精米機に供給される玄米の供給速度, 精米機の運転時間などの運転条件の特定はなく,本件出願時の技術常識からして, これが明らかであると認めることもできない。
ところで,本件明細書の発明の詳細な説明において,亜糊粉細胞層(5)につい ては,「糊粉細胞層4に接して,糊粉細胞層4より一段深層に位置して僅かに薄黄色 をした」,「厚みも薄く1層しかない」ものであり(【0015】),「亜糊粉細胞5は・・・整然と目立って並んでいる個所は少なく,ほとんどは顕微鏡でも確認しにくいほど糊粉細胞層4に複雑に貼り付いた微細な細胞であり,それも平均厚さが約5ミクロ\nン程度の極薄のものである」(【0018】)と記載され,胚芽(8)及び胚盤(9) については,「胚芽7の表面部を除去された」ものが胚芽(8)であり,それを更に\n削り取ると胚盤(9)になる(【0023】)と記載されている。しかるところ,本 件明細書の発明の詳細な説明には,米粒に亜糊粉細胞層(5)と胚芽(8)及び胚 盤(9)を残し,それより外側の部分を除去することをもって,米粒に「旨み成分 と栄養成分を保持」させることができる旨が記載されており(【0017】〜【00 23】),玄米をこのような精白米に精米する方法については,「従来から,飯米用の 精米手段は摩擦式精米機にて行うことが常識とされている」が,その搗精方法では, 必然的に,米粒から亜糊粉細胞層(5)や胚芽(8)及び胚盤(9)も除去されて しまうこと(【0024】,【0025】)が記載されている。また,本件明細書の発 明の詳細な説明には,「摩擦式精米機では米粒に高圧がかかり,胚芽は根こそぎ脱落 する」から,胚芽を残存させるには,研削式精米機による精米が不可欠とされてい た(【0029】)ところ,研削式精米機により精米すると,むらが生じ,高白度に なると,亜糊粉細胞層(5)の内側の澱粉細胞層(6)も削ぎ落とされている個所 もあれば,糊粉細胞層(4)だけでなく,それより表層の糠層が残ったままの部分\nもあるという状態になること(【0027】)が記載されている。 そうすると,精米機により,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,米粒の50%\n以上において胚盤又は表面を削り取られた胚芽を残し,白度37前後に仕上がるよ\nうに搗精することは,従来の技術では容易ではなかったことがうかがわれ,上記の とおり,本件明細書に具体的な記載がない場合に,これを実現することが当業者に とって明らかであると認めることはできない。 本件発明1は,無洗米の製造装置の発明であるが,このような物の発明にあって は,特許請求の範囲において,当該物の構造又は特性を明記して,直接物を特定す\nることが原則であるところ(最高裁判所平成27年6月5日第二小法廷判決・民集 69巻4号904頁参照),上記のとおり,本件発明1は,物の構造又は特性から当\n該物を特定することができず,本件明細書の記載や技術常識を考慮しても,当該物 を特定することができないから,特許を受けようとする発明が明確であるというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.09.26
平成28(行ケ)10262 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年9月13日 知的財産高等裁判所(1部)
このように,本件商標がワンポイントマークとして表示される場合などを考える\nと,ワンポイントマークは,比較的小さいものであるから,そもそも,そのような 態様で付された商標の構成は視認しにくい場合があるといえる。また,マーク自体\nに詳細な図柄を表現することは容易であるとはいえないから,スポーツシャツ等に\n刺繍やプリントなどを施すときは,むしろその図形の輪郭全体が見る者の注意を惹 き,内側における差異が目立たなくなることが十分に考えられるのであって,その\n全体的な配置や輪郭等が引用商標と比較的類似していることから,ワンポイントマ ークとして使用された場合などに,本件商標は,引用商標とより類似して認識され るとみるのが相当である(本件商標と引用商標の差異のうち,比較的特徴的である といえる白抜きの逆三角形部分についても,外観において紛れる場合が見受けられ る。)。さらに,多数の商品が掲載されたカタログ等や,スポーツの試合観戦の場合 などにおいては,その視認状況等を考慮すると,特に,外観において紛れる可能性\nが高くなるものといえる。 また,本件商標の指定商品は,「被服」を始め「帽子,メリヤス靴下,スカーフ, サンダル靴,ティーシャツ」等であり,日常的に消費される性質の商品が含まれ, スポーツ用品(運動用具)関連商品を含む本件商標が使用される商品の主たる需要 者は,スポーツの愛好家を始めとして,広く一般の消費者を含むものということが できる。そして,このような一般の消費者には,必ずしも商標やブランドについて 正確又は詳細な知識を持たない者も多数含まれているといえ,商品の購入に際し, メーカー名やハウスマークなどについて常に注意深く確認するとは限らず,小売店 の店頭などで短時間のうちに購入商品を決定するということも少なくないと考えら れる。
(6) 混同を生ずるおそれについて
本件商標と引用商標は,全体的な構図として,配置や輪郭等の基本的構\成を共通 にするものであり,本件商標が使用される商品である被服等の商品の主たる需要者 が,商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者 であり,商品の購入に際して払われる注意力はさほど高いものとはいえないことな どの実情や,引用商標が我が国において高い周知著名性を有していることなどを考 慮すると,本件商標が,特にその指定商品にワンポイントマークとして使用された 場合などには,これに接した需要者(一般消費者)は,それが引用商標と全体的な 配置や輪郭等が類似する図形であることに着目し,本件商標における細部の形状(内 側における差異等)などの差異に気付かないおそれがあるといい得る。 また,引用商標は,スポーツ用品(運動用具)関連の商品分野において,原告の 商品を表示するものとして,需要者の間において著名であるところ,本件商標の指\n定商品には,引用商標の著名性が需要者に認識されているスポーツ用品(運動用具) 関連の商品を含むものであるから,本件商標をその指定商品に使用した場合には, これに接する需要者は,著名商標である引用商標を連想,想起して,当該商品が原 告又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグ\nループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるもの というべきである。 したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するものとして商標登録 を受けることができないというべきであるから,これと異なり,本件商標が同号に 該当しないとした審決の判断には誤りがあるといわざるを得ない。
(7) 被告の主張について
ア 被告は,本件商標と引用商標とは,審決が認定した差異以外に,商標の 縦横比の相違,左端頂部の高さの相違,左上部の左傾斜直線の長さの相違を有する ものであり,看者に与える印象が大きく異なるというのが相当であるから,外観に おいて混同を生ずるおそれはない旨主張する。 確かに,本件商標と引用商標とを対比すると,前記のとおり,具体的な構成にお\nいていくつかの相違点が認められるものである。しかしながら,前記認定のとおり, 引用商標は,前記のような図柄であって,原告の商品を表示するものとして,いわ\nゆるスポーツ用品関連の商品分野において,高い著名性を有していたことに照らせ ば,被告が指摘するような具体的構成における差異が存在するとしても,引用商標\nと全体的な輪郭等の構成が共通していると認められる本件商標をスポーツ用品関連\nの商品を含む本件商標の指定商品に付して使用した場合には,これに接する需要者 において,当該商品が原告又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示に\nよる商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤 信するおそれがあるものというべきである。 また,具体的な構成において引用商標と相違する点があるとしても,その全体的\nな輪郭等の構成が引用商標と客観的に類似性の高いものとなっており,これをワン\nポイントマークとして使用した場合などには,一般の消費者の注意力などをも考慮 すると,出所の混同を生ずるおそれがあることは前記のとおりである。 なお,商標法4条1項15号該当性の判断は,当該商標をその指定商品等に使用 したときに,当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営 業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営\n業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれが存するかどうかを問題とする ものであって,当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは,上記判断における 考慮要素の一つにすぎないものである。被告が主張するような差異が存在するとし ても,その点については,本件商標の構成において格別の出所識別機能\を発揮する ものとまではいえないし,単に本件商標と引用商標の外観上の類否のみによって, 混同を生じるおそれがあるか否かを判断することはできない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2017.09.23
平成28(行ケ)10230 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年9月14日 知的財産高等裁判所
本件商標は,前記第2の1のとおり,平成16年6月22日に国際登録が され,同年12月13日に日本国が事後指定がされたもの(同日に商標登録出願が されたものとみなされる[商標法68条の9第1項])であって,平成18年1月 24日に登録査定がされ,同年7月21日に登録されたものである。 平成26年法律第36号による商標法の一部改正(平成27年4月1日施行)に よって,位置商標について,その出願の手続が定められた(商標法5条2項5号, 同条4項,5項,商標法施行規則4条の6〜8)が,それより前には,我が国にお いて,位置商標の出願についての規定はなく,本件商標についても,位置商標では なく,通常の平面図形の商標であると解するほかない(本件商標が位置商標ではな いことは,原告も認めている。)。 そうすると,本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているというためには, 黒い実線で囲まれたX字状の部分のみならず,靴の形状をした点線部分も,平面図 形の商標として使用されていなければ,本件商標と社会通念上同一の商標が使用さ れているということはできない。 原告各製品には,X字状の標章が付されているものの,靴の形状をした点線部分 の標章が平面図形の商標として使用されているということはできないから,本件商 標と社会通念上同一の商標が使用されているとは認められない。
(3) この点について,原告は,原告各製品には,X字状の標章が付されている 上,スニーカー自体の形状もほぼ同じであると主張するが,スニーカー自体の形状 がどうであれ,平面図形の商標として点線部分の標章が使用されているということ はできないから,原告の主張を採用することはできない。 また,原告は,本件商標の基礎登録商標に基づく主張や欧州共同体商標意匠庁な ど各国における本件商標についての判断に基づく主張をするが,商標の出願及び登 録の要件は各国において定められるべきものである(パリ条約6条1項及び3項) から,他国における本件商標についての判断と同じ判断をしなければならない理由 はないし,本件商標の基礎登録商標に関する前記1(2)の事実は,スペイン国の商標 についてのものであって,直ちに我が国の商標について判断を左右するものではな い。 さらに,原告は,商標法50条の趣旨から本件商標は取り消されるべきではない と主張するが,商標法50条の趣旨が原告主張のとおりであるとしても,本件商標 と社会通念上同一の商標の使用が認められない以上,本件商標は取消しを免れない のであって,商標法50条の趣旨によって左右されるものではない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2017.09.23
平成29(行ケ)10001 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年9月19日 知的財産高等裁判所
引用発明の「柱状物」「柱先端部」「柱状物構造」は,それぞれ,本件補正発明\nの「支柱」「先端部分」「鋼管ポール」に相当する。また,引用発明の「炭素鋼を 使用し」「柱状物を支持する支持基礎」は,本件補正発明の「前記支柱の下端部を 固定する鋼製基礎」に相当する。 そして,前記検討によれば,引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は,別 の部材により「支柱」を固定し,支柱の荷重を地盤に伝え,地盤から抵抗を受ける ことにより,「支柱の下端部を固定する」部材であって,引用発明の,「ベースの パイプの取付部に貫通穴を設けることにより,柱状物は,柱先端部が」「ベースを 貫通して土中に突出している」構成は,本件補正発明の「前記支柱は前記基礎体を\n貫通して先端部分が地中に突出していること」に相当し,引用発明の「土中に埋込 んで」は,本件補正発明の「地中に埋設され」に相当し,さらに,これらによれば, 引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は,本件補正発明の「基礎体」に相当 する。一方,「パイプ」が,本件補正発明の「基礎体」に相当するということはで きない。 したがって,本件補正発明と引用発明とは,「支柱と,前記支柱の下端部を固定 する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって,前記鋼製基礎は基礎体から構成され,\n前記基礎体は地中に埋設され,前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に 突出している鋼管ポール」である点で一致し,相違点1及び2(前記第2の3(2) イ(イ)及び(ウ))のほか,以下の点で相違する(原告主張に係る相違点3に同じ)。 「基礎体」に関して,本件補正発明は「上下に貫通した筒状」であるのに対し, 引用発明は「中央部にパイプを溶接で強固に突設し」た「ベース」と当該「ベース のパイプ取付面の四隅に配設し」た「平板状の羽根」とからなる点。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.09.23
平成29(行ケ)10049 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年9月14日 知的財産高等裁判所
本願商標のうち「Advanced Midwife」の文字部分の「A dvanced」,「Midwife」の各欧文字は,「上級の」,「助産師」をそれぞれ意味する英語である(乙3,4)から,「Advanced Midwife」の 欧文字部分からは,「上級の助産師」の意味が生じるものと認められる。また,本願 商標のうち,「アドバンス助産師」の文字部分からは,「上級の助産師」という意味 が生じるものと認められる。 そうすると,本願商標は,「上級の助産師」の意味が生じる語を日本語表記及び英\n語表記で表\示したものであって,本願商標全体としても,「上級の助産師」の意味を 生じるということができる。 ところで,1)前記1(3)のとおり,「アドバンス助産師」制度は,助産関連5団体 によって創設されたもので,「アドバンス助産師」を認証するための指標は,公益社 団法人日本看護協会が開発したものであるから,その専門的知見が反映されている ものと推認されること,2)前記1(1),(2)のとおり,原告は,専門職大学院の評価 事業のほか,助産師養成機関や助産所の第三者評価事業を行っており,助産分野の 評価を適切に行えるものと推認されること,3)前記1(6)のとおり,「アドバンス助 産師数」は,厚生労働省により周産期医療体制の現状把握のための指標例とされて いること,以上の事実からすると,「アドバンス助産師」認証制度は,一定程度の高 い助産実践能力を有する者を適切に認証する制度であると評価されるべきものと認\nめられる。また,前記1(3),(5)のとおり,「アドバンス助産師」認証制度は,平成 27年から実施され,既に1万人を超える「アドバンス助産師」が存在すること, 前記1(7)のとおり,各病院において,ウェブサイトに「アドバンス助産師」の認証 を受けた助産師が存在することを記載し,充実した周産期医療を提供できることを 広報していることからすると,「アドバンス助産師」は,国家資格である助産師資格 を有する者のうち,一定程度の高い助産実践能力を持つ者を示すものであることが,\n相当程度認知されているものと認められる。 そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,「アドバンス助産師」を,助産 師のうち,一定程度の高い助産実践能力を持つ者であると認識するということがで\nきるところ,その認識自体は,決して誤ったものであるということはない。
(3) 国家資格の中には,知識や技能の難易度等に応じて,同種の資格の中で段\n階的にレベル分けされているものがあることが認められる(乙21〜28)が,上 級の資格を「アドバンス」と称する国家資格があるとは認められないこと(甲28 参照)や前記のとおり「アドバンス助産師」制度が相当程度認知されていることか らすると,「アドバンス助産師」が「助産師」とは異なる国家資格であると認識され るとは認められないし,仮に,そのように認識されることがあったとしても,以上 の(1),(2)で述べたところからすると,本願商標が国家資格等の制度に対する社会 的信用を失わせる「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」というこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.09.12
平成27(ワ)36981等 虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求事件特許権侵害差止等反訴請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月31日 東京地方裁判所(47部)
上記(ア)の認定事実によれば,本件プロジェクトには,NTTコム のプロジェクトチームメンバーの他,Cをはじめとするベース社のメン バーやAをはじめとする被告のメンバーが関与し,A以外の者(例えば, C)からも新たなパスワード登録方法に関するアイデアが出される中で, 同プロジェクトの成果物として甲11発明が完成し,発明者をBとする 特許出願がされたことが認められる。 そして,甲11発明のパスワードの初期登録に係る部分は,1)認証サ ーバがウェブサーバを介してアクセス元の端末装置に初期ワンタイムパ スワード情報登録URLを通知する電子メールを送信し,2)端末装置の ユーザは,上記URLにおいて,認証サーバからウェブサーバを介して 送られたウェブページを見て,縦4個×横12個のランダムパスワード の中から選択し,選択したパスワードを入力し,3)認証サーバから送ら れた2回目のランダムパスワードに対し,端末装置のユーザがランダム パスワードを入力し,4)認証サーバが,2回の入力によりユーザにより 選択されて確定されたランダムパスワードの位置情報をユーザ情報とし てデータベースに登録し,5)認証サーバが,URLを通知する電子メー ルをウェブサーバを介してアクセス元の端末装置に送信する,というも のであると認められる(甲11発明に係る明細書の段落【0018】な いし【0021】参照)ところ,上記部分を具体的に着想,提示した主 体(甲11発明のパスワードの発明者)がAのみであると認めるに足り る証拠はないから,本件発明1と甲11発明の発明者が同一であるとは 認められない。
(ウ) これに対し,被告は,甲11発明の特徴的部分は「位置情報が確定 されるまで,縦4個×横12個の新たなランダムパスワードを端末装置 1が表示する処理を繰り返し行い,これにより,縦4個×横12個の新\nたなランダムパスワードについての特定の座標位置に配置されているパ スワード(すなわち数字)の入力を促す処理を繰り返すこと」にあると ころ,これと同一の特徴的部分を有する方式Cの記載された本件手順案 をAが作成し,NTTコムに送付したことに照らせば,甲11発明の発 明者はAである旨主張する。 この点,本件手順案のデータに係るプロパティには作成者として 「(省略)」と記載されている(乙31の3)が,これをもって直ちにA のみが本件手順案の内容を着想したと推認することはできず,かえって, 本件手順案より前にCにより作成された本件C文書にも,「3)認証後, OFFICのワンタイムパスワードを登録する画面において,自分のパ スワード位置と順序を指定し,確認後,登録する。4)ワンタイムパスワ ード登録完了したことを,URLと共にe−mailで利用者の携帯端 末へ通知する。(このURLは本番用)」といった記載があることによれ ば,本件手順案の内容の一部は,Aが本件手順案を作成するよりも前に 既に本件プロジェクト内において着想されていたものと認められる。し たがって,被告の上記主張を採用することはできない。
ウ 小括
以上によれば,本件発明1は特許法29条の2によって特許を受けられ ないから,本件特許1には無効理由が認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2017.09.12
平成28(ワ)13239 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月31日 東京地方裁判所(46部)
以上によれば,従来のオルタネータにおいてはブリッジ整流器が備える正 ダイオードを冷却するためにこれを熱放散ブリッジに取り付け,同ブリッジ にスロット(開口部)を設けることでその内部を冷却空気が循環するように し,同ブリッジの上面にフィンを設けることで同ブリッジの冷却を助けるこ ととしていたのに対し,電力用トランジスタ及びかさ高の制御装置を備える ブリッジ整流器があるオルタネータ/スタータにおいては,同ブリッジにス ロットを設けるための空間を確保できない問題に対応するため,同ブリッジ が外側後面に冷却フィンを有する後部軸受けに押し当てられる構成が知られ\nていた。しかし,この構成においては,後部軸受けに熱放散ブリッジ又は基\n部をしっかりと押し当てる必要があり,また,後部軸受けが非常に高温にな ると対流で冷却できなくなるという課題があった。本件発明1は,冷却流体 が機械の後部に横方向に導入され,熱放散ブリッジ及びオルタネータの後部 軸受け間に形成された流体流通路内を循環する目的のために熱放散ブリッジ の後部軸受け側の面を通路の長手方向壁,後部軸受けを上記通路の別の長手 方向壁とし,冷却手段としてフィンを上記通路内に配置する構成を採用した\n点に技術的意義があるということができる。
・・・・
原告は,被告製品のフィンが「前記流体通路(17)内に配置」されて いないという相違点があるとしても,被告製品は本件発明1の構成と均等\nなものとして,本件発明1の技術的範囲に属するというべきであると主張 する。被告製品が本件発明1の構成と均等であるというためには,特許請\n求の範囲に記載された構成中被告製品と異なる部分が特許発明の本質的部\n分でないことが必要である。 イ そこで本件発明1の本質的部分につき検討する。 本件明細書1における背景技術,発明が解決しようとする課題及び課題 を解決するための手段の記載(前記1(2))を参酌すると,前記1(3)のとお り,本件発明1は,熱放散ブリッジにフィンを設け,これに冷却空気を触 れさせて電気部品の冷却を図る構成につき,熱放散ブリッジと後部軸受け\nの間に冷却流体通路を設けて冷却空気を循環させることとし,当該通路内 に冷却フィンを設けるオルタネータ/スタータの構成とすることによって,\n熱放散ブリッジにスロットが設けられない場合であっても十分に熱放散ブ\nリッジを冷却させることができる効果を生じさせることとしたというもの である。このことに照らすと,冷却流体の通路及び冷却フィンの配置につ いて上記構成を採用したことに本件発明1の意義があるということができ\nるから,冷却フィンがどこに配置されるかを含めたその配置は,本件発明 1の本質的要素に含まれると解するのが相当である。 そうすると,被告製品において冷却フィンが冷却流体通路でなく,熱放 散部材の底面であって上側ベアリングの開口部と対応する部分に配置され ている構成は,本件発明1と本質的部分において相違するというべきであ\nる。したがって,被告製品が本件発明1の構成と均等であるということは\nできない。
ウ これに対し,原告は,本件発明1の本質的部分は後部軸受けと熱放散ブ リッジの間に長手方向の,回転シャフトと熱放散ブリッジの間に軸方向の 各冷却流体通路を備えた点にあると主張する。 しかし,上記イのとおり,本件明細書1は熱放散ブリッジにフィンを設 け,これに冷却空気を触れさせて電気部品の冷却を図る構成を従来技術と\nして明示しており,フィンによって熱放散ブリッジと冷却空気が触れる表\n面積を増やし,これによって冷却効果を図る構成を採用することが前提と\nされていること,フィンの配置は冷却効果の程度に影響すると解されるこ とに照らすと,当該配置も本件発明1の意義に含まれるというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> ピックアップ対象
2017.09.12
平成29(ネ)10041 特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明では,近用アイポイントから近用中心までの距離を小さくしているため, 近用アイポイントから近用部にかけて発生する収差が比較的小さく,良好な視覚特 性が得られ,視線を大きく下げることなく中間視から近用視へ移行することができ るとともに,近用部において広い明視域を確保することができる。 また,特定中心を基準とした近用アイポイントでの屈折力増加量(KE−KA)を 加入度(KB−KA)の60%〜90%に設定すると,近用アイポイントから近用部 に至る領域の側方領域における非点収差の集中が軽減され,像の揺れや歪みなどが 抑えられ,近用部及び中間部において広い明視域を実現することができ,さらに, 近用アイポイントから特定視部にかけて加入度の60%〜90%だけ屈折力を低下 させるとの構成により,近用アイポイントから特定視部にかけて視覚特性が改良さ\nれ,主子午線曲線の側方領域における収差集中が緩和される結果,像の揺れや歪み を軽減することができ,広い明視域を確保することができ,また,屈折力の変化の 度合いが比較的小さいため,近用アイポイントと特定視部との接続が連続的で滑ら かになるように構成することができ,特定視部の明視域を大きく確保することがで\nきる(【0018】【0019】)。
(エ) 以上によれば,本件発明は,「近用視矯正領域」と,「特定視距離矯正領 域」と,「近用視矯正領域と特定視距離矯正領域との間において両領域の面屈折力 を連続的に接続する累進領域」とを備えた累進多焦点レンズを前提に,目の調節力 の衰退が大きい人が長い時間にわたって快適に近方視を継続することを目的として, 近用アイポイントから近用中心までの距離を2mmから8mmと設定するとともに, 条件式(1)(2)の条件を満足することを特徴とする累進多焦点レンズを提供し た結果,視線を大きく下げることなく中間視から近用視へ移行することができ,近 用部において広い明視域を確保するとともに,特定視部の明視域を大きく確保する ことを実現したものであるから,本件発明の本質的部分は,近用アイポイントから 近用中心までの距離を2mmから8mmと設定したことと,条件式(1)(2)を 設定したことにあると認められる。 そして,条件式(1)(2)では,「近用視矯正領域の中心での屈折力」である KBと「特定視距離矯正領域の中心での屈折力」であるKAとの差(KB−KA)が用 いられているところ,「特定視距離矯正領域」の範囲を特定できなくては,「特定 視距離矯正領域の中心」が特定できず,その屈折力KA を求めることができない上, 条件式(2)では,前記(2)イのとおり,「特定視距離矯正領域」の範囲を特定する ことができなければ,「特定視距離矯正領域」の明視域の最大幅WFを特定すること ができない。したがって,条件式(1)(2)を満足させるためには,「特定視距 離矯正領域」の範囲を特定できることが必要であるから,「特定視距離矯正領域」 が,屈折力が一定ないしほぼ一定の領域を有する,ある程度広がりを持った領域で あることも,本件発明の技術的思想を構成する特徴的部分であり,本質に係る部分\nである。したがって,控訴人の主張は,採用できない。
(オ) 被告製品は,前記(1)(2)のとおり,いずれも「特定視距離矯正領域」,「特 定視距離矯正領域の中心」を充足せず,条件式(1)(2)を満足させるものでは ないから,本件発明とは,その本質的部分において相違することが明らかであり, 均等の第1条件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2017.09.12
平成28(ワ)25472 不正競争行為差止請求事件 不正競争 平成29年8月31日 東京地方裁判所(46部)
原告商品は,外観が別紙原告商品目録記載の各図のとおりのものであ り,原告商品形態1)〜6)を有する。すなわち,原告商品は,組立て式の 棚として,側面の帆立(原告商品形態1)),棚板の配置(原告商品形態 3)),背側のクロスバー(原告商品形態4))が特定の形態を有するほか, 帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたものであるという特徴的な形 態(原告商品形態2))を有し,また直径の細い棒材からなる帆立の横桟 及びクロスバー(原告商品形態5))も特定の形態を有するもので,それ らを全て組合せ,かつ,全体として,上記の要素のみから構成される骨\n組み様の外観を有するもの(原告商品形態6))である。このような原告 商品形態は原告商品全体にわたり,商品を見た際に原告商品形態1)〜6) の全てが視覚的に認識されるものであるところ,原告は,原告商品の形 態的特徴として原告商品形態1)〜6)が組み合わされた原告商品形態を主 張するので,以下,上記原告商品形態が他の同種商品と識別し得る顕著 な特徴を有するか否かを検討する。
ここで,原告商品及び同種の棚の構成要素として,帆立,棚板,クロ\nスバー,支柱等があるところ,これらの要素について,それぞれ複数の 構成があり得て(前記(1)ケ),また,それらの組合せも様々なものがあ り,さらに,上記要素以外にどのような要素を付加するかについても選 択の余地がある。原告商品は,原告商品と同種の棚を構成する各要素に\nついて,上記のとおりそれぞれ内容が特定された形態(原告商品形態1) 〜5))が組み合わされ,かつ,これに付加する要素がない(原告商品形 態6))ものであるから,原告商品形態は多くの選択肢から選択された形 態である。そして,原告商品形態を有する原告商品は,帆立の支柱が直 径の細い棒材を2本束ねたという特徴的な形態に加えクロスバーも特定 の形態を有し,細い棒材を構成要素に用いる一方で棚板を平滑なものと\nし,他の要素を排したことにより骨組み様の外観を有する。原告商品は, このような形態であることにより特にシンプルですっきりしたという印 象を与える外観を有するとの特徴を有するもので,全体的なまとまり感 があると評されることもあったものであり(同キ),原告商品全体とし て,原告商品形態を有することによって需要者に強い印象を与えるもの といえる。このことに平成20年頃まで原告商品形態を有する同種の製 品があったとは認められないこと(同ク)を併せ考えると,平成16年 頃の時点において,原告商品形態は客観的に明らかに他の同種商品と識 別し得る顕著な特徴を有していたと認めることが相当である。 イ 被告は,原告商品形態1)〜6)のうちの各個別の形態を取り上げ,それら がありふれた形態であり,原告商品が他の同種の商品と識別し得る特徴を 有しない旨主張する。
しかし,前記アに述べたところに照らし,原告商品形態が他の同種の商 品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は,原告商品形 態1)〜6)のうちの個別の各形態がありふれている形態であるか否かではな く,原告商品形態1)〜6)の形態を組み合わせた原告商品形態がありふれた 形態であるかを検討すべきである。したがって,原告商品形態1)〜6)のう ちの各個別の形態にありふれたものがあることを理由として原告商品形態 が商品等表示とならなくなるものではない。\nまた,被告は,原告商品形態1)〜6)のうちの各個別の形態について,特 有の機能等を得るために不可避的に採用せざるを得ない形態である旨主張\nする。しかし,上記各個別の形態について,原告商品形態とは異なる構成\nを採ることができ(前記(1)ケ),かつ,原告商品形態が上記各個別の形態 の組合せからなることに照らせば,原告商品形態が特定の機能等を得るた\nめに不可避的に採用せざるを得ない構成であるとの被告の主張は採用する\nことができない。
ウ 原告商品は平成9年1月頃から販売されたところ,被告は,原告商品形 態を備えた商品が平成元年頃から日本国内で販売されていたことを主張す る。 前記(1)クのとおり,平成元年頃から,少なくとも原告商品形態2),3)及 び5)を備えた「ETAGAIR」という名称の商品が販売された。しかし, 当該商品は,少なくとも,帆立について一方向に斜めの棒が含まれ,背面 にクロスバーがなく,原告商品形態1),4)を備えず,原告商品形態を備え ているとはいえない。そして,このことから上記商品と原告商品の外観上 の特徴は異なるといえるのであって,上記商品の販売の事実によって,原 告商品形態がありふれたものであるとか,他の商品と識別し得る特徴とは ならないということはできない。
エ 被告は,原告商品のほかにも原告商品形態を有する商品が販売されてい ると主張して,原告商品形態には,識別力がない旨主張する。 しかし,上記で被告が主張する商品について認められる事実は前記(1)ク のとおりであり,その商品の販売が開始された時期は早くても平成20年 頃である。したがって,平成20年より前に原告商品形態がありふれたも のであったことを認めるに足りない。そして,後記(4)のとおり,原告商品 形態は,平成16年頃には,原告の商品であることを示す識別力を有した と認められる。また,被告が指摘する商品は,年間の売上高も原告商品と 比べて多くなく,製造販売期間も長いとはいえず,現在では販売を終了し たものもある。そうすると,原告商品形態が平成16年頃に原告の商品を 示すものとしての識別力を有した後,上記商品によって,原告商品形態が ありふれたものになり,他の商品と識別し得る特徴を有することがなくな ったとはいえない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2017.09. 7
平成28(行ケ)10170 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月30日 知的財産高等裁判所(1部)
審決は,「x2+y2=r2」の式は,原点を中心とする半径rの円周上 の各点の座標(x,y)の方程式とみることもできるが,斜辺の長さがrとなる直 角三角形における直角をはさむ2辺の長さx,yの方程式とみることもでき,この 場合,本件条件式(|(x2+y2)1/2|≦2.50)のx,yは,それぞれ,測 定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置(水平方向外 縁位置)までの距離,及び,測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外 縁と交差する位置(鉛直方向外縁位置)までの距離を示すと解するのが自然である とする(第1解釈)。 しかしながら,審決の上記認定に従って,本件条件式のx,yを理解すると,本 件条件式は,「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が2.5mm以下であ ればよく,水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから, 本件条件式によっては,「所定領域」の形状が定まらないことになる。また,水平方 向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が2.5mm「以下」であればよいことにな るので,水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が0のもの,すなわち,所定領域 として大きさをもたないものも含むことになる。 前記(ア)のとおり,所定領域は面非点隔差成分の平均値(ΔASav)を決めるた めの基準となる範囲を示すものであって,本件条件式は,この所定領域が満足すべ き範囲を定めるものであることからすれば,本件条件式について,上記のように, 形状が定まらず,また,大きさを持たないものも含むように解することは,不自然 であるといわざるを得ない。
また,本件明細書には,「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基 準点を含む近傍の領域は,…|(x2+y2)1/2|≦1.75(mm)の条件を満 足する領域であることが望ましい。また,処方度数と測定度数とをさらに良好に一 致させるには,実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む 近傍の領域は,|(x2+y2)1/2|≦2.50(mm)の条件を満足する領域で あることが望ましく」(前記1(1) と記載されていることからすると,本件条件 式は,少なくとも,|(x2+y2)1/2|≦1.75(mm)の場合と比較して, 度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。 しかしながら,審決の上記解釈によれば,本件条件式は,所定領域の形状が特定 されるものではなく,しかも,所定領域として大きさを持たないものも含むことに なるものであるから,度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く, 上記のとおり,|(x2+y2)1/2|≦1.75(mm)の条件式と対比して,本 件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。 したがって,審決の上記解釈は,不自然であるといわざるを得ない。 なお,審決は,「所定領域」は,測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略 一定の領域(すなわち,測定基準点を中心とする略円形の領域)として設ければよ いのであり,水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく 異なるような不定形の形状の領域にすることは,必要がないばかりか,光学性能の\n低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして,本件条件式は, 測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを 前提として,その大きさを規定したものである,とも認定している。むしろ,この ように,所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となる のであれば,本件明細書の記載に接した当業者は,本件条件式が円を規定するもの, すなわち,x,yを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。 以上によれば,本件明細書において,本件条件式とともに面非点隔差成分の平均 値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔASについて,x,yが座標として用いら れていること,本件条件式のx,yを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方 向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不 自然であることなどから,本件条件式のx,yは,座標として用いられていると解 するのが相当である。そして,このように解しても,本件訂正後の本件訂正発明は, 処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構\\成を採用している にもかかわらず,レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するも のであると認められる。 したがって,訂正事項1−4は,もとより座標を示すものであると解される本件 条件式のx,yが座標であることを明記したにすぎないものであり,訂正事項1− 4に係る本件訂正発明3の第2発明特定事項は,本件明細書の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項であり,新たな技術的事項を導入しないものであ るから,本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2017.09. 7
平成28(行ケ)10187 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月30日 知的財産高等裁判所(第1部)
しかし,仮に「イリュージョン」については測定誤差の範囲内といえるとしても, それは,実際に製造販売された製品である「イリュージョン」のマイクロカプセル 顔料の形状が比較的球形に近かったという一事例を示すにとどまるものであり,本 件発明におけるマイクロカプセル顔料一般の形状が比較的球形に近いことを裏付け るに足りない(なお,前記「第4 被告の反論」の1(1)のとおり,他の原告ら製品 (「フリクション」)には球形とは相当異なった粒子が一定数含まれていたと認めら れる。)。現に,本件発明の想定する技術的範囲には,甲24の図1〜3に示される ような形状のマイクロカプセル顔料も含まれることは前記(1)アのとおりであり,例 えば全てが甲24文献の図3のような形状のマイクロカプセル顔料の場合には,粒 子径(代表径)の規定のし方による差が相当大きくなるものと推認される。\n
・・・・
本件特許請求の範囲及び本件明細書には,粒子径(代表径)の定義に関す\nる明示の記載はない。 当業者の技術常識を検討すると,平成11年11月1日から平成14年10月3 1日までの間に,筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が記載された特許出願の 公開特許公報58件のうち,レーザ回折法で測定したものが23件,遠心沈降法で 測定したものが6件,画像解析法で測定したものが8件,動的光散乱法で測定した ものが22件(うち1件は遠心沈降法と動的光散乱法を併用)であった一方,等体 積球相当径を求めることができる電気的検知帯法で測定しているものはなかったこ と(甲20),平成14年6月1日から平成17年5月31日までの間の特許出願に ついて,審判官が職権により甲20と同様の調査したところ,原告ら及び被告以外 の当業者では,電子顕微鏡法,レーザ回折・散乱法,遠心沈降法により平均粒子径 を測定している例があった一方,電気的検知帯法が用いられた例は発見されていな いこと(弁論の全趣旨)が認められる。また,種々の測定方法で得た値から,再度 計算して,等体積球相当径を粒子径(代表径)とする平均粒子径に換算していると\nも考え難い。そうすると,粒子径(代表径)について,等体積球相当径又はそれ以\n外の特定の定義によることが技術常識となっていたとは認められない。 以上のとおり,技術常識を踏まえて本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を 検討しても,粒子径(代表径)を特定することはできない。\n
(3) 原告らは,本件発明が粒度分布を体積基準で表していること,測定方法の\n記載がないこと,マイクロカプセル顔料の大きさに着目するという本件発明の特徴, 測定の難易から,本件発明の粒子径(代表径)として,光散乱相当径やストークス\n径は不適当である一方,等体積球相当径は適当である旨主張する。 しかし,粒度分布の表し方を体積基準又はそれと等価である質量基準とするのが\n通常である粒子径(代表径)には,審決が指摘するとおり,等体積球相当径の他に\nも,光散乱法による光散乱相当径,光回折法による光の回折相当径,沈降法による ストークス径があると認められる。そして,前記(2)のとおり,筆記具用インキの粒 子の大きさの測定に関する公知発明において,これらの粒子径(代表径)又は測定\n方法が相当程度採用されていたことに照らせば,これらの粒子径(代表径)又は測\n定方法も,マイクロカプセル顔料の大きさに着目する技術分野において,当業者が 採用を検討し得る有用な測定基準であると推認される。なお,原告パイロットイン キによる特許出願でも,インキの吐出性を考慮して粒子の大きさを限定するため, 遠心沈降式の測定装置を用いて体積基準の粒度分布を求めている例がみられる(乙 11【0016】【0040】)。 また,測定方法の記載がない場合に,特定の測定方法に対応しない粒子径(代表\n径)の定義を採用したものと考えるという技術常識を認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.08.24
平成27(ネ)10122 不当利得返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
訂正前の「…前記第1の位相から調節できるように固定された第1 の量だけ転位させた第2の位相を有する第3のクロック信号…」の記載 によれば,「第2の位相」の「第1の位相」からの変位量(転位の量) は,第3のクロックが調節されたとしても,第1のクロックが同じ量 だけ調節されれば,変位量に変化がなく,このような調節も「固定」 に含まれると解される。 これに対し,訂正後の「…第2の位相の前記第1の値をもつ第1の位 相を基準とした変位量は,第1の位相が前記第1の値をもっている状態 において第3のクロック信号の調整がなされるまでの間,固定された第 1の量であり,前記変位量は,第3のクロック信号が調節されたときは 調節される…」との記載によれば,変位量は,第1のクロックの調節に よらず専ら第3のクロックの調節により調節され,第3のクロック信号 が調節されれば,仮に第1のクロックが同じ量だけ調節されたとしても 変化するように,「固定」の技術的意味を変更するものと理解される。
(エ) 以上より,訂正事項2は,特許請求の範囲の減縮を目的とするもの に当たらないとともに,不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的と する訂正であるということもできない。 また,訂正事項2が,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当 該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものでな いことは明らかである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 減縮
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.08.23
平成29(行ケ)10006等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月22日 知的財産高等裁判所
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だ けではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願 当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は,本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載のうち,「急激な降下」, 「急激な降下部分の外挿線」及び「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」との各 記載が不明確であると主張するから,以下検討する。
(2) 「急激な降下」,「急激な降下部分の外挿線」との記載
ア 請求項1及び2の記載のうち「急激な降下」部分とは,動的貯蔵弾性率の温 度による変化を示す図において,左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分 を意味することは明らかである(【図2】)。また,傾きの最も大きい部分の傾き の程度は一義的に定まるから,「急激な降下部分の外挿線」の引き方も明確に定ま るものである。
イ これに対し,原告は,動的貯蔵弾性率の傾きが具体的にどのような値以上に なったときに「急激な降下」と判断すればよいか分からない旨主張する。しかし, 「急激な降下」とは,相対的に定まるものであって,傾きの程度の絶対値をもって 特定されるものではないから,同主張は失当である。
(3) 「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」との記載
ア ASTM規格(乙31)は,世界最大規模の標準化団体である米国試験材料 協会が策定・発行する規格であるところ,ASTM規格においては,温度上昇に伴 って変化する物性値のグラフから,ポリマーのガラス転移温度を算出するに当たり, ほぼ直線的に変化する部分を特段定義しないまま,同部分の外挿線を引いている。 また,JIS規格(乙13)は,温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから, プラスチックのガラス転移温度を算出するに当たり,「狭い温度領域では直線とみ なせる場合もある」「ベースライン」を延長した直線を,外挿線としている。 そうすると,ポリマーやプラスチックのガラス転移温度の算出に当たり,温度上 昇に伴って変化する物性値のグラフから,特定の温度範囲における傾きの変化の条 件を規定せずに,ほぼ直線的な変化を示す部分を把握することは,技術常識であっ たというべきである。 そして,ポリマー,プラスチック及びゴムは,いずれも高分子に関連するもので あるから,ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は,その主成分で ある高分子に関する上記技術常識を当然有している。 したがって,ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は,上記技術 常識をもとに,昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す 図において,特定の温度範囲における傾きの変化の条件が規定されていなくても, 「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で,同部分の外挿線を引くことがで きる。
・・・
このように,外挿線Aと外挿線Bの交点温度として特定された170℃という温 度は,補強用ゴム組成物の180℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着 目したことから導かれたものであって,かかる交点温度は,その引き方によっても 1℃の差が生ずるにとどまる。そうすると,外挿線Aと外挿線Bの交点温度によっ て,ゴム組成物の構成を特定するという特許請求の範囲の記載は,第三者の利益が\n不当に害されるほどに不明確なものとはいえない。
(4) 小括
したがって,本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載のうち,「急激な降 下」,「急激な降下部分の外挿線」及び「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」 との各記載は明確であって,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載が明 確性要件に違反するということはできない。請求項3及び4の各記載も同様である から,明確性要件に違反するということはできない。 よって,取消事由1は理由がある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.08.17
平成28(行ケ)10119 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月3日 知的財産高等裁判所
甲2には,上記のようにブラシを減らすことができる原理を説明する明示的な記 載はないが,甲2の【0033】における「従来の電動モータ1では,第1のブラ シ11a及び第3のブラシ11cを介して電流が流れるが,この実施の形態では第 1のブラシ89aを介して電流が流れ,ブラシ89aを通じて流れる電流量が従来 のものと比較して2倍となる。」との記載からすると,甲2においてブラシを減らす ことができるのは,均圧線を設けたことの結果として,1個のブラシから供給され た電流が,そのブラシに当接する整流子片に供給されるとともに,均圧線を通じて 同電位となるべき整流子片にも供給されることによって,対となる他方のブラシが なくとも従来モータと同様の電流供給が実現できるためであることが理解できる。 この点について,被告は,甲2には,均圧線の使用とブラシ数の削減とを結び付け る記載がないことを理由に,接続線を使用してブラシの数を半減する技術が開示さ れていない旨主張するが,そのような明示的な記載がなくとも,甲2の記載から上 記のとおりの理解は可能というべきである。また,被告は,甲2の4ブラシモータの電気回路図(図16)と2ブラシモータの電気回路図(図2)を対比すると,そ\nの配線が完全に一致すると主張するが,4ブラシモータの電気回路図(図16)に おいても,2ブラシモータの電気回路図(図2)においても,整流子片1,2,1 2及び13が+電位となり,整流子片6〜8及び17〜19が−電位になっており, その結果,ブラシ以外の電気回路(巻線及び均圧線の接続関係)に変化を加えなく とも両者がモータとして同じ電気的特性を持つことが理解できるところ,2ブラシ モータの電気回路図においては,前記の整流子片が同電位となるために均圧線の存 在が必須であることが理解できるから,甲2の4ブラシモータの電気回路図と2ブ ラシモータの電気回路図との配線が一致することは,均圧線の存在によってブラシ 数の削減が可能になることを示すものであって,このことが,甲2には接続線を使用してブラシの数を半減する技術が開示されていないことの根拠となり得るもので\nはない。
イ そうすると,甲2の記載に接した当業者は,甲2には,4極重巻モータ において,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することにより,同電位に接 続されている2個のブラシを1個に削減し,もって,ブラシ数の多さから生じるロ ストルク,ブラシ音及びトルクリップルが大きくなるという問題を解決する技術が 開示されていることを理解するものといえる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(行ケ)10038 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月26日 知的財産高等裁判所(3部)
本件発明1についての一致点の認定の誤り・相違点の看過について
原告は,本件審決が,甲11発明1は,「第一成分」と「第二成分」とを総和 として液晶組成物の全重量に基づき「10重量%から100重量%」含有する ものであるとした上で,「成分として,一般式(II−1)及び(II−2)・・・ で表される化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化合物を含有し,その含\n有量が20から80質量%であり」との構成を本件発明1と甲1発明1の一致\n点と認定したのは誤りであり,その結果,本件審決は相違点を看過している旨 主張するので,以下検討する(ただし,本件審決の「甲1発明1」の認定に不 備があることは上記2のとおりであるから,以下の判断においては,甲1発明 1が上記2(2)ア(ウ)のとおりのものであることを前提に検討を進める。)。 (1) 本件審決は,甲1発明1における「第一成分として式(1−1)及び式(1 −2)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物」が,\n本件発明1における「第二成分として,・・・一般式(II−1)・・・で表される\n化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化合物」を包含すること,及び甲 1発明1における「第二成分として式(2−1)で表される化合物の群から\n選択された少なくとも1つの化合物」が,本件発明1における「第二成分と して,・・・一般式・・・(II−2)・・・で表される化合物群から選ばれる1種又は\n2種以上の化合物」を包含することを前提として,甲1発明1において,液 晶組成物の全重量に基づいて,第一成分の重量が「5重量%から60重量%」 であり,第二成分の重量が「5重量%から40重量%」であることは,第一 成分と第二成分の総和としての重量が「10重量%から100重量%」であ ることを意味するから,本件発明1と甲1発明1は,「一般式(II−1) 及び(II−2)・・・で表される化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化\n合物を含有し,その含有量が20から80質量%であり」との点において一 致する旨認定する(別紙審決書48,49頁)。 しかしながら,1)甲1発明1における「式(1−1)及び式(1−2)で 表される化合物」と2)本件発明1における「一般式(II−1)で表される\n化合物」とを対比すると,2)のR1及びR2は,「それぞれ独立的に炭素原子 数1から10のアルキル基,炭素原子数1から10のアルコキシル基,炭素 原子数2から10のアルケニル基又は炭素原子数2から10のアルケニルオ キシ基」であるのに対し,1)のR6及びR5は,「R5は,炭素数1から12を 有する直鎖のアルキルまたは炭素数1から12を有する直鎖のアルコキシで あり,R6は,炭素数1から12を有する直鎖のアルキルまたは炭素数2から 12を有する直鎖のアルケニルである」ことから明らかなとおり,両者の関 係は,本件審決がいうように1)の化合物が2)の化合物を包含するという関係 にあるものではなく,1)の化合物の一部と2)の化合物の一部が一致するとい う関係にあるものにすぎない(例えば,式(1−1)又は式(1−2)にお いてR6が炭素数11を有する直鎖のアルキルである1)の化合物は,2)の化合 物には含まれないし,他方,一般式(II−1)においてR1がアルコキシル 基である2)の化合物は,1)の化合物には含まれない。)。そして,このこと は,甲1発明1における「式(2−1)で表される化合物」と,本件発明1\nにおける「一般式(II−2)で表される化合物」の関係にも同様に当ては\nまることである。 してみると,甲1発明1が,「式(1−1)及び式(1−2)で表される\n化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物」及び「式(2−1)で 表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物」を含有するこ\nとをもって,本件発明1における「一般式(II−1)及び(II−2)… で表される化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化合物を含有」するこ\nとと一致するということはできないのであって,この点について,本件審決 が本件発明1と甲1発明1の一致点と認定したことは誤りである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成29(行ケ)10030 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年7月27日 知的財産高等裁判所
以上によると,1)被告は,我が国における総合水処理エンジニアリング分野にお ける最大手企業の一つであり,その設立以来,「オルガノ」及びその英語表記である\n「ORGANO」をハウスマークとして使用していること,2)被告の事業の主力は 水処理装置事業であるが,薬品事業を含む機能商品事業の規模も大きく,被告の主\nな商品の市場占有率は高いこと,3)被告の薬品事業は,水処理薬品を中心にするも ので,水処理装置事業とは密接な関連性を有するということができること,4)被告 は20社以上からなるグループ企業を構成し,その子会社の多くは「オルガノ」の\n文字を冠する社名を用いているほか,幅広い分野で事業を営み,国際的な事業展開 も行っていること,5)被告は,たびたびメディアに取り上げられ,その事業内容が 一般に広く紹介されていること,6)被告は,新聞や雑誌において,「オルガノ」の文 字や使用商標1を使用して継続的に宣伝広告を行い,特に,新聞広告については, 長期間にわたり全国紙に題字広告を掲載するという目立つ態様のものであったこと, 以上の各事実を認めることができる。 これらの事実によると,「オルガノ」及びその英語表記である「ORGANO」の\n表示は,被告の略称又はハウスマークを表\示するものとして,本件商標の登録出願 日前から,取引者,需要者に広く知られるようになっており,それに伴い,「オルガ ノ」又はその英語表記である「ORGANO」を含む使用商標についても,同時点\nまでの間に,取引者,需要者に広く知られて周知,著名となっていたと認めるのが 相当である。 そして,使用商標は,ほぼ同大の図形部分及び「ORGANO」又は「オルガノ」 の文字部分から構成されているところ,このうち図形部分からは特段の観念や称呼\nが生じないのに対し,「ORGANO」及び「オルガノ」という文字部分は,その称 呼が被告の略称及びハウスマークと同一であり,商品及び役務の出所を取引者,需 要者に強く印象付ける部分であると考えられる。そうすると,使用商標のうち,「O RGANO」又は「オルガノ」の文字部分は,図形部分とは独立して出所識別標識 としての機能を果たすものということができる。\nしたがって,使用商標の文字部分からなる被告商標についても,被告の水処理装 置事業及びこれと密接に関係する薬品事業を表示するものとして,本件商標の登録\n出願日前から,周知,著名であり,本件商標の登録査定日においても同様であった と認められる。 原告の告の主張について これに対し,原告は,1)被告商標は,水処理装置事業の分野では周知であるとし ても,薬品の分野においては,周知,著名ではない,2)被告が行ってきた宣伝広告 は一般的な企業活動の一環にすぎず,新聞紙上に掲載した題字広告には「ORGA NO」の表示はなく,被告の取り扱う薬品類を表\示しているものもない,3)取引者, 需要者は,使用商標の「ORGANO」又は「オルガノ」の文字部分よりも水玉模 様の図形に注意をひかれる,4)被告商標は,特許情報プラットフォームの「日本国 周知,著名商標」に掲載されておらず,「ORGANO」又は「オルガノ」について の登録防護標章も存在しないなどと主張し,被告商標が周知,著名であることを争 う。
ア しかし,上記1)については,前記認定のとおり,薬品事業を含む機能商\n品事業は,その事業規模が大きく,水処理装置事業と並ぶ被告の主力事業であると いうことができる上,被告の水処理装置事業と薬品事業は密接な関連性を有してい るのであるから,被告の水処理エンジニアリング事業が広告宣伝等により取引者, 需要者に広く知られるようになるとともに,薬品事業についても,本件商標の登録 出願日前から広く取引者,需要者に知られるようになっていたと認めるのが相当で ある。
イ 上記2)については,一般的に,長期間にわたり継続的に行われる宣伝広 告は,商標が一般に広く知られる上で効果的な方法であり,特に,新聞広告は,全 国紙に題字広告を掲載するという目立つ態様の広告が長期間にわたり行われたもの であって,その間に「ORGANO」又は「オルガノ」という被告商標の表示も一\n般に広く知られるようになったものと認めるのが相当である。 原告は,上記の題字広告には「ORGANO」の表示はなく,薬品類も表\示され ていないと主張するが,前記認定のとおり,被告は,新聞広告に加えて,雑誌にお いて,「ORGANO」の文字を含む使用商標1を表示して広告宣伝を行うとともに,\nその事業内容はメディアにたびたび取り上げられて一般に広く紹介されているので あるから,題字広告に係る「オルガノ」という表示のみならず,「ORGANO」と\nいう表示についても一般に広く知られるようになったと認めるのが相当である。ま\nた,薬品事業については,上記ア判示のとおりであって,題字広告に薬品類の表示\nがないからといってこの認定が左右されることはない。
ウ 上記3)については,前記判示のとおり,使用商標のうち「ORGANO」 又は「オルガノ」の文字は,図形部分とは独立して出所識別標識としての機能を果\nたすものと認めるのが相当である。
エ 上記4)については,特許情報プラットフォームの「日本国周知,著名商 標」に被告商標が掲載されていないこと,及び,「ORGANO」又は「オルガノ」 が防護標章登録されていないことのみをもって,被告商標の周知著名性を認定する 妨げとはなるものではない。
◆判決本文
関連事件はこちら。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(行ケ)10275 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年7月27日 知的財産高等裁判所(2部)
上記(1)の認定事実によると,「個性心理学」は,「差異心理学」ともい われるもので,心理学のうち個人差の問題を扱う領域として古くから知られており, 国内外でこれを研究対象とする研究者や研究室があったこと,国語に関する辞書や 辞典においても,「個性心理学」についての説明が掲載されていることが認められ る。 そして,これらの事実によると,「個性心理学」という語は,心理学という学問 の一分野を示す普通名称であると認めるのが相当であり,原告の創作した創造標章 であるとは認められない。
(3) これに対し,原告は,本件審決が挙げた証拠は相当過去の事情を示すもの にすぎず,比較的最近の文献で「個性心理学」について言及しているものは甲27 3のみであること,心理学の分野で用いられる用語を説明する一般的な辞典では, 「個性心理学」を説明する項目がないことなどを指摘して,「個性心理学」は普通 名称ではない旨主張し,また,仮に「個性心理学」が普通名称であったとしても, 学問や研究対象としての心理学という極めて限られた範囲のことである旨主張す る。 確かに,近時の心理学の専門的な辞典(事典)では「個性心理学」という語は取 り上げられておらず(甲213〜229),また,近時,「個性心理学」が心理学 の学会等で取り上げられ,議論されていることを示す証拠はない。 しかし,前記のとおり,「個性心理学」が,個人差の問題を扱う心理学として存 在していたことが認められ,現時点でも,国語に関する辞書や辞典にその説明が記 載されている。また,最近の心理学の専門的な辞典には,アドラーが,独自の「個 人心理学」と呼ぶ理論体系を発展させたとして,当該理論体系を心理学の一分野と して紹介するものがあり(甲220),心理学については,一個人が提唱した理論 体系を,心理学の一分野として取り扱う例があることが認められるのであって,「個 性心理学」が,近時,心理学の学会等で取り上げられ,議論されることがなかった としても,心理学の歴史における一つの理論体系としての存在が揺らぐものではな く,それだけでいわゆる死語と化したと認めることはできない。 以上によると,「個性心理学」は,現在においても心理学の一分野を示す普通名 称というべきであり,また,極めて限られた範囲内でしか通用しない用語というこ ともできない。 また,原告は,仮に,「個性心理学」が普通名称であるとすれば,「〇〇心理学」 という語は普通名称として商標登録を受けられないことになるが,実際には,「〇 〇心理学」という語は,多数の商標登録がされていると主張するが,このような他 の商標登録例は,「個性心理学」が普通名称であるとの上記認定を何ら左右するも のではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)35763 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月27日 東京地方裁判所(47部)
本件明細書の従来技術として上記ウの公知文献は記載されておらず,同記 載は不十分であるため,上記公知文献に記載された発明も踏まえて本件発明\nの本質的部分を検討すべきである。 そして,上記公知文献の内容を検討すると,上記ウ1),2)から,取引明細 情報は,取引ごとにマッチング処理が行われることからすれば,乙4に記載 されたSaaS型汎用会計処理システムにおいても,当該取引明細情報を取 引ごとに識別することは当然のことである。 また,上記ウ3)の「取得明細一覧画面上」の「各明細情報」は,マッチン グ処理済みのデータであるから,「取得明細一覧画面」は「仕訳処理画面」 といえる。 さらに,上記ウ3)の「仕訳情報入力画面」は,従来から知られているデー タ入力のための支援機能の一つに過ぎず(段落【0002】,【0057】),表示され\nた取引一覧画面上で各取引に係る情報を当該画面から直接入力を行うこと及 び該入力の際プルダウンメニューを使用することも普通に行われていること (特開2004-326300号公報(乙5)段落【0066】-【0081】)から すれば,「取引明細一覧画面」に仕訳情報である「相手勘定科目」等を表示\nし変更用のプルダウンメニューを配置することは当業者が適宜設計し得る程 度のことである。 以上によれば,本件発明1,13及び14のうち構成要件1E,13E及\nび14Eを除く部分の構成は,上記公知文献に記載された発明に基づき当業\n者が容易に発明をすることができたものと認められるから,本件発明1,1 3及び14のうち少なくとも構成要件1E,13E及び14Eの構\成は,い ずれも本件発明の進歩性を基礎づける本質的部分であるというべきである。 このことは,上記イの本件特許に係る出願経過からも裏付けられる。 原告は,構成要件1E,13E及び14Eの構\成について均等侵害を主張 していないようにも見えるが,仮に上記各構成要件について均等侵害を主張\nしていると善解しても,これらの構成は本件発明1,13及び14の本質的\n部分に該当するから,上記各構成要件を充足しない被告製品1,2並びに被\n告方法については,均等侵害の第1要件を欠くものというべきである。
・・・
(なお,本件においては,原告から「被告が本件機能につき行った特許出願にか\nかる提出書類一式」を対象文書とする平成29年4月14日付け文書提出命令の 申立てがあったため,当裁判所は,被告に対し上記対象文書の提示を命じた上で,\n特許法105条1項但書所定の「正当な理由」の有無についてインカメラ手続を 行ったところ,上記対象文書には,被告製品及び被告方法が構成要件1C,1E,\n13C,13E,14C又は14Eに相当又は関連する構成を備えていることを\n窺わせる記載はなかったため,秘密としての保護の程度が証拠としての有用性を 上回るから上記「正当な理由」が認められるとして,上記文書提出命令の申立て\nを却下したものである。原告は,上記対象文書には重大な疑義があるなどとして, 口頭弁論再開申立書を提出したが,そのような疑義を窺わせる事情は見当たらな\nいから,当裁判所は,口頭弁論を再開しないこととした。)
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成29(行ケ)10017 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年7月24日 知的財産高等裁判所
以上指摘した点も踏まえて検討すると,まず,原告が依拠する法50 条2項及び56条の規定は,複数の指定商品等を対象とした1つの不使 用取消審判請求がされた場合,その対象となった指定商品等のいずれか について使用事実の立証がされれば,当該請求全部について不使用取消 しを免れることと,1つの不使用取消審判請求の一部について請求を取 り下げることはできないことを定めるにとどまり,不使用取消審判請求 をする場合に,審判請求の仕方に制約があるのかどうか(すなわち,原 告が主張するとおり,審判請求をする場合には,1つにまとめて請求を しなければならないのかどうか)については,何ら触れていない。そも そも,仮に請求の仕方(すなわち審判請求権の行使の仕方)に制約があ るのであれば,その旨が明示的に定められるべきであることを考慮する と,そのような明示的な定めがされているわけではない以上,上記各規 定により,原告主張のような制約が課されたと解することは困難である。 実質論として考えてみても,前記のとおり,3年以上使用されていない 商標登録は取り消されるべきであり,また,不使用取消審判手続におい ては,商標の使用について一番よく知り得る立場にある被請求人が商標 使用の事実について証明責任を負うべきであるというのが不使用取消審 判制度に関する法の趣旨である以上,多数の指定商品等について商標登 録を得た商標権者は,不使用取消審判請求を受けた場合に相応の立証の 負担等を負うことを予期すべきものである。これに対し,原告の主張を\n敷衍すると,不使用取消審判請求をされた被請求人の立証の負担や経済 的負担への配慮を優先し,多数の指定商品等のうち1つでも使用の事実 を立証すれば,全ての指定商品等について不使用取消しを免れるという のが法の趣旨であることになるが,そのような解釈は本末転倒であって, 到底成り立たないものであるといわざるを得ない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)25969 債務不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月27日 東京地方裁判所
また,別件米国訴訟の訴状の記載を検討しても,被告の上記主張が裏付 けられる。すなわち,上記(1)アのとおり,別件米国訴訟の訴状の「管轄区 域および裁判地」欄には,「オリオン電機は米国内および本地区内で過去 に事業を営んでおり現在も日常的に事業を営んでいる。」とか,「特許侵害 に関する原告の訴因は本地区でのオリオン電機の活動に直接起因してい る。」として,不法行為地を本地区(デラウェア地区)に限定するものと 解される記載がある。また,上記(1)イのとおり,「B.被告の侵害行為」 欄には,「被告は訴訟対象の特許が取り扱う基盤技術を組み込んでいるデ ィスプレイ製品を米国内で製造し,使用し,使用されるようにし,売り出 し,販売しており,米国に輸入している(またはいずれか1つ)。」とか, 「被告は本地区を含めて米国でオリオン電機ならびに第三者の製造業者, 販売店,および輸入業者(またはいずれか1つ)により製造される,使用 される,使用されるようにしている,売り出される,販売される,または 米国に輸入される特許を侵害しているディスプレイ製品を購入している。」 として,「本地区を含めて米国で」の行為を侵害行為として整理している。 そうすると,別件米国訴訟で不法行為として主張されている対象行為は, 米国内における原告の行為であると認められる。
ウ この点につき,原告は,別件米国訴訟の訴状の「管轄区域および裁判地」 欄における「オリオン電機は本地区で特許侵害の不法行為をして本地区で 他の人が特許侵害を行うよう仕向けている(またはいずれか一方)。」との 記載等を指摘するが,上記イ説示の記載など別件米国訴訟の訴状全体の記 載を総合すれば,上記イのように認めるのが相当である。 エ したがって,民訴法3条の3第8号に基づき,本件訴えの管轄が日本の 裁判所にあると認めることはできない。 (なお,念のため付言すると,この点を措いても,被告が「別件米国訴訟に おいて本件米国特許権の侵害行為として日本国内における原告の行為は対象 としていない」旨主張している以上,本件訴えのうち,当該行為に基づく損 害賠償請求権の不存在確認を求める部分は,訴えの利益を欠くことになる。)
2017.08.11
平成28(ワ)21346 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月20日 東京地方裁判所(46部)
原告は,上記2)の売りの指値注文が約定した時点が構成要件Eの「検出\nされた前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」\nに該当すると主張し,それによって,高値側の「新たな一の価格」及び 「新たな他の価格」の注文情報群が生成されているとする(原告第3準備 書面17,18頁等)。 そこで,このことを前提として検討すると,被告サービスにおいては, 上記のとおり,上記2)の時点の直後に高値側に買いの成行注文及び売りの 指値注文(上記4)の各注文)の注文情報が生成,発注された。 もっとも,上記4)の各注文のうち,売り注文は指値注文であるが買い注 文は成行注文であるところ,前記(2)のとおり構成要件Eの「注文情報」は\n指値注文に係る注文情報をいい,成行注文に係る注文情報を含まないと解 される。そうすると,4)の買い注文に係る注文情報は,構成要件Eの新た\nな「第一注文情報」に該当しないというべきである。 他方,上記6)の注文はいずれも指値注文であり,これらの注文に係る注 文情報は構成要件Eの「第一注文情報」及び「第二注文情報」に該当し得\nるものといえる。しかし,6)の各注文は,2)の時点の直後に3)の各注文が された後,3)の成行の買い注文の約定価格よりも高値側に価格が変動し, 3)の売りの指値注文が約定した5)の時点の後にされるものである。そうす ると,6)の各注文に係る注文情報は,「検出された前記相場価格の高値側 への変動幅が予め設定された値以上となった」時点である2)の時点におい て,成就の有無が判断できる他の条件の付加なく,また,直ちに生成され たものということはできない。別表1の取引においても,6)の注文は,2) の時点から約35時間50分後にされ,また,その間に5)の売りの指値注 文の約定等がされた後にされている。 そうすると,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定\nされた値以上となった場合」に,上記6)の注文に係る「第一注文情報」及 び「第二注文情報」が「設定」されたということはできない。 ウ 以上によれば,被告サービスは構成要件Eの「検出された前記相場価格\nの高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合,・・・高値側\nに・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設 定」を充足しない。
(6) これに対し,原告は,1)「注文情報」につき,ア)本件発明の特許請求の範 囲上,指値注文か成行注文を区別していない,イ)本件発明の効果に照らすと 注文が指値注文か成行注文かを区別する必要がない,ウ)発明の実施に形態に おける注文に成行注文が含まれる旨の記載がある,以上のことから成行注文 が含まれると解すべきであると,2)「場合」につき上記条件以外の条件を付 加することを排除する趣旨でないと,3)「設定」につき実際に注文情報を生 成するものでなく,情報を生成し得るものとして記録しておけば足りると, 4)被告サービスは指値注文のイフダンオーダーの中に本件発明を構成しない\n買いの成行注文を付加したものにすぎないと各主張する。 しかし,上記1)につき,ア)は,本件明細書において,「注文情報」の語そ れ自体は指値注文と成行注文の区別を明示していない一方で,前記(2)アのと おり,特許請求の範囲の記載全体をみれば,構成要件Eを含む特許請求の範\n囲の記載における「注文情報」は指値注文をいうと解されるのであり,イ)は 背景技術,発明が解決しようとする課題の各記載(前記1(1)ア,イ)の趣旨 を併せて考慮するとむしろ指値注文のイフダンオーダーに関する発明である ことが示唆される。ウ)は,本件明細書の発明の実施の形態の記載(前記1(2)) によれば,当該形態においては成行注文も生成され得る(段落【0031】) 一方で通常の成行注文につきイフダンオーダーの手順(ステップS21〜2 8)を行わないとされている(段落【0101】,【図3】,【図4】)から, 生成された成行注文はイフダンオーダーに関する注文を構成しないことが明\nらかである。そうすると,原告が指摘する上記ア)〜ウ)はいずれも構成要件E\nの「注文情報」に成行注文が含まれると解すべき根拠とならない。 上記2)及び3)については,前記(3)及び(4)において説示したところ 上記4)につき,前記?に説示したとおり,被告サービスにおける買いの成 行注文(注文番号97)は売りの指値注文(同96)と同時に注文されてい るから,当該成行注文がイフダンオーダーの一部を構成していると認められ\nるところ,前記の「注文情報」,「場合」,「設定」の各解釈に加え,本件発明 の意義が指値注文のイフダンオーダーを相場価格の変動にかかわらず自動的 に繰り返し行うことにあることを前提とすれば,イフダンオーダーにおいて 成行注文を介在させる構成は,本件発明において解決すべき課題と異なるこ\nと,成行注文によって直ちに金融商品のポジションを得る効果が得られるこ とにおいて本件発明の構成と異なるものであるから,これを本件発明外の付\n加的構成とみることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)1777 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月14日 東京地方裁判所
イ 寄与率について
被告九研は,本件各発明が本件製品1及び2の販売に寄与した割合は 10%を超えるものではないなどと主張する。 しかし,本件各発明は,共回り現象の発生を回避してクリアランスの 目詰まりをなくし,効率的・連続的な異物分離を実現するものであって, 生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関するものというべきである。\nすなわち,生海苔異物除去装置として,選別ケーシング(固定リング) と回転円板との間に設けられたクリアランスに生海苔混合液を通過させ ることによりクリアランスを通過できない異物を分離除去する装置が従 来用いられていたとしても,本件各発明の解決課題を従来の装置が抱え ていることは明らかであり,この点は需要者の購買行動に強い影響を及 ぼすものと推察される。このことと,従来の装置の現在における販売実 績等の主張立証もないことを考えると,本件各発明の実施は生海苔異物 除去装置の需要者にとって必須のものであることがうかがわれる。 他方,本件各発明が本件製品1及び2に寄与する割合を減ずべきであ るとする被告九研の主張の根拠は,いずれも具体性を欠くものにとどま る。 したがって,本件各発明が本件製品1及び2の販売に寄与する割合を 減ずることは相当でない。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)14868 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月12日 東京地方裁判所(40部)
イ ところで,広辞苑第六版(甲9)によれば,「とき」とは,「(連体修飾 語をうけ,接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場 合。」を意味するものであり,また,大辞林第三版(甲10)においても 「(連体修飾句を受けて)仮定的・一般的にある状況を表す。(...する) 場合。」とされており,用字用語新表記辞典(乙22)では「『とき』は条\n件・原因・理由・その他,『場合』よりも小さい条件のときに用いること がある。」,最新法令用語の基礎知識改訂版(乙23)では「『時』は時点 や時刻が特に強調される場合に使われるのに対して,『とき』は一般的な 仮定的条件を表す場合に使われる。」と記載されている。これらからすれ\nば,構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」の「とき」は,条件\nを示すものであると解するのが相当である。
ウ この点に関して原告は,「送信したとき」の「とき」は「同じころ」と いう意義を有するものであり,「ある程度の幅をもった時間」を意味する と主張する。 たしかに,広辞苑第六版及び大辞林第三版には,上記イで指摘した意義 の他に,原告が主張するような意義も掲載されている(甲9,10)。し かし,広辞苑第六版(甲9)には「おり。ころ。」を意味する「とき」の用 例として「ときが解決してくれる」「しあわせなときを過ごす」といった ものが掲載されており,「送信したとき」のような具体的な行為を示す連 体修飾語を受けた用例は記載されていない。また,大辞林第三版(甲10) をみると「ある幅をもって考えられた時間」を意味する「とき」の用例と して,「将軍綱吉のとき」「ときの首相」「ときは春」などというものが 掲載されており,やはり「送信したとき」のような具体的な行為を示す連 体修飾語を受けた用例は記載されていない。 そして,抽象的で,空間的及び時間的に広い概念を表現した上記各用例\nと比べると,「送信したとき」という表現は,その指し示す行為が相当程\n度に具体的かつ直接的であることから,およそ用いられる場面が異なると いうべきである。 また,原告が指摘する審決(甲11)には,「とき」という用語につい て「ある程度の幅を持った時間の概念を意味する」旨の判断がされている が,当該審決は,「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始されるときに, 前記転送手段によって前記判定領域に転送された前記特定表示態様判定用\n数値情報を読み出して判定する」という記載における「前記9個の可変表\n示部の可変表示が開始されるときに」という文言について,「前記9個の\n可変表示部の可変表\示が開始されると『同時』又は『間をおかずに』」と いう意味ではなく,「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始され」た後, 「前記特定表示態様判定用数値情報を読み出して判定する」までの間に他\nの処理がされるとしても,「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始され るときに」に当たると判断したものであって,「前記転送手段によって前 記判定領域に転送された前記特定表示態様判定用数値情報を読み出して判\n定」した後に「前記9個の可変表示部の可変表\示が開始され」たとしても, 上記文言を充足するなどと判断したものではないから,本件における「送 信したとき」の解釈において参酌することは相当ではない。 そうすると,構成要件1D及び1Fの「送信したとき」における「とき」\nが「ある程度の幅をもった時間」を意味するものということはできない。 また,本件明細書等1をみても,「送信したとき」の「とき」について, 「条件」ではなく「時間」を意味することをうかがわせる記載はない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
エ 以上から,構成要件1D及び1Fの「送信したとき」とは,「送信した\nことを条件として」という意義であると認めることが相当である。
・・・・
以上からすると,被告サーバは,第二のメッセージを受信したことを条件 として「マイミク」であることを記憶し,「マイミク」である旨の記憶をし たことを条件として「第二のメッセージ」を送信するという構成を有してい\nるものであって,第二のメッセージを送信したことを条件として「マイミク」 であることを記憶するという構成を有するものではないと認められる。\nしたがって,被告サーバは,「第二のメッセージを送信したとき」に「上 記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記 憶手段に記憶する手段」を有しているということはできないから,その余の 点について判断するまでもなく,構成要件1D及び1Fを充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成29(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
確かに,本件明細書の段落【0050】には「実施例18」との記載はあ るが,他方で,本件明細書における実施例18(b)に関する記載をみると,「比較 のために,例えば豪州国特許出願第29896/95号(1996年3月7日公開) に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を,以下のように調製した」 (段落【0050】前段)と記載され,また,実施例18の安定性試験の結果を 示すに当たっては,「比較例18の安定性」との表題が付された上で,実施例1\n8(b)については「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」と表現されている\n(段落【0073】)。そして,豪州国特許出願第29896/95号(1996 年3月7日公開)は,乙4発明に対応する豪州国特許であり,同特許は水性オキサ リプラチン組成物に係る発明であって,本件明細書で従来技術として挙げられる もの(段落【0010】)にほかならない。 上記各記載を総合すると,実施例18(b)は,「実施例」という用語が用いら れているものの,その実質は本件発明の実施例ではなく,本件発明と比較するため に,「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」,すなわち,緩衝剤が用いられていな い従来既知の水性オキサリプラチン組成物を調製したものであると認めるのが相当
◆原審はこちらです。平成27(ワ)28467
以下は類似案件です。
◆被告の異なる控訴審事件です。平成28(ネ)10046
こちらは、結論は非侵害で同じですが、1審では技術的範囲に属すると判断されましたので、それが取り消されています。また、控訴審における追加主張は時期に後れた抗弁として、却下されてます。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(行ケ)10157 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月19日 知的財産高等裁判所
前記1の認定事実によれば,実施例2においては,醸造酢(酸度10%)15部, スクラロース0.0028部等を含有する調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6 の割合で合わせて瓶詰めをしてピクルスを得た結果,当該ピクルスは,スクラロー スを添加していないものに比べて,酸味がマイルドで嗜好性の高いものに仕上が り,ピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたことが認められる。そう すると,醸造酢を含有する製品として,酸味のマスキング効果を確認した対象は, 調味液ではなくピクルスであるから,当該効果を奏するものと確認されたスクラ ロース濃度は,上記調味液におけるスクラロース濃度ではなく,これに水分等を含 むきゅうりを4対6の割合で合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であると 認めるのが相当である。 これに対し,本件明細書に記載された0.0028重量%は,調味液に含まれる スクラロース濃度であるから,当該濃度は,酸味のマスキング効果が確認されたピ クルス自体のスクラロース濃度であると認めることはできない。 他方,ピクルスにおけるスクラロース濃度は,実施例2において調味液のスクラ ロース濃度を0.0028重量%とし,この調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6 の割合で合わせ,瓶詰めされて製造されるものであるから,きゅうりに由来する水 分により0.0028重量%よりも低い濃度となることが技術上明らかである(き ゅうりにスクラロースが含まれないことは,当事者間に争いがない。)。そして,0. 0028重量%よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマ スキング効果が確認されたのであれば,ピクルスにおけるスクラロース濃度が0. 0028重量%であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは,本件明 細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため,スク ラロースを0.0028重量%で「醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品」に 添加すれば,酸味のマスキング効果が生ずることは当業者にとって自明であり(実 施例3の「おろしポン酢ソース」では,スクラロース0.0035重量%で酸味の\nマスキング効果が生じ,実施例4の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では, スクラロース0.0042重量%で酸味のマスキング効果が生じることがそれぞ れ開示されている。),このことは本件明細書において開示されていたものと認め られる。 そうすると,製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の0.000013 重量%」から「0.0028重量%」にする訂正は,特許請求の範囲を減縮するも のである上,本件訂正後の「0.0028重量%」という下限値も,本件明細書に おいて酸味のマスキング効果を奏することが開示されていたのであるから,本件 明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって,訂正事項1は,当業者によって本件明細書,特許請求の範囲又は図 面(以下「本件当初明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導か れる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものといえる から(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日 特別部判決参照),特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定 に適合するものと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 当業者自明
>> ピックアップ対象
2017.08.11
平成28(ワ)35978 営業秘密使用差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年7月12日 東京地方裁判所
前記前提事実等のとおり,本件文書1は,原告製品の製品概要, 仕様等が記載された16丁の書面であり,また,本件文書2は,表紙はなく,原告\n製品の露光に関する内容(光源の配置,露光量に関するシミュレーション等)が記 載された4丁の書面であって,いずれも原告が中国企業に対して原告製品を販売す る目的で台湾の代理店及び中国企業に提供したものと認められる。また,その内容 も,被告が自社の製品に取り入れるなどした場合に原告に深刻な不利益を生じさせ るようなものであるとは認められない。そして,被告は,原告の競合企業であり, 同様の営業活動を行っていたものであるから,被告が営業活動の中で原告が営業し ている製品の情報を得ることは当然に考えられるのであり,その一環として,本件 各文書を取得することは不自然とはいえず,被告が通常の営業活動の中で取得する ことは十分に考えられるものである(なお,原告は,競合他社の情報について開示\nを受けること自体が異常事態であり,競争者が少ない光配向装置メーカーの業界で は殊更異常と認識すべきであるとも主張するが,競争者が少ないからこそ,他社の 製品に関する情報に接する機会が多いという側面も考えられるのであるから,原告 の上記主張は,直ちには採用することができない。)。 (2)また,原告と被告が競業関係にあるとしても,原告が取引先との間で本件各 文書に関する秘密保持契約を締結したか否か,本件各文書に記載された内容が取引 先の守秘義務の対象に含まれるか否かについて,被告が直ちに認識できたとは認め られないし,本件各文書のConfidentialの記載をもって,直ちに契約 上の守秘義務の対象文書であることが示されているものともいえない。 (3)したがって,被告が本件各文書を取得した時点で,守秘義務違反による不正 開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを疑うべき状況にあったと認 めることはできず,被告に不競法2条1項8号所定の重大な過失は認められない。
2017.07.31
平成28(行ケ)10272 商標権 行政訴訟 平成29年7月19日 知的財産高等裁判所(1部)
商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に当たり,複数の構成部分を\n組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察するこ\nとが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる 場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較し\nて商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構\n成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配 的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識とし ての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけ\nを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものであ る(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5 年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民228 号561頁参照)。 (2) これを本件についてみると,原告が登録無効を主張する本件指定商品等と の関係では,本件商標の構成のうち「肉」の文字部分は,本件指定商品等に関する\n物又は役務の提供の用に供する物をいうものであるから,原告の主張するとおり, それ自体を単独でみれば出所識別標識としての機能は弱いものといえる。\nしかしながら,本件商標は「極肉.com」という文字で構成されるところ,こ\nのうち「極肉」という文字部分は,「.com」という文字部分の前に位置すること から,取引者又は需要者は,これをドメイン名を表示する一体のものとして理解す\nるものと認めるのが相当である。しかも,本件商標の構成のうち「極」は「肉」を\n修飾する形容詞であるから,「極肉」という文字自体,文法構造上分離するのは相当\nではなく,一体のものとして理解するのが自然である。のみならず,「極肉」という 文字は,これ自体から特定の定着した観念を生じさせるものではなく,いわば一体 となって造語を形成するものであるから,その一部のみが強く支配的な印象を与え るものとはいえない。 これらの事情の下においては,本件商標の構成のうち「極」の文字部分を抽出し,\nこの部分だけを引用商標と比較して類否を判断することは,許されないというべき である。
・・・
原告は,本件商標の構成のうち「極」の文字部分を抽出して引用商標と類否判断\nをしなかった審決の判断には,違法があると主張する。 しかしながら,結合商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標\nと比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対 し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる 場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めら れる場合などに限り,許されるべきである。本件商標は,上記1において説示した とおり,ドメイン名としての役割上も,形容詞と名詞が結合する文法構造上も,特\n定の観念を必ずしも生じさせない造語としての性質上も,一体として理解されると いうべきであるから,上記場合などに該当しないというべきである。その他に原告 が第1準備書面及び第2準備書面で縷々主張するところを改めて検討しても,上記 判断を左右するに至らない。原告の上記主張は,上記1(1)の判例の趣旨を正解しな いものに帰し,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.07.28
平成28(行ケ)10160 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月12日 知的財産高等裁判所
訂正事項5は,本件訂正前の特許請求の範囲の請求項 1に「針状又は糸状の形状を有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形 状を有し,シート状支持体の片面に保持されると共に」に訂正する,という ものであり,これを請求項の記載全体でみると,「…尖った先端部を備えた 針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧 されることにより皮膚に挿入される,経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った 先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し,シート状支持体の片面に保持さ れると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に 挿入される,経皮吸収製剤」に訂正するものである。 ここで,「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で 押圧されることにより皮膚に挿入される」との文言は,経皮吸収製剤の使用 態様を特定するものと解されるから,その直前に挿入された「シート状支持 体の片面に保持されると共に」の文言も,前記文言と併せて経皮吸収製剤の 使用態様を特定するものと解することが可能である。すなわち,訂正事項5\nは,経皮吸収製剤のうち,「シート状支持体の片面に保持される」という使 用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し,かかる使用態様を採る経皮吸収製 剤に限定したものといえる。 ところで,本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから,本件 訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であること が必要であり,そのためには,訂正事項5によって限定される「シート状支 持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も,「経皮吸収製剤」という物と して技術的に明確であること,言い換えれば,「シート状支持体の片面に保 持される」との使用態様が,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等によ\nり経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。 しかしながら,「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によ っても,シート状支持体の構造が変われば,それに応じて経皮吸収製剤の形\n状や構造(特にシート状支持体に保持される部分の形状や構\造)も変わり得 ることは自明であるし,かかる使用態様によるか否かによって,経皮吸収製 剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。 したがって,上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様 は,必ずしも,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等により経皮吸収製\n剤自体を特定するものとはいえず,訂正事項5によって限定される「シート 状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も,「経皮吸収製剤」という 物として技術的に明確であるとはいえない(なお,「シート状支持体の片面 に保持される」との用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわ ざるを得ないから,本件訂正発明をいわゆる「用途発明」に当たるものとし て理解することも困難である。)。 そうすると,訂正事項5による訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載 は,技術的に明確であるとはいえないから,訂正事項5は,特許請求の範囲 の減縮を目的とするものとは認められない。 なお,仮に,「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮 吸収製剤の使用態様を特定するものではなく,「尖った先端部を備えた針状 又は糸状の形状を有し」との文言と同様に経皮吸収製剤の構成を特定するも\nのであるとすれば,本件訂正発明は,「シート状支持体の片面に保持された 状態にある経皮吸収製剤」になり,構成としては「片面に経皮吸収製剤を保\n持した状態にあるシート状支持体」と同一になるから,訂正事項5は,本件 訂正前の請求項1の「経皮吸収製剤」という物の発明を,「経皮吸収製剤保 持シート」という物の発明に変更するものであり,実質上特許請求の範囲を 変更するものとして許されないというべきである(特許法134条の2第9 項,126条6項)。
・・・
被告は,訂正事項5は,請求項1の経皮吸収製剤に対して,本件明細書中 に記載され,請求項19においても記載されているシート状支持体の構成を\n追加したものであり,両者の構成及び関係は本件明細書の記載上明確である\nから,物としての態様(構成)が明確でないとの批判も当たらないし,特許\n法上,物の発明において使途の構成を規定してはいけないというような制限\nはなく,本件訂正発明が飽くまで経皮吸収製剤の発明であって,経皮吸収製 剤保持シートの発明でないことは,訂正後の請求項1の文言から明らかであ る,などと主張する。
しかしながら,訂正事項5は,経皮吸収製剤のうち,「シート状支持体の 片面に保持される」という使用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し,かか る使用態様を採る経皮吸収製剤に限定したものとみるべきであり,「経皮吸 収製剤」自体の構成を更に限定するものとみるのは相当でないこと,そして,\n訂正事項5が,使用態様の限定であるとしても,かかる限定によって,経皮 吸収製剤自体の形状,構造,組成,物性等が決まるという関係にあるとは認\nめられず,本件訂正後の経皮吸収製剤も技術的に明確であるといえないこと は,いずれも前記のとおりである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 減縮
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2017.07.28
平成29(ネ)10009等 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年7月12日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明1の構成要件1C(オキサリプラティヌムの水溶液からなり)\nが,オキサリプラティヌムと水のみからなる水溶液であることを意味するの か,オキサリプラティヌムと水からなる水溶液であれば足り,他の添加剤等 の成分が含まれる場合をも包含するのかについては,特許請求の範囲の記載 自体からは,いずれの解釈も可能である。そこで,この点については,本件\n明細書1の記載及び本件特許1の出願経過を参酌して判断することとする。
・・・
前記アの本件明細書1の記載によれば,オキサリプラティヌムは,種々 の型の癌の治療に使用し得る公知の細胞増殖抑制性抗新生物薬であり,本 件発明1は,オキサリプラティヌムの凍結乾燥物と同等な化学的純度及び 治療活性を示すオキサリプラティヌム水溶液を得ることを目的とする発明 である。そして,本件明細書1には,オキサリプラティヌム水溶液におい て,有効成分の濃度とpHを限定された範囲内に特定することと併せて, 「酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まない オキサリプラティヌム水溶液」を用いることにより,本件発明1の目的を 達成できることが記載され,「この製剤は他の成分を含まず,原則とし て,約2%を超える不純物を含んではならない」との記載も認められる。 他方で,本件明細書1には,「該水溶液が,酸性またはアルカリ性薬剤, 緩衝剤もしくはその他の添加剤」を含有する場合に生じる不都合について の記載はなく,実施例においても,添加剤の有無についての具体的条件は 示されておらず,これらの添加剤を入れた比較例についての記載もない。
しかしながら,前記イの出願経過において控訴人が提出した本件意見書 には,本件発明1の目的が,「オキサリプラティヌム水溶液を安定な製剤 で得ること」及び「該製剤のpHが4.5〜6であること」に加えて, 「該水溶液が,酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくはその他の添加 剤を含まないこと」にあること,さらに,水溶液のpHが該溶液に固有の ものであって,オキサリプラティヌムの水溶液の濃度にのみ依存するこ と,オキサリプラティヌムの性質上,本件発明1の構成においてのみ,\n「安定な水溶液」を得られることがわざわざ明記され,これらの記載を受 けて,審査官が拒絶理由通知の根拠とする引用文献1ないし3では,その ような「安定な水溶液」は得られないこと,すなわち,緩衝剤を含む凍結 乾燥物やクエン酸を含む水溶液では,「オキサリプラティヌムの安定な水 溶液」を得ることは困難である旨が具体的に説明されている。 その上で,本件意見書は,本件発明1が特許法29条2項に該当しない との結論を導いて審査官に再考を求めているのであり,その結果として控 訴人は,本件特許1の特許査定を受けているのである。 以上のような本件明細書1の記載及び本件特許1の出願経過を総合的に みれば,本件発明1は,公知の有効成分である「オキサリプラティヌム」 について,直ぐ使用でき,承認された基準に従って許容可能な期間医薬的\nに安定であり,凍結乾燥物を再構成して得られる物と同等の化学的純度及\nび治療活性を示す,オキサリプラティヌム注射液を得ることを課題とし, その解決手段として,オキサリプラティヌムを1〜5mg/mlの範囲の 濃度と4.5〜6の範囲のpHで水に溶解することを示すものであるが, 更に加えて,「該水溶液が,酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくは その他の添加剤を含まない」ことをも同等の解決手段として示すものであ ると認めることができる。 してみると,本件発明1の特許請求の範囲における「オキサリプラティ ヌムの水溶液からなり」(構成要件1C)とは,本件発明1がオキサリプ\nラティヌムと水のみからなる水溶液であって,他の添加剤等の成分を含ま ないものであることを意味すると解するのが相当である。
◆1審はこちらです。
関連事件(同一特許、異被告)です。
◆平成27(ワ)29158
同一特許の別訴事件で、1審(平成27(ワ)12416号)では技術的範囲内と判断されましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.07.25
平成28(ワ)37610 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 平成29年7月20日 東京地方裁判所(46部)
被告は,本件発信者動画は本件楽曲の著作権を本件原告動画が侵害して いることを示して批評する目的で本件原告動画の一部を引用したもので あり,その引用は公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われたから,本 件投稿行為は著作権法32条1項の適法な引用であると主張する。 イ そこで,まず,本件発信者動画における本件原告動画の利用が被告の主 張する上記批評目的との関係で「正当な範囲内」(著作権法32条1項) の利用であるという余地があるか否かにつき検討する。 前提事実 ア,イのとおり,1)本件発信者動画は冒頭から順に本件冒頭 部分(約3分38秒),本件楽曲使用部分(約2分18秒)及び本件楽曲 動画(約4分4秒)から構成され,2)本件楽曲使用部分以外に本件原告動 画において本件楽曲が使用された部分がない。ここで,本件原告動画にお いて本件楽曲が使用されている事実を摘示するためには,本件楽曲使用部 分又はその一部を利用すれば足り に照らしても,本件原告動画において本件楽曲が使用されている事実を摘 示するために本件冒頭部分を利用する必要はないし,上記の事実の摘示と の関係で本件楽曲部分の背景等を理解するために本件冒頭部分が必要で あるとも認められない。そうすると,仮に本件発信者に被告主張の批評目 的があったと認められるとしても,本件発信者動画における本件冒頭部分 も含む本件原告動画の上記利用は目的との関係において「正当な範囲内」 の利用であるという余地はない。 この点につき,被告は,本件楽曲使用部分が本件原告動画に含まれるこ とを示すために本件冒頭部分を利用したと主張する。しかし,上記各部分 の内容(前提事実 ア)に照らせば,本件楽曲使用部分が本件原告動画に 含まれると判断するために本件冒頭部分の利用が必要であると認めるこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 著作権その他
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2017.07.20
平成27(ワ)24688 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年6月28日 東京地方裁判所
不競法2条1項1号の趣旨は,周知な商品等表示の有する出所表\示機能\nを保護するため,周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自\n己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより,同 法の目的である事業者間の公正な競争を確保することにある。 商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的\nを有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的\n意味を有するに至る場合がある。そして,このように商品の形態自体が特 定の出所を表示する二次的意味を有し,不競法2条1項1号にいう「商品\n等表示」に該当するためには,1)商品の形態が客観的に他の同種商品とは 異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,2)その形態が特定 の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や 爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する 商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを\n要すると解するのが相当である。
イ これを本件について検討するに,前記第2の2(2)及び上記第4の1(1) アないしオによれば,原告製品は,原告主張に係る原告製品の形態的特徴 のうち,1)中央リングと中央リングの周囲から外側に向かって放射状に延 伸する多数の周辺リングからなり,これら周辺リングと中央リングとは略 直交するように一体化されている形状について共通した特徴を有している 点,2)原告商品のうちL型,M型,S型については,上記1)に加えて,周 辺リングの外側を外周リングで囲繞する構成を付加した形状を有する点,\n3)原告商品のうちS−II型,LL型,L−II型については,上記1)及び2) に加えて,隣接する周辺リング同士を連結部材で連結するとともに,周辺 リングの一部には外環リングと直交する半径方向に縦棒を付加した構造を\n有する点がそれぞれ認められ,当該形態は,上記(1)カの他の充填物とは明 らかに異なる特徴を有していることからすれば,上記に掲げた点において, 特別顕著性が認められる。 さらに,上記(1)アないしオによれば,原告製品はいずれも,日本国内に おいて,1)販売開始当初の頃から,その形状を撮影した写真等と共に,全 国的に宣伝広告され,文献や業界誌にも多数掲載されていたことが認めら れ,2)また,需要者である不規則充填物の購入者間において需要が高く, 直接の販売あるいは代理店を通じて,相当多数が販売されてきたものと推 認できる。したがって,周知性が認められる。
ウ この点に関し被告は,不規則充填物は,商品の陳列棚に陳列される物と は異なり,技術評価も経た上で採用に至るものであることからすれば,原 告商品の形態が商品等表示として需要者に認識されるような取引形態では\nない旨主張する。 しかし,原告商品の形態が多数の広告,文献,雑誌等に写真や図付きで 紹介されているものが多いこと,実際の注文においても,不規則充填物の 形状に基づいて見積り依頼がされる場合があること(甲108)からすれ ば,不規則充填物の取引形態が被告の主張のとおりの取引形態であると認 めることはできず,原告商品について,需要者がその形態を認識していな いとみることはできない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2017.07.20
平成28(行ケ)10238 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月18日 知的財産高等裁判所
エ 以上のとおり,本件審決が,独立特許要件の検討に当たって認定・判断した 相違点2は,本件補正後の請求項2に係る発明の構成のみによる相違点であり,本\n願発明について認定・判断した相違点2も,平成26年補正後の請求項2に係る発 明のみによるもので,本件補正後の請求項1の発明,平成26年補正後の請求項1 の発明と対応するものではない。 しかしながら,本件審決では,「本件補正発明」を「平成27年7月23日に提 出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明」,「本願発明」 を「平成26年7月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載され た発明」と定義した上で,各請求項1の記載を摘記しているのであって,本件補正 後の請求項1に係る発明を本件補正発明,平成26年補正後の請求項1に係る発明 を本願発明と認定していることが明らかである。 そうすると,本件審決は,本件補正後の請求項1に係る発明を本件補正発明,平 成26年補正後の請求項1に係る発明を本願発明と,それぞれ認定した上で,認定 した発明と対応しない相違点2を認定しているのであり,相違点2の認定を誤った ことになるが,かかる誤った相違点2の認定ないし判断を根拠に,本件補正発明及 び本願発明についての「請求項1」の記載を「請求項2」の誤記と解することはで きない。 被告は,本件における審査の経緯も,上記「請求項1」の記載が「請求項2」の 誤記であるとの理解を促すものであると主張し,前記(2)イのとおり,本件拒絶査定 においては,平成26年補正後の請求項2に係る発明は,本件拒絶理由通知書で提 示した引用例1及び引用例2から当業者が容易に発明をすることができたものであ る旨が記載されている一方で,平成26年補正後の請求項1に係る発明については 拒絶の理由を発見しないと記載されていることが認められるが,かかる審査の経緯 を参酌しても,上記判断が左右されるものではない。 よって,被告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2017.07.14
平成28(ワ)37209 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年6月22日 東京地方裁判所
原告らは,アロマテラピーサロンの需要者の間では原告ら表示が全国的に\n周知である旨主張する。 しかし,前記前提となる事実 及び 並びに前記 の各認定事実によれば, 原告ら営業が行われている範囲は帯広市及び帯広市に隣接するA町にとどま り,原告第一ホテルによるアロマテラピーに関する施術等の提供先やセミナ ーの実施先も帯広市内に所在するものであること,原告らサロン甲ホテル店 の開業に関する記事は十勝地方の地方紙に掲載されたのみであること,原告\nらサロンに関する広告が掲載された媒体は十勝地方,その中でも帯広市及び\nA町に多く配布されている生活情報誌であり,全国的に配布されているもの でないこと,原告らサロンに関する記事が全国誌に掲載されたのは1誌に1 回であること,上記全国誌や旅行会社のウェブサイトにおける原告らサロン についての記載は付随的なものにすぎないことが明らかである。なお,原告 らは,原告ら表示の周知性を基礎付ける事実として,原告らサロンのプロデ\nューサーが著名であることや乙が多くの取材を受けたことなども主張してい るが,これらは原告らサロンや原告ら表示の周知性に直ちに結びつくもので\nはないから,この点に関する原告らの主張は失当である。 これらの事情に照らせば,原告ら表示は,十\勝地方以外の地域のアロマテ ラピーサロンの利用者に広く知られていたとは認められない。そして,被告 は全国に店舗を展開して営業を行っているものの,十勝地方においては営業\nを行っておらず(前記前提となる事実 イ),十勝地方に店舗を設ける具体\n的な予定があるといった事情もうかがわれない。そうすると,原告ら表\示が 十勝地方において周知であるかについて検討するまでもなく,被告が原告ら\nとの関係において不正競争防止法2条1項1号に該当する不正競争を行って いるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2017.07.14
平成28(行ケ)10252 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年6月28日 知的財産高等裁判所
原告は,本件指定役務中,「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業, 調剤」が同一の類似群コードを付されていることを根拠に,同一類似群コー ド中の一つの役務で普通名称となっている「AKA」(本件商標)は,同一 類似群コードの他の類似の役務との関係でも質表示となるものと扱われるべ\nきであるから,本件商標は,本件指定役務中,「医業,医療情報の提供」の みならず,「健康診断,歯科医業,調剤」についても,法3条1項3号に該 当し,同項6号,4条1項16号にも該当すると主張する。 しかしながら,そもそも類似群コードを定める「類似商品・役務審査基準」 は,特許庁における商標登録出願の審査事務等の便宜と統一のために作られ た内規にすぎず,法規としての効力を有するものではない。したがって,同 一の類似群コードに属するとの形式的事実のみから,直ちに,本件商標が「医 業,医療情報の提供」と同様に「健康診断,歯科医業,調剤」の各役務との 関係においても,質表示に当たるとか,自他役務識別力がないとの結論を導\nくことはできず,かかる結論を導くには,本件商標が上記の各役務との関係 で質表示に当たることその他自他役務識別力がないことを認めるに足りる具\n体的事由の主張立証が必要となるというべきである。 しかるところ,原告は,上記のとおり,同一の類似群コードに属するとの 事実を主張するのみで,上記の具体的事由について何ら主張立証しないので あるから,これでは,本件商標が上記の各役務との関係で質表示に当たるこ\nとその他の事由により自他役務識別力がないと認めることはできないし,同 様に役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 よって,理由aは採用できない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2017.07.10
平成28(受)632 特許権侵害差止等請求事件 平成29年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所
特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても,特許権者が,事実審の 口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に訂 正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは,終局判決に対 する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と 同様に,事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえ る。 そうすると,特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張し なかったにもかかわらず,その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判 断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえ るだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させ るものとして,特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許 されないものというべきである。
(2) これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,上告人は,原審の 口頭弁論終結時までに,原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張しなかったものである。そして,上告人は,その時までに,本件無効の 抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請 求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら,それが,原審で新 たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に 対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったた めであるなどの前記1(5)の事情の下では,本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから, これをもって,上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張 することができなかったとはいえず,その他上告人において訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 104条の3
>> 特許庁手続
>> 審判手続
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2017.07. 7
平成28(行ケ)10276 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年6月28日 知的財産高等裁判所
商標法50条1項においては,使用の対象となる商標について,「登録商標 (書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びロー マ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる\n商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会 通念上同一と認められる商標を含む。…)」と規定されており,「登録商標と 社会通念上同一と認められる商標」も含むものとされている。 そこで,使用商標B−1が,本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」 といえるか否かについて検討する。
(1) 本件商標は,「Crest」の欧文字を標準文字で横書きしてなる商標で あるところ,「crest」の語は,「(ものの)頂上,山頂,波頭」などの 意味を有する英語として認識されるものであるから,本件商標からは,通常 の英語読みに従った「クレスト」の称呼が生じるとともに,その英語の意味に 従った「(ものの)頂上,山頂,波頭」などの観念が生じるものといえる。
(2) 他方,使用商標B−1は,「新潮クレスト・ブックス」の漢字及び片仮名 を横書きで一連表記してなるものであるところ,「新潮」の文字と「クレスト\n・ブックス」の文字は,漢字と片仮名という文字種の違いから,明確に区別し て認識されるものである。また,「クレスト」の文字と「ブックス」の文字に ついても,その間が「・」によって区切られていることに加え,後述のとおり, 「ブックス」の語が「書籍」を表す英語の片仮名表\記として明確に認識される ことからすると,同様に区別して認識されるものといえる。してみると,使用 商標B−1は,「新潮」,「クレスト」及び「ブックス」の3つの独立した語 が組み合わされて表記された商標として認識されるものといえる。\n そこで,以上を前提に,使用商標B−1を「書籍」についての商品識別標識 として見てみると,まず,「新潮」の漢字部分は,我が国における著名な出版 社である被告の略称として広く知られているものであり,「書籍」に使用され た使用商標B−1に接した取引者・需要者は,「新潮」の漢字部分を,当該書 籍を発行する出版社が被告であることを表示するものにすぎないと認識する\nから,この「新潮」の漢字部分は,商標の同一性という観点からは重要性を持 たない部分といえる。 次に,使用商標B−1のうち,「ブックス」の片仮名部分は,「本,書籍」 を意味する英語「book」の複数形を片仮名表記したものであることが明\nらかである。また,「書籍」の出版の分野においては,特定のシリーズに属す る書籍群に,特定のブランド名と「ブックス(books)」の語を合わせた, 「○○ブックス(books)」の名称を付けて出版,販売することが一般的 に行われていることが認められる(甲10,12,14,16,18,20, 22,23,80〜82,84〜87,89,91,92,94〜99,10 1〜104(枝番を含む。))。してみると,「書籍」に使用された使用商標B −1に接した取引者・需要者は,「ブックス」の片仮名部分を,これが付され た商品が「書籍」であること,あるいは,その商品が「特定のシリーズに属す る書籍」であることを表示するものとして認識するといえるから,これも商\n標の同一性という観点からは重要性を持たない部分であるといえる。 他方,「クレスト」の片仮名部分は,「(ものの)頂上,山頂,波頭」など の意味を有する英語「crest」を片仮名表記したものとして認識され,そ\nの意味に従った観念を生じるものといえるところ,このような「クレスト」の 語は,「書籍」との関係で特段の結びつきを有するものではないから,「書籍」 に係る商品識別標識としての機能を果たし得るものであり,商標の同一性を\n基礎づける中核的部分といえる。 この点,原告は,被告自らがそのホームページ等で「クレスト・ブックス」 を一体として使用していることを理由に挙げ,取引者・需要者からは,「クレ スト・ブックス」で一つの商標として理解され認識される旨主張する。しか し,「書籍」に関する広告等において,「クレスト・ブックス」が一連表記さ\nれていたとしても,これに接した取引者・需要者からは,「クレスト」と「ブ ックス」が独立した語として認識され,そのうち,特に「クレスト」の部分が 独立して自他商品の識別標識の機能を発揮する部分として認識されることは\n上記で述べたとおりであるから,原告の主張は採用できない。
(3) 以上のとおり,使用商標B−1のうち,商標の同一性を基礎づける中核的 部分として把握される「クレスト」の片仮名部分を,本件商標と比較すると, 両者は,片仮名と欧文字という文字種の違いからくる外観上の相違はあるも のの,「クレスト」の称呼及び「(ものの)頂上,山頂,波頭」などの観念を いずれも共通にするものであることからすると,使用商標B−1は,本件商 標と社会通念上同一の商標であると認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2017.07. 7
平成28(行ケ)10270 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年6月28日 知的財産高等裁判所
前記のとおり,本願商標は,「SeaGull−LC」の欧文字及び記 号を標準文字で表してなる商標である。\nこのうち,記号「−」(ハイフン)は,一語が二行にまたがるときのつ なぎとして使用される場合を除き「英文等で,二語を連結して一語相当の語 と」する場合(甲29)ないし「英文などで,合成度の浅い複合語の連結, …または一語内の形態素の区切りを明確にする」(乙23)場合に使用され るものである。したがって,それ自体,本願商標の構成において,商品の出\n所識別標識としての機能を有するものでないことは明らかである。\nまた,同記号を基準とした場合の前半部分である「SeaGull」の 欧文字部分は,一般に,「海カモメ」の意味を有し,「シーガル」と発音さ れる英語「sea gull」を表したものと認識されるものといってよい。\nそうすると,当該部分につき,本願商標の指定商品「業務用電子計算機用プ ログラム」との関係で,その商品の普通名称や品質等を表示するものである\nなど,商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないと見るべき事情は見\n当たらないというべきである。
他方,後半部分である「LC」の欧文字部分は,それ自体独立の意味を 持った英語その他の外国語の単語ないし略語として認識されるものと見るべ き事情は見当たらない。また,証拠(乙8の1〜乙22)によれば,欧文字 2字が,商品の管理又は取引の便宜性等の事情から,商品の規格,型式又は 種別等を表示する記号又は符号として使用される例が少なからずあること,\n本願商標の指定商品を含む「電子応用機械器具及びその部品」を取り扱う分 野に特に着目しても,同じブランド名の商品につき,ブランド名に欧文字2 字を付して,当該ブランドのシリーズ商品における型式,種別等を表すもの\nとして使用される取引の実情があることが認められる。そうすると,上記 「LC」の欧文字部分は,本願商標に接した取引者,需要者にとって,独立 の意味を持つものではなく,商品の規格,型式又は種別等を表示する記号又\nは符号として認識されるものと見るのが相当である。そうである以上,当該 部分が,本願商標の指定商品との関係で,商品の出所識別標識としての機能\nを発揮するものと見ることはできない。 さらに,本願商標を構成する「SeaGull」と「LC」の各欧文字\n部分は,上記のとおり前者は英語を表したもの,後者は記号又は符号と認識\nされることから,相互に関連性を有する語ではなく,しかも,両者の間に存 する記号「−」(ハイフン)の上記機能ないし役割を踏まえるとなおさらに,\nこれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分 的に結合しているとはいえない。 以上を総合すると,本願商標は「SeaGull」の欧文字と「LC」 の欧文字とを記号「−」(ハイフン)を介して結合してなるものであるとこ ろ,本願商標を構成する各部分が分離して観察することが取引上不自然であ\nると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く,むしろ,本願 商標の前半を構成する「SeaGull」と後半を構\成する「LC」の各欧 文字部分は,記号「−」(ハイフン)を介して視覚上明確に分離して観察さ れるとともに,「SeaGull」の欧文字部分は,取引者,需要者に対し, 商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであり, 他方,「LC」の欧文字部分からは出所識別標識としての称呼,観念が生じ ないと認められる。 したがって,本願商標については,その構成部分の一部である「Sea\nGull」の欧文字部分を要部として抽出し,この部分のみを他人の商標と 比較して商標そのものの類否を判断することも許されるということができる。 そうすると,本願商標は,その構成全体から生じる「シーガルエルシー」\nの称呼のほか,要部である「SeaGull」の欧文字部分より,「シーガ ル」の称呼及び「海カモメ」の観念を生じるものというべきである。 (
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.07. 6
平成14年(ワ)8765号 意匠権 民事訴訟 平成16年3月22日 東京地方裁判所
(1)ア(ア)本件登録意匠の意匠に係る物品は輸液バッグであり、側面視にお いて、全体が薄型の形状をしているから、通常、看者の目に多く触れるのは、正面 及び背面であると認められる。そして、製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の 境界部は、正面及び背面のほぼ中央にあり、また、輸液バッグの使用時には、同境 界部の弱シール部を連通させて使用することから、同境界部付近は、看者の注意を 引く位置にあるものと認められる。
(イ)同境界部付近の構成をみると、その基本的構\成は、同境界部の中 央に帯状の弱シール部が形成されており、その弱シール部の両側に、弱シール部よ り幅の広い強シール部が形成されている(基本的構成態様(5))というものである。 そして、その具体的構成は、製剤収納部の下端左右コーナー部の外側のシール部\nは、弱シール部より幅が広く、弱シール部の左右両側の強シール部の上半分を形成 しており(具体的構成態様(11))、溶解液収納側の袋体の上端左右コーナー部のシー ル部は、弱シール部より幅が広く、弱シール部の左右両側の強シール部の下半分を 形成している(具体的構成態様(18))というものである。 このような同境界部付近の構成において、同境界部の中央に帯状の弱\nシール部が形成されており、その弱シール部の両側に、弱シール部より幅の広い強 シール部が形成されているという基本的構成態様(5)は、同境界部付近の構成の骨格\nを特徴づけており、看者の注意を引くものと認められる。
(ウ)基本的構成態様(5)は、その全体の構成が、本件登録意匠の意匠公\n報の必要図中、背面図にのみ表れている。しかし、本件登録意匠に係る輸液バッグ\nは、前記のとおり、側面視において全体が薄型の形状をしているから、正面と背面 が、通常、看者の目に触れるものと認められ、また、イ号意匠において、溶解液収 納側の袋体の目盛り及び数字が背面側のみに記載されていることも合わせ考える と、本件登録意匠及びイ号意匠に係る輸液バッグにおいては、アルミカバーシート が付された正面のみならず、背面も、看者の目に多く触れることが認められる。し たがって、基本的構成態様(5)の全体の構成が必要図中の背面図にしか表\れていない としても、それによって、基本的構成態様(5)を要部と認定することが妨げられるこ とはないというべきである。なお、本件登録意匠の意匠公報の【アルミラミネート シートをはがした状態の参考正面図】においては、アルミラミネートシートをはが した状態で、正面にも基本的構成態様(5)の構成が表\れることが示されている。もと より、登録意匠の権利範囲を確定する上で、参考図はあくまでも参考にとどまる が、同参考図によれば、基本的構成態様(5)が、本件登録意匠の構成中において、少\nなくとも無視されるべき構成でないことは認められるといえる。\n イ 本件登録意匠の出願前の公知意匠と比較すると、基本的構成態様(5)は、 出願前の公知意匠である甲第12ないし第16号証(オーツカCEZ注−MCのパ ンフレット)、第24号証(特許第3060132号公報)、第25号証(特許第 3060133号公報)、甲第33号証(「カルバペネム系抗生物質メロペネム (メロペン)キット製剤の有用性に関する実験的研究」新薬と臨床Vol.47 No.6)、第46号証(「ホスホマイシンナトリウムダブルバッグ製剤(溶解液付き 固形注射剤)の有用性に関する実験的研究」新薬と臨床Vol.47No.2)、乙第1号 証(意匠登録第1016887号公報)、第3号証(甲第12号証と同一)、第4 号証(「溶解液付き注射用固形抗生物質キット製剤のキット有用性に関する実験的 研究」日本包装学会誌Vol.4No.1)、第37、第38号証(味の素ファルマ株式会 社ピーエヌツインのパンフレット)、第39号証(本件登録意匠の出願前に発行さ れた公開特許公報に記載されたダブルバッグタイプの輸液バッグの図面)、第44 号証(特開2000−72925号公開特許公報)、第45号証(特開平7−15 5361号公開特許公報)、第46号証(特開平5−68702号公開特許公報) 各記載の輸液バッグには見られず、本件登録意匠の創作的な部分であると認められ る。
ウ 本件登録意匠の関連意匠である意匠登録第1107512号(甲第42 号証の1、2)、意匠登録第1108821号(甲第43号証の1、2)、意匠登 録第1108822号(甲第44号証の1、2)、意匠登録第1108823号 (甲第35号証の1、2)、意匠登録第1108824号(甲第45号証の1、 2)の各登録意匠には、いずれも基本的構成態様(5)が見られる。
エ 以上によれば、製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央 に帯状の弱シール部が形成されており、その弱シール部の両側に、弱シール部より 幅の広い強シール部が形成されているという基本的構成態様(5)は、本件登録意匠の 中で需要者の注意を最も引きやすい意匠の要部に該当するというべきである。
(2)ア(ア) 原告は、ダブルバッグタイプの輸液バッグにおいて、アルミカ バーシートの視認性が重要であり、上方の製剤収納袋の吊下部を残して全面を覆 う、貼着部のシール線が表\れていない方形状のアルミカバーシートの周辺部のいず れかに、一つの小さな半円形ないしそれに近い形状の引き剥がし用突片を設けた点 が本件意匠の要部であると主張する。
(イ) しかし、本件登録意匠のアルミカバーシートに貼着部のシール\n線が表れていない点は、それ自体、外観上、目立つところではない。また、製剤収\n納側の袋体の吊下部を残して全面を覆うアルミカバーシートは、原告公知意匠に見 られ、そのアルミカバーシートには、貼着部のシール線が表\れているが、そのシー ル線は、製剤収納側の袋体の縁に沿って幅狭に存在するにすぎず、それほど目立つ ものではないから、それとの対比からしても、本件登録意匠においてアルミカバー シートに貼着部のシール線が表\れていない点は、看者の注意を引くとは認められな い。 また、本件登録意匠のアルミカバーシートの周辺部に設けられた一つ の小さな半円形ないしそれに近い形状の引き剥がし用突片は、その大きさ、形状に 鑑み、目立つものではなく、本件登録意匠の関連意匠5件の各正面図においても、 引き剥がし用突片は、位置は様々であるが、いずれもそれ程目立つものではないこ とを併せ考えると、本件登録意匠のアルミカバーシートの周辺部に設けられた引き 剥がし用突片は、看者の注意を引くとは認められない。 したがって、原告の主張に係る、上方の製剤収納袋の吊下部を残して 全面を覆う、貼着部のシール線が表\れていない方形状のアルミカバーシートの周辺 部のいずれかに、一つの小さな半円形ないしそれに近い形状の引き剥がし用突片を 設けた点は、看者の注意を引くものではなく、本件登録意匠の要部であるとは認め られない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2017.07. 6
平成23(ワ)247 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成24年6月29日 東京地方裁判所
前記ア認定のエーシーアダプタの性質,用途及び使用態様によれ ば,エーシーアダプタは,携帯用の周辺機器の充電に用いる実用品であ ると同時に,身の回りに置き,あるいは,外出時に携帯するなど,日常 生活において目に触れる機会の多い製品であるといえる。 そして,前記イの認定事実によれば,エーシーアダプタの意匠におい ては,本件登録意匠の構成態様に係る「箱状の本体の背面に折り畳み自\n在の差込みプラグを設け,底面に周辺機器に接続されるUSBコネクタ を設ける」構成(前記(1)ア(1)),「本体は,縦横の寸法が同一の正四 角形で扁平な箱状であり」(前記(1)ア(2)),「本体の全周囲は面取り がされている」構成及び「縦(横)の寸法の約0.15倍の長さを半径\nとする面取りをする」構成,「差込みプラグが本体の平面部(上面部)\nから背面部に設けられ,プラグのピンは背面の凹部に折り畳まれた状態 から,後方又は上方に起立させて使用され,プラグピンの支持部の外周 は弧状をなしている」構成(前記(1)ア(4)),本体の「正面下部にラン プを設ける」構成(前記(1)ア(5)),「USBコネクタは,底部に設け られている」構成(前記(1)ア(6))は,本件出願時にいずれも公知であ ったものといえる。
他方で,本件登録意匠の構成態様のうち,「本体の全周囲は,厚さ方\n向に厚さの約2分の1を半径とする半円弧状の面取りがされ,本体の四 角隅部は,正面視において,いずれも,厚さの約2分の1を半径とする 四半球状となっている」点(前記(1)ア(3))は,公知意匠には認められ ない構成態様であり,この構\成態様により,需要者に対し,本体全体が 丸みを帯びた柔らかな印象を与えると同時に,本体正面視の四角隅部が 四半球状となっていることにより整った印象も与えるものとなってお り,上記構成態様は,他の公知意匠にはみられない新規な創作部分であ\nるといえる。 すなわち,前記イ(イ)のとおり,乙3には,充電器に係る意匠におい て,縦横の寸法が同一の正四角形の箱状の本体において,「縦(横)の 寸法の約0.15倍の長さを半径とする面取りをしている」構成が示さ\nれているが,厚さが縦(横)寸法の約0.6倍であって,これは本件登 録意匠の2倍に当たり,縦(横)の長さと厚さとの比が異なり,さらに は厚さに対する面取り径の比が本件登録意匠よりも小さく,本件登録意 匠のような全周囲が厚さの約2分の1を半径とする半円弧状の面取り をしておらず,また,本体の四角隅部が,正面視において,いずれも, 厚さの約2分の1を半径とする四半球状となっているものともいえず, 本件登録意匠のような本体全体が丸みを帯びた柔らかな印象を与える ものとはいえない。他に本件登録意匠の上記構成態様が本件出願前に公\n然知られた形状であったことを認めるに足りる証拠はない。 以上を総合考慮すると,本件登録意匠において,需要者の注意を引き やすい特徴的部分は,「本体の全周囲は,厚さ方向に厚さの約2分の1 を半径とする半円弧状の面取りがされ,本体の四角隅部は,正面視にお いて,いずれも,厚さの約2分の1を半径とする四半球状となっている」 点を含む,本体部全体の形態であると認められる。
(イ) これに対し被告は,通常の販売・流通形態(店頭,ウェブサイト) では,需要者は,エーシーアダプタを正面又は正面やや斜めから見るの が普通であり,需要者としては正面の形態に最も注目するから,本件登 録意匠においては,携帯電話等の周辺機器との接続部分,本体の正面の 形状及びランプの位置の正面形態全体がひとまとまりとして要部とな り,特に接続部分が最重要の要部である旨主張する。 しかしながら,意匠の特徴的部分の把握に際しては,意匠に係る物品 の販売・流通時において視認し得る形状のみを前提にするのではなく, 意匠に係る物品の性質,用途,使用態様等も考慮すべきであるところ, 前記(ア)認定のとおり,エーシーアダプタは,需要者が実際に手にとっ て携帯用の周辺機器の充電に用いる実用品であると同時に,身の回りに 置き,あるいは,外出時に携帯するなどされるものであることからする と,需要者が本件登録意匠の正面の形態にのみ注目するとはいえない。 また,被告が主張する携帯電話等の周辺機器との接続部分,本体の正面 の形状及びランプの位置は,前記イのとおり,いずれも本件出願前に公 知の形状であることからすると,本件登録意匠においては,携帯電話等 の周辺機器との接続部分,本体の正面の形状及びランプの位置の正面形 態全体がひとまとまりとして需要者の注意を引きやすい特徴的部分(要 部)を形成しているとはいえないし,ましてや接続部分が最重要の要部 であるとはいえない。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
(3) 被告意匠の類似性
前記(2)ウ(ア)認定のとおり,本件登録意匠において,需要者の注意を引 きやすい特徴的部分は,「本体の全周囲は,厚さ方向に厚さの約2分の1を 半径とする半円弧状の面取りがされ,本体の四角隅部は,正面視において, いずれも,厚さの約2分の1を半径とする四半球状となっている」点を含む, 本体部の形態全体である。
そこで,この特徴的部分を中心に本件登録意匠と被告意匠を対比した上 で,両意匠が全体的な美感を共通にするか否かについて判断するに,前記(1) ウ(ア)(1)ないし(6)認定のとおり,両意匠は,この特徴的部分において共通す るのみならず,それ以外の基本的構成態様及び具体的構\成態様の多くの部分 においても共通しており,需要者に対し,全体として共通の美感を生じさせ るものと認められる。 他方で,前記(1)ウ(イ)認定のとおり,両意匠には,(1)本件登録意匠では, 本体底面に周辺機器に接続されるUSBコネクタが設けられているが,被告 意匠では,周辺機器に接続されるコードが断線防止部材を介在して,本体内 部の回路に接続されている点,(2)本件登録意匠では,本体の正面の形状が平 坦であるが,被告意匠では,中央部で周縁部よりも厚さの約0.03倍(約 0.5mm)程度膨出している点,(3)本件登録意匠では,ランプの中心が本 体右側面と底面からそれぞれ約17mmの均等な位置にあるのに対し,被告 意匠では,ランプの中心が本体底面から約12mmで,かつ,本体右側面か ら約16mmの位置にあり,本件登録意匠に比べて底面に寄った位置に設け られている点において差異があるが,これらの差異点は,需要者の注意をひ きやすい部分とはいえない上,差異点から受ける印象は,両意匠の共通点か ら受ける印象を凌駕するものではない。 したがって,本件登録意匠と被告意匠は,上記差異点を考慮しても,需要 者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認めら れるから,被告意匠は,本件登録意匠に類似している。これに反する被告の主張は,採用することができない。
以上を前提に検討するに,被告製品は,Docomo,SoftBank等の携帯 電話用のエーシーアダプタであり,一方,原告製品は,USBコネク タ(USBポート)を有するエーシーアダプタであり,上記携帯電話 の充電に使用する際には,上記携帯電話の接続口に対応したUSBケ ーブルが別途必要とされるものである。 ところで,エーシーアダプタが,携帯用の周辺機器の充電に用いる 実用品であると同時に,身の回りに置き,あるいは,外出時に携帯す るなど,日常生活において目に触れる機会の多い製品であること(前 記1(2)ウ(ア))に照らすならば,需要者は,エーシーアダプタの選 択に当たっては,充電可能な製品の種類,その他の性能\,価格,大き さ,重さのほか,デザイン,色などの諸要素を考慮するものと考えら れる。 しかるところ,原告製品と被告製品は,いずれもDocomo,SoftBank 等の携帯電話の充電に利用することができ,寸法,出力も概ね同じで あり,また,重さは原告製品の方が軽いが,ケーブルの有無が異なる から,ほぼ同程度と評価することができる。 さらに,原告製品とDocomo,SoftBank等の携帯電話用の接続ケーブ ルを合わせた価格(1360円から1753円)と被告製品の価格(1 279円から1453円)は,同じ価格帯に属するといえる。 そして,原告製品の本体の独特の丸みを帯びた印象を与えるデザイ ンは,このようなデザインを好む需要者が原告製品を選択する動機付 けになるものといえる。 他方で,(1)Docomo,SoftBank等の携帯電話のみを充電することがで きればよいと考える需要者にあっては,価格面でより安価であり,ケ ーブルが一体であって使い勝手のよい,被告製品の代替品を選択する 可能性が高いこと,(2)被告製品は,本体と一体となった接続ケーブル が本体と同色であるのに対し(甲50,乙7の1,弁論の全趣旨), 原告製品の本体の色によっては,市販されている接続用のUSBケー ブルと同色とはならないことから,この点を美観上好まず原告製品を 選択しない可能性があることが認められる。
b 次に,被告製品には,ピンク,レッド,ホワイト,ブルー,ブラッ ク等の色のバリエーションがあり(甲41ないし45,乙7の1), 原告製品にも,ホワイト,ブラック,シアンブルー,ピンク,バイオ レットの色のバリエーションがある(甲34)。 しかるところ,被告製品を購入した者が記載したインターネットの ショッピングサイト上のレビュー(利用者の感想)においては,「と にかくピンクがかわいいです。」(甲41),「見た目は真っ赤でお しゃれです。」,「赤なら自分の充電器かどうかわかりやすいのでは ないかという点にひかれて購入し」(以上,甲42)との記載がある ように,色が購入動機になっていることがうかがわれる。
c 前記a及びbの認定事実を総合すると,仮に被告による被告製品の 販売がされなかった場合には,被告製品の購入者の多くは,Docomo, SoftBank等の携帯電話用の被告製品と同種の接続ケーブルが一体と なった代替品を選択した可能性が高いものと認められる。\n また,本件登録意匠と類似する被告意匠は,被告製品の購入動機の 形成に寄与していることが認められるものの,その購入動機の形成に は,被告意匠のほか,被告製品がDocomo,SoftBank等の携帯電話用の 専用品であることが大きく寄与し,被告製品の色彩等(本体と接続ケ ーブルが同一色である点を含む。)も相当程度寄与しているものとう かがわれるから,被告意匠の購入動機の形成に対する寄与は,一定の 割合にとどまるものと認められる。 以上によれば,原告製品と被告製品の形態の違い,被告製品と同種 の代替品の存在,被告製品の購入動機の形成に対する被告意匠の寄与 が一定の割合にとどまることは,被告製品の譲渡数量の一部に相当す る原告製品を原告において「販売することができないとする事 情」(意匠法39条1項ただし書)に該当するものと認められる。 そして,上記認定の諸点を総合考慮すると,意匠法39条1項ただ し書の規定により控除すべき上記「販売することができないとする事 情」に相当する数量は,被告製品の販売数量(前記ア)の9割と認め るのが相当である。
(オ) 被告の主張について
a 被告は,Docomo,SoftBankの携帯電話用のエーシーアダプタが必要 な需要者は,当該機器が充電できればよいから,被告製品のようなエ ーシーアダプタと接続ケーブルとが一体となっている製品を選択し, 仮に被告製品が販売されなかったとした場合には,被告製品と同種の 廉価の代替品を購入するはずであり,あえて,別途上記携帯電話用の USBケーブルを必要とする原告製品を選択することはないのに対 し,他方で,多種の周辺機器の充電に用いるエーシーアダプタが必要 な需要者は,原告製品を選択することになるから,原告製品と被告製 品とでは,そもそも購入対象者が異なり,明確に棲み分けがされてい る旨主張する。 しかしながら,前記(エ)aに説示したとおり,両製品に共通する需 要者は,原告製品の丸みを帯びたデザインを重視するなどして,原告 製品を購入する可能性があるものと認められるから,被告の上記主張\nは,採用することができない。
b 次に,被告は,被告製品は,主にインターネットのショッピングサ イトで販売され,一体に接続されているケーブルを含めた全体につい て,正面から撮影された写真が掲載されているのみであり,また,被 告製品は,ほとんどその正面形状しか見えない状態でパッケージに梱 包されており,その意匠が需要者の購入動機に寄与することはなく, むしろ,インターネットのショッピングサイトにおける被告製品のレ ビューに照らしても,被告製品の購入動機となっているのは,被告意 匠ではなく,色である旨主張する。 しかしながら,被告製品が主にインターネットのショッピングサイ トで販売されていることを認めるに足りる証拠はないのみならず,被 告製品の梱包の態様(甲5,検甲1)やインターネットのショッピン グサイトの表示の態様(甲43ないし45)に照らすならば,需要者\nは,被告製品を購入するに当たり,被告製品の丸みを帯びたデザイン を看取することができるものと認められ,その意匠が需要者の購入動 機に寄与することがないとはいえない。 また,原告製品のレビューにおいて,「デザインが個人的に好きで すね。丸みがあり,艶々しています。」,「丸みを帯びたデザイン, 他機種と比較してかなり質感が高いです。」(以上,甲46),「そ のデザインと小ささ,軽さに大変満足しています。」,「iPodにマッ チしたデザインも気に入っている。」(以上,甲47)との記載があ り,これらの記載は,原告製品において,デザイン(意匠)が購入動 機となっていることを示すものといえる。加えて,被告意匠と本件登 録意匠と類似していることに照らすならば,被告意匠においても,色 のみならず,デザイン(意匠)も購入動機に寄与しているものと認め られる。 したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
オ 小括
以上によれば,意匠法39条1項により算出される原告の損害額は,被 告製品の販売数量(前記ア)に単位数量当たりの原告製品の利益額(前記 ウ(ウ))を乗じて得られた額である722万9506円から,「販売する ことができないとする事情」に相当する数量(上記販売数量の9割)に応 じた額を控除した後の72万2950円となる。
(2) 弁護士費用
本件事案の性質,審理の経過等諸般の事情を総合考慮すると,被告による 本件意匠権の侵害行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の損 害は,20万円と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2017.07. 5
平成28(行ケ)10220 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月4日 知的財産高等裁判所(4部)
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 相違点認定
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.07. 5
平成29(ラ)10002 文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件 不正競争 平成29年6月12日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
文書提出命令の申立ては,申\立てに係る文書の表示及び趣旨を明らかにしてしな\nければならない(民訴法221条1項)。 本件申立てに係る文書は,別紙文書目録記載のとおりであり,高性能\ALPSの 設計書のほかは,高性能ALPSの設計のための試験の内容を記載した文書,高性\n能ALPSで使用されている放射能\廃棄物量削減,核種除去性能に関する技術情報\nが記載されている文書,その他高性能ALPSの設計・製造・運用に関して作成さ\nれた文書というものであって,これらの表示は,文書の記載内容を類型的に示すも\nのではない。本件各文書は,個人名や組織名などで,その作成名義者は特定されて いるものではなく,作成日付や作成期間も特定されておらず,相手方における管理 態様などでも特定されていない。 また,抗告人は,本件申立てに係る文書の趣旨について,設計書には,抗告人が\n相手方に開示した抗告人の営業秘密を用いて,それ以前には相手方が有しなかった 核種除去性能に関する知見,放射能\廃棄物量削減に関する知見を前提とした設計が されており,その他高性能ALPSの設計・製造・運用に関して作成された文書等\nには,上記の各知見を前提とした記載がされているとする。しかし,核種除去性能\nに関する知見,放射能廃棄物量削減に関する知見の内容は,極めて広範囲に及ぶ抽\n象的なものである。各知見を,抗告人の営業秘密であって,相手方に開示した知見 と限定したり,相手方が有しなかった知見と限定したりするだけでは,各知見の内 容が客観的に具体化されるものではない。したがって,本件各文書に上記の記載等 があるとするだけでは,本件申立てに係る文書に記載されている内容の概略や要点\nは明らかではない。 さらに,後記で検討するとおり,本件申立てに係る文書を識別することができ\nる事項も明らかではない。 よって,本件申立ては,本件申\立てに係る文書の表示及び趣旨を明らかにしてな\nされたものということはできない。
(2)識別性について
ア 文書提出命令の申立ては,申\立てに係る文書の表示及び趣旨を明らかにして\nなされなくても,これらの事項に代えて,文書の所持者がその申立てに係る文書を\n「識別することができる事項」を明らかにしてなされれば,当該申立ては適法にな\nり得る(民訴法222条1項)。 そして,「識別することができる事項」とは,文書の所持者において,その事項 が明らかにされていれば,不相当な時間や労力を要しないで当該申立てに係る文書\nあるいはそれを含む文書グループを他の文書あるいは他の文書グループから区別す ることができるような事項を意味し,申立人側の具体的な事情と所持者側の具体的\nな事情を総合的に考慮して判断されるべきものである。
イ 相手方の事情
(ア) 高性能ALPSは,損傷した福島第一原発から発生する放射能\汚染水を処 理するための設備であって,既存ALPSよりも高性能な多核種除去設備であり,\n国が巨額を投じて行う高性能多核種除去設備整備実証事業において採用されたもの\nである。(前記1(2)キ) また,同事業の補助事業者は相手方のほか,東京電力及び東芝であり,相手方だ けでも,高性能ALPSの技術開発を推進するに当たり,設計・施工・材料の納入\n等を行う業者として,少なくとも延べ25社を採択し,相手方の多数の内部部署が, 高性能ALPSに関する業務に関わっている。(前記1(2)キ,(3)ウ) さらに,高性能多核種除去設備タスクフォースに報告された前記各報告内容(前\n記1(3)ア,イ)によれば,高性能ALPSは,フィルタ処理装置及び核種吸着装置\nのほか,様々な装置を統合した設備であって,高性能ALPSの設置・稼働に当た\nっては,吸着材の選定,吸着塔の構成,pH調整などに関して,ラボ試験,検証試\n験,実証試験が並行して行われ,課題に応じて多数の変更が加えられていったこと が認められる。 加えて,これらの事実によれば,相手方は,東京電力及び東芝とともに,高性能\n多核種除去設備整備実証事業において高性能ALPSを共同提案するに際し,多数\nの試験を繰り返し,複数の業者と事前に共同提案内容を協議したことも認められる。 (イ) 本件各文書は,1)高性能ALPSの設計書,2)高性能ALPS設計のため\nの疑似水試験,模擬液試験や実液試験の内容を記載した文書,3)高性能ALPSで\n使用されている放射能廃棄物量削減に関する技術情報が記載されている文書,4)高 性能ALPSで使用されている核種除去性能\に関する技術情報が記載されている文 書,5)その他高性能ALPSの設計・製造・運用に関して作成された文書の5つに\n区分することができる。 そして,前記1)の文書については,その対象とする高性能ALPSが最先端の技\n術が用いられた大規模な設備であること,高性能ALPSを構\成する様々な装置の 設計書を含んでいること,高性能ALPSの設計書の作成に多数の業者及び相手方\nの内部部署が関与していること,高性能ALPSの提案・設置・稼働に当たって複\n数の変更が加えられていること,管理態様も様々であることからすれば,相手方に おいて,1)の文書を区別するに当たり,相当な時間と労力を要するというべきであ る。 前記2)の文書については,そもそも,文書の表示を,「試験の内容を記載した文\n書」とするところ,試験の内容には,実際に行われた試験方法や試験結果のほか, 当該試験方法を設定するに至った経緯,当該試験結果に対する考察など多様なもの が含まれる。また,高性能ALPSの設置・稼働に当たっては,吸着材の選定,吸\n着塔の構成,pH調整などに関して,ラボ試験,検証試験,実証試験が並行して行\nわれており,さらに,各試験の前後には,多数の業者及び相手方の内部部署が関与 したものと認められる。そうすると,相手方において,2)の文書を区別するに当た り,相当な時間と労力を要するというべきである。 前記3)及び4)の文書については,文書の表示を,「高性能\ALPSで使用されて いる放射能廃棄物量削減,核種除去性能\に関する技術情報が記載されている文書」 とするところ,高性能ALPSの開発コンセプトは,フィルタ・吸着材を主体とし\nた除去プロセスの採用により,廃棄物発生量を約95%削減するとともに,フィル タ・吸着材処理技術の開発により処理対象とする62核種に対して,高い除去性能\n(NDレベル)を達成するなどというものである。そうすると,前記3)及び4)の文 書は,高性能ALPSで使用されている技術情報が記載されている文書というもの\nでしかなく,おおよそ高性能ALPSに関する文書が全て含まれるから,相手方に\nおいて,3)及び4)の文書を区別するに当たり,相当な時間と労力を要するというべ きである。 前記5)の文書についても,おおよそ高性能ALPSに関する文書が全て含まれる\nから,相手方において,5)の文書を区別するに当たり,相当な時間と労力を要する というべきである。 また,そもそも,本件各文書の相互の関係は明らかではなく,抗告人は,相手方 からの示唆があるにもかかわらず,それを明らかにしていない。本件各文書の中に は,本件仕様書にいう「重要情報」に当たる情報が記載され,相手方において厳格 に管理されている文書が含まれると認められるものの,本件各文書は,このような 文書に限定されているものでもない。 よって,相手方において,本件各文書を,相手方が所持する他の文書あるいは文 書グループから区別するに当たり,相当な時間と労力を要するというべきである。
・・・
以上のとおり,相手方は,本件各文書を,相手方が所持する他の文書あるいは文 書グループから区別するに当たり,相当な時間と労力を要する。一方,抗告人は, 申立てに係る文書の種別,作成期間,内容の概略や要点等をさらに特定することや,\n申立てに係る文書のおおよその作成部署や管理態様等をさらに特定することは困難\nではない。また,抗告人は,相手方が申立てに係る文書を区別するに当たり,不相\n当な時間や労力を要しないよう,申立てに係る文書群を特定する努力をしていない\nといわざるを得ない。 そうすると,本件申立てにおいて,相手方が,不相当な時間や労力を要しないで\n本件申立てに係る文書あるいはそれを含む文書グループを他の文書あるいは他の文\n書グループから区別することができるような事項は明らかではないというべきであ る。 よって,本件申立ては,相手方がその申\立てに係る文書を「識別することができ る事項」を明らかにしてなされたものということはできない。
2017.06.30
平成28(ネ)10047 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年10月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ところで,特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と,当該特 許の新規性,進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレ ーム解釈とは整合するのが望ましいところ,確かに,本件特許2に係る審決取消請 求事件の判決(甲12)には,控訴人が指摘するとおり,「本件特許発明2は,ケ ーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクル コネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置 が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される。」旨の記載\nがある(39頁)。しかし,上記判決は,主引用例(本件における乙3)の嵌合過 程について,「…肩部56で形成される溝部49の底面に回転中心突起53が当た り,ここで停止する状態となる。…この状態で相手コネクタ33を回転させるので はなく,回転中心突起53を肩部56に沿って動かすことで,相手コネクタ33を コネクタ31に対してコネクタ突合方向のケーブル44側にずらした状態にして, 相手コネクタ33をコネクタ突合方向に直交する溝部方向に動かすことができない ようにし,その後,回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させている」 (36〜37頁)との認定を前提に,本件特許発明2と乙3発明とを対比するに当 たり,乙3発明には,「回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に 比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」,「回転 中心突起53の上方に肩部56の上面が位置するように,相手コネクタ33が傾斜 している状態で肩部56の前側から後側(ケーブル側)へ回転中心突起53を移動 させているものであって,相手コネクタ33の回転により回転中心突起56の最後 方位置が後方(ケーブル側)へ移動するものではない」(38頁)として,乙3発 明は,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケー ブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位 置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に 位置するものではないという点において,本件特許発明2と相違する。」旨認定し ている(38頁)。上記のように,乙3発明においては,ロック突部の突部後縁の 最後方位置の変化に,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿 勢への回転を伴う姿勢の変化が関係していないこと(「回転によって,回転中心突 起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載され ているとはいえない」こと)に照らせば,本件特許発明2と乙3発明とが相違する ことを認定するについては,本件特許発明2におけるロック突部の突部後縁の最後 方位置の変化が,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢へ の回転を伴う姿勢の変化によって生じるものであれば足り,「回転のみによって」 生じること,言い換えれば,ケーブルコネクタを上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合 終了姿勢へと変化させる際に,姿勢方向を回転させることに伴って生じる「ケーブ ルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一 切あってはならないことを要するものではないというべきである。なお,同一特許 に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は,侵害訴訟における技術的範囲の 確定に対して拘束力を持つものではない。 したがって,控訴人の上記限定解釈に係る主張は,理由がない。
(イ) 控訴人は,被控訴人が,特許の無効を回避するために,自ら,「本件特許 発明2は,「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が,「ケーブルコネクタが上向 き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最 前方位置よりも前方に位置し,また,「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢 にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」 旨構成要件e及びfを限定解釈すべきことを主張しているのであるから,その技術\n的範囲の解釈に際しては,被控訴人の上記主張が前提にされるべきである旨主張す る。 しかし,特許発明の技術的範囲を解釈するについて,相手方の無効主張に対する 反論として述べた当事者の主張は,必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。 そして,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限 定は規定されていないし,前記(1)イ記載の本件特許発明2の課題及び作用効果は, ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にある とき,すなわち,コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は,常にロック溝部の溝部後縁か ら溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏 し得ないというものではない。また,そもそも,本件明細書2には,本件特許発明 2に係る実施例の嵌合動作について,「ロック突部21’の下部傾斜部21’B− 2が,ロック溝部57’の後縁突出部59’Bの位置まで達すると,該後縁突出部 59’Bに対して下部傾斜部21’B−2が該後縁突出部59’Bの下方に向けて 滑動しながらケーブルコネクタ10はその前端が時計方向に回転して水平姿勢とな って嵌合終了の姿勢に至る。」(【0053】)と記載されているように,ケーブ ルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときであっても,嵌合終了姿勢(水平姿勢)に 近づくと,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内 方に突出する突出部の最前方位置よりも後方に位置することが開示されているとい えるから,構成要件eを,「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときは,ロ\nック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する 突出部の最前方位置よりも前方に位置する」ことを規定したものと解釈することは, 誤りである。
・・・・・
ア 控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は,控訴人 が請求した無効審判請求(無効2014−800015)と同一の事実及び同一の 証拠に基づくものであるところ,上記無効審判請求については,請求不成立審決が, 既に確定した(甲8,12)。したがって,控訴人において,本件特許2が,上記 明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として,特許無効審判により 無効にされるべきものと主張することは,紛争の蒸し返しに当たり,訴訟上の信義 則によって,許されない(同法167条,104条の3第1項)。
イ なお,控訴人は,本件特許発明2が「ケーブルコネクタの回転のみによって, すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対 位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構\n成に限定されている」ものと解釈されないとすれば,本件特許発明2は進歩性を欠 く旨主張する。 しかし,本件特許発明2の要旨を上記のように限定的に認定しない場合であって も,乙3発明における嵌合動作は,相手コネクタ33の回転中心突起53をコネク タ31の溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入し,次いで,回転中心突起5 3を肩部56に沿って動かし,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56 のケーブル44側に当接している状態にして,その後,回転中心突起53を中心に 相手コネクタ33を回転させ,嵌合終了姿勢に至るというものであり,本件特許発 明2と乙3発明とは,本件特許発明2では,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブル コネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき, 上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合 終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し」ているのに対し,乙3発明では,コ ネクタ嵌合過程にて相手コネクタ33の前端がもち上がって該相手コネクタ33が 上向き傾斜姿勢にあるときのうち,少なくとも,コネクタ突合方向のケーブル44 側の端までずらした状態で回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させ るとき,回転中心突起の突部後縁の最後方位置が,相手コネクタ33がコネクタ嵌 合終了姿勢にあるときと同一の地点に位置している点,すなわち構成要件eの点で\n相違する。そして,乙3には,乙3発明の上記嵌合動作に関し,回転によって,回 転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術的思想 が記載されているとはいえず(甲12・38頁),また,乙3発明と乙7ないし1 0に記載された各コネクタとでは,その構造や形状が大きく異なるから,乙3発明\nにおいて,上記各コネクタの嵌合過程における突起部と突出部との位置関係を適用 しようとする動機付けがあるということはできないし,仮に適用を試みたとしても, 乙3発明において,上記相違点に係る本件特許発明2の構成を備えることが容易に\n想到できたとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 分割
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.06.28
平成28(行ケ)10227 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年6月14日 知的財産高等裁判所
後掲の各証拠によれば,日本工業規格(JIS)に関して,次の事実が認 められる。
ア 日本工業規格(JIS)は,昭和24年に制定された工業標準化法に基 づき制定される国家規格であり,平成27年3月末現在で,1万0599 件の規格が制定されている(乙3)。
イ 日本工業規格(JIS)の対象は,家電製品や文房具などの生活用品か ら,化学製品や産業機械まで,あらゆる技術分野(土木及び建築,一般機 械など19分野に分類)の製品に及ぶほか,文字コードやプログラムコー ド等の情報処理に関する規格,漢字の規格(JIS漢字水準),商業施設 などで利用される案内用図記号,公共施設等向けの「ピクトグラム」(絵 文字)など,多岐にわたっている(甲1の3,乙9〜23,38,4 3)。
ウ 経済産業省等は,全国の小・中・高校生等を対象に,平成18年度から 「標準化教室」と題する出前授業を実施しており,そのテキストにおい て,日本工業規格(JIS)やその身近な活用事例等を紹介している(乙 24〜27)。 また,同省は,広く一般向けに,日本工業規格(JIS)に関する各種 のパンフレットやリーフレット等を作成し,ウェブサイトに掲載して広告 を行っている(乙24,28〜31)。 エ そのほかにも,「JIS」の語は,「ジス」と称される国家規格である 日本工業規格を表す文字として,広辞苑を含む多くの辞書や書籍(乙\n1,2,20,32〜37),ウェブサイト(乙38〜40),新聞記事 (乙41〜43)に掲載され,更に,中学校の技術・家庭の教科書等にも 掲載されている(乙44〜46)。 オ 最近においても,2020年の東京五輪の開催に向け,海外からの観光 客の受入れに備え,日本工業規格(JIS)が規定する「ピクトグラム」を 国際標準に合わせて見直すことが話題となり,新聞報道されている(乙4 7〜49)。
(2)以上のとおり,「JIS」の文字は,国家規格である日本工業規格を表す\nものとして我が国において長年にわたって利用され,その対象も多数かつ多 岐にわたり,国民生活全般に密接に関わるものであり,加えて,様々な媒体 で広く取り上げられ,広告や報道がされてきたものといえる。 してみると,「JIS」の文字(引用標章)が,日本工業規格を表す標章\nとして我が国の国民一般に広く認識されており,著名な標章といえるもので あることは明らかというべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本願商標の指定役務である「飲食サービスの提供」に当たり,そ の役務を提供する事業者やその提供を受ける需要者が,引用標章を一般に 目にするとは認められず,日本工業規格について注意を払っているという 取引の実情もないから,引用標章が当該分野に係る取引者,需要者に広く 認識されているとは認められない旨主張する。 しかし,引用標章が,我が国の国民生活全般に密接に関わるものであ り,国民一般に広く認識される標章であることは上記(2)で述べたとおりで あり,「飲食サービスの提供」の分野に係る取引者,需要者のみがその例 外とされるべき理由は何ら認められない。原告は,本願商標の指定役務で ある「飲食サービスの提供」の場面において,取引者,需要者が引用標章 を目にし,これに注意を払うという取引の実情がなければ,当該取引者,需 要者が引用標章を広く認識することはないかのごとく主張するが,当該取 引者,需要者が引用標章を認識する機会は,何も「飲食サービスの提供」の 場面に限られるものではないから,原告の上記主張は理由がない。
イ 原告は,1)需要者が日本工業規格を認識する標章は「JISマーク」で あり,「JIS」の文字は定着していない,2)「JIS」の文字が,他の ものを表す略称として使用されている例があり,需要者は,「JIS」の\n文字から直ちに日本工業規格を認識するとはいえないとして,引用標章は 日本工業規格を表す標章として著名ではない旨主張する。\n しかし,「JISマーク」が日本工業規格を表す標章として国民に広く\n知られている事実があるとしても,そのことが,「JIS」の文字が日本 工業規格を表す標章として著名であることを否定する理由となるものでは\nない(両者が共に日本工業規格を表す標章として広く認識されることもあ\nり得る。)。むしろ,「JISマーク」が,「JIS」の文字をデザイン 化したマークであって(乙4の10頁,乙6参照),そこから「JIS」の 文字を読み取ることができることからすれば,「JISマーク」が日本工 業規格を表す標章として広く知られているとの事実は,「JIS」の文字\nも同様に日本工業規格を表す標章として広く知られていることを示すもの\nということができる。 また,原告が,「JIS」の文字が略称として使用されている例として 挙げるのは,「株式会社ジャパンインバウンドソリューションズ(Japan Inbound Solutions)の略称」(甲20),「JIS 香港日本人学校大 埔校」(甲21),「地震情報サイト JIS」(甲22)の3例であ り,いずれも一般に知られた「JIS」の使用例ではなく,引用標章に 接した国民一般がこれらの使用例を想起することは通常考え難いこと であるから,これらの使用例の存在が,引用標章の著名性を否定する理 由となるものではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.06.23
平成28(ワ)5104 不正競争行為差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成29年6月15日 大阪地方裁判所(21部)
ア 登録意匠と対比すべき相手方の意匠とが類似であるか否かの判断は,需要者 の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う(意匠法24条2項)ものとされてお り,意匠を全体として観察することを要するが,その際には,意匠に係る物品の性 質,用途及び使用態様,さらには公知意匠にはない新規な創作部分の存否その他の 事情を参酌して,取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として 把握し,登録意匠と相手方意匠が,意匠の要部において構成態様を共通にしている\nか否かを観察すべきものである。
イ 本件意匠の要部について検討すると,本件意匠に係る物品は,その物品の説 明によれば,柔軟性を有する合成樹脂製のシートであり,裏面を湿らせて手洗器付 トイレタンクのボウルに密着させて取り付け,ボウルの表面への埃,水垢等の付着\nを防止することができる使い捨てシートであると認められる。そして,これに別紙 意匠図面中の【使用状態を示す参考図】を参考にすると,その形状は,取り付ける 先の一般的な長方形の手洗器付トイレタンクのボウルの形状に規定されているもの ということができるから,取引者・需要者は,その規定された形状を前提として, 本件意匠につき,その形状がボウルの表面の埃,水垢等の付着し易い部分を十\分カ バーしているものであるか,その形状がボウルに密着して取り付け易いものである か,さらには取り付け易くなるよう工夫が施されるかなどの点に注目するものと考 えられる。 したがって,取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分,すなわち要部は,基 本的構成態様ではなく,具体的構\成態様のうちでも,ボウルに装着した場合の使用 状態を決めることになる,本件意匠の外周の形状,すなわち「シート」の四隅の丸 みの半径の大きさの点や,ボウルの孔に対応する「シート」に設けられた貫通孔と 湾曲部の形状及びその位置関係などの点であると認められる。 この点,被告は,本件意匠の実施品は,手洗器付トイレタンクのボウルの表面へ\nの埃,水垢等の付着を防止するという課題を解決するアイデア商品であって,その 当時,市場に同種の用途,機能を有する物品はなかったことから,本件意匠はパイ\nオニア意匠であるとして,意匠に係る物品全体の形態,すなわち基本的構成態様そ\nのものが要部であるように主張する。 しかし,本件意匠の実施品が新品種の商品であって,その基本的構成態様が新規\nなものであったとしても,意匠に係る物品の説明に明らかなように,その物品の使 用目的から,取引者・需要者は,その基本的構成態様が,取り付ける先のボウルの\n形状に規定されているものにすぎないことは容易に理解できるところであるから, 本件意匠の基本的構成態様そのものをもって,最も注意を惹きやすい部分というこ\nとはできず,その点に要部があると認めることはできないから,被告の上記主張は 採用できない。
(3) 本件意匠と原告意匠の類否
以上により本件意匠と原告意匠の類否について検討すると,本件意匠と原告意匠 の共通点は,いずれも本件意匠の要部にかかわらないものであるといえる。 他方,シートの四隅の丸みの半径の大きさが異なること,本件意匠では貫通孔が 湾曲部と離間して設けられているのに対し,原告意匠では湾曲部の中央部と細いス リットによって接続されるように設けられているという具体的構成態様における差\n異点は,いずれも本件意匠の要部にかかわるものであり,とりわけ後者のスリット を設けられている点は,本件意匠に類似する要素はなく,シートをボウルに取り付 ける際に,シートをボウルの湾曲形状に密着させるための微調整を容易にさせる工 夫として取引者・需要者の注意を強く惹くものということができる。 そうすると,本件意匠が無模様であり原告意匠に模様が施されているという差異 点を捨象したとしても,両意匠を全体として観察した場合,看者に対して異なる美 感を起こさせるものと認められるから,原告意匠は本件意匠に類似していないとい うことができる。
(4) 利用関係について
被告は,原告意匠は本件意匠と利用関係にあり,原告商品の販売等は本件意匠権 を侵害するものと主張する。 しかし,上記(3)に説示したとおり,原告意匠は,要部に係る具体的構成態様にお\nいて本件意匠と大きく異なる構成となっており,それによって全体として本件意匠\nとは異なる美感を起こさせているものであるから,原告意匠が本件意匠に係る構成\n態様全てをその特徴を破壊することなく包含しているとは認められない。 したがって,原告意匠は本件意匠と利用関係にあるとして,利用による侵害をい う被告の主張は失当である。
・・・・
なお被告は,知 的財産権の権利行使の一環として行われた侵害警告を不正競争とすることが,知的 財産権の権利行使を委縮させかねない点も指摘するが,侵害警告の段階に留まるの であれば,これを知的財産権に基づく訴訟提起と同様に扱うことはできないし,ま た他方で,客観的には権利行使とはいえない侵害警告により営業上の信用を害され た競業者の事後的救済の観点も十分に考慮されるべきである。\nしたがって,被告の上記主張を採用することはできず,このような知的財産権の 権利行使の一環であったとの主観的事情を含む被告が違法性阻却事由として主張す る事実関係については,不正競争であることを肯定した上で,指摘に係る権利行使 を委縮させるおそれに留意しつつ,そもそもの知的財産権侵害事案における侵害判 断の困難性という点も考慮に入れて,同法4条所定の過失の判断に解消できる限度 で考慮されるべきである。
・・・・
(2) 知的財産権を有する者が,侵害行為を発見した場合に,その侵害行為の差止 を求めて侵害警告をすることは,基本的に正当な権利行使であり,その侵害者が侵 害品を製造者から仕入れて販売するだけの第2次侵害者の場合であっても同様であ る。しかし,侵害品を事業として自ら製造する第1次侵害者と異なり,これを仕入 れて販売するだけの第2次侵害者は,当該侵害品の販売を中止することによる事業 に及ぼす影響が大きくなければ,侵害警告を不当なものと考えても,紛争回避のた めに当該侵害品の仕入れをとりあえず中止する対応を採ることもあり,その場合, 侵害警告が誤りであっても,第1次侵害者に対する販売の差止めが実現されたと同 じ結果が生じてしまうから,こと第2次侵害者に対して侵害警告をする場合には, 権利侵害であると判断し,さらに侵害警告することについてより一層の慎重さが求 められるべきである。したがって,正当な権利行使の意図,目的であったとしても, 権利侵害であることについて,十分な調査検討を行うことなく権利侵害と判断して\n侵害警告に及んだ場合には,必要な注意義務を怠ったものとして過失があるといわ なければならない。 以上により本件についてみるに,本件通知書の記載内容(上記第2の1(4)イ)か らすると,被告は,コープPが本件意匠権の侵害者であるとしても,製造者ではな く仕入れて販売する第2次侵害者にすぎないことを認識していたと認められる。 しかし,本件告知行為に至る経緯をみると,被告は,原告商品を本件カタログで 発見するや実物を確認することなく本件意匠権の侵害品であると断定し,僅か2日 後には,第1次侵害者である製造者を探索しようともせずに,製造者の取引先とも なるコープPに対し,権利侵害であることを断定した上で侵害警告に及んだという のである。 すなわち,上記認定した本件告知行為に至る経緯において,被告が,警告内容が 誤りであった場合に,製造者に及ぼす影響について配慮した様子は全く見受けられ ず,不用意に本件告知行為に及んだものといわなければならない。 また,そもそも原告商品が本件意匠権の侵害品であるとの判断自体についてみて も,本件については,本件告知行為を受けたコープPの代理人弁理士が,当裁判所 と同様の判断内容で原告意匠と本件意匠が非類似である旨を短期間のうちに回答し ているように,両意匠が意匠法的観点からは類似していないというべきことは比較 的明らかなことといえるが(被告は,本件意匠の実施品が同種商品の存しない新種 のアイデア商品であり,先行意匠が存しないことから,意匠権で保護されるべき範 囲を過大に考えていたように思われる。),そうであるのに被告は,原告商品を発 見して極く短期間のうちに意匠権侵害であると断定して侵害警告に及んだというの であるから,この点でも,侵害判断が誤りであった場合に製造者である原告の営業 上の信用を害することになるおそれについて留意した様子が全くうかがえず,不用 意に本件告知行為に及んだものといえる。 以上のとおり,被告は原告商品の販売が本件意匠権の侵害であるとの事実を原告 の取引先であるコープPに対して警告するに当たり,原告商品の販売が本件意匠権 の侵害との判断が誤りであった場合,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告 知となって,製造者である原告の営業上の信用を害することになることなどを留意 することなく本件告知行為をしたものと推認すべきであり,意匠権の権利行使を目 的として上記行為に及んだことを考慮しても,以上の事実関係のもとでは,そのよ うな誤信がやむを得なかったとはいえないから,被告は,本件告知行為をするに当 たって必要な注意義務を尽くしたとはいえず過失があったというべきである。 したがって,被告は,本件告知行為により原告が受けた損害を賠償する責任があ る。
2017.06.23
平成28(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月14日 知的財産高等裁判所
ア 本件審決は,「保護方法データベース」に記憶された「入力元のアプ リケーション」が保護対象データである「ファイル」を処理するのは自明 であり,機密事項を保護対象データとして扱うことは当該技術分野の技術 常識であることから,引用発明の「入力元のアプリケーション」,「識別 子」はそれぞれ,本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」,「機 密識別子」に相当し,また,引用発明の「保護方法データベース」に「入 力元のアプリケーション」の「識別子」が記憶されていることは明らかで あるから,引用発明の「保護方法データベース」は本願発明の「機密事項 を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記 憶部」に相当する旨認定・判断した。 イ(ア) しかし,前記認定に係る本願明細書及び引用例1の記載によれば, 本願発明における「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーション を識別する」ものとして定義されている(本願明細書【0006】等) のに対し,引用発明におけるアプリケーションの「識別子」は,アプリ ケーションを特定する要素(アプリケーション名,プロセス名等)とし て位置付けられるものであって(引用例1【0037】等),必ずしも 直接的ないし一次的に機密事項を扱うアプリケーションを識別するもの とはされていない。
(イ) また,本願発明は,「すべてのアプリケーションに関して同じ保護 を行うと,安全性は高くなるが,利便性が低下するという問題が生じ る」(本願明細書【0004】)という課題を解決するために,「当 該アプリケーションが,前記機密識別子記憶部で記憶されている機密 識別子で識別されるアプリケーションであり,送信先がローカル以外 である場合に」「送信を阻止」するという構成を採用したものである。\nこのような構成を採用することによって,「機密事項を含むファイル\n等が送信によって漏洩することを防止することができ」,かつ,「機 密識別子で識別されるアプリケーション以外のアプリケーションにつ いては,自由に送信をすることができ,ユーザの利便性も確保するこ とができる」という効果が奏せられ(本願明細書【0007】),前 記課題が解決され得る。このことに鑑みると,本願発明の根幹をなす 技術的思想は,アプリケーションが機密事項を扱うか否かによって送 信の可否を異にすることにあるといってよい。 他方,引用発明において,アプリケーションは,機密事項を扱うか否 かによって区別されていない。すなわち,そもそも,引用例1には機密 事項の保護という観点からの記載が存在しない。また,引用発明は,柔 軟なデータ保護をその解決すべき課題とするところ(【0008】), 保護対象とされるデータの保護されるべき理由は機密性のほかにも考え 得る。このため,機密事項を保護対象データとして取り扱うことは技術 常識であったとしても,引用発明における保護対象データが必ず機密事 項であるとは限らない。しかも,引用発明は,入力元のアプリケーショ ンと出力先の記憶領域とにそれぞれ安全性を設定し,それらの安全性を 比較してファイルに保護を施すか否かの判断を行うものである。このた め,同じファイルであっても,入力元と出力先との安全性に応じて,保 護される場合と保護されない場合とがあり得る。 これらの点に鑑みると,引用発明の技術的思想は,入力元のアプリケ ーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ設定された安全性を比較する ことにより,ファイルを保護対象とすべきか否かの判断を相対的かつ柔 軟に行うことにあると思われる。かつ,ここで,「入力元のアプリケー ションの識別子」は,それ自体として直接的ないし一次的に「機密事項 を扱うアプリケーション」を識別する作用ないし機能は有しておらず,\n上記のようにファイルの保護方法を求める上で比較のため必要となる 「入力元のアプリケーション」の安全性の程度(例えば,その程度を示 す数値)を得る前提として,入力元のアプリケーションを識別するもの として作用ないし機能するものと理解される。\nそうすると,本願発明と引用発明とは,その技術的思想を異にするも のというべきであり,また,本願発明の「機密識別子」は「機密事項を 扱うアプリケーションを識別する」ものであるのに対し,引用発明の 「アプリケーションの識別子」は必ずしも機密事項を扱うアプリケーシ ョンを識別するものではなく,ファイルの保護方法を求める上で必要と なる安全性の程度(例えば,数値)を得る前提として,入力元のアプリ ケーションを識別するものであり,両者はその作用ないし機能を異にす\nるものと理解するのが適当である。
(ウ) このように,本願発明の「機密識別子」と引用発明の「識別子」が 相違するものであるならば,それぞれを記憶した本願発明の「機密識 別子記憶部」と引用発明の「保護方法データベース」も相違すること になる。
ウ 以上より,この点に関する本件審決の前記認定・判断は,上記各相違点 を看過したものというべきであり,誤りがある。
エ これに対し,被告は,相違点AないしBの看過を争うとともに,仮に相 違点Bが存在するとしても,その点については,本件審決の相違点1に 関する判断において事実上判断されている旨主張する。 このうち,相違点AないしBの看過については,上記ア及びイのとお りである。 また,本件審決の判断は,1)引用例2に記載されるように,ファイル を含むパケットについて,内部ネットワークから外部ネットワークへの 持ち出しを判断し,送信先に応じて許可/不許可を判定すること,すな わち,内部ネットワーク(ローカル)以外への送信の安全性が低いとし てセキュリティ対策を施すことは,本願出願前には当該技術分野の周知 の事項であったこと,2)参考文献に記載されるように,機密ファイルを あるアプリケーションプログラムが開いた後は,電子メール等によって 当該アプリケーションプログラムにより当該ファイルが機密情報保存用 フォルダ(ローカル)以外に出力されることがないようにすることも, 本願出願前には当該技術分野の周知技術であったことをそれぞれ踏まえ て行われたものである。 しかし,1)に関しては,本件審決の引用する引用例2には,送信の許 可/禁止の判定は送信元及び送信先の各IPアドレスに基づいて行われ ることが記載されており(【0030】),アプリケーションの識別子 に関する記載は見当たらない。また,前記のとおり,引用発明における 識別子は,アプリケーションが機密事項を扱うものか否かを識別する作 用ないし機能を有するものではない。\n2)に関しては,参考文献記載の技術は,機密情報保存用フォルダ内の ファイルが当該フォルダの外部に移動されることを禁止するものである ところ(【0011】),その実施の形態として,機密情報保存用フォ ルダ(機密フォルダ15A)の設定につき,「システム管理者は,各ユ ーザが使用するコンピュータ10内の補助記憶装置15内に特定の機密 ファイルを保存するための機密フォルダ15Aを設定し,ユーザが業務 で使用する複数の機密ファイルを機密フォルダ15A内に保存する。」 (同【0018】)との記載はあるものの,起動されたアプリケーショ ンプログラムが機密事項を扱うものであるか否かという点に直接的に着 目し,これを識別する標識として本願発明の機密識別子に相当するもの を用いることをうかがわせる記載は見当たらない(本件審決は,参考文 献の記載(【0008】,【0009】,【0064】)に言及するも のの,そこでの着目点は機密ファイルをあるアプリケーションプログラ ムが開いた後の取扱いであって,その前段階として機密ファイルを定め る要素ないし方法に言及するものではない。)。このように,当該周知 技術においては,アプリケーションが機密事項を扱うものであるか否か を識別する機密識別子に相当するものが用いられているとはいえない。 なお,参考文献の記載(【0032】等)によれば,アプリケーショ ンプログラムのハンドル名がアプリケーションの識別子として作用する ことがうかがわれるが,参考文献記載の技術は,アプリケーションが実 際に機密ファイルをオープンしたか否かによって当該アプリケーション によるファイルの外部への格納の可否が判断されるものであり,入力元 と出力先との安全性の比較により処理の可否を判断する引用発明とは処 理の可否の判断の原理を異にする。また,扱うファイルそのものの機密 性に着目して機密ファイルを外部に出すことを阻止することを目的とす る点で,扱うファイルそのものの機密性には着目していない引用発明と は目的をも異にする。このため,引用発明に対し参考文献記載の技術を 適用することには,動機付けが存在しないというべきである。 そうすると,相違点Bにつき,引用発明に,引用例2に記載の上記周 知の事項を適用しても,本願発明の「機密識別子」には容易に想到し得 ないというべきであるし,参考文献記載の周知技術はそもそも引用発明 に適用し得ないものであり,また,仮に適用し得たとしても,本願発明 の「機密識別子」に想到し得るものではない。そうである以上,相違点 Bにつき,本件審決における相違点1の判断において事実上判断されて いるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 引用文献
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.06.22
平成18(ワ)16899 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成20年7月4日 東京地方裁判所
被告は,原告博士絵柄は(被告博士絵柄とともに),博士をイメージした 人物としての一般的要素を取り入れ,顔の表情や色調に工夫を加えて作成さ\nれているものの,著作物としての創作性が認められないありふれた表現であ\nる旨主張する。 そこで,この点についてみるに,証拠(乙1〜8)及び弁論の全趣旨によ れば,原告博士絵柄及び被告博士絵柄以外の博士をイメージした人物として, 法務省の商業登記Q&Aに用いられている博士(乙第1号証),中央出版株 式会社のさんすうおまかせビデオに用いられている博士(乙第2号証),独 立行政法人水資源機構のホームページに用いられているものしり博士(乙第\n3号証),株式会社新学社の社会科資料集6年に用いられている歴史博士 (乙第4号証),証券クエストのホームページに用いられている博士(乙第 5号証),DEX WEBのイラスト・クリップアートに表示されている3\nDCGの博士(乙第6号証),株式会社パルスのおもしろ実験室のパッケー ジに用いられている博士(乙第7号証,ただし,乙第6号証の博士と同一の もの)及び株式会社UYEKIの防虫ダニ用スプレーの宣伝に用いられてい る博士(乙第8号証)の絵柄があること,これらの絵柄の共通の要素として, 角帽を被り,丸い鼻から髭を生やし,比較的ふくよかな体型の年配の男性で あることなどを挙げることができること,が認められる。しかしながら,こ れらの博士のそれぞれの絵柄を見れば,共通の要素としての角帽,鼻,髭, 体型等の描き方にしても様々であり,まして,色づかいやタッチなどの全体 の印象を含めれば,博士をイメージさせる要素が類似するとしても,これら の博士の絵柄相互間において,表現物としての共通性があって,いずれもが\nありふれていると言い切ることはできないものというべきである。そして, 原告博士絵柄については,上記の各博士のそれぞれの絵柄と対比して,なお 博士絵柄の表現としてありふれているとまでは言えないものと認められる。
(3)したがって,原告博士絵柄は,全体としてみたとき,前記(1)のような 特徴を備えた博士の絵柄の一つの表現であって,そこに作成者の個性の反映\nされた創作性があるというべきであり,原告商品の一部を構成する原告博士\n絵柄の登場する画像の著作物として,創作的な表現とみることができるもの\nと認められる。
・・・・
原告博士絵柄と被告博士絵柄とを対比すると,原告博士絵柄と被告博士絵 柄とは,前記(1)アのとおりの共通点があり,また,同ウの由来を考慮す れば,元来,被告博士絵柄は,原告博士絵柄に似せて製作されたものという ことができるものの,同イの相違点に照らすと,絵柄として酷似していると は,言い難いものと認められる。
そして,原告博士絵柄のような博士の絵柄については,前記1(2)の乙 第1ないし第8号証でみた博士の絵柄のように,角帽やガウンをまとい髭な どを生やしたふっくらとした年配の男性とするという点はアイデアにすぎず, 前記(1)アの原告博士絵柄と被告博士絵柄との共通点として挙げられてい るその余の具体的表現(ほぼ2頭身で,頭部を含む上半身が強調されて,下\n半身がガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること,顔のつくりが下 ぶくれの台形状であって,両頬が丸く,中央部に鼻が位置し,そこからカイ ゼル髭が伸びていること,目が鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であ って,その両目の真上に眉があり,首と耳は描かれず,左右の側頭部にふく らんだ髪が生えていること)は,きわめてありふれたもので表現上の創作性\nがあるということはできず,両者は表現でないアイデアあるいは表\現上の創 作性が認められない部分において同一性を有するにすぎない。また,被告博 士絵柄全体をみても,前記(1)イの相違点に照らすと,これに接する者が 原告博士絵柄を表現する固有の本質的特徴を看取することはできないものと\nいうべきである(なお,原告商品に登場する原告博士絵柄と被告各商品に登 場する被告博士絵柄は,ともにそれぞれの商品の一部を構成する画像として\n存在するところ,動きのある映像として見たとき,原告博士絵柄と被告博士 絵柄との違いは明白である。)。 したがって,被告各商品の一部を構成する被告博士絵柄の登場する画像が\n原告商品の一部を構成する原告博士絵柄の登場する画像の複製権や翻案権を\n侵害していると認めることはできない
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> ピックアップ対象
2017.06.17
平成28(ワ)7185 意匠権侵害差止請求事件 意匠権 民事訴訟 平成29年5月18日 大阪地方裁判所
ア 以上を踏まえて検討すると,上記のとおり,本件意匠と被告意匠は,基本的 構成態様が共通しているところ,土入れ部背面部自体は要部ではないが,植木鉢の背面上方に円形孔部が形成された枠体部は本件意匠の要部であることからすれば,\n円形孔部が形成された枠体部が植木鉢背部の内側に侵入して形成された枠体部を有 する本件意匠と被告意匠とは,一定の美感の共通性が生じているといえる。 しかし,本件意匠の要部である枠体部の具体的形状において,両意匠は多くの点 で異なっている。すなわち,本件意匠と被告意匠は,内側枠体部,外側枠体部があ る点については共通するものの,本件意匠においては内側枠体部も外側枠体部も円 形孔部の円弧に沿うようにほぼ円形であるのに対し,被告意匠は,平面視において, 内側枠体部は略台形状で直線的な形状であり,外側枠体部についてもなだらかな山 状の形で,その稜線部分が直線状であることから,その印象は異なっている。また, 本件意匠においては,内側枠体部の上面が外側枠体部の上面に比して低い段差状に 形成されているのに対し,被告意匠においては,内側枠体部の上面が外側枠体部の 上面より高く,しかも,両者の間に中央枠体部が構成され,中央枠体部の上面が内側枠体部の上面から外側枠体部の上面を連結する外側に凸の円弧状に形成されてい\nることから,両者の枠体部の上面の凹凸は異なっており,上から見た印象を異なる ものとしている。
イ 以上の点をふまえ,本件意匠と被告意匠を全体としてみると,両意匠はいず れも植木鉢背面内側に入り込む給水ボトル挿入用の円形孔部を形成する枠体部が存 在することによって一定の印象の共通性は生じるものの,その枠体部の構成,枠体部を構\成する各部の高さやその形状が異なることにより,本件意匠は,枠体部が円形孔部に沿ってほぼ円形で,背部から見た場合,奥まった内側枠体部が手前に見え る外側枠体部の上面より低い形状になっていたとしてもさほどの段差感を受けるこ とがないから,全体的に丸くシンプルな印象を受けるのに対し,被告意匠は,内側 枠体部が略台形,外側枠体部が山形といった直線的な形状をしており,さらに,外 側枠体部が内側枠体部の上面より低くなっていることから,内側枠体部の形状がよ り看取しやすく,また,枠体部の上部において内側,中央,外側部分が凸凹になっ ていることとも相まって,直線的でごつごつした印象を受けるものであるから,そ れぞれの意匠を全体として観察したときに,本件意匠と被告意匠とが類似の美感を 生じるとまでは認められず,両意匠が類似しているということはできない。
◆判決本文
本件意匠・被告意匠などはこちらです。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 部分意匠
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成28(行ケ)10147 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月8日 知的財産高等裁判所
前記(3)で検討したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,濃 厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された, 新規なトマト含有飲料及びその製造方法,並びに,トマト含有飲料の酸味抑制方法 を提供するための手段として,本件発明1,8及び11に記載された糖度,糖酸比 及びグルタミン酸等含有量の数値範囲,すなわち,糖度について「9.4〜10. 0」,糖酸比について「19.0〜30.0」,及びグルタミン酸等含有量について 「0.36〜0.42重量%」とすることを採用したことが記載されている。 そして,本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体例というべき実施例1 〜3,比較例1及び2並びに参考例1〜10(【0088】〜【0090】,【表1】)には,各実施例,比較例及び参考例のトマト含有飲料のpH,Brix,酸度,糖\n酸比,酸度/総アミノ酸,粘度,総アミノ酸量,グルタミン酸量,アスパラギン酸 量,及びクエン酸量という成分及び物性の全て又は一部を測定したこと,及び該ト マト含有飲料の「甘み」,「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をしたことが 記載されている。
(イ) 一般に,飲食品の風味には,甘味,酸味以外に,塩味,苦味,うま 味,辛味,渋味,こく,香り等,様々な要素が関与し,粘性(粘度)などの物理的 な感覚も風味に影響を及ぼすといえる(甲3,4,62)から,飲食品の風味は, 飲食品中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左 右されることが本件出願日当時の技術常識であるといえる。また,トマト含有飲料 中には,様々な成分が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるとい える(甲25の193頁の表−5−196参照)から,本件明細書の発明の詳細な\n説明に記載された風味の評価試験で測定された成分及び物性以外の成分及び物性も, 本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常という ことができる。したがって,「甘み」,「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験を するに当たり,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて,これら三つ の要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては,少なくとも,1)「甘み」, 「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが,これら三つの要素のみ である場合や,影響を与える要素はあるが,その条件をそろえる必要がない場合に は,そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をする か,2)「甘み」,「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与える要素は上記三 つ以外にも存在し,その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には,当該他 の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするとい う方法がとられるべきである。 前記(3)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,糖度及び糖酸比を規定す ることにより,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みを有しつつも,トマト の酸味が抑制されたものになるが,この効果が奏される作用機構の詳細は未だ明ら\nかではなく,グルタミン酸等含有量を規定することにより,トマト含有飲料の旨味 (コク)を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて,トマト本来の甘味が より一層際立つ傾向となることが記載されているものの,「甘み」,「酸味」及び「濃 厚」の風味に見るべき影響を与えるのが,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量 のみであることは記載されていない。また,実施例に対して,比較例及び参考例が, 糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものと して記載されておらず,それらの各種成分や各種物性が,「甘み」,「酸味」及び「濃 厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや,影響を与えるがその条件 をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない。そうすると,濃厚な味 わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味 を得るために,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り, 他の成分及び物性の特定は要しないことを,当業者が理解できるとはいえず,本件 明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から,直ちに,糖度, 糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と,得られる効果という べき,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制 されたという風味との関係の技術的な意味を,当業者が理解できるとはいえない。
(ウ) また,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験の 方法は,前記(3)のとおりであるところ,評価の基準となる0点である「感じない又 はどちらでもない」については,基準となるトマトジュースを示すことによって揃 えるとしても,「甘み」,「酸味」又は「濃厚」という風味を1点上げるにはどの程度 その風味が強くなればよいのかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたこ とや,各パネラーの個別の評点が記載されていない。したがって,少しの風味変化 で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや,大きな風味変化でも加点又は減 点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず,各飲料の風味の\n評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したも のととらえることも困難である。また,「甘み」,「酸味」及び「濃厚」は異なる風味 であるから,各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの 評価基準が示される必要があるものと考えられるところ,そのような手順が踏まれ たことも記載されていない。そうすると,「甘み」,「酸味」及び「濃厚」の各風味が 本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて,各風味について の全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する,前記(3)の風味を評 価する際の方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。 以上述べたところからすると,この風味の評価試験からでは,実施例1〜3のト マト含有飲料が,実際に,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつ トマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはい えない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成28(行ケ)10037 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月14日 知的財産高等裁判所
1 本件審決の判断構造と原告の主張の理解
本件審決が認定した本件発明と引用発明(甲1発明)は,いずれも多数の選 択肢から成る化合物に係る発明であるところ,本件審決は,両発明の間に一応 の相違点を認めながら,いずれの相違点も実質的な相違点ではないとして,本 件発明と甲1発明が実質的に同一であると認定判断し,その結果,本件発明に は新規性が認められないとの結論を採用した。 その理由とするところは,本件発明1に関していえば,相違点に係る構成は\nいずれも単なる選択を行ったにすぎず,相違点に係る化合物の選択使用に格別 の技術的意義が存するものとはいえない(相違点1ないし3),あるいは,引 用発明(甲1発明A)が相違点に係る構成態様を包含していることは明らかで\nあり,かつ,その構成態様を選択した点に格別な技術的意義が存するものとは\n認められない(相違点4)というものであり,本件発明1を引用する本件発明 2ないし14,本件発明14を引用する本件発明15ないし17についても, それぞれ,引用発明(甲1発明A又はB)との間に新たな相違点が認められな いか,新たな相違点が認められるとしても,各相違点に係る構成が甲1に記載\nされているか,その構成に格別な技術的意義が存するものとは認められないか\nら,いずれも実質的な相違点であるとはいえないというものである。 要するに,本件審決は,引用発明である甲1発明と本件発明との間に包含関 係(甲1発明を本件発明の上位概念として位置付けるもの)を認めた上,甲1 発明において相違点に係る構成を選択したことに格別の技術的意義が存するか\nどうかを問題にしており,その結果,本件発明が甲1発明と実質的に同一であ るとして新規性を認めなかったのであるから,本件審決がいわゆる選択発明の 判断枠組みに従って本件発明の特許性(新規性)の判断を行っていることは明 らかである。 これに対し,原告は,取消事由として,引用発明認定の誤り(取消事由A) や一致点認定の誤り(取消事由1)を主張するものの,本件審決が認定した各 相違点(相違点1ないし4)それ自体は争わずに,本件審決には,「特許発明 と刊行物に記載された発明との相違点に選択による格別な技術的意義がなけれ ば,当該相違点は実質的な相違点ではない」との前提自体に誤りがあり(取消 事由2),また,仮にその前提に従ったとしても,相違点1ないし4には格別 な技術的意義が認められるから,特許性の有無に関する相違点の評価を誤った 違法があると主張している(取消事由3)。 これによれば,原告は,本件審決が採用した特許性に関する前記の判断枠組 みとその結論の妥当性を争っていることが明らかであり,取消事由2及び3も そのような趣旨の主張として理解することができる。 また,本件発明2ないし17はいずれも本件発明1を更に限定したものと認 められるから,本件発明1の特許性について判断の誤りがあれば,本件発明2 ないし17についても同様に,結論に重大な影響を及ぼす判断の誤りがあると いえる。 以上の観点から,まず,本件発明1に関し,本件審決が認定した各相違点(相 違点1ないし4)を前提に,各相違点が実質的な相違点ではないとして特許性 を否定した本件審決の判断の当否について検討することとする。
・・・・
本件訂正後の特許請求の範囲の記載(前記第2の2)及び本件明細書の記 載(前記(1))によれば,本件発明は,次の特徴を有すると認められる。
・・・
(1) 特許に係る発明が,先行の公知文献に記載された発明にその下位概念とし て包含されるときは,当該発明は,先行の公知となった文献に具体的に開示 されておらず,かつ,先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特 有の効果,すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果 とは異質の効果,又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合 を除き,特許性を有しないものと解するのが相当である 。 ここで,本件発明1が甲1発明Aの下位概念として包含される関係にある ことは前記3のとおりであるから,本件発明1は,甲1に具体的に開示され ておらず,かつ,甲1に記載された発明すなわち甲1発明Aと比較して顕著 な特有の効果を奏する場合を除き,特許性を有しないというべきである。 そして,甲1に本件発明1に該当する態様が具体的に開示されているとま では認められない(被告もこの点は特に争うものではない。)から,本件発 明1に特許性が認められるのは,甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果を 奏する場合(本件審決がいう「格別な技術的意義」が存するものと認められ る場合)に限られるというべきである。
(2) この点に関し,本件審決は次のとおり判断した。
・・・・
エ 以上によれば,本件審決は, (1) 甲1発明Aの「第三成分」として,甲1の「式(3−3−1)」及び 「式(3−4−1)」で表される重合性化合物を選択すること,\n(2) 甲1発明Aの「第一成分」として,甲1の「式(1−3−1)」及び「式 (1−6−1)」で表される化合物を選択すること,\n(3) 甲1発明Aの「第二成分」として,甲1の「式(2−1−1)」で表さ\nれる化合物を選択すること, (4) 甲1発明Aにおいて,「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」 態様を選択すること, の各技術的意義について,上記(1)の選択と,同(2)及び(3)の選択と,同(4)の 選択とをそれぞれ別個に検討した上,それぞれについて,格別な技術的意 義が存するものとは認められないとして,相違点1ないし4を実質的な相 違点であるとはいえないと判断し,本件発明1の特許性(新規性)を否定 したものといえる。
(3) 本件審決の判断の妥当性
本件発明1は,甲1発明Aにおいて,3種類の化合物に係る前記(1)ないし (3)の選択及び「塩素原子で置換された液晶化合物」の有無に係る前記(4)の選 択がなされたものというべきであるところ,証拠(甲42)及び弁論の全趣 旨によれば,液晶組成物について,いくつかの分子を混ぜ合わせること(ブ レンド技術)により,1種類の分子では出せないような特性を生み出すこと ができることは,本件優先日の時点で当業者の技術常識であったと認められ るから,前記(1)ないし(4)の選択についても,選択された化合物を混合するこ とが予定されている以上,本件発明の目的との関係において,相互に関連す\nるものと認めるのが相当である。 そして,本件発明1は,これらの選択を併せて行うこと,すなわち,これ らの選択を組み合わせることによって,広い温度範囲において析出すること なく,高速応答に対応した低い粘度であり,焼き付き等の表示不良を生じな\nい重合性化合物含有液晶組成物を提供するという本件発明の課題を解決する ものであり,正にこの点において技術的意義があるとするものであるから, 本件発明1の特許性を判断するに当たっても,本件発明1の技術的意義,す なわち,甲1発明Aにおいて,前記(1)ないし(4)の選択を併せて行った際に奏 される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があるとい うべきである。 ところが,本件審決は,前記のとおり,前記(1)の選択と,同(2)及び(3)の選 択と,同(4)の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり,これらの選 択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このよ うな個別的な検討を行うのみでは,本件発明1の技術的意義を正しく検討し たとはいえず,かかる検討結果に基づいて本件発明1の特許性を判断するこ とはできないというべきである。 以上のとおり,本件審決は,必要な検討を欠いたまま本件発明1の特許性 を否定しているものであるから,上記の個別的検討の当否について判断する までもなく,審理不尽の誹りを免れないのであって,本件発明1の特許性の 判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものという べきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 本件発明
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成28(行ケ)10205 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月14日 知的財産高等裁判所
明細書の発明の詳細な説明の記載は,当業者がその実施をすることができる程度 に明確かつ十分に記載したものであることを要する(特許法36条4項1号)。本件\n発明は,「加工飲食品」という物の発明であるところ,物の発明における発明の「実 施」とは,その物の生産,使用等をする行為をいうから(特許法2条3項1号),物 の発明について実施をすることができるとは,その物を生産することができ,かつ, その物を使用することができることであると解される。 したがって,本件において,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及 び出願当時の技術常識に基づいて,本件発明に係る加工飲食品を生産し,使用する ことができるのであれば,特許法36条4項1号に規定する要件を満たすというこ とができるところ,本件発明に係る加工飲食品は,不溶性固形分の割合が本件条件 (6.5メッシュの篩を通過し,かつ16メッシュの篩を通過しない前記不溶性固 形分の割合が10重量%以上であり,16メッシュの篩を通過し,かつ35メッシ ュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が5重量%以上25重量%以下である) を満たす加工飲食品であるから,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び出願当時の技術常識に基づいて,このような加工飲食品を生産することができ るか否かが問題となる。
前記認定のとおり,本件明細書には,不溶性固形分の割合が本件条件を満たすか どうかを判断する際の測定について,「日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきた け瓶詰の固形分の測定方法に準じて,サンプル100グラムを水200グラムで希 釈し,16メッシュの篩等の各メッシュサイズの篩に均等に広げて,10分間放置 後の各篩上の残分重量」を測定すること(段落【0036】。以下「本件測定方法」 ということがある。)が記載されている。さらに,「篩上の残存物は,基本的には不 溶性固形分であるが,サンプルを上述のように水で3倍希釈してもなお粘度を有し ている場合は,たとえメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に 残存する場合があり,その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不 溶性固形分を正しく測定する必要がある。」(段落【0038】)とも記載されている。
本件明細書の上記記載によれば,本件明細書には,測定対象のサンプルが水で3 倍希釈しても「なお粘度を有している場合」であって,メッシュ目開きよりも細か い不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合には,適宜,水洗することに よって塊をほぐし,メッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分の重量,すな わち「日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準 じて,サンプル100グラムを水200グラムで希釈し,各メッシュサイズの篩に 均等に広げて,10分間放置後の篩上の残分重量」(段落【0036】)に相当する 重量を正しく測定する必要があることが開示されているものと解される。 そして,本件明細書の「より一層,粗ごしした野菜感,果実感,または濃厚な食 感を呈する。」(段落【0009】),「加工飲食品は,ペースト状の食品,又は飲料の形態を有する。」(段落【0030】)との記載によれば,本件発明に係る加工飲食品 は一定程度の粘度を有するものと認められるから,段落【0036】に記載された 本件測定方法によると,実際に,各篩のメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分 により形成される塊が篩上に残存する場合も想定されるところである。 しかしながら,メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残 存している場合に追加的に水洗をすると(段落【0038】),本件明細書の段落【0 036】に記載された本件測定方法(測定対象サンプル100グラムを水200グ ラムで希釈し,各メッシュサイズの篩に均等に広げて,10分間放置するという測 定手順のもの)とは全く異なる手順が追加されることになるのであるから,このよ うな水洗を追加的に行った場合の測定結果は,本件測定方法による測定結果と有意 に異なるものになることは容易に推認される。このように,本件明細書に記載され た各測定方法によって測定結果が異なることなどに照らすと,少なくとも,水洗を 要する「なお粘度を有する場合」であって,「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固 形分が篩上に塊となって残存している場合」であるか否か,すなわち,仮に,篩上 に何らかの固形分が残存する場合に,その固形物にメッシュ目開きよりも細かい不 溶性固形分が含まれているのか,メッシュ目開きよりも大きな不溶性固形分である のかについて,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて判別 することができる必要があるといえる(本件条件を満たす本件発明に係る加工飲食 品を生産することができるといえるためには,各篩のメッシュ目開きよりも細かい 不溶性固形分により形成される塊が篩上に残存する場合であるか否かを判別するこ とができることを要する。)。 しかしながら,本件測定方法によって不溶性固形分を測定した際に,篩上に残存 しているものについて,メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が含まれている のか否かを判別する方法は,本件明細書には開示されておらず,また,当業者であ っても,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に照らし,特定の方法 によって判別することが理解できるともいえない(篩上に残存しているものが,メ ッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分を含むものであるのか否かについて,一般 的な判別方法があるわけではなく,証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば,測定 に使用される篩は,目開きが16メッシュ(1.00mm)又は35メッシュ(0. 425mm)のものと認められるから,篩上に残った微小な不溶性固形分について, 単に目視しただけでは明らかではないといわざるを得ない。)。 そうすると,当業者であっても,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術 常識に基づいて,その後の水洗の要否を判断することができないことになる。 したがって,本件発明の態様として想定される,「測定したいサンプル100グラ ムを水200グラムで希釈」しても「なお粘度を有している場合」(段落【0038】)も含めて,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の出願時 の技術常識に基づいて,本件条件を満たす本件発明に係る加工飲食品を生産するこ とができると認めることはできない。 以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明を当業者が実施でき るように明確かつ十分に記載されているものと認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成29(ネ)10005 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年6月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件各発明は,メラミン系樹脂発泡体からなる清掃具における「折り畳み可能な\n清掃具の変形能や,清掃対象面の形態に応じて変形可能\な清掃具の柔軟性等」が乏 しいという課題(【0006】)を解決することを目的とするものであり,その効 果は,「捩じり又は絞ったり,或いは,手指の動きに応じて多様な清掃対象物の汚 れを拭き取るといった布雑巾的な用法で使用可能な」ものを提供する(【0011】)\nというものであることからも,本件各発明における圧縮・加熱の工程を経たメラミ ン系樹脂発泡体が,加熱前のメラミン系樹脂発泡体「よりも柔軟な」ものになった ということは,圧縮・加熱前よりも,容易に折り畳みが可能で,清掃対象面の形態\nに応じて変形することができるようになったことを意味するということができる。 よって,本件各発明における「柔軟な」とは,容易に折り畳んだり,変形させた りできることを意味するものと認めることが相当である。
・・・
圧縮前後のメラミン系樹脂発泡体のサンプル平均を比較すると,甲45試験では, 圧縮前後の荷重の差は2.3Nであり,圧縮後のメラミン系樹脂発泡体の方が圧縮 前のものよりも,約5分の1の力で10mmたわんだとの結果になっている。しか しながら,乙11試験では,メラミン系樹脂発泡体の10mmたわみ時の荷重の圧 縮前後の差は0.06Nで,圧縮後の方がより弱い力でたわんだとの結果になって いるものの,約15%弱い力にすぎず,乙34試験では,その差は0.03Nとさ らに小さく,圧縮後の方が約5%弱い力でたわんだとの結果にとどまる。甲45試 験と,乙11試験,乙34試験の試験結果は,同一の試験機関によるものであると ころ,各試験で用いられた試料の圧縮の程度に差があることを考慮したとしても, 大きく異なるといわざるを得ないが,甲45,乙11,乙34の各報告書中には, これら試験結果に大きな差が生じ得たと考えられるような条件の記載はない。 圧縮後のメラミン系樹脂発泡体における10mmたわみ時荷重の平均値は,甲4 5試験において0.60N,乙11試験において0.41N,乙34試験において 0.62Nで,特に,甲45試験と乙34試験の数値は極めて近い。ところが,圧 縮前のものについての同数値は,乙11試験では0.47N,乙34試験では0. 65Nなのに対し,甲45試験では,2.90Nとされており,乙11,乙34の 各試験結果とは2.0N以上,約4倍の差となっているのであって,圧縮の条件等 による差が考えられない圧縮前の数値についてのみ,このような顕著な差があるこ とについて,合理的に理解することは困難といわざるを得ない。乙34報告書によ れば,厚さ40mmのメラミン系樹脂発泡体を10mmに圧縮したものについての 10mmたわみ時荷重は平均2.8N(サンプル数5)で,甲45試験と極めて近 接した数値となっていることも勘案すると,甲45試験の結果をもって,圧縮後の 方が「柔軟」になったと認定することはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成28(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月12日 知的財産高等裁判所(3部)
以上のとおり,本件審決には,本件特許発明1と甲1発明の相違点3の一 内容として相違点3−1を認定した点に誤りがあるものといえる。 しかしながら,後記4で述べるとおり,本件審決認定の相違点3のうち, 相違点3-1以外の部分に係る本件特許発明1の構成についての容易想到性\nは否定されるべきであり,そうすると,本件審決の相違点3−1に係る認定 の誤りは,本件特許発明1の進歩性欠如を否定した本件審決の結論に影響を 及ぼすものではない。
・・・・
原告は,相違点3に係る本件特許発明1の構成のうち,「第1(あるいは\n第2)の係止片が枠体の後端より後ろ向きに突設し枠体の上辺(あるいは 下辺)よりも内側に設けられ」るとの構成についての容易想到性を否定し\nた本件審決の判断は誤りである旨主張する。しかるところ,上記構成のう\nち,「係止片が枠体の後端より後ろ向きに突設」する構成が本件特許発明1\nと甲1発明の相違点といえないことは,上記3(2)で述べたとおりであるか ら,以下では,上記構成のうち,「第1(あるいは第2)の係止片が枠体の\n上辺(あるいは下辺)よりも内側に設けられ」るとの構成(以下「相違点\n3−2に係る構成」という。)についての容易想到性を否定した本件審決の\n判断の適否について検討することとする。 ア 原告は,部材を取り付けるための係止片を当該部材の最外周面よりも 少し内側に設ける構成は,甲1(図39(a)及び図49),16,17及 び63に記載され,審判検甲1及び2が現に有するとおり,スロットマ シンの技術分野において周知な構成であるとした上で,甲1発明に上記\n周知な構成を適用し,相違点3−2に係る構\成とすることは,当業者が 容易に想到し得たことである旨主張するので,以下検討する。 (ア) 甲1の図39(a)及び図49について
甲1の図39(a)(別紙2参照)は,スロットマシンの飾り枠本体に 取り付けられる第4ランプカバーの斜視図であるところ,同図に示さ れた第4ランプカバー423は,側方形状L字状に形成され,その一 辺の両サイドから後方に係止爪424が突設されている(甲1の段落 【0158】)。また,甲1の図49(別紙2参照)は,スロットマシ ンのメダル受皿の分解斜視図であるところ,同図に示されたメダル受 皿12の両サイドには,係止爪620が後方に向かって突設されてい る(甲1の段落【0205】)。 しかしながら,上記係止爪424と第4ランプカバー423の最外周 面との位置関係及び上記係止爪620とメダル受皿12の最外周面との 位置関係については,甲1には記載されておらず,何らの示唆もされて いない。 この点,原告は,これらの図面において,係止片に相当する部分とそ の取付け端の境界に実線が記載されていることから,当業者は,係止片 が部材の最外周面よりも少し内側に設けられていると理解する旨主張す る。しかし,甲1の上記図面は,特許出願の願書に添付された図面であ り,明細書を補完し,特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業 者に理解させるための説明図であるから,当該発明の技術内容を理解す るために必要な程度の正確さを備えていれば足り,設計図面に要求され るような正確性をもって描かれているとは限らない。そして,甲1は, 遊技部品を収容する収容箱と収容箱に固定される連結部材を介して収容 箱の前面に開閉自在に設けられる前面扉とから構成されるスロットマシ\nンについての発明を開示するものであり(段落【0001】),特に,連 結部材を前面扉に取り付ける取付部に載置部及び被載置部を形成するこ とによって前面扉を連結部材に組付ける際の作業性を向上させたスロッ トマシンに係る発明を開示するものであるから(段落【0002】〜 【0008】),甲1の図面において,上記取付部に関係しない部材であ る第4ランプカバー423の係止爪424やメダル受皿12の係止爪6 20の詳細な構造についてまで正確に図示されているものと断ずること\nはできない。してみると,甲1の明細書中に何らの記載がないにもかか わらず,上記図面中の実線の記載のみから,係止片が部材の最外周面よ りも少し内側に設けられている構成の存在を読み取ることはできないと\nいうべきであり,原告の上記主張は採用できない。 したがって,甲1の図39(a)及び図49には,そもそも,部材を取 り付けるための係止片を当該部材の最外周面よりも少し内側に設ける構\n成が記載されているとはいえない。
・・・
以上によれば,原告が,「部材を取り付けるための係止片を当該部材 の最外周面よりも少し内側に設ける構成」が記載されているものとして\n挙げる文献のうち,甲1及び63については,そもそもそのような構成\nが記載されているとはいえない(なお,仮に,原告主張のとおり,甲1 及び63に上記構成が記載されていることを認めたとしても,これらの\n文献には,甲16及び17と同様に当該構成が採用される理由について\nの記載や示唆はないから,後記の結論に変わりはない。)。 他方,甲16及び17には,上記構成が記載され,また,審判検甲1\n及び2のパチスロ機も上記構成を有することが認められる。しかしなが\nら,これらの文献の記載や本件審判における審判検甲1及び2の検証の 結果によっても,これらの装置等において上記構成が採用されている理\n由は明らかではなく,結局のところ,当該構成の目的,これを採用する\nことで解決される技術的課題及びこれが奏する作用効果など,当該構成\nに係る技術的意義は不明であるというほかはない。 してみると,甲16及び17の記載や審判検甲1及び2の存在から, 上記構成がスロットマシンの分野において周知な構\成であるとはいえる としても,その技術的意義が不明である以上,当業者がこのような構成\nをあえて甲1発明に設けようと試みる理由はないのであって,甲1発明 に当該周知な構成を適用すべき動機付けの存在を認めることはできない。\nしたがって,甲1発明に上記周知な構成を適用し,相違点3−2に係\nる構成とすることは,当業者が容易に想到し得たこととはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成29(行ケ)10033 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年6月8日 知的財産高等裁判所
前記1(5)のとおり,本件商品1〜3は,革製のケースであって,スイスアーミー ナイフに適合するものとして販売されているものの,その形状は略直方体であって スイスアーミーナイフ以外の物を収納することも可能であること,その販売形態は,\n収納物を伴うことなく本件商品1〜3のみで購入することが可能であること,スイ\nスアーミーナイフには,刃物であるナイフ等以外に,栓抜きやつまようじなど,他 の物も組み込まれていることからすると,第18類「small persona l leather goods」(革製の小さな身の回りの物)に該当するという ことができる。
・・・・
(2) 被告は,ビクトリノックス日本支社が使用していた標章には,いずれも「W ENGER」の文字の右上にRマークが付されているから,同標章は図形単体では なく,図形と文字を組み合わせた一体の標章として使用していたものであり,本件 商標と社会的同一性はない,と主張する。 しかし,前記1(2)(5)のとおり,本件商標と「WENGER」の欧文字とは左右 に配されており分離可能であること,ビクトリノックス日本支社のウェブサイトに\n表示されたものは,本件商標が赤で「WENGER」の欧文字は黒であることから\nすると,本件商標と「WENGER」の欧文字とは分離して観察することができる。 また,Rマークについても,登録商標を示すものとして分離して観察する ことができる。これらのことからすると,本件商標と社会通念上同一の商標が使用 されていたと認めることができる。したがって,被告の主張は,採用することがで きない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成28(行ケ)10154 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所
(1) 特許法126条1項2号は,「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には, 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが, ここで「誤記」というためには,訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいこと が,当該明細書,特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者(その発明の属す る技術の分野における通常の知識を有する者)の技術常識などから明らかで,当業 者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合 でなければならないものと解される。
(2)ア そこで,まず,本件明細書に接した当業者が,明細書の記載は原則とし て正しい記載であることを前提として,本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの 誤記があることに気付くかどうかを検討する。 (ア) 本件明細書の【0034】の【化14】には,以下に示す化合物(3) から,「EAC」が添加された反応条件下で,以下に示す化合物(4)を得る工程【化 14】が示されており(下図は,【化14】の記載を簡略化し,反応により構造が変\n化した部分に丸印を付したもの。),本件明細書の【0034】の[合成例4]の本 文には,化合物(3)に「EAC(酢酸エチル,804ml,7.28mol)」を 添加し,反応させて,化合物(4)を得たと記載されているから,明細書は原則と して正しい記載であることを前提として読む当業者は,本件明細書には,化合物(3) に酢酸エチルを作用させて化合物(4)を得たことが記載されていると理解する。
(イ) しかし,当業者であれば,以下に示す理由で,「化合物(3)に酢酸エ チルを作用させて化合物(4)を得た」とする記載内容にもかかわらず,化合物(3) に以下に示す酢酸エチルを作用させても化合物(4)が得られない,つまり,【化1 4】に係る原料(出発物質;化合物(3))と,反応剤(EAC)と,生成物(化合 物(4))のいずれかに誤記が存在することに気付くものと考えられる。 すなわち,本件明細書の【0034】の【化14】に接した当業者は,(1)ヒドロ キシ基を有する不斉炭素(20位の炭素原子)の立体化学が維持されていることか ら,【化14】の反応は,酸素原子が反応剤の炭素原子を求核攻撃することによる, 20位の炭素原子に結合した−OH基の酸素原子と反応剤の炭素原子との反応であ ること(20位の炭素原子と酸素原子間のC−O結合が切れる反応が起こるのでは なく,アルコール性水酸基の酸素原子と水素原子の間のO−H結合が切れることに よって不斉炭素の立体構造が維持されることになる反応であること。甲2,23〜\n25),(2)上記−OH基の酸素原子が酢酸エチルの炭素原子を求核攻撃しても,化合 物(4)の側鎖である,−OCH2CH2COOC2H5の構造とはならないこと(炭\n素数が1つ足りないこと)に気付き,これらを考え合わせると,【0034】の「化 合物(3)に酢酸エチルを作用させて化合物(4)を得た」という反応には矛盾が あることに気付くものということができる。 (ウ) したがって,本件明細書に接した当業者は,【0034】の【化14】 (化合物(3)から化合物(4)を製造する工程)において,側鎖を構成する炭素\n原子数の不整合によって,【0034】に何らかの誤記があることに気付くものと認 められる。
・・・・
前記3の取消事由1で判断したとおり,本件明細書に接した当業者であれば,本 件訂正事項に係る【0034】の「EAC(酢酸エチル,804ml,7.28m ol)」という記載が誤りであり,これを「EAC(アクリル酸エチル,804ml, 7.28mol)」の趣旨に理解するのが当然であるということができるから,本件 訂正後の記載である「アクリル酸エチル」は,本件訂正前の当初明細書等の記載か ら自明な事項として定まるものであるということができ,本件訂正によって新たな 技術的事項が導入されたとは認められない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2017.06.16
平成28(行ケ)10239 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所
意匠法2条2項は,「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にす\nるために行われるものに限る。)の用に供される画像であって,当該物品又はこれと 一体として用いられる物品に表示されるもの」は,同条1項の「物品の部分の形状,\n模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれ,意匠法上の意匠に当たる旨を規定 する。同条2項は,平成18年法律第55号による意匠法の改正(以下「平成18 年改正」という。)によって設けられたものである。 ところで,平成18年改正前から,家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボ タン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え,この画面上に表示された図形等\nからなる,いわゆる「画面デザイン」を利用して操作をする機器が増加してきてい た。このような画面デザインは,機器の使用状態を考慮して使いやすさ,分かりや すさ,美しさ等の工夫がされ,家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要 素となってきており,企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大してい る状況にあった。 しかしながら,平成18年改正前においては,特許庁の運用として,意匠法2条 1項に規定されている物品について,画面デザインの一部のみしか保護対象としな い解釈が行われ,液晶時計の時計表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立\nたない画面デザインや,携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠 な画面デザインについては,その機器の意匠の構成要素として意匠法によって保護\nされるとの解釈が行われていたが,それら以外の画面デザインや,機器からの信号 や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについ\nては,意匠法では保護されないとの解釈が行われていた(意匠登録出願の願書及び 図面の記載に関するガイドライン−基本編−液晶表示等に関するガイドライン[部\n分意匠対応版])。 そこで,画面デザインを意匠権により保護できるようにするために,平成18年 改正により,意匠法2条2項が設けられた。 このような立法経緯を踏まえて解釈すると,同項の「物品の操作…の用に供され る画像」とは,家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品 に代わって,画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができる\nものを指すというべきであるから,特段の事情がない限り,物品の操作に使用され る図形等が選択又は指定可能に表\示されるものをいうものと解される。 これを本願部分についてみると,本願部分の画像は,別紙第1のとおりのもので あって,「意匠に係る物品の説明」欄の記載(補正後のもの,別紙第1)を併せて考 慮すると,画像の変化により運転者の操作が促され,運転者の操作により更なる画 像の変化が引き起こされるというものであると認められ,本願部分の画像は,自動 車の開錠から発進前(又は後退前)までの自動車の各作動状態を表示することによ\nり,運転者に対してエンジンキー,シフトレバー,ブレーキペダル,アクセルペダ ル等の物理的な部品による操作を促すものにすぎず,運転者は,本願部分の画像に 表示された図形等を選択又は指定することにより,物品(映像装置付き自動車)の\n操作をするものではないというべきである(甲1,5)。 そうすると,本願部分の画像は,物品の操作に使用される図形等が選択又は指定 可能に表\示されるものということはできない。また,本願部分の画像について,特 段の事情も認められない。 したがって,本願部分の画像は,意匠法2条2項所定の「物品の操作…の用に供 される画像」には当たらないから,本願意匠は,意匠法3条1項柱書所定の「工業 上利用することができる意匠」に当たらない。
2 原告は,平成18年改正により意匠法2条2項が設けられた趣旨は,形態が, 物品と一体として用いられる範囲において,「物品の操作…の用に供される画像」に 関するデザインを広く保護しようとすることにあり,それ以上に保護対象を限定す る意図は読み取れず,本願部分の画像は,「映像装置付き自動車」という物品におけ る「走る」という機能を発揮できる状態にするための,シフトレバー等の操作の用\nに供されるものということができるから,同項の要件に適合すると主張する。 しかしながら,同項が設けられた趣旨,これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は,前記1のとおりであり,これによると,本願部分の 画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも,前記1のとおり である。原告は,本願意匠に係る物品の「操作」は,「機械など」に相当するシフト レバーをあやつって働かせることであり,「一定の作用効果や結果」に相当する「走 る」機能を得るために,「物品の内部機構\等」に相当するトランスミッション等に指 示を与えるものであると主張するが,ここでいう「映像装置付き自動車」という「物 品の操作」とは,「走る」という機能を発揮できる状態にするための「一定の作用効\n果や結果」を得るために「物品の内部機構等」であるトランスミッション等に対し\n指示を与えることをいうのであるから,シフトレバー等は,あやつって働かせる対 象である「機械など」に相当するものではなく,「物品の操作の用に供される」もの であって,このシフトレバー等「の操作の用に供される画像」であるか否かを検討 しても,意匠法2条2項所定の画像であることが認められるものではない。
2017.06.16
平成28(ネ)10083 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年5月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1) 相違点の認定について
被控訴人らは,乙1公報には「治療用マーカー」について何らの記載も示唆もな いから,本件発明が「治療用マーカー」であるのに対し,乙1発明は「治療用マー カー」ではない点も相違点として認定すべきである,と主張する。 しかし,前記1(2)ウのとおり,乙1発明は,皮膚用の入れ墨転写シールを含めた 各種用途の転写シールである。乙1公報には,乙1発明の転写シールが治療用マー カーに用いられることは明示されていないものの,皮膚用の入れ墨転写シールの用 途については限定を設けていないから,乙1発明が治療用マーカーではないとはい えない。本件発明と乙1発明との相違点4として,「本件発明が治療用マーカーであ るのに対し,乙1発明では皮膚用の入れ墨転写シールを含めた各種用途の転写シー ルである点」と認定するのが相当である。
(2) 相違点1,2及び4の判断について
被控訴人らは,乙9発明の「台紙」は「基材」と訳されるべきものであり,患者 の皮膚に接触したままにされるから,治療用の目印となるインク層を皮膚に接着さ せた後すぐに皮膚から剥がされることになる本件発明の「基台紙」とは,構造を全\nく異にし,乙1発明に乙9発明を組み合わせたとしても,本件発明との相違点4に 係る構成に想到するのは容易ではなく,また,乙9発明には「基台紙」がないから,\n乙1発明に乙9発明を組み合わせても,インク層と同一のマークを基台紙に印刷す ることを容易に想到できない,と主張する。 しかし,前記1(4)イ,ウのとおり,乙9発明の装置は,被控訴人ら主張のとおり, 「台紙」を患者の皮膚に接触したままにしておく使用方法もあるが,「台紙」が剥が れた場合のことをも想定しており,「台紙」が剥がれた場合には,「台紙」は,本件 発明において同じく皮膚から剥がされる「基台紙」と同様の機能を有するというこ\nとができる。したがって,乙9発明の「substrate」を「台紙」と訳すこ とは誤りとはいえず,また,本件発明との相違点1,2及び4についての容易想到 性についての被控訴人らの上記主張を採用することはできない。 (3) 相違点3の判断について
ア 被控訴人らは,乙1発明は,「水転写タイプ」を含む従来の入れ墨転写シ ールの課題を解決するために,「粘着転写タイプ」のシールを記載したものであって, 「水転写タイプ」を動機付けるものではなく,むしろ「水転写タイプ」を不具合あ るものとして排除している,と主張する。 しかし,乙1文献に明示的に記載されている実施例は「粘着転写タイプ」である ものの,「粘着転写タイプ」と「水転写タイプ」との違いは,セパレーターを取り除 いた後に,転写シールの粘着層をそのまま皮膚に貼り付けるか,転写シールを水で\n湿してから皮膚に押さえ付けるかの点にある(乙3)にすぎないから,乙1文献記 載の従来技術の問題点である「絵柄がひび割れる,剥離が困難」といった点は,水 転写タイプに特有のものとは認められない。また,乙1発明が課題解決の方法とし て採用した特性を持つ透明弾性層が,転写シールの粘着層を皮膚に貼り付ける前に\n水で湿すことによってその効果を発揮しないとか,その他乙1発明を水転写タイプ とすることが技術的に困難である事情は認められない。したがって,乙1発明が水 転写タイプを排除しているとはいえず,被控訴人らの上記主張を採用することはで きない。
イ 被控訴人らは,乙9発明は「基材」そのものが治療用の目印として皮膚 に転写されるから,水転写タイプを想起させるものではない,と主張する。 しかし,前記(2)のとおり,乙9発明の装置は,「台紙」が剥がれた場合のことを 想定しており,「台紙」が剥がれる場合には,「台紙」の皮膚に接着する側に配置さ れた第1インク層が皮膚に転写され,「台紙」は治療用の目印ではなくなり,インク 層のみが皮膚に転写されることとなるところ,水転写タイプもこのような構成を採\n用するものである(乙3)から,被控訴人らの主張を採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2017.06.12
平成28(ワ)12608 損害賠償請求事件,著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟平成29年2月28日 東京地方裁判所
著作権法は思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(著\n作権法2条1項1号),複製に該当するためには,既存の著作物とこれに依 拠して作成された対象物件の共通する部分が著作権法によって保護される 思想又は感情の創作的な表現に当たることが必要というべきであり,被告\nアンケート1又は2が原告追加部分に依拠して作成されたものであるとし ても,思想,感情若しくはアイディア,事実,学術的知見など表現それ自\n体でない部分や,表現上の創作性がない部分において原告追加部分の表\現 と共通するにすぎない場合には,複製に当たらないと解するのが相当であ る。
(2) 原告追加部分は,本件被告ファイルに対し,(1)「ご希望時間」欄を新設 して同欄内に午前10時から午後5時30分までの30分刻みの表示をし,\n(2)「住所・TEL」欄を「住所」欄と「電話番号」欄に分け,住所欄に「〒」 の表示をし,(3)「事故発生状況」欄の空白部分の代わりに「□その他」を 新設し,(4)「あなた」欄の「□自動車運転」「□自動車同乗」を併せて「□ 自動車(□運転,□同乗)」とするとともに,「□バイク運転」「□バイク同 乗」を併せて「□バイク(□運転,□同乗)」とし,(5)「初診治療先」「治 療先 2」「治療先 3」欄をそれぞれ「治療先 1/通院回数」「治療先 2/通院回 数」「治療先 3/通院回数」とした上で,それぞれの欄内に「病院名: /通 院回数: 回」の表示をし,(6)「自賠責後遺障害等級」「簡単な事故状況図 をお書きください。」「受傷部位に印をつけてください。」の各欄を設けた上, 「受傷部位に印をつけてください。」欄に人体の正面視図及び後面視図を設 け,(7)相談者の「保険会社・共済名」欄内のチェックボックス及び選択肢 を削除し,「加害者の保険」「保険会社名」の各欄を「加害者の保険会社名」 欄にするとともに同欄内のチェックボックス及び選択肢を削除したもので ある。これに対し,被告アンケート1及び2は,いずれも上記(6)の人体の 正面視図及び後面視図が原告追加部分とやや異なるが,その他の点は上記 (1)から(7)の点において原告追加部分と同一の記載がされている。
(3) そこで検討するに,まず,原告追加部分と被告アンケート1及び2に共 通する上記(1)の点については,相談希望者から必要な情報を聴取するとい うファイルの目的上,相談の希望時間を聴取することは一般的に行われる ことで,そのために「ご希望時間」欄を設けて欄内に一定の時間を30分 ごとに区切った時刻を掲記することは一般的にみられるありふれた表現で\nあるから,著作者の思想又は感情が創作的に表現されているということは\nできない。 また,原告追加部分と被告アンケート1及び2に共通する上記(2)〜(5)及 び(7)の点は,いずれも,本件被告ファイルの質問事項欄を前提にそれを統 合又は分割し,あるいは,各質問事項欄内の選択肢やチェックボックスを 相談者が記載しやすいように追加又は変更したものであり,いずれもアイ ディアに属する事柄にすぎないから、著作権法上の保護の対象となるもの とはいえない。 次に,原告追加部分と被告アンケート1及び2に共通する上記(6)の点(な お,原告追加部分と本件各アンケートでは,正面視及び後面視の各人体図 の具体的なデザインが異なる。)については,相談希望者から必要な情報を 聴取するという本件原告ファイルの目的に照らせば,事故状況や被害状況 を聴取するために,自賠責後遺障害等級を質問事項に設け,事故状況図や 受傷部位を質問事項に入れること,受傷部位を聴取するために,正面視及 び後面視の各人体図を設けて印を付けるよう求めたことは,いずれもアイ ディアにとどまり,あるいは一般的に見られるありふれた表現形式であっ\nて,著作者の思想又は感情が創作的に表現されていると見ることはできな\nい。
以上によれば,原告追加部分と被告アンケート1及び2の共通する部分 は,いずれも著作権法によって保護される思想又は感情の創作的な表現に\nは当たらないから,被告アンケート1及び2は原告追加部分の複製には該 当しないというべきである。 なお,原告は,被告において原告追加部分に著作物性があることを認め ているから,この点について裁判上の自白が成立し,裁判所を拘束するな どとも主張するが,本件全記録によっても被告が原告追加部分の著作物性 を自認したものとは認めることができないから,原告の上記主張は失当と いうほかない。
2017.06. 9
平成28(行ケ)10089 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年5月15日 知的財産高等裁判所
複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構\成部分が それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的 に結合しているものと認められる場合には,その構成部分の一部を抽出し,\nこの部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは, 原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商\n品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ 13 る場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じない と認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較\nして商標そのものの類否を判断することも許されるものと解される(最一小 判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9 月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民22 8号561頁参照)。
(2) これを本件についてみるに,本件商標は,「FINESSENCE」とい うアルファベット10文字を横文字にして成る文字部分(本件文字部分)と, アヤメの花のような図が白抜きされた円形の図形(本件図形)を,上下二段 に組み合わせて構成されるものであるところ,その構\成態様からして,各構\n成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分 的に結合しているものとは認められない。また,上記のとおり,本件文字部 分はアルファベット10文字を横書きにして成るのに対し,本件図形部分の 横幅は本件文字の3文字分(左から2文字目ないし4文字目)程度しかなく, その大きさの比からして,本件文字部分が本件商標の中心的構成部分に当た\nることは明らかである。加えて,原告も認めるとおり,本件文字部分は,そ れ自体造語であって一般的な用語ではないから,出所識別標識として強く支 配的な印象を与える部分であると認められる。 そうすると,本件商標のうち本件文字部分を要部として抽出し,同部分の みを引用商標と比較して商標の類否を判断することは許されるというべきで あり,この点において,本件審決の認定に誤りがあるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2017.06. 9
平成28(行ケ)10151 特許権 行政訴訟 平成29年5月31日 知的財産高等裁判所(3部)
本件審決は,刊行物1発明と刊行物2発明が多接点端子を有する電気コネ クタとしての構造を共通にすることから,刊行物1発明に刊行物2発明を適\n用する動機付けがあることを認めた上で,刊行物1発明の側方突出部26, 28に刊行物2発明を適用して,「第一接触部及び第二接触部それぞれの斜 縁の直線部分との接触を通じて相手端子に嵌合側から順次弾性接触するよう になっており,第一弾性腕の第一接触部は,該第一弾性腕の嵌合側端部から 嵌合側と反対側へ延びて相手端子との接触側に向かう斜縁を有し且つ該斜縁 よりも嵌合側と反対側に位置する下縁に凹部が形成され」るようにすること は当業者が容易になし得たことである旨判断し,この判断を前提として,刊 行物1発明と刊行物2発明,周知の技術事項(電気コネクタの技術分野にお いて有効嵌合長を長くすること)及び周知技術(相手コネクタと接触する接 点から接触部の突出基部に向けた直線と,斜縁を通る直線とでなす角度を鋭 角とすること)に基づいて相違点2に係る本件訂正発明の構成とすることは,\n当業者が容易に想到し得たことである旨判断する。 しかしながら,以下に述べるとおり,刊行物1発明に刊行物2記載のコネ クタの弾性舌部に係る構成を適用したとしても,第一弾性腕の第一接触部の\n斜縁よりも嵌合側と反対側に位置する下縁に凹部が形成される構成とするこ\nとを当業者が容易に想到し得たものということはできない。 すなわち,まず,刊行物2記載のコネクタの第一弾性舌部と第二弾性舌部 にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部は,「それぞれの斜縁 の直線部分との接触を通じてプリント回路基板23の電気コンタクトに嵌合 側から順次弾性接触するようになっており,第一弾性舌部と第二弾性舌部 は,プリント回路基板23の電気コンタクトとの接触位置を通り嵌合方向に 延びる接触線に対して一方の側に位置しており,第一弾性舌部の第一接触部 は,該第一弾性舌部の嵌合側端部から嵌合側と反対側へ延びてプリント回路 基板23の電気コンタクトとの接触側に向かう斜縁を有し且つ該斜縁よりも 嵌合側と反対側に位置する下縁を有して」いるものの,当該下縁には「凹 部」が形成されていないから(図9及び18参照),刊行物1発明の側方突 出部26の構成を,刊行物2記載のコネクタの第一接触部に係る構\成に単に 置き換えたとしても,その下縁に「凹部」が形成される構成とならないこと\nは明らかである。
そこで,刊行物1発明の側方突出部26に刊行物2記載のコネクタの第一 接触部に係る構成を適用することによりその下縁に「凹部」を形成する構\成 とするためには,刊行物1発明の側方突出部26の構成のうち,「下縁に凹\n部が形成され」た構成のみを残した上で,それ以外の構\成を刊行物2記載の コネクタの第一接触部に係る構成と置き換えることが必要となる(本件審決\nも,このような置換えを前提として,その容易性を認めたものと理解され る。)。しかしながら,刊行物1発明の側方突出部26に刊行物2記載のコ ネクタの第一接触部に係る構成を適用するに際し,上記側方突出部26が備\nえる一体的構成の一部である下縁の「凹部」の構\成のみを分離し,これを残 すこととすべき合理的な理由は認められない。そもそも,刊行物1発明の側 方突出部26の下縁に凹部が形成されている理由については,刊行物1に何 ら記載されておらず,技術常識等に照らして明らかなことともいえないか ら,当該構成の技術的意義との関係でこれを残すべき理由があると認められ\nるものではない。したがって,当業者が,刊行物1発明の側方突出部26に 刊行物2記載のコネクタの第一接触部に係る構成を適用するに当たり,刊行\n物1発明の側方突出部26における下縁の「凹部」の構成のみをあえて残そ\nうとすることは,考え難いことというほかない。 してみると,刊行物1発明に刊行物2記載のコネクタの第一接触部に係る 構成を適用したとしても,相違点2に係る本件訂正発明の構\成のうち,第一 接触部の斜縁よりも嵌合側と反対側に位置する下縁に凹部が形成される構成\nとすることを当業者が容易に想到し得たとはいえないから,相違点2に係る 本件審決の上記判断は誤りである。 なお,被告は,刊行物1発明に刊行物2発明を適用すべき動機付けが存在 することについて前記第4の2のとおり主張するが,上記で述べたとおり, 当該動機付けの存在を前提に,刊行物1発明に刊行物2記載のコネクタの第 一接触部に係る構成を適用したとしても,相違点2に係る本件訂正発明の構\ 成とすることを当業者が容易に想到し得たとはいえないのであるから,被告 の主張は,上記判断を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2017.06. 9
平成29(行ケ)10103 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月6日 知的財産高等裁判所(4部)
1 本件記録によれば,本件審決の謄本が原告に送達された日は,平成29年4月 3日であり,原告が本件審決取消訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し,これが当裁 判所に到達した日は,同年5月9日であることが明らかである。
2 審決取消しの訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は 提起することができない(特許法178条3項)ところ,上記1認定の事実によれば, 本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された平成29年4月3日から既に30日 を経過した同年5月9日(上記期間の満了日は同月8日)に提起されたものと認めら れるから,出訴期間を経過して提起されたものといわざるを得ない。
3 以上によれば,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができない ものであるから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,却下するこ ととし,主文のとおり判決する。
2017.06. 9
平成28(行ケ)10120 審決取消請求事件 特許権 平成29年5月17日 知的財産高等裁判所
そして,以上のような甲2の記載に接した当業者であれば,次のよう な技術的事項を当然に理解するものといえる。
a 均圧線の技術的意義
まず,甲2には,+電位に接続される2個のブラシ及び−電位に接続 される2個のブラシを備える4極重巻モータにおいて,同電位となる べき整流子間を均圧線で接続することによって循環電流の発生を防止 し,それによってブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決する技術が, 従来から知られた技術として記載されている(以下,当該技術を「甲2 従来技術」という。)。加えて,電気機器分野に係る教科書と解される 甲11(昭和42年発行の「電気機器各論I(直流機)」)にも,4極 重巻の直流機において,循環電流を防止して整流を容易にするために 均圧結線を用いて巻線中常に等電位である点を導体で接続すること, このような均圧結線は重巻には欠くことのできない重要な結線である こと,均圧結線の好ましい取付け場所は整流子側であることが記載さ れており(87頁19行〜88頁8行),これからすると,甲2従来技 術は,本件原出願前からの電気機器分野における技術常識として当業 者に理解されていたものと認められる(なお,本件の審判手続では,原 告(請求人)による甲11の追加提出が許可されなかった経過がある (甲28の9)。しかし,本件訴訟において,本件審判手続で審理判断 された甲1発明と甲2記載の事項に基づく進歩性欠如の有無について 判断するに当たり,上記甲11に基づいて,判断に必要となる技術常識 を認定することが許されることは明らかである。)。
b ブラシ数削減の原理
甲2記載の発明は,甲2従来技術に係る4極重巻モータ(以下「従来 モータ」という。)において,ブラシの数が4個と多いことに起因して, ロストルク,ブラシ音及びトルクリップルが大きくなるという問題点 があることに鑑み,+側及び−側のブラシをそれぞれ1個のブラシ(合 計2個のブラシ)とすることによって前記問題点を解決したものであ る。
他方,甲2には,上記のようにブラシを減らすことができる原理を説 明する明示的な記載はない。しかし,甲2の段落【0033】における 「従来の電動モータ1では,第1のブラシ11a及び第3のブラシ1 1cを介して電流が流れるが,この実施の形態では第1のブラシ89 aを介して電流が流れ,ブラシ89aを通じて流れる電流量が従来の ものと比較して2倍となる。」との記載からすれば,甲2記載の発明に おいてブラシを減らすことができるのは,均圧線を設けたことの結果 として,1個のブラシから供給された電流が,そのブラシに当接する整 流子片に供給されるとともに,均圧線を通じて同電位となるべき整流 子片にも供給されることによって,対となる他方のブラシがなくとも 従来モータと同様の電流供給が実現できるためであることが理解でき る(この点,被告は,甲2には,均圧線の使用とブラシ数の削減とを結 び付ける記載がないことを理由に,「均圧線を使用してブラシの数を減 らす」技術が記載されているとはいえない旨主張するが,そのような明 示的な記載がなくとも,甲2の記載から上記のとおりの理解は可能と\nいうべきであるから,被告の上記主張には理由がない。)。 してみると,甲2の記載に接した当業者は,甲2には,4極重巻モー タにおいて,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することによ り,同電位に接続されている2個のブラシを1個に削減し,もって,ブ ラシ数の多さから生じるロストルク,ブラシ音及びトルクリップルが 大きくなるという問題を解決する技術が開示されていることを理解す るものといえる。
イ 検討
以上を踏まえて,甲1発明及び甲2の開示事項に基づいて相違点3及び 4に係る本件発明1の構成とすることの容易想到性について検討する。\n(ア) 直流モータが回転力を維持し続けるには,整流子とブラシによって 得られる整流作用が不可欠であることは,直流モータの原理から自明の ことであるから,直流モータにおいて,ブラシ整流作用を良好に保つこと は,当然に達成しなければならない課題である。したがって,当該課題 は,同じく直流モータである甲1発明においても,当然に内在する課題と いうことができる。 しかるところ,前記ア(ウ)aのとおり,+電位に接続される2個のブラ シ及び−電位に接続される2個のブラシを備える4極重巻モータにおい て,ブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決するために均圧線を設ける 甲2従来技術が技術常識であることからすれば,同じく同電位に接続さ れた2個のブラシを複数組備える4極重巻モータであり,ブラシの整流 作用を良好に保つという課題が内在する甲1発明においても,甲2従来 技術と同様の均圧線を設けることは,当業者が当然に想到し得ることと いえる。 なお,甲2の記載では,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続する ものとされ,本件発明1の均圧部材のように「等電位となるべきコイル間 を接続する」ことが明記されてはいない。しかし,整流子とコイルが接続 されている以上,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することは, 電気的にみて,「等電位となるべきコイル間を均圧線で接続する」ことに ほかならないものといえる。 以上によれば,甲1発明において相違点3に係る本件発明1の構成(コ\nイルのうち等電位となるべきコイル間を接続する均圧部材を備えるこ と)とすることは,甲1発明に甲2の開示事項(甲2従来技術)を適用す ることにより当業者が容易に想到し得たことと認められる。
・・・・
本件審決は,本件発明2について無効理由1の成否の判断を明示しておら ず,この点において判断の遺脱があるとも評価し得るところである。他方,本件発明2が本件発明1に係る請求項1を引用する請求項2に係る発明であり,本件発明1について無効理由1が成り立たない以上,本件発明2 についても当然に無効理由1が成り立たないといえる関係にあることからす ると,本件審決の上記判断には,本件発明1と同様の理由により本件発明2に ついても無効理由1が成り立たないとする趣旨の判断が含まれるものと善解 する余地もある。しかしながら,仮にそうであるとして,上記(4)のとおり, 本件発明1について無効理由1が成り立たないとした本件審決の判断が誤り である以上,本件発明2に係る本件審決の上記判断も誤りであることは明ら かである。したがって,いずれにしても,本件発明2についての無効理由1に係る本 件審決の判断には違法がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2017.06. 9
平成28(行ケ)10191 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年5月17日 知的財産高等裁判所
(1) 本件商標は,「音楽マンション」という文字から構成されているところ,音楽という文字とマンションという文字をそれぞれ分離してみれば,前者が「音によ\nる芸術」を意味し,後者が「中高層の集合住宅」を意味するところ,両者を一体と してみた場合には,その文字に即応して,音楽に何らかの関連を有する集合住宅と いう程度の極めて抽象的な観念が生じるものの,これには,音楽が聴取できる集合 住宅,音楽が演奏できる集合住宅,音楽家や音楽愛好家たちが居住する集合住宅な どの様々な意味合いが含まれるから,特定の観念を生じさせるものではない。そう すると,「音楽マンション」という文字は,原告が使用する「ミュージション」と同 様に,需要者はこれを造語として理解するというのが自然であり,本件商標の指定 役務において,特定の役務を示すものとは認められない。したがって,「音楽マンシ ョン」という文字は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識 することができないものとはいえない。 もっとも,原告は,「音楽マンション」という文字がマンションの一定の質,特徴 等を表す用語として使用されていると主張するため,「音楽マンション」という文字が使用されている実情等を踏まえ,以下検討する。
(2) 前記認定事実によれば,原告は,平成12年3月,「音楽マンション川越」, 「ミュージション川越」などと称して,遮音性に優れたマンションを建設し,同マ ンションは,同年10月13日,「川越の音楽マンション」としてグッドデザイン賞 を受賞したこと,上記マンションは,「新建築」という雑誌,日経産業新聞,日本経 済新聞において「川越の音楽マンション」,「ミュージション川越」として紹介され たこと,原告は,平成15年2月に「ミュージション志木」という名称で遮音性に 優れたマンション(以下,「上記マンション」と併せて単に「原告マンション」とい う。)を建設したこと,その後も,「Forbes」,「PIPERS」,「音響技術」,「DIME」,「Home Theater」という各雑誌,全国賃貸住宅新聞,原告代表者執筆に係る「満室賃貸革命」という書籍が,原告マンションを「音楽マンション」として紹介したこと,原告マンションを紹介する以外に,「音楽マンション」という文字を使用したものは,平成元年4月10日の朝日新聞夕刊(大阪)の見出し(「女子学生に音楽マンション」,\n「女子学生用の音楽マンション」としたもの),又は平成16年4月13日の住宅新 報のコラム欄の文章にとどまること,上記住宅新報のコラム欄には,マンションの コンセプト化が進んでいるという例示として「音楽マンション」という文字が使用 されたにとどまり,これを具体的に説明する文章がなく,上記「音楽マンション」 という文字が特定の意味で使用されたとはいえないこと,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,「音楽マンション」という文字が「音楽の演奏が可能なマンション」というマンションの特定の質を表\す意味で使用された事例は,平成元年4月10日の朝日新聞夕刊(大阪)の見出しに「女子学生に音楽マンション」,「女子学生用の音楽マンション」と使用された一例(甲1の1及び2)にとどまり,そのほかは,いずれも原告が建設した特定のマンションを示すもの,又は上記住宅新報において使用され,特定の質を意味するか不明なものにすぎず,「音楽マンション」という文字が,個別具体的なマンションの意味を超えて,マンションの一定の質,特徴等を表すものとして一般に使用されていたものとは認められない。かえって,原告自身も,前記第2の3によれば,平成14年8月30日,「音楽マ\nンション」につき商標登録出願をしたものの,平成15年5月6日付けで拒絶理由 通知を受けたことから(甲7の1),同年6月23日,意見書を提出しているところ, 同意見書において,「音楽」と「マンション」を並べても「音楽の演奏が可能なマンション」という意味合いが生ずることはなく,上記朝日新聞夕刊(大阪)に掲載さ\nれた「女子学生に音楽マンション」という見出しについても,「音楽」には防音,演 奏という意味を含まないため,上記見出しはどのようなマンションであるかを理解 することができず,「音楽マンション」という文字がマンションの品質に係る役務で あると認識されることはない旨主張していたことが認められる(甲7の4)。 そうすると,「音楽マンション」という文字は,これが使用されている実情等を踏 まえても,特定の観念を生じさせるものとは認められず,本件商標の指定役務にお いて,特定の役務を示すものとはいえないから,需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができないものとはいえない。 したがって,本件商標は,商標法3条1項6号に該当するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2017.06. 9
平成28(ネ)10076 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成29年5月17日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「(2)ア 前記事実関係によれば,被控訴人の代表取締役を務めるBは,昭和51\n年,極真会館に入門し,平成4年5月,極真会館浅草道場を開設してその支部長に 就任し,極真会館の許可を得て極真会館を示す被控訴人各標章を継続的に使用して いたのであり,Aが平成6年4月26日に死亡した後も,平成6年5月,その後継 者であると自称して極真会館の館長に就任し,同年10月3日,被控訴人を設立し, 被控訴人各標章の使用を継続したことが認められる。その後,極真会館は極真空手 を教授する複数の団体に分裂するに至ったものの,極真会館を示す被控訴人各標章 は,本件各商標の商標登録出願当時はもとより,Aの死亡後にあっては,極真会館 又はその活動を表すものとして広く一般に知られていたことが認められる。\n他方,控訴人Xは,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継した ものの,A死亡当時,極真会館の事業活動に全く関与せず,Aが後継者を公式に指 定せず又は極真会館において世襲制が採用されていなかったことからすると,極真 会館の事業を承継した者ではないことが認められる。 そうすると,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づ き,同年3月31日,Bらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該 建物を利用して極真空手に関する事業を行うようになったものの,控訴人らの活動 は,A死亡後に分裂して発生した極真会館の複数団体のうちの一つにとどまるもの と認められる。
これらの事情の下においては,本件各商標は,Bも相当な寄与をして形成された 極真会館という団体の著名性を無償で利用しているものに外ならないというべきで あり,客観的に公正な競業秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなってい ることに照らすと,控訴人らが,極真会館の許諾を得て被控訴人各標章を使用して 極真会館としての活動を継続する者に対して本件各商標権侵害を主張するのは,客 観的に公正な競業秩序を乱すものとして,権利の濫用であると認めるのが相当であ る(最高裁昭和60年(オ)第1576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集 44巻5号876頁参照)。 現に,Bは,平成6年ないし平成7年までの間,複数の極真関連標章について商 標登録出願をし,自己名義の商標登録を受けたものの,Aの生前に極真会館に属し ていた者らが,平成14年,Bを被告として,空手の教授等に際して極真関連標章 を使用することにつき,Bの商標権に基づく差止請求権が存在しないことの確認等 を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起し(同庁同年(ワ)第1018号),同裁判所は, 平成15年9月30日,極真関連標章はAの死亡後も極真会館を表すものとして需\n要者の間に広く知られており,極真会館内部の構成員に対する関係では,Bが極真\n関連標章の商標登録を取得して商標権者として行動できる正当な根拠はないなどと して,Bの上記商標権の行使が権利濫用であるとして上記不存在確認請求を認容し, その控訴審である大阪高等裁判所(同庁同年(ネ)第3283号)も,平成16年9 月29日,極真関連標章に関し自己名義で商標登録を受けたとしても,極真会館の 外部の者に対する関係ではともかく,極真関連標章の周知性・著名性の形成に共に 寄与してきた団体内部の者に対する関係では,少なくとも極真関連標章の使用に関 する従来の規制の範囲を超えて権限を行使することは不当であるというべきであり, Bによる上記商標登録に係る商標権の行使は権利の濫用に当たり許されないなどと して,Bの控訴を棄却している。上記の理は,本件についても当てはまるものとい える。
2017.06. 9
平成28(ワ)6268 商標権侵害差止請求事件 商標権 民事訴訟 平成29年5月11日 大阪地方裁判所
(ア) 被告標章4は,まず,被告の事務所の正面玄関口の看板として表示さ\nれているところ,通常,企業の事務所においては当該企業の商品又は役務に関する 需要者向けの業務が,あるいは,そのための広告宣伝がなされるのであり,現に「AD EBiS」と「EC-CUBE」の広告物が陳列されている。そうすると,被告の事務所の正面 玄関口における被告標章4の使用は,少なくとも「AD EBiS」と「EC-CUBE」につい ての使用であると認められる。 また,被告標章4は,セッションの壁面においても表示されているところ,そこ\nには同時に,「AD EBiS」及び「THREe」の広告の表示があるから,被告は,セッショ\nンにおいて,「AD EBiS」及び「THREe」について被告標章4を表示して使用している\nと認められる。(争点2) また,これらからすると,被告4サービス中の他のものについても被告標章4を 使用するおそれがあるというべきである。
(イ) そして,被告の商号の英訳は「LOCKON CO.,LTD.」であり(甲32の1 頁,乙2の1頁,乙8),「LOCKON」との被告標章4はその略称であるから,被告標 章4が「自己の名称」を表示するものとはいえない。なお,この略称が著名である\nことを認めるに足りる証拠はないから,被告標章4が「著名な略称」を普通に用い られる方法で表示する場合に当たるものともいえない。(争点3)\n
2017.06. 9
平成28(ワ)5249 商標権侵害差止請求事件 商標権 民事訴訟 平成29年5月11日 大阪地方裁判所
(1) 前記のとおり,被告のホームページにおいて,被告サービスは,「スマート フォン対応のケイータイサイト作成ASP」,「華やかなケータイサイトが専門知識 なしで簡単に作成できる」として総括的に紹介されており,被告サービスの17の 機能の多くはホームページの作成支援に関わる機能\であることからすると,被告サ ービスは,ホームページ作成支援を主たる機能とするものであると認められる。そ\nして,前記のとおり,被告サービスは,「ASP」とされ,ASPとは,ソフトウェ\nアをインターネットを介して利用させるサービスをいうこと(弁論の全趣旨)から すると,被告標章が使用されている被告サービスは,全体として,インターネット を介してスマートフォン等の携帯電話用のホームページの作成・運用を支援するた めのアプリケーションソフトの提供を行うものであり,第42類の「電子計算機用\nプログラムの提供」に該当すると認められ,本件商標の指定役務第35類の「広告」 には該当せず,また,これに類似する役務とも認められない。
(2) これに対し,原告は,被告サービスのうちのプッシュ通知機能及びメール\nマーケティング機能に着目し,これらの機能\のうち,メールサーバによる電子メー ルの配信を提供するインターネット役務部分は広告業に当たるから,広告及び操作 画面に被告標章を表示する行為が「広告業」について被告標章を使用するものであ\nる旨主張する。
しかし,まず,被告サービスの内容は上記のとおりであり,これらの機能は,被\n告サービスの機能として広告されてはいるものの,それぞれ,被告サービスに付随\nする17種類の機能のうちの1つにすぎず,価格面でもこれらの機能\の有無によっ て区分されておらず,これら機能が独立して提供されているわけではないから,被\n告標章がそれらの機能について独立して使用されていると認めることはできない。\nそして,前記のとおり,被告サービスは全体としてインターネットを介してスマー トフォン等の携帯電話用のホームページの作成・運用を支援するためのアプリケー ションソフトの提供を行うものであると認められ,被告標章はそのような被告サー\nビスの全体について使用されているのであるから,被告サービスのうちのプッシュ 通知機能及びメールマーケティング機能\のみに着目して,被告標章が「広告業」に 使用されているとする原告の上記主張は採用できない。 また,被告サービスのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能\が,メー ルサーバによる電子メールの配信を提供する要素を含んでおり,それが広告機能を\n営むものであるとしても,それは,被告サービスによって提供されるアプリケーシ ョンソフトを被告の顧客が使用することにより自動的に行われるものであるから,\n被告の提供する役務は,そのような配信機能を有するプログラムを提供するものと\nいうべきであり,被告自身が広告配信サービスを提供していると捉えることはでき ない。
2017.06. 2
平成25(ワ)10958 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年5月17日 東京地方裁判所(40部)
本件訂正発明1の1及び1の2の意義
上記各記載によれば,本件訂正発明1の1及び1の2は,基礎杭等の造 成にあたって地盤を掘削する掘削装置に関するものであって,この種の掘 削装置として一般に使用されるアースオーガ装置では,オーガマシンの駆 動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必要となるが,リーダの長 さが長くなると,施工現場内でのリーダの移動作業や,現場へのリーダの 搬入及び現場からの搬出作業に非常な手間と時間を要するという課題及び 傾斜地での地盤掘削にあっては,クローラクレーンの接地面とリーダの接 地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長くとれず,掘削深さが制限 されるという課題があることから,本件訂正発明1の1及び1の2は,こ れらの課題を解決するために,掘削装置について,掘削すべき地盤上の所 定箇所に水平に設置し,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが, 当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケ ーシング回り止め部材を備えるものとして,リーダではなく,ケーシング 回り止め部材によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明 である,と認められる。
・・・・
原告は,本件訂正発明1の1の実施による被告の利益を算定するに当 たっては,本件発訂正明1の1を実施した工程の代金のみならず,請負 代金額の全額を基礎とすべきと主張する。 しかし,本件訂正発明1の1は,掘削装置に関する発明であり,掘削 工事以外の工程には使用されない。そして,前記「内訳明細書」(乙1 05)によれば,被告は,現場(1)について,本件訂正発明1の1を実施 した掘削工事である「先行削孔砂置換工」のみを受注したものではなく, 「道路改良工事」を受注し,上記掘削工事の他,本件訂正発明1の1を 実施していない工事である「場所打杭工」,「鋼矢板工」及び「桟橋盛 替工」の各工事を行っており,これらの工事の代金(直接工事費)につ いては,本件訂正発明1の1を実施していないのであるから,本件訂正 発明1の1の実施があったためにその余の工事の受注ができたなどの特 段の事情がない限り,本件訂正発明1の1を実施したことにより被告が 受けた利益に当たるということはできない。そして,本件において,上 記事情を認めるに足りる証拠はない。
また,被告は,現場(1)の工事について,上記直接工事費のほかに,間 接工事費として「重機組解回送費」,「重機回送費」及び「経費」の支 払を受けているが,これらについても本件訂正発明1の1の実施により 受けた利益に当たると認めるべき証拠がない。 したがって,被告が,本件訂正発明1の1を実施したことにより受領 した額は,本件訂正発明1の1の実施による先行削孔砂置換工(DH削 孔費)の14本分の代金140万円である。
イ 利益率
被告の利益率が18%であることについて当事者間に争いがない。 したがって,本件訂正発明1の1を実施したことにより被告が得た利益 額は,25万2000円(=140万円×0.18)である。
ウ 寄与率
被告は,本件訂正発明1の1の売上に対する寄与率は低いなどと主張す るので検討するに,特許法102条2項は,損害が発生している場合でも, その損害額を立証することが極めて困難であることに鑑みて定められた推 定規定であるから,当該特許権の対象製品に占める技術的価値,市場にお ける競合品・代替品の存在,被疑侵害者の営業努力,被疑侵害品の付加的 性能の存在,特許権者の特許実施品と被疑侵害品との市場の非同一性など\nに関し,その推定を覆滅させる事由が立証された場合には,それらの事情 に応じた一定の割合(寄与率)を乗じて損害額を算定することができると いうべきである。
本件では,たしかに,前記アのとおり,現場(1)において,15本のうち 1本のケーシングについては,本件訂正発明1の1を実施しない形態(下 部/1本のH形鋼)が用いられていることが認められるものの,これは, 被告の主張によれば,山(崖)側に位置するケーシングでは,下部で井桁 状を組むことが困難であることから「下部/2本のH形鋼」ではなく「下 部/1本のH形鋼」の構成が用いられているというのであって,「下部2本のH形鋼」の構\成により,「下部/1本のH形鋼」の構\成と同等ない\nしより優れた効果が得られるためではない。また,上記イで算出した利益 の額は,本件訂正発明1の1の技術的範囲に属する被告装置1を用いて行 った工事である先行削孔砂置換工(DH削孔費)により被告が得た利益額 そのものであり,それ以外の工事による利益の額は含まれていない。 さらに,被告は,各杭の「掘削長×掘削基本時間」の単価計算から求め られたものに(「掘削時間」/〔「掘削時間」+「準備時間」+「排土埋 戻し時間」〕)を乗じたものが,掘削に対しての時間の割り出し単価とな るなどと主張しており,工事費用について時間当たりの単価を算出して, 現実に掘削に要した時間に相当する分についてのみ本件訂正発明1の1が 寄与しているかのような主張をしているが,被告が「先行削孔砂置換工」 のうちの掘削作業のみを受注しているものではなく,また,一般に掘削作 業のみを受注する形態が考えにくいこと,掘削作業が「先行削孔砂置換工」 の重要部分を占めると考えられること,発注者は準備時間や排土埋戻しの ために被告に工事を発注しているものでなく,準備や排土埋戻しの作業が 利益をあげているとはいえないことなどからすると,被告の上記主張は採 用することができない。 そうすると,代替技術の存在を考慮に入れたとしても,上記額が原告の 損害であるという推定を覆滅させるに足りる証拠がないというほかないか ら,被告の寄与率に係る主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2017.05.31
平成29(行ケ)10061 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月12日 知的財産高等裁判所(3部)
そして,上記のように相違点1´を認定した場合,仮に同相違点に係る構\n成(移動体の位置検出を行うために複数の起動信号発信器を出入口の一方側 と他方側に設置する構成)が本件特許の出願時において周知であったとすれ\nば,引用発明Aとかかる周知技術とは,移動体の位置検出を目的とする点に おいて,関連した技術分野に属し,かつ,共通の課題を有するものと認めら れ,また,引用発明Aは,複数の固定無線機の設置位置を特定(限定)しな いものである以上,前記の周知技術を適用する上で阻害要因となるべき事情 も特に存しないことになる(前記のとおり,第1図に関連する「施設の所定 の部屋」を固定無線機の設置位置とする実施例の記載は,飽くまで発明の一 実施態様を示したものにすぎず,そのことにより刊行物1から「施設の各部 屋」を設置位置とする以外の他の態様による実施が読み取れないとはいえな い。)。 したがって,以上の相違点の認定(相違点1´)を前提とすれば,上記技 術分野の関連性及び課題の共通性を動機付けとして,引用発明Aに対し前記 の周知技術を適用し,相違点1´に係る本件訂正発明1の構成を採ることは,\n当業者であれば容易に想到し得るとの結論に至ることも十分にあり得ること\nというべきである。
(3) ところが,本件審決は,かかる相違点を,前記第2の3(3)イ(ア)のとおり, 「第1起動信号発信器が設けられる『第1の位置』及び第2起動信号発信器 が設けられる『第2の位置』に関し,本件訂正発明1では,『第1の位置』 が『出入口の一方側である第1の位置』であり,また,『第2の位置』が『 出入口の他方側である第2の位置』であるのに対し,引用発明Aでは,『第 1の位置』,『第2の位置』の各位置が施設の各部屋に対応する位置である 点」(相違点1。なお,下線は相違点1´との対比のために便宜上付したも のである。)と認定した上,「引用発明Aによる移動体の位置の把握は,ビ ルの各部屋単位での把握に留まる」と断定し,「刊行物1には,移動体の位 置の把握を各部屋の出入口単位で行うこと,即ち,相違点1における本件訂 正発明1に係る事項である,第1起動信号発信器が設けられる第1の位置を 『出入口の一方側』とし,第2起動信号発信器が設けられる第2の位置を『 出入口の他方側』とする点については,記載も示唆もない」から,他の相違 点について検討するまでもなく,本件訂正発明1が刊行物1発明(引用発明 A)から想到容易ではないと結論付けたものである。 これは,本来,複数の固定無線機の設置位置を特定(限定)しない(「施 設の各部屋」は飽くまで例示にすぎない)ものとして認定したはずの引用発 明Aを,本件訂正発明1との対比においては,その設置位置が「施設の各部 屋」に限定されるものと解した上で相違点1を認定したものであるから,そ の認定に誤りがあることは明らかである。 また,本件審決は,上記のように相違点1の認定を誤った結果,引用発明 Aによる移動体の位置の把握が「ビルの各部屋単位での把握に留まる」など と断定的に誤った解釈を採用した上(刊行物1にはそのような記載も示唆も ない。),刊行物1には相違点1に係る構成を適用する動機付けについて記\n載も示唆もない(から想到容易とはいえない)との結論に至ったのであるか ら,かかる相違点の認定の誤りが本件審決の結論に影響を及ぼしていること も明らかである。
(4) 以上によれば,原告が主張する取消事由2は理由がある。
(5) 被告の主張について
これに対し,被告は,刊行物1発明によって実現される作用効果からすれ ば,同発明が実現を意図しているのは,移動体がどの「部屋」(あるいは固 定無線機の設置箇所を含む一定領域)に所在するのかを把握することであり, 言い換えれば,同発明は,「固定無線機からの電波受信可能領域」(検知エ\nリア)と「その固定無線機が置かれた部屋の領域」とが,ほぼイコールであ るという認識を前提とした発明である(取消事由2に関し)とか,刊行物1 発明は大まかな範囲で対象者(物)の所在を把握することを目的とするもの である(取消事由3に関し)などと指摘して,本件訂正発明と刊行物1発明 の違いを強調し,本件審決の認定判断に誤りがない旨を主張する。 しかし,いずれの指摘も刊行物1の記載に基づかないものであり,その前 提が誤っていることは,これまで説示したところに照らして明らかであるか ら,上記被告の主張はその前提を欠くものであって採用できない。
3 以上のとおり,本件審決は,本件訂正発明1に係る相違点1の認定を誤って 同発明が想到容易ではないとの結論を導いているところ,本件審決は,本件訂 正発明2ないし7についても,実質的に同じ理由に基づいて(すなわち,本件 訂正発明2ないし5については,本件訂正発明1の発明特定事項を全て含むこ とを理由に,本件訂正発明6及び7については,相違点1と実質的に差異がな い相違点が認定できることを理由に),本件訂正発明1におけるのと同じ結論 を導いているのであるから,結局のところ,本件訂正発明全部について本件審 決の判断に取り消すべき違法が認められることは明らかである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2017.05.31
平成28(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月12日 知的財産高等裁判所(3部)
このような一部認容・一部非認容の場合に、双方が不服がある場合、実際の提訴はどうやるのでしょうか?、第1、第2事件みたいにはなってないし。。。
以上の検討結果を併せ考えれば,文言解釈のみによるのでは,構成要件\nC−2の「ファンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るもので あるというべきである。
(2) 特許発明1の構成要件C−2の技術的意義に基づく解釈
ア 上記(1)のとおり,文言解釈のみによるのでは,構成要件C−2の「フ\nァンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るものであるとすれば, 当該構成要件の技術的意義に基づきその解釈を検討すべきこととなる。
イ 本件特許発明は,小型軽量化,高効率化を目的としてブラシレスモータ を使用した携帯用電気切断機において,その回路基板の配置スペースの 確保及び冷却が問題となっていること,また,操作性を妨げないハウジ ング形状である必要があることを背景に,モータを収容するハウジング の形状を大きく変更せず,かつ,操作性を損なわずに,モータ駆動用の 回路基板の配置スペースを確保するとともにその冷却を良好に行うこと を目的とするものである(前記1(3)イ,ウ)。 このような目的を達成するために,本件特許発明は,本件実施例にお いて,ハンドルを把持する作業者による作業の妨げとならないように, 回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設け,かつ,フ ァンの回転によりファンガイド内側が負圧になることを利用して回路基 板冷却用窓からファンガイド内側に至る冷却風を発生させるために,回 路基板収容部をファンの径方向外側に配置している(前記1(3)エ,オ)。 このうち前者が小型化の目的を達成するための手段,後者が冷却の目的 を達成するための手段として把握される。
ウ(ア) しかし,これらの手段のみによって実際に上記各目的が達成される か否かは,以下のとおり,本件明細書等の記載からは必ずしも明らかで ない。
(イ) 小型化の目的に関しては,本件明細書には従来の携帯用電気丸鋸の 具体的な構造についての言及がないため,本件実施例の構\造との比較 において目的達成の有無ないし程度を評価することはできない。本件 実施例の構造それ自体から,これらが小型化の目的を達成しているか\n否かを客観的に評価することもできない。 また,仮に本件実施例の構造が小型化の目的を達成しているとしても,\n回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設けさえすれば 自ずと目的が達成されるものではなく,前提として当該スペースを有効 活用し得るような合理的な構造を有することが必要と思われるが,本件\n明細書にはこの点に関する説明はない。
(ウ) 冷却の目的に関しては,上記手段により当該目的を達成する上で, 回路基板が冷却風の通路に配置されることは必須と思われるけれども, その具体的方法として回路基板をファンの径方向外側に配置すること は,ファンの径方向外側が冷却風の通路となるような構造を一体的に\n伴わない限り,回路基板の冷却とは直接関係しない。このことは,回 路基板がファンの径方向外側である真横にあったとしても,隔壁その 他により回路基板とファンとの間の冷却風の移動が遮断されているよ うな場合を考えれば明らかである。 ここで,本件実施例においては,回路基板収容部の4側面のうち,そ の2側面に回路基板冷却用風窓が多数形成され,これらとは別の側面に 風通路となる間隔が1つ設けられ,それら以外の側面は隔壁により囲ま れる構造となっている。このうち,上記間隔は,ファンガイドの背面と\nハウジングの外壁部との間に設けられ,これによってモータ収容部と回 路基板収容部とが連通している。このような構造とともに,モータ収容\n部とファンの位置とがファンガイドによって連通する構造が採用されて\nいるからこそ,回路基板収容部内に設置された回路基板がファン風の通 路に位置して冷却の目的が達成されることとなっている。このような回 路基板収容部からファンに至る連通構造が,回路基板の一部が(a)領域 に位置することと無関係に実現し得ることは明らかといってよい。
(エ) これらの点を踏まえると,本件特許発明の目的を達成するための手 段は,本件実施例においてすら合理的に説明されているとはいえない。 そうすると,本件実施例を上位概念化したものである本件特許発明に おいてはなおさら,その目的を達成し得るとは認められないことにな る。したがって,構成要件C−2が本件特許発明の目的を達成するた\nめの構成であるとして,その技術的意義から同構\成要件の示す意味内 容を把握することはできない。 そもそも,小型化の目的に関し,本件実施例における小型化の目的達 成手段である「回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に 設けること」は,特許発明3及び4並びにその従属発明である特許発明 5にしか具体的には表れておらず,また,構\成要件C−2とは無関係で ある。冷却の目的に関しても,上記(ウ)を踏まえると,その目的を達成 する構成としては,端的に構\成要件C−3「前記回路基板の少なくとも 一部は,前記ファン風の通路内に配置されており,」が設けられている 以上,構成要件C−2は無関係と見られる。
(3) 以上によれば,構成要件C−2の「ファンの径方向外側」は,特許請求\nの範囲の文言によれば(a)領域又は(b)領域のいずれとも解釈し得るものであ り,また,その技術的意義に鑑みてもいずれの解釈が正しいのか判断し得な いものということができる。 したがって,構成要件C−2は不明確というべきである。そうである以\n上,この点に関する本件審決の認定・判断には誤りがあり,取消事由2には 理由がある。
3 取消事由1(記載要件(特許発明6〜8及び10に関するサポート要件)に関する認定,判断の誤り(無効理由1の2))について
更に進んで,取消事由1についても検討する。
(1) 特許発明6は,「モータの側方位置において,前記モータの回転軸と平 行に延びるように配置されている」回路基板(構成要件I)のみを有したも\nのであり,当該回路基板は,さらに,「前記回路基板の少なくとも一部は, 前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方 向外側に配置され」る(構成要件C−2)ものである。\n本件明細書の発明の詳細な説明において,「モータの側方位置」に配置 された回路基板(縦置き基板)としては,第2の実施の形態の第2の回路基 板60B及び第3の実施の形態の第1の回路基板60C(いずれも,モータ 収容部2aの内壁面とモータ1の固定子1B間の隙間に配置されたもの)が 記載されているが(前記1(2)カ),縦置き基板のみを有する発明は明示的 に記載されていない。そこで,縦置き基板のみを有する構成が,本件特許発\n明の課題(前記2(2)イ)を解決できると当業者が認識し得る程度に,本件 明細書の発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討する。
(2) 第2の実施の形態について
ア 第2の実施の形態の縦置き基板(第2の回路基板60B)による効果は, 以下の3点に集約される(前記1(3)キ)。
1) 制御回路30を別基板(縦置き基板)としたことで,駆動回路20 及び整流平滑回路40を搭載した第1の回路基板60Aの面積を小さ くし,ハウジング2のソーカバー5側への突出量を少なくでき,操作\n性の面で有利となる。
2)制御回路30を別基板(縦置き基板)としたことで,駆動回路20 や整流平滑回路40の発熱部品の影響を受けないようにできる。
3) 制御回路30を搭載した第2の回路基板60B(縦置き基板)をセ ンサ基板51の近くに配置することで,回転位置検出素子52と制御 回路30との電気接続を短縮して,ノイズ等の影響を受けにくい構造\nにできる。
イ(ア) このうち,前記1)の効果は,ハウジング2に設けられた凸部69A (ソーカバー5側へ突出)が小さくなることをいうものである。しかし,\nこのとき,一方で縦置き基板を収容するためにモータ収容部2aが大き くならざるを得ないことを考えると,前記1)の効果は,一概に小型化に 寄与するといってよいか定かではない。また,凸部69A及びモータ収 容部2aの形状のこのような変化が,それぞれ携帯用電気切断機の操作 性に及ぼす影響については,本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ていない。 したがって,第2の実施の形態においては,縦置き基板を設けること により小型化の目的を達成できるとは必ずしも認識し得ないし,まして, 縦置き基板のみとした場合に,携帯用電気切断機の操作性の面で有利で あることないし操作性が損なわれないことを認識することもできない。
(イ) 前記2)の効果は,冷却の目的に関わるものである。この目的の観点 から見ると,制御回路30を別基板である縦置き基板とすることで, 前記2)の効果を期待できるとしても,ブラシレスモータの固定子が熱 源となることは技術常識であるところ,そのモータの側方に縦置き基 板を設置することにより,かえってモータの固定子の発熱の影響を受 けやすくなることも予想される。そうすると,制御回路30を縦置き\n基板としたとしても,必ずしも冷却の目的を達成できるとは認識し得 ない。まして,駆動回路と制御回路の両者を搭載した縦置き基板のみ とした場合に,基板の冷却を効果的に実現し得ると認識することもで きない。
(ウ) 前記3)の効果は,小型化の目的とも冷却の目的とも独立したもので あり,本件特許発明の課題解決に寄与しないことは明らかである。
・・・
(4) そうすると,特許発明6〜8及び10は,本件明細書の発明の詳細な説 明に記載されたものではなく,また,特許発明6〜8及び10が,その課題 を解決できると当業者が認識し得る程度に,本件明細書の発明の詳細な説明 に記載されているともいえない(なお,この点は,本件特許発明において横 置き基板が必須であるか否かとは関わりない。)。 したがって,特許発明6〜8及び10は,いわゆるサポート要件を満た しているとはいえない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2017.05.31
平成28(ネ)10098 不当利得返還等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年4月12日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
当裁判所も,原審と同様に,本件各契約は,これを締結するに当たって被 控訴人において必要とされる取締役会の決議を経ておらず,控訴人はそのこと について知り得べきであったものといえるから,本件各契約はいずれも無効で あり,控訴人の被控訴人に対する反訴請求はいずれも理由がないものと判断す る。その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第 4の1ないし3(原判決20頁7行目冒頭から36頁22行目末尾まで)に記 載のとおりであるから,これを引用する。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2017.05.31
平成28(行ケ)10190 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所(4部)
(1) 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だ けではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願 当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,「当該分離して使用 するもの(4)の上部,下部,左側部(右側部)の内側及び外側に該当する部分(5, 6)((7,8))」の各部分が明確ではない旨主張する。
(2)「内側及び外側に該当する部分」の明確性
ア 「内側及び外側」の範囲
(ア) 請求項1には,分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部(右側 部)の「内側及び外側」に該当する部分との記載がある。 請求項1の記載によれば,印刷物の中央面部(1)の所定の箇所に,所定の大き さを有する分離して使用するもの(4)が印刷されており,分離して使用するもの (4)は,周囲に切り込みが入っているものである。そして,請求項1には,「内 側及び外側」の範囲を直接特定する記載はない。 したがって,分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部(右側部)の「内 側及び外側」に該当する部分とは,印刷物の中央面部(1)における,分離して使 用するものの周囲に設けられた切り込みの「内側及び外側」に該当する部分と特定 され,その範囲は特定されていないものである。 (イ) なお,本件明細書の【0014】ないし【0017】の記載によれば,本 件発明1を実施する際には,一過性の粘着剤が塗布されている部分となる「内側及 び外側」の範囲について,分離して使用するものが欠落することなく,また左側面 部と右側面部を中央面部からはがして開いた場合には左側面部又は右側面部の一方 に分離して使用するものが貼着されるなどして,これを自動的に手にすることがで\nきる程度の範囲に限定されることになる。しかし,当該範囲は,中央面部(1), 左側面部(2),右側面部(3)及び分離して使用するもの(4)の形状や材質, 分離して使用するもの(4)の周囲の切り込みの程度,粘着剤の強度等に応じて, 適宜決定されるにすぎないから,特許を受けようとする発明において,「内側及び 外側」の範囲を特定していないからといって,それが明確性を欠くことにはならな い。
・・・
(4) 小括
以上によれば,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,「当該分離し て使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5, 6)」とは,印刷物の中央面部の所定の箇所に印刷された所定の大きさを有する, その外形は特定されない分離して使用するもの(4)の,上部,下部又は左側部の いずれかのうち,その周囲に設けられた切り込みの内側及び外側であって,その範 囲は具体的には特定されない部分に該当する部分であって,請求項1の記載のうち, 「当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当す る部分(7,8)」も同様であって,これらの記載が,第三者の利益が不当に害さ れるほどに不明確であるということはできない。 したがって,「当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部(右側部) の内側及び外側に該当する部分(5,6)((7,8))」との各記載は明確であ るから,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載が明確性要件に違反するという ことはできない。請求項2及び請求項3の各記載も同様であるから,明確性要件に 違反するということはできない。 よって,取消事由1は理由がない。
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと 解される。 そして,原告は,一過性の粘着剤が塗布される位置について,分離して使用する ものの上部,下部,左(右)側部の内側及び外側に該当する部分のいずれかでよい とすると,サポート要件に違反すると主張する。
(2) 前記2(4)のとおり,特許請求の範囲請求項1に記載された発明において,左 側面部(2)の裏面の「一過性の粘着剤が塗布されている」部分は,分離して使用 するものの,上部,下部又は左側部のいずれかのうち,その周囲に設けられた切り 込みの内側及び外側であって,その範囲は特定されない部分に該当する部分であっ て,右側面部(3)の裏面についても同様である。 そして,前記1(2)イのとおり,本件発明1は,分離して使用するものについて, その周囲に切り込みが入っているにもかかわらず,広告等の印刷物に付いていて紛 失させることなく,しかも,広告等の印刷物より切り取る手間をかけずに利用する ことができる印刷物を提供することを課題とするものである。そして,前記2(2)イ のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明の記載(【0014】〜【0017】) により,当業者は,一過性の粘着剤の塗布が,左側面部2の裏側のうち,分離して 使用するものの上部,下部,左側部の少なくともいずれかに該当する部分であって, 分離して使用するものの内側及び外側のいずれにも該当する部分にされれば,本件 発明1の上記課題を解決できると認識できるものといえ,右側面部3についても同 様である。 そうすると,一過性の粘着剤が塗布される位置において,本件発明1は,発明の 詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明 1の課題を解決できると認識できる範囲のものということができる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2017.05.31
平成28(ネ)2932 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成29年4月6日 大阪高等裁判所
一審原告は,不正競争防止法5条2項により推定が一部覆滅された部 分について,同条3項を適用して使用料相当額の損害賠償請求をするこ とができると主張する。しかし,補正して引用した原判決「事実及び理 由」中の第4の7 及び において算定した同条2項により推定される 損害額は,平成23年12月17日から平成26年8月8日までの一審 被告の前記不正競争行為の全体によって生じた一審原告の損害(逸失利 益)額を算定したものであり,推定が覆滅された一部について改めて同 項3項による損害額を算定し,その合算額を損害額とすることは,同一 の侵害行為を二重に評価して損害額を算定することを意味するものであ り,許されないといわなければならない。一審原告の上記主張は,採用 することができない。
◆原審はこちら。平成27(ワ)2504
その他、当該ドメインを巡っては下記事件があります。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2017.05.25
平成28(ネ)10096 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年5月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 均等の第1要件における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であり,\n上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明の課題 及び解決手段(特許法36条4項,特許法施行規則24条の2参照)とその効果(目 的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項\n参照)を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見ら れない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによっ\nて認定されるべきである。ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題とし て記載されているところが,出願時(又は優先権主張日)の従来技術に照らして客 観的に見て不十分な場合には,明細書に記載されていない従来技術も参酌して,当\n該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定\nされるべきである。
イ 本件明細書によれば,本件発明は,従来技術では経路探索の終了時にいくつ かの経由地を既に通過した場合であっても,最初に通過すべき経由予定地点を目標\n経由地点としてメッセージが出力されること(【0008】)を課題とし,このよ うな事態を解決するために,通過すべき経由予定地点の設定中に既に経由予\定地点 のいずれかを通過した場合でも,正しい経路誘導を行えるようなナビゲーション装 置及び方法を提供することを目的とし(【0011】),具体的には,車両が動く ことにより,探索開始地点と誘導開始地点のずれが生じ,車両が,設定された経路 上にあるものの,経由予定地点を超えた地点にある場合に,正しく次の経由予\定地 点を表示する方法を提供するものである(【0018】【0038】)。また,前\n記2(1)エ(ア)のとおり,本件特許出願当時において,ナビゲーション装置が,距離 センサー,方位センサー及びGPSなどを使って現在位置を検出し,それを電子地 図データに含まれるリンクに対してマップマッチングさせ,出発地点に最も近い ノード又はリンクを始点とし,目的地に最も近いノード又はリンクを終点とし,ダ イクストラ法等を用いて経路を探索し,得られた経路に基づいて,マップマッチン グによって特定されたリンク上の現在地から目的地まで経路誘導するものであった ことは,技術常識であったと認められる。 このように,本件発明は,上記技術常識に基づく経路誘導において,車両が動く ことにより探索開始地点と誘導開始地点の「ずれ」が生じ,車両等が経由予定地点\nを通過してしまうことを従来技術における課題とし,これを解決することを目的と して,上記「ずれ」の有無を判断するために,探索開始地点と誘導開始地点とを比 較して両地点の異同を判断し,探索開始地点と誘導開始地点とが異なる場合には, 誘導開始地点から誘導を開始することを定めており,この点は,従来技術には見ら れない特有の技術的思想を有する本件発明の特徴的部分であるといえる。 したがって,探索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点の異同を判断する 構成を有しない被控訴人装置が本件発明と本質的部分を異にすることは明らかであ\nる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第4要件(公知技術からの容易性)
>> ピックアップ対象
2017.05.18
平成28(行ケ)10114 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年5月10日 知的財産高等裁判所(1部)
前記(1)によれば,本件原出願当初明細書に記載された事項は,内歯揺動型 内接噛合遊星歯車装置に関するものであって,本件原出願当初明細書には外歯揺動 型遊星歯車装置に関する記載は全くないのに対し,本件出願における本件訂正発明 1は,「揺動型遊星歯車装置」に関するものとすることで,揺動体の揺動歯車を内歯 とする限定はないものであるから,揺動体の揺動歯車が外歯であるもの(外歯揺動 型遊星歯車装置)を含ませるものであると認められる。もっとも,本件原出願の出 願前に刊行された各特許公報(甲25〜27)によれば,内歯揺動型遊星歯車装置 と外歯揺動型遊星歯車装置とに共通する技術(以下「共通技術」という。),すなわ ち,偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには依存しない 技術があることは周知の事項であると認められ,当業者であれば,揺動型遊星歯車 装置の個々の形式に依存する技術と,形式には依存しない共通技術があることを, 知識として有しているものといえる。 そこで,本件原出願当初明細書に揺動体の揺動歯車を内歯とする以外の歯車装置 へ適用することなどについての記載がないとしても,本件訂正発明1が,本件原出 願当初明細書に記載された事項の範囲内といえるか,すなわち本件原出願当初明細 書の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において,新たな技術 的事項を導入しないものであるかについて,以下,検討する。
・・・
本件原出願当初明細書に記載された技術的課題のうち,前記(2)に関しては,偏心 体軸が円周方向において非等間隔に配置されることにより生じるものであり,内歯 揺動体が外歯歯車の周りで円滑に揺動駆動することにより解決されるものであるか ら,課題を解決する手段として,外歯歯車とその周りで揺動する内歯歯車を備える こと,すなわち内歯揺動型遊星歯車装置であることが,本件原出願当初明細書に記 載された発明の前提であるといえる。なお,外歯揺動型遊星歯車装置では,揺動体 は,その外周面に外歯が設けられるものであることから必然的にその外形は円形と ならざるを得ないものであり,偏心体軸を非等間隔にしても揺動体の外周の形状は 円形のままで変わらず,装置全体の形状や他の軸の配置等には何ら影響を及ぼすも のではないから,偏心体軸を非等間隔とする技術的意義はない(本件原出願当初明 細書に記載された課題は,偏心体軸を非等間隔に配置することにも技術的意義を有 する内歯揺動型遊星歯車装置に特有のものであり,外歯揺動型遊星歯車装置におい てはそもそも課題とならないものである。)。 このように,本件原出願当初明細書の全体の記載からすると,同明細書に開示さ れた技術は,従来の内歯揺動型遊星歯車装置における問題を解決すべく改良を加え たものであって,その対象は内歯揺動型遊星歯車に関するものであると解するのが 相当であり,外歯揺動型遊星歯車装置を含むように一般化された共通の技術的事項 を導くことは困難であるといわざるを得ない。 また,本件原出願当初明細書の特許請求の範囲,発明の詳細な説明(実施例を含 む。)及び図面には,外歯歯車118を出力軸とする内歯揺動型遊星歯車装置のみが 記載され,内歯揺動型遊星歯車装置について終始説明されているのに対し,本件原 出願当初明細書に記載された技術が,揺動体の形態に関わらない共通技術であるこ と,外歯揺動型遊星歯車装置に適用することが可能であることやその際の具体的な\n実施形態,その他の周知技術の適用が可能であること等についての記載や示唆は全\nくないのであるから,本件原出願当初明細書の記載に接した当業者であっても,同 明細書に記載された発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に照らし,内歯揺動型遊 星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置に共通した課題及びその解決方法が開示され ていると認識するものではないと解される。
(4) さらに,本件訂正発明1について検討するに,証拠(甲5,24,30) 及び弁論の全趣旨によれば,揺動型遊星歯車装置には,外歯揺動型と内歯揺動型が あること,それぞれの型において,出力部材と固定部材とは相対関係にあり,入れ 替え自在であること自体は,周知技術であると認められるところ,外歯揺動型遊星 歯車装置については,外側の内歯歯車を出力歯車とする1型(外側に出力軸を,内 側に固定部材を配置するもの)と外側の内歯歯車を固定部材とする2型(内側に出 力軸を,外側に固定部材を配置するもの)の2つの型が想定されるものと認められ る。本件訂正発明1は,「前記ケーシングの内側で,該ケーシングに回転自在に支持 され,当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と,を備 え,」とされており,上記ケーシングは固定部材であるといえるから,本件訂正発明 1には,外歯揺動型遊星歯車装置については2型のもののみが含まれ,1型は含ま れないものと認められる(下図参照)。 1型(外側に出力軸,内側に固定部材) 2型(内側に出力軸,外側に固定部材) もっとも,本件原出願当初明細書には,「出力軸としての機能を兼用する外歯歯車\n118によって」(【0026】),「内歯揺動体116A,116Bには,ホローシャフトタイプの出力軸兼用の外歯歯車118が内接している。」(【0034】),「内歯揺動体116A,116Bは,その自転が拘束されているため,該内歯揺動体11 6A,116Bの1回の揺動回転によって,該内歯揺動体116A,116Bと噛 合する外歯歯車118はその歯数差だけ位相がずれ,その位相差に相当する自転成 分が外歯歯車110(判決注:「118」の誤記と認められる。)の回転となり,出 力が外部へ取り出される。」(【0038】)などの記載があり,これらの記載によれ ば,本件原出願当初明細書に記載された実施例については揺動体の内歯歯車に噛合 する外歯歯車118が出力軸として機能する内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置が記\n載されている一方で,本件原出願当初明細書には固定部材と出力歯車が入れ替え可 能であり,出力軸を固定部材に変更することができる旨の記載はないのであるから,\n同実施例を前提として外歯揺動型遊星歯車装置とする場合には,揺動体に設けられ る外歯歯車に噛合する内歯歯車が出力軸となるのであって,出力軸が外側になり, 内側に固定部材が配置される型を想定することが自然であるといえる。したがって, 本件原出願当初明細書に記載された事項から,固定部材と出力軸を入れ替えた2型 の外歯揺動型遊星歯車装置を想起することは考え難い。 また,本件原出願当初明細書に記載された内歯揺動型遊星歯車装置においては, 内歯揺動体は内周面に内歯歯車を設けることから,その内周の形状は,必然的に円 形となる。しかしながら,外周面については,複数の偏心体軸を支持することがで きる限りにおいて,自由な形状を採り得るものであるから,本件訂正発明1の中間 軸を設けるに際して,内歯揺動体との干渉を考慮する必要はないものであり,実施 例においても,揺動体の外周を非円形の形状として,その外側に中間軸を配置する 構成を採用している。さらに,中間軸への入力は,中間軸の外側に入力軸を配置し\nて行うことで装置全体の軸方向長さを短縮していることが認められる。これに対し, 外歯揺動体は,その外周の全周にわたって連続的に外歯を有するものであって,必 然的にその外形は円形となるものであるから,2型の外歯揺動型遊星歯車装置に適 用する形態では,「該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置される と共に,該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸」を備え,「前記中間軸を回転駆 動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ,前記伝動外歯歯車を介して 該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され,前記駆 動源側のピニオン,前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が,同一平面 上で噛み合う」構成を,その外形が円形である外歯揺動体を構\\成要素とする外歯揺 動型遊星歯車装置において実現することを要するものである。 しかしながら,本件原出願当初明細書に記載された実施例である内歯揺動型遊星 歯車装置を前提として,さらに,固定部材と出力軸を入れ替えた2型の外歯揺動型 遊星歯車装置とする場合には,必然的にその外形が円形となる外歯揺動体と中間軸 との間に干渉を生じることとなるから,そのままでは中間軸を配置することはでき ないことになる。本件訂正発明1を2型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用するには, 揺動体と中間軸との干渉を避けるための設計変更(揺動体に中間軸を通すための孔 を形成すること)や,中間軸への入力を他の部材との干渉を避けつつ行うための設 計変更等を要することとなるのに対し,本件原出願当初明細書には,外歯揺動型遊 星歯車装置に適用する場合の具体的な実施形態,その他の周知技術の適用が可能で\nあることなどについての記載や示唆は全くない。 したがって,偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには 依存しない共通技術があることが周知の事項であるとしても,当業者は,本件原出 願当初明細書の記載から,2型の外歯揺動型遊星歯車装置を含む本件訂正発明1を 想起することはないものと解される。
(5) 以上によれば,本件訂正発明1は,本件原出願当初明細書の全ての記載を 総合することにより導かれる事項との関係において,新たな技術的事項を導入する ことに当たらないということはできず,本件原出願当初明細書に記載した事項の範 囲内であるとはいえないから,本件原出願に包含された発明であると認めることは できない。
・・・
原告は,審決が判断した無効理由は,本件無効理由通知書及び審決の予告\nとは大きく異なるものであったにもかかわらず(審決は,本件無効理由通知書(甲 40)及び審決の予告(甲41)で判断されていない事項(「相応の工夫が必要」か\n否か,「必須の構成」を備えているか否か)について判断をした。),「相応の工夫が\n必要」か否か,「必須の構成」を備えているか否かについて,原告の意見は全く求め\nられず,原告(被請求人)に不利な審理結果を招来したことは,実質的に,特許法 153条2項の規定に違反する旨主張する。 そこで,検討するに,特許法153条2項は,審判において当事者が申し立てな\nい理由について審理したときは,審判長は,その審理の結果を当事者に通知し,相 当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定してい\nる。これは,当事者の知らない間に不利な資料が集められて,何ら弁明の機会も与 えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続 を定めたものであると解される。このような特許法153条2項の趣旨に照らすと, 審判長が当事者に対し意見を申し立てる機会を与えなければならない「当事者が申\\ し立てない理由」とは,新たな無効理由の根拠法条の追加,主要事実の差し替えや 追加等,不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなり予め告知を受けて意見\nを述べる機会を与えなければ手続上著しく不公平となるような重大な理由がある場 合のことを指し,当事者が本来熟知している周知技術の指摘や間接事実及び補助事 実の追加等の軽微な理由はこれに含まれないと解される。 本件において,本件無効理由通知及び審決の予告の判断内容と審決の判断内容を\n比較すると,審決には,「相応の工夫」や「必須の構成」といった,本件無効理由通\n知及び審決の予告には記載されていなかった判断が追加されていることが認められ\nる。しかしながら,審決の上記判断事項は,根拠法条や主要事実の変更ではなく, それまで審判手続の中で当事者双方の争点となっていた,本件出願が分割要件を満 たすものであるか否か(本件訂正発明1が本件原出願当初明細書に記載した範囲内 のものであり,本件原出願に包含された発明であるか)を判断する際に,その理由 付けの一つとして判断された事項であり,審決は,上記争点を判断の過程における 理由について審決の予告を補足したにすぎないものと解される。\nそして,審決の予告及び審決において,本件特許を無効とする理由は,本件訂正\n発明に係る特許についての出願が,分割の要件を満たすものではなく,出願日は本 件原出願の出願日に遡及しないものであるところ,本件訂正発明は,本件出願前に 頒布された刊行物である本件原出願の特許公開公報に記載された発明であるから, 特許法29条1項3号の規定に違反するものであり,特許法123条1項2号に該 当し,無効とされるべきものである,というものであって,両者に異なるところは なく,この無効理由は,本件無効理由通知により当事者に対し通知されたものと同 一のものである。 このように,審決の理由中に,本件無効理由通知及び審決の予告にはなかった新\nたな判断内容が追加されるなどしたとしても,審決の上記判断内容は,本件出願の ような分割出願が分割の要件を満たすものであるかの判断の過程における理由を補 足するものであり,「当事者の申し立てない理由」には当たらないと解されるから,\n改めて無効理由が通知されなかったことをもって,特許法153条2項の規定に違 反する違法があったということはできない。 したがって,原告の上記主張は採用する
関連カテゴリー
>> 分割
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2017.05.18
平成27(ワ)23694 著作者人格権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成29年4月27日 東京地方裁判所(47民)
「建築の著作物」(同法10条1項5号)とは,現に存在する 建築物又はその設計図に表現される観念的な建物であるから,当該設計\n図には,当該建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が\n記載されている必要があると解すべきである。 (イ) 上記1(認定事実)(2)のとおり,原告代表者は,乙から本件建物の\n外観に関する設計の依頼を受け,日本の伝統柄をデザインの源泉とし, 一見洗練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩でき るものとするとの設計思想に基づいて,原告設計資料及び原告模型を作 成し,平成25年9月6日,乙に対し,本件建物の外装スクリーンの上 部部分(2階及びR階部分)を立体形状の組亀甲とすることを含めた設 計案を提示している。そして,この時点において,被告竹中工務店は, 上記部分を立体形状の組亀甲とすることに着想していなかった(争いの ない事実)。 しかしながら,上記1(認定事実)(2)のとおり,原告設計資料及び原 告模型に基づく原告代表者の上記提案は,上記1(認定事実)(1)イの内 容が記載された被告竹中工務店設計資料を前提に,当該資料のうちの外 装スクリーンの上部部分のみを変更したものであり,上記提案には,伝 統的な和柄である組亀甲柄を立体形状とし,同一サイズの白色として等 間隔で同一方向に配置,配列することは示されているが,実際建築され る建物に用いられる組亀甲柄より大きいイメージとして作成されたもの であるため,実際建築される建物に用いられる具体的な配置や配列は示 されておらず,他に,具体的なピッチや密度,幅,厚さ,断面形状も示 されていない。一方で,上記1(認定事実)(6)のとおり,組亀甲柄は, 伝統的な和柄であり,平面形状のみならず,建築物を含めて立体形状と して用いられている例が複数存在し,建築物の図案集にも掲載されてい る。 そうすると,原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は,\n被告竹中工務店設計資料を前提として,その外装スクリーンの上部部分 に,白色の同一形状の立体的な組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置,配 列するとのアイデアを提供したものにすぎないというべきであり,仮に, 表現であるとしても,その表\現はありふれた表現の域を出るものとはい\nえず,要するに,建築の著作物に必要な創作性の程度に係る見解の如何 にかかわらず,創作的な表現であると認めることはできない。更に付言\nすると,原告代表者の上記提案は,実際建築される建物に用いられる組\n亀甲柄の具体的な配置や配列は示されていないから,観念的な建築物が 現されていると認めるに足りる程度の表現であるともいえない。\n以上によれば,本件建物の外観設計について原告代表者の共同著作者\nとしての創作的関与があるとは認められない。 (ウ) これに対し,原告は,原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表\n者の上記提案は,建物の外観に用いられることが多くない組亀甲柄を選 択し,組亀甲柄を用いるというアイデアから想定される複数の表現から\n特定の表現を選択して決定するものであることや,組亀甲柄部分の光の\n表現についても具体的に決定されているものであることをもって,創作\n的な表現である旨主張する。\n しかしながら,組亀甲柄は,建築物の図案集にも掲載され,実際に建 築物に用いられている例が複数存在することは上記(イ)のとおりであり, 建物の外観に組亀甲柄を用いること自体がありふれていないということ はできない。また,原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提\n案は,上記(イ)のとおり,組亀甲柄の大まかな色,形状,配置,配列が 決定されているにすぎず,一般的な組亀甲柄として紹介されている例 (乙11の1ないし4,12の1)と比較しても,個性の発露があると 認めるに足りる程度の創作性のある表現であるということはできない。\nさらに,原告の主張する光の表現は,具体的に明らかではなく,この点\nをもって創作性を認めることはできない。 したがって,原告の上記主張は採用できない。 イ 「共同して創作した」といえるかについて 仮に,本件建物の外観設計における原告代表者の創作的関与の有無の\n点を措いても,前記第2の1(前提事実)(2)エ及び上記1(認定事実) (3)・(4)のとおり,被告竹中工務店の設計担当者は,本件打合せで原告代 表者から原告設計資料及び原告模型に基づく提案内容の説明を聞いたこ\nとはあるが,原告との共同設計の提案を断り,その後,原告代表者と接\n触ないし協議したことはない。 また,上記1(認定事実)(2)・(4)のとおり,原告代表者の設計思想は,\n本件建物のファサードを,日本の伝統柄をデザインの源泉とし,一見洗 練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩できるもの とするなどというものであるのに対し,被告竹中工務店の設計思想は, 組亀甲柄のもつ2層3方向の幾何学構造に着目した編込み様のデザイン\nなどというものであって,原告代表者と被告竹中工務店の設計思想は異\nなる上,上記1(認定事実)(2)・(5)のとおり,原告代表者の提案内容と\n完成後の本件建物は,外装スクリーンの上部部分に2層3方向の立体格 子構造が採用されている点は共通するが,少なくとも立体格子の柄や向\nき,ピッチ,幅,隙間,方向が相違しており(具体的には,原告設計資 料及び原告模型には,本件建物の外装の上部に同じ形状及びサイズの白 色の組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置,配列することとすること,ピ ッチを「@≒500mm」,巾を「≒150mm」,向きを鉛直,隙間 を「△辺≒200mm」とする格子が記載されており,この他に,外装 スクリーンの寸法や,格子のピッチ,密度,隙間,幅,厚さ,断面形状, 表面処理に関する具体的な記載はないのに対し,本件建物においては,\nその2階以上の外装部分は,アルミキャストを素材とする白色の三次元 曲面による2層3方向の立体格子構造とされ,ピッチは「@250m\nm」,巾は「90mm」,向きは斜光,隙間は「△辺94mm」の格子 が用いられ,横方向が強調された配列とされている。),建物の外観に 関する表現上の重要な部分,すなわち本質的特徴といえる点において多\nくの相違点がある。 これらの事情に照らせば,原告と被告竹中工務店の間に共同創作の意 思や事実があったとは認められず,両者が本件建物の外観設計を「共同 して創作」したと認めることはできない。
・・・・
ア 原著作物性について
上記(1)アのとおり,原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提\n案は創作的な表現であるとはいえないから,これに著作物性を認めること\nはできない(更に付言すると,建物の著作物性を認めることもできない。)。
イ 被告竹中工務店による翻案について
また,仮に,原告設計資料及び原告模型に係る原告代表者の提案につい\nての著作物性の有無の点を措いても,上記(1)イのとおり,原告設計資料及 び原告模型と本件建物とは,その表現上の重要な部分において多くの相違\n点があり,本件建物から原告設計資料及び原告模型における表現上の本質\n的特徴を感得することはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 著作者
>> ピックアップ対象
2017.05.18
平成27(ワ)556等 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求本訴事件,特許権侵害差止等請求反訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年4月27日 東京地方裁判所(29民)
特許法73条2項は,「特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の 定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすること ができる。」と規定している。これは,特許発明のような無体財産は占有を伴うも のではないから,共有者の一人による実施が他の共有者の実施を妨げることになら ず,共有者が実施し得る範囲を持分に応じて量的に調整する必要がないことに基づ くものである。もっとも,このような無体財産としての特許発明の性質は,その実 施について,各共有者が互いに経済的競争関係にあることをも意味する。すなわち, 共有に係る特許権の各共有者の持分の財産的価値は,他の共有者の有する経済力や 技術力の影響を受けるものであるから,共有者間の利害関係の調整が必要となる。 そこで,同条1項は,「特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同 意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定するこ とができない。」と規定し,同条3項は,「特許権が共有に係るときは,各共有者 は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又 は他人に通常実施権を許諾することができない。」と規定しているのである。 このような特許法の規定の趣旨に鑑みると,共有に係る特許権の共有者が自ら特 許発明の実施をしているか否かは,実施行為を形式的,物理的に担っている者が誰 かではなく,当該実施行為の法的な帰属主体が誰であるかを規範的に判断すべきも のといえる。そして,実施行為の法的な帰属主体であるというためには,通常,当 該実施行為を自己の名義及び計算により行っていることが必要であるというべきで ある。
・・・・
上記(イ)の事実関係によれば,補助参加人は,ヤマト商工第2工場の責任者 として,水産加工機械の開発,製造に携わっていたが,同製造に要する原材料は, ヤマト商工の名義及び計算により仕入れられていたこと,補助参加人は,ヤマト商 工から固定額の金銭を受領しており,水産加工機械の販売実績によってヤマト商工 の補助参加人に対する支払額が左右されるものでないこと,顧客に対しても,水産 加工機械の販売に伴う責任等を負う主体としてヤマト商工の名が表示されていたこ\nとなどが認められ,また,本件製品との関係では,七宝商事がヤマト商工に支払っ たのは,ヤマト商工の請求に係る「BK−2フグスライサー」(すなわち,本件製 品)の代金310万円(税別)であって,ヤマト商工が同金員の全てを受領してい ること,七宝商事が補助参加人に支払ったのは,補助参加人の請求に係る「エフビ ックライサー BK−2 管理費」(すなわち,本件製品のメンテナンス料)40 万円(税別)であって,補助参加人が同金員の全てを受領していることが認められ るから,本件製品の製造販売は,ヤマト商工の名義及び計算により行われたもので あり,補助参加人の名義及び計算で行われていたものがあるとすれば,それは,本 件製品のメンテナンスにとどまり,本件製品の製造販売ではないというべきである。
b この点,原告は,本件製品は補助参加人が自ら製造販売したものであるとし て縷々主張するが,既に説示したとおり,補助参加人が形式的,物理的に製造販売 に関与したか否かが問題なのではなく,いかなる立場で関与したか,すなわち,ヤ マト商工の名義及び計算において行われる製造販売にヤマト商工の手足として関与 したのか,補助参加人の名義及び計算において行われる製造販売を自ら行ったかが 問題なのであって,原告の上記主張は,的を射ないものである。 原告は,被告の別件地裁訴訟での主張についても縷々指摘するが,同訴訟での被 告の主張がいかなるものであったかによって,本件製品の製造販売をめぐる事実関 係が左右される性質のものでないことは明らかである。また,当該主張は,補助参 加人の行為(なお,同訴訟では本件製品は対象とされておらず,同製品に関する行 為を直接問題にしたものとはいえない。)が本件専売契約に違反することを指摘す るためにされたものであることは明らかであり,その言葉尻をとらえて被告が本件 各発明の実施行為としての本件製品の製造販売の主体が補助参加人であることを認 めたなどと評価することは,不相当である。
2017.05.12
平成28(ワ)28591 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成29年4月27日 東京地方裁判所(47部)
前記(1)ア(ア)のとおり,「医の心」という語は,従前から医療関係の書 籍や番組等で頻繁に用いられている語であり,その文言からしてその意味は 医師ないし医療の心得といったものであると自然に理解できるところ,現に, 昭和62年に発行された心臓外科の権威とされる医師による「医の心」と題 する書物(乙8)では,「医の心」につき,医師の心得ないし医師の心情と の意味である旨が詳細に記載されている。 また,「医心」という語も,「医の心」を短縮した語であると解され,現 に,前記(1)ア(イ)のとおり,「医術の心得」(広辞苑第6版)といった意 味で一般に用いられている。 そして,前記(1)イ(ア)ないし(カ)のとおり,被告は,本件ウェブサイト 等を含む被告のウェブサイト及びパンフレット等において,被告標章1「医 の心」や被告標章2「医心」という語を,上記のような一般的な意義と同様 に,医師としての心構えや医師が有すべき素養等といった意味で用いている\nものであり,被告標章3「医心養成ゼミ」も,そのような「医の心」や「医 心」を養成するためのゼミであることを説明しているものである。実際に, 被告は,前記(1)イ(キ)のとおり,「医心養成ゼミ」において,医学部受験 のための知識ではなく,医師としての心構えや素養を養うことを目的とした\nカリキュラムを提供している。 以上のとおり,本件ウェブサイト等を含む被告のウェブサイト及びパンフ レットにおいて,被告標章1及び2は,医学部志望者が医師になるために学 力とともに備えるべき心構えや素養を記述的に説明した語であり,被告標章\n3も,医師として必要な心構えや素養の養成を目的とするゼミであることを\n記述的に説明した語であると認められるから,これらの標章は自他識別機能\nを有する標識として商標的に使用されているものではなく,したがって,被 告のウェブサイト及びパンフレットにおける被告標章1ないし3の使用には, 本件商標権1及び2の効力は及ばない(商標法26条1項6号)。 なお,仮に,原告から使用許諾を受けた者が本件商標を商標的に用いてい るとしても,同事実によって,被告が被告標章を商標的に使用していること にはならない。
(3) また,本件検索結果における被告標章1ないし3の表示についても,被\n告が開講している「医心養成ゼミ」に関する被告のウェブサイトの記載の 一部が表示されるものであるところ,そもそもそれが被告による使用に当\nたるか否かの点(争点(2))は措いて,その表示内容を検討しても,上記\n(2)の被告のウェブサイト及びパンフレットにおける被告標章の使用の場合 と同様に,被告標章を商標的に使用しているものではなく,本件商標権1 及び2の効力は及ばない。
2017.05.12
平成28(ワ)2818 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年4月27日 大阪地方裁判所(21民)
(1) ロボット便座βが本件発明の技術的範囲に属すること,被告らがロボット便 座βを2台製造したことは当事者間に争いがない。 しかし,被告らが同便座をそれ以外に製造した事実は認められず,また上記第2 の1(4)の展示会等で展示したものの,これをそのまま直ちに市販することを計画 したり,これにつき介護機器の認定のための手続を進めたりしている事実をうかが わせる証拠はない。 加えて被告らは,本件において,ロボット便座βが本件発明の技術的範囲に属す ることを認め,今後製造しない旨を原告に対して表明しているくらいであるから,\n以上のような事実関係のもとでは,被告らが,今後,本件ロボット便座βを製造, 使用,販売,又は販売の申出をするなどするおそれを認めることは困難といわなけ\nればならない。
(2) ただ被告日本アシストは,ロボット便座βの開発のために厚生労働省障害者 自立支援機器等開発促進事業の費用助成を受けた関係で,助成対象となったロボッ ト便座βの保存義務を課せられ(弁論の全趣旨),現に上記製造済み2台のロボット 便座βを保管していたが,証拠(乙5,乙6)によれば,それにもかかわらず,本件 訴訟係属中に,保存していた上記製造済み2台のロボット便座βにつき,うち1台 については回動駆動部並びにこれを駆動させるのに必要なモータ及び配線等を取り 外し,もう1台についても,回動駆動部を取り外してしまって,いずれももはやロ ボット便座βとはいえない状態にしていることが認められる。 被告日本アシストは,このように製造済みのロボット便座βを本件発明の技術的 範囲に属しない状態にすることにより,展示等のおそれもないことをいわんとして いるように考えられるが,上記状態では上記公法上の保存義務を果たしているとい えないことは明らかであるから,むしろ,このことにより被告日本アシストには, 関係官庁から保存義務を果たしていることの確認を求められた場合に,上記状態の ロボット便座βに取り外した部品を取り付けるなどして製品として完成させるおそ れが生じているものといわなければならず,被告日本アシストが部品を取り外した 状態のロボット便座βの部品を廃棄せずに所持していることも,そのような事態に 備えていることを裏付けているといわなければならない。 そして,被告日本アシストが,上記保存義務を果たしていることをいうためにロ ボット便座β2台を再度完成させた場合,それは,その事業のためにするものとな るから,部品取り外し済みのロボット便座β2台を再度完成させるという限度で, 被告日本アシストには,ロボット便座βを業として生産するおそれがあるといわな ければならない。
(3) したがって,原告の被告らに対するロボット便座βの製造販売等の差止請求 は,被告日本アシストに対する関係で製造の差止めを求める限度で理由があるとい うことになるが,上記(1)に説示したところによれば,同被告の関係では,これより 進んで完成したロボット便座βを使用,販売,又は販売の申出をするおそれは認め\nられない。また,上記保存義務を課せられない被告P1の関係では,上記(1)に説示 したとおり,同人に対する製造販売等の差止請求には理由がない。
(4) 以上に加え,被告日本アシストに対する関係では廃棄請求も問題となるが, 原告が被告日本アシストに求める廃棄請求の対象は,別紙物件目録で構成が特定さ\nれるロボット便座βであるところ,当該ロボット便座βは,上述のとおり本件発明 の構成要件を充足する要件となる部品が取り外されてしまっているというものであ\nる。 そうすると,これがロボット便座βに製造され得るものであったとしても,被告 日本アシストは,現在,廃棄請求の対象として特定されたロボット便座βを所有し ているということはできないことになる。 したがって,原告の被告日本アシストに対するロボット便座βの製造差止請求に は理由があるといえるものの,廃棄請求の対象となるロボット便座βを現在所有し ているわけではないことから,ロボット便座βの廃棄請求は理由がないといわなけ ればならない。
2 争点3について
原告は,被告らが,上記第2の2(3)のとおり,ロボット便座βを展示した行為を 捉え,これが特許法2条3項1号の「譲渡等のための展示」に当たるとして,これ による本件特許権の侵害行為を理由に被告P1に対して損害賠償請求をしている (ロボット便座βが本件特許の技術的範囲に属すること,被告らがロボット便座β を2台製造したことは当事者間に争いがないが,その製造の時期は,本件特許が登 録される前であるから当該製造行為は本件特許権侵害を構成しない。)。\nしかしながら,原告が損害と主張するところは,被告P1が原告との本件発明の 実施品である2013年型キレット試作品に関する製造委託契約に基づき原告から 支払を受けた金額から実施品製造に要した原価を控除した1322万7600円が 損害額と推定するものであるが,その推定する根拠は明らかではなく,およそ当該 支払がロボット便座βの展示行為と因果関係にある損害と認めることはできない。 そのほか,被告らによる展示が,「譲渡のための展示」であるとしても,被告ら がこれにより利益を得た事実は認められず,また原告の営業に影響を及ぼした事実 も認められない以上,原告において損害発生について的確な主張立証をなさない本 件において,そもそも原告に損害があったものと認定することはできない。 したがって,争点1の被告らによる本件特許権侵害行為,すなわちロボット便座 βの展示が「譲渡のための展示」に該当するかどうかを判断するまでもなく,原告 の被告P1に対する損害賠償請求には理由がない。
2017.05.10
平成27(ワ)7787 損害賠償等請求事件 商標権 民事訴訟 平成29年4月10日 大阪地方裁判所(26民)
ところで,商標権侵害について過失が推定されることとされた趣旨は,商標権の 内容については,商標公報,商標登録原簿等によって公示されており,何人もその 存在及び内容について調査を行うことが可能であること等の事情を考慮したものと\n解される。このことに鑑みると,侵害行為をした者において,商標権者による当該 商標の使用許諾を信じ,そう信じるにつき正当な理由がある場合には,過失がない と認めるのが相当である。 (イ) 本件では,前記のとおり,被告が,原告代表者や原告の理事に対して,\n本件事業を承継するとの意向を伝えたとは認められず,原被告間の本件事業の承継 に関する具体的な協議は,P1,P2及び双方の事務職員の間で行われたにとどま る。
a しかし,まず,そもそも原告は,財政難のために原告大学の募集停 止を決定したことから,本件事業の継続が困難な状況に陥り,本件事業の承継先を 探す必要に迫られていたのであり,そのような状況の中で,原告代表者及びP4は,\n平成26年4月4日に被告を訪問した際に,学生の受入れ及び学科の承継に加えて, 本件事業の承継先が見つかるとよいと考えている旨を伝えていたのであるから,被 告としては,本件事業の承継が原告の意向に沿うものであると考えてしかるべき状 況があったと認められる。
b そして,被告は,上記に近接する同月末の原告のP1からの申入れ\nを契機として検討を進め,同年5月23日にはP1が事務局のP3とともに被告の 施設を視察しているのであって,P1が原告における本件事業の中心人物であった ことからすると,上記のような原告の状況とあいまって,被告においては,P1の 上記申入れが原告の上層部の意向に基づくものであり,原告側の担当者がP1とさ\nれたと信じてしかるべき状況にあったというべきである。 また,被告が同年6月4日の執行部会において本件事業を承継する意向を固め, その旨をP2がP1に対して連絡した後,被告大学が第7回大会の共催校となるこ とを想定して,P2及び被告の事務職員がP1から同年7月11日に原告大学で開 催された第6回大会の選考委員会に招かれたことについても,同様のことがいえる。
c そして,同年8月24日,第6回大会終了後に原告大学で開催され た大会組織委員会及び大会実行委員会においては,地方公共団体,企業等の委員の ほか,原告の理事でもあるP10や原告の事務局担当者が出席する場で,被告大学 が共催校となることが承認されている。この場は,原告の大学組織内の会議でない とはいえ,原案の作成等全て原告の差配の下に執り行われるものであり,しかも, 原告の学長も出席する,大会としての最高の意思決定の場であって,それまでの単 なるP1との間のやり取りとは次元が異なるものである。したがって,そのような 場で被告大学が共催校となることが原告のP1から正式に発議され,承認されたの であるから,被告において,その方針が原告の組織内での了解を得たものであると 考えることは,極めて自然なことというべきである。 また,その後,原告の事務局が作成した文書により,被告大学が共催校となるこ とが,本件事業の後援者等の関係者や文部科学省に,対外的に報告されている。こ れらの文書は,大会組織委員会等の名義で作成されているものではあるが,実質的 には本件事業を執り行ってきた原告が発出するに等しい性質のものであるというべ きところ,特に,原告が,大学行政を所管する文部科学省に対して正式の報告文書 を作成,提出するに当たっては,通常は,しかるべき組織的決裁を経ているはずの ものであるから,被告において,そこに記載された内容が原告の組織としての方針 でもあると考えることは,極めて自然なことというべきである。
d さらに,第6回大会の直後から,第7回大会に向けた引継ぎ,準備 が始まり,引継ぎの当初から本件商標の移転登録の必要性が協議され,平成26年 10月には事務局が発足し,本件商標のロゴのデータを含め,大会の資料,データ がP3を通じて被告に引き渡されているのであって,このような事態は,少なくと も原告の事務局内部での組織的な了解を経た上でなければ通常は考え難いことであ る。 また,被告としても,原告の理事会の承認を要する前提で,既に同月に本件商標 の移転登録のための承諾書及び委任状をP3に送付した後,平成27年2月に見込 みを問い合わせたところ,P3からは,同年3月の理事会で予算が承認されれば,\nその後の手続を進めるとの回答を得ている。被告が執行部会や常任理事会等を経て 意思決定をしていることに鑑みれば,原告も同様に,事務局内で本件事業の承継に 関する情報が共有され,同月の理事会に向けて各種の会議を経て準備が進められて いるものと期待する状況があったというべきであり,よもや,P3が3,4か月に わたって,承諾書及び委任状を1人で手元に持ち続け,上司に全く報告していない とは思いもよらないところであったといえる。
e 以上からすると,原告が本件事業を継続することが困難となった中 で,原告側の種々の行動の積み重ねにより,被告において,原告が組織として被告 を共催校とすることを了解していると考え,被告が第7回大会を行うために必要な 事項については原告内部でしかるべき手続が執られ,又は執られることになると信 じることは極めて自然なことであったというべきであり,このことに疑いを生じさ せるような事情が存したとは何ら認められない。 そして,第7回大会のためには,平成27年4月の募集開始に合わせて,同年3 月にはホームページに募集要項を掲載する必要があり,その前提の下,同年1月に は第7回大会の準備を本格的に開始し,関係者に後援や役員への就任を依頼し,同 年2月には,大会組織委員会及び大会実行委員会において募集要項が確定している 段階にあったから,同年2月25日の時点で,同年3月の理事会決議を待たずに本 件商標を使用する必要が生じていたと認められ,このような事情を原告側が理解し ていると被告側が考えることにも,また理由があったというべきである。そして, 通常,登録商標の使用を許諾しない相手方に対して当該商標のロゴのデータを送付 するとは考え難い上,本件商標の使用に至るまで,本件事業の承継について原告が 異議を述べることがなかったため,被告においては,P3から本件商標のロゴのデ ータを送付されることによって,本件商標権の移転に関する原告の理事会決議に先 行して原告から本件商標を使用することがあらかじめ許諾されていたと受け止める のも無理はなかったというべきである。
(ウ) この点について,原告代表者は,被告側から原告代表\者等に対し,本 件事業の承継や本件商標の使用について,正式の申入れがなかったと供述する(7\n頁)。しかし,前記のように,原告側での本件事業の中心人物であったP1が被告と の協議に当たり,大会組織委員会で正式に承認されるなど原告の組織的な方針と理 解される種々の行動が積み重ねられた本件において,被告側から原告代表者や原告\nの理事に対して直接の申入れがされず,また,被告側において原告代表\者や原告の 理事の意思を直接確認しなかったからといって,それをもって被告の過失というこ とはできない。 また,原告代表者は,商標権のような重要な財産を譲り渡すときは,対価や譲渡\n時期について決定するものであると述べる(甲21)。しかし,本件商標は本件事業 と一体の関係にあるところ,本件事業はそれ自体としては経費の負担だけが必要な 事業であり,そのために神戸山手学園のように本件事業を承継しない判断を下す学 校法人もあったのであるから,被告として,大会の開催に必要となる経費の負担に 加えて,本件商標権の譲受けに対価の支払を要するとか,本件商標の使用料を支払 わなければならないものと予想せず,そのための協議をしなかったとしても,その\nことをもって被告の過失ということはできない。
(エ) 以上からすると,被告には,原告から平成27年5月に本件商標の使 用を指摘されて,その買取りを求められるまでの間,ホームページに本件商標を使 用するに当たり,本件商標権の移転に関する原告の理事会決議に先行して本件商標 を使用することを原告からあらかじめ許諾されており,必要な事項については原告 内部でしかるべき手続が執られ,又は執られることになると信じ,また,そう信じ るにつき正当な理由があったというべきであるから,被告による本件商標の使用に は過失がなかったものと認めるのが相当である。
2017.05. 9
平成28(ワ)298等 特許権侵害差止等請求事件,債務不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年4月20日 大阪地方裁判所(21民)
1 争点2(本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか)について
(1) 証拠(乙2の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明の実施品で ある原告製品は,本件発明の原出願である実用新案の出願日(平成26年11月2 6日)より前である同年9月22日以前に,Q2コープ連合に対して納品され,ま たQ2コープ連合においてそのチラシに掲載されて販売され,さらに同年10月1 0日には,被告において市場で取得された事実が認められるから,本件発明は,出 願前に日本国内において公然実施された (特許法29条1項2号)というべきこと になる。
(2) 上記(1)の事由は,本件特許を特許無効審判により無効とすべき事由となるが, 原告は,本件発明の原出願において原告が行った手続により,特許法30条2項に 定める新規性喪失の例外が認められる旨主張する。 そこで検討するに,特許法30条2項による新規性喪失の例外が認められるため には,同条3項により定める,同法29条1項各号のいずれかに該当するに至った 発明が,同法30条2項の規定を受けることができる発明であることを証明する書 面(以下「証明書」という。)を提出する必要があるところ,証拠(甲3)によれば, 原告は,本件発明の原出願(実願2014−6265,出願日:同年11月26日) の手続において,同年12月2日,実用新案法11条,特許法30条2項に定める 新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出した事実が認められる(特許 法46条の2,44条4項の規定により,特許出願と同時に提出されたものとみな される。)。 しかし,同証明書は,公開の事実として,平成26年6月2日,原告を公開者, Q1生活協同組合を販売した場所とし,原告が一般消費者にQ1生活協同組合のチ ラシ記載の「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(商品名:「ドラム式洗濯機の毛ゴ ミフィルター」)を販売した事実を記載しているだけであって,上記Q2コープ連合 における販売の事実については記載されていないものである。 この点,原告は,上記Q2コープ連合における販売につき,実質的に同一の原告 製品についての,日本生活協同組合連合会の傘下の生活協同組合を通しての一連の 販売行為であるから,新規性喪失の例外規定の適用を受けるために手続を行った販 売行為と実質的に同一の範疇にある密接に関連するものであり,原告が提出した上 記証明書により要件を満たし,特許法30条2項の適用を受ける旨主張する。 しかし,同項が,新規性喪失の例外を認める手続として特に定められたものであ ることからすると,権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような 場合には,本来,それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが,手 続を行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができるような密接に関連す る公開行為によって公開された場合については,別個の手続を要することなく同項 の適用を受けることができるものと解するのが相当であるところ,これにより本件 についてみると,証拠(乙16の1,2)によれば,Q2コープ連合及びQ1生活 協同組合は,いずれも日本生活協同組合連合会の傘下にあるが,それぞれ別個の法 人格を有し,販売地域が異なっているばかりでなく,それぞれが異なる商品を取り 扱っていることが認められる。すなわち,上記証明書に記載された原告のQ1生活 協同組合における販売行為とQ2コープ連合における販売行為とは,実質的に同一 の販売行為とみることができるような密接に関連するものであるということはでき ず,そうであれば,同項により上記Q1生活協同組合における販売行為についての 証明書に記載されたものとみることはできないことになる。
・・・・
上記検討した両製品において同一といえる形態的特徴のうち,本体部の形態 が長方形であるという点は,ドラム式洗濯機のリントフィルタに装着して用いる商 品である原告製品及び被告製品にとっては,リントフィルタの内面に沿って装着す るために必然的にもたらされる形態であるといえ,したがってこれは,その機能を\n確保するために不可欠なことであると認められる。また,もう一つの同一といえる 形態的特徴である本体部にスリットが存在するという点も,本件発明の効果をもた らすことに直接関係した形態であることからすると(上記第2の2(2)(10)),これも 両製品に共通する機能を確保するために不可欠な形態であるといえる。\nしたがって,これらの基本的形態で両製品の形態の同一性が認められたとしても, これによって両製品の形態が実質的に同一ということはできないというべきである (なお被告は,これらの形態の特徴をとらえて原告製品はありふた形態であって保 護されないと主張するが,原告製品が市販される以前に,同種の製品が市場に存し た事実は認められないから,商品の形態がありふれていることで保護されないわけ ではなく,機能確保に不可欠な形態として保護の限界が検討されるべきである。)。\n他方,上記検討したとおり,原告製品と被告製品は,機能確保のため必要とされ\nる形態的特徴以外の部分の細部における特徴的な形態というべき部分において形態 の差異が多数あるというのであるから,両製品の形態が酷似しているとはおよそい えず,結局,原告製品と被告製品は形態が実質的に同一であるとはいえないという べきである。
(5) これに対して原告は,両製品は主として通信販売されており,需要者が商品 を手に取って詳細に観察することがなければ両者の違いを認識し得ないから,両製 品の形態の差異は微細な差異で形態が実質的に同一であるということを妨げないよ うに主張するが,不正競争防止法2条4項に「商品の形態」は「需要者が通常の用 法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の 形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。」と定義されてい ることに明らかなように,本件で問題とすべき原告製品及び被告製品の形態とは, 上記検討したような包装袋から取り出された商品そのものの形態であって,これと 異なる前提に立つ原告の主張は失当である。 さらに,原告は,両製品の包装におけるチラシが共通することも指摘するが,原 告製品及び被告製品は,包装と一体となって切り離し得ないものではないから,原 告が指摘する包装のチラシは「商品の形態」とはいえず,原告の指摘は当たらない。
(6) 以上からすると,原告製品と被告製品とは,その形態が実質的に同一とはい えないから,被告製品は原告製品を模倣した商品とはいえず,被告が不正競争防止 法2条1項3号の不正競争をしたことを前提とする原告の請求はその余の判断に及 ぶまでもなく理由がない。
・・・・
(1) 原告は,平成27年6月11日頃,被告の取引先であるP1に対し,被告製 品は原告製品の形態を模倣した商品であり被告製品を販売する行為は不正競争防止 法2条1項3号に該当するとして,被告製品の販売の停止及び廃棄を求める内容を 記載した「申入書」と題する書面を内容証明郵便で送付している(本件告知行為)。\n上記2のとおり,被告製品は原告製品の模倣商品でないから,上記「申入書」の\n記載内容は虚偽の事実であるとともに,被告の営業上の信用を害する事実であると いうべきである。そして,原告と被告は競争関係にあるから,本件告知行為は,「競 争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」する行為といえ,不 正競争防止法2条1項15号所定の不正競争に該当する。
(2) そのほか被告は,原告がした不正競争防止法2条1項15号該当の不正競争 行為として,原告が生活協同組合に対して被告の権利侵害の事実を理由として被告 製品の取扱いをすべきでない旨申し入れた旨主張する。\n確かに証拠(乙14の1ないし3,乙15,乙30)によれば,被告は,P2か ら被告製品の販売を中止された事実,及び,P2が被告に対し,被告製品の販売を 中止する理由として,原告の営業担当者から被告製品の販売企画を中止した方がよ いとの要望を受けたという生活協同組合のバイヤーから,そのことを理由に被告製 品の差替えの要望を受けたことを挙げていたことが認められる。 したがって,これらの事実によれば,P2における被告製品の販売中止が,原告 の営業担当の従業員がもたらした行為に起因することが認められそうであるが,前 掲証拠によれば,原告の営業担当者が生活協同組合のバイヤーに伝えた内容という のは「企画を中止した方が良い的な要望」というにとどまるというのであって,そ れだけでは原告が被告の権利を侵害したといった虚偽の事実が告知されたと認める に足りないものである。また,そもそも原告の営業担当の従業員が何らかの接触を したという生活協同組合のバイヤーは,どの生活協同組合であるかを含めて特定さ れておらず,その生活協同組合のバイヤーが実際に原告の営業担当の従業員から直 接働きかけを受けたのかを確かめようがないものである。これらのことからすれば, 原告の営業担当者の行為に起因してP2が被告製品の販売を中止したとしても,そ れをもって原告の不正競争行為を認定することは困難であるといわなければならな い。
(3) したがって,被告主張に係る原告がした不正競争防止法2条1項15号該当 の不正競争については,原告が,平成27年6月11日頃,被告の取引先であるP 1に対し,被告製品は原告製品の形態を模倣した商品であり被告製品を販売する行 為は不正競争防止法2条1項3号に該当する旨記載した「申入書」と題する書面を\n内容証明郵便で送付した事実の限度で認めるのが相当であって,それ以外の生活協 同組合に対する関係では同号の不正競争のみならず不法行為を構成する事実は認め\nられない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> その他特許
>> 104条の3
>> 商品形態
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2017.04.28
平成28(ワ)16088 著作権侵害損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成29年3月23日 東京地方裁判所
原告は,原告商品の製造を委託するに当たりBが作成した原画を被告に 交付した旨主張するが,そうであるとすれば,原告があぶらとり紙の名称 を変更した時点ないし被告との取引を中止した時点で,被告に対して上記 原画の返還を求め,あるいはその保管状況を問い合わせるなどの行動をと るべきものと解される。ところが,本件の証拠上,原告がそのような行動 をとったことはうかがわれず,B が作成したという原画の存在自体定かで ないといわざるを得ない。 なお,被告商品の原画に関しては,被告が「ふるや紙」の文字は書家の 書いた色紙(乙10)によるものであると主張するのに対し,原告は,色 紙の作成者に関する被告の主張が変遷し,作成時期も不明であるので,被 告の主張は失当であるとする。被告の主張が変遷したことは原告指摘のと おりであるが,本件著作物がBの作成であると認められない以上,この点 は本件の結論に影響するものでない。 イ 被告商品は遅くとも平成12年から販売され,また,被告は被告デザイ ンに酷似する「ふるや紙」の文字を用いたあぶらとり紙を平成3年から販 売していたが(前記前提事実(2)イ),原告は,平成27年12月に B が被 告に対して書面を送付するまで,被告に対して本件著作権の侵害その他何 らの異議を唱えていない(甲5,7,弁論の全趣旨)。この点につき,原 告は被告商品の存在を認識していなかった旨主張するが,原告は(所在地 は省略)で土産物店を経営する会社であり(前記前提事実⑴ア),また, 被告商品は原告の主張によれば20年間にわたり毎年100万冊が販売さ れていたというのであるから,その存在に気付かなかったというのは不自 然と解さざるを得ない。
ウ 本件著作物を表紙デザインに用いた原告商品は雑誌で紹介されるなどし\nて広く販売されており(前記前提事実(2)ウ),A は平成5年3月に本件著 作物のうち左下の文字を除いた部分からなる商標の商標登録出願をしたが (甲33),原告は,翌年8月頃,商品の名称を「ふるや紙」から「ゆと り紙」に変更した(前記前提事実(2)ウ)。この変更の理由につき,原告は, 他社が「ふるや紙」という名称のあぶらとり紙を販売し,原告商品との誤 認混同が生じたためである旨主張するが,原告商品が「ふるや紙」として 広く知られており,A が考案したという名称につき商標登録出願をしたと いうのであれば,他社に対して商品名の変更を求めることなく,自らが変 更することは不合理と解される。 (3) したがって,原告の主張はいずれも失当であり,原告が本件著作物の著作 権者であると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2017.04.27
平成26(ワ)34678 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年4月21日 東京地方裁判所(40部)
上記各記載によれば,本件発明の意義は,次のとおりであると認められる。 従前,シリンダボア内に冷媒を導入するためにロータリバルブが採用され たピストン式圧縮機においては,吐出行程にあるシリンダボア内の冷媒がこ のシリンダボアに連通する吸入通路からロータリバルブの外周面に沿ってシ リンダボア外に漏れやすいという課題があり,このような課題はバルブ収容 室の内周面とロータリバルブの外周面との間のクリアランスを極力小さくす ることにより解決されるものの,他方で,このクリアランス管理は非常に難 しいという課題があった。 そこで,本件発明は,吐出行程にあるシリンダボアに連通する吸入通路の 入口に向けてロータリバルブを「付勢」し,ロータリバルブの外周面を吸入 通路の入口に近づけるという構成を採用することによって,圧縮室内の冷媒\nを吸入通路から漏れ難くし,よって体積効率を向上させるという作用効果を 有するものである。
・・・・
まず,被告は,本件特許の出願過程における乙26意見書に「引用文 献1〔判決注:乙21公報〕に記載された発明とは,従来からのニード ルベアリングのような転がり軸受ではなく,ジャーナル軸受を採用する ことによって,回転軸側のジャーナル部とシリンダブロック側の滑り軸 受との間のクリアランスを極めて小さくし,その結果,ロータリバルブ からの冷媒漏れを抑制するというものです。あくまでも,ジャーナル部 と滑り軸受との間のクリアランス管理に基づいて冷媒漏れの抑制を実現 しているのであって,本願発明のように,ピストンに対する圧縮反力を ロータリバルブへの付勢力に変換し,ロータリバルブの外周面を直接, 吸入通路の入口に付勢することによって冷媒漏れを抑制する技術とは明 確に異なるのです。」と記載されていることを根拠に,原告が本件発明 の技術的範囲から「クリアランスが小さい場合」を意識的に除外してい ると主張する。 しかし,乙26意見書の上記部分は,その記載内容からも明らかなと おり,乙21発明の「ジャーナル軸受を採用することによって,回転軸 側のジャーナル部とシリンダブロック側の滑り軸受との間のクリアラン スを極めて小さし,その結果」冷媒漏れを抑制する技術と,本件発明の 「ピストンに対する圧縮反力をロータリバルブへの付勢力に変換し,ロ ータリバルブの外周面を直接,吸入通路の入口に付勢することによって」 冷媒漏れを抑制する技術とが相違することを述べたものにすぎず,「ク リアランスが小さい場合」を本件発明の技術的範囲から除外したものと 解することはできない。このことは,乙26意見書の上記部分の直前に 「引用文献1〔判決注:乙21公報〕に記載された発明は・・・ジャー ナル軸受をもってロータリバルブを支持する点に特徴があります。」と 記載され,さらに,乙21公報の「回転軸を支持する軸受がジャーナル 軸受であり,それが単にシリンダブロック内に設けられた滑り軸受と, 回転軸の一部であるジャーナル部によって構成される簡単な構\造である だけでなく,そのジャーナル軸受の構成部材自体に半径方向の吸入通路\nや吸入ポートを形成して,各シリンダに対して圧縮すべき流体を吸入さ せるための吸入弁を構成しているため,軸受構\造と吸入弁の構造が簡単\nになるだけでなく,滑り軸受の円筒内面の仕上げ加工が容易に行われて, ジャーナル部とのクリアランスをきわめて小さくすることが可能になり,\n圧縮された流体が吸入弁から漏洩することがない。」との記載が引用さ れていることからも明らかである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.04.27
平成28(行ケ)10106 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月25日 知的財産高等裁判所
以上のとおり,引用発明1も,引用発明2も,蒸発(揮発)したニコチンを,肺 へ送給するに当たり,好ましい送給量を実現できるよう調整するという同一の目的 を有するものであり,また,タバコ代替品として用いられる装置に関するものであ って同一の用途を有するものである。そして,引用発明1と引用発明2とは,ニコ チン源の相違という点をもって作用が異なると評価することもできない。 よって,引用発明1に引用発明2を適用する動機付けはあるというべきである。
キ 阻害事由
原告は,引用発明1の目的は,タバコ(天然物ニコチン源)の使用をやめさせる ことであるとして,引用発明1のニコチン源を,天然物ニコチン源とすることには 阻害事由がある旨主張する。しかし,前記エのとおり,引用発明1に係る装置は, タバコをベースとした製品の代わりになるものであって,タバコ代替品としても用 いられるものであるから,引用発明1の目的を,タバコの使用をやめさせることの みにあるということはできない。原告の阻害事由の主張は,その前提において誤り である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2017.04.27
平成28(ネ)10106 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成29年4月25日 知的財産高等裁判所(4部) 東京地方裁判所
まず,本件商標と被告各標章「フェルゴッド」との部分からは,いずれも特定の 観念を生じないものである。 次に,本件商標からは「フェルガード」の称呼を生じ,被告各標章の「フェルゴ ッド」の部分からは「フェルゴッド」の称呼を生じるところ,両称呼は,「フェル」 で始まり「ド」で終わるとの点において共通するが,両称呼を一連に称呼した場合 には,称呼全体の語調,語感において異なる印象を与えるものというべきである。 さらに,本件商標と被告各標章の「フェルゴッド」の部分の外観についてみても, 同様に「フェル」で始まり「ド」で終わるとの点において共通するが,本件商標は 「フェルガード」(標準文字)から成り,「フェル」や「ド」の部分が特に強調さ れているということもなく,この点は被告各標章の「フェルゴッド」の部分につい ても同様であるから,本件商標と被告各標章の「フェルゴッド」の部分とを一体的 に観察すれば,両者の外観は異なる印象を与えるものというべきである。 以上によれば,本件商標が付された原告商品と被告各標章が付された被告各商品 とがいずれもフェルラ酸とガーデンアンゼリカを主成分とする健康補助食品であり, いずれも白色系統色を基調とする外箱を包装とする点,通信販売により販売されて いる点,認知症の患者及びその家族を需要者とする点などにおいて共通すること, 本件商標が付された原告商品について紹介する書籍,論文,記事等が複数存在する ことを考慮しても,なお,本件商標と被告各標章とを対比したときに,需要者にお いて,商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない から,被告各標章は,本件商標に類似しないというべきである。
・・・
ア 原告は,本件商標を付した原告商品が,フェルラ酸を使用した認知症サプリ メントの先駆け的な商品であって,「フェルラ酸含有食品」といえばまず本件商標 を想起するというほど,本件商標は,医師,認知症患者及びその家族のみならず, 全国的に周知された著名な商標であると主張する。 そこで検討するに,前記4(ア)のとおり,確かに,原告商品を紹介する書籍,論文, 記事等が複数存在することが認められる。しかしながら,上記各書籍の発行部数等 は明らかではないし,論文や会議での発表についてはその対象が相当程度限定され\nたものであることが推認できるほか,上記雑誌等の紹介記事をもっても,本件商標 が具体的にどの程度認知されているのかは判然としないというほかはない。現に, 原告自身が提出する証拠によっても,原告商品の利用者数は5000人ないし60 00人というのであって,我が国の人口や,そのうち認知症に罹患していると推定 される患者数やその家族の人数との比較からしても,本件商標が全国的に周知され た著名な商標であるとは認め難いというほかはない。よって,本件商標の周知性, 著名性を前提として本件商標と被告各標章との対比を行うべきかのような原告の主 張は採用することができない。
2017.04.24
平成28(ワ)20818 特許権侵害差止請求事件 特許権 平成29年4月19日 東京地方裁判所(29部)
被告らは,仮に,構成要件1Gの「切り残し突起(16)」が,本件明細書等の【図8】(b)に示す形態に限られず,例えば下図(平成23年6月27日付\nけ意見書〔乙19〕の参考図1)の符号16のような形態のものまでも含むという のであれば,かかる形態は,発明の詳細な説明に記載されたものでも示唆されたも のでもないから,本件発明1(並びに本件発明1の構成要件を発明特定事項として引用する本件発明2及び同3)についての特許は,発明の詳細な説明に記載されて\nいない発明についてされたものとして,サポート要件違反の無効理由があると主張 する。
イ 特許請求の範囲の記載が,発明の詳細な説明に記載したもの(特許法36条 6項1号)といえるか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と を対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発 明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識 できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時 の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきものである(知財高裁平成17年(行ケ)第10042 号同年11月11日特別部判決参照)。
ウ 本件特許の特許請求の範囲の請求項1には,前記前提事実(2)のとおり,連続 貝係止具において,「隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可 撓性連結材(13)で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連 結材(13)と一体に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止 め突起(3)よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)\nの夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心 よりも夫々のロープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13) を切断すると,その切り残し突起(16)が2本のロープ止め突起(3)の内側に 残るようにした」旨が記載されている。
エ 本件明細書等の発明の詳細な説明には,次の記載がある(末尾の【】は,段 落番号を示す。)。 「本発明の連続貝係止具は,隣接する貝係止具11の2本のロープ止め突起3間 が2本の可撓性連結材13で連結され,2本の可撓性連結材13は貝係止具11が 差し込まれる縦ロープCの直径よりも広い間隔で2本のロープ止め突起3寄り箇所 を連結するので,貝係止具11を一本ずつ切断するときに可撓性連結材13の一部 が図8(b)のように切り残し突起16となって基材1に残って基材1から突出し ても,図8(a)のように貝係止具11を縦ロープCへ差し込むときに切り残し突 起16が邪魔にならず,縦ロープCが2本のロープ止め突起3間におさまり安定す る。又,貝係止具11を手で持って貝へ差し込むときに手(指)が切り残し突起1 6に当たらないため手が損傷したり,薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をしても 手袋が破れたりしにくい。」【0008】 「(連続貝係止具の実施形態1)本発明の連続貝係止具は図8(a)のように前 記実施形態の貝係止具11を間隔をあけて数千〜数万本平行に配置し,上下に隣接 する貝係止具11の基材1間を丸紐状の可撓性連結材13で連結して樹脂成型して 図12(a)(b)のようにロール状に巻くことができるようにしたものである。 図8(a)の場合はハ字状の2本のロープ止め突起3の間を2本の可撓性連結材1 3で連結してあり,しかも,2本の可撓性連結材13をロープ止め突起3寄り箇所 に配置して,2本の可撓性連結材13の間隔を縦ロープCの直径よりも広くしてあ る。このようにすると貝係止具11を一本ずつ切断する場合に可撓性連結材13の 一部が切り残されて図8(b)のように基材1に切り残し突起16が発生しても, それが縦ロープCへの差込時に邪魔になることがない。また,一本ずつ切断された 貝係止具11を貝の孔に差し込むために手で持っても切り残し突起16の部分が手 に当たらないため手が怪我したり,手に嵌めた作業用手袋が破れたりしにくい。」 【0026】
オ 上記に認定したところによれば,本件明細書等の発明の詳細な説明には,2 本の可撓性連結材による連結箇所を,2本のロープ止め突起の間で,かつ,2本の ロープ止め突起寄りの箇所とする構成により,可撓性連結材を切断したときに切り残し突起が残ったとしても,貝係止具を縦ロープへ差し込むときに切り残し突起が\n邪魔にならず,また,貝係止具を手で持って貝へ差し込むときに手(指)が切り残 し突起に当たらないため手が損傷したり,薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をし ても手袋が破れたりしにくいとの作用効果を奏することが明確に記載されている。 そうすると,本件明細書等の発明の詳細な説明に接した当業者において,本件発 明1に係る特許請求の範囲に記載された構成,すなわち,2本の可撓性連結材(13)による連結箇所を,2本のロープ止め突起(3)のそれぞれから内側に離れた\n箇所であり,かつ,2本のロープ止め突起(3)間の中心よりもそれぞれのロープ 止め突起(3)寄りの箇所とする構成を採用することにより,可撓性連結材(13)を切断した際の切り残し突起(16)の高さにかかわらず,本件発明1に係る課題\nを解決できると認識できることは明らかであるから,本件発明1が,発明の詳細な 説明に記載されていないものということはできない。同様の理由により,本件発明 2及び同3が,発明の詳細な説明に記載されていないものということはできない。 したがって,被告らの主張する無効理由2は認められない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2017.04.24
平成28(行ケ)10212 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月18日 知的財産高等裁判所
(イ) 他方,原出願明細書には,絶縁球を備えない接触端子は記載されていない。 また,前記(2)オのとおり「絶縁球30には,圧縮バネから成るコイルバネ31がそ の一端部を当接させている。…なお,コイルバネ31には絶縁体被膜を与えられて いてもよい。」(【0025】),「コイルバネ31は,絶縁被膜を与えられてこ れが剥がれ落ちたとしても,介在する絶縁球30に確実に阻まれてプランジャーピ ン20に接触し得ず,プランジャーピン20に対して確実に絶縁される。つまり, プランジャーピン20に比較的大なる電流を流しても,コイルバネ31の焼き切れ を確実に防止できる。」(【0027】)との記載があり,これらは,コイルバネ 自体に絶縁体被膜が与えられており,それによってコイルバネに電流が流れるのを 防ぎ得る場合であっても,プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球を介在さ せてプランジャーピンとコイルバネとの絶縁を確実なものとする趣旨である。前記 のとおり絶縁球を備えない接触端子は記載されていないことをも併せ考えれば,原 出願明細書においては,プランジャーピンとコイルバネとの間に必ず絶縁球を介在 させてコイルバネに電流が流れないようにすることによりコイルバネの焼き切れ防 止に確実を期しており,コイルバネに絶縁体被膜を与えるなどコイルバネに電流が 流れるのを防ぐその他の手段と併用することはあっても,同手段をもって絶縁球に 代えること,すなわち,接触端子を,絶縁球を含まないものとすることは想定され ていないものと解するべきである。
3 分割出願の要件について
(1)本件特許出願の分割出願の要件
分割出願は,原出願の時にしたものとみなされるところ(特許法44条2項), そのためには,分割出願に係る発明が,原出願の願書に添付された明細書,特許請 求の範囲又は図面の範囲内のものであることを要する。 前記1のとおり,本件発明1には,プランジャーピンの大径部とコイルバネとの 間にあって,プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付け る「球の球状面からなる球状部」が導電性を有し,絶縁球を備えない接触端子も含 まれる。 他方,前記2(1)のとおり,本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1から9に係 る構成のいずれも,プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間に介在する絶縁\n球を含むものである。また,前記2(3)イのとおり,原出願明細書においては,絶縁 球を備えない接触端子は記載されておらず,プランジャーピンとコイルバネとの間 に介在する絶縁球は必須の構成とされているものと解される。\nよって,本件発明1は,絶縁球を含まない接触端子という,原出願明細書,特許 請求の範囲及び図面に記載されていない発明を含むものであるから,本件特許出願 は,分割出願の要件を満たすものということはできない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,コイルバネに電流を流さないことは,原出願明細書の背景技術に記 載された公知技術によって既に解決された課題であるから,原出願発明の課題には ならないとして,原出願発明の課題は,プランジャーピンを本体ケースに対してよ り確実に押し付け,プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことであ る旨主張する。 しかし,既存の技術によって解決可能な課題であっても,例えばより効率よく解\n決する,解決による効果をより高めるなど解決方法等につき改善の余地がある場合 も考えられる。よって,コイルバネの焼き切れを防ぐためにコイルバネに電流を流 さないことが,原出願明細書の背景技術に記載された公知技術によって解決されて いることをもって,直ちに,原出願発明の課題から除外されるとはいえない。 そして,前記2(3)アのとおり,原出願明細書に,1)比較的大なる電流を,プラン ジャーピンを介して本体ケースに流す際,コイルバネに電流が流れると抵抗加熱に よりコイルバネが焼き切れてしまうことがあること,2)プランジャーピンとコイル バネとの間に絶縁球ないし絶縁球及び導電球を介在させてコイルバネに電流を流さ ないような機構を与えた接触端子においては,コイルバネに電流を流すことなく,\nプランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができること,3)接触端 子の径(幅)を大きくして電流路の断面積を大きくする方法は,コイルバネを流れ る電流量を小さくすることができるものの,電気機器の小型化に対応する点からは, 好ましい方法ではないこと,4)原出願発明1から9に係る構成につき,「コイルバ\nネに電流を流すことなく,プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すこ とができ,接触端子に比較的大なる電流を流し得る」旨の記載があることから,原 出願明細書には,原出願発明の課題として,コイルバネの焼き切れを防ぐために, コイルバネに電流を流すことなく,プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流 を流すことができ,比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供することが記載さ れているものということができる。
イ 原告は,仮に原出願明細書において,コイルバネに電流を流さないことが課 題として記載されていたとしても,これとは別の独立した課題として,プランジャ ーピンを本体ケースに対してより確実に押し付け,プランジャーピンから本体ケー スへ確実に電流を流すという課題も記載されており,同課題に焦点が当てられてい る旨主張する。 しかし,前記2(3)アのとおり,原出願発明の目的は,比較的大なる電流を流し得 る接触端子の提供であり,そのような接触端子を得るためには,プランジャーピン を介して本体ケースへ比較的大なる電流を確実に流すことが必要となるが,その際, コイルバネに電流が流れるとコイルバネが焼き切れてしまうことがあるので,これ を防ぐために,コイルバネに電流を流さないようにする必要がある。したがって, コイルバネに電流を流さないという課題は,比較的大なる電流を流し得る接触端子 を得るためにプランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すという課題を解 決する際に生じ得るコイルバネの焼き切れの防止を目的とするものであるから,上 記両課題は別個独立のものということはできない。
ウ 原告は,原出願明細書の【0005】には,プランジャーピンを本体ケース に押し付ける押付部材としての導電球が明記されているなどとして,原出願明細書 を全体として見れば,押付部材としての導電球も開示されており,よって,絶縁球 に代えて,例えば絶縁被膜を与えない導電球を用いることも想定されている旨主張 する。 確かに,原出願明細書の【0005】には,背景技術として記載された公知技術 の1つとして,プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球及び導電球が介在し, 導電球がプランジャーピンを本体ケースに押し付ける接触端子が記載されている。 しかし,本件発明1は,絶縁球を備えない接触端子を含むものであるところ,前 記2(3)イのとおり,原出願明細書においては,プランジャーピンとコイルバネとの 間に必ず絶縁球を介在させてコイルバネに電流が流れないようにすることによりコ イルバネの焼き切れ防止に確実を期しており,コイルバネに電流を流れるのを防ぐ その他の手段と併用することはあっても,同手段をもって絶縁球に代えること,す なわち,接触端子を,絶縁球を含まないものとすることは,想定されていないもの と解すべきである。原出願明細書には,「以上,本発明による実施例及びこれに基 づく変形例を説明したが,本発明は必ずしもこれに限定されるものではなく,当業 者であれば,本発明の主旨又は添付した特許請求の範囲を逸脱することなく,様々 な代替実施例及び改変例を見いだすことができるであろう。」という旨の記載 (【0043】)があるものの,絶縁球を備えない接触端子とすることは,「本発 明の主旨」を逸脱するものといえるから,「様々な代替実施例及び改変例」の範ち ゅうに入らない。 したがって,本件発明1は,絶縁球を備えない接触端子を含むという点において, 原出願明細書に記載されていない発明を含むものである。 エ 原告は,仮に,原出願明細書に押付部材としての導電球が直接記載されてい ないとしても,押付部材として導電球を用いることは技術常識であるから,押付部 材としての導電球は,原出願明細書に記載されているに等しい事項である旨主張す る。 しかし,仮に押付部材として導電球を用いることが技術常識であったとしても, 前記ウのとおり,本件発明1が,絶縁球を備えない接触端子を含むという点におい て,原出願明細書に記載されていない発明を含むものであることに変わりはない。
2017.04.24
平成28(行ケ)10161 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月18日 知的財産高等裁判所(4部)
本件発明1の構成要件Hは,原出願明細書中,継手ピッチ19が400mmと6\n00mmのように200mm程度以上の寸法差を有する鋼矢板15の双方を施工可 能な鋼矢板圧入引抜機が提供されていなかったという従来技術が有する問題点の理\n由のうち,クランプ装置に関する問題を解決する手段,すなわち,クランプ装置を 構成する複数のクランプ部材の台座への配設箇所を組み替えて,クランプピッチを\n変更可能とすることにより,クランプする既設の鋼矢板が多様な継手ピッチを有し\nていたとしても,既設の先頭の鋼矢板をクランプ装置でクランプした状態で鋼矢板 圧入引抜機を既設の鋼矢板上に定置するという構成を採用したものということがで\nきる。 そして,クランプ装置は,チャック装置によって圧入・引抜作業を行う鋼矢板を チャックする前に,既設の鋼矢板をクランプして鋼矢板圧入引抜機を定置するもの であり,チャック装置とは別個のものである。原出願明細書には,多様な継手ピッ チの鋼矢板に対応可能な汎用性を有する鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法\nを提供するために,従来技術のチャック装置に関する問題及びクランプ装置に関す る問題の両方の解決を要することは記載されているが,クランプ装置に関する問題 を解決するためにチャック装置に関する問題の解決を要することは,記載されてい ない。したがって,原出願明細書においては,本件発明1の構成要件Hが採用した\nクランプ装置に関する問題を解決する手段としての前記構成に,請求項4記載のチ\nャック装置を必須とすることまで記載されているとはいえない。
2017.04.24
平成28(行ケ)10155 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月18日 知的財産高等裁判所
本願明細書には,前記1(2)のとおり,本願発明は,リフレクタ上に又はリフレク タに光源をガイドする及び/又は固定するための更なる別個の構成要素を必要とす\nることなく,前記光源が,前記リフレクタの反射表面に対してあらかじめ規定され\nた位置において,前記リフレクタの後方の端部におけるリフレクタの頸部に直接的 に固定されることができるような照明装置を提供し,光源が,一方の手のみによっ て,容易に,確実に,速く,リフレクタに固定されるのを可能にすることを目的と\nし,課題の解決手段として,複数のロック部材がリフレクタ上に形成されており, 前記ロック部材は,前記リフレクタの光軸の周りの又は前記光軸に平行な軸の周り の光源の回転運動の動きの経路において,前記光源が前記光軸の方向において前記 リフレクタの頸部内に少なくとも部分的に挿入されている場合,前記光源内に形成 されている対応する穿孔と嵌合し,少なくとも1つの前記ロック部材は,このよう な仕方において前記回転運動の経路における少なくとも1つの穿孔と協働し,前記 光源が前記リフレクタに対する軸方向の規定された位置に保持されるように構成し,\nこれにより,ランプ(光源)のリフレクタへの固定がリフレクタ及びランプ(光 源)とは別個の付加的な留め具を必要とすることなく行われる等の作用効果を奏す るものであることが記載されている。 上記記載によれば,本願発明は,光源をリフレクタに固定する際の作業を念頭に, 当該作業において,光源とは別個の付加的な留め具等の構成を要することなく,光\n源の,光軸の方向におけるリフレクタ内への挿入及び当該光軸周りの又はそれに平 行な軸の周りの回転運動により,リフレクタ上に形成されたロック部材と光源にお いて形成された穿孔とを係合させることにより,リフレクタへのランプの位置決め 及び固定ができるようにしたものであると理解できる。そして,かかる特徴に照ら すと,本願発明における光源が,分解されることのない一体不可分に形成されたも のに限定されると特に解すべき理由はない。 さらに,本願明細書に記載された実施形態においては,「光源」に相当するもの として,「イグナイタ4,ガラス製エンベロープ11及びランプベース18を有す るガス放電ランプ3」が開示されているところ,これも複数の構成要素から組み立\nてられるものであること,並びに,イグナイタ4がガラス製エンベロープ11及び ランプベース18に回転が確実になるような仕方において固定されることが記載さ れる一方で(【0030】,【0035】,【0036】,【0038】),これ らが分解されることのない一体不可分に形成されたものであることについては何ら 記載がない。
(ウ) 以上によれば,本願発明における光源が,分解されることのない一体不可 分に形成されたものに限定されるということはできず,これには,分解可能な複数\nの構成要素から組み立てられるものも含まれるものと解される。\n
・・・
(ア) 原告らは,本願明細書の記載を参酌すれば,本願発明の光源は,一体的固 定的に形成されたものであり,光源3の交換の際にガラスエンベロープ11,ベー ス18及びイグナイタ4が分解されることはなく一体不可分であって,光源をガイ ドする別個の構成要素を要せずに,交換すべき光源を一方の手のみによって,容易\nに速くリフレクタに固定できる光源を意味すると解すべきである旨主張する。 しかし,前記イ(イ)のとおり,本願明細書に記載された本願発明の特徴に照らす と,本願発明における光源を,分解されることのない一体不可分に形成されたもの に限定されると特に解すべき理由はなく,実施形態における「光源」に相当するも のとして記載された「イグナイタ4,ガラス製エンベロープ11及びランプベース 18を有するガス放電ランプ3」についても,複数の構成要素から組み立てられる\nものであることが記載されている一方で,分解されることのない一体不可分に形成 されたものであることについては何ら記載がない。 本願明細書の記載によれば,前記イ(イ)のとおり,本願発明は,光源をリフレク タに固定する際の作業を念頭に,当該作業において,光源とは別個の付加的な留め 具等の構成を要することなく,光源の,光軸の方向におけるリフレクタ内への挿入\n及び当該光軸周りの又はそれに平行な軸の周りの回転運動により,リフレクタ上に 形成されたロック部材と光源において形成された穿孔とを係合させることにより, リフレクタへのランプの位置決め及び固定ができるようにしたものであると理解で きる。そして,光源をリフレクタに固定する際の作業において,光源のリフレクタ への固定がリフレクタ及び光源とは別個の付加的な留め具を必要とすることなく行 われるということは,光源自体がどのように構成されたものであるか(分解される\nことのない一体不可分に形成されたものであるか)を規定するものではない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2017.04.17
平成28(ワ)12829 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年3月30日 東京地方裁判所(47部)
ア 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品に つき,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を 受けない限り,商標権を侵害するが(商標法2条3項,25条),そのよ うな商品の輸入であっても,1)当該商標が外国における商標権者又は当該 商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり(第1 要件),2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが,同一人で あるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係がある ことにより,当該商標が,我が国の登録商標と同一の出所を表示するもの\nであって(第2要件),3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該 商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標 権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実 質的に差異がないと評価される場合(第3要件)には,いわゆる真正商品 の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解する のが相当である(最高裁判所平成15年2月27日第一小法廷判決・民集 57巻2号125頁)。
イ 原告は,NIC社製のセラコート塗料を購入した米国協力業者から国際 航空貨物運送業者を介して同塗料の送付を受けた国内協力業者から購入し ており,このことは証拠(甲23ないし28,37ないし40)から明ら かであるから,原告の輸入行為は第1要件を充足する旨主張するので,検 討する。 なお,本件発言等3は平成27年11月18日頃にされたものであるか ら,ここで第1要件を充足することが立証されるべき原告の輸入行為は, 上記時点より前のものであることは当然であり,かかる観点から検討を行 うこととする。 まず,上記各証拠は作成時期が1年以上異なるものも含まれているから, これらを一体として一連の輸出入等に関する証拠であると解することはで きない。 そして,証拠(甲23,24)及び弁論の全趣旨によれば,米国に所在 する氏名不詳の者(以下「A」という。)が,平成28年4月,NIC社 に同社製のセラコート塗料を注文してこれを購入したこと,及び,米国に 所在する氏名不詳の者が,同年5月5日,品名「PAINTS.VARN ISHES & SOLUTIONS,N.E.S」について,日本に所 在する氏名不詳の者に対する輸入許可を受けたことが認められる。しかし ながら,これらは,そもそもいずれも本件発言等3より約4月以上も後の 事実であるから,本件発言等3の内容が虚偽であるか否かの点に直接関係 を有しない上,輸入許可を受けた主体がAであるかは不明であり(甲24 は公正証書〔甲39〕の確認対象になっていない。),輸入許可に係る貨 物がNIC社製のセラコート塗料であるかも不明であり,原告が上記の日 本に所在する氏名不詳の者から上記荷物を受領したと認めるに足りる証拠 もない。 次に,証拠(甲25ないし28,39)及び弁論の全趣旨によれば,A が,平成27年7月25日付けで,日本に所在する氏名不詳の者(以下 「B」という。)に対し,品名「塗料」,総個数「3」を内容とする国際 航空貨物(運送状番号808486953648)を発送して同月27日 に輸出し,同月30日付けで,品名「液体入りプラスチック容器 Cer akote」「0.8kg H−168×1pce」とする内容点検確認 を受けたことが認められる。しかしながら,上記輸出入に係る荷物がNI C社製のセラコート塗料であるかは不明であり,原告がBから上記荷物を 受領したと認めるに足りる証拠もない。 さらに,証拠(甲39,40)によれば,原告が,平成28年5月25 日付けで,Bから品名を「セラコート」とする代金の請求を受けたことは 認められるが,これは本件発言等3より約6月も後の事実であり,上記代 金の対象が本件発言等3より前の取引に係るものであることも認めるに足 りないから,本件発言等3の内容が虚偽であるか否かの点に直接関係を有 しないし,そもそも,当該「セラコート」がNIC社製のセラコート塗料 であるか自体も不明である。 そうすると,原告の提出する上記各証拠をもって,原告が,本件各発言 等の前から,米国協力業者及び国内協力業者を介して,NIC社製のセラ コート塗料を継続的に輸入したと認めることはできず,他に当該事実を認 めるに足りる証拠はない。加えて,本件全証拠を検討しても,日本国内に おいて流通するセラコート塗料にNIC社製ではない非真正品が存在しな いと認めるに足りる証拠もない。 以上によれば,原告の輸入行為が第1要件を充足すると認めることはで きない。
・・・
(なお,原告は,平成29年2月28日付及び同年3月13日付で弁論再開 を求める上申書を当裁判所に提出したところ,その中には,前記第1要件について「追加証明は十\分可能,かつ,容易であると考えている」とか「この点に\nついて,さらに的確な立証活動を予定している」との記載がある。しかしながら,攻撃防御方法について適時提出主義が採られていることはいうまでもない\nところ(民訴法156条),原告は,自らの行為がいわゆる真正商品の並行輸 入として適法である旨主張して,平成28年4月20日に本件訴訟を自ら提起 したものであり,かつ,訴訟の当初から上記主張の成否は重要な争点となって いたのであるから,原告は早期に必要な立証活動を十分に行うことが当然できたはずである(原告が上申\書で述べるように,この点の証明が容易であるならば,尚更である。)。しかも,原告は,同年10月4日の第3回弁論準備手続 期日において「次回までに主張及び立証を尽くす」と述べ,同年12月1日の 第4回弁論準備手続期日において「並行輸入の第1要件について,他に主張及 び立証はない」と述べている。さらに,上記各上申書の内容を見ても,本判決の結論を左右するに足りるような記載はない。これらの事情に照らして,当裁\n判所は,本件口頭弁論を再開しないこととしたものである。)
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2017.04.13
平成28(行ケ)10208 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年3月23日 知的財産高等裁判所(2部)
原告は,本願商標は,1)「TOMATO」の欧文字部分だけが,独立して,見る者 の注意を惹くように構成されていない,2)「TOMATO」の欧文字部分は,出所識 別表示として強く支配的な印象を与えるものではない,3)「SYSTEM」の語に出 所識別機能がないとまではいえない,と主張する。
本願商標は,「TOMATO」と「SYSTEM」とを同じ字体で同じ大きさで横一 連にまとまりよく表記されているものではあるが,「TOMATO」と「SYSTEM」\nとの間に1文字分のスペースがあり,外観上,「TOMATOSYSTEM」なる一連 の語であるとは認められない。また,本願商標を構成する「TOMATO」及び「S\nYSTEM」の語は,いずれも,我が国において広く慣れ親しまれた英単語であると ころ,「SYSTEM」(システム)の語は,一般に「複数の要素が有機的に関係し あい,全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」を意味する語であ\nり(乙7),本願指定商品又は本願指定役務と関係する情報処理の分野では,ハー ドウェア又はソフトウェアの組合せを意味する語として用いられているから(乙8\n〜10),商品の品質又は役務の質を表したものとして,出所識別表\示としての機 能がないか又は極めて弱いということができる。一方,「TOMATO」(トマト)\nの語からは,まず,野菜のトマトが想起され,そのことは,本願指定商品又は本願 指定役務の取引者又は需要者においても同様であるところ,野菜のトマトと,本願 指定商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状等又は本願指定役務の\n提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様等との関連を想定できな\nいから,非常に強い印象を取引者又は需要者に与えるものである。したがって,本 願商標においては,「TOMATO」の欧文字部分が,取引者又は需要者に対し,商 品又は役務の出所識別標識として,強く支配的な印象を与える。そして,上記説示 から明らかなとおり,「TOMATO」と「SYSTEM」との間の観念的なつながり を見いだすことはできず,本願商標全体で特定の意味合いを想起させるということ はできない。 そうすると,本願商標の要部は「TOMATO」の部分であると認められ,これを 要部として分離抽出した審決の認定に誤りはない。 したがって,原告の上記主張は採用することができず,取消事由1は,理由がな い。
(2) 取消事由2(引用商標の引用適格の欠如)について
原告は,欧文字を標準文字で「TOMATO」と表した引用商標1は,「極めて簡\n単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」(商標法3条1項5号),又は, 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない 商標」(同項6号)であるから,無効であると主張する。 しかしながら,「TOMATO」からは,一般に,野菜のトマトが想起されるとこ ろ,このように明確に特定の観念を導く単語で構成された商標が,「極めて簡単で,\nかつ,ありふれた標章のみからなる商標」ということはできないから,引用商標1 が,商標法3条1項5号に規定された商標に該当することはない。また,広く用い られる語であるからといって,直ちに出所識別機能を欠くものではなく,指定商品\n又は指定役務との関係において検討されるべきものであるところ,引用商標1が, 指定役務との関係において,出所識別機能を欠くと直ちに認めることはできないか\nら,商標法3条1項6号に規定された商標に該当することもない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができず,取消事由2は,理由が ない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.04.13
平成28(行ケ)10249 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月23日 知的財産高等裁判所
本願明細書を参酌すると,本願発明は,バッテリの電力をDCモータに給電し, 起電コイルから生じた電力の一部をバッテリに充電しながらDCモータに再給電し てDCモータを永久に稼働させ,起電コイルから生じた電力の残りを外部に永久に 供給するとしたものであり,入力した以上の電力(エネルギー)を出力するとした ものであって,明らかに永久機関とみられるものである(なお,本願発明に係る特 許請求の範囲には,トルク脈動レス発電機を「連続的」に稼働させ続ける,電力を 「連続的」に給電し続けるとの記載があるが,この「連続的」が「永久」を意味す ることは,前記1に認定の本願明細書の記載から明らかである。)。 したがって,原告が自認するとおり,本願発明は,エネルギー保存の法則という 物理法則に反するものであるから,自然法則を利用したものではなく,特許法29 条1項柱書の「発明」ではない。
(イ) 原告の主張について
原告は,本願発明がエネルギー保存の法則を破るものであると主張するが,DC モータの銅損若しくは鉄損等の損失又は起動コイルの銅損の損失,あるいは,ネオ ジム磁石と起電コイルとの間で作用する力などを全く考慮しておらず,その主張は 失当である。 また,原告は,DCモータに給電した直流電圧よりも高い交流電圧が起電コイル に発生していると主張し,本願明細書の図4の記載を援用するが,起電コイルから の出力電圧が上がったからといって,DCモータに供給される電力(消費電力)よ りも起電コイルから出力される電力が上回るということはできないから,その主張 は失当である。
(ウ) 小括
以上から,本願発明は,特許法29条1項柱書の「発明」に該当しないから,発 明該当性を欠くとした審決の判断には,誤りはない。
ウ 実施可能要件について
本願発明は,自然法則に反するものであるから,本願明細書の発明の詳細な説明 のいかなる記載をもってしても,当業者が本願発明を実施できないことは明らかで ある。 したがって,本願明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法36条4項1号の実 施可能要件を欠くとした審決の判断には,誤りはない。\n
関連カテゴリー
>> 発明該当性
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2017.04.10
平成28(ワ)19633 損害賠償請求 特許権 民事訴訟 平成29年3月29日 東京地方裁判所
◆被告の製品はおそらくこれ
(1) 原告は,原告,被告,B及びCの4者間において,本件発明の実施は本件
販売形態のみによる旨合意していた(本件実施合意)と主張する。
しかし,本件特許の出願に際して作成された本件契約書には,本件発明の
実施につき,原告,被告,B及びCの4者間で協議の上「別途定める」との
記載があるものの(本件契約書第7条),これ以外に何らの記載はなく,ま
た,「別途定める」に該当するような,本件販売形態を唯一の実施形態とす
る旨の合意がされたことを裏付ける契約書,合意書その他の書面は本件証拠
上存在しない。
この点に関して原告は,本件販売形態を唯一の実施形態とする旨の記載が
一応ある「特許発明の実施についての確認書」と題する書面(甲7の1)を
提出する。しかし,そもそも同書面には原告,B及びCの署名指印しかなく,
被告はこれに記名押印をしていないし,同書面の作成日自体,本件特許の出
願日(平成24年7月4日)から4年近くも後の平成28年4月26日であ
って,出願日当時の合意の存在を直接裏付けるものですらない。
そもそも,原告の主張自体も,本件実施合意を,いつ,どこで,どのよう
に取り決めたのかなどにつき具体的に特定しているものではない。また,原
告は,本件実施合意があったことを立証するものとして原告作成の陳述書
(甲19,22)及び被告の元従業員であるE(以下「E」という。)作成
の事情説明書(甲18,21)を提出するが,客観的裏付けを欠くことに変
わりはない上,このうちE作成の事情説明書については,「・・・という仕
組みでビジネスがされていたと考えます」(甲18・4頁),「当然,その
ような役割分担で動いていたものと理解しています」(甲21・3頁)など
という,単なるE自身の推測を述べるものでしかない。
そうすると,原告,被告,B及びCの4者間において,仮に本件販売形態
がかつて存在していたとしても,これをもって本件発明の唯一の実施形態と
する旨の合意がされていたと認めることはできない。
(2) したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求のうち
本件実施合意の債務不履行に基づく損害賠償請求は,理由がない。
2 争点(2)(特許法73条2項の適用の可否)について
原告は被告による被告各商品の製造・販売が本件特許権を侵害する旨主張す
るが,そもそも被告は本件特許権の共有者であり(前記第2,2(2)),共有
者であれば,契約で「別段の定」(特許法73条2項)をした場合を除き,他
の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができるから,被告
は,原則として,本件発明を実施することができるというべきである。
この点につき原告は,「別段の定」として,本件販売形態を唯一の実施形態
とする旨の本件実施合意があったと主張するが,上記1(1)のとおり,そのよ
うな合意があったとは認められない。そして,原告が他に「別段の定」の存在
を主張立証していない以上,本件特許権については「別段の定」は存在せず,
被告は,原則どおり,原告その他の共有者の同意を得ないで被告各商品を製造
・販売することができると認めるのが相当である。
2017.04. 4
平成27(行ケ)10242 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月20日 知的財産高等裁判所
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法 が記載されている場合(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレ ームの場合)において,当該特許請求の範囲の記載が法36条6項2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるの は,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定するこ\nとが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在する\nときに限られると解される(最高裁判所第二小法廷平成27年6月5 日判決・民集69巻4号700頁)ところ,本件発明1に係る上記記 載は,これを形式的に見ると,確かに経時的な要素を記載するものと いうこともでき,プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する と見る余地もないではない。 しかし,プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との 関係で問題とされるのは,物の発明についての特許に係る特許請求の範 囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に,その特許権の 効力が当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物\nに及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば,その 製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表\しているのかが不明で あることなどから,第三者の利益が不当に害されることが生じかねない ことによるところ,特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であ ることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても,当該製造方 法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断\nすれば一義的に明らかである場合には,上記問題は生じないといってよ い。そうすると,このような場合は,法36条6項2号との関係で問題 とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はないと思 われる。
(ウ) ここで,本件明細書の記載を参酌すると,本件明細書には「二重瞼 形成用テープは,図2に示すように,弾性的に伸縮するX方向に任意 長のシート状部材11の表裏前面に粘着剤12を塗着…し,これを多\n数の切断面Lに沿って細片状に切断することにより,極めて容易に製 造することができる。」(甲1の段落【0013】)という態様,す なわち,粘着剤を塗着した後,細いテープ状部材を形成する態様を含 めて「図1及び図2に示す実施例では,弾性的に伸縮する細いテープ 状部材の表裏両面に粘着剤2を塗着している」(同段落【0014】)\nと記載されている。また,本件発明1は,「テープ状部材の形成」と 「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず,テープ状部材に粘着剤が塗 着された状態のものであれば二重瞼を形成し得ること,すなわちその 作用効果を奏し得ることは明らかである。 そうすると,本件発明1の「…細いテープ状部材に,粘着剤を塗着す る」との記載は,細いテープ状部材に形成した後に粘着剤を塗着すると いう経時的要素を表現したものではなく,単にテープ状部材に粘着剤が\n塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎな\nいものと理解するのが相当であり,物の製造方法の記載には当たらない というべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.04. 4
平成27(行ケ)10184 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月29日 知的財産高等裁判所
オ 原告らは,本件発明の「こそぎ落とし又は溶融除去することにより」との記 載は,物の製造方法が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームであ るから,明確性要件に適合しないなどと主張する。 しかし,証拠(甲25)及び弁論の全趣旨によれば,原告らの上記主張は,本件 の特許無効審判において無効理由として主張されたものではなく,当該審判の審理 判断の対象とはされていないものと認められるから,もとより本件訴訟の審理判断 の対象となるものではなく(最高裁判所昭和42年(行ツ)第28号同51年3月 10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照),失当というほかない。 なお,この点につき付言するに,PBP最高裁判決は,物の発明についての特許 に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合に,出願時におい て当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか又はおよそ 実際的でないという事情(以下「不可能・非実際的事情」という。)が存在するとき\nに限り,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう明確性要件に適 合する旨判示するものである。このように,PBP最高裁判決が上記事情の主張立 証を要するとしたのは,同判決の判旨によれば,物の発明の特許に係る特許請求の 範囲にその物の製造方法が記載されている場合には,製造方法の記載が物のどのよ うな構造又は特性を表\しているのかが不明であり,特許請求の範囲等の記載を読む 者において,当該発明の内容を明確に理解することができないことによると解され る。そうすると,特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっ ても,当該製造方法の記載が物の構造又は特性を明確に表\しているときは,当該発 明の内容をもとより明確に理解することができるのであるから,このような特段の 事情がある場合には不可能・非実際的事情の主張立証を要しないと解するのが相当\nである。 これを本件についてみるに,本件発明の「該燃焼芯にワックスが被覆され,かつ 該燃焼芯の・・・先端部に被覆されたワックスを,該燃焼芯の先端部以外の部分に 被覆されたワックスの被覆量に対し,ワックスの残存率が19%〜33%となるよ うこそぎ落とし又は溶融除去することにより前記燃焼芯を露出させる・・・ことを 特徴とするローソク」という記載は,その物の製造に関し,経時的要素の記載があ\nるとはいえるものの,ローソクの燃焼芯の先端部の構\造につき,ワックスがこそぎ 落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状 態であることを示すものにすぎず,仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解 したとしても,本件発明のローソクの構\造又は特性を明確に表しているといえるか\nら,このような特段の事情がある場合には,PBP最高裁判決にいう不可能・非実\n際的事情の主張立証を要しないというべきである。 したがって,原告らの主張は,PBP最高裁判決を正解しないものであり,採用 することができない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.04. 3
平成28(ワ)35838 特許法違反請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年3月23日 東京地方裁判所
上記アの事実関係によれば,1)本件特許出願に係る書類及び本件拒絶 理由通知に対する手続補正書ないし意見書の作成に当たり,原告が表明し\nた意向を受けて被告が書面の案を作成して説明を行い,これを受けて原告 が意向を改めるなどした結果,本件特許出願に係る書類につき平成28年 2月13日頃に,上記手続補正書及び意見書の内容につき同年9月11日 にそれぞれ原告と被告との間で合意した内容を原告が本件委任契約に基づ き被告に対して記載を求める内容として確定させたこと,2)被告が上記各 合意内容どおりの内容を記載した上記各文書を特許庁に対して提出したこ とが明らかであるから,被告が特許庁に対して提出した上記各文書に記載 のないものは,原告が被告に対して記載を求めた内容に含まれないとみる べきである。そうすると,アイデア書(甲5)の内容,モータ駆動部に関 する文章及び原告の主張する前記補正内容につき上記各文書に記載されて いない部分があるとしても,被告がこれを記載しなかったことが応答ない し補正義務違反等に当たるとは解されない。
2017.03.31
平成27(行ケ)10252 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月27日 知的財産高等裁判所(3部)
本件のように,冒認出願(平成23年法律第63号による改正前の特許法 123条1項6号)を理由として請求された特許無効審判において,「特許 出願がその特許に係る発明の発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継 した者によりされたこと」についての主張立証責任は,特許権者が負担する ものと解するのが相当である。 もっとも,そのような解釈を採ることが,全ての事案において,特許権者 が発明の経緯等を個別的,具体的,かつ詳細に主張立証しなければならない ことを意味するものではない。むしろ,先に出願したという事実は,出願人 が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推 認させる上でそれなりに意味のある事実であることをも考え合わせると,特 許権者の行うべき主張立証の内容,程度は,冒認出願を疑わせる具体的な事 情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容,程度がどのようなもの かによって左右されるものというべきである。すなわち,仮に無効審判請求 人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく,かつ,その裏付 けとなる証拠を提出していないような場合は,特許権者が行う主張立証の程 度は比較的簡易なもので足りるのに対し,無効審判請求人が冒認を裏付ける 事情を具体的に指摘し,その裏付けとなる証拠を提出するような場合は,特 許権者において,これを凌ぐ主張立証をしない限り,主張立証責任が尽くさ れたと判断されることはないものと考えられる。 以上を踏まえ,本件における取消事由1(発明者の認定の誤り)の成否を 判断するに当たっては,特許権者である被告において,自らが本件発明の発 明者であることの主張立証責任を負うものであることを前提としつつ,まず は,冒認を主張する原告が,どの程度それを疑わせる事情(本件では,被告 ではなく,Mが本件発明の発明者であることを示す事情)を具体的に主張し, かつ,これを裏付ける証拠を提出しているかを検討し,その結果を踏まえて, 被告が発明者であると認めることができるか否かを検討することとする。
ア 原告の主張立証について
甲45図面等及び甲21図面について原告は,平成19年5月を作成日とする甲45図面等及び平成21年8月を作成日とする甲21図面を証拠として提出し,これらの証拠は,Mが,水系の取締役に就任する平成21年10月以前に,本件発明の実施に用いられる浄化槽用コンクリート製品に係る図面を作成していたこと,ひいては,本件発明を着想し,具体化していたことを示すものである旨を主張する。 しかしながら,これらの図面に示されているのは,浄化槽用コンクリ ート枠体を構成する高さ方向に4段に分割された長方形のコンクリート\n枠体の三面図及びベースコンクリートの平面図並びにそれらの寸法等で あり,当該コンクリート枠体の構築方法等を示すような記載はない。他\n本件発明の特徴的部分は,高さ方向に複 数段に分割して製作しておいたコンクリート板を用い,構成CないしI\nの各工程に従って浄化槽保護用コンクリート体の構築を行うこと,すな\nわち浄化槽保護用コンクリート体の具体的な構築方法にあるのであり,\nこの点については,上記各図面から直接読み取れるものではない。 してみると,仮に,Mが,水系の取締役に就任する以前の時期に甲4 5図面等及び甲21図面を作成した事実が認められるとしても,そのこ とは,その当時のMが,浄化槽用コンクリート枠体を高さ方向に4段に 分割して構成するというアイデア,すなわち,浄化槽保護用コンクリー\nト体の具体的な構築方法に係る本件発明の着想の背景となり得るアイデ\nアを有していたことをうかがわせる事実にすぎず,これによって,その 当時のMが,本件発明の上記特徴的部分に係る着想を得ていたことが裏 付けられるということはできない。
その他の主張立証について
そのほかに,原告は,Mが本件発明の発明者であることを示す事情と して,1)M及び原告が中心となって,本件発明の実施に用いられるコン クリート製品の製造に向けた準備を進めたこと,2)本件出願のための戸 島弁理士との打ち合わせにおいて,Mが本件発明についての説明を行っ たことを挙げる。 そこで検討するに,まず,上記1) Mが主体となって,有明コンクリートへの浄化槽用コンクリート枠体の製造の発注を行うなどし,その際,有明コンクリートがMを設計者とする甲21図面に基づいて当該コンクリート枠体の図面(甲22図面)を作成す るなどした経過を指すものであるところ,これらの経過は,本件発明の 完成を前提として,これに用いられる製品の販売等に係る事業を具体化 していく経過として把握すべきものであり,その中で,Mが主体的に活 動していることが,その前提となる本件発明を着想,具体化した者がM であることを直ちに示すものとはいえない。むしろ,その当時(平成2 2年4月ころ)のMは,水系の取締役を務め,被告と協同して水系の事 業を進めるべき立場にあったのであるから,仮に本件発明が被告によっ てされたものであるとしても,それを事業化するための活動にMが主体 的に関与することは格別不自然なこととはいえない。したがって,上記 1)の点は,必ずしもMが本件発明の発明者であることを裏付ける事情と いえるものではない。 また,上記2)の点については,そもそも戸島弁理士に対する本件発明 の説明を行った者がMであることを認めるに足りる証拠がない(被告は, 当該説明を行った者は被告である旨を主張し,戸島弁理士も被告の主張 に沿う供述(丙1)をするのであり,これらを覆して原告の主張を認め るだけの証拠はない。)。 したがって,上記1)及び2)の事情によって,Mが本件発明の発明者で あることが裏付けられるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2017.03.31
平成28(行ケ)10207 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月28日 知的財産高等裁判所(4部)
【0009】には,前記(3)のとおり,本願発明が,耳より後ろのバッテ リー11の重さや電子回路12の重さW1と,前方のディスプレイ16やカメラ1 8の重量W2とを,「つる」の13を支点として,バランス(釣合い)をとるよう にし,天秤の原理でディスプレイ16やカメラ18が,装着者の顔が動いても水平 になるものであることが記載されているところ,このような,天秤の原理による支 点より前方側と後方側のモーメントのバランス(釣合い)は,一般に「スタティッ クバランス(静的な釣合い)」といわれるものであり,「スタティックバランス」 をとることが,必ずしも「ダイナミックバランス」(運動状態にある物体について, その運動状態によって発生している力をも考慮した釣合い)をもとることにはなら ないことは,技術常識に照らして明らかである。それにもかかわらず,本願明細書 には,【0009】を含め,耳より後ろのバッテリー11の重さや電子回路12の 重さW1と,前方のディスプレイ16やカメラ18の重量W2とを,「つる」の1 3を支点として,バランス(釣合い)をとるようにすることや天秤の原理と,「ダ イナミックバランス」(動的釣合い)がとれることとの関係については,何らの記 載もない。 したがって,本願明細書の記載によっても,耳より後ろの錘W1を「ダイナミッ クバランサー」とすることや本願発明が「ダイナミックバランスドスマホ,PC」 であることの技術的意義を明確に理解することはできず,第三者の利益が不当に害 されるといわざるを得ない。
・・・
原告は,引用発明は,メガネのモーメントWLを,耳の後方に固定するしゃ もじ状部4で吸収するものであるが,引用発明において,引用例2に記載された技 術事項を適用し,PC機能や通話機能\を付加すると,アイウェア側の重さWが重く なるので,モーメントWLは大きくなり,しゃもじ状部4はこのモーメントWLに 耐えることが必要となって,しゃもじ状部4を支える耳の負担を増やしてしまうと いう不具合が生じるから,引用発明において,引用例2に記載された技術事項を適 用し,相違点に係る本願発明の構成を備えるようにすることは容易に想到できたこ\nとではない旨主張する。 しかし,引用例1には,レンズ1に液晶層を設けたときにその電源となる電池を しゃもじ状部4に埋め込んでもよいことが記載されているから,引用発明において, 引用例1の上記記載に従い,液晶層に情報を表示するために,アイウェア(メガ\nネ)という同一の分野に係る技術である引用例2に記載された技術事項を適用する ことには動機付けがある。 なお,本願発明は,耳の位置を支点として,その後方のバッテリー11や電子回 路12の重さW1と,その前方のディスプレイ16やカメラ18の重さW2とのバ ランスをとるものであるとの原告の主張によれば,本願発明も,引用発明のメガネ も,支点である耳より後の錘をW1として天秤機能をさせ,前方の重さをW2とし\nて顔が止まっても動いてもW1とW2のバランスをとり,鼻などの顔部に荷重がか からないものである点で共通するから,支点である耳に「耳かけダイナミックバラ ンスドスマホ,PC」,又は引用例2に記載された技術事項を適用したアイウェア 11の全荷重がかかるという点で異ならない。よって,この点においても,しゃも じ状部4を支える耳の負担が増えることを問題にする原告の上記主張は,失当であ る。
イ 原告は,引用例2に記載されているのは,単なるディスプレイメガネであっ て,本願発明のようにカウンタウェイトとしてのバッテリーを備えておらず,耳を 支点としてその前後のバランスをとるというような発明ではなく,本願発明とは関 係がないから,引用発明において,引用例2に記載された技術事項を適用し,相違 点に係る本願発明の構成を備えるようにすることは容易に想到できたことではない\n旨主張する。 しかし,前記アと同様に,引用例1には,レンズ1に液晶層を設けたときにその 電源となる電池をしゃもじ状部4に埋め込んでもよいことが記載されているから, 引用発明において,引用例1の上記記載に従い,液晶層に情報を表示するために,\nアイウェア(メガネ)という同一の分野に係る技術である引用例2に記載された技 術事項を適用することには動機付けがある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.03.28
平成28(ワ)7393 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年3月21日 大阪地方裁判所
別紙対比表1,2の「被告侵害部分」で特定された原告コンテンツの各記載\nは,その内容や記載の順序,文体等に照らし原告の個性が表出されているものと認\nめられるから,これらはいずれも原告の思想又は感情を創作的に表現したものとし\nて著作権法上の著作物であるということができ,したがって原告は,その作成者と してその著作権(複製権,公衆送信権)を有するものと認められる。 そして,別紙対比表1,2記載のとおり,被告は,原告コンテンツをそのまま自\nらの本件ウェブページに転載したものであり,不特定多数の者が本件ウェブサイト にアクセスして本件ウェブページを自由に閲覧することができるものであることか らすると,被告は,原告の複製権及び公衆送信権を侵害したものというべきである。
(2) 被告は,これら記載の掲載行為は著作権法32条1項の「引用」に該当する 旨主張する。 しかし,被告が引用した原告コンテンツの一部の傍らには,本件記載のようなコ メントが付されているのであって,既に説示したとおり,これらコメントを付す行 為は,原告製品ひいては原告を批評するという公益を図る目的でされたものとは認 められず,むしろ原告製品ひいては原告の信用を毀損する目的でされた違法な行為 というべきものであり,また売主の説明責任を果たすための正当な行為と認めるこ ともできないことからすれば,その引用が「公正な慣行に合致するもの」とも「引 用の目的上正当な範囲内で行なわれる」ものともということはできない。 したがって,被告による原告コンテンツの掲載行為を,著作権法32条1項の「引 用」として適法と認めることはできない。 なお,被告は,原告コンテンツはそれ自体経済的価値を有するものとして市場で 取引されるものではないなどと主張するが,その指摘はそうであるとしても,これ をもって「引用の目的上正当な範囲内で行なわれ」たということはできない。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2017.03.24
平成28(受)1242 特許権侵害行為差止請求事件 平成29年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所
出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構\成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,特許出 願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,対象製品等が特許請求の範囲から除 外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人におい て,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるよう な行動をとったものとはいい難い。また,上記のように容易に想到することができ た構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,特許権侵害訴訟において,対象製品等と特許請求の範囲に記載された構\成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとする と,先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられる\nことと等しくなる一方,明細書の開示を受ける第三者においては,特許請求の範囲 に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるこ\nととなり,相当とはいえない。 そうすると,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構\成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それ だけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識 的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきで ある。
(2) もっとも,上記(1)の場合であっても,出願人が,特許出願時に,その特許 に係る特許発明について,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,特許請求の範囲に記載された構\成を対象製品等に係る構成と置き換\nえることができるものであることを明細書等に記載するなど,客観的,外形的にみ て,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構\成を代替すると認識し ながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,明細書の開示を受ける第三者も,その表\示に基づき,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから,当該出願人において,対象 製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動を とったものということができる。また,以上のようなときに上記特段の事情が存す るものとすることは,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もっ て産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない,出願人と第三者の利害を適 切に調整するものであって,相当なものというべきである。 したがって,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構\成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観 的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構\成を代 替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲か\nら意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。
そして,前記事実関係等に照らすと,被上告人が,本件特許の特許出願時に,本 件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき,客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構\成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表\示していたという事情があるとはうかがわれない。
6 原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は 採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2017.03.24
平成28(ネ)10094 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成29年3月22日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
控訴人コスメディは,原判決が,被控訴人バイオが別件侵害訴訟の訴 訟手続を通じて控訴人ら製品が本件特許権の侵害品であるとの事実を岩 城製薬に告知した面はあると認定しながら,不正競争防止法2条1項1 4号の不正競争(虚偽事実の告知)に該当しないと結論付けた論旨が不 明であると主張する。 よって検討するに,確かに,別件侵害訴訟は,控訴人コスメディのみ ならず,その取引先である岩城製薬をも共同被告(侵害者)として提起 されたものであるところ,同訴訟においては,本件特許の無効を理由に, 本件特許権の侵害を理由とする被控訴人バイオの請求が認められず,同 請求を棄却した一審判決が控訴棄却により確定したのであるから,結果 として,同訴訟において被控訴人バイオが主張していた事実(控訴人ら 製品が本件特許権の侵害品であるとの事実)は,虚偽であったことにな り,また,かかる訴訟手続を通じて,その虚偽の事実が岩城製薬に告知 されたことになる。したがって,かかる岩城製薬に対する告知は,形式 的には不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当する。 しかしながら,かかる告知は岩城製薬に対する訴訟提起によってなさ れたものであるから,これを違法とするかどうかは,別の観点からの考 察も必要である。すなわち,訴えの提起が相手方に対する違法な行為と なるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実 的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者がそのことを知りながら又 は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを 提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当 性を欠くと認められるときに限られる(最高裁第三小法廷昭和63年1 月26日判決・民集42巻1号1頁参照)。 かかる要件を満たさないの に,訴訟提起という形による虚偽事実の告知が形式的に不正競争に当た ることを理由として,これを違法とすることは,たとえ訴訟提起の相手 方(本件では岩城製薬)との関係で違法と評価するものではなかったと しても(不正競争かどうかは,飽くまで競業者である控訴人コスメディ との関係において問題となるものである。),結局はこれを不当提訴で あると断じるに等しく,裁判制度の自由な利用を著しく阻害することと なり妥当でない(むしろ,特許権者が自己の権利を侵害されているとの 認識の下に,当該侵害者を相手方として訴訟を提起することは,当該訴 訟が不当訴訟と評価されるような特段の事情がない限り,裁判を受ける 権利の行使として当然許される行為であるというべきである。)。 したがって,かかる制度的観点からは,特許権者が,競業者ないしそ の取引先に対する関係でおよそ請求が成り立たないことを知りながら, あるいは,当然そのことを知り得たはずであるのに,あえて当該取引先 をも共同被告として訴訟を提起するなど,訴訟制度を濫用的に利用した と評価し得るような特別な事情が存する場合は格別として,そのような 場合でなければ,外形的には不正競争に当たり得るとしても,訴訟提起 自体を違法と評価することはできないというべきである。 これを本件についてみるに,控訴人コスメディは,控訴人ら製品を製 造して資生堂に販売し,資生堂において商品として完成させて岩城製薬 に販売し,岩城製薬において市販していたというのであるから,仮に控 訴人ら製品が本件特許権の侵害品に当たるとすれば,岩城製薬の行為自 体が本件発明の実施行為として本件特許権の侵害に当たるものであるこ とは明らかである。また,別件侵害訴訟においては,結果的に新規性欠 如の無効理由によって本件特許が無効にされるべきものであるとの判断 が確定しているが,被控訴人バイオが,あらかじめ本件特許にかかる無 効理由が存することを知りながら,あるいは,これを当然知り得たはず であるのに,あえて(無理を承知で)同訴訟を提訴したというような事 情はうかがわれないし(別件侵害訴訟の提起に先立ち控訴人コスメディ から無効審判請求がなされていたが,被控訴人バイオとしては,これを 争っており,かつ,提訴の時点ではまだ確定的な判断は示されていなか ったのであるから,それだけでは,被控訴人バイオが無効理由の存在を 知り,あるいは,当然知り得たというには足りない。),被控訴人バイ オに,専ら控訴人コスメディの信用を毀損する目的など,訴訟制度を濫 用的に利用したと評価されるべき不当な目的があったことを認めるに足 りる的確な証拠もない。
以上によれば,被控訴人バイオが岩城製薬を共同被告として別件侵害 訴訟を提起したのは,正当な権利行使の一環というべきであって,それ が外形的には不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当し得る行 為であったとしても,正当行為として違法性が阻却されるものと認める のが相当である。原判決の認定判断もかかる趣旨を述べるものと理解す ることが可能であって,論旨不明との指摘は当たらない。よって,これに反する控訴人コスメディの主張は採用できない。
(イ) 控訴人コスメディは,資生堂に対する告知行為の有無に関して,被控 訴人バイオは,別件侵害訴訟の被告商品の中間流通段階に位置する資生 堂をあえて飛ばして,控訴人コスメディと岩城製薬とを被告にしたもの であって,当然,別件侵害訴訟の顛末は控訴人らから資生堂にも伝わる ことを知悉していたものであるから,被控訴人バイオは,控訴人らを介 して,資生堂に伝達した(告知した)と評価すべきものであると主張す る。 しかしながら,原判決が指摘するとおり,不正競争防止法2条1項1 4号における告知とは,自己が関知した一定の事実を特定の人に知らせ る伝達行為をいうものと解されるところ,別件侵害訴訟は飽くまで控訴 人コスメディと岩城製薬を被告とするものであって資生堂を被告とする ものではないから,同訴訟の提起とその後の訴訟手続をもって資生堂に 対する告知行為と評価することは相当でないし,被控訴人バイオにその 意図があったと認めるに足りる証拠もない。
したがって,資生堂に対する告知行為を認めなかった原判決の認定判 断は正当であり,これに反する控訴人コスメディの主張は採用できない。
イ 研究成果盗用の事実を告知したとの点について
控訴人コスメディは,原判決添付の別紙一覧表(別紙問題記載箇所一覧表\)記載の各記載内容(以下「本件各記載内容」という。)は,誰がみても,一貫して,被控訴人Y2の研究室から,控訴人Xが技術情報を盗取し た(アクセスして控訴人らの事業に使用するなどしている)ことと読み取 れるし,被控訴人バイオにおいても,そのような点における悪質性を謳い あげて,別件侵害訴訟で裁判所の侵害心証を形成したかったものであるこ とは明らかであるところ,結局,被控訴人バイオにおいては,客観的証拠 に基づく具体的事実の指摘ができずに,言いっ放しになっているとして, 上記の点について不正競争(虚偽事実の告知)の成立を認めなかった原判 決の認定判断は誤りであると主張する。
しかしながら,かかる控訴人コスメディの主張も採用できない。 すなわち,不正競争防止法2条1項14号の不正競争の成立を主張する 以上,不正競争を構成する具体的事実の主張立証責任は,飽くまで不正競争の存在を主張する側にあるというべきであるから,本件各記載内容に含\nまれる研究成果盗用の指摘が虚偽事実の告知に当たると主張するのであれ ば,これを主張する控訴人コスメディの側において,かかる指摘が虚偽の 事実であることを具体的に主張立証する必要がある。 さらにいえば,本件においては,被控訴人バイオの側から,控訴人Xは, 京都薬大在籍時に被控訴人Y2の研究成果にアクセス可能であったことや,同大学在籍中に控訴人コスメディの前身となる会社を設立し,その後,本\n件特許権の登録前に,控訴人コスメディが控訴人ら製品を製造販売し始め た経緯があったこと,控訴人Xが発明者の一人となって控訴人コスメディ が平成20年に出願した特許(乙9)に係る発明は,被控訴人Y2の発明 に係る自己溶解性マイクロニードルの基材物質の一つであるヒアルロン酸 を使用していることなど,控訴人Xが何らかの形で被控訴人Y2の研究成 果にアクセスしてこれを取得し,利用したことを推認させる方向に働く具 体的事情の存在が指摘されているのであるから,控訴人コスメディにおい ても,上記推認を弱める方向に働く事実を具体的に主張立証しようとする のが通常の対応であるという余地もある。 そして,これらの主張立証の方法として最も効果的であり,かつ,控訴 人Xにとって容易であるのは,控訴人Xが控訴人ら製品を独自に開発した 過程を明らかにすることであると考えられるところ,控訴人コスメディは, 本件訴訟の控訴審に至るまで,これを全く行っていないのであるから,こ のような控訴人らの対応も含めて考えると,本件各記載内容が虚偽の事実 であると断定することには疑問があるといわざるを得ない。 したがって,上記の点(研究成果盗用の事実を告知したとの点)につい て,不正競争防止法2条1項14号における不正競争(虚偽事実の告知) の成立を認めなかった原判決の認定判断に誤りはないというべきであり, これに反する控訴人コスメディの主張は採用できない。
2017.03.22
平成28(行ケ)10186 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月21日 知的財産高等裁判所(4部)
引用発明1は,前記2のとおり,低温側変色点以下の低温域における発色状態又 は高温側変色点以上の高温域における消色状態を特定温度域で記憶保持できる色彩 記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色 性インキ組成物を充填したペン等の筆記具であり,同筆記具自体によって熱変色像 の筆跡を紙など適宜の対象に形成することができる(引用例1【0004】〜【0 006】【0012】【図4】)。 これに対し,引用発明2は,筆記具と上面に熱変色層が形成された支持体等から 成る筆記材セットであり,前記ウのとおり,同様の色彩記憶保持型の可逆熱変色性 微小カプセル顔料を,バインダーを含む媒体中に分散してインキ等の色材として適 用し,紙やプラスチック等から成る支持体上面に熱変色層を形成させた上で,氷片 や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした冷熱ペンで上記熱変色層上に筆 記することによって熱変色像の筆跡を形成するものである(引用例2【0005】 【0010】〜【0012】【0014】【0016】〜【0020】【図1】)。 引用発明2は,筆記具である冷熱ペンが,氷片や冷水等を充填して低温側変色点以 下の温度にした特殊なものであり,インキや芯で筆跡を形成する通常の筆記具とは 異なり,冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形成することができず,セットとされ る支持体上面の熱変色層上を筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するもの である。 このように,引用発明1と引用発明2は,いずれも色彩記憶保持型の可逆熱変色 性微小カプセル顔料を使用してはいるが,1)引用発明1は,可逆熱変色性インキ組 成物を充填したペン等の筆記具であり,それ自体によって熱変色像の筆跡を紙など 適宜の対象に形成できるのに対し,2)引用発明2は,筆記具と熱変色層が形成され た支持体等から成る筆記材セットであり,筆記具である冷熱ペンが,氷片や冷水等 を充填して低温側変色点以下の温度にした特殊なもので,インキや顔料を含んでお らず,通常の筆記具とは異なり,冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形成すること ができず,セットとされる支持体上面の熱変色層上を筆記することによって熱変色 像の筆跡を形成するものであるから,筆跡を形成する対象も支持体上面の熱変色層 に限られ,両発明は,その構成及び筆跡の形成に関する機能\において大きく異なる ものといえる。したがって,当業者において引用発明1に引用発明2を組み合わせ ることを発想するとはおよそ考え難い。
オ 相違点5に係る本件発明1の構成の容易想到性について
(ア) 前記エのとおり,当業者が引用発明1にこれと構成及び筆跡の形成に関す\nる機能において大きく異なる引用発明2を組み合わせることを容易に想到し得たと\nは考え難く,よって,相違点5に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たとはい\nえない。
(イ) 仮に,当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても,前記ウ のとおり,引用例2には,熱変色像を形成する熱変色体2及び冷熱ペン8とは別体 のものとしての摩擦具9のみが開示されていることから,引用発明2の摩擦具9は, 筆記具とは別体のものである。よって,当業者において両者を組み合わせても,引 用発明1の筆記具と,これとは別体の,エラストマー又はプラスチック発泡体を用 いた摩擦部を備えた摩擦具9(摩擦体)を共に提供する構成を想到するにとどまり,\n摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着して筆記具と一体のものとして提 供する相違点5に係る本件発明1の構成には至らない。
(ウ) そして,前記イのとおり,引用例1には,そもそも摩擦熱を生じさせる具 体的手段について記載も示唆もされていない。 また,前記ウのとおり,引用例2には,熱変色像を形成する熱変色体2及び冷熱 ペン8とは別体のものとしての摩擦具9のみが開示されており,そのように別体の ものとすることについての課題ないし摩擦具9を熱変色体2又は冷熱ペン8と一体 のものとすることは,記載も示唆もされていない。 引用例3(甲9),甲第10,11号証,引用例4(甲12),甲第13,14, 及び52号証には,筆記具の多機能性や携帯性等の観点から筆記具の後部又はキャ\nップに消しゴムないし消し具を取り付けることが,引用例7(甲80)には,筆記 具の後部又はキャップに装着された消しゴムに,幼児等が誤飲した場合の安全策を 施すことが,引用例8(甲81)には,消しゴムや修正液等の消し具を筆記具のキ ャップに圧入固定するに当たって確実に固定する方法が,それぞれ記載されている。 しかし,これらのいずれも,消しゴムなど単に筆跡を消去するものを筆記具の後部 ないしキャップに装着することを記載したものにすぎない。 他方,引用発明2の摩擦具9は,低温側変色点以下の低温域での発色状態又は高 温側変色点以上の高温域における消色状態を特定温度域において記憶保持すること ができる色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料からなる可逆熱変色性イ ンキ組成物によって形成された有色の筆跡を,摩擦熱により加熱して消色させるも のであり,単に筆跡を消去するものとは性質が異なる。そして,引用例3,4,7, 8,甲第10,11,13,14及び52号証のいずれにもそのような摩擦具に関 する記載も示唆もない。よって,このような摩擦具につき,筆記具の後部ないしキ ャップに装着することが当業者に周知の構成であったということはできない。また,\n当業者において,摩擦具9の提供の手段として,引用例3,4,7,8,甲第10, 11,13,14及び52号証に記載された,摩擦具9とは性質を異にする,単に 筆跡を消去するものを筆記具の後部ないしキャップに装着する構成の適用を動機付\nけられることも考え難い。
(エ) 仮に,当業者において,摩擦具9を筆記具の後部ないしキャップに装着す ることを想到し得たとしても,前記エのとおり引用発明1に引用発明2を組み合わ せて「エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ,摩擦熱により筆記時の有 色のインキの筆跡を消色させる摩擦体」を筆記具と共に提供することを想到した上 で,これを基準に摩擦体(摩擦具9)の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又は キャップに装着することを想到し,相違点5に係る本件発明1の構成に至ることと\nなる。このように,引用発明1に基づき,2つの段階を経て相違点5に係る本件発 明1の構成に至ることは,格別な努力を要するものといえ,当業者にとって容易で\nあったということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2017.03.22
平成27(行ケ)10247 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月16日 知的財産高等裁判所(2部)
前記(2)のとおり,本件訂正発明と甲1発明とは,相違点1(架橋剤で架 橋処理される前の対象物であるポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物について, 本件訂正発明は,「架橋体」からなり「2個以上の重合性不飽和基または2個以上の 反応性基を有する内部架橋剤を共重合または反応させた」ものであると特定するの に対し,甲1発明は,「アクリル酸又はアクリル酸アルカリ金属塩等の水溶性ビニル モノマーに対して,重合開始剤として0.03〜0.4重量%の量の過硫酸カリウ ム,過硫酸アンモニウムなどの過硫酸塩を使用して重合し」て得られた「生成ポリ マー」と特定する点)において相違するが,甲1発明の「アクリル酸又はアクリル 酸アルカリ金属塩等の水溶性ビニルモノマーに対して,重合開始剤として0.03 〜0.4重量%の量の過硫酸カリウム,過硫酸アンモニウムなどの過硫酸塩を使用 して重合し」て得られた「生成ポリマー」は,甲1に「過硫酸塩を用いる場合には, 架橋反応も伴」うことが記載されている(【0020】)ことからすると,自己架橋 型の内部架橋を有するものである。 他方,本件訂正発明は,「2個以上の重合性不飽和基または2個以上の反応性基を 有する内部架橋剤」を用いた内部架橋剤型の内部架橋を有するものである。 そうすると,相違点1は,「架橋剤で架橋処理される前の対象物であるポリアクリ ル酸ナトリウム塩部分中和物について,本件訂正発明は,『2個以上の重合性不飽和 基または2個以上の反応性基を有する内部架橋剤』を用いた内部架橋剤型の内部架 橋を有するものであるのに対し,甲1発明は,自己架橋型の内部架橋を有するもの である点」(相違点1’)において相違するということができる。
イ そして,本件優先日当時,前記(3)イ(イ)のとおり,紙オムツ等に使用され る吸収体を,自己架橋型として製造することと,内部架橋剤型として製造すること とは,当業者が任意に選択可能な技術であり,同ウ(イ)のとおり,自己架橋型の内部 架橋と比較して,内部架橋剤型の内部架橋には,例えば,吸収体の架橋密度を制御 し,吸水諸性能をバランスよく保つことができる等の利点があることが,当業者の\n技術常識であったものと認められる。 そうすると,本件優先日当時の当業者には,甲1発明において,使い捨ておむつ や生理用ナプキン等の吸収性物品に用いられる高吸水性樹脂に一般に求められる, 架橋密度を制御して吸水諸性能をバランスよく保つ等の課題を解決するために,自\n己架橋型の内部架橋に代えて,内部架橋剤型の内部架橋を採用する動機があったも のということができる。 また,相違点1’に係る容易想到性の判断は,「架橋剤で架橋処理される前の対象 物であるポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物」について,自己架橋型の内部架 橋に代えて,内部架橋剤型の内部架橋を採用することが容易想到であるかを検討す べきものであるから,後に「架橋剤で架橋処理される」こと(表面架橋)が予\定さ れていることが内部架橋剤型の内部架橋を採用することの妨げとなるかを検討して も,前記(3)エ(イ)のとおり,本件優先日当時,紙オムツ等に使用される吸収体を,内 部架橋剤と表面架橋剤とを併用して製造することは,当業者の周知技術であったと\n認められるから,後に表面架橋が予\定されていることが内部架橋剤型の内部架橋を 採用することを阻害するとはいえない。同様に,甲1に内部架橋剤と表面架橋剤と\nを併用する旨の記載がなかったとしても,当業者が,甲1発明において,「重合後」 に架橋剤を添加することに加えて,更に架橋剤を「重合前」又は「重合時」にも添 加することを想到することが困難であったとも認められない。 したがって,甲1発明において,自己架橋型の内部架橋とすることに代えて,内 部架橋剤型の内部架橋とすることは,当業者が容易に想到し得るものと認められる。 そして,前記(3)イ(ア)及びウ(ア)のとおり,本件優先日前に頒布された刊行物には, 「2個以上の重合性不飽和基」を有する内部架橋剤を用いること(甲16の5,6, 甲18の2,4,6),「2個以上の反応性基」を有する内部架橋剤を用いること(甲 16の5,6)が記載され,また,「2個以上の重合性不飽和基」を有する内部架橋 剤である「N,N’−メチレンビス(メタ)アクリルアミド」及び「ポリエチレン グリコールジ(メタ)アクリレート」の一方又は双方が具体的に記載されているこ と(甲16の1〜4,甲18の6)からすれば,内部架橋剤として,「2個以上の重 合性不飽和基または2個以上の反応性基を有する内部架橋剤」を選択することは, 本件優先日当時の当業者が,適宜なし得ることであったということができる。 ・・・ ア 被告は,自己架橋型の架橋構造と内部架橋剤型の架橋構\造とでは,分子 構造や網目の大きさが異なるのが一般的であるから,審決における「分子構\造が異 なる」との認定は正しいものといえ,また,内部架橋剤型であったとしても,使用 する内部架橋剤の構造,属性により大きく吸水諸特性が異なるのであり,「内部架橋\n剤型の架橋構造」同士においても,内部架橋剤の種類の違いによる分子レベルでの\n微細構造の違いによって吸水諸特性が異なるのであるから,いわんや「自己架橋型\nの架橋構造」を「内部架橋剤型の架橋構\造」と同視することは不合理である旨主張 する。 しかしながら,前記(4)イのとおり,本件優先日当時,紙オムツ等に使用される吸 収体を,自己架橋型として製造することと,内部架橋剤型として製造することとは, 当業者が任意に選択可能なものであると共に,当業者が,自己架橋型よりも内部架\n橋剤型を選択する動機があったということができる。当該吸収体において,自己架 橋型の架橋構造と内部架橋剤型の架橋構\造との分子構造が異なり,その結果,双方\nの吸水諸特性に相違が生じることがあるとしても,両者が共に選択可能な製造技術\nである以上,その置換は容易なものといわなければならない。被告が,自己架橋型 の架橋構造と内部架橋剤型の架橋構\造とが同視できる技術でなければ容易に置換で きないと主張するのであれば,それ自体失当といえる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2017.03.16
平成27(ワ)21853 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年2月24日 東京地方裁判所
このことからすれば,不競法19条1項5号イの「最初に販売された日」 に係る「商品」とは,保護を求める商品の形態を具備した最初の商品を意味 するのであって,このような商品の形態を具備しつつ若干の変更を加えた後 続商品を意味するものではないと解すべきである。
(2) これを本件についてみるに,原告は,原告テントの第2世代を第1世代と 比較すると,1)高さ調節を変更した点,2)シルバーコーティングによるUV カット加工を施した点,3)支柱を覆う細長い天幕のデザインを変更した点, 4)収納バッグの色を変更した点,5)耐水圧及びシームシーリングを施した点 で異なるから,上記「商品」とは第2世代の原告テントを指し,その販売開 始日である平成25年10月15日を「最初に販売された日」とすべき旨主 張する。 しかし,本件全証拠を精査しても,そもそも原告テントに第1世代と第2 世代があり,第2世代は第1世代と上記1)ないし5)の全ての点で異なってい ることを示すに足りる的確な証拠は見当たらない。 この点に関して原告は,「タープテント史」と題する書面(甲13の1) にその旨記載されているかのように主張するが,原告作成の証拠説明書3に よれば,同書面は本訴係属中の平成27年12月に原告自身によって作成さ れたものというのであって,その形式に照らし,証明力は極めて低いといわ ざるを得ない上,その内容をみても,「第1世代」や「第2世代」という用 語は直接的には記載されていない。しかも,同書面には,原告テントについ て,高さ調節の変更(上記1))を平成25年10月15日生産開始分から施 した旨の記載があり,この点は原告の主張とも符合しているものの,他方で, シルバーコーティングによるUVカット加工(上記2)),支柱を覆う細長い 天幕のデザインの変更(上記3))及び耐水圧(上記5))を施したのは同年4 月18日生産開始分からという記載もあって,これらは原告の主張する時期 とは必ずしも整合するものではないし,収納バッグの色の変更(上記4))に ついては記載すらされていない。 また,原告は,「ワンタッチタープテント取扱説明書」と題する2通の書 面(甲22,23)の記載に関し,原告作成の証拠説明書4において,この うち前者が第1世代の,後者が第2世代のものであると説明する。しかし, これらの書面にも「第1世代」や「第2世代」との用語はなく,各書面の作 成時期も必ずしも判然としない(甲23には「2013.0731」との記 載があり,これは2013年〔平成25年〕7月31日を意味するものと解 されるが,原告の主張する第2世代の販売開始日〔平成25年10月15 日〕と整合しない。)。しかも,上記各書面からは,原告テントにおいて3 段階調節から2段階調節への変更(上記1))及び支柱を覆う細長い天幕のデ ザインの変更(上記3))がされたことはうかがえるものの,その余の変更点 (上記2),4)及び5))は書面上直ちに確認することができない。 以上からすれば,原告の上記主張は,そもそもその前提を欠くものといわ ざるを得ない。
(3) 仮に原告の主張するとおり,原告テントに第1世代と第2世代があり,第 2世代は第1世代と上記1)ないし5)の全て点で異なっているとしても,以下 のとおり,原告が保護を求める商品の形態は第1世代から具備されていたも のというべきである。
ア 原告は,第2世代の原告テントの構成態様が次の(ア)及び(イ)のとおり であるとし,この形態が不競法2条1項3号により保護される「商品の 形態」である旨主張している。
・・・
イ 他方,原告が第1世代と第2世代の相違点として指摘するのは,上記 (2)のとおり,1)高さ調節を変更した点,2)シルバーコーティングによる UVカット加工を施した点,3)支柱を覆う細長い天幕のデザインを変更 した点,4)収納バッグの色を変更した点,5)耐水圧及びシームシーリン グを施した点という5点でしかない。そして,このうち1)は原告のいう 基本的構成態様F(具体的構\成態様のF−1及びF−2)に,2)ないし 5)は原告のいう具体的構成態様のA−7(2)),A−8(5)),B−4 (4))及びE−3(3))に相当するものと解されるとしても,その余の 構成態様,すなわち基本的構\成態様のA,B,C,D及びEと,具体的 構成態様のA−1,A−2,A−3,A−4,A−5,A−6,B−1,\nB−2,B−3,C−1,D−1,E−1及びE−2は,いずれも第1 世代と第2世代とで共通する構成態様ということになる。\nそうすると,原告が不競法2条1項3号により保護されるべき商品の 形態として主張する構成態様の大部分は,第1世代の当時から存在して\nいたものというべきである。
ウ 次に,原告の主張する上記1)ないし5)の各相違点について,以下検討 を加える。
(ア) 高さ調節
原告は,第1世代では高さ調節が3段階であったところ,第2世代で はこれを2段階に変更したと主張する。 しかし,「商品の形態」とは,「需要者が通常の用法に従った使用に 際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並 びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう」(不競法2 条4項)ものであって,商品の機能及び性能\それ自体は不競法2条1項 3号で保護される「商品の形態」には当たらないと解されるところ,高 さ調節を「3段階」で行うのか,それとも「2段階」で行うのかという 点は,まさに原告テントの機能ないし性能\それ自体の違いをいうものに すぎず,「商品の形態」には当たらないといわざるを得ない。 また,原告は,支柱の長さを変更し,テントを展開したときの高さが 8.5cm小さくなったと主張する。 しかし,証拠(甲13の1)によれば,この変更は,従前の支柱の長 さが198.6cmであったものを190.1cmに縮めたというものにす ぎず,その割合からすれば,わずかな相違点であるといわざるを得ない。 なお,原告は,原告テントを発送する場合には梱包サイズ(3辺の合 計)が160cmを超えるか否かで送料が変わるところ,上記各変更によ り梱包サイズが166cmから158cmになったため,送料が安くなり, その結果,売れ行きが伸びたなどとも主張するが,そのこと自体は形態 を変更した理由若しくは目的や効果にすぎず,結局,その外観上は大き さに関するわずかな変更がされたというにとどまるから,この点をもっ て,不競法2条1項3号で保護される「商品の形態」において顕著な変 更がされたとはいえない。
(イ) シルバーコーティングによるUVカット加工
原告は,第2世代ではテントの生地にシルバーコーティングを施して UVカットを実現した旨主張する。 しかし,この点は,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚に よって認識することができるものとはいい難く,商品の機能及び性能\そ れ自体の変更をいうものにすぎないから,不競法2条1項3号の「商品 の形態」には当たらない。 この点に関して原告は,従前はテントの中にいても太陽が透けて見え ていたのが,シルバーコーティングを施したことによりまぶしくなくな り,もって見た目や色が変化したなどとも主張するが,これを裏付ける 証拠は存在しないし,仮にそのような変化が生じたとしても,基本的に は商品の機能及び性能\の変化の範囲を超えるものではないか,外観にお いてわずかな差異を生じさせるものにすぎないから,原告の上記主張は 採用することができない。
(ウ) 支柱を覆う細長い天幕のデザイン
原告は,第1世代では支柱を覆う細長い天幕にストライプ状の柄が入 っていたのを,第2世代ではテント本体の天幕と同じ無地の色に変更し たと主張する(別紙「天幕デザイン変更図」参照)。 しかし,上記変更は,原告も自認するとおり,支柱を覆う細長い天幕 の部分にプリントされた色彩及び図柄の変更にすぎず,支柱を覆う細長 い天幕の外形的な形状自体には何ら変更がないのであるから,仮に上記 デザインが不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当するとしても, テント全体からみればわずかな変更にすぎないといわざるを得ない。
(エ) 収納バッグ
原告は,収納バッグの色を黒色に統一したと主張するが,これを裏付 ける証拠はない上,そもそもこの主張自体はテント本体の形態の変更を いうものでもないし,その変更点も,色を変更したというものにすぎな い。 なお,原告は,収納バッグの色を統一したことにより在庫リスクが減 ったとも主張するが,具体的に在庫リスクが減ったことを裏付ける証拠 は存在しないし,そもそも在庫リスクが減ったかどうかは「商品の形態」 の問題ではない。
(オ) 耐水圧及びシームシーリング
原告は,第2世代では防水処理を施した上,シームシーリングという 方法で天幕の裏側から縫い目を保護し,より防水機能を高めたと主張す\nる。 しかし,これらはいずれも需要者が通常の用法に従った使用に際して 知覚によって認識することができるものとはいい難く,商品の機能及び\n性能それ自体の変更をいうものにすぎないから,不競法2条1項3号の\n「商品の形態」には当たらないし,仮に天幕の裏側から縫い目を保護し たことにより外観に変更が生じているとしても,テント全体からみれば わずかな差異にすぎない。
(カ) 小括
以上からすれば,原告の主張する原告テントの第2世代における変更 点は,そもそも不競法2条1項3号の「商品の形態」を変更するもので はないか,仮に「商品の形態」を変更するものであるとしても,原告テ ントの第1世代の商品形態を具備しつつ若干の変更を加えたものにすぎ ないというべきであるから,第1世代と第2世代は実質的に同一の形態 であるものといわざるを得ない。
(4) 以上によれば,原告の主張を前提としても,原告が保護を求める商品の形 態を具備した最初の商品は,第2世代の原告テントではなく,第1世代の原 告テントであるというべきである。そして,第1世代の原告テントが日本国 内で最初に販売されたのは平成22年10月頃というのであるから(前記第 2,2(2)),被告テントの販売開始時点である平成27年5月2日時点で は,既に3年が経過していることになる。 したがって,被告による被告テントの販売には,不競法19条1項5号イ の適用除外事由があり,そもそも同法3条及び4条の適用がない。
2017.03.16
平成28(行ケ)10200 審決取消請求事件 実用新案権 行政訴訟 平成29年3月14日 知的財産高等裁判所
構成要件B1,B9,C1及びC2は,1)コンデンシングユニット(20)が「第 一のリード角」を備え,「第一のリード角」が,コンデンシングユニット(20)の 内縁壁(205)周りに環設されること,2)コンデンシングユニットワッシャー(3 0)が,「第二のリード角」を有し,「第二のリード角」が,「第一のリード角」に対 応し,「第一のリード角」に当接することを規定する。 「第一のリード角」は,コンデンシングユニット(20)に「備え」られ,「環設」 されるものであり(構成要件B1,B9),また,「第二のリード角」は,コンデン\nシングユニットワッシャー(30)が「有し」(構成要件C1),さらに,「第一のリ\nード角」と「第二のリード角」とは,「当接」するものである(構成要件C2)から,\nこれらが,コンデンシングユニット(20)又はコンデンシングユニットワッシャ ー(30)の構成部位を示す用語であることは,明らかである。\nもっとも,「…角が…壁周りに環設される」「…角に対応する…角」「…角が…角に 当接している」とあるのは,「角」の通常の用い方とは明らかに異なるから,構成要\n件B1,B9,C1及びC2における「リード角」の意義は,実用新案登録請求の 範囲の記載からは,直ちに明らかにはならない。 そこで,本件明細書の記載を参酌すると,1)本件考案は,従来のワッシャーは, スチームトラップとの密接の度合が劣るため蒸気が漏えいしやすい問題があったこ とから(【0002】),コンデンシングユニットとコンデンシングユニットワッシャ ーとの結合箇所に,それぞれ,「第一のリード角」及び「第二のリード角」を設けて, 互いを密接させることで蒸気の漏えいを防ぐこととし(【0004】【0011】【0 013】),また,2)「図1〜図4に示すように,…第一のリード角206がコンデ ンシングユニット20の内縁壁205周りに環設され,コンデンシングユニットワ ッシャー30は第一のリード角206に対応する第二のリード角301を有する。」 (【0011】)と記載され,図3の断面図において,「206」及び「301」が, 接合方向に対して傾斜する傾斜面として示され,当接していることが認められる。 そうすると,当業者は,構成要件B1,B9,C1及びC2の「第一のリード角」\n「第二のリード角」は,コンデンシングユニットとコンデンシングユニットワッシ ャーとの結合面に互いに対応する角度を有してそれぞれ設けられた傾斜面であり, これにより,従来のワッシャーに比べて相互の密接性を高め ,蒸気の漏えいを防ぐ ものであると理解することができる。 したがって,構成要件B1,B9,C1及びC2の記載は,不明確なものとはい\nえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2017.03.16
平成28(行ケ)10076 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月14日 知的財産高等裁判所
引用発明及び甲2発明は,共に,建築の際に用いられる羽子板ボルトに関するも のであるから,その技術分野を共通にし,横架材等を相互に緊結するという機能も\n共通している。 しかし,引用発明に回動不能構\成を採用することには,引用発明の技術的意義を 損なうという阻害事由がある。 引用発明は,前記2(2)のとおり,従来の羽子板ボルトが有する,ボルト穴の位置 がずれた場合に羽子板ボルトを適切に使用することができないという課題を解決す るために,ボルト81が摺動自在に係合する係合条孔92を有する補強係合部10b を,軸ボルト4を中心として回動可能にするという手段を採用して,補強係合具10bが軸ボルト4を中心に回動し得る横架材16面上の扇形面積部分19内のいず\nれの部分にボルト穴171が明けられても,補強係合具10bの係合条孔92にボル ト81を挿入することができるようにしたものである。引用発明に相違点2に係る 構成を採用し,引用発明の補強係合具10bを,軸ボルト4を中心として回動可能\ なものから回動不能なものに変更すると,補強係合具10bの係合条孔92にボルト81を挿入することができるのは,ボルト穴171が係合条孔92に沿った位置に\n明けられた場合に限定される。すなわち,引用発明は,横架材16面上の扇形面積 部分19内のいずれの部分にボルト穴171が明けられても,補強係合具10bの 係合条孔92にボルト81を挿入することができるところに技術的意義があるにも かかわらず,回動不能構\\成を備えるようにすると,係合条孔92に沿った位置以外 の横架材16面上の扇形面積部分19内に明けられたボルト穴171にはボルト8 1を挿入することができなくなり,上記技術的意義が大きく損なわれることとなる。 そして,引用発明の技術的意義を損なってまで,引用発明の補強係合具10bを 回動不能なものに変更し,係合条孔92に沿った位置にボルト穴171を明けない限りボルト81を挿入することができないようにするべき理由は,本件の証拠上,認\nめることができない。 そうすると,引用発明の補強係合具10bを回動不能なものに変更することには,阻害要因があるというべきである。したがって,引用発明が相違点2に係る本件発\n明1の構成を備えるようにすることは,当業者が容易に想到し得ることであるということはできない。\nそして,甲3文献に記載された事項は,「垂直材」(柱)と「横架材」(土台梁)と を接合する「羽子板ボルト」であって,上記阻害事由があるという判断に影響する ものではないから,引用発明に相違点2に係る本件発明1の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得ることであるとはいえない。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2017.03.16
平成28(ネ)10102 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成29年3月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
プログラムの著作物性が認められるためには,指令の表現自体,同表\現の組合せ, 同表現の順序からなるプログラムの全体に選択の幅が十\分にあり,かつ,それがあ りふれた表現ではなく,作成者の個性が表\れているものであることを要するという ことができる。プログラムの表現に選択の余地がないか,あるいは,選択の幅が著\nしく狭い場合には,作成者の個性の表れる余地がなくなり,著作物性は認められな\nくなる。 前記1のとおり,本件HTMLは,被控訴人が決定した内容を,被控訴人が指示 した文字の大きさや配列等の形式に従って表現するものであり,そもそも,表\現の 選択の幅は著しく狭いものということができる。
・・・
(ア) 〈form name="frm_member" action="compliance.php?ts=%ts%" method="post"〉 (甲27の1右欄)は,online.html において,新規会員登録の画面下部の「上記を全 て満たすので会員登録手続きへ進む。」のボタンをクリックすると,compliance.php に アクセスすることに関するものと解される。 HTMLに関する事典ないし辞典において,1)「」 との間の範囲が入力フォームであることを示すこと(乙35),2)フォームの送信先 や送信方法等は,上記「form」タグの属性で指定し,属性="属性値"で表すこと(乙\n20,35,36),3)「name」は,フォームに名前を付与する属性であること(乙 36),4)「action」は,フォームに入力されたデータを処理するプログラムのURL を指定する属性であること(乙35),5)「method」は,入力されたデータの送信形 式を指定する属性であり,フォームのデータのみを本文として送信する「post」と 「action」属性で指定したURLフォームのデータを追加して送信する「get」のいず れかを選択するものとされていること(乙35)が記載されている。 したがって,上記記述は,その大半が,HTMLに関する事典ないし辞典に記載 された記述のルールに従ったものであり,作成者の個性の余地があるとは考え難い。 よって,控訴人主張に係る上記の記述において作成者の個性が表れているという\nことはできない。
(イ) 〈form name="frm_member" action="./compl_check.php?ts=%ts%" method="post"〉 (甲27の2右欄)は,compliance.html において,登録申請時確認テストの画面の問\n題に全問回答した後に,下部の「確認」ボタンをクリックすると,compl_check.php に アクセスすることに関するものと解されるが,前記(ア)と同様に,作成者の個性が表\nれているということはできない。
(ウ)
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2017.03.16
平成28(ネ)10100 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年3月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被控訴人は,控訴人が,当審において,訂正の対抗主張を追加したのに対し,上 記主張は,時機に後れた攻撃防御方法の提出として,民訴法157条1項に基づき 却下されるべきである旨主張する。 控訴人は,原審において,弁論準備手続が終結されるまでの間,訂正の対抗主張 を提出することはなかったが,弁論準備手続終結後に提出された準備書面において 初めてこれを主張するに至ったため,原審裁判所により時機に後れたものとして却 下された(なお,原審において主張した訂正の内容は,「片手で」との文言の有無 の点を除き,当審における訂正の内容と同一である。)。控訴人は,平成28年9 月8日に原判決が言い渡されると,同月21日控訴を提起した。他方,同月30日 には,本件特許1ないし3に係る各特許無効審判において,審決の予告がされた。\nそこで,控訴人は,同年11月10日提出に係る控訴理由書において,訂正の対抗 主張を記載した。 上記の原審及び当審における審理の経過に照らすと,より早期に訂正の対抗主張 を行うことが望ましかったということはできるものの,控訴人が原判決や審決の予\n告がされたのを受けて,控訴理由書において訂正の対抗主張を詳細に記載し,当審 において速やかに上記主張を提出していることに照らすと,控訴人による訂正の対 抗主張の提出が,時機に後れたものであるとまでいうことはできない。また,本件 における訂正の対抗主張の内容に照らすと,訂正の対抗主張の提出により訴訟の完 結を遅延させることになるとも認められない。 よって,控訴人の訂正の対抗主張を時機に後れたものとして却下することはしな い。
・・・・
1)乙18公報には,小型化された魚釣用電動リールにおいて,リール本体を保持 した手の指による操作性の向上を考慮して,モータ出力調節体の配置を変更するこ とについての示唆があるということができること,並びに,2)魚釣用電動リールは, 手のひらにのる程度に小型化,軽量化が図られていたところ,このように小型化, 軽量化した魚釣用電動リールでは,釣竿とリール本体とを片手で把持し,その把持 した手の親指で駆動モータの出力を制御する操作部材を操作することが指向される こと及び釣竿とリール本体とを片手で把持した状態で操作することを予定した位置\nに駆動モータの出力を制御する操作部を配設することが,原出願の出願日前に当業 者に周知であったことは,前記2 ウ のとおりである。そうすると,乙18発明 において,操作部材を釣竿とともにリール本体を片手で把持保持した状態の手の親 指が届く位置に配設することは,当業者が容易に想到できたことである。 また,乙18発明において,周知技術を適用して,相違点1−1に係る本件発明 1の構成とすることは当業者が容易に想到できたものであるところ,上記構\成を備 えた場合,操作部材の前後方向への回転操作は,親指で押え付けるようにして行わ れ得るものであることは明らかである。 そうすると,乙18発明において,相違点1−3に係る本件訂正発明1の構成と\nすることは,当業者が容易に想到できたことである。
・・・
エ 以上のとおり,本件各訂正発明は,乙18発明に基づき容易に発明をするこ とができたものであって,本件各訂正によっても,本件各発明の無効理由(乙18 発明に基づく進歩性欠如の無効理由)は解消しない。
2017.03.14
平成26(ワ)8922 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成29年2月17日 東京地方裁判所
甲4書簡には,原告製品について「本製品は添付の弊社保有特許(特許第 4444410号,発明の名称:歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケ ット用ツール)の請求項1に関連するものと思料しております。」と記載さ れているところ,本件発明に係る特許に「関連する」という文言は,本件発 明の技術的範囲に属する可能性があることを指摘するものと理解するのが素\n直である。そして,被告の常務取締役であるAが,バイオデントに送付した 甲23メールには,本件発明に係る特許について「使用許諾をすべきでない との意見が大勢を占めました。」と記載されており,被告がバイオデントに 対し,本件発明に係る特許の実施許諾をする意思がないことが明らかにされ ている。これらの事実を考慮すると,被告は,バイオデントに対し,原告製 品が本件発明の技術的範囲に属しているという事実及び被告が本件発明に係 る特許について実施許諾をする意思がないという事実を通知したということ ができる。そして,特許権は独占的排他的権利であり,特許権者において実 施許諾をする意思がない場合には,当該特許を業として実施している者は実 施行為を中止するほかないところ,実際にバイオデントは原告製品の販売を 中止しているから,バイオデントも,本件各告知は原告製品の輸入及び販売 の中止を求めるものと認識していたものと認められることからすれば,甲4 書簡による本件告知1の意義がやや不明瞭であるとしても,甲23メールに よる本件告知2を併せてみれば,本件各告知は,被告が,バイオデントに対 し,本件特許権侵害を理由として本件発明の実施行為である原告製品の輸入 及び販売の中止を求める侵害警告に当たると認めるのが相当である。 そして,被告の上記侵害警告は,バイオデントが原告から輸入して販売す る原告製品が特許侵害品である旨の告知であるから,原告の営業上の信用を 害する事実の告知であると認められる。 ところで,本件発明に係る特許については,冒認出願であることを理由と して,これを無効とすべき旨の審決が確定しており,同特許権は初めから存 在しなかったものとみなされるので(特許法125条),バイオデントによ る原告製品の輸入及び販売は,被告の特許権を侵害しないし,また,被告は 特許権に基づいて権利行使することはできない。 したがって,被告のバイオデントに対する本件各告知は,本件発明に係る 特許が存在しないにもかかわらず,原告製品の輸入及び販売がその特許権を 侵害するという事実を告知したものであって,虚偽の事実の告知に当たると 認めるのが相当である。
・・・・
被告は,権利侵害を疑われる行為を行う本人に対して権利侵害の事実を申\n述する行為は,不競法2条1項14号の不正競争行為に当たらないと主張す る。 しかし,バイオデントは権利侵害を疑われる行為を行う本人ではあるもの の,バイオデントに対し,本件各告知がされることにより,バイオデントで はなく,原告製品の製造元である原告の営業上の信用が害されるのであるか ら,上記告知は,「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知」に当た るというべきである。この点に関して被告は,バイオデントは原告と同一視 されるべき地位にあるなどとも主張するが,これを認めるに足りる証拠は ない。 また,被告は,本件各告知は正当な権利行使であり違法性が阻却されると も主張するが,上記(2)で説示したとおり,被告のバイオデントに対する本件 各告知行為には,登録された権利に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法が あるというべきであるから,本件各告知は,正当な権利行使には当たらない というほかない。したがって,被告の上記主張はいずれも採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2017.03.10
平成27(ネ)10113 不正競争防止法および共有著作物の無断利用控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成29年2月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(1)ア 控訴人は,被控訴人による本件秘密情報の使用が本件契約9条2項に違 反すると主張するところ,同条項で目的外使用が禁止されるのは「相手方から入手 した秘密情報」であるから,まず,本件秘密情報が(被控訴人が)控訴人から入手 した秘密情報に当たるかを検討する。
イ 前記認定事実によれば,控訴人代表者は,前職の常光勤務当時から,金\nコロイドイムノクロマト法による各種診断薬の輸入販売等に従事したほか,病院等 に勤務する共同研究者らと共に,イムノクロマト法による血清フェリチン迅速測定 法の研究を行い,既に平成17年9月には同研究についての学会報告を行っていた ことが認められる。そして,控訴人代表者が設立した控訴人が,平成19年には生\n研との間で同社による検査薬及び機器の研究開発等のコンサルタントを引き受ける 旨の研究開発コンサルタント等契約を締結する一方,被控訴人は,平成22年8月 には生研との間で金コロイドイムノクロマト法を用いるPOCT(Point R eader)機器試薬の研究開発についての共同開発契約を締結し,同年9月には 控訴人との間で同社に対し上記機器の基本プログラム開発等を委託する旨の開発委 託契約を締結し,平成23年6月には控訴人との間で同社に対し本件事業に関する コンサルタント,同社が保有するノウハウの提供等の業務を委託する旨の本件旧契 約を締結し,同年9月には控訴人との間で同社に対し上記POCTについて糖化ヘ モグロビン測定キットに対応する専用診断薬の開発(本件開発)を委託することを 目的とする本件開発委託覚書を締結したことが認められる。 これらの事実によれば,控訴人及び被控訴人においては,金コロイドイムノクロ マト法による血清フェリチンの測定機器及び診断薬の開発について,控訴人代表者\nが最も豊富な知識と経験を有していたものであり,金コロイドイムノクロマト法に よる血清フェリチン試薬であるPSフェリチン500及びPSフェリチン100の 開発に当たっても,これに従事した控訴人及び被控訴人の従業員の中で,控訴人代 表者が中心的な役割を果たしたものと推認することができる。\nしかしながら,控訴人と被控訴人との間において,PSフェリチン500及びP Sフェリチン100についての開発委託契約又は共同研究開発契約は締結されてお らず,控訴人及び被控訴人が共に従事したPSフェリチン500及びPSフェリチ ン100の開発に伴う知的財産権やノウハウの帰属に関する明示的な合意は見当た らない。かえって,控訴人と被控訴人との間で締結された書面による合意では,本 件旧契約,本件開発委託覚書,本件契約のいずれにおいても,控訴人がした発明等 であっても,特許等を受ける権利やこれに基づく産業財産権の帰属については,控 訴人及び被控訴人の共有(ただし,持分は別途協議)とするものとされており,知 的財産権については控訴人及び被控訴人の共有とすることが基本的な両者の認識で あったと窺われる。 そうすると,控訴人と被控訴人との間の合意を根拠として,PSフェリチン50 0及びPSフェリチン100の開発に伴う知的財産権やノウハウが控訴人のみに帰 属し,被控訴人がこれを使用することができないものであって,PSフェリチン5 00及びPSフェリチン100の製造手順書に含まれる本件秘密情報が,(被控訴人 が)控訴人から入手した秘密情報に当たるということはできない。 ウ また,前記認定事実によれば,PSフェリチン500及びPSフェリチ ン100の開発に従事した被控訴人従業員(本件駐在員)は,控訴人事業所に駐在 していたものと認められるが,本件旧契約,本件契約の下で,被控訴人が金コロイ ドイムノクロマト法を用いるPOCT(Point Reader)機器及びその 専用試薬を商品化し販売を促進していくという本件事業を行うために,人材が十分\nでない控訴人従業員と共に開発に従事したものと認められ,本件駐在員に対する指 揮命令権が控訴人にあったとは認められないし,控訴人のために労働に従事させて いたとも認められない。前記イのとおり,上記開発の現場において,金コロイドイ ムノクロマト法による血清フェリチンの測定機器及び診断薬の開発について最も豊 富な知識と経験を有していたのは控訴人代表者であったことからすれば,控訴人代\n表者が,本件駐在員に対し,上記開発において行う個別具体的な実験や作業につい\nて指示を行うことが少なからずあったことが推認されるものの,そのような現場に おける個別具体的な作業の指示が控訴人の本件駐在員に対する指揮命令権を直ちに 基礎付けるものということはできないし,控訴人も自認するとおり,本件駐在員で あったC,Dらは,デザインレビューという名目で,たびたび被控訴人事業所に呼 び出されて説明を求められたことがあったほか,Cは,被控訴人の上司から控訴人 代表者とのディスカッションで決まった実験内容に即して今後の開発行為を進める\nように指示を受けていたのであり(甲88),控訴人事業所駐在前と同様に,被控訴 人の指揮命令権になお服していたことが認められる。 そうすると,本件駐在員が派遣労働者として,控訴人のためにPSフェリチン5 00及びPSフェリチン100の開発に従事したものとはいえないから,本件駐在 員が派遣労働者であることを根拠として,PSフェリチン500及びPSフェリチ ン100の開発に伴う知的財産権やノウハウが控訴人のみに帰属し,被控訴人がこ れを使用することができないものであって,PSフェリチン500及びPSフェリ チン100の製造手順書に含まれる本件秘密情報が,(被控訴人が)控訴人から入手 した秘密情報に当たるということはできない。
エ 以上によれば,本件秘密情報が(被控訴人が)控訴人から入手した秘密 情報に当たるということはできないから,その余の点を判断するまでもなく,被控 訴人の本件秘密情報の使用が本件契約9条2項に違反する旨の控訴人の主張は,理 由がない。
2017.03.10
平成26(ワ)8134 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月27日 東京地方裁判所
なお,原告は,本件明細書において,構成要件Aにいう「特定視距離矯正領\n域」は「近景よりも実質的に離れた特定距離に対応する面屈折力を有する」領域 (請求項1,【0016】)と定義されている旨主張するが,正確には,請求項1 や段落【0016】においても,「近景よりも実質的に離れた特定距離に対応する 面屈折力を有する特定視距離矯正領域」と表現されているのであって,「矯正」\n「領域」という語句が存する以上,これらの語句による意味の限定が加わり得るこ とは否定できない(すなわち,請求項1や発明の詳細な説明では,「領域A」とか 「第1領域」などといった記号的な用語を使っておらず,「矯正領域」という用語 を選択しているのであるから,その日本語の持つ意味合いをはなから無視すること はできない。)。そして,「矯正領域」という字義のほか,前記(ア)ないし(ウ)で説 示したところに照らすと,上記の「…対応する面屈折力を有する」という部分も, 眼鏡レンズ内の当該領域を視線が通過する場合に特定距離にある対象物が良く見え るような視力矯正を可能とする程度に当該領域内で一定ないしほぼ一定の面屈折力\nを有するという意味であると解するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.03.10
平成28(ネ)10061 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件各発明の構成要件D1及びD2は,「出力画像データに対し中間的な周波数成\n分のみを分離するバンドパスフィルタリングを行なうことによって,同出力画像デ ータから高周波成分及び低周波成分を除いたバンドパスデータ」と規定するもので あるから,「バンドパスデータ」には低周波成分は実質的に含まれてはいない。そし て,構成要件Eは,補正データ生成手段が,この「バンドパスデータ」に「対応し\nた画像補正テーブル」を出力するものであるが,この「対応」というものが,いか なる技術的意義を有するものかは,特許請求の範囲の記載のみからでは明らかでは ない。 そこで,検討するに,本件各発明の解決課題・作用効果は,前記1(2)(4)(5)エのと おりであって,補正データに低周波成分に対する補正を加えようとすることによっ て生じる画面中心部の輝度の低下を防止することである。また,本件各発明の実施 形態をみてみると,バンドパスフィルタリングにより低周波成分及び高周波成分を 除いたバンドパスデータを算出し,このバンドパスデータを「反転させた」画像補 正テーブルを生成し(本件明細書1の【0033】,本件明細書2の【0032】), 補正された画像を表示する際は,画像補正テーブルから得た補正データを,入力さ\nれた画像信号に加算している(本件明細書1の【0037】,本件明細書2の【00 36】)。この実施形態は,緩やかな表示むら(出力画像データの低周波成分)や細\nかい表示むら(出力画像データの高周波成分)はそのままとし(本件明細書1の【0\n012】,本件明細書2の【0012】参照),中間的な周波数成分のみを目標とし て,これを消去するとの技術思想に基づくものといえる。そして,本件各明細書に は,これ以外の実施態様の記載はない。そうすると,構成要件Eの「バンドパスデ\nータに対応した画像補正テーブル」は,バンドパスデータを打ち消す作用を持つよ うな画像補正テーブルをいうものと解される。なお,本件各明細書には,「表示むら\nは,各ピクセルの明るさが理想値と異なるために発生するので,あらかじめ各ピク セルの理想値とのズレを測定しておけば,そのズレに従って各ピクセルへの入力画 像値を補正することで,表示むらをキャンセルすることが可能\である。」(本件明細 書1の【0038】,本件明細書2の【0037】)との記載があるが,本件各明細 書には,このための具体的な構成が記載も示唆もされておらず,この記載が目標値\nを定めて補正を行うような画像補正方法を開示するとはいい難く,このような実施 形態が本件各発明に含まれるとは認められない。 以上からすると,本件各発明において,補正前のデータである出力画像データに は,その定義より低周波成分,中間的な周波数成分又は高周波成分が含まれている ところ,バンドパスデータには中間的な周波数成分のみが含まれ,その中間的な周 波数成分は補正後の画像では消去されるから,補正後の画像には,補正前のままの 低周波成分又は高周波成分のみが残ることになる。そうすると,補正前後の画像の 差分をとると,中間的な成分のみが残るはずであって,この差分に低周波成分は実 質的には存在しないことになる。 すなわち,補正前後の画像の差分の中に低周波成分が含まれるシステムは,まず, 低周波成分を分離していないことにより構成要件D1 及びD2を充足しないものと 考えられ,仮に,そのように言い切れないとしても,「バンドパスデータに対応した 画像補正テーブル」を有しないことによって構成要件Eを充足しないものであり,\nいずれにしても,本件各発明の技術的範囲に属しないこととなる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2017.03. 8
平成29(ワ)13033 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月23日 東京地方裁判所
文言侵害の成否
ア 構成要件Eは,本件発明1の特許請求の範囲の記載によれば,処理手段\nが入力手段を介して「ポインタの位置を移動させる命令」を受信すると操 作メニュー情報を表示するものである。この「ポインタの位置を移動させ\nる命令」につき,本件明細書(甲2)には,1)「入力手段を介してポイン タの位置を移動させる命令を受信する」とは,入力手段としてのポインテ ィングデバイスから,画面上におけるポインタの座標位置を移動させる電 気信号を処理手段が受信することである(課題を解決するための手段,段 落【0020】),2)命令ボタンを押し続けたままで出力手段としてのデ ィスプレイの画面上に表示されているポインタの移動命令を行う,例えば,\n利用者がマウスにおける左ボタンや右ボタンを押したままマウスを移動さ せる行為がこれに該当する(発明を実施するための最良の形態,段落【0 079】)と記載されている。これに加え,本件発明1におけるポインタ が画面上に表示され,画面上の特定の位置を指し示すものをいうことに鑑\nみると,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令」とは,利 用者が画面上に表示されているポインタの位置を移動させる操作を行うこ\nとを意味すると解するのが相当である。 一方,本件ホームアプリにおいて,原告が「操作メニュー情報」に当た ると主張する左右スクロールメニュー表示は,利用者がショートカットア\nイコンをロングタッチすることにより表示されるものであり(前記前提事\n,画面上に表示されているポインタ(ショートカットアイコン並\nびに青い線の交点及び白い円形の画像。前記1(3))の位置を移動させる操 作により表示されるとは認められない。\n以上によれば,本件ホームアプリが構成要件Eを充足すると認めること\nはできない。
イ これに対し,原告は,「ポインタの位置の移動」とは,ポインタが画面 上に表示されるか否かにかかわらず,コンピュータプログラムがポインタ\nの座標位置の情報の書換えを行うことをいうと主張するが,前記1(1)のと おりポインタは画面上に表示されるものであるから,原告の主張は前提を\n欠き,これを採用することができない。なお,本件ホームアプリにおいて は,タップ操作やスライド操作の際にもポインタの座標位置の書換えが行 われることが認められるが(甲8の1及び2),これらの操作では左右ス クロールメニュー表示は表\示されないのであるから,本件ホームアプリが 「ポインタの座標位置の書換え」により左右スクロールメニュー表示を表\ 示するものでないことは明らかである。 また,原告は,タッチパネルでは指等が触れていれば継続的にポインタ の位置を移動させる命令を受信しており,ロングタッチを識別するために 入力されるデータ群には「ポインタの位置を移動させる命令」が含まれる から,本件ホームアプリは構成要件Eを充足するとも主張する。しかし,\nこの主張は「ポインタの位置を移動させる命令」を受信してもロングタッ チと識別されるまでは左右スクロールメニュー表示が表\示されないことを いうものにほかならず,失当というほかない。
均等侵害の成否
ア 原告は,本件ホームアプリにおける「利用者がタッチパネル上のショー トカットアイコンを指等でロングタッチする操作を行うことによって操作 メニュー情報が表示される」という構\成は「利用者がタッチパネル上の指 等の位置を動かして当該ショートカットアイコンを移動させる操作を行う ことによって操作メニュー情報が表示される」という本件発明の構\成と均 等であると主張するので,この点について検討する。
・・・・
ウ 本件明細書の上記各記載によれば,本件発明1は,従来の技術において はドラッグ&ドロップを行うに際して継続的な操作に適用させるのが困難 であるなどといった問題点があったことから,1)利用者が必要になった場 合にすぐに操作コマンドメニューを画面上に表示させ,かつ,2)必要であ る間はこれを表示させ続けられる手段の提供を目的とするものである。そ\nして,上記1)を達成するために「入力手段を介してポインタの位置を移動 させる命令を受信すると」操作メニュー情報を表示し(構\成要件E),上 記2)を達成するために出力手段に表示した操作メニュー情報がポインタに\nより指定されなくなるまで命令の実行を継続する(同F)という構成を採\n用した点に特徴を有するものと認められる。そうすると,入力手段を介し てポインタの位置を移動させる命令を受信することによってではなく,ポ インタがロングタッチされることによって操作メニュー情報を表示すると\nいう構成は,本件発明1と本質的部分において相違すると解すべきである。\n
エ これに対し,原告は,利用者がドラッグ&ドロップ操作を所望している 場合に操作メニュー情報を表示することが本質的部分であると主張する。\nそこで判断するに,原告が操作メニュー情報に当たると主張する左右スク ロールメニュー表示は,ショートカットアイコンをホーム画面の別のペー\n一方,本件ホームアプリにおいてロングタッチがされた場合に常にショー トカットアイコンをホーム画面の別のページへ移動させるドラッグ&ドロ ップ操作が行われると認めるに足りる証拠はない。そうすると,ロングタ ッチがされたことをもって上記のドラッグ&ドロップ操作が所望されてい るとみることはできないから,本質的部分に関する原告の上記主張を前提 としても,均等による本件特許権の侵害をいう原告の主張は採用すること ができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.03. 8
平成28(行コ)10002 手続却下処分取消請求控訴事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなければ,外国語特許出願は 国際出願日にされた特許出願とはみなされないのであるから,国際特許出願の対象 となる国及び広域の移行期限を確認することは,当該国際特許出願を行う出願人に 当然に求められるというべきであるところ,控訴人は,現地事務所は,移行期限を 徒過しないよう十分な体制を構\築していたと主張する。
イ 前記認定のとおり(引用に係る原判決3の1(2)ウ) 本件出願の処理に当 たり,現地事務所では,補助者であるA氏が,依頼人が移行手続を指示した国及び 広域について,締切リスト(甲14)及びWIPOの期限表(甲13)を用いて,\n移行期限が30か月であるかあるいは31か月であるかを確認した上で,移行期限 が30か月である国について指示書を作成したものである。 しかし,前記認定のとおり(引用に係る原判決3の1(2)カ),締切リストには, 対象となる国又は広域の移行期限が30か月であるか31か月であるかについて区 別して記載されていない。また,前記認定のとおり(引用に係る カ),WIPOの期限表は,アルファベット順に行ごとに国名ないし広域名が記載\nされ,その国名等の右側の離れた位置に移行期限が「30」あるいは「31」など の数字で記載されているものであるから,同期限表を目視するときは「30」ない\nし「31」という移行期限の表記が縦方向に混在して記載されているように見える\nものである。 そうすると,本件出願の処理に当たり,補助者であるA氏が,締切リスト及びW IPOの期限表を用いて移行期限を確認するだけでは,同人が特許管理業務に豊富\nな経験を有していたことを考慮しても,移行期限を看過するという人的ミスが生じ 得ることは当然に想定されるものであったというべきである。
ウ そして,前記認定(引用に係る3の1(2)キ)によれば、現地事務所 において,管理者は,補助者が起案した指示書が適切に作成されているか否かにつ いて,本件システム上のリストを用いてチェックしたことは認められるものの,そ れがどのような内容のリストであるか,また,いかなる事項についてチェックした ものかについては明らかではない。これを,管理者が,締切リストを用いて移行期 限をチェックしたものと解したとしても,前記のとおり,締切リストには,対象と なる国又は広域の移行期限が30か月であるか31か月であるかについて区別して 記載されておらず,C氏作成に係る陳述書(甲50)によっても,本件において, 管理者が移行期限について,締切リストのほかに,どのような資料を用いて確認し たかについては明らかではないから,管理者が,移行指示を受けた国及び広域の移 行期限を確認したものということはできない。なお,同陳述書において,管理者は 「専門的データベース」を用いて指示書等を確認した旨記載があるものの,「専門 的データベース」の具体的内容は明らかではなく,これが移行期限を確認するに当 たり,有用なものであると認めるに足りる証拠はない。 また,平成25年3月12日付けメール(甲34)によれば,B氏が,イスラエ ル,米国,カナダについて指示書の書状及び付属書類の確認をしたことは認められ るものの,その際,B氏が,各国の移行期限の確認作業を行ったとまでは認められ ない。C氏作成に係る宣誓書(甲9の1)及び陳述書(甲12)によっても,管理 者による確認作業が,いかなる事項を対象に,どのような資料をもとに行われたか については明らかではない。その他,本件において,管理者が移行期限の確認作業 を行ったとの事実を認めるに足りる証拠はない。 したがって,本件出願の処理に当たり,現地事務所が,管理者をして,移行指示 を受けた国及び広域の移行期限の再確認作業を行ったとの事実を認めることはでき ない。また,現地事務所において管理者が移行期限の確認作業を行う体制が構築さ\nれていたとの事実も認められない。
エ このように,本件出願の処理において,移行期限を看過するという補助者に よる人的ミスが生じ得ることは当然に想定されるところ,管理者などが,移行期限 の再確認作業を行ったとの事実も,現地事務所において移行期限の再確認作業を行 う体制が構築されていたとの事実も認められない。よって,現地事務所が,本件出\n願の処理に当たり,移行期限を徒過しないよう相当な注意を尽くしていたというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2017.03. 7
平成27(ワ)4461 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月10日 東京地方裁判所
特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的\n部分であると解すべきである。 そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づ いて,特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で,特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定さ\nれるべきである。すなわち,特許発明の実質的価値は,その技術分野に おける従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれ ば,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に 明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。 ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されて いるところが,出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合\nには,明細書に記載されていない従来技術も参酌して,当該特許発明の 従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定さ\nれるべきである。 また,第1要件の判断,すなわち対象製品等との相違部分が非本質的 部分であるかどうかを判断する際には,上記のとおり確定される特許発 明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し,こ れを備えていると認められる場合には,相違部分は本質的部分ではない と判断すべきであり,対象製品等に,従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても,その\nことは第1要件の充足を否定する理由とはならないと解すべきである (知的財産高等裁判所平成28年3月25日(平成27年(ネ)第100 14号)特別部判決参照)。
イ 原告は,本件発明1の本質的部分は「一の注文手続で,同一種類の金 融商品について,複数の価格にわたって一度に注文を行うこと」及び 「その注文と約定を繰り返すようにしたこと」にとどまると主張する。 この点,確かに,本件明細書等1には,本件発明1の課題として, 「本発明は・・・システムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うこと なく指値注文による取引を効率的かつ円滑に行うことができる金融商品 取引管理方法を提供することを課題としている。」(段落【0006】) との記載がある。この記載に,「請求項1・・・に記載の発明によれば, ・・・一の注文手続きを行うことで,同一種類の金融商品を複数の価格 にわたって一度に注文できる。」(段落【0017】),「請求項1・ ・・に記載の発明によれば,・・・約定した第一注文と同じ第一注文価 格における第一注文の約定と,約定した第二注文と同じ前記第二注文価 格における前記第二注文の約定とを繰り返し行わせるように設定するこ とにより,第一注文と第二注文とが約定した後も,当該約定した注文情 報群による指値注文のイフダンオーダーを繰り返し行うことが可能にな\nる。」(段落【0018】)との各記載も併せれば,原告の主張する 「一の注文手続で,同一種類の金融商品について,複数の価格にわたっ て一度に注文を行うこと」及び「その注文と約定を繰り返すようにした こと」との部分が本件発明1の本質的部分,すなわち従来技術に見られ ない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であるように見えなくもな\nい。 しかし,本件発明1に係る特許(本件特許1)の出願時の従来技術に 照らせば,本件明細書等1に本件発明1の課題として記載された「シス テムを利用する顧客が煩雑な注文手続を行うことなく指値注文による取 引を効率的かつ円滑に行うことができる金融商品取引管理方法を提供す ること」(段落【0006】)は,本件発明1の課題の上位概念を記載 したものにすぎず,客観的に見てなお不十分であるといわざるを得ない。\n以下,詳述する。
以上の各記載に,上記エのとおり,引用文献1には既に「一の注文手 続で,同一種類の金融商品について,複数の価格にわたって一度に注文 を行う」という技術が開示されていたことも併せれば,本件発明1は, 単に一の注文手続で複数の価格にわたって一度に注文を行うだけではな く,「請求項1・・・の発明」による「売買注文申込情報」,すなわち,\n「金融商品の種類」(構成要件1B−1),「注文価格ごとの注文金額」\n(構成要件1B−2),「注文価格」(構\成要件1B−3),「利幅」 (構成要件1B−4)及び「値幅」(構\成要件1B−5)を示す各情報 に基づいて,同一種類の金融商品を複数の価格について指値注文する注 文情報からなる注文情報群を生成することにより,金融商品を売買する 際,一の注文手続きを行うことで,同一種類の金融商品を複数の価格に わたって一度に注文できるという点にその本質的部分があるというべき である。
カ これを被告サービス1についてみると,被告サービス1では「利幅」 (構成要件1B−4)及び「値幅」(構\成要件1B−5)を示す情報が 入力されないのであるから,本件発明1と被告サービス1の相違点が特 許発明の本質的部分ではないということはできない。 したがって,被告サービス1については,均等の要件のうち第1要件 を満たさない。
(4) 第2要件(置換可能性)について
次に,均等の第2要件について検討する。 原告は,本件発明1の課題は「専門的な知識がなく,必ずしも正確に相場 変動を予測することができなくても,また,常に相場に付ききりとならなく\nても,FX取引により所望の利益を得ること」にある旨主張している。 しかし,仮に本件発明1の課題が原告の主張するところにあるとしても, 本件発明1と被告サービス1とは,課題解決原理が全く異なる。 すなわち,本件発明1では,顧客に利幅(構成要件1B−4)及び値幅\n(構成要件1B−5)をはじめとして全ての注文を直接的かつ一義的に導き\n出すに足りる情報を入力させた上,これにより,買いの指値注文及び売りの 指値注文からなる注文のペアを複数生成させ,この複数の注文のペアからな る注文を行うことで,上記課題を解決している。 一方,被告サービス1では,顧客が3)「参考期間」を選択しさえすれば, 4)「想定変動幅」を提案し,専門的な知識が必要である利幅(構成要件1B\n−4)及び値幅(構成要件1B−5)を顧客に入力させることなく,複数の\n注文のペアからなる注文を行うことで,上記課題を解決している。すなわち, 被告サービス1では,顧客に全ての注文を直接的かつ一義的に決定させるの ではなく,顧客には専門的な知識が必要とされる情報を入力させないまま, 注文を行わせるものである。 このように,本件発明1と被告サービス1は,金融商品の相場変動を正確 に予測することができなくてもFX取引による所望の利益を得るという課題\nを,顧客に利幅(構成要件1B−4)及び値幅(構\成要件1B−5)という 専門的な知識が必要である情報を入力させることで解決するか(本件発明 1),それともこれらの情報を入力させないまま解決するか(被告サービス 1)という課題解決原理の違いがあり,そのため作用効果も異なってくるも のといわざるを得ない。 したがって,均等の第2要件に関する原告の主張は理由がない。
(5) 第3要件(容易想到性)について
さらに,均等の第3要件について検討する。
ア 原告は,甲15公報及び甲17公報並びに他の証券会社の提供した 「クイック仕掛け(買いゲリラ100pips)」という機能に照らせば,値幅\nを直接入力せずに他の情報を入力してこれらの情報から値幅を算出して 決定するという構成や,あらかじめ設定された値を用いるという構\成は, 被告サービス1の提供開始時において既に公知の構成であったと主張す\nるので,以下検討する。
イ まず,甲15公報の「要約」欄には,以下の記載がある。
・「注文情報生成部は,取り引きの上限価格と,取り引きの下限価格と, 同時に生成される注文情報群の数とを取得し,取得された値に基づいて, 第一注文どうしの価格差が一定となり,第二注文どうしの価格差が一定 となり,かつ,同一の注文情報群に属する第一注文と第二注文との価格 差が一定となるように,第一注文及び第二注文の価格をそれぞれ演算す る。」 また,甲17公報には,以下の記載がある。
・「前記表示手段における上側の接触位置に対応して表\示された前記価 格情報に基づいて上限価格を設定すると共に前記表示手段における下側\nの接触位置に対応して表示された前記価格情報に基づいて下限価格とを\n設定させると共に,前記注文発注手段に対し,前記上限価格と前記下限 価格との間に形成された前記発注価格帯において前記注文情報を発注さ せることを特徴とする金融商品取引システム。」(【請求項1】)
・「前記注文発注手段は,前記任意の発注条件として,前記金融商品の 注文個数情報を備え,前記発注価格帯において,前記注文個数情報に基 づく複数の前記注文情報を,それぞれの価格差が均等な指値注文を発注 するように生成することを特徴とする請求項1乃至6の何れか一つに記 載の金融商品取引システム。」(【請求項7】)
・「ポジション・ペアの数は,第一形態注文入力画面33(図8)で注文個 数入力欄(図示せず)に入力された注文個数情報の数値,又は,発注価 格帯の数値を値幅入力欄(図示せず)に入力された数値で割った値のう ちの整数値と同じ個数に等しく設定される。」(段落【0082】)
ウ 上記各記載を踏まえ,原告は,甲15公報にはトラップを仕掛ける範 囲(「取引の上限価格」と「取引の下限価格」)と,トラップの本数 (「同時に生成される注文情報群の数」)を入力し,これらの情報に基 づいて値幅及び利幅(「第一注文どうしの価格差」及び「同一の注文情 報群に属する第一注文価格と第二注文価格との差」)を一定となるよう に演算して決定する構成が開示されており,また,甲17公報にも,ト\nラップを仕掛ける範囲(タッチパネルの上下の接触位置に対応する「発 注価格帯」)と,トラップの本数(「注文個数情報」)を入力し,これ らの情報に基づいて,値幅が均等となるように演算して決定する構成が\n開示されていると主張する。 しかし,被告サービス1においては,そもそも注文情報群の数(原告 の主張する「トラップの本数」)を顧客が入力する構成とはなっていな\nい。すなわち,原告の主張によっても,被告サービス1では,顧客は6) 「対象資産(円)」欄に金額を入力するのみであり,被告サーバにおい てその額の証拠金で生成可能な数の注文情報群を生成するというのであ\nる。 加えて,前述のとおり,本件発明1(構成要件1B)と被告サービス\n1の相違点は,本件発明1では構成要件1B−4(利幅を示す情報)及\nび構成要件1B−5(値幅を示す情報)を入力するのに対し,被告サー\nビス1では2)「注文種類」ないし6)「対象資産(円)」の五つの情報を 入力する点にあるところ,甲15公報及び甲17公報にはこれらの五つ の情報の入力については何ら開示されていない。 エ さらに,他の証券会社の提供した「クイック仕掛け(買いゲリラ 100pips)」という機能についてみても,原告によれば,同機能\では利幅 及び値幅はあらかじめ設定されていて,顧客が入力するものではないと いうのである。そうすると,利幅(構成要件1B−4)及び値幅(構\成 要件1B−5)が顧客の入力に係る本件発明1に対し,利幅(構成要件\n1B−4)及び値幅(構成要件1B−5)があらかじめ設定されている\n「クイック仕掛け(買いゲリラ100pips)」の技術を適用する基礎がそも そも存在しないものといわざるを得ない。 オ 以上によれば,本件発明1の構成を被告サービス1のものに置換する\nことについて,当業者が被告サービス1の開始時点において容易に想到 することができたとはいえない。 したがって,均等の第3要件に関する原告の主張は理由がない。
・・・・
原出願である本件特許2に係る本件明細書等2の段落【0005】ないし 【0008】の記載によると,本件特許2は,従来技術の課題として,取引 開始直後の注文が成行注文のイフダンオーダーをすることができなかったこ と及びイフダンオーダーを繰り返し行えなかったことを技術課題として設定 している。 この課題を解決する手段として,本件明細書等2では,取引開始直後に約 定する成行注文の約定価格を基準として,注文情報群を生成し,これに基づ いて,決済注文である指値注文及び逆指値注文を行い,当該指値注文が約定 すると,新たな注文情報群を生成させ,これに基づいて,先行する成行注文 の約定価格と同一の価格の指値注文を行い,当該指値注文が約定すると,当 該新たな注文情報群に基づいて,当該指値注文の決済注文であって,先行す る決済注文である指値注文及び逆指値注文と同一の価格の指値注文及び逆指 値注文を行うことが開示されている。 すなわち,本件明細書等2の段落【0044】では,「・・・成行リピー トイフダンでは,一回目のイフダンでは,第一注文で買い注文または売り注 文の一方を成行で行ったのち,第二注文で買い注文または売り注文の他方を 指値で行う。・・・この第二注文の約定の後,指値の第一注文(このときの 指値価格は一回目の成行注文での約定価格とする)と指値の第二注文とから なるイフダンが,複数回繰り返される。」とされ,段落【0062】では 「ここで,本実施形態の第一注文は,一回目は成行注文で行われるが,二回 目以降は指値注文で行われる。このため,約定情報生成部14は,当該成行 注文の約定価格を,二回目以降の第一注文の指値価格に設定する。」とされ た上,【図7】においても,2回目以降の指値の第一注文の価格を1回目の 成行注文の約定価格とする旨の記載がある。そして,証拠(乙11,13) 及び弁論の全趣旨によれば,これらの段落【0044】及び【0062】並 びに【図7】は,出願当初の明細書等から補正がされていないものと認めら れる。
(4) そこで,構成要件3F−2の「前記指値注文」の構\成と,本件明細書等2 の記載とを比較すると,本件明細書等2には2回目以降の指値の第一注文の 価格を1回目の成行注文の約定価格とすることしか開示されておらず,2回 目以降の指値の第一注文の価格を任意の価格にできるといった記載はない。 また,2回目以降の指値の第一注文の価格をどのような価格にするのか,言 い換えると,1回目の成行注文の約定価格以外のどのような価格に設定する のか,そのための方法等は一切開示されていない。 そうすると,本件明細書等2の出願当初及び分割直前の明細書等には,そ の技術課題及び課題を解決するための手段からみて,2回目以降の指値の第 一注文の価格を任意の価格に設定できることが形式的にも実質的にも記載さ れていないものといわざるを得ない。 したがって,本件発明3の構成要件3F−2は,分割出願の出願日が原出\n 願の出願日へ遡及するための要件である,上記1)及び2)の要件のいずれも満 たさないから,本件発明3に係る特許出願には特許法44条2項の適用がな く,分割要件違反となるものというべきである。
(5) 原告の主張に対する判断
この点に関して原告は,本件発明2及び3の技術思想は「顧客が煩雑な注 文手続を行うことなく複数のイフダンオーダーを繰り返し行うことができて, システムを利用する顧客の利便性を高めると共にイフダンオーダーを行う際 に顧客が被るリスクを低減させることができる。」ことにあり,2回目以降 の第一注文の指値価格をどのようなものにするのかは,上記技術思想とは直 接の関係がないため,当業者において適宜選択・決定すれば足りる事項であ ると主張する。 しかし,上記(3)において引用したところからすれば,本件発明2の技術 思想は,先行する成行注文の約定価格と同一の価格の指値注文を行うところ にもあるということになる。そうすると,本件明細書等2に対し,システム が2回目以降の指値の第一注文の指値価格を決定するという構成を追加する\nことは,新たな技術的事項を導入するものというべきであるから,原告の上 記主張はその前提を欠き,採用することができない。 (6) 以上によれば,本件発明3に係る特許出願の出願日は,原出願の出願日ま で遡及せず,現実の出願日である平成26年11月13日となるところ,本 件発明2に係る特許出願の出願公開の公開日は平成25年7月11日である から(甲4の2),本件発明3の新規性は,本件発明3を下位概念化した本 件発明2によって,否定されることになる。 したがって,本件発明3に係る特許は,特許法29条1項3号に違反して されたものであるから,同法123条1項2号によって特許無効審判により 無効にされるべきものである。
・・・・
(1) 特許制度は,明細書に開示された発明を特許として保護するものであり, 明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の 趣旨に反することから,特許法36条6項1号のいわゆるサポート要件が定 められたものである。 したがって,同号の要件については,特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ,開示されているこ\nとが求められるものであり,同要件に適合するものであるかどうかは,特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に 記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか,すなわち, 発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし,当該発明に おける課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な 技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべ きものと解される。
(2) これを本件についてみるに,原告の主張によれば,構成要件3F−2の\n「前記指値注文」とは,その価格については何の限定もなく,任意の指値価 格をその指値価格とする指値注文ということになる(前記10(3))。しかる に,前記10(3)で引用した本件明細書等2の段落【0044】及び【006 2】並びに【図7】は,本件明細書等3の段落【0042】及び【0060】 並びに【図7】に相当するところ,これらの段落等にも,その技術課題及び 課題を解決するための手段からみて,2回目以降の指値の第一注文の価格を 任意の価格に設定できることが形式的にも実質的にも記載されているとはい えない。 そうすると,当業者において,本件発明3の解決手段その他当業者が当該 発明を理解するために必要な技術的事項が,本件明細書等3の発明の詳細な 説明に記載されているものと認めることはできない。
(3) したがって,本件発明3は特許法36条6項1号に規定するサポート要件 を満たしていないことになるから,本件発明3に係る特許は同法123条1 項4号によって特許無効審判により無効にされるべきものである。
関連カテゴリー
>> 分割
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第3要件(置換容易性)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.03. 6
平成28(行ケ)10107 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月28日 知的財産高等裁判所
以上により,本願優先日当時,「癌ワクチン」について,以下の技術常識 が存在したものと認められる。 ペプチドが「ワクチン」として有効であるというためには,1)当該ペプチドが多 数のペプチド特異的CTLを誘導し, 2)ペプチド特異的CTLが癌細胞へ誘導され, 3)誘導されたCTLが癌細胞を認識して破壊すること,が必要である(上記(1)エ)。 あるペプチドにより,多数のペプチド特異的CTLが誘導されたとしても,誘導さ れたCTLが癌細胞を認識することができない(上記(1)ア,ウ,オ,カ),誘導さ れたCTLが癌細胞を確実に破壊するとは限らない(上記(1)カ)などの理由により, 当該ペプチドに必ずしもワクチンとしての臨床効果があるということはできない。
(3) 引用発明は,上記2のとおり,標準治療後のHLA−A2型のリンパ節転 移陰性乳癌患者について,GP2ペプチドとアジュバントのGM−CSFを6か月 接種したところ,全ての患者においてGP2特異的CTL細胞のレベルが増加した というものであり,GP2ペプチドがワクチンとして有効であるというために必要 な,当該ペプチドが多数のペプチド特異的CTLを誘導したことを示したものであ る。これに対し,本願発明は,上記1のとおり,GP2ペプチドとGM−CSFを 投与した無病の高リスク乳癌患者に,GP2特異的CTLが増大したのみならず, 再発率が低減した,すなわち,誘導されたCTLが腫瘍細胞を認識し,これを破壊 することによって,臨床効果があることを示したものである。 上記(2)のとおり,本願優先日当時,あるペプチドにより多数のペプチド特異的C TLが誘導されたとしても,当該ペプチドに必ずしもワクチンとしての臨床効果が あるとはいえない,という技術常識に鑑みると,ペプチド特異的CTLを誘導した ことを示したにとどまる引用発明は,本願発明と同一であるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2017.03. 6
平成28(行ケ)10103 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月28日 知的財産高等裁判所
(ア) 引用発明は,前記(1)イによれば,ワイヤーの把持面又はその辺りでの結び や捻れを防止し,かつ絶縁型のワイヤーへの損傷や切断を生じないワイヤー把持具 を提供することを目的とし,かかる課題の解決手段として,ハンドル32が,ピン 33とブラケット35との間に段差状の屈曲する部分を有し,ガイド36の形状と 配置にあわせて,ハンドル32の上記屈曲と枢着接続部33の移動の円弧がよく調 整されるようにした構成を採用し,これにより,引っ張る負荷が目37に適用され\nるとき,ハンドル32がワイヤーに接触せず移動して目37の位置がワイヤーに接 近し,引っ張る動作は常にワイヤーのほぼ軸方向にあるから,ワイヤーが曲がった り,捻れたりしないという作用効果を奏するものである。 そうすると,引用発明は,前記1(2)アの本件発明の課題と共通する課題を,ハン ドル32が,ピン33とブラケット35との間に段差状の屈曲する部分を有し,ガ イド36の形状と配置にあわせて,ハンドル32の上記屈曲と枢着接続部33の移 動の円弧がよく調整されるようにした構成を採用することにより,既に解決してい\nるということができるから,上記構成に加えて,あるいは,上記構\成に換えて,ハ ンドル32を「捻った」部分を有するように構成する必要がない。
(イ) また,前記アの周知例等の記載によっても,掴線器において,長レバーの 移動により,その後端に設けられたリング部がケーブルなど他の部材と干渉するの を避けるために,長レバーを「捻った」部分を有するように構成することが,もと\nの出願日前に,当業者に周知慣用の技術であったとは認められない。すなわち,周 知例1,10ないし14,甲16及び20には,部材を「捻った」構成が記載され\nているものの,周知例1は「耐張碍子を腕金に連結する捻りストラップ」,周知例 10は「六角レンチ」,周知例11は「自動車ボデーの補修工具」,周知例12は 「回転電機巻線」,周知例13は「多穴管」,周知例14は「チューブ」,甲16 は「通い綱ロープの掛け止め補助具」,甲20は「架線走行システムの補助レー ル」に関するものであって,掴線器に関するものではなく,掴線器の長レバーと同 様の作用や機能を有する部材に関するものでもない。なお,周知例2及び甲21は,\nもとの出願日後に公開された文献であって,もとの出願日前の周知慣用の技術を示 す証拠としては失当であるが,この点を措いても,周知例2は「耐張碍子を腕金に 連結する捻りストラップ」,甲21は「引込線等をなす撚り線」に関するものであ って,掴線器に関するものではなく,掴線器の長レバーと同様の作用や機能を有す\nる部材に関するものでもない。同様に,周知例3,甲15,17ないし19及び2 2ないし27は,いずれも掴線器に関するものではないし,そこに記載されている のは,部材を「曲げた」又は「巻き付けた」構成であって,そもそも「捻った」構\ 成でもない。さらに,周知例4ないし9は,掴線器に関するものであるが,長レバ ー又はそれに相当する部材を「捻った」構成とすることについて,記載又は示唆す\nるものではない。
(ウ) したがって,そもそも,掴線器において,長レバーの移動により,その後 端に設けられたリング部がケーブルなど他の部材と干渉するのを避けるために,長 レバーを「捻った」部分を有するように構成することが,もとの出願日前に,当業\n者に周知慣用の技術であったとは認められないし,引用発明において,上記構成を\n備えるようにする動機付けもない。
(エ) むしろ,引用発明の構成に加えて,ハンドル32を「捻った」部分を有す\nるように構成する場合には,引用発明では,目37がワイヤーに近接した位置とな\nるように調整されているため,目37がワイヤーに接触するおそれがあり,目37 がワイヤーに接触しないようにするには,目37とワイヤーとの距離を遠ざけるよ うにガイド36の形状と配置を変更することや,ハンドル32の段差状の屈曲と枢 着接続部の移動の円弧の再調整をすることが必要になるから,引用発明において, その構成に加えて,ハンドル32を「捻った」部分を有するように構\成することに は,阻害要因があるというべきである。
(オ) 以上によれば,引用発明において,周知例等に記載された事項に基づいて 相違点に係る本件発明の構成を備えるようにすることが,容易に想到できたという\nことはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2017.03. 6
平成26(ワ)8133 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年2月27日 東京地方裁判所
ウ 本件明細書の上記イの記載からすると,1)装用時の光学性能を重視して処方面を非球面化した累進屈折力レンズは,測定基準点において面非点隔差が発生する\n結果,レンズメーターで測定される測定度数が処方度数と異なってしまうという課 題があったこと,2)乙4公報記載の累進屈折力レンズでは,処方度数と測定度数が 異なるという上記課題を解決するため,処方面の主注視線に沿った線上部分の一部 に面非点隔差の発生しない領域を設けることとし,当該領域をレンズをフレーム形 状に加工する際に不要部分として廃棄される位置としたこと,3)上記乙4公報記載 のものでは,不要部分として廃棄される領域において測定度数を得ることから,レ ンズの度数測定の本来の目的(装用者の処方どおりにレンズが正しく作成されてい るか否か)との関係で適切とはいえないという問題があったこと,4)本件各発明は, これらを踏まえ,装用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レ\nンズを提供することを目的としたものであって,処方面の非球面形状により発生す る面非点隔差成分と処方度数の矯正に必要な球面又はトーリック面により発生する 面非点隔差成分との差の絶対値の平均値が,レンズの度数を測定するための測定基 準点を含む近傍の所定領域に亘って所定の値以下に抑えられているとの構成を有することにより,処方面の非球面化により装用状態における光学性能\を補正する構成\nを採用しているにもかかわらず,例えばレンズメーターを用いて測定基準点を基準 として測定することにより処方度数とほぼ同じ測定度数を得ることができる,とさ れていることが認められる。 また,本件明細書の上記イの記載によれば,本件各発明の実施に際しては,上記 所定領域を広くすると,度数測定には有利となるが,その代償として光学性能が低下するため,この点を考慮して所定領域を定めなければならず,所定領域は,「装\n用状態における光学性能を良好に改善しているにもかかわらず,眼鏡店やユーザーによるレンズの度数測定を容易に行うことのできる累進屈折力レンズを提供するこ\nとを目的とする」という発明の目的を達成するように定められる必要があり,また, 装用者の処方や使用条件,製品の仕様,度数測定方法,測定器の仕様のうち少なく とも一つの条件を考慮して,平均値ΔASavを所定の値以下に抑えるべき測定基 準点を含む近傍の所定領域の大きさや形状を決定することによって,より優れた光 学性能と度数測定の容易さとの両方を得ることが可能\となる,とされていることが 認められる。
・・・・
このように,レンズメーターを用いて測定した球面度数及び乱視度数の値を処方 球面度数及び処方乱視度数と略同じ値にするため,本件各発明は,「測定基準点を 含む近傍の所定領域」とその領域における「所定の値」を設けたものであり,処方 面において改善された光学性能を犠牲にしても,レンズメーターによって測定する「測定基準点を含む近傍の所定領域」において局部的な面補正をし,面非点隔差成\n分を所定の値以下にしようとするものであるから,構成要件Cにいう「測定基準点を含む近傍の所定領域」とは,それ以外の領域とは区別された領域であることを当\n然の前提としているものというべきである。
・・・・
このように,被告製品1,2及び4は,遠用度数測定点を中心とした遠用部領域 全体(被告製品2のうち,上記図中の2)−2については,ほぼ全体),被告製品3 は近用度数測定点を中心とした近用部領域の領域全体において,面非点隔差の平均 値が本件各発明の構成要件Dにおける所定の値(0.15ディオプター)を大きく下回っている。
イ そうすると,被告各製品においては,レンズの測定基準点を含む処方面の非 点隔差は,光学設計上,一定の領域における光学性能を犠牲にしても所定の値以下とするような局部的な面補正,つまり,「所定の値以下」にされた「所定領域」を\n設ける必要がない構造であることが認められる。したがって,被告各製品は,構\成要件Cにいう「所定領域」に相当する構成を有\nしないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.03. 1
平成27(受)1876 不正競争防止法による差止等請求本訴,商標権侵害行為差止等請求反訴事件 平成29年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
そして,商標法39条において準用される特許法104条の3第1項の規定(以下「本件規定」という。)によれば,商標権侵害訴訟において,商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないとされているところ,上記のとおり商標権の設定登録の日から5年を経過した後は商標法47条1項の規定により同法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判を請求することができないのであるから,この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても,同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。また,上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると,商標権者は,商標権侵害訴訟を提起しても,相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり,商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる。 そうすると,商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。
・・・・
そこで,商標権侵害訴訟の相手方は,自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法4条1項10号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することができるものと解されるところ,かかる抗弁については,商標権の設定登録の日から5年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても,同法47条1項の上記(ア)の趣旨を没却するものとはいえない。 したがって,商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求 されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登 録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,商標権侵害訴訟の相 手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登\n録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標 であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利 の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当であ る。そして,本件における被上告人の主張は,本件各登録商標が被上告人の業務に 係る商品を表示するものとして商標登録の出願時において需要者の間に広く認識さ\nれている商標又はこれに類似する商標であるために商標法4条1項10号に該当す ることを理由として,被上告人に対する本件各商標権の行使が許されない旨をいう ものであるから,上記のような権利濫用の抗弁の主張を含むものと解される。
◆判決本文
原審はアップされていません。
関連カテゴリー
>> 104条の3
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2017.02.28
平成28(行ケ)10039 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月23日 知的財産高等裁判所
(1) 特許法29条2項は,「特許出願前にその発明の属する技術の分野におけ る通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることが できたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けること ができない。」と定めるから,引用発明は,本件発明の属する技術分野の当業者が検 討対象とする範囲内の技術的思想であることを要する。また,同法29条1項各号 に掲げる発明から進歩性判断の対象となる発明を容易に発明をすることができたか 否かを判定するに当たっては,前者と後者の構成上の一致点と相違点を見出し,相\n違点に係る上記後者の構成を採用することが当業者にとって容易であるか否かを検\n討するから,上記前者の発明は,上記後者の発明の構成と比較し得るものであるこ\nとを要する。 そこで検討するに,前記1(2)のとおり,本件発明は,2以上の薬剤を投与直前に 混合して患者に投与するための医療用複室容器に関するものであり,前記2(2)のと おり,引用発明も,2以上の薬剤を投与直前に混合して患者に投与するための医療 用複室容器に関するものであるから,本件発明と技術分野を共通にし,本件発明の 属する技術分野の当業者が検討対象とする範囲内の技術的思想であるといえる。ま た,本件発明と引用発明とは,前記3のとおり,「可撓性材料により作製され,内部 空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第1の薬剤室と第2の薬剤室に区分され\nた容器本体と,該容器本体の下端側シール部に固定され,前記第1の薬剤室の下端 部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤室に収納された第1の薬剤と,前記第 2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記第1の薬剤室と前記排出ポートとの連 通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用複室容器であり,\n前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成され, 空室となっている空間内および前記空間を形成する内面が滅菌されている医療用複 室容器。」という点で一致するから,引用発明は,本件発明の構成と比較し得るもの\nであるといえる。よって,引用発明は,本件発明の進歩性を検討するに当たっての 基礎となる,公知の技術的思想といえる。
(2) これに対し,原告は,引用文献には,本件明細書に記載された,「連通阻 害用弱シール部を設けることにより形成される空間内を確実に滅菌できる医療用複 室容器を提供する」という課題が記載されていないから,引用発明は,引用発明と しての適格性がない,と主張する。 しかし,引用発明は,上記のとおり,本件発明と,技術分野を共通にし,かつ, 相当程度その構成を共通にするから,引用文献に本件発明の課題の記載がなくとも,\n本件発明の技術分野における当業者が,技術的思想の創作の過程において当然に検 討対象とするものであるといえる。当該課題が引用文献に明示的に記載されていな いことを理由として,引用文献に記載された発明の引用発明としての適格性を否定 することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.02.28
平成28(行ケ)10178 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年2月23日 知的財産高等裁判所(2部)
本願商標は,前記第2の1のとおり,欧文字の大文字「NYLON」を横書 きしたものである。その書体は,原告も自認するとおり,「Futura」と称する 書体を太字で表したものと酷似したものであるが,「Futura」と称する書体は,\nセリフ(文字の線の端につけられる線・飾り)のない書体であるサンセリフ書体の 一種であり,フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」の「サンセ リフ」の項において,ジオメトリック・サンセリフ(直線や円弧など,幾何学的な 図形により骨格が形成されているサンセリフ体)の例の筆頭として取り上げられて いるほか,写真・イラスト,動画素材等のダウンロード素材を販売するウェブサイ トにおいて,定番フォントの1つとされている(乙4,5,7)。また,文字からな る標章を太字で表すことも,一般的に行われていることである(乙5〜11)。そし\nて,本願商標は,この書体により概ね同じ大きさで書かれた文字を,概ね等間隔に, 横一列に配置したものである。 そうすると,本願商標は,欧文字の大文字「NYLON」を,一般に知られてい る書体により,ありふれた大きさと配置で横書きしたにとどまるものであるから, これに接する需要者をして,外観上,特徴あるものとして強く印象付けられるとは いえず,欧文字の大文字「NYLON」を普通に用いられる方法で表示する標章の\nみからなる商標と認識されるにとどまるものと認められる。
・・・・
原告は,「NYLON」は,商品の原材料の表示の一部として用いられるこ\nとはあるが,単独で被服,履物,かばん類及び袋物の原材料を表示することはなく,\n本願商標の文字書体により原材料を表示したものもない一方,本願商標は,店舗の\n看板等において単独で使用するものであるから,これに接した需要者は,本願商標 の使用態様を見て,商品の原材料を表示したものではなく,店舗の名称と認識する\nことが可能であると主張する。\nしかしながら,欧文字の大文字「NYLON」が,「ナイロン」,「Nylon」, 「nylon」と同様に,商品の原材料(素材)がナイロンであることを示すため に用いられていることは,前記2(1)のとおりであり,法令上も,「NYLON」は, ナイロン繊維を示す表示として「ナイロン」と選択的に用いることが許容されてい\nる。また,本願商標の書体は,一般に知られている書体にとどまり,当該書体によ り商品の原材料(素材)を表示することが不自然なものとはいえないから,当該書\n体により商品の原材料(素材)を表示した証拠が提出されていないことをもって,\n本願商標に接した需要者が商品の原材料(素材)を表したものと認識し得ない根拠\nとすることはできない。 さらに,本願商標が設定登録された場合,その使用態様は,原告主張のような小 売店舗の看板等において単独で使用する態様に制限されるものではなく,本願役務には,顧客の商品選択が容易となるように,取扱商品の原材料(素材)その他の特 長等を説明することも含まれることからすれば,本願商標をその指定役務の取扱商 品と共に使用する態様も想定されるのであって,本願商標の使用態様を単独で使用 する態様に限定して検討することは相当でない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2017.02.27
平成27(行ケ)10231 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月22日 知的財産高等裁判所(3部)
これらの記載によれば,本件明細書は,「油脂を含むコート剤」の材 質,被覆方法,被覆の量や程度について,好ましいあるいは望ましい例 を示しているものの,それ以外の構成をとることも特に制限していない\nものと認められる。 したがって,「油脂を含むコート剤」については,材質に特に制限が ない以上,従来例のように吸収促進のための成分が含まれているものと は異なる態様のものも包含されているというべきである。 (ウ) 以上を前提に本件明細書の実施例(段落【0044】〜【0054】, 表1及び図1)の記載をみると,実施例1として,パーム油でコートし\nた黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)をコーン油と混合し て150mg/mLとし,懸濁することにより調製した被験物質(以下 「実施例1被験物質」という。),実施例2として,黒ショウガ原末を ナタネ油でコートした以外は,実施例1と同様にして調製した被験物質 (以下「実施例2被験物質」という。),及び比較例1として,黒ショ ウガ原末をコーン油と混合して150mg/mLとし,懸濁することに より調製した被験物質(以下「比較例1被験物質」という。)を,それ ぞれ,6週齢のSD雄性ラットに,10mL/kgとなるように,ゾン デで強制経口投与し,投与の1,4,8時間後(コントロールはブラン クとして投与1時間後のみ)に採血して,血中の総ポリフェノール量を 測定したところ,実施例1被験物質及び実施例2被験物質を摂取した群 の血中ポリフェノール量は,いずれも比較例1被験物質を摂取させたも のに比べて高い値を示したことが記載されている。 ここで,本件明細書の段落【0028】に,「油脂」の具体例として, パーム油,ナタネ油と並んで「とうもろこし」から得られる油脂,すな わち「コーン油」も記載されていることからすれば,上記実施例で用い たコーン油についても,黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の 体内への吸収性を高める効果を期待し得る一方で,上記実施例の結果か らは,単にコーン油に混合,懸濁しただけの比較例1被験物質では,そ のような効果がないことも認識し得るといえる。 したがって,当業者は,本件明細書の実施例の記載から,「黒ショウ ガ成分を含有する粒子」が,パーム油あるいはナタネ油と混合,懸濁さ れた状態とするのではなく,パーム油あるいはナタネ油により被覆され た状態とすることにより,本件発明の課題を解決することができると認 識するものと認められる。
(エ) そして,本件出願当時,一般に摂取されたポリフェノールの生体内に 取り込まれる量は少ないという技術常識があるにもかかわらず(前記(2) エ),本件発明には,「黒ショウガ成分を含有する粒子」自体に吸収性 を高める特段の工夫がなされていない態様が包含されており(前記(ア)), また,「油脂を含むコート剤」にも吸収促進のための成分が含まれてい ない態様が包含されている(前記(イ))ことからすれば,当業者は,本件 発明の課題を解決するためには,パーム油あるいはナタネ油のような油 脂を含むコート剤にて被覆することが肝要であると認識するといえる。 しかし,その一方,ある効果を発揮し得る物質(成分)があったとして も,その量が僅かであれば,その効果を発揮し得ないと考えるのが通常 であることからすれば,当業者は,たとえ,「黒ショウガ成分を含有す る粒子」の表面を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより,本件\n発明の課題が解決できると認識し得たとしても,その量や程度が不十分\nである場合には,本件発明の課題を解決することが困難であろうことも 予測するといえる。
(オ) ところが,本件明細書においては,実施例1の「パーム油でコートし た黒ショウガ原末」の被覆の量や程度について具体的な記載がなされて おらず,実施例2についても同様であるから,これらの実施例によって コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明\nの課題を解決できることが示されているとはいえず,ほかにそのような 記載や示唆も見当たらない。すなわち,コート剤による被覆の量や程度 が不十分である場合には,本件発明の課題を解決することが困難であろ\nうとの当業者の予測を覆すに足りる十\分な記載が本件明細書になされて いるものとは認められないのであり,また,これを補うだけの技術常識 が本件出願当時に存在したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって,本件明細書の記載(ないし示唆)はもとより,本件出願 当時の技術常識に照らしても,当業者は,「黒ショウガ成分を含有する 粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した状態が\n本件発明の課題を解決できると認識することはできないというべきであ る。
ウ 以上のとおり,本件発明は,黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の一\n部を,ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆する態様,すな わち,「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を\n含むコート剤」で被覆した態様も包含していると解されるところ,本件明 細書の記載(ないし示唆)はもとより,本件出願当時の技術常識に照らし ても,当業者は,そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは 認識することはできないというべきである。 そうすると,本件発明の特許請求の範囲の記載は,いずれも,本件明細 書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に照らして,当 業者が,本件明細書に記載された本件発明の課題を解決できると認識でき る範囲を超えており,サポート要件に適合しないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2017.02.27
平成27(行ケ)10190 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月22日 知的財産高等裁判所(3部)
そこで,以上の理解を踏まえて,本件審決の相違点2についての判断の当 否につき検討するに,本件審決は,甲1発明1において,エステル交換によ って脂肪酸エステルを含む油組成物を生成することと,本件訂正発明1に おいて,揮発性作業流体を混合物に添加することとは,環境汚染物質を除去 するために分子蒸留に付すべき脂肪酸エステルを含む油組成物を生成する という操作目的の点で技術的に軌を一にすることを理由として,甲1発明 1における「リパーゼを用いた選択的エステル交換を行って脂肪酸エステ ルを含む油組成物を生成する」構成を,周知技術である「揮発性作業流体を\n油組成物に外部から添加する」構成に置換することの容易想到性を認める\n判断をする。
しかしながら,上記エで述べたとおり,甲1公報に記載された発明は,上 記エ1)ないし3)の各課題を解決することを目的とする発明であると理解さ れるところ,このうち,上記エ1)及び3)の課題の解決のためには,「リパー ゼを用いた選択的エステル交換を行って脂肪酸エステルを含む油組成物を 生成」し,その上で分子蒸留を行うことにより,所望でない飽和および単不 飽和脂肪酸を実質的に有しないグリセリドの残余画分を得ることが不可欠 であり,この工程を,「揮発性作業流体を油組成物に外部から添加」した上 で分子蒸留を行う工程に置換したのでは,上記発明における上記エ2)の課 題は解決できたとしても,これとともに解決すべきものとされる上記エ1) 及び3)の課題の解決はできないことになる。 してみると,甲1公報に記載された発明において,「リパーゼを用いた選 択的エステル交換を行って脂肪酸エステルを含む油組成物を生成する」構\n成に代えて,周知技術である「揮発性作業流体を油組成物に外部から添加す る」構成を採用することは,当該発明の課題解決に不可欠な構\成を,あえて 当該課題を解決できない他の構成に置換することを意味するものであって,当業者がそのような置換を行うべき動機付けはなく,かえって阻害要因\nがあるものというべきである。
なお,このことは,甲1公報の記載のうち,「トリグリセリドの形態で飽 和および不飽和脂肪酸を含有する油組成物からの環境汚染物質の除去のた めの方法」に係る特許請求の範囲請求項22で特定される発明に専ら着目 してみても,異なるものではない。すなわち,当該発明においても,「(a) 該油組成物を,実質的に無水の条件下,かつ飽和および単不飽和脂肪酸のエ ステル交換を優先的に触媒するに活性なリパーゼの存在下に,…エステル 交換反応に供する工程」を要し,かつ,「(b)工程(a)において得られ た生成物を…分子蒸留に供して多不飽和脂肪酸のグリセリドに富み,かつ 環境汚染物質が優先的に除去された残余画分を回収する工程」を要するも のとされているのであるから,上記エ2)の課題とともに,上記エ1)及び3)の 課題をも解決するために,「リパーゼを用いた選択的エステル交換を行って 脂肪酸エステルを含む油組成物を生成する」構成を不可欠の構\成としてい ることは明らかといえる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2017.02.23
平成26(ワ)20319 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月27日 東京地方裁判所(40部)
「暗号」とは,一般に,「通信の内容が第三者にもれないように,おたが いに約束して使う記号(のしくみ)」(三省堂国語辞典第7版52頁〔甲 2〕),「秘密を保つために,当事者間にのみ了解されるようにとり決めた 特殊な記号・ことば。あいことば。」(広辞苑第4版99頁〔甲5〕), 「第三者に通信内容を知られないように行う特殊な通信(秘匿通信)方法の うち,通信文を見ても特別な知識なしでは読めないように変換する表記法\n(変換アルゴリズム)のこと」(ウィキペディア〔乙1〕),「秘密にした い情報をかき混ぜて(暗号)特定の者以外にはその内容が解らないようにす ること。」(情報通信用語辞典13頁〔乙3〕),「情報の意味が当事者以 外にはわからないように,情報を変換すること」(エンサイクロペディア電 子情報通信ハンドブック〔乙17〕)との意味を有するとされている。 また,「コード」とは,「文字や記号,数字などをコンピューターが識別 するためにまとめられた符号」(IT用語辞典BINARY〔乙2〕), 「データを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づい\nて表現されたもの」(情報通信用語辞典100頁〔乙3〕)との意味を有す\nるとされている。 以上を前提にすると,本件発明4及び6の構成要件A4,B4及びB6に\nいう「暗号コード」とは,通信の内容が第三者に知られることのないように, 当事者間にのみ了解されるように取り決めた特殊な記号,文字ないし数字を まとめた符号を意味するものと解するのが相当である。
(2) これを被告製品3及び4についてみるに,被告によれば,被告製品3及び 4は「ID情報」を有しているが,この「ID情報」とは単なる数字にすぎ ないものと認められる(原告も明らかに争わず,これに反する証拠も存在し ない。)。そうすると,単なる数字にすぎない以上,その内容が「第三者に 知られることのないよう」にしたものではないのであるから,被告製品3及 び4の「ID情報」は,通信の内容が第三者に知られることのないよう,当 事者間にのみ了解されるように取り決めた特殊な記号,文字ないし数字をま とめた符号ではないのであって,「暗号コード」に該当するものとはいえな い。 そして,本件全証拠を精査しても,被告製品3及び4が「ID情報」以外 に「暗号コード」に該当するような符号を使用していることを認めるに足り る証拠はないから,本件においては,被告製品3及び4は,構成要件A4,\nB4及びB6にいう「暗号コード」を充足しないというべきである。
(3) 原告の主張に対する判断
この点に関して原告は,本件発明4及び6にいう「暗号コード」とは,コ ードの一部を任意の数字(信号)を組み合わせたものとしてリセットコード を設定し,送受信するものにすぎず,辞書等における「暗号」の意味とは異 なるものであって,このことは本件明細書等の記載からも明らかであると主 張する。 しかし,明細書の技術用語は,特に明細書の中で定義して特定の意味に使 用している場合を除き,原則として学術用語を用い,その有する普通の意味 を用い,かつ特許請求の範囲及び明細書全体を通じて統一して使用されなけ ればならないところ(特許法施行規則24条参照),本件明細書等において は,「暗号コード」の意義に関し,段落【0073】において「『暗号』は 4桁の暗号コードである。」と記載されているにすぎず,「暗号コード」な いし「暗号」の意味が原告主張のようなものであることにつき,何らの明確 な定義付けもされておらず,また辞書等における「暗号」の意味と異なるな どといった示唆もされていない。したがって,「暗号コード」とは電気通信 技術に関する技術的知識を有する当業者が理解する通常の意味で解釈すべき であるから,原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2017.02.23
平成28(行ケ)10102 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月21日 知的財産高等裁判所(第4部)
そこで,引用発明2において,相違点4に係る本件発明1の構成を備えるように\nすること,すなわち,油圧導入路を備え,油室の油圧によって弁体を出力部材側に 進出させた状態に保持することを,当業者が容易に想到することができたか否かに ついて検討する。
イ 引用例2には,通孔58からの加圧エアの押圧機能に関して,「上記ピスト\nン24が後退(判決注:【図3】の左方へ移動)すると,弁操作具44は,バネ5 0の作用及び/又は従道部分68の対応面積に作用する加圧エアの力によってリリ ースされ,その弁操作具44は,【図3】のノーマル外方位置へ戻る。」(3欄9 〜13行),「図示のように圧力入口と出口及び排気孔が位置されることにより, 入口孔58からの流体圧力は,バネ50の付勢力と協働して,シリンダ12の中空 体の内部から弁操作具44及び弁部材46に作用する圧力流体の力に抗して上記の 操作具44が外方位置へ移動するのを防止する。」(3欄37〜43行)と記載さ れている。 このように弁部材46を左方に押圧する力について,通孔58からの加圧エアに よる作用とバネ50による作用とが並列して記載され,さらに「協働」する旨記載 されていることからすれば,当業者は,通孔58からの加圧エアによる作用には, 弁部材46を左方に押圧するものが含まれていると当然に理解するというべきであ る。そうであるにもかかわらず,引用発明2において,弁部材46に油圧導入路を 備えて,油室の油圧によって弁部材46を押圧するような状態にすることは,通孔 58からの加圧エアによる作用を失わせることになるから,このような状態にする ことには阻害事由があるというべきである。
ウ また,引用発明2において,弁部材46に油圧導入路を備えて,油室の油圧 によって弁部材46を押圧するような状態にすることは,弁孔53などに油圧を導 入することになり,空圧バルブ16の作用が失われることになるから,かかる点か らも,このような状態にすることには阻害事由がある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2017.02.23
平成26(ワ)1397等 不正競争行為差止等請求事件,請求異議事件 不正競争 民事訴訟 平成29年2月9日 東京地方裁判所
前記1(1)で認定した事実によると,1)原告においては,従業員から,原告に関す る一切の「機密」について漏洩しない旨の誓約書を徴するとともに,就業規則で「会 社の営業秘密その他の機密情報を本来の目的以外に利用し,又は他に漏らし,ある いは私的に利用しないこと」や「許可なく職務以外の目的で会社の情報等を使用し ないこと」を定めていたこと,2)コンフォートシューズの木型を取り扱う業界にお いては,本件オリジナル木型及びそのマスター木型のような木型が生命線ともいう べき重要な価値を有することが認識されており,本件オリジナル木型と同様の設計 情報が化体されたマスター木型については,中田靴木型に保管させて厳重に管理さ れていたこと,3)原告においては,通常,マスター木型や本件オリジナル木型につ いて従業員が取り扱えないようにされていたことを指摘することができる。これら の事実に照らすと,本件設計情報については,原告の従業員は原告の秘密情報であ ると認識していたものであり,取引先製造受託業者もその旨認識し得たものである と認められるとともに,上記1)の誓約書所定の「機密」及び就業規則所定の「営業 秘密その他の機密情報」に該当するものとみられ,原告において上記1)の措置がと られていたことは秘密管理措置に当たるといえる。 なお,原告における木型の管理状況に関し,被告三國らは,原告は,原告の事務 所内やその裏口の屋外に木型を放置していたことがしばしばあり,また,原告の従 業員が,被告三國が貸与を受け返却した木型について特段の管理を行っていた事実 もないなどと主張し,被告Aiもこれに沿った供述等をする。しかしながら,証拠 (甲60,原告代表者〔7〜8頁〕)及び弁論の全趣旨によれば,原告の事務所の\n屋外に置かれていた木型は,原告が,開発段階で没にした木型を廃棄前に置いてい たにすぎないものと認められる。また,前記1(1)イで認定したとおり,原告におい ては,中田靴木型からの納品書のほか,木型番号,サイズ及び台数を記載した木型 台数管理表で,木型の台数等を管理していたことなどに照らすと,被告Aiの上記 供述等によって直ちに上述の秘密管理性を否定することはできず,他に,秘密管理 性を否定するほどの事情もうかがわれない。 以上によれば,本件設計情報は,秘密として管理されていたものというべきであ る。
イ 非公知性について
前記1(1)で認定した事実によると,本件オリジナル木型及びそのマスター木型自 体を一般に入手することはできなかったものと認められるが,被告三國らは,市販 されている本件原告婦人靴から,その靴に用いた木型を再現して本件設計情報(形 状・寸法)を容易に把握することができる旨主張し,その証拠として,パテを流し 込んで再現木型を作成したとする乙A第7・第8号証を提出する。 しかしながら,前記1(1)イで認定したとおり,靴の皮革は柔軟性を有するため, 市場に出回っている革靴から,その靴の製造に用いた木型と全く同一の形状・寸法 の木型を再現しその設計情報を取得することはできない。乙A第7・第8号証の再 現木型が元の木型と正確に同一の形状・寸法であることの立証はない上,かえって, 被告Aiの本人尋問の結果(7頁)によると,1割程度は再現できていないという のである。さらに,被告Ai自身,別件訴訟の本人尋問において,「流通している 靴から木型を作成するのは,木型の寸法を忠実に再現しない限りは容易にできる。」 旨の供述をしており(乙A9〔15頁〕),これは,「木型の寸法を忠実に再現」 することは困難であることを自認するものといえる。 そうすると,原告主張の方法により元の木型と全く同一の形状・寸法の木型を容 易に再現することはできないというべきであり,他に,特段の労力等をかけずに本 件設計情報を取得することができるとの事情はうかがわれないから,本件設計情報 は,公然と知られていないもの(非公知)であったということができる。
ウ 有用性について
前記1(1)で認定した事実によると,本件設計情報については,コンフォートシュー ズの製造に有用なものであることは明らかであるから,本件設計情報は,生産方法 その他の事業活動に有用な技術上の情報であったということができる。
2017.02.20
平成28(行ケ)10177 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年2月8日 知的財産高等裁判所
本願商標は,別紙本願商標目録記載のとおり,「eTrike」の欧文 字を太字で一連に横書きしてなる商標であるところ,商標全体としては,辞 書等に記載された既成の語ではなく,一種の造語として認識されるものと認 められる。 したがって,本願商標からは,欧文字表記をする外国語として我が国にお\nいて最も一般的な英語の読みに従った称呼が生じるものと考えられるとこ ろ,上記一連の欧文字綴りからは,「エトライク」の称呼が自然に生じるも のといえる。
(2) 他方,本願商標は,一連表記された6つの欧文字のうち,冒頭の「e」の\n文字が小文字であり,2番目の「T」の文字のみが大文字である点に特徴が あるところ,英語では一つの語の冒頭の文字のみを大文字で表記することが\n一般的に行われていることからすれば,本願商標に接した取引者,需要者ら は,大文字の「T」以降の文字である「Trike」を一つの語としてとら え,冒頭の「e」の文字と区分して理解することも自然にあり得ることとい える。加えて,上記「Trike」及びその片仮名表記である「トライク」の\n語は,「三輪車」や「三輪の自転車またはオートバイ」を意味する既成の用 語であり(乙3,4),特に,本願商標の指定商品に含まれる「二輪自動車,三 輪自動車,自転車」に係る取引者,需要者らの間では,そのような意味を有 する用語として相応の認識が得られていると考えられること(乙3ないし1 1),他方,例えば,「Eメール」,「eコマース」,「eラーニング」な どのように,「electronic」の頭文字である「e」の文字を既成 語の冒頭に付して,電子化されたものを表す用語として用いるように,既成\n語の前に欧文字を1字置いて,様々な意味やニュアンス等を表すことが我が\n国においても一般的に行われていることといった事情に鑑みれば,本願商標 に接した上記取引者,需要者らにおいては,これを,「三輪の自転車または オートバイ」等を意味する「Trike」の冒頭に「e」の欧文字を付した 造語として認識することも自然にあり得ることであるといえる。 そして,取引者,需要者らが本願商標を上記のように認識することを前提 とすれば,本願商標の冒頭の「e」の文字からは,その自然な英語読みであ る「イー」の称呼が生じ,2文字目以降の「Trike」からは「トライク 」の称呼が生じて,全体からは,上記「Eメール」等と同様に,「イートラ イク」という一連の称呼が生じ得るものといえる。
(3) これに対し,原告は,1)本願商標は,「eTrike」の文字を一つの言 葉として全体が均整のとれた注目される図案化された商標であり,その綴り の中に配された「T」の文字は,語頭文字でもなければ,文頭文字でもない から,本願商標中の「e」と「Trike」を区切って発音することは考え られない旨,2)冒頭の「e」の文字には,長音で発声することを示す記号等 は配されていないから,そこから「イー」の称呼が生じるとはいえない旨,3) 仮に「e」と「Trike」を区切って発音するとしても,「イ」と「トラ イク」を切り離して発音することとなり,「イートライク」のように一連の 称呼は生じない旨を主張する。
しかし,本願商標が欧文字を一つの言葉のように一連表記した商標である\nことを踏まえても,冒頭の「e」の文字と2文字目以降の「Trike」の 語が区分して認識され得ることは上記(2)で述べたとおりである。原告は,本 願商標中の「T」の文字が語頭文字でも,文頭文字でもないことを指摘する が,むしろ,語頭ではなく,2文字目にある「T」が大文字とされているが ゆえに,本願商標に接した取引者,需要者らは,「T」以降の文字である「 Trike」を一つの語としてとらえ,冒頭の「e」の文字と区分して理解 すると考えられるのであるから,原告の上記指摘は当を得たものとはいえな い。 また,取引者,需要者らが本願商標の「e」の文字と「Trike」の語 を区分して認識することを前提とした場合,「e」の文字から,自然な英語 読みとして「イー」の称呼が生じ得ることは,我が国の英語の普及状況に照 らし明らかであり,そのために,必ずしも長音で発声することを示す記号等 を要するものとはいえない。 さらに,取引者,需要者らが本願商標の「e」の文字と「Trike」の 語を区分して認識したからといって,「イ」と「トライク」を切り離して発 音することが通常であるとはいえず,むしろ,わずか6つの欧文字が一連表\n記された「eTrike」の「e」と「Trike」とを殊更切り離して発 音することは不自然であって,「イートライク」の一連の称呼が自然に生じ ることは明らかといえる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.02.20
平成28(行ケ)10100 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月8日 知的財産高等裁判所
第1次審決−無効審理において訂正請求をしましたが、認められず無効審決。
第1次取消訴訟+訂正審判がなされたので、特許庁に差し戻し。
第2次審決−訂正審判による訂正認容審決。
第3次審決−無効審判が請求されたが、無効理由なしとの審決。
第2次取消訴訟−無効理由なしとした審決を取り消し(平成26年(行ケ)第10219号)。
第4次審決−無効審判の審理が再開され、再度、無効理由なしとの審決
本件請求項1の記載によれば,本件発明1の「凸部分は0.07c m(0.0275in)〜0.0889cm(0.0350in)の曲 率半径を持ち」との構成は,ゴルフボールの「表\面から延びる格子構造」\nを成す「格子部材」について,「第1の凹部分と第2の凹部分の間に設 けられた」「頂部を有」する部分である「凸部分」の「曲線の断面」が, 上記数値範囲の曲率半径を有することを特定するものといえるところ, その断面が上記数値範囲の曲率半径を有すべき「凸部分」の範囲(頂部 に相当する部分か,頂部を含まない部分でも足りるか。)については, 本件請求項1の記載自体から一義的に明らかであるとはいえない。 そこで,この点については,本件明細書の記載を考慮して解釈する必 要がある。
(イ) まず,本件明細書において,凸部分に求められる曲率半径の数値に ついて述べた記載としては,段落【0052】に,「…複数の格子 部材40の好ましい断面が図7及び8に示されている。この好まし い断面は,第1の凹面部54と,凸面部56と,第2の凹面部58 を有する湾曲面52を有している。各格子部材40の凸面部56の 半径R2は好ましくは0.0275から0.0350インチの範囲 である。」との記載があり,他にこの点に言及する記載はない。 しかるところ,段落【0052】の上記記載及び同記載に係る図 8によれば,凸面部56の頂部を含む湾曲面について,本件請求項 1と同一の「0.0275から0.0350インチの範囲」の曲率 半径とするものとされている。
(ウ) また,以下に述べるような本件明細書の記載を総合すれば,本 件発明1において凸部分の曲率半径を上記数値範囲と特定すること には,次のような技術的意義があることが理解できる。 すなわち,本件発明1においては,「各格子部材は外側球体を画 定するゴルフボールの中心から最も離れた点において頂部を有する 隆起した断面形状を持つ」(段落【0023】)ものとすることで, 「複数の格子部材の各々の頂部は0.00001インチより小さい 幅を有し」(段落【0024】),「本発明のゴルフボール20は, ゴルフボール20の外側球体のランド領域を画定する各格子部材4 0の頂部50ラインだけを有している」(段落【0048】)もの となり,その結果,「本発明による管状の格子パターンの空気力学 は,より大きな揚力と少ない空気抵抗を与え,これにより在来の同 様な構成のゴルフボールより大きな距離を飛ぶゴルフボールとな」\nり(段落【0063】),「本発明のゴルフボール20はゴルフボ ール20の最大範囲から所定の距離において小さい体積を有する。 この小さい体積は低速時において空気境界層を捕捉するに必要とさ れる最小の量であり,一方,高速時において低い空気抵抗を与える」 (段落【0068】)こととなって,前記1(2)のとおりの本件発 明1の目的(より大きな距離を得るための必要な乱流を生じさせる ため,飛行中にゴルフボールの周りを取り囲む空気の境界層を捕捉 する最小のランド領域を提供することを可能とすること)を達成す\nるものであることが理解できる。そして,本件請求項1及び本件明 細書の上記(イ)の記載においては,上記格子部材に係る「外側球体 を画定するゴルフボールの中心から最も離れた点において頂部を有 する隆起した断面形状」を具体的に特定するものとして,凸部分の 曲率半径を上記数値範囲にすることが特定されているものといえる。 以上のような本件発明1の技術的意義に係る理解及び本件明細書 の前記(イ)の記載を前提とすれば,本件発明1において,その断面 が上記数値範囲の曲率半径を有すべき「凸部分」とは,ゴルフボール の外側球体のランド領域を画定する頂部に相当する部分であると解 するのが相当である。
・・・
以上によれば,甲8及び9には,相違点2の「凸部分は0.07cm 〜0.0889cmの曲率半径を持つ」との構成が記載されているとは\n認められないから,その記載があることを前提として,甲1発明と甲3, 4,8及び9の記載事項に基づいて,当業者は相違点2に係る凸部分の 曲率半径に係る構成を容易に想到し得たとする原告の前記主張には理由\nがない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2017.02.17
平成26(ネ)10032 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成29年1月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上の審理の経過に照らすと,被控訴人によりEPMA分析等に関する報告書(乙 73,74)が提出され,これに基づき主張がされたのは平成27年12月21日 の第4回口頭弁論期日であり,その後は,被控訴人による分析結果の内容等を中心 とする控訴人各製品において2種類の蛍光体を使用しているか否か(構成要件E及\nびF’)が重要な争点の一つとして審理が進められ,控訴人及び被控訴人の双方とも, この点に関し,準備書面を提出し,主張と反論を続けてきたこと,また,技術説明 会の実施については,第7回口頭弁論期日までにされた主張,立証とそれに付随す る反論の範囲内で実施することが確認されていたものであり,これに対し,第4回 口頭弁論期日からほぼ1年が経過した平成28年12月6日の第8回口頭弁論期日 の直前に提出された,控訴人の本件追加主張及びこれに関連する証拠(甲177な いし187)は,争点及び証拠の整理を終了し,技術説明会を実施した上で口頭弁 論を終結することを予定していた期日の直前において初めて提出されたものである\nから,その審理経過などからみても,時機に後れて提出された攻撃防御方法に当た るものであることは明らかである。 そして,以上の経過に照らせば,争点の専門性を考慮しても,控訴人及び控訴人 訴訟代理人において,本件追加主張及び証拠(甲177ないし187)の提出をよ り早期に行うことが困難であったとは考えられないから,本件追加主張及び証拠は, 少なくとも重大な過失により時機に後れて提出されたものと認められる。 これに対し,控訴人は,被控訴人が,平成28年11月4日付け被控訴人準備書 面(11)において,1)Raman分析(乙32,33)では,蛍光体1粒子のみを測 定しているため他の組成の蛍光体が含まれる可能性は排除されない,2)EPMAの X−ray mapping分析(乙73,74)に関し「定量分析(濃度換算)」 はしていない,などの新たな事実が初めて開示されたことを理由として,控訴人第 14準備書面において総合的な反論を主張するに至った旨主張する。しかし,乙3 2号証及び乙33号証は,原審において被控訴人から提出された分析結果報告書で あり,また,乙73号証及び乙74号証は,平成27年12月21日の口頭弁論期 日において提出された分析結果報告書であることに加え,上記各書証の内容等を考 慮すれば,控訴人が主張する各事実について控訴人が確信するに至らなかったとし ても,より早期の段階で,本件追加主張及び証拠(控訴人177ないし187)の 提出をすることができたものと認められる。したがって,控訴人の上記主張は採用 することができない。 そして,本件追加主張及び証拠(甲177ないし187)について審理をするこ とになれば,被控訴人の反論を要するとともに,EPMA分析等に関し,さらなる 分析をするなどの追加の書証提出等が必要となり,審理を継続する必要があること は容易に推測することができ,このような手続を行わないままに本件の審理を終結 することはできないといわざるを得ないから,本件追加主張及び証拠(甲177な いし187)の提出は,本件訴訟の完結を遅延させることも明らかである。 したがって,控訴人の本件追加主張及び証拠(甲177ないし187)の提出は, 時機に後れて提出された攻撃防御方法として却下することが相当である。
2017.02.17
平成27(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月18日 知的財産高等裁判所
原告は,本件特許を含む被告保有の知的財産権について,被告は, ●●●●・・●●●に対し,通常実施権を許諾しているところ,本件訂正について,上記各社から承諾(特許法134条の2第5項で準用する同法127条)を得ていないから,本件訂正は認められない旨主張する。これに対し,被告は,ライセンスの内容について秘密保持義務を負っているから,その内容について明らかにすることはできないと主張する。そこで,検討するに,●●●●・・●●●
以上の事実によれば,被告との間で,提携,クロスライセンス及び和解等をした 企業は,●●●●・・●●●であると認められる。 そして,証拠(乙9,10)及び弁論の全趣旨によれば, ●●●●・・●●●について,本件特許に ついて,最初の訂正審判請求(甲49の1)がされた平成24年12月17日より も前に,被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認めら れる。また, ●●●●・・●●●についても,被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。 ●●●●・・●●● 原告は,事実実験公正証書(乙10)において, ●●●●・・●●●については,いずれも代 表取締役等代表\権を有する者の記名押印はなく,訂正に関する承諾権限があること の立証はない旨主張する。しかし,本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂 正は,特許権者が特許の無効理由を避けるために,その必要に応じてなすのが通例 であり,訂正の内容は,特許の専門的,技術的事項に関するものが多く,これを承 諾するか否かは,各社の代表取締役等の代表\権者が知的財産部長等に委任してその 判断に委ねるのが合理的であり,通例であると解されるところである。そして,上 記事実実験公正証書は,上記各社が訂正に関し承諾したことを上記各社の知的財産 部長等の担当者が確認した旨をその内容とするものであるから,これによれば,上 記各社とも,その知的財産担当部長等の担当者が訂正に関する承諾という事項につ いて,その代表者から委任を受けており,その上でこれを承諾したと推認するのが\n合理的であり,これらの者が各社代表取締役等の代表\権を有する者でなかったとし ても,それによって上記各社が訂正に関し承諾したとの認定が左右されるものでは ない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 また,本件特許が●●●●の契約の対象になっているか否かは明らかではないと いわざるを得ないものの,本件特許は,白色LEDを実現するために重要な技術的 意義を有するものと認められ(弁論の全趣旨),これを対象から除外して契約を行う ことは考えにくい(合理的根拠はない。)ものと認められるから,本件特許が,原告 が主張するように●●●●の契約の対象となっているものと推認することができる。 そして,●●●●の各承諾は,いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾で あるということはできないものの,いずれも訂正審判を請求することを承諾すると いう趣旨でなされたものと解される。
以上によれば,被告は,本件特許の訂正について,●●●●から特許法127条 の承諾を得ていたものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2017.02.14
平成28(ワ)5739 意匠権 民事訴訟 平成29年2月7日 大阪地方裁判所
ウ 本件意匠の要部の認定
美容用顔面カバーの用途,使用態様のほか,上記認定に係る公知意匠からすれば, 本件意匠の基本的構成態様は,本件意匠に係る物品である美容用顔面カバーにおい\nて,通常考えられる形態であって新規な形態とは認められず,本件意匠において新 規で創作性の認められる部分は,その具体的構成態様における以下の点,すなわち\n輪郭の形状において,こめかみから顎上部にかけて外形に沿った凸状の筋が設けら れている点,鼻部において,鼻の形状に合わせて両目付近から鼻尖部まで連続的に 隆起しており,隆起部分の脇に谷折りとなる略直線を構成する点,耳部において,\n耳を開口部の外形に沿って凸状の筋が構成されている点という具体的構\成にあると いえる。 そして,上記(1)の美容用顔面カバーの需要者が選択時に物品が顔にフィットす る形状であるかとともに,使用状態に影響する目,鼻及び口の部分の形状,さらに は装着のための耳掛け部の形状に注目することを考慮すれば,顔面にフィットする よう立体的に形成された美容用顔面カバーにおける鼻部の具体的な形状,耳掛け部 周辺の具体的形状が需要者の注意を最も惹く部分であり,これらが本件意匠の要部 であるといえる。
・・・
イ 差異点
具体的構成態様において,1)被告意匠は,額部において頂部がわずかに凹となっ ており,顎部において,中心部に逆V字の切れ込みを設けた曲線が構成されており,\n中央部の輪郭はこめかみから顎部に至るまで,輪郭に沿って凸状の筋が形成されて いるのに対し,本件意匠は,全体が凸の曲線であり,輪郭に凸状の筋がない点,2) 両目部において,その孔が,被告意匠は横長楕円形で両端が尖っているのに対し, 本件意匠は横長楕円形である点,3)鼻部において,被告意匠は,両目部の孔の内側 付近から鼻尖部付近まで連続的に隆起し,正中線に沿ったその頂点の折り込み線が 鼻梁を構成しているのに対し,本件意匠は,なだらかに隆起しており,鼻尖部は丸\n型であって,明確な鼻梁が認識できない点,4)耳部において,その孔が,被告意匠 は,縦長のハート型であるのに対し,本件意匠は,縦長の変形略楕円である点,5) 口部において,その孔が,被告意匠は,顔の中心線に線対称の横長のハート型で設 けられているのに対し,本件意匠は,横長の略楕円形である点において相違してい る。
ウ 以上により検討するに,被告意匠と本件意匠の上記イ認定の差異点は,上記 (3)で認定した本件意匠の要部にもかかわるものであると認められる。そして,その 中でもとりわけ,被告意匠は,鼻部において,両目部の孔の内側付近から鼻尖部ま で連続的に隆起し,正中線に沿ったその頂点の折り込み線が,明確な鼻梁を構成し\nている上,両目部の両端,あるいはハート形である口部に尖った形状の部分が現れ ることも合わさって,全体に鼻筋の通った引き締まった顔立ちの印象となっている といえるのに対し,本件意匠は,鼻尖部が丸型であり,また鼻梁を明確に認識でき ないだけでなく,両目部及び口部がいずれも単純な楕円形であることから,全体に のっぺりとした印象を与えるものであるといえ,これらから,両意匠を全体的に観 察した場合,看者である需要者に与える印象は異なっているということができる。 したがって,両意匠は類似するということはできないというべきである。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2017.02.10
平成28(行ケ)10088 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月8日 知的財産高等裁判所
事情が複雑です。本件特許出願について、第1次審決で補正要件違反(新規事項)と判断され、知財高裁にて、それが取り消されました(第1次判決 平成26年(行ケ)第10242号)。審理が再開されましたが、審判官は、再度補正要件違反(新規事項)として判断しました。理由は、現出願である実案出願に開示がなかった技術的事項を導入しているというものです。
以上を前提に,本件実用新案登録の当初明細書等と本願明細書等の記載事 項を比較すると,次のとおり,本願明細書等には,本件実用新案登録の当初 明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に おいて,明らかに新たな技術的事項を導入するものというべき記載が認めら れる。
ア 本願明細書等の請求項1の(3)ないし(15)に関する事項 本願明細書等に記載がある,シュレッダー補助器について,材質がプラ スチック製であること(請求項1の(3)及び(9)),色が透明である こと(同(11)),横幅が約35cmであること(同(8))の各事項 について,本件実用新案登録の当初明細書等には明示の記載がなく,また, 本件実用新案登録の出願時において,これらの記載事項が技術常識であっ たとも認められない。 また,シュレッダー補助器に埋め込まれた金属製爪部分及びこれに関す る記載事項(同(4)ないし(7),(10),(12)ないし(15)) については,本件実用新案登録の当初明細書等において,そのような爪部 分の存在自体が明らかでない。 したがって,これらの事項は,本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
イ 本願明細書等の図1及び図2並びに段落【0010】の図1及び図2に 関する事項
本願明細書等の図1(シュレッダー補助器の横断面図)及び図2(シュ レッダー補助器の正面図)並びに段落【0010】の図1及び図2に関す る寸法については,本件実用新案登録の当初明細書等には記載も示唆も一 切認められない。これらの事項は,本件実用新案登録の当初明細書等の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,明 らかに新たな技術的事項を導入するものというべきである。 ウ 本願明細書等の段落【0010】の図3及び図4に関する事項 本願明細書等の段落【0010】には,図3の寸法に関し,「(ム)シ ュレッダー補助器の下部外幅は6mm,」と記載され,「(ヤ)シュレッダ ー補助器が挿入し易いよう,傾斜角を,シュレッダー機本体の水平面から 測って85度とし,」と記載されている。しかしながら,本件実用新案登録 の当初明細書等の対応する図1においては,シュレッダー補助器の下部外 幅は5mmと異なる数値が記載されており,また,傾斜角については記載 も示唆も認められない。 また,本願明細書等の段落【0010】には,図4の寸法に関し,「( ヨ)シュレッダー補助器の横幅約35cm,」と記載されている。しかし ながら,本件実用新案登録の当初明細書等には,この点についての記載も 示唆も認められない。 したがって,これらの事項は,本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
(5) 以上のとおりであるから,本願明細書等に記載した事項は,本件実用新案 登録の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。 したがって,本願について出願時遡及を認めることはできないから,本願 は,平成18年8月24日(本件実用新案登録に係る実用新案登録出願の時) に出願したものとみなすことはできないとした本件審決の判断に誤りはなく, 本願出願の時は,本願出願の現実の出願日である平成20年10月10日と なる。
(6) これに対し,原告は,本件実用新案登録は,出願時と同一のものであると 認められたからこそ,登録になったのであり,原告は,本願において,その 登録になったものと同一のものを,そのまま(変更せずに)特許出願したに すぎないから,出願時遡及を認めないのは誤りであると主張する。 しかしながら,実用新案登録制度は,考案の早期権利保護を図るため実体 審査を行わずに実用新案権の設定の登録を行うものであるため,補正により 新規事項が追加され,無効理由を胚胎した出願であっても,実用新案権の設 定の登録はされ得る。そして,このような新規事項が追加されて実用新案登 録になった明細書等と同一のものに基づいて特許出願をした場合,特許出願 の当初明細書等も実用新案登録出願の当初明細書等に対して新規事項が追加 されたものになるから,その後の補正により新規事項が解消されない限り, 出願時遡及は認められないことになる。すなわち,実用新案権の設定の登録 は,登録時の明細書等が実用新案登録出願の当初明細書等と同一でなくとも され得るから,実用新案登録になった明細書等と同一のものをそのまま用い て特許出願をしたとしても出願時遡及が直ちに認められるものではない。し たがって,上記原告の主張はその前提を欠くものであって失当である。
また,原告は,本件実用新案登録の出願後,登録になるまでに何度も手続 補正をしているが,それは,いずれも被告側の指示(手続補正指令書)に従 って手続補正書を提出したものであり,被告側の指示に従って手続補正を繰 り返した結果,ようやく登録が認められたにもかかわらず,本件実用新案登 録の出願時のものとは異なるという理由で,出願時遡及を認めないのは理不 尽であるとも主張する。 しかしながら,証拠(甲2の1,4,6,8の1,8の2,11)によれ ば,手続補正指令書による被告の補正命令は,いずれも実用新案法6条の2 第1号又は第4号に関するものであって,補正後の明細書等の具体的内容を 指示したものではない。また,各手続補正指令書において,その都度,補正 した事項が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるように十分\n留意する必要がある旨の注意喚起もなされている(更に付け加えれば,出願 手続には専門知識が要求されるので,専門家である弁理士に相談することの 促しもなされている。)。 それにもかかわらず,本件実用新案登録の登録時における明細書等の内容 が,新規事項の追加によって出願時のそれと異なるものとなり,その結果, 特許法46条の2第2項による出願時遡及が認められないこととなったのは, 原告自身の責任によるものというほかない。したがって,上記原告の主張も また失当である。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> その他特許
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2017.02.10
平成28(ワ)37954 承継参加申立事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月31日 東京地方裁判所(第47民)
以上の特許請求の範囲や「発明の詳細な説明」の記載を総合すると,本 件発明は,デジタル格納部を含むユーザテレビ機器を備えた双方向テレビ 番組ガイドシステムに係る発明であるというべきである。 なお,明細書の【図1】(本件発明による例示的システムとされている。 段落【0011】ないし【0013】参照)においても,本件発明の「双 方向テレビ番組ガイドシステム」が,主設備(12),番組ガイドデータ ソース(14),テレビ配信設備(16),ユーザテレビ機器(22)を\n全て含むことが示されている。 イ 他方で,証拠(甲10の1及び2,14,16)及び弁論の全趣旨によ れば,被告物件である液晶テレビ製品は,単に放送を受信するだけで,い ずれもそれ自体に録画できるメモリー部分(デジタル格納部)を備えてお らず,録画先としては,外付けのUSBハードディスクやレグザリンク対 応の東芝レコーダーとされており,これらを被告物件に接続することによ って初めて,被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画する ことが可能であるものと認められる。
ウ 以上のとおり,本件発明は,デジタル格納部を含むユーザテレビ機器を 備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから,被告物件 (液晶テレビ製品)が本件発明の技術的範囲に属するというためには,被 告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要である\nところ,被告物件は,それ自体にテレビ番組をデジタル録画可能なメモリ\nー部分を有していないから,この点において,構成要件Cを充足しないと\nいうべきである。
エ これに対し,原告は,本件発明は「双方向テレビ番組ガイドシステム」 の発明であって,テレビ本体やデジタル格納デバイス自体の発明ではなく, 構成要件Aは「双方向テレビ番組ガイドシステム」が「ユーザテレビ機器\n(22)」自体を備えることを規定するものではないし,構成要件Cも,\nあくまで複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を構成要件の内容と\nして規定するものであって,デジタル格納デバイスを規定しているわけで はないから,被告物件自体がUSBハードディスクを備えているか否かは, 本件発明の構成要件充足性には無関係である旨主張する。\nしかしながら,原告の上記主張は,上記で説示した特許請求の範囲や明 細書の各記載(例えば,本件発明の目的が「従来双方向番組ガイドシステ ムにより提供されたものよりも高度な機能を提供するように番組ガイドを\n用いることを可能にするデジタル格納部を備えた双方向番組ガイドシステ\nムを提供すること」であるとの明細書の記載(段落【0006】)等)に 明らかに反するものであるから,採用することができない。
(2) 構成要件Dの充足性について\n ア 証拠(甲7,乙14,15)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が 認められる。
・・・
イ このように,本件特許の出願人であったユナイテッド社は,本件特許の 出願段階で,特許庁に対し,本件発明が「引用文献3」(本件の乙20に 相当する。)記載の発明とは異なり,進歩性を有することを示すことを目 的として,本件発明では,同文献記載の発明とは異なり,「番組データが 格納される前に,番組が格納される」旨主張していたものである。そして, 特許庁では,ユナイテッド社の以上のような主張をも考慮した上で,本件 発明は「引用文献3」記載の発明とは異なり,かつ同発明からは容易想到 ではないとして,特許査定をしたものと解される。そうであれば,本件発 明の構成要件Dにおける番組の格納と番組データの格納の先後関係につい\nては,ユナイテッド社の上記主張のとおり,「番組データが格納される前 に番組が格納される」ものと解すべきであり,上記特許出願人の地位を承 継した原告が上記特許出願人による上記主張内容と異なる主張を本件訴訟 においてすることは,禁反言の原則に反するものとして許されないという べきである。
ウ そうであるところ,被告物件において「番組データが格納される前に番 組が格納(録画)される」という先後関係があるものとは認められないか ら,被告物件は,構成要件Dを充足しない。
エ なお,原告は,回答書(乙14)における引用文献3についての説明は, 単に本件発明と引用文献3記載の発明の内容の違いを説明したにすぎない とも主張するが,原告の同主張を前提としても,上記特許出願人が本件特 許の出願過程において上記のような説明をしたことに何ら変わりはないか ら,原告の上記主張は上記説示を何ら左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2017.02. 8
平成28(行ケ)10068 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月7日 知的財産高等裁判所
ア 次に,引用例2に記載された技術事項を適用した引用発明は,外側ベルトの 切断端部を,タイヤの赤道面から0.15〜0.35Wの範囲に位置させるという 本願発明の構成を備えるものになるかについて検討する。
イ 引用例2に記載された技術事項における「トレッドのショルダー部」の領域 引用例2には,「トレッドのショルダー部」が航空機タイヤのどの部分を具体的 に指すのかについて記載はない。そして,「ショルダー」が「肩」の意味であるこ とからすれば,「トレッドのショルダー部」とは,トレッドの肩のような形状の部 分を指すと解するのが自然である。そして,引用例2の【図1】によれば,かかる 形状の部分は,トレッドの中でもサイドウォールに近い部分,すなわち,トレッド の端部をいうものと解される。 また,引用例2には,「高速回転時のトレッド部の変形を抑制するための採用す る0°バンドは,トレッド両端部における拘束力が少ないので,トレッドショルダ ー部の膨張変形に対する効果は少ない。」と記載され(【0026】),トレッド 両端部における拘束力とトレッドのショルダー部の膨張変形に対する効果との間に 直接の因果関係がある旨説明されており,引用例2における「トレッドのショルダ ー部」とは,0°バンドによる拘束力が少ない部分である,トレッドの端部と解す るのが自然である。 さらに,航空機用タイヤに関する特開昭63−235106号公報(乙11)に おいては,タイヤのトレッドの端部がショルダー部とされており,それ以外の部分 とは区別されている。すなわち,同公報には,タイヤのトレッドのショルダー部に 2段溝状の縦溝を設けてなる航空機用タイヤに関する発明が記載されているところ (特許請求の範囲(1)),その実施例である航空機用タイヤ1(第1図)では,トレ ッド6に設けられた縦溝20,21,22のうち,サイドウォール部4の最も近く にある縦溝22は(トレッド6の)ショルダー部を通って延びる直線溝であり,2 段溝状をなすとされているのに対し,それ以外の縦溝20,21はトレッド6のク ラウン部を通って延びる直線溝であり,略V字溝状をなす(3頁右下欄1行〜14 行)とされている。このように,航空機用タイヤのトレッド6において,そのサイ ドウォール部4に近い部分であるトレッド6の端部がショルダー部と呼ばれ,それ 以外の部分であるクラウン部から区別されている。 したがって,引用例2に記載された技術事項における「トレッドのショルダー部」 とは,トレッドの端部を意味するものと認められ,同技術事項は,ベルトプライの 両端の折り返し部を,トレッドの端部に位置するように形成するものということが できる。
ウ このように,引用例2に記載された技術事項は,ベルトプライの両端の折り 返し部を,トレッドの端部に位置するように形成するものであって,引用発明に引 用例2に記載された技術事項を適用しても,折り返し部が形成されるのは「トレッ ドゴム26」の端部である。したがって,引用発明に引用例2に記載された技術事 項を適用しても,外側ベルトの切断端部を,タイヤの赤道面から0.15〜0.3 5Wの範囲に位置させるという本願発明の構成には至らないというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.02. 8
平成28(ワ)13870 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成29年1月31日 東京地方裁判所
上記事実関係によれば,運搬台車を購入しようとする建設会社等の需要 者及びこれを使用する作業員らは,斜め上方から台車本体の載置面を見る だけでなく,車輪の取付態様その他底面の構成を観察するものと解される。\nまた,本件意匠に係る運搬台車又は被告製品の台車本体を斜め上方から見 る際には,載置面の表面だけでなく,凹部から車輪取付板の形状を認識す\nるということができる。なお,この点に関し,原告は,斜め上方からでは 凹部の底にある車輪取付板は視認できない旨主張するが,その主張の裏付 けとする写真(甲28)は,台車から約2m離れた地点において,約1m の高さから撮影したものであり,作業員らが通常の使用態様においてその ような位置のみから台車を観察するとは解し難いから,原告の主張は失当 というべきである。 そうすると,本件意匠及び被告意匠においては,原告が要部であると主 張する載置面の天板の形状等だけでなく,凹部上方から視認される車輪取 付板の形状及び底面視における車輪の取付態様や台車の骨格等も,これに 接した者の注意を引くと認められる。そして,前記ウのとおり,本件意匠 と被告意匠はこれらの点が相違するのであり,これにより両意匠から需要 者が受ける印象が異なるということができるから,前記ウの共通部分を踏 まえても,全体として異なる美感を生じさせると解される。
・・・・
原告は,被告製品は四隅に手押し棒(単管パイプ)を立設する態様でのみ使 用されるから,被告意匠が手押し棒の有無により本件意匠に類似しないとして も間接侵害(意匠法38条1号)が成立する旨主張する。 そこで判断するに,手押し棒を除いても本件意匠と被告意匠が類似するとい えないことは前項で判示したとおりであるが,これに加え,証拠(乙12〜1 5,18〜20,34)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品のような載置面 が平板な台車は,四隅に手押し棒を立設する態様のほか,手押し棒を2本立設 する態様,手押し棒を立設しない態様等でも建設現場における資材の運搬等の 用に供されると認められる。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2017.02. 8
平成27(行ケ)10201 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月31日 知的財産高等裁判所
このような技術常識を有する当業者が,本件明細書の記載に接した際には,【00 07】に記載された「顕在化した色調変化」,すなわち,比較例において観察された b*値の変化(Δb*)は,L−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可 能性があると理解し,イソ\クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化のみを反映 したものであると理解することはできないと解される。 そうすると,実施例において,アルコール類を特定量添加しpHを調整すること により,比較例に比べて飲料の色調変化が抑制されていることに接しても,当業者 は,比較例の飲料の色調変化がL−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含 む可能性がある以上,イソ\クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制され ていることを直ちには認識することはできないというべきである。 そして,本件明細書の実施例のb*値の変化(Δb*)は,0.9〜2.0であっ て,0ではないことから,L−アスコルビン酸に起因するb*値の変化(Δb*)は アルコール類の添加によってもマイナスに転じること(製造直後よりも黄色方向の 彩度が減じて青色方向に傾くこと)がないものと仮定しても,当業者は,実施例に おける飲料全体の色調変化の抑制という結果から,イソクエルシトリン及びその糖\n付加物の色調変化の抑制を認識することはできないというほかない。 また,前記(1)イ(オ),(カ)bのとおり,本件出願日当時,イソクエルシトリン及びそ\nの糖付加物が水溶液中のL−アスコルビン酸の分解を抑制することが知られていた ものと認められる。しかし,乙18によれば,イソクエルシトリン及びその糖付加\n物に相当するフラボノイド配糖体A又はBの配合によるアスコルビン酸を含む3 0%エタノール水溶液のL値の減少率の抑制の程度は,これらを配合しない場合を 100%として41.5%又は39.5%に止まり,L値の減少率を0%としたも のではない(すなわち,L値の減少が解消していない。)し,明度を示すL値(L* 値)の変化を示すものであって,本件明細書で測定している黄色方向の彩度を示す b*値の変化を示すものでもなく,また,エタノールの含有量も本件明細書の実施 例・比較例(0.01〜0.50質量%)とは大きく異なるから,当業者において, 本件明細書の実施例・比較例の条件において,L−アスコルビン酸に加え,イソク\nエルシトリン及びその糖付加物が配合されていることから,L−アスコルビン酸の 褐変が生じない(したがって,本件明細書の実施例・比較例の飲料の色調変化には, L−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化は含まれない。)と理解するものとは いえない。
ウ 以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願日当 時の技術常識に照らして,本件訂正発明9〜16は,容器詰飲料に含まれるイソク\nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより,当該容器詰飲料 の色調変化を抑制する方法を提供するという課題を解決できるものと,当業者が認 識することができるとはいえない。
エ 被告は,甲40及び甲69は,審判手続において審理判断されなかった 事実に関する新たな証拠であるから,本件訴訟において,これらの証拠に基づく審 決の違法性を主張することは許されず,取消事由3−4は,本件訴訟の審理の対象 にはならないと主張する。 しかしながら,被告も自認するとおり(前記第4の1(1)),原告は,審判事件弁 駁書(乙8)において「アスコルビン酸が酸化により黄色となることは周知の技術 的事項である」ことを指摘して本件訂正発明9〜16がサポート要件及び実施可能\n要件を欠くと主張しているから(20〜21頁),「アスコルビン酸が酸化により黄色 となることは周知の技術的事項である」ことを根拠として,本件訂正発明9〜16 がサポート要件及び実施可能要件を満たす旨の審決の判断が誤りであることを主張\nすることは当然に認められ,取消事由3−4は,そのような主張を含むものと認め られる。 そして,本件訂正発明9〜16は,被告も自認する「L−アスコルビン酸を含有 する飲料が経時変化により褐変すること」という事実(被告第2準備書面3頁,被 告第3準備書面16頁)を考慮すると,甲40及び甲69を検討するまでもなく, 被告が立証責任を負担するサポート要件の充足を認めることができないことは,前 示のとおりである。なお,被告は,「イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有す\nる容器詰飲料が,L−アスコルビン酸の非存在下においても色調変化を生じ,その 色調変化がアルコールによって抑制されること」を立証趣旨として,乙14の実験 成績証明書を提出するが,乙15(技術説明資料)及び本件訴訟の経過に照らすと, 乙2の実験成績証明書と同様に,甲69の信用性を弾劾する趣旨であり,本件明細 書において開示が不十分な発明の効果を実験結果によって補充しようというもので\nはないと解される(仮に,乙14が,甲69の信用性を弾劾するにとどまらず,こ れによりイソクエルシトリン及びその糖付加物を含有し,L−アスコルビン酸を含\n有しない容器詰飲料の色調変化を立証する趣旨であったとしても,そのような立証 は,本件明細書の記載から当業者が認識できない事項を明細書の記載外で補足する ものとして許されない。)。被告の主張は,理由がない。
オ 被告は,「アスコルビン酸を含む」という条件において実施例と比較例は 同一であることを理由として,サポート要件の充足を認めた審決の趣旨は,アスコ ルビン酸を除けば,実施例と比較例のb*値やΔb*値の絶対値は変わるかもしれな いけれども,アスコルビン酸の有無にかかわらず,アルコールの添加によってイソ\nクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されるという傾向自体は不変で あることを当業者が理解できると判断したものであり,その判断に誤りはないと主 張する。 この点について,審決は,アルコールを添加した実施例と,アルコールを添加し ない比較例の双方に,L−アスコルビン酸が含まれているとしても,このような実 施例と比較例の色調変化によって,L−アスコルビン酸の非存在下におけるイソク\nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に対するアルコール添加の影響を理解す ることができると判断するところ,L−アスコルビン酸が褐変し,容器詰飲料の色 調変化に影響を与え得るという本件出願日当時の技術常識を踏まえると,このよう に判断するためには,少なくともL−アスコルビン酸の褐変(色調変化)はアルコ ール添加の影響を受けないという前提が成り立つ場合に限られることは明らかであ るが,そのような前提が本件出願日当時の当業者の技術常識となっていたことを示 す証拠はない。したがって,本件明細書の実施例と比較例の実験結果をまとめた【表\n1】により,イソクエルシトリン及びその糖付加物に起因する色調変化の抑制とい\nう本件訂正発明9〜16の効果を確認することはできない。なお,念のため付言す れば,以上の検討は,特許権者である被告が,本件明細書において,イソクエルシ\nトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることを示す実験 結果を開示するに当たり,同様に経時的な色調変化を示すことが知られていたL− アスコルビン酸という不純物が含まれる実験系による実験結果のみを開示したこと に起因するものであり,そのような不十分な実験結果の開示により,本件明細書に\nイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されるこ\nとが開示されているというためには,容器詰飲料の色調変化に影響を与える可能性\nがあるL−アスコルビン酸の褐変(色調変化)はアルコール添加の影響を受けない ということが,本件明細書において別途開示されているか,その記載や示唆がなく ても本件出願日当時の当業者が前提とすることができる技術常識になっている必要 がある。したがって,特許権者である被告において,本件明細書にこれらの開示を しておらず,また,当該技術常識の存在が立証できない以上,本件明細書にL−ア スコルビン酸という不純物を含む実験系による実験結果のみを開示したことによる 不利益を負うことは,やむを得ないものというべきである。
カ 以上によれば,取消事由3−4のうち,サポート要件の判断の誤りをい う点は,理由がある(実施可能要件の判断の誤りをいう点は,必要がないから,判\n断しない。)。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2017.02. 8
平成28(ワ)17092 損害賠償等請求事件 平成29年1月26日 東京地方裁判所
以上に基づき,原告商標1と被告標章1の類否についてみるに,これら を全体的に観察した場合には,外観,称呼及び観念がいずれも大きく相違 する。また,被告標章1のうちその構成上その余の部分と識別可能\な「京 都赤帽」との文字部分のみをみた場合でも,原告商標1とは「京都」の有 無並びに文字数(2字か4字か)及び音数(4音か7音か)が異なってお り,外観,称呼及び観念共に明確に区別し得ると解される。さらに,原告 商標1と被告標章1は,被告標章1に「赤帽」の文字が含まれることから 称呼等の一部に共通点があるが,被告標章1の構成上この2字のみに着目\nすることは困難と解される上,「赤帽」の語は前記意味を有する普通名詞 であることに照らすと,上記共通点を類否の判断において重視することは 相当でない(なお,原告商標1が周知であるとの原告の主張については後 述する。)。 これに加えて,取引の実情をみるに,本件の証拠上,被告標章1の使用 により原告と被告の提供する役務の間に出所の混同ないしそのおそれが 生じていること,例えば,原告商標1の指定役務の需要者において,地名 と「赤帽」の語を組み合わせた名称が原告(その組合員を含む。以下同じ。) の提供する役務を示すものとして広く認識されていること,被告の提供す る役務が「あかぼう」と略称されていること,原告が舞妓を想起させる図 形を被告による使用開始前から用いていることなどの事情はうかがわれ ない。 以上によれば,原告商標1と被告標章1は類似しないと判断するのが相 当である。
エ これに対し,原告は,被告標章1のうち「赤帽」以外の部分が識別力を 有しないこと,原告商標1が周知であることを理由に,「赤帽」の部分が 被告標章1の要部であり,これが原告商標1と同一であるので,被告標章 1は原告商標1に類似する旨主張する。 そこで判断するに,被告標章1の構成は前記イのとおりであり,「赤帽」\nの文字は「京都赤帽」という一連表記された文字列の一部に存するにとど\nまる一方,舞妓の図形が中央上部に大きく配置されており,これが被告標 章1に接する者の注意を引くことに照らすと,被告標章1のうち「赤帽」 の部分のみが識別力を有し,その余の部分から出所識別機能としての称呼\n又は観念が生じないとは認められない。 また,原告商標1の周知性を裏付ける証拠として原告が提出するのは, 昭和52年〜56年の新聞記事(甲53〜59,60の1),原告作成の 機関誌等(甲60の2〜5)のほか,一部(平成20年発行のサンデー毎 日。甲68)を除いては広く頒布されているか定かでない雑誌の記事等や 放映地域が限られたテレビ報道等(甲70〜75,78,79),専ら子 供向けと解される書籍又は玩具(甲69の1及び2,76,77)にとど まる。さらに,これらの証拠上も,原告が常に「赤帽」と略称されるので はなく,「Akabou」,「あかぼう」等の表示も用いられていること\nが認められる。そうすると,「赤帽」の表示が原告の提供する役務を示す\nものとして原告商標1の指定役務の取引者又は需要者に広く認識されて いると認めるに足りないから,被告標章1のうち「赤帽」の部分が役務の 出所識別標識として強く支配的な印象を与えると解することは困難であ る。 したがって,本件において被告標章1の構成から「赤帽」の部分を抽出\nしてこの部分だけを原告商標1と比較して商標の類否を判断することは 相当でなく(最高裁平成20年9月8日判決・裁判集民事228号561 頁参照),原告の上記主張を採用することはできない。
2017.02. 8
平成27(行ケ)10230 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月25日 知的財産高等裁判所
本件のように,冒認出願(平成23年法律第63号による改正前の特許法1 23条1項6号)を理由として請求された特許無効審判において,「特許出願 がその特許に係る発明の発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者 によりされたこと」についての主張立証責任は,特許権者が負担するものと解 するのが相当である。 もっとも,そのような解釈を採ることが,すべての事案において,特許権者 が発明の経緯等を個別的,具体的,かつ詳細に主張立証しなければならないこ とを意味するものではない。むしろ,先に出願したという事実は,出願人が発 明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認させ る上でそれなりに意味のある事実であることをも考え合わせると,特許権者の 行うべき主張立証の内容,程度は,冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及 び無効審判請求人の主張立証活動の内容,程度がどのようなものかによって左 右されるものというべきである。すなわち,仮に無効審判請求人が冒認を疑わ せる具体的な事情を何ら指摘することなく,かつ,その裏付けとなる証拠を提 出していないような場合は,特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なも ので足りるのに対し,無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し, その裏付けとなる証拠を提出するような場合は,特許権者において,これを凌 ぐ主張立証をしない限り,主張立証責任が尽くされたと判断されることはない ものと考えられる。 以上を踏まえ,本件における取消事由(発明者の認定の誤り)の有無を判断 するに当たっては,特許権者である被告において,自らが本件各発明の発明者 であることの主張立証責任を負うものであることを前提としつつ,まずは,冒 認を主張する原告が,どの程度それを疑わせる事情(すなわち,被告ではなく, 原告が本件各発明の発明者であることを示す事情)を具体的に主張し,かつ, これを裏付ける証拠を提出しているかを検討し,次いで,被告が原告の主張立 証を凌ぎ,被告が発明者であることを認定し得るだけの主張立証をしているか 否かを検討することとする。
・・・
以上によれば,原告の上記2)の主張のうち,原告が,平成22年1 1月3日ころまでに,本件発明1の方法の実施に用いられる本件機器 を完成させたこと,ひいては,本件発明1を完成させたことについて は,客観性のある証拠等によって裏付けられているということができ る。 しかしながら,前記a(a)で述べたとおり,本件機器は本件発明2の 方法に用いられるものとはいえないから,原告が本件機器を完成させ たからといって,本件発明2の方法を着想し,完成させたことが認め られるものではなく,他にこれをうかがわせる証拠もない。したがっ て,原告の上記2)の主張のうち,本件発明2に係る部分は,その裏付 けを欠くものというほかない(そもそも,原告は,原告が本件発明2 の方法を着想し,具体化したことを示す具体的な事情を主張していな い。)。 ウ 小括
以上の検討によれば,原告は,本件発明1(及び本件発明3のうち,本 件発明1の方法に係る部分)については,原告がその発明者であることを 示す具体的な事情(すなわち,冒認を疑わせる具体的な事情)を主張し, かつ,これを裏付ける証拠を提出しているものといえる。 他方,原告は,本件発明2(及び本件発明3のうち,本件発明2の方法 に係る部分)については,原告がその発明者であることを示す具体的な事 情を主張しておらず,これを裏付ける証拠も提出していない。そして,原 告が,本件発明1に関しては発明者であることを示す事情を具体的に説明 している(それが可能であった)にもかかわらず,本件発明2については,\nそのような事情を一切説明していないことは,原告が本件発明2を発明し たことを積極的に疑わせる事情であるといわざるを得ない。
本件発明2について
前記(1)ウで述べたとおり、原告は、本件発明2について原告がその発明者であることを示す具体的な事情を主張しておらず,これを認めるに足 りる証拠も提出していないから,本件発明1の場合とは異なり,被告が行 うべき発明者性の主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるものという べきである。 しかるところ,被告は,本件発明2の方法を着想し,完成させた経緯に ついて,平成22年10月から11月ころに,Bの自宅において,透明 な熱収縮チューブ,針金,ライター及びノズル管を用いて,噴出量の調 整が可能なノズル管の弁構\\造を作り出した旨を主張し,Bも「誓約書」 と題する書面(甲42)において,被告が,平成22年10月から11 月ころにB方を訪れた際に,「宇都宮北道路を運転している途中で,ノ ズルの製法を思いついた」旨を述べ,B方にあった熱収縮チューブ,針 金,ライターと被告が持参していたノズル管を用いてノズル管の弁構造を作り出し,さらに作ったノズル管を用いて野外での噴出実験を行った\n旨を述べ,被告の上記主張に沿う供述をしている。 そして,Bの上記供述は,その内容が具体的で,他の証拠と整合しな い内容が含まれるものでもなく,その信用性を積極的に疑うべき事情は ないから,被告側の関係者による供述証拠としてその証拠価値に限界があ ることを考慮しても,被告の上記主張を裏付ける一応の証拠として評価し 得るものといえる。また,本件発明2は,ノズル管内に弁構造を作るとい\nう点においては本件発明1と基本的発想を同じくしているということがで きるから,たとえ被告が本件発明1を発明していないとしても,原告らと 同様にノズルの改良に取り組み,相応の問題意識を持っていた被告が,原 告から本件発明1の説明を受け,これに触発されて本件発明2の着想を得 るということは十分にあり得る事柄であるということができる。\nしてみると,被告は,被告が本件発明2の方法を着想しこれを具体化し たことについて,その具体的な事情を主張し,これを裏付ける一応の証拠 も提出しているものといえるから,少なくとも上記で述べた程度を満たす だけの主張立証をしているものということができる。
・・・
以上の検討を総合すれば,本件各発明のうち,本件発明2については,そ の発明者が被告であると認めることができるが,本件発明1及び3について は,その発明者が被告であると認めることはできない。 してみると,本件各発明の発明者をいずれも被告であると認定し,本件各 発明に係る特許は,発明者でない者の特許出願に対してされたものとはいえ ないとした本件審決の判断のうち,本件発明1及び3に係る部分は誤りであ り,他方,本件発明2に係る部分は誤りとはいえない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2017.02. 8
平成28(行ケ)10001等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月2日 知的財産高等裁判所
本件発明1から10は,物の発明であり,本件発明11から17は,方法の発明 であるところ,物の発明の実施とは,その物の生産,使用等をする行為であり(特 許法2条3項1号),方法の発明の実施とは,その方法の使用をする行為であるか ら(同項2号),上記実施可能要件を充足するためには,明細書の発明の詳細な説明において,当業者が,明細書の発明の詳細な記載及び出願時の技術常識に基づき,\n過度の試行錯誤を要することなく,物の発明については,その物を生産し,かつ, 使用することができる程度の記載があること,方法の発明については,その方法を 使用することができる程度の記載があることを要する。
イ 本件特許請求の範囲は,前記第2の2のとおりであるところ,前記3(1)イ (ア)のとおり,当業者は,葉酸の補充によってMTA等の葉酸代謝拮抗薬の抗腫瘍 活性を維持しながら投与に関連する毒性を低下させることができるという技術常識 の下,MTA等の葉酸代謝拮抗薬の投与に関連する毒性の低下及び抗腫瘍活性の維 持のために,患者の年齢,体重等の属性や身体状態等に応じて適宜の用量・時期・ 方法により葉酸を投与していた。また,ビタミンB12自体は,出願時において既知 の物質であり,筋肉内注射等の投与の方法も,技術常識として確立していた(甲7, 36等)。これらの技術常識に加え,前記3(1)イ(イ)のとおり,本件明細書の発明 の詳細な説明には,葉酸及びビタミンB12の投与の具体的内容についての記載があ ることから(【0028】【0034】【0039】),当業者は,上記記載及び出願 時の技術常識に基づき,過度の試行錯誤を要することなく,本件特許請求の範囲に 記載された投与の量・時期・方法に係る葉酸とビタミンB12をMTAと組み合わせ て投与することを特徴とする医薬を生産することができ,また,方法を使用するこ とができるものというべきである。 そして,1)葉酸代謝拮抗薬の抗腫瘍活性を維持しながら投与に関連する毒性を低 下させるために必要な葉酸の用量は広範囲にわたること及び2)葉酸は,葉酸代謝拮 抗薬と並行して投与すればよく,葉酸代謝拮抗薬よりも先に投与することは必須で はないことは,出願時における技術常識であったことに加え(前記3(2)ア (ア)(イ)),本件明細書の発明の詳細な説明に,乳腺がん腫のC3H菌株に感染さ せたマウスに対し,ビタミンB12を用いて前処置し,次いで葉酸代謝拮抗薬を投与 する前に葉酸を投与することにより,毒性の著しい低下が見られ,葉酸代謝拮抗薬 の毒性をほとんど完全に除くとの記載があり(【0049】【0052】),ヒトにお ける臨床トライアルに関し,ALIMTA(MTA)ないしシスプラチンと併用す る葉酸及びビタミンB12の投与の用量・時期・方法並びに葉酸とビタミンB12の 組合せが薬物関連毒性を低下させたことが具体的に記載されていること(【005 5】〜【0060】【0064】【0065】【表1】)に鑑みれば,本件特許請求の\n範囲に記載された投与の量・時期・方法に係る葉酸とビタミンB12をMTAと組み 合わせて投与することを特徴とする上記医薬ないし方法は,MTA毒性の低下及び 抗腫瘍活性維持のためのものということができる。 以上によれば,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明及び出願時の技術常識 に基づいて,本件発明1から10に係る医薬を生産し,使用することができ,また, 本件発明11から17に係る方法を使用することができる。
(2)甲事件原告及び丙事件原告の主張について
ア 甲事件原告は,本件明細書の【0039】記載の葉酸の投与によってMTA 毒性及び抗腫瘍活性がどのようなものになるかについては言及されていない,実施 例においても,MTA毒性の低下と抗腫瘍活性の維持を両立し得るような葉酸の投 与の時期及び方法は示されていない旨主張する。 しかし,前記(1)のとおり,当業者は,出願時の技術常識及び本件明細書の発明の 詳細な説明の記載から,過度の試行錯誤を要することなく,本件特許請求の範囲に 記載された投与の量・時期・方法に係る葉酸とビタミンB12をMTAと組み合わせ て投与することを特徴とする医薬を生産し,また,方法を使用することができ,そ の医薬ないし方法は,葉酸を本件明細書の【0039】記載の方法で投与するもの も含め,MTA毒性の低下及び抗腫瘍活性維持のためのものということができる。 イ 甲事件原告は,本件明細書の【0039】において葉酸の投与時期とされる MTA投与の約1時間前から約24時間前という短時間のうちにベースラインのホ モシステインレベルが低下することは,当業者一般に知られていなかった旨主張す る。 しかし,証拠上,出願時において,ホモシステインレベルを低下させること自体 によって葉酸代謝拮抗薬の投与に関連する毒性ないしそのリスクが軽減するという 技術常識が存在したことは認めるに足りないこと(前記2(2)ウ(オ)参照)から,短 時間のうちにベースラインのホモシステインレベルが低下することが当業者一般に 知られていなかったとしても,それは,実施可能要件違反の有無を左右するものではない。\nウ 丙事件原告は,サポート要件違反と同じ理由により,本件明細書の記載は実 施可能要件に反する旨主張するが,本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能\要件を充足するか否かは,当業者が,同記載及び出願時の技術常識に基づき,過度の試行錯誤を要することなく,その物を生産し,かつ,使用することができる程 度の記載があるか否かの問題である。他方,サポート要件は,特許請求の範囲の記 載要件であり,本件特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足するか否かは,本 件特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された説明であり, 同記載及び出願時の技術常識により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し 得るか否かの問題であり,実施可能要件とは異なる。よって,丙事件原告の上記主張は,それ自体失当である。\n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2017.01.31
平成28(ネ)10020等 特許権移転登録手続請求控訴,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
しかしながら,一審原告が一審被告らに対して本件各特許権の移転登録手 続を求める訴訟が日本国の専属管轄に属し,韓国に国際裁判管轄が認められ ないことは,前記のとおりである。したがって,専属管轄に違背する以上, 本件韓国訴訟(専属管轄に反する部分)は不適法であったといわざるを得な いのであるから,そのような不適法な訴訟において,いかに本件契約の成否 が争われ,この点について確定的な判断がなされたとしても,それは意味の ないものであったというほかはなく(これは,本来審理判断をすることがで きないはずの裁判所が審理判断を行ったという重大な瑕疵に関わる問題なの であるから,これを単なる形式論として軽視しようとする一審原告の主張は 到底採用できない。),信義則により主張を制限する前提を欠く。また,一 審原告の提訴の負担についても,そもそも日本国の裁判所において提訴する 必要があったのであるから,理由にならないというべきである。
(3) 以上によれば,争点1に関する一審原告の主張は,採用することができな い。
3 争点2(本件合意書に関する紛争の準拠法は韓国法か,日本国法か)につい て
(1) 前記認定のとおり,本件合意書9条において,本件合意書に関して紛争が 生じた場合,その準拠法は韓国法と指定されているところ,本件サインペー ジには一審被告Y及びAの署名があること,本件サインページを返送する際 にAが作成した本件カバーレター(乙9)には,「1点を除いて,貴殿の申\nし入れを全て受け入れたい」との文言があり,一審被告らは,準拠法につい ては特に異議を述べる意思はなかったと認められること等の事情からすれば, 本件合意書による契約(本件契約)の成立及び効力については韓国法による というのが,当事者の合理的意思であったと推認するのが相当であり,かか る推認を覆すに足りる証拠はない。 したがって,本件の準拠法は,韓国法であるというべきである(法の適用 に関する通則法附則3条3項,旧法例7条1項)。
(2) これに対し,一審被告らは,準拠法の指定合意が無効であるとか,取り消 されるべきであるなどと主張する。 しかしながら,ここでは,本件契約に関する合意の成否や効力を問題とし ているのではないことはもとより,準拠法に関する合意の成否や効力を問題 にしているのでもなく,飽くまで本件契約の成否について争いが生じたとき に,いずれの国の法律によってこれを判断するのが当事者の合理的意思に合 致するかを探求しているにすぎないのであるから,かかる主張は失当である。 また,一審被告らは,1)本件合意書においては日本国の特許権及び特許出 願が対象となっていること,2)本件合意書が日本語で作成されていること, 3)A及び一審被告Yは日本で本件合意書に署名したことなどからして,本件 合意書に関して紛争が生じた場合の準拠法は,日本国法とされるべきである 旨主張する。 しかしながら,1)については,日本国の特許権等が対象であるとしても, 譲渡契約自体は国外でもできる以上,譲渡契約を締結する当事者の合理的意 思が必ず準拠法は日本国法によるとの意思であると解すべき根拠はないとい うべきであるし,2)についても,本件合意書は日本語(和文)のみならず英 文でも作成されているのであるから,必ずしも決め手となるものではない。 3)についても然りであり,A及び一審被告Yが日本で本件合意書に署名して いるとの点は,合理的意思解釈を行う際の一つの要素にはなり得ても,それ だけで決め手になるものではない。 結局,前記(1)で説示した事情によれば,本件の準拠法に関する当事者の 合理的意思解釈としては韓国法によるものと解するのが相当であり,一審被 告らの主張はかかる認定を覆すに足りないというべきである。
・・・・
以上によれば,一審原告が主張するその余の点,すなわち,Aには,本 件サインページに署名するに当たり,本件米国訴訟を解決する(本件米国 訴訟を取り下げてもらう)という明確な動機があったとする点や,Aは, 本件特許権1及び同3に係る発明を完成させる能力を有しておらず,同人\nはこれらの発明の発明者ではなかったとする点を考慮しても,一審被告ら による本件サインページの返送により,平成16年4月3日の時点で直ち に本件契約が成立したと認定することは困難というべきである。 したがって,主位的主張に関する一審原告の主張は,採用することがで きない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2017.01.31
平成28(行ケ)10167 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成29年1月24日 知的財産高等裁判所
原告は,B上リング状部とB下リング状部とが,上下に分離し,箸本体から取り 外し可能であると主張する。\nB上リング状部とB下リング状部(いずれも,リング部と円筒状取付部分から成 るものとして認定されている。)から成るBリング状部は,引用意匠3そのものであ り,甲2においては,保持ユニット120(人差し指挿入穴121と中指挿入穴1 22を有する。)とされている。そして,保持ユニット120は,甲2に記載された 発明としては,箸本体とは別体の部品として構成されている。しかしながら,甲2\nの記載内容を見ても,保持ユニット120が位置調節に用いられるものであること は認められるとしても,B上リング状部とB下リング状部とが2つに分離し,また, 第2箸部材から取り外せることができるか否かを,甲2の図面から読み取ることが できず,更に進んで明細書の記載を参酌しても,この点は不明である。したがって, B上リング状部とB下リング状部とが,上下に分離し,箸本体から取り外し可能で\nあるか否か不明であるとした審決の認定に誤りはない。
(2) 原告の主張について
原告は,甲2(特許公報)に係る公表特許公報である甲8(特表\2004−53 8074号公報)の記載内容を斟酌すれば,B上リング状部とB下リング状部とが 上下に分離し,箸本体から取り外し可能であることが分かると主張する。\nしかしながら,本件において意匠が記載された「頒布された刊行物」とされたの は甲2のみであり,これとは異なる刊行物である甲8に記載された意匠が,甲2に 記載された意匠になるものでないことは明らかであり,原告の上記主張は,失当で ある(なお,甲8は,明細書と図面とが対応していないなど多数の齟齬を含み,そ の記載内容は不明確である。)。仮に,甲8の【図5】と題する図面が,B上リング 状部とB下リング状部とが上下に分離し,取り外し可能であることを示すものと理\n解するとしても,甲8に記載された発明の特徴的部分とは認められない構成を,甲\n2に記載された特許発明が有する必然性もなく,結局,上記の点が甲2に記載され ているとは認められない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2017.01.31
平成28(行ケ)10164 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年1月24日 知的財産高等裁判所(第2部)
また、本件については、被告(ローソン)は一時期、原告からライセンスを受けていたとのことです。
(2) 本件商標は,「ゲンコツ」の文字部分と「メンチ」の文字部分がいずれも 辞書に掲載されている語であることから,その組合せであると解されるものではあ るが,文字のみの商標であって,図形などとの組合せではなく,しかも,全ての文 字が,標準文字で,一連に横書きされており,各文字は,同じ字体,大きさ及び間 隔で,一体的に表記されている。また,本件商標の全体の文字数は,7文字で,多くはないところ,その称呼は,\n「ゲ」と「メ」の母音がいずれも「エ」,その次に続く音がいずれも「ン」であり, 韻を踏んだ状態になっており,リズム感があることから,全体として,7文字であ るにしては,簡潔で歯切れのいい印象を与える。 そして,食品,特に単品で販売されることのある加工食品で,一定程度の大きさ と,丸みと厚みのある形状であり得るものについては,その大きさや形状を表すために「げんこつ」,「にじりこぶし」,「こぶし」という語を使用し,これを加工\n食品の名称と組み合わせて,商品の名称とされることがあると解されるのであって, 前記のような加工食品の取引の場面においては,「げんこつ」又は「ゲンコツ」と いう語が,商品の大きさや形状を象徴的に表す語として解されることもあるといえる。\nさらに,「挽肉にみじん切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ,パン 粉の衣をつけて油で揚げた料理」を,「メンチカツ」ではなく,「ミンチカツ」と いう地域もあり(甲6,7),インターネット上においては,平成27年9月19 日の時点で,「メンチカツ」を「メンチ」と略する旨の記載もある(甲7)が,そ の他に「メンチカツ」を「メンチ」と略することを裏付ける証拠はなく,平成25 年12月頃のコンビニエンスストアのホットスナックの商品名として,「あらびき 牛肉メンチカツ」(セブン−イレブン),「ビーフメンチカツ」(ファミリーマー ト)と,「メンチカツ」を略さずに全体を取り込んだものがある一方,「メンチ」 のみを取り込んだ商品名は,被告の「ゲンコツメンチ」しか見当たらず,これらを 紹介する雑誌の記事においては,これらの商品を包括する表現として「メンチカツ」と記載されていた(甲42)。\nそうすると,メンチカツ同様に挽肉を使った料理である「ハンバーグ・ステーキ」 (挽肉に刻んだ玉葱,パン粉,卵などを加え,平たい円形にまとめて焼いた料理) (広辞苑第6版)が「ハンバーグ」と表現されているのに対し,「メンチ」の語は,挽肉にみじん切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ,パン粉の衣をつけ\nて油で揚げた料理である「メンチカツ」を表す名詞として,全国の取引者,需用者に,それほど普及しているとはいえない。\n以上によれば,本件商標において,「ゲンコツ」の文字部分だけが,取引者,需 要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは いえないし,「メンチ」の文字部分からは,出所識別標識としての称呼,観念が生 じないともいえない。
(3) したがって,本件商標は,その外観,称呼及び観念のいずれの点において も,引用商標と相違し,取引の実情を考慮しても,引用商標とは類似しておらず, 商標法4条1項11号に該当する商標ではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.01.31
平成28(行ケ)10181 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成29年1月24日 知的財産高等裁判所
(4) 本件において,上記(2)イの第1判決の認定判断に照らせば,第1判決の 拘束力は,第1審決を取り消す旨の結論(主文)が導き出されるのに必要な商標法 4条1項11号該当性についての認定判断,すなわち,1)引用商標は,本件商標登 録出願時には被告及び被告の事業ないし商品・役務を示すものとして相当程度周知 となっており,被告の事業は水処理関連事業であるが,これには薬品事業が伴うも のと認識されており,2)本件商標は,「オルガノ」と「サイエンス」の結合商標と認 められ,「オルガノ」部分は上記引用商標の周知性等からすれば,その指定商品及び 指定役務の取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的 な印象を与え,「サイエンス」の部分は指定商品である化合物,薬剤類との関係で出 所識別標識としての称呼,観念が生じにくいと認められることからして,「オルガノ」 部分を要部と解すべきであり,3)本件商標と引用商標とは,類似していると認めら れ,4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,いずれも,「化学剤」を含ん でいる点で共通する,との認定判断について生ずるものというべきである。したが って,再度の審判手続において,審判官は,第1判決が上記のとおり認定判断した 点につき,第1判決とは別異の認定判断をすることは,取消判決の拘束力により許 されないのであるから,審決が取消判決の拘束力に従ってされた限りにおいては, 再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることはできない。 そして,本件審決は,上記第2,3のとおり,第1判決と同様の理由により,本 件商標と引用商標とが類似し,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,い ずれも,「化学剤」を含んでいる点で共通するから,本件商標は,商標法4条1項1 1号に違反して登録されたとしたものであり,この認定判断は,上記第1判決の拘 束力に従ったものであることが明らかである。そうすると,再度の審決取消訴訟で ある本件訴訟において,これを違法とすることはできず,原告が,審決の当該認定 判断が誤りであると主張立証することは許されない。 本件訴訟において原告の主張する取消事由を検討すると,本件商標の商標法4条 1項11号該当性を争う部分については,第1判決の拘束力が及ぶ事項につき,こ れを蒸し返すものにほかならず,そもそも審決の取消事由とはなり得ないものと認 められるから,失当である。
・・・
(2) 本件商標と使用商標との類似性の程度
ア 本件商標「オルガノサイエンス」は,「オルガノ」と「サイエンス」の結 合商標と認められるところ,その全体は,9字9音とやや冗長であること,後半の 「サイエンス」が科学を意味する言葉として一般に広く知られていること,前半の 「オルガノ」は,「有機の」を意味する「organo」の読みを表記したものと解\nされるものの,少なくとも本件商標登録出願時に広く普及していた日本語の辞書で ある広辞苑に掲載されていない(甲133)など,「サイエンス」に比べれば一般に その意味合いが十分浸透しているものではないと認められ,さらに,後記(3)アのよ うな使用商標の周知著名性及び独創性からすれば,本件商標のうち「オルガノ」部 分は,その指定商品等の取引者,需要者に対し,商品等の出所識別標識として強く 支配的な印象を与えるものと認められる。他方,「サイエンス」は,一般に知られて いる「科学」を意味し,指定商品である化合物,薬剤類との関係で,出所識別標識 としての称呼,観念が生じにくいと認められる(最高裁平成20年9月8日第2小 法廷判決,裁判集民事228号561頁参照。)。したがって,本件商標については, 前半の「オルガノ」部分がその要部と解すべきである。
イ 本件商標の要部「オルガノ」と,使用商標とは,外観において類似し, 称呼を共通にし,一般には十分浸透しているとはいえないものの,いずれも「有機\nの」という観念を有しているものと認められる。したがって,両者は,類似してい ると認められる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.01.30
平成26(ワ)9552等 損害賠償請求事件(本訴),著作権使用料請求事件(反訴) 著作権 民事訴訟 平成28年12月15日 大阪地方裁判所
(1) 原告は,被告が公表していた,本件楽曲が被告自ら作曲した作品であるこ\nと,被告が全ろうの中,苦労をして絶対音感を頼りに作曲した状況がいずれも虚偽 であり,このような虚偽の説明を前提に原告に本件公演の実施を許可し,さらには 公演を増やすよう申し入れるなどして本件公演の実施に深く関与した行為が,不法\n行為である旨主張し,被告は,原告が主張するいずれの事実も虚偽ではないし,そ もそも本件楽曲に関する明確な著作物利用契約まで成立したとはいえないまま本件 公演が行われたのであるから被告に告知義務違反もないなどとしてこれを争ってい る。
(2) そこでまず,本件公演を行うに当たっての原告及び被告の認識を検討する に,前記認定事実によれば,原告が被告に対して本件交響曲公演の提案をした平成 25年3月頃までに,被告が平成11年頃に全ろうとなり,耳鳴り,偏頭痛,頭鳴 症等に悩まされながら,内側からの音を記譜することにより作曲活動を行ったとい う経緯が,全国紙や雑誌,全国放送のテレビ番組等で度々取り上げられるなどした ことから,そのような被告の作曲家としての人物像や作曲の状況が公衆にも相当知 られるところとなり,それとともに,著名レコード会社から発売されている本件交 響曲のCDもクラシック音楽においては異例の売上げとなっていたことが認められ る。このような経緯に加え,本件公演の広告の内容からすると,国内外の音楽家の 演奏会の企画・主催等を行うことを業とする原告が,全国で30回以上の本件楽曲 の演奏会を企画するに当たっては,作曲者とされていた被告のこのような人物像や 作曲状況を前提とし,この点が広く知られていることが重要な事情となっていたも のと認められ,仮にこれらの事情が事実でなかった場合には,本件公演を企画しな かったであろうと認められる。そして,被告においても,自らが多数のメディアに 取り上げられていた状況等を認識した上で,原告に対して公演回数の増加を強く要 求したことからして,原告からの本件交響曲公演の提案が,被告が公表していた被\n告の人物像や作曲状況を前提とし,それを重視していたものであることについて, 当然承知していたものと認められる。
(3) 次に,前記(2)の前提とされた状況について検討する。
ア まず,被告の聴力については,本件交響曲が作曲された時期に作成された 平成14年診断書では,感音性難聴を原因とする聴覚障害により身体障害2級に該 当するとされている。しかし,脳波の反応による客観的な検査が行われた平成26 年診断書においては,右が40デシベル,左が60デシベルで脳波の反応が確認さ れているところ,専門医の意見によれば,これは,ある領域においては右が30デ シベル,左が50デシベル程度の聴力があることを示しているものであること,被 告自身も3年前から聴力が戻っていると述べていることから,平成26年2月頃に おいて,被告は軽度から中等度の難聴にあったが,全ろうといえるような状況では なかったと認められる。このような被告の状態に加えて,平成14年診断書に記載 されているような100デシベルを超えるような感音性難聴の場合,自然に改善す ることは現在の医学的知見ではあり得ないとの専門医の意見や,平成11年8月頃 に聞こえない状況になかったことがうかがえることからすると,平成14年診断書 の記載はこれを採用することができず,平成14年当時,高度の感音性難聴が被告 にあったとは認められない。また,平成14年診断書の結果は,軽度から中等度の 難聴に加え機能性難聴(心因性難聴又は難聴であることを偽る詐聴)を合併したも\nのと考えられるとの専門医の意見からしても,平成11年以降,被告が全ろうの状 態で作曲していたという事実を認めることはできない。この点について,被告の妻 である証人P5は,平成13年末頃までに被告は全ろうに近い状態となったと証言 するが,上記に照らし,採用できない。 したがって,平成11年以降,被告が軽度から中等度の難聴であったことは事実 であるといえても,全ろうの音が聞こえない状態であった点は事実でなかったとい える。
イ また,被告は,全ろうの状態で,耳鳴り,偏頭痛,頭鳴症等に耐えなが ら被告自身が内から聞こえる音を記譜して本件交響曲を作曲したと公表していた\nが,前記認定事実によれば,被告が本件交響曲について関与したのは,本件指示書 を渡すなどしてP2に指示を与え,また,被告が本件交響曲における鐘の音を入れ たことにとどまる。また,ピアノ・ソナタ第2番についても,モチーフの選択やそ\nの順序等について指示をしていたにとどまる。したがって,被告が上記の状況で本 件楽曲を自ら作曲したとの点も,事実でなかったといえる。 この点について,証人P5は,被告は平成15年に完成した本件交響曲について もシンセサイザーでメロディーを作りオーケストレーションもしており,それを録 音したものを聴いたことがあるなどと証言し,陳述(乙22)している。しかし, 被告がP2に作曲を依頼したことを発表した直後の会見において被告が述べていた\nのは,本件指示書等による指示をしたことのみであり,シンセサイザーによる作曲 については何ら触れられておらず(甲172),むしろ,被告には絶対音感がなく, オーケストラ曲を作ることができなかったことから設計図を示してP2に音符を書 いてもらった旨を述べていたことからすると,証人P5の上記証言は直ちにこれを 採用することはできず,その他,本件楽曲につき,鐘の音以外のメロディー等を被 告が作成してP2に提供したことを裏付ける証拠は提出されておらず,そのような 事実を認めることはできない。 また,同証人は,近年のドキュメンタリー映画の中で被告が自ら新曲を作曲する 過程が描かれたと陳述し(乙22),その楽曲の「音楽著作権使用料支払いに関する 覚書」も提出されている(乙23)。しかし,それは,当該楽曲についてのことであ るにとどまり,それをもって本件楽曲の作曲過程についての前記の認定判断が左右 されるものではない。
(4) 以上のとおり,被告が公表し,多数のメディアで紹介されていた被告の人\n物像や作曲状況は,原告が本件公演を企画するに当たっての重要な前提事情であり, それが事実でない場合には,原告が本件公演を企画・実施することはなかったもの であるが,被告は,そのような事情を知りながら,本件公演を実施することを了承 したにとどまらず,特定の指揮者の選定や公演回数の増加を強く要求するなど,本 件公演の企画に積極的に関与したといえる。これに加え,上記の前提事情が事実で ないことが公となった場合には,それまでの新聞や雑誌の掲載,テレビの番組放映 等の数,これらに対する反響の大きさからして公演を実施することができなくなり, 予定公演数の多さから原告に多大な損害が発生するであろうことは,容易に思い至\nることができたものであったといえることを併せ考慮すると,本件公演の企画に対 する上記のような関与をするに当たり,被告において,これまで公表していた被告\nの人物像や作曲状況が事実とは異なることを原告にあらかじめ伝え,その内包され るリスクを告知する義務があったものというべきである。したがって,被告がこの 義務に反して事実を告げず,原告が多額の費用をかけ,多数の人が携わることとな る全国公演を行うことを了承し,さらには公演数を増やすように強く申し入れるな\nどして本件公演の企画に積極的に関与し,それにより原告に本件公演を企画・実施 するに至らせた行為は,原告に対する不法行為を構成すると評価するのが相当であ\nる。
・・
ア 前記のとおり,本件公演は,平成26年2月2日までのものが実施され, 同月23日以降のものは中止された。このことから,原告は,被告の不法行為によ り被った損害として,平成26年2月23日以降中止した本件公演に係る損害を主 張している。 しかし,本件において被告の原告に対する不法行為として捉えられるのは,被告 が,告知義務に違反して,原告が多額の費用をかけ,多数の人が携わることとなる 全国公演を行うことを了承し,さらには公演数を増やすように強く申し入れるなど\nして本件公演の企画に積極的に関与し,それにより原告に本件公演を企画・実施す るに至らせた行為であり,このような被告の行為がなければ,原告はそもそも本件 公演を企画・実施しなかったと認められるものである。このような不法行為の内容 からすると,原告の損害として捉えるべきは,本件公演を企画・実施しなかった場 合と比べて,本件公演を企画・実施したことの全体によって生じた損害(実施分も 含めて損益通算した損害)であると解するべきであって,中止された公演のみに着 目し,その中止による損害のみを損害として主張する原告の上記主張は採用できな い。他方,被告は,公演中止によって生じた損害と実施された公演から生じた利益 との損益相殺を主張するところ,上記のとおり,原告の損害としては本件公演の企 画・実施の全体から生じた損害を通算して把握すべきであるから,被告の損益相殺 の主張自体は採用できないが,この主張は,実質的には上記で述べたのと同趣旨を いうものと解される。
2017.01.25
平成28(ネ)10046 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記アによると,本件各明細書には,樹脂組成物の屈折率について「硬化樹 脂層の屈折率測定方法は,JIS K 7142の「プラスチックの屈折率測定方 法」(Determination of the refractive in dex of plastics)に従う。具体的には,ガラス繊維織物が含まれ ていない硬化性樹脂のフィルムを,ガラス繊維織物を含む場合と同じ条件で作成し, アッベ屈折計を用いて測定する。」と記載されていることが認められる。したがって, 樹脂組成物の屈折率については,「JIS K 7142」(甲203)に規定され たA法(板状またはフィルム状試験片に適用)とB法(粉末状,ペレット状,顆粒 状サンプルに適用)のうち,アッベ屈折計を用いるとされるA法により測定される ことが記載されていると認められる。 これに対し,ガラス組成物の屈折率については,いくつかの測定方法があり,測 定方法が相違すると測定値も異なることがあることは前記認定のとおりであるけれ ども,本件各特許の特許請求の範囲の記載では,ガラス組成物の屈折率の測定方法 が特定されていないし,また,本件各明細書における発明の詳細な説明にも,ガラ ス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないことが認められる。 もっとも,このような場合であっても,本件各明細書におけるガラス組成物等の 屈折率に関する記載を合理的に解釈し,当業者の技術常識も参酌して,ガラス組成 物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができるときには,そのように解釈 すべきである。 まず,前記アの本件各明細書の記載においては,特に,ガラス繊維織物に織られ たガラス繊維の品番ECE225,ECG75,ECG37等が特定されているの に対し,そのガラス繊維であるECE225,ECG75,ECG37等の屈折率 が表示されていないこと,その原料であるEガラスの屈折率が1.558であると\n表示されており,表\1におけるガラス繊維織物の屈折率にもその1.558が用い られていることなどを考慮すると,本件各発明における「ガラス繊維織物中のガラ ス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」は,ガラス繊維の屈折率を測定して\n得られたものではなく,繊維化する前のガラス組成物(原料)の屈折率であると認 めるのが相当である。なお,Eガラスにも各種品目があり,Eガラスの屈折率につ いては,1.548(乙あ93),1.560(乙あ11)のものもあるところ,本 件各明細書においては,Eガラスの中でも,屈折率が1.558のものが用いられ たものと推認することができる。また,本件各明細書には,硬化樹脂の屈折率の測 定方法についての記載があるのに対し,ガラス組成物の屈折率の測定法についての 記載がないのは,ガラス組成物について,商品データベース(甲26)などから, その屈折率が得られることから,独自に測定する必要性がないことによるというこ とができる。前記のとおり,実測によらないガラス組成物の屈折率は,実際のシー ト状態となったガラス繊維の屈折率とは一致しない可能性はあるけれども,上記で\n認定した「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の商品カタロ\nグ等における「屈折率」を採用することで,硬化樹脂に埋め込まれたガラス繊維を 分離して,屈折率を測定する煩雑さを回避することができることを考慮すると,こ のような定め方も不合理であるとはいえないし,本件明細書の表1によれば,ガラ\nス繊維の原料であるEガラス組成物の屈折率である1.558を用いた上で,硬化 樹脂との界面の透明性を確保することが可能となっていることが認められる。\n以上によれば,「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈\n折率」は,繊維化する前のガラス組成物の屈折率を指すものと認めるのが相当であ る。また,前記認定のとおり,「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組\n成物の屈折率」は,素材メーカーが製品とともに公表したものであることを前提と\nすると,ガラス組成物の屈折率は「JIS K 7142」(プラスチックの屈折率 の測定方法)で測定されたものと解することはできず,むしろ,ガラス組成物(E ガラス)について素材メーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法により 測定されたものと解するのが自然な解釈であるといえる。そして,素材メーカーが Eガラスについて商品データベースにおいて表示している屈折率は,小数点以下第\n3位のものが多いことからすると(甲26,乙あ11,93),少なくとも有効数字 が小数点以下第4位まで測定できる測定方法である必要がある。また,証拠(甲4 5,乙あ27,89,108)及び弁論の全趣旨によれば,小数点以下第4位まで 測定できる測定方法としては,精度の高い最小偏角法(精度は約1×10−5)と,次 に精度が高いVブロック法(精度は約2×10−5)及び臨界角法(精度は1×10− 4)のいずれかであると認められるところ,このうち表示される屈折率が上記のとお\nり小数点以下第3位のものが多く,最も精度の高いものまで要求されないことや, Vブロック法による測定が最も簡便であって,試料の作成も容易であること(乙あ 89)を考慮すると,素材メーカーがEガラスについて一般に採用する合理的な屈 折率の測定方法は,Vブロック法であると推認するのが相当である。現に,本件に おいて,控訴人及び被控訴人ユニチカが,本件シートや本件各発明の実施品のガラ ス組成物の屈折率を,専門機関に依頼した上で,Vブロック法で測定していること (甲24,乙あ74,97の1)も,このことを裏付けるものである。 なお,本件各明細書には,樹脂組成物の屈折率については,「JIS K 714 2」に規定されたA法により測定されることが記載されていること,ガラス組成物 の屈折率の測定方法については明確な記載がないものの,「ガラス繊維織物中のガ ラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」としては,繊維化する前のガラス\n組成物の屈折率が記載されており,その測定方法は前記のとおりVブロック法であ ると推認されることからすると,樹脂組成物の屈折率の測定方法については,「JI S K 7142」の「B法」を追加する本件各訂正は新規事項の追加であり,ガ ラス組成物の屈折率の測定方法については,「JIS K 7142」を追加し,あ るいはその「B法」を追加する本件各訂正はいずれも新規事項の追加である。 したがって,本件各訂正請求は,特許法126条1項の訂正要件に反するもので あり,本件各訂正請求を認めた審決は未だ確定していないことからすれば(当裁判 所に顕著な事実である。),本件においては,本件防煙垂壁が本件各発明の技術的範 囲に属するか否かについて,本件各訂正請求の内容を考慮せずに判断すべきである (仮に,本件各訂正請求を認める審決が確定すると,本件各訂正発明は,特許法1 23条1項8号の無効理由を有するものとなる。)。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成26(ワ)10848
対応する審決取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2017.01.25
平成28(行ケ)10005 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月18日 知的財産高等裁判所
審決は「ソフトコンタクトレンズ装用時に生じる特有の問題として、ソ\フトコンタクトレンズ装用中は、清涼感度の低下が起こることがあげられるが、本件特許明細書に記載された実施例19〜21において、ソフトコンタクトレンズ装用中の点眼直後の清涼感は◎と評価され、かつ、ソ\フトコンタクトレンズ装用中の点眼直後の刺激も○ないし◎と評価されていることから、本件特許発明1は、ソフトコンタクトレンズを装用中においても、十\分な清涼感を付与でき、かつ、点眼直後に清涼感を超えた強すぎる不快な刺激がない、との効果を奏する」と進歩性ありと判断していました。
特許出願に係る発明の構成が,公知技術である引用発明に他の公知技術,周知技\n術等を適用することによって容易に想到することができる場合であっても,上記発 明の有する効果が,当該引用発明等の有する効果と比較して,当業者が技術常識に 基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著な\nものであるときは,上記発明はその限度で従来の公知技術等から想到できない有利 な効果を開示したといえるから,当業者は上記発明を容易に想到することができな いものとして,上記発明については,特許を受けることができると解するのが相当 である。 これを本件についてみると,前記(1)の認定事実によれば,本件発明は,ソフトコ\nンタクトレンズ装用者に十分な清涼感を付与し,かつ,刺激がなく安全性が高い眼\n科用清涼組成物を提供するものであり,本件明細書(【0055】【表6】)に記載さ\nれている実施例19ないし21において,ソフトコンタクトレンズ装用中の点眼直\n後の清涼感は◎と評価され,かつ,ソフトコンタクトレンズ装用中の点眼直後の刺\n激も○又は◎と評価されている。 しかしながら,本件明細書(【0044】)には「各パネラーには,清涼感につい て全く感じない場合を0点,十分に強い清涼感を感じる場合を6点として7段階評\n価してもらった。同様に眼刺激について全く感じない場合を6点,強い刺激を感じ る場合を0点として7段階評価してもらった。パネラー全員の評価点を平均して, その平均値が0〜2点未満を×,2点以上3点未満を△,3点以上4点未満を○, 4点以上6点以下を◎として表に結果を示す。」と記載され,清涼感及び刺激の評価\nにおいて,◎と評価された場合であっても,7段階評価における中央値付近の「4」 の評価が含まれている。そうすると,上記評価から,直ちに本件発明1の奏する効 果が甲1発明と比較して予測できないほど顕著であると推認することはできず,そ\nの他に,甲1発明の点眼剤をソフトコンタクトレンズ装用時に適用した場合と比較\nして,本件発明1が奏する効果が当業者の予測を超える顕著なものであることを認\nめるに足りる的確な証拠はない。のみならず,前記(2)の認定事実によれば,甲1発 明の点眼剤は,目に対する刺激性が低く,良好な清涼感を付与することができ,か つ,清涼感の持続性の高いものであり,前記アのとおり,甲1発明の点眼剤をソフ\nトコンタクトレンズの装用者にも適用し得ると示唆されているのであるから,これ らの記載に接した当業者は,甲1発明の点眼剤につき,ソフトコンタクトレンズ装\n用時に清涼感を付与するために用いた場合に,裸眼時やハードコンタクトレンズ装 用時と同程度に,眼に対する刺激性が低く,良好な清涼感を付与することができ, 清涼感の持続性が高いものであることを十分に予\測することができる。しかも,甲 1発明の点眼剤の効果と本件発明の効果は,そもそも清涼感を付与し刺激性が低い という同種のものにすぎず,本件明細書には,ハードコンタクトレンズ装用時にお ける清涼感との比較評価等が一切記載されていないのであるから,本件優先日当時 の技術常識を考慮しても,具体的にどの程度の清涼感の差異があるのかは不明であ る。 したがって,本件発明1の有する効果が予測することができる範囲を超えた顕著\nなものであると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2017.01.25
平成28(ネ)10046 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(2) 法68条の2の「政令で定める処分の対象となつた物」に係る特許発明の 実施行為の範囲について
政令(特許法施行令2条)では,延長登録の理由となる処分は医薬品医療 機器等法の承認と農薬取締法の承認の二つの処分に限定されている。本件の ように「政令で定める処分」が前者の承認(医薬品医療機器等法所定の医薬 品に係る承認)に係るものである場合においては,次のとおりであると認め られる。すなわち,
ア 医薬品医療機器等法14条1項は,「医薬品…の製造販売をしようとす る者は,品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けな ければならない。」と規定し,同項に係る医薬品の承認に必要な審査の対 象となる事項は,「名称,成分,分量,用法,用量,効能,効果,副作用\nその他の品質,有効性及び安全性に関する事項」(同法14条2項,9項) と規定されている。 このことからすると,「政令で定める処分」が医薬品医療機器等法所定 の医薬品に係る承認である場合には,常に「用法,用量,効能及び効果」\nが審査事項とされ,「用法,用量,効能及び効果」は「用途」に含まれる\nから,同承認は,法68条の2括弧書の「その処分においてその物の使用 される特定の用途が定められている場合」に該当するものと解される。 医薬品医療機器等法の承認処分の対象となった医薬品における,法68 条の2の「政令で定める処分の対象となつた物」及び「用途」は,存続期 間が延長された特許権の効力の範囲を特定するものであるから,特許権の 存続期間の延長登録の制度趣旨(特許権者が,政令で定める処分を受ける ために,その特許発明を実施する意思及び能力を有していてもなお,特許\n発明の実施をすることができなかった期間があったときは,5年を限度と して,その期間の延長を認めるとの制度趣旨)及び特許権者と第三者との 衡平を考慮した上で,これを合理的に解釈すべきである。 そうすると,まず,前記のとおり,医薬品の承認に必要な審査の対象と なる事項は,「名称,成分,分量,用法,用量,効能,効果,副作用その\n他の品質,有効性及び安全性に関する事項」であり,これらの各要素によ って特定された「品目」ごとに承認を受けるものであるから,形式的には これらの各要素が「物」及び「用途」を画する基準となる。 もっとも,特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨からすると,医薬品 としての実質的同一性に直接関わらない審査事項につき相違がある場合に まで,特許権の効力が制限されるのは相当でなく,本件のように医薬品の 成分を対象とする物の特許発明について,医薬品としての実質的同一性に 直接関わる審査事項は,医薬品の「成分,分量,用法,用量,効能及び効\n果」である(ベバシズマブ事件最判)ことからすると,これらの範囲で「物」 及び「用途」を特定し,延長された特許権の効力範囲を画するのが相当で ある。 そして,「成分,分量」は,「物」それ自体の客観的同一性を左右する 一方で「用途」に該当し得る性質のものではないから,「物」を特定する 要素とみるのが相当であり,「用法,用量,効能及び効果」は,「物」そ\nれ自体の客観的同一性を左右するものではないが,前記のとおり「用途」 に該当するものであるから,「用途」を特定する要素とみるのが相当であ る。 なお,医薬品医療機器等法所定の承認に必要な審査の対象となる「成分」 は,薬効を発揮する成分(有効成分)に限定されるものではないから,こ こでいう「成分」も有効成分に限られないことはもちろんである。 以上によれば,医薬品の成分を対象とする物の特許発明の場合,存続期 間が延長された特許権は,具体的な政令処分で定められた「成分,分量, 用法,用量,効能及び効果」によって特定された「物」についての「当該\n特許発明の実施」の範囲で効力が及ぶと解するのが相当である(ただし, 延長登録における「用途」が,延長登録の理由となった政令処分の「用法, 用量,効能及び効果」より限定的である場合には,当然ながら,上記効力\n範囲を画する要素としての「用法,用量,効能及び効果」も,延長登録に\nおける「用途」により限定される。以下同じ。)。
イ 上記アによれば,相手方が製造等する製品(以下「対象製品」という。) が,具体的な政令処分で定められた「成分,分量,用法,用量,効能及び\n効果」において異なる部分が存在する場合には,対象製品は,存続期間が 延長された特許権の効力の及ぶ範囲に属するということはできない。しか しながら,政令処分で定められた上記審査事項を形式的に比較して全て一 致しなければ特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることがで きるとすれば,政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実 施をすることができなかった期間を回復するという延長登録の制度趣旨に 反するのみならず,衡平の理念にもとる結果になる。このような観点から すれば,存続期間が延長された特許権に係る特許発明の効力は,政令処分 で定められた「成分,分量,用法,用量,効能及び効果」によって特定さ\nれた「物」(医薬品)のみならず,これと医薬品として実質同一なものに も及ぶというべきであり,第三者はこれを予期すべきである(なお,法6\n8条の2は,「物…についての当該特許発明の実施以外の行為には,及ば ない。」と規定しているけれども,同条における「物」についての「当該 特許発明の実施」としては,「物」についての当該特許発明の文言どおり の実施と,これと実質同一の範囲での当該特許発明の実施のいずれをも含 むものと解すべきである。)。 したがって,政令処分で定められた上記構成中に対象製品と異なる部分\nが存する場合であっても,当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的 な差異にすぎないときは,対象製品は,医薬品として政令処分の対象とな った物と実質同一なものに含まれ,存続期間が延長された特許権の効力の 及ぶ範囲に属するものと解するのが相当である。
ウ そして,医薬品の成分を対象とする物の特許発明において,政令処分で 定められた「成分」に関する差異,「分量」の数量的差異又は「用法,用 量」の数量的差異のいずれか一つないし複数があり,他の差異が存在しな い場合に限定してみれば,僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異かど うかは,特許発明の内容(当該特許発明が,医薬品の有効成分のみを特徴 とする発明であるのか,医薬品の有効成分の存在を前提として,その安定 性ないし剤型等に関する発明であるのか,あるいは,その技術的特徴及び 作用効果はどのような内容であるのかなどを含む。以下同じ。)に基づき, その内容との関連で,政令処分において定められた「成分,分量,用法, 用量,効能及び効果」によって特定された「物」と対象製品との技術的特\n徴及び作用効果の同一性を比較検討して,当業者の技術常識を踏まえて判 断すべきである。 上記の限定した場合において,対象製品が政令処分で定められた「成分, 分量,用法,用量,効能及び効果」によって特定された「物」と医薬品と\nして実質同一なものに含まれる類型を挙げれば,次のとおりである。 すなわち,1)医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長 登録された特許発明において,有効成分ではない「成分」に関して,対象 製品が,政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき,一部において\n異なる成分を付加,転換等しているような場合,2)公知の有効成分に係る 医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において,対象製品が政令 処分申請時における周知・慣用技術に基づき,一部において異なる成分を\n付加,転換等しているような場合で,特許発明の内容に照らして,両者の 間で,その技術的特徴及び作用効果の同一性があると認められるとき,3) 政令処分で特定された「分量」ないし「用法,用量」に関し,数量的に意 味のない程度の差異しかない場合,4)政令処分で特定された「分量」は異 なるけれども,「用法,用量」も併せてみれば,同一であると認められる 場合(本件処分1と2,本件処分5ないし7がこれに該当する。)は,こ れらの差異は上記にいう僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異に当た り,対象製品は,医薬品として政令処分の対象となった物と実質同一なも のに含まれるというべきである(なお,上記1),3)及び4)は,両者の間で, 特許発明の技術的特徴及び作用効果の同一性が事実上推認される類型であ る。)。 これに対し,前記の限定した場合を除く医薬品に関する「用法,用量, 効能及び効果」における差異がある場合は,この限りでない。なぜなら,\n例えば,スプレー剤と注射剤のように,剤型が異なるために「用法,用量」 に数量的差異以外の差異が生じる場合は,その具体的な差異の内容に応じ て多角的な観点からの考察が必要であり,また,対象とする疾病が異なる ために「効能,効果」が異なる場合は,疾病の類似性など医学的な観点か\nらの考察が重要であると解されるからである。 しかし,特許発明の技術的範囲における均等は,特許発明の技術的範囲 の外延を画するものであり,法68条の2における,具体的な政令処分を 前提として延長登録が認められた特許権の効力範囲における前記実質同一 とは,その適用される状況が異なるものであるため,その第1要件ないし 第3要件はこれをそのまま適用すると,法68条の2の延長登録された特 許権の効力の範囲が広がり過ぎ,相当ではない。 すなわち,本件各処分についてみれば明らかなように,各政令処分によ って特定される「物」についての「特許発明の実施」について,第1要件 ないし第3要件をそのまま適用して均等の範囲を考えると,それぞれの政 令処分の全てが互いの均等物となり,あるいは,それぞれの均等の範囲が 特許発明の技術的範囲ないしはその均等の範囲にまで及ぶ可能性があり,\n法68条の2の延長登録された特許権の効力範囲としては広がり過ぎるこ とが明らかである。 また,均等の5要件の類推適用についても,仮にこれを類推適用すると すれば,政令処分は,本件各処分のように,特定の医薬品について複数の 処分がなされることが多いため,政令処分で特定される具体的な「物」に ついて,それぞれ適切な範囲で一定の広がりを持ち,なおかつ,実質同一 の範囲が広がり過ぎないように(例えば,本件各処分にみられるような複 数の政令処分について,分量が異なる一部の処分に係る物が実質同一とな ることはあっても,その全てが互いに実質同一の範囲に含まれることがな いように)検討する必要がある。 しかし,まず,第1要件についてみると,このような類推適用のための 要件を想定することは困難である。すなわち,第1要件は,政令処分によ り特定される「物」と対象製品との差異が政令処分により特定される「物」 の本質的部分ではないことと類推されるところ,実質同一の範囲が広がり 過ぎないように類推適用するためには,政令処分により特定される「物」 の本質的部分(特許発明の本質的部分の下位概念に相当するもの)を適切 に想定することが必要であると解されるものの,その想定は一般的には困 難である。また,第2要件は,政令処分により特定される「物」と対象製 品との作用効果の同一性と類推されるところ,これは,実質同一のための 必要条件の一つであると考えられるものの,これだけでは実質同一の範囲 が広くなり過ぎるため,類推適用のためには,第1要件やその他の要件の 考察が必要となり,その想定は困難である。 以上によれば,法68条の2の実質同一の範囲を定める場合には,前記 の五つの要件を適用ないし類推適用することはできない。
オ ただし,一般的な禁反言(エストッペル)の考え方に基づけば,延長登 録出願の手続において,延長登録された特許権の効力範囲から意識的に除 外されたものに当たるなどの特段の事情がある場合には,法68条の2の 実質同一が認められることはないと解される。
(3) 対象製品が特許発明の技術的範囲(均等も含む。)に属することについて 法68条の2は,特許権の存続期間を延長して,特許権を実質的に行使す ることのできなかった特許権者を救済する制度であって,特許発明の技術的 範囲を拡張する制度ではない。したがって,存続期間が延長された特許権の 侵害を認定するためには,対象製品が特許発明の技術的範囲(均等も含む。) に属するとの事実の主張立証が必要であることは当然である。なお,このこ とは,法68条の2が政令処分の対象となった物についての「当該特許発明 の実施以外の行為には,及ばない」と規定していることからも明らかである。
・・・
しかしながら,一審原告の主張は,要するに,医薬品の承認制度の面から, 後発医薬品として承認されたものは全て実質同一物等に当たる(先発医薬品 に係る特許発明の効力が及ぶ)と断じるに等しく,法68条の2の制度趣旨 や解釈論を無視するものであって,採用することはできない。 すなわち,後発医薬品は,先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み,同 一経路から投与する製剤で,効能・効果,用法・用量が原則的に同一であり,\n先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品をいい,両者の間に有 効性や安全性について基本的な相違がないことが前提である。また,先発医 薬品と異なる添加剤を使用することがあっても,薬理作用を発揮したり,有 効成分の治療効果を妨げたりする物質を添加剤として使用することはできず, 医薬品としての承認に当たっては,生物学的同等性試験により主成分の血中 濃度の挙動が先発医薬品と同等であることの確認が求められるものとされて いる(甲30,弁論の全趣旨)。このように,後発医薬品は,先発医薬品と 治療学的に同等であるものとして製造販売が承認されるものであり,先発医 薬品と代替可能な医薬品として市場に提供されることが前提であるから,そ\nもそも医薬品としての品質において先発医薬品に依拠するものであることは 当然である。しかし,これは飽くまで有効成分や治療効果(有効性,安定性 を含む。)が原則として同一であるということを意味するにすぎず,特許発 明の観点からその成果に依拠するかどうかを問題にしているわけではない。 これに対し,延長登録された特許権の効力範囲における実質同一は,特許 権の効力範囲を画する概念である。前記のとおり,1)法68条の2の規定は, 特許権の存続期間の延長登録の制度が,政令処分を受けることが必要であっ たために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目 的とするものであることに鑑み,存続期間が延長された場合の当該特許権の 効力についても,その特許発明の全範囲に及ぶのではなく,「政令で定める 処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が 定められている場合にあつては,当該用途に使用されるその物)」について の「当該特許発明の実施」にのみ及ぶ旨を定めるものであり,2)医薬品の成 分を対象とする物の特許発明の場合,法68条の2によって存続期間が延長 された特許権は,具体的な政令処分で定められた「成分,分量,用法,用量, 効能及び効果」によって特定された「物」についての「当該特許発明の実施」\nの範囲で効力が及ぶと解するのが相当であるものの,3)これらの各要素によ って当該特許権の効力範囲が画されるとしても,これらの各要素における僅 かな差異や形式的な差異によって延長登録された特許権の効力が及ばないと することは延長登録の制度趣旨に反し,衡平の理念にもとる結果となるから, これらの差異によっても,なお政令処分の対象となった医薬品と実質同一の 範囲で,延長された当該特許権の効力が及ぶと解すべきである。 したがって,延長登録された特許権の効力範囲における「成分」に関する 差異,「分量」の数量的差異又は「用法,用量」のうち「効能,効果」に影\n響しない数量的差異に関する実質同一は,当該特許発明の内容に基づき,そ の内容との関連で,政令処分において定められた「成分,分量,用法,用量, 効能及び効果」によって特定された「物」と対象製品との技術的特徴及び作\n用効果の同一性を比較検討して,当業者の技術常識を踏まえてこれを判断す べきであり,これを離れて,医薬品としての有効成分や治療効果(有効性, 安定性)のみからこれを論じるべきものではない。少なくとも,法68条の 2が,およそ後発医薬品であるが故に,すなわち,先発医薬品と同等の品質 を備え,これに依拠するが故に直ちに特許権の効力を及ぼそうとする趣旨の ものでないことは明らかである。 しかるに,一審原告の主張は,当該特許発明の内容に関わらず,いわば医 薬品としての有効成分や治療効果のみに着目して延長された特許権の効力範 囲を論ずるものであり,これは前記のとおりの法68条の2の制度趣旨や解 釈論に反することが明らかであって,採用することはできないというべきで ある。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> ピックアップ対象
2017.01.25
平成28(行ケ)10133 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成29年1月17日 知的財産高等裁判所
前記アのとおり,本願意匠のマウスピース部の端部には,端壁が設けられ, その中央に円形孔が形成されている。しかも,本願意匠のマウスピースカバー部は, 着色されているから,マウスピース部に注意が向けられるものであって,さらに透 明であることから,マウスピースカバーを開けたときも閉めたときも,その円形孔 を観察することができる。そして,その円形孔は,本体部に貯蔵された薬剤を患者 に噴出させる速度,方向等に影響を与えるのであるから,この点は,特に機能を重\n視する医療関係者に対し,強い印象を与えるものということができ,患者について も同様である。
(イ) これに対し,引用意匠のマウスピース部の端部は,端壁がなく,単に筒状 のまま大きく開口したものであり,マウスピースカバー部は,不透明であるところ, マウスピース部の端部に端壁がなく,単に筒状のまま大きく開口した態様の吸入器 は,従来から見られたものであり(甲4),ありふれたものである。
(ウ) なお,証拠(乙1〜3)によれば,使用者が本体部を持って,マウスピー ス部から薬剤を吸引するための吸入器において,マウスピース部に端壁を設け,薬 剤出口孔を形成した態様のものが,特許公報に記載されていることは認められる。 もっとも,当該吸入器の全体の形態は,本願意匠のように「へ」の字形状になって いる吸入器の全体の形態とは大きく相違するから,それぞれのマウスピース部の端 部の形状が有する印象は,本願意匠に係るそれとは相違するものである。したがっ て,上記特許公報の記載をもって,本願意匠に係る形態を有する吸入器において, マウスピース部に端壁を設け,薬剤出口孔を形成したものがありふれていたという ことはできず,マウスピース部の端部が需要者の注意を惹く部分でないということ はできない。
(エ) 以上によれば,本願意匠のマウスピース部の端部に端壁が設けられ,その 中央に円形孔が形成されている点は,マウスピースカバー部が透明で着色されてい ることと相まって,最も強く需要者の注意を惹く部分であり,本願意匠におけるこ の点は,需要者である患者及び医療関係者の視覚を通じて起こさせる美感に大きな 影響を与えるというのが相当である。
ウ その余の具体的構成態様について
一方,本願意匠の具体的構成態様のうち,マウスピース部の形状が断面略紡錘形\nであって,その奥行きが本体部の奥行きの約2分の1の長さであり,マウスピース カバー部の形状が全体的に少し先細りしたカップ型であり,これらに本体部を含め た形状が,左右両側面については平坦面,それ以外の面については,本体部の上端 面を除き,凸弧状面又は凹弧状面であって丸みを帯びるという形態は,吸入器にお いて従来から見られたものである(甲4)。また,本願意匠において,マウスピー ス部の上方に突出片を備え,マウスピースカバー部の正面の底部寄りに左右方向に わたる帯状凹部を形成する形態は,吸入器に配設されたマウスピース部の機能上要\n請されるものであるから,その形態は限定されるものであるし,意匠全体に占める 割合も小さなものである。さらに,本願意匠において,本体部の上端面を凸弧状面 とし,本体部の中間部の全周にわたり一条の線を表し,その下方背面に窓部等を備\nえるという形態は,吸入器の本体部の上端面,中間部,下方背面にそれぞれ離れて 位置しており,一体的に観察されるものではなく,その形態をみても,意匠的まと まりを形成するものではない。 したがって,本願意匠の具体的構成態様のうち,以上に掲げた各形態は,需要者\nである患者及び医療関係者の注意を惹く部分であるということはできず,引用意匠 と類似するその余の具体的構成態様についても,同様である。
(4) 両意匠の類否
以上のとおり,両意匠に係る物品の性質,用途及び使用態様並びに公知意匠との 関係を総合すれば,本願意匠と引用意匠は,基本的構成態様において共通するもの\nの,その態様は,ありふれたものであり,需要者の注意を強く惹くものとはいえな い。また,具体的構成態様における共通点も,需要者の注意を強く惹くものとはい\nえない。これに対し,マウスピース部の端部の形態の相違は,需要者である患者及 び医療関係者らの注意を強く惹き,視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与 えるものである。 したがって,本願意匠と引用意匠の相違点のうち,マウスピース部の端部につい て,本願意匠は,その中央に円形孔が形成された端壁を設けたものであるのに対し て,引用意匠は,端壁がなく,単に筒状のまま大きく開口した点は,マウスピース カバー部が透明で着色されていることと相まって,需要者である患者や医療関係者 の注意を強く惹くものと認められ,異なる美感を起こさせるものであり,それ以外 の共通点から生じる印象に埋没するものではないというべきである。 よって,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。
◆判決本文
関連事件は以下です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2017.01.25
平成28(行ケ)10087 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月17日 知的財産高等裁判所
ア 引用例2を主たる引用例とする主張の可否について
特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては,審判で審理判断されなかった 公知事実を主張することは許されない(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51 年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁)。 しかし,審判において審理された公知事実に関する限り,審判の対象とされた発 明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること,あるいは,複数の公 知事実が審理判断されている場合にあっては,その組合せにつき審決と異なる主張 をすることは,それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超 えるということはできないから,取消訴訟においてこれらを主張することが常に許 されないとすることはできない。 前記のとおり,本件審決は,1)引用発明1を主たる引用例として引用発明2を組 み合わせること及び2)引用発明3を主たる引用例として引用発明1又は2を組み合 わせることにより,本件特許発明を容易に想到することはできない旨判断し,その 前提として,引用発明2についても認定しているものである。原告は,上記1)及び 2)について本件審決の認定判断を違法であると主張することに加えて,予備的に,\n引用発明2を主たる引用例として引用発明1又は3を組み合わせることにより本件 特許発明を容易に想到することができた旨の主張をするところ,被告らにおいても, 当該主張について,本件訴訟において審理判断することを認めている。 引用発明1ないし3は,本件審判において特許法29条1項3号に掲げる発明に 該当するものとして審理された公知事実であり,当事者双方が,本件審決で従たる 引用例とされた引用発明2を主たる引用例とし,本件審決で主たる引用例とされた 引用発明1又は3との組合せによる容易想到性について,本件訴訟において審理判 断することを認め,特許庁における審理判断を経由することを望んでおらず,その 点についての当事者の主張立証が尽くされている本件においては,原告の前記主張 について審理判断することは,紛争の一回的解決の観点からも,許されると解する のが相当である。 なお,本判決が原告の前記主張について判断した結果,請求不成立審決が確定す る場合は,特許法167条により,当事者である原告において,再度引用発明2を 主たる引用例とし,引用発明1又は3を組み合わせることにより容易に想到するこ とができた旨の新たな無効審判請求をすることは,許されないことになるし,本件 審決が取り消される場合は,再開された審判においてその拘束力が及ぶことになる。
イ 相違点について
前記(4)イのとおり,引用発明2において,「有色塗装層」は装飾上,必須のもの である。また,引用発明2において,「有色塗装層」の形成対象は,釣竿又はゴル フシャフトに特定されている。 したがって,本件特許発明1と引用発明2との相違点は,「本件特許発明1は, 基材を透光性を有する透明又は半透明とし,基材の表裏に金属被膜層を形成すると\nともに,金属被膜層の一部にレーザー光を照射することにより剥離部を表裏面で対\n称形状に設けるのに対して,引用発明2は,釣竿又はゴルフシャフトにおいて,有 色塗装層を形成された基材の片面に金属被膜層を形成する際にマスキング処理を行 って剥離部を設ける」ものと認められる。
ウ 相違点の容易想到性について
(ア) 前記(4)イのとおり,引用発明2は有色塗装層を必須の構成とするのである\nから,引用発明2に,全光線透過率が80%以上である高分子フィルム基材を有す る引用発明1を組み合わせることには阻害要因が認められる。さらに,引用発明2 は,管状の部材の装飾に係るものであって,金属層を管の内側と外側の両面に設け ることは,相応の困難を伴うというべきである。
(イ) また,引用発明3は,前記(5)イ(イ)のとおり,レーザー光を透過し得るよ うな基板の表裏を有するのであるから,有色塗装層を必須の構\成とする引用発明2 に対し,引用発明3を組み合わせることには阻害要因があると認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2017.01.16
平成28(ワ)3234 求償金請求事件 商標権 民事訴訟 平成28年12月21日 東京地方裁判所(29部)
1 争点1(被告は,本件ライセンス契約に基づき,被告の費用と責任において, 必要に応じて原告から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審 決取消訴訟手続において防御させるべき義務を負っていたか)について
(1) 原告は,双日GMCによる本件各審判請求及びこれに引き続く本件審決取消 訴訟の提起は,本件契約書7条2項にいう「甲(判決注:被告)の販売方法に起因 してクレームを受けた」場合に当たるから,被告は,本件ライセンス契約に基づき, これらをすべて被告の責任と負担において解決すべき義務,具体的には,被告の費 用と責任をもって弁護士を選任し,必要に応じて原告から同弁護士宛の委任状を取 得して,審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させる義務を負っていたと主 張する。
(2) 双日GMCが行った本件各審判請求は,商標法53条1項に基づくものであ るところ,同条項に基づく審判請求が可能となるのは,法文上,「専用使用権者又\nは通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役 務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは 役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをした とき」(判決注:下線を付した。)である。 しかるところ,本件契約書7条は,1項において,「本契約に基づく本件商標の 使用に関し,第三者よりクレームまたは訴訟の提起を受けた場合,あるいは第三者 による本件商標の侵害行為を発見した場合,甲乙丙は直ちにその旨をそれぞれに連 絡し,当該クレームまたは訴訟に対する防御あるいは第三者による侵害行為の排除 を共同して行うものとし,これに要した費用負担については,甲乙丙が協議の上定 めるものとする。」(判決注:下線を付した。)と規定しているのであるから,双 日GMCが行った本件各審判請求及びこれに引き続く本件審決取消訴訟については, 「本契約に基づく本件商標の使用に関し,第三者よりクレームまたは訴訟の提起を 受けた場合」に当たる(少なくともこれに準ずる)ものとして,本件契約書7条1 項が適用されるものと解するのが相当である。
(3) これに対し,原告は,本件契約書7条2項の文言上,クレームをする者が一 般消費者であるか,クレームを受けた者が被告であるかなどについて限定はないか ら,同クレームが被告の販売方法に起因したものであれば,本件契約書7条2項が 適用されるべきであって,双日GMCによる本件各審判請求は,被告の販売方法に 起因するクレームであるから,同条項が適用されるべき旨主張する。 そこで検討するに,本件契約書7条は,まず1項において,「本契約に基づく本 件商標の使用に関し,第三者よりクレームまたは訴訟の提起を受けた場合,あるい は第三者による本件商標の侵害行為を発見した場合,甲乙丙は直ちにその旨をそれ ぞれに連絡し,当該クレームまたは訴訟に対する防御あるいは第三者による侵害行 為の排除を共同して行うものとし,これに要した費用負担については,甲乙丙が協 議の上定めるものとする。」と規定し,商標の使用に関して生じた紛争については, 原則として1項により規律されるべき旨を明らかにしている。ここで,本件ライセ ンス契約上,被告は,原告から許諾を受けて本件各商標を使用する(本件各商標の 付された指定商品を販売する)立場にあるから,1項にいう「本契約に基づく商標 の使用」の主体が被告となることは,本件ライセンス契約が当然に想定しているこ とである。もっとも,商標の使用といっても,当該商標が使用された商品の品質に 欠陥があり,又は商品を販売する際の販売方法に問題があって,このために顧客等 に損害を及ぼすなどしたというような紛争が発生した場合には,かかる紛争は,形 式的には商標の使用行為によって生じたものではあるが,実質的には商標に関する 紛争とはいい難く,当然に,商品を実際に製造し,又は販売した者(被告)が責任 を負担してしかるべき性質のものということができる。本件契約書7条2項に「本 件商標を付した指定商品の品質上の欠陥及び甲の販売方法に起因してクレームを受 けた場合は,全て甲の責任と負担において処理解決をすることとする。」とあるの は,このような認識に立って,被告が販売する商品の品質に欠陥があり,又は商品 を販売する際の販売方法に問題があったために顧客等から苦情を受けた場合など, 実質的にみて商標に関する紛争とはいえない場合には,被告がその責任において同 紛争を処理解決すべき旨を規定したものと解するのが相当である。 双日GMCによる本件各審判請求は,原告の主張によっても,1)被告商品が,双 日GMC商品と酷似していること,2)両商品において付された商標の位置や種類が ほぼ同じであること,3)両商品とも,被告の店舗において紛らわしい売り方をされ ていたことなどを理由にしてされたというのであり,上記3)のように,「被告の販 売方法」に着目してされた主張も存在するものの,本件各商標を付した被告商品の 販売が,双日GMCの業務に係る商品(双日GMC商品)と混同を生ずるものであ るかが問題とされているのであり,実質的に見て商標に関する紛争でないとはいい 難い。むしろ,前記前提事実及び証拠(甲1,4,6)によれば,双日GMCの保 有する関連各商標権は,平成20年10月29日に(分割前の)本件各商標権から 指定商品を「履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパを除く」)」とする商 標権が分割移転されたものであり,関連商標1ないし同5と本件商標1ないし同5 とは,それぞれ同一の商標であって,関連各商標登録の指定商品である「履物・・ ・但し,履物(サンダル靴,サンダルげた,スリッパを除く)を除く」と本件各商 とは,形式的には重複しないものの,相互に類似する関係にあると認められるから, 本件各審判請求は,商標に関する紛争そのものというべきであって,本件契約書7 条1項にいう「本契約に基づく本件商標の使用に関し,第三者よりクレームまたは 訴訟の提起を受けた場合」として,同項により規律されるべき性質のものというべ きである。 また,前記前提事実及び証拠(甲3,7,乙9)によれば,原告は,本件各審判 請求を受けた後,双日GMCの審判請求の理由を認識した上で,本件覚書に調印し, 本件各商標登録を取り消す旨の審決が確定したときは,既払ミニマムロイヤリティ の一部を被告に返還することや,被告が販売することができなくなった在庫商品に つき一定の補償をすることを約したことが認められ,他方,原告が,上記調印当時, 被告に対し,審判手続への参加その他の協力を求めたり,原告が同手続のために支 出し又は支出することとなる弁護士費用の負担を求めたりした形跡がないことから すれば,原告は,本件覚書を調印した平成25年10月1日当時,被告ではなく, 本件各商標権の商標権者であって,本件各審判請求における被請求人である原告こ そが,本件各商標権を維持できるよう努め,本件ライセンス契約に基づく被告の利 益を擁護すべき立場にあった旨認識していたことは,明らかである。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 不正使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2017.01.16
平成28(行ケ)10153 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成29年1月11日 知的財産高等裁判所
原告は,差異点(イ)に相当する凹凸形状の違い(本件登 録意匠のそれは山型であるのに対し,引用意匠1のそれは波型である点) を強調して,1)両意匠の本体部及び蓋部の外観を具体的に把握すれば,そ れぞれに統一感は生じているものの,それぞれが看者に与える印象は全く 別異のものであって,その差異を凌駕するような両意匠の共通感を看取す ることができない,2)引用意匠1と同様の形状であるバケツについては, 「腰掛け」や「簡易スツール」としての用途・機能も積極的に紹介されて\nおり,また,水を入れる際に直接手で触れたり,水位を確認する際に至近 距離から目にしたりすることも多いのであるから,凹凸形状の違いは「微 弱」な差異などではない,3)本件登録意匠の出願前から,本体部及び蓋部 の外観全体に凹凸形状が形成されたバケツが既に複数公知となっているこ とから,単に「本体部及び蓋部の外観全体に凹凸形状が形成された」点は, 本件登録意匠と引用意匠1のみに存在する共通点ではないなどと主張する。 しかし,1)については,前記のとおり,両意匠の凹凸形状がいずれも細 い筋状のものであり,これが本体と蓋を含む外観全体に一様に施されてい る点にこそ,両意匠の特徴が認められるのであって,これと比較すれば, 原告が指摘する凹凸形状の違いは,細部における差異にすぎず,「それぞ れが看者に与える印象は全く別異のものであ」ると感じさせるほどに特徴 的であるとは認められない。2)についても,たとえ引用意匠1に係るバケ ツが腰掛け等として使われることがあったとしても,バケツである以上, 第一次的な用途が水を入れること,あるいは,物の運搬,収納,保管等に あることは明らかであるし,その性質や用途からして,看者(需要者)が まず全体的な形状に着目し,これを俯瞰的にみることが多いことも明らか である。3)の主張は,要するに,「本体部及び蓋部の外観全体に凹凸形状 が形成された」点は,本件登録意匠の出願前に既に複数公知であるから, 類否判断を行う上で重視すべきではないとの主張と解されるが,複数公知 になるだけで直ちに意匠上の要部でなくなるとはいえず(ヒット商品こそ, 往々にして模倣品が現れることを考えれば当然である。),飽くまで上記 の点が本体部と蓋部の外観全体を通じて統一感を感じさせる独特の形態で あって,意匠全体における支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成し(こ のような評価を否定するに足りるほど,上記の点が陳腐化していたことを 認めるに足りる証拠はない。),看者の注意を強くひく構成態様であると\n評価される以上,これを両意匠に共通してみられる特徴的部分であるとし て類否判断を行うことは当然である。 したがって,差異点(イ)に相当する凹凸形状の違いは,共通点(A) ないし(C)が物品の外観全体にもたらす効果を凌駕し,差異性を際立た せるほどの特徴であるとは認められず,類否の判断要素としては,副次的 な要素にすぎないといわざるを得ない。 また,原告は,機能的な面からすれば,取っ手の両端部の態様や,引用\n意匠1の取っ手部に設けられた円形状孔部の存在(差異点(ア)),蓋部 の突起部及び補強用のリブの有無といった蓋部の裏面における違い(差異 点(ウ))も軽視できず,また,様々なカラーバリエーションがあること からすれば,取っ手の明暗調子の違い(差異点(エ))も軽視できないな どと主張するが,これらの差異も,両意匠を全体としてみれば,部分的な 差異や目立たない部分における細かな差異にすぎないことは明らかであっ て,共通点(A)ないし(C)が物品の外観全体にもたらす効果を凌駕し, 差異性を際立たせるほどの特徴であるとは認められず,類否の判断要素と しては,飽くまで副次的な要素にすぎないというべきである。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2017.01.16
平成27(ネ)10123 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年12月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
(ア) 別紙対比表4−1のエピソ\ード3において,本件著作物1と本件映画 とは,「翻案該当性」欄記載のとおり,2)公園に駆け付けた元恋人(婚約者)が被控 訴人(主人公)の様子に驚いて,誰かに何かされたのかと聞いたこと,3)被控訴人 (主人公)はうなずくことしかできなかったこと,4)元恋人(婚約者)が,被控訴 人(主人公)が性犯罪被害を受けたことを知ってやり場のない怒りで手近な物に当 たる様子,5)被控訴人(主人公)が元恋人(婚約者)に対して「ごめんなさい」と 謝り続けたこと,及びその著述(描写)の順序が共通し,同一性がある。 なお,被控訴人は,「翻案該当性」欄記載のとおり,1)被控訴人(主人公)が元恋 人(婚約者)に助けを求めたことも,本件著作物1と本件映画とで共通する点とし て主張するが,本件著作物1では,被控訴人が元恋人に電話を掛け,電話越しに異 変を察知した元恋人が被控訴人の状況を確認しようとし,その場にいることを命じ たという,助けを求める具体的な場面が著述されているのに対し,本件映画では, 婚約者が息を切らしながら走っていることの描写と上記2)〜5)のやりとりを通じて, 主人公が元恋人に助けを求めたことが暗に表現されているのであるから,言語の著\n作物と映画の著作物との表現形態の差異を考慮しても,本件著作物1における被控\n訴人が元恋人に助けを求める場面の著述と共通する描写が,本件映画においてなさ れているものと認めることはできない。 (イ) そして,前記(ア)の本件著作物1の著述中の同一性のある部分(以下「本 件著作物1−3の同一性ある著述部分」という。)は,それぞれの著述だけを切り離 してみれば,事実の記載にすぎないようにも見えるものの,本件著作物1−3の同 一性ある著述部分全体としてみれば,自ら助けを求めた元恋人から尋ねられたにも かかわらず,性犯罪被害に遭った事実を告げることができず,うなずくことと「ご めんなさい」を繰り返すことしかできない性犯罪被害直後の被害女性の様子と,助 けを求められて駆け付けたにもかかわらず,何も助けることができなかったという やり場のない怒りを,大声を出すことと物にぶつけるしかない元恋人の様子とを対 置して,短い台詞と文章によって緊迫感やスピード感をもって表現することで,単\nに事実を記載するに止まらず,被害に遭った事実を口に出すことの抵抗感や,被害 に遭ってしまった悔しさ,やるせなさ,被害者であるにもかかわらず込み上げてく る罪悪感をも表現したものと認められる。\nそうすると,本件著作物1−3の同一性ある著述部分は,被控訴人が被害を受け た当事者としての視点から,前記2)〜5)の各事実を選択し,被害直後の被控訴人の 状況や元恋人とのやりとりを格別の修飾をすることなく短文で淡々と記述すること によって,被控訴人の感じた悔しさ,やるせなさ,罪悪感等を表現したものとみる\nことができ,その全体として,被控訴人の個性ないし独自性が表れており,思想又\nは感情を創作的に表現したものと認められる。\n
関連カテゴリー
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2017.01.16
平成24(行ケ)10019 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成24年5月31日 知的財産高等裁判所
商標法3条1項柱書は,商標登録要件として,「自己の業務に係る商品又は 役務について使用をする商標」であることを規定するところ,「自己の業務に係る商 品又は役務について使用をする商標」とは,少なくとも登録査定時において,現に 自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標,あるいは将来自己の業務に 係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される。 これを本件についてみるに,上記認定事実によれば,1)原告は,平成21年9月 17日ころから,ウェブサイトにおける情報掲載,パンフレットの配布,プレスリ リース等を行い,東京都を中心に,原告使用商標を使用して本件店舗の宣伝,広告 を行っていたこと,2)原告は,同年10月1日,東京都千代田区丸の内に,原告使 用商標を使用し,飲食物の提供を業とする本件店舗を開店したこと,3)被告は,同 月24日,本件商標の登録出願をし,平成22年3月26日にその登録を受けたが, 現在に至るまで本件商標を指定役務である「飲食物の提供」やその他の業務に使用 したことはないこと,4)本件商標と原告使用商標(1)は,類似すること,5)原告使用 商標は,原告が経営する飲食店「ローズ&クラウン」(Rose & Crown) の頭文字である「RC」(アールシー)と,英語で居酒屋や酒場を意味する「Tav ern」(タバーン)を組み合わせた造語で,特徴的なものである上,本件店舗の宣 伝,広告及び開店と本件商標の登録出願日が近接していることからすれば,被告は, 原告使用商標を認識した上で,原告使用商標(1)と類似する本件商標を出願したもの と考え得ること,6)被告は,平成20年6月27日から平成21年12月10日ま での短期間に,本件商標以外にも44件もの商標登録出願をし,その登録を受けて いるところ,現在に至るまでこれらの商標についても指定役務やその他の業務に使 用したとはうかがわれない上,その指定役務は広い範囲に及び,一貫性もなく,こ のうち30件の商標については,被告とは無関係に類似の商標や商号を使用してい る店舗ないし会社が存在し,確認できているだけでも,そのうち10件については, 被告の商標登録出願が類似する他者の商標ないし商号の使用に後れるものであるこ とが認められる。
上記事情を総合すると,被告は,他者の使用する商標ないし商号について,別紙 2のとおり多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし,登録された商標を収 集しているにすぎないというべきであって,本件商標は,登録査定時において,被 告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標に当たらない上,被 告に将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思があったとも認め難い。
これに対し,被告は,平成20年から,いわゆるシニア起業を協力者1名ととも に計画し,予定業務について前広に商標の出願登録を行うとともに,飲食店の開業\nを目指し,神奈川県西部を中心に,いわゆる居抜きの店舗を探していたが,円高不 況,大震災等により開業リスクが高まったため,一時開業を見合わせており,経済 情勢の好転を待って小規模でも開業する予定であるなどとあいまいな主張をするの\nみで,これを裏付ける証拠を一切提出しておらず,その主張は,にわかに措信し難 い。 したがって,本件商標は,その登録査定時において,被告が現に自己の業務に係 る商品又は役務に使用をしている商標にも,将来自己の業務に係る商品又は役務に 使用する意思のある商標にも当たらず,本件商標登録は,「自己の業務に係る商品又 は役務について使用をする商標」に関して行われたものとは認められず,商標法3 条1項柱書に違反するというべきである。
(2) この点について,審決は,上記事情をもってしても,被告の本件商標に係る 使用の意思について合理的な疑義があるとはいえないと認定,判断する。しかし, 登録商標が,その登録査定時において「自己の業務に係る商品又は役務について使 用をする商標」に当たることについては,権利者側において立証すべきところ,本 件商標についてこれを認めるに足りる証拠はなく,むしろ,上記認定事実によれば, 本件商標登録は,被告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用していない商標 について,将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思もなく行われたもの というべきであって,上記審決の認定,判断は失当である。 以上のとおり,本件商標は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする 商標」に該当しないというべきであり,本件商標登録が商標法3条1項柱書に違反 しないとした審決の判断には誤りがある。
付言するに,上記認定の事実関係に照らすと,本件商標は,原告使用商標を剽窃 するという不正な目的をもって登録出願されたものとして,商標法4条1項7号(公 序良俗に反するおそれのある商標)に該当する余地もあるが,本件においては,同 法3条1項柱書該当性の判断で足りるものと解する。
2017.01.11
平成28(行ケ)10023 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年12月26日 知的財産高等裁判所(第2部)
しかしながら,引用例の【0017】の実施例において,「文書処理プログラム 24での低電力消費」と対比して,高いクロック周波数を選択することが考えら れるものは「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算\n要求」であって,「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な\n計算要求を必要とするアプリケーションプログラム」などと記載されているもの ではなく,「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要\n求」が「文書処理プログラム24」とは異なるアプリケーションプログラムでの 計算要求であることは記載されていない。そして,本願優先日当時,文書処理プ ログラムにはグラフィック機能が組み込まれているのが一般的であり,文書処理\nプログラムに組み込まれたグラフィック機能において回転する3次元画像の総天\n然色表示の形成が行えないものではないことからすると,高いクロック周波数を\n選択する「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要\n求」は,アプリケーションプログラムの実際の動作に応じた「計算条件」を示す ものであるとみることもでき,引用例の【0017】の記載に接した本願優先日 当時の当業者において,そこに記載された実施例が「アプリケーションプログラ ムのタイプに対応する動作モード」に基づいてクロック周波数を選択するもので あると認識するものということはできない。 また,引用例の【0022】の実施例において,「高度または高速の計算能力を\n必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合」と対比して,低いクロ ック周波数を選択することが考えられるものは「タイムアウト周期について活動 していないことを検出」した場合であり,例えば,「高度または高速の計算能力を\n必要としないアプリケーションプログラムを検出した場合」のような類型のアプ リケーションプログラムを検出した場合と対比されているものではないし,「高度 または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラム」を起動中に,\n「タイムアウト周期について活動していないことを検出」した場合には,高いク ロック周波数が選択されるべき「高度または高速の計算能力を必要とするアプリ\nケーションプログラム」の起動中でありながら,低いクロック周波数を選択する ことになるから,引用例の【0022】の記載に接した本願優先日当時の当業者 において,そこに記載された実施例が「アプリケーションプログラムのタイプに 対応する動作モード」に基づいて「特定の高クロック周波数で前記中央演算処理 装置12を動作させる」ものであると認識するものということはできない。 さらに,引用例の【0012】をみても,低いクロック周波数が選択される「モ デムによる通信,新しい命令が入力されない待機状態,およびその他の日常的で 単純な計算機能を実行する動作の間」と,高いクロック周波数が選択される「回\n転する3次元オブジェクトの表示を形成する,大量のデータベースの検索を実行\nする,などのさらに複雑な計算が要求される場合」とが異なったアプリケーショ ンプログラムに対応したものであることは記載されていないし,「回転する3次元 オブジェクトの表示を形成する」ことができるアプリケーションプログラムにお\nいて「単純な計算機能を実行する動作」のみを行っている間を想定すれば明らか\nなように,両者が異なったアプリケーションプログラムでしか奏し得ないことが 自明であるともいえないから,引用例の【0012】の記載に接した本願優先日 当時の当業者において,引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対 応する動作モード」に基づいてクロック周波数を選択するものであると認識する ものということはできない。 そうすると,引用例の【0012】,【0017】,【0022】等の記載を総合 しても,これらに接した本願優先日当時の当業者において,引用発明が「アプリ ケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記動作モード に応答して,・・・中央演算処理装置12を動作させる」ものであると認識するこ とはできないと認められ,このことは,引用発明が,利用可能な電池電力が限ら\nれており,その有効な管理への要求が最優先課題となっている可搬型コンピュー タにおいて当該課題を解決することを目的とするものであることをも考慮すれば, 一層明らかというべきである。 よって,引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モ ードを決定し,前記動作モードに応答して,・・・中央演算処理装置12を動作さ せる」構成を有するとした審決の認定には誤りがあり,これに起因して,審決は,\n「アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記 動作モードに応答して,・・・回路を動作させる」点を一致点として過大に認定し, 相違点として看過した結果,この点に対する判断をしておらず,結論に影響を及 ぼす違法があるものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.01.11
平成27(行ケ)10239 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年12月26日 知的財産高等裁判所(第2部)
そこで,134条の2第9項で準用する126条6項の規定の趣旨や,平成6年 法律第116号による特許法の改正は,あらゆる発明について目的,構成及び効果\nの記載を求めるのではなく,技術の多様化に対応した記載を可能とし,併せて制度\nの国際的調和を図ることを目的として,同法律による改正前の特許法36条4項が 発明の詳細な説明の記載要件として規定していた「発明の目的,構成及び効果」を\n削除したにとどまり,同法126条2項の実質上特許請求の範囲を拡張・変更する 訂正の禁止の規定は,実質的改正はされていないこと(甲60)を踏まえて,以下, 検討する。
・・・
(3) 前記(2)の記載によれば,本件発明1について,次のとおり,認められる。 すなわち,本件発明1は,バラスト水処理装置については,今後設置が義務付け られるにもかかわらず,船舶にその適当な設置場所を確保することが困難な状況に あり,船体設計の大幅な変更を必要とせず,しかも,新造船に設置する場合にも, 既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶が望まれていたこと\nに鑑み,多種多様な船舶に対して,多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適 所に容易に設置可能とする船舶を提供することを目的とするものである(【000\n5】〜【0007】)。 そして,本件発明1は,この課題を解決するために,船舶後方で,吃水線よりも 上方に位置する舵取機室内に,バラスト水処理装置を配設するという手段を採用し た(【0008】)。 その結果,バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室内に配設したことから,船 体構造や船型を大きく変更することなく,船舶内の空間を有効利用して種々のバラ\nスト水処理装置を容易に設置することができ,また,バラスト水処理装置を配設し た舵取機室が吃水線よりも上方に位置することから,緊急時にバラスト水を容易に 船外へ排水することができるという効果を奏する(【0009】)。
(4) これに対し,訂正事項1は,1)「バラスト水処理装置」によって「バラス ト水中の微生物類を処理して除去または死滅させる」時期を,「バラスト水の取水時 または排水時」という択一的な記載から「バラスト水の取水時」という限定的な記 載に変更し(構成要件A),2)「バラストタンク」及び「バラスト水配管系統に設け られ,機関室に設置されたバラストポンプ」についての記載を追加し(構成要件A),\n3)構成要件Bないし構\成要件Eについての記載を追加し,さらに,4)「緊急時に前 記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」との記\n載を追加する(構成要件G)ものであり,それによって「船舶」の発明である本件\n発明1を限定し,同じく「船舶」の発明である本件訂正発明1とするものである。 これらのうち,1)バラスト水処理装置へのバラスト水の供給時期が択一的であっ たものを1つの時期に限定した点は,本件発明1に新たな構成を付加するものでは\nなく,本件発明1の課題に含まれない新たな課題を解決するものではないことは明 らかである。
2)バラストタンク,バラスト水配管系統及びバラストポンプの記載を追加した点 は,本件発明1に新たな構成を付加するものであるが,本件発明1は,バラスト水\n処理装置を備えた船舶の発明であり,バラスト水処理装置を備えた船舶において, バラスト水を積載するバラストタンク,バラスト水の配管系統,バラスト水の取水 と排水のためのバラストポンプが備えられていることは周知の事項であるから(甲 30〜甲33),これらの記載の追加は,本件発明1の課題に含まれない新たな課題 を解決するものではない。
3)構成要件Bないし構\成要件Eについての記載を追加した点は,本件発明1に新 たな構成を付加するものであるが,本件発明1は,バラスト水処理装置を備えた船\n舶の発明であるところ,構成要件Bないし構\成要件Eは,バラスト水処理装置を備 えた船舶において備えられているバラスト水配管系統の構成について,バラスト水\n処理装置が装置入口側配管及び装置出口側配管を介してバラスト水配管系統と連結 され(構成要件B),装置入口側配管,装置出口側配管,連結点間配管に設けられた\n本件各開閉弁と,取水管路の一部を構成するが排水管路の一部を構\成しない処理装 置配管系統,取水管路も排水管路も構成しない連結点間配管を備え(構\成要件C− 1,C−2,D−1,D−2),バラストポンプと装置入口側連結点との間のバラス ト水配管系統に設けられた,バラストポンプから装置入口側連結点へ向かう方向の 流れのみを許容する逆止弁を備えること(構成要件E)を特定して,本件発明1に\nおいて多種多様に構成することが可能\であったバラスト水配管系統の構成を限定し\nているものであって,本件訂正明細書を踏まえて,構成要件Bないし構\成要件Eの 構成を検討しても,その構\成の追加により本件発明1の課題に含まれない新たな課 題を解決するものとは認められない。
4)「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように 構成する」との記載を追加した点は,本件発明1に緊急排水用管路という新たな構\ 成を付加するものであるが,前記(2)のとおり,本件発明1の緊急時にバラスト水を 容易に船外へ排水することができるという効果を,当業者にとって自明な構成によ\nり具体化したものにすぎないから,その構成の追加により本件発明1の課題に含ま\nれない新たな課題を解決するものとまでは認め難い。
(5) また,本件発明1及び本件訂正発明1は,物の発明であるが,訂正事項1 の内容からすれば,特許法101条1号及び3号の間接侵害の成立範囲が訂正事項 1により左右されることはおよそ考え難い。 原告らは,訂正事項1により同条2号の間接侵害の成立範囲が広がる可能性があ\nり,具体的には,訂正事項1により追加された配管構造等に関し,これを生産する\n等の行為について同条2号の間接侵害が成立するおそれがあると主張するが,訂正 事項1により同条2号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。すな わち,同条2号の間接侵害は,発明の対象である「物の生産に用いる物」のうち「そ の発明による課題の解決に不可欠なもの」に限って成立するものであり,その成立 範囲は,その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品に限ら\nれるというべきであるが,前記(4)のとおり,訂正事項1により,本件発明1の課題 に含まれない新たな課題が,本件訂正発明1の課題となったものとは認められない。 したがって,たとえ原告ら主張の本件バラスト水配管系統等を現実的に想定できた としても,訂正事項1が,本件訂正発明1の課題に本件発明1の課題と異なる新た な課題を追加するものではない以上,その課題の解決に不可欠なものの範囲,すな わち,その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品の範囲も,\n本件訂正発明1と本件発明1とで異なるものではないというべきであるから,訂正 事項1により同条2号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2017.01.11
平成28(行ケ)10145 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年12月22日 知的財産高等裁判所
本件商標の「ケアセンター」という構成部分は,\n少なくとも本件指定役務との関係においては介護の提供場所を一般的に表示するも\nのにすぎず,当該構成部分から役務の出所識別標識としての称呼,観念は生じない\nというべきである。他方,「くれない」という構成部分は,そもそも「ケアセンター」\nという構成部分と用語として関連するものではなく,「くれない」という用語は,本\n件指定役務の内容等を具体的に表すものではないから,本件指定役務との関係では,\n需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ る。そうすると,本件商標のうち「くれない」という構成部分を抽出し,当該構\成 部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきで ある。
・・・・
原告は,本件商標は「くれないケアセンター」全体が出所識別機能を有するにも\nかかわらず,「くれない」という構成部分のみを抽出して引用商標と類否判断し,こ\nれを肯定した審決の判断には誤りがあるというものである。 しかしながら,上記1において説示したとおり,結合商標の構成部分の一部を抽\n出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは, その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な 印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての 称呼,観念が生じないと認められる場合などは,許されるべきである(前掲最二小 判平成20年9月8日参照)。本件商標のうち「ケアセンター」は,本件指定役務と の関係では「介護施設」という役務の提供場所をいうにとどまり,それ自体出所識 別機能を有するものとは認められないのに対し,「くれない」は,「ケアセンター」\nという用語とは本来的に関連性がなく,需要者に対し役務の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えることは明らかである。そうすると,本件商標のうち「くれ ない」という構成部分を抽出して商標の類否判断をすることが許されると認めるの\nが相当である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2017.01.11
平成28(ネ)10084 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成28年12月22日 知的財産高等裁判所(第1部) 東京地方裁判所(47民)
「そして,不正競争防止法にいう「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従 った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並 びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいうところ(不正競争防止法 2条4項),前記1の認定事実によれば,控訴人商品の外面包装は,光沢のあるロー ズピンクであって,伏し目のまつ毛のデザイン及び「LuLuLun」という大き な文字等が付されていることが認められることからすると,外面包装全体が立方体 であるなどという控訴人主張に係る形態よりも,かえって,外装包装に結合した模 様,色彩,光沢及び質感が,需要者に対し強い印象を与えるものとして出所識別機 能を有するというべきであって(ただし,控訴人は,「LuLuLun」等の記載を\n控訴人商品の形態の特徴として主張するものではない(原審第1回口頭弁論調書参 照)),もとよりこれらが不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当\nするとしても,被控訴人商品が控訴人商品と類似するものではないことは明らかで ある。
・・・
控訴人は,控訴人商品の外面包装の上面及び下面,フラップラベル,その下の切 込み部分は概ね正方形であって,控訴人商品のような外面包装全体が立方体である というシンプルなデザインを採用した商品は他に存在しなかったのであり,控訴人 商品の形態は,他の商品とは異なる顕著な特徴を有するものであり,不正競争防止 法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当し,これと実質的に同一の形態の被控\n訴人商品は同項3号にいう控訴人商品の「模倣」に該当する旨主張する。 しかしながら,前記のとおり,商品の形態は,顕著な特徴を有しない限り,そも そも本来商品の出所を表示するものではなく,控訴人商品の外面包装全体が立方体\nであるなどという形態は,極めてシンプルなものであって,上記にいう顕著な特徴 であると認めることはできない。かえって,前記認定事実によれば,控訴人商品と 被控訴人商品は,外面包装に結合した模様,色彩,光沢及び質感が需要者に対し明 らかに異なる印象を与えているのであるから,上記立方体等の形態が商品等表示で\nあると認めることはできず,控訴人商品と被控訴人商品が類似するということもで きない。そのほかに控訴人の当審における主張を改めて十分検討しても,その実質\nは,同種の主張を縷々繰り返すものであって,結局のところ,不正競争防止法2条 1項1号又は3号の規定の意義を正解しないものに帰するというほかない。 したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。
2017.01.10
平成28(行ケ)10040 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年12月26日 知的財産高等裁判所(第2部)
前記a及びbによれば,コンピュータシステムの不正使用防止の技 術分野において,装置Aの記憶媒体に記憶されている情報を,特定の者に利用させ る場合につき,当該特定の者が装置Bを携行することを前提に,装置Aと装置Bと の間の距離測定を行い,その距離が所定の範囲内であるときに限り,装置Bの所持 者に当該情報を利用させることは,本願優先日には周知技術であったと認められる。
ウ(ア) 甲1発明は,前記(1)のとおり,車両側無線装置と携帯型無線装置との 間の距離を測定し,所定の間隔の範囲内である場合に,車両側無線装置が車両の施 解錠実行部に解錠指令を送出するキーレス・エントリーシステムである。 一方,甲3は,前記イ(ウ)aのとおり,携帯通信端末とカードとの距離に応じてカ ードの使用を許可するシステムであって,ここでのカードの使用とは,クレジット カードの情報を用いる電子商取引,すなわち,情報処理である。また,甲4は,同 bのとおり,多端末環境でのユーザのワークステーションへのアクセスを許可する システムであり,ここでのワークステーションへのアクセスは,当然に情報処理を 目的としている。つまり,甲3及び4に記載された技術は,情報処理システムに対 する不正使用防止の技術であるのに対し,甲1発明は,ドアの解錠システムという, 情報処理システムではないシステムに対する不正使用防止の技術であって,両者は, その前提とするシステムが相違しており,技術分野が異なる。
(イ) しかも,装置Aの記憶媒体に記憶されている情報を,特定の者に利用 させる場合につき,当該特定の者に装置Bを携行させ,装置Aと装置Bとの間の距 離測定を行い,その距離が所定の範囲内であるときに限り,装置Bの所持者に当該 情報を利用させるという周知技術を,甲1発明に適用したとしても,距離測定後に, 距離測定の対象である装置の一方から他方へ,当該一方の装置が記憶しているマル チメディアデータを,他方の装置に送信するという構成に至るものではない。
(ウ) したがって,当業者が,甲1発明と甲3又は4に記載された周知技術 を組み合わせることは,容易とはいえず,仮に組み合わせたとしても,本願発明を 発明することができたとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2017.01.10
平成28(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年12月26日 知的財産高等裁判所(第2部)
上記各記載のとおり,地盤注入の施工前に地盤抵抗圧力(注入圧力)を測定する ことは,通常のことであり,その地盤抵抗圧が工事現場のものでなければならない のは当然であるから,その測定は,注入対象範囲内そのものであるかはともかくと して,工事現場と認められる範囲で行われているといえる(本件発明1も,注入対 象範囲内そのもので地盤抵抗圧力が測定される場合に限定されるものではない。)。 そして,前記(1)のとおり,本件発明1の「流量」は,単位時間当たりの注入量(注 入速度)のことであるところ,建設省(国土交通省)の通達等である上記3)に,施 工計画時に「注入速度」を定めなければならないと記載されていることや,業界団 体の指針である上記5)にも,施工計画時に注入速度が定まっていることを前提とす る記載があることからみて,「流量」(注入速度)は,工事現場の状況等によって変 更される余地はあるとしても,注入施工の前にあらかじめ定まっているものと理解 できる。そして,「流量」(注入速度)と地盤抵抗圧力とは関連しているから(甲1 の【図26】,甲2【図2】【図3】参照)),地盤抵抗圧力を測定することは,所定 の「流量」(注入速度)を前提にしたものである。 また,地盤抵抗圧の測定が,薬液を用いて行うことが通常であるか,あるいは, 水を用いて行うことが通常であるかが上記各記載からは明確ではないにしても,上 記各記載は,薬液を用いて地盤抵抗圧の測定を行うことを排除はしていない。かえ って,上記2)には,「薬液のかわりに水を用いた注入試験における注入圧と注入速度 の関係から注入形態を予測する簡便な方法が近年提案されている。」との記載があり,\nこの記載の当然の前提として,従来から,薬液を用いた注入試験が広く行われてい たことがうかがわれる。 以上からすると,本件発明1の「(a)予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し,」\nとの構成,すなわち,注入施工に先立ち,同じ注入材(グラウト)を用いて現場試\n験注入を行い,あらかじ流量を決めて注入圧力(地盤抵抗圧力)を測定することは, 本件特許の出願時点において,測定方法の一つとして当業者に広く知られていた周 知の事項であったと認められる。
・・・
(3) 容易想到性について
本件発明1は,前記(1)のとおり,(a)(b1)(b2)の構成を有しているとこ\nろ,試験注入において,地盤抵抗圧力をどのように測定するかという点と,本施工 において,測定された地盤抵抗圧力をどのように用いてグラウト注入を行うかとい う点は,それぞれ独立の技術的事項であるから,少なくとも,地盤抵抗圧力をどの ように測定するかという(a)の構成と,本施工において,測定された地盤抵抗圧\nをどのように用いるかという(b1)(b2)の構成とは,その容易想到性を別々に\n考慮してよいものである。そうすると,上記(2)イのとおり,本件発明1の(a)の 構成は,周知技術であるから,地盤抵抗圧力(注入圧力)を限界注入圧力Prfの\n限界内で設定する甲1発明において,その注入圧力の決定について,周知技術であ る相違点2に係る本件発明1の(a)の構成を採用することは,当業者が適宜なし\n得ることである。 また,前記(1)のとおり,甲1には,審決が甲1発明を構成するものとして認定す\nる(A1)(B1)の構成のほか,(A2)(A3)(B2)の構\成が開示されている。 本件発明1の「地盤抵抗圧力」に相当する甲1発明の分岐圧力計P11の圧力値は, 2kgf/cm2であり,本件発明1の「地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力」に相当する 甲1発明の送液圧力計P0の圧力値は,30kgf/cm2であるから,甲1発明において は,地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力となるようにグラウトが負荷されている。そ うすると,甲1の(A1)〜(A3)(B1)(B2)の構成は,本件発明1の(b\n1)(b2)の構成を開示しているものといえる(審決も,本件発明2に係る無効理\n由の判断中で,甲1発明の(A1)(B1)に相当する構成が,本件発明1の(b1)\n(b2)に相当する本件発明2の構成に相当すると判断している。)。\n以上によれば,本件発明1の(b1)(b2)の構成が,甲1の記載に基づいて,\n当業者において容易に想到できるものであることも,明らかであり,審決の相違点 2の判断には,誤りがある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2017.01.10
平成27(ワ)36667 商標権侵害行為差止(等請求事件 商標権 民事訴訟 平成28年12月21日 東京地方裁判所(40部)
前記1の各事実によれば,原告は,被告に対し,本件店舗の設備のみなら ず,第三者との関係における契約上の地位や権利義務なども含めて店舗の営 業一切を譲渡していること,本件同意書において,原告と被告の発起人であ るB及びCとの間で,「のれん」や「新高揚」との店名が記載された外看板 も含めて本件店舗を譲渡する旨合意していること,ここでいう「のれん」に は「新高揚」の店名が含まれると考えられること,原告は,家紋を使用しな いことについては,被告に本件念書を差入れさせ,違約金についてまで約束 をさせたにもかかわらず,本件店舗の名称の使用については何ら文書を作成 し又は作成させていないことが認められ,これらを総合考慮すると,本件営 業譲渡契約は,被告が「新高揚」の名称を使用することを前提として締結さ れたものであると認めるのが相当である。
(2) この点に関して原告は,本件営業譲渡の交渉時に,「新高揚」の名称を使 用しないことを条件に減額に応じたとか,本件同意書の原案について,Cに 対し,「のれん」を削除するようにいったところ,Cから契約書のときに書 き換えればよいといわれて削除されなかったなどと主張し,それに沿う供述 をしている。 しかし,上記各主張を認めるべき客観的証拠はないばかりか,前記1(2) エのとおり,Cは,本件同意書について,原告の要望を受けて複数の修正に 応じていたのであるから,被告が「新高揚」の名称を使用しないことを前提 として本件営業譲渡に係る交渉がされていたとすれば,Cが「のれん」につ いてのみ本件同意書の記載の修正に応じないとはおよそ考えられない。また, 原告は,原告本人尋問において,本件営業譲渡契約書には「のれん」の記載 がなかったのでよろしいと思っていたなどとも供述するが,本件営業譲渡契 約締結時には,本件営業譲渡契約書には「引き継ぐ財産」が記載された別紙 が添付されておらず,本件営業譲渡契約書をみても「のれん」が譲渡対象と なっているか否かが明らかとなるものではないし,さらに,本件店舗の引渡 時に作成された本件営業譲渡契約書の別紙(甲6)には,本件店舗内に存在 していた物品である「商品,貯蔵品,店舗造作,器具備品,その他営業物品」 について「一式」と記載されているにすぎず,現に本件営業譲渡により引き 継がれた契約上の地位や債権債務は記載されていないから,上記別紙の記載 をもっても,本件営業譲渡の対象に「新高揚」の名称ないし「のれん」が含 まれていないということはできない。 また,本件同意書において譲渡される営業権の内容として「外看板」が記 載されていることについて,原告は,原告本人尋問において,外看板は本件 店舗が所在する部屋の賃貸借契約の貸主である大家のものであり,壊すこと もできないから気にしなかったなどと供述するが,前記1(2)クのとおり, 原告は大家に対し,被告が店舗の名称を変更する予定であり外看板の変更が\n必要である旨を告げたこともなく,被告代表者らとの間で被告がどのような\n名称を使用するかについて話をしたこともないというのであり,さらには, 原告本人尋問によれば,Cから「名称をおいおい変更する」と言われたもの のそれが具体的にいつなのかの確認もしていないというのであるから,原告 が,C又はBとの間で,「新高揚」の名称を使用しないことを条件として本 件営業譲渡に係る交渉をしていたと認めることはできない。 (3) そして,原告は,当初,Bに対し,原告の跡を継ぎ本件店舗を購入するよ う持ちかけ,「新高揚」という店名も含めて本件店舗を売却する意向を示し, 平成24年10月中旬以降,B及びCと本件店舗の譲渡に関し交渉を始めた にもかかわらず,その直前である同年9月24日に原告自ら個人として原告 商標権の商標登録出願をしていた事実をB及びCに一切告げないまま,同人 らがその事実を知らない状況で,本件営業譲渡契約を締結して1700万円 もの譲渡代金を受領した後,自らは原告商標を全く使用しておらず,将来に おいてこれを使用するための店舗の営業等の具体的な計画を有しているわ けでもないのに,被告に対し,被告標章の使用の差止めと損害賠償を求め ていることが認められる。 そうすると,「新高揚」の名称を使用できるものと信頼して本件営業譲渡 契約を締結した被告に対し,本件営業譲渡の当事者である訴外会社の代表者\nであった原告が原告商標権を行使することは,民法1条3項所定の権利濫用 に当たり許されないと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 役務
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2017.01. 6
平成28(行ケ)10126 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成28年12月21日 知的財産高等裁判所
以上のとおり,両意匠に係る物品の性質,用途及び使用態様並びに公知意匠との 関係を総合すれば,本願意匠と引用意匠は,基本的構成態様において共通するもの\nの,その態様は,ありふれたものであり,需要者の注意を強く惹くものとはいえな い。また,具体的構成態様における共通点も,需要者の注意を強く惹くものとはい\nえない。これに対し,マウスピース部の端部の形態の相違は,需要者である患者及 び医療関係者らの注意を強く惹き,視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与 えるものである。 したがって,本願意匠と引用意匠の相違点のうち,マウスピース部の端部につい て,本願意匠は,その中央に円形孔及びその周囲に4つの小円形孔が形成された端 壁を設けたものであるのに対して,引用意匠は,端壁がなく,単に筒状のまま大き く開口した点は,マウスピースカバー部が透明で着色されていることと相まって, 需要者である患者や医療関係者の注意を強く惹くものと認められ,異なる美感を起 こさせるものであり,それ以外の共通点から生じる印象に埋没するものではないと いうべきである。 よって,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。
3 被告の主張について
被告は,使用者は主に使用時に限ってマウスピース部の構成態様に注目し,購入\n時などマウスピースカバー部が閉じられた状態では,透けて見えるにすぎないマウ スピース部の端部の態様は,需要者に強い印象を与えるものとはいえない,マウス ピース部の端壁の有無は全体から一部分と認められるマウスピース部の,さらにそ の先端部分のみの相違であって,全体からすると僅かな範囲のものである,マウス ピースカバー部の着色はごく普通に行われるものである,などとして,マウスピー スの端部の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的であると主張する。 しかし,マウスピース部の端部は,需要者である患者が吸引器を使用する際に観 察するものであるし,医療関係者も,処方する薬剤を前提に機能を重視して観察す\nるものであるから,かかる部分が全体と比較して僅かな範囲のものであるとしても, マウスピース部の端部の相違点が類否判断に及ぼす影響を限定的であるということ はできない。また,マウスピースカバー部の着色が従来から見られたものであって, それ自体がありふれたものであったとしても,本願意匠においては,透明で着色さ れたマウスピースカバー部の存在によって,マウスピース部の端部の形態により注 意が向けられ,引用意匠に類似しないとの評価につながるものである。被告の前記 主張は採用できない。
◆判決本文
関連事件はこちらです。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2017.01. 6
平成28(ワ)34083 著作隣接権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年12月20日 東京地方裁判所
原告は,業務用通信カラオケ機器の製造販売等を業とする株式会社であり, 業務用通信カラオケ機器「DAM」シリーズの販売を行っている。 原告は,平成28年8月17日に発売された女性ボーカルグループ「Li ttle Glee Monster」のCDシングル「私らしく生きてみ たい/君のようになりたい」に含まれる楽曲「私らしく生きてみたい」のカ ラオケ用音源(以下「本件DAM音源」という。)を作成した。原告は本件 DAM音源につきその音を最初に固定したレコード製作者として送信可能\n化権(著作権法96条の2)を有する。 被告は,カラオケ店舗において,DAMの端末を利用して,上記楽曲のカ ラオケ歌唱を行い,その際に自身が歌唱する様子を動画撮影し,本件DAM 音源の音が記録された動画を同年9月7日にインターネット上の動画共有サイトである「YouTube」にアップロードした。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2017.01. 4
平成28(ネ)10054 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年12月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人は,1)本件シャフトデザイン等の縞模様を含むベース部分は,トルネード (竜巻)をイメージし,人間のパワーの源である赤から,シャフトのカーボンを表\nす黒に昇華していく表現であり,ゴルフ界に嵐を巻き起こすという意味を込めてい\nる,2)ブランドロゴの横字画部の右側を鋭角に伸ばすことでボールの弾道やエネル ギーの伸びと指向性を表現している,3)ブランドロゴをトルネード模様(縞模様) の上に配置することでシャフト縦方向へのパワーを表現する工夫を凝らしているか\nら,本件シャフトデザイン等には創作性が認められるべきである,と主張する。 しかし,1)縞模様は,本件シャフトデザイン及び被告シャフト以外にもシャフト のデザインに用いられた例がある(乙1の添付資料8)上に,様々な物のデザイン として頻繁に用いられ,縞の幅を一定とせずに徐々に変更させていく表現も一般に\n見られるところである。ゴルフシャフトの色として,赤,黒及びグレーの3色を用 いた例は証拠上複数見られる(甲30の3の中央の画像の真ん中のシャフト,甲3 0の4の中央の画像の一番上のシャフト,甲30の5の中央の画像の後ろのシャフ ト)。よって,本件シャフトデザイン等を縞模様とし,縞の幅を変化させ,縞の色と して赤,黒及びグレーを選択したことは,ありふれている。 また,2)いわゆるデザイン書体は,文字の字体を基礎として,これにデザインを 施したものであるところ,文字は,本来的には情報伝達という実用的機能から生じ\nたものであり,社会的に共有されるべき文化的所産でもあるから,文字の字体を基 礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を\n認めることは,一般的には困難であると考えられる。しかも,本件において,「To ur AD」のブランドロゴは,上記ア(エ)のとおり,既存のフォントを利用した上 で,「T」の横字画部を右に長く鋭角に伸ばしたものであるところ,文字として可読 であるという機能を維持しつつデザインするに当たって,文字の一字画のみを当該\n文字及び他の文字の字画を妨げない範囲で伸ばすことは一般によく行われる表現で\nあること,文字の一字画を伸ばした先を単に鋭角とすることも,平凡であることか らすれば,この表現が個性的なものとは認められない。\nさらに,3)ブランドロゴをトルネード模様の上に配置したことに関しては,シャ フトのデザインに製品等のロゴを目立つように配置することは,他のゴルフクラブ のシャフトにも頻繁に見られる(甲29,甲30の1〜5)表現であり,細長いシ\nャフトに文字を大書して目立たせる配置をすることの選択の幅は狭いから,ブラン ドロゴをトルネード模様の上に配置したことが個性的な表現とはいえない。\nよって,本件シャフトデザイン等に,創作的な表現は認められず,著作物性は認\nめられない。
控訴人は,本件シャフトデザイン等に著作物性が認められる場合であっても,複 製権等の侵害は主張せず,著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び著作者人 格権(同一性保持権)の侵害を主張するので,下記においては,念のため,仮に, 本件シャフトデザイン等に著作物性が認められるとした場合に,被告シャフトが本 件シャフトデザイン等を翻案したものであり,被控訴人が,控訴人の著作権(翻案 権,二次的著作物の譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害したといえ るか,について判断する。
・・・
上記1(2)アの認定事実に基づけば,仮に,本件シャフトデザイン等に著 作物性が認められるとした場合には,その本質的特徴は,赤と黒を基調にし,グレ ーをリングに用い,グリップ側に血液を象徴する赤,ヘッド側にカーボンを象徴す る黒を用いて,縞模様を構成する赤と黒の幅を徐々に変化させつつ,赤と黒とが馴\n染むぼかし部分を入れて,グリップ側からヘッド側へと人間の血液を象徴する赤色 部分が減少しカーボンを象徴する黒が増加していくことを具体的に表現した点にあ\nるものと認められる。
ウ これに対し,控訴人は,本件シャフトデザイン等の本質的特徴を以下のとおり主張する。 「シャフトのグリップ側の端を占める色を「色A」とし,ヘッド側の端を占める 色を「色B」とする。 シャフトには複数本のリングを等間隔に配置する。等間隔に配置されたリング間 を,色 A と色 B で塗り分け,当該2色の境目がリングと並行になるように色分けす る。リング間においては,シャフト全体で見た色の塗り分けとは逆に,グリップ寄 りに色Bを,ヘッド寄りに色Aが配置される。リング間における各色の割合である が,最もグリップ側に近いリング間は,色Aがその多くを占める。2番目にグリッ プ側に近いリング間は,色Aの占める割合が少し減り,色Bの割合が増える。3番 目にグリップ側に近いリング間は,さらに色Aが占める割合が減り,色Bの割合が 増える。これを繰り返し,最もヘッド側にあるリング間においては,色Bがほとん どの割合を占めることとなり,色Aが占める割合はわずかになる。 また,各リングのグリップ側に接する部分にはぼかし部分を入れる。ぼかし部分 の面積は,各リングそれぞれで異なっており,最もグリップに近いリング脇のぼか し部分が最も面積が大きく,ヘッド側に近いリングほどぼかし部分の面積は小さく なっていく。」 しかし,具体的な配色を捨象した,幅を変えながら縞模様が変化していくという 表現では,本件シャフトデザイン等において,人間の血液を象徴する赤とカーボン\nを象徴する黒をシャフトの地色として選択し,グリップ側からヘッド側にかけて徐々 に赤色部分が減少し黒色部分が増加していくという特徴的な表現が感得できない。\nしかも,配色を問わない上記控訴人の主張は,自身の制作意図とも矛盾しており, いずれにしても採用し得ない。
(2) 被告シャフトとの対比
ア 本件シャフトデザイン等の本質的特徴は上記(1)イのとおりであり,上記 1(2)ア(シ)で認定した被告シャフト対照表に係る色Aが赤,色B及びDが黒,色Cが\nグレーという配色になる。そうすると,1)全く同じ配色の被告シャフトはないから, 被告シャフトは,いずれも,本件シャフトデザイン等の本質的特徴である配色を備 えていない。また,2)本件シャフトデザイン等の色Aが赤であるのは,人間の血液 を象徴したものであるところ,被告シャフト1〜50(42〜46のMJカラーを 除く。),55〜68,73の色Aは白系,被告シャフト51〜54の色Aはシルバ ー系,被告シャフト74〜77,79〜81の色Aはグレー,被告シャフト42〜 46のMJカラー,82,83の色Aは黄色と,いずれも,血液をイメージしにく い色である。さらに,3)本件シャフトデザイン等の色B及びDは共に黒であり,黒 と彩度のみを異にするグレーを用いることによって,グリップ側からヘッド側へ連 続した印象を与える表現となっているものと解されるところ,被告シャフト5〜8,\n13,14,16〜19,61〜64(42〜46のMTカラー),65〜68,6 9〜72(42〜46のMJカラー),83,並びに被告シャフト9,10及び41 のブルーの色B及びD,並びに,被告シャフト5〜31,37〜64,69〜83 の色B及びCは,同系色ですらない異なる色である。 したがって,被告シャフトはいずれも,上記1)の特徴を備えないことに加え,被 告シャフト1〜4は上記2)の特徴を備えず,被告シャフト5〜31は上記2)及び3) の特徴を備えず,被告シャフト32〜36は上記2)の特徴を備えず,被告シャフト 37〜68は上記2)及び3)の特徴を備えず,被告シャフト69〜72は上記3)の特 徴を備えず,被告シャフト73〜77は上記2)及び3)の特徴を備えず,被告シャフ ト78は上記3)の特徴を備えず,被告シャフト79〜83は上記2)及び3)の特徴を 備えない。よって,被告シャフトはいずれも,本件シャフトデザイン等の本質的特 徴を直接感得させるとはいえない。 なお,被告シャフト78は,上記被告シャフト対照表の色Aが赤,色B及びDが\nメタリック黒及び黒であるから,本件シャフトデザイン等の表現上の本質的特徴の\n一部を備えているともいえる。しかし,被告シャフト78の色Cは,はっきりした 白であって,赤と黒の配色部分をくっきりと区切り,濃色である赤と黒を背景にリ ズミカルに配置されている印象があり,被告シャフト78全体の赤から黒へと徐々 に変化していくという動きを阻害しているから,血液を象徴する赤色部分がグリッ プ側からヘッド側へと減少し,カーボンを象徴する黒色部分がグリップ側からヘッ ド側へと増加していくというイメージを想起させる構成ではない。\nよって,被告シャフト78からは,本件シャフトデザイン等の表現上の本質的特\n徴を直接感得することはできない。
イ これに対して,控訴人は,被告シャフトは,色Aが色Bに遷移していく 描写がされているから,その表現には,本件シャフトデザイン等の本質的特徴が維\n持されており,直接感得できる,と主張する。 しかし,控訴人の上記主張は,本件シャフトデザイン等の表現上の本質的特徴を,\n上記第2,2(2)(控訴人の主張)アのとおりとらえることを前提としており,上記 (1)ウのとおり,その前提が誤っているから,控訴人の主張には,理由がない。
(3) 小括
よって,仮に,本件シャフトデザイン等に著作物性が認められるとしても,被告 シャフトは,本件シャフトデザイン等の表現上の本質的特徴を直接感得できるもの\nではないから,仮に,被告シャフトに創作性がある場合には,別個の著作物である こととなる。したがって,被控訴人による被告シャフト製造,頒布が,本件シャフ トデザイン等に係る控訴人の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)を侵害した とは認められない。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2016.12.28
平成28(ワ)11697 著作権侵害賠償等請求事件 民事訴訟 平成28年12月15日 東京地方裁判所(46部)
被告は言語の著作物である本件講演をインターネット上の配信サイトで配信 したものであるから,被告の行為は本件講演に係る各原告の公衆送信権を侵害 する行為に該当する。 これに対し,被告は,本件配信は「時事の事件の報道」(著作権法41条) に該当するため原告らの著作権が制限され,公衆送信権侵害は成立しない旨主 張する。そこで検討すると,まず,この点に関する被告の前記主張を前提とし ても,本件講演それ自体が同条にいう「時事の事件」に当たるとみることは困 難である。これに加え,同条は,時事の事件を報道する場合には,当該事件を 構成する著作物等を「報道の目的上正当な範囲内」において「当該事件の報道\nに伴って利用する」限りにおいて,当該著作物についての著作権を制限する旨 の規定である。本件配信は,約3時間にわたり本件講演の全部を,本件コメン トを付して配信するものであるから,同条により許される著作物の利用に当た らないことは明らかである。 したがって,本件配信は上記公衆送信権を侵害するものと認められる。
・・・
原告は上記各コメントが原告Aの名誉又は声望を害するものであると主張す る。そこで判断するに,前記前提となるび弁論の全趣旨によれば,被告による本件講演の利用方法は本件講演の映像及び音声をそのまま公衆送信するというものであり,被告による本件コメントは 本件配信が行われるインターネットの画面上で上記映像の脇に表示されるにと\nどまると認められる。また,「ラスボス」との表現については,「最後のボス」\nを表現すると一応解し得るものであるが,原告らはこれが悪意を込めた用語で\nあると主張するものの,一般的にそのような意味合いで用いられていると裏付 けるに足りる証拠を提出していない。一方,証拠(乙6)及び弁論の全趣旨に よれば,この表現は人の社会的評価を低下させる趣旨で使用されない場合もあ\nると認められるのであり,本件においても,前後の文脈及び別紙2記載のコメ ント内容に照らせば,原告Aの講演が本件講演会の見せ場であるという趣旨で 「ラスボス」との表現が使用されたと解する余地もある。さらに,被告による\n上記各コメント以外のコメントも原告Aの社会的評価を低下させるものである とは解し難い。そうすると,被告による本件講演の利用の方法が原告Aの名誉 又は声望を害するものであったと認めることはできないから,謝罪広告に関す る原告Aの請求は理由がない。
・・・
そこで,これにより原告らが被った財産的損害の額についてみるに,前記前 提となる事実に加え,証拠(甲1の1及び2,甲3〜5)及び弁論の全趣旨 によれば,本件配信は本件講演会の音声を主としており,本件配信に係る映 像は本件講演会の模様を認識できるものではないこと,原告Dの挨拶は約3 分,原告Cの挨拶は約10分であり,原告B及び原告Aの講演はそれぞれ約 1時間のものであり,その音声が全て配信されたこと,本件講演会の参加費 用は1人当たり1000円であり,被告はこれを支払って本件講演会に参加 したこと,本件配信は誰でも無料で視聴可能であるが,その総視聴者数は4\n37人であったこと,被告は本件配信の際,視聴者から配信時間を延長する ためのアイテムである「コイン」の提供を受けたのみであり,本件配信によ り経済的利益を得ていないこと,以上の事実が認められる。これらの事実を 総合すれば,本件講演の公衆送信権侵害による損害額は,原告A及び原告B につき各6万円,原告Cにつき1万円,原告Dにつき3000円と認めるの が相当である。なお,原告らは公衆送信権侵害による精神的損害の賠償も求めるが,本件の証拠上,上記損害額に加えて,原告らに賠償を認めるべき精神的損害が生 じたと認めることはできない。
2016.12.28
平成28(ネ)10010 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年12月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
以上のとおり,Crの濃度変動があるか否か不明であるだけではなく,さらに, その濃度変動の程度も何ら特定されていない球形の合金相(B)を含むターゲット は,当業者が本件発明2の課題を解決できると認識できる範囲のものということは できないから,Crの濃度変動の有無及びその程度を何ら特定しない球形の合金相 (B)を含む特許請求の範囲請求項2に記載された本件発明2は,発明の詳細な 説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。また,このような球形 の合金相(B)を含むターゲットが,当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。 したがって,本件発明2に係る請求項2の記載は,サポート要件を満たしている とはいえないから,本件発明2に係る特許は特許無効審判により無効にされるべき ものと認められる。
◆判決本文
関連事件です。こちらでは、請求項4はサポート要件を満たしていると判断されています。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.12.19
平成28(ネ)10060 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年12月14日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
以下によれば,敬晴会は,甲1契約の締結に当たり,信義則上,被控訴人に対し, 甲2発明が韓国において特許登録され得るものであるか否かに関する情報を調査・ 提供する義務(以下「本件情報提供義務」という。)を負うものと解される。
(ア) 前記1のとおり,甲1契約は,敬晴会が,被控訴人に対し,韓国において本 件皮膚再生医療技術を独占的に展開するために必要なノウハウ及び情報等を提供す るとともに,必要な知的財産権の実施を許諾(再実施許諾)するというものである から(第1条),実施許諾されるべき必要な知的財産権は,韓国において本件皮膚再 生医療技術を独占的に実施するために必要なものを指すと解される。 そして,甲1契約において,第1条を受けた第2条に甲2発明が挙げられている のであるから,甲2発明が上記の実施許諾されるべき必要な知的財産に含まれるこ とは,明らかである。さらに,甲2発明は,甲1契約において具体的に挙げられた 唯一の発明である上,本件皮膚再生医療技術に用いられる皮膚組織改善材等に係る ものであって,その内容(甲7の8参照)に照らしても,本件皮膚再生医療技術の 実施に当たり,当然に必要となるものと認められる。 そうすると,甲1契約の趣旨及び甲2発明の内容に照らし,韓国において,本件 ノウハウのみならず,甲2発明に係る技術を独占的に実施することができることは, 甲1契約の当然の前提であると解される。
(イ) そして,韓国における甲2発明に係る技術の独占的な実施は,同国において 甲2発明に係る特許権を取得することによって,可能となるものである。また,甲\n1契約の第2条には,「本基本契約において,『本件特許権等』とは,下記の特許権 及び甲(判決注・敬晴会)が今後所有権ないし実施権を取得する皮膚再生医療に関 する特許権のすべてを指す。」と記載された上で,甲2発明の出願番号が挙げられて おり,同記載内容から,甲2発明は,韓国において特許登録がされ得るものと理解 することができる。さらに,そもそも韓国において甲2発明に係る特許権を取得し 得ないことが明らかなのであれば,甲1契約によって同国における甲2発明の実施 の許諾を得る必要はない。 以上によれば,甲1契約は,甲2発明につき,韓国において特許取得のための手 続が採られ,特許登録がされる可能性のあるものであり,特許登録がされた場合に\nは,被控訴人においてその独占的実施許諾を受けられることを前提としていたもの と認められる。 そうすると,甲2発明が,韓国において特許登録され得るものかどうかに係る情 報(例えば,韓国における審査の進捗状況など)は,甲1契約の独占的実施の対象 となる権利に関するものであり,契約の重要な部分に当たるものであって,被控訴 人が甲1契約を締結するか否かを判断するに当たって必要とする情報であったもの ということができる。 (ウ) 一方,敬晴会は,甲1契約上,本件皮膚再生医療技術に関し,甲2発明を含 む名古屋大学が有する特許権に係る発明について,被控訴人に対し,再実施許諾を する立場にある。そうすると,甲2発明が韓国において特許登録され得るものであ るか否かは,甲1契約の対象となる独占的実施権に関する重要な情報であるから, 再実施許諾をする者としては,契約の相手方である被控訴人に対し,信義則上,上 記重要な情報を調査・提供する義務を負うものというべきである。
イ 敬晴会の本件情報提供義務違反について
前記1の認定事実によれば,名古屋大学が,本件国際特許出願につき,指定国と していた韓国において特許協力条約22条及び39条所定の期間内に国内移行手続 を行わなかったことから,同24条により,本件国際特許出願の効果は,韓国にお ける国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅し,甲2発明は,甲1契約 締結当時,既に韓国において特許登録を受けることができなくなっていた。 しかし,敬晴会は,これを代表する理事長である控訴人において,甲1契約の締\n結に当たり,上記のとおり甲2発明が韓国において特許登録を受けることができな くなっていたという事実を被控訴人に伝えなかったのであり,過失により,本件情 報提供義務を怠ったものと認められる。 そして,前記1の認定事実及び被控訴人代表者の供述(乙5)によれば,被控訴\n人は,1)名古屋大学が,同大学において開発した甲2発明を含む本件皮膚再生医療 技術につき,韓国内において独占的な権利を有し,あるいは,そのような権利を取 得するための手続を採り得る立場にあること及び2)敬晴会が,本件皮膚再生医療技 術に係る再実施許諾権を有しており,被控訴人に対して再実施許諾をすることを前 提として,甲1契約を締結したのであり,上記のとおり,甲2発明は,韓国におい て特許登録を受けることができなくなっていた事実を知っていれば,甲1契約を締 結しなかったものと認められる。 以上によれば,敬晴会が過失により本件情報提供義務を怠り,上記事実を被控訴 人に伝えなかった結果,被控訴人は,甲1契約を締結するに至ったものであるから, 敬晴会は,本件情報提供義務違反により,被控訴人に生じた損害を賠償する義務を 負う。
2016.12.19
平成28(ネ)10067 楽曲演奏禁止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年12月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これに対し,控訴人は,原告楽曲と被告楽曲のBPM(テンポ)がほぼ同 じである点は,両楽曲のいかなる相違点をも打ち消すほどに,同一性を示す 根拠となる旨主張する。 しかし,楽曲についての複製,翻案の判断に当たっては,楽曲を構成する\n諸要素のうち,まずは旋律の同一性・類似性を中心に考慮し,必要に応じて リズム,テンポ等の他の要素の同一性・類似性をも総合的に考慮して判断す べきものといえるから,原告楽曲と被告楽曲のテンポがほぼ同じであるから といって,直ちに両楽曲の同一性が根拠づけられるものではない。そして, 上記で述べたとおり,両楽曲は,比較に当たっての中心的な要素となるべき 旋律において多くの相違が認められることから,被告楽曲から原告楽曲の表\n現上の特徴を直接感得することができるとは認め難いといえる。他方,両楽 曲のテンポが共通する点は,募集条件により曲の長さや歌詞等が指定されて いたことによるものと理解し得ることから,楽曲の表現上の本質的な特徴を\n基礎づける要素に関わる共通点とはいえないのであって,上記判断を左右す るものではない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。 また,控訴人は,両楽曲が実質的に同一の楽曲であることは,両楽曲の歌 と伴奏をそれぞれ入れ替えたもの(甲32及び33)が聴感上違和感なく再 生できることから明らかであるとも主張するが,そのようなことが,両楽曲 の同一性を直ちに根拠づけるものでないことは明らかであるから,甲32及 び33によっても,上記判断が左右されるものではない。 その他にも控訴人は,原告楽曲と被告楽曲が実質的に同一の楽曲である旨 をるる主張するが,以上説示したところに照らし,いずれも採用することが できない。
2016.12.14
平成28(行ケ)10093 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年11月7日 知的財産高等裁判所
原告は,再使用許諾契約書は,1)提出された写しの契印の印影が各ペー ジで1つずつであり,しかも半分にすぎず,押印原本も提示されていない,2)再使 用許諾契約書が原使用許諾契約書に基づくものであれば,原使用許諾契約書が先に 作成されるはずだが,契約日は再使用許諾契約書が原使用許諾契約書に先行してお り,契約期間も,原使用許諾契約書が1年間であるのに対し,再使用許諾契約書は 半年間であることとは不自然である,3)原使用許諾契約書で被告がキリンホールデ ィングスに対して再使用許諾を認めた商標と,再使用許諾契約書でキリンホールデ ィングスがキリン協和フーズに使用許諾した商標とが一致せず不自然である,4)原 使用許諾契約書における使用許諾対象商標「KIRIN」に「麒麟」「キリン」が含 まれるとすることは,VIマニュアルの「KIRIN/キリン/麒麟」の使用区分 についての記載と整合しないし,再使用許諾契約書において「KIRIN」等を態 様の一部に含む商標及び「KIRIN」等と類似する商標について使用許諾するこ とは,VIマニュアルの「KIRIN」を変形したものの使用禁止に反する,と主 張する。 しかし,1)契約書の契印を,契約当事者全員が必ず行うという商習慣を認定する に足る証拠はなく,審判手続において提出する証拠の写しを作成する際,契印のみ が存在する契約書用紙の裏のコピーを省略することも,不合理ではない。 また,2)原使用許諾契約書の契約締結日について,被告は,平成25年12月1 日時点における使用許諾対象商標,再使用許諾先及び対価の確認,確定手続を当事 者間で完了した段階で契約締結したため,締結日が同年12月20日となったと主 張しており,そのような主張内容は不合理ではないことに加え,キリン協和フーズ による本件商標を含む被告所有商標の使用が,三菱商事への株式譲渡前から継続さ れていたのであって,新たに被告らの有する商標の使用を開始させるものではない ことからすれば,契約締結日が原使用許諾契約書と再使用許諾契約書とで異なるこ とは不自然ではない。原使用許諾契約書は,再使用許諾契約書の根拠となるもので あり,前者が後者より契約期間が長いことは,不合理ではない。 さらに,3)原使用許諾契約書と再使用許諾契約書との間で,許諾対象商標に文言 上の齟齬はあるが,許諾対象商標に「麒麟」「キリン」及び「きりん」が含まれる再 使用許諾契約書が作成された後に原使用許諾契約書が作成された上で,その許諾対 象商標が文言上「KIRIN」等となっていること,被告,キリンホールディング ス及びキリン協和フーズとの間で,許諾対象商標についての争いがあったとは認め られないことからすれば,原使用許諾契約書の「KIRIN」には,「麒麟」「キリ ン」及び「きりん」が含まれるものと被告及びキリンホールディングスとが合意し ていたものと解することができる(甲54参照)。
◆判決本文
◆関連事件です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2016.12.14
平成28(行ケ)10054 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成28年11月7日 知的財産高等裁判所
(ウ) 透明の面板を手摺の構成部分に使用する場合において,下を白く着色\nして透明度を低く,上の透明度を高く,下から上にグラデーションにより透明度を 高く変化させることは,公然知られた模様又は色彩であり,これを合わせガラス面 板の模様又は色彩として手摺の構成部分である合わせガラス面板に付することは,\n当業者にとってありふれた手法であることは,前記(1)ウ(イ)のとおりである。 また,着色された部分の色調や透明度をどの程度とするか,透明度がグラデーシ ョンにより変化している部分をどの位置にするか,透明度がグラデーションにより 変化する幅をどの程度にするかについては,構成比率を変更するものにすぎず,こ\nれらの比率を,前記第2の2の甲1の透過率を説明する参考図や使用状態を示す参 考図のようにすることは,当業者にとってありふれた設定であることも,前記(1)ウ (イ)のとおりである。
そして,前記(イ)によれば,平板の合わせガラスを着色するに当たり,合わせガラ スを構成する2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層のみに着色し,2枚のガラ\nス板をその全面において透明にすることは,当業者にとってありふれた手法である。 したがって,仮に,グラデーション模様の配されている部位が,ガラス面板であ る合わせガラスを構成する2枚のガラス板の間の中間膜ないし樹脂層に特定されて\nいることを前提としても,本件部分意匠は,意匠登録出願前に当業者が日本国内に おいて公然知られた形状と模様又は色彩の結合に基づいて容易に創作をすることが できたものといえ,意匠法3条2項に該当する。
関連カテゴリー
>> 創作容易性
>> 部分意匠
>> ピックアップ対象
2016.12.14
平成28(行ケ)10047 審決取消請求事件 実用新案権 行政訴訟 平成28年10月31日 知的財産高等裁判所
ウ 以上によれば,甲1考案は,以下のとおり,認定すべきである(なお,下線部は,審決の認定した甲1考案と相違する箇所である。)。「 高電圧を流した針電極28から電子を発生させるイオン化室23の先端に,内部に3重電極33が配設され,コイル18が巻かれたイオン回転室24を設け,イオン化室23の中に流し込まれた酸素ガスを励起して,O2+,O2(W),O(1D),O,O2(b1Σg+),O−,O2(a1Δg),O−を生成し,イオン回転室24において,生成したO−に対し,3重電極33及びコイル18によって発生した回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え,酸素分子と衝突させてオゾンを生成する酸素ガスのオゾン発生装置。」
エ したがって,審決の甲 1 考案の認定には,誤りがある。
・・・
(3) 以上によれば,本件考案と甲1考案の一致点及び相違点は,以下のとおり であると認められる。
【一致点】
高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管を有し,活性酸素種を生成さ せることができる装置。
【相違点】
本件考案は,空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性 酸素種を生成させることができる空気の電子化装置であって,励起の手段が電磁コ イルであるのに対して, 甲1考案は,イオン化室23に流し込まれた酸素ガスを励起して生成したO−に 対し,イオン回転室24において,3重電極33及びコイル18によって発生した 回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え,酸素分子と衝突させてオゾンを生成す る酸素ガスのオゾン発生装置である点。
・・・
イ 前記アのとおり,甲2及び甲3(甲45)のいずれにも,空気又は酸素 ガスに電界と磁界を同時に印加してオゾン等を発生させる装置が記載されているこ とが認められるものの,磁界のみを単独で印加することは記載されていない。
(2)ア 前記(1)イによれば,甲2又は甲3(甲45)に基づき,磁界のみを単 独で印加してオゾン等を発生させるという周知技術は認められない。 そうすると,甲1考案と甲2及び3から認められる周知技術を組み合わせても, 「回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え」るという構成が,磁界のみをかけて回\n転運動を与えるという構成になるとは認められない。\n
・・・・
エ 以上のとおりであって,甲1考案において,励起の対象が「酸素ガス」 であり,その励起手段が「3重電極」及び「コイル」であるという構成に替えて,\n励起の対象が「空気中の酸素分子」であり,その励起手段が「電磁コイル」である という構成を適用することは,動機付けを欠き,本件考案1は,甲1考案並びに甲\n2及び3に記載された周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすること ができたとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2016.12.14
平成28(行ケ)10143 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年12月8日 知的財産高等裁判所(3部)
上記1の認定に係る各事実によれば,原告は,平成8年7月頃から共同 事業者として本件事業に関与し,平成18年11月以降は本件委託契約に基 づき受託者として引き続き関与していたところ,平成25年2月時点で,遅 くとも平成26年12月31日までに本件委託契約が終了し,本件事業に係 る業務を東長寺に引き継ぐべき義務を負ったにもかかわらず,本件委託契約 期間中である平成26年2月12日に本件商標の商標登録出願をし,同年1 2月19日に設定登録を受けたものである。 また,本件事業は,「縁の会」会員に対する個人墓の販売終了により事業 が終了するものではなく,会員に対しその生前から死後に至るまで,様々な 宗教的行為等を継続的に提供するものであることに鑑みると,たとえ個人墓 の販売が完了したとしても,東長寺が本件事業の標識として引用商標を引き 続き使用し続ける必要があることは明らかであるし,仮に原告が本件商標の 設定登録をすることにより東長寺が引用商標を使用し得なくなると本件事業 の継続に重大な支障を来すおそれがあることも,容易に予想されるところで\nある。そして,上記のとおり本件事業に関わり,その内容等を熟知している 原告にとっても,これら点は当然予見し得る事情といってよい。\nしかも,原告が本件商標の設定登録を受けることにつき原告と東長寺と の間に合意があったことを裏付けるに足りる証拠はなく,むしろ遅くとも平 成26年5月頃には原告による本件商標の登録出願や他の宗教法人(常在寺) と組んでの「縁の会」の語を用いた類似事業の展開等を巡って東長寺との間 に紛争が生じていたことがうかがわれる(甲106,107)。また,原告 が本件商標権を設定登録し,その使用権を専有することになった場合,同一 商標である引用商標の使用には当然問題が生じ得ることになるのであるから, 本件事業の受託者であり,かつ,本件事業を東長寺に円滑に移行させる旨を 約束していた原告としては,設定登録に当たり,東長寺に対し,引用商標の 使用を許諾するなど,東長寺の地位に不安が生じないような配慮をするのが 当然であったといえるはずであるにもかかわらず,そのような配慮がされた 形跡は認められないのであって(甲107は,日付も入れられていない不完 全な文書であり,これによって引用商標の使用の許諾がされたとは認め難 い。),この点も,原告の背信性を裏付けるものであるといわざるを得ない。 これらの事情に加え,前記のとおり,本件商標と引用商標が同一の商標 といえること,本件商標の登録出願時に既に引用商標が東長寺の展開する本 件事業に係る標章として日本国内における周知性を獲得していたことを併せ 考慮すると,原告は,引用商標がいまだ商標登録されていないことに乗じ, これに化体された信用及び顧客吸引力にただ乗りし,他の宗教法人と展開す る本件事業類似の事業に本件商標を使用することで利益を得,又は本件事業 の継続に支障を生じさせて東長寺に損害を生じさせることを目的として本件 商標を使用するものと合理的に推認される。このことは,原告が真光寺とと もに本件事業類似の「真光寺縁の会」の事業を展開し,これについて東長寺 が了承していたことがうかがわれること(甲12の1〜4,12の8及び9, 12の12〜14,12の16,12の19,12の21〜24,12の2 6,12の28,12の30及び31,乙22,23,25,34,74, 75)を考慮しても異ならない。上記のとおり,原告が常在寺とともに展開 する「常在寺縁の会」の事業を巡っては東長寺と原告との間で紛争を生じて いると見られることに鑑みると,原告が引用商標を用いて本件事業に類似す る事業を展開することを東長寺が広く許容していたとは考え難いからである。 したがって,原告は,不正の目的をもって本件商標を使用するものと認 められる。
(2) これに対し,原告は,不正の目的はないとしてるる主張する。 しかし,原告が,東長寺との合意すなわち本件共同事業契約ないし本件 委託契約に基づき広報・広告活動を行い,その費用を支出し,また,本件事 業における会員組織の事務局の管理運営等を担っていたとしても,それ自体 は本件共同事業契約及び本件委託契約に基づく原告の債務の履行にすぎず, 本件商標の登録出願時及び設定登録時における原告の不正の目的の存在に関 する上記認定を覆すべき事情とは必ずしもいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.12.14
平成27(ワ)12415 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年12月2日 東京地方裁判所(40部)
(1) 本件発明2における「緩衝剤」は,添加されたシュウ酸またはそのアルカ リ金属塩をいい,オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「緩衝 剤」には当たらないと解することが相当である。理由は以下のとおりである。 (2)ア 化学大事典2(乙13)によれば,「緩衝剤」とは,「緩衝液をつくる ために用いられる試薬の総称」をいうものとされている。そして,広辞苑 第六版によれば,「試薬」とは「実験室などで使用する純度の高い化学物 質」であるところ,解離シュウ酸が「純度の高い化学物質」である「試薬」 に当たるとは考えがたいから,解離シュウ酸は一般的な意味で「緩衝剤」 とはいえないというべきである。
イ 次に,本件明細書2の段落【0022】には,「緩衝剤という用語は, 本明細書中で用いる場合,オキサリプラチン溶液を安定化し,それにより 望ましくない不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオD ACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸 性または塩基性剤を意味する。」と記載されている。 上記記載において,「緩衝剤」は,「酸性または塩基性剤」であると定 義されているが,広辞苑第六版によれば,「剤」とは「各種の薬を調合す ること。また,その薬。」を意味するから,「酸性または塩基性剤」は, 酸性または塩基性の各種の薬を調合した薬を意味すると考えることが自然 であるところ,解離シュウ酸は,「各種の薬を調合した薬」に当たるとは いえない。 ウ そして,本件明細書2の段落【0013】後段ないし【0016】には, オキサリプラチンが水性溶液中で分解してジアクオDACHプラチンを不 純物として生成することが記載されているが,オキサリプラチンが分解す ると,次の式のとおり,シュウ酸イオンとジアクオDACHプラチンが生 じる。また,証拠(乙39)によれば,分解により生じたシュウ酸イオン は,一部がプロトン化されてシュウ酸又はシュウ酸水素イオンになること が認められる。 したがって,オキサリプラチンの分解によりシュウ酸イオン等が生じた ということは,すなわちオキサリプラチン水溶液において不純物が生じた ことを意味するから,仮にオキサリプラチンの分解により生じた解離シュ ウ酸が「緩衝剤」に当たるとすると,緩衝剤が防止すべき分解により生じ たものが緩衝剤に当たるということになってしまい,上記イの「望ましく ない不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプ ラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得る」という緩衝剤の定 義と整合しない。 エ 前記3(2)のとおり,本件発明2は,乙14発明よりも不純物が有意に少 ない,より安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とす るものである。 ところが,本件明細書2をみると,実施例18において生成される不純 物の量と比較して,シュウ酸を添加した実施例(ただし,実施例1及び8 を除く。なお,実施例1及び8は,後記(3)エのとおり,本件発明2の技術 的範囲に含まれる実施例ではない。)において生成される不純物の量は有 意に少ないことが示されている。ここで,実施例18は,豪州国特許出願 第29896/95号(1996年3月7日公開)に記載されている水性 オキサリプラチン組成物であるが,上記出願は,乙14発明に対応するも のであるから,実施例18は乙14発明と実質的に同一であると推認され る。 したがって,本件発明2は,乙14発明とは異なり,オキサリプラチン 溶液組成物に緩衝剤を添加したことによって,不純物が少なく,より安定 な溶液組成物を提供することができたことを特徴とする発明と考えるのが 自然である。
オ 本件明細書2には,実施例1ないし17については,シュウ酸が付加さ れていることが明記されている。また,本件明細書2(段落【0039】, 【0041】〜【0045】,【0047】,【0064】)では,実施 例1ないし17について,添加されたシュウ酸のモル濃度が記載されてい るが,解離シュウ酸を含むシュウ酸のモル濃度は記載されていない。 さらに,本件明細書2は,「緩衝剤」である「シュウ酸」に,オキサリ プラチンが分解して生じた解離シュウ酸が含まれることを示唆する記載は ない。 この点に関して原告は,構成要件2Gの数値範囲の下限(5×10−5M)\nが,本件明細書2記載の実施例1及び8で示された下限(1×10−5M) よりも大きいことをもって,請求項1は解離シュウ酸を考慮したものであ ると主張するが,本件明細書2には,1×10−5Mのシュウ酸を添加した オキサリプラチン溶液中のシュウ酸イオン等のモル濃度がどの程度になる かに係る記載は何ら存在しておらず,原告の上記主張は裏付けを欠く独自 の見解というほかない。 以上からすると,本件明細書2の記載においては,解離シュウ酸につい ては全く考慮されておらず,緩衝剤としての「シュウ酸」は添加されるも のであることを前提としているというべきである。 カ また,本件明細書2における実施例18(b)に関する記載をみると,「比 較のために,例えば豪州国特許出願第29896/95号(1996年3 月7日公開)に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を,以 下のように調製した」(段落【0050】前段),「比較例18の安定性」 「実施例18(b)の非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物を,40℃で 1ヶ月間保存した。」(段落【0073】)といった記載がある。そして, 前記エのとおり,豪州国特許出願第29896/95号(1996年3月 7日公開)は乙14発明と実質的に同一であるから,上記各記載を総合す ると,実施例18(b)は,「実施例」という用語が用いられている部分 が多いものの,その実質は本件発明2の実施例ではなく,本件発明2と比 較するために,「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」,すなわち,緩 衝剤が用いられていない従来既知の水性オキサリプラチン組成物を調製し たものであると認めるのが相当である。 そうすると,本件明細書2において,緩衝剤を添加しない水性オキサリ プラチン組成物に関する実施例18は,本件発明2の実施例ではなく,比 較例として記載されているというべきである。 キ さらに,証拠(乙64,65)によれば,本件特許2の出願人が,本件 特許2に対応する米国特許出願(乙64)について,米国特許庁に提出し た意見書(乙65)において,「甲等の水溶液組成物(本願21頁に記載 されている甲等の組成物(比較例18)についての安定性データを参照) において見出されるよりも有意に少ない量でこのような不純物を生成する オキサリプラチンのより安定な溶液組成物が,オキサリプラチンの溶液組 成物に有効安定化量の緩衝剤を加えることにより得られることを,出願人 は予想外にも見出したのである。」などと記載し,緩衝剤が添加されるも\nのであること及び実施例18が比較例であることを前提とした主張をして いたことが認められる。 また,証拠(甲36)によれば,本件特許に対応するブラジル特許出願 に関し,出願人が,ブラジル特許庁に提出した拒絶処分に対する不服申立\nてにおいて,「本願発明にあるシュウ酸を緩衝剤として加えれば,不純物 が発生しないということである。」と,緩衝剤を添加する旨の主張をして いたことが認められる。 これらのことは,本件発明2においても,緩衝剤とは添加されたものに 限られると解されることの裏付けとなる事実であるというべきである。
◆判決本文
関連事件(同一特許、異被告)です。
◆平成27(ワ)29158
同一特許の別訴事件で、1審(平成27(ワ)12416号)では技術的範囲内と判断されましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.12.14
平成28(ワ)16340 商標権侵害差止等反訴請求事件 商標権 民事訴訟 平成28年11月24日 東京地方裁判所
E は,Bの死亡後も反訴被告各標章の使用を継続し,平成6年な いし平成7年までの間,複数の極真関連標章について商標登録出願を し,自己名義の商標登録を受けた。 (イ) C及びBの生前に極真会館に属していたその他の者らは,平成1 4年,E を被告として,空手の教授等に際して極真関連標章を使用す ることにつき,E の商標権に基づく差止請求権が存在しないことの確 認等を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同庁同年(ワ)第10 18号)。 同裁判所は,E の上記商標権の行使が権利濫用であるとして上記不 存在確認請求を認容し,その控訴審である大阪高等裁判所も,平成1 6年9月29日,同旨の理由により E の控訴を棄却した。 (ウ) D及びBの生前に極真会館に属していたその他の者らは,平成1 4年,E を被告として,空手の教授等に際して極真関連標章を使用す ることにつき,E の商標権に基づく差止請求権が存在しないことの確 認等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した(同庁同年(ワ)第16 786号)。 同裁判所は,平成15年9月29日,E の上記商標権の行使が権利 濫用であるとして上記不存在確認請求を認容した。 (エ) 反訴原告Aは,平成16年1月15日,E が商標登録を受けた極 真関連商標の一部について無効審判を請求したところ,特許庁は,E の受けた商標登録が商標法4条1項7号に反するものであるとして, 同年9月22日付けで登録を無効とするとの審決をした。これに対し, E は,上記審決の取消を求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起した が(同庁平成17年(行ケ)第10028号),同裁判所は,平成18 年12月26日,E の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。
(2) 前記前提事実及び上記認定事実を踏まえ,反訴原告らの請求が権利濫用 に当たるか否かを検討する。
ア 本件各商標に類似する反訴被告各標章は,前記第2の1(2)ウのとお り,遅くともBの死亡した平成6年4月26日から現在に至るまで,空 手及び格闘技に関心を有する者の間において極真会館又はその活動を表\nすものとして広く知られているところ,このような反訴被告各標章の周 知性及び著名性の形成,維持及び拡大に対しては,上記(1)認定事実ア, イ及びエのとおり,Bの生前・死後を通じ,長年にわたって極真空手の 教授や空手大会の開催等を行ってきたB及びBから認可を受けたCらを 含む極真会館の支部長らの多大な寄与があったと認められる。 他方,反訴原告らは,極真関連標章である本件各商標に係る商標権を 取得して極真空手の教授等を行っている。しかしながら,Bは後継者を 公式に指名することなく死亡し ているところ(上記(1)認定事実ウ (ア)),極真会館において世襲制が採用されていたこともうかがわれず (なお,上記(1)認定事実ア(イ)のとおり,規約には館長や総裁の地位 の決定や承継に関する定めはない。),他にBの相続人である反訴原告 Aを極真会館におけるBの後継者であると認めるに足る証拠はない。そ うすると,反訴原告Aにより設立された反訴原告会社は,極真会館の分 裂後にCらにより設立された反訴被告と同様,極真会館を称して極真空 手の教授等を行う複数の団体の一つにすぎないというべきである。 さらに,反訴原告らは,平成6年4月26日のBの死後,Cらやその 他の極真会館関係者らが極真関連標章を付して極真空手の普及活動を行 ってきたことを長年にわたり認識していたにもかかわらず,早期に本件 各商標に係る商標登録出願を行っていないのであって(反訴原告らが同 商標登録出願を行ったのは,前記第2,1(3)のとおり,平成15年以 降である。),同出願を行わなかったことに合理的な理由があったとも 認められない(これに対し,反訴原告らは,本件各商標の登録に先立ち, E の登録商標の抹消及びBの遺言が無効であることを明らかにする手続 が必要であった旨主張するが,反訴原告らの商標登録出願のためにそう した手続が必要であったとは認めることができない。かえって,E の商 標が抹消された時期は,前記第2の1(3)及び上記(1)のカ(エ)のとおり, 少なくとも反訴原告らの本件商標1〜5の各出願日より後の日であるし, また,前記第2の1(3)及び上記(1)ウ(ウ)のとおり,反訴原告らの本件 各商標の各出願日は,いずれもBの遺言が無効であることが確定した後, 少なくとも6年以上が経過した後の日であって,反訴原告らの上記主張 は,このような客観的経過とも整合しない。)。 こうした事情を総合考慮すると,反訴原告らが反訴被告に対し,本件 各商標権に基づき,極真関連商標である反訴被告各標章の使用を禁止す ることは権利の濫用に当たると解すべきである。
イ これに対し,反訴原告らは,1)反訴原告Aが極真関連標章の主体たる 地位を承継した,2)Cらは,Bの生前,Bの許諾を得て既に周知性・著 名性を獲得していた極真関連商標を使用していたにすぎず,Bの死後に は,所属していた一般社団法人国際空手道連盟極真会館とトラブルを起 こして,同会館を除名又は退会となっている,3)極真関連標章の周知性 及び著名性の維持等に対するCらの寄与があったとしても,Cらとは別 の権利義務主体である反訴被告が反訴被告標章を使用して良いことには ならないと主張する。 しかしながら,上記1)については,Bは生前,極真関連標章に係る商 標登録出願をしていないから,極真関連標章の主体たる地位が相続の対 象となる財産権であるとはいえない。また,周知に至った極真関連標章 があったとしても,それは反訴被告各標章と同様に極真会館又はその活 動を示すものとして周知になったものというべきであるから,少なくと もB個人ではなく極真会館の総裁兼館長としてのBに帰属する法的利益 であると解すべきであるところ,上記アのとおり,反訴原告Aを極真会 館におけるBの後継者であるとはいえないのであって,反訴原告Aが, 極真関連標章の主体たる地位を承継したと認めることはできない。 次に,上記2)については,Cらが極真会館の支部長に就任した時点で 反訴被告各標章が既に周知性・著名性を獲得していたと認めるに足る証 拠はなく,かえって,上記(1)認定事実ア,イ及びエのとおり,反訴被 告各標章の周知性及び著名性の形成,維持及び拡大について,Bのみな らずCらを含む支部長らの多大な寄与があったことが明らかである。な お,Cらは,Bの死後,反訴原告Aと対立し,所属していた団体を除名 又は退会となったことが認められるが(甲75,乙2),このことが直 ちにCらの上記寄与を否定する事情であるとは認め難い。 さらに,上記3)については,上記(1)エ(イ)のとおり,反訴被告がC らによって設立された団体であること,Cらが反訴被告の理事長及び理 事を務めるとともに,Cらが従前運営していた道場も反訴被告に加盟し ていることなどに照らせば,反訴被告は,Cらの運営に係る道場及び同 道場における空手教授等の活動についてもこれを承継したものと認めら れる。そうすると,Cらと反訴被告が別の権利義務主体であることが, 直ちに上記判断を左右するものではない。
2016.12.14
平成27(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年12月6日 知的財産高等裁判所
特許法36条4項1号は,明細書の発明の詳細な説明の記載は,「その発 明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすること ができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定める。\nその趣旨は,特許制度が,発明を公開する代償として,一定期間発明者に当 該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであることに鑑み,その制 度趣旨が損なわれることがないよう,発明の詳細な説明に当該請求項に係る 発明について当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載を求めるとした\n点にある。 そして,特許法上の実施とは,1)物の発明にあっては,その物の生産,使 用等をする行為であり,2)物を生産する方法の発明にあっては,その方法に より生産した物の使用等をする行為であるから(特許法2条3項1号,3号), 実施可能要件を満たすためには,それぞれ,明細書及び図面の記載並びに出\n願当時の技術常識に基づき,当業者が,1)当該物を生産できかつ使用できる ように具体的に記載すること,2)当該方法により物を生産できかつ使用でき るように具体的に記載することが必要である。 本件訂正発明は,同1,3,5,7,8が炭酸飲料という物の発明であり, 同9が炭酸飲料の製造方法という物の生産方法に関する発明であるから,こ れらの発明が実施可能要件を満たすためには,それぞれ,上記1)又は2)を満 たす必要がある。
(2) かかる実施可能要件に関し,原告は,「可溶性固形分」,「高甘味度甘味\n料によって付与される甘味の全量」及び「甘味量」の技術的意義が本件訂正 明細書の記載から把握できず,また,甘味の相対比が不明確であるため,甘 味の相対比に基づいた本件訂正発明における「全甘味量」,「高甘味度甘味 料によって付与される甘味の全量」及び「スクラロースによって付与される 甘味量」の数値範囲も不明確であって,そのような不明確な数値範囲の技術 的意義も理解できないため,実施例で用いられている甘味料以外の甘味料を 使用して,植物成分を10〜80重量%,及び炭酸ガスを2ガスボリューム より多く含む炭酸飲料を調製する場合に,甘味料をどの程度の量添加すれば, 「植物成分由来の重い口当たりと炭酸ガスに起因する苦味や刺激を軽減」し た炭酸飲料が得られるのか不明であるから,本件訂正発明を実施する際に, 本件訂正明細書の記載及び本件出願時の技術常識を考慮しても,当業者に期 待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とするものであり, 実施可能要件が満たされていないと主張する。\n(3) そこで検討するに,まず,本件訂正発明の「砂糖甘味換算」及び「砂糖甘 味換算量」という文言の意味が不明確であるとはいえず,本件訂正発明にお ける砂糖甘味換算量は,必要に応じて,換算又は測定可能なものといえるこ\nとは,前記1(取消事由5)で検討したとおりである。 また,植物成分,炭酸ガス及び可溶性固形分の含量,甘味量,並びに高甘 味度甘味料によって付与される甘味の全量については,それぞれの数値範囲 を逸脱した場合に,本件訂正発明の課題が解決できない旨が本件訂正明細書 に十分記載されており,換言すれば,それらの数値範囲内であれば,当業者\nは,本件訂正発明の課題が解決できると理解するものといえ,また,そのよ うな理解を妨げるような本件出願当時の技術常識があったとは認められない こと,他方で,スクラロースによって付与される甘味量については,その数 値範囲を逸脱した場合に,本件訂正発明の課題が解決できないことまでが本 件訂正明細書に記載されているわけではなく,単に,その数値範囲が好まし い旨が本件訂正明細書に記載されているのみであるが,この記載に接した当 業者は,その数値範囲を少々逸脱した場合でも本件訂正発明の課題が解決で きるであろうと理解するといえること,換言すれば,その数値範囲内であれ ば,当業者は,本件訂正発明の課題が当然解決できると理解するといえ,ま た,そのような理解を妨げるような本件出願当時の技術常識があったともい えないことは,前記4(取消事由3)で検討したとおりである。 そして,本件出願時の技術常識からみて,本件訂正発明の炭酸飲料を調製 するに当たり,果物又は野菜の搾汁を10〜80重量%の割合とすること(請 求項1の構成要件(1)),炭酸ガスを2ガスボリュームより多くすること(同 (2)),全甘味量を砂糖甘味換算で8〜14重量%とすること(同(4)),高 甘味度甘味料によって付与される甘味の全量を,砂糖甘味換算で全甘味量の 25重量%以上とすること(同(6)),全ての高甘味度甘味料によって付与さ れる甘味の全量100重量%のうち,スクラロースによって付与される甘味 量を,砂糖甘味換算量で50重量%以上とすること(同(7))自体が,当業者 にとって困難なことであるとは認められず,可溶性固形分含量を屈折糖度計 で測定して4〜8度のものとすること(同(3))も,当業者にとって困難な操 作であるとは認められない。 さらに,前記のとおり,本件訂正明細書には,実施例1として,ぶどう果 汁含有量50重量%,炭酸ガス3.0ガスボリューム,スクラロース0.0 065重量%,可溶性固形分含量5.1度の「グレープ炭酸飲料」を,実施 例2として,りんご果汁,レモン果汁及び人参の搾汁を合わせて31重量%, 炭酸ガス2.5ガスボリューム,スクラロース0.0075重量%及びアセ スルファムカリウム0.0035重量%,可溶性固形分含量4.5度の「果 汁入り炭酸飲料」を,実施例4として,リンゴ果汁33重量%,炭酸ガス2. 6ガスボリューム,スクラロース0.0067重量%,可溶性固形分含量6. 0度の「アップル炭酸アルコール飲料」を,それぞれ調製したことが,具体 的に記載されている(前記1(1)ス〜ソ)。また,本件訂正明細書には,甘味\n料について多数の例示があるとはいえ(同ケ),スクラロースと組み合わせ る高甘味度甘味料について具体的に例示されており(同)コ),搾汁とすべき 果物や野菜についても具体的に例示されている(同カ)。 以上を考慮すれば,本件訂正発明の(方法で)炭酸飲料を調製するに当た り,当業者が特段の困難な操作を要するとは認められず,また,その調製に 当業者の過度の試行錯誤を要するとも認められない。 よって,当業者は,本件訂正発明の(方法で)炭酸飲料を作ることができ るというべきであり,「(当該方法により)物を生産でき…る」の要件を満 たすといえる。
(4) また,そのようにして作られた本件訂正発明の数値範囲を満たす炭酸飲料 は,本件訂正発明の課題を解決する,すなわち,果汁等の植物成分と炭酸ガ スの両者を含有する飲料であって,植物成分の豊かな味わいと炭酸ガスの爽 やかな刺激感(爽快感)をバランス良く備えた植物成分含有炭酸飲料である といえる一方,そのような理解を妨げるような本件出願当時の技術常識があ ったとも認められない。 よって,本件訂正発明の数値範囲を満たす炭酸飲料は,技術上の意義のあ る態様で使用することができるというべきであり,「物を…使用できる」の 要件も満たすといえる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> 数値限定
>> ピックアップ対象
2016.12.14
平成28(ネ)10018 不正競争差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成28年11月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
不正競争防止法1条は,「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確 な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置 等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と定め,同 法2条1項3号は,「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な\n形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展 示し,輸出し,又は輸入する行為」を不正競争と定めている。 不正競争防止法が形態模倣を不正競争であるとした趣旨は,商品開発者が商品化 に当たって資金又は労力を投下した成果が模倣されたならば,商品開発者の市場先 行の利益は著しく減少し,一方,模倣者は,開発,商品化に伴う危険負担を大幅に 軽減して市場に参入でき,これを放置すれば,商品開発,市場開拓の意欲が阻害さ れることから,先行開発者の商品の創作性や権利登録の有無を問うことなく,簡易 迅速な保護手段を先行開発者に付与することにより,事業者間の公正な商品開発競 争を促進し,もって,同法1条の目的である,国民経済の健全な発展を図ろうとし たところにあると認められる。 ところで,不正競争防止法は,形態模倣について,「日本国内において最初に販売 された日から起算して3年を経過した商品」については,当該商品を譲渡等する行 為に形態模倣の規定は適用しないと定めるが(同法19条1項5号イ),この規定に おける「最初に販売された日」が,「他人の商品」の保護期間の終期を定めるための 起算日にすぎないことは,条文の文言や,形態模倣を新設した平成5年法律第47 号による不正競争防止法の全部改正当時の立法者意思から明らかである(なお,上 記規定は,同改正時は同法2条1項3号括弧書中に規定されていたが,同括弧書が 平成17年法律第75号により同法19条1項5号イに移設された際も,この点に 変わりはない。)。また,不正競争防止法2条1項3号において,「他人の商品」とは, 取引の対象となり得る物品でなければならないが,現に当該物品が販売されている ことを要するとする規定はなく,そのほか,同法には,「他人の商品」の保護期間の 始期を定める明示的な規定は見当たらない。したがって,同法は,取引の対象とな り得る物品が現に販売されていることを「他人の商品」であることの要件として求 めているとはいえない。 そこで,商品開発者が商品化に当たって資金又は労力を投下した成果を保護する との上記の形態模倣の禁止の趣旨にかんがみて,「他人の商品」を解釈すると,それ は,資金又は労力を投下して取引の対象となし得ること,すなわち,「商品化」を完 了した物品であると解するのが相当であり,当該物品が販売されているまでの必要 はないものと解される。このように解さないと,開発,商品化は完了したものの, 販売される前に他者に当該物品の形態を模倣され先行して販売された場合,開発, 商品化を行った者の物品が未だ「他人の商品」でなかったことを理由として,模倣 者は,開発,商品化のための資金又は労力を投下することなく,模倣品を自由に販 売することができることになってしまう。このような事態は,開発,商品化を行っ た者の競争上の地位を危うくさせるものであって,これに対して何らの保護も付与 しないことは,上記不正競争防止法の趣旨に大きくもとるものである。 もっとも,不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を確保することによって事 業者の営業上の利益を保護するものであるから(同法3条,4条参照),取引の対象 とし得る商品化は,客観的に確認できるものであって,かつ,販売に向けたもので あるべきであり,量産品製造又は量産態勢の整備をする段階に至っているまでの必 要はないとしても,商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能\とする段 階に至っており,かつ,それが外見的に明らかになっている必要があると解される。 以上を前提に控訴人加湿器1及び控訴人加湿器2が,「他人の商品」であるか否か を検討する。 (2) 控訴人加湿器1について
前記第2,2(3)1)のとおり,控訴人らは,平成23年11月,商品展示会に控訴 人加湿器1を出展している。商品展示会は,商品を陳列して,商品の宣伝,紹介を 行い,商品の販売又は商品取引の相手を探す機会を提供する場なのであるから,商 品展示会に出展された商品は,特段の事情のない限り,開発,商品化を完了し,販 売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになったものと認めるのが相当\nである。なお,上記商品展示会において撮影された写真(甲3の2,25)には, 水の入ったガラスコップに入れられた控訴人加湿器1の上部から蒸気が噴き出して いることが明瞭に写されているから,控訴人加湿器1が,上記商品展示会に展示中, 加湿器としての本来の機能を発揮していたことは明白である。\nところで,前記第2,2(2)3)のとおり,控訴人加湿器1は,被覆されていない銅 線によって超音波振動子に電力が供給されており,この形態そのままで販売される ものでないことは明らかである。 しかしながら,商品としてのモデルが完成したとしても,販売に当たっては,量 産化などのために,それに適した形態への多少の改変が必要となるのは通常のこと と考えられ,事後的にそのような改変の余地があるからといって,当該モデルが販 売可能な段階に至っているとの結果を左右するものではない。\n上記のような控訴人加湿器1の被覆されていない銅線を,被覆されたコード線な どに置き換えて超音波振動子に電源を供給するようにすること自体,事業者にとっ てみれば極めて容易なことと考えられるところ,控訴人加湿器1は,外部のUSB ケーブルの先に銅線を接続して,その銅線をキャップ部の中に引きこんでいたもの であるから(甲24),商品化のために置換えが必要となるのは,この銅線から超音 波振動子までの間だけである。そして,実際に市販に供された控訴人加湿器3の電 源供給態様をみると,USBケーブル自体が,キャップ部の小孔からキャップ部内 側に導かれ,中子に設けられた切り欠きと嵌合するケーブル保護部の中を通って, 超音波振動子と接続されているという簡易な構造で置換えがされていることが認め\nられるから(乙イ4,弁論の全趣旨),控訴人加湿器1についても,このように容易 に電源供給態様を置き換えられることは明らかである。そうすると,控訴人加湿器 1が,被覆されていない銅線によって電源を供給されていることは,控訴人加湿器 1が販売可能な段階に至っていると認めることを妨げるものではない。\n以上からすると,控訴人加湿器1は,「他人の商品」に該当するものと認められる。 (3) 控訴人加湿器2について 控訴人加湿器2は,控訴人加湿器1よりもやや全長が短く,円筒部が,控訴人加 湿器1よりもわずかに太いという差異があるほかは,控訴人加湿器1と同様の形態 を有するところ,実質的に同一の形態を有する控訴人加湿器1が「他人の商品」で ある以上,その後に開発され,国際見本市に出展された控訴人加湿器2が,販売可 能な状態に至ったことが外見的に明らかなものであることは,当然である。\nしたがって,控訴人加湿器2は,「他人の商品」に該当するものと認められる。
(4) 被控訴人の主張について
被控訴人は,控訴人加湿器1及び控訴人加湿器2が未完成であり,また,商品化 する具体的な開発についても未着手の状態である,そもそも,電源の供給方法も定 まっておらず商品として販売できないものであるなど,るる主張する。 しかしながら,上記(2)にて説示のとおり,控訴人加湿器1及び控訴人加湿器2は, そのままの形態で販売することが想定されておらず,電源供給部分の具体的な形状 についての改変は必要であるとしても,商品化は完了しているといえ,未完成であ るわけではない。その電源供給の具体的手段について将来的な変更の余地はあった としても,控訴人加湿器1及び控訴人加湿器2自体は,実際の形態どおりに外部電 源を引きこむものとして確定している。 そして,控訴人X1は,平成24年7月,雑貨店の店舗経営等を業とするスタイ リングライフにおいて商品仕入れを担当しているA(A)から,メールにて,控訴 人加湿器2の製品化の具体的な日程を問い合わせられた際,Aに対し,次のような メールを返信している(甲7)。 「 『Stick Humidifier』の製品化につきましては,具体的な日程は決まっており ません。製品化のお話はいくつかのメーカーさんから頂いてはおりますが,我々 の考えと合致するパートナーさんが見つかっておらず,開発がやや順延している のが現状です。購入や買い付けに関する問い合わせを多数頂いている故,1日も 早く開発を行いたいところです。」 上記記載の「製品化」は,量産のことを意味していることは明らかであり,「開発」 はそれに応じた設計変更をいうものと解され,上記記載が,控訴人加湿器2や控訴 人加湿器1が未完成で販売可能な状態ではないことをいう趣旨とは解されない。い\nったん商品化が完了した商品について,販売相手に応じて更なる改良の余地があっ たとか,その意図を有していたからといって,遡って,当該商品が商品化未了とな るものではない。上記メールの内容は,控訴人加湿器1が商品化されていないこと を裏付けるものではない。 そのほかに被控訴人がるる主張するところも,上記(1)(2)の認定判断に照らして, 採用することができない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2016.12.13
平成28(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月30日 知的財産高等裁判所
原告は,1)本件発明が本来的に治療行為,美容行為等を含んだ筋力トレーニング であること,2)本件発明が自然法則それ自体に特許を認めていること,から,本件 発明は,社会的妥当性を欠くので特許法32条に反すると主張する。 しかしながら,前記1(1)に認定のとおり,本件発明は,特定的に増強しようとす る目的の筋肉部位への血行を緊締具を用いて適度に阻害してやることにより,疲労 を効率的に発生させて,目的筋肉をより特定的に増強できるとともに,関節や筋肉 の損傷がより少なくて済み,更にトレーニング期間を短縮できるようにしたもので ある。 そうすると,本件発明は一義的に人体に重大な危険を及ぼすものではない上,本 件発明を治療方法等にも用いる場合においては,所要の行政取締法規等で対応すべ きであり,そのことを理由に,本件発明が特許を受けることが許されなくなるわけ ではない。また,特許を取得しても,当該特許を治療行為等の所要の公的資格を有 する行為において利用する場合には,当該資格を有しなければ当該行為を行うこと ができないことは,当然である。したがって,本件発明に特許を認めること自体が 社会的妥当性を欠くものとして,特許法32条に反するものとはいえない(なお, 産業上の利用可能性の有無については,前件審判・前件判決で既に取消事由とされ\nたものであり,本件は,専ら,特許法32条該当性のみを審理するものである。)。 また,本件発明は,「筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位 に巻付け,その緊締具の周の長さを減少させ」ることにより,「筋肉に与える負荷が, 筋肉に流れる血流を止めることなく阻害する」ものであるから,自然法則を利用し たものであるが,人体の生理現象そのもののような自然法則それ自体を発明の対象 とするものではない。そもそも,特許権は,業として発明を実施する権利を専有す るものであり(特許法68条),業として行わなければ,本件発明の筋力トレーニン グ方法は誰でも自由になし得るのであり,本件特許はそれを制限するものではない。 そうすると,原告の上記主張は,いずれも採用することができず,本件発明は, 公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明とすることはでき ない。 したがって,取消事由4は,理由がない。
6 取消事由5(無効理由5−2に関する判断の誤り)について
(1) 検討
旧特許法36条5項2号は,特許請求の範囲の記載について,「特許を受けようと する発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」とい\nう。)に区分してあること」との要件に適合するものでなければならないと規定して いた。これは,発明の構成に欠くことができない事項(必須要件)を全て記載する\nことを求めるとともに,必須要件でないものを記載しないことを求めることにより, 請求項の構成要件的機能\を担保したものであり,特許請求の範囲には,必要かつ十\n分な構成要件を記載することを求めたものといえる。\n前記1(1)のとおり,本件発明1の技術的意義は,筋力トレーニング方法において, 筋肉に与える負荷が,筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するものとすること, すなわち,目的の筋肉部位への血行を緊締具により継続的に適度に阻害することに より,疲労を効率的に発生させることにある。このような技術的意義にかんがみれ ば,特許請求の範囲に,「筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部 位に巻付け,その緊締具の周の長さを減少させ」ることにより,「筋肉に疲労を生じ させるために筋肉に与える負荷が,筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するも のである」ことが記載されていれば,本件発明の技術的課題を解決するために必要 かつ十分な解決手段が記載されているというべきである。
(2) 原告の主張について
1) 原告は,本件発明1の課題・効果を得るためには,所要の加圧条件を特許請 求の範囲に記載する必要があると主張する。 しかしながら,上記(1)のとおり,本件発明の課題解決手段は,本件発明1の記載 で明らかとされている一方,筋肉増大の程度は,トレーニングの態様,対象者,対 象部位等に応じて異なり,一義的に決まるものではないから,所要の加圧条件を特 許請求の範囲に記載しないことが,必須要件を記載していないことになるとまでは いえない。
2) 原告は,本件発明1が,筋肉への血流を止めることなく阻害し,これによっ て筋肉に疲労を生じさせること自体を筋力トレーニング方法と称しているのか,そ れ以外の何らかのトレーニングをすることを必須としているかも不明確であると主 張する。 本件発明の筋力トレーニング方法が,緊締具を用いて更にトレーニングを行うこ とを前提にしていることは,発明の詳細な説明から明らかであり(本件訂正明細書 の【0004】【0017】【図1】参照),そのような方法であるか否かが不明確で あるということはない。本件発明1は,そのうち,締結具によって筋肉への血流を 止めることなく阻害し,これによって筋肉に疲労を生じさせるとの部分を特許請求 の範囲に掲げたものと理解される。どのようなトレーニングがされるかは,トレー ニングの態様,対象者,対象部位等に応じて異なる上に,単なる技術常識の適用に すぎないことは自明であり,本件発明の筋力トレーニング方法を技術的に特徴付け るものではない。したがって,そのような事項は,本件発明の必須の要件ではない。 3) 以上のとおり,原告の主張は,いずれも採用することができない。
(3) 小括
以上から,本件発明1の特許請求の範囲の記載は,旧特許法36条5項2号の要 件を満たすと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2016.12.13
平成28(行ケ)10042 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月30日 知的財産高等裁判所
3 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと 解される。
(2) 特許請求の範囲の記載
本願発明の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわ ち,本願発明は,潤滑油基油と粘度指数向上剤を含み,「100℃における動粘度 が4〜12mm2/sであり,粘度指数が140〜300である」潤滑油組成物であ って,当該潤滑油基油は,「尿素アダクト値が2.5質量%以下,40℃における 動粘度が18mm2/s以下,粘度指数が125以上,且つ,90%留出温度から5 %留出温度を減じた値が70℃以下である潤滑油基油成分」(本発明に係る潤滑油 基油成分)を,「基油全量基準で10質量%〜100質量%」含有することが特定 されたものである。
(3) 発明の詳細な説明の記載
ア 本願明細書の発明の詳細な説明には,前記1(2)のとおり,本願発明は,従来 の潤滑油が,実用性能(150℃HTHS粘度)を維持しながら,さらに省燃費性\n(40℃動粘度,100℃動粘度,100℃HTHS粘度の低減)と低温粘度特性 (CCS粘度やMRV粘度の低減)とを両立するという点で,いまだ改善の余地が あったという事情に鑑みて,省燃費性,低蒸発性と低温粘度に優れ,ポリ−α−オ レフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも,1 50℃における高温高せん断粘度を維持しながら,省燃費性,NOACKにおける 低蒸発性と−35℃以下における低温粘度とを両立させることができ,特に潤滑油 の40℃及び100℃における動粘度並びに100℃におけるHTHS粘度を低減 し,粘度指数を向上し,−35℃におけるCCS粘度,(−40℃におけるMRV 粘度)を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とし,特許請求の範 囲の請求項1に記載の構成を採用することにより,省燃費性と低蒸発性及び低温粘\n度特性に優れており,ポリ−α−オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や 低粘度鉱油系基油を用いずとも,150℃におけるHTHS粘度を維持しながら, 省燃費性とNOACK蒸発量及び−35℃以下における低温粘度とを両立させるこ とができ,特に潤滑油の40℃及び100℃の動粘度と100℃におけるHTHS 粘度を低減し,−35℃におけるCCS粘度,(−40℃におけるMRV粘度)を 著しく改善することができるという効果を奏するものであることが記載されている。 イ また,【0021】ないし【0026】には,「本発明に係る潤滑油基油成 分」の尿素アダクト値,40℃動粘度,粘度指数及び90%留出温度から5%留出 温度を減じた値は,本願発明に係る潤滑油組成物の低温粘度特性,省燃費性,低蒸 発性,粘度−温度特性などと密接な関係があることが記載されていることから, 「本発明に係る潤滑油基油成分」と「その他の潤滑油基油成分」を混合した「潤滑 油基油」全体の尿素アダクト値,40℃動粘度,粘度指数及び90%留出温度から 5%留出温度を減じた値などの物性値も,同様に,本願発明に係る潤滑油組成物の 低温粘度特性,省燃費性,低蒸発性,粘度−温度特性などの物性と密接な関係があ ることが理解できる。
ウ 前記アによれば,本願発明の課題に関連する潤滑油組成物の物性は,150 ℃HTHS粘度,40℃動粘度,100℃動粘度,100℃HTHS粘度,NOA CK蒸発量,−35℃CCS粘度,−40℃におけるMRV粘度及び粘度指数であ るところ,本願明細書には,150℃HTHS粘度が2.55〜2.65の範囲内 となるように調製した実施例1ないし6及び比較例1ないし3の各潤滑油組成物に ついて,40℃動粘度(mm2/s),100℃動粘度(mm2/s),粘度指数, 100℃HTHS粘度(mPa・s),150℃HTHS粘度(mPa・s),N OACK蒸発量(1h,250℃),−35℃CCS粘度(mPa・s),−40 ℃MRV粘度(mPa・s)を測定した結果が示されている(【0117】,【表\n3】)。 そして,【0122】には,実施例1ないし6は,比較例1ないし3に比べて, 40℃動粘度,100℃動粘度,100℃HTHS粘度及びCCS粘度が低く,低 温粘度及び粘度温度特性が良好であったこと,実施例1ないし6の上記評価結果に 基づき,本願発明の潤滑油組成物が,省燃費性と低温粘度に優れ,ポリ−α−オレ フィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも,15 0℃における高温高せん断粘度を維持しながら,省燃費性と−35℃以下における 低温粘度とを両立させることができ,特に潤滑油の40℃及び100℃における動 粘度を低減し,粘度指数を向上し,−35℃におけるCCS粘度を著しく改善でき る潤滑油組成物であることが分かることが記載されているから,上記記載から,実 施例1ないし6は,本願発明の課題を解決できるものであるのに対し,比較例1な いし3は,本願発明の課題を解決できないものであることが理解できる。 エ また,実施例と比較例は全て,潤滑油としての実用性能を表\す150℃HT HS粘度が「2.60〜2.61」となるように調製されたものである(【011 7】,【表3】)。そこで,実施例1〜6と比較例1〜3において,150℃HT\nHS粘度以外の物性値をみると,1)本願明細書には,潤滑油組成物のNOACK蒸 発量は,好ましくは8質量%以上,さらに好ましくは18質量%以上であり,好ま しくは30質量%以下,特に好ましくは22質量%以下であり,18〜20質量% とすることで,蒸発損失の防止と低温特性,さらには省燃費性能をバランスよく達\n成することができることが記載されているところ(【0114】),NOACK蒸 発量は,実施例1ないし6では「10.8〜19.4」の範囲に,比較例1ないし 3では「12.2〜14.0」の範囲にあり,2)本願明細書には,潤滑油組成物の 100℃動粘度は,4〜12mm2/sであることが必要であり,特に好ましくは, 6mm2/s以上,8mm2/s以下であることが記載されているところ(【010 6】),100℃動粘度は,実施例1ないし6では「7.2〜9.0」の範囲に, 比較例1ないし3では「8.6〜8.9」の範囲にあって,これらの物性値におい て,両者の数値範囲は重なることが分かる。 他方,3)本願明細書には,潤滑油組成物の40℃動粘度は,4〜50mm2/sで あることが好ましく,特に好ましくは25mm2/s以上,30mm2/s以下であ ることが記載されているところ(【0109】),40℃動粘度は,実施例1ない し6では「25.6〜37.3」の範囲に,比較例1ないし3では「38.9〜4 0.4」の範囲にあり,4)本願明細書には,潤滑油組成物の粘度指数は,140〜 300の範囲であることが必要であり,最も好ましくは250〜300であること が記載されているところ(【0107】),粘度指数は,実施例1ないし6では 「224〜269」の範囲に,比較例1ないし3では「209〜211」の範囲に あり,5)本願明細書には,潤滑油組成物の100℃におけるHTHS粘度は,6. 0mPa・s以下であることが好ましく,最も好ましくは4.5mPa・s以下で あり,3.0mPa・s以上であることが好ましく,最も好ましくは4.2mPa ・s以上であることが記載されているところ(【0110】),100℃HTHS 粘度は,実施例1ないし6では「4.29〜5.26」の範囲に,比較例1ないし 3では「5.35〜5.49」の範囲にあり,6)本願明細書には,−35℃CCS 粘度に関し,「例えば,本発明の潤滑油組成物によれば,−35℃におけるCCS 粘度を4500mPa・s以下とすることができる。」と記載されているところ (【0115】),−35℃CCS粘度は,実施例1ないし6では「1800〜4 000」の範囲に,比較例1ないし3では「4850〜7700」の範囲にあり, 7)本願明細書には,−40℃MRV粘度に関し,「本発明の潤滑油組成物によれば, −40℃におけるMRV粘度を10000mPa・s以下とすることができる。」 と記載されているところ(【0115】),実施例1ないし6では「3700〜9 300」の範囲に,比較例1ないし3では「12500〜28000」の範囲にあ り,これらの物性値において,実施例1ないし6の数値の方が,比較例1ないし3 の数値よりも優れていることが分かる。 そうすると,前記ウのとおり,実施例1ないし6は,本願発明の課題を解決でき るものであるのに対し,比較例1ないし3は,本願発明の課題を解決できないもの であるところ,本願発明の課題を解決することができるというためには,150℃ HTHS粘度が2.60〜2.61程度となるように潤滑油組成物を調製した場合 に,40℃動粘度,100℃動粘度,100℃HTHS粘度,NOACK蒸発量, −35℃CCS粘度,(−40℃におけるMRV粘度)及び粘度指数の数値を総合 的に検討した結果,比較例1ないし3で代表される従来の技術水準を超えて,実施\n例1ないし6と同程度に優れたものとなることが必要であることを理解できる。 オ さらに,【表3】をみると,実施例1ないし6及び比較例1ないし3は,い\nずれも粘度指数向上剤を含有するものであり,「100℃動粘度が4〜12mm2/ s,粘度指数が140〜300」という本願発明の発明特定事項を満たすものであ るが,前記ウのとおり,実施例1ないし6は,本願発明の課題を解決できるもので あるのに対し,比較例1ないし3は,本願発明の課題を解決できないものであると されていることから,実施例1ないし6と比較例1ないし3の各潤滑油組成物の物 性の違いは,主として,含有する「潤滑油基油」の物性の違いによるものであるこ とが理解できる。 そして,【表1】ないし【表\3】によれば,本願発明の特許請求の範囲に含まれ る実施例1ないし5の「潤滑油基油」は,「本発明に係る潤滑油基油成分」である 基油1又は2を100質量%含有する潤滑油基油(実施例1,2,4),あるいは, 基油1又は2を70質量%と比較例2,3で用いた基油4を30質量%含有する潤 滑油基油(実施例3,5)であることから,「潤滑油基油」が「本発明に係る潤滑 油基油成分」を70〜100重量%含むものについて,「本発明に係る潤滑油基油 成分」と同じかそれに近い物性を有し,本願発明の課題を解決できることを理解す ることができる。
(4) 本願発明の課題を解決できると認識できる範囲
前記(3)によれば,本願明細書の記載に接した当業者は,「本発明に係る潤滑油基 油成分」を70質量%〜100質量%程度多量に含む,「本発明に係る潤滑油基油 成分」と同じかそれに近い物性の「潤滑油基油」を使用し,粘度指数向上剤を添加 して,100℃における動粘度を4〜12mm2/sとし,粘度指数を140〜30 0とした潤滑油組成物は,本願発明の課題を解決できるものと認識できる。 他方,本願発明は,「本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分として は,特に制限されない」ものであるところ(【0051】),一般に,複数の潤滑 油基油成分を混合して潤滑油基油とする場合,少量の潤滑油基油成分の物性から, 潤滑油基油全体の物性を予測することは困難であるという技術常識に照らすと,本\n願明細書の【0050】や【0054】の記載から,直ちに当業者において,「本 発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく,特許請求の範囲 に記載された「基油全量基準で10質量%〜100質量%」という数値範囲の下限 値により近いような「潤滑油基油」であっても,その含有割合が70質量%〜10 0質量%程度と多い「潤滑油基油」と,本願発明の課題との関連において同等な物 性を有すると認識することができるということはできない。しかるに,本願明細書 には,この点について,合理的な説明は何ら記載されていない。 (5) 本願発明のサポート要件適合性
本願発明は,前記(2)のとおり,「本発明に係る潤滑油基油成分」を,「基油全量 基準で10質量%〜100質量%」含有することが特定されたものであるが,前記 (4)のとおり,当業者において,本願明細書の発明の詳細な説明の記載から,「本発 明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく,特許請求の範囲に 記載された「基油全量基準で10質量%〜100質量%」という数値範囲の下限値 により近いような「潤滑油基油」であっても,本願発明の課題を解決できると認識 するということはできない。 また,「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく,特 許請求の範囲に記載された「基油全量基準で10質量%〜100質量%」という数 値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても,本願発明の課題を解 決できることを示す,本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はな い。 したがって,本願発明の特許請求の範囲は,本願明細書の発明の詳細な説明の記 載により,当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものという ことはできず,サポート要件を充足しないといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2016.12.13
平成28(ネ)10073 商標権侵害行為差止請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成28年11月30日 知的財産高等裁判所 横浜地方裁判所
これらの事実によれば,「がばい」は,主に佐賀県において,程度が著しいことを 意味する語として使用される方言であるが,前記のとおり平成18年に「佐賀のが ばいばあちゃん」という題名の映画が全国で放映されたのを1つの契機として,前 記アのとおり形容詞「よい」を意味する九州地方の方言である「よか」に接頭語とし て付され,非常によいという意味合いを有する「がばいよか」という語として佐賀 県に関する広告・宣伝に多用されるようになり,現在では,一般に,程度が著しいこ とを意味する佐賀県ないし九州地方の方言として知られるようになったものと推認 することができる。 以上によれば,被告標章1は,全体として,佐賀県ないし九州地方と関連性のあ る,非常に良質な石けんであるとの観念を生じるものというべきである。
(ウ) 「よか」の文字部分の抽出の可否について
前記(ア)のとおり,被告標章1は,全ての構成文字が黒色で同様の書体によって表\ されており,大きさもほぼ同じくらいで,特に目立つ文字はなく,また,文字の配置 により,全体としてまとまった印象を与えるものであるから,下段を構成する5文\n字のうちの2文字である「よか」を分離して観察することは,取引上不自然である といわざるを得ない。 さらに,前記アのとおり,「よか」については,全国的に広く用いられている国語 辞典である広辞苑及び大辞林のいずれにも,形容詞「よい」を意味する九州地方の 方言である旨が記載されていることから,取引者,需要者に対して商品又は役務の 出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 以上によれば,被告標章1のうち「よか」の文字部分のみを抽出し,本件商標1と 比較して類否を判断することは相当ではない。 なお,前記(ア)の外観に加え,「よか」と共に下段を構成する「石けん」の文字は,\n本件商標権1の指定商品の1つを示す普通名詞であるから,下段の「よか石けん」 も,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできず,した がって,被告標章1のうち下段の文字部分のみを抽出することも,相当ではない。 以上によれば,被告標章1については,全体として一体的に観察して,本件商標 1との類否を判断するのが相当である。
ウ 本件商標1と被告標章1との類否について
前記ア及びイのとおり,本件商標1と被告標章1は,外観において異なることは 明らかであり,本件商標1は,「ヨカ」との称呼及び形容詞「よい」を意味する九州 地方の方言との観念を生じるのに対し,被告標章1は,「ガバイヨカセッケン」との 称呼及び佐賀県ないし九州地方と関連性のある,非常に良質な石けんであるとの観 念を生じるのであるから,称呼及び観念においても異なる。 よって,本件商標1と被告標章1は,類似するものではない。
エ 控訴人らの主張について
控訴人らは,1)一般に,上下二段に表記される商標については,各段から個別の\n称呼が生じるものであること,2)上段の「がばい」は,日本全国の取引者,需要者間 において,出所識別標識として十分に認識されているものとはいい難く,無意義な\n語であること,「よか」には,否定的な意味もあり,「よか石けん」には,「どうでも よい石けん」という否定的な意味もあることから,「がばい」と「よか」を併せて, ものすごく良いといった意味を生ずるとは限らないことに加え,被告標章1は,下 段の「よか石けん」の部分から独立して称呼を生ずるが,「石けん」は,普通名詞で あり,また,「よ」の文字がほかの文字よりも一段と大きく太く記載されており,見 る者の注意を引きつける態様であることから,「よか」が要部となる旨主張する。 しかし,上下二段に表記される商標からどのような称呼が生ずるかは,商標全体\nの構成,各段の構\成等によって様々であり,各段から個別の称呼が生じると一般的 にいうことはできない。また,前記イ(イ)のとおり,「がばい」は,主に佐賀県にお いて使用される方言であるが,平成18年に同語を題名に含む映画が全国で放映さ れたのを1つの契機として,「がばいよか」という語として佐賀県に関する広告・宣 伝に多用されるようになり,現在では,一般に,程度が著しいことを意味する佐賀 県ないし九州地方の方言として知られるようになったものと推認することができる。 「よか」については,広辞苑(乙7)及び大辞林(乙8)のいずれにも,否定的な意 味の記載は,見られない。さらに,前記イ(ア)のとおり,被告標章1の上段の「が」 の文字は,下段の「よ」及び「石」の各文字と共に,ほかの文字よりも若干大きいも のの,目立つほどではなく,見る者の注意を引きつけるものということはできない。 以上によれば,控訴人らの主張は,採用できない。
2016.12.13
平成28(行ケ)10122 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成28年11月30日 知的財産高等裁判所
以上のとおり,両意匠に係る物品の性質,用途及び使用態様並びに公知意匠との 関係を総合すれば,本願意匠と引用意匠は,基本的構成態様において共通するもの\nの,その態様は,ありふれたものであり,需要者の注意を強く惹くものとはいえな い。また,具体的構成態様における共通点も,需要者の注意を強く惹くものとはい\nえない。これに対し,マウスピース部の端部の形態の相違は,需要者である患者及 び医療関係者らの注意を強く惹き,視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与 えるものである。 したがって,本願意匠と引用意匠の相違点のうち,マウスピース部の端部につい て,本願意匠は,その中央に円形孔及びその周囲に4つの小円形孔が形成された端 壁を設けたものであるのに対して,引用意匠は,端壁がなく,単に筒状のまま大き く開口した点は,マウスピースカバー部が透明であることと相まって,需要者であ る患者や医療関係者の注意を強く惹くものと認められ,異なる美感を起こさせるも のであり,それ以外の共通点から生じる印象に埋没するものではないというべきで ある。 よって,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。
3 被告の主張について
被告は,使用者は主に使用時に限ってマウスピース部の構成態様に注目し,購入\n時などマウスピースカバー部が閉じられた状態では,透けて見えるにすぎないマウ スピース部の端部の態様は,需要者に強い印象を与えるものとはいえない,マウス ピース部の端壁の有無は全体から一部分と認められるマウスピース部の,さらにそ の先端部分のみの相違であって,全体からすると僅かな範囲のものであるとして, マウスピースの端部の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的であると 主張する。 しかし,マウスピース部の端部は,需要者である患者が吸引器を使用する際に観 察するものであるし,医療関係者も,処方する薬剤を前提に機能を重視して観察す\nるものであるから,かかる部分が全体と比較して僅かな範囲のものであるとしても, マウスピース部の端部の相違点が類否判断に及ぼす影響を限定的であるということ はできない。被告の前記主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2016.12.13
平成28(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月28日 知的財産高等裁判所(2部)
前記(1)によれば,本件明細書には,1)技術分野につき,【0002】に は,「この開示は全体的に,リンクされたアイテムを作成するための方法とデバイス に関する。より特定には,この開示は,リンクされた装着可能なアイテムを弾性バ\nンドから作成するための方法とデバイスに関する。」と記載され,2)背景技術につき, 【0003】には,「独自に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るため の材料を含むキットは,常にいくらかの人気を博してきた。しかしながら,そのよ うなキットは通常,異なる色に色付けされた糸およびビーズのような原材料を含む だけで,使用可能で望ましいアイテムを構\\築することは個人の技量と才能に依存す\n る。従って,独自の装着可能なアイテムを作成するための材料を提供するのみでな\nく,望ましく耐久性のある装着可能なアイテムを成功裡に作成することを多くの技\n量および芸術的レベルの人々にとって容易するする(原文ママ)ように構築を簡略化\nもするキットについての必要と願望がある。」と記載され,そして,これに対応して, 3)発明の概要として,【0004】には,「ブルニアンリンク(Brunnian link)とは,チ ェインを形成するために,別の閉じたループを捕捉するようにそれ自体上で二重化 された閉じたループから形成されたリンクである。そのようなリンクを望ましいや り方で形成するのに,弾性バンドが利用されることができる。例示的キットおよび デバイスは,複雑な構成のブルニアンリンク物品の作成を提供する。しかも,例示\n的キットは,ブルニアンリンク組み立て技術を使って独自の装着可能な物品の成功\nする作成を提供する。」と記載されるとともに,4)発明を実施するための形態の説明 の総括として,【0027】には,「従って,例示的キットおよび方法は,ブレスレ ット,ネックレスおよびその他の装着可能なアイテムの作成のためにブルニアンリ\nンクの多くの異なる組み合わせおよび構成の作成を提供する。しかも,例示的キッ\nトは,潜在的なブルニアンリンク作成の能力を更に作り出して拡張するために拡張\n可能である。更には,例示的キットは,そのようなリンクおよびアイテムの簡単な\nやり方での作成を提供して,様々な技量レベルの人々に独自の装着可能なアイテム\nを成功裡に作成することを許容する。」と記載されている。 これらの記載によれば,本件明細書には,ブレスレットやネックレスなどの「独 自の装着可能なアイテム」を作成するキットは,通常,異なる色に色付けされた糸\n及びビーズのような原材料を含むだけであり,アイテムを構築することは個人の技\n量と才能に依存するため,このように材料を提供するのみでなく,アイテムを成功\n裡に作成することを多くの技量及び芸術的レベルの人々にとって容易にするように 構築を簡略化もするキットについての必要と願望があったことに鑑み,アイテムを\nブルニアンリンクアイテムとし,ブルニアンリンク組み立て技術を使ってブルニア ンリンクアイテムを簡単な方法で作成し,様々な技量レベルの人々にブルニアンリ ンクアイテムを成功裡に作成することを許容するキットを提供することが記載され ていると認められる。
イ また,本件明細書において,発明を実施するための形態として,次の(ア) 〜(エ)といった複数のキットが記載されているととともに,前記アのとおり,いずれ のキットによっても,ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し,様々な技 量レベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成することを許容するこ とが記載されている(【0027】)
(ア) 単一の列に規定された複数のピン26を有し,各ピン26に,リンク の作成中にゴムバンドの誤った開放を防止するために外向きにフレアー状になった フランジ状上部38と,ピン26の間でゴムバンドの端部を動かすために利用され るフックツール16の挿入のための間隙を提供する前方アクセス溝40が形成され たピンバー14を,3つ横並びに揃えてベース12上にサポートさせて一体構造と\nしたキット(【0009】〜【0015】,【0020】〜【0022】)
(イ) (ア)のキットに対しピンバー14を追加して,例えば5つのピンバー1 4を横並びに揃えてベース12上にサポートさせて一体構造としたキット(【001\n9】)
(ウ) 6つのピンバー14を横並びに揃えてベーステンプレート66上にサ ポートさせて一体構造としたキット(【0024】)
(エ) ベーステンプレート66のサイドに形成されたジョイント80,82 を用いて,例えば2つの(ウ)のキットを縦方向あるいは横方向に連結させて一体構造\nとしたキット(【0025】及び【0026】)
ウ そして,いずれのキットも,複数のピンバー14をベース12ないしベ ーステンプレート66上にサポートさせて一体構造としたものは,ピンバー14及\nびベース12ないしベーステンプレート66が一体をなして複数のピン26をサポ ートする構造にほかならず,このことは,段落【0011】に,「ピン26を望まし\nい揃えでサポートするために,・・・1つまたはいくつかのピンバー14がいくつか のベース12に載置されている。」との記載,すなわち,「ピン26」をサポート対 象とする旨の記載があることからも明らかである。そして,ベーステンプレート6 6も「ベース」の概念であると認められることから,いずれのキットも,複数のピ ンバー14をベース12ないしベーステンプレート66上にサポートさせて一体構\n造としたものは,ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し,様々な技量レ ベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成するための,複数のピンが (ピンバーの本体部を介して)ベースに(間接的に)サポートされた構造のもので\nあると理解できる。 そうすると,いずれのキットも,特に「ピンバー」の限定がない,本件発明1の 「一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって,/ベースと,/ ベース上にサポートされた複数のピンと,を備え,/前記複数のピンの各々は,リ ンクを望ましい向きに保持するための上部部分と,当該複数のピンの各々の前面側 の開口部とを有し,複数のピンは,複数の列に配置され,相互に離間され,且つ, 前記ベースから上方に伸びている/装置。」,又は,本件発明6の「一連のリンクか らなるアイテムを作成するためのキットであって,/リンクを望ましい向きに保持 するための上部部分と,複数のピンの各々の前面側の開口部を含み,ベースにより お互いに対してサポートされた複数のピンを備え,/前記複数のピンは,複数の列 に配置され,相互に離間され,且つ,前記ベースから上方に伸びている,/キット。」 の構成を充足するものであり,いずれのキットも本件発明の実施形態であると認め\nられる。
エ 以上によれば,本件発明の課題は,審決が認定するとおり,個人の技量 に依存することなく,様々な技量レベルの人々に,「ブルニアンリンクアイテム」を 簡単に作成するキットを提供することにあると認められる。
オ そして,本件訂正により,本件明細書は訂正されておらず,前記ア〜エ に記載の点は,本件訂正発明についても該当するものと認められる。 したがって,本件訂正によって本件発明の課題が変更されたとは認められないか ら,これを根拠とする原告の主張は理由がない。
カ これに対し,原告は,本件訂正の前後を問わず,本件発明及び本件訂正 発明〔全部〕の本質は,「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより, 無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供す ること」にあるが,仮に,本件訂正後の発明の本質が審決認定のとおり「個人の技 量に依存することのない『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』する」ことに発 明の本質があるのであれば,本件訂正により発明の本質が変更され,特許請求の範 囲を実質的に変更するものであると主張する。 しかしながら,前記のとおり,本件明細書の背景技術(【0003】)には,「独自 に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るための材料を含むキット は,・・・原材料を含むだけで,使用可能で望ましいアイテムを構\\築することは個人 の技量と才能に依存する」という課題があり,「望ましく耐久性のある装着可能\\なア イテムを成功裡に作成することを多くの技量および芸術的レベルの人々にとって容 易」となるように,「構築を簡略化もするキットについての必要と願望がある」こと\nのみが記載されており,原告主張の編み物製品のバリエーションに関する課題(バ リエーションに乏しいこと)は記載されていない。また,発明の概要についてみて も,その冒頭(【0004】)には,ブルニアンリンクの説明や,その作成に弾性バ ンドが利用可能であることに続けて,「例示的キットは,ブルニアンリンク組み立て\n技術を使って独自の装着可能な物品の成功する作成を提供する。」として,「原材料\nを含むだけで,使用可能で望ましいアイテムを構\\築することは個人の技量と才能に\n依存する」という前記課題を解決したことが記載され,原告主張の編み物製品のバ リエーションについて記載されているものではない。 そうすると,本件明細書には,発明の概要に「ベースとピンバーは,完成された リンクの向きの無尽のバリエーションを提供するように,様々な組み合わせおよび 向きに組み立てられ得る。」と記載され(【0005】),また,ベース12ないしベ ーステンプレート66とピンバー14との組合せにより,前記イ(ア)〜(エ)のいず れのキットをも構成し得ることが記載されていることを考慮しても,これらは拡張\n的な機能であって,ベース12とピンバー14を様々な向きに組み合わせることに\nより,無尽のバリエーションを提供することは,本件明細書において必須の技術事 項であるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> ピックアップ対象
2016.12.13
平成27(行ケ)10226 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月24日 知的財産高等裁判所
ア 前記(2)の認定事実によれば,本願明細書の実施例(例1)では,本願マトリ ックスを通過した白昼光に対し蒸留水を24時間常温で暴露する実験を行ったとこ\nろ,水が同期化したことが認められ,この点については当事者間に争いがないとこ ろである。しかしながら,上記実験は,実験条件の詳細が明らかではなく,本願明 細書の表1における「基準」に関する実験条件も具体的に記載されていないことか\nらすると,本願マトリックスを使用した場合とこれを使用しなかった場合における 比較実験を行ったものと認めることはできない。のみならず,水の同期化の理論的 なメカニズムは十分に解明されていない上,特開2004−2514985)公報(乙 2の【要約】,【0006】,【0011】)によれば,かえって,マイクロウェーブ,超音波,マイクロ波超音波,赤外線(遠赤外線,中間赤外線,近赤外線を含む。)な どを使用することによって,水分子の回転運動を促進し,本願水特性のように,凝 固点における水温をマイナス10度以下に降下させることが可能になるとされてお\nり,しかも,上記近赤外線(780nm〜2500nm)は,本願発明にいう入射光の 範囲(360nm〜3600nm)に含まれるのであるから,本願マトリックスを通過 しない入射光であっても水を一定程度同期化し得ることが認められ,水の同期化が 本願マトリックス以外の実験条件によって生じた可能性も残るといわざるを得ない。\nそうすると,本願明細書にいう上記実験は,水が同期化された原因が,その他の実 験条件によるものではなく,専ら入射光が本願マトリックスを通過したことによる ことまでを立証するものとはいえない。 したがって,立証事項Aが立証されたということはできない。
イ また,前記(2)の認定事実によれば,本願明細書の実施例(例14)では,男 性2名及び女性2名に対し,本願マトリックスを耳鳴り症状を示す耳の後部の頭蓋 基底部に,皮膚に穏やかな接着剤で局所的に配置する実験を行ったところ,このう ち3名の耳鳴り症状が24時間以内に消失し,1名の耳鳴り症状が1週間以内に消 失したことが認められる。しかしながら,上記実験における被験者は僅か4名にと どまり,しかも本願マトリックスを使用しない場合との比較試験を行うものではな いことからすれば,耳鳴り症状が自然治癒又はいわゆるプラセボ効果(乙11)に より消失した可能性も残るというほかない。のみならず,証拠(乙6ないし9)及\nび弁論の全趣旨によれば,キセノンが発する光のうち近赤外線を利用した耳鳴り治 療法(いわゆるキセノン光線療法)が現に実施されていることが認められることか らすれば,上記実施例における実験においても,被験者の耳の後部に照らされた光 が耳鳴り治療に一定程度有効に作用した可能性も残ることが認められる。したがっ\nて,本願明細書にいう上記実験は,耳鳴り症状が本願マトリックス自体によって消 失したものであることまでを立証するものとはいえない。 したがって,立証事項Bが立証されたものとはいえない。
ウ 以上によれば,本件立証事項が立証されたものと認めることはできず,本願 明細書は,当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載\nたものとはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,本願明細書にいう上記各実験結果はA宣誓書によって裏付けられて いる旨主張する。しかしながら,本願マトリックスを使用した実験がA教授の研究 室で行われたことはうかがわれないことからすれば,A宣誓書は,本願明細書にい う実験によって同期化された水の性質が,A教授の研究室での実験結果と同一であ るというにとどまり,水を同期化するとされる入射電磁エネルギーが本願マトリッ クスによって形成されることまでを裏付けるものとはいえない。したがって,原告 の上記主張は,A宣誓書を正解しないものであって,採用することができない。
イ 原告は,人に対する治療を目的とする発明に対し,特許出願前のごく僅かな 期間に厳格な実験を行うことを求めるのは困難を強いるものであって現実的ではな く,また,本願明細書の耳鳴り治療に関する実験はA宣誓書によっても裏付けられ ている旨主張する。しかしながら,比較実験の被験者となる耳鳴り患者の人数が少 ないことを認めるに足りる証拠はなく,耳鳴り症状の比較実験の方法についても, 例えば耳鳴り症状を示す両耳のうち片耳に限り本願マトリックスを配置すれば足り るのであるから,格別困難を強いるものとはいえず,原告の主張は,その前提を欠 く。また,A宣誓書は,「例14は,パイロット臨床実験におけるTGMの適用が4 人のヒト被験者における耳鳴り症状に対して有利な効果を有したことを実証してい る」(甲11〔53頁4行目ないし5行目〕参照)として,単に実験結果を追認する ものにすぎず,A教授の研究室で本願マトリックスによる耳鳴り症状の改善に関す る実験が行われていない以上,A宣誓書によっても本願マトリックスによって耳鳴 り症状の改善効果があることを認めることはできない。さらに,原告主張に係る報 告書(甲22)における実験も,上記(3)イで説示するところと同様に,比較試験を 行うものではなく,本件立証事項を裏付けるものとして適切ではない。したがって, 原告の主張は,その裏付けを欠くというほかなく,採用することができない。 (5) まとめ
上記によれば,本願明細書は当業者が本願発明の実施をすることができる程度に 明確かつ十分に記載したものではないとした審決の判断に誤りはなく,原告の主張\nする取消事由3(特許法36条4項15)〔実施可能要件〕に関する判断の誤り)は\n理由がない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2016.12.13
平成27(ワ)5869 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年11月8日 大阪地方裁判所
そこで,さらに上記使用が,特許法29条1項25)の「公然実施をされた」 といえるか検討するに,「公然実施をされた」というためには,発明の内容を秘密 にする義務を負わない人が発明内容を知り得る状態で使用等の実施行為が行われた ことが必要である。 しかるところ,公然実施の対象となるOBネットユニットは,小浜製鋼株式会社 によって製造され市販されていた商品にすぎないし,また証拠(乙1)からうかが われる両護岸工事の実施状況や工事内容,工事場所が公共の場であることなどから すれば,OBネットユニットの設置作業に従事した現場作業員が,OBネットユニ ットの構造について小浜製鋼株式会社から守秘義務を課せられていたことをうかが\nわせる事情はなく,かえって,工事使用前に,その構造を確認する機会も十\分あっ たものと認められるから,OBネットユニットの本件発明の構成要件D,E,Fを\n除く構成要件は,それら工事関係者に十\分認識されていたといえる。 そして,前記(3)で認定したとおり,そのOBネットユニットが,両護岸工事に おいて本件発明の構成要件D,E,Fを充足する態様で使用されたというのである\nが,その工事現場には,上記のとおりOBネットユニットの構成を確認した工事関\n係者が立ち会って,その使用態様を現認したものと推認できるから(なお,構成要\n件Eを充足する使用対象事態を撮影した写真は僅かであるが,その使用態様が特殊 なものとはいえない以上,両護岸工事現場で写真として記録が残っていないOBネ ットユニットであっても,多くは同様の態様で使用され,工事関係者らによって, その使用態様が現認されていたものと推認できる。),これらにより,本件発明は, 公然と実施されたものと認めて差し支えないというべきである。 なお,原告は,上記の認識の限度であれば,本件発明の構成要件Aの「式3≦N\n/M≦20」の数値限定,あるいは構成要件Eの「25%〜80%」の数値限定が\n認識されないと主張するが,公然実施されたOBネットユニットの使用態様が上記 限定された数値内,すなわち本件発明の下位概念に一致するのであれば,これをも って本件発明が公然実施されたといって差し支えないから,この点についての原告 の主張は失当である。
(5) したがって,本件発明は,特許法29条1項25)により特許を受けることが できないものに当たり,本件特許は,特許無効審判により無効とされるべきもので あるから,同法104条の3第1項により原告が本件特許権を行使することはでき ないというべきである。
(6) なお,原告は,上記認定に用いた各証拠(乙1,乙2,乙23)の信用性に ついて争っているのでこの点について付言するに,まず上掲の証拠によれば,両護 岸工事の行われた時期及び場所そのものは確実に認定できる事実であると認められ る上,原告の指摘にかかわらず,その後に同じ場所で同種の工事が行われた事実は 認められないから,被告が,本件訴訟提起後において両護岸工事が実施された現場 で確認したOBネットユニット(乙2,乙23)は,本件特許出願前にされた両護 岸工事において使用されたものであることは明らかである。 そして,これに中詰め材を充填して釣り上げた状況(上篠崎護岸工事につき乙1 別紙7−11,高谷護岸工事につき乙1別紙4−16A)についても,これら写真 の撮影時が両護岸工事の最中であることは,各写真の遠景に写り込んでいる建造物 等の位置関係から明らかであるから,これらにより上記(2),(3)のとおり十分認定\nできるものであり,これに反する原告の主張は失当である。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.11.28
平成28(ネ)10027 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年11月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
事案に鑑み,被控訴人が主張する本件各訂正発明に係る特許の無効理由の うち,乙16発明に基づく新規性及び進歩性欠如について,以下判断する(な お,控訴人ら 被控訴人主張の抗弁につき,時機に後れた攻撃防御方法として却下すべき旨を述べるが,少なくとも,これらの主張 が「訴訟の完結を遅延させる」ものでないことは明らかであるから,時機に後れた攻撃防御方法としての却下はしないこととする。)。
・・・
このように,乙16文献には,ユーザによって選択された商品を表示\nする際に,「はこだてビールオリジナルギフトセット」というジャンル の表題の下に,「はこだてビールギフトAセット」,「はこだてビールギ\nフトBセット」等の複数の商品の商品名,価格,写真が一覧表示された\nWebページ画像( のページ)が表示されることが記載されて\nいるのであるから,選択された商品情報の表示の際に,店舗カテゴリを\n示す情報と店舗カテゴリに分類される商品を示す情報を表示することが\n記載されているものといえるのであって,控訴人らの上記主張は,その 前提において理由がない。 なお,本件訂正を認めた訂正2016−390052事件に係る審決 (甲70)は,本件訂正発明1について独立特許要件の有無を判断する に当たり,乙16文献の記載について,上記と異なる認定(控訴人ら主 張のとおりの認定)をしているが,乙16文献の記載からは、上記で述 べたとおりのことが読み取れるというべきであるから,上記審決の認定 は是認できない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.11.27
平成28(ラ)10009 保全異議申立決定に対する保全抗告事件 著作権 民事仮処分 平成28年11月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
著作者とは著作物を創作する者をいい(法2条1項2号),著作物とは, 思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は\n音楽の範囲に属するものをいう(同項1号)。編集著作物とは,編集物 (データベースに該当するものを除く。)でその素材の選択又は配列に よって創作性を有するものであるところ(法12条1項),著作物とし て保護されるものである以上,その創作性については他の著作物の場合 と同様に理解される。 そうである以上,素材につき上記の意味での創作性のある選択及び配 列を行った者が編集著作物の著作者に当たることは当然である。 また,本件のように共同編集著作物の著作者の認定が問題となる場合, 例えば,素材の選択,配列は一定の編集方針に従って行われるものであ るから,編集方針を決定することは,素材の選択,配列を行うことと密 接不可分の関係にあって素材の選択,配列の創作性に寄与するものとい うことができる。そうである以上,編集方針を決定した者も,当該編集 著作物の著作者となり得るというべきである。 他方,編集に関するそれ以外の行為として,編集方針や素材の選択, 配列について相談を受け,意見を述べることや,他人の行った編集方針 の決定,素材の選択,配列を消極的に容認することは,いずれも直接創 作に携わる行為とはいい難いことから,これらの行為をしたにとどまる 者は当該編集著作物の著作者とはなり得ないというべきである。
イ もっとも,共同編集著作物の作成過程において行われたある者の行為が, 上記のいずれの場合に該当するかは,当該行為を行った者の当該共同編 集著作物の作成過程における地位や権限等を捨象した当該行為の客観的 ないし具体的な側面のみによっては判断し難い例があることは明らかで ある。すなわち,行為そのものは同様のものであったとしても,これを 行った者の地位,権限や当該行為が行われた時期,状況等により当該行 為の意味ないし位置付けが異なることは,世上往々にして経験する事態 である。 そうである以上,創作性のあるもの,ないものを問わず複数の者によ る様々な関与の下で共同編集著作物が作成された場合に,ある者の行為 につき著作者となり得る程度の創作性を認めることができるか否かは, 当該行為の具体的内容を踏まえるべきことは当然として,さらに,当該 行為者の当該著作物作成過程における地位,権限,当該行為のされた時 期,状況等に鑑みて理解,把握される当該行為の当該著作物作成過程に おける意味ないし位置付けをも考慮して判断されるべきである。 これに対し,抗告人は,著作者性の判断に当たっては,当該行為が行 われた状況や立場といった背景事情を捨象し,もっぱら創作的表現のみ\nに着目して判断されなければならない旨主張するけれども,複数人の関 与の下に著作物が作成される場合の実情にそぐわないというべきであり, この点に関する抗告人の主張は採用し得ない。
ウ 以上を踏まえ,前記認定事実に基づき,以下検討する。
・・・
エ このように,少なくとも本件著作物の編集に当たり中心的役割を果たし たB教授,その編集過程で内容面につき意見を述べるにとどまらず,作 業の進め方等についても編集開始当初からE及びB教授にしばしば助言 等を与えることを通じて重要な役割を果たしたというべきA教授及び抗 告人担当者であるEとの間では,相手方につき,本件著作物の編集方針 及び内容を決定する実質的権限を与えず,又は著しく制限することを相 互に了解していた上,相手方も,抗告人から「編者」への就任を求めら れ,これを受諾したものの,実質的には抗告人等のそのような意図を正 しく理解し,少なくとも表向きはこれに異議を唱えなかったことから,\nこの点については,相手方と,本件著作物の編集過程に関与した主要な 関係者との間に共通認識が形成されていたものといえる。しかも,相手 方が本件原案の作成作業には具体的に関与せず,本件原案の提示を受け た後もおおむね受動的な関与にとどまり,また,具体的な意見等を述べ て関与した場面でも,その内容は,仮に創作性を認め得るとしても必ず しも高いとはいえない程度のものであったことに鑑みると,相手方とし ても,上記共通認識を踏まえ,自らの関与を謙抑的な関与にとどめる考 えであったことがうかがわれる。 これらの事情を総合的に考慮すると,本件著作物の編集過程において, 相手方は,その「編者」の一人とされてはいたものの,実質的にはむし ろアイデアの提供や助言を期待されるにとどまるいわばアドバイザーの 地位に置かれ,相手方自身もこれに沿った関与を行ったにとどまるもの と理解するのが,本件著作物の編集過程全体の実態に適すると思われる。
(4) そうである以上,法14条による推定にもかかわらず,相手方をもって 本件著作物の著作者ということはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2016.11.22
平成28(行ケ)10079 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月16日 知的財産高等裁判所
ア 本願発明は,トレッドに発泡ゴムを適用したタイヤにおいて,氷路面におけ るタイヤの制動性能及び駆動性能\を総合した氷上性能が,タイヤの使用開始時から\n安定して優れたタイヤを提供するため,タイヤの新品時に接地面近傍を形成するト レッド表面のゴムの弾性率を好適に規定して,十\分な接地面積を確保することがで きるようにしたものである。これに対し,引用発明は,スタッドレスタイヤやレー シングタイヤ等において,加硫直後のタイヤに付着したベントスピューと離型剤の 皮膜を除去する皮むき走行の走行距離を従来より短くし,速やかにトレッド表面に\nおいて所定の性能を発揮することができるようにしたものである。\n以上のとおり,本願発明は,使用初期においても,タイヤの氷上性能を発揮でき\nるように,弾性率の低い表面ゴム層を配置するのに対し,引用発明は,容易に皮む\nきを行って表面層を除去することによって,速やかに本体層が所定の性能\を発揮す ることができるようにしたものである。したがって,使用初期においても性能を発\n揮できるようにするための具体的な課題が異なり,表面層に関する技術的思想は相\n反するものであると認められる。
イ よって,引用例1に接した当業者は,表面外皮層Bを柔らかくして表\面外皮 層を早期に除去することを想到することができても,本願発明の具体的な課題を示 唆されることはなく,当該表面外皮層に使用初期においても安定して優れた氷上性\n能を得るよう,表\面ゴム層及び内部ゴム層のゴム弾性率の比率に着目し,当該比率 を所定の数値範囲とすることを想到するものとは認め難い。また,ゴムの耐摩耗性 がゴムの硬度に比例すること(甲8〜13)や,スタッドレスタイヤにおいてトレ ッドの接地面を発泡ゴムにより形成することにより氷上性能あるいは雪上性能\が向 上すること(甲14〜16)が技術常識であるとしても,表面ゴム層を非発泡ゴム,\n内部ゴム層を発泡ゴムとしつつ,表面ゴム層のゴム弾性率を内部ゴム層のゴム弾性\n率より小さい(表面を内部に比べて柔らかくする。)所定比の範囲として,タイヤ\nの使用初期にトレッドの接地面積を十分に確保して,使用初期においても安定して\n優れた氷上性能を得るという技術的思想は開示されていないから,本願発明に係る\n構成を容易に想到することができるとはいえない。
(3) 被告の主張について
ア 被告は,本願発明の実施例と引用発明はともに従来例「100」に対して 「103」という程度でタイヤの使用初期の氷上での制動性能が向上するものであ\nり,また,引用例1の比較例と実施例を比較すると,比較例が実施例に対して表面\nゴム層(表面外皮層)を有していない点のみが異なることから,使用初期の性能\向 上は,表面ゴム層(表\面外皮層)に由来することが明らかである,そうすると,本 願発明の実施例と引用発明の性能向上はともに,タイヤ表\面に本体層のゴムよりも 柔らかいゴムを用いることにより使用初期の氷上での性能を向上させる点で同種の\nものであるから,結局,表面ゴム層(表\面外皮層)に関して,本願発明と引用発明 の所期する条件(機能)は変わるものではなく,引用例1に接した当業者は,引用\n発明の表面ゴム層(表\面外皮層)が,早期に摩滅させることのみを目的としたもの でなく,氷上性能の初期性能\が得られることを認識する旨主張する。 しかし,前記(2)のとおり,引用例1に記載された課題を踏まえると,引用発明は, あくまで早く摩耗する皮むき用の表面外皮層を設けて,ベントスピューと離型剤を\n表面外皮層とともに除去することにより,本来のトレッド表\面を速やかに出現させ るものであり,引用例1は,走行開始から表面外皮層が除去されるまでの間の氷上\n性能について何ら開示するものではない。よって,引用例1に接した当業者が,氷\n上性能の初期性能\が得られることを認識するものとは認められない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
イ 被告は,引用発明において,表面外皮層Bの硬度は,本体層Aのそれより小\nさく(引用例1の表1),硬度の小さいゴムが,ゴム弾性率の小さいゴムである旨\nの技術常識(甲4,甲5)を考慮すれば,「引用発明の「表面ゴム層(表\面外皮 層)」のゴム弾性率が「内部ゴム層(本体層)」のゴム弾性率に比し低いものとい え,「表面ゴム層のゴム弾性率」/「内部ゴム層のゴム弾性率」の値を0.01以\n上1.0未満程度の値とすることは,具体的数値を実験的に最適化又は好適化した ものであって,当業者の通常の創作能力の発揮といえるから,当業者にとって格別\n困難なことではない旨主張する。 しかし,本願発明と引用発明とでは,具体的な課題及び技術的思想が相違するた め,引用例1には,表面ゴム層のゴム弾性率を内部ゴム層のゴム弾性率より小さい\n所定比の範囲として,使用初期において,接地面積を確保するという本願発明の技 術的思想は開示されていないのであるから,引用発明から本願発明を想到すること が,格別困難なことではないとはいえない。 また,表面外皮層BのHs(−5℃)/本体層AのHs(−5℃)が,0.77 (=46/60),表面外皮層Bのピコ摩耗指数/本体層Aのピコ摩耗指数が,0. 54(=43/80)であるとしても,本願発明が特定するゴム弾性率とHs(−5 ℃)又はピコ摩耗指数との関係は明らかでないので,引用例1の表1に示すHs\n(−5℃)又はピコ摩耗指数の比率が,本願発明の特定する,「比Ms/Miは0. 01以上1.0未満」に含まれ,当該比率について本願発明と引用発明が同一であ るとも認められない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2016.11.22
平成25(ワ)34182 特許を受ける権利確認等請求事件 特許権 平成28年10月24日 東京地方裁判所
特許を受ける権利は,原始的には,発明をした者(発明者)に帰属するところ, 特許出願された発明の発明者とは,特許請求の範囲に記載された発明について,そ の具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を着想し,完成させるた めの全過程に関与した者が一人だけであれば,その者のみが発明者となるが,その 過程に複数の者が関与した場合には,当該過程において発明の特徴的部分の完成に 技術的に寄与した者が発明者となり,そのような者が複数いる場合にはいずれの者 も発明者(共同発明者)となる。ここで,発明の特徴的部分とは,特許請求の範囲 に記載された発明の構成のうち,従来技術には見られない部分,すなわち,当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分をいう。なぜなら,特許権は,従来の技術\nでは解決することのできなかった課題を,新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものであり(特許法29条参照),特許\n法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった技術課 題の解決を実現するための,従来技術には見られない特有の技術的思想に基づく解 決手段を,具体的構成をもって社会に開示した点にあるから,特許請求の範囲に記載された発明の構\成のうち,当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分の完成に寄与した者でなければ,同保護に値する実質的な価値を創造した者とはいい難い からである(知財高裁平成18年(行ケ)第10048号同19年7月30日判決 参照)。
(2) 原告従業員Aiの情報(知見)について
原告は,原告従業員Aiが本件知見1)ないし4)を有しており,これらを被告従業 員等に提供したことから,同人が本件各発明の共同発明者の一人である旨主張する。 しかし,以下に詳述するとおり,これらの知見は,公知技術にすぎないか,具体 的な技術的裏付けを伴わない単なる願望ないし要望にすぎず,本件各発明の特徴的 部分の着想から完成に至る過程への実質的関与と評価し得るものでないから,同人 が本件各発明の共同発明者の一人であることを根拠付ける理由とはならない。 (3) 本件発明1について
ア 本件発明1の目的及び効果並びに従来技術との関係について
本件明細書1の段落【0004】及び【0008】の記載によれば,本件発明1 は,α−GGよりも優れた保湿性を発揮する材料が求められていたこと,α−GG の従来の製造方法は,手間や時間がかかるなど大量生産に適さず,コストが高くな るという問題があったことに鑑みて,発明されたものであり,α−GG単独の場合 よりも保湿性が向上し,大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供するこ とを目的としたものであって,本件発明1によれば,α−GG単独の場合よりも保 湿性が向上し,大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供できるとされて いる。 他方,前記1の認定事実のほか,特表2005−532311号公報(乙4)に\nよれば,本件出願1がされた平成22年5月10日より前である平成17年10月 27日の時点において,GGを化学合成法によって製造することができること,化 学合成法によるGGの製造の際,グルコースとグリセリンとを酸性触媒を用いて反 応させること,GGを化学合成法により製造した場合,反応物中にグリセリンが残 留すること,GG組成物を保湿剤として用いることについては,いずれも公知であ ったと認められる。
イ 本件発明1−1について
(ア) 本件発明1−1の特徴的部分について
本件出願1の願書に添付した特許請求の範囲(平成25年12月24日付け手続 補正書〔乙1〕による補正後のもの)の請求項1の記載によれば,本件発明1−1 は,1)α−GGとβ−GGとを45〜75:15〜25の質量比で含むこと(以下 「構成1)」という。),2)当該糖組成物中に含まれる全糖の合計量に対するα−GG の割合が58.4〜65.3質量%で,β−GGの割合が21.6〜24.5質量% であること(以下「構成2)」という。)を発明特定事項とするものである。 そして,上記アで説示した本件発明1の目的及び効果並びに従来技術との関係に 照らすと,本件発明1−1は,糖組成物の一種であるGG組成物を保湿剤とするに 当たり,構成1)及び構成2)をともに充足するところの,α−GGとβ−GGの混合 物からなるGG組成物を用いることによって,α−GG単独の場合よりも保湿性の 向上を図ったことを特徴とするものというべきである(本件明細書1の段落【00 08】,【実施例】〔【0031】以下〕)。 そうすると,本件発明1−1は,構成1)及び2)が同発明特有の課題解決手段を基 礎付ける部分であって,これらの構成が同発明の特徴的部分に当たり,同発明のそ\nの余の発明特定事項は,同発明の特徴的部分とは認めらない。 もっとも,糖組成物中のα−GGとβ−GGの量的関係が構成2)を充足する場合, 当然に構成1)を充足することになるから,本件発明1−1の特徴的部分を画定する のは,結局,構成2)であるということになる。
(イ) 本件発明1−1の発明者について
上記(ア)の本件発明1−1の特徴的部分を前提とし,原告従業員Aiが,当該特徴 的部分における技術手段を着想し,かつ,特徴的部分の完成に至る過程に技術的関 与した者といえるかについて検討する。 そもそも,化学合成法によりGG組成物を製造することや化学合成法により得ら れるGG組成物について,原告従業員Aiが何らかの新規かつ具体的な知見を有し ていたことを裏付ける的確な証拠はない。 むしろ,前記1(1)で認定したとおり,原告が被告に化学合成法によるGG組成物 の製造を依頼したのは,原告は,酵素法によりGG組成物を試作していたものの, コスト面での難点があり,他方で,原告が自ら化学合成法によってGG組成物を製 造することは困難であったため,他社に化学合成法によりGG組成物を低価格で大 量生産することを委託することとし,候補とした2社から被告を選択したという経 緯があることからすると,原告従業員Aiは,化学合成法によりGG組成物を製造 することについて,新規かつ具体的な知見を有していたものではなく,したがって, 化学合成法により得られるGG組成物についても,新規かつ具体的な知見を有して いたものではなかったと推認するのが合理的である。 そして,本件明細書1の記載によれば,本件発明1−1における構成2)の数値範 囲は,実施例1ないし3により導き出されたものであることが認められるところ, 前記1の認定事実によれば,これらの実施例は,いずれも被告従業員Aiiを中心と する被告従業員等が実験的に導出し,その効果を確認したものであって,この過程 に原告従業員Aiが実質的に関与したとみることはできない。 そうすると,本件発明1−1の発明者ないし共同発明者と評価され得る者は,被 告従業員Aiiを中心とする被告従業員等のみであって,原告従業員Aiが同発明の 共同発明者の一人であると認めることはできない。
(ウ) この点,原告は,原告従業員Aiがα−GGとβ−GGを一定比率で含有す る組成物からなる保湿剤を着想したとか,被告従業員等に示したHPLCチャート から導き出されたα−GGとβ−GGとの比率が本件発明1−1の構成1)の数値範 囲に含まれていることなどを理由として,原告従業員Aiが本件発明1−1の共同 発明者の一人である旨主張する。 しかし,そもそも,本件発明1−1は,α−GGとβ−GGを含んでなる組成物 のHPLCによる分析方法や,α−GGとβ−GGとをHPLCにより分離する方 法に関する発明ではない。 上記の点をひとまず措くとしても,HPLCチャートのうち,平成20年5月8 日に被告従業員等に示されたもの(甲29の2)は,α−GGとβ−GGのピーク が分離されているとはいえず,この時点で,原告従業員Aiの技術的関与があった とは認められない。
他方,平成21年5月1日に被告従業員等に示された甲30のHPLC分析結果 では,各ピークの裾野はつながっているものの,α−GGとβ−GGのピーク自体 は区別できるが,HPLCの条件及び結果は,本件明細書1記載の実施例について のHPLCとは異なるものである。また,そのα−GGとβ−GGの比率が示され た分析結果(甲31のHPLC分析結果)は,本件訴訟において初めて被告に示さ れたもので,甲30のHPLC分析結果とともに示していないこと,その後,同年 11月13日の時点においても,原告従業員Aiは,被告従業員Aivに対し,α− GGとβ−GGのHPLCによる分離確認方法を問い合わせていること(乙18) からみても,上記の原告従業員Aiの知見や原告による分析結果(甲30,31) により,原告従業員Aiが本件発明1−1の特徴的部分について技術的な関与をし たものとは認めがたい。 もともと,被告従業員Aiiは,原告からGG製造の委託を受けた平成20年5月 8日の時点においても,GG自体は製造したことはなかったものの,類似の物質の 化学合成法によると,α−GGとβ−GGの比率については,概ね7:3になるで あろうということを,それまでの被告における知見や経験から予想していたもので\nあるし,実際に,その後の平成21年12月7日の打合せにおいて,「GCI見解と して,液クロでは判断し難い。NMRで確認した結果,α:β=65:35となる。」 とし,α−GGとβ−GGの比率については,概ね当初の予想どおりの結果をNM\nRで確認しているのである。 原告は,この時点でも,被告従業員等がHPLCによる分析は難しい旨を発言し ていることから,被告にHPLC分析を行う技術力はなく,原告のHPLCによる 分析結果が本件発明1−1に寄与した旨も主張するが,そもそも,HPLCによっ て分析するという分析方法を単に示唆したというだけでは,本件発明1−1につい て,共同発明者の一人とみることができるような技術的関与があったとはいえない ことは明らかであるし,上記のとおり,原告におけるHPLCによる分析も十分な\n結果とはいえない。 そうすると,被告従業員等において,上記経緯を踏まえ,その後も実験,分析を 繰り返した結果,本件出願1に至る平成22年5月10日までの間に,本件明細書 1に記載の実施例に掲げられたHPLC分析の条件及びその結果を見出し,出願に 至ったものと認めるのが相当である。そして,仮に,その際,原告のHPLCによ る分析を参考にしたとしても,そのことをもって評価試験の実施につきその内容の 策定や具体的な条件や結果を獲得する過程に原告従業員Aiが具体的かつ実効的な 貢献をしたものとは評価し難い。したがって,本件発明1−1の構成1)及び構成2) について,原告従業員Aiが技術的に寄与したものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> ピックアップ対象
2016.11.22
平成28(行ケ)10025 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月8日 知的財産高等裁判所
そこで検討するに,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその 物の製造方法が記載されている場合(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・ クレームの場合)において,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項 2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは, 出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\ であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると 解するのが相当であるところ(最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判 決・民集69巻4号700頁参照),本願補正発明1及び2に係る前記の各 記載は,いずれも,形式的にみれば,経時的な要素を記載するものといえ, 「物の製造方法の記載」がある,すなわち,プロダクト・バイ・プロセス・ クレームに該当するということができそうである。 しかしながら,前記最高裁判決が,前記事情がない限り明確性要件違反に なるとした趣旨は,プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲は, 当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定\nされるが,そのような特許請求の範囲の記載は,一般的には,当該製造方法 が当該物のどのような構造又は特性を表\しているのかが不明であり,権利範 囲についての予測可能\性を奪う結果となることから,これを無制約に許すの ではなく,前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。 そうすると,特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっ ても,前記の一般的な場合と異なり,当該製造方法が当該物のどのような構\n造又は特性を表しているのかが,特許請求の範囲,明細書,図面の記載や技\n術常識から明確であれば,あえて特許法36条6項2号との関係で問題とす べきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない。
この点,本願補正発明1に係る特許請求の範囲(請求項1)は,1)透光性 あるシート・フィルムを,80〜100cm長さの稲育苗箱の巻取り開始縁 以外の3方の縁からはみ出させる,2)これを稲育苗箱底面に根切りシートと して敷く,3)その上に籾殻マット等の軽い稲育苗培土代替資材をはめ込む, 4)この表面に綿不織布等を敷いて種籾の芒,棘毛を絡ませて固定し,根上が\nりを防止して,覆土も極少なくする,5)1)ないし4)のとおり育苗した軽量稲 苗マットを,根切りシートと一緒に巻いて,細い円筒とする,という手順を 示すことにより,「内部導光ロール苗」の構造,特性を明らかにしたものと\n理解することが十分に可能\である。 また,本願補正発明2に係る特許請求の範囲(請求項2)も,1)80〜1 00cm長さの稲育苗箱にはめ込んだ,成型した籾殻マット等の軽い稲育苗 培土代替資材の表面に,2)綿不織布等を敷いて種籾の芒,棘毛を絡ませて固 定し,根上がりを防止し,覆土も極少なくして育苗した,軽量稲苗マットに, 3)透光性あるシート・フィルムを,稲育苗箱の巻取り開始縁以外の3方の縁 からはみ出させて被せ一緒に巻いて,細い円筒とする,というように,やは り手順を示すことより,「内部導光ロール苗」の構造,特性を明らかにした\nものということができる。 そうすると,本願補正発明1及び2に係る前記特定事項は,いずれも,物 の構造,特性を明確に表\しており,発明の内容を明確に理解することができ るものである。 したがって,本願補正発明1及び2は,いずれも,特許法36条6項2号 との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームとみる 必要はなく,この点を理由に請求項の記載が明確でない(不可能・非実際的\n事情がなく,同号の要件を満たさない)とした本件審決の判断は誤りである。
(3) 以上によれば,取消事由1に関する原告の主張は正当であり,これに反す る被告の主張は採用できない(ただし,この点に関する本件審決の判断の誤 りが,本件審決の結論に影響を及ぼすものでないことについては,後記4の とおりである。)。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2016.11.12
平成28(ワ)15355 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 民事訴訟 平成28年10月31日 東京地方裁判所
a 以上のとおり,本件明細書が,「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物」 を従来技術として開示し,これよりも,本件発明1の組成物は「生成される不純物, 例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体が少ない ことを意味する。」と記載していること,解離シュウ酸は,オキサリプラチンが溶 液中で分解することにより,ジアクオDACHプラチンと対になって生成されるも のであること,本件発明1の発明特定事項として構成要件1Gが限定する緩衝剤の\nモル濃度の範囲に関する具体的な技術的裏付けを伴う数値の例として,本件明細書 は,添加されたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの数値のみを記載し,解離シュウ 酸のモル濃度を何ら記載していないこと,本件明細書には,専ら,「緩衝剤」を外 部から添加する実施例のみが開示されていると解されること,請求項1は,「シュ ウ酸」と「そのアルカリ金属塩」とを区別して記載し,さらには「緩衝『剤』」と いう用語を用いていることなどをすべて整合的に説明しようとすれば,本件発明1 における「緩衝剤」は,外部から添加されるものに限られるものと解釈せざるを得 ない。
すなわち,本件発明1は,専ら,オキサリプラチン水溶液に,緩衝剤として,シ ュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加(外部から付加)することにより,オキサリ プラチン溶液中のシュウ酸濃度を人為的に増加させ,平衡に関係している物質の濃 度が増加すると,当該物質の濃度が減少する方向に平衡が移動するという原理(ル シャトリエの原理)に従い,結果として,オキサリプラチン溶液中におけるジアク オDACHプラチン及びジアクオDACHプラチン二量体などの望ましくない不純 物の量を,シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加(外部から付加)しない場合よ りも,減少させることを目した発明と把握するべきであり,そのように把握するこ とにより,初めて,本件明細書の段落【0031】が「本発明の組成物は,オキサ リプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明して おり,このことは,オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明 の組成物中に生成される不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオ DACHプラチン二量体が少ないことを意味する。」と記載していることや,本件 明細書には,シュウ酸又はシュウ酸ナトリウムを,構成要件1Gが規定する数値の\nモル濃度だけ,オキサリプラチン溶液に「添加」する実施例のみが開示されている こと,さらには,本件明細書に開示された実施例において,解離シュウ酸の量を明 記していないことや,他の不純物の量から解離シュウ酸の量を推計することを示唆 する記載すらないことなどを整合的に説明できるのである。 また,オキサリプラチン溶液に,緩衝剤として,シュウ酸又はそのアルカリ金属 塩を添加(外部から付加)して得られたオキサリプラチン溶液組成物は,これを添 加しないオキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも,ジアクオDACHプラ チン及びジアクオDACHプラチン二量体などの望ましくない不純物の量が減少す るから,客観的構成において異なる(すなわち,「物」として異なる。)ことにな\nるということもできる。
b 他方で,仮に,本件発明1を上記のように解することなく,原告らが主張す るように,解離シュウ酸であってもジアクオDACHプラチン及びジアクオDAC Hプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させているとみなすというのであれば, 本件発明1は,本件優先日時点において公知のオキサリプラチン溶液が生来的に有 している性質(すなわち,オキサリプラチン溶液が可逆反応しており,シュウ酸イ オンが平衡に関係している物質であるという,当業者には自明ともいうべき事象) を単に記述するとともに,当該溶液中の解離シュウ酸濃度として,ごく通常の値を 含む範囲を特定したものにすぎず,新規性及び進歩性を見いだし難い発明というべ きである。すなわち,本件優先日時点において,例えば,濃度が5mg/mLのオ キサリプラチン水溶液が公知であった(乙1の1)。そして,当該水溶液中のオキ サリプラチンが分解して解離シュウ酸が生成されることは,その生来的な性質であ り(本件明細書の段落【0013】ないし同【0016】参照),シュウ酸が平衡 に関係している物質であることも同様であるところ,種々の条件下である程度の期 間保存された濃度5mg/mLのオキサリプラチン水溶液中には,解離シュウ酸が 存在し,その量が,5x10−5M以上となることが多いことが,乙13の3試験,甲2 0試験(「5x10−5M」として,有効数字を1桁とする以上,「4.86x10−5M」又は 「4.94x10−5M」も,「5x10−5M」とみて差し支えない〔乙12参照〕。),乙3 2試験及び乙37試験の各結果から,さらには,本件特許権に係る原告デビオファ ームの延長登録出願の願書(乙33)の記載から認められる(なお,上記認定は, 上記各試験が乙1の1実施例の追試として妥当であるか否かはともかく,少なくと も,公知の組成物である濃度5mg/mLのオキサリプラチン水溶液において,解 離シュウ酸のモル濃度が5x10−5M以上となることは,ごく通常のことであると認め るのが相当であることを指摘したものである。)。そうすると,公知の組成物であ るオキサリプラチン水溶液中に存在し,同水溶液の平衡に関係している物質である シュウ酸イオン(解離シュウ酸)に,「平衡に関係している」という理由で「緩衝 剤」という名を付け,上記のとおり通常存在しうる程度のモル濃度を数値範囲とし て規定したにとどまる発明は,公知の組成物と実質的に同一の物にすぎない新規性 を欠く発明か,少なくとも当業者にとって自明の事項を発明特定事項として加えた にすぎない進歩性を欠く発明というほかはない。
c したがって,本件発明にいう「緩衝剤」には,オキサリプラチンが溶媒中で 分解して生じたシュウ酸イオン(解離シュウ酸)は含まれないと解するのが相当で ある。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.11.12
平成28(ネ)10058 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成28年10月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
また,背景の基調色が濃紺色であること自体が商品の出所を表示するものであると認めるに足りる証拠はない。証拠(甲34の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,各食品メーカーは,同種の自社製品につき,同じ形状とレイアウトデザインの包装用袋を採用し,製造者又は販売者を示す標章を記載しつつ,商品ごとに部分的に記載内容や基調色を変えることを,一般的に行っており,そのような一連の商品が多数市場に流通していると認められるところ,一般消費者も,これを認識して購買しており,包装用袋の形状及びレイアウトデザインの特徴,製造者又は販売者を示す標章によって,その商品の出所を識別するのが通常であり,背景の基調色が,前記の各点以上に重要な考慮要素とされているとは考え難い。画像や文字を目立たせるために,黄色に対して青紫色などの反対色を背景に着色することは,一般的には,よく行われる色彩の選択であり,食品ないしサラダの包装用袋の商品表\示において,かかる配色が従前なかったとしても,そのことのみをもって,前記認定を左右するとは認められない。
・・・・
しかしながら,食品において,種々の新製品が開発され,流通に置かれていることは,公知の事実であり,以前に控訴人表示のような表\示がなかったことのみをもって,控訴人表示が自他商品識別力を有するに至るとは考えられない。商品名を表\示の上部などの読みやすい位置に大きく表示し,背景色が濃色の場合は白抜きにすることは,ありふれた表\示であるといわざるを得ないし,食品において,その包装用袋の一部を透明にして内容物を当該袋の外から見られるようにすることも,ありふれた表示である(甲34の1,2)。前記認定のとおり,控訴人表\示の左上の標章の部分を除けば,その余の表示部分が,自他商品識別力を有するに至っているとは認められない。したがって,控訴人の前記主張は,採用できない。\n
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2016.11.12
平成28(ネ)10051 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成28年10月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
そうすると,被控訴人商品の商品名及び「80種類の酵素と青汁」という表示を\n含む包装箱表面の模様は,緑色の背景に白抜きで商品名が記載されており,「80種\n類の酵素と青汁」という文字列が記載されているという点において,控訴人商品の 包装箱表面の模様と類似するということができるものの,商品名が配置されている\n位置や背景の形状,同一の背景の中に描かれた他の模様が著しく相違しているし, 「80種類の酵素と青汁」という文字列が配置されている位置,背景及び文字色も 大きく異なっており,その余の部分も含めた包装箱表面の模様全体としてみると,\nその類似性は低いものと認められる。 また,甲3の2,甲4の2及び弁論の全趣旨によれば,控訴人主張の控訴人商 品及び被控訴人商品の各裏面の栄養成分表示と商品説明文は,配置や記載内容は類\n似するものの,いずれも青汁という製品に共通する格別の特徴がないありふれた形 態であると認められる。 以上によれば,控訴人主張の控訴人商品の形態のうち,包装箱及び銀包の形状並 びに包装箱裏面の栄養成分表示と商品説明文については,同種の製品に共通する特\n徴のないごくありふれた形態であって,「商品の形態」を構成するものとはいえない\nし,包装箱表面の商品名及び「81種類の酵素と青汁」という文字を商品の形状に\n結合した模様として参酌しても,それらを含む包装箱表面の模様全体の類似性は低\nく,実質的に同一の形態ということはできないから,被控訴人商品が控訴人商品の 「商品の形態を模倣した商品」であると認めることはできない。
2016.11. 1
平成28(行ケ)10090 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年10月27日 知的財産高等裁判所
認定事実によれば,本件商標の登録査定時(平成26年9月8日) において,申立人は,我が国のスキンケア市場における有力メーカーの一つ\nであり,とりわけドクターズコスメの分野では,パイオニア的な存在である とともに,圧倒的なシェアを誇るトップメーカーであって,スキンケア化粧 品やドクターズコスメの取引者,需要者らに広く知られる存在であったこと, 申立人が製造,販売する商品の中でも,アクアコラーゲンゲル化粧品は,申\ 立人の設立当初から15年以上にわたって継続的に販売される主力商品であ り,全国でのテレビCMをはじめとする大規模かつ長年に及ぶ宣伝・広告等 により,近年においては,年間100億円を超える売上高を維持し,各種の 人気投票等でも常に上位にランクされるなど,人気商品としての地位を確立 し,スキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者,需要者らに広く知られ ていたこと,アクアコラーゲンゲル化粧品に係る上記宣伝・広告等の多くに おいては,「アクアコラーゲンゲル」という商品名の片仮名表記とともに,\n当該化粧品容器の画像が表記され,その中には,ドクターシーラボ標章の下\nに「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字が組み合わされた標章(引用商標1と実 質的に同一の標章)が表示され,更に,その下に,各種の商品ごとに付加さ\nれた名称(「Super Moisture」など)が表示されていることが認められる。\n そして,これらの事実を総合すると,アクアコラーゲンゲル化粧品の商品 名を片仮名で表記した「アクアコラーゲンゲル」の標章及び引用商標1は,\n本件商標の登録査定時(平成26年9月8日)において,申立人が製造,販\n売するアクアコラーゲンゲル化粧品を表示する商標として,全国のスキンケ\nア化粧品やドクターズコスメの取引者,需要者らの間において広く認識され ていたものと認めることができる。 また,商品の製造,販売を行う企業においては,その企業自体の営業標識 となるロゴやマーク(いわゆるハウスマーク)を用いるほかに,商品のブラ ンド名を表す商標を用いる場合があり,その中でも,シリーズ商品や一定の\nカテゴリーに属する複数の商品群に統一的な商標(いわゆるファミリーマー ク)を使用した上で,その中の個々の商品について,ファミリーマークに付 加して個別の商品を識別するための標章(いわゆるペットマーク)を使用す ることが一般的に行われており,また,これらのマークを組み合わせて使用 することも一般的に行われている(当裁判所に顕著な事実)。そこで,この ような取引の実情を踏まえて考察すれば,前記宣伝・広告等におけるアクア コラーゲンゲル化粧品の容器の画像中の標章に接した取引者,需要者らにお いては,その構成中のドクターシーラボ標章については,企業名である「ド\nクターシーラボ」の欧文字表記に相当する「Dr.Ci:Labo」の文字を含む図形 であり,申立人の広告等の中で単独でも用いられていることから,申\立人の ハウスマークに相当するものとして認識し,また,その下の「AquaCollagen-Gel」の欧文字については,アクアコラーゲンゲル化粧品に共通し て用いられる「アクアコラーゲンゲル」の商品名を欧文字表記したファミリ\nーマークに相当するものとして認識し,更に,その下の「Super Moisture」 などの表示については,アクアコラーゲンゲル化粧品のシリーズにおける個\n別の商品を識別するためのペットマークに相当するものとして認識し,全体 として,これらのマークが組み合わされた商標であると自然に理解するもの と考えられる。してみると,引用商標1は,その全体が,申立人の製造,販\n売するアクアコラーゲンゲル化粧品を表示するというのみならず,その構\成 中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分のみをとらえても,アクアコラーゲ ンゲル化粧品を示すファミリーマークに相当するものとして独立の商品識別 機能を果たしているというべきであり,引用商標1及びその構\成中の 「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分は,全国のスキンケア化粧品やドクター ズコスメの取引者,需要者らの間において,そのようなものとして認識され, 広く知られていたということができる。
2 本件商標と引用商標1及び2の類否について
そこで,以上を踏まえた上で,本件商標と引用商標1及び2との類否につい て判断する。
本件商標について
原告は,本件商標の構成中,「AQUA COLLAGEN GEL」の文字部分が独立し て自他商品の識別標識としての機能を果たし,これから「アクアコラーゲン\nゲル」の称呼が生じるとした本件決定の判断は誤りである旨主張するので, 以下検討する。
ア 本件商標は,別紙1記載のとおり,上段に欧文字の「Dr.Coo」を,下段 に欧文字の「AQUA COLLAGEN GEL」を,それぞれ横書きしてなる結合商標 である。 しかるところ,上記「Dr.Coo」の文字と上記「AQUA COLLAGEN GEL」の 文字とは,上下二段に分けて表記されている上,前者の文字が後者よりや\nや大きいこと,前者が大文字と小文字の組合せであるのに対し,後者は大 文字のみからなること,両者の文字数の違いにより,両者の文字列全体の 幅が大きく異なることといった相違があることからすると,両者は,外観 上明瞭に区別して認識されるものといえる。 また,本件商標から生じる観念についてみても,「Dr.Coo」の文字から は,直ちに特定の観念が生じるとは認められず,他方,「AQUA COLLAGEN GEL」の文字については,「AQUA」は「水」を,「COLLAGEN」は「コラー ゲン(硬たんぱく質の一種)」を,「GEL」は「コロイド溶液がゼリー状 に固化したもの」をそれぞれ意味する外国語として一般的に知られている ことから,これらを組み合わせた観念が生じることが考えられるが, 「Dr.Coo」の文字と結びついた観念が生じるものではないから,両者は, 観念の点においても特段の結びつきがあるものではなく,明瞭に区別して 認識されるものといえる。 加えて,前記1 で述べたとおり,「アクアコラーゲンゲル」の標章及 び引用商標1の構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が,申立人の\n製造,販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を示すものとして,スキンケ ア化粧品やドクターズコスメに係る全国の取引者,需要者らに広く認識さ れている事実からすれば,本件商標がその指定商品である「コラーゲンを 配合したゲル状の化粧品,コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類」に 使用された場合,これに接した取引者,需要者が,スキンケア化粧品等の 分野において周知な「アクアコラーゲンゲル」の標章や「Aqua-CollagenGel」の文字と称呼や欧文字の綴りを共通にする下段の「AQUA COLLAGEN GEL」の部分に特に注目することは,自然にあり得ることであるといえる。 以上を総合すれば,本件商標においては,その構成のうち下段の「AQUA COLLAGEN GEL」の文字部分が,取引者,需要者に対し商品の識別標識とし て強く支配的な印象を与える部分として認識されることがあるというべき であるから,当該部分を本件商標の要部として把握することが可能であり,\nそこから,「アクアコラーゲンゲル」の称呼が生じるとともに,申立人の\n製造,販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の 観念が生じるものと認めることができる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.10.28
平成28(行ケ)10058 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年10月26日 知的財産高等裁判所
本件発明1は,その請求項1の文言からして,少なくとも,ドライブスプロケッ トと回転軸が相互に軸方向に移動自在であるドライブスプロケット支持構造である\nと認められる。これに対し,審決は,上記1(3)のとおり,甲2発明において,ドラ イブスプロケット21がポンプハブ11に対して軸方向に移動自在でないとし,こ の点を両発明の実質的な相違点とする。この審決の判断は,甲2発明の認定を誤っ た結果,相違点の認定を誤ったものである。 そうすると,かかる相違点の認定を前提とする相違点の判断も誤りであり,これ らの誤りは,審決の結論に影響を及ぼすといえる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2016.10.28
平成28(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年10月26日 知的財産高等裁判所
(2) 引用例2(甲3)には,以下のとおり,引用発明2が開示されている。 好きな食事を任意に摂取できる食環境について,より低コストかつ迅速な配送が 可能で,管理や作業が容易であり,かつ,発送者,受取者の利用者双方の要求に臨\n機応変に適応できるような,便利で効率のよい配送システムを提供するために (【0007】【0008】),権限を有する所定の配送作業者及び利用者のみが 荷物を出し入れすることができるボックスなどの収容手段を複数有する集合住宅の 玄関などに設置された配送中継装置と,利用者端末装置と,管理装置と,中食提供 者端末装置とを備え,利用者が利用者端末装置を操作して,中食の内容,当該中食 を利用者が受け取る時間及び配送中継装置を指定した注文を管理装置に送信し,管 理装置が,上記受信した注文について,中食提供者端末装置に対して,指定された 内容の中食を製造することを指示するとともに,中食配送者端末装置に対して,上 記指定された時間までに指定された配送中継装置に中食を配送することを指示し, 中食配送者が,中食配送者端末装置が受けた指示を基に,中食提供者から受け取っ た中食を,上記指定された時間までに,指定された配送中継装置の所定のロッカー に保管されるよう配送し,配送中継装置は,所定の管理期間が経過しても利用者が 中食を取りにこないと判断した場合には,利用者のメールアドレスにその旨を通知 する,中食配送システム(【0029】【0032】【0054】〜【006 6】)。
(3) 引用発明1は,前記2(2)のとおり,集合住宅内に設置された宅配ボックス から成り,受取人宛ての荷物が配達され宅配ボックスに保管されると,通信サーバ が,荷物の受取人宅宛てに電子メールを送信する宅配ボックスシステムである。そ して,引用発明2は,前記(2)のとおり,ボックス等の収納手段を有する集合住宅の 玄関などに設置された配送中継装置から成り,利用者の注文した中食が配送され配 送中継装置に保管され,その後所定の管理時間が経過しても中食が取られない場合 には,配送中継装置が,中食の受取人である利用者のメールアドレスに通知を送る 中食配送システムというものである。 したがって,引用発明1と引用発明2は,ともに,集合住宅に設置された保管ボ ックスから成り,配達され保管された利用者宛ての荷物について,システムから利 用者に対しメール通知を行う荷物の配送システムという,共通の技術分野に属する ものである。そして,引用発明1と引用発明2は,いずれも,荷物の配送システム において,インターネット等を利用して発送者,受取者等の利用者の利便性を向上 させるという課題を解決するものということができ,引用発明1のシステムの利便 性を向上させるために,利用者端末装置や管理装置を含む引用発明2の構成を組み\n合わせる動機付けがあるというべきである。
(4) 他方,引用発明1は,自分宛ての荷物の注文が,誰によりどのようになされ たものであるのか何ら特定していないから,自分宛ての荷物の配達として,利用者 自らの注文によらない場合の配達サービス(具体的には,他者による注文に基づく 荷物の配達)に限定されないと解するのが自然であり,また,引用例1の【001 9】における「…たとえば最近のインターネット通販などによる高価な宅配物の増 加に対して極めて有効なセキュリティシステムとなる。」との記載には「インター ネット通販」が例示として挙げられているのであって,引用発明1が,インターネ ット通販のような,利用者自らが自分宛ての荷物を注文し,当該注文した荷物を配 送業者等により自身宛てに配達してもらう形態を排除していないと解するのが相当 である。 そうすると,引用発明1に対し,共通の技術分野に属し,共通の課題を有する引 用発明2を適用する上での阻害要因は何ら認められないというべきである。
(5) 原告らの主張について
原告らは,引用例1では,高価な宅配物を対象とするインターネット通販におい て,高いセキュリティシステムを適用することが開示されているにすぎないのに対 し,引用例2では,インターネットを介して中食を発注するシステムが開示されて いるものの,高価な宅配物を対象とするものではなく,また,二つの暗証番号を入 力するといった高度なセキュリティを必要とするものではないから,引用例1と引 用例2が対象とする宅配物は全く異なるものであり,単にインターネット通販に係 るものであるからといって,引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けは一 切存しないと主張する。 しかし,引用例1自体,高度のセキュリティを備えることを必然の構成としてい\nるわけではないし(甲2の【0016】〜【0019】),配送対象の荷物が高価 であるか否かや,高度なセキュリティを要するか否かが,技術分野及び課題の共通 性を阻害し動機付けを失わせるとはいえないから,原告らの上記主張は理由がない。
(6) したがって,引用発明1に対し,共通の技術分野に属し,課題においても共 通する引用発明2を適用することの動機付けがあり,かつ,適用する上での阻害要 因が何ら認められないのであるから,引用発明1におけるユーザのモバイル端末に おいて,引用発明2の技術を適用することで,発注機能を備えるよう構\成して相違 点1に係る構成とすることは,当業者が容易に想到することができたものである。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 引用文献
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2016.10.28
平成28(行ケ)10009 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年10月26日 知的財産高等裁判所
引用例2には,そこに記載された加湿器が,給水部の水位を検知する検知装置を 備えた加湿器において,表示部が,給水部の水位が一定の水位よりも低くなると,\nあらかじめ定めた第1表示内容を表\示し,モーターが所定時間以上回転した後,モ ーターを停止し,あらかじめ定めた第2表示内容を表\示するものであることが記載 され(【0005】),かかる構成にしたことにより,給水部の水位が一定の水位\nよりも低くなった後,給水を促す表示をするが,モーターが所定時間の5分間以上\n回転しているため,モーターが回転している間に使用者が給水を促す表示に気が付\nき,給水を行えば,加湿運転を停止させて部屋を乾燥させてしまうことがない,ま た,モーターの回転を低速回転とするため,加湿量が減って給水部の水位が一定の 水位よりも低くなった後はゆっくりと水位が下がり,長時間加湿できることから, その間に給水を促す表示に気が付きやすいなどと記載されている(【0009】,\n【0010】)。また,【0036】ないし【0038】には,給水部2の水位が 基準の水位よりも低くなると,ファン3を低速回転とし,ヒーター8をOFFとし, タイマーに所定時間の5分間以上の時間を設定し,表示部6には第1の表\示内容で ある「給水」及びタイマー残時間の表示をして,タイマーの減算を開始すること,\nタイマーの残時間が0となったらファン3を停止し,表示部6には第2の表\示内容 である「給水」点滅の表示をすることが記載されている。\nこれらの記載によれば,引用例2に記載の加湿器は,部屋の乾燥を防止するため に,水位が「一定の水位」より低くなった後も,モーターが所定時間以上回転し, さらに,低速回転とすることで長時間加湿をすることが可能なものである。そして,\n「第1表示内容」が「給水」という文字及びタイマー残時間を表\示するものである から,「一定の水位」は,給水が一応求められる水位であるといえるものの,タイ マー残時間分のファンの継続運転によって,上記「一定の水位」よりさらに低くな った水位における「第2の表示内容」が「給水」という文字を含む点滅表\示である ことに照らせば,上記「一定の水位」は,タイマー残時間分の加湿運転の余地があ る水位を意味するものと理解される。 したがって,引用例2における「一定の水位」は,それを下回る水位でも加湿機 能が適正に動作して加湿空気を生成することができ,それを下回る水位が検出され\nた後も加湿機能の動作を行わせることを前提とするものであるということができる。\n(ウ) 以上によれば,引用例2に記載された技術事項における,給水部の水位を 検知する検知装置が検知する「一定の水位」は,引用発明におけるフロートスイッ チ14の「第1の基準位置における接点」とは,水位の性質,すなわち,それを下 回る水位でも加湿機能が適正に動作できるか否か及び加湿機能\の動作を行わせるこ とを前提としているか否かという点において,明らかに相違する。 加えて,引用発明において,液面検出手段を構成するフロートスイッチ14は,\n「第1の基準位置H1における接点」のみならず,「第2の基準位置H2における 接点」を有するところ,「第2の基準位置H2における接点」が検出する液面高さ の「第2の基準位置」は,加湿機の運転時の場合には,水面高さ(液面高さ)が第 1の基準位置H1以上の場合には運転が継続される,すなわち,液面高さが「第2 の基準位置」を下回っても,第1の基準位置を上回る限りにおいて,加湿機の運転 が継続されるものである(【0028】)。そうすると,所定の水位を下回る液面 高さでも加湿機能が動作して加湿空気を生成することができ,それを下回る水位が\n検出された後も加湿機能の動作を行わせるものである点において,引用例2におけ\nる「一定の水位」と引用発明の「第2の基準位置H2における接点」は共通するも のであるということができる。 このように,引用例2の「一定の水位」は,フロートスイッチ14の「第1の基 準位置における接点」とは水位の性質(それを下回る水位でも加湿機能が適正に動\n作できるか否か及び加湿機能の動作を行わせることを前提としているか否かという\n点)において明らかに相違し,かつ,引用発明には,上記性質において共通する 「第2の基準位置H2における接点」が既に構成として備わっているにもかかわら\nず,引用発明において,フロートスイッチ14の「第1の基準位置における接点」 を引用例2の「一定の水位」を検知する構成に置き換える動機付けがあるというこ\nとはできない。 (エ) さらに,引用発明におけるフロートスイッチ14の「第1の基準位置H1 における接点」を,引用例2に記載された技術事項(それを下回る水位が検出され た後も加湿機能の動作を行われせることを前提した「一定の水位」を検出対象とす\nるもの)に置き換えると,引用発明におけるフロートスイッチ14の「第1の基準 位置H1における接点」は,液面高さが「第1の基準位置」を下回ったことを検出 しても加湿機能を引き続き動作させることになるから,引用発明におけるフロート\nスイッチ14の「第1の基準位置H1における接点」に係る構成により奏するとさ\nれる,加湿部の動作を自動的に停止して液体収容槽の液体の残量がないときにファ ンを無駄に動作させることを防止できるという効果(【0009】)は,損なわれ ることになる。 そうすると,引用発明におけるフロートスイッチ14の「第1の基準位置H1に おける接点」を,引用例2に記載された技術事項である,「一定の水位」を検知す る構成に置き換えることには,阻害要因があるというべきである。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2016.10.28
平成28(ネ)10042 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年10月26日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
本件発明の「押付部材」は,少なくとも一部に球状面を有するものでは足りず,その全体が球であるものに限られるということができる(仮に,一部にのみ球状面を有するものが含まれるとすれば,本件特許は違法な分割出願によるものとして新規性欠如の無効理由を有することが明らかである。)。
判決文の最後に、イ号と本件発明の対比図面が掲載されています。
証拠(甲4,甲32の1・2,乙38,54)及び弁論の全趣旨によれば,被告 製品の技術的意義につき,以下のとおり認められる。 プランジャーピンは,その大径部に略円錐面形状を有する傾斜凹部を備えている ものであるが,コイルバネにより付勢されて本体ケースの内周面に左右2箇所で接 触するように設計されている。コマ状部材は,導電性を有するものであり,その球 状部がプランジャーピンの大径部の傾斜凹部を押してこれと1点のみで接触するこ とによって傾き,本体ケースの内周面に左右2箇所で接触するように構成されてい\nる。プランジャーピン及びコマ状部材が確実に傾いて本体ケースに接触するよう, コマ状部材の中心軸とプランジャーピン底面の最深位置は,オフセットされている。 このように合計4つの電流経路を確保することにより,被告製品の電気抵抗が低 減し,被告製品を流れる電流についてコイルバネを通る経路以外の経路が存在しな いという事態が生じる可能性は低くなり,コイルバネに流れる電流量が抑えられる。\n加えて,コイルバネが●●●●●●●によって被覆されていることから,絶縁性ボ ールを使用する必要はない。 他方,本件発明においては,前記(2)のとおり,1)傾斜凹部を略円錐面形状とする ことによって,押付部材の球状面からなる球状部の中心を傾斜凹部の中心軸上に安 定して位置させることができ,それにより,押付部材を介してプランジャーピンに 伝達されるコイルバネの付勢に係る力の方向を安定させ,2)さらに,傾斜凹部の中 心軸をプランジャーピンの中心軸とオフセットさせることにより,コイルバネがプ ランジャーピンを本体ケースの中心軸に対して微小な角度を有する方向に付勢する ことを確実なものとすることによって,プランジャーピンの大径部を確実に本体ケ ースの管状内周面に接触させて本体ケースへ確実に電流を流すことを可能とするも\nのである。 以上によれば,被告製品と本件発明とは,押付部材とプランジャーピンとの接触 に関し,技術的意義を異にするものということができる。
(ウ) 控訴人の主張について
a 控訴人は,コマ状部材とプランジャーピンの材料である金属は,弾性変化す るものであるから,両部材は,必ず面で接触し,点で接触することはあり得ない旨 主張する。 しかし,甲第52号証によれば,球と平面が接触する場合,理論的には,接触部 分は点であり,接触面積を持たないものの,実際には,接触部分が変形することに よって接触面積を持ち,接触部の形状が円になり,このような接触は,「点接触」と 呼ばれる。前記(イ)において,被告製品のコマ状部材の球状部がプランジャーピン の大径部の傾斜凹部と1点のみで接触するというのも,上記点接触の趣旨であり, 控訴人主張に係る弾性変化した状態の接触を排除する趣旨ではない。
b 控訴人は,甲第4号証を根拠として,被告製品のコマ状部材は,コイルバネ から押圧されてその弾性力を受け止めており,同弾性力がコマ状部材と本体ケース との間の摩擦力よりも大きいときは,空滑りして傾かず,本体ケースに接触しない 旨主張する。 しかし,甲第4号証に掲載された被告製品の写真からは,コマ状部材が本体ケー スにわずかでも接触しているか,全く接触していないかは,必ずしも明らかではな い。また,コマ状部材の中心軸とプランジャーピン底面の最深位置がオフセットさ れていることに鑑みると,通常,コマ状部材が本体ケースに接触しないという事態 が頻繁に生じることは考えにくく,そのような事態は,被告製品の通常の用法にお いて想定されていないものと考えられる(乙54参照)。
c 控訴人は,プランジャーピンに流れる電流の総和は決まっているので,プラ ンジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができれば,コイルバネに流 れる電流量を相対的に減じることができ,コイルバネの焼切れの防止にもつながる 旨を主張する。 しかし,上記主張のとおりであったとしても,本件明細書には,被告製品のよう にプランジャーピンと本体ケースとの接触に加え,押付部材であるコマ状部材と本 体ケースとの接触により合計4つの電流経路を確保することによって被告製品の電 気抵抗を低減させるという技術的思想は,開示されていない。
d なお,控訴人は,乙第38号証に掲載された被告製品のプランジャーピンの 図においては,底部の形状が傾斜凹部をなしていないが,これは,正確なものでは なく,甲第32号証の1・2が,被告製品の正確な設計図である旨主張する。しか し,控訴人が指摘する乙第38号証の図面は,「マッシュルーム要素及びプランジャ ーの形状を大まかに描写した断面図」(乙38)であり,甲第4号証及び乙第38号 証に掲載された被告製品の写真並びに控訴人が被告製品の正確な設計図である旨主 張する甲第32号証の1・2により,前記(イ)のとおり認定することができる。
イ 構成要件Dの「押付部材」に該当する構\成の有無
前記アのとおり,被告製品のコマ状部材は,それ自体が本体ケースの内周面に左 右2箇所で接触して電流経路を確保している。 他方,前記(1)のとおり,本件明細書において,「押付部材」につき,小型化の要請 にこたえて接触端子の径(幅)を大きくすることなく,コイルバネを流れる電流量 を小さくしながら,比較的大きな電流を流し得る接触端子の提供という,本件発明 の課題を解決するための構成として,「大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部」内\nに収容されていることが開示されている。本件明細書において,「押付部材」自体が 本体ケースに接触して電流経路を確保することは,開示されていないものというべ きである。 したがって,被告製品のコマ状部材は,構成要件Dの「押付部材」に該当しない。\nほかに,被告製品の構成中,「押付部材」に相当するものはない。
ウ 「押圧」について
前記アのとおり,被告製品は,プランジャーピン及びコマ部材が確実に傾いて本 体ケースに接触するよう,コマ状部材の中心軸とプランジャーピン底面の最深位置 をオフセットしている。被告製品のコマ状部材の球状部がプランジャーピンの大径 部の傾斜凹部を押してこれと1点のみで接触することによって傾き,本体ケースの 内周面に左右2箇所で接触するという構成自体からも,通常,コマ状部材の球状部\nの中心が,プランジャーピン底面の最深位置,すなわち,傾斜凹部の中心軸上に位 置することは,考え難い。現に,別紙2は,コイルバネの付勢によって,コマ状部 材の球状部がプランジャーピンの大径部の傾斜凹部を押し,それによって,プラン ジャーピンの突出端部が本体ケースから突出するとともに,プランジャーピンの大 径部の外側面が本体ケースの内周面に押し付けられている状態であるが,コマ状部 材の球状部の中心は,明らかに傾斜凹部の中心軸からずれている。 よって,コマ状部材の球状部がプランジャーピンの傾斜凹部を押すことは,コマ 状部材の球状部の中心を傾斜凹部の中心軸上に安定して位置させるものではないか ら,構成要件Dの「押圧」に該当せず,ほかに,被告製品の構\成中,「押圧」に該当 するものはない。
・・・
しかし,特許請求の範囲に記載された構成中,相手方が製造等をする製品又は用\nいる方法と異なる部分が存する場合において,均等侵害の成立が認められるために は,上記異なる部分の全てについて均等の5要件が満たされることを要する。 前記2のとおり,本件特許請求の範囲に記載された構成と被告製品とは,1)構成\n要件Dの「押付部材」につき,本件明細書において,小型化の要請にこたえて接触 端子の径(幅)を大きくすることなく,コイルバネを流れる電流量を小さくしなが ら,比較的大きな電流を流し得る接触端子の提供という,本件発明の課題を解決す るための構成として,「大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部」内に収容されてい\nることが開示されており,「押付部材」自体が本体ケースに接触して電流経路を確保 することは,開示されていないのに対し,被告製品のコマ状部材は,それ自体が本 体ケースの内周面に左右2箇所で接触して電流経路を確保している点において異な るほか,2)構成要件Dの「押圧」は,押付部材の球状面からなる球状部の中心を傾\n斜凹部の中心軸上に安定して位置させるものであるのに対し,被告製品のコマ状部 材の球状部がプランジャーピンの傾斜凹部を押すことは,コマ状部材の球状部の中 心を傾斜凹部の中心軸上に安定して位置させるものではない点においても異なる。 控訴人は,これらの相違点のうち,構成要件Dの「押付部材」が球形であるのに\n対し,被告製品のコマ状部材が球形ではないという点についてのみ均等の5要件を 主張するにとどまるから,主張自体,失当である。 なお,前記2(4)のとおり,被告製品と本件発明とは,押付部材とプランジャーピ ンとの接触に関し,技術的意義を異にするものということができる。そして,前記 1のとおり,本件明細書には,従来技術として,金属製の本体ケースに設けられた 長穴にコイルバネを挿入した上でプランジャーピンを挿入し,本体ケースからプラ ンジャーピンの先端部分のみが突出する位置を保持されるという接触端子において, プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球を介在させ,プランジャーピンの本 体ケース内の端部が斜面となっていて,絶縁球がプランジャーピンを本体ケースの 長穴の内面に押し付けることができるようになっており,これによって,プランジ ャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができるとの構成が開示されてい\nる(【0002】,【0004】,【0006】)。したがって,本件発明においては,前記2のとおり,1)プランジャーピンの大径部に,単なる斜面ではなく,略円錐面形 状の傾斜凹部を設け,押付部材の球状面からなる球状部の中心を傾斜凹部の中心軸 上に安定して位置させるよう「押圧」すること及び2)傾斜凹部の中心軸をプランジ ャーピンの中心軸とオフセットさせることによって,コイルバネが,押付部材を介 して,プランジャーピンを本体ケースの中心軸に対して微小な角度を有する方向に 付勢することを確実なものとすることによって,プランジャーピンから本体ケース へ確実に電流が流れるようにすることが,従来技術に見られない,特有の技術的思 想を構成する特徴的部分に当たるというべきである。\n前記2によれば,本件発明と被告製品は,上記本質的部分において相違すること が明らかであるから,均等侵害の成立を認める余地はない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> ピックアップ対象
2016.10.28
平成27(ワ)2504 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成28年10月13日 大阪地方裁判所
原告は,原告標章1の上下に2本の直線を追加すると,「Z」との文字が浮かび 上がり,被告標章1も,原告標章1を構成する2つの三角形状の図形にそれぞれ3本の白線を追加したものにすぎず,同様に「Z」の文字が浮かび上がるもので,両 者は類似する旨主張する。 しかし,標章の上下に2本の直線を追加すると「Z」の文字が浮かび上がるとい ったことは,需要者が容易に認識し得るものではないことからすれば,この点が類 否に影響を及ぼすものではない。 原告標章1は,一辺を曲面の凹面で切り取られた赤色の鈍角三角形2つが上下に 凹面が来るように点対称に配置された旗のようなマークであり,被告標章1は,原 告標章1に,対置する底面に平行な3本の白い線を各鈍角三角形部分に入れたもの であるので,確かに,外周の形態及び色は類似しているといえるが,本体である鈍 角三角形に縞模様が入っているか否かは需要者が容易に区別し得るものであり,相 当異なる印象を与えるものであるから,原告標章1と被告標章1を全体として見比 べると,相当異なるものであることは一見して明らかである。 したがって,被告標章1は,原告標章1とは類似しないというべきである。
3 争点3(被告は被告各標章及び本件ドメインを使用しているか)について
被告が運営する被告2店舗は,原告標章2,7を外壁に掲げた原告店舗の近隣に あって競業関係にあり,しかも周知商品等表示である原告各標章5ないし7に類似する被告標章11,12を店舗の出入口に掲げていたというのであり,またその店\n舗名に「ゼンシン」という原告及び「全秦グループ」を他から識別する部分を含ん でいたというのであるから,その開業当初は,需要者である遊戯客に原告店舗ない し原告との関係につき一定の誤認混同を生じさせたことは優に認められるといえる (上記ア(オ)dのとおり,取引業者であるが,現に誤認混同していた実例も認められ ている。)。 しかし,上記ア(エ)によれば,そもそもパチンコ店等の需要者である遊戯客による 店舗選択は,当該パチンコ店等の経営主体がどこであるとか,どのパチンコ店グル ープの店舗であるかということを重視するのではなく,パチンコやパチスロの台の 機能や機種,出玉感,交換率等の個別店舗の具体的営業内容そのものを主要な選択要素として決せられることが認められ,これからすると当該店舗の営業主体の誤認\n混同が当該店舗の選択,ひいてはその売上げあるいは損害に結び付く関係は薄弱で あるということができる。 なお上記ア(エ)からは,需要者である遊戯客には,店員の接客態度や店舗が清潔に 清掃されているか等のサービスについても選択時に考慮する要素としている者がい ることも認められるから,それらの需要者であれば,店舗の営業主体を指し示す営 業表示を手掛かりに当該店舗で受けられるサービスを期待して店舗選択をする可能\ 性があることは否定できない。しかし,需要者であるパチンコ店等の遊戯客は,パ チンコ店を極めて頻回に利用するのが一般的であるというのであるから(週1日の 利用でも年間72日の利用になる。),仮に被告2店舗の需要者の利用が,被告標 章の使用によりもたらされた被告店舗が原告と関係する店舗であるとの誤認混同か ら始まったとしても,当該店舗のサービスを実際に経験している以上,その後の継 続的利用が原告と被告2店舗との関係についての誤認混同の影響によりもたらされ ているとは考え難いところである。 そして,そもそも原告店舗及び被告2店舗とも隠岐の島という需要者が限られた 市場の中で他の4店舗とも競合している店舗であるが,被告2店舗のうち,ゼンシ ン隠岐がもともとあったパーラー隠岐という別店舗の営業実態を実質上承継してい る関係にあることからすると,被告2店舗の営業が原告店舗の顧客の誤認混同によ り生じた需要によって継続的に成り立っているとはおよそ考えられず,むしろその 影響は極めて小さいと見る方が合理的である。 なお,本件において被告が被告標章を使用して営業を営んでいるのは隠岐の島の 被告2店舗だけであり,不正競争防止法5条2項で推定されるべき原告の損害は, 被告2店舗の営業の影響を受ける範囲,すなわち,その競合店となる原告店舗にお いて生じた損害だけが問題となるというべきであるから,被告による被告各標章の 使用態様のうち,隠岐の島の住民において認識されないような岡山県津山市所在の 本件建物の外壁に掲げられた被告標章2,6による標章の使用は原告店舗の営業に 損害を全くもたらさないことは明らかである。 したがって,このような事情を総合考慮すると,本件における被告の得た利益と 原告の受けた損害の関係に不正競争防止法5条2項の推定規定の適用があるとして も,その推定は99%の限度で覆滅されるというべきである。 なお,原告は,原告店舗と被告2店舗の営業方法の類似性,さらには原告代表者としてのP1の競業避止義務違反さえ問題としているが,そこで問題とされる損害\nは,結局のところ,営業表示の誤認混同に由来する損害ではなく,単に原告店舗の近隣に競合店である被告2店舗が出店されたことから生じる原告店舗の売上減少の\n問題にすぎないから,不正競争防止法2条1項1号の不正競争により生じる損害の 議論としては失当であり,上記認定を左右するものではない。
(4) 上記(1)アのとおり,被告が,被告2店舗で得た利益は合計6億6654万1 348円であるから,原告において損害と推定される額は,666万5413円で あると認められる。
(5) 不正競争防止法5条3項の適用による損害について
本件で問題とする原告各標章は周知商品等表示であり,これに類似する被告標章7ないし9及び11ないし13の使用の結果,現実的な誤認混同が生じた事実も認\nめられるから,顧客吸引力が全くない商標権の場合と同様の意味での損害不発生を いう被告の主張は直ちには採用できない。 しかし,上記(2)で検討したとおり,パチンコ店等では,需要者は,主に営業表示以外の営業内容そのものの要素を選択肢として店舗を選択するというのであるか\nら,営業表示により誤認混同が生じたとしても,そのことが店舗選択に与える影響は極めて小さく,しかも,その需要者は店舗を頻回に利用するというのであり,そ\nのような需要者を顧客としてつなぎとめるためには,出玉であるとか交換率である などのパチンコそのものの営業内容によって他店と競争しなければならないといえ るから,原告各標章の営業表示に顧客吸引力があるとしても,営業の場面で,これを発揮する余地は限りなく少ないというべきである。\nしたがって,本件において認定できる被告の不正競争に対して原告が受けるべき 金銭の額は極めて少額にとどまるのが相当であり,これを認めるとしても,被告が 不正競争により受けた利益に基づき認定される不正競争防止法5条2項にいう原告 の損害の額を上回ることはないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 周知表示(不競法)
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2016.10.25
平成28(ネ)10059 著作権侵害行為差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年10月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
第三に,原告各製品は,幼児が食事をしながら正しい箸の持ち方を簡 単に覚えられるようにするための練習用箸であって,その目的を実現す るために,2本の箸を連結する,あるいは,箸を持つ指の全部又は一部 を固定するというのは,いずれもありふれた着想にすぎず,このことは 甲16〜26の各製品や,乙5〜12の各公報に描かれたデザインを見 ても明らかである。また,かかる着想を具体的な商品形態として実現し ようとすれば,箸という物品自体の持つ機能や性質に加え,練習用箸と\nしての実用性が求められることからしても,選択し得る表現の幅は自ら\n相当程度制約されるのであって,美術の著作物としての創作性を発揮す る余地は極めて限られているものといえる。 (エ) 以上に基づいて検討するに,まず,箸を連結すること自体はアイデア であって表現ではない(なお,連結部分にキャラクターを表\現すること も,それ自体はアイデアであって,著作権法上保護すべき表現には当た\nらない。)し,その具体的な連結の態様を見ても,原告各製品が他社製 品(甲16〜26)と比較して特徴的であるとまではいえず,まして美 的鑑賞の対象となり得るような何らかの創作的工夫がなされているとは 認め難い。よって,前記1)の点に美術の著作物としての創作性を認める ことはできない。 次に,箸を持つ指やその位置が決まっている以上,これを固定しよう と考えれば,固定部材を置く位置は自ずと決まるものであるし,人差し 指,中指,親指の3指を固定することや固定部材として指挿入用のリン グを設けることも,例えば,原告各製品が製造販売されるより前に刊行 された乙5,7,8の各公報においても類似の構成が図示されている(す\nなわち,乙5及び乙7には,一対の箸のうち1本が人差し指と中指を入 れる2つのリングを有し,他方の1本が親指と薬指を入れる2つのリン グを有するものが図示されている。乙8には,一対の箸のうち1本が人 差し指と中指を入れる2つのリングを有し,他方の1本が薬指を入れる 1つのリングを有するものが図示されている。)ように,特段目新しい ことではない。原告各製品も通常指を置く位置によくあるリングを設け たにすぎず,その配置や角度等に実用的観点からの工夫があったとして も,美的鑑賞の対象となり得るような何らかの創作的工夫がなされてい るとは認め難い。よって,前記2)の点についても,美術の著作物として の創作性を認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2016.10.23
平成26(行ケ)10155 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年10月19日 知的財産高等裁判所(第2部)
上記の実施例と比較例によれば,食塩濃度9.0w/w%の場合には,窒素濃度 が本件発明1の範囲に含まれる1.94〜2.15w/v%の範囲であれば,本件 発明1の範囲から外れるものに比べて,塩味が向上すること,また,苦みはカリウ ム濃度が上限の3.7w/w%であっても苦み3に抑えられることが理解できる。 しかしながら,本件発明1の窒素濃度の範囲内で,窒素濃度がより高くなると, 塩味が強くなる,苦みが抑えられるという傾向があるとは認められない。 また,窒素/カリウムの重量比のみが本件発明1の範囲から外れる例は記載され ていないから,窒素/カリウムの重量比が官能評価に与える影響を,直ちに理解す\nることはできない。
・・・
e 以上によれば,本件発明1に関し,本件明細書の実施例・比較例か ら,課題を解決できることが認識できることが直接示されているのは,食塩濃度が 9.0w/w%の場合のみである。
・・・
以上によれば,本件発明1のうち,少なくとも食塩が7w/w%である減塩醤油 について,本件出願日当時の技術常識及び本件明細書の記載から,本件発明1の課 題が解決できることを当業者は認識することはできず,サポート要件を満たしてい るとはいえない。
・・・
ア 被告は,本件明細書の発明の詳細な説明に「本発明の減塩醤油類の食塩 濃度は・・・7〜9w/w%であることが好ましく」(【0009】)と記載され,具 体的には,実施例において,数値範囲を満たす減塩醤油が,塩味が強く感じられ, 味が良好であって苦みも低減されることが記載されているから,サポート要件違反 はない旨主張する。 しかしながら,本件発明のうち,当該発明の課題を解決できることを具体的に示 しているのは,上記(1)エのとおり,食塩濃度が9w/w%の場合のみである。食塩 濃度が7w/w%まで低下した場合の塩味や苦みを推認するための技術的な根拠が, 本件明細書に記載されておらず,また,どの程度になるかということについての技 術常識もない以上,【0009】の「7〜9w/w%であることが好ましく」という 一般的な記載のみをもって,食塩濃度の全範囲において発明の課題を解決できるこ とについての技術的な裏付けある記載があると認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2016.10.23
平成28(ネ)10041 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年10月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
3 争点2(オリジナル曲の演奏による著作権侵害の成否)について
(1) 1審被告らは,自ら制作したオリジナル曲を演奏することは,1審原告に著 作権管理を信託している著作者自身が許諾しているのであるから,不法行為に当た らないと主張する。 しかし,前記1の認定事実(引用に係る原判決の「事実及び理由」の第4の1(7) イ)のとおり,1審原告と著作権信託契約を締結した委託者は,その契約期間中, 全ての著作権及び将来取得する全ての著作権を,信託財産として1審原告に移転し ているから,1審原告管理著作物の著作権者は,1審原告である。そうすると,利 用者が誰であっても,1審原告の許諾を得ずに1審原告管理著作物を利用した場合 には,当該利用行為は著作権侵害に当たるといわざるを得ない。 このことは,著作権信託契約約款11条が,自作曲の自己利用に関し,著作物の 関係権利者の全員の同意を得た自己利用(委託者がその提示につき対価を得る場合 を除く。)については,あらかじめ受託者の承諾を得て,管理委託の範囲について の留保又は制限をすることができると定めていることからも,裏付けられるところ である。 以上のとおり,演奏者が1審原告に著作権管理を信託した楽曲を演奏する場合で あっても,1審原告の許諾を得ない楽曲の演奏が,1審原告の著作権侵害に当たる ことは明らかであり,1審原告には使用料相当額の損害の発生が認められるから, 著作権侵害の不法行為が成立する。
(2) 1審被告らは,1審原告が著作者自身の演奏申込みも認めない違法な運用を\n行いながら,無許諾を理由に著作者自身の演奏の不法行為責任を追及することは, 管理委託契約の趣旨に反するものであり,許されないと主張する。 しかし,著作者が自ら演奏することを許諾している場合であっても,著作物につ いてのその余の関係権利者の得るべき使用料を分配する必要があることからすれば, 著作者自身の演奏行為について演奏の不法行為責任を追及して使用料相当額を徴収 することが,管理委託契約の趣旨に反するとはいえず,1審被告らの主張は理由が ない
。 (3) したがって,1審被告らの上記主張は採用することができない。
4 争点3(1審被告らの故意又は過失の有無)について
(1) 1審被告らは,前記2(2)の各事実を認識していた上に,前記1の認定事実 (引用に係る原判決の「事実及び理由」の第4の1(4)ア)のとおり,1審被告らは, 本件店舗を開いた後は,1審原告に著作権料を支払わなければならないことを認識 していたのであるから,著作権侵害主体であることの認識があったことは明らかで あり,1審被告らには著作権侵害の故意又は過失があったというほかない。 (2) 1審被告らは,本件店舗における演奏曲目や出演者が権利者から許諾を得た かどうかを知らないから故意がない旨主張する。 しかし,著作権侵害の故意の有無の判断に当たっては,他人が権利を有する楽曲 を利用していることの認識があれば足り,具体的な楽曲名や権利者の認識までは要 しない。また,1審被告らが1審原告管理著作物の利用許諾契約を締結していない こと及び本件店舗における多くのライブにおいて,具体的な数はともかく,1審原 告管理著作物が演奏されていることについては当事者間に争いがないところ,ライ ブハウスの出演者自らが1審原告から許諾を得ることは一般的ではなく,前記1の 認定事実(引用に係る原判決の「事実及び理由」の第4の1(4)ア)のとおり,1審 被告Y2も,本件店舗以外のライブハウスに出演したことがありながら,1審原告 から許諾を得たことはなかったことに照らすと,本件店舗における演奏曲目や出演 者が権利者から許諾を得たかどうかの認識は,本件における1審被告らの主観的要 件の判断を左右するものではない。
(3) また,1審被告らは,著作権侵害の故意は,直接主体たる出演者の各演奏行 為時に存在していなければならず,その内容は,当該出演者が他人の著作物を無許 諾で演奏していること及び場の提供によって1審被告らも共同で当該楽曲を演奏し ていることの各認識ないし認容でなければならないと主張する。 しかし,1審被告らは,各出演者による演奏行為当時,著作権侵害主体であるこ とを基礎付ける事実を認識し,1審被告ら又は本件店舗は1審原告との間で1審原 告管理著作物の利用許諾契約を締結することなく,当該出演者が他人の著作物を演 奏していたのであるから,規範的な侵害主体としての故意に欠けるところはないと いうべきである。
2016.10.23
平成28(ワ)8027 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成28年10月12日 東京地方裁判所
まず,本件商標と被告各標章「フェルゴッド」との部分からは,いずれも特定の 観念を生じないものである。 次に,本件商標からは「フェルガード」の称呼を生じ,被告各標章の「フェルゴ ッド」の部分からは「フェルゴッド」の称呼を生じるところ,両称呼は,「フェル」 で始まり「ド」で終わるとの点において共通するが,両称呼を一連に称呼した場合 には,称呼全体の語調,語感において異なる印象を与えるものというべきである。 さらに,本件商標と被告各標章の「フェルゴッド」の部分の外観についてみても, 同様に「フェル」で始まり「ド」で終わるとの点において共通するが,本件商標は 「フェルガード」(標準文字)から成り,「フェル」や「ド」の部分が特に強調さ れているということもなく,この点は被告各標章の「フェルゴッド」の部分につい ても同様であるから,本件商標と被告各標章の「フェルゴッド」の部分とを一体的 に観察すれば,両者の外観は異なる印象を与えるものというべきである。 以上によれば,本件商標が付された原告商品と被告各標章が付された被告各商品 とがいずれもフェルラ酸とガーデンアンゼリカを主成分とする健康補助食品であり, いずれも白色系統色を基調とする外箱を包装とする点,通信販売により販売されて いる点,認知症の患者及びその家族を需要者とする点などにおいて共通すること, 本件商標が付された原告商品について紹介する書籍,論文,記事等が複数存在する ことを考慮しても,なお,本件商標と被告各標章とを対比したときに,需要者にお いて,商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない から,被告各標章は,本件商標に類似しないというべきである。
(6) 原告の主張について
ア 原告は,本件商標を付した原告商品が,フェルラ酸を使用した認知症サプリ メントの先駆け的な商品であって,「フェルラ酸含有食品」といえばまず本件商標 を想起するというほど,本件商標は,医師,認知症患者及びその家族のみならず, 全国的に周知された著名な商標であると主張する。 そこで検討するに,前記4(ア)のとおり,確かに,原告商品を紹介する書籍,論文, 記事等が複数存在することが認められる。しかしながら,上記各書籍の発行部数等 は明らかではないし,論文や会議での発表についてはその対象が相当程度限定され\nたものであることが推認できるほか,上記雑誌等の紹介記事をもっても,本件商標 が具体的にどの程度認知されているのかは判然としないというほかはない。現に, 原告自身が提出する証拠によっても,原告商品の利用者数は5000人ないし60 00人というのであって,我が国の人口や,そのうち認知症に罹患していると推定 される患者数やその家族の人数との比較からしても,本件商標が全国的に周知され た著名な商標であるとは認め難いというほかはない。よって,本件商標の周知性, 著名性を前提として本件商標と被告各標章との対比を行うべきかのような原告の主 張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2016.10.20
平成27(行ケ)10176 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年10月12日 知的財産高等裁判所
(カ) 以上によれば,本件出願日当時,パルスレーザー蒸着法により,アモ ルファスのInGaO3(ZnO)m(m=1〜4)を形成することが可能であるこ\nとは確認できるものの(甲3,4,6,7),mが5以上の場合は開示されておらず, mが5以上のZnOに近い組成ではアモルファス相は得られないとの指摘もされて いた(甲3)から,当業者は,mが5以上の薄膜の作成は極めて困難と認識してい たものと認められる。
エ そして,本件明細書には,かかる当業者の認識にもかかわらず,mが5 以上50未満であるアモルファスの本件化合物薄膜を作成する方法についての記載 はない。
(3) したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,mが5以上50未 満の整数である場合を含む本件発明1,2及び4について,当業者が,アモルファ スの本件化合物薄膜を形成することができる程度に明確かつ十分に記載されたもの\nであるということはできないから,実施可能要件を欠くものと認められる。\nそうすると,その余の点について検討するまでもなく,取消事由3には,理由が ある。
(4) これに対して,被告は,本件発明は,InGaO3(ZnO)m膜につい て電界効果トランジスタの活性層に適するという未知の属性を発見し,その属性は アモルファスでも奏されることを見出したものであり,mの値の数値限定にのみ意 義のある発明ではないから,透明薄膜電界効果型トランジスタという物品の活性層 を構成する材料についてmの値の全範囲にわたって物品を作製する実施例の記載が\n必要であるということにはならない,と主張する。 しかし,被告の主張するとおり,本件発明がmの値の数値限定にのみ意義がある のではないとしても,本件発明の請求項の記載には,mが5以上のアモルファス薄 膜も含まれているから,かかるアモルファス薄膜を形成することができる程度の記 載が,本件明細書に求められるというべきである。しかも,上記(2)のとおり,本 件出願日当時には,mが5以上の組成ではアモルファス相は得ることが極めて困難 であるという当業者の認識があったにもかかわらず,本件明細書にはmが5以上5 0未満であるアモルファスの本件化合物薄膜の作成方法についての記載がない以上, 本件発明1,2及び4について,当業者が,アモルファスの本件化合物薄膜を形成 することができる程度に,その作成方法が明確かつ十分に記載されたものであると\nいうことはできない。
・・・・
(2) 原告は,本件発明3に関しては,本件明細書の発明の詳細な説明に記載さ れている実施例は,単結晶のInGaO3(ZnO)5に関するものたった 1 つであ り,本件明細書の発明の詳細な説明には,MがIn,Fe,Alの場合の本件化合 物も,m=5以外の場合の本件化合物も開示されていないから,サポート要件を欠 く,と主張する。これに対し,被告は,原告は上記主張を無効審判請求時にしていなかったから,本件訴訟において主張するのは不適法である,と反論する。
(3)ア 特許法は,特許無効の審判について,そこで争われる特許無効の原因が 特定されて当事者らに明確にされることを要求し,審判手続においては,上記特定 された無効原因をめぐって攻防が行われ,かつ,審判官による審理判断もこの争点 に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかである。したがって,\n特許無効審判の審決に対する取消しの訴えにおいて,その判断の違法が争われる場 合には,専ら審判手続において現実に争われ,かつ,審理判断された特定の無効原 因に関するもののみが審理の対象とされるべきである(最大判昭和51年3月10 日,民集30巻2号79頁参照)。
イ 本件において,審判段階では,原告が主張していた本件発明3に関する 無効理由6の概要は,以下のとおりである(甲40)。 本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載に接した当業者は,高温で反応性 固相エピタキシャル成長させて形成した本件化合物単結晶薄膜を,活性層に用いる と,ノーマリーオフの透明薄膜電界効果型トランジスタを得ることができると認識 する。一方,本件発明3には,YSZなどの酸化物単結晶基板上のZnOエピタキ シャル薄膜上に,高温である800℃以上,1600℃以下で反応性固相エピタキ シャル成長して形成した本件化合物単結晶薄膜を,活性層に用いたことが規定され ていない。そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は, 本件発明3がノーマリーオフになると認識できないというべきである。
ウ そうすると,原告が本件訴訟において取消事由4と主張する,本件明細 書の発明の詳細な説明には,MがIn,Fe,Alの場合の本件化合物も,m=5 以外の場合の本件化合物も開示されていないことが,サポート要件を欠くというべ きか否かについては,審判においては現実に争われたものではなく,審理判断され たものではないといわざるを得ない。
(4) これに対して,原告は,サポート要件があることの立証責任は特許権者で ある被告にあるから,審判請求人である原告はサポート要件違反があるという争点 を指摘すれば足り,取消事由4に係る主張は不適法ではない,と主張する。 しかし,上記(3)アのとおり,審決取消訴訟における審理範囲は,立証責任の所在 ではなく,実際に審理判断された特定の無効原因といえるか否かによって画される のである。原告の主張には,理由がない。
(5) 以上のとおり,原告の取消事由4の主張は,主張自体失当であるが,念の ため,原告主張の理由により,本件発明3はサポート要件を欠くかについて判断す る。
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には,単結晶の本件化合物薄膜を形成す る方法について,「YSZ(イットリア安定化ジルコニア)基板上に育成したZnO 単結晶極薄膜上に,アモルファスのホモロガス化合物薄膜を堆積し,得られた多層 膜を高温で加熱拡散処理する「反応性固相エピタキシャル法」により,ホモロガス 単結晶薄膜を育成する」(【0007】),「上記のホモロガス単結晶薄膜の製造方法と 同様に,ZnO薄膜上にエピタキシャル成長した複合酸化物薄膜を加熱拡散する手 段を用いる」(【0008】)と記載され,ZnO薄膜上に形成する本件化合物薄膜に ついては,「MBE法,パルスレーザー蒸着法(PLD法)等により成長させる。」 (【0019】),「得られた薄膜は,単結晶膜である必要はなく,多結晶膜でも,ア モルファス膜でも良い。」(【0020】)との記載がある。 そして,実施例1として,単結晶InGaO3(ZnO)5薄膜(m=5の場合) を活性層としたトップゲート型MISFET素子の作製方法が記載されている(【0 028】〜【0031】,図1〜4)。 エ したがって,本件発明3は,サポート要件を満たしているものと認めら れ,いずれにしても,取消事由4には,理由がない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2016.10.20
平成27(ワ)5619 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年9月29日 東京地方裁判所
証拠(乙18ないし24)によれば,HTML(言語)に関しては,教 科書や辞典(乙19ないし20,22ないし24)が多数存在し,多くの 約束ごとが定められていること,HTML(言語)は,プログラミング言 語ではあるが,集計・演算等の処理をするためのものではなく,ブラウザ の表示,装飾をするための言語であり,ウェブ画面のレイアウトと記載内容が定まっているときは,HTMLの表\現もほぼ同様となり,誰が作成しても似たようなものになることが認められる。
イ それにもかかわらず,本件において,原告は,甲19の表の右側(本件HTML)のうち青色で囲った部分はAが創作性を発揮して制作した部分\nであると主張した後,主張を若干変遷させて,甲25の2ないし4頁にお いて青枠部分を除いた部分が,Aが創作性を発揮した部分である旨主張し たものの,いずれにしても,以上のような抽象的な主張をするにとどまり, 本件HTMLにおいて,誰が作成しても同様の表現になるとはいえない程度に創作性のある表\現(表現者の個性が何らかの形で表\れている部分)があるかについて個別具体的な主張立証をしていない。
2016.10.14
平成28(行ケ)10109 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年10月12日 知的財産高等裁判所
そして,証拠(乙1〜14)によれば,菓子業界においては,取扱商品としてバ ウムクーヘンを表示するに際し,「URUOIBAUM」,「HITOTSUGI\nBAUM」,「PREMIUM BAUM」,「This IZU BAUM」,「KO YAMA´S BAUM」,「WHISKY BAUM」,「WHITE BAUM」, 「EUCALY BAUM」,「ねこバウム」,「TERABAUM」などと,「BA UM」との文字部分,又はその片仮名表記である「バウム」との文字部分と,その\n他の文字部分を組み合わせた標章を用いることが少なからずあると認められる。 そうすると,本願商標のうち「BAUM」の部分は,需要者又は取引者にバウム クーヘンを認識させるということができる。
ウ また,本願商標には,「HOKOTA」の欧文字が含まれている。 そして,「HOKOTA」の文字部分は,「ほこた」との称呼が自然に生じるとこ ろ,証拠(乙15〜17)によれば,「ほこた」との称呼を有する地方自治体であ る鉾田市が茨城県に所在することが認められる。また,証拠(乙18〜25)によ れば,鉾田市を表示するに際し,「HOKOTA」又は「Hokota」との欧文\n字を用いることが少なからずあると認められる。 そうすると,本願商標のうち「HOKOTA」の部分は,需要者又は取引者に茨 城県所在の鉾田市を認識させるということができる。 エ 以上のとおり,本願商標は,需要者又は取引者に,「BAUM」の部分は, バウムクーヘンを認識させ,「HOKOTA」の部分は,鉾田市を認識させるもの である。 そして,証拠(乙26〜33)によれば,菓子業界においては,取扱商品を表示\nするに際し,「遠野バウム」,「広島バウム」,「箕面バウム」,「琉球バウム」,「原宿バウム」,「御影バウム」と,その商品の生産又は販売がされる地域名と商品名であ る「バウム」を組み合わせた標章を用いることが少なからずあると認められる。 したがって,本願商標が指定商品に使用された場合,本願商標は,その全体から, 鉾田市を産地又は販売地とするバウムクーヘンという意味を有するものとして,需 要者又は取引者に認識されるものということができる。
(2) 普通に用いられる方法について
本願商標は,「HOKOTABAUM」という欧文字を,ゴジック体の太字で表\nし,さらに,全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させている。 そして,商取引において標章のデザイン化は一般に広く行われるものであるほか, 証拠(乙5〜9,11)によれば,菓子業界においては,欧文字で表した標章を,\n全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させることもあると認められる。 そうすると,本願商標は,特殊なものとはいえず,「HOKOTABAUM」の 欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということができ\nる。
・・・・
原告は,鉾田市が本願商標の指定商品の産地又は販売地として,需要者又は取引 者に認識されているとはいえない旨主張する。 しかし,前記のとおり,商標法3条1項3号にいう商標に該当するというために は,必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は\n販売されていることを要せず,需要者又は取引者によって,当該指定商品が当該商 標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識され\nることをもって足りるというべきである。 したがって,鉾田市が本願商標の指定商品の産地又は販売地として,需要者又は 取引者に認識されているか否かは,本願商標の商標法3条1項3号号該当性の判断 を左右するものではない。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2016.10.14
平成28(行ケ)10083 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年10月11日 知的財産高等裁判所
前記認定(第2,3,(2))のとおり,特許庁は,本件審判手続において 本件職権証拠調べを行ったものであるところ,証拠(甲78,79)によれ ば,特許庁は,原告に対し,平成27年11月16日に書面審理通知書(起 案日は同月12日)を発送した上で,同月17日,審理終結通知書(起案日 は同月12日)を発送したことが認められるものの,本件職権証拠調べの結 果を原告に対して通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与\nえたことをうかがわせる証拠は全くなく,これらの手続は行われなかったこ とが推認される。
(2)ア 法56条が準用する特許法150条は,「審判に関しては,…職権で, 証拠調べをすることができる。」(1項)とする一方で,「審判長は,… 職権で証拠調べ…をしたときは,その結果を当事者…に通知し,相当の期 間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。」(5項)\nと定める。ところが,本件審判手続において,特許庁は,上記(1)のとお り,原告に対し,本件職権証拠調べの結果につき通知し,相当の期間を指 定して意見を申し立てる機会を与えなかったのであり,この点で本件審判\n手続には上記規定に違反するという瑕疵があったものというべきである。 イ また,本件職権証拠調べは,具体的にはインターネットにより「スポー ツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合キーワード検索することで 「スポーツクラブ」における「マスターズ」の語の使用例を調査したも のであるが,本件審決は,本件商標の法4条1項15号該当性を論ずる 中で,本件商標の称呼及び観念につき判断するに当たり,本件商標のよ うに「スポーツクラブ」の文字と「マスターズ」の文字が結合した場合 の「マスターズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度を評価する根拠\nの一つとして,このような本件職権証拠調べの結果である5件のスポー ツクラブのホームページに存在する記載を利用している。 さらに,法4条1項19号及び同7号該当性の判断に当たっても,本 件審決は,本件職権証拠調べの結果を利用して,本件商標中の「マスタ ーズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度につき検討している。
ウ そうすると,本件審判手続には瑕疵があり,その瑕疵は,審判の結果で ある審決の結論に一般的に見て影響を及ぼすものであったものというべ きである。このような場合,その瑕疵は,審決の結論に影響を及ぼさな いことが明らかであると認められる特別の事情,すなわち,たとえ職権 証拠調べの結果の通知がなくとも,これに対する反論,反証の機会が実 質的に与えられていたものと評価し得るか,又は当事者に対する不意打 ちとならないと認められる事情がない限り,審決取消事由となるものと 解される(最高裁判所第一小法廷昭和51年5月6日判決・判例時報8 19号35頁,最高裁判所第三小法廷平成14年9月17日判決・判例 時報1801号108頁参照)。 そこで,本件における上記特段の事情の有無を検討すると,本件職権 証拠調べは,上記のとおり具体的にはインターネットによる「スポーツ クラブ」及び「マスターズ」の語の複合キーワード検索であり,その手 法それ自体は必ずしも目新しいものではなく,一般的かつ容易に行われ 得るものではある。しかし,原告において,そのような証拠調べが行わ れることを当然に予期していたとか,予\期すべきであったと認めるに足 りる証拠はない上,そもそも,本件審判事件においては,被告は原告の 主張に対し何ら答弁せず(前記第2の2),また,その審理は職権によ り書面審理とされていた(前記(1))のであるから,本件職権証拠調べの 事実を知らない原告にとっては,何らかの追加主張ないし立証が必要で あること自体,全く予期し得なかったと考えられるのである。また,本\n件職権証拠調べの結果それ自体も,本件審決の引用するホームページ上 の記載の存在そのものはともかく,これを受けた反証活動や本件証拠調 べの結果の評価に関する反論の余地がないとはいい難い。 そうである以上,本件においては本件職権証拠調べの結果に対する反 論,反証の機会が原告に対し実質的に与えられていたものとは評価し得 ず,また,原告に対する不意打ちとならないと認めるべき事情も見当た らない。すなわち,上記特段の事情の存在は認められない。 したがって,本件職権証拠調べの結果の原告に対する通知等を欠くと いう手続上の瑕疵は,本件審決の取消事由となるものというべきである。
◆平成24(行ケ)10363号 以前に、「Augusta Club」で15号違反が争われた事件です。こちらは15号違反と認定されています。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2016.10.11
平成27(行ケ)10262 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月29日 知的財産高等裁判所
原告は,訂正事項1について,審決は,「下端部」が「先端部」と同じ意味 であることは明らかであると断定しているが,本件明細書には「先端部」という記 載はなく,「下端部(自由端部)6a」,「下端部6a」という記載しか存在しないの であるから,本件明細書に全く記載のない全く別概念である「先端部」という表現\nを用いた訂正を行うことは,本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であるとは いえず,新規事項を追加するものであり,違法である旨主張する。 しかし,本件明細書の「棚板2は,水平状に広がる平面視四角形の基板4と,基 板4の各辺から上向きに立ち上がっている外壁5と,外壁5の上端に連接した内壁 6とから成っており,」(段落【0016】),「図3(B)に示すように,・・・内壁6のうち外壁5に繋がる連接部11は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。 他方,内壁6の下端部(自由端部)6aは,外壁5に向けて傾斜した傾斜部になっ ている。」(段落【0021】)との記載によれば,図3(B)の実施形態において, 内壁6の上端部は,外壁5との連接部11であり,外壁5に繋がる固定端部である のに対し,内壁6の下端部6aは,自由端部であり,下端部6aよりも先には内壁 6の部分が存在しないことから,内壁6の先端部であると認められる。そして,こ のような内壁6の構造は,本件明細書の図5(A),(B)などにも記載されている\nものである。 したがって,訂正事項1の「先端部」との表現を用いた訂正は,本件明細書に記\n載した事項の範囲内のものであるから,原告の上記主張は採用することができない。 また,原告は,「先端部」という用語は,上下方向に限られない先に位置する部分 を指す語であるから,「先端部」は「下端部」よりも広い部分を指すことになるので, 本件発明において,「下端部」の代わりに「先端部」という語を用いると発明の範囲 を広げることになる旨主張する。 しかし,本件明細書には,「なお,本願発明の棚板は基板の周囲に外壁を備えてい るが,棚板は基板から上向きに立ち上がっていても良いし,下向きに垂下していて も良い。」(段落【0010】)と記載されているところ,後者の外壁が下向きに垂下 する構成を採用する場合,内壁の先端部は下端部ではなく,上端部となることは自\n明である。そうすると,本件明細書に明示的に記載があるのは「下端部」との語の みであるとしても,内壁の先端部について,「下端部」のみならず「上端部」も本件 明細書に記載されているに等しいものと認められるから,本件明細書に記載されて いると認められる事項が「下端部」に限定されるものでないことは明らかである。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 原告は,訂正事項1のうち,「内壁の先端部は前記基板に至ることなく前記 外壁に向かっており」との部分について,本件明細書には,「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成は記載も示唆もされていないのであるから,特許請求の範囲\nにおいてもそのように解釈されるべきであり,内壁の先端部が外壁に到達していな い場合を含む表現である「前記内壁の先端部は・・・前記外壁に向かっており」と\n訂正することは,実質上特許請求の範囲を拡張することに該当し,拡張変更に当ら ないとする審決の判断は誤っていると主張する。 審決が認定するとおり,「向かう」とは「ある場所や方向を目指して進む。また, ある状態に近づく。」(広辞苑:甲11)との意味であり,「内壁の先端部は・・・外 壁に向かっており」とは,内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びているとの意 味であると解されるから,「内壁の先端部は・・・外壁に向かっており」との構成は,\n内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びていれば足り,内壁の先端部が外壁に到 達しているか否かは問わないものであって,内壁の先端部が外壁に到達している場 合と内壁の先端部が外壁に到達していない場合とを含むものであるといえる。 もっとも,本件明細書(図3,図5(A),(B))には,「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成も記載されていることが認められるから,実質上特許請求の\n範囲を拡張することに該当するとは認められない。なお,本件明細書には,「内壁の 先端部が外壁に到達していない」構成も記載されていることが認められる(図5(J)\n(K))。 そして,訂正事項1は,内壁の先端部についての限定がされていなかった本件訂 正前の請求項1について,本件明細書の図5(D)のような,外壁と重なる「重合 部6b」を有する内壁6の構造などの「内壁の先端部は・・・外壁に向かって」い\nるものではない構成を除外することにより,本件訂正前の請求項1に記載された「内\n壁」を限定するものであると認められる。 したがって,訂正事項1は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する ものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから,原告 の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2016.10.11
平成27(ワ)7147 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年9月15日 大阪地方裁判所
すなわち均等侵害が認められるためには,本件発明と被告方法の構成に異な\nる部分が存在する場合であっても,その部分が本件発明の本質的部分ではないこと が要件となるところ,ここでいう特許発明における本質的部分とは,当該特許発明 の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成す\nる特徴的部分であると解すべきであり,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明 細書の記載に基づいて,特許発明の課題及び解決手段(特許法36条4項,特許法 施行規則24条の2参照)とその効果(目的及び構成とその効果。平成6年法律第\n116号による改正前の特許法36条4項参照)を把握した上で,特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴\n的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(知財高裁平成 28年3月25日特別部判決)。
・・・
本件発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと,本件発明は,本件 特許の特許請求の範囲請求項1の発明に係るおかゆ調理器を用いたおかゆの調理方 法として,「粉砕段階」,「加熱段階」を含む複数の動作段階を設定し,それら動 作段階の一部についてはその順序,時間,回数等を具体的に指定し,穀物の粉砕手 段及び加熱手段を一体化した組合せとすることにより,通常のおかゆの調理方法に おいて時間を要していたふやかしの時間及び全体の調理時間の短縮を図り,また, 通常の調理方法においてはかきまぜの継続によって解消していたおかゆの焦げ付き も防止するなど,より簡便,迅速に本来の風味を有するおかゆの調理ができるよう にしたものであると認められる。 ところでおかゆの調理方法として,加熱や粉砕の動作を適宜組合せることは,周 知であるから(本件明細書の【0005】),本件特許の特許請求の範囲請求項1 の発明に係るおかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法である本件発明における本質 的部分とは,調理方法を決定するところの「粉砕段階」,「加熱段階」,「待機段 階」という一連の動作段階の設定,及び各動作段階において具体的に規定された粉 砕及び加熱の動作並びに待機の順序,各動作及び待機の時間,各動作及び待機の回 数等を一体化した組合せそのものにあると認められる。 (6) これに対し,被告方法は,既述のとおり,少なくとも,その第1及び第2の 粉砕段階において,本件発明の構成要件として規定された粉砕と待機とは異なる時\n間,回数の粉砕と待機がなされるものであるから,動作等の組合せにおいて,本件 発明の一体化した組合せとは異なっており,この相違部分は本件発明の本質的部分 に存するものといわなければならない, したがって,被告方法は,均等の第1要件を充足するとは認められない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2016.10.11
平成27(ワ)17928 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年9月15日 東京地方裁判所
前記前提事実(3)ウ及び(4)記載のとおり,本件写真の画像が本件アカウント 3〜5のタイムラインに表示されるのは,本件リツイート行為により同タイ\nムラインのURLにリンク先である流通情報2(2)のURLへのインラインリ ンクが自動的に設定され,同URLからユーザーのパソコン等の端末に直接\n画像ファイルのデータが送信されるためである。すなわち,流通情報3〜5 の各URLに流通情報2(2)のデータは一切送信されず,同URLからユーザ ーの端末への同データの送信も行われないから,本件リツイート行為は,そ れ自体として上記データを送信し,又はこれを送信可能化するものでなく,\n公衆送信(著作権法2条1項7号の2,9号の4及び9号の5,23条1 項)に当たることはないと解すべきである。 また,このようなリツイートの仕組み上,本件リツイート行為により本件 写真の画像ファイルの複製は行われないから複製権侵害は成立せず,画像フ ァイルの改変も行われないから同一性保持権侵害は成立しないし,本件リツ イート者らから公衆への本件写真の提供又は提示があるとはいえないから氏 名表示権侵害も成立しない。さらに,流通情報2(2)のURLからユーザーの 端末に送信された本件写真の画像ファイルについて,本件リツイート者らが これを更に公に伝達したことはうかがわれないから,公衆伝達権の侵害は認 められないし,その他の公衆送信に該当することをいう原告の主張も根拠を 欠くというほかない。そして,以上に説示したところによれば,本件リツイ ート者らが本件写真の画像ファイルを著作物として利用したとは認められな いから,著作権法113条6項所定のみなし侵害についても成立の前提を欠 くことになる。 したがって,原告の主張する各権利ともその侵害が明らかであるというこ とはできない。 これに対し,原告は,本件リツイート行為による流通情報2(2)のURLか らクライアントコンピューターへの本件写真の画像ファイルの送信が自動公 衆送信に当たり,本件リツイート者らをその主体とみるべきであるから,本 件リツイート行為が公衆送信権侵害となる旨主張する。 そこで判断するに,本件写真の画像ファイルをツイッターのサーバーに入 力し,これを公衆送信し得る状態を作出したのは本件アカウント2の使用者 であるから,上記送信の主体は同人であるとみるべきものである(最三小判 平成23年1月18日判決・民集65巻1号121頁参照)。一方,本件リ ツイート者らが送信主体であると解すべき根拠として原告が挙げるものにつ いてみるに,証拠(甲3,4)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターユー ザーにとってリツイートは一般的な利用方法であること,本件リツイート行 為により本件ツイート2は形式も内容もそのまま本件アカウント3〜5の各 タイムラインに表示されており,リツイートであると明示されていることが\n認められる。そうすると,本件リツイート行為が本件アカウント2の使用者 にとって想定外の利用方法であるとは評価できないし,本件リツイート者ら が本件写真を表示させることによって利益を得たとも考え難いから,これら\nの点から本件リツイート者らが自動公衆送信の主体であるとみることはでき ない。
関連カテゴリー
>> 公衆送信
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2016.10. 5
平成27(ワ)482 販売差止等請求事件 平成28年9月28日 東京地方裁判所
しかるところ,原告会社は,原告会社が本件各著作物の著作権者に送付した本件 契約書案(甲41)には,「第三者が著作物の権利を侵害した場合には,これに対 処します。」との条項があって,同条項は,原告会社が,著作権者に対して,第三 者が著作物の利用をした場合にはその排除を求めることができる旨の債権を有して いることを前提とするものといえるから,原告会社は,著作権者に代位して,著作 権の侵害行為の差止め及び廃棄を求めることができると主張する。 確かに,本件契約書案には,原告会社が主張するとおり,「第三者が著作物の権 利を侵害した場合には,これに対処します。」との記載があるが,著作権者が原告 会社に対して差止請求権及び廃棄請求権を行使すべき義務を負担する旨の条項はな く,本件著作物5ないし同28の2(同11,同12の1,同12の2,同15, 同16,同17,同21の1,同21の2を除く。)の各著作権者が,原告に対し て,第三者が侵害行為を行った場合に,当該著作権者において差止請求権や廃棄請 求権を行使すべき義務を負担しているものとは認められない。他に,原告会社が, 上記各著作権者に対して何らかの債権を有していることを認めるに足りる証拠はな い。そうすると,債権者代位権(民法423条)の法意を用いて,各著作権者が有 する差止請求権及び廃棄請求権を原告会社が代位行使することができるものと認め ることは困難である。 なお,前記のとおり,本件契約書案には,「第三者が著作物の権利を侵害した場 合には,これに対処します。」との記載があり,著作権者が,著作権に基づく差止 請求権及び廃棄請求権を原告会社に行使させることを容認する趣旨を読み取る余地 もあるが,仮にそのような合意の成立が認められるとしても,非弁護士の法律事務 の取扱い等を禁止する弁護士法72条や,訴訟信託を禁止する信託法10条,著作 権等管理事業者に種々の義務を負わせた著作権等管理事業法等の趣旨からして,か かる合意に基づく請求を認めることはできないというべきである。
2016.10. 4
平成27(ネ)10017 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年9月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ また,控訴人は,特許出願のためには出願前に発明内容を他社に知られ てはならないことを認識していたから,本件小型器については,本件イベントにお いて,実演,操作説明その他詳細な製品説明,内部構造の開示を行っていないと主\n張し,甲16〜18はこれに沿う。 しかし,本件発明1の構成要件のうち,B2,B4,C1〜3,Fが本件小型器\nの展示によって公知となったことは争いがなく,かつ,本件小型器は炭酸ガスと化 粧水を混合した上で顔面等に吹き付けるためのものであって,その展示態様と業務 用大型器の実演や説明から,ガスボンベが本体内部に入っており,スプレーガンに 付属したカップ内に化粧水が入れられるべきものであること,本体上部とつながっ た管を通って炭酸ガスがスプレーガンに到達すること,炭酸ガスと化粧水が混合さ れたものが,スプレーガンのレバーを操作することによってその先端から噴射され ることは容易に看取されるといえる。本件イベント当時,特許出願のためには出願 前に当該特許発明の内容を他者に知られてはならないことを認識していたのであれ ば,このような,公然知られた又は公然実施をされたと判断される可能性がある展\n示方法を,採用することは不自然である。 控訴人は,本件小型器展示の目的を,美容院での施術の雰囲気を出すためなどと 主張するが,上記のような可能性のある展示方法を,雰囲気を出すといった曖昧な\n目的のために行うのは不合理である。しかも,本件イベントにおいて,控訴人が, 本件小型器を組み立て,液体をカップに入れた,少なくとも外観上すぐに実演でき るような状態で展示しながら,他方で,来場者の質問を受け付けなかったり,本件 小型器の実演を拒んだりしたとは想定し難い。 上記(2)ケで認定したとおり,控訴人において知的財産権関連業務を行っていたB が,本件イベントにおける展示を事前に認識していなかったこと,本件特許出願を 決めたのが本件イベントの後であったことからすれば,本件イベントへの本件小型 器の出品は,本件特許出願前には当該特許発明の内容を知られてはならないという 意識を欠いたまま行われたものであり,本件小型器の実演や説明も,業務用大型器 と同様に行われたと認めるのが相当である。 控訴人の主張には,理由がない。
ウ さらに,控訴人は,本件イベントにおいては,本件小型器の実演,操作 説明その他詳細な製品説明や,内部構造の開示等が行われておらず,公然性の要件\nを欠き,本件小型器の展示は,「特許製品以外の製品の宣伝活動や営業活動のための 展示又は客寄せのための展示」にすぎず,譲渡等を目的としたものではないから, 公然と「実施」したとはいえない,と主張する。 しかし,上記(2)キ及び(3)イで認定したとおり,本件イベントにおいては,本件 小型器の実演及び説明が行われ,展示とあいまって内部構造をも知り得る状態にあ\nったと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2016.10. 4
平成27(ネ)10016 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年9月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 前記2のとおり,1)本件発明1−1は,一次原反ロールから薬液が塗布され た二次原反ロールに至るまでの積層手段,薬液塗布手段,スリット手段及び巻取り 手段が順に連続した1つの製造ラインに組み込まれ,同製造ライン上をシートが上 記各手段を経ながら間断なく流れるように構成された二次原反ロールの製造設備で\nあるプライマシンを備えているのに対し,2)被告設備は,一次原反ロールから薬液 が塗布された二次原反ロールに至るまでの間,一次原反ロールRから積層連続シー トSを形成する積層手段であるシート合わせロール10,積層連続シートSをスリ ットするスリット手段であるスリッター101及びスリットされた積層連続シート Sを巻き取ってロール102とする巻取り手段である巻取り装置131から成る製 造ラインと,上記製造ラインとは別に設けられた薬液塗布手段であり,同製造ライ ンから移送されたロール102から繰り出される積層連続シートSに薬液を塗布す る薬液塗布装置11及び薬液が塗布された積層連続シートSを再度巻き取って二次 原反ロールRとする巻取り手段である巻取り装置132から成る製造ラインに分か れている。 そこで,本件発明1−1において一次原反ロールから薬液が塗布された二次原反 ロールを製造するプライマシンを,被告設備における上記2つの製造ラインと置き 換えても,本件発明1−1の目的を達成することができ,同一の作用効果を奏する かについて検討する。
イ 前記1のとおり,本件発明1−1の課題は,薬液塗布工程をプライマシンや マルチスタンド式インターフォルダとは別に設ける構成を採用した場合に起きる,\n薬液塗布のために原反を移送する手間や多大な設備コストが掛かるという問題の発 生を回避し,同構成よりも低コストで薬液塗布を行うことができ,かつ,薬液塗布\nの有無を容易に切替え可能である製造設備を提供することであり,その解決手段は,\n一次原反ロールから薬液が塗布された二次原反ロールに至るまでの積層手段,薬液 塗布手段,スリット手段及び巻取り手段が順に連続した1つの製造ラインに組み込 まれ,同製造ライン上をシートが上記各手段を経ながら間断なく流れるように構成\nされたプライマシンを備える構成とすることである。同構\成の採用によって,薬液 塗布手段をプライマシンやマルチスタンド式インターフォルダとは別に設ける場合 と比較して,その場合に起きる,薬液塗布のために原反を移送する手間や多大な設 備コストが掛かるという問題の発生を回避し,設備コストをより低く抑えることが でき,また,薬液を塗布しない製品を製造する場合は,プライマシンから薬液塗布 手段を省略すれば足りるので,薬液塗布の有無を容易に切り替えることができると いう効果を奏する。
ウ そして,被告設備は,前記アのとおり,一次原反ロールから薬液が塗布され た二次原反ロールに至るまでの間,一次原反ロールRからロール102を形成する 製造ラインとは別に,薬液塗布装置11が設けられており,上記製造ラインから原 反(ロール102)を薬液塗布のために薬液塗布装置11に移送するというもので ある。したがって,本件発明1−1において一次原反ロールから薬液が塗布された 二次原反ロールを製造するプライマシンを,被告設備における2つの製造ラインと 置き換えれば,少なくとも,本件発明1−1の目的のうち,薬液塗布工程をプライ マシンやインターフォルダとは別に設ける構成を採用した場合に起きる薬液塗布の\nために原反を移送する手間が掛かるという問題の発生を回避し,同構成よりも低コ\nストで薬液塗布を行うことができる製造設備を提供するという目的を達成すること ができず,薬液塗布手段をプライマシンやマルチスタンド式インターフォルダとは 別に設ける場合と比較して,その場合に起きる薬液塗布のために原反を移送する手 間が掛かるという問題の発生を回避し,設備コストをより低く抑えることができる という効果を奏しなくなることは,明らかである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> ピックアップ対象
2016.10. 4
平成27(行ケ)10229 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月28日 知的財産高等裁判所
ア 本件技術的事項が,当業者によって,本願当初明細書等の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入し ないものと認められるかについて検討する。
イ まず,本願当初明細書等には,「空気噴射装置11の正面には圧縮空気噴射 口20が設けられており」,「圧縮空気噴射口20の背面には…電磁弁22が設けら れている」,「空気噴射装置11は支持部材23によって固定されており,支持部材 23には振動センサ24が設置されている」と説明され(【0059】),さらに, 本願当初明細書等の【図面1】ないし【図面3】(別紙1本件補正明細書図面目録 の【図面1】ないし【図面3】に同じ。)には,筐体の正面上部に空気噴射口があ り,筐体の背面上部よりも下方に電磁弁があり,空気噴射口の背面側の位置に,振 動センサの設置された支持部材がある空気噴射装置が描かれている。そうすると, 本願当初明細書等には,本件技術的事項のうち,空気噴射口が正面上部となるよう にみたときの縦方向に着目した上で,2)筐体の正面上部に空気噴射口を設け,筐体 の背面上部よりも下方に電磁弁を設けることを可能にし,空気噴射口の背面側の位\n置に,振動センサの設置された支持部材を設けるという技術的事項については説明 されているということができる。 しかし,本件技術的事項には,空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦 方向に着目した上で,1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとするという 技術的事項も含まれるところ,本願当初明細書等の【図面2】には,横方向よりも 縦方向に短い筐体の形状を備える空気噴射装置が描かれており,本願当初明細書等 には,その他に,空気噴射装置の形状について言及されていない。そうすると,本 願当初明細書等には,本件技術的事項のうち,空気噴射口が正面上部になるように みたときに縦方向に着目した上で,1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いもの とするという技術的事項については説明されていないというべきである。 ウ よって,本件技術的事項は,当業者によって,本願当初明細書等の全ての記 載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内にあるということはできず, 「空気噴射装置」についてなされた本件補正は,新たな技術的事項を導入しないも のということはできない。
(4) 原告の主張
ア 原告は,本件補正は,空気噴射装置のうち,支持部材によって支持されてい る上方部分と支持されていない下方部分とに着目した場合,支持部材によって支持 されていない下方部分が,支持部材によって支持されている上方部分よりも縦方向 に長いことから,「空気噴射装置」について,「正面上部に前記空気噴射口を設けた 縦長の筐体」としたものである旨主張する。 しかし,前記(2)のとおり,「空気噴射装置」について「縦長の筐体」を備えると いう構成を付加することは,空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向\nに着目した上で,筐体の形状,並びに,空気噴射口,電磁弁及び振動センサの設置 された支持部材の位置関係を特定するという技術的事項を追加するものであって, 単に,空気噴射装置のうち,支持部材によって支持されている上方部分と支持され ていない下方部分の縦方向の長さを比較するというものにとどまるものではない。 したがって,原告の前記主張は採用できない。
イ 原告は,本件補正において,「横長」の筐体とすべきところを,「縦長」の筐 体と誤記載をしてしまっただけであると主張するが,本件補正により追加された技 術的事項の認定は,客観的になされるべきものであるから,原告の上記主張は失当 である。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2016.10. 4
平成27(行ケ)10260 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月28日 知的財産高等裁判所
ア 特許法167条は,特許無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加 人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないと 規定している。同条の趣旨は,排他的独占的権利である特許権(同法68条)の有 効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じな いように特許無効審判の一回的紛争解決を図るために,当事者及び参加人に対して 一事不再理効を及ぼすものと解される。 先の特許無効審判の当事者及び参加人は,同審判手続において無効理由の存否に つき攻撃防御をし,また,特許無効審判の審決の取消訴訟が提起された場合には, 同訴訟手続において当該審決の取消事由の存否につき攻撃防御をする機会を与えら れていたのであるから,「同一の事実及び同一の証拠」について狭義に解するのは, 紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。
イ この点に関し,平成23年法律第63号による改正前の特許法167条にお いては,一事不再理効の及ぶ範囲が「何人も」とされており,先の審判に全く関与 していない第三者による審判請求の権利まで制限するものであったことから,「同一 の事実及び同一の証拠」の意義を拡張的に解釈することについては,第三者との関 係で問題があったということができる。しかし,上記改正によって第三者効が廃止 され,一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手続に関与して主張立証を尽くすこと ができた当事者及び参加人に限定されたのであるから,「同一の事実及び同一の証拠」 の意義については,前記アのとおり,特許無効審判の一回的紛争解決を図るという 趣旨をより重視して解するのが相当である。
ウ 原告は,本件審判において,本件発明につき,引用例(甲2)を主引用例と し,これに記載された発明及び甲第1,4から11,13から18号証に記載され た発明又は周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである 旨を主張した。 しかし,前記?のとおり,確定した前件審決においても,引用例(甲2)が主引 用例とされており,また,甲第6から18号証が副引用例とされていた。 したがって,本件審判における原告の前記主張は,確定した前件審決と同一の主 引用例に基づいて本件発明の容易想到性を主張するものであり,主引用例以外の証 拠についても,上記のとおり前件審決において副引用例とされていた甲第6から1 8号証に加え,甲第1,4及び5号証を追加したにすぎない。 このように,確定した前件審決と主引用例が同一であり,まして,多数の副引用 例も共通し,証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は,「同一の事実及び同 一の証拠」に基づくものと解するのが,前記アの特許法167条の趣旨にかなうも のというべきである。 以上によれば,本件審判における原告の前記主張は,確定した前件審決と「同一 の事実及び同一の証拠」に基づくものであるから,特許法167条に該当し,許さ れない(この点に関し,本件審決が,本件審判において前件審判時に証拠として提 出されなかった甲第4,5号証が提出され,前件審判時に主張されなかった回動す るタンブラー錠用の鍵において摺り鉢形の窪みを有した鍵が周知であることが主張 されたことをもって,前件審判と同一の証拠に基づく審判請求とはいえない旨判断 したことは,誤りである。)。したがって,上記主張を排斥した本件審決の判断が誤 りであるという取消事由は,それ自体,失当というべきである。
2016.10. 4
平成28(行ケ)10020 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月26日 知的財産高等裁判所
(ア)a 本件発明1と甲1発明の相違点として,前記第2,4(1)イ(イ)b記載 のとおりの相違点2がある(当事者間に争いはない。)ところ,前記認定事実(1(2)) によれば,甲1発明は,それぞれ要冷蔵品を収納する保存室を有する上下2つの断 熱箱体により構成された業務用横型冷蔵庫に関する発明であるから,断熱箱体の内\n箱及び外箱並びにその間に充填された断熱材により区画された上下2つの保存室を 有する業務用横型冷蔵庫,すなわち,庫内が断熱材により複数に区画された業務用 横型冷蔵庫に関する発明であるといえる。 一方,前記認定事実(1(3))によれば,甲7には,断熱性の仕切壁によって区画 された,冷蔵室,冷凍室及び野菜室がある家庭用冷蔵庫における冷却の実施例が記 載されているが,家庭用冷蔵庫に限らず,庫内を複数に区画してそれぞれ異なる温 度で管理する各種冷蔵庫に有効な発明であることが記載されている。 以上によれば,甲1発明と甲7に記載された事項は,少なくとも,複数の保存室 を有する冷蔵庫に関するものという点で,技術分野が共通である。 b 前記1(2)のとおり,甲1には,特に使用用途の拡大のため,庫内に 収容できる商品の幅を広げることを目的とする断熱箱体の改良に関する発明である 旨が記載されている。そうすると,甲1発明の課題は,使用用途の拡大,収容でき る要冷蔵品の幅を広げることということができる。 一方,前記認定事実(1(3))によれば,甲7に記載された事項の課題は,温度が 低い冷気の循環による冷蔵室内や野菜室内の乾燥の防止,高湿状態である冷蔵室や 野菜室内の水分が霜となって冷却器に付着することによる冷却能力の低下の防止,\n冷却器の大型化及び背面ダクト等の設置による冷凍室,冷蔵室及び野菜室の有効容 積の圧迫の防止であるといえる。これらは,庫内の複数の区画の存在を前提として いるが,冷凍が必要な食品等については冷凍室,冷蔵が必要な食品等については冷 蔵室,特に高湿状態が望ましい野菜については野菜室の各区画を設け,冷蔵室及び 野菜室については,高湿状態に保つことを課題としていると解することができるの であって,各食品等に応じた適切な冷蔵状態を提供することで,庫内に収容できる 要冷蔵品の幅を広げることを課題としていると評価することができる。 以上によれば,甲1発明と甲7に記載された事項は,使用用途の拡大,収容でき る要冷蔵品の幅を広げることという点で,課題が共通であるということができる。 c 前記認定事実(1(2))によれば,甲1発明は,断熱箱体からなる横 型冷蔵庫の天面に,別の断熱箱体を据え付け,下の断熱箱体の内箱の内部に,圧縮 機及び凝縮器と連結されて冷媒を循環させている蒸発器を設け,前記蒸発器により 冷却された冷気を,下の断熱箱体だけではなく,上の断熱箱体にも循環させること によって,上下2つの断熱箱体を冷却するものである。 一方,前記認定事実(1(3))によれば,甲7には,圧縮機及び凝縮器と連結され た 室用冷却パイプ及び野菜室用冷却パイプを設けて冷媒を循環させ,冷凍室は,冷凍 室用冷却器により冷却された冷気を循環させることによって冷却し,冷蔵室及び野 菜室は,冷蔵室用冷却パイプ及び野菜室用冷却パイプの内部を循環する冷媒の蒸発 により,各室の内壁面を冷却し,冷気の自然対流により各室内を冷却することが記 載されている。
以上によれば,甲1発明と甲7に記載された事項は,蒸発器を 1 つ設けるか複数 設けるかという違いはあるものの,1つの圧縮機及び1つの凝縮器を,冷却器ない し冷却パイプと連結し,その中に冷媒を循環させ,冷媒の蒸発により,冷蔵庫内の 複数の保存室を冷却するという作用・機能において,共通する。\nd 前記1(2)のとおり,甲1には,上の断熱箱体の保存室の外側に冷却 空間を形成するように伝熱パネルを設け,前記冷却空間に冷気を循環させることに より前記伝熱パネルを冷却し,前記伝熱パネルの自然対流熱伝達及び輻射冷却作用 により,保存室の内部を冷却する方法(実施例3及び4)が記載されており,また, 前記方法を採用することにより,下の断熱箱体を通常の横型冷蔵庫,上の断熱箱体 を高湿度で保存する必要のある寿司ネタや野菜などを保存することができる恒温高 湿ショーケースとして使用することが可能であることが記載されている。そうする\nと,甲1は,食品の乾燥防止のため,高湿状態を維持できる,冷気の強制対流以外 の冷却方法を採用することを記載したものといえるから,甲 1 発明の上の断熱箱体 の保存室の内部の冷却方法を,食品の乾燥を防止し得る別の冷却方法に変更するこ とにつき,示唆があるといえる。 一方,前記1(3)のとおり,甲7には,冷蔵室内や野菜室内に低温となる冷凍室用 冷却器からの冷気を供給しないので,冷蔵室内や野菜室内に収納した食品が乾燥す ることもないとの記載があり,冷蔵室用及び野菜室用冷却パイプを循環する冷媒の 蒸発による冷却が,食品の乾燥防止のため,高湿状態を維持できる冷却方法である ことが記載されているといえる。そうすると,甲7には,甲1発明の前記の上の断 熱箱体の保存室を高湿度で保存する必要のある寿司ネタや野菜などを保存するため に利用する場合には,その内部の冷却方法を,甲7に記載された冷却パイプの設置 による冷媒の蒸発による冷却方法に変更することにつき,示唆があるといえる。 また,前記aのとおり,甲7には,家庭用冷蔵庫に限らず,庫内を複数に区画し てそれぞれ異なる温度で管理する各種冷蔵庫に有効な発明であることが記載されて おり,甲1発明は,複数の保存室を有する冷蔵庫であるから,甲7には,甲7に記 載された事項を甲1発明に適用する示唆があるといえる。
e 以上によれば,甲1発明と甲7に記載された事項とは,一般的な技 術分野及び課題等を共通にするだけでなく,甲1に記載された実施例3及び4と甲 7に記載された事項とにおいて,上の断熱箱体における冷却中の保存品の乾燥を防 止するという具体的課題も共通するものであるから,甲1発明につき,上の断熱箱 体の保存室の内部の冷却方法として,甲7に記載された冷却パイプの設置による冷 媒の蒸発による冷却方法を適用する動機付けがあるといえる。
(イ) 前記1(2)のとおり,甲1発明には,「断熱箱体本体の天面開口部と合 致する間口を底面に備え」る「断熱箱体」という構成が含まれるが,この「天面開\n口部」及び「間口」は,庫内ファンによって冷却室の上部に設けられた冷気吹出口 から送られる冷気を,上の断熱箱体に送ってこれを冷却し,その後,下の断熱箱体 に送ってこれを冷却するための,冷気用の開口部である。 そして,冷気を上下の断熱箱体に循環させてこれを冷却する方法においては,上 下の断熱箱体の間に冷気を通すための開口部を要するが,冷媒を上下の断熱箱体に 循環させてこれを冷却する方法においては,上下の断熱箱体の間に冷気を通すため の開口部を必要としない代わりに,冷却パイプを通すための開口部を要するのであ って,他に冷気用の開口部を設けるべき理由はないから,上下の断熱箱体の間に冷 気用の開口部を要するか否かは,上の断熱箱体を下の断熱箱体からの冷気の循環に より冷却するか否かという冷却方法の選択の問題にほかならない。 また,甲1には,前記1(2)のとおり,上下の断熱箱体を1つの「冷却ユニット」 で冷却することが可能であることが記載されており,弁論の全趣旨によれば,「冷却\nユニット」は,少なくとも,圧縮機,凝縮機及び蒸発器により構成されることが認\nめられるところ,冷却器及び冷却パイプは,冷媒の蒸発により,冷却を行う機能を\n有するものであり,前記の蒸発器に該当するものと認められるから,甲1発明に, 甲7に記載された前記の冷却方法を適用すれば,上の断熱箱体用の冷却パイプと下 の断熱箱体用の冷却器を,別途に設けることになるから,上下の断熱箱体を1つの 「冷却ユニット」で冷却することはできなくなる。 しかしながら,前記1(2)のとおり,甲1発明の目的は,業務用横型冷蔵庫の構造\nを改良し,特に使用用途の拡大のため,庫内に収容できる要冷蔵品の幅を広げるこ とにある。上下の断熱箱体を1つの「冷却ユニット」で冷却するため,蒸発器を1 つしか設けないことは,この目的と関係がない。また,前記認定事実(1(3))によ れば,甲7には,冷却パイプ内の冷媒の蒸発により冷却される保存室の内部の乾燥 を防止できることのほか,1)冷却器に湿気の多い冷蔵室や野菜室内の水分が霜とな って付着し,冷却器の冷却能力が低下することを防げること,2)冷却器を大型化し なくてよくなり,これを収納する区画を小容量化して,冷凍室の有効容積を広くす ることができること,3)冷気循環のためのダクト等を設ける必要がなくなり,冷凍 室,冷蔵室及び野菜室の区画の有効容積を広くすることができることが記載されて いる。そうすると,蒸発器を複数にして各保存室を冷却する方式を採用するか,蒸 発器を1つにして全保存室に当該蒸発器で冷却した冷気を循環させて冷却する方式 を採用するかは,当業者が設計に際して効果を考慮して適宜採用し得る設計的事項 に該当する。 以上によれば,上下の断熱箱体の間に冷気を通すための開口部がない構成になる\nことや,蒸発器を複数有する構成になることが,甲1発明に甲7に記載された事項\nを適用することの阻害事由たり得るとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2016.10. 4
平成28(行ケ)10034 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成28年9月21日 知的財産高等裁判所
イ 本願意匠における意匠に係る物品は,「容器付冷菓」(甲4)であって, 上記別表第一に列挙されている物品の区分には該当しない。そこで,願書の「意匠\nに係る物品」欄及び「意匠に係る物品の説明」欄の記載を参照すべきところ,「容 器付冷菓」は,その名称からすれば,「冷菓」が主体であって,「容器」が付随し ているものと解される。 また,本願意匠登録出願に係る「意匠に係る物品の説明」(甲4)には,「本物 品は,参考断面図に示したように,容器部内に冷菓部材を充填し,次いで前記冷菓 部材の上面全部をあん部材で覆い,次いで前記あん部材上にもち部材を点状に配設 し,これらの全体を冷凍して容器部と一体に流通に付されるものである。」と記載 されている。上記記載を参照すれば,本願意匠に係る「冷菓」は,容器部内に冷菓 部材を充填し,その上部にあん部材,もち部材を順次配設した後,これらを冷やし 固めることによって製造するものと認識される。そして,冷菓部材,あん部材及び もち部材からなる「冷菓」は,「容器」と共に流通に付されるものである。使用の 場面においても,通常,「容器」に入ったままの「冷菓」をスプーン等ですくって 食することが想定される。よって,製造,流通,及び使用の各段階において,「冷 菓」は,「容器」に充填され冷やし固められたままの一体的状態であると認められ る。 さらに,上記製造方法からすれば,本願意匠に係る「冷菓」を,その形態を保っ たまま「容器」から分離することは,容易ではないものと推認される。しかも,「冷 菓」は,製造の段階から,流通,使用に至るまで「容器」から分離されることはな いから,「冷菓」が「容器」から独立して通常の状態で取引の対象となるとはいえ ない。 これらを総合考慮すれば,本願意匠に係る物品である「容器付冷菓」は,社会通 念上,一つの特定の用途及び機能を有する一物品であると認められ,「冷菓」の部\n分のみが「容器」の部分とは独立した用途及び機能を有する一物品とはいえない。
ウ これに対して,被告は,1)「容器」と「冷菓」は全く用途の異なる物品 であって,「容器」は,単体の形状として独立して創作される,2)内容物としての 「冷菓」も,同じ容器でも異なる形態の冷菓が存在し得るから,冷菓の形状として, 独立して創作される,3)冷菓は食用に供されるが,食用に供されることのない「容 器」は,冷菓を構成する部材や部品に該当しない,4)実施の実情からしても,容器 製造業者が容器を製造販売し,冷菓製造業者がそれを購入することもある,5)冷菓 を納めた容器には蓋がされているから,容器はむしろ蓋と一体となって商品として の外観形態を構成する,6)消費者が冷菓を食するときには,冷菓は容器に収容され た別の物品として認識する,ことを理由に,容器と冷菓とは一物品ではなく,二物 品である,と主張する。
しかし,1)「容器」と「冷菓」とを分離した場合のそれぞれの用途が異なること は,後記(4)の登録意匠例のように,用途又は機能が異なる物を組み合わせた物品が\n一物品と認められることがあることを考慮すると,本願意匠に係る物品が一物品と いえないことの理由にはならず,「容器」と「冷菓」とが,社会通念上一体として 一つの特定の用途及び機能を有するといえるか否かを検討すべきである。また,「容\n器」が単体の形状として独立して創作されることがあるとしても,本願意匠に係る 「冷菓」は,「容器」と独立しては製造,流通及び使用することが困難であり,し かも,「容器付冷菓」としての物品の主体は,「冷菓」であるから,付随する「容 器」の独立性を理由として,二つの物品と認めることはできない。 2)「冷菓」が,同じ容器でも異なる形態として独立して創作されることがあると しても,物品の一部が異なる形態として創作され得るのは通常のことであり,その ことを理由として,本願意匠に係る物品が一物品であることを否定することはでき ない。3)前記1)のとおり,用途又は機能が異なる物を組み合わせた物品が一物品と認め\nられる場合,全体が同一の用途又は機能とならないことは当然であり,本願意匠に\nおいて「容器」が食用に供されないことは,「容器」が「冷菓」と共に一物品を構\n成することを否定する理由とはならない。 4)意匠に係る物品が複数の部分から構成されている場合,それぞれの部分を異な\nる業者が作成し,それらを特定の業者が組み立てることは通常あり得るし,このよ うな物品につき,各部分を異なる者が製造販売したことにより,一物品であること が常に否定されるものではない。 5)本願意匠に係る物品である「容器付冷菓」は,前記イのとおり,社会通念上, 一つの特定の用途及び機能を有する一物品であり,しかも,「容器付冷菓」の物品\nとしての主体は,「冷菓」であるから,「冷菓」に付随するにすぎない「容器」に 蓋を設ける場合があるとしても,そのことを理由として,二つの物品と認めること はできない。 6)本願意匠に係る物品である「容器付冷菓」は,前記イのとおり,社会通念上, 一つの特定の用途及び機能を有する一物品と認められ,消費者が冷菓を食する場合\nであっても,冷菓を容器とは独立した物品と認識するとはいえない。 被告の主張には,いずれも理由がない。
2016.09.14
平成25(ワ)3167等 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年8月31日 東京地方裁判所
これを本件についてみると,原告の主張によれば,本件発明の構成要件C\n及びDの「上部,下部,左(右)側部」とは「上部,下部又は左(右)側 部」を意味するのであり,左右側面部の裏面において一過性の粘着剤が塗布 される位置を,当該分離して使用するものの上部,下部又は左(右)側部の 内側のいずれか及び上部,下部又は左(右)側部の外側に該当する部分のい ずれかであればよいというのである。 これに対し,本件明細書等の発明の詳細な説明の欄には,一過性の粘着剤 を塗布する部分の具体例として,分離して使用するもの4と中央面部1の上 部境界,下部境界,左側部(右側部)境界の各境界の内側近傍と外側近傍に 接着剤を塗布したものしか記載されていない。そのため,特許請求の範囲に 記載された発明は,発明の詳細な説明及び図面に記載されたものより広い。 しかるに,このように,本件明細書等の発明の詳細な説明の欄を超えて, 一過性の粘着剤が塗布される位置を原告の上記主張のとおりでよいとすると, このうちどの部分に粘着剤を塗布すれば「葉書,チケット,クーポン券等の 分離して使用するものを広告等の印刷物より切り取る必要がなく,かつその 周囲に切り込みが入っているにもかかわらず,広告等の印刷物に付いていて 紛失させることなく,しかも手間がかからず葉書,チケット,クーポン券等 の分離して使用するものを利用することが出来る印刷物を提供すること」 (本件明細書等の段落【0006】)という本件発明の課題を解決すること ができ,また「印刷物に付いている葉書,チケット,クーポン券等を切り取 ろうとする意思を持たずに,印刷物を開くと自動的に手にすることにな る。」(同段落【0012】)の作用効果を奏することになるのか,必ずし も明らかとはいえない(乙B11及び乙B12も参照)。 したがって,当業者において,本件発明の課題解決手段や,発明を理解す るための技術的事項が,発明の詳細な説明に記載されているものとはいい難 い。
(3) 以上によれば,本件発明は特許法36条6項1号に規定するサポート要件 を充たしていないから,本件特許は同法123条1項4号により特許無効審 判により無効にされるべきものである。
・・・・
以上によれば,乙B1文献には引用発明1'が記載されており,このうち 「情報記録体」の具体例として「レスポンス用葉書」が記載されているに等 しく,引用発明1'は本件訂正発明の構成要件A\ないしI\の全てを備えて\nいるから,引用発明1’は本件訂正発明と同一である。なお,この点に関し て原告は,引用発明1'と本件訂正発明はさらに相違点があると主張するが (相違点1−1及び1−2),前記2(4)の争点(3)ア(無効理由1)におい て説示したところに照らし,いずれも採用することができない。 そうすると,本件訂正発明は引用発明1'と同一であって,なお新規性を 欠くものであるから,本件訂正に係る原告の再抗弁は,前記(1)で説示した 3)の要件を充たしていないというほかない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.09.14
平成27(ワ)23129 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年8月30日 東京地方裁判所
そこで判断するに,まず,上記1)及び2)については,前記イで説示した とおり,安定性は化粧品の製造工程において常に問題とされる化粧品の品 質特性であり,pHの調整が安定化のための一般的な手法であることから すれば,乙6ウェブページに掲載されている成分リストが販売開始から間 もない原告旧製品のものであるとしても,当業者が化粧品の安定性の確 保,向上という課題を全く認識しないということはできないし,pHの調 整という手法を採用することが困難であったということもできない。 次に,上記3)については,原告は乙6発明のpHが7.9〜8.3であ ることを前提にこれを酸性側に変更することの阻害要因を主張するが,そ のような前提を採ることができないことは前記(1)イのとおりである。こ の点をおくとしても,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件特許の出 願当時,a)リン酸アスコルビルマグネシウム単体の水溶液については, pHが8〜9の弱アルカリ性の領域においては安定とされていたが,pH が中性〜酸性の範囲においては安定性に問題があるとされていたこと(甲 30〜32,50〜55),b)リン酸アスコルビルマグネシウムを含む化 粧料について,弱酸性における安定性を改善する手法が検討されており (甲31,50〜52,61,乙10の2,25),実際にリン酸アスコ ルビルマグネシウムを含有する弱酸性の化粧品が販売されていたこと(乙 28,29)が認められる。これら事実関係によれば,リン酸アスコルビ ルマグネシウムに加え他の成分を含む化粧品については,弱酸性下におけ る安定性の改善が試みられており,現に製品としても販売されていたので あるから,原告が主張するリン酸アスコルビルマグネシウム単体の水溶液 が酸性下においてその安定性に問題があるという事情は,乙6発明の美容 液のpHを弱酸性の範囲に調整することの阻害要因とならないと解する のが相当である。 上記4)については,前記イで説示したとおり,pHの調整が化粧品の安 定性を高めるための手法として周知であったことからすると,本件発明の 実施例について吸光度の残存率の高さや性状変化の少なさといった経時 安定性の測定結果が良好であったとしても(本件明細書の【表4】〜【表\ 6】),●(省略)●予測し得る範囲を超えた顕著な効果を奏するとは認\nめられない。したがって,原告の上記主張1)〜4)はいずれも採用することができない。
(3) まとめ
以上によれば,本件発明は乙6発明に基づいて容易に発明することができ たものであるから,原告は本件特許権を行使することができない。
2016.09. 9
平成28(ラ)10013 移送決定に対する抗告事件 平成28年8月10日 知的財産高等裁判所
同法6条1項が,知的財産権関係訴訟の中でも特に専門技術的要素が強い事件類型 については専門的処理体制の整った東京地方裁判所又は大阪地方裁判所で審理判断 することが相当として,その専属管轄に属するとした趣旨からすれば,「特許権に 関する訴え」は,特許権侵害を理由とする差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟,職務 発明の対価の支払を求める訴訟等に限られず,特許権の専用実施権や通常実施権の 設定契約に関する訴訟,特許を受ける権利や特許権の帰属の確認訴訟,特許権の移 転登録請求訴訟,特許権を侵害する旨の虚偽の事実を告知したことを理由とする不 正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟等を含むと解するのが相当である。 他方,基本事件は,抗告人らの共同不法行為(詐欺)又は会社法429条に基づ\nく損害賠償請求訴訟であるから,抽象的な事件類型が特許権に関するものであると いうことはできない。そして,相手方の欺罔行為に関する主張は変遷しているもの\nの,相手方は,抗告人X1による消火器販売事業への勧誘に際し,抗告人X1の開 発した消火剤が,同人は技術やノウハウを有していないのに,同人が特許を持って おり,これまでの消火剤より性能がよいと述べたことや,他社メーカーの特許を侵\n害しないと述べたことが,詐欺に当たるなどと主張するものと解される。しかし,\n事業の対象製品が第三者の特許権を侵害するというだけで,当該事業への勧誘が詐 欺に当たるとか,取締役の任務を懈怠したということはできないから,欺\罔行為の 内容として「特許」という用語が使用されているだけで,このことをもって,基本 事件が専属管轄たる「特許権に関する訴え」(民事訴訟法6条1項)に当たるとい うことはできない。また,知的財産高等裁判所設置法2条3号は,「前2号に掲げ るもののほか,主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件」 を知的財産高等裁判所の取り扱う事件の1つとしており,第三者の特許権の侵害の 有無が争点の1つとなる場合には,専門的処理体制の整った東京地方裁判所又は大 阪地方裁判所で審理判断することが望ましいとしても,それが全て専属管轄たる「特 許権に関する訴え」に当たるということもできない。基本事件のように,審理の途 中で間接事実の1つとして「特許」が登場したものが専属管轄に当たるとすると, これを看過した場合に絶対的上告理由となること(民事訴訟法312条2項3号) からしても,訴訟手続が著しく不安定になって相当でないというべきである。
3 したがって,基本事件は,「特許権に関する訴え」(民事訴訟法6条1項) に当たらないというべきであり,東京地方裁判所の専属管轄とは認められない。
2016.09. 8
平成26(ワ)25928 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年8月30日 東京地方裁判所
ウ さらに,本件特許の出願経過からも上記解釈は裏付けられる。すなわち, 原告は,本件特許の審査段階において,特許庁から平成15年1月21日 発送の拒絶理由通知(乙8)を受けたところ,そこには「…請求項1の記 載では本願発明の目的である通過すべき経由地点の設定中にすでにそれら の経由地点のいずれかを通過してしまった場合でも,正しい経路誘導を行 うための構成である『設定指令が入力された時点での車両現在位置を探索\n開始地点として記憶し,この記憶された探索開始地点と,経路データが設 定され移動体の経路誘導が開始される時点での移動体の現在位置を比較す る』点が明確に記載されていない。…よって,請求項1は,特許を受けよ うとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではな\nい。」とされていた。原告は,上記拒絶理由通知に対応して,同年2月5 日受付の意見書(乙9)を提出し,そこにおいて「審査官殿のご指摘の通 り,本願発明における探索開始地点と経路誘導地点に関する上述の点が不 明瞭であると考えますので,『設定指令が入力され,経路の探索を開始す る時点の前記移動体の現在位置を探索開始地点として記憶する記憶手段』 と構成要件を加えることにより,探索開始地点が記憶されることを明確に\nするとともに,経路データ設定手段が『記憶した探索開始地点を基に経路 の探索を行い,当該経路を経路データとして設定する』と補正して探索開 始地点と経路データの関係を明確にし,制御手段おける記憶された探索開 始地点と誘導開始地点を比較する点を明確に致しました。」(1頁下9行 〜2行)と記載し,併せて,同日受付の手続補正書(乙10)を提出して 上記記載に沿った補正を行い,探索開始地点と誘導開始地点とを比較する ことを明確にしたものである。以上の出願経過も,構成要件Gに係る上記\n解釈を裏付けるものである。
(2) しかるところ,被告装置において,「探索開始地点」と「誘導開始地点」 を比較して両地点が異なるかどうかを判断しているものと認めるに足りる証 拠はない。 かえって,証拠(乙16の1)によれば,被告装置においては,1)経路誘 導の計算が行われ,これが終了すると,出発地点P0から目的地Pnまでの 経路を示す経路リンクのリストがメモリに保存され,2)他方で,上記1)の経 路誘導とは独立して,継続的に,車両の現在位置Cと地図データの地図リン クとのマッチングが行われ,その際,車両の現在位置Cと,地図データのノ ード間を結ぶ地図リンクとを比較することで,車両の現在位置Cと一致する 地図リンクを特定し,3)上記2)のマップマッチングで特定されたリンクが上 記1)の経路リンクの一つと直接対応すると,道路境界領域の処理は行われず, その代わりに地図リンクと一致する経路リンクに基づいて誘導が行われ,他 方で,現在位置Cが,マップマッチングによって特定された経路リンクに載 っていない場合,所定の方法で絞り込んだ道路境界領域内のリンクと現在位 置とを比較してリンク上に載っているか否かの判定をするとの作業が行われ ていることが認められる。 なお,乙16の1は,補助参加人の関連会社所属のエンジニアが作成した 宣誓書であるが,同記載内容は,被告装置の制御に関する他の証拠とも矛盾 がなく,これを特段疑う理由もないから,信用できるものといえる。 以上からすれば,被告装置では,探索開始地点と誘導開始地点とを比較し て両地点が異なるか否かを判断するという作業は行われず,あくまで,車両 の現在位置が所定の経路リンク上に載っているか否かが判定されているにす ぎないから,被告装置は本件発明の構成要件Gを充足しないものというべき\nである。
・・・・
このように,本件発明が,車両が動くことにより探索開始地点と誘導開始 地点の「ずれ」が生じ,車両等が経由予定地点を通過してしまうことを従来\n技術における問題とし,これを解決することを目的として,上記「ずれ」の 有無を判断するために,探索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点の 異同を判断することを定めており,この点は,従来技術にはみられない特有 の技術的思想を有する本件特許の特徴的部分であるといえる。 そして,本件明細書(甲2)において,上記「ずれ」を判断する方法とし て,上記両地点を直接比較する方法以外の方法は何ら記載されておらず,そ れ以外の方法が想定されていたとは認められない。 また,前記2(1)ウ認定の本件特許に係る出願経過からも,探索開始地点 と誘導開始地点とを比較して両地点の異同を判断することが本件発明の本質 的部分であることは明らかである。 なお,原告自身も,本件発明においては「探索開始地点に関する情報」と 「誘導開始地点」とを比較する旨主張している(原告第9準備書面9頁参照) ところ,上記「探索開始地点に関する情報」の中核は「探索開始地点」自体 であるから,原告の上記主張を前提としても,本件特許において,探索開始 地点と誘導開始地点との比較が本質的部分であるといえる。 以上からすれば,探索開始地点と誘導開始地点とを比較して両地点の異同 を判断することが本件発明の本質的部分というべきであり,かつその比較方 法としては,両地点を直接比較することが当然に予定されているものであっ\nて,これに反する原告の主張は採用できない。 なお,原告は,従来技術において,経由予定地点を超えた地点となったこ\nとを判断する必要性すら認識されていなかった以上,この点に関する下位概 念的な具体的な手段まで本質的部分であるとはいえないとも主張する。しか し,前述のとおり,本件発明において探索開始地点と誘導開始地点の「ずれ」 を問題とし,その有無を判断するために,上記両地点を比較することが必須 であり,この点が本件発明を特徴付けているといえるものであって,その比 較の具体的手段が単なる下位概念であるとはいえないから,原告の上記主張 も採用できない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2016.09. 8
平成27(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月29日 知的財産高等裁判所
(3) 本件公報に接した当業者の認識について
ア 前記(2)イのとおり,本件訂正前の明細書には,燐酸を示す化学式として, ホスホン酸の化学式が6か所にわたり記載されているというのであるから,「スルホ ン酸,燐酸及びカルボン酸からなる群」に含まれない「オクタデシルホスホン酸」 が作用成分として記載されていることとも相まって,本件公報に接した当業者は, 「燐酸」又は「リン酸」という記載か,ホスホン酸の化学式及び「オクタデシルホ スホン酸」という記載のいずれかが誤っており,請求項1の「燐酸」という記載に は「ホスホン酸」の誤訳である可能性があることを認識するものということができ\nる。
イ しかし,更に進んで,本件公報に接した当業者であれば,請求項1の「燐 酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて,請求項1の「燐酸」 という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるといえるかを検討 すると,前記(1)イのとおり,請求項1の「燐酸」という記載は,それ自体明瞭であ り,技術的見地を踏まえても,「ホスホン酸」の誤訳であることを窺わせるような不 自然な点は見当たらないし,前記(2)アのとおり,本件訂正前の明細書において,「燐 酸」又は「リン酸」という記載は11か所にものぼる上,請求項1の第2の処理溶 液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤としてスルホン酸,カルボン酸と並ん で「燐酸」を選択し,その最適な実施形態を確認するための4つの比較実験におい て,燐酸や燐酸基が使用されたことが一貫して記載されている。 そうすると,化学式の記載が万国共通であり,その転記の誤りはあり得ても誤訳 が生じる可能性はないことを考慮しても,本件公報に接した当業者であれば,請求\n項1の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて,請求項 1の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるとい うことはできない。 以上によれば,本件訂正事項(燐酸→ホスホン酸)を訂正することは,本件公報 に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三\n者の利益を害することになるものであって,実質上特許請求の範囲を変更するもの であり,126条6項により許されない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2016.09. 8
平成28(行ケ)10048 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年8月25日 知的財産高等裁判所
問題となった商標は、「ファイナンシャル・リスクマネジャー」と「FRM」の2段併記商標です。
当裁判所は,本件配布行為をもって,本件審判請求の登録前3年以内に日本 国内において,商標権者が,本件取消請求役務のうち,「知識の教授」に含ま れる「リスクマネジメント研修」について,本件商標と社会通念上同一と認め られる商標を使用していたことを証明したものと認められるとした本件審決の 判断は誤りであり,原告主張の取消事由2には理由があるから,その余の点に つき判断するまでもなく,本件審決は取り消されるべきものと判断する。
・・・
以上のとおり,被告は,遅くとも平成19年8月には,自社が開講する 講座について,受講希望者向けに講座の概要等を説明するための資料とし て,FRM養成講座についての記載がある案内書を作成し,その後,平成 20年6月及び平成23年10月に同案内書を改訂したが,これらの改訂 後の案内書においても,FRM養成講座についての記載はそのまま残され ていることが認められる。そして,このような事実からすれば,被告は, 要証期間である平成23年11月13日以降においても,FRM養成講座 についての記載がある本件案内書を,受講希望者らへの案内資料として保 有し,これを受講希望者らに配布するなどして使用していたことが推認さ れるものといえる。
2 「知識の教授」の役務についての使用の有無について
原告は,仮に本件配布行為が認められるとしても,要証期間内に,被告が FRM養成講座を実際に開講し,又は,開講の準備を整えていたとの事実が 認められないことからすれば,本件商標と社会通念上同一の商標を,「知識の 教授」という役務について使用したものとは認められない旨主張するので, 以下検討する。 要証期間内に,被告がFRM養成講座の名称を使用した講座を開講して いた事実が認められるか否かについて
ア 証拠上認められる客観的事実について 前記第2の2のとおり,平成22年12月にプロフェッショナル協 会が設立され,同協会が,コンサルタント協会に代わって,被告が開 講する講座に対応する資格の認定・管理等を行うこととなった際,被 告は,関係者らに対し,甲2書面をもって,従前コンサルタント協会 が認定・管理していたFRMの資格について,その名称をFRCに変 更した上で,プロフェッショナル協会において認定・管理していく旨 を通知している事実が認められる。他方,その後,被告が,関係者ら に対し,上記通知に係る事項を訂正したり,変更したりする旨の通知 をした事実をうかがわせる証拠はない。 しかるところ,甲2書面の上記内容は,被告がそれまで開講してき たFRM養成講座についても,上記資格名の変更に対応した名称に変 更することを意味するものといえるから,被告が甲2書面による通知 を行い,その後これを訂正・変更する通知も行っていないということ は,特段の事情がない限り,被告が,平成23年以降は,FRM養成 講座の名称を使用した講座を開講していないことを示す事情というこ とができる。 また,次のような事情も,被告が平成23年以降FRM養成講座の 名称を使用した講座を開講していないことをうかがわせる事情という ことができる。 すなわち,被告が開設するホームページの記載をみると,平成18 年の時点では,被告が開講する講座名として,1)リスクコンサルタン ト(マネジャー)養成講座・基礎課程,2)リスクコンサルタント(マ ネジャー)養成講座・上級課程,3)CRO養成講座に加え,4)FRM ファイナンシャル・リスクマネジャー養成講座の記載がある(甲6) のに対し,平成23年及び平成24年の時点では,上記1)ないし3)の 記載はあるものの,「FRMファイナンシャル・リスクマネジャー養成 講座」の記載はない(甲8,9)。また,平成25年,平成26年及び 平成28年の時点においても,「リスクマネジメント・プロ養成講座・ 基礎課程」,「リスクマネジメント・プロ養成講座・上級課程」等の記 載はあるものの,FRM養成講座の記載はない(甲10ないし13, 72)。 このように,被告が開設するホームページをみる限り,平成23年 以降,被告がFRM養成講座の名称を使用した講座を開講している形 跡は何らみられず,かえって,被告のホームページでは,被告が開講 する他の講座については継続して紹介されているのに対し,FRM養 成講座については,被告が当該講座を開講していたことが明らかな平 成18年当時には紹介されていたのに,平成23年以降には全く紹介 されていないことからすれば,平成23年以降は,被告において,F RM養成講座の名称を使用した講座を開講していないことがうかがわ れるものといえる。 以上のとおり,証拠上認められる客観的・外形的な事実をみる限り, 本件案内書中にFRM養成講座の記載があること以外には,被告が平 成23年以降にFRM養成講座の名称を使用した講座を開講している 形跡は見当たらず,むしろ,そのような講座を開講していないことが 積極的にうかがわれるものといえる。
2016.08.29
平成27(行ケ)10245 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月24日 知的財産高等裁判所
当初明細書等の記載には,前記1(1)のとおり,便器と便座との間隙を形成する手 段としては便座昇降装置が記載されているが,他の手段は,何の記載も示唆もない。 すなわち,補正前発明は,便器と便座との間隙を形成する手段として,便座昇降 装置のみをその技術的要素として特定するものである。 そうすると,便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以 外の手段を導入することは,新たな技術的事項を追加することにほかならず,しか も,上記のとおり,その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから, 本件補正は,新規事項を追加するものと認められる。
(3) 被告の主張について
1) 被告は,当初明細書等に接した当業者にとって,便器と便座との間に拭き取 りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく,その手段が当初明細 書等に例示されたもの限られないということは,自明の事項であると主張する。 しかしながら,便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには, その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず, 単に,他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり,当初明細書 等には,便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり,他 の手段が,当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たら ない。
2) また,被告は,公開特許公報には,便座昇降装置以外の手段で便器と便座と の間に間隙を設ける技術が開示されているから,当初明細書等に便座昇降装置以外 の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは,当初明細書等に実質的に記載さ れていると主張する。 しかしながら,上記の自明な事項の解釈からいって,他に公知技術があるからと いって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないこと は,明らかである。のみならず,上記公報に記載された技術は,容器6と座部3と の間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり,便器 と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは,全く技 術的意義を異にしている。
3) 被告の上記各主張は,いずれも採用することはできない。
・・・
3 取消事由2(サポート要件充足の有無に対する判断の誤り)について
上記2に説示のとおり,当初明細書等には,便座昇降装置により便座が上昇され た際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙を設ける手段の記載はないところ, 本件発明に係る本件補正後の明細書及び図面(以下「本件明細書」という。甲4。) は,当初明細書等の発明の詳細な説明及び図面と同旨であり,本件明細書にも,便 座昇降装置により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙 を設ける手段の記載はない。そして,本件発明15のような機械式拭き取り装置の 設置を前提として,便器と便座との間の間隙をどのように形成するかに関して何ら かの技術常識があるとは認められない。 そうすると,便器と便座との間の間隙を形成するに際して,便座昇降装置を用い るものに限定されない本件発明15は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載した ものではなく,サポート要件を充足しないものである。したがって,本件発明15 の発明特定事項を全て含む本件発明23,本件発明25ないし本件発明29,及び 本件発明30(15)もまた,サポート要件を充足しないものである。 以上から,審決のサポート要件充足の有無に対する判断には,誤りがある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2016.08.26
平成27(ワ)5281 商号使用差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成28年8月23日 大阪地方裁判所
確かに本件は,原告の元従業員が中心となって活動する被告の事業が,原告 の顧客を奪うことで成立しているように見受けられる事案であり,また事業開始が そのことを見込んでされたようにも見受けられるが,原告の既存顧客が被告に奪わ れたとするなら,それはそもそも原告が当該工事を施工できない状態であった上, 他方で被告代表者や被告従業員には原告在職時の施工実績による信用,少なくとも\n人的関係があったからと考えるのが自然であり,そこに原告商号と被告商号の類似 性が貢献している様子は認められず,また被告代表者がそのことを期待して被告商\n号を選択したとも認められない。被告による被告商号の選択使用は,被告代表者が\n供述するように,原告創業者への尊敬の念に由来すると認めるのが相当であって, 会社法8条1項にいう「不正の目的」があったとはおよそ認められない。 エ なお,さらに原告は,被告が原告と同じ行政区に本店を移転した経緯や,そ の登記手続の手順の不自然さを問題にするが,上記認定したアスベスト除去工事, ダイオキシン類対策工事等の契約締結過程等の問題からすると,そのことで原告が 主張するような利点があるとは認められないから,上記の点で被告の「不正の目的」 が推認されるわけではない。 また,原告は,被告が掲載した求人誌の求人広告の記載内容も問題にしているが, 同記載中には,旧会社を引き継ぎ4月から新体制で開始した会社であることを説明 して原告とは別会社と理解できる部分もあるし,そもそも,この求人誌は事業者で はない者を対象として掲載されているのであるから,会社法8条1項の「不正の目 的」を推認する事情とはいえない。
オ 原告は,被告が原告従業員を大量に引き抜いたことにより,原告が従前の業 務であるダイオキシン類対策工事の受注を停止せざるを得なくなったなどと主張し, この事情をも「不正の目的」を推認させる事情として主張するようであるが,「不正 の目的」は,商号を使用することに関して認められる必要があり,原告のいう事情 は,それ自体で不法行為を主張するのならともかく,商号使用についての「不正の 目的」を推認する事情とは認められない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2016.08.23
平成27(ワ)13258 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年7月27日 東京地方裁判所
ア 被告説明文による原告説明文に係る著作権侵害の成否の判断について
原告は,原告説明文は創作性を有する表現たる著作物であり,被告説明文は原告\n説明文を複製したものであって,原告の著作権に対する侵害が成立する旨主張する。 そこで検討するに,上記著作権侵害が認められるためには,まず,1)原告説明 文と被告説明文とで共通する表現部分について,創作性が認められなければならな\nい。そして,原告説明文と被告説明文は,いずれも本件商品の取扱説明書における 説明文であるところ,製品の取扱説明書としての性質上,当該製品の使用方法や使 用上の注意事項等について消費者に告知すべき記載内容はある程度決まっており, その記載の仕方も含めて表現の選択の幅は限られている。これに対し,原告は,我\nが国においては,原告が初めて本件商品を販売した際,高い品質と安全性が求めら れる日本市場向けに幼児用首浮き輪の安全適切な使用方法等を分かりやすく理解さ せるための取扱説明書は存在していなかった旨指摘するけれども,そのような状況 にあっても,本件商品の使用方法や使用上の注意事項等については,それ自体はア イデアであって表現ではなく,これを具体的に表\現したものが一般の製品取扱説明 書に普通に見られる表現方法・表\現形式を採っている場合には創作性を認め難いと いわざるを得ない。本件商品の取扱説明書において,幼児のどのような行動に着目 した注意事項を記載しておくか,どのような文章で注意喚起を行うかといった点に ついても,選択肢の幅は限られているとみられる。 次に,前記前提事実に証拠(甲4,13)及び弁論の全趣旨を総合すると,原告 説明文は,モントリー説明書の英語の説明文を日本語に翻訳した上でこれを修正し て作成されたものであり,同説明文に依拠して作成されたものと認められる。二次 的著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみにつ いて生じ,原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないこと(最高裁 平成4年(オ)第1443号同9年7月17日第一小法廷判決・民集51巻6号2 714頁〔ポパイ事件〕)に照らすと,上記1)で創作性が認められる表現部分につ\nいても,2)モントリー説明書の説明文と共通しその実質を同じくする部分には原 告の著作権は生じ得ず,原告の著作権は原告説明文において新たに付与された創作 的部分のみについて生じ得るものというべきである。そして,本件においては,上 記1)で原告説明文(日本語)と被告説明文(日本語)とで共通する表現部分につい\nて創作性が認められるとすれば,その理由は,もとより翻訳の仕方に関わるもので はなく,英文か日本文かに関わらない表現内容等によるものと考えられるから,上\n記2)では,モントリー説明書の英文を日本語に翻訳したその訳し方に創作性があっ たとしても,被告による原告の著作権侵害を基礎付ける理由にはなり得ず,表現内\n容等について原告説明文において新たに追加・変更された部分でなければ,上記「原 告説明文において新たに付与された創作的部分」には当たらないというべきである。 また,原告説明文において本件ガイドラインと共通しその実質を同じくする部分 についても,原告説明文がこれに依拠したと認められる場合には,上記2)と同様, 原告の著作権は生じないというべきである。
2016.08.15
平成28(行ケ)10075 商標登録維持決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年8月9日 知的財産高等裁判所
商標は、トヨタ自動車(株)の「MIRAI」です(登録5753538号)。
ただ、本件は、分割出願時に親出願と同じ指定商品・役務を記載していたので分割要件を満たしていないと判断された案件です。
同第5項に係る訴えは,商標法43条の3第5項の規定が違憲無効であることの確認を抽象的に求めるものにすぎないものであるから,上記訴えは,上記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるものとはいえず,不適法なものである。
◆判決本文
審決についてダイレクトリンクが張れないので、審決公報の該当部分をあげておきます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 本件商標
本件登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年11月18日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月19日に登録査定、同年3月27日に設定登録されたものである。\n
2 登録異議の申立ての理由の要旨\n 登録異議申立人(以下「申\立人」という。)は、本件商標及びその指定商品は、先願に係る以下の(1)ないし(3)のとおりの商標(以下、3件を一括して「引用出願」という場合がある。)と同一又は類似し、その指定商品においても同一又は類似するものであるから、商標法第8条第1項に違反し、当該引用出願が登録されることにより、商標法第4条第1項第11号違反となり、商標法第43条の2第1号に該当するから、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張している。
(1)商願2015ー25192(以下「引用出願1」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類、第39類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年9月8日に登録出願された商願2014−75417(以下「親出願」という。)を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、親出願と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年3月20日に登録出願されたものである。\n なお、親出願は、平成27年3月23日に、引用出願1は、同年10月5日に、それぞれ、出願却下の処分がされている。
(2)商願2015ー56246(以下「引用出願2」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、上記(1)に記載の引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第12類と同一の商品を指定商品として、平成27年6月13日に登録出願されたものである。
(3)商願2015ー68401(以下「引用出願3」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第9類、第12類及び第35類の商品及び役務と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月18日に登録出願されたものである。\n
3 当審の判断
(1)引用出願1について
引用出願1は、前記2(1)のとおり、親出願に係る新たな商標登録出願として商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がなされたものである。
しかしながら、商標法第10条第1項は、商標登録出願の分割の要件を定めたものであり、その第1項で「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定されており、同条第2項において、「前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」とされているところ、引用出願1は、親出願の出願に係る指定商品及び指定役務のすべてを指定商品及び指定役務としており、「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる(下線は、合議体による。)」としている商標法第10条第1項の要件を満たしていない。
したがって、引用出願1は、もとの商標登録出願と主張する親出願の登録出願の時に出願したものとみなすことはできないものである。
そうとすれば、引用出願1は、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成27年3月20日である。
(2)引用出願2及び引用出願3について
引用出願2及び3は、前記2(2)及び(3)のとおり、引用出願1に係る新たな商標登録出願として、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がされたものである。
そして、引用出願1は、上記(1)に記載のとおり、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成27年3月20日である。
そうとすれば、仮に、引用出願2及び3が引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の要件を満たし、同条第2項の適用を受けることができるものとして認められ、その出願日が遡及される場合があったとしても、その出願日は、引用出願1の出願日である平成27年3月20日である。
(3)商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号該当性について
上記(1)のとおり、引用出願1は、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、平成27年3月20日である。
また、引用出願2及び3は、上記(2)のとおり、仮に、商標法第10条第1項の要件を満たし、同条第2項の適用がされる場合があったとしても、その出願日は、引用出願1の出願日である平成27年3月20日である。
そうすれば、引用出願は、本件商標の出願の日(平成26年11月18日)前の商標登録出願に係る他人の登録商標ということはできない。
また、親出願及び引用出願1は、前記2(1)のとおり、既に出願却下の処分がされているものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
さらに、引用出願は、本件商標の登録査定時に設定登録されていたものではないから、本件商標は、同法第4条第1項第11号に違反して登録がされたものでもない
。
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2016.08.15
平成27(行ケ)10149 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月10日 知的財産高等裁判所
イ 相違点2の容易想到性について
(ア) 本件審決は,浚渫用グラブバケットに関する発明である引用発明1におい て,同じく浚渫用グラブバケットに関する周知技術2及び3並びに引用発明3を適 用して相違点2に係る本件発明の構成とすることは,当業者であれば容易に想到し\n得たことであると判断した。 (イ) 相違点2は,シェルの構成に関するものである。しかし,引用例1(甲1)\nには,専ら,バケットの吊上げ初期の揺れがほとんど発生せず,開閉ロープのロー プ寿命も長くなる浚渫用グラブバケットの提供を課題として(【0005】),上部 シーブ,下部シーブ,バケット開閉用の開閉ロープ及びガイドシーブの構成や位置\nによって上記課題を解決する発明が開示されており(【請求項1】〜【請求項3】, 【0006】,【0016】),シェルに関しては,特許請求の範囲及び発明の詳細な 説明のいずれにも,「各シェル部1A,1Bは軸3で開閉自在に軸支され,下部フ レーム2に取付けられている。」(【0008】)など,他の部材と共にグラブバケッ トを構成していることが記載されているにとどまり,シェル自体の具体的構\成につ いての記載はない。引用例1においては,前記⑴ア(ア)のとおり,上記発明の一実 施形態に係る浚渫用グラブバケットの側面図【図1】及び正面図【図2】に加え, 従来のグラブバケットの側面図【図6】及び正面図【図7】において,シェルが図 示されているにすぎない。 したがって,引用例1には,シェルの構成に関する課題は明記されていない。\n(ウ) もっとも,引用例3(甲4)の考案の詳細な説明中の考案が解決しようと する問題点(前記(2)ア(イ)b),周知例1(甲16)の【0002】,【0003】 (前記(3)ア(イ)),周知例2(甲26)の考案の詳細な説明中,従来技術の欠点に ついて述べたもの(前記(3)イ(イ)a)及び引用例5(甲5)の【0006】から 【0008】(前記(4)ア(イ)c)によれば,本件特許出願の当時,浚渫用グラブバ ケットにおいて,シェルで掴んだ土砂や濁水等の流出を防止することは,自明の課 題であったということができる。したがって,当業者は,引用発明1について,上 記課題を認識したものと考えられる。 前記(3)ウのとおり,本件審決が周知技術2を認定したことは誤りであるが,当業 者は,引用発明1において,上記課題を解決する手段として,周知例2に開示され た「シェルが掴んだヘドロ等の流動物質の流出を防ぐために,相対向するシェル1 1,11の上部開口部12,12に上部開口カバー13,13をシェル11,11 の内幅いっぱいに固着するか,又は,取り外し可能に装着することによって,上部\n開口部12,12を上部開口カバー13,13でふさぎ,シェル11,11を密閉 する」構成を適用し,相違点2に係る本件発明の構\成のうち,「シェルの上部にシ ェルカバーを密接配置する」構成については容易に想到し得たものと認められる。\nしかしながら,前記(4)のとおり,シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周 知技術3は,シェルの上部が密閉されていることを前提として,そのような状態に おいてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要があり,この課題を解決す るための手段である。引用例1には,シェルの上部が密閉されていることは開示さ れておらず,よって,当業者が引用発明1自体について上記課題を認識することは 考え難い。当業者は,前記のとおり引用発明1に周知例2に開示された構成を適用\nして「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し,同構\成 について上記課題を認識し,周知技術3の適用を考えるものということができるが, これはいわゆる「容易の容易」に当たるから,周知技術3の適用をもって相違点2 に係る本件発明の構成のうち,「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」す\nる構成の容易想到性を認めることはできない。\n(エ) また,前記(2)のとおり,引用例3には,海底から掻き取った海底土砂等を バケットシェル内に保持することを可能にし,かつ,水の抵抗を最小限にして,荷\nこぼれによる海水汚濁を防止し得るグラブバケットの提供を課題とし,同課題解決 手段として,シェルの上部開口部の開閉手段を設けた旨が記載されていることから, 当業者は,引用発明1において,シェルで掴んだ土砂や濁水等の流出を防止すると いう自明の課題を解決する手段として,シェルを密閉するために,「浚渫用グラブ バケットにおいて,シェルの上部開口部に,シェルを左右に広げたまま水中を降下 する際には上方に開いて水が上方に抜けるとともに,シェルが掴み物を所定容量以 上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開き,グラブバケットの水中での移 動時には,外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取り付けるとい う技術」である引用発明3の適用を容易に想到し得たものということができる。 しかし,引用発明1に引用発明3を適用しても,シェルの上部に上記のように開 閉するゴム蓋を有する蓋体をシェルカバーとして取り付ける構成に至るにとどまり,\n相違点2に係る本件発明の構成には至らない。
ウ 被告の主張について
被告は,空気抜き孔をシェルカバーの一部に設けることは,引用例5及び周知例 1に開示された公知技術ないし周知技術である旨主張するが,前記イのとおり,同 技術は,シェルの上部が密閉されていることを前提として,そのような状態におい てはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要があり,この課題を解決するた めの手段であり,引用例1には,シェルの上部が密閉されていることは開示されて いないのであるから,よって,当業者が引用発明1自体について上記課題を認識す ることは考え難く,上記技術を適用する動機付けを欠く。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2016.08.15
平成28(行ケ)10065 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年8月10日 知的財産高等裁判所
上記事実及び弁論の全趣旨によれば,本願商標の登録出願時(平成25年11月 19日)及び本件審決時(平成28年1月29日)において,亡山岸(生前の住所 地は東京都豊島区。甲19)とは別に,「山岸一雄」を氏名とする者が,複数生存 していたものと推認される。
ウ 以上によれば,本願商標は,他人の氏名を含む商標であると認められる。
(2) 「山岸一雄」を氏名とする者の承諾の有無
証拠(甲19,38)及び弁論の全趣旨によれば,原告の取締役であった亡山岸 は,本願商標の登録出願時において,原告が本願商標の登録出願をし,その商標登 録を受けることを承諾していたこと,その後,亡山岸は,平成27年4月1日死亡 したことが認められる。 しかし,前記(1)イのとおり,本願商標の登録出願時及び本件審決時において,亡 山岸とは別に,「山岸一雄」を氏名とする者が,複数生存していたものと推認され るところ,亡山岸以外の「山岸一雄」を氏名とする者が本願商標の登録について承 諾していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
(3) 小括
以上によれば,本願商標は,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けるこ とができないものというべきである。
3 原告の主張について
(1) 原告は,商標法4条1項8号において,氏名を含む商標の登録が許されない のは,1)他人のパブリシティの権利を侵害する場合(当該他人の氏名等に少なくと も周知性が認められる場合),2)パブリシティの権利以外の氏名専用権の侵害にな る場合(商標出願の願書の記載から客観的類型的に判断し,氏名保持者が不快感を 感じると判断すべき場合)に限られると解すべきところ,本願商標は,上記1)及び 2)のいずれにも該当しない旨主張する。 しかし,商標法4条1項8号の趣旨は,前記1のとおり,人の氏名に対する人格 的利益の保護,すなわち,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われるこ とがないという利益を保護することにある。そして,同号は,その規定上,「著名 な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」とし,これらについては 著名なものを含む商標のみを不登録事由とする一方で,「他人の肖像又は他人の氏 名若しくは名称」については,著名又は周知なものであることを要するとはしてい ない。また,同号は,人格的利益の侵害のおそれがあることそれ自体を要件として 規定するものでもない。したがって,商標法4条1項8号の趣旨やその規定ぶりか らすると,同号にいう「他人の氏名」が,著名又は周知なものに限られるとは解し 難く,また,同号の適用が,他人の氏名を含む商標の登録により,当該他人の人格 的利益が侵害され,又はそのおそれがあるとすべき具体的事情の証明があったこと を要件とするものであるとも解し難い。すなわち,同号は,他人の氏名を含む商標 については,そのこと自体によって,上記人格的利益の侵害のおそれを認め,その 他人の承諾を得た場合でなければ,商標登録を受けることができないとしているも のと解される。 原告の上記主張は,商標法4条1項8号が,その規定上,他人の氏名については 「著名な」ものであることを要するとはしていないこと,他人の人格的利益を侵害 し,又はそのおそれがあるとすべき具体的事情の証明があったことを要件としてい るとも解し難いことに照らし,文理解釈の範囲を超えるものといわざるを得ない。 また,同号の趣旨は,上記のとおり,人の氏名に対する人格的利益の保護にあると ころ,この人格的利益の保護の要否を,顧客吸引力の有無(周知性や著名性の有 無)により分けるというのも,同号が商品又は役務の出所の混同のおそれを要件と していないことに照らし,相当でない。さらに,自己の氏名を含む商標が登録され ることにより氏名保持者が精神的苦痛や不快感を感じるか否かを商標出願の願書の 記載のみから判断すれば足りるというのも,氏名保持者ごとに人格的利益に係る事 情は異なるにもかかわらず,その個別的事情を一切捨象するものであって,相当で ない。なお,他人の氏名を含む商標について,当該氏名を有する他人から登録異議 の申立てや無効審判請求がされたときに初めて,当該商標の商標法4条1項8号該\n当性を判断すれば足りるとするのは,同号が商標の不登録事由として規定されてい ることにそぐわないのみならず,登録異議の申立期間が商標掲載公報の発行の日か\nら2月以内に限られ(同法43条の2),同項8号に違反してされたことを理由と する無効審判は商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求することがで きないとされていることから(同法47条1項),人は,自らの承諾なしにその氏 名を商標に使われることがないという利益を確保するために,自己の氏名が含まれ る商標の登録の有無を常に確認しなければならないことになる。かかる解釈は,商 標に含まれる氏名を有する他人に負担を強いるものであって,相当でないといわざ るを得ない。 以上の諸点に照らし,原告の上記主張は,採用することができない。なお,本件 において,亡山岸以外の「山岸一雄」が不快感を感じることがないとまでは認める に足りない。
(2) 原告は,学説の状況及び氏名を含む商標が登録されている例が存在すること を挙げ,商標法4条1項8号について,他人の氏名を含む商標については,そのこ と自体によって,上記人格的利益の侵害のおそれを認め,その他人の承諾を得た場 合でなければ,商標登録を受けることができないものと解釈することは不当である 旨主張する。 しかし,原告の挙げる学説の内容は,当裁判所の判断を拘束するものではないし, 過去に氏名を含む商標が登録されている例があるからといって,本件審決における 本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断が,これに左右されるものではない。
(3) 原告は,被告が,NTT「ハローページ」電話帳を検索して同姓同名者を発 見し,これを出願人に通知して,拒絶や審決の根拠とするのは,現実に同姓同名者 が存在する蓋然性が高いにもかかわらず,氏名を含む商標が登録されている例が多 く存在していること,NTT電話帳は,プライバシー保護等の観点から,近時掲載 者数が激減しており,また,戸籍名で登録されている可能性もますます少なくなっ\nていること等に照らし,不当である旨主張する。 しかし,前記2(1)イのとおり,本件においては,NTT「ハローページ」電話帳 の掲載内容によれば,本願商標の登録出願時及び本件審決時において,亡山岸とは 別に,「山岸一雄」を氏名とする者が,複数生存していたものと推認されるのであ るから,本件審決が,本願商標の商標法4条1項8号該当性について,NTT「ハ ローページ」電話帳を検索し,その結果に基づき判断したことが,不当であるとい うことはできない。そして,これら同姓同名者の承諾を得ていないにもかかわらず, 「山岸一雄」の氏名を含む商標が登録されることにより,それらの者の人格的利益 を侵害するおそれがおよそ存在しないとまでいうことはできない。
・・・
(6) 原告は,他人の氏名を含む商標であっても,長年にわたる当該商標の使用や 指定商品又は指定役務と関連付けられた報道等での当該氏名の露出等の結果,需要 者が何人かの業務に係る商品又は役務であると認識することができ,他人の業務に 係るものと認識しない状態となった場合には,商標法4条1項8号の規定にかかわ らず,商標登録を受けることができると解すべきである旨主張する。 しかし,商標法4条1項8号について,同法3条2項に相当する規定は存しない。 原告の上記主張は,独自の見解であって,採用の限りでない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.08. 8
平成27(行ケ)10148 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月3日 知的財産高等裁判所
本願明細書には,「複数のプロセッサコア」という分散された環境に備えられた 「プレディケート予測器」において行われる「プレディケート命令の出力」の「予\ 測」処理の内容に関し,【0026】ないし【0029】の記載があり,ここには, 「概略プレディケート経路情報」を用いて,2つの履歴レジスタ,すなわち,コア ローカル履歴レジスタとグローバル分岐履歴レジスタを生成し,それを用いて「プ レディケート命令の出力」の予測を行うこと(【0026】,【0027】),並\nびに,上記グローバル分岐履歴レジスタに対応するグローバル履歴レジスタとして, 「コアローカルプレディケート履歴レジスタ」を用いる実施例(【0028】,図 6A)及び「グローバルブロック履歴レジスタ」を用いる実施例(【0029】, 図6B)が記載されている。 しかし,上記記載からは,「概略プレディケート経路情報」からコアローカル履 歴レジスタとグローバル分岐履歴レジスタという二つの履歴レジスタをどのような 処理により分けて生成するのか,また,当該二つの履歴レジスタをどのような処理 により「プレディケート命令の出力」の「予測」において使い分けるのか,さらに,\n上記二つの履歴レジスタを用いた「プレディケート命令の出力」の「予測」を信頼\n性の高く正確なものとするために「概略プレディケート経路情報」として具体的に どのような内容が必要とされるのか,把握することはできない。 したがって,本願明細書の上記記載から,「複数のプロセッサコア」という分散 された環境に備えられた「プレディケート予測器」において,信頼性の高いプレデ\nィケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成し,コア間の通信を\n最小にするために,「概略プレディケート経路を表す情報」に基づく「予\測」の処 理が具体的にどのように行われているのか明らかであるということはできない。 そして,当業者にとって,本願の優先日当時の技術常識に基づき,「複数のプロ セッサコア」という分散された環境に備えられた「プレディケート予測器」におい\nて,信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を\n生成し,コア間の通信を最小にするために,「概略プレディケート経路を表す情\n報」に基づいて行われる「予測」の処理内容が自明であることを認めるに足りる証\n拠はない。 そうすると,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が,「複数のプロセッサ コア」という分散された環境に備えられた「プレディケート予測器」において,信\n頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成し,\nコア間の通信を最小にするために,「概略プレディケート経路を表す情報」に基づ\nいて行われる「予測」の処理内容を理解することができるように記載されていると\nいうことはできない。 エ 以上によれば,本願明細書の発明の詳細な説明は,「複数のプロセッサコ ア」という分散された環境において,「プレディケート予測器」が「概略プレディ\nケート経路を表す情報」に基づいて「プレディケート命令の出力を予\測する」とい う処理を行うことにより,信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得る\nプレディケート履歴を生成することができ,同時にコア間の通信を最小にするとい う作用効果を奏するコンピューティングシステムを製造し,使用することができる 程度に記載されていない。 したがって,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明1の実施をす ることができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできない。\n
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本願明細書には,1)対象のアーキテクチャは,EDGEアーキテク チャのようなハイブリッドなデータフローのアーキテクチャであること,2)コンパ イラが,各ブロックの分岐命令に,プログラム内での分岐命令の順序にしたがって, 3ビットの「終了コード」(「出口コード」ともいう。)を割り当てること,3) 「概略プレディケート経路情報」は,コンパイラによって,分岐命令に符号化され, 特定のブロックの具体的な分岐を識別可能であること,4)予測器が,分岐命令に符\n号化された「概略プレディケート経路情報」を用いてプレディケート予測を行うこ\nとが記載されているところ,EDGEアーキテクチャにおいて,分岐命令に出口を 識別する例えば3ビットの識別子を割り当て,それを分岐命令に符号化することは, 本願の優先日前に技術常識であったから,当業者であれば,本願の「概略プレディ ケート経路情報」は,出口を識別する例えば3ビットの「終了コード」として分岐 命令に符号化された情報であると理解し,コンパイルのタイミングでコンパイラに よって,分岐命令の分岐先を,例えば3ビットの終了コードで表した形式で,分岐\n命令に符号化された情報であり,予測器によってプレディケート予\測に用いられる 情報であると理解する旨主張する。 イ しかし,原告が挙げる甲9(「Analysis of the TRIP S Prototype Block Predictor」平成21年4月)及 び甲10(「Distributed Microarchitectural Protocols in the TRIPS Prototype Proc essor」平成18年12月)は,EDGEアーキテクチャの一例である「TR IPS」という特定のアーキテクチャについて,「分岐命令に出口を識別する例え ば3ビットの識別子を割り当て,それを分岐命令に符号化すること」を記載したも のにすぎず,EDGEアーキテクチャ一般について記載したものではない。したが って,上記証拠(甲9,10)から,本願の優先日前に「EDGEアーキテクチャ において,分岐命令に出口を識別する例えば3ビットの識別子を割り当て,それを 分岐命令に符号化すること」が技術常識であったと認めるに足りず,他にこれを認 めるに足りる証拠はない。 ウ また,前記イの点を措き,仮に当業者において,本願明細書の「概略プレデ ィケート経路情報」は,出口を識別する例えば3ビットの「終了コード」として分 岐命令に符号化された情報であると理解し,コンパイルのタイミングでコンパイラ によって,分岐命令の分岐先を,例えば3ビットの終了コードで表した形式で,分\n岐命令に符号化された情報であり,予測器によってプレディケート予\測に用いられ る情報であると理解したとしても,本願発明1の「概略プレディケート経路を表す\n情報」に相当する「概略プレディケート経路情報」について,1)そのデータ形式, 2)その形式に「終了コード(出口コード)」という,本願明細書全体の記載から見 ても内容が不明なコードが関連していること,3)分岐命令への符号化という処理が コンパイラによってされること,4)予測器によるプレディケート予\測に用いられる ことが把握できるにすぎず,「出口を識別する例えば3ビットの「終了コード」と して分岐命令に符号化された情報」が,「プレディケート命令の出力」の「予測」\nを信頼性が高く,正確なものとする上で,具体的にどのような内容のものであるの かを把握することはできない。 したがって,「複数のプロセッサコア」という分散された環境に備えられた「プ レディケート予測器」において,信頼性の高いプレディケートの正確な予\測に役立 ち得るプレディケート履歴を生成し,コア間の通信を最小にするために,「概略プ レディケート経路を表す情報」に基づく「予\測」の処理が具体的にどのように行わ れているのかが,明らかであるということはできない。
(4) 小括
以上によれば,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明1の実施を することができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできないから,\n本願発明1を特許請求の範囲に含む本願は,拒絶すべきものである。
・・・・
以上によれば,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理 由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 本件審決は,最終的な結論において誤りはなかったことから,取り消すべきもの とはされなかったが,以下の問題があるから,事案に鑑み,本件審決書について付 言する。まず,本件審決は,その判断において,平成25年9月6日付けで通知し た拒絶理由及び同年12月27日付けでした拒絶査定の内容を引用した上で,本願 発明が,拒絶査定で示された理由を解消しているか否かを判断するという体裁で, しかも,前記第2の3のとおり,本件補正前の請求項と本件補正後の請求項が混在 したまま,審決の理由を示している。しかし,本件審決における判断対象は,本件 補正後の請求項であり,本件補正後の本願発明に拒絶理由が存在するか否かを判断 すべきである。また,本件審決におけるサポート要件に係る判断は,その結論部分 において,本件補正後の請求項の全てについてサポート要件を満たさない旨判断し ていながら,本件補正後の請求項1についてしかその具体的理由が言及されておら ず,実施態様の異なる他の請求項についても,サポート要件を満たさないことにな る理由は,何ら具体的に述べられていない。以上のとおり,本件審決書は,適切と はいい難いものであって,判断対象を明確にして,結論を導くに足りる理由を示す ことが望まれる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2016.07.29
平成28(行ケ)10004 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年7月27日 知的財産高等裁判所
前記認定事実(7)のとおり,被告は,平成26年4月1日,東芝ホームアプ ライアンスに対し,品名を「ASY−PWB−BRUSH」とする商品を100個 納品しているところ,東芝ホームアプライアンスにおいては,品名を「ASY−P WB−BRUSH」とする商品は,制御基盤に関する商品を指すのであるから(甲 15),被告は,東芝ホームアプライアンスに,制御基盤を100個納品したもの と認められる。
イ 次に,前記認定事実(7)のとおり,被告と東芝ホームアプライアンスとの間 で授受された伝票には,品名略号欄に「ASY−PWB−BRUSH」との印字だ けではなく,「クリーンマスター(R)」との手書文字も記載されている。 また,被告と東芝ホームアプライアンスとの間で授受された伝票のうち,「検査 表D(検査控)」と題する伝票,「受入/検収票C(受入控)」と題する伝票は,\n被告が,東芝ホームアプライアンスに,制御基盤の納品時に交付したものと認めら れる(甲16,乙10,16)。そして,これらの伝票は,東芝ホームアプライア ンスが管理していたものであるから,被告が,原告との紛争に備えるために,わざ わざ東芝ホームアプライアンスから,これらの伝票の返還を受け,「クリーンマス ター(R)」と手書文字を記載したとは考えにくい。 したがって,被告は,東芝アプライアンスに制御基盤を納品する際,その伝票に, 当該制御基盤に関して「クリーンマスター(R)」との標章を付したものと認められる。 ウ よって,被告は,平成26年4月1日,少なくとも1社に対し,制御基盤に 関する取引書類に,「クリーンマスター(R)」なる標章を付して配布したものである。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2016.07.26
平成28(ネ)10014 商標権侵害損害賠償請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成28年7月20日 知的財産高等裁判所 横浜地方裁判所 横須賀支部
しかしながら,登録商標に類似する標章の商標権者以外の者による使用が 当該商標権の侵害に当たるとするためには,その標章が,商品・役務出所表示機能\, 自他商品・役務識別機能を発揮する態様で,すなわち,需要者が何人かの業務に係\nる商品又は役務であることを認識できる態様で,使用されていることが必要である と解すべきである。なぜなら,法律上,商標の果たすべき最大の機能は,商品・役\n務出所表示機能\,自他商品・役務識別機能であり,商標権によってまず守られるの\nは,登録商標のそのような機能であり,商標権侵害とされるのは,登録商標のこの\n機能を阻害する態様の行為に限られると考えるのが合理的であるからである。
(4) そこで,検討するに,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人 は,「FRANGIPANI」を屋号として,宝石様のガラス等に貼付された医療用\nシートを耳のつぼに貼付する「耳つぼジュエリー」の施術方法を教授する「耳つぼ\nジュエリープロ通信講座」を開催しており,インターネット上にホームページを開 設して,前記講座の広告に伴う自己紹介として,1)「現在はサロンワークの傍ら, 自身のセミナー,通信講座の運営など「耳つぼジュエリスト」として後進の指導と 女性(特に育児中のママ)の起業サポートに力を注ぎ,日々「大人を教える技術」 に磨きをかける。」という被控訴人標章を含む文言を記載したこと,被控訴人標章が 記載された前記ホームページには,その上部に「FRANGIPANI」という被 控訴人の屋号の記載があり,その下に「耳つぼジュエリープロ通信講座」との記載 があったこと,被控訴人の開設したホームページには,いずれもその上部に「FR ANGIPANI」という被控訴人の屋号の記載があり,被控訴人は,当該ホーム ページ又はこれらにリンクされているページ中に,2)「耳つぼジュエリースクール では,お仕事として耳つぼジュエリーをしていきたい耳つぼジュエリストの育成も してまいりました。」,3)「そんな耳つぼジュエリストとしてのやりがいや幸せを感 じていただきたいと思っています。」,4)「また,受講いただいた方への十分なコミ\nュニケーションとサポート,サービス提供もとことんさせていただき,自信を持っ て耳つぼジュエリストデビューをしていただくまでのお手伝いをするために,今回 プレミアム特典も別に用意させていただきました。」,5)「学ぶことで,ご心配なく 取り組んでいただけます,学んだらいいかわからない,耳つぼジュエリストのYが 開発いたしました。」,6)「痛くない施術,説明するときにも役立ちます,通信教育 って途中で勉強,そんな耳つぼジュエリストとしてのやりがいや幸せ,ピンクリボ ンフェスタ2013出展。」という被控訴人標章を含む記載をし,また,投稿動画に 添える表題的な文言として,7)「ネイリストより簡単!自宅で学べる耳つぼジュエ リストのプロを目指す」という被控訴人標章を含む記載をしたことが認められる。 前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,前記ホームページ又はこれらにリンク されているページにおいて,「耳つぼジュエリスト」は,ラインストーンに貼付され\nた医療用シートを耳のつぼに貼付する「耳つぼジュエリー」の施術を業として行う\n者という意味で使用されており,「耳つぼジュエリープロ通信講座」の開催及び「D ipLoma」と題する文書の発行の主体は,「FRANGIPANI」であること が明示されているといえる。 そして,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人のほかにも,相当数 の者が,インターネット上において,「耳つぼジュエリー」の施術方法を教授する講 座を開催していたことが認められる。 以上の事実及び弁論の全趣旨によれば,本件商標権の指定役務である知識の教授 に係る事業の需要者において,インターネット上の被控訴人の前記1)ないし7)の被 控訴人標章を含む記載のあるホームページ等を見た場合,「FRANGIPANI」 が,その行う事業の一環として,その受講者に「DipLoma」と題する修了証 を発行する通信講座を開催し,その広告を掲載しており,前記講座は,前記施術を 行う技術を教授する講座であり,前記1)及び5)の記載は被控訴人が自らが前記施術 を業として行っていることを示したもの,前記2)ないし4),6)及び7)の各記載は, 一般的な資格として前記施術を業として行う者を示したものであると理解するので あって,「FRANGIPANI」という表示によって役務の出所を識別するのが通\n常であると考えられ,被控訴人標章から役務の出所を想起することはないものと認 められる。 したがって,前記の被控訴人標章の各記載は,需要者が何人かの業務に係る役務 であることを認識することができる態様により使用されているものと認めることは できず,「登録商標に類似する商標の使用」(商標法37条1号)には該当しないと いうべきである。
2016.07.23
平成27(行ウ)627 手続却下処分取消等請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年7月19日 東京地方裁判所
原告は,本件期間徒過の直接の原因につき,本件特許事務所において受 信班の受信第1担当者が,本件メールを,日付フォルダ直下の「新件午後」 フォルダへ移動すべきところ,誤って日付フォルダ直下の「印刷済み」フォ ルダに移動したためであるとしつつ,同ミスを回避することはできなかった 旨主張し,本件特許事務所の従業員が作成した陳述書にも同様の記載がある。 そこで検討するに,上記1(2)で認定した受信処理の手順の定めによれば, ALPの共有端末から本件特許事務所内のネットワーク上への受信メールの 移動は,受信班のスタッフが手作業で行うのであるから,移動先のフォルダ を誤るミスが生じ得ることは容易に予想される。それにもかかわらず,本件\n特許事務所においては,受信第1担当者が,ALPの共有端末から本件特許 事務所内のネットワーク上の日付フォルダ直下の「新件午後」フォルダ直下 に全ての受信メールを移動したことについて,何らこれを確認する態勢を採 っていなかったのであって(上記1(2)イ),その結果,本件期間徒過に至っ たものである。 また,上記1(2)の手順の定めによれば,まず,受信第1担当者が受信メー ルの件数をカウントし,受信第2担当者においてそれが正しいことを確認し た上で(上記1(2)ア),その後,印刷担当者が「新件午後」フォルダ直下に ある受信メールを印刷し,これを「新件午後」フォルダ直下の「印刷済み」 フォルダに移動した後,受信第1担当者が受信メールの印刷物の件数及び内 容と受信メールの件数及び内容とを確認する作業を行うのであるから(上記 1(2)ウ,エ),受信第1担当者が定められた手順どおりに受信メールの印刷 物の件数と受信メールの件数とを対照していれば,本件メールが印刷されて おらず,その受信処理においてミスがあったことは容易に判明したはずであ る。このように,本件期間徒過の原因についての原告の主張を前提とすると, 本件特許事務所は,受信第1担当者による受信メールの移動ミスに気付くこ とができたはずの機会があったにもかかわらず,これを看過したこととなる のであって,本件特許事務所において上記1(2)の手順の定めが遵守されてい たのかについても疑問がある。 以上によれば,本件期間徒過について「正当な理由」があったとはいえな い。
2016.07.22
平成28(行ケ)10062 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年7月20日 知的財産高等裁判所
本願商標と引用商標とを対比すると,前記2のとおり,本願商標からは, 「フォックスコン インターコネクト テクノロジー エフ アイ ティー」の称 呼及び鴻海グループに属する企業との観念が生じるとともに,「FIT」の文字部 分から,「エフアイティー」との称呼が生じるほか,その構成文字と同一の英文字\nから成る英単語の「fit」に相応した「フィット」との称呼及び「適した」,「ぴ ったりの」との観念が生じ(乙1,2),これは,原告も自認するところである。 本願商標から生じるこれらの称呼及び観念のうち,「フィット」との称呼及び「適 した」,「ぴったりの」との観念は,前記3の引用商標の称呼及び観念と同一である。 このように,対比に係る商標から2つ以上の称呼,観念が生じる場合,そのうちの 1つの称呼,観念が類似するときは,両商標は類似するというべきである(最高裁 昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12 号1621頁参照)。 本願商標の「FIT」の文字部分と引用商標とは,外観上,文字の彩色や書体等 の相違はあるものの,その相違は,上記の称呼及び観念の同一性をりょうがして上 記類似を覆すほどのものではない。 以上によれば,本願商標と引用商標とは,出所について誤認混同のおそれがあり, 両商標は,類似するものということができる。
(2) 原告は,本願商標の構成文字に,原告のグループ企業のブランドとして広く\n知られた「Foxconn」の文字が含まれ,かつ,原告の商号原語表記である\n「Foxconn Interconnect Technology」が併記さ れているという事実を軽視せず,本願商標の指定商品に係る取引においては商品の 製造主体が重視されるという取引実情にも鑑みれば,本願商標と引用商標は,事実 上,出所の混同が生じることはない旨主張する。 しかし,前記2のとおり,本願商標中,「Foxconn Interconnect Technology」の文字部分は,外観上,「FIT」の文字部分に 比べて明らかに目立たない態様であり,それほど見る者の注意をひくものではなく, 取引者・需要者に対し,本願商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印 象を与えるのは,「FIT」の文字部分である。したがって,原告主張に係る取引 の実情を考慮しても,本願商標と,本願商標の「FIT」の文字部分と同一の構成\n文字から成り,同一の称呼及び観念を生じる引用商標とは,出所について誤認混同 のおそれがあるものというべきである。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.07.22
平成28(ネ)10006 債務不存在確認請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年7月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
登録時の構成D
「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と,」
→
訂正請求時の構成D’(削除された部分を< >で,付加された部分を[ ]で示す。)
「<前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,>前前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化[,及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化]に応じて[,特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化,及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を,]前記情報処理装置が行うようにする制御手段と,」
→
訂正請求を補正した後の構成要件D”(削除された部分を< >で示す。)
「前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化,及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数<又は該数の過渡的な変化>に応じて,特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化,及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数<又は該数の過渡的な変化>に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を,前記情報処理装置が行うようにする制御手段と」
マルチタッチパネルシステムにおいて,位置検出手段により検出される2個所の 指示部位の指示位置の間の距離を算出し,算出される指示位置の間の距離又は該距 離の過渡的な変化に応じて所定の動作を行うことは,本件特許の出願前周知の技術 と認められる(甲12の58頁4〜10行目,73頁2〜12行目,甲22の【0 015】〜【0017】【0046】,甲23の【0036】【0037】【図10】 【図11】参照)である。 上記ア(ア)のとおり,甲13発明も2箇所の指示位置の間の距離の相対比又はその 過渡的変化に着目しているものであり,指示位置間の距離又はその過渡的変化を基 礎としているから,甲13発明において,上記周知技術を適用し,その距離算定方 法を構成要件B及Cの距離算定方法に置換することは,当業者が適宜なす程度のことであり,容易に想到できる。
(イ) 控訴人の主張について
控訴人は,相違点1は容易に想到できないと主張するが,相違点B及び相違点C の存在を前提とする主張であり,本件発明1と甲13発明とが,相違点B及び相違 点 C の点で相違するものでないことは,上記アに認定のとおりであるから,その主 張を採用することはできない。
ウ 小括 以上からすれば,本件発明1は,甲13発明及び周知技術に基いて,当業者が容 易に発明することができる。そうすると,本件発明1に係る特許は,特許無効審判 により無効にされるべきものと認められる。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.07.14
平成27(行ケ)10164 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年7月13日 知的財産高等裁判所
ア 本件発明のロック突部は,特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,平 坦面部分を有する突部前縁と平坦面部分を有する突部後縁とが前後方向に離間して いる形状のものである。そして,本件発明は,前記1(2)のとおり,ロック機構につ\nいて,1)ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタの一方が,平坦面部分を有する 突部前縁と平坦面部分を有する突部後縁とが前後方向に離間しているロック突部を 側壁面に有し,2)他方が前後方向でロック突部に対応する位置で溝部前縁と溝部後 縁が形成されたロック溝部を側壁面に有し,3)ロック溝部には溝部前縁または溝部 後縁から溝内方へ突出する突出部が設けられ,4)ロック突部が嵌合方向でロック溝 部内に進入し,ケーブルコネクタが前端側が持ち上がった上向き傾斜姿勢から嵌合 終了の姿勢となったコネクタ嵌合状態では,上記姿勢の変化に応じて,突出部に対 するロック突部の位置が変化する,という構成を採用することにより,コネクタ嵌\n合状態にある間は,ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動さ れようとしたときであっても,ロック突部が抜出方向で突出部と当接し,ケーブル コネクタの抜出を阻止するようにしたものである。 他方で,本件発明は,特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載 において,ロック突部の突部前縁及び突部後縁が有する平坦面部分について,その 大きさ,両面の離間の程度やその成す角度,ロック溝部やその突出部など他の構成\nとの関係などについては,特に規定していない。 そうすると,本件発明のロック突部は,平坦面部分を有する突部前縁と平坦面部 分を有する突部後縁とが前後方向に離間している形状を有し,ケーブルコネクタの ケーブルに上向き方向の成分の力が作用しても,ロック突部が抜出方向でロック溝 部の突出部と当接することにより,ケーブルコネクタの抜出を阻止するものであれ ば足り,その断面形状には,円形に近似するような,角数の多い多角形状も含まれ るものと解される。
イ 引用発明は,前記2(2)のとおり,軸方向の挿抜によってではなく,一方のハ ウジングを他方のハウジングに対し回動させることで接続又は切離しの作用を得る ことのできるコネクタであって,コネクタ31に形成された溝部49に挿入される 相手コネクタ33の回転中心突起53を支点として相手コネクタ33を回転させて, コネクタ31と相手コネクタ33を嵌合させるものである。 上記のとおり,引用発明の回転中心突起は,相手コネクタ33を回転させる際の 支点(回転中心)となるものであること,回転を円滑に行うためには,その支点の 断面は円形状であることが好ましいこと及び引用例の第3図には回転中心突起53 の断面がほぼ円形状に描かれていることに照らせば,基本的には,その断面の形状 として円形が想定されているものといえる。 しかし,引用発明において,回転中心突起の回転は,相手コネクタ33は,その 前端が持ち上がって上向き傾斜姿勢にある状態(第3図)から,コネクタ31と嵌 合した状態(第5図)までの,せいぜい90度以内のものにすぎず,引用例には, 回転中心突起53やその断面の形状が円形に限られるものであることについては何 らの記載も示唆もないから,その断面の形状は,円形に限られず,相手コネクタ3 3の円滑な回転動作やコネクタ31との嵌合に支障がない限り,円形以外の形状に することも許容されるものと解される。
ウ 引用発明においては,前記イのとおり,回転中心突起53の形状は,相手コ ネクタ33の円滑な回転動作やコネクタ31との嵌合に支障がない限り,その断面 の形状を円形以外の形状にすることも許容されるものと解されるところ,相手コネ クタ33の円滑な回転動作やコネクタ31との嵌合に支障がない範囲で,回転中心 突起53の形状を適宜変更し,その断面が,円形に近似するような,角数の多い多 角形状となるものとすることは,当業者の通常の推考の範囲内のことであるという ことができる。 そして,本件発明のロック突部の形状には,その断面形状が,円形に近似するよ うな,角数の多い多角形状となるものも含まれるものと解されることは,前記アの とおりである。 したがって,引用発明において,相違点1に係る本件発明の構成とすることは,\n当業者が容易に想到することができたことである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2016.07.14
平成27(行ケ)10186 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年7月13日 知的財産高等裁判所
原告は,乙第9及び10号証は,いずれも審判時に提出されていなかったもので あり,本件審決の違法性を争う本件訴訟において,このような証拠は許容すべきで はない旨主張する。 審決取消訴訟においては,審判手続において審理判断されていなかった資料に基 づく発明と対比して無効理由の存否を認定し,審決の適法,違法を判断することは 許されないが(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・ 民集30巻2号79頁参照),審判手続において審理判断されていた資料に基づく発 明と対比して無効理由の存否を認定し,審決の適法,違法を判断するに当たり,審 判手続には現れていなかった資料に基づいて上記発明が属する技術分野の当業者の 出願当時における技術常識を認定し,これによって上記発明の有する意義を明らか にした上で無効理由の存否を認定したとしても,審判手続において審理判断されて いなかった資料に基づく発明と対比して無効理由の存否を認定し,審決の適法,違 法を判断したものということはできない(最高裁昭和54年(行ツ)第2号同55 年1月24日第一小法廷判決・民集34巻1号80頁参照)。 本件審決は,審判手続において審理判断されていた引用発明1と対比して,「挿入 部(13)」の成形に関する相違点2の容易想到性の判断をするに当たり,審判手続 には現れていなかった周知例1及び2に基づいて,当業者の技術常識を認定し,こ れによって,引用発明1において,上記周知技術を採用して相違点2に係る本願発 明の構成とすることは,当業者にとって容易であった旨の判断をした。\nそして,乙第9及び10号証は,本件審決による上記判断の誤りの有無を判断す るに当たり,本願出願日当時の上記周知技術に関する技術常識としてテーパ形状の 拡底部を有するアンカーボルトにおける一体成形に関する技術を立証するものであ るから,本件訴訟の判断資料とすることは,許容されるものということができる。
・・・・
3 取消事由2(手続違背)について
(1)原告は,平成27年2月23日付け拒絶理由通知において,アンカーピン自 体を一体成形することは周知技術であることが示されたのに対し,同年4月27日 付けの意見書において,上記周知技術の根拠の明示を求めたが,これに対する回答 はなく,本件審決において,初めて周知例1及び2が示され,これらを根拠とした 周知技術が認定されて請求不成立の判断が出されたとして,このような手続は,原 告に対して周知例1及び2に関する反論の機会を与えることなく,不意打ちをする ものということができ,違法である旨主張する。
(2) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,本願に係る出願の経緯につき,以下の とおり認められる。
・・・
エ 原告は,平成27年2月23日付けで拒絶理由通知(甲9)を受けた。同拒 絶理由通知には,「アンカーピン自体を一体成形とすることは,本願の出願日前に周 知の技術である。」と記載され,また,前記アの特許請求の範囲請求項1の補正につ き,「本願の出願当初の明細書等には,中間部と係止部とが一体成形されるという記 載はないが,アンカーピン自体を一体成形とすることは,本願の出願日前に周知の 技術であるので,中間部と係止部を一体成形とすることは,出願当初の明細書等か ら自明な事項であると判断した。」と記載されている。 オ 原告は,平成27年4月27日付け手続補正書(甲10)により本件補正を 行い,同日付け意見書(甲11)において,前記エの拒絶理由通知記載の周知技術 につき,その根拠が示されていないことを指摘するとともに,「本願の手続補正は, 図4及び図5(判決注:別紙1の【図4】及び【図5】と同じ。)に記載のアンカー ピンは接続部分がなく,当業者が見れば中間部14と係止部16とが一体成形され ていることが自明であるのであって,これをもって出願前にアンカーピンが一体成 形されることが周知の技術であるわけではないことは明らかである。」と主張した。
(3) 前記(1)のとおり,平成27年2月23日付け拒絶理由通知において,アンカ ーピン自体を一体成形とすることは,本願の出願日前において既に周知の技術であ った旨が明記されている。 そして,原告は,同年4月27日付け意見書において,上記拒絶理由通知記載の 周知の技術に関し,平成25年11月25日付け手続補正書による補正事項につい て,当業者が別紙1の【図4】及び【図5】を見れば中間部14と係止部16とが 一体成形されていることが自明であり,これをもって,アンカーピン自体を一体成 形とすることが周知の技術であるわけではない旨主張しているが,同主張のとおり, 当業者が上記図面を見て上記一体成形を自明のこととして理解するのは,まさに, アンカーピン自体を一体成形することが,当業者に周知の技術であったからにほか ならない。 以上によれば,本件審決が周知技術として認定した「テーパ形状の拡底部を有す る杭において,テーパ形状の拡底部と拡底部以外の部分とを滑らかに連接し,一体 の外周面を形成するように一体成形すること」の主要な内容である一体成形の技術 については,周知技術であることが平成27年2月23日付けの拒絶理由通知に示 されており,しかも,これに関する原告の意見書の内容自体から,一体成形の技術 が当業者に周知されていたということができる。このような経過に鑑みると,本件 審決が,それまで審判手続において示されていなかった周知例1及び2を根拠とす る周知技術を認定したことは,原告に対する不意打ちということはできず,手続違 背には当たらないというべきである。
関連カテゴリー
>> 特許庁手続
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2016.07.12
平成27(ワ)20338 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成28年6月30日 東京地方裁判所
前記前提事実及び上記認定事実を踏まえて,原告らの本件請求が権利濫用 に当たるか否かについて検討する。
ア 前記第2の1前提事実によれば,本件各商標に類似する被告各標章は, 遅くともCの死亡した平成6年4月26日時点から現在まで空手及び格闘 技に関心を有する者の間において極真会館又はその活動を表すものとして\n広く知られているところ,上記(1)認定事実ア,イ及びエによれば,この ような被告各標章の周知性及び著名性の形成,維持及び拡大に対し,Cの 生前においては,長年にわたり極真空手の教授や空手大会の開催等を行っ てきたC及び同人から認可を受けたBを含む支部長らの寄与があり,Cの 死後においては,国内外において大規模に極真空手の教授や空手大会の開 催等を行い,その普及に努めてきたB及び同人が代表取締役を務める被告\nの大きな寄与があったと認められる。 また,原告らは,極真関連標章である本件各商標に係る商標権を取得し て極真空手の教授等を行っているが,Cは後継者を公式に指名することな く死亡しており(上記(1)認定事実ウ),極真会館において館長や総裁の 地位の決定や承継に関する定めはなく(上記(1)認定事実ア(イ)及びウ (ア)),世襲制が採用されていたこともうかがわれず,他に相続人である 原告AをCの後継者であると認めるに足りる証拠はない。そうすると,原 告らは,極真会館を称して極真空手の教授等を行う複数の団体の一つにす ぎないというべきである。そして,極真会館の分裂後にBにより設立され た被告も,上記のような団体の一つというべきである。 以上の点に加えて,原告らは,Cの死亡後,B及び被告が国内外で被告 各標章を使用して大規模に極真空手の教授等を行っていたことを認識して いたにもかかわらず,合理的な理由もなく早期に本件各商標に係る商標登 録出願を行っていないことも考慮すれば,原告らが被告に対し,本件各商 標権に基づき,極真関連商標である本件各商標やこれと類似する商標の使 用を禁止することは権利の濫用に当たると解すべきである。
イ これに対し,原告らは,1)原告Aが極真関連標章の主体たる地位を承継 したこと,2)極真関連標章の周知性及び著名性の維持等に対する寄与につ いて,Cの生前におけるBの寄与はCに帰属するものであり,Cの死後に おけるB及び被告の寄与はBの不当な行為による結果であるから保護に値 しないこと,3)被告は極真空手の最大の特徴であるフルコンタクトルール を放棄する旨表明したことなどから,原告らの権利行使が正当であると主\n張する。 しかしながら,1)については,Cは生前,極真関連標章に係る商標登録 出願をしておらず,極真関連標章の主体たる地位が相続の対象となる財産 権であるとはいえない。また,周知に至った極真関連標章があったとして も,それは被告各標章と同様に極真会館又はその活動を示すものとして周 知になったものというべきであるから,それは少なくともC個人ではなく 極真会館の総裁に帰属する法的利益であると解すべきであるところ,上記 アのとおり,原告Aを極真会館の総裁であったCの後継者であると認める ことはできない以上,原告Aが,極真関連標章の主体たる地位を承継した と認めることはできない。
次に,2)については,Cの生前における極真関連標章に対するBの寄与 がCに帰属するとの原告らの主張は,極真会館がCの社団性すら有しない 個人事業の性質を有し,直轄道場の支部長が他の支部長と異なって総本部 たるCの被用者であることを前提としているが,上記(1)ア認定のとおり の極真会館の組織及び運営に照らせば,少なくとも極真会館は社団性を有 するというべきである上,本件全証拠によっても,直轄道場の支部長と他 の支部長とで極真関連標章の使用に関する取扱いが異なっていたことを認 めるに足りる証拠はないから,原告らの上記主張の前提に誤りがあるとい わざるを得ない。また,Cの死後,Bは,後に無効とされた本件遺言に基 づいて自らをCの後継者と称し,後に無効とされた極真関連標章に係る商 標登録を受けた上で極真空手の教授等を行っているが,現時点までにおけ る被告の活動規模や実績等に照らせば,Cの死後における被告の各標章に 対するB及び被告の寄与の全てがBの上記行為の結果であるとはいえず, 当該寄与の正当性の全てが否定されることにはならないと解すべきである。 さらに,3)の点については,本件全証拠によっても被告がフルコンタク トルールを放棄したと認めるに足りる証拠はない。なお,上記(1)エ(ウ) 認定のとおり,被告は,平成27年4月16日,平成32年開催予定の東\n京オリンピック・パラリンピックにおける空手道種目の採用に向けて,公 益財団法人全日本空手道連盟との間で友好関係を構築し,互いに協力する\nことを記者会見により発表したところ,同連盟は,フルコンタクトルール\nを採用していないものであるが,このような事実があったとしても,それ 故に被告がフルコンタクトルールを放棄したことにはならない。
2016.07.11
平成27(行コ)10004 異議申立却下決定取消請求控訴事件 特許権 行政訴訟 平成28年6月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人らが本件異議申立てに際して代表\者の資格証明に関する書面及び代理人であることを証明する書面(以下,両者を併せて,「資格証明所等」という。)を添付しなかったことから,特許庁長官は,補正期間を30日と定める本件補正命令を発したが,控訴人らが上記期間内に資格証明書等を提出しなかったため,本件決定をした。本件補正命令の内容は,資格証明書等の提出を求めるという明確なものであり,また,控訴人らのような種類の法人についても,補正を命じられた不備を補正することは困難なことではないから(現に,控訴人らは,本訴提起に当たっては,控訴人らの資格証明書等を提出している。),控訴人らは,相当の期間を定めて命じた補正に従って資格証明書等を提出することをしなかったのであって,本件異議申立ては,行政不服審査法13条1項に違反し,不適法である。したがって,これらをいずれも却下した本件決定に違法は認められない。\n
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2016.07. 7
平成28(ワ)12480 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月30日 東京地方裁判所
原告は,被告ワンマン及び被告西部機販に対し,本件メンテナンス行為1 の差止めを求めるところ,製品について加工や部材の交換をする行為であっ ても,当該製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか, 取引の実情等も総合考慮して,その行為によって特許製品を新たに作り出す ものと認められるときは,特許製品の「生産」(法2条3項1号)として, 侵害行為に当たると解するのが相当である。 本件各発明は,前記1(2)のとおり,生海苔混合液槽の選別ケーシングの 円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して, 生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除 去装置において,クリアランスの目詰まりが発生する状況が生じ,回転板の 停止又は作業の停止を招いて,結果的に異物分離作業の能率低下等を招いて\nしまうとの課題を解決するために,突起・板体の突起物を選別ケーシングの 円周端面に設け(本件発明1),回転板及び/又は選別ケーシングの円周面 に設け(本件発明3),あるいは,クリアランスに設けること(本件発明4) によって,共回りの発生をなくし,クリアランスの目詰まりの発生を防ぐと いうものである。そして,本件板状部材は,本件固定リングに形成された凹 部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより,本件各発明の 「共回りを防止する防止手段」(構成要件A3)に該当する「表\面側の突出 部」,「側面側の突出部」を形成するものであること(当事者間に争いがな い)からすると,本件固定リング及び本件板状部材は,被告装置の使用(回 転円板の回転)に伴って摩耗するものと認められるのであって,このような 摩耗によって上記突出部を失い,共回り,目詰まり防止の効果を喪失した被 告装置は,本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を欠き,もはや「共 回り防止装置」には該当しないと解される。 そうすると,「表面側の突出部」,「側面側の突出部」を失った被告装置\nについて,新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方,あるいは,いず れか一方を交換することにより,新たに「表面側の突出部」,「側面側の突\n出部」を設ける行為は,本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備え た「共回り防止装置」を新たに作り出す行為というべきであり,法2条3項 1号の「生産」に該当すると評価することができるから,原告は,被告らに 対し,法100条1項に基づき,上記(1)の差止めに加えて,本件メンテナ ンス行為1の差止めを求めることができる。
・・・・
これに対し,被告ワンマン及び被告西部機販は,要旨,1本件装置1及 び2の仕入代金以外に必要経費が生じているから,これらについても被告ワ ンマン及び被告西部機販の利益から控除すべきである,2)本件特許は本件装 置1及び2の販売にほとんど寄与しておらず,本件装置1及び2の売上への 寄与率が10%を超えることはない,3)被告ワンマン及び被告西部機販が本 件装置1及び2の販売によって得た利益を原告の損害と推定することについ ての推定覆滅事由があるなどと主張する。 しかしながら,上記1)について,必要経費として控除できるのは,本件装 置1及び2の販売に直接関連して追加的に必要になった経費に限られるもの と解すべきところ,被告ワンマン及び被告西部機販の主張する経費が本件装 置1及び2の販売に直接関連して追加的に必要になったものと認められない のはもちろん,そもそも同経費が現実に生じたこと自体を認めるに足る証拠 が一切なく,その算定根拠も判然としない。また,上記2)について,本件各 発明は,生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関するものである一方,\n本件各発明が本件装置1及び2に寄与する割合を減ずべきであるとする被告 ワンマン及び被告西部機販の主張の根拠は判然としないことに照らせば,本 件各発明が本件装置1及び本件各部品の販売に寄与する割合を減ずることは 相当でない。さらに,上記3)について,被告が主張するのは,単に,原告が 販売店ではなく製造業者であるという事実にとどまるところ,同事実のみか ら,本件各発明の実施品が有する顧客吸引力にもかかわらず,原告がその取 引先への販売の機会を持ち得なかったということはできないし,ほかに原告 が取引の機会を奪われたとはいえない特段の事情もないから,法102条2 項による推定を覆滅するには足りないというほかない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2016.07. 7
平成27(ワ)6812 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月23日 東京地方裁判所
上記(ア)の本件明細書の記載によれば,圧力排出路の存在は本件発明が 解決すべき課題と直接関係するものではない。もっとも,本件発明の 効果等に関する上記 b,cの記載をみると,圧力排出路は,食材が 網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁 が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的と するものであり,汁を排出するための通路をハウジング底面において 防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余 地がある。しかし,上記の効果を奏するためには,上記通路が防水円 筒の下部縁に存在すれば足り,これをどのような部材で構成するかに\nより異なるものではない。そうすると,上記の異なる部分は本件発明 の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。
ウ 第2要件(置換可能性)について
前記イのとおり,本件発明における圧力排出路は,食材が網ドラム の底部で最終的に圧縮されて脱水される過程で生じる一部の汁が防水 円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐものである。また, これにスクリューギヤが挿入されて回転することにより,高粘度の汁 を効率的に排出することができる。 他方,前記前提事実 ウdの被告製品の構成及び別紙図17のとおり,\n被告製品のハウジングにスクリュー及び網ドラムを配置すると果汁案 内路が形成され,これが汁排出口と連通して,搾汁された汁の一部を 汁排出口へ案内する機能を果たすと認められる。また,被告製品のス\nクリュー下部に形成されたスクリューギアは,果汁案内路に挿入され て回転する(甲11)。そして,網ドラムはハウジングの上方から配置 されるものであり,果汁案内壁とハウジング底面との間に隙間が生じ ることもあり得るところ,その場合には当該隙間から汁が果汁案内路 の外側に流出するから,果汁案内路に流入した汁が内周側の防水円筒 を超えてハウジング外部に流出することはないものと考えられる。し たがって,被告製品の果汁案内路は本件発明の圧力排出路と同一の作 用効果を奏するということができる。 以上のとおり,被告製品の果汁案内路は圧力排出路と同一の作用効果 を奏するものとして,置換可能と評価するのが相当である。\nこれに対し,被告は,被告製品はハウジング底面を平坦化することに より清掃を容易にするという新たな効果が生じているから置換可能と\nはいえない旨主張する。しかし,仮にそのような効果が生じるとして も,ハウジング底面の清掃容易性は本件発明の前記課題とは無関係で あり,これをもって第2要件の充足性を否定することはできない。
エ 第3要件(置換容易性)について
本件明細書には,本件発明の実施例として,ハウジングに形成された 圧力排出路の外側のハウジング底面の上部に網ドラム底部に形成され た底部リングを載置し,その内周面と圧力排出路の外周面が上下に一 体となって,これと防水円筒の外周面により圧力排出路の上方に続く 空間を形成し,そこにスクリュー下方に突出形成された内部リング及 びその下端のスクリューギヤが挿入される例が記載されている(段落 【0045】,【0052】,【0056】,【図3A】,【図3B】)。この とき,水分(汁)の一部が内部リングと網ドラムの内部リング挿入孔 (底部リングの内側に当たる。)との間の隙間に押し込まれ,圧力排出 路に流入する(段落【0072】),すなわち,底部リング(網ドラ ム)内壁からそのまま圧力排出路の外周側の内壁を伝って圧力排出路 に流入しており,上記実施例において網ドラムの一部は圧力排出路の 外周側の壁の役割を果たしているといえる。また,本件発明と同じ技 術分野に属する搾汁機において,搾汁ケース(本件発明のハウジング に相当する。)のブッシング(同防水円筒に相当する。)の下部縁に流 路を形成せず,搾汁ケースの底部のこの部分を平坦にしたものは被告 製品の製造販売時に公知であったと認められる(甲26)。そうすると, 本件明細書の前記記載に接した当業者にとって,上記実施例の網ドラ ムないし底部リングを下方に伸長して圧力排出路の外周側の壁に代え るとともに,この部分のハウジングの底面を平坦にすることによって, 圧力排出路の外周側の壁全体を網ドラムで形成することに思い至るの は容易であるというべきである。 これに対し,被告は,ハウジングの底部を平坦にした被告製品は本件 発明と根本的に相違する旨主張するが,以上の説示に照らしこれを採 用することはできない。
オ 以上のとおり,被告製品の果汁案内路は本件発明の圧力排出路と均等で あるということができる。
・・・
3 争点 (原告の損害額)について
前記1及び2で判示したとおり被告製品は本件発明の技術的範囲に属す るところ,原告は,被告が被告製品の販売により1500万円の利益を得 たとして,特許法102条2項に基づき同額の損害賠償を請求する。これ に対し,被告は,被告製品の販売により316万9653円の損失が生じ ており,利益は得ていないと主張するところ,原告はこれに具体的に反論 せず原告主張を裏付けるに足りる証拠も提出しない。以上によれば,被告 が本件特許権の侵害行為により利益を得たと認めることはできないから, 独占的通常実施権の有無等の点について判断するまでもなく,原告の上記 請求は理由がないことになる。 本件事案の内容,経緯等に照らすと,本件において被告に負担させるべ き弁護士及び弁理士費用の額は200万円が相当であり,原告の被告に対 する本件特許権侵害による損害賠償請求はその限度で理由がある。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2016.07. 5
平成28(ネ)10017 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月29日 知的財産高等裁判所 知的財産高等裁判所
ところで,商品の基礎情報である価格等は変わる場合があるところ,顧客 の注文前に商品の基礎情報が更新された場合,Web−POSサーバ・システムが 有する情報は,更新された後の商品情報のみであるから,Web−POSサーバ・ システムは,顧客が注文した商品の価格等を把握することができない(乙20)。 また,Cookieを用いたWeb技術は,サーバ側で識別情報としてテキスト・ データをWebブラウザごとに割り当て,更に,そのテキスト・データをWebブ ラウザの情報と対応付けて管理することにより,Webサーバ側において,HTT Pリクエストの送信元を識別等するというものにとどまる(甲25)。よって,W eb−POSサーバ・システムは,Cookie情報を受信しても,顧客が注文し た商品の価格等を把握することはできない。 そして,前記(ア)のとおり,本件ECサイトの管理運営システム内のサーバは, 顧客が注文した商品の価格等を把握するために,顧客のコンピュータからリクエス ト情報とともに受信したCookie情報をもとに,顧客のコンピュータに表示さ\nれた「レジ」画面情報の原本に当たる情報を同サーバから呼び出すという制御方法 を追加で採用することにより,顧客が注文した商品の価格等を把握するに至ってい るものである。
(ウ) したがって,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する\n構成において,Web−POSサーバ・システムがCookie情報等は取得する\nものの,注文された商品に係る商品基礎情報を取得しないという本件ECサイトに おける構成を採用した場合には,本件発明のように,Web−POSサーバ・シス\nテムは,注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎情報をリアルタイム に管理することができないというべきである。
エ 小括
よって,本件ECサイトの制御方法,すなわち,オーダ操作が行われた際に,W eb−POSクライアント装置からWeb−POSサーバ・システムに送信される 情報に,注文された商品に係る商品基礎情報を含めずに,Cookie情報等を含 めるという方法では,本件発明と同一の作用効果を奏することができず,本件発明 の目的を達成することはできない。 したがって,均等の第2要件の充足は,これを認めることができない。
・・・・
前記1(2)ウのとおり,控訴人は,本件発明は,引用文献1に記載された発明に 基づいて容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定 により特許を受けることができないとの拒絶理由通知に対して,本件意見書を提 出したものである。 そして,前記1(2)ウ及びエのとおり,控訴人は,本件意見書において,引用文 献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないとい う点との相違を明らかにするために,本件発明の「注文情報」は,商品識別情報 等を含んだ商品ごとの情報である旨繰り返し説明したものである。 そうすると,控訴人は,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関\nする具体的な構成において,Web−POSサーバ・システムが取得する情報に,\n商品基礎情報を含めない構成については,本件発明の技術的範囲に属しないことを\n承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価す ることができる。 そして,本件ECサイトの制御方法において,管理運営システムにあるサーバが 取得する情報には商品基礎情報は含まれていないから,同制御方法は,本件発明の 特許出願手続において,特許請求の範囲から意識的に除外されたものということが できる。 したがって,均等の第5要件の充足は,これを認めることができない。
ウ 控訴人の主張について
これに対し,控訴人は,本件意見書において,POS管理を実現できる複数の構\n成の中から意識的にある構成を選択したり,ある構\成を排除したりしたものではな いと主張する。しかし,上記のとおり,控訴人は,本件意見書において,引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を 明らかにするために,本件発明の「注文情報」は,商品識別情報等を含んだ商品ご との情報である旨繰り返し説明していたものである。そうすると,控訴人は,本件 意見書において,本件発明のうち,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御\n過程に関する具体的な構成については,Web−POSサーバ・システムが取得す\nる情報には必ず商品基礎情報を含めるという構成を,意識的に選択したことは明ら\nかであるといえ,控訴人の上記主張は,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.07. 5
平成28(ネ)10007 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記イのとおり,控訴人は,本件特許の出願時,座席を連続して揺動させること が可能な乳幼児用の椅子等であって,揺動制御手段としてソ\レノイドを有するもの について,旧請求項1においては,座席支持機構を特段限定せず,旧請求項2にお\nいては,座席支持機構をロッド2点支持方式に限定し,旧請求項3においては,座\n席支持機構を,座席とベースとの間に,ベースに対して座席が「水平往復動可能\な スライド手段を設けたことを特徴とする」ものに限定していたものである。そして, 控訴人は,本件補正により,旧請求項1を,本件特許の特許請求の範囲から削除し, その範囲を旧請求項2及び旧請求項3に限定したものである。 このように,控訴人は,本件補正において,座席を連続して揺動させることが可 能な乳幼児用の椅子等であって,揺動制御手段としてソ\レノイドを有するものにつ いて,拒絶理由通知に対応して,座席支持機構を特段限定していない旧請求項1を\n削除し,座席支持機構にロッド2点支持方式を採用する旧請求項2(本件発明)及\nび座席とベースとの間に,ベースに対して座席が「水平往復動可能なスライド手段\nを設けたことを特徴とする」方式を採用する旧請求項3に限定したものである。そ して,本件発明の出願時には既に,座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児\n用の椅子等の座席支持機構として,コロと湾曲レールを利用した方式が存在するこ\nとは周知であり(乙3〜5),コロと湾曲レールを利用する方式に係る座席支持機 構は,上記のとおり削除された旧請求項1に係る座席支持機構\の範囲内に客観的に 含まれるものである。 したがって,控訴人は,コロと湾曲レールを利用する方式に係る座席支持機構に\nついても,本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそ のように解されるような行動をとったものと評価することができる。 よって,均等の第5要件の充足は,これを認めることができない。
エ 控訴人の主張について
控訴人は,本件特許の出願当時,動力機構としてソ\レノイドを用い,座席支持機 構としてコロと湾曲レールを利用するという各構\成を組み合わせた乳幼児用の椅子 等は存在せず,また,動力機構としてソ\レノイドを用いることから生じる課題も公 知ではなかったから,本件特許の特許請求の範囲に,座席支持機構としてコロと湾\n曲レールを利用する方式も含めることは容易ではなく,さらに,拒絶理由を回避す るために,座席支持機構についてロッドを利用した方式に限定したものでもないと\n主張する。 しかし,控訴人が,本件補正において,ロッド2点支持方式等を除く方式に係る 座席支持機構を包括的に削除したとの事実の評価は,客観的に判断されるべきもの\nである。 そうすると,このような控訴人の本件補正時における具体的な認識や本件補正の 目的は,均等の第5要件の充足に関する結論を左右するものではない。
(4) まとめ
よって,均等のその余の要件の成否について検討するまでもなく,各被告製品は, 均等の第1要件及び第5要件を充足しないから,各被告製品が本件発明と均等なも のとしてその技術的範囲に属するということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.07. 5
平成28(ネ)10026 売掛金請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年6月23日 知的財産高等裁判所 水戸地方裁判所 龍ケ崎支部
被控訴人は,仮に被控訴人の行為が著作権侵害に当たるとしても,被控訴 人は,本件ホームページ掲載行為は何ら制限されていなかったと認識してお り,したがって,被控訴人に故意過失は認められない,また,フリーペーパ ーという本件冊子の性格や,編集者としての被控訴人の立場,被控訴人は, 控訴人自身がプレスリリースした本件冊子と全く同一のものを電子データ化 して本件ホームページに掲載したにすぎないこと,被控訴人は,平成26年 11月に控訴人から著作権料を請求されるや,僅か1週間足らずの同月7日 に本件ホームページから本件電子データを削除していること等の事情からす れば,侵害の程度は著しく小さく,被控訴人の行為に違法性はないと主張す る。 しかし,被控訴人は,本件各写真が控訴人の著作物であることを知りつつ, これを掲載した本件冊子を,その許諾の範囲を超えて,電子データ化した上, インターネット上の本件ホームページに掲載したのであるから,控訴人が有 する本件各写真の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害することについて, 少なくとも過失が認められる。 また,本件における被侵害利益(控訴人が有する本件各写真の著作権)や 侵害行為の態様(電子データ化して3か月弱インターネット上の本件ホーム ページに掲載した)を考慮すれば,被控訴人が指摘する点を踏まえたとして も,違法性がないとはいえないことは明らかである。 以上によれば,本件ホームページ掲載行為による著作権侵害について被控 訴人の過失及び行為の違法性が認められるというべきであり,これに反する 被控訴人の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 翻案
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2016.07. 5
平成26(ワ)8905 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月15日 東京地方裁判所
ア(ア) 原告は,特許法102条2項の適用を主張するところ,前記前提事実及び 弁論の全趣旨によれば,原告は,被告LEDと競合するLEDを販売等していると 認められるから,原告には,被告らによる本件特許権1の侵害行為がなかったなら ば利益が得られたであろう事情が認められるといえ,同条項の適用が認められるべ きである(知財高裁平成24年(ネ)第10015号同25年2月1日特別部判 決・判時2179号36頁)。この点について,被告らは,被告LEDが譲渡等さ れなければ,原告の製品が販売されていたであろうとの条件関係が存在しないから, 原告には逸失利益の損害は生じていないと主張するが,上記のとおり原告が被告L EDの競合品を販売等していることからして,なお原告に逸失利益の損害が生じた と認定するに差し支えないというべきである。 (イ) 本件特許権1の侵害により被告らがそれぞれ得た利益の額について,被告E &Eが10万5000円の利益を得たことについては,原告と同被告との間で争い がない。また,被告立花が被告LEDの販売により得る利益が,売上高の10パー セントであることは,原告と同被告との間で争いがないところ,被告立花は,イガ ラシに対して被告LEDを2万円で販売し,それ以上に被告LEDの販売等により 売上をあげた事実は認められないから,被告立花が得た利益の額は,2000円と 認めるのが相当である(なお,被告立花は,上記売上代金を全てイガラシに返金し ているとの事情を主張するが,同事実によっても,一度発生した損害が発生しなか ったことになるわけではないし,これにより原告に生じた損害が填補されたと認め ることもできない。)。したがって,これらの額は,特許法102条2項により, 原告が受けた損害の額と推定される。
(ウ) 被告らは,1)原告が被告LEDについて原告が保有する9件の特許権を侵害 すると主張していること,2)被告LEDは,本件発明1の作用効果を奏しないか, 奏したとしても極めてわずかな効果しか奏しないこと,3)被告LEDは,被告製品 (窒化物半導体素子)にさらなる部材を付加していること,4)有色LED市場にお ける原告のシェアなどからすれば,本件発明1が被告らの得た利益に寄与した割合 は5パーセントを上回ることはなく,推定された損害額のうち95パーセント相当 額について,同推定が覆滅されるべきである旨主張する。 しかしながら,1)について,被告LEDが,原告の他の特許権に係る発明の技術 的範囲に含まれるか,含まれるとして,他の特許権に係る発明が被告LEDの売上 にいかに寄与したかについては,本件証拠によっても,判然としないというほかな い。2)について,被告LEDが本件発明1の作用効果を奏しないか,極めてわずか しか奏しないなどといった事実は認められない。3)については,被告LEDが被告 製品に部材を付加しているとしても,その価値の源泉の大半は被告製品にあるもの と合理的に推認できる。4)については,有色LED市場における原告のシェアを一 般的に示すのみでは,本件において,なお原告の受けた損害の額についての推認を 覆すには十分とはいえない。以上のとおり,損害の額の推定が一部覆滅されるべきであるとする被告らの主張は,採用することができない。
(エ) 以上の検討によれば,被告E&Eによる本件特許権1の侵害行為により原告 が受けた損害(逸失利益)の額は10万5000円と認められ,被告立花による本 件特許権1の侵害行為により原告が受けた損害(逸失利益)の額は2000円と認 められる。
2016.07. 5
平成28(行ケ)10045 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年6月29日 知的財産高等裁判所
被告は,Aが,その設立時社員となって,平成26年7月8日に設立された 一般社団法人であるが,前記1認定のとおり,1)その目的を「法人設立以前の上方 舞吉村流六世家元B(本名A)が,吉村流四世家元F及び吉村流五世家元Gから承 継してきた本邦固有の古典舞踊である,上方舞・地唄舞の技芸と振付を,京都御所 の舞指南・御狂言師たる吉村流の格式と伝統を保持しつつ,これを普及・発展させ, さらに後世に承継させ,以てわが国の文化芸術の振興に寄与すること」とし,上方 舞の実技・理論の教授及び後継者の育成,上方舞の舞踊公演会及び講習会の企画・ 開催等の事業を行うものであり,2)その会員は,師範名取,名取,弟子で構成され\nるが,従前の団体「吉村流」の会員であった者については,被告に会費を納入した 場合,当然に被告の会員とみなされ,従前の名取,師範名取の資格を有するものと され,3)その理事長を吉村流六世家元B(A)が務め,理事長(家元)は,被告を 代表し,吉村流家元としてその業務を執行し,名取試験,師範名取試験を実施し,\n理事会の承認を得て各免状を交付し,名取式,事始め等の吉村流の伝統儀礼を催行 し,各家元の年忌法要及び追善舞踊会等を主催するものとされている。また,実際 にも,前記1認定のとおり,被告の設立以前から「吉村流」の師範名取又は名取で あった者のうち多数の者は,被告に会費を納め,被告の会員として活動しており, 従前の団体「吉村流」において,家元が主体となって行っていた,個々の師範名取 や名取の活動を超えた団体としての主要な活動,すなわち,師範名取や名取の免状 の作成,交付,「上方舞吉村会」や歴代家元の追善公演等の主催などの活動は,被 告が行っている。
イ 前記1認定のとおり,本件商標の商標登録出願時において,「吉村流」は,上 方舞の流派である「吉村流」の舞踏の習得,教授等を行う者を構成員とする団体\n(団体「吉村流」)の名称(略称)又はその役務を表示するものとして,日本舞踊に\n係る需要者の間に広く認識されていたものであるが,前記アの事情に照らせば,被 告は,実質的には,従前の団体「吉村流」を法人化したものであるということがで きるから,被告が本来本件商標の商標登録を受けるべき者でないということはでき ない。 さらに,前記1認定の事実によれば,被告が設立された経緯も,団体「吉村流」 と家元個人との会計とを分別して会計の明朗化を図る必要性を契機とするものであ り,法人化に際し定められた定款(甲16)において,組織運営の明確化が図られ ているのであるから,本件商標の商標登録出願が不正の目的の下に行われたもので あるということもできない。
(4) 小括
以上によれば,本件商標の商標登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くもの があるとはいえず,また,本件商標について商標登録を認めることが商標法の予定\nする秩序に反するものであるともいえない。 したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当しない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.07. 5
平成28(ネ)10019 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年6月29日 知的財産高等裁判所 知的財産高等裁判所
控訴人は,原書籍の存在すら知らず,被控訴人の担当者から本件書籍の内容の提 示も受けていないから,原書籍に掲載され,本件書籍での使用許諾を求められてい るのが本件イラストであるとは知らなかった,むしろ,本件書籍での使用について 許諾を求められているイラストは,本件イラストのような「特集ページ」に掲載さ れたものではなく,「記事ページ」に掲載されたものであると理解していたなどと して,控訴人と被控訴人との間では,前提とする許諾の目的物が異なっていたから, 意思の合致はなく,控訴人と被控訴人との間で本件イラストの使用につき許諾が成 立することはない旨主張する。 しかし,前記(1)のとおり,被控訴人が,本件書籍が秋田書店が発行した「怪獣ウ ルトラ図鑑」の復刻版であることを明示した上で,控訴人に対し,原書籍に収録さ れたイラストの本件書籍における再使用についての許諾を求めたのに対し,控訴人 が,原書籍に収録されたイラストの内容,あるいは本件書籍に収録される予定のイ\nラストの内容について何らの質問も確認もすることなく,被控訴人に対し,本件書 籍におけるイラスト使用許諾料の振込口座を指定し,その支払を受けたことからす れば,控訴人は,原書籍に収録された控訴人作成に係るイラストについて使用を許 諾したものと認められるから,被控訴人と控訴人との間において,許諾の対象が一 致していなかったということはできない。
2016.06.28
平成28(行ケ)10003 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年6月23日 知的財産高等裁判所
申立人ら商品1は,本件商標の登録出願日である平成21年11月24日の時点において,販売開始から約15年が経過し,毎年の出荷量も数十\トン程度とほぼ安定した状況にあり,また,この間,関西地域において,テレビCMが7年間にわたって放送されたほか,ラジオCM等の各種宣伝広告も多数行われ,更には,申立人ら商品1の粒の大きさや甘さ,特定の地域でしか生産されない希少性,一粒1000円にもなる高価さなど\nが話題となり,テレビ番組,雑誌,新聞,インターネット上の情報記事等で 繰り返し紹介され,これらの宣伝や紹介の際には,常に引用商標1が使用さ れてきたことが認められる。 これらの事実を総合すると,引用商標1は,本件商標の登録出願日当時に おいて,これがいちごに使用された場合,申立人らが生産,販売する申\立人 ら商品1を表示するものとして,少なくとも関西地域及び徳島県における取\n引者,需要者の間において広く認識されていたものと認めることができる。 ・・・ JA徳島市らによるテレビCMやラジオCM等の宣伝・広告は行われていな いものの,平成25年初めころまでは,新聞記事等で引用商標1とともに紹 介されている事実が認められるほか,申立人ら商品2を紹介するテレビ番組,\n新聞記事等において,申立人ら商品2の前身となるブランドのいちごとして,\n引用商標1とともにたびたび紹介されている事実が認められるのであり,こ れらを総合すれば,引用商標1の周知性は,本件商標の登録査定時である平 成25年10月9日当時においても,なお維持されていたものと認めること ができる。 ・・・ 原告らは,申立人ら商品1が「あまおう」などの他の高級いちご\nと比べて,出荷量が圧倒的に少ない事実を指摘する。 しかし,申立人ら商品1は,そもそも徳島県佐那河内村の特定の農家の\nみが生産するいちごであるから,「あまおう」などの一般的な品種のいち ごに比べて,その生産・出荷量が圧倒的に少ないことは当然である。そし て,申立人ら商品1は,上記のような希少性が一つの理由となって話題を\nインターネット上の 情報記事等で繰り返し紹介されてきたものであり,その結果,引用商標1 が周知性を獲得するに至ったのであるから,申立人ら商品1の出荷量が他\nの高級いちごに比べて少ない点は,引用商標1の周知性を否定する事情と なるものではない。 また,申立人ら商品1の平成15年から平成25年3月までの年度ごと\nの出荷量の推移は,・・年まで約69トンから約95トンの間で推移した後,平成21年には約55トン,平成22年には約47トンと徐々に減少傾向が見られるようにな っている。しかし,申立人ら商品1は,本件商標の登録査定時(平成25\n年10月9日)の直近である平成24年12月から平成25年3月までの 出荷シーズンにおいても,約38トンの出荷量を確保しているのであるか ら,本件商標の登録査定時までに申立人ら商品1の流通量が著しく減少し\nたとまではいえず,この程度の減少傾向の存在が,引用商標1の周知性の 喪失に直ちに結びつくものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.06.28
平成27(行ケ)10202 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年6月21日 知的財産高等裁判所
前記第2「前提事実」1記載のとおり,本件商標は,昭和38年5月 24日に登録出願,昭和39年8月18日に設定登録されたものであるが,商 標公報(甲40)によれば,その出願人は「株式会社伊勢半 東京都千代田区 <以下略> 代表者 A」であることが認められる。他方,商標登録原簿(甲 41)によれば,現在,本件商標につき「東京都千代田区<以下略> 株式会 社伊勢半」を商標権者として登録がされているところ,その登録年月日は「昭 和39年8月18日」とされていることが認められる。 これらの事情を総合的に考慮すると,本件商標の商標権者は訴外会社であっ て,原告ではないと見るほかない。そうである以上,本件審判請求は,正しく は商標権者である訴外会社を被請求人としなければならないところ,原告を被 請求人としてされた不適法なものであり,かつ,その補正をすることはできな いことから,これを却下すべきであったにもかかわらず,本件審決がこれをし なかったことは違法であり,取り消すのが相当である。 これに対し,被告はるる主張するが,本件商標の設定登録が行われた昭和3 9年8月18日時点においては,原告は未だ設立されていなかったのであるか ら,原告が,本件商標の商標権者として登録されたということはあり得ない事 柄であるといわざるを得ない。なお,冒頭で認定した各事実に証拠(乙1ない し4)を併せると,昭和49年に本件商標の存続期間の更新登録がされた際, 誤って訴外会社ではなく原告が更新登録申請手続を行い,その当時,原告の商\n号が「株式会社伊勢半」,所在地が「東京都千代田区<以下略>」であって, 当初登録当時の訴外会社の商号,所在地と同様であったところから,特許庁長 官も,申請者が訴外会社とは異なることを看過して更新登録をしてしまった可\n能性はあり得るものと認められる(そのように考えれば,被告が主張する識別\n番号の点も,理解できることになる。)。しかし,商標権は,いったん設定登 録がされた後は,その存続期間が更新されていくだけであって,更新の際に, 新たな権利が設定・登録されるものではないから(商標法19条,20条参 照),更新手続が上記のように誤って行われたとしても,本件商標に係る商標 権者は,依然として訴外会社であったと解すべきものである。したがって,被 告の上記主張を採用することはできない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2016.06.20
平成27(行ケ)10126 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年6月9日 知的財産高等裁判所
次に,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,実施例2 に関して,「本例は,図4に示すごとく,アルミナシート3の両表\n面に,アルミナシート3よりも薄く,電気絶縁性を有するアルミナ 材料からなる一対の表面アルミナ層35を積層して,固体電解質シ\nート2を形成した例である。…開口用貫通穴351は,ジルコニア 充填部4(充填用貫通穴31)よりも小さく,ジルコニア充填部4 における電極5よりも大きな形状に形成してある。」との記載があ り,図4のガスセンサ素子の断面図では,表面アルミナ層の開口用\n貫通穴351の内周と電極の外周との間に隙間が形成されている態 様が示されていることが認められる。 しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1 について,表面アルミナ層の開口用貫通穴が電極の側面が露出する\n程度に電極よりも大きな形状であることを要する旨の記載はなく,また前記1(2)オで述べた本件発明1が奏する作用効果(ガスセン サ素子の早期活性化と共に,強度向上を図ることができること及び ジルコニア充填部が充填用貫通穴内から抜け出してしまうことを防 止すること)との関係からみても,電極の側面が露出する態様のも のに限定されるべき理由はない。 他方,図4に示されたガスセンサ素子は,実施例の一態様を示す ものにすぎないから,当該図面に表面アルミナ層の開口用貫通穴3\n51の内周と電極の外周との間に隙間が形成されている態様が示さ れているからといって,直ちに本件発明1の構成が当該態様のもの\nに限定されると解すべきものとはいえない。 (C) さらに,本件審決は,「ガスセンサ素子において,電極はできる 限り広い面積で測定ガスに接することが好ましいことが技術常識で あること」を前記解釈の根拠とする。 しかしながら,上記のような技術常識があるからといって,本件 発明1のガスセンサ素子における電極が,常にその上面のみならず 側面まで露出するものであることを要するとの解釈が直ちに導き出 されることにはならない。
(d)以上によれば,本件発明1の表面アルミナ層に設けられた開口用\n貫通穴は「上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成に\nついて,電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大 きな形状に形成してあることを意味するとした本件審決の解釈は, 根拠を欠くものであって誤りであり,これを前提とする本件審決の 前記判断も誤りというべきである。
b 上記aで検討したところによれば,本件発明1における「該開口用 貫通穴は,上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成には,\n電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大きな形状に 形成してあるもののみならず、前記a(a)で述べたとおり、表面アルミ\nナ層の開口用貫通穴の側面とその内側に配置される電極の側面が隙間 なく接しているものも含まれると解すべきである。 してみると,本件アルミナ接着剤層が第1電極404及び第2電極 406の側面に接して形成される態様は,相違点に係る本件発明1の 構成のうち,「該開口用貫通穴は,上記電極よりも大きな形状に形成\nしてあ」るとの構成を満たすものといえる。\nウ 以上のア及びイによれば,甲2発明(1)に甲3技術を適用することは当業者が容易に想到し得たことであり,かつ,その結果得られるガスセンサ 素子は,相違点に係る本件発明1の構成をすべて備えるものといえるから,\n成とすることは,本件出願当時の当業者において容易に想到し得たものと 認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2016.06.15
平成26(ワ)10534 契約金返還等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成28年5月27日 東京地方裁判所
1 争点1(原告サーナアルファが,被告に対し,被告が同原告に対して不正競 争防止法2条1項7号及び同法3条1項に基づく差止請求権並びに同法2条1項7 号及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を請求することにつ いて,確認の利益が認められるか)について 原告サーナアルファは,同原告によるVRC法の実施は,被告が同原告に提供し た不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらな いとして,同原告のVRC法の実施行為について,被告が同原告に対して同法3条 1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確 認を求めている。 一般に,確認の訴えは,即時確定の利益がある場合,換言すれば,現に,原告の 有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存在し,これを除去するため被告に対 し確認判決を得ることが紛争の解決のために必要かつ適切な場合に限り,許される と解すべきである。 証拠(甲12,33)によれば,被告は,原告サーナアルファに対し,弁護士を 通じ,内容証明郵便により,平成25年7月19日付け本件警告状及び同年8月2 9日付け通告書(以下「本件通告書」という。)を送付し,被告の「知的財産権 等に対する一切の侵害行為及び妨害行為を停止」するよう求めたことが認められる。 しかし,上記証拠によれば,本件警告状及び本件通告書には,被告が原告サーナ アルファに提供したとされる営業秘密に関する記載は何ら存在せず,同原告による VRC法の実施が不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正 開示に当たる旨の記載も存在しないのであって,被告が,本件警告状又は本件通告 書により,同原告に同法2条1項7号及び3条1項に基づく差止請求権や同法2条 1項7号及び4条に基づく損害賠償請求権を主張したとみることは,困難であり, ほかに,被告が,同原告に対して,同法2条1項7号及び同法3条1項に基づく差 止請求権並びに同法2条1項7号及び同法4条に基づく損害賠償請求権を主張する おそれが,現に存在していると認めるべき事情は見当たらない。 そうすると,現に,同原告の有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存在し, これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが紛争の解決のために必要かつ 適切であるということはできないから,確認の利益は,これを肯定することができ ない。 したがって,被告が同原告に対して不正競争防止法2条1項7号及び同法3条1 項に基づく差止請求権並びに同法2条1項7号及び同法4条に基づく損害賠償請求 権を有しないことの確認請求に係る同原告の訴えは,不適法である。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2016.06.15
平成26(ワ)28449 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年5月26日 東京地方裁判所
原告は平成25年4月5日〜平成27年10月末日の被告製品の売上高4 億4967万3858円に実施料率5%を乗じた2248万3692円が 本件特許権の侵害による損害額(特許法102条3項)であると主張する ところ,売上高は被告の自認する2億8279万4711円の限度で認め られ,これを上回る額を認めるに足りる証拠はない。 次に,実施料率についてみるに,前記前提事実に加え,証拠(甲2,23, 24,乙27)及び弁論の全趣旨によれば,1)本件発明は被告製品の構成\nの中核部分に用いられており,本件発明の技術的範囲に属する部分を取り 除くと被告製品はアンテナとして体をなさないこと,2) 本件発明は高さ約 70mm以下という限られた空間しか有しないアンテナケースに組み込ん でも良好な電気的特性を得ることのできるアンテナ装置の提供を目的とす るところ,被告製品はこれと同様に背が低いにもかかわらず受信性能に優\nれたアンテナ装置であって,被告はこの点を被告製品の宣伝上強調してい ること,3) 本件発明の属する電子・通信用部品ないし電気産業の分野のラ イセンス契約における実施料率については平均3.3〜3.5%ないし2. 9%とする調査結果が公表されていること,以上の事実が認められる。こ\nれらの事実を総合すると,本件において特許法102条3項に基づく損害 額算定に当たっては被告製品の売上額の5%をもって原告の損害とするの が相当である。 したがって,原告の損害額は1413万9735円となる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2016.06.15
平成25(ワ)33070 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年5月26日 東京地方裁判所
本件の各発明が被告の上記利益に寄与した割合について,本件発明1に つき被告は2.5%,原告は50%であると,同2−1及び2−2につき 被告はロ号物件につき0.3%,ニ号物件につき0.9%,へ号物件につ き0.2%,原告は30%であるとし,その余の部分につき特許法102 条2項の推定が覆滅する旨主張する。 そこで判断するに,本件明細書1(甲2)によれば本件発明1は農産物 の選別装置に関するものであって主としてリターンコンベアを設けること 及びその終端を工夫したことに,同2(甲4)によれば本件発明2−1及 び2−2は内部品質検査装置に係るものであって主として複数の光源を設 け,遮光手段を工夫したことに,それぞれ技術的意義があるものと認めら れる。その一方で,前記1(1)のとおりロ号〜ホ号物件はプールコンベアに 設定される仕分区分が集積状態によって適宜変動する構成を採用しており,\nその結果,そうでない構成と比べてオーバーフローする青果物入り受皿の\n数が減少するものと認められ,その限度において本件発明1が被告の上記 利益に寄与した割合が減少すると考えられる。 また,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,1)ロ号〜へ号物件は,選 別設備及び内部品質検査装置のほかに荷受設備(ニ号物件を除く。),箱詰 設備,封函・製品搬送設備,製函・空箱搬送設備その他の設備から構成さ\nれるものであり,上記イの利益にこれらの製造及び施工に係る利益が含ま れていること(乙38〜41),2)ロ号〜へ号物件の各設置場所に関する 入札条件(甲14〜18)上,少なくともリターンコンベアの戻し位置を 本件発明1所定の位置にすること及び内部品質検査装置において本件発明 2−1及び2−2所定の複数の発光光源を設けることは必須の要件とされ ていなかったこと,以上の事実が認められる。 上記の技術的意義及び事実関係によれば,上記利益額の一部については 特許権侵害による原告の損害額であるとの推定を覆滅する事情があると認 められ,その割合は本件発明1につき75%,同2−1及び2−2につき 95%と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2016.06.15
平成27(ワ)21850 楽曲演奏禁止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年5月19日 東京地方裁判所
上記事実関係によれば,原告楽曲と被告楽曲の旋律(上記(2)ウ)は,旋律 の上昇及び下降など多くの部分が相違しており,一部に共通する箇所がある ものの相違部分に比べればわずかなものであって,被告楽曲において原告楽 曲の表現上の特徴を直接感得することができるとは認め難い。また,両楽曲\nは,全体の構成(同ア),歌詞の各音に対応する音符の長さ(同イ)及びテ\nンポ(同エ)がほぼ同一であり,沖縄民謡風のフレーズを含む点で共通する が,これらは募集条件により歌詞,曲調,長さ,使用目的等が指定されてお り(同オ),作曲に当たってこれに従ったことによるものと認められるから, こうした部分の同一性ないし類似性から被告楽曲が原告楽曲の複製又は翻案 に当たると評価することはできない。 これに対し,原告は前記のとおり原告楽曲と被告楽曲は実質的に同一の楽 曲である旨るる主張するが,以上説示したところに照らし,いずれも採用す ることができない。 (4)さらに,念のため,依拠性について検討すると,原告は,1)実質的に同一 の楽曲を依拠することなく作曲することは不可能であること,2)被告Yに短 期間で被告楽曲を独自に作曲する経験及び能力があるとは考えられないこと,\n3)電子メールの送信日時には改ざんの可能性があることから,被告Zを担当\n者とする被告SMEが被告Yと意思を通じ,原告楽曲に依拠して被告楽曲を 作曲したと主張する。 そこで判断するに,上記(3)のとおり両楽曲が実質的に同一であるとはいえ ないから,原告の上記1)の主張は前提を欠く。また,上記2)の主張を基礎付 けるに足りる証拠はない。さらに,上記3)の主張については,証拠(乙1及 び2の各1,乙20)及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告Yがそれぞ れ被告Zに対し楽曲の完成及びこれが収められたファイルの保存先を電子メ ールにより伝えたのが,被告Yにおいては平成25年1月18日午前11時 10分,原告においては同日午前11時32分であると認められる一方,電 子メールの送信日時については,一般的ないし抽象的な改ざんの可能性があ\nるとしても,本件の関係各証拠上,被告らによる改ざんがあったことは何ら うかがわれない。 (5) 以上によれば,被告楽曲が原告楽曲の複製又は翻案に当たるとはいえない から,原告の著作権が侵害されたとは認められず,これを前提とする著作者 人格権の侵害も認められない。したがって,その余の点について判断するま でもなく,原告の請求は全て理由がない。
2016.06.15
平成27(ワ)8704 特許権 民事訴訟 平成28年5月12日 大阪地方裁判所
「電子ショッピングシステム」の意義についても,本件明細書中に明確な定 義はないが,「ショッピング」が一般的な意味において売買を指すことは明らかで あるし,加えて構成要件Fからすると,この電子ショッピングには,少なくとも「注\n文」と「受注」が起きることが必要であるし,また本件明細書の【0001】には, 【発明の属する技術分野】として「本発明は,例えばレコードショップ等が加盟す るフランチャイズ制の電子ショッピングシステムに関し,インターネットを利用し た電子商取引の技術分野に関する。」とあり,さらに【発明の効果】を記載した【0 042】に「受注データにしたがって当該会員に商品を引き渡すと共に代金を受領 することにより,自らホームページを所持しなくても,インターネットを利用した 商取引が可能となる。」とあることから,ここにいう「電子ショッピングシステム」\nとは,インターネットを利用してされる有償の商品の取引を指すものと解するのが 相当であり,その取引においては,「注文」と「受注」,すなわち売買契約締結に 向けて顧客からの具体的法律行為がなされ得ることが必要であると解される。 これに対し,原告は,電子ショッピングシステムの定義について,商品の広告, 受発注,設計,開発,決済などのあらゆる経済活動と捉えるもので,商品の宣伝で あってもこれに含まれる旨主張するところ,確かに,本件明細書には,「電子ショ ッピングシステム」でなす経済活動について,「電子商取引」(【0001】,【0 005】,【0038】,【0043】),「商取引」(【0013】,【004 2】)などとする記載があり,さらに証拠(甲19ないし21)によれば,「電子 商取引」の定義については上記原告主張に一部沿うものが認められる。 しかし,「宣伝」に触れる記載(甲19)は,取引ではなく,インターネット上 の商行為について触れるものであるし,「広告」を含む通商産業省の定義(甲20) は,その当時の郵政省の定義とは異なることからすると,これは省庁の規制目的で 対象範囲の定義をしていると理解でき,直ちに一般的に通用する定義に結びつくも のとはいえない。 そして,そもそも,ここでは本件発明の構成要件にいう「電子ショッピングシス\nテム」の定義を問題にしているのであるから,上記説示のとおり本件明細書の記載 を考慮して解すべきであって,したがって,「電子ショッピンング」に,少なくと も原告の主張するような宣伝,広告までを含んで解することはできないというべき である。 (イ) これを前提に被告システムにつき検討するに,被告システムは,前記認定の とおり,顧客は各提携企業のホームページにおいて,講演会の講師を選択し,当該 講師の「講演を依頼する」タグを選択することにより現れる問合せ画面に名称,住 所,電話番号等の自らを特定する情報を記載し,さらに講演の希望内容を入力する などして送信すると本部のサーバーがこれを受信し,それに伴って各提携企業サー バーにeメールが送信されることで各提携企業が得る上記情報を基に,顧客を訪問 する,電話ないしメール等で連絡を取り合うなど営業活動をして,顧客の希望に沿 った講演会の内容・レベル・対象・講師・構成などを聴取し,顧客と契約できるよ\nう交渉を行うという方式である。 すなわち,被告システムの役割は,講演開催運営を取り扱う各提携企業に対し, 講演開催希望者がインターネットを使ってアクセスするホームページを設けて,そ の潜在的需要を顕在化させ,もって各提携企業が営業活動をすべき講演開催希望者 の情報を得ることができるというところまでであり,その後の講演開催実現に至る までの営業活動は,インターネット外,すなわち被告システム外の接触交渉が予定\nされているというものである。また,その機会における顧客が被告システムを利用 して「お問い合わせ(講演依頼)」をする行為は,漠然とした講演開催希望に基づ くものであってもよく,したがって,これにより提携企業との間で講演開催に向け ての交渉が開始されたとしても,それだけでは当事者間に法的な関係が直ちに生じ たとはいえないから,被告システムは,それは最終的に締結されるだろう講演開催 委託契約に向けての各提携企業の営業活動の契機を与えるものにすぎないものとい える。そして,このように見ると,被告システムでされている内容は,潜在的需要 者をインターネットでアクセスさせ,その潜在的な需要を顕在化させ,その情報を もとに実際の営業活動に結びつけるという,一般的な広告宣伝の手法と何ら変わら ないものといい得る。 なお,被告システム利用者の中には,希望講師のみならず講演会開催の日時,場 所とも確定して利用する者が含まれることはあり得るところ,その場合,そのよう な「お問い合わせ(講演依頼)」によるアクセス行為は,商品購入の注文に極めて 似ているといえるが,その場合であっても,被告システムを介して,そのアクセス を受けた各提携企業は,自らが講演する主体ではなく,また掲載講師のスケジュー ルを管理している主体とも認められないから,直ちに承諾,すなわち「受注」する ことができるわけではなく,その後,講師との関係を調整して,具体的講演開催に 向けて交渉を重ねる必要があるはずであって,したがって,利用者の 「お問い合わ せ(講演依頼)」をいかに具体化しても,これを売買契約における「注文」に準じ るものということができるわけではない。 したがって,被告システムは,構成要件Aにいう「電子ショッピングシステム」\nには相当しないというべきである。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.06. 8
平成27(ネ)10091 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年6月1日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
(ア) 一審被告は,1)被告製品は,1種類の正・逆転パターンの制御しかできず, 正転角度と逆転角度を均衡にしたときのみが本件特許権の侵害となるにすぎないこ と,2)被告製品は,納品時は正転60秒,逆転60秒にセットされており,この状 態では,ブリッジ現象が生じることが明らかであり,本件特許発明1及び2の作用 効果を奏しないこと,3)被告製品の正転タイマ及び逆転タイマによる正逆転制御(1 種類のパターンでの制御)では,本件特許発明1及び2は,進歩性を欠くこと,4) 被告製品の制御は,本件特許発明の作用効果を考慮したとき,本件特許発明とは全 く別異であり,実施は不可能であるものの形式的には本件特許の請求項の制御を実\n施し得る場合が考えられるというにすぎないことを考慮すれば,被告製品における 侵害部分が,購買者の需要を喚起するということはあり得ないから,本件特許発明 1及び2の寄与率が30%を超えることはない旨主張する。
(イ) 1の点について
本件特許発明1の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」は,前記2(3)のとおり, 単なる右回転又は左回転ではなく,右回転と左回転の組合せを1パターンとして, 1種ないし複数種類のパターンを繰り返す駆動であって,1パターン内の右回転と 左回転は均衡した回転角度とされているものを意味するものと解される。被告製品 が1種類の正・逆転パターンの制御しかできないものであったとしても,結局,被 告製品は,本件特許発明1及び2を充足するような使用方法が可能である。他方,\n被告製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり,その特徴に購買者の需要喚起力 があるという事情が立証されていない以上,寄与率なる概念によって損害を減額す ることはできないし,特許法102条1項ただし書に該当する事情であるというこ ともできない。
(ウ) 2)の点について
仮に,被告製品の納品時におけるタイマセットの状態のままでは,本件特許発明 1及び2のブリッジ現象の発生の防止という作用効果を奏しないとしても,被告製 品は,前記2(3)のとおり,定期正転時間,定期逆転時間を,それぞれ,0から30 00秒の範囲で,10分の1秒単位で数値により設定することができるものである から,結局,被告製品は,本件特許発明1及び2を充足するような使用方法が可能\nである。そして,前記(イ)と同様に,寄与率なる概念によって損害を減額すること はできないし,特許法102条1項ただし書に該当する事情であるということもで きない。
(エ) 3)の点について
1種類の正・逆転パターンでの制御であると,本件特許発明1及び2が進歩性を 欠くとの点については,これを認めるに足りる証拠はない。
(オ) 4)の点について
被告製品の制御が,本件特許発明1の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」に相 当するものであることは,前記2(3)のとおりであり,被告製品の制御と本件特許発 明1及び2の制御とが別異のものであるとする一審被告の主張は,その前提を欠く。 ク 小括
以上によれば,特許法102条1項に基づく損害額は,2810万1920円で あると認められる
。 (2) 一審被告が保守作業を行ったことによる損害
一審原告は,一審被告は被告製品を保守することで,被告製品の譲受人による被 告製品の使用を継続させ,又はこれを容易にさせているということができるから, 譲受人による被告製品の使用につき,その行為の幇助者として共同不法行為責任に 基づき,損害賠償責任を負う旨主張する。 しかし,一審原告の上記主張は,幇助の対象となる使用行為を具体的に特定して 主張するものではないから,失当である上,一審被告が,被告製品について具体的 に保守行為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。また,被告製品の使用によ り一審原告が被った損害(逸失利益)は,前記(1)の譲渡による損害において評価さ れ尽くしているものといえ,これとは別に,その後被告製品が使用されたことによ り,一審原告に新たな損害が生じたとの事実については,これを具体的に認めるに 足りる証拠はない。さらに,保守行為によって特許製品を新たに作り出すものと認 められる場合や間接侵害の規定(特許法101条)に該当する場合は格別として, そのような場合でない限り,保守行為自体は特許権侵害行為に該当しないのである から,特許権者である一審原告のみが,保守行為を行うことができるという性質の ものではない。 以上によれば,一審原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条1項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.06. 8
平成27(ワ)10913 債務不履行損害賠償請求 特許権 民事訴訟 平成28年5月23日 大阪地方裁判所
2 被告らが,審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し,補正の書面を提出すべき義務を負うか否か
(1) 前記認定事実等(1)ア(ア)のとおり,米国特許出願手続における補正は,書類 を提出することによって行われるが,審査官補正の場合には,米国特許商標庁(審 査官)が審査官補正書を発行して行われると認められる。そして,前記認定事実等 (1)ア(イ)c及びdのとおり,審査官補正は,出願人が電話又は個人面接にて権限を授 与した場合に許されることから,審査官補正の場合には,出願人が補正の書面を提 出する必要はないと認められ,前記認定事実等(4)のとおり,578出願での審査官 補正でも電話面接による権限授与が行われているにとどまる。そこで,本件で,被 告らが審査官からの連絡に対して補正の書面を提出すべき義務を負うといえるため には,審査官からの連絡が審査官補正の提案でなく,出願人による補正の促しであ ったことが必要となるので,まずこの点を検討する。
ア 前記認定事実等(2)アのとおり,被告P2は,P4に対する電子メールに おいて,審査官からの補正提案を許容する旨を審査官に伝えれば,審査官は審査官 による補正を用意すると連絡しており,これによれば,被告P2は,審査官からの 連絡を審査官補正の提案であると理解したと認められる。そして,同電子メールに 記載された審査官の提案は,クレームを提案のように補正すれば,特許可能である\nという内容を電話で伝えてきたものであるところ,これは,審査官補正が,「出願を 特許として通す場合」(又は「特許申請登録の段階に於いて」),「電話又は個人面接\nにてかかる変更について権限を授与した場合に」許されるものである(前記認定事 実等(1)ア(イ)c)との定めにも適合している。そうすると,本件での審査官の提案は, 審査官補正の提案であったと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 裁判管轄
>> ピックアップ対象
2016.05.26
平成27(ワ)37086 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成28年5月18日 東京地方裁判所
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通 じて起こさせる美観に基づいて行うものであるところ(意匠法24条2項),この ためには,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規 な創作部分の存否等を参酌して,当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を 通じて注意を惹きやすい部分を把握した上で,登録意匠とそれ以外の意匠とが要部 において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し,全体としての美観を共通に\nするか否かを判断すべきである。 本件意匠に係る物品は,膣圧回復治療用具であって,これを使用する一般消費者 を需要者と観念すべきところ,本件において,同用具の公知意匠に係る証拠は提出 されていないが,膣圧回復治療用具を実際に使用する需要者にとっては,膣内に挿 入する部分は,注意を惹きやすい部分といえる。もっとも,需要者は,現実に同用 具を使用する際にどのように使用することとなるかについても着目すると考えられ るから,本件意匠のうち持ち手部分も,注意を惹く部分であることは否定できない。 したがって,本件意匠について,需要者が視覚を通じて最も注意を惹きやすい部 分は,本体部及び持ち手部分の各具体的構成態様にあるものと認められる。\n
・・・
以上のとおり,本件意匠と被告意匠1とは,需要者が視覚を通じて最も注意を惹 きやすい部分の各具体的構成態様において差異点が認められるところ,本件意匠の\n本体部には突起がないことから,滑らかな印象を与えるのに対し,被告意匠1のA 部は,多数の突起が形成されていることから,ざらざらとした印象を与える。また, 本件意匠の持ち手部にはリングを備えているのに対し,被告意匠1のB部は,底部 にブラシ状に多数の突起が形成されていることから,明らかに異なった印象を与え る。 以上の点を総合すると,前記共通点にかかわらず,本件意匠と被告意匠1とは, 全体として美観を共通にするものとはいえないから,被告意匠1が本件意匠に類似 するものとは認められない。
・・・
以上のとおり,本件意匠と被告意匠2とは,需要者が視覚を通じて最も注意を惹 きやすい部分の各具体的構成態様において差異点が認められるところ,本件意匠の\n本体部は,正面視において略「ハート」状であるのに対し,被告意匠2のC部は, 正面視において略「卵」状であり,その印象を異にする。また,本件意匠の持ち手 部には略楕円状のリングを備えているのに対し,被告意匠2のD部は,底部にブラ シ状に多数の突起が形成されていることから,明らかに異なった印象を与える。 以上の点を総合すると,前記共通点にかかわらず,本件意匠と被告意匠2とは, 全体として美観を共通にするものとはいえないから,被告意匠2が本件意匠に類似 するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2016.05.23
平成27(行ケ)10139 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年5月18日 知的財産高等裁判所
本件発明1は,前記2(2)のとおり,従来のスロットマシンにおいては,メ モリのデータに異常が生じると,遊技店の従業員等の操作により選択・設定された 設定値ではなく,あらかじめ定められた設定値を自動的に設定し,ゲームの進行が 可能な状態に復帰させているので,本来であれば,遊技店側の操作により選択・設\n定された設定値に基づく当選確率を適用して内部抽選が行われ,入賞の発生が許容 されるべきであるのに,スロットマシンにより自動的に設定された設定値に基づい てゲームが行われることとなるため,ゲームの公平性が損なわれてしまうという問 題があったことから,ゲームの公平性を図ることができるスロットマシンを提供す ることを課題とし,その解決手段として,特許請求の範囲請求項1の構成を採用し,\n特に,不能化解除手段については,第1の不能\化手段によりゲームの進行が不能化\nされた状態においても第2の不能化手段によりゲームの進行が不能\化された状態に おいても,設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段により設定値が新たに 設定されたことを条件に,ゲームの進行が不能化された状態を解除し,ゲームの進\n行を可能とする構\成を採用したものである。
(イ) これに対し,引用発明1は,前記3(2)のとおり,従来のパチンコ機におい て採用されているチェックサムを用いたエラーのチェック方式では,メモリーにバ ックアップ電源を持たないので,チェックサムの内容が電源遮断後,消去されてし まい,スロットマシン固有の設定値に関するエラーのチェックが困難であるという 問題があったことから,設定値を含む遊技データのチェックサムを,バックアップ 電源により保持することにより,電源投入時に,設定値に関するエラーの発生を検 査することができるようにし,エラーを発見した場合には,スロットマシンの遊技 を停止して,段階設定値の設定の待機待ちの状態にすることができるようにすると ともに,段階設定値を手動で変更することができるようにすることを課題とするも のであって,不能化解除手段については,第1の不能\化手段によりゲームの進行が 不能化された状態において,設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段によ\nり設定値が新たに設定されたことを条件に,ゲームの進行が不能化された状態を解\n除し,ゲームの進行を可能とするが,そもそも第2の不能\化手段を備えず,第2の 不能化手段を備えないため,第2の不能\化手段によりゲームの進行が不能化された\n状態を解除し,ゲームの進行を可能とする構\成も備えないものである。 そして,引用例1には,ゲームの公平性を図るために,第2の不能化手段及びそ\nのための不能化解除手段を備えること,第2の不能\化手段のための不能化解除手段\nを第1の不能化手段のための不能\化解除手段と共通にすることについては,記載も 示唆もない。 したがって,引用発明1において,第2の不能化手段及びそのための不能\化解除 手段を備え,その上で,更に,第2の不能化手段のための不能\化解除手段を第1の 不能化手段のための不能\化解除手段と共通のものとすることについて動機付けがあ るということはできない。
・・・
イ 審理事項通知書(甲21)によれば,「合議体の暫定的な見解」として, 「引用例1に記載されている,ステップ3のRAMチェックサム検査とステップ4 のチェックサムの一致判定とを実行するチェックサム検査手段と,ステップ5の段 階設定値が正常か否かを判定する段階設定値判定手段とは別の構成であるから,引\n用発明1における,段階設定値が適正か否かの判断を個別に行うものではない「チ ェックサム検査手段」は,引用発明1の「記憶データ判定手段」に相当するもので ある。」旨示していたことが認められる。これに対し,本件審決においては,「電 源投入時における「制御を行うためのデータ」に異常があるか否かの判定とに関す る技術が,技術的に関連の深いまとまりのある技術単位であることを考慮して,本 件発明1と引用発明1とを対比し直した。」として,本件発明1と引用発明1との 相違点として,相違点1を認定した。 しかし,審判における最終的な判断の論理が,審判手続の経過において示された 暫定的な見解と異なるとしても,審判手続において,改めて上記論理を当事者に通 知した上で,これに対する意見を申し立てる機会を当事者に与えなければならない\nものではない。そうすると,かかる機会を与えなかったことを理由として,本件審 判手続に審理不尽の違法があるとまでいうことはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> コンピュータ関連発明
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2016.05.23
平成27(行ケ)10246 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年5月18日 知的財産高等裁判所
本願商標の外観は,横一行で,「Photomaker」と「Pro」の各部分 の間に半角分の間隔を空け,「Photomaker」の各文字は灰色の輪郭のみ で,「Pro」の各文字は黒色で書された文字を灰色で縁取りすることで表されて\nいる。また,「P」の文字は,いずれも右部の弧状の部分が直線で示され,「t」の 文字は,通常の書体では左側に突き出る部分が削除され,「m」の文字は,通常の 書体では左上に突き出る部分が削除され,「a」の文字は,通常の書体では右下に 突き出る部分が削除され,上部の弧状の部分も直線で示され,「e」の文字は,そ の書き出し部分を左斜め上方向へ傾斜させ,「r」の文字は,いずれも通常の書体 では左上に突き出る部分が削除されるなどのデフォルメがされている。 そして,本願商標の全体からは「フォトメーカープロ」との呼称が生じる。また, 「Photo」は「写真」を,「maker」は「作る人」を意味し(乙3,4), 上記のとおり「Pro」の部分は,「より熟練者を対象とした」,又は「より高い機 能を備えた」という意味で理解されるのであるから,本願商標の全体からは,「写\n真を作る専門家」という観念を生じる。 また,上記(1)のとおり,本願商標の構成から「Photomaker」の部分\nを抽出して対比することも許されるところ,同部分からは「フォトメーカー」との 称呼を生じる。そして,同部分からは「写真を作る人」という観念を生じる。 したがって,本願商標は,その全体から「フォトメーカープロ」,「写真を作る専 門家」との称呼,観念を生じるほか,「Photomaker」の部分から「フォ トメーカー」,「写真を作る人」との称呼,観念を生じる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.05.18
平成27(ワ)13760 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年4月21日 東京地方裁判所
原告は,1)ストリーミングの再生回数が受信複製物の数量に当たること,2)本件動画サイトにおけるストリーミングの再生回数はダウンロードの回数と同視できることなどからすれば,本件著作物1及び2の本件動画サイトにおけるストリーミングの再生回数が著作権法114条1項にいう受信複製物の数量となる旨主張する。 (2) そこで判断するに,受信複製物とは著作権等の侵害行為を組成する公衆送 信が公衆によって受信されることにより作成された著作物又は実演等の複 製物をいうところ(同項),本件においてはダウンロードを伴わないストリ ーミング配信が行われたにとどまり,本件著作物1又は2のデータを受信し た者が当該映像を視聴した後はそのパソコン等に上記データは残らないと\nいうのであるから,受信複製物が作成されたとは認められないと解するのが 相当である。 また,前記前提事実(2)のとおり,本件動画サイトは動画をストリーミン グ配信するウェブサイトであるところ,証拠(甲19,20)及び弁論の全 趣旨によれば,本件動画サイトにアップロードされた動画をダウンロードす ることは不可能ではないが,そのためには特殊なソ\フトウェアを利用するな どの特別の手段を用いる必要があることが認められる。 以上によれば,本件著作物1及び2の本件動画サイトにおけるストリーミ ングによる動画の再生回数が受信複製物の数量に当たるということはでき ないし,これをダウンロードの回数と同視することもできない。
・・・・・
本件著作物1は,平成25年10月5日に本件動画サイトに有料動画と してアップロードされ,同月6日時点における「再生数」は1万3292 回と表示されていた。本件著作物2は,同月4日に本件動画サイトに有料\n動画としてアップロードされ,同年11月29日時点における「再生数」 は2万4539回と表示されていた。\n本件動画サイトの会員でない者が有料動画を視聴しようとするとサンプ ル動画が数秒間再生されるところ,上記の「再生数」にはこのサンプル動 画の再生数も含まれる。本件著作物1及び2に係る「再生数」の内訳は不 明である。 被告がアップロードした本件著作物1及び2のデータは,平成26年3 月頃までに本件動画サイトから削除された。(甲4,5,乙3,8,12) イ 本件著作物1は,動画配信サイト「DMM.com」にて有料でインタ ーネット配信されており,その価格は,平成25年10月5日時点におい て,HD版ダウンロードとHD版ストリーミングのセットが2480円, ダウンロードとストリーミングのセットが1980円,HD版ストリーミ ング(7日間)が390円であった。また,本件著作物2も同様に配信さ れており,その価格は,同年11月29日時点において,HD版ダウンロ ードとHD版ストリーミングのセットが2980円,ダウンロードとスト リーミングのセットが2480円,DVDトースターが2800円であっ た。 インターネット配信の上記各価格は,配信時期やキャンペーンの実施等 によって変動し,本件著作物1に係る平成28年1月15日時点のHD版 ストリーミング(7日間)が273円,本件著作物2に係る平成27年9 月28日時点のHD版ストリーミング(同)が300円となっていた。 (甲2,3,13,乙2,15) ウ 原告(変更前の商号は株式会社北都)は,取引先との間で,コンテンツ 提供基本契約を締結し,取引先に対して原告の映像等のコンテンツの配信 を許諾しているところ,ある取引先との契約では,原告がその対価として ●(省略)●を受け取ることが定められている。 (甲17,25)
(2) 原告は,1)本件著作物1及び2が本件動画サイトにおいて上記「再生数」 に記載の回数配信され,2)これらが正規に配信された場合の価格はそれぞれ 372円,2362円であり,3)この場合原告は●(省略)●を受領できた として,著作権法114条3項に基づく損害賠償を請求する。しかし,上記 の事実関係によれば,1)上記「再生数」の正確性を裏付ける証拠が何ら提出 されていない上,全体の再生回数のうち有料のストリーミング配信の回数は, 事柄の性質上,無料のサンプル動画の再生回数より大幅に少ないと考えられ る。また,2)本件著作物1及び2のストリーミング配信の正規の価格は時期 等によって変動するがおおむね1本当たり270〜390円程度であり,さ らに,3)原告は自らが使用許諾をした場合の対価につき契約条項の大半を抹 消した契約書の写し(甲17)を提出するのみであり,現実にいかなる収入 を得ていたかは明らかでない。本件におけるこれらの事情を総合すれば,被 告による本件著作物1及び2の公衆送信権の侵害に対して原告が著作権の行 使につき受けるべき金銭の額は,それぞれ50万円とするのが相当である。
2016.05.11
平成27(行ケ)10224 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年4月27日 知的財産高等裁判所
本願商標においては,「MAGGIE」と「MILANO」との間に1文字分に満 たないスペースが設けられていることから,「MAGGIE」と「MILANO」と の2つの単語からなるものであると認識し得る。 前半の「MAGGIE」の欧文字部分は,「『マギー』という女性の名又は愛称」 ほどの意味を有するといえる。そして,後半の「MILANO」の欧文字部分は, 「イタリア北部の都市」を指称する語(甲24,乙8)として広く一般に知られて いるものであり,かつ,ミラノにおいては,毎年,世界中から注目されるデザイナ ーズ・コレクションが開かれており(乙9),ファッション性の高いイメージを有す る都市として周知されているから,本願商標を本願指定商品である衣服や靴,洋品 小物などに使用する場合は,それに接する取引者,需要者は,当該「MILANO」 の欧文字を,イタリア国ミラノでデザイン等された商品であることを表す部分,す\nなわち,当該各商品の品質を表示した部分と認識するものとみるのが相当である。\nしたがって,本願商標は,その構成中,後半の「MILANO」の欧文字が,商\n品の品質を表示した部分として,格別の自他商品識別力を有しないのに対し,前半\nの「MAGGIE」の欧文字は,固有の名称であって,出所識別標識として強く支 配的な印象を与えるものであるから,当該欧文字のみを抽出し,他人の商標と比較 して商標としての類否を判断することが許されるというべきである。
イ 称呼について
(ア) 以上のことからすれば,本願商標は,その全体から「マギーミラノ」 の称呼が生じるほか,「マギー」との称呼をも生じるものと認められる。
(イ) これに対して,原告は,本願商標は,「マギー」と「ミラノ」に区切 って発音すると不自然であるから,「マギーミラノ」のみの称呼が生じると主張する。 しかし,本願商標の外観は,「MAGGIE」と「MILANO」との間にスペー スがあることから,2語から構成されるものと看取され,「マギー」と「ミラノ」と\nに区切って発音することに特段の困難も見い出せない。 原告の主張には,理由がない。 ウ 観念について
(ア) 本願商標は,その全体から「イタリアのミラノという都市の『マギー』 という女性の名又は愛称」の観念が生じるほか,上記アのとおり,その構成中「M\nAGGIE」の欧文字が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから,「『マ ギー』という女性の名又は愛称」の観念を生じる。
(イ) これに対して,原告は,「ミラノ」は人の姓としても採択されている から,とある外国人の姓名又は愛称としての「マギーミラノ」という観念が生じる こともあり,また,本願商標では,ファッションブランドの一般的な表記とは異な\nり,「MILANO」を発祥地として小さく付記したものではないから,「MILA NO」は商標中の不可分な構成要素であると主張する。しかし,「ミラノ」が人の姓として使用されることがある(甲27,48)としても,これが我が国において,イタリアの都市名としての「ミラノ」を観念する(このことは,原告も認める。)よりも,優先して観念されるとは認められない。また,ファッションブランドがその発祥地を示す場合に,発祥地を小さく付記することがあるとは認められるが(甲41,乙10〜16),当該発祥地を商標中の他の部分と同程度の大きさで表\示することがないとまではいえない(なお,原告主張によれば,本願商標に係るブランドは,もともと,イタリアの「Maggie Jeans」というジーンズブランドであったとされるから,本願商標については,「MILANO」が発祥地を示すことを意図したものであるとも考えられる。)。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.05.11
平成26(ワ)26079 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年4月27日 東京地方裁判所
この点,原告は,情報処理技術分野における用語法などからすれば,「選択」 には全てを選択することが含まれると主張し,ユーザ端末が全部のサブバンドを選 択することもこれに該当する旨主張する。 しかし,仮に,本件各発明に関連する技術分野において「選択」との文言が上記 のように用いられることがあるとしても,加入者が全部のサブバンドの差分CQI を報告する以外の選択肢がなく,常に全部のサブバンドの差分CQIを報告しなけ ればならない状態についてまで,「選択」の語義に含まれると解するのは妥当でな い。前記前提事実に記載のとおり,被告通信システム方法及び被告製品においては, 基地局により本件モードを選択している以上,加入者は,基地局からのパイロット 信号に対し,全てのサブバンドの差分CQIを報告する以外に選択の余地はないの であるから,原告の上記解釈は採用することができない。 また,原告は,本件明細書の段落【0028】,【0040】,【0069】に は,全部のクラスタが選択されることを包含する内容の記載があること,実質的に も,全部のサブバンドを選択してフィードバックした方がかえってフィードバック 情報量を削減できるといえることなども主張するが,原告が掲げた本件明細書の上 記各段落の記載によっても,常に全部のクラスタについての情報を「選択」すると いう実施形態は明示されていない。なお,本件明細書の段落【0028】には, 「フィードバック内の情報の順序を基地局が知っている限り,フィードバック内の どのSINR値がどのクラスタに対応しているかを示すためにクラスタインデクス が必要になることはない。」としか記載されていないから,仮に,この実施形態が 全部のクラスタについての情報をフィードバックする実施形態を含むとしても,こ のようなフィードバックの形態と加入者による「選択」との関係が不明であり,少 なくとも,常に全部のクラスタについての情報を報告する態様を「加入者による選 択」の一形態として含むことについて,本件明細書に明確な記載はないものという べきである。かえって,原告の主張する解釈1を採用すると,本件発明4の課題解 決のための一つの構成として規定された構\成要件4F,あるいは本件発明9の課題 解決のための一つの構成として規定された構\成要件9Eにおける「前記加入者が選 択した・・・クラスタのグループの中の・・・クラスタを・・・割り当てる」との 意義が失われるというべきで,上記の解釈1は妥当でないと言わざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.05.11
平成27(ワ)27220 著作権侵害行為差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年4月27日 東京地方裁判所
(3) 前記前提事実に証拠(甲6,乙1,4)及び弁論の全趣旨を総合すると,原 告各製品については,1)幼児が食事をしながら箸の正しい持ち方を簡単に覚えられ ることを目的とした幼児の練習用箸であり,このような用途・機能を有する実用品\nとして量産される工業製品であること,2)一方の箸には,人差し指挿入用のリング 及び中指挿入用のリングが設けられ,他方の箸には,これら2つのリングよりは大 きな,やや縦長楕円形の,親指挿入用のリングが設けられているところ,これら各 リングが配置されている位置及び向きは,リングが上記3指の位置を固定して,正 しい箸の持ち方の手の形になるようにするという目的に適った位置及び向きであり, 人体工学に基づいて設計されたものであること,3)箸本体を上部の円形部材等で連 結させているところ,これは1本1本の箸を固定して箸先の交差を防止するという 機能を果たす目的によるものであることが認められる。これら各点に照らせば,上\n記2)のリングの個数,配置,形状等及び上記3)の連結箸である点は,いずれも上記 1)の幼児の練習用箸としての実用的機能を実現するための形状ないし構\造であるに すぎず,他に,原告各製品の外観のうち,原告が被告各商品と共通し同一性がある と主張する部分を見ても,際立った形態的特徴があるものとはうかがわれない。そ うすると,原告各製品が,上記実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るよう\nな美的特性を備えているということはできない(もとより純粋美術と同視し得る程 度の美的特性を備えているということもできない。)。 なお,原告各製品について原告が保護を求めているところのものは,結局のとこ ろ,前示のとおり意匠法が意匠として保護を予定している量産され工業上利用可能\ な物品の形状等そのものであり,原告製品9と同一の形状とみられる意匠について 現に意匠登録もされている(ただ,被告各商品の販売開始時期に比してその出願・ 登録が遅かったにすぎない。)ものである。 (4) 以上によると,原告各製品は,著作権法2条1項1号所定の著作物には当た らないというべきである。
2016.05.11
平成27(ワ)29222 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成28年4月28日 東京地方裁判所
「商品の形態」とは需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいうところ(不正競争防止法2条4項),原告商品の包装箱の表面及び裏面の記載のうち被告商品と共通する部分はいずれも原告商品を説明した文章にすぎないから,商品の形状に結合した模様には当たらないというべきである。これらのことからすれば,原告商品の包装箱及び銀包の形状及び寸法,包装箱の表\面及び裏面の記載はいずれも同条1項3号により保護されるべき「商品の形態」に当たらないと解されるから,被告商品が原告商品の「商品の形態を模倣した商品」であると認めることはできない。したがって,不正競争防止法に基づく原告の請求はその余の点を判断するまでもなく理由がない。
2016.05.11
平成27(ワ)18469 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年4月28日 東京地方裁判所
著作権法において保護の対象となるのは思想又は感情を創作的に表現したものであり(同法2条1項1号参照),思想や感情そのものではない。本件において本件原告記載と本件被告記載1及び2が表\現上共通するのは「重力波と想定される」「波動による(もの)」との部分のみであるが,この部分はEMの効果に関する原告の学術的見解を簡潔に示したものであり,原告の思想そのものということができるから,著作権法において保護の対象となる著作物に当たらないと解するのが相当である。
2016.05. 6
平成27(行ケ)10179 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年4月26日 知的財産高等裁判所
そこで,本件使用商標が,本件商標と社会通念上同一の商標ということがで きるかどうか,以下検討する。
(1) 「MFX」の文字部分が本件使用商標の要部に当たるか
ア 本件使用商標は,前記1(3)アのとおりの外観を有し,「MFX」の欧 文字,「−」の記号,「EV」の欧文字,「シリーズ」の片仮名文字が, 順次,横書き一段に記載されてなるものである。 そして,「MFX」の文字部分と「EVシリーズ」の文字部分は,「−」 (ハイフン)によって接続されているのに対し,本件使用商標を構成する\n文字の大きさには特段の差異はなく,また,上記ハイフン部分を除く各文 字の間隔にも特段の差異はないから,上記ハイフンの前にある「MFX」 の文字部分は,上記ハイフンの後の文字部分と対比して,外観上まとまっ たものとして看取されるというべきである。 これに対し,上記ハイフンの後の「EVシリーズ」の文字部分は,「E V」の文字部分それ自体には,出所識別標識としての特段の称呼や観念を 生ずるものではなく,むしろ,「連続性を持つ一連のもの」との意味を有 する日本語であることを容易に理解することができる「シリーズ」の文字 部分がその後ろに付されていることや,電子応用機械器具の取引分野にお いては,それ自体としては必ずしも固有の意味を生じるものとはいえない 欧文字等の組合せを,商品の種別や型番を表す記号として用いることがあ\nることからすると,取引者,需要者において,「MFX」の語によって表\n象される一連の製品における個々の製品の種別や型番を表す語と理解する\nことができるというべきである。 イ 以上を総合すると,本件使用商標の「MFX」の文字部分は,本件使用 商標のその余の文字部分から分離して観察することが取引上不自然である と思われるほど不可分的に結合しているものではなく,むしろ,電子応用 機械器具の取引者,需要者において,被告が製造販売する製品を表すひと\nまとまりの表示として認識するものと認められ,また,本件使用商標のそ\nの余の文字部分からは,出所識別標識としての称呼や観念は生じないから, 「MFX」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るも\nのであると認められる。 したがって,「MFX」の文字部分は,本件使用商標の要部であると認 められ,本件商標は,これと同一の文字からなるものであるから,本件使 用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。
・・・・
前記1(3)によれば,被告は,要証期間内に,ワタキューセイモアに対し, 本件使用商標が表示された本件ソ\フトウェアのバージョンアップ版が格納され たCD−ROMを引き渡したことが認められる。 かかる行為をもって,本件商標と社会通念上同一の商標を,本件審判請求の 対象となった指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」について使用し たということができるかどうかについて,以下検討する。 (1) 本件集中管理装置と本件ソフトウェアの関係について\nア 前記1(1)アのとおり,本件集中管理装置の取扱説明書には,「装置全 体」の説明として,パソコン本体及びその周辺機器から構\成されるとの記 載があり,被告のウェブサイト(甲3,甲26の1及び2)や本件集中管 理装置のパンフレット(甲9),取扱説明書(甲8,25)には,パソコ\nン本体及びその周辺機器が納められたテーブルの写真や,その見取図が, 本件集中管理装置として掲載されている。 一方,本件集中管理装置の取扱説明書には,その冒頭付近で,「本管理 装置は,Microsoft®社のWindows®上で稼働するシステ ムです。」として,本件集中管理装置の本質が,むしろソフトウェア(本\n件ソフトウェア)にあると受け取れるような説明がされている(1⑴イ) ほか,その記述内容も,ソフトウェアの操作方法を説明したものと受け取\nることが十分に可能\なものになっている(甲8,25)。そして,被告が, パソコン本体及びその周辺機器自体を製造しているとは認められず,これ\nらの機器は,専ら,被告が,他のメーカーから既製品を調達して組み合わ せたものと認められる。さらに,これらの機器自体は,パソコン本体,キ\nーボード,ディスプレイ,マウス,通信アダプタ,プリンタ,無停電電源 装置といった,パソコンでソ\フトウェアを操作するために使われるありふ れたものばかりである上,汎用のものであれば足りるのであって,本件集 中管理装置を構成する機器としての特有のハード面での仕様や性能\が,被 告によって付加されているとは認められない。そして,これらの機器が集 中管理装置としての前記1(1)イのとおりの機能を果たすためには,アプ\nリケーションソフトウェアである本件ソ\フトウェアが,パソコン本体にイ\nンストールされることが必要となる。 また,前記1(1)オによれば,本件集中管理装置は,最新機器に対応す るための機能追加を,本件ソ\フトウェアのバージョンアップ版を格納した CD−ROMを用いた本件ソフトウェアのバージョンアップという形態で\n行っているものと認められるが,上記のような形態による本件集中管理装 置の機能追加に当たって,パソ\コン本体及びその周辺機器自体の更新が必 須のものであると認めるに足りる証拠はない。
イ そうすると,本件集中管理装置の機能,性能\は,専ら本件ソフトウェア\nの機能,性能\に依存しているものであって,むしろ,その本質はソフトウ\nェアである本件ソフトウェアにあるということも可能\である。そして,本 件集中管理装置を最新機器に対応させるためには,少なくとも本件ソフト\nウェアのバージョンアップが必要であり,この場合には,本件集中管理装 置が所要の機能を果たすための必須の構\成要素である本件ソフトウェアの\nバージョンアップ版が格納されたCD−ROMが顧客に販売されるから, かかるバージョンアップ版を対象とする独立の取引を観念することができ る。 以上によれば,本件ソフトウェアのバージョンアップ版は,本件集中管\n理装置の単なる付属品ではなく,それ自体を独立した商品として観念する ことができるというべきである。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2016.05. 1
平成27(ネ)10127 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年4月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
前記(2)の認定事実によれば,第1手続補正前の時点では,特許請求の範囲の請求項1において,「計算」については,「Web−POSサーバ・システム」で行われるのか,あるいは,「Web−POSクライアント装置」で行われるのかを含め,発明特定事項としては何ら規定されていなかったが,控訴人は,第1手続補正によって,特許請求の範囲の請求項1において,「計算」について,「Web−POSサーバ・システム」で行われる構成に限定し,その後にした第2手続補正において,特許請求の範囲を本件請求項1の構\成要件F4のとおり補正し,この第2手続補正に基づく特許請求の範囲の請求項1(本件請求項1)について,特許査定を受けたものであるということができる。そして,第2手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1(本件請求項1)の「該数量に基づく計算」,すなわち,本件特許発明の構成要件F4の「該数量に基づく計算」は,「Web−POSサーバ・システム」では行われず,「Webブラウザ」を備える「Web−POSクライアント装置」で行われるものと解さざるを得ないことは,前記1のとおりである。そうすると,本件出願手続において,第1手続補正前の時点では,「計算」について,発明特定事項として何らの規定もされていなかった特許請求の範囲の請求項1について,控訴人は,第1手続補正により,「計算」が「Web−POSサーバ・システム」で行われる構\成に限定し,その後の第2手続補正によって,この構成に代えて,あえて「該数量に基づく計算」が「Web−POSクライアント装置」で行われる構\成に限定して特許査定を受けたものということができる。上記事実に鑑みれば,控訴人において,「該数量に基づく計算」が,被告方法のように「Web−POSサーバ・システム」で行われる構成については,本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価することができる。したがって,均等の第5要件の成立は,これを認めることができない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.04.25
平成27(行ケ)10232 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年4月14日 知的財産高等裁判所
前記(3)に認定した事実によれば,本件審決日当時,果実を利用した飲料 や菓子等の取引分野において,「まるごと」の語の前又は後に果実を表す語\nを結合した場合,あるいは「まるごと」の語を果実を形容する語として用い た場合には,「まるごと」の語は,当該果実の果肉や果汁が残さず用いられ ていることや,当該果実がその形状のまま用いられていること(当該果実が 切り分けられたりすることなく用いられる場合のほか,その外皮部分が容器 等として用いられる場合を含む。)を表す語として,一般に理解されていた\nことが認められる。 そして,本願指定商品である「メロンを用いたクリームソーダ」の取引者,\n需要者には,かかる飲食物の提供者である飲食店や,その提供を受ける一般 消費者等が含まれると考えられるところ,前記⑵のような本願商標を構成す\nる「メロン」,「まるごと」及び「クリームソーダ」の各語の意義に加え,\n「まるごと」の語が果実を表す語と結合した場合や当該果実を形容する語と\nして用いられた場合の,上記のとおりの一般的な理解の内容に照らすと,本 願商標を構成する「メロンまるごとクリームソ\ーダ」の語は,本件審決日当 時,かかる取引者,需要者によって,「メロンの果肉や果汁が残さず用いら れたアイスクリームソーダ」や「メロンの外皮を容器としてそのまま用いた\nアイスクリームソーダ」を意味するものとして,一般に認識されるものであ\nったと認められる。 そうすると,本願商標は,本件審決日当時,本願指定商品である「メロン を用いたクリームソーダ」に使用されたときは,当該「メロンを用いたクリ\nームソーダ」が「メロンの果肉や果汁が残さず用いられたアイスクリームソ\ ーダ」や「メロンの外皮を容器としてそのまま用いたアイスクリームソー\nダ」であるという,本願指定商品の品質を表示するものとして,取引者,需\n要者によって一般に認識されるものであり,かつ,取引に際し必要適切な表\n示として何人もその使用を欲するものであったと認められるものであるから, 特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,自他商 品識別力を欠くものというべきである。 加えて,本願商標は,「メロンまるごとクリームソーダ」の文字を肉太で\nやや縦長のポップ調の書体で表してなるものであるが,この書体自体は既存\nのものであるし,文字の太さや縦長の形状であることについても,それ自体 はありふれたものの域を出るものではないから,「メロンまるごとクリーム ソーダ」の文字を普通に用いられる方法で表\示する標章のみからなるもので あって,特別に自他商品識別力を有するような特殊な構成を有しているとも\n認められない。 したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するものと認められ る。
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2016.04.22
平成28年(モ)第40004号保全異議申立事件(基本事件・平成27年(ヨ)第22071号仮処分命令申\\立事件)
そこで,上記イの判断を前提に,本件において,債権者が本件著作物の編集 著作者であるとの推定を覆す事情が疎明されているか否かについて検討する。 前記1(4)で認定した事実によると,1)債権者は,執筆者について,特定の実務家 1名を削除するとともに新たに別の特定の実務家3名を選択することを独自に発案 してその旨の意見を述べ,これがそのまま採用されて,本件著作物に具現されてい ること,2)本件著作物については,当初から債権者ら4名を編者として『著作権判 例百選[第4版]』を創作するとの共同の意思の下に編集作業が進められ,編集協 力者として関わったD教授の原案作成作業も,編者の納得を得られるものとするよ うに行われ,本件原案については,債権者による修正があり得るという前提でその 意見が聴取,確認されたこと,3)このような経緯の下で,債権者は,編者としての 立場に基づき,本件原案やその修正案の内容について検討した上,最終的に,本件 編者会合に出席し,他の編者と共に,判例113件の選択・配列と執筆者113名 の割当てを項目立ても含めて決定,確定する行為をし,その後の修正についても, メールで具体的な意見を述べ,編者が意見を出し合って判例及び執筆者を修正決定, 再確定していくやりとりに参画したことを指摘することができる。そして,執筆者 の執筆する解説は,本件著作物の素材をなしているところ,その執筆者の選定につ いては,とりわけ実務家を含めると選択の幅が小さくないこと,債権者が推挙した 当該3名の人選について,誰が選択しても同じ人選になるようなものとはいえない ことに照らせば,債権者による上記1)の素材の選択には創作性があるというべきで ある。その上,上記3)の確定行為の対象となった判例,執筆者及び両者の組合せの 選択並びにこれらの配列には,もとより創作性のあるものが多く含まれているとこ ろ,債権者が編者としての確定行為によりこれに関与したとみられるのである。そ うすると,上記1)ないし3)を総合しただけでも(その余の債権者主張事実の有無に ついて認定・判断するまでもなく),他の共同著作者の範囲はともかくとして,債 権者が本件著作物の編集著作者の一人であるとの評価を導き得るところ,本件にお いて,前記イの推定を覆す事情が疎明されているということはできない。 したがって,債権者は,編集著作物たる本件著作物の著作者の一人であるという べきである。
エ これに対し,債務者は,前記ウ1)に関し,(ア) 執筆者を推挙しただけでその 執筆者に判例を割り当てていない段階では,編集著作物の素材である解説の特定を していないから,素材の原料の提案にすぎず,素材の選択には当たらない,(イ) 債 権者の推挙した上記3名は,東京地裁知財部の部総括判事,元知財高裁判事の弁護 士及び著作権分野で高い実績を有し第3版においても執筆者になっていた弁護士で あるから,極めて「ありふれた」人選であって,創作性は全くない,(ウ) 仮に3名 の候補者を選択したのみで創作的な表現として著作権が生じるとすると,以後,同\n一の3名を選択することが複製に当たり著作権侵害となってしまう旨,前記ウ2)に 関し,(エ) 共同創作の「意思」があっても,何ら著作者性を基礎付ける事情とはな らない旨,前記ウ3)に関し,(オ) 著作権法においては,自ら物理的に創作的表現を\n表出していない者は,著作者たり得ないところ,著作者の認定においては,あくま\nでそのような客観的な創作的表現行為の有無のみが問題となるのであり,「立場」\nや「肩書」は何の意味も持たないし,「最終的な確定権限を有する者」というよう な行為者の権限を考慮することも許されない(当該権限を要件とするような解釈に 基づいて著作者の認定をすることは,同法2条1項2号,1号に反する。),(カ) 本 件編者会合における決定に参加したことは,他人が世に現出した表現について最終\n的に公表すべき表\\現であることを事後的に承認したにすぎず,本件著作物の作成に 創作的関与をしたとの評価にはつながらない,(キ) 本件編者会合後の修正について は,債権者は他者のした提案を一部事後承認したにすぎず,上記(カ)と同様に,本件 著作物の作成に創作的関与をしたとの評価にはつながらない,(ク) 債権者の前記ウ 3)の行為を債権者が本件著作物の編集著作者の一人であることの根拠とすることは, 「それまで表現されたものとして存在しなかったものを初めてつくり出す行為」を\nしていない者を著作者とすることであるから,同法2条1項2号,1号の文理に反 するし,著作物が創作され公表されるまでの間に関与する多数の者(学術論文の査\n読者から果てはマスコット・キャラクターを採択する会議に至るまでありとあらゆ る「確定者」)にいたずらに著作者の外延が拡大されてしまいかねない,(ケ) 債権 者の本件編者会合における承認及びその後の一部承認を創作的関与に含めて考える ことは,智恵子抄事件最高裁判決に反する旨をそれぞれ主張した上,(コ) 本件著作 物の編集に関し,債権者は,極めて限定的な関与しかしていないから,債権者が本 件著作物の編集著作者の一人であるとの評価は導き得ない,(サ) 債権者の関与して いない部分は,債権者の関与した箇所と分離して利用することができるから,同項 12号の共同著作物の要件(分離利用不可能性の要件)を満たさないなどと主張す\nる。
しかしながら,上記(ア)の点については,本件著作物において,執筆者の執筆する 解説が本件著作物の素材をなしていることは前記ウで説示したとおりであるところ, 本件著作物においてそのような解説を執筆する者を,いずれの判例を割り当てるか とは独立に選定することは可能であり,その場合,執筆者を推挙した段階で,「当\n該執筆者がいずれかの判例について執筆する解説」が観念されるから,これが素材 の選択におよそ当たらないということはできない。また,いずれにせよ,判例と執 筆者の組合せが特定されていなかったからといって,本件著作物における「執筆者 の執筆する解説」という素材の選択に関して債権者が寄与したことが否定されるも のではない。
上記(イ)の点については,本件著作物における解説の執筆者として,学者を選ぶか 実務家を選ぶか,実務家にしても裁判官にするか弁護士にするかについて,選択の 幅は大きく,裁判官や裁判官OBについても知財高裁・地裁知財部経験者の人数は 決して少なくないこと,現に第4版に関するそれまでの執筆者の案(本件原案のほ か,A教授が列挙した候補者の案なども含む。)では当該3名が含まれていなかっ たこと(前記1(4)ウないしカ),第3版や本件雑誌にもa判事とb弁護士は入って いないこと(別紙「著作権判例百選判例変遷表」,甲2の3),B教授は,当初,\nb弁護士を執筆者として追加することに消極の意見を表明していたこと(前記1(4) ク)などに照らすと,当該3名について,誰が選択しても同じ人選になるようなも のとはいえず,「ありふれた」人選などということもできない。
上記(ウ)の点については,ここでの執筆者3名というのは,本件著作物の執筆者と なった113名の中の一部であるところ,前記ウの判断は,当該3名を選択したの みで直ちに創作的な表現として独立の編集著作権が生じるとするものではなく,あ\nくまでも本件著作物全体の表現(素材の選択及び配列)について創作性が認められ\nる場合に,これを構成する一部の創作への関与(換言すれば,債権者が関与した部\n分が上記創作性を有する表現を形成する一部をなしているか)を問題とするもので\nあるし,また,債権者の当該行為時点について見ても,執筆者110名から1名を 削除し3名を加えて112名とする場合の当該3名の選択が問題となっているので ある。さらに,前記ウの判断は,必ずしも同1)の行為のみで編集著作者となり得る と判断しているわけではなく,同1)ないし3)を総合して編集著作者となり得ると判 断しているのであって,債権者が,同3)の行為をしているほかに,自ら同1)の行為 もしていることを,全体として評価すべきところである。
上記(エ)の点については,前記ウ2)の事情は,同3)の債権者の行為の前提となるも のであるから,同1)ないし3)があいまって全体として債権者の編集著作者性を基礎 付ける事情になるということができる。
上記(オ)の点については,本件のように共同編集著作物の著作者の認定が問題となる事案においては,編集著作物の完成に向けられた表現(素材の選択・配列)の創\n作に係る複数の者の一連の行為(一瞬の物理的な行為のみではない。)を全体とし て観察し,そのような一連の編集過程への実質的な関与の有無やその位置付け等を 総合的に検討して,一定の規範的な評価をすることは,避けられないものと解され る。そして,それ自体としては同じように見える行為についても,どのような状況 (コンテクスト)において,どのような立場(一貫して編集の主体とされ,内容に ついて決定権や責任を有する者としての行為なのか,アドバイスを求められた外部 の第三者としての行為なのか,事務的な補助者としての行為なのか等々)でそれを 行ったのかということにより,その行為の社会的な意味合いや位置付けは異なり得 るのであって,そのことが事実認定及び法的評価にも影響するのは当然というべき である。上記のような意味での行為者の立場を全く捨象して単純に裸の作為(「物 理的な」創作的表現表\\出行為)のみを取り出すことは,実態にそぐわない編集著作 者の認定をすることにつながりかねず,相当ではない。既に認定,説示したところ からすれば,本件著作物の編集過程において,債権者が,素材の選択及び配列に関 する実質的な権限を有しそれに基づき実質的な関与をしたことは明らかであって, 単に名義を貸しただけとか,単に名目的な「肩書」のみを有して形だけ関わったと いったケースとは明らかに異なる。なお,編集著作物の素材の選択・配列の確定に 関し行為者がどのような権限を有していたかという点も,編集著作者の認定に当たっ て一つの事情となり得るものであって,これを考慮すること(もとよりこれを「要 件」とするものではない。)が許されないということはない。 上記(カ)ないし(ク)の点については,当該編集著作物の編集過程において,当該者自 身が当該創作的表現を「物理的にこの世に現出させる」独自の提案作成行為をしな\nかった場合においても,当初から当該者を含めた複数の者を編者として当該編集著 作物を創作するとの共同の意思の下に共同作業をしている他の者が先行して「物理 的にこの世に現出させる」提案をした部分について,当該者が,それを修正するこ ともできたのに検討の上修正せずに,当該部分をそのとおり採用する決定に加わっ たという行為は,創作への関与として一概に無視することはできない。前記1(4) で認定した事実経過に照らすと,債権者は,本件著作物の編集過程に客観的・外形 的に関与しているのみならず,素材の選択及び配列について実質的な中身を思考し これに基づき上記行為をしているとみられるものであって,前記ウ3)の債権者の行 為は,著作物の形成ないし創作性の形成への「客観的な事実行為としての実質的な 関与」に当たるということができる。本件著作物の「創作」については,本件著作 物の完成に向けた一連の編集過程が開始される前には「それまで表現されたものと\nして存在しなかったもの」を,同編集過程が完了し本件著作物が完成した時点で「初 めてつくり出す行為」であり,その「創作」の主体が債権者を含めた複数の者とな るとみられるのであって,これが著作権法2条1項2号,1号の文理に反するとい うことにはならない。また,既に認定,説示したところに従って,債権者の同3)の 行為を債権者が本件著作物の編集著作者の一人であることの根拠としたとしても, 著作物が創作され公表されるまでの間に関与する多数の者にいたずらに著作者の外\n延が拡大することにはならない(単に名前を貸して形式的に権威付けをしただけの 者や,債務者が例に挙げる「学術論文の査読者」等,もともと創作する側の主体と は異なる立場から関与したり,表現内容の形成・変更の直接の決定権を有していな\nい者などは,共同著作者の一人とは認められない。)。「認定」ということの性質上, 個々の事案に合致した認定をして「共同編集著作者」の範囲を適切に画するほかは ないし,かえって,常に「最も早く物理的に表出した者が誰か」のみに着目すると\nいうことでは,本件のような事案で実態にそぐわない結論を導いてしまいかねない。 上記(ケ)の点については,智恵子抄事件最高裁判決は,当該個別事案における認定 を示した事例判例であって,本件における債権者のような者を編集著作者と認めて はならないとの判断を何ら含意しているものではないから,前記ウ3)に係る判断が 同最高裁判決に「反する」ということはない。 上記(コ)の点については,前記ウ1)の行為と,同2)を前提とした同3)の行為を総合 した場合に,債権者の関与が「極めて限定的」で編集著作者の一人との評価を導き 得ないものであるということはできない。 上記(サ)の点については,前記ウ3)の債権者の行為は,本件著作物全体に係ってい るし,同1)の債権者による素材の選択も,前示のとおり,他の素材の選択及び組合 せとあいまって全体の編集著作物を構成しているものであるから,債権者の関与部\n分のみを分離して個別に利用することはできない。本件著作物は,著作権法2条1 項12号の「二人以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を 分離して個別的に利用することができないもの」に当たるというべきである。 以上によると,債務者の上記各主張によって,債権者が本件著作物の編集著作者 であるとの推定を覆すことはできない。
(2) 翻案該当性ないし直接感得性(争点2)について
ア 前記1(5),(6)で認定した事実によると,1)判例の選択については,本件著作 物の収録判例と本件雑誌の収録判例とで97件が一致しており(そのうち94件は 審級も含めて全く同一であり,3件は審級のみ異なり対象事件が同一である。), 割合的には,本件著作物の収録判例113件のうち約86%が本件雑誌にも維持さ れ,かつ,当該一致部分が本件雑誌の収録判例116件のうち約84%を占めてい ること,2)執筆者(執筆者の執筆する解説)の選択については,本件著作物におけ る執筆者と本件雑誌における執筆者とで93名が一致しており,割合的には,本件 著作物の執筆者113名のうち約82%が本件雑誌にも維持され,かつ,当該一致 部分が本件雑誌の執筆者117名のうち約79%を占めていること,3)判例と執筆 者(執筆者の執筆する解説)の組合せの選択については,本件著作物における組合 せと本件雑誌における組合せとで83件が一致しており,割合的には,本件著作物 における判例と執筆者の組合せ113件のうち約73%が本件雑誌にも維持され, かつ,当該一致部分が本件雑誌における判例と執筆者の組合せ117件のうち約7 1%を占めていること,4)判例及びその解説(以下,併せて「判例等」という。) の配列については,本件著作物の判例等と本件雑誌の判例等とで合計83件の配列 (順序)が一致しており,割合的には,本件著作物の判例等113件のうち約73% の判例等の配列(順序)が本件雑誌にも維持され,かつ,当該一致部分が本件雑誌 の判例等117件のうち約71%を占めていること,5)判例等の配列を位置付ける 項目立てについても,本件著作物の大項目及び小項目の立て方と本件雑誌の大項目 及び小項目の立て方とでその大半が一致していることを指摘することができる。そ うすると,本件著作物と本件雑誌とで判例等の選択及び配列が全体として類似して いることは明らかであって,本件著作物の判例等の選択・配列の大部分が本件雑誌 にも維持されていることが確認できるとともに,本件雑誌の判例等の選択・配列を 見たときに本件著作物のそれに由来する上記各一致部分の全部又は一部を優に感得 することができる。 そして,本件著作物及び本件雑誌に掲載される判例と執筆者の執筆する解説が編 集著作物たる本件著作物及び本件雑誌の素材であるところ,その表現(素材の選択\n又は配列)の選択の幅(個性を発揮する余地)を考えると,『判例百選』の性格上, 判例の選択や判例等の配列に係る選択の幅はある程度限られるものの,執筆者の選 択すなわち誰が執筆する解説を載せるかという選択の幅は決して小さくない上,ど の判例の解説の執筆者として誰を選ぶかに係る選択の幅は極めて広いというべきで ある。そうすると,上記1)ないし5)で指摘した,本件著作物と本件雑誌とで表現(素\n材の選択又は配列)上共通する部分には,創作性を有する表現部分が相当程度ある\nものということができる(なお,編集著作物における素材の選択及び配列に係る上 記各一致部分の組合せ全体に創作性を認めることもできると考えられる。)。 以上の事情を総合すれば,本件著作物と本件雑誌とで創作的表現が共通し同一性\nがある部分が相当程度認められる一方,本件雑誌が,新たに付加された創作的な表\n現部分により,本件著作物とは別個独立の著作物になっているとはいい難い。 このように検討したところによると,本件雑誌の表現からは,本件著作物の表\\現 上の本質的特徴を直接感得することができるというべきである。
イ そして,前記1で認定したとおり,本件雑誌が本件著作物の改訂版として作 成されているものであることなどに照らすと,編集著作物たる本件雑誌が本件著作 物に依拠して編集されたことは明らかである。
ウ 以上によれば,編集著作物たる本件雑誌を創作する行為は,本件著作物に依 拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表\\現に修正, 増減,変更等を加えて,新たに思想を創作的に表現することにより,これに接する\n者が本件著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を\n創作する行為,すなわち本件著作物の翻案に該当し,本件雑誌は本件著作物を原著 作物とする二次的著作物に該当する。 また,他人の著作物を素材として利用しても,その表現上の本質的な特徴を感得\nさせないような態様においてこれを利用する行為は,原著作物の同一性保持権を侵 害しないと解すべきであるが(最高裁平成6年(オ)第1028号同10年7月1 7日第二小法廷判決・判時1651号56頁等参照),本件雑誌における本件著作 物の利用は,このような同一性保持権侵害の要件をも満たすということができる。 (3) 本件著作物を本件原案の二次的著作物とする主張の当否(争点3)について 債務者は,本件著作物は本件原案を原著作物とする二次的著作物にすぎないとし た上で,二次的著作物の著作権者が権利を主張できるのは新たに付加された創作的 部分に限られるところ,本件著作物において本件原案に新たに付加された創作的表\n現が本件雑誌において再製されているとは認められない旨主張する。 しかしながら,前記1で認定した事実に前記(1)で説示したところを総合すると, 本件原案は,最終的な編集著作物たる雑誌『著作権判例百選[第4版]』の完成に 向けた一連の編集過程の途中段階において準備的に作成された一覧表の一つであり,\nまさしく原案にすぎないものであって,その後編者により修正,確定等がされるこ とを当然に予定していたもの(編者が検討するための叩き台,提案)であったこと\nは明らかであり,実際,本件原案作成後,その予定どおり,債権者を含む編者によ\nりその修正等がされ,最終的に編集著作物の素材の選択・配列が確定されて本件著 作物として完成されるに至ったものである。そうすると,本件においては,その完 成の段階で,債権者を共同著作者の一人に含む共同著作物が成立したとみるのが相 当である一方,途中の段階で本件原案が独立の編集著作物として成立したとみた上 で本件著作物について本件原案を原著作物とする二次的著作物にすぎないとするこ とは相当ではない(なお,債務者は,最終作品の作成過程において準備的に作成さ れたものが,第三者によりコピーされ,最終作品の完成後に無断でネット上で公開 されてしまった場合に,当該準備的に作成されたものも最終作品とは別個の著作物 としての保護を受けることを指摘する。しかし,そのような事例において,第三者 によるコピーの時点で,当該準備的に作成されたものがそれ自体著作物性を肯定し 得るものであったならば,それを著作物とする著作権又は著作者人格権の行使を第 三者との関係で肯認することができるとしても,本件のように,既に完成された最 終作品の翻案が問題となっているケースにおいて,当該最終作品を,同作品の完成 に向けて準備的に作成されていた原案の一つを原著作物とする二次的著作物にすぎ ないとして,最終作品に基づく権利行使を制約することは,相当でないことに変わ りはない。)。 したがって,債務者の上記主張は,その前提を欠き,採用することができない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2016.04.21
平成27(ワ)12414 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月30日 東京地方裁判所
上記のとおり,本件発明は,「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」 に関する発明であり,医薬品の成分全体を特徴的部分とする発明であって,原 告は,その実施として,「オキサリプラチン」と「注射用水」のみを含み,それ 以外の成分を含まないとするエルプラット点滴静注液(製剤)について本件各 処分を受けたものである。これに対し,前記前提事実,上記(1)エ及び(2)の各 認定事実,証拠(乙4)並びに弁論の全趣旨によれば,被告各製品は,「オキサ リプラチン」と「水」又は「注射用水」のほか,有効成分以外の成分として, 「オキサリプラチン」と等量の「濃グリセリン」を含有するもので,オキサリ プラチンを水に溶解したもの(以下,「オキサリプラチン」と「水」又は「注 射用水」以外の成分の有無を問わず,「オキサリプラチン水溶液」という。)に グリセリンを加えたのは,オキサリプラチン水溶液の保存中に,オキサリプラ チンの分解が徐々に進行し,類縁物質であるジアクオDACHプラチンやその 二量体であるジアクオDACHプラチン二量体を主とした種々の不純物が生成 するため,オキサリプラチンの自然分解自体を抑制するということを目的とし たものであることが認められる。これを,本件発明との関係でみると,被告各 製品について政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点において,オ キサリプラチン水溶液にオキサリプラチンと等量の濃グリセリンを加えること が,単なる周知技術・慣用技術の付加等に当たると認めるに足りる証拠はなく, むしろ,オキサリプラチン水溶液に添加したグリセリンによりオキサリプラチ ンの自然分解を抑制するという点で新たな効果を奏しているとみることができ る(なお,本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」については, 保存中にオキサリプラチンが自然分解し,シュウ酸を含有するに至ることがあ ることは,前示のとおりである。また,オキサリプラチン水溶液に添加された シュウ酸がオキサリプラチンの自然分解を抑制することは知られているが,シ ュウ酸は人体に有害な物質である。)。 そうすると,被告各製品は,「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」 に関する発明であって,医薬品の成分全体を特徴的部分とする本件発明との関 係では,本件各処分の対象となった物とは有効成分以外の成分が異なる物であ り,当該成分の相違は,被告各製品について政令処分を受けるのに必要な試験 が開始された時点において,本件発明との関係では,単なる周知技術・慣用技 術の付加等に当たるとはいえず,新たな効果を奏するものというべきである。 したがって,「分量,用法,用量,効能,効果」について検討するまでもなく,\n被告各製品は,本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」の均等 物ないし実質同一物に該当するということはできない。 この点,原告は,被告各製品に含まれる「濃グリセリン」があくまで「添加 物」であるとか,被告各製品は,本件各処分の対象となった物(エルプラット 50,エルプラット100及びエルプラット200)と生物学的同等性を有す ることを前提に,本件各処分で用いられた臨床成績をそのまま利用して承認を 得たものであるなどと主張する。しかし,被告各製品が,エルプラット点滴静 注液と有効成分である「オキサリプラチン」が共通し,生物学的同等性を有す るとされており,「濃グリセリン」それ自体が「添加物」であるとしても,上記 のとおり,「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」に関する本件発明が, 医薬品の有効成分のみを特徴的部分とする発明ではなく,医薬品の成分全体を 特徴的部分とする発明であって,そのような本件発明との関係では,上述した 有効成分以外の成分の相違は,単なる周知技術・慣用技術の付加等には当たら ず,新たな効果を奏するものというべきであることからすれば,有効成分であ る「オキサリプラチン」が共通し,生物学的同等性を有するとされていること をもって,直ちに均等物ないし実質同一物と認めることはできないのであって, 原告の上記主張は,採用することができない。
(4) 小括
以上によれば,被告各製品は,本件各処分の対象となった「(当該用途に使用 される)物」ではなく,その均等物ないし実質同一物に該当するものというこ ともできない。したがって,存続期間が延長された本件特許権の効力は,被告 による被告各製品の生産等には及ばないものというべきである。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 均等
>> ピックアップ対象
2016.04.21
平成26(ワ)1690 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月28日 東京地方裁判所
被告は,本件発明2についての特許について,本件明細書2の特許の特許請 求の範囲は,単に「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」と記載するのみで, 「係入片が受片と協働してスタータにて壁パネルの下端部を強固に支持する」との 効果を奏しない「係入片」をもその範囲に含んでおり,権利の外縁を明確に記載し ていないから,明確性要件に違反すると主張する。 しかしながら,本件発明2が「壁パネルの下端部の支持構造」に関するものであ\nることから明らかなとおり,本件明細書2に接した当業者であれば,上記「係入 片」の意義について,覆い片の背部の凹所に係入し壁パネルを支持するため,凹部 の形状と照らして,同凹部に嵌合されるに適した形状を有する必要があることは容 易に認識できるというべきであるから,「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」 という記載が,明確性を欠くものとは認められない。
イ また,被告は,本件明細書2の特許請求の範囲の記載が明確であるというな らば,同明細書の発明の詳細な説明には記載されていない発明を特許請求の範囲に 含むものであってサポート要件に違反するとか,発明の詳細な説明が当業者に実施 可能な程度に明確かつ十\分に記載されておらず実施可能要件にも違反すると主張す\nるが,本件明細書2には,本件発明2(請求項1記載の発明)の実施例として, 「スタータ15を取付け片11においてチャンネル材の壁下地10にボルト18に て取付け,スタータ15の係入片8を壁パネルAの覆い片3の背部の凹所4に係入 するとともに受片9にて嵌合凸部2の下面を受けることで,スタータ15にて壁パ ネルAを強固に支持するのである。」と記載され(段落【0012】),【図1】 には,係入片4が壁パネルAの覆い片3の背部の凹所4に係入されている態様が具 体的に開示されているのであるから,サポート要件に違反するということはできな いし,前記のとおり,本件明細書2に接した当業者であれば,「係入片」の意義に ついて,覆い片の背部の凹所に係入し壁パネルを支持するため,凹部の形状と照ら して,同凹部に嵌合されるに適した形状を有するべきことを容易に認識できるので あるから,実施可能要件に違反するということもできない。\n
・・・
原告は,平成27年11月20日,被告における平成23年1月1日から平 成27年4月20日までの被告各製品の売上高及び利益の額が原告の主張する額で あることを証明するため,特許法105条1項に基づき,被告に対し,被告各製品 の販売量,販売単価,販売原価及び販売のために直接要した販売経費の額が記載さ れている書面である売上伝票,請求書控え,製造原価報告書及び経費明細書(製造 経費及び販売経費)(以下,併せて「対象文書」という。)の提出を求める文書 提出命令申立てを行った(当庁平成27年(モ)第3723号事件)。\n当裁判所は,平成27年12月2日,被告に対し,決定の確定の日から14日以 内に,対象文書を当裁判所に提出すべきことを命ずる決定(以下「本件文書提出 命令」という。)をして,同日,決定書の正本が被告に送達された。本件文書提 出命令は,平成27年12月9日の経過により確定したところ,被告は,上記提出 期限内に,対象文書を当裁判所に提出しなかった。
エ 以上のとおり,被告は,当裁判所がした本件文書提出命令にもかかわらず, 正当な理由なく,対象文書を提出しなかったものである。 そこで,民訴法224条1項又は3項の規定により,対象文書の記載に関する原 告の主張を真実と認め,又は対象文書により証明すべき事実に関する原告の主張を 真実を認めることができるかについて検討する。 対象文書は,被告の売上伝票,請求書控え,製造原価報告書及び経費明細書(製 造経費及び販売経費)であって,被告の業務に際して作成される会計帳簿書類であ るから,その記載に関して,原告が具体的な主張をすることは著しく困難である。 また,原告が,対象文書により立証すべき事実(被告における平成23年1月1日 から平成27年4月20日までの被告各製品の売上高及び利益の額が原告の主張す る額であること)を他の証拠により立証することも著しく困難である。 そうすると,民訴法224条3項の規定により,被告における平成23年1月1 日から平成27年4月20日までの被告各製品の売上高及び利益の額は,原告の主 張,すなわち,被告は,平成23年1月1日から平成27年4月20日までの間に, 被告各製品を販売して合計8億1715万2306円を売り上げ(うち平成26年 1月23日までの売上高は7億8021万6380円,同年12月21日までの売 上高は8億1685万6414円),かつ,被告各製品の利益率はいずれも15パ ーセントを下回ることはないとの事実を真実であると認めるのが相当である。なお, 被告の平成22年4月1日から平成26年3月31日までの総売上の合計が53億 6258万6000円であり,うち,完成工事高が36億2028万2000円, 兼業事業売上高が17億4230万4000円であること,同期間中の兼業事業売 上高に占める原価率は66.27パーセントであること(以上につき,甲70ない し77),被告は,被告製品1−1及び同1−2につき平成21年12月17日に, 被告製品4−1及び同4−2につき平成23年11月7日に耐火認定(建築基準法 及び同法施行令に規定する基準に適合することの認定)を受けたこと(当事者間に 争いがない。)などの事実関係からすれば,上記真実擬制に係る事実は,客観的真 実とも十分に符合しうるというべきである。
オ そうすると,被告は,本件特許権1の侵害により,8億1685万6414 円に15パーセントを乗じて算出される1億2252万8462円(うち平成26 年1月23日までの売上に係る利益は1億1703万2457円)の利益を受けた ものと認められる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2016.04.21
平成25(ワ)29520 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月30日 東京地方裁判所
ウ 以上の本件明細書1の記載によれば,「ICSネットワークアドレス」とは, コンピュータ情報/通信アドレスとして独自に定めたアドレスの付与規則を持つI CS(統合情報通信システム)において,これを構成するアクセス制御装置,アク\nセス制御装置とユーザ物理通信回線との接続点であるICS論理端子,中継装置, VAN間ゲートウェイ及びICS網サーバ等に付与される,それぞれICS内部で 唯一の識別符号を指すものであり,かつ,このうち,ICS論理端子に付されるア ドレスは,ICSネットワークフレームを構成するネットワーク制御部に格納され,\n同アドレスが直接参照されることにより,ICSネットワークフレームがICS網 内を転送されるものを意味すると認められる。
エ しかるところ,被告システムにおける「ラベル」,すなわち網内転送ラベル (outerラベル)及びVPN識別ラベル(innerラベル)の各値は,各事業所に設置 されているCEルータが,自身が接続しているVPNサイト内部のルート情報を接 続しているPEルータに配信し,これを受信したPEルータにおいて,当該VPN に属する他の事業所を接続するPEルータやPルータに配信することを繰り返すこ とにより,特定のホストアドレスを有するVPN内部のユーザへ情報を配信する場 合に通過する経路を各々のPEルータ及びPルータが蓄積した結果決定された情報 であって,被告システムにおいて「ICS論理端子」に該当しうる「PE−CEイ ンターフェイス」に網内で唯一付された識別子であるとは認められない。 加えて,網内転送ラベル(outerラベル)の値は,あくまでPEルータ又はPル ータがMPLSフレームを転送すべき次のPルータ又はPEルータを特定するため に設定された値である上,Pルータを経由するごとに貼り替えられていくのである\nから,仮に,被告システムの「PE−CEインターフェイス」に網内で唯一付され た識別子が存在しているとしても,同識別子が網内転送ラベル(outerラベル)の 値と一致するものとは認め難い。また,VPN識別ラベル(innerラベル)は,M PLSフレームが各Pルータを転送されて受信側PEルータに到着した際に同受信 側PEルータによって参照され,これによりパケットを出力すべきPE−CEイン ターフェイスが特定されるものではあるが,あくまで受信側PEルータ内部によっ てPE−CEインターフェイスを特定するものであるから,VPN識別ラベル (innerラベル)の値が,特定のPE−CEインターフェイスに網内で唯一付され た識別子と同一の値であるとは直ちには認められず,両値の同一性を認めるに足り る的確な証拠もない。
オ なお,原告は,網内転送ラベル(outerラベル)及びVPN識別ラベル (innerラベル)の「2つのラベルに含まれる情報」や「ラベルの組合せ」をもっ て,「ICSネットワークアドレス」に該当すると主張しているようにも思われる ところ,確かに,被告システムにおいて,網内転送ラベル(outerラベル)及びV PN識別ラベル(innerラベル)が付されたパケットは,最終的に所望のPE−C Eインターフェイスを経由して特定のユーザに送信されることとなるが,上記のと おり,「ICSネットワークアドレス」とは,コンピュータ情報/通信アドレスと して独自に定めたアドレスの付与規則を持つICS(統合情報通信システム)にお いて,これを構成するアクセス制御装置,アクセス制御装置とユーザ物理通信回線\nとの接続点であるICS論理端子,中継装置,VAN間ゲートウェイ及びICS網 サーバ等に付与される,それぞれICS内部で唯一の識別符号を指すものであり, かつ,このうち,ICS論理端子に付されたアドレスは,ICSネットワークフレ ームを構成するネットワーク制御部に格納され,同アドレスが直接参照されること\nにより,ICSネットワークフレームがICS網内を転送されるものを意味するの であって,単に「所望のICS論理端子にICSユーザフレームを到達させるため に同ICSユーザフレームに付される情報」一般を包括的に含む広範な概念を指す ものとは認められないから,原告の主張は採用できない。 カ したがって,被告システムは,「ICSネットワークアドレス」を有しない から,構成要件1−1A,同1−1B及び同1−2Aをいずれも充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.04.21
平成27(行ケ)10153 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年4月13日 知的財産高等裁判所
原告は,歴史と伝統を備えた超高級ブランドについて,十分な知識と経験を備え\nた超富裕層である需要者の間では,「CIFONELLI」ブランドは,「チフォネ リ」の称呼のもと,最高級の紳士スーツについて広く認識された存在となっている から,本願商標と引用商標との類否判断に当たっては,かかる取引実情を考慮すべ きと主張する。 しかし,原告が日本に進出したのは,2000年秋であり(甲7),原告商品が取 り扱われている百貨店は,東京の新宿伊勢丹(甲11),大阪の阪急メンズ大阪(甲 12),東京の銀座三越(甲13)及び東京の日本橋三越(甲14)等の数か所にす ぎない。また,原告の紹介記事等は,2000年8月ころ(甲7)及び2009年 春ころ(甲8)にファッション雑誌に掲載され,2010年2月16日公開のファ ッション情報ウェブサイトに掲載された(甲10)ほかは,原告商品を取り扱う百 貨店のパンフレット(甲9,11〜15)に記載されているだけであり,ウェブサ イト上の質問コーナーの回答中に原告商品への言及(甲16)が認められるにすぎ ない。一般に広く需要者が閲覧する雑誌及びウェブサイトへの記事掲載が,証拠上, 2000年以降現在までわずか4回にすぎないこと,百貨店のパンフレットのうち, 甲9は2011年春物の紹介であるから配布期間が短く手に取る者は限定されてい たであろうし,甲14は紳士服オーダーサロンにおける春のオーダー会の紹介とし て,原告ブランドが他のブランドと並んで紹介されているにすぎず,掲載期間及び 需要者がアクセスした期間は限定されており,甲15は伊勢丹新宿店のウェブペー ジであって,他の取り扱いブランドと同様に原告商品の仕立て料金等を表示してい\nるにすぎず,甲11〜甲13は,百貨店のフロアガイドであって,他のブランドと 同等に原告ブランドが記載されているにすぎず,ウェブサイト上の質問コーナー(甲 16)を閲覧した者が相当多数であったと認めるに足りる証拠もない。原告の日本 における売上げは,2013年及び2014年の3月〜9月(7か月分)で700 0万円近くと認められる(甲32)ものの,かかる金額が,紳士服の1ブランドの 売上げとしてその周知著名性を基礎付けるほど多額であると認めるに足りる証拠も ない。 上記の事実を総合考慮すれば,本願商標が,原告の扱う最高級の紳士服を示すも のとして,本願指定商品の需要者である男性の間で周知又は著名となっていたとは 認められない。したがって,本願商標に係る需要者層が富裕層の男性に限られ,本 願商標に係る商品が高級な男性用スーツ等に限られるとする原告の主張には,理由 がない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.04.21
平成27(ネ)10126 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年4月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これに対し,控訴人は,「手順・プロセス」が含まれていても,「構造\n・構成」に発明性を備えるものは「物の発明」であるところ,本件特許発明\nは,「テーブル」と「緩衝材」によって構成される「構\造」によって,本件 明細書に記載された発明の作用効果を得ることを目的とする「物の発明」で あって,テーブルを「設置し」と建築物等を「配置する」の前後関係は,技 術的には何ら価値がなく,本件特許発明の構成要件ではないなどと主張する。\n しかしながら,これらの控訴人の主張は,あくまでも,本件特許発明にお ける「地盤強化工法」が構造ないし構\成を意味することを前提とするもので あり,前記アのとおり,かかる「地盤強化工法」が工事の方法を指すと解さ れる以上,控訴人の上記主張は,その前提において採用することができな い。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.04.20
平成27(行ケ)10217 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年3月31日 知的財産高等裁判所
「小鯛ささ漬」の語は,一般的な辞典には固有名詞等として登載されている ものとは認められない(乙3,弁論の全趣旨)。インターネット上では,「小鯛ささ 漬」の語は,原告の構成員が販売する商品の商品名として使用されているほか(甲\n12,乙41),「小鯛ささ漬」,「小鯛笹漬」,「小鯛の笹漬」,「笹漬小鯛」の語については,少なくとも,以下のような使用例がある。 (ア) 兵庫県所在の「C商店」のウェブサイトにおいて,「選りすぐりの逸品」の 項に,商品名「小鯛の笹漬」が,「あじの笹漬」「さよりの笹漬」と並んで,笹の葉 の上に魚の切り身を載せた写真とともに表示され,「C商店の名でご支持いただいて\nいる小鯛の笹漬」,「水揚げされたばかりの小鯛などの魚を新鮮さそのままに素早く 加工。昔ながらの製法で作る笹漬は全て手作業です」との説明文が掲載されている (乙11)。
・・・
オ 上記アないしウによれば,小さな鯛を意味する「小鯛」と,魚の一般的調理 法を示す語である「ささ漬」を組み合わせた「小鯛ささ漬」は,一般的に,「小さな 鯛を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの」の意味合いを有す る複合語として,容易に理解されるものであるといえる。上記エのとおり,「小鯛さ さ漬」と同一又は実質的に同一の語が,各地方で生産,販売される上記調理法によ って調理された小鯛を示す名称として一般的に使用されていることも,同語がその ような意味合いに理解されることを裏付けるものである。
(2) そうすると,本願商標を,その指定商品である「レンコダイのささ漬」に使 用する場合には,これに接する取引者・需要者は,一般的に,「小さな鯛を三枚にお ろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」という原材料,生産方法を記述 したものとして理解,認識するといえる。 したがって,本願商標は,その指定商品の原材料,生産方法を普通に用いられる 方法で表示する標章のみからなるものであるから,法3条1項3号に該当する。\n
・・・
また,確かに,「小鯛のささ漬け」というものは,福井県若狭地方の伝統料理, 名産品の一つであることが認められる(甲3,7,8,乙53。なお,これらの文 献では,名産品としては,「小鯛ささ漬」ではなく,「小鯛のささ漬」〔甲3〕,「小鯛のささ漬け」〔甲7,乙53〕という表示が用いられているものが多い。)。しかし,\n「小鯛のささ漬け」というものが若狭地方の名産品,伝統料理であり,そのような 認識を取引者,需要者が有するとしても,前記1(1)のとおり,「小鯛ささ漬」の語 が,魚の種類と,魚についての一般的な調理法を示す「ささ漬」という一般的な語 を組み合わせたものにすぎず,また,若狭地方以外で生産,販売されている同調理 法によって調理された小鯛についても「小鯛ささ漬」,「小鯛笹漬」,「小鯛の笹漬」,「笹漬小鯛」という名称が一般的に使用されていることからすれば,「小鯛ささ漬」 の語が直ちに「福井県若狭地方の名産品」のみを意味するものと取引者,需要者が 理解するとは認められず,本願商標が,指定商品の原材料,生産方法を普通に用い られる方法で表示する標章のみからなるものであることを否定する理由とならない。\nしたがって,原告の主張は理由がない。
(2)ア 原告は,ある商標がある特定地域の名産であって,他に同じものを名産と する地域がなく,かつ,当該名産の名称が当該地域で特定の事業者又は団体構成員\nによって実質的に独占されているのであれば,その名称は「名産品であることによ って,その名称が自他商品の識別標識」となり得る,審決のような理由で「小鯛さ さ漬」のような地域名産品が商標法による保護を受けることができないとすれば, 商標法の趣旨に反するなどと主張する。 しかし,原告の主張するとおりの事実があれば,当該商標が自他商品の識別標識 となり得るとしても,それは,法3条2項の該当性の問題と解すべきことは,前記 (1)アのとおりである。そして,一般に,地域名産品の名称については,同項による 商標登録のほか,同法7条の2による地域団体商標の商標登録が考えられるのであ って,本願商標が法3条1項3号に該当するからといって,商標法の趣旨に反する などということはできない(なお,本件においては,原告は,法3条2項に基づく 主張をしないことを明らかにしていることは前記第2の4のとおりであり,原告の 構成員による本願商標の使用実績等についての主張立証もしようとしていない。)。\n
関連カテゴリー
>> 商3条1項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2016.04.20
平成27(行ケ)10052 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月31日 知的財産高等裁判所
一般に本願発明のような医薬用途発明においては,一定の予防又は治療すべき状\n態に対して,特定の医薬を投与するという用途を記載するのみで,その作用効果に ついて何ら客観的な裏付けとなる記載を伴わず,そのような技術常識もない場合に は,当業者において,実際に有用性を有するか,すなわち,課題を解決できるかど うかを予測することは困難である。\nそうすると,本願明細書の発明の詳細な説明には,式R−A−Xの化合物が, 「B型肝炎より選択された,ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」と\nいう医薬用途において使用できること,すなわちヒト又は動物の生体内におけるB 型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載され ているとはいえない。 したがって,本願発明は,発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により 当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず,特許法 36条6項1号の規定を満たさない。
(4) 特許法36条4項1号(実施可能要件)について
発明の詳細な説明の記載は,「経済産業省令で定めるところにより,その発明の 属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載したものであること」を要する(特許法36条4項1号)。\n前記(3)で判示したところによれば,本願明細書の発明の詳細な説明には,式R− A−Xの化合物を「B型肝炎より選択された,ウィルス性の感染を予防又は治療す\nるための医薬」として使用できることが,当業者が理解できるように記載されてい るとはいえない。 したがって,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明の実施をする ことができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。
(5) 原告の主張について
ア 審決の判断手法の誤りについて
原告は,審決が,審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果について, これらの各試験結果の記載が,本願の出願当初の明細書等の開示範囲を超えたもの であるか,又は本願発明の効果の範囲内での補充にすぎないものであるかの判断を 行うべきであり,当該判断を怠って,実施可能要件及びサポート要件に規定する要\n件を満たさないと判断した審決には,判断手法に誤りがあると主張する。 しかし,一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており,その補充等のため に,出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとして も,前記(3)のとおり,本願明細書の発明の詳細な説明には,式R−A−Xの化合 物を,B型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載\nされているのみで,当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとな る記載が全くないのであり,このような場合にまで,出願後に提出した薬理試験結 果や基礎出願の試験結果を考慮することは,前記(3)アで述べた特許制度の趣旨か ら許されないというべきである。 そうすると,原告が,審判手続において,審判請求書添付の試験結果及び基礎出 願の試験結果を参酌すべき旨を主張していたことからすれば(甲11,13),審 決において,同主張を明示的に排斥することが相当であったとはいえるとしても, 出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添付の試験結果や,基礎出願の 試験結果は,本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結果を補充す るものということはできないから(その上,後記イのとおり,これらの試験結果を 考慮したとしても,式R−A−Xの化合物のB型肝炎ウィルスの感染の予防又は治\n療に対する有用性を裏付けるものとは認められない。),これらの資料を考慮しな いで,サポート要件及び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法\nが違法であるということはできない。また,その点が審決の判断を左右するものと は認められないから,審決の取消事由には当たらない。 なお,原告は,本願明細書の記載は,本願の出願人による実証に基づいて導き出 されたものである旨をも主張している。しかし,仮にそうであったとしても,その ことは上記判断を左右するものではないし,そもそも,後記イのとおり,本訴にお いても,本願発明の「式R−A−X」に当たる化合物のB型肝炎ウィルスの感染の 予防又は治療に対する有用性を裏付ける客観的資料は何ら提出されていないことか\nらすれば,同主張を認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2016.04.20
平成27(ネ)10063 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成28年3月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
上記(ア)ないし(ウ)のとおりの控訴人の本件各商標の登録出願の経緯,出願 当時の認識及び本件各商標の使用状況ないし控訴人の宣伝広告等の内容を総合考慮 すると,控訴人による本件各商標の商標登録出願は,控訴人が,平成3年頃から旧 インディアン社によるインディアンブランドの潜在的周知性に着目し,旧インディ アン社と控訴人とは関わりがないにもかかわらず,同社との関連性を強調して我が 国でインディアン関連商品の販売をすることを意図し,被控訴人がその頃我が国で 先行してインディアンブランド事業を開始しているのをみて,自らもそのような被 控訴人の事業展開や宣伝広告に便乗するとともに,被控訴人による事業展開を妨げ る目的で行われたものであると認めるのが相当である。
イ 本件各商標に化体された信用性について
前記のとおり,控訴人は,本件各商標についてこれと同一の商標を商品や宣伝広 告に使用したことは全くないのであるから,そもそも本件各商標自体には,控訴人 の独自の信用が化体されているとはいえない。また,前記のとおり,控訴人は, 「Indian」ロゴや本件商標2と類似するカナダインディアン社の商標を使用した商 品を販売していたが,これらについても,自らとは関わりがない旧インディアン社 との関係を強調した宣伝広告を行っていたものである。控訴人のこのような商標の 使用は,自己の商品に係る業務について,旧インディアン社の承継人ないしはライ センシーの業務であるかのような混同を生じさせるものであり,商標法が商標の出 所表示機能\を保護するものであることからすれば,同法上,このような商標の出所 表示機能\は本来保護されるべき性質のものとはいい難く,このような商標の使用に よって形成された控訴人の信用は,控訴人独自のものとはいえず,本件各商標と類 似した商標が使用されることによって,本件各商標の出所表示機能\が実質的に害さ れるものとはいえない。
ウ 控訴人片仮名商標に基づく侵害訴訟との関係について
さらに,本件各商標は,前記1のとおり,被控訴人標章1と類似するものである ところ,そもそも被控訴人の代表者であるCは,被控訴人標章1(Indian/Motocyc le商標)と同一の商標について,本件各商標の登録出願(平成6年9月21日)よ りも先立つ平成4年2月6日の時点で,商標登録出願をしていたものであり,被控 訴人は,平成7年9月29日に被控訴人標章1に係る商標登録がされた後,その商 標権を譲り受けていたものである。 そして,同商標登録は,控訴人が請求した無効審判において,控訴人片仮名商標 と類似し,商標法4条1項11号に違反することを理由として無効審決がされ,平 成14年12月27日,同審決を維持する内容の東京高等裁判所の判決がされ,平 成15年6月12日に同審決は確定したため,遡及的に無効となったものであるけ れども,一方で,同時期に係属していた,控訴人の被控訴人に対する控訴人片仮名 商標に係る商標権に基づく商標権侵害差止等請求訴訟においては,同年12月26 日,控訴人が被控訴人らに対して同商標権に基づいて禁止権を行使することは,商 標権の濫用に当たるものとして許されないとの一審判決が言い渡され,さらに,平 成16年12月21日,前記イと同様の理由により,控訴人片仮名商標に係る商標 権の行使が権利の濫用であるとして,その控訴を棄却する控訴審判決がされ,同判 決が確定したものである。 そうすると,本件片仮名商標は,これに係る商標登録自体は有効であるものの (なお,控訴人片仮名商標に係る商標登録が商標法4条1項7号に違反するとして 被控訴人が請求した無効審判については,上記侵害訴訟の控訴審判決とほぼ同時期 である平成16月12月8日に,同号違反を否定する審決を維持する内容の判決が, 同控訴審判決とは別の裁判体によってされた。),その商標権は,被控訴人に対し ては行使できないものであるところ,仮に控訴人片仮名商標に係る商標登録がされ なければ,商標法4条1項11号違反を理由として被控訴人標章1に係る商標登録 が無効とされることはなく(なお,被控訴人標章1についての商標法4条1項7号 違反を理由とする無効理由は,別の審決取消訴訟において理由がないものと判断さ れている。),むしろ,被控訴人標章1よりも後願である本件各商標(被控訴人標 章1と類似する。)についての商標登録の方が認められなかったはずであり,また, 被控訴人標章2(「Indian」ロゴ商標)も,本件各商標と類似しているとして,商 標法8条1項違反を理由として無効審決が維持されたものであるから,同様に,控 訴人片仮名商標に係る商標登録がなければ,無効とされることはなかったはずのも のである。 そうすると,被控訴人と控訴人との間では,控訴人片仮名商標に係る商標権に基 づく権利行使が許されないとの判決が確定しているにもかかわらず,控訴人片仮名 商標が登録されていることを唯一の理由として商標登録が無効とされた商標と同一 の標章である被控訴人標章1及び2について,被控訴人標章1よりも後に出願され た本件各商標との類似性を理由として本件各商標権に基づく権利行使を認めること は不合理である。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2016.04.20
平成26(ネ)10080等 特許権侵害行為差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
被控訴人は,本件特許について本件訂正を行ったことに伴い,従前の特許発明に 基づく請求を維持したまま,限定的減縮を行った訂正後の発明に基づいて予備的請\n求を行うところ,特許権者が自らの意思に基づいて訂正請求等を行う以上,特許権 に基づく侵害訴訟においても,これを訂正の再抗弁として位置付けて,訂正後の発 明に基づく請求のみを審理判断すべきものと解されるが,本件では,後記のとおり 訂正発明1に係る訂正自体が不適法であることから,予備的請求1だけでなく主位\n的請求についても審理判断することとする。なお,予備的請求2については,被控\n訴人の主張のとおり,訂正後の請求項4に基づく請求を,訂正の再抗弁として位置 付けて審理判断する。 そして,当裁判所は,主位的請求については,控訴人は本件発明1の技術的範囲 に属する控訴人方法1を使用していると認められる(争点(1)及び(6))が,本件発 明1に係る特許には新規性欠如の無効理由はない(争点(2))ものの,進歩性欠如 の無効理由がある(争点(3))と判断する。また,予備的請求1については,訂正\n発明1に係る本件訂正は不適法であり許容されない(争点(8))上,控訴人が控訴 人方法2を使用しているとは認め難い(争点(9))と判断する。さらに,予備的請\n求2については,控訴人方法3は訂正発明4の技術的範囲に属すると認められる (争点(13))ものの,訂正発明4に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある(争 点(14))と判断する。
・・・
しかしながら,本件明細書には,スピネル型マンガン酸リチウムの製造過程にお いて用いられる電解二酸化マンガンにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態, あるいは,「本発明」における製造方法により得られるスピネル型マンガン酸リチ ウムにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態を具体的に特定する記載や,これ を示唆する記載は一切見当たらない。 したがって,本件明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実\n質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて,少なくとも明示 的な記載はないと認められる。
ウ 「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除\nく。)」との事項が,本件明細書の記載から自明な事項であるか否か 次に,「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除\nく。)」との事項が,本件明細書の記載から自明な事項であるか,すなわち,本件 出願時の技術常識に照らして,本件明細書に記載されているも同然であると理解す ることができるか否かについて検討する。 (ア) 本件発明1は,電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物又はカ リウム化合物で中和し,所定のpH及びナトリウム又はカリウムの含有量とした電 解二酸化マンガンに,リチウム原料と,アルミニウムその他特定の元素のうち少な くとも1種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し, 所定の温度で焼成して作製することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの 製造方法であるところ,このような製造方法で製造したスピネル型マンガン酸リチ ウムにおいて,原料として用いられた電解二酸化マンガンの中和に用いられたナト リウム又はカリウムがどのような形態で存在するかについては,本件出願当時,少 なくともこれがLiMn2O4の結晶構造中ではなく,その外側に存在するとの技\n術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 一方,前記5(2)イ(ウ)及び同ウのとおり,乙18文献の記載に照ら して,リチウム二次電池の正極活物質として用いられるLiMn2O4を作製する 際に,ナトリウム,ナトリウム化合物,アンモニウム化合物などの添加剤を混合し て焼成することにより,LiMn2O4の結晶構造中にナトリウムが取り込まれ,\nそれによりマンガンの溶出が抑制されることが知られていたと認められ,また,乙 15文献の記載に照らして,電解二酸化マンガンを水酸化ナトリウムで中和するこ とにより得られた二酸化マンガンは,ナトリウムを含有すること,このような二酸 化マンガンを原料にしてリチウムマンガン複合酸化物を作製すると,二酸化マンガ ン中のナトリウムは,リチウムマンガン複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出 サイトに取り込まれることが,広く知られていたと認められる。 そして,本件出願当時,中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが, 焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造\n中に取り込まれることなく存在する場合があることや,その場合のナトリウムの具 体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) これらの事情に加え,ナトリウムを添加剤として添加する場合と, 電解二酸化マンガンの中和に用いる場合とで,焼成時のナトリウムの挙動に差異が あることを示す技術常識が存在すると認めるに足りる証拠はないことに照らせば, スピネル型マンガン酸リチウムの製造工程において用いられる電解二酸化マンガン をナトリウム又はカリウムで中和処理するとの本件明細書の記載に接した当業者は, 中和処理に用いられたナトリウムやカリウムが,焼成後に得られるスピネル型マン ガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることをごく自然に理解するというべき\nである。これに対し,本件明細書の記載から,本件発明1の製造方法により製造さ れたスピネル型マンガン酸リチウムにおいて,ナトリウムやカリウムがLiMn2 O4の結晶構造中ではなくその外側に存在することを,本件明細書に記載されてい\nるのも同然の事項として理解することは,到底できないというべきである。 さらに,「本発明」におけるスピネル型マンガン酸リチウムの製造の際に用いら れる原料や製造工程の具体的な内容を含む本件明細書の記載を見ても,上記の理解 を否定すべき事情は見当たらない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2016.04.20
平成27(行ケ)10054 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月30日 知的財産高等裁判
上記のとおり,本件明細書には,本件発明に関し,水性懸濁液の投与とこれ以外 の他の形態(例えば,溶液)で投与した場合との対比や,1日1回の鼻腔内投与と この投与回数及び形態を変えた場合との対比はなされておらず,単にプラセボとの 対比による効果の有無しか記載がない。そして,本件優先日当時の技術常識を踏ま えると,水に難溶性の薬物の水性懸濁液は,他の溶媒を用いた溶液よりも,粘膜か ら吸収されにくいということはできるが,それだけでは,治療効果の具体的な違い は把握できないし,また,他の形態で投与した場合や異なる投与回数の場合の治療 効果がどの程度であったかを読み取ることも,困難である。 他方,甲1発明及び甲2発明においても,アレルギー性鼻炎に対する一定の治療 効果が期待されることは上記のとおりである。 そうすると,本件明細書の記載からは,甲1発明や甲2発明よりも,本件発明1 が,治療効果の点で優れているかどうかを理解することは困難といわざるを得ない。
イ 全身的な吸収及び代謝
本件明細書には,本件発明に関し,経口溶液と比して,鼻腔スプレー懸濁液の方 が,モメタゾンフロエートの全身的な吸収が低く,モメタゾンフロエート自体が血 漿中で定量限界以下しか存在しないという効果があることが記載されているが,経 口懸濁液と同程度の効果があることの記載しかない。そして,技術常識を踏まえて も,他の形態で投与した場合(例えば,溶液の形態での鼻腔内投与)や異なる投与 回数の場合の全身的な吸収及び代謝がどの程度であったかを推認することは困難で ある。 他方,甲1発明において,腹腔内投与及び経口投与後のモメタゾンフロエートの 血漿中の量は高くなく,比較的短期間で消失することは理解できるが,鼻腔内投与 の場合における全身的な吸収及び代謝の程度は全く不明といわざるを得ない。甲2 発明は,水性懸濁液を鼻腔内に使用した発明であるが,本件優先日において,少な くとも,鼻腔内投与の場合にモメタゾンフロエートの全身的な吸収や代謝後の残存 が常に高いという技術常識はない。 そうすると,本件明細書の記載からは,甲1発明や甲2発明よりも,本件発明1 が,全身的な吸収及び代謝の点で優れているかどうかを理解することはできないと いわざるを得ない。
ウ 全身性副作用
本件明細書には,本件発明に関し,プラセボとの対比において,HPA機能抑制\nに起因する全身性副作用がないことが記載されているだけで,他の形態(例えば, 溶液)で投与した場合との対比や,投与回数を変えた場合との対比はなされていな い。そして,当事者の技術常識を踏まえても,他の形態で投与した場合や異なる投 与回数の場合の副作用がどの程度であったかを読み取ることは困難である。 他方,前記(2)及び(3)のとおり,甲1発明及び甲2発明において,モメタゾンフ ロエートは,経口吸入及び鼻腔内吸入をしても,実用可能な程度の副作用しかない\nといえるし,本件優先日において,少なくとも,モメタゾンフロエートの全身的な 吸収が必ず高いという技術常識はない。 そうすると,本件明細書の記載からは,甲1発明や甲2発明よりも,本件発明が, 全身性副作用の点で優れているかどうかを理解することはできないといわざるを得 ない。
エ 以上によれば,本件発明には,薬としての一定の治療効果を有し,実用 可能な程度の副作用しかないことは認められるとしても,本件発明の当該効果が,\n甲1発明及び甲2発明の効果とは相違する効果であるということはできないし,ま た,本件明細書上,それらの効果とどの程度異なるのかを読み取ることができない 以上,これをもって,当業者が引用発明から予測する範囲を超えた顕著な効果とい\nうこともできない。よって,この点に関する審決の判断には誤りがある。
オ 審決は,甲1及び甲2には,1日1回の投与の記載がなく,治療効果の 程度についての記載もなく,本件発明の治療効果を予測できないと判断した。しか\nしながら,甲1発明及び甲2発明において,一定の治療効果が認められながらその 程度についての記載がない以上,当該効果が本件発明の効果よりも明らかに劣るも のと認められない限り,本件発明の効果が顕著なものであるとはいえないはずであ る。審決は,甲1及び甲2の治療効果の程度についての認定をせずに,本件発明の 効果がこれを格別上回ると判断したものであって,論理的に誤りがあるといわざる を得ない。 また,審決は,皮膚に適用した場合の全身性副作用について開示する甲1から, 鼻腔粘膜に投与された際の全身性副作用の大きさを予測できないと判断したが,本\n件発明の効果と甲1発明の効果を同質であると認めた以上,甲1発明において,鼻 腔粘膜に投与した際の全身性副作用の方が,皮膚に投与した際と比して常に優れた ものといえない限り,本件発明の効果が顕著なものとはいえないはずであり,この 点についても,審決に論理的な誤りがあるといわざるを得ない。 さらに,審決は,本件発明について,甲1発明で示された最小限の全身性副作用 よりも低いレベルの全身性副作用しかないから,顕著な効果があると判断したが, この審決の判断には,前記(1)イのとおり,モメタゾンフロエートの全身性吸収及び 代謝後の残存量の問題と全身性副作用の有無の問題を同一視した点において誤りが ある。その上,皮膚へ投与する甲1発明と鼻腔に投与する本件発明において,投与 される組織の相違による吸収性の違いがあるからといって,甲1発明の全身性副作 用が実用化できない程度に強いとは当然にはいえないはずであり,この点について 効果の顕著性を認めた審決の判断にも,論理的な誤りがある。しかも,水性懸濁液 のモメタゾンフロエートの全身性吸収の低さ及び代謝後の残存量の少なさは,本件 発明と同様,水性懸濁液の鼻腔内投与を行う甲2発明が有するはずであり,甲2発 明の副作用の程度が開示されていないとはいえ,審決が,甲1発明と甲2発明を組 み合わせて薬として実用化可能な本件発明の構\成を想到できたとする以上,この組 合せと比して本件発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討する必要があ る。しかしながら,審決では,甲1発明との対比しかなされておらず,検討が不十\n分であったといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2016.04.15
平成27(行ケ)10219 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年4月12日 知的財産高等裁判所
(ア) 本件商標と引用商標1を対比すると,本件商標より生じる「フラン クミウラ」の称呼と引用商標1から生じる「フランクミュラー」の称呼 は,第4音までの「フ」「ラ」「ン」「ク」においては共通するが,第 5音目以降につき,本件商標が「ミウラ」であり,引用商標1が「ミュ ラー」であって,本件商標の称呼が第5音目と第6音目において 「ミ」「ウ」であり,語尾の長音がないのに対して,引用商標1におい ては,第5音目において「ミュ」であり,語尾に長音がある点で異なっ ている。しかし,第5音目以降において,「ミ」及び「ラ」の音は共通 すること,両者で異なる「ウ」の音と拗音「ュ」の音は母音を共通にす る近似音である上に,いずれも構成全体の中間の位置にあるから,本件\n商標と引用商標1をそれぞれ一連に称呼する場合,聴者は差異音 「ウ」,「ュ」からは特に強い印象を受けないままに聞き流してしまう 可能性が高いこと,引用商標1の称呼中の語尾の長音は,語尾に位置す\nるものである上に,その前音である「ラ」の音に吸収されやすいもので あるから,長音を有するか否かの相違は,明瞭に聴取することが困難で あることに照らすと,両商標を一連に称呼するときは,全体の語感,語 調が近似した紛らわしいものというべきであり,本件商標と引用商標1 は,称呼において類似する。
他方,本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から\n成るのに対し,引用商標1は片仮名のみの構成から成るものであるか\nら,本件商標と引用商標1は,その外観において明確に区別し得る。 さらに,本件商標からは,「フランク三浦」との名ないしは名称を用 いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対 し,引用商標1からは,外国の高級ブランドである被告商品の観念が生 じるから,両者は観念において大きく相違する。 そして,本件商標及び引用商標1の指定商品において,専ら商標の称 呼のみによって商標を識別し,商品の出所が判別される実情があること を認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,本件商標と引用商標1は,称呼においては類似するも のの,外観において明確に区別し得るものであり,観念においても大き く異なるものである上に,本件商標及び引用商標1の指定商品におい て,商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められず,称呼 による識別性が,外観及び観念による識別性を上回るともいえないか ら,本件商標及び引用商標1が同一又は類似の商品に使用されたとして も,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。 そうすると,本件商標は引用商標1に類似するものということはでき ない。
(イ)a これに対し,被告は,本件商標は,著名ブランドとしての「フラ ンク ミュラー」の観念を想起させる場合があることから,著名ブラ ンドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる引用商標1と は,観念において類似し,称呼においても類似するから,両者は類似 の商標である旨主張する。 確かに,前記(2)アのとおり,被告使用商標ないしは引用商標1が,被 告商品を表示するものとして,本件商標の登録査定時に,我が国にお\nいて,需要者の間に広く認識され,周知となっていたのであるから,前 記(ア)のとおり,本件商標と引用商標1の称呼が類似することと相ま って,本件商標に接した需要者が,本件商標の称呼から,称呼の類似 する周知な被告使用商標ないしは引用商標1を連想することはあり得 るものと考えられる。 しかしながら,本件商標は,その中に「三浦」という明らかに日本 との関連を示す語が用いられており,かつ,その外観は,漢字を含ん だ手書き風の文字から成るなど,外国の高級ブランドである被告商品 を示す引用商標1とは出所として観念される主体が大きく異なるもの である上に,被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名に関 連する語を含む商標を用いていることや,そのような語を含む商標な いしは標章を広告宣伝等に使用していたことを裏付ける証拠もないこ とに照らすと,本件商標に接した需要者は,飽くまで本件商標と称呼 が類似するものの,本件商標とは別個の周知な商標として被告使用商 標ないしは引用商標1を連想するにすぎないのであって,本件商標が 被告商品を表示すると認識するものとは認められないし,本件商標か\nら引用商標1と類似の観念が生じるものともいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.04. 5
平成27(ワ)7540 発信者情報開示請求 著作権 民事訴訟 平成28年3月15日 大阪地方裁判所
本件日本語ドメイン名の「アクシスフォーマー.com」のうち,「.com」の 部分はいわゆるトップレベルドメインであって識別力が弱いから,本件日本 語ドメイン名の要部は,「アクシスフォーマー」の部分であるところ,これ は,不正競争防止法2条1項12号の特定商品等表示に該当する原告製品の\n名称と同一であるから,本件日本語ドメイン名は,認められる。
・・・
ところで原告製品の購入を検討しようとする需要者がインターネットを利 用する場合,原告製品名である「アクシスフォーマー」を検索ワードとして, グーグル等の検索エンジンを利用して検索するのが一般的と考えられるが, 本件サイトは,本件日本語ドメイン名に「アクシスフォーマー」を含むもの であるから,本件サイトは検索結果として上位になり,またそのドメイン名 から目的とする検索サイトであると理解されるので,上述のアクシスフォー マーという原告製品名を手掛かりにしてインターネット検索をした一般的な 需要者は,必然的に本件サイトに誘導されたものと認められる。 そして,一旦,本件サイトにアクセスした場合,本件サイトは,確かに原 告製品を販売商品として取り扱うサイトであるので,その内容に注目して閲 覧することになるが,本件サイトのウェブページの記載内容は,一般的な商 品取扱いサイトのように取扱商品の優秀性を謳うものではなく,上記(2)にみ られるように,原告製品が問題のある商品というだけでなく,それを製造販 売する原告さえも問題があるようにいうものである。すなわち,被告は,本 件発信者が大量の原告製品を抱えてこれを販売するために本件サイトを開設 したように主張するが,その本件サイトでは,原告製品に興味を持ち,その 購入を検討しようとしてインターネットを利用してアクセスしてきた需要者 に対し,ウェブページの随所において,需要者の購入意欲を損なうことを意 図しているとしか考えられない内容の記載をしているのであり,また,その 記載は,併せて製造者としての原告の信用を損なうことをも意図していると 解さざるを得ないものである。結局,これらのことからすると,本件サイト は,被告が主張するような原告製品の販売促進を意図したものではなく,む しろ原告が主張するように,原告に「損害を加える目的」で開設されたサイ トであると断ぜざるを得ないというべきである。
(4) したがって,本件サイトの契約者である本件発信者は,他人に損害を加え る目的で,原告の特定商品等表示である原告製品の名称と類似の本件日本語\nドメイン名を使用したものであり,これは不正競争防止法2条1項12号の 不正競争に当たる。
関連カテゴリー
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2016.04. 1
平成27(行ケ)10174 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年3月23日 知的財産高等裁判所
本件商標と原告使用商標とが非類似の商標であって,両商標において共通する「チ ャッカ」の文字部分も,本件指定商品及び原告商品との関係において,その需要者 に「着火」の語を直ちに想起させるものであって,格別に独創性が高いものではな いから,本件商標は,これに接する需要者をして,原告使用商標を連想させて商品 の出所について誤認,混同を生じさせるおそれある商標とはいえず,かつ,フリー ライド又はダイリューションを招くとまでもいえない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2016.04. 1
平成27(ネ)10102 損害賠償等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
プログラムの著作物の複製権又は翻案権を侵害したといえるためには,既存のプ ログラムの具体的表現中の創作性を有する部分について,これに依拠し,この内容\n及び形式を覚知させるに足りるものを再製するか,又は,その表現上の本質的な特\n徴の同一性を維持しつつ,これに修正,増減,変更等を加えて,新たな思想を創作 的に表現し,新たな表\現に接する者が従来の表現の本質的な特徴を直接感得するこ\nとのできるものを創作したといえることが必要であり,単にプログラムが実現する 機能や処理内容が共通するだけでは,複製又は翻案とはならない。\n本件においては,控訴人プログラム及び被控訴人プログラムのいずれについても, 極めてわずかな部分を除いては,適式にソースコードが開示されておらず,それぞ\nれのプログラムの具体的表現は不明というほかなく,控訴人プログラムの創作性の\nある具体的表現内容やこれに対応する被控訴人プログラムの具体的表\現内容も不明 である。もっとも,控訴人プログラムのソースコードは,約19万行と認められるから(弁論の全趣旨),その全部に創作性がないことは考えにくく,仮に,被控訴人\nプログラムが,控訴人プログラムにおいて創作性を有する蓋然性の高い部分のコー ドの全部又は大多数をコピーして作成されたものといえる事情があるならば,被控 訴人プログラムは,控訴人プログラムを複製又は翻案したものと推認することがで きる。
以下,この観点から,控訴人の指摘する点に沿って検討を加える。
(2) 控訴人の主張について
1) 被控訴人が控訴人プログラムのTemplate.mdbを複製したことは,当事者間に争いがない。 しかしながら,被控訴人がTemplate.mdbを複製したのは,専ら旧SSTとの互換性を確保するためであると認められるところ,上記のとおり,Template.mdbに格納するデータはTemplate.mdb以外のプログラムが処理をするものであり,当該データを定義するコードを除いて,Template.mdbを複製したからその余のプログラムも複製されたと推認される関係にはない。また,Template.mdbに格納するデータは,前記1(1)のとおり,作成された文字情報や各種設定情報であるから,これを定義するコードの表現に選択の幅はないか,ほぼないと認められるから,このコード自体に創作性を認めることも困難である。たがって,Template.mdbが複製されているとしても,そのことは,被控訴人プログラムが控訴人プログラムにおいて創作性を有する蓋然性の高い部分のコードの全部又は大多数をコピーしたことを推認させる事情とはいえない。
2) 控訴人プログラムには,xlsx形式(Excel2007)で出力された字幕ファイルであっても,その拡張子に「xls」(Excel2003)が付されてしまう事象が生じていたところ,平成25年にリリースされた本件プログラムでも同様の事象が生じていたたことが認められる(甲36,37,157,159)。上記事象の原因が,控訴人が主張するように,この事象に関係するコードがExcel2007が頒布開始された平成19年(2007年)より前に作成されたことによるのか,被控訴人が主張するように開発環境にExcel2007がなかったことによるのか, あるいは,単なるバグであるのか(平成25年にリリースされた製品でもそれ以前 に販売されたソフトウェアに対応する必要性はある。),いずれとも確定し難い。し\nたがって,上記事象が,控訴人プログラムのソースコードと被控訴人プログラムの\nソースコードとの特異な一致ということもできない。\nしたがって,上記事象があるとしても,そのことは,被控訴人プログラムが控訴 人プログラムにおいて創作性を有する蓋然性の高い部分のコードの全部又は大多数 をコピーしたことを推認させる事情とはいえない。
3) 控訴人は,本件プログラムには,字幕ウィンドウのハコ全体に対する表示属\n性の設定がハコ内に入力される字幕すべてに適用されないという,控訴人プログラ ムと同様のバグがあると主張する。しかしながら,テキストを全選択して属性設定をしても,その選択範囲よりも前の部分に新たに挿入した文字にその属性が反映されないのは,プログラムとして普通のことである。しかるに,そもそも本件プログラムにはハコ全体に対する表示属性設定機能\がないとの被控訴人の主張や,被控訴人プログラムのマニュアルにおける「全て個別設定になります。」との記載(甲23添付の別紙マニュアルの37頁)にかんがみると,控訴人提出の証拠(甲43〜46)によって示されているのは単なるテキストの全選択にすぎないものと認めるほかなく,本件プログラムに控訴人プログラムと同様のバグがあることを認めるには足りない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2016.04. 1
平成27(ネ)10107 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
これらの記載によれば,本件特許発明1の特徴となる技術的意義の一 つは,弾性腕の接触部についての有効嵌合長が短くなるという課題を解決するため に(【0005】【0008】),複数の弾性腕が,いずれも,端子の基部から接触線 に沿って平行に延びるという解決手段を採用することによって(【0013】,【00 25】,【0042】),端子の基部から延びる弾性腕が接触線を跨ぐことで相手端子 と当接することを防ぎ,その結果,各弾性腕を長く形成することができ(【0013】), そのため,有効嵌合長を大きく確保することができるという効果を奏する(【001 9】)ものであるから,弾性腕が,端子の基部から接触線に沿って平行に延びること は,本件特許発明1の効果を奏するために必要となる,特徴的な構成であると認め\nられる。 これに対し,本件特許発明1において,弾性腕の間に設けられた中央壁15は, 実施例で言及されているだけであるから,本件特許発明1において発明特定事項と なる必須の構成ではなく,また,本件特許1の明細書に従来技術に関する文献とし\nて掲げられた特開平8−236187号公報(甲19)に加え,特開2003−1 68505号公報(乙12),特開平6−76896号公報(乙15),バーグエレ クトロニクスジャパン株式会社カタログ(乙19。平成10年1月ころ発行)から も明らかなとおり,本件特許1の出願日及び本件特許2の原出願日である平成20 年8月5日当時において,コネクタでは,2つの端子の接触部側の間に,相手端子 を当接して停止させる効果をもたらす中央壁が必ず設けられるという技術常識は存 在しないから,当業者にとって,上記中央壁の設置が当然の構成ということもでき\nない。そして,中央壁が存在しない場合には,弾性腕の根元部分が接触線を跨ぐと, 有効嵌合長が短くなるし,仮に,中央壁を設ける場合であっても,弾性腕の根元部 分が中央壁よりも常に高い位置に設けられるとは限らないから,例えば,弾性腕の 最も根元の部分が,中央壁よりも低い位置から開始し,かつ,接触線に対して端子 溝側にある場合であっても,弾性腕が屈曲形状を有していて,中央壁よりも高い位 置で接触線を跨ぐときには,有効嵌合長が短くなることも想定され,したがって, 有効嵌合長の長さは,常に中央壁よりも高い弾性腕部分の長さになるわけではなく, 弾性腕の根元部分の位置や弾性腕の形状等にも左右される。本件特許1の明細書に 記載された従来技術としては,特開平8−236187号公報(甲19)では,相 手端子が当接する中央壁が存在しないコネクタが実施例として,特開2002−1 75847号公報(甲20)では,相手端子が当接する中央壁が設けられたコネク タが実施例として開示されているから,これらの従来技術を踏まえた本件特許発明 1は,相手端子が当接する中央壁の有無にかかわらず,有効嵌合長を長くすること を確実にする効果を目指していた発明ということができる。 そうすると,本件特許発明1は,中央壁の有無にかかわらず,有効嵌合長を大き く確保することを課題とする発明である以上,当該効果を確実に実現するためには, 弾性腕の一部だけが接触線に対して一方の側に位置すれば足りるわけではなく,そ の全体が接触線に対して一方の側に位置することが不可欠であり,複数の弾性腕全 体が接触線の一方の側にあるという発明特定事項は,本件特許発明1の本質的部分 といえる。
(エ) これに対し,被控訴人製品1,2のいずれにおいても,内側接触子2 3(「上位に位置する弾性腕」)の内側湾曲部23Aの根元部分は,直線(接触線) Xを跨っているから,弾性腕が,接触線に対して一方の側に位置しているとはいえ ない。 したがって,被控訴人製品は,本件特許発明1の本質的部分である構成要件1B\nと相違するから,均等の第1要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> ピックアップ対象
2016.03.30
平成27(行ケ)10014 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月25日 知的財産高等裁判所
(ア) 原告らは,主張1)のとおり,マキサカルシトールの効率的な製造方法を検 討する当業者は,甲第4号証の図9から,エポキシド化合物(18)及び(19) のヒドロキシメチル基をメチル基に置き換えることを着想し,動機付けられると主 張する。 しかし,前記のとおり,甲第4号証の図9記載の工程は,25位の立体配置が異 なる二種類のマキサカルシトールの予想代謝物(12)又は(13)を選択的に合\n成するための製造方法であり,まず,出発物質に試薬を適用して二重結合を有する 側鎖を導入し,次いで,これに香月−シャープレス反応を用いるという二段階の反 応を行うことにより,二重結合をエポキシ基に変換した中間体である二種類のエポ キシド化合物(18)又は(19)を選択的に生成し,さらに,各エポキシド化合 物のエポキシ基を開環することにより図9の右下に図示される2種類のステロイド 化合物を製造し,最後に,各ステロイド化合物を光照射及び熱異性化して,それぞ れから最終目的物である上記予想代謝物(12)又は(13)を生成するという一\n連の工程である。原告らの主張1)は,この一連の工程のうち終盤の,中間体(前駆 体)としてエポキシド化合物を経由するという点のみを取り出して,そのエポキシ ド化合物を得るまでの工程は,甲4発明1とは全く違うものに変更するというもの であるから,甲4発明1の一連の工程のうち,特にエポキシド化合物を経由すると いう点に着目するという技術的着想が必要である(仮に,この甲4発明1をマキサ カルシトールの合成にも応用しようとするのであれば,甲4発明1の試薬を,4− ブロモ−2−メチル−テトラヒドロピラニルオキシ−2−ブテンに代えて,マキサ カルシトールの側鎖にとって余分なテトラヒドロピラニルオキシ基〔OTHP基〕 のない下図の4−ブロモ−2−メチル−2−ブテン(臭化プレニル)を用い,それ 以外は,甲4発明1と同様の一連の側鎖導入工程,エポキシ化工程,エポキシ基の 開環工程を経る製造方法に想到することが自然である。)。 甲第4号証記載の試薬 4−ブロモ−2−メチル−2−ブテン この点,甲第4号証には,図9の一連の工程が,特にエポキシド化合物を経由す る点に着目したものであることを示唆する記載はなく,むしろエポキシド化合物は, 26位が水酸化された側鎖末端の立体配置構造が異なる2種類のマキサカルシトー\nルの予想代謝物(12)又は(13)を選択的に製造するという目的のために,香\n月−シャープレス反応を採用した結果,工程中において生成されることとなったも のにすぎないものと理解される。また,甲第4号証には,図9の合成方法によって マキサカルシトールの予想代謝物が高収率で得られたことが記載されているのみで,\n問題点の記載もなく,甲4発明1の一連の工程の改良(変更)をする際に,どの点 は変更する必要がなく,どの点を改良すべきかを示唆する記載もない(なお,仮に 改良すべき点として工程数を取り上げたとしても,側鎖導入工程,エポキシ化工程, エポキシ基の開環工程のいずれを短縮すべきなのかについての示唆もなく,二重結 合からエポキシ化を経由せず直接水酸化するという選択肢なども想定は可能であ\nる。)。 そうすると,当業者が,仮に甲第4号証の図9のマキサカルシトールの予想代謝\n物(又はその前駆体となるステロイド化合物)とマキサカルシトールの側鎖の類似 性から,甲4発明1をマキサカルシトールの合成に応用することを想到し得たとし ても,その際に,一連の工程のうち,特にエポキシド化合物を経由するという点に 着目して,最終工程であるエポキシド化合物のエポキシ基を開環する工程の方を変 更せずに,その前段階である側鎖導入工程とエポキシ化工程は変更することを前提 として,マキサカルシトールの前駆体となるエポキシド化合物を製造しようとする ことを,当業者が容易に着想することができたとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2016.03.30
平成27(行ケ)10113 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月24日 知的財産高等裁判所
(ア) 甲10には,タダラフィルは,PDE5阻害剤であって,ヒトの勃 起機能不全の処置に有用であること(前記(2)ア(ア)ないし(カ),(ケ), (コ)),その用量について,平均的な成人患者(70kg)に対して1 日当たり,概ね0.5〜800mgの範囲であり,個々の錠剤又はカプ セル剤は,1日当たり単回又は数回,単回投与又は反復投与のため,好 適な医薬上容認できる賦形剤又は担体中に0.2〜400mgの有効成 分を含有するものであることが記載され(前記(2)ア(オ)),さらに,具 体的に,タダラフィルを50mg含む錠剤及びカプセルの組成例(前記 (2)ア(キ),(ク))が記載されている。 また,「実際には,医師は,個々の患者に最も適している実際の投与 計画を決定するが,それは特定の患者の年齢,体重および応答によって 変化する。上記の投与量は,平均的な場合の例であり,より高い又は低 い用量範囲が有益であるような個々の事例が存在するかもしれないが, いずれも本発明の範囲内である。」(前記(2)ア(オ))と,実際の患者に 投与する場合には,医者が最も好適と考えられる投与計画を決定するこ とも記載されている。 さらに,タダラフィルを用いたインビトロ試験において,PDE5阻 害作用につき,IC50が2nMであったことが記載されている(前記(2) ア(コ))。
(イ) 前記(ア)の記載に接した当業者であれば,甲10発明に係るタダラ フィルにつき,平均的な成人患者(70kg)に対して1日当たり,概 ね0.5〜800mgの範囲において,ヒトの勃起機能不全の処置に有\n用であり,具体的には50mgのタダラフィルを含む錠剤ないしはカプ セルが一例として考えられること,もっとも,実際の患者に投与する場 合には,好適と考えられる投与計画を決定する必要があることを理解す ると認められるところ,タダラフィルと同様にPDE5阻害作用を有す るシルデナフィルにおいて,ヒトに投与した際,PDE5を阻害するこ とによる副作用が生じることが本件優先日当時の技術常識であったこと から(前記イ(ウ)),甲10のタダラフィルを実際に患者に投与するに 当たっても,同様の副作用が生じるおそれがあることは容易に認識でき たものといえる。そして,薬効を維持しつつ副作用を低減させることは 医薬品における当然の課題であるから,これらの課題を踏まえて上記の 用量の範囲内において投与計画を決定する必要があることを認識するも のと認められる。そうすると,そのような当業者において,前記アの技 術常識を踏まえ,甲10に記載された用量の下限値である0.5mgか ら段階的に量を増やしながら臨床試験を行って,最小の副作用の下で最 大の薬効・薬理効果が得られるような投与計画の検討を行うことは,当 業者が格別の創意工夫を要することなく,通常行う事項であると認めら れる。 加えて,前記(ア)のとおり,甲10のタダラフィルに関するインビト ロ試験の結果によれば,タダラフィルのPDE5阻害作用はシルデナフ ィル(前記イ(ア))に比べ強いことが示されているのであるから,タダ ラフィルが,インビトロ試験と同様にインビボ試験である臨床試験にお いても,強いPDE5阻害作用を発揮する可能性を考慮に入れて,タダ\nラフィルの用量としてシルデナフィルの用量である10mg〜50mg (前記イ(イ))及びそれよりも若干低い用量を検討することも,当業者 において容易に行い得ることである。 以上によれば,甲10発明について,適切な臨床における有用性を評 価するために臨床試験を行い,最小の副作用の下で最大の薬効・薬理効 果が得られるような範囲として,相違点1に係る範囲を設定することは, 当業者が容易に想到することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ア) 被告は,経口投与された医薬化合物が,作用部位でどの程度の濃度 になるかを左右する薬物動態は,様々なファクターに影響され,これら のファクターは個々の医薬化合物によって様々に異なるとともに,各フ ァクターによる影響は総合的に生体に作用するものであるから,作用部 位において当該化合物が適切な濃度になるために必要な投与量は,ヒト における臨床試験を経て初めて設定され得るものであることは,医薬分 野における技術常識であり,経口投与する際の適切な用量は,インビト ロ試験での活性でのみ決定できるものではないし,ある医薬化合物の適 切な用量を,薬物動態が異なる全く別の化合物の用量を参考にして決定 することなどできないことも,医薬分野における技術常識である旨主張 する。 確かに,実際にヒトに対して薬物を経口投与する際における適切な用 量を決定するに当たっては,インビトロ試験での活性でのみ決定できる ものではなく,最終的にはヒトにおける臨床試験を経て決定されるもの であることは被告の主張するとおりである。 しかしながら,ヒトに対する適切な用法・用量を決定することに関し, 臨床試験においては,前記ア(ウ)のとおり,非臨床試験での全成績を詳 細に検討し,同薬効,類似構造薬に関する従来の知識,経験をも加味し\nて決定されるものとされている以上,タダラフィルと同様にPDE5阻 害作用を有するシルデナフィルの用量や,タダラフィルのインビトロ試 験データを参考にすることも,当業者が当然行うことと認められる。こ の点につき,タダラフィルの用量の検討に当たり,シルデナフィルは参 考にできないほど薬物動態が異なるという知見が存在することをうかが わせる証拠もない。そして,医薬品の開発は,インビトロ試験で有用な 薬理効果が確認された化合物について,動物試験,さらにはヒトに対す る臨床試験を行い(甲24参照),最適な用量が決定されるものである が,この過程を経ること自体は,ヒトに医薬品を投与する際の適切な用 量を決定するに当たって通常想定されることであって,当業者が容易に なし得ることであるから,これらを行う必要があったことを根拠として, 医薬品の用量・用法に関する発明につき容易想到性を否定することはで きない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2016.03.30
平成27(行ケ)10203 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年3月24日 知的財産高等裁判所
ア 本件使用商標1は,別掲1のとおり,最上段に「Rubotan」の欧 文字,その下段に「LINE」の欧文字,さらに,その下段に「LIQU ID」の欧文字,「ルボタン」の片仮名文字及び「ライン」の片仮名文字 を三段に配してなる五段の標章である。
上段二段の「Rubotan」及び「LINE」の欧文字は,下段三段 の「LIQUID」,「ルボタン」及び「ライン」よりも文字が大きいこ と,「LIQUID」の下部の「ルボタン」及び「ライン」の片仮名文字 は,同じ大きさ,同じ書体でまとまりよく併記されていることからすると, 「ルボタン」及び「ライン」の片仮名文字は,「Rubotan」及び 「LINE」の欧文字の表音を示したものとして,本件使用商標1から\n「ルボタンライン」の称呼が自然に生じるものと認められる。「LIQU ID」の欧文字は,「液状」の意味を有し,本件使用商品が液状であるこ とを表示したものと理解することができ,しかも,上段二段の「Rubo\ntan」及び「LINE」の欧文字よりも文字が小さいことからすると, 出所識別標識としての機能は弱いものといえる。\n一方で,「Rubotan」の欧文字と「LINE」の欧文字は,上下 2段にまとまりよく併記されており,「Rubotan」の欧文字は筆書 き風の書体であり,「LINE」の欧文字は「Rubotan」の欧文字 よりもやや文字が大きいが,「Rubotan」の欧文字はゴシック体の 「LINE」の欧文字とは異なる筆書き風の書体であることからすると, 外観上,いずれかが顕著に際立っているということはできない。 加えて,本件使用商品は,販売名を「ルボタン ライン」とする「アイ ライナー」であり(前記(1)),本件使用商品の宣伝広告においては,本 件商品の画像とともに「ルボタンライン」,「ルボタンライン リキッド アイライナー」,「ルボタンアイライナー」などと表記され(甲22ない\nし27),本件証拠上,本件使用商品について,「LINE」の部分のみ をその出所の識別標識として使用していた事情は認められない。
イ 以上を総合すると,本件使用商標1の構成中の「Rubotan」及び\n「LINE」の欧文字は,分離して観察することが取引上不自然であると 思われるほど不可分的に結合しているものではないが,需要者,取引者に おいては,ひとまとまりの表示として認識するものと認められるから,\n「LINE」の欧文字部分が独立して自他商品識別標識として機能し得る\nものということはできない。 したがって,「LINE」の欧文字及びその表音を示した「ライン」の\n片仮名文字が,本件使用商標1の要部に当たるとの原告の主張は採用する ことができない。
ウ この点に関し,原告は,化粧品業界においては,書体,大きさ,段等を 異にする2以上の構成要素からなる商標については,それぞれの構\成要素 について商標登録を受けて使用するのが一般的であるという取引の実情が あり,このような取引の実情を考慮すると,「LINE」の欧文字が本件 使用商標1の要部に当たる旨主張する。 しかしながら,個々の商標の要部をどのように認定するかは,需要者, 取引者の認識等を前提に個別的に検討すべき問題であり,原告が主張する ような取引の実情があるからといって直ちに「LINE」の欧文字が本件 使用商標1の要部に当たることの根拠となるものではない。 したがって,原告の上記主張は理由がない。 エ 以上のとおり,本件使用商標1の構成中の「LINE」の欧文字及び\n「ライン」の片仮名文字は本件使用商標1の要部に当たるものと認められ ないから,本件使用商標1は本件商標と社会通念上同一と認められる商標 であるとの原告の主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。
(3) 本件使用商標2と本件商標の社会通念上同一性について
原告は,要証期間内に,別掲2のとおり,本件使用商品を6個梱包するた めの包装用容器(本件包装用箱)に,「 」の片仮名文字,その 下段にゴシック体で大きく表された「ライン」の片仮名文字を表\示して使用 していたものであり,「ライン」の片仮名文字の標章(本件使用商標2)は, 本件商標と社会通念上同一性のある商標であるから,原告又は通常使用権者 であるエリザベスは,要証期間内に,本件商標と社会通念上同一と認められ る商標(本件使用商標2)を本件使用商品に使用した旨主張する。 しかしながら,前記(2)ア認定のとおり,本件使用商品は,販売名を「ル ボタン ライン」とする「アイライナー」であり,本件使用商品の宣伝広告 においては,本件商品の画像とともに「ルボタンライン」,「ルボタンライ ン リキッドアイライナー」,「ルボタンアイライナー」などと表記され,\n本件証拠上,本件使用商品について,本件使用商標1の構成中の「LIN\nE」の部分のみをその出所の識別標識として使用していた事情は認められな いこと,本件包装用箱は,本件使用商品を6個梱包するための包装用容器で あること(甲95)に照らすと,本件包装用箱に接した需要者,取引者は, 本件包装用箱に付された別掲2の「ルボタン」及び「ライン」の片仮名文字 を,ひとまとまりの標章として認識し,上記標章から「ルボタンライン」の 称呼が自然に生じるものと認められるから,「ライン」の片仮名文字のみが 独立して自他商品識別標識として機能し得るものということはできない。\n
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2016.03.30
平成27(ワ)27570 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月17日 東京地方裁判所
ア 本件明細書には要旨以下の記載がある。(甲2) 従来の車両用ルーフアンテナは,カバー部材内部に配設される電子 部品に対する防水対策のため,カバー部材の底面開口をボトムプレー トでふさぐとともに該ボトムプレートの周囲を覆うガスケットを配置 するなどして密閉性を確保していた。しかし,防水対策を施すために は多くの部品及びその部品加工の精度を高める必要があり高価となる。 また,内部気圧が低くなると隙間から雨水や洗浄水が浸入するおそれ があり,いったん内部に水分が侵入すると施された防水対策のために 逆に排水されにくく,カバー部材内部の湿度が高まって電子部品の破 壊,アンテナケーブルの腐食などの問題が生じていた。(背景技術。 段落【0002】〜【0004】) 本件発明は,上記問題点を解決するため,防水対策の必要がなく構\n成が簡易で部品点数が少ない安価な車両用ルーフアンテナを提供する ことを目的とする。(発明が解決しようとする課題。段落【000 5】) 本件発明では,コイルアンテナを保持する保持筒をカバーの天井部 の底面開口より上部に位置する下端部が,カバーとルーフパネルとの 隙間から浸入しルーフパネルに沿ってカバー内を流れる雨水等と接触 することがないから,カバー内部を密閉する防水対策の必要がない。 (発明の効果。段落【0009】) カバーの上面には突出部が一体成形され,該突出部の内部には保持 筒部が下向きに一体成形され,突出部の内面壁の両側にはブースター アンプ等を係止する係止爪が一体成形される。保持筒部にはスパイラ ル式のコイルアンテナの上端部が挿入されて保持され,該アンテナの 下端はカバーの底面開口よりも上部に位置する。(実施例。段落【0 013】,【0014】,図2,4)
イ 原告は,本件の特許出願手続において,当初,スパイラル式のコイル アンテナを用いる場合にその上端部を保持する保持筒はカバーの天井部か ら下向きに一体成形されるものであることを特許請求の範囲の請求項の一 つとしており,当初の明細書及び図面にも保持筒がカバーと一体成形され る構成以外の構\成は開示されていない。(乙1の1〜4) ウ 被告製品の短軸アンテナ素子はサイズが小さくコイルの巻数が少ない ため,それのみでは車両にあらかじめ設置されているポールアンテナに比 し受信感度が低く電気特性の良好な帯域幅も少ない。これを補うため,ア ンテナカバー上部の形状に合わせて形成した広面積の金属板からなる平板 アンテナ素子を短軸アンテナ素子に通電可能に接続することで,上記ポー\nルアンテナと同程度の受信感度を確保している。(甲10) 以上認定の事実に基づいて検討すると,本件発明は,カバーと一体成形 するという構成により,簡易な構\成で部品点数を少なくするという作用効 果を奏するものということができる。これに対し,被告製品のアンテナ部 は,いずれも平板アンテナ素子と短軸アンテナ素子をネジ止めにより通電 可能に接続した複合体であり,これを別部品であるアンテナカバーに接着\n剤で固定するため,アンテナカバー及びコイル以外に少なくとも金属棒及 び絶縁体(短軸アンテナ素子の構成部品),アンテナカバー上部の形状に\n合わせて形成した金属板(平板アンテナ素子)並びに短軸アンテナ素子と 平板アンテナ素子を接続するためのネジを要する。このように被告製品は, 本件発明のカバー,保持筒及びアンテナコイルに代えて相当多数の部品を 要しその構成も複雑であるから,本件発明と同一の作用効果を奏するとい\nうことはできない。 したがって,その余の要件について判断するまでもなく,構成要件C及\nびDについての均等侵害は成立しない。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第2要件(置換可能性)
>> ピックアップ対象
2016.03.30
平成26(ワ)20422 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月17日 東京地方裁判所
本件発明の「押付部材」に対応する被告製品中の「コマ」は,別紙被告ポゴ ピン断面図のとおり,球形ではなく,一部に球状の面を有するにとどまる。被 告が押付部材は球に限られるので被告製品は構成要件D2を充足しない旨主張\nするのに対し,原告は押付部材の一部(プランジャーピンの傾斜凹部に押圧さ れる部分)が球状の面であれば足りる旨主張するので,以下,検討する。 (1) まず,特許請求の範囲の記載をみるに,本件発明は,コイルバネで付勢し てプランジャーピンを突出させる接触端子に関するものであり(構成要件A\n〜C),コイルバネがプランジャーピンを直接押圧するのではなく,コイル バネとプランジャーピンの間に「押付部材」が介在し,これがコイルバネか ら付勢を受けて,その「球状面からなる球状部」がプランジャーピンの傾斜 凹部を押圧することに特徴がある(構成要件D1〜3)。\nこの「押付部材」という語は当該部材が果たす機能をそのまま記述したも\nのであるところ,その形状に関しては,プランジャーピンの傾斜凹部に押圧 される部分が「球状面からなる球状部」であるとされるのみであり,それ以 外の部分(コイルバネから付勢される部分,コイルバネ側とプランジャーピ ン側の中間部分)の形状については特許請求の範囲に何ら記載がない。そう すると,上記押圧される部分が球状に丸くなっていればそれ以外の部分はい かなる形状でもよいと解する余地がある。他方,押付部材の形状は,上記機 能を果たし得るものに限定されると考えられる上,同機能\\を果たすものであ ればいかなる形状の部材でも本件発明の技術的範囲に含まれるとすることは, 現に発明をして明細書に開示した範囲で保護を与えるという特許制度の趣旨 に反しかねない。そこで,特許請求の範囲に記載された「押付部材」の語の 意義を解釈するため,本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明の記載及び図 面を考慮することとする。
(2) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,「押付部材」との語は一 切用いられていない。本件発明の接触端子においてプランジャーピンとコイ ルバネの間に介在する部材として開示されているのは「絶縁球」のみであり, 図面に示されたのも球のみである。 すなわち,本件発明は,背景技術として,コイルバネが直接プランジャー ピンに触れるとコイルバネに電流が流れて焼き切れてしまうので,プランジ ャーピンとコイルバネの間に絶縁球を介在させた接触端子が存在したことを 前提に(段落【0002】〜【0004】),比較的大きな電流を流し得る接 触端子を提供することを目的として(同【0008】),プランジャーピンの 大径部(コイルバネ側)の端部を切削して袋孔を形成し,その底部を円錐面 とするとともに,円錐の中心軸とプランジャーピンの中心軸をオフセットさ せることによって,プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周 面に強く押し付け,確実に電流を流すことができるようにしたものである (同【0009】,【0013】〜【0015】)。そして,実施例及び参考例 をみても,押付部材に相当する部材としては「絶縁球」のみが記載されてい る(同【0024】〜【0030】,【0032】,【0036】,【0039】 〜【0042】,【図2】,【図4】,【図6】)。 以上のとおり,押付部材として本件明細書に開示されているのは球のみで あり,これと異なる形状の押付部材があり得ることを示唆する記載は見当た らない。そうすると,本件明細書の記載を考慮すると,本件発明における押 付部材の形状は球に限られると解するのが相当である。
(3)さらに,本件特許の出願経過についてみるに,後掲の証拠及び弁論の全趣 旨によれば,1)本件特許は,特願2011−192407号を優先権の基礎 とする特願2011−271985号(原出願)から分割出願されたもので あること(甲2),2)上記優先権の基礎とされた出願及び原出願は,いずれ も名称を「接触端子」とする発明に関するものであり,特許請求の範囲,発 明の詳細な説明及び図面を通じ,プランジャーピンとコイルバネの間に介在 する部材として記載されているのは「絶縁球」のみであること(乙13,1 4),3)本件特許は平成25年4月19日に分割出願されたものであり,そ の特許請求の範囲に,プランジャーピンとコイルバネの間に「押付部材」を 介在させる旨記載されたこと(乙15),4)原告は,同年10月11日,押 付部材に係る特許請求の範囲の記載を「少なくとも一部に球状面を有する押 付部材の球状部」と補正したこと(乙17),5)これに対し,同月25日, 特許法36条6項1号違反を理由1(発明の詳細な説明には押圧部材に絶縁 球を用いることが記載される一方,請求項1には絶縁性を有しない押圧部材 が記載されていること),同法29条1項3号及び2項の違反を理由2及び 3(原出願に「押付部材」として記載されていたのは「絶縁球」のみであり, これを「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」とすることは適法な分 割出願でないので,請求項1記載の発明は原出願の公開特許公報により新規 性又は進歩性を欠くこと)とする拒絶理由通知が発せられたこと(乙4), 6)原告は,同年11月8日,上記4)の補正後の特許請求の範囲の記載を「押 付部材の球状面からなる球状部」と補正する旨の手続補正書と,絶縁性を有 しない押付部材でも本件発明の効果を奏するので,発明の詳細な説明に記載 されたものといえる旨の意見書を提出したこと(乙5,6),7)同月27日 に特許査定がされたこと(乙19),以上の事実が認められる。 上記事実関係によれば,本件発明の「押付部材」は,少なくとも一部に球 状面を有するものでは足りず,その全体が球であるものに限られるというこ とができる(仮に,一部にのみ球状面を有するものが含まれるとすれば,本 件特許は違法な分割出願によるものとして新規性欠如の無効理由を有するこ とが明らかである。)。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.03.30
平成26(ワ)9945 特許権者確認等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月17日 大阪地方裁判所
以上に認定した原告とP3社との合意内容(請求原因(4)の事実)及び原告と被告 との合意内容(請求原因(5)の事実)によれば,出願人名義を被告に変更した当時, 原告が本件発明に係る特許を受ける権利を有していたと認められ,その後,請求原 因(6)のとおり,本件特許権は,本件出願について特許法所定の手続を経て,設定の 登録がされたのであるから,本件特許権は,原告が有していた特許を受ける権利と 連続性を有し,それが変形したものであると評価することができる。 そうすると,被告は,法律上の原因なくして,本件特許権を取得したという利益 を得ているといえるから,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づいて, 本件特許権について移転登録手続を請求することができる(最高裁判所平成13年 6月12日判決・民集55巻4号793頁参照。なお,本件では,平成23年法律 第63号による改正後の特許法74条は適用されない。)。
2016.03.26
平成27(ネ)10014 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
この点,特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして,\n出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり,\nしたがって,出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとして\nも,そのことのみを理由として,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載し\nなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということはできな い。
なぜなら,1)上記のとおり,特許発明の実質的価値は,特許請求の範囲に記載さ れた構成以外の構\成であっても,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質\n的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び,その理は, 出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ,出 願時に容易に想到することができたことのみを理由として,一律に均等の主張を許 さないこととすれば,特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を,上記と異なるものとす ることとなる。また,2)出願人は,その発明を明細書に記載してこれを一般に開示 した上で,特許請求の範囲において,その排他的独占権の範囲を明示すべきもので あることからすると,特許請求の範囲については,本来,特許法36条5項,同条 6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を充たしながら,明細 書に開示された発明の範囲内で,過不足なくこれを記載すべきである。しかし,先 願主義の下においては,出願人は,限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを 作成し,これを出願しなければならないことを考慮すれば,出願人に対して,限ら れた時間内に,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲\nとこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される 場合がある。これに対し,特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者 は,当該特許の有効期間中に,特許発明の本質的部分を備えながら,その一部が特 許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを,特許請求の範囲と明細書等の記載か ら容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法理 は,特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行 使を容易に免れるものとすると,社会一般の発明への意欲が減殺され,発明の保護, 奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず,社会 正義に反し,衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって,上記 に述べた状況等に照らすと,出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到す\nることができたとしても,そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外と することは相当ではない。
(イ) もっとも,このような場合であっても,出願人が,出願時に,特許請求の 範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構\成中の異なる部分に代替する ものとして認識していたものと客観的,外形的にみて認められるとき,例えば,出 願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができる\nときや,出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構\成による 発明を記載しているときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しな\nかったことは,第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。 なぜなら,上記のような場合には,特許権者の側において,特許請求の範囲を記 載する際に,当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの,すなわち,\n当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的\nにそのように解されるような行動をとったものと理解することができ,そのような 理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから,特許権者が後にこれに反し て当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは,禁反言の法理\nに照らして許されないからである。
イ 控訴人らの主張について
(ア) 控訴人らは,化学分野の発明では,特許請求の範囲が客観的かつ明瞭な表\n現で規定されており,第三者にはその範囲以外に権利が拡張されることはないとの 信頼が生じるから,当該信頼は保護されるべきであると主張する。しかし,前記の とおり,均等による権利は,特許請求の範囲の文言上規定された範囲以外であって も,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者\nが容易に想到することができる技術に及び,第三者はこれを予期すべきであり,禁\n反言の法理に照らし均等の主張が許されないのは,上記特段の事情がある場合に限 られるのであって,化学分野の発明であることや,特許請求の範囲が文言上明確で あることは,それ自体では「特段の事情」として均等の成立を否定する理由とはな り得ないから,控訴人らの主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.03.25
平成27(行ケ)10143 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月16日 知的財産高等裁判所
原告は,本願発明は,較正液の加熱前の溶液温度のばらつきによって生じる目標 温度までの加熱時間のばらつきをなくすものであるとし,これに応じて,被告は, 本願発明にはそのような作用効果はないと反論する。 そこで,検討するに,本願発明は,較正液導入前にセンサ部の温度に応じてセン サ部を予熱するものであり,少なくとも,センサ部の温度差により生じる加熱時間\nの差は解消される。ただし,本願発明は,実際に導入された較正液の溶液温度の温 度差により,更に分析時までの加熱時間に差が生じることの解消を目的とするもの ではない。原告の上記主張は,前者の趣旨をいうものと解され,本願発明は,較正 液導入時におけるセンサ部の温度差により生じる加熱時間の差の解消という効果を 奏するものであるから,被告の上記主張は,採用することができない。 また,被告は,引用発明2は溶液の有無に関係なく温度制御を開始するものであ り,引用発明に引用発明2の加熱動作を適用すれば,予熱後に較正をする態様を採\n用すると主張する。 しかしながら,被告が上記に主張するように,引用発明2は,使い捨てカートリ ッジが挿入されると自動的に温度制御システムが起動するものであるとしても,引 用例2は,試料を電気化学セル中に入れずに温度制御を開始し,一定の加熱がなされ た後に当該セル中に試料溶液を導入するような態様を開示するものではなく,また, そのような例外的態様が示唆されているわけでもない。したがって,引用発明に引 用発明2の加熱動作を適用しても,相違点2に係る本願発明の構成には至らない。\n被告の上記主張は,採用することができない。 なお,被告は,当審において,引用発明2に加えて周知例(乙2〜7)を提出し, 較正に先立って予熱を行う態様が周知である旨の主張立証をするが,実質的に審決\nが全く取り上げていない周知技術を新たに追加するものであって,許されない。し かも,上記各文献からは,センサ部の温度にかかわらず較正前に自動的に一定時間 の予熱を行う態様のものしか認められず,センサ部の温度によって較正前に予\熱を 行うかどうかを選択する態様のものが周知の技術であったとは認めるに足りない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2016.03.25
平成27(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月10日 知的財産高等裁判所
上記(2)によれば,本件当初明細書には,第一の割り溝をエッチングにより 形成する際に,所定の形状のマスクを形成すること(段落【0008】,【0018】 【0019】),図4は図1に示すウエハーを窒化物半導体層側からみた平面図であ り,図1及び図4では,第一の割り溝は,p型層3をエッチングして,n型層2を 露出するように形成されていること(段落【0012】,【0018】,【0019】),さらに,図4では,p型層3の隅部は半弧状に切り欠いた形状となっており,この 切り欠いた部分にn層の電極を形成できること(段落【0016】)が記載されてい る。上記の切り欠いた部分はn層の電極を形成するためのものであるから,n型層 2が露出していることも技術的に明らかであるといえるものの,本件当初明細書に は,第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するのか否かについては,明示的 には記載されていないことが認められる。 しかし,当業者であれば,半導体素子の形成に際して,工程数を削減することは当然に考慮すべき事項であるところ,第一の割り溝と切り欠いた部分はともにエッ チングによりp型層3を除去してn型層2を露出させることにより形成されるもの であるから,同時に形成することが可能であり,本件当初明細書の記載に照らして\nも,p型層3表面を基準とした両者の深さを異なるものにする必要性,すなわち,\n両者を別工程で形成する必要性があるとは認められない。 そして,本件当初明細書の「図1に示すように第一の割り溝を形成すれば,第一 の割り溝の表面に電極を形成することもできる」(【0027】)との記載も併せ考慮\nすれば,本件当初明細書には,p型層3のエッチングにより第一の割り溝を形成す る際に,p型層3上に形成するマスクの形状を矩形の隅部が半弧状に切り欠いた形 状として,第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成することも当業者にとって 自明な事項であり記載されているに等しいものと認められる。 なお,本件当初明細書には「図4・・・では,p型層3を予めn層の電極が形成\nできる線幅でエッチングして,第一の割り溝11を形成し,さらにp型層3の隅部 を半弧状に切り欠いた形状としており,」(【0016】)との記載があり,「さらに という文言から,第一の割り溝を形成した後に切り欠いた部分を形成するという解 釈の余地もないわけではない。しかし,本件当初明細書の前記記載に照らせば,上 記の「さらに」は,経時的な順序を意味するのではないと解されるから,上記「さ らに」との記載があることは,第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するこ とが自明な事項であるとの認定判断を左右するものではないといえる。 したがって,本件特許の請求項1及び請求項1を引用する請求項2ないし4に「前 記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形 状で線状にエッチングにより形成すると共に,第一の割り溝の一部に電極が形成で きる平面を形成する工程と,」という記載を追加する本件補正は,願書に最初に添付 した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものと認められる。 なお,審決は,本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内のものである としたものの,これが旧法53条1項及び同法41条ではなく,現行特許法17条 の2第3項の規定する要件を満たすとの判断をしていると解され,法令の適用を誤 ったものといわざるを得ない。 しかし,同項は,「第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について 補正するときは,・・・願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・ に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定するところ,出願当 初の明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより,補正 が当業者によって,導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導 入しないものであるときは,当該補正は,明細書等に記載した事項の範囲内におい てするものということができ,補正事項が明細書等に明示的に記載されている場合 や,その記載から自明である事項である場合には,そのような補正は,特段の事情 のない限り,新たな技術的事項を導入しないものであると認められ,明細書等に記 載された範囲内においてするものであるということができると解される。 これに対し,旧法41条における明細書等に記載した事項の範囲内についても, 同記載の範囲及び出願時において当業者が当初明細書の記載からみて自明な事項を 含むものと解されるから,現行特許法17条の2第3項の解釈ともこの点において 実質的に異なるものではないということができる。 そして,本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものと 認められることは前記認定のとおりである。 以上によれば,審決は,法令の適用を誤ったものの,旧法を適用したとしても判 断内容自体には誤りはないから,本件補正が補正の規定の要件を満たすとの結論に おいても誤りはないといえる。 したがって,審決は,その結論に影響を及ぼす違法があるとまではいえないから, これを取り消すべきものということはできない。
2016.03.25
平成27(行ケ)10105 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月9日 知的財産高等裁判所
(2) まず,「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」中の「からなる」との 文言について,「から」という格助詞と「なる(成る)」という動詞とから成り立つ もので,「から」は,直前に記載されたものが素材,材料,構成要素となることを示\nす語であり,「なる(成る)」は,成立する,構成するを意味する語であることは明\nらかである。そうすると,「Aからなる」ものは,Aを「素材・材料・構成要素」と\nして「成立する・構成されている」ものを意味すると解される。\nしたがって,「(A)からなる」という場合には,Aを必須の構成要素とすること\nは明確であるものの,それ以上に,Aのみで構成され,他の成分を含まないものか,\nAのほかに他の成分を許容するか否かについて規定するものではなく,「Aのみから なる」場合をも包含する概念であると認められ,このこと自体に当事者間に実質的 な争いはない。 そして,例えば,含有する金属が一部異なると,特質が全く異なるものとなる一 部の合金における分野等と異なり,医薬液体製剤については,pHの調整や,安定 性,保存性を高めるために何らかの添加剤が含有される場合が多いことは,原告も 認めるとおり,周知のことである。 そうすると,明細書において,「からなる」の前に摘示された素材,構成要素以外\nの成分を排除することが明らかでない限り,「Aからなる」とは,Aを必須の構成要\n素とするものである以上に,他の成分については規定しておらず,単に「Aを含む」 ものがその技術範囲に含まれると理解することになるものと解され,また,他の成 分を排除するか否か規定していないからといって,「Aからなる」の語が,特段不明 確な用語と理解されるものでもない。 次に,本件明細書を見るに,その記載は,前記(1)のとおりであって,オキサリプ ラティヌムを水に溶解したオキサリプラティヌム水溶液を構成要素とする製剤であ\nることは明らかであるが,本件発明1の「オキサリプラティヌム水溶液」に他の成 分を含んではならないことを示す記載はなく,他の構成要素を含有することが排除\nされているとまではいえない。 したがって,当業者は,本件発明1は,「濃度が1ないし5mg/mlでpHが4. 5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液」を必須の構成要素とすることだけが\n特定された製剤であって,該製剤に他の構成要素が含まれることが排除されてはお\nらず,かつ,「医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含 量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のま まである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」に係 る発明と一義的に理解することが可能であるといえる。\nよって,本件発明1は明確であり,同様の理由により,本件発明2〜9も明確で ある。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,審決が,不純物や溶存酸素・窒素が許容された例の記載がある ことを本件発明が他の成分を許容する根拠の一つとしたことについて,本件明細書 の中に,これらが許容された例の記載があったとしても,それによって「からなる」 の意味が明確となるわけではなく,むしろ,発明の詳細な説明の記載を踏まえれば, 当業者は,「からなる」を,少なくとも,「酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もし くはその他の添加剤」を排除する意味と解することは極めて明確であるから,この 点を踏まえずに明確性を認めた審決は,誤りであると主張する。 確かに,医薬製剤において,通常,不純物がその製剤の構成要素とみなされると\nはいえないから,不純物に関する記載をもって,当該製剤が他の成分を排除するも のであるかどうかは判明するものでないとする点については,原告の主張するとお りである。 しかし,後記2において詳述するとおり,本件明細書を見ても,原告の主張する ように,本件発明が「酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくはその他の添加剤」 を排除することが明らかであるとはいえない。また,仮に,原告主張のように本件 明細書から,本件発明が,これら添加剤を排除することが明確であり,「オキサリプ ラティヌムの水溶液からなる」とは,オキサリプラティヌムと水のみから構成され\nる,すなわち,「オキサリプラティヌムの水溶液のみからなる」ことが明らかである とするならば,いずれにせよ,明確性要件を欠くことにはならない。
イ 次に,原告は,本件明細書には,「からなる」の意義を解釈するに当たり, 「酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくはその他の添加剤」を含んでいても安 定な製剤が得られることを示唆する記載はない旨主張する。 しかし,上記記載がないことが,上記添加物を排除することを意味するとはいえ ない上,前記のとおり,本件発明1には,「オキサリプラティヌムの水溶液」を構成\n要素とすることのみが規定されており,他の成分については規定されていないので あるから,原告主張の添加剤が含まれる例が記載されていないことは,明確性要件 を何ら左右するものではない。
ウ また,原告は,審決が,本件の国際出願におけるフランス語の原文を斟 酌しておらず,その結果,本件明細書の記載事項の判断を誤った旨主張する。 しかし,特許法184条の6第2項は,外国語特許出願に係る国際出願日におけ る明細書及び請求の範囲の翻訳文が,同法36条2項の規定により願書に添付して 提出した明細書及び特許請求の範囲とみなされる旨を規定しており,以降の審査に おいてすべて翻訳文を基準とすることが明らかにされている。したがって,本件発 明の明確性要件を判断する際に,外国語特許出願に係る国際出願日における特許請 求の範囲及び明細書の各翻訳文を考慮すれば足り,それらの翻訳文の記載から離れ て,本件の国際出願におけるフランス語の原文の記載を考慮することはできない。
エ さらに,原告は,拒絶理由通知に対する意見書(甲2)及び審判事件答 弁書(甲6)における被告の主張からみて,「からなる」が,酸性又はアルカリ性薬 剤,緩衝剤を排除する閉鎖的な意味で用いられていたとの解釈が可能であることが\n裏付けられると主張する。 しかし,特許法36条6項2号は,前記のとおり,特許請求の範囲が不明確とな る場合には,特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となって第三者に不測の 不利益を及ぼすことがあり得ることから,これを防止するために要求されるもので あり,あくまで明細書の記載要件である以上,その適否は,当該記載から客観的に 判断されるべきであって,出願経過や審判における対応を斟酌することは,かえっ て,特許が付与された権利範囲を不明確にするものといわざるを得ない。特許権の 行使場面において,その技術的範囲を判断する際に,出願経過等の事情を斟酌する ことはともかくとして,本件発明の明確性要件の判断をする際に,これらを考慮す ることは相当ではなく,原告の上記主張は採用できない。 オ 加えて,原告は,「からなる」が多義的であることを前提として,その解 釈に当たっては明細書を参酌することが必要であるが,本件明細書の記載を参酌し てもなお,「酸性またはアルカリ性薬剤,緩衝剤もしくはその他の添加剤」を含み得 るかどうかが確定できないがゆえに,特許請求の範囲が不明確である旨の主張もす る。 しかし,原告は,一方で,前記アのとおり,本件明細書の記載によれば,本件発 明に上記添加剤が含まれないことは明確であるとも述べており,その主張は一貫し ないものである。また,前記のとおり,「オキサリプラティヌムの水溶液からなる」 とは,「オキサリプラティヌム」と「水」を必須の構成要素として含むことを規定す\nるものであるが,その他の成分については何ら定めがない製剤と理解することがで きるのであるから,その他の成分について含有するかしないかを確定することは必 要ではなく,原告の主張は失当である。
2016.03.14
平成27(ネ)10104 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ア 均等侵害の第1要件は,特許請求の範囲に記載された構成と相手方が製造等をする製品又は用いる方法との異なる部分が特許発明の本質的部分でないことであ\nる。そして,特許発明における本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された構成のうち,当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部\n分であると解すべきである。
イ 本件各発明は,前記1(4)イのとおり,HMG−CoA還元酵素阻害剤として 高脂血症の治療に有用な,結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む 医薬組成物に関し,特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの 結晶性原薬を提供すること,同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題 とし,ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコ ントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態AないしCの 中で結晶形態Aが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというもので ある。 そうすると,特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶 性原薬を提供すること,同原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とす る本件各発明において,特定の結晶形態をとることが,上記課題の特徴的な解決手 段であるといえる。 そして,本件各明細書には,結晶形態AないしCの3種類の結晶形態は,水分が 同等で結晶形態が異なる形態であり,結晶形態B及びCは,「いずれも結晶形態A に特徴的な回折角10.40°,13.20°及び30.16°のピークが存在し ないことから,結晶多形であることが明らかにされる。」(本件明細書1【001 4】,本件明細書2【0015】)とあるように,CuKα放射線を使用して測定 した粉末X線回折図において,結晶形態Aに存在する3本のピークの回折角が存在 しないことによって,結晶形態Aと区別されるものであることが記載されているの みで,結晶形態B及びCに係る回折角(2θ)の数値,相対強度や粉末X線回折図 を含めその粉末X線回折パターンについての開示は一切なく,他方で,結晶形態A については,CuKα放射線を使用して測定した粉末X線回折パターンとして,別 紙本件明細書1図表目録2記載のとおりの数値が記載され,同目録3記載の【図1】の記載があるのみで,それ以上の特定はされておらず,結晶形態Aに係る回折角に\nついて,その数値に一定範囲の誤差が許容されることや15本のピークのうちの一 部のみによって結晶形態Aを特定することができることをうかがわせる記載も一切 存しない。 以上によれば,本件各発明において,構成要件C・C’に規定された15本のピークの回折角の数値は,本件各明細書において,本件各発明の課題の特徴的な解決\n手段である特定の結晶形態を,他の結晶形態,すなわち本件各発明の課題の解決手 段とはなり得ない結晶形態と画する唯一の構成として開示されたものであるということができる。\nしたがって,本件各発明において,構成要件C・C’に規定された15本のピークの回折角の数値は,本件各発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核\nをなす特徴的部分であるというべきである。
ウ そうすると,控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩 における15本のピークの回折角であるとする数値は,前記1(5)のとおり,原判決 別紙物件目録(1)記載のとおりであり,控訴人の特定する数値によったとしても,1 5本の全てが構成要件C・C’の回折角の数値と相違するのであるから,被控訴人製品は,本件各発明と課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的\n部分において相違していることになる。 以上によれば,被控訴人製品は,均等侵害の第1要件を充足しない。
(3) 均等侵害の第5要件について
ア 均等侵害の第5要件は,相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許発 明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるな どの特段の事情がないことである。
イ 前記1(3)のとおり,控訴人は,本件特許1の出願経過において,拒絶理由通 知を受け,構成要件Cの15本のピークの回折角の数値を挿入する平成23年11月29日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相\n当するものであることを表明した。また,控訴人は,本件特許2の出願経過においても,拒絶理由通知を受け,構\成要件C’の15本のピークの回折角の数値を挿入する平成25年3月8日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の 限定的減縮に相当するものであることを表明した。控訴人は,本件特許1の出願経過における拒絶理由通知において,1本のみのピ\nーク強度でしか特定されず,他のピークの特定がないので,公知文献に記載された 結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対 して,上記補正を行ったのであるから,15本のピークの回折角の数値をもって本 件発明1の結晶を特定したというほかない。 そして,本件特許2は,結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む 医薬組成物に関し,特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの 結晶性原薬を提供することを課題とし,ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に 含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上す ること及び結晶形態AないしCの中で結晶形態Aが医薬品の原薬として最も好まし いことを見いだした本件特許1を原出願とする分割出願であって,本件特許1に係 る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり,その出願 当初の特許請求の範囲の請求項1には,上記補正後の本件発明1の結晶と同じ15 本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。 以上によれば,本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は,本件各発明 の技術的範囲を,回折角の数値が15本全て一致する結晶に限定するものであると 解されるから,構成要件C・C’の15本のピークの回折角の数値と,全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は,本件各発明\nの特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。 したがって,被控訴人製品は,均等侵害の第5要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件(本質的要件)
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.03. 7
平成27(行ケ)10078 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月2日 知的財産高等裁判所
(ア) 前記(2)アのとおり,引用発明は,複数の加工具回転軸を備え,複数の砥石 によって眼鏡レンズを加工する装置を用いる従来の玉型加工の方法に,眼鏡レンズ を回転させないという構成を採用したものである。\nそして,前記(2)イのとおり,引用例には,加工具回転軸を1つとするシングルス ピンドル方式についての記載はなく,示唆もされていない。加工具回転軸が複数あ ること自体に起因して何らかの問題が発生する,又は,加工具回転軸を1つとする ことにより何らかの効果が期待できるなどといった,シングルスピンドル方式を採 用する動機付けにつながり得ることも何ら示されていない。
(イ) 加えて,前記(2)イのとおり,ダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置 は,加工具回転軸を1つとするシングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置に比 して,機械剛性が高く,加工時間も短いという利点を有するものと推認することが できるのに対し,シングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置がダブルスピンド ル方式の眼鏡レンズ加工装置に比して優位な点があることは,本件証拠上,認める に足りない。
(ウ) したがって,当業者において,本願出願当時,引用発明に係る一対の加工 具回転軸を備えたダブルスピンドル方式の眼鏡レンズの製造装置につき,あえて加 工具回転軸を1つとするシングルスピンドル方式の構成を採用することについては,\n動機付けを欠き,容易に想到し得ないというべきである。
(4) 相違点2の容易想到性について
ア 相違点2について
相違点2は,前記第2の3(2)ウ(イ)のとおり,レンズチャック軸と加工具回転軸 との軸間距離を変動させる軸間距離変動手段が,本願補正発明においては,レンズ チャック軸を加工具回転軸に向けて移動させるというものであるのに対し,引用発 明においては,一対の砥石軸を眼鏡レンズ駆動装置に固定された眼鏡レンズに向け て移動させるというものである点をいい,本願補正発明と引用発明との間に,この ような相違点が存在することは,当事者間に争いがない。 引用発明の砥石軸は,本願補正発明の加工具回転軸に相当し,また,引用発明の 眼鏡レンズは,本願補正発明のレンズチャック軸に相当する軸部材に保持されてい るものであるから,引用発明における上記軸間距離変動手段は,実質において,一 対の加工具回転軸をレンズチャック軸に向けて移動させるというものである。 よって,相違点2は,実質的には,軸間距離変動手段が,本願補正発明において は,レンズチャック軸を加工具回転軸に向けて移動させるというものであるのに対 し,引用発明においては,一対の加工具回転軸をレンズチャック軸に向けて移動さ せるというものである点をいうものと認められる。
イ 本願補正発明における軸間距離変動手段は,加工具回転軸が単数であること を前提とするものであり,加工具回転軸が複数の場合に同手段を採用することは, 事実上不可能である。\nしたがって,相違点2は,相違点1に係る加工具回転軸の個数差を前提とするも のということができ,相違点1に係る本願補正発明の構成が容易に想到し得ない以\n上,相違点2に係る本願補正発明の構成も容易に想到し得るものではない。
(5) 被告の主張について
ア 被告は,当業者において,引用例に記載されている「眼鏡レンズが砥石に当 接した直後から,眼鏡レンズには眼鏡レンズの回転を停止する方向に力が継続して 加わっている」(【0006】)という軸ずれの原因となる物理現象は,ダブルスピン ドル方式及びシングルスピンドル方式のいずれにおいても生じるものであることを 理解することができることを前提として,眼鏡レンズが回転していない状態で砥石 と当接させるという上記物理現象に対する引用発明の解決手段は,ダブルスピンド ル方式及びシングルスピンドル方式のいずれにおいても使用できるものであり,当 業者であれば,上記解決手段の適用対象が,いずれの方式の装置であるかにかかわ らず,軸ずれの課題を解決し得るものとして認識することができる旨主張する。 本件証拠上,加工具回転軸の個数と軸ずれとの間に何らかの関係があるものとは 認めるに足りず,したがって,たとえ,当業者において,上記解決手段がダブルス ピンドル方式及びシングルスピンドル方式のいずれにおいても引用発明の課題であ る軸ずれを防止し得る旨を認識したとしても,それは,引用発明の一対の加工具回 転軸を1個の加工具回転軸とすることには,つながらない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2016.03. 7
平成26(ワ)11616 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成28年2月26日 東京地方裁判所
そうすると,被告標章1からは,「ラクテンコーチョー」及び「コーチョー」のほか,「パラダイス ダイナシティ」及び「レジェンド オブ シャオ ロン ボー」という称呼が生じ得るものと解される。 この点に関して原告は,被告標章1は,図形及び文字により構成される標章であり,被告標章2は文字から成る標章であるところ,これらにおいては「楽天」及び「皇朝」の文字が大きく記載され,標章としての強い印象を与え,「楽」は「楽」の簡体字であるがこれを需要者において称呼することはできないから,被告標章1及び2の要部は「皇朝」の文字部分であり,「PARADISE DYNASTY」及び「LEGEND OF XIAO LONG BAO」の部分からは称呼が生じないから,被告標章1及び2からは「コーチョー」の称呼のみが生じる旨主張する。 しかし,被告標章1及び2において,「楽天」及び「皇朝」の黒い文字の間には湯気を上げた小籠包様の図形が茶色で表記されているものの,「楽天」と「皇朝」との間はそれほど離れておらず,「楽」の文字と「天」の文字,「皇」の文字と「朝」の文字の間隔とそれほど異ならず,\n一つのまとまりとしてみれること,「楽」が「楽」の崩し字として辞典類にも記載されていること,右下の落款様の部分は「楽天」と読むことが可能なこと,一般に,「楽天地」といえば「楽しさに満ちた天国のような土地」(広辞苑第6版2924頁)あるいは「楽園」(大辞林第3版2643頁)を意味するところ,「楽天皇朝」の文字部分と欧文字部分「PARADISE DYNASTY」との位置関係から,「楽天」が「PARADISE」に,「皇朝」が「DYNASTY」にそれぞれ対応していることが容易にうかがえることからすると,被告標章1及び2の漢字部分からは「ラクテンコーチョー」との称呼も生じ得るものと認めるのが相当である。
・・・・
前記(2)アのとおり,前提として,「皇朝」が「我が国の朝廷」との意味を有する普通名詞であることからすると,これを商品名である「小籠包」に付したとしても,もとよりその「皇朝」の部分の自他識別力は極めて弱いものというべきである。 そして,前記(2)イのとおり,被告店舗における「皇朝小籠包」の表示の使用方法は,被告店内におけるメニューに「皇朝小龍包」と表\示するものであるところ,被告店舗は,シンガポール発の小籠包専門店と宣伝されているとおり,小籠包をメニューの中心に据えた料理店であること,その他被告店舗の外観や,店内のメニュー等の記載内容からすれば,被告店舗内の小籠包のメニュー表示に「皇朝」との表\記をしても,それは被告店舗のメニューである小籠包を意味することは明らかであるから,被告店舗において供される「皇朝小籠包」につき,原告との出所の誤認を招来するものとは認められない。また,被告店舗で入手可能なリーフレット(甲6の2)においても,被告標章2が付されていること,「皇朝小籠包」の前に被告標章における「湯気を上げた小籠包様の図形」様の小さな図形が記載されていることを併せて見れば,「皇朝小籠包」との記載は,本来「楽天皇朝小籠包」と表\記すべきところをその一部を省略した表記とみることができ,前記(2)イのとおりのリーフレットのその他の記載内容からすると,被告店舗内で使用される限り,需要者である顧客は,「皇朝小籠包」との表示はあくまで被告店舗である「楽天皇朝」の「小籠包」の意味で使用されていると認識するにすぎないというべきであるから,原告との出所の誤認を招来するものとは認められない。\nさらに,前記(2)ウのとおり,原告の提出する証拠によっても,被告のウェブサイトには「皇朝小籠包」と表示するものはなく,その他原告との関連を伺わせる記載ないし表\示や,原告との関連を誤認したレストランガイド等の ウェブサイトの記載ないし表示も証拠上認められない。\n一方,原告は,前記(2)エのとおり,「皇朝」本店の名称を「明朝」と変更しているほか,同オのとおり,原告は「横浜中華街」ないし「中国料理世界チャンピオン」との表示と共に「皇朝」の文字を使用する場合が多く,原告を紹介するウェブサイトの記載もこれら「横浜中華街」ないし「中国料理世界チャンピオン」を強調するものとなっている。\n以上からすると,被告店舗において用いられた「皇朝小籠包」とのメニュー表示のうち,「皇朝」の部分そのものには顧客吸引力が認められず,「皇朝小籠包」との記載が被告店舗内で使用されている限り,当該標章の使用が被告店舗における売上げに全く寄与していないことは明らかであり,その使用によって原告に損害が発生しているものとは認められない。\nそうすると,原告は,被告に対し,法38条3項に基づく実施料相当額の損害を請求することができないというべきである。
2016.03. 7
平成27(ネ)10119 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成28年2月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原告らは,被告ウェブサイト(広告)では,まさしく削除請求を代行するとうた っており,非弁活動の広告がなされているものであるから,適法に任意削除請求が できないにもかかわらず,これが適法に可能であるように表\示しており,「役務の質, 内容」について消費者を誤認させる表示に当たる旨主張する。\n確かに,被告ウェブサイトには,原告らの主張する「削除代行サービス」「誹謗中 傷サイトを削除してきました」「専門スタッフが最速で誹謗中傷を完全消去いたしま す」「一括して削除代行を承ります」(甲1の1),「削除代行」「ネット削除の費用」 「掲示板の削除の料金」「スレッド(板)またはレス(書き込み)単位で削除いたし ます」「格安で掲示板を削除」との記載があり,その部分のみを取り出せば,被告が 顧客に代わって削除請求を代理するかのような表現がある。しかし,被告ウェブサ\nイトの表示を正確に理解するためには,原告らも認めるとおり,当該ウェブサイト\nの特定の文言のみならず,その他前後の文脈等も見る必要があるところ,トップペ ージにおける「ブログの削除」欄には,「当社では,ブログの削除代行も行っていま す。」との記載に引き続いて,「削除依頼をITの面からサポートし,解決いたしま す。」との記載(甲1の1),削除ページには,「ネット削除(削除依頼)のITサポ ート」との見出しや,「ネット削除申請サービス(技術サポート)」,との見出しがあ\nり,「ITやWEBの専門技術を生かし,削除依頼の手続きを最後までお手伝いしま す。」,「当社では,これまでの数千件以上の削除実績と経験をふまえ,最も効果的な 削除要請ができるよう,技術面からサポートいたします。」との記載(甲1の2), 相談ページには,「ITの知識も必要」「ネットの削除養成については法律知識だけ でなく,ITの知識や技術も必要になります。当社では,ITの面から削除要請を サポートしています。削除の方法が技術的に分からないようなときは,当社にご相 談下さい。」との記載(甲1の3)もある。これらによれば,原判決が述べるように, 被告が,顧客と顧客が削除を求める相手との関係でどのように関わるのかについて 明確でなく,技術的サポートの内容も具体的ではないものの,被告が顧客に代わっ て削除依頼を直接行ったり,法的助言を行ったりするものと理解することはできな い。そうすると,被告ウェブサイトが,本来,被告が適法に行うことができない法 律的な業務について,これを行うことが適法に可能であるように表\示したとまでは いうことができず,したがって,「役務の質,内容」について消費者を誤認させたと いうことはできない。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2016.03. 7
平成27(行ケ)10115 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年2月24日 知的財産高等裁判所
補正前発明は,請求項において「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを 有し」と特定され,「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けることが記載されると ともに,「前記発光素子から放射される光を入射する入射面と,前記入射面から入射 した光を反射する反射面と,前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射す る出射面」を「有する」ことが記載されているところ,この「前記発光素子から放 射される光を入射する入射面と,前記入射面から入射した光を反射する反射面と, 前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射面」は,本願明細書の 記載によれば,「光方向変換部」と呼ばれるものである。そうすると,「光方向変換 素子」中には,「光方向変換部」と「ホルダ片」を設ける部分が記載されているもの の,その「ホルダ片」を設ける部分の具体的形状が特定されていないものと解され る。一方,補正発明は,「光方向変換部」を明示するとともに,「光方向変換素子」 の具体的形状,ホルダ片を設ける態様などについて,請求項に記載のとおり「嵌合 部が形成されたケース部」に限定したものである。 そうすると,本件補正は,補正発明の「光方向変換素子」を前記のとおり規定す ることによって,補正発明を特定するために必要な事項を限定するものと認められ る。
イ 産業上の利用分野及び解決課題について
補正発明及び補正前発明は,いずれも,「光源モジュール」であり,両者の産業上 の利用分野は同一である。 また,前記1のとおり,補正発明及び補正前発明の解決しようとする課題は,光 方向の厳密な調整を不要とし,輝度ムラのない光源モジュールを提供することであ る。 したがって,補正発明及び補正前発明の解決しようとする課題は,同一であると 認められる。
ウ よって,本件補正は,補正前発明を特定するために必要な事項を限定す るものであって,補正前発明と補正発明の産業上の利用分野及び解決しようとする 課題は同一であるから,特許法17条の2第5項2号にいう「特許請求の範囲の減 縮」に該当し,これを目的要件違反とした審決の判断は,誤りである。
・・
被告は,本件補正によれば,補正発明は,「光方向変換部」(光学的機能を有する\nもの)により特定されることに加え,「ホルダ片」を嵌合するための手段である「嵌 合部が形成されたケース部」(機械的機能を有するもの)によっても新たに特定され\nることになり,「光方向変換部」により特定される補正前の「光方向変換素子」(光 学的機能を有するもの)を限定するものでないと主張する。\nしかし,前記のとおり,補正前発明の「光方向変換素子」は,請求項1にあると おり,「『入射面』と,・・・『反射面』と,・・・『出射面』とを有する『透明材料』 からなる」もの,すなわち,「光方向変換部」を「有する」,「透明材料」からなるも のであるとともに,「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し」と特定さ れ,「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けるものである(被告は,これを機械的 機能と称する。)から,本件補正は,発明特定事項を新たに追加するものではなく,\n上記主張を採用することはできない。 また,被告は,発明が解決しようとする課題が,補正前発明では,光方向の厳密 な調整を不要とし,輝度ムラのない光源モジュールを提供することであったのに対 し,補正発明では,嵌合部を持つ光方向変換素子を有する光源モジュールを提供す ることを追加しており,本件補正は,発明が解決しようとする課題を追加して変更 するものである旨主張する。 しかし,前記のとおり,補正発明は,補正前発明と同様の課題を有しているが, それに加えて,光方向変換素子がケース部と円形の光方向変換部からなり,ホルダ 片が光変換素子の嵌合凹部11aに内嵌固定されるということが,補正前発明又は 補正発明の課題であることを示す記載は存在せず,ケース部の形状やホルダ片の固 着態様に格別の意義があるとは認められないから,光方変換素子の「光方向変換部」 以外の形状を限定したからといって,新たな課題を追加したものとはいえない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 限定的減縮
>> ピックアップ対象
2016.03. 7
平成26(ワ)22603 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年2月16日 東京地方裁判所
原告は,著作権法114条2項にいう「利益」には消極的利益も含まれることを前提に,少なくとも原告カタログの作成費用が被告の「利益」に該当すると主張する。 そこで判断するに,同項は,著作権侵害行為による侵害者の利益額を権利者の損害額と推定することによって損害額の立証負担の軽減を図る趣旨の規定であるから,同項所定の「利益」は「損害」に対応するものであることが前提となると解される。ところが,原告は被告による著作権侵害行為の有無にかかわらず原告カタログの作成費用の負担を免れないのであるから,原告カタログの一部を複製して被告カタログを作成したことにより被告が当該部分に関する作成費用の支出を免れたとしても,そのために原告に原告カタログの作成費用に相当する額の損害が生じたということはできない。そうすると,上記の支出を免れたことによる被告の利益は,同項所定の「利益」となり得ないというべきである。 イ 同条3項に基づく損害 原告は,原告カタログも被告カタログも無償で頒布されていることを踏まえると,原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額の損害が発生しており,その額は原告が原告カタログの複製を許諾する対価,すなわち,原告カタログの作成費用に基づいて算定されるべきであると主張する。 そこで判断するに,前記前提事実(1)のとおり,原告と被告は共に米国コーラー社の我が国における販売代理店であって,競合関係にあるから,原告が原告カタログの全部又は一部の複製を被告に対して許諾することは通常考えられないところである。そうすると,被告による前記複製権及び譲渡権の侵害行為により原告に損害が発生したとみることができるから,原告は被告に対し著作権の行使につき受けるべき金銭の額の損害賠償を請求し得ると解するのが相当である。 しかし,原告カタログ及び被告カタログはいずれも顧客に無償で配布されるものであり,そのような製品カタログの使用料等を算定する基準が明らかでないことに照らすと,上記損害額を立証するために必要な事実を立証することは,その性質上極めて困難であるというべきである。 そこで,著作権法114条の5に基づき相当な損害額を検討するに,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,1)原告カタログは2年ごとに改訂されること(甲3,4,19),2)原告は原告カタログの作成のために500万円程度の費用を要したこと(甲9,21〜114,117,乙19。なお,原告は原告カタログの作成費用につき他社への依頼分256万2000円,従業員の作業等分461万7677円の合計717万9677円を要したと主張するところ,後者については,従業員等が多大な労力を費やしたことは認められるものの,これにより人件費が増加するなど現実の出費が生じたことを示す証拠はないので,約半分の限度で相当と認める。),3)被告は,平成25年10月31日に被告カタログ3000部の納品を受け,翌11月1日開催の記念パーティーで約200部配布するなどした後,原告から警告を受けたため被告カタログの回収及び廃棄に努めたが,約650部は配布先から回収されていないこと(甲8,乙12〜15),4)被告は平成26年3月31日に被告カタログと内容の異なる新たなカタログの納品を受けたこと(乙18),5)被告カタログの作成費用(他社への依頼分)は278万2500円であったこと(乙12),以上の事実が認められる。 上記事実関係によれば,原告は無償配布する原告カタログの作成費用を2年間の営業活動により回収することを企図していたと解されるところ,被告カタログの配布期間中これを妨げられたとみることができる。これに加え,被告カタログの作成部数及び原価(1冊当たり約927円),被告カタログには被告表現4など原告カタログと異なる部分が少\nなからず存在すること(甲3,5)を考慮すると,原告の損害額は120万円であると認めるのが相当である。
ウ 他の損害について
原告は,原告の顧客を奪われたことによって営業上の利益が得られなくなったことも損害に当たると主張する。しかし,被告が現に原告の顧客を奪って原告に営業上の損害を被らせたことをうかがわせる証拠がないことに照らすと,上記イの損害に加えて,そのような損害が生じたと認めることはできない。
2016.03. 7
平成25(ワ)19912 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年2月19日 東京地方裁判所
本件発明1−1は,加振用液圧シリンダ機構が,「ピストンロッドを共通にする複シリンダ構\成をなし,各シリンダのロッド側液室には前記定加圧部による加圧力並びにこれと平衡する圧力を導入しつつヘッド側液室に加振液圧を導入して前記加 圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした」ものである(構成要件1D)のに対し,乙22の3発明は,脈動発生装置がそのような構\成を有していない点において,両発明は相違している。 b 本件発明1−1と乙22の3発明との相違点2に関する検討 乙22の3発明に乙4の2文献に記載された技術(装置)を適用しても,加振用液圧シリンダ機構の「各シリンダのロッド側液室に定加圧部による加圧力及びこれと平衡する圧力を導入しつつ」「ヘッド側液室に加振液圧を導入して」「加圧部による負荷を無負荷状態にして加振できるようにした」構\成とすること(構成要件1D2,1D3a及び1D3b)には至らない。\n前記イ(イ)bで説示したところからすれば,乙22の3発明において,脈動発生装置を上記構成とすることが,本件出願1前に,当業者が容易に想到し得たものということはできない。
c 小括
したがって,前記相違点1に関して検討するまでもなく,本件発明1−1は,本件出願1前に,乙22の3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなかったというべきである。
・・・・
以上のとおり,本件出願1及び本件出願2については,審査請求期間内に出願審査請求がされていれば特許権の設定登録を受けられた高度の蓋然性があったということができるが,本件出願3及び本件出願4については,審査請求期間内に出願審査請求がされていたとしても特許権の設定登録を受けられた高度の蓋然性があったということはできない。 したがって,本件出願1及び本件出願2については,前記2で説示した被告の債務不履行と損害の発生との間の因果関係を肯認することができるが,本件出願3及び本件出願4については,被告の債務不履行又は不法行為と損害の発生との間の因果関係を肯認することはできない。
2016.03. 7
平成27(ワ)12748 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年2月23日 東京地方裁判所
構成要件1Iにつき,本件発明の特許請求の範囲には,「レッグレストフレーム……の当接部材」が「座席フレームの湾曲部」に「滑らかに当接」して「徐々に停止する」ものであると記載されている。この「滑らか」は,本件明細書(甲1)において定義づけられていないので,「すらすらと通るさま。つかえないさま。よどみないさま」(広辞苑〔第六版〕2103頁),「物事がよどみなく運ぶさま。すらすらと進むさま」(大辞林〔新装第二版〕1924頁)といった意味を有すると解される。また,「徐々に停止する」とは,「徐々に」が「停止」を修飾していることに照らすと,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接すると直ちに停止するのではなく,当接した後も移動を続けつつも次第に減速して停止に至ることを意味すると解される。さらに,「座席フレームの湾曲部」が座席フレームの「開放する側の両端部」にあって「下方に鈍角状に折り曲げられた」構\造を有していること(構成要件1E。なお,構\成要件1B,1E及び1Fにいう「座部フレーム」は構成要件1Iにいう「座席フレーム」と同一の部材を指すと認める。)からすれば,レッグレストフレームの当接部材に対しては,引き出す方向に対する抵抗力が次第に大きくなる一方,下方に向かう力がかかっていくと考えられる。\n以上を総合考慮すると,「滑らかに当接して徐々に停止する」とは,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても直ちに停止することなく更に引き出され続けるが,湾曲部との当接後は湾曲部から受ける力により次第に減速して,当接から多少なりとも間を置いて停止することを意味すると解される。
(2)この点につき,念のため本件明細書の記載及び本件特許の出願経過を見るに,本件明細書(甲1)においては,「発明を実施するための形態」欄において,円形当接部材が座部フレームの湾曲部の基端部に滑らかに当接すること,及び,鈍角状の上記湾曲部により徐々に停止していくので強く引き出しても衝撃がないことが記載されている(段落【0032】)。また,本件の特許出願について,引用文献(登録実用新案第3046819号公報。乙3)に基づき容易想到であるとする拒絶理由通知(乙2)に対し,原告は,特許請求の範囲(構成要件1I)に「滑らかに」を加える補正をした上,平成25年3月28日付け意見書(乙4)において,本件発明が本件明細書の上記記載のとおりの作用効果を奏するものであり,上記引用文献記載の考案は当接部が屈曲部の下側の曲線部にいきなり当接するもので,滑らかに当接し徐々に停止していくものでは全くないと述べている。\nそうすると,構成要件1Iは,レッグレストフレームを引き出した際に衝撃を感じることがないという効果を奏するために,当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても突然停止するのでなく,その後に次第に速度を落として停止することをいうものと解するのが相当であるから,前記(1)の解釈と合致するということができる。
(3) 以上を前提に被告製品が構成要件1Iを充足するかどうかについて検討するに,証拠(甲9,乙7の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,レッグレストフレームを前方に引き出していくと,同フレームに取り付けられた側面視略L字型のストッパー部材の上端ないし引き出し方向先端の角の部分が座席フレームの湾曲部に当接し,その直後にレッグレストフレームが,次第に減速するのではなく,ほぼ一瞬にして停止するものと認められる。\nしたがって,被告製品は,「滑らかに当接して徐々に停止する」ものでないから,構成要件1Iを充足しない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.02.28
平成26(ワ)6310 商標権侵害差止等請求 民事訴訟 平成28年2月8日 大阪地方裁判所
ウ 著作権法114条2項にいう「利益」とは,侵害による売上高から,そ の販売に追加的に要した費用を控除した額(限界利益)と解するのが相当 であり,侵害品の売上げによって追加的に要しなかった経費は控除すべき ではない。 本件においては,少なくとも,複写権使用料として5%,文具費(主と して紙代)として10%,発送・通信費として15%を経費として控除す べきことについて,原告らは明らかに争っておらず,このとおり認められ る。 被告は,さらに,複写機リース料等も経費として控除すべきであり,利 益率は15%であると主張するが,その裏付けは何ら提出されておらず, 被告主張に係る経費が追加的に必要となった直接経費に該当すること及び それら経費が被告主張の率であることを認めるに足りる証拠はない。 よって,本件における利益率は,前記争いのない経費を控除した70% と認めるのが相当である。
以上より,平成16年8月1日以降本件訴訟提起日である平成26年7 月8日に至るまでの間に,P2及び被告が著作権侵害により得た利益の額 は1001万6482円と認められ,原告会社については著作権法114 条2項に基づき同額の損害が生じたものと推定される。
(計算式)(1円未満四捨五入)
144 万円×(9 年+342 日/365 日)×0.7=1001 万6482 円
また,被告による侵害行為と相当因果関係が認められる弁護士費用は, 原告らの主張どおり,75万円と認めるのが相当である。 したがって,原告会社に生じた損害は,合計1076万6482円と認 められる。
2016.02.25
平成27(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年2月24日 知的財産高等裁判所
本願発明は,前記1(2)のとおり,1)省エネ行動をリストアップして箇条書にし た表などを利用する者が,各省エネ行動によってどれくらいの電力量等を節約でき\nるのかを一見して把握することが難しいことや,どの省エネ行動を優先的に行うべ きかを把握することが難しいことを「前提とする技術的課題」とし,2)「建物内の 場所名と,軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第\n三場所軸」,「時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸」及び「省エネ行動により\n節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ,省エネ行動\nの継続時間を第三時間軸の軸方向の長さとする第三省エネ行動識別領域」を設けた 「省エネ行動シート」において,「該当する第三省エネ行動識別領域に示される省 エネ行動を取ることで節約できる概略電力量(省エネ行動により節約可能な単位時\n間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能\nな電力量)を示すこと」を「課題を解決するための技術的手段の構成」として採用\nすることにより,3)利用者が,省エネ行動を取るべき時間と場所を一見して把握す ることが可能になり,かつ,各省エネ行動を取ることにより節約できる概略電力量\n等を把握することが可能になるという「技術的手段の構\成から導かれる効果」を奏 するものである。 そうすると,本願発明の技術的意義は,「省エネ行動シート」という媒体に表示\nされた,文字として認識される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」 と,面積として認識される「省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量」を利 用者である人に提示することによって,当該人が,取るべき省エネ行動と節約でき る概略電力量等を把握するという,専ら人の精神活動そのものに向けられたもので あるということができる。 なお,本願発明においては,上記のとおり,媒体として「省エネ行動シート」を 構成として含むものであるが,本願明細書の【0065】には,「以上の省エネ行\n動シート作成装置により出力された省エネ行動シートのデータは,プリンタ装置に 対してデータ出力して印刷された状態で取り出すことも可能であるし,ディスプレ\nイ装置に対してデータ出力して画面上に表示させることも可能\である。また,記録 媒体に記録したり,通信装置を利用してネットワーク上の他の装置にデータ送信し たりすることも可能である。」と記載されているように,「省エネ行動シート」とい\nう媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから,本願発明の技術的意義は,\n「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえない。
・・・
ア 原告は,自然法則の利用があるかどうかは,発明の作用,効果ではなく,特 許請求の範囲の請求項に記載された構成要件自体(発明特定事項)が自然法則に従\nう要素であるか否かによって判断すべきであり,本願発明においては,シートは典 型的には紙であり,領域や領域名は典型的にはインクによって構成されており,請\n求項には,紙とインクという自然物によって線画を所定位置に配置するという工夫 のみが記載され,本願発明の構成要件のいずれにも精神活動等である構\成要件は含 まれていないから,本願発明が自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しない ということはできない旨主張する。 しかし,前記(1)のとおり,特許を受けようとする発明が,自然法則を利用した 技術的思想の創作に該当するか否かの判断は,前提とする技術的課題,課題を解決 するための技術的手段の構成及び技術的手段の構\成から導かれる効果等の技術的意 義に照らし,全体として考察した結果,「自然法則を利用した技術的思想の創作」 に該当するといえるか否かによって判断すべきものである。そして,明細書の「発 明の詳細な説明」の記載に関して,特許法36条4項1号が,「発明が解決しよう とする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術分野における通常の知 識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」(特許法施行規 則第24条の2)により「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有す る者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるこ\nと」と定めていることからすれば,特許を受けようとする発明の技術上の意義の把 握は,同法36条5項が定める特許請求の範囲の請求項に記載された発明の発明特 定事項(構成要件)だけではなく,明細書の発明の詳細な説明をも参酌すべきであ\nる。
2016.02.25
平成27(ネ)10080 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年2月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
イ 前記1(3)のとおり,控訴人は,本件特許1の出願経過において,拒絶理由通 知を受け,構成要件Cの15本のピークの回折角の数値を挿入する平成23年11\n月29日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相 当するものであることを表明した。また,控訴人は,本件特許2の出願経過におい\nても,拒絶理由通知を受け,構成要件C’の15本のピークの回折角の数値を挿入\nする平成25年3月8日付けの補正を行い,この際,上記補正が特許請求の範囲の 限定的減縮に相当するものであることを表明した。\n控訴人は,本件特許1の出願経過における拒絶理由通知において,1本のみのピ ーク強度でしか特定されず,他のピークの特定がないので,公知文献に記載された 結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対 して,上記補正を行ったのであるから,15本のピークの回折角の数値をもって本 件発明1の結晶を特定したというほかない。 そして,本件特許2は,結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む 医薬組成物に関し, 特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの 結晶性原薬を提供することを課題とし,ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に 含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上す ること及び結晶形態AないしCの中で結晶形態Aが医薬品の原薬として最も好まし いことを見いだした本件特許1を原出願とする分割出願であって,本件特許1に係 る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり,その出願 当初の特許請求の範囲の請求項1には,上記補正後の本件発明1の結晶と同じ15 本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。 以上によれば,本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は,本件各発明 の技術的範囲を,回折角の数値が15本全て一致する結晶に限定するものであると 解されるから,構成要件C・C’の15本のピークの回折角の数値と,全部又は一\n部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は,本件各発明 の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。
◆平成27(行ケ)10081 こちらは、本件特許発明についての無効審判の取消訴訟です。この事件では、特許無効とした判断が取り消されていますが、上記事件ではイ号は非侵害と判断されています。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第5要件(禁反言)
>> ピックアップ対象
2016.02.23
平成26(ワ)29417 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成28年2月5日 東京地方裁判所
不競法2条1項1号の「商品等表示」は,「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表\示するもの」をいう。商品の形態は,商標等とは異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものでないが,1)商品の形態が客観的にほかの同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,2)その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている場合(周知性)には,商品の形態自体が商品等表\示に該当する場合もあると解される。 もっとも,実質的機能を達成するための構\成に由来する不可避的な形態についてまで,商品等表示として保護を与えると,同等の機能\を有する複数の商品間の自由な競争を阻害する結果となり相当でないから,実質的機能を達成するための構\成に由来する不可避的な形態については商品等表示に該当しないというべきである。\n(2) そこで検討するに,原告商品は,親指,人差し指及び中指をリングに挿入して箸の使用に適した位置で固定するという機能並びに2本の箸を連結するという機能\を有しており,これにより,箸の使用に習熟していない者が,箸を安定させて,かつ,正しいとされる指の位置で箸を使用する練習ができるという作用効果を有するものであるといえる。そして,正しいとされる箸の持ち方を前提にすれば,2本の箸に対してあるべき親指,人差し指及び中指の位置関係は自ずと決まっているから,それらの指の位置関係を正しい位置に固定するために指を通すリングを使用しようとすると,その位置関係及び箸に対する傾きなども自ずと定まっているものと認められる。 そうすると,原告商品形態のうち,「一対の箸が上端部又は中央より上端側の部分において連結されている連結箸」であることは,2本の箸を連結するという機能を達成するための構\成に由来する不可避的な形態であり,また,連結部位が一対の箸が上端部又は中央より上端側の部分であることは,箸として使用することからすれば当然の選択といえる。次に,「1本の箸は人差指と中指をそれぞれ入れる二つのリングを有し,他方の1本は親指を入れる一つのリングを有する」ことは,親指,人差し指及び中指をリングに挿入することで正しいとされる箸の持ち方に適した位置で固定するという機能を達成するための構\成に由来する不可避的な形態であると認められる。 以上のとおり,原告商品形態は,全体として,指にリングを通すことによって正しいとされる箸の持ち方を練習するための練習用箸の実質的機能を達成するための構\成に由来する不可避的な形態というほかない。
関連カテゴリー
>> 周知表示(不競法)
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成26(ワ)5210 損害賠償請求事件 民事訴訟 平成28年1月21日 大阪地方裁判所
本件特許発明が,シートによって鼻全体を覆うことを想定していることは先に述 べたとおりである。しかし,本件明細書の記載によれば,従来のシートでも鼻の上 部に切り込みは設けられておらず(【0005】,図2),鼻の上部に当たる目頭付近 部分は,従来技術によってもシートで覆うことが実現されていたのに対し,本件特 許発明の技術的課題は,従来のパック用シートでは,小鼻部分にシートで覆えない 大きな隙間が空き,また,シートの小鼻に対応した部分が浮き上がってしまう欠点 があったことから,顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもぴったりと覆うこと にあり,本件特許発明は,「ほぼ台形の領域」にミシン目状の切り込み線を配すると したことにより,不織布の横方向に伸びやすいという物性と相俟って,パック用シ ートが鼻筋や鼻の角度に沿って自然と横方向に伸び広がるようにし,隙間を生じる ことなく小鼻部分をもぴったり覆うようにしたものであると認められる。 これらからすると,本件特許発明は,鼻部にミシン目状の切り込み線を複数列配 することによって,従来技術では困難であった小鼻部分を覆うことを実現した点に 固有の作用効果があると認められる。そうすると,被告製品において,目頭の高さ からやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点は,このような本 件特許発明の固有の作用効果を基礎付ける本質的部分に属する相違点ではないとい うべきである。
イ 置換可能性について
証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,目頭の高さからやや下の 部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていなくとも,小鼻部分を含 めた鼻全体に密着するものであると認められる。 そうすると,被告製品も,本件特許発明の目的を達することができ,同一の作用 効果を奏するものであると認められる。 ウ 置換容易性について 前記のとおり,鼻の上部に当たる目頭付近部分は,従来技術によってもシートで 覆うことが実現されていたことからすると,切り込み線が配される台形状の領域の 上底の高さを,眼の付け根である目頭の高さよりも,目頭の1段分か2段分,下に 設けても本件特許発明と同一の作用効果を奏することは,当業者が,対象製品等の 製造等の時点において容易に想到することができたというべきである。
・・・・
(2) 被告製品の製造に関する実施料相当額
被告に納入されたパック用シート●●●●●●●●のうち,被告製品として譲渡 されたのは●●●●●●●●であり,その差である●●●●●●●●については, 納入されたが譲渡されなかったものである。しかし,被告製品のパック用シートが 特殊な形状をしていることからすると,被告は,シートの製造業者に発注して被告 製品用のパック用シートを製造させたと推認され,そうすると,被告は,パック用 シートの製造行為を行ったと評価すべきである。そして,パック用シートの製造も 本件特許発明の実施であり,侵害行為に当たるから,納入されたが譲渡されなかっ た分も損害賠償の対象とするのが相当である。 もっとも,被告は,これらについては,その価値を市場に提供して利用したわけ ではないことからすると,これを有償譲渡と同視し,前記の想定市場販売価格を基 礎として実施料相当額を算定するのは相当でない。そこで,これらシートについて は,その製造自体の価値を示すものとして,その納入価格を基礎として実施料相当 額を算定するのが相当であり,証拠(乙12)によれば,シート1枚当たりの納入 価格は●●円であると認められる。この点について,原告は,これらについても想 定市場販売価格を基礎にして実施料相当額を算定すべきであると主張するが,前記 に照らして採用できない。 また,前記(1)エにおいて考慮した事情に照らせば,これらシートの納入価格には, 美容液の価値が考慮されていないから,被告製品用のシートを製造したが譲渡しな かった場合の実施料率は,●●と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成27(行ケ)10134 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年2月17日 知的財産高等裁判所
商標法施行令は,商標法6条2項に係る区分を定める政令別表において,\n第10類として「医療用機械器具及び医療用品」を挙げているところ,省令別表で\nは,第10類の項目において,「医療用機械器具」が,「手術用キャットガット」や 「人工鼓膜用材料」,「医療用手袋」等とともに列挙されているから,第10類の「医 療用機械器具」とは,本来,医療行為に供することが予定されている商品を指すも\nのと解される。 そうすると,引用商標の指定商品である「体脂肪測定器,体組成計」とは,医療 行為に供する程度の品質,性能を保有することが予\定されている体脂肪率,筋肉量, 基礎代謝量等の体組成の測定機器を指すものというべきである。 確かに,省令別表の第10類には,「おしゃぶり」,「哺乳用具」,「綿棒」,「指サッ\nク」,「業務用美容マッサージ器」,「家庭用電気マッサージ器」や「耳かき」なども 列挙されており,医師による診断,治療の場面以外での使用が想定されているもの や,小型で安価で個人でも入手可能であり,病院以外に家庭での使用が想定されて\nいるもの,機能的に高度とはいえないものが含まれている。しかしながら,これら\nの物品は,いずれも美容,健康に関連する商品という意味において,医療行為の範 ちゅうに属する行為ないし医療行為に関連する行為に供されるものと認められるし, 高度な機能が不要であるとしても,医療行為に供されること,そのために必要な品\n質,性能が求められていることは同様であるから,当該物品に関する省令別表\の分 類は,上記判断を左右しない。
ウ これに対し,政令別表では,第9類として「科学用,航海用,測量用,\n写真用,音響用,映像用,計量用,信号用,検査用,救命用,教育用,計算用又は 情報処理用の機械器具,光学式の機械器具及び電気の伝導用,電気回路の開閉用, 変圧用,蓄電用,電圧調整用又は電気制御用の機械器具」が列挙されているところ, 省令別表では,第9類の項目において,「測定機械器具」として,温度計,圧力計,\n金属材料圧縮試験機,気象観測用機械等の種々のものが列挙されているものの,い ずれも,医療行為に供することを予定したものではないから,省令別表\の「測定機 械器具」が属する第9類の「測量用・・・の機械器具」は,元々,医療行為に供す ることが予定されていない商品を指すものと解される。\nそうすると,本件商標の指定商品である「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重 計,体重計」とは,体脂肪率,筋肉量,基礎代謝量等の体組成や体重の測定機器を 指すというべきである。そして,測定の対象自体は引用商標の指定商品と重なる部 分があるが,医療行為に供することが予定されていないという意味において,医療\n行為に供する場合よりも,品質や性能が劣るものを予\定しているというべきである。 エ なお,原告は,第9類への帰属と第10類への帰属が択一関係にあるこ とを否定すべき旨主張する。しかしながら,商標法6条1項及び2項が,商標登録 出願の際に商品の指定をすること,同商品の指定は,政令で定めた区分に従って行 うことを要求し,これに基づいて政令別表が作成されていること,政令別表\はニー ス協定の規定した国際分類に即して作成されているが,国際分類でも類別表又はア\nルファベット順の一覧表において,多数の多種多様な商品及びサービスが概括的,\n網羅的に記載されていること,政令別表を再区分化した省令別表\では,別表に商品\n名の記載がない場合を例外的な場合と取り扱っていることからすると,政令別表は,\n指定商品を指定するに当たって,可能な限りその中から選択できるように,世上存\nする多数の商品を全て列挙することを目指すものであり,そのうち,同種企業が取 り扱う可能性のある商品の類型ごとに1つの区分を設けたと考えられる。\nしたがって,省令別表は,特定の商品が多数の類型に同時に属することを,本来,\n予定していないと解するのが相当というべきである。「商品及び役務の区分解説」(乙\n3,4)においても,医院又は病院で専ら使用される電子応用の機械器具は,例外 的に,第9類の電子応用機械器具及びその部品に含まれないこと,第9類の「測定 機械器具」に該当する器具でも,専ら医療用に使用する測定機械器具については, 第10類の「医療用機械器具」に含まれることが記載されており,第9類と第10 類の商品を区別し,いずれかに分類できることを前提としている。 確かに,特定の商品がどの分類に属するかが不明な場合があることや,特定の分 類に属していた商品が,品質向上に伴って他の分類の属すると評価するのが相当な ことはあり得るといえるが,上記の指定商品の区分を設けた趣旨からして,同時に 複数の類型に帰属することは予定されていないとの前記解釈が左右されるものでは\nない。よって,本件商標の指定商品は,第9類に属するとされている以上,第10 類にも属するとの前提に立つことはできない。
・・・
確かに,「医療用機械器具」に属する具体的な商品では,大型で高額であり,医師 等の専門家でなければ入手し,使用することができないようなものが多く,このよ うな商品については,一般的な消費者が自ら購入することは考えにくく,上記推定 が及ぶものと解される。もっとも,「医療用機械器具」に属する具体的な商品の中に は,上記のような多種多様なものが含まれ,必ずしも一般消費者には入手困難とは いえない類型のものも存在するし,今後,技術革新や取引形態の変化によって,高 性能の低価格帯の製品が普及し,一般消費者も,医療用として使用されている機械\n器具を購入し,使用するようになれば,事後的に,出所について誤認混同するおそ れが生じ得ることになるから,実際に商標が使用されている具体的な商品の使用状 況,取引の実情等によっては,上記推定を及ぼすことが相当でない場合もあるとい うべきである。「類似商品・役務審査基準」において,商取引,経済界等の実情の推 移から,類似と推定した場合でも非類似と認められること,基準上は類似とならな い場合であっても類似と認められることがあると注記しているのも(甲64),例外 を許容する趣旨と解され,上記見解と整合するものである。 (2) 体脂肪計,体組成計,体重計の取引状況
そこで,以下,本件商標の指定商品とこれに関連した引用商標の指定商品の取引 の実情を,具体的に検討することにする。
・・・
以上によれば,本件査定時において,本件商標と引用商標の指定商品に関連する 体脂肪計,体組成計,体重計等の取引の実情に関し,次のことがいえる。
ア まず,業務用として販売されている体組成計及び体重計は,医療用とし て使用することを想定した機能や性能\を有し,医療用製品に該当するといえるとこ ろ,家庭用の体組成計及び体重計のシェアが極めて高い原告と被告は,医療用製品 の製造者でもある。また,医療用の体組成計しか製造していないメーカーが存在す る一方,医療用の体組成計を製造していない家電メーカーも存在し,家庭用の製品 と医療用の製品に関し,シェアが一致しているとは認められない。
イ 次に,メーカーによって,販売用のカタログの種類,掲載対象は異なる が,家庭用の体組成計や体重計のシェアが高い被告は,家庭用と業務用の両方を掲 載したカタログを用意している。また,多数の医療機器販売メーカーのカタログに おいて,小型の体脂肪計,体組成計,体重計が掲載され,販売されているが,その 中には,原告や被告の製品で,業務用のものと家庭用のものの両方が含まれている ため,医療関係者は,医療用機器の購入時に家庭用機器も併せて購入対象として検 討することになる。 小売店における体脂肪計,体組成計,体重計の販売では,業務用の大型のものは 展示されていないが,健康意識の向上に伴い,血圧計や体温計といったヘルスケア に関する製品と一緒に展示されており,一般消費者は,家庭用体組成計,体脂肪計 及び体重計を,健康維持や病気予防の目的で使用できる製品と近い性質のものと認\n識し得る。 また,近時は,ネット販売の増加もうかがわれるところ,体脂肪計,体組成計, 体重計のネット販売は,家電メーカー,医療機器メーカーに限られず,オフィス用 品取扱会社などにおいても取り扱われており,医療関係者の購入を前提とし,医療 用製品を主に取り扱うウェブサイトもあれば,一般消費者の購入を前提とし,家庭 用製品を主に取り扱うウェブサイトもある。前者では,医療用機器として大型の体 重計,体組成計以外に小型の製品も掲載され,医療用に限定されず,家庭用の体組 成計,体重計が販売されていることが多いため,主たる需要者である医療関係者に とって,医療用機器と同様に,家庭用機器が購入検討対象となる。しかも,医療用 製品を主として取り扱うウェブサイトであっても,一般消費者がアクセスすること 自体に制限はなく,購入も禁止されていないため,一般消費者も需要者となること があり,その場合の購入対象は,家庭用機器に必ずしも限られず,医療用機器も候 補となる。他方,一般消費者向けのウェブサイトであっても,業務用体重計が販売 される場合もあり,医療用製品が購入候補になることもあるし,リンクが貼られた\n業務用製品販売通販サイトへアクセスすることで,他の医療用製品等が購入候補と なることもある。
ウ さらに,医療用と家庭用の体脂肪計,体組成計,体重計において,そ の品質及び価格は様々であるが,医療用と同程度の品質及び価格が用意されている 業務用のものは,医療現場以外の学校やフィットネスクラブ等でも使用され,学生 やフィットネスクラブの会員である一般消費者が,直接接する場合がある。 具体的には,医療現場に設置されることが多いと考えられる業務用の製品は,価 格が100万円を超えるものや,一般住宅内での設定が想定できないほど大型のも のがあるが,一方,業務用の体重計であっても,価格が3万円程度で,一般家庭で の購入が十分可能\な製品もある(被告のWB−260A)。 他方,家庭用の体脂肪計,体組成計,体重計であっても,多数の機能が付加され\nていることが通常であり,1万円を超えることも珍しくない。これらの家庭用の体 重計等は,家庭用計量器の基準しか満たさないものとはいえ,その測定対象や測定 単位が医療用のものと同様のことがあり,医療関係の研究論文で使用される程度の 精度を備えていて,医療現場で購入される場合もある。
エ このように,家庭用の体重計の需要者である一般消費者は,医療用の 体組成計,体重計も入手可能な状況となっていたといえる上に,医療用の体組成計,\n体重計は,医療現場での利用に限定されず,学校やフィットネスクラブ,企業等で も利用されるから,その需要者は,医療関係者に限定されず,学校関係者やフィッ トネス関係会社,企業の物品購入部門,健康管理部門の従業員も含まれる。そして, 医療用の体組成計及び体重計のシェアの正確な数値は不明であるが,被告の医療用 の体組成計の販売台数は相当数に及び,販売シェアも小さくないから,これらの需 要者は,家庭等で被告の家庭用の体組成計を目にするだけでなく,学校やフィット ネスクラブ等で被告の医療用の体組成計を目にする機会もあることが推認される。 また,一般消費者の一部を構成する医療従事者は,一般消費者よりも高い注意力\nをもって商品を観察するとはいえ,医療用と家庭用の両方の製品を製造し,家庭用 のシェアの大半を占める原告と被告の製品に日常的に接することになるから,医療 用製品の出所について,家庭用製品の出所と区別して認識することが困難な状況と いえる。 さらに,その他の学校関係者,フィットネス関係会社や企業の物品購入部門,健 康管理部門の従業員には,一般的な消費者も含まれており,しかも,医療用と家庭 用の体重計,体組成計の測定対象は同じであり,性能等が近づきつつあるといえる\n上に,精度の違いは一般消費者には識別し難い場合があることから,性能による明\n確な区別も困難である。
オ よって,本件査定時においては,医療用の「体脂肪測定器,体組成計」 と家庭用の「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」は,誤認混同のお それがある類似した商品に属するというべきである。したがって,審決の指定商品 の類否判断の誤りをいう原告の取消事由3は,理由がある。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成27(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年2月17日 知的財産高等裁判所
他方,引用発明は,本願発明の従来技術であるスリットによる変形作用を 前提として,スリットに相当する溝孔6の長さ方向中央部に応力的に弱い部分とし て拡大溝部6aを形成することにより,狭幅部4aを形成して,狭幅部4aをスリ ット(溝孔6)間の軸部の変形の中心点(起点)としたものである。そして,変形 区域については,軸の長さ方向でいえば,本願発明が,穴(7)を挟んで頭部(3) から雌ねじ(4)の間である(変形区域(5))のに対して,引用発明は,従来技術 におけるスリットに相当する溝孔6のある領域であると認められるところ,引用発 明は,「軸部壁の弱体化部」に相当する溝孔6のある領域全体の中で,特に応力的に 弱い部分として拡大溝部6aにより狭幅部4aを形成して,軸部の変形の中心点(起 点)としたのであって,従来技術のスリットと同様,狭幅部4aの上下に位置する 溝孔6と溝孔6の間の軸部壁6が“く”の字状に折れ曲がることにより,拡開部9 が形成されるものである。 すなわち,引用発明は,従来技術のスリット(溝孔6)において,拡大溝部6a により特に応力的に弱い部分を形成して,スリット(溝孔6)間の管状部材4を折 り曲げやすくしたものに相当すると認められる。他方,本願発明は,変形区域の中 央の周範囲に穴を設けることによって,応力的に弱い部分を形成し,折り曲げる際 の起点とするものである。そして,本願発明にいう「穴」とは,閉じられた線図で 画された部分をいい,これが応力的に弱体化部を形成するところ,これに該当する のは,引用発明では,溝孔6と拡大溝部6a両方で構成される部分ということにな\nる。 この点,被告は,引用発明の「複数の溝孔6が形成された領域」は「変形区域(5)」 に,「複数の狭幅部4a」は本願発明の「軸部壁(6)の弱体化部」に相当すると主 張するところ,本願発明における「穴」及び「穴」と「弱体化部」の関係に関する 解釈を必ずしも明確に主張していないが,少なくとも,弱体化部に相当する「複数 の狭幅部4a」は,拡大溝孔6aのみによって形成される前提と解される。しかし ながら,このような被告の主張は,「穴」全部ではなく,その一部にのみ着目し,「弱 体化部」に相当するとするものであって,前提において採用できない。 したがって,引用発明は,変形区域全体が弱体化部であり,本願発明のように, 「変形区域(5)の中央の周範囲にのみ,・・・軸部壁(6)の弱体化部を持ってい る」ものではない。よって,この点において,審決の一致点の認定には誤りがあり, 変形区域と穴の位置関係に関する相違点の看過があると認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成27(ワ)8132 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 平成28年2月9日 東京地方裁判所
イ 被告ら各標章については,その全体から,「エアウィーヴシキフトンナゴミ」ないし「エアウィーヴシキブトンナゴミ」の称呼が生じ,「エアウィーヴ」の語の周知性及び「四季布団」の漢字の意義から「被告らの製造販売に係るマットレス類であって,年間を通じて使用し得る敷き布団であり,穏やかな気持ち,くつろいだ気分にさせるもの」といった観念が生じると認められる。 一方,被告ら各標章は,称呼上は13音,外観上は14文字及び記号4個又は2個(被告ら標章4は更に縦線)からなる比較的長いものであり,必ずしも一息で発音され,一目で視認され得るものでない。これに加え,被告ら標章1及び2については,「和」の文字が隅付き括弧で囲まれて目立つようになっており,その後ろに括弧付きで「なごみ」と表記されているため,被告ら標章3及び4については,「エアウィーヴ四季布団」の部分と振り仮名付きの「和」の文字部分ないし「【和】(なごみ)」の部分を分けて2段又は2列に表\記され,しかも「和」の文字等が大きいため,いずれもその外観上「和」の読み方を示すものと理解される「なごみ」の部分が,「エアウィーヴ四季布団」の部分から独立 して,被告ら各標章に接した需要者の関心を引くとみることができる。そうすると,被告ら各標章からは,上記の標章全体から生じる称呼及び観念だけでなく,「なごみ」の部分から「ナゴミ」の称呼及びこれに伴う観念が生じると認められる。
ウ 上記ア及びイによれば,本件商標と被告ら各標章は,称呼及び観念を共通にするということができる。
エ さらに取引の実情についてみるに、前記(2)イ認定の通り,本件商標は,被告ら商品の発売の少なくとも約10年前から原告によって本件商標の指定商品に含まれるタオルケット等の商品に使用されている。また,原告は大手の寝具類の製造卸売業者であり,マットレス,敷き布団等も販売している。その上,「なごみ」の語は他社の商品名を含め一般に広く使われる名詞であり,本件商標の指定商品である寝具類を使用した者が穏やかな気持ち,くつろいだ気分になることがあり得るが,これは使用者が主観的に感得するものであり,「なごみ」自体は上記指定商品の効能(保温,吸汗等)を直接表\示するものでない。そうすると,本件商標はその指定商品につき相応の出所表示機能\を有しており,「ナゴミ」と称呼される標章が原告以外のマットレスや敷き布団に使用された場合には,原告の「なごみ」という名称の商品の存在を知っている需要者において,これを原告の商品と誤認するおそれがあるということができる。 一方,被告ら各標章は,被告らの製造販売する商品の名称として広く知られた「エアウィーヴ」の文字及び被告ら商品の特徴を示す造語「四季布団」を含むものであり,これらの部分から「エアウィーヴシキフトン」ないし「エアウィーヴシキブトン」との称呼及び「被告らの製造販売に係るマットレス類であって,年間を通じて使用し得る敷き布団」と ら商品の名称のうち「【和】」の文字等は,被告ら各標章の外観上「エアウィーヴ四季布団」の部分と区別され需要者の関心を引く部分であり,シリーズ商品である「エアウィーヴ四季布団」と区別する指標ともなるから,被告ら商品を指称するに当たり「なごみ」の部分が常に省略されるとは解し難い。そうすると,「エアウィーヴ」が周知であることを考慮しても,被告ら各標章から「ナゴミ」の称呼及びこれに伴う観念が生じることがないとみることはできない。 オ 以上によれば,被告らの前記主張を採用することはできず,被告ら各標章はいずれも本件商標に類似すると判断するのが相当である。
・・・
一方,本件商標を構成する「なごみ」の語は普通名詞であって,複数の業者が各種の商品件商標を使用するタオルケット等と被告らが被告ら各標章を使用する被告ら商品は具体的な用途,機能\等が異なること(同イ及びエ),被告ら各標章中の「エアウィーヴ」の語が被告らのブランドとして周知であり(同エ),被告らは被告ら商品についても各種メディアを通じて宣伝広告活動を行ったこと(甲6〜9,乙4)に照らすと,発売から約2か月で4億円という売上額に達したことについては被告らの営業努力に起因する部分が 大きいと解される。 これらの事情を総合すると,本件における上記金銭の額は,300万円と認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成27(行ケ)10132 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年2月9日 知的財産高等裁判所
前記認定のとおり,被告は,本件商標が登録されるまで,日本国内において 製造・販売するゴルフクラブに「KAMUI」単体商標を使用することはなかった ことが認められるものの,他方で,原告と被告は,共同企業体であるカムイクラフ トを設立し,製造したゴルフクラブに「KAMUIPRO」の名称を付して販売し ていたこと(「KAMUIPRO」の商標権は原告と被告の共有である。),カムイク ラフト解消後,被告は,ゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイツアー(KA MUITOUR)に改めることとしてゴルフクラブの製造販売を継続したこと(「K AMUITOUR(標準文字)」についても商標登録されている。),一時期は,被告 のゴルフクラブが「カムイ」のゴルフクラブとして紹介されることもあったこと, 本件商標の登録出願時においても,「KAMUITOUR」,「カムイツアー」等の標 章を使用してゴルフクラブを販売しており,上記のゴルフクラブの売上本数や売上 高についても原告と同程度のものであったことなどが認められ,被告としても,当 初から,「KAMUI」と文字を共通にする上記各標章をゴルフクラブに付して販売 等しており,継続的に相応の売上げがあったものということができる。 また,前記認定のとおり,原告と被告は,共同企業体であるカムイクラフトを解 消するに当たり,カムイの新製品については,それぞれが権利を有することを合意 したことが認められるものの,この合意のみをもって,被告が原告に対し,原告が 「KAMUI」単体商標の権利を有することを約束したものとはいい難く,本件商 標の登録出願が,原告と被告との間の上記合意に反するとは認められない。その他, カムイクラフト解消後においても,被告が原告に対し「KAMUI」単体商標に関 して法的義務を負う関係にあったということもできず,本件商標の登録出願につき, 被告に何らかの義務違反があるとも認められない。 以上のような経緯等によれば,前記認定の韓国における原告と被告の「KAMU I」に係る商標に関する紛争も契機として,被告が本件商標権に基づく先行訴訟に 至ったことを考慮しても,本件商標について,直ちに本件商標の登録出願の経緯に 著しく社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認めることが到底容認し得ないよう な事情があるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成27(ワ)21233 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 平成28年1月29日 東京地方裁判所
このように,翻案に該当するためには,既存の著作物とこれに依拠して創作された著作物とを対比した場合に同一性を有する部分が,著作権法による保護の対象となる思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要であるところ,「創作的」に表\現されたというためには,厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではなく,筆者の個性が何らかの形で表れていれば足りるというべきである。そして,個性の表\れが認められるか否かについては,表現の選択の幅がある中で選択された表\現であるか否かを前提として,当該著作物における用語の選択,全体の構成の工夫,特徴的な言い回しの有無等の当該著作物の表\現形式,当該著作物が表現しようとする内容・目的に照らし,それに伴う表\現上の制約の有無や程度,当該表現方法が,同様の内容・目的を記述するため一般的に又は日常的に用いられる表\現であるか否か等の諸事情を総合して判断するのが相当である。
・・・
(3) また,本件記事2は,これまで台湾における「五術」に関わり,その際に不快な思いもしたものの,新たな試験ができたことで時代が変わり始めたなどと表現した文章であって,一つの文(文字数にして143文字)からなるものである。その表\現においては,用語の選択,全体の構成の工夫,特徴的な言い回しなどにおいて,一見して作者の個性が表\れていることは明らかである。これに対し,本件情報14ないし17は三つの文からなる文章であるが,このうち第1文は,やはり,台湾における「五術」に関わり,その際にあきれたこともあったものの,新たな制度ができたことで時代が変わったなどと表現した文章であって,文字数にして123文字からなるものであり,具体的表\現についてみても,本件情報14ないし17の第1文の表現は本件記事2の表\現と相当程度一致しており,その違いは,本件情報14及び15では31文字,本件情報16及び17では32文字でしかなく(別紙対比表2参照),「台湾における五術」,「江湖派理論」,「宗教による術数を利用した」「金儲けを目撃する度に」など,用語の選択,全体の構\成,文字の 配列,特徴的な言い回しにおいて酷似している。そして,その相違部分の内容をみても,本件記事2のうち「五術」の「学術発表にかかわって」という点を,本件情報14ないし17においては「五術」の「詐欺\発表にかかわって」に,「とても不愉快な文化の冒涜・歪曲」という点を「とても愉快な文化の笑い話・小話」に,「胸くそが悪かったのですが」という点を「呆れたのですが」に,「国家規模での認定試験」という点を「国家機関での検閲制度」に置き換えているにすぎない。\nしたがって,本件情報14ないし17は,本件記事2に依拠したうえで,同記事の内容を批判するか揶揄することを意図して上記異なる表現を用いたものといえるのであって,仮に上記相違部分について作成者の何らかの個性が表\れていて創作性が認められるとしても,他に異なる表現があり得るにもかかわらず,本件記事2と同一性を有する表\現が一定以上の分量にわたるものであって,本件記事2の表現の本質的な特徴を直接感得することができるものであるから,翻案権侵害に当たることが明らかであるというべきである。
(4) 以上のとおり,本件情報1ないし17は原告の翻案権を侵害することが明らかである。 また,そうである以上,本件情報1ないし17を本件ウェブサイトに発信する行為は,原告の公衆送信権を侵害するものであることも明らかというべきである。
関連カテゴリー
>> 著作権(ネットワーク関連)
>> 複製
>> 翻案
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2016.02.21
平成27(ネ)10109 損害賠償請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成28年2月9日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
特許法2条3項1号は,物の発明について,その物の生産,譲渡,輸入又は譲渡 等の申出をする行為を,実施行為と定義している。\n本件においては,一審原告がE&E社等を経由してエバーライト社から本件製品 を輸入,販売したことを認めるに足りる証拠はない。また,上記認定事実によれば, 一審被告も,本件プレスリリース当時,一審原告による本件製品の輸入,販売を立 証し得る直接的な証拠を有していたわけではない。 しかし,譲渡等の申出については,製品のカタログやパンフレット等を示して販\n売の申出をする行為がその典型的な例であると解されており,製品のカタログ等に\nついては,商社や代理店等がこれを作成する場合があるとしても,製造メーカーが これを作成し,販売会社がそのカタログを利用して譲渡の申出をする場合等が多い\nと推認される。 そして,現代の社会においては,カタログだけではなく,インターネットのウェ ブサイトに製品を掲載してこれを宣伝広告し,販売することも多いことからすれば, 仮に一審原告のような商社が,自社のウェブサイトに,取扱製品と同製品の販売に 必要な情報を直接掲載し,その販売をする趣旨の記載をしていれば,同製品につい て,譲渡等の申出をしていることになると解されるところである。また,そうでな\nくとも,一審原告のような商社が,自社のホームページにおいて,特定の複数の製 造メーカーを紹介した上で,その製品を販売する旨を記載し,その趣旨で当該製造 メーカーのウェブサイトにリンクを貼り,同サイトにおいて各製品の種類と仕様等\nの販売に必要なデータが説明されている場合にも,製造メーカーのウェブサイトを 利用する形での同製品について譲渡の申出をしているものと解される。すなわち,\n商社がそのウェブサイトにおいて製造メーカーのウェブサイトにリンクを貼るだけ\nで,同メーカーのウェブサイトに掲載されている製品のすべてについて常に譲渡の 申出をしていると解することはできないけれども,その商社と製造メーカーとが取\n引関係にあることが記載され,当該商社に問い合わせれば当該製造メーカーの製品 を購入することができる趣旨の記載があり,かつ,製造メーカーのウェブサイトに は,製品の種類や仕様等の販売に必要な情報が開示されているなどの状況があれば, 製造メーカーのウェブサイトにリンクを貼り,これを利用している場合でも,製造\nメーカー作成のカタログを利用する場合と同様に,製造メーカーのウェブサイト掲 載の製品について,譲渡の申出をしていると解される。\nこれを本件についてみるに,一審原告のウェブサイトは,商社である一審原告が, 「半導体 規格品からユーザー仕様まで,ニーズに合わせた半導体やデバイス製品 を豊富な製品ラインアップから提供いたします。」との記載とともに,エバーライト 社を含めた複数の取扱メーカーの名称を列記し,これによりこれらの製造メーカー と一審原告とが取引関係にあることを示した上で,各メーカー紹介のページの中で で,エバーライト社の事業内容がLEDパッケージ等であること等を個別に紹介し, その上でエバーライト社のウェブサイトにリンクを貼り,そのウェブサイトにおい\nて同社が製造販売する各製品とその製品の詳しい仕様をみることができるようにな っているというものである。LEDパッケージは,製品の部品として購入されるも のであるから,これを購入するのは,製造メーカーやその代理店等の取引業者であ ると推認されるところ,一審原告のウェブサイトを見た取引業者は,一審原告が商 社としてエバーライト社の製品(その主力は,前記認定のとおり白色LED製品で あり,本件製品はその一部である。)を取り扱っており,一審原告に問い合わせれば, エバーライト社から白色LED製品等を購入することができると理解するものであ り,また,製品の詳細については,リンクが貼られているエバーライト社のウェブ\nサイトから,その詳しい仕様も見ることができるものである。そして,一審原告の ウェブサイトにおいては,エバーライト社の製品について,一部取扱ができない製 品がある等の記載はない。 上記の状況によれば,一審被告は,一審原告のウェブサイト及びこれとリンクさ れているエバーライト社のウェブサイトを見て,一審原告がエバーライト社のウェ ブサイトに掲載されている白色LED製品等を取り扱っており,取引業者からその 商品を購入したいとの申込みがあり,価格等の条件が合致すれば,これを販売する\nと理解したものであり,一審原告がエバーライト社のウェブサイトに掲載されてい る本件製品を含む白色LED製品について譲渡の申出をしていると理解したとして\nも,無理からぬところである。 そして,一審被告は,その後本件製品と本件製品に使用されているLEDチップ の構造,構\成材料等を分析し,本件特許発明の当時の請求項1の技術的範囲に属す ることなどを確認した上で,先行訴訟を提起し,本件プレスリリースを掲載したの であり,一審被告が本件プレスリリースを掲載したとしても,一審被告には過失が あったものとは認められない。 なお,本件特許発明の請求項1については,その後訂正がなされているものの, 一審原告は,本件訴訟において,仮に一審原告が本件製品の譲渡等をしていたとし ても,本件製品は本件特許権を侵害するものではないから,一審被告による本件プ レスリリースの掲載は,不正競争行為に当たる,等の主張はしていないのであるか ら,本件の不正競争行為の過失の判断において,本件製品が本件特許発明の訂正後 の請求項1の技術的範囲に属するか否かに関し,これ以上詳しく判断する必要はな い。
ウ 一審原告の主張について
一審原告は,単に商社がメーカーのカタログを店舗に備え置いているだけで,譲 渡の申出が認められるとは限らない(カタログの内容や備え置きの態様や利用態様\nにより個別に判断されるべき問題である。),第三者(エバーライト社)の行為や顧 客の行為(クリック行為)を,一審原告の行為と評価することができる法的・事実 的根拠など存在しない,と主張する。 確かに,商社がメーカーのカタログを店舗に備え置いただけで,常に譲渡の申出\nがあると認められるわけではなく,カタログの内容やその備え置きの態様及び利用 態様により,個別に決められるべきであるというのは,一審原告主張のとおりであ る。しかし,一審原告のウェブサイトの記載からは,一審原告がエバーライト社と 取引関係にあり,エバーライト社のウェブサイトに詳細に記載されているLED製 品を販売すると理解することができるのであるから,一審被告が,一審原告のウェ ブサイト及びこれとリンクされているエバーライト社のウェブサイトを見て,一審 原告がエバーライト社のウェブサイトに掲載されている白色LED製品等を取り扱 っており,取引業者からその商品を購入したいとの申込みがあれば,これを販売す\nると理解し,一審原告が,エバーライト社のウェブサイトに掲載されている本件製 品を含む白色LED製品について譲渡の申出をしていると判断したとしても,無理\nからぬところであるのは前記認定のとおりである。 また,一審原告は,一審被告が一審原告による本件製品の輸入,販売及び譲渡の 申出があったと主張することは,事実上先行訴訟の蒸し返しである,先行訴訟と本\n件訴訟とは訴訟物が異なるものの,訴訟経済の観点から,一審被告の上記主張は信 義則に反する,と主張する。 しかし,先行訴訟と本件訴訟とは訴訟物が異なるものであり,のみならず,先行 訴訟の被告であった一審原告が本件訴訟を提起しているものであって,先行訴訟の 原告であった一審被告は,本件訴訟において被告としてその防御活動をしているに すぎず,積極的に先行訴訟の蒸し返しを行っているわけではない。また,本件訴訟 では,一審被告の本件プレスリリースが不正競争行為に当たるか否かのみならず, その行為に過失があるのか,あるいは正当行為として違法性阻却事由があるのかな ども争点になるのであり,一審被告のこれらの主張が信義則に反するということも できない。
エ 結論
以上によれば,一審被告の本件プレスリリースの掲載については,一審被告が, 一審原告のウェブサイトから,一審原告が本件製品について譲渡等の申出をしてい\nると判断したことは無理からぬところである。そして,一審被告は,その後本件製 品と本件製品に使用されているLEDチップの構造,構\成材料等を分析し,本件特 許発明の当時の請求項1の技術的範囲に属することなどを確認した上で,先行訴訟 を提起し,本件プレスリリースを掲載したのであり,一審被告が本件プレスリリー スを掲載したとしても,一審被告には不正競争防止法4条の過失があったものとは 認められない。 よって,一審原告による同法4条に基づく損害賠償請求は理由がない。
2016.02.21
平成26(ネ)10038 著作権侵害差止請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成28年1月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
甲77によれば,データメンテナンス契約に基づくデータメンテナ ンス料は,平成19年10月までは月額5000円,同年11月以降は 月額6000円であったことが認められる。 (イ) 甲69によれば,1審原告の平成18年度のデータメンテナンスに 関する売上高は10億4742万9000円であったこと,その変動経 費は,仕入高(8387万6000円),残債(−8000円),販売 手数料(165万5000円),販促費/リース料S(0円),販促費 /その他(344万3000円),外注費(6604万9000円), 物流費4385万4000円),インセンティブ(423万円),広告 宣伝費(225万1000円),その他管理費(1億4457万400 0円)であったことが認められる。 この点,データメンテナンス契約に係る利益相当額の損害については, 著作権法114条の適用はないものと解され,その損害額の算定に当た っては,売上高から変動経費だけでなく固定費も控除されるべきである。 そして,上記の売上高,変動経費額,メンテナンス料の値引き取引も 行われていたことその他諸般の事情を考慮すると,データメンテナンス 契約に基づくメンテナンス料に対する利益は,メンテナンス料が月額5 000円であるか,6000円であるかを問わず,月額3000円と認 めるのが相当である。
(ウ) 以上を前提に,1審原告のデータメンテナンス契約に係る利益相当 額の損害額を算定すると,次のとおりとなる。 a 平成18年6月から平成21年12月末までの間に販売された被告 CDDBに係る損害 別表2のとおり,上記期間において販売された被告システム(当初\n版)は22本,被告システム(2006年版)は61本である。 そして,別表2によれば,平成19年4月から平成23年4月まで\nの49か月間に販売された被告システム(現行版)は333本であり, 平均して1か月当たり6.79本の被告システム(現行版)が販売さ れたものと認められるから,平成19年4月から平成21年12月末 までの33か月間に販売された被告システム(現行版)は224本(6. 79×33=224)と認められる。そうすると,平成18年6月か ら平成21年12月末までの間に販売された被告システム(当初版, 2006年版及び現行版)は,307本(22本+61本+224本) と認められる。 したがって,上記販売本数に対するデータメンテナンス契約に係る 利益相当額の損害額は,1105万2000円である。 計算式 3000円×12か月×307本=1105万2000円 b 平成22年1月から平成22年12月末までの間に販売された被告 システムに係る損害 上記期間において販売された被告システム(現行版)は81本(6. 79×12=81)となる。そして,この期間においては,その販売 時期を問わず,平成22年12月末までに発生したデータメンテナン ス契約に係る利益相当額が著作権侵害と相当因果関係のある損害とな る一方で,販売時期によって損害の発生期間が12か月に満たないも のがあることを勘案すると,その損害額は,上記販売本数に対する1 年分のデータメンテナンス契約に係る利益相当額の半額と認めるのが 相当である。したがって,上記損害額は,145万8000円と算定 される。 計算式 3000円×12か月×81×0.5=145万8000円 c 合計 前記a及びbの合計額は,1251万円である。
2016.02.21
平成26(ワ)25013 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年1月28日 東京地方裁判所
成人1日あたり0.15〜0.75g/kg体重のイソソ\ルビトールを経口投与されるように用いられる(ただし,イソソ\ルビトールに対し1〜30質量%の多糖類を,併せて経口投与する場合を除く)ことを特徴とする,イソソ\ルビトールを含有するメニエール病治療薬。
まず,特許請求の範囲の記載を見ると,本件発明は,所定量のイソソ\ルビトールを経口投与されるように用いられること(構成要件A)を「特徴とする,イソ\ソルビトールを含有するメニエール病治療薬」の発明であり,メニエール病治療薬を用法用量により特定したものであるが,イソ\ソルビトールの投与量が構\成要件A所定の範囲に含まれるような用法があれば足りるのか(その範囲未満又は超過の投与量での用法があってもよいのか),用法用量がそのような投与量のものに限られるのか(それ以外の用法用量をも有する治療薬は本件発明の技術的範囲から除外されるのか)については,特許請求 の範囲に明示的に記載されていない。 上記アの本件明細書の記載によれば,本件発明は,従来のイソソ\ルビトール製剤(これが被告製品1を指すことは明らかであり,その標準用量は1日当たりイソソ\ルビトール1.05〜1.4g/kg体重に相当する。甲3)の投与量が過大であり,そのために種々の問題が生じるところ,その投与量を構成要件Aに記載の0.15〜0.75g/kg体重という範囲にまで削減することによって上記の問題を解消したというものである。そうすると,本件発明の治療薬は,構\成要件A記載の範囲を超える量のイソソ\ルビトールを投与する用法を排除し,従来より少ない量を投与するように用いられる治療薬に限定されるということができる。換言すると,上記範囲を超える量のイソソ\ルビトールを投与するように用いられる治療薬は,「医師のさじ加減」個々の患者の特徴や病態の変化に応じて医師の判断により投与量が削減された場合には構成要件Aに記載された量で用いられ得るものであっても,本件発明の技術的範囲に属しないと解すべきである。このことは,上記?イのとおり,実施例又は参考例において,イソソ\ルビトールの投与量を時間的推移に着目して変動させたものが見当たらないことからも裏付けられると解される。 したがって,構成要件Aの「成人1日あたり0.15〜0.75g/kg体重のイソ\ソルビトールを経口投与されるように用いられる」とは,上記の用量を,患者の病態変化その他の個別の事情に着目した医師の判断による変動をしない段階,すなわち治療開始当初から,患者の個人差や病状の重篤度に関わりなく用いられることをいうものと解するのが相当である。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 限定解釈
>> ピックアップ対象
2016.02. 3
平成27(行ケ)10171 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年1月28日 知的財産高等裁判所
そこで,本願商標の「i:na」と引用商標の「e−na」を対比す ると,いずれも欧文字3字と1つの記号(「:」又は「−」)からなり,後 半の2文字が「na」である点において共通するが(引用商標中の「a」は 「a」にアクサン記号が付されたもの),冒頭の1文字及び記号はいず れも異なる。特に,引用商標においては,冒頭の「e」の文字が他の文 字よりも大きく表記され,最も看者の注意を惹きやすい文字といえると\nころ,これと本願商標の冒頭の「i」の文字とは,その外観が明らかに 異なる。 また,本願商標の「i:na」の欧文字は,同じ大きさのデザイン化 された太い筆記体の文字が横一列に並べられたもので,全体として整然 とした印象を受けるのに対し,引用商標の「e−na」の欧文字は,手書 き風のややくだけた活字体の書体であることに加え,文字の大きさが統 一されておらず,「n」の文字が他の文字よりやや低い位置に表記され,各\n文字が横一列に整然と並べられていないことから,全体としてやや雑然 とした印象を受けるものといえる。 なお,本願商標の下段部分と引用商標は,欧文字に近接してその読み を表記する片仮名又は平仮名が表\記されている点において共通する が,いずれも欧文字部分に比して極めて小さな表記にすぎないから,こ\nの点は,外観の類否に特段の影響を与えないものというべきである。 (エ) 以上のとおり,本願商標の下段部分と引用商標は,それぞれを構成\nする欧文字3字中の2字を共通にするものの,看者の注意を惹きやすい 冒頭の文字が異なる上,文字の書体,配列等の構成も異なっており,全\n体として受ける印象においても相違することによれば,本願商標の下段 部分と引用商標は,外観において明らかに相違し,その相違の程度は顕 著であるものと認められる。
・・・
エ 取引の実情について
本願商標の指定商品である「ティッシュペーパー,トイレットペーパ ー,その他の紙類」に係る取引又は引用商標の指定役務中の「紙類の小売 等役務」及び「壁紙の小売等役務」に係る取引において,本件審決当時,商 標の称呼のみによって取引が行われる実情があることをうかがわせる証拠 はない。 かえって,ティッシュペーパー,トイレットペーパー等の商品について は,スーパーマーケット,ホームセンター,ドラッグストア等の小売店舗 において,展示販売され,商品に付された商標の外観を確認し得る態様で 販売されることが通常であると考えられるところであり,このことは,本 件審決当時,原告が本願商標を使用して製造・販売するティッシュペーパ ー及びトイレットペーパーについても,これらの小売店舗において広く販 売されている事実(甲2,5,19)からも裏付けられる。また,インタ ーネット販売においても,商品名,商品の画像等から,商品に付された商 標の外観を確認し得るのが通常であるといえる。
オ 小括
以上のとおり,本願商標の要部である下段部分と引用商標は,「イーナ」の 称呼が生じる点では共通するものの,観念において比較することができな い上,外観において明らかに相違し,その相違の程度は顕著であること,さ らに,前記エ認定の取引の実情を総合考慮すると,本願商標及び引用商標 が本願商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されたとしても,取 引者,需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれ があるものといえないから,本願商標と引用商標とは全体として類似して いるものと認めることはできない。 したがって,本願商標が引用商標に類似する商標であるとは認められな いから,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断す るまでもなく,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審 決の判断には誤りがある。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.02. 3
平成27(行ケ)10058 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年1月28日 知的財産高等裁判所
以上のとおり,本件商標は,「Enoteca」の文字部分と「I taliana」の文字部分とから構成される結合商標であるが,その\n外観上,それぞれの文字部分を明瞭に区別して認識することができるこ と,それぞれの文字部分から別異の観念が生じることに鑑みると,本件 商標の「Enoteca」の文字部分と「Italiana」の文字部 分は,それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほ ど不可分的に結合しているものと認められないというべきである。 イ 本件商標の登録査定当時には,「ENOTECA」又は「エノテカ」は,原 告及び原告が行うワインの輸入販売,小売,卸売等の事業ないし営業を表\n示するものとして,日本国内において,取引者,需要者である一般消費者 の間に,広く認識され,周知となっていたこと,本件商標の「Enote ca」の文字部分から,取引者,需要者において,原告の周知の営業表示\nとしての「ENOTECA」又は「エノテカ」の観念が生じることは,前 記ア(イ)認定のとおりである。 他方で,前記ア(ウ)認定のとおり,本件商標の「italiana」の 文字部分から「イタリアの」という観念を生じるが,本件商標の指定役務 との関係においては,本件商標の「italiana」の文字部分は,そ の役務の提供の場所,提供の用に供される物等がイタリアに関連すること を示すものと認識されるにとどまるものといえる。 以上を総合すると,本件商標が「ワインの小売又は卸売の業務について 行われる顧客に対する便益の提供」の役務及びワインに関連する役務に使 用された場合には,本件商標の構成中の「Enoteca」の文字部分は,取\n引者,需要者に対し,上記各役務の出所識別標識として強く支配的な印象 を与えるものと認められ,独立して役務の出所識別標識として機能し得る\nものといえる。 そうすると,本件商標から「Enoteca」の文字部分を要部として 抽出し,これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断すること も,許されるというべきである。 ウ これに対し,被告らは,本件商標は,外観が不可分一体で,称呼も一連 一体であり,観念についても,その構成全体から,ワインを販売・提供す\nる店舗の名称あるいは被告会社の周知な店舗名を表すものであること,本\n件商標の構成中の「Enoteca」の文字部分は強く支配的な印象を与\nえるものはいえないことなどからすると,本件商標から「Enotec a」の文字部分のみを要部として抽出することはできない旨主張する。 しかしながら,被告らの主張は,以下のとおり理由がない。 (ア) 被告らは,本件商標は,縁取りして統一的に図案化されたワインレ ッド色の「Enoteca Italiana」の文字をまとまりよく一 体的に表してなるロゴタイプの商標であり,本件商標から「エノテカイ\nタリアーナ」の一連の称呼がよどみなく生じるから,本件商標は,色彩 や形態によって外観が不可分一体であり,称呼も一連一体である旨主張 する。 しかしながら,前記ア(ア)認定のとおり,本件商標は,その構成全体\nから「エノテカイタリア−ナ」の称呼が生じるが,一方で,本件商標は,そ の構成中の「Enoteca」の文字部分と「Italiana」の文\n字部分との間に空白があること,それぞれの文字部分の冒頭の文字が大 文字で,冒頭以外の文字が小文字であることからすると,本件商標の外 観上,「Enoteca」の文字部分と「Italiana」の文字部 分とを明瞭に区別して認識することができるから,本件商標の外観が不 可分一体であるということはできない。 また,本件商標の構成全体から「エノテカイタリア−ナ」の称呼が自\n然に生じることからといって直ちに本件商標から「Enoteca」の 文字部分を要部として抽出することができないとはいえない。 したがって,被告らの上記主張は,本件商標から「Enoteca」の 文字部分のみを要部として抽出することはできないことの根拠となるも のではない。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成26(ワ)12198 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年12月24日 東京地方裁判所
このように,本件特許発明1において,加入者装置は,構成要件1Cで「候補サブキャリアのセット」の「選択」を行い,構\\成要件1Dで,上記「選択」した「候補サブキャリアのセット」に関して情報提供を基地局に行うものである。 一方,LTE規格の非周期的CQIレポートの高次階層設定サブバンドフィードバックモードにおいては,加入者装置(ユーザ端末)は,N個のサブバンドで構成されている全帯域の「N個のサブバンド全部」について,サブバンド差分CQI値を報告することとされている(当事者間に争いがない。また,前記(2)のとおり,LTE規格の仕様書には,高次階層設定サブバンドフィードバックの欄に,ユーザ端末が,各サブバンドセットについて1つのサブバンドCQI値を報告しなければならない旨の記載がある。)。 イ 原告は,本件通信システム方法において全部のサブバンドが選択されている旨主張するが(見解1),このように,LTE規格の上記モードにおいて,全てのサブバンドについて情報提供が義務付けられているとすれば,これは本件特許発明1の特徴である「選択したものについて情報提供を行う」との処理とは異なるものであって,構成要件1Cでいう「選択」や,それに引き続く構\\成要件1Dの「情報提供」があるとはいえない。 広辞苑第6版(乙3)によれば,「選択」とは,「えらぶこと。適当なものをえらびだすこと。良いものをとり,悪いものをすてること。」を意味するとされており,「選択」とは,何らかの基準を充たすものを選び出すことを意味すると解すべきである。 なお,前記(1)オ(ア)のとおり,本件明細書には,「各加入者は(中略)性能の良い(中略)複数のサブキャリアを選択して,それら候補サブキャリアに関する情報を基地局にフィードバックする。」と記載されており(甲4),これは実施例に関する記載ではあるが,各加入者が性能\\の良いものを選び出し,その選択したサブキャリアに関する情報を提供するという過程が記載されており,上記解釈を裏付けるものである。 また,選択を行う者が,何らかの基準に従って対象物につき選択を行った結果,全てが選ばれる場合も想定し得るが,上記のとおり,非周期的CQIレポートの高次階層設定サブバンドフィードバックモードにおいては,加入者装置(ユーザ端末)は,常に全てのサブバンドについてのサブバンド差分CQI値を報告することとされており,このような場合には「選択」の余地はないというべきである。 なお,前記(1)オ(ア)のとおり,本件明細書には「このフィードバックには,全てのサブキャリアについて又は一部のサブキャリアだけについてのチャネルと干渉の情報(中略)が含まれる」(段落【0010】)との記載があるが(甲4),これはあくまで,結果的に「全てのサブキャリア」が選択されることもあり得ることを前提とした記載というべきであって,常に「全てのサブキャリア」が選択されることを前提とした記載ではない。 原告は,情報処理技術分野においては,「全部の選択」等の用語の用い方はごく一般的であり,本件特許発明の「選択」の技術的意義については,単なる日本語の語義に基づくことは誤りであるとも主張する。しかし,本件特許の関連技術分野全てにおいて「選択」との文言が上記のように用いられることが通常であることを認めるに足りる証拠はないし,本件明細書においても,「選択」との文言の意義につき特段の説明はないから(甲4),原告の上記主張は採用できない。このほか,原告は,全サブバンドについてサブバンド差分CQIのフィードバックを行うことによって,情報量の低減効果があるとも主張するが,情報量の低減効果の有無と,サブバンドの「選択」の有無とは,直接関係がないことである。
ウ 以上のとおり,本件通信システム方法において全部のサブバンドが選択されているとの原告の主張(見解1)を前提にすると,本件通信システム方法では,加入者装置(ユーザ端末)において本件特許発明1の規定する「選択」をしていないから,構成要件1Cを充足せず,更に,選択したものについて「情報提供」をしているともいえないから,構\\成要件1Dも充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成26(ワ)371 債務不存在確認請求事件 特許権 平成27年12月25日 東京地方裁判所
(1) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1並びにこれを引用する同請求項2,同請求項4及び同請求項6においては,本件各発明が,「位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段」(構成要件C)を具備することを特徴とするタッチパネルシステムであることが規定されている。上記「複数の指示部位」には,当然,指示部位が2個である場合と指示部位が3個以上である場合の双方が含まれるところ,上記特許請求の範囲の記載の文理や,本件明細書において,入力検出面に3つの位置指示具が存在する場合に,当該3個所の位置(光量が0の領域)の中から最外端にある2個所の位置(光量が0の領域)を特定する実施例について説明がされていること(甲3の【0035】,【図7】)からすれば,当該タッチパネルシステムが具備するところの「距離算出手段」は,「位置検出手段により検出される指示部位が2個であれ3個以上であれ,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段」であると解される(換言すれば,「位置検出手段により検出される指示部位が2個である場合には,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出するが,位置検出手段により検出される指示部位が3個以上である場合には,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出するわけではない距離算出手段」はこれに当たらないと解される。)。なお,上記「最外端」という文言それ自体の意義については一義的でないようにも思われるが,本件明細書の【0035】,【0040】,【図7】,【図10】の記載及び弁論の全趣旨に照らせば,「最外端にある2個所」とは,「互いに最も離れた位置にある2個所」を指すものと解するのが相当である。\nそうすると,位置検出手段により検出される指示部位が3個以上である場合に,それら指示部位のうち最外端にある2個所(互いに最も離れた位置にある2個所)の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段を具備していなければ,当該タッチパネルシステムは,構成要件Cを充足しないというほかはない。
(2) これに対し,被告は,通常の用法である「2本指のピンチジェスチャ」(指示部位が2個である場合)においては,2つのタッチ位置が「複数の指示部位のうち最外端の2個所」にそのまま該当し,侵害となる以上,実用上特殊な場合である「3本指以上のピンチジェスチャ」(指示部位が3個以上である場合)を殊更取り上げることに意味はないなどと主張する。 しかしながら,前記(1)で説示したとおり,本件各発明の構成要件の充足性を判断するに当たっては,当該タッチパネルシステムが具備する距離算出手段がどのような距離算出手段であるのかが問われるのであって,被告の上記主張のように特定の使用態様(2本指のピンチジェスチャ)のみに着目することによって,「複数の指示部位」という文言が指すもののうちから「2個の指示部位」の場合のみを切り出し,その場合のみを基に侵害判断をすることは相当でない。そして,2本指のピンチジェスチャが通常の用法であるとしても,1)「複数の指示部位」という文言が「3個以上の指示部位」の場合をも含むことは当然である上,2)実際,頻度は少ないにせよ「3個以上の指示部位」が検出される場合があり得ること,3)被告自身,本件明細書(【0035】【図7】)において,3つの位置指示具が存在する場合について説明をしていることに照らすと,指示部位が3個以上である場合を取り上げることに意味がないなどということはできない。さらに,「最外端」の特定は,発明における動作原理にも関係することを考慮すると,被告の上記主張は到底採用することができない。
(3) 以上を前提として原告製品について検討すると,位置検出手段により検出される指示部位が3個以上である場合に,それら指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段を原告製品が具備していることを示す証拠はない。 かえって,証拠(甲9,18,19)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品のタッチパネルに3本ないし5本の指で1本ずつタッチしてピンチ操作を行った場合,表示イメージの拡大縮小は,最外端にある2個所(互いに最も離れた位置にある2個所)の指の間の距離に基づいて実行されるものではなく,最初及び2番目にタッチされた2本の指に基づいて実行されることが認められる。
(4) そうすると,原告製品は,構成要件Cを充足しないというほかはない。\n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成27(ワ)7033 不正競争差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成28年1月14日 東京地方裁判所
原告らの不正競争防止法2条1項3号に基づく請求に対し,被告らは,原告加湿器1及び2は同号により形態が保護される「商品」に当たらない旨主張する。 そこで判断するに,同号が他人の「商品」の形態の模倣に係る不正競争を規定した趣旨は,市場において商品化するために資金,労力等を投下した当該他人を保護することにあると解される。そして,事業者間の公正な競争を確保するという同法の目的(1条参照)に照らせば,上記「商品」に当たるというためには,市場における流通の対象となる物(現に流通し,又は少なくとも流通の準備段階にある物)をいうと解するのが相当である。 論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告加湿器1及び2は加湿器として開発されたものであり,使用するためには電源が必要になるところ,原告が平成23年11月及び平成24年6月に展示会に出品した際には,いずれも加湿器の本体を外部電源に銅線で接続することにより電気の供給を受ける構成となっていた。(甲3,5,20)\n
イ 原告らは,平成24年7月,被告スタイリングライフの担当従業員から原告加湿器2の製品化について問合せを受けたのに対し,原告らと考えの合致する製造業者が見つかっておらず,製品化の具体的な日程は決まって いない旨回答した。(甲7)
ウ 原告らは,平成27年1月5日頃,原告らのウェブサイトで原告加湿器3の販売を開始した。原告加湿器3は,加湿器本体とUSB端子がケーブルで接続され,これにより電気の供給を受ける構成となっている。(甲16,17)\n上記事実関係によれば,原告加湿器1及び2は,上記各展示会の当時の構成では一般の家庭等において容易に使用し得ないものであって,開発途中の試作品というべきものであり,被告製品の輸入及び販売が開始された平成25年秋頃の時点でも,原告らにおいて原告加湿器1及び2のような形態の加湿器を製品化して販売する具体的な予\\定はなかったということができる。そうすると,原告加湿器1及び2は,市場における流通の対象となる物とは認められないから,不正競争防止法2条1項3号にいう「商品」に当たらないと解すべきである。
・・・
そこで判断するに,同法2条1項1号は「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」旨,同条2項は「この法律にいう『美術の著作物』には,美術\n工芸品を含むものとする」旨規定している。これらの規定に加え,同法が文化の発展に寄与することを目的とするものであること(1条),工業上利用することのできる意匠については所定の要件の下で意匠法による保護を受けることができることに照らせば,純粋な美術ではなくいわゆる応用美術の領域に属するもの,すなわち,実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えている場合を除き,著作権法上の著作物に含まれないものと解される。
(3)これを本件についてみるに,証拠(甲3,5,20)及び弁論の全趣旨によれば,原告加湿器1及び2は,試験管様のスティック形状の加湿器であって,本体の円筒状部の下端に内部に水を取り込むための吸水口が,本体の上部に取り付けられたキャップの上端に噴霧口がそれぞれ取り付けられており,この吸水口から内部に取り込んだ水を蒸気にして噴霧口から噴出される構造となっていることが認められる。そして,以上の点で原告加湿器1及び2が従来の加湿器にない外観上の特徴を有しているとしても,これらは加湿器としての機能\\を実現するための構造と解されるのであって,その実用的な機能\\を離れて見た場合には,原告加湿器1及び2は細長い試験管形状の構造物であるにとどまり,美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えていると認めることはできない。\n
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 商品形態
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成26(ワ)34145 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年1月14日 東京地方裁判所
本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明の欄には,本件発明の実施形態が記載されているところ(段落【0027】〜【0134】,【図1】〜【図21】),この実施形態においては,「Web−POSクライアント装置」の表示画面に「明細フォーム」(カテゴリ,メーカコード,商品番号,商品名,単価,数量,金額といった注文商品明細が表\示されているもの。【図10】〜【図12】,【図17】〜【図21】。)が表示され,「オーダ・ボタン」のクリックに応答して,「Web−POSサーバ・システム」へ明細フォーム中のカテゴリ,メーカコード等の全フィールドを送信し,「Web−POSサーバ・システム」においてこの明細フォームを受信することとなっているところ(段落【0056】,【0111】〜【0125】,【0127】,【図12】),「オーダ・ボタン」のクリックにより「Web−POSサーバ・システム」が受信するのが「注文情報」であることから(構\成要件F4),上記明細フォームは「注文情報」に相当するので,「注文情報」には商品名,価格等の商品基礎情報が含まれている。また,本件明細書には本件発明の他の実施形態の説明も記載されているが(段落【0134】〜【0139】),いずれも「明細フォーム」を利用するものであり,「注文情報」に商品基礎情報を含まない構成についての記載は見当たらない。\nこれら本件明細書の記載を考慮して「注文情報」の意義を解釈すると,本件発明は,「Web−POSクライアント装置」の表示画面に明細フォームその他商品基礎情報を含む情報を表\示した上で,「オーダ・ボタン」のクリックに応答して,これらの情報を「Web−POSサーバ・システム」に送信するという構成を採用したものと認められる。したがって,「Web−POSクライアント装置」が送信して「Web−POSサーバ・システム」が受信する商品の注文に関する情報にカテゴリ,メーカコード,商品名,価格等の商品基礎情報が含まれていない場合には,構\成要件F4,G及びHの「注文情報」に当たらないと解するのが相当である。 ウ 「注文情報」を上記のように解釈することは,本件特許の出願経過における原告の説明とも一致する。すなわち,原告は,平成23年10月9日付け意見書(乙20)において,引用文献1(乙11)との相違点につき,1)引用文献1における注文情報は購入者ごとに生成される情報であって,この購入者ごとの注文情報は,商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報である本件発明の「注文情報」とは異なる(乙20の11〜12頁),2)用文献1には,商品注文明細情報の生成及び表示過程に関する詳細な記載がなく,ユーザが注文した情報に売上管理等に必須となる商品識別情報及びこれに対応する商品基礎情報が含まれていないのに対し,本件発明では「注文情報」に商品識別情報とこれに対応する商品基礎情報が含まれている(同12〜13頁)と説明しており,これら1)及び2)の説明は上記の解釈と整合するということができる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.01.25
平成27(行ケ)10159 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年1月20日 知的財産高等裁判所
しかしながら,本願商標は,その外観上,「Reebok」の文字部分,図 形部分及び「ROYAL FLAG」の文字部分を組み合わせて成る結合商標であ ると認められるが,前記(1)のとおり,右側に鋭角の頂点を有する黒地の三角形の左 端に縦に白線を表し,当該三角形全体を左から右に波打つように旗状に表\\した図形 を中央に大きく配し,その上段に,「Reebok」の文字を図案化された特徴の ある書体で表し,図形の下段に「ROYAL」及び「FLAG」の各文字を1文字\n程度の間隔を空けて,上段の文字部分よりも小さく,かつ細いゴシック体で表して\n成るものであり,全体としてまとまりよく表されている。これに加え,中央に配さ\nれた図形の大きさ及びその形状並びにその上段に配された「Reebok」の文字 の大きさ及びその図案化された特徴のある書体に比べ,図形部分の下段に配された 「ROYAL FLAG」の文字部分は,小さく,すなわち「ROYAL FLA G」の冒頭の「R」と「Reebok」の冒頭の「R」の文字の大きさを比べると, 前者は後者の10分の1程度の大きさしかなく,かつ細い文字で表され,しかも,\nゴシック体という一般的な書体であるから,その外観上,「ROYAL FLA G」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているというこ\nとはできない。
ウ また,「ROYAL FLAG」という一連の語は,既成語として辞書に掲 載されているものではないが,「ROYAL」及び「FLAG」は,我が国にお ける英語の普及率に照らせば,いずれも一般的な英単語であって,格別のものでは ないこと,「ロイヤル(royal)」が国語辞典に掲載されているだけでなく (甲50),これを付した複合語(例えば,「ロイヤル・ウェディング(roya l wedding)」,「ロイヤル・スマイル(royal smile)」, 「ロイヤル・ファミリー(Royal Family)」,「ロイヤルブルー(r oyal blue)」,「ロイヤル・ボックス(royal box)」,「ロ イヤル・ミルク・ティー(royal milk tea)」など)も,カタカナ ・外来語辞典等に数多く掲載されていること(甲51,52),「フラッグ(f lag)」が国語辞典に掲載されているだけでなく(甲35,41),これと他の 語との複合語(例えば,「チェッカー フラッグ(checker flag)」, 「チャンピオン フラッグ(champion flag)」,「ナショナル フ ラッグ(national flag)」,「ナショナル フラッグ キャリアー (national flag carrier)」,「フラッグ・ショップ(f lag shop)」など)も,外来語辞典等に複数掲載されていること(甲37 〜40,44),「ROYAL」又は「FLAG」の英単語を含む商標登録も数 多く存在すること(甲56〜59)等に照らせば,一般的な英単語をつないだもの にすぎないというべきである。そして,「ROYAL FLAG」の文字部分は, それ自体が自他商品を識別する機能が全くないというわけではないものの,商品の\n出所識別標識として強く支配的な印象を与える「Reebok」の文字部分との対 比においては,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印 象を与えるものであるということはできず,本件全証拠によるも,このようにいえ るだけの事情を認めるに足りない。 エ したがって,本願商標の構成のうち「ROYAL FLAG」の文字部分だ けを抽出して,引用商標と比較して類否を判断することは相当ではない。
◆関連事件です。平成27(行ケ)10158
こちらは「REEBOK ROYAL FLAG」と標準文字にて横一行で表した結合商標です。\n
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> ピックアップ対象
2016.01.22
平成26(ワ)25282 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年1月14日 東京地方裁判所
ア 乙16文献には次の趣旨の記載がある。(乙16) 楽天市場のオンラインショッピングなら,ジャンルを掘り下げていくだけで目的の商品まで簡単にたどり着くことができる。ここでは北海道・函館の地ビールを検索する。トップページの「商品名で調べる」又は「商品別」をクリックして商品名で探すこともできる。表示されているジャンル名「ドリンク・アルコール類」から開始し,その先は「ビール・地ビール」→「地ビール」→「北海道」とジャンルが絞られていき,その度にそれぞれのジャンルでの検索結果に商品名が表\示される。金額も表示されるので,わざわざ店のホームページにアクセスしなくても商品を選べるのは利点だ。(66頁) 商品別で検索したときも,商品名をクリックすれば,店舗のホームページにアクセスして,その商品の紹介ページが見られる。「はこだてビール」の店舗のホームページには「オリジナルギフトセット」というジャンルがあり,このジャンルの画像や価格,セット名を一覧表示することができたので,その中から商品を選ぶことにした。(68頁)
イ 楽天市場のトップページから順次表示されるものであり,楽天市場の全体\nルギフトセット」のジャンルは,特定の商品を取り扱う店舗のホームページに表示されるものであり,当該店舗が設定した商品分類に基づく店舗カテゴリであると,それぞれ認めることができる。そして,乙16文献に記載されたインターネットショッピングモールに係る発明(乙16発明)においては,ある共通カテゴリが示された場合に・・・のであるから,商品と共通カテゴリ及び店舗カテゴリを示す情報が相互に結び付けられるように記憶されていると認められる。また,ある店舗が取り扱う商品に係る情報から当該店舗独自のカテゴリ及びこれに分類される商品が表\示される(同)のであるから,ある商品がどの店舗カテゴリに属するか,その店舗カテゴリにどの商品が属するかを識別するに足りる情報が記憶されているということができる。
ウ 以上によれば,乙16発明は,本件各発明の前記争いのある各構成をいずれも備えていると認められる。\n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2016.01.20
平成27(行ケ)10096 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成28年1月13日 知的財産高等裁判所
本件において,引用商標の指定商品「電子応用機械器具及びその部品」には,「電 子計算機用プログラム」が含まれるところ,遅くとも本件商標の出願時には,電子 計算機用プログラムは,記録媒体に記録された電子計算機用プログラムとして店頭 にて販売されていたのみならず,インターネットを通じたダウンロードにより流通 されており,さらには,インターネット等の通信回線を通じ,サーバ上に保管され た電子計算機用プログラムを使用させる役務として提供されていたものと認められ る(甲132)。 一方,本件商標の指定役務中「ウェブログの運用管理のための電子計算機用プロ グラムの提供等」の役務で提供される内容は,いずれも「電子計算機用プログラム」 であるから,商品「電子計算機用プログラム」の製造・販売者がかかる役務の提供 を行うことも少なくないものと考えられる。また,商品「電子計算機用プログラム」 の需要者と,役務「電子計算機用プログラムの提供」の需要者は,いずれも,コン ピュータ等を用いて電子計算機用プログラムを使用する者であるから,共通すると いえる。さらに,上記認定のとおり,電子計算機用プログラム自体の流通と,電子 計算機用プログラムの提供とは,共にインターネット等の通信回線を通じて行われ ることもあると解されるから,取引形態も共通する。そして,これらの事情は,電 子計算機用プログラムの用途の内容,例えば,ウェブログの運用管理,オンライン によるブログ作成,インターネット上の情報閲覧などに限られるか否かによって異 なるものとは認められない。 したがって,商品「電子計算機用プログラム」と役務「ウェブログの運用管理の ための電子計算機用プログラムの提供等」とに同一又は類似の商標を使用する場合 は,同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそ れがあると認められる関係があるといえる。
(2) これに対して,原告は,引用商標の指定商品「電子応用機械器具及びその 部品」に含まれる「電子計算機用プログラム」はあくまでも電子応用機械器具の部 品としてのプログラムに限られるから,ウェブサイト上でのコンピュータプログラ ムの提供などとは類似しない,と主張する。 しかし,仮に,特定分野の電子計算機用プログラムが商品としてのみ流通してお り,ウェブサイト上などでは提供されてはいないという状況があったとしても,一 般的には,前記認定のとおり,電子計算機用プログラムが,インターネット等を通 じてダウンロードにより流通されると同時に,サーバ上に保管された電子計算機用 プログラムをインターネット等の通信回線を通じて使用させる役務として提供され ていたものと認められる。商品としてのみ流通している電子計算機用プログラムと, ウェブサイト上などでも電子計算機用プログラムが提供されている場合とで,その 製造・販売・提供者や商品・役務の内容,それぞれの需要者が異なると認めるに足 りる証拠はない。したがって,商品「電子計算機用プログラム」と役務「ウェブロ グの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供等」とに同一又は類似の商標 を使用する場合は,同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る商品又は役務と 誤認されるおそれがあると認められる関係があるといえる。
関連カテゴリー
>> 商4条1項各号
>> 誤認・混同
>> 役務
>> 類似
>> ピックアップ対象
2016.01.20
平成27(行ケ)10069 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年1月14日 知的財産高等裁判所
特許法29条1項2号にいう「公然実施」とは,発明の内容を不特定多数の者が 知り得る状況でその発明が実施されることをいうものである。本件のような物の発 明の場合には,商品が不特定多数の者に販売され,かつ,当業者がその商品を外部 から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん,外部からはわからなく ても,当業者がその商品を通常の方法で分解,分析することによって知ることがで きる場合も公然実施となる。 前記のとおり,本件製品は,小売店であるディスカウントショップで商品として 販売されていたため,不特定多数の者に販売されていたと認められる。また,前記 争いのない事実によれば,当業者であれば,本件製品の構成F以外の構\成は,その 外観を観察することにより知ることができ,本件製品の構成Fについても,本件製\n品の保持部分を分解することにより知ることができるものと認められる。 そして,本件製品が販売されるに当たり,その購入者に対し,本件製品の構成を\n秘密として保護すべき義務又は社会通念上あるいは商慣習上秘密を保つべき関係が 発生するような事情を認めるに足りる証拠はない。 また,本件製品の購入者が販売者等からその内容に関し分解等を行うことが禁じ られているなどの事情も認められない。本件製品の購入者は,本件製品の所有権を 取得し,本件製品を自由に使用し,また,処分することができるのであるから,本 件製品を分解してその内部を観察することもできることは当然であるといえる。 以上によれば,本件製品の内容は,構成Fも含めて公然実施されたものであると\n認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本件製品の構成Fは本件製品を破壊しなければ知ることができない\nし,本件製品のパッケージ裏面の「意図的に分解・改造したりしないでください。 破損,故障の原因となります。」との記載(甲4)により,本件製品の分解が禁じら れており,内部構造をノウハウとして秘匿するべく購入者による本件製品の分解を\n認めていないのであるから,本件製品の購入者は社会通念上この禁止事項を守るべ きであり,警告を無視する悪意の人物を想定し,本件製品の破壊により分解しなけ れば知ることができない構成Fについて「知られるおそれがある」と判断すること\nは特許権者である原告に酷である旨主張する。 しかし,本件製品のパッケージ裏面の前記記載は,その記載内容等に照らすと, 意図的な分解・改造が本件製品の破損,故障の原因となることについて購入者の注 意を喚起するためのものにすぎないといえる。本件製品のパッケージ裏面の意図的 な分解・改造が破損,故障の原因となる旨の記載により,この記載を看取した購入 者がそれでもなお意図して本件製品を分解し,本件製品を破損・故障させるなどし た場合については,販売者等に対し苦情を申し立てることができないということは\nあるとしても,この記載を看取した購入者に本件製品の構成を秘密として保護すべ\nき義務を負わせるものとは認められず,そのような法的拘束力を認めることはでき ない。また,上記記載があるからといって,社会通念上あるいは商慣習上,本件製 品を分解することが禁止されているとまでいうことはできず,秘密を保つべき関係 が発生するようなものともいえない。 仮に,原告が本件製品のパッケージ裏面に前記記載をした意図が購入者による本 件製品の分解禁止にあったとしても,前記認定を左右するものではない。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
・・・・前記認定のとおり,本件製品のパッケージ裏面の記載は,意図的な分解・ 改造が破損,故障の原因となることについて購入者の注意を喚起するためのものに すぎず,原告の意図がどのようなものであれ,これによってこの記載を看取した購 入者と販売者等との間に本件製品の分解等について何らかの法的関係を発生させる ものではない。