|
|
価値あるビジネス特許をいかに取得するか
How to obtain valuable business method patents
弁理士 古谷栄男
Hideo Furutani, Patent Attorney
目次
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.経営環境の変化と特許
1.産業革命と特許
2.IT革命と特許
Ⅲ.企業にとって価値あるビジネス特許とは
1.事業遂行とビジネス発明の価値
2.ビジネス特許としての価値
Ⅳ.特許要件
1.発明の成立性
2.新規性
3.進歩性
Ⅴ.着想を特許にする具体策
1.有効な特許を取得できない原因
2.三者ブレインストーミング
3.発明創造ブレインストーミング
Ⅵ.まとめ
Ⅰ.はじめに
企業におけるビジネス特許戦略としては、特許の取得、運用という攻めの側面と、他社特許の侵害回避、対応という守りの側面と大きくわけられるであろう。本稿では、ビジネス特許の取得に焦点を当て、企業において、いかにして価値のあるビジネス特許を取得するかというテーマについて述べる。特に、ビジネスの着想を、価値ある特許出願に結びつける具体的な手法について考察を行う。
価値ある特許出願を行うためには、どのようなビジネス発明に特許が与えられるのか、また、どのようなビジネス特許が企業に力をもたらすのかを知らねばならない。そこで、まず、企業にとってのビジネス特許の価値、ビジネス特許取得のための要件について、ビジネス特許の特質を考慮した考察を行った。
次に、これらの考察を踏まえた上で、ビジネスの着想を、価値ある特許にするための具体的手法について、まとめてみた。
筆者は、弁理士として、特許取得のための特許出願明細書を作成し、代理人として特許庁に対する手続を行うものであり、企業内の特許業務担当者という立場にない。しかし、特許権の取得をサポートする弁理士として、いくつかの企業において、ビジネスの着想を発明化して特許出願するためのコンサルティングを行ってきた。本稿において紹介する具体的手法は、このような経験を基礎としてまとめたものである。
Ⅱ.経営環境の変化と特許
1.産業革命と特許
1760年代、産業革命を成功させた英国は、特許制度を巧みに活用した。産業革命によって物の大量生産が可能となり、事業者にとって、製品に関する特許が重要な意味を持つようになった。これにより、特許取得が活発化し、新技術が次々と事業化され、それが新たな特許を生み出すという特許サイクルが動き始めたのである。産業革命は各国に波及し、それとともに、特許取得の活発化現象も各国に広がっていった*1。
2.IT革命と特許
では、今日のIT革命の中で、企業における特許の重要性はどのように変化しているのであろうか。IT革命の進行により、知恵の時代が到来したといわれている。これは、企業活動における販売網の構築を例として考えるとわかりやすい。IT革命以前であれば、いくら素晴らしい製品やビジネスのアイディアを持っていても、既に販売網を形成している企業に太刀打ちすることは困難であった。しかし、企業規模の大小を問わず平等に与えられたインターネットというインフラが登場・普及したため、従来型の販売網を有していることが大きなアドバンテージではなくなった。
上記のように、企業の競争力を決定付ける要因として、製品やサービスのアイディアの重要性が高まっている。したがって、このアイディアを権利化した特許を有しているか否かが、企業間競争の大きなウエイトを占めるようになってきている。
また、特許は、適正な競争がなされている場合に大きな力を発揮するものである。IT革命とともに、あらゆる業種において新規参入の障壁が低くなり、本格的な競争が始まり、特許の重要性が高まっている
たとえば、逆オークションで有名なPriceline.comのように、特許によって事業立ち上げの資金を調達し、成果を得た企業も現れるようになった。このような資金調達が可能となったことは、参入障壁が低くなったことによる特許の重要性の高まりを裏付けるものである。その他、IBMの特許ライセンスによるキャッシュフローの改善、テキサス・インスツルメンツが行った特許目的のM&A、株式市場が特許を評価し始めた点など、近年、企業活動における特許の重要性が高まっていることを示す現象が起こっている。
いずれにしても、産業革命によって重要性を増した特許は、IT革命とともに、さらにその重要性を増していると見てよいであろう。筆者は、企業における特許の使い方が変革したという点において、この現象を特許革命と呼んでいる。近年のビジネス特許に対する注目は、特許革命の一環であると考えられる。
Ⅲ.企業にとって価値あるビジネス特許とは
1.事業遂行とビジネス発明の価値
発明により構築されるビジネス手法やシステムなどが、企業の事業遂行に関係していなければ、当該企業にとって、そのビジネス発明の価値は低い。多くの企業にとって、自社が実施しており(あるいは実施予定であり)、利益を生み出すことのできるビジネス手法の発明は、価値が高いものとなる。また、アイディアとして優れたビジネスモデルであっても、社会インフラや技術との関係で実現性の無いものは、価値が低いであろう。さらに、利益を生む仕組みであっても、その企業のポリシーに合致せず、実施の可能性がないビジネス発明は、事業性が無く、価値が低いことになる。また、ライセンス供与を中心に据えている企業では、ビジネス発明の価値判断は違ったものになろう。
このように、ある企業にとっては価値のあるビジネス発明であっても、他の企業にとって、それはあまり価値のないものであるかもしれない。つまり、発明の事業性は、各企業によってその判断基準が異なっている。
社内から広くビジネスモデル特許のアイディアを募集するケースも増えているが、自社の方向性に合致したアイディアが多く集まるように工夫しなければ、あまりにも効率の悪い結果となるので注意が必要である。
2.ビジネス特許としての価値
事業に関する特許の価値は、当該事業をいろいろな側面からカバーする複数の特許が取得できているか否かに大きく左右される。図1に示すように、基本的なビジネス特許を取得していても、その応用特許・周辺特許を他社に押さえられているのでは、特許の価値は低いと言わざるを得ない。したがって、基本となるビジネス特許だけでなく、その応用特許・周辺特許も自社で取得し、他社の参入を排除できていることが好ましい。
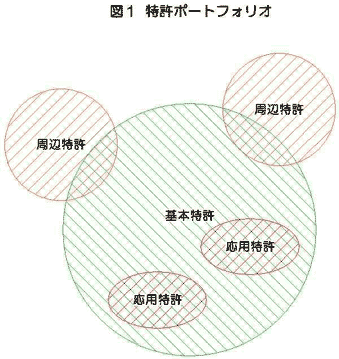
つまり、図1に示すような応用特許・周辺特許も含めた特許ポートフォリオを形成できるような特許取得戦略を構築する必要がある。
Ⅳ.ビジネス特許の要件
ビジネス発明に限らず、特許を取得するためには、法定の要件を満たさねばならない。ここでは、主たる要件である、i)発明の成立性、ii)発明の新規性、iii)発明の進歩性について述べる。
1.発明の成立性
特許法は、発明を保護対象とし、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと定義している(特許法2条)。したがって、この定義に合致しないものに特許は与えられない。ビジネス発明をはじめとするソフトウエア関連に関しては、発明に該当するか否かが問題となるケースが多いため、特許庁は、ソフトウエア関連発明の成立性について審査基準*2を定めている。
この審査基準において、経済法則や人為的な取決めなどは、自然法則を利用した技術的思想でなく、発明に該当しないとしている(審査基準 第?部 第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明 2.2参照)。したがって、ビジネスの仕組みや手法そのものは、発明に該当せず、特許は付与されない。
一方、経済法則や人為的取決めなどに関するものであっても、コンピュータを用いた装置やシステムであれば、発明に該当しうるとしている。したがって、コンピュータを用いたビジネスモデルは、発明に該当し、後述の新規性・進歩性を充足すれば*3特許を取得できる可能性がある。
2.新規性
上記発明に該当するものであっても、新規性がなければ、特許は付与されない(特許法第29条1項)。すなわち、特許出願の時点において、その発明が世の中に知られていないことが求められる。したがって、出願より前に、雑誌や論文などで発表したビジネスモデルなどは、新規性を欠くとして特許を取得することができない。
3.進歩性
成立性、新規性に加えて、進歩性が要求される(特許法第29条2項)。新規であるだけでは、特許要件を満たさない。出願時点において既に知られているビジネス手法などに基づいて、当該分野の専門家*4が簡単に思いつくような発明は、進歩性がないとして特許を取得することができない。たとえば、既に知られているビジネスモデルを、単にコンピュータ化したに過ぎないような発明は、進歩性がないといえよう(前掲審査基準 2.3.4(4)参照)。
Ⅴ.着想を特許にする具体策
1.有効な特許を取得できない原因
企業において、事業遂行に有益なビジネス特許を効果的に取得できない大きな原因として、社内体制の不備と経営責任者を含めた各人の特許化能力の不足があげられる。これらが欠けていると、着想があるにもかかわらず、特許を取得できないか、あるいは、無駄な特許の取得に終わってしまう可能性がある。
以下、新規事業全体にかかるビジネス発明と既存事業にかかるビジネス発明に分けて、着想を眠らせずに特許化するための方策を検討する。
2.三者ブレインストーミング
企業において有効なビジネス特許を取得していくためには、企業戦略に沿ったビジネス発明を見出して権利化していく必要がある。
IT革命以前において、経営責任者の会議から重要な発明が産み出されることは、ほとんどなかったと言ってよい。しかし、今や、企業戦略の根幹にかかわるような最も有益なビジネス発明は、経営責任者もしくはそれに近いポジションから生み出される可能性が高い。したがって、経営責任者や事業責任者自らが特許マインドを身につけるか、あるいは、経営方針会議に特許専門家を加えるなどの方策が必要であろう。このような仕組み作りのできていないことが、有効な特許を取得できない原因となっているケースがある。
今まで、特許出願になじみの無かった企業はもちろんであるが、既に特許出願の経験が深い企業においても、特許体制が硬直化し、純粋な技術部門からの発明しか特許化できなくなっていないか再検討が必要である。
図2に、新規事業など、初期的に経営責任者の経営判断が必要な事業に関して、着想を特許化するためのブレインストーミングを模式化して示す。図2に示すように、経営責任者、弁理士(特許担当者)、IT技術者の3つの立場の者が参加したブレーンストーミングを行う。
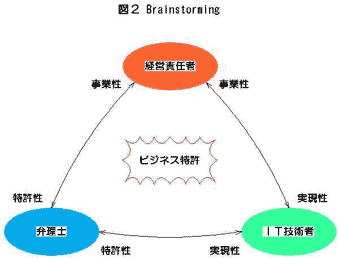
事業性の観点からビジネスモデルの着想を提示するのは主に経営責任者である。ビジネスモデルそのものが、収益性や企業ポリシーなどの点から、事業遂行に値するものでなければならない。この点の判断は、経営責任者が下すべき事項である。
これに対し、提示されたビジネスモデルの特許性を見極めるのが弁理士である。また、弁理士は、特許性の観点から、ビジネスモデルの修正案を提示する。たとえば、発明としての成立性がないビジネスモデルに対しては、コンピュータやインターネットを用いたビジネスモデルに修正する。また、進歩性を欠くビジネスモデルに対しては、進歩性を導き出せるような修正案ならびに修正の方向を提示する。
経営責任者は、修正されたビジネスモデルの事業性を再評価する。修正したビジネスモデルによって特許性が生じたとしても、事業性が失われれてしまえば、特許取得の必要性が低いからである。
システムエンジニア(SE)は、このビジネスモデルを技術的な観点から、5年、10年先も踏まえた実現性を評価する。また、場合によっては、ビジネスモデル実現のための技術的なネック指摘し、有効な解決策を提案して、技術的観点からの特許取得の方向づけを行う。
このように、経営責任者、弁理士、SEのブレーンストーミングにより、事業性、特許性、実現性を備えたビジネスモデルをつくり出すことができる(図3参照)。新規事業のビジネスモデルについては、上記のように経営責任者も含めたブレーンストーミングが有効である。
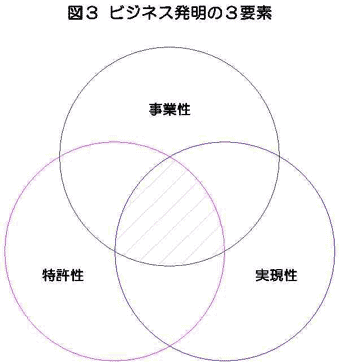
3.発明創造ブレインストーミング
上記のように、新規事業に関しては、事業性の経営判断が重要であることから、経営責任者を交えたブレインストーミングが有効であった。一方、既存事業のビジネス手法については、既に、事業性の判断が済んでいるので、上記のような形態が必ずしも好ましいわけではない。事業を執行する関係社員も多く、着想も多く生まれているはずであるから、これを効率よく特許化することが重要だからである。
しかしながら、このような着想を特許化することは、特許ポートフォリオ形成のために重要であるにもかかわらず、これを有効に特許化できていない企業も多い。その原因は、①どのようなものが特許になるのかわからないため、着想を発明化することができない。さらに、②発明化できたとしても、発明届出書のフォームなどが準備されておらず、特許化する手順が社内的に確立していない。加えて、③発明を生み出すことはできても、発明届出書を書くことができない、という3つに絞ることができる。
知的財産部門を立ち上げたばかりの企業にとっては、上記①、②、③のすべての要因を一度にクリアしなければならず、これが大きな壁として立ちはだかることとなる。このような場合、3つの要因を同時に解決することのできる、発明創造ブレインストーミングを行うことが好ましい。
発明創造ブレインストーミングは、5-6人程度のSEや企画担当者と、1人のモデレータによって行う。モデレータとしては、弁理士が好ましい。特許担当者がいる場合、当然、参加することが必要である。この発明創造ブレンストーミングの流れを図4に示す。
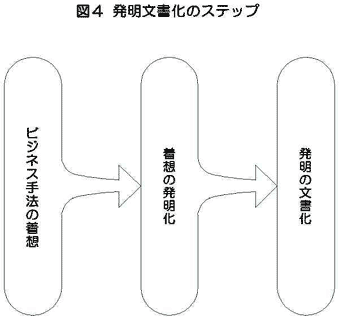
参加者は、1人につき1つの着想(ビジネス手法など)をもち寄ることを条件とする。モデレータが主導して、各参加者のそれぞれのアイデアにつき、全員で、発明の成立性、進歩性を検討する。成立性や進歩性が危ういものについては、ビジネスの着想を修正して、成立性・進歩性を出すことができないかを討論する。モデレータは、参加者の提示したビジネスの着想を特許化するために、成立性や進歩性をどのようにしてクリアすればよいか、その考え方をその着想に応じて方向づけする。このような全員討論を経て、着想を特許取得可能な発明にしていく。
着想の発明化ができれば、次に、この発明を文書化する。多くの企業では、発明届出書のフォームが決められているので、この様式に従って発明をまとめていく。この際、文章は最小限にして、図面を中心にまとめることが重要である。正しい指導のもとで、発明届出書*5を1度でも書いた経験があると、次回新たな発明をした場合に、簡単にこれをまとめることができる。したがって、参加者全員が、その場で発明届出書を作成する。モデレータは、発明届出書の作成にあたっての考え方・まとめ方などの指導を行う。
以上のようにして発明届出書が出来上がれば、これに基づいて弁理士に依頼を行い、効率よく特許出願をすることが可能となる。このブレインストーミングの参加者は、着想を発明化し、発明を届出書にまとめる過程を経験できるので、特許センスを自分のものにすることができる。したがって、次回からは、着想がうかんだときに、特許取得可能かどうかの判断を踏まえて、着想の発明化、届出書へのまとめを自分で行うことができるようになる。
知的財産部門では、届出書を見て出願の要否を決定することができる。また、外部の弁理士に対する出願依頼も、この届出書をもとに行うことができる。これにより、特許取得の社内的な流れを作ることができる。
Ⅵ.まとめ
ビジネスの着想をどのようにして特許価値に高めるかを示してきた。企業における特許の重要性が高まる中で、このような方策をうまくとれるかどうかが、企業の将来を決定付ける大きな要因となろう。なお、上記では、いくつかの方法論を示したが、特許は重要な経営資源であると考える経営責任者の意識が、大前提であり、最も大切であるという点を述べて本稿を終える。
以上
注釈
*1弁理士会研修所実務総合研究部「弁理士が教えるビジネスモデル特許の本当の知識」11頁~15頁参照
*2特許庁が、特許出願の審査を行うに当たっての運用を統一的に定めたもの。2001年1月に、新たな審査基準が運用開始された。
*3審査基準においては、ソフトウエアとハードウエア資源とが共働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有のの情報処理装置が構築される場合に、発明に該当するとしている。
*4ビジネス発明の進歩性判断において、専門家とは、当該ビジネスの専門知識とコンピュータシステムの専門知識の双方を兼ね備えた人を想定する。前掲審査基準 2.3.3参照本文へ戻る
*5発明届出書の実例は、古谷栄男他「知って得するソフトウエア特許・著作権(改訂三版)」アスキー出版P313以下を参照のこと
NOTES
この論文は、「開発工学」2000年後期号に掲載したものです。この資料は、下記の著作権表示をしていただければ、複製して配布していただいて結構です(商業的用途を除く)。
(C)2000 Hideo FURUTANI / furutani@furutani.co.jp
MAIL TO
furutain@furutani.co.jp
ビジネスモデル特許の目次へ
発表論文・資料集の目次へ
トップページ(知的財産用語辞典)へ
|